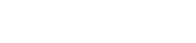ログイン
MAIN MENU
TOP > ページ内検索
サイト内検索
キーワード:
該当ページ数:2,181件
該当ページ数:2,181件
地質学会とは
地質学とは、そして日本地質学会とは
地質学とは、そして日本地質学会とは
地質学とは18紀末に生まれた言葉"Geology"を、明治初期に地質学と訳されたことばです。Geoとは地球であり、logyとは学問を意味するので、その言葉に込められた思いは「地球を科学する」ことです。しかし、Geologyという科学が生まれて以降、19世紀〜20世紀前半にはもっぱら固体地球表層の地殻の岩石や地層そして化石などを対象として地球の歴史や現象を包括的にあるいは個別的に研究する ことを主としたので、そのような分野に対して限定的にGeologyというようになりました。
しかし、20世紀後半に、人類は史上はじめてプレートテクトニクスという科学的包括的な地球観を得ました。以来、地球に関する科学をGeosciencesと一般には呼ぶようになりました。地球諸科学が融合して「地球を知る」作業が必要となったのです。このことはそもそものGeo-logy成立の精神です。今後、地質学は切迫する地球環境問題や大規模自然災害の解明などに答えながら益々発展する科学です。
日本地質学会は地質学の発展や普及を目指して,今から100年以上前の1893年に創立されました.大学をはじめ研究機関の研究者や学校の先生,地質学を学んで社会に役立てるために仕事をしている人,大学生,大学院生,地質学が好きで勉強している人など約3800人が所属し,この分野を包括し、日本の地球諸科学関連学協会の中で最大規模の学会です。
▷▷平成26年度中期ビジョン検討ワーキンググループ提言(2015年9月10日)(475KB)
議事録_任意団体(-2010.5)
任意団体 日本地質学会議事録(バックナンバー)
理事会議事録
評議員会議事録
2009年度
2009年度第12回理事会(2010.5.8開催)
2009年度第11回理事会(2010.4.3開催)
2009年度第10回理事会(2010.3.13開催)
2009年度第9回理事会(2010.2.13 開催)
2009年度第8回理事会(2010.1.19開催)
2009年度第7回理事会(2009.12.5開催)
2009年度第6回理事会(2009.11.14開催)
2009年度第5回理事会(2009.10.3開催)
2009年度第4回理事会(2009.9.3開催)
2009年度第3回理事会(2009.8.10開 催)
2009年度第2回理事会(2009.7.11開 催)
2009年度第1回理事会(2009.6.13開催)
2008年度
第14回理事会(2009.5.10.開催)
第13回理事会(2009.4.11.開催)
第12回理事会(2009.4.4.開催)
第11回理事会(2009.3.14.開催)
第10回理事会(2009.2.14.開催)
第9回理事会(2009.1.10.開催)
第8回理事会(2008.12.13.開催)
第7回理事会(2008.11.30.開催)
第6回理事会(2008.11.8.開催)
(第6〜9回議事録は1つのPDFです)
第5回理事会(2008.10.11.開催)
第4回理事会(2008.9.19.開催)
第3回理事会(2008.9.13.開催)
第2回理事会(2008.7.12.開催)
第1回理事会(2008.6.14.開催)
2007年度
第12回理事会(2008.5.17.開催)
第11回理事会(2008.4.5開催)
第10回理事会(2008.3.8.開催)
第9回理事会(2008.2.9.開催)
第8回理事会(2008.1.12.開催)
第7回理事会(2007.12.15.開催)
第6回理事会(2007.11.10.開催)
第5回理事会(2007.10.13.開催)
第4回理事会(2007.9.8.開催)
第3回理事会(2007.8.13.開催)
第2回理事会(2007.7.14.開催)
第1回理事会(2007.6.9.開催)
2006年度
第12回理事会(2007.5.12開催)
第11回理事会(2007.4..27開催)
第10回理事会(2007.3.10開催)
第9回理事会(2007.2.10開催)
第8回理事会(2007.1.13開催)
第7回理事会(2006.12,16開催)
第6回理事会(2006.11.11開催)
第5回理事会(2006.10.14開催)
第4回理事会(2006.7.8開催)
第3回理事会(2006.7.8開催)
第2回理事会(2006.7.8開催)
第1回理事会(2006.6.10開催)
2005年度
第21回理事会(2006.5.13開催)
2009年度
2009年度第3回定例評議員会(2010.4.3開催)
2009年度第2回定例評議員会(2009.12.5開催)
2009年度第1回定例評議員会(2009.9.3開催)
2008年度
第4回定例評議員会(2009.4.4開催)
第3回定例評議員会(2008.11.30開催)
第2回定例評議員会(2008.9.19開催)
第1回定例評議員会(2008.5.25開催)
2007年度
第4回定例評議員会(2007.4.5開催)
第3回定例評議員会(2007.12.15開催)
第2回定例評議員会(2007.9.8開催)
第1回定例評議員会(2007.5.20開催)
2006年度
第4回定例評議員会(2007.4.7開催)
第3回定例評議員会(2006.12.16開催)
第2回定例評議員会(2006.9.15開催)
第1回定例評議員会(2006.5.14開催)
2005年度
第7回定例評議員会(2006.5.13開催)
総会議事録
■第117年総会議事録(2010.05.23開催)
■第116年総会議事録(2009.05.17開催)
■2008年臨時総会議事録(2008.11.30開催)
沿革
学会概要
沿革
1893(明治26)
5月:東京地質学会 創立
「地質学雑誌」(The Geological Magazine . 現 The Journal of the Geological Society of Japan)創刊
1934(昭和 9)
10月:日本地質学会に改称
1953(昭和28)
日本地質学会賞 創設
1968(昭和43)
「地質学論集」創刊(75周年記念討論会論文集として)
1992(平成 4)
欧文誌「The Island Arc(現 Island Arc)」創刊
1998(平成 9)
「日本地質学会News」(地質学雑誌より分離)創刊
2008(平成20)
12月1日:一般社団法人日本地質学会 設立
2010(平成22)
5月23日:任意団体日本地質学会 解散.すべての事業及び財産を一般社団法人に移譲
2018(平成30)
創立125周年 >>125周年記念事業特設ページ
2023年10月現在 会員数:約3300名
役員
学会概要
役 員
理 事
任期:2024年6月8日〜2026年総会
※執行理事の紹介はこちら
会長(代表理事)
山路 敦(京都大学)
副会長
杉田律子(科学警察研究所)
星 博幸(愛知教育大学)
常務理事
亀高正男(大日本ダイヤコンサルタント(株))
副常務理事
内野隆之(産業技術総合研究所)(社会貢献部会兼務)
執行理事
(* 印は部会長)
【運営財政部会】
加藤猛士*(川崎地質(株))・細矢卓志(中央開発(株))
【広報部会】
坂口有人*(山口大学)(社会貢献部会兼務)・内尾優子(東京国立博物館)・松田達生(工学気象研究所)・大坪 誠(産業技術総合研究所)(社会貢献部会兼務)
【学術研究部会】
辻森 樹*(東北大学)(編集出版部会兼務)・尾上哲治(九州大学)・高嶋礼詩(東北大学)・山口飛鳥(東京大学大気海洋研究所)
【編集出版部会】
小宮 剛*(東京大学)
【社会貢献部会】
矢部 淳(国立科学博物館)・岩井雅夫(高知大学)
理 事
青矢睦月(徳島大学)
天野一男(東京大学空間情報科学研究センター)
磯粼行雄(東京大学)
大友幸子(山形大学)
岡田 誠(茨城大学)
笠間友博(箱根町役場)
加藤 潔(駒澤大学)
香取拓馬(フォッサマグナミュージアム)
金丸龍夫(日本大学)
神谷奈々(京都大学)
川村紀子(海上保安庁海上保安大学校)
清川昌一(九州大学)
桑野太輔(京都大学)
小松原純子(産業技術総合研究所)
齋藤 眞(産業技術総合研究所)
佐々木和彦(佐々木技術士事務所)
澤 燦道(東北大学)
沢田 健(北海道大学)
沢田 輝(富山大学)
下岡和也(関西学院大学)
菅沼悠介(国立極地研究所)
高野 修(石油資源開発(株) )
田村嘉之(千葉県環境財団)
中澤 努(産業技術総合研究所)
西 弘嗣(福井県立大学)
野田 篤(産業技術総合研究所)
広瀬 亘(北海道立総合研究機構)
松田博貴(熊本大学)
道林克禎(名古屋大学)
矢島道子(東京都立大学)
山本啓司(鹿児島大学)
和田穣隆(奈良教育大学)
監 事
任期:2024年6月8日〜2028年総会
岩部良子(応用地質(株))
山本正司(山本司法書士事務所)
2024年度受賞者
2024年度各賞受賞者 受賞理由
■都城秋穂賞(1件)
■H. E. ナウマン賞(1件)
■小澤儀明賞(1件)
■柵山雅則賞(1件)
■論文賞(1件)
■Island Arc Award(1件)
■小藤文次郎賞(1件)
■地質学雑誌特別賞(1件)
■研究奨励賞(5件)
■学会表彰(1件)
日本地質学会都城秋穂賞
授賞者:Gregory F. Moore氏 (アメリカ・ハワイ大学)
対象研究テーマ: 南海トラフ周辺における地質構造の三次元イメージング研究
米国ハワイ大学のGregory F. Moore名誉教授は,世界各地の付加体の地質構造や発達過程などについて,主に地質学的・地球物理学的アプローチによって多くの重要な成果をあげてこられた.Moore氏の研究対象は,日本周辺をはじめ,スマトラ島沖,モルッカ海,台湾周辺,北米オレゴン沖,中米バルバドス,コスタリカ沖,ヒクランギ沖など世界各地に広がっている.ただしMoore氏の研究の多くは南海トラフ周辺海域に集中しており,研究論文の3分の1以上が南海トラフ関係となっている.なかでも特筆すべき研究成果は,南海トラフ周辺で実施された,反射法地震探査やIODP等の海底掘削のコア試料の解析による南海トラフ付加体の構造を日米共同で解明したことであり,デコルマ面(プレート境界)やメガスプレー断層の三次元地質構造を含む,現世付加体の構造を世界に先駆けて鮮明に描き出したことである.例えば,紀伊半島沖では,南海トラフ付加体内の巨大分岐断層が,付加体の下位にあるプレート境界断層から海底面まで連続し,前面の付加体内の低角断層群を切る様子を世界に先駆けて詳細に明らかにし,巨大分岐断層の役割について詳しい議論を行っている.また四国沖では,デコルマ面を境に上盤側では海溝充填堆積物が分岐断層によるスラストや褶曲を伴いながら,付加体が形成されてゆくのに対して,下盤側では半遠洋性堆積物が非変形のまま海洋地殻とともに沈み込むさまを見事に描き出した. 南海トラフ周辺の現世付加体の詳細な地質構造描出による収束境界の地質構造やテクトニクスに関する研究では,多くの日本人研究者との共同研究においてMoore氏はリーダーシップを発揮してこられた.また,日本の若手研究者の育成に貢献するとともに,日本における現世付加体の研究が世界で認められる上で,一つの重要な役割を果たされた.Moore氏とその共同研究者が明らかにした現世付加体の地質構造は,日本の地質基盤の主要な要素の一つである陸上付加体の研究にも多大な影響を与えている. 以上のように,国際的に顕著な業績を残し,南海トラフを中心とした日本の収束境界の地質学の発展と研究者育成に多大な功績を残したMoore名誉教授は,日本地質学会都城秋穂賞に値すると判断した.
Dr. Gregory F. Moore, the University of Hawaii has made significant contributions to the understanding of the geological structures and tectonics of accretionary prisms worldwide, primarily through geological and geophysical approaches. His research encompasses diverse regions, including areas around Japan, Sumatra, the Molucca Sea, Taiwan, Oregon, Barbados, Costa Rica, and New Zealand, with a significant focus on the Nankai Trough region. Over one-third of his published work centers on this region. Notably, his significant research achievements include the joint Japan-US project to elucidate the structure of the Nankai accretionary prism through reflection seismic surveys and the analysis of core samples from IODP and other deep-sea drilling projects. Those works have vividly depicted the three-dimensional geological structure of the active accretionary prism for the first time, including the décollement and mega-splay faults. For example, off the Kii Peninsula, Dr. Moore’s research has detailed how the mega-splay fault within the Nankai accretionary prism extends continuously from the plate boundary fault beneath the accretionary prism to the seafloor, cutting through the low-angle faults in the frontal accretionary prism. This research has led to detailed discussions on the role of the mega-splay fault. Additionally, off the coast of Shikoku, his research has vividly illustrated how trench-fill sediments on the hanging wall side of the décollement are thrust and folded by splay faults, forming the accretionary prism, while on the footwall side, hemipelagic sediments subduct along with the oceanic crust without deformation.
In studies on the geological structure and tectonics of convergent boundaries through detailed investigations of the geological structures of the active accretionary prism around the Nankai Trough, Dr. Moore has exercised leadership through collaborative researches with many Japanese researchers. He has also contributed to the development of young researchers in Japan and played a crucial role in gaining global recognition for research on the current accretionary prism in Japan. The geological structures of the active accretionary prism elucidated by Moore and his collaborators have significantly influenced the study of onshore accretionary prisms, which are major elements of Japan’s geological framework.
In recognition of his internationally significant achievements and his outstanding contributions to the development of geology and the training of researchers, particularly in the Nankai Trough region, Dr. Moore is highly recommended for the Geological Society of Japan’s Akiho Miyashiro Prize.
日本地質学会H. E. ナウマン賞
授賞者:岡本 敦 会員 (東北大学大学院環境科学研究科)
対象研究テーマ: 岩石組織に基づく地殻・マントルにおける岩石−水相互作用のダイナミクスの解読
マントル岩石の岩石―水相互作用に関する研究で岡本会員は,岩石組織の詳細な観察を基礎として,マントル岩石の加水反応や炭酸塩化反応が自己促進的に進行するメカニズムを数値モデリングを通じて明らかにしている.さらに,マントル岩石のナノスケールから数百メートルスケールにわたる反応帯組織の解析を行い,従来理解が困難であった流体活動の時間スケールを推定することに成功した.そして,地球内部の流体活動と地震活動の時間スケールが整合的であることを明らかにした.これらの研究成果は,地球規模の水・炭素循環や地震活動に関する更なる研究と議論を国際的に推進することに大きな役割を果たしている. また,岡本会員は,地震発生時の急激な減圧効果を示すとされる鉱物脈の形成過程を,独自に設計した装置を駆使した水熱反応実験により再現することに成功した.この成果は,露頭規模で観察される岩石組織と地震活動を結びつける点で極めて重要であり,地震活動と流体活動の時間サイクルに関して,新たな視点からの制約条件を提供するものでもある.また,これらの実験的アプローチは,理学のみならず,地熱発電開発など工学分野の研究にも寄与するものと期待できる. 岡本会員は,これまでに数多くの論文を発表するとともに,国際学会において招待講演や基調講演を行い,国内外の学界に大きなインパクトを与えてきた.そして,上記のように数値モデリングと水熱反応実験の両面から,地殻—マントルにおける流体挙動に関する研究を推進してきた点は特筆される.このような業績と今後期待されるさらなる国際的かつ学際的活躍は日本地質学会H.E.ナウマン賞に値するものである.したがって,岡本会員は,日本地質学会H.E.ナウマン賞に値すると判断した.
日本地質学会小澤儀明賞
授賞者:羽田裕貴 会員 (産業技術総合研究所)
対象研究テーマ:鮮新-更新統の超高時間分解能解析による北西太平洋古海洋・古地磁気変動の研究
羽田裕貴会員は,緻密な野外調査を行い,鮮新―更新統の精密年代層序の構築と,高時間分解能での有孔虫酸素同位体および古地磁気分析によって,日本列島周辺海域を含む北西太平洋における古海洋変動・地磁気変動の研究において顕著な成果を挙げてきた.特に,下部−中部更新統境界の国際標準模式層断面とポイント(Global Boundary Stratotype Section and Point,GSSP)に批准された千葉セクションを含む一連の海成更新統(千葉複合セクション)においては,表層・亜表層・底生有孔虫化石を,平均160年間隔で分析することにより,超高時間分解能での酸素同位体層序を構築した.そして,数ある間氷期の中でも,現在の完新世と地球の軌道要素が,過去100万年間で最も類似している海洋酸素同位体ステージ19を精査し,海洋性と陸源性有機物の混合比や底層水酸素濃度が氷期―間氷期サイクルと一致していることを示した.さらに,羽田会員は,磁気反転が77万2900(±5400)年前であること,78万3000年前から76万3000年にかけての2万年間に古磁気方位が数度にわたり不安定となり,これが古磁気強度の減少を伴っていたことをつきとめた.これらの研究は,GSSP,海洋酸素同位体ステージ19,松山−ブルンの地磁気逆転境界という地質学における重要なテーマに大きな貢献をしたと高く評価される. 羽田会員は,これらの手法を精力的に発展させ,沿岸堆積物や湖成層を用いた鮮新―更新世の古地磁気層序の構築や火成岩礫の磁気分析などを行い,新領域の研究分野にも取り組んでいて,すでに成果の一部を発表している.これらの研究は,国内外の多くの研究者との協力研究を通じて実施されてきたが,羽田会員は,若手のリーダーとしての役割をきちんと果たしてきた.古地磁気と古環境の両研究は,地球の内部と表層で起こる地球システムの理解の上で本質的なテーマで,羽田会員の研究には今後の一層の発展が期待される.以上の羽田裕貴会員の業績と将来性は,日本地質学会小澤儀明賞に値すると判断した.
日本地質学会柵山雅則賞
授賞者:奥田花也 会員 (海洋研究開発機構 超先鋭研究開発部門)
対象研究テーマ: 沈み込みプレート境界断層の統合的すべり挙動の研究
奥田花也会員は,プレート沈み込み帯地震の発生機構解明に向け,断層の摩擦特性に関する実験的研究で顕著な成果をあげてきた.プレート沈み込み帯で採取されたコア試料や陸上のアナログ岩石,模擬物質についての変形実験,および第一原理計算に基づく原子スケールの数値実験などに基づき,海溝からマントルウェッジに至るプレート境界断層物質および関連する鉱物の物性を系統的に明らかにした. 奥田会員はまず,付加体から採取されたコア試料やその模擬物質を用い,プレート沈み込み境界の幅広い深度領域における摩擦特性を解明し,海溝型巨大地震や浅部スロー地震の発生理解に貢献した.また,地震発生領域に対応する温度・圧力下での摩擦実験に基づいて,海洋地殻を構成する変質した玄武岩が,実際の断層運動に近いと考えられる間欠的な変位挙動を生じ易く,また,スロー地震発生領域に存在する可能性のあるブルース石が,不安定滑りを起こしうることなどを示し,海洋地殻やマントルの変質プロセスで形成される岩石や鉱物が断層運動に重要な役割を果たす可能性を示した.さらにまた,断層強度を左右すると考えられる粘土鉱物内部の摩擦が,原子スケールでどのように働くかを第一原理計算に基づく数値シミュレーションによって明らかにし,結晶構造の差異による摩擦強度や特性の違いを評価することに成功した.これらの成果により,多様な物質・鉱物で構成されると考えられる実際の断層やプレート境界の強度や特性を,変形実験や数値シミュレーションに基づいて推定可能であることが示された. このように,奥田会員は,多様な手法をもちいて幅広い空間スケールでの断層挙動メカニズムの研究に取り組んでいる.また,国内外を問わず,複数の研究者・研究室と積極的に協力して先端的研究および地質学−地震学の融合的研究を行っており,今後,さらなる国際的・学際的な活躍が期待される.以上の奥田会員の業績と将来性は,日本地質学会柵山雅則賞に値すると判断した.
Island Arc Award
対象論文:Yusuke Sawaki, Hisashi Asanuma, Mariko Abe, Takafumi Hirata, 2020, U–Pb ages of granitoids around the Kofu basin: Implications for the Neogene geotectonic evolution of the South Fossa Magna region, central Japan. Island Arc. 29. e12361.
本論文は,甲府盆地周辺の新生代花崗岩類について多数のジルコンU-Pb年代測定を行い,複数の火成活動時期を特定することによって,南部フォッサマグナ地域の新第三紀以降の構造発達史の理解に再考をうながすものである.甲府盆地周辺は伊豆−小笠原−マリアナ(IBM)弧と南西本州弧との衝突による複雑な地質構造を持つが,著者らは貫入時期が異なる複数の花崗岩活動期に注目し,系統的なジルコンU-Pb年代測定を試みた.その結果,同地域の花崗岩活動が約15.5Ma,約13Ma,約10.5Ma,そして約4Maの4時期に分けられることを明示した.同地域で最古の約15.5Ma花崗岩形成がIBM弧内でのマグマ活動であったのに対して,約13Maの花崗岩類が本州弧とIBM弧との境界をまたいで貫入したことを突き止め,2つの島弧系の衝突開始時期を15〜13Maの間と制限した.また約10.5Maの火成活動はIBM弧の背弧拡大に,そして最も新しい約4Maの花崗岩形成は島弧衝突に伴う急速なマグマ形成に各々関係したと解釈した.南部フォッサマグナ地域については,これまでにIBM弧の衝突時期とプレート三重点の挙動などを想定した複数のプレート運動学モデルと古地理図が提唱されてきたが,本研究は既存の理解に再考を迫ることになった.この著しい貢献はIsland Arc Awardにふさわしいと判断した.
>論文サイトへ(wiley)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iar.12361
日本地質学会論文賞
対象論文:Nakajima, T., Sakai, H., Iwano, H., Danhara, T., & Hirata, T., 2020, Northward cooling of the Kuncha nappe and downward heating of the Lesser Himalayan autochthon distributed to the south of Mt. Annapurna, western central Nepal. Island Arc. 29. e12349.
著者らはネパールに分布する高度・低度の変成岩類と現地性堆積物にまたがる南北セクションから12試料を採取し,ジルコンのフィッション・トラック年代測定を行った.その結果,約240˚Cへの冷却時期は,大規模衝上断層の存在に影響されず,南方(下位)の約12Maから北方(上位)の1.6Maへと連続的に若くなることが示された.また3試料についてヒマラヤ地域で初めてトラック長解析を行い,高速侵食が見込まれる北方山岳地域において,南部地域よりも有意に大きな冷却速度が導かれることを示し,その予測を裏付けた.さらに,南方の低度変成岩から得られた457Maという不完全な若返り年代は,変成作用の熱源が上盤側にあったこと,つまり同地域全体が12Maよりも前に一度,高度変成岩の衝上に伴う熱変成を受けたことを示唆する.すなわち,この衝上イベントの後,上下盤が一体化してから削剥されるという構造発達史が明確化した.本論文のデータは,世界的に注目度の高いヒマラヤ造山運動に強い制約を与えるものであることから,この貢献を高く評価し,本論文が日本地質学会論文賞の授賞にふさわしいと判断した.
>論文サイトへ(wiley)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iar.12349
日本地質学会小藤文次郎賞
受賞者:岡本 敦 会員 (東北大学大学院環境科学研究科)
対象論文:Okamoto, A., Oyanagi, R., Yoshida, K., Uno, M., Shimizu, H., Satish-Kumar, M., 2021, Rupture of wet mantle wedge by self-promoting carbonation. Communications Earth & Environment, 2, 151.
本論文は関東山地三波川変成帯,樋口蛇紋岩体において,炭素が沈み込み帯のマントルウェッジに固定される過程を解明した.著者らは同岩体内の炭酸塩鉱物脈に関して,野外観察と岩石試料解析,炭酸塩鉱物の安定同位体分析,熱力学計算を行い,炭酸塩鉱物脈が,変成堆積岩中の炭質物起源の炭酸ガスによって形成されたこと,および蛇紋岩化プロセス中に生成する流体と岩石間の相互作用の詳細を説明した.特に,蛇紋岩化過程における炭酸化反応が自己促進的に,かつ断続的に進行し,固体体積の減少,流体圧の増大,脱水反応,元素移動を伴うことを示した.蛇紋岩化したマントルウェッジ内の炭酸塩脈の形成は,沈み込みによる地球深部への物質循環やテクトニックな活動と密接に関連しており,それらの過程を理解する上で重要な手がかりを提供する.本論文は,マントルウェッジの蛇紋岩化過程における炭酸化反応が,その熱力学的および物理的性質に大きな影響を与えることを論理的に指摘し,その学術的なインパクトは大きい.以上のことから,本論文の筆頭著者である岡本 敦会員が日本地質学会小藤文次郎賞の授賞にふさわしいと判断した.
>論文サイトへ
https://doi.org/10.1038/s43247-021-00224-5
日本地質学会地質学雑誌特別賞
受賞論文:牛丸健太郎・山路 敦, 2020, 天草下島北部の中新世貫入岩体の方向と応力解析. 地質学雑誌,126巻,11号,631-638.
本研究は,熊本県天草下島に分布する14〜17Maに形成された板状貫入岩体(76枚)の方位を網羅的に調査し,応力解析を実施した.日本海拡大期には,島弧に直交する引張応力が働いたと一般に考えられている.天草下島では,琉球弧に直交する西北西-東南東引張を示す大規模な流紋岩岩脈の存在が指摘されていたが,このような岩脈を代表的トレンドとすることには危険性があることを指摘し,テクトニックな評価が行えるよう,多数の小規模な貫入岩体の方位分布を用いて応力解析を行っている.傾動補正前後の応力方向の検討を行い,始新統の褶曲に参加しているかについて,得られた応力方向は褶曲形成とは不調和で,貫入岩体は褶曲後に生じた可能性が高いとした.検出された南北引張応力が通説と一致しないことを示したが, 広域テクトニクスの議論には慎重であり,局所的な放射状岩脈群の一部を観測した可能性も指摘している.検出された応力の解釈を丁寧に行っていること,レターの限られた紙面にフィールド調査,年代評価,応力解析結果の吟味,既存資料に対する議論をコンパクトにまとめた論文構成は高く評価できる.以上のことから,本論文が地質学雑誌特別賞の授賞にふさわしいと判断した.
>論文サイトへ(J-STAGE)
https://doi.org/10.5575/geosoc.2020.0033
日本地質学会研究奨励賞
受賞者:福島 諒会員(東北大学大学院理学研究科)
対象論文:Fukushima, R., Tsujimori, T., Aoki, S., and Aoki, K., 2021,Trace-element zoning patterns in porphyroblastic garnets in low-T eclogites: Parameter optimization of the diffusion-limited REE-uptake model. Island Arc, 30, e12394.
化学組成データとモデル計算を統合し,変成岩中のザクロ石から造山運動の時間規模などの地質情報を抽出しようとする研究は古くからあるが,その具体的な方法論は開発途上の段階と言える.近年の微量元素スポット分析技術の進歩に注目し,著者らはまず,ギリシャ産とグアテマラ産の低温エクロジャイト中のザクロ石を,結晶中心を通る面で精密切断し,LA-ICP-MSでのラスター分析を行った.そして,独自開発した2次元信号処理法を駆使し,ザクロ石の中心部から最外縁部に至るMnと希土類元素についての濃度プロファイルを取得した.このデータは最近の海外研究者らの論文で引用されるなど,注目を集めている.さらに著者らは2006年に提唱された「拡散律速取り込みモデル」を再検討し,本論文で得られた濃度プロファイルとの比較を行うことで,ある組成累帯構造から一意に定まるパラメータ群を整理し,それらを基に拡散律速または界面律速といった,地質帯ごとの変成カイネティクスの差異を議論できる可能性を新たに論じた.以上の貢献から,本論文の筆頭著者である福島 諒会員が日本地質学会研究奨励賞の授賞にふさわしいと判断した.
論文サイトへ(wiley)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/iar.12394
日本地質学会研究奨励賞
受賞者:木下英樹会員(京都大学大学院理学研究科,応用地質株式会社)
対象論文:Kinoshita, H. and Yamaji, A., 2021, Arc-parallel extension in preparation of the rotation of southwest Japan: Tectonostratigraphy and structures of the Lower Miocene Ichishi Group. Island Arc, 30, e12418.
日本海拡大時,西南日本はほぼ「一枚岩」として移動したとされ,当時のグラーベンの規模の小ささはそのことと調和的だとされている.しかし近年,規模の大きなグラーベンが重力探査により知多半島付近で発見されるなど,グラーベンの多様性から多方向の島弧内リフティングがあったことが指摘されてきた.そこで,背弧拡大時における島弧内変形の詳細なプロセスを解き明かす目的で,筆者らは伊勢湾西部の下部中新統一志層群の地質調査を行い,高精度の地質図を作成した結果,地質図規模の断層のスリップ方向から島弧と平行な東北東-西南西方向の引張応力を検出し,正断層と左横ずれ断層によるグラーベンが形成されたことを示した.また,整合一連とされてきた同層群中に不整合を発見して,それを境にブロック状の差別的昇降から広範囲のサグ状沈降に移行したことを示した.さらに,これらを基に,島弧と平行な引っ張りによって伊勢湾周囲にグラーベンの集合体が形成され,最終的にはフォッサマグナの深いリフト帯の形成をもたらすとともに17.5 Ma頃からの西南日本の急速な回転につながったことを提示した.これらの成果は,Supporting Informationに含まれる豊富な露頭写真からも裏付けられるように,詳細な地質調査に基づく岩相層序の観察と構造地質学的な解析から初めて明らかになったものであり,日本海拡大時における島弧内変形のプロセスの理解に大きく貢献する研究として高く評価される.以上のことから,本論文の筆頭著者である木下英樹会員が日本地質学会研究奨励賞の授賞にふさわしいと判断した.
論文サイトへ(wiley)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/iar.12418
日本地質学会研究奨励賞
受賞者:武藤 俊会員(産業技術総合研究所地質情報研究部門)
対象論文:Muto, S., Takahashi, S., & Yamakita, S., 2023, Elevated sedimentation of clastic matter in pelagic Panthalassa during the early Olenekian. Island Arc, 32, e12485.
過去の超海洋で数千万年以上にわたって継続的に堆積した遠洋深海チャートには,ペルム紀末大量絶滅直後の下部三畳系に限定された珪質粘土岩が挟まれる.本研究は,岩手県安家地域に産するこの特徴的な粘土岩について,高分解能のコノドント生層序年代に基づき堆積速度を復元し,その堆積速度が通常の層状チャートよりも明らかに高いことを示した.粘土岩が持つ高い堆積速度は,従来の放散虫生産性の低下という解釈では説明できず,超海洋中央部への細粒砕屑物(おそらく風成塵)フラックスの増加が示唆される.その原因として,グローバルスケールの陸域環境の変化,特に広域の乾燥化もしくは乾期の強化が考察されており,特徴的な粘土岩が世界でも稀な貴重な堆積記録であることが明示された.本論文は,粘土岩からのコノドント抽出における独自の工夫および詳細な露頭観察に基づく着実な観察・記載を行った結果,卓抜した新解釈を導いており,また洗練された英文執筆能力が伺えることから,今後の若手研究者にとっての好見本となると判断される.以上のことから,本論文の筆頭著者である武藤 俊会員が日本地質学会研究奨励賞の授賞にふさわしいと判断した.
論文サイトへ(wiley)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/iar.12485
日本地質学会研究奨励賞
受賞者:渡部将太会員(茨城大学大学院理工学研究科)
対象論文:渡部将太・長谷川 健・小畑直也・豊田 新・今山武志,2023,福島県南部,二岐山火山の噴火史とマグマ供給系. 地質学雑誌, 129, 307–324.
本論文は,那須火山群の二岐山火山について,空中写真や地形図などを用いた地形判読,現地調査,試料採取と岩石記載,全岩化学組成分析,および熱ルミネッセンス年代測定を行い,層序,噴出率の時間変化,マグマの生成・供給系の評価を総合的におこなったものである.従来3つに大別されていた噴出物を,溶岩と火砕物からなる11のユニットに新たに分類し,その層序区分に基づいて熱ルミネッセンス年代測定を行い,マグマ噴出率の時間変化を評価した.また,岩石記載と全岩化学組成データから,噴出物を6つの岩石タイプに区分し,鉱物組み合わせおよび組成の多様性の成因を議論した.さらに,層序,年代値,噴出率変化と成因論を組み合わせ,二岐山火山におけるマグマ生成・供給系と火山発達史を実証的かつ総合的に議論している.このように本論文は,多様な手法と結果を有機的に結び付けて,マグマの成因から火山形成史までを統合的に論じたもので,火山発達の理解に大きく資すると同時に,その総合的な取り組み方は他の火山にも適用可能な一般性を有する.以上のことから,本論文の筆頭著者である渡部将太会員が日本地質学会研究奨励賞の授賞にふさわしいと判断した.
論文サイトへ(J-STAGE)
https://doi.org/10.5575/geosoc.2022.0061
日本地質学会研究奨励賞
受賞者:吉田 聡会員(東北大学 東北アジア研究センター)
対象論文:Yoshida, S., Ishikawa, A., Aoki, S., and Komiya, T., 2021, Occurrence and chemical composition of the Eoarchean carbonate rocks of the Nulliak supracrustal rocks in the Saglek Block of northeastern Labrador, Canada. Island Arc, 30, e12381.
カナダ・ラブラドル地方のサグレック岩体は世界最古の堆積岩を含む極めて重要な地質体である.本研究では,ここに分布する原太古代の炭酸塩岩の地質学的産状を記述し,計54試料の主要・微量元素を分析した.地質学的産状や高いシリカ等の含有量から,炭酸塩岩は珪化作用による変質を受けていると考えられたが,変質の影響を慎重に吟味することで,当時の海水組成を反映する成分が抽出された.また,特定の希土類元素に見られる濃度異常が鉄酸化物の沈澱によるものであり,サグレック岩体の炭酸塩岩が塩基性熱水の影響を受けていたことが示された.本研究は,太古代の最も古い時代の堆積岩に関するデータ的価値に加え,変質した炭酸塩岩から海水組成の復元につながる研究が可能であることを示した点で意義が大きい.本論文の筆頭著者である吉田会員は本研究を主体的に進めており,彼の今後の研究が地球史の海洋環境や物質循環の理解に大きく貢献すると期待できる.以上のことから,吉田 聡会員が日本地質学会研究奨励賞の授賞にふさわしいと判断した.
論文サイトへ(wiley)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/iar.12381
日本地質学会表彰
表彰者: 夏原信義 氏 (夏原技研)
表彰業績タイトル: 実験装置の開発・製作による地質学への貢献
夏原氏は大阪大学基礎工学部の技官として,精度良い加工を施した川井型マルチアンビルを作成し,超高圧地球科学の発展初期段階での研究進展を支援した.夏原技研を創業後,日本の古地磁気学分野の各種実験装置の開発・製作と改良を一手に担い,夏原氏の岩石磁力計や消磁装置は,日本のほとんどの古地磁気学研究室に導入されるほか,地球深部探査船「ちきゅう」や諸外国の大学にも導入され,国際的にもその評価が高い.交流消磁装置付全自動スピナー磁力計は世界に類のない実験装置であり,古地球磁場強度推定の研究に大きく貢献している.さらに開発機器は,岩石ドリル,堆積物用プラスティックキューブ,ピストンコアラーと多岐にわたり,古地磁気学に限らず岩石学,層序学,古環境学や考古学などのサンプリングにおいて国内外で広く使用されている.夏原氏のこうした実験装置類とサンプリング機器類は,研究者との対話と共同作業によって開発,実用化され,研究者の要求に応じて改良・修理もされてきた.夏原氏がこれらの開発・製作によって地質学の発展に果たした貢献はきわめて大きいことから,夏原信義氏は日本地質学会表彰を受けるにふさわしいと判断した.
入会案内
入会案内
日本地質学会への入会のお誘い
いまほど「地球」が人々の心をとらえている時期はないのではないでしょうか。宇宙から眺める「地球」は、暗黒の宇宙に浮かぶまさにブループラネットであり、美しさを感じる人も多いでしょう。しかし地上の目線でこの「地球」を見た場合、地震や火山などの自然災害がしばしば人々の生活を脅かし、また人工的な環境破壊などは深刻な社会問題です。さらにグローバルな環境変動、気候変動はそのものが持っていた時系列変動のリズムを狂わす変動が現在おきつつあることが懸念されています。これらの複雑な地球でおこっている諸問題は地球科学という分野に分類されていますが、この名称は惑星としての「地球」を知る学問としての代名詞程度と考えた方が適当であるかもしれません。地質学、地学、生命地球科学など、「地球」をとらえる学問の名称は様々存在しますが、
地球を知る(知の創造への貢献)
地球を守る(人類と地球の持続的生存への貢献)
地球と歩む(当面する社会要請への貢献)
などを目的にしている事に間違いはありません。
日本地質学会は、125年以上の歴史を持つ学術団体で、上記のような「地球」に関わる問題を中心に、学術、教育、企業活動に携わる幅広い会員を有する日本最大規模の地球科学の専門学会です。当学会発行の学術雑誌(「地質学雑誌」・「Island Arc」;いずれも電子化)やニュース誌、WEBやメルマガ、広報誌ジオルジュ,そして年会(学術大会)などを通した情報発信や会員相互の情報交換は学会の基本事業です。これらの活動による高度な学術的知識をもとに、「地球」について考え、社会に発信していこうではありませんか。「地球」の未来を皆さんと語れる事を切に願います。
入会申込
入会ご希望の方は入会申込書をご提出ください(原本郵送)。
入会には正会員1名の紹介が必要です。近くに紹介者となるべき会員がいない場合はその旨お申し出ください。また、初年度の会費は、申込書郵送時から時間の間隔をおかずに下記送金先へ速やかにご送金ください。賛助会員(企業,団体)の場合の会費のお支払いついて、ご希望がある場合は,別途学会事務局までお問い合わせください。
【入会申込書送付先】〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル6F
一般社団法人日本地質学会
【会費送金先】郵便振替口座 00140-8-28067 日本地質学会
ゆうちょ銀行 〇一九(ゼロイチキュウ)店 当座 0028067
一般社団法人日本地質学会 シヤ)ニホンチシツガツカイ
個人会員(正会員・ジュニア会員)
入会申込書(正会員・ジュニア会員)のダウンロード(PDF)
会費口座座振替依頼書(PDF)(※自動引き落としを希望の方はご提出ください)
賛助会員(企業・団体)
入会申込書(賛助会員)のダウンロード(PDF)
会費(年額)
※下記は2023年度からの新しい会員種別,会費額です.詳しくは
正会員(シニア会員・一般会員)※1:12,000円
正会員(学生会員)2※ :5,000円/年、2年パック:8,000円、3年パック:9,000円)
ジュニア会員 ※3:0円(年会費不要)
賛助会員:1口 25,000円,2口以上 (賛助会員一覧はこちら)
-----------------------------------------------------
※1 シニア会員は,入会年度の4月1日時点で65歳以上の方を対象とします(4/2以降に65歳になる方は次年度からシニア会員となります).
※2 学生会員は,次の2点を守って手続きして下さい.①学生証の写しを提出すること.②パック制会費を希望の場合は一括納入すること.(学生会員の申請,パック制会費について)
※3 ジュニア会員は,正会員の権利は有しません.学術大会での発表はジュニアセッションに限定します.
-----------------------------------------------------
入会申込書は随時受付しております。基本的に当年度中(4月〜翌年3月中)にお送りいただいた書類は当年度内の入会として受付します。入会申込に関して不明な点がある場合には、地質学会事務局へお問い合わせください。
【お願い】1月〜3月中(次年度会費の納入時期)に入会申込書を提出するかたへ:入会年度の確認【当年度入会か/次年度入会か】についてご連絡を差し上げますので,お早くお返事・お手続きくださるようお願いいたします.
入会手続きのフローチャート
地質雑特別賞
日本地質学会地質学雑誌特別賞(2022年創設)
「地質学雑誌」で重要な地質記載または有⽤性の⾼い新規の研究⼿法等を発表した会員(運営規則第16条2)
※各受賞論文をクリックすると、推薦理由等をご覧いただけます。
【 受賞論文 】
2024
牛丸健太郎・山路 敦, 2020, 天草下島北部の中新世貫入岩体の方向と応力解析. 地質学雑誌,126巻,11号,631-638.
倫理綱領
日本地質学会倫理綱領
(2003年09月19日日本地質学会総会制定/2009年12月5日一般社団法人日本地質学会制定*)
日本地質学会の会員は、科学的真理を明らかにする事を目的として、誠実かつ真摯に地質学および関連科学の研究・教育および調査を行う。その成果を広く社会に公表することにより地質学および関連科学の進歩普及を図り、もって社会の発展と人類の福祉に貢献する。会員は、基本的人権を守り、良識かつ品位のある行動をとる。
1.科学者としての倫理
会員は、専門知識の向上および地質学と関連科学の発展を目指して自己研磨を図る。研究と調査においては、法を遵守し、社会的良識に従って行動する。科学的事実に対しては常に謙虚、誠実でなくてはならない。研究成果と技術上の知見を広く社会に公表し、公表にあたっては先人と他者の業績を尊重する。
2.知的交流の確保
会員は、国際交流や他分野との交流を進めることを通して学術の向上を図るとともに、研究成果と技術上の知見が科学的に広く吟味・検証されるよう努める。
3.人類と社会への責務
会員は、その専門知識と技術を適切に活用し、研究と調査の成果を広く社会に提供することを通して社会の発展と人類の福祉に貢献する。
4.地球環境への責務
会員は、地球システムの諸現象についての専門家として、地質災害の予知と防止、地球環境の将来予測、資源の適正な活用に関する情報を提供するとともに、専門知識を活かして環境の保全と改善に努める。自らの研究と調査の実施にあたっては環境への影響を最小限にするよう配慮する。
5.次世代への責務
会員は、地質学と関連科学における学術と技術の継承と発展、次世代を支える人材の育成を図る。研究や調査の成果物、重要な露頭や標本などの科学的遺産の保全に努める。
* 2009 年12月5日法人理事会において,一般社団法人日本地質学会倫理綱領として全文引継を決定.
日本地質学会著作物利用規定
日本地質学会著作物利用規定
目的
第1条 この規定は,日本地質学会の出版物等が適正にかつ広く利用されるため,日本地質学会の出版物等に掲載された論文等の著作物の著作権とその利用について規定するものである.
定義
第2条本規定における用語の定義は以下のとおりである.
出版物等 日本地質学会が出版,発行するすべての出版物,および電子媒体によって提供される情報をいう.
論文等 論文,解説,報告,論評,要旨,図,表,写真などをいう.
作成者 地質学に関する論文等を創作し,日本地質学会に論文等を投稿した者で著作権譲渡同意書に署名した者,及び著作権譲渡同意書に記名された者をいう.
その他,著作権法第2条に定める各定義は,本規定に準用する.
範囲
第3条本規定は,日本地質学会の出版物等に適用される.
著作権の制限
第4条本規定の定めは,著作権法に定める著作権の制限規定による論文等の正当な利用行為を妨げるものではない.
作成者による利用
第5条作成者が,自ら創作した論文等を利用しようとするときは,以下の場合に限り,日本地質学会の書面による許諾を得ることなしに利用することができる.
作成者(作成者でない者と共同研究する場合を含む)が自らの継続研究の素材として複製,改変して用いる場合.
作成者(作成者でない者と共同研究する場合を含む)が前号によって利用したものを含む論文等を自らの研究の成果として発表・公表したときに,日本地質学会の著作権表示(及び改変したときはその旨)を表示した場合.但し,発表・公表後速やかに発表・公表の態様に応じた必要な情報(例:論文として発表したときは,タイトル,執筆者,掲載誌など)を日本地質学会に届け出なければならない.
作成者が自ら行う授業,講義,講演,研究発表のため受講者に交付する目的で複製する場合(複製部数を問わない.),プロジェクター等により上映するために複製する場合,及びプロジェクター等により上映する場合.
作成者が自ら開設するホームページ,ブログ等において論文等のファイルをアップロードする場合.但し,アップロード後速やかにアップロードファイルのURLを日本地質学会に届け出なければならない.
2 第1項(4)については,日本地質学会がアップロードの中止を申し入れたときは,作成者はアップロードしたファイルを削除等し,ウェブを通じた開示,利用を中止しなければならない.
3 日本地質学会は,第1項に定める利用であっても,その利用が適切でないと認めたときは,その利用を中止させることができる.
一部利用
第6条作成者以外の者が,日本地質学会の1つの論文等の一部を利用する場合には,予め利用しようとする部分,利用目的,及び利用態様(改変を伴うときは,改変後の内容,形状を含む.以下本条において同様とする.)を明らかにした上で,日本地質学会からの書面による許諾を得なければならない.
2 日本地質学会は,前項の許諾に際し,条件を付することができる.
3 第1項によって許諾を受けた者は,利用に際しては,著作権表示を付さなければならない.
4 日本地質学会は,許諾を得る際に明らかにされた利用目的と利用態様が異なること,あるいは付された利用条件に違反することを発見,認識したときは,許諾を取消し,あるいは違反状態の解消のため必要な措置を執ることができる.
全部利用
第7条作成者以外の者が,日本地質学会の1つの論文等の全部を利用する場合には,予め利用目的,利用態様(改変を伴うときは,改変後の内容,形状を含む)及び利用期間を明らかにした上で日本地質学会からの書面による許諾を得ることを要する.
2 日本地質学会は,前項の許諾に際し,条件を付することができる.
3 第1項によって許諾を受けた者は,利用に際しては,著作権表示を付さなければならない.
4 日本地質学会は,許諾を得る際に明らかにされた利用目的と利用態様が異なること,あるいは付された利用条件に違反することを発見,認識したときは,許諾を取消し,あるいは違反状態の解消のため必要な措置を執ることができる.
著作者への通知
第8条日本地質学会は,作成者以外の者に対する著作物の利用を承認した場合,作成者(複数の場合は代表者)にその旨を通知する.ただし,やむを得ない場合は,ニュース誌等で告知することによって替えることができる.
違反
第9条利用条件に違反する状態が生じた場合には,日本地質学会は利用,貸与を停止する.
手続
第10条手続及び細目については別途定める.
附則(2005年12月17日)
第1条(実施期日)
この規則の実施時期は,2005年12月19日からとする.
**************************************************************************************
【申請書類】利用内容に応じて下記の書式を学会事務局にご提出下さい.(※申請書面PDFをメール添付にてお送りいただくことでも受け付けています)
◆ 一部利用の場合> 転載許可申請用紙
(注意:改版・加工して使用する場合は,そのコピーも添付してご提出ください)
◆ 全部利用の場合> 著作物利用条件同意書
転載に関する問い合わせ・書式送付先:
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル
一般社団法人日本地質学会
e-mail; journal@geosociety.jp ,電話 03-5823-1150
日本地質学会プライバシーポリシー
日本地質学会プライバシーポリシー
制定:2007年4月7日
本学会は、個人情報の収集・利用・管理についての重要性を深く認識するとともに、以下の通り適切に取り扱うよう努めます。
1.個人情報の収集
本学会は、本学会の事業目的に沿ったサービスの提供のため、個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を認識できるものをいいます。)を必要な範囲で収集します。個人情報を収集する際は、その目的を明示するとともに、提供者の意思に基づく情報の提供(登録)によることを原則とします。
2.個人情報の利用
本学会は、収集した個人情報を以下の目的の範囲で利用します。
本人確認、本学会の行う事業に関するサービス・情報の提供、会費・利用料金の請求、およびサービス提供条件の変更・停止・中止・契約解除の通知。
会員等の相互連絡、選挙・会議等の通知など本学会の運営・事業に関わる情報の提供。
事業の実施(関連学協会との連絡および協力などそのための第三者提供を含みます)。
上記の他、本学会の実施するサービスに関する情報提供(会費・利用料金の請求、および利用サービス提供条件の変更・停止・中止・契約解除の通知などを含みます)やサービス向上のための調査。
上記の各目的に付随する目的
ただし、次のいずれかの場合には利用目的以外に利用または提供することがあります。
法令に基づくとき。
提供者の同意があるとき。
事業の実施に必要な範囲内において個人データの取り扱いの全部または一部を委託する場合。
その他、本学会総会または理事会で正当な理由があると認められたとき。
3.個人情報の管理
本学会は、収集した個人情報が外部へ漏洩したり、破壊や改ざんを受けたり、紛失することのないよう適切な管理に努めます。ただし、提供者自身により開示されたり、既に公開されたりしている個人情報については、本学会の管理の対象外とします。
4.個人情報の開示および訂正等
本学会は、個人情報の提供者から自己に関する個人情報の開示の請求があったときは、原則として遅滞なく開示します。また、自己に関する個人情報の訂正等の申し出があったときは、原則として遅滞なく訂正等を行います。
付記
1.プライバシーポリシーの変更について
個人情報の保護に関する法律の変更に準じるため、または、その他の理由により、予告無くプライバシーポリシーに変更を加えることがあります。
2.個人情報の取り扱いに関する問い合わせ先
本学会における個人情報保護に関してご質問などがある場合は、下記までご連絡下さい。
日本地質学会 運営財政部会
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F
電話:03-5823-1150
FAX:03-5823-1156
学会組織・委員会(組織図)
学会組織・委員会
※各項目をクリックするとメンバーや活動詳細をご覧いただけます
役員(理事)
代議員
支部
専門部会
各種委員会
研究委員会
一般社団法人日本地質学会 組織図(2024年6月現在)[PDF版はこちら]
委員会一覧(2024.6.8-2年間)
日本地質学会 委員会委員一覧
総務委員会/広報委員会/行事委員会/専門部会連絡委員会
国際交流委員会/地質標準化委員会/地質学雑誌編集委員会
Island Arc編集委員会/企画出版委員会/地学教育委員会
生涯教育委員会/地質技術者教育委員会/利益相反マネージメント委員会
支部長連絡会議/地質災害委員会/名誉会員推薦委員会/各賞選考委員会
ジェンダー・ダイバーシティ委員会/ジオパーク支援委員会/法務委員会
地学オリンピック支援委員会/連携事業委員会/若手活動運営委員会
南極地質研究委員会/法地質学研究委員会
※任期は原則として2024年6月8日から2年間
※敬称略、委員は順不同
総会決議による規則に規定される委員会
選挙管理委員会 2024年9月設置
執行理事会の下に置かれる事業部会の業務委員会
運営財政部会の委員会
総務委員会 担当執行理事:加藤 <委員会規則>
委員長:加藤猛士(川崎地質)
副委員長:細矢卓志(中央開発)
委員:天野敦子(産業技術総合研究所)
委員:佐々木和彦(佐々木技術士事務所)
委員:福地里菜(鳴門教育大学)
広報部会の委員会
広報委員会 担当執行理事:坂口
委員⻑:坂口有人(山口大学)
委員:内尾優子(東京国立博物館)
委員:大坪 誠(産業技術総合研究所)
委員:北村有迅(⿅児島⼤学)
委員:清川昌⼀(九州⼤学)
委員:小宮 剛(東京大学)
委員:星 博幸(愛知教育⼤学)
委員:松⽥達⽣(気象⼯学研究所)
学術研究部会の委員会
行事委員会 担当執行理事:高嶋・山口
委員長:高嶋礼詩(東北大学)
副委員長:山口飛鳥(東京大学)
委員:上松佐知子(筑波大学)(古生物部会)
委員:足立奈津子(大阪公立大学)(堆積地質部会)
委員:石毛康介(電力中央研究所)(火山部会)
委員:宇野正起(東北大学)(岩石部会)
委員:黒田潤一郎(東京大学)(環境変動史部会)
委員:佐藤大介(産業技術総合研究所)(地域地質部会)
委員:竹下欣宏(信州大学)(第四紀地質部会)
委員:辻野 匠(産業技術総合研究所)(層序部会)
委員:常盤哲也(信州大学)(構造地質部会)
委員:中村謙太郎(東京大学)(鉱物資源部会)
委員:新里忠史(日本原子力研究開発機構)(環境地質部会)
委員:野々垣 進(産業技術総合研究所)(情報地質部会)
委員:松崎賢史(東京大学)(海洋地質部会)
委員:矢島道子(東京都立大学)(地学教育委員会)
委員:山口悠哉(石油資源開発)(石油石炭関係)
委員:加瀬善洋(北海道立総合研究機構)(応用地質部会)
専門部会連絡委員会 担当執行理事:尾上
委員長:尾上哲治(九州大学)(環境変動史部会)
委員:生形貴男(京都大学)(古生物部会)
委員:及川輝樹(産業技術総合研究所)(火山部会)
委員:岡田 誠 (茨城大学)(層序部会)
委員:小原泰彦(海上保安庁)(海洋地質部会)
委員:中野伸彦(九州大学)(岩石部会)
委員:斎藤 眞(産業技術総合研究所)(地域地質部会)
委員:田村 亨(産業技術総合研究所)(堆積地質部会)
委員:田村嘉之(千葉県環境財団)(環境地質部会)
委員:中村謙太郎(東京大学)(鉱物資源部会)
委員:西山賢一(徳島大学)(応用地質部会)
委員:能美洋介(岡山理科大学)(情報地質部会)
委員:三田村宗樹(大阪公立大学)(第四紀地質部会)
委員:道林克禎(名古屋大学)(構造地質部会)
国際交流委員会 担当執行理事:辻森
委員長:辻森 樹(東北大学)
委員:磯粼行雄(東京大学)
委員:針金由美子(産業技術総合研究所)
委員:益田晴恵(大阪公立大学)
地質標準化委員会 担当執行理事:内野 <委員会規則>
委員⻑:内野隆之(産業技術総合研究所)
委員:岡⽥ 誠(茨城⼤学)(層序部会)
委員:尾上哲治(九州大学)
委員:川畑⼤作(産業技術総合研究所)
委員:辻森 樹(東北⼤学)
編集出版部会の委員会
地質学雑誌編集委員会 担当執行理事:小宮 <委員会規則>
委員長:小宮 剛(東京大学)
副委員長:大坪 誠(産業技術総合研究所)
副委員長:栗谷 豪(北海道大学)
委員:池田 剛(九州大学)
委員:乾 睦子(国士舘大)(25.4.19〜)
委員:宇野康司(兵庫県立大学)
委員:宇野正起(東北大学)
委員:江川浩輔(九州大学)
委員:及川輝樹(産業技術総合研究所)
委員:大藤 茂(富山大学)
委員:奥野 充(大阪公立大学)
委員:尾上哲治(九州大学)
委員:折橋裕二(弘前大学)
委員:亀井淳志(島根大学)
委員:楠橋 直(愛媛大学)
委員:佐藤智之(産業技術総合研究所)
委員:佐野晋一(富山大学)
委員:志村俊昭(山口大学)
委員:新正裕尚(東京経済大学)
委員:末岡 茂(原子力研究開発機構)
委員:高橋 唯(慶應義塾幼稚舎)
委員:道家涼介(弘前大学)
委員:藤内智士(高知大学)
委員:常盤哲也(信州大学)
委員:西山賢一(徳島大学)
委員:野々垣進(産業技術総合研究所)
委員:延原尊美(静岡大学)
委員:松本 弾(産業技術総合研究所)
委員:三好雅也(福岡大学)
委員:本山 功(山形大学)
委員:山口飛鳥(東京大学)
委員:山崎 誠(秋田大学)
委員:吉田孝紀(信州大学)
Island Arc編集委員会 担当執行理事:辻森
委員長:長谷川 卓(金沢大学)
委員長:市山祐司(千葉大学)
委員:長谷川 卓(金沢大学)
委員:池原 実(高知大学)
委員:入月俊明(島根大学)
委員:岡崎裕典(福岡大学)(非会員)
委員:沖野郷子(東京大学)(非会員)
委員:奥平敬元(大阪市立大学)
委員:奥村 聡(東北大学)(非会員)
委員:粟谷 豪(北海道大学)
委員:後藤和久(東京大学)
委員:小宮 剛(東京大学)
委員:高橋 聡(名古屋大学)
委員:田村 亨(産総研)
委員:外田智千(国立極地研究所)
委員:羽生 毅(海洋研究開発機構)(非会員)
(注)在外委員を含めた全編集委員(Associate Editors)は雑誌サイトをご参照ください
企画出版委員会 担当執行理事:小宮 <委員会規則>
委員長:小宮 剛(東京大学)
委員:内尾優⼦(東京国立博物館)
委員:内藤一樹(産業技術総合研究所)
委員:長井雅史(防災科学技術研究所)
委員:三田村宗樹(大阪公立大学)
社会貢献部会の委員会
地学教育委員会 担当執行理事:岩井
委員長:岩井雅夫(高知大学)
委員:浅野俊雄(元東京薬科大学)
委員:阿部国広(島根半島・宍道湖中海(国引き)ジオパーク推進協議会)
委員:大信田彦磨(愛知県立海翔高等学校)
委員:坂口有人(山口大学)
委員:高嶋礼詩(東北大学)
委員:廣木義久(大阪教育大学)
委員:藤原 靖(神奈川県立生田高等学校)
委員:星 博幸(愛知教育大学)
委員:松永 豪(大阪府立泉北高等学校)
委員:矢島道子(東京都立大学)
委員:渡来めぐみ(私立茗渓学園中学校・高等学校)
生涯教育委員会 担当執行理事:矢部 <委員会規則>
委員長:笠間友博(箱根ジオパーク推進室)
委員:石橋 隆(地球科学社会教育機構)
委員:太田泰弘(北九州市立いのちのたび博物館)
委員:木田梨沙子(名古屋市科学館)
委員:先山 徹(NPO法人地球年代学ネットワーク地球史研究所)
委員:里口保文(琵琶湖博物館)
委員:白井孝明(萩ジオパーク構想推進協議会事務局)
委員:田口公則(神奈川県立生命の星・地球博物館)
委員:竹之内耕(フォッサマグナミュージアム)
委員:成田敦史(北海道博物館)
委員:細矢卓志(中央開発)
委員:増渕佳子(富山市科学博物館)
委員:矢部 淳(国立科学博物館)
地質技術者教育委員会 担当執行理事:加藤 <委員会規則>
委員⻑:竹内真司(日本⼤学)
副委員⻑:加藤猛⼠(川崎地質)
委員:亀尾浩司(千葉⼤学)
委員:⻲⾼正男(大日本ダイヤコンサルタント)
委員:小荒井 衛(茨城⼤学)
委員:坂口有⼈(山口⼤学)
委員:佐々⽊和彦(佐々⽊技術⼠事務所)
委員:立石 良(富山大学)
委員:林 広樹(島根⼤学)
委員:藤井正博(応用地質)
委員:藤代祥子(日特建設)
委員:細⽮卓志(中央開発)
その他執行理事会の下に設置される委員会及び組織
利益相反マネージメント委員会 担当執行理事:亀高
委員長:亀高正男(大日本ダイヤコンサルタント)
委員:加藤猛士(川崎地質)
委員:小松原純子(産業技術総合研究所)
委員:沢田 健(北海道大学)
委員:星 博幸(愛知教育大学)
委員:松田博貴(熊本大学)
理事会規則第14条の1項に規定され、理事会の下に設置される委員会
支部長連絡会議 担当執行理事:杉田
委員長:杉田律子(科学警察研究所)
委員:沢田 健(北海道大学)(北海道支部長)
委員:本山 功(山形大学)(東北支部長)
委員:久田健一郎(NPO法人地学オリンピック日本委員会)(関東支部長)
委員:道林克禎(名古屋大学)(中部支部長)
委員:和田穣隆(奈良教育大学)(近畿支部長)
委員:寺林 優(香川大学)(四国支部長)
委員:山本啓司(鹿児島大学)(西日本支部長)
地質災害委員会 担当執行理事:松田
委員長:松田達生(工学気象研究所)
副委員長:中澤 努(産業技術総合研究所)
委員:沢田 健(北海道大学)(北海道支部長)
委員:本山 功(山形大学)(東北支部長)
委員:久田健一郎(NPO法人地学オリンピック日本委員会)(関東支部長)
委員:道林克禎(名古屋大学)(中部支部長)
委員:和田穣隆(奈良教育大学)(近畿支部長)
委員:寺林 優(香川大学)(四国支部長)
委員:山本啓司(鹿児島大学)(西日本支部長)
委員:安藤 伸(応用地質)(応用地質部会)
委員:内野隆之(産業技術総合研究所)(地域地質部会)
委員:川畑大作(産業技術総合研究所)((連合)環境災害対応委員会委員)
委員:小荒井 衛(茨城大学)(環境地質部会)・((連合)環境災害対応委員会委員)
委員:千葉達朗(アジア航測)(火山部会)
委員:長橋良隆(福島大学)(第四紀地質部会)
名誉会員推薦委員会 担当執行理事:星
※2024.12月設置予定
各賞選考委員会 担当執行理事:亀高
※2024年第2回(2024.8.31)理事会で選出予定
ジェンダー・ダイバーシティ委員会 担当執行理事:山口
委員:天野敦子(産業技術総合研究所)
委員:大友幸子(山形大学)
委員:川口健太(九州大学)
委員:佐々木和彦(佐々木技術士事務所)
委員:沢田 輝(富山大学)
委員:下岡和也(関西学院大学)
委員:浜橋真理(山口大学)
委員:福地里菜(鳴門教育大学)
委員:藤井正博(応用地質)
委員:堀 利栄(愛媛大学)
委員:武藤 俊(産業技術総合研究所)
委員:山口飛鳥(東京大学)
ジオパーク支援委員会 担当執行理事:矢部
委員長:天野一男(東京大学)
副委員長:松原典孝(兵庫県立大学)
委員:岩井雅夫(高知大学)
委員:小河原孝彦(フォッサマグナミュージアム)
委員:小原北士(mine秋吉台ジオパーク)
委員:折橋裕二(弘前大学)
委員:郡山鈴夏(フォッサマグナミュージアム)
委員:柴田伊廣(文化庁)
委員:白井孝明(萩ジオパーク)
委員:関谷友彦(下仁田ジオパーク専門員/下仁田町自然史館)
委員:高木秀雄(早稲田大学)
委員:竹之内 耕(フォッサマグナミュージアム)
委員:佃 栄吉(産業技術総合研究所)
委員:利光誠一(産業技術総合研究所)
委員:日比野剛(白山手取川ジオパーク推進協議会)
委員:廣瀬 亘(北海道立総合研究機構)
委員:松田博貴(熊本大学)
委員:矢島道子(東京都立大学)
委員:矢部 淳(国立科学博物館)
委員:山崎由貴子(日本ジオパークネットワーク)
委員:山下浩之(神奈川県立生命の星・地球博物館)
委員:渡辺真人(京都大学)
理事会規則第14条の2項に規定され、理事会の下に設置される委員会
法務委員会 担当執行理事:亀高
委員長:松田博貴(熊本⼤学)
委員:岩森 光(東京⼤学)
委員:川村紀子(海上保安庁)
委員:斎藤 眞(産業技術総合研究所)
委員:佐々木和彦(佐々木技術士事務所)
顧問弁護士:郄木宏行(郄木総合法律事務所)
地学オリンピック支援委員会 担当執行理事:坂口
委員長:田中義洋(東京都市大学付属中学校・高等学校)
副委員長:川村教一(兵庫県立大学)
委員:浅野裕史(千葉県立佐倉高等学校)
委員:川勝和哉(兵庫県立姫路東高等学校)
委員:小泉治彦(東京理科大学)
委員:芝川明義(元大阪府立高校教員)
委員:久田健一郎(NPO法人地学オリンピック日本委員会)
委員:渡来めぐみ(茗溪学園中学校高等学校)
委員:冨永紘平(土佐清水ジオパーク推進協議会)
連携事業委員会
※2024.6.8解散
若⼿活動運営委員会 担当執行理事:星
委員長:神谷奈々(京都大学)
副委員長:桑野太輔(京都大学)
委員:菊川照英(千葉県立中央博物館)
委員:佐久間杏樹(東京大学)
委員:佐々木聡史(群馬大学)
委員:柴田翔平(茨城大学)
委員:下岡和也(関西学院大学)
委員:鈴木克明(産業技術総合研究所)
委員:郄橋瑞季(島根大学)
委員:岳 孝太郎(川崎地質)
委員:谷元瞭太(茨城大学)
研究委員会
南極地質研究委員会
委員長:大和田正明(山口⼤学)
委員:足立達朗(九州⼤学)
委員:池田 剛(九州⼤学)
委員:石川正弘(横浜国立⼤学)
委員:加々島慎一(山形⼤学)
委員:亀井淳志(島根⼤学)
委員:河上哲生(京都⼤学)
委員:北野一平(北海道⼤学)
委員:M. Satish-Kumar(新潟⼤学)
委員:志村俊昭(山口⼤学)
委員:土屋範芳(東北⼤学)
委員:角替敏昭(筑波⼤学)
委員:豊島剛志(新潟⼤学)
委員:中野伸彦(九州⼤学)
委員:馬場壮太郎(琉球⼤学)
委員:外田智千(国立極地研究所)
委員:宮本知治(九州⼤学)
法地質学研究委員会
委員長:川村紀子(海上保安庁 海上保安大学校)
委員:板宮裕実(科学警察研究所)
委員:北村有迅(鹿児島大学)
委員:組坂健人(科学警察研究所)
委員:杉田律子(科学警察研究所)
委員:平田岳史(東京大学)
公募・助成情報
公募・助成情報
※( )内の日付は募集締切です
公募情報(10/7更新)
原子力規制委員会行政職員(技術系・事務系)公募(10/31)NEW
原子力規制委員会行政職員(研究職)公募(10/31)NEW
東北大学大学院理学研究科地学専攻助教公募(12/19)NEW
JAMSTEC海域地震火山部門地震津波予測研究開発センター観測システム開発研究グループPD研究員公募(11/18)NEW
京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻地質学鉱物学分野教授公募 (12/1)NEW
2026年度東京大学地震研究所客員教員公募(10/31)
2026年度産総研イノベーションスクール人材育成コース公募(11/25)
各賞・研究助成・共同利用等(10/7更新)
2026年度東京大学地震研究所共同利用(10/31) NEW
第46回(2025年度)猿橋賞 (11/30)NEW
第67回藤原賞受賞候補者推薦(12/15)(学会締切12/1) NEW
2026年度山田科学振興財団海外研究援助(10/31)
2026年度笹川科学研究助成募集(9/16-10/15)
「環境研究総合推進費」令和8年度新規課題公募(9/8-10/10)
公益財団法人中谷財団次世代理系人材育成プログラム助成募集(10/1-11/20)
公益財団法人中谷財団科学教育振興助成(10/1−11/30)
第66回東レ科学技術賞および東レ科学技術研究助成の候補者推薦)(10/10)(学会締切9/12)
ジオパーク関連情報(8/19更新)
旭川市地域おこし協力隊(ジオパーク専門員)募集 (随時)
令和7年度むつ市ジオパーク推進員募集(随時募集)
おおいた豊後大野ジオパークにおける学生巡検等の宿泊費補助の拡充
アポイ岳ジオパーク研究者支援
PDFをご覧になるには、「Adobe Acrobat Reader」をダウンロードしてご使用ください。
2021年10月_日本地質学会の新しい表彰体系
2022年度日本地質学会の新しい表彰体系:変更の要点について
(2021.10.4掲載)
参考:各賞選考規則/各賞選考委員会規則はこちらから
会長 磯粼行雄
日本地質学会では,これまでに会員・非会員の表彰を永年行ってきました.しかし,21 世紀に入ってはや20 年が経過し,現代的な学会動向の観点から眺めた際に,これまでの伝統的な体系だけでは必ずしも十分に表彰しきれていなかった点が見えてきました.そこで,現在の学会執行部のなかで議論し,またその原案について理事会・総会でご紹介・ご承認をいただいて,2020-2021 年度に賞体系を大幅に変更しました.その中では,従来よりも賞の数を増やし,多様な年齢層の会員に対して満遍なく表彰の対象となっていただけるように配慮し,またそのための学会規則の変更を行いました.
しかし,変更箇所が多いにも関わらず,硬い言葉だけで書かれた規則改変だけでは,新たな賞体系の内容,とくに各賞の間の相違について,会員の皆様に十分理解していただけていない可能性があることを危惧します.そこで,以下に,改めて複数の賞の内容整理と相互比較を簡単に,ご説明いたします.
1)学会賞と学会功績賞(新設):本学会の最高位の表彰として「地質学会賞」が位置付けされています.この選考対象は,あくまで地質学における学術的業績の高さが評価される会員とすることには,従来から何も変更はありません.一方,このたび新設しました「学会功績賞」の対象は,以下の点で「学会賞」のそれとは区別されます.「学会賞」は,既に公表された学術論文の質的高さ(基本的に国際学術誌に発表された論文が,どの程度,世界の学会に積極的な影響を及ぼしたのか)を基に本学会を代表する学術業績をあげた会員を選考します.これに対し,「学会功績賞」は,学術論文のみならず専門書・教科書(英文あるいは和文)の執筆や学会運営等への深い貢献を評価対象の中心におくものです.
2)ナウマン賞(新設):これまで,賞の対象となる会員の年齢層が,大きく二局化していました.すなわち,学会賞がベテラン会員(基本的に50 歳以上)を対象とするのに対して,そのほかの賞はいずれも主に20-30 歳代を対象としてきました.すなわち,中堅の中でもやや年齢の高い会員に対する表彰区分が欠落していました.そこで,主に40 歳代の会員を対象にした表彰を行うために,新たに著名なEdmund Naumann 先生の名前を冠した「ナウマン賞」を創設しました.
3)「小藤文次郎賞」は,設立当初は速報性を持った短報のみを対象にした「小藤賞」という名前で設立されました.しかし,その後,重要な発見または独創的な発想を含む論文,すなわち学界に対するインパクトの高い論文に対して授ける賞として「小藤文次郎賞」が再定義されて,今日に至っています.その審査過程において,これまでは直近2 年間に発表された論文だけを対象としてきましたが,地質学分野は他分野(生物学や化学など)とは異なり,論文評価のためには2 年は短すぎ,評価が定まるまでには少なくとも5 年は必要と判断されます.そこで,今回の改正では,「小藤文次郎賞」審査期間を応募直前の5 年間に変更しました.
4)「地質学雑誌特別賞」(新設)は,これまで地質学雑誌に掲載された論説や総説以外の記事を表彰するために新たに用意されました.地質学雑誌には,原著論文および総説の他に,レター,ノート,報告,講座などの比較的短い著作が掲載されます.これらの中には,フルペーパーではないものの,重要な地質記載や有用性の高い研究手法等を提案したものも含まれます.それらについて,新たな賞を設けて表彰することにしました.
5)これまで,地質学研究を側方からサポートされた会員ならびに非会員の方々を対象に「功労賞」,「地質学会表彰」が選ばれてきました.かつては,大学において働かれた技官の方々,新技術の開発に貢献された会社の方々,また最近では中等教育の教科書出版や,テレビの教養番組作成チームなどが受賞対象となりました.このたび,新たに会員対象の「功績賞」を新設したことに伴い,主に非会員を対象とした賞として「地質学会表彰」と一括することにしました.ついては従来の「功労賞」は廃します.
6)若手の育成を目指して,学術大会の際に中高校生達のポスター展示をジュニアセッションとして開催し,優秀な発表の表彰をこれまで非公式に進めてきました.この度それを学会の正式な賞として「ジュニアセッション優秀賞」「ジュニアセッション奨励賞」を用意しました.
なお,今回の規則改正では,既存の「小澤儀明賞」と「柵山雅則賞」の対象年齢を,従来の37 歳以下から,博士号取得後5 年以内に変更し,さらに「研究奨励賞」の対象年齢も,従来の35 歳未満から,32 歳未満に変更しました.「小澤賞」「柵山賞」の年齢制限を生物学的年齢から学位取得後5年とした理由は,大学入学時の年齢のばらつきに起因する不平等をなくすことにあり,欧米でもしばしば用いられている基準です.ただし今回の対象年齢の変更により特定の年齢の会員に不利益が生じないよう,移行期間を設けることにしました.したがって上記の対象年齢の変更は,1 年遅らせて来年度募集の表彰から適用することにします.
以上の賞体系の変更の意図は,あくまで多様な会員層に対して満遍なく表彰対象となっていただくためです.この度の変更が,多数の会員にとって,さらに地質学研究を推進するブースターになることを大いに期待しております.こぞってご応募いただければ幸いです.
安全のしおり(巡検案内書より)
安全のしおり Safety Note
第121年学術大会(2014年鹿児島大会)巡検案内書より
(注:鹿児島県やその近郊である南九州地域に限った情報が含まれています)
1.諸注意 2.傷害保険 3.緊急時連絡体制 巡検案内書を頼りに野外調査へ出かける方へ
1.諸注意
野外調査に関する一般的注意事項については省略しますが,場所が変わると普段の調査とは勝手が違い,思わぬトラブルになることがあります.出発前に案内者から受けた諸注意や各種の指示を遵守してください.本案内書で取り上げた地域で特に注意を要する事項に重点を置いて,以下,安全に関する注意点を書き記すことにします.なお巡検参加に際しては,万が一に備え,保険証のコピーと個人カード(緊急連絡先,血液型,抗体の有無,持病の有無などを記載)を各自持参するようお願いします.
⑴ 9月の気候と健康管理
鹿児島市における9 月の平均気温は26.1°C で,平均最低気温は22.8°C,平均最高気温は30.1°C です(最近30 年間の統計).今回の巡検は,離島を含む南九州地方の広い範囲に分散しているため,事前に参加される各コース周辺の気温を確かめておいて下さい.南九州の9 月は,まだ日差しが強く,晴れると気温以上に暑く感じることがあります.帽子の着用や日焼け止めの使用,水分の適宜補充など,熱射病にならないように,ご自身で体調の管理をお願いします.一方,南九州とはいえ,山間部や海岸部では天候によって気温がかなり低くなることがあります.雨具や防寒具もお忘れにならないようにして下さい.
⑵ 自然災害
9 月は秋雨前線の停滞や台風の影響により雨が多くなることがあります.また集中豪雨や長雨により地盤がゆるんでいる場合,土砂災害の危険性が高まりますので,台風や長雨のあとは当日が晴れているからといって油断のないようご注意下さい.特に山間部では,短時間の雨や上流域の降雨による急な出水にも十分警戒してください.地震の際は露頭から速やかに離れ,案内者の指示に従って避難して下さい.海岸および海岸近くの低地にいる場合は,津波に備えて,速やかに高台に避難して下さい.
⑶ 危険な動植物
動物:山ではスズメバチ,山ヒル,毒蛇(マムシ・ヤマカガシ),イノシシなどに,海岸ではトゲ(有毒)のある潮だまりの生物や岩場のフジツボ(鋭利な殻)などに注意して下さい.9 月はスズメバチの巣も大きくなり,警戒心が強くなっています.マムシは夏から秋にかけて活動が活発になり,咬まれる可能性が高くなるので,注意が必要です.水辺の日だまりや,露頭下の小さな草むら,石の陰などでよく見かけます.またダニやツツガムシなどは気づきにくいので,茂みや草むらに入る際にはできるだけ素肌を出さない服装を心がけましょう.鹿児島県を含む南九州は,ツツガムシ病の患者が全国でも多い地域です.鹿児島においては,平成25 年に38人(全国344 人)の患者が発生しており全国1 位となっています.
植物:ウルシやハゼとトゲのある植物にご注意下さい.袖を覆うアームカバー(手甲)や軍手を適宜利用してください.キノコや山菜の素人同定は危険です.
⑷ 海岸での見学
海岸では足場が滑りやすく,波に足下をさらわれ転倒,死亡事故に至る危険性があります.普段使い慣れた靴も,海辺では役に立たないことが多々あります.露頭観察に夢中となり,たとえ潮が満ちるのに気づくのが遅れたとしても,落ち着いて無理のない行動をお願いします.悪天候時の高潮や,万が一地震が発生した場合には津波発生の可能性もありますので,案内者の指示に従い,安全な場所へ速やかに避難してください.海岸で調査する際には避難ルートを意識し,いざという時に慌てないよう備えてください.
⑸ 渓流・河床での見学
水量の多い渓流・河川があり,滑りやすい箇所も多いと思われます.また,険しい狭谷をなす部分も少なくありません.河床・河岸露頭に近づく場合には十分注意してください.グリップの効く靴など,各自で準備をお願いします.着替えなども用意しておくと安心です.装備が十分でない場合は,危険な箇所での観察をあきらめ,安全な場所で待っている方がいい場合もあるでしょう.不明点などは案内者に直接確認し,危険が予想される場合には個人で判断せず案内者の指示に従って行動してください.
⑹ 自然保護
巡検参加に際しては,自然保護関連法令(自然環境保全法,自然公園法,鳥獣保護法,種の保存法など)に抵触しないようご注意下さい.詳しくは,最新の環境六法または以下のURL(環境省自然環境局)を参照してください.http://www.env.go.jp/nature/
国立公園・国定公園での破壊行為禁止:自然公園法により,指定地域内における試料採取や改変が制限されています.巡検コースの一部では,標本採取やハンマーの使用に制限がありますので巡検案内者の指示に従ってください.
2.傷害保険
巡検参加者全員に国内旅行傷害総合保険に加入して頂きます.これにより,巡検中の怪我や器物破損に対する保証がなされます.ただし,この保険は一般的で,補償対象外となる例外が多々ありますし,金額的にも十分な保険ではありませんので,配布される資料で契約内容をご確認ください.また交通事故に閲しましては,移動中の怪我も旅行傷害保険でカバーされます.
3.緊急時の連絡体制
巡検中に緊急なトラブルが発生した場合,まず案内リーダーに連絡して下さい.案内リーダーが対応できない緊急事態の場合の連絡先は,下記の地質学会鹿児島大会事務局(*******)です.巡検中のトラブルについては,トラブル内容や発生日時などの必要情報を,巡検案内者(案内者が対応できない場合は代わりの参加者)が責任をもって下記緊急時連絡先まで連絡を入れるようにしてください.
緊急時連絡先:
第**年学術大会実行委員会 事務局長 ****
電話(研究室):****
E-mail:****
第**年学術大会実行委員会 巡検担当 ****
電話(研究室):****
E-mail:****
(注:連絡先情報については,当日に配布する案内書資料を参照して下さい)
以 上
日本地質学会第121年学術大会巡検担当
巡検案内書を頼りに野外調査へ出かける方へ
本案内書は皆様の野外調査の一助になるはずですが,本案内書に記載されている露頭の多くは学術的に貴重であるため,調査や試料採取にあたっては節度のある行動に努めてください.ここでは『野外調査において心がけたいこと』(2008.10.7日本地質学会理事会)から一部抜粋し(一部加筆),注意すべきポイントを記述します.
日本地質学会行事委員会
国立・国定公園,並びに自治体の条例で保護が指定されている地域等で調査する場合は,事前の許可が必要です.まず,調査を行う地域がどのような保護地区を含んでいるか,事前に確認しておきましょう.特別保護区などの範囲は,自治体や環境省等のHPで確認できる場合が多いですし,必要な手続きもオンラインで申請できますので,必ず手続きをしてから現地に入るようにしましょう.特に,試料採取を伴う許可申請の場合は,許可が下りるまでに数か月かかることもあります.
史跡・名勝・天然記念物においては,文化庁や地元自治体などへの必要な手続きなしには露頭をハンマーでたたいて岩石試料を採取するなどの破壊を伴う調査はもちろん,転石の採取もできません.やむを得ず研究上必要な場合は許可申請の手続きを行い,必要最低限の採取に留めることが重要です.許可を得ておくことによって,その成果を公表することも可能になります(その際には謝辞に許可のことを触れておくとよいでしょう).
世界遺産については,世界遺産保護条約によって保護・保全が定められていますので,国の保護計画の不備が認められた場合は登録が抹消されることもあります.高い保全意識を持って慎重に行動する必要があります.
これらの地域の巡検の際にはハンマーを持ち歩かないなど「李下に冠を正さず」といった節度ある態度を心がけましょう.
法的な保護が為されていない貴重な露頭においても,同様に露頭の保護を心がけたいものです.不必要なサンプルの採取,削剥はもちろん慎み,あらかじめ地権者や地元自治体への連絡などを行っておくことにより,トラブルを未然に防げます.コア抜きは坑が大変目立ち,また半永久的に残りますので,場所をよく選ぶよう心がけることが大切です.また,露頭面にペイントやマーカーで記号等を派手に書き込む行為も,その後きれいに消していくようなマナーが必要です.
このほか些細なことのようですが,地元の方々と良好な関係を保つということは,思いのほか重要なことです.貴重な露頭が,将来はジオパークの中の有力なジオサイトになるかもしれません.
特に法人や個人の所有地(いわゆる私有地)では,調査・試料採取にあたっては必ず許可を得るようにしましょう.学会巡検では案内者が事前に所有者の許可を得ています.
地球を愛する者として,社会から地質調査の有用性や公益性が認められ,末永く地質調査を行える環境作りには,上記のような調査に当たっての心がけが必須ですので,地球科学分野の研究者の全員の協力でこれを進めましょう.
学会の顔(執行理事:2022-)
学会の顔:2024年度執行理事
任期:2024.6.8〜2024年総会,*印:部会長
会長:山路 敦(京都大)
今期(2024年〜2026年)本会の代表理事(会長)を務めさせていただきます.私の専門は構造地質学,特に,日本列島の新生代テクトニクスです.これが古典的なテーマであるからこそ,新しい観点を持ち込むことを心掛けてきました.本会には大学院進学を機に入会し,あっという間に40年以上が過ぎました.その間,年会などで様々な方々と知り合い,本会に育てていただいたと思っています.微力ではありますが,会長職を務めてまいりますので,どうかよろしくお願い申し上げます..(....続きを読む)
副会長:杉田律子(科学警察研究所)
前期に続き,副会長を務めさせていただきます杉田です.会員の活動を支え,学会を発展させていくために,引き続き様々な規則類の整備や改正を推し進め,かつ,情報にアクセスしやすい環境を整えていきます.また,さらなるダイバーシティ推進のために,シニア会員の活躍できる場の創出にも力を注ぎたいと考えています.会長の指導の下,会員の皆様のお知恵を拝借し,しっかりと議論を重ねてより良い地質学会を目指します.
副会長:星 博幸(愛知教育大学)
地質学と関連分野の研究を始めた学生に「ぜひ入会したい」と思っていただける学会.様々な分野の現役世代の会員に「この学会が大切,やめられない」と思っていただける学会.そしてシニア層の会員に「この学会が生涯大切,やめられない」と思っていただける学会.そんな地質学会になるように引き続き汗をかきたいと思います.学術面の強化を第一としつつ,ダイバーシティーのさらなる拡大,地質学の教育と普及,広報の抜本的強化などに全力で取り組みます.
常務理事:亀高正男*(大日本ダイヤコンサルタント(株))
今期は常務理事を努めさせていただきます.社会情勢の変化に併せて,地質学会でも地質学雑誌の電子化や,会員システムのクラウド化などを進めてきました.一方で,地質学の本質は変わらないと思っています.野外調査の楽しさや学術探究の喜びをより多くの会員に感じ取ってもらいたい,その助けとなる場を地質学会として会員に提供したい.そのために,会長・副会長のもと,学会の運営が円滑に行われるように尽力していきたいと思います.どうぞよろしくお願いいたします.
副常務理事:内野隆之(産業技術総合研究所)(社会貢献部会兼務)
社会的背景もあり,地質学の基本であるフィールドジオロジーの研究が縮小傾向にあるなか,学会としても当該研究活動を維持できるように尽力していきたいと思っています.特に,日本の今後の地質学を担う若手研究者をこれまで以上にサポートしていければと考えています.どうぞよろしくお願いいたします.
理事・運営財政部会:加藤猛士*(川崎地質㈱)
産官学から様々な立場や役割の方々が集まる学会として,先端的な研究や教育普及,技術開発などの活動を通して発信される地質学に関する情報は,社会の発展及び貢献に不可欠です.運営財政部会の担当として,皆さまの学会活動を維持・発展するための環境を整備することが大切な役割であると認識して,学会運営に尽力してまいります.どうぞよろしくお願いいたします.
理事:運営財政部会:細矢卓志(中央開発㈱)
この度,新たに執行理事会委員になりました中央開発(株)の細矢です.会員にとって魅力ある学会であり続けるために,学会活動の活性化に力を入れたいと思います.また,運営財政部会担当として,微力ながら,学会員の減少を食い止め,学会の健全運営のため少しでもお役にたてるような活動をしていきたいと思います.どうぞよろしくお願いします.
理事:広報部会:坂口有人*(山口大学)(社会貢献部会兼務)
今期広報を担当いたします.学術的な「新知見」は,ものの見方,考え方,に影響を与えつつ広く浸透していきます.新しい情報を広く発信していくのは重要な社会的貢献です.そのために各種広報チャンネルを充実させつつ,幅広い層に地質学の魅力,重要性,最先端と更にその先をアピールしていければと思います.どうぞよろしくお願いいたします.
理事:広報部会:内尾優子(東京国立博物館)
地質学は,身近な暮らしから宇宙まで,基礎から応用的な研究分野まで,深く関連して支えているとても重要な科学分野です.日本地質学会は,明治の時代から地質学の発展を促進し,地質学を専門とする多様な方が所属しています.私は広報担当として,さらに活発な学会となるよう,そして,社会へ,特に次の世代を担う方に対して,「地質学」の魅力や重要性が適切に伝わることを意識しながら,時代に即した広報活動を行っていきたいと考えます.
理事:広報部会:松田達生(工学気象研究所)
今期も引き続き広報部会を担当させて頂きます.広報は学会のプレゼンスを示すのに非常に重要な役割を果たします.多岐に渡るその仕事の中で,私は主にNews誌の内容を充実させること,またgeo-Flashによる学会行事,関連イベント等の迅速な情報発信を担当させて頂きます.近年の活発な活動をみなさんに余すところなく知って頂けるよう尽力させて頂きます.
理事:広報部会:大坪 誠(産業技術総合研究所)(社会貢献部会兼務)
今期から広報部会の執行理事を務めることになりました.この2年間では,特にX(旧Twitter)などのソーシャル・ネットワーキング・サービスを積極的に活用して,学生の皆さんをはじめとする若手の地質学会への参加を積極的に促していくとともに,社会に地質学の魅力を広く伝えて学会活動をより身近に感じていただけるよう努めていきます.地質学会からのジオジオな発信にご期待ください.
理事:学術研究部会:辻森 樹*(東北大学)(編集出版部会兼務)
研究者同士がネットワーキングを築くためのプラットフォームとして,学術研究団体の重要性が再認識されています.学術大会などの活動を通じて,会員個人レベルでの学術交流が進み,その交流と研究成果が積み重なることで,新たな連携や協力が世代や専門分野を越えて生まれます.継続的な発展には若手人材の参加も欠かせません.学術研究部会として,時代の変化をしっかり見据えながら,その役割を果たしていきたいと考えています.
理事:学術研究部会:尾上哲治(九州大学)
昨年度に引き続き,学術研究部会の執行理事を務めさせていただきます.対面での学術大会は再開したものの,コロナ禍により一旦途切れてしまった世代間の研究交流を取り戻すためには,専門部会間の交流,若手・中堅・ベテラン間の交流を意識した取り組みが必要です.地質学会員の間で活発な議論が行えるように,学会運営に尽力していく所存です.
理事:学術研究部会:高嶋礼詩(東北大学)
今期も引き続き行事委員長を務めさせていただくことになりました.コロナ禍もほぼ収束し,昨年の京都大会より巡検,懇親会,ポスターセッションを含め,従来通りの学術大会が開催できるようになりました.一方で,コロナ禍で進展したショートコースをはじめとしたリモートでの講演企画等,ウェブベースの情報発信も継続・発展させ,会員の学術活動,普及活動がより便利になるようサポートさせていただきたいと考えています.
理事:学術研究部会:山口飛鳥(東京大学大気海洋研)
引き続き行事担当の執行理事を務めさせていただきます.学会の柱である学術大会が会員の皆様にとってさらに魅力的なものになるよう取り組み,その一環として,昨年から開始した学生優秀発表賞の定着に努めます.ご好評いただいているショートコースも,これまでのアンケート結果を参考に一層の充実を図ります.日本地質学会が今後も持続的発展を遂げられるよう尽力する所存ですので,どうかよろしくお願いいたします.
理事:編集出版部会:小宮 剛*(東京大学)
編集出版部会担当執行理事の小宮です.引き続き地質学雑誌編集長と新たに企画出版委員会委員長を担当します.地質学雑誌の電子化と日本語英訳機能の拡充により,邦文誌が国外の研究者にも読まれる機会が増えてきました.そこで,日本の地質をしっかりとした形で記録として残し,将来にも渡り,遍く国民に成果を還元することに加えて,国外の研究者にも伝えることが求められています.地質学雑誌が学会員・国民の期待に答えられるように微力ながら尽力する所存です.
理事:社会貢献部会:矢部 淳(国立科学博物館)
生涯教育委員会担当3期目となります.長く博物館に勤めてきた経験を活かし,学会と社会とをつなぐ役割を担います.また,地域の博物館やジオパーク拠点施設を活かすような活動も行っていきたいと考えています.どうぞよろしくお願いいたします.
理事:社会貢献部会:岩井雅夫(高知大学)
今期より社会貢献部会の執行理事を務めることとなり,地学教育委員会やジオパーク支援委員会,地震火山地質こどもサマースクールなどを担当することになりました.これまでの経験を活かし,社会基盤となる地質学の次世代若手人材育成や,社会からの理解深化,国際協働活動に繋がるよう微力ながら尽力してゆきたいと思います.ご支援ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします.
各賞-日本地質学会功績賞
日本地質学会功績賞(2022年創設)
影響⼒の⼤きい教科書の執筆,研究動向を決める新しい研究⼿法の開発,教育・普及,あるいは本学会運営などを⻑期にわたって⾏ない,本学会なら びに⽇本の地質学の発展に顕著な功績のあった会員(運営規則第16条1)
※各受賞者または対象研究テーマをクリックすると、推薦理由等をご覧いただけます。
【受賞者】
【対象研究テーマ】
2023
佐藤比呂志(東京大学地震研究所)
反射法地震探査を軸とした日本のサイスモテクトニクス研究の推進
2023
小山内康人(九州大学大学院比較社会文化研究院)
高度変成岩類を用いた造山運動と大陸の成長・進化における研究の推進
2022
高橋正樹(日本大学)
沈み込み帯のマグマ活動研究を通じた地質学の普及と社会的貢献
2022年度 名誉会員
2022年度 名誉会員
板⾕ 徹丸(いたや てつまる)会員
(1946年9⽉4⽇⽣ 75歳、特定非営利活動法人地球年代学ネットワーク 理事長)
板⾕徹丸会員は、1974年に早稲⽥⼤学を卒業後、1976年に⾦沢⼤学⼤学院修⼠課程を修了、1979年に東北⼤学⼤学院博⼠課程を修了して理学博⼠を得た。その後、東北⼤学で研究⽣と⽇本学術振興会奨励研究員を経たのち、1981年に岡⼭理科⼤学蒜⼭研究所(のちの⾃然科学研究所)講師に就任し、1987年助教授、1998年教授を経て、2016年の退職まで岡⼭を拠点に約40年間、研究と教育に従事した。
板⾕会員のこれまでの研究は多岐にわたり、三波川変成岩等においてFe-Ti-O-S系鉱物の組成共⽣関係を明らかにし、不透明鉱物に着⽬した流体相の挙動を論じた。また、温度上昇に伴う⾼圧および接触変成岩中の炭質物の結晶構造・化学組成・反射率を検討し、炭質物の⽯墨化の傾向を明らかにした。
岡⼭理科⼤学では、共同研究者らとともにK-Ar年代測定⽤の希ガス同位体質量分析計を製作するとともに、同機器を⽤いて地質・岩⽯・鉱床の年代学的研究を開始した。その結果、年代測定の精度と頻度を向上させ、国内外の様々な地質事象の解明に貢献した。代表例としては、⻄南⽇本の古⽣代・中⽣代の⾼圧変成帯と弱変成付加体についての年代測定マッピングによって、地質構造単元の境界を明らかにしたことが挙げられ、K-Ar年代測定による⽇本の新しい地体構造論の確⽴に⼤きな役割を果たした。また、分析技術を向上させることにより、第四紀⽕⼭岩のK-Ar年代測定を可能にして、時間分解能を⼤きく向上させた。これらの業績が認められ、1999年には⽇本地質学会賞を、2011年には⽇本鉱物科学会賞をそれぞれ受賞した。
板⾕会員は2014年に特定⾮営利活動法⼈地球年代学ネットワークを⽴ち上げ、岡⼭理科⼤学退職後に同法⼈の理事⻑として岡⼭県⾚磐市と研究教育連携協定を締結して地球史研究所を設⽴した。同法⼈では、地球年代学に携わる国内外の研究者と技術者が協働して先端技術の研究開発を⾏いながら、防災と資源開発等の社会的な課題に貢献できる次世代の⼈材育成を⽬指している。また、地球史研究所では⼈類紀精密年代測定法の開発研究の他、地質試料の所蔵とアーカイブ化などが進められており、板⾕会員はそれぞれの組織において中⼼的な役割を果たしている。
⽇本地質学会においては、1996年から2002年および2004年の約7年間評議員を、1996年から1999年まで各賞選考委員会委員をそれぞれ務め、2000年には各賞検討委員会委員⻑の重責を担っている。
以上のように、板⾕徹丸会員の地質学における学術研究、教育、普及、そして⽇本地質学会の運営への多⼤な貢献は、⽇本地質学会の名誉会員として相応しいものと判断し、ここに推薦する。
平 朝彦(たいら あさひこ)会員
(1946年5⽉30⽇⽣ 76歳、東京⼤学名誉教授/独⽴⾏政法⼈海洋研究開発機構 顧問/東海⼤学海洋研究所 所⻑)
平 朝彦会員は、1970年に東北⼤学理学部を卒業し、1971年にテキサス⼤学ダラス校地球科学科に進学後、1976年に同⼤学よりPh.D.を授与された。1977年に⾼知⼤学⽂理学部助⼿、1978年に同⼤学理学部の助教授、1985年に東京⼤学海洋研究所の教授にそれぞれ就任した。2002年に独⽴⾏政法⼈海洋研究開発機構地球深部探査センターの初代センター⻑に就任し、2007年に東京⼤学名誉教授の称号を授与された。2007年に海洋研究開発機構の理事に就任し、2012年から2019年までの約7年間同機構の理事⻑を務めた。同機構の理事⻑を退任後は、顧問に就任し、2020年から東海⼤学海洋研究所所⻑にも就任した。
平会員は、⾼知⼤学在任中に四万⼗帯が海洋プレート上の枕状溶岩・遠洋性堆積物および海溝充填堆積物の付加により形成された地質帯であることを明らかしに、⽇本列島における付加体研究を先導した。東京⼤学赴任後は、⽩鳳丸などを⽤い、四国沖トラフ底の乱泥流堆積物が主に富⼠川起源であることを明らかにして、南海トラフの海洋地質学的研究を推進させた。
1994年から国際深海掘削計画(ODP)理事会委員を務め、海洋研究開発機構に赴任後は地球深部探査船「ちきゅう」の建造・運⽤に尽⼒するとともに、統合国際深海掘削計画(IODP)の推進など世界の深海掘削研究に⼤きく貢献した。この功績が認められ、2014年に⽶国地球物理学連合では、平会員の名前を冠した「平朝彦国際深海科学掘削研究賞」が創設された。
平会員は国内外での学術活動に関する⼤きな貢献により、1974年にアメリカ地質学会ペンローズ研究奨励賞、2006年に⽇本地質学会賞、2007年に「プレート沈み込み帯における付加作⽤の研究」により⽇本学⼠院賞をそれぞれ受賞した。また、2018年に⽇仏の学術協⼒などの功績によりフランス政府レジオン・ドヌール勲章シュヴァリエを受章した。さらに、1994年にアメリカ地質学会フェロー、1996年にフランス科学アカデミー招待教授、1997年に⽂部省学術審議会委員、2002年に国際リソスフェアプログラム会⻑を歴任した。
⽇本地質学会においては、1986年から1994年および1997年から1999年までの約10年間評議員を、2000年から2002年に副会⻑を、そして2002年から2004年に会⻑をそれぞれ務め、本学会活動に多⼤な貢献をしてきた。
以上のように、平 朝彦会員の地質学における学術研究、教育、普及、そして⽇本地質学会の運営への多⼤な貢献は、⽇本地質学会の名誉会員として相応しいものと判断し、ここに推薦する。
⼋尾 昭(やお あきら)会員
(1944年12⽉14⽇⽣ 77歳、⼤阪市⽴⼤学名誉教授)
⼋尾 昭会員は、1967年に奈良教育⼤学教育学部を卒業後、1969年に⼤阪市⽴⼤学⼤学院理学研究科修⼠課程(地質学専攻)を修了し、1972年に同博⼠課程を単位取得退学後、1973年に同⼤学理学部助⼿に就任した。その後、講師、助教授を経て1993年に教授に昇任したのち、2008年に同⼤学を定年退職した。この間、1983年に⼤阪市⽴⼤学より理学博⼠の学位を取得し、2008年には⼤阪市⽴⼤学の名誉教授を授与された。
⼋尾会員は、主に⻄南⽇本の基盤地質体の野外調査と放散⾍⽣層序学的研究を主軸にして中・古⽣界の層序・構造の解明に尽⼒した。特に1960年代末から1980年代前半にかけて,秩⽗帯や丹波-美濃-⾜尾帯において三畳系-ジュラ系放散⾍⽣層序の⼤綱を打ち⽴て、かつていわゆる古⽣代後期の地向斜堆積物とされた地層の多くが,メランジュやスラストパイル構造などを呈するジュラ紀付加体であることをいち早く解明した。これらの研究成果は、⽇本列島における中・古⽣代の地史を⼤きく書き換えた「放散⾍⾰命」に重要な役割を果たすこととなった。
1980年代後半から2008年までの間は、⽇本だけでなく中国の中・古⽣界を対象にした共同研究などにより、多くの⽣層序学的成果をあげた。2008年以降は複数の⼤学で⾮常勤講師を務め、地学教育関係者や市⺠を対象とする講演を⾏うとともに、国内や中国をはじめとする海外において地質巡検を実施するなど、地質学教育および普及に尽⼒してきた。
⼋尾会員は、1994年から1999年に⽇本学術会議地質学研究連絡委員会委員を、2000年から2002年に同古⽣物学研究連絡委員会委員をそれぞれ務め、地質関連学界の発展に携わった。さらに,2003年から2009年に⽇本地質学会編⽇本地⽅地質誌『近畿地⽅』の編集委員⻑を、1991年から1994年に国際放散⾍研究者会議(INTERRAD)議⻑をそれぞれ務めるなど、国内外における地質学の発展および普及に尽⼒した。また、2011年からは奈良県⾃然環境保全審議会委員・温泉部会⻑に就任して、地⽅⾏政に貢献している。
⽇本地質学会においては、1973年から1989年に関⻄⽀部幹事を、1996年から1998年に同⽀部⻑を、2006年から2008年に近畿⽀部⻑をそれぞれ務めた。また、1987年から1996年に地質学雑誌編集委員会委員を、1991年から1998年の約7年間に評議員をそれぞれ務め、学会運営に⼤きく貢献した。
以上のように、⼋尾 昭会員の地質学における学術研究、教育、普及、そして⽇本地質学会の運営への多⼤な貢献は、⽇本地質学会の名誉会員として相応しいものと判断し、ここに推薦する。
Geo暦(2012)
2012年Geo暦(行事カレンダー)
2008年版 2009年版 2010年版 2011年版 …… 2013年版
2012年版 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
○印は学会主催行事.(共)学会共催・(後)後援・(協)協賛
1月January
地質学で読み解く巨大地震と将来の予測ーどこまでわかったかー
1月12日(木)
場所:秋葉原ダイビル コンベンションホール
定員:300名 参加無料
http://www.gsj.jp/Event/120112sympo/index.html
第140回深田研談話会
関東大震災を知る—歴史がつむぐ地震防災—
1月20日(金)15:00〜17:00
場所:深田地質研究所 研修ホール
定員:80名 先着順 参加費無料(受付開始2012年1月5日)
http://www.gsj.jp/Event/120112sympo/index.html
第57回日本水環境問題の最新動向
[微量科学物質による水環境問題の最新動向」
1月26日(木)
場所:自動車会館大会議室(千代田区九段南4-8-13)
http://www.jswe.or.jp/
地質調査総合センター第19回シンポジウム
「社会ニーズに応える地質地盤情報—都市平野部の地質地盤情報をめぐる最新の動向—
1月31日(火)13:00〜17:20
場所:日本大学文理学部百周年記念館
問い合わせ先:産業技術総合研究所地質分野研究企画室
gsjsympo19@m.aist.go.jp
2月February
第4回ジオ多様性フォーラム
(ジオ多様性の普及に向けて,ワインからみたジオ多様性 他)
2月10日(金)〜11日(土)
場所:京都大学博物館を予定
問い合わせ先:矢島道子 pxi02070@nifty.com
http://www.geosociety.jp/outline/content0096.html
○西日本支部平成23年度総会・第162回例会
2月11日(土)9:30〜17:30
場所:鹿児島大学郡元キャンパス
講演申込〆切:2月6日(月)17時
問い合わせ先:西日本支部庶務:宮本知治 miyamoto@geo.kyushu-u.ac.jp
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
東日本大震災を教訓とした巨大災害軽減と持続的社会実現への道
2月11日(土)13:00〜17:30
場所:日本学術会議講堂(港区六本木7-22-34)
参加申込:https://form.cao.go.jp/scj/opinion-0003.htmlまたはFAX:03-3403-1260
問い合わせ:日本学術会議事務局企画課学術 フォーラム担当 TEL:03-3403-6295
平成23年度海洋情報部研究成果発表会
2月14日(火)13:30〜17:30
場所:海上保安庁海洋情報部10階国際会議室(江東区青海2-5-18)
問い合わせ:海上保安庁海洋情報部技術・国際課 TEL:03-5500-7122
京都大学シンポジウムシリーズ「大震災後を考える」シリーズXIV
第13回情報学シンポジウム 災害と情報学
2月17日(金)13:00〜17:10
場所:京都大学百周年時計台記念館 百周年記念ホール
http://www.i.kyoto-u.ac.jp/Symposium/2012/
研究船による成果発表会「ブルーアース2012」
2月22日(水)10:00〜17:30
2月23日(木)10:00〜17:10
場所:東京海洋大学 品川キャンパス 白鷹館、楽水会館(港区港南4-5-7)
http://www.jamstec.go.jp/maritec/j/blueearth/2012/index.html
(後)第1回アジア太平洋大規模地震・火山噴火リスク対策ワークショップ
2月22日(水)〜25日(土)
場所:産業技術総合研究所つくば中央共用講堂
ポスター申込期限:2011年11月30日
http://www.gsj.jp/Event/AsiaPacific/
国際シンポジウムMISASA IV
「太陽系物質科学 〜太陽系科学ミッションと総合的物質科学研究が拓く未来像〜」
2月24日(金)〜26日(日)
場所:倉吉未来中心(鳥取県倉吉市駄経寺町212-5)
参加登録開始:2012年1月初旬
http://sympo.misasa.okayama-u.ac.jp/misasa_iv/
3月March
Project A meeting in Taiwan
"Oceanic environmental change though earth history: From Archean to
Modern ocean"
「地球史を通した海洋変遷:太古代から現在まで」
3月5日(月)〜9日(金)
場所:台湾海洋大学
http://www.archean.jp
有人月探査を見据えた 科学・利用ミッション ワークショップ
3月8日(木)9:50〜
会場:宇宙航空研究開発機構(JAXA) 宇宙科学研究所 A棟2階 大会議場
参加登録:当日受付(参加費無料)
問い合わせ先:佐藤直樹
宇宙航空研究開発機構 有人宇宙環境利用ミッション本部 システムズエンジニアリング室
TEL +81-50-3362-2882 FAX +81-29-868-3950
第7回「海洋と地球の学校」
3月13日(火)〜17日(土)
場所:海洋研究開発機構 横須賀本部(神奈川県横須賀市)、横浜研究所(神奈川県横浜市金沢区)、三浦半島周辺地域(野外巡検)
※宿泊は横須賀本部及び三浦市内(15日のみ)を予定
対 象:大学生及び大学院生(短大、高等学校専攻科を含む、応募者数により一般社会人の参加も可能)
http://www.jamstec.go.jp/j/pr/school/007/index.html
平成23年度 独)海洋研究開発機構研究報告会「JAMSTEC2012」
3月14日(水)13:00〜17:30
場所:東京国際フォーラム ホールB7(千代田区丸の内3-5-1 Bブロック7F)
http://www.jamstec.go.jp/
4月April
東北大学・海洋研究開発機構合同シンポジウム
東日本大震災から1年 何を学び、どう活かすか
4月7日(土)10:00〜17:30
会場:仙台市情報・産業プラザ多目的ホール(仙台市青葉区中央1-3-1AER5階)
問い合わせ先:海洋研究開発機構 事業推進部推進課
http://jamstec.go.jp
第142回深田研談話会 東北地方太平洋沖地震の津波の教訓
4月27日(金)15:00〜17:00
会場:深田地質研究所 研修ホール(文京区本駒込2-13-12)
http://www.fgi.or.jp
5月May
第5回ジオパーク国際ユネスコ会議
5月12日(土)〜15日(火)
会場:島原復興アリーナ、雲仙岳災害記念館(長崎県島原市平成町)ほか
参加登録:下記より4月12日(木)まで
http://www.geoparks2012.com/
○街中ジオ散歩in Tokyo「身近な地層や岩石を知ろう」徒歩見学会:2012年地質の日記念
5月13日(日)10:00-16:00
場所:東京都千代田区界隈
くわしくは,http://www.geosociety.jp/name/content0087.html
(後)地質の日記念観察会「深海から生まれた城ヶ島」
日時:2012年5月12日(土)10時〜15時(小雨決行)
詳しくは、こちら(PDF)
問い合わせ:三浦半島活断層調査会事務局
E-mail k345matsu@yahoo.co.jp
○一般社団法人日本地質学会第3回(2012年度)総会(代議員総会)
5月19日(土)14:30-16:00
会場:北とぴあ 第2研修室(北区王子1-11-1)【地図はこちら】
日本地球惑星科学連合2012年大会
5月20日(日)〜25日(金)
会場:幕張メッセ国際会議場(千葉市美浜区中瀬2-1)
http://www.jpgu.org/meeting/
6月June
講演会「津波防災の実践教育-東日本大震災に学ぶ」
6月2日(土)14:00-17:00
場所:えんてつホール(静岡県浜松市・JR浜松駅前 遠鉄百貨店新館8F)
対象:小中高教員、学生、一般
参加方法:下記URLより事前登録
http://rcme.oa.u-tokyo.ac.jp/information/20120410_99.php
第5回ジオ多様性フォーラム「ジオ多様性とは何か、その重要性を問う」
6月8日(金)・9日(土)
場所:JAMSTEC横浜事務所
くわしくは,こちらから
地質学史懇話会
6月10日(土)13:30-17:00
場所:北とぴあ9階901号室:JR京浜東北線王子駅下車3分
中陣隆夫『R.C.ディーツ:大洋底拡大説の前夜』
石渡 明『日本のオフィオライト研究史』
問い合わせ:矢島道子<pxi02070@nifty.com>
日本堆積学会2012年札幌大会
6月15日(金)〜 18日(月)
場所:北海道大学
http://sediment.jp/
○中部支部2012年年会
6月16日(土)
場所:岐阜大学教育学部
http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
資源地質学会第62回年会学術講演会
6月27日 (水) 〜 29日 (金)
場所:東京大学小柴ホール
http://www.kt.rim.or.jp/~srg/documents/2012_nenkai.pdf
第4回シンポジウム「海は学びの宝庫」
6月30日(土):13:00〜17:00
場所:東京大学本郷キャンパス・理学部1号館・小柴ホール
http://rcme.oa.u-tokyo.ac.jp/information/20120430_104.php
深田研ジオフォーラム2012
露頭からテクトニクスへー地層から読み取る日本列島の成り立ちー
6月30日(土):10:00〜16:00
場所:深田地質研究所研修ホール
http://www.fgi.or.jp/
7月July
地震発生及び火山噴火研究の将来構想シンポジウム
7月5日(木)10:00 〜7月6日(金)17:00
申込締切:6月22日(金)正午
要旨締切:6月29日(金)正午※要申込
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/YOTIKYO/nenji/h24_planning_workshop.htm
第143回深田研談話会 地形・地質から知る巨大地震・津波
7月6日(金)15:00〜17:00
会場:マイドームおおさか 8階第3研修室会議室(大阪市中央区本町橋2-5 TEL: 06-6947-4321)
参加費無料・要申込・定員80名 先着順
http://www.fgi.or.jp/
第5回シンポジウム「海洋教育から考える"津波・防災"−東南海地震に備えて−」
7月8日(日)13:00〜17:30
会場:豊橋技術科学大学 A棟101講義室 (愛知県豊橋市)
大学アクセス: http://www.tut.ac.jp/about/access.html
キャンパスマップ:http://www.tut.ac.jp/about/campusmap.html (車での来場可)
対象:小中高教員、学部学生、大学院学生、一般
参加費:無料
申込方法:事前登録→ http://rcme.oa.u-tokyo.ac.jp/information/20120411_100.php
○北海道支部:日高変成岩類地質巡検
7月14日(土)〜16日(月・祝)
申込〆切:6月11日(月)
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
サマー・サイエンスキャンプ2012
(高校生のための先進的科学技術体験合宿プログラム)
7月23日(土)〜8月26日(日)期間中の2泊3日〜5泊6日
応募〆切:6月14日(木)
http://rikai.jst.go.jp/sciencecamp/camp/
(後)「青少年のための科学の祭典」2012全国大会
7月28日(土)〜29日(日)9:30〜16:50
会場:科学技術館(東京都千代田区北の丸公園2-1)
http://www.kagakunosaiten.jp
全国各地でも開催されています.
2012年度の開催予定はこちらから
http://www.kagakunosaiten.jp/country/schedule.php
(協)International Symposium on Zeolites and Microporous Crystals 2012(ZMPC2012)
(2012年ゼオライトおよびその類縁化合物に関する国際会議)
7月28日(土)〜8月1日(水)
会場:広島市アステールプラザ(広島市中区加古町4-17)
http://www.zmpc.org/
学術会議公開講演会「東日本大震災復興の道筋と今後の日本社会」
7月29日(日)13:30〜
会場:京都大学北部総合教育研究棟益川ホール
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/154-s-1-1.pdf
8月August
(後)科学教育研究協議会第59回全国研究大会(鳥取)
「自然科学をすべての国民のものに」
8月3日(金)〜5日(日)
場所:鳥取県米子市コンベンションセンターほか
問い合わせ先:科学教育研究協議会(委員長 佐久間)
TEL/FAX:042-302-3862
e-mail:ped01345@nifty.com
第21回市民セミナー「大震災後の水環境ー何が起こったのか、どう備えるか」
8月3日(金)
場所:
東京会場:地球環境カレッジ(いであ(株)内)(東京都世田谷区駒沢)
大阪会場:いであ(株)大阪支社ホール(大阪市住之江区南港北)
申し込み・問合せ先:(公社)日本水環境学会セミナー係 山本
TEL:03-3632-5351 FAX:03-3632-5352
e-mail:yamamoto@jswe.or.jp
34th International Geological Congress:IGC
8月5日(日)〜10日(金)
会場:Brisban Australia
http://www.34igc.org
第11回中生代陸域生態系国際シンポジウム
(および韓国の恐竜サイト巡検)
シンポジウム:8月15日(水)〜18日(土)
巡検(韓国南部の恐竜化石産出地):8月19日(日)〜22日(水)
場所:韓国・光州
http://www.2012mte.org/
(共)第13回目「地震火山こどもサマースクール」(in 糸魚川ジオパーク)
8月18日(土)〜19日(日)
テーマ「東と西に引き裂かれた大地のナゾ」
参加対象:小学5年〜高校生(40名)
参加申込〆切:7月20日(金)
http://www.kodomoss.jp/ss/itoigawa
(共)日本第四紀学会2012年大会(テーマセッション)
8月20日(月)〜21日(火)
会場:立正大学熊谷キャンパス・アカデミックキューブ(埼玉県熊谷市万吉1700)
発表申込締切:6月25日(月)
http://quaternary.jp/meeting/index.html
9月September
第15回日本水環境学会シンポジウム
9月10日(月)〜12日(水)(9/12は見学会)
場所:佐賀大学本庄キャンパス(佐賀市本庄町1)
http://www.jswe.or.jp
(共)2012年度日本地球化学会年会
9月11日(火)〜13日(木)
場所:九州大学箱崎キャンパス文系地区
http://www.geochem.jp/index.html
◯日本地質学会第119年学術大会(大阪大会)
9月15日(土)〜17日(月・祝)
場所:大阪府立大学 ほか
http://www.geosociety.jp/osaka/content0001.html
ワークショップ“ULTRA-DEEP DRILLING INTO ARC CRUST: genesis of continental crust in volcanic arcs”
9月17日(月)〜21日(金)
場所:BWaikoloa Beach Marriott Resort & Spa, Kona, Hawaii, USA
http://www.jamstec.go.jp/ud2012/
第62回東レ科学講演会
9月21日(金)17:00-20:00(開場16:30 途中休憩あり)
場所:有楽町朝日ホール(有楽町マリオン11階:千代田区有楽町2-5-1)
聴講無料 事前申込不要 当日先着順:定員630名
http://www.toray.co.jp/tsf/info/inf_006.html
岩盤工学特別講演会2012(その2)
9月24日(金)講演会14:00-17:00(受付開始13:30)交流会17:10-18:30
場所:深田地質研究所 研修ホール(文京区本駒込2-13-12)
定員80名(先着順)申込は下記ホームページの所定フォームにて受付
http://www.fgi.or.jp
第144回深田研談話会「次世代の火山防災のあり方を考える」
9月28日(金)15:00-17:00(開場14:30)
場所:深田地質研究所 研修ホール(文京区本駒込2-13-12)
定員80名(先着順)
http://www.fgi.or.jp
10月October
Short Course on Shipboard Sedimentology: Data Collection, Integration, and Synthesis
10月1日(月)〜4日(木)
場所:IODP Gulf Coast Repository (College Station, Texas)
対象:大学院生以上 募集〆切:9/7(金)
問い合わせ:J-DESCサポート 海洋研究開発機構 地球深部探査センター内
info@j-desc.org Tel: 045-778-5271
http://www.j-desc.org/modules/tinyd0/rewrite/coreschool/US_short_course.html
(共)第二回津波堆積物ワークショップ
10月6日(土)10:30-15:45
場所:津市三重県総合文化センター大研修室
参加募集は締切ました
詳細はこちら
○関東支部:銚子巡検
10月27日(土)〜28日(日)
申込締切:10月20日(土)
詳細はこちら
深田研 一般公開2012
10月21日(日)10:00-16:00
場所:深田地質研究所 研修ホール(文京区本駒込2-13-12)
http://www.fgi.or.jp
2012年地質調査研修
10月29日(月)〜11月2日(金)
場所:千葉県君津市およびその周辺(房総半島中部地域)
申込締切:9月21日(金)
詳細はこちら
11月November
(後)第3回日本ジオパーク全国大会(室戸大会)
11月2日(金)〜5日(月)
会場:室戸市保健福祉センターやすらぎ(メイン会場)ほか
ジオツアー:11月2日(金)・5日(月)
参加申込締切:9月14日(金)
http://conference.muroto-geo.jp/index.html
第66回日本人類学会大会
11月2日(金)〜4日(土)
演題募集・事前参加登録締切:8月3日(金)
場所:慶応義塾大学日吉キャンパス 来往舎
http://www.gakkai.ne.jp/anthropology/66_annual_meeting/
(後)第13回「こどものためのジオ・カーニバル」
11月3日(土)〜4日(日)11:00-16:00
場所:大阪市立科学館(大阪市北区中之島4-2-1)
http://www.geoca.org/
(後)深海から生まれた城ヶ島
11月4日(日)10:00-15:00(小雨決行)
場所:三浦市城ヶ島
募集人員:30名 締切:10月19日
申込先:三浦半島活断層調査会事務局
詳細はこちらから(pdfファイル)
マントル掘削プロジェクト特別シンポジウム 海とちきゅうのフロンティア
〜ウォルター・H・ムンク教授特別講演〜
11月7日(水)14:00-16:00
場所:東京大学小柴ホール
入場:無料,開場:13:00-
http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~s-moho/sympo2012/sympo2012.html
東海地震防災セミナー2012
11月8日(木)13:30-16:00
会場:静岡商工会議所静岡事務所5階ホール
連絡先:土 隆一(土研究事務所)
Fax:054-238-3241/Tel.:054-238-3240
東京大学大気海洋研究所共同利用研究集会
「バイオミネラリゼーションと石灰化—遺伝子から地球環境まで—」
11月8日(木)13:00-17:10、9日(金) 9:30-12:00
場所:東京大学大気海洋研究所2F 講堂
交通:http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/access/index.html
詳細はこちら
海洋調査技術学会第24回研究成果発表会
11月8日(木)10:00〜9日(金)17:00
会場:海上保安庁海洋情報部10階国際会議室(江東区青梅2-5-18)
連絡先:海洋調査技術学会事務局
http://jsmst.org/
海洋プレート研究:掘削技術・成果と次の科学
11月9日(金)〜10日(土)
場所:JAMSTEC東京事務所
http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~s-moho/sympo2012/2012seminar.html
平成24年度 東濃地科学センター 地層科学研究 情報・意見交換会
11月14日(水)13:00〜17:00
場所:瑞浪市地域交流センター「ときわ」(岐阜県瑞浪市)
定員:約150名 入場無料 参加申込締切10月31日
http://www.jaea.go.jp/04/tono/index.htm
瑞浪超深地層研究所 深度300m水平坑道見学会
11月15日(木)9:15-12:00
場所:瑞浪超深地層研究所
定員:40名 入場無料 参加申込締切10月31日
http://www.jaea.go.jp/04/tono/index.htm
農業・農村の地域再生に関する技術シンポジウム
11月15日(木)11:00-16:30
場所:東北大学百周年記念会館
参加申込も下記URLより
http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2012/09/043933.html
第21回東北大学素材工学研究懇談会
鉄鋼製造プロセスにおけるエネルギー・環境問題とその解決策
11月16日(金)8:50-17:45 懇親会18:00
場所:片平さくらホール(仙台市青葉区片平2-1-1)
参加申込:所属・氏名・電話・Eメール・懇親会出席の有無を下記へ連絡(締切10/31)
受付担当:小原恵 obara@taben.tohoku.ac.jp
Techno-Ocean2012
11月18日(日)〜20日(火)
会場:神戸国際会議場
http://techno-ocean2012.com
(協)3rd Asia-Pacific Conference on Luminescence and ESR dating
11月18日(日)〜22日(木)
会場:岡山理科大学50周年記念館
http://www.rins.ous.ac.jp/eps/theme/symposium.html
「海・陸・氷床から探る後期新生代の南極寒冷圏環境変動」
—第三回極域科学シンポジウム横断セッション−
11月26日(月)〜27日(火)
会場:国立国語研究所(立川市緑町10-2:国立極地研究所から徒歩数分)
入場無料・事前申込不要
http://polaris.nipr.ac.jp/~daiyonkigroup/PolarScienceSympo_special/index.html
International Symposium on Emerging Issues after the 2011 Tohoku Earthquake
11月27日(火)
会場:筑波大学 総合研究棟D(筑波キャンパス)
講演申込締切:2012年10月12日(金)
http://www.nourin.tsukuba.ac.jp/~engei/mizuta/?page_id=171
27th Himalaya-Karakoram-Tibet Workshop
(第27回ヒマラヤ-カラコルム-チベット ワークショップ)
11月28日(水)〜30日(金)
プレ・ポスト巡検(1〜3日の3コースを予定)
場所:ネパール,カトマンズ
問い合わせ先:組織委員会 hkt27kath@gmail.com
http://www.ngs.org.np
(協)第28回ゼオライト研究発表会
11月29日(木)〜30日(金)
場所:タワーホール船堀(江戸川区船堀)
http://www.jaz-online.org
第145回深田研談話会
日本列島・地球史・「ちきゅう」そして新しい地球生命観
11月30日(金)
会場:深田地質研究所 研修ホール(文京区本駒込2-13-12)
http://www.fgi.or.jp/
12月December
○関東支部第2回ミニ巡検「八ッ場ダム地域の層序を知る」
12月1日(土)・2日(日)
くわしくは,こちらから
自然史学会連合講演会 自然災害とナチュラルヒストリー
12月1日(土)10:00-16:30
会場:栃木県立博物館 講堂
http://ujsnh.org/sympo/2012/index.html
日本海洋政策学会 第4回年次大会および定例総会
12月1日(土)9:30-17:45
会場:明治大学(和泉キャンパス)第1校舎002教室(東京都杉並区永福1-9-1)
http://oceanpolicy.jp
地球化学研究協会 第49回の霞ヶ関環境講座
12月1日(土)14:30〜
会場:霞ヶ関ビル35階東海大学校友会館(地下鉄銀座線虎ノ門・千代田線霞ヶ関、下車)
http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~e881147/Geochem/news1.html
平成24年度国土技術政策総合研究所(国総研)講演会
12月4日(火)
場所:日本教育会館 一ツ橋ホール(千代田区一ツ橋2-6-2)
http://www.nilim.go.jp/
産技連・地質関係合同研究会 地質地盤および地圏環境に関する最近の成果
12月6日(木)10:00-17:00
会場:ホテル福島グリーンパレス(JR福島駅前)
http://www.gsj.jp/HomePageJP.html
(共)第22回環境地質学シンポジウム
12月7日(金)〜8日(土)10:00-17:00
会場:産業技術総合研究所共用講堂
http://www.jspmug.org/envgeo_sympo/22nd_sympo/22nd_sympo.html
「国際的に通用する技術者教育ワークショップ」シリーズ第1回
学習・教育到達目標設定法とその達成度評価法
(エンジニアリング・デザイン能力育成科目を対象として)
12月8日(土)10:00-18:00
会場:芝浦工業大学 豊洲キャンパス 教室棟303教室
申込期限:11月15日(木)
http://www.jabee.org/OpenHomePage/news.htm#ws121208
第6回シンポジウム「海は学びの宝庫−すべての学校で進める海洋教育−」
12月8日(土)13:00-17:00
会場:東京大学本郷キャンパス・理学部1号館・小柴ホール
申込フォームより事前申込
http://rcme.oa.u-tokyo.ac.jp/information/20121013_123.php
第12回東北大学多元物質科学研究所研究発表会
12月10日(木)10:00-20:00
会場:東北大学片平さくらホール
参加申込:11月30日(金)締切
http://www.tagen.tohoku.ac.jp/general/info/event/meeting/2012/
第146回深田研談話会
巨大地震・津波の想定と課題
12月14日(金)
会場:深田地質研究所 研修ホール(文京区本駒込2-13-12)
http://www.fgi.or.jp/
Post Symposium of 4.5-session 1, the 34th IGC, Geopollution, dust, and man made strata
“A flight of stone steps in Brisbane”“ブリスベーンで見た坂の上の雲”
(共)日本地質学会環境地質部会
12月16日(日)13:00-17:30
会場:江戸川グリーンパレス402研修室(江戸川区松島1-38-1)
詳細はこちらから
第6回ジオ多様性フォーラム
12月21日(金)・22日(土)
場所:JAMSTEC東京事務所
くわしくは,こちらから
第7回「科学の芽」賞表彰式・発表会
12月22日(日)12:30-16:30
場所:筑波大学大学会館3階ホール
問い合わせ:実行委員会事務局
筑波大学東京キャンパス事務部支援課(総務)田村・青砥
03-3942-6805 <kagakunome@un.tsukuba.ac.jp>
地質学史懇話会
12月23日(日)13:30-17:00
場所:北とぴあ 902号室(北区王子1-11-1)
鈴木寿志『「要説地質年代」を訳して』
井澤英二『日本鉱業史研究会34年の歩みー鉱業史と地質学史との接点ー』
問い合わせ:矢島道子<pxi02070@nifty.com>
ウィンター・サイエンスキャンプ '12-13
12月23日(日)〜2013年1月11日 期間中の2泊3日〜3泊4日
会場:大学・研究機関等(11会場)
定員:会場ごとに10〜24名(計198名)
応募締切:11月6日(火)必着
http://rikai.jst.go.jp/sciencecamp/camp/
2013年の行事カレンダーへ
会議の予定・議事録
会議の予定
執行理事会
■ 2025年度第4回執行理事会
日時 2025年10月15日(水)18:30-
WEB会議
■ 2025年度第5回執行理事会
日時 2025年11月19日(水)18:30-
WEB会議
■ 2025年度第6回執行理事会
日時 2025年12月6日(土)10:00-
WEB会議
理 事 会
■ 2025年度第2回理事会(定例)
日時 2025年9月6日(土)14:00-
WEB会議
■ 2025年度第3回理事会(定例)
日時 2026年4月11日(土)14:00-
WEB会議
総 会
■ 2025年度(第17回)代議員総会
日時 2025年6月7日(土)14:00(時間は予定)
WEB会議
議事次第はこちら
議事録
執行理事会 議事録
2025年度
第1回(7.7)
第2回(8.4)
第3回(9.6)
第4回(10.15)
第5回(11.19)
第6回(12.6)
第7回(26.1.14)
第8回(25.2.18)
第9回(26.3.11)
第11回
2024年度
第1回(24.6.22)
第2回(24.7.20)
第3回(24.8.10)
第4回(24.9.20)
第5回(24.10.19)
第6回(24.11.16)
第7回(24.12.14)
第8回(25.1.11)
第9回(25.2.15)
第10回(25.3.15)
第11回(25.4.19)
第12回(25.5.14)
第13回(25.6.7)
2023年度
第1回(23.7.8)
第2回(23.8.5)
第3回(23.9.9)
第4回(23.10.14)
第5回(23.11.14)
第6回(23.12.9)
第7回(24.1.20)
第8回(24.2.17)
第9回(24.3.16)
第10回(24.4.13)
第11回(24.5.18)
理事会 議事録
2025年度
第1回定例(25.9.6)
第2回定例(25.12.6)
第3回定例(26.4.11)
2024年度
第1回定例(24.6.8)
第2回定例(24.8.31)
第3回定例(24.12.14)
第4回定例(25.4.19)
2023年度
第1回定例(23.9.9)
第2回定例(23.12.9)
第3回定例(24.4.13)
総会 議事録ほか
2025年度総会(2025.6.7)
・2025年度貸借対照表_pdf
2024年度総会(2024.6.8)
・2024年度貸借対照表_pdf
2023年度総会(2023.6.3)
・2023年度貸借対照表_pdf
*2019年度以前の議事録はこちらから→クリック
*任意団体の議事録はこちらから→クリック
PDFをご覧になるには、「Adobe Acrobat Reader」をダウンロードしてご使用ください。
2019年度各賞
2019年度各賞受賞者 受賞理由
■学会賞(1件)
■国際賞(1件)
■小澤儀明賞(1件)
■Island Arc賞(1件)
■論文賞(2件)
■研究奨励賞(2件)
■学会表彰(3件)
日本地質学会賞
受賞者:多田隆治 会員(東京大学大学院理学系研究科)
対象研究テーマ:精密な層序ならびに堆積物分析に基づく環境変動史解明
多田隆治会員は,これまで長年にわたり,詳細な野外調査ならびにコア観察に基づき緻密な岩相層序を確立し,それを基礎に,堆積物の物性・粒度・鉱物・元素組成の時代変遷を精密に分析・解析することにより,地球表層の環境変動史解明に関わる数々の発見と洞察に満ちた仮説を提示してきた.中でも,珪質堆積物の続成過程の理解を基に,日本海第三紀珪質岩の堆積リズムがミランコビッチサイクルを反映していることの発見や,日本海の第四紀明暗層の堆積がDansgaard-Oeschgerサイクルに対応していることを初めて見出し,日本海の海洋環境が東アジアモンスーンと共に大きく変動して来たことを明らかにした功績は大きい.また日本海への黄砂供給量が東アジアの乾湿を反映し,その供給源の変動は東アジアとグリーランドの気候テレコネクションによる可能性を指摘した.このように,多田会員による新生代の海洋および陸上地質についての詳細な堆積学的検討と,それに基づく汎世界的な気候変動との関連性に関する検討は,地球環境変動史の解明に大きく貢献すると共に,その研究手法は現在の地球環境変動史解析の基本となっている.さらに,白亜紀—古第三紀境界における隕石衝突に伴うキューバ津波イベントの規模について,精密な岩相層序と堆積物の物性解析に基づいて定量的評価を行うなど,この分野でも大きな功績を挙げた.
多田会員は,研究のみならず教育面においても,精密層序確立の重要性やその客観的な解析手法を多くの研究者や学生たちに惜しみなく伝え,環境変動に関わる地質学分野の裾野を拡げることに貢献してきた.さらにこれらの功績に加え,IODPやPAGES-SSCの国際委員,IGCP476・IGCP581の共同代表,PEPS誌やPaleoceanography誌の副編集長などを務め,環境変動史研究を通した国際的な地質学コミュニティに対し貢献すると共に,我が国の地質学の国際的発展に中心的な役割を担って来た.近年も,2013年のIODP日本海航海とその後の国際共同研究,2014年以降のAustralasian tektitesの隕石衝突サイトに関わるインドシナ調査など,国際的な研究協力や交流関係を発展させてきている.
以上のように,多田隆治会員が日本の地質学の発展に果たしてきた多岐にわたる業績はきわめて大きく,日本地質学会賞に推薦する.
日本地質学会国際賞
受賞者:Robert J. Stern氏(テキサス大学ダラス校)
対象研究テーマ:島弧—海溝系およびプレートテクトニクスの研究
米国,テキサス大学ダラス校のRobert J. Stern教授は野外地質学,岩石学,地球化学をベースとした島弧—海溝系のテクトニクスの世界的権威として有名である.Scopus(2019年3月14日)によると論文数は270,被引用数は15534である.Stern氏は1979年カリフォルニア大学サンディエゴ校(スクリプス海洋研究所)にて学位取得後,カーネギー研究所の博士研究員を経て1982年テキサス大学ダラス校に所属し現在に至る.この間米国地質学会(1993年)および米国地球物理学連合(2017年)よりフェローの称号を授与されている.学術誌の編集への貢献も顕著で,多くの国際誌の編集委員を歴任後,現在はInternational Geology Review誌の編集長として手腕を発揮している.
北マリアナ弧のアグリハン(Agrigan)火山の火山地質学・岩石学(Stern, 1978)からスタートしたStern氏の研究はやがて伊豆-小笠原-マリアナ弧(IBM弧)全体に広がり,共同研究者とともに岩石学,地球化学,テクトニクスに関する数多くの研究成果を公表した(例えば,Bloomer et al., 1989; Lin et al., 1989; Stern & Bloomer, 1992). またそれらを通し,島弧-海溝系の形成に関する数多くのインパクトの高い総括的論文を発表した(例えば,Stern, 2002, 2004). その過程でIBM弧で活躍して来た日本人科学者と交流し,共同研究が2000年代に入って急速に増えている(例えば,Kimura et al., 2005; Tatsumi & Stern, 2006; Ishizuka et al., 2006, 2014; Stern et al., 2012, 2013, 2014, 2016).Stern氏はパンアフリカ帯の形成などの原生代のテクトニクスの研究でも極めて著名である(例えば,Stern, 1994).
Stern氏の一連の研究は,日本列島の理解を大きく高めたのみならず,共同研究を通じ日本人科学者の向上を推進してきたものとして高く評価できる.さらに,Island Arc誌のAssociate editorを長年勤め同誌の国際誌としての地位向上を推進し,ODP-IODPにおいても日本人研究者とともに掘削計画の策定や提案を行うなどの貢献があった.
こうしたRobert J. Stern教授の業績と日本地質学界への多大な貢献に鑑み,同氏を日本地質学会国際賞候補者として推薦する.
2019 International Award of the Geological Society of Japan
Dr. Robert J. Stern is Professor of Geosciences and Director of the Global and Magmatic Research Laboratory at the University of Texas at Dallas, USA. He is known for his extraordinary ability in the studies of modern and ancient convergent margin processes using the principles of field geology, petrology, geochemistry and geochronology. He is a recognized world leader in those research fields and has made outstanding contributions to the geoscience community in Japan through research exchange and academic cooperation.
Prof. Stern graduated from University of California at Davis in 1974. He undertook graduate studies at the Scripps Institution of Oceanography, and received a Ph.D. at the University of California at San Diego in 1979. He spent two years the Department of Terrestrial Magnetism, Carnegie Institution of Washington as a post-doctoral fellow, focused on the geochemistry of Egyptian and Mariana igneous rocks. After his postdoctorate in 1982, he joined the Geosciences faculty at the University of Texas at Dallas, rising from assistant professor to professor and serving as Dept. Head 1997–2005.
Throughout his more than 40 years of research experience, he has made numerous, cooperative academic exchanges with Japanese researchers. Prof. Stern has been an associate editor or editorial board member of seven Science Citation Index (SCI) journals including, "Geology", "Journal of Geophysical Research". "Precambrian Research", and "Island Arc", "International Journal of Geosciences", and is now editor-in-chief of "International. Geology Review". He was elected Fellow in two distinguished academic societies (Geological Society of America, American Geophysical Union).
Prof. Stern has published over 275 scientific papers which have been cited as more than 23,000 times according to GoogleScholar. He is one of the earliest researchers that applied modern geochemical and isotope techniques to the study of East African Orogen (EAO) along eastern Africa and western Arabia. His studies in the EAO helped establish and assess Neoproterozoic crustal growth in the world largest collisional belt. Moreover his studies of the Izu-Bonin-Mariana (IBM) arc-trench system helped establish this as the best-studied example of an oceanic arc system. These studies led to further advances in our understanding of how new subduction zones form and the evolution of plate tectonics through Earth history. He has also contributed to various ODP-IODP expeditions in the IBM system. His IBM work has involved many Japanese researchers.
Based on the great scientific achievements and important contribution to the Japanese geological community as noted above, we recommend Dr. Robert J. Stern for the 2019 International Award of the Geological Society of Japan.
日本地質学小澤儀明賞
受賞者:齋藤誠史 会員(スイス,ローザンヌ大学)
対象研究テーマ:古生代末の絶滅事件と特異な還元海洋環境の出現に関する研究
齋藤誠史会員は,野外地質調査と室内分析の両方を着実に行う高い能力を備え,それを実証する質の高い論文を公表すると共に,国際学会においても多数の口頭発表を行っている.齋藤会員の研究テーマは,古生代末に起きた最大規模の生物絶滅事件の原因探索に関わるものである.具体的かつ膨大な基礎データとして,世界で最も保存良好な絶滅境界が露出する中国四川省において,詳細な野外調査を基に,大量の採取岩石試料から500 枚以上に及ぶ研磨スラブ試料と1000枚以上の岩石薄片を作成し,詳細な地質記載を行った.さらに多様な微量化学分析,ならびに同位体(炭素・硫黄・窒素)比測定を行い,その結果から,絶滅直前の海洋深層において酸素極小層の異常拡大が起こり,それに伴って浅海での絶滅が起きたと結論した.特筆すべきは,境界直前の還元環境下で晶出した微小方解石プリズムの発見とその堆積期間前後の海水の炭素・硫黄・窒素同位体比変化を示したことであり,世界でも他に例のないきわめて独自性の高い成果である.また最新論文では,自生炭酸塩岩の堆積が全海水の同位体比変化に及ぼす影響についても初めて議論した.これら研究成果は,主著者として執筆した7編の国際学術誌論文にまとめられている.個々の論文のレベルはきわめて高く,その論文被引用回数は,近年になって特に増加している.昨今の欧米の研究手法を追従した論文が多い中で,オリジナリティに溢れる齋藤会員の論文は高く評価できる.
現在,齋藤会員は,フランス国Université Clermont Auvergne(Laboratoire Magmas et Volcans)でポスドクとして研究中であり,さらなる新しい地球化学的分析手法の開発を目指している.一方,顕生代のみならず,太古代および原生代の炭酸塩岩についても,オーストラリアや中央アフリカ・ガボン共和国での野外調査に基づく研究を精力的に進めている.このような新たな分野に積極的に挑戦する研究姿勢からも,将来を期待できる素養・資質を有していると判断される.
このように齋藤会員は,豊富な専門的知識および高度な分析技術をもち,その潜在的能力は同世代の若手研究者の中でも突出しており,日本の地球科学を牽引する新世代のリーダー候補として大きく期待される.以上の理由から,齋藤会員を日本地質学会小澤義明賞に推薦する.
日本地質学会 Island Arc賞
対象論文:Catherine Chagué-Goff, Jordan Chi Hang Chan, James Goff, and Patricia Gadd, 2016, Late Holocene record of environmental changes, cyclones and tsunamis in a coastal lake, Mangaia, Cook Islands. Island Arc, 25, 333−349.
Mangaia in the Southern Cook Islands, like many other Pacific islands, is exposed to a range of natural hazards, including cyclones and tsunamis which can be generated not only by local submarine slope failures but also from earthquakes occurring at distant locations along the Pacific Ring of Fire. Chagué-Goff et al (2016) analyzed a 4.3 m-long peat sequence from the shore of Lake Tiriara, in one of the swampy areas inside an old raised coral reef (atoll) in the island interior, which records long- and short-term regional environmental changes over the past 3500 years and also the effect of human settlement. Seawater has been reported to intrude through an underground tunnel into Lake Tiriara in the island interior during cyclones. This is a unique geologic setting if tsunami deposits can be found on raised atolls, which are commonly surrounded by steep cliffs and lack coastal plains. Chagué-Goff et al aimed to identify tsunami deposits and distinguish them from cyclone deposits, based on sedimentological, geochemical and microfossil analyses. Based largely on the distinctive geochemical signature of the deposits, they eventually proposed that one probable paleocyclone deposit and three probable paleotsunami deposits were preserved in the sequence. If similar tsunami deposits are found in other raised atolls, it will help estimate the frequency of tsunami occurrence and maximum wave heights in tropical Pacific islands. This knowledge is expected to be useful for disaster risk reduction in this region.
>論文サイトへ(Wiley)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/iar.12153
日本地質学会論文賞01
対象論文:佐野弘好,2018,岐阜県西部,舟伏山岩体東部の美濃帯ペルム系〜三畳系チャート優勢層の層序と年代. 地質学雑誌,124,449-467.
本論文は,美濃帯西部,舟伏山岩体東部のチャート優勢層の分布,岩相層序,放散虫化石年代を検討し,その層序と年代を明らかにしたものである.美濃帯のペルム系チャートは,泥岩中の岩塊として産し混在岩相を形成していることから,これまで初生的な層序の全容解明にはいたっていなかった.本論文では,丹念な地質調査に基づいた岩相記載と微化石年代の決定により,チャート優勢層は,玄武岩質岩を基盤とするペルム紀シスウラリアンから後期三畳紀の遠洋性・深海成堆積物であることが明らかにされている.チャート優勢層には,堆積環境の時代変遷が,赤色チャート,砕屑性ドロマイト,黒色粘土岩,珪質ミクライト・チャート互層などの特徴的な岩相として記録されており,今後,古生代から中生代にかけての古海洋環境の時代変遷や,ペルム紀末大量絶滅事変の理解において重要な情報を与えると考えられる.また何より本論文は,地質図・断面図・柱状図に代表される各種地質データや,徹底した岩相記載および微化石年代決定など,地質学雑誌掲載論文の好例ともいえる内容から構成されている点が高く評価される.以上の理由より,本論文を日本地質学会論文賞に推薦する.
>論文サイトへ(J-STAGE)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/geosoc/124/6/124_2018.0010/_article/-char/ja
日本地質学会論文賞02
対象論文:Hitoshi Hasegawa, Hisao Ando, Noriko Hasebe, Niiden Ichinnorov, Tohru Ohta, Takashi Hasegawa, Masanobu Yamamoto, Gang Li, Bat‐Orshikh Erdenetsogt, Ulrich Heimhofer, Takayuki Murata, Hironori Shinya, G. Enerel, G. Oyunjargal, O. Munkhtsetseg, Noriyuki Suzuki, Tomohisa Irino, Koshi Yamamoto, 2018, Depositional ages and characteristics of Middle‒Upper Jurassic and Lower Cretaceous lacustrine deposits in southeastern Mongolia. Island Arc 27-3, DOI: 10.1111/iar.12243.
本研究は,モンゴルのオイルシェールの空間的および時間的分布を調べ,ジュラ紀および白亜紀の湖沼堆積物の詳細な特徴と古気候的背景を明らかにしたものである.まず,凝灰岩のジルコンU-Pb年代などから,Shinekhudag層はAptian初期に,Eedemt層はCallovian-Oxfordianに堆積したことを示し,堆積速度を評価した.Shinekhudag層のオイルシェール中には藻類起源の有機物と砕屑性粘土からなるマイクロメータースケールの葉理構造があり,降水の季節性を反映した年稿である可能性が高く,堆積速度とも整合的である.筆者らは両層堆積時の広範な湖沼発達に示される気候の湿潤化がOAEとほぼ同時期に起こっている可能性も示した.本研究は,緻密かつ詳細な現地調査とサンプルの分析に基づいて,湖沼堆積物のプロセスを明確に示すとともに,ジュラ紀−白亜紀における陸上−海洋の気候的関連性を示す重要な成果であると評価できる.以上の理由より,本論文を日本地質学会論文賞に推薦する.
>論文サイトへ(Wiley)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/iar.12243
日本地質学会研究奨励賞_01
受賞者:加瀬善洋 会員(北海道立総合研究機構地質研究所)
対象論文:加瀬善洋・仁科健二・川上源太郎・林 圭一・高清水康博・廣瀬 亘・嵯峨山 積・高橋 良・渡邊達也・輿水健一・田近 淳・大津 直・卜部厚志・岡崎紀俊・深見浩司・石丸 聡,2016,北海道南西部奥尻島で発見された津波堆積物.地質学雑誌,122, 587–602.
本論文では,北海道南西部に位置する奥尻島南部の青苗地区において,丹念な津波堆積物調査を実施し,未解明な点が多かった津波履歴を明らかにした.これらの結果に基づくと,(1)奥尻島では過去3,000–4,000年の間に少なくとも6回の津波があったこと,(2)過去に発生した津波の浸水範囲から,これらの津波は1993年北海道南西沖地震津波を超える規模であったことが判明した.日本海沿岸域における津波履歴の解明に向けた,貴重なデータと言える.また,津波堆積物を認定する上で重要となる「海水の寄与」を把握するために,有機質微生物遺骸(渦鞭毛藻シスト,有孔虫の内膜)に着目した新たな手法を提案し,その有用性も示した.さらに,本論の結果は,津波浸水想定の見直し等の資料として,国や道の防災計画の見直し等,既に行政施策への活用がなされている.以上のように,本論は学術的に高い意義をもつとともに,日本海沿岸の津波防災地域づくりに貢献する研究として高く評価できる.以上の理由により,本論文の筆頭著者である加瀬善洋会員を日本地質学会研究奨励賞に推薦する.
>論文サイトへ(J-STAGE)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/geosoc/122/11/122_2016.0042/_article/-char/ja
日本地質学会研究奨励賞_02
受賞者:葉田野 希 会員(信州大学大学院総合工学系研究科)
対象論文:葉田野 希・吉田孝紀,2018,瀬戸内区中新統瀬戸陶土層の古土壌構成が示す古風化および古気候条件.地質学雑誌,124,191–205.
本論文は中新統瀬戸陶土層とその上位層を対象に,丁寧な露頭記載,古土壌の岩石学的記載に基づいて,土壌形成に強い影響を与える堆積速度や母材の特性を考慮し,多角的に土壌形成過程と古気候を言及したものである.古土壌の形成を議論する際,古地形を正確に復元することは重要であるが,筆者らは500m以上に渡って連続する露頭観察からそれに成功し,土壌形成時の排水条件を復元したことは価値が高い.これにより信頼度の高い気候復元が可能となった.また,本論文の特筆すべき成果として,季節性の大きな気候下で形成されるヴァーティソルの特徴を持つ土壌を見いだしたことも挙げられる.これは,これまで古生物学的知見から復元されていた古気候に,季節性に関する具体的な情報をもたらした.本論文は,古気候記録媒体として古土壌を扱った数少ない国内での研究例であり,国際的に見てもレベルが高い.以上の理由により,本論文の筆頭著者である葉田野 希会員を日本地質学会研究奨励賞に推薦する.
>論文サイトへ(J-STAGE)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/geosoc/124/3/124_2017.0070/_article/-char/ja
学会表彰01
受賞者:株式会社新興出版社啓林館
表彰業績:教科書出版を通じた地学教育への貢献
地学の教育と普及の推進は本学会が取り組むべき重要な活動の一つである.学校教育では教科「理科」において地学分野の内容が扱われる.小中学校の段階では,地学には物理や化学,生物とほぼ同等の時間数が当てられ,すべての児童・生徒が地質学の基礎を含む地学分野について学ぶ.しかし高等学校では,地学関係の授業を開講している学校はかなり限定されている現状がある.近年になって科目「地学基礎」を開講する高校は多少なりとも増えているが,科目「地学」についてはいまだ非常に少ない.本学会はこの厳しい現状を直視し,地学分野の教育と普及に一層努めなければならない.
こうした厳しい状況にもかかわらず,科目「地学」の教科書が株式会社新興出版社啓林館および数研出版株式会社の二社から出版されている.この二社は旧学習指導要領下でも科目「地学II」の教科書を出版しており,地学の教育・普及の面でも大きな貢献をはたしている.高校での需要の有無にかかわらず,地学を独学する高校生や一般市民,それに大学で教養レベルの地学の内容を学ぶ学生にとって,二社の教科書の存在はたいへん重要である.さらに地学分野の専門書や参考書が限られる現状も含めて,二社の教科書出版が地質学を含む地学の教育と普及に果たしている役割は非常に大きいと言える.
今後も継続して科目「地学」の教科書が出版されることへの期待も込めて,株式会社新興出版社啓林館を日本地質学会表彰に推薦する.
学会表彰02
受賞者:数研出版株式会社
表彰業績:教科書出版を通じた地学教育への貢献
地学の教育と普及の推進は本学会が取り組むべき重要な活動の一つである.学校教育では教科「理科」において地学分野の内容が扱われる.小中学校の段階では,地学には物理や化学,生物とほぼ同等の時間数が当てられ,すべての児童・生徒が地質学の基礎を含む地学分野について学ぶ.しかし高等学校では,地学関係の授業を開講している学校はかなり限定されている現状がある.近年になって科目「地学基礎」を開講する高校は多少なりとも増えているが,科目「地学」についてはいまだ非常に少ない.本学会はこの厳しい現状を直視し,地学分野の教育と普及に一層努めなければならない.
こうした厳しい状況にもかかわらず,科目「地学」の教科書が株式会社新興出版社啓林館および数研出版株式会社の二社から出版されている.この二社は旧学習指導要領下でも科目「地学II」の教科書を出版しており,地学の教育・普及の面でも大きな貢献をはたしている.高校での需要の有無にかかわらず,地学を独学する高校生や一般市民,それに大学で教養レベルの地学の内容を学ぶ学生にとって,二社の教科書の存在はたいへん重要である.さらに地学分野の専門書や参考書が限られる現状も含めて,二社の教科書出版が地質学を含む地学の教育と普及に果たしている役割は非常に大きいと言える.
今後も継続して科目「地学」の教科書が出版されることへの期待も込めて,数研出版株式会社を日本地質学会表彰に推薦する.
学会表彰03
受賞者:加納 隆 会員(山口大学名誉教授)
表彰業績:地球科学標本室・ゴンドワナ資料室の整備と普及活動
加納 隆会員は,岩石学・鉱床学・鉱物学の専門家であり,定年退職後も幅広い知識と経験をもとに,山口大学理学部において地球科学標本室・ゴンドワナ資料室の整備に努めてきた.またそれらの資料を用いて地質学の普及活動に尽力し,特に大学における研究試料の保存の必要性を自らの実践を通じて訴えてきた.
標本室・資料室とはいうものの,その質・量ともに国内有数の地質鉱物博物館であり,地球科学標本室には国内外の鉱物・岩石標本が,ゴンドワナ資料室には南極・オーストラリア・インド・ヒマラヤなどゴンドワナ大陸の形成に係る地球史40億年をカバーする岩石試料が収蔵されている.実物標本だけでなく,地質図・文献および標本の産状を示す記録写真は山口大学の学術資産として認められている.とくに南極標本の系統的な標本保存とデータ整備は,全国に先駆けたモデルケースとなるものである.
同氏が整理・収蔵した標本数は,12000点を超え,世界の地域地質に関する図書や地質図約1,000点,各標本の産状を示すデジタル化写真は18000点に及ぶ.同氏は標本室に多くの標本を寄贈しているが,その中でも世界各地を訪ねて自ら採取した美しい鉱物・岩石標本は,ひと際目を引く.実物の標本・詳細リスト・産状の記録の3点が揃うことにより標本の価値は一層高まる.これらのデータベースを整えることにより標本検索が容易となり,国内外の研究者への資料提供や学術的成果が見込まれる.また,実物標本とデータのデジタル化と公開によって学生教育と社会教育の観点からの活用が期待される.理学部に開設した標本室のホームページ(http://gondwana.sci.yamaguchi-u.ac.jp/)では標本写真と現場写真を使って地球史40億年,ゴンドワナの地質,日本の地質,山口の地質,資源と鉱石などを解説し,学内外へ地質学の普及に努めている.
このようにして整備された標本は,大学教育に活用されていることは言うに及ばず,国内外からの来訪者にも見学の場が提供され,社会教育へ貢献してきた.同氏は,県内外の博物館など社会教育機関への標本貸出や展示への助言・講演も行っており,それらの入場者数は10万人を超えている.
長年にわたる献身的な標本整備とそれを使った地質学の普及活動は大学における学術資産の保護と活用のあるべき姿を実践したものであり,加納 隆会員を日本地質学会表彰に推薦する.
山口大学地球科学標本室・ゴンドワナ資料室WEBサイト
http://gondwana.sci.yamaguchi-u.ac.jp/
定款
定 款
一般社団法人 日本地質学会
*定款PDFダウンロードはこちらから
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本地質学会(以下「学会」という)と称する。学会の英文名称はThe Geological Society of Japan(略称J.G.S.)という。
(事務所)
第2条 この学会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この学会は、理事会の議決を経て、日本国内の必要の地に支部を置くことができる。
(目 的)
第3条 この学会は、地質学とその応用についての研究成果の公表、知識の交換、内外の関連学会との連携協力等を行うことにより、地質学の進歩と普及を図り、学術の振興と社会の発展に寄与・貢献することを目的とする。
2 第1項の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)地質学に関する研究開発の推進、奨励ならびに援助
(2)地質学に関する研究成果の公表、普及ならびに情報の提供
(3)地質学に関する調査、情報収集
(4)地質学に関する技術指導、人材育成
(5)地質学に関する教育、普及、啓発
(6)地質学に基づく献策
(7)関連する諸団体ならびに産学官の諸機関との交流および協力
(8)前号にあげるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
3 前項の事業は、日本全国において行うとともに海外との学術交流を通じて行う。
(規 律)
第4条 この学会は、総会の決議により別途定める「一般社団法人日本地質学会倫理綱領」(以下「倫理綱領」という)の理念と規範に則り、公正かつ適正に会を運営し、前条の公益目的の達成と社会的信頼の維持・向上に努めるものとする。
(公 告)
第5条 この学会の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第2章 会 員
(種 別)
第6条 この学会の会員は次の3種とする。
(1)正会員 この学会の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この学会の目的に賛同し、この学会の事業を賛助するため入会した個人、法人および団体
(3)名誉会員 正会員の中から、地質学の発展に関する功績または学会への貢献が特に顕著な者で、
代議員総会(以下「総会」という)の決議をもって推薦された者
2 正会員は、この学会に対し「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「法人法」という)に定められた以下の社員の権利を社員と同様に行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4) 法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(5) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、法人法第250条第3項および法人法第256条第3項の権利(合併契約等の
閲覧等)
3 正会員は、代議員選出のための選挙権および被選挙権を持つ。
(入 会)
第7条 入会は、総会の決議により別途定める「一般社団法人日本地質学会運営規則」(以下「運営規則」という)に従い、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会 費)
第8条 運営規則に従い、会員は規定の会費を納入しなければならない。
2 会費は一定の割合を公益に資するものとし、その割合は総会の決議により定める運営規則に別途定める。
(会員の責務)
第9条 会員は学会の目的に従い、倫理綱領を遵守しなければならない。
(資格の喪失)
第10条 会員は、次の各号の一に該当する場合はその資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡、もしくは失踪宣告を受けたとき
(3)成年被後見人または被保佐人になったとき
(4) 法人および団体が解散したとき
(5)会費を滞納し、理事会の議決があったとき
(6)総会の決議により除名されたとき
(7) 全代議員の同意があったとき
(8)この学会が解散したとき
(退 会)
第11条 会員が退会しようとするときは、退会届を提出し、任意に退会することができる。
(除 名)
第12条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議により別途定める「一般社団法人日本地質学会除名規則」に基づき、理事会および総会における各々3分2以上に当たる多数の議決によりこれを除名することができる。
(1)会員としてこの学会の名誉を傷つけたとき
(2)学会の目的に違反する行為があったとき
(3)学会の倫理綱領に著しく抵触する行為があったとき
(4)その他の正当な事由があるとき
2 前項の各号に関し、事実確認に必要な手続きは別に定める。
3 第1項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利および義務)
第13条 会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、この学会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2 会員が第10条の規定によりその資格を喪失した場合、既納の会費はいかなる事由があっても返還しない。
第3章 代議員
(定 数)
第14条 この学会に100名以上220名以下の代議員をおく。代議員の数は総会の決議により定める「一般社団法人日本地質学会選挙規則」(以下「選挙規則」という)により別途定める。
(選 任)
第15条 代議員は、正会員による選挙により正会員の中から選出する。代議員をもって法人法における社員とする。
2 代議員は役員を兼ねることができない。
3 代議員の選挙は、選挙規則に基づいて行う。
4 代議員の欠員が生じた場合は、選挙規則に従い、速やかに欠員を補充する。
5 理事または理事会は代議員を選出することはできない。
(職務・権限)
第16条 代議員は社員として総会に出席し、総会での議決権を有するものとする。
(代議員の任期)
第17条 代議員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。総会の決議によってその任期を短縮すること、および再任を妨げない。
2 代議員が法人法に基づく、総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴えおよび役員解任の訴えを提起している場合には当該訴訟が解決するまでの間、当該代議員は社員としての地位を失わない。
3 欠員または増員により選任された代議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 代議員は、その辞任または任期満了後でも後任者が就任するまでは、その任務を行う。
(代議員の解任)
第18条 代議員が次の各号の一に該当するときは、理事会および総会の各々の3分の2以上に当たる多数の議決により、解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務に違反し、またはその職務を怠ったとき
(3)その他、代議員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(代議員の報酬)
第19条 代議員は無報酬とする。
第4章 総 会
(構 成)
第20条 この学会の総会は、すべての代議員をもって構成し、法人法に定める社員総会とする。
(権 限)
第21条 総会は、法人法に定める事項およびこの定款で定める事項を議決する。
(1) 役員の選任および解任、代議員の解任
(2) 役員等の報酬の額またはその規定
(3) 定款の変更
(4) 各事業年度の事業報告および計算書類等
(5) 各事業年度の事業計画および予算
(6) 会費等の金額
(7) 会員の除名
(8) 長期借入金ならびに重要な財産の処分および譲受け
(9) 役員等の損害賠償責任
(10) 解散および残余財産の処分
(11) 合併、事業の全部もしくは一部の譲渡または公益目的事業の全部の廃止
(12) 理事会において総会に付議した事項
2 前項にかかわらず定時および臨時総会においては、予め書面をもって通知した総会の目的以外の事項は、議決することができない。
3 第1項第10号に関し、総会は、剰余金の分配に関する決議をすることはできない。
(開 催)
第22条 定時総会は毎事業年度終了後、3ヵ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき
(2) 議決権の10分の1以上を有する代議員から、会議の目的である事項および招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき
3 前項第2号の請求をした代議員は、請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合、また、請求をした日から6週間以内の日を総会の日とする招集の通知が発せられない場合には、裁判所の許可を得て、総会を招集することができる。
(招 集)
第23条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただしすべての代議員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、開催日の2週間前までに役員および代議員に通知しなければならない。
4 代議員以外の正会員は理事会の決議により別途定める「一般社団法人日本地質学会理事会規則」(以下「理事会規則」という)に従い総会に陪席することができる。
(議 長)
第24条 総会の議長は、会議のつど、出席代議員の中から選出する。
(定足数)
第25条 総会は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席しなければ、議事を開き決議することができない。
(議決権)
第26条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決 議)
第27条 総会の決議は、法人法第49条第2項に規定する事項およびこの定款に特に規定するものを除き、出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権の代理・書面による行使)
第28条 やむを得ない理由のため総会に出席できない代議員は、予め通知された事項について、書面または電磁的方法により議決権を行使し、または他の代議員を代理人として議決権を行使することができる。この場合、代議員は出席したものとみなす。
2 理事または代議員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、代議員の全員が書面または電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の同意があったものとみなす。
(報告の省略)
第29条 理事が代議員の全員に対し、総会に報告すべき事項について予め通知した場合において、その事項を総会において報告することを要しないことにつき、代議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには、その報告が総会においてあったものとみなす。
(議事録)
第30条 総会の議事については法令の定めに従って議事録を作成しなければならない。
2 議事録は速やかに全会員に公開し、議決事項を知らせるものとする。
3 議事録は総会の日から10年間、主たる事務所に備え置く。
(総会規則)
第31条 総会の運営に関し必要な事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、総会において定める総会規則による。
第5章 役員等
(種類および定数)
第32条 この学会には、次の役員を置く。
(1)理事 40名以上60名以内
(2)監事 1名以上
2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、理事のうち2名を副会長とする。理事のうち15名以内を執行理事とし、そのうちの各1名を常務理事・副常務理事とする。
(選任等)
第33条 理事および監事は、総会の決議により別途定める選挙規則に基づき、代議員の選挙により選任する。
2 理事会は、理事会規則により会長1名、副会長2名、常務理事1名、副常務理事1名および執行理事を選任し、総会はこれを決議する。
3 監事は理事または使用人を兼ねることができない。
4 理事のいずれか1名とその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一団体の理事または使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 理事会は、前2項に関し、当該者間の特別な利益の授受および供与を禁止する。
7 この学会が公益社団法人及び公益財団法人認定法(以下「公益認定法」という)の規定に基づく公益認定を受けた場合において、理事または監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務・権限)
第34条 理事は理事会を構成し、法令およびこの定款の定めるところにより、理事会が決定したこの学会の業務を分担執行する。
2 会長はこの学会を代表し、業務の執行を統括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長の業務を分担執行する。
4 常務理事、副常務理事は会長、副会長を補佐しその他の執行理事とともに、この学会の業務を分担執行する。
5 理事および執行理事の権限は理事会が別に定める職務権限規定による。
6 会長、副会長、常務理事、副常務理事および前項の業務を執行する理事は、毎事業年度ごとに3ヵ月を超える間隔で3回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第35条 監事は、次の各号に規定する職務を行う。
(1)理事の職務執行の状況を監査すること
(2)学会の業務ならびに財産の状況を監査すること
(3) 総会および理事会に出席し、意見を述べること
(4)理事が不正の行為をし、もしくはその行為をする恐れがあると認めるとき、または法令もしくは
定款に違反する事実、もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会、総会に報告すること
(5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、請求のあった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられないときは、直接理事会を招集すること
(6)理事が総会に提案しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令もしくは定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること
(7) 理事が学会の目的範囲外の行為とその他法令もしくは定款に違反する行為をするおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること
(任 期)
第36条 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のときまでとし、総会の決議によってその任期を短縮すること、および再任を妨げない。
2 監事の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のと
きまでとし、再任を妨げない。
3 補欠または増員により選任された理事の任期は、前任者または在任者の残任期間とする。
4 補欠として選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。
5 役員は、その辞任または任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(解 任)
第37条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は3分の2以上に当たる多数の議決に基づいて行わなければならない。なお、議決する前に理事会および総会でその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務に違反し、またはその職務を怠ったとき
(3) その他、役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(報酬等)
第38条 役員は、有給とすることができる。
2 役員には、職務執行に要する費用の支払いをすることができる。
3 役員の報酬は、総会の決議により定め、支給方法等については別途定める「一般社団法人日本地質学会役員報酬規則」による。
(取引の制限)
第39条 理事が次にあげる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己または第三者のためにするこの学会の事業の部類に属する取引
(2) 自己または第三者のためにするこの学会との取引
(3) この学会がその理事の債務を保証すること、その他理事以外のものとの間におけるこの学会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取り扱いについては、第51条に定める理事会規則によるものとする。
(責任の免除または限定)
第40条 この学会は、法人法第111条第1項の役員の賠償責任については、法人法第112条の規定にかかわらず、総正会員の同意がなければ免除することができない。ただし、法令に定める要件に該当する場合には、理事会および総会で各々の3分の2以上に当たる多数の議決によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この学会は、外部役員との間で、前項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金50万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第6章 理事会
(構成)
第41条 この学会に理事会をおき、理事会はすべての理事をもって構成する。
(権限)
第42条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 総会の日時および場所ならびに目的事項の決定
(2) 規則の制定、変更および廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほかこの学会の業務執行の決定
(4) 理事および執行理事の職務の執行の監督
(5) 会長、副会長、常務理事、副常務理事および執行理事の選定および解職
2 理事会は、内部管理体制の整備および以下にあげる事項、その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。また、以下の事項については、理事会の議決を経て総会の議に付すものとする。
(1) 重要な財産の処分および譲り受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任および解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更および廃止
(5) 理事の職務の執行が、法令および定款に適合することを確認するための体制、その他この学会の業務の適正を確保するために必要な、法令で定める体制の整備
(6) 第40条第1項の責任の免除および同条第2項の責任限定契約の締結
3 業務の執行は、執行理事会がこれを行う。執行理事会については別に定める理事会規則によるものとする。
(開 催)
第43条 定例理事会は毎事業年度に3回以上開催する。また、次の各号の一に該当する場合は臨時理事会を開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 会長以外の理事から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4) 第35条第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき、または監事が招集したとき
(招 集)
第44条 理事会は会長が招集する。ただし、前条第3号により理事が招集する場合および第4号後段の監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第2号、4号前段または法人法第101条第2項に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法により、開催日の5日前までに各理事および各監事に対して通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事および監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
5 事前に傍聴を希望した会員は、理事会に陪席することができる。また、理事が必要とし会長が認め
る者を招聘することができる。
(議長)
第45条 理事会の議長は、執行理事以外の理事の互選により選出された理事がこれに当たる。
(定足数)
第46条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(議決)
第47条 理事会の議事はこの定款に定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第48条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることができる理事の全員が、書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第49条 理事または監事が理事または監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、法人法第91条第2項の規定による報告についてはこの限りではない。
(議事録)
第50条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事および監事は、これに署名しなければならない。
(理事会規則)
第51条 理事会に関する事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、理事会規則による。
第7章 財産および会計
(事業年度)
第52条 この学会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(基本財産の維持および処分)
第53条 第3条第2項の事業を行うために学会は基本財産を設け、その適正な維持および管理に務めるものとする。
2 やむを得ない理由により、基本財産の全部もしくは一部を処分または担保に提供する場合は、理事会において議決に加わることのできる理事の3分の2以上に当たる多数の議決を経て、総会の議事に付す。
3 基本財産の維持および処分について必要な事項は、理事会の決議により別に定める「一般社団法人日本地質学会財産管理運用規則」(以下「財産管理運用規則」という)によるものとする。
(財産の管理・運用)
第54条 この学会の財産の管理・運用は会長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める財産管理運用規則によるものとする。
(事業計画および予算)
第55条 この学会の事業計画および予算、資金調達および設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て直近の総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じて実施することができる。
3 前項により実施されたものは、新たに成立した予算とみなす。
4 第1項の書類については、当該事業年度終了まで主たる事務所および従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供する。なお、この学会が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合においては、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(事業報告および計算)
第56条 この学会の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得たうえで、定時総会に報告しなければならない。ただし、第3号から第6号までの書類について、法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時総会への報告に代えて総会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の計算書類のほかに、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供する。また、定款を主たる事務所および従たる事務所に、代議員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告書。
(2)理事および監事の名簿
(3) 理事および監事の報酬等の支給の基準を記載した書類(役員報酬規則)
(4) 運営組織ならびに事業活動の状況の概要およびこれらに関する数値のうち、重要なものを記載した書類
(5) その他法令で定める帳簿および書類
3 前項各号の帳簿および書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第69条第2項の定めによ
るものとする。
4 第1項の定時総会終了後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
(公益目的取得財産額の算定)
第57条 会長は、公益認定法に関する施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度の末日における当該事業年度の公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
(長期借入金および重要な財産の処分または譲受け)
第58条 資金借り入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。
2 重要な財産の処分または譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
(会計原則)
第59条 この学会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
第8章 定款の変更、合併および解散等
(定款の変更)
第60条 この定款は第63条の規定を除き、総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
2 この学会が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合においては、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届けなければならない。
(合併等)
第61条 総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上による多数の議決により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部または一部の譲渡および公益目的事業の全部を廃止することができる。
2 なお、この学会が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合においては、前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解 散)
第62条 この学会は法人法第148条第1号および第2号ならびに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決により解散することができる。
(公益認定等の取り消し等に伴う贈与)
第63条 この学会が公益認定の取り消しの処分を受けた場合、または、合併により消滅する場合には、(その権利義務を継承する団体が公益法人の場合を除いて)総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、1ヵ月以内にこの学会と類似の事業を目的とする公益法人または国、もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第64条 この学会が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の議決により、この学会と類似の事業を目的とする他の公益法人または国、もしくは地方公共団体に寄付するものとし、分配は行わない。
第9章 専門部会・研究委員会・委員会
(専門部会)
第65条 理事会はこの学会の事業を推進するために理事会規則により、専門部会を設置することができる。
(研究委員会)
第66条 理事会は、会員の要請により地質学およびこれに関連する諸科学の特定課題を研究するために、理事会規則により研究委員会を設置することができる。
(委員会)
第67条 理事会は、この学会の事業を推進するために必要あるときは、理事会規則により委員会を設置することができる
第10章 事務局
(設置)
第68条 この学会の事務を処理するため、事務局および所要な事務局職員を置く。
2 事務局職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。
3 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
第11章 情報公開および個人情報の保護
(情報公開)
第69条 この学会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
(個人情報の保護)
第70条 この学会は業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
第12章 附 則
(委 任)
第71条 この学会の運営に必要な事項は、この定款に定めるほか、理事会の議決により別に定める。
(最初の事業年度)
第72条 この学会の設立初年度の事業計画および予算は第55条に関わらず、設立総会の定めるところによる。
2 この学会の設立初年度の事業年度は、この学会の成立の日から2009年3月31日までとする。
(設立時社員の氏名等)
第73条 この学会の設立時社員の氏名、住所は次のとおりである。—住所記載せず—
井龍康文 上砂正一 倉本真一 齋藤 眞 坂口有人 高木秀雄 藤本光一郎 宮下純夫矢島道子 渡部芳夫
(設立時役員の氏名等)
第74条 この学会の設立時理事・監事および代表理事は次のとおりである。
石渡 明 井龍康文 岩森 光 上砂正一 倉本真一 小嶋 智 齋藤 眞 坂口有人 高木秀雄 佃 栄吉 久田健一郎 藤林紀枝 藤本光一郎 宮下純夫 向山 栄 矢島道子 渡部芳夫 足立勝治 阿部國廣 荒戸裕之 安藤寿男 磯粼行雄 伊藤谷生 卜部厚志 永広昌之 大友幸子 岡 孝雄 小山内康人 狩野謙一 川端清司 北里 洋 木村 学 公文富士夫 紺谷吉弘 佐々木和彦 沢田順弘 柴 正博 芝川明義 高橋正樹 滝田良基 中川光弘 新妻信明 保柳康一 堀 利栄 松岡 篤 松原典孝 三宅康幸 村山雅史 山路 敦 山根 誠 吉川敏之 脇田浩二 渡辺真人
山本正司(監事)
宮下純夫(代表理事)
(法令の準拠)
第75条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法、その他の法令に従う。
支部・専門部会 目次
日本地質学会各支部
各支部名をクリックすると各支部の情報がご覧いただけます.
(2025年6月4日現在)
北海道支部(北海道)
所在地:北海道大学大学院理学研究院地球惑星科学部門 気付(幹事:池田雅志)
支部長: 沢田 健(北海道大学)
東北支部(青森,秋田,岩手,山形,宮城,福島)
所在地:山形大学 気付(幹事:岩田尚能)
支部長:本山 功(山形大学)
関東支部(茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川)
所在地:日本地質学会事務局 気付(幹事:加藤 潔)
支部長:久田健一郎(NPO法人地学オリンピック日本委員会)
中部支部(新潟,長野,山梨,静岡,富山,石川,岐阜,愛知,福井)
所在地:名古屋大学大学院環境学研究科 気付(幹事:高橋 聡)
支部長: 道林克禎(名古屋大学)
近畿支部(滋賀,奈良,京都,三重,大阪,和歌山,兵庫)
所在地:滋賀県立琵琶湖博物館 気付(幹事:里口保文)
支部長:和田穣隆(奈良教育大学)
四国支部(徳島,香川,高知,愛媛)
所在地:徳島大学 気付(幹事:安間 了)
支部長:寺林 優(香川大学)
西日本支部(岡山,広島,鳥取,島根,山口,福岡,熊本,長崎,佐賀,大分,宮崎,鹿児島,沖縄)
所在地:九州大学理学研究院 地球惑星科学部門 気付(幹事:尾上哲治)
支部長:山本啓司(鹿児島大学)
中部支部
中部支部
▶︎中部支部(過去の活動)はこちらから
最近の活動
2025年支部年会(静岡)開催報告 NEW
2025年支部年会開催のお知らせ
報告 日本地質学会中部支部2024年支部年会
日本地質学会中部支部2024年支部年会
応用地質学会中部支部 令和6年度講演会のご案内
報 告
2025.7.8掲載
中部支部2025年支部年会(静岡)開催報告
中部支部2025年年会(静岡)報告 2025年6月21日(土)に,静岡大学静岡キャンパスにて,中部支部総会および研究発表会(シンポジウム,一般講演)を開催し,6月22日(日)に瀬戸川帯南部の超塩基性-塩基性岩類の産状を視察する巡検を行った.以下にその内容を報告する.(共催:日本応用地質学会中部支部;後援:静岡大学)
2025年6月21日(土)
1.総会(参加者20名,議決権行使書提出者33名,委任状提出者3名で,定足数24名で総会は成立)
1号議案:2024年の支部活動報告・支部基金の会計監査報告がなされ承認された.
2号議案:中部支部年会の非会員研究発表会講演資格について,非会員の筆頭による研究発表は,日本地質学会会員と共同発表の場合のみ認めることが承認された.
3号議案:2026年度支部年会は新潟県で開催することが承認された.
2.研究発表会(参加者計 44名:正会員 28名,学生会員 16名,非会員 24名)
講演要旨PDFはこちらからDLできます
2-1.シンポジウム『マントル物質研究の最前線』 13:00–16:00
趣旨:地球内部の主要な構成層であるマントルは,地球表層から深部に至るダイナミクスを支える領域である.マントル物質の化学組成や物性,流体との相互作用を理解することは,対流や物質移動のメカニズムを理解する上で欠かせない知見をもたらす.近年,高圧実験やオフィオライト・高圧変成岩類から得られるデータの蓄積が進み,マントル物質研究は飛躍的に進展している.本シンポジウムでは,「マントル物質研究の最前線」をテーマに掲げ,岩石学・地球化学・構造地質学などの分野から最先端の成果を取り上げる.これにより,マントル内部における物質循環や動的プロセスの最新知見を共有するとともに,異分野間の対話を通じて統合的な理解の深化と新たな研究の展開を目指す.
趣旨説明 平内健一(静岡大学)
S-1 島弧超苦鉄質岩捕獲岩の岩石学的比較:ルソン火山弧の例 森下知晃(金沢大)
S-2 幌満かんらん岩の縞状かんらん岩・輝岩が記録するマントルの変形とメルト-岩石相互作用 田阪美樹(静岡大)
S-3 沈み込み帯におけるマントル岩石−スラブ流体相互作用 大柳良介(国士舘大)
S-4 超苦鉄質岩中のアクセサリー鉱物とマントル研究 沢田輝(富山大) マントル物質研究に関する座談会
2-2.一般講演(口頭発表)
4名の会員が口頭発表を行った.
2-3.一般講演(ポスター発表) コアタイム 16:30–17:30
計14件の多様な内容のポスター発表(P-1〜P-14)がなされた.
以下の学生会員による発表を優秀発表賞として表彰された.
外山和也, 出口琢磨,宮田佳奈,徳川聡,二村康平,延原香穂,松本拓己,上山拓馬,原田藍生,塚脇遼,檜垣悠斗,窪田虎太朗 (順不同 敬省略)
2025年6月22日(日)
3.巡検:瀬戸川帯南部の超塩基性-塩基性岩類の産状
3-1.内容:静岡県中・南部,四万十付加体南帯に属する瀬戸川帯の南部に分布する超塩基性-塩基性岩複合岩体の産状と,その周辺の地層との関連性についての観察を主目的とした一日コースの巡検を実施した.参加者数は32名であった.
3-2.案内者:狩野謙一(静岡大)・諸橋良(ふじのくに防災フェロー)・平内健一(静岡大)
3-3.行程
09:10藤枝駅北口集合
09:30藤枝総合運動場・第2駐車場
10:30〜11:30 藤枝市瀬戸ノ谷石谷山,ビク石(塩基性-超塩基性岩体)および蛇紋岩
12:30〜14:30 島田市千葉山,南西尾根“スカイペンションどうだん”周辺の瀬戸川帯滝沢衝上体の超塩基性‒ 塩基性複合岩類
15:00〜15:30 島田市牛尾,大井川右岸河床に露出する瀬戸川帯メランジュ
16:00〜16:20 島田市金谷牧之原公園,牧之原台地の地質環境
16:30 金谷駅 解散
17:00 藤枝総合運動場・第2駐車場 解散
※CPD参加証明書:研究発表会及び巡検に参加した7名の技術士の方々にCPD参加証明書を発行した.
お知らせ
2025.2.7掲載 4.22,6.11,6.16更新
日本地質学会中部支部2025年支部年会開催のお知らせ
日本地質学会中部支部では下記のとおり2025年支部年会を開催します.あわせて研究発表会(シンポジウム,一般講演),懇親会,および巡検を行いますので,皆様ぜひご参加をご検討くださいください.
会場:静岡大学静岡キャンパス
日付:2025年6月21日(土),6月22日(日)
参加要件:日本地質学会会員または日本応用地質学会員であること.
参加登録方法:参加登録のウェブサイト(https://forms.gle/zUSJ3kiC5mH8K34V8)にご記入下さい(ログインにはGoogleアカウントが必要となります).
プログラム・講演要旨集のダウンロードはこちら NEW 6.16
スケジュール予定:
6月21日(土)
受付開始 10:45
幹事会 11:00〜12:00
総会 12:00〜12:30
研究発表会 ※シンポジウム 13:00〜15:20 ※一般講演(口頭発表) 15:30〜16:30 ※ポスターコアタイム 16:30〜17:30
懇親会 17:45〜19:30
6月22日(日)
巡 検 9:00〜17:00
研究発表会予告:
※シンポジウム『マントル物質研究の最前線』
趣旨:地球内部の主要な構成層であるマントルは,地球表層から深部に至るダイナミクスを支える領域である.マントル物質の化学組成や物性,流体との相互作用を理解することは,対流や物質移動のメカニズムを理解する上で欠かせない知見をもたらす.近年,高圧実験やオフィオライト・高圧変成岩類から得られるデータの蓄積が進み,マントル物質研究は飛躍的に進展している.本シンポジウムでは,「マントル物質研究の最前線」をテーマに掲げ,岩石学・地球化学・構造地質学などの分野から最先端の成果を取り上げる.これにより,マントル内部における物質循環や動的プロセスの最新知見を共有するとともに,異分野間の対話を通じて統合的な理解の深化と新たな研究の展開を目指す.
13:00〜13:05 趣旨説明 平内健一(静岡大学)
S-1 13:05〜13:35 島弧超苦鉄質岩捕獲岩の岩石学的比較:ルソン火山弧の例 森下知晃(金沢大)
S-2 13:35〜14:05 幌満かんらん岩の縞状かんらん岩・輝岩が記録するマントルの変形とメルト-岩石相互作用 田阪美樹(静岡大)
S-3 14:05〜14:35 沈み込み帯におけるマントル岩石−スラブ流体相互作用 大柳良介(国士舘大)
S-4 14:35〜15:05 超苦鉄質岩中のアクセサリー鉱物とマントル研究 沢田輝(富山大)
15:05〜15:20 マントル物質研究に関する座談会 森下+平内
会場:静岡大学静岡キャンパス
参加費:1,000円(総会のみは無料,大学院生・学部生は無料)
参加要件:日本地質学会会員または日本応用地質学会会員であること.
参加登録:5月30日(金)までにgoogle forms(https://forms.gle/zUSJ3kiC5mH8K34V8)を通じて行ってください.google formsにログインするには,Googleアカウントが必要です.
※一般講演(口頭発表:15:30〜16:30)
一般講演については,最大4件程度を受け付けます.受付順となりますので,発表を希望される方は早めに登録をお願いいたします.
口頭発表は,対面のみで行い,各講演15分を予定しています(発表12分,質疑応答3分).
O-1 15:00〜15:45 Crは熱水で移動するか? 荒井章司(金沢大)
O-2 15:45〜16:00 北部フォッサマグナ中〜南部の中期中新世〜第四紀にかけてのテクトニクスの再検討 狩野謙一(静岡大)・宮坂晃(長野県)
O-3 16:00〜16:15 和歌山三波川帯藍閃石マイクロブーディンを用いた応力・歪解析 外山和也・道林克禎(名古屋大)
O-4 16:15〜16:30 足尾帯南西部に分布する白亜紀花崗岩類のジルコンU–Pb年代 出口琢磨(信州大)
※一般講演(ポスター発表:コアタイム16:30〜17:30)
ポスター掲示時間:10:30〜17:30
ポスターボードのサイズ:縦175 cm,横115 cm
学生・院生の一般講演(口頭発表・ポスターとも)は優秀発表賞の審査の対象となりますので,ふるってご参加ください.
P-1 紀伊半島東部, 美杉地域南部における領家深成岩類の火成活動とマイロナイト化 檜垣悠斗・竹内誠・淺原良浩(名古屋大)
P-2 通信調査に基づく1891年濃尾地震による北陸地方の液状化現象 青島晃(ふじのくに地球環境史ミュージアム)
P-3 中部地方天竜地域三波川帯結晶片岩を用いた微細構造解析 原田藍生・纐纈佑衣・道林克禎(名古屋大)
P-4 火山前線直下のマントル変形: アバチャ火山かんらん岩捕獲岩からの検討 上山拓馬・田阪美樹(静岡大)
P-5 天竜三波川変成帯の石英片岩に含まれるアルバイト・スポットに記録される塩水の浸透 松本拓己・田阪美樹・川本竜彦(静岡大)
P-6 前期三畳紀パンサラッサ遠洋深海堆積岩から産する有機質微化石 山田 翔大・高橋 聡・纐纈 佑衣・市村 駿汰・松井 和己・渋谷 知美・林 誠司(名古屋大)
P-7 接触変成域・超苦鉄質岩類中の変成反応と流体挙動:長野県伊那地域・三波川帯の例 延原香穂・森宏・築島由理恵(信州大)・永冶方敬(早稲田大)・新屋貴史(信州大)・早川由帆(中央開発株式会社)・山岡健(産業技術総合研究所)
P-8 石英を含むオキサイドガブロの変形メカニズム 二村康平・道林克禎(名古屋大)
P-9 三波川帯 金崎蛇紋岩体の蛇灰岩の組織記載 徳川聡・沢田輝(富山大)
P-10 南部マリアナ前弧海嶺かんらん岩の岩石学的特徴とその成因 宮田佳奈・道林克禎(名古屋大)・上原茂樹(静岡大)・小原泰彦(海上保安庁)
P-11 渡島大島火山のピクライト玄武岩のかんらん石捕獲結晶内部のマントルメルト/流体の情報 塚脇遼(信州大)・江島輝美(信州大)・二ノ宮淳(住鉱資源開発)・角野浩史(東京大)・荒井章司(金沢大)
P-12 野母半島長崎変成岩類における緑泥石-アクチノ閃石片岩の変形機構 窪田虎太朗・平内健一(静岡大)
P-13 日高帯 幌満かんらん岩体の動的再結晶組織 水上知行・山崎珠実・岡島由依(金沢大)
P-14 岡県西部の下部白亜系伊平層産の植物化石相 ルグラン ジュリアン・西鼻聖人(静岡大)・山田敏弘(北海道大)
講演要旨:
研究発表会に申し込まれる方は,上記のgoogle forms上に講演要旨をアップロードしてください.締切は参加登録期限と同じ5月30日(金)とさせていただきます.
講演要旨は,google formsから「中部支部年会_講演要旨フォーマット.docx」をダウンロードした上,作成して下さい.
講演要旨は日本地質学会のウェブサイトで公開し,引用できるようにする予定です.公開する際には,二重投稿や著作権侵害とならぬよう,内容についてご相談することがございます.
講演要旨はA4縦版,2頁までとします.詳しい様式は,「要旨フォーマット.docx」に記載されています.
お送り頂いたメール原稿をそのままの形で印刷する予定です.
問合せ先:平内健一(静岡大学)hirauchi.kenichi@shizuoka.ac.jp
CPD:地質技術者への継続教育の一環として,大会参加者・発表者へCPD単位を発行します.大会参加と口頭発表の参加証明書は,参加日以降にメールにて送付予定です.
【CPD単位】
一般講演:5×発表時間(h)例)15分の場合:5×1/4 h=1.25単位
研究発表会参加:1×滞在時間
懇親会(17:45〜19:30)
懇親会は静岡大学生協(第1食堂)で行います.懇親会費は一般5500円,大学院生・学部生は3000円となります.
巡検『瀬戸川帯南部の超塩基性-塩基性岩類の産状』
日時:6月22日(日)9:00〜17:00(予定)
内容:瀬戸川帯南部の超塩基性-塩基性岩類の産状
案内者:狩野謙一(静岡大学防災総合センター)・諸橋 良(ふじのくに防災フェロー)・平内健一(静岡大学理学部)
問合せ先:平内健一(静岡大学)hirauchi.kenichi[at]shizuoka.ac.jp
参加費:1人4,500円
定員:25名程度(受付順).参加者が15名以下の場合は,キャンセルすることもあります.
集合・解散場所:JR利用者は藤枝駅北口集合,金谷駅解散.自家用車利用者は藤枝総合運動場・第2駐車場.
上記のどちらの集合場所を希望されるか,事前に平内までメールでお知らせ下さい.
参加者の動向(JR利用または車で合流*)によっては,変更する場合があります.
*巡検中は自家用車の使用不可,マイクロバスで移動します.
*昼食は各自お弁当等をご準備願います.
*参加希望者は上記のgoogle formsにて5月30日(金)までに参加登録をしてください.
報告
2024.7.23掲載
中部支部2024年年会(富山)報告
中部支部2024年年会(富山)報告 2024年6月22日(土)に,富山大学五福キャンパスにて,中部支部総会および研究発表会(シンポジウム,一般講演)を開催し,6月23日(日)に能登半島地震に伴う地変を視察する巡検を行った.以下にその内容を報告する.(共催:日本応用地質学会中部支部;後援:立山黒部ジオパーク協会,富山応用地質研究会)
2024年6月22日(土)
1.総会(参加者22名,議決権行使書提出者14名,委任状提出者27名で,定足数25名で総会は成立)
1号議案:2023年の支部活動報告・支部基金の会計監査報告がなされ承認された.
2号議案:中部支部研究発表会の講演要旨をWEB上で公開することと引用可にすることが承認された.
3号議案:2024-2025年度道林克禎支部長,林誠司幹事が再任され,各県幹事等が承認された.
4号議案:2024年度中部支部基金予算案が承認された.
5号議案:2025年度支部年会は静岡県で開催することが承認された.
2.研究発表会(参加者計 76名:正会員 40名,学生会員 12名,非会員 24名)
講演要旨PDFはこちらからDLできます
2-1.シンポジウム『令和6(2024)年能登半島地震とその被害』 13:00–16:00
趣旨:令和6年能登半島地震では,大規模な海岸隆起や斜面崩壊などが発生し,能登半島北部から中部を中心に大きな被害がもたらされた.また,石川,富山,新潟などでは液状化による被害,日本海沿岸の広い範囲では津波による被害を受けた.本シンポジウムでは,地震発生以降,緊急調査や救援活動などを行なっている5名の専門家から現地の状況等を紹介いただき(各25分),その後の総合討論と併せて能登半島地震の特徴や被害の状況について知る機会とした.
※安江健一(富山大):趣旨説明
S-1.平松良浩(金沢大):能登半島の地震活動と令和6年能登半島地震
S-2.石山達也(東京大):能登半島周辺の活構造と地殻構造
S-3.塚脇真二(金沢大):令和6年能登半島地震の土砂災害とその応用地質学的な特徴 〜とくに地質遺産の被災状況について〜
S-4.呉 修一(富山県立大):令和6年能登半島地震による富山沿岸部の津波調査・解析報告
S-5.立石 良(富山大):水中ドローンを用いた2024年能登半島地震に伴う富山湾内の海底地すべり調査
※総合討論
2-2.一般講演(口頭発表) 16:10–16:40
2名の会員が,令和6年能登半島地震に関わる口頭発表(O-1〜O-2)を行った.
2-3.一般講演(ポスター発表) コアタイム 16:45–17:45
計18件の多様な内容のポスター発表(P-1〜P-18)がなされた.学生会員6名(松粼茜氏,松山和樹氏,大嶋俊介氏,奥脇健生氏,井上 創氏,及び荻野俊右氏)に,中部支部長より発表賞が授与された.
2024年6月23日(日)
3.巡検:能登半島地震に伴う地変の視察
3-1.内容:富山市から石川県輪島市門前町(能登半島西岸)までのルートで,令和6年能登半島地震に伴う地変と地質露頭の現状を視察した.参加者数38名.ほぼ一日中雨模様であったが,鹿磯漁港で短時間雨が上がり,集合写真を撮ることができた.
3-2.案内者:安江健一・立石 良・大藤 茂(富山大)
3-3.行程
7:45 富山駅北口集合---8:00 富山駅北口出発---8:50〜9:10 富山県氷見市内で液状化による道路や家屋の被害状況を視察---9:10〜10:30 能越自動車道の被害状況を視察しながら,能登半島西岸,石川県羽咋郡志賀町富来領家町へ移動---10:45〜10:55 道の駅「とぎ海街道」で休憩---11:20〜11:35 門前町琴ヶ浜で黒島火山岩類(約8Ma)の崩落現場と海底の隆起を視察---11:50〜12:10 門前町黒島漁港で海底の隆起を視察---12:15〜12:35 道の駅「赤神」で昼食---12:45〜13:10 門前町鹿磯漁港で海底の隆起を視察---13:10〜15:00 邑知低地帯を経由して氷見へ---15:00〜15:20 道の駅「氷見(番屋街)」で休憩---16:15 富山駅北口で参加者の一部下車---16:30 富山大学五福キャンパスで解散
鹿磯漁港での集合写真(2024.6.23 12:55)
2024年7月10日(水)
※CPD参加証明書:研究発表会及び巡検に参加した16名の技術士の方々にCPD参加証明書を発行した.
ご案内
2024.4.22掲載 4.30, 5.15,5.31追加
日本地質学会中部支部2024年支部年会開催のお知らせ
追加情報(5/31追加)
後援団体の追加
巡検の定員到達とキャンセル待ちについて
CPD単位の発行項目の追加
追加情報(5/15追加)
後援団体の追加
JpGUの大会予稿の転載について
ポスターボードのサイズについて
巡検の申込状況
日本地質学会中部支部では下記のとおり2024年支部年会を開催します.あわせて研究発表会(シンポジウム,一般講演),懇親会,および巡検を行いますので,皆様ぜひご参加ください.
共催:日本応用地質学会中部支部,後援:立山黒部ジオパーク協会・富山応用地質研究会
日時:2024年6月22日(土)・23日(日)
6月22日(土)
受付開始10:30
総会 11:00〜11:30
幹事会 11:30〜12:30
研究発表会(※シンポジウム 13:00〜15:30/※口頭発表 15:40〜16:40/※ポスターコアタイム 16:45〜17:45)
懇親会 18:00〜20:00
6月23日(日)
巡検 8:00〜16:30
研究発表会
会場:富山大学五福キャンパス
参加費:2000円(総会のみは無料,大学院生・学部生は1000円 参加者数が多い場合は値下げを検討します)
事前登録:6月13日(木)までにgoogle forms(https://forms.gle/xf9RJgkNPkfo1v1B9)にて参加登録・発表申し込みをしてください.巡検(6月23日)に参加する方は5月31日(金)までに登録してください(後述).
※シンポジウム『令和6年能登半島地震とその被害』13:00-15:30
趣旨:令和6年能登半島地震では,大規模な海岸隆起や斜面崩壊などが発生し,能登半島北部から中部を中心に大きな被害がもたらされた.また,石川,富山,新潟などでは液状化による被害,日本海沿岸の広い範囲では津波による被害を受けた.本シンポジウムでは,地震発生以降,緊急調査や救援活動などを行なっている専門家から現地の状況等を紹介いただき,能登半島地震の特徴や被害の状況について知る機会とする.
安江健一(富山大学):趣旨説明
平松良浩(金沢大学):能登半島の地震活動と令和6年能登半島地震
石山達也(東京大学):能登半島周辺の活構造と地殻構造
塚脇真二(金沢大学):令和6年能登半島地震の土砂災害とその応用地質学的な特徴 〜とくに地質遺産の被災状況について〜
呉 修一(富山県立大学):令和6年能登半島地震による富山沿岸部の津波調査・解析報告
立石 良(富山大学):水中ドローンを用いた2024年能登半島地震に伴う富山湾内の海底地すべり調査
総合討論
※一般講演(口頭発表)15:40〜16:40
最大4件を受け付けます.先着順ですので,希望される方は早めに上記事前登録フォームにて,発表者氏名と発表タイトルを入力してください.
口頭発表は,対面のみで行い,各講演15分を予定しています(発表12分,質疑応答3分).
※一般講演(ポスター発表)コアタイム16:45〜17:45
ポスターは10:30〜17:45の間掲示することができます.ポスター発表希望者は上記事前登録フォームにて,発表者氏名と発表タイトルを入力してください.
学生・院生の一般講演(口頭発表・ポスターとも)は優秀発表賞の審査の対象となりますので,ふるってご参加ください.
講演要旨:
一般講演(口頭・ポスター共)に申し込まれる方は上記の事前登録フォームに申し込みの上,講演要旨を,なるべくMS-Word形式の電子ファイルで安江(toyama-geo@sus.u-toyama.ac.jp)へメール添付にて送付願います.締切は6月16日(日)です.
講演要旨は日本地質学会のウェブサイトで公開し,引用できるようにする予定です.公開する際には,二重投稿や著作権侵害とならぬよう,内容についてご相談することがございます.
JpGUの大会予稿は,転載許可申請をすれば,本会の講演要旨にその全文または一部を転載できます.講演要旨の送付時に安江までご相談ください.
一般講演の講演要旨はA4版,2頁までとします.
要旨の様式は下記書式に沿ってください.お送り頂いたメール原稿をそのままの形で印刷する予定です.フォントは游明朝で統一してください.
上下余白:3 cm 左右余白:2.5 cm
タイトル:14 p(ポイント)太文字
発表者・所属機関:12 p
英文タイトル:12 p
本文は1行開けて始めてください.
本文:10.5 p
引用文献:9 p
図表は枠内に収めてください.
英文原稿の場合は,上記に準じてください.
ポスター:ポスターボードのサイズは,幅120cm・高さ180cmです.(ご要望がありましたら,安江までご連絡ください.)
CPD
地質技術者への継続教育の一環として,大会参加者・発表者・巡検参加者へCPD単位を発行します.参加証明書は,参加日以降にメールにて送付予定です.
【CPD単位】
一般講演(口頭発表):5×発表時間(h)例)15分の場合:5×1/4 h=1.25単位
一般講演(ポスター発表):5×コアタイム時間(h)例)60分の場合:5×1h=5単位
研究発表会参加:1×滞在時間
巡検:1×受講時間(h)例)日帰り8時間程度の場合=8単位
懇親会(18:00〜20:00)
懇親会を富山大学五福キャンパス内で行う予定です.懇親会費は一般5000円,大学院生・学部生は3000円を予定しています.
巡検:能登半島地震に伴う地変の視察(共催:日本応用地質学会中部支部)
日時:6月23日(日)8:00〜16:30(予定)
内容:富山市から石川県輪島市門前町(能登半島西岸)までのルートで,令和6年能登半島地震に伴う地変と地質露頭の現状を視察する.
案内者:安江健一・立石 良(富山大学)
問合せ:安江健一(富山大学)toyama-geo[at]sus.u-toyama.ac.jp ※[at]を@マークにして送信してください
参加費:1人5,000円程度(参加人数によって若干の変更があります)
大まかな予定は,8:00富山駅北口→巡検(貸切バス)→16:30富山駅です.
昼食は各自ご準備願います.
参加希望者はgoogle forms (https://forms.gle/xf9RJgkNPkfo1v1B9)にて5月31日(金)までに参加登録をしてください.
定員:27名→37名(先着順受付)
※参加希望者多数により定員を増加しましたが,増加した定員にも達しました.キャンセル待ちをご希望の方は,google forms(https://forms.gle/xf9RJgkNPkfo1v1B9)へご登録ください.
【旅行企画・実施】中部観光株式会社 観光庁長官登録旅行業 第1884号
ご案内
2024.4.19掲載
応用地質学会中部支部 令和6年度講演会のご案内
地質学会中部支部と提携しております応用地質学会中部支部より, イベントの案内を頂きました. ご興味のある方は,是非ご参加ください.よろしくお願いします.
詳細はこちらかもご覧いただけます
会場:名城大学天白キャンパス R2-261(多目的室)
※Zoomによるオンラインとの併用開催
日時:令和6年5月22日(水)
14:30〜15:45:講演会
15:50〜16:50:能登半島地震災害調査報告会
17:00〜:意見交換会(名城大学生協施設「グラン亭」)
演題: 『流体が駆動する能登半島北東部の群発地震と令和6年能登半島地震』
金沢大学理工研究域地球社会基盤学系 教授 平松 良浩様 (※Webで講演予定)
CPD:2.25h予定 (希望者に証明書を発行します)
参加費 :無料
意見交換会:4000円 ※参加費のお支払いは当日会場受付時にお願いいたします。
申込方法:以下のWebフォームよりお申し込みをお願いいたします。
https://forms.gle/asnRjqk3rKjHsoSN8
※日本応用地質学会 中部支部会員の方は、13:30から開催される総会の参加可否確認のため、 別途ご案内したご連絡フォームよりお申込みください。
申込締切日:令和6年5月7日(火)
問い合わせ先:サンコーコンサルタント(株)名古屋支店
日本応用地質学会 中部支部事務局 赤嶺
Email: jges7chubu[at]gmail.com ※[at]を@マークにして送信してください.
TEL:052-228-6132 FAX:052-223-6238
Geo暦(2007)
2007年Geo暦(行事カレンダー)
2009年版
2008年版
2007年版 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
※ マークは学会主催の行事です.
1月January
第17回大気化学シンポジウム
1月10日(水)〜12日(金)
場所:豊川市民プラザ(TEL: 0533-80-5122)
http://www.geochem.jp/index.html
1月26日(金)15-17時
テーマ:「ミューズ・セラピー(Muse therapy)」
講 師: 足立 守 氏(名古屋大学博物館教授)
場 所:深田地質研究所 研修ホール
参加費:無料
2月February
日本古生物学会第156回例会
2月2日(金)〜2月4日(日)
会場:徳島県立博物館
http://ammo.kueps.kyoto-u.ac.jp./palaeont/
第3回 GUPI GEOFORUM『地域観光資源とビジタ−産業』
2月3日(土)10:30受付開始
会場 東洋大学白山校舎
http://www.gupi.jp/forum/2006/forum03.htm
*
西日本支部2006年度総会および第153回例会
2007年2月10日(土)
会場 山口大学大学会館(吉田キャンパス)
http://geosociety.jp/branch/west/index.html
第98回 深田研談話会
2月 23日(金)15-17時
テーマ:「マグマの動きをとらえる−富士山、三宅島、小笠原硫黄島」
講 師:鵜川元雄 氏 (防災科学技術研究所)
場 所:深田地質研究所 研修ホール
参加費:無料
3月March
海洋研究開発機構「ブルーアース 07」
3月8日(木)〜9日(金)
会場:パシフィコ横浜 会議センター
詳細はこちら
*
東北支部総会・例会のご案内
3月17日(土)〜18日(日)
会場:秋田大学(秋田市手形学園町)
講演申込締切:2月15日(水)
詳しくはこちら→
第41回日本水環境学会年会
3月15日(木)〜17日(土)
場所:大阪産業大学
http://www.jswe.or.jp/index.html
Second International Conference on the Geology of the Tethys
3月19〜23日
場所:Cairo University
Correspondence: Prof. El Sayed Abd El Aziz Aly Youssef
Geology Department, Faculty of Science, Cairo University, Giza, Egypt
Fax: 002-02-5728843 Tel.: 002-02-5676887,002-012 2926034
E-mail:elsayedyoussef2005@yahoo.com, elsayedyoussef@hotmail.com
詳しくはこちらまで.
*
日本地質学会 構造地質部会 春の例会
2007年3月16日(金)〜18日(日)
場所:和歌山県白浜町 ホテルベイリリー
参加申し込みおよび講演題目締切:2006年12月20日
講演要旨締切:2007年2月10日
詳細は,構造地質部会HPへ
日本地理学会2007年春季学術大会
3月20日(火)〜22日(木)
(ただし総会・代議員会は19日)
場所:東洋大学
問い合わせ先:渡辺満久(東洋大学)
電話 03-3945-8288
http://wwwsoc.nii.ac.jp/ajg/home_J.html
日本堆積学会2007年つくば例会
2007年3月27日(火)〜 31日(土)
会場 つくばカピオ(茨城県つくば市)
http://sediment.jp/
4月April
5月May
日本地球惑星科学連合2007年大会
5月19日(土)〜24日(木)
会場 幕張メッセ国際会議場
http://www.jpgu.org/
*
日本地質学会第114年総会(2007年度代議員総会)
5月20日(日)17:00-19:00
会場 幕張メッセ(地球惑星連合大会内)
詳細はこちら
宇宙技術による防災に関するシンポジウム
5月23日(水)10:00〜16:30
場所:イタリア文化会館(東京都千代田区九段南2−1−30)
詳しくはこちら
日本地下水学会2007年春季講演会
5月26日(土)
会場 千葉大学松戸キャンパス
http://www.groundwater.jp/jagh/
6月June
*
西日本支部例会
6月2日(土)
会場:長崎大学総合教育研究棟2階多目的ホール
講演申込期限:5月21日(月)
問い合わせ先
e-mail: imura@sci.kagoshima-u.ac.jp
詳しくは、こちらまで
*
中部支部総会・シンポジウム・巡検
6月9日(土)総会およびシンポジウム
「伊豆弧の衝突と中部日本のテクトニクス」
会場:静岡大学教育学部教育実践総合センター
6月10日(日)伊豆半島巡検
問い合わせ:延原尊美 etnobuh@ipc.shizuoka.ac.jp
詳しくは、こちらまで
*
関東支部 研究発表会「関東地方の地質」
6月10日(日) 10時00分〜17時00分
会場 : 早稲田大学国際会議場 第1会議室
詳しくはこちら
第7回地図力検定
6月10日(日)札幌・仙台・東京・大阪・広島・福岡 同時開催
申込締切:5月21日(月)
財団法人 日本地図センター
南極研究観測シンポジウム:次世代の南極観測に向けて
6月15日(金)
会 場 :国立極地研究所6階講堂
詳しくはこちら
地質学史懇話会
6月16日(土)
会場:北とぴあ 901号
加藤碵一:宮澤賢治と地質学
大森昌衛:地質学史の年代学
http://www.geocities.com/jahigeo/jahigeo.html
資源地質学会シンポジウム Rare Metals ? Rare Earth Resource Symposium
6月19日(火)11時20分から17時40分
会場:東京大学山上会館(本郷キャンパス三四郎池畔)
http://www.kt.rim.or.jp/~srg/
GEOINFORUM-2007第18回日本情報地質学会総会・講演会
2007年6月21日(木)〜22日(金)
会場 島根県民会館
http://www.jsgi.org/
日本古生物学会2007年年会・総会
6月29日(金)〜7月1日(日)
会場:大阪市立大学シンポジウム:
古生代および中生代における温室期の地球生物相(6月29日)
http://ammo.kueps.kyoto-u.ac.jp/palaeont/meeting-f.html
7月July
Eurasian Geological Seminor 2007 -Geodynamic Process of Asia:Its Origin, Crustal Evolution, and Natural Resources Potential-
(International Joint Meeting by RCSP of Mongolian University of Science and Technology, Geological Information Center of Mongolia, The Nagoya University Museum, and IGCP 516)
7月18日〜28日
7/18:Meeting at Ulaanbaatar
7/19-21:Pre-symposium Field Excursionin in Gobi Desert;fossil dinosour and its eggs.
7/22-23: Scientific session
7/24-25:Post-symposium Field Excursion 1 in the Ulaanbaatar area; the Devonian accretionary complex of the Khangai-Khentei belt -evidence of the Mongol-Okhotuk Ocean-
7/24-25:Post-symposium Field Excursion 2 in the Ulaanbaatar area; Zaamar gold mining area.
7/26-28:Post-symposium Field Excursion 3 in the Oyu-Torgoi area; one of the largest copper-gold mine in the world.
場所:Mongolian University of Sciences and Technology, Ulaanbaatar, MONGOLIA
問い合わせ先:
Sersmaa Gonchigdorj
E-mail;sers_gon@yahoo.com, sers@must.edu.mn
Fax: +976-11-312291
Kazuhiro Tsukada
E-mail;tsukada@num.nagoya-u.ac.jp
Fax: +81-52-7895896
8月August
触媒道場
主催 触媒学会
8月6日(月)〜8日(水)
場所 公共の宿 山陽ハイツ(岡山県倉敷市有城1265)
詳しくは、こちらから
9月September
第15回ゼオライト夏の学校
9月6日(木)〜8日(土)
場所 東北大学川渡共同セミナーセンター
詳しくはこちらから
*
第114年日本地質学会学術大会
2007年9月9日(日)〜11日(火)
会場 北海道大学(札幌市)
大会ホームページはこちらから
2007地球環境保護 土壌・地下水浄化技術展
環境と共生する浄化技術のすべて
9月12日(水)〜14日(金)
会場:東京ビックサイト[有明・東京国際展示場]東ホール
詳しくはこちら
10月October
第3回国際シンポジウム“東および南アジアの地質学的解剖”(IGCP516)
10月8日〜14日
場所:インド・デリー大学
http://staff.aist.go.jp/hara-hide/igcp516
11月November
第4回"Gondwana to Asia"国際シンポジウム・国際ゴンドワナ研究連合2006年学術大会
11月8日〜11月10日
会場:九州大学・西新プラザ
問い合わせ先:gond-asia@scs.kyushu-u.ac.jp:中野伸彦(九州大学)
http://www.scs.kyushu-u.ac.jp/earth/2007gond-asia/
第5回火山都市国際会議 島原大会
1月19日(月)-23日(金)
会場: 島原市 雲仙岳災害記念館・島原復興アリーナ
主催: 島原市 NPO法人日本火山学会
http://www.citiesonvolcanoes5.com/jp/
12月December
将来展望シンポジウム〜海と地球の研究5ヶ年指針〜
日時:12月21日(金)13:00〜17:30
場所:海洋研究開発機構 横浜研究所 三好記念講堂
(地図:http://www.jamstec.go.jp/j/about/access/yokohama.html)
プログラム等はこちら→http://www.jamstec.go.jp/jamstec-j/maritec/rvod/forum.html
参加費:無料
地質学史懇話会総会
日時:12月23日(日)13:30〜17:00
場所:北とぴあ(JR王子駅より徒歩3分)
内容:講演2題
原 郁夫:小島丈児の業績と広島学派の形成
高安克己:小泉八雲の自然観
問い合わせ先:bk003769@ni.bekkoame.ne.jp
■2008年版行事カレンダーへ■
北海道支部
北海道支部
北海道支部2025年度例会(個人講演会)
2025.10.1掲載
以下の要領で、北海道支部2025年度例会(個人講演会)を開催いたしますので、皆様ふるってご参加ください。
日時:2025年11月15日(土)13:00-18:00
会場:オンライン開催(Google Meetを使用) 参加費無料
スケジュール概要:
12:30- 開場
13:00- 個人講演会(プログラムは後日案内)
講演申込み:2025年10月21日(火)締切
講演タイトル・発表者を明記のうえ、以下のアドレスまで電子メールでお申し込み下さい。 発表はすべて口頭形式で、発表17分、質疑3分の予定です。
講演要旨の提出:2025年11月10日(月)締切
講演ごとにA4で1〜2ページ、PDFまたはMS Wordファイルで作成し、以下のアドレスまで送付してください。 ※講演要旨PDFファイルは支部ホームページで公開します。公開を希望されない場合は、その旨を必ずお申し出ください。
申込み・問合わせ先:北海道支部庶務幹事 池田雅志
北海道大学理学研究院地球惑星科学部門
〒060−0810 札幌市北区北10条西8丁目
メール:maikeda[at]sci.hokudai.ac.jp
北海道支部2024年度例会(個人講演会)
2024.6.7掲載,6.19更新
下記の要領で、北海道支部2024年度例会(個人講演会)を開催いたしますので、皆様ふるってご参加ください。
日時:2024年6月22日(土)13:00-16:00
場所:北海道大学理学部5号館大講堂(5-203)>>案内図はこちら
参加費:一般会員500円、非会員1000円、学生無料
(個人講演会)プログラム
※右のポスター画像をクリックすると要旨集PDFをご覧いただけます
13:00- 開会の挨拶
13:10-13:35 林 圭一、大森一人、鈴木隆広、坂上寛敏、實粼颯汰、荒井昌也、片岡圭介「北海道内の温泉に付随する可燃性天然ガスの性状と地質学的起源について」
13:35-14:00 吉田達也、林 圭一、中村英人「上部白亜系-古第三系根室層群のバイオマーカー分析: 熱史の地域間比較と古環境復元に向けて」
14:00-14:25 福地亮介、沢田 健、小安浩理、石丸 聡「日勝峠に分布する周氷河性斜面堆積物のバイオマーカー分析による堆積学的評価」
(休憩)
14:40-15:05 山田陽翔、朝日啓泰、沢田 健「幌向川に分布する中新統川端層の有機物に富むタービダイト層の堆積学的調査」
15:05-15:30 松井 昭「安平町早来の露頭にみられる地層の変形の報告」
15:30-15:55 岡本 研「士別市のエゾ層群の教育資料の作成」
15:55-16:00 閉会の挨拶
■申込み・問合せ先
北海道支部庶務幹事 中村英人
北海道大学理学研究院地球惑星科学部門
〒060−0810 札幌市北区北10条西8丁目
メール宛先:hideton[at]sci.hokudai.ac.jp
北海道支部2023年度例会(個人講演会)
2023.5.19掲載,6.14,6.19更新
以下の要領で、北海道支部2023年度例会(個人講演会)を開催いたします。久しぶりに対面での開催を予定しておりますので、皆様ふるってご参加ください。
日時:2023年6月17日(土)13:00-18:00
場所:北海道大学理学部5号館大講堂(5-203)>>案内図はこちら
参加費:一般会員500円、非会員1000円、学生無料
《個人講演会・招待講演会プログラム》
画像をクリックするとポスターPDFがDLできます
13:00- 開会のあいさつ
個人講演会(発表17分,質疑3分)13:10-15:40 ※タイトル等クリックすると要旨PDFをご覧いただけます(6.19)
13:10-13:30 北野一平 「日高山脈ソガベツ沢のマイロナイト化した泥質グラニュライトの温度圧力経路」
13:30-13:50 福地亮介、沢田健、葉田野希 「諏訪湖堆積物における氷期‐間氷期スケールでの山岳地域の古植生変遷」
13:50-14:10 山本正伸,清家弘治,レオニド・ポリアク,ローラ・ゲメリ,ヨンジン・ジョ,内田翔馬,小林稔,小野寺丈尚太郎,村山雅史,岩井雅夫,山本裕二,リチャード・ジョルダン,山田桂,堀川恵司,朝日博史,安藤卓人,鈴木健太,加三千宣,永淵修,ロロイック・ダヴィド, 完新世北極古環境研究チーム 「西部北極海の後期完新世環境復元にむけて」
14:10-14:30 岡本 研 「士別市の岩石の観察からオリストストロームの成因を考えさせる学習」
(休憩)
14:40-15:00 嵯峨山積 「北海道長沼町の上部更新統〜完新統ボーリング(NGA-1)の珪藻分析」
15:00-15:20 池田雅志,沢田健,安藤卓人,中村英人,高嶋礼詩,西弘嗣 「北海道および北米カリフォルニアにおける白亜紀海洋無酸素事変期の有機分子古植生変動の比較」
15:20-15:40 竹下 徹 「北海道支部神居古潭巡検の見どころ:蛇紋岩メランジュ中のテクトニックブロックと変成岩上昇時の重複変成作用」
(休憩)
招待講演会
15:50-16:50 川野 潤(北海道大学理学研究院・准教授) 「炭酸塩鉱物の“non-classical”な形成過程とそれにまつわる最近の話題について」
16:50 閉会のあいさつ
申込み・問合わせ先:
北海道支部庶務幹事 中村英人
北海道大学理学研究院地球惑星科学部門
〒060−0810 札幌市北区北10条西8丁目
メール:hideton[at]sci.hokudai.ac.jp ※[at]を@マークにして送信してください
北海道支部神居古潭巡検のご案内
2023.5.19掲載
主催:地質学会北海道支部
標記地質巡検を下記の予定で開催します.本巡検は2018年9月に地震のために中止となった地質学会札幌大会の巡検(Eコース,竹下ほか, 2018, 地質雑,doi: 10.5575/geosoc.2018.0041)を,この度北海道支部巡検として実施するものです.ただし,道外の方の参加も可としています.基本的に当初計画された巡検(Eコース)の見学地点で露頭観察を行いますが,下記のように見学地点を一部変更します.なお,参加希望人数が下記の最少携行人数に満たない場合は中止となりますのであらかじめご了解ください.
1.日時:2023年8月18 日(金)〜19日(土)
8月18 日(金)北海道大学総合博物館前 7時45分集合,8時発
8月19 日(土)新千歳空港17 時着,北海道大学18時頃着,解散
2.見学コース(見学地点は竹下ほか, 2018を参照):
【1日目】見どころ,蛇紋岩メランジュ中のテクトニックブロック
幌加内峠(Stop 2, 3)―江丹別峠(Stop 4)―鷹泊大ヌップ川(追加の見学地点,Takeshita et al., 2023, JMG, DOI: 10.1111/jmg.12718参照)―深川(泊,イルム館を予定).なお,下幌加内ダム(Stop 1)には今回行きません. 1/25,000地形図: 沼牛,江丹別,鷹泊
【2日目】見どころ,神居古潭変成岩上昇時の重複変成作用
神居古潭峡谷(Stop 5)―班渓幌内川(Stop 7, 8)―新千歳空港―北海道大学.今回は,神居第4線川(Stop 6)および西富良野町(Stop 9)には行きません.一方,Stop 5では竹下ほか(2018)のFig. 11の露頭A, Bの両方を観察します. 1/25,000地形図: 神居古潭,石狩新城,神楽岳
3.募集人員:案内者(4名,下記)を除く最少携行人数7名.最大携行人数10名. 申し込みは,人数が最大携行人数に達し次第締め切ります.なお,参加希望者が最大携行人数を上回った場合は,地質学会会員を優先します
.
4.案内者:竹下 徹(北海道大学博物館資料部)・平島崇男(京都大学)・辛ウォンジ(国立アイヌ民族博物館)・マリ ピトン(北海道大学理学研究院)
5.参加費:
正会員(一般会員・シニア会員)30,000 円
正会員(学生会員) 18,000 円 ※下記(注)参照
非会員(一般)35,000 円(開催日までに入会手続きされる方は,会員価格で可)
非会員(学生・院生) 18,000 円(開催日までに入会手続きされる方は,下記の地質学会からの補助を受けることが出来ます)
(参加費は現地での宿泊費(1泊2食付き),現地移動バス代,団体旅行保険料を含みます.集合地の北海道大学までの旅費交通費,1日目および2日目の昼食はご自身でご負担ください).
(注)今回は学生・院生に巡検参加を勧めるため,学生・院生の参加費をかなり割安にしています.また,上記で学生・院生の参加費は会員と非会員で参加費が同額になっていますが,地質学会学生会員(今年度申請済みの方)は日本地質学会若手育成事業費から巡検参加費の補助を受けることが出来,参加費は上記の半額となります.さらに,この参加費は最少携行人数に基づき算出しており,実際の参加費はこれより安くなる可能性があります.
6.CPD参加証明書:本巡検参加者のうち,CPD取得希望者にはCPD参加証明書を発行します.取得できるCPD単位は12単位を予定しています.参加申込時に取得希望の旨を記してください.
7.参加申込:参加希望者は,メールにて下記内容を記入の上,竹下 徹(torutake@sci.hokudai.ac.jp)までお申し込み下さい.
申込記載項目:①氏名(ふりがな) ②会員・非会員の種別 ③勤務先(学生・院生は大学名と学年) ④連絡先(携帯電話番号,メールアドレス) ⑤CPD単位取得希望の有無
申込期間:2023年5月19 日(金)〜2023年7月20 日(木)なお,定員に達し次第,申込期間中であっても募集を終えます.
北海道支部令和3年度総会・例会(個人講演会)
画像をクリックするとポスターPDFがDLできます
下記の要領で、北海道支部令和3年度総会・例会(個人講演会)を開催いたしますので、皆様ふるってご参加ください。
日時:2021年7月10日(土)
会場:オンライン開催(Zoomを使用)
12:00-13:00 総会
13:30-17:00 例会(個人講演会)
個人講演会・招待講演会プログラム
(各講演をクリックすると要旨PDFがご覧いただけます)
13:30 - 開会のあいさつ
個人講演会(発表17分,質疑3分)13:40-15:40
13:40 – 14:00 山本正伸・櫻井弘道・関 宰「縄文時代以降の気候変化が北海道の狩猟漁撈採集文化に与えた影響」
14:00 - 14:20 早川 万穂・池田雅志・沢田 健・高嶋 礼詩・西 弘嗣「北海道苫前町古丹別地域の上部白亜系蝦夷層群における花粉およびパリノモルフ分析」
14:20 - 14:40 朝日啓泰・沢田 健「中期中新世石狩・日高堆積盆の有機物に富むタービダイトの有機地球化学分析による堆積プロセスの解明」
14:40 – 15:00 中元啓輔・宇野正起・亀田 純「スメクタイトの膨潤圧が断層のせん断強度に与える影響の検討」
15:00 - 15:20 加地 広美・竹下 徹「北海道東部の前弧含石炭古第三系褶曲帯中の変形バンドの発達と歪集中」
15:20 – 15:40 千葉 崇*・西村裕一・柳沢幸夫「北海道十勝沿岸域の完新世古環境復元における新第三系リワーク珪藻識別の重要性」
15:40 - 16:00 休憩
招待講演会 16:00-17:00
近藤玲介(東京大学大気海洋研究所)「北海道におけるルミネッセンス年代測定法の適用事例の紹介 −根釧台地周辺の特異な湿原群の形成史研究を中心に−」
17:00- 閉会のあいさつ
18:00 - 懇親会(オンライン、参加自由)
講演申込み
2021年6月30日(水)締切
講演タイトル・発表者を明記のうえ、電子メールまたは郵送でお申し込みください。
発表はすべて口頭形式で、発表17分、質疑3分の予定です。
講演要旨の提出
2021年7月5日(月)締切
1講演あたりA4で1〜2ページ、 PDFまたはMS Wordファイルで作成し、下記アドレスまで送付してください。
※講演要旨PDFファイルを支部ホームページに公開します。公開を希望されない場合は、その旨を必ずお申し出ください。
申込み・問い合わせ先:
北海道支部幹事庶務:Marie Python
北海道大学大学院理学研究院・自然史科学部門
〒060-0810 札幌市北区北10条西8丁目
電話011-706-4640 メール:marie[at]sci.hokudai.ac.jp
日本地質学会北海道支部令和元年度総会・例会(個人講演会)
画像をクリックするとポスターPDFがダウンロードできます
下記の要領で、北海道支部令和元年度総会・例会(個人講演会)を開催いたしますので、皆様ふるってご参加ください。
日時:2019年6月15日(土)
総会:11:00〜12:00
例会:13:00〜18:00
場所:北海道大学理学部5号館大講堂(5-203)
個人講演会・招待講演会プログラム
(各講演をクリックすると要旨PDFがご覧いただけます)
13:00 開会のあいさつ
・個人講演会(発表17分,質疑3分)13:10-15:50
13:10 - 13:30 嵯峨山積・近藤玲介・宮入陽介・横山祐典「三重県伊勢市の沖積層ボーリングコアの珪藻分析」
13:30 - 13:50 服部由季・安藤卓人・沢田健・関宰「えりも町豊似湖で確認された長鎖アルケノンの謎」
13:50 - 14:10 池田雅志・沢田健・安藤卓人・中村英人・高嶋礼詩・西弘嗣「北海道苫前地域に分布する蝦夷層群の植生バイオマーカー変動:バイオマーカー層序の可能性?」
14:10 - 14:30 朝日啓泰・沢田健・風呂田郷史「津波堆積物の有機堆積学分析:北海道東部泥炭コアの例」
14:30 - 14:50 休憩
14:50 - 15:10 宮坂省吾「サッポロの川を尋ねて―コトニ川―」
15:10 - 15:30 Marie Python, Mathieu Rospabé, Jürgen Koepke, Betchaida Payot, Juan-Miguel Guotana, Nick Dygert, Nadine Grambling, Kevin Johnson, Gyuseung Park and Oman Drilling Project Science Team「Drilling the Crust-Mantle Transition at Oman Drilling Project Sites CM1 and CM2」
15:30 - 15:50 前田仁一郎・石川暁登「北海道, 日高変成帯の千呂露変成苦鉄質岩脈に観察されるグラニュライト化作用」
・招待講演会16:00-17:00
16:00 - 17:00 田近淳(ドーコン(株)/ 道総研フェロー)「2018年北海道胆振東部地震によって発生した斜面変動」
17:00 - 閉会のあいさつ
18:00 - 懇親会
申込み・問い合わせ先:
北海道支部幹事庶務:亀田 純
北海道大学大学院理学研究院・自然史科学部門
〒060-0810 札幌市北区北10条西8丁目
電話011-706-4642 メール:kameda[at]sci.hokudai.ac.jp
北海道支部平成30年度総会・例会(個人講演会)
日本地質学会北海道支部平成30年度総会
日時:2018年6月16日(土)11:00〜12:00
場所:北海道大学理学部5号館大講堂(5-203)*会場の地図(PDF)がDLできます
日本地質学会北海道支部平成30年度例会
日時:2018年6月16日(土)13:00〜17:00
場所:北海道大学理学部5号館大講堂(5-203)*会場の地図(PDF)がDLできます
参加費:会員500円・非会員1000円・学生 無料
プログラム(wordファイル)
13:00 開会のあいさつ
招待講演会(注)講演タイトルをクリックすると要旨PDFがDLできます
13:10-14:10 佐藤比呂志(東京大学地震研究所 地震予知研究センター 教授)「北海道の地震発生ポテンシャル評価に向けた震源断層マッピング」
個人講演会(発表17分,質疑3分)14:20-17:00(注)講演タイトルをクリックすると要旨PDFがDLできます
14:20 - 14:40 宮坂省吾・坂下哲哉・岡村聡「発寒川扇状地―地すべりによる河川争奪―」
14:40 - 15:00 星野フサ・横山光・岡本研・佐藤広「北海道長流川左岸に分布する縞状堆積物の花粉分析―2万年前にマンモスゾウがおそらく見たであろう景色―」
15:00 - 15:20 嵯峨山積・佐藤明・井島行夫・岡村聡「札幌市東区の上部更新統〜完新統ボーリングコア(SL-2):層序と堆積環境」
15:20 - 15:50 休憩(地質学会札幌大会事務局からのお知らせ)
15:50 - 16:10 林圭一・川上源太郎・加瀬善洋「芦別市サキペンベツ川流域に露出する“礫岩卓越層”から得られた渦鞭毛藻シスト化石群集に基づく地質年代とその意義(予察)」
16:10 - 16:30 増本広和・亀田純「粘土鉱物の熱分解反応からみたプレート境界断層の熱履歴とすべり挙動」
16:30 - 16:50 シンウォンジ・竹下徹「炭質物ラマン温度計を用いた神居古潭変成岩類の温度構造の検討:北海道中央部神居古潭峡谷地域の例」
16:50 閉会のあいさつ
18:00〜 懇親会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
問い合わせ先:
北海道支部幹事庶務:亀田 純
北海道大学大学院理学研究院・自然史科学部門
〒060-0810 札幌市北区北10条西8丁目
電話011-706-4642 メール:kameda@sci.hokudai.ac.jp
北海道支部2017年春巡検「札幌の失われた川を歩く」
2017年春巡検「札幌の失われた川を歩く」
画像をクリックするとポスター画像がダウンロードできます
■巡検先:札幌市内 北海道大学(南側)〜北海道大学植物園〜札幌市立中央中学校(北4条東3丁目)付近を歩きます。
■日時:2017年6月18日(日)9:00〜17:00(集合:北海道大学南門 9時)
■案内者:宮坂省吾(川の案内人)・内山幸二(石の案内人)・土屋 篁(「ビルの岩石学」執筆)
■内容:
豊平川の洪水の痕跡、失われた旧豊平川を巡った2回の巡検につづく、「サッポロ巡検」の第三弾です。今回は北海道大学キャンパスの南側、北海道大学植物園、札幌市立中央中学校の周辺を歩いて巡ります。札幌の街は豊平川の広大な扇状地上につくられた街です。札幌農学校(現 北海道大学)はちょうどその扇端部に位置します。キャンパス内やその周辺では「メム」やサクシュコトニ川などにより形づくられた特徴的な地形を観察します。さらに旧河道の痕跡を追いかけながら、植物園や中央中学校の周辺へと旧河川や扇状地面をたどって行きます。また、扇状地面やその周辺に建てられた明治時代の文化財も巡り、開拓使時代の札幌の様子を偲んだり、周辺に点在する道内産の石材を使った石碑を見学したりし、それらを作っている岩石を観察します。
是非ご参加ください(本巡検はCPD:8単位の対象です)。
■参加費: 一般会員:1,000円/学部生:500円
※ 昼食は各自ご用意ください。札幌中心部での巡検ですので、飲食店で昼食をとることもできます。
■申し込み・問い合わせ:
氏名(性別)・住所・連絡先(電話 or メール)・生年月日(保険申込のため)を明記しお申込み下さい。
記入いただく個人情報は宿泊および保険の申込に使用いたします。なお、個人情報は秘匿し、巡検の終了後に破棄致します。
巡検担当: 米島真由子(m.yonejima[at]gmail.com)※[at]を@にしてメールを送信下さい。
■参加申込受付:2017年6月11日(日) 締切
北海道支部平成29年度例会(個人講演会)
日本地質学会北海道支部平成29年度例会(個人講演会)
画像をクリックするとポスターPDFがダウンロードできます
下記の要領で、北海道支部平成29年度例会(個人講演会)を開催いたしますので、皆様ふるってご参加ください。
日時:2017年6月17日(土)13:00〜17:30
場所:北海道大学理学部5号館大講堂(5-203)案内図(PDF)はこちら
参加費:一般会員500円、非会員 1000円、学生無料
プログラム
13:00 開会のあいさつ
個人講演会(発表17分,質疑3分)13:10-16:00
*タイトルをクリックすると講演要旨(PDF)がダウンロードできます。
13:10 - 13:30
宮坂省吾(川の案内人)・内山幸二(石の案内人)・土屋 篁(「ビルの岩石学」執筆)・横山光・米島真由子(巡検係)「2017年春巡検「札幌の失われた川を歩く」の紹介」
13:30 - 13:50
加藤孝幸・菅原 誠「貫入岩・褶曲構造と断層から見た渡島半島と内浦湾,奥尻海盆の成立―ユーラップジオパーク構想の調査から」
13:50 - 14:10
岡本あゆみ・竹下 徹「沈み込み初期の沈み込みチャネルの温度発展を記録している蛇紋岩メランジェ中のテクトニックブロックの温度圧力履歴:北海道中央部の神居古潭変成岩を例にして」
14:10 - 14:30
前田仁一郎・松田岳洋・中田周兵・Keewook Yi中央北海道, 日高火成活動帯に産出する鉄に富む深成岩類の年代論と岩石学」
(休憩)
14:40 - 15:00
岡 孝雄・大西 潤然別湖北岸ヤンベツ川沿いの段丘堆積物の泥炭の14C年代と上位ローム中に検出された御鉢平起源の降下火山灰について」
15:00 - 15:20
嵯峨山積・近藤玲介・重野聖之・百原 新・冨士田裕子・矢野梓水・宮入陽介・横山祐典「北海道北部猿払村の沖積層コアの珪藻分析」
15:20 - 15:40
林 圭一・川上源太郎・廣瀬 亘・渡辺真人「北海道東部能取湖周辺の新第三系層序と渦鞭毛藻シスト化石―渦鞭毛藻シスト化石群集に基づく堆積場の古環境変遷―」
15:40 - 16:00
小安浩理・西 弘嗣・郄嶋礼詩・鈴木紀毅「北西太平洋における白亜系放散虫化石層序」
16:20-17:20 招待講演会
栗原憲一 先生(北海道博物館)「地質学会が選定する北海道の化石「アンモナイト」について」
17:20 閉会のあいさつ
申込み・問い合わせ先:
北海道支部幹事庶務:亀田 純
北海道大学大学院理学研究院・自然史科学部門
〒060-0810 札幌市北区北10条西8丁目
電話011-706-4642 メール:kameda[at]sci.hokudai.ac.jp([at]を@マークに変換して下さい)
地質の日記念展示「北海道のジオサイトに見る化石」
地質の日記念展示「北海道のジオサイトに見る化石」
画像をクリックするとポスター画像がダウンロードできます
北海道は地質学的にダイナミックな形成史を持ち、それらを語る証拠は地層・岩石や化石、あるいは特徴ある地形として道内各地に残されています。本展示では、札幌市のサッポロカイギュウや沼田町のヌマタネズミイルカの実物模型、道内のアンモナイト標本、および昨年出版された『北海道自然探検 ジオサイト107 の旅』から化石関連のジオサイト(地質露頭や地質景観)の見どころをパネルで紹介し、北海道の自然の生い立ちを理解し、楽しく学ぶことのできるフィールドへお誘いします。
期間: 2017年 4月28日(金)〜 6月18日(日)
休館日: 月曜日
時間: 10:00 〜 17:00 (6 〜 10 月の金曜日は21:00 まで)
会場: 北海道大学総合博物館1 階企画展示室 【入場無料】
主催:地質の日展実行委員会・北海道大学総合博物館
共催:日本地質学会北海道支部・産総研地質調査総合センター・道総研地質研究所・北海道博物館・札幌市博物館活動センター・北海道地質調査業協会
後援:北海道教育委員会・札幌市・札幌市教育委員会
協力:沼田町化石館
問い合わせ先: 北海道大学総合博物館 〒060-0810 札幌市北区北10 条西8 丁目 TEL:011-706-2658
●市民セミナー
会場:北海道大学総合博物館 1階「知の交流」
時間:13:30〜15:00(13:00開場)
備考:申込不要・入場無料
5月20日(土) 「北海道ジオサイト107への旅に出て」 川村 信人(北海道大学 大学院理学研究院)
6月4日(日) 「ジオサイトとしての札幌の魅力」 古澤 仁(札幌市博物館活動センター)
●市民巡検—ジオサイト「藻岩山」を歩く—
6月10日(土)10:00〜15:00
集合:10時 ロープウェイもいわ山麓駅(札幌市中央区伏見5丁目3−7)
コース:ロープウェイ・もーりすカーで藻岩山の山頂まで登り、登山道沿いに歩いて下山します。
講師:岡村 聡(北海道教育大学 札幌校)
定員:高校生以上20 名(先着順)
参加費:400 円(保険料等)、ロープウェイ・もーりすカー料金(900 円)が別途必要
備考:昼食や飲み物、雨具をご持参ください。ハイキングに適した格好でお越しください。
申込方法:往復はがきに氏名・住所・年齢・電話番号をご記入の上、北海道大学総合博物館「巡検係」宛にご郵送ください。
申込締切:5月26 日(金)必着
北大総合博物館ホームページ
日本地質学会北海道支部平成28年度(2016年度)総会
日本地質学会北海道支部
平成28年度(2016年度)総会
画像をクリックするとポスター画像がダウンロードできます
日時:2017年3月11日(土)14:30〜16:30
場所:北海道大学理学部6号館2階 6-204室 (地図はこちら pdf)
総会:14:30〜16:30
1.支部長挨拶
2.議長選出
3.議 事
---A.2016年度 事業報告
---B.2016年度 会計報告
---C.2017年度 事業計画案
---D.2017年度 予算案
---E.その他
4.議長解任
「県の石(北海道)」決定記念講演会:16:45〜17:45
北海道の岩石『かんらん岩』:新井田清信(北大総合博物館、ジオラボ「アポイ岳」所長)
北海道の鉱物『砂白金』:中川充(産業技術総合研究所 北海道センター産学官連携推進室 総括主幹)
懇親会:18:15〜
問い合わせ先:
北海道支部幹事庶務:亀田 純
北海道大学大学院理学研究院・自然史科学部門
〒060-0810 札幌市北区北10条西8丁目
電話011-706-4642 メール:kameda[at]mail.sci.hokudai.ac.jp ([at]を@にして送信してください)
出版記念シンポジウム「北海道自然探検 ジオ(大地)の魅力がいっぱい!」
出版記念シンポジウム 開催報告
「北海道自然探検 ジオ(大地)の魅力がいっぱい!」
画像をクリックすると
書籍のチラシPDFが
ダウンロードできます
「北海道自然探検 ジオサイト107の旅」が,2016年5月に出版されたことを受け,表記シンポジウムが開かれました.
竹下 徹・日本地質学会北海道支部長は挨拶で次のように述べました.
支部の役割の一つに地質学の普及があり,特に若い人たちに地質の魅力を伝えることが大事です.欧米に比べると日本では,地球科学が一般の人たちになじみがないように思います.2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震以来,地質学の応用面での貢献が求められています.
北海道大学の川村信人氏が「北海道地質百選・ジオサイトの旅と私」と題して講演しました.川村氏は,この本で37のジオサイトについて執筆しています.その中で,川村氏にとっては,乙部町の邢ノ岬と釧路市の春採太郎が印象的なジオサイトだそうです.また,地質標本や露頭などを含めた地質記録リポジトリーが必要ではないかという問題提起をされました.
そのあと,編集に携わった石井,田近,鬼頭がそれぞれ発表を行いました.
さらに,日高山脈博物館の東 豊土氏は,博物館で行っている様々な普及活動を紹介されました.日高町には,ヒスイ鉱山の沢や岩内岳かんらん岩など魅力的なジオサイトが沢山あります.子供たちとその親を対象とすることで普及活動に拡がりをもたせるようにしています.
北海道立総合研究機構・地質研究所の廣瀬 亘氏は,世界ジオパークネットワークがユネスコの正式事業となり,国際誌への論文投稿が必要になるなど担当者の負担が増大している現状について話されました.
北海道立総合研究機構・地質研究所の鈴木隆広氏は,自然景観データベースを紹介されました.具体的には豊平川沿いのジオサイトをタブレットで案内するシステムを構築しています.さらに,地質研究所では,「ジオサイト写真提供のページ」を設けています.
北海道には,この本に掲載された以外にも多くの魅力的なジオサイトがあります.私たちは,北海道地質百選のウェブサイトを充実させる活動をもう少し,続けます.
皆さまのご協力をお願い致します.
出版記念シンポジウム 「北海道自然探検 ジオ(大地)の魅力がいっぱい!」
日時:2016年12月3日(土)13:30〜 シンポジウム,17:30〜 祝賀会
場所:北大理学部5号館201教室
講演「ジオサイトの旅と地質災害−崩れの旅:道南編+」
講演「自然景観データーベースの紹介と活用」
講演「北海道地質百選・ジオサイトの旅と私」
(北海道地質百選検討グループ 文責:石井正之)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
「北海道自然探検 ジオサイト107の旅」出版のお知らせ
監修:日本地質学会北海道支部 編著:石井正之・鬼頭伸治・田近 淳・宮坂省吾
出版社:北海道大学出版会 定価:2,800円+税
ISBN978-4-8329-1402-5
日本地質学会北海道支部の北海道地質百選検討グループに属するメンバーが中心となって,“北海道自然探検 ジオサイト107の旅”と題する道内のジオサイトを写真で紹介する地質・地形のガイドブックを出版しました.北海道は高緯度地域に位置し,本州にはない特 異なものも含めて,さまざまな地形・地質が見られる場所です.これら独特な景観をつくる地形や地質などを北海道の地質遺産として広く市民に知ってもらい, 北の大地(ジオ)に関心を持ってもらうことが本書の目的です.まずは,皆さまに見て頂いて,さらに周りの人に広めて下さると有り難いです.この本が,いろ いろなところで活用され,地質や地形,さらには自然へ興味を持つ入口になればと思っています.
*著者割引価格(2,240円+税)で購入できる会員限定注文用紙はこちらから(要会員ログイン)
北海道支部2016年秋巡検のご案内
巡検「三笠ジオパークと蝦夷層群の地質を学ぶ」
■ 巡検先:三笠ジオパークおよび夕張方面
■案内者:
・高嶋礼詩(東北大学学術資源研究公開センター 東北大学総合学術博物館)
・下村 圭(三笠ジオパーク)
■ 内容:三笠ジオパークと蝦夷層群をテーマに、1日目は三笠ジオパークの博物館やジオサイト(露頭)を中心に見学し、2日目は夕張周辺まで足を伸ばして蝦夷層群の半深海相と浅海相の観察を行います。2日目の見学場所には、林道を1時間程歩いて見学する露頭があります。1日目の夕方には三笠の地質とジオパークの課題(仮題)をテーマに、東北大学総合学術博物館 准教授 高嶋 礼詩 氏にご講演いただきます。
(※ 駐車スペース等の都合がありますので、各見学ポイントはレンタカーでまわります)
■ 開催日:2016年10月22日(土)〜23日(日)1泊2日
※宿泊せずに,日帰りで2日参加,どちらか1日だけの参加も可能です.お申込み用紙であてはまる参加方法を選択してください。
■ 参加費・宿泊費
・参加費(2日間の場合):会員5,000円、非会員6,000円(学生:3,000円の予定)
(1日だけの場合):会員3,000円、非会員3,500円(学生:2,000円の予定)
・宿泊費(1泊2食):5,500円 ※日帰り参加者は不要
・懇親会費:1,000円(学生:500円の予定) ※参加者のみ
・学生割引は学部生(会員・非会員とも)が対象です
■ 集合場所/合流場所:
自家用車または公共の交通機関で来られる方の集合場所
22日(土)10:30 三笠市立博物館の駐車場
札幌駅または岩見沢駅で巡検用のワゴン車に同乗して来られる方の合流場所
① 22日(土)08:30 札幌駅 北口
② 22日(土)09:30 岩見沢駅 中央口
札幌駅あるいは岩見沢駅で合流ご希望の場合は、申込み時にその旨お知らせください。
(札幌駅または岩見沢駅で合流の場合、ガソリン代をご負担下さい。札幌駅で合流の場合は500円程度の予定です)
■ 募集人数:18名
■ 申込・問合せ:お申し込みの際は,別紙「2016 年秋巡検申込書.xlsx」に必要事項を記入して巡検担当:米島に送付してください。記入いただく個人情報は宿泊および保険の申込、入林届に使用いたします。なお、個人情報は秘匿し、巡検の終了後に破棄致します。
巡検担当: 米島 真由子〔m.yonejima[at]gmail.com〕
※[at]を@にしてメールを送信下さい。
▶▶「2016 年秋巡検申込書.xlsx」のダウンロードはこちらから
■ 受付期間:2016年10月12日(水)まで
北海道支部平成28年度例会(個人講演会)
北海道支部平成28年度例会(個人講演会)
画像をクリックするとPDFが
ダウンロードできます
下記の要領で、北海道支部平成28年度例会(個人講演会)を開催いたしますので、ご出席のほどよろしくお願いいたします。
日時:2016年6月11日(土)10:30〜17:30
場所:北海道大学理学部5号館301室(5-301)[大学までのアクセス,学内マップはこちら(pdf)]
プログラム:(各演題をクリックすると要旨PDFがDLできます)
10:30 開会のあいさつ
個人講演会(発表17分,質疑3分)10:40-16:10
10:40 - 11:00 沢田健・風呂田郷史・青柳治叡
「北日本周辺海域の新第三紀オーダーの古海洋環境変動の復元」
11:00 - 11:20 岡孝雄・小野哲也
「北海道東部,標津湿原の形成過程と高層湿原化の解明」
11:20 - 12:00 宮坂省吾
「サッポロを作った古河川と豊平川の成立について」+「サッポロ巡検の紹介」
(昼休み)
13:20 - 13:40 幹事会からの諸情報提供
13:40 - 14:00 仁科健二
「地質の日関連事業、市民巡検「ぶらり・小樽の地質と軟石建造物」の報告」
14:00 - 14:20 東豊土・加藤孝幸・和田恵治
「幸太郎石−高圧変成作用を受けた蛇紋岩関連オリストストローム」
14:20 - 14:40 加藤孝幸
「超苦鉄質岩から見た北海道中軸帯の東西断面」
14:40 - 15:00 前田仁一郎・谷内元・斎藤清克・中野雅子
「北海道, 日高火成活動帯のかんらん石に富む斑れい岩中の spinel-hosted mineral inclusions」
15:00 - 15:20 前田仁一郎
「北海道総合地質学研究センターの設立について」
(休憩)
15:30 - 15:50 加瀬善洋・川上源太郎・仁科健二・林圭一・卜部厚志・郄清水康博
「化学分析による津波堆積物の認定手法の有用性」
15:50 - 16:10 林圭一・加瀬善洋・川上源太郎・仁科健二
「津波堆積物中の有機質微化石の水平・垂直分布−現世アナログとしての 3.11 津波堆積物とその歴史津波認定への応用−」
招待講演会16:20-17:20
岩崎 貴哉(東京大学地震研究所・教授)
「これまでの制御震源探査データの再解析による日高衝突帯構造の新知見」
17:20 閉会のあいさつ
問い合わせ先:
北海道支部幹事庶務 亀田 純 北海道大学大学院理学研究院・自然史科学部門
〒060-0810 札幌市北区北10条西8丁目
メール:kameda[at]mail.sci.hokudai.ac.jp ([at]を@にして送信してください)
2016年サッポロ巡検「豊平川の洪水痕跡と150年前の旧河道」
写真1(左上) 南19条大橋下流の洪水堆積物.写真2 (右上)豊平川の旧流路の説明を受ける参加者.写真3(左下) 35年前の洪水による高水敷浸食跡(写真中央護岸の一部が浸食に耐えた隔壁コンクリート).写真4(右下) 失われた左分流沿いの自然堤防を歩いて登る参加者
写真5(左) 豊平橋地点の狭窄部.写真6(右)1条大橋地点の広い川幅
写真7 豊平川を背景に集合写真
2016年サッポロ巡検「豊平川の洪水痕跡と150年前の旧河道」
2016年サッポロ巡検が『豊平川の洪水痕跡と150年前の旧河道』というテーマで行われました。内容は、札幌市の中心部を流れる豊平川の洪水史とそれに伴う札幌の街の変遷を、川沿いから市街地にかけて徒歩で見学するものでした。巡検コース、参加費、参加者数を以下に示します。
6月12日(日)
09:00 市電「山鼻19条駅」:セブンイレブン前 集合
16:00 地下鉄東西閃「バスセンター前駅」 解散
①南19条大橋下流⇒②幌平橋⇒③南大橋の上流⇒④南7条大橋⇒⑤豊平橋⇒⑥埋立てられた豊平橋左岸⇒⑦渡し守の住んだ自然堤防⇒⑧大通東5〜7丁目付近⇒⑨大通東8丁目
参加費 一般会員(非会員):1000円(2000円)、学生:500円
巡検参加者:15名(学生・院生2名)
(北海道支部巡検担当幹事:横山光、米島眞由子、宮坂省吾、西塚大)
本巡検は、主に(株)アイピーの宮坂省吾氏、明治コンサルタント(株)の重野聖之氏の案内により、①豊平川の35年前の洪水痕跡を探る、②150年前の風景を復元し、150年間での変遷を推測するものでした。
35年前の洪水痕跡についは、南19条大橋下流で洪水堆積物と更新樹木を観察し、南大橋上流では高水敷の浸食痕跡を観察しました。
150年間での変遷については、豊平橋建設による幅500mにもおよぶ網状流路の狭窄化、埋立てられた中州、自然堤防跡、失われた左分流跡を当時の建物や人々の営みを回想しながら観察しました。
豊平川がいかに洪水を頻発させてきたか、そして洪水に対する先人達の取組みを知ることができました。また、開拓によって豊平川がいかなる改修を経験してきたかを知ることができ、一札幌市民・北海道民としては非常に興味深い巡検内容だったと思います。また、街中に残された自然堤防跡を参加者全員で確認しながら進んでいくと、普段何気なく通り過ぎている道が探検コースに早変わりし、探検を楽しむような感覚の巡検にもなり、参加者の満足度も高かったものと思います。
最後に、当日は晴天に恵まれたものの風が強い1日でした。そのような天候の中、札幌市博物館活動センターの古沢学芸員には大判のパネルを用いた説明を加えて頂きました。ここに厚く御礼申しあげます。
(北海道支部巡検担当幹事:西塚 大)
2016年「地質の日」記念展示
画像をクリックするとPDFが
ダウンロードできます
北海道のジオパーク−地球の営みを体感する−
日時:4月26日(火)〜6月5日(日)9:00〜19:00
場所:札幌市資料館 1階展示室(札幌市中央区大通西13丁目)【入場無料】
関連イベント
● 市民地質巡検「ぶらり 小樽の地質と軟石建造物」
日時: 6月5日 (日) 9:30〜16:30
コース: 小樽軟石採掘跡,小樽運河プラザなど
●市民セミナー「北海道のジオパークを語る」
日時: 5月7日 (土) 13:30〜16:30
場所: 札幌市資料館 2階 研修室
詳しくは,「地質の日」のページをご参照ください.
http://www.geosociety.jp/name/content0139.html#hokkaido
北海道支部平成27年度(2015年度)総会
北海道支部平成27年度(2015年度)総会
画像をクリックするとPDFがダウンロードできます
日時:2016年2月27日(土)14:30〜16:30
場所:北海道大学理学部6号館2階 6-204室(PDF地図はこちら)
総会:14:30〜16:30
1.支部長挨拶
2.議長選出
3.議 事
A.2015年度 事業報告
B.2015年度 会計報告
C.2016年度 事業計画案
D.2016年度 予算案
E.その他
4.議長解任
講演会:16:45〜18:00
山崎新太郎(北見工業大学 工学部 社会環境工学科)「北海道における防災地質学の最前線」
懇親会:18:30〜
※2016年度北海道支部例会(個人講演会)は、2016年5月に行う予定です。詳細な案内は後程、掲示いたします。
問い合わせ先: 北海道支部幹事庶務:沢田 健
北海道大学大学院理学研究院・地球惑星科学部門
〒060-0810 札幌市北区北10条西8丁目
電話011-706-2733 メール:sawadak@mail.sci.hokudai.ac.jp
2015年度北海道支部巡検
支部巡検「裏山の自然災害―支笏湖・苔の洞門」
巡検概要:樽前山・風不死岳に源流をもつ苔の洞門では、昨年7月の直下型地震と9月の豪雨を受け、岩盤崩壊・洪水による洗掘や氾濫が発生しました。現在、一般の立入りは禁止されていますので、当巡検は洪水堆積物の露頭や自然災害のツメ跡を観察できるチャンスです。樽前火山1739年火砕流堆積物,カルデラ形成後の湖畔の地形を観察しましょう。
画像をクリックするとPDFファイルが
ダウンロードできます。(315KB)
日時:6月20日(土) 7:30〜16:30(予定) 集合・解散は札幌駅北口
見学箇所:苔の洞門および支笏湖畔
案内者:宮坂 省吾((株)アイピー 地質情報室)
定員:30名
参加費:一般(会員)3000円、一般(非会員)4000円、学生2000円
(バス代・保険・資料代込、昼食は持参してください)
申込み・問い合わせ先:北海道支部幹事庶務 沢田 健
メール sawadak [at] mail.sci.hokudai.ac.jp
(氏名・性別、会員/非会員、住所、年齢・生年月日、連絡先を明記して申し込んで下さい。個人情報は秘匿し、終了後に破棄致します。)
申込締切:6月10日(水)(定員に達し次第、締め切らせていただきます)
平成27年度例会(個人講演会)
平成27年度例会(個人講演会)
画像をクリックするとPDFファイルが
ダウンロードできます。(373KB)
下記の要領で、北海道支部平成27年度例会(個人講演会)を開催いたしますので、ご出席のほどよろしくお願いいたします。
なお、今回の支部例会では、講演参加者・発表者に対して、CPDの受講証明書を発行いたします。受付にて日本地質学会が発行する所定の様式に当日記入してください。
日時:2015年6月13日(土)9:30〜17:30
場所:北海道大学理学部5号館大講堂(5-203)
[大学までのアクセス、学内マップはこちらから(pdf)]
[プログラム] *印の付いた講演は,タイトルをクリックすると要旨PDFをダウンロードできます NEW
9:30 開会のあいさつ
個人講演会(発表17分,質疑3分)9:30-16:20
9:40 - 10:00 安藤 卓人・沢田 健・中村 英人・宮田 遊磨・尾松 圭太・高嶋 礼詩・西 弘嗣:苫前地域に分布する蝦夷層群Cenomanian/Turonian境界堆積岩の熟成度評価と堆積環境の復元
10:00 - 10:20 西村 智弘・重田 康成:北海道穂別地域における蝦夷層群函淵層の層序と軟体動物化石群
10:20 - 10:40 山本 正伸:過去2900年間の太平洋十年規模変動と日本の気候
10:40 - 11:00 圓谷 昂史・添田 雄二・廣瀬 亘・林 圭一・加瀬 善洋・大津 直・五十嵐 八枝子・畠 誠:トレンチ調査から見た北広島市音江別川流域音江別川層の堆積相と古環境
11:00 - 11:20 星野 フサ・岡 孝雄・近藤 務・中村 俊夫・関根 達夫・米道 博・山崎 芳樹・乾 哲也・奈良 智法・安井 賢:北海道厚真川流域の沖積層の地質学的研究―AZK-101孔コア(60m長)およびATP-2・ATP-3コア(13m長)のAMS14C 年代測定結果,花粉・珪藻分析結果による考察―.*
11:20 - 11:40 近藤 務・岡 孝雄・中村 俊夫・井島 行夫・前田 寿嗣・古澤 明・金川 和人・星野 フサ・関根 達夫・米道 博・山崎 芳樹・乾 哲也・奈良 智法・安井 賢:北海道厚真川下流域の上部更新〜完新統の層序―ボーリング・コアの層相変化・AMS14C年代・火山灰対比・堆積曲線による沖積層の特性の考察―*
11:40 - 12:00 嵯峨山 積・井島 行夫・藤原 与志樹・岡村 聡・山田 悟郎:北海道野幌丘陵と近隣低地のボーリングコア(中〜上部更新統)の層序検討*
--------------(昼休み)--------------
13:25 - 13:40 幹事会からの諸情報提供
---重野:技術士などのCPD(Continuing Professional Development)について
---宮坂:支笏・苔の洞門巡検の紹介
13:40 - 14:00 宮坂 省吾:イザベラ・バードが見た1874(明治7)年の樽前山火口*
14:00 - 14:20 川上 源太郎・高橋 良・輿水 健一・伊藤 陽司:羅臼町幌萌海岸で発生した地すべり調査報告
14:20 - 14:40 道総研地質研究所 津波堆積物調査チーム:北海道の日本海沿岸における津波履歴
--------------(休憩)--------------
15:00 - 15:20 在田 一則:2015年ゴルカ地震とインド-ユーラシア衝突前縁帯(ヒマラヤ)のテクトニクス*
15:20 - 15:40 貝瀬 長門・前田 仁一郎:東太平洋海膨 Hess Deep (IODP Site U1415) で採取された斑れい岩中の単斜輝石オイコクリストの形成過程: 高速拡大軸下の多様な組成のマグマの注入*
15:40 - 16:00 山下 康平・前田 仁一郎:北海道曲り沢かんらん岩体に見られる珪長質脈の微量元素組成について*
16:00 - 16:20 前田仁一郎:モホ不連続面の話し*
招待講演会 16:30-17:30
大槻 憲四郎(東北大学・名誉教授)「原発敷地内活断層評価(とくに東通原発)に関わる科学上の問題点」
17:30 閉会のあいさつ
申込み・問い合わせ先:
北海道支部幹事庶務:沢田 健
北海道大学大学院理学研究院・自然史科学部門
〒060-0810 札幌市北区北10条西8丁目
電話011-706-2733 メール:sawadak@mail.sci.hokudai.ac.jp
「地質の日」記念企画展示 「札幌の過去に見る洪水・土砂災害」
画像をクリックするとPDFファイルが
ダウンロードできます。(205KB)
札幌は自然災害の少ない街との印象がありますが、過去には大規模な洪水災害、震度6程度と推定される地震、強烈な台風などがありました。本展では、洪水災害を中心に札幌周辺の自然災害について展示・解説し、自然災害への備えの重要性を喚起します。
期間:2015年4月28日(火)〜5月31日(日) 開館時間 9:00〜17:00
月曜日は休館日です。GW連休中の休館日は7日(木)のみです。
会場:札幌市資料館1階 大通西13丁目
お問い合わせ先:札幌市博物館活動センター(電話:011-200-5002)入場無料
主催:「地質の日」展示実行委員会
共催:北海道大学総合博物館・日本地質学会北海道支部・産総研地質調査総合センター・道総研地質研究所・北海道博物館・札幌市博物館活動センター・北海道地質調査業協会
協力:国土地理院北海道地方測量部・株式会社シン技術コンサル・株式会社アイピ− 地質情報室・一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構
関連イベント
*市民セミナー:会場はともに、札幌市資料館2階研修室。入場無料/申込不要/座席数54席(立ち席可)
1)「札幌周辺の地震活動」笠原 稔氏(北大名誉教授)5月2日(土) 14:00〜15:30
2)「札幌市民が学ぶ広島土砂災害」田近 淳氏(株式会社ドーコン)5月9日(土) 14:00〜15:30
*市民地質巡検「札幌の洪水跡を訪ねる」
日時:5月24日(日)10:00〜15:00(予定)
巡検コース:中島公園を中心に豊平川沿いに徒歩で巡検
定員:30名
参加費:300円(保険代・資料代)
巡検申込方法:はがき(〒060-0001 札幌市中央区北1条西9丁目リンケージプラザ5階宛)・ファックス(011-200-5003)・e-メイル(museum [a] city.sapporo.jp)により、住所・氏名・年齢・連絡先をそえて、札幌市博物館活動センター宛お知らせください(5月14日必着・多数時抽選)抽選の結果は全員に郵送等でお知らせします。
「北海道地質百選」のウェブサイトを全面的に更新しました
北海道支部では「北海道地質百選」の活動を行ってきました.今回,2009年地質の日を期してウェブサイトを全面的に更新しました.北海道の魅力ある地質・地形を紹介しています.ぜひご覧になって下さい.
また,「北海道にはこんな面白い地質があるよ」と言う材料をお持ちであれば,どしどし投稿をお願いいたします.投稿方法などはウェブサイトをご覧下さい.
ウェブサイトは下記の通りです.
<http://www.geosites-hokkaido.org/>
お問い合わせ:日本地質学会 北海道支部 北海道地質百選事務局
〒064-0807 札幌市中央区南7条西1丁目13 第3弘安ビル
明治コンサルタント株式会社気付
北海道地質百選事務局事務局長 重野聖之
TEL 011-562-3066 FAX 011-562-3199
mail:jimu@geosites-hokkaido.org
<2014年度の活動はこちら>
<2010年度の活動はこちら>
<2009年度の活動はこちら>
2008年度各賞受賞者
2008年度各賞受賞者
■日本地質学会賞
■柵山雅則賞
■論文賞(3件)
■小藤賞
■研究奨励賞(3件)
■Island Arc賞
日本地質学会賞
受賞者:榎並正樹(名古屋大学大学院環境学研究科)
対象研究テーマ:高圧・超高圧変成岩の研究
榎並正樹氏は,造岩鉱物の詳細な共生関係と化学組成に立脚した高圧・超高圧変成岩の温度−圧力(P-T)経路を解析する手法を用いて,日本のみならず世界の重要な変成帯を研究し変成帯のテクトニクス解析に多大な貢献をした.
四国中央部の三波川変成帯においては,含有する斜長石を大量にEPMA分析して,従前の黒雲母帯の中に最高変成度の灰曹長石-黒雲母帯が存在することを見出し,三波川変成帯に代表される沈み込み型変成帯の形成を理解するための重要な知見をもたらした.また,ザクロ石の累帯構造から累進P-T経路を詳細に推定し,曹長石-Na輝石-石英共生を持つ岩石から高精度の変成圧力を決定して変成場のテクトニクスを論じた.近年では,愛媛県東部の東赤石における含ザクロ石超苦鉄質岩から沈み込み時のP-T経路を解析した.同氏はまたラマン分光分析法を駆使し,ザクロ石に包有される石英のラマンスペクトルから変成圧力条件を推定する方法を提唱した.これにより,別子地域の三波川帯の高変成度部は,従来考えられていたよりも広範囲にエクロジャイト相変成作用を経験したことが判明しつつある.これは三波川変成帯のテクトニクスを理解する上で極めて重要な知見である.
また,榎並氏は,四国の三波川変成帯に貫入する玄武岩質火山岩に捕獲されているマントル物質中からの,日本で初めての天然ダイヤモンドの産出報告にも共同研究者として参加している.この研究でもラマン分光分析法が最大限に生かされた.
榎並氏は高圧・超高圧変成岩の研究で緑れん石に着目し続けた.その成果は国際的に認められ,米国鉱物学会の Reviews in Mineralogy & Geochemistry “Epidotes volume”を共同執筆した.高圧・超高圧条件下では,緑れん石族鉱物がSrやREEの貯蔵相になってプレート収束域の地殻─上部マントル間の元素移動を担う,とした研究は極めて独創的なものである.同氏の論文は多数の研究者に引用され,変成岩岩石学に大きく貢献している.
榎並氏は,地質学雑誌やIsland Arcに多数の論文を発表し,地質学論集no.49の「21世紀に向けての岩石学の展望−I. 高圧変成帯を中心として-」や「日本地方地質誌 中部地方」の執筆も手がけているばかりでなく,岩石専門部会長や地質学雑誌編集委員などを歴任し,本学会ホームページの執筆や更新に携わり,日本地質学会の活動に大きく貢献している.
以上のように,榎並正樹氏は地質学において多大な功績・実績があり,日本地質学会賞に値するものである.
ページTOPへ戻る
日本地質学会論文賞(3件)
受賞論文:竹内 誠・河合政岐・野田 篤・杉本憲彦・横田秀晴・小嶋 智・大野研也・丹羽正和・大場穂高,2004,飛騨外縁帯白馬岳地域のペルム系白馬岳層の層序および蛇紋岩との関係.地質学雑誌,第110巻,第11号, p.715-730.
本論文は,それまでメランジュ相付加体あるいはオリストストロームと考えられてきたペルム系白馬岳層が整然相(陸棚相)堆積物であることを見いだし,また,蛇紋岩中のメランジュ・ブロックとされていた白馬岳層が蛇紋岩の構造的下位にあることを明らかにするなど,飛騨外縁帯の地質を考える上で重要な新知見を提供し,飛騨ナップ説に疑問を投げかける興味深い議論を展開している.白馬岳地域という複雑な地質の急峻な山岳地帯を綿密に地質調査した様子は,図示された5葉のルートマップや地質図から読み取ることができる.露頭写真・顕微鏡写真を交えた岩相記載がしっかりなされているほか,地質柱状対比図も適切に組み立てられている.調査結果からまとめられた総合柱状図による周辺地域との層序比較も,先行研究の情報を網羅して堅実に考察されている.記述は要点を押さえて簡潔に書かれており,図表類も丁寧かつ見やすく描かれている.本論文は,野外地質調査の成果を丁寧にとりまとめて,そのデータを基本に忠実にして必要十分に提示・考察できている点で,完成度が高くかつ学術的意義も大きいことから,日本地質学会論文賞にふさわしいものである.
受賞論文:清川昌一,2006,ベリース国に分布する白亜紀・第三紀境界周辺層,アルビオン層:チチュルブクレータに近接したイジェクタとその堆積層.地質学雑誌,第112巻,第12号, p.730-748.
本論文は,中米ユカタン半島南東部ベリース北部のK/T境界層であるアルビオン層の陸上露頭において,詳細な層序・堆積相およびその側方変化から隕石衝突現象の地質学的証拠を具体的データで論証した論文である.地質柱状に示された岩相,古流向データ,イジェクタ堆積物のダイアミクタイトに含まれる礫の粒径・円磨度・礫/基質比など,堆積学のオーソドックスな手法が中心であるが,多数の図と写真でそれらのデータがバランスよく表示されている.露頭観察と堆積物粒子の分析に基づいた研究で,ここまで隕石衝突放出堆積物の実態を明らかにできたことは注目に値する.また,膨大な先行研究の問題点を把握した上での丁寧な考察は,他分野の研究者にも読み応えがある.K/T境界の隕石衝突クレーター起源堆積物という注目度の高いテーマについて,海外のフィールドを対象に丁寧な地質調査に基づいて,現地研究者がなしえなかったことを成功した点で評価できる.よって本論文は日本地質学会論文賞にふさわしいものである.
受賞論文:Aoki, K., Iizuka, T., Hirata, T., Maruyama, S. and Terabayashi, M., 2007, Tectonic boundary between the Sanbagawa belt and the Shimanto belt in central Shikoku, Japan. 地質学雑誌,第113巻,第5号, p.171-183.
この論文は,三波川変成帯大歩危地域の変成岩から分離したジルコン粒子の各部分について,レーザー照射式誘導結合プラズマ質量分析装置を用いてU-Pb年代を決定し,構造的下位の小歩危層と川口層には白亜紀後期の砕屑性ジルコンが含まれるのに対し,構造的上位の三縄層には1,800 Maより若いジルコンが含まれないことを見出し,小歩危層と川口層の原岩は白亜紀付加体,つまり四万十帯であり,三縄層と川口層の境界が三波川帯と四万十帯の境界であると結論した.これは従来から予想されていた西南日本外帯北部のナップ構造を実証する結果であり,日本の地体構造論と構造発達史の研究を大きく進歩させるものとして高く評価される.世界で最も良く研究された変成帯である三波川帯と,付加体である四万十帯の地体構造区分が新たに明確にされたことの意義は,日本列島の地質研究のみならずプレート沈み込み帯の研究においても大きい.よって本論文は日本地質学会論文賞にふさわしいものである.
ページTOPへ戻る
日本地質学会小藤賞(1件)
受賞論文:斎藤 眞・川上俊介・小笠原正継,2007,始新世放散虫化石の発見に基づく屋久島の四万十帯付加体の帰属.地質学雑誌,第113巻,第6号, p.266-269.
屋久島の付加体は中期中新世の屋久島花崗岩による接触変成作用を被り,付加体の帰属の解明に貢献する化石の情報が全く無かった.著者らは,岩相から白亜紀付加体(四万十帯)に対比されると考えられていた屋久島の付加体から,初めて始新世の放散虫化石の抽出に成功し,九州本土の日向層群に対比されることを明らかにした.本論は,地質図幅の作成に関わる地道な研究によって発見された化石とその産出の意義を速報したものであり,地道でオーソドックスな野外地質の研究が実を結んだものと言える.屋久島は世界遺産に登録されており,その地質学的な位置づけが明らかになったことは,屋久島の地質を多くの人に知ってもらうために極めて重要な役割を果たすことになろう.このように,本論は,日本の地質構造論に重要なデータを提供しており,社会的にもインパクトが大きいことから,日本地質学会小藤賞に値する.
ページTOPへ戻る
日本地質学会研究奨励賞(3件)
受賞者:丹羽正和(日本原子力研究開発機構地層処分研究開発部門) 受賞対象論文:丹羽正和,2006,海洋性岩石のスラブで特徴付けられる付加体の岩相と変形構造〜岐阜県高山地域の美濃帯小八賀川(こやちががわ)コンプレックスを例として〜.地質学雑誌,第112巻,第6号, p.371-389.
この論文は,岐阜県高山地域の標高800mを越える山地において地道な地質調査を行い,露頭観察や岩石試料の定方位薄片の観察により,美濃・丹波帯のジュラ紀後期〜白亜紀前期付加体の実態を明らかにしている.最大の成果は,緑色岩に富むジュラ紀中期付加体である小八賀川コンプレックスの変形がtop-to-the-eastであり,従来の研究がいずれもtop-to-the-westを示しているのとは逆であることを見出した点にある.そして,ジュラ紀前〜中期とジュラ紀後期〜白亜紀前期の付加体における研究結果を比較して,付加年代によって海洋プレートの運動方向が異なる可能性を示唆した.色刷りの詳細な地質図やルートマップおよび多数の露頭・顕微鏡写真によって説得力のあるデータ表示を行い,わかりやすいモデル図を用いて適切に議論しており,複雑な美濃丹波帯の構造を見事に描いた力作として地質学の論文の模範となり,この地帯の研究に一石を投じたものとして価値がある.よって丹羽正和氏は日本地質学会研究奨励賞を授与するにふさわしい.
受賞者:長谷川 健(北海道大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻) 受賞対象論文:長谷川 健・中川光弘,2007,北海道東部,阿寒カルデラ周辺の前-中期更新世火砕堆積物の層序.地質学雑誌,第113巻,第2号, p.53-72.
本論文は,北海道の阿寒カルデラ周辺の前中期更新世火砕性堆積物について,広域におよぶ岩相の追跡と詳細な対比で40ユニットにおよぶ噴火ユニットと17の噴火グループを識別し,100万年以上にわたる層序と噴火史を組み立てた力作である.個々の火砕堆積物については岩相と岩石学的な記載が丹念に詳述されており,大量の化学分析データも見やすく示されている.精緻に認定された層序ユニットは,既存の層序を大幅に改訂しただけでなく,複数のユニットからなる噴火グループの識別を可能にし,噴火史復元の解像度を大きく向上させている.したがって,カルデラの年代と形成過程の考察に基づく火山活動の変遷史は,説得力あるものにまとまっている.また,本論には,地質図,地質断面図,柱状対比図,露頭写真,岩石学的分析値表とそれらのグラフ,噴火史復元図がバランスよく配置され,印刷制限一杯の大論文に仕上がっている.日本の火山地質研究の基礎となる重要な論文であり,筆頭著者の地道な調査・研究姿勢がよく現れている.よって長谷川 健氏は日本地質学会研究奨励賞を授与するにふさわしい.
受賞者:福成徹三(石油天然ガス・金属鉱物資源機構) 対象論文:Fukunari, T. and Wallis, S, 2007, Structural evidence for large-scale top-to-the-north normal shear displacement along the MTL in Southwest Japan. Island Arc, vol.16, no.2, p.243-261.
西南日本を内帯と外帯に分かつ中央構造線(MTL)は,白亜紀から現在までの長い活動履歴を持つ大規模な横ずれ断層として世界的に注目されている.本論文ではMTLの運動像を明らかにするために,南側に分布する三波川変成帯の地質構造に記録されている情報に着目した.緻密な野外観察を行い,数多くのデータを丁寧に整理した結果,三波川帯に記録された多くの運動指標は,横ずれではなく南北方向の正断層運動を示すことが明らかになった.さらに,褶曲軸面の傾斜がMTLに向かって低角となる変化に気付き,MTLの正断層運動に関連づけて,正断層の深度と変位量を制約する新しいモデルを提案した.MTLに沿った正断層運動の報告はこれまでにもあったが,本論文によって初めて,正断層運動の規模とMTLとの関係が明示された.新たなMTLの運動像を提示する本論文は,MTLと西南日本のテクトニクスを見直す画期的な内容を含む優秀な研究成果である.よって福成徹三氏は日本地質学会研究奨励賞を授与するにふさわしい.
ページTOPへ戻る
日本地質学会柵山雅則賞
受賞者:片山郁夫(広島大学地球惑星システム学専攻)
対象研究テーマ:沈み込み帯のダイナミクスと水の役割
片山郁夫氏は,(1) 超高圧変成岩の温度圧力履歴の解析,(2) 沈み込み帯における水の循環,および (3) カンラン石の結晶格子選択配向とマントルダイナミクスの研究において,顕著な業績をあげてきた.一連の研究によって同氏は沈み込み帯のダイナミクスの解明に大きな貢献をし,国際的にも高い評価を得ている. 超高圧変成岩の研究では,片山氏は最も高い温度圧力を経験したとされるコクチェタフ(カザフスタン北部)変成帯を調査し,ジルコンの中に保存されたダイヤモンド・コース石を含む19種類もの鉱物の分析およびSHRIMPによる同位体年代測定の結果から,同変成岩の初期温度圧力履歴を決定した.ジルコン中の鉱物から決まった温度圧力条件は母岩から得られた結果よりもより高い圧力値を示しており,変形・化学反応を受けにくいジルコンが母岩よりもより超高圧下の履歴を記憶していることが判明した.この成果は超高圧変成岩の研究に大きなインパクトを与えた. 片山氏は,赤外吸収分光・SIMS等を用いて超高圧変成岩中の無水鉱物(ザクロ石や単斜輝石など)を分析し,それらの鉱物には300〜1500 ppmの水が含有されていることを初めて見いだした.それまでは含水鉱物がマントル中の水輸送の担い手であると考えられていたが,既知の含水鉱物が3GPa, 800℃以上の高温高圧条件では不安定であることから,水をマントル深部まで運び込むことはできないと考えられていた.片山氏は無水鉱物によっても水が輸送される可能性があることを示し,マントル中の水の循環を考える上で新しい視点を与えた. 片山氏はさらに,含水条件及び温度条件によって,上部マントルの主要構成鉱物であるカンラン石の結晶格子選択配向が大きく変わることを詳細な変形実験によって明らかにした.そしてその結果を使って,東北日本で報告されているマントルの横波偏向異方性をマントルウェッジが低温・含水条件下で流動するモデルによって見事に説明した.この成果は,近年のマントルダイナミクス研究における最も重要な研究結果の一つである. 片山氏はまだ32才であるが,すでに合計43編の論文を執筆している.これらの論文が公表されてから既に800回以上の引用回数があり,同氏の研究が大きなインパクトを与えてきたことがわかる.同氏は地球惑星科学の幅広い分野に強い関心をもち,フィールド・実験・観測を融合して独自の研究分野と手法を開拓しつつある. 以上のように片山郁夫氏の質・量ともに優れた業績は,日本地質学会柵山雅則賞に値する.
ページTOPへ戻る
日本地質学会Island Arc賞
受賞論文:Chang Whan Oh, Sung Won Kim, In-Chang Ryu, Toshinori Okada, Hironobu Hyodo and Tetsumaru Itaya, 2004, Tectono-metamorphic evolution of the Okcheon Metamorphic Belt, South Korea: Tectonic implications in East Asia. Island Arc, 13, 387-402.
本論文は日韓の研究チームによる沃川帯の総合的な地球化学的研究の成果である.沃川帯は韓国や東アジアの地質構造にとって不可解ながらも重要な場所であり,本論文はこの地域の理解に重要な貢献をしている.雲母のK-Ar法や40Ar/39Ar法,ジルコンのU-Pb法による新しい年代値が提示され,岩相層序,構造,石墨結晶化度を組み合わせて,根拠に基づいた理路整然とした沃川帯の地史を組み立てている.加えて著書らは,この地域の既存データによる徹底したレビューを提示し,後期古生代の中P/T変成作用と,それに続く花崗岩貫入に伴うジュラ紀の低P/T変成作用があったことを結論づけている.そして,中国−韓国−日本のプレートテクトニクス進化過程の枠組みの中でこれらのイベントが地質学的にいかに重要であったかを論じている. 本論文は,2006年Thompson Science IndexのIsland Arc全論文中における被引用度数最高位を受けている.第一著者のOh氏はすでにIsland Arcによく引用される別の論文 (Vol. 7, p. 36-51, 1998) を著しており,最近は東アジアに関する重要な論文を国際学術雑誌に数多く発表している.こうした一連の研究は,Dabie-Sulu超高圧変成帯の東方延長に関する世界規模の議論を促進させてきている.また,Oh氏はこの数年Island Arcの共同編集者としても貢献している. 本論文の科学的なインパクトとOh氏の国際的な研究活動を総合して,2008年Island Arc賞を授与するにふさわしい.
東北支部
東北支部 2021.3.31更新
東北支部会では下記の要領で令和3年度総会を行います.
東北支部会令和3年度支部総会
日時:2022年3月27(日)13:00〜15:00 Zoom形式
13:00〜13:30 招待講演 (秋田大学・松井浩紀)「有孔虫化石に基づく過去150万年間の南極前線復元:これまでの成果と自動分類の試み」
13:30〜14:00 東北支部会総会 (活動・会計報告,2022年度以降の幹事校について)
14:00〜15:00 懇談会
申込み・問い合わせ先:
東北支部幹事庶務:郄嶋礼詩
東北大学総合学術博物館 〒980-8578 仙台市青葉区荒巻字青葉6−3
電話022-795-6620
E-mail: reishi.takashima.a7[at]tohoku.ac.jp
2020年度東北支部総会代替企画のお知らせ
2021.3.31掲載
2020年度東北支部総会代替企画のお知らせ
収束の目途が見えない新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、2019 年度に引き続き、2020 年度の総会・講演会の開催を中止といたしました。しかしながら、その代替企画として支部の8名の講師にプレコロナ時代の海外のフィールドワークや調査航海の様子についてプレゼンテーション動画を作って頂きました。それぞれのフィールドワークや航海の目的や意義に簡単に触れてもらいながら、現地の光景・調査風景や作業の様子を紹介して頂きました。支部の学会員にプレコロナ時代を思い出して頂き、ポストコロナ時代へのモチベーションを上げて頂くことを意図しています。東北支部にとどまらず、全国の日本地質学会員だけでなく、国内外から誰でも動画コンテンツを観覧できるようにし、日本地質学会YouTube チャンネルのコンテンツ充実化のきっかけの1つになればと思っています。
【プレコロナ時代のフィールドワークなどを振り返る】
「フランスと日本における白亜系の調査」高嶋礼詩
「エチオピア・アファール」加々島慎一
「タンザニア、原生代造山帯の地質調査」辻森 樹
「プレコロナ時代のフィールドワーク:パタゴニア」折橋裕二
「プレコロナ時代の最新南極内陸地質調査」宇野正起
「プレコロナ時代のフィールドワーク:琉球列島」井龍康文
「南極海・調査航海」松井浩紀
「現在と過去の太平洋深海底に挑む」平野直人
▶︎ 動画再生リストはこちらから↓↓↓
https://youtube.com/playlist?list=PLzNrN5tM0I-sF_E72_NNMyVSO5NlDXM96
▶︎一般社団法人日本地質学会 YouTubeチャンネル↓↓↓
https://www.youtube.com/channel/UC99k2wQzX5PrlTNj7GXtu6Q
<問合せ・連絡先>
支部幹事 高嶋礼詩
〒980-8578 仙台市青葉区荒巻字青葉6−3 東北大学総合学術博物館
電子メール:reishi.takashima.a7 [at] tohoku.ac.jp
2019年度東北支部総会のお知らせ
2019年度日本地質学会東北支部総会のお知らせ
新型コロナウィルスの感染拡大が憂慮されるため、
2019年度支部総会は中止致します。(2020.2.23)
日時:2020年2月29日(土)〜3月1日(日)
場所:秋田大学教育文化学部(秋田市手形学園町1-1)
日程:
2月29日(土)13:30〜
シンポジウム「東北地方の火山災害の特性と防災の課題」,支部総会議事*1,個人講演*2,18:00〜 懇親会*3
3月1日(日)9:00〜12:00
個人講演*4
参加費:1,000円
*1 総会:欠席される方は委任状(様式任意)をメール,郵便等で下記連絡先までお送り下さい.委任先は出席される会員(氏名明記)または議長として下さい.
*2 個人講演(2/29):15分程度の口頭発表とポスター発表を受付けます.メール,ファックス,郵便等で下記連絡先までお申込下さい.講演申込および要旨締切は2月17日(月)とします.連名発表者の中に会員が含まれていれば筆頭発表者は会員・非会員を問いません.講演要旨は,学術大会の様式に従って下さい.
*3 懇親会:会場から徒歩3分の藤井酒店にてキャッシュ・オン・デリバリー方式で行います.会費1500円程度(つまみのみ)で,飲み物代は注文の都度各自支払い.収容40名以内.懇親会参加ご希望の方は2月17日(月)までに下記連絡先までお申込下さい.
*4個人講演(3/1): 講演数が少ない場合には,3月1日の日程がキャンセルとなる場合もあります.
<問合せ・連絡先>
支部幹事 西川 治
〒010-8502 秋田市手形大沢28-2 秋田大学鉱業博物館
tel:018-889-2467
fax:018-889-2465
e-メール:nishi[at]gipc.akita-u.ac.jp([at]を@マークにして下さい)
見学会のお知らせ
地質見学会:能代・八峰・白神地域のジオサイトを訪ねて
東北支部会主催の地質見学会を以下の通り開催いたします.皆様,奮ってご参加ください.
「能代・八峰・白神地域のジオサイトを訪ねて」
能代・八峰地域の活断層・変動地形・海岸砂丘・素波里安山岩,白神岳複合花崗岩質岩体とマイロナイト帯,宝永岩館地震に関連した大規模地滑り地形と湖沼群(十二湖)などを一泊二日(宿泊地:八峰町)の日程で見学します.
案内人:林信太郎・藤本幸雄・西川 治
募集人数:15名
日時:2019年6月22日(土)〜23日(日)
集合・解散場所:秋田市内
概算費用:15,000〜18,000円(初日の昼食は持参)
参加申込締切:6月4日(火)
申し込み・問い合わせ先:
西川 治(秋田大学鉱業博物館)秋田市手形大沢28−2
電話 018-889-2461,2467
メール nishi@gipc.akita-u.ac.jp
2018年度東北支部総会のお知らせ
2018年度日本地質学会東北支部総会のお知らせ
▶▶▶プログラム 2019.3.14更新 NEW
日時:2019年3月16日(土)〜17日(日)(注)17日の日程はキャンセルになりました
場所:秋田大学教育文化学部3号館150番教室(60周年記念ホールの斜め向かい)
(〒010-8502 秋田市手形学園町1番1号)
アクセス:
秋田駅東口から徒歩15分
秋田中央交通 手形山大学病院線(秋田駅西口12番乗り場)秋田大学前下車(約5分)
日程
16日(土)13:30〜 支部総会議事*1,個人講演*2,18:00〜 懇親会*3
17日(日)9:00〜 個人講演*4
*1:欠席される方は委任状(様式任意)をメール,郵便等で下記連絡先までお送り下さい.委任先は出席される会員(氏名明記)または議長として下さい.
*2:15分程度の口頭発表とポスター発表を受付けます.メール,ファックス,郵便等で下記連絡先までお申込下さい.申込締切は3月4日(月),要旨締切は3月11日(月)とします.連名発表者の中に会員が含まれていれば筆頭発表者は会員・非会員を問いませんので,卒論・修論等の内容発表の場としてもご利用下さい.もちろん,ベテラン会員の発表も歓迎致します.
*3:会費4,000円程度での懇親会を予定しております.3月4日(月)までに下記連絡先までお申込下さい.
*4:講演者数が少ない場合には,17日の日程がキャンセルとなる場合もあります.
<問合せ・連絡先>
〒010-8502 秋田市手形大沢28-2 秋田大学鉱業博物館
西川 治
tel:018-889-2467
fax:018-889-2465
e-メール:nishi[at]gipc.akita-u.ac.jp
2017年度東北支部総会のお知らせ
2017年度東北支部総会のお知らせ
日程:2018年3月17日(土)午後〜18日(日)午前
場所:弘前大学理工学部 1号館426号室(弘前市文京町3)
アクセスマップ>http://www.st.hirosaki-u.ac.jp/info/access.html
講演申込締切・懇親会(17日夜)参加申込締切:3月7日(水)
申込先:支部幹事 根本直樹(弘前大学)nemoto[at]hirosaki-u.ac.jp
西日本支部
西日本支部
24.12.5掲載 25.2.25更新
西日本支部令和6年度総会・第175回例会の案内
【後援:北九州市立自然史・歴史博物館】
画像をクリックするとプログラム・講演要旨PDFをDL頂けます
開催日:2025年3月1日(土)
会場:北九州市立自然史・歴史博物館 ガイド館
講演は口頭・ポスター発表.懇親会は開催しません.
例会参加費:会員(一般)1,000円/人,会員(学生) 500円/人,非会員(一般)2,000円/人,非会員(学生) 1,000円/人
講演条件:日本地質学会会員であること.ただし、学生・院生に限り共同講演者に日本地質学会の会員がいれば,筆頭講演者が非会員でも構いません.
参加・講演申込(1月31日締切)
参加・講演申込: 次の情報を下記のオンラインフォームにご記入ください.(1) 連絡先(氏名・所属・e-mail・電話) (2)登録区分(会員(一般・学生)・非会員(一般・学生)) (3) 講演希望(口頭・ポスターを明記)
参加・講演申込フォームURL https://forms.gle/F49xeRZLRjrWTeUm7
口頭発表は15分,ポスターのサイズは,幅90cm以下,高さ170cm以下.
学生発表者には口頭・ポスターともに「優秀発表賞」を設けております.
申込締切: 1月31日(金)
講演要旨の提出(2月17日締切)
講演要旨原稿は定形のフォーマットを使用し(Word テンプレート ダウンロードはこちら),Word形式で西日本支部事務局までe-mailにてお送り下さい.
締切:2月17日(月)
提出先:西日本支部事務局 尾上哲治(onoue.tetsuji.464[at]m.kyushu-u.ac.jp)※[at]を@マークにして送信してください
CPD単位証明書の発行
地質技術者への継続教育の一環として,大会参加者・発表者へCPD単位を発行します.大会参加と口頭発表の「受講証明書」は,支部会終了後に郵送いたします.
口頭発表:0.4×発表時間(m) 例)口頭発表15分の場合:0.4×15=6単位
学会参加:1 × 滞在時間(休憩時間等は除く)
(参考)CPD重み係数表:https://www.geo-schooling.jp/
委任状
総会にご出席できない方は,下記のオンラインフォームより、委任状を2月27日(木)までにご提出ください.
委任状フォームURL https://forms.gle/9DANJ7wYkYfmoLST7
お問い合わせ先(西日本支部事務局)
〒819-0395 福岡市西区元岡744
九州大学 理学研究院 地球惑星科学部門
尾上哲治
(tel: 092-802-4246,e-mail: onoue.tetsuji.464[at]m.kyushu-u.ac.jp) ※[at]を@マークにして送信してください
23.12.4掲載 24.2.28更新
西日本支部令和5年度総会・第174回例会の案内
【共催:薩摩川内市役所】
画像をクリックするとプログラム・講演要旨PDFをDL頂けます
開催日:2024年3月2日(土)
会場:薩摩川内市川内駅コンベンションセンターSSプラザせんだい 3階会議室
講演は口頭・ポスター発表.
懇親会は開催しません.
例会参加費:
会員(一般)1,000円/人,会員(学生) 500円/人
非会員(一般)2,000円/人,非会員(学生) 1,000円/人
講演条件:日本地質学会会員であること.ただし、学生・院生に限り共同講演者に日本地質学会の会員がいれば,筆頭講演者が非会員でも構いません.
参加・講演申込
参加・講演申込: 次の情報を下記のオンラインフォームにご記入ください.(1) 連絡先(氏名・所属・e-mail・電話) (2)登録区分(会員(一般・学生)・非会員(一般・学生)) (3) 講演希望(口頭・ポスターを明記) https://forms.gle/dWW97VSdxLwa3DLP8
口頭発表は15分,ポスターのサイズは,幅90cm以下,高さ170cm以下.
学生発表者には口頭・ポスターともに「優秀発表賞」を設けております.
申込締切: 2月1日(木)
講演要旨の提出
講演要旨原稿は定形のフォーマットを使用し(Word テンプレート ダウンロードはこちら),Word形式で西日本支部事務局までe-mailにてお送り下さい.
締切:2月22日(木)
提出先:西日本支部事務局 尾上哲治(onoue.tetsuji.464[at]m.kyushu-u.ac.jp) ※[at]を@マークにして送信してください
CPD単位証明書の発行
地質技術者への継続教育の一環として,大会参加者・発表者へCPD単位を発行します.大会参加と口頭発表の「受講証明書」は,支部会終了後に郵送いたします.
口頭発表:5×発表時間(h)(15分の場合:5×1/4h=1.25単位)
学会参加:1 × 滞在時間(休憩時間等は除く)
委任状
総会にご出席できない方は,下記様式の委任状を2月29日(木)までに支部事務局へお送り下さい(e-mailでも結構です).
=============== 委任状 ==================
日本地質学会西日本支部令和5年度総会・第174回例会における議決権を, 様に委任いたします.
令和 年 月 日
御氏名:
==========================================
委任先が無記名の場合は,「議長」とさせて頂きます.
お問い合わせ先および委任状送付先(西日本支部事務局)
〒819-0395 福岡市西区元岡744
九州大学 理学研究院 地球惑星科学部門
尾上哲治(tel: 092-802-4246,e-mail: onoue.tetsuji.464[at]m.kyushu-u.ac.jp)
※[at]を@マークにして送信してください
22.11.15掲載 23.1.13,1.24,2.20,2.28更新
西日本支部令和4年度総会・第173回例会の案内
【共催:島根大学総合理工学部地球科学科】
開催日:2023年3月4日(土)
※クリックすると大きな画像でご覧いただけます
会場:島根大学教養講義室棟2号館(注) 総合理工学部多目的ホールから変更になりました.
講演は口頭・ポスター発表.
懇親会は開催しません.(注)状況によっては,オンラインでの開催を検討します.(注) オンラインでの開催は致しません.
例会参加費:一般 1,000円/人,学生 500円/人
参加条件:日本地質学会会員であること.ただし、学生・院生に限り共同講演者に日本地質学会の会員がいれば,筆頭講演者が非会員でも構いません.
画像をクリックするとプログラム・講演要旨PDFをDL頂けます
◯講演プログラム・講演要旨(PDF)はこちらダウンロードできます.(2.28掲載)
〇例会・総会への参加申込について
講演申込: 次の情報をe-mailでお知らせ下さい.〔1〕 連絡先(氏名・所属・e-mail・電話) 〔2〕 講演希望 [講演タイトル(口頭・ポスターを明記)・発表者・所属] 〔3〕 一般 or 学生
発表は口頭発表,ポスター発表とし,質疑応答込みで15分間です.
学生発表者には口頭・ポスターともに「優秀発表賞」を設けております.
ポスターのサイズは,幅1200 mm以内,高さ1800 mm以内に収めてください.
参加のみの申込: 上記の〔1〕,〔3〕を支部事務局までe-mailにてお知らせ下さい.
申込締切:講演申込・参加のみの申し込み共に2月1日(水)
申込先:小松俊文: tkomatsu[at]kumamoto-u.ac.jpと田中源吾:gengo[at]kumamoto-u.ac.jpの両方のメールアドレス宛にお願いします.
※[at]を@マークにして送信してください
お問い合わせ先(西日本支部事務局) :
〒860-8555 熊本県熊本市中央区黒髪2-39-1 熊本大学 先端科学研究部
小松俊文(tel: 096-342-3425,e-mail: tkomatsu[at]kumamoto-u.ac.jp)
田中源吾(tel: 096-342-3426,e-mail: gengo[at]kumamoto-u.ac.jp)
※[at]を@マークにして送信してください
〇講演要旨の提出について 提出締切: 2月25日(土)
講演要旨原稿は定形のフォーマットを使用し(Word テンプレート ダウンロードはこちら),Word形式で西日本支部事務局までe-mailにてお送り下さい.
〇CPD単位証明書の発行について
地質技術者への継続教育の一環として,大会参加者・発表者へCPD単位を発行します.大会参加と口頭発表の「受講証明書」は,支部会終了後に郵送いたします.
口頭発表:5×発表時間(h)(15分の場合:5×1/4h=1.25単位)
学会参加:1 × 滞在時間(休憩時間等は除く)
〇委任状について
総会にご出席できない方は,下記様式の委任状を2月28日(火)までに支部事務局へお送り下さい(e-mailでも結構です).
=============== 委任状 ==================
日本地質学会西日本支部令和4年度総会・第173回例会における議決権を,
様に委任いたします.
令和 年 月 日
御氏名:
==========================================
委任先が無記名の場合は,「議長」とさせて頂きます.
お問い合わせ先および委任状送付先(西日本支部事務局):
〒860-8555 熊本県熊本市中央区黒髪2-39-1 熊本大学 先端科学研究部
小松俊文(tel: 096-342-3425,e-mail: tkomatsu[at]kumamoto-u.ac.jp)
田中源吾(tel: 096-342-3426,e-mail: gengo[at]kumamoto-u.ac.jp)
※[at]を@マークにして送信してください
2021.12.27掲載 12.28, 1.8, 1.20更新
西日本支部令和3年度総会・第172回例会の案内
新型コロナウィルスの感染拡大が憂慮されるため、本年度支部総会、第172回例会はオンライン開催と致します。
開催日:2022年3月5日(土)
画像をクリックするとプログラム集PDFをDL頂けます
会場:Zoomオンライン(講演は口頭発表のみでポスター発表は実施しません)
参加費無料・要事前申込(1月31日締切)
発表会終了後にオンライン懇親会を開催します.
参加条件:日本地質学会会員であること.ただし、学生・院生に限り共同講演者に日本地質学会の会員がいれば,筆頭講演者が非会員でも構いません(2022年1月20日補足).
講演申込:
発表は口頭発表のみとし,質疑応答込みで15分間です.
学生発表者には「優秀発表賞」を設けております.
講演要旨原稿は地質学会学術大会のフォーマットと同じ形式(Word テンプレート ダウンロードはこちら)とし,Word形式で西日本支部事務局までe-mailにてお送り下さい(講演要旨締切日:後日連絡).
講演申込:次の情報をe-mailでお知らせ下さい.1. 連絡先(氏名・所属・e-mail・電話) 2. 講演希望(講演タイトル・発表者・所属) 3. 一般 or 学生 4. オンライン懇親会への参加 or 不参加
参加のみの申込:上記1,3,4を支部事務局までe-mailにてお知らせ下さい.
講演申込・参加のみの申込:1月31日(月)締切
申し込み先,小松俊文: tkomatsu[at]kumamoto-u.ac.jpと田中源吾:gengo[at]kumamoto-u.ac.jpの両方のメールアドレス宛にお願いします.
お問い合わせ先(西日本支部事務局) :〒860-8555 熊本県熊本市中央区黒髪2-39-1 熊本大学 先端科学研究部 小松俊文(tel: 096-342-3425,e-mail: tkomatsu[at]kumamoto-u.ac.jp)・田中源吾(tel: 096-342-3426,e-mail: gengo[at]kumamoto-u.ac.jp)
※[at]を@マークにして送信してください
CPD単位証明書の発行
地質技術者への継続教育の一環として,大会参加者・発表者へCPD単位を発行します.大会参加と口頭発表の「受講証明書」は,支部会終了後に郵送いたします.
口頭発表:5×発表時間(h)(15分の場合:5×1/4h=1.25単位)
学会参加:1 × 滞在時間(休憩時間等は除く)
委任状
総会にご出席できない方は,下記様式の委任状を2月28日(月)までに支部事務局へお送り下さい(e-mailでも結構です).
=============== 委任状 ==================
日本地質学会西日本支部令和3年度総会・第172回例会における議決権を,
様に委任いたします.
令和 年 月 日
御氏名:
==========================================
委任先が無記名の場合は,「議長」とさせて頂きます.
お問い合わせ先および委任状送付先(西日本支部事務局)
〒860-8555 熊本県熊本市中央区黒髪2-39-1
熊本大学 先端科学研究部
小松俊文(tel: 096-342-3425,e-mail: tkomatsu[at]kumamoto-u.ac.jp)
田中源吾(tel: 096-342-3426,e-mail: gengo[at]kumamoto-u.ac.jp)
※[at]を@マークにして送信してください
2019.11.5掲載 2020.2.25、3.23更新
西日本支部令和元年度総会・第171回例会の案内
新型コロナウィルスの感染拡大が憂慮されるため、
本年度支部総会、第171回例会は中止致します。(2020.2.23)
▶︎令和元 年度総会第171 回例会 講演要旨集(みなし講演)(2020.3.23掲載)NEW
【共催:北九州市立自然史・歴史博物館 いのちのたび博物館】
日時:令和2年2月29日(土)例会・総会
場所:北九州市立自然史・歴史博物館 いのちのたび博物館
博物館地図: http://www.kmnh.jp/access/#03
例会参加費:一般 1,000円/人,学生 500円/人(参加者は施設利用料(入館料等) 無料)
懇親会参加費(予定):一般 5,000円/人,学生 2,500円/人 ※懇親会はお申込者のみの受付となります(当日受付なし)
講演申込
・発表は口頭もしくはポスターです.
・口頭発表は15分(質疑込み),ポスターサイズは幅90cm以下,縦170cm以下.
・学生発表者には「優秀発表賞」を設けております.
・講演要旨原稿は地質学会年会のフォーマットと同じ形式とし,PDF(フォント埋め込み)とWord形式の両方を西日本支部事務局までe-mailにてお送り下さい.
・お申込みの際には,下記情報をあわせてお知らせ下さい.
連絡先(発表者氏名・所属・e-mail・電話)
発表様式(口頭・ポスター・どちらでも可,のいずれか)
一般 or 学生
懇親会の参加・不参加
参加のみの申込
上記1,3,4を支部事務局までe-mailにてお知らせ下さい.
講演申込・参加のみ申込 :2月14日(金)締切
CPD単位証明書の発行
地質技術者への継続教育の一環として,大会参加者・発表者へCPD単位を発行します.大会参加と口頭/ポスター発表の「受講証明書」は,当日15時以降に会場受付にてお渡しします.
ポスター発表:1×ポスター制作時間(h)(上限15)
口頭発表:5×発表時間(h)(15分の場合:5×1/4h=1.25単位)
学会参加:1 × 滞在時間(休憩時間等は除く)
委任状
総会にご出席できない方は,下記様式の委任状を支部事務局へお送り下さい.(e-mailでも結構です)
=============== 委任状 ==================
日本地質学会西日本支部令和元年度総会・第171回例会における議決権を,
様に委任いたします.
令和 年 月 日
御氏名:
==========================================
委任先が無記名の場合は,「議長」とさせて頂きます.
お問い合わせ先,および講演要旨原稿の送付先(西日本支部事務局)
〒890-0065 鹿児島県鹿児島市郡元1-21-35
鹿児島大学 理工学研究科 地球環境科 ハフィーズ ウル レーマン
(tel: 099-285-8147,e-mail: hafiz@sci.kagoshima-u.ac.jp)
2018.12.18掲載
西日本支部平成30年度総会・第170回例会の案内
講演プログラム(口頭発表) 2019.2.27更新
講演プログラム(ポスター発表) 2019.2.22公開
日時:2019(平成31年)年3月2日(土)例会・総会
場所:長崎大学 教育学部棟 本館4階
キャンパス地図http://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/access/bunkyo/index.html
・例会参加費:一般 1,000円/人,学生 500円/人
・懇親会参加費(予定):一般 5,000円/人,学生 2,500円/人
※懇親会はお申込者のみの受付となります(当日受付なし)
講演申込
・発表は口頭もしくはポスターです.
・口頭発表は15分(質疑込み),ポスターサイズは幅90cm以下,縦170cm以下.
・学生発表者には「優秀発表賞」を設けております.
・講演要旨原稿は地質学会年会のフォーマットと同じ形式とし,PDFファイル(フォント埋め込み)とWord形式ファイルの両方を西日本支部事務局までe-mailにてお送り下さい.
・お申込みの際には,下記情報をあわせてお知らせ下さい.
連絡先(発表者氏名・所属・e-mail・電話)
発表様式(口頭・ポスター・どちらでも可,のいずれか)
一般 or 学生
懇親会の参加・不参加
参加のみ
上記1),3),4)を支部事務局までe-mailにてお知らせ下さい.
※締め切りは2月15日(金)
CPD単位証明書の発行
地質技術者への継続教育の一環として,大会参加者・発表者へCPD単位を発行します.大会参加と口頭/ポスター発表の「受講証明書」は,当日15時以降に会場受付にてお渡しします.
・ポスター発表:1×ポスター制作時間(h)(上限15)
・口頭発表:5×発表時間(h)(15分の場合:5×1/4h=1.25単位)
・学会参加:1 × 滞在時間
委任状
総会にご出席できない方は,下記様式の委任状を支部事務局へお送り下さい.(e-mailでも結構です)
=============== 委任状 ==================
日本地質学会西日本支部平成30年度総会・第170回例会における議決権を,
( )様に委任いたします.
平成 年 月 日
御氏名:
==========================================
委任先が無記名の場合は,「議長」とさせて頂きます.
お問い合わせ先,および講演要旨原稿の送付先(西日本支部事務局)
〒690-8504 島根県松江市西川津町1060
島根大学 総合理工学部 地球科学科 亀井淳志
(tel: 0852-32-6454,e-mail: kamei-a@riko.shimane-u.ac.jp)
西日本支部平成29年度総会・第169回例会の案内
日時:平成30年 3月 3日(土)〜 4日(日)
場所:広島大学 東広島キャンパス 理学部 E棟002講義室
キャンパスまでの交通案内 <https://www.hiroshima-u.ac.jp/access/higashihiroshima>
3日(土)9:00〜
総会,例会,支部長講演,懇親会
4日(日)9:00〜
日本地質学会創立125周年記念行事:シンポジウム「中央構造線と中央構造線系活断層」(共催:広島大学インキュベーション事業「プレート収束域の物質科学研究拠点(略称:HiPeR)」)
地質学会創設時から提唱されていた“中央構造線”に関するシンポジウムを企画しました.
プログラム(PDF)(2018.3.1更新)
3月3日(土)総会・例会(口頭)・支部長講演会 / ポスター発表
3月4日(日)シンポジウム
・例会参加費:一般 1,000円/人,学生 500円/人
・懇親会参加費(予定):一般 5,000円/人,学生 2,000円/人
講演申込
・発表は口頭およびポスター形式を予定しております.
・口頭発表は15分,ポスターサイズは横幅90cm以下,縦180cm以下.
・優秀な発表を行った学生のための「優秀発表賞」を設けています.
・講演要旨原稿は地質学会年会のフォーマットと同じ形式とし,PDFファイル(フォント埋め込み)とWord形式ファイルの両方を支部事務局までe-mailにてお送り下さい.
・申込の際には下記の情報をあわせてお知らせ下さい。
連絡先(発表者氏名・所属・e-mail・電話)
発表様式(口頭・ポスター・どちらでも可,のいずれか)
学生か否か
懇親会の参加・不参加
講演申込締切:2月15日(木)17時
CPD単位証明書の発行
西日本支部では,地質技術者への継続教育の一環として,大会参加者・発表者へCPD単位を発行します.大会参加と口頭/ポスター発表の「受講証明書」は,当日15時以降に会場受付にてお渡しします.
・ ポスター発表:1×ポスター制作時間(h)(上限15)
・ 口頭発表:5×発表時間(h) 例)15分の場合:5×1/4h=1.25単位
・ 学会参加:1 × 滞在時間
委任状:総会にご出席いただけない方は下記様式の委任状を支部事務局へお送り下さい.
================== 委任状 ====================
日本地質学会西日本支部平成29年度総会・第169回例会における議決権を,
様に委任いたします.
平成 年 月 日
御氏名:
===============================================
問い合わせ,および講演要旨原稿送付先
西日本支部事務局 :
〒690-8504 島根県松江市西川津町1060
島根大学大学院総合理工学研究科地球資源環境学領域
亀井淳志
tel: 0852-32-6454 e-mail: kamei-a[at]riko.shimane-u.ac.jp
第三回西日本地質講習会(CPD講習会)
2017.4.10掲載
第三回西日本地質講習会(CPD講習会)
**お申込はこちらから**→http://arito.jp/cpd.html
主旨:本講習会は地質技術者と研究者が地質学の各分野の最新成果について議論し,情報交換し,互いに高め合う場とすることを目的としています.本講習会はジオスクーリングネットによるCPDポイントが発行されます.(ジオスクーリングネットのご登録はこちら)
主催:山口大学理学部地球圏システム科学科・日本地質学会西日本支部
講習会
5月17日(水)
会場:山口大学吉田キャンパス 大学会館
CPD単位:4時間(4単位) 参加費:5,000円(定員100名)
10:00-10:05 開会の挨拶
10:05-11:05 粘土鉱物の基礎 - 地質災害と関係して 澤井長雄(山口大学)
11:15-12:15 高温型変成帯の形成過程と放射年代の意味 志村俊昭(山口大学)
12:15-14:30 昼休み・ポスター発表(オプション) ・企業説明会(オプション)
14:30-15:30 岩石のデジタル化とモデリングによる持続可能な地下空間の利用 辻 健(九州大学)
15:40-16:40 建設工事における自然由来有害物質の地球科学と工学 太田岳洋(山口大学)
17:00- 懇親会(オプション)
地質巡検 「徳佐から津和野地域」
5月18日(木)
CPD単位:5単位 参加費:10,000円(最大25名)
09:00 山口大学吉田キャンパス発
「内陸部に見られる高塩濃度地下水の起源と湧出過程」 田中和広(山口大学)
17:00 山口大学吉田キャンパス着
研究発表会(オプション) 1単位 発表費3,000円
ポスター発表会.幅912mm × 1292mm以内
そのほか
・企業説明会ブース(オプション): ブース代10,000円
・懇親会:第2学生食堂「きらら」(参加費3,000円)
申込締切:5月8日(月)
お申込はこちらから→http://arito.jp/cpd.html
お問い合わせ
山口大学大学院創成科学研究科(理)
坂口有人 arito[at]yamaguchi-u.ac.jp([at]を@マークに変換して下さい)
西日本支部平成28年度総会・第168回例会の案内
2016.12.13掲載 2017.2.14更新
西日本支部平成28年度総会・第168回例会の案内
▶▷講演プログラム公開しました(2017.2.14更新)
***********************************************************************************
日時:平成29年2月18日(土)9:30〜 例会終了後 懇親会
*例会プログラムの詳細は講演確定後にお知らせします。
会場:宮崎大学(木花キャンパス)教育学部講義棟4階 L402 教室(案内図参照)
懇親会会場:宮崎市内中心部のホテルメリージュ(宮崎市橘通東3丁目1−11)
注意:
・昼食:弁当の販売はいたしません.18日は学内の生協食堂が営業しておりますし,キャンパス至近(講演会場からは歩いて3分程度)にコンビニエンスストアもありますので,それらをご利用ください.
・駐車場:車でお越しの場合は,教育学部北側(正門入って右側)もしくは東側(正門入って左側)の駐車場をご利用ください.キャンパス内のマップは,以下のURLでご確認ください.
https://www.miyazaki-u.ac.jp/guide/map/kibana
バスの時刻表:http://www.miyakoh.co.jp/bus/rosen/
・例会参加費:一般 1,000円/人,学生 500円/人
・懇親会参加費:一般 4,500円/人,学生 2,500円/人
講演申込
・発表は口頭またはポスター形式の何れかを選択。
・口頭発表は15分,ポスターサイズは横幅110cm以下,縦140cm以下。
・優秀な発表を行った学生のための「優秀発表賞」を設けています。
・講演要旨原稿は地質学会年会のフォーマットと同じ形式とし,PDFファイル(フォント埋め込み)とWord形式ファイルの両方を支部事務局までe-mailにてお送り下さい。
・申込の際には下記の情報をあわせてお知らせ下さい。
1)連絡先(発表者氏名・所属・e-mail・電話)
2)発表様式(口頭・ポスター・どちらでも可,のいずれか)
3)学生か否か
4)懇親会の参加・不参加
講演申込み締切:2月3日(金)17時
CPD単位証明書の発行
西日本支部では,地質技術者への継続教育の一環として大会参加者・発表者へCPD単位を発行します。大会参加と口頭/ポスター発表の「受講証明書」は,当日15時以降に会場受付にてお渡しします。
・ポスター発表:1×ポスター制作時間(h)(*上限15単位)
・口頭発表:3×発表時間(h)(例:20分の場合:3×1/3(h)=1単位)
・参加:1 × 滞在時間
(注)2016年6月よりCPDの算出方法が変更になりました.
委任状
総会にご出席いただけない方は下記様式の委任状を支部事務局へお送り下さい。
================== 委任状 ====================
日本地質学会西日本支部平成28年度総会・第168回例会における議決権を,
様に委任いたします。
平成 29 年 月 日
御氏名:
===============================================
問い合わせ,および講演要旨原稿送付先
西日本支部事務局 : 〒739-8526 東広島市鏡山 1-3-1
広島大学大学院理学研究科 地球惑星システム学教室
早坂康隆(tel: 082-424-7462,e-mail: hayasaka[at]hiroshima-u.ac.jp)
第二回西日本地質講習会(CPD講習会)
第二回西日本地質講習会(CPD講習会)
画像をクリックするとPDFが
ダウンロードできます
山口大学理学部地球圏システム科学科と日本地質学会西日本支部が共催し,地質技術者継続教育の一環として,基礎研究から応用研究までの最近の進歩をレビューし,情報交換を行い,研究者と技術者の互いのアップデートと地質学の発展を図ります.
主催:山口大学理学部地球圏システム科学科・日本地質学会西日本支部
場所:山口大学 大学会館2階(山口市吉田1677-1)
(1)日時:6月1日(水)10時〜 講習会5時間(5単位)
場所:山口大学 大学会館2階
参加費:会員 4000円(非会員 5000円)
参加者数:最大100名
10:00 地形学の活断層研究の10 年ダイジェスト:楮原京子 先生
11:10 断層の高速摩擦研究の10 年〜フィールドと実験室から〜:大橋聖和 先生
13:40 花崗岩マグマの形成・定置・風化:大和田正明 先生
14:50 花崗岩と土石流:金折裕司 先生
16:00 室戸:世界ジオパークへの道〜現場はここで困っている!〜:柚洞一央 先生
(2)6月2日(木)9時〜 地質巡検6時間(6単位)
参加費:会員 8000円(非会員 10000円)
参加者数:最低催行10名,最大30名
内容:須佐の地質・岩石と日本海の形成:今岡照喜 先生
その他:
・CPD 単位は1 日単位で発行します.
・地質巡検の最低催行人数は10 名です.
・企業説明会も開催します.お問い合わせください.
・初日の夜には簡単な懇親会も開催します(事前に坂口に出欠をお知らせください:3,000 円).
申込方法:ジオスクーリングネットからお申し込みください<https://www.geo-schooling.jp/>
申込締切:5月19 日(木)
問い合わせ先:山口大学理学部 坂口有人
メール arito[at]yamaguchi-u.ac.jp
tel 083-933-5764
【企業説明会】6月1日の昼休み(1時間半)に企業説明会を実施します.希望の方はご連絡下さい(ブース代10,000円)
西日本支部平成27年度総会・第167回例会
西日本支部平成27年度総会・第167回例会
★講演プログラム(口頭・ポスター)を公開しました(2016.2.12)
開催日時:平成28年2月20日(土) 9:00〜 例会終了後 懇親会
(幹事会は19日 17:00〜)
開催場所:熊本大学 黒髪南キャンパス 理学部2号館
・キャンパスまでの交通案内
http://www.kumamoto-u.ac.jp/campusjouhou
http://www.kumamoto-u.ac.jp/campusjouhou/access
・キャンパスマップ 理学部2号館は地図の7
http://www.kumamoto-u.ac.jp/campusjouhou/map_kurokami_2
例会参加費:一般 1,000円/人,学生 500円/人
懇親会参加費(予定):一般 4,500円/人,学生 2,500円/人
特別講演:佐野弘好 支部長(九州大学・教授)
例会プログラムの詳細は講演確定後にお知らせします.
講演申込>講演申込み締切:2月4日(木)17時
・発表は口頭およびポスター形式を予定しております.
・口頭発表は15分,ポスターサイズは横幅90cm以下,縦180cm以下.
・優秀な発表を行った学生のための「優秀発表賞」を設けています.
・講演要旨原稿は地質学会年会のフォーマットと同じ形式とし,PDFファイル(フォント埋め込み)とWord形式ファイルの両方を支部事務局までe-mailにてお送り下さい.
・申込の際には下記の情報をあわせてお知らせ下さい。
1)連絡先(発表者氏名・所属・e-mail・電話)
2)発表様式(口頭・ポスター・どちらでも可,のいずれか)
3)学生か否か
4)懇親会の参加・不参加
CPD単位証明書の発行
西日本支部では,地質技術者への継続教育の一環として,大会参加者・発表者へCPD単位を発行します.大会参加と口頭/ポスター発表の「受講証明書」は,当日15時以降に会場受付にてお渡しします.
・ポスター発表:2単位
・口頭発表:0.4 × 分(15分の場合:6単位)
・参加:1 × 滞在時間
委任状:総会にご出席いただけない方は下記様式の委任状を支部事務局へお送り下さい.
================== 委任状 ====================
日本地質学会西日本支部平成27年度総会・第167回例会における議決権を,
様に委任いたします.
平成 年 月 日
御氏名:
===============================================
問い合わせ,および講演要旨原稿送付先
西日本支部事務局 : 〒739-8526 東広島市鏡山 1-3-1
広島大学大学院理学研究科 地球惑星システム学教室
早坂康隆(tel: 082-424-7462,e-mail: hayasaka@hiroshima-u.ac.jp)
このサイトに関して
問い合わせ
このサイトは一般社団法人日本地質学会の公式サイトです。お問い合わせは学会事務局まで。
学会事務局
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F ▶地図_MAP
電話:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156
営業時間:平日 9:30〜18:00(土日祝・年末年始はお休み)
[事務局休業日]8月15日(金)〜18日(月),9月18日(木),22日(月),12月27日〜1月4日
=================
※学会事務局は,毎週水曜日を「ノー残業デー」としています
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします
=================
最寄駅:JR山手線神田駅 徒歩7分
都営地下鉄新宿線岩本町駅(A5出口)徒歩5分
東京メトロ日比谷線小伝馬町駅 徒歩5分
連絡先
下記アドレスに直接メールをお送り下さい。
庶務一般に関するお問い合わせ:
入退会・会費・各種変更届・書籍注文など
eメール:main[at]geosociety.jp([at]を@マークにして下さい)
広報・編集に関するお問い合わせ:
地質学雑誌・ニュース誌・メルマガ(geo-Flash)・HPについて など
eメール:journal[at]geosociety.jp([at]を@マークにして下さい)
※ いずれの場合も規定の書式等はありません.内容を明記の上,事務局までご連絡下さい.
本学会の著作権ポリシーおよび本サイトへの投稿規定等はこちらにあります。
動作確認済みブラウザ(2021.10.1現在):Safari、FireFox、Google Chrome、Edgeの最新版
このサイトは2007年9月9日にリニューアルされました。旧サイトはこちらから見ることができます。
会長あいさつ(2025年1月)
年頭の挨拶
一般社団法人日本地質学会
会長 山路 敦
地質学における大漁を願って.室津港にて
あけましておめでとうございます.初夢,というか,独創性について夢のようなはなしを最初に.
いろいろ独創的といわれる研究がありますが,知の根本問題は古代から変わらないのではないでしょうか.すなわち,その第一は,この世の起源と仕組みで,地球史やローカルな地史は前者に含まれます.また,火山活動やテクトニクスのメカニズムの研究は後者に含まれます.歴史物語としての知識の集積や,事象がどのように継起するかという経験則の把握をこえて,地史を理解するために後者は不可欠です.歴史とメカニズムの解明が両輪となって地質学は進んでゆくのです.多くの地質学者がその両方に貢献してきましたし,今後も貢献が積み重ねられてゆくでしょう.皆さんの成果もそれに含まれます.
あえて古代から,というのは,たとえば宇宙の起源です.西ローマ帝国の末期,西暦400年前後を生きたアウグスティヌスというキリスト教の教父は,「天地創造のまえ,神は何をしていた?」という異教徒からの揶揄にたいして,時間もまた創造されたのだと答えたそうです.こうした応答は,明らかに20世紀以後の宇宙論にも残響してます.17世紀の科学革命で,答え方や答えるための社会的仕組みがそれ以前にくらべて大きく変わりましたが,チャレンジすべき真に根本的な問題は古代から変わっていないのではないか.
そうした問題の第二は,自由意志の起源です.すなわち,われわれの行動がすっかり運命にからめとられているのか,そうでなければ,その自由は何に由来するのかです.アウグスティヌスは,自由意志は善悪に関して非対称であるといいます.つまり,われわれは悪をなす自由をふんだんに与えられているが,善をなす自由を持たないと.ただ神の恩寵によってのみ,人のおこないは善とされると.このように自由意志論は長く複雑な歴史をもち,また,われわれが社会をどうつくってゆくかにもかかわる根本問題なのです.成功しているか否かはおくとして,物理学者はこの問題にも果敢にチャレンジしています.たとええば,ロジャー・ペンローズは自由意志の起源を,神経細胞内の特定器官における,量子的ゆらぎで説明できると考えました.では,このチャレンジをした地質学者はおられたでしょうか.私自身は何も思いつきませんが,これについて重要な貢献をすることは,千年に一度の,地質学からの真に独創的な貢献になるのだと思います.
さて,今年は昭和100年.多事多難な時代が再びめぐってきそうな気配です.多くの学協会同様,本会にとって,会員数の減少は大きな中・長期の問題です.人口が何割も減るのだから,わが国が地下資源の輸出大国にでもならない限り,会員数の長期減少は不可避でしょう.グラフの傾きをいかに緩やかにするか,また,減少状況下で活力をいかに保つかについて,知恵をしぼらねばなりません.
本会では学生会費を新設したり,年会時に保育施設利用費を補助したり,地質技術者としてのキャリアパスを学生層に知らせたり,といった施策をすすめてきました.新入会員の獲得に努めることはもちろん,若手や中堅層へのそうした手当てはさらに伸ばしてゆくべきものと考えますが,シニア層に対する施策となると,ほぼ手付かずでした.
このことをあえて取り上げるのは,今や本会の会員の約1/3がシニア層だからです.この比率からいって,この層だけを対象に経費のかかる事業を展開することは難しいでしょう.この層の方々には退会することなく,本会の会員であることを楽しんでいただき,また,本会で活躍の場を見出していただくことが,財政面からも求められているのです.そこで,シニア層の満足度をいかに上げるかを探るため,この層の皆さんを対象に,どんな事業を希望し,また,どんなことで活躍していただけるか,まずアンケート調査を始めたところです.これについてアイデアをお持ちなら,年齢層かにかかわらず,ぜひお知らせください.老人支配にならないよう留意しつつシニア層の満足度を上げるべく,施策を考えてゆきたいと思います.
会員数の長期減少下での活力維持のために,地質学雑誌の活用はどうでしょう.人が減るとともに,知識が失われることは必定です.「だれだれが退職して,なになにができる人が居なくなってしまった」という話を最近耳にします.現在は少なからぬ人々が共有していて,たいして価値がないと思われている知識や技術であっても,『猿の惑星』にでてくる人類同様,なくしかねない思います.たとえば2060年に,定方位の薄片を作って定量的な観察することが,本会の会員にできるでしょうか.応用地質であれ地学の中等教育であれ,本会がカバーするどのサブ分野でも,失われる知識や技術はいろいろあるでしょう.ちょっとしたこと,と今は思われるものでも,そのtipsを和文で残しておくことが,地質学界の活力維持の助けになるように思います.そうしたことを,専門部会で企画されてはいかがでしょう.
はなしは変わりますが,ここで研究不正について一言.主体的に研究不正を犯さないことは当然ですが,不正事案に巻き込まれることにも注意しなければなりません.たとえば,共著者として巻き込まれないとは限りません.それを防ぐためには,安易に著者に名を連ねるべきでないでしょう.名を連ねようとするなら,共著者の資格や義務をよく理解すべきです.場合によっては,共著者になるよう要請されたとしても,謝辞で名前に言及するにとどめるよう主著者に要請することが,選択肢になり得ましょう.
不正防止のための教育は,十年ほど前から大学では必須となっています.指導教員は各学生に研究公正教育を定期的に行うよう求められていて,それを怠れば,今やそれだけでハラスメントとみなされます.十年以上前に企業に就職,または,初等中等教育の教職に就かれた皆さんが論文を執筆したり共著者に名を連ねたりするときには,オーサーシップに関する最近の規制などを調べていただくことが,ご自身や所属する組織の名誉をまもるために必要になっております.
最後になりましたが,本年が皆様にとって良い年となりますよう,心からお祈り申し上げます.
2025年1月
一般社団法人日本地質学会
会長 山路 敦
学会の顔-目次
学会の顔
賛助会員 Supporting member
名誉会員 Honorary member
執行理事 Executive Director
各賞受賞者 ▶▶ 年度毎受賞者一覧
日本地質学会賞:The Geological Society of Japan Prize
日本地質学会功績賞:The Geological Society of Japan Outstanding Contribution Award
日本地質学会都城秋穂賞:The Geological Society of Japan Akiho Miyashiro Award(旧名称:日本地質学会国際賞)
日本地質学会 H. E. ナウマン賞:The Geological Society of Japan H. E. Naumann Award
日本地質学小澤儀明賞:The Geological Society of Japan Ozawa Yoshiaki Award
日本地質学会柵山雅則賞:The Geological Society of Japan Sakuyama Masanori Award
Island Arc Award(旧名称:日本地質学会Island Arc賞)
日本地質学会論文賞:The Geological Society of Japan Best Paper Award
日本地質学会小藤文次郎賞:The Geological Society of Japan Koto Bunjiro Award
日本地質学会地質学雑誌特別賞:The Geological Society of Japan JGSJ Short Publication Award
日本地質学会研究奨励賞:The Geological Society of Japan Young Scientist Award
日本地質学会フィールドワーク賞:The Geological Society of Japan Fieldwork Award
学会表彰:The Geological Society of Japan Commendation
----------------------------------------------------------------
日本地質学会小藤賞(〜2012年):The Geological Society of Japan B. Koto Award
日本地質学会功労賞(〜2021年):The Geological Society of Japan Contribution Prize
その他
日本地球惑星科学連合フェロー(地質学会会員)
Geo暦(2018)
2018年Geo暦(行事カレンダー)
2008年版 2009年版 2010年版 2011年版 2012年版 2013年版
2014年版 2015年版 2016年版 2017年版 ------------ 2019年版
2018年版 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
○印は学会主催行事.(共)学会共催・(後)後援・(協)協賛
1月January
日本学士院 ダン・マッケンジー客員教授来日記念講演
「創始者が語るプレートテクトニクス50年」
1月11日(木)14:30〜(質疑応答を含み2時間程度)
場所:日本学士院会館(東京・上野)
聴講無料・定員150名(要申込,先着順)
英語講演(逐次通訳付き)
http://www.japan-acad.go.jp/japanese/news/2017/112201.html
うみコン2018
海と産業確信コンベンション:ブルーアースとビジネスの融合
1月16日(火)〜17日(水)10:00〜17:00
場所:大さん橋ホール(横浜港大さん橋国際客船ターミナル内)
入場無料
[同時開催]ブルーアースサイエンス・テク2018
1月16日(火)〜17日(水)
http://yokohama-umi.jp/
第206回地質汚染イブニングセミナー
1月26日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:谷 芳生(神奈川県秦野市環境保全課長)
演題:神奈川県秦野盆地の水循環調査とその教訓
http://www.npo-geopol.or.jp
火山噴火予測研究の今!及びその将来展望
1月27日(土)10:15〜13:00
会場:池袋サンシャインシティ文化会館2階
定員:180名(要予約)・参加無料
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/12/1399833.htm
2月February
第22回「震災対策技術展」横浜
2月8日(木)〜9日(金)
場所:パシフィコ横浜 Dホール
https://www.shinsaiexpo.com/yokohama/
東北大学東北アジア研究センター公開講演会
玉—その起源と東北アジア先史の「石」文化
2月10日(土)14:00〜17:00
場所:東北大学川内キャンパス
入場無料・参加申込不要
http://www.cneas.tohoku.ac.jp/index.html
(後)人と自然の博物館&県立大学自然・環境科学研究所
25周年記念フォーラム「日本の恐竜時代を探る!」
2月18日(日)13:00〜17:30
場所:人と自然の博物館 ホロンピアホール(兵庫県三田市弥生が丘)
定員300名(先着順)・参加費無料
http://www.hitohaku.jp/
明治大学危機管理研究センター第40回定例研究会
「最新の建物ごとの地震被害想定法について」(菅井径世,森保宏:名古屋大)
2月18日(日)13:00〜16:30
場所:明治大学駿河台キャンパス(参加無料)
http://www.kisc.meiji.ac.jp/~crisishp/ja/notification.html#20180126
産技連地質地盤情報分科会講演会「首都圏の地質地盤」
2月23日(金)13:00〜16:45
会場:北とぴあ・第1研修室
入場無料・参加申込不要
CPD3単位の取得ができます.
https://unit.aist.go.jp/rcpd/sgr/event/images/2017/2017chishitusjiban-kouenkai2.pdf
第207回地質汚染イブニングセミナー
2月23日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:田村憲司(筑波大学生命環境系 教授)
テーマ:土壌層位と環境汚染(仮題)
http://www.npo-geopol.or.jp
海上保安制度創設70周年記念
海洋情報シンポジウム
2月27日(火)14:00〜17:50
場所:全社協・灘尾ホール 新霞ヶ関ビル内
入場無料(事前登録制)
http://www1.kaiho.mlit.go.jp
3月March
西日本支部平成29年度総会・第169回例会
3月3日(土)〜4日(日)
場所:広島大学 東広島キャンパス
講演申込締切:2月15日(木)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
ProjectA ミーティング in 五島列島
3月3日(土)〜7日(水)
3日(土)13:30〜17:00 一般講演会(五島市福江)
4日(日)〜5日(月)五研究発表会(島市奈留島)
6日(火)〜7日(水)巡検 奈留島・久賀島 ボートによる断崖海岸巡検
後援:五島市
申込締切:12月15日(金)
参加費:大人 25,000円 学生 10,000円
http://archean.jp
国際シンポジウム「積雪地域における複合災害と研究動向」
3月3日(土)10:00〜15:00(9:30受付開始)
会場:アートホテル新潟駅前(新潟駅南口直通)4階 越後西の間
主催:新潟大学災害・復興科学研究所
日本語-英語同時通訳付
参加費無料.事前申込不要
www.nhdr.niigata-u.ac.jp/news/2018_news/20180124.html
第7回学生のヒマラヤ野外実習ツアー
3月4日(日)〜18日(日)
場所:ネパール ヒマラヤ,カリガンダキ河〜ルンビニコース
主催:学生のヒマラヤ野外実習プロジェクト
実施主体:ゴンドワナ地質環境研究所及びトリブバン大学トリチャンドラキャ
ンパス地質学教室の共同実施
www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
第1回文化地質研究会 総会・研究発表会
3月10日(土)〜11日(日)
場所:大谷大学(京都市北区)
講演要旨締切:2017年12月31日
https://sites.google.com/site/bunkageology/
第52回水環境学会(札幌)年会
3月15日(木)〜17日(土)
場所:北海道大学工学部(札幌市北区北13条西8丁目)
参加申込:2月20日(火)締切
https://www.jswe.or.jp/event/lectures/index.html
関東支部「気候変動シンポジウム 〜激変する地球と災害リスク〜」
横浜国立大学都市科学部共催
3月17日(土)13:00〜18:00
場所:横浜国立大学教育文化ホール大集会室
事前申込不要,参加費無料
http://www.geosociety.jp/outline/content0096.html
東北支部総会
3月17日(土)午後〜18日(日)午前
場所:弘前大学理工学部1号館426号室
講演申込締切・懇親会(17日夜)参加申込締切:3月7日(水)
申込先:nemoto[at]hirosaki-u.ac.jp
シンポジウム「浅層地盤・地質の詳細構造解明に資する精密物理探査の現状と課題」
3月20日(火)13:00〜17:10
主催:産業技術総合研究所 地質情報研究部門
場所:産業技術総合研究所 つくば中央 共用講堂
参加費無料,事前参加登録不要
ポスター発表申込締切:3月2日(金)
https://unit.aist.go.jp/igg/geophy-rg/symposium/
第208回地質汚染イブニングセミナー
3月30日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:中野 武(大阪大学 環境安全研究管理センター 招聘教授)
テーマ:セルビアの環境モニタリングと国際連携
http://www.npo-geopol.or.jp
4月April
関東支部2018年度総会・地質技術伝承講演会
4月21日(土)14:00〜16:45
場所:北とぴあ 7階 第2研修室
地質技術伝承講演会
講師:山根 誠氏(応用地質株式会社 技術本部 技師長)
演題:ノンテクトニック構造 −地すべり粘土と流入粘土−
http://www.geosociety.jp/outline/content0096.html#3
第209回地質汚染イブニングセミナー
場所:北とぴあ901会議室
4月27日(金)18:30〜20:30
講師:楡井 久(内閣府認証NPO法人日本地質汚染審査機構理事長・超党派水循環基本法フォローアップ委員会委員
テーマ: NPO単元調査法とチバニアン調査法との現場社会貢献度の優位性について−科学技術には厳しい科学性・倫理性が問われることが世の常である−
http://www.npo-geopol.or.jp
5月May
日本地質学会創立125周年記念式典
5月18日(金)10:00〜18:30
会場:北とぴあ つつじホール
入場無料・事前申込不要
・記念講演「地質学はどこで生まれ、どこへ行くのか」(矢島道子)
・記念式典
・祝賀会(16階天覧の間)*要事前申込・会費制(申込受付中)
http://www.geosociety.jp/125th/content0007.html
日本地質学会2018年度(第10回)代議員総会
5月19日(土)13:30〜15:30
会場 北とぴあ 第2研修室(東京都北区王子)
http://www.geosociety.jp/outline/content0152.html
日本地質学会ミニシンポジウム
「日本地質学会のジオパークへの学術的貢献」
5月19日(土) 17:30〜20:00
会場:北とぴあ 第2研修室
http://www.geosociety.jp/geopark/content0021.html
日本地球惑星科学連合2018年大会
(JPGU Meeting 2018)
5月20日(日)〜24日(木)
会場:幕張メッセ
http://www.jpgu.org/meeting_2018/
第210回地質汚染イブニングセミナー
5月25日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ902会議室
講師:三田村 宗樹(大阪市立大学大学院理学研究科教授)
テーマ:大阪層群最下部相当の帯水層での自然水位観測とその評価
http://www.npo-geopol.or.jp
OCEANS’18 MTS / IEEE Kobe / Techno-Ocean2018(OTO’18)
5月28日(月)〜31日(木)
会場:神戸コンベンションセンター
https://www.techno-ocean.com/
地質調査総合センター2018年度春季地質調査研修(参加者募集)
5月28日(月)〜6月1日(金)
研修場所:島根県出雲市長尾鼻周辺(小伊津海岸)
地質:中期中新世の牛切層の堆積岩など
参加費:60,000円
定員 6名(定員になり次第募集終了)
https://www.gsj.jp/geobank/geotraining.html
(後)日本原子力学会 特別国際シンポジウム
「断層リスクに向き合う原子力安全のアプローチ」
5月31日(木)13:30〜18:00
場所:東京大学弥生講堂一条ホール
http://www.aesj.net/activity/conference/symp20180531
第5回「震災対策技術展」大阪
5月31日(木)〜6月1日(金)
会場:グランフロント大阪内、コングレコンベンションセンター
(JR大阪駅、梅田駅徒歩3分)
http://clk.nxlk.jp/eKca5Nxn
6月June
第6回 堆積実験オープンスクール
6月3日(日)10:00 〜 17:00 (予定)
場所:京都大学理学部1号館
申込締切:5/26(土)
定員:7名(先着順)
http://www.eps.sci.kyoto-u.ac.jp/
海洋理工学会平成30年度春季大会シンポジウム
「地球内部構造と変動から地震を考える」
6月7日(木)13:00〜17:30
場所:東京海洋大学品川キャンパス
http://amstec.jp/convention/H30_spring.html
石油技術協会平成30年度春季講演会
6月13日(水)〜14日(木)
場所:朱鷺メッセ(新潟市)
http://www.japt.org/
北海道支部平成30年度総会・例会
6月16日(土)
総会:11:00〜12:00
例会:13:00〜18:00(時間は予定)
場所:北海道大学理学部5号館大講堂(5-203)
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
深田研ジオフォーラム2018
地質痕跡と古文書から過去の地震津波の実像に迫る
6月16日(土)
場所:深田地質研究所 研修ホール
申込期間:5月16日(水)〜30日(木)
定員50名
http://www.fgi.or.jp
科学的特性マップに関する対話型全国説明会
主催:原子力発電環境整備機構(NUMO)/経済産業省資源エネルギー庁
6月16日(土)〜8月1日(水)
場所:全国17会場(徳島,岡山,高知,千葉,岐阜,名古屋,札幌,青森,秋田,広島,松山,金沢,前橋,新潟,京都,福井,大津)
https://www.numo.or.jp/taiwa/2018/
Crossing New Frontiers - Tephra Hunt in Transylvania
(2018年野外研究集会)
主催:International Focus Group on Tephrochronology and Volcanology
(INTAV)(テフラ・火山国際研究グループ)
6月24日(日)〜29日(金)
場所:ルーマニア
早期参加登録締切:4月20日(金)
http://www.bayceer.uni-bayreuth.de/intav2018/
問い合せ先:首都大 鈴木毅彦(suzukit@tmu.ac.jp)
地質学史懇話会
6月24日(日)13:30〜17:00
場所:北とぴあ 8階 803号室(JR京浜東北線王子駅下車3分)
講演予定:
眞島英壽「松本達郎とプレートテクトニクス:高千穂変動と四万十帯付加体論,そしてその先へ」
柴田陽一「日本地政学史素描」
問い合わせ先:矢島道子 pxi02070[at]nifty.com
第211回地質汚染イブニングセミナー
6月29日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:原 雄 (理工学博士)
テーマ: 廃棄物資源化の真意をどこに置くか
http://www.npo-geopol.or.jp
日本海洋政策学会 創立10周年記念シンポジム
6月29日(金)15:30〜18:15(祝賀会18:30〜)
場所:笹川平和財団ビル 11階 国際会議場
http://oceanpolicy.jp
7月July
三朝国際インターンプログラム2018
7月2日(月)〜8月10日(金)
応募締切:4月22日(日)
応募条件: 地球科学または関連分野専攻の学部 3・4 年生または修士1年生 (国籍不問)で,英語でのコミュニケーション能力があること
https://intern.misasa.okayama-u.ac.jp/misip2018/
(後) 「設計業務等標準積算基準書の解説」説明会(地質編)
主催:全地連・経済調査会
7月2日(月)〜8月31日(金)
場所:全国9地区(東京、高松、大阪、仙台、名古屋、札幌、広島、新潟、福岡)
受講料:6,000円
https://seminar.zai-keicho.or.jp/seminar/detail/index/148/6
(後)第55回アイソトープ・放射線研究発表会
7月4日(水)〜6日(金)
場所:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
https://www.jrias.or.jp/
海洋政策研究所第154回海洋フォーラム
「日本で初めての国立自然史博物館を沖縄に!」
7月23日(月)13:00〜17:40(受付開始12:30)
会場:笹川平和財団ビル11階国際会議場(港区虎ノ門1-15-16)
**要事前申込**
https://www.spf.org/opri-j/
第212回地質汚染イブニングセミナー
7月27日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:山本善久(水循環基本法フォローアップ委員会幹事長)
テーマ: 水循環基本法の誕生からフォロ−アップ委員会活動の現状
http://www.npo-geopol.or.jp
2018年度第1回地区防災学会シンポジウム
九州北部豪雨から1年を振り返って:九州北部豪雨の教訓と地域防災力の在り方
7月28日(土)13:00〜16:30(予定)
場所:九州大学 大橋キャンパス多次元デザイン実験棟 (福岡市南区)
対象:地域防災力の強化に興味のある方
参加費無料・定員150名
http://www.gakkai.chiku-bousai.jp/
8月August
AOM3;The Third Asian Ostracod Meeting
8月6日(月)〜10日(金)
場所:しいのき迎賓館(石川県金沢市)
大会事務局:神谷隆宏(金沢大学)
メール:tkamiya[at]staff.kanazawa-u.ac.jp
http://www.ostracoda.net/aom3/
関東支部
地学教育・アウトリーチ巡検「箱根〜北伊豆地域の自然災害の跡を巡る」
8月7日(火)〜8日(水):1泊2日
対象:教育関係者および地学に興味のある一般の方
参加申込締切:7月6日(金) 先着順:定員20名
http://kanto.geosociety.jp/
(共)地震子どもサマースクール:火山島 伊豆大島のヒミツ
8月7日(火)〜8日8日(水)※宿泊無しの日帰り2日間
募集対象:小学5年〜高校生40名
参加費:2000円
参加申込締切:7月2日(月)
http://www.kodomoss.jp/ss/izuoshima/
第72回地学団体研究会総会(市原)
8月17日(金)〜19日(日)
会場:千葉県市原市市民会館
http://ichihara2018.com/
関東支部清澄フィールドキャンプ
8月20日(月)〜25日(土) 5泊6日
場所:東京大学千葉演習林(千葉県鴨川市清澄)
参加申込締切:7月6日(金)
http://kanto.geosociety.jp/
放射線取扱主任者試験
8月22日(水)〜24日(金)
会場:札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡
申込受付期間:5月14日(月)〜6月18日(月)
http://www.nustec.or.jp
第213回地質汚染イブニングセミナー
8月31日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ802会議室
講師:佐々木 裕子(国立環境研究所 客員研究員)
テーマ:土壌汚染対策法の改正−調査・分析法の動向と課題−
http://www.npo-geopol.or.jp
9月September
日本地質学会第125年学術大会
9月5日(水)〜7日(金)
場所:北海道大学(札幌市)
講演申込受付:4月末〜6月13日(水)
http://www.geosociety.jp/science/content0096.html(プレページ)
日本学術会議公開シンポジウム「西日本豪雨災害の緊急報告会」
9月10日(月)13:00〜17:30
場所:日本学術会議講堂(港区六本木)
定員:先着300名(参加費無料)
http://janet-dr.com/050_saigaiji/2018/050_2018_gouu/20180910_houkoku/180910_00_leef.pdf
要申込:以下の申込みフォームからお願いいたします
https://ws.formzu.net/fgen/S14170529/
(共)2018年度日本地球化学会第65回年会
9月11日(火)〜13日(木)
場所:琉球大学・千原キャンパス
http://www.geochem.jp/meeting/index.html
日本鉱物科学会2018年年会
9月19日(水)〜21日(金)
会場:山形大学小白川キャンパス
http://jams.la.coocan.jp/index.html
第35回歴史地震研究会(大分大会)
9月22日(土)〜25日(火)
場所:ホルトホール大分(大分市金池南一丁目5番1号)
プログムラム公開中(2018.6.20)
http://www.histeq.jp/menu7.html
国際ゴンドワナ研究連合(IAGR)2018年会・第15回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム
9月24日(月・祝)〜28日(金)
場所:中国西安市 Howard Johnson Ginwa Plaza Hotel
主催:中国北西大学・IAGR
2nd circularはこちらから(テキストファイル)
発表要旨締切:2018年6月30日(土)
連絡先:Prof. Yunpeng Dong(E-mail: dongyp[at]nwu.edu.cn)
日本火山学会2018年度秋季大会
9月26日(水)〜28日(金)
会場:秋田大学
http://www.kazan-g.sakura.ne.jp/J/index.html
第214回地質汚染イブニングセミナー
9月28日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ902会議室
講師:石川友之(中日本技術コンサルタント東京支社長)
テーマ:「国内外初、最先端技術診断で液流動化調査・対策に成功した例―茨城県潮来市日出地区―」
http://www.npo-geopol.or.jp
10月October
深田研一般公開2018」〜化石の日関連イベント〜
10月7日(日)10:00〜16:00
講演(13:30〜15:00)
「化石の日制定記念:世界を変えた恐竜たち」真鍋 真氏(国立科学博物館)
*第9回ほか惑星地球フォトコンテストの入選作品の展示予定されています
http://www.fgi.or.jp/?p=4099
ぼうさいこくたい2018
10月13日(土)〜14日(日)
場所:東京ビッッグサイト・そなエリア(東京臨海広域防災公園)
※地質学会も出展します「防災のための第一歩−子どものうちから身につけたい地球の知識−」http://bosai-kokutai.jp/
科学的特性マップに関する対話型全国説明会
主催:経済産業省資源エネルギー庁,NUMO
10月20日(土)〜12月18日(火)
場所:八代市,釜石市,岐阜市,熊本市,綾部市,豊岡市,下関市,四万十市,
能代市,京丹後市,豊橋市,浜松市,平塚市
プログラム:地層処分の説明,テーブルでのグループ質疑
https://www.numo.or.jp/taiwa/2018/
第215回地質汚染イブニングセミナー
10月26日(金)18:20〜21:10(時間にご注意下さい)
場所:北とぴあ901会議室
講師:日本地質汚染審査機構
テーマ:現場調査報告シンポ(仮題)
平成30年北海道胆振東部地震地質災害の教訓から学ぶ
関東平野の台地・丘陵・山岳の地質と地震災害の点検
http://www.npo-geopol.or.jp
2018年度秋期(初級者向け)地質調査研修
主催:産業技術総合研究所
10月29日(月)〜11月2日(金)
場所:島根県出雲市長尾鼻周辺(小伊豆海岸)
参加申込締切:10月19日(金)
https://www.gsj.jp/geobank/geotraining.html
11月November
(協)石油技術協会平成30年度秋季講演会
「若手技術者−何を考え何を目指す」
11月1日(木)13:00〜17:40
場所:東京大学小柴ホール
http://www.japt.org
第188回深田研談話会
「断層・褶曲はなぜそこにできるのか:再現することで見えてくる世界」
講師:山田泰広(JAMSTEC)
11月2日(金)18:00〜19:30
会場:深田地質研究所 研修ホール
定員:70名 参加無料
http://www.fgi.or.jp
平成30年度「津波防災の日」スペシャルイベント
最新科学×津波×地域防災
11月5日(月)13:00〜18:00
場所:川崎商工会議所川崎フロンティアビル2階KCCIホール
http://krs.bz/scj/c?c=285&m=44721&v=48975a9b
東京大学大気海洋研究所共同利用研究集会
「海底堆積物から地震履歴をどこまで読み取れるのか」
11月13日(火)〜14日(水)
場所:東京大学大気海洋研究所(柏キャンパス)
http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/aori_news/meeting/2018/20181113.html
IGCP608「白亜紀アジア−西太平洋生態系」第6回国際研究集会
11月15日(木)〜16日(金)(研究集会:タイ・コンケーン)
11月12日(月)〜14日(水)(プレ巡検:コラート高原のジュラ系—白亜系Khorat層群と恐竜化石群)
共催:タイ鉱物資源局,Sirindhorn博物館
http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/
第29回地質汚染調査浄化技術研修会
11月16日(金)〜18日(日)
主催:NPO法人 日本地質汚染審査機構
共催:地質汚染診断士の会・日本地質学会環境地質部会・社会地質学会
会場:日本地質汚染審査機構 関東ベースン実習センター(千葉県香取市)
会費:会員45,000円・非会員55,000円・学生:15,000円
http://www.npo-geopol.or.jp
○関東支部シンポジウム「せまりくるジオハザード−関東の自然災害−」
11月18日(日)13:00〜17:30
終了後大学周辺で懇親会を開催
場所:早稲田大学教育学部 早稲田キャンパス 6号館
○関東支部「伊豆大島巡検」
11月22日(木)〜24日(土),2泊3日(船中1泊)雨天決行
参加申込締切:11月10日(土)(定員に達した時点で締切)
http://kanto.geosociety.jp/
地球科学普及講演会「地球をぶらり」
主催:NPO法人地学オリンピック日本委員会
11月24日(土)13:00〜16:30
場所:城西大学東京紀尾井町キャンパス3号棟5F国際会議場
(千代田区平河町2-3-20)
・高橋雅紀氏「大陸から列島、そして山国へ」
・萬年一剛氏「活火山箱根の発見」
対象:中高生・一般(保護者同伴で小学生の参加可)
http://jeso.jp/index.html
15th International Symposium on Mineral Exploration (ISME-XV)
11月26日(月)〜27日(火)
場所:京都大学国際科学イノベーション棟
講演申込締切:4月30日(月)
http://www.isme-detec.org/ISMExv/
第216回地質汚染イブニングセミナー
場所:北とぴあ901会議室
11月29日(木)18:30〜20:30
講師:シティユーワ法律事務所 弁護士 佐藤恭一
テーマ:我が国のおける自然由来土壌汚染の規則−自然由来土壌汚染国家賠償訴訟の報告
http://www.npo-geopol.or.jp
平成30年度東濃地科学センター 地層科学研究 情報・意見交換会
11月29日(木)13:30〜16:45
場所:瑞浪市地域交流センター「ときわ」(岐阜県瑞浪市)
定員:約130名 入場無料
参加申込締切:11月13日(火)先着順
https://www.jaea.go.jp/04/tono/topics/topics1810_1/index.html
土岐地球年代学研究所見学会
11月30日(金) 9:00〜10:45
場所:土岐地球年代学研究所(岐阜県土岐市)
定員:30名 入場無料
参加申込締切:11月13日(火)先着順
https://www.jaea.go.jp/04/tono/topics/topics1810_1/index.html
高知大学海洋コア総合研究センター設立15周年記念公開シンポジウム
「地球を掘ってわかること〜古地震、気候変動、地球の姿〜」
(地球掘削科学共同利用・共同研究拠点の成果と今後の展望)
11月30日(金)〜12月1日(土)
会場:オーテピア ホール
https://www.kochi-u.ac.jp/marine-core/seminars/naiyo/181130_15th.html
12月December
日本地質学会第125年学術大会(2018年つくば特別大会)
12月1日(土)〜2日(日)
場所:産業技術総合研究所 つくば本部
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/top
地区防災計画学会・日本大学危機管理学部共同シンポジウム
「西日本豪雨等の教訓と地域防災力・災害復興活動」
12月1日(土) 13:30〜16:30(予定)
場所 日本大学三軒茶屋キャンパス
http://www.gakkai.chiku-bousai.jp/
第18回アジア学術会議
社会のための科学:アジアにおけるSDGsの達成に向けた戦略
12月5日(水)〜7日(金)
会場:日本学術会議(東京都港区六本木7-22-34)
7月17日:論文要旨(Abstract)提出期限
http://www.scj.go.jp/
第29回GSJシンポ地圏資源環境研究部門研究成果報告会
「粘土・粘土鉱物:枯渇の機器にある貴重な国内資源」
12月6日(木)13:30〜17:35
場所:秋葉原ダイビル
https://unit.aist.go.jp/georesenv/
(後)兵庫県政150周年記念国際シンポジウム
巨大恐竜,竜脚類の謎に迫る!
12月8日(土)13:00-17:30
場所:兵庫県立人と自然の博物館
定員:300名(先着順)・入場無料
http://www.hitohaku.jp/infomation/event/sauropoda-sympo2018.html
第18回東北大学多元物質科学研究所研究発表会
12月13日(木)〜14日(金)
場所:東北大学片平さくらホール(仙台市青葉区)
参加申込締切:12月5日(水)
https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2018/10/event20181022-02.html
国際シンポジウムMISASA VII「サンプルリターンとアストロバイオロジー」
主催:岡山大学惑星物質研究所 共催:宇宙科学研究所・JAXA
12月19日(水)〜21日(金)
場所:米子コンベンションセンター BiG SHiP(鳥取県米子市)
https://sympo.misasa.okayama-u.ac.jp/misasa_vii/
第217回地質汚染イブニングセミナー
場所:北とぴあ901会議室
12月21日(金)18:30〜20:30
講師:藤巻 宏和(東北大学名誉教授・NPO法人日本地質汚染審査機構理事)
「アスベストが引き起こした環境問題と建材中のアスベスト分析の問題点」
http://www.npo-geopol.or.jp
地質学史懇話会
12月23日(日)13:30〜17:00
会場:北とぴあ8階806号室(JR京浜東北線王子駅下車3分)
演者:清地ゆき子「地質学者としての張 資平」
(注)長田俊明氏の講演は都合により中止となりました(18/12/17)
問い合わせ:矢島道子
Geo暦(2008)
2008年Geo暦(行事カレンダー)
2008年版 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年版
※印は学会主催行事です.◯印は学会共催・後援行事
1月January
第3回国際テチスシンポジウム
(Third International Conference on the Geology of the Tethys
1月8−11日
会場 アスワン,South Valley University
第17回環境地質学シンポジウム
日程 1月10日(木)〜11日(金)
場所 日本大学文理学部 百周年記念館 国際会議場
主催 地質汚染−医療地質−社会地質学会
http://www.jspmug.org/envgeo_sympo/17th_sympo.html
NUMO技術開発成果報告会
1月17日(木)13:10〜17:20(受付12:30〜)
場 所:東京国際交流館 プラザ平成 国際交流会議場(お台場)
http://www.numo.or.jp/what/news2007/news_071219.html
2月February
日本古生物学会第157回例会
2月1日(金)〜2月3日(日)
会場:宇都宮大学(宇都宮市)
シンポジウム 中〜高緯度の両極性分布を持つ生物から見た地球史
http: http://wwwsoc.nii.ac.jp/psj5/
*第154回西日本支部例会および2007年度支部総会
2月16日(土)〜17日(日)
17日(日) 見学会「御所浦白亜紀資料館と御所浦島の地質」
会場:熊本大学理学部2号館(熊本大学黒髪キャンパス南地区)
申込締切:2月1日(金)必着
詳しくは、支部のページへ
関東アスペリティ・プロジェクト(KAP)国際ワークショップ
2月16日(土)〜19日(火)
場所:千葉大学けやき会館(巡検は房総半島)
主催:関東アスペリティ・プロジェクト・グループ,千葉大学地球科学研究グループ
詳しくはこちらから
3月March
Blue Earth'08(第24回しんかいシンポジウム・第11回みらいシンポジウム)
3月13日(木)〜14日(金)9:30〜18:00
会場 横浜市立大学金沢八景キャンパス
主催 海洋研究開発機構
詳しくはこちらから
第42回日本水環境学会年会
3月19日(水)〜21日(金)
会場:名古屋大学
http://www.jswe.or.jp/
東京大学海洋研究所共同利用研究集会
海洋リソスフェア学シンポジウム
ー海洋底深部構造と進化過程解明に向けてー
3月24日(月)13:30〜17:30
場所:東京大学海洋研究所(http://www.ori.u-tokyo.ac.jp/)講堂
詳しくは、こちらから
日本地理学会2008年春季学術大会
3月29日(土)〜31日(月)
会場:獨協大学(埼玉県草加市)
http://wwwsoc.nii.ac.jp/ajg/
海洋地球研究船「みらい」深海調査研究船「かいれい」就航10周年記念シンポジウム
北極海からマリアナ海溝まで ー挑戦し続けた10年ー
3月29日(土)10:00-17:00
場所 日石横浜ホール(入場無料)
船舶一般公開:みなとみらいで研究船に乗ろう!
3月30日(日)10:00〜16:30
場所 横浜港新港埠頭 5号岸壁、8号岸壁(赤レンガ倉庫そば)
(入場無料)
詳しくは、http://www.jamstec.go.jp/j/pr/ship/mirai/index.html
4月April
日本堆積学会2008年弘前大会
4月25日(金)〜 29日(火・祝)
会場:弘前大学創立50周年記念館
詳しくは,堆積学会HP
5月May
*日本地質学会北海道支部総会・個人講演会・地質学講演会
5月10日(土)地質の日 10:30〜17:00
会場 北海道大学高等教育機能開発総合センター(旧教養部 S1およびS3教室)
詳しくはこちらから
*近畿支部:山陰海岸「地質の日」見学会
主 催:日本地質学会近畿支部・山陰海岸ジオパーク推進協議会
後 援:兵庫県・近畿地学会・鳥取地学会
5月11(日)兵庫県浜坂港 遊覧船乗り場 AM9:30 集合
参加申込締切:4月25日(金)
詳しくは、http://kinki.geosociety.jp/
*関東支部:箱根火山見学会
5月17(土)〜18日(日)1泊2日
参加申込締切:4月18日(金)
詳しくは、http://kanto.geosociety.jp/
日本地下水学会2008年春季講演会
5月24日(土)
会場:東京農工大学農学部(府中キャンパス)
http://www.groundwater.jp/jagh/
*日本地質学会第115年代議員総会
日程 5月25日(日)予定
会場 幕張メッセ国際会議場
詳しくは、こちらから
◯日本地球惑星科学連合2008年大会
5月25日(日)〜30日(金)
会場:幕張メッセ 国際会議場
http://ww.jpgu.org
6月June
関地球地図フォーラム2008
6月5日(木)〜7日(土)
会場 国際連合大学(東京都渋谷区神宮前5-53-70)
http://www.gmforum2008.org/top.html
*関東支部:第2回研究発表会「関東地方の地質」
日時:6月8日(日)10:00〜17:00
会場:早稲田大学国際会議場第1会議室
講演申込締め切り:2008年3月31日(月)
講演要旨締め切り:2008年5月7日(水)
詳しくは関東支部のHPへ
Geoinforum2008 第19回日本情報地質学会総会・講演会
6月12日(木)〜13日(金)
場所:北海道大学百年記念会館大会議室
http://www.jsgi.org/
地質学史懇話会
6月22日(日)13:30〜17:00
場所:北とぴあ9階 902号室(JR京浜東北線王子駅下車3分)
・上杉 陽:富士山宝永噴火
・沓掛俊夫:弘法大師の地質観、自然観
* 近畿・西日本・四国 三支部合同例会
6月29日(日)
会場:兵庫県立人と自然の博物館
「丹波の恐竜化石発掘」 公開講演会 三枝春生
「篠山層群周辺の地質発達史:兵庫県中央部の中生代」シンポジウム
http://kinki.geosociety.jp/
7月July
三朝国際インターンプログラム2008
実施期間:7月1日(月)〜8月8日(金)(約6週間)
募集人員:15名程度
応募締切:2008年4月15日(木)必着
詳しくは、http://www.misasa.okayama-u.ac.jp/MISIP/2008/index_j.html
第45回アイソトープ・放射線 研究発表会
会期:7月2日(水)〜4日(金)
会場:日本青年館(東京都新宿区霞ヶ丘町7番1号)
http://www.jrias.or.jp/
日本古生物学会2008年年会・総会
7月4日(金)〜7月6日(日)
会場:東北大学
シンポジウム:環境指標としての後期新生代微古生物学と古海洋学の進展(4日)
http://wwwsoc.nii.ac.jp/psj5/
堆積学スクールOTB2008
テーマ:「タービダイトと海底扇状地のダイナミクス」
7月19日(土)〜21日(月)(集合は18日夜)
講演会場・宿泊先:北海道立厚岸少年自然の家
http://sediment.jp/
8月August
第31回国際地理学会議 (IGC 2008Tunis)
8月12日〜15日
場所 Tunis the Kram Centre
公式ホームページ>http://www.igc-tunis2008.com/
地学団体研究会2008年総会
8月22日(金)〜24(日)
会場:大東文化大学板橋キャンパス(東京都板橋区高島平1-9-1)
http://www.geocities.jp/obt_kk/2008soukai/index.html
6th International Conference on Asian Marine Geology
−Asian Waters explored by advanced research of 21st Century−
8月29日〜9月1日
場所 高知市
http://ofgs.ori.u-tokyo.ac.jp/ICAMG6/
◯第2回国際地学オリンピック
8月31日〜9月7日までの8日間
場所:フィリピン共和国
詳しくは、 http://www.jpgu.org/ieso/
9月September
◯第12回岩の力学国内シンポジウム
9月2日(火)〜4日(木)
会 場:山口大学工学部 (山口県宇部市)
講演原稿提出期限:2008年5月16日(金)
http://www.mmij-kyushu.com/JROCK2008/
◯第52回粘土科学討論会
9月3日(水)〜5日(金)
会場:沖縄ポートホテル(沖縄県那覇市西1-6-1,TEL. 098-868-1118)
申込締切:6月10日(火)必着
http://wwwsoc.nii.ac.jp/cssj2/index.html
2008年度日本地球化学会年会
9月17日(水)〜19日(金)
会場:東京大学教養学部12・13号館(東京都目黒区駒場3-8-1)
申込締切:8月29日(火)必着
http://www.geochem.jp/meeting
日本鉱物科学会2008年年会
9月20日(土)〜 9月22日(月)
会場:秋田大学手形キャンパス
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jams3/
注:日本地質学会との同時開催
*日本地質学会第115年学術大会(秋田大会)
日程:9月20日(土)〜22日(月)
場所:秋田大学
詳しくはこちらから
10月October
2008年度資源地質学会秋季講習会
10月3日(金)〜4日(土)
テーマ:西南北海道の中新世熱水活動と金属鉱化作用
巡検場所:小樽赤岩熱水系とその周辺地域の金属鉱化帯
http://www.kt.rim.or.jp/~srg/page_event.html
日本地理学会2008年秋季学術大会
10月4日(土)〜6日(月)
会場:岩手大学(岩手県盛岡市)
http://www.ajg.or.jp/
日本火山学会2008年度秋季大会
10月11日(土)〜14日(火)
場所:岩手大学
11日-13日:学術講演会/14日:巡検
http://wwwsoc.nii.ac.jp/kazan/J/index.html
日本応用地質学会平成20年度研究発表会
10月30日(木)・31日(金)
会場:横浜市開港記念会館(横浜市中区本町1-6)
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jseg/
平成20年度東京地学協会秋季公開講演会
10月25日(土)14:00〜1700
場所:東京八重洲ホール
http://wwwsoc.nii.ac.jp/tokyogeo/index.html
11月November
「地球を救う みんなの知恵」講演会
11月2日(日),13:00-15:40
場所:日本科学未来館7F みらいCANホール(参加無料)
http://www.gsj.jp/iype/be/doc/BE081102A.html
日本活断層学会2008年度秋季学術大会
11月7日(金)〜8日(土)
場所:東京大学 山上会館
設立1周年記念シンポジウム:
「活断層からの地震発生予測の諸問題 〜岩手・宮城内陸地震を例として〜」
http://danso.env.nagoya-u.ac.jp/jsafr/
平成22・23・24年度学術研究船白鳳丸研究計画企画調整シンポジウム
11月13日(木)〜14日(金)13:15〜
会場 東京大学海洋研究所 講堂
詳しくはこちら
平成20年度自然史学会連合講演会
自然史研究最前線−恐竜からDNAまで−
11月15日(土)
会場:千葉県立中央博物館
http://wwwsoc.nii.ac.jp/ujsnh/index.html
日本地下水学会2008年秋季講演会のご案内
11月20(木)〜22日(土)
会場 九州大学医学部百年講堂
http://homepage2.nifty.com/jagh_gyouji/
日本情報地質学会シンポジウム
公開地質地盤情報データベースの活用と将来展望
11月21日(金)
会場:国学院大学渋谷キャンパス学術メディアセンター1階 常磐松ホール
http://www.jsgi.org/
農村研究フォーラム2008
人口減少・低炭素社会に向けた農村地域における資源管理
−農村の叡智と資源を次世代に継承する−
11月21日(金)13:00-17:30
場 所:秋葉原コンベンションホール(秋葉原ダイビル2階)(参加無料)
http://nkk.naro.affrc.go.jp/
第17回東北大学素材工学研究懇談会
複雑な物質・材料への新たなアプローチ
11月25日(火)-26日(水)
場所 東北大学片平サクラホール
参加申込締切:11月18日(火)
http://www.tagen.tohoku.ac.jp/general/information/08112526.html
日本地震学会2008年秋季大会
11月24日(月)〜 27日(木)
場所:つくば国際会議場
http://www.zisin.or.jp/meeting/2008/
第4回 IGCP516「東南アジアの地質学的解剖:東テーチスの古地理と古環境」シンポジウム
シンポジウム:11月24日〜26日
http://staff.aist.go.jp/hara-hide/igcp516
主催:チュラロンコン大学理学部
◯第24回ゼオライト研究発表会
11月26日(水)〜11月27日(木)
会場:タワーホール船堀
http://www.jaz-online.org/
◯琉球大学熱帯生物圏研究センター共同利用研究会
有殻原生生物プランクトン研究はどこに向かうのか
11月28日(金)本部町産業支援センター
11月29日(土)モトブリゾートホテル
http://www.geosociety.jp/faq/content0129.html
第18回環境地質学シンポジウム
11月29日(土)-30日(日)
主催:地質汚染−医療地質−社会地質学会
場所:名古屋大学 野依記念学術交流館
http://www.jspmug.org/index_j.html
★日本地質学会2008年臨時総会
11月30日(日)14:00〜15:30
会場:学士会館 (210会議室)
http://www.geosociety.jp/login.html
12月December
平成20年度国土技術政策総合研究所(国総研)講演会
12月2日(火)10:00-16:50
場所 九段会館(千代田区九段南1-6-5)
http://www.nilim.go.jp
IUMRSアジア国際会議 2008
日程:12月9日(火)〜13日(土)
場所:名古屋市国際会議場(名古屋市熱田区西熱田町1番1号)
主催:日本MRS (Materials Research Society of Japan (MRS-J))
http://www.iumrs-ica2008.jp/index.html
第8回東北大学多元物質科学研究所研究発表会
12月11日(木)9:45-20:00
場所 東北大学片平サクラホール
http://www.tagen.tohoku.ac.jp/general/event/meeting/2008/
地質学史懇話会
12月23日(火) 13:30〜17:00
場所:北とぴあ8階802号室(JR京浜東北線王子駅下車3分)
八耳俊文:「日本の地球化学のはじまりと上海科学研究所」
小林巌雄:「信濃川の自然史」
西日本支部(過去の活動)
西日本支部
日本地質学会 西日本支部
平成26年度総会・第166回例会
■日時: 平成27年2月21日(土)(20日:幹事会)
2月20日(金) 幹事会:17時〜(幹事のみ)
2月21日(土) 例 会:開催時刻未定。例会終了後 懇親会
特別講演会 金折裕司氏(山口大学・教授)「断層と地震の話・アラカルト」
*例会プログラムは、講演確定後にお知らせします。
■講演申込み〆切:2月4日(水)17時
■開催場所:山口大学,吉田キャンパス,大学会館
*キャンパスまでの交通アクセス http://www.yamaguchi-u.ac.jp/info/13/616.html
*キャンパスマップ(会場は8の大学会館)http://www.yamaguchi-u.ac.jp/library/user_data/upload/Image/yoshida-map.jpg
■参加費(予定):一般 1,000円/人,学生 500円/人
■懇親会参加費 :一般 4,000円/人、学生 2,000円/人
※皆様の積極的なご参加(特に学生・院生の皆様)を期待しております.(参加人数が増える場合はさらに学生割引あり)
※総会にご出席いただけない方は委任状を下記メールアドレスへお送り下さい。
川村喜一郎(kiichiro@yamaguchi-u.ac.jp)
====================委任状======================
日本地質学会西日本支部平成26年度総会・第166回例会における議決権を、
様に委任いたします。
平成 年 月 日
御氏名:
===============================================
※講演申込について
講演は口頭・ポスターを予定しております。
講演要旨(A4一枚。PDFファイル(フォントを埋め込むようにお願いします)+Wordファイル。フォントがうまく印刷できないようならば,オリジナルのWordファイルを用いて印刷するようにします。
・地質学会年会の講演要旨原稿フォーマットにそろえてください)をご準備下さい。
・ ご準備いただいた講演要旨は、西日本支部事務局:川村喜一郎(e-mail: kiichiro@yamaguchi-u.ac.jp)宛、e-mailにて、お送り下さい。その際に下記項目をお知らせください:1)連絡先(発表者 氏名・所属・e-mail・電話)、2)発表様式希望(口頭・ポスター・どちらでも可、のいずれか)、3)懇親会の参加・不参加をお知らせ下さい。・口頭 発表は15分、ポスターサイズは90cm×180cmです。(ただし、発表様式や発表時間につきましては、ご希望に添えないことも有ります。その際はご了 承下さい)。
■講演申込み〆切:2月4日(水)17時
(問い合わせ先:西日本支部事務局:川村喜一郎(e-mail:kiichiro@yamaguchi-u.ac.jp))
なお、ご連絡いただいた個人情報は西日本支部運営以外の目的に流用することはございません。
第165回日本地質学会西日本支部 例会・総会
2014年(平成26年)2月22日10:00〜17:00に支部例会,12:15〜13:15に総会が佐賀大学本庄キャンパスの大学会館において行われ た.例会では口頭発表,ポスター発表併せて20件が行われ,40名を超える参加者があった(写真1).例会では,今年度で支部長を終えられる小林哲夫教授 (鹿児島大学)による基調講演「九州のカルデラ火山」があった(写真2).来年度からは佐野弘好教授(九州大学)に支部長が引き継がれ,新体制で支部会を 運営する.
今年から優秀発表賞を設け,厳正なる投票により,受賞者は,下記の通り,九州大学大学院生の倉冨隆さん(写真3)と池上郁彦さん(写真4)であった.今後も支部では,優秀な学生を顕彰する方針であることを総会で確認した.
例会終了後は,懇親会も行われ,盛況の内に今年度の例会は終了した.この例会においては,実行委員会として佐賀大学の角縁進教授,高島千鶴准教授に大変お 世話になった.次回開催校は,山口大学と決まっており,金折裕司教授による招待講演も予定されている.(川村喜一郎)
写真1 例会は盛況.
写真2 小林支部長による基調講演
第165回日本地質学会西日本支部例会 優秀発表賞
O-08 倉冨隆 ほか「薩摩硫黄島における浅海熱水環境中での鉄とシリカに富むマウンドの構造解析」
P-07 池上郁彦 ほか「九州南方沖・鬼界カルデラのカルデラ堆積盆の構造」
写真3 優秀発表賞 倉冨隆さん
写真4 優秀発表賞 池上郁彦さん
専門部会登録のお願い
専門部会への登録のお願い
専門部会への登録情報の確認や更新がweb上でおこなえます!!
現在,地質学会には下記の14の専門部会があります.その活動は部会によって様々ですが,年会の折にランチョンの開催,行事委員会に部会代表委員を出して年会プログラムの編成,部会として各賞の推薦なども行っています.また,各部会のメーリングリストでは,より専門性の高い議論や,シンポジウム・巡検案内などの様々な情報がタイムリーに交換されています.今後は,専門的な学術活動を担う組織としてさらなる充実が期待されています.
今までも会員の皆様へ部会への登録をよびかけてきましたが,名簿やメーリングリストが整備されていないなどの状況があり,取り組みが遅れ気味になっておりました.このたび,newsの8月号やgeo-Flashでお知らせしたように,会員情報の変更がネットで可能になり,専門部会への登録情報の確認や更新もできるようになりました.
そこで,すでに部会の活動に参加されている方も含めて,改めて全ての会員の皆様が,専門部会の登録をホームページ上から行っていただくようお願いいたします.専門部会に所属するための条件は,特にありません.会員であれば専門によって希望する部会に,自由な意思で参加することができます.複数の部会(とりあえずは3つまで)に参加することも可能です.このシステムを利用することで,名簿などが整備され,メーリングリストの構築なども容易になります.
これを機会に会員の皆様が専門部会の活動に関心を持ち,積極的に参加されるようお願いいたします.
■ 現在活動中の専門部会は以下の14です(2012年12月現在).
岩石部会/層序部会/第四紀地質部会/海洋地質部会/情報地質部会/構造地質部会/古生物部会/環境地質部会/堆積地質部会/現行地質過程部会/応用地質部会/火山部会/地域地質部会/環境変動史部会
登録は,学会HP会員ページから行っていただけます.
なお,会員ページへのログインには,会員番号からなるIDとパスワードが必要です・ログイン情報が不明の方は,学会事務局までお問い合わせ下さい.
会員ページへのログインはこちらから
(日本地質学会理事会 担当理事 藤本光一郎)
専門部会の紹介
専門部会
【専門部会からのお知らせ】
■ 会員の皆様へ:専門部会への登録のお願い(重要)(07.12.07)
各専門部会の紹介
地域地質部会
層序部会
鉱物資源部会
岩石部会
第四紀地質部会
火山部会
堆積地質部会
構造地質部会
応用地質部会
環境変動史部会
環境地質部会
古生物部会
海洋地質部会
情報地質部会
現行過程地質部会(2021年4月解散)
地域地質部会
部会長 斎藤 眞(産総研)
本部会は地質学のもっともベーシックで不可欠である地域地質研究の推進と発展を目的として,あらゆる分野の会員に参加していただいています.地域地質学の全体的な発展に常に目を配り,各賞候補者の推薦など積極的に行ってきました.今後は,地域地質に関するシンポジウムの開催や巡検など,支部とも連携をとりながら実現したいと考えています.より多くの会員の参加を希望いたします.
層序部会
部会長:岡田 誠(茨城大)
日進月歩している調査法や測定技術そして堆積性地質体形成についての研究を取り入れ,常に最新の層序体系を作り上げることを本専門部会の目的としている.本専門部会は,研究集会の開催,シンポジュウムの企画,地質学会年会講演会の企画,論文集の企画・編集,賞への推薦,などを行っている.
情報地質
部会長名:能美洋介(岡山理科大)
地質情報についての基礎的な研究から応用技術の開発に至るまでの諸問題を,地質学と情報科学との境界領域の課題として研究する学問が情報地質学である.本部 会では,地質学の一分野としての情報地質学の更なる発展を目指して,地質情報の特性の解明とその処理のための理論・技術の研究・開発,それらの成果の地質 学分野への応用,研究成果・情報の公開・交流などの活動を行う.
岩石部会 2024年9月現在
部会長:中野伸彦(九州大学)
岩石部会は主に火成岩(深成岩)や変成岩を研究している会員と地球表層の基盤をなすこれらの岩石に関心がある全ての会員に,岩石に関する国内外の様々な情報を提供しながら円滑な研究教育活動を支援することを目指している.部会に関する活動内容や情報提供の場として,毎年地質学会のランチョンを開催している.
■岩石部会のホームページ
環境地質部会
部会長:田村嘉之(千葉県環境財団)
環境地質研究委員会を発展的に解消組織した.研究内容は都市地質,地質汚染,医療地質,社会地質,人工地質,化学災害,地盤沈下,地下水盆管理など環境に関する地質学全般です.主な活動はシンポジウム・研修会でNPO日本地質汚染審査機構,地質汚染−医療地質−社会地質学会,IUGS(国際地質科学連合) GEM(環境地質学)日本支部と共催で実施している.学術大会では夜間小集会を開きトピック的な話題提供により部会の研鑽を計る.
■ 環境地質部会:2011年東北地方太平洋沖地震から学んだ地質災害防止と人工地層と地質汚染に関わる国際宣言
2021.9月現在
古生物部会
部会長:生形貴男(京都大)
本部会は,2006年大会より,それまで脊椎動物,中古生代古生物,新生代古生物の3つに分かれていた古生物部会の定番セッションを「古生物」に一本化しました.
火山部会
部会長名:及川輝樹(産総研)
火山地質学や火山岩岩石学を専門とするメンバーの集まりである.最近の活動としては,2012年水戸大会でのトピックセッション「東日本の活火山の長期噴火予測」を開催した.活発な議論を行い好評であった.これらを地質学雑誌特集号として2013年7月(119巻7号)に掲載.今後も他の部会だけでなく,火山学会などとも連携して活動を続けてゆく予定である.
■火山部会のホームページ
海洋地質部会
部会長:小原泰彦(海上保安庁)
海洋地質部会は,種々の国際プロジェクトとの連携を保ちつつ,海洋地質学の発展と若手研究者の育成を目的としている.海洋基本法の制定や地球深部探査船「ちきゅう」の運用により部会の果たすべき役割は近年増大している.学術大会のランチョンでは,各研究機関や組織から最新の研究成果や航海予定の報告を受け,今後の調査研究について議論する貴重な場を提供している.またメーリングリストにより随時情報交換を行っている.
堆積地質部会
部会長:田村 亨(産総研)
当部会は,堆積作用や堆積岩など地層を形成するさまざまな現象について調査し,その成果を発表するなどの活動をしている.この部会員は日本堆積学会にも所属している者が多く,部会も両者を統合するような活動をしている.この分野では,堆積相解析やシーケンス層序など地層の形成過程が久しく研究されてきたが,現在は新しい課題を模索している状況である.新しく,若い力を求む.
■堆積地質部会のホームページ
構造地質部会 2024年11月現在
部会長:道林克禎(名古屋大学)
1966年以来構造地質学分野の発展に関わってきた構造地質研究会が構造地質部会に2006年度より統合された.活動は,3月の例会(2006年度は南紀白浜,2007年度は長岡)のほか,2007年11月24-25日に「日本海沿岸褶曲・断層帯の形成・成長と地震活動」(於新潟大学)を開催.出版物は地質学雑誌の「特集号」として不定期に企画され,「沈み込み帯と地震」に関する特集を2009年9月(115巻9号)に掲載された.若い方の加入を大歓迎します.
■構造地質部会のホームページ
応用地質部会
部会長:西山賢一(徳島大)
応用地質学は広範な地質情報を社会が必要とする情報−社会基盤となる土木構造物の設計・施工や災害軽減のための情報−などに読み替えていく分野でもある.これには地質学のもつ様々な知識や考え方を総動員するとともに,地球物質に関する工学的視点も必要である.本部会はこのような目的で,地質学とかかわりをもつ関連諸学会との連携を通じ,応用地質学分野の普及と研究者・技術者育成を目指すものである.
第四紀地質部会 2024年11月現在
部会長 長橋良隆(福島大)
大気,海洋,陸,氷床,陸水,生物,さらに人間は,第四紀の時代を通じて,それぞれが相互作用を繰り返しながら激しく変遷し,現在に至った.第四紀地質学は,人類の時代の地球・地域環境の歴史的変遷過程やそのメカニズムを解明し,それらを基礎にして,人類を含む地圏・大気圏・水圏・生物圏の将来予測を考えます.現在を含む最新の地質時代である第四紀を扱う多様な分野の研究者・院生の参加を期待しています.
■第四紀地質部会のホームページ
鉱物資源部会
部会長 中村謙太郎(東京大)
地球に産する様々な鉱物資源を,地質学的な視点から解明する研究分野の専門部会.海底鉱物資源をはじめとする新しい資源の開発に向けた動きが活発化している中,地質学的観点に立って鉱物資源の成因解明に取り組み,この分野の発展に貢献することを目的としている.この専門部会を,鉱物資源研究者の情報交換・情報発信の場として機能させたい.
環境変動史部会
部会長: 尾上哲治(九州大)
地層や岩石中には,過去の地球環境の変動履歴が記録されている.これら地質記録から過去の地球の姿を読み解き,地球環境の変動を理解することは極めて重要である.環境変動史部会は,多様な研究手法,様々な時間スケールでの環境変動研究の発展に貢献することを目的とし,2012年10月に設立された.本部会を,環境変動研究者の情報交換・情報発信の場として機能させたい.
幹事(行事):黒田潤一郎(東京大)
2011年度各賞受賞者
2011年度各賞受賞者 受賞理由
■日本地質学会賞(1件)
■国際賞(1件)
■小澤儀明賞(1件)
■柵山雅則賞(1件)
■論文賞(3件)
■小藤賞(1件)
■研究奨励賞(3件)
■Island Arc賞(1件)
■功労賞(1件)
■学会表彰(1件)
日本地質学会賞
受賞者:岩森 光 (東京工業大学大学院理工学研究科)
対象研究テーマ:マントルにおける物質循環とマグマの発生・分化の地質学的研究
岩森 光氏は,1990年に「西南日本,中国地方中央部における新生代玄武岩火山活動の帯状構造」の研究で学位を取得した.その後,地球内部の物質分化と循環のダイナミクスに関して,連続体としての地質体の運動場モデルの数値シミュレーションや多変量解析を用いた研究を展開し,国際的にも先駆的な役割を果たしてきている.
具体的には,沈み込むプレートの年齢や速度などによる温度場の相違により,スラブからの脱水が支配されるモデルを数値シミュレーションし,その結果が日本列島の火山の分布やマントルの地震学的な構造と対比できることを示した.さらにこのモデルを発展させて,海嶺沈み込みの数値シミュレーションを行い,沈み込み帯において認められる花崗岩生成及び高温型と高圧型の対の変成帯が必然的に関連して形成し得ること,さらに沈み込み帯における火山活動とも一連のプロセスである可能性を示した.最近では,海嶺玄武岩と海洋島玄武岩の地球化学データの多変量解析により,これまでとは異なる視点から地球規模のマントルにおける物質分化と循環のダイナミクスを提唱するなど,独創性の高い顕著な業績をあげている.
これまでに岩森氏が公表した40編を超える国際誌論文の多くが単著または筆頭であり,非常に多くの被引用数や,多数の招待講演の実績によって,国際的な高い評価が裏付けられている.国内においても,地質学論集の「マントルの融解過程のシミュレーションの現状と課題」をはじめ多くの学術誌において論文を公表して,地質学における新たな視点の導入を推進している.
以上のように,岩森氏の研究はインパクトが大きく,マグマの発生やマントルにおける物質分化と循環を理解する上で,先駆的な貢献をしている.また,これらのアプローチは今後,具体的な地質現象と関連づける事によりさらに進展し,固体地球・惑星内部の物質およびダイナミクスの理解の発展に大きく寄与することが期待される.
さらに,岩森氏は日本地質学会理事及び地質学雑誌の副編集長として学会活動の発展に貢献するとともに,固体地球分野全般の長期的な科学計画のとりまとめ役としても尽力し,また文部科学省の学術調整に係わる官職を担うなど,幅広い活動を通じてこの分野の科学とコミュニティの発展のために活躍している.
以上の優れた業績に鑑み,岩森 光氏を日本地質学会賞に推薦する.
日本地質学会国際賞
受賞者:J. Casey Moore (米国カリフォルニア大学サンタクルズ校名誉教授)
対象研究テーマ:付加体の陸上および海洋地質学的研究
J. Casey Moore米国カリフォルニア大学サンタクルズ校名誉教授は,プレート沈み込み帯のテクトニクスおよび付加体水理学研究の第一人者である.とりわけ国際深海掘削計画には,その黎明期から主導的な役割を果たし,1973年のDSDP(Deep Sea Drilling Project)31次航海による日本近海での初探査から日本の研究者とともに航海に参加し,これに引き続く ODP (Ocean Drilling Program) および現在のIODP (Integrated Ocean Drilling Program) に至るまで日本の海洋地質学の発展に貢献してきた.現在進行中の「ちきゅう」による IODP 南海トラフ地震発生帯掘削計画においても,計画立案段階から関与し,共同主席研究者および乗船研究者としても参加し,計画を強力に推進している(196次航海,314次航海および319次航海).
Moore氏の代表的な研究は,中南米のバルバドス,南メキシコ,カスカディアそして西南日本沖の南海トラフにおける現世付加体のテクトニクスと水理地質,そしてアラスカコディアック島における陸上付加体の構造地質学的研究である.1970年代後半から現在に至るまで,海陸両面から,付加体の構造,メランジュの厚化モデル,デコルマ帯の水理構造,プレート境界震源域の上限要因など,常にこの分野をリードする論文を発表し続けてきた.Moore氏の研究論文は,長い間,その分野の研究者の引用するところとなっており,多くの基礎的,応用的,かつ古典的論文として認められてきた.また,これらの研究にもとづく論文特集号の編集にあたるともに,時代を画するレビューペーパーを発表し,多くの研究者の模範となってきている.また,アメリカ地質学会のフェローにも選ばれている.
以上のようにMoore氏は,日本の海洋地質学の発展にめざましい貢献を果たし,また数々の国際共同研究を時にはチーフとしてプロジェクトを成功に導き,また時には若手研究者を強力にサポートしてきた.これに加えてMoore氏は教育者としてもたいへん優れており,カリフォルニア大学サンタクルズ校には,世界中から多くの若手研究者や学生が集い氏と共に研究活動を鍛錬してきた.Moore氏は日本からの留学生にも門戸を開き,彼ら彼女らを暖かく迎え入れ,研究活動を支援してきた.Moore氏の研究室からは多くの才能有る優秀な研究者が輩出され,その出身研究者らによって本邦四万十帯と沈み込み帯研究の一翼が担われた.
以上の様にJ. Casey Moore名誉教授は,日本の地質学と地質学界に顕著な功績があり,日本地質学会国際賞に強く推薦する.
日本地質学会Island Arc賞
受賞論文:Saffer, D. M., Underwood, M. B. and McKiernan, A. W., 2008, Evaluation of factors controlling smectite transformation and fluid production in subduction zones: Application to the Nankai Trough. Island Arc, 17, 208-230.
Combining ODP data on the Nankai sedimentary package with kinetic studies involving the reaction of smectite to illite, the authors have established numerical models simulating the clay minerals’ reaction both outboard of the deep-sea trench and beneath the convergent plate junction, thereby enhancing a quantitative understanding of accretionary processes and seismicity. Heat flow (or crustal age) has the largest effect on the transformation. They showed that the eastern high heat flow slab segment initiates the transformation before arriving at the trench, whereas the western low heat flow slab segment results in negligible presubduction diagenesis and that plate convergence rate has the smallest effect on the transformation. This provides the most credible view of how clay diagenesis modulates hydrologic and mechanical behavior of the subduction boundaries. These are important information on mechanical property of the seismogenic zone as well as diagenesis and fluid circulation in the accretionary wedge.
This paper received the highest number of citations - based on the Thomson Science Index for the year 2010 - amongst the entire candidate Island Arc papers published in 2007-2008. The first author has been working in the fields of the geohydrology, active tectonics, fault mechanics, and structural geology, focusing on quantifying the relationships between fluid flow, deformation, solute transport, and heat transport in subduction zones and transform fault systems like the San Andreas Fault. He and his group have published many important results on these fields. In view of the scientific impact of the paper and international scientific activity of the first author, the Judge Panel recommends this paper for the 2011 Island Arc Award.
日本地質学小澤儀明賞
受賞者:黒田潤一郎(海洋研究開発機構)
対象研究テーマ:地球内部活動と海洋無酸素事変のリンクの解明
黒田潤一郎会員は,東京大学大学院理学系研究科修士課程在籍時から,世界各地の白亜紀黒色頁岩と,それを生み出した海洋無酸素事変について研究してきた.彼は,物質科学的視点で黒色頁岩の分析を徹底的に行った.例えば,堆積物の詳細な記載を行った上で,EPMAを用いた元素マッピング,二次イオン質量分析計を用いたマイクロスケール炭素同位体分析,バイオマーカーの同位体分析などにより,黒色頁岩堆積時の海洋環境変動を従来にない高い時間解像度で復元した.最近では,鉛・オスミウム等の同位体分析に取り組み,海洋無酸素事変に対する大規模火成活動との関係に焦点を当てた研究を進めている.彼の研究により,巨大火成岩区(LIP)の形成に伴う大規模火山活動が海洋無酸素事変と数千年以内の年代差で一致することを世界で初めて実証的に示した.彼の研究成果公表後,同様の研究が世界中で数多く発表され,いずれの研究においても,彼の結果が支持された.それにより,LIPの形成という地球内部活動が気候システムに大きなインパクトを与えてきたという従来からの仮説が,国際的なコミュニティの中で一気に浸透し,特に海洋無酸素事変の究極の成因が地球内部活動にあることが一般的な知見として認知されるに至った.彼はその後,この研究をさらに三畳紀/ジュラ紀境界の大量絶滅イベントに展開している.この研究では,北大西洋LIPの形成が三畳紀末に起こり,その後の急激な温暖化による大陸風化率の上昇が生物大量絶滅の時期に一致することを明らかにした.この発見は,三畳紀末の生物大量絶滅に関する新しい学説を生み,国内外で注目されている.
黒田会員は,現在,クロム同位体分析や放射光分析を用いた新しい古環境解析法,特に過去の海水の酸化還元変動の指標の確立に取り組んでいる.彼は,常に地質学者の視点に立って,入念な野外地質調査に基づいて研究対象を決定し,そこに最新の分析技術を取り入れるという研究姿勢を取っている.また,統合国際深海底掘削計画(IODP)第320次航海“Pacific Equatorial Age Transect (PEAT)”などの国際共同研究に積極的に参加し,IODPの科学立案・評価パネル委員も務めた.日本地質学会においてもセッションの共同コンビーナーや評議員を務め,「地球システム・地球進化ニューイヤースクール」の事務局や代表を務めるなど,幅広く活動している.このような優れた研究業績と地質学界への貢献に鑑み,黒田潤一郎会員を日本地質学会小澤儀明賞に推薦する.
日本地質学柵山雅則賞
受賞者:河野義生(High Pressure Collaborative Access Team [HPCAT])
対象研究テーマ:岩石の弾性波速度測定による地球内部の構造解明研究
河野義生会員は,横浜国立大学教育学部での卒業研究および同大学院環境情報学府での修士・博士研究を通して,ピストンシリンダー型高圧発生装置を用いた弾性波速度測定の技術開発に取り組み,「島弧下部地殻同等の高温高圧下(最大1000ºC,1.0ギガパスカル)での岩石の弾性波速度測定」(Elastic wave velocities of lower crustal rocks and plagioclase aggregates up to 1000ºC and 1GPa)の論文で2006年3月に博士(学術)を取得した.この測定は,当時欧米で実施されていた最高温度条件(600ºC)をはるかに上回るものであり,「高温下で斑れい岩類の弾性波速度が従来の予想よりも大きく低下する」という事実の発見につながった.さらに鉱物学的検討結果から,その原因が斜長石の秩序-無秩序転移であることを特定した.これらの研究により,高温条件下での岩石の弾性波速度を予測補正することなく地震波速度構造と対応させることが可能となった.これは島弧の地殻構造を理解する上で大きな意義を持っている.彼の高温高圧下での岩石の弾性波速度測定は,その後も地球内部構造の解明につながる重要な成果をあげ,国際的な学術雑誌に多数の筆頭論文として報告された.
また,河野会員は実験結果から得られた事実が実際の地質現象の解釈に応用できることも示した.コヒスタン古島弧地殻断面が露出するパキスタン北部の研究では,地質調査と岩石の弾性波速度測定から,「地震学的に認識されるモホ面の下にはざくろ石輝岩に富む層が存在し,かんらん岩の出現境界はさらに下位に位置すること」を例証した.同様のモホ下の構造は伊豆小笠原弧でも地震学的に提案されており,彼のモデルはモホ面の実態解明に今後大きく貢献すると期待される.
2006年4月から愛媛大学地球内部ダイナミクス研究センターに研究の場を移し,SPring-8において放射光X線と弾性波速度測定を組み合わせることにより,マントル遷移層まで沈み込んだスラブやその構成鉱物がもつ地震学的特徴を調べている.これら一連の成果から,「マントル遷移層領域の地震学的速度モデルを説明するには,玄武岩組成のピクロジャイト的な物質ではなく,全体としてハルツバージャイト的な化学組成物質が必要」であると報告している.この成果は国際的にも速やかに認識され,国外の研究所や大学との共同研究に発展している.
このように河野会員の研究活動は,島弧規模から地球規模の内部構造の解明に貢献してきた.その業績を高く評価し,河野義生会員を日本地質学会柵山雅則賞に推薦する.
日本地質学会論文賞
受賞論文:Yamamoto, Y., Nidaira, M., Ohta, Y. and Ogawa, Y., 2009. Formation of chaotic rock units during primary accretion processes: Examples from the Miura–Boso accretionary complex, central Japan. Island Arc, 18, 496–512.
山本由弦氏は三浦・房総半島南部の地表地質を精密に調査し,そこに露出する付加体堆積物に観察される様々な現象をそれらの時空間分布とともに明らかにし続けている.本論文では,付加体表層部に観察される乱堆積物の岩相と内部構造を詳細に記載し,これらが付加体形成初期の海底地すべりによるスランプ堆積物と付加体形成後の地震に関連した液状化による堆積物に分類できることを明らかにした.この成果は,付加体形成の初期段階において海底面傾動と地震動による浅部堆積層への影響を明らかにするものであり,堆積物の組織・構造的特徴をプロセスと対応付けた点において従来の研究とは一線を画するものであると評価できる.このような堆積物を露頭で観察できる当該地域の希少性に注目した本論文は,ジオハザードとして世界的に注目されつつある「海底地すべり」に関する沈み込み帯での貴重な研究例として日本から発信できる重要な成果であり,地質学会論文賞に値する.
受賞論文:Fujii, M., Hayasaka, Y. and Terada, K., 2008. SHRIMP zircon and EPMA monazite dating of granitic rocks from the Maizuru terrane, southwest Japan: Correlation with East Asian Paleozoic terranes and geological implications. Island Arc, 17, 322-341.
本論文は,舞鶴帯北帯の花崗岩類のジルコンSHRIMP U-Pb 年代とモナズ石のU-Th-Pb EPMA年代を多数測定し,東部の岩体は約250Ma,西部の岩体は約410Maに集中することを明らかにし,それぞれを飛騨帯とロシア沿海州のハンカ地塊に対比して,日本海拡大以前の日本列島と大陸のつながりを議論したものである.これは,舞鶴帯北帯の「夜久野岩類」が,南帯の夜久野オフィオライトとは全く起源が異なる地質体であることを提案している.また,提案された復元図上での阿武隈帯とセルゲーエフカ帯の対比の妥当性や,大江山オフィオライトの扱いに関する問題点が現出し,今後の研究における新たな検討課題が提示された.さらに,本論文では,より古い年齢を示すジルコンやモナズ石などの捕獲結晶についても丁寧に記載・議論されている.この論文は東アジア大陸縁の地質構造の解明にとって重要な貢献であり,論文賞に値する.
受賞論文:Endo, S., 2010. Pressure-temperature history of titanite-bearing eclogite from the Western Iratsu body, Sanbagawa Metamorphic Belt, Japan. Island Arc, 19, 313–335.
三波川変成帯の変成岩類は沈み込み帯の深部で形成され,その圧力—温度条件は多くの研究者により扱われてきたが,圧力—温度経路について共通見解は得られていない.遠藤氏は解析例が極めて少ないチタナイト(Tnt)を含む Ca-に富んだ岩相に着目し,累帯するTnt 鉱物の詳細な組成分析により,高圧変成岩類の形成条件を見積もる新たな方法を示した.本論文で得られた圧力温度条件は,従来の研究結果や,遠藤氏が別の手法で示した結果と整合的であり,新たに開発された方法の妥当性を示唆する.また,減圧時,つまり上昇時の温度増加を強く支持し,高い温度勾配で生じた緑簾石̶角閃岩相がエクロジャイト変成作用に先立つことも示した.これらの成果は三波川変成帯における高圧変成岩類の形成条件と沈み込みとの関係を究明する上で貴重である.以上,本論文は変成岩石学の研究として新規的で優れており,地質学会の論文賞に値する.
日本地質学会小藤賞
受賞者:Tazawa, J., Anso, J., Umeda, M. and Kurihara, T., 2010. Late Carboniferous brachiopod Plicatiferina from Nishiamada, Fukui Prefecture, central Japan, and its tectonic implications. The Journal of the Geological Society of Japan, 116, 51-54.
本短報は,梅田ほか(2008)が福井市美山町に分布する宇奈月帯の弱変成シルト岩から発見した腕足類化石の地質時代と古地理を議論したものである.まず,田沢氏らはこの化石を同定し,同帯の石灰岩から報告されていた有孔虫やコケ虫化石が示す時代(後期石炭紀)と矛盾がないことを示した.さらに,同定された腕足類がボレアル型であることを根拠に古地理的な議論が進められ,飛騨帯(宇奈月帯)が中朝地塊またはモンゴル・オホーツク造山帯の一部であったことが示唆された.田沢氏は腕足類化石の古地理的情報を基礎とした地質構造発達史に多くの重要な成果を公表しており,本短報もその1つに加える事ができる.また,共著者による弱変成層からの化石発見は丹念な地層観察の重要性を再認識させるものであり,本短報の内容と同等に高く評価すべきである.著者全員のこれからの研究活動を奨励する意味においても,本短報に小藤賞を授与すべきものと判断する.
日本地質学会研究奨励賞
受賞者:常盤哲也(日本原子力研究開発機構)
受賞論文:Tokiwa, T., 2009. Timing of dextral oblique subduction along the eastern margin of the Asian continent in the Late Cretaceous: Evidence from the accretionary complex of the Shimanto Belt in the Kii Peninsula, Southwest Japan. Island Arc, 18, 306-319.
白亜紀の環太平洋域に存在していたプレートの数とそれぞれの運動方向・速度は復元されているが,クラプレートのような消滅したプレートの位置関係を復元するのは容易ではない.しかし,そのヒントは,沈み込みの斜め成分に応じて大陸縁辺の堆積物と岩石に残された剪断変形センスにある.本論文で,常磐氏は綿密な野外調査と室内観察により,紀伊半島北部に分布する四万十帯の広い地域において岩石の剪断センスが右ずれであることを示した.四万十帯の地層は海溝近傍で堆積したので,堆積年代とプレート境界での変形年代の間に大きな差はない.常磐氏は,後期白亜紀に右ずれセンスを生じる候補をクラプレートと限定し,当時のアジア大陸東縁部において,このプレートによる右斜め沈み込みの応力が働いていたことを強く示唆した.本論文の成果は環太平洋プレート群の運動像を復元する上で極めて貴重なものであり,地質学会奨励賞に値する.
受賞者:辻 智大((株)四国総合研究所)
受賞論文:辻 智大・榊原正幸, 2009. 四国西部における北部秩父帯の大規模逆転構造. 地質学雑誌, 115, 1-16.
堆積構造に基づく地層の上下判定は,変形を受けた地質体の褶曲構造を推定するための基本であるが,緑色岩や石灰岩を含み変形が進んだメランジュでは容易ではない.本論文は,詳細な地質調査による露頭スケールの視野と,級化構造に着目した薄片スケールの視野で粘り強く上位判定を行い,その結果から四国西部の北部秩父帯に大規模な逆転構造があることを示唆した.また,この大規模褶曲体が下位の海山起源の岩体と東西走向北傾斜の断層で仕切られることも示された.褶曲体の形成メカニズムについては未確定ではあるものの,本論文で提示された地質構造に関する検討結果は,西南日本地質構造発達史の見直しの契機になる可能性を秘める.さらに,野外調査と顕微鏡観察のみで得られた証拠でメランジュの構造復元という困難な課題に立ち向かった姿勢は,多くの野外地質系若手研究者へ範を示すものと評価できる.以上のことから,本論文は日本地質学会の研究奨励賞に値する.
受賞者:隅田祥光(明治大学黒曜石研究センター)
受賞論文:隅田祥光・早坂康隆, 2009. 夜久野オフィオライト朝来岩体における古生代海洋内島弧地殻の形成と進化過程. 地質学雑誌, 115, 266-287.
本論文で研究対象となった夜久野オフィオライト朝来岩体は,古生代海洋性島弧の中・下部地殻の断片と考えられている.本研究では,詳細な野外観察を基礎とし,鏡下観察から地球化学的解析までの多様な手段を駆使することにより,朝来岩体の最下部に,より早期に存在していた苦鉄質基盤岩が部分溶融して形成されたミグマタイトが存在することが明らかにされた.特に,部分溶融をおこした苦鉄質岩類の起源,および,ミグマタイト・リューコソムと上位の石英閃緑岩〜花崗岩質岩脈・岩床の関係について詳細に検討され,苦鉄質基盤岩は背弧盆地殻起源であること,リューコソムは集積・上昇する過程で結晶分化しながらマグマへと成長し,岩脈や岩床を形成したことなどが示されている.本論文は,伊豆弧などの現在の海洋性島弧の研究,あるいは安山岩・花崗岩質マグマの成因の研究に貴重なレファレンスを提供するものと評価され,十分に研究奨励賞に値する.
日本地質学会功労賞
受賞者:石井輝秋
功労業績:日本近海の海洋底地質・岩石研究への貢献
石井輝秋氏は,故久野久教授の最後の学生として,1975 年に箱根の火山岩の岩石学的研究により東京大学大学院で博士号を得た.同年に発表したピジョン輝石温度計に関する論文および1991年に公表した総括的な論文は世界的な注目を集めた.石井氏は1977年から2010 年まで東京大学海洋研究所および海洋研究開発機構のスタッフとして勤務し,この間にフィリピン海を中心とする日本近海,特に伊豆・小笠原・マリアナ(IBM)海域の海洋底岩石研究に携わり,50 編ほどの国際誌論文を含む約170 件の研究成果を公表した.IBM 海域での国際深海掘削計画の航海で得られたマントルかんらん岩の研究は詳細な岩石学的記載が高く評価されている.また,多くの学生や若手研究者に助言・指導を行い,優れた教育上の成果も残している.
石井氏は一流の研究者・教育者である一方で,海洋地質学・岩石学の発展を支える意味において際立った功績を残している.まず,彼は「石井式ドレッジ」を開発してドレッジ技術を向上させ,様々な粒度の海底堆積物を同時かつ大量に採取することを可能にした.また,石井氏は多数の研究航海に主席あるいは研究者として乗船し,大学,分野,国籍などの枠を越えて乗船科学者の研究を親身にサポートした.海洋底の地質・岩石研究は決して一人でできるものではなく,運航日程,天候・海況,機械の調子などをにらみながら船側と交渉し,乗船研究者の適性や体調を判断しながらうまく働かせて最大の成果を挙げる駆け引きが必要であり,台風などの危険が迫れば全ての研究をあきらめて船を避難させる決断力も必要である.彼はこうした能力に長けたオーガナイザーであり,毎年数カ月を海上で過ごしてきた実践的な海洋研究者である.さらに,石井氏は国際深海掘削計画の委員を務めたほか,多くの国内研究集会を主催して論文集を発行し,海外の関連学会や巡検にも積極的に参加して世界の多くの研究者と友好関係を築いてきた.一眼レフを下げて笑顔をふりまくドクター・テル・イシイは世界中で有名である.石井氏の裏方的努力は,多くの陸上地質学者を海洋地質学へといざない,日本の優れた若手海洋底岩石研究者を育て,外国人との共同研究を活性化させ,日本の海洋底岩石学のレベルを大きく向上させた.以上の通り,日本の海洋底地質・岩石研究の発展に果たした石井輝秋氏の功績は極めて大きく,日本地質学会功労賞に値する.
日本地質学会表彰
受賞者:独立行政法人森林総合研究所・千葉県南房総市
表彰業績:海底地すべり露頭の保全と社会教育的活動
海底地すべりは,海底ケーブルなどのインフラを破壊し,時には巨大津波を誘発することから,人間社会に影響の大きいジオハザードではあるが,噴火や洪水とは違って私たちの目に触れる現象ではない.2007 年,房総半島南部の農業道路建設現場の法面に,層厚約20 m におよぶ,非常に明瞭な大規模海底地すべり地層が現れた.この露頭は,地すべり岩体の下底から上端までのカオティックな内部構造を運動方向に沿って表し,海底地すべりの岩体の破壊力を如実に物語っている.おそらく,これほど見事な海底地すべり露頭は世界的にも例がないだろう.この露頭の学術的調査は速やかに進行し,地すべり層の主体が,液状化により剪断強度を失った上部鮮新統~更新統の千倉層群畑層中の砂層であり,それを引き起こした地震は約200 万年前に発生したことが明らかになっている.
工事の発注者である独立行政法人森林総合研究所(当時は独立行政法人緑資源機構)は,この露頭が世界的にもきわめて貴重な地質遺産であることを認識し,当初から現場の学術的調査に非常に協力的であった.工事終了後には,道路の移管先である南房総市と森林総合研究所が協議し,当初の予定を変更して,露頭面積の約1/3 にあたる幅15 m・高さ15 m の主要部分の保存を英断した.その直後から,露頭の長期保存に関する対応がなされた.まず,約半年をかけて複数の塗布薬剤の耐性テストを行い,その結果をもとに,風化や剥脱などの変質を防ぐための最も効果的な薬剤が採用された.さらに,露頭正面には駐車場が整備され,見学者のための説明看板や,露頭への道路案内標識も複数設置された.農業道路が開通した2010 年3 月以降は,この海底地すべり露頭へは誰でも簡単にアクセスできるようになり,地質学関連の学会や大学の巡検や授業で使用されているほか,地元でも宿泊客に積極的に案内されている.
公共工事において出現した露頭は貴重な地質学的情報のソースであるが,ここまで大規模に保存・活用されたことは少ない.貴重な地質遺産の保存を促進する流れは地質学会を挙げて作り出さなければならない.今回の事例は,永続的な保存を英断したことに加え,薬剤選定を通じて露頭保存工学を進展させた点でも特筆すべきであり,地質学の発展と普及にも貢献した.この森林総合研究所および南房総市の壮挙は,学会を挙げて賞賛すべきものであり,地質学会表彰に値する.
Geo暦(2021)
2021年Geo暦(行事カレンダー)
2008年版 2009年版 2010年版 2011年版 2012年版 2013年版
2014年版 2015年版 2016年版 2017年版 2018年版 2019年版
2020年版 2021年版 2022年版
2021年版 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
○印は学会主催行事.(共)学会共催・(後)後援・(協)協賛
1月January
学術フォーラム・防災連携シンポジウム「東日本大震災から10年とこれから」
1月14日(木)10:00-18:30
会場:東京医科歯科大学 鈴木章夫記念講堂
主催:日本学術会議 防災減災学術連携委員会、防災学術連携体(58学会)他
参加費:無料
定員:(会場)150名(500名の定員を1/3に制限しています)
(WEB)1000名
https://janet-dr.com/060_event/20210114.html
令和2年度国土技術政策総合研究所講演会
1月18日(月)9:00-(オンデマンド配信)
参加無料,事前登録不要
http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/koen2020.html
下北ジオパーク学術研究発表会(オンライン)
1月23日(土)13:00-16:00(使用媒体:Microsoft Teams)
参加無料.要事前申込
参加方法等詳しくは,
http://shimokita-geopark.com/2020/12/17/0123presentation/
2月February
国際WEBシンポジウム
「持続可能な未来を拓く 〜コロナ時代における自然と人間との共生〜」
主催:国際花と緑の博覧会記念協会、地球環境戦略研究機関(IGES)
2月3日(水)15:00-16:00(日本時間)
要事前申し込み
https://www.expo-cosmos.or.jp/main/cosmos/symposium/20210203/index.html
産業技術総合研究所 第33回GSJシンポジウム(オンライン)
地圏資源環境研究部門 研究成果報告会
「地圏に関わる社会課題の解決に向けて」
2月5日(金)13:00-16:10
方法:Microsoft Teamsライブイベント
参加費無料
https://unit.aist.go.jp/georesenv/index.html
公開シンポジウム「桜川低地の成り立ちと里山ジオツアーの勧め」(オンライン)
2月14日(日)13:20-16:45(13:00 開場)
主催:筑波山地域ジオパーク推進協議会
参加形式:オンラインのみ(Zoomを使用)
参加申込締切:2021年2月7日(日)
https://tsukuba-geopark.jp/page/page000704.html
日本学術会議学術フォーラム(オンライン)
新たな地球観への挑戦―地球惑星科学の国際学術組織の活動と日本の貢献―
2月15日(月)13:00-17:30
オンライン開催 参加費無料
http://www.scj.go.jp/ja/event/2021/306-s-0215.html
3月March
東京大学大気海洋研究所共同利用研究集会
琉球弧ダイナミクスの新展開:島弧ダイナミクスの理解への新たな切り口
3⽉3⽇(水)-4日(木) 9:00-12:30,
場所: Zoom meeting(事前の参加登録が必要です)
https://www.aori.u-tokyo.ac.jp/aori_news/meeting/2021/20210303.html
令和2年度海洋プラスチックごみ学術シンポジウム(オンライン)
3月3日(水) 9:30-17:30(予定)
主催:環境省
参加費:無料,定員:500名
参加登録締締切:3月2日(火)17:00
講演者公募締切:1月29日(金)正午
https://www.env.go.jp/press/108945.html
Tokai University Online Workshop
Challenges of Marine Observations and Development of International Collaboration
3月6日(土) 8:30-16:00 (JST)
行事詳細はこちらから
地区防災計画学会第7回大会(オンライン)
「コロナ禍でのモデル地区での地区防災計画づくり」
3月6日(土)9:30-17:30(予定)
参加無料
対象:地域防災の強化や地区防災計画づくりに興味のある方
https://gakkai.chiku-bousai.jp/ev210306.html
○JABEEオンラインシンポジウム
自然災害列島における地質技術者の育成−大学統合期における地質学教育ー
(2020名古屋代替企画)
3月7日(日)14:00〜17:15(予定)
配信方法:ZoomにYou Tubeを連動させるオンライン方式
参加費無料.Zoom参加者は事前登録制
[zomm参加申込:2/25(木)締切]
http://www.geosociety.jp/science/content0127.html
第55回日本水環境学会年会(オンライン)
3月10日(水)〜12日(金)
500件以上の一般講演、各種のセミナーのほか、特別講演会や、全国環境研協議会研究集会にご参加いただけます.水環境が抱える課題や対策にご関心のある大勢の方のご参加を期待しております.
http://www.jswe.or.jp/event/lectures/2020per.html
4月April
5月May
日本地球惑星科学連合2021年大会
開催方式:ハイブリッド開催(完全オンライン開催になりました)
現地会場:パシフィコ横浜ノース
5月30日(日)-6月6日(日)
http://www.jpgu.org/meeting_j2021/
6月June
地質学史総会・懇話会(ハイブリッドに変更)
6月26 日(土)13:00〜(30分早くなっています)
場所:早稲田奉仕園セミナーハウス(会場も変更になりました)
〒169-8616 東京都新宿区西早稲田2-3-1
TEL:03-3205-5411(10:00-18:00)
内容:
志岐常正:「戦後京大地質学教室史―その虚像と実像」
矢島道子:『地質学者ナウマン伝』を上梓して
(注)オンラインのURLは6月20日以降、希望者に送ります.矢島(pxi02070[at]nifty.com)までご連絡ください。※[at]を@マークにしてください.(2021.5.23変更)
情報計測オンラインセミナーシリーズ
− 数理・情報科学×計測科学の高度融合による新展開−
主催:JST CREST・さきがけ研究領域"情報計測"
第1回 6月26日(土) 10:30-11:50
第2回 7月10日(土) 10:30-11:50
以降、セミナー講演を多数回に亘りシリーズで引き続き開催予定
参加費無料,要事前参加登録
https://measurement-informatics-seminars.jp/
(協)資源地質学会第70回年会学術講演会
6月30日(水)〜7月2日(金)
6/30:シンポジウム「酸化還元反応と鉱化作用」
会場 Webexを用いたオンライン開催
https://www.resource-geology.jp/report/
7月July
(後)第58回アイソトープ・放射線研究発表会
7月7日(水)〜9日(金)
開催形態:オンライン開催
演題登録期間:2021年1月12日〜3月8日
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2021/top
情報計測オンラインセミナーシリーズ
− 数理・情報科学×計測科学の高度融合による新展開−
主催:JST CREST・さきがけ研究領域"情報計測"
第2回 7月10日(土) 10:30-11:50
以降、セミナー講演を多数回に亘りシリーズで引き続き開催予定
参加費無料,要事前参加登録
https://measurement-informatics-seminars.jp/
◯日本地質学会第4回ショートコース
7月18日(日)
<午前>10:00-12:00「吾書くゆえに吾あり:論文執筆についての超個人的視点」磯粼行雄(東京大学)
<午後>13:30-15:30「地球科学の歴史から何を学ぶか」泊 次郎(科学史研究家)
申込締切:2021年7月5日(月)
http://www.geosociety.jp/science/content0134.html
(後)科学教育研究協議会 第67回全国研究大会・福島大会
7月31日(土) 〜8月2日(月)
会場:伊達市立霊山中学校(福島県伊達市霊山町)Web大会に変更になりました
大会テーマ 自然科学をすべての国民のものに
https://kakyokyo.org/
8月August
地区防災計画学会シンポジウム(第37回研究会)
コロナ時代の避難の在り方―静岡県熱海市の土石流災害等を踏まえて―
8月21日(土) 13:00-15:30(予定)
※オンライン開催(YouTubeによる同時配信・再放送なし)
参加費無料・地区防災計画学会HPから申込必要
https://gakkai.chiku-bousai.jp/
9月September
(共)2021年度日本地球化学会第68回年会
9月1日(水)〜15日(水)討論実施期間
9月6日(月)〜8日(水)Zoomセッション
9月7日(火)夜間集会
9月9日(木)総会・授賞式・受賞講演
9月9日(木)〜10日(金)弘前セッション
9月21日(火)閉会式
(注)全面オンライン開催となった場合:9月6日(月)〜10日(金)Zoomセッション
場所:オンライン会場および弘前大学会場(弘前大学50周年記念会館)のハイブリッド開催
http://www.geochem.jp/meeting/
日本科学協会主催セミナー:科学と芸術の交響、時空を超えた対話
9月3日(金)18:00〜20:30
ハイブリッド配信
①会場(港区赤坂1-2-2 日本財団ビル2階)
②オンライン(Zoom Webinar使用)
参加費:無料(事前登録制)
https://www.jss.or.jp/ikusei/rinsetsu/arts/seminar.html
〇 日本地質学会第128年学術大会(名古屋大会)
9月4日(土)〜6日(月)
会場:名古屋大学東山キャンパス + オンライン開催
※セッションはすべてオンラインで実施します.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/top
(後)第64回粘土科学討論会
9月14日(火)〜18 日(土)
(ポスター発表はリモートおよびオンデマンド方式)
会場:信州大学 長野(工学)キャンパス
http://www.cssj2.org/event/annual_meeting/
日本土壌肥料学会2021北海道大会
9月14日(火)〜16日(木)(オンライ大会)
※全面オンライン大会に変更
https://www.jssspn.org/2021/
日本鉱物科学会2021年年会
9月16日(木)〜18日(土)
場所:広島大学東広島キャンパス
http://jams.la.coocan.jp/nenkai.html
国際ゴンドワナ研究連合(IAGR)2021年大会及び第18回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム
9月17日(金)-19日(日)(会議)
9月20日(月)-21日(火)(野外巡検)
会場:中国青島
ファーストサーキュラー:
www.gondwanainst.org/symposium/2021/IAGR2021Invitation.htm
(注)中国国外の参加者については会議にはオンライン参加のみ、20〜21日の野外巡検は中止となりました。(2021/7/19追記)
2021年度日本火山学会秋季大会
9月20日(月)〜22日(水)
場所:東北大学
東日本大震災被災地及び鳴子・鬼首・蔵王地域への現地討論会も予定.
http://www.kazan-g.sakura.ne.jp/J/index.html
「地盤情報と地盤防災を学ぶー京都南部地域と木津川周辺を例にしてー」講習会
KG-NET・関西圏地盤研究会・一般社団法人関西地質調査業協会 共催
日本地質学会近畿支部ほか 協賛
9月30日(木)10:30-16:30
開催形式:オンライン会議(Zoom)
定員:200名
受講料:6,000円(税込)
詳しくは,https://www.kg-net2005.jp/index/
10月October
第31回 地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン第1回目)
10月1日(金)18:30-20:30
内容:地質汚染調査・土壌汚染状況調査概論
講師:駒井 武(東北大学大学院教授)
受講方法:ZOOMによるオンライン
申込期限:2021年9月20日まで
受講料:無料
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
◯日本地質学会第5回ショートコース
10月3日(日)
9:00-12:00 応用地質学への招待:私の現場から+α:永田秀尚(有限会社風水土)
13:30-16:30 GISとWebGISによるデジタル地質情報の利活用:宝田晋治(産総研・地質調査総合センター)
http://www.geosociety.jp/science/content0137.html
(協)資源地質学会国際シンポジウム “Gold Exploration in the Circum-Pacific”
10月14日(木) 9:00-16:55(日本時間)
形式:オンライン開催(Cisco Webex)
https://www.resource-geology.jp/
(後)第4回水循環シンポジウム(誌上開催)
主催:日本地質汚染審査機構
香澄の郷・水循環シンポジウム〜水郷水循環の街・環境公共潮来〜
(注)10月17日に茨城県潮来市にて開催を予定していましたが, 冊子を配布しての「誌上開催」に変更いたしました.
http://www.npo-geopol.or.jp/index.htm
(協)石油技術協会令和3年度秋季講演会
テーマ:脱炭素社会への移行に向けた石油開発産業の課題
10月22日(金)13:00-18:05
開催形態:オンライン開催(当日のライブ配信および後日オンデマンド配信(1週間))
https://www.japt.org/
第31回 地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン第2回目)
10月22日(金)19:30-21:30
10月29日(金)※日程が変更になりました
内容:健全な水循環と地下水
講師:
・郄嶋 洋(NPO法人日本地質汚染審査機構理事長、第一工科大学自然環境工学科教授)
・田村嘉之(NPO法人日本地質汚染審査機構副理事長、地質汚染診断士の会会長)
受講方法:ZOOMによるオンライン
申込期限:2021年10月18日まで→10月27日まで延長
受講料:無料
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm#2021.10.22geopol-sympo
(後)藤原ナチュラルヒストリー振興財団設立40周年記念公開シンポジウム
「海と地球の自然史−変わりゆく海洋環境から海洋プラスックごみまで地球の問題を考える−」
10月24日(日)13:00〜17:00(予定)
形式:オンラインと会場のハイブリッド開催(会場参加人数:100名)
場所:仙台国際センター
https://fujiwara-nh.or.jp/archives/2021/0802_134000.php
2021年度 第2回地質調査研修
10月25日(月)- 29日(金)
場所:島根県出雲市長尾鼻周辺(小伊津海岸)
研修内容:室内で岩石の見方等を理解した上で、野外での地層・岩石の観察ポイントからまとめまで、地質図を作成するための基本的事項を5日間の研修で習得します。
定員:6名(定員になり次第締切),CPD:40単位
主催:産総研コンソーシアム「地質人材育成コンソーシアム」
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2021-2.html
アースサイエンスウィーク・ジャパン講演会
・10月30日(土)13:30-16:10
震災10年、東北から地球をみつめる(オンラインとハイブリッド)
登壇者:小平秀一(JAMSTEC)・平塚 明(元岩手県立大)・平 朝彦(JAMSTEC/東海大学)・今村文彦(東北大学)
http://www.earthsciweekjp.org/plan/plan1/index.html
・10月31日(日)13:30-15:30
地質探偵が見た!日本文化と地質の関係(オンラインとハイブリッド)
http://www.earthsciweekjp.org/plan/plan2/index.html
登壇者:ウォリス サイモン(東京大学)・眞木隆志(NHKエデュケーショナル)
日本学術会議東北地区会議公開学術講演会
「災害と文明−災害に対する社会の対応−」
10月30日(土)13:30-16:30
オンライン開催
参加費無料,要事前申込(締切:10/24)
https://forms.gle/hXimXds5LhpUyjgK6
11月November
九州・沖縄地区会議学術講演会「持続可能な地域の強靭化と将来空間像
:防災・減災対策の次なるステージを目指して」
11月1日(月)14:00-16:10
オンライン開催
参加費無料,要事前申込
https://www.scj.go.jp/ja/event/2021/313-s-1101.html
第234回地質汚染・災害イブニングセミナー(オンライン)
11月5日(金)18:30-20:30
講師:宮崎 淳(創価大学法学部教授)
演題:「水循環基本法の改正と今後の展望」
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
学術会議公開シンポジウム
「21世紀の国難災害を乗り越えるレジリエンスとは:防災統合知の構築戦略」
11月6日(土)16:30-18:00
オンライン(You Tube Live配信)
参加費無料・事前申込不要
https://bosai-kokutai.jp/S40/(ぼうさいここくたいHP)
学術会議公開シンポジウム「防災教育と災害伝承」
(ぼうさいこくたいのセッションとして開催するシンポジウム)
11日6日(土)14:30-16:00
オンライン開催
定員:1000名(Zoomウェビナー)
参加費無料・要事前申込
https://www.scj.go.jp/ja/event/2021/316-s-1106-2.html
茨城大学図書館オンライン土曜アカデミー
「チバニアン誕生:方位磁針のN極が南をさす時代へ」
11月6日(土)14:00-15:30(zoomによるオンライン開催)
講師:岡田 誠(茨城大学理学部教授)
参加費無料・要申込(先着450名)
http://www.lib.ibaraki.ac.jp/news/?id=356
日本不動産学会 シンポジウム
山岳国立公園管理の将来(レクリエーション・登山のための利活用を探る)
11月10日(水)15:00-18:00
開催形態:インターネット(Zoom)配信
参加費無料・定員200名(先着順)
要参加申込:11月4日(木)
http://www.jares.or.jp/events/2021.11.10_sympo.html
第34回 地質調査総合センターシンポジウム:
防災・減災に向けた産総研の地震・津波・火山研究−東日本大震災から10年の成果と今後−
11月12日(金)10:00-15:35(予定)
方法:オンライン開催
参加費無料(事前登録制・定員500名)
https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo34/index.html
産業技術連携推進会議地質地盤情報分科会
令和3年度講演会
「地質リスクの低減に向けた地質調査・データクオリティ・解析技術」
11月22日(月)13:30-16:00
Teamsによるオンライン開催
参加費無料、要事前申込(締切:11/19正午)
https://www.gsj.jp/information/domestic/sgr/index.html
(後)第31回社会地質学シンポジウム
11月26日(金)-27日(土)
オンライン開催
発表申込締切:9月30日(厳守)
https://www.jspmug.org/envgeo_sympo/31st_sympo/31st_sympo.html
12月December
(協)第37回ゼオライト研究発表会
12 月2日(木)〜2日(金)
会場 :オンライン
https://jza-online.org/events/
第31回地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン第3回目)
12月3日(金)19:30-21:30
内容:土壌汚染状況調査の流れと調査や対策の制約・難しさについて
講師:成澤 昇(株式会社環境地質研究所、地質汚染診断士)
受講方法:ZOOMによるオンライン
申込期限:2021年11月29日まで
受講料:無料
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm#"2021.12.3&17geopol-sympo
火山国際ワークショップ2021−火山における登山者の安全確保−
12月3日(金)13:00-16:00
オンライン開催(Zoom)
参加申込・要事前申込(11/26締切)
https://www.mfri.pref.yamanashi.jp
国際シンポジウム2021 −富士山登山における噴火時の安全確保−
12月5日(日)13:00-16:30
会場:富士五胡文化センター(山梨県富士吉田市)
参加申込・要事前申込(11/26締切)
https://www.mfri.pref.yamanashi.jp
日本学術会議主催学術フォーラム
「地球環境変動と人間活動―地球規模の環境変化にどう対応したらよいか―」
12日5日(日)13:00-17:50
オンライン開催
参加費無料・要事前申込
https://www.scj.go.jp/ja/event/2021/315-s-1205.html
(協)テクノオーシャン・ネットワーク(TON)
12月9日(木)-11日(土)
会場:神戸国際展示場
完全事前登録制
https://www.techno-ocean2021.jp/
日本学術会議主催学術フォーラム:「我が国の学術政策と研究力に関する学術フォーラム―我が国の研究力の現状とその要因を探る―」
12月11日(土)10:00-17:30
オンライン開催
参加費無料・要事前申込
https://www.scj.go.jp/ja/event/2021/315-s-1211.html
JSEC2021(高校生高専生科学技術チャレンジ)オンライン表彰式
12月14日(日)16:20より
ライブ視聴アドレス
https://manabu.asahi.com/jsec/live/
第19回JSEC(https://manabu.asahi.com/jsec/)*地質学会後援
第31回地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン第4回目)
12月17日(金)19:30-21:30
内容:地質汚染調査のための地層の見方と単元調査法について
講師:風岡 修(地質汚染診断士、理学博士)
受講方法:ZOOMによるオンライン
申込期限:2021年12月13日まで
受講料:無料
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm#"2021.12.3&17geopol-sympo
地質学史懇話会[オンラインと対面のハイブリッド]
12月19日(日)13:30-16:30
場所:早稲田奉仕園(東京メトロ東西線早稲田駅下車徒歩5分)
青木滋之「ダーウィンと科学哲学 ―同時代、現代の視点から―」
加藤碵一「菜食主義とライマン・宮沢賢治余聞」
連絡先:矢島道子 pxi02070[at]nifty.com
学術会議公開シンポジウム: 「生命科学分野におけるジェンダー・ダイバーシティ−大学・企業・学協会におけるダイバーシティ推進に向けた取り組み−」
12月19日(日)14:00-18:00
オンライン開催(Zoom)
参加費無料・要事前申込
https://www.scj.go.jp/ja/event/2021/317-s-1219.html
海と地球のシンポジウム2021
12月20日(月)-21日(火)
主催:AORI・JAMSTEC
開催方法:実会場とオンライン会場を使ったハイブリッド形式
※感染症の状況により変更・中止する場合があります.
参加費無料・要事前登録(12/13締切)
https://www.jamstec.go.jp/j/pr-event/ocean-and-earth2021/
令和3年度国総研講演会
DXなど最前線の研究一挙ご紹介
12月20日(月)9:00から
オンライン(YouTube)
視聴無料・登録不要
http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/koen2021.html
2020年度各賞
2020年度各賞受賞者 受賞理由
■学会賞(1件)
■論文賞(1件)
■研究奨励賞(2件)
■Island Arc賞(1件)
■学会表彰(2件)
日本地質学会賞
授賞者:山路 敦会員(京都大学大学院理学研究科)
対象研究テーマ:理論テクトニクス研究による地殻変動史の解明
山路会員は,卓越した調査スキルによりフィールドから取得した質の高い定量的データに基づき,地質学と物理学のことばを通じた理論テクトニクス研究を長年にわたり進めてきた.研究当初には,グリーンタフ時代の変動がリフト形成に伴うものであることを地質調査によって明らかにし,日本海拡大に関する日本列島のテクトニクスモデルをフィールドデータに基づき提示した.その後,研究を地殻変動史の解明に集中させ,野外調査と理論的研究を統合する手法で,島弧の構造発達史の理解に大きく貢献した.その中で,2000 年の多重逆解法(Multiple inverse method)を始めとして,断層や変形構造に関する新たなデータ解析法を精力的に開発した.また,応力や歪みの解析ソフトウェアを独自に作成して国内外の地質学コミュニティへ広く公表し,新しい解析法の普及に尽力しただけではなく,構造変形に関する新たな描像の構築に貢献した.さらに, フィールド研究の経験を惑星科学に応用し,月の地下構造に関する新しい見方を提供した.
教育面においては,「フィールド・キャンプ」をたびたび開催するなど,野外調査の重要性,特に地質図作成法とフィールドデータの解析手法を内外の学生らに惜しみなく伝え,地質学コミュニティの裾野拡大とフィールド教育の継承・発展に貢献した.また,著書「理論テクトニクス入門」および「An Introduction to Tectonophysics」は,テクトニクスを物理現象として理解するための専門書として国内外から高い評価を得ている.
以上の研究・教育への尽力は,地質学雑誌 25 報,Island Arc 誌4 報を含む 100 報以上の優れた論文として実を結んでいる.さらに,関連する研究分野の動向に関するレビュー論文等を国内誌に公表し,国内への情報発信を積極的に進めた.このように,理論テクトニクス研究を通した地質学コミュニティへの貢献を続ける山路会員のたゆまぬ努力は賞賛に値する.
本学会運営に対する貢献として,地質学雑誌編集委員長を3期6年務め,学会誌の役割が大きく変化する時期に「講座」に代表される新カテゴリーを創設するなど,学会誌の改善や月刊での出版継続に献身的に取り組んだ.また,本学会構造地質部会長として部会活動にも大きく貢献した.さらに平成 28 年からは本学会法務委員会委員長を務めている. 以上のような山路会員の業績と,地質学および日本地質学会の発展に果たしてきた貢献を鑑み,同氏を日本地質学会賞受賞者として推薦する.
日本地質学会 Island Arc賞
対象論文:Wakabayashi, J., 2017, Serpentinites and serpentinites: Variety of origins and emplacement mechanisms of serpentinite bodies in the California Cordillera. Island Arc, 26: e12205.
Although serpentinites have long been recognized as important recorders of tectonic processes, owing to their derivation from mantle peridotite, the lack of more detailed assessments of their origins and emplacement mechanisms hindered the understanding of their connection to orogenic processes. Based on field-intensive research, the author provided a more detailed framework, showing multiple origins and emplacement mechanisms of serpentinite bodies of the California Cordillera, where the lack of terminal collision resulted in better preservation of primary orogenic relationships. He showed that serpentinites fall into two groups of tectonic affinity, one for which serpentinites belonged to the upper plate of a convergent plate boundary throughout their history, and the other for which serpentinites originated on the subducting (lower plate) of a convergent plate system but were transferred to the upper plate as a result of subduction- accretion when the subduction thrust sliced into the downgoing plate. Both tectonic affinity groups have serpentinite bodies of two subtypes, one comprising intact, but variably deformed, tectonically-emplaced sheets of serpentinized peridotite, and the other consisting of clastic sedimentary serpentinite derived from exhumed serpentinite bodies. This work has been cited as providing a new guide for research on the connection between serpentinite and tectonic processes in the world's orogenic belts.
John Wakabayashi received his B.A. in Geology in 1980 from the University of California (UC) Berkeley, and his Ph.D. in Geology in 1989 from UC Davis. After receiving his Ph.D., he worked as an engineering and environmental geologist for 16 years (1989-2005), the last 13 years as an independent consultant based in Hayward, California. In 2005 he moved to Fresno, California, to become a faculty member (now Professor of Geology) at the California State University Fresno where he has taught geology classes and conducted research since. During his applied geologic career, he worked on a variety of different projects in engineering and environmental geology, but also conducted and published research in varied aspects of tectonics and tectonic geomorphology. Since becoming an academic he has further expanded the range of his research. Most of his research focuses on active plate margin tectonics, including (1) the nature of subduction interface deformation and large-scale material movement as recorded in exhumed subduction complexes such as the Franciscan of California, across a range of temporal and spatial scales, (2) subduction initiation processes,
(3) principal orogenic components, such as serpentinites, mélanges, high-P metamorphic rocks, and ocean
plate stratigraphy, as recorders of orogenic processes, (4) connection between tectonic processes and metamorphic P-T evolution, and (5) evolution of transform fault systems. He also conducts research on long time and length scale geomorphology and linkages between surface processes and the clastic sedimentary record. A common theme of all of his research is the application of mobile reference frames to better understand the essentially four-dimensional processes of tectonics and/or geomorphology. Intensive field work, including detailed geologic mapping and petrography are also foundational components of much of his work.
>論文サイトへ(Wiley)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/iar.12205
日本地質学会論文賞
対象論文:星 博幸,2018,中新世における西南日本の時計回り回転.地質学雑誌,124,675‒ 691.
本論文は日本海拡大に関連した西南日本回転運動の現時点における総括である.本論文で著者は,西南日本の古地磁気についての直近 25 年間の自身のものも含んだ公表データを丁寧にレビューし,それらに基づいた中新世における西南日本の回転量,回転時期,および回転速度などを明らかにしている.本論文は総説だが,データレビューに基づく議論はオリジナルであり,特に長い間 15 Ma 頃と信じられていた回転時期が,それよりも 200–300 万年早く終了したという説を, 既存の年代データの丹念な見直しに基づいて立証した点は注目される.また,各地域の地質と断層運動を考慮して,回転量と回転速度についての議論を展開し,オリジナルな見積もりを得ている.これらの成果は著者が得意とする「丁寧な地質調査をベースにした年代学的・古地磁気学的調査」の一つの結実と言える.本論文は,中新世とその前後の日本列島地質発達史や古環境などの議論に影響を与えると考えられ,高く評価される.以上の理由により,本論文を日本地質学会論文賞に推薦する.
>論文サイトへ(J-STAGE)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/geosoc/124/9/124_2017.0056/_article/-char/ja
日本地質学会研究奨励賞_01
授賞者:菊川照英会員(伊藤忠石油開発株式会社)
対象論文:菊川照英・相田吉昭・亀尾浩司・小竹信宏,2018,鹿児島県種子島北部,熊毛層群西之表層の地質.地質学雑誌,124,313‒329.
本論文は鹿児島県種子島に分布する古第三系熊毛層群西之表層の詳細な地質について報告したものである.四万十帯南帯に属する本層は,層序と地質構造に不明な点が多く,堆積年代と堆積環境の詳細についてはほとんど検討されていない.菊川らは精力的な野外調査によって岩相の空間分布を詳細に把握するとともに,複数のタクサの浮遊性微化石を系統的に調査した.その結果, 西之表層が前期漸新世後期の堆積物であることや,生痕化石の検討に基づき本層が水深2000 mを超える深海で堆積したことを示した上で,北東—南西方向のスラスト群と褶曲構造によって同一層準が繰り返す地質構造も明らかにした.また,検討層準が九州南部の日南層群に対比されることを初めて示した.これらの成果は,西南日本外帯の形成史,ひいては新生代の日本列島形成史を理解する上で非常に重要な貢献である.菊川らの研究は,近年敬遠されがちな,地道な野外調査の積み重ねをベースとしており,まさに地質学の王道とも言える研究スタイルが実を結んだといえ,その研究成果は高く評価できる.この理由により,本論文の筆頭著者である菊川照英会員を日本地質学会研究奨励賞に推薦する.
>論文サイトへ(J-STAGE)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/geosoc/124/5/124_2017.0082/_article/-char/ja/
日本地質学会研究奨励賞_02
授賞者:羽地俊樹会員(京都大学大学院理学研究科)
対象論文:Haji, T., Hosoi, J., Yamaji, A., 2019, A middle Miocene post-rift stress regime revealed by dikes and mesoscale faults in the Kakunodate area, NE Japan. Island Arc, 28: e12304.
東北日本は,島弧テクトニクスについて種々のデータがそろう教科書的な地域である.この地域の中新世以降の応力場変遷に関する研究は,海外からもよく参照されている.しかし,日本海拡大が終わったとも言われる 15Ma 頃より後の中期中新世の応力状態は,断層活動が不活発だったためこれまで不明確だった.その時代に NE-SW 走向の岩脈が多いことは知られていたが,その方向が中間主応力軸なのか最大主応力軸なのかは明らかになっていなかった.羽地らは,丹念な地質調査の裏付けのもと,今世紀に入ってから発展した応力解析法を利用して,それが中間主応力軸の方向であり,この時代が弱引張の応力場であったという答えを導いた.本論文は,四半世紀にわたって欠けていた東北日本弧のテクトニクス史のピースを,実証的データに基づいて埋めることに成功した研究であり,その成果は高く評価できるものである.この理由により,本論文の筆頭著者である羽地俊樹会員を日本地質学会奨励賞に推薦する.
>論文サイトへ(Wiley)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/iar.12304
学会表彰01
授賞者:株式会社浜島書店
表彰業績:図書教材出版を通じた地学教育への貢献
日本の地学教育は,小・中学校では教科「理科」の中で,高等学校では,文系クラス中心の 2 単位科目「地学基礎」と,より進んだ内容である 4 単位科目「地学」で進められている.これら地
学についての学習は,主に「地学基礎」については 5 社,「地学」については 2 社から出版されている教科書によって支えられているが,数は少ないものの参考書も重要な役割を担っている.特に地球内部から海洋・大気,宇宙までの広大な空間や太陽系の形成,そして宇宙の誕生にまで及ぶ長大な時間スケールを学ぶ地学分野においては,図や写真等の視覚教材は学習を深めるうえで特に重要な役割を果たす.そうした中,名古屋市にある株式会社浜島書店は教科書出版社ではないにも関わらず,1968 年以来,高等学校での利用を想定した図表集(現在の名称は『ニューステージ新地学図表』)の出版を続けている.この図表集は毎年アップデートされるとともに,数年に一度,露頭写真やイラストの多くが刷新される大きな改訂も行われて,最近の科学的知見が収録されてきた.そのため,大学の授業の参考書として採用される場合もあるほどで,その利用度は大変高い.必ずしも受講率が高いわけではない地学について,こうした図書教材を継続して出版し全国展開していることは,地学分野の教育と普及に大きな貢献を果たしている.株式会社浜島書店が果たした地学教育への貢献を称え,今後もこの図表集の改訂・出版が引き続き行われることへの期待も込めて,株式会社浜島書店を日本地質学会表彰に推薦する.
学会表彰02
授賞者:鹿野和彦会員・斎藤 眞会員・川畑大作会員・尾崎正紀会員・巌谷敏光会員・脇田浩二会員・湯浅真人会員・坂 幸恭会員(故人)・斎藤靖二会員・宮下純夫会員,産業技術総合研究所地質調査総合センター
表彰業績:地質図の標準化のための JIS A 0204,JIS A 0205 の制定・改正への貢献
地質図を描くための JIS 規格が制定されたのは比較的最近である.国際的には,地質図表示のISO 710 シリーズ(1974–1984)があったが,それは各国の事情に合わせられるよう基本的事柄だけが決められていたものであった.日本でも,2002 年以前,地質図を描くための公式なルールは存在しておらず,当時,地質コンサルタント会社はそれぞれ異なる様式の地質図を作成していた. このような状況で,鹿野和彦会員を中心に,ISO 710 などを参照して地質図の描き方の JIS 案が作成された.鹿野会員は湯浅真人会員と国内の学協会,業界団体,政府機関(独立行政法人を含む) からなる原案作成委員会(委員長:坂 幸恭 元副会長)を組織して JIS 原案を作成した.この原案は,2002 年に日本工業標準調査会の審議を経て JIS A 0204 として公示された後,公共事業で使われる地質図の表記が統一され,国,都道府県等の地質調査の納品要領としてこの JIS A 0204 が採用されることになった.2008 年には JIS A 0204 が改訂されると同時にデジタル地質図に必要な事項とコードを定めた JIS A 0205 が制定され,その後も 2012 年,2019 年と繰り返し JIS A 0204 とJIS A 0205 の改訂が行われて現在に至っている.これらの改訂に携わった原案作成委員会では,坂元副会長,斎藤靖二元会長,そして宮下純夫元会長が委員長を,鹿野和彦会員,斎藤 眞会員,尾崎正紀会員,脇田浩二会員,川畑大作会員,巌谷敏光会員,湯浅真人会員が事務局を務めてきた.
これら地質図に関する JIS は,公共事業での地質調査に広く使用され,地質学の社会実装に大きな役割を果たしたことは言うまでもない.それらに対する鹿野会員をはじめとする関係者及び産業技術総合研究所地質調査総合センターの貢献は特に大きいものであり,日本地質学会表彰に推薦する.
定款・規則類_TOP
定款・規則類
■ 定 款(2022.6.11一部変更)
■ 運営規則(2025.6.7一部変更)
■ 総会規則(2022.6.11一部変更)
■ 理事会規則(2020.12.5一部改正)
■ 選挙規則(2023.6.3一部改正)
----選挙細則(2023.6.3一部改正)
----選挙管理委員会規則(2009.6.30施行)
■ 各賞選考規則(2025.4.19一部改正)
---- 各賞選考委員会規則(2025.4.19一部改正)
■ 研究奨励金規則(2023.12.9一部改正)
■ 倫理綱領(2003.09.19)
■ 行動規範(2021.4.3改訂)
■ 日本地質学会プライバシーポリシー
■ 日本地質学会広報メディア運用規則(2022.7.23施行)
■ 日本地質学会著作物利用規定
■ 電子出版細則(2011.04.02)
■ 日本地質学会ロゴマーク使用規則
-----ロゴマーク使用申請書
■ 日本地質学会学術大会に関する緊急時対応指針 (2019.4.6一部改正)
----キャンセルした講演の講演要旨の扱いについて
■ 一般社団法人日本地質学会野外調査安全指針 (2011.9.8理事会制定,2012.9.14理事会一部修正)
野外調査において心がけたいこと (2008.10.7一部改正)
安全のしおり(巡検案内書より)
巡検時等に使用する車両の制限について(2017.4.8理事会決議)
ホームページ・ニュース誌・メールマガジン投稿規程等
ホームページ・ニュース誌・メールマガジン投稿規程等
日本地質学会では学術論文からホームページの原稿等のいずれにおいても、共通の投稿ポリシーを持っております。投稿前に下記の投稿規定、保証、著作権譲渡同意書をお読み頂き、同意のうえ投稿頂けますようお願いいたします。このほか関係規約(倫理綱領・著作物利用規程・プライバシーポリシー)にも目をお通し下さい。投稿先はこちらから(会員ログインが必要です)。
投稿規定
日本地質学会Webサイトへの投稿規定
(1)倫理責任と著作権管理
日本地質学会のWebサイトへの投稿原稿に対して,その倫理性および権利侵害のないことについて著作者に保証して頂くために「保証書」に,また著作権を日本地質学会に譲渡することを同意する「著作権譲渡等同意書」に,それぞれ,画面上で同意していただいた場合に限り,電子投稿の画面に進むことができるようになっています.
(2)文献等引用方法
引用文献の記載方法は,著者名,発表年,掲載誌名などを明記し,引用文献が特定できるようにして下さい.
(3)校閲
広報委員会は,申し込まれた講演について,会則第4条に示されている日本地質学会の目的ならびに日本地質学会倫理綱領に反していないかということについて校閲を行ないます.校閲の結果,いずれかの条項に反していると判断された場合には,広報委員会は内容の修正を求めるか,あるいは受理しないことがあります.委員会の措置に同意できない場合には,投稿者は法務委員会(東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル 日本地質学会事務局気付)に異議を申し立てることができます.法務委員会は直ちに審理し,結論を広報委員会ならびに異議申立者に伝えることになります.
この受理方法は,依頼執筆者にも適用されます.異議申立てに関する詳細は学会Webサイトに掲載されます.
(4)デジタル原稿(データ)
投稿する原稿、図版、動画等のデジタル原稿(データ)は、下記のフォーマットのものが受け付けられます.
文書: MS Word, Text, PDF, RTF, XML
図、表、写真: PDF, EPS, Adobe Illustrator, MS Excel, JPEG, TIFF, PNG, GIF, Adobe PhotoShop
動画: WMV, AVI, Flash, QuickTime, MPEG2, MPEG4, H.264, DivX
著作者(代表者)は,日本地質学会Webサイトに掲載する下記表題の原稿(以下「本原稿」という.)について,以下のとおり保証し,かつ著作権を譲渡等いたします.
保証及び著作権譲渡等同意書
第1 保証
著作者は,本原稿について,以下の各号記載の事項を保証し,確約します.
1)本原稿が著作者自身の著作物であり,既にいずれかで出版公表されているものと同一ではないこと.
2)本原稿が既存の出版公表物などに対する知的財産権のいかなる侵害も含まないこと.
3)本原稿中に他から転載されているすべての図表について,転載許可を得ていること.
4)本原稿中,他の論文等の引用がある場合には,当該引用が公正な慣行に合致し,目的上正当な範囲内であること.
5)本原稿には,日本地質学会の名誉を傷つけ,その信用を毀損する盗用データ,捏造データ,その他学会の倫理綱領に反するものを含まないこと.
6)本原稿が共同著作物である場合には,代表して本書に同意する者が,すべての共著者から,本書に同意することについて同意ないし必要な権利を得ていること.
7)本原稿についての問い合わせ,苦情,紛争などが発生した場合,署名者はすべての責任を負うこと.
第2 著作権譲渡等
著作者は,本原稿について,日本地質学会著作物利用規定にしたがい,以下の各号記載に同意します.
1)本原稿のすべての著作財産権(著作権法27条,同29条に定める権利を含む)を日本地質学会へ譲渡すること.
2)本原稿について,日本地質学会ならびに日本地質学会から正当に権利を取得した第3者及び当該第3者から権利を承継した者に対し,著作人格権(公表権,氏名表示権,同一性保持権)を行使しないこと.
3)本原稿の下記の各利用形態に関する権利を日本地質学会が排他的に行使すること.
a) 複製,翻訳,翻案(出版,電子出版,翻訳出版,データベース化,ビデオグラム化,その他すべての記録メディアへの記録・掲載などを含む)
b) 展示・上映
c) 放送,有線放送,自動公衆送信(地上波,CATV放送衛星,通信衛星,インターネット,パソコン通信,その他あらゆる送信媒体及び将来開発されるすべての送信媒体による公衆送信を含む)
d) 頒布,譲渡,貸与
e) その他,本著作物に関する一切の利用(技術の進歩により将来生じうる利用形態を含む)
以上
ニュース誌表紙写真
1.投稿写真は,原則として未発表のものとする.
2.投稿写真は,プリントまたはデジタルファイル(ファイル形式:jpg , pct等)で,A4またはA3サイズに拡大したときに十分解像度があるものであること.
3.投稿写真の著作権については,地質学会に譲渡する.なお,依頼掲載写真についてはこの限りではない.
4.投稿写真全体の,日本語(20字以内)および英文のタイトルと日本語解説を付ける.
5.投稿写真が複数の場合には,それぞれに日本語(20字以内)および英文のタイトルを付ける.
6.投稿写真には,所定の様式の地質学会ニュース誌表紙写真投稿整理カードを添え,タイトルおよび解説の原稿は可能な限り電子媒体で提出することとする.
7.投稿写真は審査の上,地質学会ニュース誌表紙への掲載を決定する.
Geo暦(2009)
2009年Geo暦(行事カレンダー)
2007年版 2008年版 2010年版
2009年版 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
※印は学会主催行事です.◯印は学会共催・後援行事
1月January
第7回地球システム・地球進化ニューイヤースクール NYS-7
1月10日(土)-1月11日(日)
開催場所: 国立オリンピック記念青少年総合センター(東京・代々木)
http://quartz.ess.sci.osaka-u.ac.jp/~earth21/school/2008/index.html
第33回フィッショントラック研究会
1月9日(金)〜10日(土)
場所:金沢大学角間キャンパス 自然科学研究科図書館棟G15室
問い合わせ先:
長谷部徳子<hasebe@kenroku.kanazawa-u.ac.jp>
◯第54回日本水環境学会セミナー
水道水質管理に関する最近の話題
1月23日(金)
会場 自動車会館 大会議室
http://www.jswe.or.jp/kais/jour/calendar.html#calendar
日本古生物学会第158回例会
1月30日(金)〜2月1日(日)
会場:琉球大学・沖縄県立博物館
個人講演申込および講演予稿締切:2008年11月30日(金)
http://wwwsoc.nii.ac.jp/psj5/meetings.html
2月February
The International Groundwater Symposium 2009 (IGS-TH 2009)
2月16日〜21日
会場 タイ・バンコク
http://www.igsth2009.com/home.html
*第157回西日本支部例会および平成2008年度支部総会
2月14日(土)
会場:九州大学国際ホール(九州大学箱崎キャンパス内)
参加・講演ほかすべての申し込みの期限:1月30日(金)必着
詳しくは、支部のページへ
3月March
国際シンポジウム 1st International Geoscience Symposium
“Precambrian World 2009”: Bridging Precambrian and Modern Geosciences
3月6日〜8日
場所:九州大学西新プラザ・いのちのたび博物館(北九州自然史博物館)
http://www.kochi-u.ac.jp/marine-core/PW2009
*構造地質部会2008年度例会
3月14日(土)〜16日(月)
普及講演 会場:長岡市中央公民館大ホール
例会会場:長岡市民営国民宿舎悠久山湯元館
http://struct.geosociety.jp/struct-index.html
日本堆積学会2009年京都枚方大会
3月27日(金)〜 30日(月)
会場:大阪工業大学情報科学部枚方キャンパス
講演申込締切:2009年2月13日(金)
巡検申し込み締切:2009年2月13日(金)
ショートコース申し込み締切:2009年3月6日(金)
http://sediment.jp/
*日本地質学会男女共同参画委員会主催 金沢ワークショップ
「燃える温泉と地滑りのメッカ ー地質学と町おこしー」
3月29日(日)〜30日(月)
場所:金沢&石川県能登半島周辺
参加申込・問い合わせ先
堀 利栄 shori@sci.ehime-u.ac.jp
4月April
*関東支部:第4回地質技師長が語る地質工学余話〜地質技術伝承講演会
4月11日(土)14:00〜 国立科学博物館日本館大会議室
テーマ「農業の有する多面的機能と地質技術者の役割(仮)」
講演者 山本昭夫
参加費無料
詳しくは、コチラ
5月May
*関東支部地質見学会:茨城県平磯海岸
5月9日(土)9:30 JR常磐線勝田駅集合
費用 大人 3,000円程度
見学場所 茨城県平磯海岸(茨城県ひたちなか市)
申込締切:2009年4月10日(金)
詳しくは、コチラ
*関東支部:第5回地質技師長が語る地質工学余話〜地質技術伝承講演会
5月10日(日)地質の日14:00〜
国立科学博物館日本館大会議室
詳しくは、コチラ
*日本地質学会第116年総会
5月17(日)17:45〜18:45
会場 幕張メッセ国際会議場(3F 302議室)
http://www.geosociety.jp/members/content0038.html
*一般社団法人2009年度定時総会
5月17(日)18:45〜19:45
会場 幕張メッセ国際会議場(3F 302議室)
http://geosociety.sakura.ne.jp/jgs/
◯日本地球惑星科学連合
5月16日(土)〜21日(木) 6日間
会場 幕張メッセ国際会議場
http://www.jpgu.org/meeting/index.htm
◯原子力総合シンポジウム2009 プログラム
主催 日本学術会議 総合工学委員会
共催 日本地質学会ほか
5月27日(水)〜28日(木)
会場 日本学術会議講堂(東京都港区六本木7-22-34)参加費無料
http://www.aesj.or.jp/symposium/form.shtml
◯日本地下水学会50周年記念講演会
2009年5月29日(金)14:00〜
場所 日本科学未来館みらいCANホール
詳しくは、http://homepage2.nifty.com/jagh_gyouji/
*2009年度北海道支部総会・個人講演会・日本地質学会長講演会
5月30日(土)13:30〜
場所:北海道大学理学部7号館7-310号室(予定)
講演申込締切:4月3日(金)
詳細は支部のページへ
6月June
*関東支部:第5回地質技師長が語る地質工学余話〜地質技術伝承講演会
6月6日(土)10:00〜 国立科学博物館新宿分館
(なお,6/6は支部発表会を同会場にて引き続き行います.)
詳しくは、コチラ
*関東支部:第3回研究発表会「関東地方の地質」
6月6日(土)13:00〜17:00
会場:国立科学博物館 新宿分館(予定)
申込資格:学会員(連名の場合はどなたか一人が学会員ならば可),ただし学生
および若手研究者・技術者(35歳未満)は学会員でなくとも可.
講演申込締切:2009年4月6日(月)
詳しくは、コチラ
*2009年中部支部年会のお知らせ
6月13日(土)、総会・シンポジウム・懇親会
6月14日(日) 地質巡検
会場:山梨大学教育人間科学部講義棟
シンポジウム:「フォッサマグナ地域の地殻変動現象と中部地方の最新情報」
9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO SGEM2009
6月14日(日)〜19日(金)
会場:Bulugaria Alnena Resort
締切:Early Registration:2009年2月28日
Abstract Submission:2009年3月31日
http://www.sgem.org/
地質学史懇話会
6月20日(土) 13:30〜17:00
場所:北とぴあ803号室(東京都北区JR王子駅下車3分)
諏訪兼位「坪井誠太郎の生涯と業績」
山田直利「予察地質図(1886-1895)をよむ ーナウマンから原田・巨智部へー」
日本古生物学会2009年年会・総会
6月26日(金)〜6月28日(日)
場所:千葉大学
http://wwwsoc.nii.ac.jp/psj5/
7月July
◯第46回アイソトープ・放射線研究発表会
7月1日(水)〜3日(金)
会場 日本科学未来館(東京都江東区青海2-41)
申込締切:2009年2月28日(土)
http://www.jrias.or.jp/
8月August
◯ZMPC2009国際会議
International Symposium on Zeolites and Microporous Crystals 2009
8月3日(月)〜8月7日(金)
会場 東京都新宿区 早稲田大学
http://www.zmpc.org/
堆積学スクール2009
「第四紀サンゴ礁堆積物の層序,堆積相,化石相」
8月4日(火)〜6日(木)
会場:琉球大学ほか
http://sediment.jp/04nennkai/2009/school.html
9月September
*日本地質学会第116年学術大会
9月4日(金)〜6日(日)
会場 岡山理科大学
http://www.geosociety.jp
日本鉱物科学会2009年年会
会場:北海道大学
9月8日(火)〜 10日(木)
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jams3/index.html
◯第53回粘土科学討論会
共催:日本地質学会ほか
9年9月10日(木)〜11日(金)
会場:岩手大学 学生センター棟および人文社会科学部5号館
http://wwwsoc.nii.ac.jp/cssj2/
◯第3回国際地学オリンピック台湾大会(国際大会)
9月14日〜22日(予定)
場所 台湾
国際地学オリンピック日本委員会事務局
http://www.jeso.jp/
第12回日本水環境学会シンポジウム
9月14日(月)〜15日(火)
会場:お茶の水女子大学
http://www.jswe.or.jp/
◯2009年度日本地球化学会年会
9月15日(火)〜17日(木)
会場 広島大学理学部
共催 日本地質学会ほか
http://www.geochem.jp/index.html
◯2009地球環境保護 土壌・地下水浄化技術展
浄化ビジネス最前線 —人にやさしい環境づくりを目指して
9月16日(水)〜18日(金)
会場 東京ビッグサイト 東6ホール
協賛 日本地質学会ほか
http://www.cnt-inc.co.jp/SGR-TEX/
10月October
日本火山学会2009年度秋季大会
10月10日(土)〜12日(月・祝)
場所:神奈川県立生命の星・地球博物館
http://wwwsoc.nii.ac.jp/kazan/
北海道支部・地質百選シンポジウム
10月17日(土)
場所:かるで2・7(札幌市中央区)
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
日本地下水学会2009年秋期講演会
10月15日(木)〜17日(土)
場所:かるで
http://wwwsoc.nii.ac.jp/kazan/
日本火山学会2009年度秋季大会
10月10日(土)〜12日(月・祝)
場所:場所:かるで2・7(札幌市中央区)
http://homepage3.nifty.com/jagh
日本地震学会2009秋季大会
10月21日(水)〜23日(金)
場所:京都大学吉田キャンパス
http://www.zisin.or.jp
サイエンスアゴラ2009
地球の未来日本からの提案
10月31日(土)〜11月3日(火)
会場:国際研究交流大学村
「地球に生きる素養を身につけよう」
31日(土)14:00-17:00
「統合生物学:生物をまとめて調べると見えてくる世界」
2日(月)13:00-16:30
http://www.scienceagora.org/scienceagora/agora2009/index.html
11月November
日本活断層学会2009秋季学術大会
11月7日(土)〜11月8日(日)
会場:東洋大学
http://danso.env.nagoya-u.ac.jp/jsafr/
自然史学会連合会講演会
11月7日(土)〜11月8日(日)
会場:石川県立自然史資料館
問い合わせ:電話 076-229-3450
第26回東海地震防災セミナ−2009
11月11日(水)13:30-16:00
会場:静岡商工会議所5階ホール
問い合わせ:土 隆一(電話 054-238-3240)
農村研究フォーラム2009
農村地域の安全・安心のための社会工学と防災工学の連携
11月20日(金)13:00-17:30
場 所:秋葉原コンベンションホール(秋葉原ダイビル内2階)
http://nkk.naro.affrc.go.jp/ivent/H21/forum/forum_211120.html
◯第25回ゼオライト研究発表会
共催:日本地質学会ほか
11月25日(水)〜11月26日(木)
会場:西日本総合展示場新館展示場
リーガロイヤルホテル小倉
http://www.jaz-online.org/
12月December
IGCP507第四回シンポジウム
12月1日(火)〜6日(日)
会場:熊本大学大学院自然科学研究科
http://igcp507.kopri.re.kr
平成21年度国土技術政策総合研究所 講演会
12月2日(水)10:00-16:50
場所:日本教育会館一ツ橋ホール(東京都千代田区一ツ橋2-6-2)
http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/kouenkai/kouenkai2009/kouenkai2009.htm
第19回環境地質学シンポジウム
12月4日(金)〜5日(土)
会場:早稲田大学西早稲田キャンパス
http://www.jspmug.org/index_j.html
第46回の霞ヶ関環境講座/第37回の三宅賞受賞者の受賞記念講演
12月5日 (土)14:30〜
場所:霞ヶ関ビル35階 東海大学校友会館
http://wwwsoc.nii.ac.jp/gra/
地質学史懇話会
12月23日(水・祝)13:30から
会場:北とぴあ(東京都北区)
松田義章「神保小虎の北海道調査とその成果」
前田伸人「アレクサンダー・フォン・フンボルトの探検調査と地質学への貢献:欧州や日本の科学界への影響」
問い合わせ先:矢島道子(地質情報整備活用機構:03-5804-5711)
野外調査において心がけたいこと(08.10.7)
野外調査において心がけたいこと
2008.10.7 日本地質学会 理事会
秋風が心地好い季節になりました。会員の皆様も調査や実習等で野外に出られる機会も多いことと思います。ベテランの皆様は、今更と思われるかもしれませんが、あらためて国立・国定公園や史跡・名勝・天然記念物、あるいは一般的な露頭における調査上の注意を喚起させて頂きます。地質学会員が模範となって、節度ある行動を示していただければ幸いです。
■ 国立・国定公園、並びに自治体の条例で保護が指定されている地域等で調査 する場合は、事前の許可が必要です。まず、調査を行う地域がどのような保 護地区を含んでいるか、事前に確認しておきましょう。特別保護区などの範 囲は、自治体や環境省等のHPで確認できる場合が多いですし、必要な手続 きもオンラインで申請できますので、必ず手続きをしてから現地に入るようにしましょう。
<国立公園における届出・申請>(環境省のサイト)
■ 史跡・名勝・天然記念物においては、文化庁や地元自治体などへの必要な手続きなしには露頭をハンマーでたたいて岩石試料を採取するなどの破壊を伴う調査はもちろん、転石の採取もできません。やむを得ず研究上必要な場合は許可申請の手続きを行い、必要最低限の採取に留めることが重要です。許可を得ておくことによって、その成果を公表することも可能になります(その際には謝辞に許可のことを触れておくとよいでしょう)。
■ 世界遺産については、世界遺産保護条約によって保護・保全が定められていますので、国の保護計画の不備が認められた場合は登録が抹消されることもあります。高い保全意識を持って慎重に行動する必要があります。
これらの地域の巡検の際にはハンマーを持ち歩かないなど「李下に冠を正さず」といった節度ある態度を心がけましょう。
法的な保護が為されていない貴重な露頭においても、同様に露頭の保護を心がけたいものです。不必要なサンプルの採取、削剥はもちろん慎み、あらかじめ地権者や地元自治体への連絡などを行っておくことにより、トラブルを未然に防げます。コア抜きは坑が大変目立ち、また半永久的に残りますので、場所をよく選ぶよう心がけることが大切です。また、露頭面にペイントやマーカーで記号等を派手に書き込む行為も、その後きれいに消していくようなマナーが必要です。
このほか些細なことのようですが、地元の方々と良好な関係を保つということは、思いのほか重要なことです。貴重な露頭が、将来はジオパークの中の有力なジオサイトになるかもしれません。
地球を愛する者として、社会から地質調査の有用性や公益性が認められ、末永く地質調査を行える環境作りには、上記のような調査に当たっての心がけが必須ですので、地球科学分野の研究者の全員の協力でこれを進めましょう。
調査の前にチェックしましょう
フィールド調査を行う前に,調査地域が国立・国定公園、並びに自治体の条例で保護が指定されていないかチェックしましょう.ここに国立・国定公園そして天然記念物のリスト,また国立・国定公園内で調査するための申請・許可の電子窓口のリンクを挙げてあります(2008.5/8現在).
調査の申請と許可
国立・国定公園内での調査には,事前の申請・許可が必要です.申請および許可に必要な日数は調査区域によります.早めに準備しましょう.
■ 国立公園における届出・申請(環境省のサイト)
■ 各県の調査の場合は? 土地利用の申請・許可は各県により届け出手順が異なる場合があります.各県庁担当課等へお問い合わせください.
■ 法令リンク
自然公園法
自然公園法施行令
自然公園法施行規則
国立公園リスト
日本の国立公園(環境省サイト)
国定公園一覧(自然公園財団サイト)
国内天然記念物リスト
文化庁HPより各県別にピックアップした天然記念物(地質鉱物)を表として以下に示してあります.(リスト作成 奥平敬元:大阪公大)
都道府県
指定年
市区町村
北海道
昭和新山
1951
有珠郡壮瞥町
名寄鈴石
1939
名寄市緑丘
名寄高師小僧
1939
名寄市有利里
根室車石
1939
根室市花咲港
エゾミカサリュウ化石
1977
三笠市幸町立公民館分室
夕張岳の高山植物群落および蛇紋岩メランジュ帯
1996
夕張市空知郡南富良野町
オンネトー湯の滝マンガン酸化物生成地
2000
足寄郡足寄町
青森県
仏宇多(仏ヶ浦)
1941
下北郡佐井村
岩手県
根反の大珪化木
1936
二戸郡一戸町
夏油温泉の石灰華
1941
北上市和賀町
焼走り溶岩流
1944
岩手郡西根町
厳美渓
1927
一関市厳美町
蛇ヶ崎
1936
陸前高田市小友町
碁石海岸
1937
大船渡市末崎町
岩泉湧窟およびコウモリ
1938
下閉伊郡岩泉町
館ヶ崎角岩岩脈
1939
大船渡市末崎町
崎山の潮吹穴
1939
宮古市鍬ヶ崎
崎山の蝋燭岩
1939
宮古市鍬ヶ崎
姉帯小鳥谷根反の珪化木地帯
1941
二戸郡一戸町
浪打峠の交叉層
1941
二戸郡一戸町
葛根田の大岩屋
1943
岩手郡雫石町
樋口沢ゴトランド紀化石産地
1957
大船渡市日頃市町
安家洞
1975
下閉伊郡岩泉町
宮城県
鬼首の雌釜および雄釜間歇温泉
1933
大崎市鳴子町
球状閃緑岩
1923
白石市白川・犬卒都婆・大鷹沢大町
姉滝
1934
仙台市太白区秋保町
小原の材木岩
1934
白石市小原
歌津館崎の魚竜化石産地および魚竜化石
1975
本吉郡南三陸町
秋田県
玉川温泉の北投石
1922
仙北郡田沢湖町
■(ジ)状珪石および噴泉塔
1924
雄勝郡雄勝町
象潟
1934
由利郡象潟町
筑紫森岩脈
1938
河辺郡河辺町
千屋断層
1995
仙北郡千畑町
鳥海山獅子ヶ鼻湿原植物群落及び新山溶岩流未端崖と湧水群
2001
由利郡象潟町
男鹿目潟火山群一ノ目潟
2007
秋田県男鹿市
山形県
なし
福島県
入水鍾乳洞
1934
田村郡滝根町
見彌の大石
1941
耶麻郡猪苗代町
塔のへつり
1943
南会津郡下郷町
鹿島神社のペグマタイト岩脈
1966
郡山市西田町
茨城県
なし
栃木県
湯沢噴泉塔
1922
塩谷郡栗山村
名草の巨石群
1939
足利市名草上町
群馬県
浅間山溶岩樹型
1940
吾妻郡嬬恋村
岩神の飛石
1938
前橋市昭和町
生犬穴
1938
多野郡上野村
川原湯岩脈(臥龍岩および昇龍岩)
1934
吾妻郡長野原町
上野村亀甲石産地
1938
多野郡上野村
吹割渓ならびに吹割瀑
1938
利根郡利根村
三波石峡
1957
群馬県多野郡鬼石町・埼玉県児玉郡神泉村
埼玉県
御岳の鏡岩
1940
児玉郡神川町
長瀞
1924
秩父郡長瀞町・皆野町
千葉県
犬吠埼の白亜紀浅海堆積物
2002
銚子市犬吠埼
木下貝層
2002
印西市大字木下
東京都
なし
神奈川県
諸磯の隆起海岸
1928
三浦市三崎町諸磯
新潟県
笹川流
1927
岩船郡山北町
佐渡小木海岸
1938
佐渡郡小木町
平根崎の波蝕甌甌穴群
1940
佐渡郡相川町
清津峡
1941
南魚沼郡湯沢町・中魚沼郡中里村
小滝川硬玉産地
1956
糸魚川市小滝
青海川の硬玉産地及び硬玉岩塊
1957
青海川の硬玉産地及び硬玉岩塊
田代の七ツ釜
1937
中魚沼郡津南町・中里村
富山県
魚津埋没林
1936
魚津市釈迦堂
薬師岳の圏谷群
1945
上新川郡大山町
飯久保の瓢箪石
1941
氷見市飯久保
猪谷の背斜・向斜
1941
婦負郡細入村
横山楡原衝上断層
1941
富山県上新川郡大沢野町・富山県婦負郡細入村・岐阜県吉城郡神岡町
立山の山崎圏谷
1945
中新川郡立山町
称名滝
1973
中新川郡立山町
真川の跡津川断層
2003
・岐阜県
石川県
岩間の噴泉塔群
1954
石川郡尾口村
山科の大桑層化石産地と甌穴
1941
金沢市山科町
曽々木海岸
1942
輪島市町野町
手取川流域の珪化木産地
1957
石川郡白峰村
福井県
東尋坊
1935
坂井郡三国町
山梨県
鳴沢溶岩樹型
1929
南都留郡鳴沢村
富岳風穴
1929
西八代郡上九一色村
富士風穴
1929
西八代郡上九一色村
本栖風穴
1929
西八代郡上九一色村
鳴沢氷穴
1929
南都留郡鳴沢村
大室洞穴
1929
南都留郡鳴沢村
神座風穴 附 蒲鉾穴および眼鏡穴
1929
南都留郡鳴沢村
船津胎内樹型
1929
南都留郡河口湖町
龍宮洞穴
1929
南都留郡足和田村
吉田胎内樹型
1929
富士吉田市上吉田
雁ノ穴
1932
富士吉田市上吉田
忍野八海
1934
南都留郡忍野村
燕岩岩脈
1934
甲府市御岳町
新倉の糸魚川—静岡構造線
2001
南巨摩郡早川町
長野県
白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石
1922
南安曇郡安曇村
高瀬渓谷の噴湯丘と球状石灰石
1922
大町市大字平
渋の地獄谷噴泉
1927
下高井郡山ノ内町
中房温泉の膠状珪酸および珪華
1928
南安曇郡穂高町
横川の蛇石
1940
上伊那郡辰野町
四阿山の的岩
1940
小県郡真田町
岐阜県
根尾谷断層
1927
本巣郡根尾村
根尾谷の菊花石
1941
本巣郡根尾村
鬼岩
1934
可児郡御嵩町・瑞浪市日吉町
傘岩
1934
恵那市大井町
美濃の壺石
1934
土岐市土岐津町土岐口
飛水峡の甌穴群
1961
加茂郡七宗町
福地の化石産地
1962
吉城郡上宝村
静岡県
湧玉池
1944
富士宮市宮町
駒門風穴
1922
御殿場市駒門
万野風穴
1922
富士宮市山宮
印野の熔岩隧道
1927
御殿場市印野
手石の弥陀ノ岩屋
1934
賀茂郡南伊豆町
地震動の擦痕
1934
田方郡伊豆長岡町
丹那断層
1935
田方郡函南町
堂ヶ島天窓洞
1935
賀茂郡西伊豆町
白糸ノ滝
1936
富士宮市原・上井出
愛知県
鳳来寺山
1931
南設楽郡鳳来町
猿投山の球状花崗岩
1931
豊田市加納町
阿寺の七滝
1934
南設楽郡鳳来町
乳岩および乳岩峡
1934
南設楽郡鳳来町
馬背岩
1934
南設楽郡鳳来町
三重県
熊野の鬼ケ城 附 獅子巖
1935
熊野市木本町
月出の中央構造線
2002
飯南郡飯高町
滋賀県
石山寺硅灰石
1922
大津市石山寺辺町
綿向山麓の接触変質地帯
1942
蒲生郡日野町
鎌掛の屏風岩
1943
蒲生郡日野町
別所高師小僧
1944
蒲生郡日野町
京都府
稗田野の菫青石仮晶
1922
亀岡市稗田野町
郷村断層
1929
京丹後市網野町
東山洪積世植物遺体包含層
1943
京都市東山区今熊野南日吉町
琴引浜
2007
京丹後市網野町
大阪府
なし
兵庫県
玄武洞
1931
豊岡市赤石竹栗
觜崎ノ屏風岩
1931
揖保郡新宮町龍野市神岡町大住寺
但馬御火浦
1934
美方郡浜坂町・城崎郡香住町
神戸丸山衝上断層
1937
神戸市長田区明泉寺町
鎧袖
1938
城崎郡香住町
野島断層
1998
津名郡北淡町
奈良県
屏風岩、兜岩および鎧岩
1934
宇陀郡曽爾村
和歌山県
橋杭岩
1924
東牟婁郡古座町・西牟婁郡串本町
瀞八丁
1928
和歌山県東牟婁郡熊野川町・三重県南牟婁郡紀和町・奈良県吉野郡十津川村
白浜の化石漣痕
1931
西牟婁郡白浜町
白浜の泥岩岩脈
1931
西牟婁郡白浜町
高池の虫喰岩
1935
東牟婁郡古座川町
神島
1935
田辺市(湾内
門前の大岩
1935
日高郡由良町
鳥巣半島の泥岩岩脈
1936
田辺市新庄町
栗栖川亀甲石包含層
1937
西牟婁郡中辺路町
古座川の一枚岩
1941
東牟婁郡古座川町
鳥取県
浦富海岸
1928
岩美郡岩美町
鳥取砂丘
1955
鳥取市浜坂岩美郡福部村
島根県
大根島の溶岩隧道
1931
八束郡八束町
鬼舌振
1927
仁多郡仁多町
潜戸
1927
松江市
立久恵
1927
出雲市乙立町
石見畳ヶ浦
1932
浜田市国分町
多古の七ツ穴
1932
松江市
岩屋寺の切開
1932
仁多郡横田町
築島の岩脈
1932
松江市
隠岐知夫赤壁
1935
隠岐郡知夫村
大根島第二熔岩隧道
1935
八束郡八束町
波根西の珪化木
1936
大田市久手町波根西
唐音の蛇岩
1936
益田市西平原町
隠岐白島海岸
1938
隠岐郡西郷町
隠岐海苔田ノ鼻
1938
隠岐郡西郷町
隠岐国賀海岸
1938
隠岐郡西ノ島町
松代鉱山の霰石産地
1959
大田市久利町松代
三瓶小豆原埋没林
2004
大田市
岡山県
草間の間歇冷泉
1930
新見市草間
羅生門
1930
新見市草間
象岩
1932
倉敷市下津井
大賀の押被
1937
川上郡川上町
白石島の鎧岩
1942
笠岡市白石島
広島県
船佐・山内逆断層帯
1961
高田郡高宮町三次市畠敷町庄原市山内町
久井・矢野の岩海
1964
御調郡久井町甲奴郡上下町
押ヶ垰断層帯
1965
山県郡戸河内町廿日市市下山大畑
雄橋
1987
比婆郡東城町
山口県
秋芳洞
1922
美祢郡秋芳町
秋吉台
1961
美祢郡秋芳町・美東町
景清穴
1922
美祢郡美東町
大正洞
1923
美祢郡美東町
中尾洞
1923
美祢郡秋芳町
青海島
1926
長門市仙崎・通
石柱渓
1926
豊浦郡豊田町
俵島
1927
大津郡油谷町
須佐湾
1928
阿武郡須佐町
岩屋観音窟
1934
玖珂郡美川町
万倉の大岩郷
1935
美祢市伊佐町奥万倉
吉部の大岩郷
1935
厚狭郡楠町
須佐高山の磁石石
1936
阿武郡須佐町
徳島県
阿波の土柱
1934
阿波市
宍喰浦の化石漣痕
1979
海部郡宍喰町
香川県
屋島
1934
高松市屋島東町・中町・西町・高松町
円上島の球状ノーライト
1934
観音寺市伊吹町
絹島および丸亀島
1940
大川郡大内町
鹿浦越のランプロファイヤ岩脈
1942
大川郡白鳥町
愛媛県
八釜の甌穴群
1934
上浮穴郡柳谷村
砥部衝上断層
1938
伊予郡砥部町
八幡浜市大島のシュードタキライト及び変成岩類
2004
愛媛県八幡浜市大島
高知県
龍河洞
1934
香美郡土佐山田町
唐船島の隆起海岸
1953
土佐清水市清水
千尋岬の化石漣痕
1953
土佐清水市三崎
大引割・小引割
1986
高岡郡仁淀村・東津野村
福岡県
長垂の含紅雲母ペグマタイト岩脈
1934
福岡市西区長垂
千仏鍾乳洞
1935
北九州市小倉南区大字新道寺
鷹巣山
1941
福岡県田川郡添田町・大分県下毛郡山国町
平尾台
1952
北九州市小倉南区大字新道寺
青龍窟
1962
京都郡苅田町
芥屋の大門
1966
糸島郡志摩町
水縄断層
1997
久留米市山川町
佐賀県
屋形石の七ツ釜
1925
唐津市屋形石
八藤丘陵の阿蘇4火砕流堆積物及び埋没林
2004
佐賀県三養基郡上峰町
長崎県
七釜鍾乳洞
1936
西彼杵郡西海町
斑島玉石甌穴
1958
北松浦郡小値賀町
平成新山
2004
長崎県島原市、南高来郡小浜町
熊本県
妙見浦
1935
天草郡天草町
龍仙島(片島)
1935
牛深市牛深町
大分県
小半鍾乳洞
1922
南海部郡本匠村
風連洞窟
1927
大野郡野津町
狩生鍾乳洞
1934
佐伯市狩生
耶馬渓猿飛の甌穴群
1935
下毛郡山国町
大岩扇山
1935
玖珠郡玖珠町
姫島の黒曜石産地
2007
大分県東国東郡姫島村
宮崎県
五箇瀬川峡谷(高千穂峡谷)
1934
西臼杵郡高千穂町
関の尾の甌穴
1928
都城市関之尾町
七折鍾乳洞
1933
西臼杵郡日之影町
青島の隆起海床と奇形波蝕痕
1934
宮崎市大字折生迫
柘の滝鍾乳洞
1933
西臼杵郡高千穂町
鹿児島県
なし
沖縄県
塩川
1972
国頭郡本部町
下地島の通り池
2006
宮古島市
(関連リンク)国指定文化財等データベース(文化庁サイト)
研究奨励金(採択結果)
2025年度(第3回)日本地質学会研究奨励金採択結果
2025.4.19理事会承認
氏名
所属
研究課題
古庄航輝
茨城大学大学院
福島県中央部,磐梯火山南西麓に流下した岩屑なだれの流動過程:層相と粒度分布,粒子の形態に基づく検討
高橋恒佑
東北大学理学部知見環境科学
北海道蝦夷層群の上部白亜系における超高解像度の統合標準層序と国際標準年代尺度の確立
福井堂子
愛媛大学大学院理工学研究科
交代性閃長岩形成過程における元素の移動・濃集モデルについての広域的野外調査に基づく検証
鈴木 捷太
北海道大学大学院理学院
恵庭岳の地質学的・岩石学的研究:最新期マグマ噴火の噴火史およびマグマ系の変遷
過去の採択結果
応募要領ほか
中部支部(過去の活動)
中部支部(過去の活動)
ご案内
2023.4.12掲載
中部支部2023年支部年会開催のお知らせ
日本地質学会中部支部では下記のとおり2023年支部年会を開催します.あわせてシンポジウム,一般講演,ポスター発表,懇親会,および巡検を行いますので,皆様ぜひご参加ください.
日時:2023年6月24日(土)
受付開始 10:30
総会 11:00〜11:30
幹事会 11:30〜12:30
シンポジウム 13:00〜14:15
一般講演(口頭発表) 14:30〜15:45
ポスターコアタイム 16:00〜17:00
懇親会 17:30〜
会場:信州大学松本キャンパス
参加費:2000円(総会のみは無料,大学院生・学部生は1000円)
参加要件:日本地質学会会員であること.非会員の参加は不可.
事前登録:6月15日(木)までにgoogle forms(https://forms.gle/sr18goJvUd7sf1aK8)にて参加登録・発表申し込みをしてください.巡検(6月25日)に参加する方は6月1日(木)までに登録してください(後述).
シンポジウム『西南日本の白亜紀花崗岩類』
趣旨:2000年代以降,LA-ICPMSを用いたジルコンU-Pb年代測定が盛んに行われるようになり,日本各地の地質体の形成年代の詳細が明らかにされています.西南日本に分布する白亜紀花崗岩類もその一つであり,年代データの蓄積や形成についての議論が盛んに行われています.そこで,白亜紀花崗岩類についての年代特性や形成モデルについて考えたいと思います.
13:00〜13:05 趣旨説明 常盤哲也(信州大学)
13:05〜13:25 伊那領家花崗岩類のジルコンU-Pb年代 常盤哲也(信州大学)
13:25〜13:45 紀伊半島領家花崗岩類のジルコンU-Pb年代 竹内 誠(名古屋大学・産総研)
13:45〜14:05 日本の白亜紀−古第三紀の火成活動場とテクトニクス 山岡 健(産総研)
14:05~ 14:15 白亜紀花崗岩類についての座談会 全員
一般講演(口頭発表):(14:30~15:45)
最大5件を受け付けます.先着順ですので希望される方は早めの登録をお願いします.
一般講演は,対面のみで行い,各講演15分を予定しています(発表12分,質疑応答3分).
発表要旨(一般講演の方のみ):
一般講演に申し込まれる方は上記の事前登録フォームに申し込みの上,6月15日(木)までに常盤(tokiwa@shinshu-u.ac.jp)に講演要旨をメールにて送付願います.
後日,公表論文作成にあたって,支部年会での講演を引用することはできないことになっていますので,ご了承ください.
一般講演の講演要旨はA4版,2頁までとします。
要旨の様式は下記書式に沿ってください.字体は明朝で統一します.お送り頂いたメール原稿をそのままの形で印刷する予定です.
上下余白:3cm 左右余白:2.5cm
タイトル:14p(ポイント)太文字
発表者・所属機関:12p
英文タイトル:12p
本文は1行開けて始めてください.
本文:10.5p
引用文献:9p
図表は枠内に収めてください.
英文原稿の場合は,上記に準じてください.
CPD: 地質技術者への継続教育の一環として,大会参加者・発表者へCPD単位を発行します.大会参加と口頭発表の参加証明書は,参加日以降にメールにて送付予定です.
【CPD単位】
一般講演:5×発表時間(h)例)15分の場合:5×1/4h=1.25単位
学会参加:1×滞在時間
個人講演(ポスターコアタイム16:00-17:00)
ポスターは10:00−17:00まで掲示することができます.ポスター発表希望者は上記事前登録フォームにて,発表者氏名と発表タイトルを入力してください.なお,学生・院生のポスター発表は優秀ポスター賞の審査の対象となりますので,ふるってご参加ください.
懇親会(17:30-)
懇親会を信州大学松本キャンパス内で行う予定です.懇親会費は一般5000円,大学院生・学部生は3000円を予定しています.
巡検:大峰帯第四系と爺ヶ岳ー白沢天狗カルデラ・黒部川花崗岩
日時:6月25日(日)8:00〜16:00(予定)
内容:大峰山地(北安曇郡池田町)に分布する第四系河川堆積物と大峰火砕流堆積物,扇沢(大町市)に分布する爺ヶ岳−白沢天狗カルデラ・黒部川花崗岩を観察する.
案内者:吉田孝紀・原山 智(信州大学)
問合せ:常盤哲也(信州大学)tokiwa[at]shinshu-u.ac.jp ※[at]を@マークにして送信してください
参加費:1人5000円程度(参加人数によって若干の変更があります)
大まかな予定は,8:00信州大学→巡検(貸切バス)→16:00信州大学です.
昼食は各自ご準備願います.
参加希望者は6月1日(木)までにgoogle forms (https://forms.gle/E2J6Xyn1ZqmTe6mW7)にて参加登録をしてください.
参加者が15名以下の場合は,キャンセルすることもあります.
支部年会に関する問合せ先:
常盤哲也(信州大学)tokiwa[at]shinshu-u.ac.jp ※[at]を@マークにして送信してください
ご案内
2022.11.7掲載
地質・土木技術者を対象とした応用地質学講座(初級〜中級):
「土砂災害の疑問55 出版記念講座(中部編)」 のご案内
主催 一般社団法人 日本応用地質学会 中部支部
後援 公益社団法人 地盤工学会 中部支部,一般社団法人 中部地質調査業協会,一般社団法人 日本地質学会 中部支部
講座名称:土砂災害の疑問55 出版記念講座(中部編)
対象:初級者〜中級者(地質・土木技術者等)
開催日:2022年12月9日(金)13:00〜17:00
場所:名城大学天白キャンパス理工学部研究実験棟Ⅱ261 + Zoom によるオンライン開催
(ただし,緊急事態宣言が出た際は,オンライン開催のみとさせていただきます)
講師:
稲垣秀輝(本部,環境地質(株),編集総括)
松澤 真(本部,公益財団法人深田地質研究所,編集WG 長)
永田秀尚(中部支部,(有)風水土)
加藤弘徳(中国四国支部,荒谷建設コンサルタント)
加藤靖郎(中部支部,川崎地質(株))
準備品:書籍「土砂災害の疑問55」(成山堂書店)をテキストとして使います.参加者の方には割引価格(税込み1,800 円)で販売します.参加申し込み時に合わせてお申し込みください.
受講料:
会員(日本応用地質学会員,地盤工学会員,中部地質調査業協会会員,日本地質学会会員の方):1,000 円
非会員:3,000 円,学生:無料
受講料のお振込み先につきましては,受付確認時にご案内いたします.
募集人員:会場参加40名.申し込み先着順とし,定員になり次第締め切らせていただきます.Web 参加は定員なしです. 受付確認は,事務局からの連絡(代表者へのメール連絡)をもって替えさせていただきます. 申込方法:以下のWeb フォームよりお申し込みをお願いいたします。
https://forms.gle/eUKjBxdp7GKYS3CP7
申込・振込締切日:11月25 日(金)
問い合わせ先:サンコーコンサルタント(株)名古屋支店
日本応用地質学会 中部支部事務局 赤嶺
CPDH:3.5 単位 受講証明書を発行いたします.参加申込書に必要の有無を記載ください.
プログラム等詳細はこちら
「⼩松の⽯⽂化」現地⾒学会のご案内
標記の現地見学会についてご案内いたします。現地見学会では、小松市埋蔵文化財センターの樫田誠専門官のご講演を頂いた後に、現地見学を行います。樫田専門官には現地見学にもご同行頂ける予定です。さらに、金沢大学の塚脇真二教授にもご同行頂きます。地質学会中部支部会員も参加可能です。貴重な機会ですので、ふるってご参加ください。
主催:一般社団法人日本応用地質学会中部支部
共催:北陸地盤工学研究会
後援:一般社団法人日本地質学会中部支部,一般社団法人中部地質調査業協会,公益社団法人地盤工学会中部支部,
日時:2022年10月1日(土)13:30-17:30【雨天決行】
場所:石川県小松市内
集合場所・時間:白山市役所駐車場(12:20)
小松駅東出口乗降場(13:00)
マイクロバスに乗り合わせて現場(小松駅経由)に向かいます。
※見学現場の地図や集合場所の位置は下記PDFをご確認ください
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/outline/shibu/chubu/20221001komatsu.pdf
行程:
13:30-14:15 小松市埋蔵文化財センター(樫田先生のご講演)
14:30-15:00 遊泉寺銅山跡
15:20-15:50 観音下石切場
16:00-16:30 尾小屋鉱山資料館
17:30頃 小松駅 解散
現地案内:小松市埋蔵文化財センター 樫田誠専門官,金沢大学 塚脇真二教授
定員:20名(先着順)
参加費(各施設入場料含む):会員・後援団体会員:1,000円、学生:無料
その他:長靴やヘルメットは必要ありませんが、汚れても良い服装・靴でお願いします。
※ マスク着用、事前の体調確認をお願いします
申込み先:専用申込フォームからお申し込み下さい。→申込フォームはこちらから
申込期限:2022年9月28日(水)
【お問い合せ先】
応用地質学会中部支部事務局 担当 赤嶺
サンコーコンサルタント(株)名古屋支店気付
TEL: 052-228-6132,Email: jges7chubu[at]gmail.com
※[at]を@マークにして送信してください.
日本地質学会中部支部2022年支部年会のお知らせ
2022年支部年会 優秀ポスター賞2件:2022年6月25日(土)に金沢大学で開催さ れた日本地質学会中部支部2022年支部年会に学術ポスター発表会において,以下の2件の講演が優秀ポスター賞に選ばれました.
<優秀ポスター賞>
P1:北海道幌満カンラン岩体の変形微細構造と結晶方位ファブリック:松山和樹(名古屋大)ほか
P2:Development of a hydrated ductile shear zone and strain localization at the Moho Transition Zone in Oman Ophiolite:夏目 樹(名古屋大)ほか
(2022.6.28掲載)
2022.4.26掲載
日本地質学会中部支部2022年支部年会開催のお知らせ
日本地質学会中部支部では下記のとおり2022年支部年会を開催します.あわせてシンポジウムと一般講演を行いますので,皆様ぜひご参加ください.
日時:2022年6月25日(土)
受付開始 10:15
総会 10:30〜11:30
幹事会 11:30〜12:00
シンポジウム 13:00〜15:00
一般講演 15:15〜16:30
ポスターコアタイム 16:30〜17:30
会場:金沢大学角間キャンパス+Zoomオンライン(ハイブリッド)
参加費:無料 参加要件:日本地質学会会員であること。非会員の参加は不可(ただし、応用地質学会中部支部会員は参加可)。
事前登録:6月17日(金)までに google forms (https://forms.gle/nEHHv1wkbBFGXNSH9)にて参加登録をしてください。登録された参加予定者には後日、Zoomの接続URLを連絡します。
特別講演『海洋掘削科学:日本海』& 特別討論会『珠洲の群発地震』
趣旨1:掘削科学は科学的仮説を検証するために試料採取場所を選び,自らの力で試料を採取する重要な手法です。特別講演では,日本海での国際海洋掘削計画(IODP Expedition 346)の掘削成果について紹介してもらいます。
趣旨2:能登半島の先端の珠洲市では群発地震が続いています。その予察的な解析から,地下深部の流体の動きが関与している可能性が指摘されています。そこで,群発地震の活動様子および,流体の起源として沈み込む海洋プレートの可能性などについて考えたいと思います。
13:00〜13:05 趣旨説明 森下 知晃(金沢大学)
13:05〜13:35 日本海掘削(IODP Exp 346)成果 佐川拓也(金沢大学)
13:35〜14:00 珠洲市付近の群発地震の概要 平松 良浩(金沢大学)
14:00〜14:25 中部日本第四紀火山岩からみるスラブ起源流体の分布 中村仁美(産総研)
14:25~ 15:00 珠洲市付近の群発地震についての座談会 中村+平松+司会
一般講演:(15:15~16:30)
最大5件(先着順)を受け付けます。発表希望者は6月17日(金)までにgoogle forms (https://forms.gle/nEHHv1wkbBFGXNSH9) にて連絡してください。
講演について:
一般講演は、各講演15分を予定しています(発表12分、質疑応答3分)。
一般講演は、対面もしくはZoomによる画面共有により行う予定です。
講演要旨:
一般講演に申し込まれる方は6月17日(金)までに金沢大学・田村―長谷部(aking826@gmail.com)まで講演要旨をメールにて送付願います。
後日、公表論文作成にあたって、支部年会での講演を引用することはできないことになっていますので、ご了承ください。
一般講演の講演要旨はA4版、2頁までとします。
要旨の様式は下記書式に沿ってください。字体は明朝で統一します。お送り頂いたメール原稿をそのままの形で印刷する予定です。
上下余白:3cm 左右余白:2.5cm
タイトル:14p(ポイント)太文字
発表者・所属機関:12p
英文タイトル:12p
本文は1行開けて始めてください。
本文:10.5p
引用文献:9p
図表は枠内に収めてください。
英文原稿の場合は、上記に準じてください。
CPD:
地質技術者への継続教育の一環として,大会参加者・発表者へCPD単位を発行します。大会参加と口頭発表の参加証明書は,参加日以降にメールにて送付予定で
【CPD単位】
口頭発表:5×発表時間(h)例)15分の場合:5×1/4h=1.25単位
学会参加:1×滞在時間
個人講演(ポスターコアタイム)(16:30-17:30)
ポスター発表は10:00−17:30まで掲示することができます.ポスター及び口頭発表希望者は下記申し込み先まで,発表タイトル,発表者氏名,連絡先をお知らせください.なお,学生・院生のポスター発表は優秀ポスター賞の審査の対象となりますので,ふるってご参加ください。
6月26日(日) 巡検:白山手取川ジオパーク
大まかな予定は、8:00金沢駅-金沢大学―巡検―金沢大学―17:00金沢駅 バス移動、昼食付きで検討しています。参加費1人5000円程度の予定。参加希望者は田村(長谷部)明弘 (問合せ担当:aking826@gmail.com )まで連絡をお願いします。参加者が少ない場合は,キャンセルすることもあります。定員15名程度を想定しています。巡検申込締切:5月31日(金)。
日本地質学会中部支部2020年度総会のお知らせ
下記の通り,日本地質学会中部支部総会を開催します.併せて,シンポジウム「美濃帯の最近の研究事例」,一般講演を行います(年会・シンポの詳細は下記学会HP参照).
日時:2021年6月26日(土)10:00より
方法:Zoomによる会議方式(事前登録:6月18日(金)までにGoogle Forms ( https://forms.gle/5YGUQFbpYpaUreMc7 )にて参加登録をしてください.登録された参加予定者には後日、Zoomの接続URLを連絡します.
議案:議案の詳細はこちら(PDF)
1号議案 2020年度支部活動報告・会計報告・会計監査報告
2号議案 2020−2021年支部長選出及び支部幹事
3号議案 2021年支部年会開催県
当日,総会に参加できない方は,下記の議決権行使書あるいは委任状を支部事務局竹内(takeuchi@eps.nagoya-u.ac.jp)に6月25日までに返信してください.
議決権行使書
一般社団法人日本地質学会中部支部
支部長 道林克禎殿
6月26日の中部支部総会に出席できないため,下記の通り,議決権を行使します.
1号議案 2020年度支部活動報告・会計報告・会計監査報告 賛成・反対・保留(不要のものを消してください)
2号議案 日本地質学会中部支部規約及び運営細則改正 賛成・反対・保留(不要のものを消してください)
3号議案 2022年支部年会開催県 賛成・反対・保留(不要のものを消してください)
氏名:
2021年6月 日
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
委任状
6月26日の中部支部総会に出席できないため, 会員を代理人と定め,同総会に出席して議決権を行使する権限を委任します.
氏名:
2021年6月 日
(委任状に代理人の記入がない場合は,「議場委任」されたものとみなします)
日本地質学会中部支部 2021年支部年会
日本地質学会中部支部 2021年支部年会
日本地質学会中部支部では下記のとおり2021年支部年会を開催します.あわせてシンポジウムと一般講演を行いますので,皆様ぜひご参加ください.
日時:2021年6月26日(土)
受付開始 10:15
総会 10:30〜11:30
幹事会 11:30〜12:00
シンポジウム 13:00〜15:05
一般講演 15:15〜17:00
会場:Zoomオンライン
参加費:無料 参加要件:日本地質学会会員であること。非会員の参加は不可(ただし、応用地質学会中部支部会員は参加可)。
事前登録:6月18日(金)までにgoogle forms (https://forms.gle/5YGUQFbpYpaUreMc7)にて参加登録をしてください。登録された参加予定者には後日、Zoomの接続URLを連絡します。
参加者数:最大100名
シンポジウム「美濃帯の最近の研究事例」
趣旨:中部地方の岐阜県下には美濃帯が広く分布しており、中部地方の各大学・団体における巡検によく取り上げられる地質体である。美濃帯では、古くは放散虫化石による付加体層序学の研究が行われ、最近でもさまざまな観点から研究が進められている。現在、コロナ禍のため、複数の大学や団体にまたがった巡検を実施しづらい状況にあるものの、各大学や団体ごとの巡検が行われる際に、その内容を充実したものにするために、本シンポジウムで最新の研究事例の紹介を行う。
13:00〜13:05 趣旨説明 大谷具幸(岐阜大学)
13:05〜13:45 日本海溝の陸上アナログとしての美濃帯研究 山口飛鳥(東京大学)
13:45〜14:25 岐阜県西部,舟伏山で発見したP/T境界層 佐野弘好(九州大学名誉教授)
14:25〜15:05 美濃帯の上部三畳系チャートに記録された環境変動:カーニアン多雨事象とノーリアン天体衝突 尾上哲治(九州大学)
一般講演:15:15開始
最大7件(先着順)を受け付けます。発表希望者は6月18日(金)までにgoogle forms (https://forms.gle/5YGUQFbpYpaUreMc7) にて連絡してください。
講演について:
一般講演は、各講演15分を予定しています(発表12分、質疑応答3分)。
一般講演は、Zoomによる画面共有により行う予定です。
講演要旨:
一般講演に申し込まれる方は6月18日(金)までに岐阜大学・大谷(tmohtani@gifu-u.ac.jp)まで講演要旨をメールにて送付願います。
後日、公表論文作成にあたって、支部年会での講演を引用することはできないことになっていますので、ご了承ください。
一般講演の講演要旨はA4版、2頁までとします。
要旨の様式は下記書式に沿ってください。字体は明朝で統一します。お送り頂いたメール原稿をそのままの形で印刷する予定です。
上下余白:3cm 左右余白:2.5cm
タイトル:14p(ポイント)太文字
発表者・所属機関:12p
英文タイトル:12p
本文は1行開けて始めてください。
本文:10.5p
引用文献:9p
図表は枠内に収めてください。
英文原稿の場合は、上記に準じてください。
CPD:
地質技術者への継続教育の一環として,大会参加者・発表者へCPD単位を発行します。大会参加と口頭発表の参加証明書は,参加日以降にメールにて送付予定です。
【CPD単位】
口頭発表:5×発表時間(h)例)15分の場合:5×1/4h=1.25単位
学会参加:1×滞在時間
日本地質学会中部支部 2019年支部年会
日本地質学会中部支部 2019年支部年会
地質学会中部支部では以下の通り2019年支部年会を開催します.あわせてシンポジウムと地質巡検を計画しましたので,皆様是非ご参加ください.
日時:2019年6月29日(土)
受付開始 9:30
シンポジウム 10:00-12:00
支部総会 13:00-14:00
個人講演 14:00-16:00
ポスターセッションコアタイム 16:00−17:00
(なお講演数によりタイムスケジュールは調整されます)
会場:福井県立大学永平寺キャンパス 多目的ホール(交流センター3階)
福井県永平寺町松岡兼定島4-1-1
年会参加者は無料で福井県立恐竜博物館(常設展)を見学できます。
会場へのアクセス:
http://www.fpu.ac.jp/access/fukui/map.html
http://www.fpu.ac.jp/access/fukui/campus.html(キャンパスマップ)
参加費(総会・シンポジウム):なし
シンポジウム「恐竜渓谷ふくい勝山ジオパークとそれを取り巻く活動(仮題)」
日時:2019年6月29日(土)10:00-12:00
講演予定者(各人20分予定)
基調講演:
柴田伊廣(文化庁文化財第2課技官)
町 澄秋(恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク推進協議会 ジオパーク専門員)
三好雅也(福井大学教育地域科学部)
野田芳和(福井県立恐竜博物館副館長)
酒井佑輔(大野市教育委員会)
総合討論
(講演と講演要旨についての要領および注意はこちら)
講 演
日時:2019年6月29日(土)
個人講演 14:00-16:00
ポスターセッションコアタイム 16:00−17:00
個人講演:15分(質疑応答含む)
ポスターセッション:A0版サイズ(横841mm×縦1,189mm)が基準です(画鋲可)。1発表につき横90cm×縦180cmのボード1枚を使用します。
(講演と講演要旨についての要領および注意はこちら)
懇親会
日時:2019年6月29日(土)18:30-21:00
福井市内、福井駅周辺を予定.会費:一般5,000円、学生3,000円を予定
巡検「恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク見学」
シンポジウムに併せて,以下の要領で巡検を企画しました.ふるってご参加ください.
案内者:柴田正輝、町 澄秋、三好雅也ほか
費用:2,000円を予定(昼食代込み)。マイクロバスを用意します(福井駅発 福井県立大学永平寺キャンパス・福井県立恐竜博物館経由予定)。
巡検定員:20名
日程:2019年6月30日(日)
福井駅8:00出発--福井県立大学永平寺キャンパス8:30出発--福井県立恐竜博物館 9:00出発(恐竜化石発掘現場を含む勝山市内のジオサイトを見学)-- 恐竜博物館15:00出発-- 福井駅16:00解散予定
見学ポイント:
恐竜化石発掘現場(勝山市北谷町)の天然記念物露頭、足跡化石面など/経ヶ岳火山岩類/大矢谷白山神社の巨大岩塊/段丘地形と七里壁
資料:総会会場およびバス内で巡検資料を配布します。
参加申し込み先
準備の都合がありますので, 5月24日(金)までに参加内容(総会,シンポジウム,個人講演、ポスターセッション、懇親会,巡検の別)、連絡先を明記して,お申し込みください。なお、講演、ポスターセッションを希望される方は、講演要旨(A4サイズ2ページまで)をご用意ください。(講演と講演要旨についての要領および注意はこちら)
日本地質学会中部支部 年会担当 中田健太郎
E-mail: k-nakada@dinosaur.pref.fukui.jp
Tel:0779-88-0001
FAX: 0779-88-8720
はがき:〒911-8601 福井県勝山市村岡町寺尾51-11福井県立恐竜博物館気付 日本地質学会中部支部年会担当 中田健太郎 行
日本地質学会中部支部 2018年支部年会
日本地質学会中部支部 2018年支部年会
中部支部では下記のとおり2018年支部年会を開催します.皆様是非ご参加ください.
日程:2018年6月16日(土)〜17日(日)
6月16日(土)講 演
会場:山梨大学教育学部N号館(〒400-8510山梨県甲府市武田4−4−37)
受付:10:00〜 (参加費:2,000円,学生割引有り)
総会:10:30〜11:30
シンポジウム:13:00〜15:00
「南部フォッサマグナの過去・現在・未来」
講演者:天野一男氏(茨城大学)・松原典孝(兵庫県立大学)
狩野謙一氏(静岡大学)
内山 高氏(富士山科学研究所)
その他,講演依頼中
個人講演(口頭発表):15:15〜16:30
個人講演(ポスターコアタイム):16:30〜17:15(山梨大学大学会館多目的ホール)
懇親会:18:00-20:00(山梨大学大学会館ラウンジ)(参加費:1000円程度)
6月17日(日) 地質巡検
南部フォッサマグナ北縁地域の変動地質(定員15名程度)(参加費:1,000円程度)
バスをチャーターして移動します.
見学予定:八ヶ岳山体崩壊で生じた岩屑流堆積物,糸魚川―静岡構造線活断層系断層露頭および断層変位地形,八ヶ岳火山溶岩,ナウマンのフォッサマグナ発想の地(野辺山高原平沢峠)のしております.
案内者:福地龍郎氏(山梨大学)
日程:山梨大学集合(8:30)→韮崎市雲岸寺周辺の岩屑流堆積物→下円井断層露頭→白州断層露頭→川俣渓谷吐竜の滝八ヶ岳火山溶岩→野辺山高原平沢峠→韮崎駅(17:00予定)
宿泊:甲府駅周辺に宿泊施設には以下のものがあります.各自で予約をお願いします.なお,甲府駅北口から山梨大学までは,山梨交通バス(武田神社行で山梨大学下車)で5分(片道100円),徒歩で15分程掛かります.
ホテルニューステーション(甲府駅北口徒歩1分)http://www.nshotel.jp/
甲府ターミナルホテル(甲府駅南口徒歩1分)http://www.kofu-tabi.jp/list/terminal.html
東横INN甲府駅南口2(甲府駅南口徒歩2分)https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00132/
東横INN甲府駅南口1(甲府駅南口徒歩10分)https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00072/
その他にも色々ありますので,以下のホームページを参照して下さい。
http://www.kofu-tabi.jp/index.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPD:地質技術者への継続教育の一環として,大会参加者・発表者・巡検参加者へCPD単位を発行します.大会参加と口頭/ポスター発表の参加証明書は,参加日の15時以降に「CPD受付」(会場内総合受付付近を予定)においてお渡しします.また,巡検参加者については各コースにおいて案内者よりお渡しすることになります.
【CPD単位】
・ポスター発表:1×ポスター制作時間(h)(上限15)
・口頭発表:5×発表時間(h) 例)15分の場合:5×1/4h=1.25単位
・学会参加:1 × 滞在時間
・巡検参加:日帰り=8単位
参加申込:準備の都合がありますので,5月31日(木)までにご参加いただける内容を以下より選び,E-mailまたはハガキにてお申し込みください.なお,巡検は定員になり次第締め切らせていただきます.
参加内容:総会,個人講演(題名と口頭・ポスターの別),懇親会,地質巡検(連絡先,E-mailが望ましい)
申込先:
E-mail: tfukuchi[at]yamanashi.ac.jp([at]を@マークに変更して送信して下さい)
郵送(ハガキ):〒400-8510山梨県甲府市武田4−4−37
山梨大学大学院総合研究部教育学域 福地龍郎 宛(TEL&FAX:055-220-8219)
日本地質学会中部支部 2017年支部年会
日本地質学会中部支部 2017年支部年会
中部支部では下記の通り2017年支部年会を開催します.皆様是非ご参加ください.
日程:2017年6月17日(土)
会場:新潟県糸魚川市フォッサマグナミュージアム
(http://www.city.itoigawa.lg.jp/fmm/)
参加費:無料(懇親会を除く)
受 付(10:00から)
総 会(10:30-11:30)
シンポジウム (13:00-15:00)
「地質学とジオパーク —現状と今後の課題—」
講演者予定:糸魚川ユネスコ世界ジオパーク関係者数名および佐渡ジオパーク関係者ほか.
この他,他のジオパークに関する講演を数名程度公募します.応募される方は下記の申し込み先に5月26日(金)までにお申し込みください.
個人講演(口頭発表)(15:15-16:30)
個人講演(ポスターコアタイム)(16:30-17:15)
ポスター発表は10:00−17:15まで掲示することができます.
ポスター及び口頭発表希望者は下記申し込み先まで,発表タイトル,発表者氏名,連絡先をお知らせください.
なお,学生・院生のポスター発表は優秀ポスター賞の審査の対象となりますので,ふるってご参加ください.
懇親会 (18:00から)
場所:糸魚川市青海中学校セミナーハウス
参加費:一般3,000円程度,学生・大学院生1,000円程度を予定.
なお,青海中学校セミナーハウスに宿泊できます.宿泊希望者は宿泊費として別に900円が必要です.
また,布団の使用を希望される方はさらに寝具代として1,500円から2,000円程度必要です.
CPD:
地質技術者への継続教育の一環として,大会参加者・発表者へCPD単位を発行します.大会参加と口頭/ポスター発表の参加証明書は,参加日の15時以降に「CPD受付」(会場内総合受付付近を予定)においてお渡しします.
【CPD単位】
・ 学術大会参加に対するCPD(時間に応じて):例)7時間出席=7単位
共催:新潟大学理学部地質科学教室,糸魚川市,糸魚川市教育委員会,佐渡市教育委員会
後援:新潟大学理学部,新潟大学災害・復興科学研究所,新潟大学自然科学系附置 地球環境・地球物質研究センター,新潟大学自然科学系附置 形の科学研究センター
参加申込締切(2種類の締め切りがありますので注意してください)
総会,シンポジウム(参加のみで講演なしの場合),個人講演,懇親会,青海中学セミナーハウスでの宿泊と寝具使用の希望の有無 申込締切:6月2日(金).
シンポジウムでの講演 申込締切: 5月26日(金)
申し込み項目のうち参加したい項目と申込者の連絡先(E-mailが望ましい)とを明記して,E-mailにて下記の連絡先までお申し込みください.
申込項目:総会,シンポジウム,個人講演,懇親会,青海中学校セミナーハウスでの宿泊と寝具使用希望の有無
お間違いのないよう,お願いします.
連絡先:
〒950-2181新潟市西区五十嵐2の町8050
新潟大学理学部地質科学教室 豊島剛志
E-mil: ttoyo@geo.sc.niigata-u.ac.jp
電話: 025-262-6199
2016年支部年会開催のお知らせ
中部支部では下記のとおり2016年支部年会を開催します.詳細は下記ウェブページにて逐次お知らせいたします.
http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~sekmich/Chubu_GSJ_2016.html
2016年6月11日(土)
会 場:ふじのくに地球環境史ミュージアム(〒422-8017静岡市駿河区大谷5762)
https://www.fujimu100.jp/
支部年会:10:00〜 (参加費:2,000円,学生割引有り)
総会
シンポジウム:「地質記録から探る静岡県の低頻度大規模自然災害」
研究発表会(口頭+ポスター)
懇親会:18:00-20:00(静岡大学内)(参加費:1000円程度)
2016年6月12日(日)
地質巡検:安倍川源流部大谷崩れ(定員20名程度)(参加費:1,000円程度)
宝永地震に伴う崩壊で,日本三大崩れ.案内者:狩野謙一静岡大学名誉教授
日程:静大集合(8:30)→時の栖→静岡駅→安倍川上流部巡検→静岡駅(15:00予定)
参考文献:日本地方地質誌第4巻中部地方「22.6 大谷崩 解体していく赤石山地(南アルプス)」
宿 泊:
■静岡時の栖別館(http://www.tokinosumika.com/stokinosumika/group/)の2タイプの部屋を10日と11日で仮予約しています.
Aタイプ)和室16帖4人部屋(風呂,洗面共用):5000円/1泊朝食付,温泉券有り
一部屋を6名以上は500円割引,朝食なしで500円割引
Bタイプ)和室10帖3人部屋(風呂付き):5000円/1泊朝食付,温泉券有り
一部屋を5名以上は500円割引,朝食なしで500円割引
■個室希望の場合には,各自で静岡時の栖に予約してください.
http://www.tokinosumika.com/stokinosumika/
■その他,静岡駅周辺に宿泊の場合には各自で予約をお願いします.
CPD:
地質技術者への継続教育の一環として,大会参加者・発表者・巡検参加者へCPD単位を発行します.大会参加と口頭/ポスター発表の参加証明書は,参加日の15時以降に「CPD受付」(会場内総合受付付近を予定)においてお渡しします.また,巡検参加者については各コースにおいて案内者よりお渡しすることになります.
【CPD単位】
・ 学術大会参加に対するCPD(時間に応じて):例)7時間出席=7単位
・ 口頭発表に対するCPD:0.4×15分発表=6単位
・ ポスター発表に対するCPD:2単位
・ 巡検参加に対するCPD:日帰り=8単位
参加申し込み:準備の都合がありますので,5月27日(金)までにご参加いただける内容を以下より選び,E-mailまたは葉書にてお申し込みください.なお,巡検は定員になり次第締め切らせていただきます.
参加内容:総会,研究発表会(題名と,口頭・ポスターの別),懇親会,
地質巡検(連絡先,E-mailが望ましい),
時の栖別館宿泊希望(10日と11日,AタイプまたはBタイプ)の有無と人数
申し込み先
E-mail: michibayashi@shizuoka.ac.jp
郵 便:〒422-8529 静岡市駿河区大谷836
静岡大学理学部地球科学科 道林克禎 宛
(2016.4.7掲載)
2015年支部年会開催のお知らせ
中部支部では下記のとおり2015年支部年会を開催します.詳細は下記ウェブページにて逐次お知らせいたします.
http://www3.u-toyama.ac.jp/shige/Chubu_GSJ_2015.html
2015年6月13日(土)
会場:黒部市吉田科学館(〒938-0005 富山県黒部市吉田574-1)
支部年会:10:00〜 (参加費:1,500円)
・総会
・シンポジウム:「中部地方のジオパーク ―ジオツアーの安全・安心―(仮題)」
・研究発表会(口頭+ポスター)
懇親会:18:00-20:00(別会場を予定)
2015年6月14日(日)
地質巡検:富山県北東部の中生界(定員15名程度予定)(参加費:1,000円程度)
参加申し込み:準備の都合がありますので,なるべく6月6日(土)までにご参加いただける内容を以下より選び,右側括弧内の情報とともに,E-mailまたは葉書にてお申し込みください.なお,巡検は定員になり次第締め切らせていただきます.
参加内容:総会,研究発表会(題名と,口頭・ポスターの別),懇親会,地質巡検(連絡先,E-mailが望ましい)
申し込み先
E-mail: shige [a] sci.u-toyama.ac.jp
郵 便:〒930-8555 富山市五福3190
富山大学理学部地球科学科 大藤 茂 宛
(2015.4.3更新)
****************************************************************************************************************
2014年中部支部年会・シンポジウム・地質巡検 報告
中部支部事務局幹事
名古屋大学環境学研究科
須藤 斎
中部支部では各県持ち回りで支部年会を開催し,県幹事を中心となってその県に関係した地質についてシンポジウムや地質巡検を企画し,開催運営を行っている.今年は長野県が開催県であり,2014年中部支部年会・シンポジウム・地質巡検を,6月14日(土)と15日(日)に信州大学理学部および上高地にて開催した.
総会(6月14日10:00-10:30)
長野県環境保全研究所の富樫 均会員の議長のもと,参加者13名,委任状51名で開催された.2013年支部活動報告として,地質の日関連イベント(5月10日,名古屋大学博物館)特別講演会「日本の地質の読み方・使い方・地球をよく知って上手につきあうための基本情報」(講師:齋藤 眞氏),中部支部総会(6月29日,石川県白山市交流センター)の講演会等(6月29日)と地質巡検(6月30日,白山手取川ジオパーク),来年度の日本地質学会総会の信州大学での開催に関する準備状況の報告などがなされた.
また,支部会計の2013年決算が承認され,2015年年会を富山県で開催することが承認された.
シンポジウム「観光資源としての地形・地質」(6月14日10:40-11:50)
本シンポジウムでは,飛騨山脈,立山・黒部,および南アルプス(中央構造線エリア)の各地域のジオパークにおける活動や準備状況についての報告と議論,さらに新版長野県地質図の作成,羅臼岳火山地形の観光客へのアピール方法についての報告など,地域に根差した地質学的資源についての発表が行われた.個々の発表や質疑応答については割愛するが,参加者から活発な議論があり盛り上がった.
ポスター発表・一般講演(6月14日13:30-17:50)
ともに中部地域の地質に関する発表が中心であったが,その内容は古流向・古環境復元,ジルコン年代測定,黒部川花崗岩の研究史などの地質学的なものだけでなく,表層地盤と揺れやすさの関連性,東日本大震災へ中部地方がもたらした地質学的影響,凝灰岩層分布などの堆積学的研究,地震動による断層解析など多岐に渡った.また,IODPマントル掘削プロジェクトや地底掘削工法による坑道への影響など,今後中部地方のみならず研究を空間的・内容的に大きく飛躍させうる情報を多数含んだ発表も行われた.
参加者の声から「専門外の内容が多く戸惑いはあったが,翌日の巡検に関わる地質学的な情報や,見学地を含めた中部地方の地形形成史などを知ることができ,非常に参考になった.また,ジオパークや地質図作成が地域に住む人々に,居住する場所の学問学的知識や防災への情報を分かりやすく還元するだけでなく,『自分たちの住む土地に誇りを持てる』ように,心配りの行き届いた活動をされている点に感銘を受けた」.
懇親会(6月14日18:00-21:00)
今年は生協食堂での開催となった.原山智支部長等の挨拶を交えて会は進み,信州大学の学生たちも含めてうち解けた懇親会となった.会は20時にて閉会の予定であったが,信州名物のワインも供されていたこともあり,その後も歓談は続き大変盛況だった.
写真1 穂高連峰を望みながら原山先生に地形・地質形成史の解説を受ける.
写真2 集合写真.上高地河童橋の上流右岸で岳沢-穂高連峰を背景に.
地質巡検「上高地の成り立ちをみる」6月15日(日)
案内者を含めて17名の参加者があった.
今回の巡検対象は,現在の上高地周辺を形作っている槍穂高連峰と梓川の地形と地質発達史を知るうえで重要な地形・地質学的スポットが選ばれていた.上高地は高地の山脈の隙間に位置しながら,非常に平らな地形が広がっている稀有な場所でもある.そのような地形が形成されるうえで,過去に存在した梓川(古梓川)の流路変更や堰き止めというイベントが発生したことを知ることが非常に重要である.そこで前日のシンポジウム・ポスター・一般口頭発表などでも説明されたような埋積作用により形成された大正池をスタート地点として巡検が開始された.大正池から望むことができる焼岳の火砕流やそこから供給された大量の埋積物を示す堆積物や地形を観察しながら,さらに08-09年に信州大によって行われた大正池掘削の成果報告などを交え,まるでその時代にその場所を見ているかのような詳細な説明がなされた.東方の田代池へ移動しながら山体崩壊堆積物を観察しつつ,そこから形成された流れ山地形や扇状地に発達する湿原地帯を見学した.地質学的な情報だけでなく,様々な動植物の解説も所々で加えていただき,シンポジウムで講演された「地域に根差した,地域の人による解説が行われる」ジオパークを歩いているような気分になった.昼食前には,日本の山岳を世界に知らしめたウェストン卿を称える花崗閃緑岩でできたレリーフが世界最若の形成年代を示していることを知ったことも,この地域の地質学的な重要性を理解するうえで貴重な経験となった.
素晴らしい景色を満喫しながらの昼食の後,午後には梓川周辺を移動しながら有数の観光地である河童橋周辺で,なぜこの周辺に橋が架けられたのかという地形学的背景や河川水の供給源を解説いただいた.さらに北東へ進むと露頭の岩質が大きく変化していき,カルデラ火山地形の端に出たことが理解できた.遠くに見える山脈の形だけでも様々な情報を得ることができるのは地質屋からすれば当たり前のことであるが,山を登ることなくそれらの情報が足元や眼前に広がっており,この周辺の歴史を体感できた.それに加え,この周辺の山々,谷という谷を歩き詳細に解析されている原山先生の解説の妙により,この地域の地質学的特性だけでなく,その魅力をも満喫することができた.
本巡検は梅雨の時期にも関わらず素晴らしい晴天に恵まれ,この周辺の地質だけでなく,美しい景色と自然(や美味までも)など満喫できた.また,巡検の裏方担当として尽力された,信州大学教員や学生スタッフの皆様方にこの場をお借りし厚く御礼申し上げます.
中部支部に関するお問い合わせは,
下記中部支部事務局 須藤 斎まで.
〒464-8601 名古屋市千種区不老町
名古屋大学理学部地球惑星科学教室気付
TEL 052-789-2535,
E-mail suto.itsuki@a.mbox.nagoya-u.ac.jp
報告書等の作成に関して
報告書等の作成に関して—知っておくべきこと—
知的財産基本法が制定されそれに伴い著作物等の保護について厳格に法規制されておりますことは周知の事実でありますが,地質学会においてもコンプライアンス面からも,知的財産基本法を遵守しております.
研究成果の報告書を作成に当たり地質学雑誌等の論文を複製・転載する場合は必ず学会の許諾を取っていただく必要があります.以下に報告書等の作成に当たり必要な手続きについてお知らせいたします.
報告書等の作成に関して—知っておくべきこと—
2009年4月
日本地質学会理事会・法務委員会
1.お願い
研究成果等の報告書作成にあたり,共同研究者の論文や関連の論文を掲載する場合は,以下の通りに地質学会の許諾が必要です.販売等を目的にしない報告書を作成される場合は,論文の複製を学会側が拒否する可能性はほとんどないものと思いますが,必ず,学会から許諾を取ってください.その場合,報告書等には,「複製については**学会の許諾を得た」と記載しておく必要があります.
2.投稿中の論文査読に関連する文書について
なお,論文の公表,未公表の段階によらず,投稿論文の査読に関わる文書類は査読者の著作物に当たります(著作権法により保護されます)ので,必要な手続き無しに著者が公開する事は違法となる恐れがあります.ただし,当該団体の編集規則に査読文書類の取り扱い規定があれば,それに従うことになるものと思います.
3.論文等の著作権について(説明)
地質学雑誌掲載論文の著作権は,著者から著作権譲渡に同意してもらっていますので学会にあります.地質学会では,地質学雑誌等に掲載した論文の一部を著者自身が使うことについては許諾不要としました.ただし,論文全部をまるごと複製することには同意していませんので,全部を複製する場合は学会の許諾を必要とします.つまり,報告書等に論文をまるごと無許可で掲載すれば違法となります.
また,地質学会以外で発表した論文等で,著作権を自分が持っている場合でも(契約書に期間が定められていなければ),出版元には独占出版権が3年間あります.執筆して3年以内のものについては,特定の規定がない限り,まるごと複製,転載する場合には許諾が必要であると思われます.
参考:著作権法(昭和45年法律第48号 1971年1月1日施行 ),知的財産基本法(平成14年法律第122号 2003年3月1日施行)では以下の通りに定められています.
著作権法は,「著作物並びに実演,レコード,放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め,これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ,著作者等の権利の保護を図り,もつて文化の発展に寄与することを目的としている」ものです.
知的財産とは,知的財産基本法第二条に定義されており,以下の条文となっています(抄).
第2条 この法律で「知的財産」とは,発明,考案,植物の新品種,意匠,著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって,産業上の利用可能性があるものを含む.),商標,商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう.
2 この法律で「知的財産権」とは,特許権,実用新案権,育成者権,意匠権,著作権,商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう.
2009年度各賞受賞者
2009年度各賞受賞者 受賞理由
■日本地質学会賞(2件)
■小澤儀明賞(2件)
■柵山雅則賞(1件)
■論文賞(2件)
■研究奨励賞(2件)
■国際賞(1件)
■小藤賞(1件)
■Island Arc賞(1件)
■学会表彰(1件)
日本地質学会賞
受賞者:鳥海光弘(東京大学大学院新領域創成科学研究科・教授)
対象研究テーマ:造山帯とマントルの力学的側面の研究
鳥海光弘氏は1975年に関東山地三波川変成帯の変成岩岩石学の研究で学位を取得した.その後,一貫して,『力学が造山運動を支配した』という信念に基づき,日本,カリフォルニア,アルプスなどの変成帯の構造と変成岩の組織(形,サイズ,方向性)の解析から,造山帯が発展する過程を定量的に復元する手法の開発と解読を実践してきた.それらを列挙すると,(1)広域変成作用時の応力の定量的解析法の開発(放散虫の変形を利用した応力,応力ひずみ),(2)変成再結晶時の鉱物の移動の解析(曹長石斑状変晶と集合ざくろ石の成因),(3)太平洋型造山帯の変成鉱物ファブリックの形成機構と応力の解析である.これらの研究は,それまでの構造地質学の伝統的な手法とは異なり,地質学に粉体力学や流体力学を持ち込み,変形組織から応力やひずみを定量化して,既存の定性的な造山運動論を近代化しようとする独創的な試みであった.鳥海氏のもう一つの貢献は,実験岩石学からマントルの流動特性の定量化である.660km深度で滞留するスラブの原因を反応曲線の傾斜が負になることによる浮力の獲得だけでなく,変成再結晶作用による結晶粒の微粒化による粘性の局所的低下が滞留を促進することを実証した.更に応力計の開発や『歪み速度計』を考案した.鳥海氏が提案した計算レオロジーは,今後のマントルの研究に,物質科学分野だけでなく地球物理学分野にも大きな影響を与え,固体地球の理解に大きく貢献するだろう.
以上の研究は極めて独創的で,造山帯の力学とマントルダイナミクスを理解する上で,極めて重要な貢献をしたと思われる.そして鳥海氏は,これらの分野で欧米の主要な国際雑誌17誌に,1978年から2008年までに合計44論文を発表した.地質学雑誌などに投稿した論文(和文,英文)を併せると75論文が発表されている.
これらの研究に加えて,鳥海氏は岩波書店発行の地球惑星科学教科書シリーズを通じて編集者として, 地球科学の体系化に貢献するとともに,著作,総説などで積極的に地球科学の普及にも努めた.更に,鳥海氏は地質学雑誌の編集委員を5年にわたって務め,1995-1997年には編集委員長を務め,地質学会の発展にも貢献した.
以上の業績を踏まえ,鳥海光弘氏を地質学会賞に強く推薦したい.
受賞者:石渡 明(東北大学 東北アジア研究センター・教授)
対象研究テーマ:オフィオライトと東北アジアの地質学的研究
石渡 明氏は,卓抜した地質調査センスと岩石学分野の知識を融合させた研究により,特に「オフィオライト」をキーワードとして,日本列島を含む東アジアのテクトニクスの解明に多大な貢献をしている.夜久野岩類の研究では,火成岩・変成岩岩石学的手法を導入し,それらがペルム紀の島弧とホットスポットにともなう縁海盆に由来する異常に厚い海洋地殻の断片であることを明らかにした.これは,本邦に産するオフィオライトの系統的な研究の先駆けとなった.さらに,同氏は,アルプスやロシア極東域など,世界に産する主要なオフィオライトおよびそれに関連する変成岩や火成岩の研究を続け,総説を含めて多くの研究成果を公表するとともに,第29回万国地質学会議 (IGC) 京都大会でオフィオライト・シンポジウムを主催した.また,深海底掘削計画の立案や実施にも積極的に参加し,統合国際深海掘削計画(IODP)科学立案評価パネル(SSEP)共同議長を務めるなど,国内外の関連分野の進展に重要な役割を果たしている.氏が代表者となり現在も継続しているロシア極東域の日露共同調査の成果は,同地域と西南日本の地質構造の連続性を明らかにし,環太平洋顕生代多重オフィオライト帯の提唱に結実した.また,中国蘇魯—大別山超高圧変成帯の日中共同研究では,特に超高圧変成帯にともなう超苦鉄質岩の産状や岩石学的特徴に関していくつもの重要な知見を報告すると同時に,日本列島の基盤の形成には中生代初期におこった中朝地塊と揚子地塊の衝突型造山運動が深く関わっていたとするモデルを提唱している.また,火山岩類に関しても,グリーンタフ火山岩類の特徴を地質学的,岩石学的,地球化学的に再検討したことや,美濃—丹波帯からプルーム活動に関連したペルム紀海台由来の緑色岩類を報告するなど,多くの重要な研究を行っている.
同氏は,学会や個人のHPを通じて寄せられる地球科学関連の質問への回答,オフィオライト関連データベース「AILIS」および「偏光顕微鏡による主要造岩鉱物の簡易鑑定表」の公表や,調査グループを組織して行った平成19年能登半島地震の調査など,地球科学の教育・普及にとって,そして社会的にも重要な多くの活動を続けている.また,2期4年間,編集長としてIsland Arcの国際化に尽力するとともに,現在は同編集顧問,日本地質学会理事を努め,学会の発展にも多大なる貢献をしている.
以上のように,石渡明氏は地質学分野の研究をはじめとする多方面にわたり,多くの重要な功績・実績・貢献があり,日本地質学会賞に相応しい候補者として推薦します.
日本地質学会国際賞
受賞者:太田昌秀(元 ノルウエー極地研究所)
対象研究テーマ:極域の地質学
太田昌秀博士は,1972年以来ノルウェー極地研究所の主席研究員として,スバールバル諸島やロシア〜カナダにかけて北極圏の地質研究を主導し,多くの著作や地質図を発表された.特にスバールバル諸島の古生代前期〜先カンブリア時代後期(Grenvilliann)の変動とその年代の解明に貢献され,高圧変成岩類がカレドニア造山運動の前期サブダクション期にあたることを明らかにし,プレ−トテクトニクスの開始時期に関する重要なデータとして注目を集めた.またノルウェー政府派遣の交換科学者として日本の南極観測隊でも活躍され,北半球の夏は北極,冬は南極と,両極の地質研究を精力的に展開された.1980年代以降の日本人地質家によるスバールバル諸島の研究や,同諸島ニーオルスン国際科学村に日本が観測基地を設けることは,博士の助言や尽力なくしては困難であった.さらに日本のみならず,英米独仏露南ア・スウェーデン・ポーランドなどとの共同研究を通じて極域の地質学の発展と国際交流に大きな役割を果たされた.
太田博士は,1933年長野県に生まれ,1962年北海道大学大学院博士課程修了後1972年まで同大学理学部に勤務された.若き日の博士は,飛騨変成帯や隠岐島後を研究対象とし,1959〜63年にかけ多数の論文を発表された.また光学的手法により長石が互いに癒合しながら斑状変晶を形成する過程を解明したり,ザクロ石斑状変晶の立体構造を解析する方法を開発するなど,独創的な研究をされた.博士は,1969-70年に北海道大学ヒマラヤ学術調査隊副隊長としてネパールの調査を行い,ヒマラヤの地質学にも大きな功績を残された.それまでの探検的調査の域から出て,科学的成果として「Geology of the Nepal Himalayas」というモノグラフに集大成されたのは博士の手腕によるところであり,同調査グループとともに1973年度秩父宮記念学術賞を受賞された.
太田博士は,常々科学者の視野の狭さを戒められた.ナンセンの大部の著書「フラム号」を翻訳されたのは,そうした思いからと思われる.北極圏は,冷戦時代には軍事的に,現在は地球環境問題や資源開発に,重要な地域である.博士は,1992-99年に日露ノルウェーの北極海航路プロジェクト委員としても貢献され,2006年にノルウェー極地研究所を退職された今もオスロにあって,極域の科学の普及と国際交流に努められている.これらの功績をたたえて国際賞に推薦する.
日本地質学会Island Arc賞
受賞論文: Bortolotti, V. and Principi, G.,2005,Tethyan ophiolites and Pangea break-up
Island Arc, 14, 442-470.
This paper provides a masterful tectonic-petrologic-geochemical synthesis of the rifting and dispersion of Pangea based on the newly generated Tethyan oceanic crust now preserved in the Alpine mountain belts. It compiles Triassic to middle Jurassic ophiolitic bodies in the Tethyan and Caribbean regions in detail and proposes that the breakup of Pangea and the development of the Tethyan ophiolites progressed from east (Middle-Late Triassic) to west (Late Jurassic-Early Cretaceous). It presents the role of ophiolites in the elucidation of the timing and mechanisms of the breakup of Pangea as well as the development of Tethyan basins throughout the Mesozoic.
Based on the Thomson Science Index for the year 2007, this paper had the greatest number of citations of the candidate Island Arc papers published in 2005-2006. The first author has long worked in the fields of regional geology and geodynamics of the Northern Apennines and the peri-Mediterranean chains. He has energetically studied the stratigraphy, tectonics, and geodynamic evolution of the internal areas of these orogenic chains, in particular the successions pertaining to the Tethyan Ocean. He has published many articles on regional geology concerning the ophiolitic successions from Cyprus, the Pontic Ranges, Hellenides, Albanides, Dinarides, Romanian Apuseni, and Northern Apennines and has made great contributions in this field. We believe that this paper will contribute to future research on the geologic and geodynamic evolution of the Eurasia-Pacific region. In view of the scientific impact of the paper and the international scientific activity of the first author, the Judge Panel recommends this paper for the 2009 Island Arc Award.
日本地質学小澤儀明賞
受賞者:小宮 剛(東京工業大学大学院理工学研究科地球惑星科学専攻)
対象研究テーマ:先カンブリア時代のテクトニクスと地球史の解読
小宮 剛氏は地球史解読の研究において顕著な業績をあげてきた.氏の研究は野外地質学を根幹とし,火成岩・変成岩岩石学や同位体地球化学的手法を駆使して,地球史全体に及ぶ長時間スケールの中でのテクトニクス様式の変遷,マントルおよび核の進化プロセス,さらには地球表層環境の進化の解明を試みている.これまでに氏が国内外の共同研究者達と明らかにした多くの成果は国内外において高く評価されている.
氏が中心となって進めた研究の中でも特に世界的に大いに注目されている業績として,地球におけるプレートテクトニクスの開始時期を限定したグリーンランド,イスア地域の研究がある.日本で1980年代に確立された付加体地質学の視点と手法を用いて,従来受動的大陸縁の堆積岩とみなされていた約38億年前のイスア表成岩体について詳しい野外調査と岩石学的分析を行った結果,海洋プレート層序やデュープレックス構造を認定し,その地質体が実は世界最古の付加体であることを解明した.これは,現在とほぼ同様なプレートテクトニクスが,誕生して約8億年たった初期地球において既に機能していたことを世界で初めて示した画期的な研究成果である.イスア地域からは,世界最古の生命の存在を示すデータが報告されており,氏の研究成果は世界の地質学界に大きな衝撃を与えた.先カンブリア時代の岩石・地層を産しない日本で育った地質学者が,初期地球テクトニクスの研究でこのような学問的貢献をした例はこれまでになかった.さらに小宮氏はグリーンランドの岩石試料の他に,西オーストラリアやアフリカ南部の試料についても同時に詳しく化学分析し,太古代から原生代にかけてマントルの温度の経年変化を調べた.その結果,マントルの温度が段階的に低下したことを具体的に示した.最近では研究対象をさらに広げ,地球表層で形成された種々の堆積岩についても多様な同位体地球化学的分析を行い,過去の大気・海洋中の酸素濃度変化の推定を試みており,今後得られる成果に大きな期待が寄せられている.小宮氏はこれまでに42編の学術論文(査読のある国際誌31編,著書2編うち筆頭著者分9編;国内誌9編,うち筆頭5編)を公表した.被引用回数は300回に達しつつあり,現在も急増中である.
以上のように小宮 剛氏の業績は,特にその質の高さで群を抜いており,日本地質学会小澤儀明賞に値する.
受賞者:須藤 斎(名古屋大学環境学研究科地球環境科学専攻)
対象研究テーマ:珪藻化石生層序を用いた地質学的および古海洋学的研究
須藤 斎氏は,大学院以来一貫して珪藻化石生層序学と海洋環境変遷の研究に取り組んできた.その研究は大きく分けて,「野外地質調査に基づく珪藻化石生層序を用いた新生界の地質学的研究」と「海生珪藻キートケロス属の休眠胞子化石生層序を用いた古海洋学的研究」に分けられる.
前者に関しては,同氏は関東から常磐地域の陸上新第三系に対して珪藻化石生層序に基づく詳細な年代層序を確立し,堆積相と珪藻化石群集の変化から中部日本の新第三紀の海洋古気候変遷を明らかにした.また,産業技術総合研究所が実施している地震動予測のための平野地下構造解明の研究にも参画し,関東・新潟および常磐地域の新第三系の地下構造の解明に貢献している.後者に関しては,三陸沖,ノルウェー沖,アフリカ南西沖の深海コア,日本各地・カリフォルニアの陸上セクションを用いて,光学・走査型電子顕微鏡による形態観察と層序学的分析を行い,キートケロス属休眠胞子化石13属85種(9新属69新種を含む)の詳しい記載を行い,世界で初めて休眠胞子化石の分類体系を確立し,4,000万年前から現在に至るグローバルな時空分布と進化史を解明した.この研究によって3,370万年前にキートケロス属が短期間に種数と産出量を爆発的に増加させ,その時代まで主要な海洋一次生産者であった渦鞭毛藻類からキートケロス属を中心とする珪藻類に置き換わるという大生物イベントがあったという新事実を明らかにした.このイベントは,南極大陸に初めて本格的な氷床が発達し温室地球から氷室地球へと変化した急激な寒冷化イベントと一致し,さらに,珪藻を食べる甲殻類等を餌とするヒゲクジラ類が大量に分化していることから,海洋生態ピラミッドの上位の生物群に対しても,甚大な影響を与えた可能性を示唆している.このような成果により同氏は,統合国際深海掘削計画(IODP)の第302次航海の珪藻化石担当乗船研究員に抜擢され,世界初の北極海深海底掘削(ACEX)の研究ミッション遂行に貢献した.その成果はNatureにいち早く発表され,古海洋学に大きなインパクトを与えており,珪藻休眠胞子化石の分類を礎とする同氏のユニークな古海洋学的研究は,今後もさらなる発展が期待される.
以上の理由により,須藤 斎氏を小澤儀明賞候補者として相応しいと判断し,ここに推薦する.
日本地質学会柵山雅則賞
受賞者:水上知行(金沢大学 理工学域自然システム学類地球学コース)
対象研究テーマ:マントル構造岩石学
「国内初天然ダイヤモンドの発見」はNHK全国ニュースなど多くのマスメディアに取り上げられ,発見者である水上知行君は一気に脚光を浴びることになった.ダイヤモンドの発見は,前弧地域におけるマントル流動を見直すきっかけとなり,画期的な研究成果である.今回の発見の背景に,今までの水上知行君のマントル岩石に関する高度な知識と幅広い研究成果の蓄積が必要不可欠であった.その特筆すべき例として,2004年「Nature誌」に出版されたカンラン石のLPOに関する発表が挙げられる.この論文は,カンラン石の<a>軸がマントル流動方向に対して垂直に配列し,かつ3軸集中するいわゆる「B-type」のLPOを天然試料から世界で初めて記載したもので,そのLPO形成と沈み込みプロセスとの関係を明確に示した.マントルの主要鉱物であるカンラン石のLPOは,マントルの物性に強い影響を与えており,マントルの地震学的異方性とマントル流動の関係を明らかにするための重要な情報である.同君は,この研究成果についてアメリカ地球物理連合及び日本地球惑星科学連合大会で招待講演を行っている.また,水上知行君は四国・三波川変成帯の高変成度部に位置する東赤石超塩基性岩体の研究にも取り組んできた.険峻な山岳地帯にもかかわらず,同地域の綿密な野外調査を行い,構造地質学的・岩石学的手法を組み合わせることにより,単調な岩相からなる東赤石岩体が記録している複雑な変形・圧力・温度履歴を見事に読み解いた.その結果,東赤石岩体は100キロ以深に由来し,沈み込み帯−ウェッジマントル系の様々な情報を保持している可能性が高いことが明らかとなった.このような岩体は世界でも非常にまれで貴重なものであり,現在では国内外で多くの研究者の注目を集めている.さらに,水上知行君は高圧実験及びラマン分光法を研究に取り入れ,既に両分野で優秀な業績を挙げている.
以上のように,水上知行君は,マントル岩石の地質学的な履歴を究明するために,様々な研究手法を融合した独自の研究スタイルを築いてきた.また,確度の高いデータにもとづいた慎重な議論を行い,確実な研究成果を上げる貴重な研究者でもあり,同君は今後も地質学的分野の研究に大きく貢献できるものと確信される.よって,水上知行君を,日本地質学会の柵山賞の候補者として強く推薦する.
日本地質学会論文賞
受賞論文:高橋雅紀,2006,日本海拡大時の東北日本と西南日本の境界.
地質学雑誌,第112巻,第1号,p.14-32.
我が国の地帯構造とその発達史の研究では,新第三系と中古生界の研究者のあいだの議論がこれまで活発ではなかった.中古生界の地体構造は古第三紀までに大略完成し,新第三紀になると,日本海拡大時にブロック化して多少の相対運動をしたにすぎないと思われていたわけである.高橋氏はこの論文で,著者自身を含む多くの研究者によって蓄積されたデータを使って,そうした見方にたいして説得力のある反論を展開した.それによって,例えば中央構造線がどこに連続するかというような,日本列島の地帯構造論の重要問題を解くために,新第三紀なかんずく中新世前半のテクトニクスの理解が不可欠であることを示した.このことは,我が国の地質構造発達史の研究のありかたに,変更をせまるものである.以上の理由により本論文を,日本地質学会論文賞を受けるにふさわしい論文として推薦する.
受賞論文:守屋俊治・鎮西清高・中嶋 健・壇原 徹, 2008,山形県新庄盆地西縁部の鮮新世古地理の変遷−出羽丘陵の隆起時期と隆起過程−.
地質学雑誌,第114巻,第8号,p.389-404.
本論文は,出羽丘陵新庄盆地西縁部に分布する鮮新世の地層群について,堆積学的手法を用いてその隆起史を明らかにしたものである.筆者らは,これまで未解決であった出羽丘陵の形成史について,詳細な地質調査に基づき層序の見直しを行い,堆積学的解析により16の堆積相とそれらの組合せによる6つの堆積組相に区分し,その堆積環境の推定を行った.また複数見られる海進・海退サイクルを基準に同時間面を認定し,堆積シーケンスに区分し,堆積組相の分布パターン・古流向解析・等層厚線図をもとに,堆積時の古地理を復元した.その上で,出羽丘陵の隆起過程と隆起時期について,地層群中に含まれる凝灰岩のフィッショントラック年代値と合わせて議論している.このように,本論文は基本的な堆積学的解析手法を駆使して,古地理変遷・構造発達史の解明と堆積盆解析を実施した例として堆積学の模範となる論文である.よって,論文賞に値するものと考えられる.
日本地質学会小藤賞
受賞論文:嶋田智恵子・佐藤時幸・工藤美幸・山崎 誠,2008,IODP, Exp. 303航海で得られた北大西洋の中部第四系から産出した絶滅珪藻種Neodenticula kamtschaticaの意義.
地質学雑誌,第114巻,第1号,p.47-50.
第三紀末に絶滅した1つの珪藻種が北大西洋の中部第四系から産出するという興味深い事実を報告し,その原因を考察した短報である.この珪藻化石は再堆積であるとしても,この珪藻種は大西洋では未報告とのことで,ベーリング海峡成立以後,パナマ陸橋成立以前の太平洋と大西洋のつながりを示す重要な資料であり,これについての考察は非常に面白い.この論文はグローバルな重要性を持つ事実をタイムリーに報告し,その意義を明確に論じた短報として,十分に小藤賞に値する.
日本地質学会研究奨励賞
受賞者:石井英一(日本原子力研究開発機構)
受賞論文:石井英一・中川光弘・齋藤 宏・山本明彦, 2008, 北海道中央部,更新世の十勝三股カルデラの提唱と関連火砕流堆積物:大規模火砕流堆積物と給源カルデラの対比例として. 地質学雑誌,第114巻,第7号,no.2,p.348-365.
上記論文は,北海道中央部十勝三股地域周辺に分布する給源不明の火砕流堆積物群において,分布・累重様式・層相解析・年代測定・全岩および鉱物化学組成等を調べ,これらが一連の火砕噴火で生じたことを明らかにした論文である.さらに,このデータを基に地球物理学的データとの比較・検討を行い,同火砕流堆積物が十勝三股盆地を給源とすることをつきとめ,その盆地がカルデラであることを実証した.この研究は,主著者自らが行った堆積物の露頭観察・分析に基づいている点や,長い間不明だった 1Ma頃の大規模火砕噴火の復元に成功した点で,火山地質学を研究する醍醐味を体現しており,大変に魅力的な論文である.主著者である石井英一さんは,対象期間内に火山学のみならず地下水理特性など幅広い内容の論文を多数発表しており(主著3・副著 2),その活躍は火山学の枠に留まらず,今後の活躍が大いに期待される若手研究者である.よって, 本論文は研究奨励賞に十分に値すると考えられる.
受賞者:坂口真澄(高知大学)
受賞論文:Masumi Sakaguchi and Hideo Ishizuka,2008,Subdivision of the Sanbagawa pumpellyite-actinolite facies region in central Shikoku, southwest Japan. Island Arc, vol. 17, no. 3, 305-321.
この論文は四国中央部の三波川変成帯低温部(パンペリー石・アクチノ閃石相)における詳細な鉱物組合せ・鉱物化学組成の検討から,別子ユニットと大歩危ユニットとの間の「ナップ境界」に変成温度のギャップはなく連続的であることを明らかにした力作である.地質学において,岩石の性質が空間的にある方向へ連続して変化するということを自前の十分なデータによって証明するのは忍耐を要する困難な仕事であり,特に変成温度の低い変成岩については尚更である.これは多数のNa輝石の発見につながり,それによってミカブ帯の変成作用との連続性も明らかになった.この研究結果は三波川帯低温部の変成作用がナップ形成の後に行われた可能性を示唆し,今後の三波川帯研究へのインパクトも大きい.困難な研究に敢えて挑戦し,重要な結果を導き出したこの論文は研究奨励賞に値する.
日本地質学会表彰
受賞者:秋吉台科学博物館(代表:館長 池田 善文)
表彰業績:秋吉台研究に関する調査研究・教育普及活動
秋吉台科学博物館は,山口県美祢郡秋芳町立博物館(現在は美祢市立)として,「秋吉台の自然保護」と「学術研究の発展」を目的として, 1959年10月1日に設立された.その後,増・改築を行い,現在は展示室・講座室・研究室・資料室・レクチャールームを持つ,秋吉台の自然の研究拠点として活動を続けている.
秋吉台科学博物館では,資料収集保存・調査研究・教育普及・展示を基本として様々な活動に取り組み,特に調査研究活動と外部研究者への研究支援について,設立以来,一貫して継続されてきた.昭和30年代後半の秋芳洞精密測量,秋芳洞潜水調査に始まり,その後も鍾乳洞群の学術調査,学術ボーリング調査,地下水調査など,多くの学術調査が外部団体との連携のもと実施された.これら一連の調査研究により秋吉台研究は大幅に進展し,特に帰り水を中心にした秋吉台の地質研究に新しい一頁が開かれると共に,フズリナ生層序学,古生代後期の礁形成史等の知見が飛躍的に増大した.また近年では,自然観察会を定期的に開催すると共に,児童・生徒ならびに地域住民を対象に,秋吉台の自然に関する体験学習などの教育普及活動に尽力してきている.
秋吉台科学博物館において特筆すべきことは,町立のために財政的に苦しい中,これまで入館料を徴収することなく,多くの来訪者・研究者に対し,限られた学芸員で献身的に研究支援・教育普及活動を続けてきたところにある.この1〜2年においても,年間1万人にのぼる修学旅行・見学団体に対し,講演・化石採集・見学会などの対応を行い,多い日には5〜6校の児童・生徒に,秋吉台と地質学の面白さ・素晴らしさを伝えてきている.学術研究においても多忙な館運営の中,研究成果は昭和36年創刊以降,継続的に発行されている「秋吉台科学博物館報告」により公表されると共に,調査報告書やパンフレットなどの普及本の形で広く社会に還元されてきている.さらに外部研究者の調査基地として様々な形で研究支援を行い,これまでに多くの優秀な地質研究者をサポートしてきた.
このような秋吉台科学博物館の秋吉台研究を通じてなされた我が国地質学発展に対する多大な貢献は,日本地質学会表彰に値するものと考え,ここに推薦する次第である.
Geo暦(2010)
2010年Geo暦(行事カレンダー)
2007年版 2008年版 2009年版 --- 2011年版
2010年版 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
○印は学会主催行事.(共)学会共催・(後)後援・(協)協賛
1月January
(後)北淡国際活断層シンポジウム2010開催案内
1月17日--21日
会場 兵庫県淡路市・北淡震災記念公園セミナーハウス
http://home.hiroshima-u.ac.jp/kojiok/hokudan2010.html
(共)公開シンポジウム「人類の時代・第四紀は残った」
主催: 日本学術会議地球惑星科学委員会IUGS分科会・日本学術会議地球惑星科学委員会INQUA分科会
共催:日本地球惑星科学連合・日本地質学会・日本第四紀学会(予定)
1月22日(金) 10:00-17:15
場 所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木7-22-34)
詳しくは,こちら
第55回日本水環境学会セミナー
1月22日(金)
場所 自動車会館 大会議室
http://www.jswe.or.jp/index.html
日本古生物学会第159回例会
1月29日(金)〜31日(日)
会場:滋賀県立琵琶湖博物館
http://wwwsoc.nii.ac.jp/psj5/
2月February
◯第158回西日本支部例会および2009年度支部総会
2月13日(土)
会場:福岡大学18号館1824教室
詳しくは、こちら
◯関東支部ジオサイト観察会「長瀞の岩畳」
2月13日(土)10:30-12:00(雨天決行)
集合:秩父鉄道長瀞駅 10:30
申込締切:2月6日(土)
http://kanto.geosociety.jp/
◯関東支部ジオパーク講演会
2月13日(土)13:00-16:00(雨天決行)
会場:埼玉県立自然の博物館 2階講堂
申込締切:2月6日(土)
http://kanto.geosociety.jp/
3月March
◯関東支部秩父ジオサイトバスツアー
3月6日(土)9:00-16:00(雨天決行)
集合:西武秩父線 西武秩父駅前
申込締切:2月24日(水)
http://kanto.geosociety.jp/
◯北海道支部総会・個人講演会
3月20日(土)13:30-17:30
場所:北海道大学理学部6号館 6-204-02教室
申込締切:2月12日
詳しくは、こちら
日本堆積学会2010年茨城大会
3月26日(金)〜 29日(月)
会場:茨城大学水戸キャンパス茨苑会館
http://sediment.jp/
(協)第2回日本地学オリンピック大会
(兼 2010年第4回国際地学オリンピック・インドネシア大会日本代表選抜)
3月24日〜26日
会場:茨城県つくば市
募集締切:2009年11月30日(月)
http://jeso.jp/
(協)国際惑星地球年終了記念イベント
「惑星地球フォルム2010 in アキバー君たちと考える環境・防災・資源」
3月27日(土)〜28日(日)
場所:富士ソフトアキバプラザ6階(東京都千代田区)
http://www.gsj.jp/iype/
*第1回惑星地球フォトコンテスト表彰式ほか
日本地理学会2010年春季学術大会
3月27日(土)〜3月29日(月)
会場:法政大学
http://www.ajg.or.jp/
4月April
◯関東支部 地質技術伝承講演会・支部総会
4月18日(日)13:30-16:00(雨天決行)
会場:北とぴあ(北区王子)
http://kanto.geosociety.jp/
◯北海道支部:「地質の日」・「国際博物館の日」記念展示:
北海道大学総合博物館企画展示「わが街の文化遺 産 札幌軟石」
4月27日(火)〜5月30日(日)10:00〜16:00
会場:北海道大学総合博物館1階「地の統合」 コーナー
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
5月May
◯日本地質学会:本部イベント企画
写真家 白尾元理 講演会「地球史46億年を撮る」
5月8日(土)13:30〜15:30
場所:東京大学小柴ホール(東京都文京区本郷)
http://www.geosociety.jp/name/content0059.html
◯近畿支部:「地質の日」協賛行事
第27回地球科学講演会「大阪の温泉は本当に温泉か?−大阪平野の地下水を可視化する−」
5月9日(日)14:30-16:30
場所:大阪市立自然史博物館講堂(大阪市東住吉区長居公園1-23)
◯西日本支部:後援「地質の日」企画
身近に知る「くまもと の大地」
5月9日(日)「地質の日」 10:00〜16:00
場所:熊本市通町筋上通り入り口 びぷれす広場(熊日ビ ル)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
火山灰編年・火山活動・人間活動に関する国際野外集会およびワークショップ
「アクティブテフラ九州2010」
5月9日(日)〜17日(月)
会場:鹿児島県霧島市霧島市役所および九州内での野外巡検
http://www.ris.ac.jp/intav-jp/index.html
◯中部支部:「地質の日」記念
サイエンスフェステイバル in 五十嵐キャンパス(新潟大学)
5月16日(日)12:00~15:00
場所:新潟大学理学部
(協)日本地球惑星科学連合2010年大会
5月23日(日)〜28日(金)
会場:幕張メッセ国際会議場
http://www.jpgu.org/
◯日本地質学会第117年総会/一般社団法人第2回総会
5月23日(日)18:00〜
会場:幕張メッセ 国際会議場 304会議室
(共)原子力総合シンポジウム
原子力平和利用技術が目指すもの〜国際動向を踏まえた現状と将来像〜
5月26日(水),27日(木)
会場:日本学術会議講堂(東京都港区六本木7-22-34)
http://www.aesj.or.jp
日本地下水学会2010年春季講演会
5月29日(土)
会場:慶應義塾大学矢上キャンパス(横浜市港北区日吉)
http://homepage2.nifty.com/jagh_gyouji/
6月June
ECOLIFE FAIR 2010
6月5日(土)〜6日(日)
場所:代々木公園(東京都渋谷区)
http://ecolife2010.com/
◯関東支部 2回地質技術伝承講習会
:地質技師長が語る地質工学余話「共生型地下水利用に向けての「育水」の提唱」
6月6日(日)14:00〜16:30
場所:北とぴあ(東京都北区王子1-11-1) 飛鳥ホール
http://kanto.geosociety.jp/
石油技術協会第75回定時総会
特別講演会・平成22年度春季講演および見学会
6月8日(火)〜11日(金)
場所:福岡市福岡国際会議場(博多区石城町2-1)
http://www.japt.org/
(後)(地学)教育シンポジウム
「学校教育で地学は生き残れるか?:学会と教育現場との連携に向けて」
6月19日(土) 13:00〜18:00
場所:早稲田大学22号館202教室(東京都新宿区西早稲田1-7-14)
問い合わせ先:
日本第四紀学会企画担当幹事,産業技術総合研究所 植木岳雪 gakusetsu-ueki@aist.go.jp
地質学史懇話会
6月20日(日)13:30-17:00
会場:文京区シビックセンター4Fシルバーセンター内会議室A
・加藤碵一「宮澤賢治論の地的背景」
・菊池真一「水路図の歴史」
GEOINFORUM-2010 第21回日本情報地質学会総会・講演会
6月22日(火)〜23日(水)
会場:産総研臨海副都心センター バイオ・IT融合研究棟11階会議室
http://www.jsgi.org/
資源地質学会第60回年会シンポジウム
「リチウム・トリウム -資源とその利用-」
6月23日(水)10:55-17:00
場所:東京大学小柴ホール(本郷キャンパス)
http://www.kt.rim.or.jp/~srg/
7月July
(共)第47回アイソトープ・放射線 研究発表会発表論文募集
7月7日(水)〜9日(金)
会場:日本科学未来館(江東区青海2丁目41番)
http://www.jrias.or.jp/index.cfm/1,html
(後)「青少年のための科学の祭典」2010全国大会
7月31日(土)〜8月1日(日)
場所 科学技術館(東京都千代田区北の丸公園)
http://www.kagakunosaiten.jp/index.php
8月August
堆積学スクール2010 「未固結変形構造と脱水構造」
8月9日(月)〜12日(木)
会場:民宿さかや(大多喜町葛藤143番地)
http://sediment.jp/04nennkai/2010/school.html
第12回国際熱年代学会議(Thermo2010)
8月16日(月)〜20日(金)
会場:スコットランド・グラスゴー大学
http://www.ges.gla.ac.uk/Thermo2010
(後)日本ジオパーク糸魚川大会
8月22日(日)〜23日(月)
会場 糸魚川市民会館(新潟県糸魚川市一ノ宮)
http://geo-itoigawa.com/taikai/index.html
◯韓日地質学会室戸合同大会
8月23日〜25日
会場:国立室戸青少年自然の家
http://struct.geosociety.jp/koreajapangs2010/
第19回日本水環境学会市民セミナー
「食料と水−私たちが生きていくために−」
8月27日(金)
東京会場:地球環境カレッジホール(東京都世田谷区駒沢)
大阪会場:いであ(株)大阪支社 ホール(大阪市住之江区南港北)
http://www.jswe.or.jp/
9月September
(共)第54 回 粘土科学討論会
9 月6 日(月)〜 8 日(水)
会場:名古屋大学 IB 電子情報館
http://wwwsoc.nii.ac.jp/cssj2/
(共)2010年度日本地球化学会年会
9月7日(火)〜9日(木)
会場:立正大学熊谷校舎(埼玉県熊谷市)
http://www.geochem.jp/index.html
朝日地球環境フォーラム2010
9月13日(月)〜14日(火)
場所:ホテルオークラ(東京都港区虎ノ門2-10-4)
http://www.asahi.com/eco/sympo2010/
(共)第19回地質汚染調査浄化シンポジウム
9月16日(木)13:00-18:30
場所:富山国際会議場大手町フォーラム 多目的会議室203号
詳しくはこちら
第60回東レ科学講演会
9月17日(金)17:00-20:00
会場:有楽町朝日ホール(千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン11階)
◯日本地質学会第117年学術大会(富山大会)
9月18日(土)〜20日(月)
会場:富山大学ほか
講演申込締切:7/7(水)
参加申込締切:9/3(金)
詳しくは大会HP
http://www.geosociety.jp/toyama/content0001.html
日本鉱物科学会2010年年会・総会
9月23日(木)〜25日(土)
会場:島根大学
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jams3/
第128回深田研談話会
9月24日(金)15:00-17:00
会場:財団法人深田地質研究所 研修ホール
http://www.fgi.or.jp/FGIhomepage/index-j.html
10月October
IGCP507(白亜紀のアジア古気候)第5回国際シンポジウム(インドネシア)
10月7日(木)〜9日(土)
場所:ヨグヤカルタ市(発表)/ジャワ島中部Luk Uloのテクトニックメランジェ(巡検)
不明な点は国内コーディネーター(金沢大・長谷川卓)まで.
http://igcp507.grdc.esdm.go.id/
地球システム・地球進化 秋の学校 in 関西
10月9日(土)
場所:大阪大学豊中キャンパス理学部D501教室
http://quartz.ess.sci.osaka-u.ac.jp/~earth21/school/gakkou/gakkou.html
(協)2010 土壌・地下水環境展
10月13日(水)〜10月15日(金)
会場:東京ビッグサイト(東京国際展示場)
http://www.nikkan.co.jp/eve/dojyo/index.html
産総研オープンラボ
10月14日(木)〜10月15日(金)
場所:産総研つくば
http://www.aist-openlab.jp/
(協) Techno-Ocean 2010
10月14日(木)から16日(土)
会場:神戸国際展示場 (神戸・ポートアイランド)
http://www.techno-ocean2010.com/
日本の活断層・フォトコンテスト(締切)
10月15日(金)
受付:日本活断層学会事務局・活断層フォトコンテスト係
http://danso.env.nagoya-u.ac.jp/jsafr/fotocontest01.html
深田研一般公開
10月16日(土)
場所:深田地質研究所(文京区本駒込2-13-12)
http://www.fgi.or.jp/
日本応用地質学会平成22 年度研究発表会
10 月21日(木)〜22日(金)
会場:島根県民会館松江市
申込締切:5 月28 日(金)
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jseg/
石油技術協会主催 平成22年度秋季講演会
「資源探求フロンティア新しいエネルギー資源を求め続けて」
10月27日(水)10:30〜17:20
場所:東京大学本郷キャンパス小柴ホール(文京区本郷7-3-1)
http://www.japt.org/
11月November
東京大学大気海洋研究所柏地区研究集会
南海トラフ海溝型巨大地震の新しい描像 − 大局的構造と海底面変動の理解
11月1日(月)〜2日(火)
会場:東京大学大気海洋研究所
http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/
(協)第36回リモートセンシングシンポジウム
11月4日(木)から5日(金)
会場:防衛大学校
http://www.sice.or.jp/~rs/
第129回深田研談話会(高知)
ジオ鉄ー自然を楽しむ鉄道旅行のススメ
11月5日(金)18:00-20:00
会場:高知市文化プラザかるぽーと2階小ホール(高知市九反田2-1)
http://www.fgi.or.jp/FGIhomepage/index-j.html
第130回深田研談話会(現地・四国)
ジオ鉄ー自然を楽しむ鉄道旅行(土讃線)
11月6日(土) / 申込締切10月12日(火)
場所:高知駅集合
http://www.fgi.or.jp/FGIhomepage/index-j.html
第11回こどものためのジオ・カーニバル
11月6日(土)から7日(日)10:00-16:00
会場:大阪市立科学館
http://geoca.org/
東海地震防災セミナー2010
11 月11日(木)
会場:静岡商工会議所静岡事務所5階ホール(JR静岡駅北口西側)
日本・アイスランド地熱エネルギーフォーラム2010
11 月16日(水)9:00-17:10/レセプション 17:30-19:00
会場:国連大学3F ウ・タントホール(渋谷区神宮前5-53-70)
http://www.japanicelandgeothermal.com/jap/index.html
JSTシンポジウム
グリーン・イノベーションと社会実験
11 月17日(水)13:00-17:30
会場:江戸東京博物館ホール(墨田区横綱1-4-1)
http://www.jst.go.jp/pr/sjsympo2010.html
第19回東北大学素材工学研究懇談会
マグネシウム合金の現状と新しいアプローチ
11 月17日(水)〜18日(木)
会場:東北大学さくらホール(仙台市青葉区片平2-1-1)
http://www.tagen.tohoku.ac.jp/
◯第4回関東支部研究発表会:日本地質学会関東支部2010年秋季シンポジウム
テーマ:関東平野の地下地質構造 と形成史
場所:日本大学文理学部3号館5階
日程:11月20日(土)〜21日(日)
http://kanto.geosociety.jp/
◯2010年度近畿支部総会・シンポジウム
「中央構造線の発生と改変:白亜紀から新第三紀にかけて」
11月20日(土)
場所:神戸大学滝川記念学術交流会館
問い合わせ先:近畿支部幹事 三田村宗樹 mitamrm@sci.osaka-cu.ac.jp
海洋調査技術学会第22回研究成果発表会
11 月25日(木)〜26日(金)
会場:海上保安庁海洋情報部7階大会議室(中央区築地5-3-1)
http://www.soc.nii.ac.jp/jsmst/
平成22年度自然史学会連合講演会
東北の豊かな自然
11 月28日(日)
会場:岩手県立博物館(盛岡市上田字松屋敷34)
http://www.pref.iwate.jp/~hp0910/
12月December
平成22年度国土技術政策総合研究所講演会
12月1日(木)10:00〜17:00
場所:日本教育会館一ツ橋ホール(千代田区一ツ橋2-6-2)
http://www.nilim.go.jp/
第10回東北大学多元物質科学研究所研究発表会
12月1日(木)9:00〜20:00
場所:東北大学片平さくらホール
http://www.tagen.tohoku.ac.jp/general/info/event/meeting/2010/
(協)第26回ゼオライト研究発表会
12月2日(木)〜3日(金)
会場:タワーホール船堀(東京都江戸川区 http://www.towerhall.jp/)
http://www.jaz-online.org/
国立情報学研究所 国立大学図書館協会 共催シンポジウム
大学からの研究成果オープンアクセス化方針を考える
12月10日(金)10:00〜17:00
場所:東京大学 鉄門記念講堂(文京区本郷7-3-1 医学部教育研究棟14階)
http://www.nii.ac.jp/sparc/event/2010/20101210.html/
化学物質のリスク評価セミナー
−化学物質のこれからを知る−
12月17日(金)
場所:自動車会館大会議室(東京都千代田区九段南4−8−13)
http://www.jswe.or.jp/
地質学史懇話会
須藤 斎『知らないものを「知らせる」ために〜微化石は何に役立つのか』
菊地真一『水路地図の歴史』
場所:北とぴあ701号室(東京都北区王子)
日程:12月23日(木・休)13:00〜
問い合わせ先:猪俣道也 inomata2@nodai.ac.jp
中部支部活動報告
中部支部 活動報告
<2009年度>
1.中部支部総会(6月13日,山梨大学)
2.シンポジウム「フォッサマグナ地域の地殻変動現象と中部地方の最新情報」(6月13日,山梨大学)
3.個人講演(口頭,ポスター)(6月13日,山梨大学)
4.地質見学会「八ヶ岳火山とその周辺の地質について」(6月14日,山梨大学)
5.普及行事「小・中学生のための地学野外観察会」(名古屋地学会共催)(11月21日)
6.第117年学術大会(富山)実行委員会,見学旅行準備委員会設立
北海道支部2009活動
北海道支部活動報告
<2009年度>
1.北海道支部総会(2009年5月30日)
・個人講演会 (8件)
・日本地質学会長講演会 「オマーンから日高?マントルと海洋地殻を見る?」
日本地質学会長 宮下純夫
2.「地質の日」記念展示((2009年4月28日〜5月31日)
北海道大学総合博物館企画展示「支笏火山と私たちのくらし」.
日本応用地質学会北海道支部・北海道大学総合博物館・北海道地質調査業協会・札幌建築鑑賞会・札幌軟石文化を語る会の共催
3.支笏洞爺国立公園60 周年記念行事「支笏火山と市民のくらし」展(2009年6月2日〜7月15日)
4.北海道地質百選シンポジウム「北海道の地質 魅力発見!」(2009年10月17日)
5.北海道支部臨時総会(2010年3月20日)
・個人講演会 (8件)
Geo暦(2011)
2011年Geo暦(行事カレンダー)
2007年版 2008年版 2009年版 2010年版 … 2012年版
2011年版 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
○印は学会主催行事.(共)学会共催・(後)後援・(協)協賛
1月January
第35回フィッション・トラック研究会
1月7日(金)〜8日(土)
会場:ホテル然林房(京都市北区)
http://wwwsoc.nii.ac.jp/ftrgj/
平成22年度東京大学大気海洋研究所共同利用研究
「日本列島周辺域に分布するテフラのデータベース整備にむけて」
1月11日(火)〜12日(水)
会場:場所:東京大学柏キャンパス大気海洋研究所 講堂
http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/news/j/index.cgi?mode=art_view&id=321&lang=ja
パネル展 『神宿る熊野 〜魂を昇華させる地質遺産〜』
1月11日(火)〜22日(土)
会場:明治大学駿河台キャンパス アカデミーコモン1階(千代田区神田駿河台)
http://www.kozagawa.com/huu/topic/2010/kumano2011/4kumano20110122.htm
平成22年度地球温暖化対策技術開発成果発表会
1月13日(木)16:00〜18:00
会場:アルカディア市谷5階(大雪)(東京都千代田区九段北4-2-25)
詳しくはこちら
第1回フォーラム「ジオ多様性とは何か、その重要性を問う」
1月14日(金)〜15日(土)
会場:国際高等研究所(京都府木津川市木津川台9-3)
問い合せ先:ジオ多様性研究会事務局 矢島道子 pxi02070@nifty.com
中・下部更新統境界国際模式地に関する国際シンポジウム
1月15日(土)〜16日(日) 16日は現地見学
場所:サンプラザ市原(千葉)
詳細:会田信行 aida.nobuyuki@taupe.plala.or.jp
参考:プログラム案
2月February
環太平洋北部地域のオフィオライトと海洋底の類似岩石
2月7日(月)〜8日(火),見学旅行:9日(水)〜10日(木)
会場:東北大学東北アジア研究センター4階436会議室(仙台市青葉区川内41)
http://www.cneas.tohoku.ac.jp/labs/geo/ishiwata/SendaiSympo1.htm
○第160回西日本支部例会、2010年度総会
2月19日(土)
会場:広島大学理学部(東広島市鏡山1-3-1)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
○2010年度日本地質学会北海道支部総会・個人講演会
2月26日(土)13:30-14:50(総会)15:00-17:30(個人講演会)
会場:北海道大学大学院環境科学研究院D棟101室
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
平成22年度海洋情報部研究成果発表会
2月25日(金)13:30-18:00
会場:海上保安庁海洋情報部7階大会議室(東京都中央区築地)入場無料
問い合わせ先:海上保安庁海洋情報部(電話03-3541-3813)
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/
第17回地質調査総合センターシンポジウム
「地質地盤情報の法整備を目指して」
2月28日(月)13:00-17:30
場所:東京大学・小柴ホール(東京都文京区本郷)
http://www.gsj.jp/Event/gsjsympo.html
3月March
平成22年度海洋研究開発機構研究報告会「JAMSTEC2011」
3月2日(水)13:00-17:30
場所:東京国際フォーラム ホールB7(千代田区丸の内3-5-1 Bブロック7F)
問い合わせ先:海洋研究開発機構 事業推進部推進課
046-867-9238 renkei@jamstec.go.jp
有人潜水船「しんかい6500」就航20周年記念シンポジウム
3月6日(日)10:00-17:30
場所:東京海洋大学品川キャンパス白鷹館(港区港南4-5-7)
http://www.jamstec.go.jp/j/pr/event/6k_20th_sympo/
研究船による成果発表会「ブルーアース’11」
3月7日(月)〜8日(火)10:00-17:30
場所:東京海洋大学品川キャンパス白鷹館・楽水会館・中部講堂(港区港南4-5-7)
http://www.jamstec.go.jp/jamstec-j/maritec/rvod/blue_earth/2011/index.html
津波防災シンポジウム「津波警報!!そのときあなたは?」
3月10日(木)13:30-16:00
場所:気象庁講堂(東京都千代田区大手町1-3-4)
http://www.jma.go.jp/jma/press/1102/08b/110310tsunami.html
○東北支部2009-2010年度総会,講演会・公開シンポジウム
3月13日(日)(日程を短縮し、13日のみに変更になりました)
会場:コラッセふくしま 5階研修室
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
第1回アジア太平洋大規模地震・火山噴火リスク対策ワークショップ
3月14日(月)〜15日(火)
場所:産業技術総合研究所つくば中央共用講堂
http://www.gsj.jp/Event/AsiaPacific/
SELENE-2着陸候補地点に対する説明・討論会
3月17日(月)10:00〜17:00
場所:国立天文台三鷹キャンパス 大セミナー室
http://astrosis.ess.sci.osaka-u.ac.jp/selene2_public2/
日本堆積学会2011年長崎大会
3月17日(月)〜22日(火)
会場:長崎大学文教キャンパス総合教育研究棟3階 他
http://sediment.jp
日本地学オリンピック とっぷ・レクチャー
3月24日(木)13:00-16:30 ※事前登録必要
会場:産業技術総合研究所共用講堂
問い合わせ先:NPO法人地学オリンピック日本委員会 esolympiad@yahoo.co.jp
第2回ジオ多様性フォーラム
3月28日(月)10:00-17:00
場所:京都大学東京オフィス(港区港南2-15-1品川インターシティA棟27F)
問い合わせ先:矢島道子 pxi02070@nifty.com
4月April
第52回科学技術映像祭 入選作品発表会
4月21日(木)〜22(金)(表彰式:4/22 13:00-15:00)
場所:科学技術館サイエンスホール(千代田区北の丸講演2-1)
問い合わせ先:科学技術映像祭事務局 03-3212--8487
http://ppd.jsf.or.jp/filmfest/
saveMLAKイベント
緊急討議 「東日本大震災 被災支援とMLAK−いまわた したちにできることは」
4月23日(土)13:00-14:30
場所:学習院大学(目白) 南3号館203教室(豊島区目白1-5-1)
http://savemlak.jp/wiki/saveMLAK:Ev/20110423
日本学術会議公開シンポジウム
「新しい高校地理・歴史教育の創造−グローバル化時代を生き抜くために−」
4月23日(土)14:00-17:00
場所:日本学術会議講堂(港区六本木7-22-34)
問い合わせ先:日本学術会議事務局第一部担当 小林03-3403-5706
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf/116-s-1-1.pdf
○2011年関東支部総会および地質技術伝承講習会
【地質技術伝承講習会】
日時:4月24日(日)14:00〜16:00
場所:大田区産業プラザ(大田区蒲田1-20-20)特別会議室
テーマ:トンネル事前調査の課題と物理探査
参加費:無料、どなたでも参加できます。
【支部総会】
日時:4月24日(日)16:00〜16:30
場所:上記講習会と同会場
申込方法・総会委任状等、
詳しくは、http://kanto.geosociety.jp/
第79回「海洋フォーラム」
4月25日(月)17:30-19:00
場所:海洋船舶ビル 10階ホール(港区虎ノ門1-15-16)
問い合わせ先:海洋政策研究財団(シップ・アンド・オーシャン財団)
Tel:03-3502-1988 E-mail:kaiyoforum@sof.or.jp
http://www.sof.or.jp/jp/forum/all.php
循環とくらし第2号発刊記念シンポジウム
4月30日(月)17:30-19:00
場所:日本大学理工学部1 号館6階CSTホール(千代田区神田駿河台1-8-14)
問い合わせ先:廃棄物資源循環学会 事務局
E-mail:apply@jsmcwm.or.jp Tel: 03-3769-5099)
5月May
○2011年「地質の日」特別講演会
「微生物は如何にして地球環境を変えてきたか?〜石から探る地球環境の進化史〜」
神奈川県立生命の星・地球博物館 共催
日時:5月14日(土)13:00〜
会場:神奈川県立生命の星・地球博物館
同会場にて第2回惑星地球フォトコンテスト表彰式を行います.
http://www.geosociety.jp/name/content0076.html
○一般社団法人日本地質学会第3回(2011年度)総会(代議員総会)
日時:5月21日(土)14:00-15:30
会場:総評会館 201会議室(千代田区神田駿河台3-2-1)【地図はこちら】
議事次第等くわしくはコチラ
日本地球惑星科学連合2011年大会
5月22日(日)〜27日(金)
会場:幕張メッセ国際会議場(千葉市美浜区中瀬2-1)
http://www.jpgu.org/meeting/
(共)原子力総合シンポジウム2011
5月25日(水)〜26日(木)
会場:日本学術会議講堂(港区六本木7-22-34)
http://www.aesj.or.jp/
6月June
第24回東京国際ミネラルフェア
6月3日(金)〜7日(火)10:00〜19:00(最終日は17:00まで)
会場:ハイアット・リージェンシー東京 スペースセブンイベント会場(新宿区西新宿2-7-1)
http://www.tima.co.jp
石油技術協会・海洋研究開発機構共催シンポジウム
地下圏微生物と石炭起源の炭化水素資源
−西太平洋沿岸海域におけるエネルギー資源と生成メカニズム−
6月6日(月)13:00〜17:00
会場:東京大学本郷キャンパス小柴ホール(文京区本郷7-3-1)
http://www.japt.org/news/2011/files/h23_kaiyoukenkyu.pdf
○2011年中部支部総会・シンポジウム・地質見学会
6月11日(土),12日(日)地質見学会
会場:名古屋大学東山キャンパス環境総合館1階レクチャーホール
http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
IGCP-581 第二回シンポジウム
「アジア河川系の変遷:テクトニクスと気候」
6月11日(土)〜12日(日)
場所:北海道大学大学院地球環境科学研究院(札幌市北区)
巡検:6月13日-14日.
http://geos.ees.hokudai.ac.jp/581/
問い合わせ先:IGCP-581 LOC 山本正伸 myama@ees.hokudai.ac.jp
一般社団法人日本応用地質学会平成23年度シンポジウム
「応用地質学の変遷と将来展望」
6月17日(金)13:00〜17:30
会場:日本大学文理学部 百周年記念館国際会議場
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jseg/00-main/H23_symposium.html
問い合わせ先:日本応用地質学会事務局 KYW04560@nifty.com
地質学史懇話会
6月15日(水)13:30〜
会場:北とぴあ701号室(北区王子1-11-1)
・小澤健志「金澤藩鉱山教師E.デッケンの生涯について」
・後藤和久「宮古−八重山諸島を襲った 1771 年明和津波の歴史学的・地質学的証拠」
問い合わせ先:矢島道子 pxi02070@nifty.com
深田研ジオフォーラム2011
6月25日(土)13:30〜
会場:防災科学技術研究所 研究交流棟(つくば市天王台3-1)
申込先:深田地質研究所 fgi@fgi.or.jp
http://www.fgi.or.jp/
IUGG2011
“Earth on the Edge:Science for a Sustainable Planet”
6月28日(火)〜7月11日(月)
場所:オーストラリア・メルボルン(メルボルンコンベンションセンター)
<http://www.iugg2011.com>
早期割引参加申込締切:4月11日(月)
■2ndサーキュラーはこちらから(PDF)
■registration brochure はこちらから(PDF)
7月July
(共)第48回アイソトープ・放射線研究発表会
7月6日(水)〜8日(金)/要旨原稿締切:4月15日(金)
会場:日本科学未来館7階(江東区青梅2-3-6)
http://www.jrias.or.jp/
第161回西日本支部例会(九州考古学会との合同大会)
7月9日(土)〜10日(日)
会場:九州大学・西新プラザ(福岡市早良区西新2-16-23)ほか
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
8月August
(後)INHIGEO 国際地質学史委員会日本大会
8月2日(火)〜10日(水)
会場:愛知大学豊橋キャンパス(豊橋市町畑町1−1)
http://www.inhigeo-jp.org/index.html
第20回市民セミナー「水辺の環境調査−水辺の生物多様性と水環境総合指標−」
8月3日(水)9:40〜16:20
場所:東京会場・地球環境カレッジホール(東京都世田谷区駒沢)
大阪会場・いであ(株)大阪支社 ホール(大阪市住之江区南港北)
http://www.jswe.or.jp/
問い合わせ先:(社)日本水環境学会セミナー係 山本、窪田
Tel: 03-3632-5351 Fax: 03-3632-5352
E-mail: kubota@jswe.or.jp
IGCP-507第6回国際シンポジウム(北京)
「白亜紀のアジア古気候:その多様性,原因および生物と環境の反応」
8月15日(月)〜16日(火)
テーマセッション「熱河生物群と熱河層群」および一般セッション
場所:中国地質大学・北京校
8月17日(水)〜20日(土):巡検
場所:熱河生物群産地ほか遼寧省の非海成白亜系分布地
問い合わせ:IGCP-507国内コーディネーター 長谷川卓(金沢大)
E-mail: jh7ujr@kenroku.kanazawa-u.ac.jp
「防災と地理教育」に関する公開シンポジウム
「防災と地理教育—東日本大震災の教訓を生かして—」
8月19日(金)13:00〜17:00
場所:慶應義塾大学日吉キャンパス「来往舎」大会議室( 横浜市港北区日吉4-1-1)
申込・問い合わせ:碓井照子usuit@daibutsu.nara-u.ac.jp
第38回技術士全国大会(東京)
「地球再生へのメッセージ」〜世界・アジア・日本における技術士の役割〜
8月25日(木)〜27日(土)
会場:経団連会館(千代田区大手町1-3-2)
問い合わせ:公益社団法人 日本技術士会
http://www.engineer.or.jp/
第2回シンポジウム「海洋教育がひらく防災への道」
8月27日(土)13:00〜17:20
場所:東京大学農学部 弥生講堂
対象:小・中・高等学校教諭、学生、教育関係者、一般
参加費:無料(要事前登録)定員300名
https://www.webmasters.co.jp/RCME/symp/またはhttp://www.oa.u-tokyo.ac.jp/RCME/
問い合わせ先:東京大学理学部経理課海洋リテラシー事務 小山 ・ 太田
Tel: 03−5841−4395
E-mail: literacy_jimu@oa.u-tokyo.ac.jp
第6回「海洋と地球の学校」
8月29日(月)〜9月3日(土)
場所:青森県内(むつ市、八戸市及び周辺地域)
http://www.jamstec.go.jp/j/pr/school/006/index.html
問い合わせ先:(独)海洋研究開発機構 広報課 海洋と地球の学校 事務局
Tel: 045-778-5334(設楽)
E-mail: kaiyo-gakko@jamstec.go.jp
2011地球環境保護 土壌・地下水浄化技術展
8月31日(水)(月)〜9月2日(金)
場所:東京ビッグサイト西ホール(江東区有明3-11-1)
http://www.sgrte.jp
9月September
東京大学大気海洋研究所共同利用研究集会
南海トラフ海溝型巨大地震の新しい描像
- 大局的構造と海底面変動の理解(その2) -
日時:2011年9月 7日(水)〜 8日(木)
場所:東京大学大気海洋研究所 講堂
http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/
◯日本地質学会第118年学術大会・日本鉱物科学会2011年年会
合同学術大会(水戸大会)
9月9日(金)〜11日(日)
会場:茨城大学ほか
講演/参加申込:後日掲載
大会HPはこちら
(共)第55回粘土科学討論会
9月14日(水)〜16日(金)
参加申し込み期間:6月13日(月)〜24日(金)
会場:鹿児島大学共通教育棟3号館(鹿児島市郡元1丁目21-35)
問い合わせ先:第55回粘土科学討論会実行委員会 河野元治 kawano@sci.kagoshima-u.ac.jp
申し込み詳細
東レ先端材料シンポジウム2011
9月14日(水)10:00〜17:00
会場:東京国際フォーラム ホールA(千代田区丸の内3-5-1)
問い合わせ先:東レ先端材料シンポジウム・展示会事務局
Tel: 03-5574-0132(平日10:00~12:00, 13:00~17:00)
http://東レ先端材料シンポ.jp
(後)第61回東レ科学講演会
9月16日(金)17:00〜20:00
会場:有楽町朝日ホール(千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン11階)
http://www.toray.co.jp/tsf/index.html
第137回深田研談話会
世界一稠密高精度地震観測網で見る日本列島の様々な地震
—2011年東北地方太平洋沖地震はどう考えるか—
9月30日(金)15:30〜17:30
会場:深田地質研究所 研修ホール(文京区本駒込2-13-12)
http://www.fgi.or.jp/
10月October
第3回ジオ多様性フォーラム
地質、地形、測地、地震、水、文明などからみたジオ多様性
10月7日(金)〜8日(土)
場所:JAMSTEC東京事務所(千代田区内幸町2-2-2-23F)
問い合わせ先:矢島道子 pxi02070@nifty.com
http://www.geosociety.jp/outline/content0096.html
深田研一般公開2011
10月8日(土)
場所:深田地質研究所(文京区本駒込2-13-12)
http://www.fgi.or.jp
シンポジウム「海は学びの宝庫〜海洋教育の研究と実践〜」
10月15日(土)
場所:京大学工学部2号館213号室(本郷キャンパス)
http://www.fgi.or.jp
○原子力総合シンポジウム2011
10月19日(水)
場所:日本学術会議講堂(港区六本木7-22-34)
(共同主催)
※事前登録締切:10/5、ただし定員に達し次第締切。
http://www.aesj.or.jp/
(共)第5回国際海底地すべりシンポジウム
10月24日(月)〜26日(水)
場所:京都大学
http://www.landslide.jp/
山陰海岸ジオパーク国際学術会議「城崎会議」
10月29日(土)〜31日(月)
会場:城崎温泉 西村屋ホテル 招月庭(兵庫県豊岡市城崎町湯島1016-2)
ポスターセッション公募締切:7/22(金)
参加登録締切:10/14(金)
http://sanin-geo.jp/modules/news/index.php?page=article&storyid=51
11月November
海洋調査技術学会 第23回研究成果発表会
特別講演:11月1日(火)16:00〜18:00
特別セッション:2日(水)10:00〜12:30
場所:海上保安庁海洋情報部 7階大会議室(中央区築地5-3-1)
問い合せ先:海洋調査技術学会事務局 ac185-jsmst@canpan.org
平成23年度 東濃地科学センター 地層科学研究 情報・意見交換会
11月1日(火)13:00〜17:00
場所:瑞浪市地域交流センター「ときわ」(岐阜県瑞浪市)
定員:約150名
申込先:独立行政法人 日本原子力研究開発機構
東濃地科学センター 瑞浪超深地層研究所
地層処分研究開発部門 結晶質岩工学技術開発グループ
E-mail tono-koukankai2011@jaea.go.jp
http://www.jaea.go.jp/04/tono/index.htm
瑞浪超深地層研究所 深度300m水平坑道見学会
11月2日(水)9:15〜12:00
場所:瑞浪超深地層研究所
定員:約40名
申込先:独立行政法人 日本原子力研究開発機構
東濃地科学センター 瑞浪超深地層研究所
地層処分研究開発部門 結晶質岩工学技術開発グループ
E-mail tono-koukankai2011@jaea.go.jp
http://www.jaea.go.jp/04/tono/index.htm
2011 PERC Planetary Geology Field Symposium
11月5日(土)〜6日(日)/発表申込締切: 2011年8月上旬
会場:北九州国際会議場
問い合わせ先: 千葉工業大学惑星探査研究センター pgfs2011@perc.it-chiba.ac.jp
http://www.perc.it-chiba.ac.jp/meetings/pgfs2011/
東海地震防災セミナー2011(第28回)
11月10日(木)13:30〜16:00
会場:静岡商工会議所静岡事務所5階ホール(JR静岡駅北口西側)
問い合わせ先: 土研究事務所 Tel: 054-238-3240
第20回素材工学研究懇談会ー分離操作を高純度精製ー
11月14日(月)〜15日(火)
会場:東北大学片平さくらホール
申込締切:10/31
http://www.tagen.tohoku.ac.jp
(後)いわて三陸ジオパーク震災復興シンポジウム〜震災の記憶を伝え生かすために〜
11月25日(金)13:30〜17:00
会場:アイーナホール(いわて県民情報交流センター:盛岡市盛岡駅西通1-7-1)
http://www.geosociety.jp/outline/content0096.html
平成25〜27年度学術研究船白鳳丸研究計画企画調整シンポジウム
11月29日(火)〜12月1日(木)
会場:東京大学大気海洋研究所 講堂
申請書提出期限:平成23年10月20日(木)
http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/coop/hakuho_3_25.html
12月December
第11回東北大学多元物質科学研究所研究発表会
12月8日(木)13:00〜17:30
会場:東北大学片平さくらホール
ポスター発表申込締切:11/4,予稿提出締切:11/9,申込締切:11/30
http://www.tagen.tohoku.ac.jp/general/info/event/meeting/
JSTシンポジウム「社会の安全保障と科学技術」
12月8日(木)13:00〜17:30
会場:コクヨホール(港区港南1-8-35)
定員:305名(事前登録制)
http://www.event-info.com/jst-symposium/
第1回アジア・アフリカ鉱物資源会議
(Asia Africa Mineral Resources Conference 2011)
12月8日(木)会議および懇親会
12月9日(金)〜11日(日)フィールド巡検
会場:九州大学伊都キャンパス 稲盛ホール
http://xrd.mine.kyushu-u.ac.jp/AsiaAfrica_seminar.html
第6回深部地質環境研究コア研究発表会
12月15日(木)13:30〜16:30
会場:秋葉原UDX 南ウィング 6階 カンファレンスフロア会議室A+B
申込:12/2までメールにて
http://www.aist.go.jp/aist_j/event/ev2011/ev20111215/ev20111215.html
http://unit.aist.go.jp/dgcore/event/sympo20111215.html
第139回深田研談話会
岩盤応力と岩盤応力測定
12月16日(金)15:00〜17:00
会場:深田地質研究所 研修ホール
定員:80名(先着順)
http://www.aist.go.jp/aist_j/event/ev2011/ev20111215/ev20111215.html
地質学史懇話会
12月23日(金・休)13:30〜17:00
会場:北とぴあ701号室(北区王子1-11-1)
・原 郁夫「小籐文次郎の1880年代三波川変成帯研究」
・小松直幹「最古級の油田地下構造図ーライマンとその弟子たちの作品」
問い合わせ先:矢島道子 pxi02070@nifty.com
2010年度各賞受賞者
2010年度各賞受賞者 受賞理由
■国際賞(1件)
■小澤儀明賞(1件)
■論文賞(2件)
■研究奨励賞(3件)
■Island Arc賞(1件)
■功労賞(1件)
■学会表彰(2件)
日本地質学会賞
該当無し
日本地質学会国際賞
受賞者:Juhn G. Liou (米国スタンフォード大学名誉教授)
対象研究テーマ:低温高圧・超高圧変成作用の研究と日本の地質学界への貢献学
Juhn G. Liou(劉 忠光)氏は,水・岩石相互作用の研究,低温変成作用,高圧・超高圧変成作用の研究において,それらの分野を世界的にリードするとともに,日本の地質分野の人材育成と教育にも大きく貢献した.
Liou氏は1962年に国立台湾大学で学位取得後,カリフォルニア大学ロサンゼルス校大学院在学期(1965〜1970),アメリカ航空宇宙局有人宇宙機センター(現,ジョンソン宇宙センター)在職期(1970〜1972),スタンフォード大学在職期(1972〜現在)を通して,沸石,ぶどう石,パンペリ石,緑れん石などの含水Ca-Al珪酸塩鉱物の安定領域の決定を行い,水・岩石相互作用及び低温変成作用から,高圧・超高圧変成作用とそれに関連する造山運動へと研究を発展させていった.この一連の研究キャリアの中で,数多くの日本人地質研究者と学術交流し,共同研究を行ってきた.1976年のグッゲンハイム研究奨学金による日本滞在以来,頻繁に共同研究員や客員スタッフとして日本に滞在し,大学院生を含む幅広い研究者たちと積極的に交流を深めた.また,日本から若手研究者・ポスドクを積極的に受け入れ,若手研究者らの国際舞台への進出を援助した.
Liou氏は,これまでに342編の論文と10編の著書を公表し,2007年にはISI Web of Scienceにおいて,被引用数に関してトップ10地球科学者に選ばれた.論文のうち106編は日本人との共著である.9編の学術雑誌の特集号編集にも携わり,そのうちの3編はIsland Arc誌である.こうした,彼の長年にわたる米日間学術交流に対する貢献は,2002年に全米科学財団国際共同事業センター(日本)フェロー受賞の形で認められた.2005年に公式に教員職を退いた現在も教育・研究の現場で後輩の教育に力を入れており,Island Arc誌編集顧問や,Journal of Asian Earth Sciences誌の編集委員など,アジアの地質学分野の発展に尽力している.
彼の学術的功績は,米国鉱物学会賞(1977年),米国鉱物学会フェー(1978年),米国地質学会フェロー(1979年)の受賞などとして既に認められているが,上述のように,アジア諸国,とりわけ,日本の地質学コミュニティーにおいて,人材育成・教育に関する貢献は極めて大きく,一連の功績は日本地質学会国際賞にふさわしい.
日本地質学会Island Arc賞
受賞論文:Fu-Yuan Wu, Jin-Hui Yang, Ching-Hua Lo, Simon A. Wilde, De-You Sun and Bor-Ming Jahn, 2007, The Heilongjiang Group: A Jurassic accretionary complex in the Jiamusi Massif at the western Pacific margin of northeastern China. Island Arc, 16, 156-172.
This paper paid attention to the Heilongjiang complex in the western margin of the Jiamusi Massif, NE China, to understand the tectonic setting of the eastern Asian continental margin in the Jurassic. It provides geological and chronological data of metamorphic rocks from the complex, showing that the Heilongjiang complex is a tectonic mélange of an Early Jurassic accretionary complex. The authors propose a new idea that a continental margin existed at least since the Early Jurassic along the eastern Asian continental margin and was affected by the Late Jurassic to the Cretaceous subduction and accretionary processes. This paper has been stimulating recent researches on tectonic re-interpretation of the continental blocks and accretionary complexes in eastern Asia. It will also make great contribution to future researches on geodynamic evolution of the eastern Asian continental margin.
This paper received the highest number of citations - based on the Thomson Science Index for the year 2008 - amongst all the candidate Island Arc papers published in 2006-2007. The first author has been engaged in geological and chronological studies of eastern Asia for many years and published many other important papers on Asian geology in international journals. In view of the scientific impact of the paper and international scientific activity of the first author, the Judge Panel recommends this paper for the 2010 Island Arc Award.
日本地質学小澤儀明賞
受賞者:後藤和久(千葉工業大学惑星探査センター)
対象研究テーマ:地質学的手法による津波・高波災害履歴と規模の推定に関する研究
津波や台風に伴う高波など,過去の巨大災害の履歴や規模を知ることは防災上極めて重要であり,地質学が社会に直接的に貢献できる研究テーマでもある.その評価材料として,各国沿岸に分布する数メートル大の巨礫群に関心が集まっているが,津波起源の巨礫の認定と水理量算出の難しさゆえ,この分野の研究は進展していなかった.
同氏は,奄美大島から石垣島に渡る広範囲の島々で,総計5000個もの巨礫の分布をリーフ上で調査し,台風起源の巨礫群は,指数関数曲線で示される明瞭な陸側分布限界線を持つことを明らかにした.この限界線を用いれば,それより内陸側にある巨礫群は津波により運搬されたと認定できる.同氏の研究成果に基づけば,1771年明和津波の被災地域である宮古一八重山諸島にしか津波起源の巨礫群は存在せず,奄美諸島や沖縄緒島においては過去数千年間,巨礫を移動させるような巨大津波が発生した痕跡は無い.これは,琉球海溝での過去の地震履歴の解明や明和津波の波源推定にも繋がっていく,画期的な成果である.さらに同氏は,2004年インド洋大津波によって運搬されたタイ・パカラン岬の巨礫群の分布や特性を津波直後に丹念に調べ上げ,数値計算結果を組み合わせることで,巨礫のサイズ・空間分布から,津波流況および津波波高や水理量を定量的に復元できることを世界で初めて示した.
このように,約5年間に渡る同氏の精力的な研究により,世界中に分布する沿岸巨礫群から津波起源のものを認定できるようになり,津波の水理量をも推定できるようになった.巨礫の打ち上げ年代の測定も合わせて行えば,過去の巨大津波の履歴と規模を同時に知ることができ,画期的な進歩といえる.
同氏は,専門とする野外地質学的研究に,津波工学分野の新技術を積極的に取り入両分野を融合させた新しい研究分野を独自に切り開いた.その成果として,別紙に示したように,3年の短期間で質の尚い論文を多数山している.今や,同氏の研究とその調査地域である琉球列島の巨礫群は,世界の津波研究者から大いに注目されている.例えば,�2008年AGUJointAssemblyでの招待講演,�2009年6月に米国地質澗査所の研究者の依頼を受けて,石垣島で共同調査を実施,�来年開催予定の国際津波シンポジウムを日本に誘致し石垣島での巡検を企画,など,この分野における世界での存在感を存分に示している.その一方で,著書の執筆やメディア発信,市民向け識演会を数多く行い,自治体の防災対策にアドバイスを行うなど,普及活動にも尽力している.
以上の実績から,同氏は小澤儀明賞に相応しいと考えられる.
.
日本地質学柵山雅則賞
該当無し
日本地質学会論文賞
受賞論文:Sugawara D., Minoura K., Nemoto N., Tsukawaki S. Goto K. and Imamura F., 2009, Foraminiferal evidence of submarine sediment transport and deposition by backwash during the 2004 Indian Ocean tsunami. Island Arc, 18, 513-525.
本論文は,2004年インド洋でおきた津波による砕屑物の挙動を,タイ南西部で,津波前後の海岸から沖合までの堆積物中の有孔虫の証拠から明らかにしたものである.これまでの多く報告されている海岸遡上津波堆積物は実際に期待される津波周期よりも保存されている割合が少なく,これは海岸の堆積物が比較的容易に再移動されてしまうためと考えられる.本論文では,津波の前,津波直後および1年後という得難いコア資料において有孔虫指標の比較をおこない,砕屑物の運搬過程を推定している.このように微化石群集に基づく堆積物の挙動の可視化は,イベント堆積物研究の新たな着眼点であり,論文賞に値するものである.
受賞論文:宮田雄一郎・三宅邦彦・田中和広,2009,中新統田辺層群にみられる泥ダイアピル類の貫入構造.地質学雑誌,第115巻,第9号,p470-482.
本論文は下部中新統田辺層群にみられる泥ダイヤピル構造の形成要因を明らかにしたものである.筆者らは野外における詳細な産状記載から上昇機構を推定し,それらに基づく検証実験や,現在の海底や内陸部で活動する泥火山•ダイヤピル活動との比較を行っている.このような手法は,野外における堆積相解析の精度を向上させるだけではなく,様々の形成要因の検討を可能にしている.また,露頭での詳細な解析からは田辺層群の急激な海水準上昇やテクトニクスなど時代的背景との関連性の推定もおこなわれている.本論文はこのように堆積学研究の解析能力を十分に発揮しており,論文賞に値するものである.
日本地質学会小藤賞
該当無し
日本地質学会研究奨励賞
受賞者:佐藤雄大(国交通省国土地理院測地部)
受賞論文:佐藤雄大・鹿野和彦・小笠原憲四郎・大口健志・小林紀彦,2009,東北日本男鹿半島,台島層の層序.地質学雑誌,第115巻,第1号,31-46.
本論文は,著者らの長年にわたる地道な野外調査で蓄積した知見を背景として,東北日本の日本海側の新生界の模式的地域の下部中新統台島層について,精密な調査の結果を報告している.この層は,広域対比に用いられる台島型植物群を産することからも重要である.佐藤らは,岩相層序・古地磁気層序・火山学的な堆積機構を検討し,台島層がカルデラとその周辺に堆積・定置したさまざまな岩体の集合体であることを明らかにした.これは,東北日本でグリーンタフ層準のカルデラを発見した最初の論文でもある.また,下位の門前層と上位の西黒沢層との関係も明確にした.これらの結果,台島層とそれをとりまく地層の層序に関する長年の論争に,ほぼ決着をつけたと言える.本研究は一地域の層序に関するものであるが,調査の精密さは賞賛に値するものであり,また,グリータフ地域の標準層序の改訂という,広い波及効果をもつ.これらのことから,本論文は地質学会奨励賞にふさわしい.
受賞者:大橋聖和(広島大学大学院理学研究科地球惑星システム学専攻)
受賞論文:大橋聖和・小林健太,2008,中部地方北部,牛首断層中央部における断層幾何学と過去の運動像.地質学雑誌,第114巻,第1号,16-30.
標記論文は中部地方北部に分布する,北東—南西方向の右横ずれ活断層系牛首断層について,詳細な野外調査に基づき断層の幾何学,運動像および構造発展史を解析したものである.本論文はまず,断層面の走向の頻度分布を検討し,牛首断層の一般走向に反時計回りに10-20°斜交するR1剪断面が優勢であることを明らかにした.また,北東—南西方向の断層が北北東—南南西方向の断層に繋がれ断層屈曲部を形成し,断層屈曲部に左横ずれに伴う伸張デュープレックスが形成されたと推察した.したがって,反時計回りに斜交するR1剪断面も含めて,牛首断層はもともと後期白亜紀に左横ずれ断層として形成され,その後第四紀に右横ずれ活断層として再活動したと考えられる.本論文で明らかにされた断層の幾何学や構造発展史は確実性が高く,今後,日本列島内陸活断層の起源の研究において標準ともなるべき優れた研究である.よって,本論文は研究奨励賞に値する.
受賞者:川上 裕(石油天然ガス・金属鉱物資源機構)
受賞論文:川上 裕・星 博幸,2007,火山−深成複合岩体にみられる環状岩脈とシート状貫入岩:紀伊半島,尾鷲−熊野地域の熊野酸性火成岩類の地質.地質学雑誌,第113巻,第7号,296-309.
この研究は,熊野酸性岩類北部の火砕流堆積物と花崗斑岩の詳細な地質調査と顕微鏡観察に基づいて,花崗斑岩岩体が「コールドロンの環状岩脈とそれから派生した巨大なシート状貫入岩体」であるとする結論を導き,花崗斑岩は溶岩湖が固結したものであるとした従来の見解を否定している.南部の岩体に関する他の研究者の最近の研究結果にヒントを得たようではあるが,貫入境界をこれほど綿密に追跡した研究は珍しく,独自の調査事実に基づいて新しいモデルを提案している点も評価できる.今後の更なる成果を期待して,研究奨励賞候補論文として推薦する.
日本地質学会功労賞
受賞者:杉山了三
功労業績:地域を生かし,生徒とともに創造する地学学習
杉山会員は昭和46年に岩手県で高校教員となり,その後現在まで地域を生かした地学教育を生徒ともに創造してこられた.現在,高校の地学教育は必修ではなく,それぞれの学校に勤務する地学教員の地道な努力によって,やっと選択授業として地学が開設されるという状況にある.そのように困難な状況にもかかわらず,杉山会員は勤務地の地域地質を活かした学習指導,生徒の地学研究の指導に精力的にとりくみ,それらは多くの受賞に結実している.そして,杉山会員の地学教育へのひたむきな努力を見て育った生徒が大学の地学関係学科へ進学したり,卒業後地学教員や地質技術者として活躍する姿となって,次の世代に伝わりつつある.
杉山会員は初任校の種市高校では南部潜りを伝える水中土木科に所属し,潜水したりしながら海底の白亜系の巨大な珪化木等を調査した.次の一戸高校では馬淵川沿いの河岸段丘を調べ,県の理科発表会で発表した.三番目の遠野高校では,遠野盆地の地質(遠野物語では遠野は大昔湖であったと書かれているがこれは本当か)を6年継続して研究.平成7年から5年連続して学生科学賞に入選し,平成12年には環境庁長官賞を受賞した.さらに遠野盆地の研究は,これを教材化するという形でまとめ,国立科学博物館主催の平成19年度野依科学奨励賞を受賞した.盛岡一高では,雫石町の舛沢層と火山豆石の研究,ドミノで地震波を再現する実験などを生徒といっしょに研究し,学生科学賞の県代表に2度選ばれた.その一部は2007・2008年度の地球惑星連合大会「高校生のポスターセッション」で発表している.最近では地域の教材を活かした「ミニ造岩鉱物セット」を作成したり,生徒が作れる簡易な岩石薄片器具を開発.これにより平成20年度(第40回)東レ理科教育賞の文部科学大臣賞を受賞した.地質学関係では初の受賞である.その他,県内の先生方と共同で,地域に根ざした課題を地学実験に取り入れた実践集「岩手県の地学実験書」などを作成している.
このように杉山会員は全ての勤務地で地域の地質と係わり,それを地学の授業に生かしてきた.この地道な努力は大いに顕彰されるべきであり,日本地質学会功労賞に値する.
日本地質学会表彰
受賞者:山口県(代表者:山口県知事 二井関成)
表彰業績:阿武火山群の火山灰層の保存と観察施設建設
阿武火山群は,日本の活火山の中でも3つしかない独立単成火山のひとつである.2006年11月末,山口県萩市と阿武郡阿武町の境界付近の伊良尾山(比高約150m)の山麓を通る広域農道の工事現場の両側の法面に,阿武火山群・伊良尾火山から噴出した降下火山礫・火山灰層が露出した.露頭は幅200m,高さ50mの大規模なものである.この露頭は,伊良尾火山の約30〜40万年前のViolent Strombolian Eruption(日本語訳はまだない)で形成された地層の一部であり,調査・研究の結果以下のような火山形成史が明らかになった.
1)マグマ水蒸気爆発で噴火開始.2)スコリア丘の形成と噴煙柱由来の火山灰・火山礫の堆積.3)スコリア丘へのマグマの貫入とスコリアラフトの形成.大量の溶岩流は溶岩台地を形成し,一部は当時の川に流れ込み15km下流まで達した.4)さらに火山礫・火山灰が堆積し,その中に溶岩流が数回流れ込んだ.5)溶岩台地上の別の場所に2つの小規模なスコリア丘を形成し,それぞれ溶岩を流出した.
このような地層の露出は,阿武火山群では初めてのものであり,特に,一見摺曲したように見える降下火山礫・火山灰層は見事なものであった.今後,このような地層は現れることがないと判断し,2006年12月初旬に山口県萩農林事務所に露頭の保存を要請した.しかし,道路の安全性から保存は不可能であるとの回答であった.その後も,学術的な価値を訴え,保存の要請を続けた.その結果,2008年11月27日,山口県は地層の一部保存を決定し,2段目の法面に長さ約80m・高さ3mの屋根付の遊歩道と解説板を設置することにした.また,コンクリートブロックで覆われる1段目の法面の地層は,両側に各1ヶ所の横2m・縦6mの窓を開け地層の観察ができるようにした.さらに,剥ぎ取り標本を作製し,それらは山口大学理学部,県立山口博物館,萩博物館,萩市と阿武町の公共施設に計8枚展示されている.さらに,見学者のための駐車場と案内板が設置される.また,大堂に産出した火山弾を山口県から無償で譲渡していただき大学や博物館などの教材として利用している.
今回,山口県の英断によって,道路の設計が変更され一部ではあるが学術的に重要な地層が駐車場と屋根付きの見学施設として残されることになった.このことは貴重な地層の保存,地質学・火山学の発展や普及に多いに寄与するものと思われる.山口県のこのような貢献は「日本地質学会表彰」にふさわしいものと思い推薦する次第である.
受賞者:地球システム・地球進化ニューイヤースクール(NYS)事務局(大坪誠・坂本竜彦・岡崎裕典・ほか)
表彰業績:地球科学系の若手研究者の継続的育成活動
「地球システム・地球進化ニューイヤースクール(以下NYSと略記)」は,地球惑星科学の未来を担う学部学生・大学院生・若手研究者の研究意識の向上(ボトムアップ)と交流促進を目的に,毎年1月に院生・ポスドク・若手研究者らが自主的に開催し,全国から毎年100名を超える参加者を集め,2001年から継続して実施されている大規模な研究・勉強集会である.NYSは,地球惑星科学全般の幅広い分野をテーマに,その分野の第一線の著名な専門家を招待しての講演,参加者間の討議・意見交換,そして若手研究者の研究発表などを活発に行い,若手が自ら切磋琢磨する場を提供している.近年では研究者のみならず,ライターやサイエンスコーディネーターといったアウトリーチ関連の方々や政府のガスハイドレート開発マネージャーといった旧来のサイエンティストに当てはまらない関係者を積極的に講演に招待し,ポスドクの新たな進路開拓も視野に,若手自らの視野を広げる努力を続けている.
NYSは後援者を募り,テキスト・ポスターの印刷費や会場費程度の支援を受けつつも,特定の大学や研究機関からは独立して運営され,若手のボランティアによって成り立っている.また参加者の中から次の運営者を育て,継続的な運営が成されている.一連の活動を通じて,多くの若者に広い視野とリーダーシップが培かわれ,事務局からは優れた研究者・技術者が次々に誕生している.
この会の活動を表彰し,地質学の未来を担う若者の自発的な成長を促すことは,日本地質学会の設立目的にも合致する.NYSの活動は,全国かつ多方面の地球科学系の若手育成に継続的に貢献しており,地質学会表彰に値する.
北海道支部2010活動
北海道支部 2011.03.01更新
日本地方地質誌「1.北海道地方」出版記念行事
記念講演会の様子
日本地質学会編集の日本地方地質誌(全8巻)「1.北海道地方」朝倉書店が昨年11月に出版された.本書出版を祝い,その宣伝と活用を呼びかけるため,また,地質関連の業界や学会活動の発展に資するべく,記念行事を企画した.
日程:2011年2月26日(土)
【出版記念講演】新井田清信編集委員長
時間:17:00〜17:50
場所:北海道大学大学院環境科学研究院D棟101室
【出版祝賀会】
時間:18:00〜20:00
場所:北海道大学百年記念会館きゃら亭
記念講演には50名超,祝賀会には37名が参加し,編集・執筆に際してのさまざまなエピソードが紹介された.
2010年度日本地質学会北海道支部総会・個人講演会
日程:2011年2月26日(土)
13:30〜14:50(総会)・15:00〜17:30ごろ(個人講演会)
場所:北海道大学大学院環境科学研究院D棟101室
【総会プログラム】 13:30-14:50
A.2010年度事業報告
B.2010年度 決算・会計監査報告(会計)
C.2011年度 事業計画案
D.2011年度 予算案
E.会則変更
F.特別基金の運用方法
【個人講演】15:00-16:45 (質疑応答時間を含め各15分)
1. 石狩低地〜長沼低地における第四系掘削コアの古環境と層序
嵯峨山 積・藤原与志樹・井島行夫・岡村 聡・山田悟郎・近藤 務・外崎徳二
2. 中新世の EU-NA 衝突境界は北海道のどこにあるのか?
前田仁一郎
3. EU-NA 衝突神話の成立過程:文献による検証
前田仁一郎
4. 日高町岡春部川から発見された蛇紋岩質テクトナイト
東 豊土・加藤孝幸
5. 断層関連褶曲とブラインドスラストの観点からみた北見大和堆の再解釈大津直・田近淳6. 地質研究所におけるWeb GIS地質情報発信の取り組み
小澤 聡・大津 直・鈴木隆広・八幡正弘
7. 積丹半島の地震被害—1792年・1940年北海道西方沖地震の例—
宮坂省吾・岡村 聡・金野玲那
大成功北海道地質百選シンポジウム「北海道の地質 魅力発見!」
日時:2009年10月17日(土)13:00-17:30
会場:かでる2・7(札幌市中央区北2条西7丁目)
主催:日本地質学会北海道支部,北海道地質百選検討グループ
後援:産業技術総合研究所 地質調査総合センター,北海道立地質研究所,北海道大学総合博物館,札幌市,三笠市立博物館,沼田町化石館,北海道地質調査業協会,日本応用地質学会北海道支部,地学団体研究会北海道支部
北海道地質百選シンポジウム「北海道の地質 魅力発見!」は60名以上の方々の参加で盛況のうちに終わりました.
それぞれの分野で膨大な資料を持っている12名の講演者の方には10分という短い時間の中で貴重なジオサイトの「うんちく」話をして頂きました.それぞれが中身の濃い話であり,聞く方にとっては大変興味深いもので,頭をフル回転させて次々に登場する講演者の話に聞き入りました.参加者からは,次々と豪華メンバーが発表していく速いテンポは,地質版の「レッドカーペット」を見ているようで面白かったという声も上がりました.
日本地質学会副会長の佃 栄吉氏の基調講演「日本の地質百選とジオパーク運動」と題して,世界ジオパークネットワークに日本から洞爺湖・有珠山,糸魚川,雲仙普賢岳が参加した経緯やジオパークの特徴などを分かりやすく報告して頂きました.
また,北海道各地のジオサイト紹介では,北海道には貴重な地質があることを改めて実感することが出来ました.特に講演者より世界に誇る地質・地形・化石が北海道にあることが強調されたのも心強いことでした.
同時に,開発により消えてしまう露頭をどのように保存すると言うことに関して,会場の方から「防災をキーワードにして露頭などを保存できる」という貴重な意見を頂きました.
現在,北海道地質百選のウェブで公開されているジオサイトは119箇所です.今後,誰でも知っているジオサイトをさらにたくさん公開していき,北海道地質百選を選定できる条件を整える必要があります.
シンポジウムの寄せられた多くのご意見を生かしながら活動を進めていくつもりです.全国の学会員の方のご協力を御願い致します.
(北海道地質百選検討グループ)
「北海道地質百選」のウェブサイトを全面的に更新しました
北海道支部では「北海道地質百選」の活動を行ってきました.今回,2009年地質の日を期してウェブサイトを全面的に更新しました.北海道の魅力ある地質・地形を紹介しています.ぜひご覧になって下さい.
また,「北海道にはこんな面白い地質があるよ」と言う材料をお持ちであれば,どしどし投稿をお願いいたします.投稿方法などはウェブサイトをご覧下さい.
ウェブサイトは下記の通りです.
<http://www.geosites-hokkaido.org/>
お問い合わせ:日本地質学会 北海道支部 北海道地質百選事務局
〒064-0807 札幌市中央区南7条西1丁目13 第3弘安ビル
明治コンサルタント株式会社気付
北海道地質百選事務局事務局長 重野聖之
TEL 011-562-3066 FAX 011-562-3199
mail:jimu@geosites-hokkaido.org
< 2009年度の活動報告はこちら >
その他関連行事お知らせ・Geo暦詳細など
その他のお知らせ
2025 MicroArt
2025.2.13掲載
応募締切:2025年3月28日(金)
協賛:日本地質学会ほか
『MicroArt』は、顕微鏡写真の写真コンペ企画です。 科学が照らす微小世界には、アートにも匹敵する驚きと美しさが広がっています。本企画は、この微小世界の美しさを写真という形で共有し、多くの人々にその魅力を届ける場を提供することを目的としています。
詳しくは,http://micro-art.tokyo/
Geo暦(2013)
2013年Geo暦(行事カレンダー)
2008年版 2009年版 2010年版 2011年版 2012年版 …… 2014年版
2013年版 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
○印は学会主催行事.(共)学会共催・(後)後援・(協)協賛
1月January
2012年度 古海洋学シンポジウム
(日本地質学会環境変動史部会 後援)
1月7日(月)〜8日(火)[7日 10:00〜、8日 9:00〜]
会場:東京大学大気海洋研究所(千葉県柏市)
事前申込:2012年12月7日(金)
http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/
第13回岩の力学国内シンポジウム
併催:第6回日韓ジョイントシンポジウム
1月9日(水)〜11日(金)
会場:沖縄コンベンションセンター
事前申込:2012年12月7日(金)
http://www.rocknet-japan.org/jsrm2013/
公開シンポジウム:科学者はフクシマから何を学ぶのか?−科学と社会の関係の見直し−
1月12日(土)13:00〜18:00
会場:日本学術会議会議室6階
http://www.scj.go.jp/ja/event/index.html
公開講演会(第3回国際北極研究シンポジウム)「今、北極がアツい!」
1月14日(月・祝)14:00〜16:15
会場:日本科学未来館7階みらいCANホール
http://www.jcar.org/isar-3/lecture.html
国際シンポジウム「世界水準の大学間の協力を通したグローバル理工系人材の育成」
1月17日(木)
場所:東京工業大学大岡山キャンパス
http://www.ipo.titech.ac.jp/tierforum/index.html
持続可能な社会のための科学と技術に関する国際会議「災害復興とリスク対応のための知"Wisdom for Recovery from Disasters and Risk Control"」
1月17日(木)、18日(金)
場所:日本学術会議 講堂
先着200名/各日(Webによる事前登録制) 入場無料・日英同時通訳あり
http://www.scj.go.jp/ja/int/kaisai/jizoku2012/ja/index.html
JABEEシンポジウム「海外の技術者教育認定の実例」
1月18日(金)14時〜
場所:芝浦工業大学豊洲キャンパス
http://www.jabee.org/OpenHomePage/news.htm
GSJ第20回シンポジウム「地質学は火山噴火の推移予測にどう貢献するか」
1月22日(火)
会場:秋葉原ダイビル・コンベンションホール
http://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo20/index.html
第58回日本水環境学会セミナー「東日本大震災後の水環境における放射性物質の挙動」
1月24日(木)
会場:自動車会館大会議室(千代田区九段南4-8-13)
詳細はこちら
Neo Ceramics2013 先端セラミックス&機能性ガラス先進応用技術展・会議
1月30日(水)〜2月1日(金)
会場:東京ビッグサイト(東京国際展示場)東1ホール
http://www.neoceramics.jp/
2月February
(後)日本学術会議主催 学術フォーラム
「自然災害国際ネットワークの構築にむけて: 固体地球科学と市民との対話」
2月1日(金)13:00〜18:00
場所:日本学術会議講堂(東京都千代田区乃木坂)
詳しくはこちら
岩手県立博物館平成24年度テーマ展関連シンポジウム
2月10日(日)〜11(月・祝)
会場:岩手県立博物館 講堂
聴講無料
http://www.pref.iwate.jp/~hp0910/exhibition/exhib24/tsunami/tsunami.html
「JAMSTEC2013」(平成24年度海洋研究開発機構研究報告会)
2月13日(水)13:00〜17:30
場所:東京国際フォーラム ホールB7 [Bブロック7階](千代田区丸の内3-5-1)
参加無料/申込不要
http://www.jamstec.go.jp/
第1回TONセミナー「宇宙から海洋への貢献」
2月14日(木)16:00〜19:00
場所:海洋研究開発機構 東京事務所 会議室(千代田区内幸町2-2-2富国生命ビル23F)
E-mail:techno-ocean@kcva.or.jp
Tel:078-302-0029 Fax:078-302-1870
○日本地質学会北海道支部平成24年度総会・講演会
2月16日(土)14:30-18:00
場所:北海道大学理学部6号館2階 6-204室
詳細はこちら
黒部・立山ジオパーク研究会設立記念シンポジウム
人と大地を繋げるジオパークー世界に誇る「ジオパーク」を目指してー
2月17日(日)13:30-15:30
会場:富山県民会館302会議室(富山市新総曲輪4-18)
問い合わせ:黒部・立山ジオパーク研究会事務局
Tel:090-1396-2089 E-mail:kurobe_tateyama_geopark@yahoo.co.jp
公開シンポジウム「天文・宇宙物理分野の将来計画」
2月17日(日)9:30-17:45、18日(月)9:30〜12:30
場所:東京大学理学系研究科小柴ホール(文京区本郷7-3-1)
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/167-s-3-7.pdf
第14回情報学シンポジウム 数値シミューションと情報学
2月19日(火)13:00-17:20
会場:京都大学百周年時計台記念館 百周年記念ホール
ICTイノベーション2013Webサイト
○日本地質学会西日本支部平成24年度総会・第163回例会
2月23日(火)
会場:島根大学松江キャンパス
22日夕刻に幹事会、23日夕刻に懇親会を予定。
講演申込締切:2月15日(金)17時
詳細はこちら
J-DESC陸上掘削部会「地学雑誌特集号:陸上掘削科学の新展開」出版記念シンポジウム
2月23日(火)13:00-18:00
会場:JAMSTEC東京事務所
http://www.j-desc.org/m3/events/130223_rikujo_sympo.html
国立公園フォーラム「ジオパークを活かした地域づくり〜新しい箱根の発見〜」
2月26日(火)14:00-16:00
場所:神奈川県立生命の星・地球博物館SEISAミュージアムシアター
問い合わせ:一般財団法人 自然公園財団 03-3556-0818
http://www.bes.or.jp/
平成24年度海洋情報部研究成果発表会
2月27日(水)13:15-17:45(12:50開場)
会場:海上保安庁海洋情報部10階国際会議室(江東区青梅2-5-18)
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/GIJUTSUKOKUSAI/koho/press/20130131_kenkyu.pdf
3月March
シンポジウム「地球史と海底カルデラ:海底火山活動を記録する伊豆半島とジオパーク」
3月5日(火)〜8日(金)
5日オープニング、6日一般シンポジウム、7〜8日巡検
会場:静岡県伊豆半島下田
http://www.archean.jp/
(共)津波堆積物国際ワークショップ
(International Workshop on the 2011 Tohoku-oki tsunami deposits)
3月8日(金)
会場:東北大学工学部総合研究棟101講義室
事前参加申し込み締め切り:2月28日(木)
http://www.irides.tohoku.ac.jp/event/tdeposit/index.html
問い合わせ:菅原大助 sugawara@irides.tohoku.ac.jp
○日本地質学会関東支部『地質研究サミット』シリーズ
第1回「房総・三浦地質研究サミット」
3月9日(土)〜10日(日)
5日オープニング、6日一般シンポジウム、7〜8日巡検
会場:千葉県立中央博物館(千葉市中央区青葉町955−2)
事前登録不要 参加費無料(要旨集代は別途):参加者は無料で千葉中央博物館展示室の見学可
懇親会:9日18:00〜 一般3000円、学生1500円当日申込可(できれば事前に事務局へメールで申込を)
※CPD単位取得可
問い合わせ/申し込み:高橋直樹 takahashin@chiba-muse.or.jp
第1回アジア太平洋地域大規模地震・火山噴火リスク対策(G-EVER)国際シンポジウム
-アジア太平洋地域の地震火山災害の現状と将来展望-
3月11日(月) 9:00-18:00
場所:産業技術総合研究所 共用講堂
http://g-ever.org/ja/symposium/
第47回日本水環境学会年会
3月11日(月)〜13日(水)
会場:大阪工業大学 大宮キャンパス
http://www.jswe.or.jp/event/lectures/index.html
ICDPワークショップ “Japan Beyond-Brittle Project (JBBP) - Scientific drilling to demonstrate a feasibility of the engineered geothermal system in ductile zones –”
3月12日(火)〜16日(水)
会場:東北大学工学部(仙台市青葉区)
参加申込締切:2013年3月1日
http://www.icdp-online.org/front_content.php?client=29&lang=28&idcat=309&idart=3557&m=&s=
平成24年度海洋研究開発機構成果発表会「ブルーアース2013」
3月14日(木)10:00-17:40、15日(金)10:00-17:20
場所:東京海洋大学品川キャンパス 白鷹館 講義棟(港区港南4-5-7)
問い合わせ:運航管理部計画グループ
Tel: 046-867-9865 E-mail: riyo-kobo@jamstec.go.jp
http://www.jamstec.go.jp
変成岩などシンポジウム
3月15日(金)〜17日(日)
(日本地質学会岩石部会後援)
会場:北海道定山渓温泉 ホテル鹿の湯(札幌市南区)
参加費:21,000円
問い合わせ:竹下 徹 torutake@mail.sci.hokudai.ac.jp
(後)ひょうご恐竜化石国際シンポジウム「白亜紀前期の恐竜研究最前線」
3月16日(土)
17日関連事業あり(フォーラム・ワークショップ等)
会場:兵庫県立人と自然の博物館 ホロンピアホール(兵庫県三田市弥生が丘6)
申込締切:2月22日(金)必着
http://hitohaku.jp/top/dinosaur_symp.html
第8回「海洋と地球の学校」
3月19日(火)〜23日(土)(講義3日間、巡検2日間)
場所:高知県立青少年センターほか
http://www.jamstec.go.jp/j/pr/school/008/index.html
スプリング・サイエンスキャンプ2013
3月23日(土)〜28日(木)[うち2泊3日〜3泊4日]
申込締切:1月22日(火)必着
http://rikai.jst.go.jp/sciencecamp/camp/
International Petroleum Technology Conference(IPTC)
3月26日(火)〜28日(水)
場所:Beijing, China
http://www.iptcnet.org/
4月April
European Geosciences Union General Assembly 2013
4月7日(日)〜12日(金)
場所:Vienna (Austria)
講演要旨締切:1月9日(水)
旅費補助等希望締切:2012年11月30日(水)
http://www.egu2013.eu
日本堆積学会2013年千葉大会
4月10日(水)〜15日(月)
場所:千葉大学西千葉キャンパスけやき会館ほか
講演申込締切:3月15日(金)
http://sediment.jp/04nennkai/2013/annnai.html
第149回深田研談話会
「レアアース泥鉱床は日本を救えるか?」
4月12日(金)
申し込み締切:4/10 先着:80名
会場:深田地質研究所 研修ホール(文京区本駒込2-13-12)
http://www.fgi.or.jp/
○日本地質学会関東支部2013年度総会 地質技術伝承講演会
4月13日(土)
場所:北とぴあ(東京都北区王子1-11-1)
地質技術伝承会 14:00〜16:00(予定)CPD単位取得可
関東支部総会 16:00〜16:45(予定)
問い合わせ:笠間友博 kasama@nh.kanagawa-museum.jp
CHIKYU+10 国際ワークショップ
4月21日(日)〜23日(火)
場所:一橋講堂(東京都千代田区一ツ橋)(予定)
White paperの受付:1/7〜31
Registration:1/7〜4/5
http://www.jamstec.go.jp/chikyu+10/
○日本地質学会北海道支部「地質の日」記念展示「豊平川と共に—その恵みと災い—」
4月23日(火)〜6月2日(日)
場所:北海道大学総合博物館3階「企画展示室」
詳細はこちら
○日本地質学会北海道支部例会(個人講演会)
4月27日(土)10:00-18:00
場所:北海道大学理学部5号館2階 5-201室
詳細はこちら
5月May
○日本地質学会西日本支部 身近に知る『くまもとの大地』
5月11日(土)
場所:熊本市
http://www.geosociety.jp/name/content0099.html
第150回深田研談話会
5月10日(金)15:30〜17:30
会場:深田地質研究所研修ホール(文京区本駒込2-13-12)
定員:80名(先着順) 参加費:無料
申込締切:5/8(申込受付開始:4/15〜)
http://www.fgi.or.jp/
(後)三浦半島活断層調査会・地質情報普及講座 地質の日・記念観察会『深海から生まれた城ヶ島 』
5月11日(土)10:00〜15:00(小雨決行)
集合場所:城ヶ島バス停
申込締切:5/3 募集人数:50名
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//others-pic/2013jogashima-miura.gif
○2013年地質の日 街中ジオ散歩 in Tokyo「石神井川がつくる地形の移り変わりと地質(仮)」
5月12日(日)10:00〜16:00 雨天決行(予定)
(主催:日本地質学会・日本応用地質学会)
場所:東京都北区王子界隈(JR王子駅西側の台地上に発達する石神井川、逆川付近)
http://www.geosociety.jp/name/content0098.html
○日本地質学会近畿支部 地球科学講演会「大阪平野の地盤環境と地盤災害」
5月12日(日)14:00〜15:30
(主催:日本地質学会近畿支部・大阪市立自然史博物館・地学団体研究会大阪支部)
場所:大阪市立自然史博物館講堂
http://www.geosociety.jp/name/content0099.html
(共)2013 Western Pacific Sedimentology Meeting
5月13日(月)〜18日(土)
(13日・14日:研究発表、15日〜18日:巡検)
場所:The Longtan Aspire Resort, Taoyuan, northern Taiwan
講演要旨締切:2月28日
登録締切:3月15日
http://wpsm.ncu.edu.tw/
○日本地質学会第5回(2013年度)総会
5月18日(土)
場所:北とぴあ 第2研修室(北区王子1-11-1)
http://www.geosociety.jp/outline/content0111.html
日本地球惑星科学連合2013年大会
5月19日(日)〜24日(金)
場所:幕張メッセ国際会議場(千葉市美浜区)
5/19:パブリックセッション(一般対象:参加費無料)
5/20-24昼休み:スペシャルレクチャー(大学生・若手研究者対象)
http://www.jpgu.org/meeting/index.htm
Cordilleran Section, GSA 109th Annual Meeting
5月20日(月)〜22日(水)
場所:Fresno, CA
Abstracts Deadline: 19 Feb. 2013
http://www.geosociety.org/Sections/cord/2013mtg/
第2回TONセミナー「水産と工学の連携」
5月23日(木)
場所:海洋研究開発機構東京事務所会議室(千代田区内幸町2-2-2富国生命ビル23F)
E-mailまたはFAXにて申込,先着60名
テクノオーシャン・ネットワーク(TON)事務局
techno-ocean@kcva.or.jp FAX: 078-302-1870
地球惑星科学NYS若手合宿2013
5月24日(金)〜26日(日)
場所:東京大学検見川セミナーハウス
定員:50名(学部生以上)
参加申込締切:4/26(定員を超えた場合、締切前に申し込み終了する場合あり)
https://sites.google.com/site/nyswakate2013/home
○第3回関東支部ミニ巡検=房総・三浦研究サミット関連巡検第1弾
『房総半島南東部夷隅地方における正断層群』
5月25日(土)〜26日(日)
集合場所:JR蘇我駅(自家用車参加不可)
募集人数:10名(先着順)
参加申込締切:4/25
http://kanto.geosociety.jp/
東京大学大気海洋研究所共同利用研究集会
5月27日(月)〜28日(火)
場所:東京大学大気海洋研究所2F 講堂(千葉県柏市柏の葉5-1-5)
プログラム(日本語) Program (English)
6月June
第26回東京国際ミネラルフェア
6月7日(金)〜11日(火)10:00-18:00(最終日は17:00まで)
場所:小田急第一生命ビル2F 特別展示場(新宿区西新宿二丁目7番1号)
GSC-GSA Joint meeting in China
6月17日(月)〜19日(水)
場所:Chengdu, China - Jinjiang Hotel, Chengdu, Sichuan Province
Abstracts deadline: March 1, 2013
http://www.geosociety.org/meetings/2013china/
Astrobiology Grand Tour
6月18日(火)〜28日(金)
場所:西オーストラリア
http://aca.unsw.edu.au/node/78
深田研ジオフォーラム2013
6月22日(土)9:30-16:30(受付開始9:00)
場所:深田地質研究所研修ホール(文京区本駒込2-13-12)
申込締切:6月19日(水)[定員50名:定員に達し次第締切]
http://www.fgi.or.jp
地質学史懇話会
6月23日(日)13:30〜17:00
場所:北とぴあ8階808号室(北区王子1-11-1 京浜東北線王子駅下車3分)
・中川智視 『小泉八雲と服部一三 —富山大学ヘルン文庫の調査から見えてきた意外な関係—』
・平林憲次 『戦前から現在までの北樺太の石油開発−話題提供・石油地質を中心として−』
問い合わせ先:矢島道子 pxi02070@nifty.com
資源地質学会第63 回年会学術講演会
6月26日(水)〜28日(金)
会場:東京大学小柴ホール
http://www.resource-geology.jp/events/#p86
石油技術協会平成25年度春季講演会
6月27日(木)〜28日(金)
場所:国立オリンピック記念青少年総合センター(代々木)
http://www.japt.org/
日本古生物学会2013年年会
6月28日(金)〜6月30日(日)
場所:熊本大学
http://www.palaeo-soc-japan.jp/Japanese/index.html
森里海シンポジウム「人と自然のきずな〜森里海連環学へのいざない〜」
6月29日(土)
場所:東京都港区赤坂1丁目2番2号 日本財団ビル
参加費無料
http://fserc.kyoto-u.ac.jp/cohho/index/130629sympo
7月July
(共)第50回アイソトープ・放射線研究発表会
7月3日(水)〜5日(金)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区)
申込締切2月28日(木)
http://www.jrias.or.jp/
GSJ第21回シンポジウム
「古地震・古津波から想定する南海トラフの巨大地震」
7月10日(水)
場所:秋葉原ダイビル コンベンションホール
http://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo21/index.html
第151回深田研談話会
「放射性物質を追跡して環境変化を捉える」
7月12日(金)
申し込み締切:7/10 先着:80名 参加無料
会場:深田地質研究所 研修ホール(文京区本駒込2-13-12)
http://www.fgi.or.jp/
東京大学海洋アライアンス・日本財団共同シンポジウム
日本海:小さな海の大きな恵み
7月15日(月)
場所:日本橋三越本店(東京都中央区日本橋室町1−4−1)
定員500名 入場無料
https://www.webmasters.co.jp/utoa/symp03/
(後)国際火山学地球内部化学協会2013年学術総会
「IAVCEI2013 Scientific Assembly」
7月20日〜24日
場所:鹿児島県鹿児島市
http://www.iavcei2013.com/
サマー・サイエンスキャンプ2013
7月23日〜8月28日の期間中の2泊3日〜4泊5日
会場:大学、公的研究機関、民間企業等(58会場)
応募締切:6月14日(金)必着
http://rikai.jst.go.jp/sciencecamp/camp/
第48回地盤工学研究発表会
7月23日(火)〜26日(金)
会場:富山国際会議場、富山市民プラザ、富山県民会館
入場無料、事前申込不要
問い合わせ:地盤工学会北陸支部 025-281-2125 jibanhokuriku@piano.ocn.ne.jp
○緊急研修会『地表付近の地質学的調査における応用地質学的・土木地質学的留意点』
主催:日本地質学会関東支部
7月27日(土)10:00-17:00
会場:日本大学文理学部3号館5階3507号室
申込締切:7月19日(金)[関東支部宛 kanto@geosociety.jp]
問い合わせ:関東支部幹事長 笠間友博(神奈川県立生命の星・地球博物館)
E-mail:kasama@nh.kanagawa-museum.jp Tel:0465−21—1515
http://kanto.geosociety.jp/
変形・透水試験機設計セミナー2013
7月31日(水) 13:00 〜 8月2日(金)12:00
場所:広島大学大学院理学研究科
申込締切:6月28日(金)
問い合わせ:廣瀬丈洋 hiroset@jamstec.go.jp,片山郁夫 katayama@hiroshima-u.ac.jp
8月August
第22回市民セミナー「身近な水環境、池・沼・湖の保全を考える−ため池から琵琶湖まで」
8月2日(金)10:00-1630
場所:
東京会場:地球環境カレッジ(いであ(株)内)(東京都世田谷区駒沢)
大阪会場:いであ(株)大阪支社ホール(大阪市住之江区南港北)
申し込み・問合せ先:(公社)日本水環境学会セミナー係 戸川
TEL:03-3632-5351 FAX:03-3632-5352
e-mail:togawa@jswe.or.jp
詳しくはこちら
第14回地震火山こどもサマースクール「南から来た大地のものがたり」
8月3日(土)〜 4日(日)
集合・解散 :道の駅「下田開国みなと」(静岡県下田市外ヶ岡1-1,伊豆急行下田駅から徒歩10 分)
参加条件 :小学5年生〜高校生(全行程,保護者の同伴や特別の支援が必要なくても参加できる方)
申込締切:7/21(定員:40名)
http://www.kodomoss.jp/ss/izugeopark/
(後)室戸ジオパークサマースクール2013「来るならきいや南海地震、土佐はうちが守るきね!」
8月8日(木)〜9日(金)
場所:室戸市内の海岸、室戸市保健福祉センター、国立室戸青少年自然の家
対象:小学校5年生〜高校3年生まで
募集期間:6/15〜7/16(定員:35名)
http://ss.muroto-geo.jp/
(後)第6回地殻応力国際シンポジウム
8月20日(火)〜22日(木)
会場:仙台国際センター(宮城県仙台市)
講演申込期限:2012年11月30日(金)
http://www2.kankyo.tohoku.ac.jp/rs2013/
Joint Conference of 28th Himalaya-Karakoram-Tibet (HKT) workshop and 6th International Symposium on Tibetan Plateau(第28回HKTワークショップと第6回チベット高原に関する国際シンポジウムの合同大会)
8月22日(木)〜24日(土)
場所:Tübingen University, Germany
講演要旨締め切り:6月30日
ポストコンファレンス巡検
1. 8/25〜31:Geological Highlights of the Western Alps
2. 8/25〜30:Environment
問い合わせ:酒井治孝(hsakai@kueps.kyoto-u.ac.jp)
http://www.tip.uni-tubingen.de/index.php/en/hkt-istp-2013-tuebingen
9月September
(共)第57回粘土科学討論会
9月4日(水)〜6日(金)
会場:高知市文化プラザかるぽーと
参加・講演の申込期間 :6月3日(月)〜 14日(金)
講演要旨送付締切 :7月12日(金)
http://www.cssj2.org/
(共)2013年度日本地球化学会年会
9月11日(水)〜13日(金)
会場:筑波大学第一エリア1D、1E棟
固有セッション申込:6月13日(木)〜 7月17日(水)
共通セッション申込:6月7日(金)〜 23日(日)
事前参加登録締切:8月23日(金)(予定)
http://www.wdc-jp.biz/geochem/2013/
◯日本地質学会第120年学術大会
9月14日(土)〜16日(月・祝)
会場:東北大学川内北キャンパス ほか
講演申込締切:7/2(火)17時[郵送締切6/26(水)必着]
事前参加登録締切:8/20(火)18時[郵送締切8/16(水)必着]
仙台大会ホームページ
○第4回津波堆積物ワークショップ
9月14日(土)9:00-12:00
会場:東北大学川内北キャンパス マルチメディア棟M206号室
http://www.geosociety.jp/science/content0057.html
第30回歴史地震研究会
9月14日(土)〜16日(月・祝)
会場:秋田大学
講演発表申込締切 :5月31日(金)
講演要旨送付締切 :7月31日(水)
懇親会・巡検・昼食申込締切 :7月31日(水)
http://sakuya.ed.shizuoka.ac.jp/rzisin/menu7.html
○第5回津波堆積物ワークショップ
9月18日(水)10:00-16:15
会場:東北大学川内北キャンパス マルチメディア棟M206号室
http://www.geosociety.jp/science/content0057.html
第63回東レ科学講演会
9月20日(金)17:00-21:00
場所:有楽町朝日ホール(有楽町マリオン11F)
http://www.toray.co.jp/tsf/index.html
日本動物学会 岡山大会2013
特別講演「緑色蛍光たんぱく質の発見ー探求する心」
9月27日(金)13:00〜14:15
会場:岡山市民会館
一般公開講演会「科学の運 偶然か,必然か? -ウナギ研究40年をふりかえって-」
9月28日(土)15:00〜16:30
会場:岡山大学一般教育棟 (津島キャンパス) A棟2階 A21 教室 (A会場)
詳しくはこちら
第152回深田研談話会(現地)
9月28日(土)8:45〜16:30
見学場所(予定):神田明神・湯島聖堂、神田佐久間町、回向院ほか
参加費:3000円 定員:30名
申込締切 :9月3日(火)
http://www.fgi.or.jp/
あいちサイエンスフェスティバル2013
9月28日(土)〜11月4日(月・祝)
会場:蒲郡市生命の海科学館など
※(共)惑星地球フォトコンテスト入賞作品展
https://aichi-science.jp/
2013 International Association for Gondwana Research (IAGR) and 10th Gondwana to Asia, in collaboration with IGCP 592.
会議およびシンポジウム:9月30日(月)〜10月2日(水)
巡検(Hongseong eclogite and Imjingang Collisional Belt):10月3日(木)~4日(金)
発表要旨締切:7月31日(sungwon@kigam.re.kr) 登録締切:8月31日
場所:韓国Daejeon(大田広域市)のKIGAM(Korean Inst. Geosci. and Mineral Resources)
http://iagr2013.kigam.re.kr or http://www.elsevier.com/locate/gr
10月October
国際ミネラルアート&ジェム展 IMAGE 2013
10月4日(金)〜7日(月)
場所:ハイアット・リージェンシー東京/小田急第一生命ビル1F スペースセブンイベント会場ほか
http://www.tima.co.jp
講演会『地球深部探査船「ちきゅう」が解き明かす東北沖地震の謎』
10月12日(土)14:00〜
場所:東北大学片平キャンパス さくらホール(2階)
事前登録不要 入場無料
http://www.cneas.tohoku.ac.jp/news/2013/news130910_1.html
(共)第2回G-EVER国際シンポジウム,第1回IUGS・日本学術会議国際ワークショップ
アジア太平洋地域の災害とリスクマネジメント: 沈み込み帯の地震・津波・火山噴火・地すべり
10月19日(土)〜20日(日)[21日巡検あり]
場所:仙台市情報・産業プラザ
講演要旨投稿締切:8/20 参加登録:9/15(登録料無料,先着70名)
http://g-ever.org/en/symposium/symposium2.html
深田研 一般公開2013
10月20日(日)
場所:深田地質研究所(文京区本駒込2-13-12)
http://www.fgi.or.jp
日本学術会議:公開シンポジウム − 学協会の新公益法人法への対応の現状と展望 −
10月22日(火)13:00〜16:40
場所:日本学術会議 講堂(東京都港区六本木 7-22-34)
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/177-s-1022.pdf
The 11th International Symposium on Mitigation of Geo-Disasters in Asia
10月22日(火、カトマンズ)、24日(ポカラ)会議
10月23日、25日〜28日(日)巡検
場所:カトマンズ・ラディソンホテル及びポカラ・バラヒホテル
参加登録料(巡検経費込み):450ドル(学生は半額)
http://hils.org.np/hils/mgda/2ndCircular.pdf
(後)山陰海岸ジオパーク国際学術会議「城崎会議」
テーマ:自然の恵と災害
10月26日(土)〜27日(日)
場所:城崎温泉西村屋ホテル招月庭(兵庫県豊岡市城崎町)
要旨提出締切:9月6日(金)
http://www.sanin-geo.jp/
平成25年度 東濃地科学センター 地層科学研究 情報・意見交換会
10月29日(火)13:10〜17:00
場所:瑞浪市地域交流センター「ときわ」(岐阜県瑞浪市)
定員:約150名 申込締切:10/10
http://www.jaea.go.jp/04/tono/topics/topics1308_1/1308_1.html
瑞浪超深地層研究所 深度300m水平坑道見学会」
日時:平成25年10月30日(水)9:15〜12:00
場所:瑞浪超深地層研究所
定員:40名 申込締切:10/10
http://www.jaea.go.jp/04/tono/topics/topics1308_1/1308_1.html
11月November
The International Biogeoscience Conference 2013 Nagoya, Japan
11月1日(金)〜4日(月)
場所:名古屋大学
詳細・申込等はこちらから
第67回日本人類学会大会・総会
11月1日(金)〜4日(月)
場所:国立科学博物館筑波研究施設ほか
企画募集締切:5/31 演題募集・参加登録締切:8/9
http://www.gakkai.ne.jp/anthropology/67_annual_meeting
錦秋 筑波山地域ジオツアー
11月2日(土)9:00-17:00
場所:TXつくば駅集合・解散
参加人員:約20名 費用:2000円
http://www.geog.or.jp/tour/tourscheduled/190-25.html
東海地震防災セミナー2013
11月7日(木)13:30−16:00
会場:静岡商工会議所静岡事務所5階ホール(JR静岡駅北口西側)
連絡先:土 隆一(土研究事務所)
Fax:054-238-3241/Tel.:054-238-3240
第16回日本水環境学会シンポジウム
11月9日(土)〜10日(日)
会場:琉球大学千原キャンパス(農学部)(沖縄県西原町字千原1)
http://www.jswe.or.jp/
(共)公開シンポジウム
『新第三紀の終焉と第四紀の始まり−東海層群から読み解く気候変動− 』
11月10日(日)13:00-16:30
場所:三重県総合博物館 レクチャールーム
参加費:無料
http://www.geosociety.jp/outline/content0096.html
日本情報地質学会シンポジウム
「地質情報等の三次元モデリングとCIMについて」
11月13日(水)
会場:産総研 臨海副都心センター 本館4階 第1会議室(東京都江東区)
http://www.jsgi.org/symposium2013.html
学術フォーラム「地殻災害の軽減と学術・教育」
11月16日(土)10:00-17:00
場所:日本学術会議講堂
参加費:無料 申し込み:不要、当日先着順
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/178-s-1116.pdf
JAXAシンポジウム
「宇宙開発のためのテクノロジー最前線〜マテリアルやロケットエンジンの分野について〜」
11月18日(月)14:30-17:00
場所:東北大学片平さくらホール
申込締切:11/8
http://res.tagen.tohoku.ac.jp/~jaxasymp/form1.html
日本学術会議 九州・沖縄地区会議学術講演会
「かごしまの水を考える ‐鹿児島大学『水』研究最前線‐」
11月18日(月)14:30-17:00
場所:鹿児島大学稲盛会館【キミ&ケサ メモリアルホール】(鹿児島市郡元1丁目21-40)
入場無料
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/177-s-1118.pdf
第22回東北大学素材工学研究懇談会「金属素材供給ボトルネック解決のための新技術」
11月19日(火)10:00-17:05
場所:東北大学片平さくらホール
申込締切:10/31
http://www.tagen.tohoku.ac.jp/
日本学術会議 中部地区会議学術講演会
「大学からの知の発信 〜文理融合の視点から〜 」
11月20日(水)13:00-16:00
場所:名古屋大学物質科学国際研究センター2階野依記念講演室(名古屋市千種区不老町)【東山キャンパス】
入場無料
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/179-s-1120.pdf
第24回地質汚染調査浄化技術研修会
日本地質学会環境地質部会 ほか 共催
11月22日(金)〜24日(日)
会場:NPO法人日本地質汚染審査機構本部ミーテング・ルーム
http://www.npo-geopol.or.jp
(協)第39回リモートセンシングシンポジウム
11月25日(金)
場所:東京農業大学世田谷キャンパス
申込締切:11/1 講演申込締切:10/15
http://www.sice.jp/
森里海連環学国際シンポジウム
11月26日(火)〜28日(木)
場所:京都大学芝蘭会館
http://fserc.kyoto-u.ac.jp/isymposium/
(協)第29回ゼオライト研究発表会
11月27日(水)〜28日(木)
場所:東北大学
企画募集締切:5/31 演題募集・参加登録締切:8/9
http://www.jaz-online.org/index.html
第23回環境地質学シンポジウム
日本地質学会環境地質部会 ほか 共催
11月29日(金)〜30日(土)
場所:産業技術総合研究所(つくば)共用講堂
http://www.jspmug.org/
第22回GSJシンポジウム
「アカデミックから身近な地質情報へ」
11月30日(土)13:00-18:00
場所:AP東京八重洲通り 11F
定員:150名
http://www.gsj.jp/sympo22
12月December
第2回人工地層と地質汚染国際シンポジウム
日本地質学会環境地質部会 ほか 共催
12月1日(日)〜2日(月)※3日(火)〜4日(水)巡検
場所:1-2日:潮来ホテル(茨城県潮来市あやめ1-10-7)
詳しくはこちら
平成25年度国土技術政策総合研究所 講演会
12月3日(火)10:00-17:15
場所:日本教育会館一ツ橋ホール
http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/kouenkai/kouenkai2013/kouenkai2013.htm
日本学術会議公開シンポジウム
「増大する災害と地球環境問題に地球人間圏科学はどう取り組むか?」
12月5日(木) 13:00〜17:00
会場:日本学術会議講堂(東京都港区六本木7-22-34)
事前申込不要
http://www.jpgu.org/images/scj_sympo/scj_sympo_20131205.pdf
第13回東北大学多元物質科学研究所研究発表会
12月6日(金)9:50-20:00
場所:東北大学片平さくらホール
http://www.tagen.tohoku.ac.jp/general/info/event/meeting/2013/
産業技術連携推進会議 地質地盤情報分科会 講演会
「東日本大震災による液状化被害と地質地盤情報の活用」
12月6日(金)
会場:明海大学浦安キャンパス(浦安市明海)
https://www.gsj.jp/information/domestic/sgr/index.html
信州大学山岳科学総合研究所シンポジウム
「日本アルプスの大規模地すべり:第四紀地形学・地質学の視点から」
12月7日(月)10:00〜16:50
場所:信州大学理学部C棟2階大会議室(松本市旭3-1-1)
参加費および事前申し込み不要
http://ims.shinshu-u.ac.jp/documents/2013/event2013.html#131207
地球化学研究協会「公開講座」
(第50回霞ヶ関環境講座、第41回三宅賞受賞者受賞記念講演、第1回進歩賞受賞者研究概要紹介)
12月7日(土)14:10-
場所:霞が関ビル35階 東海大学校友会館
参加費:賛助会員および学生は無料、一般1,000円(資料代を含む)
http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~e881147/Geochem/
日本学術会議 中国・四国地区会議学術講演会
「大災害への備え—いのちと暮らしを守るために—」
12月7日(土)13:30-17:00
場所:かがわ国際会議場(サンポート高松:JR高松駅前シンボルタワー、タワー棟6階)
参加無料、要事前申込
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/177-s-1207.pdf
第155回深田研談話会
森林に学ぶ〜「持続性」を導く分子規格と社会規格〜
12月13日(金)
申し込み締切:12/11 先着:80名 参加無料
会場:深田地質研究所 研修ホール(文京区本駒込2-13-12)
http://www.fgi.or.jp/
地質学史懇話会
12月23日(月)13:30〜
場所:北とぴあ803号室(北区王子1-11-1)
・長田敏明「戦前の満州の科学博物館の活動について(仮)」
・小野田滋「地質工学の開拓者・渡辺貫とその周辺(仮)」
問い合わせ先:矢島道子 pxi02070@nifty.com
▶▶ 2014年版へ
Geo暦(詳細)2012
Geo暦:詳細等
詳細・申込方法等
★第6回ジオ多様性フォーラム
「ジオ多様性とは何か、その重要性を問う」
2012年12月21日(金)・22日(土)
場所:JAMSTEC東京事務所
12月21日 15:00-
木村 学(東京大学)「沈み込み帯の多様性と深海掘削」
山室真澄(東大・新領域)「水辺の緑と地形 −自然再生の現場から」
守屋以智雄(金沢大学名誉教授)「世界の火山の多様性」 >懇親会
12月22日 9:00〜
江頭宏昌(山形大学農学部)、「山形県庄内地方の地理的条件と伝統作物」
古川雅英(琉球大学)「ジオ多様性が紡ぐ自然放射線レベル」
他2講演
連絡先:矢島道子 pxi02070@nifty.com
★「第二回津波堆積物ワークショップ」
第二回津波堆積物ワークショップを紀伊半島にて開催いたします(第一回は日本堆積学会で今春実施).
ワークショップでは,『津波の水理』,『南海トラフ沿い津波堆積物』,『津波堆積物と津波防災』,『津波堆積物の認定』といったトピックをテーマに講演を行います.実際の津波堆積物のはぎ取り試料も用いて認定基準等についての議論も行う予定です.
翌日からの巡検は,紀伊半島において津波堆積物が見つかった場所,見つからなかった場所を周り,なぜそのような結果となったのか,また,今後の津波堆積物調査地選定のためのポイントを考えていただく内容になります(※露頭見学はありません).
日程:2012年10月6日(土)〜8日(月)
10月6日(土) ワークショップ(※この日の宿泊は各自でお手配下さい)
会場:津市三重県総合文化センター大研修室(三重県津市一身田上津部田1234 電話059-233-1111)
10月7日〜8日 巡検(鳥羽−尾鷲)
<WSスケジュール>10月6日(土)
10:30-10:40 挨拶と趣旨説明
10:40-11:10 小松原純子(産総研)「南海トラフ沿いの津波堆積物研究」
11:10-11:40 藤野滋弘(筑波大学)「津波堆積物の特徴と古津波堆積物の調査方法」
11:40-13:15 昼休み
13:15-13:45 菅原大助(東北大学)「数値シミュレーションからみた津波の水理学的特性と土砂移動の関係」
13:45-14:15 後藤和久(東北大学)「津波堆積物と津波防災」
14:15-14:45 総合討論
15:15-15:45 剥ぎ取り試料,コア観察
<巡検スケジュール>10月7日(日)
9:00
鳥羽駅前集合(『ホテル戸田家』前 出入口2を出て徒歩5分)
→集合場所MAPはこちらから
9:45–10:15
Stop 1 三重県鳥羽市相差町宇塚
11:05–11:35
Stop 2 三重県志摩市阿児町志島
12:00–12:30
横山展望台 昼食,トイレ休憩
14:00–14:20
Stop 3 三重県度会郡南伊勢町奈屋浦コガレ池
15:35–16:05
Stop 4 三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区海野
17:00
尾鷲着--尾鷲泊(シティホテル望月)
10月8日(月)
8:00
尾鷲 シティホテル望月 発
9:30–9:45
Stop 5 三重県南牟婁郡御浜町志原
10:10–10:25
Stop 6 三重県南牟婁郡御浜町阿田和
11:05–11:20
Stop 7 和歌山県新宮市佐野
移動車中-昼食
12:45–13:05
Stop 8 和歌山県東牟婁郡串本町
13:10–13:20
解散地点1 JR紀勢本線(きのくに線)串本駅
15:25–15:35
解散地点2 JR紀勢本線(きのくに線)白浜駅
15:50
解散地点3 南紀白浜空港
<募集人数> 参加申込は締切ました(8/31)→申込者へは9/5付けで参加の可否についてメールでご連絡いたしました。
●ワークショップ 定員150名(予定)
●巡検 定員15名(予定)
<参加費>※参加費は当日徴収させて頂きます。
●ワークショップのみ参加(10月6日) 2500円
●巡検のみ参加(10月7,8日) 26000円(バス代・宿泊費・保険料等含む)
●ワークショップ・巡検両方参加 28500円(バス代・宿泊費・保険料等含む)
<キャンセルについて>
巡検のキャンセルは9月14日(金)まで受付いたします.これを過ぎますと,キャンセル料を頂く可能性があります.
<問い合わせ先>
日本堆積学会津波ワーキンググループ ssjng@ml.fukuoka-u.ac.jp
★第5回ジオ多様性フォーラム
「ジオ多様性とは何か、その重要性を問う」
2012年6月8日(金)・9日(土)
場所:JAMSTEC横浜事務所
6月8日 15:00-17:30
松原 聡(国立科学博物館)「鉱物の多様性」
横山玲子(東海大学文学部 教授)「中南米の都市と建築」
高橋雅紀(産総研 主任研究員)「ジオ多様性と研究者多様性」
6月9日 9:30〜
村上哲明(首都大学東京・牧野標本館)「日本列島における野生植物種内の遺伝的多様性の分布と地史」
高木秀雄(早稲田大学 教育・総合科学学術院 教授)「日本の地質構造の多様性ー水平から垂直へ」
横山俊夫(滋賀大学)「多様であることが意味を持つとき (仮題)」
大野照文(京都大学総合博物館 教授・館長)「地球史を通じた生物進化と環境のからみ」
昼食、午後は基本的になし
基本的に発表者は30分、討議は10分、休憩(余裕)5分
連絡先:矢島道子 pxi02070@nifty.com
※詳細が記載されているWebサイトがない行事のみ掲載
2012年度各賞受賞者
2012年度各賞受賞者 受賞理由
■日本地質学会賞(1件)
■Island Arc賞(1件)
■小澤儀明賞(1件)
■論文賞(2件)
■小藤賞(1件)
■小藤文次郎賞(1件)
■研究奨励賞(3件)
■学会表彰(2件)
日本地質学会賞
受賞者:木村 学(東京大学大学院理学系研究科)
対象研究テーマ:テクトニクス,付加体地質学,沈み込みプレート境界地震発生帯物質科学
木村学氏は,北海道大学での博士号取得後,香川大学・大阪府立大学・東京大学においてテクトニクスの研究・教育に携わってきた.その研究歴の初期においては,北海道をフィールドに,プレート斜め沈み込みに伴う千島前弧スリバーの衝突を提唱した.この研究はその後,島弧会合部のテクトニクスおよび東アジア全体のテクトニクスとして拡充・一般化された.また,旧ソ連サハリン,カナダ,米国西海岸,オーストラリア等の調査に基づき,世界各地の造山帯における付加作用および大陸成長過程の解明を試みた.さらに,四万十帯中のメランジュの構造地質学的解析から沈み込みプレート境界浅部の変形過程を詳細に示した.
1990年代後半から,木村氏の主導する四万十帯の研究は沈み込み帯地震発生帯物質科学へと発展し,陸上付加体におけるシュードタキライトの認定や断層への流体圧の影響な ど,海溝型地震の震源域から破壊伝播域にかけての物性や滑り特性を天然から定量的に解明しつつある.同時に木村氏は海洋付加体の掘削研究も推し進め,統合国際深海掘削計画(IODP)における南海トラフ地震発生帯掘削計画をリードした.また,ODP第170次航海,IODP第316次航海では共同主席研究者として乗船し,コスタリカ沖中米海溝の造構性浸食作用,熊野沖南海トラフの断層運動史の解明・浅部断層の摩擦発熱の解明など多くの成果を示した.現在では新学術領域研究「超深度海溝掘削」の研究代表者として,沈み込みプレート境界に関わる幅広い研究分野の融合を具現化している.
学界活動においては,長年にわたって地質学会評議員を務め,地質学会会長時には学会の法人化を進めるなど,その発展に大きく貢献した.また,日本地球惑星科学連合の初代会長として,地球惑星科学全体の国内および国際的地位の向上に尽力した.教育面においても,プレート収束帯や付加体に関わる教科書を上梓するとともに第一線で活躍する若手研究者を数多く養成している.
木村氏の得意とするのは,その幅広い視野のもと根源的な問題を抽出し,丁寧な地質学的観察と学際的共同研究からそれを解きほぐしていく研究スタイルで,常に第一線に立ってインパクトのある成果を出し続けている.また,社会的活動にも積極的に関わり,地質学会および地球惑星科学界の発展と地位の向上に大きく貢献している.木村氏は日本地質学会賞にふさわしい優秀な業績をおさめており,ここに推薦するものである.
日本地質学会Island Arc賞
受賞論文:Barber, A. J. and Crow, M. J., 2009.Structure of Sumatra and its implications for the tectonic assembly of Southeast Asia and the destruction of Paleotethys.Island Arc, 18, 3-20.
Barber and Crow use their extensive knowledge of a wide range of geological information to address the complex paleogeography of the SE Asian region with special focus on Sumatra and its three constituent continental blocks: the East Malay, Sibumasu and West Sumatra blocks. In this paper the authors argue for a Mid Permian to Upper Triassic collision between the Sibumasu and East Malay blocks in Sumatra and discuss the possibility of later amalgamation further to the north. They also revise previous estimates for the age of the main transcurrent movements between the Sibumasu and West Sumatra blocks suggesting these were largely complete by Mid Triassic. These workers also suggest the West Sumatra Block may be correlated with the West Burma block to the north and present an interpretation of the Woyla block as an intraoceanic arc.These ideas are presented using a series of clear diagrams. The ideas presented in this paper are likely to stimulate further discussion and lead to a better understanding of the paleogeography of this region. The first author has been active in the research of eastern Asia including Japan, for more than 30 years.
This paper adds his many contributions and is a worthy recipient for the 2012 Island Arc award.
日本地質学小澤儀明賞
受賞者:山本伸次(東京大学大学院総合文化研究科)
対象研究テーマ:造山運動論
山本伸次氏は,地球史 的観点に立って固体地球 変動の解読を目指す立場から,野外地質調査を軸とした岩石学・鉱物学の研究を進めている.彼は,東京工業大学の博士課程在学中,南チベットのオフィオライト岩体について鉱物学的な研究を行い,そのかんらん岩体中のクロミタイトが深部マントル由来であることを示す直接的な(in situの)証拠を初めて見出した.それは,透過型電子顕微鏡による分析の結果明らかになったクロマイト中の微細な珪酸塩鉱物,すなわちコーサイトと単斜輝石の離溶相である.これは,珪酸塩を離溶する以前の前駆相がクロマイトの高圧多形(CaFe2O4型;圧力>12.5GPa,深さ>380km)であった可能性を示す.そして,このかんらん岩体をマントル浅部にもたらした上昇流が,マントル遷移層の深さに由来することが示唆される.この研究結果は,天然の超高圧岩石の研究におけるナノ鉱物学探査の重要性をよく示しており,2009年の国際学術誌に印刷された.
山本氏は2007年に学位取得後,2010年度までは東京工業大学において,また2011年度は東京大学において,大陸成長に関する研究を行ってきた.従来,大陸を成長させる主要なメカニズムは海洋性島弧地殻の衝突・付加であると一般に考えられてきた.これに対して山本氏は,実際の海洋性島弧地殻のほとんどはそのままマントルへと沈み込むという観測事実や,既存の付加体や島弧地殻が強制的に削られる構造浸食作用に注目し,造山帯の理解において大陸地殻の総量を減らすプロセスこそが決定的に重要であること,従って従来提案された様々な大陸成長曲線は大幅に見直す必要性があることを指摘した.この研究もいくつかの論文として国際学術誌に印刷され,本学会年会を含む国内・国外の多くの学会で発表されていて,海外でも高く評価されている.彼はInternational Association of Gondwana Research学会から2009年のBest Paper Awardを授与され,2010年夏には中国天津での同学会年会に記念講演者として招待された.
山本氏はこれまで中国,オーストラリア,カナダ,英国などの造山帯研究調査に参加してきており,室内分析のみならず野外地質調査についても精通している.これまでの地質学に関する豊富な経験と幅広い研究視野,そして優れた研究業績から,地質学会の将来を担う若手研究者として活躍が期待され,小澤儀明賞の候補者としてふさわしいと判断されるので,ここに推薦する.
日本地質学会論文賞
受賞論文:Yoshimoto, M., Fujii, T., Kaneko, T., Yasuda, A., Nakada, S. and Matsumoto, A., 2010.Evolution of Mount Fuji, Japan: Inference from drilling into the subaerial oldestvolcano, pre-Komitake. Island Arc, 19, 470-488.
本論文は富士火山の北東山麓,小御岳付近で行われた5本の学術ボーリング(最大深度650 m)の掘削試料に関する火山地質学的,岩石学的・地球化学的・放射年代学的研究成果をまとめたものである.本論文は,斑晶質玄武岩からなる小御岳火山噴出物の下に角閃石安山岩〜デイサイト質の先小御岳火山が存在すること,その結晶分化作用が富士火山とは全く異なる伊豆弧北部に特徴的なカルクアルカリ系列の傾向をとることを明らかにした.そして,15万年前頃に発生したこの顕著なマグマ組成の変化が,伊豆・箱根など周辺火山の活動パターンの変化と同期していることについて,この時期の構造発達史及び広域応力場の変化と関連づけて議論した.火山災害防止の観点から近年注目されている富士火山で初めて行われた深部学術掘削の試料について,完備したデータセットを提供し充実した議論を行った,優れた論文である.よって本論文は日本地質学会論文賞に値すると判断される.
受賞論文:Uchino, T. and Kawamura, M., 2010. Tectonics of an Early Carboniferous forearc inferred from a high-P/T schist-bearing conglomerate in the Nedamo Terrane, Northeast Japan. Island Arc, 19, 177-191.
本論文は,北上山地の根田茂帯に関する著者らの従来の研究を発展させ,この付加体中の礫岩の礫種構成や円磨度について詳細に解析したものである.砕屑岩・火山岩礫に加えて高圧型変成岩・超塩基性岩礫が多数含まれることを明らかにし,変成岩は放射年代から蓮華変成岩に,超塩基性岩はクロムスピネルの化学組成から南部北上帯の岩体群に対比された.また,変成岩・超塩基性岩礫の円磨度が他の岩種に比して著しく低いことから,その供給源を前弧域に求めた.そして,前期石炭紀の南部北上帯前縁で,付加体の一部が沈み込んで高圧型変成作用を受け,その後3000万年以内に超塩基性岩類とともに前弧域に上昇,削剥され,これらの礫が島弧の火山岩礫とともに海溝域に供給されたというテクトニックモデルが提唱された.本論文は,断片的な情報しかなかった前期石炭紀の古日本島弧−海溝系のテクトニクスの理解を大きく前進させる優れた論文であり,日本地質学会論文賞に値すると判断される.
日本地質学会小藤賞
受賞論文:佐藤峰南・尾上哲治, 2010. 中部日本,美濃帯の上部トリアス系チャートから発見したNiに富むスピネル粒子.地質学雑誌,116, 575-578.
国内の付加体に広く分布する深海性チャートは堆積速度が小さく,巨大隕石の衝突のような希なイベントを記録するポテンシャルが高い.著者は,後期トリアス紀に多く認められるクレーターの存在を念頭に,隕石衝突の痕跡が同時代のチャートに残されているという予想のもと,美濃帯犬山セクションを適切かつ丹念な方法で探査し,珪質粘土岩中からニッケルに富む多数のスピネル粒子を発見するに至った.本短報で提示された組成分析・形態観察の結果は,これらのスピネルが火成岩起源ではなく,白亜紀−古第三紀境界から報告された粒子と類似し,隕石起源であることを十分に論証している.これは,付加体中の深海性堆積物からの,世界初のイジェクタ粒子の発見である.本短報は着想から結果に至る過程も秀逸であり,今後,同様の研究が行われるならば,その模範を示したという意義も大きい.日本地質学会小藤賞の掉尾を飾るものとして,本短報の受賞を推薦する.
日本地質学会小藤文次郎賞
受賞者:坂口有人(海洋研究開発機構)
受賞論文:Sakaguchi, A., Chester, F., Curewitz, D., Fabbri, O., Goldsby, D., Kimura, G., Li, C.-F., Masaki, Y., Screaton, E. J., Tsutsumi, A., Ujiie, K. and Yamaguchi, A., 2011. Seismic slip propagation to the updip end of plate boundary subduction interface faults: Vitrinite reflectance geothermometry on Integrated Ocean Drilling Program NanTroSEIZE cores.Geology published online 8 March 2011; doi: 10.1130/G31642.1
IODP NanTroSEIZE Exp. 316では,現在,紀伊半島沖で形成されつつある鮮新〜更新統付加体浅部が掘削されたが,著者らは地表付近まで達しているプレート境界断層および前 者から分岐するメガ・スプレー断層から得られたコア(それぞれ海底下438m,271mで掘削された)について,堆積物に含まれるビトリナイト(輝炭)の反射率(Ro)を詳細に分析した.その結果,僅か20mmにも満たない暗色層とその近傍に,周囲の輝炭反射率(Ro=c. 0.2%)よりも有意に高い輝炭反射率(Ro=c. 0.6%)であることを明らかにした.著者らは,これらの輝炭反射率異常は反応速度論モデルに基づいて,地震性すべりに伴う瞬間的な剪断加熱によって引き起こされたと説明出来ることを示した.これらの断層では,1944年の東南海地震(Mw=8.1)をはじめ巨大地震が繰り返し生じているが,地表に近い断層先端部は従来非地震性である考えられて来た.しかし,今回の発見は,先の東日本大地震で発生した大津波は地表まで至った断層変位に起因するという予想とも符合し,極めて先見性のある研究となった.よって,上記坂口ほか論文が革新的な事実の発見をもたらした論文に授与されるとする小藤文次郎賞の受賞対象論文の趣旨に良く合致することから,同論文を受賞対象論文として推薦する.
日本地質学会研究奨励賞
受賞者:増渕佳子(富山市科学博物館)
受賞論文:増渕佳子・石崎泰男,2011. 噴出物の構成物組成と本質物質の全岩および鉱物組成から見た沼沢火山のBC3400カルデラ形成噴火(沼沢湖噴火)のマグマ供給系.地質学雑誌,117,357-376.
本論文は,東北日本南部に位置する沼沢火山の約5.4kaに生じたカルデラ形成噴火を対象に,噴火推移に伴うマグマ供給系の進化を,地質学・岩石学的に解明したものである.本研究では,その推移(火砕流→プリニー式→マグマ水蒸気爆発→プリニー式)に従った系統的試料採取に基づいて,本質物質は噴火の前半では白色軽石主体で・黒色スコリアが付随し,後半では灰色スコリアが主体になることを明らかにした.白色軽石と黒色スコリアの組成は一連の混合トレンドに乗る.これに加え鉱物組成・組織を総合的に検討し,両者は共通の珪長質,苦鉄質端成分を持つことが推定された.灰色スコリアの組成も混合トレンドを示すが,その苦鉄質端成分は上記とは異なり,噴火後半には別の苦鉄質マグマが混合に加わったことも解明された.以上のように噴火の推移に従う本質物質の種類・岩石学的特徴の推移を克明に明らかにし,それをもたらしたマグマ供給系の変遷を高い解像度で推定した研究成果は,日本地質学会研究奨励賞に値すると判断される.
受賞者:針金由美子(産業技術総合研究所)
受賞論文:Harigane, Y., Michibayashi, K. and Ohara Y., 2010. Amphibolitization within the lower crust in the termination area of the Godzilla Megamullion, an oceanic core omplex in the Parece Vela Basin. Island Arc, 19, 718-730.
上記の論文はフィリピン海パレスベラ海盆の古拡大軸にあるゴジラ・メガムリオン(海洋底コア・コンプレックス)に露出する海洋地殻下部起源の変斑れい岩類について,岩石組織や鉱物化学組成の面から検討し,コア・コンプレックスの上昇過程における温度変化や熱水変質作用,角閃岩化作用について論じたものである.この論文は縁海における海洋底変成・変形作用について,世界に先駆けて比較的完備したデータと興味深い議論を提供し,海洋底コア・コンプレックス一般の成因についても重要な制約条件を与えた.また,この著者らは2011年にも同誌にゴジラ・メガムリオンにおける蛇紋岩とその原岩のマントルかんらん岩の変形作用に関する論文を出版しており,最近の活発な研究活動が顕著である.以上の所見から,本論文は研究奨励賞の受賞対象論文にふさわしいと判断される.
−備考−
Harigane, Y., Michibayashi, K. and Ohara, Y., 2011, Relicts of deformed lithospheric mantle within serpentinites and weathered peridotites from the Godzilla Megamullion, Parece Vela Back-arc Basin, Philippine Sea, Island Arc, 20 (2), 174-187.
受賞者:森 宏(名古屋大学大学院環境学研究科)
受賞論文:Mori, H. and Wallis, S. R., 2010. Large-scale folding in the Asemi-gawa region of the Sanbagawa Belt, southwest Japan. Island Arc, 19, 357-370.
本論文では,四国三波川変成帯の高変成度部の構造がどのようにして形成されたかという古くからの重要な問題を解明するため,四国中央部の三波川帯の代表的ルートである汗見川周辺地域において野外および顕微鏡下での詳細な構造観察を行った.その結果,同地域の三波川帯の最高変成度周辺における鉱物帯の繰り返しが大規模な褶曲構造で説明できることを示した.さらに,同論文では,他の地域の地質構造に関する情報をまとめ,各地域での褶曲構造が巨視的な繋がりを立体的なモデルを作成して示し,鉱物帯の分布との関係について議論している.この三波川変成帯の地質構造および沈み込み帯深部におけるプロセスを統一的に解明した研究成果は,日本地質学会研究奨励賞に値すると判断される.
日本地質学会表彰
受賞者:北九州市立自然史・歴史博物館(いのちのたび博物館)
表彰業績:自然・環境保全活動および地質学の教育・普及への貢献
北九州市立自然史・歴史博物館(いのちのたび博物館)は,後期白亜紀の淡水魚類化石の発見・発掘を契機に,1978年に自然史博物館開設準備室として開設した.以来,今日まで30年余りの活動を通じて,西日本地域最大の自然史博物館として発展してきた.また,本博物館は展示面積約6,100m2の約60%において地質学関連の資料が展示されており,日本を代表する地質博物館でもある.2002年からの累計来館者は300万人を超え,そのうち学校団体の利用は約1万6000件,約100万人に及ぶ.
北九州市周辺は,かつての炭鉱地域としての地質学的地勢と東アジアに隣接する地理的条件を生かし製鉄の町として発展,四大工業地帯の1つとして日本の経済的発展を支えてきた.しかし,一方で大気汚染等の公害問題が発生し,地域環境が危機的状況に追い込まれた経験を持つ.北九州市はそれを克服するための環境保全を実践する中で,地球環境についての市民への啓蒙活動の重要性を認知し,活動のための中核機関として博物館を位置づけた.このような背景の中,地域地質資料や所蔵資料を活用した博物館が行ってきた取り組みは,博物館自然史友の会を通じた出版活動,野外地質観察会,地質学・古生物学に関する普及講座,平尾台などの天然記念物の保全活動など,環境保全活動,自然保護活動,地学教育などの多岐におよび,「いのちのたび」という館名に込められた期待を超えたものと評価される.
北九州市立自然史・歴史博物館は地質学の普及と広報にも直接的に関与してきた.第1回地質の日には特別展示【地球と生命】を開催し,合わせて記念事業を企画している.また,西日本支部例会や西日本・近畿・四国,三支部同例会を開催したほか,古生物学会や洞窟学会など地質学に関連する学会,国際シンポジウムも多数開催してきた.
以上のように,北九州市立自然史・歴史博物館は,開かれた博物館として地域に根ざし,自然・環境保全活動に加えて地質学の教育・普及に大きく貢献してきた点で大きく評価できる.本博物館のこれまでの活動内容は,日本地質学会表彰に値するものと考え,ここに推薦する.
受賞者:狩野謙一会員(静岡大学理学部)・村田明広会員(徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部)
表彰業績:教科書発行と構造地質学普及への貢献
狩野会員と村田会員は,過去40年近くにわたり様々なスケールの地質構造を研究してこられた野外地質学者である.両会員とも研究者生活の前半には,メランジュやデュープレックスといった付加体の重要な構成要素の存在を野外調査から実証された経験がある.1998年2月,両会員は協力して,学部学生および大学院生向けの教科書「構造地質学(朝倉書店,B5判,298p.)」を出版された.この教科書は好評を博し,2011年5月までに9刷,5750部が刊行された.朝倉書店によると,ここ20年間に同社の「天文学・地学」分野で刊行した書籍のうち,学部学生〜大学院生を対象とした専門性の高い書籍としては本書がトップの売れ行きであるという.また,2000年5月には本書の付録ともいうべき「構造地質学CD-ROMカラー写真集」が出版され,好評を博した.さらに本書は韓国でも注目されるところとなり,2005年10月,韓国人研究者3名による共訳の韓国語版がソウルの出版社シグマプレスから刊行された.こちらは1500部刊行され,現在「品切中」である.「構造地質学」の特色は,例えば以下の様に要約される.(1)当時の欧米の類書に書かれている内容が網羅されており,特に地質構造と広域テクトニクス場との関連が詳しく記されている.(2)島弧の構造地質学的特徴が両会員自身の研究成果を交えて詳しく記されている.(3)両会員が実際に撮影された豊富な写真が解説に用いられている.構造地質学関連の書籍は和洋を問わず多く出版されているが,1冊の教科書に(1)〜(3)をバランス良く取り入れている点が,本書の最大の特長である.日本の読者は(2)・(3)の内容から,自分に親しみのある地域の地質と関連づけて本書を読むことができた.本書が多くの読者を集めた理由は,ここにあると考えられる.
このように,本書は世界的に見ても優れた構造地質学の教科書の一つであり,日本及び韓国における構造地質学の普及に大いに役立ったことは疑いようがない.本書の刊行後,地質関連教科書の刊行が続いているが,本書の大量普及に力を得た著者もおられるかと思う.このように,狩野・村田両会員が教科書発行と構造地質学普及に向けられた努力は大いに顕彰されるべきであり,日本地質学会表彰候補としてここに推薦する.
2012年度名誉会員
2012年度名誉会員
大八木規夫 会員(1932年生まれ)
大八木規夫会員は,1958年に広島大学理学部地学科を卒業後,同大学院に進学され,1964年3月に広島大学より理学博士の学位を授与された.同年(1964年)4月に,初代所長の和達清夫さんに強く招かれて,設立間もない科学技術庁国立防災科学技術センター(1991年 に防災科学技術研究所に改組)に入所された.1975年には地表変動防災研究室長,1986年には研究部長を歴任された.1992年3月に防災科学技術研究所を定年退職された後は,財団法人深田地質研究所(現:公益財団法人深田地質研究所)理事に就任された.現在,深田地質研究所と防災科学技術研究所の客員研究員として研究活動を続けられている.
大八木会員は,対策工の検討が中心で,土質力学と安定解析に関する研究に重点が置かれていた時代に,地すべり・斜面災害の研究における地形・地質学研究の重要性にいち早く気付かれ,精力的に研究を推進されてきた.その研究スタイルは,オーソドックスな地質学的方法を基礎に地すべりを理解しようとするもので,地形学・地質学分野出身の地すべり・斜面災害の研究者・技術者に大きな影響を与え地質学の応用分野を拡大してきた.
大八木会員の地質学分野における最大の業績は地すべり構造論の提唱であり,2002年には「地すべり構造の研究」により日本地すべり学会論文賞を授賞している.また,「地すべりに関する地形地質用語委員会」の委員長として,地すべり構造論に関する様々な課題の検討を指導され,その集大成として「地すべり:地形地質的認識と用語」(日本地すべり学会発行,2004年)に纏め上げられた.本書は斜面防災を扱う地質技術者・防災研究者の必携の書となっている.また,大八木会員が始められた「50,000分の1地すべり地形分布図」(防災科学技術研究所)の企画と刊行の事業は,その後30年以上にわたって継続され,あと数年で全国が完成予定である.そして,地すべり構造論の立場から多数の地すべり地形判読の実例に基づいて要点を取り纏めた著書「地すべり地形の判読法」を2007年に刊行された.
大八木会員は,研究を進めるにあたって,地盤工学など工学分野の研究者や実務技術者とも幅広く交流を深められ,実務技術者への自然災害の理解とその防止における地質学分野からの貢献にも尽力されてきた.そして,研究で得られた知識・経験の伝承にも尽力され,若手技術者の研修指導や学生の指導にも積極的に取り組んでこられた.
以上の功績により,長年にわたって地質学をとおして社会に貢献されてきた大八木規夫会員を日本地質学会の名誉会員に推薦する.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
蟹澤聰史 会員(1936年生まれ)
蟹澤聰史会員は1955年に長野県立伊那北高等学校を卒業後,東北大学理学部地学科に入学,1959年卒業後同大学院修士課程に進学され,1964年に博士課程を修了,理学博士の学位を得授与された.同年東北大学教養部助手に採用され,後年助教授,教授に昇任された.1993年から理学部・理学研究科教授を務め,2000年に停年退官された.その後は山形大学理学部教授を務め,2002年に停年退官後も数年間にわたり東北大学,山形大学で講師を務められた.
蟹澤会員は,学生時代の長野県高遠地方の領家帯変成岩・深成岩についての岩鉱論文,南部北上山地の変成岩に関する紀要論文(学位論文)を始めとして,主に東北地方の変成岩や火成岩に関する多数の研究論文を公表され,日本列島の基盤地質の解明に多大な貢献をされてきた.特に先シルル紀基盤岩や白亜紀花崗岩の研究,東北地方の火成活動史の総括などで顕著な業績を挙げられた.なかでも,異なる系列の花崗岩における鉱物化学組成の違いについての論文、花崗岩中のフッ素の挙動に関する論文、北上山地のアダカイト質花崗岩についての論文、北上山地の構造発達史に関する論文、そして中国やエジプトの花崗岩に関する論文などは国際誌に公表され、よく引用されている.さらに,国際地質対比計画IGCP-315「ラパキビ花崗岩と関連岩石」の日本代表,万国地質学会議IGC京都大会(1992)の「花崗岩の時間的空間的比較研究」コンビーナー,IGC北京大会(1996)の「大陸プレート内と受動的大陸縁のマグマ活動」コンビーナーなども務められた.また,仙台付近の火山灰層の研究により安達火山を発見されたことや旧石器時代遺跡の年代決定に貢献されたことも特筆される.
一方,蟹澤会員は「現代の地球科学ー基礎編」などの教科書や「文学を旅する地質学」,「石と人間の歴史」などの普及書を出版され,地学の教育と普及に貢献されてきた.理系・文系の幅広い分野にわたる深い教養と多年の教育経験に裏打ちされたこれらの優れた普及書は,今後も多くの読者に読み継がれて行くに違いない.
蟹澤会員は,学会や社会においても,日本岩石鉱物鉱床学会(現鉱物科学会)会長,日本学術会議の地質学研究連絡委員会委員,金属工業事業団の調査委員,国際協力事業団の派遣専門家,大学入試センター委員,宮城県自然環境保全審議会委員を務めるなど各方面で活躍し,東北大学でも評議員を2期務めるなど要職を歴任された.
このような長年にわたる地質学の研究,教育,普及への顕著な貢献に鑑み,蟹澤聰史会員を日本地質学会名誉会員に推薦する.
(以上2名)
学会の顔:各賞受賞者
学会の顔(受賞者)
2025年度各賞受賞者
2025年度各賞受賞の詳細はこちらから
都城秋穂賞
Ali Mehmet Celâl Şengör氏
小澤儀明賞
松本廣直会員
小藤文次郎賞
岩森 光会員
論文賞
別所孝範会員ほか
亀高正男会員ほか
研究奨励賞
米岡佳弥会員
フィールドワーク賞
松山和樹会員
2024年度各賞受賞者
2024年度各賞受賞の詳細はこちらから
都城秋穂賞
Gregory F. Moore氏
H.E.ナウマン賞
岡本 敦 会員
小澤儀明賞
羽田裕貴 会員
柵山雅則賞
奥田花也 会員
小藤文次郎賞
岡本 敦 会員
論文賞
中嶋 徹会員ほか
Island Arc Award
澤木佑介会員ほか
地質学雑誌特別賞
牛丸健太郎会員ほか
研究奨励賞
福島 諒会員
木下英樹会員
武藤 俊会員
渡部将太会員
吉田 聡会員
学会表彰
夏原信義 氏
2023年度各賞受賞者
2023年度各賞受賞の詳細はこちらから
学会賞
道林克禎会員
功績賞
小山内康人会員
佐藤比呂志
小澤儀明賞
沢田 輝会員
柵山雅則賞
大柳良介会員
論文賞
入月俊明会員ほか
内野隆之会員ほか
野田篤会員ほか
吉田健太会員ほか
Island Arc Award
田村芳彦氏
研究奨励賞
原田浩伸会員
佐久間杏樹会員
鈴木康太会員
山岡 健会員
フィールドワーク賞
江島圭祐 会員
羽地俊樹 会員
2022年度各賞受賞者
2022年度各賞受賞の詳細はこちらから
功績賞
高橋正樹会員
H. E. ナウマン賞
片山郁夫会員
小澤儀明賞
石輪健樹会員
柵山雅則賞
岡粼啓史会員
宇野正起会員
論文賞
高嶋礼詩会員ほか
Island Arc Award
磯粼行雄会員
研究奨励賞
中西 諒会員
加藤悠爾会員
学会表彰
伊与原 新氏
2021年度各賞受賞者
2021年度各賞受賞の詳細はこちらから
国際賞
Brian Frederick Windley氏
柵山雅則賞
田阪美樹会員
纐纈佑衣会員
論文賞
中澤 努会員ほか
中嶋 健会員
納谷友規会員ほか
Island Arc賞
Schindlbeck, J. C氏
研究奨励賞
板宮裕実会員
菊地瑛彦会員
学会表彰
千葉セクションGSSP提案チーム
2020年度各賞受賞者
2020年度各賞受賞の詳細はこちらから
学会賞
山路 敦会員
論文賞
星 博幸会員
Island Arc賞
John Wakabayashi氏
研究奨励賞
菊川照英会員
羽地俊樹会員
学会表彰
株式会社浜島書店
鹿野和彦会員ほか
2019年度各賞受賞者
2019年度各賞受賞の詳細はこちらから
学会賞
多田隆治会員
国際賞
Robert J. Stern氏
小澤儀明賞
齋藤誠史会員
Island Arc賞
Catherine Chagueほか
論文賞
佐野弘好会員
Hiotoshi Hasegawa et al
研究奨励賞
加瀬善洋会員
葉田野 希会員
学会表彰
株式会社新興出版社啓林館
数研出版株式会社
加納 隆会員
2018年度各賞受賞者
2018年度各賞受賞の詳細はこちらから
国際賞
Millard F. Coffin氏
小澤儀明賞
澤木佑介会員
柵山雅則賞
野崎達生会員
遠藤俊佑会員
Island Arc賞
Ayumu Miyakawaほか
論文賞
高野 修ほか
小藤文次郎賞
小宮 剛会員
研究奨励賞
綿貫峻介会員
高橋 聡会員
2017年度各賞受賞者
2017年度各賞受賞の詳細はこちらから
学会賞
ウォリス サイモン会員
国際賞
Richard S. Fiske氏
柵山雅則賞
平内健一会員
Island Arc賞
纐纈佑衣ほか
論文賞
野崎 篤ほか
小藤文次郎賞
佐藤活志会員
研究奨励賞
三田村圭祐会員
功労賞
大和田 朗氏
学会表彰
「ブラタモリ」制作チーム
2016年度各賞受賞者
2016年度各賞受賞の詳細はこちらから
学会賞
荒井章司会員
国際賞
Roberto Compagnon氏
柵山雅則賞
野田博之会員
Island Arc賞
山本伸次ほか
小藤文次郎賞
菅沼悠介会員ほか
高柳栄子会員
研究奨励賞
酒向和希会員
金井拓人会員
功労賞
檀原 徹会員
学会表彰
内藤一樹会員
2015年度各賞受賞者
2015年度各賞受賞の詳細はこちらから
学会賞
脇田浩二会員
小澤儀明賞
辻 健会員
Island Arc賞
荒井章司ほか
論文賞
岩野英樹ほか
纐纈祐衣ほか
小藤文次郎賞
堤 浩之会員
氏家恒太郎会員
研究奨励賞
越智真人会員
功労賞
大山次男氏
学会表彰
白尾元理会員
2014年度各賞受賞者
2014年度各賞受賞の詳細はこちらから
日本地質学会賞
川幡穂高会員
斎藤文紀会員
日本地質学会国際賞
Prof. Bor-ming Jahn
日本地質学会小澤儀明賞
菅沼悠介会員
田村 亨会員
日本地質学会Island Arc賞
Dr. Dapeng Zhao ほか
日本地質学会論文賞
田辺 晋会員ほか
日本地質学会小藤文次郎賞
野崎達生会員
日本地質学会研究奨励賞
細井 淳会員
上久保 寛会員
武藤 潤会員
学会表彰
西岡芳晴会員
2013年度各賞受賞者
2013年度各賞受賞の詳細はこちらから
日本地質学会賞
井龍康文会員
乙藤洋一郎会員
日本地質学会Island Arc賞
Prof. Keiko Hattori ほか
日本地質学会小澤儀明賞
尾上哲治会員
日本地質学会柵山雅則賞
岡本 敦
日本地質学会小藤文次郎賞
森田澄人会員ほか
学会表彰
岡村 眞会員
静岡県袋井市
2012年度各賞受賞者
2012年度各賞受賞の詳細はこちらから
日本地質学会賞
木村 学会員
日本地質学会Island Arc賞
Prof. Barber, A. J. ほか
日本地質学会小澤儀明賞
山本伸次会員
日本地質学会論文賞
吉本充宏会員ほか
内野隆之会員ほか
日本地質学会小藤賞
佐藤峰南会員ほか
日本地質学会小藤文次郎賞
坂口有人会員
日本地質学会研究奨励賞
増渕佳子会員
針金由美子会員
森 宏会員
学会表彰
北九州市立自然史・歴史博物館(いのちのたび博物館)
狩野謙一会員・村田明広会員
2011年度各賞受賞者
2011年度各賞受賞の詳細はこちらから
日本地質学会賞
岩森 光会員
日本地質学会国際賞
Dr. J. Casey Moore
日本地質学会小澤儀明賞
黒田潤一郎会員
日本地質学会柵山雅則賞
河野義生会員
日本地質学会Island Arc賞
Dr. Saffer, D. M ほか
日本地質学会論文賞
山本由弦会員ほか
藤井正博会員ほか
遠藤俊祐会員
日本地質学会小藤賞
田沢純一会員ほか
日本地質学会研究奨励賞
常盤哲也会員
辻 智大会員
隅田祥光会員
日本地質学会功労賞
石井輝秋会員
学会表彰
(独)森林総合研究所・千葉県南房総市
2010年度各賞受賞者
2010年度各賞受賞の詳しくはこちらから
日本地質学会国際賞
Dr. Juhn G. Liou
日本地質学会小澤儀明賞
後藤和久会員
日本地質学会Island Arc賞
Fu-Yuan Wuほか
日本地質学会論文賞
菅原大助ほか
宮田雄一郎ほか
日本地質学会研究奨励賞
佐藤雄大会員
大橋聖和会員
川上 裕会員
日本地質学会功労賞
杉山了三会員
学会表彰
山口県
地球システム・地球進化ニューイヤースクール(NYS)事務局
2009年度各賞受賞者
2009年度各 賞受賞の詳しくはこちらから
日本地質学会賞
鳥海光弘会員
石渡 明会員
日本地質学会国際賞
太田昌秀博士
日本地質学会小澤儀明賞
小宮 剛会員
須藤 斎会員
日本地質学会柵山雅則賞
水上知行会員
日本地質学会論文賞
高橋雅紀会員
守屋俊治会員ほか3名
日本地質学会小藤賞
嶋田智恵子会員他3名
日本地質学会研究奨励賞
石井英一会員
坂口真澄会員
日本地質学会Island Arc賞
Bortolotti, V.氏他1名
学会表彰
秋吉台科学博物館
2008年度各賞受賞者
2008年度各賞受賞の詳しくはこちらから
日本地質学会賞
榎並正樹会員
日本地質学会柵山雅則賞
片山郁夫会員
日本地質学会論文賞
竹内 誠会員ほか
清川昌一会員
青木一勝会員ほか
日本地質学会小藤賞
斎藤 眞会員他2名
日本地質学会研究奨励賞
丹羽正和会員
長谷川健会員
福成徹三会員
日本地質学会Island Arc賞
Chang Whan Oh氏他5名
2010年度名誉会員
2010年度名誉会員
町田 洋 会員
町田 洋会員は1957年に東京大学理学部地学科地理学専攻を卒業され,さらに同大学院理学系研究科地理学専攻修士課程を1959年に修了し,同年,東京都立大学理学部地理学科に助手として赴任された.1962年に「最近数十年〜数百年間の山地斜面と谷の浸食史」で理学博士の学位を取得された.都立大学では1968年に助教授,1978年に教授に昇任され,1996年同大学を定年退職し,同時に東京都立大学名誉教授の称号を授与された.
時間指標としてのテフラの重要性に早くより認識され,まず,富士山を中心にテフラを用いた火山発達史,周辺地域の地形発達史の研究に取り組まれた.研究対象はさらに箱根火山とその東側の大磯丘陵,南関東に広がり,激しい地殻変動を受けたこの地域の複雑な地形発達史を,富士・箱根火山のテフラを時間指標として海水準変化・気候変化と関係付けながら明らかにされている.町田会員の特筆すべき業績の一つは,広域テフラの発見である.約3万年前に南九州で発生し大規模なシラス台地を作った巨大噴火 (入戸火砕流) は,その降下テフラ(姶良−丹沢火山灰AT)が日本全国のみならず朝鮮半島や大陸沿岸と周辺海域を含む広域を覆ったことを,1976年に故新井房夫と共に,堆積物の記載岩石学的な特徴による同定・対比を取り入れて明らかにされた.その後,鬼界−アカホヤ火山灰(K-Ah),Aso4火山灰など第四紀中後期の広域テフラを次々に発見し,第四紀における同一時間面をシャープに示す時間指標としてのテフラの位置を確立された.この成果は,地形発達史や微化石,堆積物層序研究と深く結びついて,日本列島とその周辺における高分解能の海水準変化,気候変化,環境変化の復元に大きく活用されている.さらに,ATやK-Ahは考古学においても旧石器〜縄文時代の重要な時間指標として日本のみならず東アジアの遺跡の編年解明に活用されている.広域テフラ研究の成果は1992年に「火山灰アトラス」としてまとめられ,日本の第四紀研究に不可欠な資料として現在も活用されている.
町田 洋会員はこのように日本におけるテフラ研究の第一人者であり,その成果と功績は海外においても高く評価され,1987年から1995年まで国際第四紀学会(INQUA)のCommission on tephrochronology (COT) の副委員長及び委員長に推挙された.また,1991年〜2002年まで連続して学術会議の第四紀研連の委員及び委員長を歴任され,2003年〜2005年には日本学術会議会員・地質科学総合研連委員長を務められた.また,2005年〜2008年には日本第四紀学会会長を務められ,2009年には同学会より学会賞を受賞された.1996年以降早稲田大学エクステンションセンターのオープンカレッジ講師を務められ,第四紀学,地質学や地形学の普及に努力されている.また,2008年から日本ジオパーク委員会の副委員長として,ジオパークの普及・啓発にご尽力されている.
テフラ研究の対象を第四紀の前半にも発展させ,その成果に基づいて,近年は日本アルプスの隆起開始時期解明等の日本列島の構造発達史に関わる研究にも取り組んでおられる.これら長期にわたるテフラ研究分野での世界的な研究成果と日本の第四紀地質学に対する多大な貢献により町田 洋会員を名誉会員として推薦する.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
石原 舜三 会員
石原舜三会員は1956年広島大学理学部地学科を卒業後,地質調査所に入所,ウラン鉱床探査に従事,1961年に米国に渡り,コロラド鉱山大学およびコロンビア大学の大学院に学び,ニューメキシコ州Questa鉱山のモリブデン鉱床の研究により修士号を授与された.その後ドイツに遊学された後1964年に地質調査所に復帰された.モリブデン鉱床を始めとする花崗岩類に伴う鉱床の研究を続け,1970年には東京大学から博士号を授与された.1978年に鉱床部鉱床研究課長に,1985年には鉱床部長を歴任された.1978年から2年間,東北工業試験所長,1989年から地質調査所所長,1991年から工業技術院院長という行政の要職に従事された,さらに,北海道大学教授として念願の研究に復帰されている.現在は産業技術総合研究所特別顧問として後輩の指導に務められている.
石原舜三会員の最も特筆すべき業績は花崗岩系列と鉱化作用の関連性について新しい理論を確立したことである.花崗岩類の岩石化学的変化に対する従来の支配的な考え方はマグマの結晶分化作用によるものであったが,石原舜三会員は花崗岩類が磁鉄鉱系列とチタン鉄鉱系列に大別でき,両者の違いは主として酸素分圧の相違に基づくマグマの差によるものであり,それぞれの花崗岩類には特有の金属鉱床が付帯することを明確にした.この学説は金属鉱床探査の上で,非常に有効なもので,帯磁率の測定は鉱床探査の折に必ず実施されている.
これらの多大なる石原舜三会員の業績が認められ,1984年に日本鉱山地質学会の加藤武夫賞,1988年には日本地質学会賞,1989年にSociety of Economic GeologistsのSilver Medalを受賞されている.また2009年にはオーストラリアのタウンズビルで開催された第10回鉱床地質学会(The Society for Geology Applied to Mineral Deposits(SGA))大会において,「花崗岩における金属鉱床の成因に関する科学的貢献」のためにSGA-ニューモント-ゴールドメダルを受賞されている.さらに中国地質科学院名誉フェロー,米国地質学会名誉フェロー,ロシア科学アカデミー在外会員などにも選出されている.
石原舜三会員はSociety of Economic Geologistsのアジア地域代表の副会長として貢献され,また日本鉱山地質学会(現資源地質学会)の編集長,会長として学会の運営に携わってこられた.黒鉱鉱床に関する最初の総括的な書籍である「Geology of Kuroko Deposits」(1974年,鉱山地質特別号)の編集など多くの特別号の編集もされている.
石原舜三会員は「地質に対するあくなき好奇心と研究魂」を後進に示し続けておられる.現在もなお年間で数回にわたる国内・海外の調査,数編の論文を執筆,シンポジウムの企画・実行をされている.この固体地球の研究に立ち向かう旺盛な精神こそ私達は見習う必要がある.これら石原会員の長年にわたる岩石・鉱床学分野の研究業績と地質学の発展に対する世界的な貢献により石原舜三会員を名誉会員として推薦する.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
藤田 崇 会員
藤田 崇会員は,1958年に大阪市立大学理工学部地学科を卒業され,1971年9月に大阪市立大学から理学博士の学位を取得されている.大学卒業後,すぐに原子燃料公社(現日本原子力研究開発機構)に入社され,人形峠でウラン鉱床の探査に従事されている.1973年には大阪工業大学工学部助手として着任され,その後講師・助教授を経て,1975年に教授に昇進されている.2001年3月に退職され,名誉教授となられている.
藤田 崇会員は,応用地質学・環境地質学が専門で,ことに自然災害科学の分野で多大な功績をあげられた.なかんずく,斜面災害の分野における地質学的研究は,亀の瀬地すべりの研究をはじめ,四国三波川変成帯や新第三系の地すべりの発生機構の解明に大きな貢献をされた.各地域での地すべりの地質学的研究から,地質規制(岩相規制と地質構造規制)の概念を提唱し,地すべりの地質学的研究を体系化された.さらに,地すべりの発生年代の研究から,地すべりの発生が第四紀変動による山地の上昇と密接に関連していることを示された.当時,このことを理解した研究者は少なかったが,故藤田和夫名誉会員はこの成果を高く評価された.最近になって,このような研究が増えていることは藤田 崇会員の先見性が実証されつつあることの証左である.
地すべり研究における藤田 崇会員の特徴は,地質・地形データの融合である.地質的特性を定量的に表すために,地形学の手法を取り入れ,これにより地すべりと地質との関連を,定量的な評価ができる手法を開発した.この手法を用いて,地質体ごとの地すべりの特性を明確にすることが可能となった.この研究成果に対し,1996年に日本地すべり学会から論文賞が与えられた.
1986年に,地質学論集28号として「斜面崩壊」が刊行された.その編集責任者は藤田 崇会員である.本書は半年で完売し,追加印刷をしたが,これも完売となり,地質学論集始まって以来の出来事となった.また,地質学会100周年事業委員として活躍されたほか,当時の将来検討委員会の応用地質分会委員長を務められた.さらに,日本地形学連合では運営委員となり,会長も務められた.
多くの論文の他,編著書の多くが好評で,「地すべり−山地災害の地質学」(共立出版),「地すべりと地質学」(古今書院)は,環境地質学・応用地質学にとっても名著であり,両者ともロングセラーである.また,日本応用地質学会刊行の「斜面地質学」は,地すべり研究者の必携書とされ,完売となった.
官公庁などの委員を数多く務められ,斜面災害対策における地質学的アプローチの重要性を他の分野の研究者,技術者,さらには行政担当者(とくに当時の建設省の技官)などに強く認識させたことはきわめて重要な貢献である.
藤田 崇会員は山地災害が自然環境の破壊をもたらした様相の詳細な観察,それに基づく地質学的要因の解明など,長年の災害研究を通して環境地質学の発展に多大な貢献をされた.以上の功績により藤田 崇会員を日本地質学会の名誉会員として推薦する.
(以上3名)
2009年度名誉会員
2009年度名誉会員
須鎗 和巳 会員(1926-2011)
須鎗和巳会員は1948年に東北大学理学部地質学古生物学教室を卒業された.同年,東北大学理学部副手として採用され,1949年理学部文部教官三級を経て,1950年に徳島大学学芸学部助手に転任,1952年同講師,1960年同助教授に昇任,1965年徳島大学教養部助教授に配置換えの後,1966年に徳島大学教養部教授になられた.
四国赴任後の須鎗会員は,秩父累帯の層序と生層序の研究に着手,その成果を1961年に東北大学博士論文「Geological and paleontological studies in central and eastern Shikoku, Japan」としてまとめるとともに,黒瀬川構造帯の一連の共同研究を推進された.その後,和泉層群の堆積学的研究にも着手,北縁部の浅海相と中軸部タービダイト相の指交関係や,阿讃山脈の地質構造の解析に貢献された.須鎗会員は,地の利を生かした野外調査を基本とする研究を推進し,その領域は,秩父累帯,領家帯和泉層群,四万十帯,室戸半島第四系,中央構造線と吉野川平野の鮮新-更新統,御荷鉾帯・三波川帯の原岩堆積年代ほかに大別できるように,古生代から第四紀まで,四国の全ての地質体に及んでいる.中でも御荷鉾帯と三波川帯の源岩堆積年代の解析は,同会員がその探求に特に情熱を注いだ感のある共同研究であり,「四国西部三波川帯主部よりの後期三畳紀コノドントの発見」(須鎗ほか,1980)により,日本地質学会小藤賞を授与された.
教育面では東北大学,徳島大学はもとより,非常勤講師を勤められた高知大学,愛媛大学等においても,同僚や後進にさまざまな指針を与え,教科書「地球科学概論」(朝倉書店,1984)をはじめとする執筆出版を通じて,地球科学の普及に大いに尽力された.指導を受けた多数の学生は,大学・研究所や教育機関に留まらず,社会の第一線で活躍しており,須鎗会員の教育・研究に対する深い理解と熱意は,世代を超えて受け継がれている.また須鎗会員は1970〜72年には徳島大学教養部長,その前後の1969〜77年には同評議員を歴任,大学行政と教育・研究の発展にも尽力された.
また,須鎗会員は「日本の地質8 四国地方」(共立出版,1991)の代表編集委員を務め,20万分の1四国地方表層地質図(高知営林局,1977)の編纂や,土地分類基本調査など,地質学の成果を世に広め,後世に残すための仕事にも力を注がれた.
以上の理由により,須鎗和巳会員を名誉会員として推薦する.
(2011年4月2日逝去)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
飯山 敏道 会員(1927-2012)
飯山敏道会員は,1957年から20年間にわたってフランスで活躍され,帰国後は地質学全般にわたる活発な教育研究活動や日仏交流のキーパーソンとして多大な貢献をされている.
飯山会員の研究は広範囲にわたるが,本領は実験といえよう.フランス滞在中に行った鉱物と熱水溶液間のイオン交換平衡を用いた元素の分配や固溶体の熱力学的性質に関する研究は今でも高い評価を受けている.自ら装置を設計されたばかりでなく旋盤で金属を加工するなど技術的な面にも造詣が深く,内熱型高温高圧実験装置を東京大学や千葉大学に先駆的に導入して多くの成果をあげるなど,熱水実験の意義を広く認識させた功績も大きい.
1976年に東京大学地質学教室の第三講座(鉱床学)の教授として帰国されてからは,スカルンを中心とする鉱床の研究や交代作用の研究,花崗岩の研究,社会問題ともなったセメントのアルカリ骨材反応の研究など,さらに広い分野の研究に取り組まれたことは多くの人々の知るところである.
1984年に開始された日仏KAIKO計画における日本側計画代表としての活躍も特筆される.同計画は潜水艇による潜行調査や海底探査,広範囲の地質調査など海陸を統合する大規模なプロジェクトであり,飯山会員はフランスとの結びつきを生かして計画の実現に尽力し,島弧海溝系の理解と日本のテクトニクスの解明にインパクトを与えたことは記憶に新しい.
これらの業績に対して,フランス政府はフランス国家功労賞騎士号,同士官号などを授与し,飯山会員を称えている.また,飯山会員は熱水実験を中心に鉱床学,鉱物学,地球化学など幅広い分野において第一線で活動している後進を数多く育成された.
1981年の日本地質学会第88年学術大会に際しては,1968年以来の懸案であった東京大学開催を大会準備委員会の責任者として成功裏に実現させた.1992年に京都で開催された第29回万国地質会議に関しては,世界的に活躍する諸外国の研究者との深い連携を背景に準備段階から組織委員として活躍され,同会議が大きな成果をあげるよう尽力された.これらは広く学界への貢献として特筆されるべきことである.
さらに,1984年に東京大学理学部助手の福山博之氏と柵山雅則氏(両名とも日本地質学会員)と学生1名がアイスランド調査中の事故で亡くなった際には,飯山会員は東京大学評議員として公務災害認定のために学内外で奔走された.公務災害適用への道を切り開かれたことは危険と隣り合わせで調査する地質学研究者とその家族を保護する上で歴史的な意味があったといえよう.
大学を辞められても今なお,房総地学会の活動に積極的に関わるなど地質学の普及教育に尽していると伺っている.
以上のような長年の地質学に対する貢献により,飯山敏道会員を名誉会員に推薦する.
(2012年9月15日逝去)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
相原 安津夫 会員
相原安津夫会員は1954年に東京教育大学理学部地質鉱物学科を卒業後,三井鉱山(動力炉・核燃料開発事業団およびサンコーコンサルタント出向)を経て,1974年に九州大学理学部地質学科石炭地質学講座の助教授として着任された.1987年に教授昇任,学内では石炭研究資料センター委員や自然災害科学西部地区部会事務局などを務め,1994年に退職後はダイヤコンサルタント顧問,国際協力事業団のインドネシア派遣専門家,福岡教育大学非常勤講師などを歴任されている.
相原会員は,石炭地質学分野で地質学に重要な貢献を残した.とりわけビトリナイト反射率を用いた有機埋没変成史と古地熱環境の情報から,九州・北海道などの堆積盆発達史や付加体テクトニクスなどに多くの知見をもたらしたことは周知のとおりである.教育面においては,九州大学在職中の20年間で理学部および教養部の教育に携わったほか,国内外10以上の大学で非常勤講師として石炭地質学の講義をされた.集中講義の受講生の中には卒・修・博論で九大の石炭顕微鏡の恩恵に浴したものも少なくない.日本国内の石炭産業が縮小撤退を余儀なくされていた折,教育研究の場で石炭地質学の維持と有機地球科学への転換を担われた.これらの成果は,2006年に開催された国際堆積学会議における石炭堆積学のセッションで,日本人発表者のすべてが相原スクール出身であったことにも現れている.
国際的には,国際石炭組織・有機岩石学委員会(ICCP)で,日本の唯一のフルメンバーとして,変動帯の炭田形成から有機変成に関わる地質特性を紹介すると共に,内外情報や研究動向の交流に携わり,新たなアソシエイトメンバーの導入につとめた.遡って1960年代はじめにオーストラリアで当時未詳であったボウエン炭田の石炭資源調査に従事し,その後の炭田開発や日本への石炭安定供給の基礎を築いた.その業績が評価され,燃料協会(現 日本エネルギー学会)および鉱山地質学会(現 資源地質学会)の技術賞を受賞された.同会員の学識は石油地質学や応用地質学の領域でも遺憾なく発揮されている(例えば,相原(1979)石炭鉱床.佐々木昭ほか編,地球科学14,岩波書店など).日本地質学会が社会に向けての情報発信や普及に対する組織的な取り組みを行う前から,同会員は「『科学の公園』をつくる会」などの活動にも参画し,児童・生徒および保護者が地質学に興味や関心を持つ場の創出に尽力している.
上記の功績により相原安津夫会員を名誉会員に推薦する.
(平成29年4月30日逝去)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
原 郁夫 会員
原会員は,1955年に広島大学地学科を卒業後,同大学大学院を経て,広島大学助手,助教授,教授を歴任され,1996年の定年退職時に広島大学名誉教授となられた.この間,ダルムシュタット工業大学鉱物学教室客員研究員として4度ドイツに留学された.また,定年退職後は,2007年まで応用地質(株)で現役の地質技術者として活躍された.
原会員は,構造地質学およびテクトニクスの分野,特に石英の変形ファブリック,層状岩体褶曲作用および日本列島変成帯テクトニクスに関する研究で多大な業績を上げ,国内外で高く評価されている.石英の変形ファブリックや褶曲作用の研究は,研究者として比較的初期(1961-1977)に行われたが,当時日本に構造地質学(構造岩石学)が育っていなかった状況の中で,原会員は国際的なレベルで先端的な研究を行われた.これらの研究成果の一部は1970年代後半にシドニー,ライデン,バルセロナおよびゲッチンゲンにおいて開催されたMicrotexture Analysis Conferenceにおいて公表されたが,原会員が一連の会議に論文( 内2 編はTectonophysicsに印刷されている)を提出した唯一の日本人であったことは特筆される.当時の欧米は,プレートテクトニクスが開花した頃であるが,一方では1950年代後半に岩石・鉱物変形実験が開始され,プレートテクトニクスを可能にしている地球内部(固体)の流動を,変形物理条件の関数として解き明かそうとしていた時代にあった.この様な動きは,日本では漸く論文集「固体の流動」,上田誠也編,東海大学出版会(1974)に見てとれるが,この論文集においても,地質学者として論文を提出しているのは原郁夫と伊藤英文のみであり,当時原会員が孤軍奮闘されていた様子が窺える.
その後,原会員は研究テーマを日本列島変成帯(特に三波川変成帯)および領家帯・中央構造線の研究に転向する(1973-1996).一連の研究は,小島丈兒,秀敬らを中心とする広島学派により1950年代から開始された徹底した地質調査に基づく地域地質学的研究であるが,一方で詳細な微細構造の解析と大量の鉱物化学組成のデータに基づく変成条件および変成温度—圧力履歴の推定を行っており,まさに総合的なテクトニクスの研究である.
また,科研費の総合研究を企画し,市川浩一郎名誉会員や水谷伸冶郎名誉会員らとともに日本の中・古生界のテレイン・テクトニクスの発展にも貢献されている.三波川変成帯のテクトニクスの研究は,Hara et al.(1992)にもっと良く纏められているが,本論文は101ページを費やし,118図を用いた超大作で,引用回数の非常に多い論文となっている.上記すべての研究は,構造地質学・テクトニクスの進展に大きく貢献するものであり,1995年に原会員の功績に対して日本地質学会賞が授与された.
以上,原会員は並はずれたバイタリティーと洞察力をもって,日本の構造地質学の黎明期に次々と世界第1線の研究を成し遂げたほか,構造地質学と変成岩岩石学を結び付け変成帯のテクトニクスの研究を世界レベルで展開した功績は大きい.さらに,原会員のパイオニア的研究に刺激を受け,現在日本では第2世代,第3世代および第4世代の構造地質学研究者が育ち活躍するなど,原会員が後進に残した影響は計り知れない.応用地質(株)に移られてからもそれは全く変わることなく,熱意を持って指導力を発揮された.原会員はまた,14の国立大学で非常勤講師として集中講義を行い,後進の指導に努めてこられた.
以上,長年わたる多大なる地質学への貢献により,原郁夫会員を名誉会員に推薦する.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
石崎 国煕 会員
石崎会員は昭和32年に徳島大学学芸学部を卒業した後,東北大学大学院理学研究科地学専攻に進学し,修士課程では高知市近郊に分布する古生界の地質学的研究に従事した.同課程修了後は博士課程に進み, 昭和37年に「Stratigraphical and paleontological studies of the Onogahara and its neighbouring area, Kochi and Ehime Prefectures, southwest Japan」の研究で理学博士の学位を授与された.博士課程修了後は,日本学術振興会の特別研究生を経て,昭和37年東北大学理学部地質学古生物学教室に助手として就任されて以来,同大学の助教授,教授として,35年間の永きにわたって地質学・古生物学に関する教育と研究に活躍され,平成9年3月末に退官された.
石崎会員は主として四国に分布する秩父帯の地質および紡錘虫の生層序学的研究に精力的に取り組んだ後,当時の将来的研究の発展をいち早く展望し,微化石の一種である,節足動物甲殻類の貝形虫化石に関する古生物学的・古生態学的研究へと転じ,我が国のこの分野のパイオニアかつ第一人者として長年活躍された.
石崎会員の貝形虫に関する研究は,それまでほとんど手を付けられていなかった古生代の貝形虫化石の分類学的研究に始まった.その後,日本各地の現世堆積物中の貝形虫の生態や分布様式,貝形虫群集とそれをとりまく環境との因果関係の解明,および詳細な分類学的研究に基づいて多くの新種記載を行い,今日のこの分野の礎を築かれた.さらに,このような現世貝形虫に関する知見に基づいて,地質学的イベントと群集形成や種の移動・消滅との関連性,鮮新−更新世における海洋環境の変動の解明など数多くの成果を挙げられた.特に,当時は十分に汎用化されていなかったコンピューターを用いて微化石群集の検討にいち早く多変量解析の手法を導入し,古環境変動を定量的に復元することに成功した.当時の古生物学における先駆的なこの試みは,この分野における嚆矢となり,数多くの研究論文として公表されただけでなく,「微古生物学」(朝倉書店,1976共著)「微化石研究マニュアル」(朝倉書店,1978共著)や「古生物学各論」(築地書館,1980共著)などの解説書の中でもまとめられた.これらは現在でも古生物学者の重要な参考書であり,国内外の数多くの研究者に研究手法が引き継がれ,地質学・古生物学の発展に多大なる貢献となっている.このような石崎会員の一連の業績に対して,昭和54年に日本古生物学会から学術賞が授与された.石崎会員は東北大学はもちろんのこと,非常勤講師を勤めた大学でも後進の指導にも熱心にあたられ,ご自身の研究分野のみならず,堪能な英語能力を生かし,東北大学で学生の学術論文の英文添削や,博士論文作成のための英語指導等を一手に引き受けた.このおかげで数多くの指導学生が国際誌への成果の公表や博士号の取得を行うことができ,現在,大学,研究所,および企業の第一線で活躍している.
また,国内外の関連学会や社会貢献活動にも多大な功績を残しており,文部省の科研費審議会のメンバー,国際古生物協会(IPA)のもとでの国際研究グループのメンバー,英国のBritish Micropalaeontological Societyが発行していたStereo-Atlas of Ostracod Shellの編集委員,日本古生物学会が発行する学術誌の編集委員や編集委員長を歴任された.さらに,日本で開催された3つの国際会議,第9回貝形虫国際シンポジウム,第3回テチス浅海域に関する国際シンポジウム,第4回底生有孔虫国際シンポジウムにおいて,幹事や組織委員を務められ,会議を成功へと導かれたほか,フランス・エジプトなどの研究者を受入れるなど,国際共同研究・国際交流活動を活発に行われている.
以上,石崎会員の長年に渡る古生物学分野の研究業績と日本の地質学に対する多大な貢献により石崎会員を名誉会員として推薦する.
(以上5名)
2008年度名誉会員
2008年度名誉会員
増田 孝一郎 会員(1927-2013)
増田会員は,1951年東北大学理学部地質学古生物学教室を卒業された.卒業直後に東北大学教育教養部に助手として採用され,同大学教育学部助教授を経たのち,宮城教育大学助教授,教授を歴任され,1992年に宮城教育大学名誉教授になられた.
増田会員は学生時代から地質学や貝類化石に関心を寄せられ,東北大学理学部の卒業論文として能登半島北部東院内層の調査をされて以来,地質学的古生物学的研究に邁進された.研究初期の成果は,仙台市付近の地質調査,特に七北田層の地質学的古生物学的研究としてまとめられ, Miyagipecten matsumoriensisの新属新種の発見提唱として知られている.その後の研究は,第三紀貝類,特に二枚貝類Pectinidsの時空分布に関する生層序学的研究に発展し,日本各地の貝類化石群の記載報告,動物地理学的検討を重ねた研究成果は1961年に博士論文「Tertiary Pectinidae of Japan」としてまとめられ,地質学雑誌や日本古生物学会の学会誌等に多数発表された.
これらの成果は,1968年の日本古生物学会研究奨励賞(学術賞)あるいは1972年の日本古生物学会論文賞を受賞し,高く評価されている.増田会員の研究は日本周辺にとどまらず,1969〜1970年に文部省海外研究員としてアメリカ・スタンフォード大学およびスミソニアン国立自然史博物館での日米貝類化石群の比較研究に発展し,地質学的生層序学的視点から環太平洋域の新生代貝類化石群の起源と移動に関して膨大な情報が整理され,今日の日本の新生代地質学古生物学研究の発展に大いなる貢献を重ねて来られた.
増田会員の研究で培われた多くの経験と成果は,地質学古生物学の教育と普及においても大いに生かされてきた.東北大学・宮城教育大学はもとより非常勤講師を勤められた筑波大学,静岡大学,千葉大学,秋田大学等において同僚や後進に研究・教育活動としてさまざまな指針を与え続け,多数の教科書や普及書の執筆,出版を通じて地質学古生物学の普及に大いに尽力された.これまでに指導された多数の学生は,大学・研究所や企業の第一線で活躍しており,増田会員の地質学古生物学への深い理解と情熱は世代を越えて揺らぐことなく存分に引継がれている.また,増田会員は,1975年から齋藤報恩会自然史博物館の学芸員を,1986年には宮城教育大学付属養護学校校長を併任され,1989年には宮城県特殊教育研究会長,東北特殊教育研究会長,1997年〜2001年には仙台市科学館友の会会長として,学校および博物館においても,教育や運営・発展に大いに寄与され,大きな功績を残された.これらの功績の一部は,「地学教育の現状と問題点,教育学部における地学教育のありかた」(地質学雑誌,1982),「教育学部における地学教育の問題点」(地質学論集,1985)として公表されている.さらに,増田会員は,1992〜93年には国立台湾大学客員教授として国を越えて地学教育の普及に尽力されている.
以上のように,地質学古生物の普及発展に,長年にわたり大きな貢献をされた増田孝一郎会員を,名誉会員として推薦する.
(2013年1月8日逝去)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
石田 志朗 会員
石田会員は1953年に京都大学理学部を卒業し,同大学大学院に進み,京都大学理学博士の学位を取得された.1959年京都大学理学部助手に採用され,同大学理学部助教授を経て,1989年山口大学理学部教授に昇任され,1994年定年退官された.
石田会員の研究は,初期の新生界新第三系の層序・地質学的研究,古植物学的研究,その後の大阪層群相当層を主とした第四系地質学的研究,そして考古学における地質学的研究で大きな業績を残されている.
新生界第三系層序・地質学的研究は,特に北陸地域・能登半島の調査にはじまり,古地理構造発達史の研究のまとめとともに,古植物学的研究でも大きな成果をあげ,これらの研究で,京都大学理学博士の学位を授与された.大阪層群相当層の第四系地質学研究は,1960年代から開始され,従来からの詳細な火山灰・内湾海成粘土層を鍵とした層序学的研究のフィールドをひろげるとともに,当時最新の年代測定手法や古地磁気層序学的手法を導入し,日本列島の第四系層序の詳細対比に大きな貢献をされ,西南日本の古地理・地質構造発達史の研究に大きな進展をもたらした.これらの研究とともに,考古学への自然科学的(地質学的)手法の導入に積極的に取り組み,考古学における堆積学的・古環境学的見地からの研究へのさきがけとなった.このように考古学・地質学の学際融合型の研究を進展させ,他分野への地質学的手法の活用を具体的に提示されたことは特筆に価する.
石田会員は長年にわたって多くの学生や研究者を育てた.また,応用地質学や農林地質学の方面を含めて,幅広い地質学の発展につくされた.それらの成果は各種の地質図幅や国土利用基本調査報告等にまとめられている.最近では重要な地質露頭や地形などの現状をまとめる調査を継続されるなど,長年にわたり日本の地質学の発展に尽くされた.石田会員のこのような研究業績と地質学や第四紀地質学への多大な貢献に鑑み,日本地質学会の名誉会員に推薦する.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
杉崎 隆一 会員
杉崎会員は,1954年に名古屋大学理学部地球科学科を卒業し,同大学助手・助教授を経て,1989年に名古屋大学理学部教授となり,1995年に定年退職となった.この間,杉崎会員は,鋭い直感力に基づき研究テーマを設定し,地球化学的手法を駆使して,地球化学・構造地質学・堆積学・地震学・応用地質学など地球科学全般にわたって多くの未解決問題にチャレンジし,新しい地球科学観を提案してきた.その主要なものは地下水の研究から始まる.まず,地下水中の溶存ガス存在度から地下水の流動方向と流速の定量化を行った.次に,シャールスタイン(輝緑凝灰岩)と呼ばれていた我が国の中・古生代緑色岩の研究に取り組んだ.緑色岩の化学組成に基づき,緑色岩の形成場とテクトニクスの解明を行い,1970年代初頭の地質学・構造地質学に大きなインパクトを与えた.勇躍,珪質堆積岩の堆積環境の研究に着手し,層状チャート・頁岩・マンガンノジュールの化学組成の特徴から,本邦中・古生代層状チャート,ジュラ紀マンガンノジュール,オーストラリアの始生代チャートの堆積環境を明らかにし,次々とNature等の国際誌に発表した.これらの研究結果は,チャート=深海性堆積物という当時一般的になりつつあった考えとは大きく異なるもので,学界に大きなインパクトを与えるとともに国際的にも注目されたことは記憶に新しい.さらに,堆積岩の研究と並行して,地震予知を目的とした地下ガス組成の観測とそれに関連する実験的研究を行い,最近では,火成岩中に存在する有機物の発見とその起源に関する研究へと発展させたのである.
杉崎会員は,これらの研究によって得られた地質学・地球化学・地球物理学に関する新たな知見に基づいて,これらの分野の“常識”を打ち破る柔軟な考え方を提示し,国内外の地球科学者に大きな影響を与えた.杉崎会員の論文は特に外国で高く評価され,日本の地質学のレベルの高さを世界に知らしめた上で重要である.
また,杉崎会員は研究と同時に後継者の育成にも全力で取り組み,多くの優れた研究者を養成した.さらに,長年,多くの大学における地球科学の集中講義で次世代の若者に地球化学・地質学・フィールドワークの魅力を伝えた功績も大きい.その意味で,日本地質学会に対する貢献度も極めて高いと言える.
以上の理由により,杉崎隆一会員を日本地質学会名誉会員候補者として推薦する.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
沖村 雄二 会員
沖村会員は,1955年広島大学理学部地学科を卒業後,同大学大学院修士・博士課程を経て,広島大学助手,助教授,教授を歴任されるとともに,11国立大学において非常勤講師を務められ,平成8年の定年退職時に名誉教授となった.この間,地質学関連の学会活動に寄与され,日本地質学会西日本支部企画委員(1971〜72年),同幹事(1992〜95年),日本地質学会広島大会運営委員(1980年および1995年),日本地質学会評議員(1994〜95年度)等を務めている.また,国,地方公共機関・団体から委託された,成羽川流域および益田地域の広域調査委員,中国地域非金属資源対策委員長,中国山地国定公園の学術調査等にも従事された.
沖村会員は堆積学と古生物学の分野で多くの業績を残された.特に,日本における最初の石灰岩に関する本格的な教科書として,1982年に出版された著書「石灰岩」は,国内外での広範な研究成果を,多数の引用とともに平易に解説したものであり,日本の炭酸塩岩堆積学の目覚ましい発展の礎となっている.また,広島大学在職時を通して関わってきた中国地方の石炭〜ペルム系石灰岩の研究では,堆積学と化石(小型有孔虫・紡錘虫)についての深い見識を駆使した地道な研究成果を,多数の論文として執筆されている.
さらに,これらの経験を生かして,多数の海外学術調査(インド・パキスタン・イラン・トルコ・ギリシャ・スバールバール諸島など)に参加し,石炭〜ペルム紀における微化石の進化と絶滅,ペルム紀〜トリアス紀の堆積相と環境変動に関する研究を行い,その成果は著書「Tethys - Her Paleogeography and Paleobiogeography from Paleozoic to Mesozoic」および国際誌を含む論文として公表されている.これらの研究成果は東南アジア・中近東・ヒマラヤ前縁地帯の地質学・古生物学に大きく貢献したものであり,国際的にも広く引用されている.
沖村会員は良き師でもあり,広島大学では多数の学生・留学生に広範な知識と地道な研究姿勢を伝授し,今日の地質学を担う後進を育成している.また,現在でも東広島市自然研究会(会員160名,会報1〜38号)の会長として,地域地質学・環境学の啓蒙と進展を目指した教育・普及活動に活躍されている. 以上,沖村会員の,その真摯な研究活動による学術的貢献,および熱心な育成・普及活動による教育的貢献から,日本地質学会の名誉会員にふさわしいものと考え推薦する.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
加藤 誠 会員
加藤会員は,1954年に金沢大学理学部を卒業し,北海道大学大学院に進んだ.1961年北海道大学理学部助手になり,北海道大学より1962年理学博士を取得された.1970年同大学理学部助教授,1981年同大学理学部教授となり,1995年定年退官後は北海道大学名誉教授となられている. 加藤会員は,中・古生代の地質,とくにサンゴ化石の古生物学研究で多大な業績をあげ,国内的にも国際的にも高く評価されている.論文などで公表されたサンゴ化石は多数におよび,古くはシルル紀,デボン紀,主に石炭紀〜ペルム紀,さらには中生代三畳紀まで幅広い.これらの研究では,日本列島の中・古生代の地質の理解を促し,日本古生物学会学術賞(1970年)・日本地質学会小藤賞(1980年)・日本地質学会論文賞(1988年)を受賞している.加藤会員の研究業績は国内にとどまらない.公表されたサンゴ化石の産出地点も,本邦や朝鮮半島の各地から,広くテーチス海の地質が分布するインド〜トルコにおよんでいる.とくに,デボン−石炭系の境界や石炭−ペルム系境界の策定に関する議論ではその中心的な役割を担い,IUGSペルム系層位委員会委員・国際古生物協会事務局長・国際石炭系会議常任委員会委員などを歴任した. 加藤会員は,長年にわたって多くの学生や研究者を育て,国レベルでは文部省学術審議会専門委員をはじめ,日本学術会議地質学研究連絡委員会や古生物学研究連絡委員会の委員を務めた.学会活動としては,日本地質学会評議員や日本地質学会北海道支部長を歴任し,日本地質学会地質学雑誌編集委員などを通して日本地質学会の発展に尽くされたことはよく知られている.また,地質学の社会貢献についても高い識見をもち,北海道防災会議の専門委員として地盤問題や地質災害に関する応用地質分野や防災行政に貢献した.さらに,北海道大学学内委員として長期間務めた資料館専門委員や北海道地区自然災害資料センター運営委員の活動は,大学総合博物館の実現に道を開いたこととして特筆されよう. 加藤会員は,「日本の地質1『北海道地方』」(共立出版)の代表編集委員を務め,最近では朝倉書店「日本地方地質誌『北海道地方』」の編集に力を注ぎ,主に地質学の成果を後世に残すための仕事を今もなお精力的に進めておられることも強調しておきたい. 以上,加藤 誠会員の古生物学分野の研究業績と日本の地質学への多大な貢献に鑑み,日本地質学会の名誉会員に推薦する.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柴田 賢 会員
柴田会員は1955年に名古屋大学理学部地球科学科を卒業,同大学大学院に進学後の1956年11月に工業技術院地質調査所に採用され,首席研究官,地殻化学部長を経て,1993年に名古屋大学理学部教授に就任された.1996年同大学定年退官後,名古屋文理短期大学教授,1999年から2003年まで名古屋文理大学情報文化学部教授を歴任された.この間,名古屋大学年代測定資料研究センター長,名古屋文理大学図書館長を兼務され,学会をリードする地質年代学の研究に邁進しながら後進の育成にも全力投球された.また,日本学術会議地球化学・宇宙化学研究連絡委員会委員,地質学研究連絡委員会地質年代小委員会委員長,Chemical Geology 編集委員,地質年代学・宇宙年代学・同位体地学国際会議の組織委員,学術審議会専門委員などを通じて,日本の地質学に大きく貢献してこられた.さらに,国際協力事業団専門家としてフィリピンやベネズエラへの技術援助にも参画された.専門の地質年代学の業績は高く評価され,1983年に日本地質学会賞「放射年代の測定」を,1988年には工業技術院長表彰を受けられた.
柴田会員は,1960年から1年間ケンブリッジ大学に留学し,また1967年から2年間カナダ地質調査所に出張してK-Ar系とRb-Sr系の同位体年代学を研鑽され,日本における同位体年代学分野の創設に先駆的かつ指導的役割を果たされると共に,地質調査所で日本列島を網羅する多数の試料を組織的に年代測定してこられた.1990年までに公表された日本の同位体地質年代の過半は柴田会員が測定されたものである.年代測定の対象は多岐にわたっており,それぞれの成果が日本列島の発達史の解析研究を大きく前進させた.とりわけ,美濃帯上麻生礫岩中の花崗片麻岩礫の年代研究,飛騨山地や南部北上山地の基盤岩類の年代研究,美濃帯堆積岩の微化石年代と同位体年代の比較研究,断層の活動を評価するガウジの年代研究は顕著な研究業績として特筆される.また,ペルム紀のSr同位体初生値の低いM−タイプの花崗岩と白亜紀前期のSr同位体初生値のやや高い花崗岩類や高温型変成岩が関東山地から九州まで点在することを明らかにし,領家帯と三波川帯の間に構造的に挟まれた地質帯の存在を提唱された.この古陸復元モデルは日本列島地帯構造の再検討を促したものとして高い評価を得ている.
柴田会員の以上のような世界的研究業績と地質学や地質年代学への多大な貢献に鑑み,名誉会員として推薦する.
(以上6名)
Geo暦(2022)
2022年Geo暦(行事カレンダー)
2008年版 2009年版 2010年版 2011年版 2012年版 2013年版
2014年版 2015年版 2016年版 2017年版 2018年版 2019年版
2020年版 2021年版 2022年版 2023年版
2022年版 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
○印は学会主催行事.(共)学会共催・(後)後援・(協)協賛
1月January
(後)原子力総合シンポジウム2021(オンライン)
1月17日(月)13:30〜16:30
Zoomウェビナーによるオンライン開催
要事前登録
https://www.aesj.net/symp20220117
第235回地質汚染・災害イブニングセミナー(オンライン)
1月21日(金)18:30〜20:30
講師:新里忠史 (日本原子力研究開発機構)
演題:「福島の森林域を中心とした放射性セシウムの分布と移行状況」
参加費:会員:無料,非会員:1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
第31回 地質汚染調査浄化技術研修会(オンライン)
1月28日(金)19:30-21:30
内容:地質汚染調査のための地層の見方と単元調査法について
講師:風岡 修(地質汚染診断士、理学博士)
受講方法:ZOOMによるオンライン
申込期限:2022年1月25日まで,受講料:無料
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
日本博物館協会緊急フォーラム
文化審議会答申「博物館法制度の今後の在り方」を読み解く−博物館の振興に向けて−
1月28日(金)13:30-17:00
zoomによるオンライン開催
参加定員:500名・参加費無料(要参加申込)
https://www.j-muse.or.jp
2月February
第35回地質調査総合センター シンポジウム
「ゼロエミッション社会実現に向けたCCSにおける産総研の取り組み」
2月10日(木)13:00-17:15(配信開始 12:30を予定)
会 場:オンライン開催
参加費:無料(事前登録制)CPD:4単位
https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo35/index.html
情報科学を活用した地震調査研究プロジェクト
(STAR-Eプロジェクト)第1回研究フォーラム
「地震×AI、STAR-Eプロジェクトで目指すイノベーション〜注目のAI企業が語る地震研究の可能性〜」
2月18日(金)9:30-12:00(開場 9:15)
主催:文部科学省
開催形式:オンライン配信(Vimeo)参加費無料
申込URL:https://star-e-project.eventcloudmix.com
(共)地質情報展2022あいち ―発見!あいちの大地―
2月19日(土)- 20日(日)
場所:名古屋市科学館イベントホール
主催:GSJ・日本地質学会・名古屋市科学館
後援:中部地質調査業協会,日本ジオパークネットワーク
https://www.gsj.jp/event/johoten/index.html
東青ヶ島海丘カルデラ熱水サイトシンポジウム
2月24日(木)13:00から
会場:オンライン開催(zoom)
主催:JAMSTEC海洋機能利用部門海底資源センター
参加申込はこちらから
プログラムなどシンポの詳細はこちら(pdf)
(後)第36回地質調査総合センター シンポジウム
「3次元で解き明かす東京都区部の地下地質」
2月25日(金)13:00-16:55(配信開始 12:45を予定)
会場:オンライン開催
参加費:無料(事前登録制)CPD:3.5単位
https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo36/index.html
第31回 地質汚染調査浄化技術研修会
2月25日(金)19:30-21:30
内容:地質汚染調査におけるボーリング調査
講師:風岡 修(地質汚染診断士、理学博士)他
受講方法:ZOOMによるオンライン
申込期限:2022年2月21日まで
受講料:無料
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
防災科学技術研究所令和3年度成果発表会
来るべき国難夕災害に備えて2022
国難にしないために:モノで守り,行動を変える
2月28日(月)13:00-17:00
会場:東京国際フォーラム(会場参加/オンライン配信)
参加無料,会場参加は要事前申込(2/14締切)
https://www.bosai.go.jp/info/event/2021/seika/index.html
3月March
第27回日本災害医学会総会・学術集会
3月3日(木)〜5日(土)
会場:広島国際会議場・広島市文化交流会館ほか
テーマ:災害医療のパラダイムシフトー何を攻め・守り・育てるのかー
https://site2.convention.co.jp/27jadm/
◯第2回JABEEオンラインシンポジウム(オンライン)
『昔と違う イマドキのフィールド教育』
3月6日(日)14時開会予定
Zoom によるオンラインシンポジウム
参加費無料
http://www.geosociety.jp/science/content0141.html
令和3年度筑波山地域ジオパーク学術研究助成金普及講演会(研究成果発表会)
3月6日(日)13:30-16:00
会場:オンライン(Zoom利用)
定員:90名(先着順)
参加無料,要事前参加登録(2/28締切)
詳しくはこちらから(PDF)
日本列島の地殻応力〜ジャパンストレスマップ(JSM)
3月7日 14:00〜17:20
場所:土木学会講堂(オンライン併用)
主催:土木学会エネルギー委員会
参加費:無料(事前登録制)CPD:1.9単位
https://committees.jsce.or.jp/enedobo/node/90
第56回日本水環境学会年会(オンライン)
3月16日(水)-18日(金)
https://www.jswe.or.jp/event/lectures/2021per.html
第236回イブニングセミナー(オンライン)
3月25日(金)19:30-21:30
演題:「赤色立体地図の原理と応用 特に最近の発展について」
講師:千葉達朗(アジア航測株式会社)
主催:NPO法人日本地質汚染審査機構
参加費:主催NPO会員(無料) 非会員(1,000円)
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
4月April
JAMSTEC海域地震火山部門令和3年度研究成果報告会
4月6日(水) 13:00-15:00
開催形式 :オンライン(ZOOMウェビナー) 日本語
参加費 :無料 ※事前登録制
参加申込締切:4月4日(月)13:00
定員:450名(定員に達した場合締切)
https://www.jamstec.go.jp/rimg/j/topics/20220406/
2022年堆積学会オンライン大会
4月23日(土)-24日(日)
主にZoomを使用したオンライン開催
http://www.sediment.jp/04nennkai/2022/2022online_annai.html
5月May
※2022年「地質の日」関連行事はこちらから
第31回 地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン第6回目)
5月13日(金)19:30-21:30
内容:地質汚染調査におけるボーリング調査
講師:風岡 修(地質汚染診断士、理学博士)他
受講方法:ZOOMによるオンライン
申込期限:5月10日まで
受講料:無料
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
2022年度 第1回地質調査研修
5月16日(月)- 20日(金)
場所:
(室内座学)茨城県つくば市(産総研)
(野外実習)茨城県ひたちなか市,福島県双葉郡広野町・いわき市周辺
定員:6名(定員になり次第締切)
CPD:42単位, 参加費:63口(1口1000円)の会費が必要です.
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2022.html
シンポジウム:地質技術者育成の課題と対策:防災・減災、国土強靭化を担う地質技術者の不足を鑑みて(オンライン)
5月21日(土)13:00-16:00
https://www.youtube.com/channel/UCSBjQkKQOIU7tGcn8TA1Wqw/featured
参加費無料,事前登録不要
主催:西日本地質人材コンソーシアム
(共)日本学術会議公開シンポジウム(ハイブリッド形式)
「チバニアン,学術的意義とその社会的重要性」
5月24日(火)13:00-17:10
場 所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木 7-22-34)
要参加申込
https://nws.stage.ac/scj_sympo220524/
2022年度 第1回地質調査研修(追加)
5月30日(月)-6月3日(金)
場所:
(室内座学)茨城県つくば市(産総研)
(野外実習)茨城県ひたちなか市,福島県双葉郡広野町・いわき市周辺
定員:6名(定員になり次第締切)
CPD:42単位, 参加費:63口(1口1000円)の会費が必要です.
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2022-1.html
6月June
第237回イブニングセミナー(オンライン)
6月17日(金)19:30-21:30
演題:「熱海で発生した泥流被害とその他の近年の土石流・泥流被害」
講師:安田 進(東京電機大学名誉教授)
主催:NPO法人日本地質汚染審査機構
参加費:主催NPO会員(無料) 非会員(1,000円)
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
地質学史懇話会(オンラインとハイブリッド)
6月18日(土)13:30-16:30
場所:早稲田奉仕園(東京メトロ東西線早稲田駅下車徒歩5分)
講演者:中川智視「19世紀アメリカにおける専門化の進展」(仮題)
五味 篤「高橋是清のペルー銀山事件と地質関係者」
問い合わせ:矢島道子 pxi02070[アットマーク]nifty.com
7月July
(後)第59回アイソトープ・放射線研究発表会
7月6日(水)〜 8日(金)
オンライン開催(zoom)
事前参加登録(7,000円)締切: 6月10日(金)17時
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2022/top
学術会議主催学術フォーラム
「国難級災害を乗り越えるためのレジリエンス確保のあり方」
7月7日(木)13:30-17:00
場所:日本学術会議講堂(オンライン配信)
参加費無料
https://www.scj.go.jp/ja/event/2022/325-s-0707.html
第31回 地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン第7回目)
7月22日(金)19:30-21:30
内容:地下水汚染調査
講師:成澤 昇(株式会社環境地質研究所、地質汚染診断士)
受講方法:ZOOMによるオンライン
申込期限:2022年7月19日まで
受講料:無料
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
(共)岩石―水相互作用国際会議(WRI-17)
7月30日(土)より→2023年8月に延期となりました(22.1.27)
会場:仙台市
https://www.wri17.com/
(後)青少年のための科学の祭典2022全国大会
7月30日(土)-31日(日)10:00-15:30
場所:科学技術館(千代田区北の丸公園)
入場無料・事前予約制
http://www.kagakunosaiten.jp/
8月August
(後)科学教育研究協議会第68回全国研究大会(岡山大会)
8月10日(水)〜12日(金)
会場 岡山理科大学 岡山キャンパス
→中止となりました.WEB岡山研究会開催(10/30)
詳しくは,https://kakyokyo.org/
第76回地学団体研究会総会(長野)
8月20日(土) 〜20日(日)
開催方式:現地開催とオンラインのハイブリッド方式
現地会場:信州大学教育学部(長野県長野市)
https://www.chidanken.jp/
(後)第9回国際地学教育会議
8月21 日(日)〜 25 日(木)
会場:くにびきメッセ(島根県コンベンションセンター)
https://ja.geoscied9.org/
日本堆積学会堆積学スクール2022「現世干潟の堆積過程」
8月28日(日)
場所:神奈川県川崎市多摩川河口干潟
http://www.sediment.jp/04nennkai/2022/2022school.html
9月September
◯日本地質学会第129年学術大会(2022東京・早稲田大会)
口頭発表(対面開催):9月4日(日)-6日(火) 会場:早稲田大学
ポスター発表(e-poster):9月10日(土)-11日(日) オンライン
※関連行事「地質情報展2022とうきょう」は同会場で9/3-9/5開催予定です.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/top
(共)2022年度日本地球化学会第69回年会
9月5日(月)-12日(月)
場所:高知⼤学朝倉キャンパス会場+オンライン会場(ハイブリッド開催)
http://www.geochem.jp/meeting/
(後)第65回粘土科学討論会
9月7日(水)-8日(木)
※討論会のみの実施,現地見学会は開催しません.
会場:島根大学
http://www.cssj2.org/event/annual_meeting/
JAMSTEC 創立50周年記念式典・研究報告会「JAMSTEC2022」
9月7日(水)13:15-17:30
Zoomオンライン開催(参加無料・事前登録制)
※YouTube配信も予定されています.
https://www.jamstec.go.jp/j/pr-event/jamstec2022/
第238回イブニングセミナー(オンライン)
9月9日(金)19:30-21:30
演題:「水銀汚染地域における土壌中水銀濃度分布とその化学形(仮)」
講師:冨安卓滋(鹿児島大学大学院理工学研究科)
主催:NPO法人日本地質汚染審査機構
参加費:主催NPO会員及び学生の方(無料) 非会員(1,000円)
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
日本鉱物科学会2022年年会・総会
9月17日(土)〜19日(月)
会場:新潟大学
http://jams.la.coocan.jp
第39回歴史地震研究会(高槻大会)
9月17日(土)-19日(月)
場所:関西大学高槻ミューズキャンパス
http://www.histeq.jp/kenkyukai.html
国際ゴンドワナ研究連合(IAGR)2022年総会及び第19回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム →※11月に延期されました(延期後の予定はこちら)
9月23日〜25日(シンポジウム)
9月26日〜27日(峨眉山巨大火山区野外巡検)
会場:中国四川省成都工科大学
ファーストサーキュラーはこちら
https://www.data-box.jp/pdir/4aa617ecc00845c284f085edba48eec5
海底地質リスク評価研究会特別講演会
9月28日(水)10:00〜11:30(予定)
場所:基礎地盤コンサルタンツ本社(東京都江東区亀戸)もしくはオンライン
講師:東邦大学理学部生命圏環境科学科 竹内彩乃 先生
テーマ:地域における再エネ導入と地域共生のあり方
参加費無料
申込先:https://forms.gle/Z3Ye4BND6ZmmR6m46
https://www.kisojiban.com/sssgr/
地層処分技術に関する研究開発報告会−第3期中長期目標期間の成果取りまとめ(CoolRepR4)について−
9月30日(金)13:30-16:45
形式:オンライン配信(YouTubeライブ)
申込方法:Web(Googleフォーム)またはEメール
https://www.jaea.go.jp/04/tisou/houkokukai/pdf/houkokukai_r04_gaiyou.pdf
10月October
第31回 地質汚染調査浄化技術研修会(現地実習)
10月14日(金)(※日程が1日だけに変更になりました;9/30)
主催:NPO法人 日本地質汚染審査機構
会場:日本地質汚染審査機構関東ベースン実習センター(千葉県香取市)
会費:主催NPO法人会員50,000円 10,000円・非会員 60,000円 20,000円
(※日程変更に伴い参加費も変更します;9/30)
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
第5回水循環シンポジウム(水郷の暮らしと水循環シンポジウム)
主催:NPO法人日本地質汚染審査機構
10月22日(土)
(午前)上戸不動の井(茨城県潮来市)等の見学会, 集合場所:潮来ホテル
(午後) シンポジウム:基調講演:宮崎 淳氏(創価大学法学部教授)「健全な水循環の維持と地下水マネジメントー流れる水は誰のものか?ー」他発表、パネルディスカッション
会場:潮来ホテル
http://www.npo-geopol.or.jp/water-sympo.htm
第14回防災学術連携シンポジウム
自然災害を取り巻く環境の変化−防災科学の果たす役割−
10月22 日(土)16:30-18:00*要参加申込
https://janet-dr.com/060_event/20221020_01.html
ノーベル・プライズ・ダイアログ東京2022
10月23日(日)10:00-17:00(予定)
場所:パシフィコ横浜会議センターメインホール(対面方式)
参加費無料
※ただし、一部の講演者はオンライン参加になります.
https://www.nobelprize.org/water-matters-tokyo-2022/ja
2022年度 第2回地質調査研修 ※定員に達したため、キャンセル待ち
10月24日(月)-28日(金)
主催:産総研コンソーシアム「地質人材育成コンソーシアム」
場所:島根県出雲市長尾鼻周辺(小伊津海岸)
内容:野外での地層・岩石の観察ポイントからまとめまで,地質図を作成する
ための基本的事項を事前のe-ラーニングと5日間の対面研修で習得します.
定員:6名(定員になり次第締切),CPD:42単位
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2022-2.html
第61回温泉保護・管理研修会
10月25日(火)-26日(水)
場所:北とぴあ つつじホール(東京都北区王子)
主催:公益財団法人中央温泉研究所
http://www.onken.or.jp/seminar.html
11月November
(協)石油技術協会令和4年度秋季講演会(ハイブリッド)
11月1日(火)13:00-18:05
場所:東京大学小柴ホール(東京都文京区)
テーマ:エネルギー安定供給とカーボンニュートラル推進の両立を目指す社会に向けて〜石油開発業界の持続的な役割〜
https://www.japt.org/
第35回ヒマラヤ−カラコルム−チベット ワークショップ(HKT-35)
11月2日(水)〜4日(金)
場所:ネパール・ポカラ
詳しくはこちら(PDF)
日本火山学会2022年度・秋季大会
11月3日(木)〜6日(日)
会場:三島市民文化会館・三島市民市生涯学習センター
(状況により開催方法・内容が変更になる可能性があります)
http://www.kazan-g.sakura.ne.jp/J/index.html
国際ゴンドワナ研究連合(IAGR)2022年総会及び第19回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム
11月4日-6日(シンポジウム)
11月7日(峨眉山巨大火山区野外巡検)
場所:中国四川省成都工科大学(Chengdu University of Technology)
COVID-19感染問題等で国内外の移動制限等がある時はオンライン会も併設する。
参加申込、問い合わせ:Prof. Hao Zou (Chengdu University of Technology, Chengdu, China. E-mail: zouhao@cdut.edu.cn
フォースサーキュラーはこちら
(後)第22回こどものためのジオ・カーニバル
11月5日(土)〜6日(日)
場所:大阪市立自然史博物館(ネイチャーホール)
http://www.geoca.org
学術会議公開シンポジウム
「私たちの地球はどんな惑星か−科学を混ぜて地球を探る」
11月5日(土)10:30-12:00
場所:テレコムセンター1F大ステージ
参加無料,事前申込不要.
https://www.scj.go.jp/ja/event/2022/331-s-1105.html
長久保赤水顕彰会創立30周年記念事業
第6回全国赤水ウオーク(2022年)−赤水ゆかりの地を訪ねるウオーク −
11月6日(日)集合:JR南中郷駅前8:45
申込方法:当日受付,参加無料
http://nagakubosekisui.org/archives/5103
令和4年国土技術研究会
11月10日(木)-11日(金)
会場:国土交通省 中央合同庁舎(千代田区霞ヶ関2丁目,オンラインでも配信)
参加無料・要事前申込(11/7締切)
https://www.mlit.go.jp/chosahokoku/giken/index.html
2020年度東京地学協会メダル 受賞記念講演会
対談:荒牧重雄・藤井敏嗣「噴火と火山防災の60余年」
11月12日(土)11:00-12:45
場所:アルカディア市ヶ谷(私学会館)6階「阿蘇」
申込期限:10月31日(月)(参加費無料,非会員の方も歓迎)
http://www.geog.or.jp/lecture/lecturescheduled/452-2020medal.html
東京大学中東地域研究センター公開シンポジウム
「深掘り! オマーン・スルタン国」
11月13日(日)14:00-17:00
会場:東京大学駒場キャンパス(Zoomによるオンライン参加も可能)
記念講演:宮下純夫(新潟大学名誉教授)「アラビア半島オマーンの自然と地質そして人々」ほか
https://park.itc.u-tokyo.ac.jp/UTCMES/2022/09/22/public_symposia/
国際シンポジウム2022「富士山地域DX〜山岳観光と次世代通信〜」
主催:山梨県富士山科学研究所
11月20日(日)13:00-16:30(予定)
Zoomによるオンライン開催
事前申込制:11/10(木)まで
https://www.mfri.pref.yamanashi.jp/
日本堆積学会20周年記念リレーセミナー(第1回)
11月24日(木)12:15-13:00
Zoomウェビナーオンライン開催(参加無料)
講演者:産業技術総合研究所 中嶋 健 氏
演題:海底自然堤防形態の定量的解析
https://sites.google.com/view/ssj20th/home
(後)第32回社会地質学シンポジウム
11月25 日(金)-26 日(土)
場所:日本大学文理学部オーバル・ホール,オンライン(Zoom)併用
特別講演
「ポストコロナ時代の国際交流 ―大学に今、何が求められているのか−」富田敬子(常磐大学・常磐短期大学 学長)Youtubeでも同時配信
招待講演
「環境地質学の対象としての有明海・八代海」秋元和實(元熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター准教授)
「呉羽山で学ぶ-ジオ・エコ・ヒトのつながり -」安江健一(富山大学学術研究部准教授)
https://www.jspmug.org/envgeo_sympo/32nd_sympo/
ミニシンポジウム「日本の山火事・野火研究:地質時代から現在まで」
11月26日(土) 13:30-16:00(予定)
場所:大阪公立大学杉本キャンパス 学術総合センター1F文化交流室
要参加申込(11/18まで)※申し込み多数の場合には先着順で受付します.
申込は,https://forms.gle/GYVs9PwNbk7jhYvD6
詳しくは,こちら(PDF)
大気海洋研究所共同利用研究集会
「フィリピン海プレート北端部テクトニクスの再検討」
11月28日(月)-29日(火)
対面とZoomのハイブリッド開催(要参加申込:11/25締切)
※追加発表も受付中(11/18締切)
https://www.aori.u-tokyo.ac.jp/aori_news/meeting/2022/20221128.html
12月December
(協)第38回ゼオライト研究発表会
12月1日(木)-2日(金)
場所:あわぎんホール(徳島県郷土文化会館)
講演申込締切:9月9日(金)
https://jza-online.org/
第239回イブニングセミナー(オンライン)
12月1日(木)19:30-21:30
演題:「福島原発事故に伴い発生した膨大な除去土壌の再生利用等の現状と課題」
講師:油井三和先生(福島工業高等専門学校)
参加費:主催NPO会員及び学生の方(無料),非会員(1,000円)
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
第37回 地質調査総合センターシンポジウム
令和4年度地圏資源環境研究部門研究成果報告会
地圏資源環境研究部門の最新研究ー新たなチャレンジと展望ー
12月7日(水)13:30-17:20(予定)
会場:ステーションコンファレンス万世橋4階(東京都千代田区神田須田町)
参加費無料・事前登録制
CPD:3.5単位
https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo37/index.html
令和4年度国土技術政策総合研究所講演会
気候変動への対応:国土交通グリーンチャレンジに向けた国総研の取り組み
12月8日(木)9:30から
会場:日本教育会館 一ツ橋ホール(東京都千代田区一ツ橋2-6-2)
参加費無料・要事前申込
http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/koen2022.html
日本堆積学会20周年記念リレーセミナー(第1回)
12月15日(木)12:15-13:00
Zoomウェビナーオンライン開催(参加無料)
講演者:池田昌之氏(東京大学)
演題:深海チャートの堆積リズムから読み解く天文学的周期の地球環境変動
https://sites.google.com/view/ssj20th/home
シンポジウム「御嶽山・箱根山・草津白根山ー水蒸気噴火および防災と観光ー」
12月16日(金) 水蒸気噴火に関する学術シンポジウム
12月17日(土) 活火山の防災と観光に関するシンポジウム
場所:長野県・木曽町文化交流センター(長野県木曽郡木曽町福島5129)
主催:御嶽山・箱根山・草津白根山ー水蒸気噴火および防災と観光ーシンポジウム実行委員会
開催方法:現地・オンライン併用
入場無料・要参加申込
https://ontake-vc.jp/satonews/news25/
地質学史懇話会(オンラインとハイブリッド)
12月17日(土)13:30-16:30
場所:早稲田奉仕園(東京メトロ東西線早稲田駅下車徒歩5分)
山田俊弘・須貝俊彦「望月勝海日記通読プロジェクト」(仮題)
今村遼平「中国地図測量史」
問い合わせ:矢島道子 pxi02070[アットマーク]nifty.com
男女共同参画推進委員会主催
「技術サロン(女子学生および社会人女性向け懇話会)」
12月17日(土)13:00-16:00【Zoomによるリモート開催】
対象:技術者及び技術士を目指す女子学生・女性社会人
内容:技術士制度の説明、技術士とのフリーディスカッション等
https://www.engineer.or.jp/c_cmt/danjyo/topics/009/attached/attach_9095_1.pdf
◯日本地質学会第6回ショートコース
法地質学/付加体地質学・沈み込み帯掘削
12月18日(日)9:30より
Zoom によるオンライン講義
http://geosociety.jp/science/content0151.html
学術会議公開シンポジウム(オンライン開催)
地名標準化の現状と課題:地名データベースの構築と地名標準化機関の設置に向けて
12月18日(日)13:00-17:00
参加無料,定員300名
https://www.scj.go.jp/ja/event/2022/331-s-1218.html
第38回 地質調査総合センターシンポジウム 美ら海から知る美ら島の歴史
―500万年間の地史を求めて―
12月21日(水)13:00〜17:00(予定)【受付開始:12:30】
会場:沖縄県立博物館・美術館(おきみゅー)博物館 講堂
定員:200名(事前登録制)
参加費:無料
CPD:3.5単位 (ジオ・スクーリングネット)
https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo38/index.html
地球掘削科学国際研究拠点・令和4年度共同利用・共同研究集会
「水中災害考古学研究への水底表層コア試料の活用」
12月21日(水)-12月22日(木)
場所:高知コアセンター・B棟セミナー室
発表形式:対面・オンライン(ZOOM)※ハイブリッド形式
参加方法:対面およびオンラインによる参加希望者はHPから申請
参加対象者:国内の研究機関に所属する研究者(学生を含む)上限100名.
参加登録締切:12/19(月)正午(先着順)
https://hibarajuku.labby.jp/news/detail/2474
STAR-Eプロジェクト 第1回研究者・学生向けイベント
アイデアソン「地震・測地などのデータに関する研究展開から社会応用までの幅広い活用方策」
12月27日(火)10:00-17:30
会場:TKP新橋カンファレンスセンター
参加費無料,定員:50人
申込締切:12月13日(火) 12:00
https://star-e-project-221227.eventcloudmix.com/
2011年度名誉会員
2011年度名誉会員
小畠郁生 会員(1929-2015)
小畠郁生会員は1954年に九州大学理学部地質学科を卒業された後,1956年に九州大学大学院理学研究科博士課程を中退され,同大学地質学教室助手,西南学院大学講師を経て,1962年に国立科学博物館研究員として着任された.1962年に「日本産バキユリテス科」の研究をまとめ理学博士の学位を取得された.国立科学博物館では1982年に地学研究部部長に昇任され,1994年に退職されるまで永きにわたって古生物学・地質学に関する教育と研究に活躍され,1996年に名誉館員となられている.国立科学博物館退職後も,1994年から2年間,(財)自然史科学研究所理事,1996年から4年間,大阪学院大学国際学部教授を歴任されている.
小畠会員は,古生物学・地質学が専門で,松本達郎教授の下,アンモナイト類の個体発生の吟味とその系統的位置の推定に取り組まれ,成長解析手段である相対成長の検討を取り上げ,その意義を考察し,かつその位置づけを行われた.この他,アンモナイトの初期殻形態,連室細管壁の微細構造とその機能的意義や,現生のオウムガイ類の生態観察によって,絶滅したオウムガイ類やアンモナイト類の生活様式,生殖方法等の推定など多岐にわたる研究に取り組まれた.そして,北海道や岩手県宮古をはじめ,日本各地の白亜系の調査・研究に精力的に取り組まれ,日本国内の白亜系の対比,さらには,白亜系の国際対比に貢献された.研究の対象はアンモナイトにとどまらず,中生代の動物全般についての研究を行い,その成果を発表された.例えば,フタバスズキリュウの発掘に携わられており,『地質學雜誌』に首長竜の発見を短報として報告されている.これらの多大な業績が認められ,1966年には日本古生物学会最優秀論文賞,1977年には日本古生物学会学術奨励金(学術賞)を受賞されている.専門の研究論文に限らず,『全国大学博物館学講座協議会研究紀要』等への博物館を中心とした社会教育に関する研究論文や,『地学教育』等への学校教育に関する研究論文まで,教育分野にまで幅広い業績を残されている.また,恐竜を中心とした化石についての書籍を多数,執筆,監修,翻訳し,一般への普及活動も十分に行われた.その著作を通して,古生物学・地質学を志した者も多いことは周知のとおりである.小畠会員は現在もなお,研究や著作をとおして,古生物学・地質学の普及教育,後進の指導に貢献されている.
以上のように,古生物学・地質学の普及発展に,長年にわたり大きな貢献をされた小畠会員を日本地質学会の名誉会員として推薦する.
(平成27年9月19日逝去)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
倉沢 一 会員(1930年生まれ)
倉沢会員は1953年横浜国立大学学芸学部地学科を卒業後,1955年に東京教育大学大学院理学研究科地質学鉱物学専攻を修了,1956年には通産省工業技術院地質調査所地球化学課に入所し,同位体地質学及び地球惑星化学分野の研究に従事された.
倉沢会員は1955年に「天城火山の地質」を地質学雑誌(要旨)と大学紀要(英文)に発表されたのを皮切りに,雲仙,多良岳,金峯山,五島列島,隠岐などの火山岩の地球化学的研究を発表し,1966年には河野義礼教授を主査として「北西九州,北松浦玄武岩類の岩石学的研究」の英語論文で東北大学から理学博士の学位を取得された.1966〜67年には東京大学久野久教授の誘いで米国地質調査所同位体地質学研究所(デンバー)にてU-Th-Pb系の測定実験を行った.1970年には日本初の本格的な「同位体地質学」の教科書をラテイス社(丸善)から出版された.この本はRb-Sr法やU-Pb法の原理と実際的な測定法および同位体データの地質学的意義を詳しく解説してあり,当時の日本の研究レベルの向上と学生の教育に大きく貢献した.また,アポロが持ち帰った月の石の希土類組成に関する論文を1972〜74年に発表し,セリウム異常の可能性を示された.その後も1980年代末まで現地地質調査に基づく日本,米国,インド,南極などの火山岩やマントル物質に関する同位体地質学・地球化学の論文を発表し続け,同会員の論文のいくつかは現在も世界中で引用されている.1978年に科学技術庁在外研究員として米国地質調査所,航空宇宙局,ジョンソン宇宙センターを訪問し,その報告(地質ニュース)は当時の研究者や研究所の様子を生き生きと伝えている.一方,1975〜83年に地質調査所企画室付を務めて以来,83〜86年に同九州出張所長,86〜88年に同海外地質調査協力室長,88〜90年に同北海道支所長,そして90〜98年に工業技術院研究協力センター長を務めるなど要職を歴任され,さらに横浜国立大学,北海道大学,山形大学,ネブラスカ大学,ルイジアナ州立大学で集中講義を行い,全国の多くの学生の研究・論文指導に関与したほか,九州大学の同位体地質学講座開設にも参与された.また,日本地球化学会など日本の関連諸学会で評議員を務め,ロンドン地質学会のクラーク・メダル選考委員も務められた.そして1998年の退職後は日本七宝作家協会,日本写真家協会に所属して芸術活動に打ち込んでいる.
以上のような長年にわたる同位体地質学・地球惑星化学分野の研究・教育への多大な貢献に鑑み,倉沢会員を日本地質学会名誉会員に推薦する.
(平成28年11月13日逝去)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
松島信幸 会員(1931年生まれ)
松島信幸会員は1955年に信州大学教育学部理科地学専攻を卒業され,その後伊那里小学校を皮切りに,小・中学校で理科教師を37年間勤められた.1992年に定年退職後,飯田市美術博物館の客員研究員になられ,現在飯田市美術博物館の顧問をなされている.
松島会員は中学生時代から地元の山々に登り始め,大学に入学後,赤石山地の高山域である南アルプスの地質の探求を開始された.当時,この山域の大部分の地層は“時代未詳層群”として一括され,詳細は不明のままであったが,大学での卒業研究以来,80年代に至るまでの一連の研究によって,大部分が四万十帯の中生界であることが明らかにされた.また,その内部に大規模な屈曲構造(逆くの字型ねじり曲がり反転屈曲)が存在することを明確にされた.さらに,中部地方の中央構造線,赤石構造帯などの位置づけを再検討され,それらが中新世に活動したことを明らかにされた.これらの成果は,日本列島中部のテクトニクス,特に赤石-関東山地の基盤岩のハの字型屈曲,伊豆-小笠原弧の衝突,フォッサマグナの形成を考察する上で多大な影響を与えている.また松島会員が中心となって作成された地質図には,1972年の「下伊那地質図」,1984年の「天竜川上流域地質図」などがある.
このほかに60年代から伊那谷の段丘に関する研究を開始されている.これにより,従来は天竜川が作った河岸段丘と信じられてきた地形が,活断層による変動地形であることを明確にしたことは,日本での活断層研究における最重要な成果の一つといえる.この成果は,伊那谷とその周辺の構造発達史論文「伊那谷の造地形史」にまとめられ,九州大学から理学博士の学位を授与された.
以上を通じての調査研究活動は,小・中学校での多忙な教職生活の中でなされたものであり,初等中等教育に携わる全国の会員を元気づけるものである.松島会員の研究で培われた多くの経験と成果は,地質学の教育と普及においても大いに生かされてきている.
1985年には有志と伊那谷自然友の会を結成し,また1988年には飯田市美術博物館の設立,1993年には大鹿村中央構造線博物館の設立に関わられた.これらの教育・普及活動は,豊富な野外調査による地質と自然への理解をベースにした,常に現場を見て判断するという現場主義によるものである. 以上のように,地域地質学の究明,およびその普及発展に長年にわたり大きな貢献をされた松島会員を名誉会員として推薦する.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
猪郷久義 会員(1932年生まれ)
猪郷久義会員は1955年に東京教育大学理学部地学科を卒業された後,1960年に東京教育大学大学院理学研究科博士課程を修了され,理学博士を取得された.その後,米国イリノイ州立地質調査所特別副地質技師,目白学園女子短期大学助教授・教授を経て,1968年に東京教育大学助手に着任された.さらに筑波大学助教授,教授を歴任され,1996年筑波大学を定年退職された後,筑波大学名誉教授となられた.筑波大学退職後も,国立科学博物館客員研究員,(財)自然史科学研究所理事長として古生物学・地質学に関する教育と研究に従事されている.
猪郷久義会員は,古生代のフズリナ,コノドント,サンゴ等および中・古生代放散虫の化石層序学的ならびに古生物学的研究を専門とし,国内・外のこの分野における指導的役割を果たされてきた.たとえば,同会員が行ったフズリナやサンゴに基づく飛騨山地の中・上部古生界の地質学的・層序学的研究の成果は,当該地帯の地質解明にとどまらず,同様な非変成古生層が含まれる南部北上帯や黒瀬川構造帯との対比や起源の推定を行う上で,きわめて重要な意義を持っている.また,わが国のコノドントの生層序学的・古生物学的研究におけるパイオニア的役割を果たし,とくにその生層序学的研究によって,従来古生層として一括されていた基盤堆積岩類中に三畳系が広く存在することを初めて明らかにした.その結果,その後急速に進展した日本列島の地史的再検討や新たなテクトニクス構築の基礎となった.いっぽう,タイを中心とする東南アジア諸地域でのフズリナ,コノドント等の化石層序学・古生物地理学的研究も国際的に高い評価を受けている.これらの研究成果は,約120編の論文としてまとめられ,学術誌に公表されている.
教育の面では,筑波大学はもとより,他の多くの大学に非常勤講師として招かれ,広く学部・大学院の研究指導にあたっている.さらに,中国,タイ,インドネシア等から留学生,研究者を数多く受け入れ,留学生教育や国際共同研究を促進した.また,多数の専門書の執筆や,さらにはNHKの教育放送を通じて幅広い社会教育活動にも積極的に尽力された.学会活動としては,同会員は日本古生物学会会長,評議員,学会誌編集委員長を歴任された.
以上のような猪郷会員の長年に及ぶ地質学ならびにこれと深く関わる古生物学の研究・教育に対する多大な貢献により,日本地質学会名誉会員に推薦する.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
籾倉克幹 会員(1935–2015)
籾倉克幹会員は,1957年に広島大学理学部地学科を卒業され,1958年農林省の地質技術者に採用された.その後北陸,中国四国,東海,九州,関東の各農政局と農林本省を歴任され,国土庁へも出向されている.この間の籾倉会員の地質学的技術成果は極めて多い.
籾倉会員は地質学の生産現場への貢献の必要性を自覚され,学生時代から所属されていた「日本地質学会」に加えて「農業土木学会」,「土質工学」に入会するとともに,「応用地質学会」や「日本地下水学会」の創立に参画され,地質学の社会的貢献の理論と実践を貫徹された方である.1961年から勤められた中国四国と東海では旱魃緊急対策のため連日電気探査と井戸掘りに終始され筆舌に尽くしがたい苦労をしておられる.これらの労苦が10ha以上の開田に結びつくと,地元から感謝されるとともに,多くの無灌漑農地の改良事業へのパイロットの役割りを果たしてきた.1968年農林本省では,全国規模の長期農業政策立案や大蔵折衝といった多忙の中,韓国の朴大統領からの要請に応えて旱魃対策調査団を組織し前羅・慶尚4道の水文地質踏査,井戸掘削と揚水試験に従事し旧河道の資源評価の重要性を報告し,国際灌漑排水会議には,「阿蘇火山西麓台地の地下水開発(1975年英文)」と「宮古島ダムに貯蔵された地下水の管理と抑制(1989年英文)」を公刊し,内外の専門家から引用されるなど国際的貢献も多い.
各地で繰り広げられていた灌漑事業においては調査計画だけでなく設計施工から管理にも関わられ,1986年には「ダム建設における地質調査と基礎処理(51p)」や「日本の地下水(1043p)」を刊行されるなど著書も多い.特に,国土庁から発行した各県版の環境地質図と環境シンポジウム論集に都市地質論文を連続5編投稿されるなどの実践が特筆に値する.1991年農林水産省環境保全室長で退官され,基礎地盤コンサルタンツ(株)の技師長として,技術研鑽を通して後進を指導されている.また籾倉会員が携わられた100%を地下水で供給している熊本市上水道事業が先年日本水大賞を受賞された.日本地質学会では評議員を3期6年間勤め,2007年には瑞宝小綬賞を授かっている.籾倉会員は,社会に貢献する日本地質学会の名誉会員にふさわしいものとして推薦する.
(平成27年5月17日逝去)
(以上5名)
各賞-日本地質学会賞
日本地質学会賞(1953年創設)
⽇本および世界の地質学の発展に⼤きく寄与する重要な学術的貢献(国内外の学術誌での論⽂執筆や学会講演・セッション企画 などにおいて,本学会の会員の⼿本となる ような功績)を⻑期にわたって⾏い,かつ本学会に顕著な貢献のあった会員(運営規則第16条1)
※2008年以降は各受賞者または対象研究テーマをクリックすると、推薦理由等をご覧いただけます。
【 受賞者 】
【 対象研究テーマ 】
2023
道林克禎
(名古屋大学大学院環境学研究科)
地殻とマントルのレオロジーと構造地質学的研究
2020
山路 敦
(京都大学大学院理学研究科)
理論テクトニクス研究による地殻変動史の解明
2019
多田隆治
(東京大学大学院理学系研究科)
精密な層序ならびに堆積物分析に基づく環境変動史解明
2017
ウォリス サイモン
(名古屋大学大学院環境学研究科)
構造岩石学と造山帯のテクトニクス
2016
荒井章司
(金沢大学大学院自然科学研究科)
かんらん岩およびかんらん岩起源物質の解析による地域・地球発達史
2015
脇田浩二
(山口大学大学院理工学研究科)
付加体地質学を基にした日本〜アジアのシームレス地質研究
2014
川幡穂高
(東京大学大気海洋研究所)
気候変動に対応した過去・現代の炭素を中心とする物質循環に関する地化学的研究
2014
斎藤文紀
(産業技術総合研究所地質情報研究部門)
沿岸堆積システムと沖積層の地層形成に関する現行地質過程的研究
2013
井龍康文
(東北大学大学院理学研究科)
琉球弧の第四紀石灰岩と海洋炭酸塩堆積物の堆積学的・地球化学的研究
2013
乙藤洋一郎
(神戸大学大学院理学研究科)
日本列島と大陸の変形を古地磁気学から探る
2012
木村 学
(東京大学大学院理学系研究科)
テクトニクス,付加体地質学,沈み込みプレート境界地震発生帯物質科学
2011
岩森 光
(東京工業大学大学院理工学研究科)
マントルにおける物質循環とマグマの発生・分化の地質学的研究
2009
鳥海光弘
(東京大学大学院新領域創成科学研究科)
造山帯とマントルの力学的側面の研究
2009
石渡 明
(東北大学東北アジア研究センター)
オフィオライトと東北アジアの地質学的研究
2008
榎並正樹
(名古屋大学大学院環境学研究科)
高圧・超高圧変成岩の研究
2007
磯粼 行雄(東京大学大学院理学系研究科 教授)
「日本列島地体構造の基本骨格の解明とP-T境界大量絶滅の研究」
2006
平 朝彦 ((独)海洋研究開発機構)
「日本の地質学の飛躍的発展の基盤を創る:付加体地質学の実証的研究から海洋底地球科学の推進まで」
2005
嶋本利彦 (京都大学大学院理学研究科 教授)
「断層の力学的挙動と地震発生過程の実験的研究」
2004
加々美寛雄(新潟大学大学院自然科学研究科 教授)
「同位体地球化学による花崗岩質地殻形成史の研究」
2004
鈴木和博(名古屋大学年代測定総合研究センター 教授)
「新しい地質学研究手段の創生・開拓とその発展」
2003
伊藤谷生(千葉大学 教授)
「反射法地震探査による日本列島の地質・地殻構造の解明」
2003
巽 好幸(海洋科学技術センター固体地球統合フロンティア)
「沈み込み帯のマグマ学」
2002
丸山茂徳(東京工業大学 教授)
「卓越した表層地質学に基づく地球史解読」
2001
(受賞者なし)
2000
(受賞者なし)
1999
勘米良亀齢(九州大学 名誉教授)
「日本列島における付加型造山運動の研究」
1999
板谷徹丸(岡山理科大学 教授)
「K-Ar年代の微量・迅速測定法の開発と日本列島の地質年代学」
1998
斎藤常正(東北大学 教授)
「化石層序学によるプレートテクトニクスの証明」
1997
三梨 昂(元 島根大学 教授)
「火山灰鍵層を用いた精密岩層層序の確立」
1996
氏家 宏(琉球大学 教授)
「有孔虫の研究とその地質学的・古海洋学的応用」
1995
原 郁夫(広島大学 教授)
「石英の変形ファブリック、層状岩体褶曲作用及びわが国の変成帯のテクトニクスに関する 基礎研究」
1995
水収支研究グループ:藤崎克博(コンサルタント)・小前隆美(農水省)・高橋 一(地球科学研究センター・原田和彦(コンサルタント)ほか
「地下水盆の環境管理に関する研究」
1993
植村 武(新潟大学 教授)
「変形構造に関する基礎理論の究明とその地質学への展開」
1993
岡田博有(九州大学 教授)
「砕屑岩の堆積地質学的研究」
1993
小松正幸(愛媛大学 教授)
「構造体−とくに日高変成帯−の岩石学的・構造地質学的研究」
1993
松田時彦(九州大学 教授)
「活断層による地震予知の研究」
1988
石原舜三(地質調査所 )
「花崗岩系列の岩石学的研究」
1988
久城育夫(東京大学 教授)
「マグマの成因に関する理論的・実験的研究」
1988
水谷伸治郎(名古屋大学 教授)
「堆積岩の続成作用に関する研究」
1983
秋山雅彦(信州大学 教授)
「アミノ酸をはじめとする有機物を対象とした古生化学的研究」
1983
市川浩一郎(大阪市立大学 教授)
「中央構造線の研究」
1983
柴崎達雄(東海大学 教授)
「水終始の研究地下水学に関してほか」
1983
柴田 賢(工業技術院 地質調査所 主席研究官)
「放射年代の測定」
1983
坂野昇平(京都大学 教授)
「変成岩岩石学,とくに高圧変成岩の相律岩石学」
1978
諏訪兼位(名古屋大学 教授)
「斜長石に関する光学的および岩石学的研究」
1978
田口一雄(東北大学 助教授)
「石油の成因に関する研究」
1978
野尻湖発掘調査団 代表者:大森昌衛(麻布大学 教授)*特別賞
「野尻湖の発掘に関する一連の研究」
1973
荒牧重雄(東大地震研究所 教授)
「火砕流の機構及び珪長質マグマの成生に関する研究」
1973
藤田至則(新潟大学 教授)
「新生代後半における島弧地域,特に日本列島の構造論的研究」
1968
加納 博(秋田大学 教授)
「本邦古生界礫岩の岩石学的研究」
1968
藤原隆代(恵泉女学園短期大学 教授)
「化石有機物の古生化学的研究」
1963
関東ローム研究グループ *飯島 東(東大助教授)ほか
「関東ロームに関する総合的研究」
1963
砂川一郎(工業技術院 地質調査所 主席研究官)
「結晶の表面構造の研究」
1958
小島丈児(広島大学 教授)
「中国及び四国における変成帯に関する研究」
1958
小林国夫(信州大学 助教授)
「氷河地形を中心とした本邦第四紀の研究」
1958
都城秋穂(東京大学 助教授)
「造岩鉱物の性質にもとづく変成作用の研究」
1953
牛来正夫(東京教育大学 助教授)
「斜長石双晶の型に関する岩石学的研究」
1953
湊 正雄(北海道大学 教授)
「本邦古生層の研究」
各賞-日本地質学会都城秋穂賞
日本地質学会都城秋穂賞(1997年創設)
地質学に関する画期的な貢献があり,加えて⽇本列島周辺域の研究や⽇本の地質研究 者との共同研究などを通じた⽇本の地質学の発展に関する顕著な功績があった会員および非会員(運営規則第16条)(旧名称:日本地質学会国際賞.2022年名称変更)
※各受賞者または対象研究テーマをクリックすると、推薦理由等をご覧いただけます。
【受賞者】
【対象研究テーマ】
2025
Ali Mehmet Celâl Şengör氏(イスタンブール工科大学)
プレートテクトニクス的造山運動論の体系化とユーラシア大陸形成史の研究
2024
Gregory F. Moore氏 (アメリカ・ハワイ大学)
南海トラフ周辺における地質構造の三次元イメージング研究
2021
Brian F. Windley氏(英国レスター大学地質学科 名誉教授)
地球史を通じたテクトニクスや造山作用に関する一連の研究と日本の地質学発展における貢献
2020
(受賞なし N/A)
2019
Robert J. Stern氏(テキサス大学ダラス校)
島弧—海溝系およびプレートテクトニクスの研究
2018
Millard F. Coffin 氏(タスマニア大学)
巨大火成岩岩石区の形成とその地球環境への影響に関する研究
2017
Richard S. Fiske(スミソニアン協会・国立自然史博)
海底噴火における水中火砕流の運搬・堆積機構
2016
Roberto Compagnoni(トリノ大学)
変成岩岩石学
2015
(受賞なし N/A)
2014
江 博明 (JAHN, Bor-ming)(国立台湾大学)
地球惑星物質の地質年代学,同位体・微量元素地球化学,地殻進化の研究
2012-2013
(受賞なし N/A)
2011
J. Casey Moore(米国カリフォルニア大学)
付加体の陸上および海洋地質学的研究
2010
Juhn G. Liou(米国スタンフォード大学)
低温高圧・超高圧変成作用の研究と日本の地質学界への貢献学
2009
太田昌秀(元 ノルウエー極地研究所)
極域の地質学
2008
(受賞なし N/A)
2007
David H. Green(オーストラリア国立大学名誉教授)
マグマ生成論およびリソスフェアの進化に関する実験岩石学・地球化学的研究
2007
Allan White(オーストラリア,ラ・トローブ大学名誉教授)
レスタイトモデルによるIタイプ・Sタイプ花崗岩の分類とその成因の研究
1999-2006
(受賞なし N/A)
1998
W.G.Ernst(米国 スタンフォード大学)
三波川変成帯の研究と日本列島のテクトニクス
1997
(受賞なし N/A)
名誉会員(一覧)
日本地質学会 名誉会員
※氏名・西暦をクリックすると推薦理由等をご覧いただけます(2008年度以降)。
2024
加藤碵一
狩野謙一
鳥海光弘
2023
嶋本利彦
宮下純夫
2022
板谷徹丸
平 朝彦
八尾 昭
2021
田崎和江
伊藤谷生
田結庄良昭
2020
西村祐二郎
小松正幸
2019
小玉喜三郎
2018
坂巻幸雄*
寺岡易司
徳岡隆夫
2017
鈴木博之
波田重煕
大場忠道
2016
熊井久雄*
2015
斎藤靖二
鈴木堯士*
2012
大八木規夫*
蟹澤聰史
2011
小畠郁生*
倉沢 一*
松島信幸
猪郷久義*
籾倉克幹*
2010
町田 洋
石原舜三*
藤田 崇*
2009
須鎗和巳*
飯山敏道*
相原安津夫*
原 郁夫
石崎国熙
2008
増田孝一郎*
石田志朗*
杉崎隆一*
沖村雄二
加藤 誠*
柴田 賢*
2007
小西健二*
小坂丈予*
2006
秋山雅彦*
岡田博有*
斎藤常正*
志岐常正*
島津光夫*
水谷伸治郎
2005
荒牧重雄
井上英二
鎮西清高*
松田時彦*
2004
木村敏雄*
坂野昇平*
久城育夫
2003
秀 敬*
藤井昭二*
羽田 忍*
氏家 宏*
2002
棚井敏雅*
唐木田芳文*
中世古幸次郎*
水野篤行*
2001
徳永重元*
猪木幸男*
首藤次男*
岩崎正夫*
杉村 新*
小高民夫*
市原 実*
今井 功*
松井 健*
石井健一*
勝井義雄*
高柳洋吉*
2000
糸魚川淳二*
植村 武
垣見俊弘*
佐藤博之*
堀口萬吉*
松本征夫*
村田正文
山田直利
佐藤 正*
吉田 尚*
1999
北川芳男*
倉林三郎*
諏訪兼位*
早川正巳*
深田淳夫*
藤田和夫*
1998
新井房夫*
宇留野勝敏*
小野寺 透*
柴田松太郎*
下山俊夫*
武田裕幸*
中川久夫*
三梨 昂*
魚住 悟
亀井節夫*
木崎甲子郎*
黒田吉益*
千地万造*
奈須紀幸*
端山好和*
星野通平*
橋本光男*
羽鳥謙三*
藤田至則*
古川和代*
山岸猪久馬*
1993
中沢圭二*
野沢 保*
小林英夫*
池辺 穣*
市川浩一郎*
大久保雅弘*
大森昌衛*
虛野義夫*
加納 博*
勘米良亀齢*
斎藤林次*
関根良弘*
茅原一也*
都城秋穂*
舟橋三男*
山下 昇*
北村 信*
1988
斎藤昌之*
加藤磐雄*
岩井淳一*
牛来正夫*
小島丈児*
小林 勇*
熊谷直一*
黒田秀隆*
豊田英義*
森本良平*
八木健三*
酒井榮吾*
立見辰雄*
小貫義男*
島田 衛*
藤岡一男*
鳥山隆三*
1983
杉山隆二*
松本達郎*
池辺展生*
井尻正二*
岩生周一*
須藤俊男*
高井冬二*
橋本 亙*
野田光雄*
山内 肇*
石川俊夫*
尾崎 博*
根本忠寛*
浅野 清*
坂倉勝彦*
竹原平一*
西田彰一*
1980
小林貞一*
津屋弘逵*
高田 昭*
赤木 健*
柳生六郎*
1978
三土知芳*
渡辺武男*
石川 渡*
兼子 勝*
柴田秀賢*
1973
今村外治*
松下 進*
原田準平*
上床国夫*
石井清彦*
小倉 勉*
坂本峻雄*
田代修一*
辻村太郎*
半沢正四郎*
藤本治義*
松本唯一*
(注)*印:逝去者(2025年3月19日現在)
2015年度名誉会員
2015年度名誉会員
斎藤靖二 会員(1939年生まれ)
斎藤靖二会員は,1964年に東北大学大学院理学研究科地学専攻修士課程を修了し,1965年に国立科学博物館に勤務した.1968年には「Geology of the younger Paleozoic system of the southern Kitakami mountainland,Iwate Prefecture(南部北上山地上部古生界の地質)」にて東北大学から理学博士を授与された.チャートの岩石学や付加体地質学を積極的に学ばれ,豪州タスマニア島やパキスタン,北米西海岸などの先カンブリア時代から中・古生界のチャートの岩石学研究を進めるとともに,日本列島における付加体地質学や珪質堆積岩の岩石学,関東山地秩父帯の放散虫生層序学的研究などを行った.それらの成果は,プレートテクトニクス理論に基づく日本列島の地質の理解を大いに進めることになり,次世代の研究者に大きな影響を与えた.
日本地質学会においては,評議員や2004年から2006年に会長を務めたほか,国内各地の大学の客員教授や外部評価委員,文部省学術審議会,文部省南極地域観測将来問題研究会,大学評価・学位授与機構,文科省南極地域観測統合本部,海洋研究開発機構IFREE評価委員会,日本学術会議,日本地球惑星科学連合評議会などの各種委員を務め,学界における地質学および地球科学の発展に貢献された.さらに,2006年からは神奈川県立生命の星・地球博物館館長となり,市民への普及活動をはじめ,教育現場や企業など様々な場所における普及講演や,『日本列島の生い立ちを読む』(岩波書店),『変動する地球新版』(岩波書店),『グラフィック日本列島の20億年』(岩波書店)など多数の図書を執筆・監修などにより,地質学の普及と振興に大きな貢献をされた.
このような長年にわたる地質学の研究,教育,普及への顕著な貢献に鑑み,斎藤靖二会員を日本地質学会名誉会員に推薦する.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鈴木堯士 会員(1933年生まれ)
鈴木堯士会員は,1961年に広島大学大学院理学研究科博士課程を修了し,高知大学に勤務した.その後,御荷鉾帯の研究に力をそそぎ,その起源がオフィオライトであることを明らかにするなど,従来の学説を覆す画期的な成果を挙げられた.高知大学在任中の1966年8月から1年半にわたって,フンボルト財団奨励奨学生としてドイツ・ダルムシュタット工科大学に留学され,X 線テクスチュア・ゴニオメータによる三波川変成岩中の鉱物(石英・かんらん石・角閃石など)の定向性の測定と解析を,パソコンを用いて自動化するなど,研究方法の開発にも努められた.
ドイツから帰国後は,ライフワークの御荷鉾緑色岩類の研究と並行して,黒瀬川構造帯や四万十帯の研究に取り組まれた.とりわけ,四国四万十帯での研究成果を1979年に「地質学雑誌」に公表し,現在でこそポピュラーになった“メランジュ”という概念の日本国内への導入に貢献された.また,文部省科学研究助成金によるニュージーランド南島の学術調査隊の代表を務め,同国のオタゴ大学との共同研究にも意欲的に取り組まれた.中国の南京大学地球科学教室と高知大学地質学教室の姉妹教室締結にも尽力された.
地質学会においては, 1970年から1982年まで6期(12年)日本地質学会評議員を勤められた. 2006年の第113年年会では,日本地質学会50年会員として顕彰もされている.また,高知県文化財保護審議会の副会長として主に地質部門を担当された.その間,2件の国及び2件の高知県の天然記念物(地質関係)指定に貢献された.その内容の多くは詳細に「日本地質学会News」に掲載されるなど,会員への周知普及も積極的におこなってきた.さらに,「日本の地質 四国地方」「四国はどのようにしてできたか」 (第18回寺田寅彦記念賞受賞) ,「寺田寅彦の地球観」(第23回寺田寅彦記念賞受賞), 「最新・高知の地質 大地が動く物語」(第23回高知出版学術賞受賞)など多数の単行本を上梓し,地質学の普及と振興に貢献された.
このような長年にわたる地質学に関する研究,教育,普及への顕著な貢献に鑑み,鈴木堯士会員を日本地質学会名誉会員に推薦する.
(以上2名)
各賞-Island Arc Award
Island Arc Award (〜2021年:日本地質学会Island Arc賞)
Island Arc https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/iar.12296
受賞論文 (Awarded Paper)
2024
Yusuke Sawaki, Hisashi Asanuma, Mariko Abe, Takafumi Hirata, 2020, U–Pb ages of granitoids around the Kofu basin: Implications for the Neogene geotectonic evolution of the South Fossa Magna region, central Japan. Island Arc. 29. e12361.
2023
Yoshihiko Tamura, Osamu Ishizuka, Tomoki Sato, Alexander R. L. Nichols, 2019 , Nishino shima volcano in the Ogasawara Arc: New continent from the ocean? Island Arc 28, e12285
2022
Isozaki, Yukio, 2019, A visage of early Paleozoic Japan: Geotectonic and paleobiogeographical significance of Greater South China. Island Arc, 28: e12296.
2021
Schindlbeck, J. C., Kutterolf, S., Straub, S. M., Andrews, G. D., Wang, K. L., & Mleneck-Vautravers, M. J., 2018, One Million Years tephra record at IODP S ites U 1436 and U 1437: Insights into explosive volcanism from the Japan and Izu arcs. Island Arc, 27: e12244.
2020
Wakabayashi, J., 2017, Serpentinites and serpentinites: Variety of origins and emplacement mechanisms of serpentinite bodies in the California Cordillera. Island Arc, 26: e12205.
2019
Catherine Chagué-Goff, Jordan Chi Hang Chan, James Goff, and Patricia Gadd, 2016, Late Holocene record of environmental changes, cyclones and tsunamis in a coastal lake, Mangaia, Cook Islands. Island Arc, 25, 333−349.
2018
Ayumu Miyakawa, Saneatsu Saito, Yasuhiro Yamada, Hitoshi Tomaru, Masataka Kinoshita and Takeshi Tsuji, 2014, Gas hydrate saturation at Site C0002, IODP Expeditions 314 and 315, in the Kumano Basin, Nankai trough. Island Arc, 23, 142–156.
2017
Yui Kouketsu, Tomoyuki Mizukami, Hiroshi Mori, Shunsuke Endo, Mutsuki Aoya, Hidetoshi Hara, Daisuke Nakamura, Simon Wallis, 2014, A new approach to develop the Raman carbonaceous material geothermometer for low-grade metamorphism using peak width, Island Arc, 23, 33-50.
2016
Shinji Yamamoto, Tsuyoshi Komiya, Hiroshi Yamamoto, Yoshiyuki Kaneko, Masaru Terabayashi, Ikuo Katayama, Tsuyoshi Iizuka, Shigenori Maruyama, Jingsui Yang, Yoshiaki Kon and Takafumi Hirata,2013,Recycled crustal zircons from podiform chromitites in the Luobusa ophiolite, southern Tibet.Island Arc, 22, 89-103.
2015
Arai, S., Okamura, H., Kadoshima,K., Tanaka, C., Suzuki, K. and Ishimaru, S., 2011, Chemical characteristics of chromian spinel in plutonic rocks : Implications for deep magma processes and discrimination of tectonic setting. Island Arc, 20, 125-137.
2014
Dapeng Zhao, M. Santosh and Akira Yamada, 2010. Dissecting large earthquakes in Japan: Role of arc magma and fluids. Island Arc, 19, 4–16
2013
Keiko Hattori, Simon Wallis, Masaki Enami, Tomoyuki Mizukami, 2010, Subduction of mantle wedge peridotites: Evidence from the Higashi-akaishi ultramafic body in the Sanbagawa metamorphic belt. Island Arc, 19, 192-207.
2012
Barber, A. J. and Crow, M. J., 2009.Structure of Sumatra and its implications for the tectonic assembly of Southeast Asia and the destruction of Paleotethys.Island Arc, 18, 3-20.
2011
Saffer, D. M., Underwood, M. B. and McKiernan, A. W., 2008, Evaluation of factors controlling smectite transformation and fluid production in subduction zones: Application to the Nankai Trough. Island Arc, 17, 208-230.
2010
Fu-Yuan Wu, Jin-Hui Yang, Ching-Hua Lo, Simon A. Wilde, De-You Sun and Bor-Ming Jahn, 2007, The Heilongjiang Group: A Jurassic accretionary complex in the Jiamusi Massif at the western Pacific margin of northeastern China. Island Arc, 16, 156-172.
2009
Bortolotti, V. and Principi, G.,2005,Tethyan ophiolites and Pangea break-up. Island Arc, 14, 442-470.
2008
Chang Whan Oh, Sung Won Kim, In-Chang Ryu, Toshinori Okada, Hironobu Hyodo and Tetsumaru Itaya, 2004, Tectono-metamorphic evolution of the Okcheon Metamorphic Belt, South Korea: Tectonic implications in East Asia. Island Arc, 13, 387-402.
2007
Graciano P. Yumul Jr., Carla B. Dimalanta, Rodolfo A. Tamayo Jr. and Rene C. Maury,2003,Collision, subduction and accretion events in the Philippines: A synthesis. Island Arc, 12, 77-91.
各賞-日本地質学会小澤儀明賞
日本地質学小澤儀明賞(2005年創設)
⽇本地質学会⼩澤儀明賞・柵⼭雅則賞:地質学に関し て優れた業績を上げた,博⼠号取得から5年以内の会員(運営規則第16条2)
※各受賞者または対象研究テーマをクリックすると、推薦理由等をご覧いただけます。
【 受賞者 】
【 対象研究テーマ 】
13
2025
松本廣直(筑波大学生命環境系)
物質的・地球化学的情報を組み合わせた超巨大海台形成史の復元と地球環境変動との関連解明
12
2024
羽田裕貴 (産業技術総合研究所)
鮮新-更新統の超高時間分解能解析による北西太平洋古海洋・古地磁気変動の研究
11
2023
沢田 輝(海洋研究開発機構)
太古代・原生代における地殻消長メカニズム変遷の地質記録断片からの解読
10
2022
石輪健樹(国立極地研究所)
海水準変動復元と固体地球モデリングに基づく南極氷床変動メカニズム解明の研究
9
2019
齋藤誠史
(スイス,ローザンヌ大学)
古生代末の絶滅事件と特異な還元海洋環境の出現に関する研究
8
2018
澤木佑介(東京大学大学院総合文化研究科)
多元素同位体比分析を駆使した原生代後期の古環境解読研究
7
2015
辻 健
(九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所)
地震探査データ解析の高精度化によるプレート境界断層の形態と応力分布に関する研究
6
2014
菅沼悠介
(国立極地研究所地圏研究グループ)
海底堆積物における古地磁気記録獲得機構と地磁気逆転年代の高精度化に関する研究
6
2014
田村 亨
(産業技術総合研究所地質情報研究部門)
統合的な手法による沿岸域の地層と地形形成に関する研究
5
2013
尾上哲治
(熊本大学大学院自然科学研究科)
付加体の海洋性岩石を用いた地球環境変動に関する研究
4
2012
山本伸次
(東京大学大学院総合文化研究科)
造山運動論
3
2011
黒田潤一郎
(海洋研究開発機構)
地球内部活動と海洋無酸素事変のリンクの解明
2
2010
後藤和久
(千葉工業大学惑星探査センター)
地質学的手法による津波・高波災害履歴と規模の推定に関する研究
1
2009
小宮 剛
(東京工業大学大学院理工学研究科地球惑星科学専攻)
先カンブリア時代のテクトニクスと地球史の解読
1
2009
須藤 斎
(名古屋大学環境学研究科地球環境科学専攻)
珪藻化石生層序を用いた地質学的および古海洋学的研究
※2006年—2008年:受賞者なし
各賞-日本地質学会柵山雅則賞
日本地質学会柵山雅則賞(2005年創設)
⽇本地質学会⼩澤儀明賞・柵⼭雅則賞:地質学に関し て優れた業績を上げた,博⼠号取得から5年以内の会員(運営規則第16条2)
※各受賞者または対象研究テーマをクリックすると、推薦理由等をご覧いただけます。
【受賞者】
【対象研究テーマ】
14
2024
奥田花也(海洋研究開発機構)
沈み込みプレート境界断層の統合的すべり挙動の研究
13
2023
大柳良介(国士舘大学理工学部)
プレート境界領域における岩石-水相互作用と反応輸送過程の実態解明
12
2022
宇野正起(東北大学大学院環境科学研究科)
プレート収束帯における動的な流体活動
11
2022
岡崎啓史(海洋研究開発機構)
高温高圧変形実験に基づく岩石レオロジー研究
10
2021
纐纈佑衣(名古屋大学大学院環境学研究科)
分光学と地質学のリンク
10
2021
田阪美樹(静岡大学理学部地球科学科)
マントルかんらん岩の物質移動と素過程
9
2018
野崎達生(海洋研究開発機構海底資源研究開発センター)
火山性塊状硫化物(VMS)鉱床の成因研究
9
2018
遠藤俊祐(島根大学大学院総合理工学研究科)
野外調査に根差した,沈み込み帯変成作用とテクトニクスの研究
8
2017
平内健一(静岡大学理学部地球科学科)
沈み込み帯と蛇紋岩のレオロジー
7
2016
野田博之(海洋研究開発機構 現 京都大学防災研究所)
断層と地震発生の力学
6
2013
岡本 敦(東北大学大学院環境科学研究科)
沈み込み帯における流体移動と水—岩石相互作用に関する岩石学的実験的研究
5
2011
河野義生(High Pressure Collaborative Access Team [HPCAT])
岩石の弾性波速度測定による地球内部の構造解明研究
4
2009
水上知行(金沢大学理工学域自然システム学類地球学コース)
マントル構造岩石学
3
2008
片山郁夫(広島大学地球惑星システム学専攻)
沈み込み帯のダイナミクスと水の役割
2
2007
青矢睦月(産業技術総合研究所地質情報研究部門)
三波川変成帯のテクトニクスと熱履歴の研究
1
2006
辻森 樹(金沢大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー非常勤講師)
低温高圧型変成帯及び蛇紋岩メランジュの地質学的・岩石学的研究
各賞-日本地質学会論文賞
日本地質学会論文賞(1987年創設)
「地質学雑誌」あるいは「Island Arc」に優れた論⽂を発表した会員(運営規則第16条2)
※各受賞論文をクリックすると、推薦理由等をご覧いただけます。
【 受賞論文 】
2025
別所孝範・鈴木博之・山本俊哉・檀原 徹・岩野英樹・平田岳史,2024,紀伊半島南部海岸地域の田子含角礫泥岩層「サラシ首層」の時代と成因について.地質学雑誌, 130, 35-54.
2025
亀高正男・菅森義晃・石田直人・松井和夫・岸本弘樹・梅田孝行・東 篤義・山根 博・杉森辰次・魚住誠司・永田高弘・松場康二・桑島靖枝・岩森暁如・金谷賢生,2019,舞鶴−小浜地域の地質:超丹波帯・丹波帯の地質構造発達史と上林川断層の横ずれインバージョン.地質学雑誌, 125,793-820.
2024
Nakajima, T., Sakai, H., Iwano, H., Danhara, T., & Hirata, T., 2020, Northward cooling of the Kuncha nappe and downward heating of the Lesser Himalayan autochthon distributed to the south of Mt. Annapurna, western central Nepal. Island Arc. 29. e12349.
2023
Yoshida, K., Tamura, Y., Sato, T., Hanyuy, T., Usui, Y., Chang, Q., Ono, S., 2022. Variety of the drift pumice clasts from the 2021 Fukutoku-Oka-no-Ba eruption, Japan. Island Arc, 31, e12441.
2023
Noda, A., Sato, D., 2018. Submarine slope‒fan sedimentation in an ancient forearc related to contemporaneous magmatism: The Upper Cretaceous Izumi Group, southwestern Japan. Island Arc, 27, e12240.
2023
内野隆之・羽地俊樹,2021,北上山地中西部の中古生代付加体を貫く白亜紀岩脈群の岩相・年代と貫入応力解析から得られた引張場.地質学雑誌,127,651‒666.
2023
入月俊明・柳沢幸夫・木村萌人・加藤啓介・星 博幸・林 広樹・藤原祐希・赤井一行,2021,近畿地方の瀬戸内区に分布する下‒中部中新統の生層序と対比. 地質学雑誌, 127, 415‒429.
2022
Takashima, R., Hoshi, H., Wada, Y., Shinjoe, H., 2021. Identification of the source caldera for the Middle Miocene ash flow tuffs in the Kii Peninsula based on apatite trace element composition. Island Arc, 30, e13039. doi: 10.1111/iar.12404
2021
納谷友規・水野清秀,2020,埼玉県加治丘陵に分布する下部更新統仏子層の層序と年代の再検討.地質学雑誌,126,183-204.
2021
中嶋 健,2018,日本海拡大以来の日本列島の堆積盆テクトニクス.地質学雑誌,124,693–722.
2021
中澤 努・長 郁夫・坂田健太郎・中里裕臣・本郷美佐緒・納谷友規・野々垣 進・中山俊雄, 2019, 東京都世田谷区,武蔵野台地の地下に分布する世田谷層及び東京層の層序,分布形態と地盤震動特性. 地質学雑誌, 125,367-385
2020
星 博幸,2018,中新世における西南日本の時計回り回転.地質学雑誌,124,675‒ 691.
2019
佐野弘好,2018,岐阜県西部,舟伏山岩体東部の美濃帯ペルム系〜三畳系チャート優勢層の層序と年代. 地質学雑誌,124,449-467.
2019
Hitoshi Hasegawa, et al, 2018, Depositional ages and characteristics of Middle‒Upper Jurassic and Lower Cretaceous lacustrine deposits in southeastern Mongolia. Island Arc 27-3, DOI: 10.1111/iar.12243.
2018
Osamu Takano and Takashi Tsuji, 2017, Fluvial to bay sequence stratigraphy and seismic facies of the Cretaceous to Paleogene successions in the MITI Sanriku-oki well and the vicinities, the Sanriku-oki forearc basin, northeast Japan. Island Arc, 26, e12184,doi:10.1111/iar.12184.
2017
Atsushi Nozaki, Ryuichi Majima, Koji Kameo, Saburo Sakai, Atsuro Kouda, Shungo Kawagata, Hideki Wada and Hiroshi Kitazato, 2014, Geology and age model of the Lower Pleistocene Nojima, Ofuna, and Koshiba Formations of the middle Kazusa Group, a forearc basin-fill sequence on the Miura Peninsula, the Pacific side of central Japan, Island Arc, 23, 157-179.
2015
岩野英樹・折橋裕二・檀原徹・平田岳史・小笠原正継,2012,同一ジルコン結晶を用いたフィッション・トラックとUPbダブル年代測定法の評価―島根県川本花崗閃緑岩中の均質ジルコンを用いて―.地質学雑誌,118,365-375.
2015
Kouketsu, Y., Mizukami, T., Mori, H., Endo, S., Aoya, M., Hara, H., Nakamura, D and Wallis, S., 2014, A new approach to develop the Raman carbonaceous material geothermometer for low-grade metamorphism using peak width. Island Arc, 23, 33-50.
2014
田辺 晋・石原与四郎, 2013, 東京低地と中川低地における沖積層最上部陸成 層の発達様式:“弥生の小海退”への応答. 地質雑, 119, 350-367.
2012
Yoshimoto, M., Fujii, T., Kaneko, T., Yasuda, A., Nakada, S. and Matsumoto, A., 2010.Evolution of Mount Fuji, Japan: Inference from drilling into the subaerial oldestvolcano, pre-Komitake. Island Arc, 19, 470-488.
2012
Uchino, T. and Kawamura, M., 2010. Tectonics of an Early Carboniferous forearc inferred from a high-P/T schist-bearing conglomerate in the Nedamo Terrane, Northeast Japan. Island Arc, 19, 177-191.
2011
Yamamoto, Y., Nidaira, M., Ohta, Y. and Ogawa, Y., 2009. Formation of chaotic rock units during primary accretion processes: Examples from the Miura–Boso accretionary complex, central Japan. Island Arc, 18, 496–512.
2011
Fujii, M., Hayasaka, Y. and Terada, K., 2008. SHRIMP zircon and EPMA monazite dating of granitic rocks from the Maizuru terrane, southwest Japan: Correlation with East Asian Paleozoic terranes and geological implications. Island Arc, 17, 322-341.
2011
Endo, S., 2010. Pressure-temperature history of titanite-bearing eclogite from the Western Iratsu body, Sanbagawa Metamorphic Belt, Japan. Island Arc, 19, 313–335.
2010
Sugawara D., Minoura K., Nemoto N., Tsukawaki S. Goto K. and Imamura F., 2009, Foraminiferal evidence of submarine sediment transport and deposition by backwash during the 2004 Indian Ocean tsunami. Island Arc, 18, 513-525.
2010
宮田雄一郎・三宅邦彦・田中和広,2009,中新統田辺層群にみられる泥ダイアピル類の貫入構造.地質学雑誌,第115巻,第9号,p470-482.
2009
高橋雅紀,2006,日本海拡大時の東北日本と西南日本の境界.地質学雑誌,第112巻,第1号,p.14-32.
2009
守屋俊治・鎮西清高・中嶋 健・檀原 徹, 2008,山形県新庄盆地西縁部の鮮新世古地理の変遷−出羽丘陵の隆起時期と隆起過程−.地質学雑誌,第114巻,第8号,p.389-404.
2008
竹内 誠・河合政岐・野田 篤・杉本憲彦・横田秀晴・小嶋 智・大野研也・丹羽正和・大場穂高,2004,飛騨外縁帯白馬岳地域のペルム系白馬岳層の層序および蛇紋岩との関係.地質学雑誌,第110巻,第11号, p.715-730.
2008
清川昌一,2006,ベリース国に分布する白亜紀・第三紀境界周辺層,アルビオン層:チチュルブクレータに近接したイジェクタとその堆積層.地質学雑誌,第112巻,第12号, p.730-748.
2008
Aoki, K., Iizuka, T., Hirata, T., Maruyama, S. and Terabayashi, M., 2007, Tectonic boundary between the Sanbagawa belt and the Shimanto belt in central Shikoku, Japan. J. Geol. Soc.Japan,vol.113, no.5, p.171-183.
2007
Hayato Ueta and Sumio MIyashita, 2005, Tectonic accretion of a subducted intraoceanic remnant arc in Cretaceous Hokkaido,Japan, and implications for evolution of the Pacific northwest. Island Arc,Volume 14,Issue 4,582-598.
2007
Yasuhio Ohara, 2006, Mantle process beneath Philippine Sea back-arc spreading ridges:A synthesis of peridotite petrology and tectonics.Island Arc, 15,Issue 1,119-129.
2006
辻 隆司・宮田雄一郎・岡田 誠・三田 勲・中川 洋・佐藤由理・中水 勝, 2005, 房総半島に分布する下部更新統上総層群大田代層と梅ヶ瀬層の高精度堆積年代―石油公団研究井TR-3コアの酸素同位体比・古地磁気・石灰質ナンノ化石に基づく年代層序―.地質学雑誌,111巻,1-20.
2006
石原与四郎・徳橋秀一, 2005, 房総半島安房層群最上部安野層の堆積様式―前弧堆積盆を埋積するタービダイト・システムの一例―.地質学雑誌,111巻,269-285.
2005
高橋雅紀・柳沢幸夫, 2004, 埼玉県比企丘陵に分布する中新統の層序 −複合年代層序に基づく岩相層序の総括−.地質学雑誌,110巻,290-308.
2005
大竹正巳, 2004, カルデラ湖における火山砕屑性重力流堆積物の堆積相と堆積様式—栗駒南部地熱地域,更新統管ノ平層の例—.地質学雑誌,110巻,331-347.
2004
高野 修・守屋成博・西村瑞恵・阿部正憲・柳本 裕・秋葉文雄,2001,新潟堆積盆北蒲原地域における上部中新統〜下部更新統のシーケンス層序と堆積システムの特徴.地質学雑誌,第107巻,585-604.
2004
Yukiobu Okamura,2003,Fault-related folds and an imbricate thrust system on the northwestern margin of the northern Fossa Magna region, central Japan. Island Arc, vol.12, 61-73.
2003
Ritsuo Nomura and Koji Seto、2002, Influence of man-made construction on environmental conditions in brackish Lake Nakaumi,southwest Japan:Foraminiferal evidence. J. Geol. Soc. Japan, 108,108-394.
2003
大村亜希子、2000,新潟県西頚城地域に分布する鮮新統の第3オーダー堆積シーケンスと堆積有機物組成. 地質学雑誌, 106巻8号, 534-547.
2002
Jun-ichi Kimura and Takeyosi Yoshida, 1999,Magma plumbing system beneath Ontake Volcano, central Japan. Island Arc, Vol.8, 1-29.
2002
石原与四郎・宮田雄一郎、1999,中期更新統蒜山原層(岡山県)の湖成縞状珪藻土層に見られる周期変動.地質学雑誌, 105巻7号, 461-472.
2001
三野浩一朗・山路 敦, 1999, 複数の応力状態を経験した地域における小断層解析:房総半島の更新統を例として.地質学雑誌, 105巻8号, 574-584.
2001
香村一夫・楡井 久, 1999, 地層の比抵抗から見た廃棄物層の特性. 地質学雑誌, 105巻10号,667-698.
2001
田上高広・長谷部徳子, 1999, Cordielleran−type orogeny and episodic growth of continents: Insights from the circum -Pacifc continental margins. Island arc 8,(2), 206-217.
2000
柳沢幸夫・秋葉文雄, 1998, Refined Neogene diatom biostratigraphy for the north west Pacific around Japan, with an introduction of code numbers for selected diatom biohorizons」1998, The Journal of the Geological Society of Japan. J. Geol. Soc. Japan, 104-6, 395-414.
1999
香村一夫・楡井 久, 1996, 東京湾埋め立て地域で観測される微動と表層地質の関係. 地質学雑誌,102巻8号, 715-729.
1999
磯崎行雄, 1996, Anatomy and genesisi of a subduction-related orogen:A new view of geotectonic subdivision and evolution of the Japanse Islands. Island Arc, Vol.5-3, 289-320.
1998
丸山茂徳, 1997, Pacific-type orogeny revised : Miyashiro-type orogeny proposed」1997, Island Arc, Vol.6-1, 91-120.
1997
横山俊治, 1995, 和泉山地の和泉層群の斜面変動:岩盤クリープ構造解析による崩壊「場所」の予測に向けて. 地質学雑誌, 101巻2号, 134-147.
1997
伊藤谷生ほか, 1996, 四国中央構造線地下構造の総合物理探査. 地質学雑誌, 102巻4号, 346-360.
1997
山野井 徹, 1996, 黒土の成因に関する地質学的検討. 地質学雑誌, 102巻6号, 526-544.
1996
酒井治孝, 1994, 北九州の下部漸新統,津屋崎層中の恋ノ浦火砕堆積物. 地質学雑誌, 100巻9号, 692-708.
1996
鎌田弘毅ほか, 1994, 大阪層群アズキ火山灰および上総層群Ku6C火山灰と中部九州の今市火砕流堆積物との対比−猪牟田カルデラから噴出したco-ignimbrite ash-. 地質学雑誌, 100巻11号, 848-866.
1995
丸山茂徳, 1994, Plum Tectonics. J. Geol. Soc. Japan, Vol.100-1, 24-49.
1995
沢田順弘ほか, 1994, 琵琶湖南部白亜紀環状花崗岩体と湖東コールドロン. 地質学雑誌, 100巻3号, 217-233.
1994
君波和雄・柏木庸孝・宮下純夫, 1992, 上部白亜系牟岐累層(四国南部)中のin-situ緑色岩類の産状とその意義. 地質学雑誌, 98巻9号, 867-883.
1994
橋本光男・田切美智雄・日下部和宏・増田一稔・矢野徳也, 1992, 関東山地児玉−長瀞町三波川変成域における層状体の構造的累積による地質構造. 地質学雑誌, 98巻10号, 953-965.
1993
佐野弘好・勘米良亀齢, 1991, Collapse of ancient oceanic reef complex. J. Geol. Soc. Japan, Vol.97-8, 631-644
1993
岡崎浩子・増田富士雄, 1992, 古東京湾地域の堆積システム. 地質学雑誌,98巻3号, 235-258.
1993
岡田尚武, 1992, Calcareous nannofossils and biostratigraphy of the Paleogene sequences of northern kyushu,Japan. J. Geol. Soc. Japan, Vol.98-6, 509-528.
1992
東野外志男, 1990, 四国中央部三波川変成帯の変成分帯. 地質学雑誌,96巻9号, 703-718.
1992
磯粼行雄・板谷徹丸, 1991, 四国中西部秩父累帯北帯の先ジュラ系クリッペ―黒瀬川内帯起源説の提唱―. 地質学雑誌, 97巻6号,431-450.
1992
塚原弘昭・池田隆司, 1991, 本州中央部の地殻応力方位分布―応力区とその成因―. 地質学雑誌, 97巻6号, 461-474.
1991
授賞者なし
1990
佐野弘好, 1988, Permian oceanic-rock of Mino Terrance, centoral Japan. Part 1. Chert facies. J. Geol. Soc. Japan, Vol.94-9, 697-709.
1990
酒井治孝, 1988, 岬オリストストローム帯の成因と高千穂変動の再検討. 地質学雑誌, 94巻12号, 945-961.
1989
高須 晃, 1986, Resorption-overgrowth of garnet from the Sambagawa politic schists in the contact aureole of the Sebadani metagabbro mass, Shikoku, Japan. J. Geol. Soc. Japan, Vol.92-11, 781-792.
1988
川村寿郎・川村信人・加藤 誠, 1985, 南部北上山地 世田米―雪沢地域の下部石炭系太平層・鬼丸層. 地質学雑誌, 91巻12号, 851-866.
1988
服部 勇, 1985, 福井県下の美濃帯中・古生層中のLength-slow chalcedonyとその地質学的意義. 地質学雑誌, 第91巻7号, 453-461.
各賞-日本地質学会小藤賞
日本地質学会小藤賞(1979年創設-2012年)
「日本地質学会小藤賞」は地質学雑誌の短報が廃止に伴い、2012年度が最終授与年です。
※各受賞論文をクリックすると、推薦理由等をご覧いただけます。
【 受賞論文 】
2012
佐藤峰南・尾上哲治, 2010. 中部日本,美濃帯の上部トリアス系チャートから発見したNiに富むスピネル粒子.地質学雑誌,116, 575-578.
2011
Tazawa, J., Anso, J., Umeda, M. and Kurihara, T., 2010. Late Carboniferous brachiopod Plicatiferina from Nishiamada, Fukui Prefecture, central Japan, and its tectonic implications. The Journal of the Geological Society of Japan, 116, 51-54.
2009
嶋田智恵子・佐藤時幸・工藤美幸・山崎 誠,2008,IODP, Exp. 303航海で得られた北大西洋の中部第四系から産出した絶滅珪藻種Neodenticula kamtschaticaの意義. 地質学雑誌,第114巻,第1号,p.47-50.
2008
斎藤 眞・川上俊介・小笠原正継,2007,始新世放散虫化石の発見に基づく屋久島の四万十帯付加体の帰属.地質学雑誌,第113巻,第6号, p.266-269.
2007
(受賞なし)
2006
内野隆之・栗原敏之・川村信人, 2005, 早池峰帯から発見された前期石炭紀放散虫化石―付加体砕屑岩からの日本最古の化石年代―.2005,地質学雑誌,第111巻,第4号,249-252.
2005
(受賞なし)
2004
鈴木寿志・桑原希世子, 佐渡島小佐渡地域から産したペルム紀放散虫.地質学雑誌,第109巻,第8号,489-492.
2003
(受賞なし)
2002
寺門靖高,2001,Re-Os dating of the Kuroko ore deposits from the Hokuroku district, Akita Prefecture, Northeast Japan. 地質学会誌, 第107巻, 5号,354-357.
2001
山北 聡・naoki Kadota,Takuya Kato,多田隆治, Shigenori Ogihara, 田近英一・ 濱田欣孝,1999,Confirmation of the Permian/Triassic conodonts from black carbonaceous claystone of the Ubara section in the Tamba Belt, Southwest Japan. 地質学雑誌, 105巻12号,895-898.
2000
(受賞なし)
1999
阪本志津枝・高須 晃,1997,青海−蓮華帯青海地域のひすい輝石岩からのコスモクロアの発見. 地質学雑誌, 103巻11号, 1093-1096.
1998
束田和弘、1997,岐阜県上宝村−重ヶ根地域から産出したオルドビス紀コドント化石について」1997、 地質学雑誌,103巻2号, 171-174.
1997
鈴木里子、1995,Metamorphic aragonaite from the Mikabu and the Northern Chichibu belts in central Shikoku, SW Japan :Identification by Micro-area X-ray Diffraction Analysis.地質学雑誌, 101巻12号, 1003-1006.
1996
加藤敬史ほか、1995, 南部北上山地大沢層(下部三畳系)よりヒボドゥス族板鰓類の発見.地質学雑誌, 101巻6号466-469.
1995
椛島太郎ほか、1993,長門構造帯,300Ma低温高圧型変成岩類と弱変成ペルム紀加体間の境界スラストの発見. 地質学雑誌, 99巻11号, 877-880.
1994
鈴木喜計ほか, 1992, 揮発性有機塩素化合物による汚染地下空気の吸引法. 地質学雑誌, 98巻8号, 783-786.
1993
JAPEX札幌鉱業所勇払研究グループほか, 1992, 北海道苫小牧東部における坑井から採取された白亜紀花崗岩. 地質学雑誌, 98巻6号, 547-550.
1992
Yasuto Osanai and Masaaki Owada, 1991, Finding of staurolite in politic granulites from the Hidaka metamorphic belt, Hokkaido Japan. 地質学雑誌, 96巻7号, 549-552.
1990
田沢純一, 1988, 北上山地産デボン紀腕足類Zdimirとその古生物地理的意義. 地質学雑誌,94巻12号, 1013-1016.
1989
Harutaka Sakai, 1987, Stome barnaclebeds and their deformation in the Muroto-misaki ojistostorome and melange Complex, Shikoku. J. Geol. Soc. Japan, Vol.93-8, 617-619.
1988
Yoshikuni Hiroi,Masashi Yokose,Tomoru Oba,Satoru Kishi,Tsuyoshi Nohara and Akira Yao, 1987, Discovery of Jurassic radiolarian from acmite-phodonite-bearing metachert of the Gosaisyo metamorphic rocks in the Abukuma terrane, Northeeastern Japan. J. Geol. Soc. Japan, Vol.93-6, 445-448.
1987
澤村昌俊・田中豊俊・千足恭平・鹿田昭男, 1986, 佐賀県鳥栖市西部で発見された珪線石を含む流紋岩. 地質学雑誌, 92巻1号, 65-68.
1986
(受賞なし)
1985
(受賞なし)
1984
(受賞なし)
1983
(受賞なし)
1982
須鎗和巳・桑野幸夫・石田啓祐, 1980, 四国西部三波川帯主部よりの後期三畳紀コノドントの発見. 地質学雑誌, 86巻12号, 827-828.
1981
(受賞なし)
1980
加藤 誠・安井敏夫, 1980, 高知県横倉山シルル系石灰岩から筆石の発見.地質学雑誌, 86巻12号, 827-828.
1979
(受賞なし)
各賞-日本地質学会小藤文次郎賞
日本地質学会小藤文次郎賞(2011年創設)
重要な発⾒または独創的 な発想を含む論⽂を発表した会員(運営規則第16条2)
※各受賞者または受賞論文をクリックすると、推薦理由等をご覧いただけます。
受賞者
対象論文
11
2025
岩森 光(東京大学地震研究所)
Iwamori, H., et al. (2021) Simultaneous analysis of seismic velocity and electrical conductivity in the crust and the uppermost mantle: a forward model and inversion test based on grid search. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 126, e2021JB022307
10
2024
岡本 敦(東北大学大学院環境科学研究科)
Okamoto, A., et al, 2021, Rupture of wet mantle wedge by self-promoting carbonation. Communications Earth & Environment, 2, 151.
9
2018
小宮 剛(東京大学大学院総合文化研究科)
Takayuki Tashiro, et al, 2017, Early trace of life from 3.95 Ga sedimentary rocks in Labrador, Canada. Nature, 549, 516–518.
8
2017
佐藤活志(京都大学大学院理学研究科)
Katsushi Sato, 2016, A computerized method to estimate friction coefficient from orientation distribution of meso-scale faults. Journal of Structural Geology, 89, 44–53.
7
2016
高柳栄子(東北大学大学院理学研究科)
Takayanagi, H., et al, 2015, Quantitative analysis of intraspecific variations in the carbon and oxygen isotope compositions of the modern cool-temperate brachiopod Terebratulina crossei. Geochimica et Cosmochimica Acta, 170, 301–320.
6
2016
菅沼悠介(国立極地研究所)ほか
Yusuke Suganuma, et al., 2015, Age of Matuyama-Brunhes boundary constrained by U-Pb zircon dating of a widespread tephra. Geology, 43, 491-494.
5
2015
堤 浩之(京都大学大学院理学研究科)
Tsutsumi, H., Sato, K.and Yamaji, A., 2012, Stability of the regional
stress field in central Japan during the late Quaternary inferred
from the stressn inversion of the active fault data. GeophyscalResearch Letter, 39, L23303, doi:10.1029/2012GL054094.
4
2015
氏家恒太郎(筑波大学生命環境系)
Ujiie ,K.,Tanaka, H., Saito, T.,Tsutsumi, A., Mori, J.J.,Kameda, J., Brodsky, E.E., Chester, F.M.,Eguchi, N., Toczko,S.and Expedition 343 and 343T Scientists, 2013, Low coseismic shear stress on the Tohoku-Oki megathrust determined from laboratory experiments. Science, 342, 1211-1214.
3
2014
野崎達生(海洋研究開発機構)
Nozaki, T., Kato, Y. and Suzuki, K., 2013, Late Jurassic ocean anoxic event: evidence from voluminous sulphide deposition and preservation in the Panthalassa. Scientific Reports, 3, 1889, doi: 10.1038/srep01889.
2
2013
森田澄人(産業技術総合研究所)ほか
森田澄人・中嶋 健・花村泰明,2011,海底スランプ堆積層とそれに関わる脱水構造:下北沖陸棚斜面の三次元地震探査データから.地質学雑誌, 117, 95-98.
1
2012
坂口有人(海洋研究開発機構)
Sakaguchi, A., Chester, F., Curewitz, D., Fabbri, O., Goldsby, D., Kimura, G., Li, C.-F., Masaki, Y., Screaton, E. J., Tsutsumi, A., Ujiie, K. and Yamaguchi, A., 2011. Seismic slip propagation to the updip end of plate boundary subduction interface faults: Vitrinite reflectance geothermometry on Integrated Ocean Drilling Program NanTroSEIZE cores.Geology published online 8 March 2011; doi: 10.1130/G31642.1
各賞-日本地質学会研究奨励賞
日本地質学会研究奨励賞(1916年研究奨励金として創設,1971年名称変更)
「地質学雑誌」あるいは 「Island Arc」に優れた論⽂を発表した満32才未満の会員(運営規則第16条2)
※2008年以降は,各受賞者または受賞論文をクリックすると、推薦理由をご覧いただけます(2007年以前については当該論文情報のみ)。
受賞者
対象論文
2025
米岡佳弥(産業技術総合研究所地質情報研究部門)
米岡佳弥, 坂田 健太郎, 本郷 美佐緒, 中里 裕臣, 中澤 努,2024,下総台地北西部の地下に分布する中部更新統下総層群清川層の層相・物性の側方変化. 地質学雑誌, 130, 223–238.
2024
福島 諒(東北大学大学院理学研究科)
Fukushima, R., Tsujimori, T., Aoki, S., and Aoki, K., 2021,Trace-element zoning patterns in porphyroblastic garnets in low-T eclogites: Parameter optimization of the diffusion-limited REE-uptake model. Island Arc, 30, e12394.
2024
木下英樹(京都大学大学院理学研究科,応用地質株式会社)
Kinoshita, H. and Yamaji, A., 2021, Arc-parallel extension in preparation of the rotation of southwest Japan: Tectonostratigraphy and structures of the Lower Miocene Ichishi Group. Island Arc, 30, e12418.
2024
武藤 俊(産業技術総合研究所地質情報研究部門)
Muto, S., Takahashi, S., & Yamakita, S., 2023, Elevated sedimentation of clastic matter in pelagic Panthalassa during the early Olenekian. Island Arc, 32, e12485.
2024
渡部将太(茨城大学大学院理工学研究科)
渡部将太・長谷川 健・小畑直也・豊田 新・今山武志,2023,福島県南部,二岐山火山の噴火史とマグマ供給系. 地質学雑誌, 129, 307–324.
2024
吉田 聡(東北大学 東北アジア研究センター)
Yoshida, S., Ishikawa, A., Aoki, S., and Komiya, T., 2021, Occurrence and chemical composition of the Eoarchean carbonate rocks of the Nulliak supracrustal rocks in the Saglek Block of northeastern Labrador, Canada. Island Arc, 30, e12381.
2023
山岡 健(産業技術総合研究所地質調査総合センター)
Yamaoka, K., Wallis, S. R., 2022. Recognition of broad thermal anomaly around the median tectonic line in central Kii peninsula, southwest Japan: Possible heat sources. Island Arc, 31, e12440.
2023
鈴木康太(エネルギー・金属鉱物資源機構)
Suzuki, K., Kawakami, T., Sueoka, S., Yamazaki, A., Kagami, S., Yokoyama, T., Tagami, T., 2022, Solidification pressures and ages recorded in mafic microgranular enclaves and their host granite: An example of the world's youngest Kurobegawa granite. Island Arc, 32, e12462.
2023
佐久間杏樹(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻)
Sakuma, A., Kano, A., Kakizaki, Y., Tada, R., and Zheng, H., 2021, Upper Eocene travertine-lacustrine carbonate in the Jianchuan basin, southeastern Tibetan Plateau: Reappraisal of its origin and implication for the monsoon climate. Island Arc, 30, e12416.
2023
原田浩伸(東北大学大学院理学研究科地学専攻)
Harada, H., Tsujimori, T., Kunugiza, K., Yamashita, K., Aoki, Sl., Aoki, K., Takayanagi, H., Iryu, Y., 2021. The δ13C‒δ18O variations in marble in the Hida Belt, Japan. Island Arc, 30, e12389.
2022
中西 諒(東京大学大気海洋研究所
中西 諒, 岡村 聡,2019,1640 年北海道駒ヶ岳噴火による津波堆積物の分布と 津波規模の推定 地質学雑誌,125,835-851
2022
加藤悠爾(筑波大学生命環境系
加藤悠爾・柳沢幸夫, 2021,秋田県出羽山地の笹森丘陵に分布する新第三系の地 質と珪藻化石層序.地質学雑誌,127,105-120
2021
菊地瑛彦(アジア航測株式会社)
菊地瑛彦・長谷川健,2020,栃木県北部,余笹川岩屑なだれ堆積物の層序・年代と運搬過程. 地質学雑誌,126, 293-310.
2021
板宮裕実(警察庁科学警察研究所)
板宮裕実・杉田律子・須貝俊彦, 2020, 石英粒子の形状および表面形態を用いた法科学的検査法の研究. 地質学雑誌,126,411–423.
2020
羽地俊樹(京都大学大学院理学研究科)
Haji, T., Hosoi, J., Yamaji, A., 2019, A middle Miocene post-rift stress regime revealed by dikes and mesoscale faults in the Kakunodate area, NE Japan. Island Arc, 28: e12304.
2020
菊川照英(伊藤忠石油開発株式会社)
菊川照英・相田吉昭・亀尾浩司・小竹信宏,2018,鹿児島県種子島北部,熊毛層群西之表層の地質.地質学雑誌,124,313‒329.
2019
加瀬善洋 会員(北海道立総合研究機構地質研究所)
加瀬善洋・ほか,2016,北海道南西部奥尻島で発見された津波堆積物.地質学雑誌,122, 587–602.
2019
葉田野 希(信州大学大学院総合工学系研究科)
葉田野 希・吉田孝紀,2018,瀬戸内区中新統瀬戸陶土層の古土壌構成が示す古風化および古気候条件.地質学雑誌,124,191–205.
2018
綿貫峻介(国際石油開発帝石株式会社)
綿貫峻介・金井拓人・坂 秀憲・高木秀雄,2017,青森県白神山地西部に発達する入良川マイロナイト帯の変形微細構造.地質学雑誌,123,533–549.
2018
高橋 聡(東京大学大学院理学系研究科)
高橋 聡・永広昌之・鈴木紀毅・山北 聡,2016,北部北上帯の亜帯区分と渡島帯・南部秩父帯との対比:安家西方地域のジュラ紀付加体の検討.地質学雑誌,122,1–22.
2017
三田村圭祐((株)建設技術研究所)
三田村圭祐・奥平敬元・三田村宗樹,2016,生駒断層帯周辺における露頭規模での脆性変形構造.地質学雑誌,122,61-74
2016
金井拓人(早稲田大学大学院創造理工学研究科)
金井拓人・山路 敦・高木秀雄,2014,混合ビンガム分布を適用したヒールドマイクロクラックによる古応力解析 中部地方の領家花崗岩類における例.地質学雑誌,120,23-35.
2016
酒向和希(愛知教育大学大学院教育学研究科)
酒向和希・星 博幸,2014,本州中部,中新統富草層群の古地磁気とテクトニックな意義.地質学雑誌,120,255-271.
2015
越智真人(東建ジオテック株式会社)
越智真人・間宮隆裕・楠橋 直,2014,四国の中新統久万層群層序の再検討:“下坂場峠層”と“富重層”.地質学雑誌,120,165-179.
2014
細井 淳(茨城大学大学院理工学研究科)
細井 淳・天野一男,2013,岩手県西和賀町周辺奥羽脊梁山脈における前期〜中期中新世の火山活動と堆積盆発達史.地質学雑誌,119, 630–646.
2014
上久保 寛(石油天然ガス・金属鉱物資源機構資源探査部)
Kamikubo, H. and Takeuchi, M., 2011, Detrital heavy minerals from Lower Jurassic clastic rocks in the Joetsu area, central Japan: Paleo-Mesozoic tectonics in the East Asian continental margin constrained by limited chloritoid occurrences in Japan. Island Arc, 20, 221-247.
2014
武藤 潤(東北大学大学院理学研究科地学専攻)
武藤 潤・大園真子, 2012, 東日本太平洋沖地震後の余効変動解析へ向けた東北日本弧レオロジー断面. 地質学雑誌, 118, 323-333.
2012
増渕佳子(富山市科学博物館)
増渕佳子・石崎泰男,2011. 噴出物の構成物組成と本質物質の全岩および鉱物組成から見た沼沢火山のBC3400カルデラ形成噴火(沼沢湖噴火)のマグマ供給系.地質学雑誌,117,357-376.
2012
針金由美子(産業技術総合研究所)
Harigane, Y., Michibayashi, K. and Ohara Y., 2010. Amphibolitization within the lower crust in the termination area of the Godzilla Megamullion, an oceanic core omplex in the Parece Vela Basin. Island Arc, 19, 718-730.
2012
森 宏(名古屋大学大学院環境学研究科)
Mori, H. and Wallis, S. R., 2010. Large-scale folding in the Asemi-gawa region of the Sanbagawa Belt, southwest Japan. Island Arc, 19, 357-370.
2011
常盤哲也(日本原子力研究開発機構)
Tokiwa, T., 2009. Timing of dextral oblique subduction along the eastern margin of the Asian continent in the Late Cretaceous: Evidence from the accretionary complex of the Shimanto Belt in the Kii Peninsula, Southwest Japan. Island Arc, 18, 306-319.
2011
辻 智大((株)四国総合研究所)
辻 智大・榊原正幸, 2009. 四国西部における北部秩父帯の大規模逆転構造. 地質学雑誌, 115, 1-16.
2011
隅田祥光(明治大学黒曜石研究センター)
隅田祥光・早坂康隆, 2009. 夜久野オフィオライト朝来岩体における古生代海洋内島弧地殻の形成と進化過程. 地質学雑誌, 115, 266-287.
2010
佐藤雄大(国交通省国土地理院測地部)
佐藤雄大・鹿野和彦・小笠原憲四郎・大口健志・小林紀彦,2009,東北日本男鹿半島,台島層の層序.地質学雑誌,第115巻,第1号,31-46.
2010
大橋聖和(広島大学大学院理学研究科地球惑星システム学専攻)
大橋聖和・小林健太,2008,中部地方北部,牛首断層中央部における断層幾何学と過去の運動像.地質学雑誌,第114巻,第1号,16-30.
2010
川上 裕(石油天然ガス・金属鉱物資源機構)
川上 裕・星 博幸,2007,火山−深成複合岩体にみられる環状岩脈とシート状貫入岩:紀伊半島,尾鷲−熊野地域の熊野酸性火成岩類の地質.地質学雑誌,第113巻,第7号,296-309.
2009
石井英一(日本原子力研究開発機構)
石井英一・中川光弘・齋藤 宏・山本明彦, 2008, 北海道中央部,更新世の十勝三股カルデラの提唱と関連火砕流堆積物:大規模火砕流堆積物と給源カルデラの対比例として. 地質学雑誌,第114巻,第7号,no.2,p.348-365.
2009
坂口真澄(高知大学)
Masumi Sakaguchi and Hideo Ishizuka,2008,Subdivision of the Sanbagawa pumpellyite-actinolite facies region in central Shikoku, southwest Japan. Island Arc, vol. 17, no. 3, 305-321.
2008
丹羽正和(日本原子力研究開発機構地層処分研究開発部門)
丹羽正和,2006,海洋性岩石のスラブで特徴付けられる付加体の岩相と変形構造〜岐阜県高山地域の美濃帯小八賀川(こやちががわ)コンプレックスを例として〜.地質学雑誌,第112巻,第6号, p.371-389.
2008
長谷川 健(北海道大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻)
長谷川 健・中川光弘,2007,北海道東部,阿寒カルデラ周辺の前-中期更新世火砕堆積物の層序.地質学雑誌,第113巻,第2号, p.53-72.
2008
福成徹三(石油天然ガス・金属鉱物資源機構)
Fukunari, T. and Wallis, S, 2007, Structural evidence for large-scale top-to-the-north normal shear displacement along the MTL in Southwest Japan. Island Arc, vol.16, no.2, p.243-261.
2007
金丸龍夫(日本大学文理学部)
金丸龍夫・高橋正樹,2005,帯磁率異方性からみた丹沢トーナル岩体の貫入・定置機構.地質雑,111,458-475.
2007
小林祐哉(総合地質コンサルタント㈱)
小林祐哉・大塚 勉,2006,美濃帯左門岳ユニットの堆積相と堆積環境.地質雑,112,331-348.
2006
曽田祐介(早稲田大学)
曽田祐介・高木秀雄,2004,朝地変成岩類に伴われる超マフィック岩類の鉱物化学組成とその意義.地質雑,110,698-714.
2006
安江健一(日本原子力研究開発機構)
安江健一・廣内大助・中埜貴元・酒井英男・奥村晃史・海津正倫,2005,活断層の横ずれ変位によって形成される変動地形と極浅部地質構造との関係:雁行断層について.地質雑,111,29-38.
2006
河尻清和(相模原市立博物館)
河尻清和,2005,高山市北部の飛騨外縁帯に産する斑れい岩類の岩石学的特徴.地質雑,111,332-349.
2006
山本和幸(東北大学)
山本和幸・井龍康文・佐藤時幸・阿部栄一,2005,沖縄本島本部半島北部に分布する琉球層群の層序.地質雑,111,527-546.
2005
高橋昭紀(東京大学理学研究科特別研究員)
高橋昭紀・平野弘道・佐藤隆司,2003,北海道天塩中川地上部白亜系の層序と大型化石群の特性.地質雑,109,77-95.
2005
尾上哲治(鹿児島大学理学部)
尾上哲治・永井勝也・上島 彩・妹尾 護・佐野弘好,2004,九州・四国の三宝山付加コンプレックスの玄武岩類の起源.地質雑,110,222-236.
2004
森山義礼(大阪樟蔭高等学校)
Moriyama, Y. and Wallis, S. R., 2002, Three dimensional finite strain analysis in the highgrade part of the Sanbagawa Belt using deformed meta-conglomerate. Island Arc, 11, 111-121.
2004
栗原敏之(新潟大学,学振特別研究員)
栗原敏之,2003,飛騨外縁帯九頭竜湖-伊勢川上流地域における中部古生界の層序と地質年代.地質雑,109,425-441.
2004
下司信夫(産業技術総合研究所)
下司信夫,2003,愛知県設楽地域に分布する中期中新世大峠火山岩体の構造発達過程とそのマグマ供給系.地質雑,109,580-594.
2003
花方 聡(秋田県産業経済労働部)
花方 聡・渡邉和恵,2001,秋田県秋田市東部「貝の沢温泉井」鮮新統有孔虫化石及び石灰質ナンノ化石層序と古環境.地質雑,107,620-639.
2003
及川輝樹(核燃料サイクル開発機構東濃地科学センター)
及川輝樹,2002,焼岳火山群の地質―火山発達史と噴火様式の特徴口.地質雑,108,615-632.
2003
青矢睦月(名古屋大学環境学研究科)
Mutsuki Aoya, 2002, Structural position of the Seba eclogite unit in the Sambagawa belt: supporting evidence for an eclogite nappe. Island Arc, 11, 91-110.
2002
広瀬 亘(北海道立地質研究所)
広瀬 亘・岩崎深雪・中川光弘,2000,北海道中央部〜西部の新第三紀火成活動の変遷:K-Ar年代,火山活動様式および全岩化学組成からみた東北日本弧北端の島弧火山活動の変遷.地質雑,106,120-135.
2002
植田勇人(新潟大学)
Hayato Ueda, Makoto Kawamura, Kiyokawa Niida, 2000, Accretion and tectonic erosion processes revealed by the mode of occurrence and geochemistry of greenstones in the Cretaceous accretionary complexes of the Idonnappu Zone, southern central Hokkaido, Japan. Island Arc, 9, 237-257.
2001
島田耕史(早稲田大学教育)
島田耕史・高木秀雄・大澤英昭,1998,横ずれ圧縮場における地質構造発達様式:紀伊半島東部、領家帯南縁部のマイロナイト化と褶曲形成の時空関係.地質雑,104,825-844.
2001
坂島俊彦(広島大学理)
坂島俊彦・竹下 徹・板谷徹丸・早坂康隆,1999,九州西部竜峰山帯の層序,構造およびK-Ar年代.地質雑,105,161-180.
2001
Andrew James Martin(核燃料サイクル開発機構)
Andrew James Martin, Kazuo Amano,1999,Facies analyses of Miocene subaqueous volcaniclastics in the Koma Mountains, South Fossa Magna, central Japan. 地質雑,105,552-572.
2001
高嶋礼詩(九州大学比較社会文化)
高嶋礼詩・西 弘嗣,1999,中蝦夷地変の再検討と北海道の白亜紀テクトニクス.地質雑,105,711-728.
2000
高見美智夫(蒜山地質年代学研究所)
高見美智夫・板谷徹丸,1998,山口県東部ジュラ紀付加体中の遠洋性堆積岩のK-Ar代とその地質学的意義.地質雑,104,149-158.
2000
田中 尚(日特建設(株))
田中 尚・宮田雄一郎,1999,高速せん断による泥質堆積物の流動変形.地質雑,105,352-363.
1999
梅田真樹(大阪市立大学大学院)
梅田真樹,1998,高知県横倉山地域のシルル−デボン系横倉山層群.地質雑,104,365-376.
1999
辻森 樹(金沢大学大学院)
辻森 樹,1998,中国山地中央部,大佐山蛇紋岩メランジュの地質:大江山オフィオライトの下に発達した320Ma青色片岩を含む蛇紋岩メランジュ.地質雑,104,213-231.
1998
星 博幸(愛知教育大学)
Hiroyuki Hoshi, Masaki Takahashi, 1997, Paleomagnetic constraints on the extent of tectonic blocks and the kinematic boundaries:Implications for Mioccene intra-arc deformation in Northeast Japan.地質雑,103,523-542.
1997
里口保文(大阪市立大学大学院)
里口保文,1995,上総層群中・下部の火山灰層序.地質雑,101,767-782.
1997
宮下由香里(愛媛大学研究生)
宮下由香里,1996,柳井南部地域領家変成帯におけるザクロ石斑状変晶と変形時相.地質雑,102,84-104.
1996
国分公貴(北海道教育大大学院)
北海道東部,新第三紀火山岩類の岩石学的性質の変遷
1996
金栗 聡(川崎地質(株))
南部フォッサマグナ富士川谷南東部に分布する富士川層の地質とナンノ化石層序
1996
大林達生(名古屋大学大学院)
砕屑性ザクロ石の化学組成からみた石川県白峰地域の手取層群の後背地
1995
北村晃寿(静大理)
貝化石による古環境解析の時間的分解能(前期更新世大桑層中部の場合)
1995
坂本隆之((株)アイ・エヌ・エー)
瀬戸川付加体中の緑色岩類の起源とそのテクトニクス上の意義
1995
近藤浩文(電力中央研究所)
北海道樺戸山地隈根尻層群の火成岩類−東北日本の白亜紀火山帯におけるアルカリに富む火成岩類の特徴
1995
竹内 誠(工技院地質調査所)
南部北上帯下部ジュラ系志津川層群中の砕屑性ザクロ石・クロムスピネル・クロリトイドの起源
1994
坂本竜彦(北大理大学院)
佐渡島中山層(中期中新世〜初期鮮新世)堆積リズム
1994
七山 太(九大研修員)
北海道中軸部南部,”中の川層群”の層序と岩層
1993
志村俊昭(新潟大学)
花崗岩質マグマの迸入と日高変成帯の衝上テクトニクス
1993
山元孝広(工技院地質調査所)
会津地域の後期中新世−更新世カルデラ火山群
1993
西村瑞恵(石油資源開発(株))
陸棚斜面−陸棚−沿岸の堆積システムの変遷と相対的海水準変動
1992
Simon Richard Wallis
The timing of folding and stretching in the Sambagawa Belt: the Asemigawa region,central Shikoku.
1992
小竹信宏
生痕化石Chondrites およびZoophycos をつくる生物群の摂食・排せつ様式
1992
渡辺真人
富山県氷見・灘浦地域の新第三系の層序―とくに姿累層とその上位層との間の時間間隙について―
1991
保柳康一
埋積と前進に伴うタービダイトの岩相変化―中央北海道・中部中新統古丹別層―
1991
高野 修
北部フォッサマグナ新第三系田麦川累層のトラフ充填タービダイトの形成過程
1991
安藤寿男
上部白亜系中部蝦夷層群三笠層の浅海堆積相分布と前進性シーケンス
1990
宮地直道
新富士火山の活動史
1990
久保田喜裕
清津峡ひん岩体の迸入形態とその意義―第三紀花崗岩類の活動様式の検討―
1990
土谷信之
秋田―山形油田地帯付近における中新世中期玄武岩類の分布と化学組成
1990
清水以知子
Ductile deformation in the low-grade part of the Sambagawa metamorphic belt in the northern Kanto Mountains, central Japan.
1989
荒井 融
丹沢山地のテクトニクス―変成岩類の相解析による考察―
1989
千木良雅弘
泥岩の化学的風化―新潟県更新統灰爪層の例―
1989
辻 隆司・宮田雄一郎
砂岩層中にみられる流動化・液状化による変形構造―宮崎県日南層群の例と実験的研究―
1989
中川充・戸田英明
Geology and petrology of Yubari-dake serpentinite melange in the Kamuikotan Tectonic Belt, central Hokkaido,Japan.
1988
磯粼行雄
秩父累帯北帯新改層とペルム紀末の黒瀬川地塊北縁収束域
1988
高田 亮
愛知県設楽地方の大峠環状複合岩体中に存在するコールドロンの構造
1987
小山内康人
静内川上流地域における日高変成帯主帯変成岩類の地質と変成分帯
1987
大塚 勉
長野県美濃帯北東部の中・古生界
1986
川村寿郎
南部北上山地日頃市地方の下部石炭系(その1)−日頃市層の層序−
1986
高木秀雄
長野県遠野―市野瀬地域における中央構造線沿いの圧砕岩類
1986
松岡 篤
高知県西部秩父累帯南帯の斗賀野層群
1986
徐 垣
富士川層群身延累層中にみられる古海底チャネルの堆積層とその形成過程
1985
饗場清文
四国中西部秩父塁帯北帯、中津・名野川地域の三波川変成作用
1985
石賀裕明
“丹波層群”を構成する2組の地層群について―丹波帯西部の例―
1984
榎並正樹
四国中央部別子地域・三波川帯の灰曹長石―黒雲母帯
1984
川村信人
南部北上山地のシルル系奥火の土層と先シルル紀花崗岩帯
1984
栗本史雄
和歌山高野山南西方のいわゆる秩父系―上部白亜系花園層―
1984
山本剛志
岐阜県上麻生付近の三畳系層状チャートの地球化学的研究
1983
矢野孝雄
長野県北部荒倉山周辺における鮮新世の火山活動
1983
中村和善
新潟県高田平野南方地域における後期新生代の構造運動―その2 地質構造の形成
1982
石塚英雄
北海道、神居古潭構造帯に分布する幌加内オフイオライトの地質
1982
氏家良博
北海道天北地域の白亜系・第三系に含まれるケロジエンの続成変化
1982
公文富士夫
徳島県南部の四万十塁類帯白亜系
1982
三宅康幸
和歌山県潮岬火成複合岩体の地質と岩石
1981
鎌田耕太郎
南部北上山地唐桑半島周辺の三畳系稲井層群(その1)―層序および古地理―
1981
鈴木清一
Mytilus edulis(斧足類)の再生有機膜殻体の鉱物化
1981
新川 公
岐阜県古城郡上宝村福地地域の地質と化石層序
1981
宮城晴耕
神居古潭帯に産するトロニエマイト質岩のSr同位体
1980
足立久男
山形吉野地域のグリーン・タフ―とくに西里沢期の不整合問題について―
1980
木村 学
小断層系・砂岩岩脈からみたラワン褶曲帯の形成機構
1980
柴 正博
小笠原諸島東方、矢部海山(新称)の地史
1980
中田節也
尾鈴山酸性岩の地質
1980
広井美邦
飛騨変成岩帯宇奈月地域の地質
1980
牧本 博
長野県下伊郡地方の入沢井超苦鉄質複合岩体の岩石学―塩川かんらん岩体の岩石記載と化学的性質―
1979
石田啓祐
四国東部の秩父類帯南帯中・古生界層序のコノドントと紡錘虫による再検討
1979
大塚則久
ナウマンゾウ(Palaeolotodon naumanni)の起源について―頭蓋の比較骨学的研究
1979
沢田順弘
島根県掛合陥没体に伴われる貫入複合岩体―非アルカリ岩のマグマ型と岩石系列に関する2、3の問題―
1979
吉川周作
大阪層群火山灰層中の火山ガラスの化学組織について
1978
小室裕明・小玉喜三郎・藤田至則
グリーンタフ造山における陥没盆地の発生機構―数値モデル実験による試論
1978
徳橋秀一
清澄層Bk層準フリッシュ型砂泥互層の堆積学的研究
1978
鳥海光弘
変成分化作用の力学的側面
1978
丸山茂徳
四国東部秩父帯中の沢呑緑石岩コンプレックスの化学的性質
1977
君波和雄
根室層群の堆積学的研究(その2)―根室層群の厚岸層のフリッシュ型砂岩のx線
1977
高安克己
沖縄県本部半島北部の第四紀石灰岩
1977
滝田良基
丹沢トーナル岩複合岩体の岩石記載と岩体形成史
1977
立石雅昭
牟婁帯南部の牟婁層群
1977
牧之内 猛
知多半島南部の地質構造と伊勢湾周辺地域の構造運動
1976
池田孝夫・嶋本利彦
粘性曲げ褶曲の数値実験
1976
小井土由光
岐阜県下呂町東部地域の濃飛流紋岩―とくに赤石溶結凝灰岩層の細分について―
1976
周藤賢治・加々美寛雄・牛来正夫
選別されたSr同位体比資料に基づく酸性岩起源物質の再検討t
1976
玉生志郎
仙台付近新第三系の秘跡法による年代測定
1975
大平芳久
中部阿武隈山地好間川花崗質岩体の構造と併入運動について
1975
コノドント団研グループ
本邦の二畳系と三畳系の境界におけるコノドントについて―あど山層基底部のコノドントフォーナの再検討
1975
沢田賢治
Geology of geosynclinal greenstones of the Chichibu and Sanbagawa belts in central shikoku
1975
林 隆夫
堅田丘陵の古琵琶湖層群
1975
渡辺暉夫
三波川帯・秩父帯中の小褶曲の形成機構についての一考察―長野県大鹿地方の例
1974
足立 守
上麻生礫岩中の泥質および石英―長石質片麻岩
1974
加々美寛雄
A Rb-Sr geochronological study of the Ryoke granites in Chubu district, Central japan.
1974
加納 隆
富山県東半部の飛騨変成岩の地質について(その1)地質構造区分船津期深成作用の特徴および変成岩類の岩相層序区分について
1974
後藤仁敏
日本産の化石軟骨魚類についての一統括
1974
田崎和江
大山降下堆積物および三瓶山降下堆積物中の粘土鉱物
1973
杉山 明
山梨県西部巨摩山地の新第三系の変質
1973
藤井厚志
砂岩重鉱物解析の一方法、上部古生界常森・大田両層の砂岩を例として
1973
丸山孝彦
阿武隈高原・鮫川・石川地方の地質と構造
1972
田中 剛
中央日本秩父古生層中の地向斜性火山岩類の化学組成
1972
田結庄良昭
大阪府北部茨木複合花崗岩体の岩石学的研究
1972
平野昌繁
花崗岩の節理を中心とした深成岩体んのbrittleな変形・破壊を考える上での問題点
1972
山本裕彦
フリッシュ型砂岩層に発達するconvolute laminationについて
1971
小野 晃
長野県高遠―塩尻地方に分布する領家変成岩の変成分帯
1971
景守紀子
大阪付近の新生代の地層より産出する木材化石の化学的組織
1971
山内靖喜
層間異常の構造解析
1970
小坂共栄・角田史栄
山梨県西部、巨摩山地第三系の地質
1970
原田一雄
沸石相―とくに地層の埋没深度による分帯に関して
1969
小玉喜三郎
城ヶ島における小断層解析
1969
西村祐二郎・濡木輝一
山口県錦町地域における非変成岩古生層と三郡変成岩類の地質学的関係
1968
真鍋 健一
福島盆地の新第三紀火山岩の古地磁気学的研究
1968
土屋 篁
木曽駒花崗閃緑岩の構造/木曽駒花崗閃緑岩体の岩相変化―とくに斜長石組成の変化についてー
1967
該当なし
1966
堀田 進
化石タマキガイに残存するアミノ酸
1965
青木直昭
房総半島の鮮新世〜更新世浮遊性有孔虫化石群
1963
小林巌雄
宮城県仙台市西方における新第三系 "白沢層"の層相変化とその堆積環境
1963
速水 格
本邦ジュラ紀の斧足類群特に層位学的分布と生物地理区について
1962
松田時彦
富士川谷新第三系の地質
1962
小林和夫・生沼 郁
秩父盆地第三紀層の粘土鉱物組成
1961
金子史朗
多摩川中流地域におけるFractureの研究
1960
浜田隆士
西南日本外帯ゴトランド系の層序と分帯
1960
端山好和
黒雲母の色およびそれと変成作用との関係について(英文)
1959
羽鳥謙三・寿円晋吾
関東盆地西縁の第四紀地史―多摩丘陵の地形発達
1958
小野寺信吾
岩手県一ノ関市で発見されたDesmostylusと,その産地付近の地質
1957
木崎甲子郎
日高変成帯南部,音調津山地のミグマタイトの構造について
1957
藤井浩二
九州八代地方中生界の砂岩
1956
勝井義雄
摩周火山の地質と岩石
1956
庄司力偉
堆積機構の基礎的研究―沈澱池につくられる累積層および砂漣
1956
津田禾粒
八尾層群の堆積環境について―いわゆるGreen Tuff地域の中新統に関する堆積環境の研究
1955
唐木田芳文
北九州白亜紀の花崗閃緑岩・花崗岩接触部における"ジルコン帯"の存在について
1955
三梨 昂
房総半島鬼泪山南部の地質
1954
苣木浅彦
硫酸塩鉱物の離溶共生に関する熱的研究
1953
勘米良亀齢
熊本県氷川地域における上部石炭系および下部二畳系
1953
関 陽太郎
岩手県宮守地方の超塩基性岩類の研究,その4,構造的研究
1952
大久保雅弘
日頃市統及び先日頃市世の不整合について
1952
加納 博・武藤矩靖
田老鉱床における𨫤の内変動帯の構造−特に線構造と落しの問題に関して
1952
小池 清
いわゆる黒滝不整合について
1951
小島丈児
西南日本外帯のいわゆる御荷鉾糸について
1951
湊 秀雄
本邦産スコロド石類の研究
1951
中山 勇
動力変成岩に於ける石英の配列機構に関する一考察/大歩危千枚岩質砂岩にみられるGetügeregel
1951
市川浩一郎
本邦三畳紀の年代区分について
1944
(昭19)
大立目譲一郎
夕張炭田辺富内地方の地質構造特に其推被せ構造に就いて
1944
(昭19)
滝本 溝
本邦産錫鉱物の研究
1943
(昭18)
湊 正雄
北上山地に於ける先坂本沢階(Pre-Snkmarian)不整合と其の意義
1943
(昭18)
掘 純郎
或るアルカリ角閃石の異常光学現象に就いて
1942
(昭17)
今井秀喜
宮城県細倉鉱山産所謂繊維亜鉛鉱に就いて
1941
(昭16)
須藤俊男
満州東辺老嶺鉄層の鉱石に就いて
1940
(昭15)
池辺辰生
平壌束方三登並に鮮原地方の地質構造
1940
(昭15)
柴田秀賢
美濃国恵那郡苗木地方の花崗岩類及びペグマタイト
1939
(昭14)
堀越義一
別子附近産変成岩中の二三の組成鉱物の性質
1938
(昭13)
松本達郎
天草御所浦島に於ける地質学的研究(特に白亜系の地史学的研究)
1937
(昭12)
吉村豊文
加蘇鉱山産バリウム長石類に就いて
1937
(昭12)
岩生周一
山口県柳井地方の花崗岩類と領家変成岩類との野外に於ける諸関係
1936
(昭11)
松沢 勲
満州熱河地方承徳附近の地質構造に就いて
1936
(昭11)
坂倉勝彦
千葉県小櫃川流域の層序
1935
(昭10)
野田光雄
北上山地西部長坂附近の地質学的研究
1934
(昭9)
渡辺武男
朝鮮遂安金山笏洞鉱床体の金銅蒼鉛鉱について
1933
(昭8)
佐々保雄
岩手県久慈地方の地質に就いて
1933
(昭8)
末野梯六
屈折率測定に標準硝子粉末を用うる方法
1931
(昭6)
大塚彌之助
三浦半島北部の層序と神奈川県南部の最新地質時代に於ける海岸線の変化について
1930
(昭5)
小林貞一
南満北鮮に発達する奥陶紀層に就いて
1929
(昭4)
冨田 達
信濃木崎湖畔森産曹達花崗包裏物斑岩のヘイステイングサイトに就いて
1928
(昭3)
今野円蔵
朝鮮大宝炭鉱附近の地質と構造
1928
(昭3)
山口鎌次
櫻島熔岩中における球状ノーライトの包裏物に就きて
1927
(昭2)
鈴木 醇
日立鉱山附近のオットレライト千枚岩の成因
1926
(大15)
半沢正四郎
沖縄島及び小笠原島の含有孔虫岩に就いて
1926
(大15)
杉 健一
丹波綾部附近の基性深成岩に就きて
1925
(大14)
上床国夫
本邦に於けるヘリウム含有天然瓦斯の研究
1925
(大14)
長尾 巧
九州に於ける白亜紀送と古第三紀層の境界に就きて
1924
(大13)
小沢儀明
秋吉台石灰岩を含む所謂上部秩父古生層の層位学的研究
1923
(大12)
瀬戸国勝
長石の化学研究
1921
(大10)
木下亀城
宝鉱山の鉱床
1919
(大8)
坪井誠太郎
三原岩に就いて/大島火山のマイクロリアリヴァライト及マイクロダイオライトの成因に就て/微粒二軸性結晶の中間屈折率を定ること
1918
(大7)
早坂一郎
詳細不明 ※大正7年受賞者に氏名があるが、詳細は判明せず(75周年史参照)
1917
(大6)
辻村大郎
火山島嶼の触磨輪廻
1916
(大5)
渡辺万次郎
本産霰石報文日
1916
(大5)
木村六郎
山口県藏目喜鉱山に於ける接触交代鉱床就きて
各賞-日本地質学会功労賞
日本地質学会功労賞(〜2021年)
※2021年廃止.以降は「日本地質学会表彰」へ統合されました.
※各受賞者または功労業績をクリックすると、推薦理由等をご覧いただけます。
受賞者
功労業績
2017
大和田 朗(産業技術総合研究所地質調査総合センター)
地質試料の新薄片作製法の開発と人材育成
2016
檀原 徹(株式会社京都フィッション・トラック)
放射年代測定等による地質学への貢献
2015
大山次男(東北大学理学部技術部)
岩石研磨薄片技術の高度化
2011
石井輝秋
日本近海の海洋底地質・岩石研究への貢献
2010
杉山了三
地域を生かし,生徒とともに創造する地学学習
2009
(該当なし)
2008
(該当なし)
2007
戸間替修一(北海道立地質研究所)
薄片等試料作成による地域地質研究への貢献
2006
(該当なし)
2005
(該当なし)
2004
(該当なし)
2003
堤 久雄(京都大学理学部:技術専門官)
特殊薄片製作法の開発と技術教育への貢献
2001
桑島俊昭(北海道大学理学部:技術専門官)
永年にわたる薄片・研磨片の製作に対して
各賞-学会表彰
日本地質学会表彰
地質学の教育活動,普及・出版活動,新発⾒および露頭保全,あるいは新しい機器やシステ ム等の開発等を通して地質学界に貢献のあった会員および⾮会員の個⼈,団体および法⼈(運営規則第16条2)
※各受賞者または表彰業績をクリックすると、推薦理由等をご覧いただけます。
受賞者
表彰業績
2024
夏原信義 氏 (夏原技研)
実験装置の開発・製作による地質学への貢献
2022
伊与原 新氏(小説家・推理作家)
地球惑星科学研究をいかした小説発表とそれによる科学知識の普及
2021
千葉セクションGSSP提案チーム
千葉セクションにおける日本初のGSSP認定
2020
鹿野和彦ほか
地質図の標準化のための JIS A 0204,JIS A 0205 の制定・改正への貢献
2020
株式会社浜島書店
図書教材出版を通じた地学教育への貢献
2019
加納 隆(山口大学名誉教授)
地球科学標本室・ゴンドワナ資料室の整備と普及活動
2019
数研出版株式会社
教科書出版を通じた地学教育への貢献
2019
株式会社新興出版社啓林館
教科書出版を通じた地学教育への貢献
2017
「ブラタモリ」制作チーム(日本放送協会)
地質学の社会への普及
2016
内藤一樹(産業技術総合研究所地質情報基盤センター)
地質図のデジタルアーカイブの構築とその整備
2015
白尾元理(写真家)
ジオフォト文化の先駆と発展,その科学的メッセージの発信
2014
西岡芳晴(産業技術総合研究所地質情報研究部門)
シームレス地質図配信システムの構築
2013
岡村 眞(高知大学総合研究センター)
地震・津波研究の新分野開拓と普及教育活動
2013
静岡県袋井市(代表者:市長 原田英之)
地層保全を活かす市民公園の先駆的取り組み
2012
北九州市立自然史・歴史博物館(いのちのたび博物館)
自然・環境保全活動および地質学の教育・普及への貢献
2012
狩野謙一(静岡大学理学部)・村田明広(徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部)
教科書発行と構造地質学普及への貢献
2011
森林総合研究所・千葉県南房総市
海底地すべり露頭の保全と社会教育的活動
2010
山口県(代表者:山口県知事 二井関成)
阿武火山群の火山灰層の保存と観察施設建設
2010
地球システム・地球進化ニューイヤースクール(NYS)事務局(大坪 誠・坂本竜彦・岡崎裕典・ほか)
地球科学系の若手研究者の継続的育成活動
2009
秋吉台科学博物館(代表:館長 池田 善文)
秋吉台研究に関する調査研究・教育普及活動
2007
北中康文氏(写真家)
写真集「日本の滝」①東日本661滝 ②西日本767滝 の出版による地質学の普及への貢献
2005
石黒 耀氏(作家)
著書“死都日本”と“震災列島”による地質学の的確な紹介
2005
産業技術総合研究所地質調査総合センター
地質情報展の開催
2004
北海道日高町
日高山脈館による地質学の普及と野外調査活動の支援
2003
新潟県県糸魚川市 市長 吉岡静夫
重要な露頭の保全と活用および博物館活動
2003
北海道様似町 町長 橋爪正利
アポイ岳周辺地域の地質調査および国際学会開催の支援
2001
株式会社クボタ
「アーバンクボタ」発行による地球環境問題や地質学的事象の一般社会への普及と啓蒙に対する貢献
2000
石川県知事 谷本正憲
犀川河床,更新統大桑層模式地露頭の保全
2000
岡山県大佐町町長 梅田和男
大佐山のコスモクロアおよびひすい輝石の露頭保全
2000
三重県 飯高町町長 宮本里美
中央構造線最大の露頭,月出露頭の保全
2000
長野県大鹿村村長 宮下寛夫
中央構造線博物館における露頭保全と野外展示活動
Geo暦(2014)
2014年Geo暦(行事カレンダー)
2008年版 2009年版 2010年版 2011年版 2012年版 2013年版
…… 2015年版
2014年版 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
○印は学会主催行事.(共)学会共催・(後)後援・(協)協賛
1月January
海底下の炭化水素資源・炭素循環と地球生命工学
1月24日(金)
場所:東京大学本郷キャンパス小柴ホール(理学部1号館2階)
http://www.jamstec.go.jp/j/pr/event/
第2回セミナー『海の魅力を伝えます!海を学び、海で働く女性から中高生へ』
1月26日(日)13:00-16:00
場所:東京大学理学部4号館2階
対象:中学・高校の生徒(女子優先ですが、男子も奮ってご参加ください)・引率保護者・引率教員
申込締切:1月25日(土)10:00 定員:80名 参加無料
プログラム概要
申込方法:Web登録はこちら
2月February
第59回セミナー「水道資源の新たな水質危機と対応の最新動向」
2月3日(月)
場所:自動車会館大会議室(千代田区九段南4-8-13)
定員:先着160名 要申込
https://www.jswe.or.jp/event/seminars/index.html
IFREE公開シンポジウム
「地球大変動IIー地殻大変動を引き起こす地球深部の巨大運動が見えてきた!」
2月8日(土)13:00-17:30
場所:建築会館ホール(東京都港区芝5-26-20)
入場無料
http://www.jamstec.go.jp/ifree/j/sympo/2013/
第157回深田研談話会「頭足類の進化古生物学」
2月14日(金)15:00-17:00
申し込み締切:1/20 先着:80名 参加無料
会場:深田地質研究所 研修ホール(文京区本駒込2-13-12)
http://www.fgi.or.jp/
ブルーアース2014
2月19日〜20日
場所:東京海洋大学 品川キャンパス
入場料無料 事前申込不要(要旨集は会場にて配布)
http://www.jamstec.go.jp/maritec/j/blueearth/2014/
○西日本支部 平成25年度総会・第165回例会
2月22日(金)[21日:幹事会]
場所:佐賀大学,本庄キャンパス,大学会館
講演申込み〆切:2月5日(水)12時
詳しくはこちら
3月March
○東北支部2012-2013年度総会・講演会
3月1日(土)
場所:山形大学小白川キャンパス 地域教育文化学部2号館
詳しくはこちら
第13回Project A春期ミーティング in 薩摩硫黄島 2014
3月4日〜3月7日
4日:シンポジウム・一般講演会(3時頃到着)、5日:シンポジウム・ミーティング、6日:巡検、7日:朝巡検(10時出発)
http://archean.jp
JAMSTEC2014
3月5日13:00-17:30
場所:東京国際フォーラム ホールB7(千代田区丸の内3−5−1)
入場料無料 事前申込不要(要旨集は会場にて配布)
http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20140205/
第3回学生のヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集
(学会推薦)
参加申込締切:2013年11月30日
実習実施時期:3月5日出発,19日帰国(15日間)
実習コース:カトマンズ−ポカラ−ムクチナート−タンセン−ルンビニ
参加費用:学生・大学院生20万円以内、その他の個人参加者:25万円以内、大学・企業などの組織派遣教員/社員:30万円以内
http://www.geocities.jp/gondwanainst/
NUMO技術開発報告会 −自然現象の確率論的評価手法の適用性−
3月6日(木)10:00-17:00
場所:三田NNホール&スペース 多目的ホール
参加費:無料 申込期限:2月24日(月)
http://www.numo.or.jp/topics/2013/14021811.html
○日本地質学会北海道支部平成25年度総会
3月8日(土)14:00-16:00
場所:北海道大学理学部5号館3階 5-301室
詳しくはこちら
平成25年度海洋情報部研究成果発表会
3月10日(月)13:15-17:45
会場:海上保安庁海洋情報部(東京都江東区青海2-5-18)
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KIKAKU/press/2014/H260218_kenkyu.pdf
学術フォーラム「世界のオープンアクセス政策と日本:研究と学術コミュニケーションへの影響」
3月13日(木)13:00-17:30
場所:日本学術会議講堂
参加:無料、要事前登録
https://form.cao.go.jp/scj/opinion-0003.html
日本堆積学会2014年山口大会
3月14日(金)〜17日(月)
会場: 山口大学吉田キャンパス大学会館ほか
http://sediment.jp/04nennkai/2014/annai.html
第284回地学クラブ講演会
微生物がつくり、人が護る:「天然記念物“オンネトー湯の滝マンガン酸化物生成地”」と「錦沼」講演会
3月15日(土)14:00-15:30
場所:地学会館講堂(東京都千代田区二番町12-2 地学会館)
http://www.geog.or.jp/lecture/lecturescheduled/203-284-.html
「ヒト−資源環境系の歴史的変遷に基づく先史時代人類誌の構築」2013年度公開研究集会
3月15日(土)12:55-17:30,16日(日)9:00-15:00
会場:明治大学駿河台キャンパスグローバルフロント1階グローバルホール(東京都千代田区神田駿河台1-1)
参加費:無料
申込締切:3月7日(金)
プログラム等はこちら
第48回日本水環境学会(仙台)年会
3月17日(月)〜19日(水)
場所:東北大学 川内北キャンパス(仙台市青葉区)
http://www.jswe.or.jp/event/lectures/index.html
International Symposium on Asian Dinosaurs
3月21日(金)〜23日(日)
場所:[20〜21日]福井県立大学(個人講演、ポスターセッション)
[23日]福井県立恐竜博物館(普及講演)
http://www.dinosaur.pref.fukui.jp/ADA/
スプリング・サイエンスキャンプ2014
3月21日(金)〜29日(土)のうち2泊3日
場所:大学、公的研究機関、民間企業等(12会場)
応募締切:1月24日(金)必着
http://www.jst.go.jp/cpse/sciencecamp/camp/
スマートフォンサイトhttp://www.jst.go.jp/cpse/sciencecamp/camp/sp/
4月April
第158回深田研談話会「地形・地質、自然史から植物の分布を読む」
4月11日(金)15:00-17:00
申し込み締切:4/9 先着:80名 参加無料
会場:深田地質研究所 研修ホール(文京区本駒込2-13-12)
http://www.fgi.or.jp/
(共)第13回重金属類・廃棄物に関わる地質汚染調査浄化技術研修会
4月25日(金)10:30〜27日(日)17:00
定員:30名
会場:潮来ホテル(JR潮来駅前)ほか
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
平成25年度笹川科学研究奨励賞受賞研究発表会
4月25日(金)9:30〜
場所:ANAインターコンチネンタルホテル(東京都港区)
http://www.jss.or.jp/ikusei/sasakawa/kenkyuu/kenkyuu.html
5月May
地球惑星科学NYS若手合宿2014
5月2日(金) 〜 4日(日)
場所:八王子セミナーハウス(東京)
定員:50名 対象:学部生以上
https://sites.google.com/site/nyswakate/2014
第6回国際レルゾライト会議 6th International Orogenic Lherzolite Conference
5月4日〜14日
場所:Marrakech, Morocco
オプション巡検:
・Pre-conference
2014年5月4日〜5月7日
場所:Beni Bousera Orogenic Peridotite
・Post-conference 1
2014年5月11日〜5月13日
場所:Middle-Atlas (Volcanics and Mantle Xenoliths)
・Post-conference 2
場所:Anti-Atlas (Pan-African Ophiolites)
2014年5月11日〜5月14日
http://www.gm.univ-montp2.fr/Lherzolite/
○Marjorie Chan教授講演会
(主催:日本堆積学会,日本地質学会,石油技術協会探鉱技術委員会)
■東京講演会
5月9日(金)15:00-17:00
場所:東京工業大学地球生命研究所セミナー室(4階)
■京都講演会
5月11日(日)15:00-16:00
場所:京都大学百周年時計台記念館国際交流ホールI
http://www.geosociety.org/Sections/International/LectureTour/
第159回深田研談話会[現地]「東西日本の地質境界を歩く」
5月17日(金)9:30-16:30(銚子駅集合/解散)
申し込み:4/1〜22 定員:20名(申込多数の場合は抽選) 参加費:3000円
http://www.fgi.or.jp/
東京地学協会春季特別公開講演会「日本と世界の奇岩に見るジオ多様性」
5月17日(土)14:00-16:30
場所:東京地学協会地学会館講堂
加藤碵一(産総研・地質情報整備活用機構)「日本奇岩百景とジオ多様性」
須田郡司(石の写真家・巨石ハンター)「世界奇岩巡礼」
参加費・予約不要
http://www.geog.or.jp/
6月June
水月湖はこうして世界の標準時計になった
6月1日(日)13:30-15:00
会場:立命館大学びわこ・くさつキャンパスエポックホール
事前申込制・参加費無料
申込締切:5月22日(木)
http://www.ritsumei.ac.jp/rs/category/tokushu/140502/file/140502-nenko.pdf
※パネル展示同時開催
奇跡の湖!ー水月湖年縞堆積物の秘密に迫るー
静岡大学地殻・マントル変動フォーラム 第3回ジオダイナミクスセミナー
6月3日(火)16:00-17:00
会場:静岡大学共通教育C棟611室
講師:唐戸俊一郎(Yale University, USA)
演題:鉱物物理の最近の話題:水(水素)と電気伝導度、超高圧での変形実験
http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~s-geo/activity.html
○中部支部 2014年支部年会
6月14日(土)〜15日(日)
14日:支部総会、シンポジウム、研究発表会、懇親会
15日:地質巡検
場所:信州大学理学部大会議室
詳しくはこちら
高校地理歴史教育に関するシンポジュウム
6月14日(土)13:00-17:00
場所:東京大学駒場キャンパス21KOMCEEレクチャーホール
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//geoFlash_img/no257/chiri_sympo140614.pdf
第14回アジア学術会議マレーシア会合国際シンポジウム
6月18日〜19日
会場:Istana Hotel(クアラルンプール、マレーシア)
http://www.scj.go.jp/ja/int/sca/index.html
資源地質学会第64回年会学術講演会
6月25日(水)〜27日(金)
会場:東京大学小柴ホール
http://www.resource-geology.jp/
公開シンポジウム「航空宇宙、船舶海洋分野等における研究開発と利用応用の橋渡しとバランス〜双方向の流れをめざして〜」
6月27日(金)9:30-17:30
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木7-22-34)
http://www.jaxa-sf.jp/
地質学史懇話会
6月28日(土)13:30-17:00
場所:北とぴあ8階803号室
相原延光『お天気博士藤原咲平の生涯と地学史における再評価(仮題)』
加藤碵一『「地文学」と「地人論」考』
深田研ジオフォーラム2014
6月28日(土)10:00-16:00(受付開始9:30)
場所:深田地質研究所研修ホール(文京区本駒込2-13-12)
藤井敏嗣『日本の火山活動と火山防災』
申込締切:6月20日(金)[定員50名:定員に達し次第締切]
http://www.fgi.or.jp
国際シンポジウム「西アジア文明学の創出1:今なせ古代西アジア文明なのか?」
6月28日(土)〜29日(日)
場所:池袋サンシャインシティ文化会館7階会議室704-705
申込不要・入場無料 先着130名
http://rcwasia.hass.tsukuba.ac.jp/kaken/
7月July
第51回 アイソトープ・放射線 研究発表会
7月7日(月)〜9日(水)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1)
発表申込締切:2月28日(金)
講演要旨原稿締切:4月11日(金)
http://www.jrias.or.jp/seminar/cat4/505.html
第14回ルミネッセンス・ESR年代測定国際会議
14th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating
7月7日(月)〜11日(金)(巡検12日〜13日)
場所:カナダ・モントリオール
http://www.led2014.uqam.ca
海洋教育セミナー&フォーラム「海の学びの万華鏡」
7月20日(日)
「海洋教育セミナー」10:00〜12:00(9:30受付開始)
「海洋教育フォーラム」13:30〜17:00(13:00受付開始)
会場:東京大学・本郷キャンパス 福武ホール
対象:小・中・高等学校教員、教育関係者、学生、一般
定員:180名 参加費:無料
http://rcme.oa.u-tokyo.ac.jp/information/20140524_502.php
(後)「青少年のための科学の祭典」2014全国大会
7月26日(土)〜27日(日)
場所:科学技術館(千代田区北の丸公園)
http://www.kagakunosaiten.jp/
島原半島の地下を見てみよう ボーリングコア公開と火山実験講座
7月20日(日)
○ボーリングコア公開10:00 - 16:30
○火山講座「火山の観測とデータのよみ方 明日からあなたも火山学者?」13:30 - 14:00
○火山実験「体験してみよう火山噴火のしくみと火山観測」14:00 - 16:30
場所:長崎県島原市国土交通省雲仙復興事務所資料館および駐車場
http://www.unzen-geopark.jp/c-event/5051
(後)「青少年のための科学の祭典」2014全国大会
7月26日(土)〜27日(日)
場所:科学技術館(千代田区北の丸公園)
http://www.kagakunosaiten.jp/
8月August
学術フォーラム「初等中等教育における海洋教育の意義と課題 −海洋立国を担う若手の育成に向けて−」
8月1日(金) 13:00〜17:30
場所:日本学術会議講堂(地下鉄乃木坂駅 すぐ)
参加無料 要事前申込
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/193-s-0801.pdf
☆第15回地震火山こどもサマースクール「島原半島に隠された九州のヒミツ」
8月2日(土)〜3日(日)
場所:島原半島世界ジオパーク
申込締切:7月18日(金)23日(水)※締切延長
http://www.kodomoss.jp/ss/shimabara/
第23回市民セミナー「黄砂と共に飛来する越境化学物質−水環境と健康に対する影響を考える−」
8月8日(金)9:45-16:35
場所:
東京会場:地球環境カレッジ(いであ(株)内)(東京都世田谷区駒沢)
大阪会場:いであ(株)大阪支社ホール(大阪市住之江区南港北)
申し込み・問合せ先:(公社)日本水環境学会セミナー係 戸川
TEL:03-3632-5351 FAX:03-3632-5352
e-mail:togawa@jswe.or.jp
詳しくはこちら
日本学術会議公開シンポジウム:学校教育にもとめられるオープンデータを活用できる人材育成
8月20日(水)
場所:日本学術会議講堂
詳しくはこちら
(共)J-DESCコアスクール・微化石コース(第8回)/第11回微化石サマースクール
8月29日(金)〜31日(日)
場所:名古屋大学理学部・環境学研究科E棟
申込締切:8月8日(金)
http://www.j-desc.org/modules/tinyd0/rewrite/coreschool/micropal.html
9月September
(共)IGCP608 Asia-Pacific Cretaceous Ecosystems(白亜紀アジア−西太平洋生態系)
第2回国際シンポジウム
9月4日(木)〜6日(土)(シンポジウム)
9月7日(日)〜10日(水)(巡検:銚子・那珂湊・双葉層群)
会場:早稲田大学 大隈講堂 小講堂
http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/
地磁気・古地磁気・岩石磁気学の最前線と応用
9月3日(水)〜4日(木)
場所:東京大学大気海洋研究所2F 講堂
http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/aori_news/meeting/2014/20140903.html
Thermo2014:第14回国際熱年代学会議
14th International Conference on Thermochronology
9月8日(月)〜12日(金)(巡検5日〜7日)
場所:フランス・シャモニー
http://www.thermo2014.fr
第17回日本水環境学会シンポジウム
9月8日(月)〜10日(水)※10日は見学会のみ
場所:滋賀県立大学
参加申込:7月1日(火)〜8月18日(月)
http://www.jswe.or.jp/event/symposium/2014/joinGuide.html
◯日本地質学会第121年学術大会
9月13日(土)〜15日(月・祝)
会場:鹿児島大学
大会HP http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0001.html
(共)2014年度日本地球化学会第61回年会
9月16日(火)〜18日(木)
会場:富山大学五福キャンパス
講演申込締切:7月16日(水)14:00
事前参加登録締切:8月29日(金)14:00
http://www.geochem.jp/conf/2014/
第11回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム、国際ゴンドワナ研究連合2014年会及び付属野外巡検
9月19日(金)〜21日(日)(会議)
9月22日(月)〜24日(水)(巡検)
場所:北京、China University of Geosciences Beijing
http://www.iagrhomepage.com
第31回歴史地震研究会(名古屋大会)
9月20日(土)〜22日(月)
会場:名古屋大学減災連携研究センター 減災ホール
講演申込締切:5月30日(金)
http://sakuya.ed.shizuoka.ac.jp/rzisin/menu7.html
(共)第58回粘土科学討論会
9月24日(水)〜27日(土)
会場:福島市A・O・Z(アオウゼ)
参加・講演申込期間:6月16日(月)〜7月11日(金)
講演要旨送付締切:7月25日(金)
http://www.cssj2.org/
あいちサイエンスフェスティバル2014
9月27日(土)〜11月3日(月)
会場:蒲郡市生命の海科学館など
※(共)惑星地球フォトコンテスト入賞作品展
https://aichi-science.jp/
(後)日本ジオパーク南アルプス大会(第5回日本ジオパーク全国大会)
9月27日(土)〜9月30日(火)
場所:長野県伊那文化会館、伊那市生涯学習センター(いなっせ)
http://minamialps-mtl-geo.jp/
10月October
東京地学協会 第287回地学クラブ講演会
10月3日(金) 16:00~17:30)
場所:地学会館講堂(麹町)
小原泰彦(海上保安庁)「海洋底科学と海底地形名」
http//www.geog.or.jp/
○関東支部:富士山巡検
10月4日(土)〜5日(日)
申込締切:9月19日(金)
http://kanto.geosociety.jp/
深田研 一般公開2014
10月5日(日)10:00〜16:00
会場:深田地質研究所(文京区本駒込2-13-12)
http://www.fgi.or.jp/
筑波大学大学院生命環境科学研究科説明会
10月6日(月)18:00〜20:00(受付17:20)
場所:筑波大学東京キャンパス文京校舎 134講義室
http://www.life.tsukuba.ac.jp/entrance/setsumeikai_20141006.pdf
(協)2014地球環境保護 土壌・地下水浄化技術展
10月15日(水)〜17日(金)10:00〜17:00
会場:東京ビッグサイト 西ホール
http://www.sgrte.jp/sgr/
○関東支部:ショートコース『地すべり破砕帯の構造地質学』
(主催:日本地質学会関東支部,日本地すべり学会関東支部)
10月18日(土) 10:00〜16:40
場所:帝京平成大学 中野キャンパス
申込締切:10月7日(火)
http://kanto.geosociety.jp/
IGCP589「アジアにおけるテチス区の発達」第3回国際シンポジウム
プレ巡検:10月19日(日)〜20日(月)
シンポジウム:10月21日(火)〜22日(水)
ポスト巡検:10月23日(木)〜26日(日)
開催場所:テヘラン,Hoveizehホテル
http://igcp589.cags.ac.cn/Symposia.htm
GSA2014
10月19日(日)〜22日(水)
場所:カナダ,バンクーバー
講演要旨締切:7月29日
http://community.geosociety.org/gsa2014/home/
第115回「海洋フォーラム」
SIDSサモア会議と『島と海のネット』の立上げ〜第3回国連小島嶼途上国会議からの報告〜
10月22日(水)17:00〜18:30(受付開始16:30)
場所:日本財団ビル 2階大会議室(東京都港区赤坂1−2−2)
参加無料
http://www.sof.or.jp/jp/forum/index.php
(後)山陰海岸ジオパーク国際学術会議「湯村会議」
10月25日(土)〜26日(日)
場所:新温泉町夢ホール(兵庫県美方郡新温泉町湯990-8)
要旨応募締切:8月29日
http://sanin-geo.jp/modules/geopark/index.php/yumura14.html
東京地学協会 秋季特別公開講演会「今時の恐竜事情」
10月25日(土)14:00〜17:00
場所:弘済会館(東京)
冨田幸光(国立科学博物館)「恐竜学の最近の進歩」(仮題)
東 洋一(福井県恐竜博物館特別館長)「日本の恐竜化石について」(仮題)
http//www.geog.or.jp/
シンポジウム「これからの理数系教育を考える」
10月26日(日)13:20〜16:40
場所:一橋記念講堂(東京都千代田区)
https://sites.google.com/site/risukeigakkai/sympo2014
11月November
第23回素材工学研究懇談会「励起反応場を用いた多次元金属ナノ・マイクロ構造創成」
11月6日(木)〜7日(金)
場所:東北大学片平さくらホール2F
申込締切:10/31
http://www.tagen.tohoku.ac.jp/
大型研究航海 計画作成ワークショップ
11月6日(木)〜7日(金)
場所:海洋研究開発機構 横浜研究所 三好記念講堂他
(9月19日まで 研究課題も募集)
http://www.jamstec.go.jp/maritec/e/large-scale_cruise/index.html
日本応用地質学会:現場研修会・講習会【伊豆大島土砂災害より学ぶ:土砂災害の要因と対策】
11月8日(土)〜10日(月)
講 師:井口 隆氏(防災科学技術研究所),千葉達朗氏(日本大学)
募集数:40名程度 締切:10月17日(金)
参加費:¥35,000(11/8集合場所にて徴収)
http://www.jseg.or.jp/00-main/pdf/140930_kensyu_oshima.pdf
平成26年度 東濃地科学センター
○ 地層科学研究 情報・意見交換会
11月11日(火)13:20〜17:00
場所:瑞浪市地域交流センター「ときわ」(岐阜県瑞浪市)
定員:約150名
○瑞浪超深地層研究所 深度300m水平坑道見学会
11月12日(水)9:15〜12:00
場所:瑞浪超深地層研究所
定員:40名
※いずれも申込締切: 10月24日(金)
申込者が多数の場合は、先着順。入場無料(要事前申込)
http://www.jseg.or.jp/00-main/pdf/140930_kensyu_oshima.pdf
第161回深田研談話会「土木工学の新しい風〜住民たちの力を引き出す道直し活動〜」
11月14日(金)15:00〜17:00[14:30開場]
会場:深田地質研究所 研修ホール(文京区本駒込2-13-12)
定員:80名 参加費無料
http://www.fgi.or.jp/
国際シンポジウム“The International Symposium on Multidisciplinary Sciences on the Earth"「地球の学際科学」
11月18日(火)〜19日(水)
場所:東京大学本郷キャンパス 武田ホール(参加費無料.要申込)
http://thmat8.ess.sci.osaka-u.ac.jp/Meeting2014/
7th South China Sea Tsunami Workshop(第7回南シナ海における津波ワークショップ)
11月18〜19日: ポピュラーサイエンス関係のワークショップ
11月20〜21日: テクニカルプログラム関連のワークショップ
11月22日 : 視察
会場:台中(台湾)
国立自然科学博物館(ワークショップ)
台湾地震博物館、原子力発電所(視察)
参加登録締切:10月30日
http://www.bictam.org.cn/?p=594
第25回地質汚染調査浄化技術研修会 技術研修会
日本地質学会環境地質部会ほか 共催
11月21日(金)〜23日(日)
会場:NPO法人日本地質汚染審査機構本部ミーテング・ルーム・八千代市民会館
参加費:会員(地質学会員・社会地質学会員を含む)39,000円(学生:35,000円)
(CPD:22単位)
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
東京都葛西臨海水族園開園25周年記念講演会
子どもと生きもの-子どもと生きものをつなぐために動物園水族館ができること-
11月24日(月・祝)13:00〜16:15
場所:東京都葛西臨海水族園 本館2階レクチャールーム
http://www.tokyo-zoo.net/topic/topics_detail?kind=event&inst=kasai&link_num=22549
学術研究船白鳳丸研究計画企画調整シンポジウム
11月25日(火)〜27日(木)
場所:東京大学大気海洋研究所 講堂
申込期限:10月10日(金)
http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/coop/hakuho_28-30.html
(協)第30回ゼオライト研究発表会
11月26日(水)〜11月27日(木)
場所:タワーホール船堀(東京都江戸川区船堀4-1-1)
講演申込締切:8月8日(金)
予稿原稿締切:10月24日(金)
http://www.jaz-online.org/
(共)第24回環境地質学シンポジウム
11月28日(金)〜29日(土)
場所:日本大学文理学部8号館1階レクチャーホール
発表登録申込締切:10月18日まで
原稿登録締切:11月5日必着
http://www.jspmug.org/
東京地学協会国内見学会「榛名山ジオツアー・日本のポンペイを訪ねて」
11月29日(土)〜30(日)(1泊2日)
案内者:下司信夫・竹内圭史
http//www.geog.or.jp/
12月December
平成26年度「国土技術政策総合研究所 講演会」
12月3日(水)10:20〜18:00 入場無料
場所:日本消防会館(ニッショーホール)(東京都港区虎ノ門2−9−16)
http://www.nilim.go.jp/
第14回東北大学多元物質科学研究所研究発表会
12月5日(金)9:30〜20:00
場所:東北大学片平さくらホール
http://www.tagen.tohoku.ac.jp/general/info/event/meeting/2014/
地球化学研究協会「公開講座」および「三宅賞」受賞者の受賞記念講演
12月6日(土)14:20〜
場所:霞が関ビル35階 東海大学校友会館
(地下鉄銀座線虎ノ門・千代田線霞ヶ関下車)
参加費:賛助会員および学生は無料、一般1,000円(資料代を含む)、懇親会へも参加できます。
http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~e881147/Geochem/
本学術会議中国・四国地区会議公開学術講演会「産官学連携による地域活性化」
12月6日(土)13:30〜17:00
場所:くにびきメッセ大展示室(松江市学園南1丁目2番1号)
入場無料(要事前申込)
http://krs.bz/scj/c?c=149&m=21728&v=2b080d11
平成26年度(第13回) 産総研・地圏資源環境研究部門研究成果報告会
「進化する地圏研究 −第三期の成果と第四期への展開−」
12月9日(火)13:30〜17:00
場所:秋葉原ダイビル コンベンションホール(千代田区外神田1-18-13)
申込〆切:11月25日(火)
http://green.aist.go.jp/ja/blog/news_jp/20841.html
第162回深田研談話会「日本の地学教育と地学オリンピックの意義」
12月12日(金)15:00〜17:00[14:30開場]
会場:深田地質研究所 研修ホール(文京区本駒込2-13-12)
定員:80名 参加費無料
申込締切:12月10日(水)
http://www.fgi.or.jp/
バイオミネラリゼーションと石灰化 -遺伝子から地球環境まで-
12月12日(金)〜13日(土)
場所:東京大学大気海洋研究所 講堂
http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/aori_news/meeting/2014/20141212.html
関東大震災空撮写真展
12月14日(日) 〜 21日(日) 9:00〜17:00
場所:横須賀市自然・人文博物館 本館常設展示室
展示解説:14日 (日) 14:00〜15:00/21日 (日) 14:00〜15:00
http://www.museum.yokosuka.kanagawa.jp/archives/exinfo/20587
東京地学協会 第288回地学クラブ講演会
12月19日(金) 16:00~17:30
場所:アルカディア市ヶ谷
藤田勝代(深田地質研究所)「ジオ鉄マップとは? その事例研究」(仮題)
http//www.geog.or.jp/
ウインター・サイエンスキャンプ'14-'15
12 月21日 〜 2015 年1月7日の期間中、 2泊3日〜6泊7日
場所:大学、公的研究機関等 (9会場)
定員:会場ごとに12〜24 名 (合計168 名)
応募締切:10月24日(金)
http://www.jst.go.jp/cpse/sciencecamp/camp/
地質学史懇話会
12月23日(火・休)13:30〜17:00
場所:北とぴあ8階806号室:JR京浜東北線王子駅下車3分
財部香枝「スミソニアン気象観測プロジェクトと博物学研究との関わり」
小野田 滋「廣田孝一とその足跡−鉄道から電力へ−」
▶▶▶ 2015年版へ
2013年度各賞受賞者
2013年度各賞受賞者 受賞理由
■日本地質学会賞(1件)
■Island Arc賞(1件)
■小澤儀明賞(1件)
■柵山雅則賞(1件)
■小藤文次郎賞(1件)
■学会表彰(2件)
日本地質学会賞
受賞者:井龍康文(東北大学大学院理学研究科)
対象研究テーマ:琉球弧の第四紀石灰岩と海洋炭酸塩堆積物の堆積学的・地球化学的研究
井龍康文会員は,炭酸塩堆積物に関する堆積学的研究,造礁生物に関する古生物学的研究,炭酸塩生物骨格・殻に関する地球化学的研究において優れた業績を挙げてきた.井龍会員の代表的な研究成果として,琉球列島の第四紀サンゴ礁堆積物(琉球層群)に関する研究がある.井龍会員は,現在の琉球列島の現世サンゴ礁の生物相・堆積相についてフィールド調査と室内での精密な記載に基づく研究を行った上で,琉球層群を構成する石灰岩の岩相区分を確立し,堆積環境を決定した.それによって沖縄本島等の島々に分布する琉球層群の層序が確立され,サンゴ礁が汎世界的海水準変動と第四紀造構運動に規制されながら形成されてきた過程が詳細に復元された.これらの成果は国際的に高く評価され,国際陸上科学掘削計画(ICDP)による掘削が予定され,さらなる発展が期待されている.井龍会員は,環礁性堆積物の堆積・続成史に関する研究でも卓越した業績を挙げている.
特に,結晶学的手法と同位体地球化学的手法を組み合わせた独自の手法で,ドロマイトの晶出履歴と母液の化学組成・同位体組成を明らかにした成果は特筆に値する.井龍会員は,炭酸塩生物骨格・殻の炭素・酸素・ホウ素同位体組成および金属元素濃度を用いて,過去の表層海水温,塩分,pH等を高分解能で復元する研究にいち早く取り組み,現生・化石サンゴや現生シャコガイ殻から,後氷期の海水温や過去200年間のENSO(エルニーニョ・南方振動)を復元するなどの優れた業績をあげた.近年は,顕生代全般をカバーする優れたプロキシとされてきた腕足動物殻の炭素・酸素同位体組成に関する研究で,従来の研究を覆す結果を示し,世界的に注目されている.
以上の研究成果の多くが学生・院生の筆頭論文として公表されていることからわかるように,井龍会員は教育にも熱心に取り組み,多くの指導学生・院生が大学や地質学関連企業に勤務している.井龍会員は,統合国際深海掘削計画(IODP)やICDPに対して,学術面(IODP第310次航海共同主席研究者等)のみならず,運営面でも国内外の委員を歴任し,世界の地球掘削科学を牽引してきた.また,Island ArcやPaleontological Researchの編集委員長としての功績も大である.さらに,地質学会では執行理事等として学会に貢献してきた.
以上のような地球科学に対する大きな貢献に鑑み,井龍康文会員を日本地質学会賞に推薦する.
乙藤洋一郎(神戸大学大学院理学研究科)
対象研究テーマ:日本列島と大陸の変形を古地磁気学から探る
乙藤洋一郎氏の研究はアジア大陸が形を変える現象について年代学を加味し古地磁気学を用いて可視化したことにある.日本列島,ロシア沿海州,琉球弧,チベット高原,インドシナ半島,インドネシア島弧と研究領域は5000 kmに及ぶ.これまでの古地磁気研究では,花崗岩が研究対象であったが,それでは変動による傾きの補正ができない.この欠点を克服するため,乙藤氏は水平面が補正できる溶結凝灰岩に着目し,熱消磁を施すことで溶結凝灰岩生成時の古地磁気データを手にいれることに成功した.乙藤氏は主として中国地方および東北地方に露出する古第三紀以降の溶結凝灰岩を対象にして古地磁気研究を行い,プレートテクトニクスも取り入れ,嘗てアジア大陸東縁部にあった日本が中新世に背弧海盆を開きながら現在の日本弧に至ったモデルを提案した.背弧海盆の急激な開きは15 Maであり,西南日本弧と東北日本弧は二つの独立したブロックであったとし,日本列島では西南日本が時計回りに,東北日本が反時計回りに回転した可能性を指摘した.日本海の掘削データや動物地理学からもモデルの妥当性が追認された.岩石学・同位体地質学的情報から日本海の拡大を引き起こした原動力はアジア大陸東縁部に流入したアセノスフェアにあるとした.ロシア沿海州での古地磁気調査研究から背弧海盆拡大を伴うアセノスフェアの流入は後期白亜紀にも生じたとした.さらにチベット・インドシナ半島の研究から東チベットの40度時計回り運動を世界に先駆けて発見した.現在のインドシナ半島はアジアから押し出されながら時計回りに回転したこと,半径700 kmの曲率をもつメコン川の曲りは現在のオロクライナル屈曲であることを示した.古地磁気学から求めたチベットの回転運動とGPS から推測される回転運動の比較研究から,回転する変動域が南東に移動している現象を見出し,アジア大陸の変形変遷史を明らかにした.大陸が衝突すると大陸が形を変えるのはプレートテクトニクスの理論が及ばない現象である.乙藤氏の研究は,地球表層の3割を支配する大陸のテクトニクス研究への登竜門と言える.彼は堆積物の磁化獲得機構や地球磁場変動研究などから地質科学一般の発展にも貢献している.彼がこれまでに公表した多数の原著論文は多くの論文に引用されており,特に日本列島形成のモデルについての論文は被引用回数が多い.以上のように,乙藤洋一郎氏の業績は日本地質学会賞に十分に値するものであり,ここに推薦する.
日本地質学会Island Arc賞
受賞論文:Hattori Keiko, Wallis Simon, Enami Masaki and Mizukami Tomoyuki, 2010. Subduction of mantle wedge peridotites: Evidence from the Higashi-akaishi ultramaficbody in the Sanbagawa metamorphic belt. Island Arc, 19, 192-207.
The Higashi-akaishi ultramafic body is the largest garnet-bearing peridotites in the SambagawaMetamorphic Belt. Through mineral chemistry of coexisting phases and coupled thermobarometriccomputations, the authors have clearly and unambiguously documented the hanging-wall, i.e.,mantle wedge origin of the Higashi-akaishi peridotite; they have further chronicled its subsequenttectonic decoupling from the stable overlying plate and descent attending high-pressurerecrystallization along the subduction channel in traction with the downgoing paleo-Pacific oceanic lithosphere. This paper provides a good constraint to consider the genesis of the Sambagawametamorphic belt and an important insight into the not-well understood melting and tectonicprocesses in the wedge mantle, for which the article is highly evaluated. It will benefit not only theHP-UHP metamorphic petrologists but also a much broader scientific community involved insubduction zone research. The paper received one of the highest number of citations− based on the Thomson Science Indexfor the year 2012− amongst the entire candidate Island Arc papers published in 2010. The firstauthor has been active in the research of the behaviour of redox-sensitive metals and volatiles in avariety of settings such as subduction zones and the Archean Canadian shield, for more than 35 years. This paper adds to her many contributions and is a worthy recipient of the 2013 Island Arc award.
日本地質学小澤儀明賞
受賞者:尾上哲治(熊本大学大学院自然科学研究科)
対象研究テーマ:付加体の海洋性岩石を用いた地球環境変動に関する研究
尾上哲治会員は,陸上付加体のフィールドワークを基軸とし,これに古生物学的,堆積学的,および地球化学的手法を取り入れ,多角的な視点から地球史の解明に挑戦してきた.彼がこれまで研究を進めてきた三畳紀という時代は,95%以上の生物種が絶滅した古生代末の全球的環境変動の直後にあたり,大絶滅の後の生物界の再編過程を知り,地球進化史を包括的に理解する上で重要な時代である.彼は九州大学の博士課程在学中,三畳紀の大洋パンサラサ海の古海洋環境復元に着目し,三宝山帯付加体の海洋性岩石の起源・形成過程の解明を目指して研究を進め,2005年に地質学会奨励賞を受賞した.具体的には,九州〜四国の三宝山帯の詳細な地質図を完成させ,三畳紀における浮遊性生物の進化史と遠洋性堆積作用のリンクやパンサラサ海での二枚貝・サンゴ化石群集の古生物地理,遠洋性堆積岩の古地磁気層序など,幅広い研究成果をあげた.彼は上記の研究過程で,付加体中の深海底堆積岩中には大気圏突入時に溶融した宇宙塵が普遍的に含まれることを見出し,これを回収することに成功した.また放散虫化石層序から三畳紀の地球に降下した宇宙塵の組成と降下量を明らかにした.過去の地球に流入した宇宙物質の組成や降下量の時間変化を解明した研究例はこれまでなく,現在は宇宙塵から三畳紀の大気酸素に関する情報を得る研究を進めている.最近の尾上会員の特筆すべき成果として,後期三畳紀の天体衝突事件の発見がある.彼は美濃帯の上部三畳系チャートに挟まれた粘土層から,隕石衝突に起源をもつ球状粒子や白金族元素異常を発見し,これがカナダのマニコーガンクレーターに由来する可能性を示した.さらに,この隕石衝突が当時の生物にどのような影響を与えたかについて詳細に検討している.米国科学アカデミー紀要に掲載されたこの成果は,多くのメディアに取り上げられた.また,この研究の契機となった三畳紀隕石起源スピネルについての短報(佐藤・尾上,2010)が2012年に小藤賞を受賞した.
尾上会員は,これまで一貫して野外調査を基礎に据えており,その能力は第一級である.さらに,様々な分野の研究者を巻き込んで研究を進める能力を有し,国際的に活躍する優れた地質学者になることが期待される.近年細分化が進む地球科学分野にあって,彼が展開してきた幅広い分野にまたがる包括的研究は高く評価されるものである.以上の実績から,尾上哲治会員を小澤儀明賞に推薦する.
日本地質学会柵山雅則賞
受賞者:岡本 敦(東北大学大学院環境科学研究科)
対象研究テーマ:沈み込み帯における流体移動と水—岩石相互作用に関する岩石学的実験的研究
岡本 敦氏は,沈み込み帯における水循環とそれに伴う水−岩石相互作用を理解するために,特に変成岩について変成反応の進行度・不均質性の評価法を確立した.東京大学大学院生時代に発表した四国中央部別子地域に分布する三波川変成帯塩基性片岩中の角閃石の組成累帯構造にギブス法(微分熱力学法)を適用した研究は,それまでの断続的な温度圧力経路の推定から確固とした連続的な温度圧力経路を天然の岩石で定量的に示した点で画期的であった.岡本氏の研究以降,天然系における鉱物の化学組成から温度,圧力,反応量,そして物質の移動量などの逐次変化を逆問題として解くことが可能になり,海洋地殻の沈み込み帯における脱水,吸水量の時間的変化が求められるようになった.さらに静岡大学博士研究員時代に,東南極リュッツォーホルム岩体の高変成度珪岩のざくろ石の粒径と形態分布が変形ステージとやきなましステージの2段階で説明できることを定量的に明らかにした.この研究では,不完全であった鉱物包有物の変形機構を記述する従来の二次元モデルを三次元モデルまで拡張し,鉱物包有物の変形機構が細粒な包有物では拡散過程の効果が高くなるのに対して粗粒な包有物では転位クリープが大きく効くことを発見した.この業績は,鉱物の粒径と形態という地質学的に観測しやすい指標を用いて天然の岩石のレオロジーを理解する道筋を与えた点で秀逸であった.さらに,鉱物包有物研究から地球内部レオロジーを推定する方法を開拓したことによって,岡本氏の研究対象である地殻内部だけでなくマントル研究にもインパクトを与えるほど応用範囲は広い.また,本研究は岡本氏の専門の岩石学ではない岩石のレオロジー研究であったにもかかわらず,静岡大学在任中の短期間で仕上げた高い力量と柔軟な発想力そして展開力は,その後現在まで随所で発揮されている.東北大学に研究拠点を移してからの岡本氏は,地殻内部の流体移動経路として変成岩に残されている石英脈に着目し,その組織から小脈中を上昇した流体の速度を求めることに成功した.この研究以前は地殻深部における流体の挙動については定性的な推論が主流であったが,岡本氏の研究によって流体と岩石の相互作用に関して定量的な考察が可能になった.最近では,海洋リソスフェアにおける蛇紋岩化作用の研究に取り組んでおり,地球深部に持ち込まれる水の貯蔵プロセスの解明が期待されている.
以上のように,岡本敦氏はその初期の研究から現在までいずれの研究においても優れた理論的考察と鋭い洞察力が遺憾無く発揮されており,優秀な業績をあげている若手研究者として柵山雅則賞に推薦する.
日本地質学会小藤文次郎賞
受賞者:森田澄人(産業技術総合研究所)・中嶋健(同)・花村泰明(JX日鉱日石開発(株))
受賞論文:森田澄人・中嶋 健・花村泰明,2011,海底スランプ堆積層とそれに関わる脱水構造:下北沖陸棚斜面の三次元地震探査データから.地質学雑誌, 117, 95-98.
本論文は,下北沖において三次元地震探査で発見された,巨大なスランプ層に関する報告である.陸棚斜面を構成する新第三系鮮新統・第四系中には,見事な覆瓦状構造と平行砂屑岩脈群が,差し渡し10 kmを越える広大な領域に形成されていることに驚かされる.これほど大規模なスランプ層は,これまで我が国の陸上地質に見いだされていない.同様の大規模なスランプ層は,大陸縁などですでに発見されているとのことだが,日本近海で発見されたということは,我が国の陸上に露出する地質時代の地層の構造の解釈においても同様の構造が存在する可能性を考慮すべきであることが,本論文で明確に示されたことになる.また,マップスケールで発達する断層などの規則的構造が1°足らずの緩斜面で形成されたことは,海底地すべりは必ずしも安息角を超える急斜面に形成されるわけではないという最近の説を裏付ける新しい発見である.このことは,陸上の地域地質から広域テクトニクスを考える難しさを示している.
以上,本論文はこれまでの地質学的常識を覆すような新発見であり,革新的な事実をもたらした論文に授与されるという小藤文次郎賞の趣旨に良く合致することから,同論文を受賞対象論文として推薦する.
日本地質学会表彰
受賞者:岡村 眞(高知大学総合研究センター)
表彰業績:地震・津波研究の新分野開拓と普及教育活動
岡村眞氏は,活断層および津波堆積物の新しい試料採取システムを独自に開発して,地震地質学を切り開いてきたパイオニアであり,またその研究の成果を基にした防災教育を熱心かつ長年に渡って実施してきた.活断層研究においては,従来の陸上トレンチ調査よりも海底調査の方が地層記録の連続性において優位であることを見抜き,深海の地質試料採取に用いられてきたピストンコアラーが浅海活断層調査に有用であると考え,国内最長級の21m連続試料が採取可能な改良型ピストンコアラーを自ら製作して,これを浅海域の中央構造線活断層系の調査に活用し,高時間分解能の断層活動履歴研究の分野に道を開いた.また,太平洋沿岸域の淡水から汽水の湖沼に,南海トラフ沿いの巨大津波堆積物が保存されているであろうと考え,従来は採取が難しかった泥質および砂質の互層を乱さずに採取するためのバイブロコアラーを独自に開発した.これを小型ボートによる浮体式の櫓に設置し,大型船が入れない小さな湖沼でも調査できるサンプリングシステムを確立し,津波堆積物を次々に発見してきた.その成果は政府の津波防災計画に反映されるものとなった.これらの研究における着眼点,手法開発,その成果はいずれもユニークでまさに地質学の新しい地平を切り開いたパイオニアと言えよう.その先見性と調査システムとして優れた研究成果は,世界からも注目されており,これまでにも米国西海岸,トルコ,ベトナム,ネパールなど7ヶ国に上記の調査システムを持ち込んで,共同研究を実施してきている.さらに,同氏は地震・津波防災における普及教育活動にもたいへん熱心であり,この10年間に地元の高知県を始め16都道府県において995回もの普及講演会を実施している.小規模なものであれば十数人程度の集会から,大規模なものであれば数百人のものまで,集会の大小を問わず懸命に津波防災の重要性を説いて回っており,将来の津波災害の被害低減のために尽力している.
以上,斬新な研究手法の開発と献身的な防災教育活動は日本地質学会表彰に相応しく,ここに推薦する.
受賞者:静岡県袋井市(代表者 市長 原田英之)
表彰業績:地層保全を活かす市民公園の先駆的取り組み
静岡県西部の丘陵を構成する鮮新−更新統掛川層群は,貝化石を多産し,浅海〜深海までの層相が連続的に分布することから,地質学的・古生物学的研究が数多くなされてきた.その貝化石群は掛川動物群と呼称され,当時の古黒潮流域に繁栄した暖流系動物群の模式として有名である.しかしながら,開発による露頭消滅などで,市民がそのような地質遺産を実感できる機会は失われつつあった.ジオパーク設立の勢いに象徴されるように,露頭の保護や整備は日本各地で進行中であるが,新第三系や第四系からなる丘陵地の場合,風化や植生被覆,露頭の小規模性など,行政がその意義を意識しなければ,露頭はありふれたものとして失われやすい状況にある.
袋井市は,このような露頭を保全・活用した宇刈里山公園を整備し,2012年5月にオープンさせた.公園では地層断面をはじめ,生の自然を展示・活用して,市民が里山の自然史を意識できるよう工夫がこらされている.公園入口には,宇刈層の断面が保全され,足元の地下の様子を実感しながら,貝化石や生痕化石,ハンモック状斜交層理,断層などから,大地の成り立ちを学べるよう観察ポイントが示されている.公園内に設置された貝化石密集層のブロック標本では,化石産状の観察を通して200万年前の温暖化した海の様子を推定させ,メタセコイアの植樹コーナーでは産出した植物化石もあわせて解説し,当時の陸上の様子を思い描けるようストーリー性ある構成となっている.市民の憩いの場であると同時に,学校や市民団体も見学に訪れ地学教材としても大いに活用されている.静岡県の丘陵地には,古刹をはじめとする歴史遺産や風習,なだらかな地形を利用した茶畑など,自然と文化・生活とが融合した日本独自の里山環境が成立している.このような身近な丘陵地の地質学的な成り立ちを深く知ることは,日本人の自然観を育む上で重要な鍵となる.袋井市は,公園整備に至る過程で地元自治会とワークショップを繰り返し,地域の地質遺産を住民とともに再発見していったが,この点でも地質学を社会に浸透させる一つのモデルケースを提示している.我々は得てして雄大な自然景観や,貴重で珍しいという価値に目を奪われがちであるが,今回の袋井市の地道な活動は身近で小規模な露頭を保全することの大切さを示した先駆的な取り組みとして高く評価され,今後の波及効果は大きいと予想される.以上の理由により,日本地質学会表彰に値すると考え,ここに推薦する.
2014年度各賞受賞者
2014年度各賞受賞者 受賞理由
■日本地質学会賞(2件)
■国際賞(1件)
■小澤儀明賞(2件)
■Island Arc賞(1件)
■論文賞(1件)
■小藤文次郎賞(1件)
■研究奨励賞(3件)
■学会表彰(1件)
日本地質学会賞
受賞者:川幡穂高(東京大学大気海洋研究所)
対象研究テーマ:気候変動に対応した過去・現代の炭素を中心とする物質循環に関する地化学的研究
川幡穂高会員は,気候変動に対応した過去・現代の炭素を中心とした物質循環に関する地化学的研究において優れた業績を挙げてきた.地質学と気候学・海洋学を化学という視点でつなぐ研究の先駆者である.外洋における堆積粒子の主な起源は沈降粒子で,セジメントトラップ係留観測を太平洋の広範囲(46°N〜35°S)に展開して気候,海洋表層環境,沈降粒子の関係を解明し,赤道域ではENSO(エルニーニョ・南方振動)と沈降粒子の関係を初めて明らかにして,それらの結果を第四紀や中・古生代の古環境解析に適用した.特に,大気経由の物質輸送として重要な風送塵について,気候変動に対応した半定量的解析を初めて行った.
生物起源炭酸塩は,物質循環とともに同位体・化学組成に基づく定量的解析に重要である.サンゴ礁生態系における二酸化炭素の放出を定量的に評価するとともに,二酸化炭素の増加による海洋酸性化に対する,炭酸塩殻を有する生物の応答を調べるため新しい室内精密飼育実験法を開発するとともに,生物起源炭酸塩の古環境定量間接指標のプロセス解析を行ってきた.現在,白亜紀を対象とした古環境復元とオマーン・オフィオライトの熱水活動の分析を統合するなど,固体地球と表層環境との繋がりについて,新しい分野を開拓している.
以上の研究成果の多くは,筆頭著作とともに院生を含む研究室の共著論文として公表されており,個人の研究とともに教育やコミュニティの共同研究にも熱心に取り組んできた.これまでに十数名の博士を誕生させるとともに,多くの指導院生が大学,官庁,企業に勤務している.
川幡会員は,オマーン・オフィオライトの学術調査を初めてアレンジし,国際全海洋研究(IMAGES)ではマリオンデフレンヌ航海の主席研究者を務めて日本の古環境研究の発展に貢献し,統合国際深海掘削計画(IODP)においては日本地球掘削科学コンソーシアムIODP部会長を2度,及び種々の国際委員を勤め,世界の掘削科学の発展にも貢献してきた.日本地質学会では代議員を務め,日本地球惑星科学連合理事・副会長として,日本全体の地球科学への功績も大きい.日本地質学会と関連する国内外の学会や連合との懸け橋として,これからも活躍が期待される.以上のような地質学,海洋学,地球化学,環境科学など幅広い分野の優れた業績と地球科学全体に対する大きな貢献に鑑み,川幡穂高会員を日本地質学会賞に推薦する.
斎藤文紀(産業技術総合研究所地質情報研究部門)
対象研究テーマ:沿岸堆積システムと沖積層の地層形成に関する現行地質過程的研究
斎藤文紀会員は,沿岸域における海洋堆積物や沖積層の地層形成に関する現行地質過程的研究において先導的な研究を行ってきた.斎藤会員は,自身の研究にいち早くシーケンス層序学視点を導入し,日本における浅海堆積学や沖積層研究の進展や普及に大きな貢献をしてきた.大陸棚から大陸棚斜面を覆う海進砂層は,世界で初めて仙台沖の研究で示され,また沿岸堆積システムの観点から沖積層の発達過程を明らかにした研究は,沖積層研究の新たな展開を切り拓いた.
しかし,斎藤会員の最も大きな貢献は,アジアのデルタ,沖積層に関する研究である.デルタの研究は,1990 年代までは欧米が中心でミシシッピ河やナイル河の研究が中心であった.斎藤会員は,1990 年代後半から,世界を代表する黄河,長江,紅河,メコン河,チャオプラヤ河,ゴダバリ河デルタにおいて,現在の堆積過程とボーリングによる堆積学的な研究を推進し,これらの地域の沖積層模式層序を確立するとともに,デルタの詳細な層相と発達過程を明らかにした.それらの研究では,デルタの堆積作用や成長過程が,数千年オーダーから季節変化まで,様々な時間スケールで明らかにされ,完新世のデルタ形成に関する新たなモデルが提示された.これにより,世界のデルタ研究は大きく進展した.さらに斎藤会員は,近年の人間活動のデルタへの影響に関する研究を推進することによって,デルタの環境保全に関する研究も推進している.また斎藤会員は,IGCP-475 等のプロジェクトを主導するとともに,国際デルタ会議をアジア各地で開催し,世界のデルタ研究の発展やアジア地域の研究の推進や人材育成に大きく貢献してきた.現在,堆積地質学の面からだけでなく,地球環境問題と関連した面から,多くのデルタ研究が行われているが,斎藤会員は,その潮流をつくり,世界のデルタ研究を牽引してきた一人である.
海外の学会等における招待講演を行っていること,多くの国際学術誌の編集委員となっていること,海外の教科書においてデルタの章の著者となっていることは,斎藤会員が国際的に評価されていることを示している.また斎藤会員の論文や著書の被引用数の多さは,研究レベルの高さと堆積地質分野に対する強い影響力を象徴している.以上のような地質学,堆積学,環境科学など幅広い分野の優れた業績と地球科学全体に対する大きな貢献に鑑み,斎藤文紀会員を日本地質学会賞に推薦する.
日本地質学会国際賞
受賞者:江 博明 (JAHN, Bor-ming)(国立台湾大学)
対象研究テーマ:地球惑星物質の地質年代学,同位体・微量元素地球化学,地殻進化の研究
江 博明氏は,地質年代学,同位体地球化学,地殻進化の研究において,それらの分野を世界的にリードするとともに,数多くの日本人地質研究者と学術交流し,日本の地質分野の人材育成と教育にも大きく貢献した.
江氏は国立台湾大学(台湾大)で学位取得後,ブラウン大学,ミネソタ州立大学ミネアポリス校において,それぞれ地球化学の修士号,博士号を取得した.その後,米国航空宇宙局有人宇宙機センター(現,ジョンソン宇宙センター)及び月科学研究所に在職し,月試料分析に携わりながら,太古代花崗岩・コマチ岩の地球化学的研究を展開し,分析法開発に携わった.その後,レンヌ第一大学に27 年間在職して,研究と教育に携わり,多数の後継者を輩出した.2003 年に台湾大に移り,続いて2004 年に中央科学院地球科学研究所所長に抜擢され,台湾の地球惑星科学分野の国際的飛躍に大きく貢献する一方で,日本から若手研究者を積極的に受け入れて国際舞台への進出を援助した.所長職を退いた2010 年以後も,台湾大において後輩の教育に尽力するとともに,Jour. Asian Earth Sci.誌編集長をはじめ,Island Arc 誌編集顧問などを務め,アジアの地質学分野の発展に大きく貢献している.
江氏は,これまでに約240 編の論文を公表し,15 編の学術誌特集号を編集した.被引用数が1 万件を超える著者の一人である.彼は,北中国地塊において約38 億年前の最古の地殻構成岩を発見した.中央アジア造山帯の花崗岩類の研究に取り組み,顕生代の付加型造山に伴って大規模地殻形成があったことを見いだした.花崗岩研究は日本列島にも及ぶ.地質学への貢献はアジアだけにとどまらず,太古代コマチ岩の希土類元素による分類の他,彼の研究によって,トーナル岩−トロニエム岩−花崗閃緑岩の組み合わせ「TTG」が地質用語として確立した.
以上のような長年の学術的功績により,彼は4 つの国際学会でフェローの称号が認められており,中国国内の9 つの研究所で名誉教授の称号を授与されていて,2012 年には台湾中央研究院の院士に選ばれた.また,2008 年にフランス教育省から騎士勲章を授与され,2013 年にはフランス地質学会Prestwich 賞を受賞した.これらの学術的業績とアジア諸国および日本の地質学コミュニティーにおける人材育成への大きな貢献に鑑み,江博明氏を日本地質学会国際賞に推薦する.
日本地質学小澤儀明賞
受賞者:菅沼悠介(国立極地研究所地圏研究グループ)
対象研究テーマ:海底堆積物における古地磁気記録獲得機構と地磁気逆転年代の高精度化に関する研究
菅沼悠介会員は,地球変動史を中心とする広い分野で多くの成果を挙げてきた.古地磁気学や年代層序学を基軸としながら,常に新たな研究手法を取り入れ,新しい研究分野に挑戦し続けている.
菅沼会員の特筆すべき成果は,海底堆積物における堆積残留磁化の獲得メカニズムの解明である.堆積物に記録される地磁気逆転や地磁気強度変動は,汎地球的な同時間面として地層対比や編年などに広く利用されてきた.堆積残留磁化の獲得メカニズムの研究では,粒子が堆積した時刻と粒子の磁化が地球磁場の方向に向いた時刻との間に時間差があることが認識されていた.この時間差を明らかにする方法を菅沼会員は新たに開発した.地球磁場逆転時には,地球磁場強度が低下しそれとともに堆積物の残留磁化の強度が減少するという事象と,10Be フラックスの増大が磁場強度低下により起こるという二つの事象を結びつけた.菅沼会員はBrunhes–Matuyama の地磁気逆転期の二つの事象を観察し,残留磁化の低下した堆積物の堆積深度と10Be フラックスの増大の堆積深度のあいだに有意な違いがあることを発見した.そして,この時間差からBrunhes–Matuyama 地磁気逆転境界年代値が,従来推定されていた年代より1万年程度若い約77 万年前であることを突き止めた.さらに,これらのデータの解析に基づき,海底堆積物における堆積残留磁化の獲得は,従来の想定である堆積物の圧密・脱水過程では説明できず,むしろ生物学的・化学的プロセスのような全く異なるメカニズムが働いている可能性を示した.これらの研究は国際誌に発表されるとともに,国内誌にもレビュー論文として報告され,大きな注目を集めている.菅沼会員はこの他にも,太古代チャート層の精密古地磁気測定に基づく約35 億年前の高速大陸移動の証拠発見や,地磁気強度変動を用いたCCD 以深の海底堆積物の年代決定に基づく東南アジアモンスーン変動の復元など,幅広い分野で成果を挙げている.
菅沼会員は,南極観測隊員として3 度南極観測に参加し,東南極氷床変動メカニズムの解明に取り組んでいる.また,日本掘削科学コンソーシアム(J-DESC)の陸上掘削部会執行部委員やANDRILL(南極地質掘削計画)の日本代表を務めるなど,分野発展への貢献も大きく,今後の幅広い活躍がいっそう期待される.以上の実績を高く評価し,菅沼悠介会員を小澤儀明賞に推薦する.
受賞者:田村 亨(産業技術総合研究所地質情報研究部門)
対象研究テーマ:統合的な手法による沿岸域の地層と地形形成に関する研究
田村 亨会員は,堆積物の層相解析,高精度粒度分析装置による粒径分布特性値の高分解能解析,地中レーダーによる地下浅層断面の高精度可視化と堆積形態の3 次元解析,石英粒子の光ルミネッセンス法(OSL)による年代測定など,近年急速に進展した分析・解析手法を巧みに統合することで,堆積過程や地形形成の3次元的変動様式を数10 年オーダーの時間の分解能で議論できる地質学研究の高精度化の手法を構築してきた.この手法により,人間活動に大きな影響を与えている短期間で発生を繰り返す環境変動にともなった平野や砂丘などの拡大・縮小様式の実体を詳細に解明することが可能となった.このような一連の研究成果は国際学術雑誌などを通して国内外へ広く発信され,多くの引用が行われている.さらに,これまでの研究成果は,メコンデルタのような地球温暖化にともなって今後人間活動に大きな影響を及ぼすと懸念されている海浜域の拡大・縮小傾向の将来予測などを高分解能で解析するための新たな研究戦略の展開へと発展することが期待される.
これまでの主な研究内容は以下のようにまとめられる.日本を代表する浜堤平野の九十九里浜平野と仙台平野において,ボーリングコア試料に基づく堆積システムの層相の相違と全粒度構成の各層相への粒径配分の不均衡を見積もることによる地層解析の新たな手法を提示した.また,ボーリング調査と地中レーダー調査を統合させ,特定の層相境界部が海水準の良い指標になることを明らかにし,層相の断面分布や平面分布から地震による断続的な隆起傾向や隆起速度の変化を明らかにした.鳥取砂丘では,地中レーダーとコア試料のOSL を用いて,砂丘の発達が冬季のモンスーン変動に大きく影響されてきたことを明らかにした.さらに,メコンデルタでは,海浜の地形と堆積物の季節・年変化をモニタリングすることにより,その形成がモンスーンに大きく影響されていることや,浜堤列堆積物のOSL 年代から数10〜数100 年の時間スケールでの浜堤列の発達の規則性を明らかにした.
このように田村会員の研究は,沿岸域での堆積学や地形学の世界最先端の研究に留まらず,テクトニクス,古気候,海岸保全など他分野へも大きく貢献してきており,今後は日本地質学会の将来を担う若手研究者として国際的な活躍が期待される.以上の実績を高く評価し,田村 亨会員を小澤儀明賞に推薦する.
日本地質学会Island Arc賞
受賞論文:Dapeng Zhao, M. Santosh and Akira Yamada, 2010. Dissecting large earthquakes in Japan: Role of arc magma and fluids. Island Arc, 19, 4–16
Dr. Zhao and the co-authors have tried to clarify causal mechanisms of large earthquakes in the Japanese Islands using high-resolution tomographic images of the crust and uppermost part of the mantle beneath the mainshock hypocenters of the large earthquakes during 1995 to 2008. They have found that the large earthquakes, as well as 164 additional crustal earthquakes, have occurred along low-velocity zones with high Poisson’s ratio anomalies, which are considered to be represented by arc magma and fluid. The finding indicates that the generation of a large earthquake is not entirely a mechanical process, but is closely related to the physical and chemical properties of materials of the crust and upper mantle, such as magma and fluids, which are produced by a combination of subducting slab dehydration and corner flow in the mantle wedge. Furthermore, the authors have pointed out that the rupture nucleation zone should have a three-dimensional spatial extent and is not just limited to the two-dimensional surface of a fault as suggested by the previous studies. The outcome of this study should contribute to a better understanding of the origin and mechanisms of large earthquakes and also be indispensable for the mitigation of large earthquake-related disasters in the future.
This paper received the highest number of citations–based on the Thomson Science Index for the year 2013–amongst the entire candidate Island Arc papers published in 2010–2012. The first author has been active in the research of seismic tomography and the effects of fluids and magma on earthquakes. This paper adds to his many contributions and is a worthy receipt of the 2014 Island Arc Award.
日本地質学会論文賞
受賞論文:田辺 晋・石原与四郎, 2013, 東京低地と中川低地における沖積層最上部陸成 層の発達様式:“弥生の小海退”への応答. 地質雑, 119, 350-367.
本論文は,いわゆる「弥生の小海退」の存否を明らかにするために,東京低地と中川低地の15 本のボーリングコアの沖積層最上部陸成層の層相解析と放射性炭素年代測定を行い,既存の7021 本におよぶ柱状図資料も用いつつ,堆積相・生物相・N 値などに基づき,最上部陸成層の発達様式を検討したものである.その結果,最上部陸成層に砂嘴・デルタフロント・干潟・河川チャネル・氾濫原の5 つの堆積相が識別され,首都圏の地盤沈下の影響などを補正した上で,それぞれの3 次元分布が精緻に描きだされた.これら各岩相,とくに河川チャネル・氾濫原堆積物の標高分布などから,3 千年前に海水準が低下した,すなわち「弥生の小海退」があったことが確認された.復元された古地理や地形発達史は説得力のあるものとなっており,ハイドロアイソスタシーやテクトニクスを含めて,本論文は今後の沿岸河口低地における研究に問題を提起するものともなっている.また,この成果は考古学分野などにも貢献するであろう.以上のことから,本論文は地質学雑誌掲載論文として優れたものであり,地質学会論文賞に値する.
日本地質学会小藤文次郎賞
受賞者:野崎達生(海洋研究開発機構・地球内部ダイナミクス領域)
受賞論文:Nozaki, T., Kato, Y. and Suzuki, K., 2013, Late Jurassic ocean anoxic event: evidence from voluminous sulphide deposition and preservation in the Panthalassa. Scientific Reports, 3, 1889, doi: 10.1038/srep01889.
三波川変成帯には別子型鉱床が数多く点在するが,二次的に三波川変成作用を被っているために,その形成時期・成因については明らかにされてはいなかった.本論文は,三波川変成帯に分布する11の別子型鉱床についてRe-Os 同位体年代を求め,これら鉱床が約150Maに生成したことを明らかにした.さらに,この年代が過去3億年間における海洋のSr87/Sr86比が最も低く,大気中のCO2濃度が最も高い時期に一致していることに着目し,中央海嶺における活発な火成活動による大気中のCO2 濃度の上昇,それに伴う地球温暖化と極域の氷床の消滅,それが引き起こす海洋大循環の停滞と還元的海洋の発達,結果としての硫化物鉱床の生成・保存,という一連の地学現象により,別子型鉱床の成因を説明した.本論文は付加体中の別子型鉱床の成因が古海洋環境変動と密接に関連することを示した独創的で優れたものである.また,従来あまり認知されてこなかったジュラ紀後期における海洋無酸素事変の存在を示唆しており,日本列島の地質を研究対象としつつ,グローバルイベントを提唱している点でも,高く評価できる.以上の理由から,本研究を中心として推進してきた野崎達生会員は小藤文次郎賞に相応しい.
日本地質学会研究奨励賞
受賞者:細井 淳(茨城大学大学院理工学研究科)
対象論文:細井 淳・天野一男,2013,岩手県西和賀町周辺奥羽脊梁山脈における前期〜中期中新世の火山活動と堆積盆発達史.地質学雑誌,119, 630–646.
本論文は,日本海拡大期から拡大直後にかけての砕屑岩と水底火山岩類を対象に,丹念な野外調査にもとづく堆積相解析によりグラーベンの埋め立て過程を推定したものである.研究対象地域はグリーンタフの一連の層序が見られる古典的なフィールドで,かつては多くの研究者の巡検ルートとなっていた地域であり,ここでの前期〜中期中新世の火山活動を伴う堆積盆発達史の解明は東北日本のグリーンタフ地域の発達史の解明に大きく役立つものと考えられる.古くから研究されてきたフィールドではあるが,火砕岩の変質が激しく岩相の側方変化も大きいことから,層序を理解することが容易ではなかった.この困難を克服するには水底火山岩類の構造と堆積相の理解が不可欠であるが,本研究はその観点を取り入れて層序を再検討し,水底火山活動と堆積過程の解釈をわかりやすいモデル図も併用して明示している.本研究は,いまだに課題の多いグリーンタフの新たな展開を期待させる優れたものと言える.以上の理由により,細井 淳会員を研究奨励賞に推薦する.
受賞者:上久保 寛(石油天然ガス・金属鉱物資源機構資源探査部)
対象論文:Kamikubo, H. and Takeuchi, M., 2011, Detrital heavy minerals from Lower Jurassic clastic rocks in the Joetsu area, central Japan: Paleo-Mesozoic tectonics in the East Asian continental margin constrained by limited chloritoid occurrences in Japan. Island Arc, 20, 221-247.
著者らは,上越地域の下部ジュラ系岩室層から砕屑性クロリトイドを発見した.同様の砕屑性クロリトイドは,これまで南部北上帯および美濃帯のジュラ系のみから得られている.また,先ジュラ系において変成クロリトイドは,日本列島のペルム紀—三畳紀の中圧型変成岩である飛騨,宇奈月,竜峰山および日立変成岩にのみ産出が知られていることを文献調査により明らかにし,これらの変成岩は中央アジア造山帯と北中国地塊の衝突帯で形成されたと推定した.さらに,クロリトイドは大陸地域の古土壌が変成作用を被って形成されると考えられので,日本のクロリトイドを含む変成岩は石炭紀—ペルム紀の受動的大陸縁の堆積物を原岩として形成されたと類推した.以上から,著者らはペルム紀に火山弧に位置していた古日本列島は,その後三畳紀に中圧型の変成岩が形成される衝突帯となり,ジュラ紀になって削剥が進み,クロリトイドが砕屑物として供給されるようになったという,ダイナミックな地質構造発達史を構築した.引用文献だけでも8ページに及ぶ本論文は,広く日本列島のジュラ紀の地層を文献調査した意欲的なレビュー論文でもある.これらの膨大な作業により数粒のクロリトイド粒子から日本列島の地史について大胆な推論を描き出した本論文は,地質学が大変夢のある研究分野であることを示した.以上のような優れた成果を挙げた上久保 寛会員は研究奨励賞に値する.
受賞者:武藤 潤(東北大学大学院理学研究科地学専攻)
対象論文:武藤 潤・大園真子, 2012, 東日本太平洋沖地震後の余効変動解析へ向けた東北日本弧レオロジー断面. 地質学雑誌, 118, 323-333.
本論説は,地殻変動の理解に不可欠な地殻とマントルのレオロジー構造を推定し,東北日本の変動現象,特に大地震後の余効変動との関わりについて,定量的視座を提供する包括的研究である.具体的には,まず東北日本弧横断方向の2 次元レオロジー強度断面を,地震波速度構造,地殻熱流量,測地学歪データ等の地球物理学的観測,岩石−温度構造モデル,および近年の実験岩石力学の結果に基づいて推定した.さらに,得られた強度断面と,地震前後の擾乱から推定される応力変化量に基づき,東北日本弧の粘性構造を推定し,余効変動解析に重要な弾性層厚と粘性率が島弧横断方向に著しく不均質である可能性を指摘した.これらの成果は,沈み込み帯の地震サイクル,特に巨大地震の再来周期を評価する際の基礎となり,地質学にとどまらず地震学,測地学および地震防災対策等にも貢献するという点で社会的にも重要な優れた知見である.よって武藤 潤会員は研究奨励賞に値する.
日本地質学会表彰
受賞者:西岡芳晴(産業技術総合研究所地質情報研究部門)
表彰業績:シームレス地質図配信システムの構築
20 万分の1 日本シームレス地質図は、日本全体を統一凡例で繋ぎ目なく表した最も大縮尺のデジタル地質図である.西岡芳晴会員は,最新のインターネット技術を積極的に導入し,当該地質図の高速で地質情報に適した配信技術を独自に開発した.とくに,画像タイル配信技術「スマートタイル」を用いたWeb サイトでは,高速で直感的な操作性を実現するとともに,画像配信にもかかわらず,あたかも凡例ごとの検索表示のような操作性を実現しており,他国の地質図配信システムと比較しても,群を抜いて優れたシステムである.これによって,大学・地質コンサルタント業界のみならず,一般の地質に興味ある方々などにも利用者層を大きく広げた.当該地質図は,使い勝手の良さから,現在,日本の地質を理解する上でなくてはならないものになっており,アクセス数は2013 年までの3 年間でおよそ20 倍に増加している.西岡氏の研究開発は,地質図の活用場面を飛躍的に広げ,地質学の社会への普及に大きく貢献しており,日本地質学会表彰にふさわしい.
Geo暦(2015)
2015年Geo暦(行事カレンダー)
2013年版 2014年版 2015年版 2016年版
2015年版 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
○印は学会主催行事.(共)学会共催・(後)後援・(協)協賛
1月January
(後)北淡国際活断層シンポジウム2015
1月12日(月)〜 17日(土)
場所:兵庫県淡路市 兵庫県立淡路夢舞台国際会議場
ポスター発表申込締切:12月14日(日)21日[締切延長]
宿泊申込締切:12月28日(日)
http://home.hiroshima-u.ac.jp/kojiok/outline01j.html
防災・減災に関する国際研究のための東京会議
1月14日(水)〜16日(金)
参加登録締切:2014年12月14日
http://monsoon.t.u-tokyo.ac.jp/AWCI/TokyoConf/jp/index.htm
第23回地質調査総合センターシンポジウム
1月16日(金)13:00〜18:10(開場:12:00)[参加無料]
会 場:東京秋葉原ダイビル 2F秋葉原コンベンションホール
(東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル2階)
参加登録 :https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo23/index.html
*CPD単位認定(CPD希望の方も事前参加登録をお願いします。)
問合わせ先:第23回地質調査総合センターシンポジウム事務局
E-mail: gsjsympo23-ml@aist.go.jp
JST-ISSC-NRF共催国際シンポジウム “Transformations to Sustainability”
1⽉29 ⽇(⽊)13:00〜17:00
会場:国連⼤学 ウ・タント国際会議場(東京都渋⾕区神宮前5-53-70)
定員:300名(参加費無料)
http://www.ristex.jp/eventinfo/FE/index.html
第2回全国海洋教育サミット
1月31日(土)〜2月1日(日)
会場:東京大学・本郷キャンパス・弥生講堂
参加費無料
http://rcme.oa.u-tokyo.ac.jp/events/post847.html
2月February
第163回深田研談話会
「メタンハイドレート 資源開発の現状と今後の展開」
2月13日(金)14:00〜16:00 ※いつもより1時間早くなります。
申し込み締切:2/10 先着:80名 参加無料
会場:深田地質研究所 研修ホール(文京区本駒込2-13-12)
http://www.fgi.or.jp/
平成26年度海洋情報部研究成果発表会
2月13日(金)
場所:海上保安庁海洋情報部
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KIKAKU/press/2015/H270114_kenkyu.pdf
○西日本支部:平成26年度総会・第166回例会
2月21日(土)[20日:幹事会]
場所:山口大学,吉田キャンパス,大学会館
講演申込締切:2月4日(水)17時
*総会へ欠席の方は,委任状をお送り下さい。
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
第171回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
2月27日(金)18:30〜20:30 [事前予約不要]
場所:北とぴあ901会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分)
講師 :安井真也氏(日本大学文理学部地球システム科学科 准教授)
テーマ :浅間火山の噴火と北関東・利根川下流域・首都圏の災害
CPD:2単位
会費:会員、地質学会会員は500円、非会員は1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
第10回海と地球の研究所セミナー
有人潜水調査船「しんかい6500」完成25周年
2月28日(土)13:30〜16:30
場所:神戸海洋博物館
参加無料、事前登録制、限定250名
http://www.jamstec.go.jp/j/pr/pr_seminar/010/
3月March
(後)Project A 2015 in Korea
3月4日(水)〜8日(日)
4日オープニング、5日セッション、6〜8日巡検
会場:韓国 大田広域市
アブストラクト締切:1月23日(金)
http://archean.jp/
平成26年度研究報告会「JAMSTEC2015」
3月4日(水)13:00〜17:30
会場:東京国際フォーラム ホールB7(東京都千代田区丸の内3-5-1)
http://www.jamstec.go.jp/j/pr/event/jamstec2015/
学術フォーラム「科学を変えるデータジャーナル−科学技術データの共有・再利用の新たなプラットフォーム構築に向けて−」
3月4日(水)10:30〜17:30
場所:日本学術会議講堂
定員:当日先着順300名、事前登録なし
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/208-s-0304.pdf
第4回学生のヒマラヤ野外実習ツアー
(学会推薦)
3月上旬(4日頃)出発,出国から帰国まで15日間
参加申込締切:2014年11月末日
定員:20名
参加費:学生,大学院生は20 万円以内(暫定)
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
第164回深田研談話会
「進化学のモデル生物としても放散虫」
3月6日(金)15:00〜17:00(14:30会場)
申し込み締切:3/4 先着:80名 参加無料
会場:深田地質研究所 研修ホール(文京区本駒込2-13-12)
http://www.fgi.or.jp/
三朝国際シンポジウム
Comprehensive Exploration of the Solar System: Sample Return and Analysis
3月6日(金)〜8日(日)
参加申込締切:2月15日(日)*旅費サポート可
場所:鳥取県三朝町、ブランナール三朝
http://sympo.misasa.okayama-u.ac.jp/misasa_v/?page_id=30&lang=ja
○2014年度東北支部総会・講演会・シンポジウム
3月7日(土)〜8日(日)
7日:シンポジウム
8日:総会・個人講演
場所:岩手大学工学部(盛岡市上田)
プログラム・詳細はこちら
海洋資源開発フォーラム
3月11日(水)
会場:ANAクラウンプラザホテル神戸(神戸市中央区北野町1-1)
参加無料、申込期限2月25日(水)
http://www.nipponkaiko.co.jp/shiryou/forum_info.pdf
○関東支部:地学教育サミット・ジオパークと教育〜楽しく元気に大地の公園〜
3月15日(日)10:00〜16:00
場所:神奈川県小田原市生涯学習センター けやき 大会議室
http://kanto.geosociety.jp/
第3回国連防災世界会議
3月14日(土)〜18日(水)
場所:仙台市(仙台国際センターほか)
http://www.wcdrr.org/
2015アジア太平洋地域地震火山ハザード・リスク情報国際ワークショップ
3月16日(月)9:40〜18:45
場所:仙台市東京エレクトロンホール宮城602会議室
http://g-ever.org/ja/workshop/
第49回日本水環境学会(石川)年会
3月16日(月)〜18日(水)
会場:金沢大学角間キャンパス(南地区:自然科学)
http://www.jswe.or.jp/event/lectures/2014per.html
研究船による研究成果発表会「ブルーアース2015」
3月19日(木)〜20日(金)
場所:東京海洋大学 品川キャンパス 白鷹館 講義棟(東京都港区港南4-5-7)
http://www.jamstec.go.jp/maritec/j/blueearth/2015/
講演会「本邦新生代層序の発展 ー微化石層序学と地質学ー」
3月20日(金)13:30〜17:00
会場:産総研共用講堂1階中会議室
参加登録不要(ただしCPD希望者はジオスクーリングネットより要申込[3単位])
https://unit.aist.go.jp/igg/ci/update/20150320sympo.pdf
第172回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
3月27日(金)18:30〜20:30 [事前予約不要]
場所:北とぴあ901会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分)
講師 :高橋正樹氏(日本大学文理学部地球システム科学科 教授)
テーマ :箱根火山の噴火と首都圏都市災害—もし東京軽石規模の大規模噴火が起こってしまったら—
CPD:2単位
会費:会員、地質学会会員は500円、非会員は1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
日本学術会議 サイエンスカフェ
「核燃料サイクルを考える—環境社会学の視点から」
3月27日(金)19:00〜20:30 [要事前予約/入場無料/定員30名]
場所:日本学術会議6−A(1),(2)会議室(建物6階)(東京都港区六本木7−22−34)
講師 :長谷川 公一(東北大学大学院文学研究科教授)
ファシリテーター:柴田 徳思(日本アイソトープ協会専務理事)
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/150327.pdf
4月April
○関東支部:2015年度総会・地質技術伝承講演会
4月18日(土)14:00〜16:45(13:30受付)
場所:北とぴあ 7階 第1研修室(東京都北区王子1-11-1)
14:00〜15:40地質技術伝承講演会[参加費無料,CPD単位(2.0)]
申込・問い合わせ:加藤 潔 kiyoshi.katoh@gmail.com
15:50〜16:45関東支部総会
委任状締切[4月17日(金)18時]
http://kanto.geosociety.jp/
北極科学サミット週間2015
4月23日(木)〜30日(木)
会場:富山国際会議場
アブストラクト締切:2014年11月10日
参加登録締切:2015年3月31日
http://www.assw2015.org/japanese/index.html
日本堆積学会2015年つくば大会
4月24日(金)〜27日(月)
会場:筑波大学大学会館(茨城県つくば市天王台1-1-1)
24日(金):ショートコース[締切:2月28日(土)]
25日(土)・26日(日):個人講演、特別講演ほか
[講演申込・要旨提出締切:3月13日(金)]
27日(月):日帰り巡検[締切:2月28日(土)]
印刷版要旨集購入申込:3月13日(金)
http://sediment.jp/04nennkai/2015/annai.html
5月May
シンポジウム:環境資源システムを支えるジオサイエンス
5月8日(金)9:30〜17:00
場所:早稲田大学理工キャンパス63号館2F(03会議室)
会費:無料(要登録)
https://sites.google.com/site/geosciencetokyo/home
近畿支部 第32回地球科学講演会
「阪神淡路大震災以降の近畿の活断層研究」
5月10日(日)13:30〜15:30
場所:大阪市立自然史博物館 講堂
くわしくは、こちら
四国支部 岩石・鉱物鑑定会
5月10日(日)11:00〜16:00
会場:愛媛大学ミュージアム中庭
くわしくは、こちら
鹿児島県地学会:地質見学会
「石の文化史,史跡と岩石の旅」(仮題)
5月10日(日)9:00-14:00
鹿児島県立博物館 集合
くわしくは、こちら
第15回アジア学術会議カンボジア会合国際シンポジウム
5月15日〜16日
会場:Angkor Paradise hotel(シェムリアップ、カンボジア)
問い合わせ先:Institute of Technology of Cambodia(ITC)
E-mail:sca2015@itc.edu.kh/info@itc.edu.kh
http://krs.bz/scj/c?c=143&m=21728&v=9765b8fb
第166回深田研談話会 世界遺産富士火山の自然と防災
5月15日(金)15:00〜17:00 参加費無料
会場:深田地質研究所 研修ホール
講師:小山真人(静岡大学教授)
申込期間:4月20日〜5月13日(定員80名,定員になり次第締切)
http://www.fgi.or.jp/
第7回(2015年度)代議員総会
5月23日(土)14:50〜
会場:北とぴあ 第1研修室
議事次第はこちら
*第6回惑星地球フォトコンテスト表彰式
*講演会「日本の地質学:最近の発見と応用2015」 同会場にて開催予定
(後)地質の日記念観察会:深海から生まれた城ヶ島
主催:三浦断層活断層研究会
5月23日(土)10:00〜15:00(小雨決行)
詳しくは,コチラ
■日本地球惑星科学連合2015年大会
5月24日(日)〜28日(木)
会場:幕張メッセ
http://www.jpgu.org/meeting/
科学上のブレークスルーに関するグローバルシンポジウム
5月26日(火)9:30〜15:00
場所:ホテルオークラ東京 別館地下2階 アスコットホールII(東京都港区虎ノ門2-10-4)
言語:英語(日英同時通訳有)
参加費無料/要申込/先着順
http://grc2015tokyo.jp
第174回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
場所:北とぴあ901会議室
5月29日(金)18:30〜20:30
講師:高松武次郎氏(元茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター長)
テーマ:都市と周辺山地の土壌に広がる慢性的重金属汚染
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
6月June
○西日本支部西日本地質講習会
講演会:6月11日(木)会場 山口大学
巡 検:6月12日(金)「山口の活断層巡検」(30名まで.最小遂行10名)
*講演会・巡検それぞれにCPD単位が発行されます.
*11日は,18:30より懇親会を予定しています(要申込).
参加申込締切:6月1日(月)
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
○中部支部2015年支部年会
6月13日(土)
年会会場:黒部市吉田科学館(富山県黒部市吉田574-1)
地質巡検(6月14日):富山県北東部の中生界(定員15名程度予定)
参加申込:6月6日(土)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
○北海道支部平成27年度例会(個人講演会)
6月13日(土)10:00-18:00
会場:北海道大学理学部5号館大講堂(5-203)
講演申込:5月15日(金)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
地質学史懇話会
6月20日(土)
場所:北とぴあ8階803号室(東京都北区王子)
澁谷鎮明:朝鮮時代の地誌と古地図に見る「気」と「脈」による国土認識
中陣隆夫:田山利三郎の海洋地質学—業績と評価
問い合わせ先:矢島道子
第1回宅地の地すべり・土砂災害・水害減災診断士認定研修会
日本地質学会環境地質部会 共催
6月25(木)〜27日(土)(時間は各日毎に異なります)
場所:大阪市立大学文化交流センター(JR大阪駅前第2ビル6F)
会費:会員10,000円/1日、非会員14,000円/1日
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
第175回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
場所:北とぴあ901会議室
6月26日(金)18:30〜20:30
講師:張 銘氏(産総研地圏資源環境研究部門地圏環境リスク研究グループ長)
テーマ:台湾の地質法について
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
「科学の芽」賞 10周年シンポジウム「科学の芽を育てるために」
6月29日(月)14:30-16:00
場所:筑波大学東京キャンパス文京校舎1階
参加申込:6月26日(金)
www.tsukuba.ac.jp/event/e201506101400.html
7月July
(後)シンポジウム「地下水の保全、涵養および利用に関する法制化に向けた現状と課題」
7月4日(土)
会場:日本大学文理学部 3号館3505講義室(世田谷区)
定員:200名(要申込)
http://jagh.jp/jp/g/activities/seminar/2015-1.html
(共)第52回アイソトープ・放射線研究発表会
7月8日(水)〜10日(金)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1)
発表申込締切:2月27日(金)
講演要旨原稿締切 :4月10日(金)
http://www.jrias.or.jp/
(共)シンポジウム「国際地質時代区分に千葉時代を設定しよう―第四紀前期/中期(M/L)境界と環境・観光問題−」
7月11日(土) 14:00〜17:00
会場 南総公民館(市原市牛久520-1 TEL:0436(92)0039)
主催:古関東深海盆ジオパーク推進協議会
共催:日本地質学会環境地質研究部会ほか
詳しくは、コチラ
○関東支部箱根火山ミニ巡検「大涌谷とは何か」
共催:箱根ジオパーク推進協議会
7月12日(日)(雨天決行)
定員:18人(先着順.お申込はお早めに!!)
費用:貸切バス代、昼食・保険代込で6,000円(予定)
申込・問合先:支部幹事長 笠間友博(神奈川県博)
(後)第13回微量元素の生物地球化学に関する国際会議
13th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements, ICOBTE 2015 FUKUOKA
7月12日(日)〜16日(木)
場所:福岡国際会議場
http://www.icobte2015.org/index.html
原子力機構_地層処分技術に関する研究開発報告会
7月14日(火) 13:00〜16:30
会場:コクヨホール(東京都港区港南1-8-35)
定員:250名程度(事前登録制:7/9締切)参加費無料
http://www.jaea.go.jp/04/tisou/houkokukai/pdf/nendo_h27_guide.pdf
(共)原子力総合シンポジウム2015
テーマ「原子力の将来のあり方」
7月16日(木)
会場:日本学術会議講堂(東京都港区六本木)
要事前申込(7/13締切)
www.aesj.net/events/symposium2015
日本学術会議 中部地区会議学術講演会
「日本海地域の未来」
7月17日(金)13:00〜16:00
場所:富山大学五福キャンパス黒田講堂会議室
http://krs.bz/scj/c?c=239&m=21728&v=405f5bf4
○東京大学大気海洋研究所共同利用研究集会
「海水準変動と氷床の安定性に関する国際研究集会」
7月22日(水)〜24日(金)
場所:東京大学大気海洋研究所 2F講堂
詳しくは,こちら
東京大学海洋アライアンス第10回東京大学の海研究
「新たな手法と視点が海洋の常識を覆す」
7月23日(木)13:00〜17:00
場所:東京大学農学部弥生講堂
http://www.oa.u-tokyo.ac.jp/news/2015/05/000608.html
○第291回地学クラブ講演会
7月24日(金)16:00〜
場所:東京地学協会 地学会館2階講堂
上野将司「最近のシルクロードをたずねてー海面下の灼熱の砂漠から氷河のかかる高山へ」
http://www.geog.or.jp/lecture/lecturescheduled/242-club291.html
(後)青少年のための科学の祭典2015 全国大会
7月25日(土)〜26日(日)
会場:科学技術館(東京都千代田区北の丸公園)
http://www.kagakunosaiten.jp/
(共)第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
7月27日(月)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1-1)
http://inqua2015.jp/
第176回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
7月31日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:土屋範芳・山田亮一・渡邊隆広(東北大学大学院環境科学研究所)
テーマ:三陸海岸ならびに仙台平野における東北地方太平洋沖地震に起因した津波堆積物中のヒ素ならびに重金属類の起源
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
8月August
○関東地下水盆と人工地層の地質環境巡検主催:地質学会環境地質部会
8月4日(火)〜8月5日(水)2日間
募集締切日:6月30日(火)
http://www.geosociety.jp/outline/content0096.html
○関東支部:巡検「秩父ジオパークをまるごと堪能する」
8月11日(火)〜12日(水) 1泊2日
場所:埼玉県秩父地域(長瀞・和銅遺跡・ようばけ・鍾乳洞・浦山ダム等)
対象:小中高教員(教員以外,非会員の参加も歓迎します)
申込締切:7月10日(金)
http://kanto.geosociety.jp/
(共)第16回地震火山こどもサマースクール in 南アルプス
8月8日(土)午前9時〜8月9日(日)午後5時
活動場所:南アルプス林道、杖突峠、板山・非持・溝口露頭、長谷公民館(戸台の化石資料室)、伊那市創造館など
宿泊先:国立信州高遠青少年自然の家(長野県伊那市高遠町藤沢6877-11)
定員:小学5年−高校生 40名(定員をこえた場合、学年などを考慮し先着順で締め切ります)
参加費:2,000円(予定)
http://www.kodomoss.jp/ss/minamialps/
IGCP608第3回国際シンポジウムおよび第12回中生代陸成生態系シンポジウム
8月15日(土)〜18日(火)シンポジウム
8月19日(水)〜20日(木)巡検:遼寧省内の熱河層群
場所:中国瀋陽,瀋陽師範大学
発表要旨 締切:6月15日(月)
Third Circular 配布(シンポジウムプログラム 発表):7月31日(金)
http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/
平成27年度全国地学教育研究大会・日本地学教育学会第69回全国大会
8月21日(金)〜24日(月)
場所:福岡教育大学
発表申込締切:6月19日(金)
予稿集原稿提出:7月17日(金)
http://www.jsese-69th-meeting.jp/
第177回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
8月28日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:宮崎 毅(東京大学名誉教授・NPO日本地質汚染審査機構理事)
テーマ:地下水挙動と農地・宅地の斜面崩壊のメカニズム
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
9月September
○関東支部:清澄フィールドキャンプ
9月1日(火)〜7日(月)
場所:東京大学千葉演習林(千葉県鴨川市清澄)
費用:35,000円(宿泊・食事・保険・レンタカー代込)
参加応募締切:7月3日(金)
http://kanto.geosociety.jp/
(共)第59回粘土科学討論会
9月2日(水)〜 5日(土)
会場:山口大学理学部・人文学部
講演申込:6月15日(月)〜 7月10日(金)
http://www.cssj2.org/
5th International Man-Made Strata and Geo-pollution Symposium
9月5日(土)〜6日(日)
場所 Urayasu Culture Hall
詳しくは,こちら
○日本地質学会第122年学術大会(長野大会)
9月11日(金)〜13日(日)
巡検:10日(木),14日(月)〜15日(火)
場所:信州大学長野(工学)キャンパス(長野市若里)ほか
[大会HP]http://www.geosociety.jp/nagano/content0001.html
(後)第11回国際化石藻類シンポジウム
9月14日(月)〜19日(土)
会場:琉球大学
(後)日本ジオパークネットワークガイドフォーラム
9月15日(火)〜16日(水)
会場:アミティ丹後(京都府京丹後市網野町網野367)
バーチャルジオツアー発表者応募締切:5月29日(金)
参加登録締切:7月31日(金)
http://jgn2015.com/
(共)2015年度日本地球化学会第62回年会
9月16日(水)〜18日(金)
会場:横浜国立大学常盤台キャンパス
http://geochem.jp/conf/2015/
(後)第4回アジア太平洋ジオパークネットワーク山陰海岸シンポジウム
9月16日(水)〜20日(日)
会場:豊岡市民会館(豊岡市立野町20-34)ほか
通常参加登録締切:7月31日(金)
http://apgn2015-jpn.com/
第32回歴史地震研究会
9月21日(月・祝)〜23日(水・祝)
会場:京丹後市峰山総合福祉センター(京都府京丹後市)
巡検等申込・講演要旨投稿締切:7月31日(金)
http://sakuya.ed.shizuoka.ac.jp/rzisin/menu7.html
(後)第10回アジア地域応用地質学シンポジウム
研究発表会:9月24日(木)〜25日(金)
シンポジウム:9月26日(土)〜27日(日)[その後、巡検予定あり]
場所:京都大学 宇治黄檗プラザ
http://2015ars.com/
(共)Arthur Holmes Meeting Tsunami Hazards and Risks: Using the Geological Record
9月25日(金)
場所:The Geological Society(英・ロンドン)
プレ巡検:22日(火)〜24日(木)
http://www.geolsoc.org.uk/ahm15
第178回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
9月25日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ902会議室
講師:難波謙二(福島大学環境放射能研究所所長)(予定)
テーマ:東京電力福島第一原子力発電所事故と放射性物質汚染ー中央では出来ない地元大学の貢献ー
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
10月October
深田研一般公開2015
10月4日(日)10:00〜16:00
場所:深田地質研究所
申込不要・入場無料
http://www.fgi.or.jp/?p=3127
第8回アジア海洋地質会議(ICAMG-8)
10月5日(月)〜10日(土)(巡検を含む)
場所:韓国済州島,JEJU GRAND HOTEL
ホスト:KIGAM & KIOST
講演要旨締切:5月31日
http://icamg-8.kigam.re.kr/ICAMG/index.jsp
(後)国際シンポジウム「沈み込み帯堆積盆地のリソスフェア・ダイナミクス」
10月5日(月)〜7日(水)(10月8日〜9日:地質巡検)
会場:東京第一ホテルシーフォート(品川区東品川)
講演要旨締切:7月15日
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/ILP2015/
第30回ヒマラヤ・カラコルム・チベットワークショップ(30th HKT 2015)
10月6日(火)〜8日(木)
場所:Wadia Institute, Dehra Dun, India
プレ野外巡検:10月5日(月)
ポスト野外巡検:10月9日(金)〜12日(月)
http://www.hktwadia2015.org/
東京都2015講演会・地質見学会
日本地質学会関東支部 後援
【 講演会 】
10月14日(水) 13:00〜16:00(予定)
会場: 測量地質健保会館 7階「大会議室」(豊島区西池袋)
参加費: [会員]1,000円
【地質見学会】
11月11日(水)9:00〜17:30(予定)
場所: 東京都あきる野市(旧西多摩郡五日市町)
参加費: [会員]4,000円
申込締切:10月6日(火)まで
http://www.tokyo-geo.or.jp/html/2015kengakukai_info
○関東支部:「富士山巡検」
10月17日(土)〜18日(日),1泊2日 雨天決行
参加費用:一般22,000円,学生・院生13,000円
CPD単位:16単位
募集人数:会員および一般・30名程度(先着順)
申込期間:8月24日(月)〜10月2日(金)(定員に達した時点で締切)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0157.html
または,http://kanto.geosociety.jp/
国際ゴンドワナ研究連合(IAGR)2015年総会及び第12回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム
10月21日(水)〜23日(金)
場所:筑波大学
野外巡検:10月24日(土)〜25日(日)
巡検コース:峰岡オフィオライト等
講演要旨締切:6月30日(火)
http://www.geol.tsukuba.ac.jp/~gansekihp/IAGR2015/
地球惑星科学NYS 2015
10月24日(土)〜25日(日)
場所:東京大学本郷キャンパス
参加申込締切:10月3日(日)
http://sites.google.com/site/nyswakate/2015
★関東支部:サイエンスカフェ
Vol. Cafe噴火列島・富士山編〜あなたは備えてますか?〜
10月25日(14:30〜16:30)
場所:「ベルギービール アグリオ」(東京都世田谷区 下高井戸駅近く)
講師:吉本充宏氏(山梨県富士山科学研究所)
詳しくはこちら
IGCP589「アジアにおけるテチス区の発達」第4回国際シンポジウム
10月26日(月)〜27日(火)
ポスト巡検:10月28日(水)〜11月1日(日)
場所:チュラロンコン大学(タイ王国バンコク市)
http://www.igcp589bangkok.org/
平成27年度 東濃地科学センター地層科学研究 情報・意見交換会
10月29日(木)13:30〜16:50
場所:瑞浪市地域交流センター「ときわ」(岐阜県瑞浪市)
※定員:約150名
詳しくは,こちら
瑞浪超深地層研究所 深度300m水平坑道見学会
10月30日(金)9:15〜12:00
場所:瑞浪超深地層研究所
※定員:40名
※締切 10月16日(金)までにお申し込み下さい。
詳しくは,こちら
第179回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
10月30日(金)18:30〜20:30[事前予約不要]
場所:北とぴあ901会議室
講師:藤原 寿和(廃棄物ネット・ワーク代表)
テーマ:戦後から今日にいたる廃棄物問題の列挙と今後の日本の国土汚染について
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
○関東支部:ミニ・ショートコース:地すべり試験ラボ見学
10月31日(土) 11:00〜16:00
場所:国土防災技術(株) 技術本部試験研究所(福島市南矢野目)
費用:3,000円 CPD単位:4単位
募集人数:10名(先着順,地質学会会員を優先します)
詳しくは,http://kanto.geosociety.jp/kousyuukai/2015/2015_siken_sc.pdf
第167回深田研談話会(現地)
テーマ「地形散歩」
10月31日(土)
集合: 深田地質研究所 10時 解散: 不忍池 16時
移動方法: 徒歩(約7km)
定員:20名(申込多数の場合は抽選)
参加費無料
http://www.fgi.or.jp/?p=3148
11月November
産業技術連携推進会議 地質地盤情報分科会 平成27年度講演会
「3次元地質地盤モデリングの進展とその利活用」
11月6日(金)13:30〜16:50 参加無料・事前申込不要
場所:北とぴあ第一研修室(JR京浜東北線王子駅北口より3分)
CPD:3単位
https://www.gsj.jp/information/domestic/sgr/index.html
2015年度春季地質調査研修
11月9日(月)〜13日(金)(4泊5日)
場所:千葉県君津市及びその周辺地域(房総半島中部域)
募集人数:6名(定員に達し次第締切)
募集期間:9月14日(月)〜10月13日(火)(募集は締切りました)
http://www.geosociety.jp/engineer/content0043.html
平成27年度国土交通省国土技術研究会
のこすこと,つくること:どちらも国土技術です
11月12日(木)・13日(金)
場所:中央合同庁舎2号館
http://www.mlit.go.jp/chosahokoku/giken/index.html
サイエンスアゴラ「フューチャー・アース 〜持続可能な地球社会に向けて〜」
11月14日(土)13:00〜17:00
場所:日本科学未 来館 イノベーションホール
http://www.jst.go.jp/csc/scienceagora/program/booth/ab_101/
参加申込締切:11月10日(火)
生命を育む地球環境の変動予測と適応─我が国におけるIGBP25年間の歩み
11月15日(日)9:00-12:00
政策研究大学院大学 (東京都港区六本木7-22-1)
http://mits10.aori.u-tokyo.ac.jp/kokusai/igbp2015/
持続可能な社会のための科学と技術に関する国際会議2015
11月15日(日)13:30-18:00
場所:日本学術会議講堂
http://www.pco-prime.com/Science_and_Technology_for_Sustainability2015/index.html
東京地学協会 地学クラブ講演会
「伊能忠敬の世界的偉業」
11月16日(月)15:00〜16:00
場所:東京地学協会 地学会館二階 講堂(千代田区二番町 12-2)
講演:西川 治(東京大学名誉教授)
http://www.geog.or.jp/
第2回アジア恐竜国際シンポジウム(ISAD2015)
11月19日(木)〜24日(火)
場所:タイ バンコク
http://www.isad2015.com/isad2015/
(後)ワークショップ「ジオハザードに対処できる人材の育成:防災国際ネットワーク構築に向けた国内連携のあり方」
主催:日本学術会議・産業技術総合研究所,東北大学災害科学国際研究所
11月20日(金)13:30〜18:00 参加申込不要
場所:東京海洋大学大講義室(越中島キャンパス第4実験棟5階)
問い合わせ:IUGS分科会委員長(国研)海洋研究開発機構,北里 洋(kitazatoh@jamstec.go.jp)
*ポスター(PDF)がこちらからダウンロードできます
第180回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
11月20日(金)18:30〜20:30[事前予約不要]
場所:北とぴあ901会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分)
講師:上砂正一(NPO日本地質汚染審査機構副理事長)
テーマ:自治体の環境行政の諸問題
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
第26回地質汚染調査浄化技術研修会
日本地質学会環境地質部会 共催
11月21日(土)〜23日(月)(時間は各日毎に異なります)
場所:関東ベースンセンター
会費:会員 45,000円(学生35,000円)
非会員 55,000円(非会員学生40,000円)
※昼食代を含む
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
★関東支部:地質研究サミット「ジオハザードと都市地質学」
11月23日(月・祝)10:00〜17:30
場所:日本大学文理学部 図書館3階
CPD単位:取得可能(6単位)
http://kanto.geosociety.jp/
(後)日本地下水学会セミナー
「東京電力福島第一原子力発電所事故による周辺水環境への影響—現状と課題—
11月24日(火)13:00〜17:40
場所:日本大学文理学部3号館
定員・100名(要予約申込、定員になり次第締切)
http://jagh.jp/
(協)第31回ゼオライト研究発表会
11月26日(木)〜27日(金)
会場:とりぎん文化会館(鳥取市尚徳町101-5)
http://katalab.org/31zeolite/
(共)第25回環境地質学シンポジウム
主催 医療地質-地質汚染-社会地質学会
11月27日(金)〜28日(土) 10:00〜18:00 [事前予約不要]
場所:日本大学文理学部オーバルホール
http://www.jspmug.org/envgeo_sympo/25th_sympo/25th_sympo.html
東京地学協会 秋季講演会
「地球の大きさと形を測る」―その歴史における伊能忠敬
11月28日(土)14:00〜16:00
場所:弘済会館4F蘭の間(千代田区麹町5-1)
講演:野上道男(東京都立大学名誉教授)
海津 優(元国土地理院地理地殻活動研究センター長)
河荑和重(国土地理院地理地殻活動研究センター研究管理課長)
http://www.geog.or.jp/
12月December
平成27年度国総研講演会
12月3日(木)10:30〜17:00
場所:日本消防会館ニッショーホール(港区虎ノ門)
特別講演「社会・経済イノベーションを導く国土技術政策」
入場無料
http://www.nilim.go.jp
国際土壌年2015記念シンポジウム
「つち・とち・いのち〜土のこと語ろう」
12月5日(土)13:00〜17:00
場所:日本学術会議講堂(港区六本木7-22-34)
参加費無料(事前参加申込締切:11/30)
http://jssspn.jp/info/notice/notice/2015-1205sympo-pressrelease.html
地球化学研究協会「公開講座」および「三宅賞」受賞者の受賞記念講演
12月5日(土)14:40〜
場所:霞が関ビル35階東海大学校友会館
参加費:賛助会員および学生は無料、一般1,000円(資料代を含む)
http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~e881147/Geochem/
東北大学東北アジア研究センター創設20周年記念国際シンポジウム:
セッション「東北アジアの地殻変動―パンサラッサから環太平洋まで」
12月6日(日)9:00-12:30
場所:仙台国際センター小会議室1
参加無料
http://www.cneas.tohoku.ac.jp/news/asia20/
産総研第14回地圏資源環境研究部門成果報告会
「強い技術シーズの創出と展開」
12月10日(木)13:30〜17:25
場所:秋葉原ダイビル・コンベンションホール
申込締切:11月26日(木)
http://green.aist.go.jp/ja/
第181回地質汚染イブニングセミナー
12月18日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ902会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分)
講師:楡井 久(IUGS GEM人工地層と地質汚染研究委員長・NPO日本地質汚染審査機構理事長)
テーマ:国民生活に関わる人自不整合と人工地層について
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
地学クラブ講演会「天然資源と紛争の政治地理学」
12月18日(金)16:00-17:00
場所:東京地学協会2F講堂
講演:大木優利氏(ジュネーブ高等国際問題研究所)
参加申込:不要(どなたも無料で参加できます)
http://www.geog.or.jp/lecture/lecturescheduled/255-club294.html
地質学史懇話会
12月23日(水・祝)13:30〜17:00
場所:北とぴあ 8階803号室(東京都北区:JR京浜東北線王子駅下車3分)
・加藤 碵一『ネパールのジオ・地震瞥見』
・秋葉文雄『珪藻化石層序の誕生から完成まで:鍵種を探し求めて』
問い合わせ先
矢島道子 pxi02070[at]nifty.com
→2016年行事カレンダーへ
ホットトピックス
地質災害情報
■平成27年5月29日 口永良部島火山の噴火に関する情報
■平成27年4月24日 2015年ネパール地震のテクトニクスとカトマンズの極軟弱地盤
■平成27年4月24日 知床半島羅臼町で海岸線沿い隆起と地すべり調査報告
■平成26年11月22日に発生した長野県北部の地震に関する情報
■平成26年9月27日 御嶽火山の噴火に関する情報
■平成26年8月20日に広島市安佐南区で発生した土石流の発生地に関する地質情報
■平成26年7月9日に長野県南木曽町で発生した土石流の発生地に関する地質情報
詳細はこちらから
Geo暦(2016)
2016年Geo暦(行事カレンダー)
2008年版 2009年版 2010年版 2011年版 2012年版 2013年版
2014年版 2015年版 ……… 2017年版
2016年版 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
○印は学会主催行事.(共)学会共催・(後)後援・(協)協賛
1月January
学術フォーラム「防災学術連携体の設立と東日本大震災の総合対応の継承」
1月9日(土)13:00〜17:30
場所:日本学術会議講堂
http://janet-dr.com
(後)公開講演会「強靭で安全・安心な都市を支える地質地盤−あなたの足元は大丈夫?−」
主催:日本学術会議
1月23日(土)13:30〜17:30
場所:日本学術会議講堂
http://www.scj.go.jp/ja/event/index.html
第182回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
1月29日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ902会議室
講師:宮澤 博(環境地水技術研究会理事長)
テーマ:「土壌への雨水浸透」と宅地開発・インフラストラクチュアーへの提言
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
2月February
○西日本支部平成27年度総会・第167回例会
2月20日(土) 9:00〜
場所:熊本大学黒髪南キャンパス 理学部2号館
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
第183回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
2月26日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ902会議室
講師:熊井久雄(NPO日本地質汚染審査機構理事,大阪市立大学名誉教授)
テーマ:国際地質年代候補「千葉時代」について
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
○北海道支部平成27年(2015年)度総会
2月27日(土)14:30〜16:30
場所:北海道大学理学部6号館2階 6-204室
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
3月March
東日本大震災5周年シンポジウム
「この5年間を,復興の加速と次への備えに活かすために」
主催:土木学会(東日本大震災復興支援特別委員会)
3月1日(火)〜2日(水)10:00〜17:00
場所:発明会館(東京都港区虎ノ門2-9-14)地下2階ホール
定員:300名
http://committees.jsce.or.jp/2011quake/node/178
JAMSTEC2016(平成27年度海洋研究開発機構研究報告会)
3月2日(水)13:00〜17:00
場所:東京国際フォーラム ホールB7
参加費無料(事前登録制)
http://www.jamstec.go.jp/j/pr/event/jamstec2016/
(後)愛媛大学ミュージアム企画展【四国の鉱物展】
共催:日本地質学会四国支部
3月2日(水)〜4月27日(水)
場所:愛媛大学ミュージアム
http://www.museum.ehime-u.ac.jp/
日本堆積学会2016年福岡大会
3月4日(金)〜8日(火)
会場:福岡大学理学部
http://sediment.jp/04nennkai/2016/annai.html
平成27年度Project A in 奄美大島
3月4日(金)〜8日(火)(7・8日:巡検)
場所:奄美大島・瀬戸内町物産館(鹿児島市金生町2-18)
発表申込締切:2月5日(金)
http://archean.jp/
平成27年度 ESR応用計測研究会・第40回フィッション・トラック研究会・
ルミネッセンス年代測定研究会 合同研究会
3月4日(金)〜6日(日)
会場:石川県金沢市 しいのき迎賓館
http://ftrgj.org/activities.htm
地球研未来設計イニシアティブ国際シンポジウム2016
多様な自然・文化複合をふまえた未来可能な社会への転換
3月5日(土)10:30〜17:30
場所:東京国際フォーラム
聴講無料・要申込
http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2016/0305.html
第5回学生のヒマラヤ野外実習ツアー(地質学会推薦)
3月5日〜20日(16日間)*暫定日程
コース:中西部ネパールヒマラヤの全断面、ポカラを通る南北のルート
暫定参加費:学生20万円以内 一般25万円以内 公費派遣者30万円以内
実施主体:ゴンドワナ地質環境研究所・ネパール国立トリブバン大学トリ
チャンドラキャンパス地質学教室の共同
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
平成27年度海洋情報部研究成果発表会
3月7日(月)13:10〜18:00
場所:海上保安庁海洋情報部10階大会議室
参加費無料(事前申込不要)
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/
『ブルーアース2016』
3月8日(火)〜9日(水)10:00〜17:45(9:30開場)
場所:東京海洋大学 品川キャンパス
入場無料(事前申込不要)
http://www.jamstec.go.jp/maritec/j/blueearth/2016/program.html
シンポジウム:MISASA VI “Frontiers in Earth and Planetary Materials
Research: Origin,Evolution and Dynamics”
3月9日(水)〜11日(金)
場所:倉吉未来中心(鳥取県倉吉市)
アブストラクト,参加登録締切:2月15日
http://www.misasa.okayama-u.ac.jp/jp/news/?eid=01247
地学クラブ講演会:コケ植物による炭酸塩岩の生物風化
3月14日(月)15:00〜
場所:東京地学協会2F講堂
内容:乙幡康之(ひがし大雪自然館)氏・羽田麻美(日本大学)氏講演
http://www.geog.or.jp/lecture/lecturescheduled/259-club295.html
第50回水環境学会(徳島)年会
3月16日(水)〜18日(金)
場所:アスティとくしま(徳島市山城町)
参加申込:2月18日(木)締切
https://www.jswe.or.jp/event/lectures/2015.html
(共)原子力総合シンポジウム「福島第一原発事故から5年を経て」
3月16日(水)13:00〜17:30
場所:日本学術会議講堂(地下鉄千代田線乃木坂駅徒歩2分)
入場無料
http://www.aesj.net/events/symp20160316
第3回地層液流動化診断士研修会のお知らせ
3月16日(水)〜30日(水)
内容:潮来日出地区現場作業見学.その後、講義と実習有り.
会費:30,000円(講義の期間は昼食付)
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
地層処分フォーラム
3月20日(日)14:00〜16:00
場所:東京国際交流館(江東区青梅2-2-1国際研究交流大学村)
参加申込締切:3月14日(月)※先着順
http://www.chisou-sympo.jp/forum_taiwa/
2016年日本地理学会春季学術大会公開シンポジウム
「ジオパークで考える科学と社会との関係」
3月21日(月)13:00〜16:30
会場:早稲田大学早稲田キャンパス教育学部14号館
http://www.ajg.or.jp/ajg/2016/03/2016-7.html
第184回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
3月25日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:張 銘(産総研・地圏環境リスク研究グループ長)
テーマ:中国の地下水汚染状況と動向
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
海洋と地球の学校2016
3月26日(土)〜27日(日)
場所:オーエンス泉岳自然ふれあい館(講義)
3月28日(月) 仙台平野(巡検)
参加申込締切:2月21日(日)
*参加者が30名に達し次第募集を終了します。
http://kaiyotochikyunogakko-2016.jimdo.com/
国際シンポジウム「いま改めて考えよう地層処分 〜世界の取り組みから学ぶ〜」
3月28日(月)13:30〜16:30
会場:丸ビルホール(東京駅前丸ビル7階)
参加費:無料
http://www.numo.or.jp/pr-info/pr/event/new_symposium16022909.html
4月April
第171回深田研談話会「関東平野と長周期地震動リスク」
4月15日(金)15:00〜17:00
講師:古村孝志(東京大学地震研究所)
80名(先着順)参加費無料
http://www.fgi.or.jp
○2016年度関東支部総会・地質技術伝承会
4月16日(土)14:00〜16:45
場所:北とぴあ 7階 第1研修室
伝承会演題(予定)「落石,斜面崩壊の岩盤斜面安定解析(数値)」
講師:萩原育夫氏(サンコ−コンサルタント(株)調査技術部 部長)
http://kanto.geosociety.jp/
第185回地質汚染イブニングセミナー
4月22日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ902会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分
講師:高嶋 洋(野田市土木部下水道主査)
テーマ:地下水法制度の更なる検討について
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
日本学術会議主催学術フォーラム「原子力発電所事故後の廃炉への取組と汚染水対策」
4月23日(土)12:30〜17:30
場所:日本学術会議講堂(参加費無料)
https://ws.formzu.net/fgen/S57675157/
「科研費審査システム改革2018」説明会
4月26日(火)13:00〜15:00
場所:安田講堂(東京大学本郷キャンパス内)
対象:研究者等(一般公募、先着順)
参加登録:3月11日(金)〜4月15日(金)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/1367693.htm
5月May
第15回重金属類・残土石処分地・廃棄物処分地診断に関わる地質汚染調査浄化技術研修会
日本地質学会環境地質部会 共催
5月5日(木)〜8日(日)
場所:関東ベースンセンター
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
第172回深田研談話会(現地)
地質技術者のための露頭写真の撮り方:箱根火山岩類を対象に
5月14日(土)10:00〜17:00
講師:白尾元理(写真家)
申込締切:4月19日(火)
http://www.fgi.or.jp/?p=3296
(共)第一回台日地質学会総合学術研討会
1st Joint Symposium of Taiwan and Japan Geological Societies in Taiwan
Geosciences Assembly (TGA)
5月18日(水)午前
(TGAは5月16日(月)〜20日(金)開催)
場所:台湾台北市南港展覧館
http://cgu-tga.org.tw/index.asp
○一般社団法人日本地質学会第8回(2016年度)代議員総会
5月21日(土)14:15〜15:15
会場 北とぴあ 第2研修室(東京都北区王子)
http://www.geosociety.jp/outline/content0170.html
日本地球惑星連合2016年大会
5月22日(日)〜26日(木)
会場:幕張メッセ 国際会議場
http://www.jpgu.org/meeting_2016/index.htm
第186回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
5月27日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分
講師:外池幸太郎 博士(エネルギー科学)
国立研究開発法人日本原子力開発機構安全研究センター
燃料サイクル安全研究デビジョン臨界安全研究グループグループリーダー
テーマ: 福島第一事故炉の燃料デブリの臨界性について
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
6月June
NUMO国際セミナー
「地層処分の安全性に関するコミュニケーション」
6月2日(木)13:30〜16:30
建築会館ホール(東京都港区芝5-26-20)
http://www.numo.or.jp/pr-info/pr/event/new_event116051609.html
*当日の動画(2016.6.20)
http://www.numo.or.jp/pr-info/pr/event/old_event116060217.html
地質学史懇話会
6月19日(日)13:00〜17:00
場所:北とぴあ8階805号室
吉岡有文:日本の科学教育映画の世界:太田仁吉と科学教育映画の曙
宇井忠英:日本列島の火山活動は活発化しているのか?
問い合わせ:矢島道子
第187回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
6月24日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分)
講師:山田一夫 博士(工学)
国立環境研究所資源循環・廃棄物研究センター主任研究員
テーマ:コンクリートを診断する
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
熊本地震国際合同調査速報シンポジウム
主催:国際地質科学連合(IUGS)環境管理研究委員会・NPO地質汚染審査機構
6月25日(土)13:30〜16:30
場所:浦安文化会館 大会議室
http://www.npo-geopol.or.jp
(共)Goldschmidt2016
6月26日(日)〜7月1日(金)
会場:パシフィコ横浜
http://goldschmidt.info/2016/index
7月July
次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト公募説明会
7月1日(金)14:30-16:30
場所:イイノホール&カンファレンスセンター
参加申込:6月29日(水)17:00
詳しくは,http://geosociety.jp/uploads/fckeditor/geoFlash_img/no.345-01.pdf
(共)第53回アイソトープ・放射線研究発表会
7月6日(水)〜7月8日(金)
*プログラム決定しました(2016.6.6)
http://www.jrias.or.jp/
放射線基礎セミナー
日本アイソトープ協会主催
7月8日(金)〜7月9日(土)
会場:東京大学農学部フードサイエンス棟 中島菫一郎記念ホール
http://www.jrias.or.jp/
NUMO国際講演会
「スイスのサイト選定におけるコミュニケーション活動」
7月8日(金)13:30〜15:45
会場 :大手町サンケイプラザ3階(東京都千代田区大手町)
講演「スイスにおける地層処分の取り組み」
トーマス・エルンスト氏(放射性廃棄物管理共同組合(NAGRA) CEO)
定員100名
http://www.numo.or.jp/topics/201616061714.html
熊本地震・3ヶ月報告会
主催:日本学術会議防災減災・災害復興に関する学術連携委員会
共催:防災学術連携体
7月16日(土)9:30〜17:45
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木)
*日本地質学会からの発表も行います
http://janet-dr.com/
国際シンポジウム 地殻ダイナミクス2016
異なる時空間スケールにおける地殻ダイナミクス過程の統合的理解
7月19日〜22日(19日:巡検)
場所:高山市民文化会館
参加申込・講演要旨:4月15日締切
http://cd.dpri.kyoto-u.ac.jp/iscd2016/index.htm
第297回地学クラブ講演会「日本の風穴」
7月29日(金)15:00-17:00
場所:東京地学協会2F講堂
参加申込不要(どなたも無料で参加できます)
http://www.geog.or.jp/lecture/lecturescheduled/268-club297.html
(後)ジオパーク新潟国際フォーラム
7月27日(水)〜29日(金)
---27日:東アジアネットワーク ワークショップ
---28日:基調講演会、パネルディスカッションほか
---29日:見学会(佐渡コース、苗場山麓コース、糸魚川コース)
会場:朱鷺メッセ(新潟コンベンションセンター)
http://www.city.itoigawa.lg.jp/geopark-forum/
第188回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
7月29日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分)
講師:佐々木裕子 博士(工学)
国立環境研究所環境リスク・健康研究センター,日本地質汚染審査機構理事
テーマ:化学物質汚染と子どもの健康ーエコチル調査
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
8月August
IGCP608第4回国際シンポジウム
8月15日(月)〜17日(水)
場所:ロシア科学アカデミー シベリア支所 トロフィムク石油地質地球物理学
研究所(ロシア・ノボシビルスク)
ポスト巡検:8月18日(木)〜20日(土)ケメロボ地域の白亜系恐竜産出層
参加登録・要旨締切:5月15日(日)
http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/
第189回(上砂追悼)Special イブニング・セミナー
8月19日(金)18:15〜21:00
場所:北とぴあ701会議室
講師:殿上義久・楡井 久ほか1名または2名
テーマ:地震時の衝撃波・P波・S波による地質環境災害
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
第70回地学団体研究会総会(小川町)
8月19日(金)〜21日(日)
場所:埼玉県小川町 リリックおがわ
http://www.chidanken.jp/index.html
第1回防災推進国民大会
主催:内閣府・防災推進協議会・防災推進国民会議
8月27日(土)〜28日(日)
場所:東京大学本郷キャンパス(安田講堂,小柴ホール等)
http://bosai-kokutai.jp/
○2016年日本地質学会東北支部総会
8月27日(土)〜28日(日)
場所:弘前大学理工学部1号館2番講義室
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
第35回万国地質学会議
8月27日(土)〜9月4日(日)
会場:南アフリカ共和国ケープタウン 国際コンベンションセンター
http://www.35igc.org/
9月September
○日本地質学会第123年学術大会(東京・桜上水大会)
9月10日(土)〜12日(月)
会場:日本大学 桜上水キャンパス(東京都世田谷区)
http://www.geosociety.jp
第33回歴史地震研究会(大槌大会)
9月11日(日)〜13 日(火)
会場:⼤槌町中央公⺠館(岩⼿県上閉伊郡⼤槌町⼩鎚)
「大槌町津波アーカイブに向けたワークショップ」も開催いたします.
(注)開催地が被災地であることを考慮し,変則的な内容となっています.
それに伴い,参加申込方法も例年とは異なります.
*プログラムが公開になりました
http://sakuya.ed.shizuoka.ac.jp/rzisin/menu7.html
第19回日本水環境学会シンポジウム
9月13日(火)〜15日(木)
会場:秋田県立大学秋田キャンパス
事前参加登録締切:8月22日(月)
http://www.jswe.or.jp/event/symposium/index.html
(共)日本地球化学会第63回年会
9月14日(水)〜16日(金)
会場:大阪市立大学杉本キャンパス
講演申込:7月14日(木)14時締切
http://www.geochem.jp/conf/2016/
(共)第60回粘土科学討論会
9月15日(木)〜17日(土)
会場:九州大学医系キャンパス
講演申込:6月13日(月)〜24日(金)
http://www.cssj2.org/
NUMO セーフティケースに関する外部専門家ワークショップ
(1) 大阪会場(定員:100 名)
9月21日(水)9:30〜17:30
会場:大阪科学技術センタービル4階401号室
(2)東京会場(定員:120 名)
9月23日(金)9:30〜17:30
会場:三田NN ビル地下1階三田NN ホール
参加費:無料 参加申込締切:9月16日(金)
詳しくは,こちら
第190回地質汚染イブニング・セミナー
9月30日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:伊藤和明(元NHK解説委員)
テーマ:災害取材体験からの東日本大震災と熊本地震
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
10月October
Techno-Ocean 2016
10月6日(木)〜8日(土)
会場:神戸コンベンションセンター
http://techno-ocean2016.jp/
(後)第7回日本ジオパーク全国大会(伊豆半島大会)
10月10 日(月)〜12日(水)
場所:静岡県沼津市・プラザ ヴェルテほか
http://7th-jgn-izu-peninsula.jimdo.com/
深田研一般公開2016
10月16日(日)10:00〜16:00
入場無料・申込不要
講演:アンモナイトの死殻は浮くか沈むか:前田晴良
mini講演&実演:富士山の謎をみんなで解明してみよう:池田 宏
http://www.fgi.or.jp
(後)藤原ナチュラルヒストリー振興財団神戸シンポジウム
ナチュラルヒストリー:これまでの貢献と今後へ期待
10月22 日(土) 13:30〜17:00
場所:兵庫県民会館けんみんホール
共催 兵庫県立人と自然の博物館
http://fujiwara-nh.or.jp/
道総研・地質研究所海洋科学研究センター
市民公開講座「小樽の温泉について知る」
10月22日(土)13:30〜16:00
場所:海洋科学研究センター(小樽市築港3-1)
入場無料
http://www.hro.or.jp/list/environmental/research/gsh/information/topics/topics20160927.html
IGCP589「アジアにおけるテチス区の発達」第5回国際シンポジウム
10月27日(木)〜28日(金)
プレ巡検:10月25日(火)〜26日(水)
ポスト巡検:10月29日(土)〜11月2日(水)
場所:Hlaing大学(ミャンマー,ヤンゴン市)
http://igcp589.cags.ac.cn/
東北大学多元物質科学研究所:イノベーション・エクスチェンジ2016
10月27日(木)13:00〜17:30
場所:東北大学片平さくらホール
入場無料
参加申込締切:10月14日(金)
http://www2.tagen.tohoku.ac.jp/general/event/Innovation_Exchange/2016/
第191回地質汚染イブニング・セミナー
10月28日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:水谷和子(一級建築士)
テーマ:豊洲地質汚染問題 状況調査虚偽記載についてご報告
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
11月November
ユネスコ世界ジオパーク学術研究合同成果発表会 in 東京大学
11月5日(土)13:30〜16:00
会場:東京大学 弥生講堂アネックス(セイホクギャラリー)
申込不要
http://www.geo-itoigawa.com/sub/topics2016.html#672
サイエンスアゴラ2016:災害とレジリエンス−平成28年熊本地震災害の教訓−
11月6日(日)10:30〜12:00 (入場無料)
会場:日本科学未来館7階未来館ホール
主催:科学技術振興機構、日本学術会議
http://janet-dr.com/01_home_calendaer/201611/161106miraikan.pdf
図書館総合展・学術著作権協会フォーラム
英国教育現場における著作物の利用とライセンス
11月10日(木)13:00〜14:30
会場:パシフィコ横浜
https://www.jaacc.jp
学術著作権協会シンポジウム
デジタル時代における教育と著作権
11月11日(金)10:30〜12:30
場所:国際文化会館岩崎小彌太記念ホール
https://www.jaacc.jp
2016年度地球惑星科学学生と若手の会
11月12日(土)〜13日(日)
場所:東京大学本郷キャンパス
内容:講演,参加者同士の研究交流,グループディスカッション,懇親会など
申込締切:10月28日 (金)
https://sites.google.com/site/nyswakate/2016
日本学術会議 学術フォーラム
科学者は災害軽減と持続的社会の形成に役立っているか?
11月13日(日)13:00〜17:30
場所:日本学術会議講堂
https://form.cao.go.jp/scj/opinion-0067.html
東京大学大気海洋研究所共同利用研究集会
バイオミネラリゼーションと石灰化ー遺伝子から地球環境までー
11月11日(金)〜12日(土)
場所:東京大学大気海洋研究所(千葉県柏市柏の葉5-1-5)
http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/aori_news/meeting/2016/2016111.html
第25回素材工学研究懇談会
放射性物質と素材プロセッシング
11月16日(水)〜17日(水)
場所:東北大学片平さくらホール
http://www2.tagen.tohoku.ac.jp/general/event/sozai/2016/
第27回地質汚染調査浄化技術研修会
日本地質学会環境地質部会 共催
11月18日(金)〜20日(日)
場所:関東ベースンセンター(千葉県香取市)
会費:会員 45,000円(学生35,000円),非会員 55,000円(非会員学生40,000円)※昼食代を含む
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
International Association for Gondwana Research 2016 Annual Convention & 13th International Conference on Gondwana to Asia
11月19日(土)〜22日(火)
場所:インド、トリバンドラム、Residency Tower Hotel
http://www.iagr2016.com
シンポジウム「熊本地震を踏まえた地域防災力強化の在り方 in 大阪」
主催:地区防災計画学会,情報通信学会災害情報法研究会,(一財)関西情報センター
11月20日(日)
場所:大阪大学中之島センター講義室304
http://www.gakkai.chiku-bousai.jp/ev161120.html
藤原ナチュラルヒストリー振興財団公開シンポジウム
「土と生き物の自然史」
11月20日(日)13:00〜16:00
場所:国立科学博物館日本館講堂
http://fujiwara-nh.or.jp/archives/2016/0810_133757.php#more
女子大学院生・ポスドクと産総研女性研究者との懇談会
11月21日(月)13:00〜17:00
会場:産総研つくばセンター中央
産業技術総合研究所 ダイバーシティ推進室 主催
対象:女子大学院生・ポスドク等
参加費無料
http://unit.aist.go.jp/diversity/ja/event/161121_div_event.html
産業技術連携推進会議 地質地盤情報分科会 平成28年度講演会
「都市平野部の地質学」
11月22日(火)13:00〜16:50 参加無料・事前申込不要
場所:北とぴあ第一研修室(JR京浜東北線王子駅北口より3分)
CPD:3単位
https://www.gsj.jp/information/domestic/sgr/index.html
第192回地質汚染イブニング・セミナー
11月25日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:炭谷 茂(元環境省事務次官)
テーマ:社会福祉と環境
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
第26回環境地質学シンポジウム
11月25日(金)〜26日(土)
場所:日本大学文理学部
25日:オーバルホール
26日:レクチャーホール
http://www.jspmug.org/envgeo_sympo/26th_sympo/26th_sympo.html
12月December
(協)第32回ゼオライト研究発表会
12月1日(木)〜12月2日(金)
会場:タワーホール船堀
http://www.jaz-online.org/
第2回防災学術連携シンポジウム「激甚化する台風・豪雨災害とその対策」
主催:日本学術会議防災減災・災害復興に関する学術連携委員会,防災学術連携体
12月1日(木)10:00〜18:00
会場:日本学術会議講堂
http://janet-dr.com/07_event/event13.html
原子力機構東濃地科学センター:地下環境シンポジウム
12月3日(土)
場所:地域交流センター「ときわ」(岐阜県瑞浪市内)
定員:100名(先着順:11/30締切)
入場無料
https://www.jaea.go.jp/04/tono/
地球化学研究協会「公開講座」および「三宅賞」受賞記念講演
12月5日(月)
場所:霞が関ビル35階 東海大学校友会館(地下鉄銀座線虎ノ門・千代田線霞ヶ関下車)
http://www.geochem-ass-miyake.com/
第16回東北大学多元物質科学研究所研究発表会
12月7日(水)〜8日(木)
場所:東北大学片平さくらホール
http://www2.tagen.tohoku.ac.jp/general/event/meeting/2016/index.html
平成28年度国総研講演会
12月8日(木)10:15〜
場所:日本消防会館ニッショーホール(港区虎ノ門2-9-16)
「生産性向上」、「維持管理・競争力強化」、「防災・減災」の3つの一般セッションを設定し、最前線の研究成果等を講演します。
http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/kouenkai/kouenkai2016/kouenkai2016.htm
第15回地圏資源環境研究部門研究成果報告会
CO2地中貯留の実用化に向けて −技術課題と産総研の役割−
12月9日(金)13:30〜17:25
場所:秋葉原ダイビル・コンベンションホール
https://unit.aist.go.jp/georesenv/information/20161007.html
第193回地質汚染イブニング・セミナー
12月16日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:宮崎 毅(東京大学名誉教授)
テーマ:土壌層と水循環
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
地質学史懇話会
12月23日(金・祝)13:30〜17:00
場所:北とぴあ8階803号室(JR京浜東北線王子駅下車3分)
眞島英壽:「日本海拡大と地球科学の方法論」
石原舜三:「日本の花崗岩研究史」
総会議事次第
※総会を構成する当該代議員(任期:〜2026年6月総会まで)へは,別途メールで開催通知,議案資料,委任状等書式をお送りいたします(5月初旬送信予定).
一般社団法人日本地質学会2025年度総会開催
2025年度総会を下記の次第により開催いたします.
2025年4月19日
一般社団法人日本地質学会
会長・代表理事 山路 敦
2025年6月7日(土)14:00〜15:30
WEB会議形式で開催いたします
総会議事次第
1.議長選出
2.開会
3.議案
第1号議案 2024年度事業報告・決算報告・監査報告
第2号議案 2025年度事業計画
第3号議案 2025年度予算案
第4号議案 運営規則の変更(各賞関連規則)
4.閉会
定款20条により,本総会は役員ならびに代議員による総会となります. 代議員には,総会開催通知とともに総会に必要な資料等を別途お送りいたします.ご都合で欠席される方は,定款28条第1項にもとづき,議決権行使書および議決権の代理行使(委任状)などにより,総会に出席したものとして議決権を行使することができます.
正会員は,総会に陪席することができます.ただし,総会規則12条3項により,許可のない発言はできません.陪席を希望される方は学会事務局までお申し出ください.
北海道支部2014年度の活動
北海道支部 2014年度活動
今年度のページに戻る
日本地質学会北海道支部平成26年度(2014年度)総会
日時:2015年2月28日(土)14:00〜16:00
場所:北海道大学理学部5号館3階 5-301室
総会:14:00〜16:00
1.支部長挨拶
2.議長選出
3.議 事
A.2014年度 事業報告
B.2014年度 会計報告
C.2015年度 事業計画案
D.2015年度 予算案
E.その他
4.議長解任
懇親会:17:00〜
※2015年度北海道支部例会(個人講演会)は、2015年5月に行う予定です。詳細な案内は後程、掲示いたします。
問い合わせ先:
北海道支部幹事庶務:沢田 健
北海道大学大学院理学研究院・自然史科学部門
〒060-0810 札幌市北区北10条西8丁目
電話011-706-2733 メール:sawadak@mail.sci.hokudai.ac.jp
2014年日高巡検:報告
本巡検は北海道中軸部が分布する日高町〜平取町の範囲において、主に古第三系の日高変成帯北部〜神居古潭帯の地質を見学するものでした。タイムテーブル、参加費、参加者数を以下に示します。
10月4日(土)
9:30〜10:00 日高山脈博物館
10:00〜16:30 ウエンザル林道巡検
19:00〜21:00 討論会『古第三紀以降のテクトニクスの未解決問題+』
10月5日(日)
8:45〜13:30 岩知志〜岩内岳巡検
13:30〜16:00 千栄巡検
参加費 一般:18000円、学生・院生:13000円
巡検参加者:19名(学生・院生4名)
巡検の案内者は、日高山脈博物館の東豊土学芸員、アースサイエンス(株)の加藤孝幸氏、北海道大学の川村信人准教授の3名で、討論会では話題提供者として上記の方々に加え5名の方の個人講演をして頂きました。
本巡検は『日高変成帯北部〜神居古潭帯の横断』というテーマで行い、ウエンザル林道では、ポロシリオフィオライト帯の緑色片岩や角閃岩、日高変成帯のかん らん岩や片麻岩、角閃岩を観察しました。岩知志〜岩内岳では始新世と考えられ、岩内ナップの一員とされる沙流川層の海嶺玄武岩、沙流川超苦鉄質岩体とみか け上盤の泥岩と低角のテクトニックコンタクト(ロジン岩化)、蛇紋岩化作用をまぬがれたかんらん岩、および炭酸ガスの鉱物固定実験の行われた蛇紋岩と常温 沈澱性の蛇紋石を観察しました。千栄にある滝の沢では、前弧海盆堆積物である蝦夷層群を観察し、中部蝦夷層群の礫岩を含む堆積シークエンスを林道を歩きな がら観察しました。討論会とあわせ当地域の古第三紀以降のテクトニクスについて考えさせられる非常に内容の濃いものでした。
巡検中は参加者の露 頭に張り付く姿や案内者と積極的に討論する姿が印象的で、また討論会は予定時間を1時間以上超過するほど盛況でした。巡検および討論会に対する参加者の熱 心な姿から、学生から社会人、研究者までの様々な人にとって、とても意義のある巡検になったとことと思います。
最後に、日高山脈博物館には展示を見学させて頂くほか数々のご協力を頂き、案内者の加藤孝幸氏には討論会の組織・運営までして頂きました。ここに厚く御礼申し上げます。
(文責 西塚大)
※写真をクリックすると大きな画像が表示されます。
日高変成帯かんらん岩
日高山脈博物館前での集合写真
討論会の状況
炭酸ガスの鉱物固定実験の行われた蛇紋岩
滝の沢の蝦夷層群中部層準“基底”礫岩
沙流川層海嶺玄武岩
岩内岳かんらん岩(採石場)
ポロシリオフィオライト帯(左奥)と日高主衝上断層(右手前)
日本地質学会北海道支部平成26年度例会(個人講演会・招待講演会)
※画像をクリックするとダウンロードできます。
下記の要領で、北海道支部平成26年度例会(個人講演会・招待講演会)を開催いたしますので、ご出席のほどよろしくお願いいたします。
5月31日(土)10:30〜17:40
場所:北海道大学理学部大講堂
[大学までのアクセス、学内マップはこちらから(pdf)]
プログラム
10:30 開会のあいさつ
▶個人講演会(発表17分,質疑3分)
10:40 - 11:00 岡 孝雄・近藤 務・中村俊夫・星野フサ・安井 賢・井島行夫・関根達夫・米道 博・宿田浩司・山崎芳樹・乾 哲也・奈良智法
北海道厚真川下流域の上部更新統〜完新統の堆積環境の変遷(その1)—コア層相解析および珪藻・花粉分析—
11:00 - 11:20 近藤 務・岡 孝雄・中村俊夫・星野フサ・安井 賢・井島行夫・関根達夫・米道 博・宿田浩司・山崎芳樹・乾 哲也・奈良智法
北海道厚真川下流域の上部更新統〜完新統の堆積環境の変遷(その2)—テフラ同定とAMS14C年代測定—
11:20 - 11:40 星野フサ・片岡香子・卜部厚志
花粉分析による北海道中山峠湿原と本州中央部苗場山山頂湿地の比較
11:40 - 12:00 関根達夫、宮坂省吾
4万年前、支笏火砕流が豊平川を堰き止めて大きな湖 ”古藤野湖”を作った
(昼休み)
13:30 - 13:50 林 圭一
渦鞭毛藻シストを用いた環境復元の展開(総説)
13:50 - 14:10 安藤 卓人・沢田 健・高嶋 礼詩
苫前地域に分布する蝦夷層群Cenomanian/Turonian境界堆積岩の有機地球化学調査による古環境・古生態系の復元
14:10 - 14:30 宮田 遊磨・中村 英人・沢田 健
大夕張地域に分布する下部白亜系堆積岩のケロジェン高分子分析による古植生変動の復元
14:30 - 14:50 東 豊土・加藤孝幸・斉藤晃生・和田恵治・佐々木克久
蛇紋岩源高温型ロジン岩と日高ヒスイ
(休憩)
15:10 - 15:30 松田岳洋・中川尚大・前田仁一郎
日高山脈北部,ピパイロ石英モンゾナイトについて
15:30 - 15:50 山下康平・前田仁一郎
マントルかんらん岩と珪長質メルトの反応による斜方輝石の多様な形成プロセス:北海道曲り沢かんらん岩体の例
15:50 - 16:10 前田仁一郎・山崎 徹
中央海嶺斑れい岩の全岩化学組成:レビュウ
▶招待講演会
16:30-17:30 木村 学(東京大学理学系研究科・教授、前地質学会会長)
「地域地質研究をどのように一般化するか。北海道研究への期待」
17:30 閉会のあいさつ
※画像をクリックするとダウンロードできます。
「裏山の地質災害—豊平川の洪水」 更新!
6月1日(日)8:30〜16:30
集合・解散:札幌駅北口
見学ポイント:幌平橋、南19条大橋、藻岩下、真駒内緑町、野々沢川、十五島公園の吊橋、小金湯温泉
案内:宮坂 省吾・関根 達夫・佐々木 啓輔・岡村 聡
<参加費>2000円(予定) <定員>35名
氏名・住所・年齢・連絡先を明記して申込んで下さい!
申込み締切:5月24日(土)
申込・問い合わせ先:
北海道支部幹事庶務:沢田 健
北海道大学大学院理学研究院・自然史科学部門
〒060-0810 札幌市北区北10条西8丁目
電話011-706-2733 メール:sawadak@mail.sci.hokudai.ac.jp
日本地質学会北海道支部・遠軽町共催 白滝ジオパーク地質見学会 報告
本見学会は遠軽町との共催により白滝ジオパークのうち、黒曜岩とその周辺の日高帯から第四系までの地質を見学するものでした。タイムテーブル、参加費、参加者数を以下に示します。
6月25日(土)
10:00〜14:30 支湧別川ルート巡検
15:00〜17:00 講演会、パネルディスカッション
6月26日(日)
8:15〜15:00 赤石山ルート巡検
15:00〜15:30 遠軽町埋蔵文化財センター見学
参加費 一般:10000円、学生・院生:6000円
見学会参加者:25名(学生・院生9名)
講演会:一般参加者70名
巡 検の案内者はアースサイエンス(株)の加藤孝幸さん、岡孝雄さん、米島真由子さん、教育大旭川校の和田恵治教授の4名で、講演会は道総研地質研究所の田近 淳さん、廣瀬亘さん、教育大旭川校の和田恵治教授の3名に講師をして頂きました。また、パネルディスカッションは上記の方々に加え、北海道大学大学院の竹 下徹教授、北見工業大学の前田寛之教授にパネリストをして頂きました。
本見学会は、黒曜石で有名な白滝の地質がどのようにして成り立ったかを 学ぶもので、光輝く黒曜石に目を輝かせていた参加者の姿が特に印象的でした。また、遠軽町の町民など一般参加者を交えての講演会、パネルディスカッション を行った際には、多くの町民に参加して頂き、ジオパークに対する関心度の高さを感じました。北海道の地質、地域発展に大きな役割が期待されるジオパークと して、参考となる白滝の取組みを学ぶことができました。
見学会に対する参加者の熱心な姿から、学生から社会人、研究者までの様々な人にとって、とても意義のある見学会になったとことと思います。
最後に、本見学会の成功には遠軽町ジオパーク課、NPO法人白滝ジオパークサポートセンターの協力が欠かせないものでした。ここに厚く御礼申し上げます。
(文責 西塚大)
露頭を前にした参加者
日高累層群の砂岩・泥岩
白滝花崗岩の大露頭
黒曜石・赤石山八号沢露頭
講演会『ジオパークとは何だ!?−遠軽の大地の遺産』
白滝国際交流センター・コピエ
巡検を終えて 一同ご満悦の様子.
環境地質部会_お知らせ(地質汚染に関わる国際宣言)
2011年東北地方太平洋沖地震から学んだ地質災害防止と人工地層と地質汚染に関わる国際宣言
2015年3月14日から27日にかけて,第3回国連防災世界会議(仙台)が開催されました.参加者は全世界から約15万人以上にものぼりました.
この世界会議を契機に,国際地質科学連合(IUGS)環境管理研究委員会(GEM)(http://www.iugs-gem.org/)の「国際人工地層と地質汚染(Man Made Strata and Geo-pollution)ワーキング・グループ(委員長:楡井 久(日本地質学会環境地質部会長))」において 2011年6月に出した「国際地質災害防止宣言」*1を総括する責務から,「2011年東北地方太平洋沖地震から学んだ地質災害防止と人工地層と地質汚染に関わる国際宣言」が出されました(下記全文参照).宣言文は日本文,英文*2を作成し,英文はIUGSのホームページ(http://www.iugs.org/)の表紙,News and Information内に掲載されています.
日本の環境地質学・災害地質学で長年蓄積されてきた概念や知識が世界に認められました.
なお,宣言文内にある人自不整合(the Jinji unconformity)も国際学術用語になっております*3.
以上,会員の皆様にご報告いたします.
*1 「Katori-Narita-Itako International Declaration for deterring geological hazards such as those occurring in the 2011 Earthquake off the Pacific Coast of Tohoku」(http://manmade.iugs-gem.org/man-made-strata-overview)
*2 「Geological Hazard Prevention Measures Learned from the 2011 Earthquake off the Pacific Coast of Tohoku and the International Declaration on Man-Made Strata and Geo-pollution」(http://iugs.org/uploads/MMS%20%20GP%20WG%20Declaration%202015.pdf)
*3上砂正一(2015)国際学術用語となった“人自不整合”.日本地質学会News,Vol18, No.6, 13.(http://www.geosociety.jp/faq/content0588.html)
環境地質部会
田村嘉之((一財)千葉県環境財団)
-------------------------------------------------------(以下全文掲載)-------------------------------------------------------
2011年東北地方太平洋沖地震から学んだ地質災害防止と
人工地層と地質汚染に関わる国際宣言
2011 年3月11日に発生した東日本大震災から4年が経過しました。我々、世界の人工地層と地質汚染の研究に係わる研究者は、あらためて帰らぬ犠牲者の方々のご 冥福を祈り、被災された方々にお見舞い申し上げます。被害地域の科学的復興の速度が高まることを心よりお祈り申し上げます。
また、原子力発電所事故による放射能汚染の被害者の健康と、汚染地が科学的で子孫へも誇れる夢のある地域復興が進むことを祈念いたします。
私達の国際ワークキング・グループ(国際地質科学連合(IUGS)環境管理研究委員会 (GEM) 人工地層と地質汚染に関わる国際ワーキング・グループ゚(MMS&GP))は、震災直後の2011年6月18日に、“2011年東北地方太平洋沖地震にか かわる国際地質災害防止宣言”をだしました(IUGS GEM)。
①液状化−流動化・地波現象被害に関わる被害と調査・対策、 ②津波被害からの避難と対策 ③福島第1原子力発電所事故からの放射能汚染の調査対策の三点です。
第3回国連防災世界会議(仙台)(2015年3月14日〜18日)を契機に、前述の国際地質災害防止宣言を総括するのも私達の国際ワークキング・グループ の責務であります。総括すると、震災後4年を経た今日でも、各内容とも正鵠を得てきています。したがって、今後の国際地震防災・減災や原子力発電所事故に よる放射能汚染調査・対策には有効で重要な宣言となりました。
一方、完新世になって、我々人間の文明が進むとともに利便性が高まり、同時に災害の 規模も大きくなってきていることです。特に、人間が陸地・沿岸を開発し利用するのにともなって、人工地層の分布は拡大し、それは加速しています。そして、 人工地層は、自然地層に比較してさらに物性的・化学的面で多様性を示します。この多様化現象も加速しています。また、人自不整合面や多様性を持つ人工地層 内では、地下水流動系も複雑です。
特に、東日本大地震から4年を経過した調査から得た教訓は、人工地層分布地域で複合災害・複合汚染が多く発生し ていることです。例をあげれば、①防波堤や津波避難用沿岸道路が津波来襲前に液流動化・地波で破壊され、その後に大津波が襲う複合災害、②液状化―流動 化・地波にともなう人工地層中の汚染物質の移動・噴出による汚染発生と拡大の複合災害、③福島第一原子力発電所事故による放射性物質高濃度汚染沿岸の人工 地層分布域では、液流動化被害・津波被害・放射性物質による汚染といったこの3重の複合災害が発生していることなどがあげられます。
人工地層と地 質汚染に関わる国際地質科学連合(IUGS)環境管理研究委員会(GEM)の国際人工地層と地質汚染ワーキング・グループ(MMS&GP)は、人工地層の 研究から、地震時の地質災害には、人自不整合と人工地層とが深く関わっていることが確認できました。また、福島第一原子力発電所事故で発生した放射性物質 の2次堆積層は、人工地層の形成過程を経ていることも確認できました。
特に、完新世になって人間の活動が加速化し、今後とも人工地層の拡大は避け てとおれません。人工地層の形成過程や人自不整合が、災害に大きくかかわることが明らかになり、第3回国連防災世界会議(仙台)を契機に、全世界の人間が 災害から避けられるように、これらの研究が益々重要になってきていることを指摘するものです。
国際地質科学連合(IUGS)環境管理研究委員会 (GEM) 人工地層と
地質汚染に関わる国際ワーキング・グループ゚(MMS&GP)
2015年3月11日
2015年度各賞受賞者
2015年度各賞受賞者 受賞理由
■日本地質学会賞(1件)
■小澤儀明賞(1件)
■Island Arc賞(1件)
■論文賞(2件)
■小藤文次郎賞(2件)
■研究奨励賞(1件)
■功労賞(1件)
■学会表彰(1件)
日本地質学会賞
受賞者:脇田浩二(山口大学大学院理工学研究科)
対象研究テーマ:付加体地質学を基にした日本〜アジアのシームレス地質研究
脇田浩二会員は,野外調査による付加体の実態解明のため世界最高レベルの付加体地質図を作成し,日本および世界の付加体地質図表現の国際標準を確立した.以前は地向斜論に基づいて“地層”として表現されていた地質体が,海洋プレート層序の破断変形プロセスを通じて形成された構造ユニットの集合体であることを明らかにし,地質調査所(現産総研)の地質図幅で初めて付加体の概念を取り入れた「八幡地域の地質」を著し,その後も付加体の地質図を多数公表してきた.特に,変形の激しい地質体“メランジュ”については,泥ダイアピルや構造変形を含む多重変形プロ
セスでその形成を説明し,付加体の基本構造の地質図表現を世界に先駆けて提示した.また,日本で確立した技術を基にアジアの付加体の解明も推進し,海洋プレート層序に基づく付加体の理解をアジア地域にも広く浸透させた.これらの研究成果は,論文及び地質図・地質構造図として多く出版され,国内外の学会・産業界・教育界で広く活用されている.
これらと並行して,日本およびアジアの地質情報の整備と流通促進のため,日本およびアジアの小縮尺地質図・地質構造図編集やデジタル化を推進するとともに,国際標準に基づく地質情報のウェブ流通を,日本およびアジアの代表として推進してきた.近年出版された2つのアジアの広域地質図では,日本からの唯一の主編者となった.更に日本およびアジアの地質図の普及を進めるため,地理空間情報システムによるデジタル化を主導し,ウェブで流通させるための,国際標準に基づく情報流通システムの確立を,日本およびアジアの代表として推進してきた.国際地質科学連合の地質情報標準管理委員会の評議委員を設立当時から10年間務め,世界中の100万分の1 地質図のウェブ流通を進めるOneGeologyプロジェクトを,アジアの代表として推進してきた.また後年,地質図Naviとして結実することになる,日本シームレス地質図の作成では,脇田氏はプロジェクトリーダーとして,ばらばらだった20万分の1地質図の凡例を統一し,地質図間で食い違う地質境界を連続させ,2005年にインターネット上で初公開して,ウェブを通じた地質図利用という新しい道筋をつけた.現在,同サイトは教育・研究・営利事業と様々な面に活用され,年間アクセス数は1200万に達している.
以上のような付加体地質学への業績と地質学の発展への貢献に鑑み,脇田浩二会員を日本地質学会賞に推薦する.
日本地質学小澤儀明賞
受賞者:辻 健(九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所)
対象研究テーマ:地震探査データ解析の高精度化によるプレート境界断層の形態と応力分布に関する研究
辻 健会員は,地震探査データの解析と解釈を基軸にし,掘削や野外調査で得られた情報とあわせ,プレート境界断層やその分岐断層の地質構造を総合的に理解すべく努力してきた.南海トラフ付加体の断層は古くから議論されているが,トラフ軸に続くデコルマと,地震を発生させると考えられている分岐断層の関係は明らかになっていなかった.これは,地震探査データの解像度の限界のためである.辻会員は,波形インバージョンという手法を改良することで,深部に発達する分岐断層の弾性波速度を高い解像度で推定した.さらに,独自に開発した岩石物理理論を使い,分岐断層の間隙水圧や応力状態を推定することに成功した.その結果,これまで不明瞭であった分岐断層とデコルマの関係が明らかとなり,付加体の断層構造が見直されることとなった.さらに,分岐断層が横ずれ運動に卓越していることなども明らかしている.これらの成果は断層のモデル化に重要な情報となっている.日本海溝では,2011年東北地方太平洋沖地震の前から、地震探査の結果をもとに潜水艇を用いた調査を継続的に実施し,熱流量や海底面の変化から2011年の地震で活動した正断層を特定することに成功している.この断層運動は,津波地震に特徴的な上盤プレートの引張過程に関係するとされ,津波の発生機構の解明の点で重要な結果となっている.さらに津波励起域では,島弧地殻が海溝付近まで迫り出しているといった地質構造も明らかにした.このように辻会員は,積極的に野外調査や研究航海に参加し,プレート境界断層の形態や応力状態の解明に貢献してきた.辻会員は,60編以上の論文を公表し,多くの招待講演を行っている.彼の地震探査データの解析能力は第1級であるが,それ以外にも衛星データを用いた地盤沈下の研究,熱水循環経路の研究,氷河の研究,間隙流体シミュレーションによる浸透特性の研究など,多岐にわたる課題を研究している.統合国際深海掘削計画IODPの第327次航海では,共同主席研究者として,国内外の研究者を取りまとめた実績がある.またJ-DESCの執行委員を務めるなど,研究以外の活動も積極的に行っている.現在,彼は九州大学の国際研究所で,研究部門長として部門全体のとりまとめを行っている.このように,候補者は国際的な次世代リーダーとしての資質もある.以上の実績から,辻 健会員を小澤儀明賞に推薦する.
日本地質学会Island Arc賞
受賞論文: Arai, S.,Okamura, H., Kadoshima,K., Tanaka, C., Suzuki, K. and Ishimaru, S., 2011,Chemical characteristics of chromianspinelin pl utonic rocks:Implications for deep magma processes and discrimination of tectonic setting. Island Arc,20,125-137.
This paper compiles major element data of spinel based on thefirst author’slong-standingresearches and other relevant literatures and haspresented an explicit relationship of geochemistry of spinel and tectonic settings. The results havealso deepenedour understanding of deep magmaticprocesses. Although the usefulness of spinelhas been shownby the first author’s number of works, the paper provides adistinctive criterion of discriminating not well understood tectonic settings of igneous bodies such as thoseof ophiolites, whichis so convenient for earth scientists who are interested in tectonics but are not experts of igneous petrology.
This paper received the highest number of citations–based on the Thomson Science Index for the year 2014–amongst the entire candidate Island Arc papers published in 2011–2012, which will contribute to increasing the impact factor of Island Arc. The first author, Dr.Shoji Arai,has been one of the most active Japanese petrologists working on mantle peridotites and deep crustal rocks from ophiolites, xenoliths and present ocean floors. Specifically he is renown for his prominent researches on spinel in mantle peridotites and volcanic rocks, whichmade him known as “Arai of spinel”. This paper adds to his many contributions andis a worthy receipt of the 2015 Island Arc Award.
日本地質学会論文賞
受賞論文:Kouketsu, Y., Mizukami, T., Mori, H., Endo, S., Aoya, M., Hara, H., Nakamura, D and Wallis, S., 2014, A new approach to develop the Raman carbonaceous material geothermometer for low-grade metamorphism using peak width. Island Arc, 23, 33–50.
地殻内部の温度構造は,地殻変動や大陸形成のプロセスを考える上で重要な基礎情報であり,それらを記録している岩石の変成温度推定とその手法確立は重要な課題である.ラマン炭質物温度計は,そのような温度推定方法の一つとして注目を集めてきた.本論文は,堆積岩起源変成岩に含まれる炭質物を対象とし,ラマン分光による比較的簡便,かつ,従来より正確な中低温での地質温度計を提案したものである.分光により得られるラマンスペクトルについて,適切なピークの分離手順・解析法を提案し,その方法を,岩質,時代,セッティングの異なる堆積岩起源変成岩に応用した.その結果,150〜400℃の範囲内では,ピーク半値幅が,既知の変成温度と直線的関係にあることを見出し,従来よりも精度の高い地質温度計となりうることを示した.この手法は,今後,変成作用や地殻内部構造の解析に広く応用されることが期待される.よって,本論文を日本地質学会論文賞に値するものとして推薦する.
日本地質学会論文賞
受賞論文:岩野英樹・折橋裕二・檀原徹・平田岳史・小笠原正継,2012,同一ジルコン結晶を用いたフィッション・トラックとU-Pbダブル年代測定法の評価―島根県川本花崗閃緑岩中の均質ジルコンを用いて―.地質学雑誌,118,365–375.
同一試料から閉鎖温度の異なる複数の年代測定を行う,いわゆるマルチクロノロジー手法は,熱履歴に基づく定量的テクトニクスモデルの構築に大きく貢献しているが,それにともない,年代データのより厳しい信頼性評価も必要になっている.本論文は,同一ジルコン粒子を用いたFT法とU-Pb法のダブル年代測定において,FT分析工程で実施するエッチングなどの化学処理がその後に測定するU-Pb年代データに与える影響を評価した.検討試料を厳選し検証を行った結果,化学処理の有無によってもU-Pb年代に有意な差はなく, 同一ジルコン粒子のFTおよびU-Pbマルチクロノロジーが十分な信頼性をもつことが示された.一連の検証は,緻密で論理的に進められており,今後のマルチクロノロジーの適用における貢献は大きいと考えられる.以上のことから,本論文を日本地質学会論文賞に推薦する.
日本地質学会小藤文次郎賞
受賞者:堤 浩之(京都大学大学院理学研究科)
対象論文: Tsutsumi, H., Sato, K.and Yamaji, A., 2012,Stability of the regional stress field in central Japan during the late Quaternary inferred from the stress inversion of the active fault data. GeophyscalResearch Letter, 39, L23303, doi:10.1029/2012GL054094.
堤 浩之会員らによる本論文は,近畿三角帯に分布する37の活断層群から得た169におよぶ断層データに応力インバージョン法を適用し,この地域の活断層群の動きがWNWESE方向の一軸水平圧縮に近い応力で説明できること,さらにはこの応力が最近十万年以上にわたって安定であったことを,データにもとづいて実証的に示した.比較的最近になって蓄積が始まった地球物理学的データだけでは理解しきれない,数万年間の過去にわたる地殻応力を解き明かしたことは,活断層研究に大きな方向性を示したものといえる.また,長期的な地殻応力データを供することによる社会的な貢献も大きいと考えられる.これらの理由から,研究を中心となって推進した堤 浩之会員を小藤文次郎賞に推薦する.
日本地質学会小藤文次郎賞
受賞者:氏家恒太郎(筑波大学生命環境系)
対象論文: U j i i e , K.,Tanaka, H., Saito, T., Tsutsumi, A., Mori, J.J., Kameda, J., Brodsky, E.E., Chester, F.M., Eguchi, N., Toczko, S.and Expedition 343 and 343T Scientists, 2013, Low coseismic shear stress on the Tohoku-Oki megathrust determined from laboratory experiments. Science, 342, 1211-1214.
氏家恒太郎会員らによる本論文は,2011年東北地方太平洋沖地震の地震断層を地球深部探査船「ちきゅう」によって掘り抜いた,統合深海掘削計画の第343次航海を代表する成果である.氏家会員らは,プレート境界断層の破砕帯から採取されたコアの構造地質学的観察と,同じ試料を用いた高速剪断試験にもとづいて,海溝付近までプレート境界断層が変位した今回の地震断層のスリップメカニズムの解明を試みた.その結果,スメクタイトを多く含む破砕物質の存在と,高速すべり時の間隙水の熱膨張によってプレート境界断層が弱化するという,これまで提示されていた描像がこの大地震で実際におきたことを明らかにした.そして,巨大災害の発生メカニズムの探求における地質学の役割を明らかにする,時宜にかなった論文としてまとめた.これらの理由から,研究を中心となって推進した氏家恒太郎会員を小藤文次郎賞に推薦する.
日本地質学会研究奨励賞
受賞者:越智真人(東建ジオテック株式会社)
対象論文:越智真人・間宮隆裕・楠橋 直,2014,四国の中新統久万層群層序の再検討:“下坂場峠層”と“富重層”.地質学雑誌,120,165-179.
中新統久万層群は中央構造線の両側に分布する最古の地層であり,中央構造線の運動史,ひいては西南日本の広域テクトニクスを制約する重要な地層である.対象論文は,地質踏査をもとに同層群の層序を再検討したもので,古典的な岩相記載をベースに幾つかの新知見を得ている.なかでも,外帯側にだけ分布する下部始新統ひわだ峠層が,久万層群とナップではなく不整合関係にあることを示したことは,中期中新世に中央構造線で大規模な衝上運動があったとする近年の仮説に対しての否定的証拠として,特筆すべき成果といえる.本論文は地域地質層序を扱いながらも,実は広範なインパクトを持つと判断される.これらの成果は地道な地質踏査が実を結んだ結果であり,その研究スタイルは大いに奨励されるべきものである.以上の理由から,越智真人会員を日本地質学会研究奨励賞に推薦する.
日本地質学会功労賞(1件)
受賞者:大山次男(東北大学理学部技術部)
功労業績:岩石研磨薄片技術の高度化
大山次男氏は,1967年4月に東北大学理学部岩石鉱物鉱床学教室(現東北大学理学部地球惑星物質科学科)の薄片室に採用されて以来,2010年3月に定年退職するまでの43年間,岩石薄片の作製とその技術の高度化に尽力した.退職後も,その薄片作製の技術力を後進に伝承するべく,再雇用職員および非常勤職員として,現役で活躍中である.この間,2001年には文部科学大臣表彰創意工夫功労者賞を受賞した.また2006年には,日本岩石鉱物特殊技術研究会(現日本薄片研磨片技術研究会)の会長職に就任し,日本全国の薄片研磨技術職員を統括し,各地で薄片技術に関するセミナーや研究会を立ち上げた.このような取り組みによって,日本の地質学や地球科学系学科の全国的な薄片技術の基礎力アップに貢献した.大山氏は強い科学的探究心も有し,薄片作製の傍ら地球科学に関する専門知識の習得にも努め,1998年には仙台市太白山の輝石安山岩中の晶洞に産するクリストバライトに関する学術論文を発表した.同論文では,晶洞に産する石英について,薄片観察・電子顕微鏡観察・X線回折を通してクリストバライトであることを見出し,安山岩固結後に揮発成分か高温流体が貫入し,そこからクリストバライトが結晶成長したことを証明した.大山氏は岩石薄片作製を通して,日本における地質学研究を支えてきただけでなく,教育にも大きな貢献を果たした.東北大学が輩出した多くの研究者・技術者・教育者が,大山氏の熱意ある献身的作業により,研究を大きく進展させることができた.以上のように,大山次男氏の地質学の研究・教育に対する貢献は極めて大きく,まさに縁の下の力持ちという存在と評価される.この貢献は日本地質学会の功労賞に値するものと考え,同賞に推薦する.
日本地質学会表彰
受賞者:白尾元理(写真家)
表彰業績:ジオフォト文化の先駆と発展,その科学的メッセージの発信
白尾元理会員は,地質をモチーフとして活躍する写真家であり,ジオフォトという新しい写真文化を開拓してきた第一人者である.これまでに国内はもとより世界各国の美しい地質をテーマとした作品を数多く発表している.卓越した写真センスと地質学的視点とを組み合わせた作品は,芸術性ばかりでなく学術的な評価も高く,教科書などにも広く採用されている.また,「新版日本列島の20億年景観50選」,「写真でみる火山の自然史」,「火山とクレーターを旅する―地球ウォッチング紀行」など,美しい写真作品とわかりやすい地質解説とを組み合わせた優れた著書を数多く出版し,地質学の教育と普及に大きく貢献している.とりわけ2012年に出版された「地球全史写真が語る46億年の奇跡」は,世界数十ヶ国の地質風景とその背景となる科学的解説とをマッチさせて地球全史を紹介する画期的な出版物であり,児童・生徒から地質の専門家まで幅広い読者層を魅了させる歴史的な業績と言えよう.また白尾会員は,日本地質学会の広報誌ジオルジュの表紙とカバーストーリーに素晴らしい作品を創刊以来提供し続けている.白尾会員の美しい作品は,ジオルジュの「顔」として同誌のクオリティを引き上げたばかりでなく,地質の美しさをもって地質学のイメージを一新するものである.また白尾会員は,日本地質学会が主催する惑星地球フォトコンテストの審査委員長をコンテスト初回から現在まで務め,コンテストの発展にも貢献してきた.そのおかげで,会員のみならずプロ・アマチュアを含む数百名のネイチャーフォトグラファーが腕を競うジオフォト最高峰のコンテストに成長しつつある.コンテストの表彰式では,入賞作品を講評し,撮影者を激励することで,この分野の発展に尽している.入賞作品は全国の自然博物館などに展示され,新しい写真文化の創造に役立っている.以上のように,写真作品を通じてジオの美しさと,その背景にある科学的メッセージを伝え,地質学のイメージを一新する白尾元理会員の業績は日本地質学会表彰に相応しく,ここに推薦する.
Geo暦(2017)
2017年Geo暦(行事カレンダー)
2008年版 2009年版 2010年版 2011年版 2012年版 2013年版
2014年版 2015年版 2016年版 ------------ 2018年版
2017年版 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
○印は学会主催行事.(共)学会共催・(後)後援・(協)協賛
1月January
(協)第14回岩の力学国内シンポジウム:JSRM2017
1月10日(火)〜12日(木)
会場:神戸大学百年記念館
http://rock.jsms.jp/jsrm2017/
県の化石の展示(日本地質学会が選考した県の石から)
1月13日(金)〜4月9日(日)
会場:荒木集成館(名古屋市天白区中平5-616)
主催:東海化石研究会・荒木集成館
入場料:大人300円
http://www.arakishuseikan.ecweb.jp
(後)地質標本館新春特別展 ふるさとの新たな主役「県の石」
1月17日(火)〜 2月26日(日)
場所:産総研地質標本館
https://www.gsj.jp/Muse/exhibition/archives/2017/2017_spring.html
(後)ふしぎ発見!鳥取砂丘(鳥取砂丘調査研究報告会)
1月21日(土)13:00〜16:30
場所:とりぎん文化会館第2会議室
主催:鳥取砂丘再生会議
http://www.tottorisakyu.jp/
第194回地質汚染イブニング・セミナー
1月27日(金)18:30〜20:30
場所 :北とぴあ901会議室
講師:古野邦雄(元千葉県環境研究センター主席研究員)
高嶋 洋(野田市道路管理課主査)
テーマ:関東地下水盆管理と水循環基本法
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
2月February
第21回「震災対策技術展」横浜
2月2日(木)〜3日(金) 10:00〜17:00
会場:パシフィコ横浜
参加費無料
https://www.shinsaiexpo.com/yokohama/
ふじのくに地球環境史ミュージアム
国際シンポジウム「人類世の到来―自然史と文化史」
会場:グランシップ(静岡市駿河区池田79-4;JR東静岡駅東口)
2月11日(土)10:00〜18:00
学術シンポジウム
第一部「人類世の山・湖・海岸」山田和芳ほか3名
第二部「人類世の動植物―多様性・栽培・移住」五箇公一ほか4名
第三部「山岳と人類世―牧畜・鉱山・遺産」Kevin Walshほか3名
2月12日(日)10:00〜12:30
公開シンポジウム『人類世の自然と文化』内山純蔵ほか3名
2月13日(月)関連施設見学ツアー
https://www.fujimu100.jp/sympo2017/
連続公開シンポジウム:熊本地震において通信とメディアが果たした役割
主催 早稲田大学国際メディア財団プロジェクト、公益情報通信学会
共催 地区防災計画学会、情報通信学会災害情報法研究会ほか
2月14日(火)14:30〜17:40
場所:一般社団法人電波産業会(千代田区霞が関1-4-1)
参加費無料・定員80名(要申込)
http://www.gakkai.chiku-bousai.jp/ev170214.html
明治大学危機管理研究センター第36回定例研究会・シンポジウム
2月19日(日)10:00〜16:30
会場:明治大学駿河台キャンパスアカデミーコモン8階308F教室
参加無料
http://www.kisc.meiji.ac.jp/~crisishp/ja/notification.html#20170113
第195回地質汚染イブニングセミナー
2月24日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ902会議室
講師:張 銘(産総研 地圏環境リスク研究グループ長)
テーマ:環境微生物による揮発性有機化合物(VOCs)複合汚染の分解
http://www.npo-geopol.or.jp
3月March
日本学術会議公開シンポジウム
「学術振興の観点から国立大学の教育研究と国による支援のあり方を考える」
3月1日(水)13:30 〜17:00
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木)
参加費無料・事前登録不要
http://www.scj.go.jp/ja/event/
平成28年度海洋研究開発機構研究報告会:JAMSTEC2017
3月1日(水)13:30〜17:30
場所:東京国際フォーラムホールB7(千代田区丸の内3-5-1)
http://www.jamstec.go.jp/j/pr/event/jamstec2017/
ブルーアース2017
3月2日(木)〜3日(金)
場所:日本大学理工学部 駿河台キャンパス1号館
http://www.jamstec.go.jp/maritec/j/blueearth/2017/index.html
(共)4th IGS (international Geoscience Symposium) Precambrian World 2” in Fukuoka
3月3日(金)〜5日(日)
会場:九州大学西陣プラザ
Abstract締め切り:11月25日(金)
J. カーシュビング教授 Caltec スノーボールアースー生物進化
W. ブローカー博士(カナダ地質調査所)太古代ー原生代大陸復元
A. ホフマン教授(ヨハネスブルグ大学)太古代の表層環境 34億年前のチャート掘削 等を予定です。
www.archean.jp
第6回学生のヒマラヤ野外実習ツアー(日本地質学会推薦)
暫定日程:3月4日〜18日の15日間
コース:中西部ネパールヒマラヤの全断面で、ポカラを通る南北のルート
実施主体:ゴンドワナ地質環境研究所とネパール国立トリブバン大学トリチャンド ラキャンパス地質学教室が共同で実施
参加申込受付期間:2016年6月1日(水)〜11月30日(水)
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
原子力発電環境整備機構(NUMO)国際講演会
「カナダにおける地層処分計画の現状と今後」
3月10日(金)13:30〜16:00
会場:建築会館ホール(東京都港区芝5-26-20)
申込締切:3月6日(月)17:00
http://www.numo.or.jp/topics/201617021710.html
東京都水道歴史館講演会
「荒川流域の地形的な特徴と治水・利水―デジタル標高地形図を題材に―」
※事前申込受付中※
3月11日(土)14:00〜16:00
会場:東京都水道歴史館3階レクチャーホール
http://www.suidorekishi.jp/event.html#event_talk03
○北海道支部平成28年度(2016年度)総会
3月11日(土)
会場:北海道大学理学部6号館2階 6-204室
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
第51回日本水環境学会年会
3月15日(水)〜17日(金)
会場:熊本大学黒髪キャンパス
https://www.jswe.or.jp/guest/entry.php
第24回GSJシンポジウム「ようこそジオ・ワールドへ」
3月18日(土)13:00〜17:00
会場:TKP神田ビジネスセンター5F(JR神田駅東口)
第一部 体験型講座
「地質学基本の“き”」高橋雅紀
第二部 講演会
「宮澤賢治とジオ・ロマン」加藤碵一
「地学オリンピックの10年-その歩みと功績-」瀧上豊・冨永紘平
「地学教育への期待」川辺文久
https://unit.aist.go.jp/igg/ja/event/sympo001.html
日本堆積学会2017年松本大会
3月25日(土)〜28日(火)
会場:信州大学理学部講義棟
25日 ワークショップ
26-27日 個人講演,特別講演,総会等,
28日 巡検
http://sediment.jp/04nennkai/2017/annai.html
第196回地質汚染イブニングセミナー
3月31日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:後藤文昭(三井住友信託銀行経営企画部CSR推進室)
テーマ:環境と金融〜土壌汚染を題材として〜
http://www.npo-geopol.or.jp
4月April
○第8回惑星地球フォトコンテスト:表彰式
4月8日(土)12:45〜13:45
場所:北とぴあ 901会議室(東京都北区王子)
http://photo.geosociety.jp/
○関東支部:2017年度総会・地質技術伝承講演会
4月15日(土)14:00〜16:45
場所:赤羽会館 4階小ホール(東京都北区赤羽南1-13-1)
地質技術伝承講演会
「(仮)環境地質調査のはなし−現場手法と解析−」
講師:岡野英樹((株)東建ジオテック 本店技術部課長)
http://kanto.geosociety.jp/
日本学術会議公開シンポジウム/第3回 防災学術連携シンポジウム
熊本地震 追悼・復興祈念行事「熊本地震・1周年報告会」
4月15日(土)11:00〜18:20
場所:熊本県庁本館 地下大会議室(熊本市中央区水前寺6-18-1)
主催:内閣府 日本学術会議 防災減災・災害復興に関する学術連携委員会/熊本
県/防災学術連携体(防災に関わる55学会のネットワーク)
参加無料・定員450名
資料:発表資料は前日の夕方にHPに掲載予定(資料の配布はありません).
参加申込み等詳細は,http://janet-dr.com/
(後)学術会議公開シンポジウム
「地質地盤情報の共有化を目指して−安全安心で豊かな社会の構築に向けて−」
4月27日(木)13:30-17:40
会場:日本学術会議講堂(港区六本木)
http://www.scj.go.jp/ja/event/index.html
第197回地質汚染イブニングセミナー
4月28日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室(東京都北区王子)
講師:田村嘉之・山浜 裕(千葉県環境財団)
テーマ:関東平野の水循環の諸問題―ローム台地での涵養・流出と地質汚染問題―
http://www.npo-geopol.or.jp/
5月May
第16回重金属類・残土石処分地・廃棄物処分地診断に関わる地質汚染調査浄化技術研修会
5月1日(月)〜4日(木)
会場:日本地質汚染審査機構関東ベースン実習センター(千葉県香取市)
http://www.npo-geopol.or.jp/index.htm
第3回西日本支部地質講習会(CPD講習会)
5月17日(水)〜18日(木)
会場:山口大学吉田キャンパス大学会館
地質巡検:18日(木) 徳佐から津和野地域
申込締切:5月8日(月)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
JpGU-AGU Joint Meeting 2017
5月20日(土)〜25日(木)
会場:千葉県 幕張メッセ
投稿早期締切 2月3日(金)12:00
投稿最終締切 2月16日(木)17:00
http://www.jpgu.org/meeting_2017/
第198回地質汚染イブニングセミナー
5月26日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室(東京都北区王子)
講師:楡井 久 (日本地質汚染審査機構 理事長)
テーマ:国民が学んだ教訓―東京豊洲新市場の地質汚染問題と液状化―流動化・地波問題からー
http://www.npo-geopol.or.jp/
6月June
第2回若手科学者サミット
6月2日(金)13:30〜18:00
場所:日本学術会議・講堂(港区六本木)
http://www.geosociety.jp/outline/content0096.html
日本古生物学会2017年年会・総会
6月9日(金)〜11日(日)
場所:北九州市立自然史・歴史博物館
http://www.palaeo-soc-japan.jp/events/
東京地学協会平成29年度春季講演会
「ネパール−自然の魅力と人々の暮らし−」
6月10日(土)13:15〜
場所:東京グリーンパレス(千代田区二番町2番地)
http://www.geog.or.jp/
西太平洋堆積学会議2017
6月12日(月)〜17日(土)
(会議:6/12-13,巡検:6/14-17,6/11夕方:アイスブレーカー)
場所:韓国光州市(Gwangju, Korea)
http://sediment.jp/08related/2017WPSM.html
○中部支部2017年支部年会
6月17日(土)10:00〜
会場:新潟県糸魚川市フォッサマグナミュージアム
シンポジウム (13:00-15:00)
「地質学とジオパーク −現状と今後の課題—」
http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
○北海道支部平成29年度例会(個人講演会)
6月17日(土)13:00〜17:30
場所:北海道大学理学部5号館大講堂
招待講演会「地質学会が選定する北海道の化石「アンモナイト」について」:栗原憲一 (北海道博物館)
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html#2017reikai
地質学史懇話会
6月17日(土)13:00〜17:00
場所:北とぴあ 8階804号室(JR京浜東北線王子駅下車3分)
平山 廉「カメの始まりから2億年の歴史を語る」
山田俊弘「17世紀西欧における「ジオコスモス」の変容:ステノの『サメの頭部の解剖』(1667)350周年を記念して」
IGCP630 Annual Symposium (2017)
“Permian-Triassic climatic & environmental extremes and biotic responses”
6月14日(水)〜16日(金)
場所:東北大学
講演申込・要旨提出,巡検申込締切:3月20日(月)
https://amarys-jtb.jp/icgp630/
2017年度資源地質学会年会
6月21日(木)〜23日(金)
--21日(水)表彰講演,国際シンポジウム,懇親会
会場:東京大学 伊藤謝恩ホール(文京区本郷7-3-1)
(赤門の隣、伊藤国際学術研究センター地下2階)
--22日(木)〜23日(金)一般講演(口頭発表,ポスターセッション)
会場:東京大学 小柴ホール(文京区本郷7-3-1)
(理学部1号館2階)
*国際シンポジウム「The Japanese Porphyry Copper Enigma」
21日(水)13:00〜18:00
//www.resource-geology.jp/events/#p221
第199回地質汚染イブニングセミナー
6月30日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:村瀬 誠(薬学博士・東邦大学薬学部客員教授)
テーマ :雨水利用と水循環について(仮)
http://www.npo-geopol.or.jp/
7月July
(共)第54回アイソトープ・放射線研究発表会
7月5日(水)〜7日(金)
会場:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
発表論文の申込締切:2017年2月28日(火)17:00
http://www.jrias.or.jp/
International Conference on Geology, Mining, Mineral and Groundwater Resources of the Sub-Saharan Africa: Opportunities and Challenges Ahead
7月11日(火)〜13日(木)
場所:ザンビア共和国、リビングストン
http://mines.unza.zm/conference/
(後)「放散虫とかたち展」
7月12日(水)〜 8月31日(木)
場所:新潟大学駅南キャンパス「ときめいと」
主催:新潟大学旭町学術資料展示館、理学部など
http://www.lib.niigata-u.ac.jp/tenjikan/kikaku/doc/k170712.html
(後)「青少年のための科学の祭典」2017全国大会
7月29日(土)〜30日(日)
会場:科学技術館(千代田区北の丸公園2-1)
http://www.kagakunosaiten.jp/
8月August
「震災対策技術展」東北
8月2日(水)〜3日(木)
場所:AERビル(仙台市青葉区中央)
https://www.shinsaiexpo.com/tohoku/
(後)科学教育研究協議会第64回全国研究大会
8月7日(月)〜9日(水)
場所:広島なぎさ中学高等学校(広島県佐伯区)
http://kakyokyo.main.jp/
○関東支部:地学教育・アウトリーチ巡検
「火山灰を追跡する-浅間火山の噴出物と噴火史」
8月7日(月)〜8日(火)1泊2日
講師:大石雅之(立正大学地球環境科学部)
参加申込:7月10日(月)締切
http://www.geosociety.jp/faq/content0715.html#kanto
福島県「県の石」選定記念特別講演会
8月20日(日)14:00開演
場所:石川町立石川小学校 クリスタルホール
http://www.town.ishikawa.fukushima.jp/event/entry/005686.html
○関東支部:清澄フィールドキャンプ
8月21日(月)〜26日(土) 5泊6日
場所:東京大学千葉演習林(千葉県鴨川市清澄)
費用:30000円(学生),40000円(社会人)程度を予定
参加申込:7月7日(金)締切
http://kanto.geosociety.jp/
第10回白亜紀国際シンポジウム(10th ISC 2017)
8月21日 (月) 〜24日 (木)
場所:オーストリア・ウィーン
UZA II (Universitätszentrum Althanstrasse)
巡検:プレ3コース,ポスト4コース(オーストラリア,スロバキア,チェコ他)
https://10cretsymp.univie.ac.at/home/
第71回地学団体研究会総会(旭川)
8月25日(金)〜27日(日)
場所:北海道旭川市大雪クリスタルホール・神楽市民交流センター
https://sites.google.com/view/soukai2017
記念式典及び第201回地質汚染イブニングセミナー
場所:北とぴあ901会議室
8月25日(金)18:30〜20:30
18:30〜19:30 第200回記念式典・各理事の祝辞
19:30〜20:30 第201回イブニングセミナー
講師:愛甲義昭(桜富士テクニカルアカデミィ日本事務所代表・NPO日本地質汚
染審査機構専門会員)
テーマ:日本地質汚染審査機構と地質汚染調査・浄化に貢献してきた思い出
http://www.npo-geopol.or.jp
9月September
日本鉱物科学会2017年年会
9月12日(火)〜14日(木)
会場:愛媛大学城北キャンパス
http://jams.la.coocan.jp/2017nenkai/2017nenkai.html
(共)2017年度日本地球化学会第64回年会
9月13日(水)〜15日(金)
会場:東京工業大学・大岡山キャンパス
参加申込:8月21日(月)17時締切
http://www.geochem.jp/conf/2017/
*プログラム公開しました
http://www.geochem.jp/conf/2017/program.html
第34回歴史地震研究会(つくば大会)
9月15日(金)〜17日(日)
場所:つくばイノベーションプラザ(TXつくば駅徒歩3分)
http://sakuya.ed.shizuoka.ac.jp/rzisin/menu7.html
○日本地質学会第124年学術大会(愛媛大会)
9月16日(土)〜18日(月)
会場:愛媛大学 城北キャンパス(松山市文京)
事前参加登録:8月21日(月)18:00 締切
大会WEBサイトはこちらから
(共)海底火山研究国際シンポジウム
9月20日(水)14:00〜18:00
場所:国立科学博物館本館2階講堂
要事前申込(定員100名)申込締切:9月13日(水)
http://www.kahaku.go.jp/news/2017/seamount/
地学クラブ講演会
ノルデンショルド一行の世界史的偉業と東京地学協会創立時の国際的文化行事
9月22日(金)14:00〜15:00
場所:東京地学協会地学会館
講演者:西川 治(東京大学名誉教授)
http://www.geog.or.jp/lecture/lecturescheduled/307-club302.html
女子大学院生・ポスドクと産総研女性研究者との懇談会 in 名古屋
9月25日(月)13:15〜17:00
会場:産業技術総合研究所 中部センターOSL棟 連携会議場
対象:女子大学院生・ポスドク等
参加費無料・事前申込制(定員60名)申込締切:9月15日(金)
https://unit.aist.go.jp/diversity/ja/event/170925_div_event.html
(共)第61回粘土科学討論会
9月25日(月)〜 27日(水)
会場:富山大学 五福キャンパス共通教育棟
http://www.cssj2.org/
第20回水環境学会シンポジウム
9月26日(火)〜28日(木)
場所:和歌山大学
特別講演会「紀の川の水環境」
http://www.jswe.or.jp/event/symposium/
第202回地質汚染イブニングセミナー
9月29日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ902会議室
講師:中澤 努(産総研地質情報研究部門情報地質研究グループ長)
テーマ:台地の下の軟弱泥層:関東平野におけるMIS6開析谷の埋積プロセスと地質特性
http://www.npo-geopol.or.jpz
IGCP589「アジアにおけるテチス区の発達」第6回国際シンポジウム
「Western Tethys meets Eastern Tethys」
9月29日(金)〜30日(土)
ポスト巡検:10月1日(日)〜5日(木)
場所:AGH University of Science and Technology(ポーランド,クラクフ市)
http://igcp589.cags.ac.cn/
10月October
(後)地球史研究所開設記念事業
主催:NPO法人地球年代学ネットワーク
▶オープニング・フェスタ
10月14日(土)10:00〜16:00
場所:赤磐市吉井会館(赤磐市周匝136-1)および周辺施設
参加費:無料
▶記念国際会議
10月15日(土)10:00〜20:30
会場:岡山国際交流センター(岡山市北区奉還町2丁目2-1)
http://jgnet.org/event20171014_1/
(後)第4回Slope tectonics 2017
10月14日(土)〜18日(水)
場所:京都大学宇治キャンパス黄檗プラザ
http://www.slope.dpri.kyoto-u.ac.jp/SlopeTectonics2017/st2017.html
第15回男女共同参画学協会連絡会シンポジウム
10月14日(土)10:00〜17:00
場所:東京大学本郷キャンパス
事前参加申込締切:9月18日(月)
http://www.djrenrakukai.org/symposium1.html
テクノブリッジフェア2017 in つくば
10月19日(木)〜20日(金)9:30〜17:00
場所:産業技術総合研究所つくばセンター
http://technobridge.aist.go.jp
第8回「海洋科学研究センター」市民公開講座
「小樽港の歴史と海洋環境」
10月21日(土) 13:30〜16:00
場所:海洋科学研究センター(小樽市築港3-1)
入場無料・要申込(10/20締切)
定員:30名(先着順)
https://www.hro.or.jp/list/environmental/research/gsh/
(共)第15回国際放散虫研究集会(15th InterRad)
10月23日(月)〜27日(金)(研究集会)
*発表要旨締切:6月15日(木)
20日(金)〜22日(日)(プレ巡検)
22日(日)(サイエンスカフェ)
28日(土)〜31日(火)(ポスト巡検)
会場:新潟大学など
http://interrad2017.random-walk.org/
IGCP608「白亜紀アジア−西太平洋生態系」第5回国際研究集会
大韓地質学会70周年記念シンポジウムと共催
10月26日(木)〜27日(金)(研究集会:韓国・済州島)
23日(月)〜25日(水)(プレ巡検:韓半島南西部白亜系)
会場:済州国際コンベンションセンター
http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/
海洋理工学会秋季大会シンポジウム
「西之島から地球を知る」
10月26日(木)
場所:京都大学楽友会館
http://amstec.jp/convention/H29_autum.html
第203回地質汚染イブニングセミナー
場所:北とぴあ902会議室
10月27日(金)18:30〜20:30
蔵冶光一郎(東京大学大学院農学生命科学研究科 付属演習林 企画部 教授)
演題:千葉県と東大のかかわりと水循環
http://www.npo-geopol.or.jp
魅せるサイエンスワークショップ02
「タイポグラフィックスー本当のフォント使いー」
10月27日(金)13:15〜15:15
場所:高知コアセンターセミナー室
参加無料
高知大学・笹岡美穂(jm-sasaokam@kochi-u.ac.jp)
日本自治体危機管理学会2017年度研究大会
10月28日(土)
場所:明治大学駿河台キャンパス
参加無料
http://www.jemaweb.org/news.html#20170907
11月November
第71回日本人類学会大会
11月3日(金)〜5日(日)
会場:東京大学本郷キャンパス
講演申込締切:8月21日(月)
http://anthrop-meeting.sakura.ne.jp/
16th Gondwana International Conference/ IAGR 2017 Annual Convention/ 1
4th International Conference on Gondwana to Asia
11月12日(日)〜17日(金)
場所:タイ・バンコク、
登録・発表要旨締切:7月31日
http://www.dmr.go.th
平成29年度国土技術研究会
「のこすこと、つくること どちらも国土技術です」
11月13日(月)〜14日(火)
会場:中央合同庁舎2号館(千代田区霞が関)
参加費無料
http://www.mlit.go.jp/chosahokoku/giken/
国際講演会 「ベルギーにおける地層処分計画の現状と今後」
主催:原子力発電環境整備機構(NUMO)※日英同時通訳付
11月14(火)13:30〜16:00
会場:三田NNホール&スペース多目的ホール(東京都港区芝)
参加申込締切:11月10日(金)17時
http://www.numo.or.jp/topics/201717102014.html
第28回地質汚染調査浄化技術研修会
共催:地質汚染診断士の会・国際医療地質協会(IMGA)Japan Chapter
・日本地質学会環境地質部会・社会地質学会
11月17日(金)〜19日(日)
場所:関東ベースンセンター(千葉県香取市)
会費:会員 45,000円,非会員55,000円,学生35,000円 ※昼食代を含む
http://www.npo-geopol.or.jp
情報通信学会・地区防災計画学会共催 国際コミュニケーション・フォーラム
「ICT×AI×防災・減災」
11月18日(土)15:00〜18:00
場所:早稲田大学早稲田キャンパス(参加費無料)
http://www.jsicr.jp/operation/forum/index.html
第26回素材工学研究懇談会
金属プロセスと素材の最近の研究開発動向
11月21日(火)〜22日(水)
会場:東北大学片平さくらホール2階会議室
http://www2.tagen.tohoku.ac.jp/general/event/sozai/2017/
火山災害軽減のための方策に関する国際ワークショップ2017
―火山監視と防災―
11月22日(水)9:30〜16:30
会場:都道府県会館(東京都千代田区平河町)
http://www.mfri.pref.yamanashi.jp/
シンポジウム:九州北部豪雨の教訓と地域防災力
11月23日(木・祝)13:00〜16:30
主催:地区防災計画学会ほか
場所:福岡大学文系センター棟4階第4会議室
対象 地域防災力の強化に興味のある方(参加費無料)
http://gakkai.chiku-bousai.jp/ev171123.html
火山噴火国際シンポジウム2017:火山噴火と防災対応
11月24日(金)10:00〜16:00
会場:ホテル談露館(山梨県甲府市丸の内)
http://www.mfri.pref.yamanashi.jp/
第204回地質汚染イブニングセミナー
11月24日(金)18:30〜20:30
場所:北トピア902会議室
講師:緒方 剛(土浦保健所長)
演題:水俣病と水質汚染健康被害(井戸水ヒ素中毒と対比して)
http://www.npo-geopol.or.jp
○関東支部:八丈島地熱巡検
11月24日(金)〜25日(土)
募集人数:12〜20人
費用:25,000円程度
*申込期限:10月31日(先着順)
http://kanto.geosociety.jp
防災推進国民大会2017
11月26日(日)〜27日(月)
会場:仙台国際センター(仙台市青葉区青葉山)
「団体別セッション」「展示ブース」「ワークショップ」「屋外展示」を公募
しています(*6月30日(金)締切)
http://bosai-kokutai.jp/
(協)第33ゼオライト研究発表会
11月30日(木)〜12月1日(金)
会場:長良川国際会議場
https://jza-online.org/events
12月December
(共)第27回環境地質学シンポジウム
12月1日(金)〜2日(土)
会場:日本大学文理学部
http://www.jspmug.org/
地球化学研究協会「公開講座」および「三宅賞」受賞者の受賞記念講演
12月2日(土)14:40〜
場所:霞が関ビル35階東海大学校友会館
公開講座「三宅泰雄先生と同位体地球化学—その後の発展の一断面」(和田英
太郎・京都大学名誉教授)
参加費:無料
http://www.geochem-ass-miyake.com/
第17回東北大学多元物質科学研究所研究発表会
12月4日(月)〜5日(火)
会場:東北大学片平さくらホール
参加申込締切:11月27日(月)(ポスター発表は11月10日(金)締切)
http://www2.tagen.tohoku.ac.jp/general/event/meeting/2017/
東北大学多元物質科学研究所イノベーション・エクスチェンジ2017
12月5日(火)13:00-18:30
会場:東北大学 片平さくらホール
参加申込締切:11月27日(月)
http://www2.tagen.tohoku.ac.jp/general/event/Innovation_Exchange/2017/
平成29年度国総研講演会
12月6日(水)10:15〜17:30
場所:日本教育会館 一ツ橋ホール
入場無料・要申込
http://www.nilim.go.jp/
地質調査総合センター(GSJ)第28回シンポジウム
「地圏資源環境の研究ストーリー:社会へつなげる研究を目指して」
12月7日(木)13:30-17:30
場所:秋葉原ダイビル・コンベンションホール
https://unit.aist.go.jp/georesenv/information/20171011.html
日本第四紀学会シンポジウム「ジオパークと学校教育」
12月16日(土)9:30〜17:00
場所:お茶の水女子大学共通一号館301(文京区大塚2-1-1)
参加費無料.どなたでも参加できます
http://quaternary.jp/event/qr.html#sympo1216
第17回日本地質学会四国支部総会・講演会・巡検
12月16日(土) 〜17日(日)
総会・講演会
16日(土) 11:00〜17:00
場所:愛媛大学メディアセンター(城北キャンパス)
巡検「道後のHigh-Mg安山岩」
17日(日) 8:30〜11:30
http://www.gsj-shikoku.com/research.html#cont03
日本地質学会市民講演会(四国支部後援)
「地質学を活用して地域イノベーションを共創しよう」
12月17日(日) 13:30-15:30
会場:愛媛大学南加記念ホール
http://www.gsj-shikoku.com/research.html#cont03
日本学術会議公開シンポジウム
「2017年 九州北部豪雨災害と今後の対策」
主催:日本学術会議土木工学・防災学術連携体ほか
12月20日(水)10:00〜17:30
場所:日本学術会議講堂
定員先着300名(参加費無料)
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/252-s-3-1.pdf
第205回地質汚染イブニングセミナー
12月22日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:相川信之(日本地質汚染審査機構理事・大阪市立大名誉教授)
演題:焼却灰の処理:都市ごみ焼却灰中の重金属の不溶化処理の一例
http://www.npo-geopol.or.jp
地質学史懇話会
12月23日(土):13:30〜17:00
場所:北とぴあ8階803号室:JR京浜東北線王子駅下車3分
(予定)
平田大二「日本の自然史系博物館を考える」
藤岡換太郎「相模湾の散策‐日本の三大深海湾の謎を探る‐」
連合フェロー
日本地球惑星科学連合(JpGU)フェロー(地質学会会員)
*JpGUフェロー制度についてはこちら(PDF)から
*JpGUフェロー紹介ページ(JpGUのサイト)はこちら
2023年度
木村 学 会員
2019年度
磯崎行雄 会員 浦辺徹郎 会員
岡田篤正 会員 北里 洋 会員
2017年度
荒井章司 会員 石橋克彦 会員
小西健二 会員
2016年度
斎藤常正 会員 斎藤靖二 会員
石原舜三 会員 町田 洋 会員
鳥海光弘 会員 嶋本利彦 会員
富樫茂子 会員
*その他の2016年度フェロー選出者の方々はこちらから
2015年度
兼岡一郎 会員 平 朝彦 会員
*その他の2015年度フェロー選出者の方々はこちらから
2014年度
岡田尚武 会員 丸山茂徳 会員
久城育夫 会員 荒牧重雄 会員
松田時彦 会員 杉村 新 会員
鎮西清高 会員 藤井敏嗣 会員
*その他の2014年度フェロー選出者の方々はこちらから
2016年度各賞受賞者
2016年度各賞受賞者 受賞理由
■日本地質学会賞(1件)
■日本地質学会国際賞(1件)
■柵山雅則賞(1件)
■Island Arc賞(1件)
■小藤文次郎賞(2件)
■研究奨励賞(2件)
■功労賞(1件)
■学会表彰(1件)
日本地質学会賞
受賞者:荒井章司(金沢大学大学院自然科学研究科)
対象研究テーマ:かんらん岩およびかんらん岩起源物質の解析による地域・地球発達史
荒井章司会員は,綿密な野外調査,緻密な偏光顕微鏡観察に基づいた岩石組織解析とEPMA, LA-ICP-MS,顕微ラマン分光分析などを駆使して,日本をはじめ世界各地の造山帯,オフィオライト及び海洋底に出現するマントル起源のかんらん岩や火山岩中の捕獲岩を研究し,マントルの物質学的進化の解明を進めてきた. 三郡帯においては世界に先駆けてEPMAによる鉱物化学データから超苦鉄質岩の接触変成作用を明らかにし,類例のないかんらん石とコーディエライトの共存を見出したことにより,日本岩石鉱物鉱床学会の研究奨励賞を授与された.また,中国山地の大江山オフィオライトの超苦鉄質岩体が溶け残りかんらん岩であることを示すとともにクロミタイトの成因を論じ,世界をリードするクロミタイト成因論へと発展させた.男鹿半島,西南日本,フィリピンやカムチャツカの火山のマントル捕獲岩から再結晶組織や交代作用の証拠を発見し,マントルウェッジの様々なプロセスを解明した.主席研究員を務めた東太平洋ヘス・ディープの国際深海掘削ではマグマとマントル岩の反応の重要性を明らかにし,その後多くのオフィオライトにおけるマントルーマグマ反応の研究へと展開した.世界中の研究者に利用される「かんらん石スピネルマントル列」の提唱やスピネルから変質マントル岩の初生的な情報を解読する手法は「スピネルの荒井」の名を世界に知らしめ,その後の地質学的・岩石学的研究に多大な影響を与え,日本鉱物科学会賞, Island Arc賞の受賞に至った.さらに,人類史上初のマントル掘削を目指すモホール計画では,その立案から主導的役割を果たした. 荒井会員は日本人のみならずフランス,エジプト,イラン,フィリピンなどの留学生を含む多くの学生を育て,多数の卒業・修了生が国内外の大学や研究所,資源・地質関連企業で活躍している.また,「日本の火成岩」(岩波書店)や新版地学事典(平凡社)で超苦鉄質岩関連の頁を執筆するなど,専門分野の成果の普及にも努めた. 学術界にあっては日本学術会議鉱物学研究連絡委員会委員,日本岩石鉱物鉱床学会会長をはじめ,金属鉱業事業団レアメタル専門検討委員,統合国際深海掘削計画科学立案評価パネル共同議長,国際陸上掘削計画科学諮問部会委員などを歴任した. 上記のように,荒井会員は地質学に関する顕著な功績をおさめたので,日本地質学会賞に推薦する.
日本地質学国際賞
受賞者:Roberto Compagnoni[ロベルト コンパニョーニ](トリノ大学)
対象研究テーマ:変成岩岩石学
コンパニョーニ教授は長年イタリアを拠点に変成岩岩石学のコミュニティーのリーダーとして活躍してきた.同氏は,沈み込み帯及び大陸衝突帯の深部に由来する岩石に記録された形成条件や圧力温度経路の検討から,造構プロセスや流体と岩石の相互作用を解明することを主要な研究テーマとしてきた.野外における観察から抽出できる情報を最大限に活かし,岩石薄片を用いたマイクロスケールでの組織観察とリンクさせて考察する研究スタイルは一貫している.地質・岩石学分野における基礎学問を重視する一方,考古学の専門家と共同の先史時代のヒスイの利用に関する研究,医学分野の専門家と連携したアスベストの研究を行うなど,地質・岩石学の重要性を幅広く社会にアピールすることに成功した.同氏は1960年代からアルプスの変成作用と造構プロセスについての多くの研究論文を発表しているが,その中でもそれまでの常識を覆したアルプス変成作用の年代論に関する研究,超高圧変成作用時でも地殻流体が豊富に存在することを浮き彫りにした研究は画期的な成果として特筆される.この分野における同氏の貢献を称え,2008年にフランス科学アカデミーからGrand Prix Leon Lutaud国際賞が授与された.同氏は複数の地質図の出版にも携わり,また数多くの若手研究者の育成にも力を注いできた. コンパニョーニ教授は日本からの数多くの変成岩研究者をトリノ大学で受け入れた.同氏は彼らにアルプス変成岩類とそれらを取り巻く地質環境を懇切に紹介するだけでなく,彼らが現地での研究に集中できるよう,自宅に泊めるなどして手厚くもてなした.その努力は多くの研究者の岩石学の知識の深化に大きく寄与した.また,日本の研究者と共に中国での調査を行い,徳島を中心に開催されたオフィオライト会議,万国地質学会議京都大会,愛媛県新居浜市で開催されたエクロジャイト会議などの機会に複数回日本に中・長期的に滞在し交流を深めた.同氏は日本地質学会の正式英文誌であるIsland Arc誌の編集委員を長年にわたり務めるとともに,よく引用される論文をIsland Arc誌に筆頭著者として発表した. 上述の通り,コンパニョーニ教授は変成岩地質学・岩石学分野において国際的に高い水準の画期的な研究成果を挙げてきたとともに,日本の研究者との共同研究や学会誌の編集などを通じて日本の地質学の発展に顕著な功績があったと認められるので,日本地質学会国際賞に推薦する.
日本地質学会柵山雅則賞
受賞者:野田博之(海洋研究開発機構 現京都大学防災研究所)
対象研究テーマ:断層と地震発生の力学
野田博之会員は,断層帯の調査,室内実験による断層の力学的・水理学的性質の決定,シミュレーションによる地震の発生機構の研究において顕著な業績を挙げてきた.野田会員は博士前期課程までは断層帯の地質調査と変形・透水実験を行い,博士後期課程・博士研究員時代にはハーバード大学,京都大学,カリフォルニア工科大学で地震学と破壊力学を学んで,本格的な地震発生シミュレーションの研究を始めた.断層調査,実験,理論・シミュレーションの全てを基礎から習得している研究者は世界的にも皆無に近く,野田会員の研究基盤は極めてユニークである. 野田会員の多彩な研究成果の中でも,以下の成果は特に重要である. 1) 花折断層の調査,摩擦・透水実験,高速摩擦すべりの理論的解析を行って,断層の力学的・水理学的性質を決定した.微小な変位によって断層は徐々に強度を失い,断層に作用する応力に耐えられなくなって地震を発生する.野田会員は特に,花折断層で実測された水理学的性質に基づいてthermal pressurizationを解析して,断層が強度を失うすべり量が大地震の解析から求められる値とほぼ同じになることを示した. 2) 実測された性質に基づいて地震発生のシミュレーションを行い,断層の性質が地震発生のサイクルと地震発生時の動的な破壊過程にどのような影響を与えるかを明らかにした.特に断層の低速下の性質と高速下でthermal pressurizationによる強度低下が起こる現象が重なることで極めて多彩な地震活動が起こることを示した.この結果は,断層クリープ,中・大規模地震,東北沖地震のような海溝型巨大地震が同じ場所で起こり得ることを示しており,大きなインパクトを与えた. 3) 摩擦すべりから流動変形への変化を記述する構成則を提唱し,それを使って大地震の発生サイクルと動的破壊過程を解析した.よく使われるリソスフェアの強度断面は断層・プレート境界の挙動によって決まり,時間とともに変化することが明らかになった. 野田会員はこれらの成果を多くの論文として国際学術誌に公表しており,それらは非常に多くの論文で引用されている.このように地質学に関して優れた業績を挙げた野田博之会員を日本地質学会柵山雅則賞に推薦する.
日本地質学会 Island Arc賞
受賞論文:Shinji Yamamoto, Tsuyoshi Komiya, Hiroshi Yamamoto, Yoshiyuki Kaneko, Masaru Terabayashi, Ikuo Katayama, Tsuyoshi Iizuka, Shigenori Maruyama, Jingsui Yang, Yoshiaki Kon and Takafumi Hirata, 2013. Recycled crustal zircons from podiform chromitites in the Luobusa ophiolite, southern Tibet. Island Arc, 22, 89-103.
Yamamoto et al. (2013) presented novel data on the U-Pb age of ancient zircon grains separated from enigmatic podiform chromitites from Luobusa ophiolite, Southern Tibet, which includes ultra-high pressure mineral inclusions and other minerals such as zircon to determine the age relationships between podiform chromitites and the host mantle peridotites. The paper is well written with sound methodology and significant results. This work not only provides strong evidence for the recycling of crustal materials during dynamic processes in the upper mantle, but also urges us to reconsider the origin of podiform chromitites from ophiolites and the mantle geodynamics. This paper received the highest number of citations–based on the Thomson Science Index for the year 2015–amongst the entire candidate Island Arc papers published in 2012–2013, which will contribute to increasing the impact factor of Island Arc. The first author, Dr. Yamamoto, is one of the most active young Japanese geologists working on continental growth and mantle geodynamics based on field works, microstructural and petrological studies on ophiolites and orogenic belts in China, Australia, Canada, UK, etc. His earlier finding of coesite lamellae (+Cpx inclusions) in chromitite provides the best document for the UHP origin of diamond-bearing chromitites. This paper adds to his many contributions and is a worthy receipt of the 2016 Island Arc Award.
>>Wiley 論文サイトへ
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iar.12011/full
日本地質学会小藤文次郎賞
受賞者:菅沼悠介(国立極地研究所)・岡田 誠(茨城大学理学部)・堀江憲路(国立極地研究所)・竹原真美(九州大学大学院理学府)・木村純一(海洋研究開発機構)・羽田裕貴(茨城大学大学院理工学研究科)・風岡 修(千葉県環境研究センター)
受賞論文:Yusuke Suganuma, Makoto Okada, Kenji Horie, Hiroshi Kaiden, Mami Takehara, Ryoko Senda, Jun-Ichi Kimura, Kenji Kawamura, Yuki Haneda, Osamu Kazaoka, and Martin J. Head, 2015, Age of Matuyama-Brunhes boundary constrained by U-Pb zircon dating of a widespread tephra. Geology, 43, 491-494.
松山-ブルン(M-B)境界は,地質時代の重要な年代較正点であるにも関わらず,正確な 年代には統一的見解が得られていなかった.菅沼悠介会員と当該論文の共著者らは,房総 半島に分布する上総層群国本層中の「千葉複合模式地層」における高解像度の古地磁気・酸 素同位体変動の復元と,MBB境界付近の層準に産する「Byk-Eテフラ」中ジルコン粒子のSHRIMP-U-Pb年代測定 を行うことで,これまで約780-781 kaとされてきたM-B境界の年代が約770.2 ± 7.3 kaに修正されることを示した.この結果は,M-B境界年代の決定にとどまらず「Byk-Eテフラ」が 地質年代較正において重要な基準面となる可能性を示すものである.さらに,「千葉複合模式地層」が日本最初の「国際標準模式地:GSSP(下部−中部更新統境界)」に認定されるための 非常に大きな貢献ともなる.以上の理由から,本論文の著者となっている全ての会員を小 藤文次郎賞の受賞対象として推薦する.
日本地質学会小藤文次郎賞
受賞者:高柳栄子(東北大学大学院理学研究科)
受賞論文:Takayanagi, H., Asami, R., Otake, T., Abe, O., Miyajima, T., Kitagawa, H. and Iryu, Y., 2015, Quantitative analysis of intraspecific variations in the carbon and oxygen isotope compositions of the modern cool-temperate brachiopod Terebratulina crossei. Geochimica et Cosmochimica Acta, 170, 301–320.
腕足動物殻は炭素・酸素同位体組成(δ13C・δ18O)に関して,周囲の海水と同位体平衡にあるとされ,数百万〜数億年スケールの古環境復元に用いられて来た.本研究では,腕足動物殻の同位体組成の殻内変異,種間差,個体差の全てを評価・検討した.岩手県大槌湾から採取した現生腕足動物Terebratulina crossei(9個体)のδ13C・δ18Oを高時間分解能で分析し,生息地の溶存無機炭素のδ13C,海水温および塩分の季節変化から算出された海水と同位体平衡で析出する方解石のδ13C・δ18Oと一致しないこととその原因,今後の古海洋研究に適した部位と信頼性を示した.また,本論文は,従来の腕足動物殻の同位体組成に関する研究およびそれらに基づく古環境復元の研究法について,根源的な再検討の必要性も示唆している. 本研究を主導した高柳栄子会員は,日本地質学会小藤文次郎賞の授賞にふさわしいと判断し,推薦する.
日本地質学会研究奨励賞
受賞者:酒向和希(愛知教育大学大学院教育学研究科)
対象論文:酒向和希・星 博幸,2014,本州中部,中新統富草層群の古地磁気とテクトニックな意義.地質学雑誌,120,255-271.
先中新統の帯状地質配列は伊豆北方で八の字型に屈曲している.この屈曲は伊豆-小笠原弧の衝突で生じ,衝突以前の帯状配列は直線的だったという理解が一般的である.しかしこれは仮説の域を出ていない.著者らは長野県南部の中新統富草層群に注目し,岩相分布と層序を検討した上で古地磁気を調べた.その結果,富草層群の古地磁気方位はほぼ北を指し,同時代の西南日本の東偏方位と大きく異なることを示した.さらに地質構造と古地磁気回転の関係を定量的に分析するオロクライン・テストを実施し,前期中新世の17 Ma頃には中央構造線が直線的であったと結論した.この成果は日本海拡大やフィリピン海の運動史に重要な制約を与えている.この地域の地域地質については,著者らがすでに地質学雑誌で公表しおり,しっかりした地質調査に根ざして新たにデータを提示し,総合的に解釈しようとする著者の姿勢も高く評価できる.研究奨励賞に十分値する研究である.
日本地質学会研究奨励賞
受賞者:金井拓人(早稲田大学大学院創造理工学研究科)
対象論文:金井拓人・山路 敦・高木秀雄,2014,混合ビンガム分布を適用したヒールドマイクロクラックによる古応力解析 中部地方の領家花崗岩類における例. 地質学雑誌,120,23-35.
本論文は,花崗岩・石英中のヒールドマイクロクラック(HC)の3次元分布を用いて古応力を復元する手法の開発と,その天然岩石への応用を行ったものである.共著者の山路により開発された情報量基準を用いた最適応力場の推定方法に基づくが,そのためには,統計的性質を保った情報を観察から抽出する必要がある.著者らは,ユニバーサルステージによるHC分布測定に伴う観測バイアスを補正する方法を考案し,中部地方の中央構造線近傍の領家花崗岩類に適用した.その結果,複数ステージの応力場を同定することに成功し,特に,約65MaのHC形成時には,中央構造線の走行とほぼ直行し低角度のσ3 軸をもつ伸長応力場であった可能性を示唆した.以上のように,本研究はマイクロクラックを用いた古応力場復元手法を大幅に改良し,中央構造線のテクトニクスの理解に寄与する重要なデータを示した.よって,本論文を研究奨励賞にふさわしい論文として推薦する.
日本地質学会功労賞(1件)
受賞者:檀原 徹(株式会社京都フィッション・トラック)
功労業績:放射年代測定等による地質学への貢献
檀原 徹氏は,30余年にわたり,フィッション・トラック(FT)年代測定,FT熱年代分析,火山灰(テフラ)分析および関連機器の開発・普及など,氏が設立した会社の業務を通じて,我が国の地質の調査・研究に大きく貢献してきた. 檀原氏の功績は,長年にわたり測定・分析手法と分析装置の開発・改良に熱心に取り組み,その成果を多くの学術論文として公表し,またそれらが広く利用されてきたことにある.FT年代測定の普及は氏の代表的な功績である.FT年代測定を業務化したことにより,だれしもがFT年代測定を試みることが可能となった.檀原氏らによるFT年代測定結果は数多くの学術論文や産総研地質調査総合センター(旧地質調査所)の地質図幅作成等で利用され,地質調査業や資源エネルギー開発でも活用されている.最近ではレーザーアブレーションICP質量分析法を利用したFT年代測定技術の開発に成功し,その技術を広く研究・業務に活用している.また同一ジルコン粒子を用いたFT法とU-Pb法によるダブル年代測定の高度化とその普及にも取り組んでいる.一方,放射年代測定や岩石・鉱物の地球化学的分析では鉱物分離が極めて重要であるが,氏は効率的な鉱物分離システムを構築し,その普及にも努めてきた. 檀原氏のもう一つの大きな功績は,テフラ粒子の屈折率測定を目的とした温度変化型屈折率測定装置の開発である.この屈折率測定装置を製品化し普及させたことにより屈折率測定が精度良くかつ容易に行えるようになり,各地でテフラの記載が拡充された.この機器の開発とFT年代測定の普及により我が国のテフロクロノロジーが精密化し,第四紀層序研究が大きく進展したことは疑いようもない事実である. 以上のように,檀原氏の長年の放射年代測定手法等の開発・普及は我が国の地質学の発展に大きく寄与しており,ここに日本地質学会功労賞に推薦する.
日本地質学会表彰
受賞者:内藤一樹(産業技術総合研究所)
表彰業績:地質図のデジタルアーカイブの構築とその整備
国立研究開発法人産業技術総合研究所地質調査総合センター(GSJ;旧地質調査所)では,2003年の同研究所発足以来、所有する多数の地質図を迅速かつ適切に利用したいという学界および社会からのニーズに応えるため,地質図のデジタルアーカイブの構築とその整備に取り組んできた. 内藤 一樹会員は,このプロジェクトを実現させるため,地質図データの整備,配信システムの構築,プログラム開発などの複雑で難解な作業に自らが取り組み,主導的な役割を果たしてきた.その結果,2013年に「地質図Navi」としてWEB上に公開することができた.内藤 一樹会員が開発・構築した「地質図Navi」は,20万分の1日本シームレス地質図をベースマップにしており,各種地質図だけでなく,活断層・火山などのGSJのデータベースや,重力異常図,地球化学図などの地球科学情報等が閲覧可能な総合的なプラットフォームといえる. これ までは,地質図幅などの地質データを入手・閲覧するには手間と費用を要したため,その利用は地球科学分野の研究者・学生や地質調査業界の技術者に限られていた.ところが,「地質図Navi」が公開されるとそれらの人々にとっての利便性が各段に向上するとともに,簡単に利用できるWEB環境であるため専門家でない市民も地質図を利用できるようになった.この ことは,「地質図Navi」の利用数が月間約2万件にものぼる事実に端的に表されている.特に近年,地震や火山噴火による被害,土砂災害や地盤災害などが増加したことが契機となって,「地質図Navi」を通じて地質図や地質データベースの有効性がさらに認識され,市民のジオハザードに対する防災意識を高めるという効果を挙げている点は高く評価される.また ,「地質図Navi」は国のオープンデータ戦略に沿うものであり,研究者や技術者だけでなく,市民も最新の地質学などの科学データにアクセス可能となる.その結果,市民の地質学への興味と理解がこれまで以上に向上するものと期待される. この ように素晴らしいシステムの開発と発展に尽力した内藤一樹会員は,日本地質学会表彰を授賞するにふさわしいと判断し,ここに授賞を推薦する.
2016年度名誉会員
2016年度名誉会員
熊井久雄 会員(1939年12月14日生まれ,76歳)
熊井久雄会員は1962年3月東京教育大学理学部地学科地質学鉱物学専攻を卒業,同年4月に農林省農地局に任官し,熊本農地事務局(現九州農政局)に農林技官を皮切りに東海農政局,1971年3月まで関東農政局に勤務し同年4月に信州大学理学部地質学科に助手として出向された.信州大学では1980年5月講師,1982年1月助教授に昇任,1988年10月に大阪市立大学理学部地学科(後に大学院理学研究科生物地学専攻に変更)教授に転任,2003年3月に同大学院を定年退職,名誉教授に任ぜられた. 日本地質学会においては,各種役員として活躍し1990年4月〜2000年3月まで評議員,1990年4月〜1994年3月,2000年4月〜2002年3月まで関西支部長(後に近畿支部長)を歴任した.第四紀専門部会を立ち上げ発足時の部会長を引き受け,地質年代に関する専門委員会にも参画し,共立出版2001年刊の日本地質学会訳編「国際層序ガイド」出版に参画し2章を翻訳執筆した.NPO日本地質汚染審査機構の理事として,地質汚染実態解析や地質条件解析などの経験を生かして若手の環境教育にも貢献している. 国際貢献では2000年10月から国際第四紀連合(INQUA)の層序委員会委員を担当し,同時にアジア・太平洋地域小委員会の委員長に任じられた.後者は1997年に日本で開催された国際会議で名称をアジア第四紀連合に変更され,4年おきに開催される国のリーダーを会長にすることになっている.2007年からは国際地質科学連合(IUGS)第四紀分科会更新世中部境界線専門調査委員会の委員にもなっている. 熊井久雄会員は地質学の普及・教育に関する多くの仕事を分担しているが,主要なものとして国際協力機構(JICA)の海外派遣専門家として,インドネシアにて1974年〜1977年,1987年〜1991年まで,インドネシア地質調査所所員に対して毎年3ヶ月間の地質調査法の指導を行なった.これに関連して,パジャジャラン大学から多くの留学生を大阪市大に招き現地調査を含む地質学を教授し多くの博士号を授与した. このような長年にわたる地質学の研究,普及及び教育への顕著な貢献に鑑み,熊井久雄会員を日本地質学会名誉会員に推薦する.
2017年度各賞受賞者
2017年度各賞受賞者 受賞理由
■学会賞(1件)
■国際賞(1件)
■柵山雅則賞(1件)
■Island Arc賞(1件)
■論文賞(1件)
■小藤文次郎賞(1件)
■研究奨励賞(1件)
■功労賞(1件)
■学会表彰(1件)
日本地質学会賞
受賞者:ウォリス サイモン(名古屋大学大学院環境学研究科)
対象研究テーマ:構造岩石学と造山帯のテクトニクス
ウォリスサイモン氏は,造山運動のメカニズム解明のため,プレート収束境界の塑性変形した岩石を対象とし,野外調査を基軸としながら,多彩な分野横断型研究を展開して来た.特に沈み込み型境界をなす三波川帯や領家変成帯において,石英,オリビン,蛇紋石の微細構造(格子定向配列)を用いた剪断センスや流動特性の決定,また野外での変形脈の産状等を用いた渦度(変形の回転成分)解析において重要な成果をおさめた.特に三波川帯での運動学的渦度解析は,国際的にも標準的手法の一つになっている.
また,運動論を時間軸や速度論も組み込んだダイナミクスへと昇華させるため,岩石学,年代測定,熱モデル計算など,複数手法の融合研究をも先駆的に行い,総合科学としての造山運動論を実践してきた.大陸衝突体における変成岩の上昇が,変成岩の流動性の増加が引き金となって起きたことを明らかにした.中国の蘇魯(スールー)超高圧変成帯では,流動性増大が変成岩の部分溶融によること,また,南チベットでは花崗岩質マグマの貫入に伴う温度上昇によることを明らかにした.三波川帯の超苦鉄質岩に記録されたオリビンの格子定向配列が,実験によって存在が示唆されていたB-typeであることに加え,それが実験の予言通りに含水条件の産物であることが岩石学的に示されたことで,現世沈み込み帯における地震波速度異方性の解釈にも重大な影響を与えた.近年,ウォリス氏らの研究は深さ約40kmでのスロー地震の発生機構を,天然の岩石が引き起こす地殻-マントル相互作用,特にブルーサイトの挙動に関係付けるに至っている.さらにウォリス氏の研究姿勢から生まれた手法開発型の研究としてラマン炭質物温度計の低温(付加体)領域への拡張がある.この業績の影響は大きく,既に複数の研究者がこの温度計の低温領域での利用を開始している.
ウォリス氏は研究のみならず教育にも意欲的に取り組んでおり,指導した学生・院生の多くが研究者やエンジニアとして活躍している.また,Island Arc誌の編集長,副会長,執行理事として日本地質学会にも多大な貢献を果たしてきた.
以上のように,ウォリスサイモン氏が日本の地質学の発展に果たしてきた多岐にわたる業績は極めて大きく,日本地質学会賞に推薦する.
日本地質学国際賞
受賞者:Richard S. Fiske(スミソニアン協会・国立自然史博物館)
対象研究テーマ:海底噴火における水中火砕流の運搬・堆積機構
スミソニアン協会のRichard S. Fiske博士は水中火砕流を見いだし,その運搬堆積機構に関する理論的体系を築き上げた世界的権威である.氏はジョンズホプキンス大学で学位取得後,1960年に東京大学地質学教室における戦後初の外国人ポストドクトラル研究員として来日し(受入:久野久教授),大学院生の松田時彦氏(東大名誉教授)と共に南部フォッサマグナ常葉層の詳細な野外地質調査を行った.常葉層中の軽石層が二重の分級堆積構造を示すことを発見し,水中火砕流の存在を世界で初めて報告した(Fiske & Matsuda, 1964).その後,米国地質調査所で氏はハワイ火山の噴火活動に関する研究やシェラネバダ山脈の中生代海底噴火堆積物に関する研究などで成果を上げ,1976年にスミソニアン協会国立自然史博物館に転任され,1980年から5年間,同博物館館長を務められた.
ハワイやシェラネバダにおける旺盛な研究活動とともに,1960年以来幾度となく来日して日本の地質学研究者と深く交流し,日本人研究者のプライオリティを尊重しながら,その研究成果を広く国際的に紹介されたことは特筆に値する.さらに国際的な海洋地質学共同研究においても日米の橋渡し役を引き受けてこられた.具体的には,1990年代には,伊豆弧海底カルデラ群で実施された詳細な調査航海に自らも乗船し,日本の潜水艇に乗り込み,日本人共同研究者らとともに,海底火山発達史や海底噴出物の運搬堆積機構に関する数々の先駆的な研究(Fiske et al., 1998; Iizasa et al., 1999; Fiske et al., 2001; Tani et al., 2008など)を行い,海底火山研究において日本が世界的なプレゼンスを得ることに貢献された.一方,西伊豆の白浜層群においても水中噴火プロセスについて数々の新知見を得て水中火砕流の運搬および定置機構の体系化を完成させたのである(Cashman & Fiske, 1991; Tamura et al., 1991など).これらの研究を通して,氏は南部フォッサマグナ地域を含む伊豆小笠原弧が海底火山噴火現象とそれに伴うテフラの運搬・定置機構プロセス研究の絶好のフィールドであることを世界に発信し,日本の地質学研究者を大いに鼓舞している.
こうしたRichard S. Fiske博士の業績と日本地質学界への多大な貢献に鑑み,氏を日本地質学会国際賞候補者として推薦する.
(英文)Dr. Richard S. Fiske of the Smithsonian Institution is a leading geological authority best known for his theory of transport and deposition mechanisms associated with subaqueous pyroclastic flow. After earning a doctorate at Johns Hopkins University, Dr. Fiske came to Japan in 1960, becoming the first ever foreign post-doctoral fellow at the Geological Institute, University of Tokyo in the post-war era (hosted by Prof. Hisashi Kuno). There, he conducted a detailed geological field survey of the South Fossa Magna together with Tokihiko Matsuda (professor emeritus, University of Tokyo), who was then a graduate student. They discovered that pumice deposits in the Fossa Magna exhibited double grading sedimentary structures and were the first in the world to report the existence of subaqueous pyroclastic flows (Fiske & Matsuda, 1964). Thereafter, Dr. Fiske joined the U.S. Geological Survey, where he studied eruptions of Hawaiian volcanoes and debris from submarine Mesozoic eruptions in the Sierra Nevada mountains. In 1976, Dr. Fiske moved to the Smithsonian Institution National Museum of Natural History, where he served as Director for five years from 1980.
It is worth noting that, amid his energetic research activities in Hawaii and the Sierra Nevada, Dr. Fiske frequently visited Japan since 1960, where he further deepened interactions with Japanese geologists and worked to broadly disseminate the results of Japanese research to an international audience while respecting the priorities of Japanese researchers. In addition, he served as a bridge for international collaborative research, connecting Japanese and American researchers engaged in marine geology. Specifically, in the 1990s, he participated in research expeditions to survey in detail submarine calderas near the Izu-Bonin arc, collaborating with Japanese researchers and even joining the crew of a Japanese submarine. Furthermore, he conducted numerous pioneering studies on submarine volcano-forming processes and the transport/deposition mechanisms of submarine volcanic debris (e.g., Fiske et al., 1998; Iizasa et al., 1999; Fiske et al., 2001; Tani et al., 2008). In so doing, Dr. Fiske helped raise the status of Japanese research on submarine volcanoes on the international stage. At the same time, Dr. Fiske made numerous new discoveries regarding subaqueous eruption processes in the Shirahama Group off the Western Izu Peninsula and completed his theory regarding transport and deposition mechanisms of subaqueous pyroclastic debris (e.g., Cashman & Fiske, 1991; Tamura et al., 1991). Through the above-mentioned research, Dr. Fiske has demonstrated to the world that the Izu-Bonin Arc, which includes the southern Fossa Magna area, is an ideal region for studying submarine eruptions and associated tephra transport and deposition mechanisms, and has been an inspiration for Japanese geologists.
Considering Dr. Richard S. Fiske’s scholarly achievements and immeasurable contributions to Japanese geology, I hereby endorse Dr. Fiske as a candidate for the Geological Society of Japan International Prize.
日本地質学会柵山雅則賞
受賞者:平内 健一(静岡大学理学部地球科学科)
対象研究テーマ:沈み込み帯と蛇紋岩のレオロジー
平内健一会員は,蛇紋岩のレオロジーが沈み込み帯でのダイナミクスへ与える影響に関して,フィールド調査と室内変形実験の2つのアプローチによって取り組み,多くの成果を挙げて来た.
平内氏は最初に黒瀬川帯やフランシスカン帯においてフィールド調査を行い,蛇紋岩の構造解析や微細組織観察によって,その変成・変形履歴の解明に取り組んだ.従来,蛇紋岩はかんらん岩の変質物として厄介者扱いされ,構造地質学分野においても研究対象からは避けられる傾向が強かった.そうしたなか平内会員は蛇紋岩がもつ特異な物性に着目し,複雑な蛇紋石組織を丹念に読み解く地道な研究を丁寧に進めた結果,蛇紋岩が地表付近ではなく上部マントル相当深度で形成され,その後地表付近に定置されるという運動像を明らかにした.
学位取得後は,蛇紋岩が沈み込み帯プレート境界の力学特性に与える影響を評価するため,固体圧・ガス圧三軸変形装置を用いて蛇紋岩の高温高圧実験を行った.その結果,(1)地震発生帯の下限が前弧マントルウェッジにおける蛇紋石の存在により限られること,(2)プレート境界における力学的カップリングの程度が蛇紋石種の違いによって大きく変化すること,(3)蛇紋石の摩擦特性がスロー地震に代表されるゆっくりとした破壊を起こすには十分であること,などを明らかにした.また,日本学術振興会特別研究員時代に留学したユトレヒト大学では,回転式剪断試験機を用いて蛇紋石の熱水摩擦実験を行い,シリカに富むスラブ起源流体の存在によって蛇紋石が滑石へと相変化し,スラブ・マントル境界強度が著しく低下する可能性を明らかにした.これらの実験結果は沈み込み帯プレート境界域におけるすべり・流動様式に対して新たな知見を与え,地震学などの分野においても高く評価されている.
静岡大学赴任後は学生とともにフィールド調査と室内実験を融合する研究スタイルを発展させ,沈み込み帯プレート境界で起きる様々な現象(スロー地震など)の解明に取り組んでいる.また最近では,かんらん岩試料の熱水変形実験に取り組み,海洋プレートの沈み込み発生機構として,トランスフォーム断層などの既存の断層面に沿った海水の浸透の重要性を指摘している.また,これまでに海洋研究開発機構による伊豆・小笠原弧における「しんかい6500」による深海底調査や新学術領域研究の「地殻流体」および「地殻ダイナミクス」に参加するなど活躍の場をさらに広げている.以上の高い実績と将来性により,平内健一会員を柵山雅則賞に推挙する.
日本地質学会 Island Arc賞
受賞論文:Yui Kouketsu, Tomoyuki Mizukami, Hiroshi Mori, Shunsuke Endo, Mutsuki Aoya, Hidetoshi Hara, Daisuke Nakamura, Simon Wallis, 2014, A new approach to develop the Raman carbonaceous material geothermometer for low-grade metamorphism using peak width, Island Arc, 23, 33-50.
Kouketsu et al. (2014) present a new, simple methodology of geothermometers, which is applicable to low−medium grade metamorphic rocks, specifically to estimating metamorphic temperatures in the range of c. 150−400 ˚C. This fine work was done by the Raman spectrum analysis of carbonaceous material from 19 metasediment samples of Jurassic to Cretaceous ages collected from widely separated areas of Southwest Japan (the Shimanto, Chichibu, Kurosegawa, Sambagawa and Mino-Tamba belts), which were metamorphosed at temperatures from 165 to 655°C. A key finding from the analysis is that there exist clear correlations between the peak width (FWHM: full-width at half maximum) of Raman bands of carbonaceous materials and metamorphic temperatures. Estimating recrystallization temperature for low-grade metamorphic minerals including carbonaceous materials has been difficult, but now can be easily conducted with the suggested geothermometers. The obtained results are due to the accumulation of highly elaborate and deliberate research. This paper will contribute widely in the future works of metamorphic terranes.
This paper also won the 2015 Island Arc Most Downloaded Award, which was presented by Wiley to the most frequently downloaded article in 2015 amongst all papers published in Island Arc during 2010−2014. In addition, it received a high number of citations–based on the Thomson Science Index for the year 2015–amongst the candidate Island Arc papers published in 2013–2014 (Volumes 22 and 23), which has considerably contributed to raising the impact factor of Island Arc. The first author, Dr. Kouketsu, is one of the most active young Japanese geologists working on the structural transition of carbonaceous materials in metamorphic and sedimentary rocks, based largely on laboratory works with rock samples collected from different places of the world. She is also interested in the application of spectroscopy to petrology and geology. This paper adds to her many contributions and is a worthy recipient of the 2017 Island Arc Award.
>論文サイトへ(Wiley)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iar.12057/full
日本地質学会論文賞
受賞論文:Atsushi Nozaki, Ryuichi Majima, Koji Kameo, Saburo Sakai, Atsuro Kouda, Shungo Kawagata, Hideki Wada and Hiroshi Kitazato, 2014, Geology and age model of the Lower Pleistocene Nojima, Ofuna, and Koshiba Formations of the middle Kazusa Group, a forearc basin-fill sequence on the Miura Peninsula, the Pacific side of central Japan, Island Arc, 23, 157-179.
本論文は、詳細な野外調査と複数のボーリングコア観察に基づき、三浦半島北部に分布する上総層群中部野島層、大船層、小柴層の岩相層序を確立し、さらに石灰質ナンノ化石層序、浮遊性有孔虫の酸素安定同位体比測定によって、野島層上部から小柴層下部に酸素同位体比ステージ(MIS49-61)を認定し、精度の高い年代モデルを構築したものである。本邦だけでなく、北西太平洋海域においても,この時代の複合年代モデルを構築した例はほとんどなく、特筆すべき研究成果である。また、筆者らは本研究の年代モデルに基づいて、コアに挟在する24枚のテフラ層の堆積年代を決定することに成功した。特に飛騨山脈が給源とされ、多摩丘陵や房総半島に広く認められるとされる広域テフラKd24およびKd25両テフラの年代値を更新したことは、関東平野のみならず、日本各地に分布する前期更新統の年代観に新たな知見を与え、ひいては今後、高精度の年代に基づく地層形成過程の復元や堆積盆発達史を考察する上で重要な意味を持つと考えられる。本論文は、詳細な野外調査による岩相記載、微化石年代と酸素安定同位体比を駆使した複合年代層序といった、層序学のオーソドックスな手法を用い、地道なデータを丹念に積み重ねが結実した優れた論文であると評価できる。以上の理由より、本論文を地質学会論文賞に推薦する。
>論文サイトへ(Wiley)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iar.12066/full
日本地質学会小藤文次郎賞
受賞者:佐藤活志(京都大学大学院理学研究科)
対象論文:Katsushi Sato, 2016, A computerized method to estimate friction coefficient from orientation distribution of meso-scale faults. Journal of Structural Geology, 89, 44–53.
断層の摩擦強度は地震防災上重要であるため,地下の条件を模擬した摩擦実験が盛んに行われている.この論文は,断層が活動したときの摩擦強度を,フィールドデータから見積もった世界初の研究成果である.すなわち佐藤氏は,断層スリップ・データの方向の多様性が,断層を動かした応力の時空的変化のみならず,断層の摩擦係数にも依存することに着目し,断層群の平均的摩擦係数を推定する方法を開発した.そして,外房地域の下部更新統の露頭でみられ,単一の応力状態で活動したと考えられる小断層群に適用した.そこで得られたデータセットの場合,岩石の通常の摩擦係数と大差ないという結果となったが,開発された方法は種々の地質体に適用可能なものであり,今後はさまざまな地域への適用が期待される.社会的重要性を持つ課題に対応して,フィールド研究の新手法を提案したこの成果は,小藤文次郎賞にふさわしいものと評価できる.
>論文サイトへ(ELSEVIER)
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01918141/89
日本地質学会研究奨励賞
受賞者:三田村圭祐((株)建設技術研究所)
対象論文:三田村圭祐・奥平敬元・三田村宗樹,2016,生駒断層帯周辺における露頭規模での脆性変形構造.地質学雑誌,122,61-74.
断層研究は,地質時代のテクトニクスばかりではなく,地震防災を考える上でも重要である.本論文は,生駒断層帯において,露頭規模の断層の構造解析,断層群の古応力解析,そして断層ガウジのK–Ar年代測定に基づき,断層群形成時の応力場と形成年代を議論したものである.解析の結果,生駒断層帯の断層群は現在とは異なる応力場において,~45–30 Maに形成されたことが明らかとなり,これらが始新世後期〜漸新世前期の伸長テクトニクスに関連したものであることが指摘された.本研究のような断層調査は先ず,断層露頭を発見することから始まるが,都市域においては断層露頭の発見は容易ではない.本論文は,このような困難な露頭状況にある都市域における詳細な野外調査に基づく断層調査のあり方の一つを示したものである.よって,本論文を研究奨励賞にふさわしい論文として推薦する.
>論文サイトへ(J-STAGE)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/geosoc/122/2/122_2015.0039/_article/-char/ja/
日本地質学会功労賞(1件)
受賞者:大和田 朗(産業技術総合研究所地質調査総合センター)
功労業績:地質試料の新薄片作製法の開発と人材育成
大和田朗氏は,1981年に通商産業省工業技術院地質調査所(現産業技術総合研究所地質調査総合センター)に入所し,現在に至るまで,35年に亘り薄片・研磨片の作製に従事してきた.その間,地質図幅作成に必要な薄片試料のみならず,従来にない新しい薄片作製法を開発することにより,地質学に関する新たな知見の拡大に大きく貢献してきた.
1996年には,セメント試料などにおける内部の割れ目を青色樹脂にて埋めることにより,流体輸送経路を可視化した薄片作製法を開発し,科学技術庁長官賞創意工夫功労者賞を受賞した.さらに,塩分及び水分を含む鉄マンガンクラストに対して,膨潤の影響を排除した高精度の薄片作製に成功し,海底の鉄マンガンクラストの形成年代と成長速度の推定に関する研究に大きな貢献をした.一方,この乾式法は,石英や硫化鉱物と粘土鉱物が共存するという,同一試料内において極端に硬さが異なる鉱物を含む試料においても,含まれている鉱物が欠けることなくすべて観察が可能な画期的な薄片作製法であった.50年以上前に日本で発見されたイモゴライトについても,世界初の薄片作製に成功し,2015年には日本粘土学会技術賞を受賞している.この乾式法に関しては特許を取得し,ライセンス契約も行っている.大学・企業・国研の若い薄片作製技術者の教育にも精力的に取り組んでおり,この教育効果は非常に大きいものである.さらに,「薄片でよくわかる岩石図鑑」(2014年誠文堂新光社刊)の執筆を行い,薄片技術の普及にも取り組んできた.
以上のように,大和田氏の新しい薄片作製法の開発と,全国の薄片作製技術者を長らく指導してきた人材育成は,地質学の研究・教育の発展に大きく貢献しており,ここに日本地質学会功労賞に推薦する.
日本地質学会表彰
受賞者:「ブラタモリ」制作チーム(日本放送協会)
表彰業績:地質学の社会への普及
「ブラタモリ」は2009年10月からシリーズ化され放送を開始したNHKの番組である.毎回タモリ氏(森田一義氏)と女性アナウンサーがある地域を訪問し,地域の自然と人間や産業との関わりについてその地域の専門家の解説を交えて紹介する.この番組の特徴は,地質や地理に関する専門的な内容を扱い,その科学的意義に加え社会や産業との関わりを明らかにする構成になっている点である.視聴率が10%以上をマークする人気番組で地質の用語や考え方,その様々な意義がほぼ毎回語られる.
地学教育と普及の現状を見ると,小学校,中学校の理科教育における地学分野の比重は決して低くないが,高校理科において地学を履修している生徒の割合は依然として高いとは言えない.したがって,自ら学ぶ意欲のある人を除き,大多数の国民は地学を小・中学校で学んだ後,地学をほとんど意識することなく日々の生活を営んでいると考えられる.このような状況の中で,地学の教育と普及に携わる教育者や学芸員,研究者等は私たちの生活基盤である地球を扱う学問である地質学の普及に日々腐心している. 現在,土曜日の夜という多くの人が聴取可能な時間帯にNHKで放送されている「ブラタモリ」ではゲストとして地学の普及に関わる学芸員・研究者などが出演して,地学的な概念や地形・地質発達過程をイラストやアニメーションを効果的に用いて説明し,視聴者の理解を助けている.タモリ氏の地理・地質好きというキャラクターに負う面も大きいが,それ以上に,訪問地や番組構成,解説する専門家などを決定する番組スタッフの地理・地質の重要性の理解がこの番組を成功に導いていると考えられる.そしてこの番組が地質学の普及に貢献しているのは明らかである.この番組が今後も長く続くことへの期待も込めて,NHK「ブラタモリ」制作チームを学会表彰に推薦する.
2017年度名誉会員
2017年度名誉会員
鈴木博之 会員(1939年11月18日生まれ,77歳)
鈴木博之会員は,1966年に京都大学大学院理学研究科地質学鉱物学専攻修士課程を修了し,その後に博士課程に進学され1969年に同志社大学工学部へ赴任された.その後,助教授を経て1998年に同大学理工学研究所・工学研究科教授に昇任され,2005年に同大学を退職なされた.
この間50年以上にわたり「四万十帯の地質構造発達史」の解明に,フィールドワークを基礎に調査・研究に従事し,これらの成果は地域地質報告書(5万分の1地質図幅)「栗栖川」(鈴木ほか 1979,共著),「江住」(立石ほか 1979,共著)および「龍神」(徳岡ほか 1981,共著),20万分の1地質図「田辺」(徳岡ほか 1982,共著)として発行されている.さらに2012年には「紀伊半島における四万十付加体研究の新展開」(地学団体研究会専報59号)をまとめられ,陸上付加体の新たな研究を展望している.紀伊半島四万十付加体において,ほぼ全域にわたる精細な地質図を作成し,白亜紀〜古第三紀の放散虫化石層序を確立した.
また,インド,ブラジル,アパラチア,マダガスカルに産出するプレカンブリア紀のイタコルマイト(撓曲性コーツアイト)の研究にも貴重な成果をあげている.
2014年に国内ジオパークに認定された南紀熊野ジオパークでは,学術専門委員会委員長として尽力された.また,四万十帯の研究に取り組む多くの若い学生,大学院生には有益な助言を与え,多数の四万十帯研究者や教育者を育て貢献された.
このような長年にわたる地質学の研究,教育,普及への顕著な貢献に鑑み,鈴木博之会員を日本地質学会名誉会員に推薦する.
波田重煕 会員(1940年8月26日生まれ,76歳)
波田重煕会員は,1966年に大阪市立大学大学院理学研究科修士課程を修了し,同年に大阪市立自然科学(現自然史)博物館の学芸員を勤務された.1969年に高知大学文理学部助手として赴任され,講師,助教授を経て1980年に高知大学理学部教授に昇任され,1994年に高知大学名誉教授を授与された.1994年には神戸大学に赴任され,2004年まで同大学教授を務められ神戸大学名誉教授を授与された.その後,2007年に神戸女子大学長・神戸女子短期大学長を勤められ, 2016年に 瑞宝中綬章を叙勲された.
この間,詳細な地質調査と多面的な手法(構造地質学・古生物学・堆積学)に基づいて,西南日本“古生代造山帯” とりわけ“黒瀬川テレーン”の起源に関する研究に取り組まれた.その成果は,ニュージーランドやタイなど海外の造山帯研究にもつながり,付加体研究を大きく進展させた.これらの基礎的研究に加えて1995年1月に発生した阪神・淡路大震災直後から,共同研究者と共に地震により地表に発生した変位・変状を調査し,内陸地震に伴う地震現象の実態の解明とそれに基づく防災意識の向上や防災教育に貢献された.
ユネスコ(UNESCO)と国際地質科学連合(IUGS)による国際協力研究プロジェクトである「地質科学国際研究計画」のリーダーとして,さらに日本学術会議の「地質科学国際研究計画」国内委員会の幹事や委員長,およびそれに関連した日本学術会議地球惑星科学委員会委員や日本学術会議連携会員として同計画を牽引され,東南アジアにおけるIGCP活動の発展とIGCPを通じた国際貢献ならびに日本におけるジオパークの設立に邁進された.
このような長年にわたる地質学に関する研究,教育,普及への顕著な貢献に鑑み,波田重煕会員を日本地質学会名誉会員に推薦する.
大場忠道 会員(1941年1月14日生まれ,76歳)
大場忠道会員は,1964年に埼玉大学文理学部を卒業し,同年に東北大学大学院理学研究科修士課程,1966年に同研究科博士課程に進学し,1969年に東北大学にて理学博士の学位を取得された.九州石油開発株式会社勤務を経て,1970年に東京大学海洋研究所に技官として採用され,2年間米国カリフォルニア大学に留学した後,1974年に同研究所の助手として採用された.1981年に金沢大学教養部に助教授として赴任され,1984年に教授に昇任された.1993年に北海道大学大学院地球環境科学研究科に異動し,2004年同大学を定年退職し,北海道大学名誉教授を授与された.
東京大学海洋研究所では,方解石とアラレ石の酸素同位体温度スケールの開発と応用を行い,黎明期における重要な知見を提示した.金沢大学では当時数少なかった安定同位体比質量分析計を広く開放し,国内の同位体分析の拠点として貢献するとともに,日本における古海洋研究の裾野を広げ,発展させることに尽力した.安定同位体を用いた古海洋学の分野では世界的にみても先駆的な研究を遂行し,氷期・間氷期サイクルにともなう日本海の環境変化の復元や,黒潮・親潮の変遷史に関する学際的かつ先進的な研究は,日本の古海洋学の発展に大きな影響を与えた.
国内外での学術活動では,国際委員として,気候変動と海洋に関する合同委員会(CCCO),海洋調査に関する科学委員会(SCOR),地球圏-生物圏国際共同研究(IGBP)の古環境変動研究(PAGES),国際全球海洋変動研究(IMAGES)の研究プロジェクの推進に尽力した.2001年には,古海洋学の国際学会である「第7回古海洋学会議(ICP-7)」を主催者として札幌において開催した.さらに,日本学術会議の第四紀学研究連絡委員を平成2年以降3期12年にわたって務め,日本の学術発展にも深く関わってきた.「第四紀学」(朝倉書店),第四紀試料分析法(東京大学出版会)などの編纂にも尽力し,第四紀地質学の普及に大きな貢献をされた.
このような長年にわたる地質学に関する研究,教育,普及への顕著な貢献に鑑み,大場忠道会員を日本地質学会名誉会員に推薦する.
2018年度名誉会員
2018年度名誉会員
坂巻幸雄 会員(1932年4月8日生まれ,86歳)
坂巻幸雄会員は,1956年に東京大学理学部地質学科を卒業し,同年に通商産業省工業技術院地質調査所に入所された.以後,37年の長きに渡り,核原料鉱物資源探査や休廃止鉱山の環境影響評価と重金属汚染の抑制手法,および地質標本管理等の研究に従事された.同調査所定年退職された後は,1994年から2年間,JICA長期派遣専門家のプロジェクトリーダーとして,モンゴル国地質鉱物資源研究所に勤務し,地質学を通じて,同国の鉱物資源開発に携わるなど国際的な貢献を行った.
地質調査所では,含ウラン二次鉱物の形成機構に着目し,表流水・地下水を用いる一般的な地球化学探査法を基礎として,ウラン鉱床に適用可能な手法を開発した.また,重金属はそのまま汚染物質の指標でもあることや,人為的な汚染の発生を試料水の導電率測定から判別する手法などを応用し,休廃止鉱山や廃棄物処分場に由来する汚染状況を効率良く判定する手法を開発し,効果的な対策に結びつけた.
こうした経験を基に,地質学的な解明が遅れがちであった環境汚染問題に積極的に関与するようになった.特に冨山平野で発生したイタイイタイ病問題に対しては,金沢高裁で被害者側が勝訴した1972年以降,住民側の選任科学者として協力を行い,2012年までの延べ40年間,発生源・岐阜県神岡鉱山への立入調査を系統的に実施し,多くの研究者とともにカドミウム汚染のメカニズムの把握やそれに見合った抑制策を提示した.この取り組みの帰結として,現在重金属類の流出はほぼ自然界レベルにまで抑制することができるようになった.また,環境汚染問題の実績が被害者住民団体の間で評価され,東京都日の出町谷戸沢・二つ塚処分場をはじめとして,敦賀市樫曲,富津市田倉,旭市海上などの廃棄物処分場の汚染水漏洩問題に関与し,現地観察に基づく主張の相当部分は,裁判所によって採用された.
2007年以降は,東京都江東区の豊洲中央卸売市場予定地で,かつて操業していた都市ガス工場によって引き起こされた深刻な土壌・地下水汚染や液状化―流動化現象に対し,環境地質学的視点からの問題提起と批判を展開し,一般の注意を喚起するなど,地質汚染問題のパイオニアとして活動を継続している.
このような長年にわたる地質学に関する研究,教育,普及への顕著な貢献に鑑み,坂巻幸雄会員を日本地質学会名誉会員に推薦する.
寺岡易司 会員(1934年1月20日生まれ,84歳)
寺岡易司会員は,1958年に広島大学理学部地学科を卒業し,同年,通産省工業技術院地質調査所地質部に採用された.海外資源特別研究官,地質部層序構造課長,首席研究官,地質部長などを歴任され,1965年には「九州大野川盆地付近の白亜系」の研究で,理学博士(広島大学)を取得された.1992年に地質調査所を退職された後,1992〜1997年に広島大学学校教育学部で教授として勤務され,2014年まで地質調査総合センターの客員研究員として勤務された.
地質調査所では,主に地質図幅調査に従事し,北部北上山地,北海道北東部,中国地方,四国九州などを対象とし,1/5万図幅を15葉,1/20万図幅を4葉,1/50万図幅を2葉作成した.また1/100万日本地質図(第2, 3版)の編纂を行い,日本地質アトラス(第2版)を編纂委員長として出版し,Geology of Japan(1960, 1977地調発行)の執筆も務めた.1973年からは,1年間,西ドイツ連邦地質調査所に交換研究員として派遣され,学会活動では地質学雑誌の編集委員も務めた.
また国際協力事業団専門家として,タイ,フィリピン,モンゴル(3回)などで,現地の大学や研究機関との共同研究を実施した.国際プロジェクトである環太平洋北面区画の地質図やテクトニックマップEATARトランセクトIV(日本−韓国)などの編纂を行った.さらに2000年以降,東アジア,中央アジアおよびアジア広域の地質図,同区画の鉱物資源や東アジア地震・火山災害図の作成も行った.
主な研究業績としては,九州東部の大野川層群に関する研究が挙げられ,層相変化に富み,莫大な層厚をもつ変動期の堆積物である本層群の地層について,詳細な層相・古流系・構造解析を行い,その堆積・変形史を明らかにし,臼杵−八代構造線の左横ずれ活動に関連づけて論述した.その際,中央構造線の西方延長,西南日本中軸帯の地体構造,和泉層群との関連にも言及した.これと並行し,四万十帯の地層群の調査を共同研究者と行い,層序・構造・変成作用を解明するとともに,砂岩モード組成,砂岩・泥岩化学組成,砕屑性ザクロ石の検討も行った.その結果,四万十帯の地層群は白亜系と古第三系−新第三系下部に大別され,前者は2つの亜層群に区分できるようになった.これらの地層群は,砕屑岩組成に違いがあり,広域にわたる層序・構造区分の枠組みが確立された.また砕屑性ザクロ石の研究では,対象を西南日本内帯から外帯にかけての上部古生界−新生界まで拡大し,砕屑性ザクロ石の化学組成をレーダーダイアグラムやMn-Mg-Ca三角図で示し,砕屑性ザクロ石のタイプ分けと各タイプの時代的・地域的消長を論じた.この手法により,アジア大陸の先カンブリア紀変成岩をはじめとする古期岩類からの砕屑物が,上記堆積岩類に多量に含まれていることを明示した.
このような長年にわたる地質学に関する研究,教育,普及への顕著な貢献に鑑み,寺岡易司会員を日本地質学会名誉会員に推薦する.
徳岡隆夫 会員(1938年3月14日生まれ,80歳)
徳岡隆夫会員は,1965年に京都大学大学院理学研究科博士課程を修了し,1967年に同大学理学部に助手として赴任された.その後,1980年に新設と なった島根大学理工学部に助教授として赴任され,1987年に同大学理学部教授に昇任された.2001年に同大学を定年退職され,島根大学名誉教授を授与 された.また1992〜2000年には島根大学汽水域研究センター長を併任された.
この間,初期には,四万十帯の前弧海盆の堆積学的研究を推し 進められ,紀伊半島の古第三系(音無川帯〜牟婁帯)を中心に,古流向解析をいち早く取り入れた堆積盆解析,礫岩・砂岩の砕屑物組成からの後背地解析で先駆 的な成果を上げ,四万十帯の堆積学的研究を先導した.また,P-T 境界についての国際的な層序学的研究,ヒマラヤ衝突帯についての共同研究,および中国帯の中・古生界の研究に貢献した.
島根大学へ異動後は,汽 水湖を対象とした研究に積極的に取り組まれ,宍道湖や中海の環境変遷を解明するとともに,全国的な海跡湖研究の推進に努め,その成果は2つの地質学論集 (nos. 36 & 39)に結実した.また,宍道湖・中海の自然環境の変遷を解明する研究を通して明らかにされた大根島玄武岩の三次元的な分布は,当時大きな社会問題となっ ていた中海干拓事業を中止に導く実質的な根拠となった.島根大学の他分野研究者とも協力して汽水域研究センターの設立に尽力し,この分野の国際的な拠点と して重要な役割を果たしつつある現在のエスチュアリ研究センターの基礎をつくった.韓国およびネパールにおける海外調査の実績を生かして,留学生を受け入 れる受け皿として大学院特別コースを島根大学に設置するなど,地質学の国際交流にも貢献された.
島根大学定年退職後も中海・宍道湖の自然保護に活躍され,2006 年には環境修復のためのNPO法人「自然再生センター」を立ち上げ,汽水環境の特性と地質学の重要性を訴えつつ,市民とともに活動を続けられている.
地質学会評議員を8期(16 年),副会長を2期(4年半)務められた.副会長在職時の1998〜2001 年は地質学会の法人化をめぐる議論の最中であり,法人化調査検討委員会委員長も務められ,学会の法人化への道筋をつけることに尽力された.また,学生の教 育・研究の指導にも卓越した力量を発揮して,多くの若手後継者の育成に成果を上げた.
このような長年にわたる地質学の研究,教育,普及への顕著な貢献に鑑み,徳岡隆夫会員を日本地質学会名誉会員に推薦する.
学部学生・院生の方へ:学生会費
2026年度から学生会費の申請について
準備中
2018年度各賞受賞者
2018年度各賞受賞者 受賞理由
■国際賞(1件)
■小澤儀明賞(1件)
■柵山雅則賞(2件)
■Island Arc賞(1件)
■論文賞(1件)
■小藤文次郎賞(1件)
■研究奨励賞(2件)
日本地質学会国際賞
受賞者:Millard F. Coffin 氏(Institute for Marine and Antarctic Studies, University of Tasmania)
対象研究テーマ:巨大火成岩岩石区の形成とその地球環境への影響に関する研究(Research on Large Igneous Provinces, implication for their formation process and impact on global environments)
Millard F. Coffin 氏は,巨大なマントル・プルームなどによって発生する大量のマグマが広大な玄武岩台地を形成する「巨大火成岩岩石区(Large Igneous Provinces, LIPs)」を提唱し,その地球科学的意義を実証的に明らかにした第一人者である.同氏はLIPs を地球物理学的,地質学的データを駆使して系統的に解析し,その詳細な形成メカニズムについて検討を行った.特にオントンジャワ海台,ケルゲレン海台などの形成メカニズムについて同氏が中心となってReviews of Geophysics 誌にまとめた論文(Coffin and Eldholm, 1994)は,LIPs に関する研究の金字塔となっている.この論文は多くの研究で引用され,同氏の研究が地球科学界に与えた影響の大きさを物語っている.これを筆頭に同氏は100 編を超える影響力の強い論文を発表している.
また,同氏はLIPs の形成に伴う火山噴火が気候や海洋環境に与えた影響についても多くの実績を残してきた.特に東京大学海洋研究所の教授であった2001〜2007 年にかけて,東京大学や海洋研究開発機構の若手研究者らと共同で研究を進め,白亜紀のオントンジャワ海台やカリブ海台の噴火活動が海洋無酸素事変の時期に一致することを明らかにし,この研究に新たな一面を切り開いた.この時期に日本の研究コミュニティーが同氏と議論を重ねながら研究領域を開拓するができたことは,大きな財産になっている.2004 年以降の同氏の業績一覧に多くの日本人研究者が名前を連ねていることからも,同氏の日本における教育・研究の影響の大きさがうかがえる.
同氏は2002〜2003 年には海洋研究開発機構の招聘研究員として統合国際深海掘削計画(IODP)に関する多くの重要な研究プロジェクトを進めることに貢献した.また,IODP の科学計画パネル(SPC)の議長として敏腕を振るうなど,国際科学計画の運営にも多くの実績をあげている.
以上のように,学術面,教育面,国際的なプロジェクトリーディングの面において,同氏が日本の地質学界に与えた功績は極めて大きい.これらの業績と日本地質学界への多大な貢献に鑑み,Millard F. Coffin 氏を日本地質学会国際賞候補者として推薦する.
Professor Millard F. Coffin is one of the leading experts who advocated the basic concept of Large Igneous Provinces (LIPs), and empirically clarified its geological significance. He has examined formational processes and mechanisms of LIPs, by analyzing geophysical and geological data in great detail. In particular, one of the papers about mechanisms of Ontong Java and Kerguelen LIPs that he and his colleagues published from Reviews of Geophysics (Coffin and Eldholm, 1994*) is the seminal work of this field. This paper has been heavily cited (>860), telling us how influential of his work is. In addition, he has published more than 100 influential papers.
He has also made a lot of work on the study of the consequences of LIPs, i.e., impact of massive volcanic eruption on the climate, ocean and life. When he was the professor of Ocean Research Institute (ORI), the University of Tokyo (2001-2007), he collaborated with young researchers at ORI and JAMSTEC, and revealed that massive eruptive episodes associated with the formation of LIPs (e.g., Ontong Java and the Caribbean Plateaus) coincided with oceanic anoxic events. His group has activated debates on this research issue. It is a great asset for Japanese young geoscientists that they experienced active discussion, and pioneered these research fields with Professor Millard F. Coffin during this tenure at ORI. The fact that many Japanese researchers are on the list of his achievements demonstrates how his influence on education and research was significant in Japan.
As an invited research scientist of JAMSTEC (2002-2003), he contributed to promoting important research projects on the Integrated Ocean Drilling Program (IODP). He has a lot of achievements in handling and planning of various international science projects, such as a chairman of the Science Planning Committee (SPC) of IODP.
In terms of academic and educational aspects, as well as his international leadership, his achievement on the Japanese geoscience community is significant. Here we recommend Professor Millard F. Coffin as a candidate for the International Award of the Geological Society of Japan in view of his achievement and a tremendous contribution on the Japanese scientific community.
*Coffin, M.F. and Eldholm, O. (1994) Large Igneous Provinces- crustal structure, dimensions, and external consequences. Reviews of Geophysics, vol. 32, p. 1-36.
▶受賞記念講演(2018.9.5 in 札幌)の内容はこちら
日本地質学小澤儀明賞
受賞者:澤木佑介 会員(東京大学大学院総合文化研究科)
対象研究テーマ:多元素同位体比分析を駆使した原生代後期の古環境解読研究
澤木佑介会員は地球史を中心とする分野で大きな成果をあげてきた.主に重金属元素の同位体比分析とジルコンの年代分析を土台に,常に最新の研究手法を取り入れ,精力的な研究を展開している.
同会員の特筆すべき成果は原生代後期の古環境解読研究である.原生代後期は大型多細胞動物出現の時代で,全球凍結や地球規模での大気海洋の酸化等の大変動が起こった時代とされ,地球史の中で最も重要な時代の一つである.同会員は,東京工業大学・東京大学を中心とした研究グループが行った原生代後期の堆積物の陸上掘削調査に参加して得られた保存のよい岩石試料のSr,Ca,Fe,Os同位体比を高時間解像度で連続的に測定した.その結果,原生代後期は地球史を通じて最も大陸風化が活発であったこと,それが海洋にCa等の栄養塩濃度を供給し海洋中の栄養塩濃度を増加させたこと,大気・海洋は酸化的-還元的環境を繰り返しながら徐々に酸化的環境に変化していったこと等を明らかにした.また,これまでの研究では鉄の化学種分析から硫化物イオン濃度の高い海洋(Euxinic ocean)が広がっていたとされてきたが,同会員は鉄の化学種分析の問題点を指摘し,Euxinic oceanの時期をより正確に特定した.これらの研究成果は,原生代後期の古環境に関する重要なデータセットとして高く評価されている.
同会員は,共同研究者とともに,太古代初期や原生代初期の地質体の研究も行っている.太古代初期の地質体の研究では,約39億年前のカナダ・ラブラドルのサグレック岩体で高精度の地質図を作成し,地質学的産状から本地域が最古の付加体であることを示した.さらに,グリーンランド・イスア地域の38億年前の生命の証拠とされる炭質物や共存する硫化物の炭素や鉄同位体から,最古の鉄還元バクテリアの存在を示唆する化学的証拠を発見した.最近は,原生代前期の大酸化イベント時の環境解読を進めるために,精力的に中央アフリカ・ガボンの地質調査,年代測定,堆積岩の化学分析等を行っている.
以上の優れた業績を高く評価するとともに,将来性を期待し,澤木祐介会員を日本地質学会小澤儀明賞に推挙する.
▶受賞記念講演(2018.9.5 in 札幌)の内容はこちら
日本地質学会柵山雅則賞_01
受賞者:野崎達生 会員(海洋研究開発機構 海底資源研究開発センター)
対象研究テーマ:火山性塊状硫化物(VMS)鉱床の成因研究
野崎達生会員は,卒業研究から現在まで一貫して地質学的・地球化学的手法に基づく鉱床学研究を行っている.特に,海底熱水鉱床を起源とする陸上の火山性塊状硫化物(VMS)鉱床の成因解明に精力的に取り組み,顕著な業績を挙げてきた.
博士課程から取り組んだ研究では,変成作用により初生的な年代決定が困難な三波川帯の別子型鉱床に対してRe–Osアイソクロン法を適用するという独創的なアプローチで挑み,その生成年代決定に世界で初めて成功した.そして,別子型鉱床の生成年代が約150 Maに集中することと,鉱床の生成場が遠洋域の中央海嶺であることを明らかにし,当時の特異な地球表層環境がもたらしたジュラ紀後期海洋無酸素事変を提唱するとともに,鉱床の生成・保存とグローバル環境変動が密接に関連するという資源地質学における第一級の命題を明らかにした.さらに,四万十帯北帯に分布する別子型鉱床にもRe–Os法を適用し,これらの鉱床が白亜紀後期の海嶺沈み込み現象に伴う鉱床であることを明らかにしたのみならず,現地性玄武岩を伴う別子型鉱床のRe–Os年代から,重要な地質イベントである海嶺沈み込み現象の時空間変遷を追跡できることを提示した.
同会員は海底熱水鉱床の研究航海にも数多く参加してきた.共同首席研究員を務めた二度の「ちきゅう」による科学掘削航海を通じて生成された人工熱水孔に着目し,人工熱水孔上に品位の高いチムニーが急激に成長することやその詳細な鉱物学的特徴を明らかにしている.これらのデータに基づき,黒鉱養殖という独創的なアイデアを着想し,現在その実用化に向けた研究を展開している.また,分析化学研究手法においても,気化法を用いたRe–Os同位体の迅速測定方法の開発や,その手法をマンガンクラストやレアアース泥,堆積岩などに適用し,新しい成果を挙げている.
以上の高い実績と将来性により,野崎達生会員を日本地質学会柵山雅則賞に推挙する.
▶受賞記念講演(2018.9.5 in 札幌)の内容はこちら
日本地質学会柵山雅則賞_02
受賞者:遠藤俊祐 会員(島根大学大学院総合理工学研究科)
対象研究テーマ:野外調査に根差した,沈み込み帯変成作用とテクトニクスの研究
遠藤俊祐会員は,綿密な地質調査・岩石記載に基づいた沈み込み帯の変成作用とテクトニクスに関する研究を展開し,注目すべき成果をあげてきた.それは以下の3つにまとめられる.(1)三波川変成帯の高変成部に位置する五良津岩体に広く分布するエクロジャイトは,粗粒であることなどにより異地性のテクトニックブロックと考えられていた.同会員は五良津岩体の変成年代をLu–Hf法により約117 Maと決定し,今まで唱えられていた三波川変成作用の2つの年代(約90 Maおよび約120 Ma)に対応した地質学的なイベントを示すことに初めて成功した.また,五良津岩体の岩石の粒径が大きいことは変成作用が高温で継続時間が他の地域より長いことによるとした.この過程で,研究例が少ない炭酸塩鉱物に富むエクロジャイトの岩石学解析や,鉄の酸化状態を変数として取り入れたシュードセクション作成など,解析法についても新たな展開を示した.(2)グアテマラ・北部モタグア断層帯は,現在活動中の沈み込み帯深部に分布すると考えられるローソン石エクロジャイトの露出で有名である.しかし,その形成条件の見積りは,低温で形成するために反応速度が遅く化学平衡が保証されず難物であった.同会員は通常の地質温度圧力計に加えて,シュードセクション法,ラマン炭質物温度計などの手法を融合し,今までより格段に誤差の少ない解析を行った.(3)秩父帯北帯での高圧変成作用の範囲が従来の理解より大幅に広いことを明らかにした.また,ローモンタイト(濁沸石)の分解が沈み込み帯における重要な脱水反応であり,地震発生領域の下限を支配する重要な反応である可能性があると指摘した.
上記の通り,同会員は多岐にわたり沈み込み型変成作用研究に大きく貢献しており,今後,日本の変成岩研究をリードする有望な若手研究者として期待される.よって,遠藤俊祐会員を日本地質学会柵山雅則賞に推挙する.
▶受賞記念講演(2018.9.5 in 札幌)の内容はこちら
日本地質学会 Island Arc賞
受賞論文:Ayumu Miyakawa, Saneatsu Saito, Yasuhiro Yamada, Hitoshi Tomaru, Masataka Kinoshita and Takeshi Tsuji, 2014, Gas hydrate saturation at Site C0002, IODP Expeditions 314 and 315, in the Kumano Basin, Nankai trough. Island Arc, 23, 142–156.
Miyakawa et al. (2014) estimated the degree of gas hydrate saturation at IODP Site C0002 in the Kumano Basin, Nankai Trough from logging-while-drilling logs and core samples obtained during IODP Expeditions 314 and 315 using Deep Sea Drilling Vessel Chikyu. Based on the excellent geophysical and geochemical data, the free gas migration in sediment is well illustrated. They found coexistence of gas hydrate and free gas, suggesting a large gas flux flowing to the southern and seaward edge of the basin from a deeper part of the Kumano Basin. This knowledge is applicable to various kinds of pore fluids and thus important to consider digenetic process of sedimentary rocks. This paper presents one of important results of gas hydrate formation obtained by the NanTroSEIZE drilling program using Chikyu. Their work has been broadly cited as the standard of the gas hydrate saturation in the seaward edge of the Kumano Basin, Japan. In addition, their findings motivate further studies on the coexistence of gas hydrate and free gas and the fluid migration in the area.
Ayumu Miyakawa graduated from Kyoto University with a BSc in 2006; he subsequently completed a Ph.D. course at the same university with the degree in 2011. He became a Postdoctoral Researcher at Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) in 2011; he served there for one year. In April 2012, he started his engagement in research at the Geological Survey of Japan (GSJ) in the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST); he is a Senior Researcher since October 2017. His main interest is in the dynamics of subduction zones. He joined Nankai Trough Seismogenic Zone Experiment as an onboard logging scientist in IODP Expedition 314. The logging data obtained during the cruse revealed the fluid migration and the hydrate deposition within the forearc basin, as mentioned in the awarded article. He is also curious about the integration of the geological/geophysical observation such as the logging data and the geodynamics modeling. He is conducting the numerical modeling to simulate the dynamics of the subduction zones. Currently, he is expanding his research to crustal stress controlling the reactivation of the fault and the openness of the fault-fracture conduit in the crust.
>論文サイトへ(Wiley)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/iar.12064
日本地質学会論文賞
受賞論文:Osamu Takano and Takashi Tsuji, 2017, Fluvial to bay sequence stratigraphy and seismic facies of the Cretaceous to Paleogene successions in the MITI Sanriku-oki well and the vicinities, the Sanriku-oki forearc basin, northeast Japan. Island Arc, 26, e12184, doi:10.1111/iar.12184.
三陸沖堆積盆はテクトニクス的にも石油・石炭地質的にも堆積学的にも重要な前弧堆積盆である.しかし,堆積盆の主要部分が海底にあるため,全容の解明が難しかった.本論文は,石油・天然ガスの探鉱のために取得された三次元地震探査断面と,基礎試錐「三陸沖」によって得られた坑井データを駆使し,この地域の上部白亜系から始新統の堆積相と地震探査断面における震探相とを詳しく解析したものである.また,解析結果をもとに,堆積環境を詳細に復元し,前弧海盆の埋積モデルを構築している.本研究成果は,三次元地震探査技術と堆積学とをリンク・統合させたいわゆる三次元サイスミック地形学の特筆すべき優れた研究結果である.本研究の結果,沈み込みに伴う三陸沖堆積盆の埋積過程がまるで航空写真で地形変化を見るかのように復元された.また本論文は,応用分野である石油・天然ガス探鉱のための技術が堆積盆解析に寄与する様子をつぶさに知らしめており,これから地質学を学ぼうとする若手に総合的な地質学の面白さを示す好例となっている.以上の理由より,本論文を日本地質学会論文賞に推薦する.
>論文サイトへ(Wiley)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/iar.12184
日本地質学会小藤文次郎賞
受賞者:小宮 剛 会員(東京大学大学院総合文化研究科)
対象論文:Takayuki Tashiro, Akizumi Ishida, Masako Hori, Motoko Igisu, Mizuho Koike, Pauline Méjean, Naoto Takahata, Yuji Sano and Tsuyoshi Komiya, 2017, Early trace of life from 3.95 Ga sedimentary rocks in Labrador, Canada. Nature, 549, 516–518.
これまで最古の生命の痕跡は38億年前のグリーンランド・イスアの堆積岩中のグラファイトとされてきた.しかし,それ以前にも地球上には海が存在し,より古い時代に生命が存在していたと考える研究者も多い.小宮 剛会員を中心としたグループは39.5億年前のカナダ・ラブラドル地域のヌリアック表成岩類の調査を継続的に行い,泥質変成岩と変成炭酸塩岩から抽出したグラファイトが生物由来の有機物であることを示した.最新鋭の分析方法を用いて測定した炭素同位体比は,グラファイトの値が十分に低く,無機炭素との値の差も大きいことから,これが自家栄養の微生物を起源としていたことを表す.また,コンタミネーションやFischer-Tropschタイプの可能性についても,慎重な分析から否定的な証拠を提示している.昨年9月に発表された上記論文の内容は,最古の生命の痕跡を1.5億年も更新し,その重要性ゆえに多くのメディアに取り上げられた.これは地球史を塗り替える重要な地質学的成果であり,本研究を主導した小宮 剛会員を日本地質学会小藤文次郎賞候補者として推薦する.
>論文サイトへ(Nature)
https://www.nature.com/articles/nature24019
日本地質学会研究奨励賞_01
受賞者:綿貫峻介 会員(国際石油開発帝石株式会社)
対象論文:綿貫峻介・金井拓人・坂 秀憲・高木秀雄,2017,青森県白神山地西部に発達する入良川マイロナイト帯の変形微細構造.地質学雑誌,123,533–549.
白神山地西部の日本海沿岸地帯には,白亜紀花崗岩体内部に南北に伸びるマイロナイト帯が知られている.綿貫峻介会員らは本マイロナイト帯を入良川マイロナイト帯と呼称し,マイロナイト帯を横切る複数の側線で詳細な構造地質学的調査を行った.その結果,本マイロナイト帯は350 m程度の幅を持ち,外側から中心部へプロトマイロナイト,マイロナイトおよび一部カクレーサイト化したウルトラマイロナイトから構成されていることが明らかとなった.また,マイロナイトの変形構造についてSEM-EBSDを用いて再結晶石英の粒径,結晶方位および粒子形態ファブリックを解析し,変形機構,変形物理条件および変形履歴について詳細に議論した.特にランダムファブリックを示すウルトラマイロナイトの薄い石英集合体については,他の鉱物との接触の影響の有無を検討するなどの慎重な解析が加えられている.また,従来の研究を補完する結果ではあるが,剪断センスや岩石帯磁率についても詳細に検討し,本マイロナイト帯が畑川構造線のマイロナイト帯の北方延長ではなく,阿武隈帯内部に発達する剪断帯であることを明確にした.本論文は構造地質学の分野で最近,世界的な関心が集まっている断層帯のアーキテクチャーや変形機構について重要な成果を得た論文と判断されるほか,同会員の剪断帯に関する総合的な構造解析能力が発揮されている.以上の理由より,綿貫峻介会員を日本地質学会研究奨励賞候補者として推薦する.
>論文サイトへ(J-STAGE)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/geosoc/123/7/123_2017.0006/_article/-char/ja
日本地質学会研究奨励賞_02
受賞者:高橋 聡 会員(東京大学大学院理学系研究科)
対象論文:高橋 聡・永広昌之・鈴木紀毅・山北 聡,2016,北部北上帯の亜帯区分と渡島帯・南部秩父帯との対比:安家西方地域のジュラ紀付加体の検討.地質学雑誌,122,1–22.
高橋 聡会員は,東北日本北部北上帯のジュラ紀付加体について,従来提唱されていた亜帯(葛巻–釜石亜帯と安家–田野畑亜帯)区分の妥当性を検証するとともに,北海道や西南日本外帯のジュラ紀付加体との対比を行った.同会員は両亜帯の境界域における詳細な地質図を作成し,岩相区分,微化石同定,砂岩組成解析といったさまざまな手法を駆使し,この亜帯区分が概ね妥当であることを示した.また,類似点・相違点を提示し,両亜帯に分布するユニットが北海道の渡島帯,西南日本外帯の秩父帯においてどのユニットと対比できるかを示した.本研究は,中生代日本列島形成史を解明する上で鍵となる重要なデータを提示し,新たな広域対比を行ったものであり,高く評価できる.また,本成果は同会員の長期にわたる地道な野外調査から得られたものであり,野外地質学をベースとした地域地質研究の重要性を示す好例でもある.以上の理由により,本論文の筆頭著者である高橋 聡会員を日本地質学会研究奨励賞に推薦する.
>論文サイトへ(J-STAGE)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/geosoc/122/1/122_2015.0034/_article/-char/ja
Geo暦(2019)
2019年Geo暦(行事カレンダー)
2008年版 2009年版 2010年版 2011年版 2012年版 2013年版
2014年版 2015年版 2016年版 2017年版 2018年版 --------
2020年版
2019年版 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
○印は学会主催行事.(共)学会共催・(後)後援・(協)協賛
1月January
平成30年度海洋情報研究成果発表会
「南海トラフ研究の最前線」
1月17日(木)13:10-18:15
会場:中央合同庁舎第4号館(千代田区霞ヶ関)
入場無料
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/jhd.html
第30回GSJシンポジウム「千葉の地質と地震災害を知る」
1月18日(金)13:00〜17:20
会場:千葉市生涯学習センター
https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo30/index.html
日本古生物学会第168回例会
1月25日(金)〜27日(日)
会場:神奈川県立生命の星・地球博物館
http://www.palaeo-soc-japan.jp/events/
第218回地質汚染イブニングセミナー
1月25日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:中山敏雄(元東京都土木技術研究所 地質研究室 主任研究員)
演題:「首都東京の地盤沈下・地下水位の変遷と現在の観測体制について」
http://www.npo-geopol.or.jp
○関東支部サイエンスカフェ
「磁場ニャン??いやいや,チバニアン」
1月27日(日)14:00開場,14:30〜16:00ころ
場所:イタリアンレストランACQUA E SOLE(アクアエソーレ)
入場料:2,000円ゲストスピーカー:岡田 誠(茨城大学)
ファシリテータ:岡山悠子(科博SCA)
https://sites.google.com/view/chibanian/
2月February
火山災害対策研究フォーラム
―東京の火山災害に備える―
2月9日(土)13:00〜16:00(受付開始:12:30)
場所:首都大学東京南大沢キャンパス講堂小ホール
事前申込・参加費不要
詳しくは,こちら
第219回地質汚染イブニングセミナー
2月22日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:木村和也(医療地質研究所)
テーマ:東京圏の6年間継続測定からみる空間放射線量率の現状−安全か、安心か、不安か−
http://www.npo-geopol.or.jp
(後)東北大学東北アジア研究センター公開講演会
2月23日(土)13:00〜17:00
場所:東京エレクトロンホール宮城(仙台市青葉区国分町)
「地球生命の起源と進化:ヒトの誕生と現在から近未来の課題まで」
講師:丸山茂徳(東京工業大学)
http://www.cneas.tohoku.ac.jp/
3月March
○西日本支部平成30年度総会・第170回例会
3月2日(土)例会・総会
場所:長崎大学教育学部棟本館4階
講演申込締切:2月15日(金)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
第5回地区防災計画学会大会
都市の防災教育研究と地区防災計画における女性の視点
3月2日(土)9:30〜18:30(予定)
会場:大阪市立大学杉本キャンパス 全学共通教育棟8号館
参加費無料
申込:地区防災計画学会HPから
http://www.gakkai.chiku-bousai.jp/ev190302.html
20th Project A in Okayama
3月4日(月)〜8日(金)
場所:地球史研究所(Institute of GeoHistory)(赤磐市周匝1548)
地球に関わる異種分野合流の研究発表会および地質巡検
学生・大学院生・若手研究者・研究者だれでも参加OK
参加料:大人 25,000円,学生 10,000円(4泊食事付)
締切:12月20日(木)
詳しくは,archean.jp
第53回日本水環境学会年会
3月7日(木)〜9日(土)
開催地:山梨大学(山梨県甲府市)
http://www.jswe.or.jp/event/lectures/2018per.html
日本地学オリンピック とっぷ・レクチャー
3月10日(日)14:00〜17:00
場所:筑波銀行本部ビル 10階大会議室
(つくば市竹園1-7)
募集人数:150名(先着)*事前登録
http://jeso.jp/index.html
第7回防災学術連携シンポジウム
「平成30年夏に複合的に連続発生した自然災害と学会調査報告」
主催:日本学術会議 防災減災学術連携委員会 防災学術連携体(56学会)
3月12日(火)10:00〜17:30
場所:日本学術会議講堂
http://janet-dr.com/060_event/20190312/190312_000_leef.pdf
国際シンポジウム「島嶼環境文明にみる地球の未来」
3月16日(土)〜18日(月)
場所 静岡県コンベンションアーツセンター
「グランシップ」11階会議ホール「風」(JR東静岡駅南口から徒歩3分)
参加費無料
https://www.fujimu100.jp/sympo2019/
International Conference on Geoscience for Society (GeoSoc)
3月14日(木)〜 17日(日)
場所:バングラデッシュ・ダッカ市
https://www.data-box.jp/pdir/7085ba17d18d49959128fd842853976a
○2018年度東北支部総会
3月16日(土)〜17日(日)(注)3/17はキャンセルになりました
場所:秋田大学教育文化学部
申込締切:3月4日(月)
要旨締切:3月11日(月)
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
第220回地質汚染イブニングセミナー
3月29日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室 (東京都北区)
講師:川辺孝幸(山形大学教授)
演題:退官記念講義/日本列島の地質構造と地質災害そして減災(仮題)
http://www.npo-geopol.or.jp
○地質情報展2019北海道—明治からつなぐ地質の知恵
3月29日(金)〜31日(日)
会場:かでる2・7(北海道札幌市)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/gyoji
○市民講演会
『動く大地のしくみを知り,地震・津波災害に備える』
3月30日(土)
会場:かでる2・7(北海道札幌市)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/gyoji#koen
4月April
○関東支部2019年度総会・地質技術伝承講演会
4月13日(土)14:00〜16:45
場所:赤羽会館 4F小ホール (東京都北区赤羽南1-13-1)
14:00〜15:40 地質技術伝承講演会
講師:横井 悟(石油資源開発(株)技術本部フェロー)
「石油地質分野におけるunconventionalあるいは非石油的な話」
参加費:無料 どなたでも参加できます
15:50〜16:45 関東支部総会
欠席の方は,委任状をご提出下さい(締切:4月12日(金)18時)
http://www.geosociety.jp/outline/content0197.html
日本学術会議主催学術フォーラム
「危機に瀕する学術情報の現状とその将来 Part 2」
4月19日(金)13:00〜17:30
場所:日本学術会議講堂
先着300名(参加費 無料)
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/273-s-0419.pdf
第221回地質汚染イブニングセミナー
4月19日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ 8階807会議室(東京都北区王子)
講師:風岡 修(地質汚染診断士・液流動化診断士・東邦大学非常勤講師・理学博士)
演題:「地質環境と宅地理学診断」
http://www.npo-geopol.or.jp
○第36回地球科学講演会「OSL年代−砂粒に刻まれた時の記憶」
4月20日(土)15:00-16:30
会場:大阪市立自然史博物館 講堂
講師:田村 亨 氏(産業技術総合研究所)
主催:日本地質学会近畿支部ほか
定員:150名 参加無料,申込不要
詳しくは
第192回深田研談話会
4月20日(土)14:30〜16:00
場所:深田地質研究所 研修ホール(東京都文京区)
講師:早坂康隆 氏(広島大学大学院理学研究科准教授)
演題:ジルコン年代学に基づく西南日本の地質構造発達史
参加費無料.70名(先着)*要事前申込
http://www.fgi.or.jp/?p=4342
トークセッション「一家に1枚 日本列島7億年」をよみとく
会場:日本科学未来館 5階 コ・スタジオ(東京都江東区2-3-6)
登壇者:磯崎行雄・辻森 樹
*地質学会のWEB教材体験会も同時開催
http://www.geosociety.jp/news/n141.html
第18回重金属類・残土石処分地・廃棄物処分地診断に関わる地質汚染調査浄化技術研修会
4月25日(木)〜28日(日)
主催:NPO法人 日本地質汚染審査機構
共催:地質汚染診断士の会・日本地質学会環境地質部会・IUGS-IMGA日本支部
会場:日本地質汚染審査機構関東ベースン実習センター(千葉県香取市)
会費:会員50,000円・非会員60,000円・学生:15,000円
http://www.npo-geopol.or.jp
5月May
阿蘇山の地下を見てみよう ボーリングコア公開と火山講座
主催:防災科学技術研究所ほか
5月12日(日)13:00〜16:30
場所:阿蘇火山博物館
(注)火山講座・火山実験の定員は150名(先着締切)
http://www.bosai.go.jp/press/2019/pdf/20190416_02_press.pdf
第193回深田研談話会
5月18日(土)14:30〜16:00
場所:深田地質研究所 研修ホール(東京都文京区)
講師:宮田真也 氏(城西大学大石化石ギャラリー学芸員)
演題:日本の魚類化石を観る
参加費無料、70名(先着)*要事前申込
http://www.fgi.or.jp/
2019年度春期(初心者向け)地質調査研修
5月20日(火)〜24日(金)
場所:島根県出雲市長尾鼻周辺(小伊豆海岸)
申込締切:5月13日(月)正午
https://www.gsj.jp/geobank/geotraining.html
日本地球惑星科学連合2019年大会
(JPGU Meeting 2019)
5月26日(日)〜30日(木)
会場:幕張メッセ
予稿投稿期間:1月8日(火)〜2月19日(火)
http://www.jpgu.org/meeting_2019/
Wiley 論文投稿ワークショップ
〜国際誌への投稿論文を初めて書く人へのアドバイス〜
5月28日(火)12:30〜13:30
会場:幕張メッセ国際会議場
講師:武藤鉄司(長崎大学・Island Arc編集委員長)
bit.ly/Wiley-JpGU2019
第222回 地質汚染イブニングセミナー
5月29日(水)18:30〜20:30
場所:北とぴあ9階901会議室 (東京都北区)
講師:門間 聖子 (応用地質株式会社 技術本部技師長室 技師長)
演題:自然由来の重金属等に関する環境リスクマネジメントと改正土壌汚染対策法
http://www.npo-geopol.or.jp
6月June
深田研ジオフォーラム2019
6月8日(土)10:00〜16:00
場所:深田地質研究所 研修ホール(東京都文京区)
講師:上野将司(応用地質株式会社社友)
演題:平野と山地の地盤災害を考える〜災害列島での調査経験から〜
定員:50名【申込多数の場合は抽選】*要事前申込
http://www.fgi.or.jp/
○関東支部:サイエンスカフェ
マンネン × シバハラ × 立体地図(ブラマンネン2)
6月9日(日) 15-17時(14時半開場)
場所:Bar de 南極料理人 Mirai
入場料:2,000円(1ドリンク込み)
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
2019年石油技術協会春季講演会
6月12日(水)〜13日(木)
場所:国立オリンピック記念青少年総合センター(渋谷区代々木)
http://www.japt.org/index.html
○東北支部会主催地質見学会
「能代・八峰・白神地域のジオサイトを訪ねて」
6月22日(土)〜23日(日)
参加申込締切:6月4日(火)
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
地質学史懇話会
6月23日(日)13:30〜17:00
場所:北とぴあ 8階803号室(JR京浜東北線王子駅下車3分)
若林 悠:天気予報における官僚制と社会―日本の気象行政の歴史分析に向けて―(6/6修正)
木村 学:北海道の地質学研究 150年,雑感
第223回 地質汚染イブニングセミナー
6月28日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ902会議室(東京都北区王子)
講師:宮崎 淳(創価大学教授)
演題:「水循環基本法の理念と地下水の法的性質〜公水私水区分論からの脱却〜」
http://www.npo-geopol.or.jp
7月July
(後)第56回アイソトープ・放射線研究発表会
7月3日(水)〜5日(金)
会場:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
発表申込締切:2月28日(木)17:00
参加費(Web要旨集含):
事前登録:7,000円/当日登録:9,000円/学生:無料 (いずれも税込)
https://www.jrias.or.jp/isotope_conference/index.html
第194回深田研談話会
7月5日(金)18:00〜19:30
場所:深田地質研究所 研修ホール(東京都文京区)
講師:芦 寿一郎 氏(東京大学大気海洋研究所海洋底地質学分野准教授)
演題:海底から探る南海トラフの断層活動と地震履歴
参加費無料、70名(先着)、*要事前申込
http://www.fgi.or.jp/
第224回地質汚染・災害イブニングセミナー
7月25日(木)18:30-20:30[日程が変更になりました(26日→25日)]
場所:北とぴあ808会議室(東京都北区 JR王子駅から徒歩5分)
講師:益子 保(公益財団法人中央温泉研究所)
演題:「温泉水の重金属排水問題〜水濁法との関係から〜」
会費:会員500円 非会員 1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
(後)青少年のための科学の祭典:2019全国大会
7月27日(土)〜28日(日)
会場:科学技術館(千代田区北の丸公園)
http://www.kagakunosaiten.jp/
入場無料.また期間中,高校生以下は科学技術館常設展示も無料
(大人は通常料金)
久留里湧水の現場見学会・久留里湧水と水循環フォーラム
―なぜ、湧水って下から湧き出るの?―
主催:NPO法人日本地質汚染審査機構
7月27日(土)
1.湧水井戸見学会(10:00〜)
集合場所:JR久留里駅前 水のみ場
2.久留里湧水と水循環フォーラム(13:00〜16:00)
会場:君津市農村環境改善センター・農事研究室(君津市久留里)
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
8月August
(後)科教協福岡大会・科学お楽しみ広場
(第66回全国研究大会福岡大会)
8月9日(金)
会場:西南学院大学 西南コミュニティセンター(福岡市早良区)
参加無料
参加者は各展示ブースを回って,自然科学,理科教育に関する
様々な体験や学びができます.児童生徒も参加可.
https://kakyokyo.org/archives/1319
(共)第20回地震火山こどもサマースクール
「研究者と丹後を巡る2日間」
8月10日(土)-11日(日)
対象 小学5年生〜高校生 24名
参加費:5,000円
参加申込締切:7月5日(金)7月19日(金)締切延長!!
http://www.kodomoss.jp/ss/tango/
○関東支部:清澄フィールドキャンプ
8月19日(月)〜24日(土) 5泊6日
場所:東京大学演習林(〒299-5505 千葉県鴨川市清澄)
応募締切日:7月5日(金)
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
第73回地学団体研究会総会(東京)
8月23日(金)〜25日(日)
場所:東京都港区 芝学園中学校高等学校
https://www.chidanken.jp
第225回地質汚染・災害イブニングセミナー
8月30日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ806会議室(東京都北区王子)
講師:山崎晴雄(首都大学東京名誉教授 理学博士)
演題:『首都圏における活断層−地層判定の重要性−』
会費:会員500円 非会員 1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
9月September
第22回日本水環境学会シンポジウム
9月5日(木)-6日(金)
場所:北海学園大学工学部(山鼻キャンパス)
http://www.jswe.or.jp/event/symposium/index.html
(後)第63回粘土科学討論会
9月10日(火)〜12日(木)
(講演会:9月10〜11日,現地見学会:9月12日)
会場:埼玉大学(さいたま市桜区下大久保225)
http://www.cssj2.org/publication/annual_meeting/
(共)日本地球化学会第66回年会
9月17日(火)〜19日(木)
場所: 東京大学・本郷キャンパス
http://www.geochem.jp/meeting/index.html
日本鉱物科学会2019年年会
9月20日(金)〜22日(日)
場所:九州大学
http://jams.la.coocan.jp/index.html
第36回歴史地震研究会(徳島大会)
9月21日(土)〜 23日(月・祝)
会場:徳島大学 地域連携プラザ 地域連携大ホール
http://www.histeq.jp/menu7.html
○日本地質学会第126年学術大会(2019山口)
9月23日(月・祝)〜25日(水)
場所:山口大学 吉田キャンパス(山口市吉田)
日本火山学会2019年度秋季大会
9月25日(水)〜27日(金)
場所:神戸大学(兵庫県神戸市)
http://www.kazan-g.sakura.ne.jp/J/index.html
第226回 地質汚染・災害イブニングセミナー
9月27日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ806会議室(東京都北区王子)
講師:張 銘(産総研 地圏環境リスク研究グループ長)
演題:「化学と科学でみる自然由来重金属類」
会費:会員500円 非会員 1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
10月October
(協力)深田研 一般公開2019
10月6日(日)
場所:深田研地質研究所(文京区本駒込)
第10回フォトコンテスト作品の展示もあります.
http://www.fgi.or.jp/
第73回日本人類学会大会
10月12日(土)〜14日(月)
会場:佐賀大学本庄キャンパス(佐賀市本庄町1)
演題登録締切:7月29日(月)
http://anthrop-meeting.sakura.ne.jp/
(協)石油技術協会秋季講演会
10月17日(木)
会場:東京大学 小柴ホール
https://www.japt.org/gyouji/kouenkai/
ぼうさいこくたい2019
「あなたが知りたい防災科学の最前線:激化する気象災害に備える」
10月19日(土)16:30-18:00
場所:名古屋市ささしまライブ24エリア・メインホールB
http://www.bosai-kokutai.jp/
関東支部共催
シンポジウム「研究の最前線:中期更新世以降の関東平野北東部の地質と地形発達」
10月19日(土) 13:20-17:00(13:00開場)
会場:つくば市役所コミュニティー棟第一会議室
主催:筑波山地域ジオパーク推進協議会
共催:日本地質学会関東支部
参加費:無料
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
関東支部:筑波山地域ジオパーク巡検
10月20日(日)
TXつくば駅9:50集合-17:00解散(予定)
募集:20人(先着順)
講師:久田健一郎(筑波大学)・杉原 薫(筑波大学)
申込期間:9月9日(月)-10月4日(金)
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
第227回地質汚染・災害イブニングセミナー
10月25日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ808会議室 (東京都北区 JR王子駅から徒歩5分)
講師:笹川みちる(NPO法人雨水市民の会理事、NPO法人雨水まちづくりサポート理事)
演題:「雨水と賢くくらすには〜墨田区の取り組みから」
会費:会員500円 非会員 1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
2019年度秋期(初級者向け)地質調査研修【参加者募集中】
10月28日(月)-11月1日(金)
場所:島根県出雲市長尾鼻周辺(小伊津海岸)
定員:6名(締切:10月11日(金))(定員になり次第締切)
https://www.gsj.jp/geobank/geotraining.html
11月November
(後)第20回「こどものためのジオ・カーニバル」
11月2日(土)-3日(日)
場所:大阪市立科学館
http://geoca.org/index.html
東京地学協会メダル受賞記念講演会
「テフラ研究,これまでの知見と展望」
11月8日(金)15:30-16:30
場所:学士会館
講演者:町田 洋博士
参加申込不要(どなたも無料で参加できます)
http://www.geog.or.jp/lecture/lecturescheduled/377-r1medal.html
国際ゴンドワナ研究連合2019年総会及び第16回ゴンドワナからアジア国際シンポ
11月8日(金)〜10日(日)
場所:高知県立県民文化会館(高知市)
野外巡検:11日〜12日,室戸ジオパーク
https://www.data-box.jp/pdir/39aafa3256dd487480194b110293927c
お問い合せ:Prof. Darren Lingley(高知大学人文社会科学部)
E-mail: lingley@kochi-u.ac.jp
第195回深田研談話会
11月15日(金)18:00〜19:30
場所:深田地質研究所 研修ホール(東京都文京区)
講師:千葉達朗氏(アジア航測株式会社先端技術研究所千葉研究室室長,フェロー)
演題:赤色立体地図の発想と応用−1枚の正射画像で立体的に地形を把握できる手法の発見
参加費無料,70名(先着)*要事前申込
http://www.fgi.or.jp/
第30回 地質汚染調査浄化技術研修会
11月15日(金)〜17日(日)
主催:NPO法人 日本地質汚染審査機構
共催:地質汚染診断士の会・日本地質学会環境地質部会・社会地質学会
会場:日本地質汚染審査機構関東ベースン実習センター
(〒287-0025 千葉県香取市本矢作1277-1:Tel:0478-59-1491)
会費:会員45,000円・非会員 55,000円・学生:15,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
日本学術会議公開シンポジウム
国連の持続可能な海洋科学の10年−One Oceanの行動に向けて−
11月6日(水)9:30 - 17:00
場所:笹川平和財団海洋政策研究所(港区虎ノ門1-15-16)
参加費無料・要事前申込
https://www.spf.org/opri/event/20191106.html
東京地学協会メダル受賞記念講演会
「テフラ研究,これまでの知見と展望」
11月8日(金)15:30-16:30
場所:学士会館
講演者:町田 洋博士
参加申込不要(どなたも無料で参加できます。)
http://www.geog.or.jp/lecture/lecturescheduled/377-r1medal.html
第195回深田研談話会
11月15日(金)18:00-19:30
場所:深田地質研究所 研修ホール(東京都文京区)
講師:千葉達朗氏(アジア航測株式会社)
演題:赤色立体地図の発想と応用
参加費無料,70名(先着)*要事前申込
http://www.fgi.or.jp/
GSSPシンポジウム 〜国際層序の意味と意義〜
11月23日(土)13:00〜17:00
会場:産総研つくば中央 共用講堂(入場無料・事前登録不要)
主催:一般社団法人日本地質学会
共催:産総研地質調査総合センター,日本古生物学会
http://www.geosociety.jp/outline/content0096.html
関東支部:地学教育・アウトリーチ巡検
11月24日(日)
集合:小湊鉄道「月崎駅」10:20
内容:チバニアンの地層見学、素掘りのトンネルの見学等
その他:今回は基本全コース徒歩です。
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html#ex2019-02
第228回地質汚染・災害イブニングセミナー
11月28日(木)18:30〜20:30 ←曜日に注意
場所:北とぴあ701会議室(東京都北区 JR王子駅から徒歩5分)
講師:山本 晃(八千代エンジニヤリング株式会社 地質・地盤部長)
演題:「地下水流動可視化の研究成果」
会費:会員500円 非会員 1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
火山災害軽減のための方策に関する国際ワークショップ
テーマ:火山噴火の危機管理
11月28日(木)9:30-16:40
会場 都道府県会館101大会議室(東京都千代田区平河町)
http://www.mfri.pref.yamanashi.jp/
国際シンポジウム2019
火山噴火とリスクコミュニケーション
11月30日(日)9:30-16:30
会場 山梨県富士山科学研究所 ホール(富士吉田市上吉田)
http://www.mfri.pref.yamanashi.jp/
12月December
国総研講演会
12月3日(火)10:00-17:00
会場:日本教育会館一ツ橋ホール
報告「令和元年台風第19号等について」ほか
http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/kouenkai/kouenkai2019/kouenkai2019.htm
「地盤情報の利活用と不動産情報」に関するワークショップ
12月4日(水)13:00-16:00
会場:地域地盤環境研究所 会議室(國民會館・住友生命ビル6階:
大阪市中央区大手前2丁目)
問い合わせ先:地質地盤情報の活用と法整備を考える会
geo.houseibi@gmail.com
https://www.geo-houseibi.jp
(協)第35回ゼオライト研究発表会
12月5日(木)-6日(金)
会場:タワーホール船堀(江戸川区船堀4-1-1)
https://jza-online.org/
第31回GSJシンポジウム(地圏資源環境研究部門 研究成果報告会)
「地下水、土壌、地中熱の基盤データ整備と利活用」
12月6日(金) 13:30-17:40
場所:秋葉原ダイビル・コンベンションホール
事前登録制・参加費無料・CPD4単位
https://unit.aist.go.jp/georesenv/index.html
第32回GSJシンポジウム
「神奈川の地質と災害」
12月12日(木)13:00ー17:35
会場:TKPガーデンシティ横浜ホールA
事前登録制・参加費無料・CPD4単位
https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo32/index.html
四国支部総会・講演会
12月14日(土)13:00〜17:00(予定)
場所:香川大学研究交流棟5階研究者交流スペース(幸町北キャンパス内)
講演申込締切:11月29日(土)
参加申込不要(無料で聴講できます).
プログラム公開しました(PDF)
http://www.gsj-shikoku.com/research.html
日本遺産「大谷石文化」石のまち宇都宮シンポジウム
12月14日(土)10:30-16:00
会場:宇都宮市文化会館小ホール
入場無料,事前申込不要(先着500名)
問い合わせ:下野新聞社営業局業務推進部 電話028-625-1104
第229回 地質汚染・災害イブニングセミナー
12月20日(金)18:30-20:30
場所:北とぴあ807会議室 (JR京浜東北線 王子駅下車)
講師:佐々木裕子(NPO法人日本地質汚染審査機構理事・薬学博士・元東京都環境科学研究所研究員)
演題:「改正土壌汚染対策法の化学分析と調査」
会費:会員500円 非会員 1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
地区防災計画学会・京都大学矢守研究室共同シンポジウム
(第33回研究会)「台風19号等の教訓と地区防災計画」
12月21日(土)13:45-16:45(予定)
場所:キャンパスプラザ京都第4講義室(京都市下京区西洞院通)
参加費無料・定員70名・事前申込制・定員に達した場合は申込締切
http://www.gakkai.chiku-bousai.jp/
地質学史懇話会
12月22日(日)13:30-17:00
場所:北とぴあ 8階803号室(JR京浜東北線 王子駅下車)
八耳俊文:岡田家武と張定訢の生涯:上海自然科学研究所化学科員の政治と科学
山田俊弘:地層累重の法則の意味:ステノ『プロドロムス』(1669)出版350周年を記念して(仮)
公開シンポジウム「令和元年台風第19号に関する緊急報告会」
12月24日(火)13:00-17:55
会場:
日本学術会議講堂(東京都港区六本木7-22-34)
常翔ホール(大阪工業大学梅田キャンパス)にて同時中継
参加費:無料
https://janet-dr.com/050_saigaiji/2019/191224/typoon19_UB_plan.pdf
2018柵山_記念スピーチ(野崎)
鉱床学は面白い,資源の偏在性には意味がある!そしてたくさんの人達に恵まれてきたことに深謝
2018年度日本地質学会柵山雅則賞
野崎達生(海洋研究開発機構 海底資源研究開発センター)
本研究に至るまで
本日はこのような名誉ある賞を頂けましたことを大変光栄に存じます.後ほどお世話になった皆様への謝辞を述べさせて頂きますが,研究活動において自分1人でできることは本当に小さく,たくさんの共同研究者に恵まれてきたおかげで頂くことができた賞であると思っております.心より御礼申し上げます.
さて,本受賞のお知らせを日本地質学会事務局から頂いた時,私はIODP Exp. 376航海のためJoides Resolution号に乗船しておりました.乗船研究者の中にサザンプトン大学のStephen Roberts教授が居ましたが,彼と雑談をしている時に『君はMasanori Sakuyamaを知っているか?彼の名前にちなんだ賞がサザンプトン大学にあるんだ』『日本の学会にも同じような賞がありますよ』という会話をした数日後に本受賞のお知らせを受け取ったので,何だか機縁を感じました.また,2か月にわたる長期航海の半ば過ぎにお知らせを受けたので,長期航海の大きな励みとなりました.改めて御礼申し上げます.
これまで,私は心からなりたいと思った職業は2つしかありませんでした.それは科学者と政治家です.なぜなら,時間はかかるかもしれませんが,どちらも或る課題に対して上流から取り組み,物事を根本的に変えられる可能性を秘めているからです.自分がなりたいと思った職業に今就けていることは,大きな幸せだと思っています.科学者に興味を持ったきっかけは,小学校の国語の授業でオゾン層破壊に関する文章を読んだことでした.そして自分なりに地球環境問題を調べた結果,地球温暖化が喫緊の課題であると気づき,それを解決する科学者になりたいと思いました.しかし,この時点では,科学者といっても白衣を着て薬品の入ったフラスコを使って,色々実験しながら時には爆発する!?といったようなイメージを漠然と抱いていました.
地球環境問題に関する勉強をしたいと思い,できたばかりの新しい学科であった東京大学工学部システム創成学科環境・エネルギーシステムコースに進学しました.卒業論文研究のテーマ紹介において,加藤泰浩助教授 (当時) が話されていたグローバル炭素循環に関する研究や海洋地殻を利用した二酸化炭素固定技術に大きな関心を抱き,卒業論文研究では加藤先生の研究室を迷わず選択し,その後博士論文まで同じ研究室でお世話になりましたが,これが地学 (地球科学) と接するきっかけとなりました.現在では,地球温暖化よりもさらに上位の問題であるエネルギー・資源問題に関心を持って研究をしています.
卒業論文研究〜修士課程にかけては,グローバル炭素循環の解明をテーマとして,特に沈み込み帯における炭素の挙動に注目して研究を行っていました.具体的には付加体中に存在する海洋地殻 (中央海嶺玄武岩) 起源の緑色岩の炭素含有量を測定し,化石年代から見積もられる海洋底での旅行時間を考慮して,沈み込み帯で岩石中から炭素が増減しているのかを追跡していました.最初は変成度の低い緑色岩,すなわち沈み込み帯浅部を対象としていましたが,沈み込み帯のより深部の岩石を研究したいと思い,三波川変成帯に分布する緑色片岩を対象としました.しかし,変成帯ではそもそも源岩の年代が決定ないことが多く,海洋底での旅行時間を求めるのが困難であることに気付きました.そこで,中央海嶺の海底熱水鉱床を起源とする別子型鉱床 (三波川帯に多数分布している) の生成年代が分かれば,その母岩である緑色片岩の噴出年代も分かると考え,Re-Os放射壊変系を用いた別子型鉱床の生成年代決定に博士課程で取り組み始めました (図1,2).
図1(クリックすると大きな画像がご覧いただけます)
図2(クリックすると大きな画像がご覧いただけます)
Re-Os同位体を用いた火山性塊状硫化物 (VMS) 鉱床の成因研究
三波川帯に分布する別子型鉱床の年代決定には,別の狙いもありました.日本列島付加体中に分布する古海洋底で生成した鉱床の分布を眺めると (図1),別子型硫化物鉱床の多くは三波川帯に分布している一方,Fe-Mn,Mn酸化物鉱床やMn炭酸塩鉱床は,秩父帯や美濃−丹波帯などのジュラ紀付加体に多く分布しています.硫化鉱物は還元的環境で安定であるのに対し,酸化鉱物は酸化的環境で安定に存在することから,これらの鉱床の年代分布が分かれば,古海洋の酸化・還元環境変遷史を読み解けるのでは?という大きな研究テーマを加藤先生から与えられ,博士論文研究として取り組み始めました.酸化物鉱床は,研究室の先輩であった藤永公一郎博士が以前から研究されていたので,私は別子型硫化物鉱床を研究することになりました.さて,博士課程とその後の研究で,四国地方の佐多岬から和歌山県にかけての三波川帯に分布する11の別子型鉱床から良好な直線性を示すRe-Osアイソクロンを得ることができました (図2).このアイソクロンを示すと一瞬で終わってしまうのですが,すべての結果を得るために4年以上の歳月を費やしました.古い文献しか残っていない鉱床もあり,そのような鉱床の調査に際しては現地のお年寄りに聞き込み調査から行い,色々とサポートしてもらいながら鉱山跡に辿り着くような,いわばリアル版ドラゴンクエストのような調査を行いつつ,鉱石試料を集めていました.その結果,三波川帯に分布する別子型鉱床の生成年代は約150 Ma (1億5千万年前) に集中することが明らかとなりました (図2).
この年代を元に,三波川帯に分布する別子型鉱床の生成場を考えてみたいと思います.これまでに得られている各種鉱物の放射年代や化石年代から,三波川変成作用のピーク年代 (=沈み込み帯最深部に達したタイミング) は,110 - 120 Maか90 Maと考えられています.また,三波川帯が大陸地殻に付加した年代は120 - 130 Maあるいは65 - 95 Maとされています.一方,別子型鉱床が古海洋底で生成した年代は約150 Maであるので,少なくとも20 Myr以上は海洋底を旅した後に沈み込み帯に達したと考えられます.当時のユーラシアプレートに対する太平洋プレートの相対速度は,バリエーションがあるものの約10 cm/yrと考えられるので,別子型鉱床の生成場は大陸地殻から数千km離れた『遠洋域の中央海嶺』であるといえます.しかし,硫化鉱物は現世のような酸化的環境下では酸化消失してしまうので,溶解せずに保護するシステムが必要です.その答えは,当時の地球環境にあると考えられます.
約150 Maのジュラ紀後期は,過去3億年間において海水のSr同位体比が最も低下した時期に相当します.これは,低いSr同位体比組成を示す熱水Fluxが多かったことを意味します.したがって,当時は現在よりも火成活動が活発であったと考えられますが,グローバル炭素循環モデルによって復元された当時の大気CO2濃度は,現在の約8倍程度であったと見積もられています.このような大気CO2濃度の下では,Global Circulation Model (GCM) によるシミュレーション結果に基づくと,地球表層の気温は現在よりも5 - 10度高かったとされており,極域に氷床が発達していなかったとされています.氷床の発達しない極域では深層水の形成 (=海洋大循環の駆動力) が阻害されるため,海洋底層まで十分な酸素を行きわたらすことができず,よどんだ還元的な底層が発達していたと考えられます.これを分かりやすくまとめると (図3),現世のように寒冷で極域に氷床が発達する環境では,活発な海洋大循環により海洋底層まで酸素がいきわたる酸化的海洋が拡がっており,マンガン団塊・マンガンクラスト・レアアース泥に有利な生成環境であるといえます.一方,海底熱水鉱床は生成すると同時に一部は酸化消失していきます.ジュラ紀後期の温暖で極域に氷床が発達しない環境では,海洋大循環の駆動力が阻害され,海洋底層に還元的環境が拡がっていたと考えれます.このような環境は,酸化物鉱床の生成に不利な一方で,硫化物鉱床の生成と保存に有利な条件であるといえます.以上のような鉱床の生成・保存とグローバル環境変動のリンケージを考えるとすべてが調和的に説明できることから,我々のグループは『ジュラ紀後期海洋無酸素事変』の存在を提唱し,別子型鉱床の生成・保存に寄与したと考えました (図3).
さらに,Re-Os同位体を用いた研究を四万十帯北帯や日立変成帯に分布する別子型鉱床にも適用し,白亜紀後期に起こった海嶺沈み込み現象と鉱化作用の解明や日本列島最古の鉱床年代値を得ることに成功しました.また,日立鉱床の研究における鉱石の記載過程において,新鉱物も見出しています.
図3(クリックすると大きな画像がご覧いただけます)
図4(クリックすると大きな画像がご覧いただけます)
VMS鉱床研究からの発展
2009年4月に独立行政法人海洋研究開発機構地球内部ダイナミクス領域 (JAMSTEC/IFREE) (当時) に就職してからは,前処理や測定に手間のかかるRe-Os同位体測定をより簡便・迅速に測定できる方法の開発に取り組みました.私が就職する半年前にJAMSTEC/IFREEにマルチコレクター誘導結合プラズマ質量分析装置 (MC-ICP-MS) が導入されたこともあり,MC-ICP-MSと気化法を組み合わせたOs同位体測定方法の開発を行いました.気化法自体は新しい手法ではありませんが,常温で気化するOsO4分子の性質を利用して,Re-Osの分離作業とOs同位体測定を一度に行ってしまうという手法です.気化法とMC-ICP-MSのマルチイオンカウンター (MIC) あるいはファラデーカップ (FC) を組み合わせて,従来よりも簡便かつ確度・精度良くOs同位体比を測定する手法を確立させました.この手法はデータの精度・確度よりもとにかくデータ数がたくさん欲しい,という研究テーマに向いており,Os同位体比組成を用いた古環境解読の研究やマンガン団塊・マンガンクラスト・レアアース泥の年代決定に最適です.また,カンラン岩のようにOs濃度の高い試料であれは,負イオン表面電離型質量分析装置 (N-TIMS) と遜色のない確度・精度で迅速Os同位体分析を行うことが可能です.これまで,マンガンクラストに成長ハイエタスは存在するのかなどに着目しながら,600個を超える様々な試料のOs同位体測定を実施してきており,一部の研究成果は論文化されています.今後,これまで測定してきた結果も徐々に論文化されていくでしょう.
また,2009年4月にJAMSTECに就職してから現在までに17度の調査航海に参加させて頂き,VMS鉱床のモダンアナログである現世海底熱水鉱床の研究を開始できたことも大きなチャンスでした.特に,2010年9〜10月に沖縄トラフ伊平屋北海丘において行われたIODP Exp. 331航海により形成された人工熱水孔に関する研究を開始し,人工熱水孔上に急成長したチムニー試料の記載・地球化学的研究を行いました.或る人工熱水孔上では,銅−鉛−亜鉛に富むチムニーが1年間で7 m,2年間で15 mの高さに急成長していたことから,『黒鉱鉱石を養殖しよう』というアイデアのもと,一風変わった研究に着手しました (図4).ちょうどこのタイミングで,2012年4月に海底資源研究開発センターがJAMSTECの新しい研究組織として発足し,さらに2014年4月から5ヶ年にわたり戦略的創造イノベーション創造プログラム (SIP) 次世代海洋資源調査技術 (海のジパング計画) が始まったことも大きな追い風となりました.SIPでは,「海洋資源の成因の科学的研究に基づく調査海域の絞り込み手法の開発」の一部を担当し,この一環として地球深部探査船「ちきゅう」を用いて沖縄トラフで行われた3度の航海 (CK14-04航海,CK16-01航海,CK16-05航海) にすべて乗船できたことが大変な幸運でした.特に,CK16-01およびCK16-05航海では若輩ながら共同首席研究員として乗船させて頂き,大きな興奮・達成感・充実感を味わうことができる航海となりました.これらの航海において,人工熱水孔から噴出する熱水の物理パラメーターを長期モニタリングすると同時に鉱物の沈殿実験を行う装置を合わせて3基設置し,約1年後にそれらの装置を回収しました.SIP「ちきゅう」航海で行った内容の多くはまだ論文化されていませんが,今後詳細な分析・解析を進めると同時に,共同研究者とともに結果の論文化に努めるつもりです.
研究を繋げる線と今後の目標
以上のようにこれまでの研究経過を眺めてくると,自分が何を専門とする研究者なのか時々分からなくなる時がありますが,現在までの研究活動を繋ぐ一貫した線は,以下の4つであると考えられます
(1) 修士課程までに培った薄片作成,XRD,XRF,ICP-QMS,EPMAなどの記載・地球化学の基礎⇒これらの基礎を最初に叩き込んで頂いたので,その後もベースを疎かにすることなく発展的な同位体研究に移ることができました.
(2) 博士課程から開始したVMS鉱床の研究とRe-Os同位体 (N-TIMS,MC-ICP-MS)⇒別子型鉱床の生成年代を知りたい,という明確な目的があったものの,Re-Os同位体という当時はまだ比較的新しかった同位体分析の基礎を博士課程で学べたことが,その後の研究の幅を広げてくれました.
(3) 異質な鉱床学≒グローバル環境変動と鉱床生成⇒環境変動と鉱床生成という正統派鉱床学とは少し異なった研究スタンスを取ることで,他の研究者と異なった視点から研究を行うことができました.
(4) 東京大学加藤研究室で培った研究スタンス・論文の書き方などの基礎⇒以上の基礎は,すべて東京大学加藤研究室在籍中に叩き込んで頂いたものであり,この基礎なしには私が今研究職としては決して生きていけなかったと思います.
学生の時に読んで大変感銘を受けた論文があります.それは,「Holland (2005) Economic Geology, vol. 100, pp1489-1589」に掲載されている論文ですが,地球史を通じたグローバル環境変動と堆積性鉱床の成因との関連性を議論している論文です.我々が普段何気なく使っている金属資源が,地球の長い営みを通じて形成されていることに大きな知的興奮と好奇心を覚えました.将来,このような論文を書くことができる研究者になれるように邁進していく所存です.また,私が専門としている鉱床学は日本では研究者人口の減少が止まらない学問分野ですが,資源の偏在性には別子型鉱床の成因で述べたような地球科学的必然性が存在します.その必然性を解明する鉱床学は,私にとって「環境・資源・浪漫 (知的好奇心)・ヒトの役に立つ」という観点をすべて満たしてくれる学問であり,大きなやり甲斐を感じています.今後,このような面白くて楽しい鉱床学に1人でも多くの日本の研究者が携わってくれることを願ってやみません.
お世話になった方々への深甚の謝辞
さて,これまで述べてきた研究成果は多くの指導者・共同研究者に恵まれてきた賜物です.特に調査航海の首席研究員を務めると実感しますが,1人の研究者ができることは本当にちっぽけで限られており,異なる専門分野を持った多くの方と共同することで,目標が達成できると思います.これまでの私の研究を支えて下さった特に8名の方々に対して,この場を借りて謝辞を申し上げたいと思います.
まず第一番にお礼を述べたいのは,卒業論文研究〜博士課程までの指導教員であり,現在も共同研究を行っている東京大学大学院工学系研究科の加藤泰浩教授です.つい余計なことを言ってしまい舌禍癖のある私でしたが,まずはそのような生活態度から厳しく指導して頂きました.また,今でも一番印象に残っているのが,Geochimica et Cosmochimica Acta誌に論文を投稿する前の原稿作成では,土日の週末に研究室に2人で缶詰になり,原稿を一文一文声に出して読みながら,自分の英語の何が悪いのかを徹底的に指導して下さいました.このような厳しく温かい指導があったからこそ,今の自分の研究者人生があるのだと本当に感謝しております.
次にお礼を述べたいのは,東京大学大学院工学研究科の (故) 玉木賢策教授です.玉木先生は私が修士課程の時に,玉木・加藤研究室の教授として赴任されたため直接の指導教員ではありませんでしたが,研究室のゼミなどを通じて常に温かいお言葉で励まして頂きました.玉木先生の偉大さが本当に理解できたのは,JAMSTECに就職して海外出張に行くようになってからです.特に,2013年にモーリシャス共和国に会議で訪れた際には,「君はKensaku Tamakiを知っているか?彼はGentleで偉大な研究者だった」と多くの方々に言われ,我がことのように嬉しかったのを記憶しています.
次にお礼を述べたいのは,東京大学大学院工学研究科の中村謙太郎准教授および千葉工業大学次世代海洋資源研究センターの藤永公一郎上席研究員です.お二人は,私が卒業論文研究で加藤研究室に配属された際に,博士課程に在籍していた研究室の大先輩です.中村謙太郎さんからは,研究に対するストイックな姿勢や研究者としてどうあるべきか,について多くのことを背中から学びました.また,藤永公一郎さんには,イラストレーターやパワーポイントの使い方など研究者にとって必須のスキルを教えて頂くだけなでなく,公私にわたって困ったことがあれば相談に乗ってもらいました.お二人が研究室の先輩として在籍しており,多くの指導を仰げたのは非常に幸運でした.
次にお礼を述べたいのは,静岡大学防災総合センターの石井輝秋客員教授です.私が東京大学加藤研究室に配属された際は,加藤先生が山口大学から異動してきた直後で研究機材が揃っていなかったため,岩石試料の切断,粉末試料の調製,薄片作成,XRD,XRF,EPMAなど,すべて当時中野にあった東京大学海洋研究所で行っていました.この時は石井先生の研究室施設を無償で使わせて頂き,種々の便宜を図って頂きました.薄片作成の際に石井先生のおっしゃった「記載のしっかりした論文は,記載を見ただけで大体の化学組成が分かる」という言葉が強く印象に残っており,それ以降記載を疎かにせずに研究をしてきたつもりです.また,中野の海洋研究所は,上記の意味では真の共同利用施設であったと思います.
次にお礼を述べたいのは,JAMSTEC地球内部物質循環研究分野の木村純一分野長代理です.私がJAMSTECに就職する前に,実験室の立ち上げのため木村さんも島根大学からJAMSTECに異動してきていました.木村さんには付きっ切りでMC-ICP-MSの使い方を何度も説明して頂き,また気化法用の導入系なども一緒に考えて準備し,分析方法の確立に取り組みました.質量分析装置のエキスパートである木村さんとJAMSTECへの異動のタイミングが近く,一緒に分析法を確立させ,その後も多くの共同研究をできていることは本当に素晴らしい巡り合わせだったと思います.
次にお礼を述べたいのは,九州大学大学院理学府の石橋純一郎准教授です.修士課程在籍中に退役済の「淡青丸」で過酷な海況の航海を体験し,「二度と調査船は乗らない」と決めていたのですが,石橋さんとは学会に向かう飛行機や,たまたまJAMSTECセミナーに来ていた際の食堂などで隣の席になり,「是非次の“なつしま”航海に一緒に乗船しましょう」と三度も誘って頂いたので,さすがに三顧の礼を断るのは失礼だと思い,断腸の思いで乗船を決意しました.予想に反して乗船した「なつしま」航海は快適で,また,陸上のVMS鉱床しか観察してこなかった自分には現世海底熱水鉱床を間近に見られる潜航調査航海は大きな衝撃でした.石橋さんは,新たな研究へのチャンスを下さった恩人です.
最後にお礼を述べたいのは,JAMSTEC高井 研研究担当理事補佐です.SIPで行った1度目の「ちきゅう」掘削航海 (CK14-04航海) で初めて一緒に乗船しましたが,「次の首席は君が務めるんだ」と言われ,ブリッジでの指示の仕方や首席としての振る舞い方,どんな時も研究を楽しむ大切さを教えて頂きました.そもそも人工熱水孔を使った黒鉱養殖研究のアイデアは高井さんの発案ですし,先日のIODP Exp. 376航海にも一緒に参加したので,掘削調査航海の楽しさを教えて下さった恩人です.
最後のスライドは,地質調査総合センターが作成している「なかよし論文データベース」からコピーした全共著者のお名前です (図5).これまでお名前を挙げさせて頂いた8名の方々以外にも,多くの人と巡り合い,助けられて研究を続けることができたのだなあということを,このリストを眺めて改めて実感しました.お世話になったすべての皆様に深甚の謝意を表します.これからも初心を忘れずに,また研究を楽しむ気持ちを常に抱きながら,新たな研究に邁進していきたいと思います.本日は誠にありがとうございました.
図5(クリックすると大きな画像がご覧いただけます)
(注)本原稿は,20108年度日本地質学会各賞の受賞記念講演・スピーチ(2018/9/5於北海道大学)のないようを基に各講演者の皆様に原稿をご執筆頂き,日本地質学会News Vol. 21, No. 12(2018年12月号)p.14-16に掲載されたものです.
2018小澤_記念スピーチ(澤木)
多元素同位体比分析を駆使した原生代後期の古環境解読研究
2018年度日本地質学会小澤儀明賞
澤木佑介(東京大学総合文化研究科)
この度は私が携わってきた「多元素同位体比分析を駆使した原生代後期の古環境解読研究」に対して小澤儀明賞をいただき,大変光栄なことと深く喜んでおります.この賞に推薦してくださった黒田潤一郎先生・菅沼悠介先生をはじめとする環境変動史部会の皆様,これまで様々なことでお世話になった先生方,先輩方,共同研究者の方々にこの場を借りて深くお礼を申し上げたいと思います.誠にありがとうございました.
まずは私の略歴を紹介させていただきたいと思います.私は2005年に東京工業大学地球惑星科学科の丸山茂徳・廣瀬敬研究室に所属し,その後も同先生の下で大学院生活を送り,2011年に博士課程を修了しました.当時丸山先生の研究室では横軸46億年研究と特異点研究という二つの大きな研究が走っており,私は後者の研究の一端を担っておりました.この時の特異点研究は約6億年前の「多細胞動物誕生時」の古環境を高解像度で読み解くことを目指しており,後述しますように南中国で陸上掘削によって採取した岩石試料から粉末試料を作成しては日々化学分析を行っておりました.丸山先生には研究の大きな方向性を示していただき,またセミナーや合宿での議論を通して多くの夢を語っていただきました.この丸山先生の姿勢は今日に至るまで私の模範であり続けております.また,当時助手であった(2007年より准教授になられた)小宮剛先生には研究遂行上の様々な実質的なご指導をいただき,現在に至るまで研究費の面も含めてサポートしていただいております.
博士号取得後は2011年4月から1年間,海洋研究開発機構の鈴木勝彦研究員のもとに学振PDとして在籍し,南中国で採取した掘削試料を用いてOs同位体比測定を通じた年代測定と古環境解読研究を行っていました.その後2012年4月に東京工業大学・地球惑星科学専攻にて助教として採用いただき,再び丸山先生のもとで研究を開始しました.丸山先生の学生は毎年異なる研究テーマを持っていて,これに携わる自分としては専門外の論文を読むことにだいぶ苦労しましたが,今となってはこの事が自身の研究の幅を広げることに繋がったと思います.2017年2月には現職である東大駒場・総合文化研究科に助教として異動し,磯崎行雄先生や小宮剛先生の研究室の皆様と共に研究活動に打ち込んでおります.
今回の受賞に際して自身の研究生活を振り返ってみると,私は同世代の研究者に比べてかなり恵まれた立場にあった事を再認識しました.まず,私は多くの海外での地質調査に連れていっていただきました.小宮先生には中国,スヴァールバル諸島,ロシア・アルタイ地域,オーストラリア,カナダ・ラブラドル地域での地質調査に参加させていただきました.また,手続き自体は自分で行いましたが,英国やアイルランド,ジンバブエ共和国,南アフリカ共和国や,ガボン共和国などでの地質調査に関しても丸山先生から金銭的なサポートをいただきました.丸山先生には廊下で会うたびに「君はいろんなものを見て,物事を俯瞰的に見れるようにならないといけない」と激励いただき,様々な地域の様々な時代の岩石を見ることで,自分の扱っている約6億年前の岩石の位置付けを常に意識するようになりました.機器分析に関しても,私が学生当時東京工業大学にて准教授でおられた平田岳史先生(現在は東京大学に異動)の研究設備を使用させていただき,後述する大量の分析データを出すことができました.海外での貴重な経験を数多くさせていただき,分析に関して不自由ない環境に身をおけたことが非常に幸運でありました.
図1(クリックすると大きな画像がご覧いただけます)
図2(クリックすると大きな画像がご覧いただけます)
同位体比測定を通じた原生代後期の古環境解読研究
地球史研究においては化石記録が変化する時代が主要な研究対象となり,その興味の対象は生物を取り巻く古環境を地質記録から読み解くことにあります.地球史における原生代後期は2度の全球凍結によって特徴付けられ,詳細な化石の研究から後生動物を含む多細胞な硬骨格生物が原生代後期から初期カンブリア紀(約7〜5億年前)にかけて段階的に大型化・多様化した事が知られています(図1).その中でも特にエディアカラ紀(6.3〜5.4億年前)の地層から多種の多細胞動物化石の初出が報告されています.このような生命の進化には海洋組成などの固体地球変動との関連が予想され,多くの研究者が同位体比測定などに基づく地球化学的手法から古環境変化の解明を試みてきました.過去の生物活動を見積もるのに良く使われる炭酸塩炭素同位体比(δ13Ccarb)を見ると,原生代後期には非常に大きな変動が複数見られ,中でもShuram変動と呼ばれる地球史上最大の炭素同位体比変動がエディアカラ紀の地層に見られます(図1).これに限らず,この時代に起きた現象を明らかにしようと様々な地域の岩石から多様な同位体比測定が先行研究によって報告されてきました.しかしこれら異なる地域から得られたデータの編纂に基づく古環境推定には,幾つか問題点があります.一般に原生代の地層は絶対年代や生層序に基づく年代制約に乏しく,ある岩石がいつ堆積したかは著者の主観による所も大きく,このような異なる地域からのコンパイルでは個々の化学指標間の本当の前後関係や同時性は議論する事ができないといった状況にありました.また,データが大量化するにつれて個々のデータに対する吟味が軽視され,風化などの堆積後の変質作用の影響の見積もり方に統一的な見解もありませんでした.
図3(クリックすると大きな画像がご覧いただけます)
図4(クリックすると大きな画像がご覧いただけます)
掘削試料を用いた多元素同位体比分析
前述の問題を解消するため,エディアカラ紀の化石を地層中に豊富に含む南中国内にて陸上掘削によって分析に用いる岩石を採取し,同じ岩石から多種の同位体比測定を行いました.掘削によって得られる岩石試料は少なくとも地表における風化や酸化の影響がなく,完全連続であるためにcm間隔の緻密さで分析点を得る事が可能です.三峡と呼ばれる地域の掘削試料から粉末試料を作成し,SrやCa同位体比を含む多種の同位体比測定を行いました.
Sr同位体比について学生時代の苦労話を紹介したいと思います.新鮮な炭酸塩岩のCaを置換しているSrの87Sr/86Sr比を測定することにより,大雑把に言うといつの時代にどれくらい大陸が削られていたかが議論可能です.大陸削剥は海洋に対する生命必須元素の最大の供給源であって,固体地球変動と生命活動を結び付けるうえで非常に有用なデータとなります.修士課程の学生だった私は何も考えずにたくさんの試料の87Sr/86Sr比を測定し続けました.測定試料のSr同位体比は0.705から0.730くらいの幅広い値を取りました(図2a, b).しかし,海水のSr同位体比は地球史を通じて,この図2cの破線のように0.710よりも低い値の中を変動するとされていたので,私のデータはそこからはずれるものばかりでした.よくよく先行研究(図2c)を見返すと,破線は数あるデータの一番低い値を繋ぎ合わせたもので,このコンパイル自体には問題があると思いますが,この図が言っている事はSr同位体比は堆積後の変質に弱く,値が堆積時よりも上昇しやすい傾向がある,という事です.自分のデータを見返してみると,87Sr/86Sr比が低く,初生的”のように思える”値を出す試料は岩石中のMn濃度,Rb濃度が低い傾向があります(図2a, b).このような傾向がある事は知られていましたが,これが必ずしも適用されない場合もあります.例えば一番高い同位体比を出す試料は,Mn濃度,Rb濃度どちらもそれほど高くはありません(図2a,b).その岩石の薄片写真を見てみると(図2d),粗粒な炭酸塩鉱物が一方向に延びていて,堆積性のミクライト質な炭酸塩岩とは異なります.変質の過程は多様であって,一概にある指標で評価できない場合の方が多いです.たくさんやって学んだ教訓は,できるだけ新鮮な岩石を初めから使って,Sr同位体比測定に至る前に様々な指標を使ってスクリーニングをして,たくさんの試料の中から最良なもののみを選定して測定した方が良いという事です.
この教訓を得た後,三峡地域の掘削試料から600個以上の粉末試料を作成し,元素濃度測定や顕微鏡観察を経たのち,厳選した試料についてのみSr同位体比測定をしました.その結果,Sr同位体比は0.710以下の値ばかりになり,Sr同位体比が連続的に遷移する様子が見えるようになりました(図3左).同一の掘削試料を用いて共同研究者が測定した炭素,硫黄同位体比についても同様に各同位体比が連続的に遷移する様子が確認されました.結局掘削試料を使って大量分析を行い,時間解像度をあげた結果,これまでの研究(図3右)とデータとして変わった事は2つあります.まず個々の指標の中での変動がより鮮明になって,エディアカラ紀の中には各指標の中に複数回の変動が含まれる事が明らかになりました. しかも各指標間の間には明確な関連が見て取れるようになりました(図3中,矢印).例えば,炭素同位体比が下がる時は,Sr同位体比が高くなり,硫黄同位体比がその少し前に下がり始めます.これらの私たちの新たな結果から新しく明らかになってきた事を次段落にて紹介します.
一般に顕生代(5.4億年前〜現在)は地球史を通じて最も大陸風化が活発な時期とされています(図2c).しかし,私どもの分析結果は,エディアカラ紀の方がSr同位体比が高く(図2c, 3),生命に必須な栄養塩の最大の供給源である大陸風化はエディアカラ紀に最大となり,この事がこの時代の急激な生命進化の土台となったと考えられます.また顕生代の研究などでは一般的にδ13Ccarbの負異常は生物活動の減少と解釈されます.しかし,エディアカラ紀のδ13Ccarb負異常はSr同位体比が高いとき,つまり大陸風化が強い時期であり,もう少し言うと栄養塩が豊富に供給されて生物活動が活発そうな時期に対応しています.硫黄の同位体比も組み合わせてこの時期に起こった事を推測します(図4).エディアカラ紀の海洋は軽い炭素同位体比を持った有機物が海洋に多量に浮遊していたと考えられています.大陸風化が卓越して堆積岩が増えると有機物が堆積岩中に取り込まれて再酸化されなくなり,酸素濃度や硫酸濃度が上昇します.これが硫黄同位体比の減少として記録されます.硫酸などの酸化剤の増加や大陸からの栄養塩供給によって微生物による有機物の分解が活発に進むと,軽い同位体比を持った炭素が海に放出されて,これによってδ13Ccarbに負異常が作られます.これらはいずれも後生動物誕生期の生命(化石,δ13Ccarb)と地球(Sr,硫黄同位体比)の共進化を支持するものであり,このように個々の同位体比から独自に推測される現象を関連付けて説明できるようになったのは掘削試料を用いた高解像度な多元素分析によってデータを得たからであると考えています.
最後に
古環境解読研究においてある2つの事象が同時である事が分かると,私たち研究者はその間にもっともらしい因果関係を考えてその事象を結びつけますが,本当に因果関係があるのかは定かではありません.また,分析機器の性能が向上し,多種の大量のデータにあふれる現代の地球科学において,論理的背景のない経験主義に基づく化学指標が横行したり,話題性先行の主張がなされたりといった事が多々見受けられるようになりました.日常生活同様,処理しきれないほどの多くの情報に振り回されがちな現代の地球科学業界において,自分が知りたいことに対して確かな戦略を立てて取り組み,常に物事の本質を見失わないようにしたいと思います.今回頂きました小澤儀明賞を励みに今後より一層研究活動に打ち込み,地質学会の発展に貢献し,また後進の育成に邁進していきたいと思います.
(注)本原稿は,20108年度日本地質学会各賞の受賞記念講演・スピーチ(2018/9/5於北海道大学)のないようを基に各講演者の皆様に原稿をご執筆頂き,日本地質学会News Vol. 21, No. 12(2018年12月号)p.10-12に掲載されたものです.
2018柵山_記念スピーチ(遠藤)
沈み込み帯編成作用の広がりの追究
2018年度日本地質学会柵山雅則賞
遠藤俊祐(島根大学総合理工学部)
はじめに
このたびは柵山雅則賞という栄誉ある賞をいただき誠にありがとうございました.これまでお世話になりました先生方,個性的で優秀な先輩・後輩・共同研究者のみなさん,に御礼申し上げます. 私の研究内容は,沈み込み帯内部のプロセスを高圧変成岩や付加体岩石の観察から読み解くことです.沈み込み帯というのは深部でも冷たい場所であるため,実際に起こっている鉱物反応や平衡状態を実験室のタイムスケールで再現できない問題があります.だからこそ天然のデータ,フィールドに根差した岩石学が重要になると考えています.今回は自己紹介として,三つの時期の話をします.子供の頃に鉱物に興味を持ったのがこの道に進むきっかけでした.それから名古屋大学理学部に入学し,岩鉱研究室に配属後は学位をとるまで,エクロジャイトの研究をしました.その後,産総研に移り,高知県北部「本山」地域の地質図幅作成を通してフィールドの重要性を再認識するとともに,沈み込み帯の岩石を幅広く研究対象にするようになりました.
子供の頃の鉱物研究
幼稚園年長〜小学生低学年の頃に綺麗な(今見るとそれほどでもない)大理石や図書館で図鑑(原色鉱石図鑑,続原色鉱石図鑑)をみて鉱物に興味を持ちました.また子供のころに大きな影響を受けた人物として,世界的鉱物コレクターの桜井欽一先生がおられました.桜井先生が亡くなる前の2年間ほど,私が9〜10歳のころ,多くの鉱物標本や毎回便箋6-8枚に及ぶ分厚い手紙をもらい,鉱物の知識や観察眼を養うことができました.また,鉱物に心ひかれたのは結晶の美しさという点が大きく,面角測定器を自作し実体顕微鏡に組み合わせて色々な鉱物の結晶形態を調べました.図1は苗木ペグマタイトの蛍石を調べた例ですが,最初に8面体,その後晶洞の温度が下がって複雑な面をもった結晶がオーバーグロースしています.8面体結晶は希土類を含み紫外線で蛍光するため,微量元素も晶相変化に関係しているかもしれません.おぼろげながら結晶形態が形成条件を反映していることを知り,面白いと思っていました.また美しいものは過不足のない図で表現されなければいけない,という信念を持つきっかけになりました.
図1(クリックすると大きな画像がご覧いただけます)
図2(クリックすると大きな画像がご覧いただけます)
名古屋大学でのエクロジャイト研究
その後,名古屋大学理学部に入学しました.3年後期に研究室配属があり,岩鉱研究室に進み,それから6年間同じ研究室でお世話になりました.当時は指導教官のサイモン・ウォリス先生と榎並正樹先生が教員としておられました.研究室配属されて最初にゼミで英語論文紹介があり,ローソン石エクロジャイトの論文を読みました.沈み込み帯深部へ水や微量元素を運ぶローソン石の面白さや低温で高圧な世界に魅せられ,高圧変成岩の世界を究めたいと思いました.卒論ではエクロジャイトのLu-Hf年代の解釈という,とっておきのテーマをウォリス先生からもらいました. Lu-Hf法はざくろ石の結晶化年代を高精度に決定できるメリットがあります.三波川エクロジャイトはなぜか116Maくらいの古いものと約90Maの新しいものがありました.卒論の段階で古い年代はざくろ石のコアを反映していると分かりました.三波川エクロジャイトには二タイプあります.五良津岩体など,粗粒な岩体の中に産するものと,その周囲のエクロジャイト質片岩があって,古い年代が出るのは粗粒の岩体だけでした.古い年代の解釈を求め,大学院進学後に西五良津岩体でフィールド調査を始めました.関川から赤石山系稜線沿いの標高差1000 mを登ると,日帰り調査では岩体中心部に踏み込めないので,ツェルトで1~2泊ビバークする気ままな調査を始めました.稜線付近は本当に険しく,尾根に這い上がるまで生きた心地がしなかったが,調査登山にはまっていました.フィールドデータはとるが,リュックに大ハンマー,寝袋と数日分の水食糧を入れて体力がない自分の体を持ち上げることを考えると,持ち帰るサンプルは数個に留めます.持ち帰った石は,いけると思ったら石なら20枚くらい薄片を作って,徹底的に組織観察しました.そうするうちに,岩石組織にはフェイクがものすごく多く,解釈はとにかく慎重に,疑ってかからないといけないことに気づかされました.それでも確からしいことは,ざくろ石は二段階成長していて,コアにだけ低圧を指標する斜長石,リムにだけエクロジャイト相を指標するオンファス輝石,のインクルージョンがあるということです(図2).それで,エクロジャイト変成の前に,別の変成作用があることを確信し,あとは岩石学的手法を駆使して定量的にP-Tパスを描きました.また地質温度圧力計やシュードセクション法など,解析手法に関しては,原理と限界をわきまえて効果的に利用することが重要です.結果としては,エクロジャイト変成の前に,高温沈み込みからより冷たい沈み込みへの移行を示す,反時計回りP-T履歴があり,その年代が古い年代に対応していて,前期白亜紀117 Ma頃に沈み込み開始イベントがあったと考えました.この考えは今でも間違っていないと思っており,より多くの地質学的証拠をそろえて三波川沈み込み帯創成期のテクトニクスをより詳細に明らかにしたいと考えています.
図3(クリックすると大きな画像がご覧いただけます)
付加体の低温変成作用の研究
ウォリス先生の指導の下,三波川帯とグァテマラのエクロジャイトの比較研究で学位をとり,フィールドに根差した沈み込み帯の変成作用とテクトニクスをより広く追究していきたいと考えていました.なんとなく読んだR.C. Newton博士のGeo-experimental methodという言葉(American Mineralogist, vol. 96, p. 457-469)が気に入り,こういう研究は低温変成(弱変成)作用でこそ威力を発揮するはずです.名古屋大を出た後,ポスドクとして産総研の地殻岩石研究グループへ移りました.沈み込み帯の低温変成作用を本格的にやるために広域かつ長期のフィールド調査ができる図幅は理想的だと思い,また秩父帯北帯の非変成付加体から高変成度の三波川まで一通り露出する「本山」地域という格好のフィールドが未整備区画として残っていました.産総研でなんとか研究職員に採用され,念願の「本山」図幅を開始しました.1/5万図幅の面積はとにかく広大で,効率よく歩いて,毎日最低10 kmのルートマップを作ることを200日余りで一つの図幅ができました.ルートマップを一直線につなげれば,札幌からだと九州まで行ける距離です.四国山地は南斜面に背丈以上に繁茂するスズタケの海に苦戦したり,走向方向にどこまでも続く苦鉄質片岩の崖を越えれなかったり,広域の調査の経験は得難いものとなりました.「本山」地域の低温変成作用について,秩父帯北帯には従来考えられていたより広範に変成鉱物が見つかり,私の出身地の地質である美濃帯付加体とはだいぶ様相が異なることを実感しました.ひすい輝石を含むアルカリ火成岩や,アルカリ角閃石を含む真っ青な玄武岩火山角礫岩(穴内マンガン鉱床群の母岩)は特に印象的でした.秩父帯北帯の付加体は三波川変成岩をつくった沈み込み帯の上盤に位置したことで一部が上昇期に三波川変成作用のオーバープリントを受けていてその南限が大規模な正断層になっていることがわかりました(図3).一番驚いたのは三波川変成の及んでいない非変成付加体(メランジュ)の玄武岩中に高圧変成鉱物のローソン石脈が非常に普遍的にみつかったことです.これまで,低圧指標のぶどう石があるということは知られていて,同じような白脈で気づかれなかったようですが,実際にはローソン石の方がたくさんあります.ローソン石脈のローソン石は特徴的な組織をもっていて,電顕画像を見て,ローモンタイトという沸石の仮像だと直感しました.まずローモンタイト脈ができ,そうしたものが沈み込むと脱水分解してローソン石+石英になる.この反応は250℃,深さ12kmというプレート境界地震発生帯に相当する条件で起こります.このプロセスは現在も研究中ですが,低温では沈み込む変質海洋地殻は玄武岩組成の系で反応が起こるのではなく,局所的な単純系の反応が起こっているようです.玄武岩系ならこんな低温で脱水は起こらないはずですが,実際には局所系の反応で局所的に脱水が起こり得る,ということです.予想できないことが天然で起こっていることに気づかされるのが低温変成作用を調べる面白さかと思います.
最後に
私はこれまで良い環境で自由に研究を続けることができました.名古屋大でのウォリス先生,産総研での宮崎一博さんを始め,これまでお世話になりました方々に改めて御礼申し上げます.今後は島根大学の学生とともに,沈み込み帯の変成作用とテクトニクスの追究を続けたいと思います.
(注)本原稿は,20108年度日本地質学会各賞の受賞記念講演・スピーチ(2018/9/5於北海道大学)のないようを基に各講演者の皆様に原稿をご執筆頂き,日本地質学会News Vol. 21, No. 12(2018年12月号)p.12-13に掲載されたものです.
2018国際_記念スピーチ(coffin)
An Engagement with Japan…and Volcanoes, Iron, and Phytoplankton in the Southern Ocean
2018年度日本地質学会国際賞
Prof. Millard (Mike) F. COFFIN (Institute for Marine and Antarctic Studies, University of Tasmania, Australia; School of Earth and Climate Sciences, University of Maine, USA; Woods Hole Oceanographic Institution, USA)
I am deeply honored to have been awarded the 2018 International Prize of the Geological Society of Japan in recognition of my contributions to the field of research on Large Igneous Provinces (LIPs), implications for their formation process, and impact on global environments. I truly appreciate the recognition by the Society, and sincerely value my long and rewarding relationships with Japanese colleagues and friends.
This contribution consists of two parts, the first a description of my engagement with Japan, and the second a summary of my recent work on Earth-Ocean-Biosphere interactions in the Southern Ocean surrounding Antarctica.
A Synopsis of My Engagement with Japan
My fascination with Japan long preceded my engagement with Japanese scientists. Japan first piqued my interest when I was a high school student in the early 1970s. A Japanese film festival held at the University of Maine, near my hometown of Bangor, Maine, USA, intrigued me, and I attended every film showing that I could, including Seven Samurai, Woman in the Dunes, Yojimbo, Rashomon, and Ugetsu Monogatari. These and other Japanese films inspired a curiosity that spurred me to further study and engagement. As a first-year undergraduate at Dartmouth College, I commenced formal study of Japan (and China) by taking a course in East Asian history, which opened my eyes to the long and captivating sweep of Japanese history. Also while at Dartmouth (1974-1978), I began tutoring Japanese and other international students in English, an activity I continued during my graduate studies at Columbia University in the City of New York (1978-1985). Such personal interactions with Japanese natives complemented my nascent knowledge and growing curiosity about the country.
Significantly, while a graduate student, I made my first visit to Japan (Tokyo) in 1980, marveling at the people, culture, and country first-hand. It was a brief visit, as I was en route from New York to Guam to board a month-long research voyage to the Shatsky Rise aboard RV Vema. It would be another 12 years before my second visit to Japan, but in that interval I gained my first extended exposure to and a deep appreciation for Japanese cuisine, specifically at the Japanese restaurant Asakusa in Canberra, Australia, where I worked from 1985 through 1989 at Geoscience Australia. Asakusa was staffed largely by spouses of diplomatic staff at the Embassy of Japan in Canberra, lending an atmosphere of authenticity and refinement to the restaurant absent in the vast majority of Japanese restaurants outside of Japan today.
My engagement with Japanese scientists commenced in 1992 on my second visit to Japan, when I attended the 29th International Geological Congress (IGC) in Kyoto. Prof Asahiko TAIRA, then at the University of Tokyo, had organized a session on scientific ocean drilling to which I contributed. That session launched a working relationship and close friendship with Prof TAIRA that continues to the present day. Scientific ocean drilling has proven to be the catalyst for many more interactions with Japanese scientists. I had moved from Australia to the University of Texas at Austin in 1990, and serving as a US member of the Joint Oceanographic Institutions for Deep Earth Sampling (JOIDES) Planning Committee (PCOM), I made my third visit to Japan (Makuhari) in 1995 to participate in a PCOM meeting. At this meeting I became acquainted with Profs Kyoshi SUYEHIRO and Kensaku TAMAKI, both then at the University of Tokyo, who became colleagues and friends. Such developing relationships with Japanese scientists in the early 1990s led to a joint Japanese-American, month-long research voyage to study the collision of the Ontong Java Plateau and the Solomon Islands aboard RV Maurice Ewing in 1995, during which I got to know Prof SUYEHIRO much better. Following this voyage, Prof TAIRA and I began planning a joint Japanese-American, month-long research voyage to study the Ontong Java Plateau that we undertook aboard RV Hakuho Maru in 1998.
Japan’s decision in the 1990s to construct the riser drilling vessel Chikyu and ultimately to co-lead the next decade (2003-2013) of scientific ocean drilling with the US led to the 1997 Conference on Cooperative Ocean Riser Drilling (CONCORD) in Tokyo, which further cemented my ties with Japanese scientists. This was the first of three major planning meetings held by Japan, the US, and Europe, respectively, for what became the Integrated Ocean Drilling Program (IODP; 2003-2013). The second meeting, the Conference on Multiple Platform Exploration of the Ocean (COMPLEX), was held in 1999 in Vancouver, and shortly thereafter I was enlisted to Co-Chair (with Judy McKenzie of ETH-Zürich) the international, 11-member, IODP Planning Sub-Committee Scientific Planning Working Group charged with developing the initial science plan for the IODP. On that Committee, I worked closely with Profs SUYEHIRO, who had moved to the Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), and Yoshiyuki TATSUMI, then at the University of Kyoto. The third and final planning meeting, the Alternative Platforms as Part of the Integrated Ocean Drilling Program Conference (APLACON) was convened in Lisbon in 2001. The IODP Initial Science Plan – Earth, Oceans, and Life – incorporated input from all three planning meetings and was published in 2001.
Just before the turn of the millennium, I received a fateful, entirely unforeseen telephone call and query from Prof TAIRA: a full professorship at the University of Tokyo’s Ocean Research Institute (ORI, now Atmosphere and Ocean Research Institute, or AORI) would become open soon, and would I be interested in applying? During 2000, I contemplated this extraordinary opportunity – as well as offers of positions in Washington, DC, USA, and Sydney, Australia – and late in the year discussed it further with Profs TAIRA, TAMAKI, and SUYEHIRO face-to-face at a University of Tokyo-JAMSTEC seismic workshop in Tokyo. In 2001, I visited Tokyo twice, investigating and interviewing for the professorship, before becoming the first non-Japanese tenured full professor in ORI’s 39-year history that boreal autumn.
As a professor at ORI from September 2001 through December 2007, I conducted an active, proposal-driven seagoing research program; taught and supervised PhD and Masters students; and established the ORI Seismic Research Center. I led or participated in six research voyages (Macquarie Ridge Complex, Hawaii, Manihiki Plateau, Ontong Java Plateau, Naturaliste Plateau), including serving as the first non-Japanese Chief Scientist aboard RV Hakuho Maru and RV Kairei, and dove to 4000+ m in Shinkai 6500. Peer-reviewed publications with Japanese co-authors currently total 21. Also during my professorship at ORI, I worked as a Senior Researcher at JAMSTEC (2002-2003), as a consultant for the Sumitomo Ocean Development & Engineering Company (2003-2005), and as a consultant for the Ministry of Foreign Affairs (2006-2007). The last involved working on Japan’s Extended Continental Shelf submission to the United Nations (UN) Commission on the Limits of the Continental Shelf under the UN Convention on the Law of the Sea.
As co-leaders of the IODP, Japan and the US agreed to alternate leadership every two years. A coin toss decided whether Japan or the US would lead the first two years of the IODP (2003-2005), and Japan won the toss. That resulted in Prof TAMAKI chairing the IODP Science Planning and Policy Oversight Committee (SPPOC), and myself chairing the IODP Science Planning Committee (SPC). Co-leadership necessitated substantial governance, management, administrative, cultural, and other changes – to which I devoted considerable effort – following the US having led international scientific ocean drilling (Deep Sea Drilling Project and Ocean Drilling Program) for the previous 35 years. Over the first two years of IODP, I headed the IODP Science Advisory Structure consisting of ~150 scientists from the ~25 IODP member countries serving on seven committees, panels, and program planning groups (PPGs). During that time, I represented Japan at 47 IODP-related meetings, 14 in Japan and 33 elsewhere in Asia, Europe, and North America. This involved flying ~575,000 km in those two years.
Although I departed Japan at the end of 2007 to become the inaugural Director of Research at the United Kingdom’s National Oceanography Centre in Southampton, I have maintained close ties with the Japanese community through cooperative research projects and scientific ocean drilling. In 2010, I was part of the shipboard scientific party aboard RV Kairei to investigate the crustal structure of the Ontong Java Plateau. Following my move back to Australia in 2011 to become the inaugural Executive Director of the new Institute for Marine and Antarctic Studies at the University of Tasmania, I chaired the Chikyu+10 IODP Workshop held in Tokyo in 2013. In 2014, I served as a member of the External Review Committee of the University of Tokyo’s Atmosphere and Ocean Research Institute (AORI), and since 2017 I have served as a member of the JAMSTEC Advisory Board. My rewarding and fulfilling engagement with Japan continues!
Volcanoes, Iron, and Phytoplankton in the Southern Ocean
The first maximum endurance research voyage of Australia’s new Marine National Facility, the research vessel (RV) Investigator, sailed deep into the southern Indian Ocean in early 2016 (Fig. 1_http://mnf.csiro.au/~/media/Files/.....), and I had the privelege of serving as Chief Scientist. The purpose of the voyage was to test the hypothesis that hydrothermal activity driven by active submarine volcanoes in the Southern Ocean fertilises surface waters with iron, thereby enhancing biological productivity beginning with phytoplankton. Phytoplankton are important because they supply half of the oxygen in Earth’s atmosphere; their growth is limited by iron supply in the anemic Southern Ocean as well as elsewhere in the global ocean. To test the hypothesis, the shipboard scientific party included geoscientists to identify and characterize active submarine volcanoes, biogeochemists to analyze water samples for iron and other trace elements, physical oceanographers to characterize ocean circulation in the study region, and marine biologists and ecologists to examine primary productivity in the study area. Shore-based researchers have augmented the shipboard scientific party.
Fig. 1. Track map of RV Investigator voyage IN2016_V01 to the Heard and McDonald Islands (HIMI) region.
*You can see the big picture when you click the image
Fig. 2. RV Investigator IN2016_V01 stations on the central Kerguelen Plateau. McDonald (west) and Heard (east) islands lie inside the HIMI Inner Marine Reserve .
Australia’s only active volcanoes, Heard and McDonald islands (HIMI) on the Kerguelen Plateau, are among the world’s most active hotspot volcanoes. Located at ~53°S approximately 4000 km from the closest ports, Fremantle, Australia (Fig. 1), and Cape Town, South Africa, the islands are rarely visited and lack any ongoing monitoring or occupation. HIMI were inscribed on the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) World Heritage List in 1997 (https://whc.unesco.org/en/list/577). They constitute the only sub-Antarctic island group that has an intact ecosystem, to which no known species has been introduced directly by humans, and where the ongoing evolution of plants and animals occurs in a natural state.
Heard Island encompasss 368 km2 and reaches a maximum reported elevation of 2745 m; the McDonald Islands are much smaller, covering 2.5 km2 and attaining a maximum reported elevation of 186 m (n.b., both elevations are less than what observations during our voyage suggest). HIMI’s volcanic activity is only recorded infrequently by satellites during brief breaks in persistent cloud cover or by observations from sporadic transiting ships. Satellite observations of ocean color show extensive blooms of phytoplankton on the Kerguelen Plateau (e.g. Bowie et al, 2015), and legacy narrow-beam echosounding data (Beaman & O’Brien, 2011) indicate many features on the Kerguelen Plateau resembling volcanic edifices, some of which are quite young (Duncan et al, 2016).
The state-of-the-art RV Investigator (http://mnf.csiro.au/Vessel/Investigator-2014.aspx), built in Singapore, was delivered to its homeport of Hobart, Tasmania, Australia in September 2014, and subsequently underwent approximately a year of trials. With a Det Norske Veritas (DNV) Silent-R classification, the 94-m, 5,893-ton (maximum displacement) ship is ideal for acoustic work from its multibeam seafloor mapping systems (Kongsberg EM122 and EM710), sub-bottom profiling system (Kongsberg SBP120), and water column echosounders (Kongsberg/Simrad EK60 and ME70) that were critical for our research program. Other key instruments for our research aboard the multi-purpose vessel were trace metal rosettes (TMRs), conductivity-temperature-depth (CTD) rosettes, in situ pumps (ISPs), a bio-optical sensor package, a deep-tow camera system, a Triaxus remotely operated towed vehicle, drifters, floats, Smith McIntyre sediment grabs, and rock dredges. Our voyage carried a full complement of 40 researchers, students, and support staff, and 20 ship’s crew.
The research voyage may be divided into three distinct components: seafloor hydrothermal system prospecting, sensing/sampling, and imaging; plateau water column transects with reference sites; and transits. During all three components, we acquired data from the multibeam systems, multi-frequency split-beam echosounders, sub-bottom profiler, gravimeter, thermosalinograph, aerosol sampling, air chemistry sampling, underway seawater analyses, expendable bathythermographs (XBTs), atmospheric underway sensors, and biological oceanography underway sensors. We also launched robotic floats for the Australian office (http://imos.org.au/facilities/argo/) of the International ARGO Program (http://www.argo.net/), the Southern Ocean Carbon and Climate Observations and Modeling (SOCCOM) project (https://soccom.princeton.edu/), and the Australia-India Strategic Research program (https://www.science.gov.au/international/CollaborativeOpportunities/AISRF/Pages/default.aspx), and drifters for the US National Oceanic and Atmospheric Administration’s (NOAA) Global Drifter Program (http://www.aoml.noaa.gov/phod/gdp/index.php). The first two components comprised the core of our scientific investigations, and they intermingled during the 26 days that we were able to devote to work over the Kerguelen Plateau. Transits, including equipment testing and a medical evacuation diversion from a great circle route, consumed 24 days.
We undertook most of our work within sight of HIMI (Fig. 2). Overall, we mapped 3,697.1 km2 of seafloor within the HIMI Marine Reserve Inner Marine Zone, or ~22% of its total area, which comprise the first multibeam bathymetry data to be acquired in this region. Water depth averages ~200 m within the Zone, with a maximum depth of ~1100 m. In the Zone, we mapped 56 previously unknown sea knolls around the McDonald Islands, and three around Heard Island. Eight dredges, including six from the newly discovered sea knolls, recovered volcanic rock for petrological, geochemical, and 40Ar/39Ar dating analyses, and eight Smith McIntyre grabs recovered sediment from around the islands for geochemical analyses.
Water column biogeochemical sampling included 50 successful CTDs, 40 TMRs, and 11 in situ pump deployments (Fig. 2). The CTDs yielded essential information on water column structure and provide water samples for 3He/4He analyses, an important proxy for hydrothermal activity, as well as for biological and microbiological analyses. Water samples from the TMRs provided critical information on dissolved iron, other trace metals, and other nutrients (N, Si, P, etc) in the water column. Particulate iron was captured by the in situ pumps.
Accompanying each CTD cast was a lowered acoustic Doppler current profiler (LADCP), which produced information on upper ocean currents. Complementing these casts were data from the shipboard ADCP. During the three phases of the voyage we deployed a total of 20 NOAA drifters to collect measurements of surface ocean currents, sea surface temperatures, and atmospheric pressure at sea level. For water column profiling, we deployed five ARGO floats for temperature and salinity data; three SOCCOM floats for dissolved oxygen, nitrate, and pH data; and two Bio-ARGO floats for dissolved oxygen, dissolved organic matter, nitrate, chlorophyll, and particle scattering data.
Observations of HIMI from the ship documented their active volcanism and hydrothermalism. Mawson Peak atop the Big Ben volcano on Heard Island appeared to be erupting continuously during the two weeks we worked around the island (Fig. 3). Whenever visible, the summit was emitting vapor, and lava was flowing down the flanks of Mawson Peak and Big Ben over glacial ice, generating steam. Fumaroles on the flanks of the McDonald Islands were also emanating steam (Fig. 4).
Fig. 3. Eruption from Mawson Peak, Big Ben volcano, Heard Island. Note vapor emission from Mawson Peak, and lava flowing over glacier and generating vapor (left).
Fig. 4. Fumaroles on the McDonald Islands.
Active volcanism and hydrothermalism on HIMI suggested that similar phenomena might be occuring on the seafloor surrounding the islands. The first indication of such seafloor activity came as soon as we arrived at the Kerguelen Plateau with observations in the split-beam echolsounder data of acoustic flares originating from the seafloor (Fig. 5). Over the ensuing course of our work around HIMI, water column acoustic data revealed several hundred flares, typically in water depths . We are combining analyses of split-beam echosounder data, deep-tow camera footage (with co-mounted conductivity-temperature probe data), water-column 3He/4He data, sub-bottom profiler data, and sediment geochemistry to determine the cause of the flares (Spain et al, submitted). In the entire Southern Hemisphere, the only other documented occurrence of acoustic flares is offshore South Georgia Island, where the flares are caused by methane bubbles being emitted from the seafloor at cold seeps (Römer et al, 2014).
Following the identification of numerous acoustic flares in our split-beam echosounder data, we deployed the deep-tow camera to investigate their cause. North of Heard Island, we were able to obtain photographs and video footage of multiple sites where bubbles were emanating from the seafloor (Fig. 6) that coincided with the locations of acoustic flares observed in the echosounder data. Extremely turbid water around the McDonald Islands severely limited visibility, and we were compelled to abandon efforts to obtain deep-tow camera efforts after only a few runs across acoustic flare locations that did not image any of their potential causes.
Fig. 5. Acoustic flare observed near the McDonald Islands
Fig. 6. Bubbles emanating from the seafloor near Heard Island. Laser dots are 10 cm apart.
Although HIMI are isolated from continental landmasses, the Kerguelen Plateau crust that they surmount is 20-25 km thick (Charvis et al, 1995), so the crustal setting of these hotspot volcanoes more closely resembles that of intraplate hotspot volcanoes on the continents (e.g., Yellowstone) than that of volcanoes along divergent plate boundaries (i.e., mid-ocean ridge volcanism). Furthermore, water depths averaging ~200 m around HIMI are much more similar to those of the 350 km2 Yellowstone Lake, with an average depth of 42 m (Sohn et al, 2017). Hydrothermalism associated with HIMI may be as extensive and diffuse as that of Yellowstone, which encompasses approximately 104 thermal features, including geysers, hot springs, mud pots, and fumaroles. Comparative volcanological and hydrothermal studies of the HIMI Marine Reserve Inner Marine Zone and Lake Yellowstone may yield new insights into both.
Acknowledgments
I am most grateful for the collegiality, support, and friendship of many individuals in Japan, including Asahiko TAIRA, Kiyoshi SUYEHIRO, the late Kensaku TAMAKI, Hidekazu TOKUYAMA, Hodaka KAWAHATA, Kyoko OKINO, Yasuyuki NAKAMURA, Junichiro ASHI, Kimihiro/Mikako/Akari MOCHIZUKI, Nobuhisa EGUCHI, Mica OKUNO, Jeffrey SCHUFFERT, Shinichi KURAMOTO, Wataru AZUMA, Seiichi MIURA, Shuichi KODAIRA, Junichiro KURODA, Ryo MIURA, Hiroyuki INOUE, Masanori IENAGA, Mizuki WATANABE, Setsuko TANAKA, Seiko ASAKA, and Tomiko KANEHARA.
References
Beaman, R. J. and O’Brien, P. E., 2011, Kerguelen Plateau Bathymetric Grid, November 2010. Geoscience Australia Record 2011/22.
Bowie, A. R., et al., 2015, Iron budgets for three distinct biogeochemical sites around the Kerguelen Archipelago (Southern Ocean) during the natural fertilisation study. KEOPS-2, Biogeosciences 12, 4421-4445.
Charvis, P., et al., 1995, Deep structure of the northern Kerguelen Plateau and hotspot-related activity. Geophys. Jour. Int. 122, 899-924.
Duncan, R. A., et al., 2016, Widespread Neogene volcanism on the Central Kerguelen Plateau, Southern Indian Ocean. Aust. Jour. Earth Sci., doi:10.1080/08120099.2016.1221857.
Römer, M., et al, 2014, First evidence of widespread active methane seepage in the Southern Ocean, off the sub-Antarctic island of South Georgia. Earth Planet. Sci. Lett. 403, 166-177.
Sohn, R., et al., 2017, Exploring the restless floor of Yellowstone Lake. Eos, 98, doi:10.1029/2017EO087035.
Spain, E., et al., in review, Shallow seafloor gas emissions near Heard and McDonald Islands on the Kerguelen Plateau, southern Indian Ocean. Geochem. Geophys. Geosyst.
(注)本原稿は,20108年度日本地質学会各賞の受賞記念講演・スピーチ(2018/9/5於北海道大学)のないようを基に各講演者の皆様に原稿をご執筆頂き,日本地質学会News Vol. 21, No. 12(2018年12月号)p.17-21に掲載されたものです.
関東支部2019年総会_190204
関東支部お知らせ
2019/02/04掲載
2019年度総会・地質技術伝承講演会
開催
関東支部では,下記のように支部総会及び地質技術伝承講演会を開催いたします.
日時:2019年4月13日(土)14:00〜16:45
場所:赤羽会館 4F 小ホール (東京都北区赤羽南1-13-1)
JR赤羽駅東口 徒歩5分,地下鉄南北線赤羽岩淵駅 徒歩10分
後援:(一社)関東地質調査業協会
プログラム:
13:30受付開始
14:00〜15:40 地質技術伝承講演会
講師:横井 悟
所属:石油資源開発(株) 技術本部 フェロー
タイトル:「石油地質分野におけるunconventionalあるいは非石油的な話」
参加費:無料,どなたでも参加できます. CPD単位取得可能(1.5)
申し込み方法:学会へのFAX,下記担当幹事へのe-mailにて受け付けます.
(メール)関東支部幹事 加藤 潔(駒澤大学:kiyoshi.katoh@gmail.com)
(FAX)日本地質学会関東支部気付 関東支部 FAX:03-5823-1156
15:50〜16:45 関東支部総会
1)支部功労賞授与式
2)2018年度 活動報告・会計報告
3)2019年度 活動方針・予算報告
*関東支部会員の方で総会に欠席される方は委任状をお願いします.
委任状送付方法:
○郵送またはFAXの場合は下記にお送りください.
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F
日本地質学会事務局気付 関東支部事務局 FAX:03-5823-1156
○E-mail送付の場合
関東支部のメールアドレス(kanto@geosociety.jp)へ委任状をご返信下さい.メールによる委任状の締切は,4月12日(金)18時までです.
17:15〜 懇親会(予定)会費等当日受付
-----------------------関東支部総会委任状-----------------------
2019 年4月13日(土)開催の日本地質学会関東支部総会に出席できませんので,
当日一切の議決権を 君(又は,議長)に委任します(空欄の場合は議長とします).
日 付:2019年**月** 日
住 所:
会員氏名:
--------------------------------------------------------------------------------------------
行動規範
一般社団法人日本地質学会行動規範
2011年9月8日 一般社団法人日本地質学会理事会 制定
2021年4月3日 一般社団法人日本地質学会理事会 改訂
本会倫理綱領を踏まえて,学会員の基本的な姿勢と責任について,学会員及び社会に明示するため,一定の規範が必要であるとの認識のもとに,必要最小限の行動規範を以下に示す.
Ⅰ.会員としての基本姿勢
(会員の責務)
1.会員は,自らが生み出す地質学及び関連科学(以下,「地質学等」という.)の専門知識,技術,及びその利活用に対し責任を有する.また,地質学等の研究,教育,調査,普及並びに啓蒙等の活動(以下,「活動」という.)を通じて,自らの専門知識,技術及び経験を活かして,社会の発展と人類の福祉及び社会の安心・安全に貢献する責任を有する.
(会員の姿勢)
2.会員は,常に謙虚かつ誠実に判断及び行動し,自らの専門知識,能力及び技術の研鑽に努め,その結果,得られた地質学等の成果が与える社会的影響を自覚し,客観的事実を明らかにするよう努力すると同時に,研究成果と技術上の知見を公表するなどして,広く社会に還元するよう努める.
(他者との関係)
3.会員は,先人・他者の成果を適切に批判あるいは正当に評価すると共に,自らの研究に対する批判に謙虚に耳を傾け,誠実な態度で意見を交え,他者と互いの能力の向上に努力する.
(他分野との連携)
4.会員は,自らの専門領域のみならず,他分野の学術団体や社会の様々なコミュニティ,さらには国際的な交流を進めることを通して学術の向上を図る.
(次世代への責務)
5.会員は,積極的に次世代に地質学等における学術と技術の継承と発展及び人材育成に努めると共に,活動の成果物,特に重要な露頭や標本等の科学的遺産の保全に努める.また,これらを達成するために社会の理解と協力が得られるよう努める.
Ⅱ.公正な会員活動
(活動の姿勢)
6.会員は,活動の立案,計画,申請,実施及び報告等の過程において,公正であることを重視し,誠実に行動する.
(透明性)
7.会員は,研究及び調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し,ねつ造,改ざん及び盗用等の不正行為をなさず,また加担しない.共同して活動を実施する者あるいは協力者の不正行為についても,その防止に努めなければならない.
(正当性の担保)
8.会員は,自らの成果と技術上の知見の正確さ及び正当性が,科学的に広く吟味及び検証されるよう努力する.
(説明責任)
9.会員は,自らの活動に関して説明を求められた場合には,その目的,方法及び成果等について明快に説明する責任がある.特に非専門家に対しては,相手の立場に立ち,分かりやすく説明する責任を有する.
(法令の遵守)
10.会員は,活動の実施及び経費の使用等にあたっては,法令や関係規則を遵守する.
(差別の排除)
11.会員は,活動において人種,ジェンダー,年齢,地位,所属,思想,信条及び宗教等によって個人を差別せず,個人の自由と人格を尊重する.
(他者への配慮)
12.会員は,活動の実施にあたって,協力者及び参加者の人格と人権を尊重し,福利に配慮する.
(環境への配慮)
13.会員は,地球環境の保全と改善に努めると共に,調査及び研究の実施にあたり,環境への影響を最小限にするよう配慮する.
Ⅲ.社会との関わり
(社会への情報提供)
14.会員は,専門知識を活かして地質災害,地球環境及び地質資源等の地質学等の関係する情報の提供,または科学的な助言を行う場合には,その影響の重大さと責任を自覚し,公益性及び中立性の観点から,客観的かつ科学的な根拠に基づき,事実を社会に周知する.
(便宜供与の排除)
15.会員は,他機関や組織と連携して事業を実施する際には,誠実に行動し,不適切な便宜供与を受けてはならない.
(利益相反)
16.会員は,自らの研究,調査,審査,評価,判断及び科学的助言等において,自らを含む特定の個人,権威,組織,あるいは異なる組織間の利益の衝突に十分に注意を払い,公共性に配慮しつつ適切に対応する.
以上
中部支部_2019個人講演
2019年中部支部年会_講演
中部支部トップへ戻る
講演申込/講演要旨送付
締切:2019年5月24日(水)
講演について
個人講演は、各講演15分を予定しています(質疑応答含む)。
ポスターセッションでは、1発表につき横90cm×縦180cmのボード1枚を使用します(画鋲可)。A0版サイズ(横841mm×縦1,189mm)を基準としてください。
個人講演およびシンポジウムでは、パソコンからのプロジェクター投影を予定しています。個人のパソコンではなく、パワーポイント、あるいは自動再生形式のデータをCDまたはメモリでご用意ください。ご自身のパソコンを使わなければならないときは、その旨をお知らせください。
講演要旨
個人講演およびポスターセッションに申し込まれる方、ならびにシンポジウム講演者は同時に要旨をメールにて送付願います。(同時に送ることができない場合、5月24日までにお送りください。またその旨をご連絡ください。)
後日、公表論文作成にあたって、支部年会での講演を引用することはできないことになっていますので、ご了承ください。
個人講演およびポスターセッションの要旨はA4版、2頁までとします。
シンポジウム講演要旨は A4版、10頁までとします。
要旨の様式は下記書式に沿ってください。字体は明朝で統一します。お送り頂いたメール原稿をそのままの形で印刷する予定です。
上下余白:3cm 左右余白:2.5cm
タイトル:14p(ポイント)太文字
発表者・所属機関:12p
英文タイトル:12p
本文は1行開けて始めてください。
本文:10.5p
引用文献:9p
図表は枠内に収めてください。
英文原稿の場合は、上記に準じてください。
関東支部_top
関東支部
一般社団法人日本地質学会 関東支部
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F 日本地質学会事務局内(MAP)
電話:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156 e-mail:kanto[at]geosociety.jp
関東支部規約/関東支部体制/幹事会議事録/過去の活動
更新情報
伊与原新さんの講演会NEW
講演会「県の石−栃木県の岩石・鉱物・化石−」と見学会NEW
清澄フィールドキャンプ 参加者募集
学生・若手会員向け「地質調査の基礎講座」 ー城ヶ島巡検ー
2025年度支部総会・講演会
お知らせ
(2025.8.12掲載,9.14更新)
伊与原新さんの講演会のお知らせ
日本地質学会関東支部では、直木賞作家・伊与原新さんをお迎えして全国の中学生・高校生を対象とした講演会を開催します。 地球惑星科学を専門とする大学教員から小説家に転身され、その専門性を活かした数々の小説を執筆されている伊与原新さんの言葉には地学の魅力がたっぷり。 ぜひご来場ください。中高生と保護者(引率の先生含む)を無料でご招待します。中高生のみの参加も歓迎します。
本イベントは、中高生(保護者)限定のイベントです。一般の方のご来場はご遠慮ください。
日時:2025年10月26日(日)14:30〜16:00 (開場:13:45)
場所:日本大学文理学部 百周年記念館 国際会議場 司会:岡山悠子(科博SCA)
対象:中高生および保護者(引率教員含む), 入場無料・要事前申込
申込サイト https://geo-kanto-iyoharashin.peatix.com
チラシPDF(高解像度)
チラシPDF
【講演者プロフィール】 神戸大学理学部を卒業後、東京大学大学院理学系研究科にて地球惑星科学を専攻し、博士課程を修了。大学勤務を経て、2010年に『お台場アイランドベイビー』で横溝正史ミステリ大賞を受賞し作家デビュー。2024年には『藍を継ぐ海』で第172回直木賞を受賞。自然科学の知見を基盤とする『八月の銀の雪』『磁極反転の日』『青ノ果テ 花巻農芸高校地学部の夏』『宙(そら)わたる教室』『蝶が舞ったら、謎のち晴れ 気象予報士・蝶子の推理』など科学の魅力と人間の営みとを織りなす作品を発表している。
お知らせ
(2025.8.5掲載,8.19,8.28,9.5更新)
講演会「日本地質学会選定 県の石−栃木県の岩石・鉱物・化石−」と見学会のお知らせ
※見学会は,諸般の事情により中止となりました.
講演会のみ実施いたします.
日本地質学会は,2016年5月10日(地質の日)に,全国47都道府県のそれぞれで特徴的に産出する岩石・鉱物・化石を「県の石」として選定することを発表しました.関東支部では関東地方の「県の石」について順次講演会を行っています.今回は一般市民の方々や学会員のために現地とオンラインのハイブリッド形式で,栃木県の「県の石」の講演会を行います.当日午前中には大谷石の建物見学会がありますので,奮ってご参加ください(CPD取得可).
大谷石の建物見学会【中止】
日時:2025年9月27日(土)10:00-11:30
見学会参加費:1500円(事前申込制)
案内者:橋本優子氏(近代建築・デザイン史家,文星芸術大学非常勤講師)
定員:20名(抽選)
CPD:1.5単位取得可
申込期間:2025年9月1日(月)〜9月17日(水)17:00締切
申込方法:下記のフォームで申し込んでください.当選者にはメールを送ります.
<コース>
10:00 東武宇都宮駅集合
Stop 1:東武宇都宮線の大谷石築堤(東武宇都宮駅すぐそば)造営1931年
Stop 2:カトリック松が峰教会聖堂(築堤のすぐそば)聖別1932年
Stop 3:中心市街地(聖堂から神社までの間)戦前・戦後の石蔵など
Stop 4:宇都宮二荒山神社石垣 江戸時代のものが現存
11:30二荒山神社解散
神社から博物館までは各自移動
*路線バスの場合,バス停「馬場町」から「中央公園博物館前」または「睦町」まで約10分,いずれかのバス停から博物館まで徒歩10分程度.
*タクシーならば約15分程度
講演会
共催:(一社)日本地質学会関東支部,栃木県立博物館
日時:2025年9月27日(土)13:00〜16:00(12:30から受付開始)
場所:栃木県立博物館講堂
対象:一般市民および学会員 小学生3年生以上(内容は大人向けです)
定員:現地100名+オンライン100名 ※オンラインでご参加の皆様には,9月25日にメールでZoomミーティングのリンクをお知らせします.
参加費:1000円(事前申込み制)
CPD:2.5単位取得可能
申込期間:2025年9月1日(月)〜9月24日(水)17:00締切り
申込方法:Peatixのページから申し込んでください.https://tochigikennoishi.peatix.com
お問合わせ先 関東支部幹事長 加藤 潔(駒澤大学)メール kiyoshi.katoh@gmail.com
<講演会プログラム> 講演者1人45分,質疑応答10分,休憩5分
13:00 - 13:05 主催者挨拶
13:05 - 13:50 『足尾銅山の歴史と製錬技術の変遷』
講師:布川嘉英氏(栃木県立博物館学芸部自然課 学芸員)
【要旨】栃木県の鉱物は黄銅鉱.これは日本屈指の銅山として知られる足尾銅山の主たる鉱石であったことが選定理由である.1877年(明治10年),古河市兵衛が足尾銅山を買収して以来莫大な投資を行い,本銅山は産銅量を飛躍的に増加させた.銅山の発展とともに,足尾の町も最盛期には宇都宮に次ぐ県内第二の都市となった.同時に大規模な鉱山開発には公害(鉱害)問題が伴い,足尾銅山は日本の公害の先駆的な事件となった.そして閉山以降も排水処理のための沈殿池は稼働し続けている.一方,煙害については,足尾銅山の技術者たちの長年にわたる研究開発により,1956年に自溶炉を導入し,製錬時に発生する硫化ガスから硫酸を製造するシステムを完成させた.これによって製錬排ガスの無公害化に成功した.
筆者は平成24年に『足尾の鉱物と製錬技術の変遷』と題して展示を制作した.これを元に,今回は製錬技術の変遷を軸にした足尾銅山の歴史について語る.
13:50 - 14:00 質疑応答
14:00 - 14:05 休憩
14:05 - 14:50 県の岩石『大谷石』
講師:橋本優子氏(近代建築・デザイン史家,文星芸術大学非常勤講師)
【要旨】2016年(平成28),日本地質学会により「県の石」として選ばれた大谷石(おおやいし)は,全国的に知名度が高い岩石・石材です.2018年(平成30)には,この石をめぐる「大谷石文化」が文化庁の「日本遺産」にも認定されています.
岩石としての大谷石は凝灰岩に相当し,産地では近世以前から石造物,家屋(伝統工法の張石蔵),土木,民具に用いられてきました.西洋式の工法・意匠が広まった明治以降は,組積造の家屋(近代工法の積石蔵)が現れ,鉄筋コンクリート造石張の帝国ホテル新館(ライト館:全館竣工1923年,基本設計=フランク・ロイド・ライト)が登場すると,大谷石は近代建築史に不朽の名を残します.
今回の講演会では,このような大谷石について,ライトとその弟子・遠藤 新の業績,並びにライト館が地域の建築シーンにもたらした影響を中心に,石材としての特性や魅力をお話いたします.また講演日の午前中には,宇都宮の中心市街地に残る大谷石建造物を訪ねるミニ見学会(1時間半予定)のご案内もいたします.
14:50 - 15:00 質疑応答
15:00 - 15:05 休憩
15:05 - 15:50 県の化石 『木の葉石』
講師:相場博明氏(財団法人教育実践学研究所長)
【要旨】栃木県那須塩原市にある塩原温泉は1,200年以上の歴史を持つ有名な温泉地だが,実は化石の産地としても有名である.とくにここから産出する植物化石は,1888年(明治21年)に研究が始まり,その保存状態は素晴らしく,絵に描いたものと間違われるほど美しい.時代は約30万年前の中期更新世(チバニアン)で,今まで200種類ほどの植物化石が報告されている.植物以外にも,チョウ,トンボ,甲虫,ハエ,ハチ,カメムシなどの昆虫化石や,魚,カエル,ネズミなどの化石も発見されている.とくに昆虫化石は化石として産出することが珍しく,これほど多く産出する場所は世界的にも珍しい.しかしながら10年前まではその研究は十分行われておらず,記載されていたのはわずか6種類のみであった.演者は,2025年に「塩原木の葉石ガイドブック-実習・同定の手引きと植物・昆虫化石図鑑-」という本を出版し,その中で89種類の昆虫とクモを同定した.その後,新たに2種の新種を含む昆虫化石が演者とその研究協力者により次々と報告され,現在は100種類以上が記載されている.本講演では,現在の塩原の化石の産出状況の概要とその意義について説明する.
15:50 - 16:00 質疑応答
16:00 - 16:05 閉会の挨拶
お知らせ
(2025.5.28掲載,7.4更新)
清澄フィールドキャンプ 参加者募集のお知らせ
応募締切日:7月11日(金)締切延長
京都大学理学部地球惑星科学専攻地質学鉱物学教室のご支援を受け,フィールド教育の継承・発展を目的とした清澄フィールドキャンプ(清澄FC)を開催します.実習フィールドは東京大学千葉演習林(清澄)内の七里川ならびにその支流ですが,地質調査の基礎的な訓練を行うには,第1級のエリアです.京都大学が行う清澄山実習(佐藤活志先生・生形貴男先生・成瀬元先生)と同時期に,同じカリキュラムで実施しますので教育効果が高まります.地質調査の基本を習得したい学生さんや若手会員のご参加をお待ちしています.学生会員(清澄フィールドキャンプ実施前に会員申請をしていただいた方も含む)は本会の若手育成事業による学生会員参加費半額補助(食事代を除く)が得られます.かなりお得になりますので,学会への入会をご検討ください.また,先生方には学生への募集のご連絡などご高配を賜りたく存じます.過去の実施報告は,ニュース誌(2024年10月号)に掲載されております(PDFはこちらから).
ご不明な点は,下記の問い合わせ先までお寄せください.
主催:一般社団法人日本地質学会関東支部
期間:2025年8月25日(月)〜8月30日(土) 5泊6日
場所:東京大学千葉演習林(〒299-5505 千葉県鴨川市清澄)
費用:非会員の方は一般60,000円,学生45,000円.会員の方は一般会員55,000円,学生会員(清澄フィールドキャンプ実施前に会員申請をしていただいた方も含む)28,250円.宿泊・食事・保険・タクシー代込.
※キャンセル料については,学会の規定により,参加確定後〜実施3日前まで 50%,実施2日前以降 100%.
定員:最大6名(学生優先,最少催行人数は4名)
募集要項および応募用紙はこちらから
応募締切日:7月4日(金)7月11日(金)締切延長(*応募書類は上記のフォーマットを使用のこと)
問い合わせ先:2025年度清澄フィールドキャンプ実行委員会
事務局長 加藤 潔(関東支部幹事長)
電話:090-1705-7516 Eメール:kiyoshi.katoh[at]gmail.com
お知らせ
(2025.4.7掲載)
学生・若手会員向け「地質調査の基礎講座」 ー城ヶ島巡検ー のお知らせ
定員に達しましたので,受付を締め切りました
日本地質学会関東支部では,標記の講座を実施します.学生・若手会員向けです.地層・堆積岩の見方を学んで露頭柱状図を作成したり,走向・傾斜の測り方を学んで測定した走向・傾斜をもとに地質構造を推定する講座です.野外地質調査に不慣れな方,堆積岩の見方を勉強したい方,城ヶ島に興味のある方,大歓迎です.また,32歳未満の学生会員の方には,本会の若手育成事業による参加費半額補助が得られます.なお,今年度も清澄FC(本格的な地質調査演習)が開催されますが,学生会員になっておくとこちらも上記の半額補助がありますので,かなりお得になります.
日時・場所:
2025年5月31日(土)10:00-16:30 集合場所:白秋碑前バス停.神奈川県三浦市城ヶ島で野外観察・調査
2025年6月1日(日)10:00-15:00 集合場所:会議室(横須賀市産業交流プラザ第一会議室(京急線汐入駅前))で露頭柱状図作成など(室内作業)
募集人数:約15名 学生優先,余裕がある場合学生以外の方も受け付けます.学生以外の方はキャンセル待ち扱いとなります(希望者は7.0CPD単位取得可能). 申込締切後参加の可否を連絡します.
参加費:会員一般5,000円,32歳未満の学生会員2,000円(補助適用後の金額です.その他の学生会員は4,000円).非会員一般6,000円,非会員学生4,000円.
申込方法:メール件名を「城ヶ島巡検」とし,下記の申込先に,氏名・ふりがな・所属・学年・年齢(保険に必要)・連絡先(携帯番号)を明記しメールで送ってください.申込者には受付メールを返信します.申込み後3日経っても返信がない場合は問い合わせてください.
申込締切:5月23日(金)(定員になり次第締め切り)定員に達しましたので,受付を締め切りました
案内者・指導者:日本地質学会関東支部幹事 笠間友博,方違重治,加藤 潔,久田健一郎
問い合わせ・申込先:加藤 潔(関東支部幹事長,駒澤大学)メール:kiyoshi.katoh[at]gmail.com
その他:
詳細については参加人数確定後ご本人宛にメールで連絡します.
事前課題を出す予定です.期限までにご提出ください.
キャンセルの場合は速やかにご連絡ください.キャンセル料:7日前〜前日50%,当日100% 4)荒天が予想される場合の中止判断は前日18:00までに行い,電話で各参加者に連絡します.
お知らせ
(2025.1.7掲載,3.24更新)
2025年度関東支部総会・講演会
関東支部では,下記のように支部総会および講演会をハイブリッド形式(会場+zoom会議)で開催いたします.
支部総会に先立って行われる講演会(共催:一般社団法人関東地質調査業協会)は,非会員の方も参加可能です.ぜひ皆様お誘い合わせの上ご来臨くださいますようご案内申し上げます.
日時:2025年4月12日(土)14:00-16:45(13:30から講演会受付開始)
場所:北とぴあ第2研修室.JR京浜東北線王子駅北口徒歩3分;東京メトロ南北線王子駅5番出口直結;東京さくらトラム(都電荒川線)王子駅前徒歩5分.
【講演会】
共催:一般社団法人日本地質学会関東支部・一般社団法人関東地質調査業協会
タイトル:「潜水船・水中ドローンによる島弧-海溝系の海底露頭観察」
講師:山口飛鳥氏(東京大学大気海洋研究所)
要旨:島弧-海溝系の海底は,堆積・侵食・地震時の変位など,さまざまな変動の記録を保持している.そのため,海底における地質過程の理解は,陸上で観察される地層や変形構造の成因を解明するうえでも重要である.本講演では,南海トラフおよび日本海で近年実施した潜航調査に基づく海底露頭の観察事例を紹介し,その意義について議論する.2023年に「しんかい6500」を用いて実施した南海トラフの調査では,潮岬海底谷の壁沿いに露出した連続露頭を観察し,南海付加体から熊野前弧海盆最下部にかけての層序を明らかにした.また,2024年に水中ドローン(小型ROV)を用いて能登半島珠洲沖・輪島沖で実施した調査では,同年の能登半島地震で形成されたと考えられる海底地震断層(主断層に付随して活動した副次的な断層)を発見した.これらの調査に先立ち,海底地形測量・反射法地震探査・採泥・掘削などの手法を用いた事前検討を行い,観察地点を選定している点も重要であり,これらの手法と適切に組み合わせることで,潜航調査の意義はさらに高まることが期待される.
講演会資料:PDFファイルこちらから
講演会の定員:会場100名+オンライン100名(ハイブリッド形式).
参加費:無料
CPD単位:1.5単位取得可(プログラムID 4227)
参加申込方法:下記の2025年度地質学会関東支部総会・講演会参加申込フォームから申し込んでください(4月10日(木)17時締切).
総会・講演会申込フォーム:https://forms.gle/x8JN3cmiLhHSQ1g27
【関東支部総会】
講演会終了後に開催されます.総会・講演会の参加申込フォーム,議案書(決算報告・予算案),議決権行使書フォームは下記の通りです.総会を欠席される関東支部会員の方は議決権行使書フォームか委任状のご提出をお願いします.
総会・講演会の参加申込フォーム:https://forms.gle/x8JN3cmiLhHSQ1g27
議案書(決算報告・予算案):PDFファイルこちらから
議決権行使書フォーム:https://forms.gle/ozyzbyCkaRTkcXR76
委任状フォーム:https://forms.gle/m2V41WYLcjyerJNY8
<プログラム>
13:30 受付開始 (ハイブリッド形式;CPD1.5単位取得可)
14:00-15:30 講演会
共催:一般社団法人日本地質学会関東支部・一般社団法人関東地質調査業協会
講師:山口飛鳥氏(東京大学大気海洋研究所)
「潜水船・水中ドローンによる島弧-海溝系の海底露頭観察」
15:30-15:40 質疑応答
15:40-15:50 休憩(講演会のみに参加の方はご退室)
15:50-16:45 関東支部総会・支部功労賞授与式(議案審議 第1号議案 2024年度活動報告・決算報告/第2号議案 2025年度活動計画/第3号議案 2025年度予算案)
委任状送付方法:下記の3つの方法があります.
1.2025年度委任状フォーム:3月下旬に支部Webサイトに掲載予定.
2.郵送またはFAX:下記にお送りください(4月10日(木)必着).
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F
日本地質学会事務局気付 関東支部事務局
FAX:03-5823-1156
3.E-mailによる送付の場合:関東支部のメールアドレス(kanto@geosociety.jp)へ
下記の内容の委任状をご送付下さい(4月11日(金)17時締切) .
-----------------
関東支部総会委任状
2025年4月12日(土)開催の日本地質学会関東支部総会に出席できませんので,
当日一切の議決権を 君(又は,議長)に委任します(空欄の場合は議長とします).
日時 2025年**月**日
住所:
会員氏名:
-----------------
問い合わせ先: 関東支部幹事長 加藤 潔(駒澤大学)
電話:090-1705-7516 Eメール:kiyoshi.katoh[at]gmail.com
関東支部_規約_体制_議事録
関東支部
関東支部トップページに戻る
幹事会議事録
2019年度
・2019年度第2回議事録(2019/5/21)
・2019年度第1回議事録(2019/4/13)
>>2018年以前の議事録はこちら(関東支部旧サイト)
日本地質学会関東支部規約
日本地質学会関東支部規約
1988年1月30日・1997年5月26日・2002年5月11日・2004年5月15日・2011年4月24日・2012年4月8日・2022年4月17日一部改正
第1条 一般社団法人日本地質学会(以下地質学会という)の定款第2条第2項に基づき一般社団法人日本地質学会関東支部をおく(以下関東支部という)。
第2条 関東支部の所在地は別途定める。
第3条 関東支部は、一般社団法人日本地質学会(以下地質学会という)運営規則第10条により、当該支部として区分された都道府県に住所登録している、地質学会の正会員をもって組織する。
第4条 関東支部は、定款第3条にあるこの学会の目的に沿って、当該地域を活動の中心として事業を行う。
2. 関東支部は、一般社団法人日本地質学会理事会規則第14条に定める支部長会議ならびに同選挙細則第5条第3項の支部選出理事との間で意思の疎通を図り、学会の目的達成と発展に寄与することとする。
第5条 関東支部には次の役員を置く。
幹事20名以内
幹事は新支部長1名・幹事長1名を互選する。
2. 役員の任期は、以下に定める関東支部総会(以下支部総会という)から翌々年の支部総会までの2年とし、再任は妨げない。
3. 役員の選任は支部総会において行い、地質学会の理事会に報告する。役員の選出方法および役員に欠員が生じた場合については別に定める。
第6条 関東支部の会議は支部総会および幹事会とする。
第7条 支部総会は支部長が招集する。
2. 幹事会は支部長が召集する。開催については別に定める。
第8条 関東支部の事業計画および予算ならびに事業報告、決算報告は支部総会において承認し、理事会の承認を得ることとする。
第9条 支部総会は、支部会員現在数の20分の1以上の出席をもって成立する。あらかじめ書面または電磁的方法により意思表示したものは出席者とみなす。
2. 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し,可否同数の時は議長が決定する。
第10条 関東支部の会計は地質学会の事業費,寄付金およびその他の収入をもって行う。
第11条 関東支部の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
第12条 関東支部規則は、学会運営規則第11条に基づき支部総会において定める。
2. 本規則は支部総会出席者の3分の2以上の議決により変更することができる。
第13条 支部は、支部活動に多大な功労・貢献があったと認められる個人、団体等を、別途定める規則に基づき顕彰することができる。
第14条 支部の運営に必要な事項はこの規則に定めるほか、幹事会の議決により別に定める。
附 則 本規約は2022年4月18日より施行する。
関東支部トップページに戻る
日本地質学会関東支部細則
日本地質学会関東支部細則
2004年5月15日制定,2005年6月11日,2012年4月8日,2022年4月17日一部改正
幹事の選出
第1条 幹事の選出は、つぎの方法による。
幹事会は任期最終年度の1月末までに、支部会員の中から選挙管理委員3名を選任し、選挙管理委員会を構成する。選挙管理委員会は幹事の選挙に関する事務を行う。
選挙人および被選挙人は支部会員とする。
選挙管理委員会は、本会ニュース誌により、期日および方法を当該年度の2月末までに明示して、幹事候補の推薦および立候補を求める。候補者の推薦は、推薦者(支部会員)の名を記して支部会員1名を推薦するものとする。
幹事候補者が定数を越えた場合、選挙管理委員会は、本会ニュース誌により幹事候補者名簿、投票期日および投票方法を公示して、支部総会において支部総会参加者による無記名投票を求める。
選挙管理委員会は得票数順で当選者を選出する。選挙管理委員会は、その結果を総会に報告し、任務を終える。
幹事候補者が定数を越えなかった場合、選挙管理委員会は,候補者名簿等の公示および投票を省略して全候補者を当選者として選出できる。
第2条 支部長は、これらの結果を支部会員に報告する。
附 則 本細則は、2012年4月18日より施行する。
関東支部トップページに戻る
関東支部体制(2024年5月1日現在)
支部長
久田健一郎(NPO法人地学オリンピック日本委員会)
幹事長
加藤 潔(駒澤大学)
幹 事(50音順)
荒井 良祐(川崎地質株式会社)
飯田 和也(武蔵野大学教育学部)
小田原 啓(神奈川県温泉地学研究所)
笠間 友博(箱根町企画課)
金丸 龍夫(日本大学文理学部地球科学科)
河尻 清和(相模原市立博物館)
澤田 大毅(株式会社 地球科学総合研究所)
廣谷 志穂(アジア航測株式会社)
冨田 一夫(鹿島建設株式会社技術研究所)
納谷 友規(産業技術総合研究所)
方違 重治(国土防災技術株式会社)
細矢 卓志(中央開発株式会社)
本田 尚正(東京農業大学)
山本 秀忠(大日本ダイヤコンサルタント株式会社)
代永 佑輔(株式会社地圏総合コンサルタント)
関東支部トップページに戻る
関東支部_過去の活動
関東支部_過去の活動
関東支部トップページに戻る
・2024年度の活動
・2023年度の活動
・2022年度の活動
・2021年度の活動
・2020年度の活動
・2019年度の活動
・2018年以前の活動
(旧関東支部サイトへ)
2024年度の活動
お知らせ
(2025.2.6掲載)
中高生向けスキー地学実習
関東支部では、次世代を担う中高生を対象に、野外での観察を通して地学の面白さを実感し、地球科学に対する理解を深めていただきたいという趣旨で、スキーを使った地学実習の後援を行っています。 冬山登山は高度な技術が必要ですが、スキーという道具を使うことで、普段の生活で気がつくことの難しい地形や自然現象について、安全面の確保されたスキー場から観察することができます。今回の中高生向け地学実習では、谷川岳の下を通る関越トンネルで越後湯沢へ入り、太平洋気候から日本海気候への変化を経験し、石打丸山スキー場では谷川連邦、六日町盆地および越後山脈などの地形観察を通じて、プレート沈み込みに伴う谷川連邦を含む脊梁山脈と日本列島の形成について学びます。 また、谷川岳を貫く清水トンネル群の建設は日本の近代史と深く関わっています。清水トンネルの歴史を通じて、地学と社会の接点についても学びます。
主催:日本地球科学普及教育協会(ジオ活クラブ)
協力:加速キッチン
後援:公益社団法人日本地球惑星科学連合(JpGU)、一般社団法人日本地質学会関東支部、公益財団法人科学技術広報財団、海の女性ネットワーク
日 時:2025年3月23日(日)
場 所:新潟県南魚沼市石内丸山スキー場
対 象:小学校5年生〜高校3年生(小学生は保護者同伴必須、中学生以上は希望する保護者は同伴可能)
スキー靴が履けてボーゲンができること。未経験者は、実習までにスキースクールなどでボーゲンまでを練習してから参加してください 今回はスキーのみ対象です。スノーボードは対象ではありませんので、ご注意ください。
人 数:20 名(保護者含む。人数上限に達した時点で募集を終了します。)
応募締切:2025年2月28日(金)(人数が定員になった時点で募集終了)
参加費:生徒 5,000円/人、保護者 12,000円/人(振り込み手数料は別です)
参加費用に含まれるもの:バス代、昼食代、リフト代、テキスト代、教材費用、保険代
参加費用に含まれないもの:スキー(靴、板、ストック)レンタル代 5,200円/人、スキー+ウェアレンタル代 8,700円/人、ヘルメットレンタル代 1,500円/人、自宅ー集合・解散場所間の交通費
備考:本実習は公益財団法人東京応化科学技術振興財団の助成金によって実施されます。
※当日のスケジュールや申し込みなど、実習の詳細は、下記よりご確認ください。
実習サイト(申込みもこちらからお入りください):
https://www.geokatz.com/2025ski/index.html
お問合せ:日本地球科学教育普及協会 小俣珠乃
E-Mail: geokatzclub[at]gmail.com
お知らせ
(2024.12.19掲載)
サイエンスカフェ「地震がつくる大地!〜隆起でできた日本列島〜」
関東支部では,地質学のアウトリートを目的として下記の通りサイエンスカフェを行います.
お申し込みの詳細は,日本地質学会関東支部サイエンスカフェのXアカウント(@GeoSoc_SciCafe)をご参照ください.
講師:宍倉正展さん(産総研)
ファシリテータ:岡山悠子さん(科博SCA)
日時:2025年1月12 日(日)15:00 ー16:45
場所:ベルギービール アグリオ(京王線下高井戸駅徒歩1分)
入場料:2,000円+1ドリンク
定員:20名
お申し込みはこちらから(Peatixのサイトへ)
一般向けの内容です(どなたでもご参加いただけます)
問い合わせ先:サイエンスカフェ担当(geo.soc.sci.cafe[at]gmail.com)(※[at]を@マークにして送信してください)
お知らせ
(2024.12.16掲載)
アウトリーチ巡検 「逗子市と鎌倉市の地質・地形観察」のお知らせ
定員に達しましたので,参加申し込み受付を終了しました
日本地質学会関東支部では,多くの方々に,野外での観察を通して地学の面白さを実感し,地球科学に対する理解を深めていただきたいという趣旨で,アウトリーチ巡検を実施しています.本年度は,神奈川県逗子市と鎌倉市に露出している鮮新世の逗子層,池子層(鮮新世),浦郷層(鮮新世から前期更新世)の海底地すべりの痕跡や火山灰層などの観察を実施します.講師は産業技術総合研究所の宇都宮正志氏と平塚市博物館の野崎篤氏です.
主催:(一社)日本地質学会 関東支部
実施日:2025年2月8日(土)(予備日:2月16日(日))
対象:当該地域の岩石・地質・地形に興味のある方(日本地質学会会員でなくても可)
募集:20人(先着順) ※最少催行人数10人(達しない場合は中止です)
講師:宇都宮正志(産業技術総合研究所)・野崎篤(平塚市博物館)
集合:京急 神武寺駅 改札口9:00(JR逗子駅,京急 金沢文庫・金沢八景駅から乗り換え).
解散:JR 鎌倉駅付近 16:00前後(予定)
予定コース(天候などにより変更になることがあります):途中,電車・バスを利用します. 1.逗子市池子の森自然公園:逗子層と池子層神武寺部層の海底地すべり,シロウリガイ類化石の観察 2.鎌倉市朝比奈周辺:浦郷層の斜交層理と火山灰層
※運動靴など足回りのしっかりした滑りにくい靴でご参加ください.
持ち物:飲み水,軍手(地図は主催者で用意.ハンマー,ルーペ,登山用ストックもあると良い)
※金沢八景駅前で昼食予定.お弁当を広げる場所はほとんどありません.駅周辺には飲食店が多くあり,飲食店で昼食をとることができます.
参加費用:2,000円(保険代,資料代等.当日集金) ※学会規定のキャンセル料が発生します.参加確定後〜巡検3日前(2月5日)まで50%,巡検2日前(2月6日)以降100%になります.ご承知おきください.2月8日が雨天等で中止になり,16日の参加が困難になった場合はキャンセル料は発生しません.
申込期間:1月7日(火)〜1月24日(金)17:00終了
※定員に達した時点で終了 申込フォーム:
定員に達しましたので,参加申し込み受付を終了しました
※個人情報の申告は保険申込みに必要なため,ご理解いただきますようお願いいたします. 申込者全員に受付結果についてのメールを返信します.実施確定後,参加者には改めて注意事項等をメールで送ります.
問い合わせ:関東支部幹事 飯田 和也(いいだ かずや) メール:k-iida[at]musashino-u.ac.jp (※[at]を@マークにして送信してください)
(担当幹事:河尻清和・飯田和也)
お知らせ
(2024.11.5掲載)
2024年度関東支部功労賞募集のお知らせ
日本地質学会関東支部では,毎年,支部の顕彰制度に基づき,支部活動や地質学を通して社会貢献された個人・団体を顕彰しています.つきましては,下記の要領で支部会員からの推薦を募集します.
関東支部功労賞審査委員会
委員長 山崎晴雄
対象者:支部活動や地質学を通して広く社会貢献をされた関東支部内に在住の個人・団体 *社会貢献や活動の評価においては,必ずしも学問的な成果を問うものではありません.
公募期間:2024年12月16日(月)〜2025年1月17日(金)
選考期間:2025年1月20日(月)〜2025年1月31日(金)
審査結果報告:NEWS誌・関東支部総会で報告します.
推薦方法:対象者氏名,推薦者氏名,推薦理由(400字から800字程度)を記述の上,メールの件名を「関東支部功労賞推薦」として,wordかPDFファイルをメールに添付して,下記の受付担当のメールアドレスへお送りください.
受付担当:関東支部幹事長 加藤 潔(駒澤大学)E-mail:kiyoshi.katoh@gmail.com
お知らせ
(2024.9.17掲載)
講演会「県の石−東京都の岩石・鉱物・化石−」のお知らせ
日本地質学会は,全国47都道府県について,その県に特徴的に産出する,あるいは発見された岩石・鉱物・化石をそれぞれの「県の石」として選定し,2016年5月10日(地質の日)に発表しました.関東支部では,関東地方の「県の石」について順次講演会を行っています.今回は東京都の「県の石」について,現地(早稲田大学早稲田キャンパス)とオンラインのハイブリッド方式で講演会を行います.なお,現地会場では化石等の展示を行う予定です.
主催 (一社)日本地質学会関東支部
日時 2024年11月10日(日)13:00〜16:00
対象 会員及び非会員 小学生3年生以上(内容は大人向けです)
会場 早稲田大学早稲田キャンパス6号館001教室
定員 現地100名(上記教室)、オンライン100名
参加費 無料(要事前申込み) ただし現地は資料代500円がかかります(高校生以下は無料配布). 現地で現金でお支払いください.
CPD 2.5単位取得可能
申込期間 2024年10月11日(金)〜10月31日(木)17:00締切
申込みフォーム https://forms.gle/GRQv9NobMWXYEp5
プログラム
13:00 開場
13:30〜13:35 開会の挨拶
13:35〜14:35 東京都の石と鉱物 -小笠原諸島の無人岩とその地質学的意義- 石塚 治 産業技術総合研究所 活断層・火山研究部門
14:35〜14:40 質疑応答
14:40〜14:50 休憩
14:50〜15:50
東京都の化石「トウキョウホタテ」と早稲田大学 守屋和佳 早稲田大学教育・総合科学学術院理学科地球科学専修
15:50〜15:55 質疑応答
15:55〜16:00 閉会の挨拶
お問合わせ先 関東支部幹事 笠間友博(箱根ジオパーク事務局)メールkasama@mh.scn-net.ne.jp
【講師および講演概要】
東京都の石と鉱物 -小笠原諸島の無人岩とその地質学的意義- 石塚 治 産業技術総合研究所 活断層・火山研究部門
小笠原諸島の島々には,無人岩(ボニナイト)を含む伊豆小笠原地域で最も古い火山岩が分布する.さらに近年の調査船と有人潜水船を用いた海底調査により,伊豆小笠原海溝と小笠原諸島の間にさらに古い火成岩類が露出していることがわかった.海底観察により島弧火山活動最初期の火成岩類の層序が明らかになり,さらに採取岩石の分析により,火山活動の時期とマグマの化学的特徴の時間空間変化が詳細に明らかになった.これによりプレート沈み込み開始及び島弧創成過程を理解するための重要な知見が得られた.本講演では無人岩の特徴とその島弧発達過程の中での位置付けについて紹介する.
東京都の化石「トウキョウホタテ」と早稲田大学 守屋和佳 早稲田大学教育・総合科学学術院理学科地球科学専修
東京都の化石に指定されたMizuhopecten tokyoensis(トウキョウホタテ)は,第20代日本地質学会会長,第2代日本古生物学会会長を務めた徳永重康によって,1906年に記載された.徳永による原記載論文では,北区王子から多産すると記されているが,東京都の都市化以前は都内の各所からの産出が知られていた.徳永がその後の研究で取り扱った標本の一部は早稲田大学構内からも産出しており,その化石は今でも早稲田大学に残されている.本公演では,トウキョウホタテ,徳永重康と早稲田大学との関わりについて紹介したい.
お知らせ
(2024.9.17掲載,10.15更新)
家族巡検「葛生化石館と周辺の石灰岩の見学」のお知らせ(締切延長)
関東支部では石灰岩をテーマに,家族で楽しめる栃木県佐野市の葛生化石館を中心とした巡検を行います.葛生化石館は,石灰岩の産地として知られた葛生地域の中核施設として,40年以上地域の地質学の普及に貢献された施設で,2022年度に関東支部功労賞も受賞されています.巡検は葛生化石館周辺の野外観察と葛生化石館の展示見学,石灰岩磨き体験(磨いた面の化石観察)の三部構成になります.
共催 (一社)日本地質学会関東支部・佐野市葛生化石館
日時 2024年10月27日(日)10:36〜16:09(時刻は電車の時間,昼食持参,小雨決行,荒天中止)
場所 葛生化石館(石灰岩磨き体験を含む)および嘉多山公園.
講師 奥村よほ子 学芸員
行程(集合・解散) 葛生駅(東武鉄道佐野線の終点)10:36集合→嘉多山公園(観察・昼食)→ 葛生化石館(見学・石灰岩磨き体験)→葛生駅16:09までに解散(全行程徒歩)
集合・解散時刻は葛生駅の時刻表をもとにしています.
雨天時は化石館へ戻ってから昼食をとります.
巡検の対象および人数 日本地質学会会員とその家族 15人程度
参加費 石灰岩磨き体験代300円と保険代を合わせ500円
持ち物 弁当・飲料水
申込締切:10月17日(木)10月24日(木)17:00締切 延長しました
申込フォーム https://forms.gle/Zdz1399Etgwdv4p7
お問合わせ先:関東支部幹事 笠間友博(箱根ジオパーク事務局)メールkasama[at]mh.scn-net.ne.jp
お知らせ
(2024.5.20掲載,6.18,6.19追加)
清澄フィールドキャンプ 参加者募集
京都大学理学部地球惑星科学専攻地質学鉱物学教室のご支援を受け,フィールド教育の継承・発展を目的とした清澄フィールド・キャンプ(清澄FC)を再開します.実習フィールドは東京大学千葉演習林(清澄)内の七里川ならびにその支流ですが,地質調査の基礎的な訓練を行うには,第1級のエリアです.京都大学が行う清澄山実習(佐藤活志先生・成瀬元先生・松岡廣繁先生)と同時期に,同じカリキュラムで実施しますので教育効果が高まります.地質調査の基本を習得したい学生さんや若手会員のご参加をお待ちしています.今年度から学生会員には本会の若手育成事業による学生会員参加費半額補助(食事代は除く)が適用されています.かなりお得になりますので,非会員の学生は,この機会にぜひ入会をご検討ください.(申込時までに入会手続きを行ってください). また,先生方には学生への募集のご連絡などご高配を賜りたく存じます.過去の実施報告は,日本地質学会News(2019年10月号,p.10はこちらから)に掲載されております.ご不明な点は,下記の問い合わせ先までお寄せください.
主催:一般社団法人日本地質学会関東支部
期間:2024年8月19日(月)〜8月24日(土) 5泊6日
場所:東京大学千葉演習林(〒299-5505 千葉県鴨川市清澄)
清澄FC現地講師:方違重治(国土防災技術株式会社),加藤 潔(駒澤大学)
費用:会員:55,000円,32歳未満の学生会員:28,250円(若手育成補助適用後の金額です),非会員一般:60,000円,非会員学生:45,000円.
(注)参加費用には宿泊・食事・保険・タクシー代が含まれます.
※キャンセル料:学会の規定により,参加確定後〜巡検3日前まで 50%,巡検2日前以降 100%
定員:最大6名(学生・若手優先;最少催行人数は4名;朝から夕方までは地質調査,入浴・夕食後は深夜まで柱状図の作成などを行う)
応募締切日:7月5日(金)(*応募書類は所定のフォーマットを使用のこと【PDFこちらから】)
問い合わせ先:2024年度清澄フィールドキャンプ実行委員会
事務局長 加藤 潔(関東支部幹事長)
電話:090-1705-7516
Eメール:kiyoshi.katoh[at]gmail.com
※[at]を@マークにして送信してください
お知らせ
(2024.5.20掲載)
学生・若手会員向け「地質調査の基礎講座」- 城ヶ島巡検
日本地質学会関東支部では,標記の講座を実施します.学生・若手会員向けです.地層・堆積岩の見方を学んで露頭柱状図を作成したり,走向・傾斜の測り方を学んで測定した走向・傾斜をもとに地質構造を推定する講座です.野外地質調査に不慣れな方,堆積岩の見方を勉強したい方,城ヶ島に興味のある方,大歓迎です.また,学生会員には,本会の若手育成事業による学生会員参加費半額補助が適用されています.
日時・場所:
2024年6月8日(土)10:00-15:30 神奈川県三浦市城ヶ島で野外観察・調査(集合場所:白秋碑前バス停)
2024年6月9日(日)13:00-16:45 横須賀市産業交流プラザ第一会議室(京急線汐入駅前)で露頭柱状図作成など(室内作業)
現地案内者:日本地質学会関東支部幹事 笠間友博,方違重治,加藤 潔
募集人数:約15名 学生優先,余裕がある場合学生以外の方も受け付けます.学生以外の方はキャンセル待ち扱いとなります(希望者は7.0CPD単位取得可能). 申込締切後参加の可否を連絡します.
参加費:一般会員:4,000円,学生会員:1,500円(若手育成補助適用後の金額です),非会員一般:5,000円,非会員学生:3,000円.
申込方法:メールのタイトルを「城ヶ島巡検」とし,下記の申込先に,氏名・ふりがな・所属・学年・年齢(保険に必要)・連絡先(携帯番号)を明記しメールで送ってください.申込者には受け付けメールを返信します.申込み後3日経っても返信がない場合は問い合わせてください.
申込締切:6月5日(水)(定員になり次第締め切り)
問い合わせ・申込先:加藤 潔(駒澤大学)
メールアドレス:kiyoshi.katoh[at]gmail.com
※[at]を@マークにして送信してください
その他:
詳細については参加人数確定後ご本人宛にメールで連絡します.
事前課題を出す予定です。期限までにご提出ください.
キャンセルの場合は速やかにご連絡ください.キャンセル料:7日前-前日50%,当日100%
荒天が予想される場合の中止判断は前日18:00までに行い,電話で各参加者に連絡します.
※コロナウィルスの感染拡大状況によっては,中止・延期することがあります.
お知らせ
(2024.1.5掲載,2.15,3.6,4.5更新)
2024年度関東支部総会・講演会開催のお知らせ(第4報)
関東支部では,下記のように支部総会および講演会をハイブリッド形式(会場+Zoom会議)で 開催いたします. 支部総会に先立って行われる講演会(共催:一般社団法人関東地質調査業協会)は,非会員 の方も参加可能です(CPD1.5単位取得可).能登半島地震の際の地形変化など,最新情報を 得ることができます.ぜひ皆様お誘い合わせの上ご来臨くださいますようご案内申し上げます. 総会および講演会の詳細,参加申込フォーム,総会議案書,議決権行使書フォームなどは 下記をご覧ください.また,総会を欠席される関東支部会員の方には議決権行使書フォームか下記の委任状送付方法でご提出をお願いします.
日時:2024年4月20日(土)14:00-16:35(13:30から講演会受付開始)
場所:北とぴあ第2研修室.JR京浜東北線王子駅北口徒歩2分;東京メトロ南北線王子駅 5番出口直結;東京さくらトラム(都電荒川線)王子駅前徒歩5分.
<プログラム>
【講演会】14:00-15:30
共催:一般社団法人日本地質学会関東支部・一般社団法人関東地質調査業協会
タイトル「デジタル詳細地形データを用いた地表面変位計測で見る地震災害」
講師:向山 栄氏(国際航業株式会社 公共コンサルタント事業部)
講演要旨:2024年1月1日に発生した能登半島沖地震では,地殻変動などにより地形が大きく 変化する現象を目の当たりにしました.今回の講演では,地震などのイベント前後の地形モデル を画像化して地表面の変位を面的かつ定量的に計測する技術を紹介します.この手法は,精度 の高い位置情報を持つデジタル地形モデルから作成した数値地形画像のパターンマッチングに よってまず水平変位量を求め,さらに画素に与えられた標高値から求めた鉛直変位量と合成して, 3次元の移動ベクトルを求めるものです.この手法によれば,地震時の断層変位や地すべりによる 変位など,人工衛星の合成開口レーダを用いた画像解析では抽出しにくい比較的大きな変位量を 計測することができます.本講演では,2016年熊本地震や2024年能登半島地震などの際に,この 数値地形画像解析で計測した興味深い地形変化の事例を紹介します.
講演会資料:PDFファイルはこちらから(2024.4.8掲載,4.13差替)
講演会の定員:会場100名+オンライン100名(ハイブリッド形式).
参加費:無料 CPD単位:1.5単位取得可
参加申込方法:2024年度地質学会関東支部総会・講演会参加申込フォーム
(4月18日(木)17時締切):https://forms.gle/FnGHpc3rzG8ABZKp9
【支部総会】15:40-16:35
支部功労賞授与式と総会を開催します.
参加申込方法:上記の2024年度地質学会関東支部総会・講演会参加申込フォーム (4月18日(木)17時締切)https://forms.gle/FnGHpc3rzG8ABZKp9
総会議案書:PDFファイルはこちらから(4.13差替)
2024年度総会議決権行使書フォーム (4月18日(木)17時締切):https://forms.gle/GpZy7mYd2SCnDbah9
委任状送付方法:下記の3つの方法があります.
2024年度委任状フォーム(4月18日(木)17時締切):https://forms.gle/nNBQNuJiyr6ZD1AC7
郵送またはFAX:下記にお送りください(4月18日(木)必着). 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F 日本地質学会事務局気付 関東支部事務局 FAX:03-5823-1156
E-mailによる送付の場合:関東支部のメールアドレス(kanto[at]geosociety.jp)へ 下記の内容の委任状をご送付下さい(4月18日(木)17時締切) . (※[at]を@マークにして送信してください)
【全体プログラム】
13:30 受付・入室開始 (ハイブリッド形式)
14:00-15:20 講演会「デジタル詳細地形データを用いた地表面変位計測で見る地震災害」講師:向山 栄氏(国際航業株式会社 公共コンサルタント事業部)
15:20-15:30 質疑応答
15:30-15:40 休憩(講演会のみに参加の方はご退室)
15:40-16:35 支部功労賞授与式
関東支部総会
議長選出
議案審議 第1号議案 2023年度活動報告・決算報告
第2号議案 2024年度活動計画
第3号議案 2024年度予算案
第4号議案 幹事選挙結果報告
-----------------
関東支部総会委任状
2024年4月20日(土)開催の日本地質学会関東支部総会に出席できませんので,
当日一切の議決権を 君(又は,議長)に委任します(空欄の場合は議長とします).
日時 2024年 月 日
住 所:
会員氏名:
-----------------
問い合わせ先: 関東支部幹事長 加藤 潔(駒澤大学)
電話:090-1705-7516
Eメール:kiyoshi.katoh[at]gmail.com(※[at]を@マークにして送信してください)
2023年度の活動
お知らせ
(2024.1.15掲載 1/24更新)
アウトリーチ巡検 「安房鴨川海岸の地質・地形観察」のお知らせ
※定員に達しましたので,参加申し込み受付を終了しました(1/24現在)
日本地質学会関東支部では,多くの方々に,野外での観察を通して地学の面白さを実感し,地球科学に対する理解を深めていただきたいという主旨で,アウトリーチ巡検を実施しています.本年度は,千葉県安房鴨川の海岸沿いに露出している枕状溶岩や八岡海岸での各種礫の観察,鴨川漁港での変成岩の観察等を実施します.講師は千葉県立中央博物館の高橋直樹氏です.
主催:(一社)日本地質学会 関東支部
実施日:2024年2月18日(日)(予備日:3月3日(日))
対象:当該地域の岩石・地質・地形に興味のある方(日本地質学会会員でなくても可)
募集:20人(先着順) ※最少催行人数10人(達しない場合は中止です)
申込期間:1月17日(水)〜2月2日(金)17:00終了 ※定員に達した時点で終了
※定員に達しましたので,参加申し込み受付を終了しました(1/24現在)
講師:高橋直樹氏(千葉県立中央博物館)
集合:JR内房線太海駅 改札口10:00(7:18新宿駅発わかしお号が便利.千葉駅8:10発,蘇我駅8:16発 安房鴨川駅で各駅停車に乗り換え1駅)
解散:JR内房線太海駅 16:00前後(予定)
持ち物:飲み水,昼食,ルーペ,軍手,ハンマー等(地図は主催者で用意)
予定コース(天候などにより変更になることがあります):全行程徒歩です.
鴨川青年の家:枕状溶岩,鴨川松島遠望
八岡海岸:地すべり,嶺岡帯構成岩石の礫(オフィオライト構成岩石が揃う)
鴨川漁港:変成岩,ドレライト,凝灰岩
参加費用:2,000円(保険代,資料代等.当日集金) ※学会規定のキャンセル料が発生します.参加確定後〜巡検3日前まで50%,巡検2日前以降100%になります.ご承知おきください.
<新型コロナ対策について>
参加にあたってはワクチン接種をお勧めします.
当日朝の体温が 37.5℃以上の場合は参加はお控えください.
巡検当日の朝に咳や鼻水,倦怠感,嗅覚異常など感染が疑われる症状がある場合は参加はお控え下さい.
巡検中のマスク着用は日本地質学会の規定に則ります.
参加者から感染者が発生した場合等は必要に応じて保健所等の公的機関へ緊急連絡先の提供をさせて頂く場合があります.
新型コロナウイルスの感染状況により巡検が中止になる可能性があります.
<申込みについて>
件名は見落とし防止のため「2月18日アウトリーチ巡検申込み」として下さい.
氏名,ふりがな,性別,2月18日時点での年齢(←保険申込みに必要なため),携帯番号,メールアドレス,所属をお知らせください.申込者全員に,受付結果についてのメールを返信します.
実施確定後,参加者には改めて注意事項等をメールで送ります.
担当:関東支部幹事 米澤正弘(よねざわ まさひろ)
メール my-yonezawa[at]y6.dion.ne.jp(※[at]を@マークにして送信してください)
申込み・問い合わせ:メールにて上記担当者まで (担当幹事:河尻清和・米澤正弘)
お知らせ
(2024.1.5掲載)
2024年度関東支部幹事選出のお知らせ
支部幹事の改選に伴い,支部幹事立候補者の受付を行います.幹事の定数は20名で,任期は2024年関東支部総会終了後〜2026年関東支部総会までとなります.立候補する支部会員は,氏名・所属・連絡先を下記に届け出てください.立候補者多数の場合は,支部総会参加者で投票を行います.
立候補期間:2024年3月1日(金)〜3月11日(月)17時締切
受付先:宛先は日本地質学会関東支部選挙管理委員会とし,メール・郵送・FAXで受け付けます.
メール:kanto[at]geosociety.jp 見出しは「関東支部選挙」でお願いします.(※[at]を@マークにして送信してください)
郵送:〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F
FAX :03-5823-1156
日本地質学会関東支部選挙管理委員会
委員長 入野 寛彦
委員 亀高 正男
河村 知徳
お知らせ
(2023.11.6掲載,11.29,12.4更新)
県の石―千葉の岩石・鉱物・化石― 講演会のお知らせ(第2報)
日本地質学会関東支部では,日本地質学会が決定した「県の石」のうち関東地方について普及のための講演会を実施しています。今回は千葉での開催です。現在決まっていることを広報します。詳細は随時関東支部のWebサイトなどで連絡させていただきます。
主催:(一社)日本地質学会関東支部
日時:2024年1月14日(日)13:00〜16:00
場所:千葉県立中央博物館講堂(Zoomを使用したハイブリッド形式)
対象:日本地質学会会員および一般の方(オンラインは会員優先)
定員:会場100名+Zoom(オンライン)100名
CPD:2.5単位取得可
申込期間:2023年12月8日(金)〜12月26日(火)17:00締切
申込方法:日本地質学会関東支部のWebサイトから申込フォームにて (締め切りました)
参加費:無料(オンラインでご参加の方).資料代300円(会場にお越しの方)
講演要旨:こちらから(PDF)
プログラム:講演者1人45分、質疑応答5〜10分、休憩5〜10分
13:00〜13:05 主催者挨拶
13:05〜13:50 県の岩石 『明治の近代化を支えた石材—房州石』講師:千葉県立中央博物館 環境教育研究科 上席研究員 高橋 直樹 氏
13:50〜14:05 質疑応答・休憩
14:05〜14:50 県の鉱物 『天然ガスを含む鉱物一千葉石』講師:国立科学博物館 研究主幹 門馬 綱一 氏
14:50〜15:05 質疑応答・休憩
15:05〜15:50 県の化石 『下総層群木下層の堆積環境と“木下貝層”の貝化石について』講師:千葉県立中央博物館 教育普及課長 伊左治 鎭司 氏
15:50〜15:55 質疑応答
15:55〜16:00 閉会の挨拶
問い合わせ先:日本地質学会関東支部幹事 米澤正弘,
メールアドレス my-yonezawa[at]y6.dion.ne.jp(※[at]を@マークにして送信してください)
お知らせ
(2023.11.1掲載)
2023年度関東支部功労賞募集のお知らせ
日本地質学会関東支部では,毎年,支部の顕彰制度に基づき,支部活動や地質学を通して社会貢献された個人・団体を顕彰しています.つきましては,下記の要領で支部会員からの推薦を募集します.
関東支部功労賞審査委員会委員長
山崎晴雄
対象者:支部活動や地質学を通して広く社会貢献をされた関東支部内に在住の個人・団体(*社会貢献や活動の評価においては,必ずしも学問的な成果を問うものではありません.)
公募期間:2023年12月18日〜2024年1月19日
選考期間:2024年1月20日〜2024年1月31日
審査結果報告:NEWS誌・関東支部総会で報告します.
推薦方法:対象者氏名,推薦者氏名,推薦理由(400字から800字程度)を記述の上,メールの件名を「関東支部功労賞推薦」として,wordかPDFファイルをメールに添付して,下記の受付担当のメールアドレスへお送りください.
受付担当:関東支部幹事長 加藤 潔(駒澤大学) E-mail:kiyoshi.katoh[at]gmail.com(※[at]を@マークにして送信してください)
お知らせ
関東地震100年関連行事 震生湖巡検のお知らせ
日本地質学会関東支部では,1923年関東地震から100年を機に,地質災害としての記憶を新たにすることを企図し,日本地質学会地質災害委員会と協力して講演会(9月30日オンラインで開催)と震生湖巡検を企画しました.震生湖は,1923年関東地震によって引き起こされた市木沢上流部の斜面崩壊で生じた堰止湖で,崩壊跡の地形も大きく改変されることなく残っています.震生湖巡検では,震生湖周辺の地形と崩壊の原因と推定される箱根東京テフラを観察します.
主催:日本地質学会関東支部・日本地質学会地質災害委員会
日程:2023年12月2日(土)10:00–15:00頃
観察場所:震生湖周辺および市木沢の中(神奈川県秦野市今泉)
集合:小田急線秦野駅改札口10:00.その後、北口5番乗場よりバス秦野18系統(畑中経由渋沢駅行)10:22発に乗り 白笹神社入口バス停下車(210円)
解散:白笹神社入口15:30頃(15:51秦野駅行210円)
対象:会員および一般の方(会員優先)
定員:20名
講師:
深田地質研究所 千木良雅弘 代表理事 理事長
箱根ジオパーク推進室 笠間友博 専門員
会費:2000円(現地集金)巡検案内書:作成予定
申込期間:11月3日(金)〜11月17日(金)17:00締切り(先着順)
申込はこちらから:https://forms.gle/CzhaByn4LG3pQE3p7
CPD単位:4単位
注意事項:ルートは健脚向け小雨決行です.連絡はメールで行います.
持ち物:弁当,飲み水,長靴.
※マスクについては地質学会の方針に従います.https://geosociety.jp/news/n160.html
お問合せ先:関東支部幹事
小田原 啓(神奈川県温泉地学研究所;odawara[at]onken.odawara.kanagawa.jp)
笠間友博(箱根ジオパーク;kasama[at]mh.scn-net.ne.jp)
※[at]を@マークにして下さい.
お知らせ
関東地震100年関連行事 講演会「関東地震から100年」のお知らせ
2023.7.31掲載
日本地質学会関東支部は,1923年関東地震から100年を機に,地質災害としての記憶を新たにすることを企図し,日本地質学会地質災害委員会と協力して,講演会と野外巡検を企画しています.講演会はオンライン形式で開催し,2名の講師にお話しいただきます.テーマは「1923年関東地震で発生した土砂災害」と「歴史地震の発生履歴から見た大地震発生の傾向分析」です.
主催:日本地質学会関東支部・日本地質学会地質災害委員会
後援:一般社団法人 関東地質調査業協会
日程:2023年9月30日(土)13:30–16:10 (入室は13:00から)
対象:地質学会会員・関東協会会員企業に所属する社員および一般の方(オンライン形式;会員優先)
定員:150名を上限とする
CPD単位:2.5取得可
申込期間:9月1日(金)〜9月22日(金)17:00締切
申込方法:専用申込フォームよりお申し込みください 締め切りました
お問合せ先:関東支部幹事 笠間友博(箱根ジオパーク)
メール:kasama[at]mh.scn-net.ne.jp ※[at]を@マークにして下さい.
プログラム
13:30〜13:33 開会 司会挨拶・連絡
13:33〜13:35 開会の挨拶 日本地質学会地質災害委員会委員長 松田達生
13:35〜14:35 『関東大震災と土砂災害』講師:井上公夫 氏(一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構)
【概要】演者は中央防災会議・災害教訓の継承に関する専門調査会(2006)の関東地震小委員会で,土砂災害地点の調査と分布状況の調査を行った.これらの調査結果をまとめて,拙著『関東大震災と土砂災害』を10年前の9月1日に発刊した.関東地震による激震や火災によって,10万5000人もの死者・行方不明者となったが,土砂災害のみでも1000人以上の犠牲者となっている.震源域が神奈川県から房総半島南部地域であったため,神奈川県を中心に激甚な土砂災害が多発した.土砂災害調査については現在も調査を継続しており,①横浜(プールの逃避行ルートを歩く),②横須賀・浦賀,③秦野・震生湖,④小田原市(根府川・白糸川流域)の4地域の現地見学会を行った,これらの結果については,いさぼうネット「歴史的大規模土砂災害地点を歩く」のコラム37,38,39,40,41,42,74,82,83,84などで公表している.ここでは,関東地震による土砂災害の分布状況と地形・地質特性の概要について説明する.
14:35〜14:45 質疑応答
14:45〜14:55 休憩
14:55〜15:55 『将来の関東地震・南海トラフ地震と地震西進系列』講師:石渡 明 氏(元地質学会会長・原子力規制委員会)
【概要】河角(1970)は関東大地震69±13年周期説を唱えたが,既に大正関東地震から100年経過した.南海トラフ地震は684年以来9回の記録があり周期性が指摘されるが,それらの間隔は90〜262(平均158)年と一定せず,最近3回(宝永,安政,昭和)の間隔は147年及び90年と短い.日本付近の大地震の時空分布を概観すると,北海道・東北地方太平洋沖から関東を経て南海トラフ,琉球・台湾へと大地震が西進する傾向が認められる(石渡, 2019).最近の例は1896明治三陸地震津波,1923大正関東地震津波,1944・46昭和南海トラフ地震津波に代表され,同様の西進系列は1854安政,1707宝永,1498明応,887仁和の南海トラフ地震にも認められる.2011東北地方太平洋沖地震は最新の西進系列の東の代表であり,過去5回の西進系列の東北地震と南海地震の間隔は18〜61年なので,次の南海地震は2029〜72年の間に来る(そして,その前に関東地震が来る)ことが予想される.
15:55〜16:05 質疑応答
16:05〜16:07 閉会の挨拶 関東支部支部長 向山 栄
16:07〜16:10 閉会 連絡
お知らせ
講演会「県の石−埼玉の岩石・鉱物・化石−」のお知らせ
2023.5.11掲載 6.15更新
オンライン参加は定員に到達しました。
現地参加は,6月22日(木)17:00まで申込み受付を延長します
(定員に到達次第終了)。
日本地質学会は,全国47都道府県について,その県に特徴的に産出する,あるいは発見された岩石・鉱物・化石をそれぞれの「県の石」として選定し,2016年5月10日(地質の日)に発表しました.本講演会では,埼玉県の「県の石」を紹介します.今回は現地(埼玉県立自然の博物館講堂)とオンラインのハイブリッド方式で行います.なお現地のみ,講演会後に埼玉県の岩石,鉱物,化石の見学(展示室および野外)を行います.
主催:日本地質学会関東支部 共催:埼玉県立自然の博物館
日時:令和5年7月8日(土)13:00〜16:00,現地開場12:00,オンライン入場12:30から
現地会場:埼玉県立自然の博物館(埼玉県秩父郡長瀞町)
対象:会員及び非会員 小学生3年生以上(内容は大人向けです)
定員:現地60名,オンライン40名(先着順)
参加費:無料(要事前申込み) ただし現地参加の場合は観覧料(一般200円,高校生・大学生100円,中学生以下無料) および保険料(100円)がかかります.当日現金でお支払いください.
CPD:2.5単位(現地),1.5単位(オンライン)
申込期間:令和5年5月23日(火)〜6月16日(金)17:00まで
オンライン参加は定員に到達しました。現地参加は6月22日(木)17:00まで申込み受付を延長します(定員に到達次第終了)。
申込方法:
現地参加用の申込フォーム https://forms.gle/8JKeYFmiyCJujmta7
※オンラインの参加者は定員に達しました
注意事項:
駐車場に限りがあるため,現地参加はなるべく公共交通機関をご利用ください.
野外見学は小雨決行,雨天時は展示見学に変更します.飲み水,帽子をご持参ください.岩石の採集は出来ません.濡れた岩盤は滑るので歩きやすい(滑りにくい)服装でお願いします.
マスクについては地質学会の方針に従ってください(https://geosociety.jp/news/n160.html)
お問い合わせ先:関東支部幹事 笠間友博(箱根ジオパーク)
メール:kasama[at]mh.scn-net.ne.jp ※[at]を@マークにして下さい
プログラム
13:00〜13:02 開会,支部長挨拶
13:02〜13:50 県の岩石と鉱物 『秩父青石の利用と宮澤賢治・保阪嘉内が歌に詠んだ岩石鉱物』講師:元埼玉県立自然の博物館長 本間岳史 氏
概要:埼玉県の県の石の「岩石」に選ばれた「片岩」と「鉱物」に選ばれた「スチルプノメレン」は,関東山地の三波川帯中に産し,いずれも埼玉県秩父郡長瀞町の荒川河床で観察することができます.長瀞の岩畳に代表される片岩は,高圧下で再結晶鉱物などが面状配列してできた「片理」をもち,褶曲・ブーディン・キンクバンド・断層・雁行脈などの変形小構造を各所で見ることができます.片岩は,原岩(変成以前の岩石)の違いによりさまざまな種類があり,緑泥石や緑簾石を生じた緑色片岩は「秩父青石」と呼ばれ,石器・古墳の石室・中世の板碑・石垣などの石材として利用されてきました.自然の博物館下の荒川河床には,褐色と白色の縞模様が虎の毛皮のように見える「虎岩」があります.虎岩は,かつては脆雲母片岩とか黒雲母片岩といわれてきましたが,1944(昭和19)年の小島丈児博士により,スチルプノメレン片岩であることが判明.1916(大正5)年に巡検で訪れた宮沢賢治が詠んだ『つくづくと「粋なもやうの博多帯」荒川ぎしの片岩のいろ』という歌は,虎岩をモチーフにしたと考えられ,翌年の巡検で秩父を訪れた保阪嘉内は,多数の岩石・鉱物を歌に詠みました.
13:50〜13:55 質疑応答
13:55〜14:35 県の化石 『県立自然の博物館の世界一のパレオパラドキシア化石コレクションとその研究』 講師:埼玉県立川の博物館 主任学芸員 北川博道 氏
概要:“パレオパラドキシア”化石は,本邦中新世を代表する大型脊椎動物化石である.世界から60標本程度しか知られていないこの化石標本の約3分の1は,埼玉県からの産出である.埼玉県の主な産出地は秩父地域と東松山市葛袋地域の2地域で,秩父地域に広がる古秩父湾堆積層からは大野原標本と般若標本の全身骨格2体を含む8標本が,葛袋地区からは臼歯化石を中心に多くの断片的な化石の産出が知られている.秩父産標本を中心に構築された県立自然の博物館のパレオパラドキシア化石標本コレクションは,その質・量ともに,世界一といえる.しかしながら,こと“パレオパラドキシア”の分類等に関しては,タイプ標本が第二次世界大戦時に戦火により失われたこともあり,非常に混乱している.“パレオパラドキシア”化石研究の課題と,演者が行ってきた秩父産の全身骨格の比較や産状比較などの研究を紹介する.
14:35〜14:40 質疑応答
14:40〜14:50 休憩
14:50〜16:00 現地見学 展示見学/野外虎岩見学 見学後解散終了
お知らせ
サイエンスカフェ「リアル!南極フィールドワーク!」
2023.4.24掲載
開催日:2023年5月14日(日)15:00–16:45
場所:ベルギービール アグリオ(京王線下高井戸駅北口から徒歩約1分)
講師:菅沼悠介氏(国立極地研究所)
ファシリテータ:岡山悠子氏(科博SCA)
内容:ペンギン・オーロラ・昭和基地・越冬隊,これらのワードは出てきません.南極地域観測隊に7回参加し南極を最もよく知る気鋭の研究者に,リアルな現地の様子,気候変動や氷床融解に関する最新の研究成果をご紹介いただきます.絶景の中での野外調査の様子にも乞うご期待.
参加対象者:どなたでもご参加いただけます(地質学会の会員/非会員は問いません)
募集人数:20名(先着順)
申込方法:下記サイトから申し込んでください(定員に達しましたので,受付を終了しました)
https://sites.google.com/view/cafeantarctica/
参加費:1500円+1ドリンク(入場料とドリンクオーダーが必要です)
問い合わせ先:geo.soc.sci.cafe[at]gmail.com ※[at]を@マークにして送信してください
日本地質学会関東支部サイエンスカフェ担当:金丸龍夫,小松原純子
お知らせ
学生・初級者向け「地質断面図」の書き方講座のお知らせ
―布良海岸巡検―
2023.4.18掲載
日本地質学会関東支部では、一昨年より標記の講座を実施しています。
館山市布良海岸付近をフィールドに、野外地質調査を実施します。学生・初級者向けです。
地層・堆積岩の見方を学び、測定した走向・傾斜をもとに地質断面図を描けるようにする講座です。
野外地質調査に不慣れな方、堆積岩の見方を勉強したい方、大歓迎です。
期日・場所:
2023年5月27日(土) 10:30〜14:30 千葉県館山市布良海岸付近で野外調査
2023年5月28日(日) 10:00〜13:00 JR総武線船橋駅〜千葉駅付近(場所未定)で地質断面図作成(室内作業)
募集人数:最大6名 学生優先、余裕がある場合学生以外も受け付けます(希望者は7.0 CPD単位取得可能)
費用:学生一人6,000円、一般一人10,000円(最寄り駅から館山駅・千葉駅までの運賃は含まず)
申込期間:2023年5月7日(日)〜5月19日(金) 定員になり次第締め切り
申込締切:5月23日(火)締切延長しました
申込方法:下記の申込先に、氏名・ふりがな・所属・学年・年齢(保険に必要)・連絡先(携帯番号)を明記しメールで送ってください。
申込者には受け付けメールを返信します。申込み後3日経っても返信がない場合は問い合わせてください。
問い合わせ・申込先:米澤正弘 my-yonezawa [at] y6.dion.ne.jp ※[at]を@マークにして送信してください
学生優先です。学生以外の方はキャンセル待ち状態の扱いとなります。5月20日(土)に可否を連絡します。
その他:
詳細については参加人数確定後ご本人宛にメールで連絡します。
事前課題を出す予定です。期限までにご提出ください。
キャンセルの場合は速やかにご連絡ください。キャンセル料―7日前〜前日:50%、当日:100%
荒天が予想される場合の中止判断は前日18:00までに行い、電話で各参加者に連絡します。
※コロナウィルスの感染拡大状況によっては、中止・延期することがあります。
担当:日本地質学会関東支部幹事 米澤正弘、加藤 潔、方違重治
お知らせ
2023年度総会・講演会開催のお知らせ
2023.2.7掲載 3.17更新
関東支部では,下記のように支部総会及び講演会を開催いたします.今年度は昨年度に引き続き「会場+オンラインのハイブリッド方式」で行います. 総会に先立って行われる講演会(共催:関東地質調査業協会)は,非会員の方も参加可能で,事前申し込みでCPD1.5単位を取得可能です.
日時:2023年4月9日(日)14:00〜16:45
場所:大田区産業プラザPiO 3階 特別会議室(京急蒲田駅前)
プログラム:13:30受付開始
①14:00〜15:40 講演会(CPD単位取得可)
講師:宇根 寛氏(元国土地理院地理地殻活動研究センター長,中央開発(株)技術顧問)
演題:「Web地図を活かして災害リスクを理解する」
概要:近年頻発する災害の中で,ハザードマップが注目されている.ハザードマップはきわめて有用な情報であるが,自然災害は,ハザードマップが想定した通りに発生するとは限らず,場合によっては想定を上回る自然現象により大きな被害が発生することもある.災害のリスクを理解するためには,土地がどのように成り立ってきたのかを把握することが重要である.本報告では,このような情報をWeb地図からどのように読み取るかを考えたい.
②15:50〜16:45 関東支部総会
3月7日現在,新型コロナ感染拡大状況により,会場の定員には人数制限もあるため,現地会場ではできるだけ少数の出席者を見込んでおります.
総会・講演会への参加はできるだけオンラインでの出席,あるいは委任状または議決権行使書による書面での総会出席をお願いいたします.
なお現地会場での参加のご希望があれば事前にお申し出を受け付けます.
支部功労賞授与式
議長選出
2022年度 活動報告(第1号議案)・決算報告(第2号議案)
2023年度 活動方針(第3号議案)・予算報告(第4号議案)
◎総会・講演会参加申し込みフォームはこちら:4月5日(水)17時締切
https://forms.gle/wwiuejM2pGrfXZ7K6
◎2023年度総会議決権行使書はこちら:4月5日(水)17時締切
https://forms.gle/LJjJEHxS3MaGiyop7
◎議案書(PDF)はこちら(※2023/4/7更新)
◎委任状
委任状送付方法:
〇郵送またはFAXの場合 下記にお送りください.4月6日(木)必着です.
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F
日本地質学会事務局気付 関東支部事務局 FAX:03-5823-1156
○E-mail送付の場合 メールによる委任状の締め切りは4月7日(金)午後6時までです.
関東支部のメールアドレス(kanto[at]geosociety.jp)へ委任状をご返信下さい .
※[at]を@マークにして送信してください
○WEBフォームからの場合 下記よりご入力ください
https://forms.gle/GcLQVDsPJwQWLzej9
--------------------------------------------
<関東支部総会委任状>
2023年4月9日(日)開催の日本地質学会関東支部総会に出席できませんので,
当日一切の議決権を 君(又は,議長)に委任します(空欄の場合は議長とします).
日時:2023年 月 日
住所:
会員氏名:
--------------------------------------------
問い合わせ先:
関東支部幹事長 笠間友博(箱根町企画課箱根ジオパーク推進室)
電話 0460-85-9560
Eメール kanto[at]geosociety.jp ※[at]を@マークにして送信してください
2022年度の活動
お知らせ
アウトリーチ巡検「相模原市の相模野台地の地形・地質観察」
2022.12.13掲載
日本地質学会関東支部では,多くの方々に,野外での観察を通して地学の面白さを実感し,地球科学に対する理解を深めていただきたいという主旨で,アウトリーチ巡検を実施しています.本年度は,相模川沿いに河成段丘が発達している相模野台地の地形と段丘を構成する地層を観察します.講師は相模原市立博物館の河尻清和氏です.
主催:(一社)日本地質学会関東支部
実施日:2023年2月19日(日)(予備日:2月26日(日))
対象:当該地域の地形・地質に興味のある方(日本地質学会会員でなくても可)
募集:30人(先着順) 最少催行人数15人(達しない場合は中止です)
申込期間:2023年1月16日(月)〜2月5日(日)*定員に達した時点で終了(申込受付は締め切りました)
申込方法:メールにて下記担当者までお申し込みください(下記参照).
講師:河尻清和(相模原市立博物館)
集合:神奈川中央交通 女子美術大学前バス停 10:00(JR横浜線 古淵駅,小田急小田原線 相模大野駅よりバス)
解散:JR相模線 原当麻駅15:30前後(予定)
予定コース(天候などにより変更になることがあります):全行程徒歩です
①相模原麻溝公園の相模原面上の谷地形⇒②大正坂の相模原段丘の関東ローム層と広域テフラ⇒③当麻東原公園から段丘地形遠望・昼食⇒④あずま坂の田名原段丘堆積物⇒⑤当麻山公園の陽原段丘礫層と湧水⇒⑥子の神(ねのかみ)坂の田名原段丘堆積物と湧水⇒⑦依知礫層⇒原当麻駅(解散)
参加費用:1,000円(保険代,資料代等.当日集金)
※学会規定のキャンセル料が発生します.参加確定後〜巡検3日前まで50%,巡検2日前以降100%になります.ご承知おきください.
<新型コロナ対策について>
参加にあたってはワクチン接種をお勧めします.
当日朝の体温が 37.5℃以上の場合は参加はお控えください.
巡検当日の朝に咳や鼻水,倦怠感,嗅覚異常など感染が疑われる症状がある場合は参加はお控え下さい.
巡検中はマスク着用をお願いします.
参加者から感染者が発生した場合等は必要に応じて保健所等の公的機関へ緊急連絡先の提供をさせて頂く場合があります.
新型コロナウイルスの感染状況により巡検が中止になる可能性があります.
申込・問い合わせ:メールにて下記担当者まで(申込受付は締め切りました)
件名は見落とし防止のため「2月19日アウトリーチ巡検申込み」として下さい.
氏名,ふりがな,性別,2月19日時点での年齢←保険申込みに必要なため,携帯番号,メールアドレス,所属をお知らせください.申込者全員に,受付結果についてのメールを返信します.
担当:関東支部幹事 米澤正弘(よねざわ まさひろ)
メール my-yonezawa[at]y6.dion.ne.jp
(担当幹事:河尻清和・米澤正弘)
お知らせ
関東支部功労賞募集
2022.11.2掲載
関東支部功労賞募集 日本地質学会関東支部では,支部の顕彰制度に基づき2022年度も支部活動や地質学を通して社会貢献された個人・団体を関東支部として顕彰いたします. つきましては,下記の要領で支部会員からの推薦を募集します.
対象者:支部活動や地質学を通して広く社会貢献をされた関東支部内に在住の個人・団体
※社会貢献や活動の評価においては,必ずしも学問的な成果を問うものではありません.
公募期間:2022年12月19日〜2023年1月21日
選考期間:2023年1月23日〜2023年1月31日
関東支部功労賞審査委員会(委員長:山崎晴雄 前支部長)を設置
審査結果報告:NEWS誌、関東支部総会
推薦方法:対象者氏名,推薦者氏名,推薦理由(400字程度)を記入の上,件名を「関東支部功労賞推薦」としてメールにて下記へお送りください.
推薦受付:箱根町企画課ジオパーク事務局 笠間友博
E-mail: kasama[atマーク]mh.scn-net.ne.jp 電話:0460-85-9560
これまでの関東支部功労賞受賞者(順不同敬称略)
2010年度 清水惠助
2011年度 府川宗雄,かわさき宙と緑の科学館
2012年度 神戸信和,松島義章,加瀬靖之,下仁田自然学校
2013年度 埼玉県立自然の博物館,早稲田大学高等学院理科部地学班
2014年度 千葉達朗,横須賀市立自然・人文博物館
2015年度 千葉県立中央博物館,神奈川県大井町・株式会社古川
2016年度 門田真人,遠藤 毅,栃木県立博物館
2017年度 故山本高司,中山俊雄
2018年度 ミュージアムパーク茨城県立自然博物館,本間岳史
2019年度 東京大学大学院千葉演習林,相模原市立博物館
2020年度 群馬県立自然史博物館
2021年度 神奈川県立生命の星・地球博物館
お知らせ
オンライン講演会「県の石 茨城県」のお知らせ
2022.11.2掲載 12.12更新
日本地質学会は,全国47都道府県について,その県に特徴的に産出する,あるいは発見された岩石・鉱物・化石をそれぞれの「県の石」として選定し,2016年5月10日(地質の日)に発表しました.2022年春に関東支部は,第1弾として,オンライン講演会「県の石 神奈川県」を開催しました.第2弾は茨城県に焦点を当てたいと思います.茨城県の「県の石」と「筑波山地域ジオパーク」のさらなる理解と普及を目的として,オンライン講演会を開催します.是非ご参加ください.
主催:(一社)日本地質学会関東支部
日時:2023年1月22日(日)13:00〜16:05(入室は12:30から)
対象:会員および非会員
CPD:3単位
参加費無料(要事前申込)
申し込み期間:2022年12月19日(月)〜2023年1月11日(水)まで
申し込み先:[専用申込フォーム]からお申し込みください.
募集人数:200人
Zoomによる同時双方向方式(講演内容の録画記録は禁止)
お問い合わせ先:加藤 潔(駒澤大学)メールアドレス:kkato@komazawa-u.ac.jp
プログラム
13:00〜13:05 支部長挨拶
13:05〜13:50 『茨城県の岩石と鉱物:花崗岩とリチア電気石を中心に』ミュージアムパーク茨城県自然博物館 小池 渉氏 【講演要旨】八溝山地南部には,白亜紀後期頃にマグマが貫入してできた花崗岩類などが,関東平野に突出した筑波山塊の主要部を構成している.この花崗岩は稲田・真壁地域では古くから御影石として採掘され,地域に根ざした文化・産業が育まれてきたことから,茨城県の岩石に指定されている.また,茨城県北部の妙見山ではリチウムペグマタイトが露出している.リチア電気石はその主要鉱物の1つで,紅,青,緑など多様な色をした柱状結晶として産しており,茨城県の鉱物に指定されている.
13:50〜14:05 質疑応答・休憩
14:05〜14:50 『茨城県の化石:ここまでわかった古代ゾウステゴロフォドン』神栖市歴史民俗資料館 国府田良樹氏 【講演要旨】ステゴロフォドンは,新生代中新世〜鮮新世の南アジアから日本に生息した,鈍頭歯型の臼歯を特徴とした長鼻類である.これまで産出した化石は臼歯や部分的な下顎骨などが多かったが, 2011年に茨城県常陸大宮市で産出した化石は,保存状態のよい頭蓋化石であった.本発表では,これまで発見されたステゴロフォドン化石について紹介するとともに,現生のゾウと比較をすることでステゴロフォドンの頭蓋や臼歯の特徴を明らかにする.
14:50〜15:05 質疑応答・休憩
15:05〜15:50 『筑波山地域ジオパークの楽しみ方』 筑波山地域ジオパーク推進協議会 冨永紘平氏 【講演要旨】ジオパークで紹介するものは,岩石や地層だけではありません.その地域の人々の生活や自然と大地の関わりに気づくことができることが,ジオパークの醍醐味といえます.例えばその地域特有の食べ物や伝統産業なども,その土地の地質・地形条件を反映していることがあるのです.本講演では,茨城県南部の筑波山地域ジオパークを対象に,地域の農水産物や工芸品などと大地の関わり及びジオパークの役割をご紹介します.
15:50〜16:05 質疑応答
幹事長挨拶(終了)
お知らせ
学生・初級者向け 「地質断面図」の書き方講座 ―布良海岸巡検―
2022.5.2
日本地質学会関東支部では,昨年より標記の講座を実施しています. 館山市布良海岸付近をフィールドに,野外地質調査を実施します。学生・初級者向けです. 地層・堆積岩の見方を学び,測定した走向・傾斜をもとに地質断面図を描けるようにする講座です. 野外地質調査に不慣れな方,堆積岩の見方を勉強したい方、大歓迎です.
期日・場所:
2022年6月4日(土) 11:00〜14:30―千葉県館山市布良海岸付近で野外調査
2022年6月5日(日) 10:00〜13:00―JR総武線船橋駅〜千葉駅付近(場所未定)で地質断面図作成(室内作業)
募集人数:最大6名―学生優先,余裕がある場合学生以外も受け付けます(希望者は7.0CPD単位取得可能)
費用:学生一人6,000円、一般一人10,000円(最寄り駅から館山駅・千葉駅までの運賃は含まず)
申込み期間:2022年5月8日(日)〜5月20日(金)定員になり次第締め切り
申込み方法:メールでのみ受付、氏名・所属・学年・年齢(保険に必要)・連絡先(携帯番号)を明記のこと
申込者には必ず受け付けメールを送信します.申込み後3日経っても返信がない場合は問い合わせてください.
お問い合わせ・申込先 米澤正弘,
アドレスは my-yonezawa@y6.dion.ne.jp
学生優先です.学生以外の方はキャンセル待ち状態の扱いとなります.5月21日(土)に可否を連絡します.
その他:
詳細については参加人数確定後ご本人宛にメールで連絡します.
事前課題を出す予定です。期限までにご提出ください.
キャンセルの場合は速やかにご連絡ください.キャンセル料―7日前〜前日:50%、当日:100%
荒天が予想される場合の中止判断は前日18:00までに行い,電話で各人に連絡します.
※コロナウィルスの感染拡大状況によっては,中止・延期することがあります.
担当:日本地質学会関東支部幹事 米澤正弘、加藤 潔、方違重治
お知らせ
2022年度総会・講演会開催のお知らせ(第二報)
2022.3.14,4.5更新
関東支部では,下記のように支部総会及び講演会を開催いたします.今回は事前申込制の「会場+オンラインのハイブリッド方式」で行います. 講演会は非会員の方も受講可能で, CPD1.5単位取得可能です.
日時:2022年4月17日(日)14:00〜16:45
場所:大田区産業プラザPiO 3階 特別会議室(大田区南蒲田1丁目20-20,京急蒲田駅前)
プログラム:
13:30 受付開始
14:00〜15:40 講演会(CPD単位取得可)
講師:中澤 努氏(産総研)「首都圏の浅部地盤の地質層序と地盤震動特性」
要旨:近年,首都圏の地下浅部の層序が明らかにされつつある.またそれに基づき地下浅部の3次元地質モデルの構築が試みられている.これまで首都圏の地震動予測等に地下浅部の地質の情報はほとんど反映されなかったが,地質層序に基づく地質モデルが構築されることで,地質と地盤震動特性を紐付けすることが可能となってきた.ここでは常時微動観測で知ることのできる首都圏の地盤震動特性,特にピーク周波数と地質層序の対応関係について,いくつかの例を挙げて論じる.
15:50〜16:45 関東支部総会
*関東支部会員の方で総会に欠席される方は委任状をお願いします.
委任状送付方法:webフォーム、郵送、FAXのいずれかの手段でお送りください。
○WEBフォームの場合(4月15日(金)18時締切)
https://forms.gle/Z8m8WweHfFCAXWeAA
〇郵送またはFAXの場合(4月14日(木)必着締切)
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F
日本地質学会事務局気付 関東支部事務局
FAX:03-5823-1156
--------------------------------------------
<関東支部総会委任状>
2022 年4月17日(日)開催の日本地質学会関東支部総会に出席できませんので,
当日一切の議決権を 君(又は,議長)に委任します(空欄の場合は議長とします).
日時:2022年 月 日
住所:
会員氏名:
--------------------------------------------
問い合わせ先:
関東支部幹事長 笠間友博(箱根町企画課箱根ジオパーク推進室)
電話 0460-85-9560
Eメール geo-museum[at]town.hakone.kanagawa.jp
3月7日現在,新型コロナ感染拡大状況により,会場の定員には人数制限もあるため,現地会場ではできるだけ少数の出席者を見込んでおります.
総会・講演会への参加はできるだけオンラインでの出席,あるいは委任状または議決権行使書による書面での総会出席をお願いいたします.
なお現地会場での参加のご希望があれば事前にお申し出を受け付けます.
支部功労賞授与式
議長選出
支部規約改正(第1号議案)
2021年度 活動報告(第2号議案)・会計報告(第3号議案)
支部役員選任(候補者の選出が選挙の場合は総会参加者で投票)
2022年度 活動方針(第4号議案)・予算報告(第5号議案)
総会・講演会参加申し込みフォームはこちらから
議決権行使書のフォームはこちら
議案書(PDF)はこちら ※2022/4/7確定版掲載
2021年度の活動
お知らせ
サイエンスカフェ「おうちで楽しむ陸と海の火山紀行」開催のお知らせ
日本地質学会関東支部では, サイエンスカフェ「おうちで楽しむ陸と海の火山紀行」を開催します。 Twitterを中心として、火山や地質の情報を積極的に発信する池上郁彦さん (タスマニア大)をお迎えして、おうちPCで世界中の陸と海の火山を旅する 方法を紹介します。福徳岡ノ場噴火の情報など、池上さんが収集、再発信 した情報を目にした方も多いはず。3Dデジタル地図の作成など地形データ の可視化、噴火情報の収集と拡散など、ネットとデータを駆使した火山の 楽しみ方を体験してください。池上さんが創るオリジナル地形表現と共に 陸と海の火山を旅しましょう。
開催日時:2022年3月21日(月・祝)15:00-16:30
開催方法:Zoomによる双方向オンライン
ゲストスピーカー:池上郁彦さん(タスマニア大学)
ファシリテータ:岡山悠子さん(科博SCA)
対象:会員および非会員(どなたでもお申し込みいただけます)
参加費:無料 定員:30名(先着順)
お申込み・詳細は、下記サイトをご参照ください。
https://sites.google.com/view/ouchivolcano/
お知らせ
2022年度関東支部幹事選出のお知らせ
支部幹事の改選に伴い,支部幹事立候補者の受付を行います.幹事の定数は20名で,任期は2022年関東支部総会終了後(無投票の場合,選挙の場合は選挙終了後)から2024年関東支部総会までとなります.立候補者多数の場合は,支部総会参加者で投票を行います.
立候補期間:2022年3月1日(火)〜3月11日(金)
候補者(支部会員)は,氏名・所属・連絡先を下記に届け出てください.
受付先:日本地質学会関東支部 メール,郵送,FAXにより受け付けます.
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル内
FAX:03-5823-1156
メール:kanto@geosociety.jp 見出しは「関東支部選挙」でお願いします.
関東支部幹事選挙 選挙管理委員会
委員長 入野寛彦
委 員 亀高正男・河村知徳
お知らせ
オンライン講演会「県の石 神奈川県」
日本地質学会は,全国47都道府県について,その県に特徴的に産出する,あるいは発見された岩石・鉱物・化石をそれぞれの「県の石」として選定し,2016年5月10日(地質の日)に発表しました.関東支部では関東地方にある「県の石」のさらなる理解と普及を目的としてオンライン講演会を行います.是非ご参加ください.
主催:(一社)日本地質学会関東支部
日時:3月5日(土)13:00〜16:05(入室は12:30から)
開催方法:Zoomによる同時双方向方式(講演内容の録画記録は禁止します)
対象:会員(定員に余裕のある場合,非会員も受け付けます)
CPD:3単位 参加費:無料(要事前申込)
申込期間:2月1日(火)〜24日(木)まで
申込はこちらから:https://forms.gle/8WWWxMkWd9JWQFMVA
定員:75人(先着順)
プログラム 講演要旨(3件)PDF はこちら
13:00〜13:05 支部長挨拶
13:05〜13:50 『鉱物少年が発見した新鉱物「湯河原沸石」』神奈川県立生命の星・地球博物館館長 平田大二氏
13:50〜14:05 質疑応答・休憩
14:05〜14:50 『丹沢の谷にサンゴの化石』神奈川県立生命の星・地球博物館外来研究員 門田真人氏
14:50〜15:05 質疑応答・休憩
15:05〜15:50 『神奈川県の岩石「トーナル岩」から読み解くダイナミックな島弧衝突の履歴』国立科学博物館・地学研究部 谷健一郎氏
15:50〜16:05 質疑応答
16:00〜16:05 幹事長挨拶(終了)
問い合わせ先:関東支部幹事長 笠間友博 kasama[at]mh.scn-net.ne.jp([at]を@マークにしてください)電話0460‒83‒8140
お知らせ
アウトリーチ巡検
川の防災と川が作った地形を巡る
〜首都圏外郭放水路見学と春日部周辺,中川低地の地形観察〜
近年増大している河川の氾濫に備える首都圏外郭放水路の龍Q館(展示)および地下神殿見学と埼玉県春日部周辺の河川地形を観察します.
実施日:2022年2月20日(日)10:30〜16:30(予定)
対象:地学に興味のある方(地質学会会員でなくても可)
定員:20人(先着順),最少催行人数15人(達しない場合は中止です)
講師:杉内由佳氏(元・埼玉県立川の博物館)
参加費:3,000円(地下神殿入場料,保険代,資料代等を含む.当日現金にて集金)※学会規定のキャンセル料が発生します.参加確定後〜巡検3日前まで50%,巡検2日前以降100%になります.ご承知おきください.
集合:北春日部駅(東武スカイツリーライン:旧東武伊勢崎線)10:30
解散:南桜井駅(東武アーバンクライン:旧東武野田線)16:30頃
予定コース: 北春日部駅集合(徒歩)→①首都圏外郭放水路(大落古利根川流入堤)→②河畔砂丘→③首都圏外郭放水路(第五立坑)→④小淵の一里塚→⑤春日部公園橋(昼食)・旧粕壁宿→春日部駅(東武アーバンクライン線:旧東武野田線)⇒南桜井駅(市民バス)⇒⑥龍Q館(展示)・地下神殿見学(予定14:00~14:55)→(徒歩)→⑦旧河道→⑧水塚→道の駅庄和(休憩)→⑨首都圏外郭放水路(第二立坑)→⑩実績浸水深の痕跡→南桜井駅解散
※ 地下神殿は予約制で入場料1000円です.100段以上の階段の昇り降りがあり,自力で歩行できることが条件となっています(エレベーター等の設備はありません).
※ 地下神殿以外の行程は(低地のため)高低差はありませんが,水平距離で4〜5㎞程度歩きます.
※ コロナ感染状況や予約の混み具合等により見学時間変更の可能性,また天候状況や点検等により放水路の稼動時は見学中止,その他の見学コース変更の可能性があります.
参加申込期間:2022年1月23日(日)〜2月13日(日)*定員に達しましたので,申込は締め切りました(2022.2.9)
申込み・問い合わせ:メールにて下記担当者までお申し込みください.件名は見落とし防止のため「2月20日アウトリーチ巡検申込み」として下さい.氏名,住所,年齢,生年月日(保険申込みに必要なため).携帯番号,メールアドレスをお知らせください.申込者全員に受付結果についてのメールを返信します.
受付担当:米澤正弘 メール:my-yonezawa[at]y6.dion.ne.jp(注:「at」を@マークにして送信してください)
(日本地質学会関東支部担当幹事:米澤正弘,田村糸子)
お知らせ
関東支部功労賞募集
日本地質学会関東支部では,支部の顕彰制度に基づき2021年度も支部活動や地質学を通して社会貢献された個人・団体を関東支部として顕彰いたします. つきましては,下記の要領で支部会員からの推薦を募集します.
対象者:支部活動や地質学を通して広く社会貢献をされた関東支部内に在住の個人・団体 *社会貢献や活動の評価においては,必ずしも学問的な成果を問うものではありません.
公募期間:2021年12月10日〜2022年1月10日
選考期間:2022年1月11日〜2022年1月31日 関東支部功労賞審査委員会(委員長:山崎晴雄 前支部長)を設置
審査結果報告:NEWS誌、関東支部総会
推薦方法:対象者氏名,推薦者氏名,推薦理由(400字程度)を記入の上,関東支部功労賞推薦としてメールもしくはFAXにて下記へお送りください.
推薦受付:箱根町立箱根ジオミュージアム 笠間友博 〒250-0631 箱根町仙石原1251 E-mail:geo-museum@town.hakone.kanagawa.jp ,FAX:0460-84-9656
これまでの関東支部功労賞受賞者(順不同敬称略)
2010年度 清水惠助
2011年度 府川宗雄,かわさき宙と緑の科学館
2012年度 神戸信和,松島義章,加瀬靖之,下仁田自然学校
2013年度 埼玉県立自然の博物館,早稲田大学高等学院理科部地学班
2014年度 千葉達朗,横須賀市立自然・人文博物館
2015年度 千葉県立中央博物館,神奈川県大井町・株式会社古川
2016年度 門田真人,遠藤 毅,栃木県立博物館
2017年度 故山本高司,中山俊雄
2018年度 ミュージアムパーク茨城県立自然博物館,本間岳史
2019年度 東京大学大学院千葉演習林,相模原市立博物館
2020年度 群馬県立自然史博物館
2021.11.25掲載
お知らせ
学生・初級者向け「地質断面図」の書き方講座―布良海岸巡検―
主催:(一社)日本地質学会関東支部
趣旨:野外地質調査を実施し、そのデータをもとに地質断面図を描けるようにする。
日時・場所・日程:2021年5月22日(土)―館山市布良海岸野外地質調査
10:10 JR館山駅改札口集合(弁当・飲み物等持参)
10:30〜15:00 布良海岸で地質調査(12:00〜13:00昼食)
15:45 JR館山駅解散(宿泊はなし)
5月23日(日):地質断面図の作成作業(千葉市生涯学習センター工作室)
9:30 JR千葉駅中央改札出て左側のベンチ付近集合、千葉市生涯学習センターへ移動
10:00〜14:30 地質断面図の作成(12:00〜13:00 昼食―周辺に飲食店あり、弁当持参も可)
15:00 JR千葉駅解散
募集人数:最大6名―学生優先、余裕がある場合学生以外も受け付けます(希望者は7.0CPD単位取得可能)
服装等:22日は汚れてもよい服装で・雨天時以外は運動靴でOK、
準備するもの:ハンマー・クリノメーター・ヘルメット(調達できない場合はその旨メールに明記のこと)、手袋、野帳等、地図は主催者側で用意
費用:学生一人6,000円、一般一人10,000円(最寄り駅から館山駅・千葉駅までの運賃は含まず)
申込み期間:2021年4月11日(日)〜4月26日(月)―定員になり次第締め切り
申込み方法:メールでのみ受付、氏名・所属・学年・年齢(保険に必要)・連絡先(携帯番号)を明記のこと。申込者には必ず受け付けメールを送信します。申込み後3日経っても返信がない場合は問い合わせてください。
アドレスは 米澤正弘 my-yonezawa@y6.dion.ne.jp
学生優先です。学生以外の方はキャンセル待ち状態の扱いとなります。4月27日(火)に可否を連絡します。
その他:
詳細については参加人数確定後ご本人宛にメールで連絡します。
事前課題を出す予定です。期限までにご提出ください。
キャンセルの場合は速やかにご連絡ください。キャンセル料―7日前〜前日:50%、当日:100%
荒天が予想される場合の中止判断は前日18:00までに行い、電話で各人に連絡します。
問い合わせはメールで、日本地質学会関東支部幹事 米澤正弘まで。
※コロナウィルスの感染拡大状況によっては、中止・延期することがあります。
担当:日本地質学会関東支部幹事―米澤正弘、加藤 潔、方違重治
お知らせ
オンライン2021年度関東支部総会報告・地質技術伝承会のお知らせ
別途お知らせのように、総会は書面会議によって開催します。書面会議の結果報告と昨年開催できなかった地質技術伝承会をオンライで下記のように行います。なお、書面会議の議事録はニュース誌でも公開します。
日時:20215月年5月23日(日)オンライン開催
13:00〜13:30 総会結果報告 関東支部功労賞表彰式も予定、議事結果報告なので質疑応答はありません。
13:30〜15:00〜地質技術伝承会 講師 北川博也 氏(株式会社ダイヤコンサルタント 本社企画・技術本部技術統括部長 )演題「地質調査、最近の動向」
なお従来通り、非会員の方でも地質技術伝承会は参加できます。地質技術伝承会は会員、非会員問わず参加費はかかりません。
CPD1.5単位取得可能です。
定員:300名
申込締切:5月13日(木)
参加申込フォームはこちら(https://forms.gle/frM1vjBQNyYYycJt7)
(お問い合わせ先) 関東支部幹事長 笠間友博
箱根町立箱根ジオミュージアム 250-0631 箱根町仙石原1251
電話0460-83-8140 ファックス 0460-84-9565
E-mail geo-museum@town.hakone.kanagawa.jp
(週4日程度出勤のため、お急ぎの場合は携帯090-9952-8363にお願いします)
お知らせ
2021年度関東支部総会(書面会議)開催のお知らせ
2021年度関東支部総会議案書に寄せられたご意見についての回答(2021.4.23追記)
【寄せられたご意見について】2021年度関東支部総会議案書の中で
「2.支部規則改正支部の研究発表会等で優秀発表者賞等の授与を支部規則に明文化してほしいとの要請が本会よりあり、関東支部規則の一部改正を行い 12 月 5 日の理事会で承認された。」の文章表現について,
「支部規則の改正は支部総会で定める」ことになっているので「12月5日の理事会で承認された」という表現は「規則の改正を提案した」になるのではないかというご意見が関東支部会員より寄せられました.
【回答】今回の関東支部規則改正案は12月5日の理事会で報告し,確認をしましたが,支部規則の改正は理事会の審議事項ではありませんので,「理事会で承認」という表現は適切ではなかったと考えます.よって,文末の「 関東支部規則の 」以下を下記のように修正します.
「関東支部規則の一部改正について検討し,改正案を12 月 5 日の理事会に報告した.」
【対応】締め切りが4月30日ですので,通常の総会では現在は審議時間ととらえ,皆様にこの件についてお伝えした次第です.提案した規則の文面については,変更がありませんので,議案書はそのままにしますが,上記回答をお含みおき,ご投票いただきますようお願い致します.
なお、最新のタイムスタンプのものを有効としますので、既に投票された方で議案に対する賛否が変わるようでしたら,お手数ですが再度フォームで送っていただければ幸いです.
-----------------------------------------------------------
2021年度関東支部総会について,新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から,今年度も書面会議(以下,書面総会)によって開催します. 書面総会に参加される方は,下記に従い,議決権行使書または委任状の提出をお願いします.Googleフォームにおける議決権行使書または委任状の提出をもって書面総会に参加したものとみなします.なお本来は総会参加者の中から議長を互選しますが,書面総会では関東支部幹事会により予め河村知徳会員(石油資源開発(株))を議長候補として推薦し,議決権行使書によって信任投票を行います.
※議長の職責
1. 定足数確認(議決権行使書および委任状の総数が関東支部会員総数の20分の1以上)
2. 各議案承認の可否確認(各議案過半数の賛成で承認)
3. 議事録への署名(議事録は支部HPやニュース誌に公開)
書面総会開催方法
1. 本総会議案書を次のリンクよりダウンロードしてください.
「関東支部2021年度総会(書面会議)議案書」(pdfファイル)
2. 下記リンク先のGoogleフォームにより、議決権行使書または委任状どちらかを記入提出してください(提出締切日:4月30日).議決権行使書または委任状どちらか一人1回のみ有効です.複数送信された場合は最も新しいタイムスタンプのものを有効とします.
関東支部2021年度総会(書面会議)議決権行使書のフォーム(https://forms.gle/BiBRZYHmT9Zfs74E7)
関東支部2021年度総会(書面会議)委任状のフォーム(https://forms.gle/SQjvFVQZY6r5XdZV6)
3. 議長および議長の指名する者により議決権行使書および委任状の集計をおこない,過半数の賛成により各議案を承認します.
4. オンライン書面総会報告(5月23日13:00〜)、地質技術伝承会と合わせてオンライン開催します。URL等は別途ご連絡します。
5. 書面総会議事録の掲載:(ニュース誌6月号,HPへの掲載:5月末)
※支部HPが見られない環境で書面総会に出席されたい会員には個別に対応します.至急,ご住所とご氏名をご連絡ください.郵送またはFAXにて対応します. また,審議事項に関する質問は個別に対応しますので,ご連絡ください.
(お問い合わせ先) 関東支部幹事長 笠間友博
箱根町立箱根ジオミュージアム 〒250-0631 箱根町仙石原1251
電話0460-83-8140 FAX 0460-84-9565
E-mail geo-museum[at]town.hakone.kanagawa.jp
お知らせ
2021.2.5掲載
サイエンスカフェ「VR!!地球科学のアソビカタ」のお知らせ
日本地質学会関東支部では,サイエンスカフェ「VR!!地球科学のアソビカタ」を開催します。
仮想現実(Virtual Reality)ってナニ?VRって役に立つ? 自らも地球科学者であり,VRを駆使して研究成果を世界に発信している芝原暁彦さんと今井拓哉さんをゲストスピーカーに迎え,VR世界の泳ぎ方,新しい情報発信の方法,VRと地球科学の相乗効果などを参加者の皆さんに体験していただきます。
日程:2021年3月21日(日)
開催場所:クラスターによるVR空間内
ゲストスピーカー:芝原明彦 (地球科学可視化技術研究所)・今井拓哉 (福井県立大学恐竜学研究所)
ファシリテータ:岡山悠子(科博SCA)
対象:会員および非会員
参加費:無料
備考:VRゴーグルは必要ありません。ご自身に管理者権限のあるスマホもしくはPCをご準備ください。
詳細は、下記サイトをご参照ください。(申込受け付けは終了しました)
https://sites.google.com/view/vr-earth/
報告
2021.1.15掲載
「オンライン講演会−おうちで学ぶ恐竜研究の最前線−」実施報告
関東支部では年に一度,会場を借りてシンポジウムを開催してきたが,今年は新型コロナウイルス感染症対策のため,支部として初めてオンラインでの講演会として企画し,12月12日(土)13時から15時にかけて実施した.運営の都合上,定員75名で先着順の事前申込み制としたが,申込み期限前に定員に達し,例年のシンポジウムと同等規模で開催することができた.また,参加者は小学生からベテラン専門家まで多様であった.
新型コロナウイルスの影響で暗くなりがちな状況のなか,テーマとして夢のある「恐竜」を取り上げることとした.恐竜は地質学の中でも最も人気のある題材と思われるが,古生物学寄りであることや,関東からの化石産出が限られることなどから,支部としてこれまで扱ってこなかった経緯がある.しかし,関東でも恐竜を展示している博物館は多く,研究内容も新たな広がりを見せており,その一端を紹介するような企画とした.
今回は,群馬県立自然史博物館学芸員の郄耼祐司氏と,筑波大学助教の田中康平氏に,古生物の専門ではない一般向けに恐竜研究の最前線を講演して頂いた.郄耼氏からは近年,関東を含め国内各地から新たな恐竜化石発見が相次いでいることを具体的な発掘調査事例を含めて紹介があり,また,CTスキャンや骨格モデルを用いた最新の研究手法についても触れて頂いた.田中氏からはカナダのアルバータ州の化石産地の様子や,恐竜の卵殻化石から恐竜の営巣や当時の環境を推定する研究を紹介して頂いた.
講演に関する質問は随時チャットで受け付け,司会を介して講演者に問いかける形式とした.両講演とも非常に多くの質問を頂き,それらに答えていく中で話が盛り上がり,参加者と講演者とのコミュニケーションが深められたように思われる.講演して頂いた郄耼氏,田中氏をはじめ参加,関与して頂いた皆様に御礼申し上げる.
関東支部幹事:澤田大毅(地球科学総合研究所)
「オンライン講演会−おうちで学ぶ恐竜研究の最前線−」アンケート集計結果
アンケート依頼数:78名 回答数:49名 回答率:62.8%
問1 地質学会会員ですか?
会員:24名
非会員:25名
問2 年代を教えてください。
高校生以下:5名
大学生〜20代:11名
30代〜40代:17名
50代〜60代:15名
70代以上:1名
問3 今回の講演会の内容はいかがでしたか?5段階で評価してください。
(1:いまいち〜5:とても良い)
問4 オンライン講演会という初めての試みでしたが、申込から当日の進行までの運営方法はいかがでしたか?
5段階で評価してください。(1:いまいち〜5:とても良い)
問5 良かったと思う点をご自由にご記入ください。(回答詳細は省略)
講演内容に関して、お二人の講演がとても興味深く面白かったという意見が多数。
運営方法に関して、画面が見やすい、自宅から気軽に参加できるなど、オンラインならではの良さを指摘する意見が多数あり。
問6 いまいちだった点をご自由にご記入ください。(回答詳細は省略)
質疑応答の時間が短い、質疑応答の時は適に画面共有を外して先生の顔が見えるようにしてほしい、あらかじめ対象年齢層(特に下限)を示してほしいなどの意見があった。
問7 今後の日本地質学会関東支部に期待する講演会やシンポジウムのテーマをご記入ください。(回答詳細は省略)
地質学に関係する様々なジャンルのテーマが挙げられていた。
問8 日本地質学会関東支部に対するご意見ご要望などがありましたらご自由にご記入ください。(回答詳細は省略)
引き続きこのような活動をしていただけると嬉しいとの回答が複数あり。
2020年の活動
案内
2020.12.10掲載
アウトリーチ巡検:川の防災と川が作った地形を巡る
〜首都圏外郭放水路見学と春日部周辺,中川低地の地形観察〜
緊急事態宣言発出を受け,新型コロナウィルス感染拡大防止のため,
巡検は中止致します.再度開催等今後については未定です.(2021/1/12)
地質学会関東支部では,多くの方々に,野外での観察を通して,地学の面白さを実感し地球科学に対する理解を深めていただきたいという主旨でアウトリーチ巡検を実施しています.本年度は,近年増加している河川の氾濫に備える首都圏外郭放水路の龍Q館(展示館)および地下神殿の見学と春日部周辺の河川地形を観察します.
主催:日本地質学会関東支部
実施日:2021年1月31日(日)
対象:地学に興味のある方(地質学会会員でなくても可)
募集:20人(先着順) 最少催行人数15人
申込み期間:12月12日〜1月15日 *定員に達した時点で終了
講師:杉内 由佳(元・埼玉県立 川の博物館,現・立正大学外部研究員)
集合:首都圏外郭放水路 龍Q館10:00(東武アーバンクライン 南桜井駅よりバス)
解散:東武スカイツリーライン(旧東武伊勢崎線)北春日部駅16:30前後(予定)
予定コース(天候などにより変更になることがあります):首都圏外郭放水路①龍Q館(巡検コース・周辺地形解説)②地下神殿見学・昼食⇒(徒歩)③水塚⇒(徒歩)南桜井駅(東武アーバンクライン線)春日部駅⇒(以下徒歩)④旧粕壁宿⇒⑤河岸場跡⇒⑥地盤沈下⇒⑦河畔砂丘⇒⑧首都圏外郭放水路入口(古利根川流水堤および第五立坑)⇒北春日部駅(解散)
参加費:3000円 (入館料,講師謝礼,保険代,資料代等.当日集金)*学会規定のキャンセル料が発生します.参加確定後〜巡検3日前まで50%,巡検2日前以降100%になります.ご承知おきください.
その他:
首都圏外郭放水路の地下神殿見学は100段以上の階段の昇り降りがあり,自力で歩行できることが条件となっています(エレベータ等の設備はありません).
当日,放水路受付で検温を行います.マスク着用が必須となっています
新型コロナウイルスの感染状況により巡検が中止になる可能性があります.
申込み・問い合わせ:メールにて下記担当者まで
件名は見落とし防止のため「1月31日アウトリーチ巡検申込み」として下さい.
氏名,住所,年齢(生年月日)←保険申込みに必要なため,携帯番号,メールアドレス,所属をお知らせください.申込者全員に受付結果についてのメールを返信します.
担当: 関東支部幹事 田村糸子(たむらいとこ) メール zy847537[at]sb4.so-net.ne.jp(※[at]を@マークに修正して送信ください)
案内
2020.12.4掲載
2020年度関東支部功労賞募集
日本地質学会関東支部では,支部の顕彰制度に基づき2020年度も支部活動や地質学を通して社会貢献された個人・団体を関東支部として顕彰いたします. つきましては,下記の要領で支部会員からの推薦を募集します.
対象者:支部活動や地質学を通して広く社会貢献をされた関東支部内に在住の個人・団体(*社会貢献や活動の評価においては,必ずしも学問的な成果を問うものではありません.)
公募期間:2020年12月17日〜2021年1月17日
選考期間:2021年1月18日〜2021年1月31日 関東支部功労賞審査委員会(委員長:山崎晴雄 前支部長)を設置
審査結果報告:NEWS誌、関東支部総会
推薦方法:対象者氏名,推薦者氏名,推薦理由(400字程度)を記入の上,関東支部功労賞推薦としてメールもしくはFAXにて下記へお送りください.
推薦受付:箱根町立箱根ジオミュージアム 笠間友博 〒250-0631 箱根町仙石原1251 E-mail:geo-museum@town.hakone.kanagawa.jp ,FAX:0460-84-9656
これまでの関東支部功労賞受賞者(順不同敬称略)
2010年度 清水惠助
2011年度 府川宗雄,かわさき宙と緑の科学館
2012年度 神戸信和,松島義章,加瀬靖之,下仁田自然学校
2013年度 埼玉県立自然の博物館,早稲田大学高等学院理科部地学班
2014年度 千葉達朗,横須賀市立自然・人文博物館
2015年度 千葉県立中央博物館,神奈川県大井町・株式会社古川
2016年度 門田真人,遠藤 毅,栃木県立博物館
2017年度 故山本高司,中山俊雄
2018年度 ミュージアムパーク茨城県立自然博物館,本間岳史
2019年度 東京大学大学院千葉演習林,相模原市立博物館
案内
2020.11.9掲載
「オンライン講演会−おうちで学ぶ恐竜研究の最前線−」
本シンポジウムは定員に達しましたので、申込受付を終了いたします。
なお、キャンセル待ちはございません。ご了承下さい。(2020.11.30 更新)
関東支部では会員および非会員の方を対象に、オンライン講演会を行います。新型コロナウィルス感染症の心配と切り離せない日々が続いていますが、今回は夢のある「恐竜」の話題で、非日常的な地質学的時間スケールの旅を体験していただければと思い、下記のように計画いたしました。是非ご参加ください。
主催:(一社)日本地質学会関東支部
日時:12月12日(土) 13:00〜15:00
対象:会員および非会員 CPD 2単位(希望者)
参加費:無料、ただし事前申し込み者のみ参加可
申し込み期間:11月12日(木)より12月5日(土)まで *定員に達しましたので、申込受付を終了いたします(2020.11.30)
申し込み先: 下記Googleフォームよりお申し込みください。
募集人数:75人(先着順)
Zoomによるオンタイム、オンライン方式(講演内容の録画記録はご遠慮ください)
プログラム
12:15〜12:45 視聴者入室
13:00〜13:05 支部長挨拶
13:05〜13:45 「日本の恐竜〜発掘と研究〜」群馬県立自然史博物館学芸員 郄耼祐司氏
【演者より】「サンチュウリュウ」など1980年代の歯や部分骨の発見、さらにその後のアマチュアによる発見を端緒として、これまでに多くの恐竜に関する学術調査が日本各地で行われてきました。恐竜が見つかった地域の中には今も発掘調査を実施している地域もあれば、研究成果を元に既存の博物館の拡張や新たに博物館が設置された地域もあります。この講演では、国内各地の恐竜発掘、恐竜研究の現状を紹介し、今後の展望について考えたいと思います。
13:45〜14:00 質疑応答 チャット方式 司会により進行
14:00〜14:05 準備休憩
14:05〜14:45 「最新研究で明らかになる恐竜のくらし」筑波大学助教 田中康平氏
【演者より】近年、恐竜研究は急速なスピードで進んでいます。これまで分からなかった恐竜たちの生き生きとした生態が、様々な方法を使って明らかになりつつあります。例えば、キラキラと輝く羽毛を持つ恐竜や、皮膜で飛翔した恐竜、水の中で生活していた恐竜など、多様な恐竜たちの存在が見えてきました。この講演では、私が専門とする恐竜の繁殖行動や子育てを中心に、恐竜たちの多彩なくらしぶりをお話ししたいと思います。
14:45〜15:00 質疑応答 チャット方式 司会により進行
15:00 幹事長挨拶 (終了)
問い合わせ先:関東支部幹事長 笠間友博(kasama@mh.scn-net.ne.jp)
報告
2020.11.2掲載
関東支部ミニ巡検「大磯丘陵北東部のテフラ」実施報告
写真:粟久保の露頭
(神奈川県平塚市土屋)前での集合写真
関東支部では,本来2月16日に開催予定であったが悪天候により中止となったミニ巡検の代替企画として10月4日(日)に本巡検を実施した.笠間友博氏(箱根ジオミュージアム・関東支部幹事長)を講師として,15名の参加者とともに大磯丘陵北東部の4か所の露頭を見て歩いた.
おりしも今年初め頃より新型コロナウイルス感染症が蔓延し,関東支部では技術伝承講習会やフィールドキャンプなど軒並み中止となったが,支部活動を再開するタイミングを見計らっていたところ,世間では7月末よりGoToキャンペーンが実施され始めたこともあり,借上げバスを使用せず徒歩移動型の巡検であれば3密になることもなく比較的安全に巡検が実施できると考えて,非接触式体温計による検温,手指のアルコール消毒,マスクの着用など考えられる感染症対策を行った上で実行した.もちろん,全員のお互いに「うつさない・うつらない」という信頼関係があって成立するものである.無事巡検が実施できたことを講師の笠間氏をはじめ皆様に感謝したい.(神奈川県温泉地学研究所 小田原 啓)
参加者の感想
10/4(日)に開催された,地質学会関東支部主催の火山灰ミニ巡検に参加した.もともとは2月に開催予定であったが,天候不順により延期となり,さらに新型コロナウイルスの影響で代替日程がこの時期となった.集合場所では非接触式体温計による検温が実施されたほか,マスクの着用を事前に依頼するなど,感染症対策が行われていた.
STOP1は「寺分の露頭」あるいは「粟窪の露頭」と呼ばれる,比較的知名度の高い露頭である.露頭の最下部にはTB-9テフラを挟在するローム層(T-Bテフラ累層)が見られ,それを不整合に覆ってMIS5.5の海成層である吉沢層が分布する.吉沢層の下部は主にラミナの発達する砂層からなり上部に向かってシルトや泥炭に漸移する.吉沢層の上部から軽石を主体としたテフラが挟在するようになり,観察した範囲では下位からKlP-3〜KlP-7のテフラが見られた.いくつかのテフラは軽石のほかに火山灰(火山豆石を含む)を主体とする部分を伴うことを特徴とするが,この火山灰はマグマ水蒸気爆発の産物であり,噴出源である箱根火山に湖などの水域があったと推定されることが案内者から紹介された.また,参加者からはこれらの火山灰部分から淡水の珪藻化石が産出することも紹介された.観察されるテフラは大部分が箱根火山起源であり,厚いテフラが高頻度で挟在することから箱根火山の活動が非常に活発な時期であったことが分かること,観察されるテフラのうちTB-9及びKlP-4は角閃石を含むことから箱根火山以外が起源と推定され,そのうちTB-9は先小御岳火山起源の可能性が指摘されていることなどが案内者から紹介された.
STOP1-1はSTOP1から約300m南方の道路沿いの露頭である.東西約200m程度にわたって断続的に露出しており,下位からTB-1〜TB-7テフラを挟在するT-Bテフラ累層が観察されるが,TB-2テフラはこの露頭では明瞭な軽石層として識別されなかった.この地点はSTOP1より数m程度標高が高いが露出するテフラがSTOP1で見られたTB-9より下位のテフラであることから,T-Bテフラ累層が北に傾斜していることが分かる.TB-1テフラは川崎市の生田緑地周辺の多摩丘陵ではバヤリースと呼ばれる軽石層に対比され,箱根火山から火砕流を伴う大規模なテフラが多数供給されたカルデラ形成期の噴出物であること,TB-2・3・5テフラは角閃石を含み箱根火山以外が給源である可能性などが紹介された.
STOP2は土取場跡地の大露頭である.露頭が切り立っているため遠方からの観察となった.大部分がMIS7.5の海成砂層(T-b層または早田層)からなり,上部にT-Bテフラ累層が重なるのが観察される.かつては砂層中にTCu-4テフラが観察されたが,露頭の下部から中部にかけて崖錐に埋もれつつあり,観察できなくなっている可能性があるとのことであった.
STOP2-2はSTOP2から約350m北方の道路沿いの露頭である.かつては道路沿いにSTOP2で見られた地層が連続的に観察できたそうであるが,現在は砂層のごく一部とTB-6・7・8テフラのみが観察可能である.TB-6・7・8テフラはいずれも粗粒の軽石を主体とする厚いテフラ層である.TB-8は角閃石を含むことが紹介されたが,巡検で観察したほかの角閃石含有テフラと異なり,軽石の粒径や層厚が大きく,見かけはほかの箱根火山起源のテフラに似ている.箱根火山でも角閃石を含むマグマの活動があったのか,あるいは箱根以外の火山からこれほどの規模のテフラが供給されたのか,どちらにしても興味深い事例であると思う.
今回は10時集合,15時解散という短時間の巡検であったが,テフラと海水準変動と箱根火山の活動の関係を観察することができ,内容は充実していた.私的な調査も含めて今回が今年度初めての野外観察だという参加者もおり,新型コロナウイルスの影響が調査研究にも及んでいることが改めて実感された.しかし,巡検は風通しの良い屋外で行われ,観察もそれほど密集して行うものでもない.今回行われていたようにマスクの着用や検温がしっかりされていれば,巡検を行っても問題ないと個人的には思うので,今後は巡検の企画が以前と同じ頻度に増えることを期待したい. ((株)ダイヤコンサルタント 下釜耕太)
2020総会(書面会議)
2020.4.20掲載 5.7更新 6.8更新
2020年度関東支部総会(書面会議)
▶関東支部書面会議議事録200523.pdf 20.6.8掲載
2020年4月11日に開催を予定していた2020年度関東支部総会について,新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から,書面会議(以下,書面総会)によって開催します. 書面総会に参加される方は,下記に従い,議決権行使書または委任状の提出をお願いします.Googleフォームにおける議決権行使書または委任状の提出をもって書面総会に参加したものとみなします.なお本来は総会参加者の中から議長を互選しますが,書面総会では関東支部幹事会により予め松浦一樹会員を議長候補として推薦し,議決権行使書によって信任投票を行います.
※議長の職責
1. 定足数確認(議決権行使書および委任状の総数が関東支部会員総数の20分の1以上)
2. 各議案承認の可否確認(各議案過半数の賛成で承認)
3. 議事録への署名(議事録は支部HPやニュース誌に公開)
書面総会開催方法
1. 本総会議案書を次のリンクよりダウンロードしてください.
関東支部2020年総会(書面会議)議案書.pdf
2. 下記リンク先のGoogleフォームにより、議決権行使書または委任状どちらかを記入提出してください(提出締切日:5月23日).議決権行使書または委任状どちらか一人1回のみ有効です.複数送信された場合は最も新しいタイムスタンプのものを有効とします.
関東支部2020年度総会(書面会議)議決権行使書のフォーム(https://forms.gle/qXe7tmW83bfH7E7U9)
関東支部2020年度総会(書面会議)委任状のフォーム(https://forms.gle/XxGLY4Dzy7nV8nDA7)
3. 議長および議長の指名する者により議決権行使書および委任状の集計をおこない,過半数の賛成により各議案を承認します(5月23日〜5月末).
4. 書面総会議事録の掲載(閉会宣言):(ニュース誌6月号,HPへの掲載:5月末)
※支部HPが見られない環境で書面総会に出席されたい会員には個別に対応します.至急,ご住所とご氏名をご連絡ください.郵送します. また,審議事項に関する質問は個別に対応しますので,ご連絡ください.
(お問い合わせ先) 関東支部幹事長 笠間友博
箱根町立箱根ジオミュージアム
〒250-0631 箱根町仙石原1251
電話0460-83-8140 FAX 0460-84-9565
E-mail geo-museum[at]town.hakone.kanagawa.jp
2020総会・伝承講習会
2020.2.14掲載
2020年度総会・地質技術伝承講演会開催のお知らせ
[行事開催に関するお知らせ]東京都における新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を受け,2020年4月11日(土)「北とぴあ」での2020年度支部総会・地質技術伝承講演会・関東支部功労賞表彰式・懇親会は行わないこととしました.
なお支部総会は延期開催の予定で,会場・日程が決まり次第,ニュース誌,geo-flash,支部MLなどでお知らせいたします.地質技術伝承講演会の開催については,別途検討したします.(2020.3.26)
日時:2020年4月11日(土)14:00〜16:45
場所:北とぴあ 第2研修室 (東京都北区王子1-11-1)
JR京浜東北線王子駅徒歩2分,東京メトロ南北線王子駅直結
プログラム:
13:30受付開始
14:00〜15:40地質技術伝承講演会
15:50〜16:45関東支部総会
1)支部功労賞授与式
2)関東支部幹事選挙(選挙の場合)
3)2019年度 活動報告・会計報告
4)2020年度 活動方針・予算報告
17:15〜 懇親会(予定)会費等当日受付
地質技術伝承講演会
参加費:無料,どなたでも参加できます.CPD単位取得可能(1.5)
申し込み方法:メールまたは学会へのFAX
1)関東支部幹事 加藤 潔(駒澤大学 kiyoshi.katoh@gmail.com)
2)日本地質学会関東支部気付 関東支部 FAX:03-5823-1156
講師:北川博也氏(株式会社ダイヤコンサルタント,九州支社地盤技術部長)
タイトル:ボーリング技術,最近の動向
関東支部総会 関東支部会員の方で総会に欠席される方は委任状をお願いします.
委任状送付方法:
郵送またはFAXの場合は下記にお送りください.
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F 日本地質学会事務局気付 関東支部事務局 FAX:03-5823-1156
E-mail送付の場合 関東支部のメールアドレス(kanto@geosociety.jp)へ委任状をご返信下さい.メールによる委任状の締切は、4月10日(金)18時までです.
--------------------------------------------
<関東支部総会委任状>
2020 年4月11日(土)開催の日本地質学会関東支部総会に出席できませんので,
当日一切の議決権を 君(又は,議長)に委任します(空欄の場合は議長とします).
日時:2020年 月 日
住所: 会員氏名:
--------------------------------------------
2020支部幹事選出
2020.4.1掲載
2020 年度、2021 年度の日本地質学会関東支部幹事選挙結果
日本地質学会関東支部選挙管理委員会
委員長 伊藤 谷生
委員 青野 道夫、入野 寛彦
2020 年 3 月 1 日(日)〜3 月 11 日(水)の立候補期間に幹事候補者が定数の 20 名を越えなかったため、日本地質学会関東支部細則第1条6にしたがい、無投票で下記の全候補者が新幹事として決定しました。
荒井 良祐(川崎地質株式会社)、小田原 啓(神奈川県温泉地学研究所)、笠間 友博(箱根ジオミュージアム)、加藤 潔(駒澤大学 総合教育研究部)、金丸 龍夫(日本大学文理学部地球科学科)、木村 克己(公益財団法人 深田地質研究所)、小松原 純子(国立研究開発法人 産業技術総合研究所)、澤田 大毅(石油資源開発株式会社)、下釜 耕太(株式会社ダイヤコンサルタント)、棚瀬 充史(株式会社地圏総合コンサルタント)、田村 糸子(中央大学 経済学部)、冨田 一夫(日鉄鉱コンサルタント株式会社)、廣谷 志穂(アジア航測株式会社)、 方違 重治(国土防災技術株式会社)、細根 清治、細矢 卓志(中央開発株式会社)、本田 尚正(東京農業大学 地域環境科学部 地域創成科学科)、向山 栄(国際航業株式会社)、山本 伸次(横浜国立大学大学院 環境情報研究院)、米澤 正弘(渋谷教育学園幕張中学校・高等学校)
以上 20 名(あいうえお順)
2020.2.4掲載
2020年度関東支部幹事選出のお知らせ
支部幹事の改選に伴い、支部幹事立候補者の受付を行います。幹事の定数は20名で、任期は2020年関東支部総会終了後〜2022年関東支部総会までとなります。立候補者多数の場合は、支部総会で投票を行います。
立候補期間:2020年3月1日(日)〜3月11日(水)
候補者(支部会員)は,氏名・所属・連絡先を下記に届け出てください。
受付先:日本地質学会関東支部あて、メール、郵送、FAXにより受け付けます。
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル内 FAX:03-5823-1156
メール:kanto@geosociety.jp 見出しは「関東支部選挙」でお願いします。
関東支部幹事選挙 選挙管理委員長 伊藤谷生
2019年の活動
支部功労賞
2020.4.1掲載
2019年度関東支部功労賞について
日本地質学会関東支部長 山崎 晴雄
>
日本地質学会関東支部では、支部の顕彰制度に基づき支部活動や地質学を通して社会貢献された個人・団体を関東支部として顕彰しています。2019年度は2件の推薦があり,受賞が認められました(選考委員長 有馬 眞)。 本来ならば支部総会での報告になりますが、総会延期を受け、ここに報告します。
相模原市立博物館:地域地質の紹介だけではなく、市民との協働体制の充実、隣接するJAXAとの連携による惑星地質学普及への取り組みが評価されました。
東京大学千葉演習林:関東における地質図学実習の拠点施設としての重要性とともに、関東支部が夏季に行っているフィールドキャンプへの惜しみない協力体制が評価されました。
(あいうえお順)
2019.12.11掲載
関東支部功労賞募集
日本地質学会関東支部では,支部の顕彰制度に基づき2019年度も支部活動や地質学を通して社会貢献された個人・団体を関東支部として顕彰いたします. つきましては,下記の要領で支部会員からの推薦を募集します.
対象者 :支部活動や地質学を通して広く社会貢献をされた関東支部内に在住の個人・団体
*社会貢献や活動の評価においては,必ずしも学問的な成果を問うものではありません.
公募期間:2019年12月10日〜2020年1月10日
選考期間:2020年1月11日〜2020年1月31日
関東支部功労賞審査委員会(委員長:有馬 眞 前支部長)を設置
審査結果報告:NEWS誌、関東支部総会
推薦方法:対象者氏名,推薦者氏名,推薦理由(400字程度)を記入の上,件名を「関東支部功労賞推薦」としてメールもしくはFAXにて下記へお送りください.
推薦受付:箱根町立箱根ジオミュージアム 笠間友博
〒250-0631 箱根町仙石原1251 E-mail:geo-museum@town.hakone.kanagawa.jp,FAX:0460-84-9656
これまでの関東支部功労賞受賞者(順不同敬称略)
2010年度 清水惠助
2011年度 府川宗雄,かわさき宙と緑の科学館
2012年度 神戸信和,松島義章,加瀬靖之,下仁田自然学校
2013年度 埼玉県立自然の博物館,早稲田大学高等学院理科部地学班
2014年度 千葉達朗,横須賀市立自然・人文博物館
2015年度 千葉県立中央博物館,神奈川県大井町・株式会社古川
2016年度 門田真人,遠藤 毅,栃木県立博物館
2017年度 故山本高司,中山俊雄
2018年度 ミュージアムパーク茨城県立自然博物館,本間岳史
ミニ巡検
2019.12.3掲載 2020.1.23更新
「大磯丘陵北東部のテフラ」ミニ巡検のお知らせ
関東支部ではシンポジウム「関東のテフラ−最近の年代観と供給源−」に合わせて、関東地方のテフラ研究で重要な役割を占めていた大磯丘陵の模式的な露頭をめぐるミニ巡検を開催します。大磯丘陵のミニ巡検は2016年に北西部で行いましたが、今回は北東部です。 路線バス+徒歩の巡検になります。昼食と飲料水をご持参ください。なお、現地にはトイレが少ないので、あらかじめご承知おきください。雨天(雪、みぞれ)中止です。
主催:日本地質学会関東支部
実施日:2020年2月16日(日)2月26日(土)訂正しました(2019.12.4)
対象:会員(空きがあれば一般参加も可能)(2020.1.23更新)
募集:20人(先着順)
講師:笠間友博 箱根町立箱根ジオミュージアム
集合:平塚市土屋「土屋橋」バス停10:00 ファミリーマート土屋橋店の近く 小田急線秦野駅、JR東海道線平塚駅より神奈中バス利用 ICカード可
費用:保険代他1000円(当日集金)
コース:粟久保→東海大学グラウンド→神奈川大学(昼食)→早田→神奈川大学 解散:神奈川大学バス停15:30頃 秦野駅、平塚駅へは神奈中バス利用
CPD単位:4.5単位
申込み・問合せ:メールにて下記担当者まで。
件名は見落とし防止のため「テフラミニ巡検申し込み」として下さい。
氏名、所属、日中連絡の付く電話番号、CPD単位の要・不要を記入してください。
申込者全員に、受け付結果についてのメールを返信します。
後日、参加者は保険申込のため性別、住所、生年月日をお伺いします。
申込締切:2020年1月31日(金)
担当 関東支部幹事 小田原 啓(おだわら けい)(神奈川県温泉地学研究所)メール odawara@onken.odawara.kanagawa.jp
シンポジウム
2019.11.7掲載 12.3更新
シンポジウム「関東のテフラ−最近の年代観と供給源−」
画像をクリックするとポスターPDFがダウンロードできます
1970年代に大磯丘陵などの詳細なフィールド調査から発展した関東地方のテフラ研究も半世紀を迎えようとしています.その間,多くの火山の噴火史が明らかになり,また広域テフラの年代精度も向上しました.日本地質学会関東支部では関東地方に分布するテフラを中心に「最近の年代観と供給源」をテーマとし,最新の研究成果に関するシンポジウムを開催いたします.是非ご参加ください.
【主催】一般社団法人日本地質学会関東支部
【期日】令和2年1月25日(土)10:00-16:30、終了後懇親会
【場所】「北とぴあ」第一研修室 北区王子1-11-1(JR京浜東北線王子駅徒歩5分、地下鉄南北線出口直結)
【対象】日本地質学会会員および一般(非会員)
【参加費】無料、事前申し込み不要
【要旨集】有料(一般1,000円、学生500円)
【CPD単位】取得可能(5単位)
【懇親会】事前申し込み必要、締め切り1月17日(金)、会費4,000円程度(当日支払い)
申し込みはEメールでkanto@geosociety.jpまで(氏名、所属をご記入ください)
【プログラム】
9:30受付開始、10:00開会、開会あいさつ
10:10〜10:50 小林 淳(静岡県富士山世界遺産センター)「富士・箱根〜伊豆諸島北部にかけての爆発的なテフラ噴火史」
10:50〜11:30 笠間友博(箱根町立箱根ジオミュージアム)「三浦半島宮田層中のテフラから得られたFT、U-Pb年代」
11:30〜12:30昼休み(周辺の飲食店をご利用ください)
12:30〜13:10 中里裕臣(農研機構)「上総・下総層群における海水準変動と更新世テフラの層位」
13:10〜13:50 中澤 努(産総研)「関東平野内陸部地下の下総層群の堆積サイクルとテフラ層序」
13:50〜14:00 休憩
14:00〜14:40 田村糸子(首都大学東京)「南関東における新第三紀/第四紀境界層準の指標テフラ」
14:40〜15:20 水野清秀(産総研)「関東まで飛んできた鮮新世以降の九州起源のテフラ」
15:20〜15:30 休憩
15:30〜16:10 鈴木毅彦(首都大学東京)「上総層群のテフラから復元する東北日本弧における巨大噴火史と関東平野の形成史」
16:10〜16:30 総合討論、閉会の挨拶、16:30終了
会場片付けの後、懇親会場へ徒歩移動
問い合わせ先
日本地質学会関東支部 幹事長 笠間友博(箱根町立箱根ジオミュージアム)
メール:geotracks.hakone@outlook.jp
電話:0460‒83‒8140 携帯090-9952-8363
巡検
2019.10.1掲載 10.16更新 10.25更新
「神津島火山巡検」のお知らせ
地質学会関東支部では,首都大学東京 火山災害研究センターとの共催により,「神津島火山巡検」を開催します.天上山838年噴火による火山灰や火砕流堆積物などを観察していただく予定です.宿泊先では案内者による話題提供,勉強会も予定しています.
共催:日本地質学会関東支部,首都大学東京火山災害研究センター
実施日:2019年11月30日(土)朝〜12月1日(日)朝,雨天決行
募集:会員および一般・15名まで(先着順,最小催行人員12名)
案内者(予定):小林 淳(静岡県富士山世界遺産センター)・村田昌則(首都大学東京火山災害研究センター)・鈴木毅彦(同)・西澤文勝(神奈川県立生命の星・地球博物館)
CPD単位:8単位(11/30 4単位,12/1 4単位)証明書発行希望者は申し込み時にお知らせ下さい。
見学ルート概要(予定)(天候等により登山中止、見学地変更の可能性あり)※10/25現在
11月30日(土):各自10:00 神津島港 現地集合→天上山白島トイレ口→山頂にて昼食→櫛が峰・ババア池→那智山北部露頭(→返浜)→宿泊先
12月1日(日)(大型船、飛行機等の時間に合わせて行動予定):宿泊先→あかばね洞門(→葱の場(もしくはありま展望台))→神津島港
◆申込方法:住所、氏名、年齢、性別、携帯電話番号、メールアドレス、所属、CPD証明書発行の要否をメールで下記へご連絡下さい.
担当幹事 細根・荒井(メール:s.hosone28@gmail.com, ken.arai@ajiko.co.jp)
申込締切:11月14日(木)17時(定員に達した時点で締め切り)
*メールがご利用いただけない場合にはFAX:03-5823-1156(地質学会事務局付け)にてお申し込みください.
◆費用:20,000円(現地での案内地移動費用は含みますが,現地までの交通費は含みません.1泊3食費、旅行傷害保険費、案内資料等の実費)
上記申し込み後に関東支部口座へ事前お振込頂きます.
◆注意点:開催2週間前の予約取り消しは費用をご負担いただきます。キャンセル料は次の通りです.(11/14まで無料,11/15〜11/27まで50%,11/28以降100%)
◆参考:集合解散時刻は以下を想定しています.この他にも航路,空路別便あります.
往路
(大型船)竹芝29日 22:00発,神津島10:00着,
(空路)調布30日 8:45発,神津島9:30着,
復路
(大型船)神津島10:30発,竹芝19:45着,
(空路)神津島9:50発,調布10:35着.
巡検
2019.9.5掲載 10.4, 10.15,11.14更新 2020.2.3更新 2020.3.14更新
地学教育・アウトリーチ巡検(チバニアン周辺)
新型コロナウィルスの感染拡大防止の観点や市原市の公共施設閉鎖などの
理由により、チバニアン巡検は中止致します。(2020.3.14)
日時:2020(令和2)年3月22日(日)10:20小湊鉄道月崎駅集合、15:30頃同駅解散予定
ただし、3月14日にダイヤ改正予定なので、変更の場合あり
場所:市原市田淵周辺
募集人数:30人(日本地質学会会員でなくても可)、定員になり次第締め切ります。
コース:月崎駅10:30出発→素掘りのトンネル見学→チバニアン到着−(昼食)−地層見学→川廻し地形見学→月崎駅
費用:1,500円(資料代、保険代、講師謝礼等)、当日徴収
講師:岡田 誠(茨城大学教授)
申込み:
①2月3日(月)からメールでのみ受け付けます。
②受け付けた方にはメールで返信します。申込み後3日以内に返信がない場合はお問い合わせください。
③申込み先のアドレスは、日本地質学会関東支部幹事 米澤正弘 my-yonezawa@y6.dion.ne.jp です。
④申込みの際、以下の事項をご記入ください。
①お名前とふりがな、②年齢、③性別、④本人緊急連絡先(携帯番号)
8.その他:
① 今回は基本全コース徒歩です。お車で来られる方は、チバニアン駐車場へ車を止めてください。
② 小雨決行です。ただし、コースが一部変更になる場合があります。
③ 参加者には後日(3月10日過ぎの予定)、持ち物や注意事項など詳細を連絡します。
巡検
2019.8.6掲載 9.3更新
「筑波山地域ジオパーク巡検」のお知らせ
*定員に達したましたので,申込受付を終了いたします.
多数のお申込をいただき,ありがとうございました.(2019.10.3, 18時現在)
地質学会関東支部では,関東各地のジオパークを応援,推進する目的で,様々な巡検を行っています.今回は,2月に第5回日本ジオパークネットワーク関東大会が開催された筑波山地域ジオパークの筑波山周辺エリアを見学する巡検を企画しました.西の富士,東の筑波と称された関東のランドマーク筑波山周辺の地形地質,そしてジオがもたらす歴史や文化を体感できる巡検です.講師は,同ジオパークの教育・学術部会長である久田健一郎先生(筑波大学)と,昨年度までつくば市ジオパーク室地球科学専門員を勤めていた杉原薫先生(筑波大学)です.寺西石材採石場では楔を打ち込んでの石割体験,稲葉酒造では日本酒の試飲も予定しています.
日程:2019年10月20日(日)
対象:どなたでも(地質学会会員でなくても可)
募集:20人(先着順)
講師:久田健一郎(筑波大学)・杉原 薫(筑波大学)
集合:TXつくば駅 9:50 解散:TXつくば駅17:00予定
見学コース(予定:天候や現地の状況等によりルート変更する場合があります)
TXつくば駅⇒桜川河川敷(古鬼怒川の礫質堆積物)⇒寺西石材採石場(加波山花崗岩・鹿沼火山灰層)⇒昼食(伊勢屋旅館)・真壁の町並み(真壁伝承館)⇒筑波山梅林(山麓緩斜面堆積物・筑波花崗岩)⇒筑波山神社⇒稲葉酒造見学・試飲⇒TXつくば駅解散
費用:8,000円(バス代,昼食代,保険代,資料代など).
*キャンセル料は次の通りです.(10月4日まで無料,10月5日から10月17日まで50%,10月18日以降100%)
*参加確定後,地質学会関東支部の口座へお振込いただきます.
申込み期間:9月9日(月)〜10月4日(金) *定員に達したましたので,申込受付を終了いたします(2019.10.3, 18時現在)
*問い合わせ:メールにて下記担当者まで
担当: 関東支部幹事 小田原啓(おだわらけい) 神奈川県温泉地学研究所
メール:odawara@onken.odawara.kanagawa.jp
*メールがご利用いただけない場合には,FAX:03-5823-1156(地質学会事務局付)にてお申し込みください.
シンポジウム
2019.8.1掲載
研究の最前線
〜中期更新世以降の関東平野北東部の地質と地形発達〜
日時:2019年10月19日(土) 13:20〜17:00(13:00開場)
会場:つくば市役所コミュニティー棟第一会議室 つくば市研究学園一丁目1番地1
主催:筑波山地域ジオパーク推進協議会
共催:日本地質学会関東支部
参加費:無料
シンポジウムの趣旨:筑波山の美しさはその山姿もさることながら、関東平野からいきなり877メートルの山体がそびえていることだと言われている。筑波山地域ジオパークではこの山と平野の特徴をテーマの一つにしているが、当地域の平野の研究については、かつては盛んに行われたが最近の研究は限られているように思われる。本シンポジウムでは当地域とその周辺に関連する最新の研究成果を持ち寄り、分かってきたことと課題を明らかにする。そのことから、関東平野の全体像のなかでしめる筑波山地域の関東平野の特性を明らかにし、ジオストーリーを構築する一助とする。
プログラム
13:20〜13:30 開会あいさつ・趣旨説明
13:30〜14:00 地形を見る目をつくばでみがこう(仮題) 池田 宏(元筑波大学・深田地質研究所)
14:00〜14:30 過去 40 万年間の関東平野の地形発達史(仮題) 須貝俊彦(東京大学大学院新領域創成科学研究科)
14:30〜15:00 関東平野中部に埋没する木下層の開析谷とその意義(仮題) 中澤 努(産総研地質情報研究部門)
15:00〜15:10 ― 休憩 ―
15:10〜15:40 筑波山周辺の丘陵と台地の成り立ち、関東平野東縁の海成段丘 大井信三(産総研地質情報研究部門)
15:40〜16:10 筑波山周辺の山麓緩斜面と土石流 大八木規夫(深田地質研究所)
16:10〜16:55 ― 総合討論 ―
16:55 終了あいさつ
問い合わせ・参加申し込み:
つくば市ジオパーク室(geo298@city.tsukuba.lg.jp)宛に、Subject欄に「関東平野シンポ」と記入し、本文中に参加者の氏名(所属)をご記入下さい。
詳細は下記サイトをご参照下さい.
https://tsukuba-geopark.jp/
2019 サイエンスカフェ
2019.6.7掲載
サイエンスカフェ
「マンネン × シバハラ × 立体地図(ブラマンネン2)」開催のお知らせ
〜話題の火山学者・萬年一剛氏とブラタモリでも使用される立体地図の制作協力者にして古生物学者でもある芝原暁彦氏によるトークセッション〜
ゲストスピーカー:萬年一剛氏(神奈川県温泉地学研究所)・ 芝原暁彦氏(地球科学可視化技術研究所)
ファシリテータ:岡山悠子氏(科博SCA)
日時:2019年6月9日(日) 15-17時(14時半開場)
場所:Bar de 南極料理人 Mirai
関内駅(JR根岸線・横浜市営地下鉄)より徒歩4分/馬車道駅(みなとみらい線)より徒歩10分
入場料:2,000円(1ドリンク込み)(*イベント終了後に演者と希望者による懇親会を開催します(4000円別途))
詳細・お申込みは下記ウェブサイトをご参照下さい.
https://sites.google.com/view/buraman2/
2019年度 清澄フィールドキャンプ
2019.4.25掲載
2019年度 清澄フィールドキャンプ 参加者募集
今年度も引き続き京都大学理学部地球惑星科学専攻地質学鉱物学教室のご支援を受け,フィールド教育の継承・発展を目的とした清澄フィールド・キャンプを実施します。実習フィールドは東京大学千葉演習林(清澄)内の七里川ならびにその支流ですが,地質調査の基礎的な訓練を行うには,第1級のエリアです.京都大学が行う清澄山実習と同時期に,同じカリキュラムで実施しますので教育効果が高まります.地質調査の基礎を習得したい学生の皆さんのご参加をお待ちしています.また,先生方には募集のご連絡などご高配を賜りたく存じます.昨年の実施報告は、学会ニュース誌(2018年10月号)に掲載されております.
主催:日本地質学会関東支部
協力:石油資源開発株式会社,株式会社ダイヤコンサルタント
期間:2019年8月19日(月)〜8月24日(土) 5泊6日
場所:東京大学演習林(〒299-5505 千葉県鴨川市清澄)
費用:40,000円程度を予定(宿泊・食事・保険・タクシー代込)
ただし,日本地質学会の学生・院生会員,または日本地質学会に入会することを確約できる学生・院生は,20,000 円とします.
定員:最大4名(学生のみ,最少催行人数は3名)
応募締切日:7月5日(金)(*応募書類は所定のフォーマットを使用のこと)
応募書類:
・募集要項及び申込書はこちら (PDFファイル)
・昨年度の実施報告はこちら (PDFファイル)
お問合せ先:日本地質学会関東支部(kanto@geosociety.jp)
(終了)サイエンスカフェ
サイエンスカフェ
「磁場ニャン??いやいや,チバニアン」開催のお知らせ
日本地質学会関東支部では,上記サイエンスカフェを開催します.
奮ってご参加ください.
日時:2019年1月27日(日)14時開場,14時半〜16時ころ
場所:イタリアンレストランACQUA E SOLE(アクアエソーレ)
ダイワロイネットホテル千葉中央 一階(京成線 千葉中央駅から徒歩1分,JR・京成線 千葉駅 から徒歩7分)
入場料:2,000円(ソフトドリンク飲み放題.アルコールは一杯のみ)
ゲストスピーカー:岡田誠(茨城大学)
ファシリテータ:岡山悠子(科博SCA)
詳細・お申込みは下記サイトをご参照下さい.
https://sites.google.com/view/chibanian/
議事録(-2017)
>最近の議事録はこちらから
■執行理事会
2022年度
第1回(22.7.9)
第2回(22.8.27)
第3回(22.10.8)
第4回(22.11.12)
第5回(22.12.10)
第6回(23.1.21)
第7回(23.2.11)
第8回(23.3.4)
第9回(23.4.8)
第10回(23.5.20)
2021年度
第1回(21.7.10)
第2回(8.1)
第3回(8.28)
第4回(9.11)
第5回(10.9)
第6回(11.13)
第7回(12.11)
第8回(22.1.8)
第9回(22.2.5)
第10回(22.3.19)
第11回(22.4.9)
第12回(22.5.14)
2020年度
第1回(20.6.13)
第2回(7.11)
第3回(8.1)
第4回(9.12)
第5回(10.10)
第6回(11.14)
第7回(12.5)
第8回(21.1.9)
第9回(2.13)
第10回(3.15)
第11回(4.3)
第12回(5.8)
第13回(6.12)
2019年度
第1回(19.6.29)
第2回(7.25)
第3回(9.2)
第4回(10.26)
第5回(11.23)
第6回(20.1.11)
第7回(2.16)
第8回(3.14)
第9回(4.4)
第10回臨時(4.21)
第11回臨時(4.22)
第12回臨時(5.7)
第13回臨時(5.23)
2018年度
第1回(18.6.16)
第2回(8.6)
第3回(9.4)
第4回(10.20)
第5回(11.23)
第6回(19.1.12)
第7回(2.23)
第8回(3.23)
第9回(4.6)
2017年度
第1回(17.6.24)
第2回(7.29)
第3回(9.15)
第4回(10.14)
第5回(11.18)
第6回(12.2)
第7回(18.1.20)
第8回(3.3)
第9回(4.7)
第10回(5.19)
2016年度
第1回(16.6.11)
第2回(16.7.30)
第3回(16.9.9)
第4回(16.10.22)
第5回(16.11.19)
第6回(16.12.3)
第7回(17.1.21)
第8回(17.3.4)
第9回(17.4.1)
第10回(17.4.8)
第11回(17.5.13)
2015年度
第1回(15.6.6)
第2回(15.7.25)
第3回(15.9.5)
第4回(15.10.10)
第5回(15.11.28)
第6回(15.12.5)
第7回(16.1.23)
第8回(16.2.20)
第9回(16.3.26)
第10回(16.4.2)
第11回(16.4.23)
第12回(16.5.21)
2014年度
第1回(14.6.7)
第2回(14.7.12)
第3回(14.8.30)
第4回(14.9.12)
第5回(14.10.11)
第6回(14.11.8)
第7回(14.12.6)
第8回(15.1.24)
第9回(15.2.14)
第10回(15.3.14)
第11回(14.4.4)
第12回(15.5.23)
2013年度
第1回(13.5.18)
第2回(13.6.8)
第3回(13.7.13)
第4回(13.9.13)
第5回(13.10.12)
第6回(13.11.9)
第7回(13.12.7)
第8回(14.2.8)
第9回(14.3.8)
第10回(14.4.5)
第11回(14.5.10)
第12回(14.5.24)
2012年度
第1回(12.6.9)
第2回(12.7.14)
第3回(12.9.14)
第4回(12.10.13)
第5回(12.11.10)
第6回(12.12.1)
第7回(13.1.12)
第8回(13.2.2)
第9回(13.3.9)
第10回(13.4.6)
---
---
2011年度
第1回(11.6.18)
第2回(11.7.16)
第3回(11.9.8)
第4回(11.10.8)
第5回(11.11.12)
第6回(11.12.13)
第7回(12.1.9)
第8回(12.2.11)
第9回(12.3.17)
第10回(12.4.7)
第11回(12.5.19)
---
2010年度
第1回(10.6.5)
第2回(10.7.10)
第3回(10.9.4)
第4回(10.9.17)
第5回(10.10.9)
第6回(10.11.13)
第7回(10.12.4)
第8回(11.1.8)
第9回(11.2.12)
第10回(11.3.5)
第11回(11.4.2)
第12回(11.5.14)
2009年度
第1回(09.6.13)
第2回(09.7.11)
第3回(09.8.10)
第4回(09.9.4)
第5回(09.10.3)
第6回(09.11.14)
第7回(09.12.5)
第8回(10.1.19)
第9回(10.2.13)
第10回(10.3.13)
第11回(10.4.3)
第12回(10.5.8)
・2009年5月執行理事会議事録(2009.5.10)
・2009年4月執行理事会議事録(2009.4.11)
■理事会
2022年度
第1回定例(22.6.11)
第2回臨時(7.23)
第3回定例(9.10)
第4回定例(12.10)
第5回定例(23.4.15)
2021年度
第1回定例(21.6.12)
第2回臨時(7.18)
第3回定例(9.11)
第4回定例(12.11)
第5回定例(22.4.9)
2020年度
第1回定例(20.5.23)
第2回臨時(20.7.11)
第3回定例(20.9.12)
第4回定例(20.12.5)
第5回定例(21.4.3)
2019年度
第1回(19.5.25)
第2回(19.9.23)
第3回(19.11.30)
第4回(20.4.4)
2018年度
第1回(18.5.19)
第2回(18.9.4)
第3回(18.12.1)
第4回(19.4.6)
2017年度
第1回(17.9.15)
第2回(17.12.2)
第3回(18.4.7)
2016年度
第1回(16.5.21)
第2回(2016.9.9)
第3回(16.12.3)
第4回(17.4.8)
2015年度
第1回(2015.5.23)
第2回(2015.9.5)
▷26年度中期ビジョン検討WG提言
第3回(2015.12.5)
第4回(2016.4.2)
2014年度
第1回(2014.5.24)
第2回(2014.9.12)
第3回(2014.12.6)
第4回(2015.4.4)
2013年度
第1回(2013.5.18)
第2回(2013.9.13)
第3回(2013.12.7)
第4回(2014.4.5)
2012年度
第1回(2012.5.19)
第2回(2012.9.14)
第3回(2012.12.1)
第4回(2013.4.6)
2011年度
第1回(2011.5.21)
第2回(2011.9.8)
第3回(2011.12.3)
第4回(2012.4.7)
2010年度
第1回(2010.5.23)
第2回(2010.9.17)
第3回(2010.12.4)
第4回(2011.4.2)
2009年度
第1回(2009.9.4)
第2回(2009.12.5)
第3回(2010.4.3)
---
・2008 年度第1回理事会議事録(2009.4.4)
■総会
2022年度総会(2022.6.11)
2022年度貸借対照表_pdf
2021年度総会(2021.6.12)
2021年度貸借対照表_pdf
2020年度総会(2020.5.23 / 7.4継続会)
2020年度貸借対照表_pdf
2019年度総会(2019.5.25)
2019年度貸借対照表_pdf
2018年度総会(2018.5.19)
平成30年度貸借対照表_pdf
2017年度総会(2017.5.20)
平成29年度貸借対照表_pdf
第8回(2016年度)総会(2016.5.21)
平成28年度貸借対照表(pdf)
第7回(2015年度)総会(2015.5.23)
平成27年度貸借対照表(pdf)
2014年度臨時総会(2014.9.13)
第6回(2014年度)総会(2014.5.24)
平成26年度貸借対照表(pdf)
第5回(2013年度)総会(2013.5.18)
平成25年度貸借対照表(pdf)
第4回(2012年度)総会(2012.5.19)
平成24年度貸借対照表(pdf)
第3回(2011年度)総会(2011.5.21)
平成23年度貸借対照表(pdf)
第2回(2010年度)総会(2010.5.23)
平成22年度貸借対照表(pdf)
第1回(2009年度)総会(2009.5.17)
平成21年度貸借対照表(pdf)
*任意団体の議事録はこちらから→クリック
PDFをご覧になるには、「Adobe Acrobat Reader」をダウンロードしてご使用ください。
2019年度名誉会員
2019年度名誉会員
小玉喜三郎会員(1942年8月25日生まれ,76歳)
小玉喜三郎会員は,1969年通商産業省工業技術院地質調査所燃料部石油課に入所後,神奈川県城ヶ島の海食台に露出する中新世の三崎累層中の小断層の詳細な解析を行い,断層の活動時代の分類とそれぞれの断層の特徴を明らかにして,それを形成した応力場の復元に成功した.この研究により,日本地質学会研究奨励金(現在の研究奨励賞)を受賞し,この成果はその後の地質調査結果を加えて,5万分の1地質図幅「三崎」として公表された.さらに,堆積作用と構造運動を一体化させた地質モデルを構築し,箱形褶曲による盆地形成シミュレーションを用いて,天然ガスを含む房総半島や東京湾周辺に分布する上総層群堆積盆の解析を実施した.このことは,資源ポテンシャル評価のために論理的な解析が重要であることを示したものといえる.
1989年以降は地質調査所の管理職を歴任し,研究所の研究企画,予算配分,実施体制の整備,研究所経営の根幹をなす方針策定などの重要な職務を務めた.1997年には地質調査所の所長に就任し,国から示された通商産業省所管の研究所の統合,独立行政法人化の方針に沿って,法人化に向けた検討を主導した.そして産業技術総合研究所という新たな総合研究所のもとで社会的要請に応えるとともに,地質情報整備と国民へのサービスの体制を向上させるための基本設計を行った.法人化への改革にあたっては,産業技術総合研究所での地質関連研究部門の設置と共に,地質調査所の研究資産継承の一元的窓口としての地質調査総合センター(Geological Survey of Japan )の設置に尽力した.
これらの経済産業行政にかかわる多大な貢献により,2013年には瑞宝中綬章を受章した.
2007年から3年間,国際連合の国際惑星地球年に対応する日本の推進団体の会長として,地質科学の社会的重要性を国内外にアピールするとともに,アウトリーチ活動を重要視し,日本におけるジオパークや地学オリンピックの活動が開始されることを支援した.
日本地質学会の活動においては,1988年から1997年の10年間5期連続で評議員を務め,このうち1988,1989,1990,1992,1993,1994及び1996年の7期の長きにわたり,第二庶務委員長をはじめとする執行委員を歴任して,学会運営に多大な貢献をした.
2016年には会員を50年続けたことにより永年会員顕彰を受け,日本地質学会創立125周年にあたる2018年には,地質学の社会的認知拡大に貢献したことにより,日本地質学会125周年記念特別表彰に輝いた.
以上のように,小玉喜三郎会員は学術研究のみならず,研究行政においても日本の地質学の発展に多大な功績を残しており,あわせて日本地地質学会の運営についても多大な貢献を行った.これらの功績や貢献の内容は,日本地質学会の名誉会員として相応しいものであると判断してここに推薦するものである.
Geo暦(2020)
2020年Geo暦(行事カレンダー)
2008年版 2009年版 2010年版 2011年版 2012年版 2013年版
2014年版 2015年版 2016年版 2017年版 2018年版 2019年版
2020年版 2021年版
2020年版 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
○印は学会主催行事.(共)学会共催・(後)後援・(協)協賛
1月January
(後)北淡国際活断層シンポジウム2020
「活断層研究の新たな展開−阪神淡路大震災から25年」
1月14日(火)-17日(金)
発表申込締切:2019年12月1日 12月15日(締切延長)
参加申込締切:2019年12月15日
https://home.hiroshima-u.ac.jp/kojiok/20circularJ.pdf
水蒸気噴火のメカニズムに関する国際ワークショップ
主催:神奈川県温泉地学研究所
1月15日(水)-16日(木)
場所:研究集会:湯本富士屋ホテル(足柄下郡箱根町湯本256-1)
一般講演会:神奈川県立生命の星・地球博物館(小田原市入生田499)
研究集会への参加は事前登録が必要。締切:2019年12月25日(水)
https://www.onken.odawara.kanagawa.jp/information/20191015-01.html
○関東支部シンポジウム「関東のテフラ−最近の年代観と供給源−」
1月25 日(土)10:00〜16:30
場所:北とぴあ第1研修室(〒114-0002 北区王子1-11-1)
懇親会は事前申込必要[締切:1月17日(金)]
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
第314回地学クラブ講演会
「地震の予測と社会:日本とイタリアの地震裁判から」
1月27日(月)13:00〜15:00
場所:東京地学協会地学会館2階講堂
講演者:纐纈一起(東京大学地震研究所)
参加申込不要(どなたも無料で参加できます)
http://www.geog.or.jp/lecture/lecturescheduled/390-club314.html
第230回 地質汚染・災害イブニングセミナー
1月31日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ808会議室 (東京都北区 JR王子駅から徒歩5分)
講師: 川辺 能成(産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門 地圏環境リスク研究グループ 上級主任研究員)
演題:「3.11東日本大震災時に発生した津波堆積物の重金属の分布とその後」
会費:会員500円 非会員 1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
2月February
第197回深田研談話会
2月7日(金)18:00-19:30
場所:深田地質研究所 研修ホール(東京都文京区)
講師:石川孝織 氏(釧路市立博物館 学芸専門員)
演題:炭鉱と鉄道‐釧路炭田を中心に-
参加費無料、70名(先着)、*要事前申込
https://www.fgi.or.jp/
○関東支部ミニ巡検「大磯丘陵北東部のテフラ」
2月16日(日)
対象:会員(空きがあれば一般参加も可能)
募集:20人(先着順)
申込締切:1月31日(金)
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
(後)海洋研究開発機構海域地震火山部門講演会
「もっと知ろう,おもしろ海の火山学」
2月23日(日・祝)13:00〜15:40
会場: 国立科学博物館日本館(東京都台東区上野公園)
参加費無料,事前登録制(定員に達し次第締切)
http://www.jamstec.go.jp/rimg/j/sympo/img2019/
第231回 地質汚染・災害イブニングセミナー
2月28日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ803会議室 (東京都北区王子)
講師:國生剛治(中央大学名誉教授)
演題:「最近の地震被害から見た液状化現象の実像」
会費:会員500円 非会員 1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
○西日本支部令和元年度総会・第171回例会
→ 中止となりました(2020.2.23)
2月29日(土)例会・総会
場所:北九州市立自然史・歴史博物館 いのちのたび博物館
講演申込・参加申込:2月14日(金)締切
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
第200回湘南地球科学の会
→ 中止となりました(2020.2.26)
2月29日(土)12:30-
会場:神奈川県立生命の星・地球博物館 講義室
藤岡 換太郎 『湘南地球科学200回の回想とこれからの地球科学』
小宮 剛『冥王代の地球史解読・最古の生命の痕跡』
磯粼 行雄『日本列島:その最初と最後についての新イメージ』
小川 勇二郎『日本がプレートテクトニクスに果たした役割と今後のスコープ』
問い合わせ:山下浩之(神奈川県立生命の星・地球博物館)
yama@nh.kanagawa-museum.jp
yama-p@yk.rim.or.jp
3月March
第36回万国地質学会議→[2021年8月に延期となりました]
3月2日(月)-8日(日)
場所:インド・デリー
https://www.36igc.org/
核-マントルの相互作用と共進化:統合的地球深部科学の創成
令和元年度成果発表会
3月2日(月)〜5日(木)
場所:ホテルメルパルク松山別館3階ラフィーネ
http://core-mantle.jp
第198回深田研談話会
3月6日(金)18:00〜19:30→無期延期になりました(詳しくは)
場所:深田地質研究所 研修ホール(東京都文京区)
講師:高木秀雄氏(早稲田大学教育・総合科学学術院 地球科学教室 教授)
演題:跡倉ナップから探る日本列島の地体構造
参加費無料、70名(先着)*要事前申込
https://www.fgi.or.jp/
日本地学オリンピック とっぷ・レクチャー→中止となりました
3月15日(日)13:00-17:00
場所:筑波銀行本部ビル10階大会議室
参加無料・先着150名*聴講者募集*
http://jeso.jp/index.html
第54回日本水環境学会年会→中止となりました
3月16日(月)-18日(水)
場所:岩手大学(岩手県盛岡市)
http://www.jswe.or.jp/event/lectures/2019per.html
第9回防災学術連携シンポジウム
テーマ「低頻度巨大災害」
3月18日(水)12:30-17:30
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木)
https://janet-dr.com/
第232回地質汚染・災害イブニングセミナー→中止となりました
3月27日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ807会議室(東京都北区王子)
講師:藤川典久(気象庁地球環境・海洋部気候情報課長)
演題:「水トピック 日本の降水量〜これまでの変化と今後の見通しを中心に〜」
会費:会員500円 非会員 1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
日本堆積学会2020年島根大会→中止となりました
3月28日(土)〜30日(月)
場所:島根大学松江キャンパス
http://sediment.jp
4月April
第233回地質汚染・災害イブニングセミナー→中止となりました
4月24日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ808会議室(東京都北区王子)
講師:西口 学(国土交通省水資源部水資源政策課長)
演題:「国の水資源政策と水循環基本法」
会費:会員500円 非会員 1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
第19回重金属類・残土石処分地・廃棄物処分地診断に関わる地質汚染調査浄化技術研修会→中止となりました
4月29日(水・祝)〜5月2日(土)(4日間・部分受講可)
主催:NPO法人 日本地質汚染審査機構
会場:日本地質汚染審査機構関東ベースン実習センター(千葉県香取市)
会費:会員50,000円・非会員60,000円・学生:15,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
5月May
▶5/10地質の日関連行事の情報はこちら
JpGU2020年大会
5月24(日)-28日(木)「延期:オンライ大会へ変更]
会場:幕張メッセ(千葉市美浜区)
http://www.jpgu.org/meeting_j2020v/
6月June
地質学史懇話会→中止となりました
6月20日(土)13:30〜17:00
場所:北とぴあ8階805会議室(JR京浜東北線王子駅下車3分)
矢島道子:『地質学者ナウマン伝』を上梓して
加藤碵一:日本列島成立史あれこれ
問い合わせ先:矢島 pxi02070[at]nifty.com
4月からの大学等遠隔授業に関する取組状況共有サイバーシンポジウム
6月26日(金)10:30-12:50
主催:国立情報学研究所
https://www.nii.ac.jp/event/other/decs/
7月July
(後)第57回アイソトープ・放射線研究発表会←中止となりました
7月7日(火)-9日(木)
会場:東京大学弥生講堂
https://www.jrias.or.jp/
JpGU2020年大会: Virtual[オンライン大会]
7月12(日)-16日(木)
http://www.jpgu.org/meeting_j2020v/
防災学術連携体「令和2年7月豪雨の緊急集会」
実況中継(ライブ配信)
7月15日(水)11:20-13:00
http://janet-dr.com/
第232回地質汚染・災害イブニングセミナー
7月31日(金)18:30-20:30
場所:北とぴあ902会議室(東京都北区王子)
講師:藤川典久(気象庁地球環境・海洋部気候情報課長)
演題:「水トピック 日本の降水量:これまでの変化と今後の見通しを中心に」
定員:24名(事前申込制・先着順)
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
8月August
(後)科学教育研究協議会第68回全国大会(福島大会)
→延期になりました
8月1日(土)〜3日(月)[延期]
場所:伊達市立霊山中学校(福島県伊達市)
https://kakyokyo.org/
国際ゴンドワナ研究連合(IAGR)2020年総会及び
第17回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム←中止となりました
8月30日〜9月1日 会議とシンポジウム
9月2日〜7日 アルタイ山地巡検(L)・2日〜5日 アルタイ山地巡検(S)
場所:ノボシビルスク(ロシア)
参加申込:3月1日まで(発表要旨:4月30日まで)
問合せ・参加申込・発表要旨送付先:
iagr2020@igm.nsc.ru & inna@igm.nsc.ru
9月September
第38回有機地球化学シンポジウム
(2020年筑波山シンポジウム)
9月2日(水)-4日(金)[中止・来年に延期]
会場:茨城県つくば市)
http://www.ogeochem.jp/index.html
第19回国際物質組織学会議(ICOTOM19)
9月6日(日)-11日(金)[中止・2021年に延期]
場所:大阪府立大学
http://icotom19.com/
日本地球化学会2020年度定時総会・各賞授賞式・受賞講演[WEB]
9月15日(火)総会・授賞式・受賞講演ほか
※学術講演は11月に予定されています。
http://www.geochem.jp/information/info/2020/200803.html
日本鉱物科学会2020年年会
9月16日(水)-18日(金)[オンライン大会]
(注)総会、授賞式のみ9/15に会場で実施
場所:東北大学青葉山新キャンパス
*講演要旨の閲覧とZOOMへの参加は無料
*参加申込締切:9/10(木)
http://jams.la.coocan.jp/2020nenkai/2020_nenkai_HP.html
○日本地質学会第127年学術大会
9月9日(水)-11日(金)[中止・1年延期]
会場:名古屋大学東山キャンパス
http://www.geosociety.jp/science/content0119.html
▶︎大会の開催中止(延期)と代替企画について(2020/5/25)http://www.geosociety.jp/faq/content0910.html
第37回歴史地震研究会 (伊賀大会)
9月26日(土)-29日(火)
場所:ハイトピア伊賀(三重県伊賀市)
http://www.histeq.jp/kenkyukai.html
2020年度第1回(初心者向け)地質調査研修
9月28日(月)-10月2日(金)
室内座学:茨城県つくば市(産総研)
野外研修:茨城県ひたちなか市、福島県いわき市
定員 6名(最小催行人数:4名)(定員になり次第締切)
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2020-1.html
(共)原子力総合シンポジウム2020
主催:日本学術会議総合工学委員会原子力安全に関する分科会
9月 30日(水) 13:00 -17:10
オンライン開催
参加費:無料( 事前登録制)
http://www.scj.go.jp/ja/event/2020/295-s-0930.html
10月October
(協)テクノオーシャン2020
テーマ:~海で会いましょう~ ーMeet at Ocean-[開催延期]
10月1日(木)-3日(金)
会場:神戸国際展示場
https://www.techno-ocean.com/
ぼうさいこくたい2020 HIROSHIMA[WEB]
頻発化する大規模災害に備える
−「みんなで減災」助け合いをひろげんさい−
10月3日(土)
http://bosai-kokutai.jp/
日本火山学会2020年秋季大会[WEB]
10月8日(木)-10日(土)
http://www.kazan.or.jp/doc/kazan2020/
(後)藤原ナチュラルヒストリー振興財団
設立40周年記念 公開シンポジウム→中止となりました
「海と地球の自然史−変わりゆく海洋環境から
海洋プラスチックごみまで地球の問題を考える−」
10月10日(土)13:30-16:30
場所:東北福祉大学仙台駅東口キャンパス
http://fujiwara-nh.or.jp/
「おうちで深田研」深田研一般公開2020オンライン
10月25日(日)10:30-15:00 WEB配信
「研究所紹介」および「化石の日2020スペシャルトーク」
のプログラムを配信します。
参加費無料 *要事前登録(申込締切10/21)
https://fukada-g.jp/?p=5134
2020年度第2回(経験者向け)地質調査研修
10月26日(月)-30日(金)
場所:島根県出雲市長尾鼻周辺(小伊津海岸)
定員:6名(定員になり次第締切)
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2020-2.html
日本地震学会2020年度秋季大会[オンライン開催]
10月29日(木)-31日(土)
https://www.zisin.or.jp/
11月November
第74回日本人類学会大会(山梨大)
11月1日(日)-11月3日(火・祝)
会場:山梨大学医学部キャンパス
http://anthrop-meeting.sakura.ne.jp/
ICDP掘削提案促進ワークショップ
「新たな掘削提案の展望-陸上から海洋まで-」
11月5日(木)- 6日(金)両日とも9:00-12:00
オンライン開催(Zoomミーティング使用)
主催:日本地球掘削科学コンソーシアム(J-DESC)
どなたでも参加できます。
http://j-desc.org/icdp_ws_2020/
日本堆積学会2020年オンライン大会
11月7日(土),14日(土):特別講演・個人講演,懇親会
(発表者が少ない場合には11月14日のみとなる場合があります)
参加費:一般会員,学生会員,非会員一般,非会員学生 すべて無料
講演申込締切:9月25日(金)
大会参加申込締切:11月11日(水)
http://www.sediment.jp/04nennkai/2020/2020online_annai.html
第31回 地質汚染調査浄化技術研修会→中止となりました
11月13日(金)〜15日(日)
主催:NPO法人日本地質汚染審査機構
会場:NPO法人日本地質汚染審査機構 関東ベースン実習センター
参加費用:会員45,000円・非会員 55,000円・学生:15,000円
*要事前申込
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
(協)第36回ゼオライト研究発表会
11月19日(木)-20 日(金)
場所:富山国際会議場
https://jza-online.org/events
(共)日本地球化学会第67回オンライン年会
11月12日(木)-26日(木)WEB上での発表資料に対する議論
11月19日(木)-21日(木)Zoomでのセッション企画
(注)地質学会員は地球化学会員と同じ参加費
(一般:2000円/学生:無料)で参加できます.
講演申込締切:9月23日(水)17時
参加申込締切:11月4日(水)17時
https://www.geochem-conf.jp/
第233回地質汚染・災害イブニングセミナー
11月20日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ701会議室(東京都北区王子)
講師:紱永朋祥 (東京大学大学院教授・日本地下水学会会長)
演題:沿岸域の地下水学―様々な時間スケールの現象を追って―
定員:24名(事前申込制・先着順)
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
堆積学スクール2020
「石油地質学の基礎と地下地質データの堆積学的解析」
11月21日(土)10:00開始,22日(日)16:00終了予定(1日目のみの参加可)
実施形態:Zoomを使用したオンライン開催
参加費:一般会員・学生会員 無料,非会員一般2,000円,非会員学生 1,000円
申込締切:11月13日(金)
http://sediment.jp/04nennkai/2020/school.html
材料研究の最新成果発表週間:ニムスウィーク2020
11月25日(水) -27日(金)
オンライン開催
参加無料(事前登録制)先着600名限定
https://www.nims.go.jp/nimsweek/
(後)第30回環境地質学シンポジウム
11月27日(金)・28日(土)
WEB開催(Zoomミーティング使用予定)
https://www.jspmug.org/envgeo_sympo/30th_sympo/30th_sympo.html
12月December
日本原子力研究開発機構
深地層の研究施設計画に関する報告会2020
12月1日(火)13:00-16:00
YouTubeライブ配信(事前申込制)※視聴は無料
参加申込締切:11月20日(金)
https://www.jaea.go.jp/04/tisou/houkokukai/houkokukai_r02.html
令和2年度自然史学会連合講演会
「九州北部から広がる自然史研究:化石からランまで」
12月6日(日)13:30-15:30
場所:北九州市立いのちのたび博物館(ガイド館)
定員:80名(申し込み制)*11月25日締切
http://www.kmnh.jp/2020/11/8226/
○関東支部「オンライン講演会−おうちで学ぶ恐竜研究の最前線−」
12月12 日(土)13:00〜15:00
Zoomによるオンタイム、オンライン方式
申込期間 11月12日(木)より12月5日(土)まで
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html#201212
海と地球のシンポジウム2020
12月17日(木)-18日(金)
東京大学大気海洋研究所・JAMSTEC共催
プログラム公開しました(11/25)
http://www.jamstec.go.jp/j/pr-event/ocean-and-earth2020/
学術会議公開シンポジウム(オンライン)
「続発する大災害から史料を守る−現状と課題−」
(第25回史料保存利用問題シンポジウム)
12月19日(土) 13:30
参加費無料・定員300人・先着受付
要事前申込
http://www.scj.go.jp/ja/event/2020/295-s-1219.html
地質学史懇話会→中止となりました
12月25日(金)13:30より
会場:北とぴあ 701号室(東京都北区王子)
志岐常正:戦後京大地質学教室史ーその虚像と実像
矢島道子:『地質学者ナウマン伝』を上梓して
問い合わせ先:矢島 pxi02070[at]nifty.com
四国支部
四国支部
2024.5.1更新
※四国支部旧ウェブサイトはこちら(2020.12月末まで閲覧可)
2024-2025 年度(2024年4月〜2026年3月)の⽀部運営体制は以下の通りです.
所在地:徳島大学
⽀部⻑:寺林 優(香川⼤学) 支部長あいさつ
代表幹事・事務局⻑:安間 了(徳島⼤学)
▷四国支部規則・運営規則(2010年12月11日施工,2019 年12月14日一部改正,2020 年12月5日一部改正)
[お知らせ]
第23回支部総会・講演会(2023.12.2開催)
第22回支部総会・講演会(2022.12.3開催)
第21回支部総会・講演会のご案内(2021.12.4開催)講演要旨掲載しました
第20回支部総会・講演会のご案内(2020.12.5開催)
----------------------------------------------------------------
第19回支部総会・講演会のご案内(2019.12.14開催)
第19回支部講演会プログラム・優秀講演賞5件
赤石山荘存続の要望書(2019.6.14)
支部長あいさつ(2024年4月〜2026年3月)
寺林 優(香川大学・創造工)
2024年4月からの日本地質学会四国支部長に選任された寺林です.前支部長の近藤康生先生(高知大学)の後を引き継ぎ, 今後2年間,四国支部の運営を代表幹事・事務局長の安間了先生(徳島大学)と協力して務めさせていただきます.
2024年は,1月1日に令和6年能登半島地震が発生し,最大震度7を観測した能登半島での甚大な被害に加え,富山県や新潟県でも大きな被害を被りました.地震および津波の発生メカニズムについての調査・研究が行われていますが,発生直後から地下流体や海底地滑りなどが原因でないかと多数の研究者がコメントして報道されています.前者については,2010年にIsland Arc誌に特集号“Fluid-rock interaction in the bottom of the island seismogenic zone”を企画した以前に,地元テレビ局から定説でないことは放送できないと言われたのとは隔世の感があります.
4月17日には豊後水道の深さ39キロメートルを震源とするマグニチュード6.6の地震が発生し,四国で初めて震度6弱を観測しました.来るべき南海トラフ巨大地震への備えが急務であることを再認識した方も多いようです.豪雨災害の多発に対しても地球科学分野の研究や知識が必要とされています.各地のジオパークの活動や各世代を対象としたテレビ番組の影響によって,地質学は身近な学問となっているようです.一方で,次世代研究者の育成については,四国内の各大学独自に委ねるのではなく連携することも必要となるかもしれません.
2025年に四国支部は設立25周年を迎えます. 四国支部は, 四国地区の地質学的研究・教育・普及活動などを目的に, 研究者・学生・企業人/一般を問わず誰でも参画でき, 四国地区の連携を深める支部を目指し, 活動を進めてまいりました. その節目に当たっての記念行事を企画できればと考えています. 2年間の任期ではありますが, 支部活動や四国内の連携が発展するよう微力を尽くしたいと思います.何卒よろしくお願い申し上げます.
支部行事2023
第23回四国支部 総会・講演会
第23回日本地質学会四国支部講演会を以下の通り開催しました.<プログラム・講演要旨集>はこちらから.
<講演会>
日時:2023年12月2日(土) 13:00〜17:00
場所:高知大学海洋コア国際研究所セミナー室(高知県南国市物部乙200高知大学物部キャンパス内)
<総会>
講演会終了後に同会場にて.
また,同講演会において,以下の6件の講演が学生賞に選ばれました.
<優秀講演賞(口頭発表)>
O2 Geochemical changes in groundwater before and after the 2018 Hokkaido earthquake: Zahra Zandvakili(高知大)ほか
O5 水槽実験の知見から推定する火星のデルタ地形の形成過程:鬼頭 蓮(高知大)ほか
<優秀ポスター賞>
P4 島根県東部に分布する山陰帯花崗岩類の固結温度・圧力の見積もり:中橋甲斐・齊藤 哲(愛媛大)
P12 北海道留萌郡小平町から産出した束柱類の上腕骨化石の再検討:三藤万琳・鍔本武久(愛媛大)
P11 愛媛県梶島における白亜紀花崗岩質マグマ生成プロセス:下岡和也(愛媛大)ほか
P14 砂箱実験の荷重データから考える付加ウェッジの変形サイクル:金澤征一郎(高知大)ほか
支部行事2022
第22回四国支部 総会・講演会
第22回日本地質学会四国支部講演会を以下の通り開催しました.<プログラム・講演要旨集>はこちらから.
<講演会>
日時:2022年12月3日(土) 13:00〜17:00
場所:高知大学朝倉キャンパス共通教育棟210室(高知市曙町2-5-1高知大学朝倉キャンパス内)
<総会>
講演会終了後に同会場にて.
また,同講演会において,以下の6件の講演が学生賞に選ばれました.
<優秀講演賞(口頭発表)>
O6 周氷河地形から読み解く過去から現在の火星地下氷分布の変遷 〜地球アナログのモンゴル調査の知見から〜:佐古貴紀(高知大)ほか
O8 愛媛県伯方島北部トウビョウ鼻周辺に産する閃長岩の成因検討:福井堂子・齊藤 哲(愛媛大)
<優秀ポスター賞>
P8 地震サイクルに伴う動的な流体圧変動量の地質学的制約:細川貴弘・橋本善孝(高知大)
P12 四国南西部御内岩体の固結圧力推定 ―ジルコンメルト包有物を用いた検討―:谷脇由華・齊藤 哲(愛媛大)
P13 現世波浪卓越型砂浜海岸にみられるPsilonichnus類の生痕学とその体積地質学的意義:吉本大志・奈良正和(高知大)
P16 高知県室戸半島に露出する古第三系室戸層に見られる乱堆積層の変形構造:松元日向子・藤内智士(高知大)
支部行事2021
第21回四国支部 総会・講演会のご案内
2021.10.18掲載 12.6 12.11更新
<第21回日本地質学会四国支部総会・講演会プログラム・講演要旨集>はこちらから
第21回支部講演会 学生賞6件:2021年12月4日(土)にオンライン(愛媛大学)で開催された第21回日本地質学会四国支部講演会において,以下の6件の講演が学生賞に選ばれました.(2021.12.11掲載)
<最優秀講演賞(口頭発表)>
O5 マンガンクラストの縞状構造は氷期-間氷期サイクルに起因するのか?:高馬菜々子(高知大)ほか
<最優秀ポスター賞>
P5 南ヨルダンの遺跡堆積物から探る後期更新世の古環境復元とホモ・サピエンス拡大との関係性:川村秀儀(高知大)ほか
<優秀講演賞(口頭発表)>
O3 高知県室戸市に露出する古第三系室戸層の砂質泥岩層と砕屑注入岩の特徴:松元日向子(高知大)ほか
O6 種子島沖海底泥火山群から採取された堆積物の地化学・年代分析による泥火山噴出機構の解明:瀬戸口亮眞(高知大)ほか
<優秀ポスター賞>
P1 絶滅種イタヤガイ科二枚貝 Amussiopecten praesignis の微細成長線分析からみた生活史:川竹 慶(高知大)ほか
P8 ジルコンメルト包有物研究:愛媛県南部御内花崗岩質岩体の例:谷脇由華(愛媛大)ほか
標記総会・講演会を,下記の通り,WEBで開催します.巡検・懇親会は実施しません.村田明広先生(徳島大学名誉教授)による特別講演を予定しています.講演会の参加に対して,技術者継続教育(CPD)の単位が認定されます.認定証の発行部数把握のため,CPD単位を希望される方は参加申し込み時にその旨お知らせ下さい.
講演会
日時:2021年12月4日(土) 13:00〜16:45(予定)
場所:WEB開催(Zoom [予定]および愛媛大学理学部地学コースHP)(本部:愛媛大学理学部)
総会
日時:2020年12月4日(土) 16:55〜17:25(予定)(講演会終了後)
場所:WEB開催(Zoom [予定])(本部:愛媛大学理学部)
<第21回日本地質学会四国支部総会・講演会プログラム・講演要旨集>はこちらから 2021.12.6掲載
講演会参加・発表申込先:鍔本(四国支部事務局):tsubamotoアットsci.ehime-u.ac.jp(アットを@に変えてください)
参加・発表申込〆切:11月19日(金)
日本地質学会の会員でない方も参加可能です.
参加申込の際には,氏名・所属・連絡先・電子メールアドレスを記してください。申し込みをされた方には,後日,Zoom [予定]の参加方法をお知らせします。
発表申込の場合は,参加申込と同時に,演題・希望発表形式(口頭/ポスター)・学生による発表の場合はその趣旨(優秀賞の対象者となるため),を付記し,講演要旨ファイル2つ(PDFとWord)を併せて添付して下さい。書式は以前の地質学会学術大会と同様とします.テンプレートは,地質学会の四国支部のHPからダウンロードできます.[PDF]・[Word] ダウンロードはこちらから
口頭発表(Zoom)の時間は,1件15分(発表12分+質疑応答3分)とします.口頭発表は,時間の都合上,8件まで受け付けます.8件を超えた場合は,学生の発表を優先します.
ポスターは,事前にPDFファイルを事務局へ送ってください(〆切:12/1(水)).ポスターのPDFは,1枚ものにして,A0サイズを目安に作成してください.PDFファイルの容量は,20MB以下としてください.送っていただいたPDFは,事務局でパスワードによるセキュリティをつけて(印刷等を不可にして)サーバに掲載します.
ポスター発表する人は,Zoom [予定]での3分間紹介(質疑応答なし)もありますので,準備をお願いします.
学生による優秀な口頭発表・ポスター発表には「優秀講演賞」・「優秀ポスター賞」を授与します.今回は,賞の決定は講演会当日ではなく,後日になります.
支部行事2020
第20回日本地質学会四国支部総会・講演会の開催予定 ※名古屋大会代替企画
2020.9.9掲載 10.21,12.4,12.9更新
第20回支部 総会・講演会のご案内 標記総会・講演会を,下記の通り,WEBで開催します.巡検・懇親会は実施しません.四国支部発足20周年を記念して,小松正幸先生(元愛媛大学学長/元理学部地球科学科教授)および山本明彦先生(元愛媛大学理学部地球科学科教授)による記念講演を予定しています.講演会の参加に対して,技術者継続教育(CPD)の単位が認定されます.認定証の発行部数把握のため,CPD単位を希望される方は参加申し込み時にその旨お知らせ下さい.
▷総会・講演プログラム・講演要旨はこちらから 2020.12.7更新
<講演会>
日時:2020年12月5日(土) 13:00〜17:05(予定)
場所:WEB開催(Zoomおよび愛媛大学理学部地学コースHP)(本部:愛媛大学理学部)
<総会>
日時:2020年12月5日(土) 17:15〜17:45(予定)(講演会終了後)
場所:WEB開催(Zoom)(本部:愛媛大学理学部)
講演会参加・発表申込先:鍔本(四国支部事務局):tsubamotoアットsci.ehime-u.ac.jp(アットを@に変えてください)
参加・発表申込締切:11月20日(金)
日本地質学会の会員でない方も参加可能です.
参加申込の際には,氏名・所属・連絡先・電子メールアドレスを記してください。申し込みをされた方には,後日,Zoomの参加方法をお知らせします。
発表申込の場合は,参加申込と同時に,演題・希望発表形式(口頭/ポスター)・学生による発表の場合はその趣旨,を付記し,講演要旨ファイル2つ(PDFとWord)を併せて添付して下さい。書式は地質学会学術大会と同様とします.テンプレートは,地質学会のHP(http://www.geosociety.jp/science/content0079.html)からダウンロードできます.
口頭発表(Zoom)の時間は,1件15分(発表12分+質疑応答3分)とします.口頭発表は,時間の都合上,8件まで受け付けます。
ポスターは,事前にPDFファイルを事務局へ送ってください(締切:12/2(水)).ポスターのPDFは,1枚ものにして,A0サイズを目安に作成してください.PDFファイルの容量は,20MB以下としてください.送っていただいたPDFは,事務局でパスワードによるセキュリティをつけて(印刷等を不可にして)サーバに掲載します.
ポスター発表する人は,Zoomでの3分間紹介(質疑応答なし)もありますので,準備をお願いします.
学生による優秀な口頭発表・ポスター発表には「優秀講演賞」・「優秀ポスター賞」を授与します.今回は,賞の決定は講演会当日ではなく,後日になります.
----------------------------------------------------------------------------------------
第20回支部講演会 優秀講演賞1件・優秀ポスター賞2件:2020年12月5日(土)にWeb(愛媛大学)で開催された第20回日本地質学会四国支部講演会において,以下の3件の講演が学生賞に選ばれました.
<優秀講演賞(口頭発表)>
O3 中新統竜串層に産する生痕化石Ophiomorpha形成者の古生態学:友直由衣(高知大)・今井 悟(高知大)・奈良正和(高知大)
<優秀ポスター賞>
P6 チリ沖コアから復元する最終氷期における南半球の偏西風経路変動:長屋芙結(高知大)・長谷川精(高知大)・長島佳菜(JAMSTEC)
P7 後期白亜紀アンモナイトScaphitesの集団解析シミュレーション:中村千佳子(愛媛大)・岡本隆(愛媛大)
支部行事2019
第19回支部総会・講演会のご案内
標記総会・講演会を今年は香川大学で開催予定です(巡検は実施しません)。講演会では、平成18年4月 に香川大学から鹿児島大学に転出された仲谷英夫先生の特別講演「香川大学での古生物研究−四国から世 界へ−」が行われます(香川大学博物館企画展「古生物研究の世界」とタイアップ)。なお,講演会の参 加者には,技術者継続教育(CPD)の単位が認定されます.
<<四国支部講演会>>
日時:2019年12月14日(土) 13:00〜17:00(予定)
場所:香川大学研究交流棟5階研究者交流スペース(高松市幸町11香川大学幸町北キャンパス内)
*総会は講演会終了後,同会場で行います.
講演会申し込み先:青矢(四国支部事務局)aoyaアットtokushima-u.ac.jp(アットを@に変えてく ださい)
講演要旨申し込み〆切:11月29日(金)
地質学会の会員でない方も参加可能です.
参加申し込みの際には氏名・所属・連絡先・電子メールアドレスを記してください.
講演要旨の書式は地質学会学術大会と同様とします.http://www.geosociety.jp/science/content0079.html#abst_form をご参照ください.
一般の口頭発表の時間は15分(質疑応答を含む)とします.口頭発表は8件まで受け付けます.
ポスターサイズは幅118cm,縦180cmを目安に作成してください.
学生による優秀な口頭・ポスター発表には「優秀講演賞」「優秀ポスター賞」を授与します.
第19回支部講演会プログラム・優秀講演賞5件
2019年12月14日(土)に香川大学で開催した第19回地質学会四国支部総会・講演会のプログラムが以下 のページからダウンロードできます.
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/outline/shibu/shikoku/2019_program.pdf
*以下の5件の講演が優秀講演賞に選ばれ,総会で表彰されました.
P5 モンゴルの年縞湖成層から復元する白亜紀中期におけるアジア内陸のオービタル~千年スケールの気候変動 石川航輝・長谷川 精・Ichinnorov N.
P8 高知県に分布する鮮新統穴内層産スダレガイ属二枚貝Paphia spp.の分類学的および系統学的検討 寒川稔朗・近藤康生・山岡勇太・中山 健太朗
P2 四国北西部,中新統久万層群明神層に含まれる火成岩礫の起源 相田和之・下岡和也・楠橋 直・斉藤 哲・谷 健一郎
O3 愛媛県北部高縄半島に分布する領家帯花崗岩類の岩石学的研究 下岡 和也・齊藤 哲
O2 アラスカ湾沿岸域における最終融氷期の古環境変動 -海底堆積物を用いた解析- 捫垣 勝哉・村山 雅史・堀川 惠司
赤石山荘存続の要望書(松田会長名)を西山支部長が代理提出(2019/6/14)
東赤石岩体(愛媛県新居浜市別子山)は沈み込み帯上盤側のウェッジマントルに由来するかんらん岩体 で,マントル物質の物理的・化学的挙動や周囲のスラブ由来物質(高圧型変成岩類)との相互作用を究明 する上で,世界的に見ても最重要地域の1つと言えます.この岩体の上,標高1550mに立つ赤石山荘が現 在,存続の危機にあります. 管理人・安森滋氏(愛媛県西条市在住)による小屋番登山842回という超人的努力により,これまで33 年間,赤石山荘は地質学者を含めた登山者に安全な宿泊先を提供し続けて来ました.ところが2018年5 月,当時75歳の安森氏が842回目の下山後に体調を崩し,自身での山荘経営を断念.後継の管理者も見つ からず,現在,山荘は安森氏の山仲間による月1回程度の臨時小屋番によってなんとか維持されています. この状況を受け,登山者の安全確保が必須と考える安森氏は,2018年10月に新居浜市に対し,また2019 年1月には愛媛県に対して次の2点を求める陳情を行いました.(1) 民営が困難となった赤石山荘を新居浜 市へ移管すること,(2) 老朽化の進む赤石山荘の現位置に新居浜市所管の避難小屋を新たに建設し,永続 的に経営すること.そして,2019年6月初頭まで,この趣旨への賛同者からの署名活動が行われていました.
地質学会は2019年4月6日,安全な研究フィールドの確保と維持を願う学術団体の立場から,新居浜市 長と愛媛県知事に対し,安森氏の陳情受け入れを求める要望書を会長名で作成し,西山賢一四国支部長に 提出を託しました.6月14日,西山支部長は安森氏らと共に石川勝行新居浜市長と面会し,4359名分の署 名と同時にこの要望書を提出しました.また愛媛県知事宛の要望書は同日,山中美幸愛媛県自然保護課長 へと提出しました.市長への提出の様子はNHK松山放送局ならびに愛媛新聞社の取材を受け,TV・web・ 紙面にて報道されました.次のURLで動画を閲覧できます(2019.8月中旬まで).
NHK松山 ひめポン!動画「東赤石山の山小屋存続求め署名提出」(2019.8月中旬まで閲覧可)
ttps://www.nhk.or.jp/matsuyama/himepon/movie/movie_190614-4.html
代議員
代議員(119名)
※代議員の任期は2024年6月8日から2026年開催予定の総会まで
※敬称略
※所属先,所属支部区の情報は当選時のものによる
(2025.4.1修正)
全国区代議員(51名)
天野 敦子 産業技術総合研究所
芦 寿一郎 東京大学大気海洋研究所
阿部 なつ江 海洋研究開発機構
安藤 寿男 茨城大学
伊規須 素子 海洋研究開発機構
石橋 隆 大阪大学総合学術博物館
伊藤 剛 産業技術総合研究所
猪股 雅美 広島大学
氏家 恒太郎 筑波大学
宇野 正起 東北大学
大藤 茂 富山大学
岡粼 啓史 広島大学
緒方 信一 中央開発(株)
奥田 花也 海洋研究開発機構高知コア研究所
小俣 雅志 (株)パスコ
折橋 裕二 弘前大学
河上 哲生 京都大学
菊川 照英 千葉県立中央博物館
斎藤 誠史 東京大学総合研究博物館
佐久間 杏樹 東京大学
佐藤 友彦 岡山理科大学
澤井 みち代 千葉大学
澤木 佑介 東京大学
清水 以知子 京都大学
志村 俊昭 山口大学
瀬戸 大暉 山形県立博物館
相田 和之 (株)蒜山地質年代研究所
高柳 栄子 東北大学
竹内 真司 日本大学
冨永 紘平 土佐清水ジオパーク推進協議会
内藤 一樹 産業技術総合研究所
中村 佳博 産業技術総合研究所
奈良 正和 高知大学
野々垣 進 産業技術総合研究所
長谷川 精 高知大学
浜橋 真理 山口大学
東野 文子 京都大学
福地 里菜 鳴門教育大学
藤代(安部) 祥子 日特建設(株)
細井 淳 産業技術総合研究所
保柳 康一 信州大学
堀 利栄 愛媛大学
松崎 賢史 東京大学大気海洋研究所
宮川 歩夢 産業技術総合研究所
武藤 俊 産業技術総合研究所
森田 澄人 産業技術総合研究所
山口 耕生 東邦大学
山粼 由貴子 日本ジオパークネットワーク事務局
山田 泰広 九州大学
山本 和幸 (株)INPEX
吉田 健太 海洋開発研究機構
地方支部区代議員(68名)
北海道支部区:1名
重野聖之 明治コンサルタント(株)
東北支部区:2名
松井浩紀 秋田大学
根本直樹 弘前大学
関東支部区:29名
井上 卓彦 産業技術総合研究所
棚瀬 充史 ㈱地圏総合コンサルタン
佐藤 大介 産業技術総合研究所
廣谷 志穂 アジア航測㈱
澤田 大毅 ㈱地球科学総合研究所
木村 英人 ㈱ソイルシステム
代永 佑輔 ㈱地圏総合コンサルタント
山下 浩之 神奈川県立生命の星・地球博物館
米岡 佳弥 産業技術総合研究所
河尻 清和 相模原市立博物館
本田 尚正 東京農業大学
向山 栄 国際航業㈱
板宮 裕実 警察庁科学警察研究所
柴田 健一郎 横須賀市自然・人文博物館
小田原 啓 神奈川県温泉地学研究所
羽田 裕貴 産業技術総合研究所
原 英俊 産業技術総合研究所
池田 昌之 東京大学
佐々木 聡史 群馬大学
志村 侑亮 産業技術総合研究所
鈴木 克明 産業技術総合研究所
三澤 文慶 産業技術総合研究所
乾 睦子 国士舘大学
入野 寛彦 ㈱地圏総合コンサルタン
杉田 匠平 大日本ダイヤコンサルタント㈱
冨田 一夫 鹿島建設㈱
外山 浩太郎 神奈川県温泉地学研究所
納谷 友規 産業技術総合研究所
方違 重治 国土防災技術㈱
中部支部区:15名
安江 健一 富山大学
長谷部 徳子 金沢大学
藤田 将人 富山市科学博物館
常盤 哲也 信州大学
森 宏 信州大学
平内 健一 静岡大学
高橋 聡 名古屋大学
片岡 香子 新潟大学
小林 健太 新潟大学
山本 博文 福井大学
竹内 誠 名古屋大学
福地 龍郎 山梨大学
山田 昌樹 信州大学
大谷 具幸 岐阜大学
纐纈 佑衣 名古屋大学
近畿支部区:9名
川勝 和哉 兵庫県立姫路東高等学校
松原 典孝 兵庫県立大学
栗原 行人 三重大学
小泉 奈緒子 和歌山県立自然博物館
里口 保文 滋賀県立琵琶湖博物館
田中 里志 京都教育大学
窪田 安打 応用地質㈱
大串 健一 神戸大学
谷 保孝 大阪工業大学
四国支部区:3名
齊藤 哲 愛媛大学
藤内智士 高知大学
寺林 優 香川大学
西日本支部区:9名
Rehman Ur Hafiz 鹿児島大学
遠藤 俊祐 島根大学
太田 泰弘 北九州市立自然史・歴史博物館
池上 直樹 御船町恐竜博物館
隅田 祥光 長崎大学
佐藤 峰南 九州大学
菅森 義晃 鳥取大学
冨松 由希 九州大学
山下 大輔 薩摩川内市役所
2020年度名誉会員
2020年度 名誉会員
西村 祐二郎(にしむら ゆうじろう)会員(1940年2月25日生、80歳)
西村祐二郎会員は,1963年に広島大学教育学部を卒業後,同大学大学院理学研究科修士課程および博士課程に進学した.1967年に山口大学に助手として赴任し,1974年には同大学理学部助教授となり,1984年には同大学教養部教授に昇任した.その後,1996年から同大学理学部教授を務め,2003年同大学を定年退職した.この間,1971年に理学博士の学位を取得し,2003年には山口大学名誉教授を授与された.
西村会員は,三郡変成岩・弱変成古生層の変成岩岩石学・年代学・テクトニクスに関する研究を一貫して行ってきた.そのなかで,白雲母や角閃石のK-Ar年代を柴田賢氏との共同研究で行い,「三郡帯」が3つの高圧変成帯の複合(三郡―蓮華帯,周防帯,智頭帯)であることを提唱した.その後,板谷徹丸氏と共同でスレート(ブドウ石―パンペリー石相程度の弱変成岩)から再結晶白雲母を高純度に分離してK-Ar年代を測定することに成功した.
中・古生代の弱変成岩が付加体とみなされるようになった1980年代以降は,その手法を三郡―中国帯だけでなく,長崎変成岩,美濃―丹波帯や秩父帯などの付加体の変成年代の解明にも応用して,微化石による海洋プレート層序の復元と組み合わせることにより,日本列島の形成発達史を大きく書き換えた.
西村会員は,1962年に日本地質学会に入会し,1985年の第92年学術大会(山口大会)では大会実行委員会の事務局長として大会を成功裏に導いた.また,2000年から2002年まで西日本支部長として支部活動の活性化に尽力した.
地域社会においては,35年に及ぶ山口大学での教育・研究成果を生かして,山口県土地分類基本調査員,山口県文化財保護審査会委員や山口県温泉審議会委員など,国や自治体の各種委員を多数務めた.このほか,改訂を8回も経た「山口県地質図(1/20万,1/15万)」やその説明書の出版に大いに関与した.また,1990年に第一学習社から出版された「山口県の岩石図鑑」はベストセラーとなり,今後の再版を望む声は大きい.
西村会員の地球科学に関する普及活動はこれらにとどまらず,地学のガイドシリーズ「山口県の地質とそのおいたち」,日曜の地学「山口県の地質をめぐって」など多数の著書を世に送り出した.山口大学退職後も,高校の「地学Ⅰ」,「理科総合A,B」の教科書や参考書,大学の「教養の地学」,「基礎地球科学」の執筆,日本地方地質誌「中国地方」の編集・執筆を行った.
以上のように,西村祐二郎会員の地質学における学術研究,教育,普及,そして日本地質学会の運営への多大な貢献は,日本地質学会の名誉会員として相応しいものと判断し,ここに推薦する.
小松 正幸(こまつ まさゆき)会員(1941年8月6日生、78歳)
小松正幸会員は,1965年に北海道大学理学部を卒業後,同大学大学院理学研究科修士課程および博士課程に進学した.1971年に新潟大学に助手として赴任し,1976年には同大学理学部助教授となり,1987年には愛媛大学理学部教授に昇任した.その後,1996年に同大学理学部長を務めた後,2003年から2009年に同大学学長に就任した.この間,1971年に理学博士の学位を取得し,2009年には愛媛大学名誉教授を授与された.
小松会員は,1965年代以降,北海道の日高変成帯に関する多数の地質学的研究成果を挙げ,従来の日高変成帯の解釈とはまったく異なる画期的な到達点を築き上げた,すなわち,1950年代以来提唱されていた地向斜造山運動にもとづく日高変成帯が,大陸性地殻と海洋性地殻の接合衝上体であることを明らかにした.これらの研究によって,日高変成帯のグラニュライト相を含む高温型変成岩類は,世界でも最も若い年代を示す構造体であることを示し,さらに下部地殻を含めた島弧および大陸性の地殻の形成に関して,画期的なモデルを提唱した.
小松会員の研究は日高変成帯にとどまらず,神居古潭帯,中部日本の飛騨帯,飛騨外縁帯,上越帯,足尾帯および領家帯,さらには西南日本の領家帯など日本列島の主要な構造帯にも及んでいる.これら構造帯に産出する蛇紋岩,オフィオライト,メランジェ,高温型変成岩および高圧型変成岩など広い分野にわたる研究対象について,多くの新事実を発見し,島弧地域における新しいテクトニクス・モデルを提唱した.
また,これらの研究を通じて,自然を観察する野外研究の面白さや重要性を学生に伝え,第一線で活躍する地質技術者ならびに研究者を多数育成した.1993年には,日高変成帯をはじめとする日本列島の高温変成帯についての研究業績により,日本地質学会賞が授与された.
小松会員は,1964年に日本地質学会に入会し,1988年から1994年に評議員を,1994年から1998年に副会長をそれぞれ務め,1998年から2002年に学会長としての重責を果たした.学会長として日本地質学会の様々な改革を行い,その後の学会法人化の基礎を築いた.また,2003年に日本学術会議第19期会員に就任し,日本の学術活動の発展に貢献した.加えて,2003年からの6年間は愛媛大学学長として国立大学法人化を機に大学改革を進め,日本を代表する地球科学分野の世界的な教育拠点となる「地球深部ダイナミクス研究センター」を設立させ,その発展に貢献したことは特筆に値する.
以上のように,小松正幸会員の地質学における学術研究,教育,普及,そして日本地質学会の運営への多大な貢献は,日本地質学会の名誉会員として相応しいものと判断し,ここに推薦する.
以上
会議でのzoomの使用に関して
会議、行事でのzoomの使用に関して
Web会議サービス:Zoom(https://zoom.us/jp-jp/meetings.html)を活用した会議開催にあたり、ご利用方法などをご案内します。
具体的には、事前に事務局から会議(ミーティング)への招待URLを配信します。
インターネットに接続できるPC、スマホ等があれば、URLをクリックしていただくだけで、会議に参加することができます。
(1)ご準備いただく環境
インターネット接続環境:高規格の通信環境は必要ありません。スマホでもアクセス可。ただし、長時間接続になるので、データ通信量をかなり消費します。(例:1時間で1GB消費)。Wi-Fiでの接続をお勧めします。
PC(内臓カメラ、マイク):ヘッドフォンや外付マイクがあれば快適です。
(2)セッティング
初めて利用する方法 https://zoomy.info/manuals/what_is_zoom/#04
2021年度 名誉会員
2021年度 名誉会員
田崎 和江(たざき かずえ)会員
(1944年3月10日生,77歳,金沢大学名誉教授)
田崎和江会員は,1968年に東京学芸大学教育学部を卒業後,1980年から1988年までカナダにおいてカナダ地質調査所堆積学石油地質学研究所のカナダ政府客員研究員やウエスタン・オンタリオ大学のリサーチアソシエイト及び主任研究員などを歴任した.1988年より島根大学理学部助教授を経て,1993年より金沢大学理学部教授を務め,2009年同大学を退職した.退職後は, タンザニアのドドマ大学などの客員教授を務めている.この間,1977年に東京教育大学より理学博士の学位を取得し,2009年には金沢大学の名誉教授を授与された.
田崎会員の研究史は,電子顕微鏡を用いた粘土鉱物学から始まっている.1974年に日本地質学会研究奨励賞を受賞した後,1980年から1988年までの間,カナダにおいて大気・水・土壌に関わる環境科学研究に専念し,地球表層部での低温の水―岩石作用に伴う粘土鉱物の形成過程に関する研究で優れた業績を残した.1989年に一連の研究成果が認められ,世界粘土学会においてベスト3女性科学者賞の一人に選ばれた.
日本帰国後は,生体鉱物化作用に着目した地球環境学関連分野の研究を精力的に行い,国内における「環境鉱物学」の創設と発展を牽引してきた.特に,温泉バイオマット中での鉱物生成過程や微生物による生体鉱物中への有害元素除去過程に関する研究は,環境浄化作用の応用研究への先駆的な成果となった.また,ナホトカ号重油流出事故調査時には重油分解細菌を発見するなど,多くの新発見を続けてきた.田崎会員はこのような持続可能な地球環境へ貢献する広義の地質学的研究テーマに加え,社会と連携して推進する市民科学的な学術活動にも積極的に参画してきた. 田崎会員は, 日本地質学会において1994年から2007年までの13年間評議員を務め,各賞選考委員長に幾度も就任するなど,長きにわたって学会運営に貢献した.特に学会における男女共同参画の重要性を説き,1994年に”女性地球科学者地位向上委員会“(仮称)の設立を呼びかけ,1995年の第102年総会・年会(広島大会)において「女性地球科学者の未来を考える委員会」の設置に尽力し,初代委員長として2008年までの長きにわたって活動した.同委員会は2008年に「男女共同参画委員会」,2020年に「ジェンダー・ダイバーシティ委員会」と現在に継続されている.田崎会員の活動は,今では当たり前となっている「ダイバーシティ推進」に対する学会内での意識改革をもたらすことに大いに貢献している.
以上のように,田崎和江会員の地質学における学術研究,教育,普及,そして日本地質学会の運営への多大な貢献は,日本地質学会の名誉会員として相応しいものと判断し,ここに推薦する.
伊藤 谷生(いとう たにお)会員
(1945年8月5日生,75歳,千葉大学名誉教授)
伊藤谷生会員は,1977年に東京大学大学院理学系研究科を修了後,同年より東京大学理学部助手,1990年より同大学理学部助教授を経て,1991年より千葉大学理学部教授を務め,2011年に同大学を退職した.その後2011年から2016年まで帝京平成大学現代ライフ学部教授を務め,2017年より地震予知総合研究振興会副主席主任研究員を務めている.この間,1997年に東京大学より理学博士の学位を取得し,2011年には千葉大学名誉教授を授与された.
伊藤会員は,日本のテクトニクス研究の第一人者として,フィールド調査と反射法地震探査結果を用い日本列島の構造形成の研究に尽力した.特に,千葉大学在職中には,日本の地質学に反射法地震探査を本格的に導入して,中央構造線,日高衝突帯,伊豆弧衝突帯などの深部地殻構造の解明を精力的に行い新たな知見をもたらした.これらの知見は単に日本列島の構造発達に対するだけでなく,活断層等の現在のテクトニクスを理解する上でも重要なものである.最近では,わが国の活断層で最大の変位速度を有する富士川河口断層帯の浅部から深部にかけての構造の研究を進めるとともに,全国の活断層のなかから震源断層の抽出に取り組んでいる.これらの研究に対して,1997年に日本地質学会論文賞を,2003年に日本地質学会賞をそれぞれ受賞している.
伊藤会員は,活断層を市民に広く理解してもらうため,地震調査研究推進本部が進めている活断層による地震危険度を地域ごとに総合的に評価する「活断層の地域評価」にも参画している.その成果として,現在「九州地域」,「関東地域」,「中国地域」,「四国地域」が公表されており,各地の地域地震防災に役立っている.伊藤会員のこれらの活動は,地質学の社会還元という観点からも大きな貢献を果たしていると言える.
伊藤会員は,2008年の日本地質学会法人化以前に評議員を長らく務め,2000年から2004年に日本地質学会行事委員長,2006年から2008年に日本地質学会副会長をそれぞれ歴任した.2008年から2011年に日本地質学会関東支部長を務めるなど,日本地質学会の学会運営に長らくかつ大きな貢献をした.
以上のように,伊藤谷生会員の地質学における学術研究,教育,普及,そして日本地質学会の運営への多大な貢献は,日本地質学会の名誉会員として相応しいものと判断し,ここに推薦する.
田結庄 良昭(たいのしょう よしあき)会員
(1943年12月11日生 77歳 神戸大学名誉教授)
田結庄良昭会員は,1967年に大阪市立大学大学院理学研究科修士課程(地質学専攻)を修了し,1970年に大阪市立大学大学院理学研究科博士課程を中途退学した後,同年神戸大学教育学部助手に就任した.1979年より同大学教育学部助教授を経て,1995年より同大学発達科学部教授を務め,2007年に同大学を定年退職した.退職後は,2009年から2014年まで放送大学兵庫学習センター客員教授を務めた.この間,1973年に大阪市立大学より理学博士の学位を取得し,2007年には神戸大学の名誉教授を授与された.
田結庄会員は,地球規模での花崗岩の研究,震災や災害に係る都市地質の研究やディーゼル車由来の微粒子などの環境地質の研究など,幅広い分野での研究を長きにわたり行ってきた.
花崗岩を対象とした研究では,岩体周縁部が塩基性で中心部が酸性となる累帯深成岩体を日本で初めて発表し,1972年日本地質学会奨励賞を受賞した.その後,日本で多くの累帯深成岩の存在を明らかにし,導入初期のEPMAを用いて花崗岩マグマの分化作用の定量的な検討を行った.また,日本における花崗岩が火成岩起源のIタイプと堆積岩起源のSタイプのふたつがあることを明らかにし,模式地のオーストラリアに1年留学して,世界の花崗岩との対比を行った.さらに,南極観測隊に参加し,内陸部のセールロンダーネ山地の調査において高温での変成岩の存在や花崗岩のタイプ分類の研究を行い,それらがインド半島南部の変成岩と同じものであり,両者が一つの巨大大陸であったことを明らかにした. 震災や災害に係る都市地質の研究では,1995年の兵庫県南部地震において建物被害の程度は地盤や地下水位の深さと密接に関係することを示した.また,2007年の兵庫県佐用豪雨,2011年の紀伊半島豪雨,2018年の西日本豪雨などについては現地調査を行い,堤防が決壊する原因についての検討を行った.
環境地質に関する研究では,大気中や道路わき粉塵の微粒子の実態とその由来について分析電子顕微鏡を駆使した研究を行った.その結果,微粒子の多くがディーゼル車由来の排気物からなり,その多くが炭素からなるが,鉛など重金属も含むことを明らかにし,環境汚染分野における研究の進展に大きく貢献した.
田結庄会員は,1994年から2001年までの間に,日本地質学会の評議員を3期務め,学会運営に貢献した.また,2000年から2003年まで日本学術会議地球化学宇宙化学研究連絡委員会(現在のIAGC(国際地球化学連合)小委員会)の委員を務めるなど,学術界の発展に寄与した.
以上のように,田結庄良昭会員の地質学における学術研究,教育,普及,そして日本地質学会の運営への多大な貢献は,日本地質学会の名誉会員として相応しいものと判断し,ここに推薦する.
2021年度各賞受賞者
2021年度各賞受賞者 受賞理由
■国際賞(1件)
■柵山雅則賞(2件)
■論文賞(3件)
■Island Arc賞(1件)
■研究奨励賞(2件)
■学会表彰(1件)
日本地質学会国際賞
授賞者:Brian Frederick Windley(英国レスター大学地質学科 名誉教授)
対象研究テーマ:地球史を通じたテクトニクスや造山作用に関する一連の研究と日本の地質学発展における貢献
Brian F. Windley博士は, 長年にわたり野外地質調査を基本として, テクトニクスや地球史分野において多くの研究業績を残した世界的に高名な地質学者である.太古代, 原生代, および顕生代それぞれの地質時代の代表的な地質体について地質調査を行い, 後世に大きな影響を及ぼす研究成果を数多く公表してきた.Windley氏の名を不動のものとした主な理由として, 多数の論文精読から導かれた総説の執筆が挙げられる.例えば, 世界最大規模の中央アジア造山帯の形成テクトニクスに関する総説では, 従来のモデルの問題点を整理した上で, 複数の島弧の識別とそれらの融合で説明する新しいモデルを提唱した(Windley et al., 2007).このようなWindley氏の一連の文献コンパイルの集大成にあたる『The Evolving Continents(1〜3版)』などの教科書執筆においては, 世界中の地質に関する4000編以上の参考文献を引用し, 地球史の全体をわかりやすく提示した.その結果, 世界中の研究者に大きな影響を与え,日本でも地球史研究が始まるきっかけを作った.これまでに公表した論文や著書は400編以上に及び, またそれらの被引用回数総数は25,000回を超える.
とくに,日本の地質学研究成果の世界への普及に特筆すべき貢献がある.Windley氏は地質学発祥の地である連合王国の出身だが, 日本人研究者が解明した造山運動や付加体の研究に関する新しい視点や独自の技術をいち早く認識し,それらを頻繁に引用することで世界の研究者に日本の地質の重要性を紹介してきた.その結果,陸上に露出した過去の付加体の識別方法, およびそれらが作る一般的な造山帯の内部構造など, 日本発の地質学貢献が世界中の研究者に知られるようになった.
Windley氏は生来の旺盛な好奇心から, 多くの日本人研究者と積極的に共同研究を行ってきた.これまでに70人以上の日本人研究者と,40編以上の共著論文や著書を発表している.共同研究のため, 訪日は12回に及び, 三波川帯などの日本での地質調査に携わった.また, 地質学会をはじめ国内の学会において共同コンビーナーや招待講演者として参加し, Island Arc誌や地質学雑誌にも複数の論文を公表した.2001年には東京工業大学に1年間滞在し, 多数の大学院生やPDを積極的に指導した.さらに, 連合王国における共同調査や学位研究の指導を通して, 我が国の若手研究者の育成に大いに貢献した.
以上のような卓抜した国際的研究業績を残し, 日本を含めて世界の地質学の発展に大きな功績を残したWindley氏を, 日本地質学会国際賞に推薦する.
The role of Japanese geology in understanding crustal accretionary evolution and the onset of plate tectonics in the Archean
Dr. Brian F. Windley is a world-renowned geologist, who has made many research achievements in the fields of tectonics and earth history based on field geological surveys for many years. He has conducted geological surveys on many representative Archean, Proterozoic, and Phanerozoic geological bodies, and has published many research results with great impacts. One of most important scientific contributions is publication of many fruitful review articles derived from numerous treatise readings. For example, a review article of the Central Asian Orogenic Belt, which is the world's largest orogenic belt, pointed out the problems of conventional models, and proposed identification of many former island arcs and a formational model of the belt through their collision and amalgamation (Windley et. al., 2007). In addition, his comprehensive compilation and review of many literatures, including more than 4000 references on geology around the world, led to publication of textbooks such as "The Evolving Continents (1st to 3rd editions)". As a result, he had a great influence on researchers all over the world and in Japan. He published more than 400 papers and books so far, and the total number of citations is over 25,000. In particular, there is a remarkable contribution to the dissemination of Japanese geological research results to the world. Dr. Windley is from the United Kingdom, the birthplace of geology, but he was quick to recognize new perspectives and unique technologies related to accretionary geology that Japanese researchers have clarified, and have introduced the importance of Japanese geology to researchers around the world. As a result, researchers all over the world have come to know the geological contributions originating in Japan, such as the methods of identifying past accretionary prisms and their internal structures exposed on land. Dr. Windley has been actively collaborating with many Japanese researchers. He has published more than 40 papers and books with over 70 Japanese researchers. For his joint researches with Japanese researchers, he visited Japan 12 times, and was also involved in geological surveys in Japan such as the Sanbagawa belt. He also participated as a joint convener and invited speaker at some conferences such as the Annual Meeting of the Geological Society of Japan, and published several papers in Island Arc. In 2001, he stayed at Tokyo Institute of Technology for a year, and actively taught many graduate students and PDs. Furthermore, he has greatly contributed to the development of young researchers in Japan through a joint research in the United Kingdom and practical education. We recommend Dr. Windley, who has made outstanding achievements in international research as described above and has made great achievements in the development of geology of Japan and world, for The Geological Society of Japan International Prize.
日本地質学会 柵山雅則賞
授賞者:田阪美樹 会員(静岡大学理学部地球科学科)
対象研究テーマ:マントルかんらん岩の物質移動と素過程
田阪会員は「マントルかんらん岩の物質移動と素過程」を明らかにするため,野外調査と室内実験のアプローチに取り組み,注目すべき成果を挙げてきた. 卒業研究において,三波川変成岩帯中に産する前弧部のマントルウェッジ起源の芋野かんらん岩の構造岩石学的研究を行った.かんらん石において含水変形時に形成される特徴的なすべり系(B-type)を見出した.同様なものの存在はすでに知られていたが,この発見によってその広域的な分布が確認され,地震学的に前弧域で観測される地震波異方性と岩石構造及びマントルにおける流動との関連性を議論する上で重要な情報となった.
博士課程在籍時には,かんらん石-輝石多結晶体を用いた粒成長・変形実験を行い,鉱物量比−粒径−粘性の関係則を構築した.さらにこの実験結果をオマーン・オフィオライトの歪み集中帯に応用し,天然の歪み集中帯における粒径と粘性率の時間変化を予想した.この研究は,実験の出発物質の合成,精確な力学データの取得のための多くの試行錯誤に加えて解析理論についても吟味を重ね,非常に丁寧に議論している点で秀逸である.
学位取得後は,アメリカ合衆国ミネソタ大学に留学し,ガス圧式変形試験機を用いてかんらん岩の高温高圧実験を行った.その結果(1)かんらん石中の鉄の多い火星マントルは,鉄が少ない地球マントルよりも柔らかいこと,(2)変形組織が定常状態に達した異方的な試料は等方的な試料に比べて強い粘性率の異方性が発達すること,(3)高歪みのかんらん岩変形において細粒鉱物混合層が形成し歪み弱化が起きること,などを明らかにした.これらの研究は,鉱物のミクロな構造と特性に基づいて,地球内部ダイナミクスを理解するという切り口で岩石の物質移動と素過程を議論している点で独創的である.これらの成果は国際誌に公表され,現在では国内外の共同研究に発展している.国内外の学会でも招待講演を多数行っている.
2017年2月から島根大学,2019年11月から静岡大学に研究の場を移し,室内実験と野外調査を融合した独自のスタイルで研究を進めている.田阪氏の研究課題の遂行能力は高く,高度な課題に取り組んで新機軸の成果を挙げている.岩石レオロジーの分野をリードする若手研究者として非常に期待している.以上のように高い実績と将来性により田阪美樹会員を日本地質学会柵山賞に推薦する.
日本地質学会 柵山雅則賞
授賞者:纐纈佑衣 会員(名古屋大学 大学院環境学研究科)
対象研究テーマ:分光学と地質学のリンク
纐纈佑衣会員は,ラマン分光学および赤外分光学的手法に関する基礎的な研究とそれらの岩石学をはじめとする地質学分野への適用の両面から,多くの注目すべき成果を公表している.
主要な成果は以下の3点にまとめられる.(1)従来は変成圧力の定性的な比較に用いられていたラマン石英圧力指標に目盛を入れることに成功し,新たな地質圧力計を提唱した.また,柘榴石包有物の詳細なラマン分光分析により,三波川変成岩からNa輝石,アラゴナイトやパラゴナイトの産出を確認した.それとともに,熱力学的解析により,エクロジャイト相泥質片岩において,パラゴナイトが Na輝石と同様に重要なNa相であることを明らかにした.そして,これらの成果と柘榴石の組成累帯構造を組み合わせることにより,三波川変成帯高温部においてエクロジャイト/非エクロジャイト両ユニットの境界を決定し,泥質片岩や塩基性片岩を含む従来想定されていたよりも広範囲の地域がエクロジャイト相条件下で再結晶していたことを明らかにした.(2)ラマンピークの面積比で表す炭質物の石墨化度を利用した従来のラマン炭質物地質温度計は,その適用可能範囲はおよそ350 ℃以上であった.これに対し,名古屋大学を中心とした研究グループの代表としてピークの半値幅を用いて400 ℃以下の低変成度試料に適用可能なラマン炭質物地質温度計を新たに提唱した.これにより,同温度計を広範囲の変成岩や変形岩などに適用することが可能となった.また,FIB-TEMを用いて,剪断歪みが炭質物の結晶化度に与える研究も行った.そしてこれらの成果を,変成岩のみならず破砕岩,隕石や全球凍結現象に関係したドロマイト岩など多種の試料に適用し,再結晶温度という新しい観点から重要な多くの知見を報告した.それらのうちでも特に,四国三波川帯の広域的温度構造から復元した沈み込み帯の温度構造とそこで進行していた変形運動の復元は注目に値する.(3)沈み込み帯で起こる諸現象に大きな役割を果たすと考えられるようになった蛇紋石族鉱物について,指導学生との協同研究により,全反射赤外分光法の適用に成功した.そして,化学組成とO-H振動バンドとの関係を論じ,これは赤外分光法活用の新たな出発点となった.
上記の成果を含めて,纐纈会員は基礎的研究およびその応用面に関する多くの研究成果を公表している.そして,今後さらに岩石学を含めた多分野の研究に貢献できることが期待される将来性豊かな若手研究者でもある.これらの点を高く評価し,纐纈佑衣会員を日本地質学会柵山雅則賞に推薦する.
日本地質学会 Island Arc賞
対象論文:Schindlbeck, J. C., Kutterolf, S., Straub, S. M., Andrews, G. D., Wang, K. L., & Mleneck-Vautravers, M. J., 2018, One Million Years tephra record at IODP S ites U 1436 and U 1437: Insights into explosive volcanism from the Japan and Izu arcs. Island Arc, 27: e12244.
Tephra stratigraphy is a fundamental tool in geology, and has long been applied for stratigraphic correlation, chronology, and volcanology. Because of continuous sedimentation and low physical disturbance, tephra layers are often well preserved in deep-sea sediments. Schindlbeck et al. (2018) analyzed the tephra records of two IODP (International Ocean Discovery Program) cores drilled in the Izu-Bonin-Mariana arc in order to assess provenance and eruptive volumes. In total, they identified 260 primary tephra layers from the sediments of the last one million years. Their careful measurements of major and trace element compositions of glass shards specified that 33 marine tephra layers were correlated to the Japan arc and 227 to the Izu arc. Additionally, they correlated eleven tephra layers to major widespread Japanese eruptions; from the 1.05 Ma Shishimuta to the 30 ka Aira. Known ages of these eruptions and refined correlation of the tephra layers established an age model and estimated sedimentation rate of the drilled deep-sea sediment. Furthermore, they calculated the minimum distal tephra volumes of all detected events, and succeeded to evaluate eruption magnitude. For some eruption event, this study evaluated the magnitude for the first time. An extensive database of 260 tephra layers presented in this study is extremely useful to applied for future researches in various fields of Earth Science, and certainly improves our knowledge of the tephra stratigraphy in Japan. Therefore, we identified that the paper by Schindlbeck and others is suitable for Island Arc Award in 2021.
>論文サイトへ(Wiley)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/iar.12244
日本地質学会論文賞
対象論文:中澤 努・長 郁夫・坂田健太郎・中里裕臣・本郷美佐緒・納谷友規・野々垣 進・中山俊雄, 2019, 東京都世田谷区,武蔵野台地の地下に分布する世田谷層及び東京層の層序,分布形態と地盤震動特性. 地質学雑誌, 125,367-385.
都市平野部の地盤は,低地は軟弱で台地は良好であるとの認識が一般的であるが,東京都心部の台地の下には世田谷層と呼ばれる軟らかい泥層が局所的に分布している.本論文は,ボーリングコアの堆積相解析,テフラ分析,珪藻・花粉化石分析により,世田谷層が,約14万年前(MIS 6)の低海面期に形成された谷に約13万年前以降(MIS 5e)の海水準上昇期に海が侵入して堆積した谷埋め堆積物であることを明らかにした.特に注目すべきは,世田谷層分布域では,常時微動観測により,台地にもかかわらず木造家屋を倒壊させやすい1 Hzの揺れを増幅させる特性が示されたことである.また,地盤震動の周波数特性を地層物性のみならず層序境界深度や堆積相構成に対応させて議論することで,地震に強いとされていた台地の災害リスクを地層の形成プロセスの観点から明らかにした.今後の都市防災に地質学が果たす道筋を示した本論文を日本地質学会論文賞に推薦する.
>論文サイトへ(J-STAGE)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/geosoc/125/5/125_2019.0001/_article/-char/ja/
日本地質学会論文賞
対象論文:中嶋 健,2018,日本海拡大以来の日本列島の堆積盆テクトニクス.地質学雑誌,124,693–722.
本論文は,日本海拡大の早期から拡大後までの日本列島の地史について,堆積盆テクトニクスの観点からまとめたものである.著者は日本海や四国海盆など日本列島周辺の海盆の研究史を振り返りつつ,新生界の代表的分布域の層序,地質構造,化石,年代などの地質学的データを丁寧にレビューし,それらを踏まえて始新世から現在までのテクトニクスと環境変動について詳細に論じている.そして,日本列島の陸域では日本海拡大に伴って多段階のリフティングが生じ,不整合で区切られたリフト堆積盆の発達があったことを示している.250編を超える文献引用に基づくレビューは圧巻で,本論文はこれからの研究者が新生代日本列島の地質学的発達史を学ぶ際のバイブル的位置付けになると考えられる.今後永く読まれると期待されることから,本論文を日本地質学会論文賞に推薦する.
>論文サイトへ(J-STAGE)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/geosoc/124/9/124_2018.0049/_article/-char/ja/
日本地質学会論文賞
対象論文:納谷友規・水野清秀,2020,埼玉県加治丘陵に分布する下部更新統仏子層の層序と年代の再検討.地質学雑誌,126,183-204.
本論文は,関東平野西部に分布する下部更新統仏子層の層序と年代を,綿密な野外地質調査とテフラ層の網羅的な記載,そして珪藻化石分析に基づく堆積環境の詳細な復元に基づき再検討し,仏子層の年代観を大幅に更新した.特に注目されるのは,陸成層と浅海成層の繰り返しからなる仏子層について,本論文ではその繰り返しの一部が第四紀初頭の2.5〜2.3 Maの汎世界的氷河性海水準変動を反映した堆積サイクルであることを明らかにした点である.本論文ではその知見に基づき,MISとの対応から仏子層の堆積年代を数万年の精度で決定できることを示した.これらの新知見は,日本最大の平野である関東平野の発達史を,将来的にはより詳細な年代解像度で解明できる可能性を提示している.さらに,仏子層からは陸域や浅海域で堆積した動植物化石が豊富に産出することから,第四紀初頭の陸域や浅海域の生物群集変遷を汎世界的環境変化と結びつけて議論するための層序学的足がかりを示したという点においても,大変インパクトが大きい論文といえる.以上の理由から,本論文を日本地質学会論文賞に推薦する.
>論文サイトへ(J-STAGE)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/geosoc/126/4/126_2020.0005/_article/-char/ja/
日本地質学会研究奨励賞
授賞者:板宮裕実 会員(警察庁科学警察研究所)
対象論文:板宮裕実・杉田律子・須貝俊彦, 2020, 石英粒子の形状および表面形態を用いた法科学的検査法の研究. 地質学雑誌,126,411–423.
板宮会員は,実務経験から土に含まれる石英の法地質学的活用に関心を持ち,本研究に着手したものである.石英粒子の表面形態は,英国では法地質学的利用について研究され実務に応用されている.日本では,石英粒子の表面形態に関する研究がほとんどなく,そのため法地質学的利用のための基礎的知見が全くない.本研究は,国内の海岸や河床の堆積物から石英を収集し,丹念に観察と計測を行い,その結果に基づき堆積環境と形態的関係を客観的に解析しようとした画期的な内容である.また,石英という堆積物には普通に見られる鉱物の形態を,堆積環境の解析に有効に活用できるようになれば,古地形や堆積場の復元に新たな手段を導入することも可能となる.被推薦者は,実社会に密接に関わりがあるが,未だに研究者が少ない法地質学の貴重な若手研究者である.本分野の発展のためにも,同人のさらなる活躍が期待される.以上の理由により,本論文の筆頭著者である板宮裕実会員を日本地質学会研究奨励賞に推薦する.
>論文サイトへ(J-STAGE)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/geosoc/126/8/126_2019.0036/_article/-char/ja/
日本地質学会研究奨励賞
授賞者:菊地瑛彦 会員(アジア航測株式会社)
対象論文:菊地瑛彦・長谷川健,2020,栃木県北部,余笹川岩屑なだれ堆積物の層序・年代と運搬過程. 地質学雑誌,126, 293-310.
本論文で筆者らは,栃木県北部の那須火山群から発生した余笹川岩屑なだれ堆積物の層序と堆積年代を明らかにし,その運搬過程について議論している.丁寧な地質調査によって岩屑なだれ堆積物の岩相と層厚の側方変化を調べるとともに,粒度や化学組成の分析も行い,地層対比と年代,及び岩屑なだれ堆積物が長距離運搬された機構について考察している.その結果,本堆積物が少なくとも33万年前以前に発生したことが示され,下流域の茨城県北部・粟河軽石層に対比可能であることも判明した.この対比は本堆積物の流走距離が実に100 km以上に達することを意味する.筆者らは,岩屑なだれが河川を流走中に水に飽和・流動化しラハールに変化したために長距離流走できたという見解を示している.本研究は地域地質の高精度化に寄与することに加え,岩屑なだれ堆積物の運搬・堆積過程という堆積学的問題についても興味深い知見と解釈を示しており,地質学的重要性が高い研究と判断できる.以上の理由により,本論文の筆頭著者である菊地瑛彦会員を日本地質学会研究奨励賞に推薦する.
>論文サイトへ(J-STAGE)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/geosoc/126/6/126_2020.0014/_article/-char/ja/
学会表彰
授賞者:千葉セクションGSSP提案チーム*
表彰業績:千葉セクションにおける日本初のGSSP認定
2020年1月,IUGS(国際地質科学連合)は千葉県市原市の「千葉セクション」を中期更新世のGSSP(国際境界模式層断面とポイント)として認定した.さらに,これまで地質年代の名称がなかった中期更新世(約77万4千年前〜約12万9千年前)は「チバニアン期」と名付けられ,日本の地名に由来した地質年代が誕生することとなった.これは言うまでもなく日本の地質学にとって画期的な出来事である.このGSSP認定にいたるまで,総勢35名からなる「千葉セクションGSSP提案チーム」は,過去70年にわたる先人の研究成果をふまえたうえで,前期−中期更新世境界に関する最新かつ高精度の地質情報を,あらゆる研究手法を駆使して解読してきた.特に過去5年間にわたって精力的に公表されてきた地磁気逆転の記録や,年代測定,微化石層序,堆積学,および環境変動に関する研究論文は,地層の連続性や境界の年代決定精度を保証するとともに,3カ所の最終候補の中から千葉セクションのGSSP認定を実現させるための大きな原動力となった.これら一連の研究成果や2017年に始まったGSSP審査の過程は,メディアでも大きく取り上げられ,地質学の一般への普及や,学校教育に大きな影響を与えたことに疑いはない.日本初のGSSP認定と「チバニアン期」の誕生いう快挙のみならず,35名の研究チームが果たした地質学の普及や地学教育への貢献を称え,千葉セクションGSSP提案チームを日本地質学会表彰に推薦する.
*構成メンバー(ABC順) 羽田裕貴(産業技術総合研究所地質調査総合センター),林広樹(島根大学大学院自然科学研究科),本郷美佐緒(有限会社アルプス調査所),堀江憲路(国立極地研究所/総合研究大学院大学極域科学専攻),兵頭政幸(神戸大学内海域環境教育研究センター),五十嵐厚夫(復建調査設計株式会社),入月俊明(島根大学大学院自然科学研究科),石塚治(産業技術総合研究所地質調査総合センター),板木拓也(産業技術総合研究所地質調査総合センター),泉賢太郎(千葉大学教育学部),亀尾浩司(千葉大学大学院理学研究院),川又基人(総合研究大学院大学極域科学専攻),川村賢二(国立極地研究所/総合研究大学院大学極域科学専攻/海洋研究開発機構),木村純一(海洋研究開発機構),小島隆宏(茨城大学理学部),久保田好美(国立科学博物館),熊井久雄(大阪市立大学名誉教授,故人),中里裕臣(農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究部門),西田尚央(東京学芸大学教育学部),荻津達(千葉県環境研究センター),岡田誠(茨城大学理学部),奥田昌明(千葉県立中央博物館),奥野淳一(国立極地研究所/総合研究大学院大学極域科学専攻),里口保文(滋賀県立琵琶湖博物館),仙田量子(九州大学大学院比較社会文化研究院),紫谷築(島根大学大学院総合理工学研究科(研究実施当時))Quentin Simon(Aix-Marseille University(フランス)),末吉哲雄(国立極地研究所),菅沼 悠介(国立極地研究所/総合研究大学院大学極域科学専攻),菅谷真奈美(技研コンサル株式会社),竹下欣宏(信州大学教育学部),竹原真美(国立極地研究所),渡邉正巳(文化財調査コンサルタント株式会社),八武崎寿史(千葉県環境研究センター),吉田剛(千葉県環境研究センター)
2022年度各賞受賞者
2022年度各賞受賞者 受賞理由
■功績賞(1件)
■H.E.ナウマン賞(1件)
■小澤儀明賞(1件)
■柵山雅則賞(2件)
■論文賞(1件)
■Island Arc Award(1件)
■研究奨励賞(2件)
■学会表彰(1件)
日本地質学会功績賞
授賞者:高橋正樹 会員(日本大学)
対象研究テーマ:沈み込み帯のマグマ活動研究を通じた地質学の普及と社会的貢献
高橋正樹会員は,一貫してプレート沈み込みにより生じるマグマ活動の研究を行い,多彩な功績を挙げると共に,多くの書籍により専門家と非専門家の橋渡しを行う重要な役割を果たされた地質学者である.
高橋会員の研究は,豊富かつ精緻なデータの収集を基本とし,火成岩体の形成過程や分類に関する新たな提案と考え方の再整理という独自の研究手法によるもので,高く評価されるべきものである.主要な研究は,次の5つのテーマに集約される.1)島弧地殻のテクトニクスと火山形成に関する研究,2)九州,大崩山火山深成複合岩体の形成機構,花崗岩系列の分類意義,東アジアの花崗岩帯のコンパイルなど,弧花崗岩に関する一連の研究,3)火口近傍の堆積物に関するプロキシマル火山地質学,4)「日本の第四紀火山カタログ」の作成や火山形成の確率論的将来予測などに基づく高レベル放射性廃棄物地層処分や地質環境長期安定性の研究,そして5)複数の火山ハザードマップ作成委員会への参画や超巨大噴火の火山災害問題についての火山災害研究である.
これらの成果をもとに,同会員は多数の教科書・参考書・一般向け入門書を執筆された.中でも「島弧・マグマ・テクトニクス」,「花崗岩が語る地球の進化」,「破局噴火」,「火山のしくみ パーフェクトガイド」などの単著は,学部・大学院教育における質の高い教科書・参考書として広く利用され,さらに非専門家に対する地質学の啓蒙に大きく貢献している.大きな社会問題である地層処分や火山災害について「地質学は,国民に科学的・合理的判断の材料を提供する義務がある」とする同会員の考えは,日本地質学会会員が共有すべきものである.同会員は,地質学会の各種委員を永く務められ,「地質学会News誌」の創刊と初期編集への尽力,普及教育事業部会長としてリーフレットの発刊,地質環境長期安定性検討委員会の立ち上げなど,大きな貢献をされた.
学術研究のみならず,公教育および普及活動においても本学会に多大な貢献をされた高橋会員は,地質学会功績賞の初代受賞者として最もふさわしい会員であると判断される.
日本地質学会 H.E.ナウマン賞
授賞者:片山郁夫 会員(広島大学大学院先進理工系科学研究科)
対象研究テーマ:地球内部での水循環に関する研究
片山郁夫会員は,沈み込み帯のダイナミクスと水の役割および海洋底への水の浸透と地殻構造の研究によって,地球内部のグローバルな水循環やマントルダイナミクスの解明に顕著な貢献をしており,国際的にも高い評価を得ている.
沈み込み帯での水循環に関する研究では,マントルの加水反応や,それにより形成される蛇紋岩の地震波特性や浸透率を調べることで,沈み込み帯での水の移動や分布が,温度構造に加えプレートの変形とも大きく関わっていることを提案した.また,加水作用によって形成される粘土鉱物や蛇紋石の摩擦特性やレオロジー特性を調べ,スロー地震を含めた多様な地震活動と沈み込み帯での水循環の関連性を指摘した.片山会員による,流体の動的な振る舞いや岩石の粘弾性特性への水の役割の解明は,沈み込み帯で見られる地震・火成活動の多様性を理解する上での新たな視点として大変注目されている.
海洋底での水循環に関する研究では,オマーン・オフィオライトの陸上掘削プロジェクトに参加し,オフィオライト構成岩石の地震波速度や電気伝導度などの物理特性を系統的に測定することで,海洋底での水循環が主に扁平なクラックに支配されることを明らかにした.海洋底では地球物理観測が実施されているが,地震波速度と電気伝導度は流体分布や連結度に対し異なる応答性を示すことから,片山会員らが進める物性の同時測定は海洋底での物質科学的な理解をさらに進めると期待される.また,計画中のマントル掘削へ向け,地殻とマントル物質の物理特性の違いや水循環の流路として働くクラックの形成プロセスに関する研究にも取り組んでいる.
片山会員は,上記の研究テーマなどについてこれまでに100編以上(うち筆頭論文33編)の査読付き論文を発表し,国内外の学界に大きなインパクトを与えてきた.同会員が,地質学のみならず地球惑星科学の幅広い分野に関心をもち,野外・実験・観測を融合させた独自の研究分野と手法を開拓してきた点は特筆される.このような同会員のこれまでの業績および今後の更なる発展への期待は,ナウマン賞に値するものである.
日本地質学会小澤儀明賞
授賞者:石輪健樹 会員(国立極地研究所)
対象研究テーマ:海水準変動復元と固体地球モデリングに基づく南極氷床変動メカニズム解明の研究
石輪健樹会員は,「海水準変動の復元と固体地球モデリングに基づく南極氷床変動メカニズム」に関する研究を行い,特に,全球的な気候変動にリンクした南極を含む氷床の変動メカニズムの分野において特筆すべき成果をあげた.同会員は,研究の第一段階として低緯度域であるオーストラリア周辺と高緯度域である南極大陸の両方を対象とする野外調査を行い,第二段階として海成・湖成堆積物を採取して,これらの試料を高精度で分析し,そして第三段階として固体地球応答モデリングを駆使して高精度の海水準変動を復元した.
石輪会員は,博士過程では,大氷床から遠く離れた熱帯地域に位置するオーストラリア北部ボナパルト湾にて海底堆積物を採取し,その多くの試料について高精度の放射性炭素年代の測定を行った.これらのデータを地質学的知見とあわせて解析し,最終氷期最盛期(約2 万年前)を含む2万9千年前から1万4千年前の期間を対象に海面変動および氷床変動を解析した.その結果,この期間に大陸氷床は,従来考えられていたような単調な1段階で拡大したのではなく,2段に分かれて発達したことを解明し,同分野で注目をあびた.
石輪会員は日本南極地域観測隊(第61次,2019年)に参加し,地形調査チームのリーダーとして,観測隊史上初のボートを用いた浅海域海底調査を含む,約2ヶ月間の極域野外調査・海洋観測を成功に導いた.南極氷床は全球的気候変動を理解する上で重要であるが,その変動メカニズムは十分に解明されてこなかった.さらに,南極氷床の融解は将来の気候変動予測においても大きな不確定要素で,氷床の発達と融解の評価は緊急の課題となっている.南極周辺の相対的海水準は巨大氷床の荷重を反映して変動するため, 固体地球応答モデルを用いた海水準の補正が必須となる.同会員は固体地球応答モデル駆使した適切な補正を通して,南極の沿岸域における海水準変動に関わる地質記録を精度高く復元した.その結果,最終氷期最盛期の数万年前より南極氷床の一部が大きく成長した可能性を初めて明らかにした.非常に難しい課題である氷床の量的な推定について,本研究は最終間氷期以降の南極氷床の変動史に定量的な制約を与えた.この成果はこの分野の研究に重要な進歩をもたらした.
このように石輪会員は,海水準変動を軸として,低緯度域と高緯度域における氷期・間氷期の環境変動を地球的規模で考察するという独自の視点を有し,地質学的手法を用いて研究を推進してきた.今後,これらの研究を南極周辺の海域での堆積物の研究に発展させ,全球的な気候変動の研究へと,自身の研究分野を幅広く展開するビジョンを有している.その独創的な研究手法と実地調査に基づく全球的気候変動に関する卓越した研究成果,そしてその将来性は,小澤儀明賞に値するものである.
日本地質学会柵山雅則賞
授賞者:岡粼啓史 会員(海洋研究開発機構)
対象研究テーマ:高温高圧変形実験に基づく岩石レオロジー研究
岡粼啓史会員は,高温高圧変形実験を軸に,プレート沈み込み帯における岩石レオロジーの研究において目覚ましい成果を挙げてきた.研究成果の多くは,既存の実験技術によるものではなく,実験装置を自ら改良し,新しい手法を提案し従来の問題点を克服していることは特筆すべき点である.岡粼会員のこれまでの研究開発成果の中でも以下の3点は特筆される.
まず,蛇紋岩の熱水環境下における摩擦実験によって,蛇紋岩の脱水温度付近でスロースティックスリップが起こることを初めて示した業績がある.これはマントルウェッジの温度条件下において,剪断帯での蛇紋岩の局所的な脱水がスロー地震の発生に重要な役割を果たすことを示唆する発見であった.さらに中深発地震発生に密接に関わっていると考えられるローソナイトを用いた高温高圧下での破壊実験により,ローソナイトの脱水反応に伴って微小なアコースティックエミッション(AE)およびスティックスリップが生じることを明らかにした.また,地震発生帯深部における含水断層帯のレオロジーを決めるために,試料中の水の量を系統的に変えて高温高圧変形実験を行い,6%の水によって強度が半減することを解明した.この研究によって,粒間に存在する水の量が断層レオロジーに大きな影響を与えることが明らかとなった.
岡粼会員は,ガス圧式と固体圧変形試験機による研究開発のみならず,最近では回転式ダイヤモンドアンビル装置を用いた放射光超高圧超大歪み変形実験にも取り組みはじめ,地殻表層から下部マントルに至るまでの岩石レオロジーの統一的理解を目指している.また,ICDPオマーンオフィオライト掘削計画へも参加し,掘削コア試料のCTスキャンデータを利用した鉱物組成解析などの変形実験以外の研究も進めている.
以上のように,同会員はプレート沈み込み帯における岩石レオロジー解明に顕著な貢献があり,今後も構造地質を含めた地質学研究を国際的に牽引していくことが嘱望される.岡粼会員の業績および今後の活躍への期待は,柵山雅則賞に値するものである.
日本地質学会柵山雅則賞
授賞者:宇野正起 会員(東北大学大学院環境科学研究科)
対象研究テーマ:プレート収束帯における動的な流体活動
宇野正起会員は,「プレート収束帯における動的な流体活動」を明らかにするために,相平衡岩石学と地球化学,水理学を融合した独自の手法を開拓し,野外調査・反応輸送解析・水熱反応実験のアプローチから特筆すべき成果を挙げてきた.
従来の変成岩岩石学は,相平衡に基づく温度・圧力といった示強性変数の推定が主流であり,元素移動解析に基づく示量性変数の推定や広域的なマスバランスを制約しようとする研究はほとんど行われてこなかった.宇野会員は,三波川変成帯の苦鉄質片岩について,詳細な全岩化学組成分析を行い,後退変成反応の進行度と対応させることで,流体が関与した大規模な元素移動が起きたことを示した.最近では,変成岩の元素輸送解析に機械学習の方法論を導入し,決定木を用いた玄武岩質変成岩の原岩化学組成の推定と,元素移動履歴を制約する新手法を開発している.
また同会員は,南極セール・ロンダーネ山地では花崗岩質脈の反応帯を用いた元素移動解析を行い,地殻にメルトから大量の過剰水が供給されることを示した.さらに,鉱物脈反応帯における燐灰石中の塩素濃度プロファイルに着目し,反応輸送モデルを適用することにより,流体流入継続時間が約10時間と非常に短いことを示した.この反応輸送モデルと相平衡解析,水理学解析を組合せることで,流体圧勾配や地殻透水率など,従来は見積もることが困難であった高温高圧下での動的な流体流動の物性を,天然岩石から実証的に制約する方法論を確立した.短時間の流体活動を岩石学的に検出できることは,岩石学の枠組みを大きく広げるものであり,地質学的現象と地球物理学的観測を同時間スケールで対比可能とする,新たな岩石学の展開と可能性を示した.
さらに北米西岸フランシスカン帯の蛇紋岩についてフィールド調査を展開し,サンアンドレアス断層直上の蛇紋岩体の詳細な反応履歴を明らかにした.蛇紋岩化反応をはじめとした体積膨張反応が引き起こす反応誘起応力に着目し,反応時の応力発生や亀裂生成,透水率変化を計測する独自の水熱反応実験装置を開発した.その結果,体積膨張する加水反応において破壊が生じ,流体流れと反応が自己加速化することを,世界で初めて実験的に示した.さらに無次元化解析から,亀裂生成や空隙閉塞などの力学・水理学応答の多様性を説明するパラメータを提唱するなど,幅広く研究を展開している.
以上のように,宇野会員は,従来の岩石学の枠にとらわれず,独創的なアイデアと研究手法に基づいて研究を進めており,これまでに蓄積した成果と大いに期待されるその将来性は,柵山雅則賞に値するものである.
Island Arc Award
対象論文:Isozaki, Yukio, 2019, A visage of early Paleozoic Japan: Geotectonic and paleobiogeographical significance of Greater South China. Island Arc, 28: e12296.
Tectonic evolution of Great South China (GSC) during early Paleozoic is fundamental for considering the origin of the Japanese Islands, but has not yet been fully understood. Nevertheless, zircon U-Pb dates of Paleozoic granitoids and sandstones have provided critical information on the continental margin along which proto-Japan began to grow. Based on currently available dataset of the dating as well as paleogeographic data, Isozaki (2019) reconstructed the early Paleozoic evolution of Japan. He suggested that the tectonic setting changed from a passive continental margin (Stage I) to an active margin (Stage II) during Cambrian when the oldest arc granitoid, high-P/T blueschist, and clastic sediments were formed. The predominant occurrence of Neoproterozoic zircons in Paleozoic rocks indicates that the relevant continental block was a part of South China, probably forming a northeastern segment of GSC. He reconstructed that GSC was probably twice as large as the present conterminous South China. In addition, he summarized the faunal characteristics of the Permian marine fauna in Japan, which are in good accordance with the relative position of GSC with respect to the North China block during the late Paleozoic. This extensive summary and novel reconstruction provided clear pictures of the geological history of the Japanese Islands and prospective for future researches for the readers of Island Arc. Therefore, we decided that the paper by Isozaki is suitable for Island Arc Award in 2021.
>論文サイトへ(wiley)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/iar.12296
日本地質学会論文賞
対象論文:Takashima, R., Hoshi, H., Wada, Y., Shinjoe, H., 2021. Identification of the source caldera for the Middle Miocene ash-flow tuffs in the Kii Peninsula based on apatite trace-element composition. Island Arc, 30, e13039. doi: 10.1111/iar.12404
紀伊半島に分布する中新世カルデラ群(大峰,大台,熊野北,熊野カルデラ)の火砕岩類は,鉱物組み合わせや全岩の主成分・微量成分化学組成が類似していることから,各カルデラの特徴を区別することが困難であった.著者らは,本論文でこれらのカルデラの火砕岩類に含まれるアパタイトの微量元素組成を明らかにし,各カルデラの火砕岩類の特徴を識別可能であることを示すとともに,噴出相である火砕流堆積物とカルデラ地下の火砕岩脈を対比することが可能であることを示した.また,紀伊半島中央部に広く分布する中新統室生火砕流堆積物と石仏凝灰岩のアパタイト微量元素組成も検討し,その組成が大台カルデラのものと一致することを明らかにした.アパタイトは埋没続成や溶結の影響をほとんど受けないため,本研究で示されたアパタイト微量元素組成に基づく方法は,従来の一般的なテフロクロノロジーの手法を適用することが困難な変質火砕物や先新第三紀火砕岩の層序対比に大きな進展をもたらすことが期待される.本論文は今後多くの研究に参照されると考えられ高く評価される.以上の理由から,本論文に日本地質学会論文賞を授与する.
>論文サイトへ(wiley)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/iar.12404
日本地質学会研究奨励賞
受賞者:中西 諒 会員(東京大学大気海洋研究所)
対象論文:中西 諒, 岡村 聡,2019,1640年北海道駒ヶ岳噴火による津波堆積物の分布と津波規模の推定.地質学雑誌,125(12), 835-851.
本論文では,内浦湾から胆振海岸西部にいたる8地域において1663 年有珠山噴火テフラUs-b の下位にあるイベント堆積物を調査した.このイベント堆積物は1640 年の駒ヶ岳噴火テフラKo-d に覆われていることから,1640 年の駒ヶ岳噴火で引き起こされた山体崩壊津波によるものと判断された.その規模を推定するため,イベント堆積物の分布調査,層厚・粒度・鉱物組成解析を行い,その結果が妥当であるかを評価するため山体崩壊物流入数値シミュレーションを用いて検討した.その結果,この堆積物は1640 年の駒ヶ岳噴火津波で説明可能であることがわかった.この研究では,分布推定地域の各地においてコア等を用いた詳細な堆積物の調査・分析を行っているだけでなく,数値シミュレーションなどの手法を加味して,その規模の検討を行っていることは特筆される.さらに,津波マグニチュードの推定も行っており,津波評価の質のさらなる向上を目指している.本研究は,近年の若手研究者による津波(堆積物)研究を代表するものであり,多面的な角度から検討した姿勢は高く評価される.以上の理由から,中西 諒会員に日本地質学会研究奨励賞を授与する.
>論文サイトへ(J-STAGE)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/geosoc/125/12/125_2019.0032/_article/-char/ja/
日本地質学会研究奨励賞
受賞者:加藤悠爾 会員(筑波大学生命環境系)
対象論文:加藤悠爾・柳沢幸夫,2021,秋田県出羽山地の笹森丘陵に分布する新第三系の地質と珪藻化石層序.地質学雑誌,127(2),105-120.
出羽山地は日本海拡大期以降の東北日本弧の古環境及びテクトニクスの変遷を解明する上で重要であるため,古くから層序・古生物学的研究が行われてきた.東北日本弧日本海側の海成中新統には複数層準に海緑石濃集層が知られており,層序対比や古環境の検討で注目されてきたが,その実態や年代には不明な点が多かった.本論文では,海緑石濃集層を含む出羽山地笹森丘陵の新第三系の地質と珪藻化石層序を詳細に調査し,数多くのセクションでの柱状図作成と岩相層序・珪藻化石層序の観点からのセクション間対比,及び地質図作成などによって,調査地域の約17 Maから4 Maまでの年代層序を確立した.従来整合とされてきた船川層と女川層との間にハイエイタスが存在することを明らかにし,海緑石濃集層の年代を推定し,海緑石濃集層で堆積が停滞していたことを実証した.これらの成果は,日本海拡大後の古環境変遷の原因を探究する上で重要な知見になった.地質を調査する若手が減少する状況で,基礎的な地質調査と精緻な研究を行っていることは高く評価される.以上の理由から,加藤悠爾会員に日本地質学会研究奨励賞を授与する.
>論文サイトへ(J-STAGE)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/geosoc/127/2/127_2020.0058/_article/-char/ja/
学会表彰
受賞者:伊与原 新氏(小説家・推理作家)
表彰業績:地球惑星科学研究をいかした小説発表とそれによる科学知識の普及
地球科学に関するフィクション及びノンフィクション小説は,地球惑星科学に携わる研究者・教育者を含む多くの国民に想像する楽しさを与えるだけでなく,専門的知識も与えてくれる.伊与原新(本名:吉原 新)氏は,固体地球物理学の研究で博士(理学)(東京大学)の学位を取得後,大学教員として地球惑星科学の研究・教育に携わり,小説家として活動するという経歴を持つ.これまでに長編・短編合わせて20編以上の作品を発表し,第30回横溝正史ミステリ大賞受賞,第38回新田次郎文学賞受賞を取得している.小説には,専門とした地球惑星科学だけでなく,広く自然科学のさまざまな専門的知識が効果的に散りばめられており,地層や岩石,化石,ハイエタスなどの専門的知識が含まれた小説もある.初期の『磁極反転の日』や『ルカの方舟』には高度な専門知識が散りばめられていたが,最近の小説ではより科学知識が洗練され読みやすくなっている.これらの伊与原氏の小説では,読者はSFの物語の世界で想像する楽しさを味わいながら,科学の知識と考え方についても知ることができる.小説による国民への地質学の科学知識の普及という点で,伊与原氏の貢献は大きいと評価される.以上の理由により,伊与原新氏に日本地質学会表彰を授与する.
各賞-ナウマン賞
⽇本地質学会 H. E. ナウマン賞(2022年創設)
地質学に関して優れた業績を上げた満50歳未満の会員(運営規則第16条1)
※各受賞者または対象研究テーマをクリックすると、推薦理由等をご覧いただけます。
【受賞者】
【対象研究テーマ】
2024
岡本 敦(東北大学)
岩石組織に基づく地殻・マントルにおける岩石−水相互作用のダイナミクスの解読
2022
片山郁夫(広島大学)
地球内部での水循環に関する研究
Geo暦(2023)
2023年Geo暦(行事カレンダー)
2020年版 2021年版 2022年版 2023年版 2024年版
2023年版 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
○印は学会主催行事.(共)学会共催・(後)後援・(協)協賛
1月January
防災・減災セミナー2022名古屋
1月5日(木)-20日(金)
会場:オンライン(防災ログWebサイト)
入場:無料(事前登録制)
CPD:5.4単位(JSCE22-1670)
主催:防災ログ実行委員会
https://clk.nxlk.jp/m/HbYcTOs9D
2022年度東京地学協会メダル表彰式・受賞記念講演会
1月15日(日)14:00-15:30
場所:学士会館210号室(東京都千代田区神田錦町)
記念講演:四万十帯,南海トラフ,そして地球深部探査船「ちきゅう」
平 朝彦氏(東京大学名誉教授,JAMSETEC顧問)
要参加申込:1月10日(火)締切,参加費無料
詳しくは,
http://www.geog.or.jp/lecture/lecturescheduled/462-2022medal.html
我が国の深海探査機能の近未来のあり方について考えるシンポジウム
1月19日(木) 10:30-17:00
場所:東京大学大気海洋研究所講堂(オンライン併用)
定員:現地参加の定員は60名
現地参加締切:1月12日 (木)17:00
オンライン参加締切:1月17日 (火)17:00
詳しくはこちら
○関東支部オンライン講演会「県の石 茨城県」
1月22日(日)13:00-16:05
参加費無料(要事前申込)
申込締切:1月11日(水)まで
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html#2022ishi
文部科学省主催 STAR-E プロジェクト
第2回研究フォーラムー先端研究と産業界の接点ー
1月24日(火)9:30-12:10
オンライン開催
参加費無料,要申込(1/23締切)
対象:情報科学を活用した地震調査研究にご興味をお持ちの方どなたでも
https://star-e-project-2023.eventcloudmix.com/
(後)原子力総合シンポジウム2022
テーマ「新たな社会状況に貢献する原子力技術の期待と課題」
1月26日(木)10:00-17:35
場所:日本学術会議講堂およびオンライン(Zoomウェビナー)
https://www.aesj.net/symp20230126
○市民対象オンラインシンポジウム
ジオパーク地域に伝わる伝承と地質学:古代からの自然観を今に活かす
1月28日(土)10:00〜14:25
zoom参加申込締切:1月20日(金)
参加費無料
http://geosociety.jp/geopark/content0022.html
オンラインシンポジウム
災害に強い社会を実現するための科学技術:南海トラフ地震・津波防災
1月30日(月)13:00-17:00
参加無料
主催:防災科研、JAMSTEC
https://clk.nxlk.jp/m/nTLY5U6YD
2月February
◯地質系業界オンライン交流会
主催: 日本地質学会
運営: 日本地質学会若手有志会
2月17日(金) 19:00-21:00
場所:Zoom によるオンライン開催
対象:どなたでも参加可能(要参加申込)
参加費無料
詳しくはこちらから
防災科研令和4年度成果発表会(ハイブリッド)
国難級災害を乗り越えるために 2023
『情報でつなぎ、災害対応を変える。』
2月21日(火)11:30-17:30
会場:東京国際フォーラム ホールB7
参加無料 ※会場参加の応募締切: 2月7日(火)
https://clk.nxlk.jp/m/rQsSa4bpD
日本堆積学会20周年記念リレーセミナー(第4回)
2月21日(火)12:15-13:00
Zoomウェビナーオンライン開催(参加無料)
講演者:産業技術総合研究所 清家弘治 氏
演題:イベント堆積作用と生痕:嵐や津波を例に
https://sites.google.com/view/ssj20th/home
2022年度「深田賞」授賞式及び記念講演
2月27日(月)14:00-16:30
開催方法:Zoomウェビナーによるオンライン配信(一般参加)
募集人数:先着80名(一般参加)
参加無料,要事前申込:2/20(月)17時締切
https://fukadaken.or.jp/?page_id=7294
3月March
○西日本支部令和4年度総会・第173回例会
共催:島根大学総合理工学部地球科学科
3月4日(土) 例会・総会
会場:島根大学総合理工学部多目的ホールほか島根大学教養講義室棟2号館
講演・参加申込締切:2月1日(水)
(注) オンラインでの開催は致しません.
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
令和4年度海洋プラスチックごみ学術シンポジウム特別セッション
3月4日(土)
場所:秋葉原UDX シアター
(対面で実施.後日録画を期間限定でYouTube 配信)
参加無料,定員80名
参加登録締切:3月2日(木)17:00
https://www.env.go.jp/press/press_01067.html
令和4年度海洋プラスチックごみ学術シンポジウム研究セッション
3月5日(日)
オンライン開催
参加無料,定員100名
参加登録締切:3月3日(金)17:00
講演申込締切:2月3日(金)正午必着
https://www.env.go.jp/press/press_01067.html
○第3回JABEEシンポジウム
「大学ー企業の架け橋教育 ユニークな実例紹介」
3⽉5⽇(⽇)13:30-18:00(予定)
開催⽅法:Zoomによるオンライン⽅式
参加無料
http://geosociety.jp/science/content0152.html
○地質情報展2023いわて
明日につなぐ大地の知恵
3⽉10⽇(金)-12日(日)
場所:岩手県立博物館〜岩手山を望める丘のミュージアム〜
(注)博物館の入館料がかかります
https://www.gsj.jp/event/johoten/2023/iwate/index.html
令和4年度筑波山地域ジオパーク学術研究助成金成果発表と教育シンポジウム
3月11日(土)13:30-16:30(オンライン)
参加締切:3月5日(日)
https://tsukuba-geopark.jp/page/page001026.html
第82回地学史研究会
3月11日(土)14:00-17:00
会場:早稲田奉仕園101号室
オンラインとハイブリッド
中陣隆夫「速水頌一郎・星野通平の海洋学的業績と思想について」
問い合わせ:矢島道子 pxi02070[at]nifty.com※[at]を@マークにして送信してください
東海大学海洋研究所主催シンポジウム
「水中考古と地球科学―文理融合から導く総合学術知」
3月12日(日)13:00-17:00
会場:東海大学静岡キャンパス8号館4階PLAT
(YouTubeによる生配信もあります)
http://www.scc.u-tokai.ac.jp/iord/
(後)観察会 「宅地開発で隠れた衣笠断層帯を歩く」
主催:三浦半島活断層調査会
3月18日(土)9:30〜15:00
場所:京急久里浜駅--久村--鞍部--岩戸トレンチ--岩戸入口--大矢部四丁目--大矢部地区の衣笠断層)
参加申込締切:3月11日(土)
詳しくはこちら(PDF)
第240回イブニングセミナー(オンライン)
3月31日(金)19:30-21:30
演題:「零細及び金採掘の管理手法:今後の展開」
講師:村尾 智(第一工科大学 環境エネルギー工学科教授)
主催:NPO法人日本地質汚染審査機構
参加費:主催NPO会員及び学生の方(無料) 非会員の方(1,000円)
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
4月April
技術士を目指そう 修習ガイダンス2023
主催:技術士会修習技術者支援委員会
4月8日(土)13:00-17:00
場所:
1)オンライン(Zoomを使用)定員 700名
2)機械振興会館(東京都港区芝公園3-5-8)定員50名
参加費:3,000円 (会員、非会員共通)
https://www.engineer.or.jp/c_topics/009/009253.html
日本学術会議公開シンポジウム・第15回防災学術連携シンポジウム
「気候変動がもたらす災害対策・防災研究の新展開」
4月11日(火)13:00-17:00
ZOOM ウェビナー 定員:1000名
https://janet-dr.com/060_event/20230411.html
日本堆積学会 2023 年新潟大会
4月22日(土)-24日(月)
会場:新潟大学
講演申込締切:3月22日(水)
https://sites.google.com/view/ssjconference2023niigata
5月May
※2023年「地質の日」関連行事はこちらから
第32回 地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン)
5月26日(金)19:30-21:30
内容:健全な水循環と地下水
講師:郄嶋 洋(NPO法人日本地質汚染審査機構理事長、第一工科大学自然環境工学科教授)
参加費:無料(事前登録制)CPD:2単位
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
ワークショップ:掘削とモニタリングによる海山沈み込みとスロー地震の関係の解明
5月27日(土)9:00〜
場所:東京大学地震研究所1号館2Fセミナー室(対面&ハイブリッド)
※要参加申込
http://www.cc.kochi-u.ac.jp/~hassy/WS_SS/
問い合わせ:橋本善孝(高知大学)hassy(at)kochi-u.ac.jp
6月June
第32回 地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン)
6月9日(金)19:30-21:30
内容:地質汚染調査・土壌汚染状況調査概論
講師:駒井 武(東北大学客員教授(名誉教授))
参加費:無料(事前登録制)CPD:2単位
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
地質学史懇話会[オンラインとハイブリッド]
6月10日(土)13:30-17:00
場所:早稲田奉仕園(東京メトロ東西線早稲田駅下車徒歩5分)
小澤健史「ドイツ・ハーツ鉱山とドイツ系日本人ペーター・ハーツィング」
今村遼平「中国地図測量史」続
問い合わせ:矢島道子 pxi02070[at]nifty.com※[at]を@マークにして送信してください
日本学術会議シンポジウム
「最終氷期以降の日本列島の気候・環境変動と人類の応答」
6月11日(日)13:00-17:20
場所:オンライン開催(事務局主会場:島根大学)
参加費無料
申込締切:2023年6月7日(水)
https://www.esrec.shimane-u.ac.jp/docs2/2023042500015/
日本応用地質学会シンポジウム
6月16日(金)13:00〜17:00
テーマ :「応用地質学のD&I−多様な人材の活躍による応用地質学の発展」
開催方法:ハイブリッド形式
現地:東京大学柏キャンパス新領域環境棟FSホール
WEB :Zoom会議方式
参加申込締切: 6月9日(金)
https://www.jseg.or.jp/00-main/symposium.html
◯北海道支部2023年度例会(個人講演会)
6月17日(土)13:00-18:00
場所:北海道大学理学部5号館大講堂(5-203)
講演申込:6月7日(水)締切
http://geosociety.jp/outline/content0023.html
(後)日本学術会議公開シンポジウム「有人潜水調査船の未来を語る」
6⽉17日(⼟)13:00-17:00
場所:日本学術会議講堂 (オンライン配信ハイブリッド)
後援:日本地質学会ほか
⼀般参加可,参加費不要
https://www.scj.go.jp/ja/event/index.html
東京地学協会2023年度 特別講演会
6月17日(土)15:00〜16:30
場所:アルカディア市ヶ谷(私学会館)3階 富士(東)
講演:石原あえか(東京大学大学院総合文化研究科教授)
「鉱物コレクターとしてのゲーテ―岩石と対話する詩人」
申込不要
http://www.geog.or.jp/lecture/lecturescheduled/476-news230617.html
第241回イブニングセミナー(オンライン)
6月30日(金)19:30-21:30
演題:PFOSからPFASへーフッ素系界面活性剤を巡る国内外の動きー
講師:柴田康行(前東京理科大学環境安全センター副センター長)
参加費:主催NPO会員及び学生の方(無料) 非会員の方(1,000円)
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
深田地質研究所 2023年度研究成果報告会(ハイブリッド)
6月30日(金)13:00〜16:10
場所:深田地質研究所 研修ホール(東京都文京区)/Zoomウェビナー
内容:当研究所の事業紹介,昨年度研究事業成果の講演.
参加費:無料(Webページより要事前申込)
https://fukadaken.or.jp/?p=7498
7月July
第4回国際黒曜石会議:
International Obsidian Conference(IOC) Engaru 2023
7月3日(月)-6日(木)
開催地:北海道紋別郡遠軽町
https://sites.google.com/view/iocengaru2023/home
(後)第60回アイソトープ・放射線研究発表会
7月5日(水)-7日(金)
会場:東京都内会場(予定)
発表演題申込締切:2月28日(火)
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2023/top
深田地質研究所 第1回深田研講座「災害地質学」
7月7日(金)10:00-16:30
開催形式:オンライン配信(Zoomウェビナー)
対象:地球科学研究に従事する若手研究者および、地質・地盤調査や環境調査、測量調査などの実務に従事する技術者
参加費:無料(定員300名)要事前申込
https://fukadaken.or.jp/?p=7540
東京地学協会2023年度 定期講演会
7月8日(土) 13:30〜16:00
会場:東京グリーンパレス(全国市町村職員共済組合連合会福祉施設)
テーマ:水蒸気噴火のメカニズムと噴火予知への課題─最新の知見と火山防災─
参加費無料。申込不要。
http://www.geog.or.jp/lecture/lecturescheduled/475-news230708.html
第32回 地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン第3回目)
7月21日(金)19:30-21:30
内容:土壌汚染状況調査の流れと調査や対策の制約・難しさについて
講師:成澤 昇(株式会社環境地質研究所、地質汚染診断士)
参加費:無料(事前登録制)CPD:2単位
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
第198回深田研談話会
跡倉ナップから探る日本列島の地体構造
7月24日(月)15:00-16:30
場所:深田地質研究所研修ホール+オンライン
講師:高木秀雄(早稲田大学)
参加申込締切:7月18日
https://fukadaken.or.jp/?p=7573
桧原湖湖底遺跡水中ドローン操縦体験と一般説明会
7月29日(土)10:00-17:00
JAMSTEC高知コア研究所・東海大学共催
場所:大山祗神社・金山集会場(福島県耶麻郡北塩原村桧原湖北部)
桧原湖湖底に眠る水中遺跡(桧原宿跡)の学術調査と関連して,
(1)これまでの研究成果を紹介する説明会
(2)水中ドローンを使用した水中遺跡の観察会,
を実際の調査現場で実施します.
参加無料
https://hibarajuku.labby.jp/news/detail/3219
8月August
科学教育研究協議会第69回全国大会
8月4日(金)〜6日(日)
会場:与野本町コミセン,埼玉県立与野高等学校(さいたま市中央区本町)
https://kakyokyo.org/
第32回 地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン第4回目)
8月4日(金)19:30-21:30
内容:地質汚染調査入門その1 地質環境問題の歴史と地質汚染 他
講師:風岡 修(地質汚染診断士、理学博士)
参加費:無料(事前登録制)CPD:2単位
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
(後)シンポジウム:地学オリンピックと学校教育のこれから
8月6日(日)10:00-12:00
開催形式:zoomによるオンライン開催
対象:小学校〜大学教員,地学教育に関心のある方
https://jeso.jp/info/20230709-01.html
(共)岩石-水相互作用(WRI-17)または応用同位体地球化学(AIG-14)合同国際会議
8月18日(金)〜22日(火)
会場:仙台国際センター
口頭発表登録締切:3月31日
参加料金早期割引締切:4月30日
https://www.wri17.com/
第32回 地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン第5回目)
8月18日(金)19:30-21:30
内容:地質汚染調査入門その2 透水層の対比方法、地質汚染調査手順の概要 他
講師:風岡 修(地質汚染診断士、理学博士)
参加費:無料(事前登録制)CPD:2単位
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
第77回地学団体研究会総会(ちちぶ)
8月19日(土)-20日(日)
開催方式:現地開催とオンラインのハイブリッド方式
現地会場:秩父市歴史文化伝承館(埼玉県秩父市)
https://www.chidanken.jp/
(後)学術会議公開シンポジウム
「オープンサイエンス時代における
学術データ・学術試料の保存・保管,共有問題の現状と将来」
8⽉20⽇(⽇)13:00-17:20
場 所:オンライン開催(⼀般参加・可)
https://www.scj.go.jp/ja/event/2023/346-s-0820.html
令和5年度第1回キャリアデザインセミナー
主催:(一財)日本応用地質学会 ダイバーシティ推進委員会
8月23日(水)13:00〜15:00
開催形式:Web 開催(Zoom Meeting を使用)
内容:キャリアデザイン紹介:杉原千鶴(国際航業株式会社)/ 武田和久(ハイテック株式会社)
参加費無料・どなたでも参加いただけます
https://www.jseg.or.jp/pdf/20230727_Career_Design_Seminar_20231st.pdf
WCFS2023 Japan
Floating Solutions for the Next SDGs
8月28日-29日:論文発表等
8月30日:オプション テクニカルツアー
場所:日本大学理工学部(東京都千代田区神田駿河台)(予定)
https://wcfs2023.nextsdgs.org/
9月September
第40回歴史地震研究会(小田原大会)
9月1日(金)〜3日(日)
会場:小田原三の丸ホール(神奈川県小田原市本町1丁目7-50)
https://www.histeq.jp/index.html
(後)第66回粘土科学討論会
9月12日(火)〜13日(水)
会場:戦災復興記念館(宮城県仙台市青葉区大町)
http://www.cssj2.org/
日本鉱物科学会2023年年会・総会
9月14日(木)〜16日(土)
会場:大阪公立大学杉本キャンパス(大阪市住吉区杉本)
http://jams.la.coocan.jp/
◯日本地質学会第130年学術大会(2023京都)
9月17日(日)-19日(火)
会場:京都大学
プレサイトはこちら
2023年防災推進国民大会(ぼうさいこくたい)
9月17日(日)-18日(月・祝)
場所:横浜国立大学(神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台)
https://bosai-kokutai.jp/2023/
(共)2023年度日本地球化学会 第70回年会
9月21日(⽊)-23日(土)
開催場所 東京海洋大学品川キャンパス会場(⼀部ハイブリッド)
口頭発表(ハイブリッド),ポスター発表(対面)
http://www.geochem.jp/meeting/
第32回 地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン第6回目)
9月22日(金)19:30-21:30
内容:地質汚染調査におけるボーリング調査その1
参加費:無料(事前登録制)CPD:2単位
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
学術会議公開シンポジウム
文化施設としての自然史系博物館を考える
9月23日(土)13:00−18:00
オンライン開催(配信,定員500名)
参加費無料・要事前登録
9月21日締切(定員になり次第締切)
https://www.scj.go.jp/ja/event/2023/348-s-0923-2.html
第242回イブニングセミナー(オンライン)
9月29日(金)19:30-21:30
演題:「地下水汚染の自然浄化作用と地圏環境リスク評価」
講師:川辺能成 先生(早稲田大学創造理工学部)
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
日本堆積学会20周年記念行事
9月30日(土)
会場:法政大学市ケ谷キャンパススカイホール
早期参加登録(9月15日締切)
https://sites.google.com/view/ssj20th/home
10月October
(協)Techno-Ocean 2023
10月5日(木)〜7日(土)
会場:神戸国際展示場2号館 ほか
https://to2023.techno-ocean.com/
JAAS年次大会2023「会いに行ける科学者フェス」
10月7日(土)〜13日(金)
会場:秋葉原UDX( 東京都千代田区外神田)&ハイブリッド
ポスター・展示募集:7/21(金)締切
https://meetings.jaas.science/
国際ゴンドワナ研究連合(IAGR)2023年総会及び第20回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム
10月8日〜9日(シンポジウム)
10月10日〜11日(糸魚川ユネスコ世界ジオパーク野外巡検)
会場:新潟大学中央図書館ライブラリーホール(新潟市西区五十嵐2の町8050)
問い合わせ:M. Satish-Kumar,iagr2023[at]geo.sc.niigata-u.ac.jp
海底地質リスク評価研究会講演会
「我が国は本当に海洋⽴国なのか?」
10月12日 (水)15:00から
会場:基礎地盤コンサルタンツ本社(ハイブリッド)
講師:阪口 秀氏(笹川平和財団海洋政策研究所 所⻑)
https://www.kiso.co.jp/sssgr/topics/events/entry-1007.html
藤原ナチュラルヒストリー振興財団九州シンポジウム
「天変地異の時代〜火山列島に生きる〜」
会場:アクロス福岡 7階大会議室(福岡市中央区天神1丁目)
ハイブリッド開催
10月15日(日) 13:00-16:45
参加費無料(要参加申込:10/5締切)
https://fujiwara-nh.or.jp/archives/2023/0801_160223.php#!
中谷医工計測技術振興財団オンラインセミナー
「学習指導要領改訂とその後」探究的な学びは生徒と教員をどう変容させるのか?
10月17日(火) 15:00-16:30
参加無料(要事前申込:10/13締切)
https://x.gd/PN9B3
2023年度日本火山学会秋季大会
10月18日(水)〜21日(土)
会場:かごしま県民交流センター(予定)
http://www.kazan-g.sakura.ne.jp/J/
深田研 一般公開2023
10月22日(日)10:00-16:00
会場:公益財団法人深田地質研究所(東京都文京区本駒込)
入場無料
https://fukadaken.or.jp/?page_id=7719
2023年度第2回地質調査研修
10月23日(月)- 27日(金)
場所:島根県出雲市長尾鼻周辺(小伊津海岸)
研修内容:野外での地層・岩石の観察ポイントからまとめまで、地質図を作成するための基本的事項を事前のe-ラーニングと5日間の対面研修で習得します。
※今回は、大学・会社等で一度は地質図を書いたことのある初級者向けの内容で行う予定です。
定員:6名(定員になり次第締切)
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2023-2.html
第4回 鉱物肉眼鑑定研修
10月25日(水)〜27日(金)
主催:産総研コンソーシアム「地質人材育成コンソーシアム」
研修場所:産総研つくば第七事業所
研修内容: 鉱山会社に勤務する技術者が、金属鉱山等で産出する鉱物を肉眼で鑑定できるよう、 実際の鉱物を用いてその特徴を理解し、判別可能な能力を身につけることを目的とします。
定員:5名(鉱業系の会社(商社含む)・組織の方に限る)
申込締切:10月2日(ただし定員に達し次第受付終了)
https://www.gsj.jp/geoschool/koubutsu/4th.html
第32回 地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン第7回目)
10月27日(金)19:30-21:30
内容:地質汚染調査におけるボーリング調査その2
参加費:無料(事前登録制)CPD:2単位
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
第62回温泉保護・管理研修会
10月30日(月)-31日(火)
場所:北とぴあ つつじホール(東京都北区王子)
主催:公益財団法人中央温泉研究所
http://www.onken.or.jp/seminar.html
11月November
山梨県富士山科学研究所
火山防災軽減のための方策に関する国際ワークショップ2023
‐大規模噴火による都市部への影響‐
11月2日(木)13:00-16:20
会場:東京・TKP東京駅大手町カンファレンスセンター(ライブ配信あり)
https://www.mfri.pref.yamanashi.jp/kazan/2023wssp/
山梨県富士山科学研究所
国際シンポジウム2023
大規模噴火による火山近傍への影響と対応
11月4日(土)13:15-16:50
会場:山梨県富士山科学研究所ホール(富士吉田市上吉田)
(ライブ配信あり)
https://www.mfri.pref.yamanashi.jp/kazan/2023wssp/2023SPleaflet.pdf
(後)第23回こどものためのジオ・カーニバル
11月4日(土)-5日(日)
会場:大阪市立自然史博物館 (ネイチャーホール)
参加費無料
http://geoca.org/
(協)石油技術協会令和5年秋季講演会
「CCS事業化に向けた取組と課題」
11月8日(水)9:30-17:30
場所:東京大学小柴ホール(ハイブリッド開催予定)
https://www.japt.org/
第199回深田研談話会
11月10日(金)15:00-16:30
テーマ:プチスポット海底火山
講師:平野 直人 氏
参加費:無料
定員:会場参加(30名)・オンライン参加(上限450名)
https://fukadaken.or.jp/?p=7791
堆積学スクール 2023「日南・宮崎層群の深海相と生痕相」
11月11日(土)〜13日(月)
講師:石原与四郎 氏(福岡大)・菊地一輝 氏(中央大)
定員:30名程度
参加申込締切:10月20日(金)
http://sediment.jp/
火山噴火と防災・観光シンポジウム2023
―草津白根山・御嶽山・箱根山―
11月17日(金)・18日(土)
会場:草津温泉ホテルヴィレッジ,またはオンライン
参加無料
要事前参加申込(11/14締切)
https://www.titech.ac.jp/event/pdf/event-33205-2.pdf
(後)第33回社会地質学シンポジウム
11月24日(金)-25日(土)
場所:日本大学文理学部(ハイブリッド)
参加登録締切:11月22日
<特別講演>(一般公開・Youtube同時配信)
タンザニアでのJICAの活動 国際協力の現場から:荒 仁
<招待講演>(参加登録者のみ)
・北海道寿都町、神恵内村の文献調査について:兵藤英明
・日本原子力研究開発機構が実施してきた超深地層研究所計画の歩み:笹尾英嗣
https://www.jspmug.org/envgeo_sympo/33rd_sympo/
2023年度「深田賞」授賞式及び記念講演会
11月29日(水)14:30〜16:15
開催方法:オンライン配信(一般参加)
【記念講演】山岳トンネルを対象とした私の地質工学を振り返る
(国際航業株式会社 最高技術顧問 大島洋志 氏)
参加費無料
申込締切: 11月22日(水)17時
※募集人数(500名)に達し次第,締め切ります.
https://fukadaken.or.jp/?page_id=7831
(協)第39回ゼオライト研究発表会
11月30日(木)〜12月1日(金)
会場:タワーホール船堀(東京都江戸川区)
内容:ゼオライト、メソ多孔体およびその類縁化合物に関連した研究の基礎から応用までをテーマに、特別講演、総合研究発表、一般研究発表を行うとともに、カーボンニュートラル特別企画の依頼講演を予定
参加申込締切:11月29日(水)12時
https://jza-online.org/events/
12月December
2023年度日本アイソトープ協会シンポジウム
「宇宙から探る未来〜カギとなる放射線〜」基調講演:土井隆雄氏
12月1日(金)13:00〜17:30
ハイブリッド開催
会場:日本科学未来館 7階 未来館ホール(東京・お台場)
参加費無料(11月10日(金)申込締切)
https://www.jrias.or.jp/seminar/cat6/114.html
New Horizons in Forensic Geoscience:
The Bedrock of International Security
in Minerals, Mining, Metals, Murders and the Missing
12月4日(月)-5日(火)
会場 Burlington House, London, UK
https://www.geolsoc.org.uk/012-FGG-New-Horizons
2023年度分野横断型研究集会
「地球表層における粒子重力流のダイナミクス」
12月6日(水)10:00-18:00
開催場所:防災科学技術研究所東京会議室(東京) & オンライン(zoom)
参加登録は12月1日(金)17時まで
https://sites.google.com/view/gravity-current2023/
第40回地質調査総合センターシンポジウム
令和5年度地圏資源環境研究部門研究成果報告会
海と陸をつなぐ地下水の動き
―地層処分研究における地圏資源環境研究部門の取り組み―
12月8日(金)13:30-17:15(予定)
会場:秋葉原コンベンションホール & Hybrid スタジオ
定員:150名(事前登録制:12/4締切),参加費無料
CPD: 3.5単位
https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo40/index.html
第32回 地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン第8回目)
12月8日(金)19:30-21:30
内容:観測井戸の設置地点・深度、電気検層 他
参加費:無料(事前登録制)CPD:2単位
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
下北ジオパーク学術研究発表会(zoom)
12月10日(日)14:00-16:00
参加無料・要事前申込
https://x.gd/svZcp
令和5年度国総研講演会
地震災害への国総研のチャレンジー関東大震災から100年ー
12月14日(木)10:00-17:25
会場:東京証券会館(東京都日本橋茅場町)
※ライブ配信あり
参加無料・要申込(締切:12/11)
https://www.nilim.go.jp/lab/bbg/koen2023.html
第60回技術サロン
12月16日(土)13:00-16:00【Zoom】
対象:技術者及び技術士を目指す女子学生・女性社会人
内容:技術士制度の説明、技術士とのフリーディスカッション等
※受験指導や技術士の斡旋等は行っておりません.技術士の方はご遠慮ください.
参加費無料,定員15名程度
申込締切:12月11日(月)もしくは定員に達した場合
詳しくはこちら(PDF)
地質学史懇話会
12月17日(日)13:30-17:00
場所:王子、北とぴあ 805号室
小澤健志:ライプニッツ(1646-1716)から見たP.ハルツィングの風車・水車計画
矢島道子:日本最初の理学博士保井コノ
問い合わせ:矢島道子 pxi02070[at]nifty.com※[at]を@マークにして送信してください
STAR-Eプロジェクト第3回研究フォーラム
〜情報科学×地震学で拓く未来と産学共創〜
12月22日(金)13:00〜15:35
対象:情報科学や地震学分野等の大学生・大学院生、当核分野における研究者等(民間企業も含む)
会場:オンライン(Zoom)
参加費無料
申込締切:12月21日(木)12:00
https://star-e-project-20231222.eventcloudmix.com/
第243回イブニングセミナー(オンライン)
12月22日(金)19:30〜21:30
演題:「自然から学ぶ放射性廃棄物処分の知恵」
講師:湯佐泰久先生(元JAEA 前富士常葉大学環境防災学部 教授)
参加費:主催NPO会員及び学生の方(無料) 非会員の方(1,000円)
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
シンポジウム「火山噴火の中長期的予測に向けた研究の現状と今後の課題」
12月23日(土)9:30〜17:30
方式 : オンライン(Zoom Webiner)
主催:地震・火山噴火予知研究協議会,火山計画推進部会
参加無料
https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/YOTIKYO/H31-R5/R5/symposiumKazan20231223.html
会費について
2026年度の会費払込について
準備中
災害に関連した会費の特別措置
日本地質学会では,災害救助法適用地域で被災された会員の方々のご窮状をふまえ,「日本地質学会に届出の住居または勤務地が災害救助法適用地域に該当する会員のうち,希望する方」は当年度(もしくは次年度)の会費を免除いたします.希望される方は,学会事務局までお申し出ください.
(参考)内閣府HP:災害救助法の適用状況
会費額についてご不明な点がある場合やその他確認したいことがある場合は,日本地質学会事務局へお問い合わせ下さい.
(e-mail:main[at]geosociety.jp FAX 03-5823-1156 TEL 03-5823-1150)
研究奨励金
一般社団法人日本地質学会研究奨励金
2024.12.2掲載 2025.4.19更新
採択結果はこちら(2025.4.19理事会決定)
若手野外地質研究者向けに研究奨励金を支給します!
2025年度募集期間
2025年1月1日〜2025年2月28日
日本地質学会では若手育成事業の一環として,野外調査をベースに研究を行う32歳未満の若手会員を対象とした研究奨励金制度を設けています.支給額は最大20万円で採択数は5件程度です.応募期間は上記の通りで,4月に支給を予定しています.詳細は,下記の奨励金規約・募集 要項・申請様式をご覧下さい.少しでも若手研究者の支援に繋がれば幸いです.該当する方は奮ってご応募下さい.
なお,本研究奨励金制度を含む日本地質学会の若手育成事業は,竹内圭史会員からの若手野外地質学者育成のための寄付金を原資として運用しています.
研究奨励金選考委員会
委員長 内野隆之
関連規則,書式のダウンロードはこちらから
申請に関するFAQはこちら
採択結果はこちら
2025年度 ⼀般社団法⼈⽇本地質学会 研究奨励⾦ 募集要項
1.趣旨
一般社団法人日本地質学会は,学術の発展と社会への貢献を目的として活動しており,その事業の一つとして,今後の活躍が期待される若手研究者へ研究奨励金(以下,奨励金)を支給します.
2.応募資格
(1)日本地質学会の正会員で,2025年4月1日時点で32歳未満の者 (2)野外調査を中核とした研究を行っている者 (3)同じ研究テーマで他から助成を受けていない(受ける予定がない)者 (4)学生・大学院生の場合は,指導教員の了解を得ている者
3.奨励金の支給額と採択件数
(1)1件:20万円以内 (2)件数:5件程度
4.募集期間
2025年1月1日〜2025年2月28日
5.助成期間
1年または2年 (2025年4月〜2026年3月31日または2025年4月〜2027年3月31日)
※支給は2025年4月下旬を予定しています.
※病気・怪我,出産・育休等,やむを得ない事由で研究を中断せざるを得ない場合,執行理事会に延長願いを提出し承認を受けることで,使用期間を最大2年間延長できます.
6.対象となる費用
野外調査・研究に直接必要な経費(旅費,宿泊費,消耗品費,調査補助員雇用費,学会参加費,雑費,レンタカー代,有料道路代,通信・運搬費等)
※本奨励金に使用できるかどうかの判断が難しい費用項目については学会事務局までお問い合わせ下さい(学会ウェブサイトのFAQでも幾つかお知らせしています).
※申請者が所属する機関・組織の間接経費(事務経費・一般管理費)は本奨励金の対象外とさせておりますので,必要に応じて所属機関での手続きをお願いします.
7.応募手続き
日本地質学会のウェブサイト(研究奨励金)より申請様式をダウンロードして下さい.申請書は,学会事務局に郵送するかまたはPDFにして電子メールでお送りください.締め切りは2月28日必着です.
[宛先] 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル6F 日本地質学会 事務局 e-mail:main@geosociety.jp
※郵送の場合,「奨励金申請書在中」と明記して下さい.また,提出書類は返却致しません.
※提出書類および個人の情報は本奨励金選考目的以外には使用致しません.
8.選考
研究奨励金選考委員会での厳正な審査の上,対象者を決定致します.結果は4月中旬〜下旬に学会ウェブサイトにて公表し,対象者には別途,通知します.なお,選考の内容に関するお問い合わせには応じかねます.
9.奨励金の中止および返金
次のいずれかに該当する事実が判明した際は,奨励金の返金を求めることがあります. (1)同じ研究テーマで他から助成を受けていることが判明した場合 (2)申請内容に虚偽があった場合 (3)会費の滞納があった場合 (4)その他,被支給者としてふさわしくないと理事会に判断された場合 ※なお,他の助成金の採択などで本奨励金を辞退する場合は,速やかに学会事務局へご連絡下さい,また,既に入金済の場合は,返金をお願いします. ※奨励金の助成期間が2年の場合で,2年目に同テーマで科研費等の他の助成金が採択され,それを受ける場合は,奨励金の2年目分は返金をお願いします.
10.その他
(1)本奨励金の使用期間が終了した後に,成果報告書および会計報告書をご提出頂きます.大学などの所属機関で会計報告書を作成される場合には,それを流用することも可能です.締め切りは1年期限の場合は2026年5月1日,2年期限の場合は2027年5月1日とします.報告書の様式は学会ウェブサイトに掲載しています. (2)領収書については,各自,5年間の保管をお願いします(鉄道・バスについては不要).(3)研究成果の概要について,日本地質学会News誌等への投稿をお願いすることがあります.
11.問い合わせ先:一般社団法人 日本地質学会 事務局
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル6F
電話:03-5823-1150,FAX:03-5823-1156
e-mail:main[at]geosociety.jp ※[at]を@マークにして送信してください
以上
規則,募集要項,申請書式のダウンロードはこちらから
一般社団法人日本地質学会 研究奨励金規則
研究奨励金募集要項
申請書式(日本語PDF)・(日本語word)
申請書式(English word)※word onlly
------------------------------------------
成果報告書(日本語)※word
決算報告書(日本語)※excel
※報告書類は,使用期間終了年の5月1日までに,上記学会事務局までメール添付でご提出ください.
FAQ
Q. 海外の大学で助教の職についていますが,応募できますか?
A. 応募条件に合っているなら,所在地や職の有無は問いませんので,応募可能です.
Q. 昨年,学会費を払えていないのですが,応募できますか?
A. 滞納があると,対象から外される(後で発覚した場合は返金を求める)ことになりますので,募集締め切り日までに支払いをお願いします.
Q. 化学分析のためのサンプリング調査でも,応募対象となりますか?
A. 応募対象は野外調査を中核とする研究です.その一部として化学分析等のためのサンプリングを含むことは問題ありません.
Q. 学会が行う巡検参加費は計上できますか?
A. 研究成果を発表するための学会参加分のみ計上可能です.巡検代は原則対象外です.
Q. タブレットPCは購入できますか?
A. 野外調査に必須な場合に限り,可能です.
Q. 支給されたお金は個人で管理できますか?
A.所属機関の指示に従って下さい.
2025年度各賞受賞者
2025年度各賞受賞者 受賞理由
■都城秋穂賞(1件)
■小澤儀明賞(1件)
■論文賞(2件)
■小藤文次郎賞(1件)
■研究奨励賞(1件)
■フィールドワーク賞(1件)
日本地質学会都城秋穂賞
授賞者:Ali Mehmet Celâl Şengör氏(イスタンブール工科大学地質工学科)
対象研究テーマ:プレートテクトニクス的造山運動論の体系化とユーラシア大陸形成史の研究
トルコの地質学者Alì Mehmet Celâl Şengör(ジェラール・シェンゲオール)氏は,多言語能力を駆使して世界の様々な地域の18世紀以来の造山論に関する大量のレビューを学生時代から進めてきた.その中でプレートテクトニクス出現前後の概念的転換パタンを明らかにし,また,現代的な造山運動論の体系化を試みてきた.これまでに300編以上の学術論文を公表し,中には100ページを超える大作も複数含まれる.地中海から中央アジアを経て極東アジアにいたるユーラシア大陸全体の地質を視野に入れた氏の造山帯研究は,世界のテクトニクスの研究者に大きな影響を与えた.中でも,極東アジアの地質総括においては,日本列島の地質の詳細に注目して,東アジアで最も詳しく研究された造山帯の例として日本の地質を世界に紹介した.こうした広視野からの研究は,プレートテクトニクスを踏まえつつ,日本列島の地質をアジア大陸の地質との関連の中にどのように位置付けるのかという点で,日本人研究者にも深い洞察を促した.
シェンゲオール氏はニューヨーク州立大学においてJ.F. Dewey, K.C.A. Burkeそして都城秋穂教授らの指導のもと博士号を取得した後,母国のイスタンブール工科大学地質工学科の教授として1981年から2022年の退職まで研究と教育を精力的に進めた(現在は名誉教授).都城氏とは1979年の岩波講座地球科学の『造山運動』とその英語版教科書"Orogeny"を共同執筆した.古典的な地向斜論と比較しつつ,プレートテクトニクスの枠組みでの造山論を解説した同書は,その後ドイツ語,ロシア語,また中国語にも翻訳出版され,世界中で広く読まれており,わが国でもプレートテクトニクス観に基づく地質学が定着する礎石の一つとなった.これらの突出した業績に基づき,シェンゲオール氏は世界の主要学会から多数の国際的な賞(欧州地球科学連合のArthur Holmesメダルなど)を授与されており,自身の複数回の来日を含め,日本の地質学界とも馴染みが深い.
以上の地質学および科学史研究への多大な貢献,および日本の地質学界への貢献は,日本地質学会都城秋穂賞にふさわしいものと評価される.
Citation for the 2025 Akiho Miyashiro Award:Plate tectonics-based studies on orogeny and geotectonic history of Eurasia
Since his undergraduate days, the Turkish geologist, Dr. Alì Mehmet Celâl Şengör, has conducted outstanding historical reviews of orogenic studies in the world from the 18th century to the present, utilizing his exceptionally gifted multi-lingual abilities. He clarified the pattern of conceptual change in geosciences during the emergence of plate tectonics and re-synthesized orogenic processes from his viewpoint. He has published more than 300 scientific works, including some with over 100 printed pages. These studies, which cover diverse geological aspects of the entire Eurasian continent from the Mediterranean area to Far East Asia via the vastness of Central Asia, have greatly influenced studies of tectonics by geologists throughout the world. He also introduced the latest advances in geological/orogenic studies in Japan to the rest of the world, emphasizing their significance as the best analyzed example of a Phanerozoic orogenic belt in East Asia. His research on global aspects of orogeny encouraged Japanese geologists to reevaluate the geology of Japan with respect to the East Asian orogenic framework.
After receiving his Ph.D. from the State University of New York at Albany under the supervision of Profs. J.F. Dewey, K.C.A. Burke, and A. Miyashiro, Dr. Şengör continued research and taught as a professor at the Istanbul Technical University (ITU) from 1981 until his retirement in 2022. He is now professor emeritus at ITU. He notably co-authored a textbook “Orogeny” (published in 1979 by Iwanami in Japanese and in 1982 by Wiley in English) with Prof. Miyashiro, in which the history of pre-plate tectonics orogenic concepts is explained in the first chapter as context for the subsequent explanations of plate tectonics-based orogeny. This book, which was later translated into German, Russian, and Chinese, became a worldwide best-seller that enlightened numerous geologists, including those in Japan. Due to his prominent achievements, he has been honored with multiple international awards/prizes (e.g. Arthur Holmes Medal from European Geosciences Union) and invited lectures. His previous visits to Japan also deepened his interactions with the Japanese geoscience community.
His overall contributions, not only to geology and the related history of science in general, but also to the geoscience community in Japan, are highly worthy of recognition through the award of the Akiho Miyashiro Award of the Geological Society of Japan.
日本地質学会小澤儀明賞
授賞者:松本廣直会員(筑波大学生命環境系)
対象研究テーマ:物質的・地球化学的情報を組み合わせた超巨大海台形成史の復元と地球環境変動との関連解明
松本廣直会員は,堆積岩に記録されたオスミウム・鉛・炭素同位体の分析を行い,高時間解像度の同位体層序を作り上げるととともに,火山灰や鉱物種の変化といった物質的な解析を組み合わせることで,巨大火成岩区の活動と海洋無酸素事変の関連を研究した.そして,過去2億年間で最も温暖であった,白亜紀を中心とした地球表層と地球深部とのリンケージに関する課題において顕著な成果を挙げた.
顕生累代最大の巨大火成岩区であるオントンジャワ海台では,白亜紀に大噴火が起こった.これは地球表層環境への甚大な影響という点で注目されてきたテーマであったが,噴火年代などに未解決の課題があった.松本会員は,まず,この噴火史の復元に取り組んだ.太平洋の白亜系遠洋堆積物に含まれる火山灰層の化学分析と年代測定を行い,OAE(海洋無酸素事変)1aの最初期にオントンジャワ海台において爆発的な噴火が発生した事実を明確に示した.堆積岩のオスミウム・炭素同位体比の分析結果より,この噴火活動で,大量の揮発性物質が放出され,海洋酸性化や貧酸素化につながったことを明らかにした.さらに,炭酸塩堆積物中に鉄が濃集していることを発見し,オントンジャワ海台の噴火活動に伴い,長期間にわたり海洋中に鉄が供給されたことを示唆した.これらの成果は,オントンジャワ海台を代表例として,大規模海台形成における噴火様式の変化と地球環境への影響を,これまでにない高時間解像度及び広大な空間スケールで提示する重要な成果となった.
松本会員は陸成層を含む古環境復元も行っており,過去の地球を理解する研究を基に,固体地球と地球表層との関連に関する普遍性を追求する課題へとレベルを向上させている.イタリア,ベルギー,ブラジル,中国などとの国際的な研究連携,宇宙起源物質,微化石,モデリングなど関連分野との共同研究も発展させている.松本会員は若手のリーダーとしての役割をきちんと自覚し,国内外の学会活動にも貢献している.以上のように,松本会員の卓越した業績と将来性は,地質学会小澤賞に値するものである.
日本地質学会論文賞_1/2
対象論文:別所孝範・鈴木博之・山本俊哉・檀原 徹・岩野英樹・平田岳史,2024,紀伊半島南部海岸地域の田子含角礫泥岩層「サラシ首層」の時代と成因について.地質学雑誌, 130, 35-54.
田子含角礫泥岩層は,四万十帯に含まれ,様々な大きさの砂岩角礫を無秩序に含む泥岩からなる.紀伊半島南部の海岸沿いに露出し,差別的な浸食作用によって砂岩角礫の突起状の地形が発達している.その特異な形状から「サラシ首層」と呼ばれ,古くから地質学的に注目されてきた.この層の成因については,長年にわたり議論が続いており,大きく二つの説が提唱されてきた.一つは,泥火山やダイアピルにより形成されたとする説,もう一つは,海底土石流による堆積物とする説である.しかしながら,これらの説のどちらが正しいのか,本層の分布状態や含まれる砂岩礫の起源,さらに地層の形成年代についての情報が不足しており,未解決の課題として残されていた.本論文は,この「サラシ首層」の成因を明らかにすることを目的とし,過去の研究史を整理した上で,多角的な岩石学・年代学的手法を用いた詳細な分析が行われた.具体的には,累重様式の詳細な検討,砂岩組成・粒度組成分析,砂岩の放射年代測定,泥岩礫の放散虫化石年代が検討された.その結果,砂岩組成や放射年代のデータから,基質が四万十帯牟婁付加シーケンスに起源を持つことが判明し,「サラシ首層」に含まれる砂岩の異地性ブロックが,それよりも若い年代を示すことが明らかとなった.そして,これらの岩石学・年代学的データと,累重様式および堆積構造の詳細な検討から,泥火山・ダイアピル説は否定され,前弧海盆内で隆起した付加体の崩壊によってもたらされた海底土石流堆積物であるとの結論が得られた.本論文の意義は,長年未解決であった「サラシ首層」の成因について,従来の仮説を包括的に検証し,新たな岩石学・年代学的データをもとに結論を導いた点にある.複合的な手法を駆使し,未解決であった地質学的問題に対して重要な知見を提供した点でも,学術的に高く評価される.
以上のことから,本論文は日本地質学会論文賞に相応しいものと評価される.
>論文サイトへ(J-STAGE)
https://doi.org/10.5575/geosoc.2023.0034
日本地質学会論文賞_2/2
亀高正男・菅森義晃・石田直人・松井和夫・岸本弘樹・梅田孝行・東 篤義・山根 博・杉森辰次・魚住誠司・永田高弘・松場康二・桑島靖枝・岩森暁如・金谷賢生,2019,舞鶴−小浜地域の地質:超丹波帯・丹波帯の地質構造発達史と上林川断層の横ずれインバージョン.地質学雑誌, 125,793-820.
本論文は,京都府舞鶴〜福井県小浜地域の地質図を作成し,ペルム系〜ジュラ系からなる舞鶴帯・超丹波帯・丹波帯の分布や地質構造を示すとともに,活断層である上林川断層の発達過程を解明したものである.地質図は南北約18 km,東西約40 kmの広範囲に及び,詳細な地表踏査や試料観察を基にした精緻な地質記載がなされている.産総研が整備している当該地域の地質図幅は作成された年代が古く,付加体地質学を考慮した地質図の公表が待たれていた.本論文では超丹波帯を3つ,丹波帯を5つの地質単元に区分し,それぞれの構造層序関係を示すとともに,褶曲や断層の形成順序を検討した.対象地域には超丹波帯付加体の模式地が含まれ,これまで不明な点が多かった同帯の全貌が初めて明らかにされた.また上林川断層について,地質図規模から露頭・標本・薄片規模までの様々なスケールでの検討をもとに,左横ずれから右横ずれにインバージョンしたことを示したことは,日本列島の活断層の形成要因に重要な示唆を与え,防災上の意義も大きい.一般に活断層調査は断層およびその近傍のトレンチあるいは露頭調査によって進められ,広域の地質調査まで及ばないことが多いが,本論文では超丹波帯・丹波帯といった基盤岩の広域の地質構造を精査することで,地質断層を再利用した横ずれインバージョンによる,活断層としての上林川断層の活動を明らかにした.本調査結果は,西南日本のペルム紀〜ジュラ紀付加体が初生的には沈み込みに伴うパイルナップ構造をもって累重し,白亜紀以降にそれらを切断する内陸の断層活動によって再配列している様子を端的に表している.本論文は,昨今減少傾向にある地道な野外地質学をベースにしたものであり,その中でも近年では類を見ない高い質の内容となっている.
以上のことから,本論文は日本地質学会論文賞に相応しいものと評価される.
>論文サイトへ(J-STAGE)
https://doi.org/10.5575/geosoc.2019.0030
日本地質学会小藤文次郎賞
授賞者:岩森 光 会員(東京大学地震研究所)
対象論文:Iwamori, H., Ueki, K., Hoshide, T., Sakuma, H., Ichiki, M., Watanabe, T., Nakamura, M., Nakamura, H., Nishizawa, T., Nakao, A., Ogawa, Y., Kuwatani, T., Nagata, K., Okada, T., Takahashi, E. (2021) Simultaneous analysis of seismic velocity and electrical conductivity in the crust and the uppermost mantle: a forward model and inversion test based on grid search. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 126, e2021JB022307
地球内部の水溶液やマグマは,地震,火山活動,地殻変動や地球全体の進化に重要な役割を担うと考えられているにもかかわらず,従来の解析方法(例えば,地震波速度あるいは電気伝導度のみの解析)では,これらの地球内部に存在する液相がどこにどれだけ存在するか,定性的にイメージングすることが難しかった.特に,地震や火山活動の主な場である深さ60 ㎞ 程度までの領域は,岩石の種類が極めて多様であり,正確な理解のためには岩石と液相を同時に推定することが必要であった.岩森 光会員を中心とした研究グループは,地震波速度構造と電気伝導度構造を統合的に解析し,地殻と最上部マントルを構成する岩石に加えて,液相の種類,液相の量・アスペクト比・連結度を同時に推定し,地球内部の水溶液やマグマを定量的にとらえる手法を初めて開発した.その成果をまとめた本論文では,さまざまな組成の岩石,マグマ,水溶液についての実験的データと理論に基づき,それらの混合物性(地震波速度と電気伝導度)を予測する数値モデルを発表した.さらに,この数値モデルを用いて,観測される地震波速度と電気伝導度から,岩石と液相の種類と量比などが求められることを示した.このような推定手法は国際的にも例がなく,今後本手法を実際の観測データに応用することにより,地殻とマントル最上部の構造イメージングが飛躍的に進むことが予想される.加えて,本研究による解析の高解像度化は,地震・火山活動の機構や地球進化の理解に資することが期待され,我が国に与えるインパクトは非常に大きい.
以上のことから,極めて独創的な発想を有している研究を主導した,本論文の筆頭著者である岩森 光会員は日本地質学会小藤文次郎賞に相応しいものと評価される.
>論文サイトへ
https://doi.org/10.1029/2021JB022307
日本地質学会研究奨励賞
授賞者:米岡佳弥会員(産業技術総合研究所地質情報研究部門)
対象論文:米岡 佳弥, 坂田 健太郎, 本郷 美佐緒, 中里 裕臣, 中澤 努,2024,下総台地北西部の地下に分布する中部更新統下総層群清川層の層相・物性の側方変化. 地質学雑誌, 130, 223–238.
更新統下総層群清川層(約20万年前の堆積物)は首都圏の台地の地下浅部に広く分布する浅海〜陸成層で,側方に層相が大きく変化することが特徴である.本層が分布する一部地域では 約14万年前の氷期に本層を侵食して谷が形成され,その谷を約12万年前の最終間氷期に堆積した軟弱な泥層からなる木下層が埋めている.このため,両層は非常に複雑な分布を呈しており,これらをきちんと区別することが課題となっていた.
著者らは清川層の層相が大きく変化する千葉県野田市でボーリング調査を行い,コアの層相,テフラ,花粉化石群集,物性を詳細に記載した.そして,清川層と木下層が花粉化石群集と物性の両面から区別できることを初めて指摘するとともに,既存ボーリングコアのデータと総合的に比較することで,千葉県北西部地域の清川層の分布を詳細に解明して本層堆積時に南側ほど海退が遅れていたことを示した.清川層とその上位にある軟弱な木下層とでは揺れの特性が異なることから,地震工学的視点からも両者の区別は極めて重要で,これらの成果は,地質地盤の三次元解析に資するほか,非専門家による両層の容易な判別を可能にし,地盤リスク評価への応用も期待される.さらに,筆者らは同地域の清川層を構成する泥層が不透水層として汚染の侵入を阻むのに対し,上位の砂泥互層が透水層として地下水利用が盛んな一方,汚染に対して脆弱であるという特性を指摘し,首都圏の地下水利用や地質汚染調査の観点からも両層の層相変化の把握が重要であることを論じている.
従来,層序学・堆積学と地盤工学・地下水学は別々に議論されることが多かったが,本論文はこれらの分野間を結びつける極めて重要な研究である.したがって,この研究をリーダーとして推進し取りまとめた本論文の筆頭著者である米岡佳弥会員は研究奨励賞に値する.
以上のことから,米岡会員は日本地質学会研究奨励賞に相応しいものと評価される.
論文サイトへ(J-STAGE)
https://doi.org/10.5575/geosoc.2024.0012
日本地質学会フィールドワーク賞
授賞者: 松山和樹会員(名古屋大学大学院環境学研究科)
対象論文: Matsuyama, K. and Michibayashi, K., 2024, Structural evolution of the Horoman peridotite complex in conjunction with the formation of the Hidaka Metamorphic Belt, Hokkaido. Tectonophysics 892, 230535.
日高変成帯の基底部に位置し,世界的にも著名なアルプス型かんらん岩体である幌満かんらん岩体では,2000年代初頭に変形組織の多様性が報告された後,構造地質学的な研究は停滞していた.そのため,同岩体の形成史の解釈は岩石学的視点によるものが大半であり,変形時の運動像・造構環境や,周囲の日高変成岩類との関係性も踏まえた包括的な解釈が不足していた.本論文では,詳細な地質図が既に存在する同岩体について,岩体内の全ユニットにまたがる2本の主調査ルートを設定した上で計画的な野外調査を行っている.具体的には概ね南北に延びる2ルート全体を網羅するように54試料を定方位で採取し,うち52試料について電子線後方散乱回折装置(EBSD)によるファブリック解析を実施している.そして,定方位試料から復元した面構造・線構造の方位,それらに付随するかんらん石結晶の格子定向配列(CPO)パターン,及びそこから導かれる剪断センスを地質図上にフィードバックし,複数の構造データに関する東西5km,南北10km規模の詳細な分布図を描出した.結果,岩体の南部から北部(構造的な見かけ下位から上位)にかけて支配的な剪断センスが逆転すること,及びかんらん石のファブリックタイプについて南部では含水条件で生じるEタイプ,北部ではメルトの関与を示唆するAGタイプが卓越することが明確化した.加えて,これらの情報をもとに同岩体と日高変成岩類の変形史の対比が行われた.これらの研究成果は,地質図規模での系統的な定方位試料採取という,フィールドワークにおける1つの作戦の有効性を,室内外での豊富な仕事量によって具現化した好例として評価できる.
以上のことから,本論文の筆頭著者である松山和樹会員は日本地質学会フィールドワーク賞に相応しいものと評価される.
論文サイトへ(Elsever)
https://doi.org/10.1016/j.tecto.2024.230535
2023年度受賞者
2023年度各賞受賞者 受賞理由
■学会賞(1件)
■功績賞(2件)
■小澤儀明賞(1件)
■柵山雅則賞(1件)
■論文賞(4件)
■Island Arc Award(1件)
■研究奨励賞(4件)
■フィールドワーク賞(2件)
日本地質学会学会賞
道林克禎 会員(名古屋大学大学院環境学研究科)
対象研究テーマ:地殻とマントルのレオロジーと構造地質学的研究
道林克禎会員は,岩⽯の変形組織の観察と分析により,岩⽯の強度や地震学的特性に関する研究を展開してこられた.特に,カンラン⽯に富むマントル岩⽯に関する研究で優れた成果をあげておられる.海洋リソスフェアを研究する上で,世界的に貴重な陸上岩体の⼀つであるオマーン・オフィオライトなど,道林会員は世界各地から数多くのマントル岩⽯試料を採取され,それらの分析により,海洋リソスフェアにおける断層を含む縦⽅向の剪断帯の発達する向きが,そのリソスフェアの形成後まもない⾼温の時期につくられた,⽔平⽅向の剪断帯のカンラン⽯の結晶軸選択配向に⽀配されていることを明らかにされた.この結果は,海洋リソスフェアの強度分布を理解する上で貴重な新知⾒である.また,道林会員は天然の岩⽯の結晶軸選択配向の測定・解析に基づいて,リソスフェアにおける地震学的異⽅性の成因に関する研究成果を挙げてこられた.例えば,オマーン・オフィオライトにおける研究では,⼀般的に⾒られるリソスフェアの主要な地震学的異⽅性が,そのリソスフェアの若い時に獲得されたものであることを⽰された.これにより,マントルの地震学的な異⽅性が測定地域の局所的なマントル流動を反映していない可能性があり,この異⽅性がプレート運動⽅向と斜⾏する可能性もあることが明らかになった.
また,道林会員は海洋リソスフェア・マントルの変形構造を体系的に研究するために,⽇本海洋研究開発機構と連携して,深海の海底などアクセス困難な場所からも岩⽯試料の採取にも成功しておられる.その研究成果によって,マントルの結晶軸選択配向パターンとそれらに付随する物理的特性の全球的な変化に対する理解が深まった.この研究の⼀環として,道林会員はカンラン岩の地震学的異⽅性の程度と特徴を図⽰できる⽅法を提案した.この図⽰法の導⼊により,岩⽯試料のP波速度の異⽅性を定量的に⽐較することが容易になり,異なるテクトニクス環境におけるリソスフェア・マントルの結晶軸選択配向の分布像を描き出す試みに⼤きく貢献された.
道林会員は⽇本地質学会の理事や⽇本地球惑星科学連合の副会⻑などを務めるなど,地球科学分野の学協会運営にも貢献しておられ,また,多くの若⼿研究者を育ててもおられる.このように道林会員の地球科学分野の発展及び⽇本地質学会への貢献は⼤きい.以上のことから,道林会員に⽇本地質学会賞受賞を授与する.
日本地質学会功績賞
授賞者:小山内康人 会員(九州大学大学院比較社会文化研究院)
対象研究テーマ:高度変成岩類を用いた造山運動と大陸の成長・進化における研究の推進
⼩⼭内康⼈会員は,造⼭帯深部でおこる変成・⽕成作⽤の研究を通じて、⼤陸地殻の進化過程の解明に携わってこられた.そして,その鍵となるいくつかのプロジェクトを⽴案・推進するとともに,若⼿研究者の育成などで重要な貢献を果たされた.
⼩⼭内会員の研究対象地域は国内外にわたり,そのうち我が国の南極観測事業への参画は1987年以降5次を数え,特に第49次隊では副隊⻑を務め,また第58次隊でも事業の推進に⼤きな責務を果たされた.そして,これらの経験を活かして,現在は情報・システム研究機構国⽴極地研究所運営会議委員や⽂部科学省南極地域観測統合推進本部委員などとして,極地研究の重要な⽅針策定に携わっておられる.
南極共同研究の⼀連の研究により,セール・ロンダーネ⼭地における⼤陸衝突境界の存在が明らかになった.さらに,ゴンドワナ⼤陸の中で,かつて南極と繋がっていたスリランカ・インドの超⾼温変成岩類に関する研究成果とあわせることによって,超⾼温変成作⽤進⾏場のテクトニクスの理解や過去の⼤陸の復元にとって重要な発⾒をされている.また,⼩⼭内会員が中⼼となって⽴ち上げたベトナム・コンツム地塊の調査プロジェクトでは,エクロジャイトや超⾼温変成岩を報告し,島弧̶海溝系から⼤陸衝突帯への移⾏過程を理解する上で重要な発⾒をなされた.そして,モンゴル調査での成果とあわせて,東アジアの形成史を論じておられる.
⼩⼭内会員のこれらの研究成果の多くは,多⽅⾯の国際共同研究として⾏われ,本邦と世界各地の研究者ネットワーク形成に多⼤な貢献をするとともに,多くの研究者育成にも繋がった.さらに同会員が共同執筆しておられる『記載岩⽯学』と『解析岩⽯学』は,岩⽯学を学ぶ上で貴重な教科書であり,教育への貢献も⼤きい.加えて,地質学会評議員や理事を⻑く努め,学会運営にも⼤きく貢献してこられた.以上の理由により,⼩⼭内康⼈会員に⽇本地質学会功績賞受賞を授与する.
日本地質学会功績賞
授賞者:佐藤比呂志 会員(東京大学地震研究所)
対象研究テーマ:反射法地震探査を軸とした日本のサイスモテクトニクス研究の推進
佐藤⽐呂志会員は,広範囲の地質調査にもとづく東北⽇本の新⽣代テクトニクスを研究した経験を基盤として,反射法地震探査を軸とした⽇本のサイスモテクトニクス研究を⻑年主導し,地表の活断層と深部の震源断層の関係を特定する研究を続けてこられた.この過程で,島弧−海溝系において地殻構造の形成に関与した断層が引き続き震源断層として挙動していることに注⽬し,サイスモテクトニクス全体像構築における地殻構造研究の重要性を鮮明にした.さらに,東北横断合同地殻構造調査を初めとした海陸統合深部構造探査等の⼤規模共同研究を遂⾏する中で,活断層−震源断層システムが⽇本列島の形成・成⻑過程の⼀部としての位置付けを持つものであることを,具体的データによって明らかされた.
佐藤会員らが明らかにしてきた活断層−震源断層システムは,⽇本のサイスモテクトニクス研究の基盤となる重要な成果であり,現在では地震学,地球物理学,測地学,地形学データとともに内陸地震発⽣の予測には不可⽋なものとなっている.
佐藤会員は,反射法地震探査を軸とした⽇本のサイスモテクトニクス研究活動の持続・発展のために,1995年兵庫県南部地震以降,⼤規模な共同研究の企画と実⾏に⻑年携わり,国内の学術活動を牽引してこられた.佐藤会員のリーダーシップにより得られた⽇本の島弧−海溝系構造探査は,先進的成果をまとめた多くの特集号に結実している.その編集にあたっては,研究者育成にも配慮された.
このように佐藤会員が⻑年主導してこられた⽇本のサイスモテクトニクス研究は,我が国の地質学界への⼤きな貢献である.佐藤会員はまた,政府の地震調査研究推進本部が進める活断層評価等にも参画して,研究成果に基づく提案を⾏うなど,地震防災⾏政を学術⾯から⽀えてこられた.以上の理由により,佐藤会員に⽇本地質学会功績賞を授与する
日本地質学会小澤儀明賞
授賞者:沢田 輝 会員(海洋研究開発機構)
対象研究テーマ:太古代・原生代における地殻消長メカニズム変遷の地質記録断片からの解読
沢⽥ 輝会員は,ジルコンのU-Pb年代および微量元素組成の測定,そして蓄積された多量のデータの統計処理によって,太古代・原⽣代における地殻消⻑メカニズムの変遷などに関して,次のような注⽬すべき成果を公表してこられた.
およそ20億年より前にできた⼤陸地殻は⼤陸地殻全体の20%程度に過ぎず,⼤陸地殻の形成年代に不均質が認められる.沢⽥会員は,この要因を理解するために,共同研究者ともに堆積年代の異なる太古代堆積岩中の砕屑性ジルコン年代分布を系統的に⽐較してその変遷を論じ,約30億年前と20億年前を境に,⼤陸地殻の形成年代が多様化したことを⾒いだされた.そして,初期地球では現在の海洋性島弧のような構造場で活発な地殻形成と消失を繰り返していたのに対して,その後は太古代を通じて個々の⼤陸サイズは次第に増⼤し,結果として様々な時代に形成された地殻が⼤陸内部に安定地塊として保存されたとするモデルを提唱しておられる.およそ10億年前からは,⼤陸地殻の総⾯積が漸減する.沢⽥会員はそれを島弧—海溝系で活発に進⾏している地殻の侵⾷および地殻物質の沈み込み現象に起因するとの⾒解を公にしておられる.これらの成果は,⺟岩の堆積年代の違いを考慮せず,ジルコン年代を⼀括して扱うことによって提唱されてきた従来の,始原的マントルからの⼤陸地殻の分化という単純なモデルに基づく考察とは⼀線を画すものである.また,これらの研究の過程で,アフリカ南部ジンバブエ地塊において現地地質調査を精⼒的に⾏い,太古代〜原⽣代における当該地域の地帯構造発達史を詳しく論じておられる.沢⽥会員は,御荷鉾緑⾊岩類中の⽕成ジルコンの年代値や微量元素組成に基づき,その原岩についても論じておられ,それは枯渇したマントルに由来する苦鉄質マグマ活動によってジュラ紀後期に形成された海台に由来することを明らかにされた.これは,御荷鉾緑⾊岩類の形成史の議論のみならずジルコン鉱物学の新たな⽅向性にとっても重要な貢献である.
沢⽥会員は,このように独⾃の地質学的視点と微⼩鉱物の組成分析に基づいて卓越した研究成果を公表してこられた.また,現在では,研究対象を超苦鉄質岩中の希少なジルコンへと拡⼤し,⼤陸地殻だけでなく海洋地殻やマントルも含む包括的な固体地球進化の解読に挑んでおられる,今後も活躍が期待できる若⼿研究者である.以上のことから,沢⽥会員に⼩澤儀明賞を授与する.
日本地質学会柵山雅則賞
授賞者:大柳良介 会員(国士舘大学理工学部)
対象研究テーマ:プレート境界領域における岩石-水相互作用と反応輸送過程の実態解明
⼤柳良介会員は,プレート境界の岩⽯-⽔相互作⽤における開放系での反応輸送過程の重要性に着⽬し,地学現象の時空間尺度を決定する新機軸の研究を展開しておられる.そのため,天然の組織観察と鉱物組成変化,⽔熱反応実験による組織再現,溶液化学と最新のデータ駆動型解析を取り⼊れた数値モデリングを融合させて研究を進めてこられた.
プレート境界における物理化学プロセスは,岩⽯・⽔反応を伴う⽔溶液の移動に⼤きく左右される.⽯英・カンラン⽯・⽔溶液系の物質移動を伴う反応速度を求めるバッチ系実験から,流通系での動的反応実験に成功し,中間⽣成物や反応溶液の組成から反応の進⾏メカニズムを⼤柳会員は明らかにされた.⽔溶液の移動を含む多相系反応は,詳細反応経路を⼀意に決める事が困難だが,データ駆動型解析を駆使することで,反応に関与した鉱物と反応速度を精緻に決定し,反応輸送モデルを推定することにも成功しておられる.また,⽔熱実験と地球化学モデリングを組み合わせた研究からは,蛇紋岩化反応の律速過程が中間⽣成物の変動で動的に変化し,流体圧が部分的に上昇することを明らかにされた.これらの研究により,岩⽯―流体反応の時空間発展に⽀配されるプレート境界の物質変化と⼒学的挙動の変動などを定量的に明らかにする,データ駆動地球科学ともいうべき研究領域の開拓が,⼤柳会員らによって始まったといえる.
同会員はまた,伊⾖・⼩笠原海溝の海⻲海⼭から,しんかい6500により採取された炭酸塩脈を含む蛇紋岩の岩⽯学および詳細な3次元岩⽯破砕組織を解析し,⽔溶液・破砕粒⼦流体の流動数理モデルを適⽤することで,炭素を含んだ⽔溶液の前弧域での,間⽋的な⽔溶液・破砕蛇紋岩の上昇が,秒速0.1〜0.01mという⾼速で⼗⽇から千⽇の時間尺度で,4万年以上にわたり繰り返し起こった事を明らかにされた.この研究は海溝斜⾯における⼒学過程に岩⽯学的な新たな視点から重要な束縛条件を与え,プレート境界での諸過程に新たな視点を提供したことになる.
上記のように,プレート境界領域の物質科学において先進的な成果を挙げ,新規分野を開拓してきた⼤柳会員は,今後も多様な分野での活躍が期待できる若⼿研究者である.以上のことから,⼤柳会員に⽇本地質学会柵⼭雅則賞を授与する.
Island Arc Award
対象論文:Yoshihiko Tamura, Osamu Ishizuka, Tomoki Sato, Alexander R. L. Nichols, 2019 , Nishino shima volcano in the Ogasawara Arc: New continent from the ocean? Island Arc 28, e12285
Nishinoshima, a small island located ~1,000 km south of Tokyo in the active Ogasawara arc,is the subaerial summit of a much larger submarine volcano. The existence of this island has been known since 1702, but its first recorded eruption was in 1973. Following a lull of four decades, it suddenly began erupting again in November 2013 and activity has continued on and off until the present day. Tamura et al. (2019) reported whole rock geochemistry of lavas and scoria dredged from the main submarine volcanic edifice in 2015 and subaerial lava blocks from the 2015 eruption sampled by unmanned helicopter. Both the submarine and subaerial samples are andesitic in composition (58–62 wt% SiO2), and similar to the andesitic composition of the 1973 eruption products and pre-1973 edifice. The crust underlying Nishinoshima volcano is 21 km thick, without any thinning due to ri[ing, and thus Nishinoshima is one of the closest arc volcanoes to the mantle on the Earth. Based on the study of these lavas and scorias from Nishinoshima volcano, Yoshi Tamura and others verified the ‘Advent of Continents hypothesis’ that was proposed by their previous paper. They discovered primitive basalt lavas on knolls surrounding Nishinoshima and olivine-bearing phenocryst-poor andesites from the submarine flanks of the volcano. Their petrological and geochemical studies revealed that andesites erupted in recent history are the result of olivine fractionation from primary andesitic magmas. These primary magmas originate from the partial melting of hydrous mantle rocks, specifically plagioclase peridotites, at relatively low pressures. The thin crust in the Ogasawara Arc region allows for this low-pressure melting. The study of Nishinoshima volcano enhances our understanding of the volcanic activity and magma evolution in the oceanic arc. Moreover, the authors provide valuable insights into the geological characteristics of Nishinoshima volcano. The implications are: (1) the rate of continental crust accumulation, which is andesitic in composition, would have been greatest soon after subduction initiated on Earth, when most crust was thin; and (2) most andesite magmas erupted on continental crust could be recycled from “primary” andesite originally produced in oceanic arcs. In summary, the significant contributions and valuable insights provided by this study make it highly deserving of the 2023 Island Arc Award.
>論文サイトへ(wiley)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iar.12285
日本地質学会論文賞
対象論文:入月俊明・柳沢幸夫・木村萌人・加藤啓介・星 博幸・林 広樹・藤原祐希・赤井一行,2021,近畿地方の瀬戸内区に分布する下‒中部中新統の生層序と対比. 地質学雑誌, 127, 415‒429.
⻄南⽇本の中軸に点在する中新統は,かつて瀬⼾内中新統として⼀括されていたが,近年の年代層序の発展に伴って,時代の異なる地層が含まれることが指摘されるようになった.近畿地⽅にのみ残存する,いわゆる瀬⼾内中新統がどんなものか,⼊⽉会員らは岩相層序と⽣層序を⻑年詳細に調査し,産出した微化⽯(珪藻・浮遊性有孔⾍・⾙形⾍)に基づき⽣層序を明らかにした.この論⽂では,鮎河,綴喜,⼭辺および⼭粕の各層群を検討し,微化⽯層序と古地磁気層序などを組み合わせることによって層群間の年代層序学的関係を明確にした.さらに,他の層群との広域対⽐を試み,近畿地⽅から中部地⽅にかけての広い範囲に分布するいわゆる“瀬⼾内区”の中新統が19〜15 Ma の汎世界的な4 回の海⽔準上昇期に関連して形成された可能性が⾼いことを指摘した.本研究は,⽇本海拡⼤期の本州弧のテクトニクス・古環境・それらへの⽣物相の応答といった問題について,今後の研究を基礎づけるものである.以上のことから,本論⽂に⽇本地質学会論⽂賞を授与する.
>論文サイトへ(J-STAGE)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/geosoc/127/7/127_2021.0002/_article/-char/ja/
日本地質学会論文賞
対象論文:内野隆之・羽地俊樹,2021,北上山地中西部の中古生代付加体を貫く白亜紀岩脈群の岩相・年代と貫入応力解析から得られた引張場.地質学雑誌,127,651‒666.
前期⽩亜紀の⼤島造⼭運動のとき,北上⼭地の中古⽣代付加体には多様な⽕成岩脈が頻繁に貫⼊した.筆者らは北上⼭地の根⽥茂帯と北部北上帯において,そうした岩脈を,読者 が利⽤できるよう,詳しい位置情報を含めて約80枚記載した.また,放射年代測定により,約130〜120 Maに岩脈群が形成されたことを明らかにした.さらにそのうえで,岩脈の姿勢から応⼒解析を⾏い,北⻄-南東⽅向の引張応⼒場を検出した.従来,⼤島造⼭運動は東⻄圧縮場下で起こったと考えられていきたが,バレミアン〜アプチアン期の⼀時期には引張場に転換した可能性を初めて⽰した.これは後続の研究で,肯定的に検証されつつある. 筆者らはこの論⽂で,今世紀に⼊って⾰新された,岩脈の応⼒解析法を利⽤している.以前の⽅法では,最⼤⽔平応⼒の⽅位しかわからず,3本の主応⼒軸のうちどれが鉛直に近いかを決定できなかったが,今⽇ではそれが可能になっている.本論⽂は,この⽅法を⽇本の中⽣代の岩脈群に初めて適⽤したもので,国内に広く分布する中⽣界の研究がそれによって展開する可能性を実例によって⽰した.以上のことから,本論⽂に⽇本地質学会論⽂賞を授与する.
>論文サイトへ(J-STAGE)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/geosoc/127/11/127_2021.0025/_article/-char/ja/
日本地質学会論文賞
対象論文:Noda, A., Sato, D., 2018. Submarine slope‒fan sedimentation in an ancient forearc related to contemporaneous magmatism: The Upper Cretaceous Izumi Group, southwestern Japan. Island Arc, 27, e12240.
⻄南⽇本に分布する和泉層群は,後期⽩亜紀の前弧海盆にかんする貴重な記録である.本論⽂は,松⼭平野で採取されたコア試料に含まれる総厚165 mの和泉層群最下部を対象に,堆積学的・岩⽯学的な観察,砂岩の組成解析,及び凝灰岩のU‒Pb年代から堆積環境の変遷を論じたものである.著者らは,本論⽂で和泉層群を6つのユニットに細分し,そこに⾒られる岩相の遷移より,堆積システムが⾮⽕⼭性の泥質斜⾯または盆地床から,⽕⼭砕屑性の砂質海底扇状地に変化したことを⽰した.また,ジルコン粒⼦の U‒Pb 年代から,凝灰岩ユニットが⼭陽帯の珪⻑質⽕⼭岩に相当することも⽰した.本論⽂は,連続性が担保されるコア試料の利点を⽣かし,研究例の少ない和泉層群の堆積学的検討を⾏った点において貴重である.また,本論⽂には,和泉層群,⼤野川層群,及び領家・⼭陽帯からの年代データがレビューされており,今後の研究に資するものと期待される.以上の理由から,本論⽂に⽇本地質学会論⽂賞を授与する.
>論文サイトへ(wiley)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/iar.12240
日本地質学会論文賞
対象論文:Yoshida, K., Tamura, Y., Sato, T., Hanyuy, T., Usui, Y., Chang, Q., Ono, S., 2022. Variety of the drift pumice clasts from the 2021 Fukutoku-Oka-no-Ba eruption, Japan. Island Arc, 31, e12441.
⼩笠原諸島南⽅の福徳岡ノ場における2021年8⽉の噴⽕は,琉球列島に多量の軽⽯をもたらし,運輸・漁業関係を中⼼に⼤きな影響を与え,マスメディアやSNS などで⼤きく取り上げられた.本論⽂はこのとき放出された軽⽯について,漂着地での実地調査および岩⽯学・地球化学的研究を実施し,⼀連の軽⽯が多様な⾊や組織を⽰すにもかかわらず,全岩組成としては⼀様な粗⾯岩質であることを⽰し,特に特徴的な⿊⾊の軽⽯が,⽕⼭ガラス中の磁鉄鉱ナノ粒⼦晶出により⿊⾊化していることを明らかにした.ナノ粒⼦の晶出はマグマの粘性を引き上げるため,噴⽕機構に⼤きな影響を与えることが近年注⽬を集めており,本⽕⼭の噴⽕にもその影響が指摘された意義は⼤きい.また,漂着現場は「安全な地学教材」としての側⾯も持つことから,軽⽯の多様性についての物質科学的な記載整理が速やかになされた点は,アウトリーチの側⾯からも意義深い.軽⽯関連現象を網羅的に記述した本論⽂は,⽣物学等の分野からの注⽬度も⾼い.以上の理由から,本論⽂に⽇本地質学会論⽂賞を授与する.
>論文サイトへ(wiley)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iar.12441
日本地質学会研究奨励賞
受賞者:原田浩伸 会員(東北大学大学院理学研究科地学専攻)
対象論文:Harada, H., Tsujimori, T., Kunugiza, K., Yamashita, K., Aoki, Sl., Aoki, K., Takayanagi, H., Iryu, Y., 2021. The δ13C‒δ18O variations in marble in the Hida Belt, Japan. Island Arc, 30, e12389.
本論⽂で著者らは,変成炭酸塩岩から造⼭運動に伴う流体‒岩⽯相互作⽤や元素移動の記録を解読する⼿法を⼀般化するために,⾶騨帯の⼤理⽯と⽯灰珪質岩のC‒O‒Sr 同位体⽐を系統的に解析した.掘削コア試料から選別した標本に対して詳細な岩⽯組織記載に基づくマイクロサンプリングを駆使し,200 あまりの点から⾼精度C‒O 同位体値を得た.酸素同位体⽐の幅は流体との同位体交換によること,⽯灰珪質岩で⾒られた低い炭素同位体⽐は広域変成作⽤に伴う脱炭酸反応によるものと結論づけた.国内の地質試料で脱炭酸反応を岩⽯学的観察と同位体地球化学の双⽅から解析し,地殻内における炭酸塩の挙動解明に向けた可能性を⽰したことは特筆に値する.これらのことから,原⽥浩伸らによるこの論⽂に⽇本地質学会研究奨励賞を授与する.
>論文サイトへ(wiley)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/iar.12389
日本地質学会研究奨励賞
受賞者:佐久間杏樹 会員(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻)
対象論文:Sakuma, A., Kano, A., Kakizaki, Y., Tada, R., and Zheng, H., 2021, Upper Eocene travertine-lacustrine carbonate in the Jianchuan basin, southeastern Tibetan Plateau: Reappraisal of its origin and implication for the monsoon climate. Island Arc, 30, e12416.
アジアモンスーンシステムの成⽴について,ヒマラヤ-チベットの隆起との関連性が古くから論じられてきたが,その開始時期はいまだ明確ではない.近年のチベット周辺地域の研究では,後期始新世に起こった明瞭な湿潤化がモンスーン気候の始まりを⽰すと⽰唆されている.その根拠の⼀つは,湖⽔成とされた中国雲南省剣⼭盆地のJiuziyan 層である.本研究で佐久間会員らは,Jiuziyan 層の炭酸塩堆積物の層序,堆積相,同位体組成を調査し,従来の⾒解を再検討した.その結果,炭酸塩は湖⽔成ではなくトラバーチンであり,その酸素・炭素同位体に年縞と考えられる明瞭な周期的変化があることが⽰された.本研究は,始新世後期においてこの地域に降⽔量の季節変化があったことを再確認したものである.本研究は佐久間会員が学位研究の⼀部として主体的に進めたものと認められ,グローバルな視点から主に炭酸塩岩の野外調査と地球化学的分析を⾏う能⼒がうかがえる.以上のことから,佐久間杏樹会員らによる本論⽂に,⽇本地質学会研究奨励賞を授与する.
>論文サイトへ(wiley)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/iar.12416
日本地質学会研究奨励賞
受賞者:鈴木康太 会員(エネルギー・金属鉱物資源機構)
対象論文:Suzuki, K., Kawakami, T., Sueoka, S., Yamazaki, A., Kagami, S., Yokoyama, T., Tagami, T., 2022, Solidification pressures and ages recorded in mafic microgranular enclaves and their host granite: An example of the world's youngest Kurobegawa granite. Island Arc, 32, e12462.
本論⽂は,世界で最も若い⿊部川花崗岩に広く分布する⾓閃⽯を含む苦鉄質⽕成包有岩(MME)に注⽬し,それと⺟岩である花崗岩の固結圧⼒が⼀致することを⽰した.また,MME のジルコンU-Pb年代が⺟岩よりも若⼲古いことを明らかにした.⺟岩のジルコンは斜⻑⽯コアと基質に産するのに対し,MME では基質にのみ産する.その観察にもとづいて,著者らは⺟岩とMME のジルコンが,それぞれ初期晶出相と末期晶出相と解釈し,MME のジルコン年代のほうが岩体の固結年代として適切であると考察した.本論⽂は,⺟岩に⾓閃⽯を⽋く花崗岩体でもMME を⽤いた固結圧⼒・年代決定の有効性が⽰され,世界各地の若い花崗岩体に適⽤することで急速な隆起・削剥メカニズムの解明に寄与することが期待される.以上の重要な貢献により,鈴⽊康太会員らによるこの論⽂に,⽇本地質学会研究奨励賞を授与する.
>論文サイトへ(wiley)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/iar.12462
日本地質学会研究奨励賞
受賞者:山岡 健 会員(産業技術総合研究所地質調査総合センター)
対象論文:Yamaoka, K., Wallis, S. R., 2022. Recognition of broad thermal anomaly around the median tectonic line in central Kii peninsula, southwest Japan: Possible heat sources. Island Arc, 31, e12440.
三波川帯の低変成度部が中央構造線と接する,紀伊半島⾼⾒⼭地域を対象として,著者らは詳細なマッピングと構造解析をおこなった.また,砕屑粒⼦を⽤いた歪み解析および炭質物ラマン温度計分析を稠密に⾏うことで,中央構造線へ向かう3 km規模の温度上昇構造を描出し,また,この温度上昇が塑性変形の変形度とは無関係であることを⽰した.さらに,熱モデル計算によるフィッティングから,温度上昇の主要因は断層活動に伴う剪断熱ではなく,⾼温流体の流⼊にあったことを論じた.この結論は,紀伊半島での既存研究と異なる新たなものである.また巨⼤断層帯周辺の地質現象を探る上で,広く適⽤可能な総合的アプローチを⽰した点も⾼く評価出来る.以上の理由から,⼭岡健会員らによる本論⽂に⽇本地質学会研究奨励賞を授与する.
>論文サイトへ(wiley)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/iar.12440
日本地質学会フィールドワーク賞
受賞者:江島圭祐 会員(山口大学大学院創成科学研究科)
対象論文:Eshima, K., 2021. Anatomy of Shaku–dake high–Mg diorite, southwest Japan: Lithofacies variations and growth process of high–Mg diorite stock. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 116, 83–95.
本論⽂は北部九州の⽩亜紀尺岳閃緑岩体について,登攀技術を駆使した徹底的な野外調査および⾼密度サンプリングをもとに,マグマ上昇から定置までの詳細な三次元的履歴を明らかにした.幾つかのマグマ注⼊ポイントから岩脈状に上昇したマグマが,ある特定の深度で半固結状態の岩体中⼼部に向かってシル状に併⼊する過程が複数回繰り返され,岩体が成⻑したことを⽰した.このような詳細なマグマ上昇・定置履歴は,岩体周縁部の層状構造や⺟岩への貫⼊様式などの野外産状の綿密な記載と,⾼密度の全岩化学組成・モード組成および記載岩⽯学的データに基づいている.本論⽂で⽰された三次元的なマグマ定置モデルは,単純な境界条件を仮定した従来の数値計算からは描像し得ないものであり,地殻内部におけるマグマ定置プロセスの理解を向上させる研究として⾼く評価される.以上の理由により,本論⽂に⽇本地質学会フィールドワーク賞を授与する.
>論文サイトへ(J-STAGE)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jmps/116/2/116_200917/_article/-char/ja
日本地質学会フィールドワーク賞
受賞者:羽地俊樹 会員(産業技術総合研究所地質調査総合センター)
対象論文:Haji, T. and Yamaji, A., 2020, Termination of intra-arc rifting at ca 16 Ma in the Southwest Japan arc: The tectonostratigraphy of the Hokutan Group. Island Arc, 29, e12366.
⽇本海が拡⼤した中新世の前半,いわゆるグリーンタフが⽇本海沿岸を厚く覆った.この論⽂が対象とした兵庫県北部の北但層群は,⼭陰地⽅のグリーンタフを代表する⽐較的厚い地層だが,層序の概要が20世紀半ばに報告されて以来,研究が停滞していた.⽻地俊樹⽒は丹念な地表踏査により,北但層群内の⼆層準で不整合を発⾒し,それにもとづいて同層群の堆積中に沈降したハーフ・グラーベンを⼆つ発⾒した.そして,それらのグラーベンを画する正断層が,東北⽇本弧のグラーベン境界断層より変位量で⼀桁⼩さいことに注⽬し,⻄南⽇本弧の伸⻑変形が相対的に⼩さかったことを⽰唆した.これは,⽇本海拡⼤時に⻄南⽇本がほぼ⼀体としてドリフトしたという説を⽀持する結果である.さらには,16 Ma 頃に伸⻑変形が終わったことも⽰した.これは,古地磁気から⽰唆されている⻄南⽇本弧の回転終了と同時であり,また,15 Ma まで伸⻑テクトニクスが続いたとする通説の⾒直しを迫る成果である.以上のような成果は,詳細なルートマップや地質図,断⾯図,写真によって裏付けられている.以上のことから,この論⽂に⽇本地質学会フィールドワーク賞を授与する.
>論文サイトへ(wiley)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/iar.12366
2023年度名誉
2023年度 名誉会員
嶋本 利彦(しまもと としひこ)会員
1946年6月26日生(77歳)京都大学名誉教授
嶋本利彦会員は1971年に広島大学大学院理学研究科修士課程を修了後,1973年に同大学大学院博士課程を休学してテキサス州立テキサスA&M大学大学院博士課程に入学し1977年に修了した.1977年に広島大学理学部に助手として着任,1986年より助教授,1989年より東京大学地震研究所助教授,1995年より教授,1998年より京都大学大学院理学研究科教授,2007年より広島大学大学院理学研究科教授を務めた.2010年に広島大学を退職後,同年から2017年まで中国地震局地質研究所客員教授,2017年以降は栄誉教授を務めている.この間,1977年にテキサスA&M大学よりPh.D.の学位を取得,2010年に京都大学名誉教授の称号を授与された. 嶋本会員は断層のレオロジーと地震発生機構の解明を目的とした研究を長年行ってきた.特に,断層のレオロジーと地震時断層の高速すべり摩擦特性に関する研究において世界をリードし,数多くの成果を挙げた.これらの研究成果は,地震発生機構の研究分野に対する地質学からの重要な貢献と認められる. 断層のレオロジーに関する研究では,岩塩を模擬物質として用い断層を脆性・中間・完全塑性に三分するモデルを提唱し,中間領域の深さでマイロナイト様の変形構造が発達すること,また地震性の滑り挙動が中間領域にまで及ぶことなどを示した.さらに,これらの成果に基づいて摩擦–流動則を提案し,脆性から完全塑性に至る断層挙動を統一的に記述することを初めて可能にした.断層の高速摩擦に関する研究では,断層のすべり速度が高速になると摩擦発熱などに起因した様々な要因により断層強度が著しく低下することを示し,低速から高速に及ぶ幅広いすべり速度条件について断層の力学的性質の全容を明らかにした.嶋本会員はこれらの研究によって2005年に日本地質学会賞,2015年にEGU Louis Néelメダル,2016年にJpGUフェロー,2019年にAGUフェローを受賞している.またJournal of Structural GeologyやIsland Arcの編集諮問委員を長年務めるなど,学術界の発展に大きく寄与した. 嶋本会員は熱意に溢れた学生指導や共同研 究を通じて多くの研究者を育成し,その多くは国内外で活躍している.さらに,試験機設計のノウハウを後進に伝えるためのセミナーを国内外で数多く開催するなど,嶋本会員が後進育成に果たした功績は大きい.嶋本会員は1995年から1999年まで,および2004年から2006年まで本学会評議員を務めた.この間に国際交流委員会委員長,各賞問題検討委員会委員長,財政問題検討委員会委員などを歴任した.2002年から2004年までは構造地質研究会会長を務め,現在の本学会構造地質部会の活動への流れの構築に貢献した.以上のように,嶋本利彦会員の地質学における学術研究,教育,普及,そして本学会の運営への多大な貢献は,本学会の名誉会員として相応しいものと判断し,ここに推薦する.
宮下 純夫(みやした すみお)会員
1946年10月20日生(76歳)新潟大学名誉教授,特定非営利活動法人北海道総合地質学研究センター理事
宮下純夫会員は1970年に北海道大学理学部地質学鉱物学科を卒業後,1973年に同大学大学院理学研究科修士課程を修了,1979年に同大学 大学院博士課程を修了した.日本学術振興会奨励研究員,オルレアン大学招聘研究員を経て,1987年に新潟大学理学部に助手として着任,その後1991年より助教授,1998年より教授を務め,2012年に退職し新潟大学名誉教授称号を授与された.現在,特定非営利活動法人北海道総合地質学研究センター理事長を務めている.宮下会員は日高変成帯におけるオフィオライト層序の復元を通じて日高変成帯が大陸地殻と海洋地殻の接合によって形成されたことを明らかにし,この地域における島弧-島弧衝突テクトニクスに重要な根拠をもたらした.また,国内のオフィオライト層序と付加体に含まれる緑色岩を研究し,日本列島のジュラ紀以降の地質体と海洋プレート運動との関係に重要な視点をもたらした.研究は国内にとどまらず,世界各地のオフィオライトや付加体中の緑色岩を精力的に調査し,それらの地質学的・岩石学的研究を推進した.特に,オマーンオフィオライトの地殻セクションの地質調査に基づき,中央海嶺のマグマプロセスとダイナミクスの解明に多大な成果をもたらした.これらの研究は国内外の学会で発表されるとともに学術雑誌に精力的に投稿され,地質学への顕著な貢献と認められる. これらの研究貢献により宮下会員は1994年および2007年に日本地質学会論文賞を受賞している. 宮下会員は新潟大学において長年にわたり地質学の教育研究に携わり,多くの学生を指導して地質学関連の企業,研究所,大学そして教育機関に送り出した.卒業生は様々な分野で活躍しており,教育と後進育成にも寄与した.また,専門である岩石学的研究にとどまらず,2004年10月に発生した新潟県中越地震では新潟大学中越地震調査団の事務局長として奔走するなど多方面で尽力し,社会における地質学の重要性を高めることに貢献した.新潟大学退職後は北海道札幌市において市民講演会で地球環境について講演するなど,地質学の普及と振興に努めている. 宮下会員は長年にわたり本学会の運営と発展に貢献した.2003年から2008年まで本学会理事を務め,この間には地質学雑誌企画部会長および地質学雑誌編集員会副委員長を歴任し地質学雑誌の充実に努めた.2008年からは2期4年間にわたり本学会会長を務めた.会長在任中の2008年12月に本学会は一般社団法人に移行し,その前後において本学会の一般社団法人化に重要な役割を果たした.その後2012年からの2年間も本学会理事を務めた. 以上のように,宮下純夫会員の地質学における学術研究,教育,普及,そして本学会の運営への多大な貢献は,本学会の名誉会員として相応しいものと判断し,ここに推薦する.
各賞-日本地質学会フィールドワーク賞
日本地質学会フィールドワーク賞(2022年創設)
フィールドワークをベースとする力作の論文や地質図等を発表した満32歳未満の若手会員に授ける賞.若手育成事業の一環として2022年に新設.
※各受賞者または受賞論文をクリックすると、推薦理由をご覧いただけます。
受賞者
対象論文
2025
松山和樹(名古屋大学大学院環境学研究科)
Matsuyama, K. and Michibayashi, K., 2024, Structural evolution of the Horoman peridotite complex in conjunction with the formation of the Hidaka Metamorphic Belt, Hokkaido. Tectonophysics 892, 230535.
2023
羽地俊樹(産業技術総合研究所地質調査総合センター)
Haji, T. and Yamaji, A., 2020, Termination of intra-arc rifting at ca 16 Ma in the Southwest Japan arc: The tectonostratigraphy of the Hokutan Group. Island Arc, 29, e12366.
2023
江島圭祐(山口大学大学院創成科学研究科)
Eshima, K., 2021. Anatomy of Shaku–dake high–Mg diorite, southwest Japan: Lithofacies variations and growth process of high–Mg diorite stock. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 116, 83–95.
Geo暦(2024)
2024年Geo暦(行事カレンダー)
2021年版 2022年版 2023年版 2024年版 2025年版
2024年版 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
○印は学会主催行事.(共)学会共催・(後)後援・(協)協賛
1月January
○関東支部:県の石―千葉の岩石・鉱物・化石― 講演会
1月14日(日)13:00-16:00
場所:千葉県立中央博物館講堂(Zoomを使用したハイブリッド形式)
定員:会場100名+Zoom(オンライン)100名
申込期間:2023年12月8日(金)〜26日(火)17:00締切
https://geosociety.jp/outline/content0201.html#2023ken-no-ishi
(後)令和5年度技術者倫理講習会
主催:日本応用地質学
1月16日(火)16:30-18:50
Zoomによりオンライン講習会
参加費:学会員・山口大学理学部地球圏システム科学科支援企業社員 1,000円,非学会員 3,000円
CPD:2.0CPDH
https://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/others-pdf/20240116oyorinrikoshu.pdf
産技連地質地盤情報分科会令和5年度講演会
「ハザードマップ作成における地質地盤情報の利活用」
1月18日(木)13:30-16:00
会場:北とぴあ 第⼆研修室(東京都北区王子),対面のみ
参加無料(事前登録制,定員100名,申込締切:1/12(金)正午)
https://www.gsj.jp/information/domestic/sgr/
防災学術連携体緊急報告会
「令和6年能登半島地震の概要とメカニズム」
1月19日(金)17:30-19:00
オンライン,参加費無料
Youtube(一般公開・申込不要)でご視聴いただけます
https://youtu.be/wO34MFfcS6A
(後)原子力総合シンポジウム2023
主催:日本学術会議総合工学委員会,総合工学委員会原子力安全に関する分科会
1月22日(月)13:00-17:10
会場:日本学術会議講堂(東京都港区六本木7-22-34)・オンライン
参加無料
https://www.scj.go.jp/ja/event/2024/353-s-0122.html
第200回深田研談話会(ハイブリッド)
謎の海底隆起?!地すべりがつくるノンテクトニック地質構造
1月 26日(金)15:00〜16:30
講師:田近 淳 氏(株式会社ドーコン 環境事業本部)
場所:深田研 研修ホール(東京都文京区)/Zoomウェビナー
定員:会場参加(30名)・オンライン参加(上限450名)、先着順
参加費無料(Webページより要事前申込)
https://fukadaken.or.jp/?p=8001
防災学術連携体:令和6年能登半島地震・1ヶ月報告会
1月31日(水)13:00-18:00
YouTube(一般公開・申込不要)
https://www.youtube.com/live/eTFKgYC-2S8?feature=shared
2月February
東京地学協会2023年度第2回定期講演会
望月勝海教授,かく記録せり―日記に読む地体構造論・地誌記述・地学教育の歴史
2月24日(土)14:00-16:00
会場:地学会館2階講堂(東京都千代田区二番町12-2)
講演者:山田俊弘(東京地学協会日本地学史編纂委員)
参加費無料・申込不要
http://www.geog.or.jp/lecture/lecturescheduled/495-news240110.html
○日本地質学会第10回ショートコース
テーマ「海底鉱物資源」
2月25日(日)
オンライン(zoom)
https://geosociety.jp/science/content0171.html
3月March
海と地球のシンポジウム2023
3月1日(金)-2日(土)
開催方法:口頭発表、ポスター発表ともに実会場にて実施いたします.
会場:東京大学弥生キャンパス 弥生講堂
発表課題募集締切:1月9日(火)
https://www.jamstec.go.jp/j/pr-event/ocean-and-earth2023
○西日本支部令和5年度総会・第174回例会の案内
共催:薩摩川内市役所
3月2日(土)
会場:薩摩川内市川内駅コンベンションセンター SSプラザせんだい 3階会議室
参加・講演申込(2月1日締切)
https://geosociety.jp/outline/content0025.html
○第4回JABEEオンラインシンポジウム
大学縮小危機のなかで、社会の要求にどのように応えるか
〜JABEEを活用した技術者の育成と輩出〜
3月3日(日)13:30〜17:20(予定)
開催方式:Zoomを用いたオンライン方式
https://geosociety.jp/science/content0167.html
水・土壌汚染研究部会セミナー(第122回)
3月6日(水)14:00-15:30
場所 おおさかATCグリーンエコプラザ(大阪市住之江区南港北)
講演 本間 勝 氏
題目 宅地造成に関わる地価形成と法規制
参加無料
https://www.ecoplaza.gr.jp/seminar_post/s20240306/
CPS/WTK & ABC ワークショップ
「生命の起源と進化を規定した惑星表層環境を考える」
主催 惑星科学研究センター CPS
3月7日(木)10:00-18:00
会場:神戸大学CPS + zoom
https://www.gfd-dennou.org/seminars/wtk/2024-03-07/
令和5年度海洋プラスチックごみ学術シンポジウム
主催:環境省
【研究セッション】(オンライン)
3月9日(土)9:00-16:30予定
対象:研究者や専門家を対象
参加費無料,定員:1000名(要参加登録3/6締切)
講演申込:1/26締切
【特別セッション】(対面)
3月19日(日)9:00-12:00予定
対象:一般の方を対象
場所:秋葉原UDXシアター (東京都千代田区外神田4丁目)
参加費無料, 定員:150名
https://www.env.go.jp/press/press_02577.html
シンポジウム 筑波山地域ジオパークの古代遺産を活かす
主催:筑波山地域ジオパーク推進協議会 教育・学術部会
3月16日(土)13:30〜16:30 (開場13:00)
場所:つくばジオミュージアム多目的室およびオンライン
定員:会場50名,オンライン90名
https://www.tsukuba-geopark.jp/event/page001314.html
『赤水図を使った現代の地理授業』報告会
高萩市教育委員会及び市内3中学校の協力により,中学1年生を対象に行った地理の授業の報告会を行います.
主催:長久保赤水顕彰会
3月16日(土)13:00-15:00
会場:高萩市中央公民館(茨城県高萩市高萩17)
入場無料
詳しくは,こちら(PDF)
国立沖縄自然史博物館誘致 東京シンポジウム
3月22日(金)16:00‐18:00
場所:笹川平和財団ビル11F国際会議場(東京都港区虎ノ門)
参加費無料 ※要事前申込 3/19締切
https://www.okinawanhm.com/
令和6年能登半島地震・3ヶ月報告会
3月25日(月)9:00-14:40
主催:防災学術連携体・日本学術会議防災減災学術連携委員会
ZOOM webinar(定員500名)
Youtube(一般公開・申込不要)での配信も予定
※日本地質学会「令和6年能登半島地震震源域の変動地形と海陸境界断層」石山達也(東京大学准教授)発表予定
https://janet-dr.com/050_saigaiji/2024/050_240101_notohantou0325.html
日本学術会議公開シンポジウム・第18 回防災学術連携シンポジウム
「人口減少社会と防災減災」
3月25日(月)15:30-18:50
ZOOM webinar(定員500名・要申込)
Youtube(一般公開・申込不要)配信も予定
https://janet-dr.com/060_event/20240325.htm
第244回イブニングセミナー(オンライン)
3月29日(金)19:30-21:30
演題:「地下水汚染の機構解明の手順 層状水での例」
講師:風岡修先生(地質汚染診断士、理学博士)
参加費:主催NPO会員及び学生の方(無料) 非会員の方(1,000円)
https://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
4月April
○2024年度関東支部総会・講演会
4月20日(土)14:00-16:45
場所:北とぴあ第2研修室(東京都北区王子)
講演:数値地形画像を用いたダイナミックな地表面変位の可視化
講師:向山 栄氏(国際航業株式会社 公共コンサルタント事業部)
https://geosociety.jp/outline/content0201.html
日本堆積学会 2024 年熊本大会
4月20日(土)-22 日(月)
会場:熊本大学(黒髪南地区)
講演申込・巡検参加締切:3/22(金)
大会参加申込締切(早期):4/11(木)
https://sites.google.com/view/ssjconference2024kumamoto
学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた国の方針に関する説明会
主催:内閣府科学技術・イノベーション推進事務局
第1回 4月25日(木) 17:30-18:00
第2回 4月26日(金) 17:30-18:00
対象:一般公開(特に、学術団体、大学、研究機関等に所属する研究者・
URA・図書館関係者、事務職員、その他学術論文等の即時オープンアクセス
にご関心がある方)
https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20240415.html
5月May
※2024年「地質の日」関連行事はこちらから
2024年度第1回地質調査研修
主催:産総研コンソーシアム「地質人材育成コンソーシアム」
5月13日(月)- 5月17日(金)
場所:
(室内座学)茨城県つくば市(産総研)
(野外研修)茨城県ひたちなか市、福島県双葉郡広野町・いわき市周辺
※今回は特に企業の地質初心者が対象となります。
定員:6名(定員になり次第締切)
参加費:84口(1口1000円)の会費が必要です.
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2024-1.html
第33回地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン 第1-4/全8回)
5月17日(金)10:00-17:30
内容:健全な水循環と地下水/土壌汚染状況調査の流れと調査や対策の制約・難しさについて/地質汚染調査入門
(zoomによるオンライン)
参加費:無料(事前登録制)CPD:6単位
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
第2回深田研講座
5月23日(木)13:00-16:15
形式:zoomウェビナーによるオンライン配信
講師:八木浩司 氏(深田地質研究所 客員研究員)
テーマ:ヒマラヤにおける斜面災害の背景とその凄まじさを理解する
参加費無料、300名(先着)*要事前申込
https://fukadaken.or.jp/?p=8170
第33回地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン 第5-8/全8回)
5月24日(金)10:00-17:30
内容:地質汚染調査・土壌汚染状況調査概論/地質汚染調査におけるボーリング調査/地下水汚染調査
(zoomによるオンライン)
参加費:無料(事前登録制)CPD:6単位
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
6月June
第33回地質汚染調査浄化技術研修会(現地研修①ボーリングコア研修)
6月1日(土)10:00-17:00
会場:千葉市文化センター 5階セミナー室 (JR千葉駅より徒歩10分)
内容:ボーリングコア・地質の記載/柱状図の作成
参加費:当NPO会員・賛助会員:9,000円 /非会員:12,000円
CPD:5単位 定員:30名
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
○日本地質学会2024年度(第16回)代議員総会
6月8日(土)14:00(時間は予定)
WEB会議形式
総会議事次第はこちら
2024年度 深田地質研究所 研究成果報告会
6月14日(金)13:00〜16:40
形式:会場参加(定員30名、先着順)/zoom ウェビナーによるオンライン配信 (定員450名先着順)
参加費:無料、*要事前申込
https://fukadaken.or.jp/?p=8205
地質学史懇話会
6月15日(土)13:30-17:00
場所:北とぴあ 807号室(東京都北区王子)
中島由美:平賀源内の秋田行き
小川勇二郎:北米コルディレラの地質とテクトニクスの新説
問い合わせ:矢島道子 pxi02070[at]nifty.com
※[at]を@マークにして送信してください
東京地学協会2024年度 特別講演会
「隆起痕跡からわかる能登半島地震の履歴」
6月15日(土)15:00-16:30(令和6年度総会終了後)
場所:東京グリーンパレス(麹町)地階「ふじ」
講師:宍倉正展(産業技術総合研究所)
参加無料・申込不要.直接会場にお越し下さい.
http://www.geog.or.jp/
7月July
(後)第61回アイソトープ・放射線研究発表会
7月3日(水)-5日(金)
会場 日本科学未来館 7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
発表申込期間:2024年1月15日(月)〜2月29日(木)12時
https://www.jrias.or.jp/
第245回イブニングセミナー(オンライン)
7月5日(金)19:30-21:30
演題:ダイナミック地形学試論−下総台地の水文地形−
講師:近藤昭彦先生(千葉大学名誉教授)
参加費:主催NPO会員及び学生(無料),非会員(1,000円)
https://www.npo-geopol.or.jp/seminer.htm
第201回深田研談話会
テーマ:海と陸から鬼界海底カルデラの実像に迫る−最新の探査技術から見えてきた縄文の巨大噴火−
7月12日(金)15:00-16:30
場所:深田地質研究所 研修ホール(東京都文京区)
講師:鈴木桂子 氏(神戸大学)
定員:会場参加(30名)、オンライン(450名)*先着順
参加費無料(要事前申込)
https://fukadaken.or.jp/?p=8305
令和6年能登半島地震・7ヶ月報告会
7月30日(火)13:00-17:00(予定)
オンライン開催
主催:防災学術連携体
https://janet-dr.com/index.html
8月August
大阪公立大学2024年度特別講演会
8月5日(月)15:00–16:30
主催:大阪公立大学大学院理学研究科地球学専攻自然災害科学研究グループ
会場:大阪公立大学中百舌鳥キャンパスA12棟(旧サイエンスホール)
講師:石渡 明氏(原子力規制委員会委員)
詳しくは,こちら
参加申し込みはこちらから(8/2締切)
(後)科学教育研究協議会 第70回全国研究大会・いわて花巻大会
8月7日(水)、8日(木)、9日(金)
会場:
花巻市立花巻中学校
花巻市立若葉小学校
花巻市文化会館(岩手県花巻市若葉町)
https://kakyokyo.org/
地学団体研究会第78回つくば総会
8月17日(土)-18日(日)
会場:つくばカピオ(茨城県つくば市)
https://www.chidanken.jp
産業技術総合研究所地質調査総合センター 研究室見学会
GSJで行う研究開発業務の見学会を実施します。
8月27日(火)13:00-17:15
対象 学部生、大学院生、既卒者
募集人数:先着30名
開催地 産業技術総合研究所つくば中央事業所7群(茨城県つくば市)
https://www.gsj.jp/information/recruit/gsj-tour2024.pdf
申込はこちら
https://forms.office.com/r/HbQCjgQwVF
9月September
(後)第67回粘土科学討論会
9月4日(水)-9月6日(金)
会場:九州工業大学戸畑キャンパス(北九州市戸畑区仙水町1-1)
すべて対面で開催予定(講演会9月4-5日、現地見学会9月6日)
https://www.cssj2.org/event/annual_meeting/
○日本地質学会第131年学術大会(2024山形)
9月8日(日)〜10日(火)
会場:山形大学小白川キャンパス
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131
報告会「JAMSTEC2024」
9月11日(水)14:00-17:45
会場:東京国際フォーラム・ホールB7(千代田区丸の内3丁目)
オンライン配信:YouTube(日本語)及びzoom(英語同時通訳)
参加無料
https://www.jamstec.go.jp/j/pr-event/jamstec2024/
日本鉱物科学会2024年度年会・総会
9月12日(木)-14日(土)
会場:名古屋大学東山キャンパス
https://jams-mineral.jp/meeting/
日本鉱物科学会2024年度年会・総会
9月12日(木)-14日(土)
会場:名古屋大学東山キャンパス
https://jams-mineral.jp/meeting/
第41回歴史地震研究会(木曽御嶽大会)
9月13日(金)- 15日(日)
場所:木曽町文化交流センター,王滝村公民館
講演申込締切:5/31(金)
http://www.histeq.jp/kenkyukai.html
(協)地盤技術フォーラム2024
9月18日(水)-20日(金)10:00−17:00
場所:東京ビックサイト・東ホール(江東区有明3丁目)
http://www.sgrte.jp/
(共)2024年度 日本地球化学会 第71回年会
9月18日(水)〜20日(金)
会場:金沢大学・角間キャンパス(自然科学本館)
http://www.geochem.jp/meeting/
第246回イブニングセミナー(オンライン)
9月27日(金)19:30-21:30
演題:「住む街で考える土と水の科学ー貝塚をヒントとしてー」
講師:宮崎 毅先生(東京大学名誉教授、もりや市民大学学長、当NPO理事)
参加費:主催NPO会員及び学生の方(無料) 非会員の方(1,000円)
https://www.npo-geopol.or.jp/seminer.htm
10月October
第6回 鉱物肉眼鑑定研修
10月2日(水)-4日(金)
場所:日本学術会議講堂(オンライン配信)
定員:4-5名(定員になり次第締切)
CPD:24単位
参加費:48口(1口1000円)の会費が必要です
https://www.gsj.jp/geoschool/koubutsu/6th.html
日本学術会議主催学術フォーラム「未来の学術振興構想−実現に向けて−」
10月4日(金)
場所:日本学術会議講堂(オンライン配信)
参加費無料
https://www.scj.go.jp/ja/event/2024/364-s-1004.html
jGnet地質学講座2024 地質学の最新研究を学ぶ(ライブ配信あり)
10月5日(土)13:00-16:30
形式:対面方式及びライブ配信(JCCAのCPD認定プログラム202408210016)
会場:岡山理科大学A0133教室(A1号館3階)
講演1「過去のプレート沈み込み帯で形成した変成岩とその地質記録」:辻森樹氏(東北大学教授)
講演2「最新・日本列島と東アジアのテクトニクス:大・南中国と大和構造線」:磯崎行雄氏(東京大学名誉教授)
申込締切:9月30日(月)
参加費3,000円(※学生・一般の聴講は無料)
https://jgnet.org/
2024年度日本火山学会秋季大会(学術講演会)
10月16日(水)〜18日(金)
会場:道立道民活動センター「かでる2・7」(予定)
http://www.kazan-g.sakura.ne.jp/J/index.html
日本珪藻学会第43回研究集会
公開シンポジウム「珪藻が出ない!」
10月20日(日) 10:30~13:00
場所:琵琶湖博物館セミナー室(滋賀県草津市下物町1091)+Zoom
シンポ参加申込10/17(木)まで:https://forms.gle/hwbxo2W1UN8uCDj99
https://diatomology.org/
2024年度第2回 地質調査研修(初級/経験者向け)
10月21日(月)-25日(金)
場所:島根県出雲市長尾鼻周辺(小伊津海岸)
定員:6名(定員になり次第締切)
CPD:42単位
参加費:84口(1口1000円)の会費が必要です
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2024-2.html
第41回地質調査総合センターシンポジウム
デジタル技術で繋ぐ地質情報と防災対策〜活断層-火山-斜面災害-海洋地質〜
10月25日(金)10:00〜17:00
会場:イイノホール& カンファレンスセンター(東京都千代田区内幸町)
定員:現地200名+オンライン500名(ともに事前登録制、定員になり次第締切)
参加費無料
https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo41/index.html
○若手巡検・研究集会 in 愛知県-岐阜県
10月26日(土) 9時集合,18時半解散
対象者:35歳以下の日本地質学会正会員
申込締切:9月27日(金)17時
https://geosociety.jp/science/content0128.html
深田研一般公開2024
10月27日(日)10:00-16:00
会場:深田地質研究所(東京都文京区本駒込2-13-12)
ラボツアーやミニレクチャー、アンモナイトアクセサリー製作などの
体験学習も豊富に用意しています.
入場無料
https://fukadaken.or.jp/?p=8452
11月November
堆積学スクール 2024
「安倍川源流域の大崩壊が流域の堆積作用と地形発達に与えた影響」
11月2日(土)午後-3日(月)夕方
場所:静岡県静岡市安倍川周辺地域
定員:13名(申し込みが多い場合は学生優先・会員優先)
参加申込締切:9月30日(月)
https://forms.gle/fEM1EK8cD6HWfohn6
国立国会図書館主催フォーラム
「オープンサイエンスを社会につなぐために ―国立国会図書館の取組を踏まえて」
(図書館総合展2024)
11月6日(水)13:00-14:30
場所:パシフィコ横浜 アネックスホール (横浜市西区みなとみらい1-1-1)
参加費無料,定員200名・要事前申込
https://www.libraryfair.jp/forum/2024/1075
○日本地質学会関東支部
講演会「県の石−東京都の岩石・鉱物・化石−」
11月10日(日)13:00〜16:00
会場 早稲田大学早稲田キャンパス6号館001教室
定員 現地100名(上記教室)、オンライン100名
参加費 無料(要事前申込み)
https://geosociety.jp/outline/content0201.html#2024ishi
第39回(2024)京都賞記念講演会
11月11日(月)13:00〜
会場:国立京都国際会館(京都市左京区岩倉)
基礎科学部門 ポール・F・ホフマン(地質学者/ビクトリア大学客員教授)ほか
入場無料,同時通訳,定員1,500名(先着)
https://www.kyotoprize.org/speech/2024
2024年度第3回 地質調査研修(中級/経験者向け)
11月11日(月)-17日(日)
場所:福岡県福岡市能古島
定員:6名(定員になり次第締切)
CPD:45単位
参加費:90口(1口1000円)の会費が必要です
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2024-3.html
(協)石油技術協会 令和6年度秋季講演会
「低炭素エネルギーシステムの社会実装に向けて〜水素・アンモニア〜」
11月12日(火) 10:30-17:30
場 所: 東京大学 小柴ホール(ハイブリッド開催)
参加費:3,000円:石油技術協会会員、賛助会員、協賛団体(所属者),学生無料
※地質学会の会員は上記金額で参加可能です.
https://www.japt.org/
(協)ポール・ホフマン博士京都賞受賞記念講演(東京・駒場)
11月14日(木)17:00~19:00 (開場:16:00)
会場:東京大学駒場キャンパス 21KOMCEE EAST K011(地下)
要事前申込(10/19締切),入場無料
https://geosociety.jp/news/n185.html
学術会議公開シンポジウム「海底地質災害と洋上風力開発」
11月14日(木)10:00-18:00
場 所:日本学術会議講堂およびオンライン配信
要参加申込
https://www.kiso.co.jp/sssgr/topics/events/entry-1155.html
第63回温泉保護・管理研修会
11月18日(月)-19日(火)
場所:北とぴあ つつじホール(東京都北区王子)
主催:公益財団法人中央温泉研究所
後援:環境省
http://www.onken.or.jp/seminar.html
「堆積構造の世界」連続講義 第1回 堆積構造の基礎
11月19日 (火) 18時から
Zoomウェビナーオンライン開催(参加無料・要事前申込)
コーディネーター:石原与四郎 先生
講師:横川美和 先生,山口 直文 先生,成瀬 元 先生
https://sites.google.com/view/taisekigakukougi?usp=sharing
国際ゴンドワナ研究連合(IAGR)2024年総会及び第21回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム
11月18日〜22日
場所・会場:マレーシア,クチンのWater Front Hotel
参加登録及び発表要旨締切:2024年3月31日
参加登録及び発表要旨提出先:iagr2024[at]curtin.edu.my
問合せ:Prof. Nagarajan Ramasamy, Curtin University, Malaysia
E-mail: nagarajan[at]curtin.edu.my
※[at]を@マークにして送信してください
国際シンポジウム
未来社会のための堅牢なサイバーライフライン
11月21日(木)-22日(金)13:00-17:00
会場 富士山科学研究所(山梨県富士吉田市字吉田)
※ハイブリッド開催 参加無料
https://www.mfri.pref.yamanashi.jp/kazan/sp/
原子力発電環境整備機構(NUMO)講演会
地層処分事業の推進と安全コミュニケーションにおける世代を超えた挑戦
11月22日(金)13:00-16:30
Zoom Video Webinarによるオンライン開催
参加無料,定員100名(先着)(申込締切:11月13日(水)13:00)
https://www.numo.or.jp/topics/202424101113.html
深田研談話会
誘発地震の実態と応用:フィールドデータ解析から大型試験片による再現実験まで
11月22日(金)15:00〜16:30(14:30開場)
講師:伊藤 高敏 氏(東北大学)
定員:会場参加(30名)・オンライン参加(上限450名)、先着順
参加費:無料(要事前申込)
申込締切: 11月15日(金)17時締切
※募集人数に達し次第、締め切ります。
https://fukadaken.or.jp/?p=8536
(後)日本応用地質学会令和6年度技術者倫理講習会
11月27日(水)13:30-17:00
Zoomによりオンライン講習会(質疑応答可能)
定員500名
要事前申込(11月19日締切,先着順)
参加費:応用地質学会会員等:2,000円,非会員6,000円
https://www.jseg.or.jp/02-committee/jseg-edu.html
「環境研究総合推進費」若手研究者による 研究成果発表会
主催:環境再生保全機構
11月29日(金)13:30〜16:40(オンライン)
参加費無料,要事前申込
https://www.erca.go.jp/suishinhi/kenkyuseika/kenkyuseika_2_r6.html
12月December
(後)第34回社会地質学シンポジウム
12月6日(金)-7日(土)
会場:日本大学文理学部図書館3Fオーバルホール+オンライン
参加費:日本地質学会会員は4,000円
https://www.jspmug.org/envgeo_sympo/34th_sympo/
第315回 地学クラブ講演会「最近の助成研究から」
12月6日(金)15:30-17:30
会場:地学会館 2階講堂
講演:栗林 梓(皇學館大・文),田嶋 智(東大・新領域・博士後期課程),山田和芳(早大・人間科学)
参加無料,事前申込不要,直接会場へ
https://www.geog.or.jp/lecture/info/2024-11-07/
【JST】ASPIRE Japan-UK Quantum Technology ネットワーキングイベント
12月6日(金)18:30-21:00
開催形式:オンライン(Zoom)
使用言語:英語
参加費無料(要事前申込:11月8日(金)17時締切)
https://www.jst.go.jp/aspire/event/event_aspire2024_uk.html
第42回地質調査総合センターシンポジウム
令和6年度 地圏資源環境研究部門 研究成果報告会
「脱炭素と社会・経済が調和したトランジションに向けて エネルギー・環境・資源制約へと対応する燃料資源地質研究」
12月6日(金)13:30-17:30
会場:秋葉原ダイビル・コンベンションホール(東京都千代田区)
※現地開催のみ
参加費:無料(要事前要録:締切12/2)
https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo42/index.html
令和6年度国総研講演会
地震災害への国総研のチャレンジー阪神・淡路大震災30年、能登半島地震から見えた課題ー
12月12日(木)10:00-17:15
会場:一橋講堂(千代田区一ツ橋 学術総合センター2階)ライブ配信あり
参加無料・要事前申込(締切12/9)
定員450名、ライブ配信1000名
https://www.nilim.go.jp/lab/bcg/kisya/html/kisya20241120.htm
第247回イブニングセミナー(オンライン)
12月19日(木)19:30-21:30
演題:「ナラティブ・アプローチとしての新たなナチュラルアナログ研究の利用法」
講師:佐藤 努先生(北海道大学大学院工学研究院資源循環材料学研究室教授,日本粘土学会会長)
参加費:主催NPO会員及び学生の方(無料) 非会員の方(1,000円)
https://www.npo-geopol.or.jp/seminer.htm
第43回地質調査総合センターシンポジウム
「地質を用いた斜面災害リスク評価−高精度化に必須の地質情報整備−」
12月20日(金)13:00-17:20
会場:アクロス福岡7階大会議室(福岡県福岡市)
※ストリーミング配信有(講演のみ)
参加費無料(要事前登録:締切12/10)
https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo43/index.html
地質学史懇話会
12月21日(土)13:30-17:00
場所:北とぴあ 806号室(東京都北区王子)
・八耳俊文:マンハッタン計画と水俣病―戦後20年日本地球化学史
・黒田和男:感銘を受けた授業―東中秀雄先生(講演延期)
問い合わせ:矢島道子 pxi02070[at]nifty.com
※[at]を@マークにして送信してください
(後)一般公開講座:大地を分ける「武山断層」
主催:三浦半島活断層調査会
12月21日(土)小雨決行 9:30-15:30
見学参加者募集中(12/17締切)
参加費:500円
詳しくはこちら
STAR-Eプロジェクト第4回研究フォーラム
〜情報科学×地震学 学官連携の未来像〜
主催:文部科学省
12月23日(月)15:00-17:35
会場:オンライン(Zoom)
対象:情報科学や地震学分野等の大学生・大学院生、当該分野における研究者等(民間企業も含む)
参加費無料(要事前登録:締切12/23 12:00)
https://evt-cipwos20241016.eventcloudmix.com/
旧会員ページ終了
2023.12.5
学会HP ・会員ページ:引っ越しました
(旧会員ページの公開は終了します)
▼新しい会員システムtop▼
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
▼▼初めてログインする方はまずこちらから▼▼
https://www.geosoc-member.jp/Member/fgform.php
2023年5月より,旧システムと併行して新しい会員ページの運用がスタートしておりましたが(参考:新しい会員管理システムの公開・利用について_2023.5.16),このたび会員ページの機能,掲載内容を新しいページに全て移行し,旧会員ページの公開は終了します.ログイン情報の管理も今後は本システムに一本化されます.また旧ページに掲載されていた記事等は,新しい会員ページ及び学会HPに掲載されています.引き続きよろしくお願いいたします.
新しい学会HP(会員ページ)でできること
ご自身の会員情報の変更,更新
他の学会員の情報の検索・閲覧(会員名簿の機能)
Island Arc無料閲覧
会員限定のお知らせの閲覧(各賞募集,選挙など)
(注)これまで旧システムで行うことができた一部の機能(専門部会の掲示板,ブログなど)は,ご利用できなくなります.ご了承ください.
▼新しい会員システムtop▼
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
▼▼初めてログインする方はまずこちらから▼▼
https://www.geosoc-member.jp/Member/fgform.php
Geo暦(2025)
2025年Geo暦(行事カレンダー)
2021年版 2022年版 2023年版 2024年版 2025年版
2025年版 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
○印は学会主催行事.(共)学会共催・(後)後援・(協)協賛
1月January
防災学術連携体シンポジウム
阪神・淡路大震災30年、社会と科学の新たな関係
1月7日(火)10:00-18:00
場所:Zoom Webinar,YouTube を用いたオンライン配信
参加費無料(要事前申込)
https://janet-dr.com/index.html
「堆積構造の世界」連続講義
第3回砕屑性堆積物の堆積構造(2)
1月11日(土)13:30から
オンライン開催,参加費無料
講師:酒井哲弥先生,成瀬 元先生
参加登録締切: 1月10日(金)12:00
https://sites.google.com/view/taisekigakukougi?usp=sharing
第203回深田研談話会
テーマ:日本の古生物学の歩みをふりかえる
1月17日(金)15:00-16:30
場所:深田地質研究所研修ホール+オンライン
講師:矢島道子(東京都立大非常勤講師)
参加費無料
https://fukadaken.or.jp/?p=8647
(後)原子力総合シンポジウム2024
1月20日(月)
会場:日本学術会議講堂+オンライン
参加費無料
https://www.aesj.net/natlsymp2024
北淡国際活断層シンポジウム2025
主催:北淡国際活断層シンポジウム実行委員会
1月23日(木)〜25日(土)
オンライン開催(Zoom webiner)参加費無料
発表申込み期限:2024年12月25日(水)
参加登録期限:2025年1月15日(水)
https://home.hiroshima-u.ac.jp/kojiok/hokudan2025.html
日本古生物学会2025年第174回例会
1月24日(金)〜26日(日)
オンライン開催(zoom)
https://www.palaeo-soc-japan.jp/
2月February
建設系CPD 協議会シンポジウム(ハイブリッド形式)
-継続学習としてのCPDプログラムの活用と実施例-
2月17日(月)14:00〜17:00
場所:日本コンクリート工学会 第4,5会議室(東京都千代田区麹町)
オンライン配信方式:ZOOM を使用したライブ配信も行います
参加費:1,000 円(税込)
申込締切:2025年2月12日(水)12:00
https://b-p.co.jp/cpd/1218.pdf
「堆積構造の世界」連続講義
第4回 生物(化学)源堆積物の堆積構造
2月21日(金)17:00から
コーディネーター:松田博貴氏
講師:松田博貴氏,狩野彰宏氏
https://sites.google.com/view/taisekigakukougi?usp=sharing
地質学史懇話会
2月23日(日)14:00-17:00
場所:北とぴあ 805号室(北区王子)※ハイブリッド
Maddalene Napolitani(フィレンツェ、ガリレオ博物館)『Earth science's visual culture in the 19th century』
問い合わせ先:矢島道子 pxi02070[at]nifty.com
3月March
○西日本支部令和6年度総会・第175回例会
3月1日(土)例会・総会
会場:北九州市立自然史・歴史博物館
参加・講演申込締切:1月31日(金)
講演要旨提出締切:2月17日(月)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
学術会議公開シンポジウム
「人流ビッグデータがもたらす新しい未来像」
主催:日本学術会議地域研究委員会地域情報分科会
3月1日(土)13:00-17:00
開催地:オンライン開催
参加費無料・要事前申込
https://www.scj.go.jp/ja/event/2025/378-s-0301.html
海と地球のシンポジウム2024
3月12日(水)〜13日(木)
開催方法:口頭発表、ポスター発表ともに実会場にて実施
実会場:東京大学弥生キャンパス 弥生講堂
【発表課題 募集中!】登録締切:12/13(金)
フォトコンテストも開催!航海に関連する最高の瞬間をご応募ください!
https://www.jamstec.go.jp/j/pr-event/ocean-and-earth2024/
学術会議公開シンポジウム
「初等教育における世界的な視野の獲得について」
主催・共催:日本学術会議地域研究委員会・地球惑星科学委員会合同地理教育・ESD 分科会、日本地理学会地理教育専門委員会
3月20日(木・祝)9:00-12:00
場所:駒澤大学(東京都世田谷区駒沢1-23-1)(日本地理学会春季学術大会開催地)
事前登録なし・参加費無料
https://www.scj.go.jp/ja/event/2025/379-s-0320.html
東京地学協会2024年度の国内見学会
「つくばの研究機関と筑波山」
3月22日(土),23日(日)
宿泊は自由.また,一方の日のみの参加も可.
案内者:目代邦康,青木正博,芝原暁彦
募集人数:20名,参加費無料
参加申込締切:3月7日(先着順)
https://www.geog.or.jp/tour/info/2025-02-12/
第248回イブニングセミナー(オンライン)
3月28日(金)19:30-21:30
演題:令和6年能登半島地震に伴う沿岸〜海域の変動 ―現地調査の成果―
講師:立石 良 先生(富山大学学術研究部 都市デザイン学系)
参加費:主催NPO会員及び学生の方(無料),非会員の方(1,000円)
https://www.npo-geopol.or.jp/
4月April
○2025年度関東支部総会・講演会
4月12日(土)14:00-16:45
場所:北とぴあ第2研修室(東京都北区王子)
講演会「潜水船・水中ドローンによる島弧-海溝系の海底露頭観察」
講師:山口飛鳥氏(東京大学大気海洋研究所)
支部総会委任状:4月11日(金)17時最終締切
https://geosociety.jp/outline/content0201.html#2025sokai
地質学史懇話会
4月13日(日)14:00-17:00
場所:早稲田奉仕園セミナーハウス101号室(新宿区西早稲田)※ハイブリッド
Marianne Klemun(ウィーン大学歴史学元教授):『Carl Diener and his trip to Japan in 1913』
問い合わせ先:矢島道子pxi02070[at]nifty.com
産総研 地質標本館 講演会「IUGSヘリテージストーンと筑波山塊の花崗岩」
4月19日(土)14:00〜15:00
講演者:杉原 薫 氏(筑波山地域ジオパーク推進協議会)
開催場所:産業技術総合研究所 地質標本館
定員:40名(事前予約必要)
https://www.gsj.jp/Muse/event/archives/20250419_event.html
5月May
※2025年「地質の日」関連行事はこちらから
「堆積構造の世界」連続講義
第5回 火山砕屑物の堆積構造
5月9日(金)17:00から2時間程度
コーディネーター:片岡香子氏
講師:片岡香子氏,前野 深氏
https://sites.google.com/view/taisekigakukougi?usp=sharing
第34回 地質汚染調査浄化技術研修会
(座学zoomオンライン研修会)
5月16日(金)9:30〜17:30(終了予定)
5月23日(金)9:55〜17:30(終了予定)
参加費無料
参加申込期限:5月14日15時まで
ただし,テキスト(資料集3,000円)をご希望の方は5月9日までにお申し込み・お振込み下さい.
https://www.npo-geopol.or.jp/
IUGS - Initiative on Forensic Geology Conference
(IUGS法地質学イニシアチブ会議)
5月21日(水)-23日(金)
会場:Spazio Europe(イタリア・ローマ市)
https://www.iugs-ifg2025.com/
2025 エネ環地研成果発表会(オンライン同時配信)
5月22日(木)-23日(金)【開場 9:30】
会場:北海道立道民活動センター かでる2・7(札幌市中央区北2条西7丁目)
参加無料,要事前申込(5/20締切)
https://www.hro.or.jp/industrial/research/eeg/pr/2025seika.html
シンポジウム 海洋地質学の50年,そしてこれから
5月24日(土)13:30-17:00 (ハイブリッドで配信予定)
場所:東京大学本郷キャンパス伊藤国際謝恩ホール
懇親会(徳山英一先生を偲ぶ会・定員250名):17:00-19:00
※懇親会参加申込・参加費振込締切:4/25 (金) 24:00
※シンポジウム参加無料.懇親会参加費10,000円
https://aori-u-tokyo.jimdosite.com/
学術会議公開シンポジウム
地名標準化の現状と課題―UNGEGNの活動を理解し日本の地名を考える―
後援:地理学連携機構
5月24日(土)13:00-17:00(オンライン開催)
定員300人,どなたでも参加いただけます
参加無料・要事前申込(5月23日締切)
https://www.scj.go.jp/ja/event/2025/382-s-0524.html
日本地球惑星科学連合2025年大会
5月25日(日)-30日(金)
会場:幕張メッセ(千葉市美浜区)+オンライン開催
投稿早期締切:2月6日(木)
https://www.jpgu.org/meeting_j2025/
6月June
東京地学協会特別講演会 地学クラブ講演会「最近の助成研究から」
6月7日(土)15:00-16:30
会場:リファレンス麹町(東京都千代田区麹町3-1-1 麹町311ビル4階 KJ404室)
講師:岩森 光(東京大学地震研究所 教授)
講演:「日本列島下のマグマ・流体と火山・温泉・地震」
参加無料,事前申込不要
https://www.geog.or.jp/lecture/info/2025-05-14/
地質学史懇話会例会
6月8日(日)13:30-17:00
場所:北とぴあ 803号(東京北区王子)
加藤茂生:東京地学協会による中国の地学調査の淵源と展開
会田信行:『最新地学事典』の中の地球科学史
深海底の保護と持続可能な開発に向けた国際海底機構先進技術ワークショップ
第2回「海底モニタリング」
主催:国際海底機構(ISA)
6月10日(火)-12日(金)
会場:オンライン+オンサイト(神戸大学百年記念館)
詳しくはこちらから
石油技術協会2025年度春季講演会
6月11日(水)〜12日(木)
場所:朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
https://www.japt.org/
2025年度深田地質研究所研究成果報告会
6月13日(金)13:00〜16:40(12:30開場)
場所:公益財団法人深田地質研究所 研修ホール(東京都文京区)
開催形式:会場参加(定員50名),オンライン参加(定員450名)
参加費無料(要事前申込)
https://fukadaken.or.jp/?p=8853
第34回地質汚染調査浄化技術研修会
(現地実習① ボーリングコア記載実習)
6月14日(土)10:00-17:00(終了予定)
参加費:当NPO会員10,000円 当NPO非会員15,000円
参加申込期限:6月10日※ただし定員になり次第締め切り
募集定員30名
https://www.npo-geopol.or.jp/
「堆積構造の世界」連続講義
第6回 生痕化石
6月20日(金)17時から(1〜1.5時間程度)
コーディネーター:奈良正和 氏
講師:奈良正和 氏
https://sites.google.com/view/taisekigakukougi?usp=sharing
○2025年中部支部年会
6月21日(土)-22日(日)
会場:静岡大学静岡キャンパス
巡検『瀬戸川帯南部の超塩基性-塩基性岩類の産状』6/22
https://geosociety.jp/outline/content0019.html#2025nenkai
第249回イブニングセミナー(オンライン)
6月26日(木)19:30-21:30
演題:地下水の知られざる減災機能−新たな水資源マネジメントに向けて
講師:遠藤崇浩(大阪公立大学現代システム科学域)
参加費: 主催NPO会員及び学生の方(無料)非会員の方(1,000円)
https://www.npo-geopol.or.jp/
日本古生物学会2025年年会
6月27日(金)〜29日(日)
会場:北海道大学(札幌市北区)
https://www.palaeo-soc-japan.jp/
7月July
(後)第62回アイソトープ・放射線研究発表会
7月2日(水)-4日(金)
会場 日本科学未来館 7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
発表申込期間:2025年2月28日(金)12時
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/jrias2025
三浦半島活断層調査会 創立30周年記念講演会
三浦半島の大地を知り減災を考える
7月6日(日)13:00-16:00
会場:横須賀市自然・人文博物館1階 講座室
申込:当日先着80名(申込不要)
詳しくはこちら
「堆積構造の世界」連続講義
7/19(土)第7回 堆積層解析1「堆積層解析の基礎」.「河川堆積相」
講師:伊藤 慎氏,柴田健一郎氏
7/28(月)第8回 堆積層解析2「沿岸堆積相」,「陸棚堆積相」
講師:田村 亨氏,西田尚央氏
8/4(月)第9回 堆積層解析3「深海堆積相」
講師:伊藤 慎氏
https://sites.google.com/view/taisekigakukougi?usp=sharing
南海トラフ海底地震津波観測網完成記念シンポジウム
7月29日(火)13:15-16:30
会場:イイノホール(東京都千代田区内幸町)
主催:防災科学技術研究所
https://www.bosai.go.jp/info/event/2025/20250620.html
8月August
東京地学協会【地図講座2025】
8月7日:講座A「Web地図で教材化、授業づくりにひと工夫」
8月7日:講座B「3次元地質地盤図で読み解く首都圏の地盤と災害リスク」
10月19日:巡検C「地形図を持って、河岸段丘の崖線、湧水、断層地形を観察しながら歩く」
11月16日:巡検D「河川争奪など地形地質の成因と人間の関わりを考えながら歩く」
参加費無料,非会員も歓迎.
https://www.geog.or.jp/lecture/info/2025-05-27/
(後)科学教育研究協議会2025年第71回大会
テーマ「自然科学をすべての国民のものに」
8月8日(金)〜10日(日)
会場:中央大学附属高等学校(東京都小金井市)
https://kakyokyo.org/
第79回地学団体研究会総会(高田)
8月29日(金)〜31日(日)
会場:ミュゼ雪小町(新潟県上越市高田駅前)
https://sites.google.com/view/takada2025/
9月September
第10回ぼうさいこくたい2025 in 新潟
9⽉6⽇(土)・7⽇(日)
場所:朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
https://bosai-kokutai.jp/2025/
防災推進国民大会2025セッション
日本学術会議学術シンポジウム/第20回防災学術連携シンポジウム
「複合災害に立ち向かう防災の知恵―新潟と能登の経験から」
9月7日(日)10:30〜12:00
会場:Zoom ウェビナーによるオンライン開催
無料,定員:1000名,要参加申込
https://ws.formzu.net/fgen/S2178437/
(後)第68回粘土科学討論会
9月10日(水)〜12日(金)
会場:産業技術総合研究所臨海副都心センター(東京都江東区青海2丁目3–26)
申込期間:6月9日(月)〜27日(金)
https://www.cssj2.org/event/annual_meeting/
○日本地質学会第132年学術大会(2025熊本大会)
9月14日(日)〜16日(月)
会場:熊本大学黒髪地区
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132
(共)2025年度日本地球化学会第72回年会
9月17日(水)〜19日(金)
口頭発表(ハイブリッド)、ポスター発表(対面)
場所:東北大学・川内北キャンパス
https://www.geochem.jp/annual-meetings/latest-annual-meeting
(共)19th International Conference on Thermochronology
(第19回国際熱年代学会議/Thermo 2025)
9月14日(日)〜20日(土)
会場:金沢商工会議所(金沢市尾山町9-13)
https://smartconf.jp/content/thermo2025/
公開シンポジウム「地球的課題解決のための資質・能力を育成する地理教育
―小学校・中学校・高等学校までの一貫カリキュラムに向けて―」
9月21日(日)9:00-12:00
場所:弘前大学(青森県弘前市文京町一番地)地理学会秋季大会第1会場
どなたでも参加いただけます.定員100人程度
参加費無料・事前申込不要
https://www.scj.go.jp/ja/event/2025/387-s-0921.html
NUMO 地層処分技術を考えるシンポジウム2025
9月23日(火・祝)13:00〜16:00(12:30開場・受付)
場所:サッポロファクトリーホール(札幌市中央区北2条東3丁目)現地開催
参加費無料・要事前申込(9/18締切)
https://www.numo.or.jp/technology/techpublicity/lecture/250923.html
報告会「JAMSTEC2025」
9月24日(水)14:30-17:45
会場:東京国際フォーラム ホールB7(千代田区丸の内)
YouTube,Zoom同時配信を予定
参加費無料
https://www.jamstec.go.jp/j/pr-event/jamstec2025/
(後)第250回地質汚染・災害イブニングセミナー(オンライン)
9月26日(金)19:30〜21:30
NPO法人アジア砒素ネットワーク3名の講師が講演予定.
参加費:主催NPO会員及び学生(無料),非会員(1,000円)
https://www.npo-geopol.or.jp/
(後)第6回アジア恐竜国際シンポジウム
9月26日(金)〜30日(火)
会場:福井県立大学永平寺キャンパス(福井県吉田郡永平寺)
https://dinoasia.asia/
第34回 地質汚染調査浄化技術研修会
(現地実習2 地下水モニタリングの基礎)
9月27日(土)10:00〜16:00(終了予定)
参加費:当NPO会員 12,000円,非会員18,000円
参加申込期限:9月20日 ※定員になり次第締切(定員20名)
https://www.npo-geopol.or.jp/workshop.htm#osensurveytraining-groundwater
◯関東支部講演会「県の石−栃木県の岩石・鉱物・化石−」・見学会
9月27日(土)
場所:栃木県立博物館講堂
定員:現地100名+オンライン100名
https://geosociety.jp/outline/content0201.html
10月October
2025年度日本火山学会秋季大会
10月1日(水)〜3日(金)
会場:キッセイ文化ホール(予定)(長野県松本市水汲)
http://www.kazan-g.sakura.ne.jp/J/index.html
産総研地質調査総合センター第8回 鉱物肉眼鑑定研修
10月1日(水)〜3日(金)
場所:茨城県つくば市(産総研)
定員:4〜5名(定員になり次第締切)
CPD:24単位
参加費:48口(1口1000円)の会費が必要です。
https://www.gsj.jp/geoschool/koubutsu/8th.html
日本土地環境学会公開シンポジウム
「多角的視点から考える土地の環境価値・評価に関する新たな指標」
10月4日(土)14:30-17:00
会場:追手門大学総持寺キャンパス(大阪府茨木市)
https://www.j-lei.jp/
2025 NEA IDKM Symposium
主催:OECD/NEA(ホスト機関:NUMO)
10月7日(火)〜9日(木)
会場:パシフィコ横浜
サイトツアー(10/10):東京電力廃炉資料館、福島第一原子力発電所
詳しくはこちら
産総研地質調査総合センター2025年度第1回追加 地質調査研修
(未経験者向け)
10月6日(月)〜10日(金)
場所:室内座学 茨城県つくば市(産総研)
野外研修 茨城県ひたちなか市、福島県双葉郡広野町・いわき市周辺
定員:6名(定員になり次第締切)
CPD:42単位 ・参加費:84口(1口1000円)の会費が必要です
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2025-1-2.html
深田研一般公開2025
10月19日(日)10:00〜16:00
会場:公益財団法人深田地質研究所(東京都文京区本駒込)
ラボツアーやミニレクチャー,アンモナイトアクセサリー製作
木の葉化石を探そうなどの体験学習も豊富に用意しています
入場無料
https://fukadaken.or.jp/?page_id=9241
Magellan Plusワークショップ:Landto-Sea Shaking Studies (L2S3-WS)
(海底・湖底堆積物を用いた地震履歴研究に関するワークショップ)
10月21日(火)〜 24日(金)
場所:国立台湾大学(台湾・台北市)
国内問い合わせ先:池原 研(産総研)/中西 諒(京都大学)
https://sites.google.com/view/land2seaworkshop/home
第12回 応用地質技術入門講座〜地表地質踏査技術の基礎〜
主催:応用地質学会
WEB学習:10月24日(金)-11月7日(金)の期間にオンデマンド教材を用いた自己学習
オンライン学習:11月13日(木)1-2時間程度のZoomによる学習
現地研修:11月19日(水)-21日(金)2泊3日(開催地:千葉県いすみ市「いすみ文化会館」付近の露頭)
参加申込締切:10月17日(金)
定員:35名(定員に達し次第締切)
https://www.jseg.or.jp/committee/jseg_edu/
シンポジウム「信頼される科学、活躍できる研究者へ」
10月25日(土)10:30-15:00
会場:日本科学未来館7F 未来館ホール(参加無料)
主催:日本科学振興協会(JAAS)
https://peatix.com/event/4534624/
◯関東支部講演会:伊与原新さんの講演会
10月26日(日)14:30〜16:00
場所:日本大学文理学部百周年記念館
対象:中高生および保護者(引率教員含む)
入場無料・要事前申込
https://geosociety.jp/outline/content0201.html
第64回温泉保護・管理研修会
10月28日(火)〜29日(水)
場所:島根県出雲市長尾鼻周辺(小伊津海岸)
場所:北とぴあ つつじホール(東京都北区王子)
主催:公益財団法人中央温泉研究所
http://www.onken.or.jp/seminar.html
ブループラネット賞 受賞記念講演会
10月30日(木)(会場:東京大学伊藤国際学術研究センター)
11月1日(土)(会場:京都市国際交流会館)
ロバート・B・ジャクソン 教授:大気を再生する ー希望・健康・そして人類のためにー
ジェレミー・レゲット博士:ポスト真実の時代に気候と自然のリスクを伝えるー活動家としての歩みから学んだこと
参加費無料・要事前申込
https://www.af-info.or.jp
11月November
国際ゴンドワナ研究連合(IAGR)2025年総会及び第22回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム
11月2日(日)〜6日(木)
会場:延世大学新村キャンパス(韓国・ソウル)
2日:参加登録とアイスブレーカー
3日・4日:シンポジウム、総会、晩餐会
5日・6日:野外討論会http://www.gondwanainst.org/symposium/2025/IAGR/IAGR 2025 Circulars.docx
火山災害軽減のための方策に関する国際ワークショップ2025
アイスランドから学ぶ火山防災
11月4日(火)13:00-17:00
会場:ビジョンセンター新橋(東京都千代田区内幸町)
参加無料・要申込(10/31 17時まで)
https://www.mfri.pref.yamanashi.jp/event/iws2025.pdf
(協)石油技術協会令和7年度秋季講演会
テーマ「変化する世界情勢と日本のエネルギー戦略〜脱炭素から低炭素への潮流転換〜」
11月6日(木)9:30〜16:40
場所:東京大学小柴ホール(東京都文京区本郷)
参加費: 石油技術協会会員,賛助会員,協賛団体(含所属者):3,000 円
※地質学会会員は,協会会員と同額で参加可能です.
https://www.japt.org/
東京地学協会秋季講演会
「令和6年能登半島地震による地形変化と災害の実態」
11月8日(土)13:00-16:30
会場:リファレンス麹町(東京都千代田区麹町3丁目)
事前申込不要,参加費無料
https://www.geog.or.jp/
第17回日韓中地理学会議
11月11日(火)〜14日(金)
会場:京都テルサ(京都市南区東九条下殿田町70)
参加登録締切・発表要旨締切:9月20日
https://www.dh-jac.net/wp/17jkc/
(後)〜発注者・若手技術者が知っておきたい〜
『地質調査実施要領』解説講習会
【大阪会場】新梅田研修センター(大阪市福島区福島)
11月12日(水)10:00-17:00
【東京会場】AP市ヶ谷(東京都千代田区五番町)
11月18日(火)10:00-17:00
主催:経済調査会・全国地質調査業協会連合会
受講料:12,100円(税込)/1名+テキスト代
定員120名程度(定員になり次第締切り)
https://seminar.zai-keicho.or.jp/
◯2025年度北海道支部例会(個人講演会)
11月15日(土)13:00-18:00
場所:オンライン開催
講演申込:10月21日(火)
https://geosociety.jp/outline/content0023.html
産総研地質調査総合センター2025年度第3回 地質調査研修
(中級/経験者向け)
11月16日(日)〜22日(土)
場所:福岡県福岡市能古島
定員:6名(定員になり次第締切)
CPD:45単位
参加費:90口(1口1000円)の会費が必要です
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2025-3.html
堆積学スクール 2025「鳥取砂丘を味わい尽くす」
11月22日(土)-24日(月,祝)
小雨決行
場所:鳥取砂丘,鳥取大学
講師:小玉芳敬 氏(鳥取大学)・田村 亨 氏(産総研)
定員:20 名(申し込み多数の場合は学生優先・会員優先)
参加申込締切:10 月 17日(金)(定員に達し次第締切)
http://sediment.jp/04nennkai/2025/2025school.html
(協)Techno-Ocean 2025
11月27日(木)〜29日(土)
会場:神戸国際展示場2号館ほか(神戸市中央区港島中町6-11-1)
https://to2025.techno-ocean.com/
(協)第41回ゼオライト研究発表会
11⽉27⽇(⽊)〜28⽇(⾦)
会場:富⼭国際会議場
https://jza-online.org/events
12月December
(後)三浦半島活断層調査会創立30周年記念 一般公開講座
宅地開発で隠れた衣笠断層帯を歩く
12月6日(土)(小雨決行)
参加申込締切:11月30日
詳しくは,こちら
地質学史懇話会総会
12月20日(土)13:30-17:00
場所:北とぴあ 803号室(東京都北区王子)
石渡 明:江原眞伍の太平洋運動(1942)の光と影
黒田和男:坪井忠二ほか《1954》「日本全国の重力測定」を読む
問い合わせ先:矢島道子 pxi02070[at]nifty.com
2024年度 名誉会員
2024年度 名誉会員
加藤碵一(かとう ひろかず)会員
1947年9月14日生(76歳) 産業技術総合研究所名誉リサーチャー
加藤碵一会員は東京教育大学理学部および同大学大学院で地質学を専攻し、1975年4月に通商産業省工業技術院地質調査所に入所した。地質部層序構造課長、国際協力室国際地質課長、首席研究官、企画室長、環境地質部長などを歴任し、1999年から地質調査所次長、2001年から産業技術総合研究所地球科学情報研究部門長、2003年から東北センター長、2006年から理事、2008年からフェロー・地質調査総合センター代表を務めた。2009年に退職後、産業技術総合研究所名誉リサーチャー、応用地質株式会社顧問、東・東南アジア地球科学計画調整委員会(CCOP)Honorary Advisorなどを務めている。この間、1977年に東京教育大学より理学博士の学位を取得、2022年秋に瑞宝中綬章を受章した。 加藤会員は本州中部の新第三系と第四系の地質学研究で多くの成果を挙げた。地質調査所の基幹業務である地質図類作成に大きく貢献し、特に主要フィールドである北部フォッサマグナの5万分の1地質図幅「坂城」、「粟島」、「長野」、「大町」、「信濃池田」を単独または筆頭で作成した。加藤会員が作成に関わった地質図類は28枚に及ぶ。それらと並行して1983年度から1985年度にかけてトルコ・アナトリア断層地域の地震・活断層・地殻変動の研究を主導した。また、CCOPに1998年から2012年まで参加し、プロジェクト推進や共同研究の調整など多国間の国際協力に貢献した。さらに、関係者の協力を受けて2003年に「Eastern Asia Geological Hazards Map」を出版した。その成果に対して2005年に日本自然災害学会から「ハザード2000国際賞」が授与された。 加藤会員は国や地方自治体の多くの専門委員などを務め、社会的に大きな功績を残した。海洋研究開発機構や防災科学技術研究所、資源・環境観測解析センターなどの運営にも外部委員として協力した。他にも、日本列島地質百選選定委員会委員、日本ジオパーク委員会委員などの委員を務め、委員活動を通じても地質学の発展に寄与した。また、大学では長年非常勤講師として人材育成に努めた。さらに、加藤会員が著した多くの書籍は地質学の教育と普及に貢献している。2000年以降はライフワークとして宮沢賢治に関する地質学的観点からの研究を続けており、それについての著作も多い。2007年には岩手県花巻市から「第17回宮沢賢治賞奨励賞」が授与されている。 加藤会員の本学会に対する功績もたいへん大きい。1994年から地質学雑誌の編集委員長を1年間務め、2002年9月から2006年5月までは副会長として学会運営に貢献した。また、本学会の日本地方地質誌(朝倉書店)刊行委員会委員長として全巻出版(2006年「中部」から2017年「東北」まで)を成し得た指導力と調整力も特筆に値する。 以上のように、加藤碵一会員は学術研究、教育、普及、社会貢献、そして学会運営に多大な功績を残しており、本学会の名誉会員として相応しい人物と判断し、ここに推薦する。
狩野謙一(かの けんいち)会員
1947年6月2日生(77歳) 静岡大学名誉教授・ 静岡大学防災総合センター客員教授
狩野謙一会員は東京大学理学部地学科および同大学大学院理学系研究科で地質学を専攻し、1974年10月に東京大学理学部に助手として着任した。1979年に東京大学より理学博士を授与され、同年4月に静岡大学教育学部講師に着任、1983年助教授、1988年に理学部へ転任、1993年より教授を務め、2013年に定年退職し静岡大学名誉教授の称号を授与された。この間、1992年10月から1年間Auckland大学名誉客員教授を務めた。現在、静岡大学防災総合センター客員教授を務めている。
狩野会員は、専門である構造地質学の観点から、西南日本内帯美濃帯の構造解析、およびそれをもとにした日本海拡大と伊豆弧衝突による大小スケールの屈曲構造形成を含む地殻構造改変の理解に大きく寄与した。また、静岡県と隣接地域にまたがる赤石山地を中心とした詳細な地質調査を行い、付加体とそれを切る断層・構造帯の形成と運動過程を実証的に示した。これらの研究成果は日本列島の地質構造発達史の理解を大きく前進させた。このように狩野会員の研究成果は日本の地質学の発展に寄与しただけでなく、静岡県の20万分の1地質図をはじめとした多くの図幅や教科書に採用され、今なお確固とした学術的基盤を形成している。
狩野会員は「歩いて調べる野外地質学」の研究者・教育者として、静岡大学在任中に多くの優秀な学生を育成した。卒業生・大学院修了生の多くは地質コンサルタントなど専門分野を生かした分野で活躍している。また、狩野会員は多くの専門書・普及書を著し、それらは地質学の教育と普及に役立っている。特に、豊富な実例を提示し構造地質学分野で日本初とも言える実践的教科書となった『構造地質学』(朝倉書店)は、プレート沈み込み帯の地質を理解する上で不可欠である付加体、メランジュ、断層と地震、褶曲等の項目に関する詳細かつ平易な解説によって高く評価され、韓国版に翻訳されるなど地球科学系の書籍としては広く普及した名著となった。この「教科書の発行と構造地質学の普及への貢献」に対して、2012年に本学会から学会表彰を受けた。また、狩野会員は国や地方自治体の数多くの委員も歴任した。
狩野会員の本学会の運営と発展に対する功績も大きい。2002年から3期6年間にわたり現在の執行理事に相当する役職である執行委員および理事、2008年から2年間は法人化後の理事を務めた。構造地質部会部会長や各賞選考委員会委員長なども歴任した。また、2003年から2008年まで地質学雑誌編集委員長として雑誌の安定した出版と発展に尽力した。
以上のように、狩野謙一会員は学術研究、教育、普及、社会貢献、そして学会運営に多大な功績を残しており、本学会の名誉会員として相応しい人物と判断し、ここに推薦する。
鳥海光弘(とりうみ みつひろ)会員
1946年12月22日生(77歳) 東京大学名誉教授
鳥海光弘会員は東京大学理学部地学科および同大学大学院理学系研究科で地質学を専攻し、1973年に東京大学総合研究資料館助手に着任した。その後、1977年愛媛大学理学部助教授、1985年東京大学理学部助教授、1991年同教授を経て、1998年から同大学大学院新領域創成科学研究科教授を務め、2010年に定年退職し東京大学名誉教授の称号を授与された。この間、1995年東京大学総長補佐、2005年新領域創成科学研究科副研究科長などを歴任した。2008年からは海洋開発研究機構上席研究員、2011年同機構地球内部ダイナミクス領域長、2013年同海洋地球生命史研究分野長などを務めた。
鳥海会員は既存の学問の枠にとらわれず数理科学および物理化学的なアプローチを駆使することで、地質学的諸問題に対して顕著な功績をあげてきた。その功績は変成岩岩石学からマントルレオロジー、造山運動、大陸のダイナミクス、地震活動の数理解析まで多岐に渡る。変成岩岩石学では、従来の化学平衡の枠を超えて流体力学や粉体力学を導入し、変成帯の構造や変形組織から歪みや応力を定量化する先駆的な研究を行った。放散虫の変形解析による歪み・応力の定量化、曹長石変晶やざくろ石変晶の幾何学解析による鉱物粒子の移動、包有物の形状解析による加熱時間や歪み速度の定量化などである。また、実験岩石学的手法により鉱物の再結晶特性を決定することでマントルレオロジーの定量化を行ったほか、応力計を考案した。さらに、非平衡・非線形系科学およびデータ駆動科学を導入することで、変成反応と流体流れの相互作用やクラック形成メカニズム、地震発生の空間相関性などを明らかにした。これらの功績により、1978年に日本地質学会奨励賞、2009年に日本地質学会賞を受賞した。2016年には日本地球惑星科学連合フェローに選出された。
鳥海会員は長年にわたり変成岩岩石学を中心として多くの後進を育てるとともに、卓越した数理科学の知識を背景に非平衡・非線形系・データ駆動科学の導入を地質学においていち早く提唱し、常に地質学界に刺激を与え続けてきた。鳥海会員が研究者育成および地質学の活性化に果たした功績は大変大きいと認められる。また、地質学に関する専門書や一般書籍の執筆・監修は30冊近くにのぼり、放送大学でも講義を担当するなど、地質学の教育、普及、啓発に積極的に取り組んできた。 鳥海会員は地質学雑誌編集委員会委員を5年間務めた後、1998年からの2年間は同雑誌編集長として雑誌の安定した出版と発展に尽力した。また、2000年から2002年にかけては評議員として本学会の運営に大きく貢献した。
以上のように、鳥海光弘会員は学術研究、教育、普及、社会貢献、そして学会運営に多大な功績を残しており、本学会の名誉会員として相応しい人物と判断し、ここに推薦する。
特定商取引法に基づく表記
特定商取引法に基づく表記(関東支部)
販売業者:一般社団法人日本地質学会
運営責任者:代表理事 山路 敦
住所:〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル内
電話番号:03-5823-1150(お電話でのお問い合わせは受け付けておりません。メールにてお問い合わせ下さい)
メールアドレス:main[at]geosociety.jp ※[at]を@マークにして送信してください
URL:http://www.geosociety.jp/
商品以外の必要代金 :
▶︎消費税
▶︎コンビニ/ATM支払い手数料
注文方法:Peatixによるチケット購入
支払方法:
▶︎各種クレジットカード(VISA、JCB、Mastercard、American Express、DISCOVER、Diners Club)
▶︎コンビニ/ATM
支払期限:
▶︎クレジットカード決済:チケット購入時点で決済
▶︎コンビニ/ATMでの支払い期限は、「お申し込みから3日以内」
引渡し時期:ご利用当日にサービスをご提供します。
返品・交換について:一旦申し込みが完了したイベントの返金・キャンセルについてはお受けできません。ただし、主催者都合やなんらかの事情でイベントが中止になった場合は全額返金いたします。※コンビニ/ATM支払いの手数料220円は返金されません。
学術大会
地質学雑誌
Island Arc
リーフレット
日韓地質学会学術交流協定調印式 レポート (2007.10.25)
日韓地質学会学術交流協定調印式 レポート
日韓地質学会学術交流協定調印式に参加して
文・写真:高木秀雄(日韓交流小委員会 委員長)
2007年10月25日に韓国江原道春川の江原国立大学で開催された韓国地質学会の総会で,日韓地質学会の学術協定の調印式が開催され,木村 学 日本地質学会会長と,Choi, Suk-Won 韓国地質学会会長との間で,協定書 (agreement) が取り交わされた(写真 1).今回の調印は,IODPの韓国代表の Lee,Young-Joo博士(KIGAM:韓国地質資源研究所)と木村会長の間で発案されたものが結実したものである.調印に先立ち,10月に日本地質学会の国際交流委員会の小委員会として日韓交流小委員会が急遽設立された.そのメンバーは大藤 茂氏,高橋 浩氏,久田健一郎氏および高木から構成され,また院生の意見を反映させるために,ソウル大学博士課程留学中の江川浩輔さんを加えることになった.高木は今回小委員会の委員長として,すでに国際交流委員会の公文富士夫委員長と韓国側の協定の文案をとりまとめ(下記),日本地質学会から派遣された次第である.
調印式では,Kee, Weon-Seo博士(KIGAM)の司会のもと厳かにとり行われ,盛大な拍手で会場は沸いた.引き続いて木村会長の日本地質学会の紹介の発表が30分ほどなされた.調印式に先立ち,今回我々を会場で案内いただいた江原大学の Cheon, Daekyo教授(韓国地質学会誌編集委員長)とともに今後の具体案を話し合った.そこでは,無理をせずに,できることを着実に進めることを確認した.たとえば両国の地質学会の年会で,何らかの合同シンポジウムを設けること,合同巡検の開催,などが話し合われ,現在来年の秋田大会で日本海の掘削やテクトニクス,環境関連のシンポジウムができないかどうか,検討をはじめるところである.さらに韓国の地質などを日本の地質学雑誌の口絵に投稿してもらうように,進めたいと話した.Cheon 教授からは,韓国地質学会のHPに早速そのことを宣伝しましょうと,また,韓国でも韓日交流小委員会を立ち上げるよう働きかける,と帰国後に連絡いただいた。
調印式の直後に,次期韓国地質学会の会長選挙が行われ,3名の候補者のなかから,忠南大学のLee, Hyun Koo 教授が選ばれた.Lee教授は早稲田大学で学ばれたことがあり,新潟大学などのグループの韓国巡検の世話をされたこともある鉱床学者であるので,今後の日韓交流のための追い風となることであろう(写真2).
写真1;左)日韓地質学会長の協定書交換.写真2;右)次期韓国地質学会会長 李 鉉具教授と.
Agreement for Academic Cooperation and Exchange
between
The Geological Society of Japan
and
The Geological Society of Korea
Article 1. This Agreement defines the principles and methods of cooperation that the Geological Society of Japan and the Geological Society of Korea wish to develop between them under equal partnership.
Article 2. The Geological Society of Japan and the Geological Society of Korea agree to promote academic cooperation between both societies through the following means:
(1)Mutual invitations to participate in scientific seminars, regular meetings and field trips
(2)Joint organization of seminars and academic meetings
(3)Joint or collaborative research activities and publications
(4)Exchange of academic materials and other information
(5)Promoting other academic cooperation as mutually agreed
Article 3. Both Societies agree to carry out the above activities in accordance with the laws and regulations of the respective countries after full consultation and approval of both Societies. It is understood that implementation of any of the types of cooperation stated in article 2 may be restricted depending upon the availability of resources and financial support. The execution of this agreement will not cause any financial obligations to either Society.
Article 4. This Agreement is valid for a period of five years from the date of signing by the representatives of both Societies. This Agreement shall be renewed after being reviewed and renegotiated by both Societies.
Article 5. This Agreement shall be executed in English.
ここで,韓国の地質学会年会の様子を簡単に紹介しよう.韓国の地質学会では春は巡検が主体となっており,今年は60周年の記念行事が行われたそうである.発表は秋に行われており,今回の春川大会では1日半の日程が組まれ,様々な分野の口頭発表とポスター発表が進行していた.江原大学は「冬のソナタ」のロケ地としても有名な春川市の南東の丘陵地に建っており,新しい建物が多く,清潔でアットホームな雰囲気の大学であった.
要旨によると,245件の発表が5つの会場と屋外のポスター会場で進められていた.口頭発表に少しだけ参加したが,Ree, Jin-Han高麗大学教授と学生さんの3件の発表では,嶋本利彦教授との摩擦実験の共同研究の成果が発表されていた.ポスターや口頭発表で示すスライドの半分程度は英語でプレゼンがなされており,韓国の大学では1年生のときから英文の洋書を読んでいることが反映されている,と江川さんから聞いた.要旨も27%が英文で書かれていた.また,要旨集は大変立派な製本であり,10件の企業広告がカラーで印刷されていたが,それらの広告は必ずしも地質関係だけではない(真露の広告もあった).会場や市内の各地には地質学会の横断幕が張り巡らされており,地質関連企業からのお祝いの献花が飾られていた(写真3).このような献花は60周年ということに限ったことではないそうである.一方,会場における企業のブースはDaewoo社の1件だけであった.夜の懇親会では,300人程度が入る大きな会場で,春川名物のタッカルビ料理でおおいに盛り上がっていた(写真2).
写真3;左)地質学会会場.横断幕が至る所でみられる.写真4;右)野天のポスター会場(夜に降雨があったが).
最後に,韓国とつながりのある地質学会員の方には,ぜひ日韓交流小委員会に加わっていただき,様々な立場,分野からご意見を賜りたいと存じます。基本的にはメールで意見交換するだけです。高木までお申し出いただければ助かります。
2018札幌大会プレページ(開催通知)
2018札幌大会プレページ(開催通知)
プレページTOP画面に戻る
「イランカラプテ − 地質学が拓く夢・未来」
日本地質学会第125年学術大会
北海道大学札幌キャンパス(北海道・札幌市)にて,
2018年9月5日(水)〜7日(金)に開催
日本地質学会は,北海道札幌市の北海道大学札幌キャンパスにて,第125年学術大会(2018年札幌大会)を「イランカラプテ − 地質学が拓く夢・未来」というテーマで9月5日(水)〜7日(金),巡検(見学旅行)を8日(土)〜9日(日)に開催します.「イランカラプテ」とはアイヌ語で「こんにちは」を意味し,最近,北海道のおもてなしのキーワードとして推奨されています.また,「地質学が拓く夢・未来」は開拓者精神あふれる,未来志向の北海道で開催する地質学会であることを表現します.なお,前回,北海道大学において開催された本学会の大会は第114年学術大会(2007年)で,今から11年前になります.
日本地質学会は本年125周年を迎えますが,2018年は北海道創立150周年に当たります.明治維新が1868年で,北海道は明治維新と同じ年に創立されたという訳です.北海道は鉱産資源に富み,最近まで多くの鉱床で種々の金属資源が稼行されたほか,特に夕張炭田に代表される質の良い石炭を産することで有名です.そのため,北海道ではその広い面積にも拘わらず,戦後,地質調査所のほか,北海道立地下資源調査所(現北海道立地質研究所)によって,地質調査が精力的に進められ多数の地質図幅が刊行されました.また,北海道中央部-西部にも西南日本の帯状構造が基本的には連続していると考えられていますが,グラニュライト相に至るまでの連続大陸地殻断面を見せる日高変成岩や典型的な高圧型変成岩である神居古潭変成岩,極めて保存の良いことで知られる幌満カンラン岩体,さらに活動的な島弧火山は本州の地質にも増して魅力的であり北海道の地質は多くの地質学者の興味を引き付けて来ました.それらの地質体の中でも白亜系蝦夷層群は,その規模,層序の連続性,アンモナイトに代表される大型化石の産出により本州からも多くの地質学者が駆け付けて生層序および堆積学的
研究を行ったほか,近年ではK-T境界や無酸素事変の研究フィールドとして注目されています.しかし,現在は北海道のフィールドで地質学的研究を行っている研究者数は非常に少ないと思われ,日本の他のフィールドと同様,野外地質離れが進行していることは残念なことです.
最近は,未曾有の被害を引き起こした2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震を始めとし,大型の地震災害,火山災害および気象災害による土砂災害が頻発しており,自然災害防止のため地質技術者の需要が大変高まっています.さらに,最近になって大型プロジェクトとして海底資源開発が開始されたほか,原子力発電の代替エネルギーとして地熱発電が再び見直され,その開発が進んでいます.原子力発電所の再稼働については後期更新世以後の活動が否定できない活断層が原発敷地内にないことが条件とされるという基準が設けられ,この判定には地質学会会員の一部が関わっています.このように,地質学の需要はかってないほど高まって来ていますが,地質学会会員数は減少の一途をたどっているほか,各大学の地質系学科等は社会の需要に応えるほどの十分な数の人材を輩出出来ていません.地質学会全体としても,この社会の地質学のニーズにどう応えていくか,本格的な対策を講ずる必要があるように思われます.
一方で,日本全国におけるジオパーク設立に向けた運動は,かってないほどの広がりを見せ,“ジオ”という用語が“バイオ”とともに国民にとって馴染みのある言葉となり地質学を後押ししています.北海道は日本のジオパーク運動を牽引しており,「洞爺湖有珠山ジオパーク」,「アポイ岳ジオパーク」,「白滝ジオパーク」,「三笠ジオパーク」および「とかち鹿追ジオパーク」の5つが「日本ジオパーク」に認定されているほか,最初の2つのジオパークは,「ユネスコ世界ジオパーク」にも認定されています.また,昨年の日本地質学会第124年学術大会では「ブラタモリ」制作チーム(日本放送協会)が地質学会表彰を受賞しましたが,国民目線で地質学がより身近になってくれば将来地質学の研究者・技術者を目指す若者も増えてくると期待されます.
北海道の地質のすばらしさは上記の通りですが,皆様には,主として本大会後半に準備されている巡検に是非参加され,北海道の地質を堪能していただきたいと思います.なお、通常の巡検とは別枠で通称ブラタモリ巡検「コトニ川・サッポロ川や豊平川の原風景」を用意しています.こちらも奮ってご参加ください.
なお,昨年の愛媛大会と同様,9月上旬の北海道は観光客が多い時期で,ホテル・旅館は大変混みあうことが予想されます.札幌大会に参加される会員の皆さんは,是非,早めの宿泊予約をお願いいたします.
札幌大会の成功に向けて,大会実行委員会,北海道大学理学研究院・地球環境科学研究院,北海道支部幹事一同努力を重ねております.実りの多い大会になりますよう,皆様のご参加を是非お待ちしております.我々は125周年地質学会札幌大会が日本の地質学の復活に向けての第一歩となることを祈っています.それでは,札幌でお会いしましょう.
日本地質学会第125年学術大会(札幌大会)実行委員会
委員長 竹下 徹
2018札幌大会プレページ_top
2018札幌大会プレページ
日本地質学会第125年学術大会
イランカラプテ* − 地質学が拓く夢・未来
2018札幌大会公式サイトはこちらから
会場:北海道大学札幌キャンパス(北海道・札幌市)
日程:2018年9月5日(水)〜7日(金)
更新情報
18/04/17 シンポ,トピックが確定しました
18/02/05 トピックセッション募集(締切:3/12)
18/02/05 大会に向けてのスケジュール
18/02/05 札幌大会 開催通知
18/02/05 札幌大会プレページ開設しました
*「イランカラプテ」とはアイヌ語で「こんにちは」という意味で,近年の北海道では,“おもてなし”のキーワードして推奨されています,
2018札幌大会トピックセッション募集
2018札幌大会トピックセッション募集
プレページTOP画面に戻る
[トピックセッション:6件]確定しました!*( )は代表世話人
文化地質学(鈴木寿志)
モホ(地殻—マントル境界)を掘り抜いたオマーン掘削プロジェクト(田村芳彦)
日本列島の起源・成長・改変(磯崎行雄)
深海科学掘削50年、過去―現在―未来(倉本真一)
北海道とその周辺地域における地震・津波研究の最前線(卜部厚志)
泥火山と地球化学的・地質地形学的・生物学的関連現象(浅田美穂)
このほか,札幌大会では,学会創立125周年を記念したシンポジウムとレギュラーセッション25件,アウトリーチ1件が,予定されています.
[シンポジウム:2件]*(発表は招待講演のみ)
国際シンポジウム:社会と地質学
前進する北海道地殻構造解明作業:テクトニクス研究の新たな展開へ
-------------------------------------------------------------------------------------------
札幌大会トピックセッション募集
締切:2018年3月12日(月)
第125年学術大会(札幌大会)は,北海道支部のご協力のもと,北海道大学札幌キャンパスを会場として2018年9月5日(水)〜7日(金)に開催されます.本年創立150周年を迎える北海道は,石炭を始め鉱産資源に富み,明治維新以降の我が国の発展に大きな役割を果たしてきました.また最近は,十勝沖で予測される巨大地震の発生確率が引き上げられました.以上より,地質学会学術大会は,資源関係に加え,地震災害や防災に関心を持つ一般市民など多くの方々から注目されるものとなるでしょう.札幌大会では,多くのセッション開催を可能にするよう,必要十分数の会場(部屋)を確保する予定です.ポスター会場については,近年のポスター発表重視の方向を満たすスペースを確保します.トピックセッションを下記要領で募集します.本大会も前回同様,シンポジウムの一般募集はありません.シンポジウムは札幌大会実行委員会および学会執行部が企画します.
1.セッション概要
セッションは例年通り「レギュラーセッション」,「トピックセッション」,「アウトリーチセッション」に区分します.レギュラーセッションは前回の愛媛大会と同じ25タイトルを予定しています(レギュラーセッションは3月下旬に行事委員会が決定します).
2.トピックセッション募集
トピックセッションは,広く地質学の領域に属し,これから新分野あるいは注目すべき分野になりそうな内容を扱うものとします.形式はレギュラーセッションと同じです(口頭発表およびポスター発表:口頭発表は15分間で,進行も15分刻み).多くの参加者が見込まれる,魅力あるセッションを積極的にご提案ください.締切後,行事委員会が応募内容を慎重に検討し,最大8件程度のトピックセッションを採択する予定です.
3.トピックセッション招待講演
トピックセッションの招待講演には前回(愛媛大会)と同じルールを適用します.
招待講演は1セッションにつき最大2名とし,会員,非会員を問いません.世話人が「自分を招待する」ことは認めません.
発表時間(質疑応答を含む)は世話人が15分または30分のいずれかを選択できます.なお,1人の発表者(招待講演者を含む)が1つのセッションで口頭発表できるのは1件です.
招待講演者の選定理由とその裏付けとなる情報(セッションテーマに関連した代表的な論文,著書等)が必要です.
会員招待講演者が招待講演の他に非招待の発表を1件申し込む場合,発表負担金はかかりません.さらにもう1件(招待講演の他にセッションで2件)発表する場合は負担金がかかります.
4.応募方法
トピックセッションを応募する会員は,次の項目内容を日本地質学会行事委員会宛(main@geosociety.jp)にe-mailでお申し込み下さい.
代表世話人(=連絡責任者,会員に限る)の氏名(和・英),所属(和・英),メールアドレス,緊急時の電話番号
セッションタイトル(和・英)
共同世話人の氏名(和・英),所属(和・英),メールアドレス
趣旨・概要(400 〜600字)
招待講演の有無
有の場合
---5-1)招待講演者の氏名(和・英),所属(和・英),会員/非会員の別
---5-2)招待講演の発表希望時間(15分または30分)
---5-3)招待講演者の選定理由(100 〜200字)
---5-4)選定理由の裏付けとなる,セッションテーマに関連した代表的な論文・著書等
他学協会との共催希望の有無,有の場合は名称
時間(原則半日(3時間)以内ですが,詳細はお問い合わせください)
地質学雑誌またはIsland Arcへの特集号計画の有無(できる限り特集号を計画してください)
その他(英語使用等)
5.採択方法
応募多数の場合や他セッションと内容が重複する場合,行事委員会は学術的なインパクトや緊急度を考慮して採択を決定します.採択されたトピックセッションはニュース誌4月号(4月末発行予定)で公表し,講演募集を行う予定です.演題登録(講演申込,講演要旨投稿)締切は6月中旬を予定しています.
6.非会員招待講演者の参加登録費
非会員招待講演者に限り参加登録費を免除します(ただし要旨集は付きません).
7.世話人が行う作業(6月中〜下旬)
代表世話人には,講演要旨校閲,講演順番決定などの作業を6月下旬までに行っていただきます(詳細は採択後にお知らせします).その期間,代表世話人は電子メールで添付ファイルを送受信できるようにして下さい.野外調査や乗船等で通信が制限される場合は,共同世話人(代理)にあらかじめ作業を依頼し,その旨を行事委員会に必ず報告してください.
ご不明の点があれば行事委員会(main@geosociety.jp)までお気軽にお問い合わせください.
学会主催の行事(その他)
学会主催の行事(その他)
(注)5/10「地質の日」関連行事はこちらから
2025年
03月 2日(日)第5回JABEEオンラインシンポジウム「高等学校での地学教育と大学での専門教育との連携」new
2024年
07月21日(日)第11回ショートコース(微化石)
03月03日(日)第4回JABEEオンラインシンポジウム「大学縮小危機のなかで,社会の要求にどのように応えるか 〜JABEEを活用した技術者の育成と輩出〜」(Youtube公開)
02月25日(日)第10回ショートコース(海底鉱物資源)
2023年
10月22日(日)第9回ショートコース(応力逆解析法)
07月02日(日)第8回ショートコース(同位体を用いた年代測定)
04月02日(日)第7回ショートコース(応力逆解析法の実習)
03月10日(金)-12日(日)地質情報展2023いわて ―明日につなぐ大地の知恵―(主催:GSJ・日本地質学会・岩手県立博)
03月05日(日)第3回JABEEオンラインシンポジウム「大学ー企業の架け橋教育 ユニークな実例紹介」(Youtube公開)
01月28日(土)市民対象オンラインシンポジウム ジオパーク地域に伝わる伝承と地質学:古代からの自然観を今に活かす(Youtube公開)
2022年
12月18日(日)第6回ショートコース(法地質学/付加体地質学・沈み込み帯掘削)
05月29日(日)地質学露頭紹介 at JpGU2022
05月24日(火)日本学術会議公開シンポジウム「チバニアン,学術的意義とその社会的重要性」(日本地質学会ほか共催)
03月06日(日)第2回JABEEオンラインシンポジウム「昔と違う イマドキのフィールド教育」(YouTube公開)
02月19日(土)- 20日(日)地質情報展2022あいち ―発見!あいちの大地―(主催:GSJ・日本地質学会・名古屋市科学館)
終了した行事(開催報告など)
2021年10月3日
第5回ショートコース 応用地質・地質調査業・GIS(地理情報システム)・デジタル地質情報の利活用などについて
2021年7月18日
第4回ショートコース 吾書くゆえに吾ありー論文執筆についての超個人的視点:磯粼行雄/地球科学の歴史から何を学ぶか:泊 次郎
2021年5月23日
第3回ショートコース 津波堆積物を理解するのに必要な基礎的堆積学:藤野滋弘/津波堆積物を理解するのに必要な応用的堆積学:後藤和久
2021年3月7日
JABEEオンラインシンポジウム
自然災害列島における地質技術者の育成−大学統合期における地質学教育ー」(2020名古屋大会 代替企画)
2020年11月29日
(第2回)コロナ禍での地質学教育に関するサイバーシンポジウム(2020名古屋大会 代替企画)
2020年10月24日
第2回ショートコース 層序学の基礎と応用:高嶋礼詩/統計解析言語Rを用いた地球科学データ解析基礎実習:上木賢太
2020年9月27日
(第1回)コロナ禍での地質学教育に関するサイバーシンポジウム(2020名古屋大会 代替企画)
2020年9月19日
第1回ショートコース 東北アジア及び日本列島の地体構造発達史:辻森 樹/大陸成長から見るたのしい太古代研究:沢田 輝(2020名古屋大会 代替企画)
2019年11月23日
「GSSPシンポジウム:国際層序の意味と意義」報告
2007年11月25日
討論会「日本海沿岸褶曲・断層帯の形成・成長と地震活動」開催報告
2007年9月10日
緊急パネルディスカッション「わが国の防災立地に対する地球科学からの提言」開催報告
報告:07.09.09緊急パネルディスカッション「わが国の防災立地に対する地球科学からの提言」
緊急パネルディスカッション「わが国の防災立地に対する地球科学からの提言」開催報告
日本地質学会理事会
日本地質学会構造地質専門部会
題目:わが国の防災立地に対する地球科学からの提言—平成19年新潟県中越沖地震にあたってー
開催日:2007年9月10日
開催場所:日本地質学会第114年学術大会N2会場(北海道大学札幌キャンパス・高等教育機能開発総合センター内)
開催時間:18:00〜21:30
主催:日本地質学会理事会・構造地質専門部会
本年7月の新潟県中越沖地震により,地質学が活断層・震源断層問題に対する本格的かつ明示的な取組みを緊急にはじめなければいけないことが浮き彫りにされました.
具体的には,なによりも第1に,地震動の評価やシミュレーションの基礎データとなる活断層・震源断層の構造全体を把握する研究に拍車をかけることが必要です.第2に,事業者からも規制当局からも独立な立場で原発防災立地の問題点について指摘し,必要な提言を行うことが喫緊の課題です.
そのため,2007年9月9日(日)〜11日(火)に北海道大学札幌キャンパスで開催した第114年学術大会において,表記の緊急パネルディスカッションを開催しました.これは,日本地質学会 構造地質専門部会の夜間小集会として理事会と共催したもので,新潟県中越沖地震に関わる地球科学的事実をパネラーから提示して頂きながら,地質学会としての新たな一歩を踏み出しました.本報告は,この緊急集会の詳細を,会員をはじめとする皆様にお送りするものです.
今回のパネルディスカッションでの発表,ならびに会場を含めた質疑をとりまとめると,以下のとおりとなります.
1. 地震防災に向けた地球科学への期待
・地質学・活断層の研究で地震発生モデルを構築すること
・潜在断層の評価をすること
・断層の深部と浅部の運動を統一的に解釈すること
2. 具体的な地球科学の課題
・限られたデータを活かす再現モデル構築への支援
・他分野との協調・連携
・地質の不均一性の中での断層発生モデルの提案
・断層深部の詳細情報の把握
・地殻のレオロジーを知ること
・被害の集中している新しい地層・第四紀層をもっと調べること
・巨視的断層パラメーター(断層の走向・傾斜・面積など)の取得と提供
3. 課題の実施案例示
・今のデータのしっかりした評価,特に海の調査
・地質構造形成に関与した主要断層の抽出
・地下地質構造の把握および表層地盤の軟弱さの分布の把握
・地球物理学と連携した,過去の弱線および地質境界の把握
・地質断層の活動性評価の事例研究
4. 国の防災立地への反映方法
・学会からの積極的・タイムリーな情報の発信
・アメリカのようなコミュニティーの作成
5. 総合的な日本地質学会の見解
・分野の壁をはずさなければ,課題の完全な解決はならない
・特に,地質学と地球物理学の互いの特性を持って協力していくべき
・地質学会の法人化の際には,学会でプロジェクトを企画すべき
今回の緊急パネルディスカッションでいただいたこれらのご指摘を踏まえて,日本地質学会はさらに検討を進めていきますが,その際には,目的を定めた学術的な研究に加えて,我が国の防災・立地に如何にそれを反映させていけるかも重要な課題だと認識しているところです.
なお,最後になりましたが,当日の会場運営ならびに報告作成にご協力いただきました各パネラーの皆様に御礼申し上げます.
集会報告
(事務局:日本地質学会構造地質専門部会 重松紀生)
1. 本集会の背景
先日の新潟県中越沖地震と柏崎原発事故に関しては,活断層の調査に関して連日マスコミで様々な見解が表明されています.今後も電力会社ならびに国を初めとする様々な機関で検討がすすむ事になるでしょうが,第3者的立場でかつ科学に依拠した指針が作られるべく努めることは,学会の重要な社会的任務だと思います.
この認識の下で,日本地質学会では,今回の一連の地震と被害について,活断層・震源断層の構造全体を把握する必要性が極めて大きいとの判断に至りました.地質学が活断層問題に本格的且つ明示的な貢献する機会と捉えるべきと考えています.
ここでの日本地質学会の基本的スタンスは,「地質学を初めとする地球科学は,原発防災立地に関わる本質的情報を事前にどれだけ事業者,規制当局,そして市民に提供していたかという深い内省の上に議論する」ことです.
その上に立って,現行の諸指針,諸基準が,地質学を初めとする地球科学の見地からみて十分か,不十分であればどのようなものが付加されなければならないか,という議論にも進みたいと考えるところです.
2. プログラム
題目:わが国の防災立地に対する地球科学からの提言—平成19年新潟県中越沖地震にあたってー
開催日:2007年9月10日
開催場所:日本地質学会第114年学術大会N2会場(北海道大学札幌キャンパス・高等教育機能開発総合センター内)
開催時間:18:00〜21:30
主催:日本地質学会理事会・構造地質専門部会
3. タイムテーブル (下線の付いた発表は別途発表資料あり)
【会場の全体司会:伊藤副会長】
1)挨拶と趣旨説明 木村 学 会長
2)地震・災害の状況と地震震源断層等に関する報告
(独)防災科学技術研究所 青井 真 (4.9MB)
日本地質学会緊急調査団 小林健太 (4.0MB)
東京大学地震研究所 佐藤比呂志 (6.2MB)
国土地理院 飛田幹男 (11.0MB)
(独)産業技術総合研究所 杉山雄一 (912KB)
3)国の安全審査の現状 佃 栄吉 副会長 (704KB)
4)今後の防災立地に向けて(パネルディスカッション)
京都大学防災研究所 飯尾能久 (1.9MB)
(独)防災科学技術研究所 青井 真
東京大学地震研究所 佐藤比呂志(1.9MB)
国土地理院 飛田幹男
(独)産業技術総合研究所 杉山雄一 (1.8MB)
日本地質学会地質災害委員会委員長 天野一男
日本地質学会構造地質専門部会会長 高木秀雄
※上記のタイムテーブルの下線の発表については,公開用の発表資料をパネラーにご用意いただきましたのでご参照下さい(氏名をクリックするとPDFファイルがダウンロードできます)。なお,この公開用資料は,基本的に日本地質学会ならびにパネラーご本人からの事前の了承無しに引用等を行うことはできませんので,ご注意下さい.
4. 会場での質疑応答要旨(発言者の敬称略)
青井:地震ハザードの評価においては,事前に想定しにくいバックグランド地震の扱いは非常に重要.地震発生後に,詳細な調査・探査を行うことにより活断層を設定できても,事前に設定出来ていたとは言いがたい.原子力のような重要構造物においては,費用をかけて事前に詳細な調査・探査をすることもできるが,全国という意味ではどこまでが想定できる地震であるかの見極めは重要.地質・活断層の研究成果に期待.また,海の調査についても期待する.また,今回の地震のようなパルスはランダムフェイズでは説明できず,断層モデルを設定するシナリオ型の地震動予測が重要.事前に断層モデルを拘束するための活断層研究の成果は重要.
佐藤:潜在断層の評価をどうするか?どこでも起こるのか?地質構造の評価の必要性.地質構造形成に関与した主要断層を抽出する.小さめの地震を評価するには地質断層まで見ないといけない?
飛田:地震断層のモデル化する上で,地下地質構造の把握および表層地盤の軟弱さの分布の把握があると有益である.
杉山(代読:佃):情報の発信が必要.地質学の発言力がない.地質学者はアウトカムを意識していないのでは?社会的還元への意欲が低い.みずから他分野との協調・連携が必要.
天野:土木学会は新潟県中越沖地震の後に学会が調査団を送り込み,学会としての統一見解を発表した.地質学会では調査団を送り込んではいるが,サイエンス分野の場合には学会として統一見解を出すのは馴染まず,研究者各自に発言の責任を持たせている.学会として何をすべきだろうか?何も発言していないのではないか?案として,①シンポをやる,②地質学会が法人化する時に学会でプロジェクトを企画しては?
高木:なぜそこに活断層が発生したのだろうか?西南日本内帯の主要な活断層の断層ガウジの年代は60-50Ma程度までさかのぼれることを示している.特に花崗岩地殻の中のどのような地質の不均一性の中で断層が発生したかを,過去の弱線および地質境界の把握を行って,地物と連携して解いていく.
伊藤:地質断層の把握の重要性を認識するべき.この拘束には地質学の情報が必要だと思う.
飯尾:物理量と地質データをどう結びつけるか.内陸の活断層地震の発生の理解には,断層の深部と浅部の運動を統一的に解釈することが必要.現在断層深部の詳細情報は地質学的に得ることができる.一方,地物側はトモグラフィーなどで断層深部のデータを持っており,これらの情報をあわせれば,データとして生きてくる.また地質学側から「こういうデータが欲しい」などの発言が欲しい.
佐藤:アメリカのようなコミュニティーの作成が必要.上部地殻のレオロジーを知るには地質学的データが必要であり,もっと早く情報を出す.現在では変動地形分野と地物分野だけで物事が進んでいる.これでは地質調査無用論が出てしまう.地質学者はいいデータを持っているのに損をしている.地質学者には地震にも興味を持って欲しい.
木村: 海を研究するコミュニティーには地質・地物という垣根がない.陸域を研究する人たちも,分野の壁をはずさなければならない.互いの特性を持って協力して研究していく必要がある.
佃:地質の断層を使ってそれが動くか検討する.研究よって明らかになった地質構造からモデルを出して,地物との協力・連携によって提示する.未解決な点が多く,まだまだやるべきことが多い.
伊藤: 地質学として地震研究にきちんと意識して取り組むべき.これまでやってこなかったことを反省する.これからは積極的に発言・提言するべき.しかしこれのプランがないのが現状である.
コンサル会社(聴衆):コンサル側から見ると,今回のようなシンポを学会としてもっとすべきなのではないか?道路維持のための報告で地盤の情報出てきたりしたが,地質学として貢献できるポイントの一つではないか.
民間会社(聴衆):原発立地におけるM6.5という基準の決め方とかを教えて欲しい.電力会社が作っているのか?コンサルは会社から依頼されてやっている.モデル化する時は,いきなり大学機関などにお願いできないから,まずはコンサル会社にお願いする.他分野と交えた積極的なシンポをきちんとやって欲しい.物理探査のデータはたくさんある.地質学者は地物学者と組んでデータを提示するべき.
佐藤:(上記の質問を受けて)地質学が地震研究に関わるのは今回が最後のチャンスでは?他の学会は予算獲得に向けてよくやっている.しかし,地質学会はやっていない.地質学者として「これやって何になるの?」に答えられなければならない.地質学者が持っている情報と力量で地質断層の評価をするべき.若手はregionalな地質を知っている人が少ない.それに対して団塊世代はよく知っている.学会がプロモートしてやっていく必要がある.
飛田:地質学者はデータを膨大に持っているので期待している.
青井:地震動の推定のばらつきは,巨視的パラメータによるものの方が大きい.微視的パラメータ(アスペリティや加速度など)も非常に重要ではあるけれど,巨視的断層パラメーター(断層の走向・傾斜・面積など)がないと始まらない.地質学側からこれを設定する際に貢献する情報を提供いただけると良い.それを活かして地物研究者が断層を議論できる.
高木: このような議論はこのシンポだけでは終わらせない.11月に再度新潟でシンポを開くので,これらをきっかけにもっと考えていきたい.
報告:07.11.24討論会「日本海沿岸褶曲・断層帯の形成・成長と地震活動」
討論会「日本海沿岸褶曲・断層帯の形成・成長と地震活動」報告
11月25日に,新潟大学において表記の討論会が構造地質部会主催・新潟大学後援で開催された.また,それに先立ち,24日に小林健太・大坪 誠・栗田裕司氏の案内で新潟県中越沖地震を起こした断層との関係が注目されている鳥越断層の地形と露頭〜中央油帯と海岸付近で新潟のNeogeneの標準層序(魚沼・灰爪・西山・椎谷・寺泊の各層)の見学を実施した.プレ巡検の模様は河本和朗氏により記載されるので,ここでは討論会の記録を記す.
今回の討論会の趣旨は,次のようなものである.
1995年兵庫県南部地震以降,日本海側で大きな内陸地震が頻発し,甚大な被害をもたらしており,3年前の10月23日に発生した新潟県中越地震に引き続いて今年7月16日に中越沖地震が発生し,柏崎刈羽原発が被災した.構造地質部会では,理事会との共催で9 月の札幌地質学会での緊急パネルディスカッション「我が国の防災立地に対する地球科学からの提言− 平成19年新潟県中越沖地震にあたって−」を開催し,原発立地問題も視野に入れた断層を含む地質構造のより精密な調査が社会的要請として重要であることが示された.このPDをキックオフとし,次の企画として,伊藤谷生地質学会副会長と構造地質部会事務局が中心となり,日本海沿岸に発達する褶曲・断層帯の形成・成長と地震活動に関する討論会を新潟大学で開催することになった.その目的は,地表付近に表れている活断層と,内陸地震の震源域(20〜10km)の震源断層とをどのようにつなげるかを考えるための勉強会,として位置づけられたものである.今回は予め招待講演者を決めて次のような口頭発表のプログラムを組み,そのほか一般からの講演申し込みを受付け,14件のポスター発表が行われた.
・2004中越・2007中越沖地震
(1)羽越沿岸域の地質構造とその形成史
小林健太:新潟地域の地質構造と活断層−中越沖地震に対する影響と反映
立石雅昭:北部フォッサマグナ新生界標準層序と地質構造
(2)地震・測地学的諸データの提示と解釈
酒井慎一・2007年中越沖地震合同余震観測グループ:複雑な2007年中越沖地震の余震分布
山田泰広・葛岡成樹・水野敏実・松岡俊文:中越地域におけるPSInSAR解析による地表変動解析とモデル実験の比較
(3)地震探査諸成果からみる地殻構造と地震活動
佐藤比呂志・加藤直子:日本海沿岸褶曲−逆断層帯における震源断層の問題について
岡村行信 :日本海東縁の地質学的歪み集中帯と震源断層
長 郁夫 :活断層のモデルと大地震連鎖のシミュレーション
・北陸〜山陰沿岸域の地質構造とその形成史(レビュー)
竹内 章:北陸〜北信越の地質構造とその形成史
山本博文:若狭湾周辺地域の地質構造
沢田順弘 :中国地方における後期新生代の諸問題
・リフト形成期〜反転期の力学的条件と堆積盆の発達過程
山路 敦: 日本海のリフティング
竹下 徹:大陸地殻のレオロジーに基づく内陸地震再来周期の一つのモデル:何故,ノーマ
ークの活断層で地震は頻発するのか?
山田泰広:コメント)アナログモデル実験による堆積盆発達過程の知見
・地震活動と断層および断層岩
藤本光一郎:震源断層掘削研究の成果と到達点:野島断層とチェルンプ断層を例として
金折裕司:山口−出雲地震帯と地質断層の再活動性
今回の参加者は73名に達し,大変盛況であり,活発な議論があった.中越沖地震の震源断層が,北西傾斜か南東傾斜かという議論が続いているが,情報が蓄積されて地震研の酒井さんが報告された中越沖地震の余震分布の断面図を見る限り,南東傾斜が優勢であるものの,バックスラスト的な北西傾斜の断層の存在も浮かび上がってきたという印象を受けた.また,能登半島や日本海の活断層を検討している岡村氏の講演をはじめ,新潟(立石・小林氏),富山(竹内氏),福井(山本氏),島根(沢田氏),山口(金折氏)など,北陸〜山陰の最近の地震多発帯からそれぞれ研究者を招いて地質学的背景と地震断層関連の話を聞くことができた.山田氏と葛岡氏のPSInSAR解析を用いた話は,人工的な変動をフィルターにかけられれば,地殻変動をとらえる上で強い武器となることを予感させた.講演会では何人かの方から地質学者の役割について触れられていたが,佐藤氏も指摘されていたように,震源域における地質がどのようになっているのか,断層を発生させる,また断層の姿勢を決める地質学的制約条件を明らかにすることが重要であることを改めて認識するよい機会であった.金折氏の講演でも,「日本の活断層」に掲載されていない,最近認識された山口県内の大きな活断層も,地質断層としてはすでに知られていたもの,という紹介があった.
参加者は大学や各研究機関はもとより,電力会社の方も数人参加されていたが,学生は新潟大を除くと少なかった.プレ巡検では初めて見る新潟の褶曲−断層帯が大変印象深くて私自身感動したが,今後さらに学生が参加しやすいような配慮も必要であろう.
今回の討論会では,今年3月の構造地質部会白浜例会にひきつづき,部会事務局メンバー(とくに重松紀生,大谷具幸,小林健太,松田達生,大坪 誠の諸氏)が中心となって準備を行った.とくに,新潟大の小林健太氏には,巡検の準備と案内,会場の準備や招待講演者の宿泊の手配に至るまで,大変お世話になった.また,前日に行われた懇親会では,後援を受けた新潟大学の代表として理学部長の周藤賢治 教授,さらに地質学会理事の宮下純夫 教授から挨拶を賜ったが,新潟大学には大きなバックアップをしていただいた.さらには新潟大学の学生さんに,受付や会場設営,進行補助から後片付けに至るまで,お手伝いいただいた.ここに厚くお礼申し上げる.講演要旨は残部があるので,ご希望の方は地質学会に問い合わせていただきたい.
なお,構造地質部会では,内陸地震と断層モデルに関する行事はこのまま終わらせることなく,来年度以降も竹下 徹 新部会長のもと,新たな事務局メンバーで,夏に地震反射断面やバランス断面図の読み方や作製法に関するセミナーを開催する予定である.そのほか,「構造地質と応用地質(とくに石油地質や防災関連)の接点」に関する例会も開催する予定である.
2007年11月28日
構造地質部会長 高木秀雄
ロンドン地質学会会長との懇談(2008.3.19)
ロンドン地質学会会長 来日
ロンドン地質学会会長のリチャード・フォーティ氏がダーウィン展開催を記念して、来日された。忙しい日程の中、3月19日、木村学地質学会会長と小一時間ほど、親しく懇談できた。
ダーウィン展は、2008年が日英外交関係樹立150周年にあたり、駐日英国大使館とブリティッシュ・カウンシルの展開する「UK-Japan 2008」の一環である。もちろん、2009年のダーウィン生誕200周年、『種の起原』刊行150周年記念の先駆けでもある。ダーウィン展はアメリカを出発して、世界各地を移動して2009年にイギリスに到着することになっている。リチャード・フォーティ氏はロンドン自然史博物館の三葉虫研究者であるが、その著書『生命40億年全史』や『三葉虫の謎』は世界的なベストセラーであり、1907年に世界で最初に創立されたロンドン地質学会200周年の記念事業を代表した会長でもある。
懇談は東京大学大学院理学系地球惑星学教室で行われた(写真上)。ロンドン地質学会は大学と石油会社等の研究者からなる学会で、長い歴史がプラスにもマイナスにもなっているとまず紹介された。ロンドン中心街に土地使用料無料で学会を構えてきたが、最近有料になったこと、バースにある出版部は世界中に出版物を発信していることなどの特殊性があることも強調された。ロンドン地質学会のかかえる現在の問題として、石油会社から若い地質学者を多く要請されているが、その野外での調査の訓練があまりうまくいっていないこと、放射性廃棄物の地下処理の問題、アーカイブスの充実等、日本の地質学会がかかえている問題と共通な問題を抱えていることを確認した。ロンドン地質学会はフランス、アメリカの地質学会と協同してこれらの問題にあたっていると、述べられたので、問題は世界共通であり、日英の地質学会の協同もさらに進めて行くべきであることを確認して懇談は終わった。
なお、佃副会長は、3月18日、国立科学博物館(上野)レストランで開催されたサイエンスカフェに出席し(写真中)、サイエンスインタプリター養成の新しい試み(写真下)を、フォーティ氏とともに体験した。写真3では、三葉虫の脱皮の様子をフォーティ氏は背広を脱ぎながら一生懸命説明している。
(理事 矢島道子)
秋田大会TOP
日本地質学会第115年学術大会
(2008秋田大会)
地球の鼓動とその恵み—地質学から迫る人と地球の未来—
第115年秋田大会は終了しました。多数のご参加を頂きありがとうございました。来年は岡山(9/4-/6)でお会いしましょう!!
■ 新著情報ーWhat's New 秋田ー
更新日
09/16
一部会場変更についてNew
09/16
口頭発表講演データの取り扱いについてNew
09/12
プレスリリースを行いました
09/05
緊急展示の申込について
09/02
講演プログラム公開しました
08/20
見学旅行追加募集します。
08/07
全体日程表を公開しました
07/10
システム障害のため講演申込締切延長:7/11、17時
06/25
緊急災害に関連した講演発表について
06/18
講演申込システムのアクセス障害について
05/26
秋田大会関連プレスリリースについて
日韓地質学会学術交流協定調印記念式典(2008.9.20)
日韓地質学会学術交流協定調印記念式典(2008.9.20: 於 秋田大会)
日韓小委員会委員長 高木秀雄
2007年10月25日に韓国地質学会学術大会で締結された日韓地質学会学術交流協定調印を記念し,日本地質学会第115年学術大会(秋田2008)に招待された韓国地質学会会長の Lee, Hyun Koo (李 鉉具) 忠南大学教授の講演が9月20日の各賞授与式で行われた.石渡 明 国際交流担当理事の経緯説明の後,高木秀雄日韓交流小委員会委員長からLee会長の紹介がなされた.Lee会長は最初に英語で挨拶をされ,その後韓国地質学会の歴史や活動について画像を用いながら日本語で紹介された(写真1).ちなみにLee 会長は,延世大学卒業後,3年間の兵役を経て早稲田大学理工学研究科に進学され,故今井直也教授のもとで鉱床学分野の学位を取得されている.また,日本地質学会新潟大会では,韓国巡検の案内者としても活躍いただいた.Lee会長の話で印象深かったのは,韓国地質学会と日本地質学会の決定的な違いでもあるその財政基盤である.すでに法人格をもつ韓国地質学会では会費や学会登録費による収入はわずかに全体の3割程度であるとのこと.また,地質学の底上げのために様々なアウトリーチ活動や学生への賞の授与も進んで実施されている.公益法人を目指している日本地質学会にとっても,参考になる話であった.講演の後,宮下純夫会長からの挨拶があり,日韓交流協定調印の記念の楯が,Lee会長に授与された(写真2).
写真1
写真2
今回の年会ではIODP関係の日韓シンポジウムが日本地球掘削科学コンソーシアム (J-DESC) で企画され,韓国のIODP Project Managerで日韓地質学会学術交流協定調印でも活躍されたLee, Young Joo 博士(KIGAM)さらには日本地質学会Island Arc 賞を受賞されて来日したOh, Chang Whan 忠北大学教授や,日本地質学会会員で単独でポスター発表に来られたChang, Tae Woo 慶北大学教授も含め,日韓交流の絶好の場となった.そこで,Lee, Young Joo 博士の学会直前の発案で,今後の日韓地質学会の交流について21日夕方に大会本部で1時間ほどの会合がもたれた (写真3).
参加者は 写真前方左から石渡 明 氏, Lee, Hyun Koo 会長,宮下純夫 会長,Chang, Tae Woo氏,高木,後方左から江川浩輔氏,Lee Youn Soo氏 (KIGAM),Lee, Young Joo氏,Oh, Chang Whan氏,久田健一郎氏である.撮影者は今回の日韓シンポの取りまとめ役である琉球大の松本 剛氏.
以下,Lee, Young Joo 氏, 石渡理事と高木でまとめた会合のメモを記す.
Collaboration items and conditions between GSK & JGS
1. Exchange invitation of Presidents of two societies →already started
2. IODP symposiums (JKOD, KCC) →already started
3. Exchange fieldtrip program (for experts & student) →on request
4. Exchange of academic information: 1-2 times/yr after annual session
5. Make (English) sessions open to each society: possibility in the
2009 meetings:
・GSK annual meeting in Cheju Island in late October
・JGS annual meeting at Okayama Science University in early September
6. Specialized group (SG) collaborations
1) Structural geology SG: started from 1998 to 2001, →to be continued
2) Seismological SG: another more specialized society exists in Japan
3) Nuclear related geological SG: some government related institutions are in
Japan, but collaboration is possible
: Geological disposal, radioactive waste: →JAEA related in Japan
: Active (Quaternary) faults →another society exists, but possible
4) Petroleum SG: another society exists, but possible →to be discussed further
なお,2009年10月下旬に済州島で開催される韓国地質学会年会では,英語のセッションがと巡検が企画される予定であり,日本海の形成過程に関する日韓合同シンポジウムを,IODP関係者だけではなく,テクトニクス,堆積学,岩石学などの研究者も含めて行ってはどうか,と高木から申し入れた.
参考)韓国の地方都市,郡部の地名については,たとえば次のサイトがある.
http://www.korea-go.to/name/cityindex.html 韓国の主な国立大学は9つの道とソウル特別市におかれており,いくつかの大学の名称はこれらの地名が省略されて使用されている.たとえばLee, Hyun Koo会長の所属する忠南大学は,忠清南道の道都で研究学園都市でもある大田広域市にあり,Lee, Young Joo氏の所属する韓国地質資源研究院(KIGAM)からも近い.Chang Tae Woo氏の所属する慶北大学は慶尚北道の道都,大邱広域市に存在する.
全体日程・プログラム
全体日程・プログラム
■全体日程表
クリックすると大きな画像でご覧頂けます。
■各講演プログラム(それぞれの日程をクリックするとpdf形式でご覧になれます)08.9.2更新
9月20日(土)午前 口頭
9月21日(日)午前 口頭
9月22日(月)午前 口頭
午後 口頭
午後 口頭
午後 口頭
ポスター
ポスター
ポスター
注意:講演タイトルが一部講演要旨と異なる場合があります。その場合は講演要旨が優先されます。ご了承ください。
9月19日(金)〜21日(日):地質情報展
9月20日(土):シンポジウム,一般発表(口頭,ポスター),表彰式・記念講演会,懇親会,関連普及行事・市民講演会,見学旅行(一部)
9月21日(日):シンポジウム,一般発表(口頭,ポスター),ランチョン,夜間小集会,就職支援プログラム,関連普及行事・生徒「地学研究」発表会
9月22日(月):シンポジウム,一般発表(口頭,ポスター),ランチョン,夜間小集会
9月23日(火)〜24日(水):見学旅行
会場・交通
会場・交通
*会場への地図・講演会場の詳細については,7月頃掲載の予定です。
◯メイン会場(一般発表,シンポジウム,表彰式・記念講演会,関連普及行事・生徒発表会)
秋田大学手形キャンパス(秋田市手形学園町1-1)
◯市民講演会:秋田大学手形キャンパス教育文化学部3号館大講義室(3−145)
秋田大学手形キャンパスまでの公共交通機関は以下の通りです
<徒歩の場合>
JR秋田駅東口から手形キャンパスまで徒歩約20分
<バス利用の場合>
・秋田駅西口バス乗場4番線 大学病院行 乗車約10分〜秋田大学前下車
◯地質情報展:秋田市民交流プラザ「アルヴェ1階きらめき広場」(秋田駅東口に隣接)
*大学構内の駐車場は学会用には確保できません.年会へは公共交通機関を利用して下さい.
表彰式・記念講演会
学会各賞表彰式・記念講演
日程:9月20日(土)15:30〜17:30
会場:秋田大学手形キャンパス教育文化学部3号館大講義室(3-145)
シンポジウム
シンポジウム
演題・要旨締切:WEB 7/10(木)17時・郵送7/7(月)必着
↓WEBからの講演申込はこちら↓
講演申込受付終了しました
下記8件のシンポジウムを開催します.9月20日〜22日の3日間(いずれも午前),各日2-3件ずつ行いますが,原則として一般公募はありません(今回は2件で一般公募があります).シンポジウムの講演者には,一般講演の一人1件の制約は及びませんので,別途一般講演を申し込むことは差し支えありません.また,本年よりシンポジウムにおいて,世話人は,会員・非会員を問わず招待講演を依頼することができます.また,非会員の招待講演者に限り参加登録費は免除となります.一般公募の採択・不採択は,コンビーナによって決定されます.講演要旨原稿は,一般講演と同じ分量ですので,こちらのページを参照して原稿の作成をお願いします.やむを得ず郵送で講演要旨を送る場合は,一般講演の申込フォームをご利用下さい.「シンポジウム」と書き添えた上,必要事項を記入し,保証書・同意書とともに7月7日必着で行事委員会宛にお送り下さい.
(各タイトルをクリックすると、詳細をご覧いただけます)
1.地震・津波堆積物研究の最先端と防災への貢献
2.新生代後期における北極海—北太平洋/北大西洋間の流通と古海洋環境変動
3.高分解能火山活動史構築の現状・課題
4.地域振興と地質学−ジオパークが開く地域と地質学の未来−
5.地球生命進化と外宇宙との相互作用
6.日韓合同深海掘削シンポジウム2008 (一般公募あり)
7.超高圧変成岩の微細解析の最前線 (一般公募あり)
8.「ちきゅう」による南海トラフ地震発生帯掘削計画ステージ1Aの成果[総括]
1.地震・津波堆積物研究の最先端と防災への貢献
Frontier of seismic and tsunami deposits and contribution to the disaster prevention
後藤和久(東北大;kgoto@tsunami2.civil.tohoku.ac.jp)・藤原 治(産総研)・藤野滋弘(産総研)
地震・津波堆積物研究は,地質学に留まらず,海岸工学や地形学などでも行われている学際分野である.本シンポジウムは,各分野の最先端の研究発表を行い,地震・津波堆積物研究の新たな展開を模索するとともに,どのように防災に生かせば良いかを議論する.
2.新生代後期における北極海—北太平洋/北大西洋間の流通と古海洋環境変動
Late Cenozoic paleoceanography between north Pacific-Arctic-north Atlantic Ocean
佐藤時幸(秋田大;toki@ipc.akita-u.ac.jp)・尾田太良・天野和孝・山崎 誠・嶋田千恵子
2004年秋に実施されたIODP Expedition 303では,新生代後期の古海洋環境変動の詳細と原因を究明するため,北大西洋高緯度海域で欠損なしの深海底連続コアの採取を行った.環境変動の解明で北大西洋〜北極海域が注目されるのは,その特異な海洋循環システムと,それによって導き出される熱循環システムの変動にある.本シンポジウムでは,様々な古生物種と地化学分析から,北極海を介した北太平洋/北大西洋間の流通史や海洋環境の変遷に焦点を当て,北半球高緯度海域の古海洋環境変動の詳細について議論する.とくに,生息地理,生息水深が異なる貝類,石灰質ナンノプランクトン,有孔虫,貝形虫,珪質微化石などの様々な古生物種の生態系/反応様式から描く海洋構造と,地化学分析から描き出される栄養塩循環モデルとの統合を試みるほか,Exp.303の最新の成果も含め,新生代後期の高緯度海域古海洋環境変遷について議論する.
3.高分解能火山活動史構築の現状・課題
High Resolution Volcanic History : Current status and Future prospects
及川輝樹(産総研;teruki-oikawa@aist.go.jp)・伴 雅雄(山形大)・奥野 充(福岡大)・下司信夫(産総研)
火山活動をより深く理解し将来予測に役立つ情報を発信するためには,より高分解能の火山活動史の構築とそれにリンクさせた岩石学的研究が重要である.90年代頃から,従来無視されていた小規模な噴火堆積物も対象とした高分解能な火山活動史の復元がいくつかの火山で行なわれるようになってきた.また,火成岩岩石学の分野においても,時空的に高分解能な岩石学的検討が行なわれるようになっている.
本シンポジウムは,将来予測につながる火山活動のより深い理解のために,これら高分解化した両研究手法を結びつける糸口を探りたい.そのため,高分解能な火山活動史構築の現状と問題点をまとめ,精緻な火山活動史が岩石学的手法を含めた火山のより深い理解にどう貢献できるか議論する.また,分解能があがるとそれだけで新たな研究分野が開けることが多い.そのため,より高分解能な活動史を編むための多方面にわたる新たな手法の導入についても議論する.
4.地域振興と地質学−ジオパークが開く地域と地質学の未来−
Geology for regional improvement with geopark
渡辺真人(産総研;mht.watanabe@aist.go.jp)・天野一男(茨城大)・沢田順弘(島根大)・斎藤 眞(産総研)・吉川敏之(産総研)
東京への一極集中が進む中,地方の経済の活性化が日本の大きな課題となっている.それぞれの地域の特性を生かした観光振興や特産品開発が,多くの地域で地域経済活性化の重要な柱と考えられている.もっとも基本的な地域の特性は地質・地形などGeoに関わる特性であり,それが地域の景観・生態系・伝統・文化のベースとなっている.したがって,地質学が地域の振興に果たす役割はきわめて大きい.本シンポジウムでは,ジオツーリズム・ジオパークと言った地球科学による観光振興を中心として,地質学が地域振興にどう活用できるか,実践例をもとに議論したい.
5.地球生命進化と外宇宙との相互作用
Evolution of Earth's life and its interaction with outer space
磯崎行雄(東京大;isozaki@ea.c.u-tokyo.ac.jp)・川幡穂高(東京大)・丸山茂徳(東工大)
地球生命史における諸重要事件が地球表層環境の激変と不可分であったことは広く理解されるようになった.中生代末の巨大隕石衝突事件を除けば,その環境変化の多くは地球固有の原因が引き起こしたと従来考えられてきた.一方,地球外の現象とくに太陽系外での諸事変が地球表層環境や生命進化に関係してきたという考えが1990年代後半から積極的に議論されるようになった.本シンポジウムではこれに関する最新の学説について議論し,21世紀の地質学/古生物学が目指すべきひとつの方向性を探る.
6.日韓合同深海掘削シンポジウム2008
2008 Japan-Korea Joint Symposium on Ocean Drilling
松本 剛(東京大)・朴 進午(***)・川幡穂高(東京大)・梅津慶太(AESTO;umetsu@aesto.or.jp)・
本シンポジウムは統合国際深海掘削計画(IODP)による日韓共同深海掘削研究を実現するため,日本と韓国(および周辺諸国)の研究者が共同で行う事実上の国際シンポジウムである.日韓近海域またはその海域に類似した地質学的背景を持つ地域での研究成果の発表を行い,日韓およびその他参加国が共同で掘削計画(プロポーザル)の策定および実効を目指す.(一般公募あり・5名程度)
7.超高圧変成岩の微細解析の最前線
Frontier of micro-analysis on UHP rocks
岡本和明(埼玉大; kokamoto@mail.saitama-u.ac.jp)・寺林 優(香川大)・Hafiz Ur Rehman(鹿児島大)
1980年代以来,超高圧変成岩の解析は岩石学的手法により進んできた.超高圧変成岩の研究の新たな突破口となる放射光,イオンマイクロプローブ,電子顕微鏡解析による最新研究成果の紹介とともに研究手法の開発の議論をする.(一般公募あり・1-2名)
8.「ちきゅう」による南海トラフ地震発生帯掘削計画ステージ1Aの成果[総括]
Nankai trough seismogenic zone experiments stage 1A
坂口有人(JAMSTEC; arito@jamstec.go.jp)・芦 寿一郎(東京大)・木村 学(東京大)
統合国際深海掘削(IODP)のもと,地球深部探査船「ちきゅう」による初めての科学掘削が本邦熊野灘沖で2007年9月から2008年2月に実施 された(南海トラフ地震発生帯掘削計画のステージ1A).これは今後数年間引き続く震源領域深部掘削の第一弾である.東南海地震(1944年 M=8.0)の分岐断層,付加体先端のプレート境界断層,熊野海盆の合計12地点33ヶ所において,海底下約190m〜1400mの掘削同時検層およびコ ア採取が試みられ成功裏に終了した.シンポジウムでは航海の報告と最新の研究成果を紹介し,幅広い議論を行っていく.本シンポジウムを付加体-地震発生帯 システム研究の記念的マイルストーンとしたい.
地学教育・普及行事
地学教育・普及行事
■地質情報展2008あきた−発見・体験!地球からのおくりもの−
■市民講演会「大地の成り立ちと人びとの生活・歴史—男鹿半島・大潟村・豊川油田をジオパークに」
■小さなEarth Scientistのつどい〜第6回小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜
■教員向け見学旅行(見学旅行 Cコース)「地学教育の素材としての男鹿半島」(9/20実施)
→詳細は見学旅行 Cコースのページを参照
地質情報展2008あきた−発見・体験!地球からのおくりもの−
日程:9月19日(金)〜21日(日) 9:00〜17:00 (入場無料)
会場:秋田市民交流プラザ「ALVE(アルヴェ)」1階「きらめき広場」
主催:産業技術総合研究所地質調査総合センター,日本地質学会,秋田市教育委
員会・秋田大学工学資源学部附属環境資源学研究センター
展示内容:地質調査総合センターが有する日本全国の各種地質情報の中から,特
に秋田県に関する様々な研究成果を,展示パネルや映像を使って紹介するととも
に,小さなお子さんにも楽しく地学を学んでもらうために体験学習コーナーを用
意しています.
問い合わせ先:産業技術総合研究所地質調査総合センター
吉田朋弘・兼子紗知 TEL:029-861-3754 e-mail:g08akita@m.aist.go.jp
市民講演会「大地の成り立ちと人びとの生活・歴史—男鹿半島・大潟村・豊川油田をジオパークに」
日時:9月20日(土)13:00〜15:00(入場無料)
会場:秋田大学手形キャンパス教育文化学部3号館大講義室(3-145)
秋田大会実行委員会・ジオパーク支援委員会 共催
白石建雄*(秋田大学工学資源学部, shiraishi@keigo.mine.akita-u.ac.jp)・佃 栄吉(日本地質学会副会長)・薄井伯征(大潟村干拓博物館)佐々木詔雄(三井石油開発(株)) 佐々木榮一(石油資源開発(株))
日本地質学会はジオパーク設立推進委員会を設置し,「地質遺産の保全とその教育・普及・観光への利用が地域の振興と活性化につながる」という理念に基づき,適切に地質遺産が保全・活用されるよう,各方面に働きかけています.本講演会では昨年に引き続き,「ジオパーク」に関連して,男鹿半島—八郎潟地域の多彩な地形・地質・産業遺産の活用可能性を探ります.さらに,「地下なる鉱脈無限の宝庫」と唄われかつて活況を呈していた秋田の鉱山業にも光をあて,日本の近代化を支えた鉱山関連産業の遺産を保存・活用していく活動を紹介し,その意義について広く市民や会員とともに考えていきます(※講演の一般公募はありません).
小さなEarth Scientistのつどい〜第6回 小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜
2007年札幌大会の発表会の様子
日本地質学会地学教育委員会では,地学普及行事の一環として,地学教育の普及と振興を図ることを目的として,学校における地学研究を紹介する「地学研究」発表会をおこなっています.秋田大会でも,小・中・高等学校の地学クラブの活動,および授業の中で児童・生徒が行った研究の発表を募集いたします.秋田県内,また東北地方の学校,さらには全国の学校の参加をお待ちしています.会場は研究者も発表するポスター会場内に,特設コーナーを用意いたします.同時並行で研究者の発表も行われますので,児童・生徒同士のみならず,研究者との交流もできます.この会を通じて生徒,研究者,市民の交流が進み,地質学,地球科学への理解が深まって,未来を担う生徒たちの学習意欲への良い刺激と励みになることを願っております.
なお,参加証とともに,優秀な発表に対しては審査のうえ,「優秀賞」を授与いたします.
下記の要領にて参加校を募集します.
1) 日時 2008年9月21日(日) 9:00〜15:00
2) 場所 日本地質学会年会ポスター会場(秋田大学)
3) 後援 秋田県教育委員会・秋田市教育委員会(予定)
4) 参加対象
・小,中,高校地学クラブならびに理科クラブ等の活動成果の発表
・小,中,高校の授業における研究成果の発表
・活動,研究内容は地学的なもの(地質や気象などの地球科学・環境科学,天文など)
5) 申し込み 2008年7月22日(火)締切.
6) 発表形式 ポスター発表(展示パネルは幅90cm×高さ180cm程度)
パネルのほかに標本等を展示される場合には,パネルの前に机を用意します.参加申込書にその旨を記載してください.その場合は展示パネルの下側が隠れる事をご了承ください.発表者は決められた時間(および随時)パネルの前に待機し説明をしていただきます.なお,遠隔地および学校行事等のために児童・生徒が参加できない場合は,発表ポスターのみをお送りいただいても結構です.
発表の具体的な準備については,申し込み後に各校あてご連絡いたします.
7) 参加費 無料(参加者・引率者とも),開催中の研究者の発表,講演も聴くことができます.
8) 派遣依頼 参加者・引率者については学校長宛,日本地質学会より派遣依頼状を出します.
9) 問い合わせ・申し込み先:
参加申し込みは,別紙書式をFAXしてください.E-mailでも結構です.
日本地質学会地学教育委員会(担当 三次)
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F
TEL:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156 e-mail:main@geosociety.jp
FAX申込書式はこちらかダウンロードして下さい。
■WORD形式
■PDF形式
見学旅行
見学旅行
■事前参加登録はこちら(近畿日本ツーリストの画面)
コース詳細(各コース名をクッリクすると詳細がご覧いただけます)
A:男鹿半島火山岩相(9/23-24)
F:地熱(9/23)
B:男鹿−能代の地形と第四系(9/23-24)
G:非金属鉱床(9/23)
C:地学教育(9/20)
H:黒鉱鉱床(9/22-23)
D:出羽丘陵(9/23)
I:北部北上帯(9/23-24)
E:鳥海火山(9/23)
J:根田茂帯(9/23-24)
K:アダカイト(9/23-24)
A 男鹿半島の火山岩相:始新世〜前期中新世火山岩と戸賀火山<男鹿半島火山岩相>
見学コース
9/23 8:30秋田大学出発→男鹿半島館山崎→潮瀬ノ岬→ 桜島→湯本温泉(泊)
9/24 8:30湯本温泉→戸賀湾→かぶき岩→入道崎→16:00秋田駅解散(秋田駅発こまち 17:07に間に合う)
主な見学対象
台島層下部の火砕岩とその産状,始新世〜漸新世の海成生痕化石とマグマ-水蒸気爆発噴出物,始新世〜前期中新世のリフティングに伴う火山活動と正断層運動,門前層と野村川層との不整合, 第四紀戸賀火山,かぶき岩入道崎の始新世の様々な火山岩・火砕岩
日程:9月23日(火・祝)〜24日(水)(1泊2日)
定員:20名
案内者(所属)*はリーダー
大口健志*(秋田大)・鹿野和彦(産総研)・小林紀彦(国際石油)・佐藤雄大・小笠原憲四郎(筑波大)
概算費用:21000円
地形図:戸賀,北浦,船川(1/2.5万)
備考:レンタカー使用.悪天候の場合(強風雨,波高),見学地点や対象を変更することがあります.昼食は各自ご用意下さい.
ページTOPに戻る
B 男鹿半島−能代地域の地形と第四系<男鹿−能代>
見学コース
9/23 8:30秋田大学正門出発→男鹿半島→男鹿温泉(泊)
9/24 男鹿温泉→潟西台地→能代市南部→大潟村→16:00秋田駅解散
主な見学対象
男鹿半島第四系層序(北浦層・脇本層・鮪川層・潟西層),広域テフラ(Km, Ks5, B-Og, Aso-1, Toya, SK, Aso-4),トラバーチン,海成段丘,完新世砂丘,活構造
日程:9月23日(火・祝)〜24日(水)(1泊2日)
定員:20名
案内者(所属)*はリーダー
白石建雄*(秋田大学)・白井正明(東京大学)・西川 治(秋田大学)
概算費用:22000円
地形図:船越,寒風山,北浦,入道崎,羽後浜田,森岳,能代(1/2.5万)
備考:中型バス使用.昼食は各自ご用意下さい.
ページTOPに戻る
C 地学教育の素材としての男鹿半島<地学教育>
見学コース
9/20 8:00秋田大学出発→寒風山→安田海岸→西黒沢海岸→入道崎→八望台と目潟→椿→脇本→17:00秋田大学解散
主な見学対象
寒風山や目潟など第四紀火山活動,第四紀層と貝化石を主とした化石群および段丘地形,海成第三紀層と第三紀火山活動,基盤岩
日程:9月20日(土)日帰り【注意】大会初日です.
定員:20名
案内者(所属)*はリーダー
藤本幸雄*(秋田西高校)・林信太郎(秋田大学教育文化学部)・渡部晟(秋田県立博物館)・渡部 均(秋田中央高校)・栗山知士(能代商業高校)・品川道夫(払戸中学校)・西村 隆(北陽小学校)・松田菜生子(下北手中学校)
概算費用:4000円
地形図:戸賀,船川(1/5万)
備考:バス使用.行程は状況で変更することがあります。昼食はご持参ください.
ページTOPに戻る
D 秋田県沿岸ー出羽丘陵新第三系に発達する変形構造<出羽丘陵>
見学コース
9/23 8:30秋田大学出発→高尾山→由利本荘市大内→鳥田目→矢島→17:00秋田駅解散
主な見学対象
北由利,中帳,鳥田目断層に伴う変形諸構造
日程:9月23日(火・祝)日帰り
定員:14名
案内者(所属)*はリーダー
西川 治*(秋田大)・奥平敬元(大阪市立大)
概算費用:5500円
地形図:羽後和田,本荘,矢島(1/5万)
備考:レンタカー使用予定,昼食はご持参下さい.
ページTOPに戻る
E 鳥海火山
見学コース
9/23 7:00秋田大学出発→鳥海山5合目鉾立(1150m)→御浜(1700m)→七五三(1790m)→御浜ー鉾立→18:40秋田駅解散(ただし雨天の場合は山麓を巡るコースに切り替える)(七五三まで登るかどうかは参加者の体力と時間により判断)
主な見学対象
鳥海山の十和田a火山灰と平安時代の火山灰,鳥海山の安山岩溶岩とその地形,御浜火口,鍋森山溶岩ドーム,山頂(江戸時代の溶岩ドーム)遠望,(雨天の場合は,象潟岩なだれとその埋没木,象潟地震,象潟郷土資料館,獅子が鼻湿原)
日程:9月23日(火・祝)日帰り
定員:20名
案内者(所属)*はリーダー
林信太郎*・山元正継(秋田大学)
概算費用:6000円
地形図:鳥海山,象潟,小砂川(1/2.5万).雨天の場合は川辺(1/2.5万)も必要
備考:かなり本格的な登山になります。フリース,レインジャケットが必要です.標高の一番高いところの予想気温は摂氏6度から14度の予定です.昼食はご持参下さい.
ページTOPに戻る
F 秋田県南部小安秋の宮地域の地熱地質<地熱>
見学コース
9/23 8:30秋田大学正門出発→小安温泉→バイナリー発電候補地→川原毛温泉→地熱発電所→三途川層→兜山・高松岳火山→18:30秋田駅,19:00秋田空港,秋田大学・市内
主な見学対象
小安温泉変質,石英脈,三途川層化石,岩相,断裂系,兜山層火砕流,上の岱地熱発電所,バイナリー発電用促進調査井など
日程:9月23日(火・祝)日帰り
定員:20名
案内者(所属)*はリーダー
高島 勲*(秋田大)・越谷 信(岩手大)
概算費用:6500円
地形図:秋の宮,稲庭(1/5万)
備考:レンタカー使用.秋田空港より羽田,伊丹,小牧便利用可,秋田駅より東京行き利用可.昼食はご持参ください.
ページTOPに戻る
G 秋田県の珪藻土,パーライト,ゼオライト鉱床<非金属鉱床>
見学コース
9/23 8:30秋田大学出発→北秋田市米内沢→北秋田市鷹巣→能代市二ツ井→藤里町→18:00秋田大学解散
主な見学対象
珪藻土鉱山,パーライト鉱山(北秋田市),ゼオライト鉱山(能代市,藤里町)で鉱山の観察及び試料採集,並びに精製工場見学
日程:9月23日(火・祝)日帰り
定員:10名
案内者(所属)*はリーダー
村上英樹*(秋田大学)・村木克行(中央シリカ)・野口泰彦(昭和化学工業)・鈴木清貴(東北ゼオライト工業)
概算費用:6500円
地形図:桂瀬,米内沢,二ツ井,藤琴(1/2.5万),鷹巣(1/5万)
備考:レンタカー使用.汚れても良い靴でご参加下さい.昼食は,道の駅「たかのす」に寄る予定です(各自負担).地形図は,コピーでよろしければ案内者が配布します.見学旅行終了後,ご希望があれば最寄りのJRの駅にお送りします.
ページTOPに戻る
H 小坂元山黒鉱鉱床の海底熱水鉱化作用と背弧海盆〜島弧の火山活動の特徴<黒鉱鉱床>
見学コース
9/22 16:00 秋田大学出発 →大館市・清風荘(宿泊)見学なし,宿泊のみ
9/23 清風荘出発→小平戸内沢→目名市沢→杉沢合流点→二井山西方白川砕石採石場→二井山→四十八滝玄武岩類→樹海ライン笹森展望台から第三系,第四系の地形→小坂(元山黒鉱露天堀り跡),日本海沿岸道高速道路トンネル工事現場(または鹿角市大葛の黒鉱礫の露頭)→17:00秋田大学解散
主な見学対象
黒鉱鉱床(元山黒鉱露天堀り跡)及びその時代の関連火成岩類 (保滝沢玄武岩類, 四十八滝玄武岩類他),中古生界の基盤岩類,新生界安山岩類,樹海ライン笹森展望台から第三系,第四系の地形,日本海沿岸道高速道路トンネル工事現場(または鹿角市大葛の黒鉱礫の露頭)
日程:9月22日(月)〜23日(火)(1泊2日)【注意】大会最終日の夕方出発です.
定員:14名
案内者(所属)*はリーダー
水田敏夫*・石山大三(秋田大学)
概算費用:15000円
地形図:白沢,大館,陸中濁川,小坂,小坂鉱山,毛馬内(1/2.5万)
備考:レンタカー使用.ヘルメットは秋田大学で準備します.昼食は各自負担.
ページTOPに戻る
I 安家-久慈地域の北部北上帯ジュラ紀付加体<北部北上帯>
見学コース
9/23 8:50盛岡駅集合→安家川上流部→大鳥→高屋敷→17:30山根・べっぴんの湯(泊)
9/24 8:30宿→川又→馬渡→女供→関→合戦場→葛巻→16:00盛岡駅解散→16:40花巻空港
主な見学対象
北部北上帯,葛巻−釜石亜帯の大鳥層の石炭紀チャート,P/T境界層,チャート−砕屑岩(中部ジュラ系)シーケンス,関層チャート・泥岩,合戦場層砂岩,安家−田野畑亜帯の高屋敷層混在岩,沢山川層枕状溶岩,安家層石灰岩,間木平層のチャート−砕屑岩シーケンス
日程:9月23日(火・祝)〜24日(水)(1泊2日)
定員:20名
案内者(所属)*はリーダー
永広昌之*(東北大学)・山北 聡(宮崎大学)・鈴木紀毅・高橋 聡(東北大学)
概算費用:19000円(2日目の昼食込み)
地形図:安家森,(陸中五日市),安家,(端神),岩瀬張,陸中関(1/2.5万)
備考:マイクロバス使用.盛岡駅集合・解散.希望によっては盛岡駅経由花巻空港解散とすることもあり.
ページTOPに戻る
J 北上山地前期石炭紀付加体「根田茂帯」の構成岩相と根田茂・南部北上帯境界<根田茂帯>
見学コース
9/23 9:50盛岡駅集合→簗川根田茂川合流点→綱取ダム貝田橋→中津川→綱取渓谷→中津川小貝沢→17:00矢巾温泉(泊)
9/24 8:20宿→川目採石場→建石林道→長野峠→早池峰ダム→16:30盛岡駅解散
主な見学対象
根田茂帯【含前期石炭紀放散虫シルト岩,泥岩珪長質凝灰岩互層,火山性砂岩,含高圧型変成岩礫礫岩,MORBに伴うFe-Mn質チャート,含Ca-Na角閃石ドレライト,高圧型変成岩テクトニックブロック】南部北上帯【シルル紀堆積岩,島弧緑色岩,斑レイ岩,角閃岩,蛇紋岩】
日程:9月23日(火・祝)〜24日(水)(1泊2日)
定員:20名
案内者(所属)*はリーダー
内野隆之*(産総研)・川村信人(北大)・川村寿郎(宮教大)
概算費用:20000円
地形図:盛岡,区界,大志田,陸中折壁(1/2.5万)
備考:レンタカー使用.・標高差100mの急斜面(上り約20分)と沢の歩行(往復約2km)あり・1日目は沢用シューズ必要(フェルト底かスパイク底の靴を推奨)・1日目の昼食はご持参ください.
ページTOPに戻る
K 北上山地に分布する古第三紀アダカイト質流紋岩〜高Mg安山岩と前期白亜紀アダカイト質累帯深成岩体<アダカイト>
見学コース
9/23 9:50盛岡駅集合→小本川支流松橋川→二升石→田野畑花崗岩体→宮古市(宿泊)
9/24 8:30宿出発→浄土ヶ浜→宮古花崗岩体→立丸峠→16:30盛岡駅解散
主な見学対象
松橋付近の古第三紀高Mg安山岩,二升石・浄土ヶ浜の古第三紀アダカイト質流紋岩,立丸峠の菫青石とホルンブレンドを含む古第三紀アダカイト質流紋岩,前期白亜紀アダカイト質累帯深成岩体の典型例である田野畑花崗岩体および宮古花崗岩体
日程:9月23日(火・祝)〜24日(水)(1泊2日)
定員:20名
案内者(所属)*はリーダー
土谷信高*(岩手大)・西岡芳晴(産総研)
概算費用:16000円
地形図:門,岩泉,宮古,土淵(1/5万)
備考:マイクロバス使用,23日の昼食は各自でご用意ください.
ページTOPに戻る
講演要旨の作成の注意点とPDFファイル作成の作り方
講演要旨の作成の注意点とPDFファイル作成の作り方
講演要旨を作成する際,著者には「保証及び著作権譲渡同意書」第1項の「保証」内容を守って頂きます.行事委員会は,要旨の内容については関知しませんが,当該「保証」内容を逸脱するものがないか校閲します.その結果,不適当とみなされる場合は,修正されるまで講演要旨の受理はされません(不服の場合は法務委員会に訴えることが可能です).
例年最も多い問題点は,引用文献の表示がない場合です.論文のように細かに引用文献を記載することはスペースの都合上不可能なので必要としませんが,雑誌名,号,ページ等,その文献にたどり着ける最低限の情報は記載して下さい.
また,要旨の体裁を無視している場合,印刷できませんので体裁を整えて頂くことになります.さらに図等の改変については,著作権法,地質学会著作物利用規定に従って下さい.
このほか,PDFファイルにフォントを埋め込んでいないもの(印刷時にずれることがあります),要旨作成時に講演番号記入用のスペースがなかったり,余白に無理があるといった場合,体裁を整えるため修正をお願いしています.これらの問題点があった場合,各コンビーナから投稿締切日から1週間をめどに修正依頼が届きます.ただ,その労力はセッションによっては膨大になりますので,あらかじめ著者で完全なものを投稿するようご協力下さい.あわせて講演要旨投稿手順のチェックシートもご参照下さい.
日本地質学会 行事委員会
2008年4月
■要旨テンプレート(Microsoft Word)■ ■講演要旨投稿手順のチェックシート■
【講演要旨PDFファイル作成時の注意点】
1)
講演要旨原稿はAdobe Acrobat Reader 4.0 以上で表示・印刷可能なPDFファイルで投稿することが必要です.
2)
ファイルサイズは3.0Mバイト以内で作成して下さい.
3)
発表(講演)番号は事務局にて左上に付記するので原稿内には記載しないで下さい.
4)
PDFファイルのセキュリティ設定は「なし」にして下さい.
5)
フォントは必ず「埋め込み」にして下さい.MacOSX以上は標準でフォント埋め込みが用意 されます.MacOS9.2.2以下,Windowsでは下記のソフトが必要です.その際,『すべてのフォント埋め込み』ないし『ハイクォリティー』等, それぞれのソフトの使用説明書に従った指定を必ずして下さい.文字数にもよりますが,できたPDFファイルのサイズが100KB未満の場合,フォントが埋 め込まれなかった可能性がありますので確認して下さい.
6)
作成したPDFファイルを自分で印刷し,図表に充分な解像度があるか,文字化けはないか確認して下さい.
7)
PDFファイルを自分のパソコンに,必ず「.pdf」の拡張子をつけて保存して下さい(Mac, Windowsとも).
■原稿フォーマット見本■
テンプレート
(Microsoft Word)
ダウンロードはこちら
【webでの講演要旨投稿の手順】
1)
参加申し込みの後,web上の講演申し込みページで,講演申し込みの手続きをします(講演申込と同時に要旨投稿をすることもできますし、講演要旨のみ後で投稿する事もできます).
2)
講演申込者のメールアドレスに「講演申込みを受付ました」のメールとともにIDが配信されます.
★★後から要旨を投稿する場合・申込内容を変更する場合★★
講演要旨投稿ページに,IDとメールアドレスを用いてアクセスします.講演要旨投稿ページの最下段からご自分にPCに保存してあるファイルを選択し,投稿動作(アップロード)をします.これにより講演申し込みサーバーにPDFファイルが格納されます.
サーバー側では,ファイル名を元のファイル名から変更し,ID.pdfの名称で格納します.「講演申込み(修正)を受付ました」のメールが講演申込者に配信されます.
IDとメールアドレスを用いて,投稿締め切りまで何度でも要旨や登録内容を修正することができます.新しいファイルを投稿すると,古いファイルに上書きされます.そのつど,「講演申込み(修正)を受付ました」のメールが配信されます.
【参考情報:PDF(Portable Document Format)ファイルの作り方】
PDFファイルの作成方法は「PDF原稿作成ガイド」http://www.gakkai-web.net/pdf/を参考にすると良いでしょう.
ソフトの紹介要望が多いので,下記にいくつか参考例を挙げます.また,"PDF作成サービス"を行う有料,無料のサイトがあります.ソフト,サイトとも検索してみて下さい.なお下記について動作確認等しておりません.また推奨するものでもありません.ご了承ください.
◯ Mac OSXの場合
フォント埋め込み型のPDF作成機能が標準で用意されています.新たなソフトは必要ありません.
◯ Mac OS 8.6-9.2の場合
Adobe Acrobat(それぞれのOS対応品,現在販売されているか不明)
EGWORD Ver.12 for Mac OS X/9/8.6(現在販売されているか不明)
◯ Windows対応品
PrimoPDF FreeのPDF変換ソフト http://www.primopdf.com/
クセロPDF FreeのPDF変換ソフト http://xelo.jp/xelopdf/(有料ソフトあり)
いきなりPDF 2000円弱 http://www.sourcenext.com/products/pdf/
Adobe Acrobat Elements 5000円弱 http://www.adobe.co.jp/
◯ MacOS9.2.2,MacOSX, Windows対応
Adobe Illustrator http://www.adobe.co.jp/
講演要旨オンライン投稿手順チェックシート
講演要旨オンライン投稿手順チェックシート
講演要旨の投稿手順および基本的注意事項です.投稿していただく前に各自でご確認下さい.
1.Word等のソフトで講演要旨原稿を作成します.
「保証及び著作権譲渡同意書」第1項の「保証」内容は守られていますか?
引用文献は表示されていますか?
要旨の体裁は守られていますか?(詳細は要旨原稿フォーマットをご確認下さい)
2.原稿をPDFファイルにします.
PDFファイルの作成方法については,本号の「PDFファイルの作り方」を参照して下さい.
フォントは「埋め込み」になっていますか?(できたファイルサイズが100KB未満の場合,フォントが埋め込まれなかった可能性がありますので確認して下さい)
ファイルサイズは3.0MB以内になっていますか?
作成したPDFファイルを印刷し,図表に充分な解像度があるか,文字化けはないか確認して下さい.また,PDFファイルを自分のパソコンに,必ず.pdfの拡張子をつけて保存して下さい.
3.原稿をオンライン投稿します.
web画面から参加申し込みを行いましたか?
講演申し込みページで,講演申し込みの手続きをしましたか?
講演要旨を投稿しましたか?
申込完了画面が表示されましたか(ログイン用のIDが表示されましたか)?
「講演申込のお知らせ」のメールが配信されましたか?
4.一度投稿した原稿を修正したい場合
ご自分の申込画面に,IDと申込時に設定したパスワードを用いてアクセスします.
画面中のPDFファイルのアイコンをクリックし,要旨原稿投稿画面を開きます.書き直した要旨のファイル選択し,投稿動作をします.
修正原稿が受け付けられると,「申込内容変更のお知らせ」メールが配信されます.(締切まで何度でも修正できます).
←講演要旨作成手順のページに戻る
就職支援プログラム
就職支援プログラム
就職に関心のある学生・若手研究者集まれ!
就職を希望する学生,若手研究者と民間企業・団体,研究機関等との情報交換を目的として,昨年度から始まった新しい取り組みのひとつで,各企業等からのブース出展と説明会形式の紹介プレゼンテーションに参加していただくプログラムです.ブースでは企業の担当者に直接質問や相談ができます.参加する企業は,地球科学関連の知識・技術をベースに,社会基盤整備に関わる調査・計画・設計・施工・維持管理,ソフトウェアやハードウェアの開発,および資源開発などを行う企業などで,今回は鉱物科学会関連の企業の参加も予定されています.会員・非会員を問わず参加できますので,学生を指導しておられる大学教職員を含め,多くの方々の参加を歓迎します.
日時:2008年9月21日(日)14:00〜
場所:秋田大学VBL・総合研究棟 2Fポスター会場
内容:主催者等 挨拶・紹介、参加各社による数分のプレゼンテーション、参加各社の個別説明会
参加対象:秋田大会に参加する学生・院生および大学教官等の会員・秋田大学の学生・院生および教官等
参加申し込み:事前の申し込みは不要です.
参加費:無料
出展申し込み:別紙「参加申込書」を日本地質学会宛に8月8日(必着)までにファックスでお送りください。スペースに限りがありますので、参加ご希望の場合はお早めにお申し込みください。詳細についてはお申し込み締め切り後にご連絡いたします。
参加申込書 ■PDFファイル ■WORDファイル
問い合わせ先:日本地質学会事務局 細川
TEL 03-5823-1150 e-mail main@geosociety.jp
秋田大会運営組織
秋田大会運営組織
日本地質学会行事委員会 / 地学教育委員会
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目8-15 井桁ビル6F
TEL 03-5823-1150,FAX 03-5823-1156
e-mail:main@geosociety.jp
■行事委員会■(2008.4.30現在)
委員長
斎藤 眞(担当理事)
委 員
吉川敏之(地域地質部会)
岡田 誠(層序部会)
北村晃寿(古生物部会)
小松原純子(堆積地質部会)
上野将司(応用地質部会)
斎藤文紀(現行地質過程部会)
坂本正徳(情報地質部会)
田村嘉之(環境地質部会)
大坪 誠(構造地質部会)
宮崎一博・青矢睦月(岩石部会)
内山 高(第四紀地質部会)
片山 肇(海洋地質部会)
古川竜太(火山部会)
大久保 進(石油,石炭関係)
中井 均(地学教育関係)
日本地質学会第115年年会(秋田大会)実行委員会
秋田大学工学資源学部附属鉱業博物館気付
〒010-8502 秋田市手形大沢28-1
Tel: 018-889-2467(西川)Fax 018-889-2465(博物館)
e-mail: nishi@ipc.akita-u.ac.jp
諸連絡の代表窓口は大会実行委員会事務局長の西川 治(TEL 018-889-2467,FAX 011-889-2465,e-mail:nishi@ipc.akita-u.ac.jp)です.また,内容によって,それぞれ担当が決まっていますので,下記の中で該当する係(代表者)に直接ご連絡下さい.複数で担当の場合,*印が代表者です.下記氏名の次のカッコ内は,各係の連絡先(TEL,e-mail)を示しています.委員の所属が特に記入されていない場合は,秋田大学の所属です.電話番号の市外局番は,明記されていないものは018です.
■実行委員会組織■
委員長:白石建雄(889-2652,shiraishi@keigo.mine.akita-u.ac.jp)
副委員長:水田敏夫
事務局長:西川 治(889-2467,nishi@ipc.akita-u.ac.jp)
総務:山元正継(yamamoto@galena.mine.akita-u.ac.jp)・石山大三・嶋田智恵子(889-2798,cshim-1008@mbp.nifty.com)
会計:川原谷 浩*(889-2454,kawaraya@cges.akita-u.ac.jp)・千田恵吾(889-2461,keigo@galena.mine.akita-u.ac.jp)
会場・機器:山崎 誠*(889-2383,yamasaki@keigo.mine.akita-u.ac.jp)・水田敏夫・石山大三・西川治・佐藤時幸(889-2371,toki@ipc.akita-u.ac.jp)
企業団体展示:山元正継*・大場 司(yamamoto@galena.mine.akita-u.ac.jp)・細野高啓
見学旅行:大友幸子*(023-628-4424,yukiko@mail.sci.hokudai.ac.jp山形大学)・越谷 信(岩手大学)・村上英樹(hidekim@cges.akita-u.ac.jp)
懇親会:水田敏夫・大場 司
普及・企画(市民講演会):白石建雄*(889-2652,t-ohba@ipc.akita-u.ac.jp)・林 信太郎*(889-2651,hayashi@ipc.akita-u.ac.jp)・西川 治
展示会場:秋田大学生活協同組合(森)(TEL.018-832-7141 FAX. 018-832-1105 mori@akita.u-coop.or.jp)
渉外:白石建雄*・水田敏夫・西川 治
宿泊・交通:近畿日本ツーリスト(株)秋田支店 日本地質学会秋田大会受付担当デスク(澤田)(TEL 896-4890,FAX 896-4922, akita@or.knt.co.jp)
保育室:千田恵吾*(889-2461, chida@galena.mine.akita-u.ac.jp秋田大学工学資源学部附属鉱業博物館)・西川 治・マミーズ・ハウス担当:鈴木(231-7201, mami-zu@waltz.ocn.ne.jp)
生徒「地学研究」発表会担当:藤本幸雄*(230214T05@akitanishi-h.akita-c.ed.jp 秋田西高校)・林 信太郎(889-2651,hayashi@ipc.akita-u.ac.jp)
地質情報展担当:村上英樹*(hidekim@cges.akita-u.ac.jp)・西川 治
近畿日本ツーリスト(株)秋田支店
日本地質学会秋田大会 受付担当デスク(担当 澤田)
TEL 018-896-4890 FAX 018-896-4922
e-mail : akita@or.knt.co.jp
営業時間:(月〜金) 9:00〜17:45
(営業時間終了以降のお申込み・変更・取消は翌日扱いとなります)
変更・取消のご連絡はFAX又はe-mailにてご連絡下さい.
お電話でのご連絡はお受け致しかねますので,ご協力よろしくお願い致します.
秋田大学生協
〒060-0808 秋田市手形学園町1-1
秋田大学生活協同組合 (担当 森)
TEL 018-832-7141 FAX 018-832-1105
e-mail : mori@akita.u-coop.or.jp
懇親会・お弁当
懇親会
参加申込締切:8月8日(水),近畿日本ツーリスト(株)扱い
日時:9月20日(土)表彰式・記念講演会終了後,18:00頃〜19:30
会場:秋田大学学生会館生協食堂で行います.
会費:正会員5,000円
名誉会員・院生割引会費適用正会員・学生会員および会員の家族は2,000円.
非会員の会費は会員に準じます.
準備の都合上,前金制の予約参加とします.秋田の郷土料理も準備して,たくさんの方々,特に院生・学生などの若手会員のご参加をお待ちしております.余裕があれば当日参加も可能ですが,予定数に達し次第〆切ります. 当日会費は1,000円高くなります.
予約申し込みはこちらのページから,大会参加申し込みと合わせて8月8日(水)までにお申し込み下さい.
当日は参加証を受付にご持参下さい.なお,参加取消の場合でも会費の返却はいたしませんのでご了承下さい.
■事前参加登録はこちら(近畿日本ツーリストの画面)
お弁当予約販売
予約申込締切:8月8日(水),近畿日本ツーリスト(株)扱い
9月20日(土)〜9月22日(月)には昼食用の弁当販売をいたします(1個700円,お茶付).
予約申し込みはこちらのページから,大会参加申し込みと合わせて8月8日(水)までにお申し込み下さい。なお,お弁当利用日より9日前〜前日までは50%、当日は100%のキャンセル料がかかります.
注意:21日(日)は,生協食堂の営業がありませんのでご注意ください。
■事前参加登録はこちら(近畿日本ツーリストの画面)
同窓会
今年度は、同窓会は開催されません。
ランチョン・夜間小集会
ランチョン申込
<申込締切 7月7日(月)必着,行事委員会扱い>
9月21日(日),22日(月)にランチョンの開催を希望する方は,
(1)集会の名称,
(2)世話人氏名,
(3)集会内容 等,
をe-mailに明記して(ハガキでも可)行事委員会(東京:main@geosociety.jp)宛に申込んで下さい.申込締切は7月7日(月)です.なお,世話人の方は,終了後集会の内容をニュース誌の大会記事用原稿としてご投稿下さい(800字以内,原稿締切10月15日).
夜間小集会の申込
<申込締切 7月7日(月)必着,行事委員会扱い>
9月21日(日)は18:00〜20:00,22日(月)は17:30〜19:00(予定)です.夜間小集会の開催を希望する方は,
(1)集会の名称,
(2)世話人氏名,
(3)集会内容(50字以内),
(4)参加予定人数,
(5)OHP・液晶プロジェクターの要・不要,
(6)その他特記すべきこと,
をe-mailに明記して(ハガキでも可),行事委員会(東京:main@geosociety.jp)宛に申込んで下さい.申込締切は7月7日(月)です.なお,世話人の方は,終了後集会の内容をニュース誌の大会記事用原稿としてご投稿下さい(800字以内,原稿締切10月15日).
保育室
保育室利用申込
(1)保育室利用要領
1) 申し込み先:秋田大会実行委員会 担当:千田恵吾
「2008年日本地質学会託児室申込書」に必要事項を記入のうえ,下記アドレス宛にe-mailまたはFaxにて送付ください.
Fax:018-889-2465 e-mail:chida@galena.mine.akita-u.ac.jp
※大会参加登録フォームからは申し込みできませんので,ご注意ください.
■■託児室申込書(words)ダウンロードはこちらから■■
2) 申し込みの際の必要事項
1.保護者氏名:地質学会員は学会登録名にてお願いします.パートナーと一緒に学会参加される方は,パートナー氏名もあわせて連絡ください.
2.子供の氏名,性別,生年月日
3.利用希望時間:9月20日(土)〜22日(月)の3日間について,それぞれ利用希望時間.
※保育室の利用可能時間は9:00〜20:00です.
4.緊急連絡用の携帯電話等番号
5.アレルギーの有無,その他注意事項
3) 利用にあたり,事前に健康状態等に関する問診票の記入が必要です.所定の問診票に記入のうえ,当日,保育室までお持ちください.問診票の書式は,地質学会の第115年学術大会ホームページの「各種申込」からダウンロードできます.
4) 受付締切日以降の申し込みは,シッターの確保ができる場合のみお受けします.なるべく受付締め切り日までにお申し込みください.保育のキャンセル・時間変更等は,9月18日(木)までに地質学会実行委員会まで連絡ください.これ以降のキャンセルについては,キャンセル料がかかります.利用当日の時間変更・延長は,シッターとご相談ください.
5) 授乳等で部屋の使用を希望される方,上記以外の時間に保育を希望される方は,事前にご相談ください.
6) 利用申込受け取り後に確認のご連絡をさせていただきます.申込されてから3日以内(土日除く)に確認の連絡がない場合は,お手数ですが秋田大会実行委員会・千田(018-889-2461)までご連絡下さい.
(2)保育室設置要領
1) 保育室の運営は,「マミーズ・ハウス」がお世話いたします.
2) 設置期間:9月20日(土)〜22日(月) 9:00〜20:00まで.
3) 保育対象年齢は生後満2ヶ月〜小学校低学年(9歳)までとなります.障害をお持ちの子供の保育は,秋田大会実行委員会(千田)までお問い合わせください.
4) 保育室:大会会場となる秋田大学手形キャンパスの和室を使用します.部屋番号等が決定しだい,利用希望者へ連絡いたします.大会受付にも保育室の場所等の情報を掲示する予定です.午睡用の寝具(布団,ベビーベッド等),遊具を用意します.トイレは保育室の近くにあります.
5) 飲料水を除く飲み物・ミルク・哺乳瓶・食事・おやつ・常用薬については保護者の方でご準備ください.食事の時間等に外へ連れ出しても結構ですが,その場合必ずシッターに知らせてください.
6) 保育室には,電気ポット,寝具(布団,上掛け他),おもちゃ,紙コップ,飲料水,麦茶を準備する予定です.
7) 利用料金は一時間あたり800円程度(1名利用の場合)を予定しておりますが,年齢・利用者数により変動する場合があります.利用料金は,利用当日に学会受付に,現金にて直接お支払いください.クレジットカード・銀行振込によるお支払いは受け付けておりません.
8) 上記の料金には,傷害保険料が含まれております.
9) 保育利用者数に応じてシッターの配置数を決定しますので,利用希望の方は必ず事前に申し込みください.
10) 病気・事故:日本地質学会ならびに秋田大会実行委員会は,保育時における病気・事故等に対する責任を一切負いません.保護者の責任において対応ください.事故の補償は,マミーズ・ハウスが加入する保険(日本興亜損害保険 総合賠償責任保険(業務内容 託児所):対人賠償1事故最高5千万円,対物賠償1事故最高500万円)の範囲でまかなわれます.万が一事故が起きた場合は,その損害額は上記保険にて補填される限度とすることをご承諾ください.当該補填額を超える損害等については責任を負いかねますので,ご了承願います.
11) 学校法定伝染病などの場合には託児をお断りいたします.病児保育については,軽い病気の場合には,シッターと相談の上,最終的に保護者様に判断して頂きます.ただし,他のお子様との集団生活であることも考慮し,通常の保育園等と同様の基準でご判断下さい
12) 大会期間中の急病等緊急の場合には,保育室に掲示の情報(休日担当医および近隣の病院に関するもの)をご利用ください.不明の点については,気軽にシッターにご相談ください.
13) 託児室内の安全については託児開始前に確認いたします.それ以外の場所については屋内外を問わず危険個所が存在する可能性もあり得ますので,託児時間以外はお子様から目を離さず,危険な場所に近づかぬよう,くれぐれもご注意ください.
(3)託児当日について
1) 利用初日には,申し込み時に秋田大会実行委員会にお送りいただいた「託児申込書」に捺印の上,保育室シッターにお渡しください.
2) 利用日ごと(初日のみではありません)に,所定の「問診票」をシッターにお渡しください.アレルギーの有無やお子様の体調等についての質問項目がありますので,必ずご利用日ごとにご記入・ご提出をお願いいたします.
3) 学会にご夫婦で参加される場合,お子様をお預けになる初日は,できましたらパートナーの方もご一緒においでください.お預けになる方とお迎えに来られる方が違う場合は,特にご一緒においでくださるようにお願いいたします.
4) 持参された食事,おやつ,着替えなどは,問診票と一緒にシッターにお渡し下さい. (詳しくは以下の5) 持ち物 の欄をご覧下さい)
5) 当日は,以下のものをお持ちください
○食べ物(必要なお子様のみ)
○飲み物(飲料水は用意しておりますので,特に必要なお子様のみ)
○着替え
○タオル(乳児のお子様はバスタオル1枚)
○エプロン
○おしぼり
○汚れ物袋(スーパーのビニール袋など):必要枚数ご持参下さい.
○ミルク(必要なお子様のみ):必要回数分小分けにされたミルクと哺乳瓶をご持参ください.
○おむつ(必要なお子様のみ):お尻ふきもあわせてご持参下さい.
※飲食物のアレルギーがある場合は,必ず問診票に明記し,受付時にシッターにお伝えください.
※紙コップを用意しておりますが,紙コップを使う事が難しいお子様については,できるだけマグカップ類をお持ち下さい.
※おもちゃは託児室に用意しておりますが,特に必要な場合は事前に相談ください.
※持ち物にはすべて名前を書いて,一つの荷物にまとめてご持参下さい.
6) お子様への投薬全般は保護者の方にしていただきます.
7) 緊急時の呼び出しについて
○急な発熱,不測の事態などには,基本的に保護者様にご対応をお願いしております.当日の参加会場および携帯番号を問診票にお間違いのないように記入して下さい.建物内は電波状況が悪い場合もありますので,参加予定会場と携帯以外の緊急連絡先も必ずご記入下さい.
8) お迎えの時間は厳守お願いいたします.
9) 保育室利用者の手荷物等については,ベビーカーおよびお子様の保育に必要なものについてのみ,保育室でお預かり可能です.
(4)保育室担当者
1) 日本地質学会秋田大会実行委員会 担当:千田恵吾
〒010-8502 秋田市手形大沢28-1 秋田大学工学資源学部附属鉱業博物館
Tel: 018-889-2461 Fax 018-889-2465 e-mail: chida@galena.mine.akita-u.ac.jp
2) 保育室運営: マミーズ・ハウス 担当:鈴木
〒010-1414 秋田市御所野元町6-2-3
Tel: 018-826-0208 Fax:018-826-0233
企業展示/書籍販売等について
企業・研究機関等関係団体による展示会の出展募集<申込締切 8月8日(金)>
地質関係機関,企業の活躍を地質学会会員に紹介するためのパネル・展示物の展示会場を設置いたします.会社紹介,研究紹介など内容は自由に構成していただき,多くの企業,機関,団体がご参加下さるようお待ちしています.
展示パネル:幅90cm×高さ180cmを単位とし,出展費は1単位あたり1万円,複数単位も可.
ブースの場合:間口4m×奥行2mを単位として,1ブースあたり5万円.
会場設備の都合上,電源を必要とする機器を持ち込みされる場合には,8月8日(金)迄に展示会場係にご相談下さい.この他色々なバリエーションについてもご相談に応じます.なお,本大会への協賛企業・日本地質学会賛助会員は出展料が無料です.
参加・展示の申込は,8月8日(金)までに下記へ電話,FAX,e-mailいずれかでお願いします.
〒010-8502 秋田市手形学園町1−1 秋田大学工学資源学部地球資源学科
出展申込先:2008年秋田大会実行委員会パネル・展示会場係,
担当者:山元正継(TEL 018-889-2375,FAX 018-837-0401,e-mail:yamamoto@galena.mine.akita-u.ac.jp)(注意:@を半角にして下さい)
書籍販売および見本展示,機器等の展示・販売申込<申込締切 8月8日(金)>
年会開催期間中の展示・販売等は,9月20日(土)〜22日(月)(会場:秋田大学)の3日間とします.問い合わせおよび申込は,8月8日(金)までに直接秋田大生協(下記)へお願いします.
〒060-0808 秋田市手形学園町1-1 秋田大学生活協同組合
担当:専務室(森),e-mail : mori@akita.u-coop.or.jp,(注意:@を半角にして下さい)
TEL. 018-832-7141 FAX. 018-832-1105
一般発表の募集要領
一般発表の募集と要領
注:シンポジウムに関しては、シンポジウムのページを参照して下さい。
一般発表の募集
演題・要旨締切:WEB 7/10(木)17時・郵送7/7(月)必着
↓WEBからの講演申込はこちら↓
講演申込受付は終了いたしました
■定番セッション一覧はこちら
■トピックセッション一覧はこちら
9月20日〜9月22日の3日間(いずれも午後)での一般発表を募集します.下記の要領にて口頭,ポスター発表を募集します.できる限りオンラインでの申込にご協力下さい.やむを得ず郵送で申し込む場合は所定の申込書に必要事項を記入の上,返信用(自分宛)の官製ハガキ,保証書・同意書,講演要旨とともに7月7日(月)必着で行事委員会宛にお送り下さい.プログラムの編成が終わり次第,発表セッションや発表日時などをe-mailで通知します(郵送の場合は返信ハガキ).なお,発表セッションや会場・時間などのプログラム編成につきましては,各セッションの世話人の協力を得て,行事委員会が決定します.
(1)セッションについて
本年会は,9月20日(土)〜9月22日(月)の3日間で一般発表を行います.専門部会の提案などにより22件の定番的セッションと,8件のトピックセッションを設けました.
(2)講演に関する条件
日本地質学会の会員は,口頭発表かポスター発表かのいずれかの方法で,1人1題に限り講演を行うことができます.共同発表の場合は上記の条件を講演者(=筆頭発表者)に適用します.非会員は筆頭発表者になれませんので,必ず7月7日(月)までに入会手続きを行って下さい.入会申込書が届いていない場合は,講演申込は受理されません.
(3)招待講演について
本年より,トピックセッションにおいては,世話人は会員・非会員を問わずに招待講演を依頼することができます.招待講演は1セッションにつき,半日あたり1講演に限ります.招待講演についても申込期日までに一般発表と同様にお申し込み下さい(世話人が取りまとめでオンライン入力をすることは可能です).定番セッションでは招待講演の設定はありません.なお,非会員の招待講演者に限り参加登録費は免除となります.
(4)講演申込上の注意
1) オンライン申込はホームページ:http://proc.jstage.jst.go.jp/proceedings/service/geosocabst/newregistration/にアクセスし,オンライン入力のフォームに従って入力して下さい.
2) 講演方法については,「口頭」,「ポスターセッション」,「どちらでもよい」のいずれかを選択して下さい.ただし,申込締切後の変更はできません.
3) 発表題目,発表者氏名について,必ず登録フォームと講演要旨の両方を一致させて下さい.
4) 共同発表の場合は全員の姓名を完記して下さい.
5) 発表を希望するセッションを第2希望まで選んで下さい.
6) コメント欄について:発表の対象とする地域の記入を要するセッションについてはこの欄に国名・県名等を入力して下さい.また,関係する一連の発表があるときは,その順番希望などもこの欄に入力して下さい.
7) 口頭発表会場には液晶プロジェクターとWindowsパソコン(OS:Windows Vista, Office Standard 2007)を用意します.パワーポイントを使用する方は,試写室において正常に作動することを事前に確認してください.特に,会場に設置するものと異なるバージョンで作成されたファイルは,レイアウトが崩れる事例が報告されていますのでご注意願います. パワーポイントを使用しない方やMacパソコンを使用される方は世話人とご相談下さい.なお,今大会からオーバーヘッドプロジェクター(OHP)および35mmスライドプロジェクターの使用はできません.
(5)講演要旨原稿の投稿について
例年と同様に講演要旨をAdobe社が策定したPortable Document Format(PDF)のファイルで電子投稿していただきます.一般講演およびシンポジウムの原稿はA4判1枚(フォーマット参照)で,印刷仕上がり0.5ページ分です.1ページに2件分ずつ印刷します.原稿はそのまま版下となり,70%程度に縮小して印刷されます.文字サイズ,字詰めおよび鮮明度には十分配慮し,PDFファイルを作成して下さい.やむを得ず郵送する場合は,オリジナルか,鮮明にコピーした現物を1枚だけ郵送(差し支えなければ折りたたみ可)して下さい.FAXやe-mailでの原稿送付は受け付けません.
一般発表の要領
(1)口頭発表
1)講演時間は1題あたり15分(討論時間3分を含む)です.講演者は,討論など持ち時間を十分考慮し余裕を持って講演を行って下さい.
2)各会場には,液晶プロジェクター,Windowsパソコンを各1台とスクリーン1幕を設置します.
(2)ポスター発表
1)1題について1日間掲示できます.各日とも発表者はコアタイム(開催日によって異なる)にその場に立会い,説明をするものとします.設置,撤去時間等については,本誌8月号に掲載されるプログラムをご覧下さい.ボード面積は1題あたり,縦180cm,横90cmです.
3)発表番号・発表名・発表者名をポスターのタイトルとして明記して下さい.
4)掲示に必要な画鋲等は,発表者がご持参下さい.
5)ポスター会場では,コンピューターによる発表や演示等も許可しますが,使用する機器については発表者がご準備下さい.また,電源は確保できませんので,予備のバッテリーをご用意下さい.講演申込の際に機器使用の有無や小机の必要性をコメント欄に記入し,事前に世話人ご相談下さい.
6)運営細則第11条(6)項により,優れたポスター発表に対して「日本地質学会優秀ポスター賞」を授与いたします.具体的な事柄については,プログラムに掲載しますのでご注目下さい.
(3)発表者の変更
あらかじめ連記されている共同発表者内での変更は認めますが,必ず事前に行事委員会へ連絡して下さい.この場合も筆頭講演者については7項の(2)の条件が適用されます.
(4)口頭発表の座長の依頼について
セッションによっては各会場の座長を参会者にお願いすることになります.あらかじめ座長依頼を差し上げることになりますが,その際にはぜひともお引き受けいただきたく,ご協力をお願いします.
講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理,引用方法,校閲について
講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理,引用方法,校閲について
(1)講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理
2003年1月から日本地質学会の出版物への投稿原稿に対して,その倫理性について著作者に保証して頂くために「保証書」に,また著作権を日本地質学会に 譲渡することを同意する「著作権譲渡同意書」に,それぞれ署名捺印をして提出していただくことになりました.本大会では,電子投稿のため,画面上で「保証 書」と「著作権譲渡等同意書」に同意していただいた場合に限り,電子投稿の画面に進むことができるようになっています.郵送の場合は,保証書及び同意書に署名捺印をして,講演要旨と共にお送り下さい.「保証及び著作権譲渡等同意書」が同封されていない講演申込は受け付けられません.
(2)講演要旨における文献等引用方法
要旨においては引用文献の記載方法は簡略化することが慣習として認められていますが,著者名,発表年,掲載誌名などを明記し,引用文献が特定できるようにして下さい.
(3)講演要旨の校閲
行事委員会は,申し込まれた講演について,会則第4条に示されている日本地質学会の目的ならびに日本地質学会倫理綱領に反していないかということについて のみ校閲を行います.校閲の結果,いずれかの条項に反していると判断された場合には,行事委員会は講演内容の修正を求めるか,あるいは講演申込を受理しな いことがあります.行事委員会の措置に同意できない場合には,当該講演申込者は法務委員会(東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル 日本地質学会事務 局気付)に異議を申し立てることができます.法務委員会は直ちに審理し,結論を行事委員会ならびに異議申立者に伝えることになります.
この受理方法は,招待講演者にも適用されます.
講演申し込み異議申し立てについて
日本地質学会行事委員会は,学術大会において学会の目的及び倫理規定に反する講演申し込みのあった要旨に対して,修正あるいは,受理を拒否することができます.法務委員会では,日本地質学会行事委員会規約に基づき,異議申立の手続及びその処理についての規則を定めています.
日本地質学会法務委員会
■日本地質学会学術大会講演申込異議申立に関する処理機構規則(PDF)■
講演要旨予約頒布
講演要旨集のみの予約頒布について
■参加登録フォームはこちらから■
申込締切 8月8日(金)18時,近畿日本ツーリスト(株)扱い
大会参加費には講演要旨集の代金が含まれていますので,大会に参加される場合は別途購入の必要はありません(ただし,学生会員・名誉会員・50年会員・非会員学部学生の参加費には,講演要旨集は含まれません.ご希望の方は,別途ご購入下さい).大会に参加されない方ならびに参加する方が複数の講演要旨集を購入される場合の予約頒布です.申込は,「12.各種申込とお支払いについて」を参照し,申し込んで下さい.要旨集の受け取り方法には,
(1)大会後に送付,
(2)会場で受取り,があります.(1)の場合は,別途送料が必要です.(2)の場合は,大会受付にて確認書の提示が必要となりますので,必ずご持参下さい.残部があれば大会当日あるいは大会後にも頒布します.売り切れの場合はご容赦下さい.
事前予約(/冊)
当日販売(/冊)
会員
3,000円
4,000円
非会員
4,000円
5,500円
*送付の場合別途以下の送料がかかります.
送料:1冊 500円,2冊 600円,3冊 800円,4冊 1,000円,5冊 1,200円
事前参加登録
事前参加登録申込および参加登録費(講演要旨集付き)について
■参加登録フォームはこちらから■
申込締切 8月8日(金)18時,近畿日本ツーリスト(株)扱い
当日会場受付での混雑緩和のため,事前に参加登録申込をお願いします.大会参加登録およびそれに伴う参加費は,全ての参加者(見学旅行のみの場合も)に必要な基本的なお申込です.ただし,会員が同伴する非会員の配偶者ならびに子供については必要ありません.
申込は,上記WEB参加登録フォーム一括申込できます.申込・支払い方法等については,「近畿日本ツーリストへの各種申込について」を参照し,申し込んで下さい.
■参加登録費
(講演要旨集付です.講演要旨集が不要の場合でも割引はありません.なお,学生会員・名誉会員・50年会員・非会員学部学生の参加費には,講演要旨集は含まれません.ご希望の方は,別途ご購入下さい)
事前申込
当日払い
正会員・共催/協賛団体会員
7,500円
9,500円
院生割引会費適用正会員
4,500円
6,500円
学生会員・名誉会員・50年会員・非会員学部学生
500円
500円
非会員(一般・院生)
12,000円
15,000円
*なお,大会に参加できなかった場合は,大会後に講演要旨集をお送りします.参加登録費用の返却はいたしませんのでご了承ください.
*シンポジウムの共催・協賛団体に会員として所属する方の参加登録費は学会員と同額になります.
近畿日本ツーリストへの申込・支払方法について
近畿日本ツーリストへの各種申込とお支払方法について
■参加登録フォームはこちらから■
(1)申込方法
オンラインによる参加登録申込等を受付けます.申込は近畿日本ツーリスト(株)秋田支店(以下KNT)が窓口となります.大会参加登録ホームページにてお申し込み下さい.参加登録・見学旅行・懇親会・講演要旨集追加注文・お弁当及び割引航空券・宿泊を同時に申込可能です.
(a) 大会登録専用HPによる申込:申込フォームに必要事項を記入して送信
(b) FAXによる申込:申込用紙に必要事項を記入の上,KNT (018-896-4890)宛送信
(2)申込受付受理
申込受付後,KNTより「受付確認書」をe-mail又はFAXにてご連絡申し上げます.その際,「登録番号」が必ず記載されております.こちらの「登録番号」はその後の問合せ,変更,取消等に必要となりますので,恐れ入りますが失念されぬようお願い致します.
(3)申込締切
8月8日(金)18:00
(4)お支払方法
銀行振込・クレジットカード決済をお選び頂けます.申込締切後,参加者の皆様へ「予約内容確認・ご請求書」を送付致します.銀行振込ご希望の方は,請求書に記載されている振込口座へ指定期日までにお振込み下さい.クレジットカード決済希望の方は,登録申込の際必ずクレジット番号などの必要事項をご記入下さい.振込期日に合わせてご指定のクレジットカードに課金致します.カード会社よりお客様に送付される明細には学会名ではなく「近畿日本ツーリスト(株)」と表示されます.
(5)参加証・各種クーポンの送付
振込期日後,お支払いの確認が取れている方へ順次発送致します.大会開催1週間前には参加者の皆様のお手元に届くようお送り致します.お支払いの確認が取れていない方へはご送付できませんので,皆様の振込期日厳守を何卒よろしくお願い致します.
(6)取消に関わる返金
所定の取消料の他に返金振込料を差し引いた額を大会終了後お返し致します.クレジットカードにてお支払の場合は,ご利用頂いたカードへご返金となります.
(7)申込後の変更・取消
申込後に変更・取消が生じた場合は,KNT宛FAX又はe-mailにてご連絡下さい.その際申込受付時に案内される「登録番号」及び「大会名」「氏名」を必ず明記下さい.
What's News AKITA2008
What's News AKITA2008
2008.9.16 一部会場の変更について
一部会場の変更について
会場準備の都合により、プログラムでお知らせしておりました一部会場が下記の通り変更となります。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、当日はお間違いのないよう会場にお越し下さい。
●就職支援プログラム:VBL・総合研究棟 2Fポスター会場(9/20、14時)
●夜間小集会「南海トラフ地震発生帯掘削」:般2-103号室(9/21、18時)
●書籍等販売コーナー:般1-208
2008.9.16 口頭発表講演データ取り扱いについて
口頭発表講演データ取り扱いについて
セッションの講演データは、主催者側の学会のやり方で取り扱うことになりますので,講演者の皆様は、その旨ご了解下さい。とくに鉱物科学会主催の合同セッションで講演される地質学会会員の方は、ご注意下さい。
●地質学会主催のセッション
基本的に半日前(午前の場合は前日午後から)からセッション開始30分前まで試写室(大学会館2F)でデータを受付けます。
なお、9/20(初日)午前中の口頭発表で使用するファイルのについては、試写室にて[9月19日16:00-17:00、9月20日8:00-8:30]で受付けます。
余裕を持って、講演前にあらかじめご対応頂きますようお願いいたします。
●鉱物科学会主催のセッション
該当セッション:「岩石・鉱物・鉱床一般」
セッション前に直接会場に行って、設置してあるPCにデータを入れるか,自分のパソコンをつなぎ替えることになります。
2008.9.5 “緊急展示”の申し込みについて
“緊急展示”の申し込みについて
学会活動の一端を広く社会に紹介するとともに,ホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害報告や社会的に影響のある新技術紹介などの「緊急展示コーナー」を設けます.ポスター展示を希望する方は,9月8日までに以下の内容で下記の実行委員会にご連絡ください。
1)発表要旨PDF(ニュース誌5月号P12参照)
2)緊急展示の必要性
3)発表代表者と連絡先
4)希望枚数(1枚:幅90×180cm)
5)展示に関わる要望(2〜5の様式は自由)
実行委員会は行事委員会と協議し,可否の判断を致します。希望にはできるだけ応えるようにしますが,展示方法等については実行委員会の指示に従ってください.
申込先 秋田大会実行委員会 西川 治
メール nishi@ipc.akita-u.ac.jp
2008.9.2 講演プログラム公開しました
講演プログラム公開しました。
各日程ごとのプログラム(pdf)を公開しました。全体日程表と会わせてご覧下さい。
<http://www.geosociety.jp/science/content0015.html>
なお、一部講演タイトルが講演要旨と異なる場合があります。その場合は、講演要旨が優先されますので,ご了承ください。
2008.8.20 秋田大会見学旅行追加募集します(8.31締切)
秋田大会見学旅行追加募集します(8.31締切)
申し込む方は8月31日までに,下記項目を明記の上,大友幸子<yukiko@e.yamagata-u.ac.jp>にお申し込みください.
申込者には,8/25以降に必ず“受付”メールを返信します(返信がない場合,不着の可能性がありますので再度連絡ください.8/20-24は不在です).なお,受付は先着順です.
●申込事項:氏名,よみ仮名,年齢,所属,E-mailアドレス,電話番号
A(9/23-24)男鹿半島の火山岩相:始新世〜前期中新世火山岩と戸賀火山 2名
B(9/23-24)男鹿半島−能代地域の地形と第四系 6名
C(9/20:大会初日です)地学教育の素材としての男鹿半島 8名
D(9/23)秋田県沿岸ー出羽丘陵新第三系に発達する変形構造 4名
F(9/23)秋田県南部小安秋の宮地域の地熱地質 6名(参加費3000円に変更予定)
G(9/23)秋田県の珪藻土,パーライト,ゼオライト鉱床 4名
I(9/23-24)安家-久慈地域の北部北上帯ジュラ紀付加体 5名
J(9/23-24)北上山地前期石炭紀付加体「根田茂帯」の構成岩相と根田茂・南部北上帯境界 6名
K(9/23-24)北上山地に分布する古第三紀アダカイト質流紋岩〜高Mg安山岩と前期白亜紀アダカイト質累帯深成岩体 6名
*E鳥海火山とH小坂元山黒鉱鉱床・・は定員に達しておりますので再募集しません.
2008.7.10 講演申込手続き締切延長(7.11,17:00締切)
講演申込手続き締切延長(7.11,17:00締切)
J-STAGEサーバのシステムエラーのため本日7/10午後数時間、講演申込システムへのアクセス障害が発生いたしました.緊急措置として、システムの締切時間を24時間延長いたしました。会員の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしました。申し訳ございません。
日本地質学会行事委員会
2008.6.25 緊急災害に関連した講演発表について
緊急災害に関連した講演発表について
秋田大会での講演の検討をされていることと思います.行事委員会でセッションの確定等を行ってから,四川地震,岩手・宮城内陸地震が発生し,それらをどのセッションに発表しようか迷っておられる方もおられるかと思います.
行事委員会としては,現在すでに起こっている事象につきましては,通常のセッションの枠内で対応する予定でおります.応用地質一般,地域地質・地域層序,ノンテクトニック,テクトニクス,環境地質,情報地質等のセッションが該当するかと思います.
その際,聴衆にインパクトのあるように,申込状況に臨機応変に対応し
1)セッション内でサブセッションを作る等,プログラム上も見える形にする
2)セッション間で講演をやりとりして関係講演をまとめる
等の対応を行い,プレス等にもアピールしたいと思います.つきましては,備考欄に四川地震,岩手・宮城内陸地震などとご記入の上,講演申し込みをお願いいたします.数多くの発表をお待ちしております.なお今後これらの地震災害に関連して新たに発生した事象については別途対応を検討するものと致します.
(行事委員長 斎藤 眞)
2008.6.18 講演申込システムのアクセス障害について
講演申込システムのアクセス障害について
講演申込システム(J-STAGEサーバ)へのアクセス障害が断片的に発生しています。
現在調査・対応中ですが、講演申込手続き中にアクセスできなくなった場合は、お手数ですが、時間をおいて再度アクセスしていただきますようお願いいたします。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
(日本地質学会行事委員会)
2008.5.17 秋田大会関連プレスリリースについて
秋田大会関連プレスリリースについて
秋田大会での講演や行事について,9月上旬にプレス発表を行う予定です.昨年の札幌大会では多数のメディアに取り上げられ,会員の皆様の研究成果が多いに注目されました.秋田大会で発表される予定の案件で,学会からのプレス発表をご希望の方は,8月25日(月)までに学会事務局(journal@geosociety.jp)にご連絡願います.全ての案件をプレス発表することはできませんが,社会への情報発信として特筆すべき成果は積極的に公表して行きたいと考えております.会員の皆様におかれましては,プレスリリース解禁日をお守りいただき,公平かつ効果的な情報発信にご協力願います.不明な点は学会事務局までお問い合わせ願います.
(日本地質学会広報委員会)
定番セッション・トピックセッション
定番セッション・トピックセッション
演題・要旨締切:WEB 7/10(木)17時・郵送7/7(月)必着
↓WEBからの講演申込はこちら↓
講演申込受付終了しました
・ セッションテーマ,(提案部会名)(地域名等特記事項),世話人(*印責任者),趣旨の順に掲載します.
・ 特に断りのないセッションは口頭とポスターの両方を募集します.
・ 提案部会に関わりなく,会員はいずれのセッションにも応募できます.ただし,応募は口頭かポスターのいずれか1件に限ります.
・ 「地域名必要」の記載があるセッションは,申込書に研究対象の地域名を記入してください.
・ 口頭発表会場には液晶プロジェクターとWindowsパソコンを用意します.ただし講演申込時に, OHPを申し込まれた方は OHPを使用することができます(昨年スライドプロジェクターの希望が無かったため,本年よりスライドの用意はありません).また液晶プロジェクターを使用される方で,Macパソコンを使用される方は世話人とご相談下さい.
トピックセッション:8件
1.ジュラ系+(読み方:ジュラケイプラス)
松岡 篤(新潟大;matsuoka@geo.sc.niigata-u.ac.jp)・堀 利栄・小松俊文・近藤康生・尾上哲治,石田直人
2002年の新潟大会プレシンポジウム以降,毎年開催しているトピックセッション「ジュラ系+」の成果を踏まえ,ジュラ系および隣接する地質系統の研究に関する到達点を共有するとともに,わが国がジュラ系研究の拠点となることを目指す.トリアス・ジュラ系境界などのGSSPの決定にかかわり,国際的にはジュラ系の研究が活発におこなわれている.また,2008年8月にはノルウェーでIGCが開催され,IGCに向けて新たな地質年代尺の構築も進んでいる.このような国際的な動きに対して,アジアから何が発信できるのかを議論したい.
2.地下地質環境の地球科学:現象と応用
吉田英一(名古屋大;dora@num.nagoya-u.ac.jp)・高橋正樹・梅田浩司・渡部芳夫
地下地質環境は,エネルギー備蓄や放射性廃棄物処分,CO2貯蔵などの様々な観点からその長期的な利用が具体的に検討されつつある.一方で,変動帯における日本の地下環境の働きとその長期的挙動を理解するためには,火山・断層活動や隆起・沈降などといった広域的な地質現象だけでなく,それらに伴う地下水流動や地球化学的・(微)生物学的な変化,さらには地下空洞掘削に伴う影響などをも考慮した複合的アプローチが不可欠と考えられる.しかしながら,地下環境利用のニーズは高まっているものの,必ずしも多面的な地質現象やその研究方法,課題に関して工学的な影響をも含めた現象を複合的かつ専門的に議論できる場が多いとはいえない.このような背景のもと本セッションでは,日本の地下地質環境に関して 重要と思われる様々な地質現象とその影響ならびに応用という観点から,様々な分野の専門家との科学的・技術的な意見交換を行うことを趣旨に開催したい.
3.グリーンタフルネサンス−水中火山砕屑岩類の堆積相解析に基づいた日本列島新生代テクトニクスの再構築−
天野一男(茨城大;kazuo@mx.ibaraki.ac.jp)・松原典孝
グリーンタフは新生代日本列島のテクトニクスを考える上でキーとなる地層であり,その研究の歴史は古い.層序を編むことを中心に進められてきたグリーンタフ研究は,1970年代にプレートテクトニクスの概念がもたらされると日本列島の発達史と共に論じられ,1990年代前半に東北日本弧において総括的な研究がなされた.しかし,その後グリーンタフ研究は一気に下火となった.一方,グリーンタフを水中火山岩という観点で捉え,その形成メカニズムを詳細に検討する研究は進められていた(山岸,1994など).しかし,これらは海岸などの露頭規模のものに限られており,広範囲にわたって検討した研究はまったくなかった.そのため,堆積相解析の結果をテクトニクスや島弧発達史の復元に利用できることは
ほとんど無かった.近年,南部フォッサマグナや東北日本の一部で,水中火山砕屑岩類の堆積相解析に基づいた新たなテクトニクス研究の成果が報告されるようになり,さまざまな分野から注目されはじめている.国際的には堆積相解析的手法にもとづいた水中火山砕屑岩類の研究は飛躍的に発展してきた.特に,陸上に露出した水中火山砕屑岩類の研究は,海洋性島弧系の研究に一石を投じるものとして注目されている(Busby et al. 2006など).本シンポジウムは堆積相解析を利用してグリーンタフ研究に一石を投じ,新生代日本列島のテクトニクスの新たな発展をめざすものである.
4.地球史とイベント大事件4:環境と生命の進化に迫る
清川昌一(九州大;kiyokawa@geo.kyushu-u.ac.jp),山口耕生,黒田潤一郎,小宮 剛
地球史46億年.地球環境は,内的・外的なフォーシングによって,様々な時空スケールで(時に激的な)進化をとげてきた.地球史初期に誕生した生命は,環境に適応した進化をとげた一方で,環境を自ら変えてきた.地球史における数々のイベントの性質とそれに対するレスポンスの解明を目指し,地層や岩石・鉱物に記録されたテクトニック変動・表層環境変動・(微)生物活動の歴史の解明に関する最新の研究動向を探る.
5.後生動物の進化と絶滅史
小宮 剛(東京工大;tkomiya@geo.titech.ac.jp)・上野雄一郎(東京工業大)・磯崎行雄(東京大)
地球生命進化史の中で重要な後生動物の飛躍的進化がおきた代境界事件(原生代/古生代/中生代/新生代)に焦点を当て,日本で初めて解明された斬新な研究成果を発表/議論する.とくに新しいタイプの後生動物の出現と直前の大量絶滅の前後の時期の表層環境激変に注目する.
6.高分解火山地質学
及川輝樹(産総研;teruki-oikawa@aist.go.jp),伴 雅雄,奥野 充,下司信夫
シンポジウム「高分解能火山活動史構築の現状・課題」に関連した研究の一般講演を募る.火山層序学,岩石学,堆積学,実験などの手法を駆使し,時空的に高分解能な火山活動史を構築した研究を募集する.
7.沖積層研究の新展開
木村克己(産総研;k.kimura@aist.go.jp),卜部厚志,三田村宗樹
平野の軟弱地盤を構成する沖積層については,近年,堆積シーケンスや 高密度な放射性炭層年代に基づいたダイナミックな地形・地層形成の捉え方, そして,ボーリングデータの空間情報処理による3次元数値モデルと地盤の可視化,地質と地盤工学特性との統合などの新しい研究が展開されてきている. 本セッションは,これまでの層序・化石に関する研究に加えて,こうした新しい研究手法からの研究も合わせて,沖積層の層序,堆積環境,地層形成,地質 ・地盤モデルやその解析手法について,総合的に意見交換ができる場として設定する.
8.「ちきゅう」による南海トラフ地震発生帯掘削計画ステージ1Aの成果
坂口有人(JAMSTEC; arito@jamstec.go.jp),芦 寿一郎,木村 学
同名のシンポジウムでは概要とハイライトが紹介されるが,本セッションではより詳細な議論と関連研究の紹介等を行い,今後の深部掘削へとつなげたい.乗船研究者および陸上研究者,そして同計画に関心を持つ広い分野から領域横断的な研究発表を歓迎する.
定番セッション:22件
9.地域地質・地域層序(地域地質部会・層序部会)(地域名必要)
吉川敏之(産総研・t-yoshikawa@aist.go.jp)・岡田 誠(茨城大)・斎藤 眞(産総研)
国内,海外問わず各地域に関係した地質や層序の発表を広く募集.地域的な年代,化学分析,リモセン,活構造,応用地質等の発表も歓迎.地質災害地の地質,惑星地質もここに含まれる.地域を軸にした討論を期待する.地質図や断面図のポスター発表を特に歓迎.
10.地域間層序対比と年代層序スケール(層序部会)(地域名不要)
里口保文(琵琶湖博物館; satoguti@lbm.go.jp)・岡田 誠(茨城大)
テフラ等の鍵層を用いて異なる地域間の層序対比に主体をおく研究や,鍵層そのものを主体とした研究,または複合的層序学等によるグローバルな年代層序スケールの構築に寄与するような研究についての講演を歓迎します.
11.海洋地質(海洋地質部会)(地域名必要)
片山 肇*(産総研・katayama-h@aist.go.jp)・徳山英一(東大海洋研)・ 芦 寿一郎(東大海洋研)・小原泰彦(海上保安庁)
海洋地質に関連する分野(海域の地質・テクトニクス・変動地形学・海域資源・堆積学・海洋学・古環境学・陸域地質での海洋環境変遷研究など)の研究発表を募集する.調査速報・アイデアの公表・海底地形地質・画像データなどのポスター発表も歓迎する.
12.砕屑物組成・組織と続成作用(堆積地質部会)(地域名必要)
野田 篤*(産総研:a.noda@aist.go.jp)・太田 亨(早稲田大)
砕屑物を構成する個々の粒子の特性(形態や化学組成)ら砕屑物(岩)の組織・組成を対象とし,砕屑物(岩)の形成・続成過程の復元,後背地や古環境,地質体の発達史を議論する.データ解析手法,現世砕屑物の組成,初期続成過程についての発表も歓迎する.
13.炭酸塩岩の起源と地球環境(堆積地質部会)(地域名必要)
山田 努*(東北大:yamada@dges.tohoku.ac.jp)・Humblet marc Andre(東北大)
炭酸塩岩・炭酸塩堆積物の堆積作用,組織,構造,層序,岩相,生物相,地球化学,続成作用,ドロマイト化作用など,炭酸塩に関わる広範な研究発表を募集する.また,現世炭酸塩の堆積作用・発達様式,地球化学,生物・生態学的な視点からの研究発表も歓迎する.
14.堆積相と堆積システム・シーケンス(堆積地質部会)(地域名必要)
廣木義久*(大阪教育大:hiroki@cc.osaka-kyoiku.ac.jp)・中条武司 (大阪市立自然史博物館)
各堆積環境における堆積相の形成過程と認定,各堆積相の分類・記載,その時空分布をもとにした堆積システムの認定や解釈などを扱う.また,堆積相解析を基礎にした堆積システム変遷の解析およびシーケンス層序学など,地層の形成過程のダイナミックな復元に関連する研究発表と議論を行う.
15.堆積作用・堆積過程(現行地質過程部会・堆積地質部会)(地域名必要)
小松原純子*(産総研・j.komatsubara@aist.go.jp)・北沢俊幸(原子力機構)
堆積作用や堆積過程に関して,実験・シミュレーション・現地観測および地層観察などに基づいた研究を募る.特定の地域や年代を超えて適応可能な新しい解析手法や多方面からのアプローチによる堆積関連の研究も募集する.
16.石油・石炭地質学と有機地球化学(石油・石炭関係・堆積地質部会)(地域名必要)
大久保 進(石油資源開発・susumu.okubo@japex.co.jp)・金子信行(産総研)
国内外の石油・石炭地質および有機地球化学に関する講演を集め,石油・天然ガス・石炭鉱床の成因・産状・探査手法など,特にトラップ構造,堆積盆,堆積環境,貯留岩,根源岩,石油システム,資源量,炭化度などについて討論する.
17.岩石・鉱物の破壊と変形(構造地質部会)(地域名不要)
河野義生*(愛媛大・kono@sci.ehime-u.ac.jp)・西川 治(秋田大)
断層岩を含む岩石・鉱物の破壊および変形機構,変形微細構造,岩石・鉱物のレオロジーや物性に関する研究を募る.観察・観測・分析・実験・理論など多方面からのアプローチによる成果を歓迎するとともに,会場での活発な議論を期待する.
18.付加体(構造地質部会)(地域名必要)
鎌田祥仁* (山口大学・kamakama@yamaguchi-u.ac.jp)・坂口有人(JAMSTEC)
現世,過去を問わず,付加体に関するすべての講演を歓迎する.付加体の形成機構,形成史,微細構造,流体移動,シュードタキライト,温度圧力構造など,様々なアプローチによる成果をもとに議論する.
19.テクトニクス(構造地質部会)(地域名必要)
大坪 誠*(産総研・otsubo-m@aist.go.jp)・丹羽正和(日本原子力研究開発機構)
地球科学の多方面から,大小様々な時間・空間スケールで起こる地質構造の成因や形成機構・発達史に関する講演を広く募集する.野外調査,観測,実験,理論などに基づいた研究発表を歓迎する.
20.ノンテクトニック構造(応用地質部会・構造地質部会)
柏木健司*(富山大 kasiwagi@sci.u-toyama.ac.jp),永田秀尚(風水土),村井政徳(中国開発調査株式会社)
テクトニックではない構造(例:堆積物の未固結時変形やランドスライド・地震などによる一過性の構造,重力性の構造その他)の記載・解析・テクトニック構造との区別や比較・応用を議論する.時代・時間やスケールを問わないので,さまざまな分野からの参加を期待する.
21.古生物(古生物部会)(地域名不要)
北村晃寿*(静岡大・seakita@ipc.shizuoka.ac.jp)・太田泰弘 (北九州博)・三枝春生 (兵庫県立人と自然の博)・須藤 斎 (名古屋大)
古生物に関する,または関連する研究の発表・討論を行う.
22.噴火と火山発達史(火山部会)(鉱物科学会と共催)
世話人:西来邦章(産総研,k-nishiki@aist.go.jp),工藤 崇(産総研)
マグマや熱水性流体の上昇過程,噴火様式,噴火推移,噴出物の移動・運搬・堆積,特定火山あるいは火山地域の発達史,火山活動とテクトニクス,およびその他火山地質やモデル化に関する幅広い視点からの議論を期待する.
23.マグマプロセス・サブダクションファクトリ(火山部会・岩石部会共催,鉱物科学会と共催)
世話人:金丸龍夫(日大,t-kanama@chs.nihon-u.ac.jp), 古川竜太(産総研)
深成岩および火山岩を対象に,マグマプロセスにアプローチした研究発表を広く募集する.発生から定置・固結に至るまでのマグマの物理・化学的挙動や,テクトニクスとの相互作用について,野外地質学・岩石学・地球化学・年代学など様々な視点からの活発な議論を期待する.
24.深成岩及び変成岩(岩石部会;鉱物科学会と共催)(地域名不要)
青矢睦月*(産総研・aoya.m@aist.go.jp),加々島慎一(山形大)
国内および世界各地の深成岩と変成岩を主な対象に,記載的事項から実験的・理論的考察まで,またマイクロスケールから大規模テクトニクスまで,様々な地球科学的手法・規模の視点に立った斬新な話題提供と活発な議論を期待する.
25.岩石・鉱物・鉱床学一般(岩石部会;鉱物科学会と共催)(地域名不要)
石渡 明*(東北大・geoishw@cneas.tohoku.ac.jp),土谷信高(岩手大)
岩石学,鉱物学,鉱床学,地球化学などの分野をはじめとして,地球・惑星物質科学全般にわたる岩石及び鉱物に関する研究発表を広く募集する.地球構成物質についての多様な研究成果の発表の場となることを期待する.
26.情報地質(情報地質部会)(地域名不要)ポスターセッションのみ,口頭講演なし
坂本正徳(国学院大・cigma@kokugakuin.ac.jp)・能美洋介(岡山理科大)
地質情報の数理解析,統計解析,データ処理,画像処理などの理論,応用,システム開発,利用技術など,最近の情報地質分野の研究結果を対象とする.また,これらの成果の地質学の広い分野への応用・普及なども歓迎する.
27.環境地質(環境地質部会)
難波謙二(福島大)・風岡 修(千葉環境研)・三田村宗樹(大阪市大)・田村嘉之*(千葉環境財団・tamura-yoshiyuki@pop07.odn.ne.jp)
医療地質,地盤沈下,湧水,水資源,湖沼・河川,都市環境問題,法地質学,環境教育,地震動,液状化・流動化,地震災害,岩盤崩落など,環境地質に関係する全ての研究の発表・討論を行う.
28.応用地質学一般(応用地質部会)(地域名不要)
上野将司*(応用地質(株)・ueno-shouji@oyonet.oyo.co.jp)・横田修一郎(島根大)
種々の地質ハザードの実態,調査,解析,災害予測,ハザードマップの事例・構築方法,土木構造物の設計・施工・維持管理に関する調査,解析など,応用地質学的視点に立った幅広い地質学研究について発表・討論を行う.
29.地学教育・地学史(地学教育部会・地学教育委員会共催)(地域名必要)
矢島道子*(地質情報整備活用機構・yajima-michiko@gupi.jp)
地学教育の現場からの多くの会員諸氏の実践発表・問題提起を歓迎する.また,地学史からの問題提起は地学自身の発展を促す.貴重な史的財産を参会者に示していただきたい.
30.第四紀地質(第四紀地質部会)(地域名必要)
吉川周作*(大阪市大, yoshi@sci.osaka-cu.ac.jp)・白石建雄(秋田大)・内山 高(山梨環科研)
第四紀地質に関する全ての分野(環境変動・気候変動・湖沼堆積物・地域層序など)からの発表を含む.また,新しい調査や研究,方法の開発や調査速報なども歓迎する.
Anayaタイ地質学会会長との懇談(2007.8.14)
Anayaタイ地質学会会長との懇談
副会長 佃 栄吉
三菱マテリアル資源開発(株)松坂総一郎氏(タイ地質学会名誉会員)のご紹介により,来日中であったタイ地質学会会長(チュラロンコン大学)のAraya Nakanart教授と木村会長及び佃副会長とで将来の両地質学会の協力について2007年8月4日に懇談を行った.タイ及び日本の地質学会,地球科学関係団体に関わる広範な情勢など,話題は多岐に渡り,相互理解のための貴重に時間がとれた.Araya会長からは,タイでは地質学会(会員約1300人)以外には大きな地球科学関係の学会がないが,新たな学会を作る様々な動きがあり,将来的に地球科学のコミュニティが発散していくことを懸念していることなど現状認識が示され,地質学会の体制強化(組織化,法人化?)を通して,会長イニシャティブを発揮して進めたいこと,また,日本地質学会との連携により,多くを学んでいきたいこと等が述べられた.これに対して,日本側からは地球惑星科学連合における関連学会の連携活動,合同大会を活用した活動などの紹介を行った.最後に連携協定文書(MOU)のドラフトをお渡しし,具体的な連携についての検討を両者で進めることを約束して終了した.なお,Araya会長は10年ほど前までDMR(タイの地質調査所)にいたこともあり,バンコクに事務所のある政府間組織CCOP(http://www.ccop.or.th/)に関しても話題となった.
日本地質学会として,幅広く国際連携を進めることにしているが,今回は会長同士がオフィシャルに会談を持つ最初の例となった.今後の具体的な連携については,現在すでに大学,研究機関,JICA/企業等で進められている共同研究,研究協力・支援活動などの情報を集約しつつ,AOGSでの共同セッション企画,IYPE,ジオパークなどの活動で具体的な新たな協力を進めることも大事であろう.なお,タイ地質学会の英文ホームページはまだない.英文ホームページへの支援,共同運営も協力の一つとなろう.
写真:Araya Nakanart教授と木村会長
タイ地質学会HP
<http://www.dmr.go.th/geosothai.html>
大韓地質学会より新年のご挨拶(2009.1.10)
大韓地質学会より新年のご挨拶
大韓地質学会の李 絃具会長より素敵な新年のご挨拶を頂きました。
大韓地質学会とは、韓国で2007年に学術協定調印が結ばれ、昨年9月の日本地質学会115年学術大会(秋田大会)では、 李会長をお招きし、日韓地質学会学術交流協定調印記念式典も行われるました。(秋田での記念式典の様子は、こちら)
クリックすると、大きな画像をご覧頂けます。
過去の学術大会
今年の学術大会
▶︎ 第132年学術大会(2025年熊本)
2025年9月14日(日)〜16日(火)
会場:熊本大学黒髪キャンパス ※対面開催
本サイトはこちら
大会開催通知(大会委員長 松田博貴)
採択されたトピックセッション
大会までのスケジュール
過去の学術大会
第131年学術大会(2024年山形)(講演要旨閲覧/DLできます)
第130年学術大会(2023年京都)(講演要旨閲覧/DLできます)
第129年学術大会(2022年東京・早稲田)(講演要旨閲覧/DLできます)
第128年学術大会(2021年オンライン)(講演要旨閲覧/DLできます)
2020名古屋大会 代替企画
第127年学術大会(2020年名古屋)中止 ※名古屋大会中止と代替企画について
第126年学術大会(2019年山口)
第125年学術大会(2018年札幌/つくば特別大会)
第124年学術大会(2017年愛媛)
第123年学術大会(2016年東京・桜上水)
第122年学術大会(2015年長野)
第121年学術大会(2014年鹿児島)
第120年学術大会(2013年仙台大
第119年学術大会(2012年大阪)
第118年学術大会(2011年水戸)
第117年学術大会(2010年富山)
第116年学術大会(2009年岡山)
第115年学術大会(2008年秋田)
学術大会に関わる情報
・キャンセルされた講演要旨の取り扱い
・講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理,引用方法,校閲について
・野外調査において心がけたいこと /安全のしおり/巡検案内書を頼りに野外調査へ出かける方へ
・巡検時等における車両運行指針
2021年顕彰式_50年会員紹介
永年会員顕彰者 1971年入会(計41名)
荒井 章司
石井 正之
永広 昌之
北里 洋
木戸 道男
君波 和雄
楠田 隆
小早川 隆
笹田 政克
佐藤 和志
高橋 治郎
高安 克己
徳山 英一
中井 均
仲谷 英夫
新井田 清信
二階堂 章信
濱塚 博
平林 憲次
別所 孝範
方違 重治
安松 貞夫
和田 信彦
大槻 憲四郎
(以下お写真の掲載省略)
赤井 静夫・大場 孝信・岡 孝雄・岡村 眞・奥田 義久・金井 克明・小宮山 梓・佐藤 隆春・佐藤 隆英・柴田 徹・菅谷 正美・武島 正幸 立石 雅昭・中野 聰志・萩原 茂・安松 貞夫・山本 尊仁・(敬称略)以上41名
---------------------------------------------------------------------------------
(お寄せいただいたコメントをご紹介します)
学会員になったのは卒業論文の頃なので確かに50年立ちました.あの頃より確かに知識は増えたし,また少しは賢くなったはずだと信じたいです.2年後には初論文からも50年です.もう少しだけ頑張るつもりです.(荒井 章司)
地質コンサルタント会社に勤務して47年.地質学の新知見に,ずいぶん助けられました.今後もう少し,地質調査で社会に貢献できたらと思っています.(石井 正之)
現役や若手の方々には,基礎科学をしっかり勉強し,独創的な研究をされることを切に期待します.(大槻 憲四郎)
永年会員(50年)顕彰の連絡をいただき,もう50年経ったのかと驚いております.この間,プレートテクトニクスが定着し,また古生物学では Biogeosciences が本流になりました.とはいえ,山や海を相手に自然と対話することは基本です.引き続き,初心を忘れずに過ごして参ります.(北里 洋)
現在は,私達の高校・大学時代に比べて,地学教育の場が激減している.今は宇宙,太陽系,地球生命進化についての新しい情報があふれている.私達の使命はこれらの情報を伝える教育の場を極力増やすことです.(木戸 道男)
50年もの間,西へ東へ地べたを這い回ってきたことになる.虎は死して皮を残す.地質屋は何を残すのだろうか?地質図だろうか.名は無理だとしても,色褪せることのない地質図は,残せただろうか?(君波 和雄)
就職と同時に入会.以降50年,理科教員として授業に向かうモチベーションを最後まで維持できたのも,会員であることが大きな支えだったと感じています.ありがとうございました.(小早川 隆)
皆様のお世話になりながら,この50年間,花崗岩,地熱,流体包有物,放射性廃棄物,地中熱の5分野で,10年くらいでテーマを変えながら研究してきました.芭蕉の不易流行に喩えるなら,私にとって地質学は不易です.(笹田 政克)
団塊の世代,大学闘争,別子銅山閉山,秩父地向斜・本州地向斜,コノドント・放散虫化石,垂直か水平運動か,科学革命の構造(クーン),プレートテクトニクスとプルームテクトニクス,面白い時代を生きてきました.(高橋 治郎)
高校2年の時,地学部顧問の”故”野村松光先生に将来,化石の研究をしたいと相談したところ,地質学を勉強することが先決で,地質学会に入ることを薦めていただきました.早くも50年がたち感慨無量です.今回の顕彰を励みに地質学・古生物学にこれからも係わっていきたいと思います.(仲谷 英夫)
何となく入会した地質学会,いつの間にか50年.生家が棚倉構造線直上にあったので卒論等の学生何人かが宿とした.私自身の成果はともかく,小さな新しい発見が次々続いて60年.地質調査は生涯の趣味となり今も続けている.(二階堂 章信)
"この50年間の地質学の進歩には,瞠目.災害の多い日本.地学を高校必修に.
札幌在住で,北国の自然を享受しています.家庭菜園(約150坪の借地)等に励みながら,合間に,お陰様で現職続けています.(萩原 茂)
大学で地質学の面白さに魅せられて以来,特にタービダイトをはじめとした地層の堆積構造や堆積システムの解明に取り組んできました.そして今なお地元の博物館等で郷土の地質の普及に努めています.(濱塚 博)
50年間日本地質学会会員であったことを顕彰して頂き,光栄です.この間,学会からは得るところは多大でしたが寄与は僅かで恐縮の限りです.愚直に会費を支払い続けて来たことを評価して頂いたものと心得ます.(平林 憲次)
朧気ながら,大学4回生の時に先生の勧めで入会した記憶があります.最先端の地質学の息吹を感じられる毎月の地質雑誌を楽しんできました.もう少し宜しくお願いします.有難うございました.(別所 孝範)
私は民間地質コンサルタントで応用地質を専門に鉄道・道路・斜面等の基礎調査に従事してきました.また,地質学会では2007年から関東支部幹事として務め,今後も微力ながら地質学普及に頑張りたいと思っています.(方違 重治)
地球科学を学べたことに感謝します.変動体は風光明媚とともに災害帯とも肌身で知りました.皆様のご健闘を祈ります.私は海のプラスチックゴミ問題に残りを注ぎます.(安松 貞夫)
大学では構造地質を専攻し北海道では水理地質や旧廃止鉱山の環境修復を担当,中国では土壌汚染調査と重金属汚染農地の修復研究まで,対象は深部から表層に代わっても学んだ地質学の視点で多様性に対応しています.(和田 信彦)
2020名古屋代替企画
* 2020名古屋大会 代替企画
日 程
内 容
備 考
2021年
3/7(日)
JABEEオンラインシンポジウム
「自然災害列島における地質技術者の育成−大学統合期における地質学教育ー」
YouTube公開中
どなたでも視聴可能です
2020年
若手会員のための地質関連企業の研究サポート
「地質系若者のためのキャリアビジョン誌」発行
▶︎冊子ダウロードはこちらから
(フルカラー28p,25社掲載)
44大学48機関へ配布しました(12/4発送)
12/5(土)
第20回四国支部総会・講演会
開催様式:WEB開催
終了しました
11/29(日)
(第2回)コロナ禍での地質学教育に関するサイバーシンポジウム
終了しました
10/24(土)
第2回ショートコース
終了しました
10/7(土)-
10/9(金)
構造地質部会2020年度オンライン例会
終了しました
日本地質学会ジュニアセッション:デジタルポスター審査(旧 小さなESのつどい)
終了しました
9/27(日)
(第1回)コロナ禍での地質学教育に関するサイバーシンポジウム
終了しました
9/19(土)
第1回ショートコース
終了しました
9/13(日)
各賞表彰・受賞記念講演会
終了しました
*第127年学術大会(2020名古屋大会)[開催中止]
日程:2020年9月9日(水)〜11日(金)
会場:名古屋大学東山キャンパス
※名古屋大会中止と代替企画について(2020.5.25)
ahm2015:Arthur Holmes Meeting(2015.9.25)
Arthur Holmes Meeting Tsunami Hazards and Risks: Using the Geological Record
The Geological Society of London(GSL)・日本地質学会 共催
*画像をクリックすると
PDFファイルがダウンロードできます。
2013年に,ロンドン地質学会と日本地質学会は学術交流協定を締結しました.この協定の趣旨に基づき,2014年9月に鹿児島で開催された第121年学術大会では国際シンポジウム「Tsunami Hazards and Risks: Using the Geological Record」が開催され,津波堆積物に関する最新の研究成果が発表され,盛会であったことは,会員の皆様の記憶に新しいことと思います.
この度,2015年9月に,鹿児島大会の国際シンポジウムと対をなす形で,標記の国際シンポジウムが開催されることになりましたので,お知らせいたします.興味のある会員の方は,是非,御参加下さい.なお.若手研究者への渡航費用の助成もありますので,奮って御応募下さい.
日程:2015年9月25日(金)
会場:The Geological Society (Burlington House)(英・ロンドン)
プレ巡検 ストレッガスライド津波堆積物など
9月22日(火)〜24日(木)
◆ ポスター発表募集中:8月7日(金)締切(要旨提出を含む)
◆ 若手研究者への渡航費用の助成:専用の申請用紙に必要事項を記入のうえ担当者までメールで送信して下さい.4月17日(金)17時(現地時間)締切です.
シンポジウムのプログラム,巡検概要,費用助成の申請用紙など,
詳細はシンポHPをご覧下さい.
<http://www.geolsoc.org.uk/ahm15>
日本−ロンドン地質学会学術交流協定(2013.8.8)
日本地質学会とロンドン地質学会の学術交流協定締結に関して
井龍康文(執行理事:国際交流担当)
この度,日本地質学会とロンドン地質学会は学術交流協定を締結しました.以下に,その全文を掲載いたします.また,日本地質学会の石渡 明会長とロンドン地質学会のDavid Shilston会長によって署名された協定書のコピーを示します.
この協定が締結される契機となったのは,昨年(2012年)8月にオーストラリアのブリスベーンで開催された第34回万国地質学会中に,ロンドン地質学会の4名(Edmund Nickless事務局長,Nic Bilham企画・渉外担当事務官, Angharad Hills女史[編集担当],Alan Lord国際交流担当理事)と日本地質学会の3名(石渡 明会長,サイモン・ウォリス副会長,保柳康一執行理事)との会談です.この会談では,両学会間で学術面での交流・協力を活発化させることで意見が一致し,その後のメールでの意見交換を行い,このような学術協定を締結するに至りました.その手始めとして,来年,鹿児島で開催される日本地質学会第121年学術大会では,両学会の共同で,津波堆積物に関する国際シンポジウムを開催する予定です.
日英交流400年に当たる2013年に本協定が締結されたことは慶ばしい限りです.これを契機として,両地質学会の交流が深まり,さまざまな学術交流が行われることが期待されます.
本協定の締結に際しては,サイモン・ウォリス副会長に御尽力いただきました.記して謝意を表します.
日本地質学会−ロンドン地質学会学術交流協定(全文)
Agreement for Academic Cooperation and Exchange
Between
The Geological Society of Japan
and
The Geological Society of London
Article 1. This Agreement outlines the principles for establishing cooperation between the Geological Society of Japan and the Geological Society of London.
Article 2. The Geological Society of Japan and the Geological Society of London agree to promote academic cooperation between both societies through the following means.
(1) Mutual invitations to participate in scientific seminars, regular meetings and field trips
(2) Joint organization of seminars and academic meetings
(3) Joint or collaborative research activities and publications
(4) Exchange of academic and educational materials and other information
(5) Promoting other academic and education cooperation in the geo-sciences as mutually agreed
Article 3. Implementation of any of the types of cooperation mentioned in Article 2 may be restricted depending upon the availability of resources and financial support. The Societies will endeavour to obtain funding from third parties to support collaboration. The execution of this agreement will not cause any financial obligation to either Society.
Article 4. This agreement is valid for a period of five years from the date of signing by the representatives of both Societies. This Agreement may be renewed after being reviewed and re-negotiated by both Societies. Either Society may terminate this agreement by giving one month’s prior notice in writing.
日本地質学会−ロンドン地質学会学術交流協定(PDF)
モンゴル地質学会との交流協定締結(2009.10.14-16)
モンゴル地質学会との交流協定締結
日本地質学会とモンゴル地質学会の交流協定の調印式が、10月14日モンゴル地質 学会のモンゴル地質調査70周年記念学術大会の際に行われました。 モンゴル地質学会からの招待を受け、地質学会からは、宮下会長と石渡理事(国 際交流担当)及び地質学会日・モンゴル小委員会の高橋裕平会員・坂巻幸雄会員 にご出席頂きました.
調印式のほかモンゴル訪問の様子を石渡理事よりご報告頂きましたのでお伝えし ます。
宮下会長と石渡及びモンゴル交流小委員会の高橋裕平さんは,12日の夕方,無事にウランバートル空港に着き,モンゴル地質学会副会長のO. Gerelさん(女性)の出迎えを受けた.
13日の朝は,まず日本大使館を訪問し,二等書記官の大川陽一さんに今回の訪問の目的と学術交流の今後の見通しなどをお話しした.その中で,モンゴルにジオパークをつくることに地質学会として協力できるかもしれない,という話に特に興味を示された.
その次にモンゴル科学技術大学のGerelさんの研究室を訪問し,岩石,鉱物,化石,地球物理などの授業を参観した.どの教室も学生であふれていて活気があった(写真1).日本語学科も訪問し,スタッフの日本語があまりに流暢なので感激した.昼は,一般人は入場できない立派な建物の迎賓館で,S. Oyun会長(国会議員でもあり,「市民の意思党(Civil Will Party)」の党首でもある.ただし,この党は党員3万人で議員は彼女1人とのこと)主催の昼食会があった(写真2).日本側の出席者は宮下会長,私,高橋裕平さん,坂巻幸雄さん,そして坂巻さんの奥さんで,モンゴル側はOyunさん,Gerelさん,地質・石油技術学部長のChuluunさん(男性),資源関係の会社のGotovsurenさん(男性),そして助手の女性1名だった.
写真1.モンゴル科学技術大学の岩石学実習の様子.
写真2.左からモンゴル地質学会副会長(国際地質科学連合 IUGS副会長)のGerel氏,同会長で国会 議員のOyun氏,日本地質学会会長の宮下氏.13日の昼食会で.
昼食会の後は,Gotovsurenさんが公用車を使って宮下会長と私を市内各地に案内して下さった.ウランバートル市街の南にある展望台(弱変成古生層がよく露出している)や市内の仏教寺院兼王宮などに行った.
14日はモンゴル地質学会のモンゴル地質調査70周年記念学術大会の1日目で,モンゴルにおける地質調査の歴史の話から始まって,個別的な地質の報告が続いたが,講演はすべてモンゴル語で行われたため,私たちにはよくわからなかった.口頭発表37件,ポスター発表25件(計62件)のうち,日本人の発表が2件(高橋氏と栗原氏,いずれもポスター),日本人が共著者の発表が5件あり,日本との交流が成果を挙げていることが伺える.私が個人的に興味深かった発表は,イギリスのH. Nigelほかのモンゴル中央部のBaga Togo Uul火山(更新世)からのザクロ石レールゾライト捕獲岩の報告(ポスター)であった.また,発表はなかったが,要旨集にはGerelほかによるモンゴル初のフルグライト(閃電岩)の発見や名古屋大学の足立守氏による「名古屋大学がモンゴル科学技術大学に設けたフィールド・リサーチ・センターの役割」という文章も載っている.
14日の昼に学会会場内の小さな階段教室に設けられた式場(写真3)で日本地質学会とモンゴル地質学会の交流協定(資料1)の調印式が行われた.宮下会長とOyun会長が協定書にサインして取り交わしたが,テレビ・チームの到着が間に合わなかったので,その後別室で再度協定書にサインするところを撮影し,両会長がインタビューに答えた.宮下会長からOyun会長に交流協定締結記念のプレートが贈られ,Oyun会長から宮下会長に馬頭琴が贈呈された.
14日の午後はモンゴル科学アカデミーの地質鉱物資源研究所を訪問し,D. Tomurhuuさんからモンゴルの地質全般やオフィオライトについての話を伺った.2006年にウランバートルで開催されたIGCP480集会の要旨集・巡検案内書をいただいた.個人的には,この研究所の顧問でアカデミー会員のO. Tomurtogoo氏(オフィオライト研究者)と学会会場で知り合えたことがよかった.
14日の夕刻から市内のレストランでモンゴル地質学会有志7名(すべて女性)による日本人歓迎夕食会が行われた.日本側参加者は宮下純夫・石渡 明・高橋裕平・栗原敏之である.シャブシャブで腹ごしらえをした後,カラオケに繰り込み,深夜まで歌って踊った.S. Jargalanさんは東北大学で博士号をとったそうで,日本語も日本の歌も上手だった.
15日は終日雪で寒かった.午前中まず自然史博物館を訪問した.12日に日本から帰国したモンゴル人がモンゴル初の新型インフルエンザ感染者だったということで,13・14日は博物館が閉鎖されていたが,15日は外国人のみ?に観覧させてくれた.ドアの取っ手にアルコールを染ませたガーゼを巻くなどのインフルエンザ対策がなされていた.そのあと,岡山市の株式会社林原社長,林原 健氏の援助で設けられた古生物研究所を訪問し,N. Ichinnorovさん(女性)の案内で恐竜化石を見学した.
この日の昼に鉱物資源エネルギー省副大臣主催で外国の代表団(といってもロシアと日本のみ)の歓迎昼食会があった.この昼食会については事前に知らされておらず,宮下会長は休養のためホテルに戻っていたので,石渡が代わって祝辞を述べた.この席には巡検や集中講義のためにモンゴルを訪問中の石原舜三氏も出席した.
16日はモンゴル地質調査70周年記念式典が盛大に行われた.まず,外国の代表団(ロシアと日本)が鉱物資源エネルギー省に招かれ,大臣のD. Zorigg氏の名前で記念メダルが授与され,厚い地質家名鑑をいただいた.その後,代表団は鉱物資源庁を訪問し,記念品をいただいた.その後,市内のギャラリーで開催されている「地質絵画展」を見学した.地質調査の様子や特徴的な風景,地質家の肖像などの大きな油絵が多数展示されていた.その後中央広場のチンギスハンの像の前で記念写真の撮影があったが,我々は間に合わなかった.1000人以上集まった模様である.
午後からは中央広場に面する大きな公会堂でモンゴル地質調査70周年祝賀会が1000人程度の規模で行われた.モンゴルの首相や鉱物資源エネルギー大臣の祝辞のあと,宮下会長が英語で祝辞を述べた(資料2)(写真4).これにはモンゴル語の通訳がついた.ロシア人の挨拶はロシア語だったが,モンゴルの大部分の地質屋はロシア語がわかるので,通訳はつかなかった.そのあと,歌や踊りが夕方まで続いた.舞台の前にオーケストラが陣取り,軍服を着た唱歌隊や民族衣装のコサック風の踊り,演歌調の独唱など,圧倒的な音量で盛りだくさんだった.
夕方からは街外れのナイトクラブの体育館のような建物で祝賀晩餐会が催された.これも数100人規模の大晩餐会で,立食ではなく10人ずつが円卓を囲む形式だった.ここで鉱物資源庁の高官からモンゴルの地質写真集をいただいた.この日の大規模なイベントは10年に1度の全国的な地質屋の慰労会という感じだったが,今回が10年前よりも規模が大きいことは,地質関係の重鎮が国会議員の補欠選挙に出ることと関連するかもしれない.
写真3.モンゴル地質学会と日本地質学会の交流協定の調印式場
写真4.モンゴル地質調査70周年記念式典で祝辞を述べる宮下会長(演壇).その左はモンゴル語の通訳.右から2人目はモンゴル地質学会のOyun会長.
そして17日朝6:55ウランバートル発の飛行機で無事に帰国した.この飛行機には朝青龍(ビジネスクラス)と幕下力士(エコノミークラス)が浴衣姿で乗っていた.我々はもちろんエコノミーである.なお,石渡は帰国後にひどい風邪をひいたが,検査の結果新型インフルエンザではなかった.
モンゴル地質学会はまだ定期刊行物を持たず,定期的な学術大会も行っていないが,モンゴル国の産業に占める地質関係者の実力は相当なもので,そのことは鉱物資源エネルギー省や鉱物資源庁が政府の役所として存在すること,地質関係の国会議員がOyunさんを含めて2人いることにも表れている.また,世界最大級の斑岩銅鉱床(Oyu Tolgoi)が発見されて,その開発が軌道に乗り出したことが大きなニュースとなっていた.
日本は1990年代から地質分野でモンゴルに対してこれまでも様々な技術協力や留学生の受け入れを行ってきており,日本で博士号をとった若い研究者は大学に採用されて高い評価を得ている.今回の訪問は,こうしたモンゴルの状況を詳しく知ることができ,また,政府・学術関係の地質関連の多くの方と交流出来たことなど,実り多いものとなった.今回の交流協定締結が今後の両国の地質関係者の更なる交流拡大につながることを期待する.
石渡 明(日本地質学会国際担当理事,東北大学東北アジア研究センター)
資料1.モンゴル地質学会と日本地質学会の交流協定(PDF)
資料2.モンゴル地質調査70周年記念式典における宮下会長の祝辞 (PDF)
日本地質学会第117年学術大会(富山大会)シンポジウム・トピックセッション募集
富山大会ニュースNo. 1
日本地質学会第117年学術大会:
2010年9月18日(土)〜20日(月・祝日)中部支部富山大学にて開催
日本地質学会は,中部支部の支援のもと,富山大学(五福キャンパス)において第117年学術大会(2010年富山大会)を2010年9月18日(土)〜20日(月)の日程で開催致します.
地質学会の学術大会は,研究の発表と議論の場である一方,日本各地の多様な地質について理解を深める絶好の機会でもあります.富山は,水深1,000 mを越える富山湾に面し,背後には標高3,000 m級の北アルプスの山々が聳えていることから,様々な環境とその変動が凝縮した縮図とみられる土地柄です.また,富山を含む中部地方に多産する恐竜化石や北アルプスの飛騨帯の岩石は,アジア大陸の地質を垣間見る窓口となっています.さらに,富山の東に接する新潟県糸魚川市には,日本初の世界ジオパークがあります.富山大会では,これらに関連したシンポジウムやこの地域の特徴的な地質を巡る見学旅行が用意されます.ここ数年来,地質学会では,社会に対する地質学の貢献や重要性をアピールすることも活動の主要な柱としてきました.この方針のもと富山大会においても,「富山の大地をゆるがす地震と恐竜(仮)」と題する市民向けの講演会を企画しています.
2007年札幌大会以来,新たな行事として就職説明会,懇親会後の同窓会が行われるようになりました.また,講演要旨投稿や参加登録の新たなシステムが導入され,クレジットカード払いが可能になりました.このほか,プレスリリースが本格的に行われるなど,多くの試みがなされて来ました.富山大会でもこれらのシステムや行事を定着させ,継続的に行うことができる体制を整えるとともに,企業展示や助成金を充実させて,学術大会をより魅力あるものにしていきたいと考えています.また岡山大会に続き,大会開催に係わる業務をイベント会社の協力のもとに行い,開催地の負担軽減のあり方を探ります.
それでは,多くの地質学会員の皆様が富山大会に参加され,研究発表と議論,会員相互の交流と親睦が活発に展開されることを強く期待します.富山大会の成功による学会活動の活性化と新たな進展に向けて,準備委員会一同,懸命に努力する所存です.皆様の御協力をよろしくお願い致します.
なお,同窓会の開催を希望される各大学地質系教室等の代表者の方は,3月31日までに大藤 茂(shige@sci.u-toyama.ac.jp)にご連絡下さい.大会予告は,ニュース誌5月号を予定しております.
2010年富山大会準備委員会
委員長 竹内 章
事務局長 大藤 茂
シンポジウム・トピックセッション募集のお知らせ
日本地質学会行事委員会
日本地質学会は,中部支部の支援のもと富山大学ほかにおいて第117年学術大会(富山大会)を2010年9月18日(土)〜20日(月)の日程で開催致します.つきましては,トピックセッションとシンポジウムの募集を下記の要領で行います.
トピックセッションは,学会内の領域をカバーしこれから新分野になりそうなトピック的な内容で,定番セッションと同様な形式(15分間の口頭発表あるいはポスター発表)の発表となります.シンポジウムは,多数の学会員が関心を持つ(あるいは持ちそうな)内容・学会外と関係した新分野の内容など,地質学会として重要視すべき研究内容を取り上げます.招待講演の取り扱いは,例年通りです.
募集締切:2010年3月15日(月)
1.大会でのセッションの概要
富山大会でも例年とほぼ同じ規模の会場を確保する予定です.ポスター会場については,近年のポスター発表重視の方向を満たすスペースを確保しています.セッションの区分も例年通り,「定番セッション」と「トピックセッション」を設定します.「定番セッション」は,前回同様の地域,地域間層序,海洋,砕屑物,炭酸塩岩,堆積相,堆積作用,石油・石炭,破壊と変形,付加体,テクトニクス,ノンテク,古生物,噴火と火山,変成岩,岩石鉱物,情報,環境,応用,地学教育,第四紀などのセッションが予想されます.なお「定番セッション」は3月に,各専門部会から選出された委員で構成される行事委員会で確定する予定です.
2.トピックセッションの募集
トピックセッションとして10セッションほどを募集します.多くの参加者が見込まれるような学術的に魅力のあるトピックセッションの企画提案をお待ちしております.例年同様トピックセッションでは非会員の招待講演は半日(3時間)あたり1件まで可能です.会員の招待講演件数には制限はありません.ただし、招待講演の場合もセッションの発表1人1件のルールが適用されますので、ご注意ください.
3.シンポジウムの募集
定番セッションの個別分野を越えた発表と討論の場として,8件程度のシンポジウムを募集します.
また,講演会場確保の関係から,各シンポジウムは原則3時間以内とします.その時間内であれば運営方法(時間の割り当てなど)はコンビーナに一任いたします.会員・非会員にかかわらずコンビーナが依頼した講演者は招待講演とすることができます.セッションとはカテゴリが異なりますので,セッション発表1人1件のルールの適用外であり,シンポジウムの講演者(会員)は,セッションでの発表も可能です.他学会・協会との共催シンポジウム開催も可能です.その場合,事前に他学会・協会との開催打ち合わせ及び承認が必要となりますので,あらかじめ地質学会事務局にご連絡ください.斬新なシンポジウム企画の提案を期待します.
4.応募方法
トピックセッション(10件程度:締切3/15),シンポジウム(8件程度:締切3/15)の企画に応募する方は,以下のような項目内容で,日本地質学会行事委員会宛(main@geosociety.jp)にe-mailでお申し込み下さい.
1) トピックセッション,シンポジウムの区別
2) 提案者名(会員に限る)メールアドレス,電話番号,FAX番号
3) タイトル(和英両方)
4) コンビーナの名前
5) 趣旨・概要,参加予想数など
6) シンポジウムの場合,発表者を一般募集するかどうか,募集する場合は募集件数も明示
7) 招待講演者(非会員)の有無,名前
8) シンポジウムの場合,他学会・協会との共催の有無
9) シンポジウムの場合,その開催時間(原則3時間以内)
10) 開催後の学会誌への特集号計画の有無
11) その他考慮すべき事情(条件:英語使用・・・等)
5.採択方法
トピックセッション,シンポジウムに多数の応募があった場合や定番セッションとの重複がある場合には,行事委員会で重要度や緊急度を考慮して調整の上,決定させて頂きます.採択されたセッション,シンポジウムは,ニュース誌5月号(5月末頃)で公表し,講演募集等を行います.現在のところ講演申込の締切は7月初旬を予定しています.
【招待講演について】シンポジウム,トピックセッションにおいてはコンビーナが招待を依頼することができます.定番セッションでは招待講演の設定はありません.
・シンポジウム:会員,非会員の招待講演が可能
・トピック:会員,非会員の招待講演が可能(非会員の場合は、半日1件まで)
【招待講演者の参加登録費について】非会員の招待講演者に限り参加登録費を免除します(要旨集は付きません.必要な場合は別途購入して下さい).世話人の方は招待講演者へのご連絡等をお願いします.
【シンポジウムの発表者一般募集について】シンポジウムの一般募集に対して発表を申し込む場合,発表希望者はコンビーナに事前に連絡をとって承認を受けてから講演申込システムに入力して下さい.コンビーナへの事前連絡なしに講演申込をした場合,発表できない場合があります.
シンポ・トピック・定番が決まりました
富山大会シンポジウム,トピック/定番セッションが決まりました
今年第117年学術大会(富山大会:9月18日〜20日開催)では下記のシンポジウム・トピックセッション等を予定しております.このほかにも特別講演会や,地質情報展はじめ多数の普及行事も企画・準備中です.募集・予告記事は、次号ニュース誌5月号で掲載予定です.また,講演申込や参加登録は5月頃受付開始予定です.
日本地質学会行事委員会
シンポジウム
タイトル
世話人セワニン/担当タントウ
備考ビコウ
富山深海長谷とその周辺部の堆積作用と後背テクトニクス・気候
中嶋 健・高野 修・金子光好
一般募集なし
海底地盤変動学シンポジウム「魁!海底地盤変動塾」
川村喜一郎・金松敏也・坂口有人・山本由弦
一般募集あり
ガスハイドレートの起源と環境・資源へのインパクトはどこまで明らかになったか? 研究動向と新展開
松本 良・角和善隆・町山栄章・棚橋 学
一般募集あり
韓日地質学会 室戸合同大会(←大会webサイト)
橋本善孝・廣瀬丈洋・江川浩輔
プレシンポとして,8/23-25別途実施ジッシ
南海トラフ沈み込み帯研究の最新成果
橋本善孝・氏家恒太郎
一般募集なし
故藤田和夫追悼シンポジウム,アジアの山地形成論:日本列島からヒマラヤまで
酒井治孝・竹村恵二・竹内章
一般募集なし
故勘米良亀齢追悼シンポジウム,造山帯を読み解く
西弘嗣・磯崎行雄・酒井治孝
一般募集なし
島孤地殻で発生するメルト-流体の挙動 -地震学、高圧実験、岩石からの制約‐
岡本和明・渡辺 了・寺林優
一般募集なし
21世紀モホール:マントル掘削計画現状と今後
阿部なつ江・海野 進・倉本真一
一般募集あり(ポスター)
トピックセッション
地球史とイベント大事件5:宇宙・生命進化・環境変動の謎に迫る
清川 昌一・山口 耕生・小宮剛・尾上哲治
平野地質:堆積と構造
卜部厚志・宮地良典
地学巡検・地学名所とガイドブック
吉田 勝・中井均(日本地質学会地学教育委員会)・天野一男氏(日本地質学会ジオパーク支援委員会)(予定ヨテイ)
河口〜内湾域における歴史時代の汎世界的な環境変動と人為的環境変化
野村律夫・秋元和實・瀬戸浩二
ジュラ系+ (読み方:ジュラケイプラス)
松岡 篤・堀 利栄・小松俊文・近藤康生・石田直人・柿崎喜宏
アジア大陸タイリクの地質チシツ
大オオツ藤フジ 茂シゲル
定番テイバンセッション
地域地質・地域層序
地域チイキ地質チシツ部会ブカイ・層序ソウジョブカ部会ブカイ
地域間層序対比と年代層序スケール
層序ソウジョブカ部会ブカイ
海洋地質
海洋地質部会カイヨウチシツブカイ
砕屑物組成・組織と続成作用
堆積地質部会タイセキチシツブカイ
炭酸塩岩の起源と地球環境
堆積地質部会タイセキチシツブカイ
堆積相・堆積過程
堆積地質部会・現行地質過程部会
昨年サクネンまでの「堆積相および堆積システム・シーケンス」と「堆積作用・堆積過程」を統合
石油・石炭地質学と有機地球化学カガク
石油セキユ・石炭関係セキタンカンケイ・堆積地質部会タイセキチシ
岩石・鉱物の破壊と変形
構造地質コウゾウチシツブカ部会ブカイ
付加体
構造地質コウゾウチシツブカ部会ブカイ
テクトニクス
構造地質コウゾウチシツブカ部会ブカイ
古コ生物セイブツ
古生物コセイブツ
噴火と火山発達史
火山部会カザンブカイ
深成岩・火山岩とマグマプロセス
火山部会カザンブカイ・岩石部会ガンセキブカイ
変成岩とテクトニクス
岩石部会ガンセキブ
岩石・鉱物・鉱床学一般
岩石部会ガンセキン
情報地質
情報ジョウホウ地質チシツ部会ブカイ
ポスター発表のみ
環境地質
環境地質部会カンキョウチシツブカイ
応用地質学一般およびノンテクトニック構造
応用地質部会
昨年サクネンまでの「ノンテクトニック構造」と「応用地質学一般」統合トウゴウ
地学教育・地学史
地学チガク教育キョウイク委員会イインカイ
第四紀地質
第四紀ダイヨンキ地質部会チシツブカイ
講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理,引用方法,校閲
講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理,引用方法,校閲について
(1)講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理
2003年1月から日本地質学会の出版物への投稿原稿に対して,その倫理性について著作者に保証して頂くために「保証書」に,また著作権を日本地質学会に 譲渡することを同意する「著作権譲渡同意書」に,それぞれ署名捺印をして提出していただいています.本大会でも,電子投稿のため,画面上で「保証 書」と「著作権譲渡等同意書」に同意していただいた場合に限り,電子投稿の画面に進むことができるようになっています.郵送の場合は,保証書及び同意書に署名捺印をして,講演要旨と共にお送り下さい.「保証及び著作権譲渡等同意書」が同封されていない講演申込は受け付けられません.
(2)講演要旨における文献等引用方法
要旨においては引用文献の記載方法は簡略化することが慣習として認められていますが,著者名,発表年,掲載誌名などを明記し,引用文献が特定できるようにして下さい.
(3)講演要旨の校閲
行事委員会は,申し込まれた講演について,定款第4条に示されている日本地質学会の目的ならびに日本地質学会倫理綱領に反していないかということについて のみ校閲を行います.校閲の結果,いずれかの条項に反していると判断された場合には,行事委員会は講演内容の修正を求めるか,あるいは講演申込を受理しな いことがあります.行事委員会の措置に同意できない場合には,当該講演申込者は法務委員会(東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル 日本地質学会事務 局気付)に異議を申し立てることができます.法務委員会は直ちに審理し,結論を行事委員会ならびに異議申立者に伝えることになります.
この受理方法は,招待講演者にも適用されます.
講演申し込み異議申し立てについて
日本地質学会行事委員会は,学術大会において学会の目的及び倫理規定に反する講演申し込みのあった要旨に対して,修正あるいは,受理を拒否することができます.法務委員会では,日本地質学会行事委員会規約に基づき,異議申立の手続及びその処理についての規則を定めています.
日本地質学会法務委員会
■日本地質学会学術大会講演申込異議申立に関する処理機構規則(PDF)■
講演要旨の作成の注意点とPDFファイルの作り方
講演要旨の作成の注意点とPDFファイルの作り方
講演要旨を作成する際,著者には「保証及び著作権譲渡同意書」第1 項の「保証」内容を守って頂きます.行事委員会は,要旨の内容については関知しませんが,当該「保証」内容を逸脱するものがないか校閲します.その結果,不適当とみなされる場合は,修正されるまで講演要旨の受理はされません(不服の場合は法務委員会に訴えることが可能です).
例年最も多い問題点は,引用文献の表示がない場合です.論文のように細かに引用文献を記載することはスペースの都合上不可能なので必要としませんが,雑誌名,号,ページ等,その文献にたどり着ける最低限の情報は記載して下さい.
また,要旨の体裁を無視している場合,印刷できませんので体裁を整えて頂くことになります.さらに図等の改変については,著作権法,地質学会著作物利用規定に従って下さい.
このほか,PDFファイルにフォントを埋め込んでいないもの(印刷時に文字化けすることがあります),要旨作成時に講演番号記入用のスペースがなかったり,余白に無理があるといった場合,体裁を整えるため修正をお願いしています.これらの問題点があった場合,各コンビーナから投稿締切日から1週間をめどに修正依頼が届きます.ただ,その労力はセッションによっては膨大になりますので,あらかじめ著者で完全なものを投稿するようご協力下さい.あわせて講演要旨投稿手順のチェックシートもご参照下さい.
日本地質学会行事委員会
2010年4月
■要旨テンプレート(Microsoft Word)■ ■講演要旨投稿手順のチェックシート■
【講演要旨PDFファイル作成時の注意点】
1)
講演要旨原稿はAdobe Acrobat Reader 4.0 以上で表示・印刷可能なPDFファイルで投稿することが必要です.
2)
ファイルサイズは3.0Mバイト以内で作成して下さい.
3)
発表(講演)番号は事務局にて左上に付記するので原稿内には記載しないで下さい.
4)
PDFファイルのセキュリティ設定は「なし」にして下さい.
5)
フォントは必ず「埋め込み」にして下さい.MacOSX以上は標準でフォント埋め込みが用意 されます.MacOS9.2.2以下,Windowsでは下記のソフトが必要です.その際,『すべてのフォント埋め込み』ないし『ハイクォリティー』等, それぞれのソフトの使用説明書に従った指定を必ずして下さい.文字数にもよりますが,できたPDFファイルのサイズが100KB未満の場合,フォントが埋 め込まれなかった可能性がありますので確認して下さい.
6)
作成したPDFファイルを自分で印刷し,図表に充分な解像度があるか,文字化けはないか確認して下さい.
7)
PDFファイルを自分のパソコンに,必ず「.pdf」の拡張子をつけて保存して下さい(Mac, Windowsとも).
■原稿フォーマット見本■
テンプレート
(Microsoft Word)
ダウンロードはこちら
【WEBでの講演要旨投稿の手順】
1)
WEBで講演申込をします:WEB上の講演申し込みページにアクセスし,画面に従って連絡者情報等を入力し,講演申し込みの手続きをします(講演申込と同時に要旨投稿をすることもできますし,講演要旨のみ後で投稿する事もできます).
2)
講演要旨PDF を投稿します:演題・発表者情報登録画面の最下段にある「アップロードファイル」欄から要旨原稿(PDFファイル)を投稿します.欄右側の「参照」ボタンをクリックし,ご自分のPCに保存してあるPDFファイルを選択します.
3)
登録内容を確認:画面下の「次へ」をクリックし,登録内容確認画面に進みます.登録内容を確認後,画面下の「登録」ボタンをクリックします.これによりサーバーにPDFファイルが格納されます.
4)
完了画面を確認して下さい:『登録が完了いたしました.受付番号は***** です.』という完了画面が表示されます.(注意!!この画面が表示されないと登録は完了していません)
5)
確認メールが届きます:登録したメールアドレスに「講演申込のお知らせ」のメールとともに受付番号(=ID)が配信されます.
重要 講演申込をされる方は別途忘れずに,事前参加登録の画面操作も行ってください!!
【後から要旨を投稿する場合・申込内容を変更する場合】
1)
IDとメールアドレスでログイン:ご自分の申込画面に,IDとメールアドレスを用いてアクセスします.
2)
新しい講演要旨PDFをアップロード:「登録内容変更」ボタンをクリックし,画面の最下段にある「アップロードファイル」欄の「修正」ボタンをクリックします.ご自分のPCに保存してあるファイルを選択し,アップロードをします.サーバー側では,ファイル名を元のファイル名から変更し,ID.pdfの名称で格納します.
3)
完了画面の確認:『登録が変更されました.受付番号は***** です.』という操作完了画面が表示されます.(注意!!この画面が表示されないと操作は完了していません)
4)
変更確認メ−ルが届きます:「講演申込内容変更のお知らせ」メールが配信されます.
5)
IDとメールアドレスを用いて,投稿締切まで何度でも要旨や登録内容を修正することができます.新しいファイルを投稿すると,古いファイルに上書きされます.そのつど,「講演申込内容変更のお知らせ」メールが配信されます
【参考情報:PDF(Portable Document Format)ファイルの作り方】
PDFファイルの作成方法は「PDF原稿作成ガイド」http://www.gakkai-web.net/pdf/を参考にすると良いでしょう.
ソフトの紹介要望が多いので,下記にいくつか参考例を挙げます.また,"PDF作成サービス"を行う有料,無料のサイトがあります.ソフト,サイトとも検索してみて下さい.なお下記について動作確認等しておりません.また推奨するものでもありません.ご了承ください.
◯ Mac OSXの場合
フォント埋め込み型のPDF作成機能が標準で用意されています.新たなソフトは必要ありません.
◯ Mac OS 8.6-9.2の場合
Adobe Acrobat(それぞれのOS対応品,現在販売されているか不明)
EGWORD Ver.12 for Mac OS X/9/8.6(現在販売されているか不明)
◯ Windows対応品
PrimoPDF FreeのPDF変換ソフト http://www.primopdf.com/
クセロPDF FreeのPDF変換ソフト http://xelo.jp/xelopdf/(有料ソフトあり)
いきなりPDF 2000円弱 http://www.sourcenext.com/products/pdf/
Adobe Acrobat Elements 5000円弱 http://www.adobe.co.jp/
◯ MacOS9.2.2,MacOSX, Windows対応
Adobe Illustrator http://www.adobe.co.jp/
講演要旨オンライン投稿手順チェックシート
講演要旨オンライン投稿手順チェックシート
講演要旨の投稿手順および基本的注意事項です.投稿していただく前に各自でご確認下さい.
1.Word等のソフトで講演要旨原稿を作成します.
「保証及び著作権譲渡同意書」第1項の「保証」内容は守られていますか?
引用文献は表示されていますか?
要旨の体裁は守られていますか?(詳細は要旨原稿フォーマットをご確認下さい)
2.原稿をPDFファイルにします.
PDFファイルの作成方法については,本号の「PDFファイルの作り方」を参照して下さい.
フォントは「埋め込み」になっていますか?(できたファイルサイズが100KB未満の場合,フォントが埋め込まれなかった可能性がありますので確認して下さい)
ファイルサイズは3.0MB以内になっていますか?
作成したPDFファイルを印刷し,図表に充分な解像度があるか,文字化けはないか確認して下さい.また,PDFファイルを自分のパソコンに,必ず.pdfの拡張子をつけて保存して下さい.
3.原稿をオンライン投稿します.
web画面から参加申し込みを行いましたか?
講演申し込みページで,講演申し込みの手続きをしましたか?
講演要旨を投稿しましたか?
申込完了画面が表示されましたか(ログイン用のIDが表示されましたか)?
「講演申込のお知らせ」のメールが配信されましたか?
4.一度投稿した原稿を修正したい場合
ご自分の申込画面に,IDと申込時に設定したパスワードを用いてアクセスします.
画面中のPDFファイルのアイコンをクリックし,要旨原稿投稿画面を開きます.書き直した要旨のファイル選択し,投稿動作をします.
修正原稿が受け付けられると,「申込内容変更のお知らせ」メールが配信されます.(締切まで何度でも修正できます).
←講演要旨作成手順のページに戻る
2010年富山大会:モンゴル地質学会より来賓(2010.9.19)
2010富山大会:モンゴル地質学会より来賓
第117年学術大会(2010富山大会)表彰式・記念講演おいて、昨年より学術交流協定を結んでいるモンゴル地質学会より, Ochir Gerel理事(モンゴル地質学会国際関係・高等教育担当理事,IUGS副会長)をお迎えし,ご挨拶を頂いた.
会場にてご挨拶を頂くDr. Ochir Gerel
来賓からのメッセージ:Message to Geological Society of Japan
It was a special honor to visit the Annual Meeting of the Geological Society of Japan (JGS) representing the IUGS and the Mongolian Geological Society. Last year the Agreement between two Societies signed, and it was the first visit of the MGS representative. JGS is a very old member of the IUGS, jointing a great number of Japanese geologists, and has pride in its achievement and contribution to the development of the international geological community.
My visit was extremely important for the future development of the MGS. This has provided me with a chance to learn first-hand about many of the important activities in which JGS is involved. Thanks to the work of all committees under the council leadership and outstanding staff the JGS is in very good shape. I learned a lot, and I and the MGS will share the knowledge and experience of JGS, and our cooperation will extend.
The Annual Meeting I attended offers an opportunity for participants to share their researches in the form of oral talk and posters, and also includes discussion on many topics. I am very glad that many topics and interesting results related to Mongolian Geology presented and discussed, and our young researchers studying Master and PhD courses in Japan attended this meeting.
MGS is planning to continue our cooperation with the JGS in many research topics, and large world programs like Geopark, YES to extend and improve scientific training, to establish important contacts to facilitate scientific exchange and collaboration.
Ochir Gerel,
Executive Committee of the Mongolian Geological Society
国際交流TOP
国際交流
学術交流協定締結学協会
■ The Geology Society of Mongolian
■ The Geological Society of Thailand
■ The Geological Society, London
■ Geological Society Located in Taipei
2022年
韓国IGC2024へのサポートレター撤回について(2022.10.27掲載)
2019年
タイ地質学会訪問(学術交流協定更新)(2019.3)
2018年
第125 年学術大会(札幌大会)における国際交流について(2018.9)
2017年
大韓地質学会創立70 周年記念国際シンポジウム参加報告(2017.10.25)
2016年
第123年学術大会(桜上水大会)における国際交流活動報告(2016.9.10-12)
2015年
2015 Fall Joint Conference of Geological Science of Korea参加報告(2015.10.28−31)
津波シンポジウム:The Geological Society of London(GSL)・日本地質学会 共催 Arthur Holmes Meeting Tsunami Hazards and Risks: Using the Geological Record(2015.9.25)
第122年学術大会(長野大会)における国際交流活動報告(2015.9.11-13)
2014年
鹿児島学術大会での国際交流(2014.9)
2013年
日本−ロンドン地質学会学術交流協定(2013.8.8)
日本−タイ地質学会学術交流協定更新(2013.3.4)
2012年
日韓地質学会学術交流協定調印(2012.9.15)
2010年
2010年富山大会:モンゴル地質学会より来賓(2010.9.19)
韓日地質学会ー室戸合同大会(2010.8.23-25)*構造地質部会のサイトへ
2009年
モンゴル地質学会との交流協定締結(2009.10.14-16)
2008年
日韓地質学会学術交流協定調印記念式典(2008.9.20)
ロンドン地質学会会長との懇談(2008.3.19)
2007年
日韓地質学会学術交流協定調印式レポート(2007.10.25)
Anayaタイ地質学会会長との懇談(2007.8.14)
韓国IGC2024へのサポートレター撤回について(2022.9.16)
韓国IGC2024へのサポートレター撤回について
日本地質学会執行理事会
日本地質学会は,大韓地質学会からの要請に基づき,2024年に韓国釜山で開催予定の万国地質学会議(IGC)2024をサポートする旨を2016年に大韓地質学会宛にサポートレターを送付し表明していましたが,このたび諸問題によりこのサポートレターを撤回するに至りました.サポートレターの撤回については2022年9月16日付けでIGC2024の現地組織委員会(LOC)に通知しております.
以下に,日本地質学会が韓国IGC2024開催に対するサポートの表明と撤回の経緯を説明いたします. また本件に関し,会長より会員の皆様に重要なメッセージがあります.会員ページをご覧いただけますようお願いいたします.
「日本地質学会 会員の皆様へ」会長メッセージはこちら(要会員ログイン→「会員へのお知らせ」をクリック→“IGC2024サポートレター撤回について:会長メッセージ(2022.10.26)”)
● 2015年,韓国の地質コミュニティーによる2024年のIGC開催地立候補に際し,大韓地質学会から日本地質学会に対して,日本国内での巡検実施などに対する協力要請がありました.日本地質学会は,韓国の地質学/地球科学コミュニティーと共に発展することを願い,大韓地質学会からの依頼に基づき,巡検の協力も含め全力でサポートする旨を表明したサポートレターを2016年4月1日付け会長名で大韓地質学会宛に送付しました.また,当時の学会長の個人的なサポートメッセージも4月23日付けで大韓地質学会宛に送付されました.同時に,韓国の開催地申請への協力案として,日本国内で潜在的に実施可能と考えられた10コースの巡検案を提示しました.
● 2016年にIGC2024の韓国開催が決定されました.その後,韓国LOCによる開催準備が開始されたものと推察されます.しかし,2016年から2021年までの約5年間,韓国LOCから日本地質学会に対して,巡検計画を含むIGC関係の情報提供や相談は一切なされませんでした.そして,2021年に韓国LOCはウェブページにおいて,突然IGC2024計画案を示しました.その中には,領有権を巡って日韓両国間で政治的に対立している竹島での巡検企画が含まれていました.また,2016年に日本側が提示した巡検案(上述)の一部の用語,具体的には[Japan Sea]という単語が[East Sea (Japan Sea)]と,日本側に無断で書き換えられていました.さらに,その他の箇所にも[East Sea]の表記が使われていました.この海域は,世界標準である国際水路機関によるガイドラインでは[Japan Sea]が唯一の名称とされていますが,現在,両国政府間の外交問題となっていることは会員の皆様もご承知のことと思います.この時点で日本地質学会は,IGC2024が韓国の政治的主張を展開するために利用されることに危惧を覚え,日本からの協力や参加が困難である状況を認識しました.
● 2021年8月末以降,こうした国際的に問題のある状況を改善し,日韓両国の良好な協力体制の基にIGC2024が開催できるよう,日本地質学会は韓国LOCに対して協議・調整を提案し,双方の合意が得られるまでの間,ウェブサイト上での巡検表示をしないことを求めました.そして,両者間の第一回目のリモート会議が2021年9月27日に開催されましたが,LOC側の反応は鈍く,具体的な議論の進展がないまま半年が経過しました.この時期以降,日本地質学会は日本学術会議メンバーと共にこの問題について議論を重ねてまいりました.その結果,この問題については日韓の当事者間だけではなく第三者の意見が必要と判断しました.2022年3月16〜18日に開かれたIUGS(国際地質科学連合)理事会に日本の委員(学術会議地球科学部門の対応委員)がリモート参加し,IUGSの参加委員全員に対してIGC2024開催案に内在する問題点(竹島巡検の計画と日本海の呼称)を説明し,IGCプログラムは国際的な合意のもと,国際的な政治的不一致を含まないことが重要であると主張しました.この理事会ではIUGS執行部から両国の関係者間できちんと協議するようにとの指示を受けました.
これを契機に,韓国LOCと日本地質学会を含む日本側関係者との間の協議が活発化し,2022年3月22日,5月12日,6月21日および7月29日に計4回のリモート会議を行いました.2022年6月21日のリモート会議において,韓国LOCは「竹島巡検の撤回」を表明し,次回のLOC会議で正式決定すると伝えてきました.そして7月29日のリモート会議において,韓国LOCは「竹島巡検の撤回」および「日本海の呼称については両論併記」を表明しました.一方,日本側からは,日本海の呼称問題解決の打開案として,近年,国際的に採用されつつある「名称自体を使わず,国際海洋コードを使用する方法」を提案しました.本提案に対し,韓国LOC側は翌週には回答したいとのことでした.
● その後1週間経過しても韓国LOC側からの回答はなく,日本側から数回にわたり回答要請のメールを送付しました.無回答状態が一ヶ月以上続きましたが,2022年9月9日に韓国LOCから日本地質学会長(ただし14年前の会長名)宛の回答が来ました.そこには,竹島巡検は中止ではなく中止を「検討中」であること(中止検討理由は時期的に天候が不安定であるため),およびIGC2024における日本海の正式表記をEast Sea/Japan SeaとすることがLOCの最終決定として記されていました.この間,LOCはウェブサイトでの表示を一切変更しませんでした(現在は、ウェブサイト上での巡検表示はされていません;2022/11/24現在).
● 日本地質学会および関係者はこの回答に大変失望しました.1年間の長い交渉を行ってきたにもかかわらず,韓国LOCは頑なに自らの主張をするのみでした.韓国LOCの最終決定に鑑み,日本地質学会は,2016年4月1日送付のサポートレターおよび2016年4月23日送付の当時の学会長によるサポートメッセージを撤回せざるをえないという結論に至りました.
日本地質学会としては,今回の件を極めて遺憾であると判断しています.韓国地質コミュニティーが今後,国際協調を踏まえたより健全な方策を模索し,IGC2024を成功に導くことを願います.
【参考1】 2016年4月1日付 大韓地質学会宛サポートレター(下記)
April 1, 2016
Dear Dr. Daekyo Cheong and Dr. Kyu-Han Kim:
I was delighted to hear about your proposal to bring the 37th International Geological Congress (37th IGC) to Busan, Korea. I am sure Korea would be an excellent location for this meeting. and I am pleased to offer my full-hearted support to GSK and KIGAM for their proposal. I think the following points make this a timely and well-considered proposal.
Korea is ideally situated to act as a hub and bring together the rapidly growing body of young, active geoscientists from throughout the Asian region.
The two proposed host institutions, the Geological Society of Korea (GSK) and Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM) , have played leading roles in promoting geological research and understanding of geosciences and both have excellent track records in organizing international conferences.
Korea has outstanding venues for hosting large international meeting. I have personally enjoyed attending the successful GSK annual meeting in Pusan in 2015.
There are many links between geoscientists in Korea and Japan both on a personal level and through their affiliated organizations. In particular, I would like to mention the Memorandum of Understanding between the Geological Societies of Korea and Japan signed in 2007. Regular meetings between the leaders of both organizations have helped develop excellent relations between our two Societies and the 37th IGC would be an ideal opportunity for further development. In particular, the Geological Society of Japan would be able to help with the conference-related field trips that would include visits to classic locations in Japan.
Sincerely yours,
Yasufumi IRYU
President of the Geological Society of Japan,
Professor of Geology at Tohoku University
【参考2】2022年9月16日付 IGC2024 LOC宛サポートレター撤回の文書
(2022.10.27掲載)
第6回ショートコース
日本地質学会第6回ショートコース
申込締切
2022年12月8日(木)
2022年12月12日(月)12:00まで締切延長します
締切ました
申込方法
ジオストアにて受講申込受付中
(コチラから)
第6回ショートコース 日程:2022年12月18日(日)
[訂正]News11月号掲載記事の曜日記載に誤りがあります.(誤)12月18日(土)(正)12月18日(日)
後援:日本地球掘削科学コンソーシアム(J-DESC)
2020年・2021年に計5回開催し,好評を博したショートコースを再開します.
第6回の前半は法地質学、後半は付加体地質学・沈み込み帯掘削に関する最新の知見を学ぶ機会を提供します.広く一般の方や,学校教員,地質調査業従事者,中堅・ベテラン研究者に受講していただきたいコースです.学生・若手研究者の皆様もぜひご参加ください.講師は,午前が我が国における法地質学の第一人者である杉田律子氏(日本地質学会副会長),午後が沈み込み帯の陸上・海洋研究に詳しい山口飛鳥氏です.
内容:(各コース,講義・質疑応答含め3時間を予定)
<午前> 9:30-12:30
法地質学の現在:杉田律子(科学警察研究所)
法地質学は地質学の知識や技術を事件や事故の解決のために利用する,地質学の一分野です.ドラマや小説で犯罪現場や衣服に残された土などが証拠資料として扱われるシーンがあり,何となくイメージを持っている方も多いと思います.しかし,日本国内では法地質学を学ぶことができる機会はほとんどありません.このショートコースでは,2020年に発行された地質学雑誌の特集号(第126巻8号)の一部をテキストとして使用し,法地質学の概要と研究,事例報告などとともに,さらに興味のある方たちのために文献の紹介もする予定です.
<午後> 14:00-17:00
付加体地質学と沈み込み帯掘削の現在:山口飛鳥(東京大学大気海洋研究所)
日本列島の基盤をなす付加体の年代や大構造は,1980年代の「放散虫革命」を経て,現在までにその大枠が明かされてきました.付加体には,古海洋の情報とともにプレート境界の変形や物質移動の情報が記録されています.付加体から沈み込みプレート境界で起こる現象を読み解く研究は,掘削船を用いた海溝域の研究と相まって発展してきました.このショートコースでは,主に2000年以後の付加体地質学と,南海トラフ・日本海溝に代表される沈み込み帯掘削の成果,および今後の展望について,構造地質学・岩石力学や地球物理学的観測の知見もとりまぜつつ紹介します.
受講料(各1日券):
地質学会会員 2,000円(日本地質学会賛助会員に所属する⽅は地質学会会員と同額です)
⾮会員 5,000円
(注)⾮会員の学部⽣・院⽣は「地質学会会員」料⾦に含まれます.「⾮会員」とは学部⽣・院⽣ではない⾮会員とします.
(注)午前のみ,午後のみの受講の場合も,受講料の割引はありません.
(注)キャンセル料について:締切日まで 0%, 会期3日前まで 60%, 会期2日前以降 100% いずれの場合も返金がある場合は,振込手数料を差し引いた額をカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2〜3ヶ月要する場合もありますので,ご了承下さい.
開催方法:WEB会議システムzoom(https://zoom.us/)によるオンライン講義
※受講申込締切後,受講者が確定しましたらzoomアクセスURL,事前資料をメールでお送りします.
定員:各コース100名(定員は事務局および講師を含み,定員を超えた場合は,会員が優先となります)
申込方法:ジオストアからの申込
※受講料のお支払いは,受講申込時にPayPal〈ペイパル〉によるクレジット決済または銀行振込を
選択いただけます.
(注)申込時にご提供いただいた個人情報は,日本地質学会プライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います.
その他:希望者には各コース毎のCPD受講証明書を発行します.午前・午後各3単位を予定.(CPDプログラムID:3405)
※CPD受講証明書の発行については,受講日当日に受講者のかたへ別途ご案内いたします.
申込締切:2022年12月8日(木)2022年12月12日(月)12:00まで締切延長します
問い合わせ先:一般社団法人日本地質学会
メール: main [at] geosociety.jp 電話 03-5823-1150
(参考)過去のショートコース
(第1回,第2回)http://www.geosociety.jp/science/content0121.html
(第3回)http://www.geosociety.jp/science/content0130.html
(第4回)http://www.geosociety.jp/science/content0134.html
(第5回)http://www.geosociety.jp/science/content0137.html
第3回JABEEシンポジウム
第3回JABEEシンポジウム
一般社団法人日本地質学会 第3回JABEEシンポジウム
『大学ー企業の架け橋教育 ユニークな実例紹介』
シンポジウムの様子はYouTubeで公開しています
YouTube概要欄のタイムテーブルをご利用いただくと,視聴したい箇所がすぐにご覧いただけます.詳しくはこちら
申込時ご希望のあった方に対して,CPD参加証明書を発行しました(PDFメール添付:3/10送信).証明書は,当日の参加確認と充分な受講時間数が確認された場合に発行しています.ご不明点がありましたら学会事務局までお問い合わせ下さい.
当日参加の方でCPD参加証明が必要な方は,別途事務局までご連絡ください.
開催日時:2023年3月5日(日)13:30〜18:00(予定)
開催方法:Zoomによるオンライン方式
参加費:会員、非会員問わず無料。
事前申込制・受付期間:1月30日(月)〜2月28日まで(火)
申込方法:こちらの専用申し込みフォームからお申し込みください
定員:先着150名
その他:希望者には受講時間に応じたCPD参加証明書を発行いたします.最大4.5単位を予定.(CPDプログラムID:3467)
開催趣旨:
当学会地質技術者教育委員会では,大学教育における技術者教育について、JABEE教育の有効性と実態を広く知ってもらうために2020年度に第1回、2021年度に第2回のオンラインシンポジウムをそれぞれ開催した。幸い多くの方の参加を得て、大学における技術者教育の重要性を広く知ってもらうことができた。
第3回は大学から企業への技術者の継続教育に焦点をあてたシンポジウムとし、技術者教育における大学の役割や取り組み、実社会での技術者教育のあり方などについて議論することを目的としている。JABEEプログラムを有する3大学からの実態・課題の報告を受けた後、実社会での専門教育の例として先端地質科学大学院大学(専門職)構想や掘削技術専門学校での技術者教育計画や実態について紹介していただく。また、大学や学会に求められる実社会での技術者教育のあり方についても紹介していただく。
これらの講演をもとに、社会から求められる大学教育について地質技術者教育の観点から議論し、新しい大学のあり方について考える機会としたい。
当日の次第(案) ※時間配分や演題は変更となることがります。
▶︎講演要旨はこちら 2023.1.26掲載
13:30〜13:35 開会挨拶
13:35〜13:40 趣旨説明
13:40〜14:10 講演1「地質技術者教育に向けた教育DX 島根大学の例」亀井淳志(島根大学総合理工学部地球科学科 教授)
14:10〜14:40 講演2「外部専門技術者(非常勤講師)による技術者教育−日本大学地球科学科の例−」竹内真司(日本大学文理学部地球科学科 教授)
14:40〜15:10 講演3「学生を送り出し,技術者継続教育も行う−地域の大学のあり方−」 坂口有人(山口大学理学部地球圏システム科学科 教授)
15:10〜15:20 休憩
15:20〜15:50 講演4「先端地質科学大学院大学(専門職)構想 −正確な年代測定技術および高度な地質調査技術をあわせもつ専門技術者の育成−」板谷徹丸(特定非営利活動法人地球年代学ネットワーク理事長)
15:50〜16:20 講演5「掘削技術専門学校の概要 −掘削技術者の育成を目指して−」島田邦明(学校法人ジオパワー学園掘削技術専門学校教務部長)
16:20〜16:50 講演6「実社会における技術者教育 −大学や学会に求める教育内容−」稲垣秀輝(株式会社環境地質 代表取締役会長)
16:50〜17:00 休憩
17:00〜17:50 総合討論
17:50〜18:00 閉会挨拶
これまでの開催履歴:
第1回JABEEオンラインシンポジウム『自然災害列島における地質技術者の育成−大学統合期における地質学教育−』 2020年3月7日(日)開催 ※シンポジウムの状況はYouTubeで公開中 https://www.youtube.com/watch?v=7hpNtONfNt0
第2回JABEEオンラインシンポジウム『昔と違う イマドキのフィールド教育』 2022年3月6日(日)開催 ※シンポジウムの状況はYouTubeで公開中 https://www.youtube.com/watch?v=hl-2sYxYiOM&t=8s
2023若手巡検・研究集会 in 北海道 洞爺湖有珠山ジオパーク地域
若手巡検・研究集会 in 北海道 洞爺湖有珠山ジオパーク地域
若手巡検・研究集会 in 北海道 洞爺湖有珠山ジオパーク地域
申込方法 学会公式オンラインストア「ジオストア」よりお申し込みください.(こちらから)
申込締切 2023年5月31日(水) 17時 受付終了しました
***************************************
主催:一般社団法人日本地質学会
運営:若手活動運営委員会
協力:洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会・洞爺湖有珠火山マイスターネットワーク
講師:横山光 教授 (北翔大学)
世話人:佐々木聡史(名古屋大学)
日時:2023年7月8日(土) 13時集合 7月9日(日) 18時解散
対象者:35歳未満の日本地質学会正会員
参加費:
正会員(学生会員):8,000円
正会員(一般会員):16,000円
※申込日までに入会された方を含みます。
※参加費の内訳はバス代・宿泊費・保険代となります.
※上記の他に食事代(1日目夕食,2日目朝,昼食)を現地で徴収します.食事代は参加者が決まり次第ご連絡いたします。(1食あたり500~1000円を想定)
※新千歳空港までの旅費は自己負担となります
※正会員(学生会員)の参加費は,日本地質学会若手育成事業より半額が補助されています.
巡検コース:
1日目:13:00 新千歳空港集合→洞爺湖ビジターセンター・火山科学館→西山山麓火口散策路→18:00宿(宿泊+研究集会)
2日目:8:00→三松正夫記念館→昭和新山(登頂)→三階滝→17:30新千歳空港解散
※通常では行けない制限区域(西山山麓火口散策路・昭和新山)を歩きます!
※雨天時 (2日目):8:00→入江・高砂貝塚館→有珠山ロープウェイ→三松正夫記念館→三階滝→17:30新千歳空港解散
主な見学対象:
[1] 洞爺湖ビジターセンター・火山科学館:2000年噴火の記録映像や洞爺湖有珠山地域の自然について学ぶ(洞爺湖有珠山地域の地形・災害遺構)
[2] 西山散策路:2000年噴火によって隆起や噴石によって変形した国道の観察(断層・噴石・災害遺構)
[3] 三松正夫記念館:1943年〜1945年の火山活動の定点観測や有感地震を行った三松正夫さんについての学ぶ(ミマツダイヤグラム)
[4] 昭和新山:1944-1945年にかけて形成した昭和新山の登山と地熱体験(隆起・地熱)
[5] 三階滝:洞爺湖有珠山地域で最も古い地層(約2700万年)の観察(花崗閃緑岩)
[6]入江・高砂貝塚館 ※雨天時:縄文時代の集落遺跡の見学.2021年に世界文化遺産に登録された(土器・貝塚).
[7]有珠山山頂火口 ※雨天時:隆起して形成した昭和新山や洞爺湖のカルデラ地形の観察(カルデラ・火山地形)
研究集会
基調講演「洞爺湖有珠山地域周辺の火山地質学(仮)」横山光教授(北翔大学)
研究発表(希望者によるポスター発表)
※研究発表を通して参加者同士の交流を深めましょう。多くの発表をお待ちしております!
集合場所 新千歳空港国内線1F (第5手荷物受取所 貸切バス待合所 新千歳空港クリニック内科側)
宿泊施設 壮瞥町農村環境改善センター(〒北海道有珠郡壮瞥町滝之町294-2 ☎0142-66-2201)
申込方法 地質学会公式オンラインストア「ジオストア」よりお申し込みください.
申込締切 2023年5月31日(水) 17時
※最少催行人数28名・定員40名
※先着順とし,定員になり次第,締め切ります
※巡検の開催決定の連絡は6月上旬までにご連絡します
※必要物・日程は参加者が決定次第お送りいたします
※制限地域を歩く際はヘルメットを着用など,安全対策にご協力をお願いいたします.
※集合場所までの往復飛行機・公共交通機関につきましては自己責任でよろしくお願いいたします.(時間に余裕のある便でご参集ください)
※キャンセルの際は速やかにご連絡をお願いいたします.(キャンセル料:20日前〜8日前(6/18〜30):20%、7日前〜前日(7/1〜7):50%、当日:100%)
問い合わせ先: 日本地質学会 若手活動運営委員会
メール(ecg.core(at)mail.com)※(at) を@に変換してください.
第7回ショートコース
日本地質学会第7回ショートコース
申込締切
定員に達しましたので,申込受付を終了いたしました(3/16).
お申し込みをいただき,ありがとうございました.
多数の受講希望が寄せられていますので,
ご要望にお応えするため,同一内容での再度開催を検討します.
申込締切:2023年3月23日(木)
※実習対応可能な人数の関係から,
参加者多数の場合には先着順とさせていただきますのでお早めにお申し込みください.
申込方法
学会ジオストアよりお申し込みください
第7回ショートコース 日程:2023年4月2日(日)
今回は応力逆解析法について実習を通じて学ぶ機会を提供します.応力逆解析法は,現在または地質学的過去の,テクトニクスの原動力を解明する方法の1つです.「逆」解析と呼ばれるのは,変形の結果として生じた地質構造から,変形の原因である応力を推定するからです.今回も多くの学生・若手研究者の皆様に受講していただきたいコースです.中堅・ベテラン研究者や学校教員,地質調査業従事者,広く一般の方も,ぜひふるってご参加ください.講師は,午前が応力逆解析法の理論に詳しい佐藤活志氏,午後が応力逆解析の露頭への適用を多く実践されている大坪 誠氏です.なお,本ショートコースではPCによる実習を含みます.本ショートコース午後の実習にはWindows OSをインストールしたPCが必要です.実習対応可能な人数の関係から,参加者多数の場合には先着順とさせていただきますのでお早めにお申し込みください.
内容:(各コース,講義・質疑応答含め3時間を予定)
<午前> 9:00-12:00
小断層や岩脈などによる応力逆解析法の基礎:佐藤活志(京都大学)
応力逆解析法のここ四半世紀ほどの発展について理論背景を含めて紹介します.テクトニクスの機構や駆動力を理解するには,地殻応力とその変遷史の解明を避けては通れません.また,地殻応力の評価は,理学的興味だけではなく,亀裂と流体移動の関係の解明や防災など応用地質的な価値も高いものです.構造地質学の分野では断層,岩脈,鉱物脈,方解石双晶など様々なスケールの地質構造を用いた応力逆解析法が開発されてきました.ここでは,それらの手法の開発の歴史についても紹介します.
<午後> 14:00-17:00
応力逆解析のための露頭観察法と解析実習:大坪 誠(産総研・地質調査総合センター)
応力逆解析のためのデータは,小断層,地震の発震機構解,岩脈や鉱物脈などの引張割れ目,方解石双晶などから得られます.ここではデータ取得方法や取得する際の注意点などを紹介します.さらに,各種応力逆解析法のソフトウエアを動かして,小断層や岩脈のデータを使って応力を推定することを実習します.実習では,データ入力方法,ソフトウエア動作方法,結果の表示,結果の読み取り方などを紹介します.実習にはWindows OSをインストールしたPCをご準備ください.
受講料(各1日券):
地質学会正会員(一般・シニア) 2,000円(日本地質学会賛助会員に所属する⽅は地質学会会員と同額です)
地質学会正会員(学生会員) 1,000円
⾮会員一般 5,000円
⾮会員学生 3,000円
(注)午前のみ,午後のみの受講の場合も,受講料の割引はありません.
(注)キャンセル料について:締切日まで 0%, 会期3日前まで 60%, 会期2日前以降 100%.いずれの場合も返金がある場合は,振込手数料を差し引いた額をカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2〜3ヶ月要する場合もありますので,ご了承下さい.
開催方法:WEB会議システムzoom(https://zoom.us/)によるオンライン講義
※受講申込締切後,受講者が確定しましたらzoomアクセスURL,事前資料をメールでお送りします.
申込方法:学会ジオストアよりお申し込みください
※受講料のお支払いは,受講申込時にPayPal〈ペイパル〉によるクレジット決済または銀行振込を選択いただけます.
(注)申込時にご提供いただいた個人情報は,日本地質学会プライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います.
その他:希望者には各コース毎のCPD受講証明書を発行します.午前・午後各3単位を予定.(CPDプログラムID:3405)
※CPD受講証明書の発行については,受講日当日に受講者のかたへ別途ご案内いたします.
申込締切:2023年3月23日(木)※実習対応可能な人数の関係から,参加者多数の場合には先着順とさせていただきますのでお早めにお申し込みください.
定員に達しましたので,申込受付を終了いたしました(3/16).
お申し込みをいただき,ありがとうございました.
多数の受講希望が寄せられていますので,ご要望のお応えするため,再度開催を検討します.
問い合わせ先:一般社団法人日本地質学会
メール: main [at] geosociety.jp 電話 03-5823-1150
(参考)過去のショートコース
(第1回,第2回)http://www.geosociety.jp/science/content0121.html
(第3回)http://www.geosociety.jp/science/content0130.html
(第4回)http://www.geosociety.jp/science/content0134.html
(第5回)http://www.geosociety.jp/science/content0137.html
(第6回)http://www.geosociety.jp/science/content0151.html
日韓地質学会学術交流協定調印(2012.9.15)
日韓地質学会学術交流協定調印
井龍康文(執行理事:国際交流担当)
写真1:9月15日行われた日韓地質学会の意見交換および日韓地質学会学術交流協定の調印後の記念撮影.前列左より,石渡日本地質学会長,Yu大韓地質学会会長.後列左より,江川会員,Choi大韓地質学会事務局長,高木執行理事,ウォリス副会長,Cho大韓地質学会副会長,井龍.
本年9月15日から17日に開催された日本地質学会第119年学術大会(大阪大会)に,大韓地質学会より,Yu, Kang-Min会長(延世大学),Cho, Moon-Sup副会長(ソウル大学),Choi, Weon-Hack事務局長(韓国水力・原子力発電株式会社)の3名が参加された.日本地質学会と大韓地質学会は,2007年以来,互いに隔年で学術大会を表敬訪問しており(ただし,昨年の訪問はなし),今年の大韓地質学会一行の来日となった.Yu会長は京都大学で学位を取得された知日家で,堆積学が専門である.
9月15日午前,大阪自然史博物館にて,日韓地質学会の意見交換および日韓地質学会学術交流協定の調印が行われた.日本側の参加者は,石渡 明会長,ウォリス副会長,高木秀雄執行理事,江川浩輔会員(産業技術総合研究所メタンハイドレート研究センター),井龍であった.江川会員は,韓国の江原大学(修士)とソウル大学(博士)に留学して堆積学の学位を取得しており,韓国語通訳が可能な若手研究者である.
会議は井龍の開会宣言に始まり,自己紹介,石渡会長の歓迎の挨拶,Yu会長の答礼に続いて,今後の日韓地質学会の交流が話し合われた.その結果,両国の交流をさらに発展させることで合意した.具体的には,主に学生を対象とした巡検の相互受け入れ(韓国の学生向け巡検を日本で実施およびその逆のケース)や両学会の学術大会で開催される国際シンポジウムへの研究者の相互招聘を活発化することで意見の一致をみた.また,日本で開催される学生向けショートコースの中には,国際的にオープンする予定のものがあるので,それらへ韓国の学生が積極的に参加して欲しいとの旨が伝達された.会議の最後には,日韓地質学会学術交流協定の調印が行われた.これは,2007年10月に締結された日韓地質学会学術交流協定の有効期限が5年間であったため,同協定をさらに5年間延長することで合意していたことを受けて,行われたものである.本文末に,交流協定の全文を掲載する.
写真2:表彰式で祝辞を述べられるYu 大韓地質学会会長.
昼食後,一行は大阪自然史博物館で行われた「地質情報展2012 おおさか− 過去から学ぼう大地のしくみ− 」(http://www.gsj.jp/event/2012fy-event/osaka2012/index.html)の開会式に参加された.佃 栄吉元副会長が引率と説明を担当した.
その後,一行は大阪府立大学に移動し,表彰式と懇親会に臨席されたYu会長からは,表彰式では祝辞を,懇親会では冒頭の挨拶をいただいた(写真2).この日の一連の行事において,Yu会長は繰り返し,「両国は社会的・外交的に厳しい状況におかれているが,我々は地質学者として将来に向かって友好関係を築くべきである」と述べられたことが強い印象として残っている.懇親会の感想を聞いてみたところ,Choi事務局長から,「韓国では立食形式の懇親会は考えられない」との感想があり,習慣の差を認識した次第である.
写真3:昼食会の様子.
9月16日には大阪府立大学特別会議室にて昼食会を開催した(写真3).参加者は大韓地質学会一行3名と日本地質学会10名(石渡会長,ウォリス副会長,井龍・高木執行理事,江川会員に加え,木村 学元会長,渡部芳夫副会長,斎藤 眞・坂口有人・西 弘嗣執行理事)の13名であった.会食は終始和やかな雰囲気で進行し,親善を深めるという目的を果たすことができた.この会食中に,学術大会の開催された堺の名産品である刃物(鋏)のセットを記念品として贈呈した.また韓国地質学会からは「Geology of Korea」(「Geology of Korea」(韓国語)B5版 802ページ 上質製本 ISBN/89-85922-89-0)を寄贈いただいた(写真4).
写真4:寄贈本「Geology of Korea」
同日午後には,Cho副会長が国際ワークショップ「Geologyof Japan」で,“U-Pb ages of detrital zircons from Korean fold-thrust belts: Implications for the Pre-Mesozoic linkage between Japan and Korea”というタイトルで講演をされた.講演後には質疑応答がなされ,東アジアの地体構造が活発に議論された(ワークショップの詳細については,大阪大会報告記事; 本号p. 10を参照).
以上,大韓地質学会一行の参加行事を時系列で紹介した.今回の来日が,日韓地質学会交流のさらなる発展の一助となれば幸甚である.
なお,2013年9月下旬に仙台で開催される日本地質学会第120年学術大会(仙台大会)では,石渡会長が環太平洋造山帯に関する国際シンポジウムを開催する予定で,韓国の研究者の招聘も計画されている.
日韓地質学会学術交流協定(全文)
Agreement for Academic Cooperation and Exchange between The Geological Society of Japan and The Geological Society of Korea
Article 1. This Agreement defines the principles and methods of cooperation that the Geological Society of Japan and the Geological Society of Korea wish to develop between them under equal partnership.
Article 2. The Geological Society of Japan and the Geological Society of Korea agree to promote academic cooperation between both societies through the following means:
(1)Mutual invitations to participate in scientific seminars, regular meetings and field trips
(2)Joint organization of seminars and academic meetings
(3)Joint or collaborative research activities and publications
(4)Exchange of academic materials and other information
(5)Promoting other academic cooperation as mutually agreed
Article 3. Both Societies agree to carry out the above activities in accordance with the laws and regulations of the respective countries after full consultation and approval of both Societies. It is understood that implementation of any of the types of cooperation stated in article 2 may be restricted depending upon the availability of resources and financial support. The execution of this agreement will not cause any financial obligations to either Society.
Article 4. This Agreement is valid for a period of five years from the date of signing by the representatives of both Societies. This Agreement shall be renewed after being reviewed and renegotiated by both Societies.
Article 5. This Agreement shall be executed in English.
日韓地質学会学術交流協定(PDF)
日本−タイ地質学会学術交流協定更新(2013.3.4)
日本−タイ地質学会学術交流協定
井龍康文(執行理事:国際交流担当)
日本地質学会とタイ国地質学会の学術交流協定を締結しておりましたが,昨年,その期限が満期となりました.そこで,昨年末より,両国地質学会の国際交流担当者が連絡を取り,協定の更新手続きをいたしました.以下に,その全文を掲載いたします.
なお,協定文は前回とほぼ同様ですが,第5条のみ微修正を加えました.以前の協定文では,交流協定を破棄する場合の告知期間が短かったため,せめて1月前までには告知するように文言を変更した次第です.
本協定の更新に際しては,久田健一郎理事に御尽力いただきました.記して,謝意を表します.
日本−タイ地質学会学術交流協定(全文)
Agreement for Academic Cooperation and Exchange
Between
The Geological Society of Japan (JGS)
And
The Geological Society of Thailand (GST)
Article 1. This agreement defines the principles and methods of cooperation that the Geological Society of Japan (JGS) and the Geological Society of Thailand (GST) wish to develop between them under equal partnership. This cooperation includes training, research, and other academic activities within the geology and earth science fields of the two societies.
Article 2. The JGS and the GST agree to promote academic cooperation between both societies in geology and earth science fields through the means as follows.
1) Exchange of academic materials and other information
2) Mutual invitations to participate in scientific seminars and annual meetings
3) Joint organization of seminars and academic meetings
4) Joint or collaborative research activities and publications
Article 3. The activities mentioned in Article 2 shall be financed according to the availability of funds. The execution of this agreement will not cause any financial obligations to either society. The societies will endeavour to obtain from third parties (regional, national, or international) the funds necessary for this cooperation.
Article 4. Both societies will endeavour to find further fields of common interest in order to develop other specific cooperation in the future.
Article 5. The agreement shall take effect on the date of signing by the respective authorities of both societies. The agreement is concluded for a period of five years. After the initial five-year period, this agreement may be renewed by mutual consent of both societies. Either society may terminate this agreement by giving one month's prior notice in writing.
日本−タイ地質学会学術交流協定(PDF)
学術大会セッションの変更について
<<2023京都大会topに戻る
【重要】学術大会セッションの変更について
【重要】学術大会セッションの変更について
日本地質学会行事委員長 高嶋 礼詩
昨年の東京・早稲田大会から,セッションを「トピックセッション」,「ジェネラルセッション」,「アウトリーチセッション」の3カテゴリに変更され,従来のレギュラーセッションは発展的に解消されました.京都大会も早稲田大会に引き継続き,上記3つのセッションで構成いたします.
学術大会セッションの魅力を高めることは,日本の地質学ならびに本会学術大会を活性化させるとともに,さまざまな世代の会員数の維持もしくは増加や大会参加者増にもつながると考えられます.そのためには,セッション企画に関わる会員や専門部会が,毎年適度な緊張感を持ってセッションの魅力向上を意識する仕組みを構築する必要があり,これは専門部会や支部の活性化にも貢献すると考えられます.学術大会のセッション区分の改訂は,その一環として昨年より実施されました. 一方,若手会員増やダイバーシティ確保を目指すための策として,年会費改定をはじめとするいくつかの大幅変更が実施されています.昨年の代議員選挙には多くの院生・ポスドク等の若手会員が立候補し,早稲田大会で実施された若手の会にも数多くの参加者が集まりました.このように,本会にも大きな変化が起こりつつあります.昨年実施した早稲田大会では,新しいセッション区分で初の学術大会を実施し,様々な課題も見えてきました.次の京都大会では昨年の経験と反省を基に,各分野からトピックセッションを積極的に提案していただき,学術大会をより盛り上げていただきたいと思います.
トピックセッション(Topical Session)
会員提案型セッションです.提案者(=世話人)は最大3名とし,研究キャリアや所属階層,ジェンダー,国籍などのダイバーシティを意識した提案者構成を強く勧めます.セッション提案書には,専門部会・委員会・支部・LOC等の提案母体の有無,他学会等の共催希望の有無(有の場合はその理由),招待講演案,過去開催実績,想定発表(演題)数,特集号計画の有無などを示していただきます.提案されたセッションは執行理事会学術研究部会を中心とする選考員によってレビューされ,提案内容や過去実績などを参考に選考されます.選考では地質学雑誌またはIsland Arc誌への特集号計画の有無も重視されます.類似するセッションが複数提案された場合は,学術研究部会がセッション統合を勧める可能性があります(その場合,招待講演は残りますが世話人は3名に調整していただきます).なお,口頭発表の演題登録数が5件に達しなかったセッションは後述のジェネラルセッションに統合します(その場合でも招待講演は残ります).従来のレギュラーセッションで実施されていたような伝統的・一般的な分野区分・名称(層序学,地域地質,構造地質など)での提案も歓迎します.
ジェネラルセッション(General Session)
従来のレギュラーセッションの枠組みを発展的に解消し,新たに一つのジェネラルセッションを設定します.本セッションはどのトピックセッションにも適合しない研究や多くの分野(disciplines)にまたがる研究などの発表の場になります.トピックセッションが上位,ジェネラルセッションが下位という関係ではありませんのでご注意ください.本セッションへの演題登録者には,関連する分野(例えば○○地質,△△地質など,専門部会名に類する分野を10程度想定)を3つ程度選んでいただき,関連性の順位を記入していただく予定です(任意).行事委員会がその順位を考慮して演題をグルーピングし,最大10程度のサブセッションにまとめて配列する予定です.本セッションの世話人は行事委員を基本としますが,口頭発表の演題登録数が5件に達しなかった(そのためジェネラルセッションに統合された)トピックセッションの提案者も世話人になっていただくことがあります.
2023京都プレサイト_top
日本地質学会第130年学術大会
2023京都大会
(プレサイト)
大会本サイト(confit)はこちらから
会期:2023年9月17日(日)〜19日(火)
会場:京都大学吉田南構内(京都市左京区)
更新情報
22/05/31 大会本サイトオープンしました NEW
22/04/10 今年も地質系業界説明会を開催します!
22/04/04 トピックセッション採択
22/02/21 トピックセッション提案募集:締切3/27(締め切りました)
22/02/21 【重要】学術大会セッションの変更について
22/02/21 130年学術大会 京都大学吉田南構内にて開催
23/02/21 京都大会プレサイト開設しました
*********************************
京都大会までのスケジュール(予定)
3月27日(月):トピックセッション提案募集締切
5月末(ニュース誌5月号)大会予告記事(演題登録・講演要旨受付開始),大会本サイトオープン
7月12日(水)演題登録・講演要旨受付締切/ランチョン・夜間小集会申込締切
8月上旬:大会プログラム公開(予定)
8月中旬:大会参加登録/巡検参加申込締切
9月17日(日)〜19日(火)京都大会
トピックセッション提案募集
<<2023京都topに戻る
トピックセッション提案募集
第130年学術大会(2023京都)
トピックセッション提案募集 締切:2023年3月27日(月)
日本地質学会行事委員会
第130年(2023年)学術大会を本年9月17日(日)〜19日(火)に京都大学で開催する予定です.前述の記事(【重要】学術大会セッションの変更について)でもお伝えしたように,昨年の大会からセッションは「トピックセッション(会員提案型)」,「ジェネラルセッション」,「アウトリーチセッション」の3カテゴリになりました.ここではトピックセッション提案を下記の要領で募集します.
1.トピックセッション概要
広く地質学に関係し,これから新分野になる可能性を秘めたセッション,多くの注目を集めると期待できるセッション,伝統的だが多くの会員に関係するセッションの提案を募集します.魅力あるセッションを積極的にご提案ください.形式は口頭発表およびポスター発表とし,口頭発表は15分間で進行も15分刻みです.セッション世話人は最大3名とし,研究キャリアや所属階層,ジェンダー,国籍などのダイバーシティを意識した世話人構成を強く勧めます.締切後,執行理事会学術研究部会が中心になって提案内容を慎重に検討の上,選考します.なお,選考では地質学雑誌またはIsland Arc誌での特集号計画の有無も重視されます.
2.招待講演
1)招待講演は1セッションにつき最大2名とし,会員・非会員を問いません.世話人が「自分を招待する」ことは認めません.
2)発表時間(質疑応答を含む)は世話人が15分または30分のいずれかを選択できます.なお,1人の発表者(招待講演者を含む)が1つのセッションで口頭発表できるのは1件です.
3)招待講演者の選定理由とその裏付けとなる情報(セッションテーマに関連した代表的な論文・著書等)が必要です.
4)非会員の招待講演者は大会参加登録費,発表負担金とも無料です.会員の場合は大会参加登録費がかかりますが,招待講演は発表負担金の対象にはなりません.なお,大会参加登録費と発表負担金は改定が検討されており,詳細については大会予告記事(ニュース誌4月号予定)でお知らせします.
3.提案方法
提案する会員は,次の項目1〜11の内容を日本地質学会行事委員会宛(main@geosociety.jp)にe-mailでお送りください.
1)代表世話人(=連絡責任者,会員に限る)の氏名(和・英),所属(和・英),メールアドレス,緊急時の電話番号
2)セッションタイトル(和・英)
3)「共同世話人(最大2名)の氏名(和・英),所属(和・英),メールアドレス
4)趣旨・概要(400〜600字程度)
5)過去のセッション開催有無,有の場合は直近大会時の口頭発表数
6)招待講演の有無
有の場合
6-1)招待講演者の氏名(和・英),所属(和・英),会員/非会員の別
6-2)招待講演の発表希望時間(15分または30分)
6-3)招待講演者の選定理由(100〜200字)
6-4)選定理由の裏付けとなる,セッションテーマに関連した代表的な論文・著書等
7)専門部会・委員会・支部・大会実行委員会(LOC)等の提案母体の有無(事前に母体の承諾を得てください)
8)他学協会等との共催希望の有無,有の場合は名称と共催希望理由(事前に共催承諾を得てください) ※共催学協会会員は地質学会会員と同じ参加登録費で大会に参加できます.ただし当該セッションでのみ発表可.
9)想定される,または直接呼びかける予定の口頭発表の数
10)地質学雑誌またはIsland Arc誌への特集号計画の有無(特集号計画を強く勧めます)
11)その他(英語使用等)
4.採択前後の注意点
類似するセッションが複数提案された場合は,執行理事会学術研究部会がセッション統合を勧めることがあります.その場合,招待講演は残りますが世話人は3名に調整していただきます.採択されたトピックセッションはニュース誌4月号または5月号(4月末または5月末発行予定)で公表し,発表募集を行います.演題登録(発表申込と要旨投稿)締切は7月初旬を予定しています.なお,口頭発表の演題登録数が5件に達しなかったセッションはジェネラルセッションに統合し(その場合,招待講演もジェネラルセッションになります),代表世話人にはジェネラルセッションの世話人の一人になっていただくことがあります.
5.世話人が行う作業(7月初旬〜中旬)
代表世話人には,講演要旨校閲や講演順番決定などの作業を7月中旬までに行っていただきます(詳細は採択後にお知らせします).その期間,代表世話人は電子メールで添付ファイルを送受信できるようにして下さい.野外調査や乗船等で通信が制限される場合は,共同世話人(代理)にあらかじめ作業を依頼し,その旨を行事委員会に必ず報告してください.
ご不明の点があれば行事委員会(main[at]geosociety.jp)までお気軽にお問い合わせください.※[at]を@マークにして送信してください.
開催通知
<<2023京都topに戻る
開催通知
日本地質学会第130年学術大会(2023京都大会)
京都大学吉田南構内(京都市左京区)にて
2023年9月17日(日)〜9月19日(火)に開催
日本地質学会は,京都市左京区の京都大学吉田キャンパスにおいて,第130年学術大会(2023年京都大会)を9月17日(日)から19日(火)に開催します.また,巡検(見学旅行)を16日(土)と20日(水)に催行します.
パンデミックの行方が今よりも不明確だった昨秋に企画をすすめたので,巡検は残念ながら日帰りのみです.しかし古生界から完新統まで,いろいろ魅力的な巡検コースを提供できるものと思います.また,京都大学と大阪公立大学で,巡検と同日に室内実習を行います.京都市付近は大地震など自然災害の歴史記録が豊富で,地質学と社会とのかかわりについて論ずる材料の多い土地です.そこで,そういった方面の市民講演会も企画しています.
宿泊施設はたくさんありますが,学術大会は連休にかかりますし,また,パンデミック前のオーバーツーリズムが夏には戻ってくるかもしれないので,早めに宿をおさえるとよいでしょう.すでに外国人観光客は戻りはじめています.
会場となる京都大学のキャンパスは,吉田神社の参道につながる東一条通りをさかいに,北側の本部構内と南側の吉田南構内に分かれます.京都大学を象徴する時計台(正式名称は百周年時計台記念館)は,本部構内にあります.大会のおもな会場は吉田南構内です.そこから今出川通りの北側の理学研究科までは,700mほどの距離です.百周年時計台記念館は,表彰式など一部の行事の会場となります.
京都駅から吉田キャンパスまでは直通バスがあり,渋滞 がなければ30分あまりで着きます.しかし渋滞する時間帯には,地下鉄烏丸線の今出川駅でバスに乗り換えると,到着時刻が予測しやすいでしょう.最寄りのバス停は京大正門前です.京都市バスのウェブサイトで,バスの便を調べることができます.
交通便利な場所ですので,多くの参加者をお迎えし,充実した大会になることと思います.大会実行委員会一同,皆様のおいでを心からお待ちしております.
日本地質学会第130年学術大会(京都大会)
実行委員会 委員長 山路 敦
トピックセッション採択結果
2023京都大会トピックセッション採択結果(2023.4.4)
提案されたトピックセッションについて、執行理事会学術研究部会が検討し、下記すべてを採択いたしました。
T1.岩石・鉱物の変形と反応 Deformation and reaction of rocks and minerals 世話人:岡本 敦 (Atsushi Okamoto)
T2.変成岩とテクトニクス Metamorphic rocks and tectonics 世話人:田口 知樹(Tomoki TAGUCHI)
T3.大地と人間活動を楽しみながら学ぶジオパーク Geopark to enjoy and learn about the earth and human activities 世話人:松原典孝(Noritaka Matsubara)
T4.中生代日本と極東アジアの古地理・テクトニクス的リンク:脱20世紀の新視点 Paleogeographic and geotectonic link between Mesozoic Japan and Far East Asia: a new view for the post-20st century 世話人:磯粼行雄(Yukio Isozaki)
T5.テクトニクス Tectonics 世話人:藤内智士(Satoshi Tonai)
T6.堆積地質学の最新研究 Latest Studies in Sedimentary Geology 世話人:白石史人(Fumito Shiraishi)
T7.鉱物資源研究の最前線 Frontiers of Mineral Resources Research 世話人:中村謙太郎(Kentaro Nakamura)
T8.フィールドデータにおける応力逆解析総決算 Stress Inverse Analysis on Field Data 世話人:大坪 誠(Makoto Otsubo)
T9 .マグマソースからマグマ供給システムまで(From magma source to magma plumbing system) 世話人:齊藤哲(Satoshi Saito)
T10.文化地質学 Culture geology 世話人:大友幸子(Yukiko OHTOMO)
T11.南極研究の最前線 Frontier of research on Antarctica 世話人:足立達朗(Tatsuro ADACHI)
T12.地球史 History of earth 世話人:冨松由希(Yuki Tomimatsu)
T13.沈み込み帯・陸上付加体 Subduction zones and on-land accretionary complexes 世話人:橋本善孝(Yoshitaka Hashimoto)
T14.原子力と地質科学 Nuclear Energy and Geological Sciences 世話人:竹内真司(Shinji Takeuchi)
T15.地域地質・層序学:現在と展望 Regional geology and stratigraphy: review and prospect 世話人:辻野匠 (Taqumi Tuzino,)
T16.都市地質学:自然と社会の融合領域 Urban Geology: Interdisciplinary research on natural and social environments 世話人:北田奈緒子(Naoko Kitada)
招待講演者の紹介
日本地質学会第130年学術大会:トピックセッション招待講演者の紹介
▶▶▶2023京都大会ウェブサイトへ戻る
世話人や専門部会から提案され,行事委員会が承認したセッション招待講演者を紹介します.なお,講演時間は変更になる場合があります.
◆ トピックセッション
T1.岩石・鉱物の変形と反応…
T2.変成岩とテクトニクス
T3.ジオパーク
T4.中生代日本と極東アジア
T5.テクトニクス
T6.堆積地質学
T7.鉱物資源研究
T8.応力逆解析
T9.マグマ
T10.文化地質学
T11.南極研究
T12.地球史
T13.沈み込み帯・付加体
T14.原子力
T15.地域地質・層序
T16.都市地質学
*タイトル(和英),世話人氏名・所属,概要を示します.*印は代表世話人(連絡責任者)です.
T1.岩石・鉱物の変形と反応
赤松裕哉(広島大学:非会員)30分 赤松氏は海洋地殻及び海洋マントルの物理特性におけるクラックの影響について研究している.特に,室内実験により得られた弾性波及び比抵抗データや掘削コア試料のCTスキャンデータなどから抽出したクラックの物理パラメーターをベイズ理論などを用いた数値計算により拡張し,地球物理観測データに厳密な物理的解釈を与えるという近年の一連の研究成果は参加者の興味を大きく引くと考えられる.
金木俊也(京都大学:会員)30分 金木会員は断層露頭観察および室内摩擦実験により,断層滑りに伴う鉱物結晶化度の変化や断層滑り挙動に関する研究を行っている.また,直近の研究では,岩石の圧密・スメクタイトの脱水などを考慮した沈み込み帯の水理学モデリングから,有効垂直応力の深度分布を見積もる研究も行っている.これらの研究成果は本セッション聴講者の興味を引くものであると期待される.
T2.変成岩とテクトニクス(なし)
T3.大地と人間活動を楽しみながら学ぶジオパーク(なし)
ページtopに戻る
T4.中生代日本と極東アジアの古地理・テクトニクス的リンク:脱20世紀の新視点
Julien LeGrand(静岡大学:会員)30分 LeGrand会員は日本各地の多数の中生層の花粉化石分析を行い,従来,年代未詳であった地層の年代決定や日本列島の中生代植物相の変遷に重要な成果を挙げてきた中堅研究者である.本セッションでは,20世紀に提案され,定説となっていた極東アジアと日本の古典的古植物相の理解に対して,今起きつつある新たな進展についての最新研究レビューをお願いしたい.
T5.テクトニクス
星 博幸(愛知教育大学:会員)30分 星会員は,地質学と古地磁気学を中心とした研究を進められており,特に近畿・中部地方をはじめとる日本列島の新生代テクトニクスに関する多くの論文を発表されてきた.これらの研究成果は造山帯における地殻変動のモデルとして,その他の研究に大きな影響を与えている.招待講演では,星会員の最新の研究成果も含めた西南日本弧の形成過程について提示していただくことを目的としている.
ページtopに戻る
T6.堆積地質学の最新研究
奥村知世 (高知大学海洋コア総合研究センター:会員)30分 奥村会員は,温泉成の炭酸塩堆積物であるトラバーチンの研究を始め,深海冷湧水に関連した炭酸塩チムニー,高知沖の宝石サンゴ,高知県龍河洞の鍾乳石など,炭酸塩堆積物に関して幅広く研究をされている.招待講演では最新の研究を紹介いただく予定である.
齋藤 有(徳島大学:非会員)30分 齋藤氏は,日本におけるハイパーピクナル流堆積物に関する先駆的な研究を行ったほか,近年ではSrなどの放射壊変源安定同位体比を指標とする堆積物供給源解析から,地球表層の堆積物移動様式の解明にアプローチする研究を進めている.招待講演では,黒潮による細粒砕屑物の運搬可能性についてSr-Nd-Pb同位体比から考察した研究例についてお話ししていただく.
T7.鉱物資源研究の最前線
見邨和英(千葉工業大学:会員)30分:見邨会員は,地球科学の研究に機械学習を応用することで新たな展開をもたらしている新進気鋭の研究者である.最先端のディープラーニング技術に基づく画像認識手法を用いて,年代の決定や海洋環境の推定に必要な微化石を高精度で検出・観測する新しいシステムの構築や,海底熱水鉱床の自動探査技術の開発・実装など,革新的かつ独創的な研究を展開している.本講演では,最新の研究展開と今後の展望について話題を提供していただく予定である.
<
T8.フィールドデータにおける応力逆解析総決算
山路 敦(京都大学:会員)30分 山路会員は,理論テクトニクス研究を長年に渡り進めてきた中で,2000年の多重逆解法(Multiple inverse method)をはじめとする応力逆解析手法を精力的に開発してきた.多くのユーザーにより地殻応力の時間変化や空間的な不均一が次々と明らかとなり,島弧の構造発達史の理解が大きく進んだ.山路会員に手法のこれまでの発展史の紹介と今後の課題や期待を提示していただくことは本セッションにとってこれ以上ない講演である.
内出崇彦(産業技術総合研究所:非会員)30分 内出氏は,地震学研究を進める中で,AIを活用した地震波形ビッグデータ処理による微小地震の震源メカニズム解の解析から,日本列島内陸部にかかる現在の応力の向きについて,日本列島規模の大局的な傾向から約20 km規模の地域的な特徴まで知ることができる「ストレスマップ」を2022年に公表した.内出氏に日本列島内陸部の現在の応力の特徴を紹介していただくことは本セッションにとってこれ以上ない講演である.
ページtopに戻る
T9.マグマソースからマグマ供給システムまで
村岡やよい(産業技術総合研究所:会員)15分 村岡会員はバソリスを構成する小規模深成岩体を対象に野外調査を主軸とした岩石学的研究を推進している.特に北部九州花崗岩バソリスに分布する低Sr含有量の深成岩体(低Sr花崗岩類)の成因について,下部地殻溶融時の低圧条件の可能性を指摘し,小規模岩体での解析結果をバソリス規模に展開した.ミクロの解析をマクロの議論に展開できる今後の活躍が期待される若手研究者である.
<
T10.文化地質学
貴治康夫(立命館高等学校:会員)30分 貴治会員は京都周辺の地質の研究に関わって,古都・京都で使用されてきた石材に興味を持ち,用途からみた岩石の特徴,開発経緯・文化的背景などについて検討するようになった.現役の庭園師・石匠と情報交換しながら庭園内の庭石や採石地を調査した成果に加え,焼き物や壁土,砥石,茶磨などの素材にも着目して京都の伝統産業と周辺地質との関わりについて論じてくださるものと期待している.
加藤友規(植彌加藤造園株式会社:非会員)30分 加藤氏は,植彌加藤造園の社長として,京都市内の名庭の維持管理を行ってきただけでなく,京都芸術大学大学院日本庭園分野の教授として,庭園文化の研究も進められている.京都の庭園文化に造詣が深く,植木だけでなく岩石の作庭における役割について,地質学者とは異なった視点で論じてくださるものと期待している.
T11.南極研究の最前線
板木拓也(産業技術総合研究所:会員)30分 板木会員は,長年に渡って現世,海底堆積物,露頭試料 まで幅広い試料を対象とした放散虫の研究を行っており, 最近ではAIを使った微化石解析システムの開発で世界的に注目される研究者である.また,南極周辺の海底堆積物を用いた最終氷期以降の氷床融解イベントの復元にも進捗が見られており,地質学会でもこのトピックについて講演いただく.
野木義史(国立極地研究所:非会員)30分 野木氏は,地球物理学を専門とし,観測船や航空機によ る地磁気異常、重力異常や地形等の観測に基づいて,ゴンドワナ超大陸分裂機構の解明や南極大陸氷床下の地質構造の推定に取り組んでいる.今回の招待講演では,主にNogi et al. (2013)で提唱された,地球物理データから見る南極大陸のテクトニクス史についてご講演いただく予定である.
ページtopに戻る
T12.地球史
千葉謙太郎(岡山理科大学:非会員)30分 千葉氏は,恐竜類の中でも角竜類を専門に,骨化石から個体成長過程や雌雄差や個体差についての古生物学的な研究を行なっている.恐竜標本から骨のがんを世界で初めて報告し,最近では骨化石から有機物を抽出するなど,古生物や地質学の分野だけでなく病理学などの研究者と共同で,最先端の恐竜研究に取り組まれている.招待講演では,モンゴル上部白亜系の絶対年代決定と最近の発掘で発見され た脊椎動物小型化石の研究について講演していただく.
梶田展人(弘前大学:会員)30分 梶田会員は,有機地球化学を専門とし,現在の地球表層システムや第四紀の気候変動の解明に関する研究を行っている.梶田会員は,海洋・湖の堆積物だけではなく,房総半島に分布する地層からもバイオマーカーを抽出し,過去の表層海水温の復元を行うなど,地質学の分野においても重要な研究成果を挙げている.招待講演では,第四紀におけるバイオマーカーを用いた温暖期の古環境復元に関する 総説について,これまでの研究と今後の展望を講演していただく.
T13.沈み込み帯・陸上付加体
小平秀一(海洋研究開発機構:非会員)30分 現行IODPによる最後の科学掘削となる日本海溝掘削計画 J-TRACKが2024年に予定されている.日本側のリードプロポーネントである小平氏にJ-TRACKの詳細を沈み込み帯に関わる地質学会員に紹介していただくとともに,興味を持つ研究者に乗船希望の機会となることを期待している.
T14.原子力と地質科学
志間正和(原子力規制庁:非会員)30分 NUMOによる文献調査が実施される中,2022年に原子力規制委員会から,地層処分の概要調査地区等の選定時に安全確保上少なくとも考慮されるべき事項について公表された.これは文献調査を行う観点からの重要な指針であることから原子力規制庁からご紹介いただく.
千木良雅弘(深田地質研究所:会員)30分 これまで国内外で数多くの岩盤の特性を調査されてきた千木良会員より,地質構造と地下水流動の不確実性についてご紹介いただき,今後のサイト選定調査に係る問題点を議論する.
T15.地域地質・層序学:現在と展望
板木拓也(産業技術総合研究所:会員)30分 地域地質・層序の研究で重要な要素は年代決定であり, 微化石は有用なツールであるが,一方で鑑定には専門的知識と習熟が必要で,今般の人口減の文脈において人材の涸渇が危惧される.その中において,板木会員はAIの機械学習による微化石判定に取り組んでおり,この問題を解決する基幹的な技術の一つになる可能性がある.この技術の実相と展望について開発者本人の口から広く地域地質研究者に報せるべきと考える.
脇田浩二(山口大学:会員)30分 脇田会員は,野外調査を基とした地質図作成とグローカルなテクトニクス研究に長年取り組み,特に付加体及びその形成機構を実証した第一人者である.さらに,日本初のWeb地質図である日本シームレス地質図の開発を主導した.野外調査を基とした研究は予定調和とコスパ重視の風潮から近年敬遠される傾向にあるが,脇田会員には足のスケールから地球スケールに至る研究経験を踏まえて野外調査の意義・魅力・醍醐味などを語ってもらう.本講演がフィールドジオロジーの再評価につながることを期待する.
T16.都市地質学:自然と社会の融合領域
竹村恵二(京都大学名誉教授:非会員)30分 竹村氏は,関西空港建設時より,理学分野の専門家として調査研究に携わり,施設施工管理に必要な工学的モデル検討の基礎的な情報の取りまとめを行った.そのほかにも, 都市インフラ整備などに必要な工学的要求事項に対して地質情報を用いて検討・対応を行った.本講演では,都市部における地質情報の収集と利活用方法などの事例を含めてご発表いただく.
ページtopに戻る
ジオストア申込者への案内(支払ほか)
ジオストアからイベント等への参加申込を頂いた方へのご案内
●銀行振込を選択のかたは、次の口座へ参加費または受講料をお振込みください。
振込のための郵便振替用紙(請求書)はお送りしません。
7日以内にお振込みをお願いいたします。
※ 振込時には、振込者氏名の前に必ず上記注文Noを入力して下さい。
三井住友銀行 神田駅前支店(普通)1711424 (社)日本地質学会 / シヤ)ニホンチシツガツカイ
郵便振替 00140-8-28067 一般社団法人日本地質学会
●クレジット決済の場合は、PayPalより
『一般社団法人日本地質学会様への支払いの領収書』メールが別途配信されます。
ご利用のカード会社によって、貴口座より引き落としとなります。
参加取消・受講取消について
※返金がある場合は、振込手数料を差し引いた額を学会からご返金いたします。
(注1)若手巡検・研究集会への参加申込者の方へ
“若手巡検・研究集会”の申し込みは先着順とし、定員になり次第、締め切ります。
本申込について、参加取消される場合には、学会事務局に直接お申し出ください。参加キャンセル料が発生しますので、ご注意ください。
巡検実施日の
20日前〜8日前:20%
7日前〜前日:50%
当日:100%
(注2)ショートコース受講申込者の方へ
予定の受講定員を超過した場合には、地質学会会員を優先します。受講申込締切後、速やかに受講可否の通知をお送りします。
ショートコースはWEB会議システムzoomによるオンライン講義です。受講専用の招待URLを会期までにお知らせします。受講料の入金確認ができない場合は、招待URLをお知らせできませんので、ご注意ください。
本申込について、受講取消される場合には、学会事務局に直接お申し出下さい。キャンセル料が発生しますので、ご注意ください。
受講締切日まで 0%
受講3日前まで 60
受講2日前以降 100%
学生会員巡検参加費用補助
学生会員の学術大会巡検参加費用補助について
学生会員の学術大会巡検参加費用補助について
2023年4月15日理事会承認
若手育成事業検討ワーキンググループ
リーダー 内野隆之
学生会員のうち大学生・大学院生を対象として,竹内圭史会員の寄付金から,日本地質学会学術大会で実施される巡検の参加費用を補助する.
補助は学術大会の巡検代(設定金額)の半額とする.なお,昼食代および現地までの交通費は原則参加者の全額負担とする. ※巡検代については,宿泊代・施設利用料等の経費を含め,昼食代は含めない (別途現地で徴収あるいは各自で購入).
本補助は支部等の巡検にも適用できるが,その場合,募集前に執行理事会へ申請し,許可を得ることとする.
以上
(注意事項追記)
参加申込手続き完了後,会員資格や参加費の内訳等を事務局で確認し,補助金額分を後日返金します.
若手育成事業の一環として行う補助であるため,社会人学生は対象となりません.
研究奨励賞及びフィールドワーク賞対象年齢に合わせて「32歳未満の学生会員」を対象とします.
ジオルジュ
ジオルジュ
ジオルジュは日本地質学会の広報誌です.グラフィカルな誌面で地球科学の最前線をわかりやすくお伝えします.サイエンスライターによる記事とプロ写真家のジオフォトによる全く新しいスタイルの雑誌です.
2018年前期号からは,六大都市(札幌,仙台,東京,名古屋,大阪,福岡)のジュンク堂にてフリーペーパーとして配布しています.なお,各店舗とも無料配布部数には限りがあり,追加入荷はいたしません.定期購読を希望されるかたへは,450円/セット(送料別)にて,お分けいたします.ご購入はオンラインストアへ
団体等で大量部数ご希望の場合は,学会事務局までお問い合わせください(電話03-5823-1150 FAX 03-5823-1156 E-mail: main[at]geosociety.jp)
ジオルジュ2024後期号 2024年11月発行
地球探訪 大きく隆起した海岸線
特集1 「ジャパンレッド」発祥の地 備中吹屋-ベンガラと銅の町-
特集2 三畳紀は今日も雨だった カーニアン期多雨現象が生命にもたらしたもの
特集3 二酸化炭素を海の森でつかまえる
山-川-海そして雪 いのちを育む水の旅 白山手取川ユネスコ世界ジオパーク
ジオルジュ コラム 恐竜の日本画を描く
伝わる作品 五感で感じる作品を手掛ける表現者 サイエンスデザイナー ササオカ ミホ氏に聞く
ジオルジュ2024前期号 2024年5月発行
特集1 掘削技術者の養成所へようこそ
特集2 新しい伝統の土佐硯はどこに?
特集3 モンスターの正体?
特集4 急峻な斜面の暮らしを守る 地すべり対策
ジオルジュ コラム 等高線ケーキ作りReport クレープを重ねて阿蘇山を再現!
ジオルジュ2023後期号 2023年11月発行
1.特集1-好奇心の扉を開いて-読み継がれてきた学習漫画『まんが化石動物記』
2.特集2-3Dプリンターで博物館展示を
3.特集3-蒼すぎる田沢湖 塩酸の温泉と人々の歴史
4.特集4-研究航海の「ごはんの時間」
5.ジオルジュ コラム 学問とエンタメのるつぼ「博物館ふぇすてぃばる!」
6.生け花でジオサイトを華麗に表現する-「ジオ生け花を楽しむ会」代表 鈴木由美子氏に聞く
ジオルジュ2023前期号 2023年5月発行
1.特集1-3D地質地盤図で見る東京都心部の地下構造
2.特集2-鉄は国家なり 日本刀とたたら製鉄
3.特集3-ラジオで伝える、恐竜学!
4.特集4-江戸時代に翻訳された地質学関連書物
5.箱根ジオパーク
6.研究者とアスリートの二足の草鞋を履く、岩石に魅せられた男-サイエンティスト・フリークライマー 中嶋 徹氏に聞く
ジオルジュ2022後期号 2022年11月発行
来るなら来なさい南海地震 高知県民の覚悟
温泉水を煮詰めてつくる「会津山塩」
漂流する軽石
研究×技術×デザイン
ジオルジュ コラム「もしもの未来」を考察する地学の授業!
自然信仰が息づく 南紀熊野ジオパーク
絶滅生物を蘇らせる!-造形師・塗装師 古田悟郎に聞く
ジオルジュ2022前期号 2022年5月発行
急派!緊急災害対策派遣隊 テックフォース
味わう地質学
かつて、絶滅したペニスがあった?
昔も今も磯めぐりが楽しい 銚子ジオパーク
ジオルジュ コラム 誕生石、ふえる
『ヒトコブラクダ層ぜっと』でマニアックに描写された恐竜の化石発掘-作家 万城目 学(まきめ まなぶ)氏に聞く
ジオルジュ2021後期号 2021年11月発行
土と炎が織りなす芸術 備前焼
地球科学×バーチャルリアリティ
池の水が抜けないように
研究者が「自叙伝的エッセイを書く」とは? -若き古生物学者・木村由莉と書籍編集者・藤本淳子に聞く“本ができるまで”
3つのマグマが生んだ萩の文化 萩ジオパーク
ジオルジュ2021前期号 2021年5月発行
ひとつなぎの大地質図への挑戦:日本シームレス地質図ができるまで
独特な演出がクセになる 奇石博物館
エオリアが育んだゴボウ
ジオ鉄」鉄道と地質のコラボレーション
男鹿半島・ 大潟ジオパーク:7000万年前から現在までをいっきに堪能
ジオルジュ2020後期号 2020年11月発行
地学に恋する君たちへ:漫画家Quro氏が『恋する小惑星』に込める想い
ドローンが突破口に!−火山ガス観測−
地下水はどこにある?
月と火山に魅せられて:ジオフォト文化を創った写真家 白尾元理氏に聞く
霧島ジオパーク:火山が集まってできた火山
鉱物を食べる
ジオルジュ2020前期号 2020年5月発行
1.地球の風景 城ヶ島を再訪する
2.土石流と蛇王伝説
3.黒曜石がつむぐ、地球と人の物語 白滝ジオパーク
4.兵庫県立加古川東高校 自然科学部地学斑に潜入!
5.夜空に人工の流れ星を
6.タイムカプセル「コンクリーション」はどうしてできる
-応用地質学者 吉田英一氏に聞く-
7.ジオルジュコラム アノマロカリス新時代
ジオルジュ2019後期号 2019年11月発行
1.地球の風景 縞状片麻岩から現れた釈迦涅槃像
2.世界最長の鉄道トンネル開通
3.水中で動く化石
4.自然をつくっていく:宍道湖・中海の干拓淡水化計画が残したもの
5.おもしろくておいしい キッチン火山実験で火山現象を伝える―火山学者 林 信太郎氏に聞く―
6.標高差1400メートルのジオの彩り:四国西予ジオパーク
7.ジオルジュコラム 地球と宇宙の風景 ―「ジオ星景写真」にトライ―
ジオルジュ2019前期号 2019年5月発行
1.地球の風景 カッパドキアでキノコ岩の謎解き
2.黒田郡水没伝承を海底に探る
3.眠れる化石の謎を解く -再発見された標本が語ること-
4.地下の世界を旅するために どうやって掘り進むのか
5.”恐竜の博物館”になるということ-むかわ町穂別博物館 櫻井和彦館長と西村智弘学芸員に聞く-
6.生きている火山の島 伊豆大島ジオパーク
7.ジオルジュコラム 水晶宮恐竜
ジオルジュ2018後期号 2018年11月発行
1.地球の風景 イグアス滝で洪水玄武岩を見る
2.海はいつまでもつのか
3.澄みすぎて貧栄養に直面する瀬戸内海-人の手で豊かな海を創る試み-
4.街の中で化石をハント!!
5.ジオルジュコラム 化石チョコレート
6.ユネスコ世界ジオパーク アポイ岳ジオパーク
7.科学をビジュアルで伝える―理系のサイエンス・イラストレーター菊谷 詩子さんに聞く―
ジオルジュ2018前期号 2018年5月発行
1.地球の風景 韓国に恐竜足跡を見に行く
2.石を知り、技術をもって形にする-石材加工の現場-
3.土石流と里山の歴史
4.博物館キャラクター”大活躍”中!「瑞浪Mio」はナニモノか?
5.放散虫で装飾を-よみがえる5億年の造形美-
6.おおいた豊後大野ジオパーク
7.地球科学を題材にした小説を書く―研究者から作家に転身した井与原 新さんに聞く―
ジオルジュ2017後期号 2017年11月発行
1.溶岩トンネルから空を見上げる
2.地すべり地帯に住む
3.「ブラタモリ」のつくりかた!
4.海の中で発見された大陸「ジーランディア」分裂と水没の謎をさぐる
5.下北ジオパークー恐山と津軽海峡の本州最北の地
6.地球の息吹を感じる島
7.台湾の地震被災地から学ぶ
ジオルジュ2017前期号 2017年5月発行
1.地球の風景 チバニアン、それともイオニアン
2.絶海の火山島 噴火後の世界-西ノ島の上陸調査で見た景色-
3.「怪異」の正体は古生物だった!?
4.地球儀の老舗「渡辺教具製作所」見学リポート
5.BARで楽しむサイエンス
6.Mine秋吉台ジオパーク
7.隕石衝突の証拠を追いかけ続けて、今がある
―JAMSTEC佐藤峰南JSPS特別研究員に聞く―
ジオルジュ2016後期号 2016年11月発行
1.地球の風景 空中に三脚を立てる(熊本県)
2.熊本地震。そのとき、博物館は?
3.ワインと地質学のビミョーな関係
4.巨木が語る地球のリズム
5.ジオパーク秩父
6.速報!国際地学オリンピック日本大会in三重
7.地球すべてが凍りついた
―ジョセフ・カーシュヴィンク博士に聞く―
ジオルジュ2016前期号 2016年5月発行
1.地球の風景 エルターレ火山の溶岩湖(エチオピア)
2.数百年後のあなたに伝えたかったこと
3.ケナガマンモスとナウマンゾウは共存したのか!?
4.地球科学を「視える化」
5.地球を食べる
6.三陸ジオパーク
7.地球深部探査船『ちきゅう』の運用で海底下を穿つ
―倉本真一センター長に聞く―
ジオルジュ2015後期号 2015年11月発行
地球外生命を探したい! でもどうやって?
自然が作る芸術-断層岩の世界-
地質の風景を切り取る-甘い誘惑-
三島村・鬼界カルデラジオパーク
クラウドファンディングで研究資金調達
ジオルジュ2015前期号 2015年5月発行
田毎の月
鮮やかによみがえる中生代の世界
天然の炭酸水 その起源は地球深部にあった
“地変国”日本を書く
ジオルジュ2014後期号 2014年11月発行
地球の風景:山水画の世界を歩く(中国・黄山)
孤高の山 富士山
小惑星探査機 はやぶさ2 地球の起源を求めて
見えないものを見てみたい 有孔虫の殻づくりを可視化する
ジオルジュ2014前期号
地球の風景:モロッコに隕石孔を見に行く
芸術は鉱物から
ミュージアムをつくろう!
火山島を観測する
桜島・錦江湾ジオパーク
地球探訪:ジュラ博物館
ジオルジュ2013後期号
地球の風景:ルートレス・コーン(アイスランド)
「デスモスチルス」は泳ぎが上手だった?
地球探訪:アイスランド
隠岐ジオパーク
古文献・古地図が語る災害リスク
大地が証言する事件の真相
インタビュー:杉田律子さん(科警研)
ジオルジュ2013前期号
地球の風景:白い岬
有人探査vs無人探査
日本でもダイヤモンドが採れた!
天より落ちる石 隕石
島原半島ジオパーク
コラム:サウルスを竜と訳した人
インタビュー:瀧上 豊さん
ジオルジュ2012後期号
地球の風景:足元に眠っていた津波記録
「カンブリア爆発」はなぜおきた?
火山と生きる—過去から現在,そして未来へ向かう三宅島—
リアルに想像する スーパーボルケイノ
糸魚川ジオパーク
コラム:日本で最初に発見された竜
インタビュー:清家弘治さん
ジオルジュ創刊号
地球の風景:うつり変わる港町
地質学があかす大津波と巨大地震
博物館レスキュー −ふるさとの宝を取り戻したいー
室戸ジオパーク
インタビュー 大木聖子さん
125周年
日本地質学会125周年を迎えるにあたって
125周年記念事業準備委員会
委員長 矢島道子
委員 天野一男・永広昌之
佐々木和彦・宮下純夫
日本地質学会は地質学の発展や普及を目指して、1893(明治26)年に創立されました。2018年に125周年を迎えます。地質学徒としては大変嬉しいことです。75周年、100周年には記念出版物が刊行され、学会の歴史や研究の動向などが総括されています。125周年に関しては、理事会のもとに125周年記念事業準備委員会(矢島、天野、佐々木、永広、宮下)が設置され、検討を重ねてきました。その結果、日本地質学会を飛躍的に発展させる絶好の好機ととらえて、本事業に取り組む方向が確認されています。この機会を、地質学の歩みを振り返り、地質学への時代の要請を鑑みて、これから何をなすべきかを一緒に考える第一歩にしたいと思います。
イギリスの地質学会は1807年に世界で最初に創立され、すでに2007年に200周年を祝いました。イギリスに続いて、1830年にフランス、1848年にドイツ、1885年にアメリカと、世界各国で地質学会が創立されました。それぞれすでに125周年を祝っています。地質学という学問が古くから確立されていたということがわかります。日本では、地質学会よりやや早く1879(明治12)年東京地学協会が、1880(明治13)年に日本地震学会が創立されています。そのような中で日本地質学会は地質学を明確に担い、営々と築き、地球科学関連学会中でも古い歴史をほこっています.
私たちの立っているこの大地がいつごろ、どうやってできたのだろうという疑問に応えようとして、地質学は始まりました。地質学の起源を18-19世紀のハットン(James Hutton、1726 - 1797)やライエル(Charles Lyell、1797 - 1875)よりも前の18世紀のビュッフォン(Georges Buffon 、1707 - 1788)、ソシュール(Horace-Bénédict de Saussure, 1740–1799)やキュヴィエ(Georges Cuvier、1769 - 1832)に求めたり、あるいはもっと前のデンマークのステノ(Nicolaus Steno, 1638 - 1686)に求めたりする人もいます。いずれにしろ、地質学は、大地の営みを知り、それを科学的に解明し、人間の生活に役立てることが大きな目標の学問です。
地球は46億年という長い時間をもっています。地質学はこの長い時間を内にもって発言することができます。生命の発生以来、どのような道をたどって、私たちヒトが生れてきたのかも明らかにしようとしています。地球は1周4万kmという大きな空間を有しています。この空間を縦横に駆け廻るのが地質学です。そして、今や、地質学はその専攻範囲を大地ばかりではなく、深海底や地底深く、あるいは、大気空間、惑星空間や宇宙空間にまで広げています。
現在、人間社会は地質学に多くの課題を突きつけています。特に2011年の東日本大震災と原発災害は、地質学の重要性を強く示しています.将来発生が予測される大地震や火山噴火、大規模自然災害などへの地質学からの貢献が求められています。また、エネルギーや資源をどこに求めていくのかに対しても、地質学からの貢献が期待されています。私たちは、営々と125年築いてきた日本地質学会の記念事業を、地質学や地質学会の発展の絶好の契機となるように今から準備を始めることを呼びかけます。
125周年に向けて、これから様々な活動が始まりますが、会員の皆様からの建設的なご提案や準備の諸活動への積極的な参加をお願いいたします。
鹿児島学術大会での国際交流(2014.9)
鹿児島学術大会での国際交流
Wallis, Simon(国際交流担当理事)
今回の大会の特徴の一つは国際交流にあったと言っても過言ではありません.学術交流協定を結んだ海外の地質学会の代表者らを招待し,また,国際シンポジウムが開催されました.
海外学協会からの代表者の招待
学会活動の更なる発展を考える上で各国の地質学会の代表者の訪問は重要と執行部は考えています.訪問の機会を最大限に活かすために,執行部同士の話あいのみならず研究の面でも発表する機会を設け,折角集まった訪問者と一般会員との交流を促すために訪問者の研究分野に合致したセッションでの講演を実施しました.
各学会の代表者と発表は次の通りです.
<韓国地質学会>
代表(1):Prof. Daekyo Cheong (会長)
セッション:第四紀地質(9/15)
タイトル:Paleoenvironmental changes of last 10,000 years from Nakdong River Estuary sediments, Korea.
発表者:Cheong, Daekyo・Paik, Seik・Shin, Seungwon・Park, Yonghee
代表(2):Prof. Young-Seog Kim (理事)
セッション: テクトニクス(9/15)
タイトル:Surface ruptures and earthquake hazards.
発表者:Kim, Young-Seog・Choi, Jin-Hyuck
<ロンドン地質学会>
代表:Prof. Alan Richard Lord(国際交流担当理事)
セッション:地学教育・地学史 (9/14)
タイトル:The Geological Society of London—past present and future
発表者:Lord, Alan・ Bilham, Nic
<モンゴル地質学会>
代表:Dr. Tumur-Ochir Munkbhat(会長)
セッション:岩石・鉱物・鉱床学一般 (9/14)
タイトル:Geology and ore mineralization at Oyu Tolgoi deposit, southern Mongolia
発表者: Munkbhat, Tumur-Ochir
<タイ地質学会>
代表:Mr. Suwith Kosuwan (理事)
セッション:テクトニクス(9/15)
タイトル:The biggest earthquake of the century in Thailand.
発表者:Wiwegwin, Weerachat・Kosuwan, Suwith・Nuchanong, Tawsaporn
14日には鹿児島市内で昼食会を催しました.参加者は,海外学協会からの招待者ら7名(Prof. Daekyo Cheong(韓国),Prof. Young-Seog Kim(韓国),Dr. Munkbhat Tumur-Ochir(モンゴル),Mr.Suwith Kosuwan(タイ),Prof. Alan Lord(イギリス), Prof. David Cope (イギリス),Mrs. Takashina-Cope)と地質学会の4名(井龍会長,Wallis国際交流担当理事,海野理事,橋辺事務局長)の計11名でした.また,15日は井龍会長主催のバスツアーに海外からの招聘者は全員参加し,現地のガイドによる桜島と鹿児島の歴史の紹介を楽しみながらグループ内の交流をはかりました.このバスツアーでは準備段階より,高柳栄子会員にお世話になりました.
国際シンポジウム「津波ハザードとリスク:地質記載の活用」
本大会では,国際シンポジウム「津波ハザードとリスク:地質記載の活用」(Tsunami hazards and risks: using the geological record)を開催しました.これはロンドン地質学会との共同開催のシンポジウムで,海外学協会との初めての共催企画でした.
津波と地質学は最近国内外で極めて注目度の高い研究課題です.イギリスは地震が少ない国でプレート境界から離れていますので,津波という現象とあまり縁のない国と考えていらっしゃる方が多いと思います.ですが,イギリスも過去に大きな津波被害をうけた痕跡があります.紀元前6100年20mの津波はスコットランドを襲い,また1755年のリスボン地震の後3m程度の津波はイングランドの西南部に到着し,場所によっては大きな被害ががありました.これらの過去のイベントを背景にイギリスはこの数年,津波リスクを再評価するプロジェクトを開始しました.2015年に同様なテーマで第2回の日本地質学会との共催シンポジウムをイギリスで開催する予定です.両シンポジウムのオーガナイザーはSimon Wallis(日本地質学会), Neil Chapman(イギリス地質学会)で,今回のconvenerとして 藤原 治氏,後藤和久氏,藤野滋弘氏は大きく活躍して下さいました.さらに藤原氏にはシンポジウム後3日間の巡検を案内して頂き,藤野氏は学会の英文誌「Island Arc」の特集を企画しています. なお, 本シンポジウムはグレイト・ブリテン・ササカワ財団からの助成を受けて開催しました.ここに記して謝意を表します.
津波シンポジウムは計14件の発表があり,そのうち4件は海外研究者でした.
シンポジウムでは,津波堆積物の認定(ストーム堆積物との区別)や津波の形成メカニズム(断層のずれや海底地滑りの重要性)などのテーマは活発に議論されました.この分野の発展に貢献する成果を期待したいです.
雑談ですが,「津波シンポジウム」は部屋121号室で行われていましたが,部屋を探そうとしていた招待者は困った表情で私に尋ねました.「『121』はどの部屋でもかいてあるみたい.『121』はいったいどこだ」.確かに『121』という数字は,廊下でも部屋でもいろいろなところで見かけました.偶然ながら鹿児島大会は121回目の学術大会でした.漢字が読めないと数字だけをたよりに表示を探しますから,混乱しやすいですね.今後も海外からの参加者のために英語混合の標識などを用意するといいかもしれません.
海外からの招待者のための見学ツアー(15日). 桜島の前.
後列(左から): S. Day教授 (ユニヴァーシティー・カッレージ・ロンドン大), J. D. Tappin教授(英地質調査所),江 博明教授 (国立台湾大),江婦人,D. Cheong 教授(Kangwon Univ. 江原大), Y.-S. Kim教授(Pukyong Univ. 釜慶大), A. Lord教授 (Senckenberg Research Institute, Frankfurt), J. D. Hansom教授 (グラスゴー大), D. Cope教授 (ケンブリッジ大),高柳栄子博士(東北大), 前列(左から):S. Wallis (名古屋大), 井龍康文会長 (東北大), S. Kosuwan氏 (タイ鉱物資源庁), Munkhbat婦人, T.-O. Munkhbat博士(Oyu-Tolgoi鉱山), Takashina-Cope婦人, C. Chague-Goff博士(ニューサウスウェールズ大)
このほかにも,日台技術研修のため来日していた台湾の地質調査所3名が大会に参加されたため,14日午前中に井龍会長との懇談の時間を設け,竹内理事と保柳理事も同席し,日本地質学会との協力関係について話し合いました.また,今回は,同じ台湾出身の江 博明教授が国際賞を受賞され,同氏に興味深い受賞講演して頂きました(受賞講演については、2014年11月号ニュース誌へ掲載).
今後も日本地質学会にとって国際的な活動を継続,発展させていくことは重要な使命です.特に,日本で行われている地質学研究の成果をどのように発信するか,国際的な連携により研究をさらに発展させていくにはどのようにするかという2つの課題は重要であり,学会をあげて取り組みたいと思います.
(予告)地質系業界説明会
今年も地質系業界説明会を開催します!
2023.4.10掲載
今年も地質系業界説明会を開催します!
日本地質学会地質技術者教育委員会では,毎年開催される学術大会の会場において,学生会員が将来就職する可能性のある地質・資源・建設分野に関わる地質系企業・団体との対面説明会を企画・開催し,学生会員が地質系業界を研究するサポートサービスを展開してきました.
今年度は,昨年度と同様に「対面での説明会」と「オンラインによる説明会」の2つを行うことにしています.
なお,対面説明会は新型コロナウィルス感染の状況が,現状よりも拡大し行政などからの集会規制が発布された場合は中止することがありますので,ご了承ください.
2023年度学生のための地質系業界説明会〜その業界の仕事を知るためのサポートサービス〜(概要)
対面説明会:2023年9月18日(月・祝) 学術大会(第130年学術大会 京都大学 2023年9月17日〜19日)期間中の18日(月)敬老の日の半日間,会場の専用ブースを訪問し,対面で説明を受け,質問する企画です.
オンライン説明会:2023年9月22日(金)午後 学会のHPを介して参加企業・団体にオンライン訪問し,説明を受け,質問する企画です.
当説明会につきましては,関係業界団体,関係学協会にもお知らせし,参加企業・団体が決まった時点で全国の40を超える地質学系学科にも案内します.
参加企業・団体の参加申し込みは6月1日から6月30日,学生会員をはじめ学生層への案内は7月上旬を予定しています.また,参加企業・団体の紹介動画などの資料を学会HPに8月中旬から掲示しますので,事前に企業・団体の情報を見てから当日訪問することができます.
今後,当学会HP,SNS,ジオフラッシュ,ニュース誌を介して詳細情報をお知らせします.
▷ 昨年(2022早稲田大会)の開催報告(pdf)はこちらから
2023京都:若手会員向けルームシェア型宿泊プラン
第130年学術大会(2023年京都大会)
若手会員向けルームシェア型宿泊プランのご案内
受付は終了しました
日本地質学会第130年学術大会が2023年9月17日(日)〜19日(火)の3日間開催されます。それに伴いまして、今大会では若手会員向けの宿泊施設をご用意いたしました。「若手同士の交流」と「低価格化」の観点から、本プランは、相部屋でのご案内となっております。内容をよくご確認の上、ご検討ください。
<対象者>
若手会員(35歳以下の正会員)
<ルームシェア型宿泊プランの主旨>
「学会先での宿泊費を抑えたいけれど、ホテルの部屋をシェアする相手が見つからない...」「地質学会で仲間をつくりたい!」といった若手会員のために、日本地質学会ではこの度、“ルームシェア型宿泊プラン”を企画いたしました。学術大会での若手会員の宿泊先確保を支援し、若手同士の交流機会をつくることで、若手会員の皆様の研究活動をサポートしたいと考えております。是非、本プランをご活用いただき、研究仲間の輪を広げていただきたいと思います
<申し込みにあたっての注意事項>※必ず、お読みください※
男女別室の見知らぬ人同士の相部屋となります。お互いが快適に過ごせるよう、ご配慮をお願いいたします。
若手の学術大会参加を支援するための企画です。学術大会への参加が必須事項ですので、その点をご留意ください。
定員を超過した場合、学生・ポスドクを優先とさせていただきますので、予めご了承ください。
キャンセルは原則禁止ですので、ご注意ください。
<宿泊プランの詳細・お申し込み方法>
設定期間:2023年9月17日(日)〜19日(火)(宿泊数は選択可)
宿泊施設:関西セミナーハウス 〒606-8134京都市左京区一乗寺竹ノ内町235-1-1 URL: https://www.kansai-seminarhouse.com 修学院駅から徒歩約15分(会場まで市バスまたは徒歩で約40-50分)
宿泊料金:一人 6,200円/1泊 (食事なし・酒類を持ち込む場合は+500円/人)
受入可能人数:最大23名 (和室3室(8名,6名,6名),トリプル1室,ツイン1室)
お申し込み方法:オンラインフォーム
申込期間:2023年7月1日(土)〜2023年8月18日(金)受付は終了しました
お支払い方法:ご自身でホテルに直接お支払いください。
<お問い合わせ先>
日本地質学会若手活動運営委員会:ecg.core(at)gmail.com (at)は@に置き換えて下さい
第8回ショートコース
日本地質学会第8回ショートコース
申込締切
2023年6月22日(木)
申込方法
学会ジオストアからお申し込みください
申込受付は終了しました
第8回ショートコース 日程:2023年7月2日(日)
内容:(各コース,講義・質疑応答含め3時間を予定)
<午前> 9:00-12:00
レーザーアブレーションーICP質量分析法(LA-ICP-MS法)によるU-Th-Pb年代測定法の原理と最前線:平田岳史(東京大学)
複合的な地質現象を理解する上で,岩石あるいは鉱物の年代情報は重要な制約条件を提供します.年代測定には複雑な化学操作と高度な分析技術が必要であり,これまでは同位体分析を専門とする特定の研究者のみが入手できる情報でした.しかし分析技術の急速な進歩により,今では誰もが精密年代情報を活用できるようになりました.講演者は分析化学者として20年以上にわたり年代情報の高精度化・高速化を図ってきました.本講演では,分析手法の原理を紹介するとともに、得られる年代情報の精度や正確度(誤差)が,どのような要因に支配されているのかを紹介させていただきます.また講義では,私達の研究グループが目指す年代測定の未来についてもご紹介できればと考えています.
<午後> 14:00-17:00
砕屑性ジルコンU-Pb年代を用いた地質学研究:竹内 誠(名古屋大学)
近年,Laser-ICP-MSの導入により,ジルコンのU-Pb年代測定が比較的容易に短時間で多量にできるようになり,地質学に様々な新しい情報をもたらしました.特に,化石が得られない変成岩の原岩の堆積年代の制約や年代を利用した後背地解析などで大きな成果がありました.本講演では,砕屑性ジルコンのU-Pb年代が地質学研究に果たす役割について紹介し,さらに,これまでに報告された研究事例から,後期白亜紀の沈み込み帯での堆積作用と地質構造発達史を中心に紹介します.
受講料(各1日券):
地質学会正会員(一般・シニア) 2,000円(日本地質学会賛助会員に所属する⽅は地質学会会員と同額です)
地質学会正会員(学生会員) 1,000円
⾮会員一般 5,000円
⾮会員学生 3,000円
(注)午前のみ,午後のみの受講の場合も,受講料の割引はありません.
(注)キャンセル料について:締切日まで 0%, 会期3日前まで 60%, 会期2日前以降 100%.いずれの場合も返金がある場合は,振込手数料を差し引いた額をカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2〜3ヶ月要する場合もありますので,ご了承下さい.
開催方法:WEB会議システムzoom(https://zoom.us/)によるオンライン講義
※受講申込締切後,受講者が確定しましたらzoomアクセスURL,事前資料をメールでお送りします.
定員:各コース100名(定員は事務局および講師を含み,定員を超えた場合は,会員が優先となります)
申込方法:学会ジオストアからお申し込みください
※受講料のお支払いは,受講申込時にPayPal〈ペイパル〉によるクレジット決済または銀行振込を選択いただけます.
(注)申込時にご提供いただいた個人情報は,日本地質学会プライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います.
申込締切:2023年6月22日(木)
その他:希望者には各コース毎のCPD受講証明書を発行します.午前・午後各3単位を予定.(CPDプログラムID:3405)
※CPD受講証明書の発行については,受講日当日に受講者のかたへ別途ご案内いたします.
問い合わせ先:一般社団法人日本地質学会
メール: main [at] geosociety.jp 電話 03-5823-1150
(参考)過去のショートコース
(第1回,第2回)http://www.geosociety.jp/science/content0121.html
(第3回)http://www.geosociety.jp/science/content0130.html
(第4回)http://www.geosociety.jp/science/content0134.html
(第5回)http://www.geosociety.jp/science/content0137.html
(第6回)http://www.geosociety.jp/science/content0151.html
キャンセルした講演の講演要旨の扱いについて
キャンセルされた講演要旨の取り扱い
学術大会にて発表を申し込まれた講演を講演要旨冊子体印刷後にキャンセルした場合,該当講演の要旨は印刷物として存在することになります.この講演要旨の扱いについて,以下の通りとします.
1.講演をキャンセルした場合,講演要旨も取り下げたものとします.講演要旨集(冊子体)に要旨は残りますが,キャンセルされた講演の要旨は引用できません.J-STAGE上には講演要旨は掲載しません.
2.学術大会終了後,地質学雑誌ニュース誌にキャンセルされた講演を掲載し,キャンセルされた旨を周知します.
3.次年度以降の学術大会にて,キャンセルした講演の要旨を再掲し,発表を希望する場合は,再掲する要旨に「本講演は第○○年学術大会にて発表をキャンセルしたもので,本講演要旨は第○○年学術大会講演要旨集(冊子体)に掲載されたものを再掲したものである」旨を明記してください.
4.天災や主催者側の都合等でプログラムが中止となった場合は,「講演したもの」とみなし,J-STAGE上でも講演要旨を掲載します.ただし,学術大会においては専門家による議論には供されていないため「災害のためプログラム中止」等との文言を付記します.
一般社団法人日本地質学会
行事委員長
※第122年学術大会(2015年長野大会)から適用
※2017年9月14日 項目4追加
※2019年4月 6日 一部改訂
(注)2021年(127年学術大会)以降は,講演要旨の冊子体作成はありません.2021年以降は,キャンセルされた時点で要旨も非公開となります.
講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理,引用方法,校閲について
講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理,引用方法,校閲について(シンポジウム・セッション 共通)
2021.6月更新
(1)講演要旨の倫理責任と著作権管理
本学会は,本学会出版物への投稿原稿に対して,その倫理性について著作者が保証する「保証書」および著作権を本学会へ譲渡することに同意する「著作権譲渡同意書」に署名捺印をして提出していただいております.学術大会の講演要旨投稿では,オンライン画面上で「保証書」と「著作権譲渡等同意書」の内容に同意していただいてから電子投稿画面に進めるようになっています.
「保証及び著作権譲渡等同意書」ダウンロードはこちらから
(2)講演要旨における文献引用
引用した文献の情報を必ず記載して下さい.講演要旨では文献記載の簡略化が認められています.著者名,発表年,掲載誌名など,文献を特定できる必要最低限の情報を明記して下さい.
(3)講演要旨の校閲
行事委員会は,すべての(招待講演を含む)講演要旨について,学会の目的ならびに倫理綱領(定款第4条)に反していないかという点について校閲を行います.校閲によりいずれかの条項に反していると判断された場合,行事委員会は修正を求めるか,あるいは発表申込を受理しないことがあります.行事委員会の措置に同意できない場合,発表申込者は法務委員会(学会事務局気付)に異議を申し立てることができます(下記参照).
講演申し込み異議申し立てについて
日本地質学会行事委員会は,学術大会において学会の目的及び倫理規定に反する講演申し込みのあった要旨に対して,修正あるいは,受理を拒否することができます.法務委員会では,日本地質学会行事委員会規則に基づき,異議申立の手続及びその処理についての規則を定めています.
日本地質学会法務委員会
■日本地質学会学術大会講演申込異議申立に関する処理機構規則(PDF)■
シンポジウム「チバニアン,学術的意義とその社会的重要性」20220524
日本学術会議公開シンポジウム「チバニアン,学術的意義とその社会的重要性」
日本学術会議公開シンポジウム
「チバニアン,学術的意義とその社会的重要性」
クリックするとPDF(プログラム)がDLできます.
日時:令和4年(2022年)5月24日(火)13:00〜17:10
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木 7-22-34)
入場無料
※本シンポジウムはハイブリッド形式で行います.
主催:日本学術会議地球惑星科学委員会IUGS 分科会、地球惑星科学委員会地球惑星科学国際連携分科会INQUA 小委員会,
東北大学学術資源研究公開センター総合学術博物館
共催:日本地質学会、日本地球惑星科学連合、日本古生物学会、日本第四紀学会,福井県立大学恐竜学研究所
後援:東京地学協会、 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立極地研究所、国際地質科学連合(IUGS),茨城大学
千葉県市原市の地層「千葉セクション」が、国際基準の地層境界である「国際境界模式層断面とポイント(GSSP)」に認定され、約77万4千年前〜約12万9千年前の地質時代の名称が「チバニアン」と名づけられました。本シンポジウムでは、チバニアンの決定における過程を振り返り、その科学的および社会的な意義を紹介します。
以下のリンクからお申し込みくださるようお願い申し上げます.多くの方々のご参加をお待ちしております.
▼▼▼ 参加申込はこちらから ▼▼▼
https://nws.stage.ac/scj_sympo220524/
問い合わせ:西 弘嗣(福井県立大学恐竜学研究所)
Email:hiroshi.nishi.b3(a)tohoku.ac.jp ※(a)を@にしてお送りください。
招待講演者の紹介
日本地質学会第129年学術大会:セッション招待講演者の紹介
▶▶▶東京・早稲田大会ウェブサイトへ戻る
世話人や専門部会から提案され,行事委員会が承認したセッション招待講演者を紹介します.なお,講演時間は変更になる場合があります.
トピックセッション
T1.変成岩とテクトニクス
T2.西南日本弧の成立
T3.南大洋・南極氷床
T4.地球史
T5.グローカル層序学
T6.日本列島の起源再訪
T7.マグマ・供給システム
T8.文化地質学
T9.石油天然ガス石炭
T10.鉱物資源研究
T11.堆積地質学
T12.火山現象と防災
T13.都市地質学
T14.ジオパーク
*タイトル(和英),世話人氏名・所属,概要を示します.*印は代表世話人(連絡責任者)です.
T1.変成岩とテクトニクス:無し
T2.新生界地質から読み解く西南日本弧の成立—付加体形成から背弧拡大まで—
木村 学(東京海洋大,会員)30分 木村会員は,これまでプレート収束帯のテクトニクスに 関する研究を長年にわたり進めてきた.近年は特に,南海トラフ周辺の地質学・地球物理学的なデータに基づき,フィリピン海プレートの運動,四万十付加体,南海付加体トラフの研究成果を発信され続けている.招待講演では木村氏の成果の取りまとめを依頼し,本セッションの目指す多 角的な議論の下敷きとなる西南日本の成立過程論のモデルを提示していただく.
T3.南大洋・南極氷床:地質学から解く南極と地球環境の 過去・現在・未来
関 宰(北海道大,非会員)30分 関氏は堆積物からアイスコアまで幅広い試料を対象とし, 主に有機物分析に基づく古気候復元から地球気候システム の解明を進めている.とくに過去の二酸化炭素濃度復元に おいてマイルストーンとなる論文を発表するなど世界的に注目される研究者であるが,近年は南 極周辺の海底堆積物の分析から,過去の温暖期における急 激な氷床融解イベントの復元にチャレンジしており,地質学会でもこのトピックについて講演頂く.
平野大輔(国立極地研究所,非会員)30分 平野氏は海洋物理学を専門とし,とくに南極沿岸域にお ける周極深層水の貫入と南極氷床・棚氷の相互作用による 融解について,近年顕著な業績を挙げている業界でも注目 の若手研究者である.今回の招待講演では地質学会ではあ まり馴染みのない現代海洋における海洋循環と南極氷床の 相互作用,とくに急激な棚氷・氷床の融解現象について講演頂く.
ページtopに戻る
T4.地球史
泉 賢太郎(千葉大,非会員)30分 泉氏は,生痕化石を専門とされており,太古の生態系や 古生物の行動様式の進化について研究を行っている.中でも,前期ジュラ紀の温暖化に伴う海洋環境変動と生物相へ の影響や,第四紀更新世における古環境復元などの研究は,古生物学と地質学の観点からのアプローチにより世界的に も注目される.招待講演では,生痕化石を中心とした生物 の行動史について最新の成果も踏まえて講演していただく.
齋藤諒介(山口大,非会員)30分 齋藤氏は,これまで,ペルム紀末大量絶滅直後における 地球表層環境と生物の応答に関して研究を行ってきた.齋 藤氏は,有機化学的手法を用いた前期三畳紀の研究を率先して行ってきた研究者であり,堆積有機分子の解析や元素 分析によって,前期―中期三畳紀の海洋の酸化還元状態や当時の陸上の植生変化について明らかにしてきた.招待講 演では,これまでの研究成果について,最新のアイデアを 踏まえて講演していただく.
T5.グローカル層序学・年代学
岡田 誠(茨城大,会員)30分 岡田会員は日本初のGSSPである「チバニアン」の認定に 尽力した研究チームのリーダーで,千葉セクションの地層 を対象とした岡田氏らの一連の研究成果は,国際地質年代 尺度の進展に大きく貢献した.また,チバニアンの認定に よって,日本の一般社会において層序学の認知度が大いに 高まった.岡田氏には日本のローカルな地層の研究が,グローバルな貢献,とりわけ,国際基準となる地質年代の認 定に至った道のりを講演していただく予定である.
松本廣直(JAMSTEC,会員)30分 堆積物中に記録されている古海洋Os同位体記録 (187Os/188Os)は,強力な層序対比ツールとして近年注目を 集めている.Os同位体比は海洋での滞留時間が短いために, マントル由来の大規模な火成活動の開始や隕石衝突が起こ った時代の層準を高解像度で特定することができ,層序対 比に加えて古環境イベントに対しても用いられるようになりつつある.松本会員は白亜系中部のオスミウム同位体比 層序を検討することにより,この時代の様々な層序対比基 準面や大規模火成活動イベントを見出すことに成功した.本講演では,Os同位体比を用いた層序学・古環境学研究の 現状と今後の展望について解説いただく予定である.
ページtopに戻る
T6.日本列島の起源再訪
谷 健一郎(国立科学博,会員)15分 とくに谷会員は,伊豆小笠原弧などの海洋性島弧や島弧衝突帯における地殻形成過程を研究してこられた.陸上での野外調査また日本周辺の海洋調査を手広く行なってこら れた.伊豆衝突帯の系統的なジルコン年代測定からそのテ クトニクスを制約した仕事が代表作で,最近では日本列島 花崗岩類について多数のジルコン年代測定を試みておられる.今回は,日本列島の起源に関係する大和堆の地質学/ 岩石学について講演をお願いする.
田中源吾(熊本大,会員)15分 田中会員は,介形虫など節足動物化石の機能形態学・古環境学および古生態学を専門とする.現生介形虫群の情報に基づき,古環境復元やイベント堆積物の認定,また化石 化過程を研究している.最近では,日本産古生代介形虫の 古生物地理区を考察している.今回は,希少な日本産介形 虫,サンゴ,三葉虫,コノドントなどの最新情報の紹介と,それらの古生物地理学的意義について講演をお願いする.
T7.マグマソースからマグマ供給システムまで
谷内 元(産総研,会員)30分 谷内会員は, 沈み込み帯火山岩類の詳細な岩石学的検討 に基づいた成因研究を推進している. 特に北海道北部の利尻山の玄武岩質初生マグマの多様性やアダカイト質マグマの成因について, スラブ由来の超臨界流体の水流体とメル トへの分離の可能性を新たに指摘し, 沈み込み帯での火成 活動に新しい知見を与えている. これらの研究成果は3編の論文としてトップランクの国際誌に公表しており, 今後の活躍が期待される若手研究者である. 今回は, これまでの利尻山研究の総括を, 最新の成果も踏まえて講演していただく.
T8.文化地質学
中谷礼仁(早稲田大,非会員)30分 中谷氏の専門は建築史,歴史工学,建築理論である.著書は,インドネシアからアフリカ北部に及ぶ広大な地域を1年弱巡歴した建築論的旅の記録である.講演ではプレート運動の影響を強く受ける地域に住む人々の叡智と暮らしを,地質,建築構法,古代文明,グローバライゼーションの実相などの多層的な視点からお話いただく予定である.
ページtopに戻る
T9.カーボンゼロエミッションに貢献する石油天然ガス石炭地質学・有機地球化学
徂徠正夫(産総研,非会員)30分 徂徠氏は,産総研地質調査総合センター地圏資源環境研究部門CO2地中貯留研究グループ長として「CO2地中貯留における遮蔽性能評価に関する研究」・「グローバル元素循環モデルに基づいたCO2およびN2O収支の評価」等の日本・世界をリードするCCU研究を推進しておられる.
辻 健(東京大,会員)30分 辻会員は,九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所において,CO2の貯留層をモニタリングし地下貯留層の状態を把握してモデリングを組み合わせることで将来の状態を評価する研究を行っておられ,またブルー水素等にも造詣が深い.
T10.鉱物資源研究の最前線
野崎達生(JAMSTEC,会員)30分 野崎会員は,日本の鉱物資源研究をリードする第一人者であり,最先端のOs同位体分析を駆使した鉱床形成年代決定や,海底熱水鉱床研究における新たな成因論の構築,さらには革新的な資源養殖の提案など,極めて独創的な研究を展開し続けている.本講演では,当該分野の最新の話題を提供して頂く予定である.そのお話を聞ける機会は,本セッションに関係する全ての研究者にとって非常に有意義なものになると期待される.
T11.堆積地質学の最新研究
渡邊 剛(北海道大,会員)30分 渡邊会員は,炭酸塩骨格に成長縞を残すサンゴやシャコ貝などの生物源炭酸塩の地球化学分析をもとに,超高解像での古環境復元に取り組んでおられる.鮮新世温暖期のエルニーニョ現象の発見や地球温暖化が西インドの気候システムに与えた影響の解明,20世紀の黒潮流量の長期復元など,将来の環境変動を見積もる上でも重要な成果を次々と出されている.招待講演では最新の研究を紹介いただく予定である.
ページtopに戻る
T12.火山噴出物から読み解く火山現象と防災への応用:無し
T13.都市地質学:自然と社会の融合領域
野々垣 進(産総研,会員)30分 野々垣会員は,3次元地質モデリングの第一人者であり,都市の地下地質モデリングの技術開発と実践について実績がある.3次元地質モデリング技術の紹介とともに,DX戦略に対応した地質情報の社会実装について,最新の情報と課題を整理していただく.
T14.大地と人間活動を楽しみながら学ぶジオパーク:無し
ページtopに戻る
大会申込Q&A
大会申込Q&A
【演題登録編】 >>【参加登録編】へ
Q:演題登録専用のアカウント登録をしたはずなのにログインできません.
A:
アカウント登録しただけでは、登録完了にはなりません(仮登録の状態です)。
アカウント登録後、登録したメールアドレスあてに
【日本地質学会第124年学術大会(2017年愛媛大会)】メールアドレス本登録のお願い
という自動返信メールが配信されます.このメール文中に明記されているURLをクリックし,本登録を完了させてください.ここまでの操作を行えば,任意で登録した〔ログインID〕と〔パスワード〕でログインできるようになります.
※URLのリンクの有効期限は本メール送信日時より24時間以内となっておりますので,ご注意ください.
Q:1人何題まで発表できますか?
A:
トピック・レギュラーセッション(全34セッション)では,1人2題まで発表できます.ただし2題発表する場合には発表負担金(1,500円)をお支払い下さい(1題のみの場合は無料).また,同一セッション内で口頭2件やポスター2件の発表はできません.詳しくは,セッション発表の募集要領『2)発表に関する条件・制約』を参照してください.
Q:発表負担金はどこで支払えばよいですか?
A:
演題登録画面には課金システム機能はありません. 事前参加登録画面にトピックセッション(T1〜T9)・レギュラーセッション(R1〜R25)での発表件数を選択する項目があります.『2件(1,500円)』を選択いただければ,事前参加登録費とともに発表負担金も課金され請求されます.
※トピック・レギュラーセッションにて招待講演者になっている発表者が,もう1題を別セッション(または招待されているセッションと同一セッションの異なる発表形式)で一般発表する場合には,発表負担金(1,500円)は発生しません(招待講演分は発表負担金の発生する”2件目”としてカウントしません).
Q:非会員も演題登録(発表)はできますか?
A:
招待講演者を除き,非会員の発表はできません.現在,非会員のかたで愛媛大会において発表を予定されているかたは,演題登録に合わせて入会申込の手続きもしてください(締切時点で入会申込が確認できない場合,登録が取り消されます).セッション共催団体の会員は共催セッションのみ発表できますが,それ以外の他セッションで発表を希望する場合には,必ず入会手続きを行ってください.
Q:入会申込中(承認待ち)のため,会員番号(ID)もないのですが,演題登録はできますか?
A:
入会承認がまだのかたでも演題登録はできます.お早めにアカウント登録の手続きをしてください.会員区分の項目欄に『入会申込中』と入力してください.会員番号等の入力方法については注釈に従ってください.
Q:筆頭著者でなければ発表はできないのですか?
A:
筆頭著者でなくても発表は可能です(筆頭著者は会員・非会員を問いません).
ただし,発表者は地質学会の会員でなければなりません.
共同発表(複数の著者の発表)の場合には,講演要旨(pdf)に明記する著者名の
うち,発表者が分かるように発表者氏名に下線を引いてください.
※非会員が発表者になっている場合には,登録が取り消される場合があります.
Q:前回大会において急遽発表キャンセルをしてしまったため,今年の大会で同内容で発表したいのですが.演題登録してもいいですか?
A:
前回の学術大会にて発表を申し込まれた講演を講演要旨印刷後にキャンセルした場合,該当講演の要旨は印刷物として存在することになります.キャンセルした講演の要旨を再掲し,発表を希望する場合は,再掲する要旨に「本講演は第○○年学術大会にて発表をキャンセルしたもので,本講演要旨は第○○年学術大会講演要旨集に掲載されたものを再掲したものである」旨を明記してください.
詳しくは行事委員会から発表の『キャンセルした講演の講演要旨の扱いについて』を参照して下さい.
Q:演題登録画面のキーワードの入力欄を増やす方法は,どうすればよいですか.
A:
キーワードはデフォルトで5件まで入力できるようになっています.入力欄を増やしたい場合は,【追加】ボタンをクリックしてください.キーワードは最大10件まで登録できます.
※キーワードの入力は任意です(必須項目ではありません).
※『所属機関情報』や『著者情報』の件数・人数入力欄の増減も同様の操作で対応できます.
Q:演題登録画面の『著者情報』に21人以上の共著者を登録したいのですが.
A:
演題登録画面上では『著者情報』の入力は最大20件までしか登録できません.
21人以上登録したい場合には,演題登録時の受付番号(C00〜ではじまる数字)と21人目〜の著者情報(氏名と所属先名:和英とも)を学会事務局に連絡してください.プログラム作成時に反映します.
Q:講演要旨がまだ出来上がっていないので,演題登録ができません.どうしたらいいですか?
A:
まず先にアカウント登録を行ってください.
演題登録画面には”講演情報”のほかに,”著者・所属機関情報(一度登録しておけば書き換える必要の無い項目)”の入力もあります.締め切り間際になってから全ての項目を登録しようとするのではなく,発表題目や共著者情報などはとりあえず”仮情報”で構いませんので,まずはアカウント登録しておくことをおすすめします.”講演情報”も,”著者・所属機関情報”も締切日時まで繰り返し修正していただけます.
※締切(7/5日,18時)までには,完成原稿をアップロードしてください!!
Q:(演題登録締切後)講演要旨に誤りを見つけてしまったので,差し替えたいのですが.
A:
演題登録締切後,著者(発表者)の都合による要旨の差替え(演題内容の修正)依頼は受け付けません.
演題登録締切後,すぐにプログラムデータの整理・講演要旨の校閲作業を開始し,限られた時間の中で各世話人が要旨の校閲作業をしております.
修正原稿は,その都度校閲をしなければならなくなり,世話人の手間も増えることとなりますから,期日内にきちんと講演要旨を完成させ,登録を済ませていただきますよう,何卒ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします.
※要旨の校閲後に世話人から修正を求められた際,求められた箇所以外の修正をしてしまう著者(発表者)がまれにいますが,世話人に指摘された箇所のみを修正してください.
Q:演題登録の締切は延長されますか?
A:
昨年同様,演題登録の締切延長はありません.7月5日(水)18時締切厳守(郵送は6/29日(木)必着)です.余裕をもってお早めにご登録ください.
【参加登録編】
Q:講演要旨は付きますか?
A:
参加登録費が有料か無料かで異なります(詳しくはこちらもご覧下さい).
(a)参加登録費が有料のかたには,必ず講演要旨集が1冊付きます.
→正会員・院生割引会費適用正会員・非会員一般・非会員院生
(b)参加登録費が無料のかたには,講演要旨集は付きません.
→名誉会員・50年会員・学部割引会費適用正会員・非会員学部学生・
非会員招待者・同伴者(非会員で会員の家族に限る)
※(b)のかたが講演要旨を希望する場合は,別途ご購入ください.
事前参加登録の『追加講演要旨』の注文欄で【注文する】を選択し,
『冊数選択』欄と『受取方法』欄の項目も選択して,お申し込みください.
Q:地質学会会員が招待講演者になった場合,参加登録費はどうなりますか.
A:
学会員は参加登録費は有料です(免除にはなりません).必ず参加登録してください.
※シンポジウム,各セッションともに,参加登録費が免除になるのは,非会員招待講演者に限ります.
Q:講演要旨集の「後日発送」は,いつ頃送付されてきますか?
A:
大会会期終了後の発送です(別途送料がかかります).会期前の送付はできません.
Q:キャンセル料(取消料)はかかりますか?
A:
事前参加申込期間中の変更・キャンセルの場合は取消料はかかりません.締切後につきましては,申し込んだものにより,キャンセル料がそれぞれ異なりますのでご注意ください.
参加登録費:
申込締切後〜9/13日(大会3日前)60%,9/14日(大会2日前)以降100%
※後日,講演要旨をお送りします.
追加講演要旨:
申込締切後〜9/13日(大会3日前)60%,9/14日(大会2日前)以降100%
懇親会:申込締切後100%
弁当:申込締切後〜9/13日(大会3日前)50%,9/14日(大会2日前)以降100%
巡検:申込締切後〜9/13日(大会3日前)まで50%,9/14日(大会2日前)以降100%
Q:Web上で事前参加登録をしましたが,確認メールが届きません.
A:
入力したメールアドレスが間違っている可能性があります.学会事務局へ連絡してください.
Q:事前参加登録をしましたが,登録内容の修正の仕方が分かりません.
A:
事前参加登録の申込時に,①[初回申込]確認,②[ご請求]連絡の2通のメールが必ず自動返信されています(クレジット決済まで完了した人は③決済完了のお知らせメールも届きます).
[初回申込]確認メールの文中には,
・【変更・修正】および【取消】操作をおこなうための案内
・【変更・修正】および【取消】操作の画面にログインするためのURL
・ログインに必要な[お申込No.]と[パスワード]
が明記されております.説明をよく読んでお手続きください.
※できるだけ,一番最初に取得した[お申込No.]と[パスワード]で登録内容の【変更・修正】をしてください.何度も何度も新規でお申込すると,[お申込No.]と[パスワード]を登録した回数分取得することになり,重複申込者の確認漏れの原因にもなります.
Q:参加費無料の会員種別の人は,事前登録をしなくてもよいですか?
A:
当日の参加登録でも構いません.ただし,講演要旨の購入を希望される場合は,数に限りがあり,事前予約と当日購入では冊子体の価格が異なりますので,事前参加登録にてご予約することをおすすめします.ここ数年,大会会期中に講演要旨集の売り切れが続いておりますので,なるだけ事前にお申込みください.
Q:代理での申込はできますか?
A:
可能です.ただし,申込の重複や連絡先/発送先の登録には注意してください.とくに非会員招待講演者や外国人招待者などを代理で登録する場合は,代理で登録してくださるかたの連絡先を確認書やクーポンの送付先として登録してください(海外の住所では,確認書やクーポンの発送を,ご本人の手元に届くよう間に合わせることができません).また,登録時の確認メールは日本語のみです.
Q:巡検だけに参加したいのですが.
A:
地質学会会員は巡検だけに参加する場合でも,基本の参加登録費がかかります.事前参加登録【画面A】からお申込ください.
非会員のかたで,『巡検協賛学協会』のいずれかにご所属されているかたは,【画面B】からお申込みください.
Q:大会には参加しませんが,講演要旨だけの購入はできますか?
A:
講演要旨だけの予約購入も可能です.事前参加登録【画面C】からお申し込みください.ただし,講演要旨の発送は大会終了後になりますので,ご了承ください.
Q:Web登録がうまくできません。
A:
連絡先など,登録情報の自動取得が行えない場合はこちらを参考にしてください(自動取得は日本地質学会会員のみ利用できます).
正しく操作を行っているにも関わらず,エラーが出る場合は学会事務局へご連絡ください.
Q:クレジット決済ができません。
A:
次のような場合はクレジット決済ができません.
○タブレット(iPadやスマートフォンなど)で事前参加登録をした場合.
タブレット(iPadやスマートフォンなど)は対応機種にはなっていませんので,クレジット決済はご利用できません.クレジット決済をしたいかたは,PCをご利用ください.
○勤務先のサーバーのセキュリティレベルの都合.
所属先のPCから事前参加登録をし,クレジット決済をしようとしたところ,クレジット決済の画面に切り替わらないことがあります(所属先のサーバーのセキュリティレベルの都合でクレジット決済ができないようです).その場合はご自宅のPC(個人でプロバイダ契約しているサーバー経由)から事前登録しクレジット決済を行ってください.
Q:同伴者の欄に【大学の友人】や【職場の同僚】を登録してもいいですか?
A:
【大学の友人】や【職場の同僚】は同伴者にはなれません.それぞれ別個に参加登録してください.あくまでも,同伴者は【会員の家族】を想定しての申し込み欄です.なお,会員の家族でも夫婦や親子で地質学会会員の場合は,同伴者にはなれませんので,別個に会員として参加登録してください.
Q:私は地質学会会員(正会員)ですが,所属先の身分は大学院生なので【正[院生割引]会員】の会員種別で参加登録してもよいですか?
A:
大学院生でも正会員のかたは,【 正 会 員 】で参加登録してください.
【正[院生割引]会員】として参加登録できるのは,今年度にかかる割引会費申請者に限ります.申請を出さなかった会員(今年度の学会費が12,000円だった人)は【正会員】ですので,正会員の会員種別で参加登録してください.
※今年度の割引会費の申請は,今年の3月末で締め切りました.今から遡って申請することはできません.
Q:私は地質学会会員(正会員)ですが,セッション共催団体(または巡検協賛団体)では院生会員なので,そちらの会員種別で参加登録してもよいですか?
A:
地質学会会員のかたは,地質学会の会員種別で参加登録してください.
「セッション共催団体」や「巡検協賛団体」の会員種別でお申し込みできるのは,地質学会非会員のかたに限ります.
Q:事前参加登録をしたのに,確認書の参加費が当日払いの金額になって届きました.
A:
事前参加登録をしても,確認書を郵送する時点で参加登録費の入金が確認できなかった場合は,当日の参加登録費の金額で確認書を発行し,ご請求します.
所属先(会社や大学,研究所)からの公費払いの都合で,参加登録費の入金が遅くなる場合は,この限りではありませんが,必ず学会事務局に予めの連絡をしてください.
Q:昨年,確認書やクーポンが届きませんでした./大会終了後に受け取りました.
A:
確認書やクーポンは郵送でお送りします.申込の際,発送時期に確実に届く住所を記入・入力してください(所属先へ送付を希望される方は,とくにご注意ください).発送は大会10日前にはお手元に届くように発送する予定です.締切後に送付先変更を希望される場合は,学会事務局へご連絡ください.また,下記のような場合にも早めにご連絡ください.
例1)会社勤めのかた:大会直前まで出張(現場で野外調査)し,出張先から大会に参加するため,出張先(宿泊先)に確認書やクーポンを送ってほしい./直接大会会場で受け取りたい.
例2)大学職員・学生のかた:夏季休暇中は事務が閉まっていて,郵送物が届きにくい/届かない.
※昨年(2016年,東京・桜上水大会)からは,参加登録費の合計金額が有料のかたのみ確認書や名札等を郵送しています.それ以外のかた(合計金額が0円で支払が発生しないかた)は,大会当日の受付で名札をお受け取り下さい.
Q:宿泊予約はできますか?
A:
事前参加登録システムからは宿泊予約はお受けしておりません.各自手配をお願いします.
●学会専用の宿泊予約はこちらから(外部サイト:東武トップツアーズ).
●ホテルリスト・価格はこちらから.
※松山市内の宿泊予約の状況について
松山市内では地質学会同期間中に医学系などの他学会,10月のえひめ国体の事前行事の開催が予定されており,既に宿泊予約が大変混み合っています.そのため旅行社を通じて宿泊施設の確保を進め,地質学会専用の宿泊予約サイトを準備いたしました.ただ,松山市内だけでは難しいため,近郊(奥道後,今治,西条など)にもエリアを拡げての確保も行っており,本予約サイトでは室数の追加補充を順次行って行く予定です.確保数にも限りがありますので愛媛大会に参加予定の皆様におかれましては,各自,早めに交通手段の確保.宿泊予約をされるようおすすめいたします.
Q:自分の疑問が解決する答えが載っていませんでした.
A:
ご不明な点がありましたら,学会事務局へご連絡ください.
共催・協賛団体
2018札幌大会:セッション共催団体一覧
セッション共催団体(セッション番号)
日本火山学会(T2)
日本原子力学会バックエンド部会(R24)
日本鉱物科学会(T2)
石油技術協会探鉱技術委員会(R9,10,11,12)
日本堆積学会(R9,10,11,12)
日本有機地球化学会(R9,10,11,12)
日本地球掘削科学コンソーシアム(J-DESC)(T4)
(注)今大会では「巡検協賛団体」の設定はありません.
(2018/6/1 現在)
参加登録フローチャートの画面に戻る
巡検申込状況
巡検申込状況
(8月21日,18時 締め切りました)
[申込締切] Web: 8/21(月)18:00、FAX/郵送による申込は 8/14(月)に締め切りました。
【巡検コースの詳細はこちら】
班
コース名
定員(最小催行)
申込件数
A
松山市周辺の瀬戸内火山岩類 (9/19)
20(13)
15
B
中央構造線断層帯の地形地質 (9/19)
20(13)
20
C
室戸ユネスコ世界ジオパーク (9/19〜20)
20(13)
4
D
四国西予ジオパーク (9/19)
20(13)
20
E
久万層群と三崎層群 (9/19〜20)
20(14)
18
F
三波川帯 (9/19〜20)
15(10)
15
G
岩国−柳井領家帯 (9/19)
20(13)
4
H
アウトリーチ巡検 (9/19)
25(17)
8
※定員に近い班は黄色マーカーで示しています.
※定員に達した班はピンク色マーカーで示しています.
◆参加申込人数が各巡検コースの最小催行人員に達しなかった場合,巡検を中止することがあります.→巡検実施に関する案内はこちらから.
◆巡検協賛団体の会員の方は,会員同様にお申込を頂けます.それ以外の非会員の方は,申込締切時点で定員に余裕があれば参加可能となります.ご承知おき下さい.
◆Hコース<アウトリーチ巡検>は,一般市民を優先対象とします.
そのほか、巡検のお申込については,こちらをご一読ください.
大会直前連絡(2017愛媛)
大会直前連絡 2017愛媛大会
2017.9.4更新 宿泊地アンケートにご協力ください.
■■■
愛媛大会参加にともない,松山市や近隣の市内にご宿泊予定のかたは,宿泊に関する簡単なアンケートに,ぜひご協力ください.
アンケートは本日(9/4)発送の確認書(【受付提出用】)の上段に記入欄が設けてあります.アンケート記入済みの【受付提出用】の書類を,愛媛大会の会場受付にてご提出ください.
2017.9.4更新 確認書を発送しました.
■■■
愛媛大会の事前参加登録をしたかた(参加費合計額が有料のかた)にあてて,確認書や記名済の名札,クーポン類(懇親会やお弁当を注文されたかたのみ)を発送いたしました.年会当日の受付にて,【受付提出用】の書類を全員に提出していただきますので,忘れずにご持参ください.
なお,参加登録費の合計金額が0円のかたには別途メールでご案内をいたします.
【お願い】事前参加登録者が都合により年会への参加をキャンセルしたい場合には,必ず日本地質学会事務局までご一報ください( 申込項目により取消料が異なります).
2017.9.4更新 【お詫び】講演プログラムのリンクを修正しました.
■■■
各シンポ・セッション毎の講演プログラム(PDF)へのリンク不備があり,プログラムをご覧いただけない状態が続いていました.PDFファイルへのリンク設定を修正しました.ご迷惑をおかけし,申し訳ありませんでした.
→愛媛大会の日程・講演プログラム.
2017.9.4更新 参加 or 講演キャンセル,発表者変更希望について
■■■
講演キャンセルをする場合は,必ず事前に行事委員会(会期前は学会事務局,会期中は学会本部)に連絡して下さい.また,やむを得ない事情により,あらかじめ連記された共同発表者内で発表者の変更を希望する場合も,必ず事前に行事委員会(会期前は学会事務局,会期中は学会本部)に連絡して下さい.この場合も,シンポジウムおよびアウトリーチセッション以外の場合は「会員に限り1人1題(発表負担金を支払った場合は2題)」の制限を守るものとします.代理人の代読,会場内での突然の発表者変更,発表順序の変更は認めません.
・(重要)キャンセルした講演の講演要旨の扱いについて
大会への参加をキャンセルする場合は,出来るだけ事前に学会事務局までご連絡をお願いいたします。また,お申込内容別に取消料が発生いたします。
▶取消に関わる取消料と返金について
連絡先:*[at]を@マークにして送信して下さい.
〜9/15まで:学会事務局<main[at]geosociety.jp>
9/16〜9/18:現地事務局
電話:080-5363-8921 <gsj2017ehime[at]academicbrains.jp>
愛媛大会に関する直前のご連絡
■■■
発表や大会参加に関する直前連絡,大会当日の連絡などを,本ページに公開します.
巡検参加について
巡検へ参加される方へ
1)愛媛大会への事前参加登録および巡検参加申込みは,8 月21日(月)に締め切りました.
締切時点で申込者数が最小催行人数に達しなかった一部のコースにつきましては,残念ながら催行中止となりました.催行コースの参加者への詳しい連絡は,各コースの案内者よりご連絡いたします.
巡検案内書は,今大会も地質学雑誌123巻7号および8 号(2017年7月および8月号)に掲載いたします.また,J-STAGE<http://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja>にて公開をいたします.なお,予告記事でもお知らせの通り,巡検参加者には各参加コース箇所の巡検案内書を巡検当日に配布します.
2) 重要 「野外見学,調査,試料採取における注意喚起」をご一読下さい
巡検へ参加される方は,参加の前に是非「野外見学,調査,試料採取における注意喚起」をご一読下さい。
「野外調査において心がけたいこと」国立・国定公園や史跡・名勝・天然記念物、あるいは一般的な露頭における調査上の注意点
「安全のしおり(巡検案内書より)」巡検や野外調査における安全上の注意点と自然保護に関する注意点
「巡検案内書を頼りに野外調査へ出かける方へ」露頭での調査や試料採取にあたっての注意点(「野外調査において心がけたいこと」から一部抜粋)
[巡検実施の可否について](2017年8月22日)
8月21日締切時点の巡検申込者数が,最小催行人数に達しなかったため,残念ながら一部の巡検コースは「中止」とさせて頂きます.催行中止となった各コースの参加者へは,別途直接ご連絡をいたします.
班
コース名
実施の可否
A
松山市周辺の瀬戸内火山岩類(9/19)
実施します
B
中央構造線断層帯の地形地質(9/19)
実施します
C
室戸ユネスコ世界ジオパーク(9/19〜20)
中止
D
四国西予ジオパーク(9/19)
実施します
E
久万層群と三崎層群(9/19〜20)
実施します
F
三波川帯(9/19〜20)
実施します
G
岩国ー柳井領家帯(9/19)
中止
H
アウトリーチ巡検(9/19)
中止
2017愛媛_保証・同意書
<郵送での要旨を投稿する場合は、原稿に必ず添付して下さい>
保証及び著作権譲渡等同意書(日本語版) PDF
Guaranty and Agreement(英語版)_PDF
一般社団法人日本地質学会 殿
保証及び著作権譲渡等同意書
著作者(下記)は,一般社団法人日本地質学会(以下,日本地質学会)によって発行される日本地質学会第124年学術大会(愛媛大会)「講演要旨集」に掲載する下記表題の原稿(以下「本原稿」という.)について,以下のとおり保証し,かつ著作権を譲渡等いたします.
第1 保証
著作者は,本原稿について,以下の各号記載の事項を保証し,確約します.
著者全員が投稿原稿を読み,投稿に同意していること.
本原稿が著作者自身の著作物であり,既にいずれかで出版公表されているものと同一ではないこと.
本原稿が既存の出版公表物などに対する知的財産権のいかなる侵害も含まないこと.
本原稿中に他から転載されているすべての図表について,転載許可を得ていること.
本原稿中,他の論文等の引用がある場合には,当該引用が公正な慣行に合致し,目的上正当な範囲内であること.
著作物には,日本地質学会の名誉を傷つけ,当該出版物の信用を毀損する盗用データ,捏造データ,著作物に関する利害を持つ者の合意に反するもの,その他学会の倫理綱領に反するものを含まないこと.
本原稿が共同著作物である場合には,代表して本書に署名捺印する者が,すべての共著者から,本書に著名捺印することについて同意ないし必要な権利を得ていること.
本原稿についての問い合わせ,苦情,紛争などが発生した場合,署名者はすべての責任を負うこと.
本著作物を作成するに当たって行われた調査・研究行為が,適切な方法でなされたものであること.
第2 著作権譲渡等
著作者は,本原稿について,以下の各号記載に同意します.
本原稿のすべての著作財産権(著作権法27条,同28条に定める権利を含む)及び2次著作物の創作・利用に係る権利を日本地質学会へ譲渡すること.
本原稿について,日本地質学会ならびに日本地質学会から正当に権利を取得した第3者及び当該第3者から権利を承継した者に対し,著作人格権(公表権,氏名表示権,同一性保持権)を行使しないこと
上記1項と矛盾する契約を他の第三者と締結しないこと.
本原稿の下記の各利用形態に関する権利を日本地質学会が排他的に行使すること.
a) 複製,翻訳,翻案(出版,電子出版,翻訳出版,データベース化,ビデオグラム化,その他すべての記録メディアへの記録・掲載などを含む)
b) 展示・上映
c) 放送,有線放送,自動公衆送信(地上波,CATV放送衛星,通信衛星,インターネット,パソコン通信,その他あらゆる送信媒体及び将来開発されるすべての送信媒体による公衆送信を含む)
d) 頒布,譲渡,貸与
e) その他,本著作物に関する一切の利用(技術の進歩により将来生じうる利用形態を含む)
以上
日付 年 月 日
本原稿表題
著作者(代表者) 印
署名者が代表する共著者すべての氏名
学会記入【講演番号: 】
学会記入【受付番号: 】
2017愛媛大会_招待講演者
日本地質学会第124年学術大会:セッション招待講演者
世話人や専門部会から提案され,行事委員会が承認したセッション招待講演者(予定)の概要を紹介します(タイトルをクリックする).なお,講演時間は変更になる場合があります.
トピックセッション(9件)
T1.文化地質学
T2.鬼界カルデラ研究の成果
T3.変動帯日本列島内安定陸塊
T4.日本列島の起源・成長・改変
T5.三次元地質モデル研究
T6.極々表層堆積学
T7.スロー地震の地質学
T8.中央構造線と活断層系
T9.「泥火山」
レギュラーセッション(25件)
R1.深成岩・火山岩
R2.岩石・鉱物・鉱床学一般
R3.噴火・火山発達史
R4.変成岩とテクトニクス
R5.地域地質・地域層序・年代層序
R6.ジオパーク
R7.グリーンタフ
R8.海洋地質
R9.堆積物の起源・組織・組成
R10.炭酸塩岩
R11.堆積過程・環境:地質
R12.石油・石炭地質
R13.岩石・鉱物の変形と反応
R14.沈み込み帯・陸上付加体
R15.テクトニクス
R16.古生物
R17.ジュラ系+
R18.情報地質とその利活用
R19.環境地質
R20.応用地質・ノンテク構造
R21.地学教育・地学史
R22.第四紀地質
R23.地球史
R24.原子力と地質科学
R25.鉱物資源と地球物質循環
T1. 文化地質学
・波田善夫(岡山理科大学生物地球学部生物地球学科:非会員)30分
波田氏(植物生態学,前岡山理科大学学長)は,1999年設立の岡山理科大学『岡山学』研究会の初代代表であり,2002年発行のシリーズ『岡山学』1の巻頭言に,「『岡山学』は,岡山というひとつの地域に焦点を当て,自然科学,人文科学,情報科学の分野を統合して総合的に検討しようとする試みです.」と述べている.講演での『岡山学』研究会設立のきっかけ,地質・地形,植物,農耕などは,文化地質学に指針を与えるものとなる.
・藤田勝代(深田地質研究所主任研究員,深田研ジオ鉄普及委員会幹事:会員)30分
「ジオ鉄」は,藤田氏が,2008年に加藤弘徳氏・横山俊治氏とともに,「国際惑星地球年」(2007-2009年)の理念に基づき,鉄道を利用して地質・地形を気軽に楽しむ旅行を企画構想したのが始まりである.2009年に第1路線JR四国土讃線のジオ鉄が,2011年に第3路線JR四国 予土線のジオ鉄が公表され,現在は第7路線「三陸鉄道」を取り組まれている.講演での「ジオ鉄」の課題意識や取り組みなどは,「文化地質学」の社会活用に有益である.
T2.最近の鬼界カルデラ研究の成果と今後の課題
・耼畑光博(都城市教育委員会:非会員)15分
耼原氏考古学分野の新進気鋭の研究者であり,ライフワークとして鬼界アカホヤ噴火より,南九州の縄文社会や文化の盛衰について,土器研究からアプローチしている.
・ 杉山真二((株)古環境研究センター:非会員)15分
杉山氏は考古学分野のシニア研究者である.彼はライフワークとして鬼界アカホヤ噴火より,南九州の環境変化を花粉,プラントオパール,珪藻等の生物遺骸からアプローチし,これまで多大な研究成果をあげている.
ページTOPに戻る
T3.変動帯日本列島内安定陸塊の探査
・趙 大鵬(東北大学理学部地球物理学科:非会員)30分
趙氏は,地震波トモグラフィーの日本における第一人者である.特に,西南日本におけるフィリッピン海プレートから日本海までの詳細な三次元P及びS波速度モデルを提案している.さらに,同じ場所の地震波減衰トモグラフィーも詳細に決めている.彼のデータは吉備高原安定陸塊説を支持している.指示する理由を詳細に説明する講演を期待している.
・松多信尚(岡山大学教育学部:非会員)30分
吉備高原域安定性の検証には,最先端活断層研究による検討が不可欠である.松多氏はフォッサマグナや台湾等の活断層に取り組んで来たが吉備高原域も研究している.変動地形の判読を数多くの地域で行っているほか,多くの活断層のトレンチ調査を遂行し活断層の判定能力は高い.さらに物理探査などの調査も広く取り入れて正確な活断層の抽出を行っている.安定性を地球科学的に示していく指針を深める重要な議論が期待される.
T4.日本列島の起源・成長・改変
・鳥海光弘(海洋研究開発機構イノベーション本部:会員) 15分
・土谷信高(岩手大学工学部:会員)15分
両氏は日本列島の地質を永年研究してきた実績を持つ.最近,ジルコン年代学による新たな新事実が次々に発見され,日本列島の地体構造の理解が大きく変わろうとしている.地域地質に深い理解を持つ両氏に講演していただくことによって,昨今忘れられがちな地域地質学の威力をアピール出来ると考える.是非講演を御願いしたい.
ページTOPに戻る
T5.三次元地質モデル研究の新展開
・西山昭一(応用地質(株):非会員)30分
西山氏は地質調査業界において長年第一線で各種三次元地質モデル構築を業務として取り組み,三次元モデラーを自社開発され,この分野で業界をリードされている.現在,土木・建築分野での三次元地質モデルの技術課題解決に向けたコンソーシアムをけん引されている.西山昭一氏には,本セッションにおいて,その事例と今後の課題を紹介して頂く.
・藤井哲哉((独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構:非会員)30分
藤井氏は,JOGMECのメタンハイドレート研究開発グループ課長を長年務め,これまでにメタンハイドレート開発にかかる多くの三次元地質モデリングや時間軸を含めた移動集積シミュレーションスタディを手がけており,国際誌掲載論文も多い.このため,今般,本セッションにおいて資源開発業界における地質モデリングに関する最新知見の提供を行っていただく.
T6.極々表層堆積学:「堆積物」への記録プロセスの理解
・池原 研(産業技術総合研究所:会員)30分
池原氏は,堆積学,海洋地質学を専門としており,東北沖や日本海,南海トラフなど幅広い海域において,現世から過去の堆積物を堆積学的に研究され,様々な環境での表層堆積物や表層での堆積・擾乱プロセスについて詳しい.特に,東北沖地震後の仙台湾やその沖合の表層コアを用いて,タービダイトの堆積プロセスや生物・振動による堆積物の擾乱について検討されており,堆積物の堆積・記録プロセスを語る上では欠かせないテーマである.上記の理由から池原氏を招待講演者として推薦した.
・長尾誠也(金沢大学環日本海域環境研究センター:非会員)30分
長尾氏は地球化学・環境放射化学を専門としており,河川水流域から海洋沿岸域において,放射性核種や安定同位体比を用いて移動する物質の起源推定や移行挙動を検討し,流域全体における物質循環について詳しく研究されている.地球化学的な視点から見た物質循環・動態の議論は堆積物の表層プロセスを理解する上で,不可欠である.上記の理由から長尾氏を招待講演者として推薦した.
T7.スロー地震の地質学
・小原一成(東京大学地震研究所:非会員)30分
小原氏は,スロー地震研究の第一人者である.小原氏に地震・測地観測から得られるスロー地震像を紹介して頂くことで,地質学的研究から得られるスロー地震像と今後どう共有し,互いにフィードバックさせながらスロー地震発生像の理解を深めていくのか議論したい.松山大会が開催される四国西部はスロー地震の活動が西南日本の中で最も活発な地域であるので,小原氏による招待講演は時期的・開催場所的に絶好の機会であると言える.
・Ake Fagereng(Cardiff University:非会員)30分
Fagereng氏は,スロー地震の地質学研究をリードする研究者である.Fagereng氏に地質学的に見たスロー地震の原因に関するこれまでの研究成果を紹介して頂き,地質学的にみた浅部と深部スロー地震の類似性と相違,ゆっくりすべりのレオロジーなどを議論したい.
ページTOPに戻る
T8.中央構造線と中央構造線活断層系
・斎藤 眞(産業技術総合研究所:会員)30分
斎藤氏は5万分の1地質図幅「砥用地域」,20万分の1地質図幅「八代及び野母崎の一部」などの調査・研究を通して,それまで中央構造線の延長と考えられてきた臼杵ー八代構造線の両側に同じ地質体が存在するとの知見を得,九州に中央構造線はないとの結論に達した.このことは,本セッションの中心的な課題とするところであり,招待講演者として選定した.
・伊藤谷生(帝京平成大学:会員)30分
伊藤氏は長年反射法地震波探査の研究に携わってきた.特に本セッションのテーマに関わっては,多数の共同研究者らとともに,四国東部の中央構造線を横断する30 km超の深部に及ぶ地質構造を明らかにしたことは特筆される.中央構造線と中央構造線系活断層帯との関係についての最新の知見が拝聴できることを期待して招待講演者として選定した.
T9.「泥火山」の新しい研究展開に向けて
・中野 優(海洋研究開発機構:非会員)30分
JAMSTECが熊野海盆から四国沖にかけて展開している地震・津波観測監視システム(DONET:Dense Oceanfloor Network system for Earthquakes and Tsunamis)は,南海トラフの地震,津波,地殻活動の観測のために,海底に設置された強震計,広帯域地震計,水圧計,温度計,ハイドロフォンなどによるデータを常時取得している.熊野海盆で既に知られる14の泥火山のうち海盆東側に分布するものは,一部がDONET敷設海域に重複するために,DONETがそれら泥火山の微細な活動をも捉えていると考えられる.しかしながら,未だDONETデータから泥火山活動に伴うシグナルを抽出するには至っていない.今後,熊野〜四国沖に分布する泥火山の活動を解明するにあたってDONETと泥火山研究の連携を模索するために,中野氏に,DONETが取得するデータや主に低周波地震に関する解析成果などについてご紹介をいただき,さらにDONETデータの利用方法や私たちが注目するべき泥火山活動に伴うシグナルの検出方法など議論を拡げていただく.
・中田亮一(海洋研究開発機構高知コア研:非会員)30分
中田亮一氏は新進気鋭の若手地球化学者で,水圏の希土類元素やその他の化学物質の挙動に関する研究など,多岐にわたるフィールドで活躍されている.泥火山もその一つとして研究されており,泥火山から排出される3つの異なる系(泥・水・ガス)を一つのシステムとして捉え,泥火山噴出物の起源物質や深度を求めた.また近年特に海洋資源開発などで注目度の高いREE(レアアースエレメント,希土類元素)が,泥火山を多く擁する油田地帯で濃集する過程を議論している.中田氏には油田地帯の泥火山における起源物質・深度・深度解析実例から,油田におけるREE濃集にかかる可能性まで,ご自身の一連の研究成果に沿ってご紹介いただく.
ページTOPに戻る
R1.深成岩・火山岩とマグマプロセス(招待講演なし)
R2.岩石・鉱物・鉱床学一般
・山田亮一(東北大:非会員)30分
山田氏は,長らく黒鉱鉱山の探査に従事され,その後,東北大にて黒鉱鉱床の成因を島弧発達過程の視点から研究されてきた.同氏の研究の時空間能の高いデータは,現世の海底熱水鉱床や岩石ー流体反応の広がりを理解する鍵となると期待される.招待講演では,黒鉱鉱床の変質とその時空間的広がりに関する最新の話題を提供して頂く予定でである.
R3.噴火・火山発達史と噴出物(招待講演なし)
R4.変成岩とテクトニクス
・高須 晃(島根大学:会員)30分
高須氏は,岩石組織観察と熱力学的な解析に基づき,国内外の高圧・超高圧変成岩を用いてプレート収斂域での物質移動に関する時空間スケールについての研究を展開してきた.特に,本大会を開催する愛媛県にも重要な露頭がいくつも存在する,四国中央部のエクロジャイトの研究では,低変成度の変成帯の中に温度圧力履歴の異なる高変成度の岩体が産することの発見と意味づけを行い,今日に至る三波川変成帯の研究史の中でも一つのターニングポイントとなる重要な貢献をしている.近年ではキルギスタンとの国際共同研究で天山山脈の高圧・超高圧変成岩を題材に大陸衝突帯の物質移動に関しても重要な知見をいくつも提示しており,その貢献もあり2012年にはキルギス国立科学アカデミーから名誉博士号を授与されている.高須氏には,高圧・超高圧変成岩の沈み込みと上昇過程,その際に伴われる物質移動を含めたプレート収斂域のダイナミクスに関する魅力的な講演を期待する.
・石塚英男(高知大学:会員)30分
石塚氏は,徹底した野外調査,岩石組織観察と相平衡岩石学的解析に基づき,国内外および陸域・海域の高圧型・高温型変成岩など幅広い地域・岩石を対象として,詳細な地質学的研究を推進してきた. 中でも,神居古潭変成帯,秩父帯などにおける詳細な変成分帯と全岩化学組成の融合に基づく原岩形成から変成作用に至る地史の解明,あるいは,日本南極地域観測隊の地質学分野の活動におけるセールロンダーネ山地やエンダービーランド地域などの先導的な調査・解析など,日本の地質学・岩石学にとって多岐にわたる重要な貢献が認められる.石塚氏には,多様な地域・岩石を対象としてきたからこそ得られた変成岩研究による地質学の重要性に関する講演を期待する.
R5.地域地質・地域層序・年代層序(招待講演なし)
R6.ジオパーク(招待講演なし)
R7.グリーンタフ(招待講演なし)
R8.海洋地質
・多田隆治(東京大学:会員)30分
多田隆治氏は海域および陸域双方の地質記録からアジアモンスーンの進化に関する研究を進め,2013年には自らが代表プロポーネントとして計画された日本海および東シナ海北部のIODP(国際深海掘削計画)Expedition 346に共同主席研究者として乗船した.現在,その成果がまとめられつつあり,そこから明らかにされつつあるアジアモンスーン変動の時代変化や日本海の海洋循環との関係に関する新知見などについてご講演頂く.
・池原 実(高知大学:会員)30分
池原 実氏は長年にわたって様々な指標を用いた古海洋学的研究を行っており,特に南大洋においてはIODPの掘削提案を行う中心的な役割を果たしている.今後数年間は南極海においてIODPによる掘削航海が立て続けに計画されていることなど,これから注目される研究テーマとして関心が向けられている.池原氏には,南大洋が気候変動に果たす役割について最新の研究成果や国内外の研究動向,今後の課題についてご講演頂く.
ページTOPに戻る
R9.堆積物(岩)の起源・組織・組成
・宮田雄一郎(山口大:会員)30分
宮田氏は,砕屑物の粒子形状・定向配列プロセスを中心に研究を実施されており,その結果は堆積場の判別や未固結変形過程の成因究明に応用されている.当セッションの重要課題の一つである砕屑物の組織についてご蓄積されてきた定量解析方法についてご講演頂き,砕屑物の形状・組織から何が読み取れるのかを考えるきっかけとしたい.
R10.炭酸塩岩の起源と地球環境
・浦田健作(大阪経済法科大:会員)30分
浦田氏は,カルストの主体となる洞窟と地表地形との関係を地下水によって結ばれたカルスト・システムとして捉え,地質学・地形学的観点からカルスト科学およびカルスト形成過程に関する研究に一貫して取り組んでいる.鍾乳石の地球化学的情報を用いた古環境解析が盛んに試みられているが,カルストそのものを古環境データベースと考えて日本各地のカルストについて炭酸塩岩の地質構造,地形形成,環境変動などの形性要因の影響を解明する研究も進めている.今回は,カルストシステム研究に関するレビューと最新の知見をご紹介いただき,カルストシステムや古環境復元についての研究をさらに発展させるきっかけとしたい.
R11.堆積過程・堆積環境・堆積地質
・成瀬 元(京都大学大学院理学研究科:会員)30分
成瀬氏は,堆積物重力流について,実験,野外調査,組織解析,モデリングといった多様な側面から,その挙動や堆積過程についての研究を行ってきた.成瀬氏はこの分野を世界的にリードする研究者の一人である.2015年に公表された,混濁流とその堆積物についての研究の方向性を示した論文は世界をリードする研究者らによって著されたのもので,成瀬氏はその著者の1人に名前を連ねている.成瀬氏には混濁流のモデリングについて,研究の方向性を含めたレビューを行って頂く予定である.今後の研究の方向性を議論する機会としたい.
ページTOPに戻る
R12.石油・石炭地質学と有機地球化学
・鈴木徳行(北海道大学:会員)30分
鈴木氏は有機地球化学的手法を用いた石油天然ガスの成因や探鉱に関する研究に一貫して取り組んでおり,この分野をリードする研究者である.また,バイオマーカーや炭素・水素同位体比に関する研究により,地球史や地球生物の進化についても数多くの業績を上げている.このような堆積有機物に関する研究は,炭化水素資源の成因論に留まらず,古海洋学,古気候学,古生物学,堆積学などの進歩と連動して地球生命システム科学の中心を担ってきた.本講演では,有機地球化学に基づく炭化水素資源・地球生物システムに関する幅広い知見をご紹介頂き,石油・石炭地質学および有機地球化学の更なる発展について考える機会としたい.
R13.岩石・鉱物の変形と反応
・増田俊明(静岡大:会員)30分
増田氏は,地殻由来の天然の岩石から歪み,応力,変形機構といった情報を読み取る構造地質学的研究に長年取り組んでおられる.講演では理論,実験,天然の解析と多岐に渡る研究成果から,天然の岩石から変形の各要素を読み取る手法の現状と展望についてお話いただき,2011年東北地方太平洋沖地震後に浮き上がった地殻の変形と応力状態の理解に向けて活発な議論を展開したい.
・内出崇彦(産総研:非会員)30分
内出氏は,微小地震から大地震まで規模の異なる多くの地震データの解析によって,震源過程の違いなど地震の性質を多様な観点から研究しておられる.講演ではこれまでの研究成果をご紹介いただき,地震学の観点から地殻の強度や地殻にかかる応力をいかに推定するか,その試みや問題点について活発な議論を展開したい.
R14.沈み込み帯・陸上付加体
・岡本 敦(東北大学:会員)30分
岡本氏は地殻におけるクラック形成,流体移動および鉱物脈沈殿プロセスの解明のために,野外調査,岩石化学分析,室内実験による鉱物脈合成およびモデリングなどの幅広い手法を用いて研究をされてきた.研究結果は,国際論文としてこれまで数多く公表されている.岡本氏の研究成果は,沈み込み帯における流体・物質移動,物性変化,地震発生といった幅広い分野にわたって関連するものであり,本セッションに参加する研究者の様々な視点による議論が期待できる.
・山本由弦(JAMSTEC:会員)30分
山本氏は,主として新第三系三浦ー房総付加体を対象に構造地質学的研究を精力的に進め,浅部での付加体・前弧海盆発達過程,帯磁率異方性を用いた歪み履歴の解析,シュードタキライトの発見など重要な研究成果をあげられてきた.最近では,地球深部探査船「ちきゅう」による室戸沖限界生命圏掘削調査(T-Limit)に乗船参加し,プレート境界断層の記載を行っている.本招待講演では,山本氏がこれまでに明らかにしてきた浅部プレート境界断層の実像について紹介して頂く予定である.
ページTOPに戻る
R15.テクトニクス
・大坪 誠(産総研:会員)30分
大坪会員は,過去から現在にいたる地殻のダイナミクスの理解をめざし,日本列島各地で応力逆解析による過去から現在にいたる地殻応力の解明などに取り組んでおられる.本講演では,海溝型巨大地震に関連する大規模断層と考えられる宮崎県延岡衝上断層の運動像を,応力の時間変化と流体の関与を中心に,南海トラフ海溝型巨大地震の迫る四国における招待講演として期待する.
・北 佐枝子(広島大:非会員)30分
北氏は,東北大学理学部時代に断層岩を学んだ経験のある稀有な地震学者であり,東北日本沈み込み帯のスラブ内地震の発生機構や,日高山脈下の地球内部構造など,日本列島下のテクトニクスに一石を投じる研究を精力的に進められている.近年取り組んでおられる南海トラフのスロー地震と地震波減衰構造の研究を中心に,南海トラフのスロー地震発生域のほぼ直上に位置する松山での招待講演をお願いしたい.
R16.古生物(招待講演なし)
R17.ジュラ系+
・佐野晋一(福井県立恐竜博:会員)30分
佐野氏は厚歯二枚貝の研究を牽引してきた.また,ベレムナイトの研究も共同研究者とともに進めている.これまでにこれらの分類群について多くの研究業績をあげている.近年,佐野氏はジュラ・白亜系の手取層群について,層序の再検討を積極的に行っている.招待講演では,アジアにおけるジュラ系・白亜系境界の広域対比に関する講演を期待している.
ページTOPに戻る
R18.情報地質とその利活用(招待講演なし)
R19.環境地質(招待講演なし)
R20.応用地質学一般およびノンテクトニック構造
・奥野 充(福岡大:会員)30分
奥野氏は九州の火山を中心に,年代測定をもとにした火山の噴火史に関する研究を続けられてきた.2016年熊本地震をきかっけに,火山体の崩壊・地すべりについても調査されている.本講演では阿蘇カルデラ内,京大火山研究センターなどで発生したアースフローの特徴や成因・メカニズムについて報告していただき,火山地域で発生する地すべりについて理解を深める糧としたい.
R21.地学教育・地学史(招待講演なし)
R22.第四紀地質(招待講演なし)
R23.地球史
・牛久保孝行(海洋研究開発機構高知コア研究所:非会員)30分
牛久保氏は,二次イオン質量分析計を用いた局所同位体分析の専門家である.その研究対象は多岐に渡り,地球の岩石だけでなく隕石研究でも多くの業績を出されている.今回の地球史セッションでは,地球初期のジルコンの研究や,原生代の硫黄同位体分析について紹介していただく.
・亀山真典(愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センター:非会員)30分
亀山氏は,マントルダイナミクス研究の第一人者である.数値シミュレーションによるマントルダイナミクスの研究や,シミュレーションに必要な計算手法の開発で,これまで多くの業績をあげてこられた.地球史セッションでは,超大陸サイクルやマントル深部の熱化学構造の理解を目指した最新の研究成果について講演していただく.
ページTOPに戻る
R24.原子力と地質科学
・小林大和(経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部放射性廃棄物対策課課長:非会員)30分
小林氏は,経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部 放射性廃棄物対策課課長として,日本の地質環境における地層処分の実施可能性について,国の審議委員会である放射性廃棄物ワーキンググループ等での議論の取りまとめを行っており,今後の地層処分事業/研究開発の現場と課題について最新の話題を提供していただく.
・大江俊昭(東海大学工学部原子力工学科:非会員)30分
大江氏は,核化学や元素の拡散,吸着現象などの地球化学的な観点から,放射性元素の粘土中での挙動,反応についての研究を進めつつ,そのモデルシュミレーションに関する研究を専門的に展開してきた.とくに近年では,地層処分における人工バリア材料と天然バリア(地質環境)との相互反応に着目した研究を実施している.これらの知見は,地層処分のサイト選定やサイト調査において不可欠であり,当該分野の最新の話題を提供していただく.
R25.鉱物資源と地球物質循環
・高橋嘉夫(東京大:非会員)30分
高橋氏は,放射光をはじめとする最先端のツールを駆使して原子・分子レベルの化学的素過程を突き詰めることで,地球における物質循環,環境変動,さらには資源形成に至るまでをも明らかにする,地球化学の第一人者である.資源に関する研究においても,有用元素の挙動と濃集プロセスを原子・分子レベルで突き止め,そこから今まで明らかとなっていなかった資源の成因を次々に解き明かしており,そのお話を聞ける機会は,資源研究者をはじめとする聴講者にとって非常に有意義なものになるはずである.本講演では,資源成因を明らかにするための最先端の手法と成果について話題を提供して頂く予定である.
企業研究サポート:報告(2016東京・桜上水大会)
若手会員のための地質関連企業研究サポート:報告
若手会員のための地質関連企業研究サポート
(2016東京・桜上水大会 報告)
企業個別ブースでの説明の様子 休憩室でのPRの様子
企業個別ブースでの説明の様子
休憩室でのPRの様子
熊本地震,豪雨災害にも見舞われた今年は,阪神淡路大震災から20年,東日本大震災から5 年の年になり,“防災”や“環境”に関して重要な理学である地質学に対して社会的要請が一層強くなった年でした.また,今後の日本のエネルギー政策として“地熱”・“地下資源”も注目を集めています.地質学会では,実際に企業で活躍されている地質技術者と語り合い,大学で学んだ地質学が企業でどのように生かされているのか,学生・大学院生および教員の方々が,企業の生の声を聴くことができるような場を提供したいと考え,今年も就職支援プログラムを開催しました.今回は10回目で,経団連の「採用選考に関する指針」を踏まえて行っています.
事前のPRとしては,学会HPの他,大学関係者向けにポスター配布を行いました.開催当日は,例年と同様に,大会2 日目の午後2 時半から5 時まで行い,例年とほぼ同数の民間企業9社が参加しました.
今年の会場は,学術大会会場と同じ建屋の4 階で参加しやすい場所でしたが,会場の都合で隣2 部屋に分かれての開催となり,学生の方に両方の部屋を訪問して頂くことの難しさを感じました.また,今年も昨年と同様に,会員休憩室にプロジェクタを設置し参加企業の説明スライドを上映する,当日午後から会員が集まる場所での呼び込みを行うなどのPRを行いました.参加者は,昨年度よりもやや少ないものの30余人の学生・院生の方々が参加し,企業の個別ブースで業界のこと,業界での技術者としての活躍を熱心に聞く姿が見られました.
来年度も,就職希望の学生・院生の皆様,教員の皆様には,ぜひ会場に足を運んでいただき,企業での地質技術者の活躍の様子について大いに情報収集していただくようお願いいたします.
最後に,本行事に参加いただいた企業9社の皆様,企画にご協力いただいた賛助会員,関連企業の皆様,および大会準備委員会,行事委員各位に,改めて御礼申し上げます.
緒方信一(運営財政部会担当 執行理事)
参加企業一覧(順不同)
エネルギー・測量・設計・解析グループ
・石油資源開発株式会社
・三井石油開発株式会社
・株式会社パスコ
・株式会社建設技術研究所
・株式会社地層科学研究所
地質調査グループ
・川崎地質株式会社
・株式会社地圏総合コンサルタント
・日本綜合建設株式会社
・中央開発株式会社
▶2017(愛媛大会)出展募集に戻る
参加登録TOP
2017愛媛大会事前参加登録のご案内
下のフローチャートに従って進み,該当する申込画面をクリックして
それぞれ申込手続きをおこなって下さい.
事前参加登録締切:8月21日(木)18時(web)
FAX/郵送:8月14日(月)必着
参加登録に関わるお申込(参加,要旨集,巡検,懇親会,弁当)は,オンラインによる大会専用参加登録システム(会員・非会員にかかわらずどなたでも申込可)をご利用の上,お申し込み下さい.
郵送で申し込む場合は,学会事務局までお問い合わせ下さい.郵送用申込書等必要な書式をお送りします.提出書類をご準備の上,8月14日(月)必着で学会事務局までお送り下さい.
大会参加登録およびそれに伴う参加費は,参加者(巡検のみ参加の場合も)に必要な基本的なお申し込みです.会員が同伴する非会員の家族等(以下,同伴者)についても懇親会・巡検・お弁当については事前に申込が必要です.申込は,会員と同伴者の計2名まで一括申込が可能です.
画面 A へ
画面 B へ
画面 C へ
※巡検協賛学協会・セッション共催団体リストはこちらから
参考>>会員情報を自動取得するには?(PDF)
2018札幌大会_スケジュール
札幌大会に向けてのスケジュール
プレページTOP画面に戻る
札幌大会に向けてのスケジュール
会期に合わせ,例年より2 〜3週間早めの日程になります.各項目に関して,余裕をもってご準備をお願いします.
3月12日(月)トピックセッション募集締切
4月末(ニュース誌4月号)大会予告記事(演題登録・講演要旨受付開始)
6月13日(水)演題登録・講演要旨受付締切
7月末(ニュース誌7月号)大会プログラム記事
8月初旬〜10日頃 大会参加登録/巡検/懇親会参加申込締切
9月5日(水)〜7日(金)第125年学術大会(札幌大会)
9月8日(土)〜9日(日)ポスト巡検
大会申込Q&A
大会申込Q&A
【演題登録編】 >>【参加登録編】へ
Q:演題登録専用のアカウント登録をしたはずなのにログインできません.
A:
アカウント登録しただけでは、登録完了にはなりません(仮登録の状態です)。
アカウント登録後、登録したメールアドレスあてに
【日本地質学会第126年学術大会(2019山口大会)】メールアドレス本登録のお願い
という自動返信メールが配信されます.このメール文中に明記されているURLをクリックし,本登録を完了させてください.ここまでの操作を行えば,任意で登録した〔ログインID〕と〔パスワード〕でログインできるようになります.
※URLのリンクの有効期限は本メール送信日時より24時間以内となっておりますので,ご注意ください.
Q:1人何題まで発表できますか?
A:
トピック・レギュラーセッション(全31セッション)では,1人2題まで発表できます.ただし2題発表する場合には発表負担金(1,500円)をお支払い下さい(1題のみの場合は無料).また,同一セッション内で口頭2件やポスター2件の発表はできません.詳しくは,セッション発表の募集要領『2)発表に関する条件・制約』を参照してください.
Q:発表負担金はどこで支払えばよいですか?
A:
演題登録画面には課金システム機能はありません. 事前参加登録画面にトピックセッション(T1〜T7)・レギュラーセッション(R1〜R25)での発表件数を選択する項目があります.『2件(1,500円)』を選択いただければ,事前参加登録費とともに発表負担金も課金され請求されます.
※トピック・レギュラーセッションにて招待講演者になっている発表者が,もう1題を別セッション(または招待されているセッションと同一セッションの異なる発表形式)で一般発表する場合には,発表負担金(1,500円)は発生しません(招待講演分は発表負担金の発生する”2件目”としてカウントしません).
Q:非会員も演題登録(発表)はできますか?
A:
招待講演者を除き,非会員の発表はできません.現在,非会員のかたで山口大会において発表を予定されているかたは,演題登録に合わせて入会申込の手続きもしてください(締切時点で入会申込が確認できない場合,登録が取り消されます).セッション共催団体の会員は共催セッションのみ発表できますが,それ以外の他セッションで発表を希望する場合には,必ず入会手続きを行ってください.
Q:入会申込中(承認待ち)のため,会員番号(ID)もないのですが,演題登録はできますか?
A:
入会承認がまだのかたでも演題登録はできます.お早めにアカウント登録の手続きをしてください.会員区分の項目欄に『入会申込中』と入力してください.会員番号等の入力方法については注釈に従ってください.
Q:筆頭著者でなければ発表はできないのですか?
A:
筆頭著者でなくても発表は可能です(筆頭著者は会員・非会員を問いません).
ただし,発表者は地質学会の会員でなければなりません.
共同発表(複数の著者の発表)の場合には,講演要旨(pdf)に明記する著者名の
うち,発表者が分かるように発表者氏名に下線を引いてください.
※非会員が発表者になっている場合には,登録が取り消される場合があります.
Q:過去大会において急遽発表をキャンセルしました.今大会で同内容で発表したいのですが.演題登録してもいいですか?
A:
前回の学術大会にて発表を申し込まれた講演を講演要旨印刷後にキャンセルした場合,該当講演の要旨は印刷物として存在することになります.キャンセルした講演の要旨を再掲し,発表を希望する場合は,再掲する要旨に「本講演は第○○年学術大会にて発表をキャンセルしたもので,本講演要旨は第○○年学術大会講演要旨集に掲載されたものを再掲したものである」旨を明記してください.
詳しくは行事委員会から発表の『キャンセルした講演の講演要旨の扱いについて』を参照して下さい.
Q:演題登録画面のキーワードの入力欄を増やす方法は,どうすればよいですか.
A:
キーワードはデフォルトで5件まで入力できるようになっています.入力欄を増やしたい場合は,【追加】ボタンをクリックしてください.キーワードは最大10件まで登録できます.
※キーワードの入力は任意です(必須項目ではありません).
※『所属機関情報』や『著者情報』の件数・人数入力欄の増減も同様の操作で対応できます.
Q:演題登録画面の『著者情報』に21人以上の共著者を登録したいのですが.
A:
演題登録画面上では『著者情報』の入力は最大20件までしか登録できません.
21人以上登録したい場合には,演題登録時の受付番号(C00〜ではじまる数字)と21人目〜の著者情報(氏名と所属先名:和英とも)を学会事務局に連絡してください.プログラム作成時に反映します.
Q:講演要旨がまだ出来上がっていないので,演題登録ができません.どうしたらいいですか?
A:
完成原稿の有無に関係なく、まず先に アカウント登録 を行ってください.
演題登録画面には”講演情報”のほかに,”著者・所属機関情報(一度登録しておけば書き換える必要の無い項目)”の入力もあります.締め切り間際になってから全ての項目を登録しようとするのではなく,発表題目や共著者情報などはとりあえず”仮情報”で構いませんので,まずはアカウント登録しておくことをおすすめします.”講演情報”も,”著者・所属機関情報”も締切日時まで繰り返し修正していただけます.
※締切(7/3(水),18時)までには,完成原稿をアップロードしてください!!
Q:(演題登録締切後)講演要旨に誤りを見つけてしまったので,差し替えたいのですが.
A:
演題登録締切後,著者(発表者)の都合による要旨の差替え(演題内容の修正)依頼は受け付けません.
演題登録締切後,すぐにプログラムデータの整理・講演要旨の校閲作業を開始し,限られた時間の中で各世話人が要旨の校閲作業をしております.
修正原稿は,その都度校閲をしなければならなくなり,世話人の手間も増えることとなりますから,期日内にきちんと講演要旨を完成させ,登録を済ませていただきますよう,何卒ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします.
※要旨の校閲後に世話人から修正を求められた際,求められた箇所以外の修正をしてしまう著者(発表者)がまれにいますが,世話人に指摘された箇所のみを修正してください.
Q:演題登録の締切は延長されますか?
A:
演題登録の締切延長はありません.7月3日(水)18時締切厳守(郵送は6/26(木)必着)です.余裕をもってお早めにご登録ください.
【参加登録編】
Q:講演要旨は付きますか?
A:
参加登録費が有料か無料かで異なります(詳しくはこちらもご覧下さい).
(a)参加登録費が有料のかたには,必ず講演要旨集が1冊付きます.
→正会員・院生割引会費適用正会員・非会員一般・非会員院生
(b)参加登録費が無料のかたには,講演要旨集は付きません.
→名誉会員・50年会員・学部割引会費適用正会員・非会員学部学生・
非会員招待者・同伴者(非会員で会員の家族に限る)
※(b)のかたが講演要旨を希望する場合は,別途ご購入ください.
事前参加登録の『追加講演要旨』の注文欄で【注文する】を選択し,
『冊数選択』欄と『受取方法』欄の項目も選択して,お申し込みください.
Q:地質学会会員が招待講演者になった場合,参加登録費はどうなりますか.
A:
学会員は参加登録費は有料です(免除にはなりません).必ず参加登録してください.
※シンポジウム,各セッションともに,参加登録費が免除になるのは,非会員招待講演者に限ります.
Q:講演要旨集の「後日発送」は,いつ頃送付されてきますか?
A:
大会会期終了後の発送です(別途送料がかかります).会期前の送付はできません.
Q:キャンセル料(取消料)はかかりますか?
A:
事前参加申込期間中の変更・キャンセルの場合は取消料はかかりません.締切後につきましては,申し込んだものにより,キャンセル料がそれぞれ異なりますのでご注意ください.
参照>>2019年山口大会取消に関わる取消料と返金について
Q:Web上で事前参加登録をしましたが,確認メールが届きません.
A:
入力したメールアドレスが間違っている可能性があります.学会事務局へ連絡してください.
Q:事前参加登録をしましたが,登録内容の修正の仕方が分かりません.
A:
事前参加登録の申込時に,①[初回申込]確認,②[ご請求]連絡の2通のメールが必ず自動返信されています(クレジット決済まで完了した人は③決済完了のお知らせメールも届きます).
[初回申込]確認メールの文中には,
・【変更・修正】および【取消】操作をおこなうための案内
・【変更・修正】および【取消】操作の画面にログインするためのURL
・ログインに必要な[お申込No.]と[パスワード]
が明記されております.説明をよく読んでお手続きください.
※できるだけ,一番最初に取得した[お申込No.]と[パスワード]で登録内容の【変更・修正】をしてください.何度も何度も新規でお申込すると,[お申込No.]と[パスワード]を登録した回数分取得することになり,重複申込者の確認漏れの原因にもなります.
Q:参加費無料の会員種別の人は,事前登録をしなくてもよいですか?
A:
当日の参加登録でも構いません.ただし,講演要旨の購入を希望される場合は,数に限りがあり,事前予約と当日購入では冊子体の価格が異なりますので,事前参加登録にてご予約することをおすすめします.ここ数年,大会会期中に講演要旨集の売り切れが続いておりますので,なるだけ事前にお申込みください.
Q:代理での申込はできますか?
A:
可能です.ただし,申込の重複や連絡先/発送先の登録には注意してください.とくに非会員招待講演者や外国人招待者などを代理で登録する場合は,代理で登録してくださるかたの連絡先を確認書やクーポンの送付先として登録してください(海外の住所では,確認書やクーポンの発送を,ご本人の手元に届くよう間に合わせることができません).また,登録時の確認メールは日本語のみです.
Q:巡検だけに参加したいのですが.
A:
巡検だけに参加希望のかたは,事前参加登録【画面A】からお申込ください.
巡検申込専用画面をご用意しました.
Q:大会には参加しませんが,講演要旨だけの購入はできますか?
A:
講演要旨だけの予約購入も可能です.事前参加登録【画面B】からお申し込みください.ただし,講演要旨の発送は大会終了後になりますので,ご了承ください.
Q:Web登録がうまくできません。
A:
連絡先など,登録情報の自動取得が行えない場合はこちらを参考にしてください(自動取得は日本地質学会会員のみ利用できます).
正しく操作を行っているにも関わらず,エラーが出る場合は学会事務局へご連絡ください.
※会員情報の取得が可能なかたは,日本地質学会会員(web上の会員情報に登録されている会員のかた)に限ります.
※新入会員のかたは,会員情報の取得はできません.直接,必要事項を入力して登録してください.
Q:クレジット決済ができません。
A:
次のような場合はクレジット決済ができません.
○タブレット(iPadやスマートフォンなど)で事前参加登録をした場合.
タブレット(iPadやスマートフォンなど)は対応機種にはなっていませんので,クレジット決済はご利用できません.クレジット決済をしたいかたは,PCをご利用ください.
○勤務先のサーバーのセキュリティレベルの都合.
所属先のPCから事前参加登録をし,クレジット決済をしようとしたところ,クレジット決済の画面に切り替わらないことがあります(所属先のサーバーのセキュリティレベルの都合でクレジット決済ができないようです).その場合はご自宅のPC(個人でプロバイダ契約しているサーバー経由)から事前登録しクレジット決済を行ってください.
Q:同伴者の欄に【大学の友人】や【職場の同僚】を登録してもいいですか?
A:
【大学の友人】や【職場の同僚】は同伴者にはなれません.それぞれ別個に参加登録してください.あくまでも,同伴者は【会員の家族】を想定しての申し込み欄です.なお,会員の家族でも夫婦や親子で地質学会会員の場合は,同伴者にはなれませんので,別個に会員として参加登録してください.
Q:私は地質学会会員(正会員)ですが,所属先の身分は大学院生なので【正[院生割引]会員】の会員種別で参加登録してもよいですか?
A:
大学院生でも正会員のかたは,【 正 会 員 】で参加登録してください.
【正[院生割引]会員】として参加登録できるのは,今年度にかかる割引会費申請者に限ります.申請を出さなかった会員(今年度の学会費が12,000円だった人)は【正会員】ですので,正会員の会員種別で参加登録してください.
※今年度の割引会費の申請は,今年の3月末で締め切りました.今から遡って申請することはできません.
Q:私は地質学会会員(正会員)ですが,セッション共催団体では院生会員なので,そちらの会員種別で参加登録してもよいですか?
A:
地質学会会員のかたは,地質学会の会員種別で参加登録してください.
「セッション共催団体」の会員種別でお申し込みできるのは,地質学会非会員のかたに限ります.
Q:事前参加登録をしたのに,確認書の参加費が当日払いの金額になって届きました.
A:
事前参加登録をしても,確認書を郵送する時点で参加登録費の入金が確認できなかった場合は,当日の参加登録費の金額で確認書を発行し,ご請求します.
所属先(会社や大学,研究所)からの公費払いの都合で,参加登録費の入金が遅くなる場合は,この限りではありませんが,必ず学会事務局に予めの連絡をしてください.
Q:昨年,確認書やクーポンが届きませんでした./大会終了後に受け取りました.
A:
確認書やクーポンは郵送でお送りします.申込の際,発送時期に確実に届く住所を記入・入力してください(所属先へ送付を希望される方は,とくにご注意ください).発送は大会10日前にはお手元に届くように発送する予定です.締切後に送付先変更を希望される場合は,学会事務局へご連絡ください.また,下記のような場合にも早めにご連絡ください.
例1)会社勤めのかた:大会直前まで出張(現場で野外調査)し,出張先から大会に参加するため,出張先(宿泊先)に確認書やクーポンを送ってほしい./直接大会会場で受け取りたい.
例2)大学職員・学生のかた:夏季休暇中は事務が閉まっていて,郵送物が届きにくい/届かない.
Q:宿泊予約はできますか?
A:
事前参加登録システムからは宿泊予約はお受けしておりません.各自手配をお願いします.また下記の情報もご参考にして下さい.
※宿泊予約はお早めに
★ 宿泊予約のご案内 7/30(火)締切 取扱(株)防長トラベル
★ 若手会員向け ルームシェア型宿泊プランのご案内 7/31(水)締切 先着順
Q:自分の疑問が解決する答えが載っていませんでした.
A:
ご不明な点がありましたら,学会事務局へご連絡ください.
学術大会保証・同意書
※学術大会の講演要旨投稿では,オンライン画面上で「保証書」と「著作権譲渡等同意書」の内容に同意していただいてから電子投稿画面に進めるようになっています.
一般社団法人日本地質学会 殿
保証及び著作権譲渡等同意書
著作者(下記)は,一般社団法人日本地質学会(以下,日本地質学会)によって発行される日本地質学会学術大会「講演要旨集」に掲載する下記表題の原稿(以下「本原稿」という.)について,以下のとおり保証し,かつ著作権を譲渡等いたします.
第1 保証
著作者は,本原稿について,以下の各号記載の事項を保証し,確約します.
著者全員が投稿原稿を読み,投稿に同意していること.
本原稿が著作者自身の著作物であり,既にいずれかで出版公表されているものと同一ではないこと.
本原稿が既存の出版公表物などに対する知的財産権のいかなる侵害も含まないこと.
本原稿中に他から転載されているすべての図表について,転載許可を得ていること.
本原稿中,他の論文等の引用がある場合には,当該引用が公正な慣行に合致し,目的上正当な範囲内であること.
著作物には,日本地質学会の名誉を傷つけ,当該出版物の信用を毀損する盗用データ,捏造データ,著作物に関する利害を持つ者の合意に反するもの,その他学会の倫理綱領に反するものを含まないこと.
本原稿が共同著作物である場合には,代表して本書に署名捺印する者が,すべての共著者から,本書に著名捺印することについて同意ないし必要な権利を得ていること.
本原稿についての問い合わせ,苦情,紛争などが発生した場合,署名者はすべての責任を負うこと.
本著作物を作成するに当たって行われた調査・研究行為が,適切な方法でなされたものであること.
第2 著作権譲渡等
著作者は,本原稿について,以下の各号記載に同意します.
本原稿のすべての著作財産権(著作権法27条,同28条に定める権利を含む)及び2次著作物の創作・利用に係る権利を日本地質学会へ譲渡すること.
本原稿について,日本地質学会ならびに日本地質学会から正当に権利を取得した第3者及び当該第3者から権利を承継した者に対し,著作人格権(公表権,氏名表示権,同一性保持権)を行使しないこと
上記1項と矛盾する契約を他の第三者と締結しないこと.
本原稿の下記の各利用形態に関する権利を日本地質学会が排他的に行使すること.
a) 複製,翻訳,翻案(出版,電子出版,翻訳出版,データベース化,ビデオグラム化,その他すべての記録メディアへの記録・掲載などを含む)
b) 展示・上映
c) 放送,有線放送,自動公衆送信(地上波,CATV放送衛星,通信衛星,インターネット,パソコン通信,その他あらゆる送信媒体及び将来開発されるすべての送信媒体による公衆送信を含む)
d) 頒布,譲渡,貸与
e) その他,本著作物に関する一切の利用(技術の進歩により将来生じうる利用形態を含む)
以上
日付 年 月 日
本原稿表題
著作者(代表者) 印
署名者が代表する共著者すべての氏名
学会記入【講演番号: 】
学会記入【受付番号: 】
2018札幌_招待講演
日本地質学会第125年学術大会:セッション招待講演者
世話人や専門部会から提案され,行事委員会が承認したセッション招待講演者を紹介します(タイトルをクリックする).なお,講演時間は変更になる場合があります.
トピックセッション(6件)
T1.文化地質学
T2.モホ(地殻ーマントル)
T3.日本列島の起源・成長・改変
T4.深海科学掘削50年
T5.北海道の地震・津波研究
T6.泥火山
レギュラーセッション(25件)
R1.深成岩・火山岩
R2.岩石・鉱物・鉱床学一般
R3.噴火・火山発達史
R4.変成岩とテクトニクス
R5.地域地質・地域層序・年代層序
R6.ジオパーク
R7.グリーンタフ
R8.海洋地質
R9.堆積物の起源・組織・組成
R10.炭酸塩岩
R11.堆積過程・環境:地質
R12.石油・石炭地質
R13.岩石・鉱物の変形と反応
R14.沈み込み帯・陸上付加体
R15.テクトニクス
R16.古生物
R17.ジュラ系+
R18.情報地質とその利活用
R19.環境地質
R20.応用地質・ノンテク構造
R21.地学教育・地学史
R22.第四紀地質
R23.地球史
R24.原子力と地質科学
R25.鉱物資源と地球物質循環
T1. 文化地質学
■児島恭子(札幌学院大学:非会員)30分
児島氏(札幌学院大学教授;アイヌ史,日本史)は,民俗学や文化史にも詳しく,『エミシ・エゾからアイヌへ』(2009)という優れた著書がある.また,児島氏は,〈アイヌ語地名の政治学〉の観点から,アイヌ世界の地名発生について,地名の起源や地名を巡る歴史を,アイヌ史を援用して議論している.北海道のみならず日本列島各地に散見される〈アイヌ語地名〉の理解を深めることは,文化地質学においても新たな視点を与えるものとなる.
■百瀬 響(北海道教育大学:非会員)30分
百瀬氏(北海道教育大学教授;文化人類学,北方文化)は,アイヌ文化および北方少数民族に関する文化人類学的研究を主要テーマとしている.また,アイヌ文化のみならずロシア極東の北方少数民族にも詳しく,フィールドワークの経験も豊富である.北海道のアイヌ文化やロシアの北方文化についての多様性や現代的課題の知識は,伝説・伝承を対象とした事例研究では特に重視されるべきで,文化地質学への有用な知見を提供するものである.
T2.モホ(地殻ーマントル境界)を掘り抜いたオマーン掘削プロジェクト(招待講演なし)
T3.日本列島の起源・成長・改変
■土谷信高(岩手大学:会員)15分
土谷会員は,日本列島の地質を永年研究してきた実績を持つ.最近,ジルコン年代学による新たな新事実が次々に発見され,日本列島の地体構造の理解が大きく変わろうとしている.
■野田 篤(産業技術総合研究所:会員)15分
野田会員は,西南日本の白亜系和泉層群を対象に野外調査を行い,さらに世界の前弧盆地一般の形成過程についてのコンパイルに基づき新しい解釈を提案している.日本の地域地質に関する深い知識から世界に向けて新しい概念を導きつつある両会員に講演していただくことによって,昨今忘れられがちな地域地質学の威力をアピール出来ると考える.是非講演をお願いしたい.
ページTOPに戻る
T4.深海科学掘削50年,過去—現在—未来
■平 朝彦(海洋研究開発機構:会員)30分
平会員は,四万十帯陸上地質研究から南海トラフの海域調査研究,掘削研究まで幅広く活躍され,深海掘削研究のリーダーとして長く国内研究コミュニティーを牽引してきた.地球深部探査船「ちきゅう」の建造やIODPの立ち上げなどにも中心的に貢献されてきた経験から,これまでの深海掘削の成果のポイントをまとめ,これからの深海掘削に求められる研究についての大所高所からの視点で講演を依頼したい.
■野木義史(国立極地研究所:非会員)15分
地球環境の敏感なレスポンスとして極域での研究が注目されているが,野木氏は極域研究のリーダーとして活躍され,また深海掘削航海の経験も持ち合わせ,極域における深海掘削の新たな視点から,今後の方向性を含めた講演を依頼したい.
T5.北海道とその周辺地域における地震・津波研究の最前線
■谷岡勇市郎(北海道大学:非会員)30分
谷岡氏は,津波波源に関する数値計算の専門家であり,北海道の太平洋側や日本海側での多くの研究業績がある.また北海道行政における津波想定に関して各種委員を務め,北海道の津波防災に関する最新の知見を有している.
■平川一臣(北海道大学名誉教授:非会員)30分
平川氏は,北海道の太平洋や日本海沿岸において,津波堆積物に関する先駆的な取り組みを行っており,津波履歴の復元や波源の推定に関する多くの成果がある.谷岡氏と同様,行政の津波想定に関する委員を務めており,最新の知見を有している.これらから,両氏は招待講演者として適任であると考える.
ページTOPに戻る
T6.泥火山と地球化学的・地質地形学的・生物学的関連現象
■田近 淳((株)ドーコン:会員)30分
日本における泥火山研究は,ここ北海道新冠地方の陸上泥火山から始まった.陸上の泥火山は海底のそれとは異なり,再訪性が高く緻密な常時観測が可能である点で,いまだ完全に理解されたとは言い難い泥火山の研究を推し進めるに重要な研究対象である.新冠泥火山と十勝沖地震との関連やそれらの活動の背景などについて,元北海道立地質研究所の田近会員により詳細なご講演をいただく.
ページTOPに戻る
R1.深成岩・火山岩とマグマプロセス(招待講演なし)
R2.岩石・鉱物・鉱床学一般
■木村純一(JAMSTEC:会員)30分
木村会員は,島弧沈み込み帯火山岩の岩石学的・地球化学的研究を通じ,島弧マグマの成因解明に取り組んでこられた.近年は,沈み込む海洋プレートスラブの脱水・変成過程,脱水したスラブフルイドが引き起こすマントルウェッジかんらん岩の融解による島弧初生マグマの生成過程を研究されている.この研究ではこれらの過程における鉱物や岩石,流体やマグマの元素マスバランスを解くことによって,スラブ・マントル・地殻内の物理化学条件を推定する事を試みている.さらに,地球化学モデルと岩石学的観察事実や地球物理学的観測結果の間の整合性を検討することにより, 島弧沈み込み帯でおこる複雑な 地質現象に重要な
制約を与えることに成功している.本招待講演では,沈み込み帯システムにおける物質循環に関する最新の話題を提供していただく予定である.
■辻森 樹(東北大:会員)30分
辻森会員は,青色片岩などのプレート境界岩を丹念な野外調査・岩石組織観察・地球化学分析から研究され,プレート沈み込みのダイナミクスの素過程の理解と地球変動史の解読に精力的に取り組んでこられた.特に近年,プレート境界岩の造岩鉱物の局所同位体分析により,これまで『未読』であった全く新しい物質科学的な情報を抽出・蓄積されつつある.ご講演ではこれらの未読情報の統合解析から,太古代〜顕生代の4つの年齢における造山帯の緑色岩・高圧変成岩を研究対象に,プレート境界のプロセスと経年変動を読み解く重要性について紹介される.さらには固体地球の進化史の物質科学的な検証,特に再生地殻成分の大循環と固体地球の長周期変動の体系化に関するあらたなプロトコルについて伺える予定である.
R3.噴火・火山発達史と噴出物(招待講演なし)
R4.変成岩とテクトニクス
■榎並正樹(名古屋大:会員)30分
榎並会員は,野外調査,岩石組織観察及び造岩鉱物の緻密な化学組成分析を主な手法として,四国三波川帯をはじめとする国内外の変成帯を対象に詳細な地質学的研究を推進されている.また,岩石学にラマン分光学を応用し,ザクロ石に包有される石英のラマンスペクトルから変成圧力条件を見積もる手法を確立するなど,相平衡のみに縛られない変成岩の温度圧力解析の端緒を切り開いたと言える.近年では,教科書も上梓されるなど,後進の育成と分野の発展への貢献は枚挙にいとまがない.これまで長年にわたり蓄積されてきた研究成果とともに,プレート収束域における沈み込み変成作用の累進進化に関する新たな展望を紹介していただくことは,招待講演として有益なものになると期待される.
R5.地域地質・地域層序・年代層序(招待講演なし)
R6.ジオパーク(招待講演なし)
R7.グリーンタフ(招待講演なし)
R8.海洋地質
■多田隆治(東京大学:会員)30分
多田会員は,海域および陸域双方の地質記録からアジアモンスーンの進化に関する研究を進め,2013年には自らが代表プロポーネントとして計画された日本海および東シナ海北部のIODP (国際深海掘削計画)Expedition 346に共同主席研究者として乗船した.現在,その成果が増えつつあり,今年のPEPSでは特集号もまとめられた.
■池原 実(高知大学:会員)30分
池原会員は,長年にわたって様々な指標を用いた古海洋学的研究を行っており,特に南大洋においてはIODPの掘削提案を行う中心的な役割を果たしている.また,昨年度より新学術領域研究が採択され,古海洋研究班のリーダーとして研究を推進している.今後数年間は南極海においてIODPによる掘削航海が立て続けに計画されていることなど,これから注目される研究テーマとして関心が向けられている.池原会員には南大洋が気候変動に果たす役割について最新の研究成果や国内外の研究動向に加え,今後の課題についてご講演いただく.
ページTOPに戻る
R9.堆積物(岩)の起源・組織・組成(招待講演なし)
R10.炭酸塩岩の起源と地球環境
■渡邊 剛(北海道大学:会員)30分
渡邊会員は,炭酸塩骨格に成長縞を構築するサンゴや二枚貝などの生物源炭酸塩の同位体分析や微量元素分析などの地球化学分析を手法として,高解像度での地球環境変動の復元について研究をおこなわれている.特に,鮮新世温暖期におけるサンゴの酸素同位体組成比(水温,塩分の指標)の研究からは,70年分の大気と海洋環境変動の季節変動および経年変動パターンやエルニーニョ現象の詳細を明らかにされ,将来の環境変動を見積もる上でも重要な発見をされている.渡邊会員は,現在ハワイを拠点に精力的に研究を進められており,招待講演では,サンゴ礁地球環境学に関する最新の話題を提供していただく予定である.
R11.堆積過程・堆積環境・堆積地質
■成瀬 元(京都大学大学院理学研究科:会員)30分
成瀬会員は,堆積物重力流について,実験,野外調査,組織解析,モデリングといった多様な側面から,その挙動や堆積過程についての研究を行ってきた.彼はこの分野を世界的にリードする研究者の一人である.2015年に公表された,混濁流とその堆積物についての研究の方向性を示した論文は世界をリードする研究者らによって著されたのもので,成瀬会員はその著者の1人に名前を連ねている.成瀬会員には混濁流のモデリングについて,研究の方向性を含めたレビューを行っていただく予定である.今後の研究の方向性を議論する機会としたい.
ページTOPに戻る
R12.石油・石炭地質学と有機地球化学
■荒戸裕之(秋田大学:会員)30分
荒戸会員は,反射法地震探査記録を用いた石油・天然ガスの成因や探鉱に関する研究に長年取り組んでおられ,この分野をリードしてきた研究者の一人である.また,国の基礎調査に関するワーキンググループの委員長として,海域の三次元地震探査調査による堆積盆地評価に関する議論をまとめられた.招待講演では,本邦周辺海域で実施されてきた基礎調査による三次元地震探査記録を用いた堆積盆地の解析について話題を提供していただく予定である.
R13.岩石・鉱物の変形と反応
■増田俊明(静岡大:会員)30分
増田会員は,地殻由来の天然の岩石から歪み,応力,変形機構といった情報を読み取る構造地質学的研究に長年取り組んでおられる.講演では理論,実験,天然の解析と多岐に渡る研究成果から,天然の岩石から変形の各要素を読み取る手法の現状と展望についてお話いただき,2011年東北地方太平洋沖地震以降に重要視されるようになった地殻の変形と応力状態の定量的理解に向けて活発な議論を展開したい.
■土屋範芳(東北大:会員)30分
土屋会員は,地質学,岩石学,地球化学,計測工学を基礎に,地熱エネルギー開発に関する研究に長年取り組まれている.昨今,再生可能エネルギーの一つとして地熱エネルギーの開発に期待が寄せられているが,高温岩体とそれを取り巻く流体の循環について不明な点も多く,土屋会員は,これらの問題の解明に挑戦している.札幌大会では,地熱エネルギーの可能性と,開発に対し地質学が挑戦・貢献するべき研究,特に超臨界岩体の変形,流体流動,反応に関する研究について紹介いただく.
R14.沈み込み帯・陸上付加体
■木村 学(東京海洋大学:会員)30分
木村会員は,南海トラフ地震発生帯掘削計画(NanTroSEIZE)をリードし,四万十付加体や日本列島のテクトニクス研究においても数多くの重要な成果をあげられてきた.本招待講演では最近のNanTroSEIZEや陸上地質研究成果を通じて明らかとなったアジア太平洋グローバルテクトニクスの新展開と日本列島沈み込み帯論について紹介していただく予定である.
■山本由弦(JAMSTEC・会員)30分
山本会員は,主として新第三系三浦ー房総付加体を対象に構造地質学的研究を精力的に進め,浅部での付加体・前弧海盆発達過程,帯磁率異方性を用いた歪み履歴の解析,シュードタキライトの発見など重要な研究成果をあげられてきた.最近では,地球深部探査船「ちきゅう」による室戸沖限界生命圏掘削調査(T-Limit)に乗船参加し,プレート境界断層の記載を行っている.本招待講演では,山本会員がこれまでに明らかにしてきた浅部プレート境界断層の実像について紹介していただく予定である.
ページTOPに戻る
R15.テクトニクス
■酒井治孝(京都大学:会員)30分
酒井会員は,ヒマラヤ・チベット山塊上昇のテクトニクスや,それに伴うモンスーン気候や環境の変動について,堆積学,構造地質学,第四紀学,熱年代学などの手法を駆使して複合的に研究されてきた.昨年度末で京都大学退職という節目を迎えられた折でもあり,ライフワークともいえるヒマラヤの一連の研究成果について,網羅的なご紹介をお願いしたい.
■植田勇人(新潟大学:会員)30分
植田会員は,綿密な野外地質調査に基づいて,過去のプレート沈み込み帯でどのような地層が形成され,それらが地下でどのように移動し変動したかを精力的に研究されている.植田会員のメインフィールドである北海道での学会開催にあたり,空知−エゾ海盆の起源,高圧変成岩の上昇,蛇紋岩メランジの成因,中生代における北西太平洋の海洋プレートの復元など,日高山脈近傍の地質学的研究に基づくさまざまな話題提供を期待したい.
R16.古生物
■守屋和佳(早稲田大学:会員)30分
守屋会員は,これまでに,アンモノイド類の進化古生物学的研究および地球化学的手法を用いた古環境変動の研 究に取り組んでこられた.本講演ではアンモノイドの生息水深や古生態に関する同位体を用いた研究について,レビューを交えて紹介していただく予定である. 北海道を代表する古生物であるアンモノイドについて,最先端の研究に触れる機会となることを期待している.
R17.ジュラ系+
■安藤寿男(茨城大学:会員)15分
安藤会員は,IGCP608のプロジェクトリーダーとしてアジアの白亜系研究を牽引している.中国やモンゴルなどの研究者と共同研究を展開し,中生界の国際対比や環境変遷史の分野で国際的に活躍している.招待講演では,ご自身の体験も交えて,アジアにおけるジュラ系・白亜系の広域対比に関する講演を期待している.
ページTOPに戻る
R18.情報地質とその利活用(招待講演なし)
R19.環境地質(招待講演なし)
R20.応用地質学一般およびノンテクトニック構造
■山崎新太郎(京都大学防災研:会員)30分
山崎会員は,比較的安価な魚群探知機とモーターボートを用いて,海底・湖底の詳細な地形測量を可能とする新しい地形計測手法を提案している.その手法は,猪苗代湖や屈斜路湖などの複数の湖や,箱根火山東岸の相模湾海底での調査に適用されており,強い地震動を誘因とした大規模な地すべりによる水底地形を抽出することに成功している.この一連の研究は,従来の手法では把握することが困難であった湖底・海底地すべりの痕跡を,比較的安価な方法で抽出しうることを示したもので,応用地質学的に重要な研究といえる.招待講演では,この一連の研究をご紹介いただく.
R21.地学教育・地学史(招待講演なし)
R22.第四紀地質
■岡田 誠(茨城大学:会員)30分
岡田会員は, 前期ー中期更新世境界の国際標準模式地(GSSP)の候補地として挙げられる千葉県市原市の地層「千葉セクション」に関わる日本の研究チームの中心的研究者として分析・検討を推進されている.これまでの「千葉セクション」レビューと現状での課題などについて報告を行っていただく.
R23.地球史
■阿部彩子(東京大学大気海洋研究所:非会員)30分(予定)
阿部氏は,古気候モデル研究の第一人者である.彼女のグループでは,大気-海洋のモデルに加え,氷床や地形,植生までを組み込んだ複雑な系での長期的変動のモデリングに挑んでいる.彼女らのグループにより,これまで数々の古気候学の謎が解明されてきた.日射に対する氷床のヒステリシス的な応答に着目して氷期-間氷期の10万年周期変動を説明した研究もその一つだ.このような長時間スケールの気候モデリングは,地質試料を用いた古環境研究とも密接に関連する.招待講演では,最新の成果を踏まえて解説していただく.
■海保邦夫(東北大学:会員)30分
海保会員は,これまで,微化石記録,安定同位体組成,有機分子化石記録などを駆使して,P-T境界やK-Pg境界の生物大量絶滅の生物相と環境に関する研究を精力的に行ってきた.主要な成果である底生有孔虫を用いた海洋溶存酸素指標の確立や,K-Pgでの小惑星衝突時のモデリング,P-T境界における有機分子や安定同位体組成を用いた古環境解析は活発な議論を呼んできた.招待講演では,これまでの海保会員の成果について,最新のアイデアを踏まえて講演していただく.
ページTOPに戻る
R24.原子力と地質科学
■日高 洋(名古屋大:非会員)30分
日高氏は,自然界で生じる核反応を元素の同位体変動から検出し,その現象解明に取り組んでおり,オクロ天然原子炉は,その研究対象の一つである.天然原子炉から採取された様々な試料を分析して得られた一連の同位体データから解明された原子炉内外における放射性核種の中〜長期にわたる移行挙動,核分裂メカニズムについて紹介していただく.
R25.鉱物資源と地球物質循環
■森下祐一(静岡大学:非会員)30分
森下氏は,金,白金族元素,レアメタルなどの資源の成因を研究する資源地質学の第一人者であり,最先端の二次イオン質量分析計による微小分析を駆使することで,今まで明らかとなっていなかった有用元素の挙動と濃集プロセスを解明するなど,非常に独創的な研究を展開し,この分野をリードし続けている.本講演では,当該分野の最新の話題を提供していただく予定である.そのお話を聞ける機会は,本セッションに関係する全ての研究者にとって非常に有意義なものになると期待される.
2018札幌大会_参加登録TOP
2018札幌大会事前参加登録のご案内
事前参加登録の受付は終了しました
締切:2018年 8月10日(金)18時(web)
参加登録に関わるお申込(参加,要旨集,巡検,懇親会,弁当)は,オンラインによる大会専用参加登録システム(会員・非会員にかかわらずどなたでも申込可)をご利用の上,お申し込み下さい.
郵送で申し込む場合は,学会事務局までお問い合わせ下さい.郵送用申込書等必要な書式をお送りします.提出書類をご準備の上,8月3日(金)必着で学会事務局までお送り下さい.
大会参加登録およびそれに伴う参加費は,参加者(巡検のみ参加の場合も)に必要な基本的なお申し込みです.会員が同伴する非会員の家族等(以下,同伴者)に ついても懇親会・巡検・お弁当については事前に申込が必要です.申込は,会員と同伴者の計2名まで一括申込が可能です.
*セッション共催団体リストはこちらから
*大会申込Q&Aはコチラ
<参考>会員情報を自動取得するには?(PDF)
巡検申込状況
2023京都大会巡検申込状況
[申込締切] 8/8(火)18:00 締切
申込受付はオンラインのみ。FAXやe-mail、郵送による申込受付は行いません。
【巡検コースの詳細はこちら】
2023年8月8日締切後の催行決定コースは次の通りとなりました。
班
コース名(催行日)
定員(最小催行)
申込者数
催行
A
京都盆地-奈良盆地断層帯とその周辺の第四系 9/20
15(10)
15
決定
B
山陰海岸ジオパーク地域兵庫県新温泉町〜香美町周辺に分布する新第三紀北但層群とそのジオサイト 9/20
23(13)
2
中止
C
瀬戸内区中新統:鮎河層群と綴喜層群 9/20
15(10)
14
決定
D
琵琶湖西岸に分布する後期白亜紀花崗岩体と岩脈類 9/20
21(10)
10
決定
E
但馬地域の舞鶴帯南帯 9/20
23(16)
16
決定
F
超丹波帯と丹波帯(プレ)9/16
23(15)
23
決定
G
淀川の氾濫と河川改修(プレ/アウトリーチ) 9/16
20(3)
20
決定
H
ワークショップ:堆積学の水理実験・理論講習会(プレ) 9/16
15(1)
15
決定
I
ワークショップ:オープンソースGISをつかってみよう 9/20
20(3)
11
決定
◆ 巡検参加を取りやめたい方は,必ず地質学会にご連絡下さい.無断で参加取消することの無いよう,お願いします.
◆ 巡検参加を取りやめた場合,お申し出の時期により参加取消料が発生します.ご注意下さい.
2022年顕彰式_50年会員紹介
永年会員顕彰者 1972年入会(計44名)
伊藤谷生
今岡照喜
大竹敏則
香川重善
栗田光雄
河野忠臣
紺谷吉弘
近藤直門
鈴木達郎
須藤 茂
田北 廣
津村善博
徳橋秀一
西村 昭
西脇二一
長谷川四郎
東野外志男
松本 良
丸山茂徳
吉田尭史
池田保夫
宇野泰光
大橋俊夫
(以下お写真の掲載省略)
石井久夫,井上正澄,狩野謙一,小出和男,小林武彦, 小宮 学(2022/4/29逝去),柴田秀道, 白石和行,傍島武師,中屋志津男,成尾英仁, 西田高久,林 隆夫,原田憲一,平社定夫, 牧本 博,宮城晴耕,山崎晴雄,山粼安正, 湯浅真人,吉田光廣
2019年山口大会_巡検へ参加されるかたへ
巡検へ参加される方へ
[重要]台風17号接近に伴う巡検実施可否などの関連情報は,こちらから(随時更新中)
1)山口大会への事前参加登録および巡検参加申込みは,8 月22日(木)に締め切りました.
全てのコースが実施となります.各コースの参加に関する詳しい連絡は,各コースの案内者よりご連絡いたします.
巡検案内書は,今大会も地質学雑誌125巻7号および8 号(2019年7月および8月号)に掲載いたします.また,J-STAGE<http://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja>にて公開します.なお,予告記事でもお知らせの通り,巡検参加者には各参加コース箇所の巡検案内書を巡検当日に配布します.
2) 重要 「野外見学,調査,試料採取における注意喚起」をご一読下さい
巡検へ参加される方は,参加の前に是非「野外見学,調査,試料採取における注意喚起」をご一読下さい。
「野外調査において心がけたいこと」国立・国定公園や史跡・名勝・天然記念物、あるいは一般的な露頭における調査上の注意点
「安全のしおり(巡検案内書より)」巡検や野外調査における安全上の注意点と自然保護に関する注意点
「巡検案内書を頼りに野外調査へ出かける方へ」露頭での調査や試料採取にあたっての注意点(「野外調査において心がけたいこと」から一部抜粋)
[巡検実施の可否について](2019年8月31日現在)
班
コース名
実施の可否
A
<プレ>ジオパーク (9/22)
募集定員に達しましたので
実施予定です
B
石灰石と石炭 (9/26)
募集定員に達しましたので
実施予定です
C
白亜紀カルデラ (9/26)
募集定員に達しましたので
実施予定です
D
長門峡と活断層(9/26)
募集定員に達しましたので
実施予定です
E
<プレ>中生代化石 (9/22)
募集定員に達しましたので
実施予定です
F
地すべり(9/26)
募集定員に達しましたので
実施予定です
G
超古原生岩体と深部流体 (9/26)
募集定員に達しましたので
実施予定です
H
秋吉台と秋芳洞(9/26)
募集定員に達しましたので
実施予定です
2019山口_開催通知(プレページ)
2019山口(プレページ)
日本地質学会第126年学術大会
(2019山口大会)
山口大学吉田キャンパス(山口県・山口市)にて
2019年9 月23日(月)〜25日(水)に開催
日本地質学会は,山口県山口市の山口大学吉田キャンパスにて,第126年学術大会(2019年山口大会)を9月23日(月)〜25日(水),巡検(見学旅行)を22日(日)と26日(木)に開催します.
山口県は,「地質の博物館」といわれるほどに,秋吉台をはじめ多くの優れた地質遺産があり,明治以降優れた研究の舞台となってきました. 萩市出身の地質技術者高島得三は,明治7年(1874年)に「山陽山陰地質記事」という日本最古の地質図を作成しています.また,山口大学の初代学長「松山基範」は,昭和4年(1929年)に地球磁場の反転を世界に先駆けて唱え,地磁気の逆転期にその名を残しています.また戦後も多くの研究の舞台となり,優れた成果をもたらしてきています.
山口県には,現在2つのジオパークがあります.Mine秋吉台ジオパークと萩ジオパークです.どちらも,まだ国内ジオパークで,認定からの日も浅いですが,そのぶん活力に満ちあふれていて,地域住民が生き生きとジオを語る姿を見ることができます.Mine秋吉台は,約3億年前の石灰岩,約2億年前の石炭層,約1億年前の銅鉱山などが見所です.萩では,後期白亜紀の花崗岩,中新世の斑れい岩,第四紀の単成火山群など,3つの時代のマグマ活動を見ることができます.秋吉台へは車で40分くらい,萩へは1時間弱で行くことができます.その他のお勧めは,外国人も多く訪れる下関市北部の角島,長門市の元乃隅稲成神社などが人気のスポットで,中新世の安山岩の柱状節理などが近くの露頭で観察できます.また,長門市青海島や萩市須佐では遊覧船で北長門海岸国定公園の美しい海岸の風景を楽しめるだけでなく,白亜紀のルーフペンダントや須佐層群などを見て回ることができます.
山口大学の吉田キャンパスは,飛行機では山口宇部空港から約1時間,新幹線の新山口駅から山口線で20分ほどの距離にあります.最寄り駅の「湯田温泉」は,温泉街で宿泊施設や飲食店も多く,“夜の楽会”も楽しめます.湯田温泉以外では,新山口駅付近にもホテルがあります.観光シーズン,連休にかかる時期でもあり,早めの予約をお願いします.
地質巡検は,定番の秋吉台の石灰岩(カルスト台地)や白亜紀のカルデラ,中生代の化石,津和野の花崗岩と深部流体,活断層,新生代地すべり,アウトリーチ巡検など,盛りだくさんです.いずれも,日帰り巡検で,お手軽かつお財布にも優しいコース設定を予定しています.この機会に,是非山口の地質を堪能してください.
山口大会は,どんな大会になるでしょう?ドキドキとワクワクが,いっぱいです.大会実行委員会一同,皆様のご参加を心からお待ちしています. 一緒にワイワイ・ガヤガヤしましょう.
2019年1月
日本地質学会第126年学術大会(山口大会)実行委員会
委員長 脇田浩二
2019山口_top(プレページ)
2019山口プレページ_top
日本地質学会第126年学術大会
会場:山口大学吉田キャンパス(山口県・山口市)
日程:2019年9 月23日(月)〜25日(水)
山口大会HP(本サイト)はこちら
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/top
更新情報
19/05/07 若手会員向けルームシェア型宿泊プラン(7/31締切・先着順)
19/04/15 宿泊予約はお早めに!
19/01/25 トピックセッション募集(締切:3/12)
19/01/25 大会開催通知
19/01/25 山口大会プレページ開設しました
山口大会に向けてのスケジュール(予定)1/25現在
各項目に関して,余裕をもってご準備をお願いします.
3月12日(火)トピックセッション募集締切
5月末(ニュース誌5月号)大会予告記事(演題登録・講演要旨受付開始)
7月3日(水)演題登録・講演要旨受付締切/ランチョン・夜間小集会申込締切
8月下旬(ニュース誌8月号)大会プログラム記事
8月19日(月)大会参加登録/巡検/懇親会参加申込締切
9月23日(月・祝)〜25日(水)第126年学術大会(山口大会)
2019山口_トピック募集(プレページ)
2019山口_トピック募集(プレページ)
トピックセッション募集締切
*** 2019年3月12日(火) ***
日本地質学会行事委員会
第126年学術大会(山口大会)は,西日本支部のご協力のもと,山口大学山口キャンパスを会場として2019年9月23日(月・祝)〜25日(水)に開催されます.山口県には,日本最大のカルスト地形である秋吉台や美しい海食海岸地形を示す須佐ホルンフェルスなど,地質学的に重要かつ風光明媚なスポットが数多くあります.また古生代から新生代までほぼ全ての地層が分布することから,地質学に対する一般市民の関心も高いと考えられ,実りある学術大会の開催が期待されます.山口大会では,多くのセッション開催を可能にするよう,必要十分数の会場(部屋)を確保する予定です.ポスター会場については,近年のポスター発表重視の方向を満たすスペースを確保します.トピックセッションを下記要領で募集します.本大会も前回同様,シンポジウムの一般募集はありません.シンポジウムは山口大会実行委員会および学会執行部が企画します.
1.セッション概要
セッションは例年通り「レギュラーセッション」,「トピックセッション」,「アウトリーチセッション」に区分します.レギュラーセッションは例年と同じ25タイトルを予定しています(レギュラーセッションは3月下旬に行事委員会が決定します).
2.トピックセッション募集
トピックセッションは,広く地質学の領域に属し,これから新分野あるいは注目すべき分野になりそうな内容を扱うものとします.形式はレギュラーセッションと同じです(口頭発表およびポスター発表:口頭発表は15分間で,進行も15分刻み).多くの参加者が見込まれる,魅力あるセッションを積極的にご提案ください.締切後,行事委員会が応募内容を慎重に検討し,最大8件程度のトピックセッションを採択する予定です.
3.トピックセッション招待講演
トピックセッションの招待講演には例年と同じルールを適用します.
招待講演は1セッションにつき最大2名とし,会員,非会員を問いません.世話人が「自分を招待する」ことは認めません.
発表時間(質疑応答を含む)は世話人が15分または30分のいずれかを選択できます.なお,1人の発表者(招待講演者を含む)が1つのセッションで口頭発表できるのは1件です.
招待講演者の選定理由とその裏付けとなる情報(セッションテーマに関連した代表的な論文,著書等)が必要です.
会員招待講演者が招待講演の他に非招待の発表を1件申し込む場合,発表負担金はかかりません.さらにもう1件(招待講演の他にセッションで2件)発表する場合は負担金がかかります.
4.応募方法
トピックセッションを応募する会員は,次の項目内容を日本地質学会行事委員会宛(main@geosociety.jp)にe-mailでお申し込み下さい.
1)代表世話人(=連絡責任者,会員に限る)の氏名(和・英),所属(和・英),メールアドレス,緊急時の電話番号
2)セッションタイトル(和・英)
3)共同世話人の氏名(和・英),所属(和・英),メールアドレス
4)趣旨・概要(400〜600字)
5)招待講演の有無
有の場合
5-1)招待講演者の氏名(和・英),所属(和・英),会員/非会員の別
5-2)招待講演の発表希望時間(15分または30分)
5-3)招待講演者の選定理由(100〜200字)
5-4)選定理由の裏付けとなる,セッションテーマに関連した代表的な論文・著書等
6)他学協会との共催希望の有無,有の場合は名称
7)時間(原則半日(3時間)以内ですが,詳細はお問い合わせください)
8)地質学雑誌またはIsland Arcへの特集号計画の有無(できる限り特集号を計画してください)
9)その他(英語使用等)
5.採択方法
応募多数の場合や他セッションと内容が重複する場合,行事委員会は学術的なインパクトや緊急度を考慮して採択を決定します.採択されたトピックセッションはニュース誌5月号(5月末発行予定)で公表し,講演募集を行う予定です.演題登録(講演申込,講演要旨投稿)締切は7月初旬を予定しています.
6.非会員招待講演者の参加登録費
非会員招待講演者に限り参加登録費を免除します(ただし要旨集は付きません).
7.世話人が行う作業(7月初旬〜中旬)
代表世話人には,講演要旨校閲,講演順番決定などの作業を7月中旬までに行っていただきます(詳細は採択後にお知らせします).その期間,代表世話人は電子メールで添付ファイルを送受信できるようにして下さい.野外調査や乗船等で通信が制限される場合は,共同世話人(代理)にあらかじめ作業を依頼し,その旨を行事委員会に必ず報告してください.
ご不明の点があれば行事委員会(main@geosociety.jp)までお気軽にお問い合わせください.
会員の学術・教育・社会貢献活動
会員の学術・教育・社会貢献活動
このコーナーでは,地質学会員の「学術,教育,社会貢献活動」をご紹介しています.皆様からの情報をお待ちしています. 例えば,,,
自身の学術論文掲載がメディアや所属機関からプレスリリースされた.
研究成果に関して、テレビやラジオ番組に出演する.
ジオパークの新規開設や整備・更新をメディアで紹介された
興味深い授業内容として、メディア等で取り上げられた........などなど.
ただし、番組、著書・雑誌、既存施設や教室などの紹介や宣伝が目的ではなく、会員の研究や活動の成果の紹介が目的です。客観性、公共性、速報性、新規性および内容を考慮し、広報委員会で掲載を判断します.(日本地質学会広報委員会)
(2025/03/03)
岡本敦会員(東北大学)の研究成果(岩石亀裂内でのシリカ析出による流体圧振動を発見 ―流体が引き起こす地震発生モデルを実験室で再現―)が、東北大学からプレスリリースされました。 東北大学HPプレス記事はこちら(2025.2.28)
(2023/11/22)
酒井治孝会員が,令和6年度秩父宮記念山岳賞を受賞することが決定しました.業績題名「ヒマラヤ山脈形成史の研究」詳しくはこちらから(日本山岳会のサイト)受賞式は12/7(東京;京王プラザホテル)です.
(2024/09/07)
岡本敦会員(東北大学)、大柳良介会員(国士舘大学)の研究内容が、東北大学からプレスリリースされました。 東北大学HPプレス記事はこちら(2024.9.5)
(2023/07/04)
辻森 樹会員らによる 「Progressive lawsonite eclogitization of the oceanic crust: Implications for deep mass transfer in subduction zones」(Geology, v. 51, no. 7, p. 678–682)の掲載内容が東北大学からプレスリリースされました.東北大学HPプレス記事はこちら(2023年7月3日)
(2023/05/26)
石橋 隆会員等の研究グループは、北海道河東郡鹿追町および上川郡愛別町より、新種の鉱物「北海道石」を見出し、2023年1月に国際鉱物学連合において命名承認・登録を受けました (登録番号IMA2022-104). プレスリリースの記事はこちら(pdfリンク)
(2023/04/24)
自らが発見したレアアース泥の重要性についての情報発信・科学教育活動を通じて,持続可能な社会を拓く国産海洋資源開発への国民の理解増進に寄与された加藤泰浩会員らが,文部科学大臣表彰の科学技術賞(理解増進部門)を受賞しました.https://www.it-chiba.ac.jp/topics/pr20230407/
(2023/04/21)
日本の深海底堆積岩を対象とした宇宙物質流入と地球生命史に関する研究が評価され、尾上哲治会員,佐藤峰南会員,野崎達生会員が,文部科学大臣表彰の科学技術賞(研究部門)を受賞しました.https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/topics/view/1936/
(2023/04/21)
日本の地名にちなんだ初めての地質年代「チバニアン」の誕生へとつながった,上総層群における松山-ブリュン地磁気逆転の系統的研究が評価され,岡田 誠会員,菅沼悠介会員が,文部科学大臣表彰の科学技術賞(研究部門)を受賞しました.https://www.ibaraki.ac.jp/news/2023/04/07011951.html
(2023/04/18)
日本の標準地質図としてインターネットを通じて広く利用されている20万分の1日本シームレス地質図の作成において中心的な役割を担った,脇田浩二会員,斎藤 眞会員,西岡芳晴会員,宮崎一博会員,宝田晋治会員の5名が,令和5年度文部科学大臣表彰の科学技術賞(開発部門)を受賞しました. https://www.aist.go.jp/aist_j/news/prz20230411.html
(2022/04/26)
学術大会の教育・普及関連行事である「地質情報展」の企画運営に長年に渡り携わってこられた斎藤 眞理事ほか3名が,令和4年度文部科学大臣表彰の科学技術賞(理解増進部門)を受賞しました. https://www.gsj.jp/researches/topics/2022-prize01.html
(2022/04/04)
星 博幸会員出演 体感!グレートネイチャーSP「北アメリカ大陸誕生!-消えた謎のプレート-」 グランドキャニオン、デビルズタワー、ヨセミテ、イエローストーンなど、北アメリカ大陸を形作る絶景を余すことなく紹介するとともに、大陸誕生の秘密を明らかにする。
4月9日(土)19:00 NHKBSプレミアム放送予定 詳しくはこちら
(2022/03/28)
磯粼行雄会員出演 コズミック フロントΩ「地磁気逆転」
放送予定:NHKBS4K,3月31日(木)4:28-4:57
地球の磁場は宇宙の様々なエネルギーから私たちを守ってくれるが、向きが変わる「地磁気逆転」で何度も地球生命に危機があったという。それは何か?今後は?https://www4.nhk.or.jp/P5162/x/2022-03-30/44/19389/2867671/
(2022/03/15)
竹下光士会員による「THE GALLERYセレクション展 GEOSCAPE MTL中央構造線」が開催されます.
東京 2022年4月5日(火)-18日(月)/大阪 5月6日(金)-18日(水)
会場:ニコンプラザ東京THE GALLERY、ニコンプラザ大阪THE GALLERY 詳しくはこちら
(2022/03/09)
辻森 樹会員らによる 「Neoproterozoic eclogite-to granulite-facies transition in the Ubendian Belt, Tanzania, and the timescale of continental collision」(Journal of Petrology, egac012, in press)の掲載内容が東北大学からプレスリリースされました.
東北大学HPプレス記事(2022年3月7日)
「東北大、汎アフリカ造山帯で大陸衝突の時間スケールを解明」(2022年3月7日 日経電子版)
(2022/02/15)
吉田健太会員らによる「Variety of the drift pumice clasts from the 2021 Fukutoku-Oka-no-Ba eruption, Japan」(Island Arc, Vol.31, e12441)の掲載内容がJAMSTECからプレスリリースされました.
JMSTECプレス記事はこちら(2022年2月10日)
(2022/02/15)
宇野正起会員らによる「Machine‐learning techniques for quantifying the protolith composition and mass transfer history of metabasalt」(Scientific Reports) 12: 1385. の掲載内容が東北大学からプレスリリースされました.
「変質した岩石の化学組成を機械学習で復元! ―地球内部の元素循環の統一的な解明へ―」 https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2022/02/press20220210-01-machine.html (2022年2月10日)
(2021/02/08)
石澤尭史会員らによる「Paleotsunami history along the northern Japan trench based on sequential dating of the continuous geological record potentially inundated only by large tsunamis」(Quaternary Science Reviews)279, 107381.の掲載内容がプレスリリースされました. 「三陸海岸北部において1611年慶長奥州地震津波の物的証拠を発見 —日本海溝沿いで発生する巨大津波の頻度に関する新たな知見—」
東北大学HPプレス記事はこちら(2022年2月3日)
(2022/01/31)
田村芳彦会員(JAMSTEC)が研究を進めている西之島の火成活動に関する最新の知見がコズミックフロントで紹介されます。
コズミックフロント「巨大火山が覚醒する!?西之島2020-2021」 小笠原に浮かぶ絶海の火山島・西之島の最新映像。2020年夏に起きた過去最大級の噴火で島の様子は一変!火山島の地下で今、何が起きているのか?!
放送予定:NHKBSプレミアム,2月2日(日)23:45-(初回放送日: 2022年1月27日 )
https://www.nhk.jp/p/cosmic/ts/WXVJVPGLNZ/episode/te/NGQV85N89G/
(2021/01/23)
宇野正起会員らによる「Volatile-consuming reactions fracture rocks and self-accelerate fluid flow in the lithosphere」(Proceedings of the National Academy of Sciences) 119, 3, e2110776118. の掲載内容が東北大学からプレスリリースされました.
「化学反応によって岩石が破壊され、水や二酸化炭素が持続的に固定されるメカニズムを解明」
東北大学HPプレス記事はこちら(2022年1月18日)
(2022/01/21)
小宮 剛会員が,最新の地球史研究についてTV番組で紹介します。
番組タイトル:サイエンスZERO 月が教えてくれる!? 地球と生命“共進化”の謎
放送予定:NHKEテレ1,1月23日(日)23:30-24:00
https://www.nhk.jp/p/zero/ts/XK5VKV7V98/
(2021/01/14)
読売新聞夕刊に、「チバニアン外伝」(計8回の連載予定)の掲載が始まりました。チバニアン承認の礎となる房総半島の地層研究に関わった地質学者(新妻信明会員・岡田 誠会員・菅沼悠介会員)の物語です。
Twitterはこちら
記事全文はこちら
(2022/01/12)
小宮 剛会員,澤木佑介会員,JAMSTECなどで研究が進められている地球史研究が番組で取り上げられました。
番組タイトル:ヒューマニエンス「“塩” 進化を導いた魔術師」
放送予定:NHKBSプレミアム,1月13日(木)20:00-21:00
https://www.nhk.jp/p/ts/X4VK5R2LR1/
(2021/12/06)
大柳良介会員らをによる「Hadal aragonite records venting of stagnant paleoseawater in the hydrated forearc mantle」(Communications Earth & Environment) DOI: 10.1038/s43247-021-00317-1 の掲載内容がJAMSTECからプレスリリースされました.
JAMSTEC_HPプレスリリース記事はこちらから(2021年12月3日)
(2021/09/02)
岡本 敦会員らによる Okamoto, A., Oayangi, R., Yoshida, K., Uno, M., Shimizu, H., Satish-kumar, M., 2021.
Rupture of wet mantle wedge by self-promoting carbonation. (Communications Earth & Environment, 2, 151.) DOI:10.1038/s43247-021-00224-5 の掲載内容が東北大学からリリースされました.
沈み込み帯における二酸化炭素の固定化が マントルの破壊を引き起こす ― 炭素の循環とプレート境界での地震現象との関係性を示唆 ―
東北大学HPプレス記事はこちら(2021年8月26日)
(2021/05/24)
中澤 努会員,野々垣 進会員ら,産総研を中心とするグループにより,東京都心部の地下数十メートルまでの地質構造を3次元で立体的に見ることができる次世代地質図「3次元地質地盤図〜東京23区版〜」が作成・公開され,産総研からプレスリリースされました.
産総研HPプレスリリース記事はこちらから(2021年5月21日)
(2021/04/16)
小嶋智会員、平内健一会員ら出演 NHKが以下の番組を放映します。
4/29(木)22時〜 NHK-BSプレミアム・BS4K
コズミックフロント:「水惑星」地球 大地創世のヒミツに迫れ
今、科学者たちは実験室に地球内部の様子を再現することで、大地創造のメカニズムの解明に挑んでいる。長い年月をかけて生み出される風景は、プレートの動きがカギを握っている。その際、太陽系で地球がもつ「表面を覆う水」の存在が原動力となっていたことがわかってきた。地球表面の水は、プレートの激動を生み、マグマを生み出す元となることで、私たちが暮らす大地を創造する重要な役割を果たしてきたのだ。日本各地の地質学にまつわる名所で撮影を行い、最新研究から地球のメカニズムに迫ります。
https://www.nhk.jp/p/cosmic/ts/WXVJVPGLNZ/
(2021/04/16)
辻森 樹会員ら東北大学グループによる「Evidence for crustal removal, tectonic erosion and flare-ups from the Japanese evolving forearc sediment provenance」(Earth and Planetary Science Letters, v. 564, 116893)の掲載内容が東北大学からプレスリリースされました.
東北大学HPプレス記事はこちら(2021年4月7日)
(2021/02/02)
辻森 樹会員らによる 「Crustal evolution of the Paleoproterozoic Ubendian Belt (SW Tanzania) western margin: A Central African Shield amalgamation tale」(Gondwana Research, v. 91, p. 286-306)の掲載内容が東北大学からプレスリリースされました.
東北大学HPプレス記事(2021年1月27日)
https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2021/01/press20210127-02-africa.html
「東北大、中央アフリカ楯状地の地史を復元」(2021年1月27日 日経電子版)
https://r.nikkei.com/article/DGXLRSP603970_27012021000000
(2021/01/26)
石橋 隆会員 監修 NHKが以下の番組を放映します。
<番組タイトル> 「所さん!大変ですよ」ブーム到来!?不思議な鉱物の世界
<放送予定>
2021年1月28日(木)19:30-19:57 NHK総合1・東京
2021年2月3日(水)23:45-0:12 NHK総合1・東京
※オンドマンド放送、国際放送も予定されています.
<内容>いま色とりどりの石に魅せられた“鉱物女子”が増えていることが判明!鉱物を使った実験や、鉱物で作る料理?など驚きの楽しみ方を紹介する。番組サイトはこちらから
(2020/11/17)
ウォリス サイモン会員出演 NHKが以下の番組を放映します。
番組タイトル:NHK国際放送「Groud Detective Simon Wallis」第1回秩父ジオパーク編
11/25(水)9:30〜/15:30〜/22:30〜
11/29(日)20:10〜
-----------------------------------------
(202012/21追記)
第2弾「銚子ジオパーク」の放送が決定。
2021年1月6日(水)9:30〜/15:30〜/22:30〜 と
2021年1月10日(日)20:10〜 の4回、NHKワールドで放送。放送後はオンデマンドでの視聴も可能です。
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/live/
番組HPはこちら
-----------------------------------------
日本の地質を海外の人にわかりやすく紹介する目的で、NHK 国際放送が15分の短い番組を複数の企画しています。第一回では、秩父地方を紹介しますが、そこでウォリス サイモン会員が案内人として出演します。番組の特徴として、日本地質と食文化のリンクを探り出すことがあります。良い反響があればシリーズという可能性もあるそうです。海外に向けて日本の地質の面白さを宣伝できると良いと考えています。興味のある方はぜひみて、コメントもしてください。
(2020/0715)
田村芳彦会員出演 NHKが以下の番組を放映します。私はその一部に出演し、また番組のCG制作に協力しました。これらは沈み込み帯のマグマ活動に関する自分の研究活動の一環であり、2018年に地質学会の国際誌Island Arcにおいて発表した研究成果を基にしたものです。日本地質学会員の活動とIsland Arcを広く知ってもらう良い機会と思います。
<番組タイトル> コズミックフロント☆NEXT 「奇跡の新大陸!? 西之島 地球史の冒険者たち」
<放送予定>
2020年7月23日(木)22時〜 NHK・BSプレミアム/BS4K
2020年7月29日(水)23時45分〜 NHK・BSプレミアム ほか
<内容>小笠原諸島・西之島。知られざる地球史をひもとくために火山と生物の専門家が調査に挑んだ。噴火が激しい時には無人ヘリで溶岩を採取し、地球に大陸を生み出すカギとなる安山岩を入手。噴火が一時休止した時には上陸調査を敢行し、新しく生まれた大地を生き物がどのように進出するのか、その最前線を目撃。5年間にわたるスーパー・ハイビジョン撮影の貴重な記録を1時間番組にまとめて編集しました。採取された溶岩を用いた研究はIsland Arcにおいて2018年に発表され、Island Arc Most Downloaded Award 2020をうけている。https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iar.12285
(2019/04/01)
清水麻由子会員らによる「Provenance identification based on EPMA analyses of heavy minerals: Case study of the Toki Sand and Gravel Formation, central Japan」(Island Arc,28, Issue 2, e12295(2019))の掲載内容が日本原子力研究開発機構からプレスリリースされました.原子力機構のHPプレス記事
(2019/03/26)
木村光佑会員,早坂康隆会員,川口健太会員,藤原弘士会員ほかによる「島根県津和野地域の舞鶴帯から古原生代18.5億年花崗岩質岩体の発見とその意義」(地質学雑誌,125,153-165(2019))の掲載内容が広島大学からプレスリリースされました.報道各社より周知されております.広島大学HPプレス記事
2019山口_若手宿泊プラン
2019年山口 若手会員向宿泊プラン
19.5.7掲載 19.9.3更新
第126年学術大会 2019年山口大会
若手会員向けルームシェア型宿泊プランのご案内
[申込受付は終了しました]
日本地質学会第126年学術大会が2019年9月23日(月)〜25日(水)の3日間開催されます。それに伴いまして、今大会では若手会員向けの宿泊施設をご用意いたしました。「若手同士の交流」と「低価格化」の観点から、本プランは、相部屋でのご案内となっております。内容をよくご確認の上、ご検討ください。
<対象となる若手会員>
山口大会へ参加する定収のない学生(学部,修士,博士)およびポスドク研究員等
<ルームシェア型宿泊プランの主旨>
「学会先での宿泊費を抑えたいけれど、ホテルの部屋をシェアする相手が見つからない...」「地質学会で仲間をつくりたい!」といった若手会員のために、日本地質学会ではこの度、“ルームシェア型宿泊プラン”を企画いたしました。学術大会での若手会員の宿泊先確保を支援し、若手同士の交流機会をつくることで、若手会員の皆様の研究活動をサポートしたいと考えております。是非、本プランをご活用いただき、研究仲間の輪を広げていただきたいと思います。
<申し込みにあたっての注意事項>※必ず、お読みください※
男女別室の見知らぬ人同士の相部屋となります。お互いが快適に過ごせるよう、ご配慮をお願いいたします。友人同士等での同室希望を出すことも可能です.ただし部屋割りの際はご希望通りにならないこともあることをご了承ください。
若手の学術大会参加を支援するための企画です。学術大会への参加が必須事項ですので、その点をご留意ください。
原則として、収入のない若手会員が対象となりますが,非会員の方もお申し込み下さい。申込数に余裕があれば受け入れ可能です。
キャンセルは原則禁止ですので、ご注意ください。締切日以降のキャンセルは、ご自身で宿泊施設に直接ご連絡ください。
<宿泊プランの詳細・お申し込み方法>
設定期間:2019年9月22日(日)〜25日(水)
宿泊施設:カリエンテ山口(山口県婦人教育文化会館) 〒753-0056山口市湯田温泉5-1-1 URL: http://www.y-caliente.jp/ 湯田温泉駅から徒歩約20分 会場まで徒歩約40分
宿泊料金:一人 4,308円/1泊 (食事なし 税・奉入湯税込)
受入可能人数:最大48名(4名×9部屋=36名 6名×2部屋=12名)
お申し込み方法:オンラインフォームから[こちらから]
申し込み締切【延長】:9月18日(水)2019年7月31日(申込み順に受入。満員になり次第終了。)
お支払い方法:ご自身でホテルに直接お支払いください。
<お問い合わせ先>
日本地質学会事務局:main[at]geosociety.jp
2019山口_招待講演
日本地質学会第126年学術大会:セッション招待講演者
▶山口大会ウェブサイトへ戻る
世話人や専門部会から提案され,行事委員会が承認したセッション招待講演者を紹介します(タイトルをクリックする).なお,講演時間は変更になる場合があります.
トピックセッション
T1.日本海拡大に関連した...
T2.大学・博物館の学術標本の未来
T3.人新世の堆積学
T4.文化地質学
T5.南海トラフ地震発生帯...
T6.中国地方活断層,地震活動
T7.日本列島形成史の新景観
レギュラーセッション
R1.深成岩・火山岩
R2.岩鉱一般
R3.噴火・火山発達史
R4.変成岩とテクトニクス
R5.地域地質
R6.ジオパーク
R7.新生代の地質事変
R8.海洋地質
R9.堆積物の起源・組織・組成
R10.炭酸塩岩の起源...
R11.堆積過程・堆積環境...
R12.石油・石炭地質学
R13.岩鉱の変形と反応
R14.沈み込み帯・陸上付加体
R15.テクトニクス
R16.古生物
R17.ジュラ系+
R18.情報地質
R19.環境地質
R20.応用地質
R21.地学教育・地学史
R22.第四紀
R23.地球史
R24.原子力と地球科学
R25.鉱物資源
トピックックセッション:7件
T1.日本海拡大に関連したテクトニクス,堆積作用,マグマ活動,古環境
佐藤 壮(気象庁札幌管区気象台,非会員)30分:佐藤氏は弾性波探査による地殻構造探査を精力的に行っている研究者である.最近はプレート構造研究および日本海地震津波防災研究プロジェクト研究の一環として日本海の地殻構造探査を行い,大和海盆の詳細な地殻構造を明らかにしたSato et al., 2014, 2018).氏にはこれまでの日本海地殻構造探査のリビューを含め日本海地殻の最新情報を提供していただきたい.
磯粼行雄(東京大,会員)30分:磯粼会員は地球史および日本列島形成史について精力的に研究している.氏の調査対象は主に先中新世の地層および古生物であるが,日本列島形成史における日本海拡大事件の重要性も強く認識しておられる(Isozaki, 2019; 磯粼,2019).氏には広い視点から日本海拡大の地質学的意味について論じていただきたい.
T2.大学・博物館における学術標本の未来―人口減少・災害多発社会における標本散逸問題を考える―
真鍋 真(国立科学博物館,非会員)30分:真鍋氏は,現在国立科学博物館標本資料センターのコレクションディレクターの重責を担っておられ,日本の博物館関係における標本の現状・問題点および動向を一番よく把握・認識している研究者であある.またご本人も,恐竜および大型化石研究の第一人者として様々な研究論文・一般普及書を記述されており,研究者としての標本問題に関する視点も合わせ持ち,招待講演者としてこれほどふさわしい方はいない.
鈴木まほろ(岩手県立博物館,非会員)30分:鈴木氏は,生態学関係の標本問題に関して以前から関心を持ち,調査・研究を実施してきた生物学者である.博物館所属生物標本問題や活用事例に関しての研究論文も公表され,昨年は全国の博物館・大学研究者へ向けての生態学標本問題の調査も実施しておられる.本セッションでは鈴木氏の調査によって浮かび上がってきた生物系自然史標本の問題点・動向などについて講演していただく予定である.
ページtopに戻る
T3.人新世の堆積学
磯辺篤彦(九州大,非会員)30分:磯辺氏は我が国を代表する海洋マイクロプラスチック(MP)研究者の1人で,環境省環境研究総推進費(海洋プスチックごみ分野)の代表を務める.専門は海洋物理で,日本がMPのホットスポットであることをいち早く突き止めた.最近ではMPのグローバル分布量の将来予測を行い,50年後に浮遊MP量が現在の4倍になることを報告した.海洋プラスチックに極めて造詣が深く招待講演者としてふさわしい.
中嶋亮太(JAMSTEC,非会員)15分:中嶋氏は,米国スクリプス海洋研究所でマイクロプラスチック(MP)の研究に携わり,現在はJAMSTECに新設される海洋プラスチック動態研究グループでMP分析技術開発や深海におけるプラスチック汚染の研究を進めている.米国を中心とする国際海洋プラスチック有識者会議(PAGI)のメンバーであり,海洋プラスチック問題(特に堆積物MP)について造詣が深く招待講演者にふさわしい.
T4. 文化地質学
根井 浄(元龍谷大,非会員)30分:根井氏(元龍谷大学文学部教授;日本山岳修験学会副会長;肥前島原松平文庫長)は,古文書などの歴史資料に立脚し,石碑解読などの現地調査を交えながら人々の信仰の歴史を明らかにしてきた.とくに「海」や「山」に関する宗教民俗に詳しく,複数の大著を著している.海については,「補陀落渡海」という海の彼方に存在すると信じられてきた観音浄土を目指す即身成仏的な行について調査してきた.山については,雲仙普賢岳を中心に展開してきた山岳修験者たちと16世紀に出現したキリシタンたちとの宗教的対立について詳しい.いずれも日本の自然を人々がどのように捉えていたか考える上で,重要な論考である.本招待講演ではとくに九州の火山に焦点を当て,そこで展開された山岳修験と地質の関係についてご講演いただく予定である.
後 誠介(和歌山大・災害科学教育研究センター,会員)30分:後会員は,熊野学研究委員として1984年から地域学としての熊野学に係る調査・普及に携わってきた.2004年に「紀伊半島の霊場と参詣道」が世界遺産(文化)に登録されてからは,「熊野はなぜ霊場になったのか〜地質からみて〜」や「地質からみた熊野」をテーマとして,講演・執筆を続けてきた.2014年の南紀熊野ジオパークの認定に際しては,その構想段階から学術専門委員として地質学的知見を整理するとともに,熊野の歴史・文化を地形・地質から読み解く視点を主導してきた,ジオパークガイド養成講座(座学・現地実習)の指導,資料集・展示・映像などの監修,ジオツアーの企画協力のほか,自身も講演・執筆を続けている.本招待講演では熊野の霊場の文化景観を地質学的に解説していただく予定である.
T5.集大成! 南海トラフ地震発生帯掘削計画
木村 学(東京海洋大,会員)30分:木村会員はIODP南海トラフ地震発生帯掘削計画のリーダーであり,数多くの研究成果を出している.また本計画は多くの関連分野を横断する大型研究であるが,全体を俯瞰し,幅広い分野の聴衆に成果を理解してもらうためにも最適の人物である.
倉本真一(JAMSTEC,会員)30分:倉本会員は地球深部探査船「ちきゅう」を運行する海洋研究開発機構・地球深部探査センターのセンター長として本計画の立ち上げから携わってこられた.倉本会員は地質学研究者として,この分野に最適な探査船のあり方も模索して来られており,この10年における掘削技術の進歩と限界をレビューしてもらう.それは将来の地質掘削プランの大きなヒントになるだろう.
T6.中国地方の活断層, 地震活動とひずみ集中帯
飯尾能久(京都大・防災研,非会員)30分:飯尾氏は上部地殻内で地震が発生する理由として下部地殻からのひずみ集中を提唱され,これは現在では内陸直下型地震の発生モデルの主流となっている.また,鳥取県西部〜中部域において永年稠密な地震観測を行ってきており,本セッションに対して地震学の立場から大きく貢献する.
西村卓也(京都大・防災研,非会員)30分:西村氏は山陰地域に独自のGPS測地観測網を設置して,本地域でひずみの集中が起こっていること(山陰ひずみ集中帯の存在)を発見された第一人者である.西南日本全域のGPS解析も行なっており,中国地方を取り巻く広域の地殻変動に関して幅広い知識を有する.
T7.日本列島形成史の新景観
野田 篤(産総研,会員)15分:野田会員は西南日本の白亜系和泉層群を対象に野外調査を行い,さらに世界の前弧盆地一般の形成過程についてのコンパイルに基づき新しい解釈を提案している.日本の地域地質に関する深い知識から世界に向けて新しい概念を導きつつある同氏に講演していただくことによって,昨今忘れられがちな地域地質学の威力をアピール出来ると考える.
堤 之恭(国立科学博物館,会員)15分:堤会員は近年の日本のジルコン年代測定を牽引するリーダーの一人で,独自の手法開発と実際の年代測定において多くの研究者との協力を通して多大な成果をあげられている.是非講演をお願いしたい.
ページtopに戻る
レギュラーセッション:25件
R2.岩石・鉱物・鉱床学一般
辻森 樹(東北大,会員)30分:辻森会員は,青色片岩などのプレート境界岩を丹念な野外調査・岩石組織観察・地球化学分析から研究され,プレート沈み込みのダイナミクスの素過程の理解と地球変動史の解読に精力的に取り組んでこられた.特に近年,プレート境界岩の造岩鉱物の局所同位体分析により,これまで『未読』であった全く新しい物質科学的な情報を抽出・蓄積されつつある.ご講演ではこれらの未読情報の統合解析から,太古代〜顕生代の4つの年齢における造山帯の緑色岩・高圧変成岩を研究対象に,プレート境界のプロセスと経年変動を読み解く重要性について紹介いただく.さらには固体地球の進化史の物質科学的な検証,特に再生地殻成分の大循環と固体地球の長周期変動の体系化に関するあらたなプロトコルについて伺える予定である.
R4.変成岩とテクトニクス
西山忠男(熊本大,会員)30分:西山会員は,野外調査や鉱物組織観察といった岩石学の基礎を重視されつつ,一貫して変成岩や火成岩におけるパターン形成,反応と変形の連結現象,拡散といった物理化学プロセスを研究されてきた.特筆すべきは,他分野の理論を効果的に導入しながら非平衡開放系や不可逆過程の問題に取り組み,平衡論を軸とする従来の岩石学研究とは一線を画す成果を上げてこられた点である.その多岐にわたる研究は岩石成因に新たな描像を与え,「動的な岩石学」の端緒を開いたと言える.本招待講演では,多分野の手法の融合により得られた最新の研究成果に関する話題が期待される.
R6.ジオパーク
竹之内 耕(フォッサマグナミュージアム,会員)30分:竹之内会員は,糸魚川ユネスコ世界ジオパーク設立当初から中心的に活動を展開してきた.また,その経験を生かして日本ジオパークネットワーク(JGN)でも指導的な役割を担ってきた.現在日本のジオパークの課題について話題提供者として適任の人材である.
R8.海洋地質
多田隆治(東京大,会員)30分:多田会員は海域および陸域双方の地質記録からアジアモンスーンの進化に関する研究を進め,2013年には自らが代表プロポーネントとして計画された日本海および東シナ海北部のIODP(国際深海掘削計画)Expedition 346に共同主席研究者として乗船した.現在,その成果が増えつつあり,今年のPEPSでは特集号もまとめられた.
池原 実(高知大,会員)30分:池原会員は長年にわたって様々な指標を用いた古海洋学的研究を行っており,特に南大洋においてはIODPの掘削提案を行う中心的な役割を果たしている.また,昨年度より新学術領域研究が採択され,古海洋研究班のリーダーとして研究を推進している.今後数年間は南極海においてIODPによる掘削航海が立て続けに計画されていることなど,これから注目される研究テーマとして関心が向けられている.池原氏には南大洋が気候変動に果たす役割について最新の研究成果や国内外の研究動向に加え,今後の課題についてご講演いただく.
ページtopに戻る
R9.堆積物(岩)の起源・組織・組成
竹内 誠(名古屋大,会員)30分:竹内会員は,西南日本の付加体・変成帯から内帯の陸成層,東北地方の古生代整然層に到るまで幅広い地質体を対象に,主に砂岩組成や重鉱物の化学組成などのデータをもとに後背地解析の研究を進めてきた.最近では,砕屑性ジルコンのU-Pb 年代を用いて各地の堆積物の層序や後背地,運搬経路などについての研究を行っている.招待講演では,最近の研究成果の一部を紹介して頂き,後背地研究の今後の展開を議論するきっかけとしたい.
原 英俊(産総研,会員)30分:原会員は,砂岩組成や全岩化学組成などの従来的な手法に加え,砕屑性ジルコンのU-Pb 年代や放散虫化石などの複数の年代軸を組み合わせることで,四国の四万十帯の形成史や後背地についての新しいモデルを提唱している.招待講演では白亜紀から古第三紀にかけて四万十帯付加体が経験した後背地の変化などについて紹介して頂き,堆積物が持つ様々な情報を地史の理解にどう活かすのかなど,今後の研究のあり方について考える機会としたい.
R10.炭酸塩岩の起源と地球環境
上野勝美(福岡大,会員)30分:上野会員は,後期古生代から前期中生代の有孔虫の分類,生層序,古生物地理,炭酸塩堆積場の環境復元,東アジアの地質構造発達史などに関する研究にこれまで精力的に取り組んでこられた.山口大会開催地にある石炭〜ペルム系秋吉石灰岩に関する研究においても,数多くの重要な研究成果をあげられてきた.招待講演では,秋吉石灰岩での年代層序を基にした炭酸塩堆積相の時代的変遷,海洋島起源石灰岩から海水準変動を読み取る試みなどについて講演頂く予定である.
R11.堆積過程・堆積環境・堆積地質
成瀬 元(京都大,会員)30分:成瀬会員は,堆積物重力流について,実験,野外調査,組織解析,モデリングといった多様な側面から,その挙動や堆積過程についての研究を行ってきた.彼はこの分野を世界的にリードする研究者の一人である.2015年に公表された,混濁流とその堆積物についての研究の方向性を示した論文は世界をリードする研究者らによって著されたのもので,成瀬会員はその著者の1人に名前を連ねている.成瀬会員には混濁流のモデリングについて,研究の方向性を含めたレビューを行って頂く予定である.
David Hodgson(リーズ大,非会員)30分:David Hodgson氏は,世界各地で露頭観察などの野外調査をベースに堆積盆解析を行ってきた.特に重力流堆積物を主な研究対象として海底のチャネル-レビーシステムやローブシステムといった堆積体の堆積過程や形態の特徴を明らかにする研究を精力的に進めてきた.重力流堆積物そのものや重力流堆積物が作り出す堆積体に関わる最新の研究の動向をお話いただくとともに,成瀬会員による講演を併せて,重力流とその堆積物についての研究の方向性を議論する機会としたい.
R12.石油・石炭地質学と有機地球化学
荒戸裕之(秋田大,会員)30分:荒戸会員は,反射法地震探査記録を用いた石油・天然ガスの成因や探鉱に関する研究に長年取り組んでおられ,この分野をリードしてきた研究者の一人である.また,国の基礎調査に関するワーキンググループの委員長として,海域の三次元地震探査調査による堆積盆地評価に関する議論をまとめられた.招待講演では,本邦周辺海域で実施されてきた基礎調査による三次元地震探査記録を用いた堆積盆地の解析について話題を提供して頂く予定である.
R13.岩石・鉱物の変形と反応
岩森 光(JAMSTEC/東京大,会員)30分:岩森会員は,地球内部の物質分化と循環のダイナミクスに関して,野外調査のみならず,地質体の運動場モデルの数値シミュレーションや多変量解析を用いた研究を展開し,国際的にも先駆的な成果を発信続けておられる.山口大会では,沈み込み帯での流体の役割についてご自身の研究を交えてご教示いただく予定である.
片山郁夫(広島大,会員)30分:片山会員は,沈み込み帯深部条件での流動特性に関して,岩石変形実験や野外調査から,地震発生ダイナミクスおよび地球内部での物質循環に関する研究成果を数多く発信されている.また,近年は超深度掘削モホール計画に参画されており,国際的に地質学をリードされている研究者の一人である.山口大会では,大陸・海洋プレートのレオロジー構造についてご自身の研究を交えてご教示いただく予定である.
R14.沈み込み帯・陸上付加体
古市幹人(JAMSTEC,非会員)30分:古市氏は,計算科学の専門家であり,主に粒子法シミュレーションコードの開発と応用において世界をリードしている.世界でも圧倒的な規模を誇る25億粒子数のDEM砂箱実験によって南海掘削海域で実測されている応力場の再現に成功したほか,付加体内部に存在する応力ネットワークを提案するなど,興味深い成果を発信されている.本講演では,最近の実験成果を紹介いただく.沈み込み帯のヒミツ解明に計算工学から切り込む,必聴の講演.
大橋聖和(山口大,会員) 30分:大橋会員は,野外調査と岩石力学実験の両方からアプローチする新進気鋭の研究者である.最近ではOSL(光刺激ルミネッセンス)信号の断層によるリセット条件を実験的に検証している.その結果,比較的浅い断層掘削であっても最新活動年代を決定できるという.現世付加体の断層が,いつ,どんな順番で活動してきたのか.定量イメージへの期待がふくらむ.“未来を見逃すな”
ページtopに戻る
R15.テクトニクス
金折裕司(山口大,会員)30分:金折会員は,本大会開催地である山口県を始めとした西南日本の内陸活断層やネオテクトニクスについて,野外調査などを基に研究してこられた.本講演では,金折氏の代表的な業績である,マイクロプレートモデルに基づいた西南日本のテクトニクス論について,包括的な講演を頂く.また,金折氏は地域防災やアウトリーチ活動についても多くの功績を残しており,その経験に根差したユニークな切り口にも期待したい.
野田 篤(産総研,会員)30分:野田会員は,海洋地質学的知見や陸上の地質記録,数値モデル,砂箱を用いたアナログ実験などの結果を総合し,沈み込み帯における前弧堆積盆の分類と発達様式に関する優れた論文を近年立て続けに発表されている.本講演では野田氏の前弧堆積盆に関する最新の知見をご紹介いただくことにより,前弧堆積盆からみた沈み込み帯のテクトニクスの理解を深めたい.
R16.古生物
江崎洋一(大阪市立大,会員)30分:江崎会員は,海洋生物,特に生物礁を用いた地球環境と生物群集の相互作用に関する研究を行っている.地質学会山口大会では,後期古生代の海山性石灰岩体である秋吉台にちなみ,石灰岩・生物礁をキーワードとして,地球生物相の進化,礁生態系の復元と変遷,ならびに地球環境復元に関するこれまでの研究をご紹介頂きたい.
R17.ジュラ系+
脇田浩二(山口大,会員)30分:脇田会員は,付加体地質について長年にわたる研究実績がある.とくにジュラ紀付加体の野外地質調査にもとづく研究について多大な業績を残されている.地質図の国際的な基準を策定する分野でも活躍されている.招待講演では,ご自身の体験も交えて,野外地質調査の魅力についてのエピソードを含めた講演を期待している.
ページtopに戻る
R20.応用地質学一般およびノンテクトニック構造
廣瀬 亘(道総研,会員)30分:平成30年9月6日に発生した北海道胆振東部地震では,厚真町等で広範囲に顕著な斜面崩壊が多発した.その崩壊の発生件数および分布密度は特異なものであるため,斜面災害に関わる研究者から注目を集めている.廣瀬氏ら北海道立総合研究機構・地質研究所の地形学および地質学を専門とする研究者らは地元の研究機関としてこの災害の解明に重点的に取り組んでおり,継続的に調査報告を行っている.特に,廣瀬氏は火山地質学を専門とし,顕著な崩壊をもたらした火山灰層とそれらが作る地形の発達について広く調査し,重要な考察を行っている.本講演では廣瀬氏に以上を解説頂き,この特異な斜面災害のメカニズムについて議論を行う.
R23.地球史
臼井寛裕(JAXA,非会員)30分:臼井氏はこれまで火星の表層環境史を地質学を武器に研究されてきた.招待講演では,火星研究の現状と探査の将来展望について,最新の成果を踏まえて解説していただく.
早坂康隆(広島大,会員)30分:早坂会員は,野外地質調査を基軸とし,岩石化学/年代学/構造地質学的手法を用いて日本列島を含むアジア,北東シベリア,西太平洋地域のテクトニクスに関する研究を行ってきた.長年の調査が実り,島根県舞鶴帯において木村光佑氏らとともに日本最古の岩石を発見した.招待講演では,最新の成果を踏まえて中国地方の地質およびアジアとの関連性を紹介していただく.
ページtopに戻る
R24.原子力と地質科学
日高 洋(名古屋大,非会員)30分:日高氏は,自然界で生じる核反応を元素の同位体変動から検出し,その現象解明に取り組んでおり,オクロ天然原子炉は,その研究対象の一つである.天然原子炉から採取された様々な試料を分析して得られた一連の同位体データから解明された原子炉内外における放射性核種の中〜長期にわたる移行挙動,核分裂メカニズムについて紹介していただく.
R25.鉱物資源と地球物質循環
森下祐一(静岡大,非会員)30分:森下氏は,金,白金族元素,レアメタルなどの資源の成因を研究する資源地質学の第一人者であり,最先端の二次イオン質量分析計による微小分析を駆使することで,今まで明らかとなっていなかった有用元素の挙動と濃集プロセスを解明するなど,非常に独創的な研究を展開し,この分野をリードし続けている.本講演では,当該分野の最新の話題を提供して頂く予定である.そのお話を聞ける機会は,本セッションに関係する全ての研究者にとって非常に有意義なものになると期待される.
報告_2019.11.23「GSSPシンポジウム:国際層序の意味と意義」
「GSSPシンポジウム:国際層序の意味と意義」報告
日本地質学会会員
石渡 明,北里 洋,天野一男
齋藤 眞,斎藤文紀,岡田 誠
羽田裕貴,松岡 篤
画像をクリックするとPDFファイル
をDLして頂けます
このシンポジウムは日本地質学会の主催、産総研地質調査総合センターと日本古生物学会の共催で2019年11月23日(土)13:00-17:30に産総研つくば中央の共用講堂で行われた。当日は雨の中、約80人が参加した。GSSPとは、Global boundary Stratotype Section and Point(「国際境界模式層断面とポイント」)のことで、今話題のチバニアンは、地球全体の新生代第四紀の中期更新世/前期更新世境界のGSSPを、千葉県市原市(いちはらし)田淵の養老川沿いの上総(かずさ)層群国本(こくもと)層の露頭に設定し、これまで名前がなかった中期更新世の時代を「チバニアン」と名づけるものであり、国際地質科学連合(IUGS)は2020年1月17日に釜山で開催された会議でチバニアンのGSSPを正式に決定した。なお、IUGSの地質年代表は、
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//name/ChronostratChart_jp.pdf
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//name/ChronostratChart.pdf
にある(和文/英文、最新版)。
本シンポジウムのプログラムは次の通りである。
第1部 国際層序について
開会あいさつ 松田博貴(日本地質学会会長)
北里 洋 国際層序とは(地質学の歴史と現在の国際的状況)
天野一男 日本における国際層序への取り組み
齋藤 眞 地質学に関する国際標準の国内への適用
第2部 年代層序単元・地質年代単元とGSSP
斎藤文紀 第四系のGSSPと細分:チバニアンや人新世
岡田 誠 新たなGSSPの提案:「千葉セクション」
羽田裕貴 千葉複合セクションから明らかになった地球環境変動
松岡 篤 中生界のGSSPがなかなか決まらないのはなぜか
総合討論 磯粼行雄(司会) 閉会あいさつ 西 弘嗣(日本古生物学会会長)
●北里 洋はIUGSの財務理事を務めている。地質学は長大な時間の流れの中で地球の歴史を扱うユニークな自然科学である。IUGSは、100万人に及ぶ世界の地質学関係者を代表して、あらゆる分野の地質科学の振興と発展を促している。その一つとして地質時代の標準化がある。中期更新世の基底の境界を日本に置こうという提案に象徴される、地質時代の定義とその境界基準の策定が好例である。地球の歴史を読み解く際の基本である層序の編纂に欠かせない地層命名規約はIUGS 傘下の国際層序学委員会で策定しているが、日本では1952年にそれに準拠した地層命名規約を作っている。これは世界で3番目のことであった。
●天野一男は、日本地質学会による訳本「国際層序ガイド」の出版と「日本地質学会地層命名の指針」の策定について報告するとともに、「第三紀問題」を取り上げた。第一紀(ほぼ古生代に相当)・第二紀(ほぼ中生代に相当)は100年以上前に抹消されたが、第三紀は1968年に英国で非公式名称とされ、1989年には米国でも非公式名称とされた。そして2009年に国際層序委員会で第三紀が正式に地質時代表から抹消されたが、日本では「新第三紀」(Neogene)、「古第三紀」(Paleogene)という形で第三紀という名称が残っている。「新成紀・古成紀」、「新獣紀・古獣紀」という名称の提案もあったが、まだ採用されていない。また「第四紀」については,2009年に下限が変更になり、鮮新世に含められていたGelasianを第四紀に含めるようになった。
●齋藤 眞は地質図に関する日本産業標準(JIS)であるJIS A0204とJIS A0205の2019年3月の改正について解説した。またこれらのJISが当初からISOや国際年代層序表などの国際基準に基づいて作成されてきた経緯についても述べた。これらJISは、公共事業等では強制標準として扱われるため、そういう方面に進む学生には知っておくべき事であることも述べられた。
●斎藤文紀によると、完新世/更新世境界はグリーンランドの氷床コア(掘削試料)にGSSPが設定されたが、日本の福井県の水月湖の堆積物コアが副模式標本として採用された。これは「副」ではあるが、日本の地質層序がGSSPに採用された最初である。2018年に完新世の3期区分とその名称が決定され、下からGreenlandian, Northgrappian, Meghalayanになった。各期の開始年代は11.7, 8.2, 4.2千年前(ka)である。Meghalayanの基底は、インドの鍾乳洞の鍾乳石の中にGSSPが打たれた。この時期以後の寒冷化により世界中で多くの文明が消失し、日本で青森県の三内丸山遺跡の縄文時代集落が消滅したのもこの頃である。また、更に新しい地質時代として、西暦1950年頃を境界としてそれ以後を人新世(Anthropocene、または人類世)とする提案が準備されており、そのGSSPの候補地の1つとして日本の別府湾が検討されている.
(質問に答えて)チバニアンの1つ後の時代である後期更新世も、まだ時代名とGSSPが決まっていないが、国際的にこのGSSPの検討は動きが鈍く、(広域火山灰層が多くて有利な)日本からの提案も今のところない。
●岡田 誠はチバニアン提案グループの代表である。千葉セクションおよび周辺地層の平均堆積速度は2m/1000年と速く、そのためGSSP申請に必要とされた海洋同位体ステージ20-18をカバーする5万年間の詳細な層序データを得るためには、1つの露頭では無理で、複数の近隣露頭を合わせた複合セクションにならざるを得ない。チバニアンの基底層準は房総半島の多くの地点に露出しているが、最も広範囲に露出しアクセスのよい場所が、養老川沿いの千葉セクションである。「チバニアン」の語は、ストレートな命名であるチビアンでは日本語的に違和感があるため、二重形容詞格を用いたチバニアンの名称で提案している。同様な語法を採用した地質時代名は他にないが、パナマ人をPanamanではなくPanamanianと呼ぶ例がある。
(質問に答えて)GSSPのゴールデン・スパイク(金釘)は肉眼的に明瞭な地層境界に打つことになっており、チバニアンのスパイクは白尾(びゃくび)火山灰層の基底に打つ予定である。逆から正への地磁気逆転境界はこの層準より数m上(露頭最上部)にある。
●羽田裕貴によると、チバニアン露頭の層準を含むMIS(酸素同位体ステージ)19は、過去100万年間で軌道要素の条件がMIS1(完新世〜現在)に最も類似し、今後の気候変動の予測にMIS19の研究が重要である。MIS19では温暖期が約1万年で終了したので、既に温暖期が1万年以上続くMIS1でも、人為的な影響がなければそろそろ寒冷化して氷期に入る可能性も考えられる。
●松岡 篤は国際ジュラ系層序小委員会のvoting memberを務めている。中生界のGSSP設定率は古生界や新生界より低く(図1)、ジュラ系/白亜系境界にもまだGSSPが設定されていない。国際白亜系層序小委員会のBerriasianワーキンググループは、白亜系の下限をヨーロッパから中米にかけての当時の低緯度海域に分布が限られるカルピオネラという浮遊性微化石のアクメ帯(注)の下限とすることを決定し、その基準をもちいてGSSPの候補としてフランス南部のセクションを推薦している。この取り扱いについての大きな問題は、カルピオネラが太平洋地域からは全く産出しないことと、アクメ帯(注)の下限という化石帯境界が、どの程度に同時性を保持しているかがわからないことにある。さらに、白亜系の基底をBerriasianにするのかValanginianにするのかについても議論が続いている。中生界の各系のvoting memberは圧倒的に欧米の出身者が多く、アジア人は少ない。「国際」と言っても、欧米中心の議論になっており、GSSP設定に関して重要な意味をもつ国際会議は、ほとんどが欧米で開催されている。また、このような国際会議へのアジアからの出席者の数はきわめて少ない。
(注:定義にかかわる分類群が多産する層位範囲で規定される化石帯)
図1.地質時代の期の数とGSSP数の変化(石渡原図)。各年のIUGSの地質年代表に基づく。中生代のGSSP設定率は古生代や新生代より低い。注:「期」がない「世」は1期と数え(シルル紀プリドリ世と2018年以前の完新世)、カンブリア・オルドビス紀の無名期も各々1期と数える。なお、2019年のGSSP数はチバニアンを含まない。
総合討論
最後の総合討論では下記のような討論が行われた。
Q:チバニアン露頭を含む1/5万地質図「大多喜」は未刊行だが?
A(産総研):数年後の出版を目指して努力している。油田ガス田図等は刊行済みである。
Q:チバニアンは日本の地名なのだから、日本では「千葉期」と呼ぶべきではないか?
A(岡田):確かにその方が国内的に地質学への興味喚起を行う上でよいかもしれないが、地質学会では「チバニアン期」といった呼び方をすることを決めている。今後の議論が必要である。
2020.1.20掲載
開催通知
日本地質学会第127年学術大会(2020名古屋大会)
名古屋大学東山キャンパス(愛知県・名古屋市千種区)にて
2020年9月9日(水)〜11日(金)に開催
日本地質学会は,名古屋市の名古屋大学東山キャンパスにて,第127年学術大会(2020年名古屋大会)を9月9日(水)〜11日(金),巡検(見学旅行)を9月8日(火)と9月12日・13日(土・日)に開催します.
名古屋は日本のほぼ中心に位置し,交通の便もよく,皆様の旅程も容易に計画することができます.またすべての学会会場を東山キャンパスの西側に位置する教養教育院に設け,場所的に集中した複数の会場でコンパクトに行う予定です.地下鉄の「名古屋大学」駅1番出口を出て5分くらいで到着できます.
学術大会では多様な学問領域が議論されることでしょう.この学問的な多様さというものは,生物の多様さと同様に,学問領域の健全さ,強さを示していると思います.研究領域が広く,様々な手法で問題と取り組み,異なる研究領域の研究者と触れ合うことが地質学の強みであると同時に,新たな展開を生むことにつながると私は信じています.特に若手研究者にとって,所属する大学以外の研究者と触れ合い,議論し,情報交換を行うことが,新しい考えを生むことにつながります.私自身,修士1年の時に初めて地質学会で発表した際に受けた(そして答えられなかった)質問は今でも忘れることができません.そしてその問題を,その後も考えるきっかけとなりました.これからの地質学を支える若手が,名古屋の大会で新たな展開を得られればと望む次第です.もちろんこれらは若手に留まらず,参加者全員にとって,大会が自身の研究成果の発表の場,さらなる研究の展開の場,情報交換の場,そして「旧友」に出会い,近況を互いに語らう場としても重要でしょう.そのような場を作っていけるよう,実行委員会は努力したいと思います.
名古屋近辺では,日本の地質を見直すきっかけとなった美濃帯の中古生界,愛知県の石にも選定された師崎層群の深海性化石群を始め,多様な地質体を観察することができます.それらのうちから,巡検として今回は以下の8つのコースを考えました.名古屋城(石垣などの岩石の観察),舟伏山周辺(美濃帯の付加体),新城市周辺(領家帯・三波川帯・中央構造線),中新統師崎層群(コンクリーションと深海性化石群),揖斐川町(接触変成岩と花崗岩類),名張〜松阪周辺(四万十帯,三波川帯,変形岩),そして瀬戸層群(陶土層)です.皆様に楽しんでいただけたらと思います.
名古屋大会が研究に関する活発な議論の場となり,これからの地質学を発展させる機会となることを望んでいます.そのために,大会実行委員会一同,開催に向けて頑張りたいと思います.皆様の127年学術大会へのご参加を心からお待ちしています.名古屋にいりゃーせ!
2020年1月
日本地質学会第127年学術大会(名古屋大会)実行委員会
委員長 大路樹生
トピックセッション募集
トピックセッション
応募のあった、下記7件のトピックセッションを採択致しました。(3/17 行事委員会)
広域観測・微視的実験連携による沈み込み帯地震研究の新展開(木下正高)
海底地盤変動学のススメ(川村喜一郎)
スロー地震に関する地質学的・実験的・地震学的研究の連携と進展(氏家恒太郎)
二次改変された過去の弧-海溝系の復元:日本およびその他の例(磯崎行雄)
文化地質学(大友幸子)
災害多発社会における学術資料・標本散逸問題―大学・博物館は何をすべきか−(堀 利栄)
地球年代学が拓く高精度火山噴火史・発達史(上澤真平)
※( )は代表世話人
トピックセッション募集 締切:2020年3月10日(火)
第127年学術大会(名古屋大会)は,中部支部のご協力のもと,名古屋大学東山キャンパスを会場として2020年9月9日(水)〜11日(金)に開催されます.トピックセッションを下記要領で募集します.本大会も前回同様,シンポジウムの一般募集はありません.シンポジウムは名古屋大会実行委員会および学会執行部が企画します.
1.セッション概要
セッションは例年通り「レギュラーセッション」,「トピックセッション」,「アウトリーチセッション」に区分します.レギュラーセッションは昨年と同じ25タイトルを予定しています(レギュラーセッションは3月下旬に行事委員会が決定します).
2.トピックセッション募集
トピックセッションは,広く地質学の領域に属し,これから新分野あるいは注目すべき分野になりそうな内容を扱うものとします.形式はレギュラーセッションと同じです(口頭発表およびポスター発表:口頭発表は15分間で,進行も15分刻み).多くの参加者が見込まれる,魅力あるセッションを積極的にご提案ください.締切後,行事委員会が応募内容を慎重に検討し,最大8件程度のトピックセッションを採択する予定です.
3.トピックセッション招待講演
トピックセッションの招待講演には例年と同じルールを適用します.
1) 招待講演は1セッションにつき最大2名とし,会員,非会員を問いません.世話人が「自分を招待する」ことは認めません.
2) 発表時間(質疑応答を含む)は世話人が15分または30分のいずれかを選択できます.なお,1人の発表者(招待講演者を含む)が1つのセッションで口頭発表できるのは1件です.
3) 招待講演者の選定理由とその裏付けとなる情報(セッションテーマに関連した代表的な論文,著書等)が必要です.
4) 会員招待講演者が招待講演の他に非招待の発表を1件申し込む場合,発表負担金はかかりません.さらにもう1件(招待講演の他にセッションで2件)発表する場合は負担金がかかります.
4.応募方法
トピックセッションを応募する会員は,次の項目内容を日本地質学会行事委員会宛(main@geosociety.jp)にe-mailでお申し込み下さい.
1) 代表世話人(=連絡責任者,会員に限る)の氏名(和・英),所属(和・英),メールアドレス,緊急時の電話番号
2) セッションタイトル(和・英)
3) 共同世話人の氏名(和・英),所属(和・英),メールアドレス
4) 趣旨・概要(400〜600字)
5) 招待講演の有無
有の場合
5-1)招待講演者の氏名(和・英),所属(和・英),会員/非会員の別
5-2)招待講演の発表希望時間(15分または30分)
5-3)招待講演者の選定理由(100〜200字)
5-4)選定理由の裏付けとなる,セッションテーマに関連した代表的な論文・著書等
6) 他学協会との共催希望の有無,有の場合は名称
7) 時間(原則半日(3時間)以内ですが,詳細はお問い合わせください)
8) 地質学雑誌またはIsland Arcへの特集号計画の有無(できる限り特集号を計画してください)
9) その他(英語使用等)
5.採択方法
応募多数の場合や他セッションと内容が重複する場合,行事委員会は学術的なインパクトや緊急度を考慮して採択を決定します.採択されたトピックセッションはニュース誌5月号(5月末発行予定)で公表し,講演募集を行う予定です.演題登録(講演申込,講演要旨投稿)締切は7月初旬を予定しています.
6.非会員招待講演者の参加登録費
非会員招待講演者に限り参加登録費を免除します(ただし要旨集は付きません).
7.世話人が行う作業(7月初旬〜中旬)
代表世話人には,講演要旨校閲,講演順番決定などの作業を7月中旬までに行っていただきます(詳細は採択後にお知らせします).その期間,代表世話人は電子メールで添付ファイルを送受信できるようにして下さい.野外調査や乗船等で通信が制限される場合は,共同世話人(代理)にあらかじめ作業を依頼し,その旨を行事委員会に必ず報告してください.
ご不明の点があれば行事委員会(main@geosociety.jp)までお気軽にお問い合わせください.
名古屋TOP
2020名古屋大会プレページ_top
日本地質学会第127年学術大会
会期:2020年9月9日(水)〜11日(金)
開催中止(1年延期)となりました
会場:名古屋大学東山キャンパス(愛知県・名古屋市千種区)
[関連行事]地質情報展2020なごや
日程:9月20日(土)〜22日(月・祝) 場所:名古屋市科学館
※情報展も大会同様に中止(1年延期)となりました
更新情報
20/07/22 代替企画の情報をお知らせします NEW
20/05/25 大会の開催中止(延期)と代替企画について
20/04/13 新型コロナウィルス感染拡大防止に関する学会の対応
20/03/17 トピックセッション決定しました!
20/01/31 トピックセッション募集(締切:3/10)
20/01/31 大会開催通知
20/01/31 名古屋大会プレページ開設しました
2020名古屋代替_ショートコース
要旨・開催報告▶︎ 日本地質学会News vol.24, No. 6, p.6-7(2021年6月号掲載)
日本地質学会第1回・第2回ショートコース
本年秋の学術大会が新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止(来年に順延)になったことを受け,その代替企画について執行理事会が中心となって検討してきました.その結果,代替企画の一つとして「日本地質学会ショートコース」を開催することになりました.検討を進める中で,大学の地球惑星科学系学科では地質学の基礎的内容でありながら学科構成スタッフの偏りのために学部生や大学院生に十分教えられていないトピックがあり,そうした内容を本学会が少しでもカヴァーできないかという意見がありました.また,地質技術者や学校教員,学芸員等が現在の地質学の知見や研究方法等について学ぶ機会があると良いという意見もありました.こうした意見を踏まえて,地質学の土台を支える基礎知識や最近ホットな研究の話題など,会員・非会員を問わず多くの方々に知っていただきたいトピックを「日本地質学会ショートコース」で紹介することになりました.本年9月19 日(土)に第1回目を,10月24 日(土)に第2回目をオンラインで開催し,各回2名の研究者に話題提供していただきます(午前1名,午後1名).その道の精鋭によるコースをぜひこの機会に受講していただきたいと思います.
2020年7月11日
日本地質学会行事委員長 星 博幸
第1回 日程:2020年9月19日(土)
内容:(各コース、講義、質疑応答を含め3時間程度を予定)
<午前> 東北アジア及び日本列島の地体構造発達史:辻森 樹(東北大学)
https://researchmap.jp/tatsukix
日本列島の地体構造発達史は,列島各地の研究成果の集積とともに,より確からしいものへと段階的に改訂されてきました.長寿命の太平洋型造山帯として,列島には数億年間にわたる大陸縁のダイナミックな変動が記録されています.さらに,身近な郷土の地形,そして気候や生態系にも,その地体構造の不連続が影響を及ぼしています.本コースでは,日本列島の地体構造を考える上で基本となる構造線や基盤の不連続境界など,列島の大構造を復習します.また,すさまじい勢いで理解が進んできた東北アジアの地質学的新知見を総括し,その発達史と大構造について学習します.その他,一家に1枚「日本列島7億年ポスター」制作秘話も紹介します.
<午後> 大陸成長から見るたのしい太古代研究:沢田 輝(海洋研究開発機構)
https://researchmap.jp/hsawada
25億年以上前の太古代地質というと,活動的な造山帯の日本からは遠い海外の地質というイメージがあるかもしれません.一方,成長し続ける西之島のように,日本の地質環境と地球史初期との類似性が見出されてもいます.プレート沈み込みや島弧火成活動といった,日本列島では身近に感じる地球の活動.太古代地球はどのような形であったのか? 今の地球とどの程度異なっていたのか? いま論争となっている部分を中心に,わかっているようでわかっていない太古代地球について,主に大陸成長研究の側面から,その難しさとたのしさを紹介します.講演や学会発表とは一味違う濃厚な時間を提供できればと思います.
第2回 日程:2020年10月24日(土)
内容:(各コース、講義、質疑応答を含め3時間程度を予定)
<午前> 層序学の基礎と応用:高嶋礼詩(東北大学)
https://researchmap.jp/read0155080
本コースでは層序学の基礎編として,岩相層序,生層序,古地磁気層序,化学層序(酸素,炭素,ストロンチウム,オスミウム同位体比層序),サイクル層序,年代層序の概要を解説します.そしてこれらの層序学的手法を用いた国際標準年代尺度の作成,GSSPの認定,日本の地層での研究例を紹介します.応用編では,アパタイト微量元素組成を用いたオルドビス紀〜第四紀のテフラ層序の研究を紹介します.この手法を用いると,埋没続成,溶結,風化などによって火山ガラスが変質した凝灰岩についても高精度で対比可能になります.日本には変質した凝灰岩の露出が卓越する地域がよくみられることから,ジルコン年代と組み合わせることにより,日本の地層の対比精度向上への貢献が期待できます.
<午後> 統計解析言語Rを用いた地球科学データ解析基礎実習:上木賢太(海洋研究開発機構)
https://researchmap.jp/kentaueki
多変量解析や数理に基づくデータ解析は,地球科学においても年々その重要さを増しています.本講座では,実際の地球科学データを題材として,データ解析の実習を行います.講義として,多変量解析や線形回帰,モデル選択などの概念を解説するとともに,地球科学,特に岩石化学組成へ適用した研究の例を示します.さらに実習として,統計解析向けの言語及び実行環境フリーソフトウェアである「R」を用いて,基礎的な解析を各自のパソコン環境上で実際に行います.通常のパソコン環境が整っていれば問題なく実習を行うことが可能です.必要な事前準備(RおよびR studioのインストール)のための資料や,実習で使用するデータ等は事前に配布します.
参加費(各1日券):
会 員 2000円(賛助会員に所属する⽅は会員と同額)
⾮会員 4000円
(注)⾮会員の学部⽣・院⽣は「会員」料⾦に含まれます.「⾮会員」とは学部⽣・院⽣ではない⾮会員とします.
(注)午前のみ,午後のみの受講の場合も,参加費の割引はありません.
(注)キャンセル料について:締切日(9/7・10/12)まで 0%, 会期3日前(9/16・10/21)まで 60%, 会期2日前(9/17・10/22)以降 100% いずれの場合も返金がある場合は,振込手数料を差し引いた額をカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2〜3ヶ月要する場合もありますので,ご了承下さい.
定員:各コース100名(定員は事務局および講師を含み、定員を超えた場合は,会員が優先となります)
申込方法:専用申込画面(こちら)よりお申込みください 受付終了しました
その他:希望者には各コース毎のCPD受講証明書を発行します。
申込受付期間: 第1回分 8月5日〜9月7日(月) / 第2回分 9月24日(木)〜10月12日(月)受付終了しました
問い合わせ先:一般社団法人日本地質学会
メールmain [at] geosociety.jp 電話 03-5823-1150
2020名古屋代替:サイバーシンポ
コロナ禍での地質学教育に関するサイバーシンポジウム(日本地質学会主催)
● 第1回(20/09/27開催)
● 第2回(20/11/29開催)
第3回(00/00/00開催)
第2回コロナ禍での地質学教育に関するサイバーシンポジウム(日本地質学会主催)
2020.11.2更新
コロナ禍での地質学教育に関する情報交換・共有を目的とした第2回サイバーシンポジウムを開催します。
現在の困難な状況で,学校(大学,高等学校等)や研究所,博物館,ジオパークなどでは,教員や研究者,学芸員らがそれぞれのできる範囲で苦心して教育・普及活動を進めています。それぞれの実施事例やアイディアを共有できれば,今後しばらく続くと予想される困難な状況でも教育・普及活動の質の向上あるいは低下抑制が期待できます。大学や高校での授業(実験や野外実習を含む),卒業研究や修士研究,研究所や博物館での教育普及活動などをどのように工夫して進めているかについて情報交換・情報共有する場を提供します。地質学に限らず,野外活動(フィールドワーク)や実験・実習を伴う分野の皆様にも広く参加していただきたいと思います。
9月に実施した第1回サイバーシンポジウムでは100名を超える参加者(視聴者)があり,チャットでのコメントや質問も数多く寄せられ大変盛況でした。参加者は学会員だけでなく非会員の地質を専門としない方も多数おられました。参加者アンケートでは次回への期待の声が多数寄せられました。今回は海外で活躍する方にも話題提供していただき,国際的な情報交換・共有も目指します。
日本地質学会行事委員長 星 博幸
開催日時:2020年11月29日(日)9:30-12:15
開催方法:YouTubeライブ配信 どなたでも視聴可能.事前申込不要.参加費無料.
※シンポ終了後,シンポの各講演は一定期間YouTubeで公開しています
プログラム(一部仮題)
9:30 開会
9:35〜10:35 <大学の取り組み>
1. コロナ禍における学部生・大学院生の教育および研究:実験室での取り組み(北島弘子:テキサスA&M大学,College of Geosciences)
2. 香港大学の紹介とCovid-19影響下での研究教育活動(安原盛明:香港大学,School of Biological Sciences)
3. コロナ禍における九州大学地球惑星科学科の取り組み(尾上哲治:九州大学理学研究院)
4. オンデマンド実験実習科目の実施例:役に立った技術の紹介(金丸龍夫:日本大学文理学部)
10:45〜11:15 <高校の取り組み>
5. オンライン学習の利点・難点と地学教育普及のための活動実践例(福本奈由:大阪府立茨木高等学校)
6. コロナ禍の本校(愛知県立海翔高等学校)における地質学教育の現状と課題(大信田彦磨:愛知県立海翔高等学校)
11:20〜11:50 <研究所・博物館の取り組み>
7. 既存の地質コンテンツの有効活用:「地質の日」事業と「地質情報展」における地質調査総合センター(産総研)の取り組み(荒岡大輔:産業技術総合研究所地質調査総合センター)
8. かはくVRとは!?臨時休館中に公開したコンテンツについて 〜効果的な活用方法を考えながら〜(田中庸照:国立科学博物館)
11:50〜12:15 <ライブ総合討論>
12:15 閉会
各プレゼンテーションは15分です(発表12分+ライブ質疑応答3分)。
途中5〜10分程度の休憩をはさみます。
視聴者の皆様はYouTube上で質問・コメントを書き込み,ライブ総合討論ではそれらを活かしたディスカッションを考えています。
問い合わせ先:日本地質学会事務局( main@geosociety.jp )
第1回コロナ禍での地質学教育に関するサイバーシンポジウム(日本地質学会主催)
2020.8.20更新
コロナ禍での地質学教育に関する情報交換・共有を目的としたサイバーシンポジウムを開催します。現在の困難な状況で,学校(大学,高等学校等)や博物館・科学館,ジオパークなどでは,教員や学芸員らがそれぞれのできる範囲で苦心して教育・普及活動を進めています。それぞれの実施事例やアイディアを共有できれば,今後しばらく続くと予想される困難な状況でも教育・普及活動の質の向上あるいは低下抑制が期待できます。大学や高校での授業(実験や野外実習を含む),卒業研究や修士研究,博物館やジオパークでの教育普及活動などをどのように工夫して進めているかについて情報交換・情報共有する場を提供します。地質学に限らず,野外活動(フィールドワーク)や実験・実習を伴う分野の皆様にも広く参加していただきたいと思います。
日本地質学会行事委員長 星 博幸
開催日時:2020年9月27日(日)9:30-12:15:終了しました
開催方法:YouTube 公開中 (こちらからご視聴いただけます)
どなたでも視聴可能.事前申込不要.参加費無料.
※シンポの配信内容は一定期間YouTubeで公開中です
●プログラム●
9:30 開会
9:35〜10:35 <大学の取り組み>
1. 地球惑星環境学科(東京大学)の取り組み(後藤和久・東京大学大学院理学系研究科)
2. 地球科学系講義科目のオンライン化実践:オンデマンド配信用動画作成における気づきを中心として(乾 睦子・国士舘大学理工学部)
3. コロナ渦における地学系実験・実習の実施:茨城大学理学部における事例紹介(岡田 誠・茨城大学理学部)
4. 前期をほぼ無傷で終了した山口大学の例(坂口有人 山口大学)
10:45〜11:15 <中高の取り組み>
5. オンライン学習の軌跡:試行錯誤の現状と今後の課題(渡来めぐみ・茗溪学園中学校高等学校)
6. 高校における地学教員としての課題と(コロナ禍における)地質学教育の実践例(松永 豪・大阪府立泉北高等学校)
11:20〜11:50 <博物館・ジオパークの取り組み>
7. 学校休校と臨時休館をきっかけにうまれた「おうちミュージアム」とは(渋谷美月・北海道博物館・北海道大学大学院環境科学院環境起学専攻)
8. オンラインでの野外地質見学ツアーの試みについて(白井孝明・萩ジオパーク)
11:50〜12:15 <ライブ総合討論>
12:15 閉会
・各プレゼンテーションは15分です(発表12分+ライブ質疑応答3分)。
・途中5〜10分程度の休憩をはさみます。
・視聴者の皆様はYouTube上で質問・コメントを書き込み,ライブ総合討論ではそれらを活かしたディスカッションを考えています。
問い合わせ先:日本地質学会事務局( main@geosociety.jp )
備 考:11月下旬または12月上旬に第2回シンポジウムを開催予定です。詳細は日本地質学会ホームページに掲載します。
2020名古屋代替_WEB表彰式
2020年度名誉会員証授与・永年会員顕彰ならびに各賞受賞式・受賞記念講演会(WEB)
⽇時:2020年9⽉13⽇(⽇)14:00から1時間程度
開催方法:YouTubeライブ配信:終了しました
ライブ配信の内容は、限定公開中です-------->
プログラム(予定)
会長挨拶
新名誉会員紹介,新名誉会員挨拶(ビデオ):⻄村祐⼆郎会員/⼩松正幸会員
永年会員顕彰 顕彰者からのコメント紹介(司会代読予定)
日本地質学会表彰 受賞挨拶(ビデオ):浜島書店 常務取締役 村松哲二様/⿅野和彦会員
⽇本地質学会奨励賞 受賞挨拶(ビデオ):菊川照英会員/⽻地俊樹会員
(休憩)
⽇本地質学会論⽂賞 受賞スピーチ(ビデオ):星 博幸会員
⽇本地質学会Island Arc賞 受賞スピーチ(ビデオ):John Wakabayashi ⽒
⽇本地質学会賞受賞講演(ビデオ講演約30分):⼭路 敦会員
閉会あいさつ
>名誉会推薦理由はこちら
>各賞受賞者推薦理由はこちら
永年会員顕彰者 1970年入会(計33名)
石井輝秋
上野将司
大原一男
小笠原憲四郎
加藤碵一
兼岡一郎
佐藤興平
白木敬一
田沢純一
藤岡換太郎
細谷正夫
本間岳史
松川正樹
宮下純夫
森 慎一
山口佳昭
横山俊治
滝沢 茂
(以下お写真の掲載省略)
相原延光,縣 孝之,礒田喜義,奥野 満,神田 哲,沢田順弘,
滝沢洋雄,長沢元之,布目眞澄,原田知子,藤井敏嗣,藤山 敦,
松田丞司,屋鋪増弘,和田秀樹 (敬称略) 以上33名
---------------------------------------------------------------------------------
(お寄せいただいたコメントをご紹介します)
コロナ禍にあって,私は地学教育の社会貢献の大きさを痛感し実践しています。「禍」の「示」は神(自然)が下す,「咼」は「災い」。「転禍為福」(てんかいふく)です。これを機に人生の飛躍を目指したいものです。(相原延光)
入会後早50年、驚くとともに会への貢献度や参加率が気になります。今年の50年会員の方々の中には、ご無沙汰の方が多数おいでになり、お会い出来るのを楽しみにして居りましたが、その機会を奪われ残念です。来年お会いしましょう。 (石井輝秋)
企業の地質技術者として軸足を他学会において活動してきましたので、日本地質学会では学術大会の応用地質一般の世話人や行事委員としての経歴程度のため、この度の顕彰を恐縮しつつも嬉しく思います。(上野将司)
永年会員顕彰のお知らせをいただき、もう50年になろうとすることに驚いています。 最近の研究成果については、各領域の125周年特集で拝見させていただき、研究の進歩に 目を見張っております。ますますのご発展を祈念いたしております。(大原一男)
学会とは主として年代学を通してのお付き合いで、50年も経ったことに驚いております。入会当時に比して、放射年代が地質学の研究者に広く根付いていることを喜ぶとともに、その年代値の的確な扱いを願っています。(兼岡一郎)
断層運動や摩擦すべり・磨砕実験で結晶が細粒化(ナノサイズ)すると非晶質化し物性特性(融点、磁性、密度など)が変わる。このようなナノ粒子の生成と反応は断層運動に如何なる影響をあたえるか。(滝沢 茂)
約50年間,おもに南部北上山地の古生層と腕足類化石を研究できたこと,また,地向斜造山論からプレートテクトニクスへの移行期に日本地質学会の会員であったことは幸せでした.学会のご発展を祈ります.(田沢純一)
長年ボンヤリと過ごしてきた小生へ、顕彰をとの突然の申し出で戸惑っています。これを機に少しは自己改革をと思います。なお、所属の日本化学会では70歳以上は会費免除につき、本会でも同様の措置をと願います。(長沢元之)
ただ年数を重ねただけの私でも、顕彰いただけることを恐縮すると共に、大変感謝しております。定年後も公立高校で非常勤講師を続けています。6年前より勤務校のカリキュラムから地学分野が除外されたことが残念です。(布目眞澄)
私は大学4年の折に入会しそれからもう50年になりますか。学会誌にはほとんど論文を書いたことはありませんが、巡検には毎年参加し、日本全土の地質旅行を終えています。体が許す限り参加したいと思っています。(藤岡換太郎)
顕彰の栄誉に浴し心よりお礼申し上げます。50年の在籍期間中でも、昨今の強大化した自然災害に対し地質学の知識、フィールドワークの重要性が増しています。役に立つ地質学の普及に学会の更なる発展を願っております。(藤山 敦)
会員としての50年,年会と巡検はできる限り参加してきました.特に巡検の 知見は,県立高校の教員として授業や教員仲間との調査研究に生かすことがで きました.定年後の県自然博物館の勤務でも資料の活用ができました.(細谷正夫)
永年顕彰いただけること、誠にありがとうございます。大学学部時に入会して50年。博物館活動を通して、地域研究、地学への普及活動を継続してきました。今後も少しでも、学会に寄与できればと思っております。(森 慎一)
あまりお役になれずに年月が過ぎましたが、元気でおります。今の新型コロナ禍を無事に過ごして、この後の年会でご迷惑にならないように、皆様にお会いしたく存じます。どうかご自愛の上ご活躍ください。(山口佳昭)
50年前,「野外地質学のテーマが無くなった時が,辞める時」と覚悟して,地質学を仕事にしてきたが,野外地質学徒の減少と反比例して,生活世界ではその役割は益々大きく,研究テーマも尽きない.学会には現場の分かる人材の育成を期待する.(横山俊治)
地質図など目にみえる研究成果により多くの人が恩恵を受けました。汗と筋肉痛の大勢の努力の成果は重なり重層で厚味のある地図として手にとることができます。多くの目で見ることは基本的に重要な一歩となります。歩く、見る、触れる、考える、(和田秀樹)
若手研究者のページ_TOP
若手研究者のページ
学部学生,院生等若手研究者の活動や関連する情報をご紹介します.
お知らせ・活動
若手巡検 in 長瀞・皆野地域(10/18開催)NEW
学生会員に対する巡検参加費の補助について
学術大会におけるダイバーシティ認定ロゴ導入ほか若手会員向けの取り組み (2025年熊本大会)
若手活動運営委員会発足(2023.4月)[設立趣意・委員会規則][委員会メンバーはこちら]
若手野外地質研究者向け研究奨励金制度
「地質系若者のためのキャリアビジョン誌」発行
地質系の学部生・院生が、将来の進路のひとつである地質コンサルタントなどの専門技術分野の業態を理解してもらうための冊子を刊行しています。
▶︎冊子(PDF)ダウロードはこちらから
[終了したお知らせ]
[終了]地質系業界オンライン交流会 (2025/2/14開催)
[終了]若手巡検 in愛知県-岐阜県 (2024/10/16開催)
[終了]地質系業界オンライン交流会 (2024/2/16開催)
[終了](2023京都大会)夜間小集会:学生・若手のための交流会 開催 (2023/9/18)
[終了](2023京都大会)若手会員向けルームシェア型宿泊プラン
[終了]若手巡検・研究集会 in 北海道洞爺湖有珠山ジオパーク地域(2023/7/8-9実施)
[終了]地質系業界オンライン交流会 (2023/2/17開催)
若手研究者の活動をご紹介します
ニュース誌「院生コーナー」では常時投稿をお待ちしています..
原稿は1500〜5000文字程度,図・写真3点以内を目安に,e-mailでお送りください.
タイトルをクリックするとそれぞれの報告記事(PDF)をご覧いただけます
北海道大学理学院自然史科学専攻地球惑星システム科学講座 ジオテクトニクス研究グループ亀田研究室紹介
畑 良太(北海道大学・理学院・修士課程2年)
News2021年8月号掲載
砕氷艦「しらせ」での海氷観測
高橋啓伍(総合研究大学院大学 5年)
News2021年7月号掲載
私のインターンシップは学術研究船「白鳳丸」〜KH-21-3航海で経験したこと〜
松尾晃嗣郎(九州大学大学院理学府地球惑星科学専攻)
News2021年6月号掲載
研究室紹介 早稲田大学 堆積学研究室
中野有紗(日本地質学会会員:早稲田大学創造理工学研究科 地球・環境資源理工学専攻博士課程1年)
News2021年5月号掲載
研究室紹介 愛媛大学理学部理学科地球科学コース:地質・古生物系研究室
吉永亘希(九州大学・理学府・修士課程1年)
News2021年4月号掲載
白鳳丸による南極海調査航海(KH-19-6 Leg4)乗船報告
山本一平(日本地質学会会員:東京大学地球惑星科学専攻 修士課程1年)
News2021年3月号掲載
International Conference on Ophiolites and the Oceanic Lithosphere 参加報告
長荑薫平(日本地質学会会員:広島大学大学院先進理工系科学研究科修士課程1年)
News2020年5月号掲載
第9回ハットンシンポジウム:花崗岩の花崗岩による花崗岩のための国際花崗岩会議
下岡和也(日本地質学会会員:愛媛大学理工学研究科地球進化学コース修士課程1年)
News2020年4月号掲載
※今後記事アーカイブを進めていく予定です.
2020名古屋代替_JABEEオンラインシンポ
2020名古屋代替_JABEEオンラインシンポ
20.10.6掲載 21.4.2更新
←3月7日(日)YouTubeのライブ配信を行いました.現在も公開中です.
当日のシンポジウムでは、多くのご質問やご意見をいただき、ありがとうございました。
当日お答えできなかったご質問は、こちらに掲載しています。
参加者アンケート結果(PDF)はこちらから
JABEEオンラインシンポジウム
自然災害列島における地質技術者の育成
−大学統合期における地質学教育ー
近年,日本列島各地では豪雨や台風による災害が頻発している.加えて地震や火山による災害も多発している.同時に今年は,新型コロナウィルス(COVID-19)禍のため,防災・減災のための調査,対策などの行動に制限が加わり,さらに専門教育や普及活動にも弊害が生じている.
これらの自然災害は,日本列島の地質や地形に密接な関係をもって発生している.このような日本列島に住む我々が防災・減災により安全で安心した生活をおくるためには,足下の自然の特徴を科学的に把握して,対策をたてることが重要である.同時に,それに携わる人材の輩出,育成が社会から求められている.
大学における地質学の専門教育に加え,卒業後の地質技術者としての養成教育は,この社会の要請に応えるものであり,今後,一層精力的に行われなければならない.一方,大学では国立大学の統合や大学教員の削減など,充実した専門教育の展開が困難になっている.
日本地質学会では本テーマを議論するため名古屋大会でのシンポジウムを企画したが,新型コロナウィルス禍のために同大会が順延となった.代替企画としてオンラインシンポジウムを開催し,大学における技術者育成プログラム(JABEE:日本技術者教育認定機構)を通じて,大学での地質学教育のあり方と今後,地質技術者の養成の現状と将来,企業での地質技術者の継続教育(CPD)について考えていきたい.
2020年10月
地質技術者教育委員会
委員長 天野一男
日時:2021年3月7日(日)14:00〜17:15(予定)
配信方法:ZoomにYou Tubeを連動させるオンライン方式
参加費無料.Zoom参加者は事前登録制(Youtube視聴の場合は申込不要)
【zoomでの参加申込はこちらから】締切ました
(注)CPD単位の発行をご希望の場合は,zoomでの参加をお申込みください。(CPD:1時間1単位)
▶︎シンポの内容は,YouTubeで公開中
プログラム【敬称略】※タイトルをクリックすると講演概要(PDF)がDLできます
開会挨拶
趣旨説明 理事・地質技術者教育委員会委員長 天野一男(東京大学空間情報科学研究センター客員研究員)
「JABEEの近況」三田清文(一般社団法人日本技術者教育認定機構専務理事)
「地質学教育をディフェンスするJABEE」理事・広報委員長 坂口有人(山口大学理学部教授)
「私立大学におけるJABEE教育 」地質技術者教育委員会委員 竹内真司(日本大学文理学部教授)
「地質調査業とJABEE制度」 中川 渉(応用地質株式会社取締役経営企画本部長)
「JABEE 修了生におけるJABEE のメリット」 井田貴史(応用地質株式会社エネルギー事業部専任職)
「島根大学地球科学科のJABEEコースで体験したメリット 〜学生の立場から〜」 仲山 暢(島根大学大学院自然科学研究科修士課程)
「地質学会のJABEEとCPDに対する取り組み」理事・副会長・地質技術者教育委員会副委員長 佐々木和彦(応用地質(株))
「総合討論:大学の生き残りをかけた教育の質の保証と社会への貢献(仮)」
閉会挨拶
お問い合わせ:日本地質学会事務局 main[at]geosociety.jp([at]は@マークにして送信してください)
当日お答えできなかった質問など
①Zoomチャットでの質問(1)
質問:JABEEにおけるデザイン能力とは、具体的にはどういうものでしょうか?
回答:JABEEは学習・教育到達目標を定める際に必要な9項目の知識・能力観点のなかで、(e)として「種々の科学、技術及び情報を活用して社会の要求を解決するためのデザイン能力」が規定されています。ここでの「デザイン」とは「エンジニアリング・デザイン」を示し、単なる設計図面作成ではなく、「必ずしも解が一つでない課題に対して、種々の学問・技術を利用して、実現可能な解を見つけ出していくこと」であり、そのために必要な能力が「デザイン能力」であると説明しています。 具体的には、以下の内容を参考にするなどして、学習・教育到達目標を設定する必要があると解説されています。
解決すべき問題を認識する能力
公共の福祉、環境保全、経済性等の考慮すべき制約条件を特定する能力
解決すべき課題を論理的に特定、整理、分析する能力
課題の解決に必要な、数学、自然科学、該当する分野の科学技術に関する系統的知識を適用し、種々の制約条件を考慮して解決に向けた具体的な方針を立案する能力
立案した方針に従って、実際に問題を解決する能力
②Zoomチャットでの質問(2)
質問:島根大学の地球科学科は入試倍率が国内トップクラスと言えるくらい高いと認識しています。受験生はJABEEを意識して志願されておられるのでしょうか?
回答:JABEEを意識して志願する学生は、講師である自分自身を含め少ないと感じています
質問:もしも高校生の時にJABEEの存在と、その意義を理解していたら、志願先としての大学選びに影響しましたでしょうか?
回答:もしも高校生の時にJABEEの存在を知っていたら、その学科がある大学を必ず志望していたと思います。その中でも島根大学は特色が豊かで、有意義な時間をおくれると考えたと思います。
回答:島根大学の新入生は50名で、うち高校での地学履修者は5名未満ですが、アンケートによれば地学に興味があった学生は50%を占めます。学生は大学のなかで次第に地質技術者へ興味を持って行く印象です.
意見:高校にJABEEの存在と意義をより一層宣伝したいと思います。
回答:高校生、大学生向けのパンフレットをJABEEでは準備しております。ご活用ください。
③Zoomチャットでの質問(3)
質問:島根大学では学科全員がJABEE履修でしょうか?それともコース制でしょうか?
回答:島根大学では50名が一括JABEE認定です.※解説:地球・資源及び関連するエンジニアリング分野では、現在9大学でプログラムが認定されており、そのうち島根大学と千葉大学の2つが学科全体でJABEE認定されています。
④Zoomチャットでの質問(4)
質問:島根大学では、JABEE制度運営において学部間の協力はどうですか?
回答:島根大学には現在,2学部に6コースのJABEEプログラムが認定されています.それらのプログラム間では,年に一度の連絡者会議により,情報共有や連絡調整を行っています。
⑤Youtube チャットでの質問(1)
質問:「日本地質学会のJABEEとCPDに対する取り組み」で、「修得技術者」と説明したのは「修習技術者」ではないですか?
回答:ご指摘ありがとうございました。そのとおりです。上記スライドの11枚目と12枚目の「修得技術者」は「修習技術者」の誤りです。
⑥Youtube チャットでの質問(2)
意見:社会以前に,地質学の専門教育に携わる大学教員や教育を受ける学生がJABEEについてよく知らない,または関心がないという状況をなんとかする必要があると思います。地質学会として,例えばショートコースで地質技術者の仕事の紹介や地質調査業の紹介,最新の調査技術の紹介などをするのは意義があるのではないかと思っています。
意見:こうした活動を継続的に行い、世間に広くアピールすべきです。
2021年学術大会:トピック募集
2021.2.1掲載
***2021年学術大会***
トピックセッション募集 締切:2021年3月10日(水)
128年学術大会を本年9月に開催予定です.開催形態など まだ未定な部分もありますが,トピックセッションを下記 の要領で募集します.今回も例年同様シンポジウムの一般 募集はありません.シンポジウムは大会実行委員会及び学 会執行部が企画する予定です. なお,昨年の名古屋大会で開催ができなかった下記7セッ ションについては,本年あらためて開催の予定です.
広域観測・微視的実験連携による沈み込み帯地震研究の 新展開(世話人代表:木下正高)
海底地盤変動学のススメ(世話人代表:川村喜一郎)
スロー地震に関する地質学的・実験的・地震学的研究の 連携と進展(世話人代表:氏家恒太郎)
二次改変された過去の弧-海溝系の復元:日本およびその 他の例(世話人代表:磯㟢行雄)
文化地質学(世話人代表:大友幸子)
災害多発時代における学術資料・標本散逸問題―大学・ 博物館は何をすべきか−(世話人代表:堀 利栄)
地球年代学が拓く高精度火山噴火史・発達史(世話人代 表:上澤真平)
1.セッション概要
セッションは例年通り「レギュラーセッション」,「トピ ックセッション」,「アウトリーチセッション」に区分しま す.レギュラーセッションはこれまでと同じ25タイトルを 予定しています(レギュラーセッションは行事委員会が決 定します).
2.トピックセッション募集
トピックセッションは,広く地質学の領域に属し,これ から新分野あるいは注目すべき分野になりそうな内容を扱 うものとします.形式はレギュラーセッションと同じです (口頭発表およびポスター発表:口頭発表は15分間で,進行 も15分刻み).多くの参加者が見込まれる,魅力あるセッシ ョンを積極的にご提案ください.締切後,行事委員会が応 募内容を慎重に検討し,採択する予定です.
3.トピックセッション招待講演
トピックセッションの招待講演には例年と同じルールを適用します.
1) 招待講演は1セッションにつき最大2名とし,会員,非会員を問いません.世話人が「自分を招待する」ことは認めません.
2) 発表時間(質疑応答を含む)は世話人が15分または30分のいずれかを選択できます.なお,1人の発表者(招待講演者を含む)が1つのセッションで口頭発表できるのは1件です.
3) 招待講演者の選定理由とその裏付けとなる情報(セッションテーマに関連した代表的な論文,著書等)が必要です.
4) 会員招待講演者が招待講演の他に非招待の発表を1件申し込む場合,発表負担金はかかりません.さらにもう1件(招待講演の他にセッションで2件)発表する場合は負担金がかかります.
4.応募方法
トピックセッションを応募する会員は,次の項目内容を日本地質学会行事委員会宛(main@geosociety.jp)にe-mailでお申し込み下さい.
1) 代表世話人(=連絡責任者,会員に限る)の氏名(和・英),所属(和・英),メールアドレス,緊急時の電話番号
2) セッションタイトル(和・英)
3) 共同世話人の氏名(和・英),所属(和・英),メールアドレス
4) 趣旨・概要(400〜600字)
5) 招待講演の有無
有の場合
5-1)招待講演者の氏名(和・英),所属(和・英),会員/非会員の別
5-2)招待講演の発表希望時間(15分または30分)
5-3)招待講演者の選定理由(100〜200字)
5-4)選定理由の裏付けとなる,セッションテーマに関連した代表的な論文・著書等
6) 他学協会との共催希望の有無,有の場合は名称
7) 時間(原則半日(3時間)以内ですが,詳細はお問い合わせください)
8)地質学雑誌またはIsland Arcへの特集号計画の有無(で きる限り特集号として出版して下さい)
9) その他(英語使用等)
5.採択方法
応募多数の場合や他セッションと内容が重複する場合, 行事委員会は学術的なインパクトや緊急度を考慮して採択 を決定します.採択されたトピックセッションはニュース 誌4月or5月号(4月or5月末発行予定)で公表し,講演募集 を行う予定です.演題登録(講演申込,講演要旨投稿)締 切は7月初旬を予定しています.
6.非会員招待講演者の参加登録費
非会員招待講演者に限り参加登録費を免除します(ただし要旨集は付きません).
7.世話人が行う作業(7月初旬〜中旬)
代表世話人には,講演要旨校閲,講演順番決定などの作業を7月中旬までに行っていただきます(詳細は採択後にお知らせします).その期間,代表世話人は電子メールで添付ファイルを送受信できるようにして下さい.野外調査や乗船等で通信が制限される場合は,共同世話人(代理)にあらかじめ作業を依頼し,その旨を行事委員会に必ず報告してください.
ご不明の点があれば行事委員会(main@geosociety.jp)までお気軽にお問い合わせください.
第3回ショートコース_2021.5.23
日本地質学会第3回ショートコース
日本地質学会は,コロナ禍で延期になった学術大会(名古屋大会)の代替企画の一つとして,昨年(2020)秋にオンラインによる「日本地質学会ショートコース」を2回開催しました。いずれも大変好評で,ショートコースの継続的な実施を望む声も多く寄せられました。それを受けて学会内で検討し,「大学で学部生や大学院生に十分教えられていない内容を学会がカヴァーする」,「地質技術者や学校教員,学芸員等が現在の地質学の知見や研究方法等について学ぶ機会を学会が提供する」というショートコースの目的を果たすには継続的な実施が必要と判断し,年4回程度のペースで継続的に実施する方針が確認されました。皆様にはこのショートコースをぜひ積極的に受講いただき,地質学の基礎的・応用的知識を習得していただくとともに,先端研究・技術の一端に触れていただきたいと思います。
2021年3月
日本地質学会行事委員長 星 博幸
第3回 日程:2021年5月23日(日)
今回は「津波堆積物」をキーワードに,その調査によって津波とそれを引き起こした地震の実像を探るための知識と研究事例を提供します。講師はこの分野をリードするお二人の研究者です(午前1名,午後1名)。
内容:(各コース、講義、質疑応答を含め3時間程度を予定)
<午前> 9:00-12:00
津波堆積物を理解するのに必要な基礎的堆積学:藤野滋弘(筑波大学)
津波堆積物は過去にその地域で発生した津波の物証であり,将来の津波災害を軽減するための基礎情報として重要です.しかしながら地球表層では津波以外の現象でできた堆積物の方が圧倒的に多く,津波堆積物を識別するには様々な地層の特徴を知っている必要があります.また,津波が浸水した場所であっても必ず津波堆積物ができて地層中に保存されるわけではなく,津波堆積物を探す場合には適切な調査地を選定することも重要です.そこで本講義では学部学生や大学院生などを主な受講者として想定し,津波堆積物を識別して理解するために必要な堆積学の基礎を解説します.
https://researchmap.jp/sfujino
<午後> 15:00-18:00
津波堆積物を理解するのに必要な応用的堆積学:後藤和久(東京大学)
津波堆積物研究では,様々な要因で形成される地層中のイベント堆積物から,津波堆積物を適切に認定することが最も重要な作業です.津波堆積物を認定できれば,次に津波の発生時期や規模の推定などの応用的研究を行うことができるようになり,津波リスク評価につながります.本講義では,学部生や大学院生など津波堆積物研究を行ったことのない方を主対象として,地層中からイベント堆積物が見つかった後,どのようなプロセスで津波堆積物研究を行うのかを概説します.そして,津波堆積物研究に残る課題を理解し,独立して津波堆積物研究を行うために必要な基礎知識を習得することを目指します.
https://researchmap.jp/7000003536
参加費(各1日券):
会 員 2000円(賛助会員に所属する⽅は会員と同額)
⾮会員 4000円
(注)⾮会員の学部⽣・院⽣は「会員」料⾦に含まれます.「⾮会員」とは学部⽣・院⽣ではない⾮会員とします.
(注)午前のみ,午後のみの受講の場合も,参加費の割引はありません.
(注)キャンセル料について:締切日(5/12)まで 0%, 会期3日前(5/20)まで 60%, 会期2日前(5/21)以降 100% いずれの場合も返金がある場合は,振込手数料を差し引いた額をカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2〜3ヶ月要する場合もありますので,ご了承下さい.
開催方法:WEB会議システムzoom(https://zoom.us/)によるオンライン講義
定員:各コース100名(定員は事務局および講師を含み、定員を超えた場合は,会員が優先となります)
申込方法:申込受付は締め切りました(5/12)
その他:希望者には各コース毎のCPD受講証明書を発行します.午前午後各3単位を予定
.(CPDプログラムID:2879)
申込締切:2021年5月12日(水)
問い合わせ先:一般社団法人日本地質学会
メールmain [at] geosociety.jp 電話 03-5823-1150
(参考)過去のショートコース(第1回,第2回)
http://www.geosociety.jp/science/content0121.html
2021名古屋プレ_TOP
2021名古屋大会プレページ_top
大会WEBサイトはこちらから
日本地質学会第128年学術大会 名古屋大会
会期:2021年9月4日(土)〜7日(火)
会場:名古屋大学東山キャンパス(愛知県・名古屋市千種区)
+ オンライン開催
[関連行事]地質情報展2021あいち
日程:10月8日(金)〜10日(日) 場所:名古屋市科学館
更新情報
21/05/17 大会ウェブサイト(本サイト)オープンしました
21/04/20 学術大会「誌面ブース」のご案内
21/04/20 おもな日程・締切スケジュール
21/04/20 名古屋大会プレページ開設しました
「誌面ブース」のご案内
学術大会「誌面ブース」のご案内
学術大会「誌面ブース」のご案内
画像をクリックするとPDFファイルがDLできます
第128年学術大会(2021名古屋大会)は、新型コロナウィルス感染防止のためにオンラインをベースに開催する こととなりました。そのため例年好評であった展示ブースの代替として誌面ブースを実施いたします。
日本地質学会が「2021名古屋大会プログラム&誌面ブース」という冊子を発行し、これを全ての大会参加者に郵送いたします。これはプログラムと一体となっておりますので、各ブースは確実に読者の目に触れることでしょう。例年なら、約1,000名弱の研究者、地質技術者、学芸員、ジオパーク専門員、教員など国内の地質関係者が幅広く参加しております。本冊子はこれら関係者を網羅する新しい媒体となるでしょう。
ぜひとも誌面ブースへのご出展を検討して頂けますよう,お願いいたします。
配布対象者:
学術大会参加申込み者:大学および研究機関の地質研究者、地質技術者、自然博物館等の学芸員、ジオパークの地質専門員、理科教員、一般など1,000名弱(例年の対面式と同数参加の場合)。
掲載料:
1ページ: 35,000円/見開き2ページ: 60,000円
(冊子発送後に見本誌と共に請求書を送付いたします)
冊子:A4サイズ、フルカラー印刷体、参加者の自宅もしくは勤務先へ郵送
スケジュール:
申し込み締切:6月30日(水)
原稿締切:7月30日(金)
発送:8月下旬
学術大会:9月4日(土)から7日(火)
原稿:PDF形式(20MB以内)、A4サイズ1ページもしくは見開き2ページ.指定のウェブサイトから送付してください
申し込み方法:下記URLから申し込んでください。
http://photo.geosociety.jp/booth.html
主な日程
主な日程
日 程
行 事
5/20頃
演題登録受付開始(予定)
6/30(水)
演題登録締切
8/19(木)
大会参加登録締切
9/4(土)
セッション1日目(RT),ジュニアセッション
9/5(日)
午前: LOC主催シンポウム(現地+RT配信),
午後: 市民講演会(現地+RT配信),表彰式(RT配信),受賞講演(RT or OD配信),懇親会(RT)
9/6(月)
セッション2日目(RT)
9/7(火)
セッション3日目(RT)※
10/8(金)
〜10(日)
地質情報展(現地 or オンライン開催)
(OD=オンデマンド;RT=リアルタイム;現地=現地開催)
※ 口頭発表申込数が少ない場合は7日を取りやめ,会期を短縮する可能性があります.
第4回ショートコース
日本地質学会第4回ショートコース
申込締切
2021年7月5日(月)
2021年7月15日(木)
申込方法
追加募集も申込受付は終了しました
第4回 日程:2021年7月18日(日)
今回は地質学のあり方や論文を書くことの本質について考える機会を提供します.多くの学生・若手研究者の皆様に受講していただきたいコースです.中堅・ベテラン研究者や学校教員,地質調査業従事者,広く一般の方も,地質学の調査・研究や教育あるいは科学について見つめ直すよい機会になるに違いありません.講師は,午前が日本の地質学をリードしてきた研究者の一人である磯粼行雄・本会会長,午後が『プレートテクトニクスの拒絶と受容:戦後日本の地球科学史』などの地球科学史研究で知られる泊 次郎氏です.
内容:(各コース,講義・質疑応答含め2時間程度,延長の場合は最長3時間)
<午前> 10:00-12:00
「吾書くゆえに吾あり:論文執筆についての超個人的視点」磯粼行雄(東京大学)
現代の科学者にとって論文公表は, 研究を継続する上で不可避である.しかし, そもそも論文を書くことの本質が何であるのかを自ら問う機会は意外に少ない.最近では公表論文数や被引用回数,あるいはインパクトファクターなどの数値指標神話がはびこるが,演者自身はそれとは異なる評価基準を探ってきた.ここでは極めて個人的な視点を紹介し,特に若い世代の研究者達が論文執筆の意味を再考する一助としたい. https://researchmap.jp/read0183762
<午後> 13:30-15:30
「地球科学の歴史から何を学ぶか」泊 次郎(科学史研究家)
私は地球科学の歴史を調べてきました.日本の地質学界では1980年代半ばまでプレートテクトニクスが受け入れられなかったのはなぜなのか,日本では地震の予知を目指して140年以上も研究が続けられてきたのに,大きな進展がないのはなぜなのか,大気中の二酸化炭素濃度が増えれば,地球が温暖化するという説は120年以上も前から唱えられてきたのに,それへの懐疑論がなくならないのはどういうわけなのか,などです.こうした疑問に答えるには,科学の論理だけでは不十分です.科学と社会との関係性を考慮することによって初めて説明できる,というのが得られた結論です.講演では,これらの疑問に対する私なりの解答を紹介するとともに,地球科学や地球科学者のあり方について,私見を述べる予定です.
(参考)*学会News誌、HPに掲載された書評
http://www.geosociety.jp/faq/content0107.html
「プレートテクトニクスの拒絶と受容 戦後日本の地球科学史」
泊 次郎 著.東京大学出版会 A5, 258ページ,ISBN978-4-13-060307-2 \3,800+税(2008年6月2日発行)
参加費(各1日券):
会 員 2,000円(賛助会員に所属する⽅は会員と同額です)
⾮会員 5,000円
(注)⾮会員の学部⽣・院⽣は「会員」料⾦に含まれます.「⾮会員」とは学部⽣・院⽣ではない⾮会員とします.
(注)午前のみ,午後のみの受講の場合も,参加費の割引はありません.
(注)キャンセル料について:締切日まで 0%, 会期3日前まで 60%, 会期2日前以降 100% いずれの場合も返金がある場合は,振込手数料を差し引いた額をカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2〜3ヶ月要する場合もありますので,ご了承下さい.
開催方法:WEB会議システムzoom(https://zoom.us/)によるオンライン講義
定員:各コース100名(定員は事務局および講師を含み、定員を超えた場合は,会員が優先となります)
申込方法:申込受付は終了しました
(注)申込にご提供いただいた個人情報は、日本地質学会プライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います.
その他:希望者には各コース毎のCPD受講証明書を発行します.午前午後各3単位を予定.(CPDプログラムID:2917)
申込締切:2021年7月5日(月)2021年7月15日(木)追加募集いたします!!
問い合わせ先:一般社団法人日本地質学会
メールmain [at] geosociety.jp 電話 03-5823-1150
(参考)過去のショートコース
(第1回,第2回)http://www.geosociety.jp/science/content0121.html
(第3回)http://www.geosociety.jp/science/content0130.html
招待講演者
日本地質学会第128年学術大会:セッション招待講演者の紹介
▶▶▶名古屋大会ウェブサイトへ戻る
世話人や専門部会から提案され,行事委員会が承認したセッション招待講演者を紹介します.なお,講演時間は変更になる場合があります.
トピックセッション
T1.地震研究の新展開
T2.海底地盤変動学ススメ
T3.スロー地震
T4.弧-海溝系の復元
T5.文化地質学
T6.学術資料・標本散逸問題
T7.火山噴火史・発達史
レギュラーセッション
R1.深成岩・火山岩
R2.岩鉱一般
R3.噴火・火山発達史
R4.変成岩とテクトニクス
R5.地域地質・地域層序
R6.ジオパーク
R7.新生代の地質事変記録
R8.海洋地質
R9.堆積
R10.炭酸塩岩の起源...
R11.石油・石炭地質学
R12.岩鉱の変形と反応
R13.沈み込み帯・付加体
R14.テクトニクス
R15.古生物
R16.ジュラ系+
R17.情報地質
R18.環境地質
R19.応用地質
R20.地学教育・地学史
R21.第四紀
R22.地球史
R23.原子力と地球科学
R24.鉱物資源
*タイトル(和英),世話人氏名・所属,概要を示します.*印は代表世話人(連絡責任者)です.
T2.海底地盤変動学のススメ
馬場俊孝(徳島大:非会員)30分 馬場氏は,長年にわたって,津波モデリングの研究に携わってきた.特に,海底地すべりに関する津波の研究は, 有名で,駿河湾での地震による海底地すべりに起因する津 波の研究や,南海トラフでの研究など,多数の業績を残している.このように,海底地すべりに関して議論をすると きに,津波モデリングの観点からの知見を講演を通じて, インプットするには最もふさわしい人物である.
松山昌史(電中研:非会員)15分 松山氏は,原子力リスク研究センターにおいて,津波工学,海岸工学の観点から,海底地すべりによる津波リスク について評価する事業に携わってきた.その中で,地盤工 学的なアプローチや実験的な手法を取りまとめる役割を中 心的に担い,沿岸における海底地すべり災害について工学 的立場で,総合的に理解することを強く進めてきた.この ような地質学には基づかない,海底地すべり研究は,海底 地すべりを多角的視点で考察する上では欠かせない存在である.
T3.スロー地震に関する地質学的・実験的・地震学的研究の連携と進展
小原一成(東京大地震研:非会員),30分 小原氏は,世界を代表するスロー地震研究者である.南海トラフを中心に地震・測地観測で得られたスロー地震像 を紹介して頂くことで,暖かい沈み込み帯におけるスロー 地震の発生過程と発生環境を地質学的に理解していくうえでの,示唆に富んだ重要な提案と議論がなされることが期 待出来る.
西川友章(京都大・防災研:非会員),30分 西川氏は,地震学を専門とする新進気鋭の若手研究者である.海底地震観測網と陸域地震・測地観測網に基づいて明らかにした日本海溝におけるスロー地震の全貌をまとめた論文を昨年Science誌に公表した.西川氏の招待講演はタイムリーであり,今後日本海溝のような冷たい沈み込み帯におけるスロー地震の発生過程と発生環境を地質学的に理解していくうえでの,示唆に富んだ重要な提案と議論がなされることが期待出来る.
ページtopに戻る
T4.二次改変された過去の弧-海溝系の復元:日本およびその他の例
沢田 輝(JAMSTEC:会員),30分 沢田会員は大学院での研究テーマ以来,地球史を通した大陸地殻の成長パタンの解明を目指し,特に先カンブリア 時代の多様な年代の砂岩中の砕屑性ジルコン年代の測定を行った.また並行して世界中の公表されたデータのコンパイルを行い,従来とは大きく異なる大陸地殻成長曲線を提案した.日本における堆積岩研究では従来にない大きな時空間を対象にした研究を進めている同会員に最新の成果と研究展望を紹介していただきたい.
山本啓司(鹿児島大:会員),30分 山本会員は,岩石の変形と変成作用について,野外調査,微細構造解析,化学分析などを駆使して研究してこられた.主な成果として,パキスタン北部のコーヒスタン古島弧地域に露出するグラニュライトの産状と,Sm–Nd同位体年代から同岩体の島弧・大陸衝突と連動した形成過程の解明,さらにカザフスタン北部,中国中央東部,およびパキスタン北部の超高圧変成帯に異なる変成深度の薄板状の岩体の累重ナップ構造の確認とその形成過程の解明などがある.また日本では,中央構造線(MTL)近傍,領家帯のマイロナイトの低角度構造の解明から,マイロナイトが領家帯の深部構造に由来することを提唱された.また近年では,琉球弧徳之島に産する変成岩類のジルコンU–Pb–Hf同位体比測定から,それらの起源を南中国地塊東南部カタイシアと推定されている.野外調査に基づく最新の成果をご紹介いただく.
※(セッション世話人と行事委員会より)当初予定していた今岡照喜さん(山口大:会員)の招待講演は,ご本人の都合によりキャンセルとなりましたため,山本啓司さんに変更いたしました.
T5.文化地質学
三澤裕之(秀明大学:非会員),30分 三澤氏(山形考古学会会員)は,山形県の社会科高校教員として教育に携わりながら山形県内の遺跡の研究を行っている.山形県立西高等学校校長退職後に山形県学事文書課に勤務しながら,これまで収集した考古資試料の整理を行っている.三澤氏は40数年前に山形県最上町の材木遺跡発掘に参加し,当時発掘後の遺跡地表面(畑)で数10個の緑色の石を採集した.それらの一部には玉に加工途中の遺物があり,近年この緑色の石がヒスイかどうかを明らかにすべく,フォッサマグナミュージアム,東北大学等ヒスイに関連する研究者に鑑定を依頼した結果,緑色の石英であることが判明した.しかし,研究者らもこのような緑色の石英が国内に産する例を見たことがないという状況である.また三澤氏は山形県近隣の縄文遺跡の出土品でヒスイ製と記載されているものを調査し,比重の測定からいくつかが緑色の石英であることを明らかにしつつある.本招待講演では,材木遺跡で表面採集された緑色の石英の特徴,鉱物鑑定の結果,産地推定の困難さの現状,東北地方の縄文遺跡 にも流通していた緑色石英についてご講演いただく予定である.
藤本幸雄(秋田地学教育学会:会員),30分 藤本会員は,高校教員退職後も秋田地学教育学会会員,日本地質学会会員としてこれまで東北地方の基盤岩類や秋 田県の新第三系,第四系の地質の調査研究や普及教育を行ってきている.また男鹿ジオパーク,白神海岸ジオパーク も支援してきている.藤本会員は縄文時代後期の伊勢堂岱 遺跡(北秋田市)の環状列石,縄文時代中期〜後期の大湯 環状列石(元鹿足市)の地質学的,岩石記載学的な面から 調査を行っている.大湯環状列石の石材は,岩石の種類,礫 径,円磨度,帯磁率などについて検討し,あせて周囲の河床 礫,石材由来の岩体の節理系,帯磁率の調査を通して石材 の由来と採集地の評価を行っている.伊勢堂岱遺跡につい ても岩石の種類,礫径,円磨度,帯磁率などに加え河床礫,段 丘礫,湯車層(段丘礫層の下に分布)について検討し,石 材の採集地を推定している.これまでもトピックセッショ ン「文化地質学」では遺跡の石材についての研究が多く発 表されているが,藤本会員の環状列石の研究のような,河 床礫,段丘礫,段丘の下位の地質等総合的を検討するよう な研究は少ない.本招待講演では,環状列石の石材の種類 だけでなく,礫径や円磨度を元に,周囲の河川の河床礫, 段丘礫等から石材の採集地を絞り込んでいった過程につい て講演していただく予定である.
ページtopに戻る
T6.「災害多発社会における学術資料・標本散逸問題―大学・博物館は何をすべきか−」
大路樹生(名古屋大博:会員),30分 大路会員は,現在名古屋大学館長の重責を担っており, 日本の国立大学や大学博物館における標本の現状・問題点 および動向をよく把握・認識している研究者である.また ご本人も,海洋生物化石研究の第一人者として世界各地で の調査・試料採取また,それら学術標本を用いた様々な研 究論文や一般普及書を記述している.加えて研究者としての標本問題に関する視点も合わせ持ち,招待講演者として ふさわしい.
T7.地球年代学が拓く高精度火山噴火史・発達史
伊藤久敏(電中研:会員),30分 伊藤会員は,近年LA-ICP-MSを用いて精力的に火成岩の ジルコンU-Pb年代測定を行っている.特に最近は更新世の 火山噴出物にこの手法を適用している.U-Pb年代を適用す るにはこの地質年代は若いが,迅速かつ高精度な年代値を 得ることに挑戦している.さらに,海外の研究者との共同 研究も精力的に取り組み,U-Th/He年代を併用したダブル 年代測定にも取り組み始めた.一連の研究は特に大規模珪 長質噴火活動史を明らかにする上で重要な研究である.
望月伸竜(熊本大:会員),30分 望月会員は古地磁気学を専門とし,特に最近は,火山岩 を対象とした高分解能の古地磁気年代推定に取り組んでい る.従来,困難とされていたテフラ層の定方位採取法を開 発し,その残留磁化方位と永年変化率から,大規模カルデ ラ噴火の継続時間に関する新知見を見出している.この手 法は, 溶岩とテフラ, あるいは溶結凝灰岩とそのcoignimbrite ashの対比や時間差推定などにも有効である.こ れらの関連研究例を紹介してもらい,火山地質学・編年学 における新たな展開の契機となることを期待したい.
R1.深成岩・火山岩とマグマプロセス
今山武志(岡山理科大:会員)30分 今山会員は,地質年代学,岩石学,テクトニクス学を専 門とし,ヒマラヤ造山帯を中心に,国際的なフィールドで 研究を展開している.最近はモンゴルやパキスタンなどの 火山岩・深成岩類の研究にも取り組んでおり,K-Ar法や U-Pb法による年代測定と岩石学的・地球化学的分析を行っ て,マグマの成因や地殻の進化過程,テクトニクスを解明 している.これらの研究をはじめとし,世界各地のフィー ルドワークで蓄積された年代学的・岩石学的データを基に, 北東アジア地域における地質構造発達史の概要と最新の知 見について講演していただく.
ページtopに戻る
R3.噴火・火山発達史と噴出物
伴 雅雄(山形大:会員)30分 伴会員は,火山学・岩石学を専門とし,主に東北日本地 域の火山を対象に研究を展開している.地質学的,岩石学 的,地球化学的データを基に,個々の火山の形成史や深部 マグマプロセスを高分解能で解明する研究事例を積み重ねている.特に最近は,活動的火山である蔵王火山において, 将来の噴火推移予測や防災・減災対策に関する研究も精力 的に行っている.本講演では,これら最新の研究成果を交 えながら,火山地質学および岩石学的データをどのように 噴火予測に活かせるかを紹介していただく.
R4.変成岩とテクトニクス
河上哲生(京都大:会員)30分 河上会員は主に高温変成岩を対象として野外調査に基づ く岩石学的研究を展開しており,南極を含む世界各地のフィールドを研究対象としている.特に副成分鉱物の消長に 注目した大陸地殻での流体活動履歴の読み取りで興味深い 成果を多数挙げている.これまでに第44次と51次の南極調 査隊に参加するとともに,最近では第61次南極調査隊夏隊 (2019〜2020)においてセール・ロンダーネ山地地質チームのリーダーとして野外調査を実施している.講演では,最新の南極調査成果を交えながら,大陸地殻の形成と進化プ ロセスに関する知見を紹介していただく.
R9.堆積
田村 亨(産総研:会員)30分 田村会員は,沿岸域の地層・地形の形成過程について精 力的に研究を行っている.コア試料の層相解析や古環境解 析などの従来的な手法に加え,地中レーダ探査やOSL年代 測定といった最新の技術を組み合わせることで,高分解能 で時空間的に解析する手法を開発し,世界各地の海岸砂丘 やデルタなどの研究に適用してきた.このような進歩的な 研究による貢献が認められ,2014年度には日本地質学小澤 儀明賞を受賞している.本招待講演では,メコンデルタの 地層・形成過程に関するレビューと最新の研究成果につい てお話しして頂く.
ページtopに戻る
R10.炭酸塩岩の起源と地球環境
小宮 剛(東京大:会員)30分 小宮会員は,初期地球の表層テクトニクスや物質循環, 海水組成の変遷と生命進化などに関する研究成果を数多く 発信されている.特に近年,カナダ・ラブラドルから世界 最古の表成岩を発見し,初期地球の表層環境と生命の起源, 進化を解読するための重要な成果を提出された.招待講演 では,世界最古の炭酸塩岩の化学組成分析から明らかにな った初期太古代の海洋組成や初期生命の痕跡について最新 の話題を講演頂く予定である.
R11.石油・石炭地質学と有機地球化学
早稲田 周(石油資源開発:非会員(有機地球化学会会 員))30分 早稲田氏は,有機地球化学的手法を用いた石油・天然ガ スの根源岩能力評価や探鉱に関する研究に長年取り組んで おられ,この分野をリードしてきた研究者の一人である.招待講演では,安定同位体およびクランプト同位体を用い た天然ガス評価法の最近の進展について話題を提供して頂く予定である.
R12.岩石・鉱物の変形と反応
西山忠男(熊本大:会員)30分 西山会員は,これまでに長崎変成岩などの野外調査をベ ースとして変成作用・交代作用における反応帯形成や,脱 水反応に伴う水圧破砕など,岩石の反応と変形・破壊現象 を結びつける独創的な研究を進めてこられた.これらの沈 み込み帯での流体が関与する反応プロセスは,近年,観測 が進んでいるプレート境界でのさまざまな地震現象の本質 的な理解の鍵を握っている可能性も高い.本講演では,西 山会員の最近の大きな発見であるマイクロダイヤモンドと 超高圧条件におけるシュードタキライトについてのエキサ イティングな話を紹介していただく.
纐纈佑衣(名古屋大:会員)30分 纐纈会員は,レーザーラマン分光分析を用いた炭質物温 度計(Raman CM thermometry)の手法開発から実践に至 るまで携わる数少ない研究者であり,その対象も堆積岩・ 変成岩から断層,隕石と多岐にわたる.温度・圧力・時間・ 変形が多様に影響する炭質物の熟成度スペクトラムは,地 質体の解析にいかにして役立てられるのか.深部から浅部, 100万年から秒単位までの適用例をご紹介いただく.
ページtopに戻る
R13.沈み込み帯・陸上付加体
大坪 誠(産総研:会員)30分 大坪会員は構造地質学を専門としている.野外調査を中 心に据えながら主に古応力解析と物性を組み合わせて,構 造発達史に定量的な物理量を付与して解釈する研究に魅力 がある.近年,沖縄トラフの背弧拡大場の形成史を琉球ト レンチとの相互作用として注目し,陸上調査だけでなく, 海洋掘削を見据えたプロジェクトの立案代表者として活躍 している.今回は,海洋掘削プロジェクトの提案内容とそ の背景を中心とした講演をお願いする予定であり,沈み込 み帯・陸上付加体セッション参加者との活発な議論が期待 できる.
仲田理恵(東京大・地震研:非会員)30分 仲田氏は海底地震計の波形トモグラフィーを用いて沈み 込み帯の速度場の解析を行ってきた,地球物理学者である. 特に紀伊半島沖南海トラフ浅部の上盤での低速度帯の存在 を指摘し,地質学的な付加体構造発達史に新たな議論を提 供した.近年ではスロー地震のメカニズムにも視野を広げ, 日向灘沖のスロー地震帯における海洋掘削プロジェクトの 立案リーダーを務めている.今回は,日向灘沖海洋掘削プ ロジェクトの提案内容とその背景を中心とした講演をお願 いする予定であり,沈み込み帯・陸上付加体セッションの 参加者と活発な議論が期待できる.
R14.テクトニクス
中村佳博(産総研:会員)30分 中村会員は,野外地質調査に加え,高温高圧実験に基づ く炭質物のグラファイト化の反応速度論的解析を武器に, 変成岩・付加体地域の構造地質学的研究に新風を吹き込む 気鋭の研究者である.中村会員は近年,長野県大鹿村周辺 の「大河原」図幅作成のための調査を行われており,その 過程で得られた新たな知見をもとに,鹿塩マイロナイトお よび領家帯・三波川帯の地質情報から復元する日本列島の テクトニクスに関してご講演を頂く.
志村侑亮(産総研:会員)30分 志村会員は,紀伊半島中央部に分布する付加体と高圧変 成岩類の研究を精力的に進められている若手研究者である. 紀伊半島中央部は,秩父帯が欠損し,四万十帯と三波川帯 が直接接するという点において,日本列島のテクトニクス および付加体の構造発達に重要な意味を持つ地域であり, 詳細な野外地質調査と年代・被熱・構造解析に基づく新た な知見をご紹介いただく.
ページtopに戻る
R22.地球史
杉谷健一郎(名古屋大:会員)30分 杉谷会員は西オーストラリアや南アフリカの太古代の珪 質堆積岩に含まれる有機物(炭質物)の微細構造の解析か ら,初期生命の進化に関する研究を精力的に行ってきた. 欧米豪の研究者達との共同研究も多く,国際的に活躍され ている.招待講演では,地球初期の生命の姿と進化につい て,最新の成果を踏まえて紹介していただく.
長谷川 精(高知大:会員)30分 長谷川会員は,地球の気候変動と惑星環境の歴史を地層 や堆積物の解析から復元する研究を行っている.風成層か ら過去の大気循環システムの復元,湖成年縞から白亜紀温 室地球の年スケール気候変動の復元,さらには地球の地層 との比較から火星環境の復元まで,多岐にわたる.招待講 演では,最新の成果を踏まえて研究を紹介していただく.
R23.原子力と地質科学
若杉圭一郎(東海大学:非会員)30分 若杉氏は,地層処分に関する安全評価研究を長年にわた って進められ,放射性廃棄物のソースターム(環境に放出 される放射性物質などの種類,性状,放出量など)から人 間への影響に至るまで幅広い研究を展開している.また, OECD/NEAでの勤務やIAEA国際スクールでファシリテー ターを務めた経験を持ち海外の放射性廃棄物処分にも精通 している.本年2月に公開された原子力発電環境整備機構 (NUMO)の技術報告書(2021)*の国内レビュー委員会の委 員も務められた.地層処分は昨年北海道の2町村で文献調 査が開始され,新たなフェーズへ移行しつつあることを踏まえ,講演では地層処分の現状,NUMOの技術報告書レビ ュー結果,地質環境分野における課題等について紹介頂く. (*https://scct.numo.or.jp/GeoCom2/faces/project/view. xhtml)
R24.鉱物資源と地球物質循環
平田岳史(東京大:会員)30分 平田氏は,世界最先端の極微量分析・局所分析を駆使し た研究で世界をリードする分析化学の第一人者である.平 田氏によって活発に研究開発が行われている超高精度な局 所分析技術,局所分析を応用した2D・3D元素マッピング技 術,様々な時間スケールで適用可能な高精度同位体年代学 は,鉱物資源分野にも革命をもたらし得る画期的な成果として注目される.本講演では,当該分野の最新の話題を提 供して頂く予定である.そのお話を聞ける機会は,本セッ ションに関係する全ての研究者にとって非常に有意義なも のになると期待される.
ページtopに戻る
第5回ショートコース
日本地質学会第5回ショートコース
申込締切
締切を延長します:2021年9月24日(金)
2021年9月21日(火)
申込方法
締切ました
第5回 日程:2021年10月3日(日)
今回は応用地質・地質調査業・GIS(地理情報システム)・デジタル地質情報の利活用などについて学ぶ機会を提供します.今回も多くの学生・若手研究者の皆様に受講していただきたいコースです.中堅・ベテラン研究者や学校教員,地質調査業従事者,広く一般の方も,ぜひふるってご参加ください.講師は,午前が地質を中心としたコンサルタント(博士・技術士・応用地形判読士)として地質調査業界で長年活躍されている永田秀尚氏,午後が火山学専門家でありGISやデジタル地質情報の利活用に詳しい宝田晋治氏です.
内容:(各コース,講義・質疑応答含め3時間を予定)
<午前> 9:00-12:00
応用地質学への招待:私の現場から+α:永田秀尚(有限会社風水土)
私が携わった現場の経験をもとに,応用地質学について振り返ってみます.岩石・岩盤の強度,岩盤と地下水,斜面変動についての事例を紹介し,そこから地質学の知識を応用することの意味と大切さを考えます.また,コンサルティングジオロジストはエンジニアへの情報伝達者でもあるわけですから,地質情報の特性や伝達法についての理解も必要で,その点についての考え方を提示します.さらに,地質学を学ぶ学生諸氏の進路選択の一助となればという思いで,地質コンサルタントとその働き方についても紹介します.
<午後> 13:30-16:30
GISとWebGISによるデジタル地質情報の利活用:宝田晋治(産総研・地質調査総合センター)
産総研地質調査総合センター(GSJ)では,1882年の発足以来およそ140年にわたり地質図を始めとする数多くの地質情報の整備を行っています.それらのデータは,デジタル化が進められており,GISを使ってさまざまな用途に利活用できます.また,GSJでは30近いデータベースを公開しており広く利用されています.ショートコースでは,QGISによる地質情報のデジタル化,利活用の方法の他,各種データベースの紹介を行います.さらに,WebGISによるデジタル地質情報の利活用の事例として,アジア太平洋地域地質ハザード情報システム,火山災害予測支援システム,CCOP地質情報総合共有システム,OneGeology等についても紹介させて頂く予定です.
参加費(各1日券):
地質学会会員 2,000円(地質学会賛助会員に所属する⽅は地質学会会員と同額です)
⾮会員 5,000円
(注)⾮会員の学部⽣・院⽣は「地質学会会員」料⾦に含まれます.「⾮会員」とは学部⽣・院⽣ではない⾮会員とします.
(注)午前のみ,午後のみの受講の場合も,参加費の割引はありません.
(注)キャンセル料について:締切日まで 0%, 会期3日前まで 60%, 会期2日前以降 100% いずれの場合も返金がある場合は,振込手数料を差し引いた額をカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2〜3ヶ月要する場合もありますので,ご了承下さい.
開催方法:WEB会議システムzoom(https://zoom.us/)によるオンライン講義
※参加者には近日中にzoomアクセスURL,事前資料をメールでお送りします(9/27現在)
定員:各コース100名(定員は事務局および講師を含み、定員を超えた場合は,会員が優先となります)
申込方法:専用申し込みフォームはこちらから (注)申込時にご提供いただいた個人情報は、日本地質学会プライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います.
その他:希望者には各コース毎のCPD受講証明書を発行します.午前午後各3単位を予定.(CPDプログラムID:2983)
申込締切:締切を延長します:2021年9月24日(金)2021年9月21日(火)
問い合わせ先:一般社団法人日本地質学会
メールmain [at] geosociety.jp 電話 03-5823-1150
(参考)過去のショートコース
(第1回,第2回)http://www.geosociety.jp/science/content0121.html
(第3回)http://www.geosociety.jp/science/content0130.html
(第4回)http://www.geosociety.jp/science/content0134.html
山形大会開催通知
2024山形大会開催通知
日本地質学会第131年学術大会
(2024山形大会)
山形大学小白川キャンパス(山形市小白川町)にて
2024年9月8日(日)〜9月10日(火)に開催
日本地質学会は,山形市小白川町の山形大学小白川キャンパスにおいて,第131年学術大会(2024年山形大会)を9月8日(日)から10日(火)に開催します.また,巡検(見学旅行)を7日(土)と11日(水)〜12日(木)に催行します.
山形大学での開催は39年ぶりになります.この間に山形での開催の機運が高まった時期もありましたが叶わず,間隔がかなり長くなってしまいました.39年前に開催されたときには,山形大学の当時の地学関係の皆さんが総動員されて,とても活気のある明るい大会にしていただいたことを思い出します.
今回は山形大学の地質学会関係者数が少ないなどのため,なるべく無理のない実施内容にするようにしております.そのため,トピックセッションの充実など,広く会員の皆様にご協力をお願いする次第です.LOCとしましてはできる限りのことを行う所存です.特に,会場運営と懇親会は力を入れて行います.また,巡検はLOC以外の方々にもご協力いただき8コース準備しております.層序,化石,変成岩/深成岩,地質災害,文化地質,火山,鉱床といったいろいろ魅力的な巡検コースを提供できるものと思います.山形駅近くの催事場では,例年通りに地質情報展が開催されます.同催事場では山形の風土に関連した地学的現象についての市民講演会も企画しております.
宿泊施設はある程度の数がありますが,学術大会は連休にかかっていることもありますので,ある程度早めに宿の予約をされると良いかと思われます.
会場となる山形大学小白川キャンパスはJR山形駅から約2kmに位置しております.
山形駅からベニちゃんバスという山形大学前に停まる市営バスが1時間に2便程度運行されており,運賃は100円です.小白川キャンパスは新幹線駅からバスで10分,徒歩30分の場所に立地しており,宿泊施設も駅周辺や駅とキャンパスの中間の商業地区に多くあります.
こぢんまりとしたキャンパスです.会場は正門を入ってまっすぐ250mほど入ったところにあります.3つの建物に分散しておりますが,お互いの距離はさほどありません.山形市内には小白川キャンパスの他に医学部の飯田キャンパスがありますのでお間違えの無いように.
都会から離れた,のんびりとした立地のため,心身のリフレッシュの場としてはうってつけだと思われます.山形の街並みも年々変わっておりますが,基本的な雰囲気は変わっておらず,戦火を免れた城下町の名残が散在しているようですので,街中を散策いただくのも良いかもしれません.
大会実行委員会一同,多くの皆様のご参加を心からお待ちしております.
日本地質学会第131年学術大会(山形大会)
実行委員会
セッションについて/トピック提案募集
セッションについて/トピック提案募集
※トピックセッション提案募集 締切:2024年3月27日(水)はこちらから
※大会までのスケジュールはこちらから
【重要】学術大会セッションについて
日本地質学会行事委員長
高嶋礼詩
一昨年の東京・早稲田大会から,セッションを「トピックセッション」,「ジェネラルセッション」,「アウトリーチセッション」の3カテゴリに区分し,従来のレギュラーセッションは発展的に解消されました.山形大会も早稲田大会,京都大会に引き継続き,上記3つのセッションで構成いたします.
学術大会セッションの魅力を高めることは,日本の地質学ならびに本会学術大会を活性化させるとともに,さまざまな世代の会員数の維持もしくは増加や大会参加者増にもつながると考えられます.そのためには,セッション企画に関わる会員や専門部会が,毎年適度な緊張感を持ってセッションの魅力向上を意識する仕組みを構築する必要があり,これは専門部会や支部の活性化にも貢献すると考えられます.学術大会のセッション区分の改訂は,その一環として実施しました.
一方,若手会員増やダイバーシティ確保を目指すための策として,年会費改定をはじめとするいくつかの大幅変更が実施されました.近年の代議員選挙には多くの院生・ポスドク等の若手会員が立候補し,早稲田,京都大会で実施された若手の会にも数多くの参加者が集まりました.このように,本会にも大きな変化が起こりつつあります.次の山形大会では過去二年間の経験と反省を基に,各分野からトピックセッションを積極的に提案していただき,学術大会をより盛り上げていただきたいと思います.
トピックセッション(Topical Session)
会員提案型セッションです.提案者(=世話人)は最大3名とし,研究キャリアや所属階層,ジェンダー,国籍などのダイバーシティを意識した提案者構成を強く勧めます.セッション提案書には,専門部会・委員会・支部・LOC等の提案母体の有無,他学会等の共催希望の有無(有の場合はその理由),招待講演案,過去開催実績,想定発表(演題)数,特集号計画の有無などを示していただきます.提案されたセッションは執行理事会学術研究部会を中心とする選考員によってレビューされ,提案内容や過去実績などを参考に選考されます.選考では地質学雑誌またはIsland Arc誌への特集号計画の有無も重視されます.類似するセッションが複数提案された場合は,学術研究部会がセッション統合を勧める可能性があります(その場合,招待講演は残りますが世話人は3名に調整していただきます).なお,口頭発表の演題登録数が5件に達しなかったセッションは後述のジェネラルセッションに統合します(その場合でも招待講演は残ります).従来のレギュラーセッションで実施されていたような伝統的・一般的な分野区分・名称(層序学,地域地質,構造地質など)での提案も歓迎します.
ジェネラルセッション(General Session)
従来のレギュラーセッションの枠組みを発展的に解消し,新たに一つのジェネラルセッションを設定します.本セッションはどのトピックセッションにも適合しない研究や多くの分野(disciplines)にまたがる研究などの発表の場になります.トピックセッションが上位,ジェネラルセッションが下位という関係ではありませんのでご注意ください.本セッションへの演題登録者には,関連する分野(例えば○○地質,△△地質など,専門部会名に類する分野を10程度想定)を3つ程度選んでいただき,関連性の順位を記入していただく予定です(任意).行事委員会がその順位を考慮して演題をグルーピングし,最大10程度のサブセッションにまとめて配列する予定です.本セッションの世話人は行事委員を基本としますが,口頭発表の演題登録数が5件に達しなかった(そのためジェネラルセッションに統合された)トピックセッションの提案者も世話人になっていただくことがあります.
アウトリーチセッション(Outreach Session)
一般市民向けのポスター発表で,市民講演会と同じ発表会場となります.通常の研究発表ではなく,専門外の人に興味を持ってもらえるような内容を募集します.発表会場は,市民講演会と同じ場所となります.山形大会では,市民講演会の会場は学術大会の会場と離れているため,ご注意ください.
topに戻る→
トピックセッション提案募集 締切:2024年3月27日(水)
日本地質学会行事委員会
第131年(2024年)学術大会を本年9月8日(日)〜10日(火)に山形大学で開催する予定です.前述の記事(【重要】学術大会セッションの変更について)でもお伝えしたように,2022年大会からセッションは「トピックセッション(会員提案型)」,「ジェネラルセッション」,「アウトリーチセッション」の3カテゴリになりました.ここではトピックセッション提案を下記の要領で募集します.
1.トピックセッション概要
広く地質学に関係し,これから新分野になる可能性を秘めたセッション,多くの注目を集めると期待できるセッション,伝統的だが多くの会員に関係するセッションの提案を募集します.魅力あるセッションを積極的にご提案ください.形式は口頭発表およびポスター発表とし,口頭発表は15分間で進行も15分刻みです.セッション世話人は最大3名とし,研究キャリアや所属階層,ジェンダー,国籍などのダイバーシティを意識した世話人構成を強く勧めます.締切後,執行理事会学術研究部会が中心になって提案内容を慎重に検討の上,選考します.なお,選考では地質学雑誌またはIsland Arc誌での特集号計画の有無も重視されます.
2.招待講演
招待講演は1セッションにつき最大2名とし,会員・非会員を問いません.世話人が「自分を招待する」ことは認めません.
発表時間(質疑応答を含む)は世話人が15分または30分のいずれかを選択できます.なお,1人の発表者(招待講演者を含む)が1つのセッションで口頭発表できるのは1件です.
招待講演者の選定理由とその裏付けとなる情報(セッションテーマに関連した代表的な論文・著書等)が必要です.
非会員の招待講演者は大会参加登録費,発表料金とも無料です.会員の場合は大会参加登録費,発表料金とも有料です.
3.提案方法
提案する会員は,次の項目1〜11の内容を日本地質学会行事委員会宛(main@geosociety.jp)にe-mailでお送りください.
代表世話人(=連絡責任者,会員に限る)の氏名(和・英),所属(和・英),メールアドレス,緊急時の電話番号
セッションタイトル(和・英)
共同世話人(最大2名)の氏名(和・英),所属(和・英),メールアドレス
趣旨・概要(400〜600字程度)提案する分野・テーマに関する国内外における研究の動向,学術的な重要性,今後の展望など.
過去のセッション開催有無,有の場合は直近大会時の口頭発表数
招待講演の有無 有の場合 6-1)招待講演者の氏名(和・英),所属(和・英),会員/非会員の別 6-2)招待講演の発表希望時間(15分または30分) 6-3)招待講演者の選定理由(100〜200字) 6-4)選定理由の裏付けとなる,セッションテーマに関連した代表的な論文・著書等
専門部会・委員会・支部・大会実行委員会(LOC)等の提案母体の有無(事前に母体の承諾を得てください)
他学協会等との共催希望の有無,有の場合は名称と共催希望理由(事前に共催承諾を得てください) ※共催学協会会員は地質学会会員と同じ参加登録費で大会に参加できます.ただし当該セッションでのみ発表可.
想定される,または直接呼びかける予定の口頭発表の数
地質学雑誌またはIsland Arc誌への特集号計画の有無(特集号計画を強く勧めます)
その他(英語使用等)
4.採択前後の注意点
類似するセッションが複数提案された場合は,執行理事会学術研究部会がセッション統合を勧めることがあります.その場合,招待講演は残りますが世話人は3名に調整していただきます.採択されたトピックセッションはニュース誌4月号または5月号(4月末または5月末発行予定)で公表し,発表募集を行います.演題登録(発表申込と要旨投稿)締切は6/19を予定しています.なお,口頭発表の演題登録数が5件に達しなかったセッションはジェネラルセッションに統合し(その場合,招待講演もジェネラルセッションになります),代表世話人にはジェネラルセッションの世話人の一人になっていただくことがあります.
5.世話人が行う作業(7月初旬〜中旬)
代表世話人には,講演要旨校閲や講演順番決定などの作業を7月初旬までに行っていただきます(詳細は採択後にお知らせします).その期間,代表世話人は電子メールで添付ファイルを送受信できるようにして下さい.野外調査や乗船等で通信が制限される場合は,共同世話人(代理)にあらかじめ作業を依頼し,その旨を行事委員会に必ず報告してください.
ご不明の点があれば行事委員会(main[at]geosociety.jp ※[at]を@マークにして送信してください)までお気軽にお問い合わせください.
大会までのスケジュール(予定)
3月27日(月):トピックセッション提案募集締切
4月末(ニュース誌4月号):大会予告記事(演題登録・講演要旨受付開始)
6月19日(水):演題登録・講演要旨受付締切/ランチョン・夜間小集会申込締切
7月中旬:大会プログラム公開(予定)
8月下旬:大会参加登録/巡検参加申込締切
9月8日(日)〜10日(火)学術大会
topに戻る→
山形大会プレサイト(top)
日本地質学会第131年学術大会
2024山形大会
(プレサイト)
会期:2024年9月8日(日)〜9月10日(火)
会場:山形大学小白川キャンパス(山形市小白川町)にて
本サイトオープンしました
更新情報
24/05/08 本サイトオープンしました
24/05/07 まもなく講演申込受付開始します
24/01/19 トピックセッション提案募集:締切 3/27(水)
24/01/19 【重要】学術大会セッションの変更について
24/01/19 開催通知
24/01/19 大会プレサイト開設しました
大会までのスケジュール(予定)
3月27日(水):トピックセッション提案募集締切
4月末(ニュース誌4月号):大会予告記事(演題登録・講演要旨受付開始),大会本サイトオープン
6月26日19日(水):演題登録・講演要旨受付締切/ランチョン・夜間小集会申込締切 【日程訂正しました】
7月中旬:大会プログラム公開(予定)
8月下旬:大会参加登録締切
9月8日(日)〜10日(火)学術大会
第2回JABEEオンラインシンポジウム
日本地質学会主催:第2回JABEEオンラインシンポジウム
▶︎開催報告はこちら 2022.5.12掲載
第2回JABEEオンラインシンポジウム
『昔と違う イマドキのフィールド教育』
シンポジウムの内容をYouTubeで公開しています(2022.3.25公開)
趣旨
地質学教育においてフィールド教育は最も基本的な教育項目であり、地質学を学ぶ上で最も重要なもののひとつです。また、地質技術者として社会で活躍するために必要な技術といえます。昔からフィールド教育は大学で活発に展開されてきましたが、時代と共に大学をめぐる状況も変わり、フィールド教育の実施方法も多様になっています。地質技術者教育委員会では、本シンポジウムにおいてJABEE認定大学におけるフィールド教育の実際を報告してもらい、それを題材として現代に即したフィールド教育について考えてみることにしました。
シンポジウム概要
日程:2022年3月6日(日)14時開会予定13:30〜18:30(予定)※これまでご案内していました14時開催が、13時半開催に変更となります。
開催形態:Zoom によるオンラインシンポジウム
参加費:会員・非会員問わず参加無料
参加申込締切:3月3日(木)<参加申込は締め切りました>
※締切後,申込者へzoomアクセスURLをメールでお知らせします.
CPDポイント:最大4.7(※参加時間に応じて発行します)
演題と講演予定者 講演概要はこちらからDLできます
13:30 開会(司会:佐々木和彦(地質技術者教育委員会副委員長))開会挨拶:会長 磯粼行雄,趣旨説明:天野一男(地質技術者教育委員会委員長)
13:40〜14:15 講演1「茨城大学におけるフィールド教育」小荒井衛(茨城大学大学院理工学研究科 教授)・小柴理人(茨城大学大学院理工学研究科 修士1年)・橋本果歩(茨城大学大学院理工学研究科 修士1年)
14:15〜14:50 講演2「島根大学におけるフィールド教育としての進級論文」林 広樹(島根大学総合理工学部地球科学科 准教授)
14:50〜15:25 講演3「千葉大学における多様な地球科学のフィールド教育」金川久一(千葉大学理学研究院 教授)・小野誠仁(千葉大学大学院融合理工学府)
15:25〜15:35 休憩
15:35〜16:10 講演4「新潟大学理学部理学科地質科学プログラムにおけるフィールド教育と安全対策」豊島剛志(新潟大学理学部理学科 教授)
16:10〜16:45 講演5「山口大学におけるフィールド教育のPDCAサイクルとシステム化」大橋聖和(山口大学理学部地球圏システム科学科 准教授)
16:45〜17:15 講演6「現場を診る力 〜継続は力なり〜」栃本泰浩(川崎地質株式会社 代表取締役社長)
17:15〜17:25 休憩
17:25〜18:10 総合討論 座長:天野一男
18:10〜18:30 閉会 閉会挨拶:天野一男
問い合わせ先:日本地質学会事務局(main[アット]geosociety.jp)※[アット]を@マークにして送信してください
学術大会セッションの変更について
<<2022早稲田大会topに戻る
【重要】学術大会セッションの変更について
学術大会セッション変更に関するzoom説明会(2/10開催 動画公開中)
【重要】学術大会セッションの変更について
日本地質学会行事委員長 星 博幸
本年9月開催予定の東京・早稲田大会から,セッションを「トピックセッション」,「ジェネラルセッション」,「アウトリーチセッション」の3カテゴリに変更します.従来のレギュラーセッションは発展的に解消します.
学術大会セッションの魅力を高めることは,日本の地質学ならびに本会学術大会を活性化させるとともに,さまざまな世代の会員数維持(願わくば増加)や大会参加者増にもつながると考えられます.そのためには,マンネリ化,発表者・参加者の固定化,不活発などが複数のセッションに指摘されている現状を打破し,セッション企画に関わる会員や専門部会が毎年適度な緊張感を持ってセッションの魅力向上を意識する仕組みを構築する必要があります.これは専門部会や支部の活性化にも貢献すると考えられます.
若手会員増やダイバーシティ確保を目指すための策として,年会費改定をはじめとするいくつかの大幅変更が検討されています.また,今回の代議員選挙には多くの院生・ポスドク等の若手会員が立候補し,本会に大きな変化が起こりつつある気配を感じます.地質学ならびに本会学術大会を活性化させるためにセッションを変革する時機が到来していると私は考えます.
研究発表の場になるのはトピックセッションとジェネラルセッションです.アウトリーチセッションは従来通り,一般市民向けのアウトリーチ活動を行う場で研究発表セッションではありませんのでご注意ください.以下ではトピックセッションとジェネラルセッションについて概要を説明します.会員の皆様は魅力あるトピックセッションをぜひ積極的にご提案ください.なお,セッション説明会を2月にオンラインで開催します.日時は学会ウェブサイト,メルマガ,SNS等で連絡します.
トピックセッション(Topical Session)
会員提案型セッションです.提案者(=世話人)は最大3名とし,研究キャリアや所属階層,ジェンダー,国籍などのダイバーシティを意識した提案者構成を強く勧めます.セッション提案書には,専門部会・委員会・支部・LOC等の提案母体の有無,他学会等の共催希望の有無(有の場合はその理由),招待講演案,過去開催実績,想定発表(演題)数,特集号計画の有無などを示していただきます.提案されたセッションは執行理事会学術研究部会を中心とする選考員によってレビューされ,提案内容や過去実績などを参考に選考されます.選考では地質学雑誌またはIsland Arc誌への特集号計画の有無も重視されます.類似するセッションが複数提案された場合は,学術研究部会がセッション統合を勧める可能性があります(その場合,招待講演は残りますが世話人は3名に調整していただきます).なお,口頭発表の演題登録数が5件に達しなかったセッションは後述のジェネラルセッションに統合します(その場合でも招待講演は残ります).
ジェネラルセッション(General Session)
従来のレギュラーセッションの枠組みを発展的に解消し,新たに一つのジェネラルセッションを設定します.本セッションはどのトピックセッションにも適合しない研究や多くの分野(disciplines)にまたがる研究などの発表の場になります.トピックセッションが上位,ジェネラルセッションが下位という関係ではありませんのでご注意ください.本セッションへの演題登録者には,関連する分野(例えば○○地質,△△地質など,専門部会名に類する分野を10程度想定)を3つ程度選んでいただき,関連性の順位を記入していただく予定です(任意).行事委員会がその順位を考慮して演題をグルーピングし,最大10程度のサブセッションにまとめて配列する予定です.本セッションの世話人は行事委員を基本としますが,口頭発表の演題登録数が5件に達しなかった(そのためジェネラルセッションに統合された)トピックセッションの提案者も世話人になっていただくことがあります.なお,本セッションでは招待講演の募集はありません.
トピックセッション提案募集
<<2022早稲田大会topに戻る
トピックセッション提案募集
2022年学術大会(東京・早稲田)
トピックセッション提案募集 締切:2022年3月10日(木)
日本地質学会行事委員会
第129年(2022年)学術大会を本年9月4日(日)〜6日(火)に早稲田大学で開催する予定です.前述の記事(【重要】学術大会セッションの変更について)でお伝えしたように,今大会からセッションは「トピックセッション(会員提案型)」,「ジェネラルセッション」,「アウトリーチセッション」の3カテゴリになります.ここではトピックセッション提案を下記の要領で募集します.
1.トピックセッション概要
広く地質学に関係し,これから新分野になる可能性を秘めたセッション,多くの注目を集めると期待できるセッション,伝統的だが多くの会員に関係するセッションの提案を募集します.魅力あるセッションを積極的にご提案ください.形式は口頭発表およびポスター発表とし,口頭発表は15分間で進行も15分刻みです.セッション世話人は最大3名とし,研究キャリアや所属階層,ジェンダー,国籍などのダイバーシティを意識した世話人構成を強く勧めます.締切後,執行理事会学術研究部会が中心になって提案内容を慎重に検討の上,選考します.なお,選考では地質学雑誌またはIsland Arc誌での特集号計画の有無も重視されます.
2.招待講演
招待講演は1セッションにつき最大2名とし,会員・非会員を問いません.世話人が「自分を招待する」ことは認めません.
発表時間(質疑応答を含む)は世話人が15分または30分のいずれかを選択できます.なお,1人の発表者(招待講演者を含む)が1つのセッションで口頭発表できるのは1件です.
招待講演者の選定理由とその裏付けとなる情報(セッションテーマに関連した代表的な論文・著書等)が必要です.
非会員の招待講演者は大会参加登録費,発表負担金とも無料です.会員の場合は大会参加登録費がかかりますが,招待講演は発表負担金の対象にはなりません.なお,大会参加登録費と発表負担金は改定が検討されており,詳細については大会予告記事(ニュース誌4月号予定)でお知らせします.
3.提案方法
提案する会員は,次の項目1〜11の内容を日本地質学会行事委員会宛(main@geosociety.jp)にe-mailでお送りください.
1)代表世話人(=連絡責任者,会員に限る)の氏名(和・英),所属(和・英),メールアドレス,緊急時の電話番号
2)セッションタイトル(和・英)
3)「共同世話人(最大2名)の氏名(和・英),所属(和・英),メールアドレス
4)趣旨・概要(400〜600字程度)
5)過去のセッション開催有無,有の場合は直近大会時の口頭発表数
6)招待講演の有無
有の場合
6-1)招待講演者の氏名(和・英),所属(和・英),会員/非会員の別
6-2)招待講演の発表希望時間(15分または30分)
6-3)招待講演者の選定理由(100〜200字)
6-4)選定理由の裏付けとなる,セッションテーマに関連した代表的な論文・著書等
7)専門部会・委員会・支部・大会実行委員会(LOC)等の提案母体の有無(事前に母体の承諾を得てください)
8)他学協会等との共催希望の有無,有の場合は名称と共催希望理由(事前に共催承諾を得てください) ※共催学協会会員は地質学会会員と同じ参加登録費で大会に参加できます.ただし当該セッションでのみ発表可.
9)想定される,または直接呼びかける予定の口頭発表の数
10)地質学雑誌またはIsland Arc誌への特集号計画の有無(特集号計画を強く勧めます)
11)その他(英語使用等)
4.採択前後の注意点
類似するセッションが複数提案された場合は,執行理事会学術研究部会がセッション統合を勧めることがあります.その場合,招待講演は残りますが世話人は3名に調整していただきます.採択されたトピックセッションはニュース誌4月号または5月号(4月末または5月末発行予定)で公表し,発表募集を行います.演題登録(発表申込と要旨投稿)締切は7月初旬を予定しています.なお,口頭発表の演題登録数が5件に達しなかったセッションはジェネラルセッションに統合し(その場合,招待講演もジェネラルセッションになります),代表世話人にはジェネラルセッションの世話人の一人になっていただくことがあります.
5.世話人が行う作業(7月初旬〜中旬)
代表世話人には,講演要旨校閲や講演順番決定などの作業を7月中旬までに行っていただきます(詳細は採択後にお知らせします).その期間,代表世話人は電子メールで添付ファイルを送受信できるようにして下さい.野外調査や乗船等で通信が制限される場合は,共同世話人(代理)にあらかじめ作業を依頼し,その旨を行事委員会に必ず報告してください.
ご不明の点があれば行事委員会(main[at]geosociety.jp)までお気軽にお問い合わせください.※[at]を@マークにして送信してください.
2022早稲田プレサイト_top
日本地質学会第129年学術大会
東京・早稲田大会
(プレサイト)
会期:2022年9月4日(日)〜6日(火)
会場:早稲田大学(東京都新宿区)
本サイトオープンしました
https://confit.atlas.jp/geosocjp129
更新情報
22/05/18 本サイトオープンしました
22/01/31 セッション変更に関するzoom説明会(2/10開催)
22/01/28 トピックセッション提案募集:締切3/10
22/01/28 【重要】学術大会セッションの変更について
22/01/28 早稲田大会プレページ開設しました
学術大会セッション変更に関するzoom説明会
<<2022早稲田大会topに戻る
学術大会セッション変更に関するzoom説明会
学術大会セッション変更に関するzoom説明会
本年9月開催予定の東京・早稲田大会から,セッションを「トピックセッション」,「ジェネラルセッション」,「アウトリーチセッション」の3カテゴリに変更します.従来のレギュラーセッションは発展的に解消します.(詳しくはこちら)
このセッション変更に関するZoom説明会を2月10日(木)12:30から開催します。セッション世話人に限らず,学術大会に参加される方,講演を予定されている方は是非ご参加ください.
説明会の動画をYouTubeで公開しています.(22.2.10公開)
トピック: 学術大会セッション変更に関する説明会
時間: 2022年2月10日(木)12:30から(40分程度を予定)
https://us02web.zoom.us/j/87423858446
ミーティングID: 874 2385 8446
パスコード: 885804
地質学露頭紹介 at JpGU2022
地質学露頭紹介 at JpGU2022
2022.2.8掲載 5.18更新
とっておきの露頭、解釈がむずかしい露頭などなど
地質学の露頭について、おおいに語りましょう!
▶︎▶︎YouYube公開中です
日本地質学会会員、または日本地球惑星科学連合(JpGU)2022年大会に参加登録をした方は(地質学会非会員でも)、Zoomで発表・参加できます(CPD単位も取得可)。それ以外の方もYouTubeライブ(同時配信)で視聴できます。
日本地質学会2021年オンライン学術大会で好評を博した「地質学露頭紹介」の第2弾! 今回はJpGUと共同開催です。JpGU2022の大会期間中にオンラインで開催します。
とっておきの露頭、解釈がむずかしい露頭、専門家から意見をもらいたい露頭など、さまざまな露頭の写真を持ち寄り、その学術的意味についてZoomで解説したり意見交換したりするスペシャルイベントです(研究発表セッションではありません)。参加者全員で楽しみましょう。写真の芸術性よりも学術的な重要性や疑問、おもしろさなどを重視します。露頭(の写真)を見れば地球惑星科学にかかわる人なら何か言いたくなる・聞きたくなるはず! 地球惑星科学系の学生や研究者はもちろん、地球惑星科学をあまり知らない方からの発表や質問を大歓迎します! なお、発表または参加によりCPD受講証明書を発行します(発表:1単位,参加:1単位/時間;希望者のみ)。
発表(露頭紹介)は一人スライド最大3枚で、うち1枚はスライド一面露頭写真にしてください。解説は5分以内で,質疑応答含め一人の持ち時間は最長10分です。イベント終了後,紹介した写真と簡単な解説を日本地質学会ニュース誌(冊子)と地質学会ウェブサイトに記名記事として掲載します。参考までに、2021年9月の地質学露頭紹介の記事を次のサイトでご覧いただけます。 http://www.geosociety.jp/faq/content0983.html
開催日時・プログラム
日時:2022年5月29日(日)14:00〜15:15(予定)
方法:オンライン(Zoom)+YouTubeライブ配信
<プログラム>
座長:星 博幸
13:55 挨拶
14:00 辻 智大(山口大)国内最長到達の阿蘇4火砕流堆積物
14:10 早坂康隆(広島大)広島市安佐北区の80 cm厚姶良Tnテフラ
14:20 木村英人(興亜開発)市原市南部古敷谷川Byk〜Ku2B連続露頭と西川右岸露頭
(休憩)
14:35 星 博幸(愛知教育大)愛知県知多半島の礫ヶ浦礫岩(中新統)
14:45 竹下 徹(北海道大)閉じた褶曲と褶曲の重複について
14:55 木戸 聡(福井県立敦賀高)飛水峡のチャート・甌穴群と珪質頁岩
15:05 討論・雑談
15:15 挨拶・終了
発表(露頭紹介)申込
発表申込期限:5月9日(月)18時 5/16(月)18時まで延長します
発表申込はこちらから 発表申込は締め切りました
参加方法
Zoom参加 地質学会会員(事前申込不要):学会ウェブサイトの会員ページ(要会員ログイン)に掲示されるZoomのID・パスコードを利用して参加してください。 ※ CPD受講証明希望の会員は次の(2)で参加登録してください。▶︎▶︎会員ページログインはこちらから
Zoom参加 JpGU2022に参加登録する地質学会非会員、またはCPD受講証明希望する地質学会会員(要申込):次のリンク先で氏名、メール、JpGU個人ID番号を入力し、Zoomパスコードを取得してください。▶︎▶︎参加申込はこちらから
YouTubeライブ(同時配信・事前申込不要)でどなたでも視聴できます:地質学会ウェブサイトのトップページに接続URLを掲示しますので、当日そこから接続してください。ただし発表に対する質問・コメント等はできません。 ※ YouTubeライブ視聴はCPD受講証明の対象外です。▶︎▶︎YouYube視聴はこちらから
問い合わせ先
日本地質学会事務局 main[at]geosociety.jp
※[at]を@マークにして送信してください
地質系業界オンライン交流会
地質系業界オンライン交流会 2025.2.14開催!
参加申込締切:2025年2月13日(木)23:59
クリックすると大きな画像をご覧いただけます
昨年度に引き続き、2024年度も若手活動運営委員会主催で地質系業界オンライン交流会を開催することとなりました。 この交流会は、地質学に関わる民間企業や官公庁等に就職を考えている学生・若手研究者向けのイベントであり、地質学に関わる企業・団体に就職をした若手職員の方との交流会を企画しています。 どのようなお仕事をされているのか、特にやりがいを感じた仕事、学生時代の経験で役に立ったこと、業界でのキャリア形成など、企業説明会や就職説明会などとは異なる若手職員ならではのお話をしていただき、参加者からの質問に答えていただく予定です。地質系の民間企業だけではなく、研究所やジオパークの職員など、広く地質学に関わる仕事を行っている方とお話しできる貴重な機会になりますので、奮ってご参加ください。 参加費は無料で、会員・非会員を問わずご参加いただけますので、周囲の興味がありそうな方にも回覧いただけますと幸いです。 詳細は以下の通りでございます。
日時:2025年2月14日(金)17:30–19:30
場所:Zoomによるオンライン開催
対象:35歳以下の学生・若手研究者(会員・非会員を問いません)
タイムテーブル:
17:30–17:40 趣旨説明
17:40–18:50 各業界の方との座談会(ブレイクアウトルームを使用)
18:50–19:30 懇談会
参加業界:
産業技術総合研究所
蔵王ジオパーク推進協議会
石油資源開発株式会社
川崎地質株式会社
株式会社マリン・ワーク・ジャパン
なお、事前参加登録が必要となりますので、以下のリンク先Googleフォームよりご登録ください。
事前参加登録はこちら>>https://forms.gle/RwQL8z5qAJSHMcJWA
フォーム入力締切:2025年2月13日(木)23:59
ご不明な点等ございましたら、地質学会若手活動運営委員会(ecg.core[at]gmail.com)までご連絡ください。
※[at]を@マークにして送信してください。
第9回ショートコース
日本地質学会第9回ショートコース
第9回ショートコース:応力逆解析法
申込締切
申込締切:2023年10月16日(月)
申込方法
締切ました
学会ジオストアよりお申し込みください
日程:2023年10月22日(日)
今回は,4月に応募者多数につき締切日前に申し込みを締め切らせていただいた応力逆解析法のショートコース(第7回)を再度行います.
応力逆解析法は,現在または地質学的過去の,テクトニクスの原動力を解明する方法の1つです.「逆」解析と呼ばれるのは,変形の結果として生じた地質構造から,変形の原因である応力を推定するからです.今回も多くの学生・若手研究者の皆様に受講していただきたいコースです.中堅・ベテラン研究者や学校教員,地質調査業従事者,広く一般の方も,ぜひふるってご参加ください.講師は,午前が応力逆解析法の理論に詳しい佐藤活志氏,午後が応力逆解析の露頭への適用を多く実践されている大坪 誠氏です.なお,本ショートコースではPCによる実習を含みます.本ショートコース午後の実習にはWindows OSをインストールしたPCが必要です.第7回を受講された方も再受講可能ですが,内容は第7回と同じですのでご留意ください.
内容:(各コース,講義・質疑応答含め3時間を予定)
<午前> 9:00-12:00
小断層や岩脈などによる応力逆解析法の基礎:佐藤活志(京都大学)
応力逆解析法のここ四半世紀ほどの発展について理論背景を含めて紹介します.テクトニクスの機構や駆動力を理解するには,地殻応力とその変遷史の解明を避けては通れません.また,地殻応力の評価は,理学的興味だけではなく,亀裂と流体移動の関係の解明や防災など応用地質的な価値も高いものです.構造地質学の分野では断層,岩脈,鉱物脈,方解石双晶など様々なスケールの地質構造を用いた応力逆解析法が開発されてきました.ここでは,それらの手法の開発の歴史についても紹介します.
<午後> 14:00-17:00
応力逆解析のための露頭観察法と解析実習:大坪 誠(産総研・地質調査総合センター)
応力逆解析のためのデータは,小断層,地震の発震機構解,岩脈や鉱物脈などの引張割れ目,方解石双晶などから得られます.ここではデータ取得方法や取得する際の注意点などを紹介します.さらに,各種応力逆解析法のソフトウエアを動かして,小断層や岩脈のデータを使って応力を推定することを実習します.実習では,データ入力方法,ソフトウエア動作方法,結果の表示,結果の読み取り方などを紹介します.実習にはWindows OSをインストールしたPCをご準備ください.
受講料(各1日券):
地質学会正会員(一般・シニア) 2,000円(日本地質学会賛助会員に所属する⽅は地質学会会員と同額です)
地質学会正会員(学生会員) 1,000円
⾮会員一般 5,000円
⾮会員学生 3,000円
(注)午前のみ,午後のみの受講の場合も,受講料の割引はありません.
(注)キャンセル料について:締切日まで 0%, 会期3日前まで 60%, 会期2日前以降 100%.いずれの場合も返金がある場合は,振込手数料を差し引いた額をカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2〜3ヶ月要する場合もありますので,ご了承下さい.
開催方法:WEB会議システムzoom(https://zoom.us/)によるオンライン講義
※受講申込締切後,受講者へzoomアクセスURL,事前資料をメールでお送りします.
申込方法:学会ジオストアよりお申し込みください(こちらから)
※受講料のお支払いは,受講申込時にPayPal〈ペイパル〉によるクレジット決済または銀行振込を選択いただけます.
(注)申込時にご提供いただいた個人情報は,日本地質学会プライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います.
その他:希望者には各コース毎のCPD受講証明書を発行します.午前・午後各3単位を予定.
※CPD受講証明書の発行については,受講日当日に受講者のかたへ別途ご案内いたします.
申込締切:2023年10月16日(月)
問い合わせ先:一般社団法人日本地質学会
メール: main [at] geosociety.jp 電話 03-5823-1150
(参考)過去のショートコース
(第1回,第2回)http://www.geosociety.jp/science/content0121.html
(第3回)http://www.geosociety.jp/science/content0130.html
(第4回)http://www.geosociety.jp/science/content0134.html
(第5回)http://www.geosociety.jp/science/content0137.html
(第6回)http://www.geosociety.jp/science/content0151.html
第4回JABEEシンポジウム
第4回JABEEオンラインシンポジウム
大学縮小危機のなかで、社会の要求にどのように応えるか
〜JABEEを活用した技術者の育成と輩出〜
YouTube公開中
開催報告はこちら(2024.4.3掲載)
日時:2024年3月3日(日)13:30〜17:20(予定)
開催方式:Zoomを用いたオンライン方式
学生減に伴う大学規模適正化という文科省の方針にしたがって、地球科学分野でもいろいろな大学で学科再編、地球科学の縮小が検討されている。一方で、異常気象による災害、地震や火山災害に対応する技術者やエネルギー・有用資源の確保に関わる技術者の必要性が叫ばれている。 地球科学系の大学では、そのような社会の要求に応えて技術者教育を行い、社会に輩出しなければならない。そのためには、大学教育において社会の要求を的確に把握する必要がある。あわせて、技術者教育に適した教育プログラムの構築、教育の質の向上、教育システムの継続的改善などが必要である。さらに、これらの教育システムが第三者機関からの審査を受け、適正であるとの評価を得ることも重要である。
JABEEはこれらを実践するための国際的な取り組みである。すなわち、JABEE制度を活用すれば、社会の要求を把握した質の高い教育の結果、社会の要求に適した技術者を社会に輩出することができる。
今回のシンポジウムでは、JABEE認定プログラムを有している大学・学科から、社会の要求を把握する手法について報告を受け、それをもとにした質の高い、そして技術者育成のための教育について説明を受ける。あわせて、専門業界の技術的あるいは人事的な面から、大学に求めるものを提言してもらう。
シンポジウム最後の総合討論では、上記講演を受けて、大学における社会の要求に応える教育について議論し、そのためにJABEEがどのような役割を果たしているかを考えたい。
JABEE認定プログラムを有している学科の教員、学生や実社会で活躍する地質技術者をはじめ、地球科学が縮小する懸念のある、あるいは専門就職者数を多くしたい学科の教員、学生にも多く参加いただきたい。
次第:(敬称略)
13:30〜13:40 開会挨拶 学会長 岡田 誠
趣旨説明 地質技術者教育委員会委員長 天野一男
連絡事項 地質技術者教育委員会副委員長 佐々木和彦(司会)
▷講演要旨(PDF)はこちらから 2024.1.30掲載
13:40〜14:05 講演1「社会の要求」をどう把握するか〜日本大学の例〜」講師 日本大学 文理学部地球科学科 教授 竹内真司
14:05〜14:30 講演2「教育成果の社会への還元について〜山口大学の例〜」講師 山口大学 理学部地球圏システム科学科 教授 坂口有人/講師 山口大学 名誉教授(元理事・副学長) 田中和広
14:30〜14:55 講演3「学科全体の教育の質の向上について〜島根大学の例〜」講師 島根大学 総合理工学部地球科学科 教授 林 広樹
14:55〜15:15 講演4「“未来のふつうを創る建設業”でJABEE修了生が実感すること」講師 日特建設株式会社 名古屋支店事業部営業部 課長補佐 藤代祥子
15:15〜15:25 休憩
15:25〜15:50 講演5「地球科学分野関連企業の専門技術者から大学教育に望むこと」講師 株式会社パスコ 中央事業部防災技術部 副部長 小俣雅志
15:50〜16:15 講演6「地質系業界の人事担当者が大学教育に望むことについて」講師 応用地質株式会社 事務本部人事企画部 グループリーダー 津野洋美
16:15〜17:15 総合討論 コーディネータ 天野一男
17:15〜17:20 閉会挨拶 天野一男
アンケートなどの連絡事項 佐々木和彦
参加締切:2024年2月26日(月)
申込方法:専用フォームよりお申し込みください.お申し込みはこちらから 参加申し込みは締め切りましました.
参加者:200名(先着順) 会員,非会員を問いません.無料です.
CPD:希望者にはCPD証明を発行します(最大3.66)※CPDプログラムID 3849
問い合わせ:一般社団法人 日本地質学会 事務局
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル6F
電話:03-5823-1150(代表) FAX:03-5823-1156
Eメール:main[at]geosociety.jp ※[at]を@マークにして送信してください.
設立趣意書
[若手活動運営委員会委員会規則(pdf)]
一般社団法人日本地質学会若手活動運営委員会設立趣意書
1. 委員会名称
一般社団法人日本地質学会若手活動運営委員会
(Management Committee of Early-Career Geologist Activities)
2. 若手活動運営委員会を必要とする理由
地質学の学術的発展および社会的振興において,学部生, 院生, ポスドク, 企業職員, 助教等のアーリーキャリア, いわゆる“若手”の活発な学術活動は,重要な要素の一つである.しかし,日本地質学会 (以下, 地質学会) では近年, “若手”会員が減少する状況にあり,地質学の発展・振興のためには, 若手人材の確保と活動の継続化を目指していく必要がある. そのためには, 若手会員同士の交流を促進すること,また,若手の意見が学会に届く環境を整備することなどにより, 学会活動に魅力を見出してもらうことが重要である.そこで,若手会員による主体的かつ継続的な活動を支援・推進するために,地質学会に若手活動運営委員会 (以下, 当委員会) を設置することを提案する. 地質学会に当委員会を設置することにより, 若手会員同士の分野横断的な討論と交流の場を提供できるだけでなく, 若手人材と学会活動の架け橋となることで, 地質学の学術的発展と社会的振興,ひいては学会活性化にも繋がると期待する.
3. 当委員会の活動予定期間
地質学会理事会で承認された日から, 当委員会または地質学会理事会が当委員会の活動の停止を決定した時点まで.
4.当委員会の主な事業および設置年度の経費予算案
(1) 当委員会は次に掲げる活動を行う.
ア 地質若手巡検・研究集会の開催
イ 地質学会学術大会やニュース誌等における若手活動に関する情報提供
ウ 学部学生・大学院生向けオンライン交流会の開催
エ ニュース誌院生コーナーの編集
オ 他学会の若手会または関連団体との情報交換
カ その他,若手人材の育成に資する活動
(2) 設置年度は, 当委員会設置の提案時点で上記(1)アの活動について経費を要求する予定である(下表参照). また, 当委員会の開催する企画について, 必要に応じ, 予算の追加申請や, 地質学会が契約する会議システムの利用申請を行う.
設置年度の若手巡検・研究集会予算(案)
省略
5. 代表者および予定される委員
代表者 神谷奈々
所属 京都大学
(住所等略)
予定される委員 (50音順)
神谷 奈々 (京都大学 一般会員)
菊川 照英 (千葉県立中央博物館 一般会員)
桑野 太輔 (千葉大学 一般会員)
佐久間杏樹 (海洋研究開発機構 一般会員)
佐々木聡史 (名古屋大学 一般会員)
志村 侑亮 (産業技術総合研究所 一般会員)
下岡 和也 (愛媛大学 学生会員)
鈴木 克明 (産業技術総合研究所 一般会員)
6. 当委員会規則案
別紙の通り.
以上
(2023年4月15日理事会承認)
第10回ショートコース
日本地質学会第10回ショートコース
第10回ショートコース:海底鉱物資源
(受講者の皆さまへ)受講料の入金確認が完了した方々へ,zoomアクセスURLをメールでご連絡いたしました(2/22,15:30頃)
申込締切
締切延長!!:2月19日(月)
申込締切:2024年2月16日(金)
申込方法
締め切りました
学会ジオストアからお申し込みください
日時:2024年2月25日(日)9:00〜12:00,14:00〜17:00
今回は,海底鉱物資源のショートコース(第10回)を行います.
内容:(各コース,講義・質疑応答含め3時間を予定)
<午前> 9:00-12:00
海底鉱物資源概論:その研究と開発の過去、現在、未来 講師:中村謙太郎(東京大学)
人類が直面する地球規模の環境問題を克服し,持続可能な社会を築いていくための重要な鍵の一つが,レアメタルと呼ばれる一群の金属資源です.海底鉱物資源は,このレアメタルの供給源として期待されている資源であり,その開発に向けた動きが世界的に注目されています.本ショートコースでは,この海底鉱物資源の研究と開発の歴史を紹介するとともに,開発に向けた現状と将来展望・課題について解説します.
<午後> 14:00-17:00
海底鉱物資源の探査と成因研究の最前線 講師:町田嗣樹(千葉工業大学)
海底鉱物資源を探し分布の様子を明らかにすることは,資源を開発するためのみならず,それらが何故そこにあり,どの様にして生まれたのかという成因を明らかにするうえで必要不可欠です.近年,資源開発の観点からは,より低コストの探査手法の開発が求められており,可能な限り広範囲を対象とし,そこから効率よく資源そのものを見つける,もしくは有望海域を絞り込むための技術開発が盛んに行われています.一方,資源成因論は,それぞれの資源が記録する地質情報を如何に高い時空間分解能で引き出すか,もしくは,複数の資源の地質学的な関連性に着目してそこから個々の資源の成因を制約するといった,最新の分析技術と多角的な視点を駆使した研究が展開されています.前半の資源概説を踏まえて,探査手法と成因に関する研究の最前線をご紹介します.
受講料(各1日券):
地質学会正会員(一般・シニア) 2,000円(日本地質学会賛助会員に所属する⽅は地質学会会員と同額です)
地質学会正会員(学生会員) 1,000円
⾮会員一般 5,000円
⾮会員学生 3,000円
(注)午前のみ,午後のみの受講の場合も,受講料の割引はありません.
(注)キャンセル料について:締切日まで 0%, 会期3日前まで 60%, 会期2日前以降 100%.いずれの場合も返金がある場合は,振込手数料を差し引いた額をカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2〜3ヶ月要する場合もありますので,ご了承下さい.
開催方法:WEB会議システムzoom(https://zoom.us/)によるオンライン講義
※受講申込締切後,受講者へzoomアクセスURL,事前資料をメールでお送りします.
申込方法:学会ジオストアからお申し込みください締め切りました
※受講料のお支払いは,受講申込時にPayPal〈ペイパル〉によるクレジット決済または銀行振込を選択いただけます.
(注)申込時にご提供いただいた個人情報は,日本地質学会プライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います.
申込締切:2024年2月16日(金)
支払方法:クレジット決済 or お申し込み後,下記いずれかへお振り込みをお願いいたします.(振込期日:2月19日(月))
三井住友銀行 神田駅前支店(普通)1711424(社)日本地質学会 / シヤ)ニホンチシツガツカイ
ゆうちょ銀行 〇一九(ゼロイチキュウ)店 当座 0028067 一般社団法人日本地質学会 シヤ)ニホンチシツガツカイ
郵便振替 00140-8-28067 一般社団法人日本地質学会
※銀行振り込みの場合,振込用紙はお送りしません.直接お振込をお願いいたします.
※今回はクレジットカード決済はご利用いただけません.
※2/19までに入金の確認が取れない場合,アクセスURLをお知らせできません.ご注意ください.
※システムが修復しました.クレジットカード決済もご利用いただけます.1/18,11:00現在
その他:希望者には各コース毎のCPD受講証明書を発行します.午前・午後各3単位を予定.当日ご希望をお伺いします.
問い合わせ先:一般社団法人日本地質学会
メール: main [at] geosociety.jp 電話 03-5823-1150
※[at]を@マークにして送信して下さい.
第5回JABEEオンラインシンポジウム
第5回JABEEオンラインシンポジウム
高等学校での地学教育と大学での専門教育との連携
〜地球科学の中等教育から高等教育にどのように繋げるか〜
シンポジウムの動画はYouTubeで公開しています。
こちらから
[zoom参加者へのおもな注意事項]
・アカウント名は個人識別のためフルネームで表示してください。
・マイクはミュートに、ビデオはOFFにしてください。
・質問は「全員」宛のチャットへ随時お寄せください。
・講演内容の撮影・録画・録音は禁止です。スクリーンショットとして画像保存もしないでください。
日時:2025年3月2日(日)13:30〜17:20(予定)
開催方式:Zoomを用いたオンライン方式
日本地質学会地質技術者教育委員会が毎年3月に開催していますJABEEオンラインシンポジウムについてお知らせします。 今回は、地学教育委員会との共催で「高等学校での地学教育と大学での専門教育との連携」をテーマに開催します。 高等学校・大学の教員をはじめ、実社会の専門技術者など、多方面のお立場の講師から、いわゆる「高大連携」「高大接続」についてご講演いただきます。皆さま、是非、ご参加・ご視聴くださいますようお願いいたします。
主催:日本地質学会地質技術者教育委員会
共催:日本地質学会地学教育委員会
プログラム:(敬称略)
(司会:地質技術者教育委員会委員 藤代祥子(日特建設㈱ ))
13:30〜13:35 開会挨拶 学会長 山路 敦(京都大学名誉教授)
13:35〜13:40 趣旨説明 地質技術者教育委員会委員長 竹内真司(日本大学教授)
13:40〜14:00 講演1 「高等学校における地学教育の実態:全国の地学の履修状況」 講師:高木秀雄 早稲田大学教授
14:00〜14:20 講演2 「神奈川県・東京都・千葉県の公立高等学校における地学教育の格差」講師:藤原靖(地学教育委員会委員、神奈川県立相模原弥栄高等学校教諭)
14:20〜14:40 講演3 「ジオパークを軸とした探究的な自然科学・防災リテラシー教育」講師:今井康浩 (高知県立室戸高等学校 校長)
14:40〜15:00 講演4 「高等教育におけるいわゆる『高大接続』の実態〜高等学校での模擬授業〜」講師:立石 良 (地質技術者教育委員会委員 富山大学准教授)
15:00〜15:20 講演5 「高等教育におけるいわゆる『高大接続』の実態〜大学入試における地学受験制度と地学教育 促進への取組み〜」 講師:堀 利栄(愛媛大学教授)
15:20〜15:30 休憩
15:30〜15:50 講演6 「島根大学における高大連携の試み」 講師:向吉秀樹(島根大学准教授)
15:50〜16:00 講演7 「地球科学の仕事あります!」全国の高校にポスター配布 講師:坂口有人(地質技術者教育委員会委員、山口大学教授)
16:00〜16:20 講演8 「いわゆる『高大接続』における地学教育への産業界からの期待」 講師:向山 栄(国際航業株)
16:20〜17:10 総合討論 「地質学会として『高大接続』にどのように取り組むか」 座長:坂口有人(地質技術者教育委員会委員、山口大学教授)パネリスト:講師全員
17:00〜17:15 閉会挨拶 副会長 杉田律子(科学警察研究所)
17:15〜17:20 司会:地質技術者教育委員会委員 藤代祥子(日特建設㈱ ) アンケート、CPD付与、当委員会企画の紹介など
<<講演概要はこちら(PDF)>>
参加申込締切:2025年2月25日(火)
申込方法:専用フォームよりお申し込みください.お申し込みはこちらから ※当日視聴用のZoomのURLは2月27日(木)頃、 お申し込みのメールアドレスに送信します。
参加者:200名(先着順) 会員,非会員を問いません.無料です.
CPD:希望者にはCPD証明を発行します(最大3.33)(プログラムID:4217)
問い合わせ:一般社団法人 日本地質学会 事務局
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル6F
電話:03-5823-1150(代表) FAX:03-5823-1156
Eメール:main[at]geosociety.jp ※[at]を@マークにして送信してください.
若手巡検2024 in 愛知県-岐阜県
若手巡検 in愛知県-岐阜県
運営:日本地質学会若手活動運営委員会
講師:高橋 聡准教授(名古屋大学)
世話人:佐々木聡史(群馬大学)
日時:2024年10月26日(土) 9時集合 18時半解散
対象者:35歳以下の日本地質学会正会員※非会員の申込みは事前に地質学会への入会届の提出(今回,入会された方も含みます)
参加費: 正会員(学生会員):3,250円 正会員(一般会員):6,500円
※内訳はバス代・保険代となります.
※昼食は参加者の自己負担となります.
※正会員(学生会員)の参加費は,日本地質学会若手育成事業より半額が補助されています.
主な見学地:
〇桃太郎神社セクション 下部三畳系 珪質粘土岩層
〇鵜沼 セクション 中部三畳系チャート層
〇坂祝 セクション 上部三畳系 〜下部ジュラ系 チャート層
※一部地域ではヘルメットを着用し歩きます!
集合場所:名古屋駅
申込方法:地質学会HP「ジオストア」よりお申し込みください
申込締切:2024年9月27日(金) 17:00
※定員に達しましたので、締め切りました(9/27、AM11:00)。
※最少催行人数20名・定員28名 ※先着順とし,定員になり次第,締め切ります
※巡検の開催決定の連絡は10月10日までにご連絡します
※必要物・日程は参加者が決定次第お送りいたします
※集合場所までの往復飛行機・公共交通機関につきましては自己責任でよろしくお願いいたします.(時間に余裕のある便でご参加をお願いいたします)
問い合わせ先:
日本地質学会若手活動運営委員会:(eco.core[at]gmail.com)
第11回ショートコース
日本地質学会第11回ショートコース
第11回ショートコース:微化石
【お知らせ】
林先生の講義は7/28(日)午前9:00から開講いたします。:受講者の方にzoomアクセスURL等詳細情報をメールにてお知らせいたしました。(2024.7.23)
午後の回の休講について:7/21午後14:00-17:00「微化石データ活用の最前線」 講師:林 広樹(島根大学) は都合により休講といたします。なお現在、別日程にて開催を調整中です。詳細が決まりましたら、改めてご案内いたします。誠に申し訳ありませんが、何卒ご了承ください。7/21は,午前の回のみ開講いたします。受講者の方にzoomアクセスURL等詳細情報をメールにてお知らせいたしました。(2024.7.17)
申込締切:2024年7月12日(金)
申込方法:学会ジオストアからお申し込みください
日時:2024年7月21日(日)9:00〜12:00,14:00〜17:00
今回は,「微化石」のショートコース(第11回)を行います.
内容:(各コース,講義・質疑応答含め3時間を予定)
<午前> 9:00-12:00
「微化石一般と放散虫」 講師:松岡 篤(新潟大学)
微化石とは,顕微鏡で観察するサイズの化石のことです.特定の分類群をさす用語ではなく,サイズで区分した化石といえます.放散虫,有孔虫,珪藻,円石藻などのような単細胞生物の殻や骨格が主要な微化石ですが,貝形虫のような多細胞生物の硬組織の場合もあります.植物の花粉や胞子は有機質微化石とよばれます.堆積物からは,同じ処理法で多様な微化石が得られることも普通にあります.
このショートコースでは,微化石を得るための一般的な処理方法から観察方法について説明します.また,放散虫をとりあげ,どのような研究があるのかを実例をあげて解説します.さらに,教育普及ツールとして開発した放散虫トランプを使った実習を行います.なお,実習ではファイルを共有することなどによりトランプを適宜示します.放散虫トランプはネット販売されているので入手可能ですが,受講に際して必携ではありません.
<午後> 14:00-17:00
「微化石データ活用の最前線」 講師:林 広樹(島根大学)
微化石は地層中から大量かつ連続的に得られ,また世界的に広く分布する種が多いことから,古くから「示準化石」や「示相化石」として使われてきました.近年,放射年代測定の高精度化や,天文軌道要素校正の導入により,数百万年前程度の地質時代についても数万年未満の精度で年代決定ができるようになってきました.そうした新技術が,微化石による年代決定にも新たな視点をもたらしています.また,全世界の海洋底に堆積している微化石群集についてデータベース化が進められており,それと現在の海洋データを紐づけることにより,過去の水温や塩分といった環境復元を高精度で行えるようになってきています.このショートコースでは,後期新生代の浮遊性有孔虫を例としてとりあげ,微化石の応用的な側面,特に年代決定と環境復元について最新動向を解説します.
受講料(各1日券):
地質学会正会員(一般・シニア) 2,000円(日本地質学会賛助会員に所属する⽅は地質学会会員と同額です)
地質学会正会員(学生会員) 1,000円
⾮会員一般 5,000円
⾮会員学生 3,000円
(注)午前のみ,午後のみの受講の場合も,受講料の割引はありません.
(注)キャンセル料について:締切日まで 0%, 会期3日前まで 60%, 会期2日前以降 100%.いずれの場合も返金がある場合は,振込手数料を差し引いた額をカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2〜3ヶ月要する場合もありますので,ご了承下さい.
開催方法:WEB会議システムzoom(https://zoom.us/)によるオンライン講義
※受講申込締切後,受講者へzoomアクセスURL,事前資料をメールでお送りします.
申込方法:学会ジオストアからお申し込みください
※受講料のお支払いは,受講申込時にPayPal〈ペイパル〉によるクレジット決済または銀行振込を選択いただけます.
(注)申込時にご提供いただいた個人情報は,日本地質学会プライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います.
申込締切:2024年7月12日(金)
支払方法:クレジット決済 or お申し込み後,下記いずれかへお振り込みをお願いいたします.(振込期日:7月16日(火))
三井住友銀行 神田駅前支店(普通)1711424(社)日本地質学会 / シヤ)ニホンチシツガツカイ
ゆうちょ銀行 〇一九(ゼロイチキュウ)店 当座 0028067 一般社団法人日本地質学会 シヤ)ニホンチシツガツカイ
郵便振替 00140-8-28067 一般社団法人日本地質学会
※銀行振り込みの場合,振込用紙はお送りしません.直接お振込をお願いいたします.
※7/16までに入金の確認が取れない場合,アクセスURLをお知らせできません.ご注意ください.
その他:希望者には各コース毎のCPD受講証明書を発行します.午前・午後各3単位を予定.当日ご希望をお伺いします.
問い合わせ先:一般社団法人日本地質学会
メール: main [at] geosociety.jp 電話 03-5823-1150
※[at]を@マークにして送信して下さい.
50年会員顕彰
永年会員顕彰者 1973年度入会者,2023年度会費まで納入済(計40名)
天野一男
井内美郎
打江 進
加戸敬亮
加藤眞人
鹿野和彦
栗原俊己
黒田登美雄
嶋崎統五
清水岩夫
菅谷政司
田切美智雄
竹内 章
田中俊廣
佃 栄吉
成田 賢
西山忠男
廣井美邦
宮坂省吾
宮崎精介
米澤正弘
(以下お写真の掲載省略)
相田喜久夫・岡市正秀・小田康則・角和善隆・我謝昌一・酒井 彰・坂本正夫・坂本 満・宍戸俊夫・下平眞樹・中川重紀・中原伸幸・長峰 智・中山 健・深沢徳明・堀江一教・三宅康幸・宮田雄一郎・渡辺拓美(敬称略)
---------------------------------------------------------------------------------
(お寄せいただいたコメントをご紹介します)
入会してから早50年.学会でいろいろと勉強させていただいた上に,表彰してくださるとお聞きして,心温まる思いです.(宮粼精介)
この度は永年会員顕彰のお知らせを頂き,ありがとうございました.地質学に関わるようになって,もう50年もたつのかという思いと,この50年で何をやってきたのだろうという思いとが錯綜しております.顕彰を受けるに値するようなことは何もしておらず,心苦しい思いもありますが,己の人生を考える一つの節目ととらえたいと思います.(田中俊廣)
すでに実業界(土木地質)から引退した身ですが,大変恐縮しております.(栗原俊己)
この度の顕彰ありがとうございます.本学会のますますの発展に期待いたします.(井内美郎)
9月学術大会(山形)のご盛況と日本地質学会のますますの発展を祈ります.(黒田登美雄)
在会年数のみで何のお役にも立っておりませんのに,「永年会員顕彰」たいへん恐縮に存じます.研究環境の劣化は本当に厳しい状況ですが,「初志」を大切に頑張って下さい.日本地質学会の更なる進化・発展を心よりお祈り申し上げます.(菅谷政司)
この度は思いがけずにも2024年度永年(50年)会員表彰のお知らせを頂き,驚きました.これまでにほとんど貴学会での活動をしていないにも拘らず,この様な表彰の機会を頂き感謝しております.最近では天北西方沖試掘井の花粉・胞子化石調査(2021〜2022年)に携わりましたが,これが私の人生最後の地質調査となりました.(嶋粼統五)
顕彰のお知らせを頂き,心から感謝しております.私にとっての50年間はとても短いものという感じですが,この機会にじっくり思い返す所存です.貴会の益々の御発展を祈念致します.(成田賢)
元気でやっています.皆様によろしく.(酒井彰)
退職後高校地学クラブの顧問を続けています.(岡市正秀)
ご連絡ありがとうございます.学術大会に参加できず申し訳ございません.現在も細々と近教育に携わらせていただいております.地質学会のますますのご発展を祈念をいたします.(宍戸俊夫)
地学教育の重要性が増しています.「地学基礎」の高校必修化に向けて,地質学会の支援を強く要望します.(中原伸幸)
この度は永年顕彰を頂戴し誠に光栄に思います.地質学と学会の益々の発展を祈念しております.(加藤眞人)
自然との対話を重ね,あっという間の50年でした.これからも地域に根ざし地質を楽しみたいと思います.地質学会のますますの発展をおいのりします.(我謝昌一)
永年会員として顕彰いただけるとのこと,ありがとうございます.(下平眞樹)
熊本大会開催通知
日本地質学会第132年学術大会(2025熊本大会)
熊本大学黒髪キャンパス(熊本市中央区)にて
2025年9月14日(日)〜9月16日(火)に開催
日本地質学会は,熊本市中央区の熊本大学黒髪キャンパスにおいて,第132年学術大会(2025年熊本大会)を9月14日(日)から16日(火)に開催します.また,巡検(見学旅行)を12日(金)〜13日(土)と17日(水)〜18日(木)に催行します.熊本大学での開催は1992年以来33年ぶりになります.33年前に開催された際には,私は一講演者として参加しましたが,当時の熊本大学の地学関係の皆さんが精力的に動き,とても活気溢れる大会であったことを記憶しております.その後,熊本大学は2016年の熊本地震,2020年からのコロナ禍を経験しましたが,ようやくかつてのように賑やかで活発な学究活動を展開できるようになりました.
現在,熊本大学の地質学会関係者は少ないため,今回の大会ではなるべく無理のない実施内容にするようにしております.そのため,トピックセッションの充実など,広く会員の皆様にご協力をお願いする次第です.LOCとしましてはできる限りのことを行い,参加者の皆様が満足のいく充実した大会にしたいと考えております.また巡検は,LOC以外の方々にもご協力いただき9コースを準備しております.層序,化石,変成岩,深成岩,火山,震災遺構,博物館,ジオパークといったいろいろ魅力的な巡検コースを提供できるものと思います.また熊本城近くの熊本城ホールでは,例年通りに地質情報展が開催されます.同ホールでは,近年,熊本をはじめ周辺地域で新たに発見されている恐竜に焦点をあて,子供から大人まで楽しめる市民講演会も企画しております.
宿泊施設はある程度の数はありますが,学術大会は連休にかかりますし,海外からの旅行者の方々や半導体関連企業の熊本進出に伴う出張者の増加などで,宿が取りにくい場合もございます.ある程度早めに宿の予約をされると良いかと思います.
会場となる熊本大学黒髪キャンパスは,熊本市街中心部の通町筋から北東約2.5kmに位置しており,徒歩では35分程度で着きます.黒髪キャンパスは旧第五高等中学校(北キャンパス)と旧熊本高等工業学校(南キャンパス)の敷地からなり,主な会場となる北キャンパスには,緑豊かな構内に国指定重要文化財「五高記念館」・「化学実験場」やかつて教鞭を執った夏目漱石とラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の碑や銅像がございます.会場は正門(国指定重要文化財「赤門」)を入って,これらの歴史的文化財の中を300mほど入ったところになります.また表彰式会場である工学部百周年記念館のある南キャンパスにも,レンガ造りの国指定重要文化財「工学部研究資料館(機械実験工場)」や登録有形文化財「本部(旧熊本高等工業学校本館)」があります.さらに両キャンパスは「黒髪町遺跡」として知られ,縄文時代早期から奈良・平安時代の土器などが出土しています.会期中の合間を縫って構内を散策されるのもお勧めです.
熊本大学黒髪キャンパスへは,熊本駅(25分,運賃350円),桜町バスターミナル(15分,運賃250円)ならびに通町筋(10分,運賃220円)から,熊本大学前に停まる路線バスが1時間に4〜8便程度運行されています.宿泊施設は桜町バスターミナルから通町筋までの中心商業地区に多数あり,熊本駅や水前寺公園周辺にもございます.
熊本城を中心に発展を遂げてきた熊本は,歴史と現代が融合した街になります.また東には阿蘇の山々が,西には有明海から天草諸島が広がり,豊かな自然と海の幸・山の幸に恵まれています.大会と共に,熊本を堪能していただければと思います.大会実行委員会一同,多くの皆様のご参加を心からお待ちしております.
2025年1月
日本地質学会第132年学術大会(熊本大会)
実行委員会委員長 松田博貴
セッションについて・トピック提案募集
セッションについて/トピック提案募集
※トピックセッション提案募集はこちらから
※大会までのスケジュールはこちらから
採択されたトピックセッション(タイトル・代表世話人)
T1.変成岩とテクトニクス(北野一平)
T2.マグマソース・マグマ供給系から火山体形成・熱水変質まで(齊藤 哲)
T3.文化地質学(森野善広)
T4.岩石・鉱物の変形と反応(向吉秀樹)
T5.沈み込み帯・陸上付加体(橋本善孝)
T6.中琉球の新たな地体構造単元:徳之島帯の特徴と研究課題(山本啓司)
T7.堆積地質学の最新研究(松本 弾)
T8.原子力と地質科学(竹内真司)
T9.大地と人間活動を楽しみながら学ぶジオパーク(松原典孝)
T10.テクトニクス(中嶋 徹)
T11.都市地質学:自然と社会の融合領域(中澤 努)
T12.地球史(桑野太輔)
T13.地域地質・層序学:経過と集大成(辻野 匠)
T14.九州の火山テクトニクス(辻 智大)
T15.海域火山と漂流軽石(石毛康介)
トピックセッション提案募集 締切:2025年3月21日(金)
申し込みはこちらから
【重要】学術大会セッションについて
2025年1月
日本地質学会行事委員長
高嶋礼詩
2022年の東京・早稲田大会から,セッションを「トピックセッション」,「ジェネラルセッション」,「アウトリーチセッション」の3カテゴリに変更され,従来のレギュラーセッションは発展的に解消されました.熊本大会でも,上記3つのセッションで構成いたします.セッション区分の改訂から3年が経ち,多くの方が新たなセッション区分に慣れてきたと思います.各セッションに対する新鮮さを持続させるためにも,各トピックセッションを企画していただく方々には,各分野・トピックの国内外での動向や進展,今後の展望などもご考慮の上,積極的に提案していただき,学術大会をより盛り上げていただきたいと思います.
トピックセッション(Topical Session)
会員提案型セッションです.提案者(=世話人)は最大3名とし,研究キャリアや所属階層,ジェンダー,国籍などのダイバーシティを意識した提案者構成を強く勧めます.セッション提案書には,専門部会・委員会・支部・LOC等の提案母体の有無,他学会等の共催希望の有無(有の場合はその理由),招待講演案,過去開催実績,想定発表(演題)数,特集号計画の有無などを示していただきます.提案されたセッションは執行理事会学術研究部会を中心とする選考員によってレビューされ,提案内容や過去実績などを参考に選考されます.選考では地質学雑誌またはIsland Arc誌への特集号計画の有無も重視されます.類似するセッションが複数提案された場合は,学術研究部会がセッション統合を勧める可能性があります(その場合,招待講演は残りますが世話人は3名に調整していただきます).なお,口頭発表の演題登録数が5件に達しなかったセッションは後述のジェネラルセッションに統合します(その場合でも招待講演は残ります).従来のレギュラーセッションで実施されていたような伝統的・一般的な分野区分・名称(層序学,地域地質,構造地質など)での提案も歓迎しますが,提案書には各分野における近年の研究の動向や注目すべき進展などを記述いただければと思います.
ジェネラルセッション(General Session)
従来のレギュラーセッションの枠組みを発展的に解消し,新たに一つのジェネラルセッションを設定します.本セッションはどのトピックセッションにも適合しない研究や多くの分野(disciplines)にまたがる研究などの発表の場になります.トピックセッションが上位,ジェネラルセッションが下位という関係ではありませんのでご注意ください.本セッションへの演題登録者には,関連する分野(例えば○○地質,△△地質など,専門部会名に類する分野を10程度想定)を3つ程度選んでいただき,関連性の順位を記入していただく予定です(任意).行事委員会がその順位を考慮して演題をグルーピングし,最大10程度のサブセッションにまとめて配列する予定です.本セッションの世話人は行事委員を基本としますが,口頭発表の演題登録数が5件に達しなかった(そのためジェネラルセッションに統合された)トピックセッションの提案者も世話人になっていただくことがあります.
トピックセッション提案募集 締切:2025年3月21日(金)
申し込みはこちらから(https://forms.gle/5upA21HW8HTTtid8A)
日本地質学会行事委員会
第132年(2025年)学術大会を本年9月14日(日)〜16日(火)に熊本大学で開催する予定です.前述の記事(【重要】学術大会セッションの変更について)でもお伝えしたように,2022年大会からセッションは「トピックセッション(会員提案型)」,「ジェネラルセッション」,「アウトリーチセッション」の3カテゴリになりました.ここではトピックセッション提案を下記の要領で募集します.
1.トピックセッション概要
広く地質学に関係し,これから新分野になる可能性を秘めたセッション,多くの注目を集めると期待できるセッション,伝統的だが多くの会員に関係するセッションの提案を募集します.魅力あるセッションを積極的にご提案ください.形式は口頭発表およびポスター発表とし,口頭発表は15分間で進行も15分刻みです.セッション世話人は最大3名とし,研究キャリアや所属階層,ジェンダー,国籍などのダイバーシティを意識した世話人構成を強く勧めます.締切後,執行理事会学術研究部会が中心になって提案内容を慎重に検討の上,選考します.なお,選考では地質学雑誌またはIsland Arc誌での特集号計画の有無も重視されます.
2.招待講演
招待講演は1セッションにつき最大2名とし,会員・非会員を問いません.世話人が「自分を招待する」ことは認めません.
発表時間(質疑応答を含む)は世話人が15分または30分のいずれかを選択できます.なお,1人の発表者(招待講演者を含む)が1つのセッションで口頭発表できるのは1件です.
招待講演者の選定理由(「業績が多い」という理由だけでなく,招待講演者の研究内容がセッション趣旨とどのように関係するのか等の記載もお願いします)とその裏付けとなる情報(セッションテーマに関連した代表的な論文・著書等)が必要です.
非会員の招待講演者は大会参加登録費,発表負担金とも無料です.会員の場合は大会参加登録費がかかりますが,招待講演は発表負担金の対象にはなりません.なお,大会参加登録費と発表負担金は改定が検討されており,詳細については大会予告記事(ニュース誌4月号予定)でお知らせします.
3.提案方法
提案する会員は,専用webフォーム(https://forms.gle/5upA21HW8HTTtid8A)からお申し込みいただくか,次の項目の内容を日本地質学会行事委員会宛(main[at]geosociety.jp)にe-mailでお送りください.
代表世話人(=連絡責任者,会員に限る)の氏名(和・英),所属(和・英),メールアドレス,緊急時の電話番号
セッションタイトル(和・英)
共同世話人(最大2名)の氏名(和・英),所属(和・英),メールアドレス
趣旨・概要(400〜600字程度)提案する分野・テーマに関する国内外における研究の動向と進展,学術的あるいは産業,社会的な重要性,今後の展望など.
過去のセッション開催有無,有の場合は直近大会時の口頭発表数
招待講演の有無 有の場合:6-1)招待講演者の氏名(和・英),所属(和・英),会員/非会員の別 6-2)招待講演の発表希望時間(15分または30分) 6-3)招待講演者の選定理由(100〜200字) 6-4)選定理由の裏付けとなる,セッションテーマに関連した代表的な論文・著書等
専門部会・委員会・支部・大会実行委員会(LOC)等の提案母体の有無(事前に母体の承諾を得てください)
他学協会等との共催希望の有無,有の場合は名称と共催希望理由(事前に共催承諾を得てください) ※共催学協会会員は地質学会会員と同じ参加登録費で大会に参加できます.ただし当該セッションでのみ発表可.
想定される,または直接呼びかける予定の口頭発表の数
地質学雑誌またはIsland Arc誌への特集号計画の有無(特集号計画を強く勧めます)
1ダイバーシティ認定ロゴ(EDI)付与希望の有無→詳しくは,「学術大会におけるダイバーシティ認定ロゴ導入の取り組み」
その他(英語使用等)
4.採択前後の注意点
類似するセッションが複数提案された場合は,執行理事会学術研究部会がセッション統合を勧めることがあります.その場合,招待講演は残りますが世話人は3名に調整していただきます.採択されたトピックセッションはニュース誌4月号または5月号(4月末または5月末発行予定)で公表し,発表募集を行います.演題登録(発表申込と要旨投稿)締切は7月上旬を予定しています.なお,口頭発表の演題登録数が5件に達しなかったセッションはジェネラルセッションに統合し(その場合,招待講演もジェネラルセッションになります),代表世話人にはジェネラルセッションの世話人の一人になっていただくことがあります.
5.世話人が行う作業(7月初旬〜中旬)
代表世話人には,講演要旨校閲や講演順番決定などの作業を7月初旬までに行っていただきます(詳細は採択後にお知らせします).その期間,代表世話人は電子メールで添付ファイルを送受信できるようにして下さい.野外調査や乗船等で通信が制限される場合は,共同世話人(代理)にあらかじめ作業を依頼し,その旨を行事委員会に必ず報告してください.
ご不明の点があれば行事委員会(main[at]geosociety.jp)までお気軽にお問い合わせください.
大会までのスケジュール(予定)
3月21日(金):トピックセッション提案募集締切
5月末(ニュース誌5月号):大会予告記事(演題登録・講演要旨受付開始)
7月9日(水):演題登録・講演要旨受付締切/ランチョン・夜間小集会申込締切
8月頭:大会プログラム公開(予定)
8月12日(火):巡検参加申込締切
9月1日(月):大会参加登録締切
9月14日(日)〜16日(火)学術大会
50年会員顕彰_2025熊本
50年会員顕彰者 1974年度入会者,2024年度会費まで納入済(計42名,敬称略)
会田信行・浅川行雄・足立勝治・足立久男・大久保 進・大塚富男・岡本正也・加藤芳郎・鎌田耕太郎・川原和博・鴈沢好博・木村 学・熊田政弘・公文富士夫・境垣内隆雄・坂本 治・嵯峨山 積・佐藤悦郎・佐野弘好・鈴木 哲・高須 晃・谷岡誠一・谷口純造・檀原 徹・鳥居 孝・長井孝一・中村盛之・中村由克・西ケ谷 修・野村律夫・濱田 治・原山 智・藤井光男・藤崎克博・藤本勝彦・古野邦雄・保科 裕・前田仁一郎・益子 保・松本仁美・山崎孝成・吉水一郎(以上42 名,敬称略)
会田信行
足立久男
大久保 進
大塚富男
加藤芳郎
川原和博
公文富士夫
佐藤悦郎
鈴木 哲
檀原 徹
野村律夫
濱田 治
藤井光男
藤崎克博
藤本勝彦
保科 裕
前田仁一郎
益子 保
松本仁美
※お写真をお送りいただい方のみ掲載させていただきました.
---------------------------------------------------------------------------------
(お寄せいただいたコメントをご紹介します)
下仁田自然学校に所属して,跡倉ナップを追求しています.これからもよろしくお願いいたします.(保科 裕)
小学校教員でしたので研究生活とは無縁でした.しかし,本会に在籍させていただいたお蔭で,地球科学に興味を持ち続けられたと思います.感謝しています.(松本仁美)
「永年会員顕彰」のご案内ありがとうございます.学術会議法案が国会を通過し、学問の自由が脅かされる今日ですが,日本地質学会の益々の発展を祈願します.(足立久男)
地質学会会員50年、顕彰ありがとうございます.地質コンサルタント会社に就職しより多くの知識習得を目指して学会に加入しましたが,得ることばかりで寄与は少なく恐縮しております.これからも若手技術者の育成に尽力して参りたいと思っています.(加藤芳郎)
50年会員の顕彰ありがとうございます.地質学会の一層の発展を願います.(鴈澤好博)
元気に晴耕雨読の生活を楽しんでおります.(公文富士夫)
永年会員の顕彰,有り難うございます. (前田仁一郎)
最近は下仁田ジオパークのお手伝いをしています.(大久保 進)
ありがとうございます.現在,芝浦工業大 学柏高等学校で講師をさせていただいています.微力ではありますが,地質学の普及そして地学教育に貢献させていただいています.(藤本勝彦)
これからも微力ながら頑張りたいと思います.(会田信行)
若手巡検2025 in 長瀞・皆野地域
若手巡検 in 長瀞・皆野地域
運営:日本地質学会若手活動運営委員会
講師:永冶方敬 准教授(早稲田大学),田口知樹 准教授(早稲田大学)
世話人:郄橋瑞季(島根大学),谷元瞭太(茨城大学),柴田翔平(新潟大学),都丸大河(東北大学),下岡和也(関西学院大学),佐々木聡史(群馬大学)
日時:2025年10月18日(土)
集合:8時15分(大宮駅) 解散:18時30分(熊谷駅)
対象者:35歳以下の日本地質学会正会員※非会員の申込みは事前に地質学会への入会届の提出(今回,入会された方も含みます)
参加費: 正会員(学生会員):4,300円,正会員(一般会員):8,600円
※内訳はバス代・保険代となります.
※昼食は参加者の自己負担となります.
※正会員(学生会員)の参加費は,日本地質学会若手育成事業より半額が補助されています.
主な見学地:埼玉県 長瀞・皆野地域
景勝地を眺めながら,それらをかたちづくる変成・変形岩をじっくり観察します.
特に,雁行脈・岩畳・虎岩などの代表的な露頭を巡り,関東以西を貫く三波川変成帯の変成作用・変形活動の一端を学びます.
※一部地域ではヘルメットを着用し歩きます!
集合場所:大宮駅
申込方法:地質学会HP「ジオストア」よりお申し込みください
申込締切:2025年10月3日(金) 15:00 ※締切ました。
※最少催行人数20名・定員26名 ※先着順とし,定員になり次第,締め切ります
※巡検の開催決定の連絡は10月3日までにご連絡します
※必要物・日程は参加者が決定次第お送りいたします
※集合場所までの往復飛行機・公共交通機関につきましては自己責任でよろしくお願いいたします.(時間に余裕のある旅程でのご参加をお願いいたします)
問い合わせ先:
日本地質学会若手活動運営委員会:(ecg.core[at]gmail.com)
出版物
出版物在庫案内
出版物在庫案内
※地質学論集,講演要旨(一部閲覧不可)の検索閲覧はCiNiiからできます
※地質学雑誌・講演要旨(一部閲覧不可)の検索閲覧は、J-STAGE からもできます
ご希望の方は本会事務局宛お申込みください.なお,送料の明記のないものは実費を頂戴いたしますので,お問い合わせください.(非会員の方も購入可能です.価格は下記会員頒価とは異なります)
現金書留または郵便振替 00140−8−28067
No. 38以前の論集 : 院生割引申請者・学生は4割引,正会員は2割引
No. 40以降の論集 : 院生割引申請者・学生のみ2割引
※在庫の無いものは、複写サービスをご利用いただけます。 →文献コピーサービス
地質学論集
*No.40以前も一部残部あります
会員頒価
第 40 号 中央構造線のネオテクトニクス—その意義と問題点—
3,200円
第 41 号 中部九州後期新生代の地溝.
3,100円
第 42 号 西南日本の地殻形成と改変.
3,100円
第 43 号 浅部マグマ溜りとその周辺現象の地球科学.
2,000円
第 44 号 島弧火山岩の時空変遷.
2,800円
第 46 号 火山活動のモデル化.
1,900円
第 45 号 シーケンス層序学ー新しい地層観を目指して※売り切れ
第 47 号 日高地殻—マントル系のマグマ活動.
3,000円
第 48 号 Cretaceous Environmental Change in East and South Asia (IGCP350) Contributions from Japan—
2,100円
第 49 号 21世紀を担う地質学.
2,500円
第 50 号 構造地質 特別号—21世紀の構造地質学にむけて—※売り切れ
2,500円
第 51 号 地震と地盤災害—1995年兵庫県南部地震の教訓—.
3,000円
第 52 号 オフィオライトと付加体テクトニクス.
3,000円
第 53 号 本州弧下部地殻と珪長質マグマの生成・活動システム.
3,900円
第 54 号 タフォノミーと堆積過程—化石層からの情報解読—.
2,900円
第 55 号 ジュラ紀付加体の起源と形成過程※売り切れ
第 56 号 古領家帯と黒瀬川帯の構成要素と改変過程.
2,900円
第 57 号 砕屑岩組成と堆積・造構環境.
2,800円
第 58 号 地震イベント堆積物−深海 底から陸上までのコネクション−
2,900円
第 59 号 沖積層研究の新展開 詳細→
2,400円
講演要旨集・巡検案内書ほか
会員頒価
送料
第117年学術大会講演要旨集(2010年・富山大会)
4,000円
〒500円
*上記のほかに2002新潟,2003静岡,2004千葉,2006高知の要旨集も残部あり。価格等はお問い合わせ下さい。
*このほかの要旨集のバックナンバーについては,WEBより閲覧可能です。→コチラから
定価
送料
第112年見学旅行案内書(2005年・京都大会)※「案内書の欠落部分について」
2,000円
〒350円
第113年見学旅行案内書(2006年・高知大会)
・CD-ROM版(カラー)[冊子版は売り切れました]
2,500円
〒120円
第114年見学旅行案内書(2007年・札幌大会)
・CD-ROM版(カラー)[冊子版は売り切れました]
2,400円
〒120円
第115年見学旅行案内書(2008年・秋田大会)
・CD-ROM版(カラー)/・冊子版
2,500円
お問い合わせ下さい.
第116年見学旅行案内書(2009年・岡山大会)
・CD-ROM版(カラー)/・冊子版
2,800円
お問い合わせ下さい.
第117年見学旅行案内書(2010年・富山大会)
・CD-ROM版(カラー)/・冊子版
2,800円
お問い合わせ下さい.
第118年見学旅行案内書(2011年・水戸大会)
・CD-ROM版(カラー)/・冊子版
2,800円
お問い合わせ下さい.
第119年巡検案内書(2012年・大阪大会)
・CD-ROM版(カラー)のみ
2,500円
〒120円
第120年巡検案内書(2013年・仙台大会)
・CD-ROM版(カラー)のみ
2,500円
〒120円
第121年巡検案内書(2014年・鹿児島大会)
・CD-ROM版(カラー)のみ
2,500円
〒120円
日本地質学会リーフレットシリーズ
定価(会員頒価)
1.大地の動きを知ろう—地震・活断層・地震災害—※売り切れ
300円(200)+送料
2.大地のいたみを感じよう?地質汚染 Geo−Pollutions
300円(200)+送料
3.大地をめぐる水—水環境と地質環境—
400円(300)+送料
4.日本列島と地質環境の長期安定性 (2011年1月刊行)
600円(500)+送料
地質リーフレットシリーズ
定価(会員頒価)
1.箱根火山 ※売り切れ
1,300円(1,000)+送料
たんけんシリーズ
1.箱根火山たんけんマップー今、生きている火山
400円(300)+送料
2.屋久島地質たんけんマップー洋上アルプスは不思議な地質がいっぱい
400円(300)+送料
3.城ヶ島たんけんマップー深海から生まれた城ヶ島
400円(300)+送料
4.富士山青木ヶ原溶岩のたんけんー樹海にかくされた溶岩の不思議ー
400円(300)+送料
5.長瀞たんけんマップー荒川が刻んだ地球の窓をのぞいてみようー
400円(300)+送料
*20部以上購入の場合割引有り
電子書籍シリーズ
・地学を楽しく!ジオツアー・ジオパーク・地学オリンピック(電子書籍)詳しくはこちら
定価1,380円
その他
・下敷き : 「干渉色図表」・「偏光顕微鏡による鉱物鑑定表」(英語版)※20枚以上おまとめ購入の場合,30%OFF
定価 400円/枚
(会員頒価300円)+送料 ※2023年12月価格改定
・学会オリジナルフィールドノート 詳しくはこちら 再販開始・価格改定(20225.10月)
定価 1200円/冊
(会員頒価900円)
+送料
・学会オリジナルクリアファイル(A4) 詳しくはこちら
3枚1セット500円/冊
+送料
・地質学雑誌特集号(冊子)「球状コンクリーションの科学―理解と応用―」詳しくはこちら
定価3,000円/冊
(会員価格2,600円)
+送料370円
学会編著・訳編の出版物:出版社・書店にてお求め下さい
定価(本体価格)
「はじめての地質学ー日本の地層と岩石を調べるー」2017年9月発行 ベレ出版 ISBN: 978-4-86064-522-9
1,600円
「日本地方地質誌 <全8巻>1. 北海道地方〜8.九州・沖縄地方」
*会員特別割引の専用申込書は、会員ページからダウンロードして下さい
各巻会員特別価格あり.
詳細は専用申込書で
「国際層序ガイドー層序区分・用語法・手順へのガイド」共立出版 ISBN: 4-320-04638-2
4,000円
「地質基準」共立出版 ISBN4-320-04636-6
2,800円
「地震列島日本の謎を探る」東京書籍 ISBN: 4-487-79419-6
1,500円
「地質学調査の基本ー地質基準ー」共立出版 内容詳細はこちら→
2,800円
「地質学用語集—和英・英和—」共立出版 ISBN4-320-04643-9
4,000円
「デジタル地質学用語集—和英・英和—」Win版(CD-ROM)→CD-ROMの内容詳細はこちら
※このCD-ROMは書店では販売していません.共立出版への直接注文となります.
*会員特別割引販売の申込書は 会員のページからダウンロードできます。
3,500円
「フィールドジオロジー シリーズ(1-9)」共立出版
*会員特別割引販売の申込書は会員のページからダウンロードできます。
定価2,000〜2,100円
各巻会員特別価格あり.
詳細は専用申込書
地学読本「地学は何ができるか─宇宙と地球のミラクル物語─」 愛智出版 ISBN 978-4-87256-414-3
*会員特別割引販売の申込書は会員のページからダウンロードできます。
2,800円
地球全史スーパー年表 日本地質学会[監修]岩波書店 ISBN-10: 4000062506
1,300円
産業技術総合研究所(旧地質調査所)発行の地質図幅は一部取り扱っています.事務局まで(main@geosociety.jp)お問い合わせ下さい.
Island Arc 日本語要旨 2012. vol. 21 Issue 3 (September)
Vol. 21 Issue 3 (September)
通常論文
[Review Articles]
1. Tephrostratigraphy of the Pliocene to Middle Pleistocene Series in Honshu and Kyushu Islands, Japan
Yasufumi Satoguchi and Yoshitaka Nagahashi
本州および九州の鮮新−中部更新統テフラ層序
里口保文・長橋良隆
日本の鮮新−更新統は,各堆積盆または地域ごとに詳細な調査と記載が行われてきたが,それら地域間の層序対比は,複雑な地質構造のために難しいものとなっている.各地域の層序は,多くのテフラ層によって確立されており,地域間の層序はいくつかの広域テフラによって対比されている.本論では,日本における鮮新統から中部更新統の広範囲な層序モデルを,テフラ層序,古地磁気層序,生層序に基づいて確立した.この層序モデルは,島弧である日本弧周辺の環境変遷や爆発的火山活動の解明に重要なものといえる.
Key Words : Japanese archipelago, Pleistocene, Pliocene, stratigraphic correlation, tephrostratigraphy, widespread tephra.
[Research Articles]
1. Mineral chemistry and geothermobarometry of Moshirabad pluton, Qorveh, Kurdistan, western Iran
Ali A. Sepahi, Mohammad Maanijou, Seddigheh Salami, Sara Gardideh and Tayebeh Khaksar
イラン西部コルデスターン州ゴルヴェ周辺のモシラーバード深成岩体の鉱物化学組成と地質温度圧力
モシラーバード深成岩体はイラン西部ゴルヴェ,サナンダジュ‐シールジャーン変成帯の南西部に位置する.深成岩体は閃緑岩,モンゾ閃緑岩,石英閃緑岩,石英モンゾ閃緑岩,トーナル岩,花崗閃緑岩,花崗岩,アプライト,ペグマタイトからなる.本研究では多様な岩石種から31試料の全岩組成,異なる岩相から15試料の鉱物化学組成を分析した.マグマの性質を鉱物化学組成によって記載し,モシラーバード深成岩体が定置した圧力と温度を見積もった.長石類の組成はほぼ二成分系で,斜長石の組成はAn5からAn53,アルカリ長石の組成はOr91からOr97の範囲を示す.深成岩体中の有色鉱物は黒雲母と普通角閃石である.黒雲母組成と全岩化学組成に基づけば,モシラーバード深成岩体はカルクアルカリマグマから形成された.角閃石類はカルシウム角閃石(マグネシオ普通角閃石とエデン角閃石)である.普通角閃石―斜長石温度計で算出した晶出温度は550–750°Cの範囲である.これらの温度は,深成岩類が後退変成作用を受け鉱物組成が変化したことを示している.普通角閃石中のアルミニウム地質圧力計はモシラーバード深成岩体が2.3–6.0 kbar,深度7–20 km相当で定置したことを示しているが,広域の地質を考慮するとこの圧力範囲よりも低圧であったと思われる.角閃石類の変質により圧力が過剰に見積もられたのであろう.
Key Words : Al-in-hornblende, geothermobarometry, hornblende–plagioclase thermometry, Iran, mineral chemistry, Moshirabad, Qorveh.
2. Detrital chromian spinels from beach placers of Andaman Islands, India: A perspective view of petrological characteristics and variations of the Andaman ophiolite
Biswajit ghosh, Tomoaki Morishita And Koyel Bhatta
インド領アンダマン島のクロムスピネル砕屑粒子から俯瞰するアンダマンオフィオライトの特徴と多様性
Biswajit ghosh・森下知晃・Koyel Bhatta
インド領アンダマン島の海岸で採取した砕屑性スピネルの化学組成分析から,アンダマン・オフィオライトの全体像を俯瞰し,オフィオライトが形成されたテクトニクスについて検討した.調査地域全体から,Cr# (=Cr/(Cr+Al)原子比)の高いスピネルが含まれていることかは,オフィオライト全体として島弧的環境での火成活動の影響を受けていることが示唆される.また,スピネルのCr#は,島の南部から北部に向かって低い値を示す割合が増加することから,南部地域には溶融程度の低いかんらん岩が分布していることが予想される.これらのことから,アンダマン・オフィオライトを形成したテクトニックセッティングについて推定した.
Key Words : Andaman ophiolite, arc-dominant area, detrital chromian spinel, MORdominant area, paleogeodynamic setting.
3. Hf–Nd isotope constraints on the origin of Dehshir Ophiolite, Central Iran
Hadi Shafaii Moghadam, Robert J. Stern, Jun-Ichi Kimura, Yuka Hirahara, Ryoko Senda and Takashi Miyazaki
中部イランDehshir Ophioliteの成因に関するHf-Nd同位体組成からの制約
Hadi Shafaii Moghadam・Robert J. Stern・木村純一・平原由香・仙田量子・宮崎 隆
サイプラスから北西シリア,南東トルコ,北東イラク,南西イランを通ってオマーンに延びるアラビア縁・オフィオライト帯は,後期白亜紀(約100Ma)に形成された総延長3000kmのネオテチス海北縁の収束帯である.イランのザグロス・オフィオライトはこの収束帯の一部で,外帯(OB)と内帯(IB)オフィオライト帯に細分される.我々はこのオフィオライト帯の内帯,デシル・オフィオライトに着目し,はじめてのNd-Hf同位体測定結果を報告する.我々の結果は,デシルの苦鉄質・珪長質火山岩が,インド洋海嶺マントルドメイン起源である事を明らかにした.そのうち苦鉄質溶岩はすべての類似したHf同位体組成を有するが,珪長質岩脈は非放射性Ndをより多く含む.珪長質岩はTh/NbとTh/Yb比が高くそれらは非放射性Nd量と比例ため,堆積物か大陸地殻成分に汚染されていると考えられる.
Key Words : Hf–Nd isotope, Late Cretaceous, ophiolites, subduction initiation, Zagros.
4. Late Permian post-ophiolitic trondhjemites from Central Iran: a mark of subduction role in growth of Paleozoic continental crust
Ghodrat Torabi
イラン中央部ペルム紀後期のオフィオライト形成後のトロニエム岩体:古生代大陸地殻成長に沈み込みが果たした役割の痕跡
アナーラク地域のペルム紀後期トロニエム岩は,アナーラクオフィオライトとその上位の変堆積岩類に貫入するストックや岩脈として産する.これらは北部アナーラク東西主要断層に沿って露出している.これらの優白質貫入岩類には全てのオフィオライト構成岩類と変成岩類の包有物が含まれる.貫入岩は角閃石,斜長石(灰曹長石),石英,ジルコンと白雲母からなる.二次鉱物は緑泥石(ピクノ緑泥石),緑簾石,曹長石,磁鉄鉱と方解石である.全岩主要・微量元素組成により,貫入岩は高いSiO2 (67.8–71.0 wt%),Al2O3 (14.9–17.1 wt%)とNa2O (5.3–8.6 wt%),低いK2O (0.1–1.5 wt%; 平均値: 0.8 wt%), 低いRb/Sr比 (0.01–0.40; 平均値: 0.09),低いY (3–6 ppm), Ti, NbとTaの負異常,弱い負または正のEu異常,LREEに富み,HREEを分別していることで特徴づけられる.これらの岩石はコンドライトで規格化したREEパターンの勾配で2−40倍の肥沃化を示す.アナーラクトロニエム岩の地球化学組成的特徴は,10 kbar以上での苦鉄質な原岩の溶融を反映している.野外産状と全岩化学組成から,これらの岩石が沈み込んだアナーラク海洋地殻の溶融によってもたらされたマグマが結晶化したことがわかる.本研究により,ザクロ石角閃岩の溶融が研究地域の大陸地殻形成の重要な要素であることが明らかになった.
Key Words : Anarak, continental crust, Iran, Late Permian, Paleo-Tethys, Trondhjemite.
地質学雑誌
地質学雑誌
for English, Please click here
※地質学雑誌は,128巻(2022年)より完全電子化となりました.原則冊子体は作成していません.
■ 電子ジャーナル閲覧(J-STAGE)
■ 特集号(2023年〜)
■ 原稿の投稿・編集規則
■ 著者の皆様へ(受理時のご連絡)
■ オープンファイル/データファイル
■ 購読と複写サービス
■ S1M投稿査読システム画面操作案内
■ 転載申請・著作権について
■ 編集委員会メンバー
(お知らせ)
球状コンクリーションの科学―理解と応用―:冊子販売はこちらから
プレプリントサーバーに掲載された原稿の受付について 2022.2.15
地質学雑誌完全電子化実施,2022年1月を目標 2021.4.19
地質学雑誌原稿テンプレート(Wordファイル)をご利用下さい(2013.1.22.2015.1月一部改正)
地質学雑誌は,日本地質学会が発行する月刊の学術雑誌です.本誌は,日本の地質学の発展をささえながら,創刊以来125年以上の道を歩んできました.
本誌は,地質学に関連する分野の最新の研究成果を論説,短報等として,また研究成果や研究技術等のまとめを総説,ノート等として,和文または英文で紹介することを目的としています.本誌は新規性・一般性に富んだ調査研究結果,技術,理論,アイデア等の呈示を重視しているとともに,国内外の地域地質の記載に重点をおいた報告を歓迎しております.また,地質学に関連した資源,環境,自然災害,および地学教育等にかかわる研究等も取り扱っております.
本誌は,その内容の充実を測るために質の高い査読編集体制を組み,投稿原稿をできるだけ速やかに発行することに努めております.
電子ジャーナル閲覧:オンラインでチェック
地質学雑誌は「科学技術情報発信・流通総合システム」(J-STAGE)にて,1巻1号から全文無料閲覧が可能です。
→2022年(128巻)からは完全電子化となり,受理された原稿は随時公開となります。
↑↑無料閲覧はこちらから↑↑
(読者の皆様へ)科学論文では,学説の検証可能性を保証することが重要です.そのため,地質学雑誌掲載論文には,重要な証拠となった試料がどこで得られたかを示しているものがあります.言うまでもないことですが,見学や採取を行う場合,各自の責任において地権者や関係官庁への連絡と許可の取得の必要があることにご注意下さい.詳しくは,http://www.geosociety.jp/publication/content0073.html
(一般社団法人日本地質学会)
ページTOPへ戻る
購読と複写サービス
※地質学雑誌は2022年1月(128巻)から完全電子化の電子ジャーナルとなります.冊子体の販売は行いません.雑誌1巻1号の論文から全てJ -STAGE上で無料閲覧していただけます.バックナンバー(〜127巻12号)冊子体のご購入については,学会事務局(main@geosociety.jp)までお問い合わせください.
(注)地質学雑誌内に収録されていても,学術論文以外の文献は収録されていないものもあります(お知らせ記事,雑報,追悼記事,講演要旨...など).それら文献については,学会事務局までお問い合わせください.
学会の出版物に関して,有料で複写サービスを行っています(在庫のある出版物は原則購入をお願いします).必ず複写箇所の詳細(出版物名・論文名・著者名など)を明記して,FAXもしくはe-mail でご連絡下さい.
複写料金
会 員
(ページ×30円)+送料
非会員
(ページ×50円)+送料
*FAX送信サービス(郵送とあわせてFAXでもお送りします):
5ページまで:200円,6〜10ページ:300円(10ページ以上の場合は、ご相談下さい)
申込先:FAX 03-5823-1156 e-mail: main@geosociety.jpまで(@を半角に修正してお使いください)
ページTOPへ戻る
オープンファイル/データファイル
オープンファイルは,受理論文から,生データ部分(調査・実験・解析・計算等の一時データや事実の記載等)を著者の希望に応じてホームページに掲載するも のです.■オープンファイル入口はこちら(127巻12号まで)
128巻掲載論文より,J-STAGEのデータサーバーであるJ-STAGE Dataのデータファイルとして公開するよう変更になりました. J-STAGE Dataのデータファイルは,独立したDOIとメタデータが付与され外部サービスとも連携するため,検索されやすく,元論文の注目度向上も期待されます.データファイルに変更を加える場合,変更後のデータファイルが新規に作成され,変更前の版(変更履歴加筆)とともにJ-STAGE Dataで永続的に公開されます.データファイルを撤回した場合も,メタデータ,DOIの記載,および変更履歴はJ-STAGE Dataに残ります.
J-STAGE Datat地質学雑誌のページはこちらから https://jstagedata.jst.go.jp/geosoc
(参考)地質学雑誌投電子版稿編集出版規則 細則1 地質学雑誌データファイル掲載細則
地質学雑誌 投稿案内
■ 投稿する前に・・・
投稿前には必ず投稿編集出版規則をご一読頂き、投稿原稿の内容を十分ご確認下さい.また,保証書を忘れずにご提出下さい.
[投稿時に必要な提出書類] 保証書 (注)保証書の郵送は必須です
■ 投稿編集出版規則ほか
地質学雑誌投稿編集出版規則(電子版)(2024年8月31日一部変更)
--参考>引用文献:雑誌略名について(2011.9.20更新)
地質学雑誌原稿テンプレート(2017年12月現在)
地質学雑誌投稿編集出版規則(旧冊子版の規則)
■ 投稿のご案内
2007 年1月より電子投稿・査読システムの運用を行っています。電子投稿・査読システムは、直接WEBサイトに送信するため簡便で、ファイル が正常に送付されたかその場で確認することができるため確実で、投稿から受理までに要していた期間が少なからず短縮され、自分の投稿原稿が査読・編集過程 のどの段階にあるかを随時知ることができます。現在はJ-STAGEを通じて,ScholarOne Manuscriptsを利用しています.*電子投稿システムの画面操作については下記マニュアルをご参照ください
→ ScholarOne Manuscripts 画面操作・著者投稿マニュアル
地質学雑誌 電子投稿入り口 (杏林舎サーバーにて行います) ◀◀◀ 新規投稿,修正原稿の投稿いずれもこちらから
ページTOPへ戻る
著者の皆様へ(受理時のご連絡)
★重要★ 必ずお読み下さい→ 受理後の論文掲載のためのご案内・ご連絡
*著作権譲渡等同意書ダウンロードはこちらから
S1M投稿・査読システム画面操作案内
著者:投稿画面操作マニュアル
担当編集委員:画面操作マニュアル
査読者:画面操作マニュアル
転載申請・著作権について
日本地質学会の出版物を転載・引用される場合は,「日本地質学会著作物利用規定」をご参照の上,必要な場合は,書面にて転載手続きを行って下さい.
◆ 日本地質学会著作物利用規定はこちらから(H17.12改正)
【その他,著作物利用に関わる参考資料】
情報発信における学会の著作権管理と倫理責任–投稿原稿などの著作物についての保証書署名と著作権等譲渡のお願い (日本地質学会News誌5巻12号2 頁記載)
著作権等譲渡同意書への署名捺印のお願い(日本地質学会News誌5巻12号同書3 頁記載)
編集委員長名の転載に当たっての注意事項 (地質学雑誌108 巻12 号829-830 頁記載)
【申請書類】利用内容に応じて下記の書式を学会事務局にご提出下さい
◆ 一部利用の場合> 転載許可申請用紙
(注意:改版・加工して使用する場合は,そのコピーも添付してご提出ください)
◆ 全部利用の場合> 著作物利用条件同意書
転載に関する問い合わせ・書式送付先:
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル
一般社団法人日本地質学会
e-mail; journal@geosociety.jp ,電話 03-5823-1150
ページTOPへ戻る
地質学雑誌編集委員会 (2025年7月1日現在)
委員長
小宮 剛(東京大)
副委員長
大坪 誠(産総研)
栗谷 豪(北海道大)
編集委員
池田 剛(九州大)
乾 睦子(国士舘大)(25.4.19〜)
宇野康司(兵庫県立大)
宇野正起(東北大)
江川浩輔(九州大)
及川輝樹(産総研)
大藤 茂(富山大)
奥野 充(大阪公立大)
尾上哲治(九州大)
折橋裕二(弘前大)
亀井淳志(島根大)
楠橋 直(愛媛大)
佐藤智之(産総研)
佐野晋一(富山大)
志村俊昭(山口大)
新正裕尚(東京経済大)
末岡 茂(原子力研究開発機構)
高橋 唯(慶應義塾幼稚舎)
道家涼介(弘前大)
藤内 智士(高知大)
常盤哲也(信州大)
西山賢一(徳島大)
野々垣進(産総研)
延原尊美(静岡大)
松本 弾(産総研)
三好雅也(福岡大)
本山 功(山形大)
山口飛鳥(東京大)
山崎 誠(秋田大)
吉田孝紀(信州大)
任期:2024.6.8〜2026総会
地雑TF_アンケート行う背景(18/06/01)
地質学雑誌あり方についてのアンケート
2018年6月
地質学雑誌タスクフォース(TF)
地質学雑誌が原稿不足で毎月発行が危ぶまれる状況にあり,また同時に会員減により学会財政が厳しい状況にあります.これらをふまえ,地質学雑誌についてのアンケートを行いますので,ご回答下さいますようお願いいたします.
アンケートの回答受付を終了しました.
たくさんのご回答をいただき,ありがとうございました.
締切:9月末
【このアンケートを行う背景について】
地質学雑誌は今年度末の125周年特集号シリーズの終了後,毎月発行が危ぶまれる状況にあります.これまでも欠号を出す危機がしばしばありましたが,投稿数の長期的推移を見ると,月刊のままでは毎年複数の欠号が出ることが数年のちに常態化すると予想されます.こうしたことから昨年来,本タスク フォースは完全電子化(冊子体の廃止)や隔月刊化などの対応を検討してきました.
完全電子化では,受理後PDFができた論文からアップロードするので,号という区切りがなくなり,欠号の危機は完全になくなります.しかし,直接雑誌を手にする利便性や,図書館等でのプレゼンス,会員の学会所属意識を毀損するとの意見もあります.隔月刊化では,欠号の危機は当面避けられますが,10年後20年後も安定的刊行が可能かは不透明です.
また,地質学雑誌をどうするかは,ニュース誌をどうするかという事とも連動し,以下の1994〜1997年の状況に戻すことも考慮対象になります.
一方で,近年の会員数の減少に伴い,学会の収入も減少しています.現在の出版スタイルを維持するならば,将来的には会費の値上げも検討しなければいけない状況にあります.
このため本タスクフォースでは.地質学雑誌の今後のあり方について会員各位のご意見をうかがいたいと考えていますので,アンケートをお願いするものです.
1. 地質学雑誌の変遷(近年)
1993年(99巻)まで B5版,ニュース部分を含む.
1994年(100巻)〜1997年(103巻)A4版,ニュース部分も含む.
1998年 科研費の補助をもらうために,ニュース部分を分離.
現在,科研費補助がなくなり,また冊子発行3か月後からWeb公開中
なお,この数年,編集委員会では,報告・巡検案内・解説等のカテゴリを増やし,投稿増を狙ってきました.
2. 本学会の会員の動向と投稿状況
会員数約3600名.少子化の影響等により60〜70人/年減が続いています.
メールアドレスを登録し,geo-Flashが届く会員は2200人程度で,会員の約60%にとどまります.
地質学雑誌の投稿数は,1998年以降漸減しています.研究者がインパクトファクター付きの国際誌を目指さざるを得ない状況,会員減に伴う投稿者数の減少,細分化した専門分野の雑誌に原稿が流れたこと,などが理由と見られます.
3.経費面を含めた検討
近年会員数は減少傾向にありますが,会員減が現在のペースで進むと仮定した場合,雑誌出版を含む現状の学会活動のレベルを維持するためには,将来的に会費の値上げが必要となります.
※以下,あくまで現状の会員減のペースが保たれ,雑誌等でその経費節減分を賄ったと仮定した場合です.
地質学雑誌とニュース誌を完全に電子化し紙媒体を廃止した場合,当面の会費の値上げは避けらます.
地質学雑誌を隔月にした場合に,ニュース誌を毎月送付すると学会財政にメリットはあまりありません.ニュース誌も隔月にすると数年は会費の値上げが避けられそうですが,各種お知らせが遅れます.
地質学雑誌とニュース誌を毎月合併号にすると,3年程度は会費の値上げは避けられそうですが,論文の載らない号がでることがあります.
地質学雑誌とニュース誌を電子化し,紙媒体を希望者のみに配布する場合,数年は会費の値上げは避けられます.紙媒体を希望する会員が半数とすると,紙媒体の不要な会員は会費をある程度下げられる可能性がある一方,紙媒体の必要な会員の会費は上昇します.反面,事務局業務の増加が全体的な経費増になることは考慮が必要です.
4.アンケートのお願いにあたって
本タスクフォースは,メール登録会員の数を認識した時に衝撃を受けました.現状で即座に完全電子化した場合,多くの会員に不利益が及ぶのは必至で,本タスクフォースとしても,苦慮しているところです.このためぜひアンケートにご協力ください.
著者プロフィール欄の新設_2014.12.12
著者プロフィール欄の新設『地質学雑誌投稿編集出版規則』(2014.12.6 改正)はこちら地質学雑誌編集委員会 2014年12月6日の理事会において,当委員会が提出した『地質学雑誌投稿編集出版規則』の改正案が承認され,地質学雑誌は2015年第1号から掲載論文の末尾に著者プロフィール欄を設けることになりました.ここで,本改正について説明させていただきます.まずは,改正の背景です. 地質学を専攻する学生にとって1970年代頃までは,もっぱら学ぶことが岩石学・鉱物学か層位学・古生物学か大雑把に2つの選択しかなく,いずれにしても国内のフィールドで研究することが普通でした.今日から見て,かつての地質学会は,比較的均質性の高い集団でした.会員諸氏にとって地質学雑誌の権威は高いものでしたが,多くの掲載論文は理解が可能であり,各自のフィールドとの関連で,なにがしかの興味を持って記事を眺めることができました.しかしその後,地質学でも専門分化・高度化が進行しました.それに応じて地質学雑誌も多様なテーマを扱うようになり,多くの会員にとって内容が理解しにくく興味を持ちにくい論文が多くなってしまいました.年会における口頭発表でも事情は同じです.その結果,会員間の交流の範囲が狭まっているのではないでしょうか.今や地質学会は不均一な集団であると考えます. さて,こうした現状認識のもとで,地質学界の総合誌である地質学雑誌はどうあるべきでしょうか.地域地質を母国語で記載した論文を載せることは,地質学雑誌にとって変わることのない重要な役割ですが,そのような論文は減っています.上記の状況を考えると,会員間の学術交流を活性化することが重要です.すなわち,総説やノートを通じて他の会員の研究成果を理解できるようにすることはもちろんですが,理解とまでは行かずとも会員諸氏の活躍の様子をより可視的にすることが,地域地質の記載とならんで,今後は本誌の重要な役割であると考えます.そのため,当委員会でできる措置として,著者プロフィール欄を新設することにしたわけです. 著者プロフィール欄には,著者の皆さんの顔写真・氏名・現職・略歴・研究内容・当該論文での役割・E-mailアドレス・URLを記していただきます.会員間で文字通り顔の見える関係を築くきっかけとして,この欄を使っていただければ幸いです.著者プロフィール欄にはいくつもの利点があります.学生諸氏にとって,著者の略歴はキャリアパスを考える手がかりになるでしょう.活躍する姿がこれまで以上に可視的になることによって,著者自身にはポストや研究資金を得る手がかりになるでしょう.さらにまた,地質教室や企業などの組織にとっては,新人を獲得するための情報源になるでしょうし,構成員の活躍を見せることで,新人を獲得するための宣伝の場として利用していただくこともできるでしょう.また,当該論文における各著者の役割を明記していただくことで,2番目以降の著者の寄与の重要性が読者に伝わることでしょう.当委員会としては,この欄の新設で投稿が増えることを期待しています. 最後に,著者プロフィール欄にかんする規定の細かいところをご説明します.この欄では,各著者につき文字数を最大250に制限しています(スペースを含まない文字数).著者多数の場合は,5名までとします.その結果,この欄は2段組の紙面のうち最大で片段に満たないスペースを占めることになります.代表著者のみプロフィールを記すという選択も可能です.最近の規則改正により,論文1編あたりのページ制限を若干緩和したので,この欄を新設しても新たな制限緩和はしません.スペースが小さいため,口絵だけは著者プロフィール欄を付けないことにします.この欄に記すことは個人情報ですので,でどれだけのことを公にするか,編集委員会としては著者の選択を尊重します.著者の希望によっては,この欄を付けないことを当委員会は認めます.また,複数著者による論文では,著者ごとに記述する項目が異なることもあるでしょう.また,最近,国際誌では論文を完成させるにあたっての各著者の寄与を書くことが,求められるようになってきています.当委員会で議論した結果,本誌では当面,それを受理のための条件とはしないことにしました.しかし,著者のご判断によって,当該論文での役割を著者プロフィールに記していただいてかまいません.次の例は,全項目を記した例です.
地質花子■〇〇大学大学院〇〇学研究科〇〇学専攻助教.05年␣〇〇大学〇〇学部卒,10年␣〇〇大学大学院〇〇学研究科博士後期課程修了(〇〇学博
士),10年␣学術振興会特別研究員,12年␣〇〇研究所研究員,14␣年から現職.研究内容:〇〇地域の層序および地学教育,特に〇〇による〇〇の解
明.本研究では,地質調査・総括・原稿執筆・編集委員会との対応を担当.E-mail: xxx@xxx.xxx.ac.jp,URL:
www.xxx.ac.jp/xxx/xxx.html.
ここで記号■は全角スペース,␣は半角スペースを表します.次の例は,記載項目が少なくて顔写真もない例です.地質花子■研究内容:〇〇地域の層序および地学教育,特に〇〇による〇〇の解明.
論文の第1ページに著者名・所属が記されているので,氏名だけでは著者プロフィールとして成立しません.したがって,それだけの著者プロフィールは認めません.ただし,氏名と顔写真なら認めます.『地質学雑誌投稿編集出版規則』(2014.12.6 改正)はこちら
2012年度Island Arc編集委員会報告
2012年度Island Arc編集委員会報告
日本地質学会Island Arc編集委員会
日本地質学会の公式英文誌としてIsland Arc(IAR)が発行されてから,今年で21周年となります. 2013年からは,IARの出版が全面的にオンライン化され,カラーによる図表類の出版に制限がなくなりました.ここでは出版社であるWiley社から送られてきた出版報告をもとに,IARの現状を日本地質学会の会員の皆様に御紹介したいと思います.
第21巻に19編の論文を掲載
2012年発行の第21巻には19編(Pictorialの1編およびInvited paperの1編を含む)の論文が掲載され,総ページ数は349ページでした.残念ながら,このページ数は2012年の契約ページ数(825ページ)に大きく及ばない数字です.
IARの論文数と総ページ数を振り返ってみますと,2006年は44編(548ページ),2007年は47編(606ページ),2008年は37編(594ページ)でしたが,W-B社と2009年以降のページ数増の契約を行ったため,2009年は40編(672ページ),2010年は52編(734ページ)と増加傾向にありました.しかし,2011年に37編(555ページ)と減少してからは,2年続けての減少傾向にあります.2012年は特集号が1つも組まれなかったことが,このような論文数ならびに総ページ数が大幅に減少した原因の1つと考えられます.しかし,2013年には2つの特集号が組まれ,また現在の投稿数は過去半年間で40件(新規が30件)におよんでいます.このような投稿傾向が継続し,受理論文の数が増加すれば,2013年には,論文数や総ページ数は2009年の水準に回復できることが期待されます.
第21巻掲載論文の第1著者の所属は,日本が15編で最も多く,続いてイラン(3),中国(2)韓国(2),インド(1),オーストラリア(1)となっています.一方,論文の投稿数では,日本(47),中国(9),イラン(8),インド(4),アメリカ(2),韓国(1),その他の国(3)となっています.2012年以降,イランからの投稿数が増加する傾向が認められます.しがたいまして,今後は,台湾・インドネシア・マレーシア・ニュージーランドなどのアジアやオセアニアの周辺諸国からの投稿を促す必要があると思われます.
2012年IFは1.071
本年6月にトムソンロイター社より2012年のインパクトファクター(IF)が発表されました.2012年のIAR のIFは,昨年よりわずかに上昇し「1.071」でした. 2006年の0.762以降,2007年の0.837,2008年の1.038,2009年の1.182と,わずかではありますが上昇傾向にありましたが,2010年は1.027に下降し,2011年には1.012となっていました.一方, IARのGeosciences(Multidisciplinary)分野での位置は,2009年の82位(153誌中),2010年の105位(165誌中),2011年の113位(170誌中)と低下傾向にあり,2012年は113位(170誌中)で横ばいでした.
IFは必ずしも雑誌や掲載論文の質を表すものではありません.また,論文が内容ではなく,掲載雑誌のIFの高低で判断されるという弊害があることも指摘されています.しかし,最近は,論文の投稿先を選ぶ際に,IFを考慮に入れる方が多くなっており,これは特に若手研究者に著しい傾向です.よって,IFの上昇は,IARの発展のために欠かせない要件だと言えます.2012年IFの対象論文(2010年および2011年にIARに掲載された論文)をみてみると,相当数の論文が未引用となっており,これがIARのIF低迷の原因の1つとなっています.「日本の研究者は,日本人の研究をリファーしないことで,書いた論文のステータスがあがると思っているようにみえる」という話をした海外の研究者がいるそうですが,IARには質の高い論文が多く掲載されていますので,論文作成の際には,積極的なIAR掲載論文の引用をお願い致します.
Island Arc賞
2013年の「Island Arc賞」は,
Hattori, K., Wallis, S., Enami, M., and Mizukami, T. (2010)
Subduction of mantle wedge peridotites: Evidence from the Higashi-akaishi ultramafic body in the Sanbagawa metamorphic belt. Island Arc, v. 19, 192–207
に授与されました.授賞式は日本地質学会120年学術大会(仙台大会)において行われ,石渡会長から賞状とメダルが、Wiley Blackwell社より賞金が服部様に贈呈されます.
最多ダウンロード賞
2013年の「最多ダウンロード賞」は,2007年〜2011年に出版された論文のうち,2012年に最もダウンロードされた論文に対して,Wiley社より与えられます.ただし,同一論文に複数回授賞しないという制約があります.以上の規則に基づいた2013年最多ダウンロード賞は,
Ayalew, D., and Ishiwatari, A. (2011)
Composition of rhyolite from continental rift, continental arc and oceanic island arc: Implications for the mechanism of silicic magma generation. Island Arc, v. 20, p. 78–93.
に授与されました.
今後のIARに関して
2013年よりIARは完全電子ジャーナル化しました.今後,完全電子化のメリットであるカラー図版の無料化とともに,受理からオンラインで論文が掲載されるまでの期間の短縮化を図り,さまざまな研究領域の学術論文を迅速に掲載できる国際誌として発展させていいきたいと考えております.
既に別途ご報告しましたように,当面現雑誌名の「Island Arc」を継続することが決まりました.IARは地質学雑誌と同様,地球科学に関する幅広い研究領域をカバーする国際学術雑誌です.最近では,古生物や古気候,珊瑚礁,ハイドレート,CO2貯留などに関する論文の投稿が徐々に増えてきています.今後もさまざまな研究領域から論文の投稿数が増加されるよう,皆様にご協力頂きたいと思います.
IARの論文数や引用度を向上させるための試みとして,特集号やReview Paperの企画がこれまでに行われてきました.現在,4つの特集号の企画が進んでいます.皆様方が関係される国内外での研究集会や学会で発表された論文に基づいて,新たな特集号の企画や提案を編集事務局へお寄せ下さい.また,それぞれの研究分野の学術動向に照らし合わせたReview Paperのご提案も心よりお待ちしています.
2008年〜2011年の4年間,編集委員長を務められた井龍康文様と前川寛和様が継続されていた特集号の編集作業が一段落しました. 2012年より伊藤 慎と海野 進が編集委員長を務めさせていただいていますが,この1年半の間,前両編集員長には,私どもの編集作業全般にわたって多大なご協力を頂いてまいりましたことをご報告するとともに,お二人のご尽力に心より謝意を申し上げます.編集事務局長は2009年より原 英俊が担当してまいりましたが,2014年3月で交代の予定です.
今後とも,皆様方には,IAR編集委員会に対しまして,御支援をよろしくお願い申しあげます.
S1M査読システム:画面操作方法(担当編集委員用)
地質学雑誌電子投稿・査読システム:画面操作方法(担当編集委員用)
詳しい操作手順はこちらから
注意:編集委員会用メーリングリスト(ML)と査読システム:ScholarOne Manuscripts(S1M)の併用になります.まずは、MLへの報告を忘れずに行って下さい!
編集委員会の基本の流れ
(1)まずは編集メーリングリストへ:報告・相談・検討(委員会全員に公開)
(2)メーリングリスト上で委員長からの決済を受ける(委員会全員に公開)
(3)査読システム上での画面操作(担当委員が操作した画面内容は、担当委員・著者・委員長陣のみ閲覧可)
注1>査読者は論説,総説は2名.報告・レター・ノート・フォトなどは1名(場合によっては2名)
注2>査読者候補を決めたらMLに報告し、委員長の決済を受けて下さい。選定に悩んだ場合も、MLにご相談下さい。
注3>著者に編集委員が含まれる場合は、査読者選定は、委員長陣・幹事・事務局間でのみ行う。査読報告は、査読者の氏名通知か・不可がわかるまで、氏名はふせて(査読者Aとか)MLで報告する.
注4>全編集委員に査読結果等を開示しない方が良いと判断される場合は,MLには流さず,編集委員長陣のみに報告する.
■ 担当編集委員の作業手順 ■(各項目をクリックすると詳細説明に移動します)
(1)-(6)までをまとめて「担当編集委員画面操作・編集マニュアルPDF」にも記載しています
(1)原稿の担当
(2)査読者選定→システムへログイン→査読打診・査読依頼
------------------------------------------------------------------------------------------
(3)編集委員の判定その1:査読結果の取りまとめ→まずはMLへ報告
(4)編集委員の判定その2:システム画面から著者へ結果返送
------------------------------------------------------------------------------------------
(5)修正稿が提出された場合
(6)その他
(1)原稿の担当
まずはML上で:新規投稿原稿の紹介→担当幹事を決定.(編集委員長からの担当幹事の打診は,まずはML上で行います)
その後システムを通じて担当依頼操作がなされ,原稿が閲覧できるようになります.
システムから原稿担当の通知メールが届きます
件名:[GEOSOC] 投稿論文の担当依頼 原稿番号:GEOSOC-2012-***
(2)査読者選定→システムへログイン→査読打診
・査読者は論説,総説は2名.報告・レター・ノート・フォトなどは1名(場合によっては2名)
・査読を依頼したい査読者候補をまず編集MLへ報告し、委員長決済を受ける.選定に悩んだ場合もまずはMLにご相談下さい。 (注意:著者に編集委員が含まれる場合は、査読者選定は、委員長陣・幹事・事務局間でのみメールで行う)
システムへログイン。この画面は「著者」「査読者」「編集委員」として共通で使用します。
「Associate Editor(編集委員)」のタブを選択して、進みます。
(※画面表示は現在のものとは若干異なります)
担当委員が作業するべき論文数が表示されています。
下記のように【1 査読者の選出】は、査読者を選定して依頼するべき原稿が1編ある事を示しています。
・システム画面上から候補者に宛てて査読打診操作を行う
画面下方の「査読者検索機能」を使って候補者をリストに表示させる。
画面のステータス欄【依頼】ボタンをクリックすると、査読者宛に送信される依頼(打診)メールの文面がウィンドウに表示される。
「Body」欄に査読者あてのコメントを記入できる。査読依頼に際して,査読者宛のコメントがあればコメント欄に記入し,メール文面を確認して、画面右下【保存して送信】ボタンをクリック
査読打診操作が完了。下記のように【返答待ち】の表示になります。
査読が承諾された場合は、【承諾】の表示になります。
・ 査読者は【打診承諾】の回答操作をした時点から原稿PDF をダウンロード出来ます。候補者が査読を断った場合は、システムから担当委員宛に通知メールが届きますので、別途候補者を再選定して下さい。
*打診したい査読者が,検索しても出てこない場合
(3)編集委員の判定その1:査読結果を取りまとめ→まずはMLへ報告
・査読者からの査読結果が戻った場合、担当委員宛に【査読完了】の通知メールが送信されます。それを受けて, 担当編集委員は,システムへログイン
【1 編集委員の判定】と表示されているので,クリック。
画面右側の査読者氏名の欄:【査読を見る】をクリックすると、査読者からの査読結果画面に移行します。
査読者からの査読結果画面
査読結果を取りまとめ,MLに報告→委員長からの決済を受ける.
(注意:著者に編集委員が含まれる場合は,査読者の氏名通知可・不可にあわせて、氏名はふせて(査読者Aとか)MLへ報告する.また,全編集委員に査読結果等を開示しない方が良いと判断される場合は,MLには流さず,編集委員長陣+事務局のみに報告する)
画面TOPに戻る
(4)編集委員の判定その2:システム画面から著者へ結果返送→マニュアルPDFからご確認ください
(5)修正稿が提出された場合→マニュアルPDFからご確認ください
(6)その他→マニュアルPDFからご確認ください
担当編集委員画面操作・編集マニュアルPDFはこちらから ※上記の(1)-(6)について記載があります
Island Arc 日本語要旨 2011. vol. 20 Issue 4 (December)
Vol. 20 Issue 4 (December)
通常論文
[Research Articles]
1. Fault tectonic analysis of Kii peninsula, Southwest Japan: Preliminary approach to Neogene paleostress sequence near the Nankai subduction zone
Pom-yong Choi, Satoshi Nakae and Hyeoncheol Kim
西南日本・紀伊半島における断層構造解析:南海沈み込み帯近傍での新第三紀の古応力変遷に関する予察的研究
Pom-yong Choi,中江 訓,Hyeoncheol Kim
紀伊半島を含む南西日本外帯の南部は構造的 ‘shadow zone’ に属し,活断層と第四系堆積物があまり発達していない.そこでこの地域の造構履歴を構築するために,上部白亜系付加体ならびに下部— 中部中新統前弧盆堆積物に発達する断層と引張割れ目を解析した結果,Event 1〜Event 6の活動が復元された.NNW—SSE方向に貫入した中期中新世平行岩脈群に関連することからEvent 3はこの時期に活動的であったこと,またEvent 5の圧縮方向は現在の紀伊半島におけるWNW方向の地殻変動速度ベクトルと良く一致すること,などが特徴的である.さらに南東韓国および南西日本の歪軌跡 図により,現在の紀伊半島における圧縮方向はヒマラヤ山脈とフィリピン海の2つの構造領域が結合した応力場に調和することが明らかになった.
Key Words : fault tectonic analysis, Kii peninsula, paleostress sequence, plate motion vector, Southwest Japan, tectonic ‘shadow zone’.
2. Lower crustal melting via magma underplating: Elemental and Sr–Nd–Pb isotopic constraints from late Mesozoic intermediate–felsic volcanic rocks in the northeastern North China Block
Chaowen Li, Feng Guo and Weiming Fan
マグマのアンダープレーテイングによる下部地殻の溶融:北中国ブロック北東部における中生代後期の中性〜フェルシック火山岩類の元素組成とSr-Nd-Pb同位体組成からの制約
Chaowen Li, Feng Guo and Weiming Fan
北中国ブロック北東部に分布する白亜紀前期の(それぞれ126 Maと119 Maに噴出した)二つのグループの中性〜フェルシック溶岩のAr-Ar年代測定,主要および微量元素分析,Sr−Nd-Pb同位体分 析を行った結果,それらが不均質な下部地殻と下盤の玄武岩類との間の混合物の溶融に由来する可能性があることがわかった.二つのグループは,高Kカルクア ルカリからショショナイトの性質を示し,軽希土類元素(LREE)とLIL元素に富み,様々な程度にHFS元素に枯渇し,中程度の放射性Srと非放射性 Nd,Pbの同位体組成で特徴づけられる.グループ2に比べ,グループ1の火山岩類は,比較的高いK2O 量と高いAl2O3/ (CaO + K2O + Na2O)比,高いHFSEの濃集と低いNb/Ta比,高い Sr–Nd–Pb同位体比をもつ.グループ1は,エンリッチマントル由来のマグマと放射性Sr,非放射性Nd, Pbの同位体組成をもつ下部地殻との混合物に起原をもち,一方,グループ2のマグマは,同じマントル由来の成分と低いSr, Nd, Pb同位体比をもつ別のタイプの下部地殻との混合物が融解したものである.給源におけるグループ1からグループ2へのシフトは,融解条件の変化に一致して いる.下盤の玄武岩と下部地殻の両者の含水条件下での融解が,より初期の高いNb量と低いNb/Ta比をもち,残留のTiに富む鉱物をほとんどあるいは全 く含まないメルトを生み出した.一方,より若い低Nb,高Nb/Ta比のマグマは,水を欠き,給源にTiに富む鉱物を残す系において融解した.中性〜フェ ルシック火山岩類の2つのグループの生成は,北中国ブロック東部における同時期のリソスフェアが薄くなることによって発生したマグマのアンダープレーティ ングと関連している.
Key Words : early Cretaceous, geochemistry, intermediate–felsic volcanic rocks, lower crust, magma underplating, North China Block.
3. Arc magmatism in eastern Kumaun Himalaya, India: A study based on geochemistry of granitoid rocks
D. Rameshwar Rao and Rajesh Sharma
Eastern Kumaun Himalaya(インド)における島弧火成活動:花こう岩質岩類の地球化学的研究
D. Rameshwar Rao and Rajesh Sharma
Kumaun地域東部の花こう岩質岩の岩石化学的研究から,インドの前縁部が古原生代後期に活動的な島弧であったことが示唆される.Askotクリッペを 伴う東部AlmoraナップとChhiplakotクリッペにおける花こう閃緑岩のメルト生成は,沈み込み帯の堆積物を巻き込んだ古原生代の角閃石とザク ロ石,あるいはそのいずれかを含む苦鉄質の給源の含水下での部分溶融を伴う沈み込みに関係した過程によって引き起こされた.沈み込みに関係した火成弧で一 般的な中〜高Kの塩基性岩類は,Chhiplakotクリッペの高K花こう閃緑岩類の生成をも説明することができる.さらにAskotクリッペを伴う AlmoraナップとChhiplakotクリッペにおける眼球状片麻岩は,それに伴う花こう閃緑岩と地球化学的類似性を示し,互いに起源的に何らかの関 係があることを示唆している.
Key Words : arc magmatism, augen gneisses, geochemistry, granodiorites, Kumaun Himalaya of India, Paleoproterozoic.
4. Block-and-ash flow deposit of the Narcondam Volcano: Product of dacite–andesite dome collapse in the Burma–Java subduction complex
Tapan Pal and Anindya Bhattacharya
Narcondam火山の火山岩塊火山灰流堆積物:バーマ−ジャワ沈み込み帯コンプレックスにおけるデイサイト−安山岩ドーム崩壊の生成
Tapan Pal and Anindya Bhattacharya
アンダマン海にあるナルコンダム島は,バーマ-ジャワ沈み込み帯コンプレックスの火山列におけるデイサイト-安山岩ドーム火山が占めている.安山岩組成の 火砕物の分布は,ドーム近傍に限られ,主に火山岩塊火山灰流堆積物と少量のベースサージ堆積物を形成している.火砕堆積物のほかに,デイサイト質溶岩が ドームの中央を占める一方で,安山岩質溶岩が主にドームの基底部分に認められる.火砕堆積物は安山岩の無発泡〜わずかに発砲している岩塊と火山礫,火山灰 からなる.ドームの崩壊によって生じた高温の岩屑は,最初は,下部は粒子支持,上部は基質支持の塊状層から逆級化層として堆積した.この一連の層は,火山 礫角礫岩から凝灰角礫岩へと繰り返す互層に覆われる.これらの堆積物は,ラハール堆積物というよりはむしろ基底アバランシュとして見なすことができる.こ の基底アバランシュは,級化層理〜平行葉理をもつ一連の薄く成層した灰雲サージ堆積物によって区切られる.
Key Words : ash-cloud surge, dacite–andesite volcanics, grain flow, pyroclastics.
5. Late Carboniferous – Middle Permian arc/forearc-related basin in Central Asian Orogenic Belt: Insights from the petrology and geochemistry of the Shuangjing Schist in Inner Mongolia, China
Yilong Li, Hanwen Zhou, Fraukje M. Brouwer, Wenjiao Xiao, Zengqiu Zhong, and Jan R. Wijbrans
中央アジア造山帯における石炭紀後期−ペルム紀中期の島弧-前弧に関係した堆積盆:中国内蒙古におけるShuangjing片岩の岩石学的および地球化学的洞察
Yilong Li, Hanwen Zhou, Fraukje M. Brouwer, Wenjiao Xiao, Zengqiu Zhong, and Jan R. Wijbrans
Solonker縫合帯は,内蒙古における中央アジア造山帯の発達を記録している.しかしながら,Solonker縫合帯の縫合の時期について2つの解釈 が存在する.すなわち,(i) ペルム紀−三畳紀前期とする解釈と(ii)デボン紀中期あるいはデボン紀後期−石炭紀とする解釈である.Xar Moron断層帯に沿うLinxi地域に分布するShuangjing片岩は,中央アジア造山帯の東部分におけるSolonker縫合帯の南縁に位置 し,Solonker縫合帯の形成時期の情報を与えてくれる.Shuangjing片岩の詳細で系統的な岩石学的および地球化学的解析により,この岩石が 火山性堆積岩を原岩とし,緑色片岩相の累進変成作用を受けたものであることが明らかになった.Shuangjing片岩の原岩が火山岩のものは,カルクア ルカリ系列に属し,大部分中性岩で酸性岩がそれに続く.大陸縁の火成弧において起こった火山活動は,マントル交代作用の結果として生じたプレート沈み込み に関係した火成活動により引き起こされた.Shuangjing片岩の堆積岩の部分は,大陸棚から深海平原への漸移帯を反映してい る.Shuangjing片岩の形成は,島弧-前弧に関係した海洋盆の閉鎖を示唆している.その時期は,レーザーアブレーションICP質量分析法によって 求めた火成ジルコンの年代によって制約を受ける.すなわち,炭酸塩質黒雲母−斜長石片岩の298±2 Maという年代が得られており,この片岩は272±2 Maの花崗岩によって貫入している.Linxi地域では,島弧−前弧盆の南への沈み込みが,その上に載る大陸地殻の上昇,崩壊,浸食 を引き起こした.崩壊が,北部中国クラトン北縁の火山弧に沿う展張と広域的な火成作用を生じた.また,島弧−前弧に関係した海洋盆の 閉鎖は,ペルム紀後期から三畳紀中期の衝突型花崗岩類の形成とそれに続くSolonker縫合帯の衝突の終焉をもたらした.
Key Words : arc/forearc-related basin, Central Asian Orogenic Belt, geochemistry, Inner Mongolia, petrology, Shuangjing Schist.
Island Arc 日本語要旨 2012. vol. 21 Issue 1 (March)
Vol. 21 Issue 1 (March)
招待論文
[Review Articles]
1. Review of the Pilbara Craton and Fortescue Basin, Western Australia: Crustal evolution providing environments for early life
Arthur Hugh Hickman
西オーストラリアのピルバラクラトンとフォーテスキュー堆積盆:初期生命の生息環境を整えた大陸の進化
Arthur Hugh Hickman
この総説では、約35〜26億年前にわたる西オーストラリア・ピルバラクラトンの発達史と、そこに残された初期生命の証拠を包括的に取り上げる。約35〜32億年前にかけて8回の周期的火成活動によりピルバラ超層群が形成され、大規模な花崗岩が貫入して、東ピルバラ地塊が形成された。島弧の付加や衝突で形成された西ピルバラ地塊は、約30億年前に東ピルバラ地塊と衝突した。約29-28億年前の後期花崗岩類の広域な貫入により、ピルバラクラトンは大陸として安定化した。約28−26億年前にはプルーム活動によるリフティングが起こり、フォーテスキュー堆積盆が発達した。このような大陸地殻の発達は、熱水環境や浅海環境等の初期生命の生息場を整え、ストロマトライト等の発達につながった。
Key Words : continental crust, early life, Fortescue Basin, Paleoarchean, Pilbara Craton.
通常論文
[Research Articles]
2. Denudation history of the Kiso Range, central Japan, and its tectonic implications: Constraints from low-temperature thermochronology
Shigeru Sueoka, Barry P. Kohn, Takahiro Tagami, Hiroyuki Tsutsumi, Noriko Hasebe, Akihiro Tamura and Shoji Arai
木曽山脈の削剥史とそのテクトニックな解釈:低温領域の熱年代学による制約
末岡 茂・Barry P. Kohn・田上高広・堤 浩之・長谷部徳子・田村明弘・荒井章司
約0.8 Ma以降に隆起した断層地塊山地である木曽山脈の削剥史や削剥速度分布を,フィッション・トラック法(FT法)および(U–Th–Sm)/He法(He法)によって求めた.9地点のジルコンFT年代(59.3–42.1 Ma),18地点のアパタイトFT年代(81.9–2.3 Ma),13地点のアパタイトHe年代(36.7–2.2 Ma)が得られた.アパタイトFT年代とアパタイトHe年代は,ジルコンFT年代に匹敵する古い年代のグループと,<18 Maの若い年代のグループに分けられた.若い年代は,木曽山脈の隆起に伴う削剥を反映していると考えられ,これらの値や分布を基に,0.8 Ma以降の削剥速度(1.3–4.0 mm/yr),基盤隆起速度の上限(3.4–6.1 mm/yr),および木曽山脈の隆起モデルを推定した.古い年代は,山脈隆起開始以前の長期にわたる準平原化(平均削剥速度:<0.1 mm/yr)を反映していると考えられる.
Key Words : apatite, denudation, fault-block mountain, fission-track thermochronology, (U–Th–Sm)/He thermochronometry, LA-ICP-MS, peneplanation, Kiso Range.
3. A large amount of fluid migration around shallow seismogenic depth preserved in tectonic mélange: Yokonami mélange, the Cretaceous Shimanto Belt, Kochi, Southwest Japan
Yoshitaka Hashimoto, Mio Eida, Takayuki Kirikawa, Ryoko Iida, Mie Takagi, Noriko Furuya, Akira Nikaizo, Taketo Kikuchi and Toshio Yoshimitsu
構造性メランジュに記録された沈み込みプレート境界地震発生帯浅部における大量の流体移動:高知県白亜系四万十帯横波メランジュ
橋本善孝・栄田美緒・桐川隆之・飯田亮子・高木美恵・古谷紀子・二階蔵晃・菊池岳人・吉満敏夫
本論文の目的は沈み込みプレート境界地震発生帯浅部における流体の移動様式と移流量を明らかにすることである。対象地域は高知県白亜系四万十帯横浪メランジュである。北縁は五色ノ浜断層で、微細組織から過去の地震断層だと考えられる。メランジュ面構造とほぼ平行な剪断脈はほぼ石英からなり、移流によって形成され、岩石1m中に合計1mmほどの平均厚さを持つ。流体包有物からの温度圧力はおよそ175-225˚C/143-215MPaであった。この温度条件から先の石英を溶解する流体量はおよそ岩石体積の100倍である。沈み込みよって持ち込まれる粘土鉱物の脱水する温度条件であり、その流体の通過する場であったと考えられる。
Key Words : fluid flow, seismogenic zone, subduction zone
Island Arc 日本語要旨 2010. vol. 19 Issue 2 (June)
Vol. 19 Issue 2 (June)
通常論文
[Pictorial Articles]
1. Lake shoreline deformation in Tibet and mid-crustal flow, Simon R. Wallis, Hiroshi Mori, Kazuhiro Ozawa, Mayumi Mitsuishi, Chie Shirakawa
チベット高原における湖岸段丘の変形と中部地殻の流動
Simon R. Wallis,森 宏,小澤和浩,三石真祐瞳,白河知恵
[Review Articles]
2. Late Mesozoic subduction-induced hydrothermal gold deposits along the eastern Asian and northern Californian margins: Oceanic versus continental lithospheric underflow, Wallace Gary Ernst
アジア東縁部と北部カリフォルニア縁辺部における中生代後期の沈み込み由来の熱水性金鉱床:海洋と大陸リソスフェアの沈み込みの比較
Wallace Gary Ernst
中生代後期における古太平洋プレートの沈み込み時,膨大な金鉱床が中国の東部〜中央部と東アジアの延長部およびクラマス山と北部カリフォルニア・シェラネ バダ山麓で形成された.東アジアでは,初期の横ずれ運動と305-210 Maの大陸衝突が,高圧〜超高圧変成作用を伴う造山運動を引き起こしたが,広範な中性〜酸性の火成活動ないしは大量の熱水性金鉱床は伴わなかった.同様 に,北部カリフォルニアでは,380 Maから160 Maの間,軽微な展張および圧縮を伴う横ずれ運動が,海洋性テレーンのエピソディックな衝突(stranding)を引き起こしたが,わずかな花崗岩質マ グマの活動とわずかな金鉱床をもたらすに留まった.しかし,これら両者の大陸縁辺域において,白亜紀の海洋リソスフェアのほぼ正面衝突による破壊は,持続 的な沈み込み(underflow)を引き起こし,深度100 kmの火成活動の場に達し,沈み込んだ苦鉄質〜超苦鉄質プレートは脱水して,大量のカルクアルカリマグマによる島弧火成活動をもたらした.中〜上部地殻へ の深成岩体の上昇は二酸化炭素と硫黄を含む流体を放出する,あるいは接触変成作用を受けた母岩脱ガス作用を引き起こした.このような熱水流体は金を破砕帯 や断層帯に沿って運び,やがて冷却し,流体の混合を起こし,蛇紋岩や大理石といった対照的な組成の母岩と反応し,局所的に沈殿させた.これとは対照的に, 大陸地殻が100 kmまで沈み込むと,わずかな花崗岩質メルトとわずかな金鉱脈のみが形成された.大陸縁や島弧における貴重な金属を含む流体の移動には,大陸リソスフェア ではなく海洋リソスフェアが長期にわたって継続的に沈み込むことを必要とする.
Key Words : Continental plate subduction, hydrothermal gold deposits, oceanic plate subduction
[Research Articles]
3. Orthopyroxene–cordierite mafic gneiss from the Nomamisaki metamorphic rocks, Southern Kyushu, Japan: Implication for western continuation of the Usuki–Yatsushiro Tectonic Line, Takeshi Ikeda, Aya Hiramine and Tetsuji Onoue
南部九州,野間岬変成岩類中の斜方輝石−菫青石塩基性片麻岩:臼杵−八代構造線の西方延長の推定
池田 剛,平峯 綾,尾上 哲治
南部九州,野間岬に分布する野間岬変成岩類から斜方輝石−菫青石を含む塩基性片麻岩を見い出した.鉱物組み合わせは斜方輝石,菫青石,黒雲母,斜長石,イ ルメナイトである.最高変成温度は,斜方輝石と黒雲母のFe, Mg 交換反応に基づく温度計を用いて,680℃と推定された.圧力の上限を菫青石の安定領域から推定し,菫青石 = ザクロ石 + 石英 + 珪線石 の反応より,4.4 kbar と見積もった.これらの変成条件より野間岬変成岩類が低圧高温型の変成作用を被ったことが明らかになった.変成年代に議論の余地が残されるが,変成条件の 比較より,野間岬変成岩類は肥後変成岩類の西方延長とみなすことができる.従って,肥後帯の南限を定義する臼杵−八代構造線は,南部九州では野間岬変成岩 類の東側に位置すると考えられる.
Key Words : Orthopyroxene, cordierite, Nomamisaki metamorphic rocks, Usuki–Yatsushiro Tectonic Line
4. Formation and deformation processes of late Paleogene sedimentary basins in southern central Hokkaido, Japan: Paleomagnetic and numerical modeling approach, Machiko Tamaki, Shigekazu Kusumoto and Yasuto Itoh
中央北海道南部域における古第三紀堆積盆の形成過程と変形運動評価 〜古地磁気学的手法と数値モデリングからのアプローチ〜
玉置真知子,楠本成寿,伊藤康人
中央北海道南部域における古第三紀堆積盆の形成過程と変形運動を評価するため,古地磁気学的手法と数値モデリングからアプローチをおこなった.馬追−夕張 地域に分布する古第三紀堆積物の古地磁気偏角は,中新世の回転運動の影響を除いた結果,有意な東偏を示し堆積期間中の回転運動が示唆される.また,プルア パート運動に伴って形成したとされる南長沼堆積盆をディスロケーションモデリングで再現した結果,必要とされる横ずれ量は約30 kmであることが示された.堆積期間から想定される横ずれ速度は約10 mm/yrとなる.本研究の結果から,南長沼堆積盆を形成した横ずれ断層は古第三紀の主要な構造境界であることが示唆され,その活動はユーラシア東縁の広 域な再配列に影響を与えたと考えられる.
Key Words : dislocation modeling, late Paleogene, paleomagnetism, pull-apart basin, southern central Hokkaido
5. Geochemistry of the Zargoli granite: Implications for development of the Sistan Suture Zone, southeastern Iran, Mehdi Rezaei-Kahkhaei, Ali Kananian, Dariush Esmaeily and Abbas Asiabanha
Zargoli花崗岩の地球化学:イラン南東部Sistan Suture Zoneの発達因
Mehdi Rezaei-Kahkhaei,Ali Kananian,Dariush Esmaeily,Abbas Asiabanha
Zahedan北西部において北東ー南西方向に分布するZargoli花崗岩は,始新世から漸新世の広域変成作用を受けたフリッシュタイプの堆積物であ る.鉱物のモード比と化学組成は,この深成岩体が,黒雲母花崗岩と黒雲母花崗閃緑岩で構成されていることを示し,迸入時に周囲の岩石と混合し,そのため化 学組成がわずかにAlに富んでいる.これらの岩石のSiO2量は62.4-66 wt%で,Shandのアルミナ飽和指数[Al2O3/(CaO+Na2O+K2O)]は約1.1である.化学組成のばらつきは,主に結晶分化および黒雲 母の不均一な分布による.これらの岩石の特徴は,大陸衝突後に形成される典型的な花崗岩質岩に類似している.コンドライトで規格化された希土類元素パター ンは,(La/Lu)N=2.25-11.82で,著しいEuの負の異常(Eu/Eu*=3.25-5.26)をもつ.ジルコン飽和温度計は,妥当なマグ マからのジルコンの晶出温度(767.4-789.3℃)を与える.これらの特徴は,中間的なMg# 値[=100Mg/(Mg + Fe)] (44–55),Fe + Mg + Ti (millications) = 130–175, Al–(Na + K + 2Ca) (millications) = 5–50などの値を考慮すると,これらの岩石が石英-長石に富む変成した火成岩からなる下部地殻の脱水を伴う部分溶融に由来することを示唆している.
Key Words : I-type, Iran • geochemistry, meta-igneous source, petrogenesis, post-collision granite, Sistan Suture Zone, Zargoli granite
6. Early Oligocene alkaline lamprophyric dykes from the Jandaq area (Isfahan Province, Central Iran): Evidence of Central–East Iranian microcontinent confining oceanic crust subduction,
Ghodrat Torabi
Jandaq地域(イラン中部エスファハーン地域)に分布する漸新世初期のアルカリ・ランプロファイアー岩脈:海洋地殻の沈み込みを規制する中部−東イランマイクロコンチネントの証拠
Ghodrat Torabi
Jandaq地域に分布するランプロファイアーは南北方向の8つのほぼ平行な岩脈群として,Pis-Kuh層の始新世火山岩と堆積岩を切って産する.これらランプロファイアーは,主に,ケルスート閃石,単斜輝石,カンラン石,長石,イルメナイト,スピネル等の初生鉱物からなる.これらはアルカリ成分,TiO2, LIL元素,軽希土類元素(LREE)に富み,SiO2量は41.7-46.2 wt%である.鉱物学的および化学的な特徴から,カンプトナイトとアルカリランプロファイアーに分類される.これらの岩石は,Euの正の異常を示し,重希土類元素(HREE)に対し,LREEに著しく富むとともに,広い範囲のZr/Hf比を持つことで特徴づけられる.これら岩石の地球化学的特徴は,ランプロファイアー・マグマが沈み込みスラブの脱水溶融によって生じた炭酸塩成分に富んだ流体による交代作用を顕著に受けた角閃石-ざくろ石レルゾライトの低度の溶融に由来することを示唆している.Jandaq地域のランプロファイアの火成活動は,三畳紀から始新世までの海洋地殻を閉じこめる中央〜東イランの微小大陸の沈み込みと漸新世初期のJandaq地域の展張盆によって引き起こされた減圧下での溶融に起因している.
Key Words : alkaline rocks, central Iran, dyke, early Oligocene, Jandaq, lamprophyre
7. Geochemistry and petrology of garnet-bearing S-type Shir-Kuh Granite, southwest Yazd, Central Iran, Mariyam Sheibi, Dariush Esmaeily, Ann Nédélec, Jean Luc Bouchez and Ali Kananian
中部イラン,ヤズド地域南西部に分布するざくろ石を含むSタイプSir-Kuh花崗岩の地球化学と岩石学
Mariyam Sheibi,Dariush Esmaeily,Ann Nédélec,Jean Luc Bouchez,Ali Kananian
中央イランに分布するジュラ紀Shir-Kuh花崗岩質バソリスは,ジュラ紀の砂岩と頁岩を貫いている.バソリスは,(i)北部の花崗閃緑岩質相,(ii)バソリス全体に広く分布するモンゾ花崗岩質相,(iii) 北西縁部に沿って分布する優白色花崗岩質相,の3相からなる.花崗閃緑岩は,主に斜長石,石英,カリ長石,黒雲母からなり,少量の白雲母,ざくろ石,菫青石,イルメナイト,ジルコン,モナザイトを含む.花崗閃緑岩質相は,主にCaに富んだ斜長石の核部と黒雲母の細粒の集合体で特徴づけられる様々な量のレスタイト鉱物を含む.花崗閃緑岩と同様の構成鉱物をもつモンゾ花崗岩は,菫青石を含むややマフィックなものから白雲母に富むフェルシックなものまで幅がある.小規模な岩株や岩脈として産する優白色花崗岩は,主に石英,カリ長石,Na斜長石からなる.バソリスは,過アルミナ質,カルクアルカリ質で,Na2O量(=2.74%),Al2O3/(CaO + Na2O + K2O) (A/CNK)比 (=1.17), K2O/Na2O 比(=1.39),(87Sr/86Sr)i = 0.715)の値から示されるように典型的なSタイプである.また,Rb, ThやK等のLIL元素に富み,NbやTi等のHFS元素に乏しい.コンドライトで規格化した希土類元素のパターンは,軽希土類元素(LREE)に富むこと((La/Yb)N=4.5-19.53),未分化の重希土類元素((Gd/Yb)N=0.98-2.88),顕著なEuの負の異常で特徴付けられる.Shir-Kuh花崗岩の初生マグマは,地殻中の斜長石に富む変成堆積岩起源(変成グレイワッケの局所的なアナテクシス)で,マントルの溶融した成分からの熱の導入を伴う.結晶分化作用に先立つ初生メルトからのレスタイト結晶の分離は,バソリス内での効果的な分離プロセスであったと考えられる.
Key Words : garnet, Iran, peraluminous, restite, S-type granitoids
8. Pressure-temperature history of titanite-bearing eclogite from the Western Iratsu body, Sanbagawa Metamorphic Belt, Japan, Shunsuke Endo
三波川変成帯・西五良津岩体の含チタナイトエクロジャイトの温度‐圧力履歴
遠藤俊祐
四国中央部三波川帯の西五良津岩体は主に玄武岩および石灰質堆積物を起源とするエクロジャイト岩体のひとつである.本研究は,チタナイトを含むエクロジャイトに焦点を当て岩石学的研究を行った.西五良津岩体は緑簾石‐角閃岩相の変成作用の後,エクロジャイト相変成作用を経験している.温度‐圧力履歴は初期に反時計回り,続いて時計回りという複雑な経路が導出され,三波川沈み込み帯の熱的進化における2つの比較的高温な時期に対応すると考えられる.初期の反時計回り経路は沈み込み開始直後の高温沈み込みに関係づけられる.一方,エクロジャイト相変成作用は,ほかの三波川エクロジャイト岩体において見積もられている温度‐圧力条件とほぼ一致し,各エクロジャイト岩体は連続した大規模なユニットを構成している可能性が高い.また,時計回りの温度‐圧力経路は高温沈み込みへの遷移を示唆し,三波川帯の上昇が海嶺沈み込み直前に起こったとするモデルと調和的である.西五良津岩体は1つの海洋沈み込みサイクルの履歴を保持している可能性が示唆される.
Key Words : eclogite, pressure–temperature path, Sanbagawa Belt, subduction zone tectonics, titanite
9. Geological and mineralogical study of eclogite and glaucophane schists in the Naga Hills Ophiolite, Northeast India, Naresh C. Ghose, Om Prakash Agrawal and Nilanjan Chatterjee
インド北東部,Naga Hillsオフィオライトにおけるエクロジャイトと藍閃石片岩の地質学的および鉱物学的研究
Naresh C. Ghose,Om Prakash Agrawal,Nilanjan Chatterjee
一連の低圧〜高圧変成組合せが,インド−ユーラシア衝突帯のインド・ミヤンマー地域北部,Naga Hills中部地域に分布する白亜紀後期〜始新世のオフィオライト帯の変成塩基性岩と変成チャートに認められる.オフィオライトは,ざくろ石レールゾライトの捕獲岩を含むかんらん岩テクトナイト,層状超苦鉄質−苦鉄質沈積岩,変成塩基性岩,玄武岩質溶岩,火砕岩,斜長岩,遠洋性堆積物からなり,これらは中程度に変成した付加体の堆積岩/基盤岩(すなわちNimi層/Naga変成岩)と海洋性堆積物(Disang flysh)との間のスラスト境界において,ばらばらになった覆瓦状の岩体として産する.オフィオライトは古第三紀のオフィオライト由来の粗粒な砕屑性の堆積物からなるJopi/Phokphur層に覆われる.変成塩基性岩は,バロア閃石と藍閃石を含む高変成度の緑簾石エクロジャイト,藍閃石片岩,低変成の緑色片岩,ぶどう石−クリノクロア片岩を含み,西方スラスト境界で溶岩流と超苦鉄質沈積岩を伴う.変成塩基性岩は,化学組成上,中央海嶺玄武岩にみられるような枯渇したマントル由来のlow-Kソレアイトの性質をもつ.地質温度計は,20 kb,525℃のピーク温度圧力条件を示す.岩体上昇時に後退変成作用を受け,バロア閃石とオンファス輝石が藍閃石に置換され,さらに二次的にアクチノ閃石,曹長石,緑泥石が形成されている.核部のエクロジャイトが連続的に藍閃石片岩と緑色片岩の層に取り囲まれている変成塩基性岩のレンズは,岩体が後退変成作用を受けつつ上昇した証拠を与える.ざくろ石レールゾライトに認められるS-Cマイロナイトと藍閃石片岩の'mica fish'は,オフィオライトが上昇した剪断帯における脆性変形作用を示している.
Key Words : ductile deformation, eclogite, garnet lherzolite, glaucophane schist, Indian Plate, quenched basalt, Naga Hills Ophiolite
10. Large-scale folding in the Asemi-gawa region of the Sanbagawa Belt, southwest Japan, Hiroshi Mori and Simon Wallis
Laura Baker Hebert and Michael Gurnis
西南日本,三波川帯・汗見川地域の大規模褶曲
森 宏,Simon Wallis
一般的に三波川帯は構造的上位ほど,より高変成度となっている.この逆転は,典型的な沈み込み場での初生的な逆転温度構造を反映していると解釈可能である.しかし,四国中央部でみられる変成度の分布の繰り返しは,初生的な温度構造が変成ピーク後の変形の影響を受けてきたことを示す.この繰り返しはテクトニックな不連続作用と広域的な褶曲に起因すると考えられてきた.初生的な沈み込み帯での連続性の保存程度を決定するためには,これら二つの解釈の識別が重要である.岩相および構造解析データは,最高変成域中央部に変成作用後の大規模褶曲が存在することを示す.この褶曲は変成帯の分布が示す温度軸に一致する褶曲軸をもち,この範囲での変成度の繰り返しが,大きな不連続を必要としない,大規模褶曲によって説明可能であることを示す.
Key Words : Asemi-gawa , ductile deformation , fold vergence , large-scale fold , protolith stratigraphy , Sanbagawa Belt
Island Arc 日本語要旨 2010. vol. 19 Issue 1 (March)
Vol. 19 Issue 1 (March)
特集号:Thematic Section:Fluid-rock interaction in the bottom of the inland seismogenic zone
Guest Editors : Masaru Terabayashi, Kazuaki Okamoto, Hiroshi Yamamoto and Yu-Chang Chan
1. Dissecting large earthquakes in Japan: Role of arc magma and fluids
Dapeng Zhao, M. Santosh and Akira Yamada
日本における地殻大地震発生域の地震学的解剖:島弧マグマと流体の関与
趙 大鵬,M. Santosh, 山田 朗
近年の高解像度地震波トモグラフィーによって得られた,1995-2008年に日本列島で発生した地殻内大地震の発生域における3次元地震波速度構造とそ の解釈について,本論文において統合的論述を行う.最も特徴的な構造異常は,本震の震源直下の地殻とマントル最上部において明瞭な地震波低速度・高ポアッ ソン比である.これは,沈み込むスラブの脱水とマントルウェッジ内のコーナーフローによってもたらされた島弧マグマや流体の存在を示唆している.また,1885-2008年の期間に発生した164個の地殻内地震(マグニチュード5.7-8.0)の分布には,地殻・マントル最上部内の地震波低速度異常 の分布との間に明らかな相関が認められる.これらを踏まえ,現在までに行われてきた日本における地球物理学的観測事実を説明するための定性的モデルを提案 する.大地震の震源核の形成は,応力・摩擦といった物理的プロセスのみならず,沈み込みのダイナミクスや地殻・上部マントルの構成物質の物理的・化学的特 性,特に島弧マグマと流体が深く関与していると考える.
Key Words : arc magma, fluids, large earthquakes, mantle wedge, seismic tomography, slab dehydration
2. Silicification of pelitic schist in the Ryoke low-pressure/temperature metamorphic belt, Southwest Japan: Origin of competent layers in the middle crust
Masaru Terabayashi, Hiroshi Yamamoto, Eri Hiwatashi and Kouki Kitajima
西南日本の低P/T比型領家変成帯における泥質片岩の珪化作用:中部地殻におけるコンピテント層の起源
寺林 優,山本啓司,樋渡絵理,北島宏輝
西南日本の岩国—柳井地域において,白亜紀の低P/T型領家変成帯中にコンピテントな珪化岩が分布する領域があることを確認し,それが中部地殻での地震波反射面であるブライトレイヤーに相当するものであることを提案する.珪化岩は緑色片岩相の泥質変成岩の中に厚さ数メートルから15メートルほどの層状あるいはレンズ状岩体として露出する.珪化岩分布領域の構造上の厚さは約1キロメートルである.珪化岩層またはレンズのみかけの下側とその下位にある黒雲母片岩との境界は明瞭であるが,上位側の泥質片岩との境界は漸移的である.珪化岩を構成する鉱物は細粒の石英,少量の白雲母と黒雲母であり,有色鉱物の一部は変質して脱色している.このことは,珪化作用が泥質片岩の色を淡灰色や乳白色に変えたことを意味する.珪化岩中には片理面と高角度で交わる石英脈が発達するが,下位の黒雲母片岩中には流動変形を被った片理に平行な石英脈が認められる.このような石英脈の出現様式は,珪化岩が下位の黒雲母片岩に対してコンピテントであることを示している.このようなコンピテンスの大きな差は,地震波の明瞭な反射面となると考えられる.中部地殻に珪化岩層がある程度の頻度で存在していると,地震波を強く反射するブライトレイヤーとなる可能性がある.
Key Words : bright-layer, competence, large inland earthquake, seismogenic layer, silicification
3. Simultaneous measurements of compressional wave and shear wave velocities, Poisson’s ratio, and Vp/Vs under deep crustal pressure and temperature conditions: Example of silicified pelitic schist from Ryoke belt, Southwest Japan
Yuki Matsumoto, Masahiro Ishikawa, Masaru Terabayashi and Makoto Arima
地殻深部相当の温度圧力条件下におけるP波・S波速度、ポアソン比、Vp/Vs比の同時測定:西南日本領家帯に産する珪化泥質片岩の例
松本有希, 石川正弘, 寺林優, 有馬眞
P波・S波同時発信型のデュアルモード圧電素子を用いた岩石の弾性波速度測定では,P波速度(Vp)とS波速度(Vs)を同時測定することが可能であり,弾性波速度や弾性率,そしてそれらの温度微分係数・圧力微分係数をより精密に測定することが可能である.特に,測定試料長の変化に依存しないパラメータであるVp/Vs比は,従来のシングルモード圧電素子を用いた測定実験(VpおよびVsを個別に測定)と比較して,格段に測定精度が向上した.本論では,西南日本領家帯に産する珪化泥質片岩を例として,P波・S波速度,ポアソン比,Vp/Vsの同時測定の結果を示し,デュアルモード圧電素子を用いた岩石の弾性波速度測定の意義を述べる.
Key Words : bright spot, elasticity, Vp/Vs, Poisson's ratio, quartz, Ryoke Belt
4. Trace-element compositions of single fluid inclusions in the Kofu granite, Japan: Implications for compositions of granite-derived fluids
Masanori Kurosawa , Satoshi Ishii and Kimikazu Sasa
甲府花崗岩の単一流体包有物の微量元素組成:花崗岩起源流体の組成に対する意味
黒澤正紀、石井 聡、笹 公和
島弧の花崗岩起源流体の化学組成と挙動を検討するため,甲府の中新世黒雲母花崗岩体の晶洞・ペグマタイト・石英脈の石英に含まれる流体包有物を粒子線励起X線分析法(PIXE)で分析した.流体包有物の大部分は水を含む二相包有物で,岩塩を含む多相包有物も岩体上部の石英脈に観察された. 晶洞の流体包有物の元素組成から,花崗岩固結時の初生的な放出流体は数百〜数十ppmのMn・Fe・Cu・Zn・Ge・Br・Rb・Pb・Baを含み,塩濃度約10wt%の組成だったと推定された.この流体は,花崗岩の固結条件と包有物の均質化温度に基づき,温度530〜600 °C・圧力約 1.3〜1.9 kbで形成されたと考えられる.多相包有物は,岩体内を上昇する流体の一部が沸騰して生じた可能性が高い.多相包有物は,数百〜数万ppmのFe・Mnと数百〜数千 ppm のCu・Zn・Br・Rb・Pbを含み、約35 wt % の塩濃度である.晶洞や石英脈の二相包有物の組成多様性は,副次的には地表水による希釈の影響も伴うが,大部分は鉱物の晶出によって説明される.そのため,花崗岩体中の花崗岩起源流体の組成と挙動は,初生的な放出流体の鉱物晶出や沸騰・希釈によって説明される可能性がある.
Key Words : fluid inclusion, granite, hydrothermal ore deposit, PIXE, trace element
5. Geographical distribution of helium isotope ratios in northeastern Japan
Keika Horiguchi, Sadato Ueki, Yuji Sano, Naoto Takahata, Akira Hasegawa and George Igarashi
東北日本におけるヘリウム同位体比の空間分布
堀口桂香,植木貞人,佐野有司,高畑直人,長谷川昭,五十嵐丈二
東北日本において,温泉ガス中に溶存するヘリウム同位体比を測定し,その空間分布を詳細に調べた.その結果,火山フロント沿いの同位体比には地域的な分布がみられ,北緯38º〜39ºの地域は多くの観測点で2〜5 RAであるのに対し,北緯39.0º〜39.5ºの地域では1 RA程度であり,地殻起源4Heの卓越した分布を示した.こうした火山フロントに沿った地域差は,高密度観測を実現した本研究によって初めて明らかにされた事実である.
また,同位体比の空間分布と,地球物理学研究により推定された地下構造とを比較検討し,両者の空間的特徴には関係性があることを見出した.これは,ヘリウム同位体比の空間分布が,深部流体やメルトの起源と挙動を探るための有力な手段であることを示唆する.
Key Words : 3He/4He ratios, northeastern Japan, seismic tomography, subduction zone
通常論文
1.Geochemistry of late Cenozoic lavas on Kunashir Island, Kurile Arc
Alexey Y. Martynov, Jun-Ichi Kimura, Yuri A. Martynov and Alexsander V. Rybin
クリル弧国後島の後期新生代溶岩の地球化学
Alexey Y. Martynov, 木村純一, Yuri A. Martynov and Alexsander V. Rybin
クリル弧南帯の国後島の中期中新世から第四紀溶岩の主成分元素,微量成分元素,Sr-Nd-Pb同位体組成について検討した.溶岩は玄武岩から流紋岩で,マフィック溶岩は典型的な海洋島弧の特徴を持ち,顕著な地殻あるいはリソスフェアの混染は認められない.溶岩は島弧横断方向の組成変化を示し,背弧側に向かって流体で動きにくい元素の濃集がみとめられる.しかし,この傾向はBやSbやハロゲンのような元素にはみとめられない.Sr-Nd-Pb同位体組成はインド洋マントルドメインの特性を示す枯渇マントルから由来したことを示す.NdとPbは火山フロントで放射性であるがSrはより放射性が弱い.Nd同位体比はTh/NdあるいはNb/Zrのような液層濃集元素比の変化と連関しており,高電荷イオン元素や重希土類元素を運搬することができるスラブメルトあるいは超臨界溶液によってスラブ由来の堆積岩成分がマグマ組成に寄与したことをしめす.流体可溶の元素たとえばBaは,すべての玄武岩に富んでおり,変質海洋地殻由来の流体の寄与が示唆される.このように,クリル弧の溶岩はスラブ堆積物と変質海洋地殻双方の組成の影響を受けている.このようなマグマ供給系は中期中新世から現在まで活動的である.
Key Words : across-arc variation , incompatible element , Indian Ocean mantle , Kurile Arc , late Cenozoic , Sr–Nd–Pb isotopes
2. Mineral classification from quantitative X-ray maps using neural network: Application to volcanic rocks
Takeshi Tsuji , Haruka Yamaguchi, Teruaki Ishii, Toshifumi Matsuoka
ニューラルネットワークを用いた鉱物マッピング手法の開発:火山岩への適用
辻 健,山口はるか, 石井輝秋,松岡俊文
電子線マイクロプローブアナライザによって得られた元素マップから,鉱物マップを作成する手法を開発した.元素マップから鉱物を推定する際には,各鉱物の元素組成を考慮する必要がある.しかし,火山岩のように多数の鉱物が混在している岩石では,多種類の元素を考慮しないと鉱物マップの作成が困難である.つまり,多次元空間で元素組成を比較する手法の導入が不可欠といえる.本研究では,自己組織化マップと呼ばれているニューラルネットワークを用いて,数種類の元素マップから鉱物を分類することを試みた.自己組織化マップでは,教師無しの学習を行うことにより,多次元の入力(元素)データを二次元平面に射影することができる.その多次元の元素データが射影された二次元平面上において,各鉱物のクラスタリングを行うことにより,鉱物マップを作成することができる.本研究では,ファン・デ・フーカプレート海嶺東翼部から取得された海洋性玄武岩試料に,自己組織化マップを用いた鉱物分類手法を適用した.その分類された鉱物マップから,枕状玄武岩中心部,枕状玄武岩縁部,塊状玄武岩といった岩層による鉱物組成・テキスチャの特徴を定量的に評価することができた.さらに多種類の鉱物が混在する岩層に対する本手法の有効性を調べるため,変質玄武岩に対して鉱物マッピングを行った.変質玄武岩は多くの二次鉱物を持つが,自己組織化マップを用いることで,8種類の鉱物に分類を行うことができた.この結果から鉱物数が増えた場合でも,自己組織化マップによる分類が有効であることが示された.
Key Words : electron probe microanalyzer (EPMA) , mineral distribution map , self-organizing map (SOM) , volcanic rocks, X-ray intensity maps
3. Internal reflection pattern of Korea Strait shelf mud (Nakdong River subaqueous delta) off southeast Korea and implications for Holocene relative base-level change
Gwang H. Lee, Dae C. Kim, Mi K. Park, Soo C. Park, Han J. Kim, Hyeong T. Jou and Boo K. Khim
韓国南部沖,朝鮮海峡陸棚上に分布する泥質堆積物(洛東江の水中デルタ)の音波探査記録の反射パターンとその完新世浸食基準面変化復元における意義
Gwang H. Lee, Dae C. Kim, Mi K. Park, Soo C. Park, Han J. Kim, Hyeong T. Jou and Boo K. Khim
朝鮮海峡の陸棚上に分布する泥質堆積物(洛東江の水中デルタ;KSSM)は,朝鮮半島(韓半島)南部沖の内側陸棚における最も顕著な完新世堆積物である.マルチチャンネル・スパーカーによって得られた音波探査断面とコア試料の14C年代により,KSSMの堆積物が最も厚い(層厚60m以上)領域で3つのユニットが認められた.それらは,(i) 基底部の薄い海進期堆積体(暦年代>8000年),(ii) 中部の厚い(層厚40m以上)プログラデーショナルな堆積様式を示す堆積体(暦年代=2600〜8000年),(iii) 上部の薄い海進期堆積体(暦年代<2600年)である.KSSM内部における音波探査記録の反射パターンは,本地域では完新世の大部分の期間,浸食基準面が比較的深い環境(現在の水深70mより深い場所)にあったことを示す.その後,浸食基準面は中部層の堆積時には20mほど徐々に深くなり,上部層堆積時には上昇した.これらのデータは,地域的な海洋環境に対しては,浸食基準面の方が相対的海水準より鋭敏に応答することを示している.
Key Words : base-level change , Korea Strait shelf mud , sealevel change , subaqueous delta
4. Late Cretaceous-Cenozoic exhumation of the Yanji area, northeast China: Constraints from fission- track thermochronology
Xiaoming Li, Guilun Gong, Xiaoyong Yang and Qiaosong Zeng
中国北東部、Yanji地域の白亜紀後期−新生代の上昇:フィッション・トラック熱年代学からの制約
Xiaoming Li, Guilun Gong, Xiaoyong Yang and Qiaosong Zeng
中国、ロシア、北朝鮮との境界に位置し,顕生代花崗岩類が広く露出するYanji地域は、南のNorth China Blockと北東のJiamusi-Khanka Massifsとの間の造山コラージュの一部をなすと考えられてきた.本研究では,Yanji地域における花崗岩試料のアパタイトのEPMA分析とともに,アパタイトおよびジルコンのフィッション・トラック分析により,後期中生代以降の冷却と上昇、浸食の履歴について詳細に調べた.その結果,(i)ジルコン、アパタイトのフィッション・トラック年代について,それぞれ91.7-99.6 Ma、76.5-85.4 Maという値が得られた,(ii)すべてのアパタイトのフィッション・トラック長は,平均値12-13.2 µmで、単峰型の分布をもち,EPMA分析の結果,塩素を含むフッ素燐灰石であった,(iii)アパタイトのフィッショントラック粒子年代とトラック長に基づく熱史モデリングの結果,時間−温度パスは同様のパターンをもち,冷却は15 Ma以降加速された.以上の結果から,われわれは95-80 Maと約15-0 Maの二つの急速な冷却期と80-15 Maの緩慢な冷却期を含む連続的な冷却が後期白亜紀以降,Yanji地域の上昇削剥を通じて起こったと結論する.最大の上昇削剥は、35℃/kmの定常状態の地温勾配下で5 km以上である.テクトニック・セッティングを考慮すると,この上昇削剥は恐らく後期白亜紀以降のユーラシア・プレート下への太平洋プレートの沈み込みに関係している.
Key Words : exhumation, fission-track, late Cretaceous–Cenozoic, Pacific Plate subduction, Yanji area
5. Geophysical implications of Izu-Bonin mantle wedge hydration from chemical geodynamic modeling
Laura Baker Hebert and Michael Gurnis
地球化学・地球力学結合モデルに基づく伊豆・小笠原弧のマントルウェッジの水和における地球物理学的意義
Laura Baker Hebert and Michael Gurnis
本研究では,北部伊豆・小笠原弧の沈み込み帯に関する2次元力学モデルを用いて,地表の地形,重力,ジオイド異常と適合した,マントルウェッジ中に局在する低粘性(ηLV= 3.3 x 1019〜4.0 x 1020 Pa s)・低密度(周囲のマントルと比較して約-10 kg/m3)領域の形状を示す.この低粘性,低密度領域の形状を生じさせた水和構造は,地下150〜350kmにおけるウェッジマントルへの流体の放出によるものである.この結果は,北部伊豆・小笠原弧の沈み込み帯に関する地球化学・地球力学結合モデルや日本列島の下のマントルウェッジに関する非結合モデルによる検討結果と矛盾しない.流体の起源は,沈み込んでいくリソスフェアの蛇紋岩もしくはマントルウェッジ中の安定な含水相(蛇紋石や緑泥石など)であろう.本モデルを用いることにより,他の沈み込み帯においても,地表での地球物理学的観測値の異常を伴う特異な低粘性領域の存在を予測することができる.
Key Words : geoid , gravity, GyPSM-S, Izu–Bonin, low-viscosity channel, topography
6. Neoproterozoic podiform chromitites in serpentinites of the Abu Meriewa-Hagar Dungash district, Eastern Desert, Egypt: Geotectonic implications and metamorphism
Fawzy F. Abu El Ela and Esam S. Farahat
エジプト東砂漠、Abu Meriewa-Hagar Dungash地域の新原生代蛇紋岩中のクロミタイト:造構的解釈と変成作用
Fawzy F. Abu El Ela and Esam S. Farahat
エジプト東砂漠のAbu Meriewa-Hagar Dungash地域において,ハルツバージャイトとダナイト起原の蛇紋岩中のクロミタイトと滑石-炭酸塩岩が,メタガブロ、変成火山岩類(枕状溶岩),変成堆積岩類と共に、パンアフリカン造山運動で形成されたオフィオライトメランジュを構成している.クロミタイトは散点的に分布し,塊状かつ球状の形態をもつ.クロミタイトを構成するクロマイトの核部は高いかつ限定された範囲のCr# 値(=0.65–0.75) とMg# 値(=0.64–0.83)をもち、元の組成が変成作用で改変されなかったことを示している.それ故,クロマイトの核部はクロミタイトを含む高度変成岩の初生マグマ組成および造構的関係を知る上での信頼できる指標として用いることができる.一方,縁部はCr,Fe,Mnに富む高Cr,低Fe3+のスピネルで,AlとMgに枯渇している(Cr#=0.75-0.97、Mg#=0.29-0.79).これは、緑色片岩相−角閃岩相(500-550℃)までの条件下の広域変成作用を受けたことによる.初生クロマイトの組成は、クロミタイトが,周囲の変成火山岩類と同様に,スプラサブダクション帯(島弧縁辺域)における高Mgソレアイト質、おそらくボニナイト質マグマに由来することを示唆している.Abu Meriewa-Hagar Dungash地域のクロミタイトは,メルトと岩石の相互作用によって形成されたものであろう.クロマイトの高いCr#値は,より深所での初生玄武岩質マグマとの相互作用とそれに続く混合による枯渇したハルツバージャイトの部分溶融を示唆している.このようなCrに富むクロマイトはエジプト東砂漠のクロミタイトに普遍的に産し,広範囲の熱異常を示唆しており,おそらくArabian-Nubian Shieldの発達における重要なダイナミックな特徴と関係している.このことは,プルームの相互作用に関係した,おそらくArabian-Nubian Shieldの初期の発達の際の弧状テレーンのoblique convergenceによるアセノスフェアの上昇を含むモデルについての興味を呼び起こす.
Key Words : chromitites , Egypt , Neoproterozoic , ophiolites , Pan-African , serpentinites
7. Aragonite and omphacite-bearing metapelite from the Besshi region, Sambagawa belt in central Shikoku, Japan and its implication
Yui Kouketsu and Masaki Enami
四国中央部別子地域三波川帯におけるアラゴナイトとオンファス輝石を含む変泥質岩の産出とその意義
纐纈佑衣, 榎並正樹
四国中央部三波川変成帯・別子地域の曹長石−黒雲母帯に属する変泥質岩から,アラゴナイトとオンファス輝石の産出を確認した.両鉱物は,パラゴナイトや石英とともにざくろ石の包有物としてのみ産する.一方,基質は,主にフェンジャイト,方解石,曹長石,石英から構成されている.ざくろ石中のアラゴナイト+オンファス輝石+石英の組合せの形成温度圧力は,P >1.1–1.3 GPa, T = 430–550 °Cと見積もられた.また,この試料や周辺の変泥質岩中のざくろ石に包有される石英は,三波川エクロジャイトのそれと同程度の高い残留圧力を保持している.これらの結果は,(1)アラゴナイトとオンファス輝石を含む変泥質岩やその周囲の岩石は,エクロジャイト相変成作用を経験した後に,より低圧の条件下で再結晶したこと,および(2)別子地域・三波川帯におけるエクロジャイト相変成作用を経験した領域は,従来の想定よりも広がることを示唆している.
Key Words : aragonite , eclogite facies , omphacite , Raman spectroscopy , Sambagawa belt
8. Tectonics of an Early Carboniferous forearc inferred from a high-P/T schist-bearing conglomerate in the Nedamo Terrane, Northeast Japan
Takayuki Uchino and Makoto Kawamura
根田茂帯礫岩中の低温高圧型変成岩礫から復元された前期石炭紀前弧テクトニクス
内野隆之,川村信人
前期石炭紀付加体からなる根田茂帯から,低温高圧型変成岩礫や超苦鉄質岩礫を特徴的に含む礫岩を見出した.礫の堆積学的・岩石学的検討から,古アジア大陸東縁部における前期石炭紀島弧−海溝域のテクトニクスを復元した.低温高圧型変成岩礫の主要構成礫である含ザクロ石フェンジャイト片岩礫(モード比:8.4%)は,フェンジャイト冷却年代(347-317 Ma;40Ar-39Ar年代)・ザクロ石組成・鉱物組み合わせから蓮華変成岩に相当する.超苦鉄質岩礫である含クロムスピネル緑泥石岩(モード比:6.4%)は,クロムスピネル組成からオルドビス紀島弧型オフィオライトである宮守−早池峰超苦鉄質岩コンプレックスに相当する.礫の円磨度は,島弧(南部北上帯)起源の火山岩・深成岩などの礫が亜角礫〜超円礫であるのに対し,低温高圧型変成岩礫や超苦鉄質岩礫は角礫〜亜角礫である.この円磨度の差異は後者の原岩が,堆積場(海溝域)により近い位置に露出していたことを示す.このことに加えて,島弧浅海域で堆積した南部北上帯の礫岩に後者の礫はほとんど含まれていないことから,低温高圧型変成岩礫や超苦鉄質岩礫の原岩は前弧域に露出していたと考えられる.また,礫岩の堆積年代(前期石炭紀)と,礫となった低温高圧型変成岩の冷却年代とを考慮すると,低温高圧型変成岩が沈み込み帯深部域から上昇しはじめ前弧域で露出するまでの時間は,30 m.y.以内であった.
Key Words : conglomerate , Early Carboniferous accretionary complex , forearc ridge , high-P/T schist , Nedamo Terrane , tectonic model , ultramafic rocks
9. Subduction of mantle wedge peridotites: Evidence from the Higashi-akaishi ultramafic body in the Sanbagawa metamorphic belt
Kéiko Hattori, Simon Wallis, Masaki Enami and Tomoyuki Mizukami
沈み込むマントル・ウェッジ由来のペリドタイト:三波川変成帯に産する東赤石超苦鉄質岩体の例
服部恵子,Simon Wallis,榎並正樹,水上知行
四国三波川変成帯に産する東赤石岩体は,沈み込み帯における超高圧変成作用を経験した希な含ざくろ石超苦鉄質岩体である。 この岩体は,およそ2 × 5 kmの大きさであり,主に蛇紋岩化を免れたダナイトと少量のウェールライト質岩から構成されている。ダナイトは,Irタイプ白金族元素とCrに富む全岩組成を有し,かんらん石はMgとNiに,そしてスピネルはCrに富む.一方,ウェールライト質岩は,Irタイプ白金族元素とCrに乏しく,易水溶性元素に富んでいる.そして,かんらん石はダナイトを構成するものと比べてNiとMg に乏しく,単斜輝石はAlに乏しい透輝石である.これらの全岩組成や鉱物組成の特徴から,ダナイトをはじめとするかんらん石に富む岩相は,部分溶融の程度が高い溶け残りマントルであり,ウェールライトなど単斜輝石に富む岩相は,島弧下のマントル・ウェッジが部分溶融することによって形成されたメルトの集積相であると考えられる.したがって,東赤石超苦鉄質岩体は,沈み込むスラブによる引きずり込みとマントル流動によって100 km以深にもたらされ高圧変成作用を受けた,前弧域下のマントル・ウェッジの一部であると解釈される.そのような,マントル・ウェッジの活発な流動は,三波川帯の形成が 沈み込み活動の初期段階であったため,スラブ上面に接するマントル・ウェッジが通常の沈み込み帯と比べて高温であり,そこには蛇紋岩が安定に存在せず大きいすべり摩擦が生じたことにより促進された.このような高温条件と活発なマントル流動は,三波川帯の沈み込みが開始した白亜紀当時の北東アジア大陸直下で起きた,アセノスフェアの上昇と東方への水平流動と関係している可能性がある.
Key Words : eclogite , exhumation , garnet peridotites , mantle flow , oceanic subduction , subduction
地質学論集
地質学論集
地質学論集とは、その経緯
日本地質学会は、1968年4月に創立75周年の記念事業を行い、そのときの記念シンポジウムの内容をフルペーパーとして発行することを決め、1968年7月に第1号が発行されました。以後は、年会のシンポジウムのほか科学研究費の総合研究のまとめなども論集として発行されるようになり、発行以来2006年までの38年間に59号を数えました。43号以降は版型もB5版からA4版に変更されています。なお、この十数年の急激な情報伝達手段の変化ならびに研究環境の変化に伴い、学会としての学術誌の発行、普及は残念ながら徐々に困難な状況になり、2004年には、学会の根幹事業である地質学雑誌の発行体制について検討する中で、残念ながら地質学論集は廃止となりました。
バックナンバー
バックナンバーは本会事務局にて購入できます。
■ 在庫案内ページ
CiNii(国立情報学研究所)から閲覧できます
■ CiiNii論文検索ナビゲータ(国立情報学研究所のサーバー)
国立国会図書館デジタルコレクションからも閲覧できます
※一部の号(52, 53, 54, 58, 59号)は,デジタル化対応されておりません.現在国会図書館へ対応を要望中ですが,デジタル化の具体的な時期は未定です.
■ 国立国会図書館デジタルコレクション
リーフレット詳細
リーフレット
▶▶リーフレット購入希望の方はこちら
地質リーフレットたんけんシリーズ5
長瀞たんけんマップー荒川が刻んだ地球の窓をのぞいてみようー
長瀞の岩畳は『ジオパーク秩父』でも重要なみどころのひとつです。長瀞の岩石はどこでできたのか、地形や地質のおはなし、長瀞の楽しみかたなどが、わかり やすく解説されています。観察ポイントごとに写真やイラストが付いていますので、野外での観察にも最適です。教材としても是非ご活用下さい。
編集:日本地質学会長瀞たんけんマップ編集委員会(高木秀雄・本間岳史・露木和男)
発行:一般社団法人日本地質学会
A2版 8折 両面フルカラー印刷 2016年2月20日発行
定価400円(会員頒価 300円)*20部以上ご注文の場合は割引あり
地質リーフレットたんけんシリーズ4
富士山青木ヶ原溶岩のたんけんー樹海にかくされた溶岩の不思議ー
編集:日本地質学会地学教育委員会(編集委員:小尾 靖・鈴木邦夫・高橋正樹・矢島道子)
発行:一般社団法人日本地質学会 2014年3月31日
A2版 8折 両面フルカラー印刷
青木ヶ原の「溶岩」をテーマにした新しいリーフレットができました。道の駅や西湖コウモリ穴など,アクセスしやすい観察ポイントです.写真やイラストをふんだんに使用し,わかりやすく火山現象を解説しています。
定価400円(会員頒価 300円)*20部以上ご注文の場合は割引あり
日本地質学会リーフレット4
日本列島と地質環境の長期安定性
編集 一般社団法人日本地質学会 地質環境の長期安定性研究委員会
発行 一般社団法人日本地質学会
2011年1月刊行 B2版 両面フルカラー印刷
地質環境の長期的利用の観点から、日本の地質環境を分かりやすくまとめたリーフレット。最新のデータに基づき、日本列島の断層運動、火山・マグマ活動等の特徴、そして将来予測の考え方を示しています。多くの方々に活用して頂けることを願っています。
定価 600円(会員頒価 500円)(20部以上ご注文の場合は割引あり)
地質リーフレットたんけんシリーズ3
城ヶ島たんけんマップー深海から生まれた城ヶ島ー
日本地質学会地学教育委員会 編著
2010年9月一般社団法人 日本地質学会 発行
A2版 8折 両面フルカラー印刷
岩礁海岸を中心とした豊かな自然景観を楽しめる城ヶ島。ハンディタイプのリーフレットが出来ました。 裏面は、城ヶ島の空中写真に示した観察ポイントごとに写真やイラスト付きでわかりやすく解説。野外での観察にも最適です。教材としても是非ご活用下さい。
定価400円(会員頒価 300円)(20部以上ご注文の場合は割引あり)
※再入荷(増し刷り)しました!2024.7.23現在
地質リーフレットたんけんシリーズ2
地質リーフレットたんけんシリーズ2
屋久島地質たんけんマップー洋上アルプスは不思議がいっぱいー
編 著:日本地質学会地学教育委員会・屋久島地学同好会
2009年3月31日 日本地質学会 発行
A2版 12折 両面フルカラー印刷
定価400円(会員頒価 300円)(20部以上ご注文の場合は割引あり)
かわいいキッキくんとシカノスケ博士が屋久島の地質をわかりやすく紹介してくれます。 裏面は、地図で示した観察ポイントごとに写真やイラスト付きでわかりやすく解説。ハンディタイプで、野外での観察にも最適です。教材としても是非ご活用下さい。
地質リーフレットシリーズ1
※売り切れ
B2版.5万分の1地質図と解説からなります.箱根火山の研究史から最新の研究成果までフルカラーで詳しく紹介されています.
紙は,水に強く、鉛筆等での書き込みも容易なレインガード紙を使用していますので野外での調査・巡検に最適です.広くご活用下さい!
学会では今後各地の国立公園をターゲットに,地質リーフレットを製作していく予定です.子供版「箱根火山たんけんマップ」ともども,皆様のご意見・ご要望をお待ちしております.
会員頒価 1000円/部 売り切れ
(20部以上の場合は割引あり)
日本地質学会国立公園地質リーフレット1「箱根火山」編集委員会編
協力:神奈川県立生命の星・地球博物館,神奈川県温泉地学研究所,関東第四紀研究会,
NPO法人地質情報整備活用機構(GUPI),神奈川県,アジア航測(株)
地質リーフレットたんけんシリーズ1 箱根火山たんけんマップ ー今、生きている火山ー
A2版フルカラー、小・中学生向け地質リーフレット。箱根火山の観察ポイントをわかりやすく探検マップにまとめました。コンパクトで野外での見学に最適です。教材としてもぜひご活用下さい。
探検マップを持って、さあ!フィールドに出かけよう。
定価400円(会員頒価 300円)
上記のほか下記「日本地質学会リーフレット」シリーズも好評発売中です。
大地の動きを知ろう—地震・活断層・地震災害— ※売り切れ
定価300円(会員頒価200円)
大地のいたみを感じよう?地質汚染Geo−Pollutions
定価300円(会員頒価200円)
大地をめぐる水—水環境と地質環境—
定価400円(会員頒価300円)
購入希望の場合は,氏名・送付先・電話番号・購入冊数を明記の上,メールもしくはFAXで学会事務局までお申し込み下さい.会社名等での請求書が必要な方はその旨明記して下さい.
メール:main@geosociety.jp(@を半角にして下さい)
ファックス:03-5823-1156
また箱根のリーフレットは、神奈川県立生命の星地球博物館や箱根周辺の土産物ショップなどでも販売しています.
Island Arc
お知らせ
NEW Wileyの査読システムREXにおいて査読者が添付ファイルをアップロードできるようになりました。 REXの改良にともなう機能について、あるいはこれからの更新予定案件はこちら(2024.12.26)
Wileyとオープンアクセス転換契約を締結している研究機関(下記リンク)に所属する著者は、機関の費用負担でオープンアクセスとして論文を公表できる可能性があります。詳細については、所属機関のAPC支援事業担当者にお問い合わせください。こちらから(2024.9.24)
Island Arcのオンライン投稿・査読のプラットフォームがScholorOneからResearch Exchange (REX)に変更されました。また、オンライン出版の論文デザインもリニューアルします。 REXについては、こちらのサイトの動画を参照ください。REX Submission(投稿サイト)はこちらから(2024.6.27)
Accepted Articles廃止のお知らせ:2023年3月以降、受理原稿(Accepted Articles: AA)の早期オンライン掲載が 廃止されます。ワイリー社全体の方針で、背景に出版物の責任問題(出版規範 委員会の定義では、AA版と正式版[Version of Record: VOR版]のどちらも 出版物扱い)、取り下げ・撤回増加の懸念、ペーパーミル問題の悪化(論文 作成・販売する違法組織織を利用した不正論文の増加)、があります。(2023.2.21)
LaTeXテンプレートを公開しました。クラウド型共同執筆ツールのAuthoreaでも利用可能です。
facebookでは最新情報を随時更新しています
2020年からIsland Arcが新しく変わります(出版までの時間の大幅短縮,論文アクセスの迅速化,超過ページ料金の廃止,編集事務局の強化など)
Island Arc
ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2023: 162/201 (Geosciences Multidisciplinary)
Impact Factor(2023): 1.0
Earth Sciences of Convergent Plate Margins and Related Topics
Published on behalf of the Geological Society of Japan in association with the Japan Association for Quaternary Research, Japan Association of Mineralogical Sciences, Palaeontological Society of Japan and the Society of Resource Geology
Island Arc is the official English journal of the Geological Society of Japan. The Journal publishes original research articles dealing with earth science research activities in the western Pacific rim and Asia, as well as in other parts of the world. Papers in the following fields will be considered: structure, dynamics and evolution of plate convergence zones including trenches, island and continental arcs, back-arc basins and collision zones in modern and ancient settings.
最新号のご案内
↑↑↑最新刊はこちらから↑↑(wileyのサイト)
*Vol.25(2016年)から,論文とあわせて日本語抄録が掲載されています。Wiley社のページよりご覧下さい。また,学会の会員ページからログインすると全文が無料閲覧できます。
▶▶Wiley Online Libraryの便利な機能のご紹介(pdf)
Award
■ Island Arc Award (2007 - )
■ Most Downloaded Award (2010 - )
購読方法
■オンライン購読(購読費)
Island Arc は2013年(Vol. 22)より完全電子ジャーナル化いたしました(オンライン閲覧のみ)。
地質学会会員の方:無料でオンライン閲覧が可能です。会員ページにログインしてご覧ください。※各会員のID とパスワードが必要となります.ログイン方法の詳細はこちら.
非会員の方:個人でのオンライン購読契約は行っておりません。図書館等の購読契約している機関等でご覧ください。
研究所・図書館及び企業など,機関購読を申し込まれる場合には,代理店を通されるか,あるいは直接Wiley社へお申し込みください.
「機関購読料サイト」http://ordering.onlinelibrary.wiley.com/subs.asp?ref=1440-1738&doi=10.1111/(ISSN)1440-1738
Island Arc 投稿案内
Manuscript submissions to Island Arc can now be made online through REX. Submit articles quickly and easily through a safe and secure site, and track the progress of your manuscript any time of the day.
■ オンライン投稿入り口(REX Submissionサイト)」
Island Arc 電子投稿(Wiley社サーバーにて行います)
※投稿にあたり,ご不明な点があれば,IAR編集事務局(Island_Arc_editorialoffice@wiley.com)へお問い合わせください.
■ Wiley社 Island Arcのページ
※特集号を企画されたい方は、特集号のタイトル(暫定可)、内容説明を Island Arc 編集事務局宛にお送りください。企画が承認された後、特集号の流れのご案内とご提出いただくリストのひな形をお送りいたします。
転載許可申請等
下記をご参照ください
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1440-1738/homepage/Permissions.html
編集委員会:Editorial Board/Editorial Advisory Board
こちらから(wileyのサイト)
Island Arcについての問い合わせ先
Production Editor:Jovel Domingo (IAR[at]wiley.com)([at]を半角に修正して下さい)
Editorial Assistant:Juhi Jahan (Island_Arc_editorialoffice[at]wiley.com)([at]を半角に修正して下さい)
2020年からIsland Arcが新しく変わります
2020年からIsland Arcが新しく変わります
◆投稿から出版までの時間が大幅に短縮されます!:「Island Arcは出版までに時間がかかる」そんなイメージをお持ちではありませんか?それは過去の話です.Island Arcでは査読体制の強化と編集体制の改善に加え,日本語要旨が廃止される2020年からは,投稿から出版(オンライン掲載)までの時間が標準で3ヶ月程度となる見込みです.また,年間1号の出版となるためEarly Viewの段階を経ず,受理された論文は五月雨式に出版されます.これにより各種データベースへの論文の登録が早まります.
◆論文アクセスの迅速化:Island Arcに掲載された論文のQRコードを掲載します.要旨だけでなく全文へのアクセスが迅速になります.
◆超過ページ料金の廃止:長い論文が推奨されるわけではありませんが,超過ページ料金の心配なく,論文を投稿いただけるようになりました.
◆編集事務局の強化:編集事務局が海外に移転され,2〜3名体制で査読・編集・出版プロセスの支援が行われます.質問対応などに遅延が生じない体制ができました.
また,すでに始まっているサービスですが,
◆Video Abstractの掲載が可能です:ビデオにより専門分野外の読者にもアピールしやすい論文紹介が可能になりました.
Island Arcでは投稿者や読者の皆様の利便性を向上するとともに,日本地質学会を代表する,さらに魅力的な国際誌を目指して,これからも様々な改革を行ってまいります.
Island Arcアクセスはこちらから
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
(2019年12月 Island Arc編集委員会)
(2020年12月一部変更)
Island Arc 日本語要旨 2015. vol. 24 Issue 1 (March)
Vol. 24 Issue 1 (March)
特集号
Carbonate sedimentation on Pacific coral reefs
Guest Editors: Hiroya Yamano and Yasufumi Iryu
太平洋のサンゴ礁における炭酸塩の堆積過程
山野博哉・井龍康文
1. Preface
Hiroya Yamano and Yasufumi Iryu
序文
山野博哉・井龍康文
本特集号は,太平洋の日本,ニューカレドニア,タヒチにおける最近の炭酸塩研究からなる.層相区分に関して,粒径や構成物を用いた区分とともに,サンゴや大型底生有孔虫を指標とした区分の詳細化が紹介されている.層相とともに炭酸塩に記録される同位体比や微量金属も古環境の指標として有用である.本特集では,炭酸塩(シャコ貝)を用いた古環境復元が紹介されている. この特集号の編者と著者の多くは,去る2011年10月に亡くなったGuy Cabioch博士と共同研究を進めていた.本特集号の成果は彼との共同研究の成果の一部であり,本特集号を彼に捧げるものである.
2. Modern carbonate sedimentary facies on the outer shelf and slope around New Caledonia
Hiroya Yamano, Guy Cabioch, Bernard Pelletier, Christophe Chevillon, Hiroyuki Tachikawa, Jérôme Lefêvre and Patrick Marchesiello
ニューカレドニアの島棚の現世炭酸塩堆積層
山野博哉・Guy Cabioch・Bernard Pelletier・Christophe Chevillon・立川浩之・Jérôme Lefêvre・Patrick Marchesiello
ニューカレドニア周辺の島棚において,水深75-720mの33地点から現世堆積物を採取し,粒径と構成物に基づいて層相区分を行った.層相は,1) ロドリスとマクロイド,コケムシ,大型底生有孔虫,2) コケムシ,大型底生有孔虫,泥,3) 浮遊性有孔虫と泥,4) 無藻性サンゴ の4つに区分された.それぞれの層相は基本的に水深に規定されていたが,海底の地形によっては水深の小さい地点からの堆積物が混入する場合もあった.こうした層相は同様の緯度にある他地域でも観察されるため,ニューカレドニアの炭酸塩層相は熱帯・亜熱帯における層相を代表するものであると考えられる.
Key Words: carbonate sediment, coral reef, rimmed shelf, New Caledonia.
3. An identification guide to some major Quaternary fossil reef-building coral genera (Acropora, Isopora, Montipora, and Porites)
Marc Humblet, Chuki Hongo and Kaoru Sugihara
第四紀の主要な造礁性サンゴ(ミドリイシ属,ニオウミドリイシ属,コモンサンゴ属,ハマサンゴ属)の同定ガイド
Marc Humblet・本郷宙軌・杉原 薫
化石サンゴの同定は古環境復元と海水準復元,古生態学研究,進化の解明には不可欠である.従来から化石サンゴの同定には骨格表面の形質に注目して分類を行なう現生サンゴの同定手法が適用されている.しかし,露頭と掘削コアから産する化石サンゴの骨格表面は生物侵食や堆積物などの影響を受けているため,その観察が困難なことが多い.そのため,これらの化石サンゴの同定には骨格断面に注目することが必要であり,骨格の内部構造と表面の形質の関係性を理解することが重要となっている.本研究は造礁サンゴの主要な4属である,ミドリイシ属とニオウミドリイシ属,コモンサンゴ属,ハマサンゴ属に注目し,その内部構造を初めて詳細に記載した.ミドリイシ属の特徴は,成長方向に並行および直交する規則的な網目状構造の共骨を持つことである.また,サンゴ個体を鉛直方向の断面で見ると,梯子のように明瞭な横隔板を確認できる.ニオウミドリイシ属はミドリイシ属に似ているが,中軸サンゴ個体と放射サンゴ個体に明瞭な差が認められない.また,サンゴ個体の成長方向は不規則であり,共骨の構造もミドリイシ属に比べて不規則である.コモンサンゴ属はニオウミドリイシ属とミドリイシ属よりも小さいサンゴ個体を持ち,サンゴ個体を鉛直方向の断面で見ると,棘状の隔壁を持つ管状部を確認できる.また,共骨は成長方向に直交する長い棒状部を持ち,それらは骨格表面で棘などの突起部となる.さらに,この棒状部同士をつなぐ短い棒状部も特徴である.ハマサンゴ属のサンゴ個体の大きさはコモンサンゴ属と同程度であるが,サンゴ個体同士が近接しており,隙間が少ない.また,サンゴ群体を鉛直方向の断面で見ると,成長方向に並行および直交する密な網目状の構造が確認できる.本研究成果は第四紀の化石サンゴの同定ガイドとして役立つだろう.
Key Words: Acropora, cross section, internal structure, Isopora, Montipora, Porites, quaternary corals, taxonomic identification.
4. Preliminary identification of key coral species from New Caledonia (Southwest Pacific Ocean), their significance to reef formation, and responses to environmental change
Chuki Hongo and Denis Wirrmann
ニューカレドニア産造礁サンゴの鍵種同定:サンゴ礁形成への重要性と環境変動に対する応答
本郷宙軌・Denis Wirrmann
過去のサンゴ礁生態系の形成と維持に寄与してきたサンゴ(鍵種)を地質記録から復元することは,将来の気候変動と人間活動に対するサンゴ礁生態系の応答を理解する際に重要である.本研究ではニューカレドニアのサンゴ礁掘削試料(完新統と更新統)を解析したところ,19属33種のサンゴを同定した.とくに,Goniastrea retiformisとIsopora palifera,Dipsastraea pallida/speciosa complex,corymbose Acropora sp.,massive Porites sp.,encrusting Porites sp.が鍵種であることが明らかとなった.これらのサンゴは完新世の海面上昇に対応してサンゴ礁生態系を形成・維持してきたため,将来の海面上昇(0.2—0.6m/100年)に対してもこれらのサンゴがサンゴ礁生態系を形成・維持できる可能性が高い.しかし,現在は他の環境変動の影響を受けてこれらの鍵種は減少傾向にあるので,鍵種の保全に向けて取り組んでいくことが必要である.
Key Words: barrier reef, coral reef, Holocene, key coral species, New Caledonia.
5. Modern and Pleistocene large-sized benthic foraminifers from Tahiti, French Polynesia, collected during IODP Expedition 310
Kazuhiko Fujita and Akitoshi Omori
IODP第310次航海で採取された,フランス領ポリネシア・タヒチ島周辺の現世及び更新世の大型底生有孔虫
藤田和彦・大森明利
本論文は,統合国際深海掘削計画(IODP)第310次航海において,フランス領ポリネシアのタヒチ島周辺で採取された表層堆積物及びティアレイ(Tiarei)海域で掘削された更新統に産出する大型底生有孔虫(0.5 mm径以上の底生有孔虫)の組成と分布について報告する.現世堆積物からは,生体・遺骸それぞれ少なくとも6属と22属の大型底生有孔虫が同定された.表層堆積物における有孔虫の産出個体数は主に水深と底質の種類に依存する.遺骸群集組成は堆積環境と水深によって変化する.サンゴ礁内側の礁湖群集はSchlumbergerina alveoliniformisの優占によって,礁外側の斜面や島棚群集はAmphistegina属の優占によって,それぞれ特徴づけられる.Amphistegina lessoniiの相対頻度は水深の増加とともに減少し,陸棚ではAmphistegina bicirculataやPlanostegina sp. が増加する.主に火山砕屑性砂岩・シルト岩や生砕物性グレインストーンからなる更新統試料は大型底生有孔虫化石の産出に乏しく,種多様性も低い.更新統試料には主にAmphistegina lobifera,Heterostegina depressa, Eponides repandusが産出する.群集組成は掘削地点間でほとんど変化しない.これらの更新世大型底生有孔虫化石群集は現世の礁外側斜面の水深30 m以浅にみられる群集と類似する.サンゴ化石の組成やウラン−トリウム年代の結果と統合すると,ティアレイ海域の更新統は海洋酸素同位体ステージ3の時期に礁外側斜面環境で堆積したと考えられる.
Key Words: benthic foraminifer, depositional environment, Expedition 310, Integrated Ocean Drilling Program, Marine Isotope Stage 3, Pleistocene, Tahiti.
6. Late Holocene coral reef environment recorded in Tridacnidae shells from archaeological sites in Okinawa-jima, subtropical southwestern Japan
Ryuji Asami, Mika Konishi, Kentaro Tanaka, Ryu Uemura, Masahide Furukawa and Ryuichi Shinjo
沖縄島の遺跡から出土したシャコガイ殻化石による完新世後期のサンゴ礁環境解析
浅海竜司・小西美香・田中健太郎・植村 立・古川雅英・新城竜一
シャコガイ科(Tridacnidae)は世界最大の二枚貝であり,過去のサンゴ礁環境を高時間解像度で知るうえで有用な地質試料である.本研究では,沖縄島の新城下原第二遺跡と古我地原貝塚遺跡から出土するシャコガイ殻化石の季節分解能解析から当時のサンゴ礁環境を復元した.試料は保存状態が良く,続成カルサイトセメントの付加が少ないものを選別した.試料の放射性炭素年代(約4,000〜2,000年前)は沖縄の貝塚時代の初期〜中期に相当し,遺跡の出土物類から推定される年代と整合的である.シャコガイ殻には年輪に相当する縞構造がみられ,酸素同位体比(δ18O)の時系列データが示す年周期と概ね対応する.現在のサンゴ礁で同位体平衡で形成されるアラゴナイトのδ18Oと比較すると,殻化石の値は約0.1〜0.7‰も低い.これは,当時の遺跡近傍のサンゴ礁域が現在よりも水温が高く(<1〜3℃),塩分が低かった(<1〜2 psu)ことを示唆する.当時の気候状態や海水準などを考慮すると,本研究で用いたシャコガイは小規模なサンゴ礁池内,あるいは外洋水との交換に乏しい半閉鎖的な礁池内で生息した可能性がある.すなわち,生息域の海水が日射による温度上昇を受けやすく,天水や河川水によって希釈されやすい状況にあったと考えられる.これには,沖縄の貝塚時代の漁労様式(サンゴ礁池に石垣を積み上げて潮汐を利用する漁労方法)が少なからず関わっていた可能性がある.
Key Words: archaeological sites, coral reef, fossil giant clams, Okinawa-jima, oxygen isotopic composition, salinity, water temperature.
Island Arc 日本語要旨 2007. vol. 16 Issue 2 (June)
Island Arc 日本語要旨 2007. vol. 16 Issue 2 (June)
1. Spatial and temporal evolution of arc volcanisms in the NE Honshu and Izu-Bonin arcs: Evidence of small-scale convection under the island arc-
Satoru Honda, Takeyoshi Yoshida, Kan Aoike
東北日本弧および伊豆—小笠原弧の島弧火山活動の空間・時間的変化:島弧下の小規模対流の証拠?
本多 了, 吉田武義, 青池 寛
東北日本弧と伊豆—小笠原弧の最近10 Myrの島弧火山活動は,幾つかの顕著な特徴を示している.東北日本弧では,火山活動域が島弧に対して垂直な方向に伸びた数個の群れからなる空間分布を示している.また,火山活動域は,少なくとも最近5 Myrの間では,背弧側から火山フロント側に向かって移動したように見える.また,これらの群れの位置は5 Maに入れ替わったように見える.一方,伊豆—小笠原弧にも,東北日本弧の群れと似た島弧を横切る海山列がある.そこでは約17 Maから3 Ma頃までの間に火山活動があったが,現在は島弧に平行な軸を中心に拡大が起こっている.我々は,数値モデルの結果により,これらの特徴が,少なくとも定性的には,島弧下で起こっている小規模対流によって説明できる事を示す.また,モデル計算の結果から,伊豆—小笠原弧のテクトニクスに関する幾つかの推測ができる.伊豆—小笠原弧では,沈み込むスラブの角度が,次第に増加した可能性がある.この事により,島弧を横切る海山列に沿った火山活動が消滅し,最近の島弧に沿った狭い地域で起こっている拡大が説明できる.海山列の走向は,島弧に対して斜交しているが,それは,本来的な特徴ではなく,海山列形成後の島弧の走向に沿った背弧側の横ずれ運動によるものと解釈される.これらの推測は,伊豆—小笠原弧の今後の詳細な地形学的,年代学的研究により検証出来るであろう.
Key words: arc volcanism, Izu-Bonin, northeast Honshu, small-scale convection, volcanic fingers.
2. The Oka belt (Southern Siberia and Northern Mongolia): a Neoproterozoic analog of the Japanese Shimanto Belt?
Alexander Kuzmichev, Evgeny Sklyarov, Anatory Postnikov and Elena Bibikova
南シベリア〜北モンゴルのオカ帯は日本の四万十帯の原生代後期アナログか?
オカ帯は砕屑岩と緑色片岩よりなり,南シベリアのサヤン地域から北モンゴルにかけて約600 kmの延長をもつ.オカ帯の年代と構造セッティングは,長年にわたってこの地域で最も矛盾に満ちた問題だった.我々は小論でオカ帯が原生代後期末に付加体として形成されたことを提唱する.オカ帯は覆瓦状の衝上構造を示し,これはもともと原生代後期の海側へ衝上した付加プロセスを反映する.古生代前期の造山運動はその構造にわずかな影響を与えたにすぎない.オカ帯は海嶺玄武岩,若干の海洋島玄武岩,そして恐らく遠洋性の堆積物からなる衝上体を含み,いくつかの地点ではそれらが斑れい岩や蛇紋岩を伴う.これらの岩石は,この付加プリズムに沈み込み,それにトラップされた海洋性リソスフェアを代表する.オカ帯の内帯には付加プリズムの更に深いレベルから上昇した青色片岩も存在する.また,オカ帯の北部には,N型海嶺玄武岩と地球化学的に類似する苦鉄質深成岩体及び酸性火山岩を産する.この部分は日本の四万十帯の第三系の部分によく類似し,それと同様に付加プリズム下への直角な海嶺沈み込みを経験した.このイベントは753±16 Ma(ジルコンU-Pbディスコーディア年代)に起こった.オカ帯では,原生代後期の中頃に日本とよく似た南シベリアの大陸地殻下への沈みこみが始まり,付加体の形成が開始された.付加プリズムは原生代後期の後半を通じて存在し,膨大な量のシアル質の物質を集積して隣接する大陸を成長させた.現在のところ,オカ帯の調査はまだ進んでおらず,今後の研究と発見が期待される.
Key words: accretionary prism, blueschists, Central-Asian Fold Belt, Mongolia, Neoproterozoic tectonics, Sayan, Siberia
3.Structural evidence for large-scale top-to-the-north normal displacement along the MTL in Southwest Japan
Tetsuzo Fukunari and Simon Wallis
西南日本における中央構造線に沿った大規模正断層運動の構造的証拠
福成徹三, Simon R. Wallis
中央構造線は三波川変成帯と領家変成帯を分断する大規模なテクトニック境界である.中央構造線の横ずれ運動は多くの研究者により明らかにされてきた.一方,中央構造線近隣の三波川帯において新たに野外調査を実施することにより,中央構造線近隣には北落ちの正断層運動を示す二次的な断層及び延性的なシアバンドが多く存在していることが明らかとなった.これらの剪断構造の走行及び空間的な分布は,剪断構造の発達が中央構造線の運動に関係していたことを示す. これらの結果は中央構造線が広範囲にわたる正断層として動いていたことを示唆する中央構造線の正断層運動は三波川帯の上昇を説明する要因の一つとなり得る.また,この正断層運動は三波川帯内の褶曲の幾何学的な分布を説明することが可能である.
Key words: estimate of deisplacement, Median Tectonic Line, normal displacement, south-
west Japan
4. Micropaleontological and seismic observations for early developmental stage of the southwestern Ulleung Basin, East Sea (Sea Japan)
Hyesu Yun, Songsuk Yi, Jinyong Oh, Hyunsook Byun ,Kooksun Shin
日本海,対馬海盆南西部の微古生物学的・地震学的データと海盆の初期進化過程
日本海の南西端に位置する対馬海盆は,厚い新第三系堆積物からなる.Pohang盆地の陸上試料と対馬海盆南西部の掘削試料を用いて渦鞭毛虫の詳細な研究を行い,海盆の初期進化を検討した.海盆はリフト形成時に堆積した厚い堆積物によって充填されており,それらは主に陸成層からなるが,これは対馬海盆が伸張場において形成されたことを支持する.海盆の形成は17-16.4 Maにさかのぼる.また中新世の掘削試料から始新世〜漸新世の保存の良い渦鞭毛虫群が発見されたことから,リフトの形成は漸新世かそれ以前と考えられる.この結果は日本海拡大のプロセスを議論するための束縛条件となる.
Key words: biostratigraphy, paleoenvironment, Pohang Basin, syn-rift, Ulleung Basin.
5. The oceanic substratum of Northern Luzon: Evidence from xenoliths within Monglo adakite (Philippines)
Betchaida Payot, Sebastien Jego, Rene C. Maury, Mireille Polve, Michel Gregoire, Georges Ceuleneer, Rodolfo A. Tmayo Jr., Graciano P. Yumul Jr., Herve Bellon and Joseph Cottoen
ルソン島北部の海洋性基盤:モングロ・アダカイト中の捕獲岩からの証拠(フィリピン)
ルソン島北部バギオ地域のモングロ村付近に露出する8.65 Maのアダカイト質貫入岩床は,一連の超苦鉄質・苦鉄質捕獲岩を含んでいる.それらは多い順に,典型的なマントルかんらん岩の組織・鉱物組成・全岩組成を示すスピネル・ダナイト,それらに由来する蛇紋岩,平滑ないしややエンリッチした微量元素パターンを示す縁海玄武岩マグマに類似した角閃石に富む斑れい岩,そしてそれと同じ化学組成の玄武岩ないし斑れい岩に由来する角閃岩である.同様に沈み込み帯マグマの特徴を示す石英閃緑岩の捕獲岩も1個だけ得られた.1つの角閃岩捕獲岩の全岩K-Ar年代は115.6 Ma(バレミアン)である.我々はこれら一連の捕獲岩の起源について,上昇中のアダカイト・マグマが,厚さ30〜35 kmのルソン島の地殻のある深さに位置していた白亜紀前期のオフィオライト複合岩体から捕獲してきたものと考える.それらはルソン島北部に露出するイサベラ・オーロラ及びプーゴ・レパントのオフィオライト岩体に対応するものだろう.
Key words: adakite, dunite, gabbro, Luzon crust, ophiolite, the Philippines, xenolith
6. Very low-grade metamorphic study in the pre-Late Cretaceous terranes of New Caledonia (SW Pacific Ocean)
Potel, Sebastien
ニューカレドニア先白亜紀後期テレーンの極低度変成作用
ニューカレドニア中央部の白亜紀前期以前のテレーンは,2回の高圧低温イベントによって極低度の変成作用を被っている.本研究ではフィロケイ酸塩鉱物の結晶化度,EPMA分析,記載岩石学データをもとに変成条件を解析した.ジュラ紀後期の最初の変成のイベントは極低度(anchizone)から低度(epizone)の条件で,北東から南西に向かってイライトのKüblerインデックス値(KI)と緑泥石のÁrkaiインデックス値(ÁI)が減少する.この傾向は緑泥石温度計によっても確認されている.調査地域南部に分布するSenonianの‘formation à charbons’中には,変成作用後に形成された非変成堆積物が存在するが,これらは続成作用のKI値をもつ.2回目の変成作用は始新世の高圧イベントであり,調査地域北部において1回目のジュラ紀後期の変成作用をオーバープリントしている.この地域の変成条件は南西から北東に向かって増加するが,KIとÁIのパターンは異なる傾向を示す.緑泥石温度計によって計算された温度もまた,南西から北東に向かって298±8℃から327±16℃と増加する.両地域における高圧低温変成条件は,Kに富む白雲母のb セルの大きさ(b0>9.04Å)からも支持される.緑泥石温度計と雲母のb セルの大きさから圧力の下限を見積もると,始新世の変成地域は1.3 GPa(ニューカレドニア北部から得られた1.5 GPaと一致),ジュラ紀後期の変成地域は1.1 GPaであった.
Key words: hig-pressure/low-temperature, illite crystallinity, New Caledonia, phyllosilicates, very low-grade metamorphism
7. Westward younging disposition of Philippine ophiolites and its implication for arc evolution
Graciano P. Yumul Jr.,
フィリピンのオフィオライトの西へ向かって若くなる配列と島弧発達史におけるその意義
フィリピン島弧系の様々なオフィオライト岩体には,西へ向かって次第に若くなる配列傾向が見られる.これは,始新世にフィリピン島弧系が北西に移動する過程で時計回りに回転し,その西縁がスンダ地塊・ユーラシア大陸縁と衝突したことによって形成された.この相互作用の結果,オフィオライトとメランジュはフィリピン島弧系の西側に付加して行った.露出する海洋リソスフェア断片の空間的・時間的関係に基づいて,ここでは新たに4つのオフィオライト帯を提唱する.東から西へ次第に若くなる順に,第1帯はフィリピン東部の白亜紀後期の完全な層序をもつオフィオライトとそれに伴う下底変成域よりなり,第2帯はそのすぐ西側の白亜紀前期〜後期の不完全な苦鉄質−超苦鉄質岩体とメランジュよりなる.第3帯は(中央)フィリピン変動帯とスンダ地塊・ユーラシア大陸縁に跨る衝突帯に定置した,白亜紀から始新世を経て漸新世に至るオフィオライト岩体群である.第4帯は(その西の)パラワン及びサンボアンガ・スールー地域に露出する大陸縁上に定置したオフィオライト岩体に対応する.このオフィオライト帯の区分案は,横ずれ断層に境される始新世のサンバレス・オフィオライトを除いて,(中央)フィリピン変動帯全体が白亜紀の原フィリピン海プレートの破片を基盤としていることを示唆する.これは,フィリピンの東縁部のみに原フィリピン海プレートの物質が含まれるとする従来のモデルに対立する.
Key words: ophiolites, Philippine Sea Plate, Philippines, space-time relationship, Sundaland-Eurasian margin
追記:本論文の著者のG. P. Yumul Jr. 氏は,2003年に本誌に発表した論文により,本年第1回Island Arc賞を受賞することが決定しました.本誌の今号213ページに受賞論文,推薦文,著者略歴,写真が掲載されていますので,ご覧下さい.
オープンファイル
オープンファイルとは
オープンファイルは,受理論文から,生データ部分(調査・実験・解析・計算等の一時データや事実の記載等)を著者の希望に応じてホームページに掲載するものです.印刷上限をオーバーする場合だけでなく,誌面のスリム化にも役立ちます.膨大なデータをご用意されている場合には,投稿編集出版規則のオープンファイルの細則をご参照のうえ、編集委員会に申し出て下さい.
投稿編集出版規則:オープンファイルの細則(PDF)はコチラから
オープンファイル
119
vol.127, no.12(2021.12月号)
安邊・佐藤 p.709-725
118
vol.127, no.12(2021.12月号)
内田ほか p.701-708
117
vol.127, no.11(2021.11月号)
内野ほか p.651-666
116
vol.127, no.10(2021.10月号)
江島 p.605-619
115
vol.127, no.10(2021.10月号)
新正ほか p.595-603
114
vol.127, no.9(2021.9月号)
山田 桂ほか p.575-591
113
vol.127, no.9(2021.9月号)
相田ほか p.563-574
112
vol.127, no.9(2021.9月号)
田口ほか p.545-561
111
vol.127, no.8(2021.8月号)
有留ほか p.489-495
110
vol.127, no.8(2021.8月号)
野口ほか p.461-478
109
vol.127, no.8(2021.8月号)
柚原ほか p.447-459
108
vol.127, no.7(2021.7月号)
相川ほか p.431-436
107
vol.127, no.7(2021.7月号)
入月ほか p.415-429
106
vol.127, no.6(2021.6月号)
前浜ほか p.363-376
105
vol.127, no.6(2021.6月号)
榎並ほか p.313-331
104
vol.127, no.5(2021.5月号)
Kawaguchi et al p.293-304
103
vol.127, no.4(2021.4月号)
長田ほか p.237-243
102
vol.127, no.2(2021.2月号)
古澤ほか p.91-103
101
vol.127, no.2(2021.2月号)
加藤ほか p.105-120
100
vol.127, no.1(2021.1月号)
志村ほか p.51-58
99
vol.127, no.1(2021.1月号)
末岡ほか p.25-39
98
vol.127, no.1(2021.1月号)
小山内ほか p.1-24
97
vol.126, no.11(2020.11月号)
図子田ほか p.645-654
96
vol.126, no.11(2020.11月号)
磯粼ほか p.639-644
95
vol.126, no.11(2020.11月号)
牛丸・山路 p.631-638
94
vol.126, no.10(2020.10月号)
長田・大藤 p.597-601
93
vol.126, no.10(2020.10月号)
沢田ほか p.551-561
92
vol.126, no.9(2020.9月号)
石崎ほか p.473-491
91
vol.126, no.9(2020.9月号)
鹿野ほか p.519-535
90
vol.126, no.5(2020.5月号)
宮田ほか p.251-266
89
vol.126, no.5(2020.5月号)
伊藤・村松 p.285-290
88
vol.126, no.4(2020.3月号)
納谷・水野 p.183-204
87
vol.126, no.4(2020.3月号)
志村ほか p.223-230
86
vol.126, no.3(2020.3月号)
亀谷ほか p.157-165
85
vol.126, no.3(2020.3月号)
山元ほか p.127-136
84
vol.126, no.3(2020.3月号)
内野 p.113-125
83
vol.125, no.11(2019.11月号)
杉本ほか p.827-832
82
vol.125, no.11(2019.11月号)
金子ほか p.781-792
81
vol.125, no.9(2019.9月号)
廣木 p.699-705
80
vol.125, no.9(2019.9月号)
久田 p.635-654
79
vol.125, no.7(2019.7月号)
中嶋ほか p.483-516
78
vol.125, no.6(2019.6月号)
竹内ほか p.453-459
77
vol.125, no.6(2019.6月号)
仲田ほか p.447-452
76
vol.125, no.6(2019.6月号)
柚原ほか p.405-420
75
vol.125, no.5(2019.5月号)
志村ほか p.349-365
74
vol.125, no.5(2019.5月号)
太田ほか p.329-427
73
vol.125, no.4(2019.4月号)
鈴木ほか p.307-322
72
vol.125, no.4(2019.4月号)
細井ほか p.379-295
71
vol.125, no.2(2019.2月号)
志村ほか p.195-200
70
vol.125, no.2(2019.2月号)
Aoki et al p.183-194
69
vol.125, no.2(2019.2月号)
池田ほか p.167-182
68
vol.125, no.1(2019.1月号)
田村ほか p.22-39
67
vol.124, no.12(2018.12月号)
Haraguchi et al p.1049-1054
66
vol.124, no.12(2018.12月号)
尾上 p.1021-1032
65
vol.124, no.11(2018.11月号)
大信田ほか p.919-933
64
vol.124, no.11(2018.11月号)
Haraguchi et al p.935-940
63
vol.124, no.10(2018.10月号)
山田ほか p.837-855
62
vol.124, no.10(2018.10月号)
細井ほか p.819-835
61
vol.124, no.9(2018.9月号)
中嶋ほか p.693-722
60
vol.124, no.7(2018.7月号)
常盤ほか p.539-544
59
vol.124, no.6(2018.6月号)
古澤ほか p.435-447
58
vol.124, no.4(2018.4月号)
伊藤ほか p.271-296
57
vol.124, no.2(2018.2月号)
柿崎ほか p.124-140
56
vol.123, no.12(2017.12月号)
植木・丹羽 p.1061-1066
55
vol.123, no.12(2017.12月号)
羽地・山路 p.1049-1054
54
vol.123, no.12(2017.12月号)
内野・鈴木 p.1015-1033
53
vol.123, no.11(2017.11月号)
志村ほか p.925-937
52
vol.123, no.10(2017.10月号)
小山内ほか p.879-906
51
vol.123, no.9(2017.9月号)
古澤 p.765-776
50
vol.123, no.9(2017.9月号)
川㟢 p.699-706
49
vol.123, no.5(2017.5月号)
竹内ほか p.335-350
48
vol.123, no.1(2017.1月号)
Yamasaki p.23-29
47
vol.122, no.12(2016.12月号)
山野井 p.634-652
46
vol.122, no.12(2016.12月号)
常磐 p.625-635
45
vol.122, no.10(2016.10月号)
増渕 p.533-550
44
vol.122, no.8(2016.8月号)
高橋 p.375-395
43
vol.122, no.4(2016.4月号)
田辺 p.135-153
42
vol.122, no.3(2016.3月号)
山元 p.109-126
41
vol.122, no.3(2016.3月号)
生田ほか p.89-107
40
vol.121, no.11(2015.11月号)
池田 p.403-419
39
vol.121, no.10(2015.10月号)
古角 p.359-372
38
vol.120, no.7(2014.7月号)
山元 p.233-245
37
vol.120, no.4(2014.4月号)
萬年 p.117-136
36
vol.120, no.2(2014.2月号)
Tsuchiya et al p.37-51
35
vol.119, no.12(2013.12月号)
小杉ほか p.743-758
34
vol.119, no.10(2013.10月号)
浦本ほか p.693-698
33
vol.119, no.10(2013.10月号)
宮城ほか p.665-678
32
vol.119, no.7(2013.7月号)
大井ほか p.488-505
31
vol.119, no.7(2013.7月号)
中谷ほか p.457-473
30
vol.119, no.6(2013.6月号)
清家・平野 p.397-409
27
vol.119, no.4(2013.4月号)
沢田ほか p.267–384
26
vol.119, no.3(2013.3月号)
鈴木ほか p.205–216
25
vol.119, no.1(2013.1月号)
伊藤ほか p.39-44
24
vol.118, no.11(2012.11月号)
勝部ほか p.762-767
23
vol.118, no.11(2012.11月号)
田中ほか p.723-740
22
vol.118, no.6(2012.6月号)
植木ほか p.387-392
28
vol.118, no.4(2012.4月号)
池田ほか p.220-235
29
vol.118, no.1(2012.1月号)
Adachi et al p.39-52
21
vol.117, no.10(2011.10月号)
新井 p.547-564
20
vol.117, no.8(2011.8月号)
鹿島ほか p.451-467
19
vol.117, no.6(2011.6月号)
増渕・石崎 p357-376
18
vol.117, no.5(2011.5月号)
工藤ほか p277-288
17
vol.116, no.10(2010.10月号)
森下ほか p.523-543
16
vol.115, no.8(2009.8月号)
岩野ほか p.427-432
15
vol.115, no.6(2009.6月号)
隅田・早坂 p.266-287
14
vol.115, no.2(2009.2月号)
本郷 p.64-79
13
vol.114, no.11(2008.11月号)
嶋村 p.560-576
12
vol.114, no.10(2008.10月号)
引地・山路 p.540-545
11
vol.114, no.10(2008.10月号)
丹羽ほか p.495-515
10
vol.113, no.7(2007.7月号)
山下ほか p.340-352
09
vol.113, no.3(2007.3月号)
内村ほか p.95-112
08
vol.112, no.11(2006.11月号)
川浪ほか p.639-653
07
vol.112, no.7(2006.7月号)
新井・太田 p.439-451
06
vol.112, no.6(2006.6月号)
新井・太田 p.430-435
05
vol.111, no.5(2005.5月号)
小林ほか p.286-299
04
vol.110, no.10(2004.10月号)
辻森 p.591-597
03
vol.110, no.8(2004.8月号)
高橋ほか p.463-479
02
vol.109, no.4(2003.4月号)
Nomura p.197-214
01
vol.108, no.6(2002.6月号)
Nomura p.394-409
Island Arc 日本語要旨 2013. vol. 22 Issue 1 (March)
Vol. 22 Issue 1 (March)
特集号
Frontier of micro-scale analysis of HP and UHP rocks
Guest editor: Kazuaki Okamoto, Masaru Terabayashi and Hiroshi Yamamoto
高圧、超高圧岩の微小解析の最前線
岡本和明・寺林 優・山本啓司
<序文>
沈み込み,衝突,上昇過程を解明するため,数多くの高圧,超高圧変成岩に関する研究が行われてきた.これらの高圧,超高圧変成岩の基礎的な岩石記載により,高圧,超高圧鉱物の多くは低圧条件の鉱物に部分的,もしくは完全に置き換えられていることが明らかになってきた.高圧,超高圧鉱物は,より固い鉱物中に包有物として保存されている場合や,離溶組織を示している場合がある.そのため,高圧,超高圧変成岩に対して,温度圧力条件の推定,局所領域の年代測定,岩石変形組織解析などが有効である.これらを中心とした新しい様々な側面からの解析は,高圧,超高圧変成岩の研究に新知見をもたらしている.
1. Metamorphic P–T evolution of high-pressure eclogites from garnet growth and reaction textures: Insights from the Kaghan Valley transect, northern Pakistan
Hafiz Ur Rehman, Hiroshi Yamamoto and Shin Keijiro
ざくろ石の成長と反応組織に基づく高圧変成岩の温度圧力履歴:パキスタン北部カーガーンバレーからの知見
Hafiz Ur Rehman・山本啓司・秦 圭治郎
パキスタン北部のカーガーンバレーにはヒマラヤ変成帯の岩石が分布している.この地域ではインドプレートがアジアプレート下に100 km以深まで沈み込んで超高圧に達したことがわかっている.カーガーンバレーのマフィック岩については昇温期,ピーク,降温期の少なくとも三つの変成イベントが識別できる.ざくろ石の組成累帯構造と包有物,および主要構成鉱物間の反応関係は,ざくろ石のコアが昇温期に,中間部は超高圧の条件(2.3 ± 0.4 Gpa,766 ± 107℃)で形成されたことを示す.ざくろ石の縁辺部が角閃石と接していることとシンプレクタイトの存在から,角閃石エクロジャイト相から角閃岩相に至るときの温度圧力条件は平均して1.5 ± 0.2 Gpa,710 ± 75℃であったと推定できる.ざくろ石の累帯構造は,Caに乏しく相対的に広い領域を占めるコアとCaに富む薄い中間部,および縁辺部から構成され,最外縁に沿って緑泥石と角閃石を生じている.これらの特徴はざくろ石が大きく成長した時期が概ねインド−アジアの衝突より前であり,縁辺部は衝突後の上昇期に形成されたことを示す.
Key Words : eclogites, garnet growth, Himalayan Metamorphic Belt, Kaghan Valley, P–T evolution.
2. Redox state at ultrahigh-pressure metamorphism: Constraint from the Chinese Continental Scientific Drilling eclogites
Kazuaki Okamoto, Borming Jahn, Tzeng Fu Yui and Masahide Akasaka
超高圧変成作用における酸化還元状態:CCSD(中国大陸科学掘削)エクロジャイトからの制約
岡本和明・Borming Jahn・Tzen-Fu Yui・赤坂正秀
流体組成を推定するため,CCSD(中国大陸科学掘削)エクロジャイトの炭素鉱物の同定を行った.グラファイトと黄鉄鉱がエクロジャイト中に含まれており,変成作用に伴う脱水流体がH2O に富む(CO2 に乏しい)ことを示す.本研究で用いたエクロジャイト試料には,CaEs 成分(Ca0.50.5AlSi2O6)に富む単斜輝石が含まれている.よって,単斜輝石中のFe3+ は電子線マイクロアナライザーの分析値から求めることはできない.メスバウワー分析により単斜輝石中のFe3+/Σfeを求め,フェンジャイト−ざくろ石−単斜輝石—コース石の鉱物組み合わせを用いた圧力温度計から本研究試料のエクロジャイトの変成圧力温度条件を求めた.その結果,,3-4 GPa, 650-780 ℃であることを見積もった.本研究で得られた圧力温度条件は,これまでCCSD エクロジャイトの研究で報告されているものより,低い変成条件であり,Fe3+の正確な見積もりが重要であることを示している.
Key Words : Fe3+ content in clinopyroxene, redox state, ultrahigh-pressure eclogite
3. Micro-X-ray absorption near edge structure determination of Fe3+/ΣFe in omphacite inclusion within garnet from Dabie eclogite, East-Central China
Masaru Terabayashi, Takashi Matsui, Kazuaki Okamoto, Hiroaki Ozawa, Yoshiyuki Kaneko and Shigenori Maruyama
中国中央東部大別山エクロジャイト中のザクロ石に包有されたオンファス輝石の三価鉄/総鉄比のマイクロX線吸収微細構造による決定
寺林 優・松井 隆・岡本和明・小澤大成・金子慶之・丸山茂徳
大別山超高圧変成帯エクロジャイトのザクロ石に包有されているオンファス輝石のFe3+/∑Feを放射光マイクロビームによるX線吸収端近傍構造解析によって求めた.大別山超高圧変成帯東部のShimaからWumiaoにいたる,南北約20kmのトラバースで採取されたエクロジャイト10試料のザクロ石中に包有されたオンファス輝石のFe3+/∑Feは0.18〜0.59で,電子線マイクロアナライザによる分析値から計算で見積もったFe3+/∑Fe(0.00〜0.31)よりも高い.大部分のエクロジャイトの地質温度計による形成条件は500〜700℃の範囲になる.地質温度圧力計で求めた温度圧力条件は花崗岩類のウェットソリダスより低温となる.
Key Words : Dabie, eclogite, micro-XANES, omphacite inclusion, ultrahigh-pressure
4. Northward extrusion of the ultrahigh-pressure units in the southern Dabie metamorphic belt, east-central China
Hiroshi Yamamoto, Masaru Terabayashi, Hyugo Okura, Takashi Matsui, Yoshiyuki Kaneko, Masahiro Ishikawa and Shigenori Maruyama
中国南大別変成帯の超高圧ユニットの北向き押し出し上昇
山本啓司・寺林 優・大倉飛雄虎・松井 隆・金子慶之・石川正弘・丸山茂徳
中国中央部の大別造山帯は三畳紀に中朝地塊と揚子地塊が衝突して生じたと考えられている.大別造山帯南部のShima–Wumiao 地域において変成岩類の構造解析を行い,変成複合岩体をほぼ水平に重なる4つのテクトニックユニットに区別した.それらを構造下位から順にユニットI, II,III, およびIV と呼ぶ.全てのユニットにおいて珪長質片麻岩が優占的である.ユニットI にはエクロジャイトと少量の泥質片麻岩,ユニットII にはコース石仮像を含むエクロジャイトが含まれる.同様にユニットIII は泥質片麻岩,石灰質変成岩,およびエクロジャイト(稀にコース石を含む)を,ユニットIVは角閃岩と少量の泥質片麻岩を含む.定方位試料の剪断変形構造によると,ユニットI とIIでは上盤側が北向きに変位するセンスが卓越し,ユニットIII とIV では上盤側が南向きの変位センスが卓越する.ユニットI–IIとIII–IVで剪断センスが逆になることは超高圧の ユニットII とIIIがユニットI とIVに対して相対的に北に押し出されるように上昇したことを示している. 変成帯形成時のプレート沈み込みと上昇の向きは逆傾向のはずなので,大別造山帯における超高圧変成作用は,中朝地塊が南向きに揚子地塊の下に沈み込んだことによるものと考えられる.
Key Words : Dabie, exhumation, shear sense, structure, ultrahigh-pressure.
5. Rheological contrast between glaucophane and lawsonite in naturally deformed blueschist from Diablo Range, California
Daeyeong Kim, Ikuo Katayama, Katsuyoshi Michibayashi and Tatsuki Tsujimori
カリフォルニア・ディアブロレンジに産する藍閃石片岩中の藍閃石とローソン石の強度比
Daeyeong Kim・片山郁夫・道林克禎・辻森 樹
本論文では,ローソン石を含む藍閃石片岩の変形微細組織から,藍閃石とローソン石の強度比を議論した.解析したカリフォルニア・ニューイドリア産の藍閃石片岩は主に藍閃石とローソン石から成るが,結晶選択配向の集中度ならびに結晶のアスペクト比は,藍閃石が卓越する領域の方が強い傾向を示す.このことは,ローソン石に比べ藍閃石の塑性強度が低く変形が集中したこと意味する.沈み込んだ低温高圧変成岩のレオロジーは主に藍閃石に支配されると考えられる.
Key Words : blueschist, crystal-preferred orientation, glaucophane, lawsonite, rheological contrast, strain localization.
6. SHRIMP U–Pb dating of zircons related to the partial melting in a deep subduction zone: Case study from the Sanbagawa quartz-bearing eclogite
Miyuki Arakawa, Kazuaki Okamoto, Keewook Yi, Masaru Terabayashi and Yukiyasu Tsutsumi
深部沈み込み帯での部分融解に関わるジルコン・シュリンプ U-Pb 年代; 三波川石英エクロジャイトの研究例
荒川 幸・岡本和明・Keewook Yi・寺林 優・堤 之恭
四国中央部の三波川変成岩から部分融解組織を持つエクロジャイトの露頭が発見された.部分融解年代を決定するために,部分融解部分とホストのエクロジャイトに関して,ジルコンU-Pb SHRIMP 年代測定を行った.部分融解領域のジルコンは,円形で,セクター構造を持っている.コアとマントルのU-Pb 年代は,130-113 Ma(平均年代 120 Ma)で,リムの年代は115-104 Ma である.エクロジャイト中のジルコンは均質なコアと薄いマントルト,リムから構成されている.U-Pb 年代は123-112 Ma に集中している.これらの証拠より,120 Ma にエクロジャイト相の変成作用が起こり,110 Ma に部分融解が起きたと結論される.
Key Words : eclogite, partial melting, Sanbagawa high P–T metamorphic rocks, zircon U–Pb age dating.
7. Recycled crustal zircons from podiform chromitites in the Luobusa ophiolite, southern Tibet
Shinji Yamamoto, Tsuyoshi Komiya, Hiroshi Yamamoto, Yoshiyuki Kaneko, Masaru Terabayashi, Ikuo Katayama, Tsuyoshi Iizuka, Shigenori Maruyama, Jingsui Yang, Yoshiaki Kon and Takafumi Hirata
南チベット・ルオブサオフィオライトに産するポディフォームクロミタイトから得られたマントル内を循環した地殻起源ジルコン
山本伸次・小宮 剛・山本啓司・金子慶之・寺林 優・片山郁夫・飯塚 毅・丸山茂徳・Jingsui Yang・昆 慶明・平田岳史
南チベット地域・ルオブサオフィオライトに産するポディフォームクロミタイトからジルコンを系統的に分離し,レーザーアブレーションICP質量分析法により,それらのU-Pb年代を求めた.得られた年代値は約100-2700Maと非常に幅広く,それらの多くはコンコーディア曲線上にプロットされ,本オフィオライトのクロミタイト形成から期待される年代より“異常”に古い.また,これらのジルコン中には,石英や長石といった地殻起源鉱物が包有物として存在し,マントル鉱物はみられない.従来から,インド洋およびそれに遡るテチス海マントルは,地殻物質による汚染を受けていることが指摘されているが,クロミタイトから得られた異常に古い年代値をもつ地殻起源ジルコンは,かつて上部マントルへもたらされた後,最終的にクロミタイトに捕獲されたリサイクル地殻物質であると結論づけられる.
Key Words : crustal contamination, Gondwana breakup, Neo-Tethys mantle, podiform chromitite, zircon U–Pb dating.
通常論文
[Research Articles]
1. The tectonic evolution of a Neo-Tethyan (Eocene–Oligocene) island-arc (Walash and Naopurdan groups) in the Kurdistan region of the Northeast Iraqi Zagros Suture Zone
Sarmad A. Ali, Solomon Buckman, Khalid J. Aswad, Brian G. jones, Sabah A. Ismail and Allen P. Nutman
イラクZagros縫合帯北東部クルディスタン地域におけるネオテーチス(始新世—漸新世)島弧(WalashおよびNaopurdan層群)のテクトニックな進化
WalashおよびNaopurdan層群は,イラクZagros縫合帯(IZSZ)における下位の異地性衝上地塊の一部を構成する.WalashおよびNaopurdan火山岩類から分離したマグマ性の長石から得られた40Ar/39Ar年代は始新世から漸新世を示す(43.1±0.15〜24.31±0.6Ma).WalashおよびNaopurdan層群は,現在Hasanbag火成複合岩体として知られる(以前はGemo–Qandil層群として知られた)白亜紀の島弧に関係した岩石(106〜92Ma)からなる上部異地性岩体の構造的下位を占める衝上シートを構成する.WalashおよびNaopurdan異地性岩体下部は前地盆地であるRed Beds系に衝上している.WalashおよびNaopurdan層群の火山性および亜火山性の地層は,Mawat, Galalah–Choman, LerenそしてQalander– Sheikhan地方において研究された.これらの岩石の殆どは,NaopurdanおよびWalash両岩系において,玄武岩質から安山岩質である.記載岩石学的研究によって,これらの岩石は緑色片岩相の変質を受けているが,火成起源の斜長石,輝石,普通角閃石が残存する初生的な斑状組織が保持されていることが分かった. LREE/HREEのエンリッチメントおよび高い Th/Nb,Nb/Zrから,WalashおよびNaopurdanの岩石が異なる沈み込み帯に関係した特徴を有することが分かる.具体的には,Naopurdanでは島弧ソレアイト,Walashではカルクアルカリからアルカリ岩である.よって,WalashおよびNaopurdanの地層は,43〜24Maに発達した,それぞれ背弧および島弧系に由来する.従って,IZSZはネオテーチスの衝突前に関係した二つの沈み込みセッティングにおける早期白亜紀(Hasanbag火成複合岩体)から始新世—漸新世(Walash–Naopurdan層群)の火山活動を全て記録している.おそらく中期中新世に,最後のネオテーチス海がイラン大陸の下に沈み込み,アラビアプレートとの衝突が起こった結果,最終的な大陸—大陸衝突が始まった.これがトルコからイラクおよびイランを経てオマーンにいたるアラビアプレートの縁辺全域に沿ったイベントの連続性を強調する.
Key Words : 40Ar–39Ar geochronology, arc, Iraq, Naopurdan, Walash, Zagros.
2. Determination of 2D strain from a fragmented single ammonoid
Atsushi Yamaji and Haruyoshi Maeda
アンモナイト断片からの二次元歪み推定に関するノート
山路 敦・前田晴良
従来,変形したアンモナイトから,変形前の巻き方が対数螺旋であったと仮定して,歪みが見積もられてきた.小論では肋の間隔に注目し,平面巻きアンモナイトで,Rf/φ歪み解析法の一種,hyperbolic vector mean methodにより歪み楕円とその95%信頼限界が決定できることを示す.この方法では,断片であっても半巻き以上が残っていればよい.北上山地から産した半巻きのアンモナイト断片を例にして,この方法を説明する.
Key Words : strain analysis, ImageJ, hyperboloid model, slaty cleavage
3. How the Mariana Volcanic Arc ends in the south
Robert J. Stern, Yoshihiko Tamura, Harue Masuda, Patty Fryer, Fernando Martinez, Osamu Ishizuka, and Sherman H. Bloomer
マリアナ火山弧はいかにして南端で終わるか
Robert J. Stern・田村芳彦・増田晴江・Patty Fryer・Fernando Martinez・石塚 治・Sherman H. Bloomer
南部マリアナ島弧—海溝系は急速に変形しており,その結果,島弧と背弧海盆のマグマ系の異常な相互作用をもたらしている.本論では,この地域の火山の新たな地球化学的情報を提示し,考察する.グアム北西30 kmにある活動を停止した海底火山であるTracey海山は,マリアナ弧最南端にある成層火山である.Tracey海山は深さ125 kmの沈み込んだスラブの上に位置し,最近では0.527±0.023 Ma (40Ar/39Ar 年代)に典型的な島弧性のマフィックおよびフェルシック溶岩のバイモーダルな噴火をしている.非公式にアルファベット海底火山群(ASVP)と呼ばれる,変わった一群の玄武岩質小海山群が,Tracey海山の南西で次の島弧火山があるべき場所に見つかっている.これらのうち6火山の試料について調べた.熱水活動に示されるように,ASVPのうち少なくとも2火山は最近活動している.単一の成層火山をつくるような噴火中心の集中が見られないことは,ASVPが背弧拡大の強い影響下にあることを反映したものである.これに対して,南部ASVPは南方の東西に走るマリアナ海溝チャレンジャー海淵に沿って沈み込んだ太平洋底の狭いスラブの急速なロールバックによる南北拡大の影響を受けている.ASVP溶岩組成はTracey海山や他のマリアナ弧の溶岩とは明らかに異なり,マリアナトラフの背弧海盆玄武岩に類似した特徴を示す:マフィックなソレアイト質で,低K2O,枯渇したLREE,低87Sr/86Srを有し,海溝に近いより島弧的な溶岩からさらに西方の背弧海盆玄武岩類似の組成へと変わる傾向を示す.通常とは異なるASVPのテクトニックな背景は,長期間活動を続ける島弧火山下で互いに混じり合い,上昇噴火して分散したASVP小火山群を形成した異なる島弧マグマバッチが,強い組成勾配をもったマントルの融解をどのように反映するかについて比類のない展望を提供するものである.
Key Words : back-arc basin, basalt, Mariana Arc, Mariana Trough
Island Arc 日本語要旨 2013. vol. 22 Issue 2 (June)
Vol. 22 Issue 2 (June)
Island Arc Award (2013)
Subduction of mantle wedge peridotites: Evidence from the Higashi-akaishi ultramafic body in the Sanbagawa metamorphic belt.<Island Arc, 19, 192-207 (2010)>
Hattori, Keiko; Wallis, Simon; Enami, Masaki; Mizukami, Tomoyuki
沈み込むマントル・ウェッジ由来のペリドタイト:三波川変成帯に産する東赤石超苦鉄質岩体の例
服部恵子・Simon Wallis・榎並正樹・水上知行
▶▶日本語要旨はこちら
通常論文
[Research Articles]
1. Sedimentary facies and biofacies of the Torinosu Limestone in the Torinosu area, Kochi Prefecture, Japan
Hiromichi Ohga, Bogusław Kołodziej, Martin Nose, Dieter U. Schmid, Hideko Takayanagi and Yasufumi Iryu
一ツ淵鉱山(高知県佐川町鳥巣地域)に分布する鳥巣石灰岩の堆積相および生物相
大賀博道・Bogusław Kołodziej・Martin Nose・Dieter U. Schmid・高柳栄子・井龍康文
高知県一ツ淵鉱山に分布する上部ジュラ系〜下部白亜系(チトニアン階〜ベリアシアン階)鳥巣石灰岩(層厚55.5 m)の堆積学的・古生物学的検討を行った.本鉱山の鳥巣石灰岩は,干出面を境として上部と下部に区分され,両者は堆積相と化石相に基づいて,それぞれ2つおよび3つのユニットに細分される(下位より順にユニット1〜5とする).ユニット2,3,5から,石灰海綿(層孔虫およびケーテテス類),マイクロエンクラスター(主にLithocodium aggregatumとBacinella irregularis),微生物岩が多く認められた.造礁サンゴの産出頻度は相対的に低く,富栄養あるいは濁った海域に特有の造礁サンゴ(Microsolenidae属)が卓越する.層序・堆積相・化石相の検討結果より,本鉱山でみられる鳥巣石灰岩の堆積環境は,海水準変動とそれに関係した陸源砕屑物の流入に規制されていたと推定される.
Key Words : Lower Cretaceous;microbialite, microencruster;stromatoporoid, Torinosu Limestone, Upper Jurassic
2. Petrographic study of the Miocene Mizunami Group, Central Japan: Detection of unrecognized volcanic activity in the Setouchi Province
Eiji Sasao
中部日本に分布する中新統瑞浪層群の記載岩石的研究:瀬戸内区における未知の火山活動の検出
笹尾英嗣
中部日本に分布する中新統瑞浪層群の供給源を明らかにするため,単一のボーリングコアから採取した砂岩の全鉱物・重鉱物組成,斜長石の組成,および全岩化学組成分析を行った.その結果,研究に用いた砂岩は,1)黒雲母とアルバイトからオリゴクレイスが卓越するもの,2)角閃石とラブラドライトが卓越するもの,3)輝石とアンデシンが卓越するものの3つに区分された.このうち,黒雲母が卓越するタイプは基盤の花崗岩から,その他の2つは火山灰として供給されたと推定された.瑞浪層群に火山灰を供給した火山活動は,鉱物・化学組成の変化から2つのフェーズがあると考えられた.瑞浪層群の砂岩の記載岩石学的性質からは,これまでに知られていない火山活動の存在が示唆された.
Key Words : chemical composition, Mizunami Group, petrography, plagioclase indices, provenance
3. Theoretical and quantitative analyses of the fault slip rate uncertainties from single event and erosion of the accumulated offset
Zhikun Ren, Zhuqi Zhang, Tao Chen and Weitao Wang
地震イベントの年代決定と累積オフセットの侵食が与える断層の平均変位速度の不確実性に関する理論的ならびに定量的解析
断層の平均変位速度は,断層の活動度や地震発生ポテンシャルを評価するための重要な指標であるが,その決定には,地震イベントの年代決定に起因する問題や累積オフセットの侵食による改変にともなって生じる不確実性を伴うことが多い.この研究では,信頼度の高い断層の平均変位速度を求めるための方法として差動法を提案する.この方法は,横ずれ断層に沿った新旧段丘のオフセットの差異と年代差の比で断層の平均変位速度が求められ,従来の方法で生じた誤差を取り去ることができる.この差動法を適用することにより,Altyn Tah断層とKunlun断層の平均変位速度を〜5−10 mm/年に修正することができた.このような遅い平均変位速度は,従来の測地学的ならびに地質学的データに基づいて求められた変位速度や短縮速度,ならびにこれらの断層の主要部分で発生した大規模地震の1000年オーダーでの発生間隔と合致する.
Key Words : differential method, erosion of the accumulated offset, fault slip rate;, Holocene, single event effect
4. Paleomagnetic constraints on Miocene rotation in the central Japan Arc
Hiroyuki Hoshi and Masakazu Sano
日本弧中部の中新世回転運動に対する古地磁気学的制約
星 博幸・佐野正和
本州中部,設楽地域北部に分布する津具火山岩類(約15 Ma)の玄武岩と安山岩(溶岩,貫入岩)を12地点で採取し,岩石磁気を測定した.9地点で決定された正極性および逆極性の古地磁気方位はほぼ南北の偏角を示し,同時期の平行岩脈群から報告されている古地磁気方位と有意な差がない.今回取得した方位と平行岩脈群の既報方位を合わせて,約15 Ma古地磁気方位と古地磁気極を決定した.今回決定した古地磁気方位の考察から,筆者らは次の3点を結論した.(1)本州中部の「ハ」型屈曲(関東対曲)構造の西翼側は,17.5〜15 Maに西南日本主部に対して反時計回りに回転した.(2)本州弧と伊豆-小笠原弧の衝突開始は15 Maよりも前である.(3)日本海拡大に伴う西南日本の時計回り回転運動は15 Maまでに完了した.
Key Words : arc–arc collision, Izu–Bonin (Ogasawara) Arc, Japan Arc, Middle Miocene, paleomagnetism, Shitara, tectonic rotation, Tsugu volcanic rocks
5. Major element variation of the Skaergaard pyroxene and its petrologic implications
Yun-Deuk Jang and H. Richard Naslund
スケアガード貫入岩体の輝石の主要元素組成変化とその岩石学的な示唆
スケアガード貫入岩体の成層帯LS,上部周縁帯UBS,周縁帯MBS中の輝石の組成変化を明らかにするためにEPMA及び鉱物分離による分析を行った.一般にどの帯においても岩体の固結に伴って,輝石は同様の主要元素組成変化を示す:SiO2, MgO, Al2O3, and TiO2は漸減し,FeOとMnOは漸増し, CaO, Fe2O3, and P2O5は系統的な変化を示さない.LSとMBSの輝石はWager and Brownが報告したのと同様の組成変化を示す.晶出温度は概ね従来の推定に近い変化を示す.スケアガード貫入岩体の輝石が見せる分化に伴うなめらかな主要元素組成変化は,最初の貫入後に注入されたマグマがほとんどなかったことを示している.これらの結果は,スケアガード貫入岩体は閉じたマグマ溜り内のその場での結晶化を代表するものであるという考えを支持する.
Key Words : crystallization temperature, differentiation, geochemical variation, pyroxene, Skaergaard intrusion
6. Geological setting of basaltic rocks in an accretionary complex, Khangai–Khentei Belt, Mongolia
Kazuhiro Tsukada, Yuki Nakane, Koshi Yamamoto, Toshiyuki Kurihara, Shigeru Otoh, Kenji Kashiwagi, Minjin Chuluun, Sersmaa Gonchigdorj, Manchuk Nuramkhaan, Masakazu Niwa and Tetsuya Tokiwa
モンゴル国ハンガイ−ヘンテイ帯の付加体中の玄武岩の形成場
束田和弘・中根 有城・山本鋼志・栗原敏之・大藤 茂・柏木健司・Minjin Chuluun・Sersmaa Gonchigdorj・ Manchuk Nuramkhaan・丹羽正和・常磐哲也
モンゴル国ハンガイ−ヘンテイ帯の付加体中に含まれる玄武岩類について,その産状と地球化学的特徴を記載した.この玄武岩類は, MORBに比べて K, Ti, Fe, P, Rb, Ba, Th, Nbに富み,プレート内アルカリ玄武岩の特徴を有する. またこの玄武岩類は中期古生代の層状放散虫チャートを整合に覆われることより,遠洋域にて形成されたと推定される.したがって,中期古生代の遠洋域(モンゴル−オホーツク海)にて,アルカリ玄武岩質火山活動が起こっていたことが明らかとなった.
Key Words : accretionary complex, Central Asian Orogenic Belt, Khangai–Khentei Belt, Mongolia, OIB
7. Transport process of sand grains from fluvial to deep marine regions estimated by luminescence of feldspar: example from the Kumano area, central Japan
Masaaki Shirai and Ryo Hayashizaki
長石のルミネッセンス特性により推定された砂粒子の河川から深海にかけての運搬過程:熊野地域における解析例
白井正明・林崎 涼
ルミネッセンス年代測定の原理を利用した露光率(BLP-2)という指標を提案し,河川から深海に到る砂粒子の運搬過程の評価を試みた.紀伊半島南東の熊野地域において,長石粒子の赤外光励起ルミネッセンス強度(IRSL)から現世堆積物試料の長石粒子に露光粒子が含まれる割合(BLP-2)を算出した.その分布をもとに,熊野トラフ底の表層堆積物中のタービダイトの起源となったイベントの性質をはじめ,熊野地域の砂粒子の運搬についていくつかの推察を行った.今後測定粒子数を増加させることにより客観的なデータを得ると共に,ルミネッセンス年代測定を適用可能な更新世後期まで遡って砂粒子の運搬過程に新しい知見を加える事が期待される.
Key Words : bleaching, feldspar, infrared stimulated luminescence, origin of turbidites, sand grain, sediment transport process
地質学雑誌投稿の手引き
地質学雑誌投稿の手引き
日本地質学会News2003年1月号掲載
2011年11月一部改正
論文題名について
諭文題名のつけ方は特に投稿規定にもありません.というのも確定した地質学論文題名命名法などというものがないからです.著者のセンスが問われるところです.一言で言えば過不足なく内容が想像でき,かっより多くの読者の関心を引くような魅力的な題名であるべきでしょう.とはいっても常識的に次のようなことをご検討ください.
(1)羊頭狗肉を避ける.つまり内容と一致しない題名はつけない.当たり前だと思われるでしょうが,これが意外にあるのです.論文を書きはじめたころにタイトルをつけてしまい,その後主旨が異なってきたのにそのままにしておく場合,内容の一部にしかすぎない部分のみタイトルにしてしまう場合,大げさなタイトル,和文と英文タイトルがまったく違う場合などさまざまです.
(2)「恐竜謎の絶滅事件の真相」などと週刊誌まがいの題名も困ります.かといって,編集委員会としてとくに最初の段階では制限は設けません.アトラクティブなタイトルとの兼ね合いをどうするかは難しい問題です.編集上の他とのバランスの問題もあります.査読意見に異論がある場合は筆者のほうからも積極的に議論してください.
(3)地域地質の記載的な論文なら,対象とする地質時代や地域名を含むことは必要なことでしょう.
(4)「新潟県○○地域の中新世後期の褶曲運動」といった地域名を付す場合,英文タイトルでは,最後にcentral Japanとかnortheastern Japanとかつけたほうが良いと思います.この点では厳密に日本語タイトルと1対1に対応していなくても結構です.
(5)「・・・について」というタイトル,しかもその英文タイトルを“About ・・・“とするのはやめたほうがよいでしょう.
(6)連続して投稿を計画している場合,「・・・その1」「・・・その2」という題名の付け方はなるべく避けてほしいものです.各論文はそれ自体で完結しているべきだと思います.また,編集の都合からも「その1」が査読中なのに「その2」が先に受理されても印刷できません.
(7)Central Japan か central Japan か
英語表題でCentral Japanとすべきかcentral Japanとすべきかと,著者からときどき問い合わせをいただきます.地質学会では,従来原則として機械的に小文字を用いています.もちろんCentral Japanは地理的名称として固有名詞であり,その限りで使われる分にはさしつかえないのですが,かならずしも地質学的な地域区分とあわない場合がでてくることがあり,単にタイトル末尾にいれる場合はより広義の意味合いをもつcentral Japanを用いています.もちろん,タイトルそのものに用いられる場合,しかも本文で「ここでいうCentral Japanは,糸静線以東,・・・」などと定義した上でNeotectonics of Central Japan等とする場合はこの限りではありません.
(8)長い論文タイトルは避ける
短いタイトルはパンチがありますが,長いタイトルなら内容を表現しやすくなります.しかし,タイトルが3行以上もあると,読者としてはそれだけで読む気が失せるでしょう.適当な長さのタイトルを付けてください.
(9) サブタイトル
メインタイトルとサブタイトルの区切りには,コロンを使ってください.「○○地域の○○:□□法による□□の発見」という具合です.英語論文では,サブタイトルの前後に横棒「―」を付けません.コロンを使います.日本語論文でも,横棒でメインタイトルとサブタイトルを区切ることを避けてください.
著者名と所属・連絡先の標記について
著者の所属の表記は(編集委員会としては)常に悩む問題です.特に英文の住所表記については,掲載論文ごとに格差がありますが,これは海外からの別刷り請求が届く住所表記が原則です.誰の何大学,都市名(市),郵便番号,Japanが最低限です.邦文表記では所属大学のみなどという例がありますが,それでは不親切です.公的機関の連絡先については必要最低限を心がければ良いでしょう.
アブストラクトについて
アブストラクトは論文の他の部分が完成した段階で,最後に作成することが多いでしょう.従って,査読時にも本文の修正が続いている段階ではほとんど内容に関するコメントがつかない場合があります.ところが,ひとたび論文が出版された時には,読者は表題とアブストラクト(それに図表類)を一覧してその内容を概観しますから,ある意味ではその論文を読んでもらえるかどうかが最初に判断される最も重要な部分とも言えます.従って,長々と小型論文の様に導入部・対象物の説明・結果・解釈...等と書いていては最後まで読んでもらえません.また,通常はアブストラクト中に文献の引用を行うことは希です.まずは簡潔にすること.そしてその論文のオリジナリティーや価値を明確に記述すること.場合によっては,結論を先に書いて,詳しい内容は後にまわすのも良いかも知れません.語数は厳密に制限(論説,総説の場合:和文400字,欧文300語)されていますから,初めに長めに書いて,後から削っていく手もあります.
キーワードについて
論説・総論には,キーワードを欧文で付けていただきますが,この選択も悩ましい場合があります.基本的には,電子アブストラクトなどに再録されて検索されるときに,検索者の意図に応じてご自分の論文が確実にヒットされるように,必要最小限のキーワードを選択することになります.しかし,検索者のワードの選択はまちまちですから,最善を尽くすとなると多数のワードを登録したくなるのも人情です.編集委員会では,ワード数が5〜6個を標準と考えています.ここでのワードとは,単語と熟語の両者を指しますが,他人が検索する時に多数の単語からなる熟語を用いる可能性は少ないので,なるべく語数の少ない熟語に止めるべきです.さらに,毎年地質学雑誌最終号で掲載論文の索引を作成しています.ここでの対象地域別のとりまとめの参考のため,日本の地域地質の論文の場合には必ず県名等をキーワードに入れていただくようお願いします.
論文見だしのフォーマットについて
論文の見だしについては,投稿規定に実例として示されていませんが,これまで出版された論文の誌上での体裁をご参考にしていただいています.雑誌内での掲載論文の体裁が統一されていることは非常に重要ですから,投稿時に事前にチェックして下さい.ご参考に,地質学雑誌上では以下の見だしフォーマットで統一しています.
大見だし:「ゴシック,中央そろえ, 上下に1行空行」
中見だし:「ゴシック,行頭に番号とピリオド,左寄せ」
小見だし:「ゴシック,行頭に括弧付き半角番号,左寄せ改行無し」
これ以下の見出しについては,著者の自由としていますので,最小限上記の体裁で投稿原稿も作成して下さい.
調査結果の記載について
野外地質調査結果の記載は地質学分野の研究論文において重要な位置をしめることはいうまでもありません.必要かつ十分な記載は,極端にいえばそれらの解釈やそれに基づく考察が誤りであっても,その結果の事実だけは後日の役に立ちうる成果となって残ります.ここでははじめて投稿される方を対象に初歩的な指摘を次にのべます.
(1)主要な記載事項を絞る
ある地域を調査した結果をなんでもかんでもすべて記載する必要はありません.たとえば構造発達史が主題の論文に『○○地域ではA層にベントナイト層が挟まれており,これは化粧品原料として毎年100t加工されており,その品質は・・』と記述するとか,直接関係ないけれどたまたま採取した鉱物のX線回折チャートなどをせっかく測ったからのせてやろうとする必要はないですね.総合的にある地域を調査した結果であっても各論文ごとに完結した記載が望ましいわけです.
(2)記載と考察はわける
結果の項目ごとに考察をいれることは原則的にはやるべきではありません.こうした場合その論旨は飛躍していることが多いのです.たとえば『この礫岩は大部分が花崗岩の円礫からなり,その最大礫径は10cmである.このことから,本礫岩の礫の供給は○○地域に由来することが推定される.また,礫は引っ張り剪断をうけて破砕していることが多い.このことは本礫岩分布域にその堆積後南北性の引っ張りが働いたことを示している. …』などといった書き方は記載と解釈の混同があり,かつ論旨展開に無理があり好ましくありません.しかし短い論文などで「結果と考察」と題して,両者を平行的に記述した方が読者にとって理解しやすくなる場合などはこの限りではありません.
(3)地層名の新称や再定義は客観的かつ必要最小限に
一般的な地層命名法に従うことはいうまでもありませんが,とくに日本の場合は大抵の地域はすでに調査されていることが多いので,既存調査結果との違いや対比を明確に示しておくことが必要です.他の研究者がトレースできるような情報(位置図・地質柱状図・岩相・・・,地質調査所の5万分の1地質図幅の記載などは1つの参考になります)をきちんと与えるような記載であるべきです.また新規性を強調したいあまり,なんでもかんでも新しい名前を付けたくなるかもしれませんが,それは避けるべきです.ある人が最下位にある火山灰層にA火山灰層と名付けた後,別の人がこの火山灰は黒雲母(biotite)が多いからB火山灰層と新称し,さらに,他の人はこれはクリスタルアッシュ(crystal ash)が主であるからとしてC火山灰層と名付け混乱しているという笑えない実例すらあります.これは地質構造の命名においても同様です.内容的に新規性がないのに,全くおなじ断層や褶曲に対して他人の定義した名前に同意できないからといって改名する類の行為も慎むべきです.
図表類について
地質学の分野では他の研究分野にもまして,図表類の良し悪しが論文の評価を定める重要なポイントになりえます.地質学雑誌は投稿論文の図表類の製図は行いませんので,著者の原図類がそのまま(あるいは縮小されて)掲載されます.査読の過程で繰り返し指摘されることを以下に要約いたしますので,投稿前に参考にして下さい.
(1)インデックス図には,論文中で出てくる主要な地名を表示すること.
インデックス図は,対象地域の位置関係を一目で理解してもらうために不可欠ですが,その他に論文中で触れている地域・地点を理解するのにも重要な役割を持っています.縮尺によっては全ての地名を表記することは不可能ですが,逆に本文中の重要な地名はどれかの図中に示されているように気をつけて下さい.
(2)地質図と地質断面図が一致すること.
これはそもそも断面図がおかしい場合があります.極端な例では,地質図の背斜構造が断面図では向斜構造になっていたりします.断面線の位置がずれているために貫入岩がぬけていたりすることもあります.また.地層の模様が両者で異なっていたりする(とくに,地質図で横縞なのに,断面図で縦縞になったりする)ことがあります.違う機会に作った図の場合に多いミスでしょう.
(3)方位の真北は左右対称に.
北を表すのは真北・磁北,地図上の北と3種類ありますが,通常論文に掲載される程度の縮尺では真北を使うのが妥当です.この場合方位を表す矢印は左右対称の図柄で示して下さい.また,図ごとに図柄が変わるのもややみっともないので,とくにあらたに作る場合は統一することをお勧めします.縮尺の表現も同様です.
(4)緯度経度を人れる.
著者にとっては自明の調査地域でも,読者にとってはそうであるとは限りません.とくにサンプルや化石の採取地点を示す場合など緯度経度を入れることを忘れないで下さい.使用する測地系は,日本の場合,2002年4月から施行されている改正測量法にしたがって,世界測地系としてください.何らかの理由で他の測地系を使用する場合にはかならずそれを明記してください.位置図などに使用する地形図・地勢図などが,旧日本測地系のままのものである場合がありますので注意してください.
(5)模様はわかりやすく.
海岸地域の地質図の場合は,沖積層ないし第四紀層を白抜きにすると海域と区別しにくくなる場合があります.また,隣接した岩体・地層の模様が込み入りすぎていると識別がしづらくなります.とくに縮小する場合は実際に縮小コピーなどで出きばえをチェックした方がよいと思います.手書きの模様はなるべく避けて下さい.また,地層の境界線と断層などの構造線は太さを別にして下さい.
(6)図表の大きさに配慮する.
図表は印刷時の大きさでデザインして下さい.拡大または縮尺で,著者の意図と異なるデザインで印刷されることを避けるためです.そのために, 1ページが2段組で印刷されることを考慮して,図をデザインして下さい.図は1段の幅または2段分の幅を占めます.それぞれ,8cmと17cmの幅です.高さは最大で24cmです.図の横幅が,それらの幅の9割程度の幅になるようにデザインすると,バランスがいいものです.また,等倍でデザインすることには,図中の文字をもっとも美しく見せる効果があります.例えば10ポイントのフォントは,10ポイントで印刷されることを前提にデザインされているからです.さらにまた, 6ポイント程度より小さい文字は,使用しないで下さい.
また,スペースを有効に使ったデザインを考えて下さい.論文には関わりのない地域までを索引地図に含めたり,不定形の図の配置が不必要な空白を生じさせていたり,図の中に入れられる方位記号や縮尺を外に出して図の外形が大きくなったりしている例が非常に多く見られます.また,単なるインデックスの日本地図などは,縮小して他の図に組み込むなどすれば,総ページ数を圧縮するのにも役立ちます.また,図中に数式を入れる場合は,「数式の書き方方に関する細則」を考慮して下さい.
(7)キャプションと言語は統一する.
論文の図表全てについて,説明文の言語は欧文に統一することになっていますが,これは図表中で使われている文字も含みます.ただし,固有名詞(地名等)に和文表記を併記することは構いません.
(8)図と表の違いは?
本来,表とは活版印刷で版組みできるものだけと定義されてきました.そのため,文字と横線だけで構成されている付図を表として認めてきましたが,地質学雑誌の印刷方法が変更されて以降,表として提出された原稿も現在はそのまま写真印刷されています.従って,「縦線や斜めの直線がちょっと入っているから表ではない」とは認識していませんが,不整合を波線でいれたり,ワープロや切り張りで文字を回転させている場合など,複雑なものは現在も図として扱っていただいています.図表番号の振り直しは大変やっかいな作業ですから,事前に十分検討して下さい.また,表中に数式を入れる場合も,「数式の書き方に関する細則」を考慮して下さい.
(9)出版済みの図表の引用の際の注意.
引用する付図についての著作権の問題も,近年重要になってきました.地質学雑誌で,掲載論文ごとにコピーライトの表示を入れたのもごく最近からです. 他人の論文の図を引用するときには,「掲載雑誌の出版社または著者に承諾を得る」という原則は十分に認識して下さい.編集委員会としては,当該の図表に引用に関する手続きは投稿者が責任をもってクリアしている前提で作業していますが,ひとたび地質学会のコピーライトマーク付きで出版されてしまうと,万が一のクレームは当該出版社から学会に直接来ることになります.多くの国際出版社の規約を見ると,投稿者本人が自身の付図を使いまわすことにはそれほど神経質ではないようですが,だからといって,第三者の著者にメールで承諾を得たからコピーを使えるかどうかは疑問な場合もあります.図表の引用に際しては,「Written permission from the copyright hoder」が必要かどうかよく調べておいて下さい.
また,誰かの付図を許可を得る必要が無いようにするためにちょっと変更(追加修正)して,「Modified after 誰々」とするのは著作権の侵害にならないでしょうか?どのくらいModifyすれば新たなオリジナリティーが発生するのでしょうか?これらの判断は原則として投稿者にまかせられていますが,地質学雑誌あるいは地質学会に迷惑がかからないような事前の措置を十分に行っておくようにお願いします.
口絵・図版・写真
「百聞は一見にしかず」などと言いだすまでもなく,地質学論文における写真の効用には抜群なものがあります.層序や構造を示すすぐれた露頭写真,証拠となる微化石の顕微鏡写真,鉱物・岩石の組織・産状を一目瞭然に示す写真,衛星画像写真など枚挙にいとまがありません.地質学雑誌においても口絵の写真の欄は評判がよい企画の1つですが,次のことにご注意下さい.
(1)あたりまえのことですが,未発表のものに限ります.とくに商業誌に掲載されたものは注意してください.もちろん口頭発表はこの限りではありません.
(2)投稿規定にあるように地質学雑誌掲載論文の著作権は日本地質学会に帰属します.論文中の写真類も当然含まれます.
(3)原則として,写真中にスケールを表示してください.顕微鏡写真の場合のスケール・バーの表示,露顕写真におけるスケールまたは大きさのわかるものの表示(たとえばコインとか人物など),遠景写真などはこの限りではありません.
(4)なるべくなら,写真のスケッチを示してもらったほうが理解しやすいのです.あるいは写真中に矢印や記号をいれるなど工夫して下さい.どこを不整合や断層が通っているのか,著者のいう00構造とはどこを指しているのか読者にわかりにくい場合があります.
(5)写真の枚数が不必要に多い投稿論文がままあります.写真集ではありませんから必要不可欠なものに絞ってください.
(6)論文中にカラー写真をどうしても入れたい場合は相談に応じますが,実費の負担をしていただきます.
(7)すぐれたキャプションは写真の価値を高めます.十分に吟味した簡潔な文章を練って下さい.
未公開文献の引用と謝辞
過不足や偏りのない引用文献が望ましいことはいうまでもありません.先人の成し遂げた業績を正当に評価し,自己の研究の位置付けを明確にするためにも必要なことです.以下の点についてご配慮ください.
(1)卒業論文や修士論文など,印刷されていないものの引用は原則としてできません.これにも異論があるところでしょうが,編集委員会で何回かにわたって議論した結果です.理由としては部外者がその論文を閲覧して引用部分の真偽を事実上チェックできないことが多いためです.また,いわば未公表のデータに準ずるので,部外者の勝手な引用による論文のプラィオリティ侵害を防ぐ意味もあり,このように規定されてきました.しかしながら,最近投稿論文の成立に不可欠な引用文献として引用を必要とする場合が見られる場合が出てきました.本来は印刷出版された報告が科学情報として社会に共有されているわけですが,事情により引用を避けられない場合には,編集委員会の判断として以下の回避策を認める場合もあります.
・最近は,大学あるいは教室ごとに,利用規程が定められる傾向にあります.そうした規定があれば,それに従ってください.
・脚注や私信扱いとして引用し,その内容の再現性が検証できる最低限の生データをアペンディックスで記載する(化石データなら写真テーブルなども).その際,論文の著者から事前に同意を得ておくこと(謝辞や共著者)が必要でしょう.
・投稿者が関係している(指導した)卒論などでは,上記の連絡などが可能ですが,戦前の卒論など筆者が既に存在しない場合や他大学の場合には,内容の転記の許可が簡単には取れません.その場合には,管理者(指導教官か大学当局)から引用に関する許可を取る必要があるでしょう.これは先に触れた著作権の問題に対する事前の防備策にもなります.
(2)従来配布が限られている印刷物は引用文献として問題があるとされていますが(総研報告書など),いまや配布状況はかなり改善されているのでケースバイケースとすることになっています.そこで,このような印刷物を投稿者が引用したい場合には,査読者が内容をチェックできるようにコピーを投稿時に同封して下さい.また,受理出版後に読者の要求に応じてコピーを送付できるならば,配布の限られた印刷物でも引用を認める場合があります.(ここでの引用対象はあくまでも印刷物です.出版組織名と場所が標記できなければ引用文献欄に記載できません.)
(3)投稿者本人に限らず,平行して準備している研究成果は引用できません.準備中と投稿中が相当します.引用が不可欠な場合には,それらの論文が受理されるまで査読を中断して待っていただいています.また,投稿中の論文が受理された段階で引用は可能になりますが,この場合でも,査読者が受理原稿のコピーを要求する場合がありますので,印刷中の論文を引用する場合にはご準備下さい.なお,出版時にも印刷中の場合には,印刷中の論文のページ数は確定できないので,巻とページの代わりにDOI (Document Object Identifier)を引用文献欄に記載していただきます.
(4)謝辞の書き方も難しい点があります.誰にでも謝辞を述べればよいというものでもありません.謝辞にのった方には原則として査読をお願いできませんので本当に当該論文に関与した方に限った方がよいと思います.また,査読者や編集委員会の担当委員などに謝辞を述べていただく場合もありますが,これは筆者の判断におまかせします.
地名対照表について
欧文による投稿には,周知のものを除いて人名・地名・地層名などの対照表をつけるように投稿規定で指定されていますが,最近はあまり見かけなくなってしまいました.あまり厳密には扱っていないのですが,欧文論文で日本・中国・韓国等の地域を扱った場合には,読者の便宜を図るために文末に地名の欧文と現地表記(漢字など)の対照表をつけていただくよう査読時に指示する場合もあります. 日本の場合に限らず,欧文で地名を記述するときに現地の発音にかなっているかどうか確信が無い場合などは,対照表により誤解を避けることができますので,ぜひご検討下さい.
投稿原稿のページ数見込みについて
投稿規定にも明記されていますように,原稿は400字詰め用紙か40字30行の印刷で提出するように指定されています.また,投稿カードにも原稿の刷り上がりページ数を記入いただくようになっています.これらは,編集時に雑誌の構成の際の重要な情報となっているのです.最近ワープロの打ち出しでの投稿がほとんどですが,驚くことに上記の1200字の規定を守っている例の方が少ないのです.さらに,付図類の縮尺や挿入位置の指定もなく,投稿カードの刷り上がりページ数も不明とされている場合などに至っては,編集委員会で字数を数え,付図を縮小した後レイアウトまで行わなければなりません.このような膨大な手間は,本来投稿者の義務であることは言うまでもありませんし,ページ制限ぎりぎりの場合などは,投稿規定違反かどうかの判断も下せません(この例では既に投稿規定違反ですが).また,投稿者の意図に反する様な付図類の縮小なども生じかねませんから,ぜひ投稿前にご自分の原稿のレイアウトや分量を計算するよう心がけて下さい.
記入例
下記の記入例を参考にして下さい(PDFファイル)
・欧文雑誌名略記例
・雑誌名等を引用する際の略記例
・鉱物名などの略号
・地質学雑誌における古生物記載法
Island Arc 日本語要旨 2007. vol. 16 Issue 1 (March)
Island Arc 日本語要旨 2007. vol. 16 Issue 1 (March)
Pictorial Article
Garnet metagabbro-ultramafic complexes in the Pekulney Range, northeast Russia
Akira Ishiwatari, Galina V. Ledneva, Boris A. Bazylev, Yasutaka Hayasaka, Suren A. Palandzhyan, Odin L. Morozov, Kazuto Koizumi, Vasily D. Stcherbakov and Sergey D. Sokolov
ロシア北東部,ペクルニー山脈のざくろ石変斑れい岩−超苦鉄質岩体
石渡 明, Galina V. Ledneva, Boris A. Bazylev, 早坂康隆, Suren A. Palandzhyan, Odin L. Morozov, 小泉一人, Vasily D. Stcherbakov and Sergey D. Sokolov
特集号
Fluids and metamorphism:竹下 徹, 宮崎一博
1. Chemical reaction diversity of geofluids revealed by hydrothermal experiments under sub- and supercritical states
Noriyoshi Tsuchiya and Nobuo Hirano
熱水実験による亜臨界,超臨界状態における地殻流体の化学反応多様性
土屋範芳,平野伸夫
花崗岩および石英の溶解実験を亜臨界から超臨界状態にいたる600℃,60MPaまでの範囲で行った.従来,超臨界状態は,液体でも気体でもない均質な'相 'と考えられていたが,溶解実験の結果は,超臨界状態が, 'liquid-like' 域 と 'vapor-like' 域の2つに区分でき,'liquid-like' 域は亜臨界状態の液体に近い化学反応性を,'vapor-like' 域は亜臨界の気体に近い化学反応性を示すことを明らかにした.また, 臨界状態を可視化して臨界点を測定できる実験システムを考案し,H2O-CO2-NaCl 系流体の臨界点を直接明らかにした.
Keywords: geofluid, supercritical state, chemical reaction, critical point, dissolution, water-rock interation, hydrothermal experiment
From an initial transient to a steady-state in metamorphic reactions: an experimnetal approach in the system dolomite- quartz - H2O
Tadao Nishiyama, Aiko Tominaga and Hiroshi Isobe
変成反応における初期遷移状態から定常状態への遷移:ドロマイト−石英−水系の実験によるアプローチ
西山忠男, 富永愛子, 磯部博志
ドロマイト−石英−水系の反応実験により,反応帯形成過程における同時進行反応の相対的な反応速度の時間変化を追跡した。出発物質としてはドロマイト単結晶+石英粉末+水と石英単結晶+ドロマイト粉末+水の2種を用意し,それぞれ別個に金チューブに封入した。0.1GPa, 600oCの条件下で反応させ,以下の結果を得た。
1) 45−71時間の比較的短時間の実験では,珪灰石やタルクを含む準安定な累帯配列が見られたのに対し,168−336時間の長時間実験では,それらの鉱物は出現しなかった。2)短時間実験では累帯配列の様式は同じドロマイト結晶の場所により異なっていた。3)短時間実験での多様な累帯配列は長時間実験では特定の累帯配列に収斂する。4)ドロマイト結晶には反応帯が形成されるのに対し,石英結晶にはいかなる反応帯も形成されない。これらの現象は初期遷移状態から定常状態への遷移を記録していると考えられる。定常拡散モデルにより累帯配列の安定性について考察し,石英の周囲に反応帯が形成されない理由を体積変化の観点から検討した。
Key words : metamorphic reactions, transient state, steady state, diffusion, reaction zone, kinetics
Chemical mass balance in a reaction zone between serpentinite and metapelites in the Nishisonogi metamorphic rocks, Kyushu, Japan: implications for devolatilization
Yasushi Mori, Tadao Nishiyama and Takeru Yanagi
西彼杵変成岩類の蛇紋岩-変泥質岩反応帯における化学マスバランスと流体生成
森 康, 西山忠男, 柳 哮
蛇紋岩と変泥質岩の反応帯における化学マスバランスから、交代作用にともなう流体生成について検討した。西彼杵変成岩類(九州西部に分布する低温高圧変成帯)では、蛇紋岩と泥質片岩の間の反応帯から多数の鉱物脈が伸びている様子が見られる。反応帯と鉱物脈に含まれる流体包有物が同じ均質化温度を示すことから、両者は同時に形成されたと考えられる。反応帯形成前後の化学マスバランスをアイソコン法により推定したところ、反応帯はプロトリスに比べSiO2、MgO、H2O、K2Oに枯渇していることが明らかになった。これらの成分は、反応帯の成長時に流体相を形成し、鉱物脈を通じて放出されたと考えられる。以上の結果は、反応帯が流体起源になりうることを示す。
Key words : fluid, reaction zone, vein, serpentinite, metasomatism, isocon, Nishisonogi metamorphic rocks
Trace element compositions of jadiete (±omphacite) in jadeitites from the Itoigawa-Ohmi district, Japan: implications for fluid processes in subduction zones
Tomoaki Morishita, Shoji Arai, Yoshito Ishida
糸魚川?青海地域産ヒスイ輝岩中のヒスイ輝石(およびオンファス輝石)の微量元素組成
森下知晃,荒井章司,石田義人
糸魚川?青海地域に産するヒスイ輝岩中のヒスイ輝石(およびオンファス輝石)の微量元素組成をLA-ICP-MSを用いて測定した.これらの輝石の始源的マントル値で規格化した微量元素組成パターンの特徴は軽希土類/重希土類の比が高いこと,イオン半径が大きいために液相濃集元素として振る舞う(LIL)元素,および価数が大きいために液相濃集元素として振る舞う(HFS)元素の両方が多いことである。また,本研究のヒスイ輝石はしばしば自形・累帯構造を呈する事,形成温度圧力条件などから,沈み込み帯で発生した流体からの直接的な結晶化か,もしくは強度の交代作用を受けて形成されたと考えられる。このヒスイ輝岩を形成した流体は,蛇紋岩に関連し,周囲の岩石類と様々な程度で相互作用をした結果形成された可能性がある。
Key words : jadeitite, Itoigawa-Ohmi, trace-element, fluid, subduction, serpentinite
5
Tectono-metamorphic evolution of the Cretaceous Shimanto accretionary complex, ecntral Japan: Constraints from a fluid inclusion analysis of syn-tectonic veins
Hidetoshi Hara and Ken-ichiro Hisada
四万十帯白亜系付加コンプレックスの変成テクトニクス:同造構時鉱物脈中の流体包有物解析からの制約
原 英俊,久田健一郎
関東山地四万十帯白亜系付加コンプレックスの大滝層群にて,2つの構造性鉱物脈(D1・D2ベイン)の水に富む流体包有物のマイクロサーモメトリーから,変成テクトニクス発達史を明らかにした.地温勾配が20-50℃/kmと仮定したとき,D1ベインにおけるマイクロサーモメトリー解析結果から,D1ステージにおける温度・流体圧条件はそれぞれ270-300℃と140-190MPaとなる.またD2ステージのスレート劈開発達時は,D2ベインのマイクロサーモメトリーとイライト結晶度から,300℃および270 MPaを超える変成作用が推定される.D1の付加時からD2のスレート劈開を伴う変成作用の時期にかけて,流体圧は約80 MPa増加する.流体圧が静岩圧に達しているとすれば,この圧力増加現象は,秩父帯付加コンプレックスが四万十帯付加コンプレックスへ衝上したことでもたらされたと考えられる.衝上運動に引き続き,白亜紀最後期に四万十帯・秩父帯付加コンプレックスは同時に変成作用を受けたことになる.
Key words : P-T-d path, micro-thermometry, fluid circulation, quartz vein, slaty cleavage, accretionary complex, Otaki Group, Kanto Mountains
Formation of a high-temperature metamorhpic complex due to pervasive melt migration in the hot crus
Kazuhiro Miyazaki
熱い地殻の浸透メルト移動による高温変成コンプレックス形成
宮崎一博
九州中央部肥後変成コンプレックス (HMC)及び中国柳井地方領家変成コンプレックス(RMC-Y)の変成温度構造と花崗岩質岩の空間分布をみると,高変成度岩はミグマタイトもしくは変成作用と同時期の花崗岩質岩を伴っている.これらの岩石の緊密な関係は花崗岩質メルトの輸送と固結による潜熱の放出が熱源として機能していたことを示している.今回提示した熱モデルによれば,メルト移動速度が増すほど,地殻が任意の温度に上昇するのに必要なメルト移動継続時間とメルト固化体積は減少する.そして,HMC形成時のメルト移動速度はRMC-Yの約3-10倍であり,メルト移動継続時間は約1/10であったと推定できる.RMC-Y南部ユニットは花崗岩の量比が大きいにもかかわらず,変成P/T比が中部及び北部ユニットより高い.RMC-Yの異なる構造ユニットのこの一見矛盾する観察結果も今回提示した熱モデルにより説明できる.即ち,中部及び北部ユニットのメルト移動速度は南部ユニットのそれに比べ速かった可能性がある.結果的に,高温変成コンプレックスの変成P-Tトレンド及び花崗岩質岩の空間分布の違いは熱い地殻のメルト移動速度と継続時間の違いで説明できることを熱モデルは示している.
Key words: high-T metamorphism, Higo, melt migration, Ryoke, thermal modeling
一般論文
Implication of the temporal sulfur isotopic variation during the 2000 eruption of Miyakejima Volcano, Japan
Akira Imai, Nobuo Geshi, Taketo Shimano, and Setsuya Nakada
三宅島火山2000年噴火期間中の硫黄同位体比の経時変化とその示唆
今井 亮, 下司信夫, 嶋野岳人, 中田節也
三宅島火山の2000年噴火の期間中、火山活動の時間的変化を追跡するために、硫黄同位体比の変化を調べた。2000年7月から9月までの間欠的噴火によって放出された火山灰から抽出された水溶性硫酸根のd34S値は,それぞれの噴火で約3‰の変動があるものの、+5‰から+11‰の範囲である。2000年12月から2001月までの間山麓に設置した金属銅トラップによって捕集された硫酸ミストのd34S 値は+6.2‰であった。これらの火山体内の熱水系において同位体平衡にあった硫酸根の硫黄同位体組成は、間欠的な水蒸気噴火およびマグマ水蒸気噴火の後、カルデラの下にあった熱水系の温度が上昇したことを示す。その後、2001年1月から3月の間に捕集された硫酸ミストのd34S値は+9.0‰、2001年5月の小規模噴火によって噴出した火山灰の水溶性硫酸根のd34S値は+11.0‰で、火山体内の熱水系の温度が低下したことを示している。
Key words : Miyakejima volcano, eruption, volcanic ash, sulfur isotope, subvolcanic hydrothermal system, isotopic fractionation
Geochemical characterization of the organic matter, pore water constituents and shallow methane gas in the eastern parts of the Ulleung Basin, East Sea(Japan Sea)
Ji-Hoon Kim, Myong-Ho Park, Urumu Tsunogai, Tae-Jin Cheong, Byong-Jae Ryu,Young-Joo Lee,Hyun-Chul Han, Jae-Ho Oh and Ho-Wan Cheng
東海(日本海)Ulleung海盆(対馬海盆)東部海底堆積物中の有機物,間隙水,間隙メタンガスの地球化学的特徴
Ji-Hoon Kim, Myong-Ho Park, 角皆 潤,Tae-Jin Cheong, Byong-Jae Ryu, Young-Joo Lee, Hyun-Chul Han, Jae-Ho Oh, and Ho-Wan Chang
Ulleung 海盆(対馬海盆)東部から採取されたピストンコアの堆積物,間隙水,headspaceガスの化学分析を行い,堆積物中の有機物と間隙流体の起源を検討した.コアは数枚のテフラを含む泥質堆積物からなり,0.5%を越える全有機体炭素を含む. C/N比およびδ13Corg値から有機物は海洋性有機物(藻類)起源であると考えられる.一方Rock-Eval熱分解によると有機物は熱的に未熟成であり,陸上植物に由来することを示唆する値を示した.この相反する結果は,海洋性の有機物が著しい酸化作用を受けたことに起因するものと考えられる.一方間隙水中の硫酸イオンの濃度はいずれのコアでも深度とともに直線的に減少し,硫酸イオン-メタン境界(SMI)深度は調査地域南部域で海底下3.5 mであり,北部域では6 mよりも深いことが明らかになった.SMI深度の地域差はメタン上昇フラックスの違いを反映している可能性がある.南部域のコアではSMI以深においてメタン含有量の急激な上昇も観察され,直下におけるメタン生成やSMI付近における嫌気的メタン酸化(AMO)の進行を示唆した.一方,北部域のコアでは SMI以深でもメタン含有量の増加はほとんど観察されなかった.δ13CCH4値を計測したところ,全てのコアで-83.5から-69.5‰の範囲にあり,いずれもメタンは微生物起源であることが明らかになった.またδ13CCH4値の鉛直分布はSMIに向けて減少して,SMI付近で最小となる傾向がみられ,この際にδ13CCH4値はメタン量増加に相関して減少した.これらは調査地域で普遍的にAMOが進行していることを反映していると考えられる.
Key words : Atomic C/N ratio, δ13Corg , Rock-Eval pyrolysis, SMI, AMO, Ulleung Basin, East Sea (Japan Sea)
Tectono-metamorphic history of the Tacagua ophiolitic unit (Cordillera de la Costa, northern Venezuela): insights in the evolution of the southern margin of the Caribbean plate
Alessandro Ellero, Alessandro Malasoma, Michele Marroni, Luca Pandolfi and Franco Urbani
ベネズエラ北部,海岸山脈のタカグア・オフィオライト質ユニットの構造変成史:カリブ海プレート南縁部の進化についての考察
カリブ海プレートの南縁部はベネズエラ北部の海岸山脈によく露出しており,そこには大陸性及び海洋性のユニットからなる地塊が融合して産する.海岸山脈においては,カラカス付近の海岸沿いに変成した海洋性ユニットが露出し,その中のタカグア・ユニットは変成した蛇紋岩及びMORB的な化学特徴を示す変塩基性岩によって特徴づけられる.これらの岩石は断片化されたオフィオライト層序を代表し,随伴する泥質・砂質片岩及びそれと互層する石灰質片岩の原岩は,恐らく深海の半遠洋性及びタービダイト性堆積物であろう.タカグア・ユニットでは多段階の変形史が復元され,D1からD4まで4回の褶曲期が認められる.地質学的な状況は,タカグア・ユニットがまず沈み込みプロセスに巻き込まれたことを示唆する.そして,野外で観察されるその後のプロセス(D2からD4)はタカグア・ユニットの上昇削剥過程に関係しているかもしれない.この後期の変形史は,カリブ海・南米プレート境界に平行な移動方向(D2及びD4褶曲期)とそれに垂直な移動方向(D3褶曲期)を特徴とする各変形時期の繰り返しよりなる.これら全ての地質学的証拠は,タカグア・ユニットが斜め沈み込みの卓越する状況下で発達し,横ずれ,圧縮,伸長のテクトニクスが時間とともに繰り返し現われたことを示唆する.
Key words : ophiolite, Tecagua unit, oblique convergence, Caribbean plate, Venezuela
Discovery of Jurassic ammonoids from the Shyok Suture Zone to the northeast of Chang La Pass, Ladakh, northwest India and its tectonic significance
Masayuki Ehiro, Satoru Kojima, Tadashi Sato, Talat Ahmad and Tomoyuki Ohtani
北西インド,ラダック地方チャン峠北東のシュヨク縫合帯からジュラ紀アンモノイドの発見とその意義
永広昌之,小嶋 智,佐藤 正,Talat Ahmad,大谷具幸
北西インド,ラダック地方のチャン峠北東のシュヨク縫合帯から,中期ジュラ紀カロビアンを指示するアンモノイド化石,MacrocephalitesとJeanneticerasを見いだした.シュヨク縫合帯は,インド−アジア大陸衝突帯に位置し,白亜紀島弧(ラダック弧)の背弧域〜背弧海の諸岩類からなると考えられている.上記アンモノイドは,シュヨク縫合帯からの初めてのジュラ紀化石であり,この地帯からの最古の年代データである.ソルタック層として新たに定義された含アンモノイドジュラ系は,おもに砂岩薄層をはさむ陸源泥岩からなり,おそらくはラダック弧の大陸基盤の一部をなしていたと考えられる.
Key words : Shyok Suture Zone, Tsoltak Formation, Jurassic, ammonoid, Ladakh Arc, Himalaya
Petrological variation of large-Volume felsic magmas from Hakkoda-Towada caldera cluster : implications for the origin of high-K felsic magmas in the Northeast Japan Arc
Takashi Kudo, Minoru Sasaki, Yoshihiro Uchiyama, Akifumi Nozawa, Hisashi Sasaki, Takeshi Tokizawa and Shinji Takarada
八甲田-十和田カルデラクラスターにおける大規模珪長質マグマの岩石学的多様性:東北日本弧における高カリウム珪長質マグマの起源について
工藤 崇・佐々木実・内山祥弘・野沢暁史・佐々木寿・時沢武史・宝田晋治
八甲田-十和田カルデラクラスター(HTCC)の大規模珪長質マグマは, HK(高カリウム)タイプとMLK(中〜低カリウム)タイプに区分される.両タイプの成因は,マントル由来マグマの結晶分化作用と地殻の同化作用により説明可能であり,それらの程度はHKタイプでより高い.マグマの時間変遷に注目すると,MLKタイプは活動全期間を通して噴出しているのに対し,HKタイプは初期のみで噴出している.HTCCの活動以前には数百万年間の火山活動休止期があることから,活動初期の地殻は冷えており,マグマ供給経路も未発達であったと考えられる.この環境がマグマの結晶分化と地殻の同化を促進させ,HKタイプマグマを生成した.その後,繰り返されたマグマの供給によって,地殻の温度が上昇するとともに安定したマグマ供給経路が構築された結果,結晶分化と同化の程度が低いMLKタイプマグマが生成された.東北日本弧中軸部の鮮新世〜第四紀火山活動において,HKタイプマグマの出現は極めて稀である.このことは,その生成にはある特別な条件が必要であることを示している.長期の火山活動休止による冷えた地殻がその条件の1つである可能性が考えられる.
Key words: Hakkoda-Towada caldera cluster, high-K felsic magmas,large-volume felsic magmas, magmatic evolution, Northeast Japan Arc, petrological variation, temporal variation
The Heilongjiang Group: a Jurassic accretionary complex in the Jiamusi Massif at the western Pacific margin of NE China
Fu-Yuan Wu, Jin-Hui Yang, Ching-Hua Lo, Simon A.Wild, De-You Sun and Bor-Ming Jahn
Heilongjiang層群:中国北東部,西太平洋縁Jiamusi地塊のジュラ紀付加コンプレックス
ジュラ紀における東アジア大陸縁の造構場については議論がある.本論文ではこの問題について地質年代学的研究を行うために,中国北東部のJiamusi地塊西部に位置するHeilongjiangコンプレックスを選んだ.野外調査・記載岩石学的研究から,Heilongjiangコンプレックスは主に構造的に重なった花崗片麻岩・大理石・苦鉄質-超苦鉄質岩・青色片岩・緑色片岩・石英岩・白雲母-曹長石片岩・両雲母片岩からなり,これらはメランジであることが示された.大理石・両雲母片岩・花崗片麻岩はまず確実に,Heilongjiang層群が密接に伴うJiamusi地塊の高変成度片麻岩複合岩体である Mashanコンプレックスに由来する.超苦鉄質岩・青色片岩・緑色片岩・石英岩(チャート)はオフィオライト構成岩に類似する.花崗片麻岩のジルコンU -Pb年代265±4 Maは,原岩の花崗岩がJiamusi地塊のペルム紀バソリスと同時代に定置したことを示す.花崗片麻岩・雲母片岩の黒雲母・フェンジャイトの 40Ar/39Ar年代は,184-174Maの前期ジュラ紀の後期の変成年代を示す.Mashanコンプレックスを含むJiamusi地塊の初期構成層は,おそらくゴンドワナからの異地性岩塊の一部を生じ,後期汎アフリカ造山運動により影響され,そして前期ジュラ紀にはアジア大陸縁に衝突した. Jiamusiブロックと中央アジア造山帯の東部との間の海洋地殻の沈み込みは,Zhangguangcai山脈での大量のジュラ紀花崗岩の生成を招いた.したがってJiamusi地塊と西側の中央アジア造山帯の衝突は,中央アジア造山帯とは無関係で,環太平洋付加作用の結果であると考えられる.アジア大陸縁に沿うジュラ紀付加コンプレックスの広範な発達はこの解釈を支持する.
Key words : Heilongjiang complex, Jiamusi Massif, Jurassic subduction, northeastern China, ophiolite
Triassic mid-oceanic sedimentation in Panthalassa Ocean: Sambosan accretionary complex, Japan
Tetsuji Onoue and Hiroyoshi Sano
パンサラッサ海におけるトリアス紀大洋性堆積作用
尾上哲治,佐野弘好
ジュラ紀新世〜白亜紀古世付加体である三宝山付加コンプレックスは,パンサラサ海起源の玄武岩,石灰岩,チャートなどの海洋性岩石で特徴づけられる.本研究では,九州南部球磨?五木地域に分布する三宝山海洋性岩石の岩相層序・化石年代から,1)上部トリアス系玄武岩層,2)上部トリアス系浅海成石灰岩層,3)石灰岩角礫岩層,4)中部トリアス〜上部ジュラ系珪質岩層を復元した.これらの層序はそれぞれ海山,海山頂部浅海相,海山上部斜面相,深海相に比較される.復元した珪質岩層の層序から,パンサラサ海の大洋底では,放散虫チャートの堆積がトリアス紀中世からジュラ紀中世頃まで引き続いたことが明らかになった.この期間中,トリアス紀新世カーニアンにはノーマルホットスポット起源の海洋島玄武岩が海山を形成し,海山頂部の浅海域では浅海成石灰岩層の堆積が起こった.珪質岩層の上部ノーリアン放散虫チャートは,この浅海成石灰岩に由来すると思われる再堆積物を含むことから,海山頂部で堆積した浅海成石灰岩層と同時異相として深海環境で堆積したと考えられる.
Key words : Triassic, oceanic sedimentation, Panthalassa, limestone, chert, basalt, Sambosan accretionary complex, Japan
Geochemistry and origin of Archean volcanic rocks from the Upper Keewatin assemblage (~2.7 Ga), Lake of the Woods greenstone belt, Western Wabigoon Subprovince, Superior Province, Canada
Osamu Ujike, Alan M, Goodwin and Tomoyuki Shibata
カナダ,スペリオル区西ワビグーン亜区ウッズ湖緑色岩帯,上部キーワチン火山岩類(約27億年前)の地球化学と成因
氏家 治,Alan M, Goodwin,柴田知之
標記火山岩類は,コマチアイト・ソレアイト・Nbに富む玄武岩〜安山岩(NEBA)と通常のカルクアルカリ岩(NCA)・アダカイト・ショショナイトの5 種に分類できる。コマチアイトマグマはマントルプルームから生じ,他のマグマは始生代島弧系で生じた。海洋スラブの溶融深度の違いにより2種類のアダカイトマグマが生じ,マグマとマントル物質の相互作用によって,アダカイトマグマはAl2O3/Y比とHFSEの相対量が低下し,マントルは諸種マグマの起源岩へと組成変化した。プルームの熱的影響を受けたマントルウエッジからはNEBA・NCA・ソレアイトのマグマが,熱的影響の及ばなかった部分からはショショナイトマグマが生じた。
Key words : Archean, adakite, NEBA, shoshonite, arc volcanism, mantle plume, greenstone belt
投稿案内
投稿案内
地質学雑誌 投稿案内
こちらをご確認ください
https://geosociety.jp/publication/content0002.html#touko
Island Arc 投稿案内
Manuscript submissions to Island Arc can now be made online through REX. Submit articles quickly and easily through a safe and secure site, and track the progress of your manuscript any time of the day.
■ 電子投稿入り口
Island Arc 電子投稿(Wikey社サーバーにて行います)
■ Wiley Island Arcのページ
■ 日本地質学会 Island Arcのページ
ニュース誌 投稿案内
全会員に毎月郵送で配布されます。
■ 記事
各種案内、会員の声、書評など掲載希望の方は事務局にお問い合わせ下さい。原稿投稿は,依頼原稿を除いて,原則会員に限ります。
原稿送付先 ※[at]を@マークにして送信してください.
■ 表紙写真
1.投稿写真は,原則として未発表のものとする.
2.投稿写真は,プリントまたはデジタルファイル(ファイル形式:jpg , pct等)で,A4またはA3サイズに拡大したときに十分解像度があるものであること.
3.投稿写真の著作権については,地質学会に譲渡する.なお,依頼掲載写真についてはこの限りではない.
4.投稿写真全体の,日本語(20字以内)および英文のタイトルと日本語解説を付ける.
5.投稿写真が複数の場合には,それぞれに日本語(20字以内)および英文のタイトルを付ける.
6.タイトルおよび解説の原稿は可能な限り電子媒体で提出することとする.
7.投稿写真は審査の上,地質学会ニュース誌表紙への掲載を決定する.
原稿送付先 ※[at]を@マークにして送信してください.
■ 広告掲載
ニュース誌の掲載広告を募集しています.学会直接取り扱いになりますので、カラー印刷・掲載サイズなどご相談に応じます.是非ご利用ください。
○広告掲載価格(単位:円)
価格(モノクロ)
カラー
表4
60,000
+10,000
表3
50,000
−
表2
40,000
−
記事中
35,000
−
注:表4以外でカラーをご希望の場合は価格表とは異なります.1/2ページの料金は,上記の×0.6になります.
お得な割引価格も設定しています!
詳しくは、学会事務局までe-mail: main@geosociety.jp 電話03-5823-1150
または、詳しくはこちら
geo-Flash(メールマガジン)・ホームページ
geo-Flash(ジオフラッシュ)は,地質学に関わる,あるいは学界活動に関する情報をいち早く会員の皆様にお届けすることを目的としています.メールアドレスを登録してある会員に,毎月2回(第一・第三火曜日)定期配信されます.緊急のニュースがある場合は臨時号を出します.メールマガジンには記事の概略が掲載され,全文はホームページに掲載されますので長文や図版・写真も大いに歓迎します.会員の皆様からの情報も積極的に載せていく予定ですので、大いにご活用いただきますようお願い申し上げます.原稿送付先 ※[at]を@マークにして送信してください.
■ お知らせ
地質学会会員もしくは執筆を依頼された方は投稿することができます.メールマガジンを通じて会員に広報したい内容がありましたら,お知らせください.メールマガジンでの広報が適切と判断したものを発信していく予定です.支部例会,専門部会のお知らせなど,全会員向けでないものでも受け付けます.
■ いろいろコラム
ご自身の専門分野のことや、研究・教育環境、技術環境、フィールドで怖い思いをしたこと、最近感じたこと、地質学会のホームページにてアピールしたいこと、他会員に役立つと思われることなど自由に書いて下さい.図・写真は大いに歓迎します.原稿長さは特に定めませんが節度ある範囲とします.
■ 地球なんでもQ&A
これは地球科学に関する想定問答集であり、読者からの質問に直接答えるものではありません.コーナーのトップには「これは地質学会としての統一見解ではな く、読者の理解の一助としてインターネット委員会が整備したものです」と明記され,それぞれの記事に解説者の名前と所属がつきます.希望があれば解説者本 人や所属機関のホームページへのリンクを貼ることができます.中学理科以上の知識を有し、地球や地質に関心のあるインターネット読者が対象です.一般的な 地球や地質に関する疑問や関心に応え,専門的になりすぎないようにして下さい.
原稿長さ:400字程度
図・写真:オリジナルの写真および図版をお願いします.ラフスケッチやからボランティアイラストレーターに清書を依頼できますのでお知らせ下さい.
投稿記事は他の設問とのバランスも考慮されて校閲されます.また引用は適切に行ってください.
■ ヘッダーの写真とトップページのキャッチコピー
全ページのヘッダー背景写真、およびトップページのキャッチコピーは、リロードするたびにランダムに表示されます。ヘッダーの背景写真は900x110 pix以上の画像ファイル,キャッチコピーは550x170 pix以上の画像ファイルをお送り下さい,なおキャッチコピーの文字はこちらで埋め込むこともできます.
投稿する原稿、図版、動画等のデジタル原稿(データ)は、下記のフォーマットのものが受け付けられます.
文書: MS Word, Text, PDF, RTF, XML
図、表、写真: PDF, EPS, Adobe Illustrator, MS Excel, JPEG, TIFF, PNG, GIF, Adobe PhotoShop
動画: WMV, AVI, Flash, QuickTime, MPEG2, MPEG4, H.264, DivX
Island Arc 日本語要旨 2006. vol. 15 Issue 4 (December)
Island Arc Vol. 15 Issue 4(December) 日本語要旨
特集号 Thematic Section: The COREF Project: Coral-reef front migration in the RyukyuIslands
井龍 康文
1. An introductory perspective on the COREF Project
Yasufumi Iryu, Hiroki Matsuda, Hidekaki Machiyama, Werner E. Piller, Terrence M. Quinn and Maria Mutti
サンゴ礁堆積物は,熱帯〜亜熱帯浅海域の古環境変化を復元するために有用である.なかでも,サンゴ礁の分布の北限・南限(サンゴ礁前線と呼称する)に位置するサンゴ礁は,第四紀の氷期・間氷期サイクルに関連した気候変化や海水準変動に鋭敏に応答したと考えられる.そこで,我々は,北西大西洋におけるサンゴ礁の分布の北限に位置する琉球列島において,1) サンゴ礁前線の移動の実態,規模,推進メカニズムの解明,2) 第四紀気候変動に対するサンゴ礁の応答の解明,3) 地球表層の炭素循環におけるサンゴ礁の役割の解明を主目的として,陸上掘削および海洋掘削を実施する科学計画であるCOREF計画を立案した.本計画により,1) 琉球列島におけるサンゴ礁の成立時期,2) 氷期における黒潮の流路,3) 炭酸塩岩の初期続成作用における気候や海水準変動の影響も明らかになると期待される.
Key words: coral, Integrated Ocean Drilling Program, International Continental Scientific Drilling Program, limestone, Quaternary, reef, Ryukyu Group, Ryukyu Islands, sealevel
2. Bathymetry, biota and sediments on Hirota Reef, Tane-ga-shima; the northernmost coral reef in the Ryukyu Islands
Emiko Ikeda, Yasufumi Iryu, Kaoru Sugihara, Hideo Ohba and Tsutomu Yamada
種子島広田沖のサンゴ礁(琉球列島における北限のサンゴ礁)の地形,生物相,堆積物
池田恵美子ほか
琉球列島における北限のサンゴ礁が分布する種子島において,島南東部の広田礁の地形,生物相,堆積物を調査した.広田礁の地形は,岸から沖合に向かって,浅礁湖,沖合平坦面,礁縁,礁斜面に区分される.浅礁湖は,岸側凹地とパッチ帯に細分される.沖合礁原は水深が1.7 m前後の平坦面であるが,中琉球や南琉球のサンゴ礁では,これに対応する地形区は,内側礁原,礁嶺,外側礁原に分化しており,内側礁原ならびに外側礁原の水深は平均低潮位潮位にほぼ一致している.この差異の原因として,中琉球や南琉球と比較して,北琉球における後氷期の礁成長が遅く始まったことや礁の成長速度が小さかったことが想定される.広田礁の造礁サンゴ群集は高緯度地域を特徴づける種を含む.一方,海藻群落は熱帯〜亜熱帯種を多く含む.
Key words: algae, coral, coral reef, Ryukyu Islands, Tane-ga-shima
3. Paleoenvironmental interpretations of Quaternary reef deposits based on comparisons of selected ten modern and fossil larger foraminifera from the Ryukyu Islands, Japan
Kazuhiko Fujita, Hiroaki Shimoji and Koichi Nagai
琉球列島に産出する現世および化石大型有孔虫10分類群の比較に基づく第四紀サンゴ礁堆積物の古環境解釈
藤田和彦ほか
現世大型有孔虫群集データを用いて,大型有孔虫を含む石灰岩の堆積環境を復元する新たな方法を提案した.まず,琉球列島宮古島西方沖水深200 m以浅から採取された表層堆積物試料を用いて,形態に特徴のある10種類の有孔虫分類群について,遺骸殻 (1-2 mm径) の水深および地形分布を調べた.その結果,特定の粒径を対象としたことで,各分類群の分布範囲は従来報告されていた分布範囲よりも狭くなった.また,10 分類群の在不在データを基にした多変量解析により,異なる堆積環境に対応する4つの群集が識別された.次にこの現世データを基にして,琉球層群の大型有孔虫石灰岩の堆積環境を推定した.化石群集と現世群集のデータを合わせた多変量解析や現世アナログ法の結果,化石群集が堆積した環境は現在の島棚の水深50 -100 m付近に類似することが推定された.この結果は堆積相や生砕物組成から推定された結果と一致する.本研究が提案する古環境推定方法は北西太平洋のサンゴ礁複合体堆積物の古環境を復元する上で有用である.
Key words: larger foraminifera, multivariate analysis, paleoenvironmental analysis, Quaternary, Ruykyu Group
4. Latitudinal changes in larger benthic foraminiferal assemblages in shallow-water reef sediments along the Ryukyu Islands, Japan
Kaoru Sugihara, Naoto Masunaga and Kazuhiko Fijita
琉球列島のサンゴ礁浅海域における大型底生有孔虫群集の緯度変化
杉原 薫ほか
琉球列島内での大型底生有孔虫群集の緯度変化を明らかにするために,石垣 島,久高島と種子島のサンゴ礁礁原堆積物中の大型底生有孔虫の種構成や個体数を明らかにした.石垣島,久高島と種子島では,25,24と13タクサの大型底 棲有孔虫がそれぞれ確認された.Baculogypsina sphaerulata,Neorotalia calcarとAmphystegina spp.は全島で卓越してみられたが,石垣島と久高島で普通にみられたCalcarina gaudichaudiiを含むCalcarina 属数種は,種子島は全くみられなかった.これらの結果は,緯度の増加に伴う表層海水温の低下などを原因とする各タクサの生息北限の違いを反映していると考えられる.
Key words: biogeography, coral reefs, larger foraminifera, latitudinal changes, Ryukyu Islands, taxonomic composition
5. Culture-dependent and _independent analyses of subsurface microbial communities in oil-bearing strata of the Sagara oil reservoir
Keiichi Sasaki, Akio Omura, Tetsuo Miwa, Yoshihiro Tsuji, Hiroki Matsuda, Toru Nakamori Yasufumi Iryu, Tsutomu Yamada, Yuri Sato and Hiroshi b
南西諸島伊良部島西方沖の島棚縁下に発達する低海水準期サンゴ礁の230Th/234Uおよび14C年代測定
佐々木圭一ほか
琉球諸島伊良部島西方沖の島棚縁下から地震波探査によって発見されたマウンド状地形の地質と成因を明らかにするために,水深118.2mで海底掘削が行われた.回収された試料に造礁サンゴと石灰藻からなるバウンドストーンが含まれることから,マウンド状地形が小規模ながらサンゴ礁であることが判明した.そしてαスペクトル230Th/234Uおよび加速器質量分析計14C年代測定により,このサンゴ礁が30.5〜22.2kaの低海水準期に形成されたことが明らかになった.以上の結果は,琉球列島のような西太平洋亜熱帯域にも,最終氷期最盛期にサンゴ礁が発達したことを示す.また,低Mg方解石セメントが形成されていることから,サンゴ礁が離水した可能性がある.これは,当時の海水準が現在より少なくとも126m低下したことを意味する.
Key words: coral reef, last glacial maximum, Ryukyu Islands, sealevel, U-series dating
6. Characterization of magnetic particles and magnetostratigraphic dating of shallow-water carbonates in the Ryukyu Islands, Northwestern Pacific
Saburo Sakai and Mayumi Jige
北西太平洋,琉球列島に分布する第四系浅海性炭酸塩堆積物に含まれる磁性粒子の特定と古地磁気年代
坂井三郎,地下まゆみ
琉球列島に分布する第四系浅海性炭酸塩堆積物(琉球層群)の形成年代を推定するために,透過型電子顕微鏡による磁性粒子の観察と古地磁気年代測定を行った.琉球層群に含まれる磁性粒子は,主に磁鉄鉱/磁赤鉄鉱からなる単磁区粒子(40-140 nm)で構成されており,その形態と粒子サイズは磁性バクテリアを起源とする磁鉄鉱の特長を示した.透過型電子顕微鏡下では多磁区粒子は認められなかった.これらの結果から,琉球層群中には磁性バクテリアが遍在し,その磁鉄鉱/磁赤鉄鉱粒子が残留磁化の担い手であることが明らかとなった.古地磁気層序を適用した結果,琉球層群はハラミロサブクロンを含んでおり,本研究で解析した琉球層群の形成開始時期は,グレートバリアリーフの形成開始時期(ブルーン期以降)とは異なっている.
Key words: biogenic magnetite, magnetostratigraphy, Pleistocene, Ryukyu Islands, shallow-water carbonates
7. Floral changes in calcareous nannofossils and their paleoceanographic significance in the equatorial Pacific Ocean during the last 500,000 years
Shun Chiyonobu, Tokiyuki Sato, Reika Narikiyo and Makoto Yamasaki
石灰質ナンノ化石から見た赤道太平洋地域過去50万年間の古海洋
千代延 俊ほか
赤道太平洋地域の第四紀後期の古海洋環境を明らかにするために,東西赤道太平洋に位置するODP Hole 807AとODP Hole 846Bの石灰質ナンノ化石群集解析を行った.調査結果はいずれのHoleも約20-30万年前を境に石灰質ナンノプランクトン生産量および小型のコッコリスの相対頻度がいずれも減少するのに対し,し暖流系種および下部透光帯種の相対頻度が増加する傾向を示した.これは赤道太平洋域の湧昇流強度弱体化が 20-30万年前に発生したことを示唆している.またHole 807Aでのより顕著な暖流系種相対頻度の増加は,西赤道太平洋地域でWPWPがより拡大したことを示す.
Key words: calcareous nannofossil, latest Quaternary, paleoceanography
一般論文
1. Prograde P-T path of jadeite-bearing eclogites and associated HP/LT rocks from western Tianshan, NW China
Wei Lin and Masaki Enami
中国北西部・西部天山地域に産するヒスイ輝石を含むエクロジャイトおよび高P/T変成岩類の累進P-T経路
林 緯・榎並正樹
中国北西部・西部天山地域Akeyazhi川流域に位置するKuldkoulaの緑色片岩帯中には,ヒスイ輝石を含むエクロジャイトや青色片岩類が局所的に産する.これらのP/T型変成岩類に含まれるざくろ石は,全体として結晶の中心部から周縁部にかけてMgが漸増,Mnが漸減する昇温型累帯構造を示し,低 Ca/高Feの核部と高Ca/低Feの外縁部に二分される.ざくろ石の核部は,ヒスイ輝石-オンファス輝石(Xjd=0.34-0.96),バロワ閃石?タラマ閃石?パーガス閃石,パラゴナイト,緑れん石,ルチル,石英と少量の曹長石を包有する.他方,ザクロ石の外縁部には,少量のオンファス輝石,藍閃石,緑レン石,ルチルと石英が包有物として認められる.また,基質部には主要なエクロジャイト相の鉱物としてオンファス輝石,藍閃石,パラゴナイト,ルチルおよび石英が産する.これらの鉱物共生より見積もられる平衡条件は,ざくろ石の核部形成時において0.9GPa/390℃- 1.4Gpa/560℃外縁部形成時には1.8 GPa/520℃エクロジャイト相変成作用ピーク時で2.2GPa/495℃-2.4GPa/℃である.これらの変成条件と鉱物の組成共生関係の連続的な変化は,研究対象とした高P/T型変成岩類が,次のような反時計回りのP-T経路を経験したことを示す:(I)青色変成相高圧部?エクロジャイト相低圧部条件下の沈み込み初期,(ii)ほぼ等温条件下での圧力上昇を示す沈み込み後期,(iii)わずかな冷却をともなう沈み込み最末期,この,沈み込み最後の時期に認められる負のP-T経路は,(I)沈み込みスラブによる連続的な沈み込み帯の冷却と(ii)上昇開始直前に起こったスラブ上部の逆転した温度構造を横切る変成岩類の移動の記録である可能性が高い.
Key words: China, counterclockwise pressure-temperature path, eclogite, glaucophane, high-pressure/low-temperature metamorphism, jadeite, western Tiansban
2. SHRIMP U-Pb ages of the Latest Oligocene-Early Miocene rift-related Hidaka high-temperature metamorphism in Hokkaido, northern Japan
Tadashi Usuki, Hiroshi Kaiden, Keiji. Misawa, and Kazuyuki Shiraishi
漸新世最末期-中新世前期のリフトに関連する日高高温変成作用の高感度高分解能イオンマイクロプローブU-Pb年代
臼杵 直ほか
日高変成帯におけるグラニュライト相変成作用の時期を決定するため,泥質グラニュライト3試料から分離したジルコンを高感度高分解能イオンマイクロプローブ (SHRIMP)を用いてU-Pb年代測定を行った.ジルコンの被覆成長リムやプリズム状のジルコンのU-Pb年代は23.7±0.4Maから17.2±0.5Ma(206Pb/238U年代,31分析)を示す.このことは漸新世最末期-中新世前期に日高変成帯にグラニュライト相変成作用が起こった有力な証拠である.この高温変成作用は千島海盆と日本海盆のリフティングの間にアセノスフェアの上昇によって引き起こされたと考えられる.
Key words: back-arc rifting, granulite, Hidaka Metamorphic Belt, SHRIMP U-Pb age, zircon
3. Organic facies and geochemical aspects in Neogene neritic sediments of Takafu syncline area of central Japan : Paleoenvironmental and sedimentological reconstructions.
Sawada Ken
中部日本、高府向斜地域の新第三系浅海性堆積物における有機物相および有機地球化学的特徴:古環境および堆積学的復元
沢田 健
中部日本、高府向斜地域に分布する新第三系浅海性堆積物において、ケロジェン・マセラルの有機岩石学的記載と、その炭素同位体比(13C)およびバイオマーカーの有機地球化学的分析を行い、新第三紀の古日本海南縁地域(海域)の古環境と堆積システムの年代変化を復元した.高府向斜地域には上部中新統〜下部鮮新統の千見層(青木層)、境ノ宮層(小川層)、下部柵層が分布する.これらの地層中のケロジェン・マセラル組成の変化は、従来の堆積相解析や古生物学研究から推定されている堆積およびテクトニクス史とよく一致していた.ケロジェン・マセラルの13C値の変化は古日本海南縁域周辺の陸上植生の変化を反映し、一方、バイオマーカー組成の変化は浅海域で生物生産を担う海生プランクトン群集の変化を反映していると推察した.さらに、それらの変化傾向が同調していることから、新第三紀の古日本海における陸上植生と海洋生物生産の共進化の可能性を指摘した.
Key words: biomarker, carbon isotope composition, kerogen, land-ocean linkage, Neogene paleo-Japan Sea, neritic paleoenvironment
4. In-situ hydraulic tests in the Active Fault Survey Tunnel, Kamioka Mine, excavated through the active Mozumi-Sukenobu fault zone and their hydrogeological significance.
Tsuyoshi Nohara, Hidemi Tanaka, Kunio Watanabe, Noburo Furukawa and Akira Takami
茂住-祐延断層を貫く活断層調査トンネルにおける原位置水理試験とそれらの水理地質学的重要性
野原 壯ほか
跡津川断層帯の茂住-祐延断層を貫く世界初の活断層調査専用トンネルにおいて,活断層の水理地質学的調査と原位置水理試験を行った.その結果,地下深部の活断層本体が絞り込まれ,その近傍の小断層に関連した導水構造が把握された.活断層に沿って,その両側に2つの非対称な導水構造が認められた.そのひとつは,地表とトンネル間の連続したほぼ垂直な導水構造で,もうひとつは古い天水起源の水を蓄えた主な帯水層と推定された.地表から調査が困難な地下深部の構造の連続性に着目した原位置での調査の結果,この主な帯水層中で,小断層沿いのせん断による充填鉱物の破壊と割れ目の発達が生じ,二次的に間隙率が増加したことが示された.
Key words: active fault, Atotsugawa Fault system, discharged water, hydraulic test, Mozumi-Sukenobu Fault, tunnel
Island Arc 日本語要旨 2006. vol. 15 Issue 3 (September)
Island Arc Vol. 15 Issue 3(September) 日本語要旨
特集号
Dynamic sedimentation in forearc basins: Results from the Choshi and Sagara drilling projects
北里 洋、和田秀樹、Kevin Pickering、平 朝彦
1. Origins of hydrocarbons in the Sagara oil field, Central Japan
Tomohiro Toki, Toshitaka Gamo and Urumu Tsunogai
相良油田における炭化水素ガスの起源
土岐知弘、蒲生俊敬、角皆 潤
2002年1〜3月に実施された相良油田掘削計画(最大深度200.6 m)において静岡県相良油田(34°44’N, 138°15’E)から孔内ガス及び地下水を採取した。相良油田から産出する相良原油は成因として微生物の関与が指摘されていた。本研究では、相良油田の掘削孔内ガスおよび地下水試料中の炭化水素ガスの濃度および炭素同位体比を測定し、相良油田内に分布する炭化水素ガスの成因について検討した。メタンの炭素同位体比及びメタン/エタン比から、相良油田における炭化水素ガスはすべての深度において有機物の熱分解起源の特徴を示した。各炭化水素ガス相互の炭素同位体比の傾向から、軽炭化水素ガスの重合反応が起きている可能性は小さい。
Key words : Sagara oil field, SDP, hydrocarbons, free gas, in situ fluid, carbon isotope, thermogenic origin, microbial origin
2. Geochemical characteristics of Tertiary Sagara oil from an active forearc basin, Shizuoka, Japan
Svetlana Yessalina, Noriyuki Suzuki and Hiroyuki Saito
活動的な前弧堆積盆に産する静岡県第三紀相良石油の地球化学的特徴
Svetlana Yessalina, 鈴木徳行,斉藤裕之
相良油田は掛川堆積盆中にあり,太平洋側の前弧堆積盆にある油田として数少ないものの一つである.掛川堆積盆には石油生成能力の低い堆積岩類が多く,相良石油の起源はいまだ明らかにされていない.石油炭化水素組成は,相良石油がわずかに微生物分解作用を受けていること,移動にともなう汚染や化合物の分別作用を受けていることを示している.芳香族炭化水素組成から見積もられる有機熟成度はビトリナイト反射率にして0.9-1.2%程度あり,高い熟成度にある.顕著な高等植物起源バイオマーカー,高いPr/Ph比,乏しい有機硫黄化合物によって特徴づけられており,相良石油は沿岸成,デルタ成,河川成の砕屑性堆積岩に由来していることが示唆される.掛川堆積盆の大深度において陸源有機物に富む石油根源岩から生成した石油が,活動的な前弧堆積盆で形成された多くの断裂や断層を通じて地表付近に達し相良油田を形成したものと考えられる.
Key words: biomarker, forearc basin, higher plants, Sagara oil
3. Geochemical characteristics of crude oils from the Sagara oil field, Shizuoka Prefecture, Japan
Susumu Kato, Amane Waseda and Hideki Nishita
静岡県相良原油の地球化学的特徴
加藤 進・早稲田 周・西田英毅
相良油田から採取した原油6試料について地球化学的分析を行い,新潟原油と比較することによってその特徴を明らかにし,根源岩や原油の移動プロセスについて考察した。
相良原油の特徴として,1)低硫黄の軽質原油,2)環境指数が小さい,3)Ph/nC18比が小さく,Pr/nC17比やオレアナン/ホパン比が大きい,4)ステラン組成では相対的にC29が多く,C28が少ない,5)炭素同位体組成が軽い,が挙げられる。
相良原油の根源岩は主に海成有機物からなるが,新潟原油の根源岩よりも陸源有機物に富み,より酸化的な環境で堆積したと推定される。炭素同位体組成やC28ステランの相対量は根源岩の年代が古第三紀であることを示唆している。堆積盆の深部で生成された原油が断層に沿って上方に移動し,集積したと推測される。
Key words : Sagara oil field, Niigata oils, light hydrocarbons, Pr/nC17 ratio, Pr/nC18 ratio, oleanane/hopane ratio, carbon isotope compositions
4. Lithological and physical properties for core samples from the Sagara oil field -Oil occurrence in Sagara core sample-
Satoshi Hirano, Yoshiaki Araki, Koji Kameo, Hiroshi Kitazato and Hideki Wada
相良油田より掘削されたコア試料の岩相および物性と石油の産状
平野 聡、荒木 吉章、亀尾 浩司、北里 洋、和田 秀樹
静岡県榛原郡相良町にて地表から200.60 m深の学術掘削を行ない、岩石試料の記載、物性測定の後、試料中の石油の産状と比較した。本掘削地域においては、空気浸透率が10-11 m2以上の場合、流体の通路または貯留岩層としてのポテンシャルがあることが明らかになった。得られたコア試料は、中新世後期の相良層群に属する泥岩、砂岩、礫岩である。空気浸透率は、岩相を問わず主に炭酸塩セメントの有無に直接的に反映されている。炭酸塩セメントが発達する岩相では空気浸透率が低く、石油とは共存しない。したがって、このような炭酸塩セメントの発達過程は、石油の移動や貯留岩層の形成に大きな影響を与えるということが言える.
Key words : carbonate cement, porosity, permeability, stable isotope, forearc sediments, Sagara Drilling Program(SDP)
5. Culture-dependent and _independent analyses of subsurface microbial communities in oil-bearing strata of the Sagara oil reservoir
Takuro Nunoura, Hanako Oida, Noriaki Masui, Fumio Inagaki, Ken Takai, Satoshi Hirano, Kenneth H. Nealson, and Koki Horikoshi
相良油田地下生命圏の微生物生態解析
布浦拓郎・笈田花子・益井宣明・稲垣史生・高井 研・平野 聡・Kenneth H. Nealson・掘越弘毅
相良油田掘削により採取した(最大深度200m)コア試料を用い、石油含有層及び非含有層の微生物群集を培養法及び非培養法により解析し、比較検討した。細菌数は石油を含む層で特異的に増大し、また、16S rRNA遺伝子クローン解析からは、石油含有層序ではPseudomanas stutzeriが圧倒的に優占することが示唆された。一方、培養可能な微生物群集を評価でも、16S rRNA遺伝子クローン解析の結果と同様、石油含有層では石油分解を行うPseudomanas stutzeriの優占が示された。今回の研究により、相良油田では石油含有層序には特定の石油分解菌が濃集していることが明らかになった。
Key words : subsurface microbial community, Sagara oil reservoir, Pseudomonas, petroleum
6. MIS11-19 pollen stratigraphy from the 250m Choshi core , NE Boso Peninsula, central Japan: Implications for the early/mid-Brunhes (400-780ka) climate signals
Masaaki Okuda, Hiroomi Nakazato, Norio Miyoshi, Takeshi Nakagawa, Hiroko Okazaki, Saneatsu Saito and Asahiko Taira
房総半島250 m 銚子コア等に基づく更新世中期の花粉層序とその古気候学的意義
奥田昌明・中里裕臣・三好教夫・中川 毅・岡崎浩子・斎藤実篤・平 朝彦
房総半島北東域の浅海成層(犬吠層群)から得られた250 m 銚子コアのMIS11-19部分に対して花粉分析および関連考察を行うことにより,更新世中期における花粉ベースの氷期間氷期指標を認定ならびに花粉層序の構築を行った.銚子コアに対する花粉と酸素同位体のマルチ分析の結果は,スギ属等の温帯性針葉樹とトウヒ属等の北方性針葉樹の交代がδ18O 曲線と万年オーダーで相関し,また指標テフラを介して外洋のSPECMAP 等スタックとも合致することを示した.またこれら花粉群と気温の関係を現生の表層花粉データを用いて確認した結果,上記の温帯性/北方性針葉樹比が更新世中期における氷期間氷期サイクルの指標になり得ることが示された.さらに同様の花粉比計算を琵琶湖のMIS1-11 花粉層序(Miyoshi et al. 1999)に適用した結果,この変化は日本列島中軸部におおむね共通することが認められ,過去80万年間を通じての広域花粉層序が得られている.
Key words : Boso Peninsula, Inubo Group, Middle Pleistocene, palynology, temperate/boreal
7. Effect of depositional processes on the origin and composition of organic matter, examples from the Pleistocene sediments in the Choshi Core, Boso Peninsula
Akiko Omura, Koichi Hoyanagi and Satoko Ishikawa
有機物組成とその起源に及ぼす堆積作用の影響:房総半島の更新統銚子コアの例
大村亜希子,保柳康一,石川仁子
千葉県銚子地域に掘削された更新統のコア試料(銚子コア)を対象として堆積環境変化と有機物の堆積作用との関連を検討した.銚子コアは,岩相・生痕化石相と堆積環境指標である有機物組成の三角ダイヤグラム上での分布領域・形態のはっきりした陸源有機物の増加にもとづき,上方浅海化する陸棚堆積物で構成されていると解釈された.C/N比・堆積有機物の安定炭素同位体比測定と堆積有機物の顕微鏡観察の結果,これらの堆積物に保存されている有機物には海洋プランクトン起源と陸上植物起源の両者が含まれ,海洋起源有機物の大部分が形態的特徴のないアモルファス有機物であることがわかった.約50万年前以前は,陸源有機物の増加に伴って有機炭素濃度は増加するが,これ以降は浅海化に伴う陸源砕屑物の流入による希釈と酸化効果が働いたと考えられ,有機炭素濃度は減少傾向を示す.
Key words : kerogen composition, δ13C value, sedimentary environments, Pleistocene, Choshi core, basin margin, Boso peninsula
8. Age model, physical properties and paleoceanographic implications of the upper Quaternary core sediments in the Choshi area, central Japan
Koji Kameo, Makoto Okada, Moamen El-Masry, Toshio Hisamitsu, Saneatsu Saito, Hiroomi Nakazato, Naohiko Okouchi, Minoru Ikehara, Hisato Yasuda, Hiroshi Kitazato and Asahiko Taira
銚子地域で掘削された中部更新統コアの年代モデルと物性データおよびその古海洋学的重要性
亀尾浩司,岡田誠,Moamen El-Masry,久光敏夫,斎藤実篤,中里弘臣,大河内直彦,池原実,安田尚人,北里洋,平朝彦
北西太平洋における中期更新世の海洋環境の変遷を明らかにするために,1998年に千葉県銚子市北西部において陸上ボーリングが行われ,全長250mの連続した更新統コアが得られた.本研究では,そのコアの岩相層序を明らかにした上で,石灰質ナンノ化石と古地磁気の検討を行い,コア中に88万年前から46万年前までの4つの基準面を見いだした.このことに基づくと,このコアの酸素同位体比曲線は同位体比ステージ24から11までに相当することが明らかになり,同層準の年代モデルを確立できる.さらに,MSCLによる堆積物物性の検討結果は,帯磁率と堆積物密度の変動が氷期・間氷期サイクルと連動しており,その変化が黒潮フロントの動きと同調していることを示している.
Key words : Choshi area, Northwestern Pacific, late Pleistocene, age model, physical property, oxygen isotope record, calcareous nannofossils, magnetostratigraphy
一般論文
1. Zircon U-Pb ages from tuff beds of the upper Mesozoic Tetori Group in the Shokawa district, Gifu Prefecture, central Japan
Nao Kusuhashi, Ai Matsumoto, Masaki Murakami, Takahiro Tagami, Takafumi Hirata, Tsuyoshi Iizuka, Takeshi Handa, and Hiroshige Matsuoka
岐阜県荘川地域に分布する手取層群(中生界上部)の凝灰岩層のジルコン・ウラン鉛年代
楠橋 直・松本 藍・村上雅紀・田上高広・平田岳史・飯塚 毅・半田岳士・松岡廣繁
中部日本に分布する中生界上部手取層群は,植物化石や海生・非海生動物化石を多産し,とくに哺乳類や恐竜を含む多様な脊椎動物化石の産出層としてよく知られている.手取層群は中期ジュラ紀から前期白亜紀における東アジアの生物相を理解するうえで重要な地層である.しかしながら,手取層群の堆積年代についてはいまだによくわかっておらず,そのため他地域との正確な対比は非常に難しい.手取層群の累層の信頼できる年代決定の第一歩として,岐阜県高山市荘川地域(旧大野郡荘川村)に分布する手取層群より凝灰岩試料を採取し,それらに含まれるジルコン粒子を用いてレーザーアブレーション誘導結合プラズマ質量分析計 (laser ablation inductively coupled plasma massspectrometry: LA-ICPMS) によるウラン鉛年代測定をおこなった.牛丸層,御手洗層,大黒谷層から得られた最も若く信頼性の高いウラン鉛年代はそれぞれ,130.2 ± 1.7 Ma, 129.8 ± 1.0 Ma,117.5 ± 0.7 Ma (誤差はすべて2SE) であった.荘川地域に分布する手取層群は,上部ジュラ系から下部白亜系であると考えられていた.しかし,本研究の結果により,同地域の手取層群は九頭竜亜層群から赤岩亜層群まですべてが下部白亜系であることが明らかになった.牛丸層,御手洗層,大黒谷層は, Hauterivian 階の上部からBarremian 階,Hauterivian 階の上部から Barremian 階,Barremian 階からAptian 階にそれぞれ対比される.
Key words : U-Pb geochronology, LA-ICPMS, zircon, Tetori Group, Gretaceous, Gifu Prefecture, Shokawa, central Japan
Island Arc 日本語要旨 2006 vol. 15 Issue 2(June)
無題ドキュメント
Island Arc Vol. 15 Issue 2(June)
1. Major and trace element provenance signatures in stream sediments from the Kando River, San'in district, southwest Japan
Edwin Ortiz and Barry P. Roser
島根県神戸川の河川堆積物における主成分元素・微量元素の起源特性
島根県神戸川流域における基盤岩は2つに大別される.白亜紀−古第三紀の花崗岩類・珪長質火山岩類が上流地域に卓越し,より苦鉄質な主に中新世の火山岩・火山砕屑岩が下流域に分布する.また地球化学的に特徴のある三瓶山アダカイト質火山噴出物が西方に分布する.流域の河川堆積物86試料の2つの粒度区分(180μm以下と180-2000μm)について,主成分元素と14微量元素の蛍光X線分析を行い,淘汰と起源岩種の変化による粒度区分間の組成の差異を調べた.<180μm粒度区分では180-2000μm粒度に比べ,SiO2が減少し大部分の他の主要元素および微量元素が増している.Na2O・K2O・Ba・Rb・Srは180-2000μm粒度に比べ乏しいかまたは小さな差異を示す.花崗岩類が卓越する流域からの堆積物は,K2O・Th・Rb・Ba・Nbにより富むことで中新世火山岩類からの堆積物と識別される.花崗岩類起源の<180μm粒度区分もまたZr・Ce・Yに富む.一般に中新世火山岩類起源の堆積物は,その苦鉄質な起源を反映してより多くのTiO2・Fe2O3*・Sc・V・MgO・P2O5を含む.起源に三瓶火山を含む堆積物は,アダカイトの特徴を反映して高いSr・CaO・Na2O と低いYで特徴づけられ,この特徴は掃流物質が均質化されるにつれ組成がより変化しなくなる下流の主流路まで持続する.起源岩の平均に対して規格化すると,<180μm粒度がいくつかの元素で富化されているのに比べ,180-2000μm粒度の組成がその起源からあまり分別されていないことが示される.粒度区分間の差異は花崗岩類起源の堆積物で最も大きい.堆積物の風化指数は比較的低く,起源岩の風化は中程度で温和な気候であったことを示す.いくつかの花崗岩類起源の<180μm粒度では180-2000μm粒度に比べジルコンの濃集が生じているものの,Th/Sc・Zr/Sc比は全体として下流域における起源岩と均質化の両方を密接に反映している.
Key words : stream sediments, geochemistry, major elements, trace elements, provenance, sorting, weathering, Kando River, Japan
2. Geomorphic characteristics of the Minjiang drainage basin(eastern Tibetan Plateau) and its tectonic implications: new insights from a DEM study
Hui-ping Zhang, Shao-feng Liu, Nong Yang, Yue-qiao Zhang and Guo-wei Zhang
チベット高原東部の岷江(Minjiang)流域の地形学的特徴とそのテクトニックな意義:DEM研究からの新しい見解
張 会平, 劉 少峰, 楊 農, 張 岳橋, 張 国偉
岷山(Minshan)山脈とその周辺地域はチベット高原の東縁辺における主要な大陸斜面をなす。岷江流域は四川盆地に隣接するこのチベット高原の東縁辺に位置する。Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)で得られた数値標高モデル(DEM)の解析に基づき、岷江流域の中で異なる特徴を有する領域に分けることができる。北から南への単調な起伏度の増加は、高原における第四紀堆積物の形成および四川盆地に対するチベット高原東縁辺の広域的隆起に起因する。またDEM解析によって明らかになった岷江流域の二次的な流域の形及びそれらに分布する河川水路のプロフィールは、東西方向に非対称である。岷江主流域においては、東部の二次流域の輪郭長さおよび面積は西部のものより小さい値を示す。これらの違いは岷山山脈における第四紀の隆起の空間的な変化に起因すると考える。また西部より東部における河川長さと分岐比が小さい値を示すことは、東部の河川系が発達途上であることとその若さを示唆する。
Key words: geomorphology, Minjiang drainage basin, Tibetan Plateau, SRTM-DEM
3. Middle Miocene to Quaternary primary basalt and high magnesian andesite magmas of north Hokkaido, Japan: Source mantle characteristics and degrees of partial melting
Hiroyuki Ishimoto, Kenji Shuto and Yoshihiko Goto
北部北海道における中期中新世〜第四紀の初生玄武岩及び高マグネシア安山岩質マグマ:起源マントルの特徴と部分溶融度
石本博之,周藤賢治,後藤芳彦
北部北海道における中期中新世〜第四紀の未分化玄武岩及び高マグネシア安山岩は3つの時期からなる大規模な火山活動により生じたものであり,これらは初期(12-10Ma),中期(9-7Ma),後期ステージ(3-0Ma)のものに区分される.本研究は,これら3期にわたって産する未分化岩類に含まれるカンラン石及びスピネルの化学組成及び全岩化学組成などから,初生マグマの分離深度や起源マントルにおける部分溶融度の時空変遷を考察した.その結果,初期と中期を境に溶け残りマントル中のスピネルのCr/(Cr+Al)が低下していることや初生マグマの分離深度が浅くなったことが推定できた.すなわち起源マントル物質の改変やそれに伴うウェッジマントル内の温度構造の変化が示唆され,これは中期中新世における二つの背弧海盆(日本海盆及び千島海盆)拡大に関連する可能性が高い.
Key words: degrees of partial melting, North Hokkaido, olivine fractionation, primary magma, segregation depth, Tertiary volcanism
4. Characteristics of subcontinental lithospheric mantle beneath Baegryeong Island, Korea: spinel peridotite xenoliths
Young-Woo Kil
朝鮮,白 令羽 島下の大陸下リソスフェア・マントルの特徴:スピネルかんらん岩捕獲岩
白 令羽 島の中新世アルカリ玄武岩中に見出されるスピネルかんらん岩についての地球化学的データは,リソスフェアの組成,化学的プロセス,平衡温度圧力条件に関する情報を提供する.スピネルかんらん岩捕獲岩はプロトグラニュラー組織とポーフィロクラスチック組織の中間的な組織を呈し,上昇するアルカリ玄武岩マグマによって偶然に捕獲されたものである.捕獲岩は深さ50〜70 km,温度800-1100℃の場所に由来する.スピネルかんらん岩捕獲岩のモード組成と鉱物化学組成の変化は,捕獲岩が1〜10%の分別溶融を被ったことを示す.白_島のスピネルかんらん岩は部分溶融によるメルト抽出後に潜在的なマントル交代作用を被った.スピネルカンラン岩を肥沃化した交代作用の媒体はカーボナタイト・メルトであった.
Key words: Baegryeong Island, lithospheric mantle, spinel peridotite, metasomatism.
Island Arc 日本語要旨 2006 vol. 15 Issue 1(March)
Island Arc Vol. 15 Issue 1(March) 日本語要旨
特集号
Thematic Section: Evolution of ophiolites in convergent and divergent plate boundaries (Part 2)
Yildirim Dilek, 小川勇二郎, Valerio Bortolotti, Piera Spadea
1. Initiation and evolution of intra-oceanic subduction in the Uralides: Geochemical and isotopic constraints from Devonian oceanic rocks of the Southern Urals, Russia
Piera Spadea and Massimo D'Antonio
ウラル造山帯における海洋内沈み込みの開始と進化:ロシア・ウラル山脈南部の海洋起源岩石の地球化学的・同位体的特徴
ウラル造山帯の南部はデボン紀後期〜石炭紀初期の衝突型造山帯であり,デボン紀初期〜中期の海洋内収束域であるMagnitogorsk島弧(MA)と西ヨーロッパ・クラトン縁辺部との衝突によって形成された.MAと大陸縁辺部の境界はウラル主断層帯(MUF)として定義され,これはオフィオライトや大陸性高圧低温型変成岩の存在によって特徴づけられる縫合帯である.
ウラル山脈南部における造山運動以前のイベントや動力学を解明するため,非移動性のインコンパチブル微量元素(REEやHFSE)分析やSr-Nd- Pb同位体地球化学的手法をMA産岩石に適用した.特に島弧形成初期のボニナイトやアンカラマイト,島弧成熟期の島弧ソレアイト系列,島弧ソレアイト〜カルクアルカリ系列の中間型,およびカルクアルカリ系列の岩石について研究を行った.MAの火成作用の特徴として起源物質の特異性が挙げられる.例えば枯渇したN-MORBタイプのマントル起源物質に由来する岩石や,スラブ起源の水に富む流体によってエンリッチした岩石がみられる.その他Nd,Pb同位体組成からもエンリッチしている証拠が確認されたが,その程度は少ない.
造山運動以前のイベントに関する更なる情報がMindyak地塊の変ハンレイ岩類から得られた.この岩石は海洋底におけるロジンジャイト化とその後の高温変成作用を被った多様なハンレイ岩を原岩とする.この高温変成作用の年代は島弧形成初期の火成年代と一致し,初期島弧における沈み込みが約410 Maに起こったことを意味する.したがって,海洋内における収束開始から最終的な大陸衝突までの間隔を31 Maと見積もることができた.この値は西太平洋で現在起こっている衝突現象から得られた値と調和的である.
初期の火成作用の特徴と高温変成岩の解析から, MUFオフィオライトの多くが,複雑な造山運動以前の進化史をもつテチス型に属することが分かった.
Key words: arc-continent collision, Southern Uralides, intra-oceanic island arc, metamorphic sole, geochemistry, Pb-, Nd-, Sr-isotopes, forearc ophiolites
2. Geodynamic significance of ophiolites within the Calabrian Arc
Francesca Liberi, Lauro Morten and Eugenio Piluso
(イタリア南部)カラブリア弧のオフィオライトの地球動力学的重要性
アペニン山脈南部のカラブリア弧北部には,ネオテーチスに属する海洋リソスフェアの断片が断続的に露出している.それらは低温高圧型変成作用を受けたオフィオライト岩類を含み,変成超苦鉄質岩及び変塩基性岩と,変泥質岩,変砂質岩,大理石,石灰質片岩の互層よりなる.これらのオフィオライト岩類は,カラブリア弧北部のナップの重なりの中で中間的な位置を占め,上盤側のヘルシニア期大陸地殻と下盤側のアペニン石灰質ユニットの間にある.文献によれば,これらのオフィオライト岩類はいくつかの構造的・変成岩岩石学的ユニットに区分される.地球化学的特徴は変塩基性岩がソレアイト的な(T-MORB型の)非アルカリ岩に由来することを示し,蛇紋岩の原岩としてはハルツバージャイトとレールゾライトが示唆される.
異なる露頭から得られた変塩基性岩の圧力・温度・変形履歴はある程度共通した特徴を示す.(1) 累進変成作用期は,典型的なアルプス型の地温勾配に沿い,最高350℃,0.9 GPaに達した.この時期の高圧変成鉱物は,圧縮テクトニクスによって形成された普遍的な葉状構造に沿って再結晶している.(2) 後退変成作用期は2つに区分される.前期は400℃,0.3 GPaに至る等温減圧的な経路で特徴づけられ,後期は温度低下の経路をたどる.低圧条件で第2回目の変形が起き,1 mmから10 mスケールの非対称褶曲が形成され,それらによって西方へ張り出す大構造が描き出される.第3回目の変形は脆性的な引張構造によって特徴づけられる.
異なる露頭から得られた構造的・変成岩岩石学的発達史は共通しており,温度圧力計と変形史による解析から,これらの岩石は,アルプス造山期の沈み込みと上昇運動の過程で,(上盤側が)西へ張り出す付加プリズム中の構造的板状岩体として振舞ったことを示す.当時の海洋リソスフェアの沈み込みは現在の東方に向かっていた.ネオテーチスの閉塞後,本地域のヘルシニア期大陸地殻が,アフリカ側大陸縁の一部またはアフリカとヨーロッパの間の大陸性小プレートとして,オフィオライト質付加プリズムに対して衝上した.
Key words: Calabrian Arc, ophiolites, high pressure/low temperature metamorphism, Neo-Tethys, accretionary wedge
3. Age and petrogenesis of plagiogranite intrusions in the Ankara m四ange, central Turkey
Yildirim Dilek and Peter Thy
トルコ中央部,アンカラメランジュの斜長石花崗岩貫入岩体の年代と岩石成因
トルコ中北部,イズミール・アンカラ・エルジンカン縫合帯(IAESZ)中のアンカラメランジュは,中生代前期にサカリヤ及びキルゼヒール両大陸塊の間に発達した海洋性基盤岩の残骸を代表するオフィオライト断片を含む.このオフィオライト中の蛇紋岩化した上部マントルかんらん岩と下部地殻岩石は,輝緑岩及び斜長石花崗岩の岩脈によって切られており,それらの岩脈は既存の海洋リソスフェア中に同時に定置したことを示す相互貫入関係を示す.斜長石花崗岩脈のジルコンU-Pb年代値は179±15Ma程度のコンコーディアを示し,これはこの分化した岩石の結晶化年代と解釈される.しかし,この岩石のジルコンの4番目の分離試料は,1.7 Gaより古い残存成分の存在を示し,これはバルカン半島のロドプ・ストランジャ変成岩体中央部の先カンブリア系に由来する可能性がある.斜長石花崗岩の岩石学的形成モデルを検討した結果,玄武岩質初生メルトが,無水あるいは水に飽和した条件で,早期に角閃石が関与しない結晶分別作用を高程度(< 70%)まで行うことによって,アンカラメランジュの斜長石花崗岩の希土類濃度を容易に実現することができる.同時期の輝緑岩の微量元素組成およびその他の地球化学的特徴は,斜長石花崗岩に類似し,共通の初生メルトを示唆する.斜長石花崗岩脈・輝緑岩脈双方のTa-Nbパターンは,島弧に関連した岩石成因の典型的特徴を示し,涸渇したくさび型マントルへの沈み込みスラブ由来成分の付加によって説明できる.これらジュラ紀前期のオフィオライト質基盤岩類と岩脈は地中海東部地域でパレオテーチスとネオテーチスの間の背弧域で形成された.イズミール・アンカラ・エルジンカン海はこの背弧環境で発達し,関連する縫合帯は何段階もの発達史を示す.
Key words: Ankara m四ange, plagiogranite intrusions, Early Jurassic ophiolites, Tethys, fractional crystallization, Izmir-Ankara-Erzincan suture zone, Turkey, eastern Mediterranean.
4. Oceanic plateau accretion inferred from Late Paleozoic greenstones in the Jurassic Tamba accretionary complex, southwest Japan
Kazuto Koizumi and Akira Ishiwatari
西南日本のジュラ紀付加体,丹波帯の後期古生代緑色岩から推定される海台付加過程
小泉一人・石渡 明
ジュラ紀付加体,丹波帯中の緑色岩の産状は主に,チャートや石灰岩の大規模岩体に密接に伴って産する大規模緑色岩と,泥岩を基質とする混在岩中にチャートや石灰岩,砂岩などと共にブロックまたはレンズとして産する緑色岩(混在岩中緑色岩)の2つに分けられ,前者は構造的上位のいわゆる丹波帯
|| 型地層群に含まれる化石や放射年代から,どちらも形成年代は古生代後期と考えられている.大規模緑色岩は一様にE-MORB的な海台玄武岩に類似した組成を示すのに対して,混在岩中緑色岩は海洋島玄武岩とN-MORBから構成される.これらの違いは,付加した海洋底リソスフェアの構造の違いに起因し,厚い海台を形成していた岩石はそれほど破断されずに大規模緑色岩体として付加体中に取り込まれたのに対し,比較的薄い海洋地殻や小規模な海山・海洋島は,破断・変形されて混在岩中緑色岩として取り込まれたのだろう.このことは厚い緑色岩体を含む付加体の形成において,大規模海台の付加が重要であることを示す.
Key words : Mino-Tamba Belt, greenstone geochemistry, La-ICP-MS Cpx trace elements, oceanic Plateau,
5. Podiform chromitites in the lherzolite-dominant mantle section of the Isabela ophiolite, the Philippines
T. Morishita, E. S. Andal, S. Arai and Y. Ishida
マントル部分がレルゾライトに富むイザベラ・オフィオライト(フィリピン)中のポディフォーム型クロミタイト
森下知晃,Eric S. Andal,荒井章司,石田義人
一般にマントル部分がレルゾライトに富むオフィオライトからはクロミタイトの産出が少ない.フィリピン,イザベラ・オフィオライトのマントル部分はレルゾライトに富み,低速拡大海洋底起源であると考えられているが,ポディフォーム型クロミタイトが産出する.本論文ではクロミタイトとその近傍のカンラン岩の記載岩石学的特徴と鉱物化学組成を報告し,このクロミタイトが海洋底から島弧的なテクトニックセッティングへの変更に伴い海洋底起源のマントル物質中に,島弧起源の性質を持つマグマが通過する際に,メルト供給量が多い部分でカンラン岩の融解とそれに引き続くメルト―マントル反応によって形成されたとするモデルを提案する.
Key words : podiform chromitite, ophiolite, melt-rock. interaction, rare earth element, supra-subduction
6. Dredge petrology of the boninite- and adakite-bearing Hahajima Seamount of the Ogasawara (Bonin) forearc: An ophiolite or a serpentinite seamount?
Akira Ishiwatari, Yuki Yanagida, Yi-Bing Li, Teruaki Ishii, Satoru Haraguchi, Kazuto Koizumi, Yuji Ichiyama and Masaru Umeka
小笠原(ボニン)前弧,無人岩とアダカイトを産する母島海山のドレッジ岩石学:オフィオライトか蛇紋岩海山か?
石渡 明・柳田祐樹・李 毅兵・石井輝秋・原口 悟・小泉一人・市山祐司・梅香 賢
白鳳丸KH03-3航海及び淡青丸KT04-28航海において,母島海山の数地点から1,000個以上の岩石標本がドレッジされた.この海山は北西−南東に延びた60×30 km大の長方形を呈し,頂部は平坦で水深約1,100 mである.標本は主にオフィオライト岩類よりなり,火山岩類はMORB類似のソレアイト玄武岩・輝緑岩,カルクアルカリ玄武岩・安山岩,無人岩,高Mgアダカイト質安山岩,デイサイト,流紋岩を含む.斑れい岩類はトロクトライト,かんらん石斑れい岩,かんらん石斑れいノーライト(転移ピジョン輝石含有),斑れい岩,ノーライト及び角閃石斑れい岩で,海嶺玄武岩型と島弧玄武岩型の鉱物化学組成を示す.超苦鉄質岩類は主に涸渇したマントルハルツバージャイト(スピネルCr#50-80)及びそれが蛇紋岩化した岩石で,ダナイト,ウェルライト,輝石岩などの火成集積岩を伴う.この岩石組合せは沈み込み帯域 (SSZ)起源を示す.従来のドレッジ結果も考慮すると,超苦鉄質岩はこの海山の北東−南西方向に延びる2つの地帯に沿って産し,そこには蛇紋岩や斑れい岩の角礫岩も多いが,それ以外の地域は超苦鉄質岩を産しない.伊豆小笠原マリアナ前弧沿いに,10 km大の円錐形の蛇紋岩海山が多数配列するが,母島海山はこれらと異なり,オマーンオフィオライトのイズキ岩体と形や大きさが類似するオフィオライト衝上岩体と解釈した方がよい.ドレッジ標本の多くが円礫でマンガン殻が薄い(<2 mm)ことは,母島海山が海面上に隆起し波食を受たことを示唆する.この状況は,海洋地域の数少ないオフィオライトの地表露出域,マコーリー島に似る.太平洋プレート上の小笠原海台が母島海山の東に隣接し,この海台の衝突と沈み込みが前弧オフィオライトの上昇を引き起こした可能性がある.
Key words: Izu-Bonin-Mariana forearc, boninite, adakite, MORB-like tholeiite, gabbro, depleted harzburgite
7. Mantle process beneath Philippine Sea back-arc spreading ridges: A synthesis of peridotite petrology and tectonics
Yasuhiko Ohara
フィリピン海背弧拡大軸下のマントルプロセス:カンラン岩岩石学とテクトニクスに基づく考察
小原泰彦
背弧海盆拡大軸下で起こっているマントルプロセスの一般則を得るため、フィリピン海背弧海盆拡大軸のうち、パレスベラリフトとマリアナトラフについて、カンラン岩の岩石学的特徴とテクトニックセッティングの関係について検証を行った。パレスベラ海盆拡大軸(パレスベラリフト)は、高速−中速型の拡大速度を有していたにも関わらず、テクトニクスとカンラン岩の組成が、超低速−低速拡大軸のそれに類似していることが特徴的である。また、海洋コアコンプレックスが拡大セグメントの全長に渡って発達していること、及びカンラン岩が拡大セグメントの中央に露出していること、という2つの観察事実は、パレスベラリフトの特異性を更に際立たせている。パレスベラリフトは、部分融解程度の低い肥沃な融け残りカンラン岩(レールゾライト・ハルツバーガイト)、含斜長石ハルツバーガイト及びダナイトを産するが、これらの岩相は、赤道大西洋中央海嶺のロマンシュ断裂帯や、インド洋・北極海の超低速拡大軸から報告されているものに類似している。パレスベラリフトにおけるテクトニクスとカンラン岩の組成のこれらの特徴は、浸透的なメルトの移動と浸透的なメルト−マントル相互反応が、パレスベラリフト下の重要なマントルプロセスであったことを示している。グローバルな観点では、この「浸透的メルト移動タイプマントルプロセス」は、超低速拡大軸のような厚いリソスフェアを有する拡大軸のセグメント中央で生じることが期待される。一方、マリアナトラフは、典型的な低速拡大軸であり、カンラン岩をセグメント端に産する。その岩相は、一般的な深海カンラン岩に典型的に見られる、融け残りのハルツバーガイトと、貫入脈を有するハルツバーガイトである。マリアナトラフにおけるテクトニクスとカンラン岩の組成のこれらの特徴は、チャネルによるメルト(あるいは流体)の移動と限定的なメルト−マントル相互反応がマリアナトラフ下の重要なマントルプロセスであったことを示している。グローバルな観点では、この「チャネル形式メルト移動タイプマントルプロセス」は、セグメント端における低温の壁岩カンラン岩の存在のために、あらゆる拡大軸のセグメント端におけるリソスフェア浅部で生じることが期待される。
Key words : Philipping Sea, backarc basin, peridotite, mantle process, porous melt flow, channeled melt flow, melt-mantle interaction
8. Zircon sensitive high mass-resolution ion microprobe UミPb and fission-track ages for gabbros and sheeted dykes of the Taitao ophiolite, Southern Chile, and their tectonic implications
Ryo Anma, Richard Armstrong, Toru Danhara, Yuji Orihashi
チリ南部タイタオ・オフィオライトの斑糲岩およびシート状脈岩から分離したジルコンのSHRIMP U-Pb年代とフィッショントラック年代とテクトニックな意義
安間 了・Richard Armstrong・檀原 徹・折橋 裕二・岩野 英樹
タイタオ・オフィオライトはチリ三重点のごく近傍に露出する。斑糲岩と超塩基性岩は複雑に褶曲されるが、シート状岩脈はブロック回転のみを受けている。斑糲岩とシート状脈岩から分離したジルコンのSHRIMP U-Pb年代測定およびFT年代測定を行った。斑糲岩は、5.9±0.4 Maから5.6±0.1 Maの放射年代幅を持つが誤差の範囲で一致する。デイサイトのU-Pb年代は5.2±0.2 Maであった。これらの年代は、マグマが6 Maの海嶺衝突事件の間に生じ、ごく短い期間に定置したことを示す。チリ海嶺の短いセグメントが6 Ma衝突事件の時に定置したのだろう。
Key words : Taitao ophiolite, ridge subduction, ridge collision, SHRIMP, fission track dating, emplacement
9. Tectonic control of bioalteration in modern and ancient oceanic crust as evidenced by carbon isotopes
Harald Furnes, Yildirim Dilek, Karlis Muehlenbachs and Neil R. Banerjee
炭素同位体により証拠づけられる現世と過去の海洋地殻における生物変質へのテクトニックな支配
現在の低速・中速拡大海洋地殻である中央大西洋(CAO)とコスタリカリフト(CRR)の玄武岩質枕状溶岩の生物変質したガラス質縁部に広く存在する炭酸塩について炭素同位体の値を検討した.CAOの生物変質したガラス質試料のδ13C値は-17から+3 パーミル(VPDB)の間の広い範囲を示し,他方CRRの試料の値は-17から-7パーミルとずっと狭い範囲にある.この変動はガラスの微生物変質の間の異なった微生物代謝の生産物と考えられる.一般的に低いδ13C値(-7パーミル以下)は,有機物の酸化の間に微生物が生成したCO2から沈澱した炭酸塩によるものである.0 パーミル以上の正のδ13C値は,H2とCO2からCH4を製造するメタン棲のArchaeaによるCO2の利用の結果であろう.低拡大速度のCAO地殻でのH2の高い生産は,CRR地殻がずっと少ない断層とおそらくは少ないH2生産を有し層状の偽層序を示すのとは対照的に,海洋底近くないし海洋底上の断層で区切られ強く蛇紋岩化したかんらん岩の結果であろう.異なる拡大速度で生じたと考えられる2つのオフィオライトの枕状溶岩のガラス質縁部からのδ13C値の比較はこの解釈を支持する.アルバニアのジュラ紀のミルディタオフィオライト複合岩体(MOC)は,生物起源炭酸塩が類似のδ13C値範囲を持ち,低速拡大のCAO地殻のそれと似た地質構成を示す.西ノルウェーの後期オルドビス紀のSolund-Stavfjordオフィオライト複合岩体(SSOC)は,中程度の拡大速度の中央海嶺での発達の地質構造的・地球化学的証拠を有し,CRRのそれと似た生物起源炭酸塩のδ13C値を示す.この比較研究の結果に基づけば,拡大速度に依存する海洋リソスフェアのテクトニックな発達が微生物の進化に重要な支配をしており,そしてδ13C値がガラス質の生物変質した溶岩の生物起源炭酸塩に保存された,と結論できる.
Keywords: Bioalteration of oceanic crust, ophiolites, spreading rates and mid-ocean ridges, carbon isotopes of lavas, microbial life in upper oceanic crust, Costa Rica Rift, Mirdita ophiolite
10. Serpentinite textural evolution related to tectonically controlled solid-state intrusion along the Kurosegawa Belt, northwestern Kanto Mountains, central Japan
Ken-ichi Hirauchi
関東山地北西部,黒瀬川帯沿いのテクトニックに固体貫入した蛇紋岩の変形史
平内健一
関東山地北西部の黒瀬川帯には,蛇紋岩体が山中白亜系(前弧海盆堆積物)と南部秩父帯の地層群(ジュラ紀〜前期白亜紀の付加体)の地質境界に沿って点在する.本研究では,蛇紋岩を微細組織と蛇紋石の組成に基づいて3タイプ(塊状蛇紋岩,アンチゴライト蛇紋岩,クリソタイル蛇紋岩)に区分した.塊状蛇紋岩はかんらん石・輝石の仮像組織を保持しており,蛇紋岩化作用の後に変形を被っていないことを示す.アンチゴライト蛇紋岩は仮像を構成するリザーダイトとクリソタイルを置換して形成され,アンチゴライトは形態定向配列をなす.それらは場所によりクロムスピネルのポーフィロクラストやアンチゴライトの細粒化を伴い,比較的高温高圧条件での延性変形によって特徴づけられる.クリソタイル蛇紋岩は繊維状クリソタイルの一定方向の発達を伴い,地下浅部の低温条件で,上記の蛇紋岩を置換または重複して形成される.アンチゴライト蛇紋岩とクリソタイル蛇紋岩の面構造は共に蛇紋岩体の延長方向に平行であり,下部地殻や上部マントルでのほぼ完全な蛇紋岩化作用を受けた蛇紋岩が,断層帯に沿って固体貫入した時の連続的な変形をあらわしている.
Key words : serpentinite, chrysotile, antigorite, deformation texture, solid-state intrusion, Kurosegawa Belt, Kanto Mountains.
一般論文
1. Integrated description of deformation modes in a sedimentary basin: a case study around a shallow drilling site in the Mizunami area, eastern part of southwest Japan
Yasuto Itoh, Kenji Amano and Naoki Kumazaki
堆積盆内変形モードの総合的記載:西南日本東部,瑞浪地域の浅掘坑井周辺でのケーススタディ
伊藤康人, 天野健治, 熊崎直樹
堆積盆のテクトニクスを反射法地震探査・坑井掘削・古地磁気学を統合して解析する.西南日本東部の瑞浪地域で,浅掘斜坑井が反射法地震探査と地質調査によって示された断層を貫通している.坑壁画像の地質構造を用いて方位付けしたコア試料について,古地磁気測定を行った.熱消磁・交流消磁実験によって6層準で安定な特徴的残留磁化が確認され,等温残留磁化の段階獲得実験から主な強磁性鉱物はマグネタイトと考えられた.坑井での構造解析から推定された多段階の変形を補正した後に,特徴的磁化方位は従来の研究結果と同様に中期中新世以前の島弧の時計回り回転を反映する東偏した方位を示す.信頼できる古地磁気データをコンパイルして,中期中新世以降に伊豆−小笠原弧の衝突によって引き起こされた西南日本東部の差動的回転を記述した.本研究で示されるのは次の2点である:(i)瑞浪地域は,赤石構造線で境される高変形帯の近傍にある.(ii)西南日本前弧側の変形は赤石構造線周辺に集中しており,衝突イベントによって顕著な破断を伴わず緩やかに屈曲した背弧側と大きく異なっている.
Key words : borehole, seismic interpretation, logging, paleomagnetism, differential rotation, collision, southwest Japan
2. Tephrostratigraphy and paleoenvironmental variation in late Quaternary core Sediments of the southwestern Ulleung Basin, East Sea (Sea of Japan)
ll-Soo Kim , Myong-Ho Park , Byong-Jae Ryu and Kang-Min Yu
日本海(East Sea)鬱陵海盆(Ulleung Basin)の堆積物コアにおける後期第四紀のテフラ層序学的・地球化学的・古環境学的変化
日本海(East Sea)の鬱陵海盆(Ulleung Basin)で採取された2本の堆積物ボーリングコアにおける後期第四紀のテフラに関するテフラ層序学的,地球化学的,古環境学的なデータを記載した.堆積物は海洋酸素同位体ステージ1-3に対比され,主としてシルト砂・ラピリテフラ・火山灰層を挟む泥からなる.その中で,鬱陵島由来のラピリテフラ層(9.3 kaの鬱陵=隠岐テフラ)は主として塊状ガラス粒子からなる.一方,九州南部由来の火山灰層(22-24.7 kaの姶良丹沢火山灰)は平板状あるいは気泡壁ガラス粒子からなる.またラピリテフラ層よりSiO2含有量が高く,Na2O+K2O含有量が低い.地球化学的なデータ(C/N比・水素インデックス・S2ピーク)及びTmaxの推定によると,テフラ層以外のコアの細粒堆積物は多くが海洋起源であることを示す.Termination1の間,コアの有機炭素含有量は増加した.これは対馬海峡(KoreaStrait)における氷河衰退時の対馬暖流の流入に起因すると考えられる.
Key words : tephra layers, total organic carbon, Ulleung Basin, East Sea (Sea of Japan), late Quaternary
3. 40Ar/39Ar ages of the Blueschist facis pelitic schists from Qingshuigou in the Northern Qilian Mountains, Western China
Yongiiang Liu , Franz Neubauer, Johann Genser, Akira Takasu, Xiaohong Ge and Robert Handler
中国西部,祁連山脈北部の清水溝に産する青色片岩相泥質片岩の40Ar/39Ar年代
劉 永江, Franz Neubauer, Johann Genser, 高須 晃, 葛 肖虹, Robert Handler
中国祁連山脈北部の清水溝に産する泥質片岩は主に藍閃石,ざくろ石,白色雲母,クリノゾイサイト,緑泥石,紅簾石を含む.これらの片岩の同位体年代値は,清水溝の高変成度青色片岩の形成に新しい束縛条件を与える.白色雲母の40Ar/39Ar 年代は442.1-447.5 Ma(1つの鉱物粒についての全溶融年代)及び445.7-453.9 Ma(白色雲母分離試料の積分年代)を示す.これらの年代(442.1-453.9 Ma)は青色片岩相の変成ピーク年代またはその直後の上昇定置過程における冷却年代を示す.我々の40Ar/39Ar 年代値は,本地域のエクロジャイト及び青色片岩の既公表年代値と同様であり,このことはエクロジャイトと泥質片岩が1つの沈み込みイベントで同一の高圧変成作用を受けたことを示す.この年代学的証拠と,残存海盆で堆積したシルル紀フリッシュ層及びデボン紀モラッセ層の発達から,我々は祁連山脈北部のもとになった海洋がオルドビス紀の末には閉塞し,デボン紀には急速な造山帯の隆起があったと結論する.
Key words: blueschist, eclogite, 40Ar/39Ar dating, metamorphism, Northern Qilian
4. Geochemistry of geopressured hydrothermal waters in the Niigata sedimentary basin, Japan
Huilong Xu, Jianwei Shen and Xuewu Zhou
新潟堆積盆における岩圧下の熱水の地球化学
新潟堆積盆の地熱水は化学組成により4つのグループ(Na-SO4型,Na-SO4-Cl型,Na-Cl型,Na-Cl-HCO3型)に区分される.Na-SO4型の地熱水は,通常堆積盆の外側部分で水-岩石反応の結果生じる.Na-Cl型の地熱水はさらに化学組成と同位体組成により,初生的Na-Cl型の岩圧下の地熱水と混合Na-Cl型の地熱水に細分される.初生的Na-Cl型の岩圧下の地熱水は,地下深くに封じられた変質化石水を含む岩圧下の熱水系に起源をもつ.この地熱水は堆積層の上部ないし地表へと上昇し,一般に天水起源の地下水とは混合しない.この型の水は熱伝導により冷やされ,熱水におけるCl-の濃度は海水のそれと非常に似ている.δDとδ18O値は温度によらずおよそ一定である.初生的Na-Cl型の岩圧下の地熱水は,主に褶曲した新第三紀層の背斜軸に沿って分布する.混合Na-Cl型の地熱水は,岩圧下の熱水系の放出活動に関係しており大部分は活断層に沿って生じる.この型の地熱水は,岩圧下の熱水系が突発的なテクトニックイベントにより活断層に沿って放出され,天水起源の浅い地下水が岩圧下の地熱水と混合することにより生じる.
Keywords: geothermal water, geopressured hydrothermal system, expulsion activity, isotope chemistry, Niigata sedimentary basin
5. Mineralogical and geochemical study of newly discovered mafic granulite, NW China:implication for tectonic evolution of Altay orogenic belt
Hanlin Chen, Zilong Li, Shufeng Yang,Chuanwan Dong,Wenjiao Xiao and Yoshiaki Tainosho
中国北西部より新たに発見された苦鉄質グラニュライトの鉱物学的・地球化学的研究:アルタイ造山帯の構造発達史
Hanlin Chen, Zilong Li, Shufeng Yang, Chuanwan Dong, Wenjiao Xiao, 田結庄良昭
中国北西部アルタイ造山帯から苦鉄質グラニュライトを発見した.この岩石は斜方輝石(XMgが高くAl2O3含有量は少ない),単斜輝石(TiO2, Al2O3含有量が少ない),角閃石と黒雲母(XMgが高く,F, Clに乏しい)を含む. 岩石は750-780℃,6-7 kbarのピーク変成作用の後,時計回りの温度圧力経路をたどり590-620℃,2.3-3.7 kbarの後退変成作用を被った.全岩組成は高いMg/(Mg+Fe2+)比とAl2O3含有量が特徴的であり,U, Th, K, Rbに乏しい.希土類元素パターンは軽希土に富み,Euの正の異常が若干みられる.MORBにて規格化したスパイダー図ではNb, P, Tiに枯渇している.したがって,この岩石は島弧の形成および沈み込みの両方あるいはどちらか一方と密接に関係したカルクアルカリ玄武岩であると考えられる.この岩石の143Nd/144Nd比は高く,εNd(0)>0であることから,その起源は枯渇したマントルであろう.この苦鉄質グラニュライトの成因は,島弧で形成されたカルクアルカリ玄武岩が地殻深部に沈み込み,グラニュライト相の変成作用を被った後に衝上断層の活動により上昇したと考えられる.
Key words: mafic granulite, mineralogy, geochemistry, tectonic evolution, Altay orogenic belt
Island Arc 日本語要旨 2005 vol. 14 Issue 4
The Island Arc Vol. 14 Issue 4(December) 日本語要旨
特集号その1
Uplift of the Himalaya-Tibet region and the Asian Monsoon: Geologic, Geomorphic & Environmental Consequences
Guest Editor:Pitambar Gautam,渡辺悌二,西 弘嗣,安成哲三
1. Geology of the summit limestone of Mt. Qomolangma (Everest) and cooling history of the Yellow Band on the Qomolangama Detachment
Harutaka Sakai, Minoru Sawada, Yutaka Takigami, Yuji Orihashi, Tohru Danhara, Hideki Iwano, Yoshihiro Kuwahara, Qi Dong, Huawei Cai and Jianguo Li
エベレスト(チョモランマ)山頂の石灰岩の地質とチョモランマ・デタッチメント下のイエローバンドの冷却史
酒井治孝,澤田 実,瀧上 豊,折橋裕二,檀原 徹,岩野英樹,桑原義博,Qi Dong, Huawei Cai and Jianguo Li
エベレスト山頂のオルドビス紀のミクライト質層状石灰岩は,三葉虫,介形虫,ウミユリを含むペロイド質石灰岩礫を含む陸棚縁辺の堆積物である.一方,デタッチメント断層直下のイエローバンド石灰岩は変成しており,その87Rb/86Sr年代は40Ma頃にテチス堆積物が構造的に厚くなり,変成作用を被ったことを示す.白雲母の40Ar/39Ar年代は33.3Maと24.5Maの熱イベントを記録しており,前者はバロビアン型の,後者は変成帯の上昇に伴う減圧による高温型の変成作用に対応している.砕屑性ジルコンとアパタイトのFT年代は各々14.4±0.9Ma, 14.4±1.4Maであり,デタッチメントによりテチス堆積物の最下部が〜14.4Maに350℃から100℃まで急冷し,変成帯が地表に露出し始めたことを示唆する.
Key words : Mt.Everest, Qnomolangma detachment, Yellow Band, 40Ar/39Ar age,87Rb/86Sr isochron age, fission track age. (40・39・87・86は上付)
2. Tectonic and climatic control of the changes in the sedimentary record of the Karnali River section (Siwaliks of Western Nepal)
Pascale Huyghe, Jean-Louis Mugnier, A.P. Gajurel and B. Delcaillau
西ネパール・カルナリ川流域のシワリク層群に記録されたテクトニクスおよび気候変動
Karnali川流域に露出する5000m以上に及ぶシワリク層群において,堆積相,粘土鉱物,Nd同位体比に関する研究を行い,テクトニクスおよび気候変動に関する考察を行った.
本研究の堆積物中には,2つ時期に大きな変化がみられる.一つは 9.5Maで,ここでは蛇行河川から網状河川への変化がみられる.もう一つは6.5Maで,網状河川の水深が浅くなる変化である.前者の9.5Maの変化は,Nd同位体比が最低値から急速に増加する時期と一致している.この同位対比の変化は,Ramgarh スラストの活動により,13〜10MaにKarnali堆積盆の中にレッサーヒマラヤの岩石が露出され,それが浸食されたためにこの同位体比の変化が生じたと考えられる.このとき,隆起にともなうMain Boundary Thrustの前進が網状河川の発達も促した.一方 後者の6.5 Maには,粘土鉱物の変化が網状河川の堆積相の変化と同時に生じ,スメクタイト/カオリナイト比が高い方へシフトする.後背地の岩石に変化はみられないので,この粘土鉱物の変化は環境の変化によると考えてよい.一方,堆積相の解析からは,6.5Maにはモンスーン気候の強化による降水量の増加が推定され,河川系の変化と一致する.この河川システムの変化は,時代に違いがあるものの,Karnaliセクションでは,中央から西ネパールまで広く認識される. Karnali セクションに認められる2つのイベント,スメクタイト/カオリナイト比の増加とNd同位体比の減少は,同時期のベンガル扇状地の堆積物にも認められている.
Key words: Himalaya, Siwaliks of Nepal, Karnali section, Neogene, facies analysis, clay mineralogy, neodymium isotope, climate, tectonics.
3. Late Pleistocene pollen assemblages from the Thimi Formation, Kathmandu Valley, Nepal
Khumn Paudayal
ネパール・カトマンドウ盆地における後期更新世の花粉群集組成
カトマンドウ盆地を埋積する連続堆積物の上部を構成するテイミ層は,後期更新世における河川末端に堆積した細〜中粒砂,シルト,シルト質粘土,粘土の互層によって特徴づけられる.40試料に基づいた花粉化石層序から,裸子植物群が被子植物群や草本類より優勢であったことが明らかにされた. Pinus属とQuercus属に含まれる複数の種は,現在のネパールではそれぞれ分布高度が異なるため,本研究ではこれらのtaxaの識別を試みた. Pinus wallichiana, Pinus roxburghii, Abies spectabilis, Tsuga dumosa,Picea smithianaなどの裸子植物は,Quercus lanata, Q. lamellosa and Q. leucotrichophora and Q. semecarpifolia, Betula, Juglans, Myrica, Castanopsis, Symplocos などの木本性被子植物より優勢であった.テイミ層の花粉群の深度による組成変化は少なかった.僅かな木本性被子植物と優勢なイネ科をはじめとする草本類からなるテイミ層の花粉群は,後期更新世におけるカトマンドウ盆地が冷涼から温暖な気候であったことを示す.
Keywords: Kathmandu Basin, Thimi Formation, pollen record, paleoclimate, Late Pleistocene.
4. A latest Jurassic-earliest Cretaceous radiolarian fauna from the Xialu Chert in the Yarlung Zangbo Suture Zone, Southern Tibet: comparison with coeval western Pacific radiolarian faunas and paleoceanographic implications
Atsushi Matsuoka, Qun Yang, and Masahiko Takei
南チベットヤールンツァンポー縫合帯のシャルー・チャートから産出したジュラ紀末−白亜紀初期放散虫化石:西太平洋地域の同年代放散虫群集との比較と古海洋学的意義
松岡 篤・楊 群・武井雅彦
シャルー・チャートからのジュラ紀末ないし白亜紀初期(Pseudodictyomitra carpatica帯)の放散虫群集は,西南日本の鳥巣層群から得られた同年代の北半球中緯度(温帯)群集と多くの共通要素をもつ.一方,シャルー・チャートからの群集は,マリアナ海溝から得られた同年代の熱帯群集との共通性に乏しい.シャルー・チャートが南半球で堆積したことは明らかなので,シャルー・チャートからの放散虫群集は南半球の中緯度(温帯)群集を代表しているとみなされる.ジュラ紀末から白亜紀初期にかけて,テチス海と太平洋には,赤道を挟んで鏡像関係にある中緯度放散虫群集の分布が復元される.
Key words : Xialu chert, latest Jurassic, earliest Cretaceous, radiolaria, paleoceanography
5. Glacial geomorphology and Ice Ages in Tibet and surrounding mountains
Matthias Kuhle
チベットと周辺山岳における氷河地形学と氷河時代
1973 年から,アジアの高地での氷河作用の最大範囲を示す新しいデータを得た.最終氷期にチベットを覆った氷床に関するデータは北半球の氷河作用を根本から考え直させる.氷床が中緯度に,巨大なサイズで(240万 平方キロメートル),そして,標高の高いところ(海抜6000m)に存在していたということは,アルベドの変化に伴う,地球大気の大きな(substantial)寒冷化を引き起こし,また,夏のアジアモンスーン循環をとめるとされている.ヒマラヤの南側面では,モレーンが海抜460mまで達し,祁連山地域のある,チベット高原の北斜面では海抜2300mまで達していることが発見された.カラコルム, Aghil,クンルン山脈の北斜面では,モレーンは海抜1900m下にまでみられる.チベットの南での,erratics(迷子石)のX線撮影解析によると,かつての氷の厚さは少なくとも1200mであることが分かった.また,ヒマラヤやカラコルムの氷河による研磨や羊背岩は,かつての氷河の厚さが 1200−2700mあったことを示唆している.この証拠を基にすると,1100−1600m低い平衡線(ELA)が再現され,チベット全体のほとんどを覆う,240万平方キロメートルの氷床が存在していたことになる.さらに,様々な方法によって得られた放射性年代は,この氷河作用を同位体ステージ3−2 の時代(W_rmian=最終氷河期,約c.6000-c.18000年前)に区分している.
Key words: glacial geomorphology, Ice Ages, Tibetan ice sheet, former glaciation of central Asia, Quaternary climate
6. Holocene calcrete crust deposits on the moraine of Batura glacier, northern Pakistan
Tetsuya Waragai
パキスタン北部,バツーラ氷河の堆石堤に見られる完新世カルクリートクラストの形成過程
藁谷 哲也
パキスタン北部,バツーラ氷河の堆石堤に見られるカルクリートクラストについて鉱物・化学組成,氷河氷や氷河周辺の地表水の化学組成,AMSによる14C 年代をもとに形成過程が分析された.その結果,クラストは約0.2mm以下の鉱物片からなる層と,主にCaOを約60%含む微細なカルサイト層が級化し,ラミナをつくっていた.氷河氷や融氷水は,周辺の炭酸塩岩の溶解に起因して多量のCa2+とHCO3-を含むため,カルクリートは氷河と堆石堤の間につくられた一時的な水流又は池の水分が蒸発する過程で発達したと推察される.クラストの14C年代から,カルクリートはバツーラ氷期後期の約8,200cal BPに形成を完了した.
Key words : calcrete, calcite, glacial stage, AMS14C age, Karakoram Mountains (注14はCに上付)
7. Sensitivity of the Central Asian climate to uplift of the Tibetan Plateau in the coupled climate model (MRI-CGCM1)
Manabu Abe, Tetsuzo Yasunari , Akio Kitoh
気象研究所大気海洋結合気候モデルにおけるチベット高原の上昇に対する中央アジアの気候の感度
阿部 学,安成 哲三,鬼頭 昭雄
中央アジアの乾燥化はチベット高原の上昇が要因とされているが,まだ不明な点も多い.本研究では,チベット高原の高さと中央アジアの乾燥化の関係を,気象研究所大気海洋結合気候モデル(MRI−CGCM1)を用いて調べた.中央アジアの春季から夏季の降水量の減少と蒸発量の増加,また,潜熱及び顕熱フラックスの高原の高さによる違いが,高原の高さが現在の40%と60%の間で顕著に現れた.今回の数値実験によって,中央アジアの顕著な乾燥化は高原が現在のだいたい半分を超えたときに現れることが示唆された.
Key Words : general circulation model(GCM), Central Asia, arid climate, Tibetan Plateau uplift.
8. The historical Saklei Shuyinj and Chateboi glacier dams as triggers for lake outburst cascades in the Karambar valley (Hindukush)
Lasafam Iturrizaga
ヒンドゥークシュ山脈,カランバール谷における氷河湖決壊連鎖の発生トリガーとしての過去の氷河せき止め
カランバール谷では,19世紀中頃から,破壊的な氷河湖決壊が生じてきた.しかしこれまでのところ,これらの決壊の正確な発生源は不明であった.地形学的な野外調査と住民インタビューを行った結果,水平距離40kmの区間に9つの氷河でせき止めがあった可能性を復元できた.その中でも特に,最大の可能性を持っているチャテボイ氷河とサクレイ・シュイジ氷河の2つに焦点をあてて検討した.湖底堆積物,湖岸段丘,氷性堆積物の観察から,これら2つの氷河が連結した湖を形成したと考えられ,一連の決壊を生じさせた.カランバール谷では,現在でもチャテボイ氷河が谷をせき止めることがあり,下流域の村に恒久的な災害をもたらす原因となっている.
Key words: ice-dammed lakes, outburst floods, outburst cascades, backwater ponding, Hindukush-Karakoram.
9. Slow mass movement in the Kangchenjunga area, eastern Nepal Himalaya
Dhananjay Regmi and Teiji Watanabe
ネパール・ヒマラヤ,カンチェンジュンガ地域のマスムーブメント
Dhananjay Regmi, 渡辺悌二
ネパール最東部のカンチェンジュンガ・ヒマールにおいて,ソリフラクション・ローブの動きを観測した.5,412-14m(傾斜31度)の斜面において,グラスファイバーチューブによって測定した地表面付近の平均移動速度は11mm/年で,5,322-25 m (22度)の赦免状での値の3倍近くに達した.両斜面でマスムーブメントが生じる深さには大きな差はなかった.ストレイン・プローブによる観測の結果,モンスーン初期に物質移動が始まったことがわかったが,降水量・土壌水分が共に少ないことから,マスムーベメント量が小さいと推察された.
Key words: ground temperature, Nepal Himalaya, soil displacement, soil moisture solifluction, strain probe.
10. Debris flow disaster at Larcha, upper Bhotekoshi Valley, central Nepal
Danda Pani Adhikari and Satoshi Koshimizu
中央ネパールのボテコシ渓谷上部に位置するラーチャ地域の土石流災害
Danda Pani Adhikari,輿水達司
ヒマラヤでは特に夏のモンスーン時期に,地滑りや土石流に関係する破損,破壊,負傷者等が頻繁に認められる.この論文では,中央ネパールのボテコシ渓谷上部を走るアルニコハイウエーから109kmに位置するラーチャ地域で,1996年7月に起きた悲惨な状況を報告する.ラーチャ地域の22戸のうち16戸が流され,2戸が一部破損で,54人が瞬く間に亡くなった.この現象につきメディアは,原因を氷河湖からの流出水による土石流によるものと注目した.しかし,地質学,地形学および土木地質学からの検討により,氷河湖の流出水によるのではなく,モンスーンによって渓谷の狭い谷に堰き止められた水が限界を越え,地滑りを誘発した土石流が原因と結論した.
Key words : Debris flow, Larcha, upper Bhotekoshi Valley, Arniko Highway, monsoon, glacial lake outburst flood, colluvium, Lesser Himalaya, Higher Himalaya.
11. Integration of magnetism and heavy metal chemistry of soils to quantify the environmental pollution in Kathmandu, Nepal
Pitambar Gautam, Ulrich Blaha and Erwin Appel
土壌の磁気性質と重金属濃度の統合によるネパール,カトマンドゥー市における環境汚染度の定量化
カトマンドゥー市街の土壌の磁気帯磁率(c)と飽和等温残留磁化(SIRM)には有意な変化が認められ,これらの変化に基づく環境汚染の評価が可能である. cの強度によって土壌の深度区分を通常(normal, < 10-7 m3 kg-1),中間的強化(moderately enhanced, 10-7 to <10-6 m3 kg-1)および強化(highly enhanced, ウ10-6 m3 kg-1)に分けることができる.道路および工業区域から離れた地点の土壌は一般に通常である.道路に近いところの土壌では,cは深度数cmで最大を示し,20cmの深さまでは高い値である.それより深くでは深さとともにcは減少し,moderateをへて,深さ~30−40 cmでは通常normalになる.公園では,上層部の土壌のcは中間moderately enhancedである.土壌のSIRMはmedian acquisition fields (B1/2) によって三つの成分に分けられる.それらはソフト (B1/2 = 30−50 mT: 磁鉄鉱様化合物),ミデイアム(B1/2 = 120−180 mT: おそらくマグヘマイあるいはsoft coercivityの赤鉄鉱)およびハード (B1/2 = 550−600 mT: 赤鉄鉱)である. 地表近くでのSIRMはソフトが卓越しており,都市環境汚染は磁鉄鉱様化合物の富化によることを示している.
いくつかの土壌断面での重金属AAS分析によると,Cu, PbおよびZnでは濃度変化が大きく,濃度変化比(最大含量/最小含量の比)はそれぞれ 16.3, 14.8および9.3である.ラニポカリでは,いくつかの金属の含量はcとよく相関し,両者の対数値は直線関係にある.しかし,ラトナパークでは,cと SIRMはともにCu, Pb およびZnと明瞭な正の相関関係を示すが,Fe (Mn), Cr, Ni および Co との相関関係は弱いかあるいは負の関係さえ示す.このような違いは地質起源・土壌起源・生物起源および人為起源の要因の変化に由来し,それらの変化は時間的にも空間的にも変わる.しかし,環境汚染(基本的には交通による)を受けた土壌断面では,cはいくつかの市街元素(Cu, Pb, Zn)の濃度に基づく汚染指数と明確な直線関係を示す.したがって,cは市街地汚染度の定量化に有効なパラメータとして使える.
Keywords: heavy metals, environmental pollution, Kathmandu, magnetic susceptibility, soil magnetism, isothermal remanence.
特集号 その2
Evolution of Ophiolites in Convergent and Divergent Plate Boundaries: Introduction
Yildirim Dilek,小川 勇二郎,Valerio Bortolotti,Piera Spadea
1. Tethyan ophiolites and Pangea breakup
Valerio Bortolotti and Gianfranco Principi
テチス海のオフィオライトとパンゲア大陸の分裂
パンゲア大陸の分裂は,ペルム紀-三畳紀の大陸リフト群の発生に引き続いて,三畳紀にのちのアフリカとヨーロッパ,アフリカと北アメリカ,南北アメリカの間の大陸縁に沿って始まった.
中-後期三畳紀にパンゲアの東部赤道部を切って,古テチス海の分岐ないし新しい海洋(東テチス海)として一つの海洋盆が開き,大陸リフト盆地が西方へと発達していった.西テチス海と中央大西洋が開き始めたのは中期ジュラ紀になってからであった.
周地中海と周カリブ海地域の海洋性残存物(中生代オフィオライト)と大西洋の地殻から得られたデータから,パンゲア大陸の分裂の時期についてのモデルを作ることができた.
東テチス海では,中-後期三畳紀MORBオフィオライト,中-上部ジュラ系MORB・IATからなるsupra沈み込みオフィオライト,および中-上部ジュラ系の下部変成岩が分布しており,三畳紀から中期ジュラ紀にかけて海洋拡大が活発だったことを示唆する.まだ拡大が活動的だった中期ジュラ紀には早くも圧縮の時期になり,ジュラ紀ミ白亜紀境界頃に海洋が閉じ,引き続いて造山帯が生成した.現在見られる散在するオフィオライト群は造山運動の結果であり,後からの構造運動による乱れを取り除くと東テチス海のオフィオライト群は一つの直線をなす.
西テチス海では,中-上部ジュラ系MORBオフィオライト群のみが存在するが,その当時はまだ海洋拡大の時期であった.海洋の消滅は後期白亜紀に始まり始新世に完了した.西テチス海と中央大西洋を結ぶ地域に沿っては,パンゲア大陸の分裂は左横ずれねじり構造運動により生じた.
西テチス海とカリブテチス海を結ぶ中央大西洋では,海洋拡大は同時に生じ,現在もなお続いている.カリブテチス海はおそらく後期ジュラ紀ミ前期白亜紀に開いた.データから浮かぶ全体像は,パンゲア大陸の分裂が東から西へ向け,中-後期三畳紀から後期ジュラ紀-前期白亜紀へと若くなっていることを示唆する.
Key words: Paleozoic Pangea breakup, ophiolites, Eastern Tethys, Western Tethys, Caribbean Tethys, Triassic, Jurassic
2. Mesozoic to Tertiary tectonic history of the Mirdita ophiolites, northern Albania
Valerio Bortolotti, Michele Marroni, Luca Pandolfi and Gianfranco Principi
北アルバニア,ミルディタ オフィオライトの中生代から第三紀の構造発達史
本論文では,地質学的・構造地質学的データに基づき北アルバニアのミルディタ オフィオライトナップの構造発達史を提唱する.ミルディタオフィオライトナップは,東西2つのオフィオライトユニットに構造的に覆われるオフィオライト下のメランジであるルビクコンプレックスを含む.ミルディタオフィオライトナップの歴史は前期三畳紀にリフティング期に始まり,中期-後期三畳紀にアドリア海とユーラシアの大陸縁の間で海洋拡大が続いた.その後,前期ジュラ紀に海洋盆は沈み込み帯の発達を伴う収束運動の影響を受けた.ミルディタオフィオライトナップの東西両ユニットにSSZに関係するマグマ層序が見られることから,この沈み込み帯が存在したことがいえる.中期ジュラ紀の連続的な収束は,海洋間期と縁辺期の2つの時期の海洋リソスフェアのオブダクションをもたらした.海洋間期は,下部変成岩の発達をもたらす若くまだ熱い海洋リソスフェアの西への衝上運動により特徴づけられる.後期ジュラ紀にオフィオライトナップの大陸縁の上への定置により縁辺期が生じた.この第2期の間にオフィオライトの定置がルビクコンプレックスの発達をもたらした.前期白亜紀にオフィオライトの最後の定置があり,続いてバレミアン期-サントニアン期のプラットフォーム炭酸塩が不整合に覆って堆積した.後期白亜紀から中期中新世に,変形フロントのアドリアプレートの方向への漸進的な移動の間にミルディタオフィオライトナップは西方へ移動した.中期-後期中新世には,展張テクトニクスによりナップ全体が薄化した一方,アドリアプレートの西端地域では依然として圧縮が活発であった.概して,中新世の変形が今日観察されるミルディタ オフィオライトの上昇と露出をもたらした.
Key words: ophiolites, obduction, tectonic, Mesozoic, Tertiary, Mirdita, Northern Albania
3. Petrogenesis and tectono-magmatic significance of volcanic and subvolcanic rocks in the Albanide-Hellenide ophiolitic melanges
Emilio Saccani and Adonis Photiades
アルバニデ-ヘレニデ オフィオライトメランジの火山岩及び火山深部岩の岩石成因論と構造-火成作用的意義
ミルディタ-サブペラゴニア帯(アルバニデ-ヘレニデ造山帯)には,オフィオライト層序に伴われるオフィオライトメランジが広く分布しており,それらは構造-堆積性の「ブロック インマトリックス型」のメランジからなる.この論文では,主メランジユニットに貫入している火山岩及び火山深部岩である玄武岩質岩について,化学組成と岩石成因論とともに生成の本来の構造場を解明する目的で研究した.
これらのメランジに取り込まれた玄武岩質岩は,(1)三畳紀の中間-アルカリ型プレート内玄武岩(WPBs),(2)三畳紀の通常型(N-MORB)及び富化型(E-MORB)海嶺玄武岩,(3)ジュラ紀N-MORB,(4)MORBと島弧ソレアイトの中間的な地球化学的特徴をもつジュラ紀玄武岩(MORB/IAT),(5)ジュラ紀ボニン岩類,を含む.これらの岩石は相異なる火成活動を記録しており,それらはテチス海のミルディタ-サブペラゴニア地域における構造運動の原動力と時代によるマントル進化に関係している.
主に堆積過程により生じたメランジユニットはSSZ環境に由来する物質が卓越することで特徴づけられ,他方で構造性の過程が優勢だったメランジユニットでは海洋性物質が卓越する.対照的に,構造的に似たメランジユニット間では組成上の差異は見られない.この事実は,それらのメランジユニットがヘレニデからアルバニデに至る単一のメランジ帯とみなされ,その生成は相異なる物質を取込むメカニズムにより支配されていたことを示唆する.
MOR・SSZ型アルバニデ-ヘレニデオフィオライトの表層の玄武岩類の大部分はメランジに取り込まれている.しかし島弧ソレアイト類の玄武岩は,それらが量的には最も多いオフィオライト岩型であるにもかかわらず,これまでのところメランジ中には見つかっていない.このことから,海洋内弧の主部を構成する岩石はメランジの生成に関与しなかったと思われる.他方,おそらく前弧域で生成したであろう岩石は堆積性メランジ中に多く見られる.しかも,多くのメランジに含まれる三畳紀のE-MORB・N -MORB・WPBsは現在のオフィオライト層序には見られない.だがそれでも,玄武岩類は中期三畳紀以後にアルバニデ-ヘレニデ帯全体が一つの海洋盆であった証拠となっている.
Key words: petrogenesis, basalts, ophiolitic melange, Albanides, Hellenides
4. Hydrothermal Alteration and Tectonic Evoluution of an Intermediate- to Fast Spread Backarc Oceanic Crust : Late Ordovician Solund-Stavfjord ophiolite,Western Norway
Hege Fonneland, Harald Furnes, Karlis Muehlenbachs and Yildirim Dilek
中速〜高速拡大した背弧海洋地殻の熱水変質と構造発達過程:ノルウェー西部,オルドビス紀後期のソルンド−スタブフィヨルド・オフィオライト
ノルウェー西部のソルンド−スタブフィヨルド・オフィオライト複合岩体(SSOC)はオルドビス紀後期の海洋リソスフェアの残骸であり,カレドニアの背弧海盆における中速〜高速拡大によって形成された.その地殻部分の内部構造や火成岩の特徴は,SSOCが沈み込み帯上における複雑な多段階の海洋底拡大の歴史をもつことを示唆する.リフト系の延伸テクトニクスに伴う最も若い地殻部分は,よく揃ったオフィオライト層序を持ち,玄武岩質火山岩類,層状岩脈群から噴出岩層への漸移帯,層状岩脈群,及び上部塊状斑れい岩を含む.主要元素および微量元素の分布における幅広い変化は,火成作用から予想される範囲をはるかに超えた地殻岩石の熱水変質による元素の大規模な再移動を示す.噴出岩層中の火山岩類ではK2Oが著しく富化しているが,岩脈群と噴出岩層の漸移帯の近くまたは漸移帯中では銅と亜鉛が最も濃集している.全岩δ18O値はオフィオライト層序の下位に向かって減少傾向を示し,その変化は火山岩中で最大で岩脈群中で最小である.緑れん石・石英組合せのδ18O値は火山岩中で260-290℃,漸移帯中で420℃,岩脈群中で280-345℃,そして斑れい岩中で 290-475℃の温度を示す.87Sr/86Sr同位体比は火山岩中で最も変化幅が広くて値も高く(0.70316-0.70495),一般に岩脈群中で最も変化幅が小さく値も小さい(0.70338-0.70377).計算された水/岩石比の最小値は火山岩類と斑れい岩中で最も変化が大きく(0- 14),岩脈群中で最も変化幅と値が小さい(1-3).緑れん石のδD値(-1〜-12‰)は計算されるオルドビス紀の海水のδ18Oとともに現在の海水の値と同様である.火山岩類は低温および高温の水循環を両方経験しており,その結果K2Oの富化とδ18O値の大きなばらつきを生じた.マグマ溜り上の高温反応帯における金属元素の溶脱の結果として,斑れい岩の亜鉛が著しく枯渇しているが,そこから放出された熱水の湧昇と沈殿によって,岩脈群中では亜鉛が富化している.この研究によって,SSOC地殻の上部には,広域的な緑色片岩相低温部の変成作用の影響にもかかわらず,海洋底の熱水活動がほぼそのままの状態で保存されていることが示された.
Key words : Norwegian Caledonides, ophiolite, volcanism, tectonic activity, hydrothermal alteration, O- and Sr-isotopes.
5. Chromite in the mantle section of the Oman Ophiolite : a new genetic model
Hugh Rollinson
オマーン・オフィオライトのマントル部分のクロム鉄鉱:新しい成因モデル
この論文ではオマーン・オフィオライトのマントル部分のクロム鉄鉱類についてその組成データ(主要元素,白金族元素(PGE)濃度,オスミウム(Os)および酸素同位体)を総括する.オマーン・オフィオライトのクロミタイト中のクロム鉄鉱類はCr#の高い無人岩的なものからCr#の低い海嶺玄武岩 (MORB)的なものまで一連の組成変化傾向を示す.Cr#の高いものはTiに乏しく,分化したPGEパターンを示し,イリジウム類(IPGE)に富む. Cr#の低いものはTiに富み,未分化なPGEパターンを示す.このようなクロミタイトの組成変化は,かなり組成の異なるメルトからの結晶作用を反映している.このメルト組成の幅広い変化が生じた原因として,メルト−岩石反応,即ち玄武岩質メルトがハルツバージャイト・マントルと反応し次第にCrに富むメルトを形成していったためであるという考えを提案する.こう考えれば,従来のモデルと対照的に,異なるクロム鉄鉱のタイプを説明するために構造環境の変化を想定する必要がなくなる.
Key words : chromitite, PGE, melt-mantle interaction, tectonic setting
6. Magma generation and crustal accretion as evidenced by supra-subduction ophiolites of the Albanide-Hellenide Subpelagonian zone
Luigi Beccaluva, Massimo Coltorti, Emilio Saccani and Franca Siene
アルバニア・ギリシャ造山帯サブペラゴニア帯の沈み込み帯域オフィオライトの証拠に基づくマグマ形成と地殻の付加作用
ミルディータ・サブペラゴニア帯のオフィオライトはアルバニア・ギリシャ造山帯にほぼ連続して配列し,ミルディータ区域の西部では海嶺玄武岩(MORB) 組合せ,東部(即ちミルディータ東部およびピンドスとヴリノス)では多量の島弧ソレアイト(IAT)と若干の無人岩を伴う沈み込み帯域(SSZ)組合せを含む.加えて,MORBとIATの中間的な地球化学的特徴を示す玄武岩がミルディータ区域の中部とアストロポタモス地域(ピンドス)で発見された.これらの玄武岩は典型的なMORBと互層し,無人岩質岩脈に貫かれる.
これら様々なオフィオライト岩体の苦鉄質親マグマの相異なる組成的特徴は,それらの給源マントルが部分溶融とメルト抽出により次第に枯渇化したことによって説明できる.レールゾライト質給源マントルの部分溶融(10〜20%)は典型的なMORBマグマと単斜輝石に乏しいレールゾライト質の溶け残りかんらん岩を生産した.この溶け残りかんらん岩が沈み込み帯域において,水の存在する条件で10%部分溶融することによってMORB/IATの中間組成の玄武岩が形成されたが,IAT玄武岩と無人岩は,様々な程度に沈み込み帯起源の流体による富化を受けた同じ給源マントルから,それぞれ10〜20%と30%の部分溶融によって形成された.さらに,無人岩はより枯渇した給源ハルツバージャイトから水が関与した低い程度の部分溶融によって形成されたのであろう.
全岩と鉱物の化学組成の間のマスバランス計算に基づく一般化された岩石学的モデルは,大部分の貫入岩類(超苦鉄質沈積岩から斑れいノーライトと斜長石花崗岩まで)も層状岩脈群および火山岩類(玄武岩から流紋デイサイトまで)も,SSZオフィオライトの地殻部分全体の成因は,現在の太平洋の海洋性島弧に見られるIATピクライトとよく似た組成のTiに乏しいピクライト質の親マグマが浅い場所で結晶分化したことによって説明できる.
テーチス海域のSSZオフィオライトの形成について,最も妥当な構造論的・火成論的モデルを概述すると,海洋プレート間の沈み込み帯の低速収束運動によるIAT組成の初期島弧の形成.その後のスラブの後退,マントル・ダイアピル上昇,そして島弧軸から前弧域までの伸張運動によるMORB/IAT中間組成玄武岩や無人岩マグマの形成,となる.
Key words: magma generation, supra-subduction zone, Tethyan ophiolites, Albanides, Hellenides.
7. Origin of layering in cumulate gabbros in the Oman ophiolite: insights from magnetic susceptibility measurements in the Wadi Sadm area
Kiichiro Kawamura ,Hosono Takahiro, Huda Mohamed Allawati, Yujiro Ogawa and Hidetsugu Taniguchi
.オマーンオフィオライトの層状斑糲岩の層構造の起源:ワジサダム地域の帯磁率測定からの洞察
川村喜一郎・細野高啓・Huda Mohamed Allawati・小川勇二郎・谷口英嗣
オマーンオフィオライト,サダム地域の層状斑糲岩の800 cmの連続セクションで帯磁率と帯磁率異方性を測定した.そのセクションでは,3ユニットが認められ,帯磁率は,優黒色層から優白色層へ上位に減少する傾向であった.帯磁率の減少は,主としてオリビンの変質による磁鉄鉱の減少を表している.この傾向は,層状斑糲岩のオリビンのサイクリックな沈積を示唆している.また,層状斑糲岩の磁化ファブリックと粒子ファブリックから,単純剪断が類推される.以上から,斑糲岩の層構造は,初期的に沈積,後生的に単純剪断を被ったと考えられる.
Key words: Cumulate gabbro, Magnetic susceptibility, AMS, Grain fabric, Simple shear
8. Transpressional tectonics of the Mineoka belt in a TTT-type triple junction, Boso Peninsula (Japan)
Ryota Mori. and Yujiro Ogawa
房総半島沖海溝−海溝−海溝型三重点に関連する嶺岡帯のトランスプレッショナルテクトニクス
森 良太,小川勇二郎
嶺岡オフィオライトのエンプレイス時における変成・変形条件に関連する搬入プロセスを理解するため,嶺岡帯に産出する変成岩・深成岩塊(ノッカー)の構造解析を行った.その結果,二つの変形ステージが見られ,より深部(延性〜脆性下)での岩塊内に発達する後退変成作用を伴う褶曲や断層による変形と,より浅部(脆性下,沸石相)での周辺の岩石(蛇紋岩)との境界で発達する断層に分けられることが確認された.これら二つのステージともトランスプレッショナルな条件で起こり,また後期のものは現在の嶺岡帯のテクトニクスと一致する.それは嶺岡帯のテクトニクスが新第三紀付加体形成以降のフォアアークスリヴァー断層帯として位置づけられることを意味する.
Key words: knocker, Mineoka Ophiolite, transpression, mylonitization, brecciation, forearc sliver.
9. Tectonic accretion of a subducted intraoceanic remnant arc in Cretaceous Hokkaido, Japan, and implication for evolution of the Pacific NW
Hayato Ueda. and Sumio Miyashita.
白亜紀北海道に沈み込んだ残存島弧の付加と,北西太平洋の発達に対する意義
植田勇人,宮下純夫
北海道イドンナップ帯の白亜紀付加体から,九州−パラオ海嶺のような海洋性残存島弧起源の付加コンプレックスが見出された.当コンプレックス中には,島弧起源の緑色岩を火山岩礫岩,次いでチャートが覆う原層序が残されており,背弧拡大により遠洋域で活動を停止した残存島弧の履歴を示すと解釈される.残存島弧の沈み込みを契機に沈みこむ海洋地殻の年齢が不連続に変化するため,白亜紀北海道に見られるように,付加様式や沈み込み変成作用の急激な変化がおこる.また,残存島弧起源付加体の存在は,白亜紀北海道に沈み込んだ海洋プレートが,現世フィリピン海のように海洋性島弧や背弧海盆を擁していたことを示唆する.
Key words: accretionary complex, subduction zone tectonics, intraoceanic remnant arc, circum-Pacific ophiolite, Idonnappu Zone, Hokkaido.
10. Tectonic rotation during the Chile ridge collision and obduction of the Taitao ophiolite (Southern Chile)
Eugenio Andres Veloso Espinosa, Ryo Anma and Toshitsugu Yamazaki
チリ海嶺の衝突とオブダクション中に生じたタイタオ・オフィオライト(チリ南部)のテクトニックな回転
Eugenio Andres Veloso Espinosa,安間 了,山崎俊嗣
チリ沖三重点近傍のタイタオ・オフィオライト(<6 Ma)の定置過程を古地磁気学的手法を用いて解明した.直線的な消磁曲線を持つ火山岩類とシート状岩脈の安定残留磁化方位は,比較的小さな反時計回りの回転を生じたことを示す.下位の複雑に褶曲された斑糲岩・超塩基性岩類は,時計回り回転を示唆する高保磁力成分と,大きな反時計回り回転を示唆する低保磁力成分が得られた.前者は海嶺衝突時の,後者はオブダクション中の変形を記録しているのだろう.復元された斑糲岩とシート状岩脈の構造は,オフィオライトがセグメント境界に近いチリ海嶺で生成したことを示す.定置中の深成岩類の回転によって生じた隙間に向かって火山岩類は噴出した.
Key words: Taitao ophiolite, obduction, paleomagnetism, block rotation, Chile Ridge.
11. Hahajima Seamount: an enigmatic tectonic block at the junction between Izu-Bonin and Mariana Trench
Kantaro Fujioka, Wataru Tokunaga, Hisayoshi Yokose, Jyunzo Kasahara, Toshinori Saito, Ryo Miura and Teruaki Ishii
母島海山:伊豆・小笠原海溝とマリアナ海溝の会合点にある不可思議なテクトニックブロック
藤岡換太郎,徳長 航,横瀬久芳,笠原順三,佐藤利典,三浦 亮・石井輝秋
伊豆・小笠原海溝とマリアナ海溝の会合点にある母島海山は長方形をした特徴的な海山である.この海山からは蛇紋岩や簿にないと等の岩石からなる.白鳳丸による地形調査やドレッジ,「しんかい2000」による潜航観察を行った.その結果この海山がもとは現在の母島の南にあったブロックでこれがパラセベラ海盆を拡大させたトランスフォーム断層によって東に移動し,その後太平洋プレートの上にあったトランスフォーム断層がその下へ沈み込むことによってできたテクトニックブロックであると考えた.
Key words: Hahajima Seamount, Izu-Bonin Arc, serpentine seamount, Parece Vela Basin, transform fault
一般論文
1. Sedimentary and biotic evidence of a warm-water enclave in the cooler oceans of the Latest Ordovician glacial phase, Yangtze Platform, South China Block
Yue Li, Ryo Matsumoto and Steve Kershaw
南シナ地塊,揚子台地のオルドビス紀氷河期末期の冷水海洋に存在した暖水塊の堆積学的・生物学的証拠
Yue Li、 松本 良、Steve Kershaw
Hirnantian 期に揚子台地は南シナ地塊の西部に位置しており,これはゴンドワナ大陸北東岸の南半球の中〜低緯度地域に相当する.この地域はHirnantia動物群で代表されるようなKosov動物群区の一部をなし,堆積学的データによると,沿岸斜面や陸棚からの冷水性海流による影響が卓越していた.また, Ashgill期の筆石類を含む黒色頁岩(Wufeng層)の堆積後,海退によってHirnantian期に浅海性炭酸塩(Kuanyinchiao層)がその上に堆積した.本研究では,揚子台地において潮間〜沿岸の堆積相でHirnantia動物群の典型的な化石を欠く地層が局所的に数カ所産出することを見出した.いくつかの暖水性の特徴(放射状海緑石,ペロイド,異なる単体サンゴや様々な底生貝類の存在)が浅海地域に断片的にみられ,これら地域ではグレーンストーンやパックストーンが形成された.上記のような暖水的特徴をもった地層は,Hirnantian氷期の間氷期において形成された可能性もあるが,これら浅海層の産出が揚子台地内部に限られていることから,南東の高緯度地域からもたらされた冷水性海流が揚子台地の沿岸で局部的に遮られたと考えられる.Hirnantian期に南シナ地塊東部に相当する大陸がゴンドワナの高緯度地域からの冷水性海流の流入を妨げ,揚子台地のいくつかの地域では暖水性の浅海堆積物が堆積したと考えられる.
Key words : Latest Ordovician, carbonate litho/biotic facies, palaeogeography, shallow marine belt of the Yangtze Platform, South China Block
2. Characterization of the Mefjell plutonic complex from the Sor Rondane Mountains, East Antractica : implications for petrogenesis of Pan-African plutonic rocks of East Gondwanaland
Zilong Li,Yoshiaki Tainosho, Jun-ichi Kimura and Kazuyuki Shiraishi
東南極セールロンダーネ山地Mefjell深成複合岩体の特徴:東ゴンドワナ大陸における汎アフリカ造山運動期の深成岩類の起源.
Zilong Li、田結庄良昭,木村純一,白石和行
500-550 Maの汎アフリカ造山運動期に活動した深成岩類によって構成されるMefjell深成複合岩体は,東南極セールロンダーネ山地の先カンブリア代の基盤岩に貫入しており,セールロンダーネ縫合帯の一部を形成している.この岩体の岩相は閃長岩質岩や花崗岩質岩(主にモンゾ花崗岩質岩)であり,鉄に富む含水苦鉄質鉱物や初生的なチタン鉄鉱の存在から高温および酸素分圧の低い環境での結晶化が考えられる.閃長岩質岩はメタアルミナスで,アルカリ元素, K2O/Na2O比,Al2O3, FeOt/(FeOt+MgO) 比 (0.88-0.98),K/Rb比 (800-1000),Ga (18-28 ppm),Zr (~2100 ppm),Baに富む.またこれらはMg# [Mg/(Mg+Fe2+)],Rb,Sr,Nb,Y,Fに乏しく,LREE/HREE比は低〜中度でREEパターンはEuの正の異常を示す.一方,花崗岩質岩はメタアルミナスからパーアルミナスでRbに富み,高いSr/Ba比,LREE/HREE比,低いK/Rb比,そしてEuの負の異常によって特徴づけられる.閃長岩質岩と花崗岩質岩のほとんどはY/Nb>1.2であり,初生マントルで規格化したスパイダー図でNb,Ti,Srに枯渇していることから,沈み込みが関与した地殻物質が起源と考えられる.したがってこれら閃長岩質岩と花崗岩質岩は,マントル起源の玄武岩の貫入による熱によって鉄に富む下部地殻物質が脱水溶融を起こし,得られたマグマの分別結晶作用によって形成されたと考えられる.Mefjell深成複合岩体の高いZr含有量と地球化学的判別図によるテクトニクスの推定から,閃長岩質岩と花崗岩質岩はともに通常のAタイプ花崗岩であり,造山運動後に同一のテクトニクスによって形成されたと考えられる.Mefjellの閃長岩質岩は地球化学的に東南極のGjelsvikjellaおよびM殄lig-Hofmannfjella西部地域のチャーノッカイトと類似しており,花崗岩質岩は南インドのアルミナスなAタイプ花崗岩に対比できる.これら岩体の形成は,ゴンドワナ超大陸形成時の造山運動に関連している.
Key words:syenitic rocks, granitic rocks, geochemistry, petrogenesis, East Antarctica, Gondwanaland
3. Basalt and tonalite from the Amami Plateau, Northern West Philippine Basin: New Early Cretaceous ages and geochemical results, and their petrologic and tectonic implications
Rosemary Hickey-Vargas
西フィリピン海盆北部,奄美海台の玄武岩とトーナル岩:白亜紀前期の年代値と地球化学的データからみた岩石学意義とテクトニクス
西フィリピン海盆北部の奄美海台からドレッジにより得られた玄武岩とトーナル岩の地球化学データ(低い87Sr/86Sr比 [0.70297-0.70310],中度の143Nd/144Nd比 [0.51288-0.51292],ややLREEに富み[La/Yb=4.1-6.6], La/Nb比は高い [1.4-4.3])によると,これらは海洋性島弧内部で形成された岩石の特徴を示す.トーナル岩中の普通角閃石の加熱により,115.8+0.5 Maのプラトー年代と117.0+1.1 Maの40Ar/39Arアイソクロン年代が得られた.一方斜長石はArが逸脱したパターンを示し,年代値は70-112 Maと幅広い.この結果は過去に報告されたK/Ar年代よりも古く,奄美海台が白亜紀前期の沈み込みに由来する火成作用によって形成されたことを意味する.これはジュラ紀〜暁新世の複合的島弧地塊(これらは現在西フィリピン海盆北部に分散され,フィリピン諸島やハルマヘラを構成している)の拡大によって西フィリピン海盆が形成されたというテクトニックモデルを支持する.
奄美海台のトーナル岩と玄武岩は,より若い年代を示す北部の九州パラオ海嶺や丹沢複合岩体のトーナル岩のような,フィリピン海プレート下への太平洋プレートの沈み込みによって形成された岩石に比べて高いSr/Y比と低いY含有量および87Sr/86Sr比を示す.玄武岩の地球化学的データによると,奄美海台を形成した白亜紀前期の沈み込み帯はスラブ溶融が卓越しており,当時は若くて熱いプレートが沈み込んでいたと考えられる.一方,奄美海台のトーナル岩の成因はスラブ溶融ではなく,玄武岩質マグマの結晶分化作用または玄武岩質島弧地殻の部分溶融による可能性が高い.
Key Words : geochemistry, basalt, tonalite, Amami Plateau, Northern West Philippine Basin)
4. Correlation of Hakkoda-Kokumoto Tephra, a widespread Middle Pleistocene
tephra erupted from Hakkoda caldera, northeast Japan
Takehiko Suzuki Dennis Eden, Toru Danhara and Osamu Fujiwara
八甲田カルデラから噴出した中期更新世広域テフラ,八甲田国本テフラの対比
鈴木毅彦、Dennis Eden、檀原 徹、藤原 治
東北日本,本州弧北端の八甲田カルデラから噴出し,本州の大半を覆った中期更新世初頭の広域テフラ,八甲田国本テフラ(Hkd-Ku)を認定し,広域にわたり対比した.給源近傍の模式地ではプリニアン降下軽石とそれを覆う火砕流堆積物からなる.遠隔地のHkd-Kuは,coignimbrite ash-fall depositとして堆積した.斑晶鉱物組合せ,火山ガラスの屈折率・化学組成,斜方輝石の最大屈折率,古地磁気特性により,男鹿,房総,大阪において認定された.房総と大阪における層位から噴出年代は約760 ka(MIS 19.1-18.4)と推定され,ブリュンヌ-松山古地磁気境界直上の鍵層となる.Hkd-Kuは偏西風の風上方向となる給源から830 km南西の大阪でも見出され,他の日本列島のcoignimbrite ash-fall depositと同様な分布を示す.
Key words : Hakkoda-Kokumoto Tephra, widespread tephra, ignimbrite, co-ignimbrite ash-fall deposits, Hakkoda caldera, Northeast Japan, Middle Pleistocene
5. Distribution of Early Tertiary Volcanic Rocks in South Sumatra and West Java
R. Soeria-Atmadja and Dardji Noeradi
南スマトラおよび西ジャワにおける第三紀前期の火山岩類の分布
スマトラとジャワにおける第三紀から第四紀の火山活動の変遷は,次の3つの段階に区分できる.(1) 第三紀前期(43-33 Ma)における溶岩流をともなう島弧型ソレアイトの活動,(2) 第三紀後期(11 Ma)におけるソレアイト質枕状玄武岩の噴出,(3) 鮮新世〜第四紀における中度のカリウムを含むカルクアルカリ火成作用.本研究による古第三紀火山岩類の野外データや,南スマトラおよび西ジャワ北部における深部データから,この時代の火山岩類はより広範囲に分布していることが明らかになった.これは西ジャワ北部の火山岩類の東方延長が不明だったため,過去の研究では南カリマンタンへ延長していたためである.ところが,ジャワ島南海岸に産出する第三紀前期の火山岩類は,はるか東方のFloresまで追跡が可能であることが判明した.上記のような南スマトラと西ジャワ北部の古第三紀火山岩類の産出は,古第三紀に存在していた火山弧によって説明可能である.この火山弧の形成は,白亜紀後期〜古第三紀に存在した南スマトラと西ジャワに平行な海溝に沿ったインドプレートの北東方向へ沈み込みに関連している.
Key words:Paleogene volcanic rocks, South Sumatra and West Java
6. Texture and petroIogy of modern river, beach and Shelf Sands in a volcanic back-arc Setting, northeastern Japan
Atsushi Noda
北東日本の火山性背弧域における現世河川・浜・陸棚砂の粒度と組成
野田 篤
火山活動が活発な地域における河川・浜・陸棚の現世砂質堆積物が,(1)どのような空間分布をもち,(2)どのようなメカニズムによって形成されたのかを明らかにするために,北海道道東の網走湾とその周辺地域を対象とし,堆積物の粒度組成とモード組成の分析を行った.試料間の関係を探るためには,粒度組成とモード組成に中心対数比変換を適用したのち,クラスター解析と主成分分析を用いた.その結果,粒度組成から4つの堆積域(I; 再生堆積域,II; 残存堆積域,III; 現世堆積域,IV; 浜域),モード組成から4つの組成域 (A-D)を分類した.各組成域 (A-D) の分布は,基本的に後背地に分布する源岩の種類に規制されていると考えられる.また,モード組成の成熟度 (Q/FR%) は河川(1.2),Zone IV (1.7),Zone II (2.2),Zone I (3.6),Zone III (7.0) の順に増加し,リサイクルによる堆積物ほど高い成熟度を示す.
Key words:modern sand; beach; shelf; grain size; modal composition; multivariate analysis; provenance analysis
Island Arc 日本語要旨 2005 vol. 14 Issue 3
The Island Arc Vol.14 Issue3 (2005. September) 日本語要旨
1. Prograde eclogites from the Tonaru epidote amphibolite mass in the Sambagawa metamorphic belt, central Shikoku, Southwest Japan
Yasuo Miyagi and Akira Takasu
西南日本四国中央部三波川変成帯中の東平緑れん石角閃岩体の累進的エクロジャイト
宮城康夫・高須 晃
四国中央部三波川変成帯中の東平緑れん石角閃岩体は主にざくろ石緑れん石角閃岩からなり,その他に少量のエクロジャイトおよび蛇紋岩−透輝石角閃岩をともなう.東平岩体の原岩は層状はんれい岩であり,最初に角閃岩相〜グラニュライト相の高温変成作用を受けた.その後,沈み込み帯において,緑れん石青色片岩相を経てエクロジャイト相(700-730℃,≧1.5 GPa)に達する昇温変成作用を記録した.エクロジャイト化した東平岩体は三波川変成作用が進行する付加体下部まで上昇し,緑れん石角閃岩相の後退変成作用を受けた.さらに周囲の灰曹長石黒雲母帯の三波川結晶片岩類とともに三波川昇温変成作用を被った.東平岩体をはじめとするエクロジャイトを含む岩体(東赤石岩体,五良津岩体など)と三波川結晶片岩類は,同じ一つの沈み込み帯のもとで高圧型変成作用を受け,各々の変成圧力条件(=深度)まで達したものであると考えられる.そして,これらのエクロジャイト岩体は,その上昇の過程で,上盤側の付加体下部の三波川結晶片岩類の現位置に迸入し,最終的に緑れん石角閃岩相の三波川変成作用を被った.
Keywaords : eclogite, epidote-blueschist, garnet, amphibole, P-T trajectory, Tonaru mass, Sambagawa belt, subduction, prograde metamorphism.
2. Mineral chemistry of spinel peridotite xenoliths from Baengnyeong Island, South Korea and its implications for paleogeotherm of the uppermost mantle
Sung -Hi Choi and Sung-Tack Kwon
韓国ペンニョン島のスピネルかんらん岩捕獲岩の鉱物化学および上部マントルの古地温勾配への示唆.
韓国(北西端)ペンニョン島(白●島)の鮮新世ベーサナイト中に含まれるマントル起源捕獲岩にはスピネルレールゾライトとスピネルハルツバージャイトがある.ペンニョン島の捕獲岩の全体的な組成範囲は中国東部の原生代以後のリソスフェアマントル起源捕獲岩のものと一致し,枯渇した始生代大陸下マントルの存在を示す組成的証拠を欠く.捕獲岩の鉱物化学組成によって平衡温度圧力を見積もり,起源となったマントル領域の古地温勾配を組み立てた.捕獲岩から求めた古地温勾配は820℃,7.3 kbarと1,000℃, 20.6 kbarの2点を通る.中国の原生代以後のリソスフェアマントル起源捕獲岩から得られたものと同様に,ペンニョン島の地温勾配は,地殻・マントル境界の深さにおいて熱伝導モデルで計算されるものよりもかなり高温であり,恐らくリソスフェアの薄化による熱的擾乱を反映している.ハルツバージャイトとレールゾライトの間には有意な温度・圧力の差はなく,ペンニョン島下のこの範囲の深さではハルツバージャイトとレールゾライトが交互に存在することを示唆する.
Key words: Baengnyeong Island, paleogeotherm, post-Archean lithospheric mantle, South Korea, spinel peridotite xenolith
3. Late Oligocene post-obduction granitoids of New Caledonia : a case for reactivated subduction and slab break-off.
Dominique Cluzel, Delphine Bosch, Jean-Louis Paquette, Yves Lemennicier, Philippe Montjoie, Rene-Pierre Menot.
ニューカレドニアの漸新世後期のオブダクション後の花崗岩類:沈み込みの再開とスラブの破断が起きた場合
ニューカレドニア南部では,漸新世後期の花崗閃緑岩とアダメロ岩が,始新世後期に定置した超苦鉄質の異地性岩体中に貫入している.従来の解釈では,これらの起源は下方の大陸地殻の溶融によるとされていたが,我々の新しいデータは,これらの高カリウム〜中カリウムのカルクアルカリ花崗岩類は大陸地殻起源のメルトと混合していない火山弧マグマの化学的・同位体的特徴を示す.これらのマグマは恐らくニューカレドニアの西海岸沿いに地球物理学的な痕跡が残る漸新世の沈み込み帯で形成されたものだろう.これらのSr, Nd,Pb同位体比は,同位体的にほとんど均質なマントルウェッジ由来を示すが,一方で結晶分化作用によって説明できないいくつかの微量元素比のばらつきは,給源マントル物質の(微量元素組成の)不均質性を示す.一部のやや若い時代の花崗岩類が著しく重希土類に枯渇することは,それらの捕獲岩として産するざくろ石に富む地殻下部物質(グラニュライト)との平衡によるのだろう.しかし,結晶分化作用に関係なくNb, Ta, Hfが比較的濃集していることは,既にアンダープレートしていた苦鉄質物質との適度な混合,マントルウェッジの不均質な加水作用,そしてNbに富む上昇するマントル物質との混合,のいずれかを表す.(超苦鉄質岩体の)オブダクション後のスラブの破断は,リソスフェアマントルより下での物質混合とそれに引き続く不均質化に重要な役割を演じたものと考える.ここで記述した漸新世後期の沈み込みは,南方へニュージーランド北部の異地性岩体まで延長していた可能性がある.
Keywords: granitoid, Oligocene, obduction, volcanic-arc magmatism, slab break-off, geochemistry, isotopes, New Caledonia, Southwest Pacific
4. Complete mantle section of a slow spreading ridge-derived ophiolite : An example from the Isabela Ophiolite(Philippines)
Eric S.Andal, Shoji Arai and Graciano P. Yumul,Jr.
低速拡大海嶺起源のオフィオライトの完全なマントル断面:フィリピン,イサベラ・オフィオライトの例
イサベラオフィオライトは,フィリピンのルソン島北部の東海岸に沿って完全なオフィオライト層序を示し,北東ルソン地塊の白亜紀基盤岩コンプレックスをなす.このオフィオライトはフィリピン変動帯の東縁に沿って配列する一連のオフィオライトおよびオフィオラト質岩体の最北端に位置する.この論文ではイサベラオフィオライトの性質と特徴について新知見を報告する.
イサベラオフィオライトのかんらん岩は比較的新鮮で,スピネルレールゾライト,単斜輝石を含むハルツバージャイト,枯渇したハルツバージャイト,ダナイトよりなる.モード組成,特に輝石の量は,南から北へ向かって肥沃なレールゾライト,単斜輝石を含むハルツバージャイト,枯渇したハルツバージャイトの順に枯渇傾向を示す.モード組成の変化は記載岩石学的な組織の変化を伴う.
スピネルのクロムナンバーは部分溶融程度の指標となるが,その変化は記載岩石学的観察と調和的である.更に,イサベラオフィオライトかんらん岩は現在の中央海嶺から得られる深海底かんらん岩と,スピネルやかんらん石の主要元素組成,単斜輝石の希土類元素組成において類似性を示す.これらの岩石・鉱物組成はイサベラオフィオライトが肥沃なレールゾライトを伴う(L型とH型の)中間型のオフィオライトであり,多くのオフィオライトでは欠如しているマントル断面の深部を代表することを示唆する.
肥沃なかんらん岩の産出は,オフィオライトのマントル断面の最下部を調査できる稀な機会を提供する.ある連続したマントル断面におけるかんらん岩の組成変化幅の大きさは,現在拡大中の中央海嶺下の溶融したマントル断面のよいアナログとなるかもしれない.
Keywords: mantle column, mantle peridotite, ophiolite, partial melting
Island Arc 日本語要旨 2005 vol. 14 Issue 2
The Island Arc Vol.14 Issue2 (2005. June) 日本語要旨
1. Petrogenesis and tectonic implications of early Cretaceous high-K calc-alkaline volcanic rocks in the Laiyang basin of the Sulu belt, eastern China
Feng Guo, Weiming Fan, Yuejun Wang and Chaowen Li.
郭 鋒・範 蔚茗・王 岳軍・李 超文
中国蘇魯帯莱陽盆地の白亜紀前期高カリウム・カルクアルカリ系列火山岩の岩石成因と構造的意義
中国東部の蘇魯高圧・超高圧変成帯の北側に位置する莱陽盆地に産する白亜紀前期の高カリウム・カルクアルカリ火山岩類は,粗面玄武岩から粗面安山岩にいたる様々な岩石よりなる.この玄武岩・安山岩類は107〜105 Maに噴出し,SiO2は50.1〜59.6%, MgOは2.6〜7.2%の範囲にわたり,Ba, KなどのLILEや軽希土類(LREE)の富化及びHFSEの枯渇で特徴づけられ,高いSr同位体比 (87Sr/86Sr(i)=0.70750〜0.70931)と低いNd同位体比 (εNd(t)= -17.9〜-15.6)を持っている.それらはより早期の蘇魯帯のランプロファイアーと地球化学的に類似し,両者が共通のLILEとLREEに富む給源マントルに由来することを示唆する.したがって,両地域を境する地表部分の五蓮−青島−烟台(Wulian-Qingdao-Yentai)断層が華北地塊と揚子地塊の岩石圏境界であると考えるべきではない.珪長質の溶岩は93〜91 Maに噴出し,SiO2は61.6〜67.0%,MgOは1.1〜2.6%の範囲で変化し,玄武岩類と同様の微量元素パターンを示すが,より高いSr同位体比(87Sr/86Sr(i)=0.70957〜0.71109)とより低いNd同位体比(εNd(t)=-19.1〜-17.5)を示し,これらの性質は蘇魯帯のIタイプ花崗岩と共通し,スラブ溶融実験で得られたメルトとも共通する.これらと早期の玄武岩・安山岩類との間には10 Ma 以上の活動時期の違いがあり,いくつかの元素(例えばP, Ti, Sr)について組成ギャップがある.これらを説明するために,珪長質岩については地殻物質起源を提案した.これらのメルトの原岩は,火成岩源の変成岩が優勢だったが,玄武岩・安山岩及び/またはランプロファイアーマグマからの苦鉄質集積岩もかなり関与していた.莱陽盆地に前期白亜紀の高カリウム・カルクアルカリ岩が多量に噴出したことは,この盆地が,厚くなった岩石圏が次第に引き伸ばされて薄くなる,造山帯の崩壊過程に対応した引張場にあったことを支持し,ジュラ紀末期の造山帯前縁盆地から白亜紀前期以後の断層盆地へと変化したことを反映している.
Keywords: Geochemistry, post-orogenic extension, high-K calc-alkaline volcanism, early Cretaceous, the Sulu belt, eastern China
2. Refined early to middle Miocene diatom biochronology for the middle- to high-latitude North Pacific
Mahito Watanabe and Yukio Yanagisawa
中・高緯度北太平洋の前期ー中期中新世珪藻化石年代層序の高精度化
ODP Leg 145 Site 887(北東太平洋Patton-Murray海山)の試料を用い、珪藻化石層序と古地磁気層序を直接対応させることにより、前期ー中期中新世(18- 11Ma)の中高緯度北太平洋珪藻化石層序の数値年代を改訂した。2万年から4万年の間隔で試料を採取することにより従来の研究より精度を高め、従来古地磁気層序と対応のついていなかった第二次生層準についても初めて対応関係を明らかにした。また、北西太平洋で確立された第二次生層準が北東太平洋でも有用であることも明らかとなった。今回改訂された珪藻化石層序とその年代は、石灰質微化石の産出が少ない中高緯度太平洋の海底堆積物の研究に大きな役割を果たすと期待される。本論文においてDenticulopsis praedimorpha var. prima n. var. を記載した。
Key words : diatom, biostratigraphy, biochronology, Miocene, north Pacific, ODP, Site 887
3. Origin of Mesozoic Gold mineralization in South Korea
Seon-Gyu Choi, Sung-Tack Kwon, Jin-Han Ree, Chil-Sup So and Sang Joon Pak
韓国における中生代金鉱化作用の起源
韓国の中生代金銀鉱床は中生代花崗岩と密接に伴っている.ジュラ紀の金銀鉱床は白亜紀のものと産状,変質のスタイル,金の品位,鉱物組み合わせ,流体包有物,そして安定同位体比において区別できる.ジュラ紀の鉱床は,深部に貫入した花崗岩に関係するメソゾーン環境で形成されたが,白亜紀のものは,浅部に貫入した花崗岩に関係するエピゾーン環境で形成された.ジュラ紀の含金鉱床(約165〜145 Ma)は造山帯型金鉱床特有の鉱液組成を示し,恐らくアジア大陸縁へのイザナギ海洋プレートの直角沈み込みによる圧縮場で形成された.一方,横ずれ断層及びカルデラに関係する断裂とそれに伴う火山・深成活動は,陸弧セッティングにおける白亜紀の金銀鉱脈鉱床(約110〜45 Ma)の形成に重要な役割を演じたであろう.
Keywords: gold, Mesozoic magmatism, Korea, fluid inclusions, stable isotope
4. Geology and Geochemistry of Karasugasen Lava Dome, Daisen-Hiruzen Volcano Group, Southwest Japan
Jun-Ichi Kimura, Mamiko Tateno, and Isaku Osaka
西南日本大山−蒜山火山群烏ヶ山溶岩ドームの地質と地球化学
西南日本大山−蒜山火山群烏ヶ山溶岩ドームの地質と地球化学について詳細な検討を行った.烏ヶ山は約26kaに噴火した溶岩ドームで,ブルカノ式降下火山灰噴火に始まり,溶岩ドームの成長にともない8以上のブロックアンドアッシュフローと1回の軽石流を発生した噴火主相に発展し,その後ブルカノ式降下火山灰噴火とサブプリニー式軽石噴火で終了した.この噴火シークエンスは58,26,17kaに起こった大山火山最新の3噴火に共通している.烏ヶ山噴火のマグマは典型的なアダカイトであり,島弧の典型的デイサイトに比べて高いSr/Y,低いHREE/LREEを示す.烏ヶ山のマグマは大山−蒜山火山群のそれと良く類似しており,大山−蒜山火山群はおよそ100万年に渡りアダカイトを噴出し続けていたことになる.その間に起こった100km3を超えるアダカイトマグマの供給は,大量で均質なマグマソースが存在し続けた事を示しており,例えば沈み込むフィリピン海プレートスラブの融解によって発生したと考えることができる.スラブ融解は烏ヶ山,さらに大山−蒜山火山群のマグマソースを説明するのに有力なメカニズムである.
Key words: Adakite, Daisen-Hiruzen Volcano Group, Eruption sequence, Geochemistry, Geology, Karasugasen, Lava dome, Slab melting, SW Japan
5. Paleostress fields from calcite twins in the Pyeongan Supergroup, South Korea
Seong-Seung Kang, Jun-Mo Kim and Bo-An Jang
韓国,平安累層群の方解石双晶からみた古応力場
朝鮮半島南部の沃川(Ogcheon)帯北東部に沿って分布する古生代後期から中生代前期の平安累層群の古応力場について,方解石変形ゲージ(CSG)法を用いて研究した.双晶の歪み量と双晶の密度や幅との関係は,天然の低温における石灰岩の変形条件の指標として用いられており,それらについての従来の研究結果と本研究の結果を合わせると,研究地域の方解石脈は恐らく170℃以下の温度で形成されたのだろう.2つの標本中で,方解石脈から2つの異なる古応力場の主方向が推定されたが,他の2つの標本からは1つの方向のみが推定された.この結果は,平安累層群においては,中生代の変形作用が2回以上のテクトニック・イベントによって起こったことを示唆する.最大圧縮軸の2つの方向は北東−南西と北西−南東を向いており,それらは多くの断層系から推定された古応力方向とよく一致する.本研究及び他の研究の古応力解析結果を綜合すると,平安累層群の最大圧縮軸の方向は大宝(Daebo)造山期以前(三畳紀後期)の北東−南西方向から大宝造山期中(ジュラ紀前期〜白亜紀前期)の北西−南東方向へと,中生代の間に変化したことが示唆される.
Keywords: paleostress, Pyeongan Supergroup, calcite strain gauge technique, twin, Mesozoic
6. Geochemistry of adakitic quartz diorite in the Yamizo Mountains, central Japan ーImplications for Early Cretaceous adakitic magmatism in the Inner Zone of Southwest Japan ー
Yutaka Takahashi, Shin-ich Kagashima and Masumi U. Mikoshiba
八溝山地に分布する前期白亜紀アダカイト質石英閃緑岩の化学組成−西南日本内帯,前期白亜紀アダカイト質火成活動の考察−
八溝山地には,前期白亜紀の石英閃緑岩及び角閃石斑れい岩からなる小規模岩体が複数分布している.石英閃緑岩はSrに富みYに乏しく,Sr/Y-Y図上でアダカイトの領域に入るものが多く,Sr同位体比初生値は0.7038〜0.7046であり,海洋地殻の部分溶融によって形成されたように見える.しかし,エクロジャイトやざくろ石角閃岩の部分溶融によってアダカイト質石英閃緑岩の化学組成を導くのは困難である.一方,上部マントルにおいて生成された玄武岩質初生マグマの角閃石・斜長石を主とした分別結晶作用によってアダカイト質石英閃緑岩の化学組成は説明可能であり,角閃石斑れい岩は結晶集積岩とみなすことが出来る.
Key words : geochemistry, adakite, TTG, slab melting, fractional crystallization, cumulate, quartz diorite, hornblende gabbro, Yamizo Mountains.
7. Partial melting controls on the northwest Kyushu basalts form Saga-Futagoyama
Hidehisa Mashima
佐賀両子山産北西九州玄武岩における部分溶融作用の支配
佐賀両子山地域に分布する北西九州玄武岩類について,主成分元素および固相濃集元素組成に基づき成因を考察した。佐賀両子山の玄武岩類は鉄に乏しいもの (IPG)と鉄にとむもの(IRG)に分けられる。主成分元素および固相濃集元素の挙動は,IPGの組成変化は起源物質の部分溶融過程に支配され,IRG はIPGから単斜輝石の結晶分化によって生じたことを示す。IRGは北西九州玄武岩類では稀であり,IPGと他産地の北西九州玄武岩類の組成近似性は,起源物質の部分溶融過程が北西九州玄武岩類の化学組成変化を支配することを示す。また,IPGのAlに乏しい特徴は,その起源物質が通常のマントルとは異なることを示す。
Key Words : Northwest Kyushu, basalt, partial melting, major element, compatible
element.
8. Rapid tectonics of the Late Miocene Boso accretionary prism related to the Izu-Bonin arc collision
Yuzuru Yamamoto and Shunsuke Kawakami
伊豆-小笠原弧衝突に関連した後期中新統三浦房総付加体のテクトニクス
伊豆-小笠原弧の衝突帯近傍である房総半島南部の西岬層および鏡ヶ浦層において,付加年代・後期中新統以降の回転年代・テクトニクスの解明を目指し,構造・古地磁気・放散虫生層序の解析を行った.房総半島南部は,ほぼ東西に延びる褶曲・衝上断層帯で特徴づけられるが,これらは南端の西岬層北西部で北西-南東方向へ変化する.古地磁気および構造解析によって,回転は2回のステージがあったことが判明した.最初の回転は,西岬層の付加後かつ鏡ヶ浦層の堆積以前に起こり,2回目の回転は,1Maの伊豆ブロックの衝突に対応する.西岬層北西部が時計回り方向に約65-80度回転したのに対し,東部での回転量は25- 30度程度であった.被覆層である鏡ヶ浦層の回転量は,時計回り方向に11-13度であった.放散虫生層序検討によって,西岬層の堆積年代は9.9- 6.8Maの期間を少なくとも含むことが示された.一方鏡ヶ浦層下部の堆積は,4.19-3.75Maの間に始まったことが示された.これらの結果から,西岬層の付加年代および最初の回転運動は,6.80-3.75Maの間に制約される.西岬層の屈曲構造は,丹沢ブロックの衝突によって形成された見込みが強い.西岬層の付加,丹沢ブロックの衝突,そして新しい堆積盆(鏡ヶ浦層)の形成が,2.61-3.05m.y.の短い期間に起こったことが示された.
Key words: arc collision, accretionary prism, Boso Peninsula, Izu-Bonin island arc, Tanzawa block
9. The rate of fluvial incision during the late Quaternary in the Abukuma Mountains, northeast Japan, deduced from tephrochronology
Takahiro Yamamoto
テフラ層序から求めた福島県阿武隈山地における第四紀後半の河川下刻量
数万年から数十万年に及ぶような地質環境の長期将来予測は,高レベル放射性廃棄物の地層処分において不可欠の技術である.本研究では,指標地形面の編年から河川下刻率の定量的な見積もりを行った.このような計測は,段丘面が発達する海岸部では容易であるものの,阿武隈山地のような内陸山間部では段丘面の発達が貧弱なためほとんど試みられたことがない.本研究では山地内の断片的に分布する段丘堆積物をテフラ層序から低位,中位,高位に区分し,これらが低海面期のステージ2〜3,5.2〜5.4,6の時期に対応することを明らかにした.この編年をもとに比高量を下刻率に直すと各段丘とも1m/万年となりほぼ一定の値が得られる.
Key words : Abukuma Mountains, river incision, Quaternary, tephrochronology, geologic disposal, Japan.
Island Arc 日本語要旨 2005 vol. 14 Issue 1
The Island Arc Vol.14 Issue1 日本語要旨
1. Fault rock analyses from the northern part of the Chelungpu fault and their relation to earthquake faulting of the 1999 Chi-Chi earthquake, Taiwan
Kohtaro Ujiiie
車籠埔断層北部での断層岩解析から読み取る1999年台湾・集集地震におけるすべり過程
要旨:1999年台湾・集集地震では地表地震断層が既存の車籠埔断層沿いに出現した。
車籠埔断層北部で得られた近地の強震記録は高周波地震動をほとんど欠いており、大変位(10-15 m)と速いすべり速度(2-4 m/s)を伴っていることから、地震時に断層は低摩擦下ですべったと考えられている。車籠埔断層北部での浅部掘削によって採取された1999年の地震ですべった可能性のある2つの断層帯を解析したところ、断層浅部におけるすべりメカニズムが、未固結断層角礫における粒子流動あるいは水圧破砕を伴った粘土質ガウジの流動であることが明らかとなった。これらはいずれも断層浅部において低摩擦すべりをもたらすことから、断層深部での速いすべりが浅部へ円滑に伝わることが可能であったと考えられる。強震記録と断層岩解析結果は、地震時に低摩擦すべりがそれぞれ断層深部と浅部で起こったことを示しており、その結果、車籠埔断層北部では断層深部から地表に至るまで大変位が生じたと考えられる。
Key words: fault breccia, granular flow, clayey gouge, slip localization, low dynamic friction, Chelungpu fault, Chi-Chi earthquake
2. Fractal Size and spatial distributions of fault zones: An investigation into the Seismic Chelungpu fault, Taiwan
Kenshiro Otsuki 断層帯のフラクタルなサイズ分布と空間分布:台湾車龍埔断層に関する解析結果
台湾車龍埔地震断層の北部を貫くボーリングコアについて、断層破砕帯の厚さTに関するフラクタル解析を行った。特徴的な厚さTc (約40 cm)以下の集団のサイズ分布のフラクタル次元は通常の脆性断層の値の範囲内にあるが、T>Tcの断層集団のそれは異常に大きい。サイズ分布と空間分布(情報次元)のフラクタル次元は、Tの平均分布密度の増加とともに増加するが、これらは通常の脆性断層集団の進化傾向とは逆である。これらの解析結果を説明するためには、Tcより大きなTの増加速度が断層変位の減少関数でなければならない。この特殊な関係は、T>Tcで効果的に作動したすべり不安定性のメカニズムであるelastohydrodynamic lubricationと関係している。
Key words: Chelungpu fault, Chi-Chi earthquake, fault zones, fractal, size frequency, spatial distribution, elastohydrodynamic lubrication.
3. Clayey injection veins and pseudotachylyte from two boreholes penetrating the Chelungpu fault, Taiwan: Their implications for the contrastive seismic slip behaviors during the 1999 Chi-Chi earthquake
Kenshiro Otsuki
台湾車龍埔断層を貫く2本のボーリングで発見された粘土貫入脈とシュードタキライト:1999年集集地震での対照的な断層すべり挙動に対する意義。
1999年台湾集集地震後に、車龍埔断層の北部と南部で得られた断層岩ボーリングコアを解析した。北部の断層岩は軟質粘土より成り、粘土の貫入脈が伴われることから、地震の際に異常な高圧が発生し、elastohydrodynamic lubricationが効果的に作動したらしい。南部の断層帯には、破砕された古いシュードタキライトが伴われている。その溶融度は低く、すべりは高い粘性の溶融層のバリアーによって抑制された。これらの断層岩は過去に繰り返した地震イベントによって形成されたものだが、対応する2つの摩擦すべりのメカニズムは集集地震の際にも作動し、北部での滑らかで大きなすべり、南部での不規則で小さなすべりという対照的な挙動の原因となったと思われる。
Key word : Chelungpu fault, Chi-Chi earthquake, clayey injection veins, elastohydrodynamic lubrication, pseudotachylyte, frictional melting.
4. Some Isotopic and Hydrological Changes in the 1999 Chi-Chi Earthquake, Taiwan
Chung-Ho Wang,
1999年台湾集々地震に伴う地下水の同位体及び水理学的変化
我々は、チェルンプ断層の近くのチョウシュイ河扇状地において、台湾での1999年集々地震(Mw=7.5)の最中とその後での地下水位と同位体組成の変動を報告した。水理学的な変動における三つの点を指摘した。(1)集々地震に伴い、チョウシュイ河扇状地の下位の地下水は、同位体組成においてチョウシュイ河の表層水の値に向かっての明瞭なシフトがみられる。これは、地下水と河川水との水の交換が助長されたことを示唆する。(2)幾つかの観測井において、それまで異なっていた地下水での水位や同位体組成が、集々地震時に相対的に同じような値へと変換された。これは異なる地下水間で起こった地震時の水の交換を示唆しており、多分に地下水間での半透水層の破壊や枝分かれによる透水率の増強を意味する。(3)地震時の水位レベルの応答パターンは同位体組成における値のシフトとは明瞭に異なっており、これらが異なるメカニズムのよって作られたことを示している。
Key words : Chi-Chi earthquake, groundwater level, groundwater flow, oxygen isotope
5. Late Paleozoic adakites and Nb-enriched basalts from northern Xinjiang,NW China: evidence for the southward subduction of the Paleo-Asian Oceanic Plate
Haixiang Zhang, Hecai Niu, Hiroaki Sato, Xueyuan Yu, Qiang Shan, Boyou Zhang, Junichi Ito, Takashi Nagao
中国北西部,新疆北部の古生代後期のアダカイト及び高ニオブ玄武岩:古アジア海洋プレートの南方への沈み込みの証拠.
中国西北部,新疆北部のカザフスタン・ジュンガル地塊北縁のデボン紀前期,土竜格庫都克(Toranggekuduk)層群からアダカイトと高ニオブ玄武岩よりなる火山岩類が発見された.
この地域の安山岩〜デイサイトはアダカイトの地球化学的特徴を持つ.Al2O3, Na2O, MgOそしてMg#が比較的高いことはアダカイトが玄武岩質下部地殻の溶融ではなく,沈み込む海洋
地殻の溶融によって形成されたことを示す.SrIとεNd(t)がMORBよりもやや高いことは,スラブ溶融の過程における海洋堆積物の関与を暗示する.アダカイト溶岩の間に挟まれる高ニオブ玄武岩溶岩はシリカに飽和しており,典型的な島弧玄武岩に比べてNbとTiが高い(HFSEに富む)特徴がある.それらはスラブ由来の流体によって交代作用を受けたウェッジマントルかんらん岩の部分溶融によって形成された.本地域のアダカイトが新生代のものに比べて明瞭なSrの正異常とやや高いHREE濃度を示すことは,古生代の古アジア海沈み込み帯の温度勾配と古アジア海海洋スラブの溶融深度が,始生代と新生代の場合の中間だったことを示す.新疆北部,カザフスタン・ジュンガル地塊北縁におけるアダカイトと高ニオブ玄武岩の分布は,デボン紀前期に古アジア海の海洋プレートがカザフスタン・ジュンガルプレートの下へ南向きに沈み込んでいたことを示す.
Key words : adakite, Nb-enriched basalt, Central Asian Orogenic Belt, Kazakhstan-Junggar Plate, the Paleo-Asian Ocean, subduction
Island Arc 日本語要旨 2004. vol. 13 Issue 4
The Island Arc Vol.13 Issue4 日本語要旨
1. A Brief History of Petrotectonic Research of the Sanbagawa Belt,Japan
Shohei Banno
三波川変成帯の岩石学的・地体構造論的研究史の概略
三波川結晶片岩の岩石学的研究は小藤文次郎(1856-1935)によって始められ,鈴木 醇(1896-1970)及び堀越義一(1905-1992) は四国中央部別子地域で精力的な記載岩石学的研究を行った.P. Eskola(1883-1964)の変成相の概念に基づく岩石学的研究は,日本では1950年代に都城秋穂によって低い圧力/温度比(低P/T型)の阿武隈変成帯において始められ,続いて関 陽太郎と坂野昇平によって高P/T型の三波川変成帯で行われた.1970年代には,独特の逆転した温度構造の存在が確立された.こうして1990年代までに三波川変成帯の地質学的,記載岩石学的特徴が明らかになった.現在の研究は,地質年代学的,構造地質学的,地体構造論的,そして地質熱学的観点から新しい定量的モデリングを行い,この変成帯の古典的なイメージを再検討しつつある.
Keywords Comtemporary debate, Facies series, Research history, Sanbagawa
2. Zircon U-Pb ages and tectonic implications of メEarly Paleozoicモ granitoids at Yanbian, Jilin province, NE China
Yanbin Zhang, Fuyuan Wu, Simon A. Wilde, Mingguo Zhai, Xiaoping Lu and Deyou Sun
中国東北地方,吉林省延辺の「古生代前期」花崗岩類のジルコンU-Pb年代とその地質構造的意義.
延辺(朝鮮族自治州)地域は中国の中央アジア造山帯(CAOB)の東部に位置し,顕生代花崗岩類の広汎な貫入によって特徴づけられる.従来,延辺花崗岩類は,華北地塊北縁に沿って東西に延びる地域に,主に古生代前期に定置したと考えられていた(いわゆる「カレドニア期」花崗岩類).しかし,それらの年代決定はほとんどなされてなかったので,今回5つの典型的な「カレドニア期花崗岩類」(黄泥嶺,大開,孟山,高嶺,百里坪の各底盤)を選んでジルコンU-Pb 同位体法による年代測定を行った.我々の新しい年代データは,これらの花崗岩類の定置年代が古生代後期から中生代後期(285-116 Ma)にわたることを示す.即ち,華北地塊北縁には「カレドニア期花崗岩類」は全く存在しないことがわかった.これらの花崗岩類の活動時期は,我々の新しいデータに基づいて,ペルム紀(285±9 Ma),三畳紀(249-245 Ma),ジュラ紀(192-168 Ma),及び白亜紀(119-116 Ma) の4つに区分できる.285±9 Maのトーナル岩は古アジア海の華北地塊下への沈み込みに関連しているらしく,次に三畳紀の大陸衝突と同時期の249-245 Maのモンゾ花崗岩類が貫入した.これは,CAOBの造山帯地質体群と華北地塊との衝突及び古アジア海の最終的な閉塞過程を代表する.ジュラ紀花崗岩類は古太平洋プレートの沈み込み,及びそれに続く佳木斯(ジャムス)−ハンカ地塊と三畳紀に合体した既存の中国大陸との衝突の産物である.そして,白亜紀前期の花崗岩はアジア大陸東縁の伸長場で形成された.
Key words : U-Pb geochronology, Zircon, Granitoids, Yanbian, NE China
3. Accretion and post-accretion tectonics of the Calamian Islands,
North Palawan Block (Philippines)
Lawrence R. Zamoras and Atsushi Matsuoka
フィリピン北パラワンブロックのカラミアン諸島における付加および付加後のテクトニクス
フィリピン北パラワンブロックの付加コンプレックスには,上部古生界から中世界にいたる堆積層が分布する.それらは,チャート(リミナンコン層),砕屑岩(グインロ層),多くの石灰岩ユニット(コロン層,ミニログ層,マラジョン層)である.カラミアン諸島の異なる層序のチャート・砕屑岩層の漸移関係の研究に基づき,3つの付加体が識別された.それらは,北部ブスアンガ帯,中部ブスアンガ帯,南部ブスアンガ帯である.これらは東アジアの付加体中でのイベントとして,まず,北部ブスアンガ帯が中部ジュラ紀に始まり,中部ブスアンガ帯が後期ジュラ紀に,南部ブスアンガ帯が後期ジュラ紀から初期白亜紀に付加した.いくつもの海山上の石灰岩ブロックが,チャート・砕屑岩層序に並列して存在している.後期白亜紀に東アジアの沈み込み付加作用が終わると,この地域も安定化した.中期漸新世には海洋底拡大によってアジアと北パラワンブロックの間が断たれ,拡大は南へ移動した.中期中新世には,北パ
ラワンブロックとフィリピン島弧とが衝突した結果,東部カラミアン諸島のNE-SW方向の構造がNW-SE方向へと時計回りに回転し,カラミアン諸島の大構造が出来上がった.
Key words:accretionary complex, chert-clastic sequence, radiolarian biostratigraphy, subduction tectonics, Calamian, North Palawan Block, Philippines.
4. Was a slab window opened during the subduction of plate boundaries in Mid-Cretaceous SW Japan ? - A two-dimensional numerical analysis of the subduction of a spreading ridge
Takamoto Okudaira and Yoshiko Yoshitake
白亜紀西南日本にプレート境界は沈み込んだのか? −拡大海嶺の沈み込みに関する二次元数値解析
白亜紀西南日本に形成された多量の花崗岩や広域変成帯は,活動的拡大海嶺 (クラ−太平洋海嶺またはファラロン−イザナギ海嶺)のユーラシア大陸への沈み込みとそれに伴うスラブウィンドウの形成にその原因が求められてきた.本研究ではこのシナリオを検証するため,活動的拡大海嶺の沈み込みとそれに伴うスラブウィンドウの形成による,大陸地殻への熱的影響に関する二次元数値解析を行った.シナリオの妥当性は,様々なモデルパラメータに基づく計算結果を白亜紀西南日本の地質と比較することによって検討された.具体的な地質学的制約条件は,和達・ベニオフ面付近での角閃岩相−グラニュライト相変成岩の欠如(低温高圧型三波川変成帯の存在),そして大量の花崗岩(領家・山陽帯の花崗岩類)を生成するために必要な下部地殻塩基性岩の十分な融解である.検討の結果,上記二つの地質学的制約条件を同時に満たすようなモデルパラメータは存在しないことが明らかとなった.これは,白亜紀西南日本においては,活動的拡大海嶺の沈み込みとそれに伴うスラブウィンドウの形成に対して否定的であることを示している.これまでの研究と今回の解析結果を考慮した場合,白亜紀西南日本においては,次の二つのテクトニックシナリオを描くことが出来るであろう. (1)活動的拡大海嶺はユーラシア大陸に対して沈み込まなかったが,海嶺軸は大陸沖に停滞し,長期間にわたって若い (熱い)海洋プレートを供給し続けた.(2) 海嶺は沈み込む直前にその活動を停止した(非活動的海嶺の沈み込み).二つのシナリオとも,白亜紀西南日本に沈み込んだのは活動的拡大海嶺ではなく,若い (熱い)海洋プレートであったというものである.
Key words:Mid-Cretaceous igneous activity, Ryoke-Sanyo granitoids, Sambagawa metamorphic belt, slab window, SW Japan, spreading-ridge subduction, thermal modeling.
5. Heat influx and exhumation of the Shimanto accretionary complex: Miocene fission track ages from Kii Peninsula, southwest Japan
Noriko Hasebe and Hiroaki Watanabe 四万十付加体の上昇削剥と熱の流入:西南日本紀伊半島から中新世フィッショントラック年代値の報告
付加体の形成過程やレベルの異なる構造体が露出する過程に,地域的な地質現象が与える影響を理解するために,フィッショントラック(FT)法を用いた年代学的マッピングを,西南日本・紀伊半島で行った.ここに分布する白亜紀付加体では,本来あるべき沈み込み帯に平行な帯状構造が乱されて,四万十付加体が北側に張り出している.東西〜12キロメートル,南北〜15キロメートルの調査地域から26のジルコンFT年代値を得たところ,それらは以下の3つのグループに分けることができた.(1)北西ー南東方向の谷沿いに分布する~15 Ma (~10から~20 Ma にわたる)の年代値,(2)調査地の北西部に分布する~50 Maの年代値,(3)上記2つのグループよりも古い年代値.8試料から得られたFTの長さ分布も考慮に入れ,中新世の年代値を,~50 MaのFT年代値として記録されている広域的な上昇・削剥の後,熱の流入および冷却が空間的に不均一に生じた結果によるものと解釈した.
Key words:Shimanto accretionary complex, fission track geochronology, heat influx, local exhumation , Kii Peninsula.
Island Arc 日本語要旨 2004. vol. 13 Issue 3
The Island Arc Vol.13 Issue3 日本語要旨
1. Thrust geometries in unconsolidated Quaternary sediments and evolution of the Eupchon fault, SE Korea
YOUNG-SEOG KIM, JOON YOUNG PARK , JEONG HWAN KIM , HYEON CHO SHlN AND DAVID J. SANDERSON
韓国南東部の未固結堆積層中の低角逆断層とユプチョン断層の発達
韓半島は,アジア大陸の東端の比較的安定した地域に位置すると長い間信じられてきた.しかし,その南東部から最近10以上の第四紀断層が知られて来た.それらの一つであるユプチョン断層は,小学校の建設中に発見されたものである.しかも,それは原子力発電所に近接している.この第四紀断層の性質と特性を理解するために,2箇所でトレンチ調査を実施した.本断層は,主断層(走向N20E,傾斜40SE),変位約4 mを示し,副断層は,未固結の第四紀層を切っている.調査の結果,この断層系には,シンセティックとアンティセティックの断層,上盤に背斜構造,引きずり褶曲,バックスラスト,ポップアップ構造,フラットランプ構造,デュープレックスなどが見出された.これらは,固結した低角逆断層システムに普通に伴うものに非常に類似している.断層系の上部には,いくつかの破砕部が観察され,断層が上方に伝播して,上部で止まったことを示している.主断層に沿う礫は,断層に沿って長軸方向をそろえている.第四紀層と下位の第三紀安山岩または白亜紀堆積岩との間の不整合面は,逆断層センスの本断層で変位している.断層の下部では,センスは正断層であるので,もともと正断層だったものが,第四紀に逆断層に転化したものであることを示している.断層の長さと変位の関係から推定された第四紀の断層の延長は200-2000 mに及ぶ.この地域の現在の水平最大主応力軸の方向は,ユプチョン断層の斜めずれから期待されるごとくENE-WSWであり,それ逆断層成分をもつ右ずれ走向断層であると考えられる.
2. Metamorphism and metamorphic K-Ar ages of the Mesozoic accretionary complex in Northland, New Zealand
YUJIRO NISHIMURA, PHILIPPA M. BLACK AND TETSUMARU ITAYA
ニュージーランド,ノースランドにおける中生代付加コンプレックスの変成作用と変成K-Ar年代
ニュージーランド北島北方に露出するWaipapa Terraneの中生代付加コンプレックスは,沈み込みに伴う弱変成作用をうけ,北東から南西に向かって沸石相,ぶどう石−パンペリー石相,パンペリー石−アクチノ閃石相低温部に分帯される.泥質変成岩中の炭質物d002 値が3.642−3.564 Åを示すことから,その変成温度は300℃以下とみなされる.泥質変成岩27試料中の再結晶白雲母のK-Ar年代は,180−130 Maを示す北部ユニットと150−130 Maの南部ユニットとに区分される.前者はOtago南東海岸のCaples Terraneの年代群に,また後者はウエリントン付近のYounger Torlesse Subterraneの年代群よりやや古いが,ネルソン付近のCaples・Waipapa Terranesの年代群に対応する.
キーワード;付加コンプレックス,沈み込み変成作用,石墨化作用,K-Ar 年代,変成作用のピーク年代,ノースランド,ワイパパテレーン,ケープラステレーン,トーレステレーン
3. Character of sediment entering the Costa Rica subduction zone: Implications for partitioning of water along the plate interface
Glenn A. Spinelli and Michael B . Underwood
コスタリカ沈み込み帯に持ち込まれる堆積物の性質:プレート境界に沿う海水の区分に関する解釈
ニコヤ半島沖の堆積物からは,それがコスタリカ沈み込み帯に持ち込まれることによって大量の水分が搾り出される.地震反射データと深海掘削計画Leg 170の結果から,堆積物の上部約135 m(0-210 mにおよぶ)が半遠洋性堆積物であり,下部の約215 m(0-470 mにおよぶ)は遠洋性炭酸塩軟泥である.我々はコスタリカプレート上の,各7 m以下の長さの60本のピストンコアサンプルの地域的な組成を差異を調べた.半遠洋性堆積物は平均すると,10 wt%以下がオパール,60wt%程度がスメクタイトであり,海溝に平行方向の違いはなかった.遠洋性チョークは2wt%程度のオパール,1wt%以下のスメクタイトであった.沈み込む堆積物のうちの大半(96wt%程度)は,最初間隙に蓄えられるが,沈み込み過程の初期のうちに間隙水は,圧密とテクトニックな圧縮によって排出される.スメクタイトの層間水として蓄えられた約3.6体積%が沈み込み帯に入る.そして,たったの0.4%がオパールに閉じ込められる.沈み込みフロントから30 km入ったところの,6 kmより深いところまで沈み込んだ堆積物は,間隙率が15%以下となり,温度は60℃以上となる.このような条件では,オパールとスメクタイトの間歇的に生じる脱水反応が局所的な流体過剰圧力を作り出す.それによって,流体の流れのパタンに影響が現れ,プレート境界の断層に沿う有効応力が減少する.
キーワード:コスタリカ,沈み込み,スメクタイト,生物源シリカ,オパール,地震発生帯
4. EVIDENCE FOR HIGH-CA BONINITE MAGMATISM FROM PALEOGENE PRIMITIVE LOW-K THOLEIITE, MUKOOJIMA, HAHAJIMA ISLAND GROUP, SOUTHERN BONIN (OGASAWARA) FOREARC, JAPAN
Kosuke Maeharai and Jinichiro Maeda
小笠原諸島母島周辺の向島に分布する未分化な低Kソレアイトの中の高Caボニナイト活動を示す根拠小笠原諸島, 母島周辺の向島に分布する未分化な低Kソレアイトから高Caボニナイト質包有物を発見した.母島から約50 km北に位置する父島はボニナイトの模式地であるが,母島周辺ではボニナイトの産出はこれまで報告されていない.この高Caボニナイト質包有物は非顕晶質であり,かんらん石,Caに富む単斜輝石,斜長石,クロムスピネル,不透明鉱物と濃褐色のガラスからなる.包有物とホストの鏡下の産状から2つのマグマの混合が示され,そのことからボニナイト質マグマと未分化なソレアイト質マグマが古第三紀の母島周辺で時空的に密接な関係をもって活動したことが示唆される.これら2つのマグマは未分化であり,わずかに異なったSr・Nd同位体を示すことから,それぞれ異なった起源マントルに由来したものと考えられる.これら2つの起源マントルは母島周辺に同時に存在し,高Caボニナイトの起源マントルは未分化ソレアイトの起源マントルに比べ,高い含水量と浅い深度の内の 1つ,あるいは両方の特徴をもっていたと考えられる.
キーワード:小笠原前弧,母島,高Caボニナイト,マグマ混合,向島,小笠原諸島,未分化ソレアイト
5. K-Ar geochronology on the temporal change of eruptive style in the eastern Izu peninsula, central Japan
Ayako Ozawa, Takahiro Tagami and Masafumi Sudo
中部日本,伊豆半島東部における火山活動形態の変化時期のK-Ar年代学
最近のK-Ar年代測定により,伊豆半島東部における火山の活動形態が0.3-0.2 Maのあいだに複成火山から単成火山へと変化したことが明らかとなった.変化の時期をより精度よく決めることを目的として,最も若い複成火山である天城火山の遠笠山安山岩と,最も古い単成火山のひとつで,部分的に遠笠山安山岩を覆っている遠笠山火山からあわせて10試料を採取し,K-Ar年代測定を行った.測定の結果,遠笠山安山岩は少なくとも0.34 Maから0.20 Maまで噴出したのに対し,遠笠山火山は0.26-0.29 Maの間に噴火したことがわかった.これは,遠笠山安山岩の北部は遠笠山火山の噴火の後で噴出したことを示唆する.過去のデータとあわせると,伊豆半島東部における火山の活動形態の変化は0.29-0.20 Maの間におき,その間単成火山,複成火山両方の活動が重なっておきていたと考えられる.
キーワード:東伊豆,K-Ar年代測定,質量分別,単成火山,複成火山第四紀
Island Arc 日本語要旨 2004. vol. 13 Issue 2
The Island Arc Vol.13 Issue2 日本語要旨
1. The expulsion of geopressured hydrothermal system associated with the destructive earthquakes and buried active faults in the Shinanogawa seismic belt, Japan
Huilong Xu and Yasue Oki
信濃川地震帯における破壊的な地震に伴って圧力を受けた熱水システムの噴出と埋没した活断層
北部フォッサマグナの信濃川地震帯は,ユーラシアプレートとオホーツクプレートの境界の信濃川に沿って発達する.圧力を受けた熱水システムが,北部フォッサマグナに広域に発達する.多くの破壊地震がこのシステムに関連して発生する.このシステムは深い所から活断層に沿って上昇して地震を引き起こし,流体の通路を広げる.温度,電気伝導度,Cl-の濃集が,北東方向に直線的に分布して,破壊地震の震源域である信濃川地震帯を特徴づける埋没した活断層を示している.地下水の温度異常帯は地震のマグニチュードの分布と密接に関連している.これは地震断層の大きさを示している.圧力を受けた熱水システムに由来するこの直線的異常帯で,歴史的な破壊地震がない場合は,近い将来大きな地震が起こりそうであることを意味する.信濃川地震帯での活断層上に,4箇所の地震の起こりうる地域について,議論した.
キーワード:フォッサマグナ,信濃川地震帯,圧力を受けた熱水システム,水の化学,活断層,起こりうる地震の場所
2. Jurassic depositional records and sandstones provenances in Hefei basin,Central China : Implication for Dabie orogenesis
Zhong Li, Renwei Li, Shu Sun and Qingchen Wang
中国ヘフェイ盆地のジュラ紀における堆積記録と砂岩の供給地:ダビー造山運動に対する意義
南部ヘフェイ盆地のジュラ紀の砂岩の鉱物組成と主元素組成から,それらはダビー山地に由来することが分かった.それは大陸性島弧複合岩体に帰せられる.下部から中部ジュラ系では,リサイクルの造山帯または複合した起源から,上部ジュラ系の島弧性造山帯(Zhougongshan 層)へ変化している.ダビー造山帯では,ジュラ紀後期に侵食のため次第に削剥された島弧が露出した.それは,特にFenghuangtai期の後に顕著になった.さらに,島弧はもともと前期古生代からトリアス紀には,存在していたことが,すでに公表されている同位体年代データによって分かっている.ダビー地塊の色々な地層の大理石とFenghuangtai層の大理石礫からの炭素・酸素同位体比率から,それらの源岩はダビー山地からすべて盆地にもたらされたものであることが分かった.堆積盆地での著層の積み重なりからは,ジュラ紀には,引張りではなく圧縮場であったことも分かった.それらは,逆級化層を作り,北方へ沈み込む揚子江プレートに影響を受けた堆積物である.さらに,後期中生界における広域的上昇削剥過程に関しても議論した.
キーワード:中生界,砂岩の供給源,堆積層序,ダビー山地,ヘフェイ盆地.
3. Early exhumation of the collisional orogen and concurrent infill of foredeep basins in the Miocene Eurasian-Okhotsk Plate boundary, cental Hokkaido, Japan : inference from K-Ar dating of granitoid clasts
Gentaro Kawakami, Kazunori Arita, Toshinori Okada and Tetsumaru Itaya
北海道中央部の中新世ユーラシア−オホーツクプレート境界における衝突型造山帯の初期の削剥と,それに同期した前縁堆積盆の埋積:花こう岩礫のK-Ar年代値からの推定
北海道中央部の日高衝突帯西縁に形成された前縁堆積盆は,中部(〜上部)中新統のタービダイト堆積物により埋積されている.夕張山地に分布する川端層のモンゾ花こう岩礫8試料の黒雲母K-Ar年代は44.4〜45.4 Maで、花こう閃緑岩1試料の年代は42.8 Maである.花こう岩礫の主成分全岩化学組成によれば,全ての試料がSタイプの過アルミナ質花こう岩(アルミナ飽和度:1.12〜1.19)である.上記の年代学的・岩石学的特徴は,川端層花こう岩礫と日高帯北東部に分布する始新世花こう岩体,とくに欝(うっつ)岳岩体(43 Ma)や紋別岩体(42 Ma)との類縁関係を示す.前縁堆積盆は,厚化する衝上断層帯前面でのリソスフェアの押し曲げによる沈降域である.本論の結果は中期中新世のタービダイトの堆積が,日高帯における急激な西方への衝上運動とその削剥に同期しており,この初期の山脈形成が北海道中央部における第三紀の褶曲−衝上断層システムの衝上運動によるものであることを示唆する.
キーワード:黒雲母KミAr年代,花こう岩礫,中新統川端層,前縁堆積盆,日高帯,北海道
4. Major faults determine the location of the Tongonan Geothermal Field : evidence provided by rock alteration and stable isotope geochemistry
Graeme L. Scott
主要断層群の位置に形成されたTongonan地熱地帯
岩石変質と安定同位体地化学にもとづく根拠フィリッピンレイテのトノガン地熱地帯において,岩石変質と安定同位体地化学に基づく主要断層の影響を評価した.フィリッピンにおいては,鉄に富みカルシウムに乏しい酸性変質が特徴的に剪断帯に沿って生じている.後に生じたナトリウム交代作用は,上部Mahiao系の貯留層からもたらされたマグマ起源の塩水の分離により,10000mg/kgに達する高塩素濃度下のものである.低角度の剪断帯からマグマ起源水が導入された結果,天水の活発な対流が発生し,これは貯留槽層からSiとKを溶出した.同時に,高温下での酸素同位体交換が直ちに生じ,これは現在も剪断された低変質岩において小規模に引き続いている.これらの低変質剪断岩は年2cmのクリープにより地熱水を供給している.この地熱水は,300℃以下の低温の天水と混合する事によりδDはほぼ一定(-35‰±5‰)でδ18Oだけが6‰程度シフトする.δDの10‰程度の変動幅は,雨水による地下水涵養(5‰)と塩水の沸騰による濃集(5‰)で説明できる範囲である.湧水と岩石化学組成をもとに岩石水比を1500と仮定すると,毎秒50リットルの流量のもとでは 30立方kmの貯留層は,およそ300万年の地熱システムを構成してきたことになる.
キーワード:Tongonan, Leyte, 地熱,安定同位体,岩石変質地球化学,フィリッピン断層
5. Tectono-metamorphic Evolution of the Ogcheon Metamorphic Belt, South Korea : Tectonic Implications in East Asia
CHANG WHAN OH , SUNG WON KIM , IN-CHANG RYU , DEOK SU LEE ,
TOSHINORI OKADA , HIRONOBU HYODO AND TETUMARU ITAYA
南韓国オケヒョン変成帯の変成テクトニクス発達史:東アジアのテクトニクスに対する制約
オケヒョン変成帯(OMB)の発達史は,韓半島,中国,日本列島のテクトニクスを考察する上で重要な束縛条件を与える.OMBに産する砂質岩150試料について得られた化学的特徴に基づけば,堆積深度が北方へ向かって大きくなったことが示唆される.これらの結果と,酸化物鉱物の分布,炭素鉱物の総量を考慮すると,OBMの形成はハーフグラーベンで起こった可能性が高い.OBM全体として102-277Maを示す雲母に対するK-Ar年代は,142- 192Ma(ジュラ紀)の年代がほぼ全域から得られるのに対して,216-277Maの古い年代が変成帯中央部の中位層を構成する変成堆積物に,白亜紀の年代は白亜紀花崗岩の貫入を受けた地域にのみ特徴的に認められる.これらの年代と変形構造を考慮に入れると,OMB ではジュラ紀および白亜紀(102-192Ma)の花崗岩活動の熱的影響が強く認められる(少なくとも一部は角閃岩相の変成作用を受けている)ものの, 216-277Maの年代は,後退変成作用時の冷却年代を示していると考えられる.これらのことは,雲母に対するAr-Ar年代測定,ジルコンに対するU -Pb年代測定結果とも調和的である.
UMBの変成テクトニクス発達史は次のようにまとめることができる:(1)OBMの成り立ちは後期原生代のロディニア分裂に伴う大陸内リフトの形成で始まり,これは南シナブロックのフンナンオラコーゲンの延長と見なすことができる.(2)リフト内の堆積作用はオルドビス紀まで続いた.(3)南北シナブロックの衝突によって引き起こされた圧縮応力場のもとで,中圧中温変成作用が後期古生代に起こった.(4)前期〜中期ジュラ紀に起こった,イザナギプレートのアジア大陸に対する沈み込みによって花崗岩マグマの活動が起こり,低圧高温変成作用が起こった.
キーワード:Okcheon 変成帯、プレート内リフト、M1中圧中温変成作用、M2低圧高温広域熱変成作用、炭質物d002値(002は下付です)
Island Arc 日本語要旨 2004. vol. 13 Issue 1
The Island Arc Vol.13 Issue1 日本語要旨
1. Evolution of accretionary complex along the north arm of the Island of Sulawesi,Indonesia
Y. S. Djajadihardja , Asahiko Taira , Hidekazu Tokuyama , Kan Aoike, Christian' Reichert, Martin Block , Hans U. Schluter, Sonke Neben
北スラウェジ海溝付加プリズムの構造が反射地震記録によって明らかにされた.その記録によれば,付加プリズムは,1) 海溝域,2) ZoneA, 3) ZoneB, 4) ZoneCの4つの構造区に別けられる.ZoneAは活動的なインブリケーション構造を有し,デコルマ面が明瞭に発達している.ZoneBはアウト・オブ・シークエンス・スラストを有することで特徴づけられ,小規模なスロープ・ベーズンを伴う. ZoneCは前弧の構造的高まりであり,厚い堆積物に覆われている.また,海洋地殻上面の形状は,沈み込む前と,沈み込んだ後の両者ともに起伏が激しい特徴を有する.北スラウェジ海溝に沿った付加プリズムの発達は,中期中新世に活動したソロング断層に沿った,東スラウェジとバンガイ-スラ小大陸の衝突による影響が認められる.その理由は,この衝突により,スラウェジ島北アームの右回転を伴う大規模な北上が発生し,その結果,セレベス海盆プレートの南方へ沈み込みが起こり,北スラウェジ海溝付加プリズムが発達したためである.このため,北スラウェジ海溝付加プリズムは東に比べ,西で大規模に認められる.北スラウェジ海溝の収束速度は,西部で5km/ma,東部で1.5km/maと見積もられており,海溝東西での付加プリズムの発達程度の差異と調和的である.また,収束速度,付加プリズムの発達規模,さらに,周辺地域の地質学的情報を統合した結果,北スラウェジ海溝付加プリズムの形成は,約5Ma前から開始したと考えられる.この北スラウェジ海溝付加プリズム内部構造は南海トラフと極めて類似していることから,付加プリズム形成の構造発達史に両者の共通性が認められると考えられる.
2. Long-term changes in distribution and chemistry of middle Miocene to Quaternary volcanism in the Chokai-Kurikoma area across the Northeast Japan arc
Hirofumi Kondo, Kazuhiro Tanaka, Yukihiro Mizuochi and Atushi Ninomiya
東北日本弧を横断する鳥海−栗駒地域における中新世中期から第四紀に至る火山活動の分布と化学組成の長時間変化
背弧海盆(日本海)の拡大終了以降,概ね一定の沈み込みの条件が継続している東北日本を対象に,火山活動の時空分布特性とマントル内の高温領域の進化に係わる相互関係を明らかにすることを目的として,火山の集中域の1つである鳥海−栗駒地域において,既存文献による火山単元の分布と層序のコンパイル,放射年代測定,全岩化学分析を含めた詳細検討を実施した.日本海の拡大が停止した14Ma以降,火山活動は東西の枝状の領域に集中しており,マントルウェッジ内の高温領域は,島弧の伸長方向に火山活動を偏在化させる要因として継続的に存在していた.一方,14Ma以降の火山活動の時空間的変遷において,時間とともに活動が限られた領域(火山フロント側と背弧側のクラスター)に集中していく傾向が認められる.このような変化は,日本海の拡大停止以降のマントル内の冷却に伴う温度構造の進化プロセスに起因し,マントルダイアピルの上昇可能領域が縮小する傾向にあったことを示している.
3. Geochemistry of the oldest MORB and OIB in the Isua supracrustal belt (3.8Ga),southern West Greenland: implications for the composition and temperature of early Archean upper mantle
Tsuyoshi Komiya, Shigenori Mruyama, Takafumi Hirata, Hisayoshi Yurimot and Susumu Nohda
近年,地球の表層環境と固体地球変動の相互作用について研究が進んできた.固体地球変動を定量化するには地球の体積の80%を占めるマントルの経年変化が重要である.本研究では,太古代初期(38億年前)のイスア表成岩帯の中央海嶺と海洋島玄武岩起源の緑色岩の組成から当時のマントルの温度と組成を推定した.マグマ組成は造構場に強く依存する.本研究ではイスア表成岩帯が付加体起源であることを示したさきの研究に基づき,付加体地質学から玄武岩の造構場を初めて決定し,その親マントルの温度・組成を推定した.その結果,当時のマントルは,従来の推定より大幅に低温で,約1480℃であり,鉄含有量にも富むことがわかった.
4. The petrogenesis of orthopyroxene-and amphibole- bearing andesites, Mustique, Grenadine Islands, Lesser Antilles Arc: Isotope, trace element and physical constraints.
Terence Edward Smith, Matthew Thirlwall, Paul Eric Holm and Michael Jphn Harris
小アンチル弧マスティーク島に産する斜方輝石安山岩と角閃石安山岩の成因:同位体・微量元素組成および物理条件からの制約
小アンチル弧のマスティーク島には,漸新世のカンラン石単斜輝石玄武岩,複輝石安山岩,単斜輝石角閃石安山岩が,溶岩流および小規模な貫入岩として産する.これらの岩石は,Sr-Nd-O同位体比に関してほぼ均質であり,全てのマグマが,単一の起源物質(沈み込み成分に汚染されたマントルウェッジ)に由来すると考えて良い.しかしながらこれらの岩石について,液相濃集元素含有量,希土類元素パターンを比較すると,2つのグループに分けることができる.これらの微量元素組成の違いは,本質的には部分融解程度の差によって支配されている.また,斑晶鉱物の組成とその組み合わせを考慮すると,玄武岩質マグマの結晶作用は8kbより低圧で起こったことが予想され,最大で65%の結晶が初生マグマから分離したと考えられる.
5. Strain geometries in the Sanbagawa metamorphic belt inferred from deformation structures in metabasite
Ichiko Shimizu and Shizuo Yoshida
塩基性岩の変形から推定される三波川変成帯の歪形態
三波川変成帯では変成チャート中の放散虫化石の歪解析に基づいて,東西性の一軸伸長変形が支配的であると考えられてきた.しかし,中〜高変成度地域では放散虫化石の保存状態が悪いため,歪について限られた情報しか得られていない.本研究では塩基性岩の変形構造から推定される歪形態について報告する.四国中央部汗見川流域の枕状溶岩の形態は,一軸扁平型に近い変形を示す.一方,関東山地三波川帯の塩基性片岩に含まれる黄鉄鉱のプレッシャーシャドウは伸長型の歪を示した.北部秩父帯に属する低変成度地域では枕状溶岩の気泡の歪解析から扁平型の歪が得られた.これらの観察事実は,三波川変成帯の歪場が一様ではなかったことを示唆する.
キーワード:歪,変形,変成作用,三波川帯,秩父帯,枕状溶岩,プレッシャーシャドウ
6. Paleomagnetism of a pyroclastic flow deposit and its correlative widespread tephra in central Japan : possible tectonic rotation since the late Pleistocene
Yasuto Itoh and Haruo Kimura
中部日本の火砕流堆積物と広域テフラの古地磁気からみた後期更新世の回転運動
中部地方に分布する後期更新世の上宝火砕流堆積物とそれに対比されるKs22テフラは,安定な初生残留磁化を保持している.上宝火砕流堆積物の熱残留磁化が傾動補正後に大きく東偏した方位を示すのに対して,Ks22の堆積残留磁化の偏角は有意に小さい.このテフラを挟む浅海成堆積物からも同様に北向きの古地磁気方位が得られているので,両者の方位の違いは残留磁化獲得時期のずれに起因するものではなく,構造回転を表すものと考えられる.上宝火砕流堆積物の偏角値のばらつきは,後期更新世の右横ずれ断層活動により,中部地方で差動的回転が生じていることを示唆する.
7. Missing ophiolitic rocks along the Mae Yuam Fault as the Gondwana/Tethys divide in northwest Thailand
Ken-ichiro Hisada, Masaaki Sugiyama , Katsumi Ueno, Punya Charusiri and Shoji Arai
タイ王国は2つの大陸地塊,シブマスとインドシナから構成される.三畳系メー・サリアン層群は,北西タイにあるメー・ホンソン−メー・サリアン地域に分布し,主に砂岩・頁岩.礫岩,その他に層状石灰岩やチャートからなる.本層群の砂岩は砕屑性クロムスピネルを産出し,これら砕屑性クロムスピネルの供給源は,海洋底かんらん岩,クロミタイト,プレート内玄武岩である.現在本地域あるいは周辺地域には,上記の岩石の露出は知られていない.このような3種の岩石を主体としたオフィオリティックな岩石の露出は,縫合帯あるいは地帯境界を意味するものと思われるが,今回の砕屑性クロムスピネルの発見は,ゴンドワナ−テーチス境界が,メー・ユアン断層帯に沿っていたことを暗示する.
8. Similarities between strike-slip faults at different scales and simple age determining method for active faults
Young-Seog Kim and David J.Sanderson
水平ずれ活断層のスケールと時代間の相関について
いくつかのスケールの異なる水平ずれ活断層に関して,その幾何学的特徴,たとえば二次的破断や関連する構造(破壊ゾーンなど),断層のスタイルなどについて検討した結果,断層のスタイルはスケールに関係ないが,異なるテクトニックセッティングごとに異なるスタイルが生じていることが分かった.それらは,たとえば膨張や収縮ゾーンの連結や断層壁,つながり,先端などに関してや,主断層の発達場所や断層の発達史におけるステージに関してである.それぞれに自己相似性のあるGozo faultとSan Andreas faultの2つの活断層についてフラクタル次元を求めたところ,断層の破壊ゾーンの地表への表れは1.35,であるのに対して,主断層の地表への表れは 1.005と低く,これは二次的な破壊の複雑性によるものと考えられる.断層の発達史の統計的解析にもとづくと,代表的な地震断層の1回の変位に関する最大変位と破壊延長長さの比は約10-4と求められたが,この比は大規模な地震断層についてのデータにもとづくものでしかない(Gozo faultやSan Andreas faultなど).多くの地質時代の断層に関しては,累積変位と断層延長長さの比は約10-2〜10-1(Gozo約10-2,San Andreas fault約10-1)である.最も最近の累積変位量は破断の変位の累積であるから,地震断層の地震時の変位量,最大累積変位量,断層延長長さなどから,その断層の時代を求めることが可能である.推定される活断層の時代は,T = (dmax/u)・I(M)(ここでdmax: 最大累積変位量,u :地震時の変位量,I(M):再来周期)で求められる.
9. High-resolution shallow seismic and GPR investigations revealing the evoution of the Uemachi fault system,Osaka,Japan
Mohamed Rashed and Koichi Nakagawa
大阪の市街地を南北に縦断する上町断層は逆断層型活断層とされている.断層軸部の位置は以前の調査により概略が知られていた.ここでは上町断層にほぼ直交する大和川の河川敷を利用して,反射法地震探査と地中レーダによる地下構造探査を行った.断層軸部付近全体にわたって,逆断層に伴う撓曲の存在を確認できたが,浅層部では高角の正断層らしきものが認められたため,軸部付近を対象に,長さ百数十mの測線12本について地中レーダ探査を実施した.その結果,軸部の地表付近で,地塁を構成するような連続する正断層群の存在を確認した.この正断層の成因は,深部層の逆断層変位による被覆層の水平伸張変形に伴って形成されたと解釈された.
10. Petrochemical evidence for off-ridge magmatism in a back-arc setting from the Yakuno ophiolite,Japan
Yuji Ichiyama and Akira Ishiwatari
京都府夜久野地域のペルム紀夜久野オフィオライトは変火山岩,変斑れい岩,トロクトライトから構成される.変火山岩はT-MORBやE-MORBの特徴を示し,その産状や化学組成は夜久野オフィオライトが海台ではなく背弧海盆に由来することを示す.トロクトライトは変斑れい岩に貫入し,オフリッジのN- MORB火成作用で形成された後期貫入岩であると考えられる.トロクトライト中の粒間単斜輝石はTiO2量が変化に富み,不均質な粒間メルトから結晶化したと考えられる.E-MORBからN-MORBへの地球化学変化は,背弧海盆の進化に伴うマントルソース組成とマグマの生成深度の変化を反映している.
Island Arc 日本語要旨 2003. vol. 12 Issue 4
The Island Arc Vol.12 Issue4 日本語要旨
1. Mass movements caused by recent tectonic activity- the 1999 Chi-chi
earthquake in central Taiwan
Wen-Neng Wang, Huei-long Wu, Hiroyuki Nakamura, Shang-Chih Wu, Shoung
Ouyang and Ming-Fang Yu
最近のテクトニックな変動で生じたマスムーブメント:台湾中部での1999年周周地震での例
1999 年9月に台湾中部で起きた周周地震(Ms=7.7)は,甚大な被害をもたらした.その約2年後の2001年7月に,トラジ台風が650 mm/dayの大雨をもたらした.これらが引き金となって中部および一部東部台湾の広い範囲で地すべりが生じた.周周地震では約1000箇所で,またトラジ台風では約6000箇所で合計2400 m2の広さの地すべりが起きたことがSPOT データで判明した.その範囲は周周地震の最大加速度の地域とみごとに一致する.研究した地域は第三紀の堆積岩と変成度が分布し,固結度は東に向かって上がる.地すべりは,西をChelungpu断層に,東をLinshan断層によって境される地帯に主として分布し,その数はLinshan断層の東側では非常に少ない.それに反して,トラジ台風によって引き起こされた地すべりはその両方の地域に発生した.地震による地すべりは震央からの距離にほぼ比例するが,振動よりも岩石の種類により依存していることが分かった.
2. K-Ar ages of the Ohmine Granitic Rocks,Southwest Japan
Tomoaki Sumii and Hirono Shinjoe
大峯花こう岩類は,紀伊半島中軸部に分布する中新世花こう岩である.周辺に分布する中新世の主要な火成岩類の中では,大峯花こう岩類についてのみ詳細な年代が従来不明であった.本論文では,大峯花こう岩類の主要6岩体(洞川,白倉,川迫,旭,天狗山,白谷)について,それぞれ1から2地点の試料について黒雲母K-Ar年代を求めた.大部分は14.8 Maから14.6 Maの範囲に集中したが,地球化学・岩石学的には,それらは複数のマグマバッチによることが示唆される.また大峯花こう岩類も含め,紀伊半島に分布する大規模な中新世珪長質火成岩類(熊野酸性岩や室生溶結凝灰岩)が全て同時期の活動であることも分かった.
3. Early Miocene rotational process in the eastern part of southwest Japan
inferred form paleomagnetic studies
Yasuto Itoh and kazuyz Kitada
古地磁気学的研究からみた西南日本東部の前期中新世の回転過程
日本海拡大初期の火山砕屑岩と海進性堆積岩類が発達している金沢・医王山地域で、傾動補正を行った前期中新世の古地磁気方位をもとめ、西南日本東部の回転過程を考察した。段階熱消磁実験の結果、医王山層上部の8地点で安定初生磁化ベクトルが分離された。平均方位は偏角36.4°、伏角51.6°(α95=12.1°) である。従来の古地磁気および年代データをあわせると、背弧拡大に関連した西南日本の時計回り回転運動は、前期中新世に開始し、日本海沿岸の急速な沈降 (前期中新世末期)と共に加速したと考えられる。同じ時期の西南日本東部の古地磁気方位の比較から、背弧拡大後に島弧内部で相対回転が生じたことが示唆される
4.
5. In situ pressure-temperature conditions of a tectonic melange:
Constraints from fluid inclusion analysis of syn-melange veins
Y. Hashimoto, M. Enjoji, A.Sakaguchi and G. Kimura
紀州白亜系四万十帯において、メランジュ形成時の温度・圧力を鉱物脈に捕獲された流体包有物を用いて推定した。対象とした鉱物脈はメランジュブロックのネック部にのみ発達し、頁岩マトリックスに切られており、鉱物脈にマトリックスが注入している様子が観察される。推定された圧力範囲は81 (+15) MPa 〜 235 (±18) MPa 、また温度範囲は150 (±25)°C to 220 (±31)°Cであった。地震発生帯の温度規制モデルが正しいとすると、上記の温度圧力範囲は地震発生帯に入っているが、メランジュの変形機構は主に圧力溶解作用であるので、メランジュは地震間に形成されたことが考えられる
6. U-Pb zircon ages and Sr-Nd-Pb isotopic compositions for periman-Jurassic
plutons in the ogcheon belt and Ryeongnam massif,Korea: their tectonic
implications and correlation with the China Qinling - Dabie belt and the
Japan Hida belt
Cheong-Bin Kim, Ho-Wan Chang and Andrew Turek
韓半島に分布するOgcheon褶曲帯とRycongnam岩体を構成する先カンブリア紀の火成岩・堆積岩は,変成変形作を被り,二畳紀からジュラ紀にはマフィック〜フェルシックな深成火成岩の貫入を著しく受けている.本研究では,これらの深成火成岩に対する,7つのU-Pbジルコン年代とSr-Nd-Pb 同位体比組成を報告する.Ogcheou帯に分布する花崗岩類については,217±3.1 Ma, 206.4±3.6 Ma, 178.8±2.9 Ma, 173.0±1.7 Maの,Rycongnam岩体では252.2±2.9 Ma, 203.8±3.3 Ma, 177.8±2.4 Maの低コンコーディア年代を得た.一方これらの試料に対する高コンコーディア年代は先カンブリア紀を示し,Sr-Nd-Pb同位体比の特徴と併せて,これらのマグマは先カンブリア紀の基盤岩類の再溶融で形成されたことが示唆される.Ogcheon褶曲帯とRycongnam岩体では252-173Maにほぼ同時に深成火成岩の活動が起こったことが明らかになったが,それと共に,これらの地質帯の境界をなし,韓半島最大級の変形帯であるHonam剪断帯の活動しに対しても重要な束縛条件を与えてくれる.本地域の深成火成岩の活動時期は,南中国におけるQinling-Dabie超高圧変成帯の形成時期,日本列島における深成火成岩の活動時期とほぼ同一であり,これらの異なる地質現象の同時性は,アジア大陸東縁部における応力場の広域変化を示していると考えられる.
7. Insights into Operation of the "Subduction Factory" from the Oxygen
Isotopic Values of Southern Izu-Bonin-Mariana Arc
Emi Ito, R.J.Stern and C.Douthitt
酸素同位体による南部伊豆−小笠原−マリアナ弧におけるsubduction factoryの働き方についての考察
酸素は地球上で最も豊富な元素であり,島弧火山岩の酸素同位体分析は,沈み込んだ物質とマントル物質からの酸素の比率を敏感に示す可能性がある.本論文では南部伊豆−小笠原−マリアナ(IBM)弧の火山岩全岩,単斜輝石とガラス試料の合計225の酸素同位体分析結果を報告する.マリアナトラフのガラス及び mafic斑晶と平衡にある玄武岩質溶液は,どれも5.7‰に近い値が得られた.これらのデータは,IBM弧の本源マグマはほとんど完全にマントル酸素と平衡にあることを示している.もし沈み込んだ地殻物質の同化が地殻的元素増加の原因であるとすれば,沈み込んだ堆積物からの微量の溶液がマントルカンラン岩と混合し,その混合マントルの融解したものがIBM弧マグマとなったものと思われる.
8. Petrography, Diagenesis and Provenance of Eocene Tyee Basin Sandstones, Southern Oregon Coast Range : A New View from Sequence Stratigraphy
In-Chang Ryu
南部オレゴン海岸地域における始新タイエー砂岩の岩石記載,続成作用,
供給源:シークエンス層序学からの新しい視点
オレゴン州南部海岸地域の付加体および前弧堆積体である始新統タイエー堆積盆地の諸特徴の理解のために,砂岩岩石学をシークエンス層序学の枠組みでとらえることが重要である.主な粒子の詳しい量的比較によって,各堆積シークエンスごとに砂岩組成に差異があることが分かった.この差異は供給源が主として近隣のクラマス山地の変成岩から,より遠方のアイダホバソリスークラル火山弧への急激な変化によるものとして,理解できる.さらに,粒子の組成はロースタンドシステムズトラクトからハイスタンドシステムズトラクトへの系統的変化を示している.このことは,堆積盆地の海水面と供給源のテクトニクスが堆積パタンの砂岩組成を律することがあることを示している.それに加えて始新統タイエー堆積盆地の砂岩は下位へむかって自生鉱物が増加していることであり,それは埋没にともなって初期にゼオライト,後期に石英が,またスメクタイトからクロライト・スメクタイト混合層鉱物へと変化することを示す.この自生鉱物の下方への増加は埋没深度の増加に伴う鉱物組成の変化とも密接に関連している.
多くの最初期の間隙がこれら自生鉱物に満たされていくと,浸透率の低下によって,貯留岩としての特性を持つようになる.しかし,この貯留岩に必要な間隙率と浸透率は,現在は堆積盆地の一部に認められるにすぎない.これらの貯留岩としての能力はタイエー堆積盆地の複雑な続成作用によっており,砕屑粒子の時空的な変化,堆積パタン,そし埋没深度に直接的に関連しているのである.
9. The petrogenesis of the Ulsan carbonate rocks from the southeastern
Kyongsang Basin, South Korea
Kyounghee Yang, Jin-Yeon Hwang and Sung-Hyo Yun
韓国慶尚堆積盆地南東部のウルサン炭酸塩岩の成因
韓国の中生代の韓国慶尚堆積盆地のウルサン炭酸塩岩は,従来古生代の石灰岩と考えられていたが,本論ではそれを再検討する.この炭酸塩岩は一部に磁鉄鉱の鉱床を含み,それは所々で中生代の堆積岩,火山岩,花崗岩などに囲まれた超苦鉄岩を伴う.切った切られたの関係と露頭観察から,これらの炭酸塩岩は貫入岩であり,周辺の中生界よりも若いことが分かった.ウルサン炭酸塩岩は希土類元素や微量成分に乏しく,炭素と酸素の同位体比はδ13CPDB = 2.4-4.0‰,δ18OSMOW = 17.0-19.5‰ である.このような露頭からの証拠と地球化学的特徴は,ウルサン炭酸塩岩が地殻中の炭酸塩メルトから生じたことを示している.それはアルカリ岩質のAタイプ花崗岩の貫入を伴う地殻中の炭酸塩岩のメルト・流体混合物質に起源を持つことを示している.シリカに不飽和で強アルカリ質のマントル起源の典型的なカーボナタイトと比較すると,ウルサン炭酸塩岩は規模が小さく,シリカに飽和し,わずかにアルカリ岩質であることが特徴である.
東海(日本海)の拡大に伴うコールドロンの崩壊またはリフトシステムの形成のような深所に由来するテクトニックな断裂に沿って,このような地殻中の炭酸塩メルトが上昇しやすかったのかもしれない.
10. Multiple geneation of pseudotachylyte in the brittle to ductile regimes,
Qinling-Dabie Shan ultrahigh-pressure metamorphic complex,central Chine
Aiming Lin, Zhiming Sun and Zhenyu Yang
カタクレーサイトとマイロナイトに関連した二つのタイプのシュードタキライトが中国秦嶺―大別山衝突造山帯に発達した大河鎮剪断帯に存在する.マイロナイトに関連したシュードタキライト(M-Pt)は,マイロナイトのような塑性変形作用を受けており,カタクれーサイトに関連したシュードタキライト(C- Pt)により貫入されている.M-Ptに含まれている石英と長石のポーフィロクラストは塑性変形を受けているに対して,C-Ptに含まれている石英と長石のポーフィロクラストはこのような塑性変形を受けていない.M-Ptににられる動的再結晶により形成された石英と長石の細粒バンドはマイロナイトとM- Ptの面構造とほぼ平行しており,一部のポーフィロクラストに沿って発達している.M-Ptは,逆断層の衝上運動に関連した秦嶺―大別山超高圧変成帯の急激な上昇過程で,地震断層破壊が深部の塑性変形領域に伝播したことによって形成されたことが,本研究の結果により示された.M-Pt形成時の温度・圧力は,それぞれ450-600°Cと400-800MPaであると推定される.
同一断層帯にM-PtとC-Ptとが共存することは,逆断層の衝上運動に関連した秦嶺―大別山超高圧変成帯の急激な上昇過程において,繰り返しの地震断層すべりが脆性破壊領域だけではなく,塑性変形領域にも起きていることを示している.
Island Arc 日本語要旨 2003. vol. 12 Issue 3
The Island Arc Vol.12 Issue3 日本語要旨
1. Clarification of the regional and local in situ stresses using the CCBO technique and numerical analysis
SEONG-SEUNG KANG, JUN-NO KIM, KATSUHIKOKANEKO, KATSUHIKO SUGAWARA AND YUZO OBARA
CCBO(同心円オーバーコアリング)法を用いた広域および地域的現位置応力測定と数値解析
鳥形山の開削された採石場において,CCBO(同心円オーバーコアリング)法を用いて現位置応力測定を行った.さらにバックおよびフォワード解析法を用いて,それらと人工的に作られた斜面の安定性についての3次元有限要素法についても解析した.最大水平圧縮応力軸はNE-SW方向であり,バック解析では,地域的なものと広域的なものの方向はよい一致を示した.しかし,テクトニックな最大水平圧縮応力は現位置測定値よりも大きい値を示す.それは,テクトニック応力の推定に,重力の影響が考慮されておらず,それが,CCBOによる現位置応力では考慮されているためである.フォワード解析では,水平応力値は CCBO値とよい一致を示した.鉛直方向の応力は,深度とともに水平方向よりも急速に増大する.その結果,開削の比較的浅い部分で水平と鉛直応力との比が最大となり,この比は深度とともに小さくなる.つまり,鉱山開削により形成された人工的斜面の応力場は地域的な現位置応力の水平成分に依存することが分かった.
2. UHP metamorphic records hidden in zircons from amphibolites in Sulu terrane, eastern China
Fulai LIU, Zeming ZHANG, I.KATAYAMA,Zhiqin Xu and S.Maruyama
東部中国スルテレーンに産する角閃岩中のジルコンに記録された超高圧変成作用
東部中国スルテレーンに層状またはブロック状に産する角閃岩は,角閃石+斜長石+緑簾石±石英±黒雲母±イルメナイト±チタナイトの鉱物組み合わせを有している.また,同テレーンには,28kbar以上の高圧で形成されたエクロガイト相の岩石も分布している.今回,この角閃岩に含まれるジルコン中の包有物として,コーサイトを含む超高圧鉱物の組み合わせ(コーサイト,ザクロ石,オンファサイト,ルチル,アパタイト,フェンジャイト,マグネサイト)を,ラマン分光・電子線プローブ微小域分析によって確認した.これらの超高圧鉱物はジルコンの中央部に,一方石英などの低圧鉱物は周縁部に産する傾向がある.これらの超高圧鉱物の化学組成は,エクロガイト相岩石の基質部を構成する鉱物とほぼ同一の化学組成を有し,これらから推定される最高変成作用の温度圧力条件は,エクロガイト相岩石のそれらに匹敵する.これらの観察事実は,本地域の角閃岩は,超高圧エクロガイト相の岩石が,下降変成作用の過程で角閃岩相の変成作用を被ったことを示している.
3. Lithology and palynology of Neogene sediment on the narrow edge of the Kitakami Massif(basement rocks), northeast Japan: A significant change for depositional environments due to plate tectonics
Koji Yagishita, Akiko Obuse and Hiroshi Kurita
北部北上山地東縁(太平洋岸)には,上部白亜系Santonianとされる浅海性堆積層を主とする種市層がほぼ南北方向に狭く分布する。しかし,北端部では明瞭な基底礫岩層を有する河川堆積層が見られ,この堆積層は産出する微化石に基づいて第三系と考えられたがその詳細な年代は不明であった。岩相解析から網状河川の堆積場を示すこの堆積層からは,明らかに異地性(再堆積)であることを示すチップ状の泥炭層があり,始新世を指示する渦鞭毛藻化石群集が産出する。しかし同時に産出する花粉化石群集は後期漸新世〜中新世を示唆する。また泥炭層は径40cm以上の巨礫群をドレープ状に被い,さらに巨礫群には洪水に伴うarmored mud ballも含まれることが判った。これら誘導化石の産状および岩相から,該当する北上山地東縁は中新世の大陸より分離した,弧状列島上の急峻なる後背地をもつ網状河川系の堆積環境であった,との結論を得た。
4. Cenozoic deformation history of the Tan-Lu fault zone (north China) and dynamic implication
YUEQIAO ZHANG, WEI SHI AND SHUWEN DONG
北中国のタンルー断層帯の新生界変形史とそのダイナミックな解釈
北中国のリフト盆地に関連させて,白亜系と第三系の岩石中のスリップベクトルの野外での解析を行った結果,タンルー断層帯の新生界変形史は3つの主たるフェーズに区分された.すなわち,初期第三紀の正断層とNW-SE方向の水平引っ張り,中新世の正断層とNE-SW からNNE-SSW方向の水平引っ張り,および第四紀における右水平ずれとENE方向のトランスプレッションである.最初のものは,北中国におけるリフト盆地の形成に直接関与し,アジア大陸下への太平洋プレートの沈み込みのロールバック効果によるものである.二番目のものは,日本海の拡大に伴うものかもしれない.最後のものは,タンルー断層帯中央部付近に限られ,インド・ユーラシア衝突の後期の影響がこの遠隔地まで及んだものである.
5. Lithofacies and eruption ages of Late Cretaceous caldera volcanoes in the Himeji-Yamasaki district, SW Japan: Implicaton for ancient large-scale felsic arc volcanism.
Takahiro Yamamoto
西南日本内帯姫路―山崎地域に分布する後期白亜紀火山岩の層序と噴火年代を再検討し,異なる陥没カルデラを埋積した15の累層に区分し直した.その活動時期は82〜65Maにわたる.各累層が埋めるカルデラの直径は1〜20kmで,高角度の不整合面で囲われている.いずれの累層も基盤の角礫からなる岩屑なだれ堆積物をレンズ状に挟んだ,厚い火砕流堆積物からなる.後期白亜紀西南日本での単位面積あたりカルデラ形成マグマ噴出率は,ニュージーランドのタウポ火山地域などよりも1桁以上小さく,新生代後半の東北日本と同程度である.西南日本内帯の膨大な後期白亜紀火成岩も,生産性の低い珪長質マグマ活動の長期間の蓄積により形成されたものである.
6. Evolution of the Komiji Syncline in North Fossa Magna, central Japan
---Paleomagnetic and K-Ar age insights---
SACHIKO NIITSUMA, NOBUAKI NIITSUMA AND KOZOU SAITO
北部フォッサ・マグナ南西縁の褶曲構造の一つである込地向斜の軸部には鮮新統柵層が分布する.この研究では,柵層中の安山岩類の古地磁気とK-Ar年代測定を行った結果,込地向斜を形成した褶曲運動は,4.42±0.12Ma以降に始まり1.65 Maにはほぼ終了したことが明らかになった.古地磁気測定用の定方位試料は,浅海性堆積物中へ貫入する安山岩岩床で4地点と河川性堆積物中に狭在する安山岩溶岩の3地点から採取した.熱消磁と交番磁場消磁実験の結果,これらの試料からは安定した残留磁化が検出された.各地点の残留磁化方位は,堆積岩の走向傾斜を用いて傾動補正を行うと,D = 169.0°, I = -58.5°,α95 = 9.0°の逆帯磁方位によく集中し,褶曲テストに合格する.このことは込地向斜の形成前に,溶岩と岩床は定置したことを示している.また古地磁気測定を行った試料から新鮮な4試料を選び,石基を用いてK-Ar年代測定を行った.その結果,岩床から採取した3試料は,4.42±0.12,4.49± 0.12,4.69±0.12 Ma,溶岩から採取した1試料は5.91±0.26 Maを示し,Gilbert逆磁極期に対応する.これらの安山岩類を狭在する込地向斜は,1.65 Maの広域対比されているTZ100凝灰岩層を狭在する更新統の堆積物に不整合で覆われている.従って込地向斜の形成は,最も新しい岩床の年代である 4.42±0.12Ma以降の鮮新世に起き,更新世初めにはほぼ終了していたと考えられる.今回明らかになった込地向斜の形成時期は,南部フォッサ・マグナにおける丹沢ブロックの衝突以降であることから,フィリピン海プレートの北西進が北部フォッサ・マグナの変形に影響している可能性があることを示唆する.
Island Arc 日本語要旨 2003. vol. 12 Issue 2
The Island Arc Vol.12 Issue2 日本語要旨
特集号
Geologic and Tectonic Framework of East Asia Preface
S.Arai and Y.I. Lee
1. Collision, subduction, and accretion events in the Philippines: a synthesis
G. P. Yumul, Jr., C. B. Dimalanta, R. A. Tamayo, Jr. and R. C. Maury
フィリピンでは衝突および沈み込み帯複合岩体中に過去から現在までの様々なテクトニックな環境の重複が読み取れる.漸新世の古・東ルソントラフの沈み込み停止後に,中新世のルソンの反時計周りの回転によりマニラ海溝での沈み込みがバギオ地方で始まった.この回転はパラワン小大陸のフィリピン変動帯への衝突をももたらした.パラワン-中部フィリピン地域にはいくつかの衝突に関連した付加帯がある.マチ-プハダ地域は,ムルッカ海プレートの断片である沈み込み帯起源の上部白亜系プハダ・オフィオライトを基盤とする.これらの発達史の解明はフィリピン諸島のテクトニクスにとって重要であり,新たな解釈を試みる.
2. Early Cretaceous sinistral shearing and associated folding in the South Kitakami Belt, NE Japan
M. Sasaki
東北日本,南部北上帯南半部において,変形構造の詳細なマッピングと歪の半定量的な測定とから,前期白亜紀構造発達史を議論した.本地域の前期白亜紀構造発達史は以下のとおりである.1)高歪度の‘スレート’からなる南北〜北東トレンドの左横すべり剪断帯形成と,それに伴う波長 5〜10 km の褶曲の形成,2)上記褶曲を切る約 120 Ma 花崗岩類の貫入と,それらの花崗岩体の縁に沿い上記地質構造を改変する左横すべり高温マイロナイト帯の形成,3)上記構成要素の上昇後,後期アプチアン〜アルビアン宮古層群の堆積.また小論では南部北上帯南半部の前期白亜紀左横すべり剪断運動の変位・変形の復元モデルを示した.
3. Palustrine calcretes of the Cretaceous Gyeongsang Supergroup, Korea: variation and paleoenvironmental implications
I. S. Paik and H. J. Kim
韓国の白亜系ギョンサン堆積盆地の珪質湖沼成堆積物を5つの層(下位からジンジュ,ジンドン,ギョンチョンリ,フワンサン,ダデーポ)について岩相および土壌化の観点から調べ,湿地成カルクレート形成における地質学的影響を論じた.土壌性炭酸塩の発達の程度は,ダデーポ,ジンドン,ジンジュ,ギョンチョンリ,フワンサンの順に低くなる.ダデーポ層に最も発達するのは湖沼のサイズが最小であったからである.カルクレート生成は湖沼のサイズおよび気候の乾燥度に依存する.ギョンサン累層群中で上部から下部白亜系で湿地成カルクレートの発達度が高くなるのは乾燥度の上昇による.また様々な発達度は湖沼環境の時空的変化を示している.
4. The age of the pterosaur and web-footed bird tracks associated with dinosaur footprints from South Korea
C.-B. Kim, M. Huh, C.-S. Cheong, M. G. Lockley and H.-W. Chang
最近,鳥類,翼竜,恐竜などの歩行跡の化石が発見されている韓国の南西端の白亜系ウハングリ層の絶対年代を測定した.これらの複数種の跡の同一場所からの発見はアジア初であり,化石の産出頻度や量では他に類を見ない.周囲の凝灰岩の年代は,全岩Rb-Sr法では96.0Ma(安山岩質ラピリ凝灰岩), 81.0Ma(珪長質凝灰岩)および77.9Ma(フアンサン溶結凝灰岩)である.K-Ar年代は若めで,83.2〜68.8Maであった.歩行跡化石は,鳥類,翼竜では96〜81Maであり,恐竜では96〜78Maと推定される.これらの生物はセノマニアンからカンパニアンにかけて同一環境下で共存していたものと結論できる.
5. Dinosaur tracks from the Cretaceous of South Korea: distribution, occurrences and paleobiological significance
M. Huh, K. G Hwang, I. S. Paik and C. H. Chung
韓国の白亜系非海成堆積物からは多くの恐竜化石が産出する.中でも恐竜の歩行跡の化石は世界的に有名である.これまで27の恐竜歩行跡化石がギョンサン堆積盆地などの白亜系から発見されている.鳥脚類のものがもっとも多い.それらの多くは大形の足跡と広い蹄の印象を有するカリリクニウムと同定される.多くの獣脚類の歩行跡はニュウンジュ堆積盆地で発見されており,多種の小〜中形の鳥に似た足跡および他の大形の足跡よりなる.竜脚類の歩行跡はサイズ,形状,歩行パターンが変化し,多種類の竜脚類の存在を示す.これら韓国での多様な歩行跡化石は,白亜紀に朝鮮半島の南部に分布した湖沼周辺で多種の恐竜が繁栄していたことを示唆する.
6. Fusulinoidean faunal succession of a Paleo-Tethyan oceanic seamount in the Changning-Menglian Belt, West Yunnan, Southwest China: An overview
K. Ueno, Y. Wang and X. Wang
中国雲南省西部の昌寧−孟連帯に分布する古テチス海山型石灰岩からのフズリナ群集変遷を報告する。調査した魚塘寨セクションは最下部の玄武岩類とそれに重なる純粋な塊状炭酸塩岩からなり、層厚は約1100mに達する。その岩相的特徴は、例えば秋吉石灰岩のような日本の中・古生代付加体中に見られる海山起源炭酸塩岩のそれと酷似する。本研究では、前期石炭紀後期のSerpukhovianから中期ペルム紀後期のMidian(Capitanian)にいたる連続した17のフズリナ群集を識別した。魚塘寨セクションに見られる群集変遷は典型的な熱帯テチス型のそれと類似するが、属の多様性は南部中国やインドチャイナなどの古テチス海陸棚域のものよりも低い。また、前期石炭紀中頃においては、パンサラッサ海だけでなく古テチス海においてもホットスポットに関連した海底火成活動が活発であったようである。
7. Paleozoic sedimentation and tectonics in Korea: A review
Y.I. Lee and J.I. Lee
テーベックサンとピョンナム堆積盆の下部および上部古生界を解析した.下部古生界は主としてユースタティックな変動に支配された海成堆積物よりなる.その時期朝鮮半島は低緯度にありストームの影響をしばしば受けた.上部古生界は非海成の堆積物よりなる.堆積物の上方への組成変化は衝突帯の上昇と削剥があった事を示唆する.上下の古生界の間には不整合がある.この不整合に対応する朝鮮半島での出来事は不明である.朝鮮半島と中国大陸とのテクトニックな対比は議論がある.中国の衝突帯の東方延長はイムジンガン帯であるとされるが,最近の古生物学,堆積学,層位学的情報がうまく盛り込まれておらず,更なる吟味が必要である.
8. Geochemistry and tectonic implications of Proterozoic amphibolites in the northeastern part of the Yeongnam massif, South Korea
Y. Arakawa, K.H. Park, N.H. Kim, Y.S. Song and H. Amakawa
韓国の嶺南地塊北東部のHaenggongni角閃岩とOkbang 角閃岩は、原生代の変堆積岩類のWonnam 層群の中に岩脈状あるいは包有岩として産している。両角閃岩はソレアイトの特徴を示し、フラットな希土類元素パタ−ンと低いインコンパティブル元素含有量、および低いZr/Y, Ti/Y, La/Nb, Ta/Yb比を持っている。これらはE-MORBの特徴を示している。このことは、角閃岩の原岩が引張場のリフト帯で形成されたことを示唆している。嶺南地塊における以前の研究を考慮すると、角閃岩の原岩には3つのタイプ(E-MORB, WPB, VAB)が存在する。これらの特徴はプレ−ト内玄武岩(WPB)の特徴を示す角閃岩が卓越する京畿地塊や沃川帯とは明らかに異なっている。
9. Paleozoic ophiolites and blueschists in Japan and Russian Primorye in the tectonic framework of East Asia: a synthesis
A. Ishiwatari and T. Tsujimori
日本海を挟む日本とロシア沿海州には古生代前期・後期両方のオフィオライトが存在する.随伴する青色片岩のK-Ar年代は,西南日本では300Ma(蓮華)と200Ma(周防)だが沿海州では250Maであり,中国蘇魯大別衝突帯の超高圧変成岩や東アジアの主な中圧変成帯の岩石と同年代である.我々は蘇魯衝突帯の東方延長について「八重山突出部説」を提唱する.この衝突帯は朝鮮を迂回して黄海を南下し,八重山諸島石垣島の200Ma青色片岩として表れ,沈み込み帯に転化して西南日本とロシア沿海州に至る.この地域でのオフィオライト・青色片岩ペアと大規模な付加体との繰り返し形成は,マリアナ型(非付加型)・南海型(付加型)沈み込みの交互交代を示す.
10. Petrological feature of spinel lherzolite xenolith from Oki-Dogo Island: an implication for variety of the upper mantle peridotite beneath SW Japan
N. Abe, M. Takami and S. Arai
隠岐島後の捕獲岩としてレールゾライトは他の岩石よりまれである.レールゾライトは比較的枯渇度は低く(スピネルのCr#は0.26以下),完全に無水であり交代作用の形跡は見当たらない.基本的に溶け残り岩であるが,かんらん石が通常のものより鉄に富む(Fo86)場合がある.単斜輝石のコンドライト規格化希土類元素パターンはU字形である.溶け残りかんらん岩は,後の鉄に富む集積岩の形成により汚染され,鉄や軽希土類元素に富むようになった.同様の希土類元素パターンは集積岩が余り発達しない黒瀬のかんらん岩にも認められる.従って,交代作用時にかんらん岩は,鉄などよりもっと顕著に広範囲に軽希土類元素に富化した.
11. Metasomatized harzburgite xenoliths from Avacha volcano as fragments of mantle wedge of the Kamchatka arc: an implication for the metasomatic agent
S. Arai, S. Ishimaru and V.M. Okrugin
カムチャツカ弧南部のアバチャ火山に大量に産するかんらん岩捕獲岩について検討した.これらは島弧マグマに捕獲されているウェッジ・マントル物質である.初生的な岩相は枯渇したハルツバーガイトであり,かんらん石のFo値とスピネルのCr#はそれぞれ91〜92,0.5〜0.7である.かんらん石はスラブ起源のSiに富む流体によりしばしば二次的斜方輝石(Ca,Crに乏しい)に交代されている.交代されたハルツバーガイトでは斜方輝石の総量が40体積%にまで増加する.しばしばクラトン下に認められるハルツバーガイトはこの交代ハルツバーガイトに類似しており,マントル・ウェッジでのSiの付加により形成された可能性がある.
12. Silicic arc volcanism in Central Luzon, Philippines: Characterization of its space-time and geochemical relationship
G.P. Yumul, Jr., C.B. Dimalanta, R.A. Tamayo, Jr. and H. Bellong
中部ルソン島のシリシック火山岩には化学組成と時空分布にある関係がある.5Maの火山ではシリシックであり,5〜1Maでは玄武岩〜安山岩質,1Maより若い火山では玄武岩〜デイサイト質まで組成変化が大きい.マニラ海溝からの南シナ海の沈み込み角度の変化により,年代とともに噴出中心も前弧から背弧まで変化する.Ce/Yb比は前弧(20〜140)と背弧(20〜60)のシリシック岩で高く,中心弧(20)と背弧(20〜30)の玄武岩〜安山岩で低い.この島弧横断的な組成変化はスラブ,マントル,地殻物質の影響であるとともに,部分溶融,分化,マグマ混合およびマントル/メルト相互反応などの化学的過程がもたらした.
Island Arc 日本語要旨 2003. vol. 12 Issue 1
The Island Arc Vol.12 Issue1 日本語要旨
1. Quaternary reactivation of Tertiary faults in the southeastern KoreanPeninsula: Age constraint by optically stimulated luminescence dating.
Jin-Han Ree, Young-Joon Lee, Ed J. Rhodes, Youngdo Park,
Sung-Tack Kwon,Ueechan Chwae, Jeong-Soo Jeon, Bongjoo Lee
韓半島南東部には二つのグループの第四紀の断層が知られている.第1のグループはNEE走向の高角右水平ずれ断層であるが,第2のグループはNEE走向の低角逆断層である.後者は,既存の正断層が再活動したものである.第四紀の堆積物の光励起ルミネッセンス(OSL)年代測定法によると,それを切る逆断層が,3万2千年以降も活動したことを示す.これらの断層は,北東アジアにおける現在の地震活動を考慮すると,現在の応力場で再び動きうると考えられ,韓半島南東部は地震学的には安定であるという考えは再考すべきである.
2. Absence of Archean basement in the South Kunlun Block: Nd-Sr-O isotopic evidence from granitoids
Chao Yuan, Min Sun, Mei-Fu Zhou, Hui Zhou, Wenjiao Xiao, Jiliang Li
チベット高原の北西縁に位置するクンルン地域は,南北の2つのブロックに区分される.北ブロックはタリムクラトンの一部をなすことが知られているが,南ブロックについてはその地質学的特性や成因についてよく解っていない.本論文では,南クンルンブロックの主要構成岩石である花崗岩類(471〜214Ma)について,Sr-Nd-O同位体組成を決定し,これらの花崗岩類の形成にはマントル由来のマグマが重要な役割を果たしていたことが明らかになった.これらの試料について1.1-1.5GaのNdモデル年代が得られ,これは本ブロック中の変成岩類に対する年代とほぼ一致するが,北クンルンブロック中の基盤岩類のそれ(2.8Ga)とは有意に異なる.従って,南クンルンブロックには太古代地殻は存在しないと考えられる.そうであるならば,南北両ブロックは最初は同一のブロックであったものが後に分裂・再衝突したとする「マイクロコンティネントモデル」は成り立たないことになる.
3. Late Cenozoic Volcanic Activity in the Chugoku Area, Southwest Japan Arc:Activity during Back-arc Basin Opening and Re-Initiation of Subduction
Jun-Ichi Kimura, Tomoyuki Kunikiyo, Isaku Osaka, Takashi Nagao,
Seiki Yamauchi, Susumu Kakubuchi, Shomei Okada, Norie Fujibayashi,
Ryuhei Okada, Hisashi Murakami, Takashi Kusano, Koji Umeda,
Shintaro Hayashi, Tsuneari Ishimaru, Atushi Ninimiya and Atsushi Tanase
中国地方における後期新生代の火山活動史について,新たに得られた108のK-Ar年代と,既存の年代データをもとに議論する.およそ26Mysにわたる島弧の火成活動史は,日本海背弧盆の拡大と,フィリピン海プレートの沈み込み再生のテクトニックイベントを含んでいる.中国地域の火山活動は,日本海リフティングに伴っておよそ26Maに背弧域から始まり,20-12Maには前弧方向へと拡張しアルカリ玄武岩の活動が卓越した.この第三紀火山弧は4Maまで活動が続き,4-3Maの不活発期を境に,背弧側へと再び縮小を開始した.1.7Ma以降はアダカイト質デイサイトの活動が,火山フロント沿いに起こった.背弧域から拡張期の活動は,日本海形成に関与したマントルアセノスフェアの上昇に関連しており,第四紀以降の活動域の縮退とアダカイトの活動は,再生したフィリピン海プレートの沈み込みによるマントルの温度低下とスラブ融解に関連していると見られる.
4. Paleomagnetism of Pleistocene widespread tephra deposits and its implication for tectonic rotation in central Japan
Hiromi Iwaki and Akira Hayashida
広範囲に堆積した1枚のテフラは瞬間的な地球磁場方位を記録していることから,地磁気経年変化を考慮せずに地域間の磁化方位の比較に使える可能性がある.本論文では,近畿地方から房総半島にかけて分布する約1.8Maの広域テフラの恵比須峠-福田テフラに注目し,第四紀の中央日本における相対的な回転運動の有無を検討した.残留磁化方位を比較すると,大阪・京都,三重,新潟地域に分布する福田火山灰層の方位はほぼ等しく,偏角が約-170°であったのに対し,岐阜県高山地域の恵比須峠火砕堆積物の偏角は約-155°であった.このことから,高山地域と大阪・京都地域の間で,第四紀に有意な回転運動が起こっていたことが示唆される.
5. Fault-related folds and an imbricate thrust system on the northwestern margin of the northern Fossa Magna region central Japan
Yukinobu Okamura
北部フォッサマグナ北西部に位置する西頸城山地からその沖合の直江津沖堆積盆地に発達する褶曲構造を,断層関連褶曲の考え方を用いて解析し,深部構造モデルを提案した。それぞれの背斜構造の断面形態とgrowth strataの形状から,一連の褶曲群がfault-bend foldとfault-propagation foldとに区分され,全体として3枚のスラストシートからなると考えた.また,バランス断面法に基づいて,スラストは地下十数kmの上部地殻と下部地殻の境界付近まで達すると推定した。さらに,北部フォッサマグナの褶曲構造もいくつかのスラストシート上に形成されている可能性を指摘した。
Island Arc 日本語要旨 2007. vol. 16 Issue 3 (September)
Island Arc 日本語要旨 2007. vol. 16 Issue 3 (September)
特集号:
Geology and geophysics of the Philippine Sea and adjacent areas in the Pacific Ocean
小原泰彦, 徳山英一, Robert J. Stern
1. Variation of crustal thickness in the Philippine Sea deduced from three dimensional gravity modeling
Takemi Ishihara and Keita Koda
3次元重力モデルから得られたフィリピン海の地殻の厚さの変化
石原丈実, 神田慶太
フィリピン海中北部の地殻の厚さを重力データから求めた。広域的な重力変化の補正としては九州—パラオ海嶺の両側でリソスフェアの厚さに15kmの差があることのみ考慮した。地殻の厚さが6kmで一定という仮定の下にマントルブーゲー異常を計算し、地殻の厚さを3次元重力インバージョン法により求めた。四国海盆の南部と西端部では地殻が5 km程度と薄く、パレスベラ海盆の北西部と北東部では地殻が厚いという結果が得られた。この地殻の厚さの変化は四国・パレスベラ両海盆の海底拡大時のマグマ供給の変化によっており、一方後者は拡大速度の変化や過去の火山フロント近くでの活発な火成活動との関係がありそうだ。この結果では、九州—パラオ海嶺北部や大東海嶺域の海嶺部分で15kmを越す厚い地殻、西フィリピン海盆東北部や北大東海盆で5kmより薄い地殻の存在も示唆している。
Key words: crustal thickness, gravity, Kyushu-Palau Ridge, mantle Bouguer anomaly, Parece Vela Basin, Philippine Sea, Shikoku Basin, three-dimensional
modeling, West Philippine Basin.
2. Fault configuration produced by initial arc rifting in the Parece Vela Basin as deduced from seismic reflection data
Mikiya Yamashita, Tetsuro Tsuru, Narumi Takahashi,Kaoru Takizawa, Yoshiyuki Kaneda, Kantaro Fujioka,Keita Koda
反射法地震探査データから得られたパレスベラ海盆の初期リフティングに伴う断層分布
山下幹也, 鶴 哲郎, 高橋成実, 瀧澤 薫, 金田義行, 藤岡換太郎, 神田慶太
パレスベラ海盆は伊豆小笠原島弧と九州パラオ海嶺によって挟まれたフィリピン海プレートにおける背弧海盆の一つである.過去の背弧海盆の拡大やリフティングの痕跡を明らかにするためには詳細な地殻構造を明らかにすることが重要であるため,海洋研究開発機構および石油天然ガス・金属鉱物資源機構によって取得されたマルチチャンネル反射法地震探査データに対して重合前深度マイグレーション適用による高精度地殻構造イメージングを行った.得られた結果から500m以上の変位を持つ断層が見られ,伊豆小笠原側では火山活動に伴う堆積物によって一部を覆っているのが確認された.断層分布からパレスベラ海盆拡大時の初期リフティングは非対称であることが明らかになった.
Key words: back-arc basin, Izu-Ogasawara Arc, Kyushu-Palau Ridge, Parece Vela Basin, pre-stack depth migration.
3. Seismic study on oceanic core complexes in the Parece Vela backarc basin
Yasuhiko Ohara, Kyoko Okino and Junzo Kasahara
パレスベラ海盆の海洋コアコンプレックスの地震学的研究
小原泰彦, 沖野郷子, 笠原順三
本研究ではフィリピン海・パレスベラ海盆の海洋コアコンプレックスの地震学的構造を決定した。大西洋中央海嶺のアトランティスマシッフ海洋コアコンプレックスの統合国際深海掘削計画による掘削調査等の結果とも合わせ、本研究は海洋コアコンプレックスの内部構造の理解を大きく前進させるものである。パレスベラ海盆のカオス地形区を構成する海洋コアコンプレックスの一つで、マルチチャンネル反射法地震探査の時間マイグレーション記録上において、往復走時0.15秒に存在する連続性の良い、明瞭でスムーズな反射面が認められ、「D反射面」と名付けた。「D反射面」はアトランティスマシッフ海洋コアコンプレックスで報告されているものと類似している。一方、海底地震計を用いた広角地震波屈折法探査からカオス地形区の速度構造モデルを決定した。それによれば、カオス地形区の下では6 km/s以上という速いP波速度の領域が存在しており、カオス地形区の海洋コアコンプレックスの核は主にハンレイ岩質であると考えられる。本研究とアトランティスマシッフの最近の研究とを合わせ考察すると、「D反射面」は海洋コアコンプレックス一般に見られるものであり、それはハンレイ岩体中に生じたローカルな断裂帯に沿った変質フロントを現していると考えられる。カオス地形区では海洋コアコンプレックスを形成させるに至ったデタッチメント断層の活動が3回生じたと考えられる。最初と2回目のデタッチメント断層の活動では、表層の玄武岩層と深部のハンレイ岩質の核が露出したが、最後のデタッチメント断層の活動では、表層の玄武岩層のみが露出した。
Key words: Atlantis Massif, detachment, D-reflector, gabbroic core, multichannel seismic profiling, oceanic core complex, Parece Vela Basin, P-wave velocity structure.
4. Oceanic Crust and Moho of the Pacific Plate in the Eastern Ogasawara Plateau Region
Takeshi Tsuji, Yasuyuki Nakamura, Hidekazu Tokuyama, Millard F Coffin and Keita Koda
東部小笠原海台周辺の海洋地殻とモホ面
辻 健,中村恭之,徳山英一,Millard F Coffin,神田慶太
小笠原海台周辺の海洋地殻とモホ面の構造を解明するために、反射法地震探査データに対して瞬間位相を用いた速度解析を行い、海洋地殻内の音波速度構造を推定した。そして推定された速度構造を用いて深度断面図を作成した。海台の南側では、海洋地殻内の構造とモホ面を明瞭な反射面として同定でき、モホ面が海台に近づくにつれて深くなることが明らかとなった。一方、海台の北側では、海洋地殻とモホ面が音響的に不明瞭であり、海底は起伏に富んでいる。この海台北側の不連続的なモホ面は、火成活動に伴う起伏の激しい地質境界を表しているか、厚いモホ遷移帯を表していると考えられる。小笠原海台の北側に位置する鹿島断裂帯においても海洋地殻とモホ面の音響特性が変化しており、海台と断裂帯に囲まれた海域で火成活動が活発であることが示唆された。
Key words: magmatic activities, Moho, oceanic crust, Ogasawara Plateau, seismic attributes, seismic velocity.
5. Cenozoic stratigraphy and sedimentation history of the northern Philippine Sea based on multichannel seismic reflection data
Yu Higuchi, Yutaka Yanagimoto, Kazuyoshi Hoshi, Sadao Unou, Fumio Akiba, Kunishige Tonoike and Keita Koda
反射法地震探査記録に基づく北部フィリピン海盆の層序と堆積史
樋口 雄、柳本 裕、星 一良、宇納貞男、秋葉文雄、外池邦臣、神田慶太
平成10年度から実施された「大水深域における石油地質等の探査技術等基礎調査」の一環として、北部フィリピン海において収録された累計26,825.2kmに達するMCS反射法地震探査記録の解釈結果および既往の海洋掘削孔データの対比に基づき、これらの海域の層序区分および岩相区分を行った。この海域には始新統から鮮新・更新統に至る各層準相当層が分布することが明らかになった。その層厚は大半の海域で500m±であるが、奄美三角、小笠原舟状両海盆では2,000m以上に達している。
海嶺を構成する基盤岩と堆積層との間には、1.堆積層が基盤にオンラップする 2.両者が断層により接する 3.海嶺火山岩の一部と堆積層が指交関係を呈する、という三種の層位関係が認められ、これらの確認は基盤岩、堆積層それぞれの年代の検証、およびテクトニクスを知る上で大きな手がかりとなる。
各海盆ごとに堆積層の分布形態、層厚、基盤との層位関係は、それぞれ固有の特性を呈する。南および北大東海盆の間には始新統の岩相、層位関係に大きな差異が見られ、それぞれの起源を異にすると考えられる。また南大東海盆の一部では、当海域で最も古い下部始新統が大東海嶺などの一部と指交関係を呈し、同時期における局地的火山活動の存在を示唆している。
九州パラオ海嶺の西側各海盆の東縁部には主に漸新統からなる厚い堆積エプロンが発達し、同海嶺の活動を記録している。また古伊豆小笠原弧のリフティングにより拡大したとされる四国・パレセベラ海盆には主に中新統以新の半遠洋性堆積物を主体とする堆積物が北に向かって層厚を増す形で分布している。
小笠原弧周辺は小笠原舟状海盆に発達する古伊豆小笠原弧の活動の痕跡と考えられる厚い漸新統を除いては大量の鮮新世以降の火砕性堆積層が分布し、これらは現在に至る同弧の活発な火山活動から由来したものである。
各海域の層準別層厚分布を概観すると、大局的に堆積の中心は時代とともに西から東に向かって移動し、島弧活動、海盆拡大を繰り返したフィリピン海の島弧海溝系の形成プロセスを反映していると考えられる。
Key words: acoustic basement, Cenozoic, Daito Ridge and basin region, Philippine Sea, pre-stack depth migration, sediment distribution, sedimentation history, seismic stratigraphy, Shikoku Basin.
6. Carbonate deposits on submerged seamounts in the northwestern Pacific Ocean
Hideko Takayanagi, Yasufumi Iryu, Tsutomu Yamada, Motoyoshi Oda, Kazuyuki Yamamoto, Tokiyuki Sato, Shun Chiyonobu, Akira Nishimura, Tsutomu Nakazawa and Satoshi Shiokawa
北西太平洋の沈水海山上の炭酸塩堆積物
高柳栄子,井龍康文, 山田 努, 尾田太良, 山本和幸, 佐藤時幸,千代延 俊,西村 昭,中澤 努, 塩川 智
北西太平洋に分布する海山(6海域16海山19地点)で掘削されたコア試料の浅海性炭酸塩岩の岩相ならびに堆積年代を検討した.その結果,本海域の海山上の浅海性炭酸塩岩は,必ずしも温暖期のみではなく,寒冷期にも多く堆積していることが明らかとなった.また,浅海性炭酸塩岩とそれらの基盤岩の年代には,大きな差異がないことが明確になった.以上の結果は,本海域の海山上の浅海性炭酸塩岩の形成・発達は,汎世界的な気候変動よりも,地域的な造構運動・火成活動に強く規制されていることを示している.また,浅海性炭酸塩岩を構成する生物の組成には時代変遷が認められ,その変遷は,従来の研究で指摘されてきたように,海水成分の変化を反映しているものと類推される.
Key words: Cenozoic, Late Cretaceous, limestone, northwestern Pacific Ocean, seamount, shallow-water carbonate.
7. Growth History and Formation Environments of Ferromanganese Deposits on the Philippine Sea Plate, Northwest Pacific Ocean
Akira Usui, Ian J. Graham, Robert, G. Ditchburn, Albert Zondervan, Hiroshi Shibasaki, and Hajime Hishida
北西太平洋フィリピン海プレート域の産する鉄・マンガン酸化物の形成史と形成環境
臼井朗, Ian J. Graham, Robert, G. Ditchburn, Albert Zondervan, 柴崎洋志, 菱田元
北西太平洋はプレート収束域に位置する活発な変動帯である。ここには堆積起源の鉄・マンガン酸化物が予想外に広く且つ広い水深帯に分布するらしい。地質環境の異なる6地域のマンガンクラストについてベリリウム同位体分析を行ってmmスケールの成長年代を測定した結果、古いものは1500万年(中期中新世)にさかのぼりそれらの平均成長速度は4〜7mm/百万年である。成長過程で基盤の崩壊・変形などによる局地的な速度変化・中断があるものの、全海域で現在もマンガンクラストの連続成長が続いている。これらは海洋環境を記録する堆積岩と見なせると同時に、資源評価の上からはクラスト・団塊の広範な分布が期待できる。
Key words: 10Be/ 9Be dating, ferromanganese crusts, growth rates, hydrogenetic, mineral resources, Philippine Sea Plate.
Island Arc 日本語要旨 2007. vol. 16 Issue 4 (December)
Island Arc 日本語要旨 2007. vol. 16 Issue 4 (December)
1. (Pictorial)
Large-scale chaotically mixed sedimentary body within the Late Pliocene to Pleistocene Chikura Group, Central Japan
Yuzuru Yamamoto,Yujiro Ogawa, Takayuki Uchino, Satoru Muraoka and Tae Chiba
千倉層群(鮮新統上部ー更新統)に見られる大規模乱堆積物
山本由弦, 小川勇二郎, 内野隆之, 村岡 諭, 千葉 妙
2.Plate-Plume-accretion tectonics in Proterozoic terrain of northeastern Rajasthan, India: evidences from mafic volcanic rocks of North Delhi Fold Belt.
Mahshar Raza, Mohd Shamim Khan and Mohd Safdare Azam
インド,北東ラジャスタンの原生代テレーンにおけるプレート-プルーム-付加テクトニクス:北デリー褶曲帯の苦鉄質火山岩からの証拠
インド楯状地北西部のAravalli山脈の北部は,北デリー褶曲帯を構成するお およそ3つの原生代の火山-堆積区すなわちBayana,Alwar,Khetri盆地からなる.これら3盆地の苦鉄質火山岩の主要元素,微量元素及び希土類元素は顕著なばらつきを示す.BayanaとAlwar火山岩は典型的ソレアイトで低Tiの大陸洪水玄武岩(CFB)と類似するが,前者は富化,後者は平坦な不適合希元素・希土類パターンを示すという相違がある.Khetri火山岩はソレアイトとカルクアルカリ玄武岩の漸移的組成を示す.BayanaとAlwarソレアイトのメルトは,おそらくマントルプルームの存在下でスピネルの安定領域において共通の起源物質の部分溶融により生じた.地表への上昇の間にBayanaソレアイトは地殻との混合を被ったがAlwarソレアイトは影響されずに噴出した.地球化学的にはKhetri火山岩は原生代の沈み込み帯の上側のマントルで生成した島弧的玄武岩である.約1,800Maに北東ラジャスタンの大陸リソスフェアは上昇するプルームにより引き延ばされ薄化し断裂された.そして生じたリフトは種々の程度の地殻の伸張を被った.地殻の伸張と薄化は,種々の程度に溶融してソレアイトメルトを生成したアセノスフェアの浅化を促進し,リフト盆地毎に異なる地殻の厚さに応じて異なる程度のリソスフェアの混合を生じた.Khetri帯の沈み込みに伴う玄武岩の存在は,クラトン西縁の盆地が成熟した海洋盆地へと発展したことを示す.
Key words : Aravalli, geochemistry, Indian shield, plume-tectonics, Proterozoic volcanism, Rajasthan
3. Pseudosection analysis for talc-Na pyroxene-bearing piemontite-quartz schist in the Sanbagawa belt, Japan
Taro Ubukawa, Akiko Hatanaka,Keisaku Matsumoto and Takao Hirajima
三波川変成帯のタルクーアルカリ輝石組み合わせを持つ紅簾石石英片岩に対するシュードセクション解析
鵜生川太郎, 畑中晶子, 松本啓作, 平島崇男
三波川変成帯四国高越地域の紅簾石石英片岩中にタルクの多様な出現様式を確認した.タルクは(A)基質に発達するもの,(B)プルアパート部に発達するものに分けられる.Aタイプのタルクは,エクロジャイトユニットではアルカリ輝石や藍閃石,ザクロ石帯ではアルバイトや緑泥石と共に片理を構成する.Bタイプのタルクはアルカリ角閃石のマイクロブーディン構造プルアパート部にアルバイト・緑泥石とともに発達する.NCKFe3+MASH系における岩石成因論的グリッド,シュードセクション法を用い,観察された鉱物の組成や組み合わせから岩石が経験した変成温度圧力を解析した.その結果,タルクーアルカリ輝石—フェンジャイト組み合わせは約560-580℃,18-20kbarで安定であり,プルアパート部に発達するタルクは約565-580℃,9.5-10.5kbarでアルカリ角閃石消費反応により形成されたことがわかった.エクロジャイトユニットの紅簾石石英片岩は地下約50-60kmで高圧変成作用を受けたのち,ほぼ等温状態で地下30kmの深さまで上昇したと考えられる.
Key words: eclogite facies, Kotsu area, piemontite-quartz schist, pseudosection, Sanbagawa
Belt, talc-phengite-aegirineaugite assemblage.
4. Eclogites from the Chinese continental scientific drilling borehole, their petrology and different P-T evolutions
Yong-Feng Zhu, H.-J. Massonne and T. Theye
中国大陸科学掘削孔から得られたエクロジャイト:それらの岩石学と様々な温度圧力経路
中国東部の蘇魯超高圧変成帯における中国大陸科学掘削(CCSD)孔の異なる深度から採集された4つのフェンジャイト含有エクロジャイトについて,電子線マイクロプローブを用いて研究した.ざくろ石とオンファス輝石の組成累帯構造は中程度であるが,フェンジャイトの組成は一般に1つの標本中でも変化に富み,コアからリムへSi量が減少する.これらの鉱物の化学組成変化に基づき,いろいろな地質温度圧力計を応用して温度圧力条件を絞り込んだ.標本B218の温度圧力経路は3.0 GPa(約600℃)から1.3 GPa(約550℃)への減圧で特徴づけられる.B310のエクロジャイトは3.0 GPa,750℃の条件を示す.B1008のエクロジャイトは650℃,3.6-3.9 GPaの条件(ステージI)から出発し,2.8-3.0 GPaまで減圧されて温度が750-810℃へ上昇した(ステージIIとIIIa).その後この岩石は高圧(2.5-2.7GPa)を保ったまま620-660℃まで冷却された(ステージIIIb).後退変成作用の条件は大体670℃,1.3 GPaである(ステージIV).B1039のエクロジャイトは約600℃,3.3-3.9 GPaの条件(ステージI)から出発し,3.0 GPa, 590-610℃への減圧(ステージII),そして630℃への中程度の等圧温度上昇(ステージIII)という温度圧力経路を示す.ステージIVは650℃,1.3 GPaの条件で特徴づけられ,このステージの最中あるいは後に(水に富み)部分的にカリウムに富む流体が岩石中に浸透し若干の変化を引き起こした.この流体の比較的高い酸素フガシティーにより,新しく形成された鉱物にはアンドラダイトと磁鉄鉱が含まれる.我々は以上の発見が「沈み込み流路」を通じた物質の流れによって最もよく説明できると考える.以上から我々はCCSD地点におけるエクロジャイト,石英長石質岩,及びかんらん岩などの超高圧変成岩の組合せが,超高圧条件下で始めから一体となっていた1つの地殻の断片を代表しているという,従来から広く信じられている考えは不可能であると結論する.これらの超高圧岩石が一体となったのは上昇過程のかなり後期である.
Key words: CCSD, eclogite, kyanite, phengite, subduction channel, Su-Lu UHP terrane
5. Protolith natures and U-Pb SHRIMP zircon ages of the metabasites in Hainan Island: implications for the geodynamic evolution of South China since late Precambrian
De-Ru Xu, Bin Xia, Peng-Chun Li, Guang-Hao Chen, Ci Ma AND Yu-Quan Zhang
中国南部海南島の変苦鉄質岩の原岩特性とSHRIMPジルコン年代:先カンブリア時代後期以降の変動
中国南部海南島の古生代火山砕屑性堆積岩に含まれる変苦鉄質岩の原岩特性と,SHRIMPおよびCLを用いたジルコン年代の解析を行った.島の東〜中部のTunchang地域はハンレイ岩質岩,ハンレイ岩〜輝緑岩質岩および枕状溶岩を原岩とする変苦鉄質岩が産出し,これらは化学組成から海洋性島弧での火成作用起源である.ジルコン年代は442-514 Maの火成活動年代,2488 Maのinherited年代,1450 Maの火成活動年代の3つの異なるステージを示す.一方北西部のBangxi地域はゲンブ岩質,ハンレイ岩質,ピクライト質岩を起源とする背弧海盆的な特徴を示す変苦鉄質岩からなり,269 Maの火成活動年代を示す.以上の結果から,Tunchang地域の原岩結晶化年代は約450 Ma以前であり,数多くのinherited年代が得られたことから,この岩石の原岩は大陸地殻近傍で組成的にNMORBに類似したマントルに由来するであろう.一方Bangxi地域の原岩形成年代は約270 Maであるが,これは大陸地殻上の背弧海盆の拡大とその後の小規模な海盆の形成年代を記録していると考えられる.約450 Maの年代を示すオフィオライト的な岩石が海南島だけでなく揚子地塊からも確認されていることから,南中国地塊におけるカレドニア造山運動は大陸内の活動ではなく,海洋物質の関与があったものと考えられる.ここでは海南島がカンブリア紀までカタイシア地塊の一部であったとして,先カンブリア時代後期以降の南中国地塊の変動モデルを提唱する.このモデルで強調していることは,Nanhuaトラフあるいは揚子地塊とカタイシア地塊の間にあった古南中国海(Paleo-South China ocean)の残骸のさらなる拡大がオルドビス紀中期〜後期の海洋性島弧を形成したこと,そして後者の沈み込みがほぼ同時期の低速での海洋底拡大を伴うであろうことである.その後,石炭紀前期〜ペルム紀前期における古テチス海の沈み込みにより,小規模な海盆が南中国地塊の南端に形成されたと考えられる.
Key words: Gondwana, Hainan Island, intraoceanic subduction, metabasite, Paleo-Tethys,SHRIMP U-Pb dating on zircon, South China.
6. CHIME monazite ages of metasediments from the Altai orogen in northwestern China: Devonian and Permian ages of metamorphism and their significance
Changqing Zheng, Takenori Kato, Masaki Enami and Xuechun Xu
中国北西部アルタイ地域の変成岩中のCHIMEモナザイト年代:デボン紀及びペルム紀の年代とその意義
鄭 常青, 加藤丈典, 榎並正樹, 徐 学純
中国北西部のアルタイ地域に産する緑色片岩相─角閃岩相の変成岩中のモナザイトCHIME年代を測定した.モナザイトCHIME年代より,本地域はペルム紀(261-268Ma)の中・西部とデボン紀(377-382Ma)の東部の2つのユニットに分けられることが明らかになった.デボン紀のCHIME年代は,これまでに報告された東部ユニットの花崗岩類の鉛-鉛同位体年代と一致し,花崗岩類の定置はsyntectonicであると考えられていることと調和的である.中・西部ユニットのペルム紀のCHIME年代とこれまで報告されている火成岩の年代から,地殻物質と海洋プレートの沈み込と急速な上昇又は削剥が示唆される
Key words: Altai orogen, Central Asian Orogenic Belt, CHIME dating, medium pressure–temperature, metamorphism, monazite.
ニュース誌・ホームページ・geo-Flash(メールマガジン)投稿ガイド
ニュース誌・ホームページ・geo-Flash(メールマガジン)投稿ガイド
ニュース誌・ホームページ・geo-Flashでは下記の投稿をお待ちしております.情報発信のプラットフォームとしてご活用下さい.
ニュース誌
全会員に毎月郵送で配布されます。掲載希望の方は、、
■ 記事
■ 表紙写真
1.投稿写真は,原則として未発表のものとする.
2.投稿写真は,プリントまたはデジタルファイル(ファイル形式:jpg , pct等)で,A4またはA3サイズに拡大したときに十分解像度があるものであること.
3.投稿写真の著作権については,地質学会に譲渡する.なお,依頼掲載写真についてはこの限りではない.
4.投稿写真全体の,日本語(20字以内)および英文のタイトルと日本語解説を付ける.
5.投稿写真が複数の場合には,それぞれに日本語(20字以内)および英文のタイトルを付ける.
6.投稿写真には,所定の様式の地質学会ニュース誌表紙写真投稿整理カードを添え,タイトルおよび解説の原稿は可能な限り電子媒体で提出することとする.
7.投稿写真は審査の上,地質学会ニュース誌表紙への掲載を決定する.
geo-Flash(メールマガジン)
geo-Flash(ジオフラッシュ)は,地質学に関わる,あるいは学界活動に関する情報をいち早く会員の皆様にお届けすることを目的としています.メールアドレスを登録してある会員に,毎月2回(第一・第三火曜日)定期配信されます.緊急のニュースがある場合は臨時号を出します.メールマガジンには記事の概略が掲載され,全文はホームページに掲載されますので長文や図版・写真も大いに歓迎します.会員の皆様からの情報も積極的に載せていく予定ですので、大いにご活用いただきますようお願い申し上げます.
■ お知らせ
地質学会会員もしくは執筆を依頼された方は投稿することができます.メールマガジンを通じて会員に広報したい内容がありましたら,お知らせください.メールマガジンでの広報が適切と判断したものを発信していく予定です.支部例会,専門部会のお知らせなど,全会員向けでないものでも受け付けます.
■ いろいろコラム
ご自身の専門分野のことや、研究・教育環境、技術環境、フィールドで怖い思いをしたこと、最近感じたこと、地質学会のホームページにてアピールしたいこと、他会員に役立つと思われることなど自由に書いて下さい.図・写真は大いに歓迎します.原稿長さは特に定めませんが節度ある範囲とします.
■ 地質マンガ原作
地質学のおもしろさや魅力を広く伝えるための四コママンガです。下書きを送って頂ければ、イラストレーターのKeyさんに清書を依頼します.ただしボランティアで描いて下さってますので掲載まで時間が掛かる場合がありますがご了承下さい.
■ 天然記念物めぐり
■ 海外便り
投稿する原稿、図版、動画等のデジタル原稿(データ)は、下記のフォーマットのものが受け付けられます.
文書: MS Word, Text, PDF, RTF, XML
図、表、写真: PDF, EPS, Adobe Illustrator, MS Excel, JPEG, TIFF, PNG, GIF, Adobe PhotoShop
動画: WMV, AVI, Flash, QuickTime, MPEG2, MPEG4, H.264, DivX
ホームページ
日本地質学会の公式ホームページ(www.geosociety.jp)は,年間5万人以上の閲覧がある国内有数の地質情報サイトです.掲載記事は長期間アーカイブされますので,何年経っても閲覧され続けます。
■ 地球なんでもQ&A
これは地球科学に関する想定問答集であり、読者からの質問に直接答えるものではありません.コーナーのトップには「これは地質学会としての統一見解ではなく、読者の理解の一助としてインターネット委員会が整備したものです」と明記され,それぞれの記事に解説者の名前と所属がつきます.希望があれば解説者本人や所属機関のホームページへのリンクを貼ることができます.中学理科以上の知識を有し、地球や地質に関心のあるインターネット読者が対象です.一般的な地球や地質に関する疑問や関心に応え,専門的になりすぎないようにして下さい.
原稿長さ:400字程度
図・写真:オリジナルの写真および図版をお願いします.ラフスケッチやからボランティアイラストレーターに清書を依頼できますのでお知らせ下さい.
投稿記事は他の設問とのバランスも考慮されて校閲されます.また引用は適切に行ってください.
■ 博物館の地学関連行事
■ ヘッダーの写真とトップページのキャッチコピー
全ページのヘッダー背景写真、およびトップページのキャッチコピーは、リロードするたびにランダムに表示されます。ヘッダーの背景写真は900x110 pix以上の画像ファイル,キャッチコピーは550x170 pix以上の画像ファイルをお送り下さい,なおキャッチコピーの文字はこちらで埋め込むこともできます.
投稿する原稿、図版、動画等のデジタル原稿(データ)は、下記のフォーマットのものが受け付けられます.
文書: MS Word, Text, PDF, RTF, XML
図、表、写真: PDF, EPS, Adobe Illustrator, MS Excel, JPEG, TIFF, PNG, GIF, Adobe PhotoShop
動画: WMV, AVI, Flash, QuickTime, MPEG2, MPEG4, H.264, DivX
Island Arc 日本語要旨 2008. vol. 17 Issue 1 (March)
Island Arc 日本語要旨 2008. vol. 17 Issue 1 (March)
1. (Pictorial)
Textural varieties in the Indochinese metamorphic rocks: A key for understanding Asian tectonics
Nobuhiko Nakano, Yasuhito Osanai and Masaaki Owada,
インドシナ地域に認められる変成岩組織の多様性:アジア大陸形成テクトニクス解明への鍵
中野伸彦, 小山内康人, 大和田正明
2.Geology, ore deposits, and hydrothermal venting in Bahía Concepción, Baja California Sur, Mexico
Antoni Camprubí, Carles Canet, Augusto A. Rodríguez-Díaz, Rosa M. Prol-Ledesma, David Blanco-Florido, Ruth E. Villanueva and Abigail López-Sánchez
メキシコBaja California Sur州Concepción湾周辺の地質,鉱床および熱水噴出孔
Concepción湾はバジャカリフォルニア半島の東岸に位置し,12〜6Maのリフト活動にともなって形成された北西—南東方向の正断層に沿って分布する. 主に島弧由来の漸新世〜 中新世のComondú層群が露出しており,これは当地域のカルクアルカリ火
山岩や火山砕屑岩シーケンスの主要部分を構成している.また,鮮新世〜第四紀の堆積岩,溶岩流,ドームや火山砕屑物も少量みられる.この地域の新第三紀火山活動は大陸の伸張とその後の海盆の拡大の影響により,島弧型からプレート内部型へと変化している.本地域には多くのMn鉱床がみられるが,これらは脈状,角礫状,あるいはstockworkとして産出し, Mn酸化物( pyrolisite ,coronadite,romanechite),ドロマイト,石英,バライトからなる.この鉱床はComondú層群の火山岩および局所的に鮮新世の堆積岩に胚胎されることから,中新世中期から鮮新世にかけて形成されたと考えられる.この鉱化帯は上述の正断層系に沿って形成されており.これはEl Boleo地域のCu-Co-Zn-Mn鉱床の特徴と類似している.湾周辺の陸上や海底には多数の温泉が存在するが,これらもまた同様の断層系の存在と密接に関連している.湾の南側での陸上および海底における高い地温は,最近の火山活動によるものであると考えられ,湾内においても潮間帯の温泉や浅海での熱水噴出により高い地温が確認されている.海底の噴出孔(深さ5〜15m,87℃)の周辺では,オキシ水酸化鉄の周囲に沈積した黄鉄鉱と辰砂が確認されている.一方,潮間帯の噴出孔(62℃)では,オパール,方解石,バライトおよびBaに富むMn酸化物が集合体を形成しており,その
表面はケイ酸塩—炭酸塩ストロマトライト様の温泉華によって覆われている.付近には,玉髄,方解石,バライトによって形成された,厚さ約10〜30cmの殻皮状形の脈もみられる.熱水の同位体組成を測定したところ,天水の高いd18O値と噴出口周辺の海水の値との混合値が得られた.以上の結果から,現在の噴出孔周辺にみられるBaに富むMn酸化物の沈積は,中新世〜鮮新世に形成された熱水性Mn鉱床の形成過程を示していると考えられる.
Key words : crustal extension, Gulf of California, Manganese, shallow submarine vents,volcanism.
3.Geochemistry, K-Ar geochronology and Sr-Nd-Pb isotope compositions of pitchstone in Gohado, southwestern Okcheon Belt, South Korea
Cheong-Bin Kim, V.J. Rajesh and M. Santosh
韓国沃川帯南部,ゴハドのピッチストーンの地球化学,K-Ar年代およびSr-Nd-Pb同位体組成
韓国沃川帯南西部のゴハド地域(訳者注:木浦(モッポ)近郊の島)の白亜紀後期の火山礫凝灰岩と流紋岩中に貫入した岩株として産する塊状のピッチストーン(火山ガラス,松脂岩)の地球化学,Sr-Nd-Pb同位体の特徴,そしてK-Ar年代を報告する.このピッチストーンは非常に分化していて,SiO2は72 〜 73w t % であり,K2O/Na2O比は1.04〜1.23で,MgO/FeOt比が低い(0.17-0.20).このピッチストーンはややアルミナの過剰があり,ASI値(Al2O3/(Na2O+K2O+CaO)モル比)は1.1よりもかなり低い.またこのピッチストーンは一般的なカルクアルカリ岩の特徴を示しアルカリ含有量が多い.希土類(REE)組成は中程度に分化した性質を示し,(La/Yb)N比は11〜16である.コンドライトで規格化したREEパターンは重希土に対して軽希土の濃集を示し,中程度のEu異常を示す(Eu/Eu*は0.53〜0.57の間で変化).始原マントルで規格化した微量元素図においては顕著なNbの負異常が観察され,これは沈み込みに関連したマグマおよび地殻起源の花崗岩に特徴的である.これらは全て陸弧起源のIタイプ花崗岩の特徴である.このピッチストーンはZr含有量が98.5〜103.5ppmであり,ジルコン温度計は749-755℃(中央値752℃)を与える.代表的なピッチストーン標本のK-Ar年代測定により58.7±2.3と62.4±2.1Maの年代が得られ,その平均は61Maである.この岩石はほぼ一定の87Sr/86Sr同位体初生比(0.7104〜0.7106)を示し,143Nd/144Nd初生比も0.5120の一定値を示す.これらの岩石のεNd(61 Ma)値は−12である.枯渇マントルモデル年代(TDM)は1.54〜1.57 Gaの間である.鉛同位体比は206Pb/204Pb=18.522-18.552,207Pb/204Pb=15.642-15.680,そして208Pb/204Pb=38.794-38.923である.これらの鉛同位体比はゴハドのピッチストーンが陸弧の環境で,多分苦鉄質ないし中間質の,1.54〜1.57Gaの年代をもつ下部地殻物質の部分溶融によって形成されたことを示唆する.
Key words : continental arc, Okcheon Belt, pitchstone, South Korea, Sr-Nd-Pb isotope.
4. Ductile deformation and development of andalusite microstructures in the Hongusan area: Constraints on the metamorphism and tectonics of the Ryoke Belt
Yoko Adachi and Simon R. Wallis
本宮山地域の塑性変形と紅柱石微細構造の発達:領家帯の変成作用とテクトニクスへの制約
足立容子, Simon R. Wallis
領家帯本宮山地域には変化に富む紅柱石微細構造が見られることが以前より知られている.この多様な紅柱石組織の成因を解くため,露頭レベルの変形構造から,微細構造,微細組織と全岩化学組成の関係を調査した.結果,複雑に見える紅柱石組織は,領家帯の広域変成作用時と近傍の花崗岩による接触変成作用時の二段階の昇温と広域変形時期の関係および全岩化学組成が連関して生じたものであることが判明した.また,広域変成作用から約10Myの時間間隔を置いた花崗岩の貫入が非常に広い接触変成帯を持っていることが明らかとなり,これは領家変成作用の及ぼした地殻熱環境の変遷を解明するための有効な制約条件となるであろう.
Key words : microstructures, Ryoke metamorphic belt, tectonics, whole-rock chemical compositions.
5. Paleostress reconstructions based on calcite twins in the Joseon Supergroup, northeastern Ogcheon Belt(South Korea)
Jun-Mo Kim, Bo-An Jang, Yuzo Obara and Seong-Seung Kang,
韓国の沃川褶曲帯東北部地域の朝鮮累層群に分布する方解石双晶の分析による古応力の推定
金準模,張普安,尾原祐三,姜聲承
韓国の沃川褶曲帯東北部地域の朝鮮累層群に分布する方解石双晶の測定を行い,堤川-丹陽地域の古応力の推定を行った.具体的には,堤川-丹陽地域で得られた方解石の双晶の方向,個数,厚さ,c-軸などを測定し,CSG法(Calcite Strain Gauge Technique)を用いて双晶の平均厚さ,平均密度,全体ひずみ,主ひずみと主方向を評価するとともに,双晶が生成された温度を推定した.さらに,最大圧縮方向は,時代とともに北東—南西から北北西─南南東あるいは北西─南東,最後に北─南に変化したことを示し,この三つの方向は,それぞれ古生代からジュラ初期の松林造山運動(Songrimorogeny),ジュラ初期からジュラ古期の大宝造山運動(Daeboorogeny),白亜紀の佛国寺造山運動(Bulgugsa orogeny)と関連があると推論した.
Key words : calcite twin, Jecheon-Danyang, maximum shortening axis, Ogcheon Belt, paleostress.
6. Evolution of West Rota Volcano, an extinct submarine volcano in the southern Mariana Arc: Evidence from sea floor morphology, remotely operated vehicle observations, and 40Ar/39Ar geochronological studies
Robert J. Stern, Yoshihiko Tamura, Robert W. Embley, Osamu Ishizuka, Susan G. Merle, Neil K. Basu, Hiroshi Kawabata and Sherman H. Bloomer,
南部マリアナ弧・西ロタ海底火山の発達過程:海底地形,無人潜水艇による調査およびアルゴン年代からの証拠
Robert J.Stern,田村芳彦,Robert W. Embley,石塚 治,Susan G. Merle,Neil K. Basu,川畑 博and Sherman H. Bloomer,
3000kmに及ぶ伊豆小笠原マリアナ弧は典型的な海洋性島弧である.海洋性島弧における流紋岩の成因は大陸地殻の成因と密接な関わりを持っている.西ロタ火山(West Rota Volcano)はマリアナ弧南部ロタ島の40km西北西,現在噴火を続けているNW Rota-1の30km南に位置する海底カルデラ火山である.伊豆弧の北部のスミスカルデラとほぼ同様なカルデラを持ち,玄武岩から流紋岩の多様なマグマを噴出している.無人潜水艇による詳細な観察と採取された岩石の分析により,このカルデラの活動時期と噴火様式が明らかになってきた.55万年〜35万年前に安山岩質の成層火山として成長した西ロタ火山であったが,4-6万年前に流紋岩質の海底巨大噴火により海底カルデラを形成した.その後静かな噴火により2mに及ぶユニークな巨大流紋岩軽石を噴火し,玄武岩質の寄生火山を生じている.流紋岩の生成,カルデラの形成と南部マリアナの正断層,および地殻構造との関係も示唆された.
Key words : bimodal magmatism, hydrothermal mineralization, Mariana Arc, pumice, Quaternary volcano, submarine caldera.
7. Sr-Nd isotopes and geochemistry of the infrastructural rocks in the Meatiq and Hafafit core complexes, Eastern Desert, Egypt: Evidences for involvement of pre-Neoproterozoic crust in the growth of Arabian-Nubian Shield
Ali A. Khudeir, Mohamed Ali Abu El-Rus, Samir El-Gaby, Osman El-Nady and Wagih W. Bishara
エジプトの東砂漠に分布するMeatiqとHafafitコアコンプレックスの基盤岩のSr-Nd同位体と地球化学的特徴:原生代後期以前の地殻がArabian-Nubian楯状地の形成に関与した証拠
MeatiqとHafafitコアコンプレックスはエジプトの東砂漠に分布する広域的なドーム型上昇地域(swell)であり,これらのswellは二つの異なる主要構造層序学的ユニットからなる.構造的に下位のユニットは局所的に脆性変形を被った片麻岩質花崗岩及び高変成片麻岩と片岩からなる.構造的に上位のユニットはパンアフリカンのオフィオライト質メランジュナップからなる.これらの二つのユニットの境界は低角主衝上断層であり,マイロナイトは境界にそって発達している.主要元素及び微量元素の分析データは片麻岩質花崗岩が火山弧あるいはプレート内部起源のものであることを示唆する.一方,全ての片麻岩質花崗岩及び上部ユニットの岩石は低いSrの初生値(Sri)(<0.7027),また正のeNd(t)値(+4.9 to +10.3)及び原生代後期のNdモデル年代を示す(片麻岩質花崗岩試料では,TDM=592-831Ma).これらの値は比較的に若いとされるArabian-Nubian楯状地の他の地域で得られた値と調和的であるものの,片麻岩質花崗岩のεNd(t)値及び一部の不適合元素比を説明するために,マントル起源のみならず,より古い大陸地殻の影響も考えざるを得ない.著者の地質学的,Sr-Nd同位体及び地球化学的データと既存のジルコン形成年代を考え合わせると,東砂漠には原生代後期より古い,800Maまでに分裂した大陸地殻が存在したと推測される.後のリフトの形成やその他のイベントによって,海洋地殻が形成され,リフトから離れた大陸地殻にはプレート内部アルカリ玄武岩貫入した.これらの玄武岩質マグマの貫入は古い大陸の下部地殻における溶融を誘発した可能性があり,700Ma-626Maの間に貫入した花崗岩体はこのように形成したことも考えられる.古い大陸に分布する花崗岩体およびその他の岩石はパンアフリカンナップのoverthrustingによって変形を被っており,この変形は東部ゴンドワナランドと西部ゴンドワナランドの間の斜め収束に起因するであろう.Meatiq地域とHafafit地域,両方のコアコンプレックスに分布する片麻岩質花崗岩のRb-Sr同位体値は619±25Maのアイソクロン年代を示し,そのSriは0.7009±0.0017であり,またMSWDは2.0である.この年代はパンアフリカンのナップ形成・移動の時期を現していると著者は解釈する.NW-SE軸を持つMeatiqとHafafit 複背斜は継続した東・西部ゴンドワナランドの間の斜め収束に起因する可能性がある.
Key words : anticlinorium, core complexes, Gondwanaland,infrastructural rocks, island arc, juvenile crust, Nd model age,Pan-African orogeny, pre-Neoproterozoic crust.
8. Thermal maturity assessment of the Upper Triassic to Lower Jurassic Nampo Group, mid-west Korea:Reconstruction of thermal history
Kosuke Egawa and Yong Il Lee,
韓国中西部・上部三畳〜下部ジュラ系藍浦層群の熱熟成度評価と熱史復元
江川浩輔,Yong Il Lee
韓国中西部に位置する忠南盆地の上部三畳〜下部ジュラ系藍浦層群の熱史を明らかにするため,イライト結晶度の測定および砂岩の顕鏡観察が行なわれた.藍浦層群は,変無煙炭に富む非海成堆積岩類から成る.同層群の構造的上位には,衝上断層を挟んで基盤岩類が分布する.イライト結晶度は,アンチゾーンからエピゾーンへと,下部ほど高くなる傾向を示し,埋没変成作用を示唆する.また,下部ほど砕屑粒子の変形度が高くなり,最下部層では延性変形組織が観察される.得られたイライト結晶度に基づくと,最深埋没時の温度は約340℃,埋没深度は約10kmと推定され,観察結果と一致する.忠南盆地やその周辺に藍浦層群より若い堆積岩類が分布しないことから,同層群の深部埋没作用は,ジュラ紀大宝造山運動時に生じた基盤岩類の衝上断層運動によるテクトニックな荷重に起因すると考えられる.その後の熱水変成作用により,地域的なイライト結晶度の異常や変無煙炭化が促進された.
Key words : Daebo orogeny, Early Mesozoic, illite crystallinity,Nampo Group, sandstone petrography, South Korea, thermal history.
9.Paleocene large-scale normal faulting along the Median Tectonic Line, western Shikoku, Japan
Yasu’uchi Kubota and Toru Takeshita
四国西部,中央構造線沿いの暁新世の大規模正断層運動
窪田安打, 竹下 徹
西南日本の中央構造線(MTL)は,三波川変成岩類と上部白亜系和泉層群の境界断層として定義され,両者の接合は和泉層群の堆積後に生じた.筆者らは,詳細な野外調査と既往研究に基づき古第三紀のMTL沿いの運動史を復元した.和泉層群中には,MTLの北側約2km以内に,東西方向の大規模北フェルゲンツ褶曲が分布する.さらに,MTL沿いに最大層厚約400mのブーディン構造の発達で定義される擾乱帯が分布するほか,東西方向の北フェルゲンツ小褶曲が発達する.この地質構造は,MTLのtop-to-the-northの正断層運動により形成されたと推論される.正断層運動による三波川変成岩類の最終的な上昇は,下部始新統ひわだ峠層の堆積が示す三波川変成岩類の浸食前の暁新世に生じたとみられる.
Key words : kinematic history, Median Tectonic Line, normal faulting, Paleocene.
10. Sandstone diagenesis of the Lower Cretaceous Sindong Group, Gyeongsang Basin, southeastern Korea: Implications for compositional and paleoenvironmental controls.
Yong Il Lee and Dong Hyun Lim
韓国南東部Gyeongsang盆地の下部白亜系Singdong層群の砂岩の続成作用:組成・古環境による支配との関連
クスにより生じた非海成堆積盆地である.堆積は盆地西縁に沿って分布するSindong層群に始まった.Sindong層群は3つの岩相層序ユニットからなる:すなわち下位よりNakdong層(扇状地成),Hasandong層(河川成),Jinju層(湖成)である.Sindong層群の砂岩は砕屑物組成により4つの岩石相(petrofacies)に区分される.岩石相Aは下部Nakdong層からなり平均組成Q73F12R15,岩石相Bは上部Nakdong層・下部Hasandong層からなり平均組成Q66F15R18,岩石相Cは中部Hasandong層〜中部Jinju層からなり平均組成Q49F29R22,岩石相Dは上部Jinju層からなり平均組成Q26F34R41である.砕屑物組成の変動はSindong層群の砂岩の続成鉱物組み合せに影響した.イライトとドロマイト/アンケライトは岩石相A・Bの重要な続成鉱物であり,方解石と緑泥石は岩石相C・Dの主要な続成鉱物である.続成鉱物の大部分は続成段階の前期の生成と後期の生成に区分される.前期続成時の方解石は,おそらく砂岩堆積時の乾燥〜亜乾燥気候により支配され,主に岩石相C
に生じており岩石相A・Bには見られない.後期の方解石はSindong層群の砂岩すべてに存在する.Caイオンは頁岩の続成作用とHasandong層・Jinju層砂岩の前期方解石の分解に由来するのであろう.岩石相Aと下部Bの唯一の続成粘土鉱物であるイライトは,深部埋没の間にカオリナイトが変化した生成物と推定される.これに先立つカオリナイトの存在はNakdong層堆積時の湿潤な古気候から推定される.岩石相C・Dの緑泥石はスメクタイト質粘土の変化物か,乾燥〜亜乾燥気候でのアルカリ間隙水からの沈殿物と解釈される.後期続成鉱物の出現は,堆積物組成と古気候に支配された前期続成鉱物の分布に大きく依存している.
Key words : continental basin, Cretaceous, paleoclimate, petrofacies, sandstone diagenesis
11.Mantle heterogeneity beneath the Antarctic-Phoenix Ridge off Antarctic peninsula
Sung Hi Choi, Won Hie Choe and Jong Ik Lee
南極半島沖,南極−フェニックス海嶺下のマントルの不均質性
海嶺下のマントル物質の性質を理解するために,我々は南極海のドレーク海峡にある化石拡大軸の南極−フェニックス海嶺(APR)から得られた玄武岩のSr,Nd,Pb同位体組成を検討した.採集地点の近くにはホットスポットの存在は知られていない.我々はAPRの海嶺軸下の浅部マントルに小規模な同位体的不均質性を見出した.この地域では肥沃な(E型の)海嶺玄武岩(MORB)が通常の(N型の)海嶺玄武岩と共存する.このE型玄武岩は,(i)N型玄武岩に比べて年代が比較的若い,(ii)APRが活動を停止した後で噴出した,(iii)肥沃なマントル物質から低い程度の部分溶融によって形成された.APRの活動停止が恐らくこの地域の部分溶融程度の減少を引き起こしたのだろう.そして,この地域周辺の枯渇したマントル中に散在していた地球化学的に肥沃なマントル物質がまず最初に溶融する部分となってE型MORBを形成したと解釈する.
Key words : Antarctic-Phoenix Ridge, E-type MORB, heterogeneity, Sr-Nd-Pb isotopes.
Island Arc 日本語要旨 2008. vol. 17 Issue 2 (June)
Vol. 17 Issue 2(June)
1. Pictorial
Active basal slip zones in the Jin’nosuke-dani landslide, Mt. Hakusan, Central Japan
Kiichiro Kawamura, Yujiro Ogawa, Tetsuro Kitahara, Ryota Endo, Ryo Anma, and Norio Oyagi
中部日本,白山の甚之助谷地すべりでの活動中の基底すべり帯
川村喜一郎,小川勇二郎,北原哲郎,遠藤良太,安間了,大八木規夫
2. Mesozoic paleogeography and tectonic evolution of South China Sea and adjacent areas in the context of Tethyean and Paleo-Pacific interconnections
Di Zhou, Zhen Sun, Han-zong Chen, He-hua Xu, Wan-ying Wang, Xiong Pang, Dong-sheng Cai, and Deng-ke Hu,
テーチス海と古太平洋間のつながりの観点から見た南シナ海と周辺地域の中生代の古地理
周 蒂,孫 珍,陳 漢宗,許 鶴華,王 万銀,龐 雄,蔡 東昇,胡 登科
中生代の間,南シナ海と周辺地域はユーラシア大陸の南東縁辺に分布していた.同地域における中生代の地質発達史に対するテーチス海と古太平洋のテクトニクスの影響について活発な議論がされてきた.本論文は6つの異なる時代に関する岩相分布図をコンパイルし,さらに変形と火成作用に関する情報を総括して,南シナ海と周辺地域の古地理とテクトニクスの関係を議論する.その結果,以下のような履歴が明らかになった.三畳紀初期に古期テーチス海はソンダ(Song Da)海峡を通して,東方へ本研究地域まで広がっていた.その後,研究地域の東部と西部はそれぞれ異なる地質学的な履歴を持つようになる.三畳紀後期に西部はインドシナ地塊と南中国地塊の衝突が原因であるインドシナ造山運動によって隆起し,ソンダ海峡は閉ざされた.一方,東部及び南東部では,古太平洋の海進が起こり,東広東(Guangdong)-北西ボルネオ海が形成された.ジュラ紀初期にその海進はさらに進み,西方に分布する中期テーチス海とつながるようになった.その結果,テーチス海域から大量の海水とともに多くの生物が流入した.ジュラ紀中期にテーチス海域の東方において短期間の海進が起こり,雲南(Yunnan)-ビルマ海が形成された.ジュラ紀後期-白亜紀初期の間,中期テーチス海及び古太平洋の沈み込みは調査地域に重要な影響を与えた.その結果,白亜紀中期または後期に大規模な「環東南アジア沈み込み付加帯」が形成された.本論文では,南シナ海北東部の新生代堆積物の下位に,同付加帯の延長が分布することを提案する.
Key words: Mesotethys, Mesozoic, paleogeography, South China Sea, South-east Asia, subduction zone, tectonic evolution, West Pacific.
3. Evaluation of factors controlling smectite transformation and fluid production in subduction zones: Application to the Nankai Trough
Demian M. Saffer, Michael B. Underwood and Alexander W. McKiernan,
沈み込み帯におけるスメクタイトの分解と流体の放出をコントロールする要素の評価: 南海トラフへの応用
スメクタイト属粘土鉱物のイライトへの変化は,沈み込み帯の運動学的・水文学的な振る舞いに影響を与える重要な過程とみなされている.このイライト化作用は、結合水の放出に伴う間隙流体の圧力の増加をもたらし,鉱物学的変化とそれに続くセメント化作用によって断層の滑り安定性が減少する間に,本来の摩擦強度が増加する可能性がある.また,放出された結合水は間隙水を清新にする役割を担っている.本研究では,南海トラフ周辺の2つの横断調査から得られたODPドリルサイトのデータとスメクタイトの分解の数値モデルを用い,(i) スメクタイトの分解の広域分布と海溝に沿った流体放出の定量化,および (ii) その水文学的・運動学的意義の評価を行った.紀南海山列(室戸沖の横断調査)の軸に沿って高い熱流量(約180 mW/m2)がみられたが,これは粘土鉱物の分解が海溝の外側で起こったことを意味している.一方,そこから100 km南西の足摺沖横断調査地域の低い高い熱流量(約70-120 mW/m2)は,沈み込み以前の軽微な続成作用によるものである.この結果は,足摺沖調査域に沿ってより多くの結合流体が沈み込んだことを意味している.足摺沖調査域の予測されるピーク流体ソース(約6-10 x 10-15/s)は,室戸沖調査域(約1.2-1.3 x 10-14/s)に比べてかなり高く,海溝から約10 kmシフトしている.より一般的に述べると,熱流量,付加プリズムの先端の角度,流入する堆積物の厚さ,およびプレート収束速度の全てが,海溝周辺における分解反応の進行と結合水の放出の広域的分布に影響を与えているといえる.以上のような流体放出の場所のシフトや流体量は,流体の通り道を抑制するために重要であり,粘土鉱物の分解と断層の運動を結びつけるための情報を与えてくれる.
Key words: clay transformation, fluid flow, pore pressure, smectite, subduction zones.
4. Contribution of subducted Pacific slab to Late Cretaceous mafic magmatism in Qingdao region, China: A petrological record
Jin Zhang, Zhang Hong-fu, Ji-feng Ying, Yan-jie Tang and Li-feng Niu
中国,青島地域の白亜紀後期の苦鉄質マグマ活動に対する沈み込んだ太平洋スラブの影響:その岩石学的証拠
張 瑾,張 宏福,英 基豊,湯 艶傑,牛 利鋒
中国,青島地域の劈石口(Pishikou)苦鉄質岩脈の産出は華北剛塊東縁の白亜紀後期(86-78 Ma)の苦鉄質マグマ活動の起源について重要な制約条件を与える.劈石口苦鉄質岩脈は青島地域の白亜紀のLaoshan(Laoは山偏に労,shanは山)花崗岩類の岩体中に分布し,かんらん岩質及びグラニュライト質の捕獲岩,捕獲結晶及び巨晶を含む.劈石口苦鉄質岩脈の岩石はベーサナイトで,低いSiO2(<42 wt%)とAl2O3 (12.5 wt%),高いMgO (>8 wt%), 全アルカリ(Na2O+K2O>4.8 wt%, Na2O/K2O>1), TiO2 (>2.5 wt%), CaO (>9 wt%),そしてP2O5 (>1 wt%)をもつ.微量元素含有量はイオン半径の大きい親石元素(LILEs)と軽希土類元素(LREEs)に著しく富み(ΣREE=339-403 ppm, (La/Yb)N=39-42),高イオン価元素(HFSE)の枯渇がない.これらの岩石は放射壊変起源のSrとPbに富みNdに乏しい[(87Sr/86Sr)i>0.7059, εNd=2.7-3.8, (206Pb/204Pb)i=18.0±0.1)].Nb/La, Nb/U, Nb/Thなどの重要な元素比は海嶺玄武岩(MORBs)及び海洋島玄武岩(OIBs)と対応する.従って劈石口苦鉄質岩脈は青島地域の白亜紀前期の苦鉄質岩脈とは完全に異なる地球化学的特徴を示すが,日本海の背弧海盆玄武岩とは類似している.この地球化学的特徴は劈石口苦鉄質岩脈がある種のアセノスフェア給源から形成されたが,それは沈み込んだ太平洋スラブ由来の物質に汚染されていたことを示唆する.従って,この苦鉄質岩脈の発見は,華北剛塊東縁の青島地域の白亜紀後期マグマ活動への沈み込んだ太平洋スラブの影響を示す岩石学的証拠を提供している.
Key words: asthenospheric source, contribution of subducted Pacific slab, Late Cretaceous,mafic dike, Qingdao.
5. Rapid evolution of the Eocene accretionary complex (Hyuga Group) of the Shimanto terrane in southeastern Kyushu, southwestern Japan
Saito Makoto
九州南東部四万十帯の中期始新世付加体(日向層群)の急速な形成
斎藤 眞
九州南東部の四万十帯の始新世付加体(日向層群)の層序と地質構造を詳細に検討した.その結果,暁新世以前の海洋プレートに,暁新世〜前期漸新世の泥岩,珪質泥岩,中期始新世の前期の赤色泥岩,中期始新世の中頃の膨大なトレンチフィルのタービダイトの順に堆積した海洋プレート層序が認識できた.さらに後期始新世には付加体表層を覆うシルト岩が堆積したと考えられる.
このうち,中期始新世の前期の赤色泥岩は玄武岩の活動を伴い,大陸縁辺部から供給されたと考えられる珪長質凝灰岩を挟むことから,トレンチにかなり近い位置で玄武岩の活動と赤色泥岩の堆積が起きたと判断できた.また,中期始新世以前に付加は起きておらず,太平洋プレートの運動方向が大きく変わった時期とほぼ同じ中期始新世の中頃に,粗粒陸源砕屑物が一気に供給され,急速に日向層群の付加体の形成が始まったことが認識できた.推定される海洋プレートの年代や,赤色泥岩を伴う火山活動の年代から,日向層群が堆積したプレートはフィリピン海プレート北部の年代によく類似することが明らかになった.
また日向層群には,赤色泥岩にできた衝上断層を境として,それより上位の陸源砕屑岩が衝上断層で積み重なる構造が認められる.この地質構造は日本のジュラ紀付加体のチャート砕屑岩コンプレックスと極めてよく似た地質構造をもつ.すなわち,両者とも海洋プレートの直上でなく,海洋プレート層序の中間にデコルマができ,それより上部だけが覆瓦構造をなしている.このことから,日向層群は日本のジュラ紀付加体のチャート砕屑岩コンプレックスと同様の付加プロセスで形成されたことか明らかになった.
Key words: accretionary complex, Eocene, Pacific Plate, radiolaria, rotation, Shimanto.
6. Microbially induced formation of ooid-like coated grains in the Late Cretaceous methane-seep deposits of the Nakagawa area, Hokkaido, northern Japan
Robert Gwyn Jenkins, Yoshinori Hikida, Yoshito Chikaraishi, Naohiko Ohkouchi and Kazushige Tanabe
北海道天塩中川地域に分布する後期白亜紀メタン湧水堆積物から産出した微生物活動起源のウーイド状被殻粒子
Robert Gwyn Jenkins, 疋田吉識,力石嘉人,大河内直彦,棚部一成
ウーイド粒子は,同心円構造をもつ球状微小炭酸塩粒子であり,熱帯浅海域の波浪影響下で形成されることが多い.今回,北海道天塩中川地域に分布する上部白亜系に挟在するメタン湧水堆積物中から,ウーイド状粒子の密集層を発見した.ウーイド粒子のメタン湧水環境下での形成は知られていない.そこで,メタン湧水環境下におけるウーイド状粒子の成因を明らかにすることを目的に,メタン湧水堆積物とウーイド状粒子の産状・薄片観察,バイオマーカー分析,EPMA分析を行った.その結果,今回発見されたウーイド状粒子は,嫌気性メタン酸化古細菌による嫌気的メタン酸化に伴う炭酸塩の沈殿が,海底面極近傍において起きたことによって形成されたことが明らかになった.
Key words: authigenic carbonate precipitation, biomarker, fluid flow, hydrocarbon seep, microbe, microbialite.
7. Tectonic implications of paleomagnetic data from upper Cretaceous sediments in the Oyubari area, central Hokkaido, Japan
Machiko Tamaki and Yasuto Itoh
中央北海道・大夕張地域に分布する上部白亜系堆積物の古地磁気学的研究
玉置真知子・伊藤康人
ユーラシア東縁におけるテクトニクスを解明するため,中央北海道・大夕張地域に分布する上部白亜系蝦夷層群を対象に古地磁気学的研究を行った.段階消磁実験によって8地点から安定な特徴的残留磁化が得られ,褶曲テストによりこれらの磁化方位は傾動前に獲得したと考えられる.伏角誤差補正後の古地磁気伏角は,白亜紀以降有意な南北移動を被っていないことを示唆している.したがって,大夕張地域はシホテアリンを含むモンゴリア東部近隣の現在の緯度周辺に存在していたと考えられる.古地磁気偏角からは,大夕張地域と東アジア縁辺との間で差動回転を示唆する結果が得られ,大陸縁辺に沿った地殻ブロックの再配列を示唆している.
Key words: central Hokkaido, differential rotation, inclination shallowing, Late Cretaceous, paleomagnetism, Yezo Group.
Island Arc 日本語要旨 2008. vol. 17 Issue 3 (September)
Vol. 17 Issue 3 (September)
1. Kematerrane: A fragment of a back-arc basin of the early Cretaceous Moneron-Samarga island-arc system, East Sikhote-Alin range, Russian Far East
Alexander I. Malinovsky, Vladimir V. Golozoubov, Vladimir P. Simanenko and Ludmila F. Simanenko
ケマテレーン:東シホテ-アリン地域の前期白亜紀Moneron-Samarga島弧系の背弧海盆の断片
ケマテレーンはシホテ-アリン地域のバレミアン期(?)-アプチアン期からアルビアン期の一連の火山岩-堆積岩類であり,Moneron-Samarga島弧系の背弧海盆の堆積物と考えられている.多様な堆積物の組成的特徴は,火山活動の影響下の斜面の堆積環境を示す.スランプ褶曲の方向の解析から,重力滑動による南東から北西への堆積物の集積が示された.陸源性岩石の組成の特徴は,エンシアリックな火山性島弧が砕屑物の主な給源であったことを示す.玄武岩質岩の岩石化学的特徴は,これらの地層が島弧の背後寄りに限られていたことを示す.
Key words: back-arc basin, basalt, Early Cretaceous, geodynamic environment, island arc, sandstone, Sikhote-Alin, terrane, turbidite.
2. Subdivision of the Sanbagawapumpellyite-actinolitefacies region in central Shikoku, southwest Japan
Masumi Sakaguchi and Hideo Ishizuka
四国中央部三波川変成帯におけるパンペリー石−アクチノ閃石相地域の細区分
坂口真澄, 石塚英男
四国中央部三波川変成帯に広く分布する低変成度岩類には,パンペリー石−アクチノ閃石相(PA相)を特徴づける鉱物組合せが産出する.本研究では,既報の地域と新たな8地域を対象として,パンペリー石-アクチノ閃石-緑簾石-緑泥石の鉱物組合せを用いた相対地質温度計の再検証と同温度計を利用したPA相地域の細区分を行った.その結果,上記の鉱物組合せにおける緑簾石のFe3+/(Fe3+ + Al)値は、緑泥石のFe2+/(Fe2+ + Mg)値の減少に伴い,わずかに減少する傾向があるものの,この変化は変成温度と良い相関が認められ,地質温度計の有効性が再確認された.そして,同温度計から,調査したPA相地域を3つの変成温度部に細区分した.出来上がった細区分の検討から,変成温度は,従来の泥質片岩でなされた結果と同じ傾向で,高変成度域から離れるにつれて低くなり,更に,細区分境界は別子ユニットと大歩危ユニットの構造境界を横切って連続していることが明らかになった.このことは,変成温度境界と構造境界の関係の見直しを迫るものである.
Key words: mineral compositions, pumpellyite–actinolitefaciesmetabasites, Sanbagawa Belt, thermal structure
3. SHRIMP zircon and EPMA monazite dating of granitic rocks from the Maizuruterrane, southwest Japan: Correlation with East Asian Paleozoic terranes and geological implications
Masahiro Fujii, Yasutaka Hayasaka and Kentaro Terada
舞鶴帯北帯の花崗岩類のSHRIMPジルコンおよびEPMAモナザイト年代:東アジアの古生代テレーンとの対比およびその地質学的意義.
藤井正博,早坂康隆,寺田健太郎
西南日本内帯の舞鶴帯北帯は花崗岩類と変成岩類からなり,付加体中に狭在する大陸地殻の断片であることが知られている.北帯の起源を明らかにするために,花崗岩類の年代測定を行った.その結果,北帯の西部岩体と東部岩体から,それぞれ,シルルーデボン紀(424 – 405 Ma)とペルムートリアス紀(249 – 243 Ma)のSHRIMPジルコン年代を示す花崗岩類の存在が明らかとなった.花崗岩類の貫入年代,ロシア沿海州と西南日本の地質学的類似性などから,前者はロシア沿海州のハンカ地塊に,後者は西南日本内帯の飛騨帯に対比することができる.また,舞鶴帯北帯の定置プロセスとして,舞鶴帯—飛騨外縁帯に沿うトリアス紀—ジュラ紀後期の右横ずれ運動を提案する.
Key words: dextral strike-slip movement, EPMA monazite U–Th–total Pb dating, Khanka Massif, Maizuruterrane, SHRIMP zircon U–Pb dating, South Kitakamiterrane, southern Primoye, southwest Japan.
4. Variations in sediment thickness and type along the northern Philippine Sea plate at the Nankai Trough
Toshihiro Ike, Gregory F. Moore, Shin`ichiKuramoto, Jin-Oh Park, Yoshiyuki Kaneda and AsahikoTaira
フィリピン海プレート北縁の南海トラフにおける堆積層の層厚と種類の変化
池 俊宏, Gregory F. Moore,倉本真一, Jin-Oh Park,金田義行, 平 朝彦
本論は,南海トラフから四国海盆北部にかけて広域的そして局所的にも変化するベースメントの形状,堆積層の厚さ,堆積層の種類を示す. 反射法地震探査の結果を基に,サイスミック層序を解釈し,その相違により地域を三つに分けた.ベースメントの起伏は,概ね四国海盆西方で〜400m,中央で1500m以上,東方で〜600m.堆積物の厚さは,概ね西方で600m以上,中央で〜2000m、東方で〜1200mである. 堆積層の下部には、高振幅で連続性の良い反射面(LSB-T)があり,中新世タービダイトと解釈できる. 四国海盆東方は.タービダイトを含む,厚い半遠洋性堆積物から構成されており,これらの地域差は,伊豆小笠原弧の影響を示唆する.
Key words: basement topography, Nankai Trough, sequence stratigraphy
5. Tectonics and sedimentation around Kashinosaki Knoll: A subducting basement high in the eastern Nankai Trough
Toshihiro Ike, Gregory F. Moore, Shin`ichiKuramoto, Jin-Oh Park, Yoshiyuki Kaneda and AsahikoTaira
樫野崎海丘周辺のテクトニクスと堆積作用:南海トラフ東側の沈み込む地形的高まり
池 俊宏, Gregory F. Moore, 倉本真一, Jin-Oh Park, 金田義行, 平 朝彦
本論は,南海トラフ地震発生帯(NanTroSEIZE)のリファレンスサイト,樫野崎海丘の周辺で得られた反射法地震探査の結果を基に,南海トラフ沿いにある他2点のリファレンスサイトとの相違を示す.紀伊半島南東沖南海トラフの堆積物は,海洋地殻上面の起伏により,その厚さと種類が大きく変化する.堆積層の下部には、高振幅で連続性の良い反射面(LSB-T)があり,中新世タービダイトと解釈できる.その厚さは,約100-200 mと変化し,地形的低まりに多く分布する.その一方,樫野崎海丘の北西側斜面でも明瞭に確認され,タービダイト流のbody thicknessが,海丘の高さに匹敵していた可能性を示唆する.
Key words: Nankai Trough, ridge subduction, turbidite sedimentation
6. Underplating of mélange evidenced by the depositional ages: U-Pb dating of zircons from the Shimantoaccretionary complex, southwest Japan
Tadahiro Shibata, Yuji Orihashi, Gaku Kimura and Yoshitaka Hashimoto
堆積年代により証拠づけられたメランジの底付け:四万十付加体のジルコンの ウラン-鉛年代測定
柴田伊廣, 折橋裕二, 木村 学, 橋本善孝
付加プリズムの成長は,前面での付加作用と付加プリズム基底面での底付け作用によりなされる.プリズムが厚くなり成長するにつれ,底付けされた地層群には海洋側・構造的下方へ若くなる系統的な年代極性が期待される.この仮説を検証し底付けの過程を解明するため,四万十帯の後期白亜紀-前期古第三紀の底付けしたメランジ群に含まれるジルコン粒子のU-Pb年代をLA-ICP-MSレーザー法で測定した.その結果はひとつの底付けメランジの中に系統的だが断続的な年代極性があることを明らかにした.このことは,底付けが数百万年間に間欠的に生じたこと,底付けしている時期の間には大量の堆積物が,底付けが生じる深さよりずっと深い所まで沈み込んでいたことを示す.
Key words: accretion, LA-ICP-MS, melange, Shimanto Belt, subduction.
7. Geochemistry of I-type granitoids in the Karaburun Peninsula, West Turkey: Evidence for Triassic continental arc magmatism following closure of the Palaeotethys
Sibel Tatar Erkül, HasanSözbilir, FuatErkül, CahitHelvacı, YalçınErsoy and ÖkmenSümer
トルコ西部Karaburun半島に産出するIタイプ花崗岩類の地球化学:古テチス海閉塞後の三畳紀大陸弧火成作用
アルプス造山運動の影響を被った変成岩地塊には,古〜新テチス海の形成に関連した三畳紀花崗岩類が広域的に産出する. Karaburun花崗閃緑岩は,トルコ西部にみられる古テチスのメランジに貫入した非変成深成岩体である. これは240–220 Maの年代を示し,2つの小さなストックに分かれて産出する.この深成岩体の組成範囲は広く,花崗閃緑岩からトーナル岩,閃緑岩に及ぶ.SiO2含有量は54–65重量%と幅広く,カルクアルカリ岩に分類される. また,これらは非アルカリ岩であり,モルAl2O3/(Na2O+K2O)比は0.74–1.00とメタアルミナスな特徴を示す.多くの岩石でノルムに透輝石が計算され(0.36–8.64), Na2O > K2Oである. コンドライトの化学組成によって規格化されたREEパターンでは,様々な程度でLREEに富む傾向を示し,LaN = 57.79–99.59、(La/Yb)N = 5.98–7.85であり,Euの負の異常(Eu/Eu* = 0.62–0.86)を示す. これら岩石は,海嶺花崗岩によって規格化された微量元素パターンではK、Rb、Ba、Th、Ceに富み,Ta、Nbに枯渇した傾向をもつことから,沈み込み帯におけるIタイプ花崗岩の特徴をもっている. 始源的マントルの化学組成によって規格化された多元素パターンでは,花崗閃緑岩にHFSE(Nb、Ta、Zr)、Sr、P、Tiの明らかな枯渇がみられる. Karaburun花崗閃緑岩の微量元素によるモデリングにより,この岩石は、沈み込みの影響によって組成が改変されたマントルウェッジの部分溶融によって形成されたと考えられる. また,その後の分別結晶化作用および若干の同化分別結晶化作用における地殻物質の関与もみられる. Karaburunメランジにおける典型的な大陸弧型花崗閃緑岩の産出は、沈み込み—付加モデルが妥当であることを示し,古テチス海閉塞後の三畳紀に活動的大陸縁辺部が存在していたことを意味している.
Key words: active continental margin, mantle wedge, Neotethys, Palaeotethys, Triassic, volcanic arc granitoids
Island Arc 日本語要旨 2008. vol. 17 Issue 4 (December)
Vol. 17 Issue 4 (December)
特集号
Thematic Section: IGCP 516 Geological Anatomy of East and South Asia: Paleogeography and Paleoenvironment in eastern Tethys
Guest editors: K. Hisada and G. P. Yumul Jr
1.Crustal thickness and adakite occurrence in the Philippines: Is there a relationship?
Carla B. Dimalanta and Graciano P. Yumul, Jr.
フィリピンにおける地殻の厚さとアダカイト産出:その関係は?
アダカイトは様々なテクトニックセッティングのもと,世界中で数多く認められる様になってきた.この火山岩の特徴的な化学組成の形成モデルは,沈み込んだ若くて熱い海洋スラブの部分溶融に始まり,斜め沈み込み,低角もしくはフラットな沈み込み,またはスラブの断裂に求められるようになってきた.アダカイト質メルトの生成を説明するため厚い地殻の部分溶融を指摘している研究者もいる.アダカイト形成場の概要を明らかにするため,本研究ではフィリピンにおけるアダカイトやアダカイト質岩の希土類元素比を用いた.試料採取地域の地殻の厚さ求めるため,地球物理データを組み合わせた.高Sm/YbとLa/Yb比は,アダカイトやアダカイト質マグマの生成において,角閃石およびガーネットの関与を意味する.残留相としての角閃石とガーネットの存在は,厚い地殻(〜30—45km)に相当する高い圧力を示唆する.沈み込む若い海洋地殻の溶融とは異なったプロセスで形成されたアダカイトやアダカイト質岩は,重希土類元素の特徴を説明のために30kmの形成深度を必要とする.もしマントル物質の関与がないとすれば,地殻の厚さはアダカイトやアダカイト質岩形成の最重要要素である.
Key words: adakites, amphibole, crustal thickness, garnet, Philippines, rare earth elements.
2. Baguio Mineral District: An oceanic arc witness to the geological evolution of northern Luzon, Philippines
Graciano P. Yumul, Jr., Carla B. Dimalanta, Tomas A. Tam III and Estephanie Gera L. Ramos
バギオ鉱床地域:フィリピン,北部ルソンの地質学的進化に関する海洋島弧の証拠
バギオ鉱床地域には,この地域の地質学的およびテクトニック進化を証拠づける,沈み込みに関連した縁海から島弧セッティングにいたる特徴を示す岩石が露出している.手元にある陸上および海域からのデータは,前期中新世(開始期)から中期中新世(発達期)にかけて起こった,東(プロト東ルソントラフに沿った沈み込みの終焉)から西(マニラ海溝に沿った沈み込みの開始)への弧の極性の反転と整合的である.地球物理学的モデリングと地球化学的データの解析から,この鉱床地域の地殻の厚さとして30±5kmという値が得られる.沈み込みに関連した複合的な弧の火成活動とオフィオライトの付加が地殻の厚化に寄与した.本鉱床地域にみられる漸新−中新統のジグザク層およびクロンダイク層に関する最近の知見から,これらの岩石が堆積した縁海には,それに隣接した,シリカに富む岩相により特徴づけられた地帯からの侵食物が供給されたことが明らかになった.さらに,おそらく鉱化したターゲットを見分けるために利用される探鉱マーカーであるアダカイト質岩石,高透水帯,伸張帯が,この鉱床地域には一般的である.この鉱床地域が被った地質学的進化過程は,一般的な意味で世界各地の島弧進化に共通しており,特に北部ルソン地域で際立っている.
Key words: crustal thickness, island arc, marginal basin, mineralization, Philippines, subduction.
3. Buruanga Peninsula and the Antique Range: Two contrasting terranes in Northwest Panay, Philippines featuring an arc-continent collision zone
Lawrence R. Zamoras, Mary Grace A. Montes, Karlo L. Queaño, Edanjarlo J. Marquez, Carla B. Dimalanta, Jillian Aira S. Gabo and Graciano P. Yumul, Jr.
ブルアンガ半島とアンティーク山脈:島弧-大陸衝突帯の特徴を有するフィリピン,北西パナイ(Panay)の2つの対照的地質体
ブルアンガ(Buruanga)半島は,付加コンプレックスの典型的ユニットである,石灰岩ブロックを伴ったチャート−砕屑岩シーケンスの繰り返しによって構成されている.本研究によって新しい岩相層序ユニット,ウニドス(Unidos)層(ジュラ系チャートシーケンス),サボンコゴン(Saboncogon)層(ジュラ系珪質泥岩-陸源性泥岩と石英質砂岩),ギボン(Gibon)層(ジュラ系?層状遠洋性石灰岩),リベルタット(Libertad)変成岩(ジュラ系-白亜系粘板岩・千枚岩・片岩),そしてブルアンガ層(鮮新統-更新統礁性石灰岩)が提唱された.ブルアンガ半島の最初の3つの堆積岩シーケンスは,ブスアンガ(Busuanga)島,北パラワンテレーンの海洋プレート層序と近い類似性(遠洋性石灰岩を伴う下部-中部ジュラ系チャートシーケンスが中部-上部ジュラ系砕屑岩によって覆われる)を示す.さらに,ブルアンガ半島,サボンコゴン層のJR5-JR6に相当する珪質泥岩は,中部ブスアンガ帯,グインロ(Guinlo)層のJR5-JR6に相当する泥岩に対比することができる.これらの発見はブルアンガ半島が北パラワンテレーンの一部であることを示唆している.ブルアンガ半島の岩相は,アンティーク(Antique)山脈の礁性石灰岩やアルコース質砂岩を伴う,中部中新統の玄武岩質〜安山岩質火山砕屑性および溶岩流堆積物とは明らかに異なる.これらによって,これまでに示されてきたパラワン小陸塊とフィリピンモバイル帯の境界,つまりはブルアンガ半島とアンティーク山脈の間の縫合帯が確証された.この境界は同様にそれらの間の衝突帯と考えられる.
Key words:arc-continent collision, Buruanga peninsula, Busuanga Island, chert-clastics- limestone sequence, North Palawan terrane, ocean plate stratigraphy.
4.. Paleogeographic reconstructions of the East Asia continental margin during the middle to late Mesozoic
Yong Il Lee
中生代中−後期の東アジア大陸縁の古地理復元
東アジアの大陸縁の中生代古地理図は,韓国と日本に分布する堆積物の最近の研究成果によって書き直されてきた.韓半島と西南日本内帯は,中期−後期中生代の時期に堆積物供給の役目を交代していた.それは,活動的大陸縁における二国間の密接な古地理的関係を示唆するものである.中期ジュラ紀の初期から後期ジュラ紀の最初期の間に,海溝充填堆積物の供給源でありそして付加コンプレックスが付加した韓半島南東部に沿って,美濃−丹波海溝が発達した. 西南日本の飛騨外縁帯の手取層群下部白亜系石英アレナイト礫は,韓半島南部の中央や東部中央に分布する先中生代石英アレナイト層からもたらされた.それは手取堆積盆が石英アレナイト礫堆積時に,古地磁気学的データによればこれらの2地域が遠距離と思われていたことに反して,韓半島東部の中央が近接していたことを示唆する.韓半島南東部に分布する非海成Gyeongsang堆積盆の北部の後期白亜紀の前期の放散虫チャートの礫や砂は,西南日本に分布する隆起した美濃−丹波付加コンプレックスからもたらされた.それは美濃−丹波帯が,東部韓半島と地続きであったことを示唆する.これらの新発見は,従来の考えと対照的に,西南日本のテクトニック・ブロックのコラージュが,後期白亜紀の前期のあとに寄せ集まったことを意味するかもしれない.
Key words:active continental margin, East Asia, Mesozoic, paleogeography, provenance.
5.Early Cretaceous paleogeography of Korea and SW Japan inferred from occurrence of detrital chromian spinels
Ken-ichiro Hisada, ShizukaTakashima, Shoji Arai and Yong Il Lee
砕屑性クロムスピネルの産出から推定される韓国と西南日本の白亜紀前期の古地理
久田健一郎,高島 静,荒井章司,Yong Il Lee
Sindong層群は韓半島南部のハーフ・グラーベンのNakdongトラフに堆積した.Gyeongsang 堆積盆のSindong層群Jinju層からの砕屑性クロムスピネルの産出は,その後背地にマフィックから超マフィック岩が露出していたことを意味する.Jinju層からのクロムスピネルは,きわめて低いTiO2やFe3+で特徴付けられる.さらに,Cr#の範囲は0.45から0.80におよび,Mg#とともに単純なトレンドを形成している.クロムスピネルの化学組成は,クロムスピネルの供給源がマントルウェッジ起源のかんらん岩あるいは蛇紋岩であることを意味している.その源岩に束縛条件を与えるために,UlsanとAndongの蛇紋岩を岩石学的に検討した.Andong蛇紋岩中のクロムスピネルはJinju層のクロムスピネルとは異なり,Ulsan蛇紋岩はそれらとは部分的に類似する.さらにJinjuクロムスピネルは,西南日本の長門構造帯や東北日本の上越帯を含む飛騨外縁帯の中生代堆積物から産出した砕屑性クロムスピネルに似ている.これはNakdongトラフの主要断層や東側に位置していた基盤岩中に,かんらん岩や蛇紋岩が露出していたことを示唆する.すなわち,Nakdongトラフは,日本海形成以前には,飛騨外縁帯の岩石で境されていたと結論付けられるであろう.
Key words:circum-Hida Tectonic zone, detrital chromian spinel, Gyeongsang Basin, Jinju Formation, Nagato tectonic zone, Sindong Group
6.Petrology of the Yugu peridotites in the Gyeonggi massif, South Korea; Implications for its origin and hydration process
Shoji Arai, Akihiro Tamura, Satoko Ishimaru, Kazuyuki Kadoshima, Yong-Il Lee, and Ken-ichiro Hisada
韓国,キョンギ地塊のユーグーかんらん岩の岩石学:起源と加水過程について
荒井章司,田村明弘,石丸聡子,角島和之,Yong-Il Lee,久田健一郎
韓国,キョンギ地塊のオクチョン帯との境界付近のユーグー地域に産するかんらん岩類はマイロナイトから強いポーフィリティック組織を呈し,多くはスピネル・レールゾライトである.そのほか少量のダナイト,ハルツバーガイト,ウェブスタライトがレールゾライトに伴っている.角閃石はネオブラストとしてのみ見られ,コアがホルンブレンド,リムがトレモライトという累帯構造を有している.ポーフィロクラストは1000℃程度の平衡温度を有しているのに 対し,ネオブラストは800℃と比較的低温を示す.かんらん石はレールゾライトではFo90-91,ダナイトやハルツバーガイトではFo91程度の組成を示す.スピネルのCr#(Cr/(Cr+Al)原子比)はかんらん石のFoとともに変化し,レールゾライトで0.1から0.3,ダナイトやハルツバーガイトで0.5前後となる.単斜輝石ポーフィロクラスト中のNa2O含有量は比較的低く,最も枯渇度の低いレールゾライトで0.3から0.5重量%である.ユーグーかんらん岩類はポーフィロクラストの鉱物組成の点で,大陸かんらん岩よりも島弧や海洋底のかんらん岩に類似する.組織や鉱物学的な特徴は,ユーグーかんらん岩が加水されつつ冷却し,マントルから地殻条件へもたらされたことを示唆する.ほとんどの単斜輝石と角閃石は同様のU字形の希土類元素パターンを示すが,後者の方が10倍ほど濃度が高い.加水化は,スラブ起源または地殻中の流体により,軽希土類元素の富化を伴って進行した.マントル・ウェッジまたは海洋底のかんらん岩が,キョンギ地塊の高圧変成帯を形成した大陸の衝突によりユーグーかんらん岩として貫入した. キョンギ地塊のかんらん岩は,同地塊の西方延長であると思われる中国のダービー・スールー衝突帯のかんらん岩(ざくろ石を含むこともある)より低圧を示している.
Key words: : alpine-type peridotites, continental crust, Korean peninsula, metasomatism, spinel lherzolites, Yugu
7.Geological relationship between the Anyui Metamorphic Complex and Samarka terrane, Far East Russia
Satoru Kojima, Kazuhiro Tsukada, Shigeru Otoh, Satoshi Yamakita, Masayuki Ehiro, Cheikhna Dia, Galina Leontievna Kirillova, Vladimir Akimovich Dymovich and Lyudmila Petrovna Eichwald
極東ロシア,白亜紀アニュイ変成岩体とジュラ紀サマルカ帯の地質学的関係
小嶋 智,束田和弘,大藤 茂,山北 聡,永広昌之,Cheikhna Dia, Galina Leontievna Kirillova, Vladimir Akimovich Dymovich and Lyudmila Petrovna Eichwald
白亜紀の変成年代を持つアニュイ変成岩体は,変成したチャート,結晶片岩,片麻岩,ミグマタイト,超苦鉄質岩からなり,サマルカ帯のジュラ紀付加体の北縁部中にドーム構造をつくって分布している.両者の関係は断層であるが,サマルカ帯とアニュイ変成岩体のチャートおよびその変成相中の石英の粒径,結晶度および岩相が徐々に変化することは,少なくともアニュイ変成岩体の一部は,サマルカ帯の変成相であることを示している.サマルカ帯の珪質泥岩から得られた放散虫の年代はTithonian(ジュラ紀最後期)であるので,その付加年代はそれよりもやや後であることがわかる.このことは,本地域の付加体が,サマルカ帯の中では最も若い地質単元の一つであることを示している.サマルカ帯とアニュイ変成岩体の関係や年代・岩相は,西南日本の丹波-美濃-足尾帯と領家変成岩体の関係に類似している.両地域とも,ジュラ紀付加体のより下位の(若い)部分が白亜紀後期の花崗岩質マグマによる貫入を受け変成している.太平洋型造山帯の地殻発達は,(1)海洋性堆積物と大陸からもたらされた陸源性タービダイトの付加,(2)高温低圧型変成岩の形成を伴う,その次の沈み込み・付加イベントによる花崗岩質岩の貫入というサイクルにより達成されてきた.
Key words: Anyui Metamorphic Complex, crystallinity index, Jurassic accretionary complex, low-grade metamorphism, radiolaria, Samarka terrane, Sikhote-Alin
8.Structure and age of lower structural unit of the Taukha terrane of Late Jurassic-Early Cretaceous accretionary prism, Southern Sikhote-Alin
Igor’V. Kemkin and Yojiro Taketani
シホテアリン南部に分布するジュラ紀後期〜白亜紀前期の付加プリズムであるタウハテレーンの構造的下部ユニットの構造と年代
Igor’V. Kemkin,竹谷陽二郎
本論は,ロシアのシホテアリン南部に分布するタウハテレーンの構造的下部ユニット(エルダゴウ層)中の堆積層の構造と年代に関する詳細なデータを提示する.ベネフカ川流域に露出するこのユニットの岩相を検討した結果,エルダゴウ層は,海洋プレート上の堆積層の変形した断片を現していることが判った.すなわち本層は,遠洋性堆積物(チャートと粘土質チャート)から半遠洋性堆積物(珪質泥岩)を経て大陸斜面堆積物(泥岩,シルト岩,タービダイト)まで,海洋プレート上のすべての堆積相を有している.その堆積層から得られた放散虫化石層序の分析から,チャートはオックスフォーディアン中期〜ベリアシアン初期,チャートと陸源堆積物(タービダイト)の漸移層である珪質泥岩はベリアシアン前期,陸源堆積物の下部はベリアシアン後期〜バランギニアン後期の年代であることが判明した.このデータから,この海洋プレートの付加はバランギニアン期の後に起こったと結論される.
Key words : Erdagou Formation, Late Jurassic-Early Cretaceous accretionary prism, Mesozoic period, Mesozoic radiolaria, Sikhote- Alin, Taukha terrane
9. Radiolaria-dated Lower Permian clastic-rock sequence in the Fukuji area of the Hida-gaien terrane, central Japan, and its inter-terrane correlation across Southwest Japan
Toshiyuki Kurihara and Masao Kametaka
飛騨外縁帯福地地域の下部ペルム系砕屑岩層とその西南日本における地帯間対比
栗原敏之,亀高正男
本論では,飛騨外縁帯福地地域の水屋ヶ谷層について放散虫化石による時代決定を行い,本層が西南日本の非付加体型地帯(島弧−前弧/背弧海盆のセッティングで形成された地質体)における下部ペルム系を代表する地層であることを示した.水屋ヶ谷層は,全体として厚さ300mを超える砕屑岩層からなり,下部層の珪長質凝灰岩や凝灰質砂岩泥岩互層にPseudoalbaillella u-forma morphotype I群集帯〜Pseudoalbaillella lomentaria区間帯およびAlbaillellasinuata区間帯の放散虫化石を含む.これまで水屋ヶ谷層を中部ペルム系とする解釈もあったが,本層がAsselian〜Kungurianの化石を含む凝灰岩・砕屑岩相の下部ペルム系であることが明らかになった.西南日本では同様の下部ペルム系が長門構造帯と黒瀬川帯から報告されている.いずれも火山弧に由来する珪長質凝灰岩が卓越する部分があり,前期ペルム紀における火山弧の形成は,これら非付加体型地帯群が共通して経験した広域的なテクトニックイベントである可能性がある.
Key words : Early Permian, Fukuji, Hida-gaien terrane, magmatic arc, Mizuyagadani Formation, radiolarians, stratigraphic correlation.
10. Metamorphic and cooling history of the Shimanto accretionary complex, Kyushu, Southwest Japan: Implications for the timing of out-of-sequence thrusting
Hidetoshi Hara and Katsumi Kimura
九州四万十帯付加コンプレックスの変成・冷却史:アウトオブシーケンススラストの活動時期との関係
原 英俊,木村克己
九州四万十帯付加コンプレックスにおいて,地震性アウトオブシーケンススラストである延岡スラストの上盤(三方岳ユニット)と下盤(神門ユニット)から,イライト結晶度,イライトK-Ar年代,ジルコンのフィッション・トラック年代を解析した.求められた変成温度及び変成・冷却の時期は,延岡スラストの発達に関係する付加コンプレックスの変成テクトニクスを明らかにする.イライト結晶度は,後期白亜系の三方岳ユニットが300−310℃,中期始新世の神門ユニットが260−310℃の変成を受けたことを示す.イライトK-Ar年代及びジルコンのフィッション・トラック年代は,三方岳ユニットの変成時期が46−50Ma(平均48Ma)であることを示す.また神門ユニットの変成は,堆積終了後の40Ma以降に起きたと考えられる.これらのことから三方岳ユニットは冷却が始まる48Maに,延岡スラストに沿って神門ユニットへ衝上をはじめ,そして少なくとも40Ma以降まで続いた.したがって延岡スラストは,約40−48Maに活動していた.これらの結果は,延岡スラストの活動期間が10myを超えることを示唆する.
Key words : illite crystallinity, K-Ar age, Nobeoka thrust, seismogenic thrust, Shimanto Belt, zircon fission-track age.
通常論文
1. K-and Si-rich glasses in harzburgite from Damaping, north China
ZHU, Yongfeng
北中国,大麻坪のハルツバージャイト中のKとSiに富むガラス
朱 永峰
北中国,漢諾Hannuoba地域の大麻坪Damaping〔河北省北西部〕で採集された無水スピネルハルツバージャイト〔捕獲岩〕中の単斜輝石の海綿状リムにあるカリウムとシリカに富むガラス(SiO2=65.3-67.4%,K2O=7.1-9.8%)についての研究結果を報告する.単斜輝石の融食された表面形態及び(均質なコアと部分溶融したリムの間の)顕著な組成累帯構造は,初生的単斜輝石の分解溶融がこのシリカに富むガラスの形成に関与したことを示唆する.単斜輝石の溶融程度は15%より高かったと推定される.7.0〜9.8%のK2O含有量をもつガラスを,閉鎖系において単斜輝石の15%の部分溶融で形成するには,もとの単斜輝石のK2O含有量が1%以上でなくてはならず,これは大麻坪ハルツバージャイトが地球の非常に深い部分に由来することを示唆する.(〔〕内は訳者が補った)
Key words : Damaping, glass, Hannuoba, harzburgite, mantle xenolith.
2. Dehydration of clastic sediments in subduction zones: a Theoretical study using thermodynamic data of minerals
Ying Li, Hans-Joachim Massonne, Arne Willner, Hong Feng Tang, Cong Qiang Liu
鉱物の熱力学的データを用いた沈み込み帯における砕屑岩の脱水に関する理論的な解析
季 営,Hans-Joachim Massonne,Arne Willner,唐 紅峰,劉 叢強
K2O-Na2O-CaO-MgO-FeO-Fe2O3-Al2O3-TiO2-SiO2-H2Oの系において10〜35 kbar,300〜900℃の圧力温度範囲で算出した二つの異なる堆積岩試料及び一つの玄武岩試料に対するシュードセクションから,沈み込み帯における海洋地殻から放出されるH2Oの量に関する有用な情報が得られた.冷たい沈み込み帯(20kbar,300℃から35kbar,500℃)において,120kmの深さでも変堆積物中に3〜4重量%のH2Oを貯蔵する含水鉱物が存在する.一方,同じ条件下の変塩基性岩からは深さ100〜120kmの間で1重量%のH2Oが放出されるが,4.5重量%のH2Oはより深いところへ運ばれる.高温沈み込み帯(100km深さにおいて上記の冷たい沈み込み帯より300℃高温)の場合は,深さ50〜80km間の変堆積岩の脱水は緑泥石及びパラゴナイトの消滅に起因する.計算では,80kmより深いところでも唯一安定な含水鉱物であるフェンジャイトのモードはほとんど一定なので,さらなる脱水は起こらない.同じく高温沈み込みによる圧力温度経路を経てきた変塩基性岩は,深さ40〜80kmの間で連続的に脱水し,脱水量は3重量%H2Oである.深さ120km以上では,岩石中に残るH2Oは0.4重量%以下になる.現在活動する沈み込み帯の平均的なもの(地温勾配〜6℃/km)では,堆積物と玄武岩の主要な脱水はそれぞれ70〜10kmと80〜120kmの深さで起こる.120kmより深く沈み込んだ変堆積物と変玄武岩が貯蔵するH2Oはそれぞれ1.3重量%と1.6重量%である.今回の計算結果として示された堆積物の脱水挙動は,沈み込み帯における流体の沈み込み帯深部への移動が,冷たい沈み込み帯において最も効率よく起こるという一般的な見解に合致する.また,初期地球で予想される高温沈み込み帯では,海洋地殻中のH2Oの多くは120kmより浅いところで放出されるために,島弧火成活動には関与しなかったと考えられる.
Key words : dehydration of sediments, H2O, hydrous minerals, phase relationships, subduction zones, thermodynamic calculations.
Island Arc 日本語要旨 2009. vol. 18 Issue 1 (March)
Vol. 18 Issue 1 (March)
特集号
Geological Anatomy of East and South Asia: Paleogeography and paleoenvironment in Eastern Tethys IGCP 516(Part 2)
Guest editors: K. Hisada and G. P. Yumul Jr
1. Structure of Sumatra and its implications for the tectonic assembly of Southeast Asia and the destruction of Paleotethys
Anthony .J. Barber and Michael J. Crow
スマトラの地質構造,および東南アジアの形成とパレオテチスの閉鎖に対するその意義
東南アジアは,古生代に起こったリフトイベントでゴンドワナから分離し,海洋地殻の沈み込みにより古生代後期から中生代前期にアジアへ衝突した大陸地塊で構成されていることが一般に受け入れられている.マレー半島とスマトラは,東から西に3つの大陸地塊で構成されている.それらは,カタイシア型のペルム紀動植物群集を伴う東マラヤ地塊,氷海性ダイアミクタイトと解釈されている後期石炭紀−前期ペルム紀“含礫泥岩”を伴い,マレー半島西部とスマトラ東部を含むシブマス地塊,そしてふたたびカタイシア動植物群集を伴う西スマトラ地塊である.ウォイラナップとよばれるさらにもう一つのユニットは,白亜紀中頃に西スマトラ地塊上に衝上した海洋内島弧と解釈できる.シブマスと東マラヤの衝突,そしてパレオテチスの閉鎖の年代に関しては様々な意見がある.タイ国では,パレオテチスが中期三畳紀まで存在したという証拠が放散虫岩により示されている.一方マレー半島では,地質構造の証拠と花崗岩貫入の年代から,パレオテチスの閉鎖が中期ペルム紀〜前期三畳紀であったということが考えられている.西スマトラ地塊はカタイシアに由来し,激しい変形を被った地帯である中央スマトラ構造帯に沿う右横ずれ断層により,シブマスの西縁へと定置したことが指摘されている.これらの構造ユニットは東南アジアにおいてさらに北方へと追跡できる.東マラヤ地塊はインドチャイナ地塊の一部と考えられ,シブマスはタイ国から中国南部まで追跡できる.また,中央スマトラ構造帯はミャンマーのモゴック帯に対比され,西スマトラ地塊は中新世に広がったアンダマン海により切り離されてはいるものの西ビルマ地塊へと連続する.そして,ウォイラナップはミャンマーのマウギーナップに対比される.
Key words : Malay peninsula, Myanmar, Paleotethys, Permo-Triassic, Sibumasu, West Sumatra block.
2. Classification of the Sibumasu and Paleo-Tethys tectonic division in Thailand using chert lithofacies
Yoshihito Kamata, Katsumi Ueno, Hidetoshi Hara, Megumi Ichise, Thasinee Charoentitirat, Punya Charusiri, Apsorn Sardsud, and Ken-ichiro Hisada
タイ王国におけるチャート岩相に基づいたシブマスーパレオテチスの地体構造区分
鎌田祥仁, 上野勝美, 原 英俊, 一瀬めぐみ, Thasinee Charoentitirat, Punya Charusiri, Apsorn Sardsud,久田健一郎
岩相や含まれる化石相,さらにその層序をもとにタイ国において,2つのタイプのチャートを同定した.“遠洋性チャート”は密集する放散虫殻を含む隠微晶質石英の基質からなり,陸源性砕屑物を含まない.また,剪断を受けた泥質基質に異地性岩塊のブロックとして取りこまれている.“半遠洋性チャート”も微晶質石英が卓越する基質を持つ一方で,放散虫殻だけでなく有孔虫などの石灰質殻を含む.“遠洋性チャート”はデボン紀から三畳紀中世の堆積期間を示しているのに対し,“半遠洋性チャート”の堆積年代は三畳紀の中世から新世に限定される.岩相および層序学的特徴は,“遠洋性チャート”がパレオテチスを起源とすること,“半遠洋性チャート”はシブマス東縁で堆積していたことを示す.これらの“遠洋性”および“半遠洋性チャート”の分布は,南−北走向を呈して,2つの帯状地域に分かれる.このうち西側は,“半遠洋性チャート”や氷河性堆積物,さらにシブマスの構成岩類のみから成る先カンブリア系を覆う中・古生界で構成される.東側は遠洋性のチャートと石灰岩が,その構成岩類に含まれることからインタノン帯に比較される.このインタノン帯はパレオテチスの堆積岩類が分布するということだけでなく,パレオテチス構成岩類の構造的下位にシブマスの構成岩類が占めていることでも特徴付けられる.この意味でシブマスとパレオテチス分布境界は,シブマス地塊とインドチャイナ地塊の衝突に伴う南−北走向の低角逆断層である.
Key words : chert, hemipelagic, Mesozoic, Paleo-Tethys, Paleozoic, pelagic, radiolaria, Sibumasu, Thailand.
3. Geochemistry and Geochronology of Late Triassic volcanic rocks in the Chiang Khong Region, Northern Thailand
Weerapan Srichan, Anthony J. Crawford and Ronald F. Berry
タイ国北部Chiang Khong 地域における三畳紀新世火山岩類の地球化学および地質年代学
Chiang Khong-Lampang-Tak火山帯のChiang Khongセグメントは,苦鉄質〜珪長質火山岩,火山砕屑岩,およびそれらに伴う貫入岩類で構成され,(NNE-SSW走向で)子午線状に分布する3亜帯に区分される.付随する堆積岩類のほとんどは,非海成の赤色層と礫岩である.Chiang Khongの3つの代表的溶岩は,三畳紀新世(223-220Ma)のレーザーアブレーションICP-MS法によるU-Pbジルコン年代を示す.Chiang Khong西亜帯と中央亜帯の珪長質岩卓越シーケンスは,高Kカルクアルカリ岩系列の玄武岩質〜珪長質溶岩で, まれに苦鉄質岩脈を伴う.西亜帯の溶岩は全ての分別レベルにおいて,中央亜帯の相当岩石より,HFS元素がわずかに低い.これに対して東亜帯はE-MORBと背弧海盆玄武岩の漸移的組成を示す苦鉄質溶岩と岩脈が卓越する.東亜帯の岩石は,高Kシーケンスの玄武岩類よりFeO*とTiO2に富み,軽希土類元素に乏しい.西亜帯と中央亜帯の玄武岩類およびドレライト質岩脈は,東亜帯の溶岩と岩脈の組成的に一致する.最近のChiang Khong岩類の地球化学的検討は,それらが大陸縁の火山弧のようなセッティングで噴出したと結論づけている.しかし珪長質溶岩が卓越すること,非海成堆積物を伴うことから,我々は対案として,衝突後の伸張的セッティングを起源とすることを提案する.三畳紀中世後期〜三畳紀新世初期の衝突・造山イベントが,タイ国北部から中国雲南地域において裏付けられた.Chiang Khong-Lampang-Tak火山帯には,この造山イベントに先行する三畳紀古世−中世の放射年代を示す火成弧の溶岩がみられないことや,Chiang Khong火山岩類の地球化学特徴が他地域の衝突後のマグマ形成場におけるものと良く似ていることを考慮すると,Chiang Khong地域は衝突後に急速に成長するベースンレンジ型の伸張場で形成される典型的火山帯の特徴を示す.
Key words : Chiang Khong-Lampang-Tak Volcanic Belt, Late Triassic volcanic rocks, postcollisional magmatism, Thailand tectonics.
4. Lower permian glacially influenced deposits in Phuket and adjacent islands, peninsular Thailand
Tianpan Ampaiwan, Ken-ichiro Hisada and Punya Charusiri
タイ王国半島部プーケットおよび周辺諸島部におけるペルム系下部の氷河性堆積物
Tianpan Ampaiwan,久田健一郎,Punya Charusiri
東南アジアのシブマス・ブロックは氷河海成堆積物を含み,二畳紀前期にゴンドワナ縁辺域から分離したことが提唱されてきた.タイ王国におけるプーケットやその周辺島嶼におけるペルム系下部含ダイアミクタイト・シーケンスの相解析やドロップストーンとダンプ構造の認定は,堆積物が氷河海成・土石流堆積物起源であることを示唆している.研究地域のペルム系下部含ダイアミクタイト・シーケンスは,コ・シレ層とコ・ヘ層に対応し,両層とも三つの主要な層相で構成される;ダイアミクタイト,砂岩,細粒岩相.下位のコ・シレ層は400mの厚さを有し,葉理の発達した泥岩で特徴づけられる;Cruziana生痕相を伴ったドロップストーンとダンプ構造の存在は,氷河による影響を受けた沿岸域の氷漂流運搬堆積作用を示している.コ・シレ層はコ・ヘ層(層厚400m)のダイアミクタイト・シーケンスによって覆われる.再堆積の組織とともに板状そしてレンズ状の形態をした層理の発達が弱い,あるいは強いダイアミクタイトは,コ・ヘ層内のダイアミクタイトが土石流であることを示している.ダイアミクタイトやドロップストーン中の礫の似たような岩相はおそらく土石流ダイアミクタイトがかつて存在した氷河堆積物が再移動したものであることを示唆している.氷河によって影響を受けた沿岸環境の証拠は,シブマス・ブロックがおそらくゴンドワナの北西オーストラリア縁辺に位置していたのであろうとする古地理的解釈を支持する.
Key words : dropstone structure, dump structure, Early Permian, glaciomarine, Gondwana, Sibumasu block.
5. Lopingian(Late Permian)foraminiferal faunal succession of a Paleo-Tethyan mid-oceanic carbonate buildup: Shifodong Formation in the Changning-Menglian Belt, West Yunnan, Southwest China
Katsumi Ueno and Satoe Tsutsumi
パレオテチス大洋型炭酸塩ビルドアップにおける楽平世(後期ペルム紀)有孔虫群集変遷:南西中国,雲南西部の昌寧−孟連帯に分布する石佛洞層の例
上野勝美,堤 聡依
この論文では,東アジアにおけるパレオテチス海の閉鎖域の1つと考えられている,南西中国,雲南西部の昌寧−孟連帯に分布する石佛洞層からの楽平世(後期ペルム紀)有孔虫群集変遷について検討した.石佛洞層は,この地帯にみられる厚い石炭−ペルム系炭酸塩岩の最上部を成す層序単元である.この炭酸塩岩は海洋島玄武岩からなる基盤上に発達したもので,パレオテチス大洋域の海山あるいは海台起源であることが知られている.本研究では,昌寧−孟連帯北部の耿馬地域に位置する石佛洞層の模式セクションにおいてフズリナ類16種と小型有孔虫類37種を見いだした.その層序分布に基づき,下位よりCodonofusiella cf. C. kwangsiana帯,Palaeofusulinaminima帯,Palaeofusulina sinensis帯の3フズリナ化石帯を設定した.これら3化石帯はそれぞれ,呉家坪期,前期長興期,後期長興期に対比される.このうち,呉家坪期の化石帯は昌寧−孟連帯の大洋型炭酸塩岩体から今回はじめて報告されたものである.石佛洞セクションにおけるPalaeofusulina sinensis帯上部の最後期ペルム紀有孔虫群集には,群集多様性の突然の低下と産出量の大幅な減少が記録されてはいるものの,パレオテチス遠洋浅海環境での有孔虫群集が楽平世のほぼ全期間にわたり基本的に高い多様性を保持していたことを本研究では明確に示した.また石佛洞層の群集は,南部中国などの環テチス海陸棚域でみられる群集と,多様性の高さにおいて比較できる.今回報告したパレオテチス大洋域の有孔虫群集は,西南日本のジュラ紀付加体中にある上村石灰岩産の群集で代表される同時期のパンサラッサ大洋域の群集よりも明らかに多様性が高い.パレオテチス大洋型ビルドアップは恐らく,古赤道遠洋域における有孔虫群集の発展にとって特に適した環境を提供していたことが示唆される.
Key words : Changhsingian, Changning-Menglian Belt, foraminiferal faunal succession, Late Permian, Lopingian, Paleotethys, Shifodong Formation, Southwest China, West
Yunnan, Wuchiapingian.
6. Sedimentary facies of Carboniferous-Permian mid-oceanic carbonates in the Changning-Menglian Belt, West Yunnan, Southwest China: Origin and depositional process
Tsutomu Nakazawa, Katsumi Ueno and Xiandong Wang
中国雲南省の昌寧-孟連帯に分布する石炭-ペルム系大洋型炭酸塩岩の堆積相:起源と堆積プロセス
中澤 努,上野勝美,王 向東
堆積年代がVisean(前期石炭紀)からChanghsingian(後期ペルム紀)に及ぶ巨大な炭酸塩岩体が,パレオテチス海の閉鎖域である中国雲南省の昌寧-孟連帯に分布する.炭酸塩岩体は玄武岩の基盤の上位に発達し,炭酸塩岩体内には陸源砕屑物質の挟在が全くない.これらの事実は,この炭酸塩岩体が,おそらくホットスポット起源の孤立した海洋島で形成されたことを示している.炭酸塩岩は浅海の炭酸塩プラットフォーム相とやや水深の大きい斜面相に分けられる.これらは同時異相であり,海洋島およびその周辺にかけての一連の炭酸塩堆積システムを構成している.このうち炭酸塩プラットフォーム相はプラットフォーム縁辺相,砂浜相,ラグーン相,干潟相に細分される.調査した魚塘寨セクションでは層序学的に下位から上位にむけて縁辺相から砂浜やラグーン相などの内側相へと変化し,炭酸塩プラットフォームがプログラデーションしていることが読み取れる.また下部石炭系には縁辺相の礁形成者としてワームチューブが認められるが,このような高エネルギー環境でのワームチューブの繁栄はこの時代には特異といえる.しかしその他の礁あるいはマウンド形成者の繁栄時期および干潟相の出現時期は,パンサラッサ海の秋吉石灰岩や青海石灰岩と同様であり,それらの産出はおそらく汎世界的なものであると考えられる.
Key words : Changning-Menglian Belt, Late Paleozoic, mid-oceanic carbonates, ocean island, Paleo-Tethys, sedimentary facies, Southwest China
7. Middle Permian radiolarians from Anmenkou, Chaohu, Northeastern Yangtze platform, China
Masao Kametaka, Hiromi Nagai, Sizhao Zhu and Masamichi Takebe
中華人民共和国,揚子プラットフォーム北東部巣湖地域庵門口から産出した中期ペルム紀放散虫化石
亀高正男,永井ひろ美,朱 嗣昭,武邊勝道
揚子プラットフォーム北東部,安徽省巣湖地域の庵門口セクションにおいて中部ペルム系Gufeng層の放散虫生層序を検討した.Gufeng層は下部の含リン酸塩ノジュール泥岩部層(PNMM)と,上部の珪質岩部層(SRM)に区分される.前者は主にリン酸塩ノジュールを含む泥岩からなり,後者は主にチャート・珪質泥岩・泥岩の互層から構成され,ポーラスチャートを挟む.PNMM下部から産出するアンモナイトはWordianの年代を示す.SRMのチャート・珪質泥岩・泥岩からは放散虫と海綿骨針が豊富に産出し,それらはWordian-Capitanianの年代を示唆する.放散虫の群集構成はSRM下部ではAlbaillellariaが優勢だが,SRM中部から上部にかけてはEntactinariaやSpumellariaが優勢となる.これらの放散虫化石はPseudoalbaillella longtanensis-Pseudoalbaillella fusiformis, Follicucullus monacanthus, Follicucullus scholasticus-Ruzhencevispongus uralicusの3つの放散虫化石帯に対比される.これらの放散虫と海綿骨針の群集は,堆積深度が150〜500m程度の水深であったことを示唆している.Gufeng層の放散虫化石群集は,中期ペルム紀の東部Paleotethysにおける,熱帯域での相対的に浅い水深の放散虫群集の代表例と考えられる.
Key words : biostratigraphy, Gufeng Formation, Middle Permian, northeastern Yangtze platform, radiolarian, sedimentary environments, sponge spicule.
8. Permo-Triassic Barrovian-type metamorphism in the ultrahigh-temperature Kontum Massif, central Vietnam:Constraints on continental collision tectonics in Southeast Asia
Nobuhiko Nakano, Yasuhito Osanai, Masaaki Owada, Yasutaka Hayasaka and Tran Ngoc Nam
中部ベトナム・コンツム超高温変成岩体に認められるペルム紀-トリアス紀Barrovian-type変成作用:東南アジアにおける大陸衝突テクトニクスへの制約
中野伸彦,小山内康人,大和田正明,早坂康隆,Tran Ngoc Nam
超高温変成作用で特徴づけられる中部ベトナム・コンツム地塊から藍晶石や十字石を含む中圧型の変成岩を見出した.これらは,同地塊北部に分布する.ザクロ石—ゼードル閃石—藍晶石片麻岩の変成鉱物組み合わせおよび変成組織の解析から,620〜650℃・1.1〜1.2 GPaのピーク圧力条件と730〜750℃・0.7〜0.8 GPaのピーク温度条件および時計回りの履歴が明らかとなった.モナザイトU-Th-PbEMP年代は246±3Maをしめす.これらの温度・圧力履歴と変成年代は,コンツム地塊南部に分布する超高温変成岩体と類似する.従って,コンツム地塊に認められる中圧型の変成作用は,超高温変成作用の成因と考えられているインドシナ-南中国地塊の衝突に密接に関連すると考えられ,本論はアジアにおける小大陸集合テクトニクスおよびその際の中〜下部地殻の物理現象に制約を与える.
Key words : Barrovian-type metamorphism, continental collision, garnet-gedrite-kyanite gneiss, Kham Duc complex, Kontum Massif, Permo-Triassic age, Vietnam.
9. Stress behavior from fault data sets within a transtensional zone, South Central Cordillera, Luzon, Philippines: implications to mineral occurrences
Mario A. Aurelio, Jocelyn B. Galapon, Violet T. Hizon and Dominic B. Sadsad
フィリピン,ルソンの南中央コルディレラにおける,横ずれ伸張場の断層データセットから求められる応力変化:鉱物産出との関係について
フィリピン,北部ルソンの南中央コルディレラのバギオ鉱床地域〜アンサン・チュバ・ベンゲット地域における構造的特徴は,NEからENE方向の断層により支配され,NNW-SSE方向の横ずれ伸張スリップを伴う.この長さ50km,幅25kmの長く伸びたテクトニックゾーンは,西はプゴ断層,東はテボ断層によって境にされる.これらの断層は,ともにフィリピン断層システムから分岐している.フラクチャーと鉱物脈システムの詳細な構造地質学的(特にマイクロテクトニックな)解析は,地域構造の方向に強く調和てきであることを示す.計算されたσ3方向の伸張ストレス軸は,平均N150°を示し,境界断層の走向に対しほぼ平行である.テクトニックストリップに関係した鉱床の存在とその産出見込みは,横ずれ伸張と鉱物産出との間に密接な関係が明らかである.
Key words : fault analysis, mineral occurrences, Philippine Fault System branches, South Central Cordillera, stress directions, transtensional strip.
10. Petrogenesis and tectonic setting of bimodal volcanism in the Sakoli Mobile Belt, Central Indian shield
Talat Ahmad, Kabita C. Longjam, Baishali Fouzdar, Mike J. Bickle and Hazel J. Chapman
インド中部・Sakoli Mobile Beltにみられるbimodal volcanismの成因とテクトニクス
インド中部・Sakoli Mobile Beltには,弱変成玄武岩および流紋岩が,変成堆積岩類とともに産する.玄武岩及び流紋岩の全岩化学組成は,それぞれ異なるトレンドをしめすが,両者とも高いREEおよびLIL元素の含有量で特徴付けられる.また,primitivemantleで規格化したパターンでは,U, Pb, Thの正の異常やNb, P,Tiの負の異常が認められる.これらは,典型的な大陸地域のリフト帯で認められる火山活動の特徴をしめす.Sm-Nd同位体組成により,1675±180 Maのアイソクロン年代が得られ,depleted mantleでのモデル年代は,玄武岩が2000〜2275 Ma,流紋岩類が2462〜2777Maをしめす.これは,流紋岩質マグマを形成した原岩が玄武岩質マグマのそれよりも古いことを表す.従って,Sakoli Mobile Beltに認められるbimodal volcanismの成因は,リフト帯におけるマントル起源の玄武岩質マグマの活動,および一部のマグマが地殻内にとどまることによって生じた地殻の部分溶融による流紋岩質マグマの形成で説明可能なのかもしれない.流紋岩中の比較的高いCrおよびNi含有量は,玄武岩との関連を示唆する.
Key words : bimodal volcanism, Central Indian tectonic zone, crustal contamination, enriched mantle source, magma underplating, rift tectonics.
11. Chromitite and peridotite from Rayat, northeastern Iraq, as fragments of a Tethyan ophiolite
Sabah A. Ismail, Shoji Arai, Ahmed H. Ahmed and Yohei Shimizu
イラク北東部ラヤト地域に露出するテティアン・オフィオライトの断片としてのクロミタイトおよびかんらん岩
Sabah A. Ismail,荒井章司,Ahmed H. Ahmed,清水洋平
オフィオライト帯であるザグロス・スラスト帯のイラク部分のラヤト地域から,初めてオフィオライト的な岩石(クロミタイトおよび蛇紋岩化したかんらん岩類)が岩石学的に詳細に調べられた.初生的な珪酸塩鉱物のほとんどは変質により消失しているが,クロムスピネルは残留しており,初生的な岩石学的性質の推定を可能にしている.蛇紋岩の原岩は単斜輝石を欠くハルツバーガイトであり,クロムスピネルのCr#(Cr/(Cr+Al)原子比)は0.5から0.6である.この性質を持ったハルツバーガイトはオマーンなどのテティアン・オフィオライトのマントル部分に最も普遍的に存在し,クロミタイトのホストとして最も適したものとされる.スピネルのCr#が0.6である一つのサンプルを除いて,クロミタイトのスピネルのCr#は0.7前後と高い.クロミタイト中のスピネルのCr#のこの程度の変化はオマーン・オフィオライトでも認められる.ラヤト地方のこのクロミタイト・ポッドを有するかんらん岩は,テティアン・オフィオライトの一つであるオマーン・オフィオライト(テティス海のリソスフェア断片)と同様な岩石学的性質を有するオフィオライトに由来する.これは,従来の地質学的な解析よりなされた解釈と整合的である.
Key words: chromitite, harzburgite, Iraq, Oman ophiolite, Rayat, Tethyan ophiolite.
通常論文
1. Cenozoic geodynamic evolution of the Andaman-Sumatra subduction margin: a Current understanding
Partha Pratim Chakraborty and Prosanta K. Khan
北アンダマンースマトラ沈み込み帯の新生代地質構造発達史-最新の知見
アンダマンースマトラ縁辺域は,ジャワ海溝,外弧プリズム,スリヴァー断層,前弧,海膨群,島弧の内側の火山群,背弧(引張応力場にあり,拡大軸を有する)より構成されており,沈み込み帯-付加帯複合体という独特の場にある.本論文では,現在までの知見をレビューし,本地域におけるテクトニクスを明らかにするうえで重要な地表および地下地質に関するいくつかの新たなデータを検討する.海溝沿いの一帯では,沈み込みに起因する変形が白亜紀から継続的にあるいは断続的に起こった.斜め沈み込みにより,アンダマンースマトラ縁辺域の北部で横ずれ断層が生じ,これにより沈み込み帯と右横ずれ断層群の間に,スリヴァープレートが形成された.スリヴァー断層は始新世に生じ,スマトラ島沖の外弧リッジからアンダマン海を経て,北方のサガイン断層へと連続する.本地域では,地域的なプレート運動により,多様な堆積盆が形成・発達した.さまざまな層準に,始新世の海溝充填堆積物を伴った,南北方向に伸張した白亜紀のオフィオライト岩体が多数みられる.それらは,一連の東傾斜の衝上断層に沿って上昇してきたものである.南北および東西方向の横ずれ断層によりプレートの沈み込みが規制され,その結果として前弧海盆が発達し,そこには漸新世から中新世・鮮新世にかけての時期に珪質砕屑岩・炭酸塩岩が堆積した.アンダマン海の背弧の形成は,2つのフェーズに分けられる.すなわち,11Ma頃のリフティングと4〜5Maの拡大である.アンダマン地域における島弧内側の火成活動は前期中新世に広がり,同時期以降,火成活動は珪長質から玄武岩質へと組成が変化した.
Key Words : Andaman-Sumatra margin, forearc basin, oblique subduction, subduction-accretion complexes, trench-slope basin
2. Across-arc geochemical variation of Quaternary lavas in West Java, Indonesia: Mass-balance elucidation using arc basalt simulator model
Yoga Andriana Sendjaja , Jun-Ichi Kimura and Edy Sunardi
インドネシア西ジャワ第四紀溶岩の島弧横断方向の地球化学変化:島弧玄武岩シミュレーターモデルによるマスバランスの検討
Yoga Andriana Sendjaja,木村純一,Edy Sunardi
インドネシア・スンダ弧はオーストラリアプレートとユーラシアプレートの収束帯にそって発達している.スンダ弧には20以上の第四紀火山が島弧にそって形成されている.西ジャワはスンダ弧の一セグメントであり10以上の火山が分布し,それらは和達・ベニオフ面深度120〜200kmの範囲と対応している.我々は6つの第四紀火山から採取した207試料の溶岩を検討した.溶岩は玄武岩からデイサイトの組成範囲を示す.液相濃集元素濃度は火山フロントから背弧にかけて増加し,それは低-カリウム岩系から高-カリウム岩系への変化と対応している.玄武岩溶岩のNd-Sr同位体組成は中央海嶺玄武岩(MORB)組成とインド洋堆積物(SED)組成の間に散開しており火山フロントの低-カリウム系列岩の方がより放射性のNdを多く含んでいる.このことは主としてインド洋堆積物起源の沈み込みスラブ由来のフルイドと,MORB起源マントル由来のメルトが混合して西ジャワのマグマが発生した事を示唆している.液層濃集元素の始源マントル規格化パターンは島弧横断方向わたって相互に類似しているが,背弧側ほど規格化パターンの傾斜がきつく,Srの正のスパイクが弱くなる.このことは背弧側マントルほど低い部分融解度で融解したとともに,SEDフルイド組成が火山フロントと背弧との間で変化していることを示している.フルイド組成の変化は,多成分微量元素組成とSr-Nd同位体組成を用いたフルイド付加部分融解モデルで説明が可能である.このようなスラブフルイドの組成変化は,スラブSED中のSrに富んだ含水珪酸塩鉱物,たとえばゾイサイト,がマグマ発生に関与しない浅い深度で選択的分解をおこす事によって説明可能である.背弧側玄武岩をつくるにはさらなるSrの枯渇とフルイド量の減少が必要である.このような島弧横断方向の組成変化は多くの島弧玄武岩に認められる.それらの原因は,スンダ弧と同じ成因である可能性がある.
Key Words : arc magma, Indonesia, slab fluid, Sr-Nd isotopes, Sunda Arc, trace element
3. Intergranular trace elements in mantle xenoliths from Russian Far East: Example for mantle metasomatism by hydrous melt
Junji Yamamoto, Shun’ichi Nakai, Koshi Nishimura, Ichiro Kaneoka, Hiroyuki Kagi, Keiko Sato, Tasuku Okumura ,Vladimir S. Prikhod’ko and Shoji Arai
極東ロシアに産するマントル捕獲岩の粒間微量元素組成:含水メルトによる交代作用
山本順司,中井俊一,西村光史,兼岡一郎,鍵裕之,佐藤佳子,奥村 輔,Vladimir, S. Prikhod’ko,荒井章司
極東ロシアに産するマントル捕獲岩の主要元素組成及び微量元素組成から粒間成分の存在を突き止めた.マントル捕獲岩の全岩微量元素組成には明らかな負異常がCe, Th及びHFSEに見られる.しかし構成鉱物の微量元素組成にはそのような異常は見られない.これは全岩組成を左右するほど微量元素に富んだ粒間成分の存在を示唆し,LA-ICP-MSを用いたその場分析によりその存在が確認できた.また,メルト包有物からも粒間成分と同じ微量元素組成が得られたことから,この粒間成分はマントル流体であることが判明した.さらに,顕微ラマン分光分析によってメルト包有物の内壁から含水鉱物が検出されたため,この粒間成分はマントル中の含水交代流体であると言える.
Key Words : intergranular component , LA-ICP-MS , mantle wedge , mantle xenolith , melt inclusion
リーフレットシリーズ
リーフレットシリーズ一覧
*新しいリーフレットの企画も募集しています.詳しくはこちら
購入希望の場合は,学会事務局までお申し込み下さい.
mail:main@geosociety.jp(@を半角にして下さい) FAX:03-5823-1156
また箱根のリーフレットは、神奈川県立生命の星地球博物館や箱根周辺の土産物ショップなどでも販売しています.
*画像をクリックすると各リーフレットの詳細がご覧頂けます。
地質リーフレット
たんけんシリーズ4
青木ヶ原溶岩のたんけんー樹海にかくされた溶岩の不思議ー
定価400円
(会員頒価300円)
2014年3月31日発行
地質リーフレット
たんけんシリーズ5
長瀞たんけんマップー荒川が刻んだ地球の窓をのぞいてみようー
定価400円
(会員頒価300円)
2016年2月20日発行
地質リーフレット
たんけんシリーズ3
城ヶ島たんけんマップー深海からうまれた城ヶ島ー
定価400円
(会員頒価300円)
2010年9月発行
日本地質学会リーフレット4
日本列島と地質環境の長期安定性
定価600円
(会員頒価500円)
2011年1月発行
地質リーフレット
たんけんシリーズ2
屋久島地質たんけんマップー洋上アルプスは不思議がいっぱいー
定価400円
(会員頒価300円)
2009年3月発行
日本地質学会リーフレット3
大地をめぐる水ー水環境と地質環境
定価400円
(会員頒価300円)
地質リーフレット
たんけんシリーズ1
箱根火山たんけんマップ ー今、生きている火山ー
定価400円
(会員頒価300円)
2007年5月発行
日本地質学会リーフレット2
大地のいたみを感じようー地質汚染Geo−Pollutions
定価300円
(会員頒価200円)
地質リーフレット1
箱根火山
定価1300円
(会員頒価1000円)
2007年7月発行
※売り切れ
日本地質学会リーフレット1
大地の動きを知ろうー地震・活断層・地震災害ー
定価300円
(会員頒価200円)
※売り切れ
リーフレット企画募集
リーフレット企画募集案内
表1.リーフレットの種類と対象
日本各地の地質を専門家や一般の方々,そして子供達にわかりやすく紹介するリーフレットを募集します.大地に関する地質研究の成果を積極的に社会に還元しましょう.手続きは下の図のようになります.企画に関わる細則と必要書類は,学会ホームページまたは事務局<main@geosociety.jp>へお問い合わせ下さい.
リーフレット企画出版委員会
→これまで出版されたリーフレットを見る
図1.リーフレット企画・出版の流れ
企画出版に関わる書類
(アイコンをクリックすると各書類がダウンロード出来ます)
■ 企画提案書
■ 著作権譲渡等同意書
■ 著作物使用承認申請書/許可書
-----------------------------------------------------------------------
■ リーフレット出版細則(3種類:地質リーフレット/たんけんシリーズ/日本地質学会リーフレット)
フィールドノート
学会オリジナル フィールドノート
再販記念キャンペーン
会員・非会員問わず 特別価格800円!(2026.3月末まで)
ご好評いただいております,学会オリジナルフィールドノートの再販を開始します.今回増刷分より価格改定いたします.また10冊以上のご注文には割引価格を設けました.ノートの使用はほぼ変更はありません(しおりひもがなくなりました).
名入れサービスもこれまで同様に承ります(有料)。卒業記念やイベントでのグッズなど幅広くご利用下さい。 名入れ(箔押し)のための版代が別途加算されます(目安:45文字/100冊/30,000円程度(ノート代別).文字数,印字サイズなどにより価格は異なります)。詳しくは事務局までお問い合わせ下さい。
ビニールコーティングの表紙は,水や摩擦・衝撃にも強く野外調査に最適です。ぜひご活用ください。
サイズ:12×19cm.
中:レインガード紙使用.2mm方眼.
カバー:ハードカバー,ビニールコティング,金箔押し.
色:ラセットブラウン(小豆色)
通常価格(2026年4月以降)定価:1200円 会員頒価:900円
※10冊以上おまとめ購入の場合,定価1100円(会員頒価800円)
ご希望の方は学会事務局まで main[at]geosociety.jp
The Journal of the Geological Society of Japan
The Journal of the Geological Society of Japan
日本語ページはこちらから
↓Submit New Manuscript & Author MENU↓
https://mc.manuscriptcentral.com/geosoc
■ Instruction for Authors ■ Guaranty ■ Author Agreement
「Journal Scope」
The Journal of the Geological Society of Japan (JGSJ) is issued monthly by the Geological Society of Japan (est. 1893), which is the largest society of its type in Japan, with approximately 4300 members. The JGSJ publishes original research papers in geology and related fields in the form of Articles (Ronsetsu in Japanese) or Short Articles (Tanpou), and publishes reviews of research and technical advances as Review Articles (Sohsetsu) or Notes (Nohto), in either English or Japanese. The journal places an emphasis on publishing original, novel, and widely applicable scientific results, techniques, theory, and ideas, and attaches great importance to descriptions of regional geology, both in Japan and internationally. The journal also welcomes research papers concerned with natural resources, the environment, and hazards, as well as geology education. To advance the quality of the journal and ensure the timely publication of a rich variety of material, the journal is served by a full Editorial Board comprising many active researchers in various fields.
「Unique features of the journal」
(1) Stable, high-quality publication
The JGSJ has been published continuously for 110 years since its inception in 1893, comprising 115 volumes and 1363 issues to date. The Editorial Board has recently been strengthened (see point (4) below) to ensure the reliable publication of high-quality material. In addition, all papers published since 1893 are freely available via the Internet, thereby providing worldwide access to a wealth of research information and data. For all papers, the journal provides English- and Japanese-language versions of the title, authors’ names and
affiliations, abstract, keywords, and reference list, which ensures easy searching and access. To maximize efficiency, the journal employs an on-line submission and peer-review system.
For the archiving of past issues of the journal and for the on-line submission and peer-review system mentioned above, the journal employs J-STAGE (Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic), as established by the Japan Science and Technology Agency (JST) (see http://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc).
(2) International access
For all papers in JGSJ, bibliographic information (title, authors’ names and affiliations, abstract, keywords, and reference list) is provided in English, as well as captions and legends for the figures and tables, thereby providing access to readers across the world. Over the past 5 years since 2004, 14 papers (3.8% of the total papers) have dealt with geology outside of Japan and 5 foreign authors (1.3%) have published in the journal. When Pictorials are taken into account, these figures increase to 46 papers (12.4%) and 25 foreign authors (6.7%), respectively, providing an indication of the potential for international contributions as full papers (e.g., Articles and Short Articles).
(3) Citations of journal papers, publishing authors, and the Editorial Board
The number of citations of JGSJ papers (as assessed using the Cited Reference Search as part of the Web of Science) shows an increasing trend, from about 10 per year in the 1960s to 60–80 per year or more in the 2000s. Most of the members of the Editorial Board are active researchers at the forefront of their respective international communities, covering numerous fields related to geology and earth science. For special issues, members of the editorial board work together with guest editors in the review and publication process, thereby ensuring the timely publication of high-quality papers on specific topics.
Island Arc 日本語要旨 2009. vol. 18 Issue 2 (June)
Vol. 18 Issue 2 (June)
特集号
Microchronology and Microchemistry: Problems, perspectives and geological applications
Guest editors: Tetsumaru Itaya and Simon Wallis
1.Microstructurally controlled monazite chronology of ultrahigh-temperature granulites from southern India: Implications for the timing of Gondwana assembly
M. Santosh, Toshiaki Tsunogae, Yoshiyuki Tsutsumi and Masayuki Iwamura.
南インドの超高温変成岩に含まれるモナザイトの微細組織をもとにした年代学:ゴンドワナ大陸集合の時期について
M. Santosh,角替敏昭,堤 之恭,岩村誠之
南インドAchankovil剪断帯およびMadurai岩体最南部の超高温グラニュライトについて,EPMAによるU-Pb年代測定を行った.この超高温変成岩は,ざくろ石,菫青石(後退変成鉱物),石英,メソパーサイト,黒雲母,斜長石,Fe-Ti酸化物を含み,一部の岩石には斜方輝石や珪線石もみられる.また微量のジルコンとモナザイトを含み,珪線石はざくろ石の包有物としてのみ産出する.組織の詳細な解析から,ざくろ石,斜方輝石,スピネル,メソパーサイトはピーク変成作用時に形成された鉱物であり,菫青石±斜方輝石±石英や菫青石+スピネル+Fe-Ti酸化物のようなピーク後に形成された鉱物組み合わせもみられる.地質温度圧力計による解析結果から,ピークおよび後退変成作用の温度圧力条件は,それぞれ940-1040℃,8.5-9.5 kbar,3.5-4.5 kbar,720±60℃である.円摩された,おそらく砕屑性のモナザイトからは,原生代中期〜後期の幅広い年代が得られた.その中の若いものは660-600Maの年代を示すことから,原岩の堆積岩は600Maまでに堆積したことが考えられる.一方,多くのモナザイトは変成作用時の成長を示す,これらは原生代最末期〜カンブリア紀初期の年代を示し,533-565Maにピークをもつが,これがピーク変成作用の時期を意味するとはかぎらない.ピーク時に安定な鉱物と共生する均質なモナザイトの測定により,ピーク変成作用は580-600Ma起こったと考えられる.隣接するグラニュライト岩体の年代との比較から,インドにおけるゴンドワナ大陸の衝突時期は580-600Maであり,過去に報告されている500-550 Maの年代はピーク後の熱イベントを意味すると考えられる.
Key word : Gondwana, microchronology, monazite, southern India,ultrahigh-temperature metamorphism
2. K-Ar and 40Ar/39Ar phengite ages of Sanbagawa schist clasts from the Kuma Group, central Shikoku, southwest Japan
Nguyen D. Nuong, Tetsumaru Itaya, Hironobu Hyodo and Kazumi Yokoyama
西南日本四国中央部久万層中の三波川片岩礫の白雲母K-Arと40Ar/39Ar年代
Nguyen D. Nuong,板谷徹丸,兵藤博信,横山一巳
西南日本四国中央部久万層の礫岩には三波川片岩礫を含む.その変成度と原岩は様々である.泥質片岩中の白雲母のK-Ar及び40Ar/39Ar年代測定結果は低変成度から高変成度まで同じ年代(82-84Ma)を示した.その年代は四国中央部三波川変成帯の白雲母年代より明らかに古い.それは久万—三波川変成岩は汗見川-三波川変成岩より上昇時期が早かったことによる.また,上昇プロセスは関東-三波川における上昇プロセスと汗見川-三波川のプロセスとの中間的であった.角閃岩中の白雲母40Ar/39Arプラトー年代(103Ma,107Ma)は変成帯の上昇初期を示し,ピーク変成年代に近い.
Key word : 40Ar/39Ar age, argon closure system, exhumation tectonics, K-Ar age, Kuma Group, phengite, Sanbagawa schist clasts
3. Petrology, geochronology and tectonic implications of Mesozoic high Ba-Sr granites in the Haemi area, Hongseong Belt, South Korea
Seon-Gyu Choi, V.J. Rajesh, Jieun Seo, Jung Woo Park, Chang Whan Oh, Sang Joon Pak and Sung Won Kim
韓国ヘミ地域のホンソン帯に産する中生代高Ba-Sr花崗岩の岩石学及び年代学とそのテクトニクス
中国北部大陸塊と南部大陸塊の衝突は韓半島ではペルム紀(290-260Ma)に始まった.キョンギ山塊内にあるヘミ地域ホンソン衝突帯,それは中国におけるDabie-Sulu衝突帯の東方延長と考えられているが,衝突後に形成された中間組成の捕獲岩を含む高Ba-Sr花崗岩からなる.その花崗岩は先カンブリアの岩石に貫入した産状を呈す.中間組成の捕獲岩はショショナイトに類似しているが花崗岩は高Kカルクアルカリ岩系列に入る.コンドライトに規格化されたREEパターンでは両岩石ともLREEに富むとともに顕著なEuの負異常を持たない.両岩石の化学的な類似性はその成因においてマントル起源物質が関わっていると言える.しかしながら,高Ba-Sr花崗岩の形成には地殻成分が深く関わっている.SHRIMPジルコンU-Pb年代測定からその結晶化年代は233±2Maであった.この年代はホンソン帯におけるトリアス紀衝突事件より僅かに若い.このように地球化学データー,ジルコンU-Pb年代,広域テクトニクスからヘミ高Ba-Sr花崗岩は衝突後のテクトニクスで形成されたと言える.その成因には中生代の衝突後に生じたリソスフェアの剥離モデルで説明できる.
Key word : High Ba-Sr granite, post-collisional, lithospheric delamination, Haemi, Hongseong Belt, Dabie-Sulu
4. Regional-Scale Excess Ar wave in a Barrovian type metamorphic belt, eastern Tibetan Plateau
Tetsumaru Itaya, Hironobu Hyodo, Tatsuki Tsujimori, Simon Wallis, Mutsuki Aoya, Tetsuo Kawakami and Chitaro Gouzu
東チベット高原バロー型変成帯で発生した広域過剰アルゴン波
板谷徹丸,兵藤博信,辻森 樹,Simon Wallis,青矢睦月,川上哲生,郷津知太郎
チベット高原の東部に分布するバロー型変成帯から系統的に採集した変成岩からの黒雲母と白雲母についてレーザー段階加熱法40Ar/39Ar年代測定を実施した.その結果,変成温度が600℃を超えた珪線石帯では,およそ40Maの冷却年代が得られた.しかし,その温度より低い変成域では,同様な試料から46-197Maの不一致年代が得られた.珪線石帯の変成ピーク年代はモナザイトCHIME年代(64Ma)やアパタイトSHRIMP年代(67Ma)から得られており,藍晶石帯までの変成岩からの黒雲母の見かけ年代(46-94Ma)は不完全な脱ガスによる母岩由来の過剰アルゴンに起因すると推察される.一方,藍晶石帯高温部では,黒雲母が130-197Maの見かけ年代を示す.藍晶石帯におけるこの異常に古い見かけ年代はおそらくより高温の珪線石帯の鉱物から脱ガスされ移動してきた過剰アルゴンを黒雲母が捕獲した結果であろう.この過剰アルゴンの起源は珪線石帯の白雲母が分解したとき生じたものと考えられる.また,共存する白雲母には異常な量の過剰アルゴンがみられないことから,研究地域は白雲母のアルゴン閉鎖温度以下まで冷却した後,黒雲母の閉鎖温度に達した段階でちょうど移動してきた過剰アルゴン波にさらされて黒雲母にだけ異常な量の過剰アルゴンが捕獲された.つまり黒雲母にだけ異常な量の過剰アルゴンを持つ藍晶石帯高温部は過剰アルゴン波の発生とその移動を記録している場所であると考えることができる.このように超高圧変成作用後の上昇冷却過程での白雲母の分解は超高圧変成帯でよく見られる異常に古いK-Ar年代を与える要因の一つと理解することができる.広域変成帯に発生する過剰アルゴン波を見いだしたのは今回が初めてであろう.この研究では,また,雲母類のアルゴン閉鎖温度は従来考えられてきたより十分に高温であり600℃近くまで達することもあり得ることが明ら
かになった.
Key words : 40Ar/39Ar analyses, Barrovian type metamorphism,closure temperatures, Eastern Tibet, excess argon wave,Longmenshan orogenic belt
通常論文
1. Timing of dextral oblique subduction along the eastern margin of the Asian continent in the Late Cretaceous:
Evidence from the accretionary complex of the Shimanto Belt in the Kii Peninsula, Southwest Japan.
Tetsuya Tokiwa
後期白亜紀のアジア大陸東縁部における右斜め沈み込み時期:西南日本紀伊半島に分布する四万十帯付加体からの証拠
常盤哲也
古地磁気やホットスポット軌跡によると,コニアシアンからカンパニアンにおけるユーラシアプレートには,クラプレートよる右斜め沈み込みが生じていたと考えられている.しかし,このクラプレートの右斜め沈み込みについて,地質学的な証拠はない.そこで,本研究では,西南日本に分布するコニアシアンからカンパニアン前期の四万十帯美山層において,構造地質学的研究を行った.その結果,美山層のメランジファブリックは露頭および顕微鏡スケールのどちらにおいても右ずれを示し,マップスケールにおいて確認されたスラストシステムも右ずれを示すことが明らかとなった.このことは,コニアシアンからカンパニアン前期のアジア大陸東縁部において,クラプレートによる右斜め沈み込みが生じていたことを示唆する.既存の構造地質や時代に関する情報を合わせて考えると,西南日本における左斜め沈み込みから右斜め沈み込みの変換点は89Ma,右斜め沈み込みから左斜め沈み込みの変換点は76Maであったと考えられ,白亜紀の東アジア大陸縁におけるプレート運動の復元モデルと良い相関関係を示す.
Key words : accretionary complex, Cretaceous, mélange, plate motion, shear direction, Shimanto Belt, Southwest Japan.
2. Occurrence conditions of hyperpycnal flows, and their significance for organic-matter sedimentation in a Holocene estuary, Niigata Plain, Central Japan
Mamiko Yoshida, Yuka Yoshiuchi and Koichi Hoyanagi
ハイパーピクナル流の発生条件とそれに伴う陸源有機物濃集の意義:新潟平野完新統のエスチュアリー堆積物を例として
吉田真見子,吉内佑佳,保柳康一
タービダイトには斜面崩壊を起源とするものと洪水を起源とするハイパーピクナイトがある.本研究では,縄文海進に伴って形成された新潟平野完新統のエスチュアリー堆積物中に挟在されているハイパーピクナイトを対象に,エスチュアリー内の環境変化とハイパーピクナル流の発生との関連性や,それに伴う有機物の堆積作用を明らかにした.ハイパーピクナイトは,エスチュアリー堆積物の最上部(約5,000年前)に挟在され,上方粗粒化と細粒化のセットを繰り返し,陸源有機物と淡水生の珪藻化石を多く含むことを特徴とする.本研究の結果は,エスチュアリー堆積物最上部の堆積期間に淡水が流入する割合が増加し,それに伴ってラグーン内の塩分濃度が低下したことを示す.この塩分濃度の低下はラグーン内の水の密度低下を招き,洪水発生時にハイパーピクナル流を発生しやすい状況を作っていたと解釈できる.また,ハイパーピクナイトの最上部には,陸源有機物の濃集層が存在する.この特徴は,海成堆積物において,崩壊性タービダイトと洪水を起源とするハイパーピクナイトとを区別するための重要な指標になると考えられる.
Key words : diatom fossil, estuarine lagoon, hyperpycnite, Niigata Plain, organic matter, river floods.
3. Style of fluid flow and deformation in and around an ancient out-of-sequence thrust: An example from the Nobeoka Tectonic Line in the Shimanto accretionary complex, Southwest Japan
Hideki Mukoyoshi, Tetsuro Hirono, Hidetoshi Hara, Kotaro Sekine, Noriyoshi Tsuchiya, Arito Sakaguchi and Wonn Soh
アウトオブシーケンススラストの変形及び流体の移動様式−四万十付加体中に発達する延岡構造線を例に−
向吉秀樹,廣野哲朗,原 英俊,関根孝太郎,土屋範芳,坂口有人,徐 垣
アウトオブシーケンススラスト(OST:プレート沈み込み境界の深部から派生する大規模逆断層)における岩石の変形およびそこでの流体の移動様式を明らかにするために,かつてのOST(海底下7-9km相当)と解釈されている,四万十付加体中に発達する延岡構造線の野外地質調査を実施した.その結果,延岡構造線は下盤に厚い剪断帯を伴い,その厚さは岩相に依存して走向方向に100-300mと変化することが明らかになった.黒色頁岩主体の砂岩頁岩混在層からなる剪断帯は,厚さが相対的に薄く,直線的な剪断面に沿って,数mmから数cm厚の鉱物脈が産出する.一方,砂岩主体の砂岩頁岩混在層からなる剪断帯では,厚さが相対的に厚く,規則的に配列するレンズ状の砂岩ブロックを多く含み,微小クラックを充填する大量の鉱物脈がその砂岩ブロック中に含まれる.これらの鉱物脈の光学顕微鏡像およびカソードルミネッセンス像の考察より,砂岩優勢の薄い剪断帯中の鉱物脈は,剪断面形成と同時に高間隙圧の流体が流れた痕跡であり,頁岩優勢の厚い剪断帯中の鉱物脈は,微小クラックが形成されるたびに少しずつ流体を排出した痕跡であると考えられる.また,これらの深部OSTの剪断帯の特徴を先行研究による浅部OSTのそれと比較した結果,浅部OSTでは急激な滑りを伴う脆性破壊と局所化した流体移動の繰り返しが生じているのに対し,深部OSTでは岩相に依存して,脆性破壊および延性変形が共存し,様々な様式の流体移動を伴うことが明らかになった.
Key words : cathodoluminescence, fluid flow, illite crystallinity,Nobeoka Tectonic Line, out-of-sequence thrust, Shimanto accretionary complex.
4. Petrochemistry of sandstones from Neoproterozoic basins of the Bastar craton, Central Indian Shield: Implications for paleoweathering, provenance and tectonic history
Hamiduulah Wani and Mohammad E. A. Mondal
中央インド楯状地,Bastar cratonの新原生代盆地の砂岩の岩石化学:古風化,給源,造構史に関して
Chandarpur GroupとTiratgarh Formationの新原生代の砂岩について,その給源,テクトニック・セッティング,風化環境を決定するために,記載岩石学的解析および希土類元素を含む主要,微量元素の化学分析を行った.砂岩のサンプルは全て石英に著しく富むが,長石や岩片に非常に乏しい.これらは,記載岩石学的および地球化学的に,subarkose,sublitharenite,areniteに分類される.Chemical Index of Alteration(CIA,平均値68)とTh/U比(平均値4.2)は,これら砂岩が中程度の風化を受けたことを示唆している.Post Archean Australian ShaleおよびUpper ContinentalCrustと比較すると,全ての砂岩サンプルは,概してSiO2以外の主要元素,Zrを除く微量元素,希土類元素に著しく枯渇している.鉱物構成,給源およびテクトニック・セッティングの決定に有効な元素比平均値[Al2O3/SiO2(0.02),K2O/Na2O(10),Eu/Eu*(0.67),(La/Lu)n(10.4),La/Sc(3),Th/Sc(1.2),L a/Co(0.22),Th/Co(0.08),and Cr/Th(7.2)など]は,これらの砂岩がフェルシックな給源をもち,非活動的縁辺域に由来することを支持している.これらの鍵となる元素比はSiO2の広い範囲にわたって大きな変動を示さないことから,石英に富む砂岩の原岩の特徴を決定する際の有意性も検証する.軽希土類元素に富みEuの強い負の異常をもつ希土類元素パターンも,これらの砂岩の給源がフェルシックであることに起因する.砂岩の原岩はBaster cratonの花こう岩と片麻岩で,ごく一部はBaster cratonのより古い表層部の岩石に由来するかもしれない.古原生代のSakoli schistsの主要元素は,新原生代の砂岩と比較すると,Sakoli schistsが塩基性の岩石に由来し,活動的縁辺域で堆積したことを示唆している.しかしながら,Sakoli schistsと原生代砂岩のCIA値にはほとんど差が無く,Baster cratonにおいて,原生代を通じて中〜高度の同様な風化環境が広がっていたことを示している.我々の研究は,給源およびテクトニックセッティングが,古原生代の苦鉄質な給源が卓越する活動的縁辺域から新原生代の花こう岩および片麻岩(珪長質な給源)が卓越する非活動的縁辺域へ変化したことをも示唆している.
Key words : Bastar craton, Neoproterozoic sandstones, Paleoproterozoic Sakoli schists, petrochemistry, provenance, tectonic history, weathering.
5. Melt-wall rock interaction in the mantle shown by silicate melt inclusions in peridotite xenoliths from the central Pannonian Basin(western Hungary)
Csaba Szabó, Károly Hidas, Enikö Bali, Zoltán Zajacz, István Kovács, Kyounghee Yang, Tibor Guzmics and Kálmán Török
西ハンガリー,中央パノニアン盆地産かんらん岩捕獲岩中のシリケイトメルト包有物からみたマントル内におけるメルト− 母岩相互作用
西ハンガリー,Balkony-Balaton Highland Volcanic Field,Szigliget産の等粒状組織をもつ角閃石を含む二つのスピネルレールゾライト捕獲岩の組織ならびに地球化学的特徴を検討した.これらは,単斜輝石縁部に多数の初生シリケイトメルト包有物と,斜方輝石(稀にスピネル)の古い割れ目(healed fractures)に沿って認められる二次的なシリケイトメルト包有物を含む. シリケイトメルト包有物は,主にシリケイトガラスと二酸化炭素に富む気泡からなる.単斜輝石と斜方輝石は特にFe,Mg,Na,Al量に関して顕著な累帯構造をもつ.単斜輝石の核部は,初生マントル組成に近い微量元素分布を示し,縁部はTh,U,軽希土類元素(LREE),中希土類元素(MREE)に富む.捕獲岩試料Szg08中の角閃石は,異常に高いRb,Ba,Nb,Ta,LREE,MREEをもつ.シリケイトメルト包有物中のシリケイトガラスの組成は,玄武岩質粗面安山岩,安山岩からフォノライト組成まで広い範囲に及び,特にP2O5に富む.初生および二次的シリケイトメルト包有物は,共に不適合微量元素(主にU,Th,La,Zr)に著しく富み,わずかにHfの負の異常を示す.単斜輝石縁部での初生シリケイトメルト包有物の取り込みと同様に,累帯構造をもつ輝石は,おそらく熱い揮発性成分を含むメルトとマントルの壁岩との相互作用により,部分溶融とそれに続く単斜輝石の晶出後に形成された.このシリケイトメルトは斜方輝石の微小割れ目を埋め,その結果,二次的なシリケイトメルト包有物が形成された.
Key word : central Pannonian Basin, Hungary, melt-mantle interaction, mantle xenolith, silicate melt inclusion
Island Arc 日本語要旨 2009. vol. 18 Issue 3 (September)
Vol. 18 Issue 3 (September)
特集号
Papers arising out of 22nd Himalaya-Karakorum-Tibet Workshop (HKT22)
Guest Editor : Jonathan Aitchson and Simon Wallis
1. Sediment sequences and paleosols in the Kyichu Valley, southern Tibet (China), indicating Late Quaternary environmental changes
Knut Kaiser, Zhongping Lai, Birgit Schneider, Werner H.Schoch, Xuhui shen, Georg Miehe and Helmut Brückner
中国,南部チベットKyichu Valleyにみられる堆積シーケンスと古土壌が示す後期第四紀における環境変化
チベット高原は環境変化に非常に敏感であり,その環境変化は中央アジアおよびその周辺域の環境にも影響を与える.したがって,本地域における環境変化に関する知見は重要である.Kyichu Valley(ラサ川)およびその支流は容易にアクセス可能な地域であるにも関わらず,南部チベットにおける後期第四紀の地形変化はほとんど知られていない.そこで,本地域の環境変化を明らかにするために,Kyichu Valleyの中流および下流域の12セクションで,堆積学的・古土壌学的・年代学的(AMS14C年代およびルミネッセンス年代)・古植物学的検討を行った.標高3600〜4000mでは氷河の痕跡は見出されず,これはKyichu Valleyは最終間氷期以来,氷河に覆われたことはなかったということを意味している.本地域はテクトニックに活動的であり,古い河川谷が沖積層に覆われるため,aggradationalな堆積体が形成されている.このため、氾濫原上に河川や湖沼に特有の堆積構造がみられない.後期第四紀に,Kyichu Valleyの河口域は湖沼となったが,それは本谷が合流するYarlung Zhangbo Valleyに形成されたダム湖の一部であった.本谷の両岸では,最終氷期最盛期前には黄土が,最終氷期最盛期前およびその後には風成砂が主に堆積した.最終間氷期,最終氷期,完新世の古土壌がみられることより,土壌の形成時の環境は温暖〜冷涼かつ湿潤〜亜乾燥であったと思われる.崩積堆積物の年代は,Kyichu Valleyの両岸斜面が広範に無植生となったのは,主に後期更新世の浸食とそれに引き続く完新世の二次的な浸食によるものであることを示している.また,古植物学的検討により,本地域では後期完新世に,森林から草木や低木の散在する草原へと環境が変化したことが判明した.森林の消滅や浸食の進行といった後期完新世の環境変化の少なくとも一部は人間活動によって促進され,地域的な気候の乾燥化と冷涼化を増進したと推定される.
Key words: colluvial , eolian , fluvial , lacustrine , Lhasa River
2. Anisotropy of magnetic susceptibility and petrofabric studies in the Garhwal synform, Outer Lesser Himalaya: Evidence of pop-up klippen.
Upasana Devrani and Ashok K.Dubey
レッサーヒマラヤ外帯のガーワル向斜構造における構造岩石学及び帯磁率の異方性解析から推定されるポップアップクリッペ群の存在
レッサーヒマラヤ外帯西部に位置するガーワル向斜構造域における,野外地質学的観察及び岩石学的記載と帯磁率異方性解析は,同地域の形成史を理解するために有用である.帯磁率の主軸は短い空間スケールにおける大きな変化を示し,これは重複変形の存在,また正断層運動に適した応力場の影響を示唆する.向斜構造の軸から離れた翼領域では,岩石は低度緑色片岩相までの変成作用を被っている.一方,褶曲軸部に近づくにつれて変成度は緑泥石−黒雲母帯まで上昇する.変成度が異なる領域の境界には衝上断層が存在し,大規模なポップアップクリッペ群構造として説明できる.
Key words : fault reactivation , Himalayan seismicity , neotectonic stress , strain , superimposed deformation
3. Provenance and thermal history of the Bayan Har Group in the western-central Songpan-Ganzi-Bayan Har terrane: implications for tectonic evolution of the northern Tibetan Plateau
Guo-Can Wang, Robert P. Wintsch, John I. Garver, Mary Roden-Tice, She-Fa Chen, Ke-Xin Zhang, Qi-Xiang Lin, Yun-Hai Zhu, Shu-Yuan Xiang and De-Wei Li
西部〜中部Songpan-Ganzi-Bayan HarテレーンにおけるBayan Har層群の起原及び熱史:北部チベット高原のテクトニックな発達の解釈
北部チベット高原に分布するSongpan-Ganzi-Bayan Harテレーンには,三畳紀のタービダイトが卓越する.三畳紀Bayan Har層群タービダイト中の砕屑性ジルコンのU-Pb年代は,400-500 Ma, 900-1000 Ma, 2400-2500 Maにピークをもつ. これらの結果は, 北方のEast Kunlun, Altyn, Qaidam, Qilian, Alaxa地域の先三畳紀の基盤岩の最近公表されたU-Pbジルコン年代とよく一致し, Bayan Har層群の原岩にこれらの岩石が含まれることを示唆している. このことは, Bayan Har 層群の石質アレナイトと北方のEast Kunlunテレーンの三畳紀前〜中期層の砂岩との組成上の類似性からも支持される. 石炭紀〜二畳紀中期のメランジュ層とその上に載る後期二畳紀あるいは三畳紀の地層との間の露出状況の良い傾斜不整合の露頭は, 二畳紀中期と二畳紀後期の間に広域的な変形作用が起こったことを示している. この変形作用は、QiangtangテレーンとNorth China Plateの間に起こった比較的穏やかな衝突, および古テチス海の閉塞の結果であるかもしれない. Bayan Har層群のタービダイトは, 再びひらいた海盆の陸棚環境で堆積した. Bayan Har層群の砕屑性のジルコンを用いたフィッション・トラック年代は, 堆積前および堆積後の年代を示し, 飛跡が熱的に修復される温度(250-300℃)に達しなかったことを示唆している. Uの低濃集によって定義される282-292 Maのピーク年代もまた北方の花こう岩の給源を反映しているように思われる. 南部地域の豊富な火山岩片をもつ二つの石質アルコースから得られた自形のジルコンは, およそ237 Maのピーク年代を与え, おそらく最も古い堆積年代を記録している. 卓越する堆積後の170-185 Maのピーク年代は, ジュラ紀初期に最高温度に達したことを示唆している. いくつかの試料には, およそ140 Maのより新しい熱事件(thermal event), すなわち最も不安定なジルコンにのみ影響を与えるような短時間の熱事件をあらわしているように思われる.
Key words : Bayan Har Group turbidites , detrital zircon fission-track age dating , detrital zircon U-Pb age dating , northern Tibetan Plateau , provenance , tectonic evolution , thermal history
4. Origin of the Gangdise (Transhimalaya) Permian arc in southern Tibet: Stratigraphic and volcanic geochemical constraints
Quan-Ru Geng, Zhi-Ming Sun, Gui-Tang Pan, Di-Cheng Zhu and Li-Quan Wang
南部チベット、二畳紀Gangdise(Transhimalaya)島弧の起源:層位学的および火山岩の地球化学的制約
南部チベットGangdise テレーンの中生代および新生代火山岩は,新テチス海の沈み込みによって生じたと考えられてきた.しかし,後期古生代の火山岩およびそのテクトニックセッティングはほとんど研究されていない.我々は,中部Gangdiseテレーンに位置する,断層で周囲と画された東西方向に伸張した隆起帯中にみられるペルム系の火山岩・堆積岩シーケンスに関する層位学的・地球化学的検討を行った.本地域の堆積岩はプラットフォーム性の炭酸塩岩と陸源性砕屑岩より構成されており,これは北部ゴンドワナ一帯に浅海性堆積盆が広がっていることを意味する.また,ペルム系堆積岩からは,当時,海退もしくは隆起があり,地域的に河川が形成されたことが判読される.火成活動には,玄武岩の噴出とそれより後の珪長質マグマの噴出という2つのステージが認められる.前者はMaizhokunggar(Tangjia)およびLhunzhubに露出するソレアイト質玄武岩溶岩によって代表され,その年代は前期〜中期ペルム紀である.下部ペルム系玄武岩は相対的にMgOに富み(4.58〜12.19%),中部ペルム系玄武岩はAl2O3含有量が高い(11.75〜21.22%).両時代の玄武岩とも,LIL元素および軽希土類元素に富み,顕著なNbとTbの負のアノマリーを示す.全希土類含有量および軽希土類元素/重希土類元素比は,前期ペルム紀から中期ペルム紀にかけて増加した.Sr,Nd,Pbに関しては初生同位体比に変動が認められ,これは,スラブ由来の流体による交代作用あるいはマグマの進化過程における同化作用および分別結晶作用に特徴的な,地殻とマントルの反応に起因するものと考えられる.これらの層位学的および地球化学的データは, Gangdiseテレーンに残されている中生代の島弧の形成前に,古生代に古テチス海の南方への沈み込みによる島弧の形成があったとする仮説を支持する.
Key words : Gangdise , geochemistry , island arc , Paleotethys , Permian , stratigraphy , Tibet , volcanic rocks
5. Apatite fission track constraints on the Neogene tectono-thermal history of Nimu area, southern Gangdese terrane, Tibet Plateau
Wanming Yuan, Jun Deng, Qiugen Zheng, Jinquan Dong, Zengkuan Bao, Paul R. Eizenhoefer, Xiaotong Xu and Zhixin Huang
チベット高原、南ガンディステレーンに位置するニム地域におけるアパタイトフィッショントラック解析からの新第三紀熱・テクトニック履歴への制約
南ガンディステレーンに位置するニム地域の新生代の火山性地層から採取された岩石試料5個のアパタイトフィッショントラック解析は単純な年代分布を示す.最古・最新の中心年代(central age)は6.8±0.6 Maと9.7±1.2 Maである.
最長・最短トラック長は14.2±2.3 mmと12.9±1.7 mmであり,トラック長分布は単一の熱イベントで形成される単一のピークを示す.本研究で新しく記載された年代は,9–5 Maに起きた水平圧縮を伴うテクトニックイベントに起因するチベット北部盆地における高速堆積時期とほぼ一致する.トラック長モデリングから3つの異なる冷却ステージを定義できる.第1ステージ(12–8 Ma)は比較的安定した時期であり,温度は120–110°Cであり,冷却はあったとしてもかなり限られているので,当時の地形は起伏が少なかったと推定できる.第2ステージ(8–2 Ma)は速い冷却を伴い,温度は〜110°C から地表付近に相当する〜15°Cまで下がった.このステージは,現在のガンディス山脈でみられる地形の起伏をつくりだしたヒマラヤ造山帯における衝突のfar-field effectに関係づけることができる. この時期の平均上昇速度は1.41–0.95 mm/a であり,標高は〜5900 mまで達したと推定される.最後の第3ステージは鮮新世以降の地表付近での熱履歴を示す.
Key words : cooling-uplifting , fission track , Gangdese terrane , tectonics , thermal history
(一般論文)
1. Formation of chaotic rock units during primary accretion processes: Examples from the Miura−Boso accretionary complex, central Japan
Yuzuru Yamamoto, Manami Nidaira, Yasufumi Ohta and Yujiro Ogawa
付加過程最初期の乱堆積物の形成:三浦房総付加体を例として
山本由弦, 仁平麻奈美, 大田恭史, 小川勇二郎
付加体上部に発達する乱堆積物は,付加前,付加中,付加直後の詳細なテクトニクス情報を記録している.上部中新統の三浦房総付加体の詳細な検討を行い,3つのタイプの乱堆積物を見出した.砂もしくは礫層ブロックと泥質岩マトリックスで構成される乱堆積物(タイプ3)は,伊豆弧上での三崎層・西岬層の堆積直後に起こった重力崩壊に伴うスランプによって形成された.これらの運動方向から示された斜面の姿勢は,はじめほぼ水平であった海底面が,北西方向に傾動し,最終的には逆の南東方向の傾動へと変化したことが明らかになった.北西側への傾動・地すべりは,付加直前に海底面が陸側へ傾動したことを示し,南東へのそれは,堆積物が変形前線(Deformation front)通過後に,断層運動によって海溝側へと傾動が変化したことを示している.マトリックスが砂もしくは礫主体に構成されている乱堆積物(タイプ1,タイプ2)は,付加中および付加後に起こった,巨大地震による砂層の液状化および貫入によって形成された.
これら乱堆積物は,造構運動による斜面の傾動や古地震イベントといった,付加過程初期における表層付近の変動を知る上で,非常に有用である.
Key words : accretionary complex, Boso, liquefaction, mélange, Miura, slumping
2. Foraminiferal evidence of submarine sediment transport and deposition by backwash during the 2004 Indian Ocean tsunami
Daisuke Sugawara, Koji Minoura, Naoki Nemoto, Shinji Tsukawaki, Kazuhisa Goto and Fumihiko Imamura
有孔虫データに基づいた2004年インド洋大津波による海底堆積作用の解明
菅原大助,箕浦幸治,根本直樹,塚脇真二,後藤和久,今村文彦
2004年インド洋大津波により生じた海底下の堆積作用を明らかにするため,タイ南西部沿岸域において津波前後で採取した堆積物試料を用いて微古生物学的分析を行った.分析に供した試料は,津波前の1998年に水深6〜15 mの3地点,津波後の2005年と2006年に水深4.5〜30 mの10地点から採取した.試料から検出した有孔虫殻について種・属の同定を行い,それらの産出頻度を分析した結果,底生有孔虫の分布パターンが津波後に海側へ移動していたことが認められた.また,津波後の前浜〜沖浜の堆積物からは,潮間帯を生育域とする膠着質有孔虫が検出された.これらのことは,津波の引き波により前浜〜沿岸域の堆積物が海側へ運搬されたことを示している.一方,沖浜を生育域とする浮遊性および底生有孔虫の分布パターンに関しては,陸側への移動は殆ど認められなかった.本海域では,沖浜の海底において押し波による陸側への堆積物の運搬は生じなかったと思われる.本研究の結果,および既往の関連研究のレビューから,海底における津波の堆積作用について次のような解釈が導かれた.(1)津波襲来の際,引き波により大量の海浜物質が堆積物流となって海域へ運搬される.(2)従って,過去の津波の痕跡は沖浜の堆積場において異地性の物質の集積として識別されうる.(3)底生有孔虫の群集変化は痕跡の識別規準として有力であると考えられる.
Key words : backwash, foraminifer, sediment flow, 2004 Indian Ocean tsunami, 2004 Sumatra–Andaman earthquake
3. Occurrence of Alaskan-type mafic-ultramafic intrusions in the North Qilian Mountains, northwest China: Evidence of Cambrian arc magmatism on the Qilian Block
Chien-Yuan Tseng, Guo-Chao Zuo, Huai-Jen Yang, Houng-Yi Yang, Kuo-An Tung, Dun-Yi Liu and Han-Quan Wu
中国北西部,北Qilian山地におけるアラスカ型苦鉄質-超苦鉄質貫入岩の産状:Qilian Blockにおけるカンブリア紀の島弧火成作用の証拠
中国北西部,北Qilian山地において,Zhamashi苦鉄質-超苦鉄質貫入岩の野外での産状,鉱物学的および岩石学的性質,全岩組成,年代について研究を行った.Zhamashi貫入岩体は,超苦鉄質岩,ガブロ,ドレライトからなり,おおよそ同心円状の累帯構造をなす. 超苦鉄質岩は層状沈積岩で,ダナイトからウェールライト,かんらん石単斜輝岩を経て,単斜輝岩へと連続的に変化する.ガブロとドレライトもまた,層状あるいは塊状の沈積岩で,ノーライト質ガブロからホルンブレンドガブロを経て閃緑岩へと連続的に変化する.超苦鉄質岩と隣接するガブロは,岩相的,構造的に不連続である.両者の境界面は,急勾配かつ明瞭で,破砕されている.接触変成帯は,Zhamashi貫入岩体と周囲の岩石の間で良く発達している.貫入岩体の同心円状の累帯構造と大陸地殻への貫入は,Zhamashi貫入岩体がアラスカ型であることを示す二つの主要な証拠である.クロムスピネルと単斜輝石の化学組成,(Na2O + K2O)–FeO–MgO (AFM)図における全岩化学組成の変化のトレンドも,アラスカ型であることを支持している.ジルコンのSHRIMP年代から推定されるZhamashi貫入岩体の年代は、513.0±4.5 Maである.Zhamashi貫入岩体の本源マグマは,マントルかんらん岩の部分溶融によって生じた未分化マグマに組成的に近い.島弧性の環境の中で、その本源マグマが、低圧かつ水に富んだ条件下での分別結晶作用によって分化し、全ての主要岩種が形成された.Zhamashi貫入岩体の同心円状の累帯構造は,層状岩体の形成とそれに続くダイアピリックな再迸入の2つのステージを経て形成された.アラスカ型貫入岩体の産状は,Qilian Block北縁の活動的大陸縁とカンブリア紀の島弧性火成作用を示唆している.
Key words : Alaskan-type, arc magmatism, Cambrian, mafic–ultramafic intrusion, North Qilian Mountains, Qilian Block
Island Arc 日本語要旨 2009. vol. 18 Issue 4 (December)
Vol. 18 Issue 4 (December)
1. Role of southeastern Sanandaj-Sirjan Zone in the tectonic evolution of Zagros Orogenic Belt, Iran
Ramin Arfania and Sohrab Shahriari
イランに分布するザグロス造山帯の構造的発達における南東部Sanandaj-Sirjan帯の役割
ザグロス造山帯南東部に位置する南東部Sanandaj-Sirjan帯は、典型的な中央イランの層序学的な特徴をもつEsfahan-Sirjan Blockと古生代〜中生代初期の変成岩類に分けられる. Main Deep断層(Abadeh断層)は, 両者を分ける主要な断層である. 本論文の目的は、イランに分布するザグロス造山帯の構造的発達における南東部Sanandaj-Sirjan帯の役割を地質学的証拠に基づいて明らかにすることにある. 新しい形成モデルは, 石炭紀後期〜二畳紀初期に中央イラン・マイクロコンチネントがゴンドワナ大陸北東縁から分離したときにネオテチス1が誕生したことを示唆している. 三畳紀後期、新しい拡大海嶺であるネオテチス2が形成され、Shahrekord-DehsardテレーンをAfro-Arabianプレートから分離した. ザグロス堆積盆は,ネオテチス2の南西に位置する受動的な大陸縁で形成された。Naien-Shahrebabak-BaftとNeyrizの2つのオフィオライト帯は, 白亜紀後期におけるネオテチス1のリソスフェアの沈降に関係して, それぞれネオテチス1の北東部およびネオテチス2の南西部で発達した. 中央イラン・マイクロコンチネントの暁新世れき岩とザグロス堆積盆の鮮新世れき岩の堆積は, 大陸衝突による上昇運動と直接関係していると結論づけることができる.
Key words : Esfahan–Sirjan Block , Main Deep Fault , Sanandaj–Sirjan Zone , Shahrekord–Dehsard Terrane , Zagros Orogenic Belt
2. Reconstructing the evolution of fault zone architecture: Field-based study of the core region of the Atera Fault, Central Japan
Masakazu Niwa, Yukihiro Mizuochi and Atsushi Tanase
中部日本の阿寺断層における断層破砕帯の発達過程の復元
丹羽正和,水落幸広,棚瀬充史
不均質な構造をもった断層破砕帯の発達過程を復元する目的で,西南日本の阿寺断層の破砕帯を対象に,露頭〜顕微鏡スケールでの詳細な記載を言った.破砕帯は熔結凝灰岩,花崗岩及び苦鉄質火山岩類の岩片を含む断層角礫からなる幅約1.2mの断層コアを伴う.断層コアを挟んで発達するダメージゾーンは,西側では熔結凝灰岩の断層角礫,東側では花崗岩のカタクレーサイトで特徴づけられる.断層コアは特に,摩損・粉砕に伴う岩片の細粒化が顕著である.苦鉄質火山岩類の岩片は,破砕帯近傍に分布する1.6Maの年代を示す火山岩を起源とすると考えられ,断層コアの形成時期を拘束する証拠となる.断層コアの近傍には,地震時の細粒物質の高速注入による形成を示唆する脈が発達する.花崗岩カタクレーサイト中には,カオリナイトに富む粘土を主体とする基質中に,構成鉱物の著しい破砕を伴わない硬く新鮮な花崗岩の岩片を含む幅約30cmの副次的な断層コアが発達し,その特徴からは,露出する破砕帯の中で最も新しいすべり面を示していると解釈される.断層破砕帯における既往の地質学的・水理学的研究に基づくと,粘土に富む断層コアは,周囲のダメージゾーンに比べてより低透水であると考えられる.
Key words : asymmetry, Atera Fault, clay mineral, deformation structure, fault zone, Japan, repeated fragmentation
3. Petrologic evolution of Palau, a nascent island arc
James Hawkins and Osamu Ishizuka
パラオ諸島における初期島弧のマグマ進化
James Hawkins, 石塚 治
北緯7度30分付近に位置するパラオ諸島は, 2500km以上にわたって連なる九州パラオ海嶺において, 唯一火山岩類が海面上に露出する地域である. 規模の小さい島々は主に礁成石灰岩からなるが, 大きい島々には玄武岩〜デイサイトさらにはボニナイトにわたる組成範囲の火山岩が分布する. 角れき岩がもっとも広く分布し, シル, 溶岩流, ダイクがそれに続き, 枕状溶岩はまれである. 一方パラオ海嶺から採取された岩石試料は,パラオ諸島陸上部に露出する岩石に加えて高Mg玄武岩を含む. 火山活動は後期漸新世に始まり, 前期中新世までに停止した. すべての火山岩類はlow-Kのソレアイト系列に属し, MORB組成の玄武岩類はない. 希土類元素及びHFS元素組成は, 枯渇したマントル起源であることを示している. LIL元素及び軽希土類元素に富む特徴は, 沈み込むスラブの脱水反応により供給されたフルイドの寄与を示す. Ce/Ce*及びEu/Eu*には, 島弧起源の火山砕屑物の寄与は認められない. プレート運動の復元と古地磁気データは, パラオ諸島を含む島弧が, 恐らく北上するトランスフォーム断層の延長上に形成され, その後90度時計回りに回転したことを示唆する.この過程で伸張場になった時期に, 枯渇したマントル中により高温のマントルが上昇し, 圧縮場に転じた時点で薄い遠洋性堆積物を伴った海洋地殻の沈み込みが開始したと考えられる.
Key words : Palau Arc , subduction initiation , West Philippine Basin evolution
4. Northern Barbados accretionary prism: structure, deformation, and fluid flow interpreted from 3-D seismic and well-log data
Deniz Cukur, Gwang H Lee, Jeong G. Um, Dae C. Kim, Jin Kim
3次元震探データおよび検層データに基づくバルバドス付加プリズム北部の構造,変形様式,流体挙動
沈み込みに起因する構造,変形,流体の挙動を明らかにするために,バルバドス付加プリズム北部における3次元震探データおよび掘削中検層データを検討した.海底地形の振幅およびコヒーレンスの解析結果は,衝上断層の方向が,衝上断層フロントでは北北東方向であるが,断層の約5km西方では北および北北西へと大きく変化していることを示している.これらの衝上断層群の間には,三角形の形状を呈し,顕著な断層が発達していない区域(静的区域)がみられ,それは堆積物の強度が弱い部分に相当すると思われる.デコルマ中には北東方向に伸び,静的区域を覆った,低振幅・高コヒーレンス帯がみられる.これは,いわゆるArrested consolidation(圧密が妨げられた)層に相当する.この事実は,圧密の妨げは,衝上断層が覆瓦構造を欠き,そのために付加プリズムにおける流体が垂直方向へ排出されていることと関連している可能性を示唆している.デコルマと沈み込みつつある海洋底地殻の先端部のフラクタル解析の結果は,デコルマの起伏は海洋底地殻の地形と対応することを示している.衝上断層下,海洋底地殻上に位置する堆積物の差別的圧密作用および海洋底地殻からデコルマまでを切る断層が,デコルマの起伏の形成や断層運動を引き起こす要因であるのかもしれない.
Key words : Barbados accretionary prism , coherence , décollement , fractal analysis , seismic amplitude
5. Relationship between statistical thermal alteration index and vitrinite reflectance for sedimentary rocks in northern Japan with reference to effects for unconformity, faulting, and contact metamorphism
Yoshihiro Ujiie
不整合,断層および接触変成作用に関連した北日本の堆積岩における「統計的熱変質指標(stTAI)」とビトリナイト反射率との関係
氏家良博
筆者は二つの有機熟成指標、統計的熱変質指標(stTAI)とビトリナイト反射率(RO)を利用して,不整合,断層および接触変成作用を受けた北日本の第三系と上部白亜系の地史を解明してきた.stTAIは顕微鏡下で観察されるマツ属,モミ属,トウヒ属等の有翼型花粉の明度を画像解析して得られる指標であり,初期ダイアジェネシスから前期カタジェネシス(石油生成段階の前半;RO≦1.0%)までの続成作用に適用できる.続成作用の進行につれて,堆積岩に含まれるビトリナイトの反射率は一般に増大傾向を示すのに対し,堆積岩中の化花粉のstTAIは減少傾向を示す.不整合または断層を挟む一連の堆積物層序において,stTAIはROよりも不整合や断層の影響を敏感に現す.この事実は,RO≦0.7%の前期続成段階でstTAIが急激に減少するのに対し,ROはRO≧0.8%の中・後期続成段階で急激な増大を示すことに由来する。接触変成作用では、火成岩岩脈に近づくにつれてROは徐々に増大するのに対し,stTAIは規則的な減少傾向を示さない.これまでの調査からは,stTAIはROに比べて被熱時間に敏感であり,逆にROはstTAIに比べて被熱温度に敏感であることが判明した.
Key words : contact metamorphism , faulting , organic maturation , statistical thermal alteration index , unconformity , vitrinite reflectance
Island Arc 日本語要旨 2010. vol. 19 Issue 4 (December)
Vol. 19 Issue 4 (December)
[Pictorial Articles]
1. Miocene dextral movement of Tanakura Shear Zone: Evidence from the Western Marginal Fault, Hanawa Town, Northeast Japan
Dohta Awaji, Ryota Sugimoto, Hiroyoshi Arai, Kenta Kobayashi and Hideo Takagi
福島県塙町の棚倉破砕帯西縁断層に認められる中新世の右横ずれ運動
淡路動太,杉本良太,新井宏嘉,小林健太,高木秀雄
特集号:Thematic section: Paleoclimates in Asia during the Cretaceous: Their variations, causes, and biotic and environmental responses (IGCP Project 507) Part 1
Guest Editors : Yong Il Lee and Helmut Weissert
白亜紀におけるアジア古気候:多様性,原因および生物と環境の反応(IGCP project 507),その1
1. Preface
Yong Il Lee and Helmut Weissert
序文
Yong Il Lee and Helmut Weissert
IGCP507は,2006年から5カ年計画で白亜紀アジアの古気候とその変動要因を知るための情報収集を目的とし,様々な時間スケールで気候変化と相互に反応する物理的・生命科学的システムの理解を到達点と考えている.具体的には,南アジアおよび東アジアの詳細な調査を行い,陸域および海域の堆積物について様々なプロキシーデータの解析を通じて古気候学的な情報を抽出してきた.そして古気候の空間的な多様性と経時的変化について明らかにし,さらに構造運動,相対的海水準の変動,火成活動および軌道要素などを考慮した上で,どのような強制力要因が古気候を支配するのか,の解釈を目指している. 本号と次号の特集では,それぞれ韓国ソウルとモンゴル国ウランバートルで行われた第二回,第三回国際シンポジウムの科学成果を集約した.本号には層序,堆積,堆積岩地球化学,古環境および堆積年代と火成活動に関連する砕屑性ジルコンの放射年代に関する6本の論文が掲載されている.
2. Fourth- to third-order cycles in the Hakobuchi Formation: Shallow-marine Campanian final deposition of the Yezo Group, Nakagawa area, northern Hokkaido, Japan
Hisao Ando, Yoshitaka Tamura and Daisuke Takamatsu
北海道北部中川地域の蝦夷層群函淵層(上部白亜系カンパニアン階)に見られる浅海成第3−4オーダー堆積サイクル
安藤寿男,田村芳隆,高松大祐
北海道中軸部に分布する蝦夷層群は,白亜系(アプチアン期〜マストリヒシアン期)と一部暁新統を含む古アジア大陸東縁の前弧盆堆積物である.北海道北部中川地域では蝦夷層群最上部の函淵層の西縁相がよく露出しており,24の堆積相と6の堆積組相が認定でき,主にストーム卓越型の外浜〜陸棚砂質堆積物からなり,一部はエスチュアリー,河川で堆積した.堆積相や堆積組相の層厚・累重様式・側方変化から6の堆積シーケンスと3つのシーケンスセットが認められる.函淵層は大型化石(イノセラムスやアンモナイト)層序からカンパニアン階と位置付けられ,第3〜4オーダーの相対海水準変動による陸域システムの東方への前進と西方への後退を繰り返しながら形成された.
Key Words : Campanian,Cretaceous, depositional sequence, Hokkaido, sequence stratigraphy, shallow-marine sediments, Yezo forearc basin, Yezo Group
3. Indicator of paleosalinity: Sedimentary sulfur and organic carbon in the Jurassic–Cretaceous Tetori Group, central Japan
Takashi Hasegawa, Tsuyoshi Hibino and Shunji Hori
古塩分指標:ジュラ−白亜系手取層群中の堆積性硫黄と有機炭素
長谷川卓,日比野剛,堀 峻滋
全硫黄(TS)と全有機炭素(TOC)の含有量比を用いて,ジュラ−白亜系手取層群の古環境を復元した.一般にTOC/TS比は現在の海や汽水の堆積物を,淡水性堆積物から区別するために用いられる.まず示相化石により海,汽水または淡水の古環境が推定されている手取層群試料について分析した結果,海成ないし汽水成堆積物と淡水成堆積物は明瞭に区別できた.この手法を古環境未知の手取層群に応用した結果,福井県大野市和泉の石徹白亜層群上部層の中部に,一時的な海水ないし汽水環境の発達を示す地層が見つかった.富山県立山町の手取層群最上部に同様な環境の発達が示唆されたが,同層群堆積末期の古地理を考える上で重要である.この手法は東アジアのジュラ−白亜系の広域対比を行う上で一定の役割を果たすかもしれない.
Key Words : brackish, Cretaceous, freshwater, organic carbon, paleoenvironment, pyrite, sulfur, Tetori Group
4. ‘Thailand was a desert' during the mid-Cretaceous: Equatorward shift of the subtropical high-pressure belt indicated by eolian deposits (Phu Thok Formation) in the Khorat Basin, northeastern Thailand
Hitoshi Hasegawa, Suvapak Imsamut, Punya Charusiri, Ryuji Tada, Yu Horiuchi and Ken-ichiro Hisada
白亜紀中期にタイは砂漠だった:タイ北東部コラート盆地に露出する風成堆積物(Phu Thok層)から見る亜熱帯高圧帯の低緯度シフト
長谷川精,Suvapak Imsamut,Punya Charusiri,多田隆治,堀内 悠,久田健一郎
現在のアジア地域の気候および大気循環システムは,チベット高原の存在に強く影響を受けている.チベット高原隆起後の現在の大気循環システムとは異なり,隆起前における大気循環システムがどのようであったかを示す直接的な地質証拠は示されていなかった.一般に,砂漠地帯の分布は亜熱帯高圧帯の分布を反映し,砂漠(風成)堆積物中には卓越地表風系の古風向が記録されるため,過去の亜熱帯高圧帯の軸部の位置が復元可能である.タイ北東部コラート盆地北部には,白亜紀の風成堆積物であるPhu Thok層が広く露出している.本研究ではPhu Thok層に対して堆積学的検討を行い,白亜紀を通したアジア低緯度域における亜熱帯高圧帯の緯度分布変動の復元を試みた.Phu Thok層に記録される古風向パターンの時空変動を解析した結果,白亜紀においてコラート盆地は主に北東貿易風帯に属していたこと,更に,同層が堆積した初期には同盆地よりも北に位置していた亜熱帯高圧帯の軸部が,同層主部が堆積した時期には同盆地最北部にまで南下し,その後同層が堆積末期には再び北上した可能性が示された.またPhu Thok層の古地磁気極性変動パターンは,同層下部の2つの正-逆磁極期と同層上部の長い正磁極期からなることを示し,標準古地磁気層序(GTS2004)のChron M1n~C34nと対比される可能性が示唆された.この結果はPhu Thok層の堆積年代が,中国南部の四川盆地に見られる砂漠堆積物(Jiaguan層)の堆積年代と同様に,白亜紀中期(約126 Maから約99~93 Ma)である事を示唆する.これらの結果と古風向パターンから,白亜紀中期にはアジア大陸低緯度域において砂漠環境が拡がっていたこと,そして亜熱帯高圧帯の軸部が現在よりも低緯度側にシフトしていたことが示唆された.
Key Words : Cretaceous, desert, magnetostratigraphy, paleo-wind, subtropical high-pressure belt, Thailand
5. Preferred orientation of the trace fossil Entradichnus meniscus in Eolian dune strata (Djadokhta Formation) at Tugrikiin Shiree, southern Mongolia and its paleoecological implications
Koji Seike, Hitoshi Hasegawa and Niiden Ichinnorov
モンゴル南部Tugrikiin Shireeにおける上部白亜系Djadokhta層から産出する生痕化石Entradichnus meniscusの定向配列およびその古生態学的意義
清家弘治,長谷川精,Niiden Ichinnorov
モンゴル南部Tugrikiin Shireeに分布する上部白亜系Djadokhta層砂丘堆積物からは,恐竜類の体化石だけでなく,無脊椎動物によって形成された生痕化石が豊富に産出する.本論文ではDjadokhta層から産出する生痕化石 Entradichnus meniscusを記載し,その古生態学的意義を報告する.E. meniscusとは細長く,分岐や裏打ちがなく,メニスカス構造を有する円筒状の生痕化石である.この生痕化石は砂丘前置面の層理に沿って産出し,直線的もしくは緩やかに蛇行した形態を示す.この生痕化石の伸長方向を測定したところ,ほぼすべてのE. meniscusは砂丘前置面の最大傾斜方向に定向配列していることが判明した.このことは,E. meniscus形成者が砂丘前置面の下をその最大傾斜方向(下向き)に掘り進んでいたことを示している.なお,同様な産状は北米のジュラ系砂漠堆積物におけるE. meniscusにおいても知られている.このことから,このような定向配列は,乾燥した砂丘環境におけるE. meniscusに普遍的な特徴である可能性がある.また,この下向きにのみ掘り進む行動は,乾燥環境での砂丘地形に対する応答様式であると解釈できる.
Key Words : desert environment, ichnology, paleoecology, trace fossil
6. Soft-sediment deformation structures in Cretaceous non-marine deposits of southeastern Gyeongsang Basin, Korea: Occurrences and origin
Hee-Cheol Kang, In Sung Paik, Ho Il Lee, Jung Eun Lee and Jong-Hwa Chun
韓国慶尚堆積盆南東部の白亜系非海成堆積物に見られる軟質堆積物の変形構造:その産状と起源
Hee-Cheol Kang, In Sung Paik, Ho Il Lee, Jung Eun Lee and Jong-Hwa Chun
韓半島南東部の海岸線地域に沿って露出する慶尚堆積盆の白亜系 Seongpori 層と Dadaepo 層には,堆積時もしくは直後に生じた軟質堆積物の多様な変形構造が 0.5〜2 km にわたって発達している.これらのほとんどは湖成層と互層する河川平野相に含まれる.本研究では,異なる種類の軟質堆積物変形構造の特性を,その構造を有する堆積物の堆積学的特徴に基づいて,通常の堆積構造,変形の時期と機構,そして誘因機構とを比較しながら解釈する.軟質堆積物の変形構造は以下の4群に区分できる:(i) 荷重構造(荷重痕,球状−柱状構造),(ii) 貫入構造(皿状−柱状構造,砕屑性岩脈・岩床),(iii) 延性攪乱構造(渦巻き褶曲,スランプ構造),(iv) 脆性変形構造(堆積同時性断層,転位角礫).これらの構造をもたらす最も可能性の高い誘因機構は地震衝撃である.この解釈は次の野外観察事実に基づいている:(i) 白亜紀に何度かにわたって再活動した活発な断層帯にある研究地域の構造的位置づけ;(ii) 変形構造が単一の層準に限られること; (iii)変形層準に多様な軟質変形構造が広域に出現し側方に連続すること;(iv) 重力性地滑りもしくはスランプを示す堆積斜面がないこと;(v) 実験的に形成された構造との類似性.したがって,研究地域の軟質堆積物変形構造は,予測マグニチュード5以上の地震に伴う衝撃によって生じたと解釈される.そして,前期〜後期白亜紀の2層の発達や進化の間の,活発なテクトニクス・堆積過程の断続的な記録を表している.
Key Words : active tectonic processes, fluvial plain facies, Gyeongsang Basin, seismic shocks, seismites, soft-sediment deformation structures
7. Detrital zircon geochronology of the Cretaceous Sindong Group, Southeast Korea: Implications for depositional age and Early Cretaceous igneous activity
Yong Il Lee, Taejin Choi, Hyoun Soo Lim and Yuji Orihashi
韓国南西部,白亜系Sindong層群の砕屑性ジルコン年代学:堆積年代と前期白亜紀火成活動に対する解釈
Yong Il Lee, Taejin Choi, Hyoun Soo Lim, 折橋裕二
Gyeongsang(慶尚)盆地は韓国南東部に位置する白亜系最大の非海成堆積盆である.Sindong(新洞)層群は同堆積盆の最下部を構成し,下位からNakdong(洛東)層,Hasandong(霞山洞)層およびJinju(晋州)層に区分される.Sindong層群の堆積年代はValanginianからAlbianの範囲とされてきた.本研究ではレーザーアブレーションICP質量分析装置を用いて,Sindong層群から抽出した砕屑性ジルコンのU-Pb年代測定を新たに試みた.Sindong層群は白亜系マグマ起源の砕屑性ジルコン(138-106Ma)を顕著な量含み,この年代幅はSindong層群の堆積前,もしくは堆積時に起こった火成活動の期間を示している.前述した3層それぞれの最も若い砕屑性ジルコンの年代は層序に相関して若くなり,Nakdong層では118Maを,Hasandong層では109Maを,Jinju層では106Maを示した.したがって,Sindong層群の堆積年代はAptian後期からAlbian後期の範囲であることを示唆し,この結果は以前考えられていた堆積年代よりもかなり若いことになる.また,Sindong層群に砕屑性ジルコンを供給した下部白亜系の火成活動場は時間の経過とともに位置を変え,初期ステージの間では給源が中部から北部で起こり,中期〜後期ステージの間では中部から南部に移行したことが明らかとなった.本研究は,東アジア大陸縁の前期白亜紀火成活動の期間が,これまで知られているものよりもさらに小さかった(2000万年程度)ことを示唆する最初の報告である.
Key Words : Cretaceous, depositional age, Gyeongsang Basin, magmatism, U–Pb zircon age
通常論文
[Review Articles]
2. Review and new interpretation for the propagation characteristics associated with the 1999 Chi-Chi earthquake faulting event
Kwangmin Jin and Young-Seog Kim
1999年チチ地震の断層運動に伴う伝播特性のレビューと新解釈
Kwangmin Jin and Young-Seog Kim
1999年,台湾中西部においてチチ地震(MW=7.6)が発生した.Chelungpu断層を再活性化し,その結果として延長100 kmの地表地震断層を引き起こした.断層の走向は北-南から北北東-南南西であるが,断層の南部分の北端は時計方向に回転して東-西方向を向き,より短い北北西方向の断層にジャンプする.最大垂直変位量は, Shihkang-Shangchi断層帯のShihkang地域において認められ,8-10 mである.Shihkang-Shangchi断層帯は,断層と破断が最も集中する二つの断層セグメント間を結ぶ破砕帯として,複雑な断層パターンを示す.チチ地震断層の最近の幾何学的,運動学的,地球物理学的研究に基づいた我々の新しい解釈では,Shihkang-Shangchi断層帯は単純に終端をもつ断層帯ではなく,おそらく’over step zone’ないしは’transfer zone’であることを示唆する.地表地震断層沿いのすべり解析は,断層が3つの断層セグメントからなり,すべり量が,すべり方向と断層の走向がなす交差角に部分的に依存することを示している.われわれの数値モデルは,クーロン応力変化が主に地表地震断層の終端部や屈曲部に集中することを,また,スリップパターンは,断層が北東に伝播していることを示している.これらのことは,断層が及んでいないShangchiセグメントに沿った将来の地震活動の高い可能性を示唆している.したがって,今後の地震災害研究においては,Shangchiセグメントの地震発生の可能性の評価,地震活動の間隔,地震災害を減じる方策に焦点を当てるべきである.
Key Words : Chelungpu Fault, Chi-Chi earthquake, fault damage zone, linkage zone, Shangchi segment, Shihkang–Shangchi Fault Zone, surface ruptures.
[Research Articles]
3. Tectonic implications of the geochemical data from the Makran igneous rocks in Iran
Jamshid Shahabpour
イラン,マクラン火成岩類の地球化学的データのテクトニックな意味
Jamshid Shahabpour
現在のオマーン湾がその名残であるネオテチス海が閉じたことによって形成されたマクランは,地球上で最も大規模な付加体のひとつである.マクラン島弧系の構造的発達を,スラブの傾斜配列の空間的な多様性をもつ北傾斜の沈み込み帯を考慮して明らかにした.ジュラ紀中期から暁新世初期の急角度のスラブの傾斜配列により,中生代のマグマ弧と弧内の展張場においてできた盆地Proto-Jaz Murian凹地が発達した.これらは外弧のオフィオライトメランジュの発達とZagros orogenic beltに属するSanandaj-Sirjan zoneのMakran地域への延長であるBajgan-Durkan continental sliverの発達を伴った.暁新世後期から鮮新世初期にかけて中程度から緩い角度のスラブ傾斜配列になり,その時生じたProto-Jaz Murian 展張盆からJaz Murian圧縮盆への転換は,South Jaz Murian断層に沿ったJaz Murian凹地の南部の上昇とJaz Murian 圧縮盆背後の古第三紀〜新第三紀マグマ弧の成長を伴った.第四紀の浅いスラブの傾斜は,Yazd-Tabas-Lut 微小大陸塊の南部に広くわたって,内陸部に第三のマグマ弧の形成を引き起こした.Makran 島弧系は,Zagros 島弧系が過去に経験したように,将来,同様のテクトニックイベントを経験する可能性がある.しかしながら,現在のオマーン湾と同様の将来の残存した盆地は,東方で存続し続けるであろう.
Key Words : island-arc, Makran, metallogeny, tectonic inversion
4. Sealevel history recorded in the Pleistocene carbonate sequence in IODP Hole 310-M0005D, off Tahiti
Yasufumi Iryu, Yasunari Takahashi, Kazuhiko Fujita, Gilbert Camoin, Guy Cabioch, Hiroki Matsuda, Tokiyuki Sato, Kaoru Sugihara, Jody M. Websterand and Hildegard Westphal
タヒチ島沖IODP Hole 310-M0005Dで掘削された更新世炭酸塩に記録された海水準変動
井龍康文,高橋靖成, 藤田和彦,Gilbert Camoin,Guy Cabioch,松田博貴,佐藤時幸,杉原 薫,Jody M. Websterand,Hildegard Westphal
統合国際深海掘削計画(IODP)第310次航海で採取されたコア試料の検討により,タヒチ島周辺の化石礁は後氷期シーケンスと更新世シーケンスよりなることが明らかとなった.更新世シーケンスは主にサンゴ礁堆積物よりなり,火山砕屑物を伴う.タヒチ島南岸のマラア沖で掘削されたHole 310-M0005Dでは,更新世シーケンスが層厚70 m(海底面下33.22〜101.93 m;現海面下92.85〜161.56 m)にも渡って掘削されたため,同シーケンスが最もよく観察できる.同孔の更新世シーケンスは,岩相変化,堆積学的特徴,古生物学的特徴(含有化石)により11の堆積ユニット(上位から下位に向かって,サブユニット1〜11)に区分される.無節サンゴモ,造礁サンゴ,大型有孔虫から古水深変化を復元した結果,更新世シーケンスの堆積時に2回の海水準上昇があったことが明らかとなった.これらのうち,2回目の海水準上昇には,一時的な海水準の低下が介在したことが示唆される.2回目の海水準上昇はターミネーションII(TII,酸素同位体ステージ6〜5eに対応する融氷イベント)に対比される可能性が高いため,想定される一時的な海水準低下はTII時にあったとされる‘sealevel reversal’に相当すると思われる.南太平洋の熱帯域では,更新世サンゴ礁に関するデータは限られているため,本研究は,更新世海水準変動,サンゴ礁生態系の進化,第四紀気候変動に対するサンゴ礁の応答を明らかにするために重要な情報を提供する.
Key Words : DP Hunter, Hole M0005D, IODP Expedition 310 ‘Tahiti Sea Level’, Pleistocene, sealevel change, Tahiti
5. Significant cooling during exhumation of UHP eclogite from the Taohang area in the Sulu region of eastern China and its tectonic significance
Daisuke Nakamura and Takao Hirajima
中国東部・蘇魯地域のTaohang産・超高圧エクロジャイトにおける冷却を伴う上昇とそのテクトニクスにおける意義
中村大輔・平島崇男
中国東部・蘇魯地域における藍晶石エクロジャイト中に含まれるザクロ石のコアの組成とオンファス輝石コアの組成に温度圧力計を適用した結果,約700℃, 3.4GPaの温度圧力条件が得られた.一方,ザクロ石のリムとそれに隣接するオンファス輝石のリムの組成に対して温度計を適用した所,1.5GPaで566±54℃の温度が得られ,本試料が減圧時に明瞭な冷却を伴っていることが解った.これまでの推定では,蘇魯地域の超高圧変成岩は等温減圧を示しており,大きな岩体の中心部に位置していた為,周囲からの熱の影響を受けなかったと解釈されている.一方,今回得られた履歴は,本研究地域の岩石が超高圧変成岩体の縁に位置しており,周囲からの冷却を受けた結果と考えられる.
Key Words : eclogite, garnet-clinopyroxene thermometer, partial equilibrium, Sulu region, ultrahigh-pressure
6. Amphibolitization within the lower crust in the termination area of the Godzilla Megamullion, an oceanic core complex in the Parece Vela Basin
Yumiko Harigane, Katsuyoshi Michibayashi and Yasuhiko Ohara
ゴジラメガムリオンのターミネーション部における下部地殻の角閃岩化作用
針金由美子,道林克禎,小原泰彦
フィリピン海パレスベラ海盆のゴジラメガムリオンにおいてKR03-1-D10地点から採取された変形したハンレイ岩と角閃岩を用いて,古拡大軸近傍の下部地殻に生じた著しい角閃岩作用を明らかにした.この地点はデタッチメント断層の終了点であるターミネーション部である.ハンレイ岩は斜長石,単斜輝石と角閃石のポーフィロクラストと細粒基質部からなり,非対称組織の発達したマイロナイトで特徴づけられる.斜長石はNaに富む組成を示し,角閃石は単斜輝石のMg#とほぼ同じ組成を示す.角閃岩は斜長石と角閃石のポーフィロクラストと細粒基質部からなるポーフィロクラスト状組織で特徴づけられ,斜長石はハンレイ岩よりも低い組成を示すが,角閃石はハンレイ岩と同じ組成を示す.以上の結果から,角閃岩はハンレイ岩に生じた一連の熱水活動を伴う変成反応により形成されたことが示唆される.ハンレイ岩と角閃岩に地質温度計を適用させて温度を推定した結果は,高温(650-840℃)であった.従ってターミネーション部において,ゴジラメガムリオンの発達に関連した角閃岩化作用が古拡大軸近傍の下部地殻で生じた可能性が示唆される.
Key Words : amphibolite, amphibolitization, gabbroic rock, Godzilla Megamullion, Parece Vela Basin, retrograde metamorphism.
Island Arc 日本語要旨 2010. vol. 19 Issue 3 (September)
Vol. 19 Issue 3 (September)
特集号:Thematic Section:Bridging the gap separating geological studies and disaster mitigation countermeasures for earthquakes and tsunami
Guest Editors : Kazuhisa Goto, Osamu Fujiwara and Shigehiro Fujino
地震・津波堆積物研究の最前線−防災への貢献を目指して
後藤和久,藤原 治,藤野滋弘
1. Preface
Kazuhisa Goto, Osamu Fujiwara and Shigehiro Fujino
序文
後藤和久,藤原 治,藤野滋弘
地震,津波が多発する日本では,昔から海岸工学者や地質学者によって活発に研究が行われている.しかし,未だに両者の研究の隔たりは大きく,津波堆積物などの地質学的痕跡をどのように防災に生かすか,十分な検討がなされていない.そのような中,2008年に行われた日本地質学会第115年学術大会(秋田)でのシンポジウム「地震・津波堆積物研究の最先端と防災への貢献」が開催された.本特集号では,海岸工学などの手法を用いることで,地質学的痕跡をどのように防災に活用していくかに注目し,このシンポジウムで発表された6編の論文を収録した.
2. Millennium-scale recurrent uplift inferred from beach deposits bordering the eastern Nankai Trough, Omaezaki area, central Japan
Osamu Fujiwara, Kazuomi Hirakawa, Toshiaki Irizuki, Shiro Hasegawa, Yoshitaka Hase, Jun-ichi Uchida and Kohei Abe
南海トラフ東部の御前崎周辺の海浜堆積物から推定される1000年スケールで繰り返す隆起イベント
藤原 治,平川一臣,入月俊明,長谷川四郎,長谷義隆,内田淳一,阿部恒平
御前崎の南西岸には駿河湾西岸から遠州灘沿岸の他の地域と異なり,明瞭な4段の完新世海成段丘が分布する.ボーリング調査の結果,下位の3段の段丘についてビーチ堆積物の上限(旧海面高度)と離水年代を推定できた.これらの段丘は3020–2880 BC頃,370–190 BCよりやや前,1300–1370 ADよりやや前,に発生した3回の地震隆起を記録している.1回当たりの隆起量(地震間の沈降を差し引いた残存量)は1.6-2.8 mと推定される.このような局地的・永久的な隆起の蓄積は,既存の安政東海地震の断層モデルでは説明できず,プレート境界のメガスラストから分岐する高角逆断層の動きが関係している可能性が高い.
Key Words : beach deposits, marine terrace, Nankai Trough, Omaezaki, paleoearthquake, uplift
3. Detailed measurements of thickness and grain size of a widespread onshore tsunami deposit in Phang-nga Province, southwestern Thailand
Shigehiro Fujino, Hajime Naruse, Dan Matsumoto, Norihiko Sakakura, Apichart Suphawajruksakul and Thanawat Jarupongsakul
タイ南西部パンガー県における陸上津波堆積物の詳細な粒度・層厚平面分布
藤野滋弘,成瀬 元,松本 弾,坂倉範彦,Apichart Suphawajruksakul,Thanawat Jarupongsakul
陸上に残された津波堆積物の粒度・層厚の巨視的な特徴を明らかにした.流向に平行な測線上で2004年インド洋津波の堆積物の粒度と層厚を測定したところ,内陸への細粒化傾向,薄層化傾向が認められた.局所的に地表が侵食されることによって津波堆積物は一部で粗粒化するものの,全体的には内陸へ向かって細粒化する傾向を示した.これは沿岸に浸入した津波が減速するにしたがって粗粒なものから順次堆積したことを反映している.津波堆積物の層厚は局所的な地形の起伏によって変化しやすいものの,平坦な場所では内陸へ向かって漸移的に薄くなる傾向を示した.内陸への薄層化傾向は内陸ほど堆積物の供給量が少なくなることを反映していると考えられる.
Key Words : grain size, Indian Ocean tsunami, Phang-nga, sediment thickness, Thailand, tsunami deposit
4. Features and formation processes of multiple deposition layers from the 2004 Indian Ocean Tsunami at Ban Nam Kem, southern Thailand
Hajime Naruse, Shigehiro Fujino, Apichart Suphawajruksakul and Thanawat Jarupongsakul
タイ南部 Ban Nam Kemで見つかった2004年インド洋津波堆積物中の多重層理構造の特徴と形成プロセス
成瀬 元,藤野滋弘,Apichart Suphawajruksakul,Thanawat Jarupongsakul
津波堆積物中の多重層理構造は,これまで沿岸域の地層からしばしば報告されているが,その形成プロセスについては明らかになっていないことが多い.そこで,本研究はタイ南部Ban Nam Kemで見つかった2004年インド洋津波堆積物を調査し,多重層理構造の特徴とその形成プロセスを明らかにした.調査した津波堆積物には4つの内部層理構造が見られた.堆積構造の解析から,そのうち2つの層理構造は寄せ波,残りの2つは引き波による堆積物であることが明らかになった.野外調査結果および津波の非対称な水理学的特性を考慮し,本研究は多重層理を示す津波堆積物の形成プロセスの模式的モデルを提案する.
Key Words : 2004 Indian Ocean Tsunami, grading, multiple layers, oscillatory currents, terrestrial tsunami deposit, Thailand
5. Distribution of boulders at Miyara Bay of Ishigaki Island, Japan: A flow characteristic indicator of tsunami and storm waves
Kazuhisa Goto, Tetsuya Shinozaki, Koji Minoura, Kiyohiro Okada, Daisuke Sugawara and Fumihiko Imamura
沖縄県石垣島宮良湾における巨礫分布を用いた古津波・高波の流況復元
後藤和久,篠崎鉄哉,箕浦幸治,岡田清宏,菅原大助,今村文彦
本研究では,沖縄県石垣島宮良湾のリーフ上に堆積している巨礫群のサイズ・空間分布を調べた.巨礫群は,最大633トンもの巨大なリーフまたはサンゴ岩塊からなる.湾内の一部では,内陸方向に向けて指数関数的に巨礫サイズが減少することで特徴づけられる,巨礫群の海側分布限界が存在する.この限界線は,琉球列島における台風に伴う最大規模の高波または津波によって形成されたと考えられる.一方,湾内に存在する巨礫のうちの68%は,この限界線より内陸側に分布している.これらは,最大規模の高波でも説明できないことから,津波により運搬され堆積したと考えられる.14C年代測定値に基づくと,津波起源と認定される巨礫のうち少なくとも69個は,1771年明和津波により打ち上げ,または再移動し,現在位置に堆積したと考えられる.
Key Words : 1771 Meiwa tsunami, boulder, Ishigaki Island, Miyara Bay, storm wave, tsunami
6. Sources and depositional processes of tsunami deposits: Analysis using foraminiferal tests and hydrodynamic verification
Jun-Ichi Uchida, Osamu Fujiwara, Shiro Hasegawa and Takanobu Kamataki
津波堆積物の供給源及び堆積過程について〜有孔虫殻を用いた分析と水力学的検証から〜
内田淳一,長谷川四郎,藤原 治,鎌滝孝信
津波堆積物中に含まれる有孔虫群集から津波の振幅及び周期を復元するため,津波のパラメータを,堆積物の供給源における水深と堆積物の運搬距離の関数として定式化した.この式を,これまでの研究事例に適用し,津波の振幅及び周期を復元した.いくつかの例で復元された津波のパラメータは現実の津波のパラメータとほぼ一致するが,他の例では非現実的な大きな値となった.この原因として,(1)海底谷などのローカルな地形による津波の増幅,(2)主として有孔虫の不正確な同定による,堆積物の供給源の水深及び運搬距離の過大評価が考えられる.本論の成果は有史以前の津波の規模の復元や,津波堆積物とストーム堆積物の区別に有用である.
Key Words : critical depth, foraminifera, sediment transport, tsunami, tsunami deposits
7. Inundation flow velocity of tsunami on land
Hideo Matsutomi and Kensuke Okamoto
津波の氾濫流速
松冨英夫,岡本憲助
津波氾濫流速の推定は津波研究において重要な課題の一つである.本研究では,先ず現地調査データに基づいて,氾濫流速uと氾濫水深の関係を検討している.次に,Cv =(g:重力加速度,hf:建物前面での浸水深,hr:建物背面での浸水深)と定義された流速係数を実験的に検討し,実際的なものとして0.6を提案している.さらに,代表的な構造物模型周りの水際線(津波痕跡線)分布を実験的に検討し,現地調査結果と調和的であることを示している.そして,これらの検討結果に基づいて,実際的な氾濫流速推定式を提案している.この提案式から推定される氾濫流速は,現在開発されている津波砂移動モデルの照査に有用と考えられる.
Key Words : field survey, hydraulic experiments, inundation flow velocity, tsunami
通常論文
[Research Articles]
1. Subhorizontal tectonic framework of the Horoman peridotite complex and enveloping crustal rocks, south-central Hokkaido, Japan
Hiroshi Yamamoto, Natsumi Nakamori, Masaru Terabayashi, Hafiz Ur Rehman, Masahiro Ishikawa, Yoshiyuki Kaneko and Takashi Matsui
北海道中央南部の幌満かんらん岩体と周囲の地殻起源岩石が構成する水平的な地質構造
山本啓司, 中森夏美, 寺林 優, Hafiz Ur Rehman, 石川正広, 金子慶之, 松井 隆
北海道の幌満かんらん岩体とその周囲に分布する岩石との境界を追跡して幌満地域の地質構造を明らかにした.幌満かんらん岩体は厚さ約1200mの板状の地質体であり,全体として東に緩く傾斜している.幌満かんらん岩体の下位は白亜紀−古第三紀の付加コンプレックスからなり,かんらん岩との境界付近の堆積岩層に発達するリーデル剪断面は上位側が西に衝上する変位を示す.幌満かんらん岩体は,片麻岩類と貫入岩類からなる日高変成岩類に覆われている.かんらん岩体と変成岩類の境界面はドーム状である.境界面近傍に分布する剪断変形を受けた片麻岩類の微細構造は,上位側が東にずれる正断層型の変位を示す.これらの観察内容と既報の研究成果を総合すると,幌満かんらん岩体はアジア縁辺部(東北日本)と日高地殻ブロックとの衝突の際にアジア縁辺部の上に定置したものと考えられる.
Key Words : emplacement, Hokkaido, Horoman, peridotite, structure
2. Evolution of Mount Fuji, Japan: Inference from drilling into the subaerial oldest volcano, pre-Komitake
Mitsuhiro Yoshimoto, Toshitsugu Fujii, Takayuki Kaneko, Atsushi Yasuda, Setsuya Nakada and Akikazu Matsumoto
富士山の火山発達史:埋没した先小御岳火山掘削からの検討
吉本充宏,藤井敏嗣,金子隆之,安田敦,中田節也,松本哲一
富士山北東斜面での山体掘削の結果,玄武岩質の岩石を主体とする富士山火山や先小御岳火山の下位に,普通角閃石を含むデイサイトから安山岩質の岩石を特徴的に含む先小御岳火山が存在することが明らかとなった.先小御岳火山の活動年代は,K-Ar年代測定の結果,260ka-160kaと推定される.その活動は,穏やかな溶岩流噴火から始まり,玄武岩質安山岩からデイサイトの爆発的噴火へ推移した.その後,短い休止期を挟み,約100kaまで溶岩流主体の小御岳火山が活動,再び,短い休止期を挟んで爆発的な富士火山の活動に移行した.3火山の長期噴出率は,3 km3/ka以上の富士火山に対し,先小御岳火山や小御岳火山はかなり小さい.また,富士火山の全岩化学組成はSiO2量の変化に乏しいのに対し液相濃集元素が大きく変化する.一方,先小御岳火山は伊豆—ボニン弧の火山と同様にSiO2量の増加と共に液相濃集元素が増加する組成変化を持つ.これらの火山活動の変化は,150kaごろのこの周辺地域のテクトニクスの変化によって引き起こされた可能性が高い.
Key Words : basalt, drilling core, eruptive history, Fuji Volcano, hornblende dacite, Komitake Volcano, pre-Komitake Volcano
3. Temporal variations in channel patterns and facies architecture in a gravelly fluvial system: The Paleogene Iwaki Formation on the Joban Coalfield, a forearc basin in Northeast Japan
Kenichiro Shibata, Makoto Ito, Nagayuki Nemoto and Sakae O'hara
礫質河川システムの流路形態と堆積相構成の時間的変化:常磐炭田古第三系石城層
柴田健一郎,伊藤 慎,根本修行,大原 隆
福島県常磐炭田地域に分布する古第三系白水層群石城層を例として,前弧域で形成された礫質河川システムのシーケンス層序学的特徴を検討した.礫質河川堆積物の三次元的な堆積形態や構成堆積相の累重様式などの特徴と,常磐沖に分布する古第三紀浅海堆積物や周辺地域の同時代の地層との比較検討に基づくと,石城層の礫質河川堆積物は3サイクルの小規模な相対的海水準の上昇にともなった一連の相対的海水準の上昇に対応して形成されたと解釈される.礫質河川堆積物は癒着した河川流路堆積物とバー堆積物で主に構成され,それらの形態的特徴や累重様式には顕著な時空的変化は認められない.一方,礫質河川堆積物全体や,それを構成する3サイクルの河川流路堆積物複合体には明瞭な上方細粒化サイクルが認められ,従来の河川システムのシーケンス層序モデルの特徴と一致する.従って,石城層の礫質河川システムは,スタンダードなシーケンス層序モデルにおける1つのバリエーションを示すと考えられる.このようなバリエーションは,急勾配,短流路,粗粒堆積物の多量な供給など,前弧域で形成される河川システムの特徴を反映している可能性が考えられる.
Key Words : forearc basin, gravelly fluvial deposits, nonmarine sequence stratigraphy, Northeast Japan, Paleogene
4. SHRIMP U–Pb zircon chronology of ultrahigh-temperature spinel–orthopyroxene–garnet granulite from South Altay orogenic belt, northwestern China
Zilong Li, Yinqi Li, Hanlin Chen, M. Santosh, Wenjiao Xiao and Huihui Wang
中国北西部,南アルタイ造山帯から産出したスピネル-斜方輝石—ざくろ石超高温グラニュライトのSHRIMP U-Pb ジルコン年代
Zilong Li, Yinqi Li, Hanlin Chen, M. Santosh, Wenjiao Xiao and Huihui Wang
中国北西部,南アルタイ造山帯から産出したスピネル-斜方輝石—ざくろ石超高温グラニュライトの特徴的な鉱物組合せ,鉱物組成,ジルコンSHRIMP U-Pb年代について調べた.アルタイ造山帯は古生代に形成されたシベリアプレートとカザフスタン−ジュンガルプレートとの間に発達した付加体である.本研究で解析した超高温変成岩は,スピネル+石英の共生と減圧時に生じた斜方輝石,スピネル,珪線石,菫青石からなる連晶等のピーク変成作用時および後退変成作用時の鉱物組合せおよび微細構造を残している.石英と共生するスピネルは低いZnO量をもち,斜方輝石はAlに富み,Al2O3量を最大で9.3 wt%含む.変成作用のピーク温度は950℃以上で,超高温変成作用の条件を満たしており,変成岩類は時計回りの温度−圧力経路を経て上昇した.超高温変成岩に含まれるジルコンは累帯構造を示し,残留ジルコンからなる核部と変成作用で形成され縁部をもつ.核部は499±8 Ma(7点)と855 Ma (2点)のバイモーダルな年代を示し,丸みを帯びた砕屑性のジルコンは490−500 Maの年代をもつ.グラニュライトは,ジルコンのU-Pb閉止温度を越える900℃以上の温度条件で形成されていることから,大勢を占める499±8 Maの年代は,大陸縁における約500 Maの火成岩区から供給されたジルコンとともに,原岩の形成年代を示していると解釈できる.超高圧変成岩類は,古アジア海の北方への沈み込みとそれに伴うシベリアプレートとカザフスタン−ジュンガルプレートの付加−衝突テクトニクスに密接に関係して形成され,その後,減圧により急速に上昇した.
Key Words : mineral reaction, zircon SHRIMP U-Pb age dating, tectonometamorphic evolution, ultrahigh-temperature granulite, South Altay orogenic belt
5. Stratigraphy of the mid- to upper-Cretaceous System in the Aridagawa area, Wakayama, Southwest Japan
Akihiro Misaki and Haruyoshi Maeda
和歌山県有田川地域の“中部”〜上部白亜系層序
御前明洋,前田晴良
和歌山県有田川地域の矢熊池周辺に分布する白亜系の層序学的研究を行った.産出する大型化石から,断層で区切られたブロックの一つにはAlbian階中部〜上部が,他のブロックにはTuronian階中部〜Santonian階が分布することがわかった.Albianの堆積物は,豊富な遊泳生物とは対照的に底生生物をほとんど含まず,また,生物撹拌が弱く葉理の発達した泥岩が卓越する.これは貧〜無酸素環境下での堆積を意味し,海洋無酸素事件の影響が示唆される.四国でも同様の堆積物が知られており,世界的な環境変動の影響を直接受ける広大な堆積盆が秩父帯上に存在した と思われる.調査地域の上部白亜系は,四国で報告されたもの同様その層厚が極端に薄く,白亜紀後期の前半にはこの堆積盆の堆積速度が非常に遅かったと推定される.
Key Words : Albian, ammonoids, Aridagawa, benthos, bioturbation, Chichibu Belt, Cretaceous, Oceanic Anoxic Events (OAEs), Southwest Japan, Wakayama
6. Parentage of low-grade metasediments in the Sanbagawa belt, eastern Shikoku, Southwest Japan, and its geotectonic implications
Kazuo Kiminami
四国東部三波川帯の低度変成堆積岩の原岩層とその地体構造上の意義
君波和雄
四国東部の穴吹地域と神山地域の三波川帯低変成度部(緑泥石帯)は,岩相や地質構造から北部と南部に分けられる.砂質片岩と泥質片岩の全岩化学組成の特徴は,北部と南部がそれぞれ四万十帯北帯のKS-IIユニット(コニアシアン-カンパニアン)とKS-Iユニット(後期アルビアン-前期コニアシアン)の変成深部相であることを示唆する.三波川帯の原岩層の年代を考慮すると,三波川変成帯・北部から北部秩父帯南部に向かって堆積年代は大局的に古くなる.一方,三波川帯および北部秩父帯に含まれる級化した砂質片岩・砂岩は,多くが南上位を示す.これらのデータは,四国東部の三波川変成帯〜北部秩父帯の層理・片理が何らかの造構運動により北傾斜から南傾斜に転換した可能性を示唆する.北に若くなる年代極性や地質構造,すでに報告されているビトリナイト反射率などから,北部秩父帯は三波川変成帯の上載層をなしていたと推定される.
Key Words : Chichibu belt, geochemistry, geotectonics, Sanbagawa belt, Shikoku, Shimanto belt
7. Influence of shear angle on hangingwall deformation during tectonic inversion
Yasuhiro Yamada and Ken McClay
インバージョン背斜構造の形態における単純せん断方向の影響
山田泰広,Ken McClay
応力場の転換に伴って正断層が逆断層として再活動するときに形成される背斜構造の形態は,上盤せん断変形の方向(せん断角)と断層形状によって支配される.本論では,バランスドクロスセクション法を応用した数値シミュレーションを行って,せん断角の変化に伴う変形形態の影響について検討し,モデル実験結果などと比較した.その結果,背斜構造の最終的な形態や変形同時堆積物の層厚変化,断層変位量などは伸張時と圧縮時の両方のせん断角によって支配されること,一般に応力場の転換に伴ってせん断角が低角化すること,この低角化に伴って深部で正断層・浅部で逆断層という変位パターンを持つ断層が形成されることなどが明らかになった.
Key Words : hangingwall deformation, inclined simple shear, numerical simulation, tectonic inversion
最終原稿提出の際のお願い(著者へ)
地質学雑誌:最終原稿(受理原稿)ご提出の際のお願い
1)採択メールのコメントご確認ください
担当幹事,査読者からの最終コメントが採択メール上に表示されている場合がありますので,ご確認のうえ,最終原稿作成の際に反映させて下さい.
2)入稿の作業のため,下記をご提出をお願いします
学会事務局宛(journal[at]geosociety.jp)に下記をご提出ください.
文章データ
図表類のデータ
著作権譲渡等同意書[郵送]
1.文章データ(テキスト)
word等の汎用形式でご提出ください.PDFデータは印刷用には使用できません.下記の必要な情報がそろっているか,今一度ご確認ください.
表題・著者名・所属先(いずれも和英)/柱(ヘッダー)/key word(英)/英文要旨/和文要旨(総説・論説の場合)/ 本文 / 文献欄 / 図表説明文 /著者貢献orプロフィール(共著の場合は必須)
2.図表類のデータ
印刷所での互換性を考慮し,下記のいずれかのデータ形式で保存してください.
(a)psd. jpg. tif. eps.(解像度は,掲載サイズ等倍で300〜350dpiが望ましい).PDFデータは印刷用には使用できません.
(b) ai.(llustrator形式.文字化け防止のため,文字はアウトライン化して下さい)
(注)Table(表)に関するお願い:論文本体にTableを掲載する場合:表も上記いずれかの画像データとしてご提出下さい。地質学雑誌では,表の組版は行っていません。Excelデータをご提出頂いても印刷には使用しません(表組が動いたり,文字が切れる可能性があります)。
[データファイルについて]
データファイルは,J-STAGE Dataにまとめて事務局からアップロードします.受理時にデータをご提出ください.
キャプションとは別にデータファイル全体に付すタイトル(英)をお知らせください.(500文字以下):論文本体のタイトルとは別に,データファイルの内容をまとめて示すタイトルをつけてください.(注)J-STAGE Dataは,元論文から独立してdoiが付与され利活用されることを目的としているため,「元論文を見ていない,知らない状態でも内容を理解できるタイトル」を付してください.NG例: Supplementary data to "論文のタイトル".
J-STAGE Dataに搭載するTableはできるだけ“csv形式” で提出してください:数値データの場合、汎⽤的で機械可読可能なデータ形式(CSV形式やTSV形式)のファイルをアップロードしてください。その際には、総務省の「統計表における機械判読可能なデータ作成に関する表記⽅法」資料にある、統計表のレイアウトでのチェック項⽬を遵守する(ファイル内の数値データは数値属性とする、セルを結合しない、数式を使⽤せず数値にする)ことも⾮常に重要です。ぜひともご参照のうえ、ご留意のほどお願いします。また、⽇本語を含むCSVファイルは⽂字コードをUTF-8に設定してください。UTF-8以外の⽂字コードでは⽂字化けしてプレビュー表⽰されます。
(参考)J-STAGE DataでのFAIR原則に沿った研究データ公開(JST; 科学技術振興機構)
学会事務局へのデータの送付方法:
メディアでの送付(郵送),メール添付,データ便など送付方法は問いません.また,受理後に修正がなく,査読システムS1M上にアップロードされているデータが上記形式の場合はデータの送付は不要です.ただし,PDF形式のデータは印刷用には使用できません.同意書のみ郵送して下さい.
3.著作権譲渡等同意書を郵送してください
下記より著作権譲渡等同意書をダウンロードし,必要事項を記入して学会事務局宛に原本を郵送して下さい.
(郵送先)〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル 日本地質学会
▶︎同意書ダウンロードはこちらから
・著作権譲渡等同意書への署名捺印のお願い(News誌2002年12 月号掲載)
3)著者校正の予定
入稿後,著者校正のため校正刷り(PDFメール添付)をお送りいたします。出張等の長期不在予定(メールの送受信が困難など)がある場合は,あらかじめご連絡下さい。
注意:巡検案内書の校正については,別途案内書編集委員会よりご連絡を致します。
4)別刷および著者負担金
著者校正送付時に別刷の注文確認を行います.別刷費用や規定頁超過による著者負担金は,出版後,事務局庶務担当者よりご請求させて頂きます.費用については,編集規則「細則3 出版印刷費用等に関する細則」をご参照のうえあらかじめ概算のご確認をお願いいたします.
なお、別刷の購入如何に関わらず、掲載に関わる以下場合で著者負担金が発生いたします。ご留意ください。
規定頁を超過して掲載する場合(16,000円/ページ)*原稿種別により規定頁は異なります.
著者校正段階で、図表類の差替えを行う場合(600-800円/点)
価格表等くわしくは、編集規則をご参照ください.
一般社団法人日本地質学会
事務局編集担当
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F
eメール:journal[at]geosociety.jp([at]を@マークにして下さい)
Island Arc 日本語要旨 2011. vol. 20 Issue 1 (March)
Vol. 20 Issue 1 (March)
[Pictorial Articles]
1. Late Cretaceous forearc ophiolites of Iran
Hadi Shafaii Moghadam and Robert J. Stern
イランにおける白亜紀後期の前弧オフィオライト
Hadi Shafaii Moghadam and Robert J. Stern
特集号:Thematic section: Paleoclimates in Asia during the Cretaceous: Their variations, causes, and biotic and environmental responses (IGCP Project 507) Part 2
Guest Editors : Takashi Hasegawa and Hisao Ando
白亜紀におけるアジア古気候:多様性,原因および生物と環境の反応(IGCP project 507),その2
長谷川卓,安藤寿男
2. Preface
Takashi Hasegawa and Hisao Ando
序文
長谷川卓,安藤寿男
第507次国際地球科学計画(IGCP)では,白亜紀におけるアジアの古気候の発達に焦点を当てている.本プロジェクトに参画する研究者は白亜紀の気候変化の原因について議論し,テクトニクス,軌道周期あるいは火山活動を強制力とする気候撹乱を探り,また気候変化に対する生物圏における反応を調べている.本特集はIsland ArcのIGCP507に関する特集の第2弾で,19巻4号に掲載された内容を補うものであり,同プロジェクトの第2回(ソウル)および第3回(ウランバートル)国際シンポジウムのプロシーディングスとして編集された.本特集にはアジアにおける白亜紀の堆積環境を扱った5つの論文が掲載されている.その内容は,有機地球化学,微古生物学および古植物学を手法とした研究,そしてシベリア東部から古太平洋北西縁に渡る範囲の古地理・古気候の総括を行った研究成果である.
3. Late Cretaceous paleoenvironment and lake level fluctuation in the Songliao Basin, northeastern China
Dangpeng Xi, Xiaoqiao Wan, Luba Jansa and Yiyi Zhang
中国東北部・松遼堆積盆地における後期白亜紀の古環境および湖水準の変動
Dangpeng Xi, Xiaoqiao Wan, Luba Jansa and Yiyi Zhang
中国の松遼堆積盆地東部の湖成層の研究により,ヤオチァ層のサントニアン上部では相対的に乾燥し,かつ暑い古気候であったが,カンパニアン下部のネンチァン層では相対的に温暖湿潤になったことが解ってきた.ヤオチァ層上部は淡水湖環境で堆積したが,ネンチァン層下部は汽水の影響下で堆積した.ヤオチァ層上部の有機炭素含有量は平均0.15%であるが,水素指標は36 mgHC/gTOCであって,これらのことはこの堆積岩が石油根源岩には不向きであり,有機物が木本類や草本類に由来することを示唆している.それとは対照的に,ネンチァン層下部の油母頁岩と黒色頁岩の水素指標は619 mgHC/gTOC,有機炭素含有量は平均3.37%である.これらはケロジェンの起源が藻類と草本類の混合物であり,当時の水域で生物生産性が増加したことを示している.黒色頁岩と油母頁岩のプリスタン/フィタン比およびC295α,14 α,17 α (H)スティグマスタンの20R/(20R+20S)比は低く,最も存在比の高いノルマルアルカンはn-C23である.これらは藻類,バクテリア類および高等植物によって有機物が供給される無酸素的堆積環境を示唆している.油母頁岩では相対的にガンマセランの存在量が多くSr/Ba比が高いが,これらは汽水の存在と塩濃度による湖の成層を示唆している.ヤオチァ層上部からネンチァン層下部にかけての堆積の期間,松遼の湖水準は上昇を続け,湖底で酸素が欠乏するような深い湖環境が形成されていった.湖水深の増加に付随して湖底は富酸素的な状態から無酸素的状態に変わり,高等植物が支配的であった供給有機物はバクテリア,藻類および高等植物の混合物へと変わったことで,石油根源物質が濃集しやすい環境が形成された.
Key Words : Cretaceous, lake level fluctuations, microfossil, organic geochemistry, paleoclimate, paleoenvironment, sea ingressions, Songliao Basin
4. Polycyclic aromatic hydrocarbons in the Jurassic–Cretaceous Tetori Group, central Japan
Takashi Hasegawa and Tsuyoshi Hibino
ジュラ−白亜系手取層群中の多環芳香族炭化水素
長谷川卓,日比野剛
手取層群試料中の多環芳香族炭化水素(PAH)の分布から,堆積環境や有機物熟成度を推定した.福井県大野市和泉セクションにおける熱熟成度は,赤岩亜層群上部ではビトリナイト反射率換算値が1.35%以下だが,下位に向かって増加し,九頭竜亜層群では2%を超える.PAHの層序分布は熱熟成度分布によりほぼ説明できる.富山県立山セクションのPAH分布もほぼ同様に説明できる.和泉の石徹白亜層群から検出したコロネンは堆積当時の山火事に由来する可能性がある.含硫黄PAHは,淡水成層の試料も含め,両セクションの試料ほぼ全てから検出された.一部の還元態硫黄が再酸化されて元素硫黄となって堆積物中に残り,含硫黄PAH形成に寄与したと推察される.手取層群の含硫黄PAHは海成層と淡水成層とを区別する指標にはならない.
Key Words : coronene, methylphenanthrene index, MPI-1, PAH, paleoenvironment, polycyclic aromatic hydrocarbon, Tetori Group, thermal maturity
5. Early Cretaceous palynofloral provinces in China: western additions
Jianguo Li and David J. Batten
前期白亜紀の花粉古植物区:西部への追加
Jianguo Li and David J. Batten
中国西部の西蔵(チベット)を含む地域において,2つの明瞭な前期白亜紀の花粉古植物地区が認識できた.一つは,cheirolepidiaceanに属する花粉粒子Dicheiropollisの産出によって示され,もう一つは異なる裸子植物花粉の多産,特にAraucariacitesとCallialasporites,によって特徴付けられる.それらの境界はヤールン−ザンボ縫合線に一致する.縫合線の北側では西蔵-塔里木Dicheiropollis 地区が新疆南部から青海-西蔵台地の中・北部,そして雲南の西部にまたがる広い地域を占めている.縫合線の南側の南部西蔵Araucariacites-Callialasporites 地区は南部ゴンドワナ(植物)界と類縁性を持つ.他の花粉古植物地区と群集組成が類似する点がいくつかあるが,これらの2地区は明瞭であり,異なる気候を反映していると考えられる.Dicheiropollis 地区については高温乾燥から準乾燥状態が示唆され,Araucariacites-Callialasporites 地区については,より湿潤でやや冷涼な気候が示唆される.
Key Words : Words : Early Cretaceous, Gondwana, paleoclimate, palynofloral province, palynofloral realm, Tethys, western China
6. Pseudofrenelopsis fossils from Cretaceous gypsum beds in Guixi, Jiangxi Province, China and their geological significance
Bainian Sun, Jing Dai, Yongdong Wang, Hui Jia, Defei Yan and Zikun Jiang
中国江西省貴渓の白亜系中の層状石膏から産出したPseudofrenelopsisとその地質学的意義
Bainian Sun, Jing Dai, Yongdong Wang, Hui Jia, Defei Yan and Zikun Jiang
中国江西省貴渓市におけるチョウチァティエン層の層状石膏中に植物圧縮化石が発見された.本研究ではPseudofrenelopsis (Cheirolepidiaceae)の2種のクチクラの特徴を走査型電子顕微鏡で調べた.それらはPseudofrenelopsis papillosa Cao ex ZhouとPseudofrenelopsis guixiensis Bainian Sun et Dai sp. nov. である.それら2種の節間表皮と,葉の向軸および背軸側のクチクラを詳細に解析した結果,絶滅属であるPseudofrenelopsisの形態学的および解剖学的特徴についての知識を広げることができた.クチクラの特徴比較に基づいて,新種のPseudofrenelopsis guixiensis Bainian Sun et Dai sp. nov. を提案した.この種と既知の種との違いは,この種が葉の背軸側に毛を持つこと,節間の表皮にある気孔がしばしば副細胞を共有すること,下皮を欠くこと,そして表皮細胞に乳状突起を持たないことである.Pseudofrenelopsis属化石の分布は下部白亜系に限られるため,チョウチァティエン層の年代が前期白亜紀であることが確実になった.Pseudofrenelopsis属の化石は,クチクラが肥厚していること,副細胞に明瞭な乳状突起を持つこと,および強くクチン化した垂層細胞壁を持つことなど,明らかな乾生形態の特徴を示している.また同属の化石の産出は層状石膏に伴っており,赤色層の層準にも近い.これら全ての特徴は堆積場が乾燥気候下にあったことを示している.
Key Words : China, Early Cretaceous, gypsum, Jiangxi Province, Pseudofrenelopsis
7. The Cretaceous of the East Asian continental margin: Stratigraphy, paleogeography, and paleoclimate
Galina L. Kirillova
白亜紀の東アジア大陸縁辺:層序・古地理・古気候
Galina L. Kirillova
東アジア大陸縁辺,サハリンおよび北海道における,層厚 6 - 10 km におよぶアプチアン−マストリヒシアン期の陸源堆積物のシーケンスについて,岩相層序対比の検討から,これらをもたらした単一の海成堆積盆の存在が明らかとなった.この堆積盆は,セノマニアン期中期まではテチス系−北方系混在動物群と東方に傾斜する堆積面で特徴付けられる.アルビアン期中期からセノマニアン期にかけての活発な火山活動や構造運動が大陸縁の隆起をもたらし,海岸線が東方に移動していった.古植物学的研究は以下のように多くの古気候変動を見出している.アプチアン期は相対的に温暖であったが,アルビアン期初期にはより冷涼になった.広葉の顕花植物が卓越するアルビアン期後期〜セノマニアン期には温暖最盛期となった.後期白亜紀には東アジアの火山帯は標高3000mに達する山脈を形成し,経度方向の気候帯や植生分布を制御した.この制御は緯度的な制御より効果的であった.チューロニアン期に顕花植物のスズカケノキ科(Platanaceae)が広く生息したことは相対的な冷涼化を示している.さらに植物群の証拠は,コニアシアン期初期から温暖気候が進行し,汎世界的な海進に対応するカンパニアン期に最温暖期となったことを指示している.温暖気候の結果として,マストリヒシアン期初期は高多様性生物群によって特徴付けられる.マストリヒシアン期中期になると,動植物群の多様性は減少し季節性の影響が増大していき,マストリヒシアン期末期には冷涼化が起こった.セノマニアン期後期からマストリヒシアン期後期を通じて,石炭の集積期は5つ認められる.大陸縁の陸棚,三角洲,斜面タービダイト相には 0.3〜2.2 %の有機炭素が含まれており,石油・ガスの直接的な徴候とともに,炭化水素探鉱にとっての有望性の証拠とみなされている.
Key Words : correlation, Cretaceous, East Russia, Hokkaido, lithostratigraphic succession, paleoclimate, paleogeography, petroleum potential, sedimetary environments
通常論文
[Review Articles]
8. Comparison of rhyolites from continental rift, continental arc and oceanic island arc: Implication for the mechanism of silicic magma generation
Dereje Ayalew and Akira Ishiwatari
大陸リフト帯,陸弧及び海洋性島弧の流紋岩の比較論:シリカに富むマグマ形成のメカニズムとの関連
Dereje Ayalew,石渡 明
エチオピアの大陸リフト帯(漸新−中新世及び第四紀の双方),日本の前期中新世陸弧(日本海拡大に関連する鷲走ヶ岳流紋岩),そして伊豆・小笠原の海洋性島弧という,明瞭に異なる3つの構造場に産する流紋岩について化学組成を議論する.これらを比較すると,海洋性島弧の流紋岩はCaO, Al2O3, Srに富み,K2Oや微量元素に極端に乏しい.対照的にエチオピアの大陸リフト帯の流紋岩はCaO, Al2O3, Srに乏しくK2Oや微量元素に富む.陸弧の鷲走ヶ岳流紋岩は,Nbに乏しい特徴はあるものの,エチオピアの流紋岩とよく似た化学的傾向を示す.これら3つの異なる構造場の流紋岩の化学的特徴の顕著な違いは,マグマが由来した給源物質の違いを示す.今回の比較検討結果は,大局的な構造場と地殻の性質(年代,厚さ,組成)の違いにも関わらず,大陸と陸弧のリフト帯に関連した流紋岩においてはマントル起源マグマからの結晶分化作用が支配的であるのに対し,海洋性島弧の流紋岩においては若い苦鉄質地殻物質の部分溶融が重要であることを示す.
Key Words : continental arc, continental rift, fractionation of mantle-derived magma, oceanic island arc, partial melting of mafic crust, rhyolites
[Research Articles]
9. Constant slip rate during the late Quaternary along the Sulu He segment of the Altyn Tagh Fault near Changma, Gansu, China
Yeong Bae Seong, Hee Cheol Kang, Jin-Han Ree, Chaolu Yi and Hyeon Yoon
中国甘粛省昌馬付近のAltyn Tagh断層のSulu Heセグメントで測定された後期第四紀における一定のすべり速度
Yeong Bae Seong, Hee Cheol Kang, Jin-Han Ree, Chaolu Yi and Hyeon Yoon
地質学的手法によって求められる千年スケールのすべり速度が,測地学的手法で求められる数十年スケールのすべり速度と矛盾しないのかとの疑問は,チベット高原内における大陸内変形の実体を評価する上で非常に重要である.われわれは,地形学的特徴,リモートセンシングデータ,宇宙線生成核種10Beを用いて求めた地形表面露出年代に基づいて, 中国甘粛省昌馬付近のAltyn Tagh断層のSulu Heセグメントの時間平均すべり速度を決定した.調査域では,第四系扇状地堆積物(Qf1, Qf2, Qf3)は,Altyn Tagh断層に沿った左横ずれ運動により変位している.それらの変位は非常に大きいため,扇頂が扇状地から離れているものも認められる.断層変位の総計は,少なく見積もっても,Qf1では429 ± 41 m,Qf2では130 ± 10 m,Qf3では32 ± 1 mである.また,Qf1およびQf2の地形表面露出年代は,それぞれ100–112 kaおよび31–43 kaである.したがって,Qf1およびQf2の堆積時依頼のすべり速度は,3.7 mm/yrと見積もられる.
Key Words : Altyn Tagh Fault, cosmogenic 10Be dating, displacement, Slip Rate
10. Petrochemistry and tectonic setting of mafic volcanic rocks in the Chon Daen–Wang Pong area, Phetchabun, Thailand
Apichet Boonsoong, Yuenyong Panjasawatwong and Keatisak Metparsopsan
Chon Dean-Wang Pong地域(タイ国ペッチャブーン県)における苦鉄質火山岩類の地球化学的特徴とテクトニックセッティング
Apichet Boonsoong, Yuenyong Panjasawatwong and Keatisak Metparsopsan
Chon Dean-Wang Pong地域に分布する苦鉄質火山岩類と半深成岩類は,おそらく,タイ北東部のwestern Loei Volcanic Sub-beltの南方延長に当たる.これらは変質が少なく,ペルム紀から三畳紀にかけて形成されたと思われる.通常,斑状組織をなし,斜長石,単斜輝石,斜方輝石,角閃石,Fe-Ti酸化物,未詳の苦鉄質鉱物,燐灰石の斑晶を様々な量比で含む.また,まれにシリイット組織も認められることがある.石基は多くの場合インターグラニュラー組織を示すが,ハイアロオフィチック,インターサータル,オフィチック〜サブオフィチック組織を示すこともある.石基を構成する鉱物は,斑晶あるいは微斑晶のそれと同じで,変質したガラスを含むこともある.斑晶の斜長石は,定向配列を示すことがある.研究対象とした岩石類は,化学的に,グループI,グループII,グループIIIの3つのマグマグループに分けられる.これらのマグマグループは,Zr/Ti比が異なり,グループIの平均Zr/Ti比は83 ± 6,グループIIは46 ± 12,グループIIIは29 ± 5である.この特徴に加えて,グループIは,グループIIとグループIIIに比べ,高いP/Zr比,低いZr/Nb比を持つ.グループIとグループIIは,ソレアイト質安山岩−玄武岩,マイクロ閃緑岩−マイクロガブロからなり,グループIIIは,カルクアルカリ安山岩−マイクロ閃緑岩からなる.マグマの類縁性とN-MORB規格化図におけるNbの負の異常から,これらの岩石は島弧形成に関係した溶岩類であると考えられる.コンドライトで規格化した希土類元素パターンとN-MORB規格図における研究対象とした溶岩類と北部琉球弧の第四紀の溶岩類との類似性は,Chon Dean–Wang Pong地域の苦鉄質火山岩類と半深成岩類が火山弧で形成されたことを結論づける.
Key Words : mafic volcanic and hypabyssal rocks, Permian –Triassic, porphyritic, tholeiitic, volcanic arc
11. Chemical characteristics of chromian spinel in plutonic rocks: Implications for deep magma processes and discrimination of tectonic setting
Shoji Arai, Hidenobu Okamura, Kazuyuki Kadoshima, Chima Tanaka, Kenji Suzuki and Satoko Ishimaru
深成岩中のクロムスピネルの化学的性質:深部マグマ過程およびテクトニック・セッティングの識別
荒井章司,岡村英伸,角島和之,田中小満,鈴木健之,石丸聡子
超マフィック〜マフィク深成岩(マントルかんらん岩,ダナイト,ウェールライト,トロクトライト,かんらん石ガブロ)中のクロムスピネルの化学的性質を,それらの岩石のテクトニック・セッティング(中央海嶺,島弧および海洋ホットスポット)を考慮してまとめた.上記3つのセッティングは,スピネルの組成範囲はTi含有量とCr#(Cr/(Cr+Al)原子比)によりを識別できる.そのセッティング間の関係は噴出岩中のスピネルの場合と同様であるが,Ti含有量は系統的に深成岩の方が低い.同じ岩相で比べた場合,Ti量は島弧,海嶺,ホットスポットの順に高くなる.このスピネルの性質は,特にダナイトを扱う時に有用である.オマーンとリザードの両オフィオライトのダナイトに応用して起源を論ずる.
Key Words : chromian spinel, Cr/(Cr + Al) ratio, tectonic setting, Ti content, ultramafic plutonics
12. 83 Ma rhyolite from Mindoro – evidence for Late Yanshanian magmatism in the Palawan Continental Terrane (Philippines)
Ulrich Knittel
ミンドロ島(フィリピン)の83 Maの流紋岩−パラワン大陸地塊における後期Yanshanian火成作用の証拠
Ulrich Knittel
83±1 Maの低変成流紋岩の発見によって,パラワン大陸地塊の北東端に位置する北部ミンドロ島における火成作用の存在がはじめて明らかになった.この地塊は,南シナ海の開裂の結果として漸新世に南東中国から分裂した.白亜紀,流紋岩質火成活動が南東中国に拡がっていたことから,この低変成流紋岩の発見は,白亜紀のパラワン大陸地塊と南東中国との地質学的関連をはじめて結びつけるものであり,さらに,ミンドロ島北東部が,以前考えられていたような東方のフィリピン変動帯の一部ではなく,パラワン大陸地塊の一部であったということをも示唆している.
Key Words : U-Pb dating of zircons, Mindoro, Philippines, late Cretaceous rhyolite, volcanism, Palawan Continental Terrane
引用文献:雑誌略名について
地質学雑誌:参照
引用文献:雑誌略名について
地質学雑誌編集出版規則細則「引用文献の書式に関する細則」に示されている論文以外の,代表的なものの省略の仕方をまとめてみましたので,参考にして下さい.ここにも ない単語の省略形については,ブリティッシュコロンビア大学図書館のウェブサイト(http://woodward.library.ubc.ca/research-help/journal-abbreviations/)に準拠して省略して下さい.
■■引用文献・略記例(PDF)はこちらからダウンロード■■
■■編集出版規則および細則(PDF)はこちらからダウンロード■■
Island Arc 日本語要旨 2011. vol. 20 Issue 2 (June)
Vol. 20 Issue 2 (June)
Island Arc Award (2011)
Title: Evaluation of factors controlling smectitetransformation and fluid production in subductionzones: Application to the Nankai Trough.
Authors: Demian M. Saffer, Michael B. Underwoodand Alexander W. McKiernan
References: Island Arc, 17, 208–230 (2008).
沈み込み帯におけるスメクタイトの分解と流体の放出をコントロールする要素の評価:南海トラフへの応用
通常論文
[Research Articles]
1. Oxygen and lead isotopic characteristics of granitic rocks from the Nansha block (South China Sea): Implications for their petrogenesis and tectonic affinity
Quanshu Yan, Xuefa Shi and Naisheng Li
南沙微小地塊 (南シナ海)の花崗岩質岩の酸素同位体及び鉛同位体の特徴:成因とテクトニックな類似性について
Quanshu Yan, Xuefa Shi and Naisheng Li
南シナ海地域の先新生代の地史は,今なお議論されている問題である.南シナ海の発達を明らかにするためには,微小地塊に含まれる花崗岩類の成因と帰属をより正確に理解することが必要である.本研究では,南沙微小地塊の2カ所のドレッジで回収された花崗岩質岩試料の全岩酸素同位体比および鉛同位体比を求めた.酸素同位体のデータをすでに公表されているストロンチウム同位体のデータと結びあわせることで,グループIの岩石類(δ18O = 6.00–7.20‰; average = 6.64‰)が,微小地塊の南東側における中生代沈み込み帯から付加された物質あるいは流体によって汚染されたマントルに由来することが明らかになった.グループIIも同様にマントルに由来するが,二次的に地殻物質による汚染を受けている.南沙微小地塊は高い放射性鉛比 (206Pb/204Pbi = 18.602–18.756, 207Pb/204Pbi = 15.660–15.713, 208Pb/204Pbi = 38.693–38.893)をもち,このことは,南沙微小地塊が構造的に南陵县-海南地塊あるいは南シナ地塊に属することを意味している.この結論は,以前に行われたNd同位体の研究結果と良い一致をみる.我々の研究の結果は,南シナ海に散点的に分布する他の微小地塊の中には,南シナ地塊の破片が含まれる可能性を示唆している.先新生代における南シナ海地域の発達史をより正確に求めるためには,さらなる研究が必要である.
Key Words : Geochemistry, granitic rock, Mesozoic era, Nansha microblock, petrogenesis, South China Sea
2. In-situ stress at a site close to the Gofukuji Fault, central Japan, measured using drilling cores
Yasuo Yabe and Kentaro Omura
掘削コアから推定した牛伏寺断層近傍の地殻応力
矢部康男・小村健太朗
牛伏寺断層近傍で行った掘削により深度327mと333mで採取されたコア試料に,変形率変化法(DRA),AE法,AE率変化法(AERA)を同時適用し,地殻応力を推定した.いずれの深度でも,横ずれ断層型の応力場が推定された.掘削時に,深度333mでは,孔壁を構成する岩石である花崗閃緑岩の引張強度と同程度の約6.4MPaの引張応力が孔壁に作用した.深度327mでは引張応力は,同強度よりも小さかった.これらは,Drilling-Induced Tensile Fractureが深度329-334mで発生したことと整合する.牛伏寺断層に作用する法線応力に対するせん断応力の比は0.4-1.0で,室内岩石実験の摩擦係数と同程度である.これは,地震の再来間隔に基づく長期評価で,地震発生の切迫度が高いと評価されている同断層の強度がすでに回復していることを表しているのであろう.
Key Words : core method, fault strength, Gofukuji Fault, in-situ stress
3. Relicts of deformed lithospheric mantle within serpentinites and weathered peridotites from the Godzilla Megamullion, Parece Vela Back-arc Basin, Philippine Sea
Yumiko Harigane, Katsuyoshi Michibayashi and Yasuhiko Ohara
フィリピン海パレスベラ背弧海盆のゴジラメガムリオンから採取された蛇紋岩と風化したかんらん岩に残されたマントルリソスフェアの変形構造
針金由美子・道林克禎・小原泰彦
フィリピン海パレスベラ海盆のゴジラメガムリオン全体から採取された蛇紋岩と風化したかんらん岩の変形構造過程を明らかにした.これらは構造ごとにマッシブ,フォリエーテッド,マイロナイトに分けられた.岩石に残されていた初生的な鉱物(斜方輝石,単斜輝石,スピネル)には塑性変形の際に見られる微細構造が観察されたが,蛇紋石にはそのような変形構造は見られなかった.以上の観察結果からマントルリソスフェアにおいて延性剪断帯が発達したことと,変形の後に蛇紋岩化作用が生じたことを示唆する.これらの構造を持つ岩石がゴジラメガムリオン上に分布していることから,マントルリソスフェアに生じた変形構造はゴジラメガムリオンの形成過程に関連していたと考えられる.
Key Words : Godzilla Megamullion, Parece Vela Basin, peridotite, Philippine Sea, serpentinite
4. Slab partial melts from the metasomatizing agent to adakite, Tafresh Eocene volcanic rocks, Iran
Mohammad R. Ghorbani and Rasoul N. Bezenjani
イラン,Tafresh 始新世火山岩類中のアダカイト生成に関わるスラブ部分溶融と交代作用
Mohammad R. Ghorbani and Rasoul N. Bezenjani
Urumieh–Dokhtar Magmatic Assemblage (UDMA)の一部をなすTafresh地域に分布する始新世火山岩類は,延長2000 kmにわたって地球化学的および鉱物学的にユニークな特徴をもつ.顕著な急勾配をもつ希土類元素パターンと角閃石斑晶の広範な出現は,主に安山岩質組成からなる始新世火山岩類で卓越する二つの大きな特徴である.アダカイト,すなわちここでは,角閃石(+黒雲母)に富むデイサイト(SiO2=61-64 wt%)の岩株と岩脈,を伴う火山岩類全体の地球化学的および鉱物学的特徴の一致は,一連の火山岩類の成因に関するスラブ由来のメルトの役割を明らかにするための鍵になる.スラブに由来する溶融は,混成岩(安山岩)のもととなったマントルウエッジの交代作用を受けた部分で生じている現在進行中のプロセスである.スラブ溶融交代作用の顕著な特徴をもつ玄武岩類の存在は,スラブ溶融を支持するもう一つの証拠である.島弧性のカルクアルカリ火山岩類とスラブ溶融交代作用を受けた玄武岩類および混成安山岩類との互層の存在は,スラブの溶融が沈み込みによって引き起こされたことを示唆している.爆発的な噴火の結果と考えられるTafreshカルデラの形成は,アダカイトの火山活動がガス成分を含むマグマの活動であることと調和的である.マグマがガス成分を含んでいたであろうことは,含水鉱物が普遍的に認められることからわかる.始新世の時代,沈み込むスラブはTafresh地域直下の角閃岩-エクロジャイトの形成に十分な深さに達していたと考えられる.沈み込みの幾何学的配置や下位に位置するマントルのより急激な地温勾配によって生じたスラブの変形は,UDMAに特有の岩石の組合せの発達を助長したスラブ融解を引き起こしたと考えられる.
Key Words : adakite, Eocene, metasomatized mantle, geochemistry, Iran, Urumieh–Dokhtar
5. Sedimentary history with biotic reaction in the Middle Permian shelly sequence of the Southern Kitakami Massif, Japan
Yuta Shiino, Yutaro Suzuki and Fumio Kobayashi
南部北上帯中部ペルム系の化石層について,その堆積過程と古生物の応答
椎野勇太,鈴木雄太郎,小林文夫
日本などの活動的大陸縁辺部で見られるような地殻活動は,堆積盆において様々な底質環境を生む原動力となる.そのため,生物遺骸が複数の供給過程を経て埋没した場合は,その堆積盆における見かけ上の生物多様性が高くなるため,化石生物相とその変遷を理解する上で大きな障害となる.本研究は,活動的な堆積盆であった宮城県気仙沼市上八瀬地域の中部ペルム系について,生物遺骸群の埋没過程および個生態学的特性を考慮した堆積相解析を基軸として,当時の堆積環境および後背地の時空的変遷を明らかにすることを目的とした.上八瀬地域の中部ペルム系は,下位から細尾層,上八瀬層,黒沢層に区分される.細尾層は,陸棚上部から沖浜へと変遷する堆積環境を示しており,後背地には活発なデルタシステムが想定された.一方,下部外浜から外側陸棚へと堆積環境が変遷する上八瀬層について,生物遺骸の個生態および埋没過程を復元すると,1)砂浜,2)沿岸のリーフ,3)堆積盆に近接する孤立した硬質な浅海底質,を後背地とすることが明らかになった.そのため,生息場の異なる生物,ひいては相反する温度指標種とされる生物遺骸までもが共産し,見かけ上の混合生物相が形成されていた.上位の黒沢層は,堆積環境としては細尾層下部に対応するものの,デルタシステムの影響が低く,化石生物の多様性が著しく低い点で異なる.生層序学的研究によれば,ペルム紀キャピタン期の最初期は,細尾層と上八瀬層の境界付近に対比される.上八瀬層で見出された孤立した硬質性の浅海底質は,キャピタン期初期に南部北上帯の近隣各地で形成された可能性が高く,広域に渡って見かけ上の高多様性を生み出していたと考えられる.
Key Words : biostratinomy, Guadalupian, Paleozoic, taphonomy, tectonics, Tethys
6. Detrital heavy minerals from Lower Jurassic clastic rocks in the Joetsu area, central Japan: Paleo-Mesozoic tectonics in the East Asian continental margin constrained by limited chloritoid occurrences in Japan
Hiroshi Kamikubo and Makoto Takeuchi
上越地域下部ジュラ系岩室層の砕屑性重鉱物:本邦クロリトイドの限定的産出が示すアジア東縁の中古生代テクトニクス
上久保 寛,竹内 誠
上越地域に分布する下部ジュラ系砕屑岩層である岩室層から,本邦で3例目となる砕屑性クロリトイドを発見した.この発見は,本邦においてジュラ紀砕屑岩にのみ限定的に砕屑性クロリトイドが産することを示し,ジュラ系の後背地において,これまでに指摘された活動的火成弧から開析された火成弧への変化に加えて,含クロリトイド変成岩の削剥が進行していたことを示す. ジュラ紀砕屑岩に産する砕屑性クロリトイドの供給源として,日本各地に散点して分布するペルム–三畳紀含クロリトイド変成岩類が候補と考えられ,本邦ではこれら以外に先ジュラ紀含クロリトイド変成岩は知られていない.この変成岩類は,飛騨変成岩類,宇奈月変成岩類,竜峰山変成岩類および日立変成岩類であり,共通して石炭–ペルム紀の原岩堆積年代が報告され,また日立変成岩類を除き共通してペルム–三畳紀の変成年代が推定されている.さらに,日立変成岩類の変成年代も白亜紀以前の時代がある可能性がある.一般的に多くの含クロリトイド変成岩は,その原岩がAlに富む過程に強度風化作用が関わることから,風化の発達する安定大陸から変成作用を生じる造山帯への地質環境の変化を示す.従い,本邦の含クロリトイド変成岩類は,元来一つの変成帯として形成され,東アジアに当時存在した大陸の縁辺に堆積した原岩を起源とすると考えられる.既存の古生物学および岩石学分野の研究に基づけば,このペルム–三畳紀変成帯は,中央アジア造山帯と北中国地塊との衝突境界に関連すると推定される.本邦ペルム–三畳紀砕屑岩の後背地の変化から,この大陸衝突帯に参加していた地質体の上昇・削剥の順序に起因して砕屑物供給の時間的変化が生じた事が示唆される.
Key Words : continental collision, deeply weathered soil, detrital chloritoid, Iwamuro Formation, Jurassic deposits, provenance
7. Reaction microstructures in corundum- and kyanite-bearing mafic mylonites from the Takahama Metamorphic Rocks, western Kyushu, Southwest Japan
Kazuhiro Arima, Takeshi Ikeda and Kazuhiro Miyazaki
西九州,高浜変成岩に産するコランダム,藍晶石を含む苦鉄質マイロナイトの反応組織
有馬和宏,池田 剛,宮崎一博
西九州に産する低圧高温型の長崎変成岩の一つである高浜変成岩には,高変成度のマイロナイトが産する.その中の苦鉄質岩にはマーガライト集合体がコランダム,藍晶石を包有する反応組織がみられる.これは,CaO-Al2O3-SiO2-H2O 系の以下の後退変成反応で説明される.
3 Al2O3 + 2 Al2SiO5 + 2 Ca2Al3Si3O12 (OH) + 3 H2O = 2 Ca2Al8Si4O20(OH)4 (1).
corundum kyanite clinozoisite fluid margarite
質量保存および化学ポテンシャル図の解析より,藍晶石とコランダムの中に存在する化学ポテンシャル勾配が,岩石中でのCaO, SiO2 の移動を駆動したと考えられる.
岩石のマイロナイト化の時期は,露頭や薄片の観察から最高変成作用と反応(1)の間と推定される.最高変成作用と反応(1)の温度圧力を推定することによって,マイロナイト化の温度圧力条件は,530〜640℃,1.2 GPa 以上と見積られた.この圧力は島弧下の下部地殻に相当する.
Key Words : margarite-forming reaction, mylonites, reaction microstructure, Takahama Metamorphic Rocks
8. SHRIMP dating of magmatism in the Hitachi metamorphic terrane, Abukuma Belt, Japan: Evidence for a Cambrian volcanic arciar
Michio Tagiri, Daniel J. Dunkley, Tatsuro Adachi, Yoshikuni Hiroi and C. Mark Fanning
阿武隈帯日立変成地域における火成作用のSHRIMP年代測定:カンブリア紀火山弧の存在
田切美智雄,Daniel J. Dunkley,足立達朗,廣井美邦,C. Mark Fanning
日立変成地域の変成された火山岩類及び深成岩類のSHRIMP年代値から,赤沢層,玉簾層,西堂平層は,約5億年前のカンブリア紀後期の日本最古の地層であることを示した.火成岩類の化学組成から,赤沢層と玉簾層はカンブリア紀後期の火山弧であったと結論した.他方,砂泥互層が卓越する西堂平層は,大陸棚や大陸斜面で堆積したものである.赤沢層と大雄院層の間には約1.5億年の不整合がある.ハイアタスや最近の年代値の結果から,日立カンブリア系の所属について北中国地塊や佳木斯(じゃむす)−カンカ地塊との関係を論じた.
Key Words : Abukuma Belt, Cambrian volcanic arc, Hitachi metamorphic terrane, North China block, SHRIMP zircon age, unconformity
9. Evolution of animal multicellularity stimulated by dissolved organic carbon in early Ediacaran ocean: DOXAM hypothesis
Akihiro Kano, Yoko Kunimitsu, Tetsuhiro Togo, Chiduru Takashima, Fumito Shiraishi and Wei Wang
初期エディアカラ紀の海洋での溶存有機炭素により促された動物の多細胞化:DOXAM仮説
狩野彰宏,國光陽子,東郷徹宏,高島千鶴,白石史人,王 偉
ガスキエス氷期(約580 Ma)後に開始した海洋の酸化が多細胞動物の進化を促した要因だとされているが,それ以前に少なくとも海綿動物は出現していた.動物進化の第一のステージを説明するために,本論は溶存有機炭素の蓄積と動物の多細胞化を関連づけたDOXAM仮説を提唱する.南部中国などに分布する地層の地球化学的研究によると,マリノアン氷期(655-635 Ma)直後の層状化した海洋で,膨大な溶存有機炭素が滞留したとされる.有機炭素は濾過栄養動物の食料になり,海綿・刺胞動物を頂点とした食物連鎖の基礎となった.同様の生態系と海洋構造はIODP第307次航海で掘削された現在の深海サンゴマウンドにもある.この仮説は原始的な動物門(海綿・刺胞動物)が濾過栄養であることと整合的である.濾過栄養生態系の進化は有機炭素溜りを取り除き,海洋を酸化させたかもしれない.その後,新原生代末の生物進化は左右相称動物の出現という第二のステージへと移行した.
Key Words : animal evolution, carbon isotope, dissolved organic carbon, Doushantuo Formation, IODP, Neoproterozoic
10. Bacterial symbiosis forming laminated iron-rich deposits in Okuoku-hachikurou hot spring, Akita Prefecture, Japan
Chizuru Takashima, Tomoyo Okumura, Shin Nishida, Hiroko Koike and Akihiro Kano
秋田県奧奥八九郎温泉の縞状鉄沈殿物を形成する微生物の共生関係
郄島千鶴,奥村知世,西田伸,小池裕子,狩野彰宏
縞状鉄鉱層に類似した鉄質沈殿物は現世の温泉環境でも見られ,鉄沈殿に関わる微生物群集とプロセスを直接的に検討できる.奧奥八九郎温泉の源泉に発達する鉄沈殿物はフェリハイドライトとアラゴナイトで構成されるsub-millimeter オーダーの縞状組織を示す.走査型電子顕微鏡観察や遺伝子解析の結果は,微好気性の鉄酸化細菌がフェリハイドライトを沈殿させたことを示す.源泉は酸素を含まず,鉄酸化細菌の生息には適さないが,沈殿物中に認められるシアノバクテリアの光合成が酸素を供給していた.奧奥八九郎温泉の鉄沈殿物のシアノバクテリアと鉄酸化細菌の共生関係は,縞状組織が光合成活動の強度を反映した可能性があることを示す.本研究は鉄沈殿についての新しい微生物モデルと浅海性縞状鉄鉱層に対する新しいメカニズムを提供するかもしれない.
Key Words : banded iron formation, cyanobacteria, ferrihydrite, iron-oxidizing bacteria, photosynthesis
Island Arc 日本語要旨 2011. vol. 20 Issue 3 (September)
Vol. 20 Issue 3 (September)
通常論文
[Pictorial Articles]
1. Basal slip plane of the Kurotaki unconformity in the Boranohana area along the Pacific coast of the Boso peninsula, Central Japan
Makoto Otsubo, Naofumi Yamaguchi, Shin’ichi Nomura, Nozomi Kimura and Hajime Naruse
千葉県勝浦海岸ぼらの鼻で認めれた黒滝不整合の剪断面
大坪 誠,山口直文,野村真一,木村希生,成瀬 元
[Review Articles]
2. Timing of collision of the Kohistan–Ladakh Arc with India and Asia: Debate
Hafiz Ur Rehman, Tetsuzo Seno, Hiroshi Yamamoto and Tahseenullah Khan
コヒスタン−ラダック弧のインドおよびアジアとの衝突時期についての論争
Hafiz Ur Rehman,瀬野徹三,山本啓司,Tahseenullah Khan
コヒスタン−ラダック弧は,島弧地殻断面の露出域として知られている.この島弧の形成,アジア−インド両大陸との衝突の時期,衝突時の位置に関して盛んに議論がなされてきた.概ね受け入れられている説は,102~75 Maに赤道付近もしくは北半球低緯度地域で島弧がアジアと衝突し,55~50 Maにインドが衝突したとするものである.近年,島弧とインドの衝突が61 Ma以前で,島弧を含むインドとアジアの衝突を50 Ma頃とする説が提唱されている.後者の衝突順による最も詳細なモデルでは,コヒスタン−ラダック弧は赤道付近でインドと衝突・合体し,北緯30°以北でアジアに衝突したとされる.この場合,インドプレートの北進速度が60 Ma頃以降は異常に大きい値 (30 ± 5 cm/yr)であったことになる.本論では,種々の既存データ,特にオフィオライト,青色片岩,52Ma以前の海成層の分布に着目して検討し,島弧とアジアの衝突が先で,島弧を含むアジアとインドの衝突が後とするのが妥当と結論する.
Key Words : Asian Plate, Indian Plate, Kohistan–Ladakh Arc, Northern Suture, Southern Suture, timing of collision.
[Research Articles]
3. Petrogenetic modeling of rock variety in the Khalkhab–Neshveh pluton, NW of Saveh, Iran
Mehdi Rezaei-Kahkhaei, Dariush Esmaeily and Fernando Corfu
イラン,サヴェー北西部のKhalkhab-Neshweh深成岩体を構成する岩石類の成因モデル
Mehdi Rezaei-Kahkhaei, Dariush Esmaeily and Fernando Corfu
Khalkhab–Neshveh深成岩類は,Urumieh–Dokhtar Magmatic Arcの一部をなし,一帯を覆う後期漸新世から前期中新世の玄武岩類や安山岩類を貫いている.石英モンゾ斑糲岩,石英モンゾ閃緑岩,花崗閃緑岩,花崗岩の組成をもち,medium-Kからhigh-K,メタアルミナス,Iタイプの特徴をもつ深成岩である.単斜輝石,斜長石,角閃石,燐灰石,チタナイトの晶出に強く支配された弱い分別トレンドを示し,K2Oを除く主要な元素は,SiO2に対して負の相関を示し,Al2O3, Na2O, Sr, Eu, Yは曲線的なトレンドをもつ.玄武岩質マグマとデイサイト質マグマの混合,重力分別晶出作用,in situ結晶作用を含むマグマの分化作用の3つのプロセスのうち,in situ結晶作用が,Khalkhab–Neshvehマグマの発達に寄与した可能性が最も高い.この結論は,すべての岩石種が同じレベルに産すること,花崗岩質岩中に塩基性の捕獲岩を欠くこと,Na2O, Sr, Euの曲線的な分化トレンド,モンゾ閃緑岩と花崗岩それぞれの87Sr/86Sr比が一定であること(前者は0.70475,後者は0.70471)からも支持される.In situ結晶作用は,1050℃以上の温度条件下において貫入岩体の周辺部で発生した斜長石と単斜輝石斑晶の沈積と石英モンゾ斑糲岩と石英モンゾ閃緑岩におけるこれら斑晶の濃集,および約880℃におけるホルンブレンド,斜長石,そして後期の黒雲母の絞り出し作用と分化作用を経て生じた.
Key Words : in situ crystallization, Iran, magma mixing, petrogenetic modeling, Urumieh–Dokhtar Magmatic Arc.
4. Calcareous nannofossil biostratigraphic study of forearc basin sediments: Lower to Upper Cretaceous Budden Canyon Formation (Great Valley Group), northern California, USA
Allan Gil S. Fernando, Hiroshi Nishi, Kazushige Tanabe, Kazuyoshi Moriya, Yasuhiro Iba, Kazuto Kodama, Michael A. Murphy and Hisatake Okada
米国北カリフォルニアに分布する前弧海盆堆積物,下部〜上部白亜系ブッデン・キャニオン層(グレート・バーレイ層群)のナノ化石層序の研究
Allan Gil S. Fernando, 西 弘嗣,棚部一成,守屋和佳,伊庭靖弘,小玉一人,Michael A. Murphy and岡田尚武
北カリフォルニアに分布するブッデン・キャニオン(Budden Canyon)層のノースフォーク・コットンウッド・クリーク(North Fork Cottonwood Creek)・セクションにおいて,BC/UC化石帯を用いてナノ化石層序を設定した.この化石層序と古地磁気層序を統合すると,本層はオーテビリアンからチューロニアン中期の地質時代を示し,各ステージ境界も本層の中に設定することができた.これらの結果から,ヒューリング砂岩部層(Huling Sandstone Member)の基底とチカバリ部層(Chickabally Member)の上部に,不整合の存在が推定される.ナノ化石群集は,バレミアンとアプチアン初期までは冷水塊の影響下にあるが,アルビアンからチューロニアンでは暖流化の群集へと変化することから,中期白亜紀の温暖化の影響を受けていることがわかる.従来の研究では,海洋無酸素事変の存在はブッデン・キャニオン層から報告されていなかったが,有機物量の変化からOAE2の存在が示唆される.
Key Words : biostratigraphy, Budden Canyon Formation (BCF), calcareous nannofossils, California, Cretaceous, Great Valley Group (GVG), oceanic anoxic event 2 (OAE2).
5. Thermal histories of Cretaceous basins in Korea: Implications for response of the East Asian continental margin to subduction of the Paleo-Pacific Plate
Taejin Choi and Yong Il Lee
朝鮮半島の白亜系堆積盆の熱史:古太平洋(イザナギ)プレートの沈み込みに対する東アジア大陸縁辺部の応答に関する考察
Taejin Choi and Yong Il Lee
古太平洋(イザナギ)プレートの沈み込みに対する東アジア大陸縁辺部の応答を理解するために朝鮮半島の白亜系堆積盆の熱史を検討した.イザナギプレートは東アジア大陸に対し,白亜紀前期には斜め方向に,白亜紀後期には直交方向に沈み込んでいた.Pull-apart basinである鎭安堆積盆(Jinan Basin)におけるイライト結晶度とアパタイトのフィッショントラック年代検討結果は,同堆積盆の堆積物の埋没温度が287°Cに達したことを示す.その後,同堆積盆では95〜80 Maおよび約30Ma以降という2回の冷却期があった.同様の冷却パターンは,韓国における白亜紀最大の堆積盆である慶尙堆積盆(Gyeongsang Basin)でも認められる.鎭安堆積盆ならびに慶尙堆積盆は,95〜80Maに主に上昇により冷却したが,イザナギプレートの沈み込み方向の変化によるtranspressional force (斜め圧縮力)のため,鎭安堆積盆の方が慶尙堆積盆よりもやや早く上昇した.朝鮮半島の白亜系堆積盆,中国東北部の花崗岩類,西南日本の付加コンプレックスの熱史の比較検討より,朝鮮半島を含む東アジア大陸縁辺部で95〜80 Maに生じた上部白亜系の地域的な上昇は,当時,北東方向に移動しつつあったIzanagi–Pacific ridgeの沈み込みによって促進され,約80Maには上昇が終了した.
Key Words : active continental margin, Cretaceous, fission-track dating, Korean peninsula.
6. Alkaline lamprophyric province of Central Iran
Fereshteh Bayat and Ghodrat Torabi
中央イランのアルカリ・ランプロファイア分布域
Fereshteh Bayat and Ghodrat Torabi
中部−東部イランマイクロコンティネントの西部には,古生代のランプロファイア類が良く露出している.ここではランプロファイア類は,火山や岩脈,岩頸(plug)をなして産する.構成鉱物は,角閃石,単斜輝石,斜長石,カリ長石,かんらん石,クロムスピネル,チタナイト,黒雲母,イルメナイトである.噴出岩の産状をもつランプロファイアは,主に斑状組織,トラキティック組織,マイクロリシック組織,バリオリティック組織をもち,岩脈や岩頸では間粒状組織が一般的である.これらのランプロファイアには,広域的に変成作用を受けているところがある.岩石学的・地球化学的な性質から,これらがアルカリ・ランプロファイアとカンプトナイトに分類されることがわかる.アルカリ(Na2O + K2O)やLIL元素,軽希土類元素に富み,微量元素濃度は,プレート内玄武岩に類似する.本研究により,ランプロファイア類は,交代作用によって生じた角閃石を含むスピネルレルゾライトの様々な程度の部分溶融に由来することが示唆される.古生代前期から後期にかけての古テチス海洋地殻の沈み込みがマントル内に流体を富ませた結果,ランプロファイアの火成作用が大小の断層に沿って生じたと考えられる.この中部イランにおける広範囲な地域の限定的かつ典型的なランプロファイアの火成作用は,古生代が長く続いたにも関わらず,中部イランの火成作用でみる限り,比較的静かな時代であったといえる.
Key Words : Alkaline lamprophyre, Central Iran, metasomatized mantle, Paleo-Tethys, Paleozoic.
7. Phengite geochronology of crystalline schists in the Sakuma–Tenryu district, central Japan
Nguyen Dieu Nuong, N. G. O. Xuan Thanh, Chitaro Gouzu and Tetsumaru Itaya
中部日本佐久間—天竜地域における結晶片岩のフェンジャイトK-Ar年代学
Nguyen Dieu Nuong, N. G. O. Xuan Thanh,郷津知太郎・板谷徹丸
佐久間天竜地域には主に泥質片岩と塩基性片岩を産する.その変成帯は白倉ユニットと瀬尻ユニットに分帯される.両ユニットから泥質片岩を採集し,そのフェンジャイトのK-Ar年代測定と炭質物のXRD分析を実施した.年代と炭質物の結晶面間隔d002の関係を調べた結果,変成温度の上昇とともに前者では年代が古く(66-73Ma)なり四国中央部三波川高圧変成帯と同じ傾向であった.後者では若く(57-48Ma)なり関東山地の四万十高圧変成帯と同じ傾向であった.この対照的な年代と変成温度の関係は変成帯の上昇過程におけるテクトニクスの違いに因る.つまり,前者ではピーク変成作用とその後の上昇冷却過程におけるフェンジャイトK-Ar系の閉鎖が3100万年以上かかり,後者では1300年以下であったことに因る.沈み込むプレート境界の性質の違いが変成帯の上昇過程の違いをもたらしたと解釈する.
Key Words : age–temperature–structure relation, d002 of carbonaceous material, exhumation processes, K–Ar phengite ages, Sanbagawa schists, Shimanto schists.
8. Submerged reefal deposits near a present-day northern limit of coral reef formation in the northern Ryukyu Island Arc, northwestern Pacific Ocean
Hiroki Matsuda, Kohsaku Arai, Hideaki Machiyama, Yasufumi Iryu and Yoshihiro Tsuji
北西太平洋琉球列島北部,現世サンゴ礁北限域の沈水サンゴ礁性堆積物
松田博貴, 荒井晃作, 町山栄章, 井龍康文, 辻 喜弘
現在のサンゴ礁北限近傍に位置する奄美大島北方ならびに喜界島南西方海域において,氷期にもサンゴ礁が存在したか否かを明らかにするために,高解像度音波探査を実施した.その結果,奄美海脚の中央部ならびに東側の陸棚縁から陸棚斜面上部にかけて,海底面直下のよく成層した堆積物中に,比高15m,幅400m程度のマウンド状高まりが,複数存在することが明らかとなった.これらは,強反射面と不明瞭な内部構造に特徴づけられ,サンゴ礁あるいは粗粒炭酸塩堆積物であると考えられる.また喜界島南方沖の陸棚縁付近の海底面には,不規則な地形的高まりが確認された.以上の結果から,これらのマウンド状高まりは,最終氷期に形成されたサンゴ礁の可能性が指摘される.
Key Words : coral reefs, high-resolution seismic survey, Kuroshio, Last Glacial Maximum, Ryukyu Islands.
9. Fluid inclusion microthermometry for P–T constraints on normal displacement along the Median Tectonic Line in Northern Besshi area, Southwest Japan
Tetsuzo Fukunari, Simon R. Wallis and Toshiaki Tsunogae
西南日本別子地域北部における流体包有物解析から得られた中央構造線正断層運動の温度・圧力条件推定
福成徹三,Simon R. Wallis,角替敏昭
中央構造線は三波川変成帯と領家変成帯を分かつ一次的なテクトニック境界である.この断層帯の大規模な北落ち正断層運動は三波川高圧変成帯の上昇に寄与した可能性がある.中央構造線の運動に関連して三波川帯中に発達した二次断層に付随する石英脈の流体包有物解析は,正断層運動が250度以上の温度条件で始まったことを示す.脈を構成する石英とカリ長石の微細構造も約300度で変形を受けたことを示唆し,流体包有物解析の結果をサポートし,変形の深度が10km程度であったことを示唆する.流体包有物の等容積線と三波川帯後退変成時の温度圧力経路は整合しない.周辺岩石の半塑性変形及び脈周辺の熱水変成の欠如から,岩石と流体の温度条件は同様であったと推定される.これらの観察は中央構造線近傍にて脈内の流体が静岩圧より低かったことを示唆する.
Key Words : exhumation of the Sanbagawa Belt, fluid inclusion, fluid pressure, Median Tectonic Line, microthermometry.
10. CHIME monazite dating as a tool to detect polymetamorphism in high-temperature metamorphic terrane: Example from the Aoyama area, Ryoke metamorphic Belt, Southwest Japan
Tetsuo Kawakami and Kazuhiro Suzuki
高温変成帯における複変成作用を検知するツールとしてのCHIMEモナズ石年代−領家変成帯青山高原地域の例
河上哲生,鈴木和博
領家変成帯青山高原地域において,砂泥質ミグマタイトと阿保花崗岩(新期領家花崗岩)のCHIMEモナズ石年代測定を行った.その結果,ミグマタイト中のモナズ石は,主としてコアで96.5±1.9 Maの年代を,リムやパッチ状の若返り部で83.5±2.4 Maの年代を与えた.83.5±2.4 Maの年代は,砂泥質ミグマタイトが卓越するザクロ石−菫青石帯のモナズ石で広く観察された.また,阿保花崗岩は79.8±3.9 Maを与えた.砂泥質ミグマタイトに見られる83.5±2.4 Maの年代と,阿保花崗岩の年代の良い一致は,阿保花崗岩を含む新期領家花崗岩による熱的影響および流体活動の影響が,広くザクロ石−菫青石帯全体に及んでいたことを示している.ザクロ石−菫青石帯に対する接触変成作用がこれまで変成鉱物組合せから見いだされていなかった理由は,ミグマタイトが接触変成作用を受ける前に,既に高温のザクロ石−菫青石組合せを有していたためであろう.その一方で,モナズ石には接触変成作用が明瞭に記録されている.従って,グラニュライト相の変成岩に対する角閃岩相高温部の接触変成作用など,主要な変成鉱物の成長によって認識することが困難な複変成作用を認識するためのツールとして,野外でのCHIMEモナズ石年代の広域マッピングは威力を発揮するだろう.
Key Words : electron microprobe dating, fluid, migmatite, monazite, polymetamorphism, rejuvenation.
オープンファイル詳細
オープンファイル
File No119:vol.127, no. 12
論説:泥ダイアピル周辺の砕屑岩脈の方位解析による広域応力と局所応力の検出:中新統田辺層群の例
安邊啓明・佐藤活志
(vol.127, no.12, p.709-725)
Appendix Table 1. Clastic dike data: lithofacies, sub-area, azimuth (clockwise angle from N after correction for declination), and dip.
Appendix Table 2. Paleostress analysis data: material, sub-area, detected stress name, azimuth and plunge, and mixing coefficient. Plots are shown in Figures 7–10.
File No118:vol.127, no. 12
論説:四国四万十帯カルサイト脈の同位体組成からみた沈み込み帯地震発生深度の流体の起源
内田菜月・村山雅史・松原友輝・坂口有人
(vol.127, no.12, p.701-708
Fig. A1. Locations of vein samples with annotations corresponding to sample numbers in Table 1. Base maps are partly modified from the Digital Topographic Map (Geospatial Information Authority of Japan).
File No117:vol.127, no. 11
論説:北上山地中西部の中古生代付加体を貫く白亜紀岩脈群の岩相・年代と貫入応 力解析から得られた引張場
内野隆之・羽地俊樹
(vol.127, no.11, p.651-666)
Table A1-A3.
Table A1. Detailed information for dike outcrops. Abbreviations: ND (Nedamo Belt); NK (North Kitakami Belt); R. (River); and S. (Stream).
Table A2. Instrumentation for LA–ICP–MS analyses.
Table A3. U–Pb isotopic data for zircons recovered from the rhyolite. Abbreviations: 2nd st. (secondary standard zircon); and Disc. (discordant data).
File No116:vol.127, no. 10
論説:北部九州,尺岳北部に産する火成岩類の熱水変質作用と分化・集積作用を伴 う混合作用における組成変化
江島圭祐
(vol.127, no.10, p.605-619)
Table A1-A6.
File No115:vol.127, no. 10
論説:四国西部中新統久万層群の酸性凝灰岩のジルコンU–Pb 年代
新正裕尚・折橋裕二
(vol.127, no.10, p.595-603)
Table S1. Summary of LA–ICP–MS operating conditions.
File No114:vol.127, no. 9
論説:貝形虫化石群集に基づく新潟県新津丘陵北部域の更新世の古環境変化
山田 桂・楠 慧子・飯田里菜・久須美晨夫
(vol.127, no.9, p.575-591)
Table S1. Occurrence list of fossil ostracods from the Niitsu Hills, Niigata Prefecture, central Japan.
File No113:vol.127, no. 9
論説:四国北西部,中新統久万層群明神層に含まれる火成岩礫の起源
相田和之・下岡和也・谷 健一郎・楠橋 直・齊藤 哲
(vol.127, no.9, p.563-574)
Table S1-S5, Fig.S1-S3
File No112:vol.127, no. 9
論説:湯ノ沢カルデラ,尾開山凝灰岩の高精度・高確度噴出年代の決定
田口春那・折橋裕二・佐々木実・宮嶋佑典・岩野英樹・平田岳史
(vol.127, no.9, p.545-561)
Table A1.Results of K–Ar age dating of the Obirakiyama Tuff, Yunosawa Caldera. Data sources: 1) Muraoka and Hase (1990); 2) Muraoka (1991); 3) Metal Mining Agency of Japan (1980); and 4) Nemoto (1998).
Fig. A1. Particle size distributions of zircon crystals recovered from five samples of the Obirakiyama Tuff, Yunosawa Caldera.
File No111:vol.127, no. 8
報告:九州南部の大隅花崗閃緑岩体に発達する節理系
有留千博・山本啓司
(vol.127, no.8, p.489-495)
Table A1. Strike and dip of joints in the Osumi granodiorite batholith. See Fig. 3 for location.
File No110:vol.127, no. 8
論説:山陰帯島根県雲南地域に分布する大東花崗閃緑岩の火成活動
野口将志・亀井淳志・鈴木博美・小林夏子
(vol.127, no.8, p.461-478)
Appendix 1-5.
Appendix 1. Lithofacies distribution within the study area. Base topographic map provided by the Geospatial Information Authority (GSI) of Japan [URL2].
Appendix 2. Whole-rock and modal compositions and values of magnetic susceptibility for the Daito granodiorite, Hiyodori granite, and Mue granite.
Appendix 3. EPMA data for plagioclase, hornblende, and biotite in the Daito granodiorite.
Appendix 4. EPMA data for magnetite in the Daito granodiorite.
Appendix 5. Partition coefficients and starting compositions utilized in the Rayleigh fractionation modeling.
File No109:vol.127, no. 8
論説:北部九州東部に分布する田川変成岩類の変成作用
柚原雅樹・清浦海里・日郄万莉亜・外田智千・早坂康隆
(vol.127, no.8, p.447-459)
Appendix 1. LA-ICP-MS U-Pb age data for zircon samples from the Tagawa metamorphic rocks (sample 14060710).
File No108:vol.127, no. 7
レター:青森県南部,碇ヶ関カルデラ主要構成噴出物(虹貝凝灰岩)のジルコンLAICP- MS U–Pb 年代
相川裕貴・折橋裕二・佐々木 実・中尾魁史・高久雄一
(vol.127, no.7, p.431-436)
Appendix 1. Bulk chemical composition of the Nijikai Tuff (sample no. 09081301).
File No107:vol.127, no. 7
論説:近畿地方の瀬戸内区に分布する下–中部中新統の生層序と対比
入月俊明・柳沢幸夫・木村萌人・加藤啓介・星 博幸・林 広樹・藤原祐希・赤井一行
(vol.127, no.7, p.415-429)
Figs A1-A4
Tables A1-A5
Table A1. List of fossil ostracods from the Ayugawa and Tsuzuki groups.
Table A2. List of fossil diatoms from the Ayugawa and Tsuzuki groups.
Table A3. List of fossil diatoms from the Yamabe and Yamagasu groups.
Table A4. List of fossil planktonic foraminifers from the Yamagasu Group.
Table A5. Data sources for the stratigraphic correlation (Fig. 6) among the selected groups of the Miocene in the Setouchi Geologic Province. Abbreviations: D (diatom), PF (planktonic foraminifera), CN (calcareous nannofossil), R (radiolarian), O (ostracod), Sr (strontium isotope dating), FT (fission track dating), U–Pb (U–Pb dating), and M (magnetostratigraphy).
Fig. A1. Photographs of diatom species from the Kaya Tuffaceous Mudstone Member of the Okuyamada Formation, Tsuzuki Group.
Fig. A2. Photographs of diatom species from the Yamabe and Yamagasu groups (part 1).
Fig. A3. Photographs of diatom species from the Yamabe and Yamagasu groups (part 2).
Fig. A4. Photographs of diatom species from the Yamabe and Yamagasu groups (part 3).
File No106:vol.127, no. 6
論説:新島(燃島)の後期更新世末期–完新世の石灰質微化石群集と鹿児島湾奥の古 環境復元
前浜悠太・鹿野和彦・大木公彦・入月俊明・林 広樹
(vol.127, no.6, p.363-376)
Tables A1-A3
Table A1. List of fossil benthic foraminifera species in each sample.
Table A2. List of fossil planktonic foraminifera species in each sample.
Table A3. List of fossil ostracod species in each sample.
File No105:vol.127, no. 6
巡検案内書:岐阜県西部・揖斐川町春日地域の火成岩と接触変成岩
榎並正樹・纐纈佑衣・加藤丈典・壷井基裕・丹羽健文
(vol.127, no.6, p.313-331)
Tables S1-S2
Table S1. Representative analyses of major constituent minerals in a basic nodule collected from Stop 1d.
Table S2 . Whole-rock compositions of lamprophyre collected from Stop 3.
File No104:vol.127, no. 5
レター:Discovery of Early Permian tonalite from the high P/T Triassic Suo Metamorphic Complex, Eastern Yamaguchi Prefecture, SW Japan
Kenta Kawaguchi et al
(vol.127, no.5, p.293-304)
Tables S1-S4
Table S-1. LA-ICP-MS zircon U–Pb data of consistency standard sample YO1.
Table S-2. LA-ICP-MS zircon U–Pb data of three tonalite mylonite samples.
Table S-3. LA-ICP-MS detrital zircon U–Pb data of psammitic schist sample.
Table S-4. XRF whole-rock chemical compositions of the four tonalite mylonite samples.
File No103:vol.127, no. 4
レター:熊本県天草市,前島花崗閃緑岩のジルコンU–Pb 年代
長田充弘・大藤 茂
(vol.127, no.4, p.237-243)
Fig. A1.Tables A1-A2
Fig. A1. a) Microphotograph of sample MGD-02 (crosspolarized light). Afs: Alkali feldspar, Bt: biotite, Pl: plagioclase, Qtz: quartz. b) Cathodoluminescence images of the concordant zircons separated from sample MGD-02. The diameter of each spot (with the spot number) is 25 μm. The yellow scale bar is 50 μm.
Table A1. The LA-ICPMS analytical conditions for U–Pb dating in this study.
Table A2. The U–Pb zircon data in this study. C (D): concordant (discordant) data.
File No102:vol.127, no. 2
論説:緑色普通角閃石の主成分および微量成分元素組 成による美浜テフラと四国沖MD012422 コアから検出されたクリプトテフラとの対比と 給源の推定.
古澤 明・佐々木俊法・後藤憲央
(vol.127, no.2, p.91-103)
Appendix 1. Glass composition data for StHz and ATHOG of MPI-DING. Abbreviations: average (Av.), standard deviation (SD), uncertainty at 95% confidence level (U), and number of analyses (n). Preferred value data are from Jochum et al. (2006).
File No101:vol.127, no. 2
論説:秋田県出羽山地の笹森丘陵に分布する新第三系の地質と珪藻 化石層序
加藤悠爾・柳沢幸夫
(vol.127, no.2, p.105-120)
Figs. A1–A4. Maps showing the location of samples.
Figs. A5, A6. Route maps of the stratigraphic sections Ra and Ma.
Figs. A7–A10. Age vs thickness plots of selected stratigraphic sections.
Figs. A11–A15. Light photomicrographs of diatoms.
Table A1-A18.
Table A1. List of diatoms used for diatom bathymetric index Bd2.
Tables A2–A18. Occurrence charts of diatoms from stratigraphic sections A–Z.
File No100:vol.127, no. 1
レター:赤石山地中央部の小渋川地域に分布する陸源砕屑岩から得られた前期白亜紀 最末期の砕屑性ジルコン
志村侑亮・中村佳博・常盤哲也・杉本大志・水戸創也
(vol.127, no.1, p.51-58)
Appendixs 1-2
Appendix 1. Cathodoluminescence images of concordant zircon grains from samples 17112505 (a–d), OS2-30 (e–i), and 17112502 (j–m). Scale bars are 20 μm. Circles show the locations of analytical spots. Ages of detrital zircons ≤ 1200 Ma and >1200 Ma are 238U–206Pb and 207Pb/206Pb ages, respectively, in Ma. Age uncertainties are given at the 1 σ level.
Appendix 2. Analytical operating conditions for LA-ICPMS U–Pb isotopic dating. Appendix 3. LA-ICP-MS U–Pb isotopic data. Discordant data are shaded gray.
File No99:vol.127, no. 1
論説:フィッション・トラック熱年代解析およびU–Pb 年代測定に基づいた南九 州せん断帯に分布する破砕帯の活動時期
末岡 茂・島田耕史・照沢秀司・岩野英樹・檀原 徹・小北康弘・平田岳史
(vol.127, no.1, p.25-39)
Figs. A1-A2, Table A1
File No98:vol.127, no. 1
論説:八幡浜大島に分布する大島変成岩体のジルコンU–Pb 年代と地体構造上の意義
小山内康人・北野一平・中野伸彦・足立達朗・米村和紘・吉本 紋・宮下由香里・米虫 聡・小松正幸
(vol.127, no.1, p.1-24)
Table A1-A15, Table B
File No97:vol.126, no. 11
報告:愛知県設楽地域東部の貫入岩体の全岩化学組成,輝度および変質度
図子田和典・岡村太路・二村康平・束田和弘・竹内 誠
(vol.126, no.11, p.645-654)
Appendixs 1-2
Appendix 1. Photographs of polished surfaces of the samples versus distance from the samples Ft1, Sh1, and Tb1. Ft: Futto; Sh: Shimohara; Tb: Tochibata.
Appendix 2. Whole-rock chemical composition of the trace lements in Futto and Tochibata samples.
File No96:vol.126, no. 11
レター:紀伊半島西部,和泉層群最上部からの古第三系の発見
磯粼行雄・長谷川 遼・益田晴恵・堤 之恭 (vol.126, no.11, p.639-644)
Appendix 1. Methods for zircon separation and U–Pb dating.ジルコン分離およびU–Pb 年代測定手法の説明.
Appendix 2. Example Cathodo-luminescence images of detrital zircons with oscillatory zoning (from Sample KRH) . オシラトリー累帯構造を持つ砕屑性ジルコンのCL像の例(試料KRH).
Appendix 3. U–Pb age. U–Pb 年代.(Table A1. Sample KRH.試料KRH./Table A2. Sample MJK.試料MJK./Table A3. Sample SGD.試料SGD./Table A4. Sample NTK.試料NTK./Table A5. Sample TKO2.試料TKO2./Table A6. Sample SB1.試料SB1./Table A7. Sample SB2.試料SB2./Table A8. Sample CCO.試料CCO./Table A9. Sample SBR.試料SBR.)Table A10. Summary of the youngest age clusters for dated zircons in the nine sandstone samples (n = number of grains). 砂岩9試料中のジルコンが持つ最若年代集団のまとめ (n は粒子数).
Appendix 4. Tera-Wasserburg diagrams of U–Pb ages for zircons from all nine sandstone samples. 砂岩9試料中のジルコンU–Pb 年代のコンコーディア図.
Appendix 5. Measurements of secondary standard sample (OD-3). 二次標準試料(OD-3)の測定値.
File No95:vol.126, no. 11
レター:天草下島北部の中新世貫入岩体の方向と応力解析
牛丸健太郎・山路 敦
(vol.126, no.11, p.631-638)
Appendix 1. Locations and orientation data (dip direction and dip) for sheet intrusions and bedding.
File No94:vol.126, no. 10
レター:北海道神居古潭変成岩類班渓幌内ユニットからの新たなジルコンU–Pb年代
長田充弘・大藤 茂
(vol.126, no.10, p.597-601)
Fig. A1, Tables A1-A2
Fig. A1. a) Photomicrograph (cross-polarized light; scale bar is 300 μm) of sample PKP2 (pelitic schist). Abbreviations Chl: chlorite, Ms: muscovite, Q-A: quartz and albite. b) Cathodoluminescence (CL) images of zircon grains from sample PKP2 with 206Pb/238U ages. Yellow open circles show measurement spots (25 μm). Scale bar is 50 μm. c) Concordia diagram of sample PKP2. Red solid and blue open circles denote concordant and discordant grains, respectively. Abbreviations N: number of concordant and discordant zircon grain. d) Probability density plot of all data (bin width is 50 million year). Abbreviations n: number of concordant zircon grain, YSG: youngest single grain 206Pb/238U age.
Table A1. LA-ICPMS analytical conditions for U–Pb dating based on Kouchi et al. (2015).
Table A2. The U–Pb zircon data for secondary standard zircons (91500 and OD-3) and sample PKP2. 206Pbc: common 206Pb (%). R: Rejected data, C (D):Concordant (discordant) data..
File No93:vol.126, no. 10
論説:東京都産古生代前期造山帯の断片:関東山地東部, 黒瀬川帯高圧型変斑れい岩および花崗岩類のジルコンU–Pb 年代
沢田 輝・磯粼行雄・坂田周平
(vol.126, no.10, p.551-561)
Open Online Table 1. Analytical results of zircon U–Pb dating by LA-ICP-MS. Values for f206 indicate the fractional amount of common Pb and those of Conc. indicate concordance between 207Pb/235U and 206Pb/238U ages (%). LA–ICPMS によるジルコンU–Pb 年代測定の結果.f206は測定された206Pb のうちのコモン鉛の割合を示し,Conc. は 207Pb/235U 年代と206Pb/238U 年代の一致率を示す.
File No92:vol.126, no. 9
論説:草津白根火山,本白根火砕丘群の地質と形成史
石崎泰男・濁川 暁・亀谷伸子・吉本充宏・寺田暁彦
(vol.126, no.9, p.473-491)
Appendix 1-2(PDF)
Appendix 1. Sampling locations for whole-rock chemical analyses. Numbers in parentheses correspond to outcrop numbers in Figures 2 and 3.
Appendix 2. Whole-rock chemical and modal compositions of the eruption products of the Motoshirane Pyroclastic Cone Group. Sampling locations are shown in Appendix 1. Modal compositions were determined by pointcounting to a total of ~2000 point for each sample. Phenocrysts were defined as those measuring >0.2 mm along their longest axis. Total Fe is expressed as Fe2O3. Loss on ignition (LOI) was measured by igniting the powdered samples at 900°C for 2 h. Abbreviations: Dw = densely welded lava-like section; JB = jointed block; SC = scoria; BB = breadcrust bomb; tr = present in samples but not observed in point counts; nd = not detected.
File No91:vol.126, no. 9
論説:鹿児島湾奥,新島に露出す る最上部更新統〜完新統の層序と起源
鹿野和彦・柳沢幸夫・内村公大・奥野 充・中村俊夫
(vol.126, no.9, p.519-535)
Figs. S1-S4, Tables S1-S4
Table S1. Occurrence chart of diatoms in the uppermost Pleistocene to Holocene sediments exposed on Shinjima Island.
Table S2. List of molluscan fossils collected from the Moeshima Shell Bed, Location 1, and from the Lower Shinjima Silt Bed, Location 3.
Table S3. Refractive indices of constituent minerals in the Southern Shinjima Pumice, Shinjima Pumice, and Sakurajima– Satsuma tephra Sz-14.
Table S4. Bulk chemical compositions of pumice samples collected from the Moeshima Shell Bed and from the Sz- 12 (S-BP) and Sz-13 (S-AP) tephras at Location 1.
Fig. S1. Comparison of previous stratigraphy with the proposed divisions.
Fig. S2. Photomicrographs of diatom slides. Scale bar = 50 μm. A = Assemblage F (Sample 12050402, Shinjima Pumice, Location 2); B = Assemblage F (Sample SJ12-01, Shinjima Pumice, Location 4); C = Assemblage F (Sample 15012009, Southern Shnjima Pumice, Location 1); D = Assemblage FM (Sample 12071607, Sz-13 tephra, Location 1); E = Assemblage M (Sample 12070401-1, Upper Shinjima Silt Bed, Location 1); F = Assemblage M (Sampleple 12050411, Lower Shinjima Silt Bed, Location 4). Assemblage F = Freshwater diatom assemblage with very rare marine diatoms, Assemblage FM = Mixed assemblage of freshwater and marine diatoms. Assemblage M = Marine diatom assemblage with rare brackish to freshwater diatoms.
Fig. S3. (A) Photograph taken on August 20, 2013 showing the succession from the Shinjima Pumice to the Moeshima Shell Bed exposed at Location 4. The gravelly tuffaceous deposit is ~2.8 m thick. This outcrop is almost completely covered by vegetation. (B) Photograph taken in 1975, showing a normal fault displacing the exposed succession at the same location. Photograph courtesy of Kimihiko Oki.
Fig. S4. Photohraph taken on January 21, 1994, showing the succession from the Southern Shinjima Pumice to the Moeshima Shell Bed, exposed at Location 1. The gravelly tuffaceous deposit is ~1.8 m thick. This large outcrop is covered by an embankment, talus, and thick vegetation.
Fig. S5. Harker diagrams for the pumices from the Moeshima Shell Bed and the Sz-12 (S-BP) and Sz-13 (SAP) tephras. Numbers 1–8 correspond to the last digit of the sample numbers shown in Table S4. The major element compositions of Sz-5, 7, 8, 9, 10, and 11 and those of Sz-14 are adopted from Takahashi et al. (2011) and Yamamoto et al. (2013).
File No90:vol.126, no. 5
論説:九州北部福岡県筑豊炭田の始新統直方層群下部のジルコンU–Pb 年代
宮田和周・長田充弘・仁木創太・服部健太郎・大林秀行・平田岳史・大藤 茂
(vol.126, no.5, p.251-266)
Appendix 1. Photomicrographs of the tuff and tuffaceous rocks (a–d) of the Sanjakugoshaku Formation in plane-polarized (left) and cross-polarized light (right). (a), SARUTA, a tuffaceous mudstone including numerous glass shards; (b), HONDA, a laminated tuffaceous mudstone; (c), MIYAWAKA, a vitric tuff; (d), EBITSU, a vitric tuff including rhyolitic volcanic fragments. Abbreviations: Pl = plagioclase; Qtz = quartz; V = volcanic fragment.
Appendix 2. Cathodoluminescence images of the selected zircon grains from the tuff and tuffaceous rocks of the Sanjakugoshaku Formation and 238U–206Pb ages. The circles indicate the spots analyzed via LA-ICPMS.
Appendix 3. Analytical settings and standard materials for U–Pb zircon dating.
Appendix 4. U–Pb zircon data of the tuff and tuffaceous samples from the Sanjakugoshaku Formation, Nogata Group, and standard zircon in this study. Abbreviations: C = concordant grain; D = discordant grain.
File No89:vol.126, no. 5
報告:新潟県に分布する7 枚の第四紀テフラのLA-ICP-MS によるジルコンU–Pb 年代
伊藤久敏・村松敏雄
(vol.126, no.5, p.285-290)
Fig. A1. Locations and outcrop photographs for sampled tephras. a) HK10, b) Odaira, c) Og, d) Yokokura, e) Kimigaeri,
f) Oguriyama, g) Shimizu Pass. Topographic maps are from the Geospatial Information Authority of Japan.
Table A1. LA-ICP-MS zircon U–Pb analytical results for the Niigata tephras. Data in italics (>75% common Pb contamination or >2 Ma) were excluded for further U–Pb analyses.
File No88:vol.126, no. 4
論説:埼玉県加治丘陵に分布する下部更新統仏子層の層序と年代の再検討
納谷友規・水野清秀
(vol.126, no.4, p.183–204)
Appendix 1.Occurrence of diatoms in the Bushi Formation.
Appendix 2.List of typical tephras and chemical compositions of volcanic glass shards with low TiO2–MgO and high K2O contents in Lower Pleistocene deposits, central Japan.
File No87:vol.126, no. 4
報告:紀伊半島中央部に分布する四万十帯白亜系東川コンプレックスから得られた砕屑性ジルコンU–Pb 年代
志村侑亮ほか
(vol.126, no.4, p.223–230)
Appendix 1.LA-ICP-MS U–Pb isotopic data. Discordant data are shown in gray color. 206Pbc: common 206Pb (%).
File No86:vol.126, no. 3
報告:草津白根火山,白根火砕丘群,弓池マールおよび逢ノ峰火砕丘の岩石学的特徴
亀谷伸子ほか
(vol.126, no.3, p.157-165)
Appendix 1. Whole-rock compositions and modal compositions. Total Fe expressed as Fe2O3. For plotting on Harker diagrams (Fig. 5), FeO* was calculated as FeO + (0.8998×Fe2O3). Mineral and groundmass (glass + microphenocryst + microlite) abundances are in vol% (calculated on a vesicle-free basis) based on >2000 point counts. Loss on ignition (LOI) was measured by igniting the powdered samples at 900°C for 2 h. Abbreviations: Vol. Bl.: volcanic block; tr: present in samples but not observed in point counts; n.d.: not detected.
File No85:vol.126, no. 3
論説:富士山東方で1.1kaに発生した大規模火山性斜面崩壊
山元孝広ほか
(vol.126, no.3, p.127-136)
Supplement 1.Results of major elements composition analysis for volcanic glasses by Energy Dispersive X-ray Spectrometry. 161212c = Kozushima-Tenjyosan tephra. OYM-03-01, g-sample and g1-1 = volcanic glass shards in OYM03. エネルギー分散型エックス線分析による火山ガラスの主成分 組成測定結果.161212c =神津島天上山テフラ.OYM-03- 1, g-sample 及びg1-1 = OYM03 中の火山ガラ
File No84:vol.126, no. 3
論説:三重県志摩半島の黒瀬川帯蛇紋岩中ドレライト岩塊の地球化学と起源
内野隆之
(vol.126, no.3, p.113-125)
Appendix Table. Whole-rock major- and trace-element geochemical data for standard samples (certified reference materials). “Measured” indicates values analyzed in this study, and“ certified” indicates known certified values
File No83:vol.125, no. 11
報告:赤石山地中央部に分布する秩父帯付加体の砕屑性ジルコンU–Pb 年代
杉本大志ほか
(vol.125, no.11, p.827-832)
Appendix 1-5. LA-ICP-MS U–Pb isotopic data. Analyses shown in italics are discordant data. All errors are quoted as 1σ.
File No82:vol.125, no. 11
論説:富山県に分布する太美山層群のジルコンU–Pb年代
金子一夫ほか
(vol.125, no.11, p.781-792)
Appendix. U–Pb isotopic data of the unknown zircon samples and zircon standards (Nancy 91500 and OD- 3). (C) concordant data set; (D) discordant data set; (IC) data from a spot containing an inclusion or a crack; (R) data from a spot containing resin or data from a zircon grain that detached from the resin during laser ablation. Data shown in italics (D, IC, and R in the column labelled “Remarks”) were rejected before calculation of isotopic ages
File No81:vol.125, no. 9
ノート:看板・新聞折り込み広告と教科書における地図の北を表す記号の使用と大学生の理解
廣木義久
(vol.125, no.9, p.699-705)
Caption File
Fig. A1, Table A1-A2
References
File No80:vol.125, no. 9
論説:Excel のソルバー機能を利用した熱力学計算方法:重心座標系の化学式を用いた熱力学計算への適用例
久田公一
(vol.125, no.9, p.635-654)
Appendix 1
Appendix 2
Appendix 3
Appendix 4
Appendix 5
Appendix 6
Appendix 7
Appendix 8
File No79:vol.125, no. 7
論説:富山県八尾地域の新生界年代層序の再検討とテクトニクス
中嶋 健・岩野英樹・檀原 徹・山下 透・柳沢幸夫・谷村好洋・渡辺真人・佐脇貴幸・中西 敏・三石裕之・山科起行・今堀誠一
(vol.125, no.7, p.483-516)
Caption_file
Appendix 1
Appendix 2
Figure A1-A7
Table A1-A5
File No78:vol.125, no. 6
報告:飛驒山地加賀沢の花崗岩類のジルコンU–Pb 年代
竹内 誠・柴田 賢・カ スイ・山本鋼志
(vol.125, no.6, p.453-459)
Appendix 1. U–Pb isotopic data for zircons analyzed in this study. All errors are 2σ. Analyses shown with shading are discordant and are not included in the probability density plots and histograms.
File No77:vol.125, no. 6
報告:愛媛県久万高原町の三波川変成岩類中に新たに見つかった“粗粒な”変塩基性岩体
仲田光輝・楠橋 直・齊藤 哲・大藤弘明・奈良正和
(vol.125, no.6, p.447-452)
AFig. S1-Table S2
Fig. S1. Geological route map around the outcrops of the metabasite body. The location of this area is shown in Fig. 1.
Fig. S2. Rock sections. (a–d) Color images of (a–d) of Fig.3. (e–i) Metabasite clasts sampled from the basal conglomerate of the Hiwadatoge Formation unconformably overlying the metabasite at outcrop NMMGB003.(j) Metabasite clast sampled from the basal conglomerate of the Hiwadatoge Formation exposed at Nakajo. The location of the outcrop is indicated by the white star (B) in Fig. 1. The scale bars equal 1 cm.
Fig. S3. Photomicrographs of a metabasite sample collected at outcrop NM-MGB002 under (a, c, e, g) plane-polarized light and (b, d, f, h) cross-polarized light. (a, b) Color images of (a, b) of Fig. 4. The scale bars for (a,b), (c, d) and (e, f) equal 1 mm, and that for (g, h) equals 0.5 mm. Abbreviations: Act, actinolite; Al, albite; Mtx, matrix; Ppc, “ porphyroclast”; Ttn, titanite, Zo, zoisite.
Table S1. SEM-EDS data (wt%) for minerals within the metabasite samples collected from outcrop NMMGB002 and the basal conglomerate of the Hiwadatoge Formation (outcrop NM-MGB003; samples NM-HTFg116 and 310). Abbreviations: Chl, chlorite; Phn, phengite; Ttn, titanite.“ –” indicates below the detection limit.
Table S2. Whole rock chemical composition (wt%) for the metabasite samples collected from outcrop NMMGB002 and the basal conglomerate of the Hiwadatoge Formation (outcrop NM-MGB003; samples NM-HTFg099 and 100) quantified by XRF.
File No76:vol.125, no. 6
論説:北部九州白亜紀花崗岩類,添田花崗閃緑岩のU–Pb ジルコン年代とSr・Nd 同位体比組成:添田花崗閃緑岩の再区分
柚原雅樹・亀井淳志・川野良信・岡野 修・早坂康隆・加々美寛雄
(vol.125, no.6, p.405–420)
Appendix 1. Whole-rock chemical compositions of the hornblende porphyritic facies of the Irahara Granodiorite.
File No75:vol.125, no. 5
論説:紀伊半島中央部に分布するジュラ紀秩父付加体と白亜紀四万十付加体の境界周辺の地質構造と 砕屑性ジルコンU–Pb 年代
志村侑亮・常盤哲也・竹内 誠・山本鋼志
(vol.125, no.5, p.349-365)
Appendix 1. LA-ICP-MS U–Pb isotopic data. Rejected data are shown in gray color. 206Pbc: common 206Pb (%).
File No74:vol.125, no. 5
論説:紀伊半島中央部高原川地域の白亜紀付加コンプレックスの砕屑性ジルコンU–Pb 年代
太田明里・竹内 誠・ナドミド バヤルト・山本鋼志
(vol.125, no.5, p.329-347)
Appendix 1. U–Pb isotopic data of zircons analyzed in this study. All errors are 2σ. Analyses shown with a shadow are discordant and are not included in the probability density plots and histograms.
File No73:vol.125, no. 4
論説:岐阜県高山市本郷地域における飛騨外縁帯の砕屑岩層から得られた砕屑性ジルコンのU–Pb 年代とその意義: 森部層およびジュラ系堂殿層(新称)の堆積年代
鈴木敬介・栗原敏之・植田勇人
(vol.125, no.4, p.307-322)
Supplementary Figure 1. Map showing the location of sandstone samples selected for petrographic analyses and U–Pb detrital zircon dating (except for sample 0609-03) in the Hongo area.
Supplementary Table 1. U–Pb zircon dating results. Abbreviations:Ra = age ratio; σc = concordance error; SE =standard error.
Supplementary Table 2. Results of U–Pb zircon dating on the Plešovice standard. Abbreviations: Ra = age ratio;σc = concordance error; SE = standard error.
File No72:vol.125, no. 4
論説:出羽山地東縁,秋田県角館町周辺の上部漸新統および中新統の層序
細井 淳・工藤 崇・羽地俊樹・岩野英樹・檀原 徹・平田岳史
(vol.125, no.4, p.279-295)
Table A1. Zircon U–Pb analytical data.
Table A2. Zircon fission-track data.
File No71:vol.125, no. 2
報告:日高変成帯南部,黄金道路沿いに露出するかんらん石ノーライトの岩石学的特徴
志村俊昭・小島 萌・大橋美由希・山根幹生・Anthony I. S. Kemp
(vol.125, no.2, p.195-200)
Table A1. Whole rock chemical compositions and, Sr and Nd isotope ratios of the olivine norite.
File No70:vol.125, no. 2
論説:U–Pb zircon dating of the Sanbagawa metamorphic rocks in the Besshi–Asemi-gawa region, central Shikoku, Japan, and tectonostratigraphic consequences.
Aoki, K., Seo, Y., Sakata, S., Obayashi, H., Tsuchiya, Y., Imayama, T., Yamamoto, S. and Hirata, T
(vol.125, no.2, p.183–194)
Table A1. LA-ICP-MS U–Pb concordia data from zircon analyses.
File No69:vol.125, no. 2
論説:山口県東部、柳井地域に産する領家帯蒲野花崗閃緑岩のマグマ過程.
池田雄輝・大和田正明・西塚 大・亀井淳志
(vol. 125,no. 2, 167–182)
Table A1-A4
Table A1. Representative chemical compositions of garnet. FeOT: total Fe. Alm=100*Fe/(Fe+Mn+Mg+Ca), Sps=100*Mn/(Fe+Mn+Mg+Ca), Pyr=100*Mg/(Fe+Mn+Mg+Ca), Grs=100*Ca/(Fe+Mn+Mg+Ca).
Table A2. Representative chemical compositions of plagioclase. FeOT: total Fe. An=100*Ca/(Ca+Na+K), Ab=100*Na/(Ca+Na+K), Or=100*K/(Ca+Na+K). Positions from A to A’ correspond to the analytical points shown in Fig. 7.
Table A3. Representative chemical composition of biotite. FeOT: total Fe. Mg# = 100*Mg/(Fe+Mg).
Table A4. Representative chemical composition of hornblende. FeOT: total Fe. Mg# = 100*Mg/(Fe+Mg).
File No68:vol.125, no. 1
論説:房総半島に分布する上総 層群の広域テフラ−特に上総層群下部におけるテフラ層序と新たな対比−
田村糸子・水野清秀・宇都宮正志・中嶋輝允・山崎晴雄
(vol.125, no.1, p.23-39)
Open File(PDF): Sampling locality maps based on the 1:25,000 topographic maps “Onjuku” (a–d), “Kazusa-Ohara” (e), and “Katsuura” (f and g) of the Geographical Survey Institute, Japan.
File No67:vol.124, no. 12
報告:Geochemical database of Japanese islands for basement rocks: compilation of domestic article
Satoru Haraguchi, Kenta Ueki, Kenta Yoshida, Tatsu Kuwatani, Mika Mohamed, Shunsuke Horiuchi and Hikaru Iwamori
(vol.124, no.12, p.1049-1054)
ppendix A (pdf). Articles compiled in the DODAI until the end of 2017.
Appendix Table 1 (pdf). Characteristics of worldwide databases, some domestic databases, and the DODAI. (The numbers of references and samples were compiled from EarthChem until the end of 2017).
Appendix Table 2 (csv). Compiling geochemical data of DODAI.
File No66:vol.124, no. 12
総説:美濃帯層状チャートの堆積寄稿に関する3つの問題
尾上哲治(vol.124, no.12, p.1021-1032)
PDF (1.9MB)
補遺:上部三畳系層状チャートの主要元素分析結果について
Fig. A1. Geologic and location maps of the study sections along the Kiso River, central Japan. Modified after Wakita (1988).
Fig. A2. Field occurrence of Late Triassic bedded chert at Sakahogi in the Inuyama area in the Mino Belt, Japan. (a) lower Upper Norian (lower Sevatian; Epigondolella bidentata conodont zone) bedded chert. (b) upper Upper Norian (upper Sevatian; Misikella hernsteini conodont zone) bedded chert. Scale bars, 5 cm.
Table A1. Major element data for samples from the Sakahogi section. Major element compositions of the Sakahogi chert and claystone samples normalized to 100 wt%.
Table A2. Analytical results of major element in reference material (JCh-1) by XRF.
File No65:vol.124, no. 11
論説:三重県に分布する中新統一志層群上部の浮遊性有孔虫・珪藻化石層序
大信田彦磨・林 広樹・柳沢幸夫・栗原行人・星 博幸
(vol.124, no.11, p.919-933)
Appendix 1. Map showing sample localities. Base map is a topographic map downloaded from the Geospatial Information Authority of Japan (GSI; http://www.gsi.go.jp).
File No64:vol.124, no. 11
報告:New geochemical data for back-arc basin basalts from DSDP Leg 58 Sites 442–444 and the ODP Leg 131 Site 808, Shikoku Basin Keywords: Shikoku Basin, back-arc basin basalt, DSDP Leg 58 Site 442–444, ODP Leg 131 Site 808, recent analytical technique
Satoru Haraguchi, Koichiro Fujinaga, Kentaro Nakamura, Yasuhiro Kato, Asuka Yamaguchi, and Teruaki Ishii
(vol.124, no. 11, p.935-940)
Appendix
Appendix A. Analytical Methods.
Appendix Table 1. Bulk rock composition of samples estimated using XRF for DSDP Leg 58 Sites 442–444 and ODP Leg 131 Site 808.
Appendix Table 2. Bulk rock composition of samples estimated using ICP-MS for DSDP Leg 58 Sites 442–444 and ODP Leg 131 Site 808.
File No63:vol.124, no. 10
論説:栃木県北部,福島県南部に分布する中期更新世火砕流堆積物群の層序
山田眞嵩・河合貴之・西澤文勝・鈴木毅彦
(vol.124, no. 10,p.837-855)
Appendix. Major-element contents of volcanic glass shards obtained by EDS measurement.
File No62:vol.124, no. 10
論説:岩手県西和賀町に分布するグリーンタフのジルコンFT およびU–Pb 年代とその意味
細井 淳・中嶋 健・檀原 徹・岩野英樹・平田岳史・天野一男
(vol.124, no. 10,p.819-835)
Table A1. Summary of zircon U-Pb data by LA–ICP–MS.
Table A2. Summary of zircon FT data.
File No61:vol.124, no. 9
論説:日本海拡大以来の日本列島の堆積盆テクトニクス
中嶋 健
(vol.124, no. 9,p.693-722)
Fig. S1-S2(PDF)
Fig. S1. Chronostratigraphic correlations, including inferred paleostress regimes and tectonic events, for the Hokuriku district and the Toyama Trough. The geomagnetic timescale is after ATNTS2012 (Gradstein et al., 2012). Diatom biostratigraphy is after Yanagisawa and Akiba (1998). The Intra Lower Teradomari Unconformity Horizon (ILTU) is after Muramoto et al. (2007).
Fig. S2. Tectonostratigraphic and paleoenvironmental relationships in the Sea of Japan from the middle Miocene to the early Pliocene (compiled from: Hanagata et al., 2001; Japanese Association for Petroleum Technology, 2014; Nakajima, 2013; and Sato et al., 1991). The planktonic foraminifera zonation is from Blow (1969) and Maiya (1978), the benthic foraminifera zonation from Maiya (1978), and the nannofossil zonation from Martini (1971) and Sato et al. (1991). Abbreviations: F.O., First occurrence; L.O., Last occurrence; PFSS, Planktonic Foraminiferal Sharp Surface (after Maiya and Inoue, 1981).
File No60:vol.124, no. 7
論説:赤石山地四万十帯白亜系赤石層群から得られた砕屑性ジルコンU-Pb年代
常磐哲也・市谷和也・志村侑亮・竹内 誠・山本鋼志
(vol.124, no. 7,p.539-544)
Appendix1-5 (PDF)
Appendix 1-5. LA-ICP-MS U–Pb isotopic data. Analyses shown in italics are discordant data.
File No59:vol.124, no. 6
論説:火山ガラスの主成分および微量元素組成による鹿児島市永田川河口部で掘削 されたボーリングコアに挟まれる火砕流堆積物の識別
古澤 明・大木公彦・宮脇理一郎
(vol.124, no. 6,p.435-447)
Appendix1(PDF 681KB)
Appendix 1. Glass composition data for Aira-Tn tephra and ATHO-G of MPI-DING Reference Glasses. Av., average; SD, standard deviation; U, uncertainty at the 95% confidence level; n, number of analyses. Preferred values are from Jochum et al. [2006].
Island Arc 日本語要旨 2012. vol. 21 Issue 2 (June)
Vol. 21 Issue 2 (June)
Island Arc Award (2012)
Structure of Sumatra and its implications for the tectonic assembly of Southeast Asia and the destruction of Paleotethys.
<Island Arc, 18, 3–20 (2009)>
Anthony J. Barber and Michael J. Crow
スマトラの地質構造,および東南アジアの形成とパレオテチスの閉鎖に対するその意義
▶▶日本語要旨はこちら
通常論文
[Research Articles]
1. Effects of tides and weather on sedimentation of iron-oxyhydroxides in a shallow-marine hydrothermal environment at Nagahama Bay, Satsuma Iwo-Jima Island, Kagoshima, southwest Japan
Shoichi Kiyokawa, Tomomi Ninomiya, Tomoaki Nagata, Kazumasa Oguri, Takashi Ito, Minoru Ikehara and Kosei E. Yamaguchi
浅海熱水環境における水酸化鉄の堆積作用への潮汐・気象状況の関連性:鹿児島県・薩摩硫黄島長浜湾
清川昌一・二宮知美・永田知研・小栗一将・伊藤 孝・池原 実・山口耕生
鹿児島県薩摩硫黄島にある長浜湾は浅海熱水活動が活発で水酸化鉄堆積作用を研究する上で非常に恵まれたところである.湾内の船付き場は人工的な防波堤に囲まれ,外洋からの影響が小さく,大量の水酸化鉄が沈殿している.湾内は赤褐色の海水からなり,海底には1.5mにおよぶ堆積物がたまっている.約2週間の湾内濁度変化断面図の作成および表層長期カメラ撮影により赤褐色海水の動きを明らかにした.その結果,天候が穏やかな場合は潮汐の影響が大きく,満潮時に外洋水が湾内に入る.小潮のときは潮の流れが小さいために沈殿が起こりやすい.台風では波・うねりの影響で海底がかき混ぜられ非常に濁る.大雨時には海岸線の水酸化鉄に富む砂の隙間を通って雨水が流れ込み,多くの鉄物質を供給する.鉄堆積物形成にはこのような自然現象の影響も重要である.
Key Words : Fe-oxyhydroxides, hot spring, rain, shallow-marine, storm, tide.
2. High-resolution lithostratigraphy and organic carbon isotope stratigraphy of the Lower Triassic pelagic sequence in central Japan
Hironobu Sakuma, Ryuji Tada, Masayuki Ikeda, Yuichiro Kashiyama, Naohiko Ohkouchi, Nanako O. Ogawa, Satoko Watanabe, Eiichi Tajika and Shinji Yamamoto
中部日本,下部三畳系遠洋性堆積物層序の高解像度復元および有機炭素同位体比変動
佐久間広展・多田隆治・池田昌之・柏山祐一郎・大河内直彦・小川奈々子・渡部哲子・田近英一・山本信治
三畳紀前期を通じた全球的な古環境変動を明らかとするため,中部日本,犬山地域において,詳細な野外調査に基づき,下部三畳系遠洋性堆積物層序の高解像度復元を行った.さらに,高解像度年代モデルを確立するため,含有される有機物の炭素同位体比を測定し,南中国の浅海成炭酸塩岩から得られた高解像度炭素同位体比変動と対比した.その結果,SmithianおよびSpathianを通じた,超海洋パンサラサの遠洋性堆積物層序に関する,高解像度年代スケールが得られた.本年代モデルから,Smithian後期を通じた堆積速度の急激な上昇が明らかとなり,パンサラサへの陸源砕屑物の供給量が増大した可能性が示唆された.
Key Words : carbon isotope, Lower Triassic, mass extinction, pelagic sequence, Permian–Triassic boundary, siliceous rock.
3. Petrogenesis of anhydrous clinopyroxenite xenoliths and clinopyroxene megacrysts in alkali basalts from the Ganseong area of South Korea
Sung Hi Choi and Nak Kyu Kim
韓国,Ganseong(アンソン)地域のアルカリ玄武岩に包有される無水の単斜輝石岩捕獲岩類と単斜輝石巨晶の岩石成因論
韓国Ganseong地域の後期新生代アルカリ玄武岩には多量の超苦鉄質捕獲岩と単斜輝石巨晶が含まれる.捕獲岩の大部分を占めるのは無水の単斜輝石に富むウェールライト―単斜輝石岩類で,ウェールライトからかんらん石単斜輝石岩,単斜輝石岩の範囲に及ぶ.本研究では記載岩石学と鉱物・全岩化学組成に基づいて,ウェールライト―単斜輝石岩類の捕獲岩と単斜輝石巨晶の成因について検討する.炭酸塩やアパタイトを欠き,Ti/Eu比が高く,単斜輝石に富む鉱物学的特徴から,Ganseong地域のウェールライト―かんらん石単斜輝石岩の起源としてかんらん岩―メルト反応は除外される.これらの全岩化学組成(例えば苦鉄質メルトと比べて,MgO量に比してCaO含有量が高く,U,K,PやTiなどの不適合元素濃度が低いこと)は,輝石岩類は結晶化したマグマそのものではなく,少量の残液を含む集積岩であることを示している.無水で斜方輝石を含まない鉱物組み合わせ,かんらん石→単斜輝石→斜長石という晶出順序,鉱物化学組成(例えば同じMg#に対して低Cr#,高TiO2含有量のスピネルや,TiO2およびNa2O含有量の高い単斜輝石)から,親マグマ候補として比較的水に乏しいプレート内アルカリ玄武岩が最もらしい.単斜輝石巨晶の組織と組成から,高圧下でホストマグマから結晶化したのではない.単斜輝石巨晶はウェールライト―輝石岩類の単斜輝石で定義される組成トレンドのFeに富む端成分を占める.輝石岩捕獲岩と単斜輝石巨晶の間でMg#が漸次減少し,大きな組成差がないことは,同様の親マグマの分別と分化であることを示している.単斜輝石巨晶は,Ganseongウェールライト―単斜輝石岩類を形成した一連のマグマの進化過程において,より分別が進んだ段階で結晶化したペグマタイト質の単斜輝石岩の破片であろう.
Key Words : clinopyroxene megacryst, Ganseong, Korea, wehrlite–clinopyroxenite.
4. Lateral variations in the lithology and organic chemistry of a black shale sequence on the Mesoarchean seafloor affected by hydrothermal processes: The Dixon Island Formation of the coastal Pilbara Terrane, Western Australia
Shoichi Kiyokawa, Takashi Ito, Minoru Ikehara, Kosei E. Yamaguchi, Shoichiro Koge and Ryo Sakamoto
太古代中期の熱水活動に関連した黒色頁岩層の岩相・有機炭素の側方変化:西オーストラリア・ピルバラ海岸グリーンストーン帯・デキソンアイランド層
清川昌一・伊藤 孝・池原 実・山口耕生・高下将一郎・坂本 亮
西オーストラリア・ピルバラ海岸グリーンストーン帯中のデキソンアイランド層は,32億年前の海洋性島弧起源の地質帯で,熱水活動の痕跡と当時の海底になまった珪質な地層が広く分布する.デキソンアイランドでは,海岸線に5㎞に渡って連続露頭が続き,当時の海底環境を復元できる貴重な場所である.有機物に富む熱水脈の影響を受けた火山岩上に10−20mの黒色チャート層が広く覆っており,2層の凝灰岩層を鍵に層序対比より堆積層の側方変化を明らかにした.黒色チャートの有機物炭素量はおよそ0.1wt/%で,炭素同位対比は脈とともに–40 to –25‰であり,熱水活動の直後に正断層の影響を受けていた.当時の海底は非常に淀んだ無酸素の状態であり,有機物を含む熱水から供給された有機物が分解されずに,熱水起源のシリカとともに広く海底を覆っていたと考えられる.
Key Words : Archean, carbon isotopes, black chert, black chert vein, greenstone belt, hydrothermal system, komatiite, normal fault.
編集委員会より(バックナンバー)
編集委員会より(バックナンバー)
地質学雑誌では図版を廃止しました
(地質学雑誌編集委員会委員長 山路 敦 2013.9.30 )
地質学雑誌を含め,かつては学術誌の印刷の品質が低かったため,重要な証拠写真は図版として本文とは違う光沢紙に印刷し,論文の末尾に添付するのが普通でした.このほど地質学雑誌では,図版を廃止することになったことをお知らせします.
廃止の理由は,まず,地質学雑誌でも全ページにコート紙を用いるようになり,紙質と印刷の品質において,図版と本文とのあいだで差がなくなったことが挙げられます.また,図版にはページ番号が振っていないので,図版があるとページ数の見積もりや出版費の計算などの事務が繁雑になります.さらにまた,図書館を通じて論文の複写依頼をする際,ページ番号がないことが落とし穴になって,図版部分が欠如したコピーが送られて来るというような事もおこっています.地質学雑誌で図版を含む論文は,最近は年に1編程度であり,図版がなくても 1ページ大の写真は掲載できるので,廃止による不都合はないと判断したわけです.
図版の廃止を趣旨とした「地質学雑誌投稿編集出版規則」改正案は,2013年9月の理事会で承認されました.今後も地質学雑誌への投稿をお願いします.
(117巻6月号 2011年6月)
地質学雑誌の「短報」がなくなりました!
(地質学雑誌編集委員長 小嶋 智)
地質学雑誌の「短報」と「論説」の違いは,ページ制限があるかどうか,日本語要旨をつけるかどうか,アブストラクトの制限文字数の多寡という3点のみで,「短報」というジャンルを設ける本質的な意味はほとんどなくなっていました.そこで,地質学雑誌編集委員会では「短報」を廃止することを検討してきましたが,「小藤賞」との関連もあり,簡単には廃止できませんでした.この問題を執行理事会で検討して頂いた結果,(1)「短報」を廃止すること,(2)「小藤賞」は「小藤文次郎賞」と名称を変更し,地質学雑誌掲載論文に限らず広く重要な発見または独創的な発想を含む論文を対象に表彰することが決定されました.この変更は2011年4月2日の理事会で承認され,「短報」廃止を盛り込んだ新しい地質学雑誌編集出版規則が2011年5月21日の理事会で制定されました.この規則は2011年6月1日から施行されており,「短報」の廃止だけでなく,引用文献の書式例を増やす,数式の書き方に関する指針を定めるなど,新しい細則も加えていますので,投稿を考えておられる方は,是非一度目を通して下さい.
「短報」が廃止されたからといって,地質学雑誌は,これまでの「短報」のような内容の論文の受付を拒否するものではありません.今後も,新しい発見を「短い論説」として,ぜひ地質学雑誌にご投稿下さい.お待ちしています!「4ページの論説」の投稿をお待ちしています
(117巻1月号 2011年1月)
新年おめでとうございます.地質学雑誌は,今月号から若干体裁を変更しています.ひとつは,英数字をTimes 系のフォントに変更したことです.それにより,Abstract など英語の部分が読みやすくなったことと思います.もうひとつは,掲載論文が広く参照され,引用されることを期待して,科学技術振興事業団オブジェクト識別子(以下JOI と書きます)を表示することにしたことです.
いわば,論文ごとに割り当てられる背番号がJOI です.地質学雑誌の第酈巻第pページから始まる文献を論文A とすると,JOI は JST.JSTAGE/geosoc/v.p になります.後 日,論文A を引用した別の論文B がどこかの雑誌に載った場合,電子ジャーナルで論文B をみると,文献リストの論文A の欄に論文A へのリンクが張られます.そのリンクからただちに地質学雑誌の論文A が参照できる,というのが,文献の「国際的背番号制」です.じつはhttp://joi.jlc.jst.go.jp /の後にJOI を連結した記号列が,J-STAGE のサーバー中の論文A の「抄録」のページのURL になっています.例えば,第116 巻(2010 年)の最初の論文は,http://joi.jlc.jst.go.jp/JST.JSTAGE/geosoc/116.1 です.「抄録」ページからは,論文のPDF ファイルが無料で閲覧できます.
今月号から,JOI を各論文の第1 ページ右上に印刷することにしました.J-STAGE のサーバーで論文が公開されるのは,印刷から3ヶ月程度後なので,JOI を使ったリンクが有効になるのもそれからです.国際的に通用しているDOI についても議論しています.地質学雑誌掲載論文は,今まで以上に参照され,引用され易くなるはずですので,投稿をおねがいします.
ページTOPへ戻る
(114巻2月号 2008年2月)
電子投稿の場合でも保証書については,著者の署名・押印が必要となります.ご協力をお願いいたします.
電子編集システム導入から丸2年が経過し,さほど大きな問題も発生せず順調に稼動しています.学会は,この12月に一般社団法人として新しいスタートをき りました.これにあわせて,15年間採用されてきた現行の地質学雑誌の表紙が来年1月号から一新します.現在最終的なデザインの微調整が行われています. 会員の方に広く「新しくなった地質学雑誌の表紙」を受け入れていただければと思います.先日,ある先生からロンドンにある地質学会(The Geological Society)を訪れた際に撮った写真をいただきました.それは,あの慣れ親しんだ表紙の「地質学雑誌」が書架に配架されている写真でした.邦文誌とし ての地質学雑誌ですが,少しでも外国の方に読んでいただけるような雑誌に工夫していかなければと切に感じます.1月号から導入される英文要旨のネイティブ チェック制は,それに向けての一歩となるはずです.
編集委員会では,毎月の編集作業と同時に,様々な編集作業に関わる規則の見直しなども行っています.現在「投稿規定」では「Ⅲ.外国語原稿 1.論説・総 説と短報・報告の原稿は日本の学会で一般に用いられる外国語でもよい.」とされていますが,最近では英語以外の外国語は「日本の学会で一般に用いられる」 とはみなされなくなってきたために,「これらの原稿は英語で書いていただこう」ということになりました.したがいまして「投稿規定」の外国語原稿は,すべ て英語原稿に替えることになりました.
またニュース誌10月号や地質学会HPでもご紹介(2008.10.8)いたしま したように,「ベテランの皆様は,今更と思われるかもしれませんが,あらためて国立・国定公園や史跡・名勝・天然記念物,あるいは一般的な露頭における調 査上の注意を喚起させて頂きます.地質学会員が模範となって,節度ある行動を示していただければ幸いです.」(「野外調査に心がけたいこと」より)という ように,サンプリン・モラルの徹底が強く求められております.これに対応して,投稿時に確認・提出していただく「保証書」の内容に以下の事柄の追加がなさ れることになりました.追加事項(下線部)として,「8.本著作物を作成するに当たって行われた調査・研究行為が,適切な方法でなされたものであること」 があります.これは,まさに正規な手続きを経て採集に至ったことを保証するものです.また「5.著作物には,日本地質学会の名誉を傷つけ,地質学雑誌の信 用を毀損する盗用データ,捏造データ,著作物に関する利害を持つ者の合意に反するもの,その他学会の倫理綱領に反するものを含まないこと」も同様な趣旨に 基づくものです.このような追加された「保証書」も1月号掲載原稿分から採用されることになりますのでご注意ください.なお今後は,電子投稿の場合でも保証書については,著者の署名・押印が必要となります.ご協力をお願いいたします.
ページTOPへ戻る
(113巻5月号 2007年5月).
地質学雑誌に「報告(Report)」という新しいカテゴリーが加わりました。
制限ページ数は6ページです。詳しくは編集規則(PDF)をご覧下さい。
毎年,全国の地学系の教室で取り組まれている卒業研究や修士論文の数は,相当数に昇るものと思われます.それらの中には,一次データとしては大変 貴重なものが多数含まれています.しかし,それらの多くは各大学や指導教員のもとに保管されているのみで,全く日の目をみないで死蔵されている例が多いの ではないでしょうか.また,以前には多くの大学で発行されていた紀要が,廃止されている例も多く,そうした一次データを公表する場も少なくなっている様に 思われます.新潟大学でも和文の研究報告は廃止されています.重要な露頭の記載や,ルートマップ,岩石の分析値や化石の記載など,膨大な貴重なデーターが 公表されずに眠り続けているとしたら,大変残念な事態です.
地質学雑誌に,データの報告を主としたカテゴリーを加えることによって,そうした一次データの公表の場を提供する事が出来るのではないかという ことで,編集委員会企画部会で現在検討を進めているところです.この議論は,全国の地学系の教室で行われている膨大な卒業研究や修士論文によって得られて いる,貴重なデータの公表の場を設けるという趣旨で発想されています.会員の皆様からの積極的なご意見をお待ちしています
Island Arc 日本語要旨 2012. vol. 21 Issue 4 (December)
Vol. 21 Issue 4 (December)
通常論文
[Pictorial Articles]
1. Unconformity between a Late Miocene–Pliocene accretionary prism (Nishizaki Formation) and Pliocene trench-slope sediments (Kagamigaura Formation), central Japan
Yuzuru Yamamoto, Shun Chiyonobu, Toshiyuki Kurihara, Asuka Yamaguchi, Shoko Hina, Mari Hamahashi, Hugues Raimbourg, Romain Augier and Leslie Gadenne
房総半島南部における上部中新統ー鮮新統付加体(西岬層)と鮮新統斜面堆積物(鏡ヶ浦層)境界にみられる不整合
山本由弦・千代延 俊・栗原敏之・山口飛鳥・比名祥子・浜橋真理・Hugues Raimbourg・Romain Augier・Leslie Gadenne
[Research Articles]
1. Phase equilibria and metamorphic evolution of garnet-mica-plagioclase gneisses from the Qiliping terrane in the western Dabie Orogen, central China
Jing-Sen Zhang, Jing Zhang, Jun-Jie Zhou and Hong-Fen Zhang
中国中央部,大別(Dabie)造山帯西部の七里坪(Qiliping)陸塊に産するザクロ石−雲母−斜長石片麻岩の相平衡と変成の進化過程
大別−蘇魯(Dabie-Sulu)造山帯の高圧・超高圧変成岩帯に広範囲に露出する片麻岩類には通常,エクロジャイト相変成作用の証拠が見られない.大別造山帯西部の七里坪地域のザクロ石−雲母−斜長石片麻岩類は,ザクロ石,フェンジャイト,黒雲母,斜長石,石英,ルチル,イルメナイト,緑泥石,緑簾石と普通角閃石からなる.石英,緑簾石とルチルの包有物を伴うザクロ石の斑状変晶はわずかに組成累帯構造を示しており,核からマントルにかけてパイロープ成分が増加しスペサルティン成分が減少するが,マントルからリム部にかけてはパイロープとグロシュラー成分が減少しスペサルティン成分が増加する.高Siのフェンジャイトの晶出は,片麻岩類が高圧変成作用を受けたことを示している.NCKMnFMASHTO (Na2O-CaO-K2O-MnO-FeO-MgO-Al2O3-SiO2-H2O-TiO2-O) 系で計算した代表的な2試料の温度-圧力模式図によると,組成累帯構造を示すザクロ石から復元した変成温度‐圧力経路は,昇温変成期作用が496 ± 15°C で17.6 ± 1.5 kbarから555 ± 15–561 ± 15°Cで最高圧力21.8 ± 1.5–22.7 ± 1.5 kbar へとわずかな圧力増加を伴う温度上昇で特徴づけられることを示す.後退変成過程の初期は,10.3 ± 1.5–11.0 ± 1.5 kbarで最高温度608 ± 15–611 ± 18°Cへの温度上昇を伴った減圧が支配的である.後退変成過程の後期は,圧力・温度ともに顕著に減少する.昇温期変成作用にはザクロ石,蘭閃石,ヒスイ輝石,ローソン石,フェンジャイト,石英,ルチル±緑泥石を含む鉱物組み合わせが予想されるが,これは現在観察されるものとは異なる.このような高圧変成作用は,高Siフェンジャイトおよびザクロ石の核からマントルにかけての組成と温度-圧力模式図を併用することによって一部を復元できる.このことは,揚子−中朝地塊衝突期に起きたテレーンの沈み込みと上昇過程について重要な制約を与える.
Key Words : garnet mica plagioclase gneiss, metamorphic evolution, P–T pseudosection, Qiliping terrane, western Dabie Orogen.
2. Geochemistry of Cenozoic volcanic rocks in Tengchong, SW China: relationship with the uplift of the Tibetan Plateau
Yutao Zhang, Jiaqi Liu and Fanchao Meng
西南中国,騰沖(Tengchong)の新生代火山岩類の地球化学:チベット高原の隆起との関係
西南中国,雲南省騰沖には,新生代火山岩類(CVRT)が広く分布する.これらの岩石は玄武岩,安山岩(卓越タイプ),デイサイトからなる.ほとんどの試料は非アルカリ岩系列で,その中でも高Kカルクアルカリ岩系列である.これらの岩石はSiO2 が49.1−66.9 wt.%,TiO2 含有量は高くなく,0.7 –1.6 wt.%の範囲を示す.微量元素濃度と元素比(たとえば Nb/U, Ce/Pb, Nb/Laなど)は幅広い範囲を示す.87Sr/86Sr 値は0.7057–0.7093, 143Nd/144Nd 値は0.5120−0.5125の間で変化する.206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb,208Pb/204Pb比はそれぞれ17.936–19.039,15.614–15.810,38.894–39.735の範囲を示す.CVRTの地球化学的特徴は,島弧火山岩類に類似する.我々はこれらのマグマが,先行した沈み込み過程で交代作用を受けていたリソスフェリックマントルで生じたと提唱する.チベット高原の隆起史の研究から,我々はCVRT噴火に至る地質構造運動プロセスが隆起イベントと同期していることを見い出した.ゆえに,我々はチベット高原の隆起が騰沖の衝突造山運動を収束させ,これがさらにCVRTマグマの生成と噴出を促したと提案する.
Key Words : Cenozoic volcanic rocks, geochemistry, petrogenesis, Tengchong, Tibetan Plateau.
3. Geochemistry of Devonian–Carboniferous clastic sediments of the Tsetserleg terrane, Hangay Basin, Central Mongolia: Provenance, source weathering, and tectonic setting
Narantuya Purevjav and Barry Roser
中央モンゴルハンゲイ盆地ツェツェルレグテレーンのデボン紀−石炭紀の砕屑堆積物の地球化学:供給源とその風化過程および造構場
モンゴルのデボン紀−石炭紀ツェツェルレグテレーンは中央アジア造山帯(CAOB)複合岩体の一部をなす.ツェツェルレグテレーンは主に砕屑性堆積岩類からなり,ハンゲイ−ヘンティー盆地南部にある.テレーンはエルデネトソゲート(中期デボン紀),(ツェツェルレグ(中・後期デボン紀),ジャルガラント層群(前期石炭紀)に分けられる.ハンゲイ—ヘンティー盆地の後背地と造構場については非活動的縁辺域から島弧まで,種々の説がある.確立された記載岩石学的・全岩地球化学的指標を用いて,堆積物の供給源とその風化作用,堆積場について制約を与えるため,ツェツェルレグテレーンから砂岩・泥岩94試料を採取した.記載岩石学的には砂岩は未成熟で,エルデネトソゲート層群はQ22F14L64, ツェツェルレグ層群はQ14F17L69, ジャルガラント層群はQ18F12L70であった.Lv/L比は0.81−1.00(平均値:0.95),P/F比は0.68−0.93(平均値:0.83)である.フレームワーク粒子組成は,開析されていないか遷移期の島弧で堆積したことを示している.地球化学的には砂岩はグレイワッケに分類される.層群ごとの砂岩と泥岩の地球化学的な平均値の差はわずかで, SiO2は平均65.54-68.62 wt%の範囲にある.これらの特徴と,組成区分図上の弱いトレンドは,堆積物の未成熟さを反映している.平均的な上部大陸地殻組成との比較,主要元素判別図と変質で動きにくい元素比は,源岩の平均組成がデイサイトと流紋岩の間であることを示す.エルデネトソゲート層群の変質化学指標Chemical Index of Alterationは, Kの交代作用の影響を補正すると最大約78で,原岩が中程度に風化していたことを示す.ツェツェルレグとジャルガラント層群はそれぞれ61と63と低い最大値を示し,ほとんど風化していない,構造運動が活発な供給源に由来することを示す.造構場を判別するこれらのパラメーターは,同時代のその他のCAOBと同様,大陸島弧環境を示唆する.この島弧的な源岩は,デボン紀中期〜石炭紀前期のモンゴル—オホーツク海にあった陸塊の上に堆積したのであろう.
Key Words : CAOB, geochemistry, Mongolia, provenance, tectonic setting, Tsetserleg terrane.
4. Eocene volcanism during the incipient stage of Izu–Ogasawara Arc: Geology and petrology of the Mukojima Island Group, the Ogasawara Islands
Kyoko Kanayama, Susumu Umino and Osamu Ishizuka
伊豆—小笠原島弧形成初期ステージの始新世火山活動:小笠原群島聟島列島の地質と岩石
金山恭子・海野 進・石塚 治
伊豆—小笠原弧形成初期の始新世の火山噴出物で構成される小笠原群島聟島列島の詳細な火山地質および火山岩の記載岩石学的・地球化学的特徴を報告する.聟島列島を構成する島弧ソレアイト,希土類元素に高度に枯渇した高Siボニナイト系列および低枯渇度の低Siボニナイト系列岩は父島列島の火山岩類に対比される.ボニナイト系列の複数のマグマタイプが互層していることから同時に活動していたと考えられる.聟島における枕状溶岩を主体とする下位層から火砕岩を主体とする上位層への岩相変化から,噴火環境が深海底から浅海の比較的爆発的な噴火へと変化したことが示唆される.聟島列島の高Siボニナイトは全岩化学組成から3種類に分類される.
Key Words : arc tholeiite, boninite, geochemistry, Mukojima Island Group, Ogasawara (Bonin) Islands, volcanic geology.
5. Existence of multiple units with different accretionary and metamorphic ages in the Sanbagawa Belt, Sakuma–Tenryu area, central Japan
Yukiyasu Tsutsumi, Atsushi Miyashita, Kenji Horie and Kazuyuki Shiraishi
佐久間—天竜地域の三波川帯中に存在する異なる付加—変成年代を持つ複数のユニット
堤 之恭・宮下 敦・堀江憲路・白石和行
佐久間—天竜地域の三波川帯は,西部・東部2つのユニットから成る.西部・東部ユニットそれぞれのサンプル(T1及びT5)の砕屑性ジルコンU-Pb年代は後期白亜紀に集中し,最も若いジルコンは94.0 ± 0.6 Ma及び 72.8 ± 0.9 Maの年代を示した.変成白雲母K-Ar年代はそれぞれ69.8 ± 1.5 Maと56.1 ± 1.2 Maであった.最も若いジルコン年代はそのサンプルの堆積年代の上限を,変成白雲母K-Ar年代は上昇年代及び堆積年代の下限を示す.この結果は,T1とT5はそれぞれ異なる堆積—上昇年代を持ち,さらにT1が上昇に転じる頃にT5は堆積〜沈み込みの過程にあったことを示す.さらに,三波川帯の形成過程において,沈み込みと上昇の経路が同時に存在していたことを示唆する.
Key Words : deposition, detrital zircon, metamorphism, Sanbagawa Belt, white mica.
6. Geochemistry and Sr-Nd-Pb isotopic constraints on the petrogenesis of Cenozoic lavas from the Pali Aike and Morro Chico area (52°S), southern Patagonia, South America
Mi Kyung Choo, Mi Jung Lee, Jong Ik Lee, Kyu Han Kim and Kye-Hun Park
南米パタゴニア南部,パリ・アイケとモロチコ地域 (52°S) に産する新生代溶岩類の成因に関する地球化学的・Sr-Nd-Pb同位体的制約
南米最南端のパタゴニアにおけるマグマ生成とジオダイナミックな進化過程を明らかにするため,パリ・アイケからモロチコ地域 (52°S) に分布する後期中新世〜第四紀の溶岩台地の地球化学組成・同位体(Sr-Nd-Pb)分析を行い,マグマの溶融過程とソースマントルについての制約を与えた.パリ・アイケ溶岩はアルカリ岩系列 (パリ・アイケ: 45–49 wt.% SiO2; 4.3–5.9 wt.% Na2O+K2O),モロチコ溶岩は非アルカリ岩系列 (モロチコ: 50.5–50.8 wt.% SiO2; 4.0–4.4 wt.% Na2O+K2O)で,比較的未分化な苦鉄質火山岩 (パリ・アイケ: 9.5–13.7 wt.% MgO; モロチコ: 7.6–8.8 wt.% MgO)からなり,典型的なプレート内海洋島玄武岩の特徴を持つ.パリ・アイケとモロチコ溶岩の不適合微量元素比と同位体比は,多くの新第三紀南部パタゴニアスラブウィンドウ溶岩とは異なり,より肥沃な特徴を示し,HIMU的な玄武岩に類似している.希土類元素モデリングによると,これらの溶岩はザクロ石レルゾライトの低い部分溶融度(パリ・アイケ溶岩: 1.0–2.0%; モロチコ溶岩; ~2.6–2.7%)で生成されたことを示唆する.南パタゴニア溶岩のSr-Nd-Pb同位体組成の主要な系統的変化は,地理的配置と関連している.49.5°Sよりも北側で噴出した南部パタゴニア溶岩と比べて,パタゴニア南部のパリ・アイケとモロチコ溶岩は低い87Sr/86Sr,高い143Nd/144Ndと206Pb/204Pb比を持ち, HIMU的な特徴を持つ.枯渇したHIMU的な同位体組成を示すアセノスフェア領域は,パタゴニア南部の主要なマグマソースであった (たとえば,パリ・アイケ,モロチコやカムス・アイケ火山地帯).このことは,パタゴニア南部のアセノスフェアの同位体組成に大きな不連続があることを示唆している.地球化学的・同位体データと地質学・地質構造学的な復元に基づいて,パタゴニア南部下のHIMUアセノスフェアマントル領域は西南太平洋下の巨大HIMU領域と関連すると考える.
Key Words : Asthenosphere, HIMU-like ocean island basalt, Morro Chico, Pali Aike, Patagonia, Sr-Nd-Pb isotope.
Island Arc 名称変更について
Island Arc 名称変更について
新名称の募集に際し,Island Arcを含め,2013年1月31日の締切までに,41の提案をいただきました。
これらの名称について,Editorial Advisory Board, Associate Editors, Editor-in-Chief, Executive Editorにて、1回目の投票を行いました。
今回の名称変更に当たっては,(1)地球科学(地質科学)の広範囲の領域を含む雑誌であること,(2)特定の地域や時代,あるいは対象に特化した内容の雑誌では無いこと,などを内外に広くアピールすることが大きな目的でしたので,1回目の投票結果をもとに,2回目の投票を行いました。
その結果,現雑誌名「Island Arc」の継続を支持する意見が大多数と判断され,「Island Arc」を継続することとなりました。
今後のIsland Arc誌発展と改善に向けて,編集委員・編集事務局一同,努力いたします。
原稿のご投稿や査読のご協力を今後ともよろしくお願いいたします。
平成25年5月7日
Island Arc編集委員長
伊藤 慎
海野 進
※一般原稿に加え,特集号企画も随時受け付けております。企画を検討される方は,Island Arc編集事務局までお問い合わせください。投稿方法等についてご案内させていただきます。
Island Arc Most Downloaded Award
Most Downloaded Award
Wiley社より,過去5年に出版された論文のうち,前年1年間に最もダウンロード数の多かった論文に対して与えられる.
受賞論文 (Awarded Paper)
2020
Nishinoshima volcano in the Ogasawara Arc: New continent from the ocean? Yoshihiko Tamura, Osamu Ishizuka, Tomoki Sato, Alexander R. L. Nichols
2019
Geochemical characteristics of zircons in the Ashizuri A-type granitoids: An additional granite topology tool for detrital zircon studies. Yusuke Sawaki, Kazue Suzuki, Hisashi Asanuma, Satoki Okabayashi, Kentaro Hattori, Takuya Saito, Takafumi Hirata
2018
Dan Matsumoto Yuki Sawai Koichiro Tanigawa Osamu Fujiwara Yuichi Namegaya Masanobu Shishikura Kyoko Kagohara Haruo Kimura, 2016, Tsunami deposit associated with the 2011 Tohoku‐oki tsunami in the Hasunuma site of the Kujukuri coastal plain, Japan. Island Arc 25, 369-385.
2017
Jingyan Li, Feng Guo, Chaowen Li, Liang Zhao, Miwei Huang, 2015, Permian back‐arc extension in central Inner Mongolia, NE China: Elemental and Sr–Nd–Pb–Hf–O isotopic constraints from the Linxi high‐MgO diabase dikes.Island Arc, 24-4, 404-424.
2016
Yui Kouketsu, Tomoyuki Mizukami, Hiroshi Mori, Shunsuke Endo, Mutsuki Aoya, Hidetoshi Hara, Daisuke Nakamura, Simon Wallis, 2014, A new approach to develop the Raman carbonaceous material geothermometer for low-grade metamorphism using peak width.Island Arc,23,33-50.
2015
Shinji Yamamoto, Tsuyoshi Komiya, Hiroshi Yamamoto,Yoshiyuki Kaneko, Masaru Terabayashi, Ikuo Katayama,Tsuyoshi Iizuka, Shigenori Maruyama, Jingsui Yang,Yoshiaki Kon and Takafumi Hirata, 2013,Recycled crustal zircons from podiformchromitites in the Luobusa ophiolite,southern Tibet. Island Arc, 22,89–103(2013)
2014
Hickman, A. H., 2012, Review of the Pilbara Craton and Fortescue Basin, Western Australia: Crustal evolution providing environments for early life. Island Arc, 21, 1-31. (2012)
2013
Dereje Ayalew and Akira Ishiwatari, 2011, Comparison of rhyolites from continental rift, continental arc and oceanic island arc: Implication for the mechanism of silicic magma generation. Island Arc, 20, 78-93.
2012
Fu-Yuan Wu, Jin-Hui Yang, Ching-Hua Lo, Simon A. Wilde, De-You Sun and Bor-Ming Jahn, 2007, The Heilongjiang Group: A Jurassic accretionary complex in the Jiamusi Massif at the western Pacific margin of northeastern China. Island Arc, 16, 156-172.
2011
Sugawara,D., Minoura, K., Nemoto, N., Tsukawaki, S., Goto, K. and Imamura, F., 2009, Foraminiferal evidence of submarine sediment transport and deposition by backwash during the 2004 Indian Ocean tsunami. Island Arc, 18, 513-525
2010
Bortolotti, V. and Principi, G., 2005, Tethyan ophiolites and Pangea break-up. Island Arc, 14, 442-470.
Island Arc 日本語要旨 2013. vol. 22 Issue 4 (December)
Vol. 22 Issue 4 (December)
通常論文
[Research Articles]
1. Geochemistry of eclogite- and blueschist-facies rocks from the Bantimala Complex, South Sulawesi, Indonesia: Protolith origin and tectonic setting
Adi Maulana, Andrew G. Christy, David J. Ellis, Akira Imai, Koichiro Watanabe
インドネシア,南スラウェシ,バンティマラ複合岩体のエクロジャイト相および青色片岩相変成岩類の地球化学的研究:源岩の起源およびテクトニックセッティング
Adi Maulana・Andrew G. Christy・David J. Ellis・今井 亮・渡辺公一郎
インドネシア,バンティマラ複合岩体のエクロジャイト相および青色片岩相変成岩類の全岩の主成分元素および微量元素組成を初めて報告した.微量元素組成は,エクロジャイトの源岩がE-MORB,N-MORBおよび斑糲岩質集積岩であったことを示唆する.青色片岩の源岩はより多様であり,N-MORB,大洋島玄武岩(OIB),島弧玄武岩(IAB)を含む.MORBに由来する試料は1試料を除いてエクロジャイト相の環境に到達したが,より厚い地殻(OIB, IAB)に由来すると推定される試料は,沈み込んだ深度が浅かった(青色片岩相)ことが特筆される.本研究により,後期ジュラ紀のスンダランドの東南縁辺部の下に沈み込んだ海洋底の多様性が明らかにされた.
Key Words: Bantimala, blueschist, eclogite, geochemistry, Indonesia, Sulawesi.
2. Geodynamic evolution of a forearc rift in the southernmost Mariana Arc
Julia M. Ribeiro, Robert J. Stern, Fernando Martinez, Osamu Ishizuka, Susan G. Merle, Katherine Kelley, Elizabeth Y. Anthony, Minghua Ren, Yasuhiko Ohara, Mark Reagan, Guillaume Girard and Sherman Bloomer
マリアナ弧南端部前弧リフトの地質構造発達史
Julia M. Ribeiro・Robert J. Stern・Fernando Martinez・石塚 治・Susan G. Merle・Katherine Kelley・Elizabeth Y. Anthony・Minghua Ren・小原泰彦・Mark Reagan・Guillaume Girard・Sherman Bloomer
マリアナ弧南端部は,新第三紀後半にはマリアナトラフの拡大により伸張場におかれ,3.7-2.7 Maには玄武岩マグマが活動した.現在この地域,すなわち南東マリアナ前弧リフト(SEMFR)は,浅いスラブ上の水和した前弧リソスフェアにのる伸張場である.前弧域では通常マグマは生産されにくいと考えられるが,SEMFRでは海底拡大に伴い,島弧や背弧海盆にみられるマグマに類似する化学的特徴を持つマグマが,広く活動したことが明らかになった.このマグマは,スラブ由来の流体が付加された枯渇したマントルの減圧融解により,高い部分溶融度で深さ23 ± 6.6 km,1239 ± 40°C程度で生産されたと見積もられる.現在SFMERでは非マグマ的な構造運動が継続している.
Key Words: forearc rift, Mariana arc, seafloor spreading, subduction zone.
3. Detrital anisotropic grandite garnet as an indicator of denudation level of Permian volcanic arc in the provenance of the South Kitakami Belt, Northeast Japan
Makoto Takeuchi
東北日本,南部北上帯の後背地のペルム紀火山弧の削剥レベル指標としての光学的異方性を示す砕屑性グランダイト
竹内 誠
南部北上帯の中部ペルム系〜上部三畳系中の砕屑性ザクロ石はほとんどがグランダイトからなり,そのうち光学的異方性を示すものの割合は,ペルム紀〜中期三畳紀において増加し,後期三畳紀にかけて減少する.これらのグランダイトはスカルン起源のものと推定される.スカルンの発達では,初期のマグマの貫入による接触変成作用で岩体の周囲広範囲で光学的等方性のグランダイトが形成され,中期の岩体冷却時や後期の熱水期で貫入岩体の近傍で割れ目などに沿って光学的異方性を示すグランダイトが形成される.光学的異方性を示す砕屑性グランダイトの増減は,このようなスカルンを伴う火山弧の累進的削剥を示している.光学的異方性を示すグランダイトの割合から火山弧の削剥量を見積もる方法は,東アジアのペルム紀古地理や地殻変動を明らかにする上で役立つものである.
Key Words: grandite, oscillatory zoning, Permian, sandstone, sector twinning, skarn, Triassic, uplift, volcanic arc.
4. U–Pb zircon age from the radiolarian-bearing Hitoegane Formation in the Hida Gaien Belt, Japan
Manchuk Nuramkhaan, Toshiyuki Kurihara, Kazuhiro Tsukada, Yoshikazu Kochi, Hokuto Obara, Tatsuya Fujimoto, Yuji Orihashi and Koshi Yamamoto
飛騨外縁帯一重ヶ根層の含放散虫珪長質凝灰岩から得られたU-Pbジルコン年代について
Manchuk Nuramkhaan・栗原敏之・束田和弘・高地吉一・小原北士・藤本辰弥・折橋裕二・山本鋼志
シルルーデボン紀の放散虫年代については,まだ未確定の部分が多い.その点において,放散虫化石を含む珪長質凝灰岩中のジルコン同位体年代は,放散虫化石年代決定の上で,きわめて有効なツールとなる.著者らは,飛騨外縁帯一重ヶ根層のPseudospongoprunum tauversi と Futobari solidus–Zadrappolus tenuis群集の境界に挟まれる珪長質凝灰岩層のジルコンについて,LA-ICP-MSを用いて年代測定を行った.その結果,426.6 ± 3.7 Maの年代値が得られ,両群集の境界はLudlowian 〜 Pridolianであることが明らかとなった.F. solidus–Z. tenuis群集の年代の上限については,408.9 ± 7.6 MaのジルコンSHRIMP年代が過去に黒瀬川帯より報告されているため,同群集のレンジはLudlowianもしくはPridolian 〜 Pragianである.
本結果は,一重ヶ根層の放散虫化石年代だけではなく,福地ー一重ヶ根地域全体のオルドビス〜ペルム紀の層序・古環境変遷復元にも大きく貢献する.オルドビスーシルル紀に活発であった苦鉄質〜珪長質火山活動は,前期デボン紀に次第にtropical lagoonに変化した.そして静穏なラグーン環境は,中期ペルム紀に再び苦鉄質火山活動の場に変化した.
Key Words: radiolarian biostratigraphy, Silurian, U–Pb LA-ICP-MS age.
5. New SHRIMP U–Pb zircon ages of granitic rocks in the Hida Belt, Japan: Implications for tectonic correlation with Jiamushi massif
Xilin Zhao, Jianren Mao, Haimin Ye, Kai Liu and Yutaka Takahashi
飛騨花崗岩類の新たなSHRIMPジルコンU-Pb年代:飛騨帯とJiamushi地塊との地質構造的関連
Xilin Zhao・Jianren Mao・Haimin Ye・Kai Liu・高橋 浩
飛騨帯の花崗岩類は古期及び新期花崗岩類に区分されており,立山地域の試料についてSHRIMPを用いてジルコンU-Pb年代を測定した.古期花崗岩(片麻状花崗岩)2試料は245±2及び248±5 Maを示し,新期花崗岩は197±3 Maを示した.また,珪長質片麻岩は330±6 Ma,243±8 Ma及び220 Maを示し,それらはそれぞれ,飛騨古期変成作用,古期花崗岩の貫入及びマイロナイト化作用の時期を示す.これらの年代,構成岩石,Sr-Nd同位体の性格から,飛騨帯は中央アジア造山帯東縁に位置するJiamushi地塊から分離したものと考えられる.
Key Words: Central Asian Orogenic Belt, Hida Belt, Jiamushi massif, SHRIMP U–Pb zircon dating.
6. Chronological and paleoceanographic constraints of Miocene to Pliocene ‘mud sea’ in the Ryukyu Islands (southwestern Japan) based on calcareous nannofossil assemblages
Ryo Imai, Tokiyuki Sato and Yasufumi Iryu
石灰質ナンノ化石群集に基づく中新世〜鮮新世の琉球列島‘泥海(島尻層群)’の年代層序学的・古海洋学的復元
今井 遼・佐藤時幸・井龍康文
琉球列島沖縄本島には,中新統〜更新統の島尻層群,更新統の知念層および琉球層群が分布する.島尻層群は主に泥岩と砂岩からなり,琉球層群は礁成石灰岩からなる.また知念層は,島尻層群と琉球層群との中間的な岩相を示す.この「泥海(島尻層群)」から「サンゴ海(琉球層群)」への岩相変化は,琉球列島の背弧海盆すなわち沖縄トラフの形成により,黒潮が背弧側へ流入したことに関連していると考えられている.我々は,沖縄本島南部で掘削された「南城R1(堀止深度2119.49 m)」の試料を用いて,島尻層群(豊見城層・与那原層)の石灰質ナンノ化石生層序の確立と石灰質ナンノ化石群集解析と岩相層序に基づいた後期中新世から後期鮮新世の古海洋環境復元を目的に研究を行った.その結果,4つの化石基準面が認定され,豊見城層は上部中新統(NN11〜NN12;CN9a〜CN10a–CN10b)に,与那原層は上部中新統から上部鮮新統(NN12〜NN16;CN10a–CN10b〜CN12)に対比されることが判明した.豊見城層および与那原層下部堆積時(>8.3〜5.3 Ma)は,低いコッコリス生産量とSphenolithus abiesの多産から,貧栄養環境であったと推定される.与那原層中部堆積時(5.3〜3.5 Ma)は,コッコリス生産量の増加およびsmall Reticulofenestra spp. の多産から,富栄養環境への変化が想定される.与那原層上部堆積時(3.5〜>2.9 Ma)は石灰質ナンノ化石の産出頻度が低いことより,再び貧栄養環境へ戻ったと考えられる.島尻層群の堆積相および底生有孔虫に関する先行研究の結果を併せて考察すると,以上の海洋環境の変化は堆積盆地の浅海化に起因すると結論される.
Key Words: biostratigraphy, calcareous nannofossil, Miocene, paleoceanography, Pliocene, Ryukyu Islands, Shimajiri Group.
[Review Articles]
7. Origins of Birimian (ca 2.2 Ga) mafic magmatism and the Paleoproterozoic ‘greenstone belt’ metallogeny: a review
Frank K. Nyame
約22億年前のBirimian苦鉄質火成活動の起源と古原生代の緑色岩帯の金属鉱床生成
古原生代の苦鉄質火成活動の記録が保存されている西アフリカ盾状地のBirimianは,従来,玄武岩質〜安山岩質の岩石が占めていると多くの研究者によって記述されてきた.しかしながら,この火成岩帯の起源や付随する鉱床の成因に特徴に関して,まだ議論が続いている.本総括論文では,関連する従来の研究を概括し,Birimianの高品質の金属鉱床(マンガン鉱床や金鉱床等)が苦鉄質岩類に伴って産出すること自体がその成因に示唆を持つことを提案する.
Key Words: Birimian, greenstone belt, metallogeny, West African Craton.
[Research Articles]
8. Late Triassic ammonoid Sirenites from the Sabudani Formation in Tokushima, Southwest Japan, and its biostratigraphic and paleobiogeographic implications
Yasuyuki Tsujino, Yasunari Shigeta, Haruyoshi Maeda, Toshifumi Komatsu and Nao Kusuhashi
徳島県木頭地域の寒谷層からの後期三畳紀アンモノイドSirenitesの産出とその生層序学的・古生物地理学的意義
辻野泰之・重田康成・前田晴良・小松俊文・楠橋 直
徳島県木頭地域に分布する寒谷層上部よりSirenites senticosusが発見された.この種は,後期三畳紀の前期カーニアン期後期の指標化石であるAustrotrachyceras austriacumと共産することが知られており,同地域の寒谷層上部は下部カーニアン階上部に対比できる.S. senticosusの分布は,主にテチス海を中心に知らており,日本の後期三畳紀アンモノイド類は,低緯度地域のテチス型動物群と類似性が高い.一方,日本の同時代の二枚貝類は,高緯度地域のボレアル型動物群と類似性があることがすでに指摘されている.この結果は,日本の後期三畳紀のアンモノイド類と二枚貝類の古生物地理的傾向が明らかに異なることを示している.
Key Words: ammonoid, Carnian, Kurosegawa Belt, Sabudani Formation, Sirenites senticosus, Southwest Japan, Tethyan affinities, Tokushima, Triassic.
▼▼ Vol. 22-4はこちら ▼▼
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iar.2013.22.issue-4/issuetoc
会員の方は無料で閲覧出来ます(要ログイン)。
ログイン方法はこちらから>>> https://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
野外見学,調査,試料採取における注意喚起
野外見学,調査,試料採取における注意喚起
科学論文では,学説の検証可能性を保証することが重要です.そのため,地質学雑誌掲載論文には,重要な証拠となった試料がどこで得られたかを示しているものがあります.言うまでもないことですが,見学や採取を行う場合,各自の責任において地権者や関係官庁への連絡と許可の取得の必要があることにご注意下さい.
詳しくは,下記をご覧ください.
「野外調査において心がけたいこと」
国立・国定公園や史跡・名勝・天然記念物、あるいは一般的な露頭における調査上の注意点
「安全のしおり(2014年鹿児島大会 巡検案内書より)」
巡検や野外調査における安全上の注意点と自然保護に関する注意点
「巡検案内書を頼りに野外調査へ出かける方へ」
露頭での調査や試料採取にあたっての注意点(「野外調査において心がけたいこと」から一部抜粋)
「巡検時等における車両運行指針」の策定に関して(2017.4.8)
一般社団法人日本地質学会
Island Arc 日本語要旨 2013. vol. 22 Issue 3 (September)
Vol. 22 Issue 3 (September)
特集号
Zircon multichronology: Fission-track, U-Pb, and combined fission-track–U-Pb studies
Guest Editors: Hideki Iwano, Yuji Orihashi, Masatsugu Ogasawara and Takafumi Hirata
ジルコンとマルチクロノロジー:フィッション・トラック法とU-Pb法,およびそれらを組み合わせた年代研究
岩野英樹・折橋裕二・小笠原正継・平田岳史
1. Preface
Hideki Iwano, Yuji Orihashi, Masatsugu Ogasawara and Takafumi Hirata
序文
岩野英樹・折橋裕二・小笠原正継・平田岳史
ウランやトリウムを含むジルコンは,同一粒子に対しU-Pb法,フィッション・トラック(FT)法,(U-Th)/He法など複数の手法(マルチクロノロジー)が適用可能な対象のひとつである.ジルコンはほとんどの岩石に普遍的に存在し,物理的・化学的安定性が高い(風化に強い)ことから,900℃という高い閉鎖温度のU-Pb法を使うことで,地球形成初期にまで年代測定が展開できる.閉鎖温度の低いFT法を用いれば200-300℃の,(U-Th)/He法ではさらに低い熱年代情報も得られ,堆積盆解析や大地形の上昇・削剥といった地形発達史,地層や構造運動解明などに優れている.本特集はFT法とU-Pb法を使った最新の方法論的研究,年代測定に必要不可欠な標準試料,そしてFT法とU-Pb法を組み合わせた熱年代学応用研究例を紹介する.
2. A review of the present state of the absolute calibration for zircon fission track geochronometry using the external detector method
Tohru Danhara and Hideki Iwano
外部ディテクターを用いたジルコンフィッション・トラック年代測定における絶対校正のレビュー
檀原 徹・岩野英樹
外部ディテクター法を用いたジルコンのフィッション・トラック(FT)年代測定において,ここ20年間継続された絶対年代較正に関する研究をレビューした.潜在FT全長とエッチングされるFT長との関係が考慮されたことで正確な絶対較正FT年代式が導かれた.年代の異なる10個の年代標準試料の実験結果から,絶対較正FT年代が次の3つのパラメータを基準として成り立つ: (1) 238U 自発核分裂壊変定数(λf)は8.5 × 10-17 a-1, (2) 熱中性子線量ガラスIRMM540の使用,(3) ジルコン外部面と白雲母ディテクター間の実験定数 は[GQR] = 1.35.FT法による絶対ウラン濃度データを使い, ウラン定量を質量分析計で行う新しいFT年代測定に向けたシミュレーションも示した.FT年代測定法は,年代標準試料に基づいた年代較正とともに,他の年代測定に依存しない独立した年代較正が成り立つと著者らは主張する.
Key Words: absolute calibration, dating, fission track, uranium concentration, zircon.
3. Zeta equivalent fission-track dating using LA-ICP-MS and examples with simultaneous U–Pb dating
Noriko Hasebe, Akihiro Tamura and Shoji Arai
ゼータ法に対応したLA-ICP-MSによるフィッショントラック年代測定とウラン-鉛年代測定の同時実施例
長谷部徳子・田村明弘・荒井章司
FT年代測定に必要なウラン濃度の分析にLA-ICP-MSを利用すると, U-Pb年代測定に必要なデータも同時に収得できる.FT年代式には不確定な係数がいくつかあるため,年代が既知の標準試料を利用するゼータ較正を施すよう国際的に勧告されている.本報告では,FT年代測定とU-Pb年代測定を同時に行うためのLA-ICP-MSのデータ取得法や,ゼータ法に対応するFT年代式およびその統計的取り扱いについて提案を行う.年代標準試料を分析し実験的に決定したNIST SRM610ガラスに対するゼータ較正値は,最適な係数を用いて計算で求めたゼータ較正値とおおむね一致した.238U-206Pb年代決定においても, NIST SRM610ガラスを外部標準試料として年代標準試料の分析を行い,補正係数0.920±0.034を求めた.実際に仁左平デイサイトのジルコンの年代決定を行ったところ,同一粒子を利用したFT法およびU-Pb法による同時年代決定で,推奨値である22 Maを両手法で得ることができた.
Key Words: Fission-track, LA-ICP-MS, U–Pb, zeta calibration.
4. Potential Mesozoic reference zircon from the Unazuki plutonic complex: geochronological and geochemical characterization
Kenji Horie, Mami Takehara, Yoshimitsu Suda and Hiroshi Hidaka
宇奈月深成岩体から採取した中生代ジルコンの標準試料としての可能性:年代学的・地球化学的特徴
堀江憲路・竹原真美・隅田祥光・日高 洋
マイクロビームを用いたU-Pbジルコン年代測定を行う上で標準ジルコンは不可欠である.本研究では中生代の標準ジルコンとして,飛騨帯の北東部,宇奈月地域の音谷石英閃緑岩から回収したOT4ジルコンを提案する.OT4ジルコンの分析は高感度高分解能イオンマイクロプローブ(SHRIMP II)で行った.OT4ジルコンは組成累帯構造を示し,粒子によってはUとThの含有量が比較的高い(それぞれ988 ppmと1054 ppm).207Pbで始原鉛を補正した206Pb/238U年代は均質であり,その重み付き平均は191.1 ± 0.3 Ma (95% confidence limit)であった.OT4ジルコンは高い結晶度を保持しており,均質な希土類元素存在度パターンとHf濃度(8651 ±466 ppm)は,OT4ジルコンが二次的な影響を受けていないことを示唆する.均質なHf濃度に加え,ジルコンTi温度計(733 ± 34 ℃)とZr飽和温度(728℃)が良い一致を示すことから,OT4ジルコンは比較的短時間に結晶化したと考えられる.OT4ジルコンには,マイクロビームU-Pb年代分析を行う上で十分な量の206Pb(>2 ppm)と207Pb (>0.1 ppm)が含まれており,中生代の標準ジルコンとして可能性を秘めている.
Key Words: Hf content, quartz diorite, SHRIMP, Ti thermometry, U–Pb dating, Unazuki, zircon.
5. SHRIMP U–Pb age of SoriZ93 zircon from the Sori Granodiorite, Northeast Japan: a potential reference zircon of Late Cretaceous age
Masatsugu Ogasawara, Mayuko Fukuyama, Kenji Horie, Tomoaki Sumii, Mami Takehara and Masafumi Sudo
沢入花崗閃緑岩から分離されたジルコンSoriZ93のSHRIMP U-Pb年代:白亜紀後期の年代を持つ標準試料としての可能性
小笠原正継・福山繭子・堀江憲路・角井朝昭・竹原真美・周藤正史
足尾山地の沢入花崗閃緑岩から黒雲母年代標準試料(SORI93)を調整した際の残試料より,ジルコンを分離濃集した(SoriZ93).SHRIMPによるU-Pb分析測定を行い,白亜紀後期の年代を持つ標準試料としての検討を行った.沢入花崗閃緑岩からは岩石粉末標準試料JG-1が調製され,微量成分組成や同位体比分析の標準試料として広く用いられている.黒雲母とジルコンが分離された岩石試料はJG-1が採取された採石場と同一の場所から得られた.SoriZ93ジルコンの結晶の大きさや均質性は良好で年代標準試料としての要件を満たしている.206Pb/238U 年代は93.9 ± 0.6 Maであり,黒雲母K-Ar年代よりも130万年程度大きいが,これは両年代系の閉鎖温度の違いによるものである.白亜紀後期の火成岩の年代測定を行う時に,分析システムの検証に用いられる2次的標準試料として用いることが可能である.
Key Words: Late Cretaceous, SHRIMP U–Pb dating, Sori Granodiorite, SoriZ93, zircon standard.
6. Geological framework and fission track dating of pseudotachylyte of the Atotsugawa Fault, Magawa area, central Japan
Hideo Takagi, Kosuke Tsutsui, Hiroyoshi Arai, Hideki Iwano and Tohru Danhara
跡津川断層真川露頭のシュードタキライトの産状とフィッショントラック年代
高木秀雄,・筒井宏輔・新井 宏嘉・岩野英樹・ 檀原 徹
跡津川断層真川露頭で発見されたシュードタキライト(以下PST)脈と周辺の母岩(飛騨花崗岩)中のジルコンフィッショントラック(以下FT)年代測定を実施した.PST脈3試料のFT年代は48.6–50.2, 55.1, 60.9 Ma,母岩は56.1-60.1 Maであるのに対し,同じ母岩の白雲母K−Ar年代は149Maであった.トラック長解析によると,上記2番目のPST試料に短縮化したトラックを含むジルコンが存在し,年代に複数のピークが認められることなどから混合分布の分離を試みたところ,そのピーク年代として52.5Maという値が得られた.母岩の若いFT年代は地下に潜在する古第三紀花崗岩の貫入による熱的影響が示唆され,跡津川断層は50Ma頃から活動していた.
Key Words: Atotsugawa Fault, fission track age, pseudotachylyte, zircon.
7. Rift-related origin of the Paleoproterozoic Kuncha Formation, and cooling history of the Kuncha nappe and Taplejung granites, eastern Nepal Lesser Himalaya: a multichronological approach
Harutaka Sakai, Hideki Iwano, Tohru Danhara, Yutaka Takigami, Santa Man Rai, Bishal Nath Upreti and Takafumi Hirata
大陸リフトに起源を持つ前期原生代のクンチャ層と, 東ネパールのレッサーヒマラヤを覆うクンチャ・ナップとタプレジュン花崗岩の熱履歴:マルチ年代学的アプローチ
酒井治孝・岩野英樹・檀原 徹・瀧上 豊・Santa Man Rai・Bishal Nath Upreti・平田岳史
レッサーヒマラヤを南北120 kmに亘って広く覆うクンチャ・ナップの起源と熱履歴を明らかにするために,東ネパールのタプレジュン・ウインドウにおいて地質調査を行い,クンチャ層とタプレジュン花崗岩のジルコン,アパタイト,雲母についてマルチ年代学的研究を行った.クンチャ層に貫入した花崗岩体のジルコンのU-Pb年代は1852±24 Maと1877±21 Ma, 白雲母のAr-Ar年代は約1650 Maを示した.しかしジルコンとアパタイトのフィッション・トラック(FT)年代は,各々6.2〜4.8 Ma,2.9〜2.1 Maを示した.クンチャ層の結晶片岩中の砕屑性ジルコンのU-Pbインターセプト年代は1888±16 Maを示し,これはクンチャ層下部の堆積年代を示すものと考えられる.同じ試料中の砕屑性ジルコンとアパタイトのFT年代は, 各々5.4 Maと2.5 Maを示す.砕屑性ジルコンには16億年より若いものは全く認められなかった.これはクンチャ・ナップを構成する岩石が16億年前以降,中新世のヒマラヤ造山期まで熱的なイベントを被ってないことを示す.
ハイヒマラヤ結晶質岩ナップ中の片麻岩, およびレッサーヒマラヤの眼球片麻岩中のジルコン粒子は,17 Maに鉛ロスを示す熱イベントを被っており,その影響はタプレジュン花崗岩体の周縁にも及んでいる.
クンチャ層とその上位のカリガンダキ累層群,およびタプレジュン花崗岩は,カナダ北西部のウオップメイ造山帯中のコロネーション累層群とヘプバーン貫入岩体に対比される.この二つの累層群は大陸リフトとそれに引き続く非活動的大陸縁辺に堆積したものと解釈される.
すべてのジルコンとアパタイトのFT年代は, クンチャ・ナップとその上を覆うハイヒマラヤ結晶質岩からなるナップの双方が,ナップの前縁から北方に向かって側方に冷却したことを示す.ナップの前縁部からナップ中央部に位置するタプレジュンまでの間では,中〜後期中新世の間に,ジルコンのFTの閉鎖温度である240℃の等温線が,約10mm/年の平均速度で北方に後退したことが分かった.
Key Words: fission-track age, Kali Gandaki Supergroup, Kuncha nappe, Nepal Himalaya, Taplejung window, thermochronology, U–Pb age, zircon.
8. Emplacement of hot Lesser Himalayan nappes from 15 to 10 Ma in the Jumla–Surkhet region, western Nepal, and their thermal imprint on the underlying Early Miocene fluvial Dumri Formation
Harutaka Sakai, Hideki Iwano, Tohru Danhara, Takafumi Hirata and Yutaka Takigami
西ネパール,ジュムラ-スルケット地域における,15〜10 Maのホットなレッサーヒマラヤ・ナップの前進,およびナップ直下の前期中新世の河川成デュムレ層の熱変成
酒井治孝・岩野英樹・檀原 徹・平田岳史・瀧上 豊
弱く変成した前期中新世の河川堆積物デュムレ層,およびその上を覆うクンチャ・ナップとレッサーヒマラヤ結晶質岩ナップのマルチ熱年代学的研究を行い,その変成作用の時期と起源を明らかにすると同時に,これらのナップの前進と冷却の履歴を明らかにすることができた.
デュムレ層中の砕屑性ジルコンのU-Pb年代分布のピークは,約10億年前と5〜6億年前にあるが,同じジルコン粒子のフィッション・トラック(FT) 年代測定の結果は,11〜10 Maに熱的イベントを受けたことを示す.クンチャ層の上に重なるノーダラ・コーツァイトの砕屑性ジルコンのU-Pb年代は17億年より古いことを示すが,同じジルコンのFT年代は9.5 Maを示す.デュムレ層とクンチャ層の砕屑性ジルコンのU-Pb年代分布の差は,前期中新世にデュムレ層が堆積した時にはクンチャ層は地表に露出してなかったことを物語っている.
結晶質岩ナップ基底のMain Central Thrust (MCT) 直下の剪断帯, MCT zoneの両雲母ガーネット片岩中の砕屑性ジルコンのU-Pb年代は,6億年より古い年代を示すが,同じジルコンのFT年代は7.8 Maを, 白雲母のAr-Ar年代は19 Maを示す.よってデュムレ層の変成作用を起こした熱は,その上を覆ったナップに由来するものと解釈される.従って,デュムレ層が熱変成作用を被り, 240 ℃以下に冷却した約10 Ma以前に,ナップは現在の位置に到達していたことを示す.
クンチャ・ナップの前縁部に貫入したパラジュール・コーラ花崗岩のジルコンのU-Pb年代は18.9億年前を示すが,そのFT年代は前期中新世に熱的イベントを被ったこと,また14.7 Maには240 ℃以下に,10.3 Maには100 ℃以下に冷却したことを示す.これらの熱年代学的データは,クンチャ・ナップの先端部が15〜14 Maに地表に露出し,直ぐに冷却したが,ナップの内部は120 km余り前進する間,一貫してホットな状態だったことを示す.シワリーク層群と現在の河川の堆積物から報告されていた,砕屑性ジルコンやアパタイトの若いFT年代は,ホットな変成岩ナップの前進に伴う下盤のレッサーヒマラヤ堆積物の熱変成作用に由来するものと判断される.
Key Words: Dumri Formation, fission-track ages, Kuncha nappe, Lesser Himalaya, MCT zone, Nepal Himalaya, U–Pb ages.
9. An inter-laboratory evaluation of OD-3 zircon for use as a secondary U–Pb dating standard
Hideki Iwano, Yuji Orihashi, Takafumi Hirata, Masatsugu Ogasawara, Tohru Danhara, Kenji Horie, Noriko Hasebe, Shigeru Sueoka, Akihiro Tamura, Yasutaka Hayasaka, Aya Katsube, Hisatoshi Ito, Kenichiro Tani, Jun-ichi Kimura, Qing Chang, Yoshikazu Kouchi, Yasuhiro Haruta and Koshi Yamamoto
U-Pb年代測定用二次スタンダードOD-3ジルコンの研究室間評価
岩野英樹・折橋裕二・平田岳史・小笠原正継・檀原 徹・堀江憲路・長谷部徳子・末岡 茂・田村明弘・早坂康隆・勝部亜矢・伊藤久敏・谷 健一郎・木村純一・Qing Chang・高地吉一・春田 泰宏・山本 鋼志
U-Pb年代測定用マルチ粒子の二次スタンダードとして,漸新世の年代をもつ川本花崗閃緑岩三原岩体のジルコン(OD-3)を配布し,研究室間比較調査を行った.11の年代学研究室が参加し計23個の年代値が報告された.U-Pb年代は2つの手法(高感度イオンマイクロプローブ法とレーザーアブレーションICP質量分析法)で測られ,すべての年代値は良い一致を示し,加重平均238U–206Pb年代は33.0 ± 0.1 Ma (2σ)となった.U-Pb年代データには古い年代粒子やU-Pb年代の不均質は示されなかった.フィッション・トラック(FT)年代から加重平均32.6 ± 0.6 Ma (2σ)が得られた.U-Pb法とFT法には閉鎖温度に差があるにも関わらず両年代が一致することは,OD-3ジルコンが比較的急冷したのち再加熱を被っていないことを示唆する.OD-3は新生代ジルコンのU-Pb年代研究を行ううえで有用かつ信頼性のある二次スタンダードとなりうることが示された.
Key Words: Kawamoto Granodiorite, secondary standard, U–Pb dating, zircon.
通常論文
[Research Articles]
1. Instantaneous paleomagnetic record from the Miocene Kozagawa Dike of the Kumano Acidic Rocks, Kii peninsula, Southwest Japan: cautionary note on tectonic interpretation
Hiroyuki Hoshi, Naohiro Kamiya and Yuu Kawakami
西南日本,紀伊半島の熊野酸性岩類古座川岩脈から得られた「瞬間的な」古地磁気記録:テクトニクス解釈の注意すべき例
星 博幸・神谷直宏・川上 裕
熊野酸性岩類(中期中新世の火山-深成複合岩体)の時計回りに偏向した古地磁気方位は,日本海拡大に関連した西南日本の時計回り回転運動を示すものと考えられてきた.しかし,この方位は約14.3 Maの通常時とは異なる(地磁気逆転あるいはエクスカーション時の)古地磁気状態を示すものであり,回転運動を示すものではないと筆者らは結論する.熊野酸性岩類南部の古座川岩脈を構成する花崗斑岩は安定な残留磁化を持つ.10地点で決定された逆帯磁の残留磁化方位は集中度が非常に高い.この方位は南から時計回りセンスに約40°偏向し,伏角が深い.この残留磁化は地質学的にごく短い期間の(瞬間的な)古地磁気を記録したものである可能性が高い.また,古座川岩脈の古地磁気方位は熊野酸性岩類の主体をなす花崗斑岩ラコリス状岩体(北岩体,南岩体)の方位と一致しない.この不一致は残留磁化の獲得タイミングが異なっていたためと推定される.
Key Words: paleomagnetism, rock magnetism, Kozagawa Dike, Kumano Acidic Rocks, Middle Miocene, Kii peninsula, Southwest Japan, tectonic rotation, instantaneous paleodirection.
2. Textures and processes of laminated travertines formed by unicellular cyanobacteria in Myoken hot spring, southwestern Japan
Tomoyo Okumura, Chizuru Takashima and Akihiro Kano
西南日本妙見温泉に発達する縞状トラバーチンの単細胞シアノバクテリアによる組織形成プロセス
奥村知世・高島千鶴・狩野彰宏
鹿児島県妙見温泉に発達するトラバーチンの表面組織と温泉水化学組成の28時間連続観測結果は,Thermosynechococcus elongatus BP-1と近縁の中等度好熱性(〜55℃)単細胞シアノバクテリアの日周期活動(光合成・走光性)がサブミリメートルオーダーの縞組織を作ることを示した.このトラバーチンの縞組織は,暗色のアラゴナイト層と,明色のカルサイト層からなる.暗色層のアラゴナイトは,昼間,シアノバクテリアがトラバーチン表面へ移動して作るバイオフィルム内で,針型結晶の放射状凝集体として晶出していた.一方,暗色のカルサイト層は,日没後からバイオフィルム上で沈殿する菱形結晶のデンドライト構造により形成されていた.温泉水の物理化学条件は安定していたので,炭酸カルシウムの多形変化は,シアノバクテリアが分泌する細胞外高分子物質の様な微生物的要因に関係している.トラバーチンが水面まで成長すると,頂部にやや低温(25−40℃)な環境が発達し,そこではフィラメント状シアノバクテリアがマットを作る.妙見温泉のトラバーチンで見られた縞組織に関わる地球微生物学的プロセスや,微生物群集の環境条件への応答は,同様の組織を持つ太古の炭酸塩堆積物中を理解するための新たな知見となりうる.
Key Words: aragonite, biofilm, calcite, cyanobacteria, daily lamination, moderate thermophiles, travertine.
出版物
学会出版物
◆ 地質学雑誌:
The Journal of the Geological Society of Japan
◆ 日本地質学会News:
News The Journal of the Geological Society of Japan
◆ 学術大会講演要旨:
Ann. Meet. Geol. Soc. Japan, Abstr
◆ 学術大会巡検案内書:
Excursion Guidebook, Geol. Soc. Japan,
◆ Island Arc
◆ 地質学論集(2004年 廃止)
The Memoir of the Geological Society of Japan
◆ リーフレット
Leaflet
◆ 電子書籍シリーズ
e-book
◆ その他
others
出版物在庫案内
各種投稿案内
関連出版物:The Geology of Japan(正誤表もこちらから)
電子書籍_地学を楽しく
▶日本地質学会から電子書籍を出版しませんか
電子書籍シリーズ
「地学を楽しく!:ジオパーク・ジオツアー・地学オリンピック」
[Kindle版/PDF版]
吉田 勝,天野一男,中井 均 編集
一般社団法人日本地質学会 発行
紙の本の長さ(目安):約260ページ,価格:¥1,380,ISBN 978-4-907604-00-4
ご購入は,
Kindle版>Amazon Kindleストアから↓↓
http://www.amazon.co.jp/dp/B00HFIK1WW
*Kindle版は,Amazonが販売する電子ブックリーダー端末(Kindle)か,スマートフォン、タブレットなどで読むことができます。
PDF版>学会オンラインストア『ジオストア』から↓↓
*PDF版は各章ごとの分割販売も行っています!
http://geosociety2.sakura.ne.jp/store3/ec/
【目次】
はじめに
第1章 ジオツアーとガイドブック(城ヶ島たんけんマップ/日曜地学ハイキング/ヒマラヤのジオツアーとガイドブック/ヒマラヤジオエクス―ションで思ったこと)
第2章 ジオパーク(室戸ジオパークと防災学習/山陰海岸ジオパークにおけるジオツアーと博物館の役割/ジオパークにおけるツイッターの活用を考える/田淵ジオサイト(中・下部更新統境界の国際模式地候補地)とジオパーク/ネパールヒマラヤのジオパーク計画)
第3章 地学オリンピック(日本地学オリンピック大会に参加して ―高校教員の記録―/国際地学オリンピック試験問題の特徴について/地学教育の国際動向をみる)
【はじめに】より抜粋
本書は「ジオツアーとガイドブック」,「ジオパーク」,「地学オリンピック」の3章で構成しました.各章とも,日本或いは国外のいろいろなところでの著者らの実践に基いた報告数編で構成されています.これらの内容については,各章の初めに編集者による内容紹介があります.2011年3月11日の東北東日本大震災は,地学の重要性を如実に示す事件でした.野外事実を無視した理論と恣意的なデータ操作に基いた将来の津波の規模に対する想定が,いかに自然からかけ離れたものであったか,自然に忠実にその歴史を追う学問−地学−がいかに重要であり,自然の姿を反映するものであるかが示されたと言えるでしょう.
本書が地学の面白さと重要性を国民各層に広く知ってもらえるよう,そして片隅に置かれて来た地学教科の復権に僅少でもお役に立てば,編者らとして望外の幸せです.
講演要旨
学術大会講演要旨
要旨集: バックナンバー
残部のあるものは,本会事務局にて購入できます。
◆ 在庫案内のページへ
下記より,PDFで閲覧可能です。
※災害調査等の速報的な内容を主とするため,準備・受付期間が短く,要旨集(冊子体)への収録ができない「緊急展示」の講演要旨も閲覧できます。
◆ J-STAGE(1970〜,緊急展示[2004〜])
http://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosocabst/-char/ja/
Island Arc 日本語要旨 2014. vol. 23 Issue 3 (September)
Vol. 23 Issue 3 (September)
通常論文
[Research Articles]
1. Triassic warm subduction in northeast Turkey: Evidence from the Ağvanis metamorphic rocks
Gültekin Topuz, Aral I. Okay, Rainer Altherr, Winfried H. Schwarz, Gürsel Sunal and Lütfi Altınkaynak
トルコ北東部における三畳紀の暖かい沈み込み:Ağvanis変成岩類からの証拠
テーチス海域におけるペルム紀〜三畳紀の沈み込み史では付加体形成は希であり,主に北西トルコからチベットで起きている.本論では北部トルコに分布する三畳紀の付加体であるAğvanis変成岩類の地質,岩石,年代データを報告する.Ağvanis変成岩類は長さ20 km,幅6 kmで南南東—北北西走向の菱形地累をなし,東PontidesとMenderes-Taurusブロックの衝突帯に近接した北アナトリア(Anatolia)活断層によって画されている.変成岩類は主として緑色片岩相〜緑廉石角閃岩相のメタベイサイト,千枚岩,大理石,少量のメタチャートと蛇紋岩からなり,海洋起源の岩石種と大洋島玄武岩,中央海嶺玄武岩,島弧ソレアイトの特徴を示すメタベイサイトの存在から付加体が変成作用を受けたものと解釈される.これらの岩石には始新世初期の石英閃緑岩,優白質花崗閃緑岩,デイサイトの岩頸や岩脈が貫入している.変成条件は470–540°C,∼0.60–0.90 GPaと推定される.接触変成帯の外側から採取したフェンジャイト—白雲母についての段階的な40Ar/39Ar年代測定から180-209 Maをピークとする年代分布が得られ,変成作用が209 Ma以前に起きたことを示唆する.すなわち,Ağvanis変成岩類は北東トルコにおける三畳紀後期かそれよりやや古い沈み込みを表わしている.推定された温度圧力条件は定常状態にある平均的な沈み込み帯よりも高温であり,現在のカスケードのような高温沈み込み帯であったとするのが最も説明しやすい.これに対して始新世初期の石英閃緑岩岩頸の周囲の接触変成鉱物組合せは,現在の浸食面が始新世初期には深さ14 kmにあったことを示唆しており,変成岩類が再度埋没したことを示す.白雲母のピークAr-Ar年代が一部乱されていることは,埋没と火成活動による加熱によって起きたと考えられ,東PontidesとMenderes–Taurusブロックの間の衝突によって起きた衝上運動に関係しているのであろう.
Key Words: 40Ar/39Ar dating;Ağvanis;Eastern Pontides;metamorphism;thermobarometry;Triassic accretionary complex
2. Age of the Taishu Group, southwestern Japan, and implications for the origin and evolution of the Japan Sea
Takashi Ninomiya, Shoichi Shimoyama, Koichiro Watanabe, Kenji Horie, Daniel J. Dunkley and Kazuyuki Shiraishi
長崎県対馬に分布する対州層群の年代とその意義
二宮 崇・下山 正一・渡邊 公一郎・堀江 憲路・Daniel J. Dunkley・白石 和行
日本海南西部,対馬に分布する対州層群は,層厚5000m以上の海成層で,日本海拡大期の情報を供給する重要な地層と考えられている.その年代は,前期始新世から前期中新世まで,ゆっくり堆積した地層と考えられてきた.本研究では,対州層群の岩相層序の再検討を行うとともに,最下部,下部・中部境界,それに最上部の凝灰岩の3試料から,ジルコンを抽出し,SHRIMPによる U–Pb年代測定をおこなった.その結果,対州層群が,17.9–15.9 Maの短期間に急速堆積したこと,対州層群は日本海沿岸に広く分布する同時期の多くの地層群と対比できることが明らかになった.これらの結果は,日本海および日本列島形成史を考える上で重要な知見である.
Key Words: early to middle Miocene;Japan Sea;SHRIMP U–Pb dating;Taishu Group
3. Geochemistry and petrogenesis of the Cretaceous A-type granites in the Laoshan granitic complex, eastern China
Quanshu Yan and Xuefa Shi
中国東部ロウ山(Laoshan)複合花崗岩体中の白亜紀Aタイプ花崗岩類の地球化学および成因
南北中国地塊間の三畳紀縫合帯の東側に分布するロウ山花崗岩体の後衝突期花崗岩について主要・微量元素組成,Sr, Nd, Pb同位体組成を測定した.花崗岩類はアルカリ岩質のAタイプであり,より詳しくはA1花崗岩に細分される.微量元素組成は大洋島玄武岩とエンリッチした中央海嶺玄武岩の中間的な特徴を示し,結晶分化によりBa, Sr, P, Tiに枯渇し,スラブ流体の付加によりCs, Rb, Th, Uに富む.ロウ山花崗岩類の同位体組成はエンリッチしたマントル(EMI)と下部地殻物質の混合を示す.ロウ山A1花崗岩類はEMI的なデラミネートしたエクロジャイト起源物質(沈み込んだ中生代太平洋スラブ流体による付加を受けた)と同地域に先行するIタイプ花崗岩の融け残りグラニュライトあるいは変成岩からなる下部地殻物質の混合によって生じたと考えられる.混合マグマは主にアルカリ長石の分別を経てロウ山花崗岩体中にAタイプ花崗岩として定置した.
Key Words: A-type granites;Jiaodong Peninsula;Laoshan granitic complex;petrogenesis
4. Migration of a volcanic front inferred from K–Ar ages of late Miocene to Pliocene volcanic rocks in central Japan
Hitomi Nakamura, Teruki Oikawa, Nobuo Geshi and Akikazu Matsumoto
関東山地火山岩年代から制約する火山フロントの移動とマントル構造の変化
中村仁美・及川輝樹・下司信夫・松本哲一
関東山地は,赤城—浅間—八ヶ岳—富士が形成する第四紀火山フロントの前弧域に位置し,新第三紀の火成岩を産する(兼岡ほか,1993).
本研究では,関東山地の地質学・層序学的調査を行い,火山岩生成年代を決定することで,火山フロントが移動した可能性を検討し,その原因としてのテクトニクスとマントル構造の変遷を議論する.
年代測定から,火山フロントの著しい西側への屈曲は,3Ma頃生じたことが分かった.北進していたフィリピン海プレートが,その東端のdead endで太平洋プレートの妨げを受け,オイラー極が北に移り,北西へ進路を変更した(高橋,2006).マントルウェッジはより冷たくなり,フィリピン海および太平洋スラブからの脱水はより深部へ移り,マグマの生成場は,より深部・高温である西側へと移る.その結果,マントル構造とメルト分布が大きく変化し,火山の分布が全体的に西に移り,火山フロントの移動に至ったと考えられる.
Key Words: central Japan;K–Ar ages;Philippine Sea Plate;subduction;volcanic front
▼▼ Vol. 23-3はこちら ▼▼
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iar.2014.23.issue-3/issuetoc
会員の方は無料で閲覧出来ます(要ログイン)。
ログイン方法はこちらから>>> https://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
Island Arc 日本語要旨 2014. vol. 23 Issue 1 (March)
Vol. 23 Issue 1 (March)
通常論文
[Research Articles]
1. Subsidence of the Miyako-Sone submarine carbonate platform, east of Miyako-jima Island, northwestern Pacific Ocean
Kohsaku Arai, Hideaki Machiyama, Shun Chiyonobu, Hiroki Matsuda, Keiichi Sasaki, Marc Humblet and Yasufumi Iryu
北西太平洋宮古島東方に発達する炭酸塩プラットフォームの沈降運動
荒井晃作・町山栄章・千代延 俊・松田博貴・佐々木圭一・Marc Humblet・井龍康文
北西太平洋宮古島東方に位置する宮古曽根炭酸塩プラットフォームの北西側斜面において詳細な地形マッピングおよび無人探査機ハイパードルフィンによる潜航調査を実施した.地形調査の結果,宮古曽根北西斜面には約140 m,330 m,400 m,680 mを外縁水深とするテラスが発達していることが判明した.また,琉球弧を横切る方向の断層運動によって形成されたと考えられる複数の北西—南東方向のリニアメントが形成されていることを確認した.無人探査機により水深519 mの斜面から121 mのプラットフォーム上までの潜航調査を行った.ビデオカメラの画像から,テラスの外縁と斜面の上部には固結した炭酸塩岩の露頭が存在するが,斜面下部は生物砕屑物からなる未固結の現世の粗粒砂に覆われていることが確認できた.露頭から採取した岩石からは,中〜後期更新世の年代値を示す石灰質ナンノ化石が産出した.これらの年代値や岩相は,採取した岩石が琉球弧に広く分布する琉球層群(琉球石灰岩)に相当することを示す.なお,潜航調査では,後期中新世〜前期更新世に形成された島尻層群に相当する珪質砕屑岩は見つからなかった.調査地域では,同一の堆積環境下で同じ年代に堆積したと考えられる炭酸塩岩が,西落ちの正断層によって西側に向かって水深を増している.宮古曽根炭酸塩プラットフォームの沈降運動はこの様な断層運動に伴うものである.沈降運動の開始を正確に議論することは難しいが,少なくとも0.265 Ma以降にもこの様な沈降運動が続いていることは確実である.
Key Words: bathymetric survey, calcareous nannofossils;Cenozoic, Ryukyu Group, Ryukyu Islands;subsidence, tectonics
2. Carbon isotope stratigraphy of Torinosu-type limestone in the western Paleo-Pacific and its implication to paleoceanography in the Late Jurassic and earliest Cretaceous
Yoshihiro Kakizaki and Akihiro Kano
古太平洋西部の鳥巣式石灰岩(ジュラ紀後期〜白亜紀初期)の炭素同位体比と古海洋学的な示唆
柿崎喜宏・狩野彰宏
ジュラ紀後期(キンメリッジアン期後期)から白亜紀初期(ベリアシアン期前期)にかけて古太平洋西部で堆積した鳥巣式石灰岩から,はじめて体系的な炭素同位体層序のプロファイル(δ13C 値)が示された.鳥巣式石灰岩のδ13C プロファイルは3区間の同位体異常にもとづき,同時期のテチス海のプロファイルとの地域間対比が可能である.さらにキンメリッジアン期後期の鳥巣式石灰岩のδ13C 値はテチス海のδ13C 値に比べて1‰ほど低く,その地域差はチトニアン後期に消失することが判明した.このことは,ジュラ紀後期に大陸移動に伴って海洋循環が活発になり,溶存無機炭酸のδ13C 値が汎世界的に均質になったことを示唆している.
Key Words: carbon isotope, chemostratigraphy, Japan, Late Jurassic to earliest Cretaceous, paleoceanography, Paleo-Pacific, Torinosu-type limestone
3. A new approach to develop the Raman carbonaceous material geothermometer for low-grade metamorphism using peak width
Yui Kouketsu1, Tomoyuki Mizukami, Hiroshi Mori1, Shunsuke Endo, Mutsuki Aoya, Hidetoshi Hara, Daisuke Nakamura and Simon Wallis
半値幅を用いた低変成度岩に適用可能な炭質物ラマン温度計の開発
纐纈佑衣・水上知行・森 宏・遠藤俊祐・青矢睦月・原 英俊・中村大輔・Simon Wallis
西南日本の6地域(四万十帯,秩父帯,黒瀬川帯,三波川帯,美濃–丹波帯)で採取された堆積物起源の付加体堆積岩および変成岩19試料を用いて,岩石中に含まれる炭質物のラマン分光分析を行った.分析に用いた岩石はすでに変成温度が見積もられており,その温度範囲は165 ℃から655 ℃である.低温領域における炭質物のラマンスペクトルは,いくつかのD-band(DefectまたはDisorder構造に起因)が顕著であり,G-band(Graphite構造に起因)は~280℃以上で確認された.400 ℃以上ではG-bandの強度が他のバンドに比べて有意に高くなり,650 ℃以上でG-bandのみになった.この結果は,変成温度の上昇に伴い,炭質物が非晶質から結晶質な構造へと変化したことを示す.この構造変化に伴う炭質物ラマンスペクトルの変化を定量的に評価するため,ピーク分離方法を詳細に検討し,各温度領域で安定な解を得る適切な分離手法を確立した.分離したピークの変数と見積もられている変成温度との相関を調べた結果,150 ℃から400 ℃付近において,D1-bandとD2-bandの半値幅と変成温度の間に負の相関があることが明らかとなった.また,これらの関係式を導出することによって,半値幅を用いた新しい炭質物ラマン温度計を提案した.この温度計は,従来の炭質物ラマン温度計では正確な温度見積もりが困難であった低温領域(< 〜300 ℃)をカバーしており,付加体堆積岩から変成岩をまたいで,簡便かつ高精度な温度見積りを可能にした.
Key Words: carbonaceous material, FWHM, geothermometer, low temperature metamorphism, Raman spectroscopy
4. Abrupt Late Holocene uplifts of the southern Izu Peninsula, central Japan: Evidence from emerged marine sessile assemblages
Akihisa Kitamura, Masato Koyama, Koji Itasaka, Yosuke Miyairi and Hideki Mori
中部日本,伊豆半島南端における後期完新世の突発的隆起:離水した海洋生物群集からの証拠
北村晃寿・小山真人・板坂孝司・宮入陽介・森 英樹
伊豆半島南端の海食洞内の隆起した海洋固着動物群集は保存状態と種構成から,5つの帯に区分される.最上位のI帯(海抜2.7-3.5m)は塊状石灰岩を呈し,イワフジツボとゴカイの一種のヤッコカンザシの棲管から成る.II帯(海抜2.35-2.7m)は保存状態の良いイワフジツボが優占する.III帯(海抜2.0-2.35m)は,主にイワフジツボとヤッコカンザシの棲管から成る.IV帯(海抜1.6-2.0m)は,非常に新鮮なイワフジツボとヤッコカンザシの棲管から成る.最下位のV帯(海抜1.0-1.6m)は,非常に新鮮なケガキとヤッコカンザシの棲管が共産する.14C年代測定の結果と現生の固着動物の帯状分布は,調査地域が西暦570-820年,西暦1000-1270年,西暦1430-1660年にそれぞれ0.9-2.0m,0.3-0.8m,1.9-2.2mの隆起があったことを示す.
Key Words: emerged sessile assemblages;Holocene;Izu Peninsula;uplift events
5. Chrome spinel in normal MORB-type greenstones from the Paleozoic–Mesozoic Mino terrane, East Takayama area, central Japan: Crystallization course with a U-turn
Takashi Agata and Mamoru Adachi
岐阜県東高山地域に分布する美濃帯中古生層中のノーマルモルブ型緑色岩のクロムスピネル: Uターンのある晶出経路
縣 孝之・足立 守
東高山地域のN-MORB型緑色岩中に産する斑晶クロムスピネルのMg/(Mg+Fe2+),Cr/(Cr+Al)及びFe3+含有量はそれぞれ0.54〜0.77,0.21〜0.53,0.07〜0.22 p.f.u. (O=4)と変動する.スピネルの組成は,斑晶鉱物の組合せの間で有意の差が認められた.オリビン–スピネルの組合せでは,スピネルはCrに富むものからAlに富むものまで広い組成範囲を示し,比較的Fe2+とFe3+に乏しい.オリビン–斜長石–単斜輝石–スピネルの組合せでは,比較的高いCr/(Cr+Al)を持ち,Fe2+とFe3+に富んでいる.オリビン–斜長石–スピネルの斑晶を持つ玄武岩は,Alに富むスピネルとFe2+とFe3+に富むスピネル双方を含有する.オリビン–スピネル平衡関係は,オリビン–スピネル組合せのスピネルが分別作用の進行とともにCrとFe2+に富むものからAlとMgに富むものへと組成を変化したことを示唆する.一方,オリビン–斜長石–単斜輝石–スピネルでは,分別とともにCr/(Cr+Al)は増加し,Mg/(Mg+Fe2+)は減少するという逆の変化が示される.スピネル全晶出経路は,Mg/(Mg+Fe2+)–Cr/(Cr+Al)変化図上でUターンを見せる.折返し点はオリビン–斜長石–スピネル組合せのスピネル組成領域にあり,Uターンは斜長石晶出が開始した結果と解釈される.
Key Words: chrome spinel, crystallization course, greenstone, N-MORB, Paleozoic–Mesozoic Mino terrane, zoning of chrome spinel
▼▼ Vol. 23-1はこちら ▼▼
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iar.2014.23.issue-1/issuetoc
会員の方は無料で閲覧出来ます(要ログイン)。
ログイン方法はこちらから>>> https://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
Island Arc 日本語要旨 2014. vol. 23 Issue 2 (June)
Vol. 23 Issue 2 (June)
Island Arc Award (2014)
Dissecting large earthquakes in Japan: Role of arc magma and fluids. <Island Arc, 19, 4–16 (2010)>
Dapeng Zhao, M. Santosh and Akira Yamada
日本における地殻大地震発生域の地震学的解剖:島弧マグマと流体の関与
趙 大鵬,M. Santosh, 山田 朗
▶▶日本語要旨はこちら
通常論文
[Invited Paper]
1. Ambiguous biogeographical patterns mask a more complete understanding of the Ordovician to Devonian evolution of Japan
Mark Williams, Simon Wallis, Tatsuo Oji and Philip D. Lane
曖昧な生物地理学的特徴に隠れた日本列島のオルドビス紀からデボン紀の地質履歴
Mark Williams・Simon Wallis・大路 樹生・Philip D. Lane
オルドビス紀からデボン紀までの日本の化石群の古生物地理学的特徴を理解するためには,複雑な時間的・環境学的・古地理学的な影響を考慮する必要がある. 種のレベルでは、南部北上・飛騨外縁・黒瀬川の各テレーン間における三葉虫・腕足類・貝形虫の化石群は限られた類似性しか示さない.その原因の一つは有殻動物群が断片的な層序学的分布を示すことである.その結果、珊瑚と汎熱帯性の放散虫を例外として,日本列島の古生代テレーンの動物群はテレーン間より東アジアの他の地域とオーストラリアとの類似性が強い. 南部北上テレーンのシルル紀の動物群は北米・ヨーロッパ・中央アジア・オーストラリアとの関係を示唆し、南中国あるいはゴンドワナ大陸の近辺に位置していたことを強く指示する決定的な証拠はない.一方,中期デボン紀の腕足類・三葉虫群は北中国との関係を強く示唆する. 飛騨外縁テレーンの三葉虫・珊瑚・貝形虫の化石群は種類レベルでも当時西側に位置していた大陸域,とりわけ中央アジアとヨーロッパとの類似点が多い.このことは中央アジア造山帯,あるいはそれに関連する地層の続きが日本列島まで伸びていたことを示唆する. また、際だった多様性を持つ同テレーンの貝形虫・三葉虫は東アジアの大陸棚域に生息した動物群との関係を示唆する.黒瀬川テレーンの主要な生物地理学的な指標は珊瑚と三葉虫から示される. これらの動物群は中央アジア・オーストラリア・南中国のシルル・デボン紀との関係を示す. 日本の古生代動物群の生物地理学的な多様性は日本の化石記録の不完全性に加えて、それらの動物の異なる生活様式,生理機能, 幼生時の拡散能力に起因すると考えられる. 古生代の日本列島基盤は北中国地塊あるいは南中国地塊の近辺, または南中国地塊の北方に位置する一つの島弧として形成したとする諸説があるが、 現時点での古生代化石群の知識をレビューすることでそれぞれの解釈の問題点が浮き彫りになった.
Key Words: biogeography, brachiopods, corals, early Palaeozoic, Japan, ostracods, palaeogeography, radiolarians, trilobites
[Research Articles]
1. Petrogenesis of the late Cretaceous K-rich volcanic rocks from the Central Pontide orogenic belt, North Turkey
Kürsad Asan, Hüseyin Kurt, Don Francis and Ganerød Morgan
北トルコ,中央Pontide造山帯の後期白亜紀高K火山岩類の成因
トルコ, 中央Pontideに広く分布する沈み込みに関連した火山岩類は, Sinop地域から北ではHamsaros火山岩層をなす.火山岩類は高Kカルクアルカリ岩, ショショナイト, 超高K組成を示す.火山岩類の40Ar/39Ar年代は後期白亜紀(約82Ma)で同時期であったことを示す.始原的マントルで規格化した微量元素パターンは, いずれの溶岩もLIL元素(Rb, Ba, K, Sr), Th, U, Pb及び軽希土類元素(LREE: La, Ce)が高度に濃集し, 典型的な沈み込み帯溶岩の特徴を示す.不適合微量元素濃度は高Kカルクアルカリ岩からショショナイトを経て超高K溶岩へと系統的に増加する.さらに, 共存する高Kカルクアルカリ岩質溶岩 (87Sr/86Sr 0.70576–0.70613, 143Nd/144Nd 0.51245–0.51253)よりもショショナイト及び高K溶岩は顕著に高い87Sr/86Sr (0.70666–0.70834)と低い143Nd/144Nd (0.51227–0.51236)初生値を示す.地球化学的データおよび同位体組成は, ショショナイトならびに超高K岩類は, 高Kカルクアルカリ岩類からはいかなる浅所プロセスによっても導くことはできず, 異なるマントルソースに由来することを示す.ショショナイトおよび超高K岩類は沈み込んだ堆積物がリサイクル, 融解し生じた交代作用による脈起源であり, 高Kカルクアルカリ岩類は沈み込み帯起源の流体によって交代作用を受けたマントルリソスフェアに由来する.
Key Words: biogeography, brachiopods, corals, early Palaeozoic, Japan, ostracods, palaeogeography, radiolarians, trilobites
2. Oligocene crustal xenolith-bearing alkaline basalt from Jandaq area (Central Iran): implications for magma genesis and crustal nature
Samineh Rajabi, Ghodrat Torabi and Shoji Arai
中部イラン,ジャンダク地域の地殻起源捕獲岩を含む漸新世のアルカリ玄武岩:マグマの生成および地殻の性質についての示唆
Samineh Rajabi・Ghodrat Torabi・荒井章司
中部イラン,ジャンダク地域南西部Tobeirehの漸新世のアルカリ玄武岩類はCEIM(イラン微小大陸)中東部に露出し、捕獲岩を含む.玄武岩はかんらん石,単斜輝石,斜長石、スピネル,チタン磁鉄鉱よりなり,アルカリ,チタン,LREE,LILE,HFSEに富む.アセノスフェアの富化したざくろ石レールゾライトの中程度の部分溶融によって形成された.富化は三畳紀から始新世のCEIMの沈み込みによる.マフィック−超マフィック捕獲岩はスピネル(低Cr),かんらん石,高Al輝石,斜長石よりなる.高Alグラニュライト捕獲岩はヘルシナイト,斜長石,コランダム,珪線石よりなり,HFSE, LREEに富み,正のEu異常を示す.グラニュライトはAlに飽和,Siに不飽和な,含斜長石レスタイト起源であろう.これらの捕獲岩は当地域の下部地殻を代表する.
Key Words: alkaline basalt, aluminous granulitic xenolith, central-east Iranian microcontinent, Jandaq, mafic-ultramafic xenolith, Oligocene.
3. Gas hydrate saturation at Site C0002, IODP Expeditions 314 and 315, in the Kumano Basin, Nankai Trough
Ayumu Miyakawa, Saneatsu Saito, Yasuhiro Yamada, Hitoshi Tomaru, Masataka Kinoshita and Takeshi Tsuji
南海トラフ熊野海盆IODP 314・315次航海C0002掘削サイトにおけるガスハイドレートの飽和度
川歩夢・斎藤実篤・山田泰広・戸丸 仁・木下正高・辻 健
統合国際深海掘削計画(IODP)314・315航海で取得された物理検層情報およびコア情報から,南海トラフ熊野海盆南東縁のC0002サイトにおけるガスハイドレートの飽和度を推定し,ガスハイドレートを形成するガスの移動について検討した.飽和度計算には,2種類の比抵抗値と音波速度値を使用し,このほかに必要な間隙率や地温勾配などの値は,他の検層データやコアデータを用いて算出した.3種類の数式を用いた解析の結果,C0002サイトでのガスハイドレート飽和度は最大30%程度であるが,高解像度データを用いた解析ではガスハイドレートが局所的に農集(飽和度60%以上)している砂層が確認され,堆積盆浅部でのガスハイドレートとフリーガスの共存も明らかとなった.これらは,北西側に位置する熊野堆積盆深部からのガスがこの地域に大量に供給されたことを示唆する.
Key Words: Chikyu, Expedition 314, Expedition 315, free gas, gas hydrate, Integrated Ocean Drilling Program, Kumano forearc basin, logging data analysis, Nankai trough, Site C0002.
4. Geology and age model of the Lower Pleistocene Nojima, Ofuna, and Koshiba Formations of the middle Kazusa Group, a forearc basin-fill sequence on the Miura Peninsula, the Pacific side of central Japan
Atsushi Nozaki, Ryuichi Majima, Koji Kameo, Saburo Sakai, Atsuro Kouda, Shungo Kawagata, Hideki Wada and Hiroshi Kitazato
三浦半島に露出する下部更新統上総層群中部野島層,大船層,小柴層の地質と年代モデル
野崎 篤・間嶋隆一・亀尾浩司・坂井三郎・甲田篤朗・河潟俊吾・和田秀樹・北里 洋
三浦半島に露出する下部更新統上総層群中部で露頭踏査とボーリングコアの記載に基づき岩相層序を確立し,野島層上部が砂質泥岩と泥岩の互層から,大船層が泥岩から,小柴層下部が砂質泥岩,泥質砂岩,砂岩からなることを明らかにした.またコアから採取した浮遊性有孔虫Globorotalia inflataの酸素安定同位体比に基づき,野島層上部から小柴層下部にMIS49—61までを認定し,年代モデルを構築するとともに,コア中に狭在する24枚の凝灰岩層の堆積年代を決定した.このうち房総半島の上総層群黄和田層中に狭在するKd25およびKd24に対比される凝灰岩層の堆積年代はそれぞれ1573 kaと1543 kaである.
Key Words: age model, forearc basin, Globorotalia inflata, Kazusa Group, Kd24, Kd25, Lower Pleistocene, MIS, Miura Peninsula, nannofossils
▼▼ Vol. 23-2はこちら ▼▼
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iar.2014.23.issue-2/issuetoc
会員の方は無料で閲覧出来ます(要ログイン)。
ログイン方法はこちらから>>> https://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
Island Arc 日本語要旨 2014. vol. 23 Issue 4 (December)
Vol. 23 Issue 4 (December)
特集号
Petrogenesis and chemogenesis of oceanic and continental orogens in Asia: Recent progress (P-I)
Guest Editors: Rehman Hafiz Ur, Tsujimori Tatsuki, Okamoto Kazuaki and Spengler Dirk
アジア地域の造山帯構成岩の岩石化学成因論:最近の話題 I
Rehman Hafiz Ur・辻森 樹・岡本和明・Spengler Dirk
1. Preface
Rehman Hafiz Ur, Tsujimori Tatsuki, Okamoto Kazuaki and Spengler Dirk
序文
Rehman Hafiz Ur・辻森 樹・岡本和明・Spengler Dirk
本特集号は,「日本地球惑星科学連合2013年度連合大会国際シンポジウム」の講演を中心として,アジア地域(中東アジアを含む)の造山帯構成岩の岩石化学成因論に関する最近の話題まとめたものである.
収録した論文のテーマは,プレート境界域の太平洋型・大陸衝突型造山帯を構成する高圧・超高圧変成帯,オフィオライトの構成岩類の他,大陸リフト帯のマントル捕獲岩の研究など多岐にわたる.
特集号(本号・次号)の序文として本号掲載の5編についての内容を紹介した.
2. Modelling of the phase relations in high-pressure and ultrahigh-pressure eclogites
Chunjing Wei and Zuolin Tian
高圧・超高圧エクロジャイトの鉱物相関係モデリング
高圧・超高圧ローソン石エクロジャイトの鉱物組成共生関係をモデリングした.MORB全岩組成をもちいたシュードセクションの計算結果は,ローソン石エクロジャイト相において,低温高圧,低温超高圧,中温超高圧の3つの亜相を区別し,それぞれの亜相において安定な鉱物組み合わせとざくろ石のパイロープ・グロシュラー成分,及び,フェンジャイトのSi含有量の温度・圧力に対する変化傾向と全岩組成依存性を予測した.また,モデリングは,それぞれの亜相の鉱物組み合わせが減圧で変化するさいに,ローソン石の脱水反応,すなわち,ローソン石の消滅とそれに伴う藍閃石・緑れん石(あるいは,藍晶石)の形成によって,大量の水流体を放出することを予想した.
Key Words: basic rock, geothermobarometer, HP-UHP eclogites, pseudosection.
3. Composite metamorphic history recorded in garnet porphyroblasts of Sambagawa metasediments in the Besshi region, central Shikoku, southwest Japan
Yui Kouketsu, Masaki Enami, Takeshi Mouri, Mitsuya Okamura and Tsuyoshi Sakurai
四国中央部別子地域の三波川変泥質岩中に含まれるザクロ石斑状変晶に記録された複合変成履歴
纐纈佑衣・榎並正樹・毛利 崇・岡村光哉・櫻井 剛
四国中央部の別子地域三波川帯に産する変泥質岩中のザクロ石に記録された複合変成履歴について検討した.当地域におけるザクロ石の多くは,成長した後に融食を被った内側部分とその後に再成長した外側部分で特徴づけられる複合累帯構造を示す.ザクロ石の内側部分はNa相包有物として主にパラゴナイトを,また稀にオンファス輝石や藍閃石を含む.一方,外側部分は稀にアルバイトを含んでいるがパラゴナイトは見出されない.内側部分はエクロジャイト相条件に相当する高い残留圧力を保持する石英を包有しているのに対し,外側部分は緑簾石–角閃岩相程度の条件に相当する低い残留圧力を保持する石英を含んでいる.これらの情報から,複合累帯構造を示すザクロ石は,累進エクロジャイト相ステージ → 減圧・加水反応ステージ → 累進緑簾石–角閃岩相ステージの変成履歴が推定される.エクロジャイト相変成作用を被ったと考えられる複合累帯ザクロ石を含む変泥質岩は,オンファス輝石 + ザクロ石の組合せを保持する変塩基性岩の広がりから提案されていたエクロジャイトユニットよりも広範囲に分布している.このことは,従来の想定よりも多くの堆積岩類が塩基性岩類と共にマントルへと沈み込んでいる事を示す.また,本研究により,(1) ザクロ石の化学組成累帯構造,(2) Na相包有鉱物の種類,(3) 石英包有物の残留圧力の組合せが,従来の手法では検討の難しかった変泥質岩が被った高P/T型累進変成作用時の温度圧力条件を評価するのに有効な手法である事が示された.
Key Words: chemical zoning, garnet porphyroblast, metasediment, Raman spectroscopy, residual pressure, Sambagawa belt, sodic phase mineral.
4. The formation of rodingite in the Nagasaki metamorphic rocks at Nomo Peninsula, Kyushu, Japan – Zircon U–Pb and Hf isotopes and trace element evidence
Mayuko Fukuyama, Masatsugu Ogasawara, Daniel J. Dunkley, Kuo-Lung Wang, Der-chuen Lee, Tomokazu Hokada, Kenshi Maki1, Takafumi Hirata and Yoshiaki Kon
長崎県野母半島の長崎変成岩類中のロディンジャイトの形成―U-PbとHf同位体と微量元素からの証拠
福山繭子・小笠原正継・Daniel J. Dunkley・Kuo-Lung Wang・Der-Chuen Lee・外田智千・牧 賢志・平田岳史・昆 慶明
長崎県野母半島に分布する長崎変成岩類中の蛇紋岩メランジには,岩脈状と塊状の2種類のロディンジャイトが観察される.共に短柱状ジルコンが含まれ,岩脈状ロディンジャイトには多孔質ジルコンも存在する.短柱状ジルコンは,ロディンジャイトの主要構成鉱物であるザクロ石が包有物として観察されることから,ロディンジャイト化の際に結晶化したと考えられる.またこのジルコンには初生的な流体包有物が存在し,流体の存在下にあったと分かる.一方で多孔質ジルコンは,短柱状ジルコン形成の後に,熱水から直接結晶化したと考えられる.短柱状ジルコンのSHRIMP U-Pb年代は108-105Maと得られ,沈み込み帯におけるロディンジャイト化の年代を示す.岩石の微量元素組成とジルコンのHf同位体は,ロディンジャイト化に関与した流体がMORB組成を反映し,ロディンジャイトの原岩からLILE元素を溶脱させSrを付加したことを示唆し,この間,HFSE元素は動かなかったと考えられる.
Key Words: Cretaceous subduction, Hf isotope, rodingite, the Nagasaki metamorphic rocks, zircon SHRIMP U–Pb dating.
5. Petrofabrics of olivine in a rift axis and rift shoulder and their implications for seismic anisotropy beneath the Rio Grande rift
Munjae Park, Haemyeong Jung and Youngwoo Kil
リオグランデ・リフト軸部,側面の捕獲岩中のかんらん石ファブリックとリフト下の地震波異方性との関係
大陸リフト帯に伴うマントル捕獲岩は,マントルの構造と上部マントルの変形に関わる物理化学的性質に関係する重要な情報を提供する.リオグランデ・リフト下の変形過程と上部マントルで起こっている地震波異方性を理解するため,リフト側面のアダムズディッキンズ(AD)とリフト軸部のエレファントバット(EB)からの変質スピネルペリドタイトの研究を行った.かんらん石の格子定向配列(LPO)をSEM/EBSD 分析で求めた結果,リフト側面のADかんらん岩は,(100)[001]卓越すべり,C−type LPOを示す.一方,リフト軸部のEBかんらん岩は,(010)[100]卓越すべり,A-type LPO を示す.地球化学データと微細組織観察により,リフト側面部(ADかんらん岩)では流体を伴うメルトが局所的なマントル肥沃化を起こし,含水条件下でかんらん岩が変形(かんらん石 C-type LPO)したことが示された.一方リフト軸部(EBかんらん岩)では,減圧部分融解によるマントルの枯渇化が無水条件での変形(かんらん石A-type LPO)を引き起こした.これらの観察は,リオグランデ・リフト(RGR)帯の上部マントルの局所的な含水化と物理化学的不均一性の証拠となる.このRGR 帯の下部で観察される地震波異方性は,不均質伸張のような引張破断やRGR帯下のかんらん石ファブリックに起因する.
Key Words: lattice preferred orientation, metasomatized spinel peridotite, olivine, Rio Grande rift, seismic anisotropy.
6. Petrology of mantle diopsidite from Wadi Fizh, northern Oman ophiolite: Cr and REE mobility by hydrothermal solution
Norikatsu Akizawa and Shoji Arai
北部オマーンオフィオライトのワジ・フィズにおけるマントル・ディオプシダイトの岩石学:熱水によるCrとREEの移動性
秋澤紀克・荒井章司
主にディオプサイドで構成される岩石である「ディオプシダイト」は,マントルかんらん岩中でシリケイト成分に富んだ高温の熱水から晶出したと考えられている.本論文において我々は,最上部マントル部でクロマイト・Crに富んだディオプサイド(
Island Arc 日本語要旨 2015. vol. 24 Issue 2(June)
Vol. 24 Issue 2(June)
Invited Article
1. Evolution Processes of Ordovician-Devonian Arc System in the South-Kitakami Massif and its Relevance to the Ordovician Ophiolite Pulse
Kazuhito Ozawa, Hirokazu Maekawa, Ken Shibata, Yoshihiro Asahara, Masako Yoshikawa
オルドビス紀−デボン紀の南部北上山地島弧発達過程とオルドビス紀オフィオライトパルスとの関連
小澤一仁・前川寛和・柴田 賢・淺原良浩・芳川雅子
南部北上山地のオルドビス紀島弧オフィオライト(早池峰・宮守オフィオライト)と高圧低温型変成岩類(母体変成岩),および関連する古生代初期の地質体に関する年代,地質,岩石,地球化学的データと新たに得た補足データに基づいてオルドビス紀-デボン紀の南部北上島弧発達過程を再検討し,次のようなシナリオを得た.後期デボン紀以前に東から西への沈み込み極性の変化があり,早池峰・宮守オフィオライトは,東に向かう沈み込み帯の上で,上盤プレート展張に駆動された背弧海盆拡大の初期と前弧域拡大の後期の断熱融解ステージとそれらに挟まれたスラブ由来流体の影響を強く受けた中期融解ステージを経て形成された.弱いプレート間カップリングの条件下でスラブ後退とそれに引き続くスラブ断裂によって発生した非定常的三次元マントル流動が中期から後期の融解を支配したというテクトニックモデルを提案する.オルドビス紀オフィオライトパルスを特徴づける含水鉱物に富んだマントルを持つオフィオライトは,〜5億年前のマントルの熱状態や水の循環の特異性を反映していると考えられる.
Key Words : Hayachine-Miyamori ophiolite, island arc evolution, ophiolite pulse, South Kitakami.
Rseach Article
2.Graphitization of carbonaceous material in sedimentary rocks on short geologic time-scales: An example from the Kinsho-zan area, central Japan
Natsumi Mori, Simon wallis and Hiroshi Mori
中部日本・金生山地域を例にした,地質学的短時間スケールにおける堆積岩に含まれる炭質物の石墨化
森 なつみ・サイモン ウォリス・森 宏
初期の非晶質な炭質物は,被熱にともなってより結晶質になる.その構造変化は最高被熱温度のみならず被熱時間にも依存
する.10万年以上の時間スケールにおいて熱を被った天然試料のラマンスペクトルは,結晶化度が定常状態に達することを示す.一方,室内実験の研究では,3.5週間,1000℃の加熱後でも炭質物の結晶化度はほとんど変化しないことが示されている.
結晶化作用についての時間スケールのさらなる制約には,数年〜数万年スケールでの検証が必要であり,このような長時間の時間スケールに関しては,被熱時間の長さが明らかである炭質物を含有する天然の岩石を例とすることでのみ,導くことが可能である.岐阜県・赤坂石灰岩地域の幅13mの岩脈周辺に発達
する接触変成作用についての熱モデリング結果は,被熱時間スケールが1〜100年であることを示す.ラマンスペクトルは,岩脈の3m以内において炭質物の結晶化度の著しい増加を示す.接触変成域において推定される温度と炭質物の結晶化度の比較結果は,岩脈近傍であっても,炭質物が定常状態に達しないことを示す.この変化は,数年の被熱時間スケールにおいて(モデリング温度が)550℃以上で開始する.天然の地質学的な条件下では,炭質物の結晶化作用における定常状態の獲得には,約100年以上の時間スケールの加熱が必要である.本研究は,岩石中の炭質物結晶化作用のカイネティクスを決定するために,天然実験研究を用いることが有用であることを示す.
Key Words : carbonaceous material, contact metamorphism, Raman spectroscopy, thermal modeling
3.Laboratory measurements of‘porosity-free’intrinsic Vp and Vs in an olivine gabbro of the Oman ophiolite: Implication for interpretation of the seismic structure of lower oceanic crust
Satoshi Saito, Masahiro Ishikawa, Makoto Arima, Yoshiyuki Tatsumi
オマーンオフィオライト産かんらん石斑れい岩の「空隙フリー」P波・S波速度測定:下部海洋地殻地震波速度構造の解釈における意義
齊藤 哲・石川正弘・有馬 眞・巽 好幸
海洋地殻条件のような比較的低圧下での弾性波速度測定実験では,試料内に存在する空隙が岩石のP波速度(Vp),S波速度(Vs),Vp/Vs比に強く影響を与えてしまう.一方,ピストン・シリンダー型高温高圧発生装置を用いて広い温度圧力下(室温〜400℃,0.2〜1.0GPa)で測定実験を行うことにより,海洋地殻条件における岩石の「空隙フリー」Vp,Vs,Vp/Vs比を精度良く求めることが可能である.本論では,オマーンオフィオライトに産するかんらん石斑れい岩の「空隙フリー」Vp,Vs,Vp/Vs比を求め,下部海洋地殻地震波速度構造の解釈における意義を述べる.
Key Words : elastic wave velocity, gabbro, oceanic crust, Oman ophiolite, piston-cylinder high-pressure apparatus, porosity.
4.Foldback reflectors near methane hydrate bottomsimulating reflectors: Indicators of gas distribution from 3D seismic images in the eastern Nankai Trough
Marc Humblet, Chuki Hongo and Kaoru Sugihara
メタンハイドレート海底疑似反射面の縁辺に見られる「折り返し反射面」:東部南海トラフの三次元反射法地震探査記録におけるガス分布の指標
大塚宏徳・森田澄人・棚橋 学・芦 寿一郎
海底下浅部における流体の分布や挙動を理解することは,ガスハイドレートの形成や全球的な炭素循環を考えるうえで重要である.反射法地震探査を用いたガス分布の推定は,多くの場合ガス分布の境界は不明瞭である事に加え,系統的な手法が確立されていないことから容易ではない.本研究では東部南海ト
ラフで実施された三次元反射法地震探査に認められた,ガスハイドレートの形成や流体移動に関連するとみられる特徴的な反射面について報告する.その形態からこの反射面を本研究では「折り返し反射面(Foldback reflector, FBR)」と呼ぶ.FBRはガス(メタン)ハイドレート海底擬似反射面(Bottom simulating reflector, BSR)の縁辺から下方に向けて折り返すことを繰り返 した形状をしており,全体として地層に平行な「折り目」を持つ蛇腹状の構造を呈する.FBRは折り返す毎に位相を反転させる.FBRを側方に跨いで異なるサイスミックファシスが認められ,BSRより下位の地層は相対的に低振幅で高周波数成分に乏しく反射面が不明瞭な傾向を示すのに対し,BSR分布の外側にある地層は明瞭な反射面を維持している.また,反射面が不明瞭な領域は周囲より弾性波速度が低い領域に対応している.このような低速度異常および反射特性は堆積層中にガスが存在することを示唆している.FBRは隆起帯の良く成層した堆積層に発達する傾向がある.FBRの傾斜方向は,FBRの発達する地層の傾斜に規制されているとみられる.FBRの縁辺はしばしば反射強度の大きい反射面に対応している.このようなFBRの発現は,BSRと同様に地域的な隆起や層理面沿いの流体移動がFBRの発達に関わっていることを示唆している.
Key Words : 3D seismic survey, accretionary prism, fluid migration, methane hydrate, uplift.
5.Cretaceous granitoids and their zircon U-Pb ages across the south-central part of the Abukuma Highland, Japan
Shunso Ishihara, and Yuji Orihashi
日本,阿武隈高地,中央南部に分布する白亜紀花崗岩類および含まれるジルコンU-Pb年代の東西変化
石原舜三・折橋裕二
阿武隈変成深成岩帯の中央南部を横切る東西方向で,花崗岩類のジルコンU-Pb年代を調べた.測定ジルコン年代は,古典的分類法である“旧期”,“新期”花崗岩類を支持しない.西部地域の竹貫・御斉所変成岩類において花崗岩類を西から東へ第Ⅰ帯,第Ⅱ帯,第Ⅲ帯に分けると,第Ⅲ帯で緑色片岩相に貫入する入遠野石英閃緑岩中の花崗閃緑岩が調査地域内で最も古い121 Maを示した.北方の花崗閃緑岩も112 Maと,やや大きい値を示す.しかし,竹貫-御斉所変成岩類に貫入する他の花崗岩類は103−99 Maと若い年代を示すに過ぎない.両雲母花崗岩と黒雲母花崗岩類は99 Ma態度の若い年代を示した.阿武隈変成帯と領家変成帯の花崗岩活動は石英閃緑岩質マグマの上昇・貫入に始まり,両雲母花崗岩の貫入で終息した.畑川破砕帯以東の花崗岩類からは110−106 Ma(4試料)が得られ,北上山地と同様な古い値は得られなかった.日本列島全体としての白亜紀の花崗岩活動は,北上山地,阿武隈高地,領
家帯,そして西南日本の山陰帯へと若くなる傾向がみられる.
Key Words : Abukuma Highland, Cretaceous granitoids, U-Pb age, zircon.
6.Petrology and geochemistry of ultrahigh-temperature granulites from the South Altay orogenic belt, northwestern China: Implications for metamorphic evolution and protolith composition
Xiaoqiang Yang, Zilong Li, Huihui Wang, Hanlin Chen, Yinqi Li and Wenjiao Xiao
南アルタイ造山帯の超高温グラニュライトの岩石学・地球化学:変成条件の変遷と源岩組成の示唆
中国北西部,南アルタイ造山帯の超高温(UHT)グラニュライトは下部地殻の構成物と古生代における中央アジア造山帯のテクトニックな進化について重要な解答を提供する.本論文はアルタイUHTグラニュライトの源岩と変成条件の進化を理解するために,全岩地球化学及び鉱物の特徴を明らかにした.アルタイグラニュライトは−9.27〜−3.95と負の判別関数値(DF)を示すことから,堆積岩,おそらくは泥質岩起源と思われる.920−1010℃へ,9kbar以上のピーク変成温度圧力条件とスピネル(低ZnO)+石英及び斜方輝石(Al2O3 9.2 wt%以下)+珪線石+石英の共生は,超高温変成作用を示す.二段階の後退変成作用が認められる;はじめに750℃,5.2-5.8 kbarに等温減圧し,次いで4.8−5.2 kbar,520−550℃ へと温度が低下した.先行研究と合わせて,アルタイUHT泥質グラニュライトが示す時計回りの温度圧力変化は,シベリアプレートとカザフスタン−ジャンガープレート間の衝突・付加過程を示唆すると考えられる.
Key Words : geochemistry, mineral characteristics, provenance reconstruction, P-T estimate, South Altay orogenic belt, ultrahigh-temperature granulite.
7.Geologic evidence for late Quaternary repetitive surface faulting on the Isurugi fault along the northwestern margin of the Tonami Plain, north-central Japan
Tadashi Maruyam, Masaru Saito
砺波平野北西縁に分布する石動断層の第四紀後期における地震断層活動
丸山 正・齋藤 勝
砺波平野北西縁に分布する石動(いするぎ)断層の第四紀後期の活動性を明らかにするため,航空レーザ詳細地形データ解析,現地踏査,トレンチ掘削調査を実施した.その結果,同断層が更新世後期以降に地震断層を伴う地震運動を繰り返し,その最新活動は完新世後半であることが明らかになった.変動地形学的に認定される石動断層の活断層トレースは短い区間に限定されるが,これは同断層に平行して流れる小矢部川の侵食や埋積の影響を受けたことによるものであり,地震断層を伴う大地震を引き起こす規模の断層が伏在している可能性がある.
Key Words : active fault, backthrust, Isurugi fault, LiDAR,thrust fault, trenching.
8.Tectonic reconstruction of batholith formation based on the spatiotemporal distribution of Cretaceous-Paleogene granitic rocks in southwestern Japan
Kazuya Iida, Hikaru Iwamori, Yuji Orihashi, Taeho Park, Yong-Joo Jwa, Sung-Tack Kwon, Tohru Danhara, and Hideki Iwano
西南日本に分布する白亜紀−古第三紀花崗岩の時間空間分布に基づく成因とテクトニクスの復元
飯田和也・岩森 光・折橋裕二・Taeho Park・Yong-Joo Jwa・Sung-Tack Kwon・檀原 徹・岩野英樹
本論文では,沈み込み帯における花崗岩の成因とテクトニックセッティングを明らかにするために,西南日本白亜紀?古第三紀の花崗岩の詳細な年代測定を行った.鳥取,岡山,香川県に分布する92サンプルのU-Pbジルコン年代測定を行い,南から北にかけて段階的に年代が若くなることを示した.このよう
な移動を説明するモデルとして,海嶺沈み込みと沈み込み角度の変化が考えられる.数値計算により両モデルの溶融領域を計算し,観測との比較を行った.海嶺沈み込みモデルでは,セグメントを伴った45 km幅のリッジが1.6 cm/yrで沈み込むことにより溶融領域がおよそ再現できることが分かった.一方で,沈み込み角度の変化で説明する場合,沈み込み角度が37°から20°に変化することにより,段階的な時空間変化を再現できることが分かった.海嶺沈み込みモデルの方が,火成活動が全体として限られた期間に起こる点をより良く説明する.
Key Words : age, granite, heat source, ridge subduction, SW Japan, zircon.
9.Dating of altered mafic intrusions by applying a zircon fission track thermochronometer to baked country rock, and implications for the timing of volcanic activity during the opening of the Japan Sea
Hiroyuki Hoshi, Hideki Iwano, Tohru Danhara, and Naoyoshi Iwata
変質苦鉄質岩の年代を被熱母岩のジルコンFT熱年代測定によって決める:日本海拡大期の火山活動タイミング
星 博幸・岩野英樹・檀原 徹・岩田尚能
変質苦鉄質岩の貫入年代を一般的な放射年代測定で決めるのは難しい.我々は今回,貫入によって焼かれた母岩にFT熱年代学の手法を適用することで変質苦鉄質岩の貫入年代決定を試みた.長野県高遠地域に分布する変質ドレライト岩脈の年代を決定するために,母岩の白亜紀花崗岩から試料を採取した.貫入面から8mm以内のジルコンは一様に17〜16 MaのFT年代を示した.FT長解析により,白亜紀以降に蓄積されたFTはドレライト貫入時にリセットされ,現在見られるFTはその後に生じたものであることが確認された.貫入面から20 mmまで範囲を広げると,FTがリセットされたジルコンとそうでないジルコンの混合による年代が得られた.以上の結果はドレライトの年代が17〜16 Maであること,および被熱母岩に対するFT熱年代測定が変質苦鉄質貫入岩の年代決定に有効であることを示す.西南日本東部では18〜15 Maに火山フロントが前弧側に張り出し,火山活動が散在的に起こった.これは日本海拡大期に前弧側マントルウェッジまで熱いアセノスフェア物質が侵入したためかもしれない.なおアパタイトはより若いFT年代を示し,中期中新世以降の局所的なマグマ活動の影響を受けた可能性がある.
Key Words : apatite, dolerite, fission track dating, fission track thermochronometry, geochronology, Japan Sea opening, mafic intrusion, Miocene, Southwest Japan, zircon.
10.Petrogenesis of diabase from accretionary prism in the southern Qiangtang terrane, central Tibet : Evidence from U-Pb geochronology, petrochemistry and Sr-Nd-Hf-O isotope characteristics
Jin-Xiang Li, Ke-Zhang Qin, Guang-Ming Li, Jun-Xing Zhao, and Ming-Jian Cao
中央チベット,南部Qiangtangテレーンの付加体中のダイアベースの成因論
Lhasa及びQiangtangテレーン間のBangong-Nujiang(BNS)縫合帯は,重要な境界を占め,その岩石学的成因についてはよくわかっていない.南部Qiangtangテレーンの付加体のダイアベース中のジルコンは181.3 ± 1.4 MaのU-Pb年代を示す.ダイアベースはソレアイト質玄武岩組成であり,やや軽希土類元素に富むパターン,さまざまな程度に富む不適合元素(Th, Rbなど),HFS元素(Nb, Taなど)異常を欠く点で,エンリッチした中央海嶺玄武岩(E-MROB)に類似する.相対的に均質な全岩Nd同位体組成(εNd(t)=7.3-9.1)とジルコンのHf-O同位体組成(εHf(t)=14.8-16.1,δ18O=4.57-6.12 ‰)は,地殻の混染がほとんどなく枯渇したマントルが融解したことを示す.全岩化学組成変化からダイアベースはBangong-Nujiang海の中央海嶺とプルームの相互作用によって生じたと考えられる.
Key Words : diabase, petrogenesis, Qiangtang terrane, Tibet, zircon Hf-O isotope.
[Thematic Article]Petrogenesis and chemogenesis of oceanic and continental orogens in Asia: Recent progress, Part II
11.Extensive normal faulting during exhumation revealed by the spatial variation of phengite K-Ar ages in the Sambagawa metamorphic rocks, central Shikoku, SW Japan
Toru Takeshita, Koshi Yagi, Chitaro Gouzu, Hironobu Hyodo,and Tetsumaru Itaya
西南日本,四国中央部三波川変成岩中のフェンジャイトK-Ar年代の空間変化に基づき明らかにされた上昇削餝時の広範囲な正断層活動
竹下 徹・八木公史・郷津知太郎・兵藤博信・板谷徹丸
変成岩の地表に向けての上昇において,変形モードは上昇とともに延性変形から脆性変形に変化する.我々は猿田川地域の三波川変成岩(広義)を構成する泥質片岩中のフェンジャイトK-Ar年代が断層活動によって乱されていないかを検討するため,その空間変化を調査した.その結果,我々は下位ガーネット帯とアルバイト−黒雲母帯およびアルバイト−黒雲母帯と上位ガーネット帯の2つの境界を横切って,年代が約5百万年変化していることを明らかにした.これらのフェンジャイトKAr年代の空間変化は,おそらく脆性-延性転移の条件(約300℃)で生じたD2時相の大規模な正断層活動によって変成岩層が切断されたことによる.理由はアクチノライト岩が前者の境界に形成されているからである.ここで,D2時相直前には変成岩層が水平であり,変成岩の上昇速度が以前推定されていた値,1km/百万年であった仮定すると,5百万年のフェンジャイトK-Ar年代の変化は,以前の研究で報告されていた北傾斜の低角正断層に沿って約10 kmの変位が生じたことを示す.アクチノライト岩からのフェンジャイト40Ar/39Ar年代(約85 to 78 Ma)は周囲の断層活動を受けていない泥質片岩のK-Ar年代と合理的に比較出来る.その理由として周囲の泥質片岩のK-Ar年代も,フェンジャイト中のアルゴンの拡散閉止温度(約500−600℃)よりもはるかに低い脆性-延性転移の温度条件以下に冷やされてからの経過時間を示していることが考えられる.
Key Words : exhumation, normal faulting, phengite K-Ar ages, Sambagawa metamorphic rocks.
[Thematic Article]Carbonate sedimentation on Pacificcoral reefs, Part II
12.Carbonate sedimentation in seagrass beds on Ishigakijima, Ryukyu Islands, southwestern Japan
Keita Fujita, Ryuji Asami, Hideko Takayanagi, and Yasufumi Iryu
琉球列島石垣島の海草藻場における炭酸塩の堆積過程
藤田慶太・浅海竜司・高柳栄子・井龍康文
われわれは,海草藻場の生物相・堆積相を検討し,そこでの炭酸塩の堆積過程を明らかにするため,琉球列島石垣島の名蔵および吉原において,海岸から沖合に向けて引いた3本の測線上で,海草藻場の生物学的・堆積学的調査を行った.両地点では海草藻場は沿岸に対してほぼ並行に配列し,その分布幅は60 mから110 m以上に達する.海草藻場の卓越種はThalassiahemprichiiおよびCymodocea rotundataであり,随伴種としてC. serrulataがみられた.海草の被覆率には明瞭な季節変化がみられ,平均被覆率は夏期から秋期(7〜10月)に相対的に高く,冬期から春期(1〜4月)に相対的に低かった.海草藻場の表層堆積物は,中粒〜極粗粒砂大の生砕物が優勢であり,grainstoneないしpackstone様の岩相を呈していた.生砕物として,サンゴ,サンゴモが多く認められ,底生有孔虫,軟体動物,ウニ,ハリメダが伴ってみられた.名蔵では,grainstone/packstoneの下位に,rudstone様の岩相を呈する粗粒な堆積物(サンゴ片を含む)が認められた.表層堆積物の直下(海底から10〜20 cm以深)の堆積物は黒色を呈しており,海草藻場一帯では海底下に還元環境が広がっていることが示唆された.名蔵および吉原のコア試料より採取されたサンゴ片(それぞれ,コア深度24.5 cmおよび16.5 cm)の放射性炭素年代は,それぞれ2781〜2306 cal BPおよび4374〜3805 cal BP(2σ)であった.これは,海草藻場での堆積速度が極端に遅い(<0.1 mm/年)ことを示している.堆積物の流入量は,冬期から夏期にかけて(1月〜7月)よりも,夏期から冬期にかけて(7月〜1月)の方が多く,これは夏期から冬期に風や嵐によって大量の堆積物が運搬されるためだと考えられる.堆積物の流入量は,名蔵では74〜96 kg CaCO3/m2/年,吉原では21〜57 kg CaCO3/
m2/年で,周囲と比べて著しく多く,これは海草藻場が堆積物をトラップする機能を有していることを示す.このように,琉球列島の海草藻場では,多量の堆積物が流入しているにも関わらず,堆積速度が極端に遅く,流入した堆積物のほぼ全ては海草藻場の外へ移動していると思われる.
Key Words : carbonate, Ryukyu Islands, seagrass, seagrass bed.
Island Arc 日本語要旨 2015. vol. 24 Issue 3(September)
Vol.24 Issue 3 (September)
[Island Arc Award 2015]
Chemical characteristics of chromian spinel in plutonic rocks: Implications for deep magma processes and discrimination of tectonic setting. < Island Arc, 20, 125-137 (2011) >
Shoji Arai, Hidenobu Okamura, Kazuyuki Kadoshima, Chimav Tanaka, Kenji Suzuki and Satoko IshimaruReferences
[Pictorial Article]
Seamount subduction likely provoked prolific mass wasting on the slope in the central part of the East Sakhalin accretionary wedge, eastern Russia
Sergey Zyabrev
[Research Articles]
1. Early to Middle Miocene rotational tectonics of the Ou Backbone Range, northeast Japan
Jun Hosoi, Makoto Okada, Tomohiro Gokan, Kazuo Amano and Andrew James Martin
東北日本奥羽脊梁山脈における前期〜中期中新世の回転テクトニクス
細井 淳・岡田 誠・後閑 友裕・天野 一男・Andrew James Martin
東北日本では中新世に反時計回りの回転運動が起こったことが知られているが、その詳細な時期やメカニズム,それに関連した具体的な堆積場の変遷についてはよくわかっていない.本研究は,詳細な層序,堆積場の変遷が解明されている岩手県西和賀町周辺を対象とし,古地磁気,岩石磁気学的研究を実施した.その結果,本地域は15Ma頃の短期間で,約45°反時計回りに回転したことが判明した.これを踏まえ,以下のように本地域のテクトニクスと堆積環境変遷との関係を考察した.1)16Ma以前,静穏な環境下で砂岩・泥岩が堆積.2)16〜14Ma頃,反時計回り運動とともに堆積場が急激に沈降し,連続的かつ爆発的な火山活動が起こった.3)14Ma頃,回転運動・火山活動は収束し,静穏な堆積環境に戻った.本結果は回転運動が堆積盆発達に影響を与えたことを示唆する.
Keywords: counterclockwise rotation, Green Tuff;Miocene;northeast Japan, Ou Backbone Ranges, paleomagnetism, paleostress;tectonics
2.Linkage of deep sea rapid acidification process and extinction of benthic foraminifera in the deep sea at the Paleocene/Eocene transition
Hodaka Kawahata, Ritsuo Nomura, Katsumi Matsumoto and Hiroshi Nishi
暁新世/始新世境界における深海底での海洋酸性化と底棲有孔虫の絶滅
川幡穂高,野村律夫,松本克美,西 弘嗣
ODP Site 1220で採取されたP/E境界(5,500万年前)の堆積物を地球化学的および古生物学的見地より高時間解像度で分析した.その結果,①浮遊性有孔虫の一部の残存より,海洋表層での生産と海底での溶解,②石灰質底生有孔虫の無産出から,膠着質の底生有孔虫のみが生存と結論した.ボックスモデルの計算より,当時の大気中の二酸化炭素濃度は280-410ppmと推定された.現在,大気中への二酸化炭素量放出速度はP/E境界の30倍に相当し,今世紀末に南極海底層水がアラレ石に不飽和となるので,深海底の石灰質底生有孔虫はP/E境界同様,海洋酸性化により絶滅を含めて厳しい状況におかれると推測される.
Keywords: agglutinated foraminifera, benthic foraminifera, carbon cycle, ocean acidification, Ocean Drilling Program (ODP), The Paleocene/Eocene (P/E) transition
2. Paleoenvironments of the evolving Pliocene to early Pleistocene foreland basin in northwestern Taiwan: An example from the Dahan River section
Tsun-You Pan, Andrew Tien-Shun Lin and Wen-Rong Chi
台湾北西部大漢渓セクションに認められる前縁堆積盆地での鮮新世−前期更新世の古環境変動
ルソン火成弧の中国大陸東縁部への衝上にともない,後期中新世以降,台湾山脈と前縁堆積盆地が衝上帯の西方で形成されている.この研究は,台湾北西部の大漢渓セクションでの堆積相解析と石灰質ナノ化石による生層序学的検討を行ったものである.本研究の成果は,鮮新世から前期更新世の北西台湾前縁堆積盆地における堆積環境の変遷と堆積作用と堆積盆地テクトニクスの相互作用に関しての新たな知見を提供する.石灰質ナノ化石の生層序学的研究により,上部桂竹林層と上位の錦水頁岩層はNN15,卓蘭層はNN16−NN18の生層序帯にそれぞれ対応することが明らかとなった.さらに,NN15−NN16の境界は,錦水頁岩層と卓蘭層の境界にほぼ対応することが明らかとなった.下位より上部桂竹林層,錦水頁岩層,卓蘭層ならびに楊梅層で構成される前縁堆積盆地埋積物には,3つの主要な堆積環境が識別された.前期鮮新世の上部桂竹林層の堆積期には,波浪作用ならびに潮汐作用の卓越した沖合環境が卓越していた.後期鮮新世になると堆積環境が深海化し,錦水頁岩層が形成された.更新世の下部卓蘭層堆積期には,堆積環境は浅海化し,波浪卓越型のエスチュアリーが発達し,堆積盆地の急速な埋積が行われた.さらに,上部卓蘭層から楊梅層の堆積期には,蛇行河川ならびに砂質網状河川へと堆積環境が変化した.したがって,研究対象層準では,およそ4 Maから1 Maまでの鮮新世から更新世にかけて,前縁堆積盆地において深海化とその後の浅海化,ならびに浅海化にともなう埋積物の粗粒化が発生したことが明らかとなった.
Keywords: foreland basin, Plio–Pleistocene, sedimentary environments, stratigraphy, Taiwan
4.Two modes of climatic control in the Holocene stalagmite record from the Japan Sea side of the Japanese islands
Tomomi Sone, Akihiro Kano, Kenji Kashiwagi, Taiki Mori, Tomoyo Okumura
完新世石筍に記録される日本海側での2つの気候モード
曽根知実,狩野彰宏,柏木健司,森 大器,奥村知世,沈 川洲,堀 真子
新潟県糸魚川市の洞窟で採集した石筍FG01は酸素同位体比に完新世(1万年前以降)の東アジア冬期モンスーン強度を高解像度で記録する.本研究では,新たにFG01の炭素同位体比とMg/Ca比を解析した.その結果,水の浸透経路における方解石沈殿の重要性とともに,糸魚川での完新世古気候が6.4 kaを境に2つのモードに分けられることが示された.前期完新世では温暖・湿潤化に伴う土壌二酸化炭素の増加が,後期完新世ではモンスーン変動に伴う降水量変動が古気候指標に反映されていたと解釈できる.また,解析結果は1) 約7千年前に起こった植生変化,3)後期完新世で顕著な数千年〜数百年スケールの変動を示唆する.
Keywords: East Asian winter monsoon, Holocene climate mode, Japan, Mg/Ca ratio, millennial-scale variation, oxygen and carbon isotopes, prior calcite precipitation;stalagmite
5.Early Cretaceous I-type granites in the southwest Fujian Province: new constraints on the late Mesozoic tectonic evolution of southeast China
Xilin Zhao, Kai Liu, Minggang Yu, Yang Jiang, Jianren Mao, Xiaohua Zhou and Shengyao Yu
福健省南西部の前期白亜紀のI-タイプ花崗岩類:中国南東部の後期中生代のテクトニクス進化に関する新たな制約
中国福健省南西部のSukeng深成岩体の2試料から得られたジルコンの生成年代を決めるためにレーザーICP-MS分析を行った.2試料のジルコンは100.47±0.42 Maと102.46±0.69 MaのU-Pb年代を示すことから,Sukeng深成岩体の形成は銅―金―鉛―亜鉛―モリブデン鉱化作用に関係したSifang及びLuoboling深成岩体と同時であることがわかった.どの深成岩体もI-タイプ花崗岩類であり,高Kから中Kのカルクアルカリ系列のメタアルミナ岩型に属し,Al2O3/(CaO+Na2O+K2O)モル比の平均値が0.95,87Sr/86Sr初生値が0.70465-0.70841,101 MaにおけるεNd(t)が-1.72〜-7.26,2段階のNdモデル年代(T2DM)は1.16から1.60 Gaである.3つの深成岩体のジルコンは101 MaにおけるεHf(t)が-3.5〜6.25,T2DM年代が0.74から1.46 Gaであり,これらのI-タイプ花崗岩が原生代中期から後期の大陸地殻の部分融解メルトとマントル由来のマグマの混合によって生じたことを示唆する.この火成活動はCathaysian地塊内の小大陸同士の衝突によって下部地殻が厚くなったことと関係しており,これは白亜紀前期の太平洋プレートの沈み込みによって引き起こされたものである.
Keywords: U–Pb age, geochemistry, I-type granites, mantle materials, microcontinents, cathaysian block
Island Arc 日本語要旨 2015. vol. 24 Issue 4(Dec)
Vol.24 Issue 4 (December)
[Research Articles]
1. Fission track and U–Pb zircon ages of psammitic rocks from the Harushinai unit, Kamuikotan metamorphic rocks, central Hokkaido, Japan: constraints on metamorphic histories
Ayumi S. Okamoto, Toru Takeshita, Hideki Iwano, Tohru Danhara, Takafumi Hirata, Hirotsugu Nishido and Shuhei Sakata
北海道中央部神居古潭変成岩中の春志内ユニット砂質岩のジルコンU-Pb年代とフィッション・トラック年代:変成史の制約
岡本あゆみ・竹下 徹・岩野英樹・檀原 徹・平田岳史・西戸裕嗣・坂田周平
北海道中央部に分布する神居古潭変成岩類の変成史を制約するため,春志内ユニットの変成砂質岩2試料中のジルコン結晶に対してフィッション・トラック(FT)およびU-Pb年代測定を行った.最も若いU-Pb年代集団の加重平均年代は100.8±1.1 Maおよび99.3±1.0 Ma(2σ)を示した.これらのジルコンは火成起源のoscillatory zoningを示しているため砕屑性ジルコンと推測され,上記の加重平均年代は堆積年代の上限を示す.一方で,FT pooled age は最も若いU-Pb年代集団の加重平均年代とほぼ同じ約90 Maを示した.この事実はFTのリセットが供給源地において起こり,神居古潭変成岩を形成する過程では起こらなかったことを意味する.これらの新しいデータと以前に報告された白雲母K-Ar年代より,春志内ユニットは約100 Ma以降に堆積し,最大深度を経験した後,上昇時(約58 Ma)に局所的な熱イベントの影響を受けたことが推測される.
Key words: deformation microstructures, fission track ages, Kamuikotan metamorphic rocks, U–Pb ages, zircon.
2. Permian back-arc extension in central Inner Mongolia, NE China: Elemental and Sr–Nd–Pb–Hf–O isotopic constraints from the Linxi high-MgO diabase dikes
Jingyan Li, Feng Guo, Chaowen Li, Liang Zhao, and Miwei Huang
中国北東部,中央内モンゴルのペルム紀背弧拡大:Linxi(臨沂)高MgOダイアベース岩脈の元素及びSr-Nd-Pb-Hf-O同位体からの制約
中国北東部,中央内モンゴル臨沂地区の前期ペルム紀(272±2 Ma)のダイアベース岩脈は高いMgO(10.4–12.3 wt%),Cr(301–448 ppm),Ni(167–233 ppm)含有量を有し,LIL元素及び軽希土類元素に富み,HFS元素(Nb, Taなど)に乏しく,枯渇したマントル様のSr [87Sr/86Sr(i) = 0.70315-0.70362],Nd [Nd(t) = +6.8–+7.4],Pb [206Pb/204Pb]同位体比とジルコンHf [Hf(t) = +14.7–+19.1]同位体比を有するが,通常のマントルよりもやや高いジルコン18O(5.2-6.0 ‰,平均5.7 ‰)を示す.これらの地球化学的データは臨沂ダイアベースがリサイクルした地殻成分によるメタソマティズムを受けた枯渇マントルに由来することを示す.元素及び同位体組成のモデリングの結果,初生マグマは沈み込んだ古アジア海スラブから放出されたおよそ1%の堆積物流体を含む枯渇マントルの5〜10%の融解で生じたことが示唆される.中央内モンゴル全域にE-MORBからN-MORB的なREEパターンを示す同時代のマフィック岩が広く分布することを考え,前期ペルム紀のマフィック火成活動は古アジア海の北方への沈み込みに対応する背弧拡大と岩石成因論的に関係していると提唱する.ペルム紀マフィック火成活動と本地域から新たに得られた変成・堆積年代は,古生代末までに古アジア海が閉塞したことを示す.
Key words: back-arc extension, central Inner Mongolia, Early Permian, highly depleted mantle, sediment-fluid metasomatism, Sr–Nd–Hf–Pb–O isotopes.
3. Recognition of shear heating on a long-lived major fault using Raman carbonaceous material thermometry: implications for strength and displacement history of the MTL, SW Japan
Hiroshi Mori, Simon Wallis, Koichiro Fujimoto and Norio Shigematsu
炭質物ラマン温度計を用いた長期間活動を続ける断層の剪断熱評価:西南日本・中央構造線の強度と変位履歴の推定
森 宏・ウォリス サイモン・藤本光一郎・重松紀生
断層運動により長期間にわたって発生する剪断熱の規模は,議論の分かれる問題であるとともに,地殻内部の断層強度を論じる上でも重要である.炭質物結晶化のカイネティクスに関する実験結果と熱モデリング結果との比較は,炭質物ラマン温度計が,深部から上昇してきた断層帯周辺に露出する岩石を用いた,地質学的時間スケールにおける剪断熱研究に良く適合することを示す.西南日本に分布する中央構造線(MTL)は,総延長800 km以上の日本陸上最大の断層である.炭質物ラマン温度計をMTLに近接する泥質岩に適用した結果は,MTLの断層面に対して垂直方向に約150 mの範囲において約60 ºCのピーク温度の上昇を示す.この熱異常と断層との空間的関係は,熱異常が剪断熱に起因することを示す.熱モデリング結果は,記録された熱異常と急激な温度勾配が,数千年の時間スケールでの非常に速い変位速度と整合的であることを示す.しかしながら,この変位速度は,一般的な観測値の範囲からは外れている.このことは一つの解釈として,横ずれ断層運動時に形成された初生的な幅の広い熱異常が,正断層運動の影響により短縮したことが考えられる.変位速度,初生的な熱異常の幅,熱の継続時間およびピーク温度に対する制約結果は,摩擦係数µが0.4以上であることを示す.
Key words:Keywords: carbonaceous-material, coefficient of friction, core analysis, Median Tectonic Line, Raman spectral analysis, Sanbagawa (Sambagawa) belt, shear heating, thermal anomaly, thermal modeling.
関連出版物:The Geology of Japan
関連出版物のご案内「The Geology of Japan」
>正誤表はこちら(2016.9.20更新)
【書籍の紹介】
日本列島の地質学的成り立ちや日本列島で詳細な研究が行われてきた島弧の形成過程を,国際的に広く紹介することは非常に重要です.残念ながら,それらの研究成果の一部は日本語で発表されており,日本人の研究成果や日本の地質に対して関心をもつ海外の研究者のアクセスの妨げとなってきました.よって,日本の地質を総括した英文の出版物が必要さとされ,これまで,数冊の書籍が出版されてきました.しかし,そのような趣旨で書かれた書籍が,最後に出版されてから,すでに25年が過ぎています.この間,地球科学は急速な進歩を遂げました.これは,日本の地質に関しても同様であり,数多くの新事実が明らかになり,日本列島の地質発達史は大幅に書き換えられました.よって,今回,出版された“The Geology of Japan”は,この進歩と研究の最前線を国内外の研究者に紹介する重要な役割を担うと期待されます.本書は,日本列島の地質に関して先端的な研究を行ってきた地球科学者70名以上によって執筆され,以下の12章から構成されています(Google Booksで“The Geology of Japan”という語で検索すれば内容の一部を閲覧できます).
Ch. 1: Geological Evolution of Japan: an Overview
Ch. 2: Regional Tectonostratigraphy---2a. Paleozoic basement and associated cover---2b. Pre-Cretaceous accretionary complexes---2c. Paired metamorphic belts of SW Japan: the geology of the Sanbagawa and Ryoke metamorphic belts and the Median Tectonic Line---2d. Cretaceous–Neogene accretionary units: Shimanto Belt---2e. The Kyushu–Ryukyu Arc---2f. Izu–Bonin Arc---2g. Hokkaido
Ch. 3: Ophiolites and ultramafic rocks
Ch. 4: Granitic rocks
Ch. 5: Miocene–Holocene volcanism
Ch. 6: Neogene–Quaternary Sedimentary Successions
Ch. 7: Deep Seismic Structure
Ch. 8: Crustal Earthquakes
Ch. 9: Coastal geology and oceanography
Ch. 10: Mineral and hydrocarbon resources
Ch. 11: Engineering geology
Ch. 12: Field geotraverse, geoparks and geomuseums.
“The Geology of Japan”では,日本列島の基盤岩類の形成とテクトニクスとの関係が紹介された上で,火成作用について解説されています.また,地質学と他の分野とのリンクのため,地震学・土木工学・資源の分野の専門家も執筆しています.さらに,海外の研究者が,日本の地質を見学する場合を想定して,公共交通機関を使用した巡検コースが紹介されています(第12章).それらの紹介には,ジオパークや博物館の情報も含まれています.なお各章の最後には,地質学的に重要な名称が,漢字・ローマ字・かなで表記してあります.
【購入方法】http://www.geolsoc.org.uk/GOJAPPをご参照下さい.
日本地質学会会員は,ロンドン地質学会の会員と同じ特別価格(37.50GBP+送料 13.50GBP:日本円で約8,000円)で購入可能です.(注)日本地質学会を通じての購入手続きは現合行っておりません.
本書は,日本地質学会と学術交流協定を締結しているロンドン地質学会の出版物でありますが,その企画段階から,日本地質学会の会員が主導的な役割を果たして完成しました.
正誤表
編著者より訂正のご連絡がありましたので,お知らせします。(2016.9.20更新)
The Geological Society 出版物のサイト>
http://www.geolsoc.org.uk/GOJAPP
****************************************************************************
Ch. 2e fig 10,
(誤)Sanbgawa -> (正)Sanbagawa
P 285, Fig. 5.18. Caption, last line:
(誤)Kagishia Prefecture -> (正)Kagoshima Prefecture
P.393, Fig. 8.23. & P. 394, Fig. 8.24. labels:
(誤)Chueto -> (正)Chuetsu,
(誤)Chueto-Oki -> (正)Chuetsu-Oki
P. 458, Fig. 11.1. label:
(誤)Akashi Kaiyo Bridge
(正)Akashi Kaikyo Bridge
p. 471, Fig. 11.18, 3rd diagram:
(誤)2007 Mid Niigata Prefecture Eq. -> (正)2004….
Ch. 11(p. 471, Fig. 11.18)
2004 Mid Niigata Prefecture Earthquake
2007 Noto Peninsula Earthquake
2007 Off Mid Niigata Prefecture Earthquake
Ch. 8 (p. 393, Fig. 8.23, p. 394, Fig. 8.24, p. 397, Table 8.2)
2004 Niigata-ken Chuetsu
2007 Noto Hanto
2007 Niigata-ken Chuetsu-Oki
P. 489, Left Column, Section title:
(誤)Excursion 2 Itoigawa-Shizuoku -> (正)…Shizuoka
P. 489, Right Column, Lines 3 and 7:
(誤)ITSL -> (正)ISTL
P. 494, Left Column, 2nd paragraph from bottom: Mikabu Belt (most mafic volcanic rocks belonging to a Cretaceous ophiolite.
The age of the Mikabu ophiolite is Jurassic
規則改正20.9.12(編集委員会より)
編集規則改正20.9.12(編集委員会より)
地質学雑誌投稿編集出版規則
細則(オープンファイル,特集号,別刷費用など)も含む(2020年9月12日一部改正)
今月上旬には台風10号が南西諸島から九州西方を北上し,広く暴風雨の被害をもたらしました.会員の皆様におかれましては,いかがお過ごしでしょうか.
さて,9月12日の地質学会理事会で,地質学雑誌投稿編集出版規則(以下,規則と記します.)の改定案が承認されました.改定後の規則を,本号に掲載いたしました.主な変更内容を,以下にご説明いたします.
B. 1.の変更:「投稿原稿の筆頭著者は会員に限る.」という原則は変わりませんが,地質学雑誌編集委員会が適当と認めた場合,非会員を筆頭著者とする原稿も査読プロセスに回せるようになりました.非会員からの投稿の動きがあり,今後も学際的な内容の原稿が非会員から投稿される可能性があるという現状に対応したものです.地質学雑誌を,地質学と関連分野に広く開かれた成果発表・議論の場として,会員の皆様に多様な論文をご覧いただきたいと考えております.また,そうすることで,地質学雑誌への投稿原稿数を少しでも増やせたらと期待しております.
H. 1. 9)の新設:現段階では拘束力が強くありませんが,「論文の結論を裏付けるデータ,資料等全ては,適切な公開リポジトリに記録・保管して共有するか,読者の求めに応じて公開できることが望ましい.」に始まる,本誌のデータ共有ポリシーを付け加えました.論説とレターが主たる対象となります.研究データのオープンアクセス推進と共有(異分野間での共有を含む)は,今や国際的な流れですので,Island Arc誌と同等の「推奨」をすることとなりました.ここでの公開レポジトリには,論文の本文,オープンファイル,および地質学雑誌の「報告」記事を含みます.
H. 4. 5)の変更:2019年4月6日より,日本語論文の文献欄に日本語の引用文献を記す際,英訳を一ヶ所にまとめて示すこととなっています.ところが,URLの引用については,同様な変更がなされていませんでした.この度,URLの引用においても,英訳を一ヶ所にまとめることとしました.
細則4の変更:日本語と英語以外の引用文献を日本語論文の文献欄に記す際,これまでは文献の末尾に(in Russian)のように原語名を記していました.しかし,これでは英語論文の文献欄の書式(I. 8.)と合わず,しばしば混乱の原因となっていました.そこで,日本語論文の文献欄の書式も原則英語論文と合わせるように規則を改訂いたしました.また,具体的な用例を新たな規則に合わせて修正いたしました.
以上が主要な変更内容です.データ共有ポリシーが目新しい点ですが,これまでも多くの著者の方には,データのオープンアクセスにご協力いただいておりますので,さほど大きな変更点とは考えておりません.
お陰様で今月号をもちまして,地質学雑誌も通巻1500号となりました.今月号は,論説3編,レター1編,報告1編という多様な論文から構成されています。今後とも,会員の皆様に様々な情報を提供できる雑誌を編集して参りますので、多様な研究成果を地質学雑誌にご投稿いただきますよう,よろしくお願い申し上げます.
地質学雑誌編集委員会
委員長 大藤 茂
(地質学雑誌126巻9号編集委員会より;2020年9月号)
日本地質学会News(ニュース誌)
日本地質学会News バックナンバー
※各冊子PDFをダウンロードしていただけます.
2025年 Vol.28 No.1-12
Sep_no.09
Aug_no.08
Jul_no.07
Jun_no.06
May_no.05
Apr_no.04
Mar_no.03
Feb_no.02
Jan_no.01
2024年 Vol.27 No.1-12
Dec_no.12
Nov_no.11
Oct_no.10
Sep_no.09
Aug_no.08
Jul_no.07
Jun_no.06
May_no.05
Apr_no.04
Mar_no.03
Feb_no.02
Jan_no.01
2023年 Vol.26 No.1-12
Dec_no.12
Nov_no.11
Oct_no.10
Sep_no.09
Aug_no.08
Jul_no.07
Jun_no.06
May_no.05
Apr_no.04
Mar_no.03
Feb_no.02
Jan_no.01
2022年 Vol.25 No.1-12
Dec_no.12
Nov_no.11
Oct_no.10
Sep_no.09
Aug_no.08
Jul_no.07
Jun_no.06
May_no.05
Apr_no.04
Mar_no.03
Feb_no.02
Jan_no.01
2021年 Vol.24 No.1-12
Dec_no.12
Nov_no.11
Oct_no.10
Sep_no.09
Aug_no.08
Jul_no.07
Jun_no.06
May_no.05
Apr_no.04
Mar_no.03
Feb_no.02
Jan_no.01
2020年 Vol.23 No.1-12
Dec_no.12
Nov_no.11
Oct_no.10
Spt_no.09
Aug_no.08
Jul_no.07
Jun_no.06
May_no.05
Apr_no.04
Mar_no.03
Feb_no.02
Jan_no.01
2019年 Vol.22 No.1-12
Dec_no.12
Nov_no.11
Oct_no.10
Spt_no.09
Aug_no.08
Jul_no.07
Jun_no.06
May_no.05
Apr_no.04
Mar_no.03
Feb_no.02
Jan_no.01
2018年 Vol.21 No.1-12
Dec_no.12
Nov_no.11
Oct_no.10
Spt_no.09
Aug_no.08
Jul_no.07
Jun_no.06
May_no.05
Apr_no.04
Mar_no.03
Feb_no.02
Jan_no.01
2017年 Vol.20 No.1-12
Dec_no.12
Nov_no.11
Oct_no.10
Spt_no.09
Aug_no.08
Jul_no.07
Jun_no.06
May_no.05
Apr_no.04
Mar_no.03
Feb_no.02
Jan_no.01
2016年 Vol.19 No.1-12
Dec_no.12
Nov_no.11
Oct_no.10
Spt_no.09
Aug_no.08
Jul_no.07
Jun_no.06
May_no.05
Apr_no.04
Mar_no.03
Feb_no.02
Jan_no.01
2015年 Vol.18 No.1-12
Dec_no.12
Nov_no.11
Oct_no.10
Spt_no.09
Aug_no.08
Jul_no.07
Jun_no.06
May_no.05
Apr_no.04
Mar_no.03
Feb_no.02
Jan_no.01
2014年 Vol.17 No.1-12
Dec_no.12
Nov_no.11
Oct_no.10
Spt_no.09
Aug_no.08
Jul_no.07
Jun_no.06
May_no.05
Apr_no.04
Mar_no.03
Feb_no.02
Jan_no.01
2013年 Vol.16 No.1-12
Dec_no.12
Nov_no.11
Oct_no.10
Spt_no.09
Aug_no.08
Jul_no.07
Jun_no.06
May_no.05
Apr_no.04
Mar_no.03
Feb_no.02
Jan_no.01
2012年 Vol.15 No.1-12
Dec_no.12
Nov_no.11
Oct_no.10
Spt_no.09
Aug_no.08
Jul_no.07
Jun_no.06
May_no.05
Apr_no.04
Mar_no.03
Feb_no.02
Jan_no.01
2011年 Vol.14 No.1-12
Dec_no.12
Nov_no.11
Oct_no.10
Spt_no.09
Aug_no.08
Jul_no.07
Jun_no.06
May_no.05
Apr_no.04
Mar_no.03
Feb_no.02
Jan_no.01
2010年 Vol.13 No.1-12
Dec_no.12
Nov_no.11
Oct_no.10
Spt_no.09
Aug_no.08
Jul_no.07
Jun_no.06
May_no.05
Apr_no.04
Mar_no.03
Feb_no.02
Jan_no.01
2009年 Vol.12 No.1-12
Dec_no.12
Nov_no.11
Oct_no.10
Spt_no.09
Aug_no.08
Jul_no.07
Jun_no.06
May_no.05
Apr_no.04
Mar_no.03
Feb_no.02
Jan_no.01
2008年 Vol.11 No.1-12
Dec_no.12
Nov_no.11
Oct_no.10
Spt_no.09
Aug_no.08
Jul_no.07
Jun_no.06
May_no.05
Apr_no.04
Mar_no.03
Feb_no.02
Jan_no.01
2007年 Vol.10 No.1-12
Dec_no.12
Nov_no.11
Oct_no.10
Spt_no.09
Aug_no.08
Jul_no.07
Jun_no.06
May_no.05
Apr_no.04
Mar_no.03
Feb_no.02
Jan_no.01
2006年 Vol.9 No.1-12
Dec_no.12
Nov_no.11
Oct_no.10
Spt_no.09
Aug_no.08
Jul_no.07
Jun_no.06
May_no.05
Apr_no.04
Mar_no.03
Feb_no.02
Jan_no.01
2005年 Vol.8 No.1-12
Dec_no.12
Nov_no.11
Oct_no.10
Spt_no.09
Aug_no.08
Jul_no.07
Jun_no.06
May_no.05
Apr_no.04
Mar_no.03
Feb_no.02
Jan_no.01
2004年 Vol.7 No.1-12
Dec_no.12
Nov_no.11
Oct_no.10
Spt_no.09
Aug_no.08
Jul_no.07
Jun_no.06
May_no.05
Apr_no.04
Mar_no.03
Feb_no.02
Jan_no.01
2003年 Vol.6 No.1-12
Dec_no.12
Nov_no.11
Oct_no.10
Spt_no.09
Aug_no.08
Jul_no.07
Jun_no.06
May_no.05
Apr_no.04
Mar_no.03
Feb_no.02
Jan_no.01
2002年 Vol.5 No.1-12
Dec_no.12
Nov_no.11
Oct_no.10
Spt_no.09
Aug_no.08
Jul_no.07
Jun_no.06
May_no.05
Apr_no.04
Mar_no.03
Feb_no.02
Jan_no.01
2001年 Vol.4 No.1-12
Dec_no.12
Nov_no.11
Oct_no.10
Spt_no.09
Aug_no.08
Jul_no.07
Jun_no.06
May_no.05
Apr_no.04
Mar_no.03
Feb_no.02
Jan_no.01
2000年 Vol.3 No.1-12
Dec_no.12
Nov_no.11
Oct_no.10
Spt_no.09
Aug_no.08
Jul_no.07
Jun_no.06
May_no.05
Apr_no.04
Mar_no.03
Feb_no.02
Jan_no.01
1999年 Vol.2 No.1-12
Dec_no.12
Nov_no.11
Oct_no.10
Spt_no.09
Aug_no.08
Jul_no.07
Jun_no.06
May_no.05
Apr_no.04
Mar_no.03
Feb_no.02
Jan_no.01
1998年 Vol.1 No.1-12
Dec_no.12
Nov_no.11
Oct_no.10
Spt_no.09
Aug_no.08
Jul_no.07
Jun_no.06
May_no.05
Apr_no.04
Mar_no.03
Feb_no.02
Jan_no.01
投稿稿編集出版規則改正
地質学雑誌電子版投稿編集出版規則主要な変更点
地質学雑誌投電子版稿編集出版規則はこちらから
(2022.12.10承認)
地質学雑誌投稿編集出版規則
細則2_特集号に関する細則
細則5_講座に関する細則
オーサーシップについて:故人などを共著者に加えることを可能とする。 ∵故人が担当した部分の責任ついても考慮
受付処理について、実態に即した形にする。査読に要した期間を実態に即した形にするため
Editor reject(査読に回さない)を、明確な形で、可能とする
紙ベースでの投稿の名残があるので、その点を修正
受理から出版までを実態に即した形にする。受理後に要した期間を実態に即した形にするため
冊子体についても、規則に加筆(特集号についても)
著者の貢献の記述のガイドラインをより明確に。
特集号において、投稿が遅れている論文の取り扱いについて。
遅れている論文の定義の変更:
:従来は特集号提案の受諾から3ヶ月→3ヶ月に延長。(3ヶ月はほとんど機能していないため)
:最初に受理された論文の受理日から一年を経ても受理されない論文(新たなルール)
∵ 従来は冊子体でまとめて印刷する形式だったので、ある程度歯止めがあった。現在は、特集号といえども随時になってしまったので、遅れた論文があってもあまり問題が顕在化されず、そのまま放置のケースが多い。実際125周年特集号(2018年)が未だ完結していない。
(127巻9号編集後記より)
新型コロナウイルス感染症の「第5波」が夏休み期間と重なり,私が在職している富山でも予定していた野外実習を延期せざるを得なくなりました.皆様は,いかがお過ごしでしょうか.
さて,12月号までの受理原稿が出揃っていない状況ですが,来年1月からの完全電子化への準備は進みつつあります.9月の日本地質学会理事会で,地質学雑誌電子版投稿編集出版規則の内容が審議されました.現行の規則からあまり大きく変えないように心掛けましたが,以下のような主要な変更点があります.
まず,現行規則では,原則として受理された原稿を受付処理順に月1回出版しておりました.完全電子化後は,受理順に,J-STAGEの所定のURLに論文の書誌情報とPDFファイルを出版・公開するようになります.論文は,原則として毎年1つの巻・1つの号にまとめるという形にします.また,論文毎に識別番号をつけて1からページ番号をふることを考えています.
地質学雑誌特集“号”や連載講座“号”を構成する論文も上記のルールに沿って出版し,“号”を構成する全ての論文が受理・出版された後に,日本地質学会またはJ-STAGEのウェブサイト上でVirtual Issueという形(前文,構成論文の著者,題名,書誌情報URL等を1つのページにまとめたもの)でも公開するという扱いとします.
毎年1巻1号の出版となるので,口絵(Pictorial)というカテゴリー名をフォト(Photos)に改めます.ただ,完全電子化に伴いカラーページの著者負担が廃止となりますので,フォトのあり方は今後考えていく必要があるのかも知れません.
完全電子化に伴い,国際動物命名規約に従って,動物化石の命名法的行為を含む原稿については,出版前にZooBankへの登録をお願いすることとなりました.
現行のオープンファイルは,J-STAGEのデータサーバーであるJ-STAGE Dataのデータファイルとして公開するよう変更いたします.J-STAGE Dataについては,以下の例が参考になります. 第四紀研究 <https://jstagedata.jst.go.jp/jaqua>
日本リモートセンシング学会誌 <https://jstagedata.jst.go.jp/rssj>
J-STAGE Dataのデータファイルは,独立したDOIとメタデータが付与され外部サービスとも連携するため,検索されやすく,元論文の注目度向上も期待されます.データファイルに変更を加える場合,変更後のデータファイルが新規に作成され,変更前の版(変更履歴加筆)とともにJ-STAGE Dataで永続的に公開されます.データファイルを撤回した場合も,メタデータ,DOIの記載,および変更履歴はJ-STAGE Dataに残ります.
>一定以上に長い原稿は編集委員会や査読者の作業を増やし,受理までの期間を長引かせるので,ページ数制限を現行通り残して,超過分には負担金を設定することとしました.ただし,超過ページに対する負担金,別刷料金等を定めた出版印刷費用等に関する細則(細則3)の具体的内容については,12月の理事会で審議することとなります.
地質学雑誌の9月号は,特集号「日本海拡大に関連したテクトニクス,堆積作用,マグマ活動,古環境(その2)」として,総説1編,論説4編を掲載いたします.これらの力作を執筆して下さった皆様と,編集の労をとって下さった世話人の皆様に厚く御礼申し上げます.会員の皆様には,引き続き,様々なカテゴリーの原稿をご投稿いただけたらと思います.また,地質学会員が興味を持つような題材をお持ちの非会員の方にも,投稿をお勧めいただければ幸いです.今後とも,よろしくお願い申し上げます.
地質学雑誌編集委員会
委員長 大藤 茂
(理事会報告)地質学雑誌完全電子化実施,2022年1月を目標
(理事会報告)地質学雑誌完全電子化実施,2022年1月を目標
2021年4月3日開催の理事会において,地質学雑誌の完全電子化の方針と実施スケ ジュールについて話し合われました.
理事会では,昨今の会員の減少に追い討ちをかけるように,コロナ禍で会員減 少が加速し(会員数昨年度比162名減;ピークの1999年会員数5200名→ 2021年3月末3217名),会費収入の大幅減により,本学会には,もはやコロナ禍 以前と同じような活動を行う財政的な体力はないことが説明されました.このような学会のひっ迫した財政状況に鑑み,地質学雑誌の完全電子化について, 来年(2022年)1月より開始することを目標に,実現に向けた検討をすすめることになりました.一方で,現在,地質学雑誌と一緒に毎月郵送されているニュース誌(日本地質学会News)については,当面は現状と同じ月刊(12回/年)での冊子配布を維持することが確認されました.
今後は,地質学雑誌の完全電子化実現に向けて,電子化の技術面及び編集作業 の問題点の洗い出しとその解決策の検討をすすめることになります.編集出版 作業の迅速化,オープンデータサーバの活用等,電子化のメリットを最大限に感じていただけるような体制づくりに努めます.検討状況については,ニュース誌やジオフラッシュを用いて,会員の皆様に随時ご報告させていただきます. 地質学雑誌の完全電子化は,現在すすめている学会運営全体の見直しの一環として位置づけられています.並行して,学生・院生会員の会費や大会参加費の見直し,シニア会員制度の創設,ショートコースの充実,学会公式SNSの立ち上げ等,新規入会促進や長く会員を継続してもらうための魅力ある会員サービスについても現在検討を進めているところです.こちらもニュース誌やジオフラッ シュ等により会員の皆様に随時検討状況をご報告させていただく予定です.
会員の皆様には,本学会のこのような状況をご理解いただき,ご協力を心より お願い申し上げる次第です.
(【geo-Flash】No.517 2021/4/20掲載)
(無料閲覧)J-STAGE 地質学雑誌のサイトはこちらから
地質学雑誌オンデマンド印刷版年間購読受付のお知らせ
プレプリントサーバーに掲載された原稿の受付について
編集委員会からのお知らせ
著者の役割分担の明記について
(2022年3月1日)
投稿者の方から,「地質学雑誌では,研究全体の統括者を最終著者とするルールはないのか」という主旨のご質問がありましたので,編集委員会の見解をお伝えいたします。地質学雑誌には,お申し越しのような明確な規則や申し合わせはありません。「研究全体の統括者」を最終著者とする雑誌もありますが,地質学雑誌の場合「研究全体の統括者」の指定席はありません。また,役割分担として明記されているcorresponding authorは,これまでの経緯から「連絡責任者」の英訳となっております(地質雑,111/4,253,2005)。 論文に明記された著者の役割は,文責の分担を明らかにし,今後の研究協力や議論を進める上で重要な情報となるだけでなく,職場での業績評価のエヴィデンスとなることもあります。そこで,著者の皆様は,責任著者,研究統括者等の著者の役割分担を,文献リストに続く著者貢献の欄(場合によっては「著者プロフィール」の欄)に必要に応じて明記してください。どうぞよろしくお願い申し上げます。
プレプリントサーバーに掲載された原稿の受付について
(2022年2月15日)
国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)で,日本語対応の新たなプレプリントサーバーが立ち上がる予定です。現行の地質学雑誌投稿編集出版規則 では,プレプリントサーバーに掲載された原稿は受け付けることも引用する こともできません。今後,受け付け及び引用について,学会内で早急に議論を進めていきたいと思います。
特集号一覧
地質学雑誌特集号:Special Issue(2023年〜)
地質学雑誌は,128巻(2022年)より完全電子化となり,J-STAGE 上でどなたでも閲覧できます.完全電子化後の特集号はVirtual Issueとして公開されます.
特集 球状コンクリーションの科学―理解と応用― Spherical concretions: understandings and applications- (2023年)
世話人 吉田英一・西本昌司・長谷川 精・勝田長貴 ▷もくじ(一覧)
冊子販売中(こちらから)
特集 球状コンクリーションの科学
球状コンクリーションの科学
▶︎冊子販売(会員価格:2,600円/冊+送料,5/31締切)のご案内はこちらから
特集 球状コンクリーションの科学―理解と応用―
Special Issue Spherical concretions: understandings and applications
世話人 吉田英一・西本昌司・長谷川 精・勝田長貴
edited by Hidekazu Yoshida, Shoji Nishimoto, Hitoshi Hasegawa, Nagayoshi Katsuta
目 次
※掲載論文はそれぞれJ-STAGE画面へリンクしています.
(前文)Preface
(フォト)国内の上部白亜系におけるアンモノイドを含むコンクリーションの産状.御前明洋, 村宮悠介/Modes of occurrence of concretions containing ammonoids from the Upper Cretaceous in Japan. Akihiro Misaki, Yusuke Muramiya 128 巻 1 号 p. 27-28,公開日: 2022/02/22
(総説)球状コンクリーションの理解と応用.吉田 英一/Spherical concretions : understandings and applications. Hidekazu Yoshida 129 巻 1 号 p. 1-16,公開日: 2023/01/26
(論説)双葉層群足沢層(上部白亜系コニアシアン階下部)浅海成細粒砂岩の大型アンモナイト密集層と巨大炭酸塩コンクリーション濃集層.大森 光,安藤寿男, 村宮悠介, 歌川史哲, 隈 隆成, 吉田英一/Large ammonoid shellbed and huge calcareous concretion bed in shallow-marine fine sandstone of the lower Coniacian Ashizawa Formation, Futaba Group, Northeast Japan. Hikaru Omori , Hisao Ando, Yusuke Muramiya, Fumiaki Utagawa, Ryusei Kuma, Hidekazu Yoshida 129 巻 1 号 p. 105-124,公開日: 2023/02/22
(レター)男鹿半島鵜ノ崎海岸の中新統西黒沢層・女川層中に見られる巨大鯨骨ドロマイトコンクリーション群の形成条件.隈 隆成,西本昌司, 村宮悠介, 吉田英一/The formation conditions of gigantic dolomite concretions including whale bones exposed in Unosaki coast, Oga peninsula, Japan. Ryusei Kuma, Shoji Nishimoto, Yusuke Muramiya, Hidekazu Yoshida 129 巻 1 号 p. 145-151,公開日: 2023/02/22
(ノート)名古屋港で採集された完新世炭酸塩コンクリーションの14C年代測定.南 雅代, 隈 隆成, 浅井沙紀, 郄橋 浩, 吉田英一/14C dating of Holocene carbonate concretions collected in Nagoya Port area, central Japan. Masayo Minami, Ryusei Kuma, Saki Asai, Hiroshi A. Takahashi, Hidekazu Yoshida 128 巻 1 号 p. 239-244,公開日: 2022/11/03
(総説)玄能石および玄能石コンクリーションの産状と成因.村宮悠介, 吉田英一/ A review of the occurrence and the origin of glendonite and glendonite concretion Yusuke Muramiya , Hidekazu Yoshida 128 巻 1 号 p. 395-409,公開日: 2022/12/29
(論説)球状コンクリーションの展望:地球と火星での続成過程解読の観点から.Marjorie A. Chan/A Perspective on Concretions: Deciphering Diagenesis from Earth to Mars. Marjorie A. Chan 128 巻 1 号 p. 445-464,公開日: 2022/12/29
(総説)地球と火星に見られる球状鉄コンクリーションの産状と成因.長谷川 精,吉田英一,城野信一/Occurrence and formational mechanisms of spherical Fe-oxide concretions on Earth and Mars.Hitoshi Hasegawa, Hidekazu Yoshida and Sin-iti Sirono 129 巻 1 号 p. 199-221.
(ノート)微小領域蛍光X線マッピングの応用:鉄コンクリーション内部に見られる鉄バンドの形成プロセスと移動速度の評価.勝田長貴, 城野信一, 梅村綾子, 河原弘和, 吉田英一/Applications of micro-X-ray fluorescence mapping to iron bands in iron-oxide concretion to evaluate its formation and reaction rate. Nagayoshi Katsuta, Sin-iti Sirono, Ayako Umemura, Hirokazu Kawahara, H Hidekazu Yoshida 128 巻 1 号 p. 81-86,公開日: 2022/05/21
(論説)球状鉄コンクリーションの鉄殻成長過程の実験的解明.岡村裕之,城野信一/Experimental study on the growth process of iron rind of Fe-oxide concretions.Hiroyuki Okamura and Sin-iti Sirono 129 巻 1 号 p. 255+262
(レター)画像解析と数値シミュレーションによる鉄コンクリーションのサイズ分布と空間分布の起源の解明.城野信一, 田村美紗樹/Origin of the size and spatial distribution of iron-oxide concretion derived from the image analysis and numerical simulation. Sin-iti Sirono , Misaki Tamura 128 巻 1 号 p. 173-177,公開日: 2022/09/22
(ノート)炭酸カルシウムコンクリーションの水理・力学特性.竹内真司, 後藤 慧, 中村祥子, 吉田英一/Hydro-mechanical characterization of calcium carbonate concretions Shinji Takeuchi, Satoshi Goto, Sachiko Nakamura, Hidekazu Yoshida 128 巻 1 号 p. 371-375,公開日: 2022/12/29
(ノート)コンクリーション生成メカニズムの工学的応用事例.丸山一平, 吉田英一, 山本鋼志, 野口貴文/Engineering application examples of concretion formation mechanisms. Ippei Maruyama, Hidekazu Yoshida, Koshi Yamamoto, Takafumi Noguchi 128 巻 1 号 p. 281-285,公開日: 2022/12/08
地質災害調査
奈良県上北山村西原の国道169号土砂崩れ
奈良県国道169号法面崩壊地調査結果
1.はじめに
奈良県奈良市と和歌山県新宮市を結ぶ国道169号線では、2007年1月30日に法面崩壊が発生し、車が巻き込まれ、三名の命が失われた。本国道は、紀伊半島を南北に縦貫する延長約167kmの幹線道路で、半島内陸部と沿岸部とを結ぶ広域ネットワークの役割を担っているが、現在は崩壊地付近が閉鎖されている。崩壊原因のすみやかな究明と、安全を確保した上での開通が待たれているところである。
今回、次のように合同調査を実施した。調査時には、崖から不安定な石が落下する危険性があり、また、警察の調査も進行中であったため、調査は必ずしも十分ではなかったが、一応の結論が得られたので、その結果をとりまとめる。
期日: 2007年2月6日 午後1:00〜4:00 調査参加者 千木良雅弘(京都大学防災研究所、日本応用地質学会関西支部長、日本地すべり学会理事)
諏訪浩(京都大学防災研究所)
釜井俊孝(京都大学防災研究所)
藤田 崇(断層研究資料センター)
三田村宗樹(大阪市立大学)
天野一男(茨城大学、日本地質学会地質災害委員長)
後藤 聡(山梨大学、土木学会・同上小委員会委員)
大田英将(大田ジオリサーチ、同上小委員会委員)
稲垣秀輝(株式会社環境地質、同上小委員会委員)
調査結果はこちらから(618kb)
平成19 年(2007 年)能登半島地震 現地調査速報 (2007.6.20)
東京都渋谷区の温泉施設の'07.06.19爆発と緊急提案
地質災害委員会
東京都渋谷区の温泉施設の'07.06.19爆発と緊急提案
当会正会員の中野啓二氏より、爆発事故に関する見解が寄せられましたので、掲載いたします.なお、本見解は中野氏の個人的見解ですので,ご了解下さい。
(日本地質学会地質災害委員会)
*1;Terra-Fluid Systems 代表 中野啓二
〒300-1216 茨城県牛久市神谷5-32-23
E-mail;keizi.nakano@nifty.com
1. 「爆発」のあらまし
2007年6月19日午後2時半頃、東京都渋谷区松濤1丁目という東急渋谷駅から300mほどの住宅密集地にある温泉施設「シエスパ」別棟で温泉付随メタンガス爆発が発生した。その結果、3人もの方々が亡くなられ、通行人1人含む3 人の方が重症を負われた大惨事が起きた。この別館の地下で爆発が起こり、別舘は、屋根や壁が残らず吹き飛ばされ、押し曲げられた鉄骨・鉄枠のみの残骸と化して、ガス爆発の激しさを示している。
消防・警察の捜索などにより、泉源の井戸口元・気水分離器・貯湯槽が設置されていた上記別棟地下で爆発が起こったと鑑定されている。
事件後、温泉水汲み上げに付随したメタンガスの管理の杜撰さや「温泉法の盲点」が指摘されている。東京都は、事件翌日6月20日には、保健所・警察・消防共同による都内の温泉施設の一斉点検を実施した。また、すぐに警視庁は施設運営会社、設備・建物の設計・施工を担当した建設会社など約10箇所を業務上過失致傷容疑で捜索を行う予定との報道が成されている。一方、温泉行政を統括する環境省大臣談話として、温泉法の不備があり、検討した旨の発言があった。東京都石原知事も、この問題に対し、法改正を視野に入れ、専門家委員会を直ちに立ち上げ検討に入ることを声明した。
2. 今回の爆発事故のその危険の広域性と原因に関連して
今回爆発を引き起こした温泉汲み上げに付随する水溶性メタンガスは、マスコミなどでは「南関東ガス田」がその起源とされている。
このような温泉揚湯に付随する水溶性可燃ガスは、決して「南関東ガス田」だけでなく、化石海水を主たる温泉水成分とする食塩泉(かん水)揚湯には、量の多少はあるが、可燃性ガスが付随していることは一般的である。したがって、わが国においては、新第三紀以降の海成堆積岩を多孔質温泉貯留層(砂岩層や礫岩層など)とする殆どの温泉では、温泉揚湯に伴った引火を引き起こす程度の可燃性ガスを付随することが多い。このほか、四万十層群相当層の砂岩泥岩互層などの裂か型温泉貯留層から湧出する温泉にも、メタンガスを主成分とする可燃性ガスをかなりの量伴うこともある。
このような地質条件は、表日本や裏日本の日本国中における平野や丘陵部を作る地層であり、四万十層群の地質は一部山地を構成する地質として日本全体に広く分布するので、北は北海道から沖縄まで日本中に広範に温泉付随可燃性ガスによる爆発事故の可能性を持つ温泉が分布すると共に、平野部や丘陵部において都市型温泉リゾ−トや温泉付きマンションなどとして、可燃性温泉ガス湧出地点が人口密集地に次々と創り出され、温泉ガス爆発の危険性の広域化と深刻化が加速している。
また、今回のガス爆発について、各種報道によれば、施設管理者や施設設計施工者の責任が問われているが、それはそれで当然の責任を負うべきと考える。しかし、この事件はそれだけの責任で良いのだろうかと大きくは2つの疑問を持つ。
その1つは、温泉開発には、3段階の許可申請(?温泉掘削許可申請、?動力設置許可申請、?温泉利用許可申請)を、最寄の保健所を通じて、上記?と?は都道府県知事の許可申請、上記?は上記?は知事・特例市長・区長の許可申請の下に温泉施設が利用されたりしている。都道府県知事は、上記?と?の許可申請について、各自然環境保全審議会温泉部会に諮り、その段階に応じて必要な技術的助言と呼ばれる行政指導が行われながら、それらの首長名で許可書が交付される。この中の「温泉利用許可申請」という段階では、温泉施設管理者などの利用当事者から、温泉配管・貯湯槽・浴槽・送湯ポンプなど硫化ガス対策やレジオネラ菌などの温泉入浴関連施設などの各種図面だけでなく、可燃性ガスの大気中への排出システムをも含む施設図などの図面が都道府県・特例市・区などの温泉担当部局に許可申請として提出される。各温泉担当窓口は、これら図面を元に、可燃性ガスが大気中に安全に放散出来るのかのチェックも含めて、温泉利用施設の全体に対する安全性について担当部局によるチェックが行われ、これらが了承されると、「温泉利用許可証」として首長名により温泉施設利用の許可が下りるというシステムになっている。このような温泉行政のチェックシステムの中で、メタンガス排気管が設置され使われているのである。その時のチェックと、点検はどのようになっていたのかも今回の爆発事故の重要な反省点と考えることが、責任論に対する疑問点の第1点である。
一昨年の「東京都北区浮間の温泉掘削現場のメタンガス火災」で東京都では急遽、掘削時におけるメタンガス火災に関する指導要綱が作成された。この指導要領も掘削時のどのような作業状況・作業段階で危険が高まるのか特段の記載もなく、メリハリのない危険回避指導書となっているような印象を持っている。この東京都北区浮間の火災事故についての拙著コメント(地質学会災害研究委員会HP)でも述べたように、温泉付随メタンガスの大気放散という現行の処理法に、第2の疑問を持っている。
東京都の温泉随伴メタンガス火災が議論された委員会では、掘削後の温泉施設利用に伴う可燃性ガスの安全性については議論されることはなかったらしい。そして、「メタンガスの比重が大気の4分の1程度と軽いことを利用して、安全に大気中に放散する」という形の処理についての検討はなかった。この『不要な温泉付随可燃性ガスを大気中に捨てる』という安易な処理法こそが、温泉行政当局・温泉施設管理者に「可燃性危険物」である温泉付随メタンガスを慎重かつ厳格なチェックや管理しないで、可燃性ガスを伴う温泉を漫然と利用しているという危険極まりない状況を醸成してきたのではないか。メタンガスは、炭酸ガスの約10倍以上といわれる室温効果ガスであり、地球環境に大きな負荷を与えるものである。環境に優しい温泉利用システムに取り組めば、現下の技術ではメタンガスを燃料資源として有効利用する観点があれば、現行法の処理と違ったものと成り、可燃性ガスを見る視点も「ポイ捨て」といった視点ではなく、管理し利用するというより安全側の視点に変わったのではないかと悔やまれる。
また、報道によれば、当の温泉調査会社や掘削会社もメタンガスの危険性について、温泉施設運用会社の親会社に「強く警告していた。その後の管理に憤りを覚える」とかの記者会見報道がなされている。この記者会見内容自身、温泉資源開発・保全に携わる一員として、恥ずかしさを覚えた。メタンガスは「室温効果ガスとして、全世界的に炭酸ガス排出と共に、排出削減が叫ばれている」ガスで、これを温泉という地下資源を『癒しを与える場』として使う一方で、環境破壊物質を平然と撒き散らす、このような地質屋の姿勢は社会的に受け入れられるものではない。社会が専門家(地質研究者・技術者も含む)に寄せる大きな期待や要請は多岐にわたるが、その中の1つとして環境改善に対する期待や要望がある。上記の地質関係者の姿勢は、社会の「科学技術の予見性」から「少しでも環境悪化防止・より良い環境創出」といった期待や要望に対し、逆に背を向けた姿勢であると言わざるを得ない。
また、京都議定書という「室温効果ガス排出削減」の国際批准に主導的役割を果たしてきた日本の環境省が、現在の温泉行政の所管官庁である。この所轄官庁が、温泉随伴可燃性ガスを「大気放散」という室温効果ガス撒き散らしを指導していること自身、環境省の室温効果ガス対策へのダブル・スタンダ−ドで、世界から真意が問われることである。このような、官・民渾然一体となった可燃性温泉ガスへの「ポイ捨て」姿勢が、都内の可燃性ガス付随の温泉施設において警報装置も殆どが設置していないという、安全意識の希薄さ・環境配慮の欠落を生ませていると結論せざるを得ない。さらに言えば、世界に誇る日本の癒し文化の1つである温泉文化において、一部の温泉において室温効果ガスを故意に大気放散させて温泉が維持されているといった「反癒し・反環境」行為を、平然と行政の技術的助言という行政指導の元で行っていることは一種のモラル・ハザ−ドではないのか。
このような、温泉開発・利用の技術者、施設管理者や温泉行政側において、温泉随伴可燃性ガスに対する「ポイ捨て」というモラル・ハザ−ドを起こしている状況が、今回渋谷の惨劇を間接的に引き起こしたと考える。
3. 今後の温泉随伴可燃性ガス爆発防止と日本の温泉文化の発展のために
可燃性ガス随伴温泉利用のシステムを環境により優しくしかつ随伴可燃性ガスの安全な処理は、現下の技術では、まず第一に燃料資源として活用し室温効果の高いメタンガスから炭酸ガス(室温効果// CH4:CO2 ≒ 10以上:1)に変換して大気中に排気する。決して、現行のような室温効果が炭酸ガスの10倍以上といわれるメタンガスをそのまま『ポイ捨て』の大気放散はさせない。可燃性ガスを燃料とする時、従来は鉱業法等の規制対象とされていたが、温泉井戸については、隈なく安全かつ環境に優しく処理をするという点では、町の中のガソリンスタンドに準じた消防法の適用で、その安全性を担保する。メタンガスを燃焼すると、1molのメタンガスからは1molの炭酸ガスと 2molの水が出来る。
1molメタンガス 2mol酸素 1mol炭酸ガス 2mol水
CH4 + 2O2 −−> CO2 + 2H2O
このように、メタンガスガスを燃焼させ炭酸ガスに変換させると、室温効果は約10分の1になる。このようにして、メタンガスを燃料として利用し、炭酸ガスに変換させることにより、メタンガス随伴温泉利用システムは、環境に少しは優しい温泉利用システムに変換することができる。ただし、将来、メタンガスの有効利用と環境負荷に対しもっと優れた技術が開発されれば、新しい技術の方に移っていくことを前提としている。「癒しの文化としての日本の温泉文化」を支える施設として環境により優しいシステムに改善して行くことは文化的にも重要なことである。
通常、温泉システムは、揚湯・送湯ポンプ・照明などに電力エネルギ−を必要とし、入浴施設にはかぶり湯・流し湯など真水をお湯にするボイラ−装置に見られる給湯加温エネルギ−が必要とされる。これら電力と加温のエネルギ−は、ガス・熱電併給システム(コ−ジェネレ−ション・システム;以下コ−ジェネと呼ぶ)で行えば、温泉随伴可燃性ガスを燃料として使用でき、エネルギ−変換効率を80%近くまで高めることができて、温室ガス排出削減効果も大きい。このような、ガス・コ−ジェネの中で温泉随伴可燃性ガスが燃料として利用され、消防法に基づいた危険管理が現在のようなガス警報器が設置されていないなどという状況は解消されると考える。このコ−ジェネ設備は初期投資が大きいが、室温ガス削減権ファンドなど政策投資的資金の導入や政策的補助金・低金利融資などにより、普及をはかられることが望まれる。
さらに付け加えるならば、都市部のコ−ジェネの入浴施設は、新潟中越地震時に見られたように地震災害時のライフライン切断時においても利用できる大型入浴施設となり、地域の入浴施設として地震復興の重要な拠点ともなりうる。このように見れば、自治体もこのような可燃性ガス随伴温泉施設の政策的展開も人口密集地では必要ではなかろうか。
このような施設に変換すれば、水溶性可燃ガスを伴う温泉資源も、単に危険な面だけを持った地下資源ではなく、温泉施設の作り方・管理のありようにより、日本の温泉文化の担い手として胸の張れる環境に優しい温泉資源となり、ライフラインが破壊されるような大災害時の非常用入浴施設として地震復興に阿智あがる勇気と力を後押しする能力を待った地下資源へと変貌する。
そこで、以下には、具体的にどのようにしたら危険で環境に優しくない温泉資源・温泉施設を、日本の誇れることが出来る、環境に優しい温泉文化および地震災害時の復興拠点を担う温泉資源・温泉施設へと変換出来るのか、現在気が付くところで、提案をしたい。
緊急対策
1)全国の可燃性ガス随伴温泉点検調査。点検対象を、温泉泉源の温泉湧出母岩が、四万十層群相当層の堆積岩類、新第三紀以降の堆積岩類である温泉について、調査は次の2段階で行う。
・1段階目は、可燃性ガスが随伴するか否かを、ガス検知管で行う。
・2段階目は、随伴する場合のみについて、通常の揚湯状態において、その量について定量。
2)可燃性ガスを随伴する温泉は、直ちに消防署へ届け出、施設の安全化について消防法の下に指導と安全化改善施工の確認・点検を受ける。
今後の対策
1)温泉揚湯に伴い可燃性ガスが随伴する場合、可燃性ガスはきちんと集め全部燃焼することを基本とする。可燃性ガスが微量で、収集できず燃焼不可能のものか、別途定める処理法で処理する。
2)政策的融資や室温ガス排出権ファンドなどによるガスコ−ジェネの普及をはかる。
3)温泉開発は、既述したように、法的に、温泉開発・管理者は温泉掘削から温泉利用までの間に3段階の許可申請(a掘削許可申請、b動力設置申請、c利用許可申請)を最寄の保健所を通じて、各都道府県の知事。特例市市長ないし区長宛に申請し、許可を得なければならない。
このような温泉開発・利用における法的システムにのっとり、2度と今回のような温泉随伴可燃性ガスの悲劇を起こさせないための提案を、以下、行いたい。
この前提となるのが、現下のメタンガス関連技術においては次善の策として、室温効果ガスである温泉随伴メタンガスを、基本的には燃料として活用し、環境負荷を軽減させるよう炭酸ガスに変換して排出する。このことにより、わが国が世界に誇りうる温泉文化の裏の一部で行われている室温効果の高い『メタンガスのポイ捨て』を止め、環境に優しいシステムの中で世界に胸の張れる温泉文化を発展させていく土壌を作ることである。
以下、各許可申請時に、検討されるべきメタンガス問題への提案である。
a:温泉掘削申請時の処置
・温泉掘削中の火災を防ぐために、東京都は北区浮間の温泉掘削現場火災を踏まえ、全国に先駆けてガイドラインを作った。作ったことは評価できるが、実際の掘削ガス火災の危険は、暴噴時や揚湯時といったある条件において危険が増大するのであり、掘削中最初から最後まで高度の監視体制・緊張を強いることはかえって危険と考えられる。したがって、他の道府県や都も、温泉掘削作業のどのような時に引火の危険があるのか、掘削工程の中で再度危険度の検討する必要があると考える。
・現在「建設物価」の中の温泉掘削という工事費積算の工事仕様のガイドラインを示す本の中には、温泉井戸が基本的には部分セメンテイングとなっている。このことは、掘削した井戸の穴にケーシング・パイプとの穴をあけられた地質との間に縦の隙間を作ることと成る。 この縦の隙間は、天然ガス・環境汚染物質などを地質・地層のバリヤ−性能をなくし、上下方向に移動させる通路を人為的に作ることとなる。石油・天然ガス地域で、石油ガス井のセメンテイングが不十分で、井戸周りからメタンガスが漏れ出し、井戸周辺の大規模なセメント注入が行われ、メタンガスの地表への漏れ出しをとめさせたこともある。このように、温泉井戸を掘削する場合には、井戸の周辺地質と挿入されたケ−シングパイプとの間は原則フルホ−ルセメンテイングとする。
・掘削終了時に行われる連続揚湯試験後の温泉成分析(温泉中分析)時には、ガス検地管による可燃性ガス随伴の有無とその時の量についても定量する。
・可燃性ガスを随伴する井戸であれば、井戸口元・検量口など井戸地表設備は開放的な条件下の地表設置とし、蓋付きコンクリ−ト桝や地下施設とすることは不許可とする。
b:動力設置申請時の処置
・動力装置申請書には、随伴可燃性ガス分析結果も添付し、かつ随伴可燃性ガスに対応した井戸口元構造になっていることを証明し、各都道府県温泉などの担当部局はそれらを確認のうえ動力許可申請の許認可に対応する。
・ 動力装置設置後の保健所立会いの新規温泉泉源の湧出量・泉温・温泉分析に、温泉分析本分析の指定項目に可燃性ガスの分析・定量を追加する。
・別途可燃性ガス安全対策の専門家の会議で検討し、安全かつ環境に優しい方法で可燃性ガスを処理し後述の設置設計指針など、例えば、気水分離機・曝気装置付き貯湯槽・ガスモニタリング・爆発防止システムなど、の設置義務基準およびそれらの設計基準などを上記専門家会議で決めた基準に従い消防法適用案件となるか、順来どおりの保健所などの管理に置くかの判定基準の策定、それに応じた各種基準に従った温泉利用設備設計書の点検・確認を行政側は行う。
c:温泉利用許可申請
・従来の申請添付書類(温泉入浴施設の設計図・配管図・その付属施設の設計図・設備関連図など)と共に、可燃性ガス随伴の有無や随伴した場合にはその基準に基づいたガス燃焼ボイラ−などの諸施設の構造設計図・設備図などの確認検査を、保健所は消防本部と共に行う。
・温泉施設運転後の確認は、消防署によりガソリンスタンドで行われているような定期・抜き打ち安全点検検査により、施設管理者側の可燃性ガスに対する安全モニタリング・管理点検体制を点検指導する。
以上の事柄を提案したいが、再度まとめると、以下のように要約される。
・温泉随伴可燃性ガスは、全国の温泉で付随している可能性があり、その危険性から温泉分析成分の1つとして加え、全温泉で可燃性温泉ガス随伴の有無・量について把握する。
・温泉随伴可燃性ガスは、室温効果ガスであるので、基本は燃焼資源として有効活用するにより、消防法適用下の可燃性危険物扱いとし、施設運用者側・行政側の管理堆積を強化する(管理点検をガソリンスタンド並みにする)。
・このことは、同時に、可燃性ガスの殆どの温泉で行われている「室温効果ガスポイ捨て温泉シツテム」を「環境により優しい温泉システム」に変換し、わが国の温泉文化を名実共に世界に誇れる「癒し文化」とする基礎とする。
・可燃性温泉ガス専門家に、諸施設の安全基準とその管理について、指導要綱を緊急に作成してもらう.
以上。
平成19年(2007年)新潟県中越沖地震
地質災害委員会
平成19年(2007年)新潟県中越沖地震:速報・関連リンク
【平成19年(2007年)新潟県中越沖地震】 気象庁命名
The Niigataken Chuetsu-oki Earthquake in 2007
発生時刻: 平成19年(2007年)7月16日10時13分
震源の位置: 新潟県上中越沖 北緯37.5度、東経138.6度、深さ約17km
マグニチュード 6.8、 最大震度 震度6強
状況
■新潟大学調査団が緊急調査を開始しています。
■金沢大学現地調査団
20日から現地被害状況調査を開始します。
■信州大学調査団
今週末より調査開始予定です。
■山形大学地域教育文化学部生活総合学科生活環境科学コース地学(川辺)研究室
2007年新潟県中越沖地震地質災害調査報告(→調査報告はコチラから)
その他、会員の方で緊急調査を行っている方、あるいはご予定の方は、学会事務局までご連絡願います
関連リンク
■気象庁:地震情報
■産業技術総合研究所 平成19年(2007年)新潟県中越沖地震
■海洋研究開発機構 遠地実体波を用いた震源破壊過程の解析結果など
■国際航業(株)現地航空写真など
2006年集中豪雨災害緊急調査報告
2006 年集中豪雨災害についての緊急調査報告
参加者:小坂共栄,鈴木啓助,三宅康幸,原山 智,公文富士夫,大塚 勉,村越直美
(文責:公文富士夫)
経過・日程
7月21 日(金) 土砂災害の実態を知り,緊急調査の打ち合わせ
・長野県土木課への事情聞き込みと調査団による調査の申し入れ
・岡谷市への調査の申し入れ 7月22 日(土) ・9:00 信州大学理学部出発(松本市)6名
小坂,三宅,鈴木,原山,公文,大塚,村越
・10:00 岡谷市湊の災害現地本部へ到着
現地本部の首脳陣は,行方不明者の捜索を再開するかどうか,という相談と現地視察のために留守であった.電話で連絡を取ってもらい,1時間余待機するも,捜索活動の妨げになることと危険性が去らないという理由で,調査を見合わせるように指示された.湊での調査は後回しにして,別の場所での調査を行うことにした.・11:00 前日地滑りの「おそれ」が報じられた岡谷市花岡地区の西側斜面で地滑り調査.
・13:40〜14:30 昼食・休憩
・14:50〜18:00 岡谷市川岸地区での災害調査
・19:00 松本着
簡単なまとめ行った.行方不明者が発見され,天候にも問題がなければ,翌日も原山・大塚・村越が調査にでることにした.
調査結果の概要
1.岡谷市花岡地区の「地滑り」の有無
21 日夜に地滑りの恐れがあるということから住民が避難した花岡地区の西側の山塊を調査した.航空写真や地形図では地滑り地形が認められたからである.地滑りのトレースに直行する方向で尾根に沿って地表での亀裂や滑落崖の存在をチェックしたが,新しい亀裂等は見いだされなかった.1〜3mほどの比高をもつ滑落崖様の微地形は何段も認められた(その一部は戦中・戦争直後につくられた段々畑の跡という指摘あり)が,新期の活動を示すものはなかった.
花岡地区の山裾につくられた畑の斜面(土手)の崩壊が1ヶ所でみられ(花岡1の手前のブルーシートの部分),表層地滑りのミニチュアとしても,興味深いものがあった
2.岡谷市川岸地区の「土石流」
比較的広い集水域を持つ谷でるにも関わらず,出口が狭く絞り込まれていることが,この谷の地形的特徴である.おもに2つの経路を流れてきた流水が,谷の出口にある狭窄部(高速道路の橋脚のある位置)で収斂して勢いを増加させ,その周囲および下流側に襲いかかったものと思われる.川岸地区では1名の方が亡くなられたが,その狭隘部分にある住宅で被害を受けられた.流路に橋が架かり,暗渠になった部分が埋積され,詰まったことも要因の一つであろう.
本流では流路からはみ出したような流れの跡が見られないこと,流れが慣性力をもって運動した痕跡がないこと,傾斜の変換点や平な場所で横に広がった流れ(flood flow)にすぐに転換していることなどの点からみて,厳密な意味の土石流と言うよりは,洪水流と見た方が良いと思われる.
写真3
洪水時には芦ノ沢側の雨水が左側の道路を流れ下り(路面の浸食状態から見てかなりの水量と流速があったはず),その一方で本流側の水路(水田の向側の凹みで重機が動いているところ)を多量の洪水流が流れ下った(ただし,水路から溢れ出すほどではなかった).
写真4
両者が合流したのが赤い自動車の先にある橋の部分(今も水が流れている部分).合流部の右手の家屋が大きな被害を受けた.また,その下流側へも多量の土砂を運び出し,多くの家屋に土砂が侵入した.
平成16年7月福井豪雨 写真続報
2004年浅間噴火:関連リンク
静岡大会特別セッション「宮城県沖及び宮城北部の地震と地質災害」
令和2年台風10号による災害の情報
令和2年台風10号による災害の情報
▶︎産総研地質調査総合センター
2020年9月6日に発生した宮崎県椎葉村下福良の斜面崩壊地の地質
上空からの御嶽山の噴煙の写真(2014.10.10)
上空からの御嶽山の噴煙の写真
石渡 明(日本地質学会会員)
御嶽山噴火の約4.5時間後、2014年9月27日16時24〜26分に御嶽山北西方上空の航空機から撮影された御嶽山噴火の噴煙の写真をお送りします。 撮影者は東北大学理学部地球惑星物質科学科4年(東北アジア研究センターで卒論研究中)の鈴木陽一君です。彼はロシアに短期留学していましたが、ドバイ経由でエミレーツ航空EK318便(17:35成田着予定、実際には17:45着)にて帰国する際、韓国上空を経て福井県沖から日本上 空に入ったところでこれらの写真を撮影しました。 その際、能登半島が右前方に見えた(つまり飛行機は北に向かって飛んでいた)とのことなので、この飛行機のパイロットは御嶽山の噴煙を避けるために、直前で北方に回避した可能性があります。 つまり、この写真はその回避行動の際に、御嶽山の北西方(ないし北方)から撮影されたと考えられるわけです。 その後、この飛行機は新潟県・群馬県上空を経て成田に着陸したとのことで、この回避行動のために約10分の遅れが生じた可能性があります。上昇して東へたなびく御嶽山の噴煙を、西から低角に照射する太陽光で見事に撮影した貴重な写真だと思いますので、撮影者の了解を得て会員の皆様に紹介いたします。
※それぞれクリックで拡大
(時系列順に上段左から右、下段左から右の順に並んでいます)
(2014.10.10)
2014年7月9日南木曽,8月6日岩国,8月17日福知山・丹波における土砂災害
2014年7月9日南木曽,8月6日岩国,8月17日福知山・丹波における土砂災害
若月 強・山田隆二・酒井将也(防災科学技術研究所)
竹田尚史(筑波大学地球学類)
2014年は8月の広島災害をはじめ複数の土砂災害により,多くの人命が失われた.防災科学技術研究所では,南木曽,岩国,福知山・丹波において,災害直後に現地調査を実施した.ここでは,降雨,地質,地形の特徴に関する結果と見解を述べる.
1.2014年7月台風8号による南木曽土石流災害
(http://mizu.bosai.go.jp/c/c.cgi?key=nagiso_debris_flow)
2014年7月9日の台風8号による豪雨によって,長野県南木曽町読書地区の梨子沢では9日17時41分に土石流が押し寄せて1名が犠牲となった.避難勧告が出たのは被災から約10分後,土砂災害警戒情報が出たのは18時15分であった.
表1 観測点における積算雨量の最大値
(拡大は画像をクリック)
1.1. 降雨 南木曽町の雨量計(長野県河川砂防情報ステーションで閲覧可能)の中で,降水量が多かったのは蘭と三留野であることから,南木曽岳付近だけの局所的な豪雨であったと考えられる(表1).両地点では,10分雨量は約20 mm,1時間雨量は約70 mm,2時間雨量は約100〜120 mmを記録しており,3時間以上の雨量はあまり増えていない.すなわち,雨が強くなり始めてわずか2時間程度で土石流が発生した.2時間までの平均降雨強度は最大100年程度の再現期間となる.なお,同じ花崗岩地域である防府市における土石流災害(2009年7月:表1)と比較すると,10分〜3時間雨量に両地域に大きな違いはないが,防府の6時間雨量は南木曽の約2倍になっており強い雨が約6時間降り続いたことがわかる.
1.2. 岩質と風化土層 土石流が発生した梨子沢付近の地質は,5万分の1地質図「妻籠」によると,南木曽町役場より南西部には苗木・上松花崗岩が分布しており,岩相は粗粒黒雲母花崗岩(Ga1)である(以下,上松花崗岩と呼ぶ).南木曽町役場より北東部には領家帯の木曽駒花崗岩が分布しており,岩相は中粒斑状角閃石黒雲母花崗岩(Gk)である(以下,木曽駒花崗閃緑岩と呼ぶ).梨子沢では,山頂の南木曽岳(1,679m)を含む上流域に上松花崗岩,中〜下流域に木曽駒花崗閃緑岩がそれぞれ分布している.南木曽岳周辺の標高1000m以下の場所しか確認できていないが,木曽駒花崗閃緑岩の地域には厚さ3 m以上の原位置風化土層が散見されるのに対して,上松花崗岩の風化土層は概して1 m以下である.ただし,標高が高くなり斜面勾配が大きくなるほど風化土層が薄くなる傾向があるため,崩壊が発生した1000m以上の高標高部の土層構造については詳しく調べる必要がある.また,右横ずれの活断層である馬籠峠断層が梨子沢を横断しており(木曽山脈西縁断層帯−地震調査研究推進本部http://www.jishin.go.jp/main/yosokuchizu/katsudanso/f045_kiso-sanmyaku.htm),基盤岩はかなり破砕されていると思われる.
1.3. 地形 梨子沢は,南木曽岳の西側斜面に位置しており,その流域面積は3.32 km2, 流域長は3.37 km,比高は1234 m,起伏比(流域の勾配)は0.366であり,南木曽町の中でも勾配と面積が最も大きな流域の1つである.流域面積と起伏比が大きくなると,一般的に土石流の危険性は高くなる(若月・石澤,2009,地形).2009年防府災害における土石流災害地と比較しても,梨子沢の値はかなり大きい結果となった.被災した住宅地は,梨子沢からの土石流が繰り返すことによる扇状地が木曽川の河岸段丘上に覆い被さった地形上に形成されている.
1.4.災害の様子 今回の土石流災害は,山頂付近の上松花崗岩と木曽駒花崗閃緑岩の斜面における崩壊から始まったようである.土石流化した崩土は渓床の堆積物を巻き込んで規模を増大させながら流下したと考えられる.土石流の流路の地質は木曽駒花崗閃緑岩である.土砂の堆積域では,堆積した礫の9割以上が木曽駒花崗閃緑岩であり,上松花崗岩は1割以下であった.すなわち,源頭部には上松花崗岩が存在する場合もあるが流路は木曽駒花崗閃緑岩のみであるため,木曽駒花崗閃緑岩の分布域の渓床から多くの土砂が供給されたことが考えられる.堆積した上松花崗岩の礫に着目すると,南木曽岳付近の上松花崗岩の分岐域ではほぼ全ての場所で粗粒花崗岩の基盤岩や河床礫が存在していたのに対して,梨子沢から流出した岩石は粗粒花崗岩と細粒花崗岩がおおよそ半分ずつであった.この細粒花崗岩は,上松花崗岩岩体の中で初期に冷却された部分であり,他の岩体(ここでは木曽駒花崗閃緑岩)との接触部付近に分布している可能性がある.山頂付近の崩壊場所の花崗岩が粗粒か細粒かを今後確認したい.土石流の砂礫は堰堤(2.5万分の1地形図では大梨子沢では4基,小梨子沢では1基が確認できる)にある程度有効的に捕獲されたが,一部が住宅地など生活の場である扇状地に押し寄せることで災害となった.被災した家屋は河川(梨子沢)の屈曲部の攻撃斜面側にあり,流路を曲がりきれなかった巨礫など砂礫が溢れだした.氾濫した砂礫は犠牲者が発生した家屋から扇状に下方に広がった.また南木曽岳では,梨子沢がある西側斜面だけでなく反対側の東側斜面でも崩壊が発生した.
また,南木曽では数年から数十年おきに災害が発生している.防府では約100年以上の周期性が報告されており,南木曽のほうが土石流の頻度は大きい.
1.5. 南木曽のまとめ 以下は,データが足りないため仮説に過ぎないが,南木曽の花崗岩斜面は防府に比べて急勾配な斜面が多いため,土層が薄くて風化(粘土化)も不十分であると考えられる.そのためすべり面までの降雨の浸透が速くてかつ土層の可能水分貯留量が少なくなり,今回のようなわずか2時間の豪雨で斜面が不安定になった可能性がある.断層活動により基盤岩が脆弱化されることで,粘土分を欠くマサの生成(土層生成)が速められた可能性もある.渓床も急勾配であるため当然土砂が動きやすかったと考えられる.土石流の頻度からみても,急勾配流域では土砂移動が活発といえるが,このような場所では活発な侵食により土層は薄くなるため,マサ化が一層促進され,益々崩壊や土石流が発生しやすくなると考えられる.
2.2014年8月6日の岩国市における斜面崩壊
(http://mizu.bosai.go.jp/c/c.cgi?key=2014_iwakuni2)
2014年8月6日の豪雨により,山口県岩国市の新港町,保木,角,和木町瀬田,守内など複数箇所で斜面崩壊が発生して住宅などに被害を与えた. 特に,新港町では,崩土が流動化して流れ下り複数の建物を破壊した.これにより1名が犠牲になった.災害発生直後の5時53分に消防への通報があったことから,崩壊は8月6日5時50分頃発生したと考えられる.
2.1. 地質 5万分の1地質図「大竹」によると,新港町の崩壊地の基盤岩石は,白亜系上部広島花崗岩類岩国花崗岩の中−粗粒黒雲母花崗岩であり,風化層は概して薄い.また,保木と角の崩壊地の基盤岩石は,中粒斑状角閃石黒雲母花崗閃緑岩であり厚層風化していた.守内や和木町瀬田の崩壊地の基盤岩石は,ジュラ系の玖珂層群柏木山チャート岩体のオリストストローム(泥質海底地すべり堆積物)及び泥岩である.
2.2. 降雨 山口県土木防災情報システムのデータから,10分および1, 2, 3, 6, 24時間の積算雨量の最大値を計算した(表1).上述した各崩壊地点に近い,「岩国土建」「松尾峠」「沖市」「寺山」の値を見ると,崩壊発生時刻である6日6時前後は,2時間雨量や3時間雨量の最大値の時刻と概ね一致しており,10分雨量や1時間雨量の最大値の時刻からは30分前後遅れている.「岩国土建」における時間雨量と累積雨量の経時変化によると,8月1日0時から5日0時までに124mmの先行降雨があった.8月1日0時から6日12時までの累積雨量は344mmに及ぶ(上記URL参照).
また,新港町と同じ花崗岩地域の災害である2009年7月の防府災害,2014年8月の広島災害,2014年7月の南木曽災害における雨量と比較すると,新港町に最も近い「岩国土建」の値は,防府災害の雨量に近く,広島災害の雨量はこれらよりかなり大きい(表1).南木曽災害の雨量は10分〜3時間までは「岩国土建」の値とよく似ているが,6時間雨量と24時間雨量がかなり小さい.
2.3.斜面崩壊地の崩壊形状と土層構造の例 岩国市新港町の斜面崩壊地1カ所において,崩壊形状の簡易計測と簡易貫入試験による土層構造調査を実施した.その結果,斜面勾配は22°,崩壊深は約1.5〜2m,崩壊幅は約15m,崩壊長約45mであった.崩壊地の斜面勾配はかなり小さく,崩壊深は1m以下で崩れることが多い一般的な花崗岩斜面の崩壊深よりもやや大きい.崩壊地脇には崩土に相当する厚さ1.7mの軟弱な砂質土層が存在する.崩土が通過した流送部は最大30度と崩壊地よりも急勾配であり,花崗岩の岩盤が露出している.流送部脇の急斜面の土層はかなり薄いことから,急斜面では崩壊が発生しにくいものと考えられる.なお,2009年の防府土砂災害(花崗岩地域)でも今回のように,急勾配の流路に接続する緩勾配斜面での崩壊が多数発生した.
3.2014年8月15日から17日の丹波市・福知山市における崩壊・土石流災害
(http://mizu.bosai.go.jp/c/c.cgi?key=2014_fukuchiyama)
2014年8月15日から17日までの豪雨により,福知山市街地では広範囲に浸水被害が発生するとともに,隣接する丹波市を中心に多数の斜面崩壊や土石流が発生した(丹波市調べでは196カ所).それにより,死者1人,住宅全壊16戸(全て市島町)の被害が発生した.その他,福知山市山野口(崩壊により住宅全壊),綾部市の舞鶴若狭道(2カ所の法面崩壊)などでも多数の被害が出ている.空中写真から判断すると,多くの土石流は斜面崩壊が流動化したものと判断される.
3.1. 崩壊・土石流と地質 5万分の1地質図「福知山」によると,崩壊や土石流が多数発生した丹波市市島町,氷上町,春日町には,中生界丹波帯の頁岩が広範囲に分布している.一方,市島町徳尾の大原神社付近から北西側(親不知〜奥榎原)は丹波帯頁岩の災害地(南東側)に隣接しているが,崩壊や土石流はほとんど発生していない.この場所には,超丹波帯の砂岩(古生界二畳系中〜上部高津層,Ts)が分布しており,斜面に土層がほとんど形成されていないことを確認した.土層がほとんどないため崩壊が発生しなかったと考えられる.
3.2. 斜面崩壊地の崩壊形状と土層構造の例 丹波市市島町の北側に隣接する福知山市岩間の斜面崩壊地1カ所において,崩壊形状の簡易計測と簡易貫入試験による土層構造調査を実施した.その結果,崩壊面の勾配34.4°,崩壊深は約1.5m,崩壊幅約20m,崩壊長約25mの表層崩壊であり,土層は粘土質であることが明らかになった.また,崩壊面の土層どうし,または崩壊地外の土層どうしを比較するとその深さにややばらつきがあった.付近の地質は,5万分の1地質図「福知山」によると,丹波帯(ジュラ系下部〜中部II型地層群三俣コンプレックス)の頁岩(砂岩及びチャートのレンズを含む,Mm)であり,頁岩を基盤岩の主体とし,一部にチャートが確認できる.風化されにくいチャートが崩壊地に混在していることが,この深さのばらつきの一因であると考えられる.
追記
※本記事は,第121年学術大会(鹿児島大会)での緊急展示としてポスター発表された内容を元にニュース誌掲載用にまとめられたものです(2014年11月号ニュース掲載).
若月 強・山田隆二・酒井将也,竹田尚史,2014,2014 年豪雨による土砂災害調査(7 月9 日南木曽および8 月6 日岩国・8 月17 日福知山・丹波).日本地質学会第121年学術大会講演要旨.U-1.
(2014.11.11)
霧島山新燃岳2011年噴火:関連リンク
霧島山新燃岳2011年噴火:関連リンク
産業技術総合研究所・地質調査総合センター:
産総研・地質調査総合センターによる調査結果
霧島山(日本の第四紀火山より)
霧島山(火山衛星画像データベースより)
気象庁:
噴火予報・警報:霧島山(新燃岳)
霧島山(新燃岳)の解説
東京大学地震研究所:2011年1月新燃岳(霧島火山群)の噴火
防災科学技術研究所:霧島山(新燃岳)情報
国土地理院:霧島山(新燃岳)の噴火に関する対応
アジア航測(株)賛助会員:平成23(2011)年霧島山(新燃岳)噴火情報(空撮写真ほか)
パスコ(株)賛助会員:2011年1月霧島山系・新燃岳の噴火におけるTerraSAR-Xによるモニタリング NEW 2011.3.8追加
新燃岳関連サイト
●は、新燃岳情報が存在するもの
政
府
内閣
●
内閣府 災害緊急情報
消防
総務省消防庁 災害情報
国
交
省
●
本省 災害情報(新燃岳関連)
●
砂防部(新燃岳関連サイト)
●
九州地方整備局(新燃関連記者発表)
●
九州地方整備局(新燃岳関連サイト)
●
宮崎河川国道事務所
川内川河川事務所
鹿児島国道事務所
災害調査
●
砂防部・宮崎河国 PDF
他
省
庁
林
野
庁
森林整備部
九州森林管理局 災害情報
九州森林管理局 報道発表
鹿児島森林管理署
宮崎南部森林管理署
宮崎森林管理署都城支署
環
境
省
自然環境局
●
九州地方環境事務所
●
えびの自然保護官事務所
気
象
庁
●
噴火予・警報
●
新着情報
●
火山の状況に関する解説情報
●
噴火に関する火山観測報
●
降灰予報
●
福岡管区 地震・火山緊急発表
●
福岡管区 新着情報
●
鹿児島地方気象台
●
鹿児島地方気象台 災害時支援
●
宮崎地方気象台
研
究
機
関
●
産総研 地質調査総合センター
●
防災科研
●
地理院 地理地殻活動研究センター
●
東大 地震研
●
京大 防災研
●
九大 地震火山観測研究センター
国総研 砂防研究室
土研 火山土石流チーム
現地写真
●
砂防広報センター
個
人
サ
イ
ト
●
てるみつ部屋ブログ
●
ある火山学者のひとりごと
●
群大 早川教授
●
レスキューナウ
●
ウェザーニュース
Twitter
●
鹿児島大学:井村隆介准教授
●
群馬大学 :早川由紀夫教授
●
宮崎県知事 :河野俊嗣
宮
崎
県
庁
●
宮崎県庁 消防
●
宮崎県庁 砂防課
都城土木事務所
小林土木事務所
宮崎県庁 林務
市
町
村
●
えびの市
●
小林市
●
高原町
●
都城市
鹿
児
島
県
庁
●
鹿児島県庁 危機管理防災課
鹿児島県庁 砂防課
姶良・伊佐地振局(湧水町、霧島市)
大隅地域振興局(曽於市)
鹿児島県庁 林務
市
町
村
湧水町
●
霧島市
曽於市
火山防災
マップ
●
霧島火山防災マップ(2009.3 表)
●
霧島火山防災マップ(2009.3 裏)
ラ
イ
ブ
カ
メ
ラ
●
霧島市:大浪池(鹿児島県砂防)
●
霧島市田口(宮崎河国)
●
霧島市:猪子石(気象庁)
●
霧島市:霧島総合支所(霧島市)
●
霧島市:国分上野原 録画
●
霧島市:霧島ロイヤルホテル 録画
●
霧島市:牧園町 (KTS鹿児島放送)
●
霧島市:霧島町(NHK)
●
高原町:矢岳床固工 (宮崎河国)
●
高原町:下川原橋 (宮崎河国)
●
高原町:大淀川砂防(宮崎河国)
●
高原町: (NHK)
●
えびの市:えびの高原(環境省)
小林市:市立病院屋上(小林市)
空
撮
●
JAXA(宇宙航空研究開発機構)
●
アジア航測
●
国際航業
●
パスコ
●
NASA
降灰
調査
●
産総研・地質調査総合センター
●
ダイヤコンサルタント
マ
ス
コ
ミ
宮
崎
●
宮崎日日新聞
●
MRT 宮崎放送
●
UMK テレビ宮崎
●
NHK 宮崎
●
共同
●
読売
●
毎日
●
朝日
●
産経
鹿
児
島
●
南日本新聞
●
MBC南日本放送
●
KTS 鹿児島テレビ放送
●
KKB 鹿児島放送
●
NHK 鹿児島
●
読売
●
共同
●
毎日
●
朝日
●
産経
雨
風
灰
SO2
ほか
レーダー
●
ウェザーnews
●
国交省レーダー雨量
雨量
観測所
●
霧島市:高千穂河原 (宮崎河国)
●
都城市:御池(宮崎河国)
鹿児島県
●
土砂災害発生予測システム
宮崎県
●
土砂災害警戒区域情報
風
●
気象庁 ウィンドプロファイラ(市来)
空路
●
VAAC(航空路火山灰情報センター)
環
境
省
浮遊粒
子状物質
●
都城市吉尾町(都城高専)
●
都城市姫城町(都城自排局)
SO2
●
都城市吉尾町(都城高専)
●
都城市姫城町(都城自排局)
ヒスパニョーラの地質とテクトニクス(ハイチの地震に寄せて)
ヒスパニョーラの地質とテクトニクス(ハイチの地震に寄せて)
小川 勇二郎 (東電設計株式会社)(2010.01.19)
今回のハイチ地震は、とても他人事ではない。丁度、阪神淡路大地震15周年の行事や放送が行われていた時であったから、なおさらである。筑波大学の八木勇治准教授によると、くしくも今回の地震は阪神と類似のメカニズム、規模であるようだ。
図1.カリブ海の地帯区分(Case and Holcombe (1980)による)。これで見るように、ケイマントロフは、南北をトランスフォーム・フラクチャーゾーンで囲まれた大規模な横ずれ断層帯となっていて、 現在のヒスパニョーラはその東方延長上にあることがわかる。しかし、それは地史的にみると、キューバから東南東へ伸びる白亜系を主体とする地帯を斜めに横 切っていることがわかる。つまりヒスパニョーラは、複雑な横ずれプレート境界の上にある、との説であった。なお、ten Brink et al. (2009)は、ヒスパニョーラの東部に、ゴナベマイクロプイレートを設けている。それによると図5で示すように、今回の地震は、このマイクロプレート境 界で起きたものとなる。黒く囲んだ島がヒスパニョーラ。ポルトープランスは黒丸印。
(クリックすると大きな画像がご覧いただけます)
カリブ海は、日本からは遠いために、どのような地質やテクトニクスが行われているかは、ピンと来ない方もおられよう。しかし、有名なKT境界のチシュールブ・インパクトによる津波堆積物の研究には、日本からも何人もの方が参加しているし、付加体で知られるバルバドスもカリブプレートの東端である。ハイチは、通称ヒスパニョーラ島の西半分を占める。東部はドミニカである。西方には、キューバとジャマイカ、東方にはプエルトリコなどがあり、それらはGreater Antillesを作っている。カリブ海の東を限るLesser Antillesが主として火山島弧であるのに対して、前者は、むしろ中生代から第三紀の岩石を主体とする。それらのかなりの個所にオフィオライトや火山性の岩石や変成岩(エクロジャイト相のものも)なども含まれる(図1)。それは地体構造的にはアパラチアとアンデスを結ぶものであり、アメリカ東海岸を南下して、オクラホマのウォシタ山地からテキサスを経て、メキシコに伸び、そこからポロチック・モタグアフラクチャゾーンに沿って再度東へと向かい、このGreater Antillesに達する。ただし、アパラチアを特徴づける古生界は、グアテマラ、ホンジュラスまでであり、カリブ海へはそれらが横ずれ断層で引きちぎられて、実在しない模様である。この方向性はそのまま東へカリブ海をぐるりと回り、ベネズエラから、今度はアンデスへと続いている(図1)。
図2.Greater Antillesの地質概念図(King (1969)による)。キューバから続く白亜紀主体の地層(オフィオライト、変成岩を含む)は、ケイマントロフの南北のフラクチャーゾーンに切られる形となっていて、北限の延長上にプエルトリコ海溝が位置する。 ヒスパニョーラの北側からはバハマプラットフォームが、南側からベアタリッジが衝突する形となっている。矢印はポルトープランス。
もともと太平洋側にあったカリブ海の前身が(白亜紀後半のLIP(巨大岩石区、洪水玄武岩)と信じられているが、依然としてインパクト説も根強い。しかし今回はこれについては立ち入らない)、相対的に東進して南北アメリカの間に割って入り、(パナマ地峡がチョークされる形で)大西洋側に取り込まれたのがカリブプレートであるというのが定説である。この運動は現在もカリブプレートのゆるやかな拡大として続いているが、その過程で、その南北の境界がトランスフォーム・フラクチャーゾーン系を作ってずれている(実際は斜め沈み込み成分がある箇所もある)(図1,2,3)。カリブプレートの南側の境界には、ベネズエラ北岸に非常に厚い泥質堆積体がフラワーストラクチャを作って付加体まがいの構造物として発達する。北側の境界が、今回の地震を起こした断層を含む、ケイマンフラクチャーゾーンを主体とする断層帯である。ここは、現在はカリブ海からガルフ、バハマにかけて礁性の石灰岩が卓越する環境で、ヒスパニョーラには、その一部のバハマプラットフォームが北から衝突し、南側からはベアトリッジが衝突している(図2)。プエルトリコ海溝の西方延長であるヒスパニョーラの北岸と、カリブ海側の南岸には、部分的に付加体または類似の構造(南側のはムエルトススラストベルトと呼ばれる)が形成されている(図4)。
図3.ヒスパニョーラ周辺の海域の構造図(Case and Holcomebe (1980)による)。北側と南側に、付加体類似のスラストベルトが発達している。カリブプレート内部には、沈み込みは知られておらず、北側からは北米プレートが、相対速度約2 cm/yrで、斜めに沈み込んでいる。
図4.南側のカリブ海側に発達するムエルトススラストベルトのサイズミックプロファイルの解釈図。われわれになじみ深いたとえば南海トロフ付加体と類似する構造だが、沈み込みによるものではない、というのが、ten Brink et al. (2009)の見解。
図5.以上を総合するテクトニックマップと概念的断面図(ten Brink et al. (2009)による)。今回の地震は、EFZ(エンリクィロ断層帯)と示される左横ずれ成分の勝った断層に沿って生じたもののようだ。それは、雁行しつつ西方のジャマイカ、それ にケイマントロフの南限の断層帯に続くもののようだが、かなりの水平ずれを示すので、おそらくマイクロプレートの境界となっているのであろう。(一般に、 フラクチャーゾーンは、水平ずれ成分はほとんどないとされる。)
ケイマンフラクチャーゾーンは、比較的細い東西に延びる二本の断層系でその中央部は典型的な中央海嶺地形が発達している。この断層帯の東方延長は、キューバから今回のヒスパニョーラへと、大陸地殻的ブロックを横切る形で、プエルトリコ海溝へと続き、そのままカリブプレートの周辺を限る沈み込み境界へと続く(図1,2,3)。このように、この付近の断層系は起源的にはトランスフォーム断層帯であるが、現在は斜め沈み込みの境界になっている(図5)。つまり、今回の地震を起こした断層は、基本的にはカリブプレートの北縁を限る断層帯のある部分ではあるが、複合的であるといえる。ten Brink et al. (2009)は、ヒスパニョーラ西部(ハイチ)にゴナベマイクロプレートを想定している(図5)。それによると今回の地震は、このマイクロプレート境界で起きたものとなる。このようにヒスパニョーラの地質とテクトニクスは、周囲に付加体をもつという点において、また島弧を横切る形で活断層帯が発達するという点で、日本の地質とテクトニクスに一脈通じるものがある(後述)。
このヒスパニョーラ島の地質はキューバと類似するが、オフィオライト、タービダイト、サンゴ礁性石灰岩などがよく研究されている東部のドミニカ地域と比べて、西部のハイチの陸上の地質の研究はそれほど多くない。しかし、最近、ten Brink et al. (2009)などによって、島の北側と南側に発達するスラストベルトについて、地球物理的、モデル実験的な研究が発表され、その意義が論じられている(地球物理的論文は、この論文にリストアップされている)。くしくもこの論文では、島弧(と彼らは書いている)であるヒスパニョーラのブロックがリジッド(剛体的)なため、北側からのプレート境界での応力が南方へ伝播し、被害が大きい地震が起きるかもしれない、との警告を発していた。彼らは、南北のスラストベルトが、互いに相反するフェルゲンツを持つ、英語で言うと、”bivergent” thrust beltsを示すことに着目し、それが、インドネシアのチモール、パナマ、バヌアツなどで見られる状況と類似するので、双方からの沈み込みによるものか、それともほかの理由からかを検証した。彼らは結論として、北側の北米プレートがヒスパニョーラに斜めに沈み込み、そこに北フェルゲンツのフォアウェッジを作るが、「島弧」のリジッドなブロックにさえぎられて応力が南方へ伝播して、南フェルゲンツのレトロウェッジを作るのだ、ということを示した(図4,5)。後者の部分には、かなり厚い堆積体が形成されていて、ほとんど付加体類似の構造をとる(図4)。しかし、北側のものは付加体であるが、南側のものはプレートの沈み込みによるものではないため、みかけである、とのことである(プレートの沈み込みによる場合のみを付加体とする)。
以上のような地体構造とそのテクトニクスを、比較検討という面から日本に当てはめると、類似点があることに気づく。たとえば、太平洋またはフィリピン海プレート側にスラストベルトや付加体が発達し(それらは海側フェルゲンツである)、本州弧北部から北海道の日本海側には、断層帯または褶曲帯が発達している。これは、3 Ma以降の水平圧縮と、最近になって始まった日本海側での沈み込みのために、あたかも本州弧を挟むような形で両側に相反するスラストベルト(bivergent thrust belt)が発達しているように考えられなくもないということに似ている。しかも、本州弧の(特に日本海側には)は古期の岩石主体の地殻の上に第三紀以来の堆積物がたまって変形しているという点からも、類似する。本州弧の地殻は最大35 kmと厚く、ヒスパニョーラと同じく、相対的にリジッドであろう。そのようなところに、最近、阪神・淡路、中越、能登沖などの比較的大きな地震も起きている。メカニズムがすべて同類ではないだろうが、基本的な構造は非常に類似しているといえる(図3を南北さかさまにして裏からみると、非常によく似ているといえる)。斜め沈み込みの程度は異なるが、このようなテクトニクスは、地球上のプレート境界、特に縁海・島弧・海溝系では普通に起こりうるものとして、今後も注目すべきであろう。
追加1.カリブプレートの周辺の簡略化されたテクトニックマップ.(2010.1.21修正)
追加2.日本周辺の簡略化されたテクトニックマップ(左)と、それを南北逆にして鏡像にしたもの(右)(2010.1.21修正)
(私 見) 今回の地震から何を学ぶべきであろうか?「備えよ常に」は、われわれ活動的な変動帯に住むものにとっての共通の心構えであろうが、地質屋として、ほかに提言があるとすれば、次の3点であろう。
1. 古傷は、活断層とされていればもとより、されていないものでも、いつ動くか分からない。そもそも、古傷が動いた、ということを言っても解決にならない。その古傷は、最初は古傷ではなかったはずであるから、なぜそこに最初の断層ができたか、その必然性、メカニズム、テクトニクスの発達史的意義を知るべきである。
2. われわれの周辺には、非常に高い確率で将来動く断層が知られている。実際、いつかは必ず動くであろう。抜本的な対策を早急にとるべきであろう。最も重要なのは、ライフラインのバックアップである。
3. そのほかに、地質研究者としてもできることは、GPSの動態と活断層、活構造との関連を監視することであろう。それら具体的な研究に関しては、皆で知恵を出し合い、地球物理学者、地震学者主体の予知研究に、地質屋からも、主体的な行動がとれるようにすべきであろう。
(文 献;引用してないものも含む。最近の知見に関しては、以下のten Brink et al. (2009)に詳しい)
Case, J.E. and Holcombe, T.L., 1980, Geologic-tectonic map of the Caribbean region (1:2,500,00). U.S.G.S.
Kerr, A.C., Tarney, J., Marriner, G.F., Nivia, A., and Saunders, A.D., 1997, The Carribean-Colombian Cretaceous Igneous Province: The internal anatomy of an oceanic plateau. In: Mahoney, J.J. and Coffin, M.F. (eds.), Large Igneous Provinces – Continetal, Oceanic, and Planetary flood volcanism, Geophysical Monograph 100, AGU, pp. 123-144.
King, P.B., 1969, Tectonic map of North America (1:5,000,000). U.S.G.S.
Mattson, P.H., 1974, Cuba. In: Spencer, A.M. (ed.), Mesozic-Cenozic orogenic belts. Scotish Academic Press, Geological Socciety Special Publication, No. 4, pp. 625-638.
Moores, E.M. and Twiss, R.J., 1995, Tectonics, Freeman, 415pp.
Witschard, M. and Dolan, J.F., 1990, Contrasting structural styles in siliciclastic and carbonate rocks of an offscraped sequence: The Peralta accretionary prism, Hispaniola Geological Society of America Bulletin, v. 102, p. 792-806.
ten Brink, Uri S., Marshak, S. and Bruña, José-Luis Granja, 2009, Bivergent thrust wedges surrounding oceanic island arcs: Insight from observations and sandbox models of the northeastern Caribbean plate Geological Society of America Bulletin, v. 121, p. 1522-1536.
現地調査団発足について
地質災害時の現地調査団発足について
現地調査団を発足する場合は事務局(main[at]geosociety.jp)までお問合せ下さい.
※[at]を@マークにして送信してください.
四川大地震現地体験報告
四川大地震現地体験報告
宮崎眞一(非会員)
四川大地震を成都で体験したので報告します。
私は日本地熱学会会員で地熱地質が専門です。今、四川大学に語学留学しています。
(1) 地震の時の様子
地震の時、私は成都の市街地にある四川大学で授業中でしたが、先生の一声でみな4階の教室から急いで下の緑地に降りました。校舎の外壁が少しはがれて落ちてきて緊迫しましたが、皆無事に外に出ました。震度は3から4未満程度で、日本でならあわてて外に飛び出すほどではなかったように思います。揺れ方はドンドン、ガンガンというものではなく、ユラリユラリと2分間くらいかなり長く続いたようです。
中国人や外国人は皆恐怖に怯えていましたが、日本人のみが平静でした。
(2) 成都市街地の被害
成都市街地の被害はほとんどありません。建物の倒壊もなく、人的被害もほとんどありません。中国のビルは鉄筋コンクリートの柱と床に、レンガを積んで壁を作っています。最近の超高層ビルもそうです。しかし倒壊したビルはありませんし、レンガも崩れていません。街のレンガ塀も倒れていません。私の校舎の外壁が少しはがれ落ちたのは、本来2棟の独立した建物のつなぎ目に塗ったモルタルがはがれ落ちたものです。市街地には老朽化した木造やレンガ積み家屋も多く、少しの風でも倒れそうなイメージですが、これもほとんど無事で、屋根瓦も落ちていません。成都市街地は震源地から70〜80kmしか離れていませんが、被害のなさは不思議なくらいです。地震の翌日からも成都市街地では食べ物、飲み物などはほぼ平常通りに売っていました。
なお、一点注意が必要なのは行政区画の呼び方です。「成都市」という呼び名には2つのランクがあります。市街地の区部だけを指す場合と、行政単位の成都市です。東京都の23区部と三多摩を含めた東京都に相当します。混乱するのは、地震の被害の大きい都江堰市や彭州市は成都市の一部分だということです。東京都に青梅市が含まれるのと同じで、成都市に都江堰市や彭州市が含まれます。しかし通常成都市と言うと、成都市街地の区部を指すことが多いようです。報道や統計を読む場合は注意が必要です。
(3) 成都市街地内の様子と人々の反応
地震の日は多くの人は野外で夜を明かしたようです。翌日からは緑地などにはテントが増えてきました。しかし3日目頃からは市街地はほぼ平静に戻りました。一部の人たちは余震を恐れてテントなど野外で寝ていました。
成都の人々はこんな地震は初めての体験ということで、相当に動揺しているようです。欧米やアジア、アフリカから来ている留学生もほとんどがショックを受けて夜も寝られないと言っています。夜も平気で寝ているのは日本人くらいです。
このことは世界各地での地震の報道を日本人の感覚で聞いては、「地質現象」としては正しくても、「社会現象」としては誤りが多いだろうと感じます。逆に日本人は地震に慣れている上に日本の建築物の強さにも慣れているので、外国の建築物の弱さを忘れて油断してしまいます。注意を要する点です。
地震からちょうど1週間目の19日の夜に「マグニチュード6から7の余震に注意」という余震の注意報が四川省地震局から出されました。これで成都市街地は大混乱になりました。緑地を求めて逃げる人、車で逃げる人などで深夜を越えても騒いでいました。翌日からは緑地でのテントやビニールシートの仮設テントがそれまでの4〜5倍に増えました。地震局の説明では、被害の激しい山岳地帯では二次災害が心配されるので、注意喚起したとのことです。この大混乱も翌日には収まってきたようですが、精神的動揺は高まっているようです。
中国の一般の人たちは「マグニチュード」と「震度」の区別を知らないようで、これも混乱の原因です。なお、中国の震度の数字は日本の震度の数字とは異なります。
私は成都市街地にはおりますが、激しい被災地は見ていませんし地震そのもののデータもありません。感想程度の報告です。ただ日本の友人達からの連絡を聞くと、日本では成都市街地も大被害を受けているように受け取られているようですが、それは誤解です。これは報道の問題だと思います。
2008年5月12日中国四川省の地震について
中国四川省の地震
発生日:2008年5月12日(月)
発生時間:14:28(現地時間), 15:28 (日本標準時間)
震源地:中華人民共和国 四川省、北緯31度01分5秒、東経103度36分5秒
震源の深さ:19km
マグニチュード:7.9 -> 8.0 (5月18日修正)
関連断層:龍門山断層
2008年5月12日中国四川省の地震について
東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻
池田 安隆
四川省・成都の北西約100 km を震央とする大地震が5月12日15:28(日本時間)に発生し甚大な被害をもたらしました.この地震のモーメント・マグニチュード(Mw)は7.8 (1)であり,これは大正関東地震(1923年;Mw 7.9)の規模に匹敵し,プレート内部で起こる地震としては最大級です.
余 震は,龍門山断層帯(Longmen Shan Fault Zone)に沿って,主震の震央から北東方向約 300 km にわたって帯状に分布しています (1).また,発震機構は,ほぼ南北走向・東傾斜の節面と北東走向・西傾斜の節面とからなる逆断層型であり(1),後者が余震分布と調和的であることから 今回の地震を起こした断層面であると考えられています.これらのデータは,今回の地震が龍門山断層帯の活動によるものであることを強く示唆します.同断層 帯に沿って地表地震断層が出現したかどうか未だ十分な情報がありませんが,地震直後に現地入りした静岡大学の林愛明氏によれば,最大3 mの垂直ずれを伴う北西傾斜の地震断層が出現したとのことです(2).
私たち(東郷正美, 越後智雄,田力正好,岡田真介,池田安隆)は,数年前から中国地震局の何宏林氏等と共同で,チベット高原南東部の康定断層帯(Kangding Fault Zone;鮮水河-小河断層帯 Xianshuihe-Xiajiang Fault Zone とも呼ぶ;付図参照)の研究を行っています.今年もついひと月前迄現地調査を行い成都を経由して帰国したばかりのところに,突然飛び込んだ大地震の知らせ でした.正直に告白すると,龍門山断層帯がこのように大きな地震を起こすとは,私は予想していませんでした.むしろほとんど死んだ断層であると思っていた のです.
龍門山断層帯は,揚子プラットフォームの北西縁を画する西傾斜の逆断層帯(の一 部)であり(付図参照),主な活動時期は三畳紀後期〜白亜紀です.この時期に,四川盆地とその南西の雲南省東部には,赤色砂岩・頁岩を主とする厚い陸成層 が堆積していているので,これらの地域は典型的な foreland basin を成し,その北西側には大規模な山脈が形成されていたと考えられています(3).揚子プラットフォーム上にはそれ以降,山脈の荷重による沈降を示すような 堆積物は存在せず,したがって龍門山断層帯の活動は衰えたと考えられます.第四紀におけるこの断層の垂直ずれ速度は1 mm/年以下であり(4),チベット高原内部に発達する横ずれ断層群のすべり速度(5)に比べて一桁小さな値です.
三畳紀後期〜白亜紀における山脈と盆地との境界は,現在のチベット高原の縁とは必ずしも一致しません.両者が一致しているのは四川盆地の北西縁だけで,それ より南西では,かつて foreland basin だったところが隆起してチベット高原の一部になっています(付図参照).今回地震が起こった四川盆地の北西縁は 5000 m にもおよぶ起伏があり,これは高ヒマラヤ南斜面に匹敵します.この起伏が形成された時代はもちろん新第三紀〜第四紀ですが(3) (6),上述のようにその原因を龍門山断層帯の活動に帰することはできそうにありません(3).チベット高原がどうやって拡大してきたか,そのメカニズム は未だ十分理解されていません.何故ここでこんな大きな地震が起きたのかを解明するには,一見無関係に見えるこの大問題を解くことが必要です.
(1) USGS Earthquake Center, http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/us2008ryan.php
(2) 広島大学・奥村晃史氏よりの私信,2008年5月17日.
(3) Burchfiel, B. C., Chen, Z., Liu,Y., and Royden, L. H., 1995, Tectonics of the Longmen Shan and adjacent regions: International Geology Review, 37, 661_735.
(4) たとえば,Densmore, A.L., et al., 2007, Active tectonics of the Beichuan and Pengguan faults at the eastern margin of the Tibetan Plateau, Tectonics, 26, TC4005.
(5) たとえば,He, H., and E. Tsukuda, 2003, Recent progresses of active fault research in China, J. Geography, 112, 489-520.
(6) たとえば,Kirby, E., et al., 2002, Late Cenozoic evolution of the eastern margin of the Tibetan plateau: Inference from 40Ar/39Ar and (U-Th)/He thermochronology, Tectonics, 21, 1001.
(クリックすると大きな画像がご覧頂けます)
震源域とその周辺の地形・活断層と主な歴史地震の分布.活断層(赤線)と歴史地震の震央(マグニチュード7以上)は,主として「中国活動構造図」(中国地 震 局,2007)による.青い太線は,揚子プラットフォームの北西縁(Burchfiel et al., 1995 による).
地球惑星科学連合大会での緊急発表
地球惑星科学連合大会で地質学会会員からは下記3件の報告がなされます。
(5月26日、幕張)
1)寺岡易司・奥村公男・神谷雅晴
2)奥村公男・寺岡易司・神谷雅晴
3)神谷雅晴 ・寺岡易司・奥村公男
東アジアの地質図,鉱物資源図等を用いて、被災地域の地質を説明いた
します。参考資料は、
http://www.gsj.jp/jishin/china_080512/index.html
地球惑星科学連合大会緊急ポスターセッション
5月26日 場所:ポスター会場
掲示時間: 10:00-19:30
コアタイム: 17:15-18:45
ミャンマーサイクロン
水文水資源学会、気象学会合同:7件
四川省地震
地震学会:14件
測地学会:4件
地質学会:3件
緊急現地調査報告会
5月26日12時50分ー13時30分 場所:303号室
静岡大学 林 愛明 教授が現地調査結果を速報
外部関連リンク
USGS Earthquake Center:速報および地震概説、過去の記録などがまとめられています。
http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/eqinthenews/2008/us2008ryan/
産総研:震源地域の地質、構造、過去の地震、文献などがあります。
http://www.gsj.jp/jishin/china_080512/index.html
東京大学地震研究所:震源解析(暫定解その2)や簡単なテクトニクス解説があります。
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/topics/china2008/
名古屋大学NGY地震学ノート:震源解析と解説があります。
http://www.seis.nagoya-u.ac.jp/sanchu/Seismo_Note/2008/NGY8a.html
筑波大学西村直樹・八木勇治さん:震源解析の図とアニメーションおよび解説があります。
http://www.geol.tsukuba.ac.jp/press_HP/yagi/EQ/20080512/
JAXA:陸域観測技術衛星「だいち」による地震前後の地形変化
http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/img_up/jdis_av2_eq_080515.htm
日本建築学会:各種情報が網羅されている
GUPI(地質情報整備・活用機構)
http://www.gupi.jp/link/link-a/sichuan.html
政府の対応(外務省発表)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/jishin08.html
ミャンマーサイクロン災害に関する情報
ミャンマーサイクロン災害に関する情報
サイクロン名:ナルギス(Nargis)
5月2日にミャンマー上陸
最大瞬間風速:72 m/s
5月11日現在の国連人道問題調整事務所の発表によると、「行方不明者は22万人、死者数は6万3000〜10万人、救援が必要な被災者は122万〜192万人」と推計。
国連人道問題調整事務所
http://ochaonline2.un.org/Default.aspx?tabid=3876&alias=ochaonline2.un.org/japan&language=ja-JP
JAXA:陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)による緊急観測
http://www.eorc.jaxa.jp/imgdata/topics/2008/tp080508.html
http://www.eorc.jaxa.jp/imgdata/topics/2008/tp080509.html
土木学会:緊急現地調査報告
http://www.jsce.or.jp/report/47/index.shtml
日本建築学会
http://wiki.arch.metro-u.ac.jp/saigai/index.php?2008%C7%AF5%B7%EE%A5%DF%A5%E3%A5%F3%A5%DE%A1%BC%A1%A6%A5%B5%A5%A4%A5%AF%A5%ED%A5%F3%A4%CB%A4%E8%A4%EB%C8%EF%B3%B2
政府の対応(外務省発表)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/myanmar/cyclone.html
被災状況
入国VISAなどの問題もあり、国際人道支援や現地調査なども遅れているようです。そのなか(社)土木学会の緊急現地調査報告によると(上記URL参照)、河口から90km上流の支流にも高潮が押し寄せ、浸水被害をもたらしていることなどが19日に発表されました。被災された方々は、いまだに浸水した場所での生活を余儀なくされ、生活環境の悪化による感染病などの蔓延など、二次災害が懸念されています。
未曾有の災害に対する学会の対応に付いて
未曾有の災害に対する学会の対応について
地質学会の対応
地質学会会員の皆様
ミャンマーのサイクロン、中国四川省の大地震と、アジアで尊い多くの命が奪われる大規模な自然災害が立て続けに発生いたしました。命を落とされた人々のご冥福をお祈りし、困難に立ち向かっている方々の奮闘をお祈りしたいと思います。
これらの災害に対して、地質学はその科学的な解明に寄与し、災害を小さくするために貢献することが求められています。すでに日本地質学会会員による現地調査、あるいはこれまで関連する研究をされて来た会員などによる説明等、多くの情報が寄せられております。それらを学会のサイトに公開、リンクを形成いたしました。
日本地質学会は、中国地質学会に対し、お見舞いのメッセージと、今回の地震に私たちがどのように対応したいと考えているかを説明するメッセージを発信することといたしました。
私たちの職業的使命の一つはこれらの自然災害の対策と研究であります。地質学を学びつつある学生、大学院生諸君の社会的使命の一つもまたこれらの自然災害の対策と研究です。こうした使命に鑑み前例にないことではありま
すが、学会のサイトに人道支援の募金を実施している権威ある組織へのリンクを形成いたしました。多くの方々による支援を呼びかけたいと思います。
2008年5月21日
日本地質学会・会長 木村 学
日本地質学会・理事会
お見舞いメッセージ
中国地質学会からのお返事
(中文・英文:クリックするとPDFがご覧いただけます)
現地調査などを予定されている方は、ぜひ学会事務局までご一報願います。
地質学会では、他学会との連絡を行い、現地での混乱や救援活動に支障の無いよう支援していきます。MLの立ち上げなども支援できますので、ぜひご一報願います。
緊急人道支援に関して
お近くのコンビニ、銀行など、あるいはインターネットによる募金が可能です。
募金には各団体の活動趣旨にご留意ください。
http://www.jrc.or.jp/sanka/help/index.html
NHK
http://pid.nhk.or.jp/event/category4_1.html
ドラえもん募金
http://www.tv-asahi.co.jp/doraemonbokin/
カンガルー募金
http://www.tbs.co.jp/kangol/
Yahooボランティア
http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/1301007/index.html
イーココロ:各種ショッピングポイントが寄付されます
http://www.ekokoro.jp/
日本ユニセフ協会
http://www2.unicef.or.jp/bof/bo.html
岩手・宮城内陸地震TOP
平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震
地震概要 6月14日08時43分ころ、岩手県内陸南部の深さ約10kmで、M7.2の地震がありました。この地震により、岩手県奥州市と宮城県栗原市で震度6強、宮城県大崎市で震度6弱を観測したほか、東北地方を中心に、北海道から関東・中部地方にかけて震度5強〜1を観測しました。気象庁はこの地震を、「平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震」と命名しました。また英語名称は「The Iwate-Miyagi Nairiku Earthquake in 2008」と命名しました。(気象庁HPより)
調査に行かれる方へ 「岩手・宮城内陸地震」に関連して多くの会員から現地調査の速報など様々な情報をお寄せ頂いております。今後も調査などを予定されている方は、ぜひ学会事務局までご一報願います<main@geosociety.jp>。地質学会では、他学会との連絡を行い、現地での混乱や救援活動に支障の無いよう支援していきます。MLの立ち上げなども支援できますので、ぜひご一報願います。
地質災害委員会 委員長 藤本光一郎(担当理事)
地質学会 地質災害調査
★現在活動中の現地調査団はこちら
解説・報告書
2008年岩手・宮城内陸地震の地質学的背景
2008年岩手・宮城内陸地震(Mj7.2)は、「餅転(もちころばし)ー細倉構造帯」北部の活断層としては記載されていない断層の深部延長の破壊によって発生した。中新世の正断層の逆断層としての反転運動によって引き起こされたと推定される。
佐藤比呂志・加藤直子(東京大学地震研究所) 阿部 進((株)地球科学総合研究所)
岩手・宮城内陸地震 墓石転倒率分布調査
この調査は、今回の地震による揺れの強さの詳しい分布を明らかにすることを目的として、地震後10日〜15日の期間に4日間行った。北は岩手県奥州市水沢から南は宮城県大崎市古川まで、南北約60 km、東西約30 kmの範囲の墓地53ヶ所において、墓石の転倒率(墓石の全数に対して何本の転倒したか)を数えた。
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター) 小栗尚樹(東北大学大学院理学研究科) 原田佳和(東北大学理学部)
茨城大学班報告
[調査対象]荒砥沢ダム上流部および冷沢流域における地表変状及び大規模崩落
天野一男・藤縄明彦・本田尚正・松原典孝(茨城大学理学部)
山形大学・千葉県地質環境センター合同調査チーム 荒砥沢ダム上流地すべり調査報告
荒戸沢上流部の地すべりについて現地での地質調査と空中写真および地形図の解析によって,地すべりが古い地すべりの再活動であったことを明らかにした.また,地すべりの発生が強震動にあることは間違いないが,その前提として,古い地すべり末端付近で開析が進んで比較的深い谷が形成されていたことによる可能性を示した.
川辺孝幸(山形大学地域教育学部)・風岡 修・香川 淳・楠田 隆・酒井 豊・古野邦雄・吉田 剛(千葉県環境地質センター)
地理情報システムを用いた地震災害とカルデラ構造との関連の検討
布原啓史((株)テクノ長谷),吉田武義,山田亮一(東北大・理)
筆者らは,産学官連携プロジェクトとして,自然由来の土壌汚染や水質汚濁の原因解明に資する目的で,デジタル化された地質図上に,様々な地質・地形・地圏環境に関する情報を統合化しつつある.1),2)これまでに公表した具体的なコンテンツとして,東北地方における地すべり地形,活断層分布及び河川の重金属バックグランドなど,また,全国レベルとして,鉱山や変質帯分布図,独自の土壌や岩石分析値などがある.今般,これらを土台として,東北地方のカルデラ構造3),4)分布および大規模斜面崩壊地点分布などを統合し,今回の地震災害と地質構造との関係を検討した.
関連リンク
国際航業 空中写真とレーザ自動差分抽出図など
http://www.kkc.co.jp/social/disaster/200806_iwatemiyagi/
産総研 現地調査写真、地質解説など
http://www.gsj.jp/jishin/iwatemiyagi_080614/index.html
気象庁 http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/2008_06_14_iwate-miyagi/index.html
Hi-NET http://www.hinet.bosai.go.jp/topics/iwate-miyagi080614/
防災科技研(K-NET)http://www.k-net.bosai.go.jp/k-net/topics/Iwatemiyaginairiku_080614/inversion/
東大地震研 http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/topics/Iwate2008/
名古屋大(NGY地震学ノート)http://www.seis.nagoya-u.ac.jp/sanchu/Seismo_Note/2008/NGY9.html
筑波大(八木研究室)http://www.geo.tsukuba.ac.jp/press_HP/yagi/EQ/20080613/
USGS http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/us2008tfdp.php
岩手・宮城内陸地震現地調査団(調査報告ほか)
岩手・宮城内陸地震現地調査団
岩手・宮城内陸地震(M=7.2)の調査に行かれる方へ
「岩手・宮城内陸地震」に関連して多くの会員から現地調査の速報など様々な情報をお寄せ頂いております。今後も調査などを予定されている方は、ぜひ学会までご一報願います。地質学会では、他学会との連絡を行い、現地での混乱や救援活動に支障の無いよう支援していきます。MLの立ち上げなども支援できますので、ぜひご一報願います。
地質災害委員会 委員長 藤本光一郎(担当理事)
★現地災害調査団発足についてはこちら
活動状況: 調査報告は随時掲載・更新いたします
■秋田大学教育文化学部調査班
調査対象:土砂災害,地震動調査
当面の調査場所:中心は秋田県湯沢市,東成瀬村,6/18に宮城県側をヘリコプターで調査予定
当面の調査期間:6/16-6/28
班長:林 信太郎(秋田大学教育文化学部)
■山口大学 地形・地質班(調査報告はコチラから→)8.25UP
調査対象:斜面崩壊、地表断層
当面の調査場所:奥州市から栗原市
当面の調査期間:7/1-7/5
班長:金折裕司(山口大学理学部)
班員:福塚康三郎(八千代エンジニヤリング(株))
■茨城大学班(調査報告はコチラから→)
調査対象:地形・地質,斜面崩壊
当面の調査場所:栗原市および奥州市
当面の調査期間:6/29(日)-6/30(月)
班長:天野一男(茨城大学理学部)
班員:藤縄明彦(火山学),本田尚正(自然災害),松原典孝(グリーンタフ地質学),天野一男(構造地質学),所属は全員茨城大学理学部理学科地球環境科学コース
■高知大学・富山大学合同調査班
調査対象:宮城岩手内陸地震,荒砥沢ダム上流部の地すべり
当面の調査場所:荒砥沢ダム上流部の地すべり
当面の調査期間:8/9(土)-8/15(金)
班長:横山俊治(高知大学)
班員:柏木健司(富山大学)
<その他の調査チーム>
■東北大学東北アジア研究センター石渡 明ほか(調査報告はコチラから→)
岩手・宮城内陸地震 墓石転倒率分布調査
■山形大学・千葉県地質環境センター合同調査チーム(調査報告はコチラから→)
荒戸沢ダム上流地すべり調査報告
2008年岩手・宮城内陸地震の地質学的背景
2008年岩手・宮城内陸地震の地質学的背景
佐藤比呂志・加藤直子(東京大学地震研究所)
阿部 進((株)地球科学総合研究所)
Geologic setting of the 2008 Iwate-Miyagi Nairiku earthquake
Hiroshi Sato, Naoko Kato (Earthquake Research Institute, The university of Tokyo), Susumu Abe (JGI, Inc.)
2008年岩手・宮城内陸地震(Mj7.2)は、「餅転(もちころばし)ー細倉構造帯」北部の活断層としては記載されていない断層の深部延長の破壊によって発生した。中新世の正断層の逆断層としての反転運動によって引き起こされたと推定される。
地震学的特徴
2008年6月14日午前8時43分,岩手・宮城県境付近を震源とする岩手・宮城内陸地震が発生した(図1).マグニチュードは7.2であり,震源域は北北東-南南西にのびる長さ45km,幅15kmの領域である(気象庁,2008).地震研究所地震予知情報センターによる発震機構解では,断層面の走向はN22Eであり,西傾斜の場合の傾斜角は49度と求められている.気象庁の一元化震源による余震分布では,本震付近の余震分布は西傾斜を示す(気象庁,2008).
図1.2008年岩手・宮城内陸地震震源域の地質構造概念図.
本震は気象庁(2008),震源断層は気象庁(2008)の余震分布から推定.餅転-細倉構造帯(片山・梅沢,1958)の位置・活断層分布・地質情報 は,建設技術者のための東北地方の地質編集委員会編 (2006)による.カルデラの分布はSato (1994),ブーゲ異常の値は広島ほか(1990,1991).A-A’: 図3の反射断面の位置.
*画像をクリックすると大きな画像がご覧頂けます
震源域の地質構造の特徴
震源域の奥羽山脈の東縁部から北上山地の間は,日本海の形成に伴う背弧リフトの東縁に相当し(Sato, 1994),西側低下の2000万年前〜1500万年前に活動した正断層群が分布する.リフト形成期には火山活動を伴い,とくに奥羽山脈では背弧海盆で噴出した珪長質の火山噴出物が厚く堆積した.リフト期の正断層活動の終了後,東北日本の奥羽山脈は隆起に転じ,800万年前から200万年前には多数の珪長質カルデラが形成された.これらのカルデラは10km程度の直径を有することが多く,ピストンシリンダー型である.これらのカルデラはクラスターをなして分布し,島弧の伸びと平行に約50km間隔で形成されている(例えばSato, 1994; Yoshida, 2003).震源域の南部はとくに古いカルデラの集中的な分布で特徴づけられ,第四紀の安山岩質の成層火山である栗駒山火山を含め地熱地帯を構成している.
地質構造を特徴付けるのは,背弧海盆の形成に伴う正断層群の形成と珪長質大規模カルデラの形成に伴うドーム状の隆起,鮮新世(500万年前)以降に生じた西傾斜の正断層の逆断層としての反転運動である.2003年の宮城県北部は,西傾斜のかつての正断層の逆断層運動によって発生した(Kato et al., 2003).活断層としては震源域の北縁部で出店断層がマッピングされている(活断層研究会,1991).胆沢扇状地を東西に横切る測線では数状の西傾斜の古い正断層が明瞭にイメージングされている(Kato et al., 2006; 阿部ほか,2008).活断層として知られる出店断層は,中新世の正断層の反転運動と,反転運動に伴って正断層の高角度部分が逆断層によってショートカットされて形成された断層である.
震源断層と地質構造
図2. 2008年岩手・宮城内陸地震震源域の地質構造俯瞰図.
*画像をクリックすると大きな画像がご覧頂けます
震源域は地質図・重力異常などから推定される地質構造と震源分布の特徴から,北北東-南南西方向に三つの地域に区分される(図1,2).遠地実体波の解析による断層面上のすべり量分布は,中部区間の浅部で最大値をとる(引間,2008).地表地震断層については,東北大学・岩手大学のグループや産業総合研究所によって報告されている.地表トレースは,概ね片山・梅沢(1958)が記載している「餅転(もちころばし)ー細倉構造帯」と一致する.これらの地表変位が観察された場所は,遠地実体波の解析結果から大きなすべりが求められた領域と良好な一致を示す(石山ほか,2008;遠田ほか,2008a, 2008b).一元化震源による余震分布は,中央部では全体として西傾斜の配列を示し,地表変位が認められた位置が震源域の東端に位置することと調和する.ただし,震源断層としては西傾斜であるものの,地表変位では西側低下の衝上断層による変位が見られる地点もあり,楔状の逆断層など浅部でのより複雑な断層形状が推定される.また,「餅転ー細倉構造帯」の東側には白亜系の花崗岩類が狭小に露出するが,大局的には中新世のハーフグラーベンのエッジ部分に相当している可能性が高い.こうした構造形態は,図3に示す胆沢扇状地を横切る反射法地震探査断面に類似し,「餅転ー細倉構造帯」も中新世の西傾斜の正断層の逆断層としての反転運動を示唆する.
図3. 震源域北部を横切る反射法地震探査断面と余震分布.阿部ほか(2008)の断面に加筆.
震源分布:気象庁一元化処理震源 2008/6/14 08:40 - 24:00,投影測線直交方向±10km範囲について表示.反射法地震探査断面は阿部ほか(2008)による.
*画像をクリックすると大きな画像がご覧頂けます
北部での震源分布は,12-10kmで緩く西に傾斜するほぼ水平な面に沿った分布を示している.この領域での制御震源探査では,地下12km程度の東に緩く傾斜するほぼ水平な反射面と出店断層のリストリックな形状を示す断層の深部延長が10km程度の深さまで検出されている(阿部ほか,2008).また,出店断層の東側にも北上山地に至る間に,2条の中新世の正断層がありこれらの深部延長は地下12km程度で緩い西傾斜をなすと推定されている(Kato et al., 2006).こうした制御震源による探査結果と地質構造の解釈結果とを比較すると,今回の地震によって出店断層とその東側のリストリックな形状の深部の低角部分のみが動いた可能性が高い(図3).しかしながら,出店断層もしくはより東側に位置する断層の高角部分(ランプ)まで破壊した証拠はない.
震源断層の走向方向には地震発生深度の下限は,南ほど浅い.とくに震源域の南部には,栗駒山の火山をはじめとして,とくに鮮新世から更新世前期に活動した珪長質の大規模カルデラが分布し,高温領域を形成している.これらの領域の上部地殻は,高温領域の浅化に伴って地震発生層も薄化している.さらに直径10km程度のカルデラの存在によって,地殻上部はカルデラ周辺の壁の部分のみで強度を支えるような状態になっている.このため余震分布でも一様な面で破断した痕跡は示さない.おそらく,カルデラ間の地殻上部を破断するような横ずれ断層など,複雑な震源断層分布を示すものと推定される.
まとめと課題
今回の地震は,地質断層として記載されていた「餅転ー細倉構造帯」(片山・梅沢,1958)の深部延長の逆断層運動によって発生した.地表変位が観察された地点もこの断層と良好な一致を示している(石山ほか,2008: 遠田ほか,2008).この断層については,これまでの研究では活断層として認識されたものではなかった.そうした意味では,ノーマークの活断層の深部延長で発生した地震であり,活断層としては適切な評価がなされていなかった.変動地形学的な今後の検討を待つ必要があるが,地質断層から見て地表トレースとして長さ10〜15kmに渡って追跡される可能性が高い.東北日本は逆断層型の断層変位を示すため平均変位速度の大きな断層は,丘陵と平野などの地形境界を区分する断層となる.今回の断層は丘陵地形の中に形成されていて,変動地形学的には大規模な断層は想定しにくい地域に位置していた.東北日本に分布する断層の鮮新世以降の総変位量には大きな違いがあり,日本海沿岸の断層の変位量に比べ,北上低地帯の周辺の総変位量は5〜7分の1程度である(佐藤,1989).こうした少ない変位速度が,活断層としての認定を妨げた可能性はある.
この地震から導かれる教訓としては,改めて総合的な研究の重要性が上げられる.今後,地質構造や地球物理学的な探査結果から導かれる結果と合わせて,変動地形学・第四紀地質学の知見を活用し,より総合的な内陸地震の長期評価を行っていく必要がある.
謝辞
小論を作成するにあたり,東北大学大学院理学系研究科今泉俊文教授・石山達也博士・鈴木啓明氏には,地表地震断層の調査結果や文献についてご教示いただいた.気象庁一元化震源のデータを使用させていただいた.
文献
阿部 進・斉藤 秀雄・佐藤 比呂志・越谷 信・白石 和也・村上 文俊・加藤 直子・川中 卓・黒田 徹 , 2008, 制御震源及び自然地震データを用いた統合地殻構造探査 - 北上低地帯横断地殻構造調査を例として -,物理探査学会第118回学術講演会講演要旨.
広島俊男・駒澤正夫・須田芳朗・村田泰章・中塚 正, 1990, 秋田地域重力図,重力図(ブーゲー異常),no.2,地質調査総合センター.
広島俊男・駒澤正夫・大熊茂雄・中塚 正・三品正明・斎藤和夫・岡本國徳, 1991, 山形地域重力図,重力図(ブーゲー異常),no.3,地質調査総合センター.
石山達也・今泉俊文・大槻憲四郎・越谷 信・中村教博,2008,2008年岩手・宮城内陸地震の地震断層調査(速報).http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/topics/Iwate2008/fault_by_THK/
引間和人,2008,遠地実体波解析(暫定解).http://taro.eri.u-tokyo.ac.jp/saigai/iwate/index.html#A.
片山信夫・梅沢邦臣,1958,7万5千分の1地質図幅「鬼首」および同説明書.27p.
Kato, N., Sato, H., Imaizumi, T., Ikeda, Y., Okada, S., Kagohara, K., Kawanaka, T. and Kasahara, K., 2004, Seismic reflection profiling across the source fault of the 2003 Northern Miyagi earthquake (Mj 6.4), NE Japan: basin inversion of Miocene back-arc rift. Earth Planets Space, 56, 1255-1261, 2004.
Kato, N., Sato, H. and Umino, N., 2006, Fault reactivation and active tectonics on the fore-arc side of the back-arc rift system, NE Japan, Journal of Structural Geology, 28, 2011-2022.
活断層研究会編,1991,新編 日本の活断層.東京大学出版会,437pp.
気象庁, 2008,「平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震」について(第6報),報道発表資料,平成20年6月17日10時30分.
建設技術者のための東北地方の地質編集委員会編 , 2006, 建設技術者のための東北地方の地質. 408p.
佐藤比呂志,1989, 東北本州弧における後期新生界の変形度について.地質学論集,32,257-268.
Sato, H., 1994. The relationship between late Cenozoic tectonic events and stress field and basin development in northeast Japan. J. Geophys. Res., 99, 22261-22274.
Sato, H., Imaizumi, T., Yoshida, T., Ito, H. and Hasegawa, A., 2002. Tectonic evolution and deep to shallow geometry of Nagamachi-Rifu Active Fault System, NE Japan. Earth Planet. Space, 54, 1039-1043.
遠田晋次・丸山 正・吉見雅行,2008a, 2008年岩手・宮城内陸地震速報,緊急現地調査速報(第1報:2008.6.15),http://unit.aist.go.jp/actfault/katsudo/jishin/iwate_miyagi/report/080615/index.html.
遠田晋次・丸山 正・吉見雅行,2008b, 2008年岩手・宮城内陸地震速報,緊急現地調査速報(第2報:2008.6.17),http://unit.aist.go.jp/actfault/katsudo/jishin/iwate_miyagi/report/080617/index.html.
Yoshida, T., 2001, The evolution of arcmagmatism in the NE Honshu arc. Japan. Tohoku Geophys. Jour., 36, 2, 131-149.
備考:なお、上記記事は地質学会の依頼により佐藤会員にご執筆いただきました(原稿受理日2008.6.18)。また同内容は、東京大学地震研究所HPにも掲載されています。
岩手・宮城内陸地震 墓石転倒率分布調査:結果所見 (2008.6.30)
岩手・宮城内陸地震 墓石転倒率分布調査 結果所見
2008年6月30日
東北大学東北アジア研究センター 教授 石渡 明
東北大学大学院理学研究科地学専攻 院生 小栗尚樹
東北大学理学部地球惑星物質科学科 学生 原田佳和
調査概要
クリックすると大きな画像がご覧いただけます.
この調査は、今回の地震による揺れの強さの詳しい分布を明らかにすることを目的として、地震後10日〜15日の期間に4日間行った。北は岩手県奥州市水沢から南は宮城県大崎市古川まで、南北約60 km、東西約30 kmの範囲の墓地53ヶ所において、墓石の転倒率(墓石の全数に対して何本の転倒したか)を数えた。墓石は、上部の棹石(さおいし)の断面が正方形に近くて縦長のもののみを数え、横長のもの、平板状のもの、五輪塔その他の不規則な形状のものは数えなかった。典型的な棹石は底辺が30〜40 cm、高さが60〜90 cmである。棹石が完全に落下している場合のみを「転倒」とし、ずれたり回転したりしていても台の上に残っている場合は「不転倒」とした。なお、地震発生から調査までかなり日数が経過したために、墓石が復元されている場合も多かったが、墓石の傷、欠け、周囲の痕跡などで地震時に転倒したと判断されるものは「転倒」とし、この判断に迷う場合は「不転倒」とした。傷や欠けの見落としもあると思うので、今回の調査による転倒率は、地震直後に計数した場合に比べてやや低い可能性がある。
所見
1.墓石転倒率が最も高いのは、岩手県奥州市胆沢町萩森の公葬地と同市衣川村野崎の大原公葬地で、どちらも52〜53%の墓石が転倒している。これら2地点は、調査した墓地の中で震央に最も近い(約10 km)距離にある。このことは、震央の近くで最も地震の揺れが強かったことを示している。今回の地震による、墓石の転倒率が50%を越える地域の範囲は、2007年3月25日の能登半島地震の場合と同程度であり、2000年10月6日の鳥取県西部地震や2004年10月23日の中越地震(いずれも半径20 km程度)に比べるとやや狭い。
2.転倒率が20〜50%の墓地は4ヶ所あり、奥州市胆沢町大原付近から一関市厳美町地区を経て宮城県栗原市栗駒町鳥沢地区へ南北に並んでいる。転倒率が10〜20%の墓地は宮城県栗原市・大崎市にかけて、震央から南へ向かって40 km程度の範囲に拡がっており、震央から約50 km離れた大崎市古川市街の墓地でも1%以上の墓石が転倒している。一方、震央の東側に当たる岩手県奥州市水沢から平泉を経て一関市に至る北上川沿いの平野部では、震央から20 km程度しか離れていないのに、転倒率が10%を超える墓地はなかった。また、震央の南西側にある鳴子温泉や川渡温泉の墓地では、灯籠や碑板など、棹石に比べて不安定なものも倒れておらず、棹石のずれもほとんど見られなかった。これらのことは、今回の地震の強い揺れが主に南〜南東の方向へ拡がったことを示している。
以上
茨城大学班報告(2008.7.9)
岩手・宮城内陸地震 日本地質学会調査団茨城大学班報告
2008年7月9日掲載
天野一男(班長)・藤縄明彦・本田尚正・松原典孝
(茨城大学理学部理学科地球環境科学コース)
※各写真・図をクリックすると大きな画像がご覧頂けます。
図1 調査位置図.
[調査日]2008年6月29日(日)・30日(月)
[調査対象]荒砥沢ダム上流部および冷沢流域における地表変状及び大規模崩落(図1,地点1〜4).
[地質の概要]通産省資源エネルギー庁(1976)によれば,荒砥沢ダム上流部付近及び冷沢上流部付近には火砕流起源で一部溶結した軽石質凝灰岩を主体とする上部中新統の小野松沢層が分布し,その上位に一部第四系北川層及び新期安山岩類が分布する(図2).本調査地域は,後期中新世〜鮮新世に形成された栗駒南麓のコールドロン北東部に相当する(図3;天野・佐藤,1989).
図2.周辺地質図(通産省資源エネルギー庁,1976).クリックすると大きな画像がご覧になれます。
図3.周辺地域におけるコールドロン分布図(天野・佐藤,1989).栗駒南麓のコールドロンを矢じるしで示した.
[各地点における調査結果]
1.荒砥沢ダム北方(地点1)における地表変状
写真1 荒砥沢ダム北方で確認できる東北東-西南西〜東西走向の破断面.
産業技術総合研究所活断層研究センター2008年岩手・宮城内陸地震速報緊急現地調査速報第4報における地表変状を確認した.産業技術総合研究所活断層研究センター2008年岩手・宮城内陸地震速報緊急現地調査速報第4報では荒砥沢ダム上流の大規模地すべりの東方において上下,右ずれ変位それぞれ最大3〜4mの横ずれ断層を報告している(http://unit.aist.go.jp/actfault/katsudo/jishin/i・・・・).ここではおおよそ東北東−西南西〜東西走向の破断面が確認でき,破断面の傾斜はおおよそ垂直である.北側上がりで,場所によっては高さ数メートルの破断面が確認できる(写真1).成層構造の発達した凝灰質シルト岩と(写真2),最大30cm程度の軽石を含む軽石質凝灰岩(写真3)が認められる.一部で,それらの上位に直径2m以上の複輝石安山岩塊が認められる(写真4).破断面には粘土が発達し,線構造が認められる(写真5)が,これらが今回の活動により生じたものかどうかは不明である.破断面に沿って一部古い地形変状と思われるものが認められることは,この破断面の過去における活動を示唆している.破断面上にあったと思われる立ち木はしばしば大きく転倒している.また,破断面に沿って直径数十cm〜数mの岩塊が掘り起こされていることもある(写真6).東西性の破断は場所によっては並行して数条確認できる.地表変状は道路西方にも認められ,ここでは東西性の地表変状のほか,北北東−南南西の地表変状も認められる.北北東−南南西の地表変状は破断面が露出することは稀で隆起が認められる(写真7).
写真2 成層構造の発達した凝灰質シルト岩.水を含み柔らかい.
写真3 軽石を多く含む軽石質凝灰岩.
写真4 直径約2mの複輝石安山岩塊.
写真5 破断面に認められる線構造.
写真6 転倒した立ち木と掘り起こされた礫.
写真7 南北性の地表変状.隆起が認められる.
2.荒砥沢ダム上流部(地点2)での大規模崩落
写真8 荒砥沢ダム左岸に露出する凝灰質シルト岩に認められる植物化石.
写真9 荒砥沢ダム左岸で認められる凝灰質シルト岩,凝灰質砂岩互層.
写真10 荒砥沢ダム上流の溶結凝灰岩に認められる柱状節理.
コールドロン埋積層下部は葉理の発達した植物化石を含む凝灰質シルト岩,凝灰質砂岩,軽石質凝灰岩の互層からなる(写真8,9).これらは湖成層・火砕流堆積物である.上部は溶結凝灰岩からなり一部は強溶結し,しばしば柱状節理が発達する(写真10).層理面はほぼ水平である.下位の凝灰質シルト岩,凝灰質砂岩,軽石質凝灰岩を切る破断面は,平滑で垂直に近い.北側破断面の一部は,湾曲が認められず平面的で荒砥沢ダム北方で認められた東西性地表変状に連続しているように見える(写真11).西側破断面の一部も同様に平面的で,その走行は地点①で認められる北北東−南南西走向の地表変状に並行しているように見える(写真12).また,それらの破断面は比高100m以上にわたって平面的であることが特徴である.これらはそれぞれ東西性及び北北東−南南西性の弱線に沿った破断に起因する可能性を示している.上部の溶結凝灰岩中では,柱状節理が破断面となっていることが多い.下位の凝灰質砂岩,凝灰質シルト岩,軽石質凝灰岩の互層および上位の溶結凝灰岩における破断面はフレッシュであり,今回の大規模崩落に伴って形成されたものと考えられる.崩落崖の下にはブロック状の岩塊と不淘汰で細かく破砕した凝灰岩〜凝灰質シルトの土砂が認められる.立ち木が地表と共に残されているものも認められ,一部では道路があまり破砕されず直下に落下している(写真13).また,地層の一部が破壊されずにブロック状に残っているものも認められる(写真14).
写真11 荒砥沢ダム上流模崩落地の北側破断面.破断面の走向はおおよそ東西方向.
写真12 荒砥沢ダム上流崩落地の西側破断面.下部は白色を呈す成層構造の認められる凝灰質砂岩,凝灰質シルト岩,軽石質凝灰岩の互層.上部は柱状節理が認められる溶結凝灰岩.
写真13 荒砥沢ダム上流の崩落地における直下に落下した道路.
写真14 荒砥沢ダム上流崩落地で認められるブロック状に残った地層の一部.
3.荒砥沢ダム北方(地点3)における東西性地表変状東方延長部で認められる大崩落
写真15荒砥沢ダム北方の東西性地表変状東方延長部に認められる崩落地.上部では柱状節理の発達が顕著.
沢による侵食斜面最上部付近で起こり,崩落面上部に露出している崖面の主体が溶結凝灰岩に発達した柱状節理の面であることが特徴的である(写真15).崩落崖の下にはブロック状の溶結凝灰岩と,巨礫サイズ以下に細かく破砕した凝灰岩等の不淘汰な土砂が認められる.
4.冷沢上流(地点4)での大規模崩落
崩落は沢による侵食斜面最上部付近で起こったものと考えられる.崩落面に露出している崖面の主体は溶結凝灰岩に発達した節理面である.崩落崖の下にはブロック状の溶結凝灰岩と,巨礫サイズ以下に細かく破砕した凝灰岩等の不淘汰な土砂が認められる(写真16,17).その中にはしばしば堆積時の構造を残している直径5m以上の大型の岩塊が認められる(写真18).立ち木が表土と共に残されているものや表面を土塊が流れ下ったことにより葉を毟られた立ち木や土塊が流れた擦過痕が認められる(写真19).
写真16 冷沢上流崩落地における崩落崖下の土砂.
写真17 冷沢上流崩落地で認められる溶結凝灰岩.
写真18 冷沢上流崩落地で認められる直径5m以上の大型の岩塊.
写真19 冷沢上流右岸で認められる,土塊が流れ下ったことにより葉を毟られた立ち木と流れ下った土塊.摩過痕が認められる.
5.土石流
それぞれの崩落地では,土石流が発生した痕跡が認められる.冷沢上流では沢沿いに数十cm〜数mの厚さで不淘汰火山砕屑物が堆積し,その上を数cm〜数十cmの厚さで泥が覆う(写真20).沢の下面より数メートル上の河岸鞍部には土石流が流下した時に出来たと思われる擦過痕が認められる(写真21).荒砥沢ダム左岸では不淘汰火山砕屑物が皺状に堆積しているものが認められる(写真22).土石流堆積物の構成粒子は,周辺に露出する溶結凝灰岩,軽石質凝灰岩,凝灰質砂岩,凝灰質シルト岩に類似しており,土石流の構成材料が山体崩壊によって生じた土石起源であることを示している.
写真20 冷沢上流で認められる土石流堆積物.写真奥が上流.
写真21 冷沢上流左岸鞍部に認められる摩過痕.
写真22 荒砥沢ダム左岸で認められる土石流堆積物.写真右から左へ流下したものと考えられる.
[まとめと考察]
荒砥沢ダム上流部周辺の崩落地は荒砥沢ダム上流部(地点2)に代表されるような崩落面の比高が100メートルに及ぶ崩落と,冷沢上流(地点4)のような比高数十メートル以下の崩落に分けられる.地点2と地点3崩落は地点1で認められる破断面の延長線上にある.これらの崩落は既存あるいは新しく形成された断層や節理などの弱線に沿って起こった可能性がある.一方,地点4に見られるような崩落は地震動によって,東西性や北北東−南南性などの断層・節理やネットワーク状の風化面に沿ってブロック化し,支えを失ったブロックが一団となって一気に崩れ落ちた山体崩壊(岩屑なだれ的な崩壊・流動)と考えられる.地点2,地点3で認められる溶結凝灰岩の崩壊の特徴も地点4と類似していることから,同様の崩壊メカニズムによるものと考えられる.
今回の調査結果をもとに,荒砥沢ダム周辺の崩落の発生は,断層や節理といった地質構造を反映したものである可能性を指摘した.しかし,未だ余震が収まらず,崩落地での小崩落も続いているため,露頭での詳細な検証は困難である.今後,周辺の綿密な地質調査を含めて,再検討の必要がある.
[引用文献]
天野一男・佐藤比呂志,1989,東北本州弧中部地域の新生代テクトニクス.地質学論集,no.32,81-96.
通産省資源エネルギー庁,1976,昭和50年度広域調査報告書(栗原地域).52p.
地質災害現地報告会 9/22開催(於 秋田大会)
地質災害現地報告会(於 日本地質学会第115年学術大会:秋田)
日時:2008年9月22日(月)午前9時〜12時
会場:一般教育1号館302
第一部 2008年四川大地震
2008年中国四川大地震の地震断層と活断層の現地調査
林 愛明(静岡大)
2008年5月12日チベット高原と四川盆地の境界部でMw7.9の大地震が発生し,中国の中部から西部にかけた 広い地域に大規模な被害をもたらした.地震直後の現地調査により,四川大地震は3本の既存の活断層からなる龍門山断層帯の東側の2本が動いて起きたことが明らかされた.この2本の地表地震断 層の総延長は285キロメートルに達しています.龍門山断層帯沿いに,総延長285kmの地表地震断層が出現し,わずかの横ずれ変位を伴い,最大5m以 上の上下方向の変位が生じました.四川大地震に伴って出現した地表地震断層の長さと断層変位量は,ともに内陸逆断層タイプ地震として最大規模のものである.また,地表地震断層沿いに,過去にも大地震を起こしたことを示す「活断層地形」が現地調査でも確認された.本講演では,これまでの現地調査結果をご報告する.
第二部 2008年岩手・宮城内陸地震
2008年岩手宮城内陸地震震源域の地質構造
佐藤比呂志・加藤直子(東京大)・阿部 進 (地科研)・越谷 信(岩手大)・石山達也・今泉俊文
(東北大)
震源域北部での反射法地震探査や既存の地学的資料を元に,震源域の地質構造と震源断層との関連について説明する.また,震源域の中央部での未解決の諸問題と,実施している反射法地震探査の概要について紹介する.
2008年岩手・宮城内陸地震に伴う地震断層
越谷 信(岩手大)・石山達也・今泉俊文・大槻憲 四郎・中村教博・丸島直史(東北大)・杉戸信
彦 (名大)・堤 浩之(京大)・廣内大助(信州大)・佐藤比呂志(東大)
2008年岩手・宮城内陸地震(Mj 7.2)の震源域である岩手県一関市周辺地域において,地震断層による可能性のある地表変位が主として段丘面や沖積低地面や道路などの人工構造物に認められた.これらの地表変状の形状や分布について報告する.
岩手宮城内陸地震にともなうpreseismicとcoseismicな地下水・温泉の変動と地震発生
大槻憲四郎・鹿島雄介・南須原美恵(東北大)
地下水変動観測網の一部である震央距離35kmと60kmの深層ボアホールにおいて,顕著なcoseismicな地下水位と水温の変動が観測された.しかし,明瞭なpreseismicな変動は観測されなかった.他方,震源域にある温泉群では,3地域にのみ地震の前に水温・湯の色・湧水量に明瞭な変化が認められた.このことは,preseismicな地殻変形が著しく局所化して,これらの“ツボ”に着目した地震予知法の開発を進めるべきであることを示唆する.
平成20年岩手宮城内陸地震による土砂災害概要−秋田大学土砂災害調査班報告
大場司・山元正継・近藤梓・鈴木真悟・林信太郎(秋田大)
秋田大学土砂災害調査班は,地震直後から秋田県,宮城県,岩手県内の土砂災害の調査を行ってきた.本報告では,調査を行った土砂災害の状況を報告するとともに,その地質・地形学的背景について述べる.さらに,土砂災害が多く発生した地域の地質・地形の特徴および,その地域地質の従来研究の諸問題についても考察する.
2008年岩手・宮城内陸地震による地盤災害と地形
金折裕司(山口大)・○福塚康三郎(八千代エンジニヤリング)・佐藤忠信(神戸学院大)・中井
卓巳(アーステック東洋)・飯島康夫(八千代エンジニヤリング)・福塚健次郎(アーステック
東洋)
主な地盤災害(特に斜面災害)の発生箇所において,新旧の地形情報を用いて地盤災害と地形との関連性を検討した結果,いずれも過去に斜面崩壊ないし地すべりが発生したことを示す地形であることが明らかとなった.地盤災害のリスク評価に際して 新旧の地形情報を関連付けることの重要性を報告する.
2008年岩手・宮城内陸地震と東北四県での地震地質被害−荒砥沢ダム上流の地すべりを中心に−
川辺孝幸(山形大)
2008年岩手・宮城内陸地震で発生した被害について,調査をおこなった結果過去に発生した古い地すべりが今回の地震の強震動によって再活動したものであることが明らかになった宮城県栗原市荒砥沢ダム上流域の地すべりを中心に,秋田県や山形県での被害についても報告する.
岩手・宮城内陸地震にともなう大規模地滑りの地質学的特徴
天野一男・藤縄明彦・本田尚正・松原典孝(茨城大)
荒砥沢ダム上流部および冷沢流域で発生した大規模地滑りについて,現地調査の結果をもとに地滑りのメカニズムを地質学的観点から考察する.
一般発表
「応用地質学一般」のサブセッションとして7編(口頭4編,ポスター発表3編)
口頭発表:9月22日(月)午後2時30分〜3時30分
ポスター発表:9月22日(月)午後1時〜2時
地理情報システムを用いた地震災害とカルデラ構造との関連の検討
地理情報システムを用いた地震災害とカルデラ構造との関連の検討
Relationship between earthquake disasters and caldera structures using of GIS
布原啓史((株)テクノ長谷),吉田武義,山田亮一(東北大・理)
Abstract
The authors investigate caldera structures and the large scale landslide resulted from Iwate-miyagi inland earthquake by the own GIS database which has been compiled several environmental hazard factors such as known landslide topographies, active fault system, metal mines and hydrothermal alteration zones on geologic context. The resulted map from the GIS database suggested that the caldera structure is closely related to the distribution of the large scale landslides.
1.地質・地形・地圏環境GISデータベース
筆者らは,産学官連携プロジェクトとして,自然由来の土壌汚染や水質汚濁の原因解明に資する目的で,デジタル化された地質図上に,様々な地質・地形・地圏環境に関する情報を統合化しつつある.1),2)これまでに公表した具体的なコンテンツとして,東北地方における地すべり地形,活断層分布及び河川の重金属バックグランドなど,また,全国レベルとして,鉱山や変質帯分布図,独自の土壌や岩石分析値などがある.今般,これらを土台として,東北地方のカルデラ構造3),4)分布および大規模斜面崩壊地点分布などを統合し,今回の地震災害と地質構造との関係を検討した.
2. 大規模地すべりとカルデラ構造
写真1.荒砥沢ダム上流の大規模地すべり.幅900m長さ1300m最大深さ150m以上,推定移動土砂量7000万m3におよぶ10). (6月18日撮影)
第1図.栗駒山周辺の地質図とカルデラ構造および土砂災害発生位置,地質図は東北地方デジタル地質図1)を一部修正して使用.斜面変動箇所は日本地すべり学会資料9)より一部引用
*クリックすると大きな画像がご覧頂けます。
今回の地震で荒砥沢ダム上流部に発生した大規模地すべり(写真1)は,栗駒山南麓カルデラ5)のカルデラリム近傍に位置している(第1図).また中小規模の斜面変動も,同カルデラの内部に多数発生している.
今回の地震に伴って発生した大規模地すべりは,相互の空間的関連からみる限り,震源近傍(上盤側)に位置していたカルデラの存在が重要な要因であった可能性が高い6)7).脊梁山地に分布するカルデラ内部にはそれを充填する大規模火砕流堆積物の上に後カルデラ期の湖成堆積物が載ると共に,それを後火山活動期の火砕岩や溶岩が緩傾斜で広く覆っている場合が多い.多くのカルデラで,キャップロックを成す後火山活動期の火山岩類が,固結度が低い湖成堆積物の層理面に沿う塑性流動によって生じたすべり面で,大規模な地すべりを起こしている7)8).また,第四紀火山の下に伏在するカルデラの,特に熱水変質が進んだ壁に沿って,多数の地すべり地形が分布する例もある6)7).
荒砥沢ダム上流に発生した大規模地すべりでは,末端部に砂泥互層(湖成堆積物)が分布し,主滑落崖では,厚さ50m以上の塊状軽石凝灰岩の上位に,厚さ60mのデイサイト質溶結凝灰岩が覆っているのが認められる.今回の大規模地すべり発生箇所の地質も,固結度が弱く密度の低い凝灰質湖成堆積物の上位に,硬質で比較的高密度の火山岩類が分布するキャップロック構造を有している.
3.東北地方のカルデラ分布と自然災害ハザード
脊梁山地には12Ma以降に形成されたカルデラが南北に配列している.とりわけ,栗駒火山周辺には,カルデラが密集してカルデラクラスタを構成している(第2図)3)4).今回の地震断層は,マントルから下部地殻にかけて,低速度体が発達し,地震発生層が薄い脊梁火山列分布域の海溝側肩部(火山フロント)に沿っている.この地帯は脊梁山地のカルデラクラスタ分布域と重なっている.伏在カルデラを第四紀火山が覆う今回の地震災害域と同様の地質的環境は,東北地方の多くの地域で認められる.これらの主に後期中新世から鮮新世にかけて形成されたカルデラについては,栗駒地域同様,第四紀火山噴出物に広く覆われ,その構造の詳細が不明な場合が多い.今後,これらのカルデラについて,その地質構造と地すべり分布の関係に関する情報をさらに整理し,今後の防災・減災に生かすことが望まれる7).
第2図.東北地方のカルデラと地質断層,第四紀火山の分布状況.地質断層,第四紀火山,および活断層分布は東北地方デジタル地質図1)を使用.
*クリックすると大きな画像をご覧頂けます。
参考文献
1) 建設技術者のための東北地方の地質,東北建設協会,2006.
2) 地圏環境インフォマティクス,東北大学大学院環境科学研究科,2008.
3) 吉田武義・相澤幸治・長橋良隆・佐藤比呂志・大口健志・木村純一・大平寛人:東北本州弧,島弧火山活動期の地史と後期新生代カルデラ群の形成,月刊地球,号外27,p.123〜129,1999.
4)吉田武義・中島涼一・長谷川昭・佐藤比呂志・長橋良隆・木村純一・田中明子・Prima,O.D.A・大口健志:後期新生代,東北本州弧における火成活動史と地殻・マントル構造,第四紀研究,vol44,No.4,p.195〜216,2005.
5) 大竹正巳,栗駒南部地熱地域,赤倉カルデラの層序と火砕流噴出・陥没様式,地質雑,vo1.106,No.3,p205〜222,2000.
6) 大八木規夫・池田浩子,地すべり構造と広域場からみた澄川地すべり,地すべり, Vol.35,No.2, p1〜10,1998.
7) 大八木規夫,東北地方北部における地すべり地形と後期中新世−更新世のカルデラ,深田地質研年報, No.1,p112〜127,2000.
8) 大八木規夫,東北地方南部における大規模地すべり地形とカルデラ−主として会津地域について−,深田地質研年報, No.2,p121〜135,2001.
9)2008年岩手・宮城内陸地震による斜面災害の空中写真判読図,(社)日本地すべり学会,http://japan.landslide-soc.org/
10) 平成20年岩手・宮城内陸地震 荒砥沢ダム上流地すべり調査報告,(社)日本地すべり学会東北支部,http://wwwsoc.nii.ac.jp/thb-jls/
本稿は日本地質学会のために特別に寄稿頂きました。
Haiti Earthquake/ハイチ地震について
ハイチ地震について
We express deepest condolences for those who have lost their families, relatives and friends due to the Haiti Earthquake of January 12, 2010. We also express our hearty sympathy to those who were injured and lost their homes by the earthquake. As geologists who live in the world's most seismic country, we regret that our level of science does not yet enable any prediction of an earthquake, and international co-operation is not yet enough to support suffered people. We ask every member of our society to make donation through Japanese Red Cross or other organization to help survival of the people and reconstruction of the country. We hope our basic studies in various fields of geological sciences contribute to understand seismic processes and help mitigation of the seismic disasters.
January 19, 2010
Geological Society of Japan
日本地質学会会員の皆様
2010年1月13日6時53分(日本時間)にカリブ海の島国であるハイチ共和国南部でM7.0の地震が発生しました.この地震は北米プレートとカリブプレートのプレート境界近傍の内陸断層の活動による直下型地震と考えられています.人口の密集する首都の直下が震源となったために,多くの家屋が倒壊し,数十万人規模の死者が予想されるなど甚大な被害が出ています.くしくも兵庫県南部地震から15年が経過して多くの報道や番組放映などがされたこともあり,突然襲う地震災害の恐怖を,人々に改めて感じさせることになりました.
地質学は地震の発生や地震動に関する科学的な解明に寄与し,災害を小さくするために貢献することが求められています.その役割は,今後ますます大きくなると考えられます.地質学会は,国内の災害だけでなく,2008年5月の中国の四川大地震の時などにも,学会のウェブサイトやgeo-Flashなどによって災害情報やその地質学的背景の説明,様々な情報提供先の紹介,寄付を集めている人道的支援団体の紹介などを行いました.
今回ハイチで発生した大地震についても,日本地質学会は,四川大地震と同じような対応措置をとることにいたしました.地質学的な背景の解説とともに,さまざまな地震や災害の情報を学会のサイトに公開,リンクを形成いたしますので,ご利用ください.また,ハイチの大地震に関する情報提供の可能な方は,是非ご協力をお願いいたします.提供いただける方は地質学会事務局までお申し出ください.
最後になりましたが,今回の地震で亡くなられた多くの人々のご冥福をお祈りするとともに,困難に立ち向かっている方々の奮闘をお祈りしたいと思います.
2010年1月19日
日本地質学会地質災害委員会委員長
藤本光一郎
チリ地震津波とチリのテクトニクス
チリ地震津波とチリのテクトニクス
安間 了(筑波大学生命環境科学研究科)
図1:南米大陸パタゴニア地方のテクトニクスと火成作用。
「海水がふくれ上がって、のっこのっことやって来た」
三陸沿岸で夜明けの海を見つめていたある漁師は、吉村昭の取材に対してこんな言葉で1960年チリ地震津波の襲来を伝えたという。これほどドラマティックではなかったにせよ、2010年2月28日に我々が目のあたりにした光景も、まさにこのようなものであった。そしてこのような光景は、天正14年にも、貞享4年にも、享保15年と天保8年にも、明治元年と明治10年、大正11年にも三陸沿岸でみられたという。チリ沖合で発生した遠地津波が日本に到達することは、けっしてめずらしいことではないのである。
南米チリ共和国は、火山や地震活動に関しては、日本以上に活動的な地域である。ここ数年の例をあげても、2007年1月22日から始まったPuerto Aysenフィヨルド内で起きた地震活動(これは噴火を伴ったと考えられている)と津波、2008年5月に始まり4000人を避難させたChiaten火山の噴火、そして2010年2月27日の巨大地震と大規模な災害がチリ南部で次々と起こっている(図1)。この巨大地震は低角逆断層の震源メカニズムをもち、プレートの沈み込みと直接関連しているが、ほかの活動は斜めに沈み込むプレートの横ずれ成分を解消するように発達したLiquine-Ofqui断層帯に沿って生じている。また、Villarrica火山をはじめとするチリ中央部の活火山の活動も、近年活発になってきているようである。
図2:1973年から2010年2月25日までの震源分布と20世紀以降に生じた大地震の震源域(東京大学地震研究所ホームページより)。チリ三重点近傍は地震計の数も少ないが、地震の数そのものも北側に比べて明らかに少ない。
チリのテクトニックセッティングを概観してみよう。図1にプレートと第三紀以降の火成活動の分布を示した。ここで目につくのは、沈み込む海洋プレートと火成活動との関係である。チリ海嶺が沈み込んでいるタイタオ半島の北側では、北側に向かって次第に古くなるナスカ・プレートがおよそ9 cm/yの速度で東北東へ、南側では南に向かって次第に古くなる南極プレートがおよそ2cm/yの速度でほぼ真東に向かって南米大陸の下に沈み込んでいる。パタゴニア(南米大陸の南緯40度以南の地域)南部では、14 Maから始まったチリ海嶺の沈み込みがすでに完了しており、地下にはいわゆるasthenospheric windowが期待される地域であるが、活火山の分布はまばらである。一方、より冷たいスラブが沈み込むパタゴニア北部からチリ中央部では、密に分布する活火山がほぼ直線状の火山前線を形成している。不思議なことに、冷たいスラブが沈み込んでいる場所の方が、火山活動は活発なのである。パタゴニア南部では、中期中新世の花崗岩が火山前線よりも前弧側にまばらに分布していることが知られているが、これがナゾを解く鍵かもしれない。
地震もまた、沈み込む海洋プレートにその活動が規制されているようである。1960年チリ地震の震源域は、ナスカ・プレートが沈み込む領域に破壊域が限定されている(図1)。さらに過去に生じた地震の分布(図2)と比べると、地震はチリ海嶺沈み込み帯付近では少ないこと、北側にいくほど多くなること、20世紀以降に発生したMw > 8.2 以上の地震もナスカ・プレート側に集中していることがわかる。ナスカ・プレートの沈み込み速度が南極プレートよりも早いことに加え、沈み込むスラブの温度や浮力によって、上盤とのカップリングが異なるためと考えられる。
このようなコントラストは、地質にも現れている。タイタオ半島沖では、堆積物の供給量が多いバーケル川などの河川が流入しているにもかかわらず、付加体は全く発達しておらず、造構浸食が進んでいる。一方、より古いスラブの沈み込むタイタオ半島南側の海域では、付加体が形成されつつある様子が地震波探査などで示されている。所はかわり、形は変えつつも、西南日本と東北日本のようなテクトニックなコントラストが、チリでも観察されるのである。
図3:コンセプシオン近郊のチリ国道5号線法面に記録された地殻変動の記録。断層面上の条線(図4)を観察すると、単純な正断層ではなく、横ずれ成分が大きいことがわかる。
図4:図3露頭の断層面。条線は横ずれ成分が大きいことを示している。
図5:タイタオ半島(1960年チリ地震の震源域南端)先端部にみられる横ずれ断層に伴うpressure ridge。
さて、チリにおける地震活動を示すいくつかの露頭を紹介したい。図3は、コンセプシオン付近のチリ国道5号線の法面に現れた活断層群である。上位の褐色の地層はいわゆるローム層であり、下位の凝灰質岩の変位に伴って変形している。一見すると正断層のように見えるが、断層面上の条線の向きから横ずれ成分が大きいことがわかる(図4)。したがって、地すべりではなく、テクトニックな変形によって生じた断層であると思われる。図5はタイタオ半島最先端部に分布する超塩基性岩中に発達する横ずれ断層とそれに伴うpressure ridgeである。この地域は1960年チリ地震の破壊域の最南端部に当たる。この断層が1960年地震の時に動いたかどうかは定かでないものの、巨大地震が末端部で歪を解消するときに、何らかの役割を果たしたのではないかと考えている。
アイスランド火山噴火と噴煙
アイスランド火山噴火と噴煙
鈴木雄治郎(海洋研究開発機構)
*画像をクリックすると大きな画像がご覧になれます。
エイヤフィヤトラ氷河噴火
図1:2010年2月8日の桜島昭和火口の様子.2010年に入りこのような爆発的な噴火がほぼ毎日起こっている.
4月中旬に起こったアイスランドでの噴火はヨーロッパの約30カ国の空港を一時閉鎖に追い込み,経済的にも大きな損害を与えた.日本国内でも,桜島で千mに達する噴煙を出すような噴火がほぼ毎日起こっていて(図1),噴煙災害はけっして対岸の火事ではない.
アイスランドの噴火は島の南に位置するエイヤフィヤトラ氷河(Eyjafjallajökull)で覆われた地点(図2)で4月14日に約190年ぶりに開始し,溶岩の流出と噴煙柱と呼ばれる噴煙の上昇が続いた[脚注1].噴火初期
図2:アイスランドの地質図と地形図.赤☆印は4月に噴火したエイヤフィヤトラ氷河噴 火.緑☆印は3月のフィムヴォルズハゥルス噴火地点.青☆印はカトラ火山.(Landmælingar Íslands[1]の図に加筆)
には噴煙は高度10km以上に達する噴煙柱を形成し,その時点で西もしくは北西からの風が卓越していたために噴煙は欧州各国に流れる事態となった.噴火開始から数日経つと噴煙柱の高度は3〜5kmの高さまで減少したが,欧州航空網の混乱は続き,空港の再開までに約1週間かかった[脚注2].(エイヤフィヤトラ氷河噴火については東京大学地震研究所[3]やIceland Met. Office [4]などの解説も詳しい.)
火山噴煙
図3:火山噴火の概念図.高温・高圧状態で溶けたマグマは,火道と呼ばれる経路をつたって地表に出る.地表に近づくにしたがって圧力が下がるため,マグマ中の揮発成分がガスとして急膨張しマグマは粉々に破砕する.火山ガスとマグマの破片の混合物が火口から噴出する.
一概に噴煙と言っても,その意味は広いため注意が必要である.噴煙は,火山灰・軽石・火山ガス(水蒸気,CO2, SO2)などの火口から噴出してきたもの(噴出物)とそれと混合した周囲の空気や水蒸気の混合物である.噴煙の構成である火山灰:軽石:火山ガス:空気:水蒸気の質量比は無限の組み合わせがあり,噴煙は火山灰を多く含む灰色のものから,ほとんど雲と見分けがつかないような空気と水蒸気を主要成分とする白色のものまでバリエーションを持つ.灰色の噴煙に含まれる火山灰を航空機が吸い込むとエンジンが停止する危険性があり,今回の噴火では4月15日にスカンジナビア半島まで灰色の噴煙が広がっている様子が衛星から観察された.その後の火山灰の拡大はそれほど大きくなかったが[脚注3],安全を重視してSO2などの火山ガスを主体とする“噴煙”の広がりを警戒した結果,空港閉鎖が長期化したと考えられる.
今回の噴火で再認識させられたのは,「航空機のエンジン停止という最悪の事態を避けつつも空港閉鎖という経済的損害を最小限に食い止めるためには,噴煙拡大を正確に観測し予測することが重要」ということである.噴煙の挙動は,その流体的振る舞いに加え,風や地形の影響や火山灰が噴煙から分離する影響など,複合的な問題であるため,未だ十分な理解が得られていない.まずは,これまでに分かっている噴煙の挙動について概略を解説する.
火山内部では,マグマが減圧した時に溶け込んでいた火山ガスが急膨張する.この急膨張によってマグマは粉々に破砕され,噴煙として火口から爆発的に噴出する(図3).加速された噴煙は火口で音速を超えて衝撃波を発生させることもある[脚注4].火口直上ではその慣性で上昇するが,火口での初期運動量だけで重力に打ち勝って上がれる高さは限られる(例えば,秒速100mで噴出したとしても放物運動で上がれる高さはたかだか500m).噴煙はその上昇中に周囲の大気を取り込んで,取り込んだ空気を火山灰の熱で膨張させる.それによって噴煙は浮力を獲得し,上空数km〜数十kmまで上昇することができる.すなわち,噴煙上昇とはマグマの熱エネルギーを位置エネルギーに変換する現象と言い換えることができる.
図4:火山噴煙の概念図.噴煙の観測量としては,人工衛星から噴煙柱高度,傘型噴煙の高度と半径が得られ,野外観察により降灰分布が得られる.噴火に伴う空気振動が計測されることもある.
浮力を得た噴煙は上昇を続けるが,空気は上空にいくほど薄くなるため,ある高度で空気と膨張した噴煙の密度が釣り合うことになる.噴煙はその高度(密度中立高度)よりも上昇することはできず,水平方向に拡大する.正確には,噴煙が密度中立高度に達した時点では,噴煙はまだ上向きの余分な運度量を持っているため,密度中立高度よりも上に慣性で上昇する.噴煙は最高到達高度に達すると,上向きの運動量を失い密度中立高度に流
図5:噴煙柱・傘型噴煙の3次元シミュレーション.噴出物の濃度が1%の等値面を表 している.数値計算はSuzuki and Koyaguchi (2009)[8]を用いた.
れ下る.その形が「傘型噴煙」と呼ばれる由縁である(図4).傘型噴煙は密度中立高度で卓越する風に強く影響を受け,火山灰と火山ガスが運搬される.この領域が,エイヤフィヤトラ氷河噴火で欧州に拡大した噴煙に相当する.火山灰は大きな粒子から順に傘型噴煙から分離して落ちていくため,火山から離れるにしたがって地表に堆積するする粒子サイズは小さくなる.数十μm以下の小さな粒子や硫酸の微粒子に変化したSO2ガスはエアロゾルとして長期に渡って大気中に滞留し,地球全体の気温低下を引き起こす.
火山灰や火山ガスの大気中への分布や降灰分布を予測するためには,火口からどれだけの火山ガスとどの粒子サイズの火山灰がどの高度まで運搬されるかという問題と,一旦傘型噴煙に流入した火山ガスと火山灰がどのような風(風向・風の強さ)によって移流し拡散していくかという問題に整理される.前者の問題に関しては,近年噴煙の3次元シミュレーションが発達し(Suzuki and Koyaguchi, 2009 [8]),火口から出た噴煙全体が傘型噴煙へと成長する様子が再現できるようになってきていて(図5),火山灰が上空にどれだけ運ばれるかを再現する前段階に達している. 後者の問題に関しては,傘型噴煙を対象とした数値モデルが提案されていて(例えば,PUFF[9], Fall3D[10],Tephra2[11]),火山直上での粒子濃度分布を境界条件として与えた時に風や拡散によって火山灰が広がる様子を再現できるようになってきた(図6).正確な災害予測の実用にはもう少し時間はかかるが,噴煙柱の3次元シミュレーションと傘型噴煙の降灰モデルを結合することで,火口の噴火条件から火山灰と火山ガスの分布を予測できるようになる段階に入りつつあると言える.
図6:火山灰分布の数値シミュレーション(Krazmann et al., 2010 [9]).上空の風に流されて火山灰が移流していく様子が再現できている.
図7:フィリピン・ピナツボ火山1991年噴火の写真(Fire and Mud, 1995 [5]).
[脚注1] エイヤフィヤトラ氷河噴火に先立ち,3月には同じエイヤフィヤトラ氷河でフィムヴォルズハゥルス(Fimmvörduháls)噴火が起こっていている.「4月の噴火は数週間の休止後に再噴火した」と解説がされることもあるが,フィムヴォルズハゥルス噴火の火口はエイヤフィヤトラ氷河噴火の火口と10km程度離れていることに注意されたい(図2).速報によると,フィムヴォルズハゥルス噴火の溶岩はSiO2が47%の玄武岩質であり,エイヤフィヤトラ氷河噴火の火山灰はSiO258%と安山岩質である[2].距離と時間が近いこの2つの噴火の連動性は現段階では明確でなく,今後の物質化学研究もしくはモデル研究が期待される.エイヤフィヤトラ氷河噴火の東にあるカトラ火山(図2)に関しても,過去にエイヤフィヤトラ氷河噴火の直後にカトラ火山が大噴火を起こしたという経験則から今回もその噴火を危惧する声がある.しかし,この2つの火山が連動しているかどうかについても明確な答えは得られていない.
[脚注2] 今回の噴火はその規模に対して空港一時閉鎖などその影響は予想以上に大きなものとなった.参考までに,1991年のフィリピ ン・ピナツボ噴火(図7)での噴煙柱の高度は30kmを超し,数年前のチリ・チャイテン噴火でもその高度は20kmを超した.ピナツボ噴火ではアメリカ軍 の空軍基地が降灰の影響で使用不可能となり,政治的な理由もあるもののこの噴火がアメリカ駐留軍のアメリカからの撤退につながったと言われている.国内で も,2000年三宅島噴火(図8)では噴煙柱は12kmに達した,
図8:三宅島2000年噴火の写真(撮影者:富士常葉大学 嶋野岳人).
図9:1875年アスキャ火山噴火の降灰分布図(Carey et al., 2010 [6]).
[脚注3] アイスランドでは島東部にあるアスキャ(Askja)火山で1875年に大きな噴火が起こり,その時の火山灰は少量ながらもヨーロッパ各地で観察されている(図9).
[脚注4] 高速噴出に伴う衝撃波の発生は今回の噴火でも見事に観察されている[7].
[1] http://www.lmi.is/english/
[2] http://www.earthice.hi.is/page/IES-EY-CEMCOM
[3] http://outreach.eri.u-tokyo.ac.jp/2010/04/201004_iceland/
[4] http://en.vedur.is/about-imo/news/2010/
[5] Newhall, C. G. and Punongbayan, R. S., Fire and Mud, University of Washington Press, Seattle, 1996.
[6] Carey, R. J., Houghton, B. F., and Thordarson, T., Tephra dispersal and eruption dynamics of wet and dry phases of the 1875 eruption of Askja Volcano, Iceland, Bulletin of Volcanology, vol. 72, 259-278, 2010, doi:10.1007/s00445-009-0317-3.
[7] http://http.ruv.straumar.is/static.ruv.is/vefur/20042010_myndir_omar.wmv
[8] Suzuki, Y. J., Koyaguchi, T., A three-dimensional numerical simulation of spreading umbrella clouds, J. Geophys. Res., vol. 114, B03209, 2009, doi:10.1029/2007JB005369.
[9] Kratzmann, D. J., Carey, N. S., Fero, J., Scasso, R. A., Naranjo, J.-A., Simulations of tephra dispersal from the 1991 explosive eruptions of Hudson volcano, Chile, J. Volcanol. Geotherm. Res., vol. 190, 337-352, 2010, doi:10.1016/j.jvolgeores.2009.11.021.
[10] Folch, A., Costa, A., Macedonio, G., FALL3D: A computational model for transport and deposition of volcanic ash, Computers & Geosciences, vol. 35, 1334-1342, 2009, doi:10.1016/j.cageo.2008.08.008.
[11] Bonadonna, C., Connor, C. B., Houghton, B. F., Connor, L., Byrne, M., Laing, A., Hincks, T. K., Probabilistic modeling of tephra dispersal: Hazard assessment of a multiphase ryolitic eruption at Tarawera, New Zealand, J. Geophys. Res., vol. 110, B03203, 2005, doi:10.1029/2003JB002896.
【2011年地質災害関連情報】
2011年度地質災害関連情報
■ 東日本大震災
■ 平成23年台風12号による紀伊半島における地盤災害
■ その他
ニュージーランドクライストチャーチ地震の地質学的側面 3.1掲載
衝撃波が発生した新燃岳の爆発的噴火 2.15掲載
新燃岳噴火とハザードマップと霧島ジオパーク 2.12掲載
霧島山新燃岳2011年噴火情報:関連リンク 1.31更新
【2012年度地質災害関連情報】
2012年度地質災害関連情報
■平成24年7月北部九州豪雨災害に関する地質情報が産総研のHPに掲載されました。(2012.7.25)
災害と緊急調査:(産総研地質調査総合センターHPへのリンク)
「平成24年7月九州北部豪雨による熊本県、阿蘇カルデラ北東部で発生した斜面崩壊の地質学的背景」
新燃岳噴火とハザードマップと霧島ジオパーク
新燃岳噴火とハザードマップと霧島ジオパーク
2011.2.14掲載 *無断転用禁止
霧島市企画政策課霧島ジオパーク推進室
室長 坂之上浩幸
平成23年1月26日の噴火に始まった今回の新燃岳の活動は,今後どのような経過をたどっていくのか,未だ予断を許さない状況で,霧島山周辺の自治体は緊張を強いられています.ここでは,ここ2年ほどの新燃岳の様子を紹介していきたいと思います.
写真1 1月26日噴火
平成20年8月22日,新燃岳における火山性微動の振幅が大きくなり,小規模な噴火が観測されました.気象庁による噴火警戒レベルは2(火口周辺規制)とされ,霧島山北東部の小林市方面で降灰が観察されました.これがこの一連の噴火活動の始まりであったと考えられます.
同年10月には火山性微動,噴煙量ともに少なくなり,噴火警戒レベルは1(平常)に戻されましたが,その後コバルトグリーン色であった火口内の池の色が,一時期茶褐色に変色するなどの現象が観察されています.
平成22年3月30日には小規模な噴火が起き,噴火警戒レベルは2に引き上げられました.4月に入り,警報は一時解除されますが,5月には再びレベル2となりました.
写真2 平成22年3月14日の火口.
写真3 平成22年7月10日の噴火.
平成22年7月10日にも小規模な噴火が起きています.噴煙は火口縁上300mまで上がり,雲まで到達しましたが,この時の噴火ではコックステールジェットが観察されています.また,火口縁南部分で小規模な火砕流が発生したようです.(写真3 霧島ネイチャーガイドクラブ提供)
この冬,寒くなり始めた頃から白い噴気が高く登る場面が多く見受けられるようになり,ついに年明けの1月19日には降灰を伴う噴火がありました.霧島山南東部の都城市から日南市にかけて降灰があり,都城市夏尾地区では周囲が一面雪とまちがうばかりに白く変貌しています.(写真4都城市西岳市民センター提供)
1月26日午後3時過ぎ,細く噴煙をたなびかせる間欠的な噴火が続いた後,激しい噴火がはじまりました.写真1はその時の噴火の始まりを火口から西へ約3000mの地点の新湯温泉入口から撮影したものです.(平成23年2月8日現在立入り禁止)この噴火を皮切りに活発な噴火活動が始まり,風下側の新燃岳東部・南東部にあたる高原町,都城市には大量の火山灰・軽石が降下しています.
2月1日7時54分には,激しい空振を伴う爆発的噴火が起き,霧島市霧島,同牧園町高千穂地区を中心に,ガラスが破砕されるなどの被害がありました.あるホテルでは窓ガラスが100枚割れたり,また,出入り口のガラス戸がアルミフレームごと変形したり(写真5),地下にあったガラス引き戸も明り取りの吹き抜けから衝撃が入ったのか,粉砕されており,空振の激しさを物語っています.
また,この噴火では立入禁止区域である3000mの区域を越えて,噴石が飛散し山火事を起こしています.この噴火で立入禁止区域が4000mに拡大されました.
その後,火口内の溶岩湖の直径が600mになり,断続的に噴火が続いている状況です.(2月7日時点)今回の新燃岳の噴火活動は,まだまだ終息が見えない状況で予断を許されない状況です.
写真4 降灰による都城市内の様子.
写真5 空振によるフレームの変形.
さて,霧島山をとりまく5市2町の自治体(宮崎県都城市,高原町,小林市,えびの市,鹿児島県湧水町,霧島市,曽於市)でつくる環霧島会議という組織があります.この組織は県境を越えて観光・防災・広報・教育などの共通の課題に広域的に取り組むために平成19年に設立されました.この中の防災部会で,霧島山の噴火にともなう災害対策のために,国土交通省宮崎河川国道事務所及び鹿児島大学井村准教授にご協力をいただき,「霧島火山防災マップ」を平成21年に作成し,霧島山周辺の世帯に配布しました(図1参照).
図1 霧島火山防災マップ.
図2 副読本「ふるさとの山霧島山」.
この防災マップには,噴火の可能性が高い火山が噴火した場合の溶岩流,火砕流・火山泥流などの到達経路と範囲がシミュレーションにより表示されており,今回の新燃岳の噴火に際し大きく役立っています.
また,昨年9月,環霧島地域では霧島山とその周辺が日本ジオパークとして認定されました(図2参照).ジオパーク活動の推進においては,「防災」や「教育」という一面も大切なことです.防災マップ作成後に開催した住民向けの火山防災講演会やジオガイド要請講座を通じて,多くの方に火山災害の脅威と防災について周知活動を続けるとともに,
写真6 霧島火山防災講演会.
小・中学校でも霧島山の火山の成り立ちや自然を解説した副読本「ふるさとの山霧島山」を活用するといった,火山地域に住むために必要な防災情報の提供に取り組んできました(写真6).
いつ終わるとも予測がつかない新燃岳の噴火ですが,霧島ジオパークにはこの火山活動も織り込み済みで,霧島ジオパークのテーマは「自然の多様性とそれを育む火山活動」です.火山活動があるから,ミヤマキリシマなどの植物が植生遷移を繰り返すという自然のサイクルをここで観察することができます.
噴火が収まり,規制が解除になりましたなら,この地球の息吹が感じられる霧島山に皆様是非おいでください.
最後に,新燃岳の活動が早期に終息し,環霧島地域の皆様が一日も早く通常の生活に戻れることを願ってやみません.
■ 霧島ジオパークのサイト(リンク)
鹿児島県南大隅町船石川の土石流災害
2010年7月に発生した鹿児島県南大隅町船石川の土石流災害
井村隆介(鹿児島大学・大学院理工学研究科)
*画像をクリックすると大きな画像がご覧になれます。
2010年7月に発生した鹿児島県南大隅町船石川の土石流災害
写真1 西側から見た南大隅町の土石流発生現場(7月6日11時ころ撮影.鹿児島県提供)
2010年7月4日から5日にかけて,鹿児島県南大隅町の船石川で土石流が発生した.流出土砂は,既設の砂防ダムにトラップされ,大浜集落の数百メートル手前で止まった(写真1).町は5日,集落の50世帯91人に避難勧告を出した(7月20日現在,継続中).その後,7日午前1時ころに比較的規模の大きな土石流が発生し,あふれた土砂が大浜集落の一部と国道269号を埋め,海にまで達したが,けが人はなかった.土石流は7月8日昼までの間に合計7回観測された.
土石流の発生源となった崩壊は,阿多火砕流がつくる火砕流台地の縁で発生した.崩壊土砂は,北側の大浜川水系(写真1向かって左の流れ)と南の船石川水系(写真1向かって右の流れ)に落ち,船石川水系のものが土石流化して遠くまで流れ下った.船石川では2007年7月にも同じ場所で崩壊・土石流が発生しており,今回の土石流はそのときの源頭部がさらに上流側に広がる形で発生した.大浜川水系への崩落は,船石川側のそれに引きずられるようにして起こったものである.災害現場周辺では,6月末までに900mmを超える累積雨量を観測していたが,土石流発生時にはほとんど雨を観測していない.崩壊のタイミングやその規模などから,船石川で発生した崩壊はいわゆる深層崩壊であると判断できる.
写真2 船石川2号えん堤付近から見た源頭部(7月15日11時ころ井村撮影)
周辺の地質は,大隅花崗岩を基盤とし,その上に下位より阿多鳥浜軽石,阿多鳥浜火砕流,円レキ層,ローム層,阿多軽石,阿多火砕流および台地上の火山灰・ローム層が載る.崩壊部に露出した阿多火砕流溶結部の下からは多量の湧水が認められ,崩壊は阿多火砕流の溶結部と非溶結部との境界で発生したと考えられる(写真2).船石川上流部の崩壊地に見られる阿多火砕流溶結部の下面は下に凸になっており,同じ溶結・非溶結部境界でも特にここが水を集めやすいところであることがわかる.火砕流台地上を含めた周辺地質については現在も調査を継続中で,追って報告する予定である.
住民が避難をしている中での調査を許可していただいた南大隅町,写真や情報を提供してくださった鹿児島県に感謝します.最後に,現在も避難されている方々や被災地の一日も早い復興をお祈りいたします.
【2010年地質災害関連情報】
2010年度地質災害関連情報
2010年7月16日 広島県庄原市北部の土砂災害地域の地質(産総研HPより) 7.31
2010年7月15日に発生した岐阜県南部の集中豪雨災害地域の地質情報(産総研HPより) 7.27
2010年7月に発生した鹿児島県南大隅町船石川の土石流災害 7.20掲載
鹿児島県南大隅町で起こった斜面崩壊(土石流)の地質学的背景(産総研HPより) 7.9
火山ガス災害(2010年6月20日)が発生した酸ヶ湯温泉付近の地質について(産総研HPより) 6.23
アイスランド火山噴火と噴煙
チリ地震津波とチリのテクトニクス
ヒスパニョーラの地質とテクトニクス (ハイチの地震に寄せて)
Haiti Earthquake/ハイチ地震について
衝撃波が発生した新燃岳の爆発的噴火
衝撃波が発生した新燃岳の爆発的噴火
2011年2月15日掲載
後藤章夫(東北大学東北アジア研究センター)
写真:高圧ガスを噴出する噴火模擬実験.半球状に広がるのが,高圧ガスを詰めた容器の口を開いた瞬間に発生した衝撃波で,中央にキノコ雲のように立ち昇るのが,噴出するガスの流れ.(撮影:東北大学流体科学研究所)
1月19日から始まった新燃岳の噴火活動は,26日には本格的なマグマ噴火へと移行し,27日からは爆発的な噴火がしばしば発生するようになった.2月1日7時54分には,火口から3kmほどの湯之野で458.4Paの空振が観測される爆発があり,これにより窓ガラスが割れるなどの被害が出た.このような活動活発化に伴い,1月26日からは火口から2km以内の立ち入りが規制され,その後,31日には3km,2月1日には4kmへと,その範囲は順次拡大されている.9回目となる爆発が2月3日に起こってからしばらくの間,噴火活動は比較的小規模なものに限られていたが,2月11日にはまた爆発があり,活動終息の見通しは立っていない.(以上,気象庁HP及び霧島市HP参照)
2月1日の爆発で被害が出たこともあり,この噴火では,「空振」という言葉がにわかに注目された(雲仙普賢岳の噴火で,「火砕流」という言葉が広く認知されたのに似ている).しかし空振は決して珍しい現象ではなく,2004年の浅間山噴火でもガラス破損などの被害が出ているし(例えば横尾ほか2005),程度の差こそあれ,むしろ噴火が起これば必ず空振が発生すると思った方がよい.
空振は読んで字のごとく,空気の振動のことで,広い意味では「音」もこの中に含めて良いだろう.しかし火山の分野で空振というと,比較的低い周波数の波を指すことが多く,人間に聞こえる限界の20Hzより低い周波数帯もこの中に入る.こういう波が発生すると,何も聞こえないのに窓ガラスがカタカタ震えるといったことが起きる(もちろん,ある程度の圧力が必要).新燃岳の活動でも,爆発的噴火よりも前にはこういった空振が観測されていた.空振の発生原因はいくつも考えられ,特定するのは必ずしも容易でないが,有珠2000年噴火で小規模な水蒸気噴火が継続した期間に観測された空振については,映像との比較から,泥のたまった火口で気泡がはじけることで発生していたと推定された(青山ほか2002).またそういった破裂現象を伴わない噴火でも,空振は噴出率の変化で起こりうる.噴出率が増すと周囲の空気が圧縮され,それが遠方へと伝播するからだ.噴出率が減少すれば,膨張(減圧)が発生・伝播することになる.
1月27日以降の爆発的噴火に伴う空振は,これら小規模な低周波振動とは性質を異にする.特に空振被害を出した2月1日の噴火では,山頂から山麓に向かって,山肌が白く変わっていく様子が映像にはっきり捉えられるとともに,大きな爆発音が鳴り響いた.これは火口を埋めた溶岩の下に高圧の火山ガスが溜まり,それが一気に解放されて衝撃波が発生したためと考えられる(写真参照).低周波の空振は圧力がゆっくり変化するのに対し,衝撃波は圧力がステップ状に上がり,その後,一旦変化前の圧力より低くなってから,もとの大気圧に戻る.山肌の変色は,衝撃波の通過で火山灰が巻き上げられたか,それに続く圧力低下で水蒸気が凝結した(雲が発生するのと同じ)ためと考えられる.
空振は,山が雲で隠れていても観測できる,大気が比較的均一なため伝播経路の影響を受けにくい,などの理由で,近年火山観測に多用されている.しかしその解釈はモデルに依存するのが現状と言わざるを得ない.現在新燃岳周辺では,地震をはじめ,様々な観測が展開されている.空振を含め,様々なデータを組み合わせることで,噴火ダイナミクスが解明されると期待される.
NZクライストチャーチ地震の地質学的側面
ニュージーランド・クライストチャーチ地震の地質学的側面
小川勇二郎; 2011. 2. 27
*Table. 1以外の図・写真は、クリックすると大きな画像をご覧頂けます。
今回の地震
2011年2月22日現地時刻12時51分43秒(21日 23:51:43.0s UTC)にニュージーランド南島クライストチャーチ近郊でM6.3の地震が起きた。震源の深さは約5 kmとされている(表1;図1,2)。この地震は、2010年 9月 4日に約70 km西方で起きたM7.0のDarfield地震(右水平ズレ)の余震域の東端に位置し、余震の一つと考えられる(筑波大学、八木勇治氏による)。今回、この一連の地震の地質学的側面の一部を紹介し、あわせて非震性海嶺の衝突の例かもしれないテクトニクスとして紹介したい。
図1.クライストチャーチ周辺の地形図。直南に、今回述べるバンクス半島がある。また北東方へヒクランギ・トロフや海底谷が伸びている。地図の幅は約200 km。
図2.赤星が今回、青星は、2010年9月の震央。丸印は、2010年9月の地震の余震。オレンジ四角は、クライストチャーチ市の位置。(英国地質調査所のHPによる)。
図3.赤星が今回、青星は、2010年9月の震央。丸印は1843年以降のM6以上の地震の震央分布(英国地質調査所のHPによる)。南島の西縁から北東に延びるアルパイン断層、および分岐して太平洋に延びる斜め沈み込み帯(ヒクランギ・トロフ)が、ニュージーランドを特徴づける。
表1.今回のクライストチャーチ地震の諸元。英国地質調査所(BGS)のHPから。UTC: Coordinated Universal Time(世界標準時)。ニュージーランドは、これより13時間早い。
ニュージーランドの置かれたテクトニックな意義
図4.ニュージーランドのテクトニックな情報(上は、Chochran et al., 2006, 下はAAPGのPlate tectonic mapより)。
ニュージーランドは、現在、北西からチャレンジャー・プラトー、東からキャンベル・プラトー(チャサム・ライズはその一部)がぶつかって、タオルを絞るようになっている。クライストチャーチは、チャサム・ライズの丁度衝突する所に位置する(図4)。ニュージーランドは、こうしてねじれることによって発達してきたと言えるが、大きな地震は、従来アルパイン断層周辺のものが注目されていた。
上に述べたように、西方と東方に大陸地殻があって、北島の東では西方へ、また南島の南西では東方へ、沈み込みが生じている。北島の西海岸に沿って有名なアルパイン断層(活断層)が走っていて、日本でも多くの研究者が訪ねている。また、中古生代の付加体やその深部である、トアラス超層群やオタゴ(ハースト)・シストは、クライストチャーチの北方および南西方に広く分布しており、日本チームの研究も多い。
AAPGによるプレートテクトニック・マップによると(図4)、東西の太平洋プレートとオーストラリアプレートのホットスポット固定にもとづく絶対変位(赤矢印)から、キャンベルおよびチャレンジャープラトー両大陸地殻を乗せた部分の相対変位は、西へ約2-3 cm/yrであることが分かる。これが、すべてアルパイン断層やヒクランギ・トロフでの沈み込みによって消化されているか、それとも内陸部にひずみが蓄積する別の要因があったかは、今後解明されるべき問題だろうが、今回、比較的大きな地震が起きたことは、後者を示唆する。それに関しては以下の状況が見て取れる。
ニュージーランドの新第三紀アルカリ岩
図5.オレンジが、第四紀を中心とするいわゆる北島の島弧的な火山岩。一方、赤が新第三紀を中心とするアルカリ岩タイプのもの。これが現在の島弧火山活動とどう関連するか、またどのようなテクトニックな意義をもつものか、さらに、今回の地震にどのように関連するか、注目される。クライストチャーチは、南島ほぼ中央の赤い半島の直北に位置する。(Sewell et al., 1992による)。
あまり知られていないようだが、ニュージーランドの主として南島の東海岸に沿っておよび内陸部に、島の方向にほぼ平行に、新第三紀のアルカリ玄武岩を主とする火山岩が分布している(図5)。
図6.バンクス半島の新第三紀の火山体(直径約40 km)。西に向かって撮影(Sewell et al., 1992の地質図幅のケースの表紙)。向こう側が、リットルトン火山、こちら側がアトロア火山と呼ばれている。クライストチャーチは、すぐ右上に位置する。
図7.バンクス半島の火山岩のハーカー・ダイアグラム(Sewell et al., 1992による)。典型的なハワイ型のアルカリ岩系列が多い。南島には、図8でみるように、このような火山岩が南北にかなり分布するようだ。
図8.リトルトンおよびアカロア火山体主要部の地質図(約10-5 Maの年代と言う)(Sewell et al., 1992による)。図の幅は約40 km。この西部に、北北東—南南西へ、火山帯を正断層的にずらす断層が知られていた。ただし、第四紀層は切っていなく、今回の地震とは無関係の模様。この火山体が衝突していたとしたら、なんらかの衝突地形(丹沢山地のような)ができていてもよいが、それは見当たらないようである。非震性海嶺は衝突地形を形成することなしに、沈み込みが生じ始めているのであろうか?
図9.ティマル(クライストチャーチから約80 km南方)付近のアルカリピローバソールトの露頭(白いインターピローの物質は、ドロマイト)。近くにドロマイトの岩脈があった。(1976年8月のIGCの巡検にて。サム・トンプソン, III氏撮影)。
解釈と展望
クライストチャーチの北方には、図4に見るように、北島の東沖から南西へ南島に入り込むように、ヒクランギ・トロフと呼ばれる斜め沈み込み境界がある。このトロフの北西斜面は付加体として、多くの研究例があり、海洋地球科学界では、南海トロフ、バルバドス、カスカディアと並ぶ第四の海溝付加体として、比較研究が進んでいる。その地形的な影響は、クライストチャーチの東方の海底谷にも表れているが(図1,4)、今回の地震が、このヒクランギ・トロフの陸上延長としてとらえるべき場所での特徴的な地殻変動の一端なのか、バンクス半島の衝突ないし沈み込みによるものなのか、またはそれらの複合的なものなのかは、即断は許されない。
図10.リトルトン火山体からクライストチャーチ市方面にかけての断面図。左方の縦線はボーリングの位置であって、断層を示しているのではない。(左が北西側。Sewell et al., 1992による)。
クライストチャーチ市は図1、10で示すように、鮮新統から第四紀にかけての約1 kmの厚さの堆積物をためるカンタベリー盆地に位置する。9月の地震を起こした断層は、従来のサイズミック・プロファイルでは、明瞭ではなかったとのことである。
9月の地震の時には、畑に右ずれのリーデルシアのエシェロンの割れ目系—地震断層が生じた。特に、今回の2回の地震は、従来活断層としては知られていなかった断層の再変位または新生断層か、とも考えられているが、いきなり新生断層が地表にまで現れる例はあまりなく、速い堆積や侵食速度によって、過去の地震断層がかき消されていたのかもしれない。今回は、液状化も生じ、お湯が噴き出したという。人工のお湯か天然の温泉かは、不明であるが、9月の地震断層では今後トレンチ調査も行われると聞いている。多方面からの調査研究が、それらの意義を明らかにすることだろう。
なお、非震性海嶺の衝突としては、九州への九州・パラオ海嶺の例があり(Wallace et al., 2006)、それとの比較検討も待たれる。
なお、9月の地震については、以下で知ることができる。
http://www.geonet.org.nz/news/article-sep-4-2010-christchurch-earthquake.html
http://www.gns.cri.nz/Home/News-and-Events/Media-Releases/Most-damaging-quake-since-1931/Canterbury-quake
[追記: 2011.3.1]
なお、以下のHPによると、
http://www.geonet.org.nz/news/feb-2011-christchurch-badly-damaged-by-magnitude-6-3-earthquake.html
次の二つのような図が公表されている。それによると、前回のDarfield 地震と、今回のChristchurch地震の余震域は、エシェロン上に並ぶように分布することがわかる。また、発震機構は、逆断層成分のある横ずれ断層で、おそらく、ほぼ東西のP軸を持つ応力場を示している。なお、ニュージーランドの研究者の私信によると、クライストチャーチでの想定以上の揺れは、上に述べた新第三紀の火山体からの反射波が寄与したためと言う。
文 献
Cochran, U., Berryman, K., Zachariasen, J., Mildenhall, D., Hayward, B., Southall, K., Hollis, C., Barker, P., Wallace, L., Alloway, B, and Wilson, K., 2006, Paleoecological insights into subduction zone earthquake occurrence, eastern North Island, New Zealand. Geological Society of America Bulletin, 118;1051-1074. doi: 10.1130/B25761.1
Gibson, G. M. and Ireland, T. R., 1996, Extension of Delamerian (Ross) orogen into western New Zealand: Evidence from zircon ages and implications for crustal growth along the Pacific margin of Gondwana. Geology, 24, 1087-1090. doi: 10.1130/0091-7613(1996)024<1087:EODROI>2.3.CO;2
Nicol, A., and Wallace, L.M., 2007, Temporal stability of deformation rates: Comparison of geological and geodetic observations, Hikurangi subduction margin, New Zealand: Earth and Planetary Science Letters, 258, 397–413, doi: 10.1016/j.epsl.2007.03.039
Sewell, R.J.,Weaver, S.D., and Reay, M.B., 1992, geology of Banks Penisula, Scale 1:100,000. Institute of Geological and Nuclear Sciences Geological Map 3.1 sheet. IGNS Ltd.s, Lower hutt, New Zealand.
Wallace, L.W., Ellis, S., Miyao, K., Miura, S., Beavan, J., and Goto, J., 2009, Enigmatic, highly active left-lateral shear zone in southwest Japan explained by aseismic ridge collision. Geology, 37;143-146. doi: 10.1130/G25221A.1
関連情報リンク
関連情報リンク
===公的機関===
気象庁
防災科学研究所: Hi-net,だいち(ALOS)衛星画像, 東日本大震災協働情報プラットフォーム
地震調査研究推進本部資料
東大地震研
国土地理院: 災害情報集約マップ(地質学的に有益)
京都大学防災研究所
USGS
ハーバード大: (断層破壊伝播アニメ有り) 日本語版こちら
海洋研究開発機構(JAMSTEC): (緊急調査:断層破壊域南限の構造)
産総研地質調査総合センター: (津波堆積物ほか)
北海道立総合研究機構 地質研究所: (津波調査第1報)、(津波調査第2報)
千葉県環境研究センター: 東北地方太平洋沖地震 関連情報(千葉県内における液状化調査の結果など)
===学協会===
地盤工学会
日本学術会議(第一次緊急提言)
===企業===
アジア航測株式会社(地震後に撮影された航空写真)
ESRIジャパン株式会社(東北地方太平洋沖地震のソーシャルメディアマップ)
株式会社パスコ(緊急情報サイトで,原発サイト周辺の避難指示範囲,推定震度分布,標高10m以下の地域の分布を掲載)
国際航業株式会社(津波シミュレーションによる予測図)
中日本航空株式会社災害後の緊急撮影 航空写真 撮影ポイントはこちら
===団体・個人サイト===
筑波大(八木研究室)(断層破壊伝播アニメ有り)
名古屋大(山中研究室)(NGY地震学ノート)
山形大(川辺研究室)
気象庁の石川有三さんのページ
ALL311:東日本大震災協働情報プラットフォーム
東日本を襲った超巨大地震に関して (会長 宮下純夫) (2011.3.14)
東日本を襲った超巨大地震に関して
東日本を襲った超巨大地震に関して
2011年3月11日に発生した日本の観測史上最大であるマグニチュード9の超巨大地震「2011年東北地方太平洋沖地震」は,甚大な被害をもたらしました.なかでも大津波の襲来により,多くの人命が失われたことは痛惜の思いです.被害に遭われた方々へお見舞いを申し上げますとともに,亡くなられた方々への哀悼の意を表します.
今回の地震は,長期間にわたって強い余震が発生する事が予想されています.また,日本列島全域にわたって地震活動が活発化しており,更なる災害を警戒する必要がありますが,そうした災害が起こらない事を願っています.
地質学は,地層や岩石などに刻印された過去の様々な変動の歴史を読み取りますが,過去の履歴を精密に解析することによって,将来起こりうる事変を予測することが出来ます.実際に,今回のような超巨大地震が1000年毎位に発生していたこと,そしてそうした超巨大地震が迫っている可能性も最近明らかにされ始めていましたが,残念ながら今回の事態には間に合いませんでした.
日本地質学会は,今回の超巨大地震に関する地質学的観点からの調査や,津波堆積物などに記録された過去の超巨大地震の履歴研究などの推進に努めるとともに,復興をはじめとして,長期的な防災・減災対策にそれらの研究の成果を生かせるように努力する所存です.
会長 宮下純夫
(2011/3/14)
東日本大震災に関する会員からの投稿情報
東日本大震災に関する会員からの投稿情報
茨城県女化稲荷神社における地震被害報告 (水垣桂子, 2011/5/17)
津波浸水域について (新沼正彦, 2011/4/6)
女川町へのアクセス状況 (大槻憲四郎, 2011/4/6)
茨城県女化稲荷神社における地震被害報告
水垣桂子
産総研地質調査総合センターの会員、水垣桂子です。
産総研つくばセンターも建物や実験機器類がかなり損傷し、本震から数日間は自宅待機となりました。その期間にたまたま見かけた被害状況を報告いたします。本震の震源(破壊開始点)からは離れた内陸部での被害の一例となればと思います。
場所は茨城県龍ケ崎市飛び地、女化稲荷神社です。
調査日は本震から3日後の3月14日で、倒れたものなどは既に整理されており、落下方向などはわからなくなっていました。
写真の位置および撮影方向を図に示します。
写真1: 神社本殿前の鳥居で、最上部の横木(正しくは笠木+島木)と額束が落ちていました。周囲は危険なためロープを張って立入禁止となっていました。鳥居の両側にある台座にも何か乗っていたものと思われますが、周辺にそれらしいものは見当たらず、地震以前から撤去されていたものかどうかはわかりません。
写真2:同じ鳥居を正面から撮影したもの。鳥居下の石畳の損傷状況から推測すると、「女化神社」と書かれた額束はほぼ真下に落下したのではないかと思われます。本殿にはこれといった被害は無いようでした。
写真3:稲荷社であるため、本殿までの参道に何本か鳥居があります。その中締め(?)とも言える位置にあるのがこの鳥居です。こちらは横方向の笠木および貫がすべて落下してしまい、縦の柱2本だけとなっていました。落ちた笠木等は片側に集められており、落下方向はわかりません。
写真1と写真3の間の参道には複数の鳥居があり、形式や材質も様々ですが、これらには特に大きな損傷は無いようでした。
写真4:境内にある灯籠が崩れていました。これも片づけられているため、落下した方向等はわかりません。この写真の左奥が写真1の鳥居、右奥が本殿となります。
なお、この周辺の住宅では、外見からわかるほどの大きな被害は認められなかった模様です。
牛久の市街地では、住宅の瓦が落ちてビニールシートで覆ってあるのを何軒か見かけました。
(2011/5/17)
津波浸水域について
新沼正彦
岩手県大船渡市末崎町細浦在住の会員「新沼正彦」です。
大船渡や陸前高田の津波浸水域について報告します。大船渡市南部の湾口近くにある細浦港に自宅があります。全壊流失しました。
特に被災調査というわけではなく、自分の避難生活や身内の安否確認で大船渡市や陸前高田市街を被災3日後に回りました。
津波の浸水域は、概ね標高13mラインまでのようです。高いところで15mほど低いところで10mといったところです。
そのため、行政の設定した一時避難場所(明治三陸津波が基準)避難場所ごと流された事例が多かったようです。特に陸前高田市では。
大船渡市でも同様です。
自宅裏の高台(標高10mほど)が避難場所に指定されていたのですが、津波はそれを3〜4m超える高さで来たようです。地元の地形を知っている住民が、とっさの判断で避難者をさらに高台に誘導したため近所にいた住民や勤め人に犠牲者がなかったようです。
自宅周辺には、明治や昭和の津波到達位置を示す石碑が数か所設置されておりますが、いずれもこれを数m超えています。
津波を目撃した叔母は、「最初は海水面が静かに上昇し、数mの高さになって家々を飲み込みんだあと一気に壁のように海面が高く競り上がり、波頭が砕けた。」と言っておりました。
(2011/4/6)
女川町へのアクセス状況
大槻憲四郎
宮城県女川町で行っていた温泉水ラドン・炭酸ガス濃度観測の機器を撤収するため、4月5日女川町を訪れた。災害調査を予定しておられる方のため、石巻−女川の交通状況等をお知らせする。
三陸自動車道は、すくなくとも石巻河南インターチェンジまでは支障なく利用できた。ここで高速道路を下り、108号線に沿って石巻市街地を東に向かった。冠水の形跡が残っているのは貞山堀を過ぎた所からで、壁等に残っている水位の跡は1.5m程度である。道路脇には少量の泥と浮遊物の残骸が集められていたが、警察官による交通整理のためもあり、自動車の流れはスムースであった。旧北上川に架かる石巻大橋は、軽微な損傷を受けているものの、交通に支障はなかった。その先の牧山トンネルは冠水しなかったようである。このトンネルを出て398号線との交差点あたりから状況は一変し、木造家屋のほとんどは全壊し、津波で流された自動車などが散乱していた。その様な津波被害の状況は石巻線渡波駅・県立水産高校あたりまで続いた。残骸の山は道路の両側に寄せられており、自動車は支障なく通ることができた。より東の万石浦小学校やイオンあたりから万石浦北岸を走る398号沿いでは、一部が浅く冠水しただけで、家屋の破壊状況は軽微のようであり、このような状況は湾奥の石巻線浦宿駅あたりまで続いていた。万石浦沿岸の被害が比較的軽微なのは、狭い湾口に押し寄せた強い津波の流れが、広い湾内に流入することで弱まったためであろう。
女川町主要部に入る峠からは女川湾を望むことができるが、被害状況は惨憺たるものであった。標高20mほどの高台に建つ町立病院と女川港の南端にあるマリンパルの茶色の鉄筋コンクリート建物のみが残っているだけで、木造家屋はもちろんのこと、モルタル造りや鉄筋コンクリート製の建物もほとんどが全壊の状況であった。地盤が沈下し、マリンパルの建物近くの埠頭は浅く冠水していた。残骸は脇に寄せられていて、市街地の道路は通行できた。石巻線女川の駅舎は残っていたが、駅前広場と温泉施設「ゆぽっぽ」の2階部分は跡かたも無くなっていた。その裏の4階建の建物は3階までは津波で壊されており、数m高い位置にある3階建ての女川町役場も骨格を残すのみとなっていて、エントランスには自動車が突っ込んでいた。女川湾北西角から北に延びる谷にある清水町も、跡形も無くなっていた。
町の災害対策本部は旧市街地北側裏手の高台にある女川第二小学校に設けられ、役場もここに移転している。この地続きには広大な女川運動公園があり、体育館が避難所として使われていた。野球場には自衛隊が宿営し、テニスコートには風呂が開設されていた。小生は温泉施設「ゆぽっぽ」の源泉を利用させてもらってラドンと炭酸ガス濃度変化を観測させて頂いていたが、この源泉もこの高台の片隅にある。貯湯タンクが地震動で壊れ、観測機器類は水漬になっていた。
帰路は石巻市街地ではなく、240号線・日和大橋、海岸の工場地帯を通った。この一帯は津波にまともに晒された所で、工場群と住宅は壊滅状態であった。
(2011/4/6)
【初出時、白山神社はかろうじて浸水を免れたとの記述がありましたが、誤りでした。白山神社は拝殿、幣殿、本殿ともに浸水被害を受け、現在白山神社再建委員会が組織され再建に向けた活動を行なっているとのことです。関係者の皆様に謹んでお詫び申し上げ、ここに訂正いたします。(2012/2/20)】
東日本大震災に関する地質学からの提言 (2011.4.5)
東日本大震災に関する地質学からの提言
一般社団法人 日本地質学会 会長 宮下 純夫
2011年3月11日は,日本の歴史にとって忘れえない日となった.マグニチュード9の東日本を襲った超巨大地震と大津波による甚大な被害,そして原子力発電所の被災によって,日本はこれまでに経験した事がない困難な時期を迎えている.破滅的な被害からの復旧・復興のグランドデザインを考える上で,また,今後の防災・減災対策を講じていくために地質学的観点からの提言を行う.
今回の巨大地震と大津波は想定外であったと言われている.今回の地震は日本の観測史上最大で,津波も想定を遥かに越える規模であった事が,被害を甚大なものとした.しかし,数百年毎に一度の頻度で超巨大地震が発生している可能性に,一部の研究者は気付いていた*1.海岸近くの地層に,過去の大津波の痕跡(津波堆積物)が報告されており,その研究から,日本では観測された事がない超巨大地震が大津波をもたらしていた事が,北海道*2でも,東北日本太平洋側*3でも報告されていたのである.また,そうした堆積層が何層にもわたって存在しており,その年代頻度から次の襲来が迫っている事も警告されていた*4.こうした超巨大地震は,最近数十年間においてもスマトラやチリなどで発生し,甚大な被害を与えたことは記憶に新しい.これらの超巨大地震が今回と同じ海溝型地震であることを考えれば,そして上記の最近の研究結果からみて,超巨大地震は想定しておくべき事であった.
今回の大震災に関する地質学的観点からの被害調査に関しては,津波堆積物の精密な解析が急務である.津波堆積物に関して,過去の巨大地震の痕跡やその頻度,規模などを詳細に解析することは,日本海側でも急務である.特に,深刻な原子力発電所の被災状況を考えると,その重要性はいくら強調しても足りない.また,広範囲に生じた地盤の変状や液状化,中山間地での斜面崩壊なども調査・研究が必要である.一方,直下型地震や大噴火も甚大な被害をもたらす.これらに対する基礎的研究を推進することも,将来への防災・減災にとって重要である.
地質学的研究は,日本列島全体で見ると数千年に一度位の頻度で,超巨大噴火であるカルデラ噴火が発生している事*5,さらに,10万年前後の周期でみると氷河期が襲来する事*6も示している.こうした,一人の人間の一生を越えるような間隔で襲ってくる大災害に,如何に向かい合って行くのかが問われている.地球の上に生きている我々人類は,その長期的生存の戦略のために,足下の地球について深く知る事が必要不可欠である.今回の大震災は,改めて地質学の重要性と役割を痛感させた.
また,今回の大震災は,自然災害に対する知識を育成する重要性についても,改めて痛感させた.今回の甚大な被害の中でも,これまでの津波被害に関する教育・啓発によって,幸いにして多くの命が救われた例も多く報告されている.ところで,初等・中等教育における地学教育は,地学教員の採用もほとんどなく,希望しても受講できない高校が多いなど,理科教育の中での地位は極めて低い現状*7は.残念でならない.足下の地球を良く知る事が,防災・減災にとって何よりも重要であり,地学教育の位置づけの低さを改善する必要があることを強調したい.
今回の大震災に際し,巨大災害に関する地質学的研究の推進とともに,火山学,地震学,地形学などの広汎な地球科学関連分野との協力関係を推進して,足下の地球を深く理解することに務めたい.
*1 平川一臣ほか, 2000, 月刊地球号外, 31, 92-98.
*2 Nanayamaほか, 2003, Nature, 424, 660-663.
*3 宍倉正展ほか, 2007, 活断層・古地震研究報告 第7号, 31-46.
*4 藤原 治ほか編, 2004, 地震イベント堆積物.地質学論集, 58号.
*5 高橋正樹, 2008, 破局噴火.祥伝社新書, 69ページ.
*6 町田 洋ほか編, 2007, 地球史が語る近未来の地球.東京大学出版会, 9ページ.
*7 田村糸子, 2008, 地質学雑誌, 114, 157-162
(2011/4/5)
津波被災地現地報告(その1)
津波被災地現地報告(その1)
大石雅之(岩手県立博物館)
岩手県沿岸の津波被災地を訪れ、予備的調査を行ったので、速報として報告します。
このたびの「2011年3月11日東北地方太平洋沖地震」による震災・津波災害で犠牲になられた多くの方々に哀悼の意を表し、被災されたさらに多くの方々にお見舞い申し上げます。また、捜索、救命、救援、復興にあたる人々に心からねぎらいの言葉を贈りたいと思います。当方にも、多くの方々からお見舞いのメールや電話をいただきました。それらの方々は異口同音に自分に何かできることはないか、といっていただきました。心より感謝いたします。
岩手県立博物館は、特別展示室のガラスにひびが入りましたが、被害は概して軽少で、3月22日から展示室の公開を再開しています。しかし、平成23年度の特別展示はすべて中止となることが決まり、その予算は岩手県の災害復興にまわされることになっています。
地質学会会員の中でも被災地に近い場所に居住する者として、いちはやく現場に向かいたかったのですが、地震当初のライフライン寸断とガソリン不足のために、初動が遅れてしまいました。そしてやっと、3月25日と29日に当館同僚の吉田充とともに岩手県沿岸の一部の地域に行くことができました。ここではその報告を行います。結果的には、災害発生直後では道路事情が悪く、通行規制もあったので、2週間後の行動で妥当だったように思われます。以下に当初関係者に電子メールで報告したものをベースに時系列で記述します。
3月25日 陸前高田市〜大船渡市方面
事前に、1)高台から写真を撮影する、2)最大遡上高や浸水深などを読み取る、3)津波堆積物を採取する、4)被災遺構候補を探す、の4つを目標にし、自然の営力の結果を見ることを主眼に置いた。1)は記録として当然で、2)は測量器材を使わないが、1/25000地形図でおおよその標高を読み取って指標になるものを撮影して後日の測量に使えるようにした。3)については、当初平成23年度テーマ展「砂−砂粒から大地をさぐる」を準備していたことと関連するが、前記のようにこの特別展示は中止になった。しかし、資料収集は継続することとし、とくに既に砂を採取した地点での最新の津波堆積物の採取に努めた。4)は宇井忠英北海道大学名誉教授、岩松暉鹿児島大学名誉教授ほかの方々から強く勧められ、また非常に重要なことだと考えて被災遺構保存を実現すべく行動を始めていることの一環である。
第1図.陸前高田市内に向かう。津波で被災した市街地と無傷の民家の違いが歴然としている。
住田町世田米から気仙川に沿って国道340号線を陸前高田市に向かう。同市横田町三日市(河口から約8km)で車窓から気仙川に材木や瓦礫の集積が見えるようになる。市内に近づき、いよいよ緊張する。国道45号線の迂回路となっている廻館橋の渋滞を右に見て左へカーブすると、突然道路の両側が材木や瓦礫の山となった。竹駒町の氷上山登り口の目印となる大きな水晶のような形の塔の下部も壊れている。しばらく行くと市内方面は通行止めで、氷上山の麓を大船渡へぬける道路へと曲がる。高台から荒涼とした陸前高田の市街地が見える。市街地方面に向かう道路へ右折すると、路上に壊れかけた民家があり、もどって別の道の坂をさがる。そこでは、海辺の野球場までほとんど遮るものがないくらいに視界が広がっていた(第1図)。
陸前高田の市内の様子は、メディアが映像で伝えるとおりの荒涼とした風景になっている。新たに言葉で表現するすべを知らない。メディアの映像で伝わらないのは、そういった風景が自分のまわりに360度展開していることと被災地をそよぐ海風の匂いだ。津波の先端が到達して破壊された家屋とこれより高い位置で津波を免れて何事もなかったかのような家屋との違いが、あまりにも歴然としている。
体育文化センターは、陸前高田市立博物館、市立図書館、市中央公民館、市民体育館がならび、芝生が広がるこのエリアは市民の憩いの場だった。しかし、建物は残っているものの、瓦礫の廃墟と化していた。接近してみると開口部は材木や瓦礫、そして自動車の残骸で塞がれ、まったく無残な姿になっていた。市立博物館は2階の天井まで破損し、入口は瓦礫と自動車の残骸がつまっていた。屋根のアンテナは健在だったので、博物館の最上部は水没を免れたと思われる。2006年8月19日に岩手県立博物館が陸前高田市立博物館と共催で実施した地質観察会「玉山金山の水晶と氷上花こう岩」で参加者受付をしたこの博物館の玄関の写真と比べると、言葉もない。公民館の前に花崗岩巨石が転がっていたが、名板の文字が上下逆になっていた。地質観察会受付写真の遠方にこの巨石が写っていたが、その上にあったブロンズ像がどうなったのかはわからない。博物館職員4名のうち、3名が亡くなられたことが確認されたようだ。教育委員会生涯学習課課長補佐のS氏は今の博物館を築き上げた中心人物であり、考古学や民俗学が専門だが、自然史にも大きな貢献をした人だ。2月2日に宮古市の浄土ヶ浜パークホテルで開催された「いわて三陸ジオパーク」推進協議会設立総会の際に会って話をしたばかりだったが、残念ながら亡くなられた。亡くなられた方々に慎んでご冥福を祈りたい。
次に、大船渡市の碁石海岸付近にある大船渡市立博物館へ行った。高台にある大船渡市立博物館は健在だったが、閉館中で無人だった。碁石海岸付近も、宿泊したことのある「ごいし荘」をはじめ、無残な姿になっていた。その後、三陸自動車道で大船渡湾をまわった。東岸の太平洋セメント工場の付近では、重油がもれたらしく、最高水位の痕が建物に黒くくっきりと残っていた。出火しなかったのが不幸中の幸いだ。三陸鉄道「りくぜんあかさき」駅から望む赤崎町は、膨大な量の瓦礫と材木とゴミと家の屋根、そして不自然に散在する船からなる景観だった。もうこれ以上雑然とした状態にならないというほどで、茫然とする以外ない。
第2図.大船渡市合足で最大遡上高を示す「引波痕」。
蛸の浦から綾里方面に抜け、「合足(あったり)の津波石」に行ってみた。これは、明治三陸大津波で運ばれてきたといわれる巨石で、岩手県教育委員会による『岩手県天然記念物(地質・鉱物)緊急調査報告書』の八木下晃司岩手大学助教授(当時)の記載によれば、1.1×2.5×1.3mの粘板岩である。杉林のある海岸でもともと人家はなく、巨石がひとつだけあって、周囲に他の巨石はない。内心、津波石が増えていることを期待したが、津波石はまったくもとのままであった。しかし、ここでは、枯れ葉で覆われる谷の斜面が津波で洗われて明瞭に枯れ葉が除去され、黒色の土の色が見えている。これにより、津波石付近で約10mの最高水位であったことがわかり、また津波で表皮が剥がされた杉の木でも水位が明瞭にわかった。さらに地形図で読み取る標高で16-17mほどの谷の分岐付近で、引波によって海側になびいて倒れた草とそうでない草との境界が最大遡上高を示していた(第2図)。ここではこれを仮に、枯れ枝や草の「引波痕」とよぶ。最大遡上高を知る有効な手がかりになる。等高線の読み取りと写真さえあれば、後日正確な測量が可能であるので、今後の大雨以前にできるだけ多くの地点での確認が望まれる。
綾里の港では防潮堤の内側に何艘も船があり、街中瓦礫と残骸ばかりである。綾里の港側では等高線の読みで6〜7mが最大遡上高であり、峠には、明治三陸大津波で知られる最高の最大遡上高38.2mの「明治三陸大津波水位表」が東北電力の電柱に設置されているが、今回はここまで津波は遡上していない。白浜側では、等高線が読みづらいが、32mの標高点と県道に対する津波にゴミの位置から24mほどの最大遡上高が読み取れる。この地点は、3月26日付の朝日新聞にある港湾航空技術研究所の「綾里地区で23.6m」とある場所と思われる。ここでは、明治三陸大津波の最大遡上高をかなり下回っている。破壊はされたが、防潮堤の効果があったと思われる。また、港側と白浜側で最大遡上高が大きく異なる。峠にある「明治三陸大津波伝承碑」には、「野を越え山を走りて道合に至り両湾の海水連絡せるに至る」とあるが、今回の状況から推測して白浜側から港側に注いだ可能性も考えられる。
白浜海岸の防潮堤の大部分は破壊され、本来の位置から移動して陸側に散在していた。防潮堤の底面の幅が狭く、鉄骨との接続が脆弱に思えた。海岸の崖は約15m(=目測で不正確)ほどが津波で洗われて露頭になっている。白浜の集落は高台にあり、今回は無事であった。
泊で宿泊したことのある民宿「嘉宝荘」がなくなっていて愕然とし、越喜来の惨状を見るころには暗くなり始めた。吉浜は、首藤伸夫東北大学名誉教授に教わったところによると、かつて新沼武左衛門という名主が主唱した高地移転がよく守られ、今回も人的被害がなかったようである。この日は時間切れで行くことができなかった。
(2011/4/5)
津波被災地現地報告(その2)
津波被災地現地報告(その2)
大石雅之(岩手県立博物館)
3月29日 宮古市重茂〜同市田老方面
10時前に宮古到着。宮古市内手前から三陸自動車道宮古中央ICに入り、金浜の宮古南ICで国道45号線に出る。この交差点の手前から民家の惨状が始まる。3階建ての宮古湾温泉マースの2階までが被災していた。ファミリーマートは完全に破損し、JR山田線は線路が土手から外れて大きく曲がっていた。この土手にも津波による泥がかぶる。この付近の防潮堤は、海側は無傷だが陸側は大きく破損して中の土層が見える。ここで津波堆積物採取。
津軽石川にかかる水門はほとんど何事もなかったかのようだったので、上流側の被害軽少を期待したが、上流側へ行くとまったくそういうことはなく、相変わらず瓦礫の荒野だった。津軽石川にかかる稲荷橋を渡って、宮古市運動公園の野球場へ行く。野球場は防潮堤のすぐ陸側にある。堤防直下陸側にはえぐられたような穴が並ぶ。野球場は内野スタンドの椅子、ネットその他が無惨に破壊されている。グラウンドはすべて泥をかぶっている。野球場玄関の泥水の汚れで、約4.5mの浸水深を読み取る。この付近の赤前中の集落では、無惨にも二階建ての建物の1階と2階が分離し、それぞれ横倒しになっていた。宮古湾東岸の道路も破損が多いが、すでに応急的に修復されていた。路肩の崩落もあったが、ガードレールのかわりに海側に丸太を並べただけであった。
白浜では、海面から6mほどの堤防があるが、堤防内側の集落の海側半分ほどの民家は、土台のみであったり半壊であった。ここで漁師さんが話しかけてくる。「船は全部流された。堤防内側の作業小屋は流された。60kgほどの機械が100mほど離れたところにあった。津波は何回か堤防を越えたようだ。山の向こう(太平洋側)はすごいらしいね、死人もでているようだし」。津波堆積物採取。
白浜峠を越え、太平洋側の鵜磯(ういそ)へ行く。鵜磯小学校の校舎付近の校庭に瓦礫が重なり、校庭の木に自家用車が横倒しに引っかかっていた。校舎の時計は2時50分で止まっている。2階建て校舎の1階はガラスが破損、2階は破損していないように見える。小学校門柱付近の斜面の草に引波痕があり、それがない草との境界を、道路に交叉する30m等高線から遡上高29mと読み取る。小学校の正面に津波で荒涼となった細い谷を通して太平洋が見える。可能なら津波がせまる様子を小学校の先生に聞きたいものだ。
鵜磯の北約1kmの宿浜はもともと民家がなく、岸壁と漁業施設のみがあったが、漁業施設は全壊であった。斜面の10mほどのところの木立にボートが引っかかっている。宿浜に降りる道路に沿って、両脇の斜面に草の引波痕が残る。道路の傾斜に平行に近い状態で水が駆け上がった様子がわかる。道路を横切る等高線の30m付近が最大遡上高であった。この地点に青スプレーのマーカーと「仲組6」と書かれた木杭があった。すでに来た別の調査隊または地元の自治体などによるものとみられる。
立浜はさらに1km北にあり、岸壁はかなり破損していた。引波で倒れた木と立ち木の境界は約6m、道路のゴミと草の引波痕の等高線読みで、最大遡上高27mであり、「仲組2」青マーカーもあった。
引き返して、鵜磯の南約1kmの荒巻では、海側の民家の後片付け中であった。道路でおおむね24mの遡上高を読み取った。アスファルト道路は寸断され、通行不可であったので、もどって、音部里へ向かう。音部里集落が見えるところまで来ると、集落はほとんどが全壊であることがわかった。スペクタクル映画のセットとCGの背景画を思う。ここでは重機での作業が進められていた。集落入口の墓場の下側は墓石がほとんど転倒し、草の引波痕で約15mの遡上高を読み取った。
時間がなく、明治三陸で18.9mの姉吉(魹ヶ崎の入口)は断念し、宮古方面へもどる。閉伊川には瓦礫はほとんどなかったが、ところどころに自動車や船の残骸が点在していた。宮古駅に近い宮町付近は何事もなかったように見える。しかし、山田線跨線橋を越えると状況は一変し、宮古市役所前の宮古大橋で、堤防の内側に大型船が横転している。滝のような黒い水のテレビ映像で見た船だ。築地、光岸地、鍬ヶ崎は全壊家屋の廃墟で瓦礫の山であった。
第1図.宮古市浄土ヶ浜の引波痕。破壊されたレストハウスの右側の山の斜面に明瞭に浸水深を示す枯れ葉の除去された跡が見える。
浄土ヶ浜ビジターセンターへ向う坂で約13mの最大遡上高を読み取る。浄土ヶ浜は想像より瓦礫は少なく、材木がやや集積する程度だった。浄土ヶ浜レストハウスは二階まで破損し、その付近の山の斜面には、水に浸かって表面の枯葉が洗い落とされて黒土が見えるところとその上との境界が明瞭であった(第1図)。浸水深約7〜8mであった。蛸の浜の橋から下に望む歩道橋は崩落していた。
宮古市日出島へ向かう。潮吹荘の佐々木福司氏は宮古層群の重要な化石をもっていることで関係者にはよく知られている。国立科学博物館の加瀬友喜氏も心配し、名古屋大学の大路樹生氏情報のグーグルパーソンファインダーで生存がわかっていたので、安心して訪ねることができた。潮吹荘は標高20数メートルで無事で、宮古層群化石保管庫も無事であった。潮吹荘そのものを見るかぎり、何事もなかったかのように見えるが、潮吹荘の下のレベルの民家は全壊で土台だけになっていた。佐々木福司氏はひとりでスコップをもって道路の土砂の除去作業をやっていた。「自分は、別の所にいて大丈夫だった。最初の波が小さいので海に降りた人が次の大きい波でさらわれた。隣の女遊戸(おなつぺ)では避難指示がよく、ひとりの犠牲者も出なかった。潮吹荘の下の民家では嫁さんがお義母さんの手を引いて逃げ、お義母さんはずぶぬれになったが助かった。ここでは船は1艘も残っていない」など話していた。日出島の宮古層群は露頭がよくなっていた。
次に田老に向う。南端の水産加工工場から惨状は始まる。国道脇の「三陸大津波ここから昭和8年」の表示が空しい。養呂地川は瓦礫の川で、川の中に家やトラックの残骸がある。田老では呆然として、フィールドノートに記録を書くどころではなかった。地形図でみる防潮堤は、北東を上にしたX字状とすると、左象限が市街地、右象限が漁港、上象限も町並み、下象限は地図では田畑と針葉樹である。田老駅前から下象限に入ると瓦礫の荒野が広がる。野球場があったようだ。左象限の市街地に入ったところで車を止めて、堤防の上にあがる。言葉にできない無惨な町並みが広がる。無傷に近いビルの上部以外、低い家屋の大部分は全壊だ。戦災は見たことはないが、戦災より徹底して破壊されているように思える。2階だけ残った家屋に「3/29再OK」の赤マーカーがあった。屋根が残るが鉄筋が見えている家、一見無傷で残ったと思えた家も傾いている。これだけたくさんの瓦礫はいったいもともとどこにあったのだろう。右象限の漁港はほとんどが、瓦礫が点在する砂浜と化している。漁業施設も土台だけとなり、上象限と右象限の間の防潮堤はほとんど破壊されている。
第2図.宮古市田老の津波表示板の遠望。10mの昭和三陸大津波、15mの明治三陸大津波の表示が見えるが、「明治」より高い位置に今回のゴミが見える。左の道路では、道路が左から右へ登るカーブで約21mの最大遡上高がわかる。
「昭和三陸津波10m」「明治三陸津波15m」の表示のある田老港東の岸壁わきの法面に向かう。上象限も瓦礫と全壊家屋の荒野。3階までが被害にあった「たろう観光ホテル」だけがたたずむ。「三王閣(休業中)」へ向かう道路の登り口に宮古層群の好露頭があり、断層での繰り返しをうかがわせる。坂の途中のわきに横転した自動車があり、その上側の道路わき斜面に草の引波痕があり、最大遡上高約21m。津波表示の法面の「昭和」が曲がって破損している。コンクリートの法面には金網があり、「明治」の約1m上にゴミがあり、10mほど南では2mあるいはそれ以上上にゴミ、つまり約17mかそれ以上の津波最大水位を示す(第2図;後日この写真を見ると20mほどかと思われるが、正確な測量が望まれる)。「平成」の表示を加える必要があるだろう。
そろそろ暗くなりかけているが、三王岩の遊歩道を行く。遊歩道の破損や落石があるが、三王岩の園地まで行く。三王岩はそのままだったが、園地は崩落した大小さまざまな落石で埋まっていた。
小本経由で盛岡にもどる。盛岡の夜景を見て、地続きのところに先ほど見た田老の廃墟があるとは信じられない思いになった。
筆者は岩手県立博物館で地質学部門を担当しているが、地質学の学芸員としては自然災害に関する展示を行う必要があると考え、2006年1月28日から3月12日まで「ハザードマップ−減災から共生へ−」を実施し、その中で津波のハザードマップも紹介した。また、2008年4月からは「いわて自然史展示室」で小さな津波コーナーを設置している。「ハザードマップ展」終了からほとんど5年目で本当の津波災害が起きた。展示でもっと強いメッセージを出すべきであったという自責の念にかられる。
また、今回の災害から得られた教訓は、この地域で将来も繰り返されるであろう災害を軽減させ、またわが国の中枢部を襲うことが懸念される、来るべき3連動地震(東海・東南海・南海)に備えるための重要な情報を提供すると考えられる。そのために、被災遺構等を保存し、これを活用していくことを真剣に検討する必要がある。
調査に同行した吉田充氏(岩手県立博物館)、被災遺構保存に関するメールのやりとりで有益なご助言をいただいた宇井忠英北海道大学名誉教授、岩松暉鹿児島大学名誉教授、首藤伸夫東北大学名誉教授、伊藤和明防災情報機構会長、斎藤徳美岩手大学名誉教授に感謝申し上げる。
(2011/4/5)
宮古市重茂半島川代の津波コマ撮り写真と姉吉の最大遡上高
宮古市重茂半島川代の津波コマ撮り写真と姉吉の最大遡上高
大石雅之(岩手県立博物館)
「2011年3月11日東北地方太平洋沖地震」による津波の記録写真を紹介する。これは筆者が3月31日に岩手県立博物館藤井忠志氏から受け取ったCDに保存されている。撮影者は宮古市田老町の大上幹彦(おおうえみきひこ)氏で、撮影場所は重茂半島の太平洋側の宮古市と山田町の境界付近で、撮影ポイントは山田町側であり、宮古市川代の海岸の景観が撮影されている。大上氏はブナ林の調査をしていたが、地震の後、海岸の撮影を開始している。
第1図.宮古市姉吉の海岸。海側から西方を望む。津波は右側の鞍部を乗り越えたとみられる。地形図では30mほどの標高が読み取れる。
現地の写真と地形図との対応が不明確であったので、4月2日に現地に行った。川代に行く途中で、3月29日に行くことができなかった姉吉に寄った。姉吉の集落は海岸より700mほど内陸にあり、海よりの道路脇に「此処より下に家を建てるな」と書かれた「津浪記念碑」がある。その50mほど下流まで津波の痕跡があった。ここまでガードレールの破損や木材や木屑の散乱があった。また、青テープ付き木杭が立てられていた。等高線の読みで最大遡上高は約40mであった。明治三陸大津波の綾里白浜の38.2mを越える可能性があり、後日正確な測量が必要である。姉吉の海岸は荒涼たる景観で、津波に洗われて全面露頭になっていた(第1図)。
千鶏、石浜の集落の惨状を見てから、川代に到着した。撮影ポイントは集落の南側の道路脇の標高20mほどの空き地の高台であった。
CDには266点の写真が記録されており、1〜20が植物調査、21〜88が津波、89〜266は後日の津波被害の写真である。
第2図.宮古市川代の景観 (1, 2011年3月11日15:02)
第3図.宮古市川代の景観 (2, 15:18)
第4図.宮古市川代の景観 (3, 15:18)
第5図.宮古市川代の景観 (4, 15:18)
第6図.宮古市川代の景観 (5, 15:48)
撮影: 大上幹彦氏(第2〜6図)
写真は15時2分から始まっている(第2図; デジタルカメラの記録は「14時43分」となっているが、19分遅れと藤井氏から伝言されている)。中央に民家、右手に杉の木が立ち、左遠方約800m先に館ヶ崎と岩礁や小島が見える。その後15時9分には岩礁付近の水位が上がって15時10分に岩礁は水没し、15時12分には右手の防波堤も水没するが、15時16分にはふたたび現れ、山田町側の小根ヶ崎に白波が現れる。15時18分18秒には館ヶ崎に白波が現れ(第3図)、防波堤に滝のように海水が落ちるようになってさらに水位が上がり、18分43秒には白波が岸に到達して軽トラックを飲み込み、ボートを起こして杉の木に到達する(第4図)。18分54秒には波が家を襲い、杉の木を白波が激しく包む(第5図)。館ヶ崎に現れた白波は25秒で杉の木に到達したことになり、115km/hほどの速度で迫ったことになる。その後2コマほどピントが合わない草地が映し出されているので、恐怖を感じた撮影者がこの間逃げ惑ってシャッターを押したと思われる。15時20分には水位の上がった水面に瓦礫と民家の屋根が浮かぶ映像が映し出され、館ヶ崎に白波が現れ、15時21分には岩礁が大きく現れ、水が引いている。その後は道路を山田町方面に150mほど歩き、やや高い位置の木立越しに撮影した映像となり、水位の上下が読み取れる。15時47分には、民家がなくなって下半分の枝が失われた杉の木の映像が映し出されている(第6図)。
これらの写真は、津波が岸に到達する以前の状況が映し出されている点で貴重であると考えられる。上記の記述からもわかるように、最初はゆっくりと水位が上昇し、その後水位が下がり、直後に高速の大きな波が到達したことがわかる。さまざまな証言で、一度水が引いたときに家に貴重品を取りに行った人や、漁港の船のロープを直しに行った人たちが犠牲になったことが知られているが、この映像はそのことを裏付けている。この日に鵜磯小学校で会った、この小学校の卒業生で宮古市千徳在住の男性は、「ここ数年の津波は規模が小さいので、ああまたかと油断した人が多かったのでは」と話をしていた。ここで紹介したコマ撮り写真は、さらに詳細に解析することで、重要な情報が得られると思われる。
川代から山田町に出てその惨状を見る。鯨と海の科学館は、外見は一見無傷に見えたが、ガラスは割れ、中で天井から吊るされているマッコウクジラ骨格はゴミを噛み、クロミンククジラの頭骨にゴミがのっていた。床は展示物やゴミが散乱していた。この付近の「老人保健施設霞露」には多数の車が天井や2階にのっていた。山田町中心地の郵便局の屋上には船がのっていた。
貴重な資料を使わせていただいた大上幹彦氏と藤井忠志氏に深く感謝申し上げる。
(2011/4/5)
2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震による仙台地域の墓石転倒率について
2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震による仙台地域の墓石転倒率について
石渡 明・宮本 毅・平野直人(東北大学東北アジア研究センター)
主な結論
(1)今回の巨大地震による墓石転倒率は1978年宮城県沖地震より低い。
(2)墓石の転倒率が高い地域は沿岸部と内陸部の2列になっている。
仙台地域の墓地129ヶ所において、2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震(M9.0)による墓石の転倒率を3月13日から4月4日にかけて調査し、1978年6月12日の宮城県沖地震による墓石転倒率分布と比較した。調査範囲は5万分の1地形図「仙台」の全体と「岩沼」の北半部及び「白石」の北東端部にわたる東西約30 km、 南北約30 kmの地域で、仙台を中心として北東は利府、西は愛子(あやし)、南西は村田、南は岩沼を含む。
この調査は、形状ができるだけ一定した物体に対する地震波の影響を評価するため、標準型の墓石(図1:縦長の直方体で断面がほぼ正方形のもの、いわゆる棹石(さおいし))のみについて、転倒しているものと転倒していないものを数えた(図1は大きく変位しているが倒れていない)。横長や不定形の墓石、五輪塔などは計数から除外した。また、統計的有意性に配慮して墓石の全数が30基以上の墓地についてのみ計数した。墓石の新旧や耐震施工の有無は計数において考慮しなかった。これらは、見ただけでは判断が難しく、厳密さを追及すると調査の能率が著しく悪くなるためである。耐震施工されている新しい墓石は倒れにくいはずであるが、実際に揺れが強かった墓地ではそのような墓石も倒れており、見回った印象では耐震施工により墓石転倒率が低減される程度は恐らく10%前後であろう。津波の被害を受けた沿岸部については、墓石が地震で倒れたのか津波で倒れたのか判断が難しい墓地(図2)は除外したが、津波の影響が少ないと判断される墓地のデータは採用した。
第1図.大きく変位した標準型の墓石。この型の墓石のみを数えた。
第2図.津波で水深2 m以上冠水した墓地。ここのデータは採用しなかった。
第3図.2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震による仙台地域の墓石転倒率分布(今回の調査結果に基づく)。
第4図.1978年6月12日の宮城県沖地震による仙台地域の墓石転倒率分布。東北大学理学部地質学古生物学教室(1979)のデータに基づいて作図。
今回の巨大地震による仙台地域の墓石転倒率分布を図3に、1978年宮城県沖地震の際の墓石転倒率分布図(同縮尺、同図法で描き直したもの)を図4に示す。これら2つの地震による墓石転倒率とその分布が非常に異なることは一目瞭然であり、それらの特徴をまとめると次のようになる。
(1)1978年宮城県沖地震に比べて今回の地震は規模が大きかったにも関わらず、墓石の転倒率は地域全体で低く、特に仙台市中心部で墓石の転倒が非常に少なかった。1978年の地震では仙台市東部の海岸平野を中心に墓石転倒率が80%以上の墓地が17ヶ所もあったが、今回はそのような高転倒率の墓地は全くなく、転倒率68%の墓地が1ヶ所あったが(図5)、他はいずれも50%以下であった。
(2)1978年宮城県沖地震の墓石転倒率の分布をみると、仙台市東部の海岸平野中心部で転倒率が最も高く、その周辺に向かって転倒率が低くなる同心円状の分布が顕著だったが、今回の地震では山側の広い地域にも墓石の転倒が拡がっており、転倒率が比較的高い地域は海岸線と平行な2列の帯状に分布しているようにみえる。ただし、1978年の地震については山側の墓地の調査が行われておらず、1978年の地震による山側の高転倒率地域の有無は断言できない。
第5図.今回の調査で最大の墓石転倒率を示した仙台市の墓地の様子。
この調査結果についての考察は、次のようである。
(1)気象庁の発表資料などによると、今回の地震と1978年の宮城県沖地震の震央は近接していて、いずれも仙台市東方170 kmほどの場所であるが、震源の深さは今回が24 kmであるのに対し、宮城県沖地震は40 kmとかなり深かった。今回は震源が浅かったために断層のずれが海底に大きく現れ、波高10 m以上の大きな津波を引き起こしたと考えられる。宮城県沖地震の津波の高さは数10 cmだった。このことは、今回の地震を発生させた断層が全体として比較的浅いところで動いたことを意味し、1978年宮城県沖地震の場合に比べて断層の周囲の岩石がより脆弱であったと考えられ、そのために比較的長周期の地震波が卓越し、地震の規模が大きかった割には、墓石を効果的に転倒させるような短周期の地震波があまり発生しなかったことを示唆する。
第6図.仙台市の丘陵部の墓地における小規模な地すべり。
第7図.仙台市の丘陵部における住宅地の斜面崩壊。
第8図.仙台市の丘陵部における舗装道路の損壊。
第9図.仙台市の東北大学東北アジア研究センターの建物の損壊。
(2)宮城県沖地震以後の33年間で、墓石の耐震化が進んだので、今回の墓石転倒率は、耐震化以前の状態よりも全体として10%程度低くなっている可能性がある。しかし、このことは広域的な転倒率分布のパターンにはあまり影響しないであろう。
(3)今回と同様に転倒率の高い地域が数列の帯状になった場合として、1993年の釧路沖地震がある。この地震は釧路沖約20 km, 深さ107 kmを震源とする深い場所で起きた地震であり、震央に近い海岸沿いでは比較的転倒率が低く、震央から離れた場所に転倒率の高い地域がまだら状に現れた(田近ほか, 1994)。内陸直下型地震では通常、震央を中心とする同心円状の転倒率分布になるが(石渡ほか, 2009)、ときどき震央から離れた場所に比較的転倒率が高い「異常震域」が現れることがある。例えば2007年能登半島地震の場合は、震央から約30 km離れた七尾市の丘陵部に異常震域が現れた(野村, 2007)。異常震域が発生する詳しいメカニズムはわからないが、一般論としては、いろいろな経路を通ってきた地震波がある地域で干渉し合って振幅が大きくなる場合が考えられる。今回のように震源が遠い海溝型地震の場合は、揺れの強い地域と弱い地域が干渉縞のように何回も繰り返し現れることが考えられる。因みに、今回の地震で最大震度を記録したのは海岸沿いではなく、内陸の栗原市であった。なお、地震波の位相のずれによっては、逆に干渉し合って振幅が小さくなることもあるはずで、今回仙台市中心部で墓石転倒率が低かったのはそのような理由によるのかもしれない。
墓地の調査の過程で、丘陵地の小規模な斜面崩壊や地すべりを多数の地点で目撃した(図6,図7)。平野部での液状化はあまり目撃しなかったが、恐らく津波の被害を受けた沿岸部では液状化も発生していたと考えられる。道路の舗装の破壊や陥没も至るところで見られた(図8)。コンクリート製の建物の地震による損壊は少なかったが、我々の東北アジア研究センターの建物は上部が大きく損壊し(図9)、危険度判定の結果立ち入り禁止になっている。
今回の地震は、この調査が一段落した4月初めの時点で、既に死者が1万人を超え、行方不明者と合わせて27,000人以上が犠牲になった大災害である。末筆ではあるが、犠牲者のご冥福をお祈りするとともに、被災された方々にお見舞い申し上げる。そして、今回の調査にご協力いただいた寺院や霊園の関係者の方々や墓参中の一般の方々にお礼申し上げる。また、貴重なコメントをいただいた吉田武義教授に感謝する。
文献
石渡明・小栗尚樹・原田佳和 (2009) 岩手・宮城内陸地震(2008)の墓石転倒率分布とその地質学的考察.東北アジア研究, 13, 1-16.
野村正純 (2007) 能登半島地震;旧七尾市における建造物の被害。地球科学, 61, 255-263.
東北大学理学部地質学古生物学教室(1979) 1978年宮城県沖地震に伴う地盤現象と災害について. 東北大学理学部地質学古生物学教室研究邦文報告, 80, 1-97.
田近 淳・深見浩司・岡崎紀俊・小澤聡・遠藤祐司・黒沢邦彦・大津 直・荻野 激・石丸 聡・秋田藤夫(1994) 1993年釧路沖地震による地盤現象と災害.北海道立地下資源調査所調査研究報告, 23.
(2011/4/5)
東日本大震災情報マップ
東日本大震災 情報マップ
マーカー表示 複数Overlay表示
Overlay消去
地質図
● QuiQuake- 地震動マップ即時推定システム(産総研)のデータ表示:
計測震度相当値の分布 最大速度分布 地盤の液状化推定
● 2011年3月11日東北地方太平洋沖地震に伴う津波被災マップ: 日本地理学会災害対応本部津波被災マップ作成チーム(2011)のデータ表示:
津波の遡上範囲、家屋の多くが流される被害を受けた範囲
* 会員の皆様からの投稿情報を順次追加していきます。
情報をお持ちの方はこちらよりご投稿お願いします.
* 地質データには産業技術総合研究所地質調査総合センターによる「20万分の1日本シームレス地質図」を利用しています.
東日本大震災対応作業部会報告 (2011.6.6)
東日本大震災対応作業部会報告
2011年5月21日
一般社団法人日本地質学会 東日本大震災対応作業部会
1.はじめに
2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は,我が国観測史上最大のマグニチュード9の超巨大地震であり,500kmに達する震源域の広がりや20mを超える断層のすべり量,3分以上の継続時間,巨大津波の発生など,いずれも観測史上経験したことのない桁違いのイベントであった.このような超巨大地震が,どのようなメカニズムで発生し,今後どのような経過をたどるのか,前例がないだけにわからない点が多い.
また,被災地の広範な広がりや残された傷跡の深さという点においても今回の災害は未曾有のものであり,とりわけ津波被害はこれまでの対策の深刻な遅れを浮き彫りにした.さらに東京電力福島第一原子力発電所の事故は今なお予断を許さぬ状況が続いている.
このような未曾有の大災害を事前に予測し,被害を防ぐ,あるいは軽減することがなぜできなかったのかという反省や悔しさは学会員の共通の思いであり,それを今後の活動につなげていくことが求められている.本作業部会は執行理事会のもと,東北地方太平洋沖地震の特徴やその意味について地質学の立場から総括を行い,今後の復旧や復興,防災や減災に必要な情報を得るためには何をすべきかについて検討したので報告を行う.
2.総括 ―地質学コミュニティの重い責務と課題―
(1)集積されつつも活かされなかった地質学的知見
地震調査研究推進本部による海溝型地震の長期評価において,東北地方は宮城県沖を除くといずれも発生確率は低く評価され,今回大きな被害を受けた岩手県や福島県の太平洋側の地震動予測も低いものであった.これは,東北沖日本海溝の沈み込み帯においては,数10年〜100年周期でM7からM8クラスのプレート境界地震は周期的に発生するものの,1億年以上経過して冷却の進んだ太平洋プレートが沈み込むために今回のような超巨大地震は起こりにくいと考えられてきたこと,古い文書記録が少ないために西南日本に比べて地震の履歴に関する記録が不完全であることなどによる.年間8cmの太平洋プレートの沈み込みが与える影響については,地震観測と近年のGPSによる日本列島の歪速度観測などに基づいて,相当部分が非地震性のすべりで解消されると考えられてきた(1).
一方,地質構造の解析から鮮新世以降の東北日本の水平短縮量は4-15kmと見積もられている(2).その短縮が3.5-5Maから始まった(3)と仮定すると年間の短縮速度(地質学的短縮速度)は数㎜/年であり,明治以来の測地やGPS観測などによって見積もられている短縮速度(測地学的短縮速度)はそれより一桁大きいことが指摘されていた(4).この短縮速度上の差違は,プレート沈み込みによって蓄積される歪の相当部分が弾性的変形であり,従ってプレート境界でのすべり(地震)によって解消されることを強く示唆していたと考えるべきである.近年の地震学的な研究から東北沖の日本海溝から沈み込むプレート境界は強く固着していることが示されたが(5),このことは“太平洋プレート沈み込みの影響の相当部分が非地震性のすべりで解消される”と考えられてきたことと既に矛盾していたのである.さらにまた,地質学的にも東北沖の沈み込み帯においては付加体の分布が狭く構造浸食作用が活発なことも知られており(6),このこともプレート境界が強く固着させられ続けていることを十分推察させるデータといえる.
古文書に基づく東北地方における地震の履歴は不完全ではあるものの,東北沿岸の広範囲の津波堆積物の解析から,869年に貞観地震というM8.4以上とされる巨大地震が発生したことが知られていた(7).さらに福島県浪江の標高4mの完新世Ⅰ面で過去4000-4500年に4ないし5回の津波イベント堆積物の存在が確認されており,最新のイベントが貞観時代であったことから,今回のような巨大津波を起こすイベントの約1000年の周期的発生も想定されていた(8).
このように東北日本沖日本海溝で超巨大地震の発生が迫っていることを予測し得る地質学的データは集積しつつあったと言えよう.それにもかかわらず,このような重要な知見を防災・減災政策に活かすことができず,今回の大震災を迎えてしまったことは痛恨の極みである.地質学コミュニティに反省と改革が迫られているといえよう.
(2)地震災害と地域防災教育,市民の防災意識向上の課題
今回のような超巨大地震の再来周期が数100年から1000年程度であるとするならば,数千年以上の期間にわたるプレート境界地震の発生の頻度や履歴,変形蓄積のデータが重要になり,それらを地形や地層に残されている記録の解析から取得しなければならない.実際の変形過程の物質科学的検討も必要であろう.地質学的研究の意義は一層高まると同時に,それを実際の防災や減災に反映させていくところまで含めて重い責務が課されてくるであろう.
一方,被害という点においても東日本大震災は広範な地域に深い傷跡を残した.震源域に近い沿岸部は津波によって多数の生命と生活基盤や都市基盤が一挙に失われた.内陸部においてもダムの決壊などで多数の犠牲が出たほか,関東平野のような震源域から離れた地域においてもかつてない液状化の被害がもたらされた.余効変動とみられる広域的な地殻変動は現在も進行中であり,その影響を見積もることは港湾施設や道路,大型施設などの復旧にとって極めて重要である.まだ収束の兆しを見せない福島第一原発事故による地質汚染の影響も深刻である.今回の未曾有の大災害からの復旧・復興にあたっての地質学の果たすべき役割も大きい.
震災の中で,地域の防災教育や市民の防災意識の高さから多くの人命が救われた例も少なくなかった.世界でも有数の地震火山国である日本においては,住民一人一人が国土の特徴や自然災害の基本的な事柄を知ることは何よりも長期的な防災や減災につながると考える.
そこで,(1)沈み込み帯のプレート境界で発生する超巨大地震の実態解明を進め防災や減災に資するという点と,(2)未曾有の災害からの復旧復興への貢献,(3)防災に関する教育や啓発活動というような長期的な防災・減災に資するという点から提言の骨子をまとめたい.学会の役割という点においては,(1)は主として学術研究の推進であり,(2)(3)は主として社会貢献の範疇に属する.
3.提言の骨子
(1)超巨大地震の実態解明と防災・減災へ向けて
今回の地震によって沈み込み帯のプレート境界地震の発生モデルの再考が迫られている中で,地質学的証拠からの活動履歴や活動範囲の推定が大きな意味を持ってくる.実態解明のための調査や探査は学術的にも重要な課題であるが,それにとどまらずに研究の成果が防災に活かされるように積極的に働きかけることがより必要になるだろう.
また,今回の震災では津波災害への深刻な対応の遅れが浮き彫りになった.津波は発生してから到着まで時間差が存在するので,震源域の海底で発生状況をモニターできれば防災上有効な手段となる.以上の観点から述べる.
1)東北地方太平洋沖地震による海底地震断層の全面的緊急調査・探査
世界的にも稀なM9以上の超巨大地震によってどのような現象が生じるのかを正確に把握することは,次のプレート境界地震に備えるための基礎的情報となる.様々な観測やモニタリングを行い,超巨大地震を発生させる沈み込み帯における歪の蓄積および解放過程を明らかにしなければならない.地質学的観点からは,海底地震断層周辺での精密地形測量や試料採取などによって周囲の地層の変形,大規模海底地滑り堆積物の分布などを詳細に調べ,今回のような超巨大地震の活動履歴や変位量を明らかにする.6000mを超える日本海溝の深度に対応可能な技術開発の必要もある.
2)南北両域における大地震への緊急対策
今回の震源域の南北領域,北側では三陸沖北部,十勝沖,根室沖,南側では房総沖においてはエネルギーの蓄積が進んで大地震の発生確率が高まっているので早急な調査や対応が望まれる.北海道の太平洋沿岸では大きな津波イベントの履歴はかなり明らかになっているほか(9),房総沖でも大きな津波が想定される.陸上,海底双方の調査から,過去の活動履歴や変形を明らかにする.津波発生とその規模をただちに通報するシステムは防災上有効であり,新たな津波防災システムを構築する必要がある.
3)全国的な沈み込み帯のプレート境界地震の履歴の調査と津波対策
長期評価によって今回の地震の前に高い発生確率が予想されていたのは,南海・東南海・東海地域であった.また,日本三代実録などの歴史文書は,9世紀後半のおよそ30年間に,東北地方を襲った貞観地震に加え,関東地方の地震や南海トラフ沿いの地震などが集中して発生したことを伝えており,対応の緊急性が高まったと言えるだろう.その他の地域も含めて全国的に陸上では津波堆積物と海水準変動の組合せにより,また,海底では精密海底地形図作成と海底断層や堆積物調査により,過去のプレート境界断層の活動履歴や変位量を組織的に調査する必要がある.
また,前項で述べた津波防災システムをはじめ,津波避難ビルや避難路の整備など今回の震災の教訓を活かして早急に津波対策を強化すべきである.
(2)復旧・復興への貢献
1)余効変動による地盤の沈降や隆起
今回の地震により東北地方太平洋側は広い範囲で数10cmの沈降(牡鹿半島では最大120cm)が生じ,石巻では高潮による被害が伝えられている.1960年チリ地震(M9.5)では,チリ中南部沿岸のほぼ全域が1〜2m程度沈降したことが明らかとなっている.しかし,その後の余効変動により隆起が30年以上も継続し2m程度の累積隆起が起きていることが報告されている(10).津波による最も被害の受けた港湾部の復旧や復興では,余効変動がどの程度の期間にどの程度進行するかは重要な制約条件となる.測地学的なモニタリングとともに,力学的なシミュレーションや地形・地質学的データから過去の地震の経過を読み解き今後の余効変動を予測する必要がある.
2)液状化
地盤専門家の調査によって東北地方から東京湾岸までの広範囲の液状化が確認された.千葉県浦安・茨城県潮来市・東京湾岸では埋立地や旧河道で過去最大規模の液状化が起こったことが明らかにされている.余震が続く中で,旧河道や堤防の液状化の再発も認められる.一方,被害は埋め立て時期の違いや液状化対策の有無により明暗がはっきりしており,仙台空港は津波被害があったものの液状化の損傷は少ない.液状化の損害は家屋のみならず水道・ガス等のライフラインに及ぶため,液状化対策の基礎となる精密な地盤調査を早急に行い,適切な対策を行う必要がある.
3)斜面災害やダム決壊
今回の地震では,多くの斜面崩壊があり山間地の道路や沿岸の鉄道が不通になった.これらは小規模な表層崩壊・岩盤崩落であり,地すべりは栃木県・福島県・宮城県の一部に限定された.仙台市では宅地造成の盛土で地すべりが発生し,民間での対策工のあり方が問題となっている.2008年岩手・宮城内陸地震で発生した荒砥沢ダム上流のような大規模な地すべりは発生しなかったが,福島県須賀川市の藤沼貯水池でアースフィルダム(高さ18.5m,1949年築造)が決壊し下流の集落に大きな被害が出た.決壊の原因は,堤体の締め固め不足・地震動により堤体内の間隙水圧の上昇が考えられ,同様な構造の堤体の点検の必要がある.今後の余震や誘発地震,さらに梅雨の時期を迎え,豪雨などの影響でさらなる斜面災害や河川の氾濫,土石流の発生も懸念される.危険個所の特定や対策を急ぐ必要がある.
4)地質研究者・技術者の参画
これまで地震被害に対しては土木研究者・技術者が中心となり,被害状況の報告と対策を提示してきた.家屋・道路・港湾といった構造物被害に対し,その地震動や液状化に対する設計を今後の指針に加えることにより社会的な責任を負ってきたといえよう.一方,地質研究者・技術者は活断層や斜面災害に対して提言をしてきたが,それらが社会に十分に認知されてきたかは考える必要があるだろう.斜面災害においては地質構成・地質構造・地下水の把握が重要であり,対策工設計の検討には地質専門家が積極的に参画することが望ましい.地域地質に詳しい専門家が復旧復興プラン策定の段階に参加できるような体制づくりが望まれる.そのためには,他学会との連携を深めるとともに,基盤的な地質情報に加えて新しい学問的知見を行政に集約し活かす組織づくり・戦略が必要になる.
5)原発事故による地質汚染
福島第一原子力発電所の事故による放射性物質が大気中や海水中を拡散して深刻な土壌汚染や海洋汚染を生じさせ,生態系にも影響が出ている.また,汚染された土壌を経由して地下水汚染が発生する恐れもあるので注意が必要である.さらに原発において大量の冷却水漏れも明らかになり,その影響が深刻化する恐れもある.原発建屋の地下水理構造,汚染物質の移流・拡散経路さらにはその分布の把握には,早急な地質・水質調査が必要である.その一方で,高レベルの放射能汚染が進行している可能性も高いことから,調査員の安全を確保しつつ汚染経路を遮断する対策が求められる.放射性物質による地質汚染という,これまでにない対策に関しては地質・水理・環境の多分野の研究者・技術者が関わる必要がある.
絶対安全と言われていた「5重の壁」は崩れ,福島第一原発だけでなく国内のすべての原子力発電所および関連施設について,震災時の放射能漏れ事故に備えた対策を早急に立てる必要がある.
6)被災地域の自然・文化資産の修復と保全
今回の震災では各地域の固有の自然や文化も大きな被害を受けた.被災地域には貴重な標本や文化財,関連資料など自然・文化資産を収蔵・展示し,地域文化の発信や自然環境の保全,市民教育などの拠点となっている博物館などが多数存在するが,その多くが深刻な被害を受けた.標本類が失われたり損傷を受けたりしたばかりか,多数の職員が犠牲となった博物館すらある.被災館からの資料・標本類の回収・一時保管,損傷した標本の修復作業などは自然系の博物館のネットワークを通じてボランティアベースで一部始まっているが,一刻も早く本格的作業にはいる必要がある.
(3)長期的な防災・減災へ向けて
1)人材育成
地震に関連する地質調査だけでなく,復旧や復興の調査,地質汚染の調査などで,地質学に関連する多様な分野の専門家が多数必要とされるだろう.学会・大学・研究機関・関連企業の連携の下,先に書いたような課題に答えることのできる人材の育成を進める必要がある.また,すでに現場で活躍している技術者の研修や,地質専門ではない技術者への地質学の基礎的な研修なども検討課題である.
2)防災教育(地学教育)
一人一人が地球の営みや自然災害に対する基本的な知識を身につけておくことは,いつ起こるかわからない自然災害から自分を守るうえで大切なことである.盛土や埋め立てられた造成地などでは地震時に地盤災害が発生しやすいというようなことは地質学的には常識的な事項であるが,十分に社会に浸透しているとはいえない.防災知識の広報や普及に力を注ぐとともに,基礎となる地学教育の充実に組織的に取り組む必要がある.
まず,学校での地学の教育を充実させる必要がある.新しい指導要領で地震火山の両者を小学校・中学校段階で学ぶことになった.しかしながら,高校段階では,地学の履修者が少なく,地学を学習できる環境も十分ではないという現状があり,地学の教員,あるいは地学を教えることのできる教員を増やす努力を継続しなければならない.
また,学校が地域の避難所に指定されて地域防災の拠点となっている場合が多く,今回の震災でも多くの教員が献身的に活躍されたことはしばしば報道された.小中高の校種を問わず,また専門を問わず,学校教員が自然災害に関する基礎知識を身につけることも重要であろう.教員研修にあたっては学会なども協力できる可能性がある.
一方で,社会教育・生涯教育における地学を充実させることも大事であろう.博物館などの社会教育施設やジオパークなどがその拠点となるので,ハードとソフトの両面から充実を図る必要がある.
また,防災の教材として実物の持つインパクトは非常に大きい.近年の震災では兵庫県南部地震で地表に露出した野島断層の一部や断層でずれた民家などを北淡町が保存・公開し,訪れる多くの人々に強い印象を与えている.被災地を考慮しつつ,何らかの形で今回の被災の爪跡を残すことができれば,この震災を後世に伝えるとともに防災意識の喚起に大いに役立つであろう.
3)地質の情報を社会の基盤情報に
今回の震災で津波堆積物のような重要な知見が活かされなかったのは,広報や普及活動の問題だけではなく,地質学的な知見や情報を社会の基盤情報として取り扱う仕組みが不十分なことにもよると考えられる.そのためには,地質学コミュニティとして地質の情報の持つ意味や重要性を広く訴えるとともに,良質の情報を継続的に提供していくことが必要である.
4.終わりに
今回の震災や原発事故を受け,科学技術に対する国民の信頼は大きく揺らいでいる.作家の高村薫氏は,原発事故に対して「科学技術のモラルの問題である」と発言している(11).しかし,復旧・復興を進める上で,正確な科学技術の知識はその基盤とならなければならない.
私たちは,科学技術に対する信頼を回復するためにも,この災害を未然に防ぐことができなかったことを謙虚に認め,深く反省しなければならないだろう.自然から学ぶという原点に帰り,超巨大地震の実態の解明や沈み込み帯でのプレート境界地震の履歴などの調査を関連する諸分野との連携をとりつつ進めていく.一方で,復旧・復興や防災・減災に向けて改めて足元からできることを始めていく必要があるだろう.また,そのための人材育成や,防災や地球の営みに関する知識を広め,地質情報を社会の基盤としていくための取り組みを一層強化する必要がある.
今回の作業部会の報告では,沈み込み帯でのプレート境界地震の実態解明や調査の必要性と重要性についてはかなり検討を行ったが,復旧・復興や防災・減災への貢献,人材育成,教育などについては十分に議論を行うことができなかった.今後理事会を中心により深く詰めていただくことを最後に申し添えたい.
文献
(1) たとえば島崎,2011,科学,v.81,n.5,397-402.
(2) 佐藤,1989,地質学論集,32,257-268,Okada and Ikeda, 2011, (submitted)
(3) Sato,1994, JGR, 99, 22261-22274,守屋ほか,2008,地雑,114,389-404.
(4) たとえば池田,1996,活断層研究,15,93-99;池田,2003,月刊地球,25巻2号,125-129,池田,2011,190回予知連資料 .
(5) Suwa et al., 2006, JGR, 111, doi:10.1029/2004JB003203
(6) たとえばvon Heune and Culotta, 1989, Tectonophysics, 160, 75-90.
(7) 宍倉ほか,2007,活断層・古地震研究報告,7,31-46;澤井ほか2007,,歴史地震,22,209-209.
(8) 今泉ほか,2008,東北地方太平洋沿岸域における地質調査.宮城県沖地震における重点的調査観測(平成19年度)成果報告書,107-132.
(9) たとえばSawai et al., 2004, Science, 306, 1918-1920.
(10) 宍倉ほか,2004,活断層・古地震研究報告,4,265-280.
(11)「郄村薫さんが語る“この国と原発事故”」2011年5月3日の NHK News Watch 9のインタビュー,http://cgi2.nhk.or.jp/nw9/pickup/index.cgi?date=110503_1
参考情報
作業部会メンバー:
藤本光一郎 (東京学芸大学 日本地質学会常務理事)幹事
山本 高司 (川崎地質(株)日本地質学会関東支部幹事長)幹事
池田 安隆 (東京大学大学院理学系研究科)
伊藤 谷生 (帝京平成大学 日本地質学会関東支部長)
佐藤比呂志 (東京大学地震研究所)
重松 紀生 (産業技術総合研究所 活断層・地震研究センター)
宍倉 正展 (産業技術総合研究所 活断層・地震研究センター)
中山 俊雄 (前日本地質学会関東支部長)
藤井 敏嗣 (東京大学地震研究所)
平田 直 (東京大学地震研究所)客員
検討経過:
2011年4月29日
作業部会開催
作業部会員からの地震や津波,災害についての報告を受け議論
2011年5月2日
作業部会報告案起草(幹事の藤本がとりまとめ担当)
以後,メールや電話による報告案の審議と修正作業
2011年5月21日
総会と理事会で報告案の審議
作業部会と執行理事会で再検討のうえ決定
日本の自然放射線量
日本の自然放射線量
今井 登 (産業技術総合研究所 地質情報研究部門)
われわれの身の回りにはもともと宇宙線や大地、建物、食品などに由来する放射線があり、この値が異常であるかどうかは自然状態の放射線量と比較して初めて知ることができる。このような自然放射線量は場所によって大きく異なっており、これを知るには実際にその場所に行って線量計で測定しなければならないが、これを大地のウランとトリウムとカリウムの濃度から計算によって求める方法がある。計算で求める方法は元素データが手元にあれば手軽に行うことができ、現地に行ってわざわざ測定する必要がないので、時間・手間・費用を省くのに大いに役立つ。また逆に、今現在、高線量の値が出ている地域でも、自然状態での放射線量を求めるのに役立つと考えられる。自然放射線量を計算で求めるには、大地に含まれるウランとトリウムとカリウム(放射性K-40)の濃度を用いるが、すでに公表されている元素の濃度分布図である地球化学図のデータを用いることができる(https://gbank.gsj.jp/geochemmap/)。
地上1mの高さでの線量率D(nGy/h)の計算は下記の式を用いた(湊進,2006)。
D = 13.0 CK + 5.4 CU + 2.7 CTh
図1.日本の自然放射線量 (GIFはここから)
[1999〜2003年試料採取、2004年発表]
ここでCK(%), CU(ppm), CTh(ppm)はそれぞれカリウム、ウラン、トリウムの濃度である。単位はナノグレイ(nGy)であるのでこれをマイクログレイ(μGy)に換算して表したのが図1である。シーベルトは人体に対する影響の程度を考えて定められた単位であり、ベータ線とガンマ線の場合には、全身に均等に放射線が吸収されたとき1グレイ=1シーベルトと換算できるので、グレイとシーベルトは同じと考えてよい。ウラン、トリウム、カリウムは花崗岩地域で高濃度に含有され、図から分かるように花崗岩などが分布する地域で高い線量になっており、地質図と密接な関係があることが分かる。
自然放射線量の実際の計測値としては、現在線量計を用いて全国各地で測定し公表されている。つくば市でも産業技術総合研究所(http://www.aist.go.jp/taisaku/index.html)や高エネルギー研究所(http://rcwww.kek.jp/norm/)などがリアルタイムで計測値を公表している。自然放射線量の測定を1970年代から全国的に実測を行ったのが放射線医学研究所であり、全国数百点のデータを元に都道府県別に分布図が描かれている(http://rcwww.kek.jp/kurasi/page-41.pdf)。この他に、大学、地方公共団体、放射線地学研究所が実際に測定した線量測定データを編集しまとめた結果(http://www3.starcat.ne.jp/~reslnote/A8_8.htm#30)、また、文部科学省/放射線計測協会が簡易放射線測定装置「はかるくん」を貸し出して全国の自然放射線の計測を行い都道府県別の平均値が公表されている(http://rika.s58.xrea.com/)。
参考文献
Beck, H. L., DeCampo, J. and Gogolak, C.(1972): In situ Ge(Li) and NaI(Tl) gamma-ray spectrometry. USAEC Report HASL-258, New York, N.Y. 10014. [DOE Scientific and Technical Information]
今井 登・寺島 滋・太田充恒・御子柴(氏家)真澄・岡井貴司・立花好子・富樫茂子・松久幸敬・金井 豊・上岡 晃・谷口政碩(2004): 日本の地球化学図, 産業技術総合研究所地質調査総合センター.
湊 進(2006): 日本における地表γ線の線量率分布,地学雑誌,115, 87-95. [Journal@rchive]
地質調査総合センターホームページ 「海と陸の地球化学図」
(2011/4/12)
日本の自然放射線量
自然放射線量データの表示
■ 自然放射線量
計算で求めた自然放射線量(地上1m, 今井ほか(2004)の元素分布データ、計算式はBeck et al.(1972)による)(海と陸の地球化学図より)。
ベータ線とガンマ線の場合には、全身に均等に吸収されたとき 1グレイ(Gy)=1シーベルト(Sv)と換算できる。
■ 地質凡例
日本シームレス地質図
の詳細はこちら
地図拡大表示時には地質図を地図上でクリックして凡例を表示出来ます。
注: (2011/5/27 追記)
■ 屋外で計測される自然放射線量は、大地からの放射線量(上記マップ)と宇宙線による放射線量を合わせた値となります。日本の緯度における宇宙線による放射線量は約0.33 mSv/年(海抜 0m)と見積もられています(国連科学委員会(UNSCEAR)2000年報告書)。例えば、上記マップの赤で示された地域では、1.11 mSv/年(大地から) + 0.33 mSv/年(宇宙線から) = 1.44 mSv/年 以上の自然放射線量が見積もられます。
■ 放射線測定器で表示される値を意味のある値に換算する仕方は、測定器の性質や測定方法により異なります。(参考サイト:放射線計測の信頼性について:産業技術総合研究所)
■ 「日本の自然放射線量」マップの基となる試料採取と分析値についての注意点は、「地球化学図の注意点:産業技術総合研究所」を参照してください。
このマップについて:
地質データは産業技術総合研究所地質調査総合センターによる「20万分の1日本シームレス地質図」を利用しています. (産業技術総合研究所地質調査総合センター (編) (2010) 20万分の1日本シームレス地質図データベース(2010年11月11日版). 産業技術総合研究所研究情報公開データベース DB084,産業技術総合研究所地質調査総合センター.)
「海と陸の地球化学図」へのリンクが正しくなかったため、試料詳細データのページが開けなかった点を修正しました。(2011/6/13)
参考情報: 花崗岩類からの放射線量について詳しく知りたい方は「花崗岩類からの放射線量」もご参照ください。 (2011/6/21 追加)
グレイとシーベルトの単位の表記が誤っていた箇所を訂正しました。「1グレイ=1シーベルトと換算できる」のは、ベータ線とガンマ線の場合という条件を明記しました。(2011/7/28)
試料採取時期等の記載要望がありましたので、採取時期等を記載いたしました。(2014/10/20)
本記事及び図の出版物やWeb等での利用を希望される場合は,下記へお問い合わせ下さい。
産総研地質調査総合センターの研究成果情報の利用について<https://www.gsj.jp/license/index.html>
または,
産業技術総合研究所地質調査情報センター
地質・衛星情報サービス室
TEL: (029) 861-3601 FAX: (029) 861-3602
復旧復興にかかわる調査・研究事業-報告01
東日本大震災で被災した南三陸地域の自然史標本と「歌津魚竜館化石標本レスキュー事業」
東北大学総合学術博物館 永広昌之・佐々木 理・根本 潤・鹿納晴尚
(News誌2012年3月号掲載)
1.はじめに
図1 南三陸地域の津波被災博物館等施設(自然史資料標本を所蔵・展示していたもの)位置図(国土地理院「10 万分の1 浸水範囲概況図:2011 年4月18 日」に加筆).
2011年3月の東北地方太平洋沖地震とそれによって引き起こされた大津波は東日本の太平洋岸地域に大きな被害(東日本大震災)をもたらした.東日本大震災では多くの博物館等も被災したが,とくに三陸海岸沿いでは津波による被害が大きく,地質標本を含む多くの資料標本が破損し,流失した.地質標本は地球史を考える上で欠くことのできない重要な歴史資料であり,現在の研究・教育に活用するとともに将来に安全に引き継がれなければならないものである.東北大学総合学術博物館では,地質学会の東日本大震災対応作業部会報告書に係る研究・調査・事業プランとして「歌津魚竜館化石標本レスキュー事業」を申請し採択された.この事業では,宮城県南三陸町の「歌津魚竜館」からレスキューされた資料標本を安全に保管・継承し,展示等に活用するために,標本の洗浄・消毒および修復などの作業を行ったが,ここでは南三陸地域の博物館等の被災状況・レスキュー活動について簡単に報告した上で,本事業について紹介する.
2.南三陸地域の自然史標本を収蔵する博物館等の被災状況
宮城県南三陸地域には,気仙沼市の岩井崎プロムナードセンター,南三陸町の歌津魚竜館,石巻市の雄勝公民館,女川町のマリンパル女川,石巻市鮎川のおしかホエールランドおよび鯨類研究所鮎川実験所などの自然史標本収蔵・展示施設があり,津波により被災した.これらの館の被災状況調査・資料標本レスキュー作業はライフラインの回復を待って4月以降に行われた.宮城県に自然史分野を扱う博物館はなかったので,東北大学総合学術博物館は文化庁文化財レスキュー宮城の自然史標本担当となり,文化庁・県文化財保護課などと協力して,レスキュー活動に参加した.歌津魚竜館については次章で述べることとし,ここでは,その他の各館に収蔵・展示されていた主として化石・鉱物・岩石等の地質分野の標本類のレスキュー作業の概要について紹介する.
図2 南三陸町管の浜の津波被災状況.左奥は水産振興センター(2 階が魚竜展示室:その左側道路下にクダノハマギョリュウ現地保存の建物がある).中央は漁協の建物で,屋上に数台の車が載っている.
岩井崎プロムナードセンター
岩井崎プロムナードセンターは,気仙沼湾入り口の,中部ペルム系岩井崎石灰岩がつくる半島の基部にある.一部3階建ての建物の3階床上まで水没し,建物骨組みはかろうじて残ったが,壁や内部はほぼ完全に破壊され,標本類の多くは見つけ出すことができなかった.同センターには地元気仙沼のペルム紀化石標本や岩井崎石灰岩の岩石標本・薄片を中心に多数の地質標本があったが,5月21日の調査で回収されたのは腕足類など10点のみであった.回収された標本は,同定後気仙沼市に返却された.
雄勝公民館
雄勝公民館は,雄勝湾の細奥部から200mほど内陸に入った河川沿いの低地にあり,2階建ての建物全体が水没し,壊滅的な被害を受け,屋上には流された観光バスが残置している.2階に展示室があり,雄勝地域で発掘されたウタツギョリュウ(レプリカ)標本等が展示されていたが(その展示物の詳細は不明),5月18日の調査の際にはウミユリ石灰岩の標本1点のみが確認された.
マリンパル女川
マリンパル女川は牡鹿半島基部東側の女川湾に面した女川漁港の海岸から数10mの位置にある.道路をはさんで建つ水産観光センターと水産物流通センターからなり,前者に各種の展示があり,1階にこの地域に関連する化石展示コーナーが東北大学総合学術博物館の協力のもと設置されていた.この地域は地盤沈下が著しく,満潮時には2つの建物の間の道路に海水が入り込んでくる.マリンパルは建物の3階屋上まで冠水し,展示室の内部はほぼ完全に破壊された.しかし,5月18日の調査で,土砂の流入があり,重油にまみれてはいたが,化石展示ケースの破損は軽微であることが確認され,6月21日に44点の化石標本すべてが回収された.化石標本は東北大学への搬入後,合成洗剤等で洗浄したが,異臭が残り,今後の処置を検討中である.
おしかホエールランド
おしかホエールランドは,牡鹿半島先端に近い半島南西部の鮎川漁港に面した低地にある.2階建の施設2階床上まで浸水,1階展示室には多量の瓦礫が流入堆積した.1階展示室には多数の液浸標本が展示されていたが,2体を残し流失した.2階天井から吊下げられていた鯨骨格標本は肋骨の先端まで浸水したが,流失を免れた.また,2階展示室の標本類は津波による被害は受けなかった.2階展示室の標本は,仙台市科学館へ搬入され,保管されている.1階展示室の液浸標本は国立科学博物館に移送された.また,骨格標本は,現在2階展示室で保管しているが,今後西尾製作所(京都市)に移送し,洗浄保存処理等を行う予定である.
鯨類研究所鮎川実験所
鯨類研究所鮎川実験所(旧ホエールランド)は鮎川港にあり,平屋建の建物は完全に水没した.保管されていた冷凍標本はすべて損壊し,骨格標本は散乱した.骨格標本はおしかホエールランド2階展示室へ搬入され,西尾製作所(京都)への移送が計画されている.
図3 魚竜館(水産振興センター2 階)の被災状況.左側壁の大型標本はベザーノ産三畳紀魚竜化石(レプリカ),右奥の壁の標本はドイツ産ジュラ紀魚竜標本.
図4 魚竜館から回収された魚竜等の化石標本類
3.南三陸町歌津魚竜館と魚竜館標本レスキュー事業
歌津魚竜館
南三陸町は旧歌津町と旧志津川町が合併したもので,魚竜館は歌津地区の管の浜に位置している.南三陸町には,中部ペルム系からジュラ系が広く分布している.1970年に,歌津地域のペルム系−三畳系境界部付近の地質調査を行っていた,ペルム・三畳系ワーキンググループは歌津館崎西海岸に分布する下部三畳系大沢層から脊椎動物化石を発見した.この化石の調査・発掘・同定の作業は地元東北大学の理学部地質学古生物学教室に任され,同年冬に現地調査と発掘作業が行われた.発掘作業では館崎西岸や岸からやや離れた沖合の岩礁など,大沢層のいくつかの層準から標本10個体が採集された.これらはクリーニングののち,気仙沼市(旧本吉町)大沢の大沢層模式地から採集された3個体をあわせて研究され,世界最古の新種の魚竜,Utatsusaurus hataii Shikama, Kamei and Murata(和名:ウタツギョリュウ)として1978年に公表された.館崎の魚竜産地および魚竜標本(歌津町教育委員会所蔵標本)は1973年に国の天然記念物指定を受けている.ホロタイプは東北大学総合学術博物館に所蔵・展示されている.ウタツギョリュウ化石は南三陸町・気仙沼市以外でも,登米市(旧登米町,旧津山町),石巻市(旧雄勝町),女川町など各地の大沢層から発見されている.
図5 搬出をまつドイツ産魚竜標本(鉄製フレームが海水で腐蝕し,さびている).
図6 クレーンによる大型標本の搬出(奥の建物がクダノハマギョリュウ現地保存の建物).
1985年には,歌津町管の浜の海岸で町職員によって魚竜化石が発見された.この産地の地層は当初大沢層と考えられ,標本もウタツギョリュウとされていたが,その後産出層準は上位の中部三畳系伊里前層最下部であり,種も異なることがわかった.この標本は産出地点の地名をとって,クダノハマギョリュウと呼ばれている.
このような相次ぐ魚竜化石の発見を受けて,1990 年,歌津管の浜魚港の一角に町おこしの拠点として,「魚竜館」が建設された.展示施設としての「魚竜館」は,水産振興センター2 階展示室とセンター裏のクダノハマギョリュウを現地保存している魚竜館(狭義)からなる.また,歌津町は,1999 年三畳紀魚竜ベザーノサウルスの産地として有名なイタリア北部の町ベザーノと友好都市条約を結ぶとともに,魚竜館を会場とする国際魚竜化石サミットを開催した.これらの活動を通じて,魚竜館は,寄贈・購入等で受け入れた多くの魚竜標本を所蔵・展示する「魚竜博物館」へと発展した.最近では水産振興センター1階の物産館・レストランとあわせ,年間6万人を超える来館者を受け入れていた.
なお,旧志津川町では,1952年,佐藤 正氏によって細浦湾東岸に分布する下部〜中部ジュラ系細浦層から魚竜化石(ホソウラギョリュウ)が発見されている.これがわが国における最初の魚竜化石の発見であったが,当時は魚竜研究が進んでおらず,この化石が魚竜であることは1990年代に入るまで明らかにはされなかった.わが国から知れれている魚竜化石は南三陸地域のこれら3種だけである.
図7 ドイツ産魚竜標本の修復作業.右:劣化したボード殻の切り取り,左:新たなボードへの貼り付け.((株)トゥーポイント提供)
魚竜館標本レスキュー作業
魚竜館は,伊里前湾北東奥の元の海岸に露出していた露頭を覆う露頭保存施設(狭義の魚竜館)とその前面の埋め立て地に立つ水産振興センターからなる.津波は水産振興センター2 階屋根を大きく越え,建物全体が完全に水没したが,建物外壁は残った.展示標本類は波に飲み込まれたものの,その移動は展示室内にほぼとどまった.4月4日の予備調査以降,4月13日,4月18日,6月10日,その他数回にわたる調査と小型の標本のレスキュー事業が行われ,50数点あった魚竜,アンモノイド,貝類等の化石標本は,一部損壊したものもあったが,2点を除いて回収された.また,考古資料も,東北大学埋蔵文化財調査室によりほぼすべてが回収され,洗浄や整理の作業の後南三陸町に返還されている.
大型魚竜標本および和船の回収は,重量やサイズの問題があり,困難であったが,10月30日〜11月1日に大型クレーン車を導入して搬出した.化石標本類は現在総合学術博物館と仙台市科学館で保管され,魚竜館の再建をめざし,修復作業が行われつつある.
なお,1978年に記載されたウタツギョリュウ標本のうちの2体は地元歌津町教育委員会の所蔵となり,うち1体は天然記念物指定を受けていた.これらは町村合併後内陸部の志津川地域入谷の郷土文化保存伝習館に収蔵されており,被災をまぬがれていたことが2012年2月に明らかとなった.
大型魚竜館標本の修復作業
図8 仙台市科学館での企画展「復興 南三陸町・歌津魚竜館−世界最古の魚竜のふるさと」の会場風景.右奥は修復されたドイツ産魚竜化石,左奥はベザーノ産三畳紀魚竜化石(レプリカ),手前は各種の魚竜化石標本類(レプリカを含む).
回収された魚竜等の標本や復元レプリカのいくつかは破損し,修復が必要な状態にある.また,大型のドイツ・ホルツマーデン産ジュラ紀魚竜化石(Stenopterygius:125.5 cm×294.5 cm)は海水による裏打ちボードの劣化や金属フレームの腐蝕が認められ,安全に保管し,将来に引き継ぐためには早急な手当が求められていた.そこでこの標本の修復を地質学会の東日本大震災対応作業部会報告書に係る研究・調査・事業プランの一部として実施することとした.このための経費は地質学会からの助成金のほか,東北地質調査業協会からの支援金を用いた.
標本の修復作業は,裏打ちボードとフレームの交換で,(株)トゥーポイントに依頼した.作業は2011年12月に行われ,化石に直接する部分を除いてボードを切り取り,弱化部分を取り除いた後,新たなボードに貼り付け,ステンレス製フレームで強化した.古い金属フレーム(鉄製)の内部には海水が残存していた.
この修復によって,当該標本は一般展示を行える状態となり,現在,東北大学総合学術博物館の委任管理のもと,仙台市科学館エントランスホールにおいてベザーノ産三畳紀魚竜標本(レプリカ)とともに展示され,自然史標本の被災や郷土の学術遺産に関する情報提供に活用されている.なお,歌津魚竜館および魚竜標本の意義を広く知ってもらい,魚竜館の復興を目指すために, 2012年2月7日〜3月25日,他のレスキューされた標本や関連する標本を加えた企画展「復興 南三陸町・歌津魚竜館−世界最古の魚竜のふるさと」(仙台市科学館・南三陸町と共催)を,仙台市科学館で開催している.
(2012/2/20)
東日本大震災対応の取り組みについて (2011.6.6)
東日本大震災対応の取り組みについて
1.今後の東日本大震災への取り組み
5月21日の総会で承認された2011年度事業計画においては東日本大震災に対して以下の取り組みが提起され,それらに関連して200万円の震災関連事業費が予算に計上されている.
1. 被災会員,被災地域の大学や研究機関などに対する支援
2. 災害に関する知識や情報の提供・発信
1) 水戸大会でのシンポジウム
2) 緊急リーフレットの準備
3) HPの活用
3. 地質学的観点からの災害調査と大規模自然災害に対する学術研究の推進
4. 提言など
学術会議,政府機関,一般社会に向けた提言
すでに環境地質部会で6月4日にシンポジウム「人工改変地と東日本大震災」を開催したほか,独自の企画をしている専門部会もある.会員各位や各専門部会におかれては,地質学会にふさわしい事業を積極的に提案していただきたい.
また,9月の水戸大会では,「大規模災害のリスクマネージメント―東北地方太平洋沖地震に学ぶ―」と題するシンポジウムが企画されているほか,震災に関連する活動の成果や経験を交流する場として夜間集会を持つ予定である.
2.東日本大震災対応作業部会の設置と報告
4月2日の理事会で上記内容の事業計画案および会長名の提言が承認された.提言はすでにNews誌第4号やホームページに掲載されているが,1)超巨大地震は想定しておくべきであったこと,2)津波堆積物の詳細な解析が急務であること,3)長期的視点に立つ地質学が防災にとって重要であること,4)地学教育の重要性などを骨子としている.
一方,関東支部から「2011年東日本大震災を受けて地質学研究者・技術者・教育者としての社会的・歴史的責任を検討する臨時特別委員会の設置」という提案が出された.
これらを受けて執行理事会では,今回の地震の地質学的な背景や総括を行うとともに提言作成へ向けて,執行理事会のもとに作業部会を組織して議論を開始することとした.作業部会のメンバーは以下のとおりである.
池田安隆・伊藤谷生 ・佐藤比呂志・重松紀生・宍倉正展・中山俊雄・平田直・藤井敏嗣・藤本光一郎(幹事)・山本高司(幹事)
作業部会では,4月29日に会合を持って議論を行ったほか,メールなどによって議論を進めた.また,5月21日の総会および理事会において議論された内容も反映させて作業部会としての報告がまとめられた.今後の専門部会や会員のそれぞれの領域での研究,分析,社会貢献,教育,実践などの活動の参考にしていただければ幸いである.
(常務理事 藤本光一郎)
「東日本大震災対応作業部会報告」
津波で墓石が丸くなった!−岩手県大槌の墓石の津波による侵食について
報告:津波で墓石が丸くなった!−岩手県大槌の墓石の津波による侵食について
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
2011年7月12日の朝日新聞朝刊1面に,「震災4ヶ月,手を合わせ」という題の小さな記事が写真入りで掲載された.この写真には, 岩手県大槌の江岸寺の墓前で手を合わせる家族の姿が写っている.そして,この家族の周囲では,全ての墓石が倒れているように見える.しかし,私たちの墓石 転倒率調査の結果によると(http: //www.geosociety.jp/hazard/content0055.html),震源からの距離が同程度の仙台付近で も転倒率は7.8%(墓地128ヶ所の平均)と低く,なぜ100%近い墓石が倒れているのか疑問だった.津波で水没した仙台平野の海岸部の墓地でも,津波 で倒れた墓石は少数だった.この疑問を解決するため,7月31日に現地調査を実施した.その結果,驚くべき被害の実体がわかったので報告する.
大槌の市街地は,北西から南東へ並行して流れる北側の大槌川と南側の小槌川がつくった一辺が1.5 kmほどの一つの海岸平野に発達している.江岸寺はこの2つの川の間に延びる丘陵の東端部に位置し,町役場や大槌駅から300mほどの距離にある.江岸寺 の裏山から南東方向へ大槌市街を展望すると(図1),手前の墓地から遠方の海岸(大槌湾)まで,少数のビル以外は建物がほとんど残っておらず,この甚大な 被害の様子から,この墓地まで津波が到達したことがわかる.山の下の平地部分に立って見ると,墓石が転倒している領域は平地から比高差7 m程度までで,この部分のブロック塀は流出油による火災のため赤灰色に変色しているが,それより高い部分には津波が到達しておらず,墓石の転倒やブロック の変色は見られない(図2).平地部分の墓石は,転倒しているというよりも,ひどく破壊されている.例えば,横長の倒れにくい墓石は原位置にそのまま鎮座 しているが,片側が大きく割れている(図3).これは,同じ墓地内の他の墓石などが津波に流され,この墓石に当たったために割れたものと思われる.この墓 石は北側(谷の上流側)が割れており,この墓石を割った津波の流れは引き波(大槌川の谷を満たした海水が海に戻る流れ)であったと思われる.この墓石は, 図1の左下部分にも後方から見た姿が写っている.また,ある縦長の標準型の墓石は,津波により南側へ倒されて後ろの花崗岩の側壁に寄りかかったが,流され てきた他の墓石などが次々とこの墓石に当たったために,墓石が真っ二つに割れ,表面が侵食されて削られ,墓石の表面に彫られた字がほとんど読めない状態に なっている(図4).そして,その下の基礎の石材も,角や縁が丸く侵食されている.この墓石もやはり山側から海側へ倒れているので,津波の引き波によって このような被害を受けたものと思われる.この墓石は,図2の左下の部分にも,その一部が写っている.津波で浸水していない裏山の斜面の高い場所にある墓石 は,地震の揺れではほとんど転倒していないので,平地部分の墓石の被害は,大部分が津波によるものと考えられる.
岩手県大槌で観察された,このような津波による墓石の破壊や侵食は,仙台平野では全く見られないものである.仙台平野の津波で浸水した墓地では,ガレキや ゴミやヘドロが墓石の間に沢山流れ着いていて,流されてきた船,車,大きなドラム缶などが当たって倒された墓石もいくつかあるようだが(上記ホームページ または地質学会News, 14(4), 9-11の第2図),墓石同士がぶつかり合って墓石が割れたり侵食されて丸くなったりするという現象は起きていない.大槌の津波の引き波がいかに物凄い流れであったかがわかる.
高校地学の教科書に必ず載っている,堆積物の移動開始流速と粒子の大きさとの関係を示すユルストローム・スレドボリ図によると,60cm以上の大きさがあ る墓石を水流によって移動させるためには,1000cm/s(36 km/h)以上の流速が必要である.つまり,この墓地を襲った津波の引き波の流速は,自動車が走る早さに達していたと考えられる.これは,豪雨の際に山間 地で発生する土石流のスピードとパワーに匹敵する.平野部でも海岸堤防などの津波による破壊は主に引き波によることが報告されているが,大槌のように急傾 斜の谷が海岸に没するリアス式海岸の場合は,谷を遡上した津波が海に戻る際の引き波の流速が特に大きくなり,巨大な破壊力を生じたものと考えられる.この 墓地は,大槌川からは南西方向へ最も離れた山沿いにあるので,これでも流速は遅い方で,恐らく大槌川沿いの引き波の速さは,この墓地における流速よりも更 に大きかったと考えられる.
末筆ではあるが,この津波によって犠牲になった方々に哀悼の意を表するとともに,ご遺族と被災された方々に心からお見舞い申し上げる.
図1.江岸寺の裏山から見た墓地と大槌市街地の津波被害の様子.図3の墓石を裏から見た様子が画面左下に写ってい る.
図2.江岸寺墓地の津波被害を受けた部分(画面下半部)と受けなかった部分(画面上半部)の違い.図4の墓石の一部が画面左下に写っ ている.
図3.右側(北側)が大きく割れた横長の墓石.基礎の石材も右側の角がとれて丸くなっている.
図4.津波で南側へ倒され,流されてきた岩石などが当たって大きく2つに割れ,角がとれて丸くなった標準型の縦長の墓石.表面に彫ら れた字が侵食のためにほとんど読めなくなっており,基礎部分の石材も丸くなっている.
追記
8月16日に石巻市及び仙台市宮城野区の津波被災地域の墓石の被害状況に関する調査を行った.津波が到達した範囲にある墓石のほぼ 100%が倒壊した墓地も複数あったが,墓石そのものが大きく割れたり侵食されて丸くなったりした例はあまりなかった.ただし,石巻市門脇の西光寺墓地 (日和が丘の南側)では,漂流物の火災の影響を受けた部分(門脇小学校の西側,同校はこの火災で全焼)において,墓石が大きく割れたり,角が取れて丸く なったり,表面が剥離したりする現象が顕著に見られた. 従って,大槌の江岸寺におけるそれらの現象も,火災の熱による墓石の膨張とその後の収縮による熱的破壊が主な原因である可能性が高い.津波による墓石の転 倒や破壊には,津波の流向・流速・水深などだけでなく,漂流物の性質,大きさ,量,そして火災の有無など様々な要因が関与し,地震の揺れによる墓石の転倒 より複雑で扱いにくい.津波で被災した墓地の調査方法はまだ手探りの状態である.しかし,大槌の墓石の転倒方向や破壊された墓石の形状などから推定した流 向(引き波)と流速(40km/h程度以上)は多分間違っていないと思う.
門脇小学校.津波の漂流物による火災で全焼.この小学校は西光寺の墓地に囲まれている.
墓石1.火災の熱で同心円状(玉ねぎ状)の割れ目が入った墓石.大槌の墓石の割れ目とは形状が違うようにも見える.(石巻市門脇西光寺墓地)
墓石2.火災の熱で表面が剥離した墓石.(同墓地)
(2011/8/10)
東日本の太平洋沿岸各市町村の2011.3.11津波による人的被害について
東日本の太平洋沿岸各市町村の2011.3.11津波による人的被害について
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
東日本の太平洋沿岸部の各市町村における今年3月11日の大震災(主に津波)による死者・行方不明者の統計(表1)を見て気がついたこと述べ,今後の防災や土地利用計画の参考に供したい.資料は河北新報と朝日新聞の記事及び河北新報社の「東日本大震災全記録」(2011.8.5発行)に基づく.
1.死者・行方不明者が最も多かったのは宮城県石巻市(4043人)であり,岩手県陸前高田市(2122人)がこれに次ぐ.石巻市は津波の浸水面積が最大であり(73km2),陸前高田市では18mの高さの津波が市街を襲った.死者・行方不明者が1000人以上に達するのは岩手県大槌町から宮城県東松島市までの6つの市町村であり,500人以上は岩手県宮古市から福島県南相馬市までの14の市町村である.この他に福島県最南部のいわき市でも347人,千葉県旭市でも13人の死者・不明者が出た.複数の死者が出た青森県水沢市から千葉県旭市まで(表1の範囲)は直線距離で560kmあり,これはほぼ今回の地震の余震域の長さに対応する.
2.死者・行方不明者の人口比が最も高かったのは宮城県女川町,岩手県大槌町,陸前高田市で,各自治体の人口の8〜9%(津波浸水域の人口の12〜13%)が亡くなった.死者数が最多の石巻市の人口比は2.5%(浸水域人口の3.6%)であった.北は岩手県野田村から南は福島県大熊町までの25の市町村で人口比0.2%以上の死者・行方不明者が出た.
3.津波による被害が大きかった沿岸部の範囲内でも,岩手県普代村,岩泉町,宮城県松島町,利府町,塩釜市では特に人的被害が小さかった.普代村から岩泉町にかけては20mを超える高さの津波が襲来したが,普代村では高い防潮堤が津波を防ぎ,住民を守った.岩泉町は海岸に平野がほとんどなく,低地に住む人が少なかったことが被害を小さく抑えたと思われる.松島町・利府町・塩釜市は,入口が狭くて多くの島や半島に守られた湾の奥にあるという地形的な利点が幸いしたと思われる.
4.深刻な津波被害を受けた岩手県宮古市から宮城県東松島市までの範囲内では,岩手県大船渡市の人的被害が比較的小さかったことが目立つ.同市綾里(りょうり)の白浜では津波の高さが26.7mに達し,これは宮古市田老の37.9mに次ぐ高さであり,大船渡港にも10mを超える高さの津波が来ていて,これは山田町や釜石,気仙沼と同程度である.死者・行方不明者の数(448人)においても,その人口比(1.0%)においても,大船渡市の被害が周辺市町村に比べて顕著に少なかった理由については,(1)市街地や集落が他の市町村よりも標高の高いところにある,(2)防災教育が徹底していて多くの人が早く高所に避難した,(3)津波の破壊力(流速)が弱かった,などいくつかの可能性が考えられる.大船渡市は,1960年のチリ地震津波で最も人的被害が多かったため(死者53人,全国の死者・行方不明者142人の1/3以上),他の市町村より津波被害の記憶が鮮明で,住宅の高台移転や防災教育に熱心だった.市役所,学校,病院,警察なども高台にあり,低地は商業ビルや工場として利用されていた.郊外でも,大船渡市吉浜では集落を高台に移転し低地は水田にしたため,今回の津波でも人的被害が少なかった(行方不明1人のみ).また,チリ地震後に世界最大級の湾口防波堤が建設され,今回の津波で破壊されたものの,津波の勢いを弱め,市街への到達を遅らせて避難の時間を稼ぐ上で一定の効果があったと考えられる.つまり,津波対策を考えた土地利用,住宅の高台への移転,湾口防波堤の設置などが人命を救ったことがはっきりと数字に表れているわけで,大船渡市は他の三陸市町村の今後の防災・土地利用計画のモデルとなるだろう.
5.東北最大の沿岸都市である仙台は,海岸平野部で多数の死者・行方不明者を出し,津波浸水地域の面積(52km2)では石巻(73km2)に次ぐが,2番目の大都市である福島県いわき市(15km2)よりも人的被害の人口比がやや小さかった.津波の高さは仙台港で7m程度(ただし若林区荒浜では12m以上),いわき市江名港でも7m程度であった.仙台の市街地は内陸の台地や丘陵地に発達し,海岸平野は主に水田や商工業施設,公共施設などに使われている.台地や丘陵地にある都市は坂が多くて生活に不便であるが,津波や洪水に対する防災上は有利であり,この土地利用が仙台市全体の人的被害を軽減したと思われる.これには,伊達政宗が44歳の時に発生した1611年12月2日(旧暦10月28日)の慶長津波の経験が生きているのかもしれない.この時の仙台〜岩沼の津波の高さは7m程度,伊達領内の死者は1783人とされる.政宗はその2年後の1613年に慶長遣欧使節を派遣しており,復興は早かったようだ.沿岸市町村では,津波被害軽減のために今後もこのような土地利用に努めるべきだと思う.しかし,浸水域人口比では仙台の方がいわき市の2倍以上の被害があり,これは避難が遅れたことや浸水域内またはその直近に避難場所が少なかったことが原因と思われる.海岸平野の犠牲者を少しでも減らすために, 十分な高さの丈夫な津波避難ビルや高架道路などの建設,避難路や警報機の整備,避難訓練の定期的な実施などが望まれる.そしてこれは,南海トラフ沿いや日本海側を含め,海岸線をもつ全ての市町村が緊急に行うべきことだと思う.
粗稿を読んで貴重なコメントをいただいた(社)日本石材産業協会技術顧問(元地質調査所)の服部 仁氏,住鉱資源開発(株)の田代寿春氏(大船渡出身),(株)地圏総合コンサルタントの棚瀬充史氏に感謝する.末筆ながら,今回の地震・津波で亡くなられた方々のご冥福をお祈りし,被災された方々にお見舞い申し上げる.
詳細は画像をクリックしてください。
東日本大震災に対する学会員の声
東日本大震災に対する学会員の声
2011年8月23日配信のgeo-flashにて募集した『東日本大震災に対する学会員の声』にお寄せいただいた内容をご紹介いたします。
東日本大震災について地質家の取り組みが求められる課題の総ざらえを考えよう
志岐 常正
東日本大震災についての会員の声が募集されています。私にもいろいろと述べたいことがあります。とくに地質学抜きにはできないことが少なくないこと、それなのに社会にその認識がないことを痛感しています。本当は今こそ地質家の出番です。
しかし、今回、以下には、私が関心を持っている調査・研究課題を列挙してみたいと思います。正直なところ、今の私には、それら課題のほんの一部にさえ取り組む力がありません。それで会員の皆様にその実行をを訴えたいと思う次第です。どなたかに参考にして頂ければ幸です。
実は以下は、ある研究団体の討論のために、研究分野別でなく、地域別でもなく、社会的緊急性が高く(既に遅すぎるものもあるが)、かつ問題性が高いと思われる順に、大小取り混ぜて課題を記してみたものです。系統的な整理を意図していない点は了承ください。
現地の状況や訴え、要求は、日々変化しています。とくに原発事故の被害は、当初の認識をはるかに越えて広がっていることが分かってきました。以下に挙げた項目は、今のこれらをフォロウしていない点で不充分です。また、筆者の専門や経歴を反映した切り口に特徴だけでなく欠陥があるかと思います。各機関や研究者その他により既に調査が進行している問題については省略するか、ごく簡単に触れるだけにします。
東日本大災害について調査・検証を望む問題を、社会地質学的視点からの提起する
I :当面の調査と今後の研究
*津波被災地の土地利用、とくに仮説住宅設置場所問題
津波災害発生以来、仮説住宅の設置場所の問題が関係者、自治体を悩ませた。筆者は、3月中旬から5月にかけて、今回の巨大津波で浸水した場所でも利用できるところがあるはずであることを、関係自治体その他に電子メールや郵便で伝えた。この問題が2011年の夏に入っても解決されていないところがあると聞く。土地の所有関係など社会的問題も関係するだろうが、津波巨大の再来予想、”災害グレイゾーン”(志岐2011 日本応用地質学会関西支部講演「東日本地震・津波大災害地復興ストラテジーに関する地質学的意見」参照)の時系列的変化などを踏まえて現地で検討することが、仮説住宅などの臨時的施設だけでなく、長期にわたる土地利用、地域復興を考える上で有効、必要であると考える。
*高台への住宅地などの移転計画
高台へ移転すれば、津波災害を避けることができる。しかし、地質を無視した安易な高台開発は、地震の際の盛土造成地崩壊の因を造る。なお、今回の津波で冠水した高台住宅地(昭和三陸津波災の後で開発)があると聞くが、高台の高度に関しても、上記グレイゾーンの時系列変化への対応が考慮されることを希望する。つまり、そこは当分は安全である可能性が高い。
高台に限らず、新たに住宅地を建設する際には、居住者の日常生活の保証が条件とされなければならない。とくに高台は、加齢するだけで、坂の登り降りが難行苦行となることを忘れてはならない。老人、障害者などが生活必需品を入手できない街をつくってはならない。小児、老人、障害者などのための施設、学校、医師の域内居住、コンビニ、商店などが欠けた”近代的”街が如何に住みづらいかは、近年、都会の各所で観られるところである。この教訓に学ばねばならない。場所毎に事情は違う。具体的な検討が必要である。
*瓦礫の処理
防波堤、堤防などの建設に使うことを検討している自治体がある。色川大吉氏も同様のことを提案しつつ、采配は地元に任せるのが良いと言っておられる(7月19日、朝日)。 端的に言えば賛成である。いや、それ以外の智恵はなさそうに思われる。もちろん、分別処理の問題など、いろいろな困難があるに違いない。ただ寄せ集めるのでなく泥分を混ぜるなどして必要強度を造る必要がある。どこからその泥を得るかについては、周辺地域(海域を含む?)の地質、泥質の調査が必要である。下手をすると新たな環境(防災条件を含む)破壊の要因を造りうる。
なお、瓦礫はそれ自身堆積物として堆積構造を持ち、津波の侵入、遡上、引きなどの状況を記録する。つまり今後の津波対策を検討する物証である。形成、堆積当時のままで残っているところは、ほとんどないと思われるが、写真記録を検討すればなんらかの情報が得られるかもしれない。打ち上げられた舟も同様である。
*痕跡の高さ
建物の壁や樹木にのこる痕跡の高さは盛んに調査されている。つまり調査の盲点ではないのでここではとくに触れない。しかし、今後の復興計画、とくに避難場所や水産施設などを含む構造物の建設計画の基本として極めて重要であることは言うまでもない。
*防波堤、防潮堤、堤防の修理、建設
防波堤、防潮堤の高さ、効果、破損などが論議されている。 破損した防波堤の破損状態の調査は重要である。押し波(潮)の圧力、段波の力、越流落下水の洗掘力、引き波(流れ)の力などのどれか一つによる説明で足れりとせず、工事の手抜きやセメントの質をも含めて、多角的、総合的に検証、計算すべきである。まず、現地での注意深い観察が必要である。
防波堤の役割に関しては、高さ不足で越流したところでも、それなりの効果があったという意見がある。津波のエネルギーは減殺されたに違いない。しかし、津波は水深が小さいところへ至れば水面の高さを増す(津波とはどういうものか参照)。つまり、防波堤や防潮堤は津波の波高を大きくする役割を果たした場合があることも検討しなければならない。原発の両側の、原発関係の工作物がないところでは、波高は10メートル程度であった。福島第一原発の沖合には、バーか堆のようなものがあったという話がある。実際に、そのためかと思われる波の砕けが当日の写真に見られる。この堆と、原発の防波堤自身とが、原発にあたった津波の打ち上げを高めた可能性がある。
三陸リアス式海岸での地形による津波の波高増大については、問題自体は常識的であり、専門家によって計算もされているので、ここでは触れない。しかし、津波というものの力学的特質、砕波後の流れへ変化、引き流れの性質などの現れや効果を、これまで以上に個別場所の地形に即して検討し、沈水堤、防波堤、防潮堤、港湾護岸、河川堤防などの設計・計画を再検討することが望まれるのだろう。
*港湾や水産設備の再建
"グレイ度" が高い、そして将来にわたって低くなることはない場所でも、生業は回復せねばならない。そこで、少しでも安全性を高めるために大きな工学的取り組みが計画されようとしている。しかし、養殖を主とする仕事と沖に出てする漁労とでは、必要な道具も設備も異なる。数トンの数隻の舟を必要とするところと99トンの多数の舟を入れる港、1000トンの船舶を停泊させる港湾では構造も規模も全く違う。とくに三陸海岸では地形や水況などの自然条件を反映して、揚げる水産物の種類にも、場所(地区、港湾)毎にそれぞれ特徴がある。これらを一括して、地域計画の専門家なるものにデザインをさせるなどは危険である。水産設備と平常居住地との分離も議論さえているが、これについても同様のことが言える。上にも記したように、居住地は高台にすれば良いと単純には言えない。地元の知識と経験に基づく意見を調査、集約することが重要である。一方、岩手県は、複数の展望的なデザイン案をすでに提示しているが、三陸地方の自然と人文の特徴とその場所による違いがなかなか良く考えられいるので、中・小の自治体、さらには地区毎の検討のたたき台に充分になると思われる。
三陸海岸の南部は宮城県に属する。上記の問題はこの地域にも当てはまる。重厚長大の一律的大規模 "開発" は地域水産業を破壊する。このことが宮城県当局によって認識、重視されることを強く希望する。
*地盤沈下、それからの回復見込み
地震発生以前の状態(平均海水医面など)を明かにする必要がある。測地学的検討は、当然、関係行政研究機関によって、組織的に実施されるであろうが、細かくは、現地での聞き取りが役立つかも知れない。
沈下した地盤の自然回復(隆起)は、地震直後から始まっているが、今後の土地利用を考える上で当てにして良い速度にはならない。完全には元に戻らない(ーだから、リアス式海岸地形や平野が形成されている)。ほぼ回復した時が次ぎの地震津波の起こる時である。これは調査よりも社会教育の問題である。このことが地元で理解されているか否かは聞き取り調査のテーマであろう。
*地盤沈下地域の土地利用
地盤が沈下した地域は、場所により程度の差こそあれ、グレイの濃い地域として残る。その前提で土地利用を考えねばならない。たとえば湖沼として漁労や観光に生かす。干拓、塩抜き、埋め立てを行い農地に戻すなど、それぞれの現状と生活者の必要に応じたデザインが必要である。塩抜きの方法については各種の方法が検討され、一部はすでに始められていると聞く。先に一部の行政に参考意見として伝えたが、佐賀県の有明海干拓の長い経験(綿を使う)も検討に値すると考える。現地での経験交流が望ましい。
*配電網の鉄塔などの維持・管理、妥当性の点検
福島第一原発事故では、まず地震動による鉄塔の倒壊で主要電源が失われたとされて いる。送電鉄塔の倒壊などということはこれまで極めて稀な事態であって、原因の究明が注目される。基礎地盤の地質や施工状況などが、第3者によって公正に点検される必要がある。問題は、福島原発に限らず全国の原発その他、配電システム全体、さらにエネルギーの安定供給問題に関わり重要である。
*ダムの決壊・復旧問題
ダムの決壊原因、復旧するか否か、復旧するとすればどのようにするかの問題は、地元や専門家の間で検討されていると考える。
*原発の立地
福島第1原発の事故のもとは、そもそも原発をそこに置いたことにある。その経過が検証されなければならない。おそらくこの問題の根は社会的に非常に深いが、ここではそれが、原子物理学ではなく、むしろ、社会における地質学の位地、役割の現状に由来することを指摘したい。言うまでもなく、この問題は福島第1原発事故だけに限ることではない。
*福島第一原発の施設破壊は津波だけが原因か
津波に襲われる前に地震で諸施設に損傷が生じていたのではないかは問題である。福島第一発電所では、地震後(津波は警報発令中で未だ襲来していなかった時期)に建家の冷却水系のタンクで水位低下を示す警報が鳴り、運転管理部の職員2人がタンクの配管がある地下に入って津波に呑まれた(8月2日毎日)。今後の地震防災にために、第三者を加えて、徹底した調査・検討がなされる必要がある。それには地質学的検証が欠けてはならない。
*電気系統、とくにコンピュータ制御の総ての機器、設備の耐震性、被災リスクの点検
福島原発事故は、複雑な電気エネルギー、とくにコンピュータなしに成り立たない現代社会の、根本的脆弱さを露呈した。たとえば多くの地震計が地震で(!)破損し、津波の規模の予測計算を誤らせた。深刻で笑えぬ矛盾である。この際、上記鉄塔だけでなく、総ての電気系統の重要設備、施設について、構造物それ自体でなく、それらの基礎地盤、基礎工事、立地条件(地震だけでなく斜面崩壊や洪水、火災、などのリスク、人為的破壊に関係して)の点検、調査を要請する。とくに地理・地質学的調査が肝腎である。
*気象と海洋の調査の問題点
放射性汚染物質の、当初、その後、今後の広がりの調査・検証が重要であることはいうまでもない。その対象は、陸、海、空に渡る。いずれの調査も後手、後手に回っただけでなく、必要規模、精度に遠く及んでこなかった。この事態は早急に改善されなければならない。例えば、原発でのメルトダウンの発生直後には、海水の汚染は沖合には及んでおらず、漁労は可能だったはずである。しかし、海流の状況について、コンピュータシュミレーションは行われたものの水産に生かされず、現地での調査は、そもそも調査船が圧倒的に不足であったと思われる。
今後の汚染分布予測については、大気や水だけでなく、むしろ固体の堆積物の堆積地質学的調査が情報を提供する。
汚染だけでなく、津波そのものの運動の記録も、堆積物に見ることができる。これについては後述する。
*原発事故による放射能汚染と被災者の生活問題
被災者、避難者の生活の実情は、当然ながら多くのところが取りあげて報告している。それでも多くの盲点があるかと思われるが、それらはまず現地に至ってこそ認識できるものに違いない。放射能汚染については、今頃になって稲藁の汚染が明らかになるなどと、とくに問題が深刻である。そもそも、初めに同心円で地域を区切って汚染程度を想定したことが、自然(この場合はとくに気象)を無視した非科学的なやり方であった。果たせるかな、すぐに多くの矛盾が生まれ、現在までそれが続いている。これに関わる要調査項目は、多すぎてかえって今ここに挙げ難い。また、狭義の地質学の範疇から外れる問題が多うので省略する。
*とくに放射能汚染の除去と元の土地への復帰展望について
避難者にとって、今後避難が何時まで続くのかは、重大な問題である。まず、汚染の細かい調査が徹底的に進められなければならない。汚染物質の動きや滞留は堆積地質学的問題であり、調査には、そのセンスが求められる。それは、汚染物質の除去にも必要である。
なお、汚染がどのくらい少なくなれば元の生活場所に戻ってよいのかは、避難住民にとって最大の関心事であるが、放射能というものや、それによる障害リスクについての丁寧な説明が必要である。一般住民は、確率論的思考の教育を受けたことがなく、リスクの我慢の程度は選択の問題であると言われても困る。また、汚染物質が徹底的に除去されても、なおかつ元の生活場所に戻れない場所が必ずある。このことは、隠さずに明らかにせねばならない。この問題について当事者の立場に立とうとするとき、何をどう調査すべきなのか、できるのか。それは自然科学の範囲を大きく超えた問題である。
*地元における調査・復興プラン策定可能性とその実情
原発事故の影響を受けていない地域でも、津波で被災した中・小の自治体、とくに専門的職員が多く被災し失われた自治体では、独自の復興プラン策定がほとんど不可能に近い場合があるという。岩手県の場合、上に記したように、県から提出された案は、充分に参考になるものと考える。他地方の、過去の災害で被災したところの専門職員の援助は求められている。これまでの災害の被災体験者や調査経験者による調査、検証も、客観的(岡目八目的)セコンド・オピニオンの提供として参考になるかも知れない。復興プランの地元での検討・策定の現状を聞き、緊急で必要であるならば地質学的問題に関して助言を試みることを避けてはならないだろう。
上に三陸海岸の場合を記したが、仙台平野の場合でも、たしかに平野全体を俯瞰して、復興プランを考えることは必要ではあるが、地域の状況は、上に記したように、同じく地盤沈下で浸水しているところでも、たとえば水田としての復旧が可能なところ、水域として有効利用を考えねばならないところとでは、今後の方策が根本的に異なる。その具体化については、チョットした水門の設置、運用についてさも、狭い地域ごとの現地農民の知識なしには図れるものではない。
いわゆる地域計画専門家やコンサルタントには、自然の地質、水文、気象などを知らず、地域の実際を無視した観念的な理想を描いているに過ぎない者がいる。壮大な絵を描くことを好む専門家は警戒した方が良い。中には、巨大企業群や大手デイビロッパーの独占的利益を計る狙いを隠していることもあり得る。福島原発設置の場合が正にそうであった。 今後、このような問題が具体化され、地元の住民生活、産業などがどう変わっていくかについては、長期にわたる追跡調査が必要であろう。
*防災に関する知識普及状況
以上に述べたことは、福島原発事故被災・避難者の深刻な精神生活問題を除けば、ほとんどすべて、自然、すなわち地球科学の対象に属し、しかも、大なり小なり地質学・地理学に関わる。このことが、被災地や被災地外の行政や一般の人々にどう認識されているかは、今後の防災・減災ために重要であり、現地調査の最重要項目の一つである。
いわゆる "想定外" 問題は、原発事故に関しては責任逃れの言い訳にすぎないことはありありとしているが、地震の規模に関しては、存在を認めざるを得ない。しかし、津波の規模に関しては、若干事情が異なる。この問題に関しては、別に記述したいが、今回、昭和三陸津波の経験者が少なからず犠牲となったことは、深刻な教訓として捉えられなければならない(「津波とはどんなものか」を参照されたい)。
もっと一般的に言えば、学校や社会における地学教育の軽視、後退が、今回の被災増大の背景にある。このことを当の地学関係者が述べたとき、痛恨の言葉としてでなく手前みそととられる可能性は小さくないのではないだろうか。だが、その実態を調べ、主張をせねばならない。
*科学的思考
"関西では大地震は起こらない" という神話が、多数の専門家の警告に関わらず、兵庫県南部地震の前に広がっていた。原発の、いわいる安全神話は造られたものであるが、それが一般にかなりの程度に浸透していた経過と理由は科学的に検証されねばならない。聞き取り調査がかなり有効であろう。
今の学校・社会教育には重大な欠陥があるのではないだろうか。自然と人文に関する学習は、教師のよほどの工夫がない限り、面白くない暗記物である。 もっと基本的には、自然や社会には、確率的事象があること、漸次的変化の間に蓄積された矛盾が閾値に達して激変を起こすこととがあること、などは、理科教育を含む今の学校教育のどこでも学習できないことが問題である。被災現地の実情の調査・検証は、この根本的問題を考えるための具体的事例を提供するだろう。
Iの結語に代えて
現在、宮城県と岩手県では、復興についての方策に大きな違いがある。前者は、単なる復元でなく”創造的復興を図るべきであるとの 考えのもとに、有名研究機関に依頼して計画を作成し、県下全域を上からまとめようとする。これに対して岩手県では、各地域の実情に即し、下からの発意や要求、自主的動きを大事にしている。これに関係する具体的問題の例については、上にも若干触れた。実際には、東日本でけ見ても、被災のメカニズムや経過は極めて多様、複雑であり、とても重厚長大方式の従来型の手法でうまくいくとは思えない。しかし、問題は東日本の復興問題に止まらず、大ゼネコンや”原子力村に深く関わる大独占企業の、日本全体の未来展望に関わり、根が深い。その中で、地域住民が、災害や環境破壊から地域を守り、生き甲斐のある生活設計を考えるに役立つ科学的・具体的知識や情報を提供する調査が、今要求されている。
II:地球科学的基礎研究テーマ
以下には、被災現地での調査要求には直接には関係しないが、災害発生の自然的メカニズムの把握を深めることは将来の防災や、地域復興と将来設計のために重要であり、そのために貢献しうる地質学的基礎研究課題を若干挙げ、コメントする。
A:堆積地質学的調査が、津波災害の発生直後から行われいる。その調査結果は、基礎的課題についてのものであっても、他のどの専門からのアプローチに増して、津波と津波災害に関する資料、情報を提供する。
*津波による砂礫堆積物などの堆積状況
これまでは、津波の遡上高や侵入範囲などに注意が集中する傾向があったが、津波による地積物、とくにそのBedformに注目すれば、津波の侵入や引き流れなどの方向や強さが推定できる。今後の地域計画に役立つ可能性がある。
*津波は陸に達しないうちに砕波する場合が多いとおもわれるが、動画記録を見ると、気仙沼では、津波が砕波しないで川を遡上り、さらに両岸低地域に氾濫したように見える。ただし道路では奔流となるが、引き波(流れ)は静かに始まる。
個別地域について、映像に見る波や流れの場所による違いや変化を解析し、残された堆積物や被害状況の調査結果と結び付ければ、津波というものの性質を、より深く認識することが出来るだろう。
*陸上地積物は残りにくい。今回の陸域への遡上堆積物が、今後人為的影響がない場合、どのように保存されるかは過去の津波堆積記録の保存ポテンシャルを考えるうえで重要である。長いスパンでの時系列的調査が望まれる。
*海底、特に沖合堆積物は、高い保存ポテンシャルをもつ。今回、浅海、さらに海溝に至る深海に堆積して形成された”物証”(ツナミイアイト)の調査は、津波というものの全的理解のための基礎的な、資料を、世界で初めてうることができる。これは日本の科学の世界に対する責任である。
*液状化記録堆積物
首都圏を含む関東地方で、東北地方にも増して広範に甚大に液状化被害が発生した。その実態と対策の調査・研究がすすめられている。液状化の場の条件、とくに過剰間隙水圧の発生に関係する被覆物の厚さ、物性などの測定、報告を望みたい。
B:地盤のテクトニクスに関係する諸問題
a)津波の規模の予測に関する問題については、経過の告白、残念の思いなどの吐露を含 めて、多くの報告や言説がだされている。たとえば8月1日付け朝日の「M9、「常識」に死角(瀬川茂子)」はよく整理されている。地震学者を含む自然科学者の言説はもちろん、科学雑誌やマスコミ記事などにも、客観性や科学性を失った責任転嫁や一方的決めつけが見られないことは喜ばしい。(いわゆる”原子力村”の、原子力エネルギー開発関係者の見苦しい言動とは対象的である。) 今回の東北・関東沖での超巨大地震の発生規模予測の失敗の要因、それが示す今後の研究課題については、筆者にも意見がないわけではないが、ここでは記述を省略する。一つだけ触れておくとすれば、近年、プレート力学境界断層群を”分岐断層”と捉えるのが一般的になっているが、テクトニクス、ストレス・歪み蓄積の無意識的過小評価に繋がっているのではないだろうか。
b)広域テクトニクスの問題に関係し、阿武隈山地東縁に、海岸線にほぼ並行に走る双葉断層には今回なにも起こらなかったであろうか。東北日本から関東にかけての広い範囲で、ストレスー歪みが東西圧縮から伸張に変わったはずであり、それによる断層や割れ目の発生に関する報告がもう少しありそうなものと思われる。もちろん、もっと遠く、たとえば新潟に起こる地震、所謂誘発地震の発生も、このような応力場変化の問題として、今後詳しく解析され、今後の大地震発生予測に生かされるだろうことを期待する。
東日本大震災に対する学会員の声-補足1
東日本大震災に対する学会員の声:補足1
2011年8月23日配信のgeo-flashにて募集した『東日本大震災に対する学会員の声』にお寄せいただいた内容の補足です。
津波とはどんなものか―東日本大震災の津波災害について検討するために―
以下、今後の防災に関係して、今回の津波災害で何故被災者が増えたのかという問題 意識で、なるべくやさしく書いてみます。しかし、理科系の学歴を持つ市民だけでなく、一般の地質家にさえも分かり難いかもしれません。(専門家間で検討されたものではありません。間違いがあるかも知れません。検討を御願いします。)
1:津波で死なないために津波の特性をもっと知ろう
○津波は本来、長波(極浅水波)である。
極めて広汎な海底が動くことにより生ずる注1。 表面が一見水平的。
観察していても、何処まで水面が上がるか予測できない。岸で恐怖を感じないで見ていると、見る見る水面が上がってきて溺れる。
防潮堤を越えると水は水面を水平化しようとして10分以上〜何10分も越え続ける。(初めは落下し洗掘も起こす。)
水の分子は、かなり水平的に、水面から水底近くの深部まで同じ速度で、長い周期で往復運動。
この水の動き(流れ)が、地形勾配が小さく妨害物がなければエネルギーを保って陸上まで遡上する。
河川や運河があると、その流れに克つて、とくに陸地深く遡上する。上流からの洪水とぶつかり、また満潮が重なると、水位が大きく高まり、しばしば川の堤防を越えて氾濫する。海岸沿いの低地に後ろの山側の川から浸水することがある。
○水深が浅いところに津波が入ると、質量を保存しようとして水面が高くなる。
波の進行速度が遅くなり、波の形が波長が短く高さが高いものに変化する。段波になる。さらに砕けうる。水の粒子(”分子”)の運動速度は逆に速くなる。
防潮堤を越えて浸水する津波の水面は、初め低い。下の方でビルの間の道を流れているなと思って観ているうちに、遅れて波としての性質が現れ(?)、水面が上がってくる。(流速も結構速いー自転車〜自動車並み)。
○妨害物、たとえば防波堤があれば、津波のエネルギーは減殺されるが、水面は高くなる。堤高を越えれば浸水する。一旦越えれば、波の谷がくるまで何10分でも越え続ける。
沈水堤、防波堤、防潮堤などの構造物があっても、そのために津波の高さが高くなり、浸水につながることがある。(福島第1原発の場合も?ーテレビ画像を解析の要あり。)
○段波、砕波、砕波後の流れもエネルギー大。
とくに砕波は空気を取り込み圧搾→爆発するため破壊力大。
防潮堤、防波堤に段波がぶち当たり砕波し、コンクリート構造物を破壊。(福島第一原発の場合は?→テレビ画像を解析の要。)
○波は重合、回析、反射する。→局地的に水面が上がる。
これらはとくに湾の奥で起きる。段波をなしていれば特別高く海崖にぶち当たる。
その状況は、同じ湾でも津波によって同じでない。過去の例や3.11津波について、個別に検証する要がある。これらに防波堤の果たした役割も。
○運搬力大。海浜、瀕海の物質を打ち上げ、一方では運び去る。
浸食、運搬、堆積、それによる被災とその長期継続が起こる。
砕波すれば、とくにそこでは水底を浸食、底質物を陸側に運び出す。海浜に砂丘や砂州があれば、また前浜が急勾配でも、そこで砕波し、それらを構成する砂を陸側へ運ぶことが多い。
どこから何が、何処へ運ばれたか?堆積記録(ツナミアイト)調査は今後の防災を考えるに極めて重要。(陸上から海溝底まで。)
瓦礫の処理は大問題。瓦礫は堆積物である。その眼で堆積状況解析、処理を。
○引き波の流れは、低いところに集まり、下刻する。→破壊の帯線状集中。
復興計画策定(今後の津波の挙動を想定するなど)に重要。
2:専門家から強調され、比較的良く知られている注意事項
複数の海底断層が連動することがある。巨大津波が起こる。
太平洋の対岸での地震による津波が日本の海岸に達することがある。
火山爆発、斜面崩落、隕石落下などによっても津波は起こる。
第2波、第3波の方が大きいことが少なくない。
おそらく引き波(引き流れ)との関係がある。
地震が小さくとも油断できない。
海底断層の動きが”ぬるぬる”だと、かえって大きな津波が起こる。
「引き波から始まるとは決まっていない」
(正しい。しかし、異常な引き波が起こればそれは津波である。)
津波はしばしば火を伴う!
3:とくに指摘、強調しておきたい事項
1)地震津波発生には周期性がある。海底断層活動(地震)の周期性による。
災害リスクのグレイゾーンが時と共に変わる。
→ 地域計画における防災・減災の検討に重要な要である。
2)プレート沈み込みには直接関係ない海底断層でも、動けば津波を生じうる。(例えば若狭原発群の場合)
3)東日本が復興する前に、西南日本で超巨大地震・津波が起こる怖れ大。日本経済沈没も。従来の対策はこの連動に対してなされていなかった。誰でも知っているはずだが呑気。化石燃料(とくにガス)基地、コンビナート(+港湾)、原発(+港湾)での防災は進んでいるのか?数多の盲点あり。
4)津波防災の盲点(船舶に関する例)
船舶は本来浮くように造られているので運ばれやすい。→凶器になりうる。ところが、大船舶は津波警報が出てすぐには出航出来ない(出来るだけの人員がいないー注2)。
4:専門的質問、問題提起など
従来の堆積地質学的調査では、津波の遡上高、遡上範囲など、一部の問題に注意が集まり、たとえば水流の速度については、被災に関係があるにも関わらず関心が向けられ難かったと言われる(今村談話:朝日新聞記事による)。もう少し津波の特性に踏み込んで防災問題につなげることが必要であろう。
<問題と質問>
水粒子の速度はどこまで速くなりうるか? 遡上流は、初めは射流なのか?
射流は乱流になり難い。(水面は比較的にスムース。)このことも、観察者に恐怖を大きくは感じさせなかったのでは?
跳水によって水位が高くなる場合はないか(川からの浸水に関係ないか?)。
津波は比較的に砕波し難い性質を持つと思われる(志岐の考え)が、水底に傾斜の急なところがあれば、砕け寄せ波を造る(下記)。さらに、崖があれば当然に砕ける。海岸に防波堤や沈水堤などを設置すれば、津波は砕け寄せ波をなしうるだろう。その際のエネルギー放出が、それら人工物を破壊する役割を果たすだろう。
砕けた波は空気とともに泡をなして平均海水面より高く上がる。福島第一原発では、この現象も起こったのではないか。
その後の水の運動はどのような特徴を持つのか?(風波などは砕波して後、岸に近づくにつれて一旦普通の波の状態に戻るが? )
防波堤、防潮堤、沈水堤の役割を、”それなりに役にたった”では済ましてはならないのでははなかろうか。これらに関して上に触れた諸問題が、個別に具体的検討されることを期待する。今後の再建、あるいは撤去、再設計に基づく配置・建設などのための必須条件であろう。
津波の特性と術語の解説(一部重複)
津波は、水深に比べて充分に長い波長を持つ波、すなわち長波である。極浅水波の性質を持つと言っても同じ。
深海での津波の伝搬速度は極めて大きく、水深4000mのところを通る振幅1mの津波では200m/sとジェット機並みである。一方、流れ(水粒子の運動)の速度は遅く、5cm/s に過ぎない。浅いところ入れば、ツナミの伝搬速度は遅くなり、水粒子の速度は速くなる。
射流:長波の伝搬速度よりも大きな平均流速を持つ流れ。フルード数が1より大きい。常流:長波の伝搬速度よりも小さい平均流速を持つ流れ。フルード数が1より小さい。
跳水:射流から常流への遷移現象。水路床の勾配、幅、高度、形状などの急変するところで起こる。激しい乱流をなすためエネルギーを消費する。跳水を経験した直後の流れは厚さが増大し、断面平均速度が減少する。河川では、トランンスバースバーやある種のアンテイデューン(反砂堆)が形成される。
深海での津波の伝搬速度は極めて大きく、水深4000mのところを通る振幅1mの津波 では200m/sとジェット機並みである。一方、流れ(水粒子の運動)の速度は遅く、5cm/s に過ぎない。しかし、浅いところ入れば、ツナミの伝搬速度は遅くなり、水粒子の速度は速くなる。
一般に砕波には崩れ波、巻き波、砕け寄せ波などがある。海底が極めて急勾配な場合に波の全面が全体的に崩れるのが砕け寄せ波で、波長が極めて長く、波高が小さな波(津波はこの特徴を持つ)だけに起こるとされている(荒巻:1971「海岸」)。
以下、市民対象の講演で触れることがあります。
もちろん津波(体)は剛体ではありませんが、マスとしての質量が巨大であるから云々という話です。
運動エネルギー=質量×速度の二乗÷2
力=質量×加速度
(加速度は速度の変化率)
(中学理科)
E=mV2/2
F=mα
(高校理科)
津波のmは極めて大きい!
注1)東北・関東沖地震は30年以内に97%と予測。範囲は専門地震家には予測外。巨大津波の可能性は津波・津波地質専門家は気付き、注意を初めていた。
注2)港湾に船舶が入ると、乗員は少数の保安要員を残し、上陸して居なくなる。津波の来襲まで1時間以上ある場合にも、船を沖に出せる保証はない。港湾や海岸に位置するコンビナートの津波防災を考える上で死活的盲点である。たとえば、今のままでは、風向きにもよるが、和歌山市は火の海になる(筆者はかねて、機会ある毎に警告しているが、なかなか、その実効が現れない)。
平成23年台風12号による紀伊半島における日本地質学会地質災害調査団(仮称)の募集
平成23年台風12号による紀伊半島における日本地質学会地質災害調査団(仮称)の募集
会員の皆様
今回の台風12号では紀伊半島を中心に大きな災害になっているのはご存じの通りと思います。
地質学会は、地質災害調査団を結成し、関連学会とともに、地質災害の原因解明に当たりたいと考えております。
意欲のある方を募集します。
連絡先: 日本地質学会事務局 (main@geosociety.jp)
大会にかかるため,地質災害委員会委員長の斎藤(saitomkt@ni.aist.go.jp)に必ずccしてください。
【期限 9月9日(金)】
地盤災害合同調査団:報告
平成23年台風12号による紀伊半島における地盤災害合同調査団
geo-Flashやホームページにて調査団の希望者を募り、奈良県班、和歌山県班に分かれ調査を行うこととなりました。
届いた調査報告書等を随時こちらのページでお知らせいたします。
下記調査報告名をクリックすると、PDFをダウンロードできます。
□平成23年9月28日 奈良県班 調査報告(9月23〜25日)[PDF] NEW
□平成23年9月17日 奈良県班 調査報告(9月17日)[PDF]
復旧復興にかかわる事業プランの採択事業 (2011.9.10)
復旧復興にかかわる調査・研究事業
採択された事業は以下の通りです。
事業名
申請者氏名
放射性セシウムに汚染された水田土壌のカヤツリグサ科マツバイによるファイトレメディエーション(12.8.3掲載)
榊原正幸・佐野 栄
微生物による放射性物質の除洗の実証実験
高橋正則
関東平野内陸部の住宅地での盛土材質の相違による液状化要因の解明(13.3.31掲載)NEW
ト部厚志
福島第一原子力発電所周辺の放射線量の測定方法と地質学的除染方法の検討(12.8.3掲載)
上砂正一ほか
仙台平野海岸部における津波被害と液状化被害の識別
川辺孝幸ほか
標本レスキュー関係
歌津魚竜館大型標本レスキュー事業(12.2.20掲載)
永広昌之
陸前高田市立博物館地質標本救済事業(12.4.25掲載)
大石雅之
*調査–事業報告のあるものはタイトルをクリックして下さい。
復旧復興にかかわる調査・研究事業-報告02
陸前高田市立博物館地質標本救済事業報告
岩手県立博物館 大石雅之
(News誌2012年5月号掲載)
1 はじめに
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の津波により被災した陸前高田市立博物館所蔵の地質標本について,「陸前高田市立博物館地質標本救済事業」を実施したので報告する.
陸前高田市立博物館は,昭和34年に東北地方で最初に登録された公立博物館であり,地域の文化史から自然史にわたる約15万点の資料を保有していた.同館はこのたびの津波災害により壊滅的な被害を受け(図1),6人の職員全員が死亡または行方不明となった.このため同市立海と貝のミュージアムや市教育委員会の職員が岩手県内の博物館等の協力を得て資料救出を行い(図2),再生のための作業を進めてきた.この事業は,文化庁の被災文化財等救援委員会による事業の中に位置づけられ,陸前高田市の要請により岩手県教育委員会主導のもとに4月当初から岩手県立博物館が中心となって進めてきたものである.なお,岩手県全体の自然史資料救援の状況については,鈴木・大石(2011),大石(2011)が概要を述べている.
図1 陸前高田市立博物館の玄関付近に集積した瓦礫.自動車1台と花崗岩のモニュメントも玄関に押し寄せた.2011年3月25日撮影.
図2 陸前高田市立博物館地質展示コーナー付近.落ちた天井と瓦礫の下に隠れていた自動車がこの日までに引き出されていた.50cmほどの砂泥の堆積がまだ残されている.2011年4月27日撮影.
2 実施事業の概要
陸前高田市立博物館から救出された資料は,4月から5月にかけて市内矢作町の山間部にある旧陸前高田市立生出小学校に自衛隊の協力により運搬され(図3),海と貝のミュージアムの熊谷 賢氏や市立博物館元館長本多文人氏を中心とした市職員が他機関職員の協力を得ながら洗浄等の作業を進めてきた.
地質標本については,校舎軒下にブルーシートに包まれて保管された状態から本事業の作業が始められた.事業は,岩手県立博物館が企画し,標本管理に熟達した全国の地質系学芸員等の参加を募って8月と10月に行われた.この事業は,同定,台帳・データベース再構築作業のための第1次的段階とし,地質標本を洗浄,乾燥させて整理し,室内で扱うことができるようにすることを目的とした.協力支援は日本地質学会(8月)のほかに,日本古生物学会(10月)からいただいた.また,東北地質調査業協会からも支援の申し出をいただいた.
図3 旧生出小学校校舎軒下に運搬される地質標本.2011年5月7日撮影.
(1)実施期日
第1次作業は平成23年8月1日〜4日に,第2次作業は10月4日〜7日に実施した.また,補足作業は8月29日〜31日,11月16日,12月7日,13日に行った.
(2)実施場所
作業は,上記の旧生出小学校で実施した.なお,被災地は宿泊場所の確保が困難であったため,当初は寝袋持参で旧生出小学校に宿泊することも検討したが,被災資料にともなう夏場のカビの発生などによる住環境の悪化が心配されるようになっていた.しかし,第1次,第2次作業のいずれについても作業場所にほど近い「ホロタイの郷『炭の家』陸前高田市交流促進センター」を宿泊場所として確保できた.この施設は素泊まりであったので,事業参加者による買い出しと自炊(係と当番)も作業の一環として位置づけた.
(3)事業参加者
原則として地質系の博物館学芸員と大学の地質系教員に地学系学芸員メーリングリスト(8月)と日本古生物学会のメーリングリスト(10月)で参加を呼びかけた.また,公務の出張での参加を原則としたが,休暇で自費の参加者などの場合は,一括して盛岡市社会福祉協議会でボランティア活動保険に加入した.保険料は補助があって無料であった.参加者は,24機関からの33名であった(付記).
本事業は,岩手県教育委員会から文化庁の被災文化財等救援委員会へ依頼して,救援委員会から県外の機関等へ依頼するしくみになっていることから,参加依頼についてはそのような手続きで進めた.自家用車参加の希望者には,岩手県教育委員会生涯学習文化課より災害派遣等従事車両証明書を発行し,高速道路通行料金無料での参加ができるように手配した.
(4)作業対象標本の概要
陸前高田市立博物館所蔵地質標本の大半は陸前高田市内から採集されたものである.陸前高田市は南部北上山地に位置し,主として先シルル紀の花崗岩や変成岩,上部古生界,白亜紀花崗岩が分布する.日本の中・古生界の大部分は大型化石に乏しい付加体からなるのに対して,南部北上山地の古生界は化石の豊富な浅海成の正常堆積物からなり,その分布はわが国で最も広い.陸前高田市は,古生界の中でも石炭系やペルム系が広く分布し,これらの地層はわが国のこの時代の地史を明らかにする上で重要な位置を占めている.このため,陸前高田市立博物館所蔵の標本は地質学的にたいへん貴重である.
なお,気仙隕石と関連資料はミュージアムパーク茨城県自然博物館の特別展のために貸出し中であったので被災せず,9月に岩手県立博物館を通して陸前高田市立博物館に返却された.
(5)作業の方法
旧生出小学校校舎軒下に仮置された樹脂製コンテナ等131箱の標本について作業を進めた.次亜塩素酸ナトリウムによる除菌の手順などは,先行して進められていた海水損文化財の安定化処理方法を参考にした.作業開始前に樹脂製コンテナに通し番号をつけた.作業中はゴム手袋や防塵マスクなどを着用した.
a 樹脂製コンテナの詰め替え 収蔵庫で樹脂製コンテナなどに収納されていた標本のほかに,砂泥が堆積した博物館内で拾い集められた標本もあり,コンテナによっては多くの標本が詰め込まれた状態になっていたので,これを数箱に分配し,新たなコンテナに枝番号をつける.
b 資料情報の記録 標本ラベルに記録されている標本番号・学名・産地・採集者名などの資料情報を必要に応じて転記し,ラベルや標本の紛失・混入を防ぐ.
c 洗浄(1)土砂を歯ブラシやタワシなどを使って水道水でざっと落とす.コンテナ内にあるメモや袋等をできるだけ元の標本と一緒に扱う(図4).
d 除菌 標本とラベルを次亜塩素酸ナトリウム400倍希釈水溶液に2〜3分浸ける.紙,袋類もあわせて除菌する.
e 洗浄(2)残った砂や泥の汚れを水道水で落とす.細かな隙間の汚れは,歯ブラシなどを使って除去する.ヘドロや油分を含む場合は,中性洗剤水溶液を使って取り除く.
f 乾燥 水分を拭き取り,水切りかごなどで乾燥させる.ラベルはキッチンペーパーの上に置いてアイロンがけをする.乾燥には1日または数日かける.
g 収納・整理 乾燥後,チャック付きポリ袋にラベルと標本を別々に収納し,さらにそれらを大きな袋にまとめて収納する.もとのコンテナと同じ標本構成で収納し,同じ箱に入っていたものを一か所にまとめておく(図5).
h 樹脂製コンテナごとの撮影・記録 コンテナごとに写真撮影を行い,標本の種類の概要と点数を1枚のカード(A4)に略記する.この作業は,上記「f 乾燥」「g 収納・整理」と前後することもある.
図4 本事業の地質標本洗浄作業.旧生出小学校で2011年8月2日撮影.
図5 本事業の地質標本整理作業.旧生出小学校で2011年10月6日撮影.
3 事業実施結果
本事業開始当初は,作業対象地質標本は樹脂製コンテナ等131箱であったが,コンテナの詰め替えや他分野の資料に混入していたものも追加されたことから,樹脂製コンテナは255箱に増えた.収納された標本は3,260点あり,コンテナに収納されていない大型岩塊23点を含む標本実数は3,283点となった.
標本にはラベルが保存されていないものが少なからずあり,今後の標本整理に支障をきたすことも予想される.しかし,ラベルがなくとも母岩の岩質や化石の産状などによりある程度産地が推定できるものもあり,とくに陸前高田市矢作町飯森(いも)のペルム紀化石が比較的多いことがわかっている.また,市内の石炭系から産出したと思われるサンゴ化石を含む石灰岩も多い.新第三紀の化石,岩石・鉱物も多数含まれる.
なお,本事業ではペルム紀化石産地の見学と被災地の視察も行った.本事業の活動状況については,すでにいくつかの紹介記事(兼子, 2011; 川端, 2012; 間嶋, 2012; 平田, 2012)が発表されているので,参照されたい.
4 地質標本救済事業の意義と自然史標本に関する問題
津波によって被災した標本にかかわる作業は誰しもはじめての経験であったので,作業の手順は試行錯誤の要素が強かった.しかし,日常的に地質標本を扱っている専門家一人ひとりが自ら方法を考え,参加者同士相談しながら作業にあたったことで,大きな支障もなく事業が進められたといえる.このように,異なった機関の専門家が共同してひとつの作業を行うことになったわけだが,大規模な研究プロジェクトでもないこうした地道な事業としては,画期的なことだったといえる.
前述したように,本事業は文化庁の被災文化財等救援委員会の「東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援事業」の枠組みの中で実施されたが,その要項には自然史標本が救援の対象として明示されていない.当初から「被災文化財等」の「等」で自然史標本も対象にしているという情報があったが,このことで若干の混乱がみられた.もともと文化財と自然史標本との両方の分野にまたがる議論が従来ほとんどされてこなかったこと,つまり両分野それぞれの中で議論が終始していたことが,今回の震災を契機にしてあらためて浮き彫りにされたということかもしれない.
そもそも自然史標本と文化財との関係はどうなっているのだろうか.自然史標本は,母集団(自然界)にはたくさんあるので,もともとはあまり価値を有さないともいえる.一方,「文化財」とは『広辞苑』で「文化活動の客観的所産としての諸事象または諸事物で文化価値を有するもの」といわれる.もともと価値を有さない自然史標本は,学術活動があって価値が生ずると考えられるが,そのことは当該学術コミュニティの中では重要視されても,その外側ではそういった情報は共有されてこなかったのではないか.
自然史標本の意義に関しては,自然史博物館の重要性の再認識と自然史標本の公的保護制度についての議論がはじまっており(斎藤ほか,2011; 西田,2012),この問題は今後大いに議論されるべきだと考えられる.
5 おわりに
博物館資料の救済事業は,地域のアイデンティティの物的証拠の復活を意味し,関連学問分野のありようも問うていると考えられる(真鍋,2011a, b).陸前高田市立博物館の地質標本の救済事業は,今後も多くの作業を必要としている.とくにこれからは,標本の大分類とコンテナの組み替え,専門家による標本の鑑定・同定と産地推定などが必要である.そしてデータベース化やラベルの出力により博物館資料として活用できる標本群へと再生させる必要がある.なお,平成24年4月1日をもって海と貝のミュージアムは廃止となり,陸前高田市立博物館は旧生出小学校において本多文人新館長のもとに再出発した.
報告の最後に,本事業について「東日本大震災対応作業部会報告書に係る研究・調査事業プラン」により助成をしていただいた日本地質学会に深謝の意を表する.また,本多文人氏・熊谷 賢氏ほか市職員,遠野市立博物館前川さおり氏,現地でご助言をいただいた神奈川県立生命の星・地球博物館斎藤靖二館長と平田大二氏をはじめ,本事業にかかわったすべての方々と機関に厚く御礼申し上げる.
6 文献
平田大二(2012)陸前高田市立博物館の地質標本レスキュー作業にかかわって.神奈川県博物館協会会報,(83), 59-67.
兼子尚知(2011)陸前高田市立博物館の地質標本レスキュー事業参加報告. GSJ Newsletter, (84), 3-4.
川端清司(2012)「東北地方太平洋沖地震及び津波」で被災した陸前高田市立博物館の地質資料レスキュー. Nature Study, 58(3), 5-7.
真鍋 真(2011a)東日本大震災:学術コミュニティが取り組むべき現在と未来. 全科協ニュース, 41(5), 5-7.
真鍋 真(2011b)地域の記憶を継承する場としての博物館. 海洋と生物, 33(5), 395-402.
間嶋隆一(2012)日本古生物学会博物館レスキュー活動に参加して. 化石, (91), 56-59.
西田治文(2012)標本レスキュー,過去を未来へ-自然界の文化財を守り伝えることの意義-. 岩槻邦男・堂本暁子(監修)災害と生物多様性〜災害から学ぶ,私たちの社会と未来〜, 70-73.
大石雅之(2011)岩手県における被災自然史標本の救済活動.学術の動向, 2011.12, 38-39.
斎藤靖二・西田治文・真鍋 真(2011)公開シンポジウム「緊急集会:被災した自然史標本と博物館の復旧・復興にむけて-学術コミュニティは何をすべきか?」を開催して. 学術の動向, 2011.12, 56-59.
鈴木まほろ・大石雅之(2011)津波被災標本を救う〜つながる博物館をめざして〜.生物の科学遺伝, 65(6), 2-6.
付記 陸前高田市立博物館地質標本救済事業参加者一覧(24機関33名)
————————————————————————————
第1次作業参加者(8月1日〜8月4日)15機関20名
大石雅之・吉田 充(岩手県博),永広昌之(東北大総合学術博),遠藤大介(筑波大博士後期課程1年),兼子尚知(産総研地質標本館),小池 渉・細谷正夫(茨城県自然博),奥村よほ子(佐野市葛生化石館),横山一巳(国科博),立澤富朗((有)ジオプランニング),佐藤たまき(東京学芸大),加藤久佳(千葉県中央博),大島光春・佐藤哲哉・樽 創(神奈川県生命の星・地球博),河本和朗(大鹿村中央構造線博),川端清司(大阪市自然史博),先山 徹・松原 尚志(兵庫県人と自然博),澤田結基(福山市大)
————————————————————————————
第1次補足作業参加者(8月29日〜8月31日)4機関5名
大石雅之,真鍋 真(国科博),伊左治鎭司・加藤久佳(千葉県中央博),高橋みどり(静岡科学館)
————————————————————————————
第2次作業参加者(10月4日〜10月7日)13機関16名
加納 学(三笠市博),小林快次(北海道大総合博),大石雅之・吉田 充,永広昌之,川村寿郎(宮城教育大),菊池佳子(同大修士課程1年),千葉和昌(同大4年),兼子尚知,奥村よほ子,高桑祐司(群馬県自然史博),川辺文久(文科省初等中等教育局),間嶋隆一(横浜国大),大路樹生(名古屋大博),松原尚志,大橋智之(北九州市自然史・歴史博)
————————————————————————————
第2次補足作業参加者(11月16日,12月7日,12月13日)1機関2名
大石雅之・吉田 充
————————————————————————————
(2012/4/25)
復旧復興にかかわる調査・研究事業-報告03
放射性セシウムに汚染された水田土壌のカヤツリグサ科マツバイによるファイトレメディエーション
愛媛大学 榊原正幸・佐野 栄
(News誌2012年8月号掲載)
1 はじめに
2011年3月11日,東北地方太平洋沖地震に起因して,東京電力の福島第一原子力発電所において未曾有の世界における最大規模の原子力事故が発生した.そして,様々な要因が重なり,国際原子力事象評価尺度のレベル7(深刻な事故)に相当する多量の放射性物質が外部に漏れ出した.同レベルの原子力事故は,1986年4月26日に旧ソビエト連邦で起きたチェルノブイリ原子力発電所事故以来2例目である.
8月29日に文部科学省によって公表された福島第1原発から半径100キロ圏内の原発事故で放出された放射性Csによる土壌汚染の分布図によると,国際原子力機関(IAEA)が緊急事態の対応として一時的な住居の移転などを求める放射性物質の濃度の1000万Bq/m2を超える極めて高い数値を示した区域は,警戒区域内にある福島県大熊町(2946万Bq/m2)のほか,原発から北西方向の双葉町や浪江町の一部の地点で,チェルノブイリ原発事故の際に一時的な住居の移転が求められた55万5000 Bq/m2を超える区域は,南相馬市,富岡町,大熊町,双葉町,浪江町,飯舘村の6市町村34地点であった. また,農林水産省も同日,福島,宮城,栃木,群馬,茨城,千葉県の農地における137Csおよび134Csの濃度分布図を作成した.これによると,コメの作付けが制限された地域以外では,伊達市霊山町下小国,いわき市川前町下樋売,大玉村大山および相馬市東玉野など福島県内の4市村の合わせて9ヶ所の畑で,制限の目安とされる5,000 Bq/kgを超える放射性Csを検出したことが明らかになった.一方,コメの作付けが制限されている地域では,水田を中心に浪江町南津島,飯舘村長泥および大熊町野上などで,20,000 Bq/kgを超える放射性Csが検出された.
さて,著者らは,カヤツリグサ科ハリイ属のマツバイ(Eleocharis acicularis)が多種類の重金属に対して耐性を有し,多種類の重金属を同時に吸収・蓄積できる超集積植物であることを報告した(榊原ほか,2006, 2008, 2010, 2011a; Ha et al, 2008, 2009a, b, 2011; Sakakibara et al, 2009, 2011b;藏本ほか,2011).また,マツバイは,北海道から沖縄まで全国各地の湖沼,ため池,水路や水田などに群生する抽水性かつ繁殖力旺盛な多年草であるという点も,理想的なファイトレメディエーション植物としての性質を有していると言える.本研究事業では,福島第一原子力発電所事故によって発生した水田の放射性Cs汚染をカヤツリグサ科ハリイ属のマツバイ(Eleocharis acicularis)を用いて効率良く除染するフィールド実験を行った.なお,この研究事業成果は,すでに2つの学会で発表している(榊原・久保田,2012a, b).
2 実験方法
本研究の実験は,福島県郡山市の福島県農業総合センターの協力のもと,同センター内の水田において実施した.それは,(1)放射性Csに汚染された水田土壌に自生するマツバイの放射能濃度の測定,および(2) )放射性Csに汚染された水田土壌におけるマツバイの栽培実験およびその放射能濃度測定,である.以下にその方法を示す.
(1)自生マツバイの放射能濃度測定
福島県農業総合センターの水田内に自生するマツバイは,稲の株の隙間にわずかに自生しているものが発見された(Fig. 1a).それらの体高は最高で7 cm程度で,小さいものが多い(Fig. 1b).放射能濃度測定用のマツバイ試料の採取は,2011年8月11日に行った.
Fig. 1. E. acicularis growing naturally in the paddy field of the Fukushima Agricultural Technology Center.
(2)マツバイの栽培実験およびその放射能濃度測定
実験開始時に,水田にはすでに稲が栽培されていたため,マツバイの栽培実験は日当たりの良い水田の縁で行った.栽培実験では,マツバイを[1]コンテナ栽培法および[2]直植え栽培法の2つの栽培方法で8月11日に水田へ移植し,24日間栽培実験を行った.実験終了後のマツバイの採取は9月4日に実施し,それらの134Csおよび137Csの放射能濃度を測定した.各栽培方法は以下の通りである.
[1]コンテナ栽培法:市販のプラスティックコンテナ(縦36cm×横50×高さ11cm)にマツバイを約1 kgずつ移植する.本実験では計5つのプラスティックコンテナを用意した.この栽培実験では,愛媛県松山市南高井の用水路に自生しているマツバイを採取・輸送し,使用した(Fig. 2a).実験では,このマツバイを根を下にして,プラスティックコンテナに並べ(Fig. 2aおよびc),放射性Csに汚染された水田土壌に設置した(Fig. 2d).栽培実験開始時の設置場所の水深は2〜5 cm程度であった.
[2] 直植え栽培法:この方法では,放射性Csに汚染された水田土壌にマツバイを直接移植した.使用したマツバイは(1)の実験と同じである.栽培時に,マツバイの根が地表下数cmになるように移植した.また,マツバイの葉20〜30本程度(20 g程度)が一株になるように,10 cm程度の間隔で植えた(Fig. 3aおよびb).
Fig. 2 Photographs of E. acicularis by the container cultivation method in the paddy field in the Fukushima Agricultural Technology Center (FATC). a: E. acicularis before the cultivation experiments, growing naturally in the Masuyama Plain, b, c, and d: translanting the E. acicularis into the plastic container and moving to the paddy field in the Fukushima Agricultural Technology Center, e and f: the E. acicularis after transplanting over 24 days.
Fig. 3 E. acicularis by the direct cultivation method in the paddy field of the Fukushima Agricultural Technology Center. a and b: translanting the E. acicularis to the paddy field in the Fukushima Agricultural Technology Center, c and d: the E. acicularis after transplanting over 24 days.
3 分析方法および栽培地点の水・堆積物の重金属濃度
3.1 分析方法
上記栽培実験(1)および(2)のマツバイは,9月4日に分析用試料を採取した.採取したマツバイは十分に水で洗浄し,それを分析試料とした.マツバイの放射性Csの放射能濃度測定は,財団法人 九州環境管理協会においてゲルマニウム半導体検出器を用いたγ線測定によって行われた.
134Cs(半減期:2.06 年)は,壊変に際して複数のγ線を段階的に放出するため,その測定時に,試料の形状によってはサム効果(複数のガンマ線が重なって検出される効果)が生じる.このサム効果の補正を実施しない場合,134Csの放射能濃度は一般的に真値より低めの値を示す.したがって,以下に示したデータでは,旧科学技術庁マニュアルに準拠し,検出器の効率校正および試料解析時におけるサム・コインシデンス効果補正が取り入れられている.
3.2 栽培地点における水田土壌の放射性Csの放射能濃度
今回,栽培実験を行った福島県農業総合センターの水田土壌の放射性Csの放射能濃度は,同センターによって3,800 Bq/kgであることが明らかにされている.
4 実験結果
4.1 マツバイの生育状況
実験期間中のマツバイの生育状態は極めて良好であった.移植したマツバイは,コンテナ栽培法および直植え栽培法ともに,24日後にはバイオマスを増大させていた(Fig.2eおよびf,Fig.3cおよびd).9月後半から水田の水が落とされ,マツバイが枯れだしたため,実験を終了した.ただし,湛水した状態のまま継続すれば,福島県の気温から考えて,11月末頃までマツバイの栽培が可能であると判断される.
マツバイ中の放射性Csの放射能濃度
上記実験におけるマツバイの放射性Csの放射能濃度を測定した結果をTable 1に示す.まず,センター内の放射性Csに汚染された水田土壌に自生するマツバイの放射能濃度は,134Csが3,080 Bq/kg,137Csが3,090 Bq/kg,総放射性Csが6,170 Bq/kgと高濃度であった.栽培実験で使用した愛媛県松山市のマツバイの初生値は検出限界値以下で,24日間の栽培実験後の放射性Csの放射能濃度は,[1]のコンテナ栽培法の場合,134Csが494 Bq/kg,137Csが552 Bq/kg,総放射性Csが1,046 Bq/kgで,[2]の直植え栽培法の場合,134Csが521 Bq/kg,137Csが635 Bq/kg,総放射性Csが1,156 Bq/kgであった.
放射性Csによって汚染された水田におけるマツバイの栽培方法
本研究の結果,放射性Csに汚染された水田におけるマツバイによるファイトレメディエーションは,「コンテナ栽培法」が最もリスクが低く,実践的かつ効率的であると考えられる.それは以下のような理由によっている;
[1]コンテナ栽培法は,直植え栽培法と比較して,短時間に,均質にかつ多量のマツバイを水田に移植可能である,
[2]実施者が直接汚染土壌に接触せずに実施可能である,
[3]除染終了時のマツバイの撤去が効率的にかつ短時間で実施できる,
[4]マツバイ撤去時にそれを洗浄して泥を除去する必要がない.
マツバイによる放射性Cs汚染された水田のファイトレメディエーションの実用性
今回の実験結果は,マツバイによる放射性Cs汚染された水田のファイトレメディエーションが実用化にまで展開することが可能になったことを示している.特に,福島県で実施したマツバイの栽培実験における「コンテナ栽培法」と「直植え栽培法」は,実験終了時の総放射性Csの放射能濃度はほぼ同じ値となり(Table 1),有意な差が認められなかった.したがって,実際の除染作業では,実施者の外部被曝リスクを低減するために,「コンテナ栽培法」の方がより現実的であると言える.
来年度,著者らの研究グループは,福島県の協力を得てどれくらいの期間でどれくらい放射性Csを低減できるかを実証するフィールド試験を実施する予定である.
Table 1 Radioactivity concentration of E. acicularis in the experimetns.
謝辞:フィールド実験の際には,福島県農業総合センター・生産環境部の佐藤睦人氏および住鉱資源開発株式会社の水落幸弘氏にご協力いただいた.また,白河農業高校の根本氏には実験期間中のマツバイの写真撮影にご協力いただいた.以上の方々に,記して謝意を表する.
文 献
Ha, N. T. H., Sakakibara, M., Takehana, D., Sano, S., and Sera, K., 2008, Accumulation of heavy metals by Eleocharis acicularis in an abandoned mining site of Hokkaido, Japan.
Proceeding of The 14th Symposium on Soil and Groundwater Contamination and Remediation, 550-553.
Ha, N. T. H., Sakakibara, M., Sano, S., Hori, R. S., and Sera, K., 2009a, The potential of Eleocharis acicularis for phytoremediation: case study at an abandoned mine site. CLEAN – Soil, Air, Water, 37, 203-208.
Ha, N. T. H, Sakakibara, M., and Sano, S., 2009b, Phytoremediation of Sb, As, Cu and Zn from Contaminated Water by the Aquatic Macrophyte Eleocharis acicularis. CLEAN - Soil, Air, Water, 37, 720-725.
Ha, N. T. H., Sakakibara, M., and Sano, S., 2011, Accumulation of Indium and other heavy metals by Eleocharis acicularis: An option for phytoremediation and phytomining. Bioresource Technology, 102, 2228-2234.
藏本 翔・榊原正幸・佐野 栄・世良耕一郎(Kuramoto, S., Sakakibara, M., Sano, S. and Sera, K.),2011,カヤツリグサ科マツバイによる重金属汚染水のファイトレメディエーションにおけるクリンカアッシュの有効性.第18回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会講演集(Proceeding of The 18th Symposium on Soil and Groundwater Contamination and Remediation),445-448.
榊原正幸・原田亜紀・佐野 栄・堀 利栄・井上雅裕(Sakakibara, M., Harada, A., Sano, S., Hori, R. and Inoue, M.),2006,マツバイを用いたファイトレメディエーションによる重金属に汚染された水環境の浄化.第12回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会講演集(Proceeding of The 12th Symposium on Soil and Groundwater Contamination and Remediation),545-548.
榊原正幸・大森優子・佐野 栄・世良耕一郎・濱田 崇・堀 利栄(Sakakibara, M., Ohmori, Y., Sano, S., Sera, K., Hamada, T. and Hori, R.),2008,マツバイによる廃止鉱山残土堆積場の重金属汚染された水・底質環境の浄化.第14回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会講演集(Proceeding of The 14th Symposium on Soil and Groundwater Contamination and Remediation),130−133.
Sakakibara, M., Harada, A., Sano, S., and Hori, R. S., 2009, Heavy metal tolerance and accumulation in Eleocharis acicularis, a heavy metal hyperaccumulating aquatic plant species, Geo-pollution Science, Medical Geology and Urban Geology, 5, 1-8.
榊原正幸・ 菅原久誠・Ha, N. T. H.・彦田真友子(Sakakibara, M., Sugawara, H., Ha, N. T. H. and Hikoda, M.,),2010,マツバイ中の植物珪酸体における重金属集積.第20回環境地質学シンポジウム論文集(The Proceedings of the Twenty Symposium on GEO-Environments and GEO-Technics),251-254.
榊原正幸・藏本 翔・岡崎健治・伊東佳彦・大日向昭彦・竹花大介(Sakakibara, M., Kuramoto, S., Okazaki, K., Ito, Y., Obinata, A. and Takehana, D.),2011a,セレンに富む残土排水のカヤツリグサ科マツバイによるファイトレメディエーション.第18回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会講演集(Proceeding of The 18th Symposium on Soil and Groundwater Contamination and Remediation),310-312.
Sakakibara, M., Ohmori, Y., Ha, N.T.H., Sano, S., and Sera, K., 2011b, Phytoremediation of heavy metal-contaminated water and sediment by Eleocharis acicularis. CLEAN−Soil, Air, Water, 39, 735-741.
榊原正幸・久保田有紀(Sakakibara, M. and Kubota, Y.),2012a,放射性セシウムに汚染された水田土壌のマツバイによるファイトレメディエーション.第21回環境地質学シンポジウム論文集(The Proceedings of the Twenty-First Symposium on GEO-Environments and GEO-Technics),11-16.
榊原正幸・久保田有紀(Sakakibara, M. and Kubota, Y.),2012b,福島県における放射性Cs汚染土壌のカヤツリグサ科マツバイによるファイトレメディエーション.第18回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会講演集(Proceeding of The 18th Symposium on Soil and Groundwater Contamination and Remediation),154-156.
(2012/8/3)
新潟県南魚沼市のトンネル爆発に関連する地質情報
新潟県南魚沼市のトンネル爆発に関連する地質情報
5月24日に新潟県南魚沼市のトンネル工事現場において4名の方々が亡くなられた爆発事故がありました。亡くなられた方々とご遺族に対し謹んで哀悼の意を表します。
● 燃料資源の研究をされている産総研の金子信行会員に「新潟および関東地方の天然ガスの起源と賦存状態について」の解説を書いていただきました。(2012.6.2)
解説記事はこちらから、、、
● 産業技術総合研究所地質調査総合センターのサイトに当該地域の地質の解説が掲載されました。トンネル周辺の地質の特徴や油田・ガス田の分布地域との位置関係などの情報を見ることができます。(2012.6.1)
・産総研による地質解説記事へのリンクはこちら→ 「新潟県南魚沼市八箇峠トンネル(仮称)周辺の地質」
復旧復興にかかわる調査・研究事業-報告04
福島第一原発周辺の放射線量の測定方法と放射能地質汚染の研究
日本地質学会環境地質部会長:楡井 久
調査団長:上砂正一
調査団:愛甲義昭*・上砂正一*・香川 淳*・木村和也*・楠田 隆*・佐藤恭一*・楡井 久* 布施 太郎*・古野邦雄*・増田俊壽*・笠原 豊・田村喜之 岡野英樹(*現地調査員)
(News誌2012年8月号掲載)
※Fig. 1〜7はクリックすると別画面で大きく表示できます。
1 はじめに
今回の福島第一原子力発電所の事故に伴って大気中に放出された放射性物質は,自然の営力によって拡散し降下・沈積しているので,気象条件(雨,風など)・地形(山地,丘陵,斜面の方向や傾斜,表流水の集積しやすいところなど)・植生(広葉樹、常緑樹、草地など)・地質条件(土粒子の粒度分布,岩種,多孔質の差など)・土地利用(森林,耕作地,宅地など)により分布(堆積)状況が異なるはずである.実測される放射線量は,表層の植生や微地形,地質条件によっても影響を受けていることが考えられるが,ほとんどの場合画一的な調査を行っている.これは土壌汚染対策法と同じで,自然の法則を無視した方法である.また,地上高50cm,1mで測定する方法では必ずしも堆積の場での測定では無く,高くなればなるほど(空気による吸収があるが,遠方からの放射線の放射線量(率)に対する寄与が相対的に大きくなるため)情報がぼやけてくる.今回のように広域に降下・沈積している放射性物質による地質汚染の場合,最も適切な測定方法と測点設定などの調査手法を立案することが課題である.
測定機器
調査員 : 総勢42名
携帯型放射線量測定装置:[1]RT-30(GEORADIS社 携帯型放射線量・成分測定装置ガンマ線スペクトロメータ)1台,[2]Radi(堀場製作所製PA-1000)3台,[3]エアカウンター(エステー(株))1台,[4]エアカウンターS(エステー(株))1台,[5]LK3600(中国製,GM型計数管)1台 合計7台を使用した.地層の放射能強度測定は堀場製「放射能簡易測定キット(PA-K)」を用いた.
調査方法
(1)福島第一原子力発電所から放出された放射性物質による放射線量分布図を作成するために,車載機による広域的な空間放射線量(率)を測定した.
(2)計画的避難地域に指定されている福島県南相馬郡飯舘村二枚橋の農用地・宅地を借り受け空間放射線量(率)・表層汚染調査等の現地調査を実施した.
(3)調査期間:2月20日〜3月4日
2 広域的な空間放射線量(率)の測定
2011年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故から,調査時点でほぼ1年になる.関東,東北(福島のみ)の国道・県道をくまなく測定した結果,この1年間で二つの巨大な放射能汚染地域があることが判明した.福島原発から放出された放射性物質は福島県だけでなく,栃木県,群馬県,茨城県,千葉県,東京都まで拡散し,汚染地域が連なる広域汚染地帯を形成している.放射性物質は2つの巨大プリュームとして検出され,一つは福島原発から北西に延び福島市から南下して栃木・群馬へと広がるフクトグン−プリューム(FukuToGun Plume),もう一つは福島原発から南下して茨城−千葉−東京へと広がるチバラキト−プリューム(ChIbarakiTo Plume)である(Fig.1,2,楡井2011).
放射線測定は,GEORADIS社製RT-30とGPSからなる測定システムChIbarakiNo.1を車内(地表面上ほぼ80cm)に搭載し,一般道,高速道路を福島から関東地方にかけて車で走行しながら行った.しかし,車内での測定であり,車体自体による放射線の吸収による放射線量の減衰があるため,測定値を補正して屋外に対応する線量に換算した(Fig.3).
Fig.1. フクトグン−プリューム(FukuToGun Plume).
Fig.2. チバラキト−プリューム(ChIbarakiTo Plume).測定はRT-30(GEORADIS社製)を車内に搭載し,走行しながら行った.車内では線量が減衰するため,補正をする必要がある.図中の線量は係数(別図参照)を掛け,屋外と同じレベルになるよう補正した値である.
Fig.3. 屋外に対応する線量換算.
3 農用地・宅地の空間放射線量(率)調査・表層汚染調査等の現地調査
福島県の現地測定箇所の選定については,放射性物質の分布状況から判断して,高濃度で広範囲に広がっているフクトグンプリュームで,このような特異な分布形態になった原因を解明する目的として,阿武隈山地の中央分水界の東側斜面を選んだ(Fig.4).
調査地での測定はChIbarakiNo.1で調査地周辺の核種分析とRadi等で調査地内の地表および1m高さの空間放射線量(率)の測定と地表面下の放射線量測定を行った.地表面下の測定に当たっては周辺の影響を受けないように簡易的に測定する方法を確立する目的でタングステンシートや鉛板で簡単なコリメータを自作して測定した (Fig.5).タングステンシートは1面遮蔽であるが,鉛は3面遮蔽にして測定した結果,3面遮蔽の方が効果は大であった.遮蔽効果を比較できるように測定器は堀場製のPA-1000(Radi)を2台用いた.現在,さらに改良を加えた補助装置を制作・検証中である.
Fig.4. 福島第一原発からの空間放射線量(率).
Fig.5. 垂直方向の放射線量(率)測定(左はタングステンシート、右は鉛).タングステンシートは50mm×50mm,t=1.2mmのもの8枚使用.
(1)地質汚染調査に基づいた放射線量単元調査
原発事故により広範囲に汚染された地域では,計算上の放射線量率の値は測定する高さで変化しないと考えられるので,50cm〜1mの高さで測定されている(環境省,2011).但し,計算値は,理想化された条件下で計算されているものであり,現場での測定値を考える場合は注意が必要である.実際に,地表面で測定した値と高さ50cmや1mでの計算上の値でも違いがある(東京都健康安全研究センター,2011).理論計算する場合の条件は,無限遠の平坦面を考え,かつ放射性物質が平坦面上に均一に分布している場合で,さらに放射線を遮蔽する障害物(建物などの構造物や樹木,あるいは地面の凸凹など)がないといった非現実的なものである(田崎晴明,2011).今回の福島第一原発の事故で大気中に放出された放射性物質は自然の営力によって広範な地域に拡散しているので,気象条件・地形・植生・地質条件・土地利用により堆積状況が異なり,測定地点間でさえも分布状況が違う可能性がある.したがって,平坦でもなく,不均一に分布していると考えられる放射性物質による放射線量(率)の高さ1mでの測定では,理想的な条件下で考えられる様な無限遠からの放射線の寄与は期待できないが,測定位置を中心にして最大で半径100m以下の領域の地表面および地表面下(数cm)にある放射性物質から飛んでくるγ線を測定していると期待できる.
そのため数mから20〜30mの放射性物質の濃度不均一をそのまま反映しているとは考えられない.また,50cm,1mで測定する方法では必ずしも堆積の場での測定では無く,高くなればなるほど(空気による吸収があるけれども,一般的に遠方からの放射線の影響の効果が相対的に大きくなるので)放射線強度の濃淡のコントラストが不明瞭になると考えるべきである.
本報告の調査対象地とした放射性物質で高濃度に汚染されている地域での測定結果では,地表面と1m高さで測定した値は大きく異なっている(Fig.6,Fig.7福島県計画的避難区域で測定).地表面での測定値は1m高の測定値よりも平均1.15倍(高濃度の範囲は1.38倍)で,より詳細に放射性物質の存在を明確にしていると考えられる.これは,地表面の測定では表層地質,植生,微地形(地表面の微小な形態,たとえば畑の畝や土壌の塊など)に直接影響された結果であると考えられる.
現時点で測定される放射線量は地表に降り積もった放射性物質によって支配されているので,地表面での測定が原則重要となる.自然の営力によって堆積した物質は自然界にコントロールされるので画一的な調査手法ではとうてい汚染マップは描けないし,最も重要な汚染のプロセスが全くブラックボックス化してしまう.
放射能汚染は放射性物質(自然及び人工放射性元素)が環境中にばら撒かれることである.通常,放射能汚染は,放射性核種(放射性同位体)を採掘したり,濃縮作業をしたり,生産したり,使用したりしている間に漏洩や事故によって生じる.しかし,3.11大震災に伴う福島第一原発の過酷事故では,チェルノブイリ原発事故以来と言われるほど大量に放出された放射性物質が広範な地域に降り注ぎ重大な放射能汚染を引き起こしたことである.事故によって放出された放射性物質の量は,ソースターム(source term)と呼ばれ,その正確な分布範囲と状況を確認することが課題である.
大量の放射性物質の放出,広範囲に拡散・沈積して約1年が経過し,放射性物質の分布状況は水平方向にも垂直方向にも変化していると考えられる.このようなことから,放射線量(率)測定といえども地質汚染単元調査法で,どの核種がどの範囲でどの程度の濃度(量)がどの深度まで存在しているのかを明らかにすべきである.例え層相が同じであっても,深度方向調査は可能な最小単位(1cm程度)で行うことが望ましい.調査方法は地質汚染と同じ考え方であるので,平面探査では,地形・表層地質(シルト層,粘土層,砂層,礫層など)・植生条件によって測定地点や間隔を決定する.メッシュ調査では概況を確認してから微地形などに考慮しながら絞り込み調査を行うべきである.
今回,畑地での深度方向調査では植生(根)や凍結の影響で-1cm,-2cmは測定できず-1.5cmで測定した.地表面から-3cm以下は放射線量がかなり低下することが確認された.-3cm以下は地表面からの影響を受け1μSv/hを下回らなかった.正確な値を取得するには,鉛等で遮蔽しながら測定するか,ブロックサンプリングあるいは貫入試料を採取して可搬型のガンマ線ベクレル測定器,ゲルマニウム半導体検出器を用いて測定する方法がある.
Fig.6.
Fig.7.
(2)放射能簡易測定キットPA-Kによる測定
調査団が行った測定は,地表面および地表面高+1.0mの放射線量,地表面下-5cm(一部では-15cm)までの各深度の放射線量で,地表面下の試料は放射能簡易測定キットPA-K(以下PA-Kと言う.)による測定である.
植生の影響で-1cm,-2cmは測定できず-1.5cmで測定した.地表面から-3cm以下は放射線量がかなり低下する.-3cm以下は地表面からの影響を受け1μSv/hを下回らなかった.
垂直方向に掘削しながら放射線を測定した場所で,掘削した地層をPA-Kで現地測定し,測定後ビニール袋で持ち帰り,自然乾燥した後,鉛板を貼った流しのところでPA-Kで再測定した.結果をFig.8に示す.
ペアの図は右が現地測定,左が試験室の鉛板上で測定.いずれも,測定値こそ異なるが,数値的には同じ傾向を示しておりほぼ3〜4cm程度まで放射性物質が浸透している範囲と想定される.現在被災地において掘削処理が行われているが,簡単な測定器を用いて管理すればより効果的な対策が可能と考えられる.
放射能対策に係る調査は,地質汚染と同様にきちんと汚染状態を調査して行うべきである.
現地空間放射線量(率)測定
現地測定
ラボ測定
Fig.8. PA-Kで測定した垂直方向の地層放射能強度.
4 考察
一般的に放射線量(率)の測定では,放射性セシウムが地表だけに降り積もった状況を考えた議論であり,今回の報告に示したようにセシウムが土壌中にも沈積している場合には一考の余地があります.このような場合,放射線量(率)の測定値には遠くからの放射線の寄与は弱まり,近くからの放射線の寄与が相対的に大きくなると考えられています.この傾向は土壌中に深く染み込むほど近傍の放射線の寄与が大きくなるということである.これは土壌によるγ線の吸収効果のためである.したがって,放射性物質が表面だけでなく地表面下にまで沈積分布するようになると,測定される放射線量(率)は測定地点からの近い領域に存在する放射性物質分布を反映するようになる.一方,地表面上での測定では地表面の微形態(畑地の畝や土塊など)にも大きく影響されるため,測定地点を中心にして半径20cm(最大でも30cm程度)程度の半球(空気中には放射性物質は浮遊していないと考えると,測定面(地表面)下の半球である)内にある地表および地中の放射性物質からのγ線(使用した線量計がβ線を遮蔽あるいはカットしてしまうタイプならば)を測定していることになる.したがって,数十cm程度の濃度不均一をそのまま反映することになると考えられる.
雪面上での測定値について
雪上での測定値を考える場合,雪は基本的にH2O(水)と同じであるから,その「減衰長:cm」は水と同じと見なしてよい.減衰長は平均自由行程とも呼ばれる.γ線が減衰長だけ進むと,γ線の強度は約2.72分の1に弱められる.要するに,減衰長は遮蔽効果の目安になる量である.水の減衰長は大体12cmであるが,実際に積もっている雪の密度は氷そのものではなく,多分0.5g/cm3以下であろう.したがって,積雪中の減衰長は25〜30cm位であろう.なお,土壌の減衰長は約7cmである.測定地点で積もっている雪に放射性物質が混ざっていなければ土の表面にある放射性物質の上に,積雪45cmであれば,積雪量の1/4程度の約10cmの土を被せたのと同じ遮蔽効果を示すことになる.もし,雪に放射性物質が混ざっていれば測定時に雪中の放射性物質からのγ線も測定してしまうので,測定値から積雪下にある土壌中の放射能強度(ベクレル値)を計算するのはかなり困難である.最低限前もって現地で雪中の放射能強度を測定しておく必要がある.
PA-Kによる深さ方向の測定値について
垂直方向に掘削しながら放射線を測定した場所で,掘削した地層(土壌を含む)をPA-Kで測定し,測定後ビニール袋で持ち帰り,自然乾燥した後PA-Kで再測定した.この場合,地層の放射能を測定する条件がかなり異なっている.調査や対策の現場では試料を風乾させて測定するのは非常に困難で有り,汚染対策をしながらの測定では結果を出す間にかなりの時間を要することになり現実的ではない.したがって,湿潤状態での測定を行い,試料を持ち帰って風乾状態での測定を比較検討することにした.
その他の問題点として,
[1] 現地でのPA-Kでの測定時に簡易キット自体を周辺(汚染地域であるので試料以外の現地での放射性物質からの放射線(自然放射線40Kも含めて))を遮断して測定しているかである.今回の測定は,周辺より放射線量の少ない雪で覆われたビニールハウス内で実施したが,測定にあたっては環境中の放射線の影響を受けていた,現在はPA-Kが周辺の放射線の影響をあまり受けないように遮蔽装置を用いて測定するように改良している.成果については今後の機会に報告したい.
[2] 地層の放射能測定は含水状態によって変化すると考えられる.持ち帰った試料は,実験室でi.乾燥前の湿った状態・含水状態で測定し,ii.同試料を遠心沈殿による水の分離を行い,iii.105℃で乾燥し含水測定を実施した.ii,iiiについては,分離した水と乾燥試料をPA-Kで測定した.さらに,現地測定とラボで測定した地質サンプルについては放射能強度をゲルマニウム検出器による測定を依頼中である.
この一連の作業も時間を要し,短時間で測定可能な方法を見いだすには,今後の検討課題である.
[3] 試料の形状と線量計との位置関係について,試料を容器に均等に隙間なく均一に入れないと試料形状の変化が放射能強度分布の変化の原因になることが想定される.現地測定では汚染を防ぐためにマリネリ容器に食品用ラッピングフィルムを敷いて試料を詰めた.試料には草根,礫,木片などが混入しており理想的状態に詰め込まれていない.この対策としてはミキサーなどを利用して試料作成を行うなどの方法が考えられる.この点についても今後の課題となる.
[4] 放射性物質に汚染された地域では,土壌,水,農作物,食品,製品,廃棄物にいたるまで物質から発する放射能を検出・測定が求められている.医療地質研究所(MGRI)の協力のもと,わずかな放射能レベルでも短時間で高い分解能と精度(Cs-137検出下限値(正味計数値:3σ以上)5Bq/kg以下 (10分測定時),3Bq/kg以下 (15分測定時)測定容器:600mLマリネリ容器)でベクレル現地測定(GEORADIS社製据置型・ガンマ線スペクトロメータRT-50を使用)し,[1]の遮蔽装置での測定成果を検証する計画である.
5 まとめ
放射性物質による汚染の場での地層単元と階層性を確認すること,それには,以下の事項を詳細に調査することが重要である(楡井,2011).
[1]発生源からの発生状況
[2]地層の透水性・透気性・吸着性などを明らかにする
[3]表流水の集水域の単元と階層性
[4]大気流動の単元と階層性
[5]地下水の流動系の単元の階層性
やはり,放射能汚染と言っても現在のような状況になったプロセスをまず解明しておかないと広範囲に精度よく調査しても完璧な除去は困難である.
福島第一原子力発電所での過酷な事故は,自然災害の中での事故といえども根本的にはヒューマンエラー(人的ミス)による広範な放射能汚染事故である.
複数の要因が重なった汚染機構解明は地道な空間放射線量(率)測定が目的達成の最短距離である.調査の最重要課題は安価なハンディタイプで誰でも使える計測器を被災地に数多く配布し,ヒューマンパワーで数多く測定していくことで対策の緊急性・方向性がより鮮明になり,風評被害(スティグマ)の克服や食の安全を守っていくことにもつながっていくと考えられる.
福島県内の放射線量測定は現在も続けられており,災害復旧事業費で得られた結果を基に新たな測定法の開発につなげ,さらに放射能の現地測定技術なども開発中である.今後は,放射線測定・調査研究委員会に引き継ぎ,原発事故で被害を被っている地域に地質学会としてさらなる貢献をしたい所存である.
今回得られた成果は,日本地質学会119年大会で発表する.
謝辞
現場測定で特に,RT-30による福島,関東一帯の道路測定および現地交渉については医療地質研究所(MGRI)の協力を得た.
本報告をまとめるにあたり,NPO日本地質汚染審査機構で仮報告を行い,聴取者から適切な助言をいただきより良い方向に修正できた.さらに,放射線測定・調査研究委員会委員長相川信之博士(大阪市立大学名誉教授)からは粗稿に対して有益なご指摘をいただき,さらに報告内容が改善されたここに記して感謝いたします.
参考文献
楡井 久,2011,地質汚染調査からみた放射能汚染調査と放射性廃棄物処理について.平成23年「放射性廃棄物管理専門研究会」,報告書, 京都大学原子炉実験所, 87—98.
環境省,2011,環境省告示第百十号,環境大臣が定める放射線の量の測定方法,環境大臣細野豪志.2011年12月28日.
東京都健康安全研究センター,2011,空間放射線量の測定の高さによる違いについて,http://monitoring.tokyo-eiken.go.jp/monitoring/sokutei/sokutei.html.
田崎晴明,2011,ベクレルからシーベルトへ..学習院大学理学部物理学教室田崎研究室webサイト.http://www.gakushuin.ac.jp/~881791/housha/docs/BqToSv.pdf (公開:2011年6月1日,最終更新日2011年7月2日)
その他記録写真等は以下よりご覧ください。
▶▶記録写真
▶▶測定装置
▶▶簡易放射能測定キットによる測定
▶▶簡易放射能測定キットによる現地測定
(2012/8/3)
復旧復興にかかわる調査・研究事業-報告05
関東平野内陸部の住宅地での盛土材質の相違による液状化要因の解明
新潟大学災害・復興科学研究所 卜部厚志
2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震によって,関東地方南部では埋立地などの人工地盤を中心に多くの地域で液状化が発生した.このうち,千葉県の浦安地域などの東京湾沿岸の埋立地では,顕著な液状化により多くの建物に被害が及んだ.埋立地における液状化被害は,国内外のこれまでの地震によっても繰り返されてきた現象である.一方で,関東地方内陸部の埼玉県,千葉県や茨城県内においても,一部の地域で液状化による建物被害が発生しており,千葉県や茨城県では現在の利根川流域に被害が集中している.このため,本研究では,関東地方内陸部の液状化被害に着目して,液状化被害の記載と分布,立地地盤と液状化の発生要因について検討を行った.現地調査は,茨城県の潮来市日の出地区,埼玉県久喜市南栗橋地区と神栖市深芝地区で行った.この結果,日の出地区と南栗橋地区は浚渫砂による盛土造成による地盤,深芝地区は砂利採取後の埋め戻し地盤であり,人工地盤において顕著な被害が発生していることが明らかとなった.また,潮来市日の出地区については,液状化の発生と建物被害要因を解明するため,被災地におけるボーリング調査や粒度分析による検討を行った.
第1図 潮来市日の出地区での液状化被害
調査地域の宅地地盤の形成過程と液状化の被害概要
1)茨城県潮来市・日の出地区
日の出地区は,内浪逆浦と呼ばれた潟湖を干拓し,その後に盛土造成した住宅地である.土地変遷の履歴は,まず,昭和6年より潟湖に囲み土手(堤防)を設置して排水により干拓を行い農地化した.次いで,鹿島臨海工業地域の開発にあわせた住宅地の需要から,昭和44年より北浦等の周辺の潟からの浚渫土砂により盛土をして宅地化した場所である.盛土は,浚渫船からパイプによる送水によって行われている.また,潟湖に直接,浚渫によって盛土したのではなく,およそ30年以上の間,旧潟湖の湖底の泥層や砂層を乾陸化したことが,通常の埋立地の形成過程と異なる.後述するように,この造成過程の中で乾陸化したことは,地層の強度の増加と関連している.
日の出地区では,建物(木造住家)の傾き,建物(木造住家)の沈下,道路の変形,側方流動など液状化による典型的な被害が広範囲で発生した.特に3丁目,4丁目,5丁目,6丁目,8丁目において被害が集中し,旧潟湖の縁辺部に相当する日の出地区の南部や北部では,被害が少なかった.第1図に,建物の外見上の傾きを基準として,全壊程度(内閣府の1次被災判定の基準)の傾き,半壊程度の傾きと建物の傾きがない(あるいはごく僅か)の3段階に区分による建物被害の分布を示す.全体としては,日の出地区の住宅の約50%が半壊程度以上の被害を受けている.外見上の建物被害がわずかな街区では,道路や宅地の変形もごくわずかであることが多い.また,日の出地区周辺の自然地盤の低地(田んぼ)や宅地ではほとんど液状化は発生しておらず,浚渫盛土された日の出地区のみで液状化が発生した様相を示している.一方で,日の出地区内を詳細にみると浚渫盛土による造成地のすべてにおいて液状化が顕著なわけではない.浚渫以前の空中写真(1948年米軍撮影)と比較しても,地区のなかでより湿潤な部分と被害の集中域は一致していない.このため,地区内において液状化による建物被害が集中した要因を解明する必要がある.
ボーリングによる詳細調査については後述する.
2)埼玉県久喜市・南栗橋地区
南栗橋地区は,埼玉県東部の利根川流域に位置する.地形環境は,旧利根川水系による自然堤防と流路跡の低地帯から構成され,南栗橋地区は,旧流路跡の低地や氾濫原にわたる地形部分を造成して宅地化した土地である.土地変遷の履歴は,昭和57年頃から宅地造成が計画され,平成元年頃より工区ごとに囲み土手(堤防)を設置して,東方に位置する権現堂川(旧利根川流路)の遊水池化工事の際の浚渫土砂により盛土をしたものである.盛土は,浚渫船からパイプによる送水によって行われている.
南栗橋地区では,建物(木造住家)の傾き,建物(木造住家)の沈下,道路の変形など液状化による被害が発生した.特に12丁目に被害が集中しており,造成前の空中写真による地形解析から,湿潤な地盤と推定される7丁目等では被害はほとんど発生していない.また,南栗橋地区周辺の自然地盤の低地(田んぼ)では液状化は発生しておらず,浚渫盛土された宅地の一部で液状化が発生した.
3)茨城県神栖市・深芝地区
深芝地区は,茨城県南東部の利根川下流域,霞ヶ浦の南部に位置する.地形環境は,河川や潟湖周辺の低地帯を宅地化した土地である.土地変遷の履歴の詳細は不明であるが,深芝地区を含め周辺地域の浅層部には,河川起源の砂礫層が分布することが知られている.このため,農地の地下の砂礫層を砂利として採取し,周辺の下総層群の砂層によって埋め戻すことが広く行われている地域である.
深芝地区では,建物(木造住家)の傾きや建物(木造住家)の大きな沈下など液状化による被害が発生した.しかし,液状化による沈下や変形は,宅地敷地部分のみにおいて発生し,道路部分は変形していない特徴がある.前述の日の出地区や南栗橋地区では,宅地で液状化が発生している街区では道路も大きく変形しており,宅地と道路部分が一体となって液状化したことを示している.しかし,深芝地区での液状化による建物被害は,宅地の敷地のみで発生しており,砂利採取して埋め戻した農地が宅地として開発され,埋め戻した部分のみが液状化したことを示している.このことは,周辺地域において砂利採取して埋め戻された農地が陥没や変形をしていることからも,液状化発生の要因が砂利採取後の埋立にあることを支持している.
第2図 日の出地区でのボーリング試料の層相
第3図 日の出2丁目コアの粒度組成
第4図 日の出6丁目コアの粒度組成
※図の拡大はそれぞれ図をクリック
潮来市日の出地区でのボーリング調査と粒度分析
1)コア試料の層相
日の出地区は,浚渫による盛土で造成されているが,同じ浚渫盛土による地盤の中で液状化の発生程度に差異がある.この要因の解明は,液状化の予測につながる課題である.また,液状化した地区において,液状化した地層の層位を明らかにすることは,復旧方法や防止策の策定につながる重要な課題である.このため,液状化被害が顕著な4丁目,5丁目,6丁目,8丁目の公園内と,建物被害が比較的軽微な2丁目と7丁目の公園内で,深度5〜6mまでの表層地盤のボーリング調査をおこない,層相の観察,液状化の有無,粒度分析用試料の採取等を行った(第2図).
コア観察の結果,液状化による建物被害が顕著な4丁目,5丁目,6丁目,8丁目の表層地盤は,深度3〜4m程度まで浚渫による中〜粗粒砂層で構成され,2丁目と7丁目では深度2m程度まで浚渫による粗〜中粒砂層で構成されていることがわかった.浚渫による砂層の下位は,4丁目,5丁目,6丁目,8丁目では旧潟湖に堆積した泥層を主体とする層相であり,2丁目と7丁目では旧潟湖に堆積した砂層から構成される.6丁目などのコア試料では,浚渫砂層との境界の泥層上部が硬化していた.また,コア試料の層相から,液状化の顕著な層位の記録を行った.4丁目,5丁目,6丁目,8丁目のコア試料では浚渫砂層のほぼ全体が液状化しているのに対して,2丁目と7丁目のコア試料では浚渫砂層の全体ではなく一部の層位のみが液状化していた.各地点ともに,浚渫砂層下位の旧潟湖に堆積した泥層(泥層に挟在する砂層)や砂層は堆積構造が認められ液状化していないことが明らかとなった.建物被害との関係は,被害が多い地区において浚渫砂層の層厚が厚く(6丁目は除く),被害の少ない地区では浚渫砂層の層厚が薄い傾向がみられる.また,被害の少ない地区での浚渫砂層は被害の多い地区と比較して,全体に粗粒な傾向もある(第2図).
2)粒度組成
液状化による建物被害は,浚渫砂層の層厚や粒度と関連している可能性が高い.より詳細に検討するため,各コア試料を10㎝ごとに採取し,沈降管法によって粒度分析を行った.粒度範囲は−1φ〜5φとして,0.2φごとの粒度分布を求めるとともに,平均粒径(Mean),分級度(Sorting),歪度(Skewness),尖度(Kurtosis),最頻値(Mode),中央粒径値)(Median)も求めた.例として,2丁目と6丁目の粒度分析結果を示す(第3図,第4図).
2丁目コアの浚渫砂層の平均粒径は1.5〜2.5φを示し,淘汰度は0.6〜0.8を示す.全体には均質ではなく層位ごとに差異があることが特徴である(第3図).コア観察での液状化が顕著な層位は平均粒径が2φを示す.一方,6丁目コアの浚渫砂層の平均粒径は1.8〜2.2φ程度で2丁目と比較すると全体に均質である.
一般に建築系や地盤工学分野での液状化指針は,幅広い粒度の範囲を液状化する可能性がある砂層としている.日の出地区のコア試料の粒度分析結果をこれらの指針に当てはめると,すべての地区の浚渫砂層と自然地盤の砂層が液状化の可能性の高い粒度範囲を示す.今回の潮来地区の地震動と継続時間では,2丁目と6丁目あるいは自然地盤での砂層の液状化や建物被害に差異があるため,液状化指針への当てはめでは今回の被害の差異を説明できない.
2丁目や6丁目コアなどの平均粒径の分布からみると,建物被害の少ない2丁目と7丁目では,平均粒径にバラつきがあり,一部の層位において液状化したものの全体には及ばず,逆に建物被害の多かった地区でのコアは浚渫砂層の平均粒径がそろっており,液状化が発生した層位が上下の層位に拡大して,浚渫砂層のほとんどが液状化したものと考えられる.このように,浚渫砂層の層厚だけでなく,粒度構成の相違が建物の液状化被害の発生程度と大きく関係している可能性がある.
液状化被害復旧への課題
現在の地震による被害程度を判定する制度では,液状化による被災が十分に評価されず,被災者への生活再建支援につながらない.液状化の被害判定の拡充も必要であるが,具体的な支援の拡充が急務であると考えられる.
また,液状化は地盤を改良しない限り,繰り返して発生する災害であることから,今後予測される地震リスク(首都直下型,房総半島沖地震)を考え,建物復旧の工法と費用の選択をする必要がある.地盤の改良は,建物の更新時に実施すると工法の選択や費用の面でも安価となる.地盤環境,地震リスク,建物更新,費用など検討した上で,適切な復旧方法の検討が必要であり,液状化リスクの評価として,理学的な粒度分析の解釈も必要となっている.
(2013/3/11)
その他の,復旧復興にかかわる調査・研究事業はこちらから
地質災害の報告
地質災害の報告
地質災害委員会では,最近の広島土砂災害,御嶽山噴火などをはじめ,地質災害の関連情報をより多くより広く発信するため,学術大会緊急展示でのポスター内容を発表者の方々にお願いして,学会ニュース誌・HPへ掲載させて頂くことにしました.
地質学の防災への貢献という観点から今後もニュース誌や地質学雑誌の報告に原稿をお寄せ頂ければと思います.
地質災害委員会委員長 斎藤 眞
■2014年7月9日南木曽,8月6日岩国,8月17日福知山・丹波における土砂災害
■2013年(平成25年)山口・島根豪雨災害の概要と調査報告
【2014年度地質災害関連情報】
■平成26年11月22日 に発生した長野県北部の地震に関する情報
・長野県北部の地震[2014年11月22日](産総研地質調査総合センターHPへのリンク)
■平成26年9月27日 御嶽火山の噴火に関する情報
・御嶽火山の噴火に関する情報(産総研地質調査総合センターHPへのリンク)
・上空からの御嶽山の噴煙の写真(石渡 明:日本地質学会会員)
■平成26年8月20日に広島市安佐南区で発生した土石流の発生地に関する地質情報
・斎藤 眞ほか,2015,2014年8月20日広島豪雨による土石流発生地域の地質.地質学雑誌,121巻9号,339-346.(2015年9月号掲載)→J-STAGEへ(準備中)
・広島市で発生した土石流及び斜面崩壊の発生地に関する地質情報(産総研HPへのリンク)
・広島市安佐南区周辺の地質図(産総研:シームレス地質図へのリンク)
・2014年8月20日広島における土砂災害,特に地質要因(高橋裕平:名古屋大学PhD登龍門推進室)
■平成26年7月9日に長野県南木曽町で発生した土石流の発生地に関する地質情報
・土砂災害研究情報 (産総研地質調査総合センターHPへのリンク)
・長野県南木曽町で発生した土石流の発生地に関する地質情報 (産総研地質調査総合センターHPへのリンク)
2014年8月20日広島における土砂災害,特に地質要因(2014.9.2)
平成26年8月20日に広島市安佐南区で発生した土石流の発生地に関する地質情報
・斎藤 眞ほか,2015,2014年8月20日広島豪雨による土石流発生地域の地質.地質学雑誌,121巻9号,339-346.(2015年9月号掲載)→J-STAGEへ(準備中)
・広島市で発生した土石流及び斜面崩壊の発生地に関する地質情報(産総研HPへのリンク)
・広島市安佐南区周辺の地質図(産総研:シームレス地質図へのリンク)
・2014年8月20日広島における土砂災害,特に地質要因(高橋裕平:名古屋大学PhD登龍門推進室)
*********************************************************************************************************************
2014年8月20日の未明に,広島市で局所的大雨による土砂災害が発生し,70名を超える方々の尊い人命が奪われました.ここに謹んで哀悼の意を表します.
日本地質学会では,学術団体として,地質学的な見地から,この度の土砂災害の背景・要因を学会員ならびに社会に周知する使命があると考え,災害発生地の地質に詳しい高橋裕平氏(名古屋大学PhD登龍門推進室)に記事の執筆を依頼し,快諾を得ました.ここに,高橋会員から寄稿された記事の全文を公開いたしますので,御覧下さい.
日本地質学会長 井龍康文
2014年8月20日広島における土砂災害,特に地質要因
高橋裕平(名古屋大学PhD登龍門推進室)
広島で局所的な大雨により土砂災害が発生し,多くの方がお亡くなりになりました.はじめにお悔やみ申し上げます.
今回の災害は居所的な大雨が第一義的な原因であるが,これに被害地域に特徴的な地質地形の要因が加わり,さらに自然を無視した宅地開発など人為的な要素も関与し被害が拡大した.小論ではこの地域の地質の要因について筆者の見解を述べたい.
1.広島土砂災害概要
2014年8月20日午前3時20分から40分,広島市では局地的な短時間大雨によって安佐北区可部,安佐南区八木・山本・緑井などの住宅地後背の山が崩れ,同時多発的に大規模な土石流が発生し,多くの住宅が土砂に巻き込まれた.警察や消防,それに自衛隊による夜を徹する懸命の救助活動や行方不明者の捜索活動が行われた.災害直後は引き続く断続的な雨でしばしば救助・捜索活動が中断することもあった.広島市は避難勧告を徐々に解除しているが,自宅が流失して帰れない人も多い.9月1日には災害地そばを通るJR可部線が開通した.
広島県災害対策本部が9月2日8時30分現在として発表した資料では,死者72人・行方不明者2人・重傷者8人・軽傷者36人になっている.同資料での広島県内の家屋の被害は,全壊24軒・半壊41軒・一部損壊65軒・床上浸水76軒・床下浸水208軒になっている.県有施設では可部高等学校で法面崩壊,県営緑丘住宅では1階及び2階部分に土砂が流入,敷地内の集会所が半壊している(広島県災害対策本部,2014).
2014年8月は,被災地付近では災害発生の直前の19日の時点で,平年を大きく上回る降水量が記録され,地盤の緩みが進行していた.さらに災害発生当時,広島市北西部では中国山地西部を通過した秋雨前線に南から暖かく湿った空気が流入し,積乱雲が連続的に発生したと推定されている.気象台ではこれほどの雨量は想定できなかったとしている(毎日新聞,2014a).
2.広島市の地質概略
広島市は山間部と平地部に大きく分けられる(脇田・井上,2011).広島市の山間部は数百mの標高の山塊で北東–南西方向に谷が走っている.この北東–南西方向は断層に規制される.山間部の地質の大部分は後期白亜紀花崗岩(広島花崗岩)である.代表的な岩相は石英や長石などの鉱物が数mm前後の粗粒花崗岩で,広範囲に風化が進んでマサ土となっている.山頂付近では1mm程度の細粒の花崗岩が分布する.山間部には花崗岩のほか,ジュラ紀あるいはそれ以前の堆積岩や火成岩が,花崗岩のルーフペンダントとして山地山頂付近に分布する.これらの細粒花崗岩や古期岩類は,粗粒花崗岩に比べ風化の程度は弱い.
広島市の平野部は市内を流れる太田川の扇状地堆積物と近世以降の干拓地や埋立地からなる.河川の自然争奪や人工的な付け替えも行われている.平野部と山地の境界付近の山麓に崩壊堆積物からなる緩斜面が発達することがある.
3.災害地
3.1地理・土地利用
土砂災害が起きた安佐南区や安佐北区は広島市街の北部で,広島中心部から順調なら車で20分程度,鉄道なら広島駅からJR可部線で30分程度と至便で急速に宅地開発が進んでいる.市内中心部に比べ平地部が狭くなっているため,宅地開発が山麓にまで及んでいる.
宅地化の状況を知るため,昭和57年修正測量・現地調査の2万5千分の1地形図「祇園」と最近の同地域の地形図(国土地理院,2014a)で比較した.土砂災害があった安佐南区八木から緑井にかけた地域では,昭和57年当時でも斜面(山麓)に宅地があるが,密度は少なく,田畑の記号も目立つ.最近の地形図では宅地は密となり,さらに傾斜が急な地域にも宅地が広がっている.また,谷筋に道路が作られその周りが宅地となっている.JR可部線から太田川にかけた平地部では昭和57年当時には畑が広がっていたが,最近の地形図では道路が整備されかつての畑のほとんどが宅地となっている.
3.2土砂流出
国土地理院の写真判読図(国土地理院,2014b)によると,この地域の山麓の谷筋に土砂流出があり住宅地を巻き込んで,さらにJR可部線にまで土砂が達している.同図は時事ドットコム(2014)で見ることができる.その後も国土地理院では新たな航空写真を利用するなどして判読図を更新している。
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201408/2014082200865
3.3地質
産総研地質調査総合センター(2014)に当該地域のシームレス地質図に地質単元や地名それに今回被害の大きかった地域がわかるよう加筆した地質図が掲載されている.併せて5万分の1地質図も載っている.ここではそれらに基づき解説する.
https://www.gsj.jp/hazards/landslide/20140820-hiroshima.html
それによれば,斜面崩壊の発生した安佐南区山本付近(地点①と土石流の発生した安佐南区緑井付近(地点②)は後期白亜紀の広島花崗岩の分布域で,表層が風化して真砂(マサ)になっている場合が多い.複数の土石流が発生した安佐南区八木付近(地点③)では,谷の下部は広島花崗岩だが,地形が急峻な谷の上部はジュラ紀の付加体の岩石で,広島花崗岩による接触変成作用を受け堅硬である.安佐北区可部東では根谷川沿いの土石流(地点④)は広島花崗岩の分布域で,そこから東に入ったところ(地点⑤)では,広島花崗岩と断層をはさんで東側に分布する後期白亜紀の高田流紋岩との境界部で発生している.
被害が甚大であった緑井地区と八木地区の土砂災害について,地質のいくつかの要因を5万分の1地質図(高橋,1991)で考察してみる.この地質図は四半世紀前の出版で,最近の産業技術総合研究所の地質図に比べ都市地質や地質災害の記載が十分でない.また,阪神淡路大震災以前の発行であったため,活断層の記述もわずかである.しかしながら現地調査に基づく山麓斜面堆積物の分布が示されて,さらに花崗岩について現地調査から細粒相が地形的高所に分布することまでが明快に示されている.
災害地周辺をながめると,花崗岩が風化した同じようなマサ土のところでも場所によっては土砂流出が起きていない.これは尾根付近には風化の程度が弱い熱変成作用を受けたジュラ紀堆積岩や細粒花崗岩の分布の有無で説明できる.
すなわち,土砂災害が甚大な地域(八木,緑井)は,風化の程度が弱いジュラ紀堆積岩や細粒花崗岩がマサ化した中粗粒花崗岩の上部に乗った形となっている.降雨がこの地域にあると,尾根付近では比較的堅硬な岩石が分布するため雨水が十分浸透せず,帽子の上を雨水が流れるように,山地中腹から麓に分布する風化花崗岩や斜面堆積物に雨水が流れ,同時に降っている雨水に加わることとなる.つまり雨量以上の雨水が中腹から麓に流入し土砂流出が甚大になったと考えられる.加えてこの地域の斜面の傾斜は急で,しかも宅地開発が斜面,特に谷筋にも及んでいたことで人的及び物的被害が大きくなった.広島大学海堀正博氏の報告(毎日新聞,2014b)によると流出した堆積物に硬質の堆積岩や流紋岩の岩塊が見られるという.前者は尾根付近のジュラ紀の堆積岩,後者はこの地域に分布する珪長質な岩脈等に由来すると考えられる.
4.人的要因と宅地開発規制の報道
本災害は崩れやすい地質や谷筋を造成した宅地開発が人的被害を大きくした.このことに関連して京都大学防災研究所の釜井俊孝氏は「広島市の被災地は谷筋の奥まで宅地化されている.谷筋はもともと土石流の通り道で,地盤の流動性が高い.激しい雨に加え,社会的な要因が重なり,大規模な土砂災害になってしまった.」と述べている(京都新聞,2014).
毎日新聞の防災の日の社説(毎日新聞,2014c)では,宅地開発規制の議論を提言している.危険な場所での宅地開発規制は,なかなか進まないが,政令市と東京都だけで,土砂災害の恐れのある危険箇所は2万8000カ所を超える.土砂災害警戒区域の指定は政令市によって差があり,広島市以外も札幌,仙台,名古屋各市の低さが目立つという.
5.まとめ
小論ではこの地域の地質の要素が今回の土砂災害を大きくしたであろうことを述べた.そして山裾に及ぶ宅地開発が人的・物的被害を拡大したことを加えた.
現実を振り返ると,家を購入するにあたり,多くの人は非日常的な地質災害まで考慮しない.ローンが残っていながら家屋を消失した方も多いはずだ.自然を無視した宅地開発云々の論評は被災した方々には酷である.日本では,狭い地域に人口が密集せざるを得ない事情があり,また,家を購入する際,日常の便利さを優先するであろう.今後の気象・地質災害に向けた現実に即した策は,何らかの気象災害が予想されれば早めの避難,そして地質災害にも補償を受けられる保険に加入することかもしれない.
【引用文献とサイト】
地質調査総合センター(2014)広島市で発生した土石流及び斜面崩壊の発生地に関する地質情報.2014.08.22.https://www.gsj.jp/hazards/landslide/20140820-hiroshima.html
広島県災害対策本部(2014)8月19日(火)からの大雨による被害等について(第40報).2014.9.2.http://www.bousai.pref.hiroshima.jp/hdis/info/1592/notice_1592_1.pdf
時事ドットコム(2014)土砂流出、50カ所で=航空写真を分析—国土地理院.http://www.jiji.com/jc/zc?k=201408/2014082200865
国土地理院(2014a)地理院地図(電子国土Web).(9月1日確認) http://portal.cyberjapan.jp/site/mapuse4/#zoom=5&lat=35.99989&lon=138.75&layers=BTTT
国土地理院(2014b)平成26年8月20・21日撮影斜め写真による写真判読図.2014.08.30.
京都新聞(2014)広島土砂災害,宅地開発が一因 京都・滋賀でも可能性.京都新聞ウェブ,2014.08.21. http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20140821000022
毎日新聞(2014a)広島豪雨:バックビルディング現象の可能性.毎日新聞ウェブ,2014.08.20. http://mainichi.jp/select/news/20140820k0000e040235000c.html
毎日新聞(2014b)広島土砂災害:「真砂土以外の地質でも発生」研究者指摘.毎日新聞ウェブ,2014.08.22. http://mainichi.jp/select/news/20140823k0000m040083000c.html
毎日新聞(2014c)社説:社説:防災の日 身を守る力を備えよう.毎日新聞ウェブ,2014.09.01. http://mainichi.jp/opinion/news/20140901k0000m070082000c.html
高橋裕平(1991)広島地域の地質.地域地質研究報告(5万分の1地質図幅),地質調査所,41p.
脇田浩二・井上 誠編(2011)地質と地形で見る日本のジオサイト-傾斜量図がひらく世界-.株式会社オーム社,168 p.
(2014.9.2)
2013年(平成25年)山口・島根豪雨災害の概要と調査報告
2013年(平成25年)山口・島根豪雨災害の概要と調査報告
川村喜一郎・金折裕司・坂口有人・仁田 彩・藤井美南(山口大学)・
山口大学-日本地質学会西日本支部合同調査団
はじめに
昨年10月の伊豆大島豪雨災害、そして今年8月の広島豪雨災害など,最近,記録的な豪雨による土砂災害によって人的被害が続発している.同様に,山口県でもこのような土砂災害が繰り返されてきている.記憶に新しい山口県の豪雨災害は,2009年(平成21年)中国・九州北部豪雨のときに,7月21日防府市を中心に発生した土石流災害であろう.県内では,死者17名,負傷者35名という大惨事をまねいた.
ここで紹介する2013年(平成25年)の山口・島根豪雨災害は,防府市を中心とした土石流災害発生から4年後のことであった.この豪雨災害を紹介する前に,まず, 4年前の土石流災害がどのようなものだったのか,“過去に学ぶ”という意味を込めて,簡単に振り返ることにしよう.
気象庁の報告によると,2009年7月21日は,山口県の北の海上をゆっくり南下する梅雨前線に向かって,暖かく湿った空気が流れ込み,前線の活動が活発になっていた.7月20〜21日の2日間に,防府市や下松市では300mmを超える降雨量が記録された.国土交通省砂防部の報告では200件近い土砂災害が発生したことが示されている.そのほとんどはがけ崩れであり,土石流65件,地すべり4件となっている.
大川ほか(2010)によると,土石流の源頭部は,白亜紀後期の防府花崗岩の中でも,おもに粗粒黒雲母花崗岩の分布域にあり,源頭部に発達したマサ化した花崗岩からなる厚い風化帯と土石流発生との因果関係が指摘されている.このように,2009年の土石流災害は,地質的な素因が深く関わっていることが指摘されてきており,土砂災害の原因究明に,地質学者の果たす役割は大きいであろう.
2013年の山口・島根豪雨災害の概要
2013年7月26日から8月3日にかけて,気象庁の災害時気象速報によると,日本付近に暖かく湿った空気が流れ込んだことにより,大気の状態が不安定になっていた.特に28日は,中国地方を中心に暖かく湿った空気が流れ込み,雨雲が次々と発達したため(バックビルディング現象と呼ばれている),島根県と山口県で,午前中を中心として記録的な大雨となった.
山口市阿東徳佐では,28日朝から昼前までの7時間に,ほぼ連続して時間雨量30〜60mmの降雨があり,累積雨量300mmを超える大雨となった.一方,萩市須佐では,昼前に時間雨量138.5mm(観測史上最大)となり,累積雨量で約350mmを記録した.いずれの地域でも前日には降雨がなく,短時間の記録的な降雨によって土砂災害が引き起こされた.
内閣府の防災情報によると,山口県では,土石流等56件,がけ崩れ26件が生じ,死者2名,行方不明者1名であった.国道191号と315号が土石流,がけ崩れなどによって数か所で寸断された.これによって孤立した3地域では,ヘリコプターによって287名が救助されるといった事態に至った.家屋被害は全壊22戸,半壊16戸を含め,約1000戸であった.JR山口線と山陰線において,盛り土崩壊や橋梁の流出があったが,ほぼ1年後に復旧し,平成26年8月23日に全線の運転が再開された.各地でライフラインが寸断され,山口市と萩市において,最大約3500戸が断水するとともに,電柱の倒壊や流出により停電が相次いだ.
ハザードマップの限界を感じた日
7月28日朝から降り始めた雨は,山口大学吉田キャンパスのある山口市吉田でも激しくなり,時間雨量は萩市須佐を上回り,143mmに達した.山口市の土砂災害・洪水・高潮ハザードマップ(山口市防災ハンドブック)の設定雨量は「24時間で240mm」であり,今回の豪雨では1時間で設定値の半分を超える降雨があったことになる.明らかにハザードマップのシナリオを上回る記録的な降雨であったと言える.
当然,上記ハザードマップに描かれた浸水域とは異なる浸水パタンが起きた.ハザードマップの浸水域と浸水深は,山口市の中心部を流れる主要河川の椹野川が氾濫した場合を想定して描かれている.しかし,今回の豪雨では短時間で記録的な降雨があったために,主要河川に流れ込む小河川(水路など)において氾濫が生じた.著者の一人川村の住む山口市白石の住宅地域は,ハザードマップの洪水想定では浸水するはずが無かったのだが,28日には,みるみる内に水がやってきて,最終的には膝上まで浸水した.ハザードマップは,災害に対する注意喚起という意味では重要な基礎資料となりうるが,次に起きる災害が必ずしも,ハザードマップのシナリオ通りになるとは限らないことを思い知らされた.
緊急調査の概要
28日の記録的な豪雨の翌日29日にはある程度,土砂災害や河川の氾濫などの被害情報がマスコミやインターネット,知人からの連絡などを通じて入ってきて,土砂災害の概要がみえてきた.私たちは,山口大学理学部地球圏システム科学科のスタッフとして,日本地質学会西日本支部と連携して,災害調査団をいち早く結成するべく動きだし,8月初旬には災害調査団を結成した.
その後,8月9日と13日,9月2日,9日に現地調査を行った。9月14〜16日の日本地質学会年会(仙台)において,ポスター発表で緊急調査報告した.現地調査のときには,災害復旧途上の箇所がいくつもあり,住宅に流れ込んだ土砂の後片付け等の最中であった.このよう混乱のなかで,日本地質学会の腕章やシールを貼ったヘルメットは大変役立った.
写真1 須佐トンネル付近の土石流発生地の源頭部.萩市須佐.
(拡大は画像をクリック)
写真2 表層崩壊の全貌.山口市阿東船平地区.写真左側に表層崩壊の源が,右端に崩壊物が堆積している.崩壊物の左隣の斜面は草がそのままで生えており,ほとんどダメージを受けていないことがわかる.写真左端から供給された崩壊物は少なくとも,写真中央の斜面を飛び越えて下方(右端)に移動したようである.
(拡大は画像をクリック)
写真−1と2に示す土石流の源頭部と表層崩壊はいずれも,白亜紀後期の凝灰岩類や火山岩類からなる阿武層群の分布域に発生したものである.
写真−2に示した表層崩壊では粘土化した凝灰岩が滑落面に認められ,これが地質的素因であると推測された.2009年(平成21年)の中国・九州北部豪雨災害、そして今年の広島豪雨災害などでは,土砂災害の地質的素因として,マサ化した風化花崗岩の存在が注目されているが,凝灰岩における土砂災害メカニズムについても,これらの被災地域で,さらに詳しく調べる必要があることを実感した土砂災害でもあった.
写真−1に示す土石流の源頭部には,地下水の急速な排出をうかがわせる直径数cmの「パイピングホール」が認められた.短時間の記録的な降雨によって風化帯に蓄えられた雨水がクイックサンド状態を誘発し,パイピングホールをつくって一気に噴出したことが推定される.
今後,詳細な調査を行い,土砂災害を軽減するために,地質学的知見に立った情報発信をしていきたいと思っている.
参考文献
土木学会地盤工学委員会・地盤工学会中国支部,2013,平成25年7月山口・島根豪雨災害現地調査結果報告書.土木学会中国支部,44p.
福岡浩・羽田野袈裟義・山本晴彦・宮田雄一郎・汪発武・王功輝,2010,平成21年7月中国・九州北部豪雨による防府市土砂災害.京都大学防災研究所年報,53A,85-91.
気象庁,2013,災害時気象速報:平成25年7月28日の島根県と山口県の大雨.災害時自然現象報告書,2013年第1号,気象庁,20p.
国土交通省,2009,平成21年の土砂災害.http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/jirei.html
内閣府,2013,7月26日からの大雨等による被害状況について.内閣府防災情報のページ,http://www.bousai.go.jp/updates/h25ooame07/.
大川侑里・金折裕司・今岡照喜,2012,白亜紀防府花崗岩体で発生した土石流の分布と性状.応用地質,52,6,248-255.
牛山素行,2013,平成25年7月山口.島根の豪雨による災害の特徴.自然災害科学,32,2,207-215.
山口県,2009,災害記録〜平成21年7月21日豪雨災害〜.http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a10900/bousai/20090721saigai.html
追記
本記事は,第120年学術大会(仙台大会)での緊急展示としてポスター発表された内容を元に,ニュース誌(2014年12月号,Vol. 17-12)掲載用にまとめられたものです.
川村喜一郎,仁田 彩,藤井美南,古賀 源,中嶋 新,濱田 毬,和田彩花,坂口有人,金折裕司(山口大学),日本地質学会西日本支部・山口大学合同調査団,2013,2013 年7 月28 日 山口・島根豪雨災害の調査.日本地質学会第120年学術大会講演要旨.U-1.
(2014.12.12)
2015年ネパール地震のテクトニクスとカトマンズの極軟弱地盤(2015.5.7)
2015年ネパール地震のテクトニクスとカトマンズの極軟弱地盤
京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻 酒井治孝
2015年4月24日,現地時間午前11時41分に中央ネパール西部で発生したM 7.8の地震は,人口密度の高い首都カトマンズを初め, レッサーヒマラヤの山岳地帯の住民に大きな被害をもたらした。本地震の震源は北緯28.147度,東経84.708度,震度15.0 kmであり(アメリカ地質調査所による), その余震は現在もまだ続いている。この地震による死者は日毎に増加し,5月1日現在6000名を超えているが,震源域となったゴルカ地方一帯の山間部の被害状況に関する情報がまだ届いてないので, さらに死者数,被災者数は増えるものと思われる。
本稿ではこの地震が発生したテクトニクスについて地質学的観点から解説すると同時に,本震の震源から離れたカトマンズ盆地に震災が何故集中したのかについて,カトマンズ盆地の地下地質構造の観点から考察する。
震源地域の地質構造
ヒマラヤ山脈の南斜面からガンジス平原の北縁に至る幅200kmの地帯は,インドプレートとユーラシアプレートが衝突するプレート境界に成っており,3本の主要な大断層がヒマラヤ弧に平行に走っている。ガンジス平原の北縁を走っているのがヒマラヤ前縁断層(HFT: Himalayan Frontal Thrust), レッサーヒマラヤ南麓の主境界断層(MBT: Main Boundary Thrust), そして一番北側のグレートヒマラヤ南麓の主中央断層(MCT: Main Central Thrust)である(図1&2)いずれも低角度で北に傾斜した逆断層(スラスト)である。
図1.ネパールの地質帯区分と2015年4月25日に中央ネパールで発生したM 7.8
の地震の震央の位置.(Sakai et al., 2013を改変)
図2.カトマンズを南北に横断する地質断面図に投影した,M 7.8の地震の震源,(Pandey et al., 1999を改変)
HFTからMBTまでの幅最大90 kmの地帯はシワリーク帯と呼ばれる丘陵地帯であり,ヒマラヤが侵食され,土砂が運搬・堆積した河川の堆積物から成る。MBTからMCTの間の幅約80〜120 kmの地帯はレッサーヒマラヤと呼ばれ,厚さ10 km程度の19億年前〜約1600万年前にわたる堆積岩から構成されている。レッサーヒマラヤの堆積物の上には,MCTに沿って高ヒマラヤ変成岩類が衝上しており,その一部はレッサーヒマラヤの堆積物を南北約100 kmにわたって,ほぼ水平に覆ってナップと成っている。カトマンズは丁度,北方に位置するランタンヒマラヤから南にのびるカトマンズ・ナップの中心に位置している(図1& 2)。
これら3つの断層の活動時期は北から南に向かって若くなっている。すなわち,一番北側のMCTは約2200万年前から約1000万年前に活動し,MBTは約1000万年前から現在まで活動が続いている。そして一番南のHFTは約250万年前に活動が始まったと推定されている。これら3つの断層は, 地下では1本のプレート境界断層である主ヒマラヤ断層(MHT: Main Himalayan Thrust)に収束しているものと考えられている。
今回のネパール地震の震央はMCTに伴われる巨大な断層帯,MCTゾーン(厚さ1〜3 km)の真上に位置している。その地下15 kmは丁度レッサーヒマラヤ堆積物の基底近くに相当し,主ヒマラヤ断層(MHT)の位置とほぼ一致する。従って今回の地震は,グレートヒマラヤ直下のユーラシアプレートとインドプレートの境界断層面上で破壊と滑りが生じ,上盤側のユーラシアプレートがインドプレートの上に滑り上がったものと判断される。
本地震の余震はカトマンズの北方や東方にまで広がっており,これまでに観測された余震の分布に基づき,東大地震研究所は165 km×105 kmの震源断層を推定している。また地震波のインバージョンによる解析に基づき,断層破壊が震源から東南東方向に進み,その滑りはカトマンズ盆地周辺で最大4.3mに達している。この地域は1934年に発生したM 8.0のビハール-ネパール地震(Sapkota et. al., 2013)や1988年のM 6.6のウダイプール地震(Ghimire & Kasahara, 2008)でも大きな被害を被ったが,その震源はインド大陸との衝突の最前線に位置するMBTやHFTと推定されており,本地震とは異なる。ネパールでは1994年以降,フランスやアメリカの支援のもと地質鉱山局に国立地震センターが開設され,微小地震が観測されるようになった。そのデータによると本地震発生以前にも,本震の震央周辺とその東の地域では活発な微小地震が発生していることが報告されている(Pandey et al., 1999)。
カトマンズ盆地の脆弱な地下地質
カトマンズ盆地は標高1500 mから2800 mの山々に取り囲まれた,南北約30 km, 東西約25 kmの山間盆地であり,盆地底の平均標高は1340 mである。カトマンズ盆地の地下地質は, 主に地表地質調査とボーリング調査,重力探査の結果,三層構造をしていることが分かっている。下部はレッサーヒマラヤの現地性の変堆積岩類から成り,その上をMCTに沿ってグレートヒマラヤから100 km余り南に前進してきたカトマンズ・ナップが覆っている(図2)。両者は複向斜構造を成し,その主軸はカトマンズ盆地の南に位置するフルチョウキ山を通っている。基盤を成すこの2つの地層の上には, 約100万年前から現在に至る期間に,河川と湖で堆積した地層が厚く堆積している。
このカトマンズ盆地を埋めて堆積した地層はカトマンズ盆地層群と呼ばれ,次の三層からなる:下部の網状河川堆積物,中部の泥質湖成堆積物,上部の湖成デルタと河川の堆積物。その全層厚は最大600 mに達するが,何れも半固結〜未固結である。軟弱な地盤として特に注意すべきは中部の湖成層であり,盆地中心部では平均層厚は約200 mに達するが,側方に薄層化し盆地縁辺部では尖滅し,デルタや河川の堆積物に移化する。この湖成層の主体を成すのが現地でカリマティ(Kalimati)と呼ばれる,黒色で有機質なシルトまじりの粘土層である。100万年前から1.1万年前まで存在した古カトマンズ湖の周囲に繁茂していた植物片と湖に生息していた珪藻遺骸が,北側の花崗岩質の岩石の風化によってできた粘土層と混じった特異な地層である。
私達の研究グループは,中央ヒマラヤ地域のインドモンスーンの変動史を復原する目的で,カリマティ層を貫通する学術ボーリングを2000〜2003年に行なった(Sakai et al. 2001)。その時,最初の試掘をトリブバン大学トリチャンドラ・キャンパスの時計台の下で行なった。この時計台は1934年のビハール-ネパール地震の時に崩壊し,建て直されたものである。掘削して驚いたのは,上部40〜50 mの地層の脆弱さであった。最上部の砂層は10〜15 mで,粗粒な花崗岩質な粒子からなり含水率が高く,未固結状態であった(図3)。その下には深度40〜45 mまで軟弱なカリマティ層が広がっていた。含水率が高い上にメタンを主成分とする天然ガスを含み,掘削されたコアが地上に上がってきてしばらくは,小さな泡が発生していた。コアは簡単に自重で崩壊してしまう程度の強度しかなかった。深度45 m以深になるとコアは次第に固結し,100 m以深では半固結状になった。
時計台の位置は,今回多くの建造物が倒壊したカトマンズの旧王宮とその周囲の市街地の直ぐ北東に位置しており,地下構造に変わりはないものと思われる。地下10〜20 mに広く分布する最上部の砂層とカリマティ粘土層の境界付近には,地下水を貯留した帯水層が分布しており,カトマンズのあちこちで自噴し,昔からドウンゲ・ダーラ(石の水道)として利用されてきた。この地層境界付近の脆弱な地層が,地震の揺れを増幅し,多くの建物を倒壊させた原因の一つであることは間違いない。
図3. カトマンズ市街地の中心部に位置するトリブバン大学トリチャンドラ・キャンパスの時計台横のボーリング調査によって判明した軟弱な地下地質.(Sakai et al.,2001を改変)
今後の防災事業に対する提言
私達が2000年に実施した古カトマンズ湖掘削プロジェクトによって,首都があるカトマンズ盆地の地下地質は脆弱であり,大きな建造物を建てる際には深くまで基礎工事をする必要があることが分かった。そこで,この事実をネパール国民に広く知ってもらい,注意喚起を促すために,ネパールの新聞やテレビでも報道してもらった。テレビ放送の翌日には,建設省の元事務次官と言う人物が私達のキャンプを訪問し,軟弱なコアを見て私達の主張に納得されたようであった。しかし,その後ネパールでは内戦状態が続くなど国情が不安定で,そんな警告にはお構いなしに,高層ビルが建てられてきた。まずは政府が建築の基準を見直すことから始める必要があるだろう。
またこれまで地下構造について地震波探査が行なわれていないので,上部の半固結〜未固結堆積物の深度分布や基盤高度の情報が極めて乏しい。人口密集地なので爆破地震探査をすることは難しいだろうが,バイブロサイズなどの人工震源を使った地下構造探査が必要である。また地震動に対する地層の挙動を知るためには,コアの物性について,採取したその場で測定したデータが必要である。また,野外調査に基づくカトマンズ盆地の地質図や液状化予想図,および盆地内を走っている活断層についての詳細な調査が必要であろう。
文献
Ghimire, S. and Kasahara, M., 2008, Source process of the Ms=6.6, Udayapur
earthquake of Nepal-India border and its tectonic implication. J. Asian Earth Sci., 31,
128-138.
Pandey, M, R., Tandukar, R.P., Avouac, J.P and Heritier Th., 1999, Seismotectonics of
the Nepal Himalaya from a local seismic network. J. Asian Earth Sci., 17, 703-712.
Sakai, H., Fujii, R., Kuwahara, Y., Upreti, B. N. and Shrestha, S., 2001, Core drilling of
the basin-fill sediments in the Kathmandu Valley for paleoclimatic study: preliminary
results. J. Nepal Geol. Soc., 25, Special Issue, 9-18.
Sakai, H., 2001, Stratigraphic division and sedimentary facies of the Kthmandu Baisn
Group, central Nepal. J. Nepal Geol. Soc., 25, Special Issue, 19-32.
Sapkota, S.N., Bollinger, L., Klinger, Y., Tapponnier, P., Gaudemer, Y. and Tiwari, D.,
2012, Primary surface ruptures of the great Himalayan earthquakes in 1934 and 1225.
Nature Geoscience, 6, 71-76.
東大地震研究所の情報が掲載されたホームページのURL は以下の通り:
www.eri.u-tokyo.ac.jp/
(2015.5.7掲載.2015.5.15一部修正)
知床半島羅臼町で海岸線沿い隆起と地すべり調査報告(2015.5.20)
知床半島羅臼町で発生した地すべりの現地調査報告
2015年4月24日に北海道の知床半島羅臼町で海岸線沿いの海底部分が隆起しているのが地元住民に目撃され,大変な話題となりました.海底隆起の原因は,地すべりに伴う現象であることが現地を調査しました大学や行政機関によって示されましたが,地すべりと海底隆起のメカニズムについては未だに研究者間で議論が続いています.このたび,北海道立総合研究機構地質研究所からこの現象についての速報が出されましたのお知らせします.
(北見工業大学 山崎新太郎)
◆ 平成27年4月24日に発生した羅臼幌萌海岸の地すべり調査報告(速報)
(北海道立総合研究機構地質研究所のサイトへ)
http://www.hro.or.jp/list/environmental/research/gsh/information/topics/topics20150522.html
(2015.5.20掲載)
口永良部島火山の噴火に関する情報(2015.5/29)
口永良部島火山の噴火に関する情報
産業技術総合研究所地質調査総合センターより関連情報が発表されました(2015.5/29).
平成28年(2016年)熊本地震:関連情報
平成28年(2016年)熊本地震に関する情報
産業技術総合研究所地質調査総合センターより関連情報が発表されました(2016/4/15)
熊本地震における地震断層露頭の発見 大橋聖和,田村友識(山口大学)(2016/4/26)
国立大学法人山口大学大学院創成科学研究科および一般社団法人日本地質学会は2016年4月22日〜4月24 日の期間,熊本県上益城郡益城町および阿蘇郡西原村において布田川断層の地表地質調査を行い,平成28 年熊本地震の際に活動したものと考えられる計3つの断層露頭を発見しました.
[報告]阿蘇カルデラ北西部に出現した亀裂群の成因解明(地表地震断層か否か)(2016/05/19)
向吉秀樹1,内田嗣人1,大久雅貴2,佐野達也2
(1: 島根大学大学院総合理工学研究科,2: 島根大学総合理工学部)
調査期間:2016年4月30日〜5月2日(3日間)
2016年10月8日阿蘇山中岳の噴火に関する情報
2016年10月8日阿蘇山中岳の噴火に関する情報
・産業技術総合研究所地質調査総合センターより関連情報が発表されました(2016/10/11)
博多駅前陥没事故現場付近の地質に関する情報
博多駅前陥没事故現場付近の地質に関する情報
「博多駅前陥没事故現場付近の地質に関する情報」
・産業技術総合研究所地質調査総合センターより関連情報が発表されました(2016/11/11)
平成29年7月5日-6日の豪雨による大分県日田市小野で発生した斜面崩壊の地質学的背景
平成29年7月5日-6日の豪雨による大分県日田市小野で発生した斜面崩壊の地質学的背景
「平成29年7月5日-6日の豪雨による大分県日田市小野で発生した斜面崩壊の地質学的背景」
・産業技術総合研究所地質調査総合センターより関連情報が発表されました。
https://www.gsj.jp/hazards/landslide/20170705-oita.html
(2017年7月7日掲載)
2018年1月23日草津白根火山の噴火に関する情報
2018年1月23日草津白根火山の噴火に関する情報
株式会社パスコのウェブサイト「災害撮影[事業活動と社会貢献]」に「2018年1月草津白根山火山活動モニタリング」が掲載されました。(2018.1.26) NEW
合成開口レーダー(SAR)衛星「TerraSAR-X」による撮像で噴火口が確認できます。
産業技術総合研究所のウェブサイトに「草津白根火山の噴火に関する情報」が掲載されました。(2018.1.24) NEW
2018年3月新燃岳の噴火に関する情報
2018年3月新燃岳の噴火に関する情報
● 株式会社パスコは空間情報事業者として人工衛星や航空機などを用いて災害時の状況把握のために緊急撮影を行っています。「2018年3月 霧島山系・新燃岳 火山活動モニタリング」の情報を掲載しています。http://www.pasco.co.jp/disaster_info/20180308/ NEW
2018年3月7日撮影の衛星画像(合成開口レーダー(SAR)衛星「TerraSAR-X」では、火口内の溶岩ドームの形状が、その表面構造も含めて確認できます。
2018年3月6日撮影の衛星画像(光学衛星「SPOT 7」、「ASNARO-1」)では、火口周辺の降灰範囲が確認できます。
2018年3月1日撮影の衛星画像(光学衛星「SPOT」、「ASNARO-1」)では、噴火当初の東〜東南東方向へ流れる噴煙と、その方向に狭い範囲での降灰が認められます。
● 2018/3/2 中馬辰紀氏 撮影
平成30年7月 台風第7号及び前線等に伴う大雨に関わる災害
平成30年7月 台風第7号及び前線等に伴う大雨に関わる災害
平成30年7月豪雨による斜面災害地の地質(産総研 地質調査総合センターのサイト)
広島県安芸郡熊野町川角5丁目の斜面崩壊/愛媛県宇和島市吉田町の斜面崩壊
平成30年北海道胆振東部地震
(1)株式会社パスコ:
平成30年北海道胆振東部地震について航空調査の様子
(2)産総研: 地震・津波研究情報トップ
平成30年北海道胆振東部地震の関連情報(新規)
海陸シームレス地質情報集S-4「石狩低地帯南部沿岸域」の紹介(新規)
厚真町付近の地質(新規)
札幌市清田区の地質(新規)
(3)北海道立総合研究機構地質研究所:速報・対応状況
北海道胆振東部地震の余震(2019年2月21日発生)による被害調査 NEW
「平成30年北海道胆振東部地震」への地質研究所の対応について
令和2年7月豪雨災害関する情報
令和2年7月豪雨災害に関する情報
▶ 産総研地質調査総合センター
2020年7月4日に豪雨災害が発生した球磨川流域の地形・地質
▶ 防災科学技術研究所
令和2年7月3日からの大雨に関する防災科研クライシスレスポンスサイト
2020年7月6日〜7日九州北部における浸水について(速報)NEW
令和2年7月豪雨により福岡県および熊本県で発生した洪水災害の調査報告NEW
▶ 熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター
2020年7月豪雨に伴う熊本県南部における災害調査速報 小国町,大分県日田市周辺を含む(第3報)NEW
2020年7月豪雨に伴う熊本県南部における災害調査速報(第2報)NEW
2020年7月豪雨に伴う熊本県南部における災害調査速報(第1報)
▶ 防災学術連携体
「令和2年7月豪雨の緊急集会」(各発表の動画が公開されています)
日時:7月15日(水)11:20-13:00 (日本地質学会からの話題提供あり)
公開:防災学術連携体 ホームページ http://janet-dr.com/
▶ 国土地理院
令和2年7月豪雨に関する情報 NEW
令和3年2月 福島県沖を震源とする地震
令和3年2月 福島県沖を震源とする地震
▶ 地震調査研究推進本部事務局
2021年2月13日福島県沖の地震に関する情報
▶ (速報)2月13日夜の福島県沖を震源とするM7.3の地震:地震発生時・直後の仙台市内の様子(画像あり) 辻森 樹・高嶋礼詩
▶ 産業技術総合研究所
2021年2月13日23時07分の地震による福島県二本松市沢松倉の崩壊地の地質
2021年2月13日23時07分の地震による福島県相馬市内の崩壊地の地質
▶ 国際航業株式会社・株式会社パスコ
令和3年2月 福島県沖を震源とする地震 現地斜め写真(2/14撮影)
▶ アジア航測株式会社
2021年2月13日発生の福島県沖地震被害状況(2/14撮影)
▶ 防災学術連携体
令和3年2月13日の福島県沖の地震について 特設ページ
令和3年10月7日に千葉県北西部で発生した地震の関連情報
▶︎産業技術総合研究所
令和3年(2021年)10月7日に千葉県北西部で発生した地震の関連情報
▶︎地震調査研究推進本部
2021 年 10 月7日千葉県北西部の地震の評価
(速報)2月13日夜の福島県沖を震源とするM7.3の地震:地震発生時・直後の仙台市内の様子(辻森 樹・高嶋礼詩)
(速報)2月13日夜の福島県沖を震源とするM7.3の地震:地震発生時・直後の仙台市内の様子
辻森 樹・高嶋礼詩(東北大学)
2021年2月13日午後11時8分ごろ,福島県沖(北緯37.73度,東経141.8度)でマグニチュード7.3(推定)の地震が発生した.震源の深さは約55 kmで,東北地方を中心に広範囲で揺れを観測し(仙台市青葉区は震度5強),気象庁は翌日14日に会見を開き,10年前に起きた東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の余震と説明した.西北西-東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型の地震で,日本海溝に沈み込む太平洋プレートの「スラブ内地震」と考えられる(気象庁 報道発表資料「令和3年2月13日23時08分頃の福島県沖の地震について」2月14日1時10分).https://www.jma.go.jp/jma/press/2102/14a/kaisetsu202102140110.pdf
以下,辻森と高嶋の個別リポート
地震発生時,私(辻森)はちょうど自宅(大学宿舎)で眠りについた直後で,長い揺れで目が覚めた. 2018年の学術大会(札幌大会)を襲った北海道胆振東部地震の時は,札幌市内のホテルで飛び起きたが,今回はジワジワ目が覚めた感がある.ベッドのなかから「まだ揺れてる,,,」とツイートできたほど,揺れは比較的長く続いた.「大きな縦揺れが10秒あまり」(NHK NEWS WEB「震度6弱 NHK仙台局 大きな縦揺れが10秒あまり」2021年2月13日 23時20分)とのことだが,大きな揺れのタイミングではまだ夢のなかにいたようで,長い揺れが収まり,寝室からでてから,地震後の部屋の惨状に今回の地震がかなり大きなものであったことを知った.まず,テレビでニュースを見ようとしたが,テレビが消えていた(テレビを載せていた棚が壁から移動し,その隙間にテレビが落下).食卓テーブルの上に置いていた物のほとんどが横滑りして床に散らかっていた.台所の食器棚2つも20 cmほど横に移動し,シンクは棚からの落下物で埋まっていた.さらに,壁に飾っていた絵画5つのうち4つが落下,机や棚の上に設置していた電子楽器類も床に転がっていた.幸いにも停電・断水にはならなかった.
地震発生当時の夜は午後10時頃までは複数の学生が大学(川内キャンパス)で実験をしていたが(私もその頃までは大学に居た),幸い,地震発生前には皆帰宅していた.メールなどで留学生を含めて複数の学生の安否が確認できた.しかし,実験室が心配だったので,遠方に住む娘に安否を電話で伝えながら着替えて,折りたたみ式ヘルメットとアマチュア無線機をショルダーバックに入れて,徒歩2分の距離の大学に向かった.地下鉄の運転停止で,地下鉄駅(仙台地下鉄東西線川内駅)前のバス停には遅い時間の割に人が目立った.大学に向かう途中,地震後,タクシーで大学に駆けつけ,実験装置の状態を確認し終えて下宿に帰る途中だった博士課程の学生とすれ違い,実験装置の無事の第一報を受けた.大学に到着すると,学生の部屋などは,床に書類や文房具が散乱した状態であったが,水漏れや発火がないことを確認できたので,部局長にメールで状況を伝え,帰宅した.帰宅後は,自宅の床の片付けを先延ばしし,モバイルバッテリーの充電の他,水筒に水の確保と浴槽に水をためてから就寝した.Webのニュースで地震の状況を調べたい気持ちもあったが,疲れていたので余震も全く気にならず朝まで熟睡した.
図1. 地震によるコンクリートのひび割れの様子
(東北大学川内キャンパス,撮影:辻森).
翌朝,大学に着くと,夜には気が付かなかった建物及びその周辺のひび割れが目立った(図1).学生の部屋では想像以上に床に落下したマグカップが割れていたようで割れ物のゴミが集められていた.週末にも関わらず,既に学生らが被害状況を撮影した後,自主的に片付けを終えていて感心した.幸い私の居室は部屋の隅の花瓶が1つと,ティーパック受けの小皿が1枚割れただけで,壁に新しくできたひび割れを除いて大きな被害はなかった.地震対策として,キャスター付きの机・テーブルは固定するのが正しいのだが,私の居室では2つの机を日常的に動かしていて固定していない.今回,居室のなかで非固定の机・テーブル2つが大きく水平移動していたものの,机上に不安定に積み上がった書類も小物もパソコン用の液晶モニターも崩れずにそのままの状態にあったのは驚いた.私は10年前の東日本大震災を経験しておらず,今回の地震は札幌大会で経験した北海道胆振東部地震と同等の地震の経験になった.地震は避けることのできない自然現象という意識はあるものの,実際に大きな地震が起こってみると改めて日常的な地震への備えが不十分であることを率直に反省した.
(2021年2月14日 辻森 樹)
《2月14日-15日未明》地震が起きた時,私(高嶋)はちょうど就寝直後で,大きな揺れと家のきしむ音で飛び起きた.家族は全員2階で寝ていたが,2階は本が数冊落ちたくらいでとくに被害はなかったので,1階の様子を見るために下に降りた.東日本大震災後にできた家のため,本棚や食器棚などの収納家具は全て立て付け・ドア付きが幸いし,何も落下物は無かった.とくに収納家具のドアに緩くゴムをかけていたことで,落下をかなり防げたと思われる.しかし息子の飼育している水生生物の水槽付近が大惨事を引き起こしていた.まず居間の海水魚水槽周辺と金魚水槽の周辺は揺れによって海水・淡水がそれぞれこぼれて床が水浸し.特に海水魚水槽付近では延長コードにも海水が侵入していたため,まずは海水除去に時間を取られ,40分ほど拭き掃除をすることとなった.続いて,玄関へ移動.ここにも,3つの淡水魚水槽から水が吹きこぼれ,水浸しになっていた.ここには4つの水槽があり,それぞれの住人は,ナマズx2,二ホンウナギ,メダカx10,ギラファノコギリクワガタであったが,いずれも地震の前後を通して全く平常通りで,地震予知に全く役に立たないと痛感しつつ,さらなる拭き掃除に時間を費やした.1時過ぎに家がひとまず落ち着いたので,大学からの安否情報確認メールに返信し,標本館と研究室に車で向かった.私の居室・実験室は震災後に一時的に建てられた2階建てのプレハブ(その後恒久施設として残ることとなった)にあり,公式名称も「仮設校舎A」という,まるで実名報道不可の様な名前の建物である.しかし,この建物はコンクリのべた基礎で,比較的丈夫な作りだったため,幸い,実験室のビーカー等のガラス機器類が一部落下により破損しただけで,棚が外れたりゆがんだりすることもなく大きな被害はなかった.最も心配していた薬品棚も,薬品を全てケースに収納し,さらに耐震固定をしていたため無事だった.東日本大震災の際は,薬品棚が倒れて,取り出しする面が床を向いていたために,薬品を取り出すこともままならなかったが,今回,きちんと固定していたことが功を奏したのかもしれない.大量のサンプルも落下措置をしていたため無事だったし,居室も本が数冊落ちていただけで済んだ.続いて自然史標本館の展示室・収蔵室をみたが,やはりここも落下物や破損はほとんど確認されなかった.展示品の吊り下げた浮遊性有孔虫化石の石膏模型が絡まっていたのと(図2),収蔵庫の数10cmサイズのアンモナイトが1つ落下して割れた程度で済んだようである.当館は高層建築でないことと,安全衛生委員会の定期巡視の際に様々な指摘を受けており,その都度,落下防止等の措置を講じていたことも,被害の回避につながったものと思われる.
図2.東北大学自然史標本館の浮遊性有孔虫化石の石膏模型展示.
絡まっているが破損は無し
(東北大学青葉山キャンパス,撮影:郄嶋).
図3.東北大学理学部地学棟5階,井龍教授室.
多くの書物が落下
(東北大学青葉山キャンパス,撮影:井龍康文).
図4.東北大学理学部地学棟6階,鈴木紀毅准教授室.
つっかえ棒により転倒は免れたが,書籍の多くが落下
(東北大学青葉山キャンパス,撮影:郄嶋).
《2月15日》翌朝,さらに被害状況確認を行った.6階建ての地学棟は高層階ほど被害が大きく,井龍教授の部屋(5階)や長濱教授・鈴木准教授の部屋(6階)はコンピューターや書籍,観葉植物などの落下が激しかった模様で(図3,4),同じフロア―の学生実習室では顕微鏡5台が落下により破損した.学生部屋のパソコン・モニター等も多くが落下もしくは転倒していた.また,理学部の建物の多くは,エレベーター部分と居室・実験室部分が短い渡り廊下でつながった構造であるが,この連結部が大きく破損していた(図5).これは10年前の東日本大震災でも同様であった.機械類の被害の実態が分かるまではしばらくかかりそうである.我々の博物館が標本置き場にしている化学棟6〜8階はさらに被害が大きく,本棚も固定していたが,壁ごと外れて倒れていたり,中のものが飛び出していた(図6,7).転落防止措置を行っていたものは比較的軽微で済んでいたが,それでも本の落下を完全に止めることができなかった(図8).化学棟の6階以上の高層階は東日本大震災後に居室としての使用が禁止されていたのは,判断として正解だったと思われる.
図5.東北大学理学部化学棟6階
エレベーター/居室の接合部分が大きく破損
(東北大学青葉山キャンパス,撮影:郄嶋).
図6.東北大学理学部化学棟6階
博物館標本・文献保管スペース1.
(東北大学青葉山キャンパス,撮影:吉田武義).
図7.東北大学理学部化学棟6階
博物館標本・文献保管スペース2.
(東北大学青葉山キャンパス,撮影:郄嶋).
図8.東北大学理学部化学棟6階,
落下防止措置済み博物館標本・文献保管スペース
(東北大学青葉山キャンパス,撮影:郄嶋).
(2021年2月15日 高嶋礼詩)
2021.02.15掲載,02.16写真追加
2021年8月13日福徳岡ノ場の噴火
福徳岡ノ場の噴火
国立研究開発法人海洋研究開発機構 海域地震火山部門
上席研究員 田村 芳彦
2021年8月13日の午前6時20分頃、気象衛星ひまわりが福徳岡ノ場からの噴煙を観測した。噴火開始時刻はウエイク島のハイドロフォンに記録されているデータから午前5時50分と推測されている。噴煙高度は16㎞に達していた。海上保安庁が8月16日に航空機による観測を実施したときは、既に噴火は終了していたが、直径約1kmの東西にかっこ型をした二つの新島が確認された。そして、国土地理院によると、新島の東側の陸地は9月5日にはすでに海没していた。今回の噴火は3日間と極めて短期で、その噴出物は1986年の噴火による軽石と類似している。この短期間に噴出して漂流した大量の軽石が南西諸島に漂着して、被害を起こし、注目を集めている。さらに、この軽石は黒潮にのって伊豆諸島にも到着しつつある。
福徳岡ノ場とはどんな火山なのか
日本の火山はプレートの沈み込み帯に形成されている。海溝に沿って海洋プレートが沈み込むと、沈み込まれるプレートの上に、弧状の火山の列ができる。日本の南では、伊豆小笠原海溝に沿って、太平洋プレートがフィリピン海プレートに沈み込むことによって、東京から南へ、伊豆大島、三宅島、八丈島と続いていく伊豆小笠原弧が形成されている。福徳岡ノ場は、伊豆小笠原弧の火山の一つである(図1)。近年噴火を続けている西之島からさらに335 km南、東京からは約1,300 kmの位置にある。硫黄島の南南東56㎞、南硫黄島の北北東5㎞の位置にある海底火山である。海上保安庁の海域火山データベースに、福徳岡ノ場のこれまでの噴火活動や、海洋情報部が収集してきた海底地形、地質、地震波探査、地磁気および重力などの調査結果が示されている
(https://www1.kaiho.mlit.go.jp/GIJUTSUKOKUSAI/kaiikiDB/kaiyo24-2.htm)。
図1 東京から南に連なる伊豆小笠原弧の火山島と海底火山。伊豆大島、三宅島、八丈島のように北部は火山島が多く、南部は海底火山が多い。西之島は2013年からの噴火活動で注目されている。これらの海域火山(火山島と海底火山)は伊豆小笠原海溝から、太平洋プレートがフィリピン海プレートに沈み込むことによって形成された沈み込み帯の火山である。(※画像をクリックすると大きな画像が閲覧できます)
南硫黄島の北の海域には、北福徳カルデラと呼ばれる16km×10kmの海底カルデラがある(図2)。カルデラとは、巨大噴火で大量のマグマが噴き出した後に空洞ができて、そこが陥没してできた地形のことだ。南硫黄島は北福徳カルデラのカルデラ壁の一部を形成しており、福徳岡ノ場はこの北福徳カルデラ内の中央火口丘と考えられている。北福徳カルデラの海面下2 km(海底下1.5㎞)以深には地震波の低速・高減衰域が存在し、地殻を構成する岩石の溶融体が存在する可能性が指摘されていた(西澤他、2002)。カルデラの内部は低地震波速度、低密度および低磁化の火山砕屑物が埋めており、カルデラの基盤はすり鉢状の形状を示し、その下には低地震波速度・高地震波速度減衰域および高密度の岩石の溶融体(マグマ)が存在し、この熱により基盤の一部が熱消磁している(小野寺他、2003)。
このカルデラの中央火口丘である福徳岡ノ場は、過去にも噴火記録があり、最近では1986年に新島を形成するような噴火を起こした。しかし、その新島は波で削られ2ヶ月で海没している。さらに、2005年、2010年にも軽石を噴出する爆発的噴火をおこしている。2010年噴火後の山頂部は直径1.5 km×1 kmの北東-南西方向に伸びた楕円形をしており、水深約30mで平坦面をなしていた(図2)。そして、頂部の北側には直径約200 mの複数の火口が600 mに渡り連なっていた(伊藤ほか、2011)。これらの火口が今回の噴火にも使用されたかどうかは不明であるが、直径約1kmの東西にかっこ型をした新島が、もともと浅い福徳岡ノ場の山頂部平坦面に形成されたのは間違いないだろう。
図2 福徳岡ノ場周辺海域の地形図(伊藤ほか、2011)。福徳岡ノ場は南硫黄島と連続した火山体の一部と考えられる。南硫黄島の北には北福徳カルデラがあり、福徳岡ノ場はこのカルデラ内の中央火口丘である。(海上保安庁ホームページhttps://www1.kaiho.mlit.go.jp/GIJUTSUKOKUSAI/kaiikiDB/map/24.png)(※画像をクリックすると大きな画像が閲覧できます)
軽石から分かること
今回の噴火で大量の軽石が噴出して漂流した。軽石は爆発的な噴火で噴出したマグマが、急冷されて固まったものである。地下のマグマには大量のガスが溶け込んでいるが、噴火に伴って、マグマからほとんどのガスが放出される。溶岩噴出のようにゆっくりとした噴火をすると、ガスが抜けて緻密な岩石になるが、今回のような高い噴煙を形成する爆発的な噴火をすると、ガスが膨張しながらマグマが固結するため、空隙の多いスカスカの岩石(軽石)となる(図3)。空隙のため全体の密度は水よりも軽くなり、海面を漂流する。水がしみこんで空隙を満たすと沈降するが、空隙の形が複雑なため、長い期間漂流を続ける。例えば、比重2.5のマグマが発泡しても、ガスと液体が分離すると、ほぼ比重は変わらない溶岩として固まる。一方、マグマ中に含まれるガスが発泡して抜けきることができないと、マグマの体積はガスと共に膨張していき、軽石のようなスカスカの岩石となる。単純に計算すると、ガスの膨張により体積がほぼ5倍となると比重が0.5となり、今回のように水に浮く漂流軽石となる。写真で見るように軽石の中はほとんど空隙である。地下にあったマグマが、膨張して大量の軽石となったということができる。
図3 気象庁啓風丸で採取されJAMSTECで分析した軽石の一つ(サンプル番号18)を分割した写真。表面は噴火、漂流により円摩されているが、内部は発泡し、ガラスが引き延ばされて繊維状になったり、発泡してスポンジ状になったりしている。表面上の粒状に見えるのは、単斜輝石を主体とする鉱物の集合体。(※画像をクリックすると大きな画像が閲覧できます)
2021年8月22日に、気象庁の海洋気象観測船「啓風丸」は北緯25度30.3分、東経138度53.3分付近(福徳岡ノ場から約300km西北西の海上)において漂流する軽石を採取した。JAMSTECでもその中のいくつかの分析をおこなった(図3)。分析結果は2021年10月20日に行われた日本火山学会秋季大会で、「福徳岡ノ場から2021年8月に噴火した軽石(速報)」として発表された。軽石は、これまでの噴火と同様のトラカイトという組成をもつ珪長質な火山岩であった。トラカイトは、アルカリ成分が多く(Na2O酸化ナトリウムとK2O酸化カリウムの総量が10 %前後)、シリカ(SiO2重量%)成分が60-70 %の火山岩である。アルカリ成分が少なくなると通常の安山岩となる。西之島の噴火は安山岩であるのに対して、福徳岡ノ場や硫黄島のマグマはアルカリ成分が多い特徴的な組成をもつ。その違いの原因はよくわかっていないが、沈み込むプレートの不均一性に由来するものかもしれない。噴出した軽石には組成的なバリエーションがほとんどなく、一様にトラカイトの組成を示している。しかし、鉱物に含まれている成分(メルト包有物)を分析した結果、玄武岩マグマの組成を示し、今回の爆発的噴火にはマントルの深いところ(30㎞以深)から来た玄武岩マグマが関与している可能性が示唆された。玄武岩マグマの地殻内のマグマ溜まりへの貫入が、爆発的な噴火を引き起こした可能性がある。今回のように地表に噴出していない玄武岩マグマが、黒幕として噴火に関与した例はいくつか議論されている。玄武岩マグマが熱源として地殻を融解し、安山岩マグマの噴出に関与した大山火山(Tamura et al., 2003)の例、伊豆弧において海底カルデラの成因に玄武岩マグマが関与している例(Shukuno et al., 2006; Tamura et al., 2009)などである。沈み込み帯のマントル深部(地下30㎞以上)では、高温・高圧状態で、玄武岩マグマが生成する。この玄武岩マグマが上昇してきて地殻内にとどまると、大量の熱を発生する。この熱は潜熱と呼ばれ、マグマが結晶化するときの熱である。この玄武岩マグマの潜熱が、安山岩の地殻を溶かす、または固結した安山岩をリモービライズする熱源となる。過去に地下で固まったトラカイトは、新たに上昇してきた玄武岩マグマの潜熱により再融解して、大量の軽石を生成した可能性がある。今後の噴火予測・減災に資するためにも、福徳岡ノ場の軽石を形成したトラカイトマグマの成因を追求していきたい。
引用文献
海上保安庁(2021)海域火山データベース、https://www1.kaiho.mlit.go.jp/GIJUTSUKOKUSAI/kaiikiDB/kaiyo24-2.htm
伊藤弘志、加藤正治、高橋昌紀、斉藤昭則(2011)伊豆-小笠原弧、福徳岡ノ場火山における2010年噴火後の火山地形 海洋情報部研究報告 第47号 平成23年3月18日、9-13。
西澤あずさ、小野智三、坂本平治、松本良裕、大谷康夫(2002)海底火山「福徳岡ノ場」における海底地震観測、水路部研究報告、38、101-123。
小野寺健英、加藤剛、瀬尾徳常(2003)重力・地磁気異常から推定される福徳岡ノ場付近の地殻構造 海洋情報部研究報告第39号平成15年3月28日、23-31。
Shukuno, H., Tamura, Y., Tani, K., Chang, Q., Suzuki, T. & Fiske, R. S. (2006). Origin of silicic magmas and the compositional gap at Sumisu submarine caldera, Izu-Bonin arc, Japan. Journal of Volcanology and Geothermal Research 156, 187-216.
Tamura, Y., Yuhara, M., Ishii, T., Irino, N. & Shukuno, H. (2003). Andesites and dacites from Daisen volcano, Japan: partial-to-total remelting of an andesite magma body. Journal of Petrology 44, 2243-2260.
Tamura, Y., Gill, J. B., Tollstrup, D., Kawabata, H., Shukuno, H., Chang, Q., Miyazaki, T., Takahashi, T., Hirahara, Y., Kodaira, S., Ishizuka, O., Suzuki, T., Kido, Y., Fiske, R. S. & Tatsumi, Y. (2009). Silicic magmas in the Izu-Bonin oceanic arc and implications for crustal evolution. Journal of Petrology 50, 685-723.
(2021年11月22日掲載)
令和4年8月3日からの東北・北陸地方豪雨災害
令和4年8月3日からの東北・北陸地方豪雨災害
▶ アジア航測株式会社・朝日航洋株式会社 共同撮影
2022(令和4)年8月3日からの大雨による被害状況(アジア航測株式会社のサイト)
2022(令和4)年8月3日からの大雨による被害状況(朝日航洋株式会社のサイト)
▶ 国際航業株式会社
令和4年8月豪雨:新潟県・山形県・福島県の斜め撮影(2022年8月5・6日撮影)
防災情報提供サービス 無償版Bois
▶ 株式会社パスコ
2022年8月3日からの大雨災害:8月6日撮影の航空写真(新潟県・山形県・福島県)を掲載しました
2022(令和4)年9月 台風14号災害関連
2022(令和4)年9月 台風14号災害関連
▶ 株式会社パスコ災害緊急撮影
9月20日,21日撮影航空写真(宮崎県・熊本県)ほか
▶ 国際航業株式会社災害調査活動
9月20−22日撮影(宮崎県,熊本県,大分県)
令和5年7月九州地方豪雨災害
令和5年7月 九州地方豪雨災害の情報
2023.7.18掲載
令和5年7月 九州各地における豪雨災害(福岡県・熊本県)の航空写真:国際航業株式会社(株式会社パスコとの共同撮影)https://www.kkc.co.jp/category/disaster/ [1]
2023年7月 前線による大雨災害:株式会社パスコ(国際航業との共同撮影および自社撮影)https://corp.pasco.co.jp/disaster/heavy-rain/20230704.html [2]
九州での記録的大雨被害状況(2023年7月):アジア航測株式会社https://www.ajiko.co.jp/news_detail/1385 [3]
令和5年7月7日からの大雨による被害状況等の航空写真(九州北部):朝日航洋株式会社https://www.aeroasahi.co.jp/news/591/ [4]
令和5年(2023年)7月の大雨災害(九州北部・熊本県)斜め写真撮影:中日本航空株式会社https://www.nnk.co.jp/research/disaster/ [5]
令和6年能登半島地震の関連情報
「令和6年能登半島地震」に関する会長談話
2024年1月1日午後4時ごろに発生しました「令和6年能登半島地震」により犠牲になられた方々に心から哀悼の意を捧げ,ご冥福をお祈りします.同時に,未だ安否不明の方々の一刻も早い救出と,被災者の皆様におかれましては,一日も早く日常生活を取り戻されることをお祈りいたします.
地震・津波に伴う災害の予測や減災に向けた取り組みを進める上で,当該地域の地質の成り立ちを理解することは必要不可欠です.日本地質学会は,会員による地質学的研究をサポートし,最新の学術的知見を活用した自然災害の予測と防災・減災方策を社会と連携して追求する所存です.
今後,令和6年能登半島地震に関する調査報告や研究成果については,会員から報告があり次第,学会公式ウェブサイト*などから随時発信してまいります.
一般社団法人日本地質学会
会長 岡田 誠
*日本地質学会地質災害関連情報サイト:http://geosociety.jp/hazard/
※「地質の日」オンライン一般講演会 令和6年能登半島地震による地殻変動と地盤災害 2024/5/12(日)YouTube
令和6年能登半島地震の関連情報
地震調査研究推進本部地震調査委員会
令和6年能登半島地震の評価(令和6年2月9日) 2.21 new
令和6年能登半島地震の評価(令和6年1月15日) 1.16
令和6年能登半島地震の評価(令和6年1月2日)
防災学術連携体
令和6年能登半島地震情報
令和6年能登半島地震・7ヶ月報告会 7月30日(火)▷こちらから
令和6年能登半島地震・3ヶ月報告会 3月25日(月)▷ YouTubeライブ配信
令和6年能登半島地震・1ヶ月報告会 1月31日(水)▷ YouTube(公開中)▷プログラム・各発表資料はこちらから※日本地質学会からの発表「能登半島周辺海域の活断層」岡村行信(産総研)
緊急報告会「令和6年能登半島地震の概要とメカニズム」1月19日(金)17:30-19:00 YouTube(一般公開・申込不要)
産総研地質調査総合センター:令和6年(2024年)能登半島地震の関連情報
第八報 2024年能登半島地震に伴う斜面崩壊の崩壊箇所と地形・地質との関係(予察) 2.19 new
第七報 能登半島地震で発生した能登半島北東部の斜面崩壊発生地域の地質概説 1.30
第六報 2024年能登半島地震の緊急調査報告(津波の浸水状況調査) 1.30
第五報 能登半島北部沿岸域の構造図と令和6年(2024年)能登半島地震の余震分布 1.16
第四報 2024年能登半島地震の緊急調査報告(海岸の隆起調査)1.12
第三報 AIによる自動検測に基づく2024年能登半島地震の余震分布
第二報 長期的な隆起を示す海成段丘と2024年能登半島地震の地殻変動
第一報 地震発生域周辺の活断層
能登半島北部周辺に刻まれた日本海発達の歴史 −20万分の1地質図幅「輪島」(第2版)を刊行−(2019年)1.9追加
S-1.海陸シームレス地質情報集「能登半島北部沿岸域」(2010(平成22)年2月26日出版)1.9追加
東京大学地震研究所
【研究速報】令和6年能登半島地震
国土地理院
令和6年(2024年)能登半島地震に関する情報
防災科学技術研究所
クロスビュー:令和6年能登半島地震
科学技術振興機構(JST)
J-GLOBALでの地震関連の収録情報公開 ※J-GLOBALは、JSTが運営する、無料で研究者、文献、特許などの科学技術・医学薬学等の 二次情報を閲覧できる検索サービスです。 検索結果からJST内外の一次情報等へ案内します。1.30
国際航業株式会社
令和6年能登半島地震
株式会社パスコ
令和6年能登半島地震
アジア航測株式会社
令和6年能登半島地震被害状況(2024年1月)
朝日航洋株式会社
令和6年能登半島地震による被害状況等の航空写真
中日本航空株式会社
斜め写真撮影/航空レーザ計測 1.9
金沢大学
令和6年能登半島地震 緊急調査 被災写真2−2(能登町布浦中心)フォトグラメトリ用途(調査日:2024年1月12日) 1.15 ※(注意:複数ページあり.写真一番下の矢印から次のページにいける)
令和6年能登半島地震 緊急調査 被災写真2−1(珠洲市飯田港ー上戸(重点),見附島周辺,能登町松波,能登町布浦ー赤崎(重点)(調査日:2024年1月12日) 1.15 ※(注意:複数ページあり.写真一番下の矢印から次のページにいける)
令和6年能登半島地震 緊急調査写真 1.15更新 撮影場所:石川県河北郡内灘町/撮影:ロバート・ジェンキンズ(金沢大学理工学域地球社会基盤学類)・佐藤 圭(金沢大学国際基幹教育院GS教育系) (撮影者より)共有した写真は調査研究などにご自由にお使いください.写真はNikon Z6IIで撮影しました.
弘前大学
能登町における令和6年能登半島地震により発生した津波の痕跡調査報告(第1報)岡田理奈(理工学研究科 東北日本地盤災害研究講座)ほか 2.8
技術者教育
技術者教育(JABEEとCPD)
技術者教育(JABEEとCPD)
MENU(項目をクリックすると該当箇所に遷移します)
1.委員会について
設置の背景
活動内容
委員会構成
最近の活動
キャリアビジョン誌
2.JABEEについて
組織
JABEE認定
関連の分野
3.CPDについて
技術士
CPD
ジオ・ネット
4.学会行事のCPD
1.地質技術者教育委員会について
委員会設置の背景についてはこちら
日本列島はプレートの沈み込み帯に形成された島弧として、ユーラシア大陸の東縁に位置しています。そのため、変化に富んだ地形や四季折々の美しい自然の変化を楽しむことができます。一方、地震や火山といった災害や台風や集中豪雨といった自然災害が頻繁に発生する場所でもあります。私たちは豊かな自然の恵みを受ける代償として、自然災害に対応していかなければならない運命にあるとも言えます。
自然災害に効果的に対応するためには、日本の自然のしくみを科学的に理解し、災害の現場で的確な判断と技術的な対応ができる専門の技術者が必要不可欠となります。この技術者を養成することは,日本の大学等の高等教育機関にとって重要なミッションであるとともに急務となっています。
高等教育機関における国際的に通用する技術者教育を展開するプログラムの審査・認定をめざして、1999年に一般社団法人日本技術者教育認定機構(JABEE)が設立されました。その認定分野の一つに「地球・資源及びそのエンジニアリング分野」があり、これが自然災害に対応する専門技術者の養成プログラムに対応しています。現在9つの大学でプログラムが認定され、プログラム修了生は,コンサルタントや建設・土木関係企業、行政等における技術者として活躍し、特に自然災害への対応に大きく貢献しています。
一方、専門技術者となってからも専門知識や技術に対する研鑚を続ける必要があります。とくに技術士ではContinuing Professional Development(CPD)と呼ばれる継続教育を受けることが義務付けられています。そのためには、学会などが主催する講習会や研修会がその場として活用されています。
日本地質学会では、地質技術者の高等教育のためのJABEEを支援する「JABEE委員会」と地質技術者のCPDを支援する「技術者継続教育委員会」をそれぞれ設置し、活動してきました。しかしながら、両委員会の活動は不可分であるため、両委員会を合併させた「地質技術者教育委員会」に発展させ、2019年からは活動をさらに活発化させています。
2021年3月
地質技術者教育委員会
委員長 天野一男
[委員長あいさつ]
天野一男前委員長の後任として、地質技術者教育委員会委員長を拝命致しました日本大学の竹内真司です。当委員会では、学生等の地質系企業への専門就職や地質系企業に就職された専門技術者の皆さんの継続研さん(CPD)をサポートするための様々な活動を行っています。特に学生等のサポートとしては、毎年の学術大会における「学生のための地質系業界説明会」の開催や、卒業後の進路のひとつである地質コンサルタントなどの専門技術分野の企業を紹介した「地質系若者のためのキャリアビジョン誌」を発行しています。また、社会の要求に応える技術者教育プログラムを実践するJABEE認定校や地質系企業における現状と課題などをテーマとした「JABEEオンラインシンポジウム」を毎年3月に開催しています。さらには、全国的に地学離れが懸念される現状を踏まえ、高等学校等を対象としたJABEE地球・資源分野の紹介ポスターの発行と配布を行っています。 自然災害が多発する災害大国日本において防災・減災を担う地質系技術者の継続的な育成は必要不可です。当委員会では、上記の活動等を通して、地質系技術者の育成と継続的教育をサポートしています。多くの産官学の皆様の本委員会イベントへの参加をお待ちしています。今後とも当委員会の活動へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
2024年7月
地質技術者教育委員会委員長 竹内 真司
(2)活動内容
主な活動内容は以下のとおりです。
地質技術者の教育に関する情報の発信
地質技術者の教育に関する企画の立案
JABEE「地球・資源及び関連のエンジニアリング分野」認定プログラムの審査協力
地球・資源分野運営委員会活動への参画
CPDに関する土質・地質技術者生涯学習協議会など関連団体の活動への参画
ジオ・スクーリングネットをベースとした会員の継続教育(CPD)支援
(3)委員会構成
委員構成は、学会委員会組織を参照ください。
(4)最近(2021年3月以降)の活動状況
>過去の委員会活動はこちら
1.委員会開催
委員会開催実績はこちら
2025年度第1回委員会4月8日
2024年度第5回委員会12月19日
2024年度第4回委員会10月28日
2024年度第3回委員会8月28日
2024年度第2回委員会7月11日
2024年度第1回委員会4月22日
2023年度第3回委員会1月11日
2023年度第2回委員会11月7日
2023年度第1回委員会8月2日
2022年度第4回委員会12月25日
2022年度第3回委員会 10月27日
2022年度第2回委員会 5月27日
2022年度第1回委員会 4月21日
2021年度第7回委員会 2月14日
2021年度第6回委員会 12月8日
2021年度第5回委員会 10月28日
2021年度第4回委員会 8月17日
2021年度第3回委員会 7月26日
2021年度第2回委員会 6月1日
2021年度第1回委員会 4月2日
2.関連する委員会などへの出席
出席実績はこちら
2024年度 地球・資源分野JABEE委員会 第3回委員会 2025年3月25日
2024年度 土質・地質技術者生涯学習協議会 2025年3月24日
2024年度 地球・資源分野JABEE委員会 第2回委員会 2025年1月8日
2024年度 土質・地質技術者生涯学習協議会 幹事会 2024年7月3日
2024年度 地球・資源分野JABEE委員会 第1回委員会 2024年6月27日
JABEE設立25周年記念大会 2024年5月8日
2023年度 地球・資源分野JABEE委員会 第3回委員会 2024年3月25日
2023年度 土質・地質技術者生涯学習協議会 2024年3月14日
2023年度 地球・資源分野JABEE委員会 第2回委員会 2024年1月19日
2023年度 土質・地質技術者生涯学習協議会臨時会議 2023年9月14日
2022年度 土質・地質技術者生涯学習協議会 2023年3月14日
2023年度 地球・資源分野JABEE委員会 第1回委員会 2023年6月27日
2022年度 地球・資源分野JABEE委員会 第4回委員会 2023年3月29日
2022年度 地球・資源分野JABEE委員会 第3回委員会 2023年1月13日
2022年度 地球・資源分野JABEE委員会 第2回委員会 2022年10月21日
2022年度 地球・資源分野JABEE委員会 第1回委員会 2022年4月19日
2021年度 土質・地質技術者生涯学習協議会 2022年3月15日
2021年度 JABEE地球・資源分野運営委員会 2022年3月15日
2021年度 JABEE地球・資源分野運営委員会 2022年1月31日
2021年度 JABEE地球・資源分野運営委員会 2021年12月23日
2021年度 JABEE地球・資源分野運営委員会 2021年6月29日
2020年度 JABEE地球・資源分野運営委員会 2021年3月31日
2020年度 土質・地質技術者生涯学習協議会 2021年3月16日
3. JABEE関連(シンポジウムなど)
2025年版ポスター
new 高校生へのJABEE普及ポスター作製・発送 2025年7月中旬 1,687箇所の高等学校および関連する高等専門学校にJABEE地球・資源分野を紹介するポスターを発送 ポスターPDFのDLは「こちら」
第5回JABEEオンラインシンポジウム『高等学校での地学教育と大学での専門教育との連携〜地球科学の中等教育から高等教育にどのように繋げるか〜』 共催:地学教育委員会 2025年3月2日 ※YouTube公開中
当学会が運営参加している地球・資源分野JABEE委員会が、分野の教育機関における教育実態などについて「地球・資源分野JABEE認定プログラム情報交換会議」を2024年11月25日に開催し、当委員会委員も関係者として参加しました。会議の状況は「こちら」
高校生へのJABEE普及ポスター作製・発送 2024年7月中旬 1,600を超える全国の高等学校および関連する高等専門学校にJABEE地球・資源分野を紹介するポスターを発送 ポスターPDFのDLは「こちら」
第4回JABEEオンラインシンポジウム『大学縮小危機のなかで、社会の要求にどのように応えるか 〜JABEEを活用した技術者の育成と輩出〜』2024年3月3日【開催報告】 ※YouTube公開中
第3回JABEEオンラインシンポジウム『大学ー企業の架け橋教育 ユニークな実例紹介』2023年3月5日 ※YouTube公開中
高校生へのJABEE普及ポスター作製・発送 2022年9月21日 1,200を超える全国の高等学校および関連する高等専門学校にJABEE地球・資源分野を紹介するポスターを発送 ポスターPDFのDLは「こちら」
第2回JABEEオンラインシンポジウム『昔と違う イマドキのフィールド教育』2022年3月6日 YouTube公開中/開催報告掲載
高校生へのJABEE普及ポスター作製・発送 2021年7月20日 800を超える全国の高等学校および関連する高等専門学校にJABEE地球・資源分野を紹介するポスターを発送 ポスターPDFのDLはこちら
JABEEオンラインシンポジウム(WEB 2021年3月7日)※YouTube公開中
4.地質系業界説明会など
「2023年度 地質系若手人材動向調査報告」2025年2月28日 資料は「こちら」(News誌3月号vol.28, no.3 p.11-14掲載) なお、調査対象大学や調査結果一覧は会員ページ(ログインはこちら)をご覧ください。
「2024年度学生のための地質系業界説明会」はこちら
□ 対面説明会の様子(写真):2024年9月9日 山形大学にて
□ オンライン説明会の様子(写真):2024年9月13日Zoomにて
□ 開催報告は「こちら」(準備中)
「2022年度 地質系若手人材動向調査報告」2024年2月8日 資料は「こちら」なお、調査対象大学や調査結果一覧は会員ページ(ログインはこちら)をご覧ください。
「2023年度学生のための地質系業界説明会」を開催:参加企業の一覧と参加企業の紹介資料は「こちら」
□ 対面説明会の様子(写真):2023年9月18日 京都大学にて
□ オンライン説明会の様子(写真):2023年9月22日Zoomにて
□ 開催報告は「こちら」
「2021年度 地質系若手人材動向調査報告」を作成 2022年11月29日 資料は「こちら」なお、調査対象大学や調査結果一覧は会員ページ(ログインはこちら)をご覧ください。
「2022年度学生のための地質系業界説明会」を開催:参加企業の一覧と参加企業の紹介資料は「こちら」
□ 対面説明会:2022年9月5日(月)早稲田大学にて 開催状況は「こちら」
□ オンライン説明会:2022年9月16日(金)Zoomにて 開催状況は「こちら」
□ 開催報告は「こちら」
「名古屋大会におけるWEBを活用する業界研究サポートサービス〜地質系企業・団体へのオンライン訪問〜」開催:参加した地質系企業・団体の紹介資料は「こちら」
□ 実施報告(参加学生、企業・団体へのアンケート結果を含む)はこちら
5.CPD関連
土質・地質技術者生涯学習協議会 「新しいCPDの登録区分・重み係数表のためのweb」を更新 2023年6月10日
土質・地質技術者生涯学習協議会 「CPDの登録区分・重み係数表」を更新 2023年3月31日
「技術士(CPD認定)」にかかわる解説を作成 2022年11月30日 資料は「こちら」
(5)「地質系若者のためのキャリアビジョン誌」
地質系の学部生・院生が、将来の進路のひとつである地質コンサルタントなどの専門技術分野の業態を理解してもらうため、2020年度および2021年度に広報委員会と地質技術者教育委員会が協力して同誌を刊行しました。ご協力いただいた企業は2020年度が25社、2021年度は73社であり、これら多くの情報を全国の40を超える地質系大学などに送付しました。
企業と大学の橋渡しのお手伝いを日本地質学会が行うものであり、今後さらに推進するつもりです。
地質系若者のためのキャリアビジョン誌2025 原稿募集のお知らせ
本年も全国の48の大学・機関に配布いたします.
配布:2026年1月下旬
配布先:全国大学の地質系学科等44大学48機関の学生・院生 2,200名
協賛金:3万円(税込)
原稿規格: A4縦、PDF形式、20MB以内、塗り足しは対応しておりません。
原稿締切: 2025年12月19日(金)
掲載企業数 : 131社(2024年度全国区・地方区のべ数)以上の見込み
そのほか: 会社の特徴、仕事の魅力、やりがいなどキャリア教育に資するものを記してください。政府の就活ルールにより、1月刊行の弊誌には採用人数、給与、福利厚生など具体的すぎる求人情報はご遠慮下さい。本誌刊行後に見本誌,請求書を送付いたします。
■ 申込はここから
バックナンバー
2024年版(171MB) フルカラー139p,131社掲載 全国の地質系大学に発送
2023年版(37MB) フルカラー113p,99社掲載 全国の地質系大学に発送
2022年版(175MB) フルカラー101p,91社掲載 48大学 2020部配布
2021年版(273MB) フルカラー92p,73社掲載
2020年版(18.5MB) フルカラー28p,25社掲載
2.JABEEについて
日本技術者教育認定機構(JABEE)(https://jabee.org/)
地球・資源分野JABEE委員会(https://www.geojabee.jp/)
(1)組織
JABEEとは、 Japan Accreditation Board for Engineering Educationの略称で、一般社団法人日本技術者教育認定機構という非政府系組織のことです。JABEEは、1999年度に設立され、2001年度から技術者を育成する教育プログラムを審査・認定してきました。2024年度までの認定プログラムの累計は、海外のプログラムを除き174教育機関の529プログラムであり、認定プログラムの修了生は累計で約37万人に達しています。
(2)JABEE認定
JABEEでは、技術者を育成する教育プログラムを「技術者に必要な知識と能力」「社会の要求水準」などの観点から認定しています。
JABEEの認定基準は、技術者教育認定の世界的枠組みであるワシントン協定などの考えに準拠しているため、認定プログラムの技術者教育は国際的に同等であると認められ、認定プログラムの修了者は、世界に通用する教育を受けた技術者であると言えます。
JABEEの認定には、以下の特徴があります。
同じ専門分野の審査チームによる審査を通じて、プログラム自身による教育の質保証と改善を応援します。
認定基準は、科学技術の専門知識、デザイン能力、コミュニケーション能力、チームワーク力、技術者倫理など技術者に求められる国際的な要件に沿ったものです。
認定プログラムの修了者は、国家資格である技術士の第一次試験が免除されます。
JABEEの2024 年度認定審査サマリーレポート(2025年4月1日 https://jabee.org/doc/summary2024.pdf)によれば、2024年度の技術士第二次試験全体の合格者に対する修了者の割合は20.8%となっており、昨年度の19.6%から増加しています。さらに年代別で見ると、20代の44%、30代の40%、40代の8%(40歳以上の修了者はまだ極めて少数のため、合格者はほとんどいません)が修了者となっています。合格者の平均年齢は全体で42.1歳であったのに対し、修了者は33.5歳でした。また、通常の大学卒業年齢で修習技術者となった後に技術士第二次試験を受験できる最年少(26歳)の合格者は全体で40名ですが、そのうちの23名(58%)は修了者でした。以上のように、JABEEの認定が若い技術士を生み出すための推進力の1つとなっていることが分かります。
(3)地球・資源及び関連のエンジニアリング分野
JABEE認定プログラムのエンジニアリング系学士課程・修士課程での教育機関には16の専門分野があります。日本地質学会が関係する分野は、「地球・資源及び関連のエンジニアリング分野」といいます。
この分野は、一般社団法人資源・素材学会、一般公益法人日本地下水学会、一般社団法人日本地質学会および一般社団法人日本応用地質学会の4学会により構成される「地球・資源分野JABEE委員会(HPはこちら)」が運営しています。
「地球・資源及び関連のエンジニアリング分野」の認定プログラムの累計は12であり、2024年4月現在では以下の9プログラムが運用されています。なお、掲載順は、運用年度の早い順(同年度は五十音順)です。
島根大学総合理工学部地球資源環境学科(2003年度運用開始)
東京都立大学都市環境学部都市環境学科地理環境コース(2003年度運用開始)
日本大学文理学部地球科学科地球環境学プログラム(2003年度運用開始)
北海道大学工学部環境社会工学科資源循環システムコース(2003年度運用開始)
山口大学理学部地球圏システム科学科地域環境科学コース(2004年度運用開始)
茨城大学理学部理学科地球環境科学コース地球科学技術者養成プログラム(2006年度運用開始)
千葉大学理学部地球科学科(2006年度運用開始)
新潟大学理学部理学科地質科学プログラム地質エンジニアリングコース(2006年度運用開始)
富山大学 都市デザイン学部 地球システム科学科(2021年度運用開始)
3.CPDについて
詳しくは、日本技術士会のホームぺージ(https://www.engineer.or.jp/)をご覧ください。
(1)技術士
1957年に、科学技術に関する技術的専門知識と高等の応用能力及び豊富な実務経験を有し、公益を確保するため、高い技術者倫理を備えた優れた技術者の育成を図るため、文部科学省所管の認定制度として技術士法が制定されました。
技術士とは、技術士法により認定された技術者(Professional Engineer)のことです。技術士には、「専門的学識」「問題解決」「マネジメント」「評価」「コミュニケーション」「リーダーシップ」「技術者倫理」各々の項目において最低限備えるべき資質能力(コンピテンシー)が定められています。
(2)CPD
CPD(Continuing Professional Development)とは、技術者の継続教育を意味し、日本技術士会では、技術士CPD(継続研鑚)と呼んでいます。技術士においては、2001年4月1日に施行された技術士法改正に伴い、海外の技術者資格に比べて明確ではなかった、資格を得た後の継続教育が義務づけられるようになりました。
技術士CPDは、CPDの実施形態、CPDの時間重みを考慮したCPD時間によって評価されます。その時間数を登録して年間に必要な継続教育を受けた証明を行うことは継続的な資質向上に努めていることを示すことになります。
(3)ジオ・スクーリングネット
ジオ・スクーリングネット(https://www.geo-schooling.jp/)は、土質・地質技術者の生涯にわたる学習記録を支援するためのWEBシステムのことで、日本地質学会が加盟している「土質・地質技術者生涯学習協議会(事務局 全国地質調査業協会連合会)」が運用しています。
●CPDの実施形態と時間重み係数
「自己学習管理」で登録可能なCPDの内容は,土質・地質技術者の技術力(知識・経験)につながるものを対象とするほかは,特別な条件・制限は設けられていません。CPDの登録区分や時間重み係数は,GEO-Netの規定に従います.
CPDの登録区分・重み係数表(2025年4月修正版)
CPD重み係数表の注意事項
●CPD証明書
登録したCPDについて,「CPD証明書」を発行することができます。証明書の発行では,(1)CPDの登録期間,(2)CPDの登録形態について,独自に設定することが可能です。
4.学会行事のCPD登録などについて
日本地質学会では,学術大会と大会に伴う巡検の他,ショートコースや各種講演会・シンポジウム,支部主催のイベント等の参加者及び講師・案内者に対してCPDを発行し,地質技術者の継続教育を支援します。CPDの重み付けは,原則としてGEO-Netの規定に従います。
●CPD参加証明書
イベント参加者のうち,CPD取得希望者には「CPD参加証明書」を発行します。「CPD参加証明書」は,参加者が保管するための半券と,日本地質学会が保存するための半券で構成されています。参加者用の半券は各自で保管し,必要に応じて関係機関に提出してください。
(注1)CPDを付与するイベントは専門的な内容のイベントとし,一部の一般向けのイベント(例えば,ジオ散歩等)の参加者に対してはCPD参加証明書を発行しません。
(注2)Youtube Liveのような参加が確認できない形態のイベントの参加者に対してもCPD参加証明書を発行しません。なお、この場合自己学習として登録することはできます。詳しくは「CPDの実施形態と時間重み係数」をご覧ください。
●学会行事を企画する場合の手続き
CPDを発行する学会主催の各種行事を企画する場合,GEO-NetにプログラムのID登録を行います.本部,支部,専門部会,研究委員会などで行事の企画内容が決まり次第,事前に「CPDイベント登録申請フォーム」に記入,または同様の内容をメールにて事務局にお知らせください.折り返し,「CPD参加証明書」の書式をお送りします.
イベント開催時には,CPD取得希望者に「CPD参加証明書」を配布し,半券(学会控え)を回収して事務局へお送りください.
「CPDイベント登録申請フォーム」のDLはこちらから(Excel形式)
プレスリリース(2015年)
プレスリリース(2015年)
ジオパークのユネスコ正式事業化決定に関して
発表形態:資料配付(11月19日)
発表先:文部科学記者会・科学新聞社
■ 配布資料:全文はこちら
日本地質学会第122年学術大会(長野大会)
発表形態:資料配付(9月3日)
発表先:文部科学記者会・長野県庁会見場・科学新聞社
記事解禁日時:設定なし
■ 配布資料:本文(PDF:24.7MB)
理科得点調整および地学関連科目に関して,大学入試センターに申し入れ提出
平成27年1月に実施されました大学入試センター試験の理科の得点調整および地学関連科目の内容について受験生の立場にたった申し入れ書を(独)大学入試センター理事長に提出いたしましたので,お知らせいたします.
要旨:
地学関連科目の平均点が他分野より低かった.特に「地学」は40.91点と著しく低く,「物理」との間に20点以上もの開きがあったが,得点調整はなされなかった.一部に偏った設問や,複雑な出題・解答形式があった.今回の試験問題を検証し,今後は偏り無く,理解力と考察力を問い,平均点が著しく低くならないよう努めて頂きたい.受験者数が1万人未満であっても得点調整できる方策を早急に検討して頂きたい.
発表形態:資料配付(4月16日)
発表先:文部科学省記者会
■ 配布資料:頭書き(PDF) / 本文(PDF)
次期学習指導要領改訂に関する要望書を文科大臣に提出
次期学習指導要領改訂を前に,将来の日本を背負って立つ高校生の立場にたった要望書を文部科学大臣に提出いたしましたので,お知らせいたします
要旨:
○ 高校理科の基礎4科目の必修化による,自然科学全般の学習。
○ 前改訂により地学関連科目の履修者が増加した点は評価。
○ 「地学基礎」における地球環境・自然災害と人間との関わる内容の継続。
○ 「地学基礎」に野外調査,地質図,土壌・土と地質災害について追加。
○ 自然災害に関する教訓を「科学と人間生活」に追加。
○ 「科学と人間生活」に,地震・火山活動の発生機構としてのプレートテクトニクス理論の追加。
発表形態:資料配布(4月2日)
発表先:文部科学記者会
記事解禁日時:設定無し
■ 配布資料:本文(PDF)
地学の知識を減災のソフトパワーに―東日本大震災4年目を迎えて―
東日本大震災から早くも4年目を迎えようとしています。あのような被害を二度と起こさせないためにも、地質学会として標記の声明を発表(プレスリリース)いたしました.地質学の知識が、防災・減災に実際に役立つことを学会としては願ってやみません.
発表形態:資料配布(3月2日)
発表先:文部科学記者会
記事解禁日時:設定無し
■ 配布資料:本文(PDF)
プレスリリース(2007年)
日本地質学会第114年学術大会関連プレスリリース(9/10)
■ 件名:日本で初めての天然ダイアモンド発見(PDF)
内容:
日本で初めて、天然に産するダイアモンドが見つかったことを報告します。名古屋大学の水上知行博士(日本学術振興会特別研究員)は、愛媛県での露頭岩石中に天然ダイアモンドが含まれていることを発見しました。
日本地質学会第114年学術大会関連プレスリリース(8/24)
■ 概要説明資料(PDF)
(資料1、資料2−1、資料2−2、資料2−3、資料3−1、資料3−2)
内容:
1) 日本地質学会第114年学術大会を下記の日程で、北海道大学(札幌)にて開催します。
開催日:2007年9月9日(日)〜11日(火)
場所:北海道大学札幌キャンパス、高等教育機能開発総合センター
札幌市北区北17条西8丁目
http://www.hokudai.ac.jp/bureau/gaiyou/2006/sapporo.html
学術大会ホームページ:http://www.ep.sci.hokudai.ac.jp/~mmgc/GSJ-Sapporo2007/
学術大会を取材希望の方は、事前(学会事務局もしくは実行委員会)、もしくは当日(会場受付)申し出てください。
2)日本地質学会は新潟県中越沖地震発生直後から、関係機関との調整のうえ、地質学の専門家による現地調査を支援して参りました。新潟大学、信州大学、金沢大学、山口大学などの調査結果をポスター発表します。
3)緊急パネルディスカッション
「我が国の防災立地に対する地球科学からの提言」—平成19年新潟県中越沖地震にあたってー
主催:日本地質学会理事会、同構造地質研究部会
日時:9月10日、18時〜21時
場所:学術大会N1会場(北海道大学札幌キャンパス、高等教育機能開発総合センター)
趣旨:この度の新潟県中越沖地震により、地質学が活断層・震源断層問題に対する本格的かつ明示的な取組みを緊急にはじめなければいけないことが浮き彫りにされました。具体的には、なによりも第1に、地震動の評価やシミュレーションの基礎データとなる活断層・震源断層の構造全体を把握する研究に拍車をかけることが必要です。第2に、事業者からも規制当局からも独立な立場で原発防災立地の問題点について指摘し、必要な提言を行うことが喫緊の課題です。今回は,新潟県中越沖地震に関わる地球科学的事実をパネラーから提示して頂きながら、地質学会としての新たな一歩を踏み出すものです。
プログラム等については資料1をご覧下さい。
4)特筆すべき個人(団体)学術発表
第114年学術大会で発表予定の特筆すべき研究成果をご紹介します。
(1) 「北海道東部,厚岸町床潭沼コアに認められた1843 年大津波および3層の先史巨大津波痕跡」(重野 他;資料2−1)
※北海道東部太平洋岸において、7−8世紀まで遡れる津波記録を湖の堆積物記録から初めて明らかにした。当該地域の地震繰り返し記録を編纂する上で、きわめて重要なデータを提供している。
(2) 「過去3,000年間における沖縄海域の海面水温変化 —海底洞窟科学入門—」(北村 他;資料2−2)
※沖縄海域の過去3000年間の海水表面温度の推移を、海底洞窟の堆積物の研究から初めて明らかにし、温暖化の開始時期や、珊瑚の発達環境などに関する新見地を得た。現在の珊瑚の白化問題にも関係する、重要な基礎データを提供している。
(3) 「アンモノイドの縫合線形状における量的形質の系統性」(生形;資料2−3)
※アンモナイトの縫合線に、隠された進化の歴史を読み取る事ができる事を、数値的に明らかにした。
5)特別シンポジウム開催
13件の特別シンポジウムを個人講演とは別に開催します。内容については、学術大会のホームページ(http://www.ep.sci.hokudai.ac.jp/~mmgc/GSJ-Sapporo2007/)をご覧下さい。
(1) 海底地滑り(地滑り学会 共催)
(2) 海洋地殻・マントルの“その場研究”の進展と今後の展望:21世紀モホール計画の実現を目指して
(3) 地震探査から見た日本列島の地殻構造
(4) 大規模カルデラ火山—構造・噴火—堆積プロセス・長期予測
(5) プレート収束境界における岩石の沈み込み・上昇テクトニクス:造山帯(変成帯)形成過程研究の新展開
(6) 地質学の社会教育・普及へ研究者に求められるもの
(7) 内陸地震の震源下限深度における岩石—流体相互作用:地質時代のブライトレイヤーから読み解く地殻内流体の挙動
(8) 最終間氷期の環境変動—日本列島陸域と周辺海域の比較と統合—
(9) 遺跡形成における地質現象(北海道考古学会・低湿地遺跡研究会 共催)
(10) 地球温暖化は悪いのか?
(11) 沖積層研究の新展開—地質学と土質工学・地震防災との連携—(第四紀学会 共催)
(12) 地質環境の将来予測と地層処分:予測科学としての地質学
(13) 温室期の気候変動
6)教育・普及行事
(1) 地質情報展2007北海道—探検!熱くゆたかなぼくらの大地—(資料3−1)
日時:9月7日(金)—9日(日)、9:00〜17:00(入場無料)
場所:北海道大学クラーク会館、およびJR札幌駅西コンコース
主催:産業技術総合研究所地質調査総合センター、北海道立地質研究所、日本地質学会
内容:北海道にまつわる地質情報をわかりやすく展示、紹介し、小さなお子さんにも楽しく地学を学んでもらう体験学習コーナーなどを開催します。
連絡先:産業技術総合研究所地質調査総合センター(谷田部・吉田;Tel. 029-861-3754, e-mail: g07event@m.aist.go.jp)
http://www.gsj.jp/Info/event/2007/johoten_2007/ にて広報中
(2) 市民講演会「地質遺産の活用でまちおこしージオパークの試みー」
日時:9月9日(日)、13:00〜15:00(入場無料)
場所:北海道大学札幌キャンパス理学部5号館大講義室
主催:札幌大会実行委員会、ジオパーク設立推進委員会
内容:地質遺産の保全とその教育・普及・観光への利用が地域の振興と活性化につながるという理念に基づき、北海道の自然を地質遺産として活用していく意義などを考えていきます。
(3) 小さなEarth Scientistのつどいー第5回 小・中・高校生徒「地学研究」発表会—(資料3−2)
日時:9月9日(日)、9:00〜16:00
場所:学術大会ポスター発表会場
主催:日本地質学会
共催:北海道教育委員会、札幌市教育委員会
内容:地学教育の普及と振興を目的に、学校で行われている地学研究の成果発表を行います。北海道内の各地から7校、遠く四国の香川県、兵庫県、三重県などを含む道外11校、小中高合わせて18校、22テーマで創意あふれる研究発表が行われる予定です。
(4) 北海道Geo-Week2007 (資料3−3)
http://www.ep.sci.hokudai.ac.jp/~mmgc/GSJ-Sapporo2007/geoweek2007.htm にて広報中
地質学会札幌大会の周辺日程で、地質関連の行事が連続して予定されています。「ジオ」を研究・教育や活動の対象としている地質学関連の学会や協会など11団体が、9月に札幌市などを会場に、大会やシンポジウムなどを連続して開催します。
9/2(日) :ジオ・フェスティバル in Sapporo
9/3(月)-4(火) :地すべり・応用地質 現地見学会
9/6(木)-7(金) :全地連 技術e-フォーラム
9/7(金)-9(日) :地質情報展2007北海道
9/8(土)-14(金) :日本地質学会第114年学術大会・地質見学旅行・市民講演会
9/12(水)-14(金):第15回粘土科学討論会・見学会
連絡先
日本地質学会
〒101−0032
東京都千代田区岩本町2−8−15
電話:03−5823−1150
Fax:03−5823−1156
e-mail:main@geosociety.jp
ホームページ:http://www.geosociety.jp
広報委員会 担当理事:倉本真一
日本地質学会第114年年会実行委員会
北海道大学・理学院・自然史科学専攻・地球惑星システム科学講座 気付
〒060-0810 札幌市北区北10条西8丁目
TEL 011-706-4636 FAX 011-746-0394(講座事務室)
e-mail:torutake@mail.sci.hokudai.ac.jp
実行委員会事務局長 竹下 徹
地質災害調査
地質災害Q&A
プレスリリース(2008年)
プレスリリース(2008年)
日本地質学会第115 年学術大会について(9/12)
1) 中国 四川大地震、岩手・宮城内陸地震緊急現地調査報告について
2) 市民講演会「大地の成り立ちと人々の生活・歴史男鹿半島・大潟村・豊川油田をジオパークに」
3) 特筆すべき学術発表
・日本最古の地層を発見!(資料3-1)
・日光男体山は活火山!(資料3-2)
4) 教育・普及行事について(資料4-1,4-2)
■概要説明資料(PDF)
(プレス発表資料 資料1、 資料2、資料3-1、 資料3-2、資料4-1、資料4-2)
アジアで発生した大規模自然災害に関する緊急声明(5/26)
日本地質学会は、ミャンマーサイクロン災害、四川省大地震で被災された方々へのお見舞いと、学会としての今後の活動方針をまとめ、5月25日開催された日本地質学会第115年総会にて緊急声明を全会一致で採択しました。これを皆様にお伝えするとともに、今後他学会とも連携し、地質学的な専門家集団としての立場から支援していきます。
なお、日本地質学会は、5月12日に発生した四川大地震に関して、中国地質学会へお見舞いの書簡を送りました(5月20日発送)。そして中国地質学会からは5月22日にその返信をいただきました。
■概要説明資料(PDF)
(プレス発表資料 資料1、 資料2、 資料3)
プレスリリース(2009年)
プレスリリース(2009年)
行政刷新会議のこれまでの事業仕分けについての意見書(11/20)
内閣府行政刷新会議によって行われているいわゆる事業仕分けに関し、刷新会議議長ならびに文部科学大臣に対し、添付のような意見書を提出しました。
■行政刷新会議のこれまでの事業仕分けについての意見書(PDF)
日本地質学会第116 年学術大会について(8/21)
1) 日本地質学会第116年学術大会(資料1)
2) 特筆すべき個人の発表
■後期白亜紀野モンゴルに生息していた“草食系”恐竜は何を食べていたのか?(8/28解禁)(資料2)
3) 関連行事
■市民講演会「大地から考える地球環境 —地質と生物・農業の深い関係—」 (資料3)
■特別講演会 地質学と医学の融合ー癌発生のメカニズムー(資料4)
■地質情報展2009おかやま−ワクワク・発見・瀬戸の大地− (資料5)
■ジオパークワークショップ ジオパークによる地域活性化を目指して(資料6)
■小さなEarth Scientistのつどい〜第7回小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜
■「科学を文化に−学校教育・地学分野のこれから—」シンポジウム(資料7)
■一般向け講演会:岡山生まれた地球深部探査船「ちきゅう」の活躍
(■プレス発表概要資料)
TOP/委員会のあゆみ
ジェンダー・ダイバーシティ委員会
ジェンダー・ダイバーシティ委員会TOP
本委員会は、女性地球科学者をとりまく環境や就職状況を把握し、女性研究者の地位向上を目指すとともに、男性・女性研究者が共に互いを尊重しつつ個性と能力を十分発揮できる環境づくりのための活動を行っています。1995年の設立以来、男女共同参画促進のためのワークショップ、地質学会における大規模アンケート調査や学会保育室の立ち上げと維持および情報・研究交流会など、地道な活動を行って参りました。
女性研究者の方々、また企業・研究所などにお勤めの女性技術者や女子学生・院生の皆様、なにか困ったことがありましたらお気軽に本委員会までご相談ください。また、女性会員に限らず会員の皆様、男女共同参画に関する事などなにかございましたら本委員会までお問い合わせください。
お問い合わせ先:<danjyo@geosociety.jp >
2009年12月 男女共同参画委員会
委員長 堀 利栄
お知らせ
学術大会における ダイバーシティ認定ロゴ「ECS ・EDI」導入の取り組み NEW
JpGU2022若手キャリアパス相談実施(5/29-6/3:JpGU参加者対象)現在開催されているjpGUで、若手キャリアパス相談が実施されます。学生さんやポスドク・若手研究者などの方々の今後の多様なキャリアパスのために このキャリア相談を是非ご利用ください. 2022.5.23掲載
委員会名称変更について:男性・女性のみならず,様々な性自認に対応し,加えて日本社会の変容・国際化に伴う多様な国籍・背景を持つ会員のためのダイバーシティ推進も本委員会の活動に内包されると捉えるため,委員会名称を変更しました.(旧)男女共同参画委員会 →(新)ジェンダー・ダイバーシティ委員会(2020年12月5日理事会承認)
委員会のあゆみ
日本地質学会における男女共同参画に関する委員会活動は、1994年度の日本地質学会第4回定例評議員会において、地球科学分野における女性研究者の研究および教育環境、就職状況の現状を把握し、女性地球科学者の地位向上のための活動を行うために委員会の設置が認められた時点からはじまりました。
日本地質学会男女共同参画のあゆみ 2020年度ver(女性会員と総会員数の変化/国立大学における女性教員率及び女子学生率/学会各賞の男女比/名誉会員の動向) 2021.2.17掲載
日本地質学会会員の男女比(2000年・2007年)
委員会メンバー →こちらから
沿革・活動
*A: 第1回夜間小集会のビラ。クリックすると大きな画像がご覧頂けます。
*A': 第1回の研究交流会(金沢)の様子.
2021年8月 学術大会(名古屋大会)における ダイバーシティ認定ロゴ導入の取り組み
2021年8月1日 座談交流会 (ジェンダー・ダイバーシティ委員会Workshop) 「地質分野の多様性を増やすには:持続可能で闊達な学会を目指して」
2020年12月5日 委員会名称を「男女共同参画委員会」から「ジェンダー・ダイバーシティ委員会」に変更
2011年11月12-13日 南相馬巡検実施 (報告はこちらから)
2009年3月29−30日 日本地質学会男女共同参画委員会主催で金沢・氷見ワークショップ「燃える温泉と地滑りのメッカ-地質学と町おこし-」を開催、子供を含め14名の参加があった。(開催報告はこちら→)
2008年4月 「男女共同参画委員会」への名称変更および規約改正を承認される。
2007年12月 本委員会の名称変更願いを理事会および評議員会に提出。
2007年9月 地質学会年会において開かれた委員会において本委員会の名称変更について議論。
2001年 「女性地球科学者の未来を考える委員会」の委員会規約が制定され、2001年10月1日から施行される。
1999年11月 長野県国立高遠少年自然の家で女性地球科学者の研究交流会(学習会・巡検・懇親会)を開催(参加者18人:女性12人男性6人,News誌Vol.2, No.12,p.16).
1998年9月 地質学会第105年々会(松本大会)における保育室の開設が本委員会委員を含む女性会員(特に藤林紀枝・清水以知子両氏)および松本大会準備委員長秋山雅彦氏の尽力で実現。
以後、地質学会第109年々会(新潟大会)まで本委員会の関係者が保育室世話人グループと協力して保育室の運営を担当する。2002年の地質学会第109年々会(新潟大会)以降は大会準備委員会単独の扱いになり、2004年の千葉大会より大学生協とタイアップしての総会における保育室の運営が毎年行われるようになる。(年会保育室のあゆみはコチラ→)
1998年6月 東北大学八甲田植物実験所にて女性地球科学者の研究交流会(学習会・巡検・懇親会)を開催(参加者13人:女性10人男性3人,News誌Vol.1, No.7,p.27)*C写真。
1996年 上記アンケート結果を日本地質学会のHPおよび地質学雑誌で公表。
1996年10月5-6日 金沢大学にてアンケート結果の報告会をかねた第1回の研究交流会[女性地球科学者の研究交流会 -地球と環境を語りましょう-]を開催(22名の参加)*B写真。
1995年〜1996年 本委員会事務局(愛媛大学)にて結果を集計。
1995年 地球科学系における女性のための環境調査アンケートを実施。(アンケート結果はこちら→)
1995年4月 地質学会第102年総会・年会(広島大会)において第1回委員会を開催する。*A参考ビラ
正式名称「女性地球科学者の未来を考える委員会」が決定される。
1995年3月 田崎評議員による提案で日本地質学会において”女性地球科学者地位向上委員会“(仮称)の設立が日本地質学会評議員会で承認される。
*B:地質学会における交流会
*C:八甲田交流会-01
*C:八甲田交流会-02
保育室のあゆみ
男女共同参画委員会
年会保育室のあゆみ補足
1998年 第105年々会(松本)において初めて保育室を開設。
1998-2001年 本委員会の関係者が保育室世話人グループと協力して保育室の運営
2002-2003年 大会準備委員会扱い
2004-2007年 大学生協とタイアップしての保育室運営
2008-2009年 外部託児施設への保育委託
2010年 学童保育(GEO-KIDS応援)プログラム予定
1998年 地質学会第105年総会・年会(松本大会)保育室世話人グループ担当
1999年 地質学会第106年総会・年会(名古屋大会)保育室世話人グループ担当
2000年 地質学会第107年総会・年会(松江大会)保育室世話人グループ担当
2001年 地質学会第108年総会・年会(金沢大会)大会準備委員会および保育室世話人グループ担当。
2002年 地質学会第109年総会・年会(新潟大会)大会準備委員会扱い。
2003年 地質学会第110年総会・年会(静岡大会)大会準備委員会扱い。
2004年 地質学会第111年総会・年会(千葉大会)千葉大学生協扱い。
2005年 地質学会第112年学術大会(京都大会)京都大学生協扱い。
2006年 地質学会第113年学術大会(高知大会)高知大学生協扱い。
2007年 地質学会第114年学術大会(札幌大会)北海道大学生協扱い。
2008年 地質学会第115年学術大会(秋田大会)会場外保育施設扱い。
2009年 地質学会第116年学術大会(岡山大会)会場外保育施設扱い。
→男女共同参画TOP頁にもどる
95年アンケート結果
男女共同参画委員会
地球科学系における女性のための環境調査アンケートについて
1995年10月に調査のためのアンケート用紙を約700ヶ所に郵送し、1995年末〜1996年初頭にかけて集計を行った。アンケートには、4年生以上の地球科学系学生205名、研究所・大学153ヶ所、企業(公)34社、企業に勤める女性技術者12名から回答をいただき、女性地球科学者・技術者のおかれる現状の解析を行った。その結果を1996年6月の定例評議員会に報告するとともに、プライバシーに配慮しつつ、地質学会のHPおよび地質学雑誌のニュース欄にて公開した。
→男女共同参画TOP頁にもどる
ワークショップ報告(09.03.29-30)
男女共同参画委員会
金沢・氷見ワークショップ「燃える温泉と地滑りのメッカ-地質学と町おこし-」開催報告
日程:2009年3月29日−30日
日本地質学会における男女共同参画活動の草分け的存在である田崎和江教授が2009年3月金沢大学を退職されるため、多数委員の希望で09年3月末に1泊2日のワークショップを金沢・氷見にて行いました。参加者は、子供も含めて14名でした。ちょうど春休み期間中だったので小学生や中学生のお子様連れの女性研究者の方も何組か参加いたしました。初日は、氷見にて大規模地滑り地帯の見学*F写真1、田崎先生が関わった地質学から貢献した村おこしの現場の見学*F写真2、翌日は、金沢大学での足湯*F写真3と授乳室*F写真4の見学を行いました。氷見では、地元の矢方憲三さんに地質学や子供向けの観光&見学スポットをガイド頂き、大変お世話になりました。残念ながら、旅館の営業時間の関係で「燃える温泉」の見学ができませんでしたが、様々な地球科学関係の女性研究者の方々と交流を深める有意義なワークショップとなりました。また、地質学はどのように地元に貢献できるか?、大学での女性研究者へのサポートをどのように進めていくべきか?を考えさせられる2日間でした。なお本ワークショップは、日本地質学会から一部サポート頂き開催いたしました。ここにお礼申し上げます。
F1
F2
F3
F4
→男女共同参画TOP頁にもどる
意見・提言2010
意見・提言2010
宇宙航空研究開発機構(JAXA)の「はやぶさ」関連プレス発表資料についての要望書
2011年1月21日
日本の惑星探査機「はやぶさ」が地球に持ち帰ったカプセルの中に,小惑星「イトカワ」の微粒子が含まれていたという宇宙航空研究開発機構(JAXA)の発表は,2010年末の大ニュースでした.しかし,その発表内容については,ニュース誌13巻12号15頁の記事のように,地球外物質と判断した根拠などについていくつか疑問があり,一般向けの発表とはいえ,もう少し科学的な正確さが必要なのではないかという印象を多くの会員が持ったと思います.そこで,日本地質学会会長からJAXA理事長に対し,プレス発表に科学的な正確さを確保するよう求める要望書を郵送しました.この要望書およびそれに対するJAXAの担当者からの回答文を掲載いたします。
■ 貴機構の「はやぶさ」関連プレス発表資料についての要望書(2010.12.22)
■ JAXAからの回答(2011.1.21)
日本地質学会 会長 宮下純夫
小惑星探査機「はやぶさ」の帰還に関して声明
2010年6月15日
小惑星探査機「はやぶさ」が小惑星イトカワでの探査を終えて地球に帰還し,試料回収カプセルが無事回収された快挙に,日本地質学会から祝意を表します.「はやぶさ」が,小惑星イトカワの構造や表面状態について多くの興味深い知見をもたらし,様々な技術的困難を乗り越えて地球に帰還したことは,関係者の粘り強い心血を注いだ努力の賜物です.今回の探査に携わられた多くの関係者の皆さまの労をたたえます.
地球上の変動やこれまでの変遷過程を理解する上で,直接的なサンプルが果たしてきた役割は大きなものがあります.地質学の発展はまさにそうした直接的なサンプルやフィールドでの観察によって支えられてきました.月から得られた岩石試料が,月のみならず,地球の生成・発展の解明にとっても大きな役割を果たしたことは,よく知られています.
今後も始原天体などへのサンプルリターン探査がおこなわれ,地球・惑星・生命の起源と進化に関する解明が進むことを期待しますとともに,日本地質学会としてもそうした先端的・学際的な研究の発展のために力を尽くす所存です.
日本地質学会 会長 宮下純夫.
高等学校理科地学担当教員の増員に関する要望
2010年6月14日
今般の学習指導要領の改訂にともなう平成24年度からの高等学校理科の先行実施に関し,本学会は文部科学大臣,各都道府県教育委員会教育長,政令指定都市教育委員会教育長に対して下記のような要望を提出しました.
一般社団法人日本地質学会
詳しくはこちら→
「科学技術基本政策策定の基本方針(案)」に対する日本地質学会のコメント
2010年6月7日
総合科学技術会議では第4期科学技術基本計画の策定に向けての検討を進めており,「科学技術基本政策策定の基本方針(案)」に対するパブリックコメントを募集していました.
日本地質学会では,研究・教育における基盤的経費の充実や,大学院博士課程学生に対する支援の拡充,若手研究者の身分の安定化,高校地学教員の配置などについて,まだ議論中の論点を中心にコメントとして提出することにしました.パブリックコメントのフォーマットとして,項目ごとに文書をまとめる形になっているので,以下,「基礎研究の抜本的強化」「科学・技術を担う人財の強化」「全体」の3項目について,提出したコメントを紹介します.
なお,「科学技術基本政策策定の基本方針(案)」の本文については,総合科学技術会議の以下のURLを参照ください.http://www8.cao.go.jp/cstp/pubcomme/kihon4/honbun.pdf
詳しくはこちら→
第四紀と更新世の新しい定義と関連する地質時代・年代層序の用語について
2010 年1月22日
詳しくは「地層命名の指針」ページへ
意見・提言2009
意見・提言2009
行政刷新会議のこれまでの事業仕分けについての意見書
2009年11月20日
内閣府行政刷新会議によって行われているいわゆる事業仕分けに関し、刷新会議議長ならびに文部科学大臣に対し、添付のような意見書を提出しました。
■行政刷新会議のこれまでの事業仕分けについての意見書(PDF)
プレスリリース(2010年)
プレスリリース(2010年)
日本地質学会第117年学術大会(富山)について(9/13)
発表形態:
資料配付(9月7日).
現地説明会(9月13日 14時より 会場:富山大学理学部A239号室)
発表先:
文部科学省記者会,富山県県庁記者クラブ,科学新聞社
記事解禁日時:説明会終了次第(既にホームページ上で公開されているものは除く)
概要:
1)学術大会のご案内 (資料1)
2)特筆すべき学術発表(解禁日時制限あり)
・肉食恐竜,もっと低い姿勢.従来の復元姿勢に変更を迫る −足跡と骨格化石から.ゴビ砂漠における日本-モンゴル共同調査隊の成果− (資料2)
・温暖な地球と寒冷な地球の移行期を知る手掛かり −高知県に鮮新世から第四紀への連続地層− (資料3)
・津波警報・被害評価の死角 −海底地すべりによって増幅される海底地震の津波− (資料4)
そのほか
3)表彰
4)関連行事
・地質情報展2010とやま —海・山ありて富める大地— (資料5)
市民講演会 北陸の大地をゆるがす地震と恐竜
ミニ講演会 ジオパークへ行こう,富山の恐竜化石など
地学オリンピック:目指せ金メダル!
惑星地球フォトコンテスト入賞作品展示
そのほか最新成果の展示と解説,体験コーナーなど
・小さなEarth Scientistのつどい 第8回小,中,高校生徒「地学研究」発表会
■説明資料(PDF)(概要・資料1 資料2 資料3 資料4)
プレスリリース(2011年)
プレスリリース(2011年)
第118年学術大会(水戸)* について(9/27)
*正式名称:日本地質学会第118年学術大会・日本鉱物科学会2011年年会合同学術大会(水戸大会)
発表形態:
資料配付(8月26日).
現地説明会(8月31日(水),茨城県庁4F 記者室にて,14 時〜15 時)
発表先:
文部科学省記者会,茨城県県政記者クラブ,科学新聞社
記事解禁日時:平成23年9月6日(既にホームページ上で公開されているものは除く)
概要:
1)学術大会のご案内 (資料1)
・ シンポジウム「大規模災害のリスクマネージメント―東北地方太平洋沖地震に学ぶ―」
・ シンポジウム「太陽系固体惑星地質探査:イトカワから火星・金星まで」 ほか
2)特筆すべき学術発表(解禁日時制限あり)
・ 大震災の影で注目されてこなかった,もうひとつの地震災害 (資料2)
・ 宇宙空間で作られたダイアモンドの姿 (資料3)
そのほか
3)表彰
4)関連行事
・市民講演会「東日本大震災と地震・津波・原発」 (資料4)
都司嘉宣 「巨大津波の教訓」
澤井祐紀 「地層が語る過去の巨大地震と津波」
石橋克彦 「2011 年東北地方太平洋沖巨大地震と福島原発震災」
・地質情報展2011みと (資料5)
東日本大震災関連ポスター展示
特別講演会「日本のジオパーク−列島の大地に学ぶ」
地学オリンピック:目指せ金メダル!
惑星地球フォトコンテスト入賞作品展示
そのほか最新成果の展示と解説,体験コーナーなど
・小さなEarth Scientistのつどい 第9回小,中,高校生徒「地学研究」発表会
■説明資料(PDF)( 概要 資料1 資料2 資料3 資料4 )
意見・提言2012
意見・提言2012
おおい町大島の県道法面工事における露頭保全のお願い
2012年11月20日
おおい町大島の県道法面工事における露頭保全のお願い
(2012年12月18日掲載)
「高レベル放射性廃棄物の地層処分について」—地質環境の長期的安定性の観点から(学術会議の報告を受けて)—
2012年11月22日
一般社団法人日本地質学会は,日本学術会議9月11日付け報告書「高レベル放射性廃棄物について」に対して,地球科学界を代表する日本地質学会として積極的に関与し,地質学関連学界が社会に対して果たすべき責務として以下のコメントを公開します.
「高レベル放射性廃棄物の地層処分について」—地質環境の長期的安定性の観点から(学術会議の報告を受けて)—
(2012年11月22日掲載)
ラクイラ地震裁判における科学者への実刑判決を憂慮する
2012年11月2日
日本地質学会は、イタリアの2009年ラクイラ地震に関する裁判において、6人の地球科学者が過失致死罪で禁錮6年の実刑判決を受けたことについて、重大な懸念を表明する。
全文はこちら、、、
ラクイラ地震裁判における科学者への実刑判決を憂慮する
Concern about the outcome of the L'Aquila prosecution(英語版)
(2012年11月6日掲載)
「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画の見直しについて(審議経過報告)」に対する日本地質学会のコメント
2012年5月19日
文部科学省では、東北地方太平洋沖地震を踏まえた「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」の見直し審議の経過報告をまとめ、これに対する意見募集を行いました。これに対して、日本地質学会から以下のとおり意見を提出しましたので紹介します。
なお,「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画の見直しについて(審議経過報告)」の本文については,以下のURLを参照ください.
意見募集中案件詳細
日本地質学会より提出した意見書はこちら、、、
「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画の見直しについて(審議経過報告)」に関する意見(2012.5.19)
(2012年5月20日掲載)
プレスリリース(2012年)
プレスリリース(2012年)
「高レベル放射性廃棄物の地層処分について」—地質環境の長期的安定性の観点から(学術会議の報告を受けて)—(11/22)
発表形態:資料配付
発表先:文部科学省記者会
一般社団法人日本地質学会は,日本学術会議9月11日付け報告書「高レベル放射性廃棄物について」に対して,地球科学界を代表する日本地質学会として積極的に関与し,地質学関連学界が社会に対して果たすべき責務として以下のコメントを公開します.
「高レベル放射性廃棄物の地層処分について」—地質環境の長期的安定性の観点から(学術会議の報告を受けて)—
ラクイラ地震裁判における科学者への実刑判決を憂慮する(11/6)
発表形態:資料配付
発表先:文部科学省記者会
日本地質学会は、イタリアの2009年ラクイラ地震に関する裁判において、6人の地球科学者が過失致死罪で禁錮6年の実刑判決を受けたことについて、日本地質学会は下記の声明を発表いたしました。
全文はこちら、、、
ラクイラ地震裁判における科学者への実刑判決を憂慮する
Concern about the outcome of the L'Aquila prosecution(英語版)
第119年学術大会(大阪大会)について(9/7)
発表形態:資料配付
発表先:文部科学省記者会、大阪府政記者クラブ、大阪科学・大学記者クラブ
■説明資料(PDF)(本文 資料1 資料2 資料3 資料4 資料5)
概要:
1)日本地質学会第119年学術大会(大阪大会)を開催 (資料1)
公開シンポジウム
「上町断層の地下構造と運動像 —都市域伏在活断層の地質学—」
「西日本の海溝型地震と津波を考える」
2)特筆すべき個人、団体の学術発表
(1)衛星情報から僅かな地盤のズレを検知することによる広域災害警戒技術 (資料2)
(2)巨大津波によってえぐられた気仙沼湾の海底 −気仙沼湾復興を目指した最新観測調査− (資料3)
【既報の成果に関する研究発表】
(3)Japan Trench Fast Drilling Project (JFAST): 2011年東北地震の巨大滑りを理解するための掘削調査 (資料4)
3)表彰
4)関連行事
(1)市民講演会「地震・津波・地盤災害 〜知ること、伝えること〜」(資料5)
(2)地質情報展2012おおさか 「過去から学ぼう 大地のしくみ」
(3)小さなEarth Scientistのつどい 第10回小、中、高校生徒「地学研究」発表会
5月10日地質の日第5回事業のご紹介(4/27)
発表形態:資料配付
発表先:文部科学省記者会
記事解禁日時:平成24年4月27日
■説明資料(PDF/JPEG)( 本文 添付資料1 添付資料2 添付資料3 )
東日本大震災にかかる地質学の役割と対応について(2/28)
発表形態:資料配付
発表先:文部科学省記者会
記事解禁日時:平成24年2月28日
1.概要:
(1)提言
海溝型地震・津波に対して,地質学的知見が集積されつつも防災・減災に大きく活かしきれなかったことを鑑み,地質学コミュニテイの重い責務と課題を総括し,超巨大地震の実態解明,地震災害と地域防災教育,市民の防災意識向上等を2011 年4 月に会長より緊急の提言を公表(別紙1参照),その後作業部会による,より包括的な報告書をまとめ2011 年5 月に公表いたしました(別紙2参照).これら提言を基に,学会として長い目で見た事業計画を定め,来年度の各専門部会・事業部会・支部等で実施するところです.
・会長提言 [http://www.geosociety.jp/hazard/content0051.html]
・東日本大震災対応作業部会報告 [http://www.geosociety.jp/hazard/content0059.html]
超巨大地震の実態解明と防災・減災へ向けて
復旧・復興への貢献
長期的な防災・減災へ向けて
(2)講演会・展示会の開催
防災・減災を視野に入れた最新の学術的知見の解説,地質学の普及と教育,情報発信のあり方に関するシンポジウムの開催,また展示パネルや映像それに標本,体験コーナーなどを使って地質学に触れることができる展示会などを催しました.
2011年9月:市民講演会「東日本大震災と地震・津波・原発」
2011年9月:地質情報展(共催:独立行政法人産業技術総合研究所地質調査総合センター・国立大学法人茨城大学)
2012年3月17 日(予定):日本地質学会構造地質部会緊急例会「社会への発信とリテラシー」
2012年9月(予定):公開シンポジウム「大規模災害のリスクマネージメント—東北日本太平洋沖地震に学ぶ—」
(3)復旧復興にかかわる調査・研究事業
日本地質学会として学術的な復旧事業を会員より公募し,下記のとおり実施しております.
放射性セシウムに汚染された水田土壌のカヤツリグサ科マツバイによるファイトレメディエーション
歌津魚竜館大型標本レスキュー事業
微生物による放射性物質の除染の実証試験
関東平野内陸部の住宅地での盛土材質の相違による液状化要因の解明
陸前高田博物館標本レスキュー事業
福島第一原子力発電所周辺の放射線量の測定方法と地質学的除染方法の検討
2.復旧復興にかかわる調査・研究事業の成果:
(1)水田除染の切り札「マツバイ」:セシウムを効率的に吸収
(2)よみがえる地元の自然文化財:被災博物館のレスキュー事業(別紙3参照)
(3)液状化する造成地としない造成地.いったい何が違うのか?(別紙4参照)
3.シンポジウム「社会への発信とリテラシー」
■説明資料(PDF)( 資料 別紙1 別紙2 別紙3 別紙4 )
意見・提言2011
意見・提言2011
林原生物化学研究所の地質学・古生物学研究に関する要望書
2011年2月14日
新聞報道などでご存知と思いますが、株式会社林原の経営破綻により、複数の本学会会員を含む地質・古生物系職員の研究活動、恐竜化石を中心とする貴重な標本や文献の管理、国際的な学術協力関係などに支障が出る可能性が懸念されます。そこで地質学会会長から同社社長と管財人あてに、これらの事項に関する要望書を発送しました。その全文を掲げます。
■ 林原生物化学研究所の地質学・古生物学研究に関する要望書(2011.2.14)
一般社団法人日本地質学会 会長 宮下純夫
(2011年2月24日掲載)
地質調査研修とは?
地質調査研修
日本地質学会では,社会貢献事業の一端として,支部や他学会・機関と連携した研修事業等を企画,実施することとしています.その背景には,国内の地質調査業や関連事業団体からの地質調査技術の研修要請に対する定常的な仕組みがほとんど存在していないことが挙げられます.日本地質学会では,地方支部のネットワーク等を有効に利用して,これらの社会要請に幅広く対応できる体制を構築していくべきと判断し,2012年度よりモデル事業を立ち上げることとしました.充実した地質調査研修プログラムをご用意いたしますので,是非ご参加ください.
2012年7月
日本地質学会社会貢献部会
▶▶【お知らせ】地質調査研修中止のお知らせ(2017.3.13 掲載)
2016年
■2016年度秋季調査研修(11/14-11/18)実施報告
2015年
■2015年度秋季地質調査研修(11/9-11/13)実施報告
■2015年度春季地質調査研修(5/18-5/22)実施報告
2014年
■2014年度秋季地質調査研修(11/25-11/29)実施報告
2013年
■2013年度秋季地質調査研修(11/18-11/22)実施報告
■2013年度春季地質調査研修(5/27-5/31)実施報告
2012年
■2012年度秋季地質調査研修(10/29-11/2:房総半島中部地域)
2011年
■2011年度春季地質調査研修(地学情報サービス株式会社実施)
2012年度秋季研修実施報告
2012年度地質の調査研修(4泊5日)
写真でみる2012年度地質の調査研修(2012.10.29〜11.2に実施)の実施状況
写真1 初日の林道沿いでのルートマップ作成中の様子(清和県民の森:清澄向斜南翼の清澄層下部分布域)。
写真2 初日林道沿いで作成したルートマップの清書後の比較(初日夜)。1マス(5mm)は10複歩。作成されたルート図には、凝灰岩鍵層、走向・傾斜、岩相などの情報も記載されている。上方が北(磁北)。
写真3 ほぼ100%地層が連続して露出する猪の川(黒滝沢:清澄背斜北翼)沿いで、砂岩泥岩互層中の主な凝灰岩鍵層を確認(2日目)。
写真4 確認した主な凝灰岩鍵層には、鍵層名(通称名)の標識がつけられる(2日目)。
写真5 猪の川沿いでのルートマップの作成は、黒滝不整合直情の黒滝から、上流に向かって始まります(3日目)。
写真6 この凝灰岩はなんという鍵層だったかな(3日目)?
写真7 夜の作業風景。昼歩きながら鉛筆で作成したルートマップのルート図や地質情報を清書(墨入れ)し、その後、岩相の違いなどを色鉛筆で表現する(3日目)。
写真8 猪の川(黒滝沢)沿いで作成した安野層分布域のルートマップの清書後の比較(3日目の夜)。1マス(5mm)は20複歩である(写真2と比べた場合、同じ距離が2倍の範囲をカバーする)。
写真9 嶺岡構造帯を構成する始新世の層状石灰質チャートブロック(5日目)の観察。嶺岡山地北麓白滝神社の白絹の滝。
写真10 嶺岡構造帯を構成する始新世の枕状溶岩ブロックの観察(3日目)。鴨川市新屋敷の鴨川青年の家。
写真11 東海岸の勝浦市吉尾漁港東方の海蝕崖で、黒滝不整合直下の清澄層上部のタービダイト砂岩や凝灰岩鍵層の堆積構造などの観察(5日目)。
写真12 修了証書受領後の記念撮影(勝浦海中公園)。参加者には、この他に、土質・地質技術者のための継続教育(CPD)40単位が与えられる(5日目)。
※2012年度地質の調査研修の実施報告については,日本地質学会News,Vol. 15, No.12,14-15(2012年12月号)にも掲載されています.
2016年度秋季地質調査研修実施報告
2016年度秋季地質調査研修の実施報告
上記研修を2016年11月14日 (月) 〜11月18日 (金)にかけて、房総半島中部をほぼ東西に横切る清澄山系において、ゆるやかな褶曲構造をなして分布する安房層群上部(中新世後期〜鮮新世)の天津層、清澄層、安野層を主な対象に行った。
本研修は、民間地質関連会社から、誰でも参加できる若手技術者向けの地質調査研修を毎年やってほしいという産総研地質調査総合センター(元の工業技術院地質調査所)への要請がきっかけとなって2007年度より始まった。初めの5年間の2011年度までは、産総研地質調査総合センターの外部研修プログラムとして、つくば市の地学情報サービス㈱の管理運営の下で行われたが、その後2012年度からは、日本地質学会主催、産総研地質調査総合センター共催という形で現在に引き継がれ、今年で10年目、今回は12回目の研修である(春と秋に行った年度もある)。
2014年度までの8年間は、小櫃川支流猪の川(黒滝沢)上流の東京大学千葉演習林内でのルートマップづくりが中心的な作業だったが、昨年初めに起きた千葉演習林に至る猪の川林道沿いでの崖崩れによる通行止め状態の継続により、昨年度同様、今年度も小櫃川上流七里川沿いでのルートマップづくりが主たる作業となった。
今回は、4社から定員6名(内女性1名)の参加があった。受付開始後数日後には定員に達し、定員数を増やせないかという問合せや、キャンセル待ちの人も出るなど申込み状況は好調であったが、参加できなかった人には申し訳なかった。これまでは、石油・天然ガス開発、地熱開発、鉱山開発などの資源・エネルギー分野の上流部門の会社からの参加が主流であったが、今回は、北海道の土木・地質コンサルタント会社から2名の参加があったのはひとつの特徴であった。講師は、徳橋秀一(産総研地圏資源環境研究部門客員研究員)と細井 淳(産総研地質情報研究部門研究員)が務めた。
今回の研修は、初日の夜半に雨が降ったが昼は降ることはなく、また後半は小春日和に恵まれるなど、幸いにも比較的天候に恵まれた。初日夜の雨のため一部実施スケジュールの順序を入れ替えたが、ほぼ予定のスケジュールを実施し、事故もなく無事終了することができた。
以下に、各日ごとの実施内容の概要を記す。
1日目:2014.11.14 (月) 曇り
午前10時30分にJR外房線君津駅に集合、近くで昼食を取った後、初日の研修先である小糸川上流の清和県民の森に向かう。途中、旅館で荷物を下ろし着替えをした後に、研修先の清和県民の森渕が沢林道に到着。午後は、清澄向斜南翼部に位置する渕ヶ沢林道及び渕ヶ沢奥米林道沿いに分布する安房層群清澄層最下部のタービダイト砂岩優勢互層の特徴や主な凝灰岩鍵層の特徴とそれらの上下関係を観察した。特に、タービダイト砂岩層の直上に細粒のタービダイト泥岩が載る清澄型(K型)タービダイトの特徴を観察した。次にクリノメーターを使って層理面の走向・傾斜の測定法(写真1)やルート図の作成法の練習を行った後に、実際に上記林道沿いで地質学的情報を記載したルートマップの作成を行った(写真2)。夜は、昼に作成したルートマップの清書(墨入れと色鉛筆による色塗り)を行い(写真3)、お互いのルートマップを比較した(写真4)。
2日目:2016.11.15 (火) 曇り
夜半に雨が降り河川の流量の増大が予想されたことから、当初予定していた清澄背斜北翼の小櫃川上流の七里川でのルートマップづくりを変更して、午前は、前日に引き続き、清和県民の森の渕ヶ沢林道につづく渕ヶ沢奥米林道沿いに分布する清澄層最下部のタービダイト砂岩優勢互層分布域のルートマップを作成した(写真5)。雨上がりで林道沿いの草むらが湿っていたこともあり、山ヒルの活動が活発であった(写真6)。午後は、清澄背斜北翼に位置し、小櫃川支流の笹川の片倉ダム周辺に伸びる三石山林道に行き、まずは、同林道の峠(三石山頂上付近)にある三石山観音寺(三石観音)境内周辺で安房層群を不整合に覆う上総層群基底の黒滝層(基底礫岩層)を観察した(写真7と8)。次に、同林道沿いに分布する清澄層のタービダイト砂岩優勢互層の特徴(写真9)や代表的な凝灰岩鍵層であるKy26(ニセモンロー)タフ(写真10)や三浦半島で名前のついたKy21(Hk)タフを観察した(写真11)。また、清澄層下位の天津層の泥岩層(写真12)や天津層の泥岩が粗粒化する層準でみられる生痕化石も観察した。さらに、三石山林道沿いにある片倉ダムによって形成されるダム湖(笹川湖)が、未固結のタービダイト砂岩を主体とする清澄層の分布域を避け、主に不透水層の泥岩から成る天津層の分布域に位置するように、ダムサイトが天津層と清澄層の境界部に建設されていることを確認した(写真13)。午後の最後は、清澄背斜南翼に位置する田代林道沿いの天津層と清澄層の境界部を観察し(写真14)、前日の清澄向斜南翼の渕ヶ沢林道沿いで観察した凝灰岩鍵層の一部を再確認した(写真15)。夜は、ルートマップの清書作業を行い互いに比較するとともに(写真16)、講師による昔の野帳に記載されたルートマップなどを閲覧した。また、テキストを使って研修地の地質や地層を学習した。
3日目:2016.11.16 (水) 曇りのち晴れ
午前は、清澄背斜北翼に位置する小櫃川上流七里川沿いの清澄層中部から下部(タービダイト砂岩優勢互層)及び天津層上部(多数の凝灰岩層を挟む泥岩層)の分布域を上流に向かって歩きながら、堆積物と主な凝灰岩鍵層(三石山林道でも観察した清澄層中部のKy21=Hkタフなど)を観察した。特に、初日の午後および2日目の午前に歩いた清澄向斜南翼に位置する清和県民の森の林道沿いで観察した清澄層最下部の厚いタービダイト砂岩優勢互層中に上下に離れながら挟まれていたいくつもの凝灰岩鍵層が、清澄背斜北翼の七里川では、清澄層の厚い礫質なタービダイト砂岩層直下の天津層の最上部の泥岩層中に、上下に密集して産出していることを確認した。すなわち、清和県民の森ではこの間にあった多数の厚いタービダイト砂岩層が、ここでは存在していないという岩相および層厚の顕著な変化が認められることを確認した。このような清澄層と天津層境界部でみられる清澄向斜部と清澄背斜部の間の地層の顕著な特徴の変化は、震探記録などでよくみられる背斜軸部への地層の収れん現象が地層で観察される例であることを説明した。このあとさらに上流に向かって歩きながら、天津層上部の代表的な凝灰岩鍵層(三浦半島で名前のついたAm78=Okタフなど)を観察し、今度は下流に向かって引き返しながら、天津層上部から清澄層中部分布域のルートマップを作成した(写真17)。午後は、午前に引き続く形で、七里川下流に向かって歩き、清澄層の中部〜上部が分布する地域の堆積物や主な凝灰岩鍵層(三石山林道でも観察したKy21タフやKy26タフなど)を観察しながらルートマップを作成した(写真18〜21)。そして、清澄層上位の安野層との境界部に出てくる安野層基底の凝灰岩鍵層An1(さかさ)タフを確認したところでこの日のルートマップづくりを終了した(写真22と23)。夜は、昼作成したルートマップを清書するとともに、この地域の過去の調査や研究の成果について図面などをみながら学習した。
4日目:2016.11.17 (木) 晴れ(小春日和)
午前は、前日に引き続き清澄背斜北翼の七里川沿いで、清澄層上位の主に泥岩優勢な砂岩泥岩互層から成りスランプ堆積物も含む安野層分布域を上流に向かって歩きながら、地層の特徴や主な凝灰岩鍵層を観察した。また、清澄層型タービダイトとは特徴を異にする安野層型(A型)タービダイトの特徴についても観察した。その後、前日ルートマップづくりを終了した清澄層との境界部から下流に向かってもどりながら、安野層分布域のルートマップを作成した(写真24〜26)。昼食後、午前の作業の残りである安野層最上部から黒滝不整合分布域のルートマップを作成した(写真27)。特に黒滝不整合前後では、露頭表面を少し丹念に削りながら、不整合の位置(基底礫岩から成る黒滝層の基底)と思われるところを確認した(写真28)。その後、東隣りの養老川流域に車で移動し、蛇行する養老川沿いに平行して伸びる養老渓谷中瀬遊歩道沿いで、上総層群の代表的なタービダイトサクセッションである大田代層や梅ヶ瀬層を観察した(写真29〜32)。また、安房層群の清澄層や安野層のタービダイトとは特徴に異にする上総層群の大田代層型(O型)タービダイトの特徴についても、直接の観察によって理解を深めた。夜は、ルートマップの清書作業の他、5,000分の1地形図へのデータの書込み作業を行い、できあがったルートマップや5,000分の1地形図の比較を行った(写真33と34)。
5日目:2016.11.18 (金) 晴れ(小春日和)
午前は、安房層群上部の天津層、清澄層、安野層が堆積した前弧堆積盆(清澄海盆)の南側を縁取る外縁隆起帯を形成していたと思われる嶺岡構造帯を構成する代表的な岩石(蛇紋岩、層状石灰質チャート、枕状溶岩)を嶺岡山地周辺で観察した(写真35〜37)。その後、東海岸を北上し勝浦海中公園に移動した。午後は、まず吉尾漁港東方の海蝕崖先端のボラの鼻に向かった(写真38)。干潮時間に合わせての訪問であったが、残念ながら潮の引きが十分でなかったために、黒滝不整合が清澄層上部を浸食しながら直接覆う黒滝不整合を正面からみられる先端のボラの鼻には行けなかった。そのため、その様子を防波堤の先端からの遠望で確認した(写真39)。また、黒滝不整合を覆う上総層群最下部の黒滝層の特徴的な堆積物は海蝕崖の下に散在する転石で観察した。黒滝不整合直下のタービダイト砂岩優勢互層には、房総中央部の三石山林道や七里川沿いで観察した特徴的な凝灰岩鍵層Ky26(ニセモンロー)タフが挟在していることから、ここでは、黒滝不整合が清澄層上部まで浸食し、七里川沿いでルートマップづくりをしながら観察した清澄層最上部とその上位の安野層全体が浸食されていることが、凝灰岩鍵層との関係から確認できた(不整合下での浸食現象の確認)。また、浸食されずに残ったKy26タフの上部にみられる変形構造が水抜けによって生じたことを示す現象などを観察した(写真40)。このあと、西隣の勝浦海中展望塔のある隣の浜辺に行き、ここの海蝕崖で、房総中央部の三石山林道や七里川で観察した清澄層中部の凝灰岩鍵層Ky21(Hk) タフを再度観察(写真41)。房総半島中央部では、Hkタフやその下位の凝灰岩鍵層はタービダイト砂岩優勢互層中に挟まれていたが、ここでは間のタービダイト砂岩層が極端に薄層化するか消滅しているために泥岩優勢互層中に挟まれ、凝灰岩鍵層同士が上下に密集して存在すること(同時異相現象)を確認するとともに、そこに大小の共役断層群が発達しているのを観察した(写真42)。
これで本研修で予定していたスケジュールを終了したことから、勝浦海中公園のある浜辺で、恒例の修了証書と参加証明書(CPD40単位取得証明書)の手渡し式を行うともに、修了証書受領記念集合写真を撮影した(写真43)。その後、海中公園の駐車場で帰りの身支度をした後、午後2時半過ぎにJR外房線の勝浦駅で解散した。講師陣は使っていた車を茨城県土浦市のレンタカー店に営業時間内(午後7時まで)に返すために、急ぎ北上しぎりぎり間に合わせることができた。
本研修の後始末として、参加者のみなさんには、実施後毎回行っているアンケートへの協力をお願いした。また今回新たな試みとして、小櫃川上流七里川沿いで作成したルートマップデータを基にした七里川流域の地質図や断面図の図学的作成、これらのデータを基にした東海岸の黒滝不整合下での大まかな浸食量の算出を宿題として出した(写真44)。一方講師側の後始末としては、本研修の記録と復習のために、研修中に撮った多くの写真に簡単な説明を加えて編集した一日ごとの実施記録をパワーポイント上で作成、テキストで使っている基本的な図面ファイルを集めた資料編とともに、約1週間後に参加者に送った。5日間にわたる詳細な実施記録の作成は、講師にとっては労力的にかなりの負担であるが、研修で学んだことが復習や会社での報告などを通して最大限身につき今後の業務に活かされることを願って、これまで毎回作成し参加者に配ってきている。
本研修実施にあたっては、担当理事の杉田律子氏を初めとする地質学会の関係者、産総研地質調査総合センターの関係者にお世話になった。また、東大千葉演習林の関係者にも間接的にお世話になった。ここにお礼を申し上げます。
(徳橋秀一・細井 淳)
ページTOPに戻る
写真でみる2016年度秋季地質調査研修の様子
写真1 渕ヶ沢林道(清澄向斜南翼)において、鍵層Ky8(滝つぼ)タフの直下での走向・傾斜の測定(初日午後)。
写真2 渕ヶ沢奥米林道(清澄向斜南翼)でのルートマップの作成の様子(初日午後)。
写真3 野帳に書かれたルートマップの清書(初日夜)。
写真4 清書したルートマップの比較(初日夜)。1マス5mmが10複歩。
写真5 朝もやの中でのルートマップの作成(2日目午前)。渕ヶ沢奥米林道。
写真6 山ヒル発見(2日目午前)。渕ヶ沢奥米林道。塩をかけて振り落します。
写真7 三石山観音寺裏にそびえるご神体(2日目午後)。基底礫岩層(黒滝層)からできている。
写真8 三石山観音寺裏にみられる基底礫岩層(2日目午後)。
ページTOPに戻る
写真9 三石山林道(清澄背斜北翼)でみられる割れ目構造の発達した清澄層上部の厚いタービダイト砂岩層(2日目午後)。
写真10 三石山林道でみられる清澄層上部の鍵層Ky26(ニセモンロー)タフ(2日目午後)。下部のゴマシオ状凝灰岩の2層構造が特徴。
写真11 三石山林道にみられる清澄層中部の鍵層Ky21(Hk)タフ(2日目午後)。堆積構造の発達した優白質のゴマシオ状凝灰岩が特徴。1〜2m上位に黒色スコリアから成るアワオコシタフを伴う。
写真12 薄い凝灰岩層を多数挟む泥岩から成る天津層最上部(2日目午後)。
写真13 片倉ダムサイトからみた天津層と清澄層の境界付近(2日目午後)。ダムサイトは岩相の異なる両累層の境界部に建設されている。
写真14 田代林道(清澄背斜南翼)の天津層・清澄層境界付近(2日目午後)。
ページTOPに戻る
写真15 天津層・清澄層境界直下にみられる斜交層理の発達したKy8(滝つぼ)タフ(2日目午後)。
写真16 渕ヶ沢奥米林道のルートマップの比較(2日目夜)。1マス5mmが10複歩。写真4の右側下端につづく。
写真17 小櫃川上流七里川沿い(清澄背斜北翼)でのルートマップの作成(3日目午前)。清澄層(手前)と天津層(奥)の境界付近。
写真18 七里川の清澄層上部(タービダイト砂岩優勢砂泥互層)分布域でのルートマップ作成(3日目午後)。
写真19 三石山林道でもみた清澄層中部のKy21(Hk)タフとの再会(3日目午後)。
写真20 三石山林道でもみた清澄層上部のKy26(ニセモンロー)タフとの再会(3日目午後)。
ページTOPに戻る
写真21 七里川の支沢に入ってのルートマップ作成(3日目午後)。
写真22 七里川における清澄層(右側)とその上位の安野層(左側)の境界付近(3日目午後)。
写真23 安野層の基底付近に出てくるAn1(さかさ)タフ(3日目午後)。
写真24 七里川における安野層下部の泥岩優勢砂泥互層(4日目午前)。
写真25 安野層中部のタービダイト砂岩優勢砂泥互層(4日目午前)。
写真26 向斜構造軸部ならぬ安野層中部のスランプ堆積物(4日目午前)。
ページTOPに戻る
写真27 七里川における安野層最上部(黒滝不整合付近)(4日目午後)。
写真28 黒滝不整合の境界か(折り尺基底)(4日目午後)。砂質泥岩〜泥質砂岩と凝灰岩の成層構造の上に、厚い塊状の礫岩層(黒滝層の基底礫岩層)が重なる。
写真29 養老渓谷の上総層群大田代層のタービダイト砂層の観察(4日目午後)。表面をたわしで磨いている。
写真30 浮かび上がったタービダイト砂層の内部構造(4日目午後)。たわしで磨いた表面をばけつを使って水で洗い流す。
写真31 養老渓谷中瀬遊歩道で養老川を横断する飛び石のうえで記念撮影(4日目午後)。バックは、上総層群梅ヶ瀬層最下部のタービダイト砂層優勢砂泥互層。
写真32 梅ヶ瀬層のタービダイト砂層優勢砂泥互層の拡大写真(4日目午後)。褐色部がタービダイト砂層で白色部が泥岩層。
ページTOPに戻る
写真33 七里川沿いのルートマップの比較(4日目夜)。1マス5mmが20複歩。左側ページの上端が右側ページの下端につづく。左側ページの分が前のページに書いてあり、みえていないものもある。
写真34 ルートマップのデータを記載した5千分の1地形図の比較(4日目夜)。
写真35 嶺岡中央林道でみられる蛇紋岩の露頭(5日目午前)。
写真36 嶺岡山地北鹿の白絹の滝に露出する層状石灰質チャートの観察(5日目午前)。
写真37 東海岸の鴨川青年の家敷地で観察される枕状溶岩(5日目午前)。千葉県の天然記念物。
写真38 勝浦市吉尾漁港東方のボラの鼻に向かう海蝕崖(5日目午後)。手前にみえるのは清澄層上部のタービダイト砂岩層優勢砂泥互層。
写真39 防波堤からみたボラの鼻の黒滝不整合(5日目午後)。清澄層上部の鍵層Ky26(ニセモンロータフ)直上まで黒滝不整合が切り込んで浸食している。
写真40 ボラの鼻に至る海蝕崖沿いに観察されるKy26タフ上部にみられる水抜け変形構造。
写真41 勝浦海中公園の海蝕崖でみられる清澄層中部のKy21(Hk)タフのゴマシオ状凝灰岩とその約1m上位のスコリアタフ(通称名:“アワオコシ”タフ)(5日目午後)。正断層で何度も上下にずれている。
写真42 清澄層中部の泥岩優勢砂泥互層にみられる大小の共役断層群(フラクタル現象か?)(5日目午後)。
ページTOPに戻る
写真43 勝浦海中公園の浜辺で修了証書受領記念写真(5日目午後)。参加者にはCPD40単位も付与される。
写真44 ルートマップデータを基に図学的に描かれた小櫃川上流七里川沿いの地質図と断面図の一例。宿題として研修終了後に提出されたものである。
ページTOPに戻る
関連のニュース
関連のニュース
大学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準「地球惑星科学分野」の公表
2014年9月30日に日本学術会議より、標記の参照基準地球惑星科学分野が公開された。(全文はこちら)
ここでは、参照基準地球惑星科学分野の内容を簡単に紹介し,参照基準策定の意義と各大学における今後の活用について説明し,大学教育に携わる皆様の注意を喚起したい。
[日本学術会議 第22期地球惑星科学委員会 大学教育問題分科会委員長 西山忠男]
詳細は下記を参照
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//others-pdf/20141104.pdf
(2014年11月4日掲載)
鉱業法第100条の2に基づく鉱物の探査に係る許可申請について
2012年1月21日より施行された改正鉱業法では、「鉱物の探査」行為に関する許可制度が新設されました。資源開発や科学的調査などの目的に関わらず地震探査法や海での電磁法などが許可申請の対象となるとのことですので、ご確認ください。
鉱業法第100条の2に基づく鉱物の探査に係る許可申請について(平成25年12月12日)
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//others-pdf/20131213-1.pdf
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//others-pdf/20131213-2.pdf
(2013年12月13日掲載)
日本学術会議の提言「東日本大震災に係る学術調査—課題と今後について—」
昨年度、日本学術会議による「東日本大震災にかかわる協力学術研究団体の活動の調査(第2回)」が実施され、日本地質学会も調査に協力いたしました。
調査の分析・考察結果は、今年の3月に提言「東日本大震災に係る学術調査—課題と今後について—」にまとめられました。本調査の結果をもとに、文部科学省からの「震災に関する学術調査の実施についての審議」依頼に対して、提言の10ページ「3.文部科学省への回答」の内容が日本学術会議から文部科学省への回答として提出されましたので紹介します。
・日本学術会議の提言「東日本大震災に係る学術調査—課題と今後について—」(平成25年3月28日)
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-t170-1.pdf
・記録「東日本大震災にかかわる協力学術研究団体の活動の調査(第2回)調査報告書」(平成25年6月27日)
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/kiroku/1-250627.pdf
(2013年7月19日掲載)
南相馬巡検報告(2011.11.12-13)
男女共同参画委員会
南相馬巡検報告 (2011年11月12日−13日)
男女共同参画委員会で企画した南相馬巡検(現地見学会・研究交流集会)が2011年11月12-13日に開催されました。本委員会では今年度秋に研究・交流集会を計画していましたが、3.11東日本大震災の被害地域での開催が委員会のメール会議および9月11日の水戸大会の男女共同参画委員会ランチョンで提案され、実施することになりました。参加者は10人(女性5人,男性5人)でした.
今回は田崎和江さんと高橋正則さんに現地での案内や夜の学習会での解説等をしていただきました.また南相馬市の庄建技術株式会社および,社長の鈴木克久さんには今回の集会巡検開催に当たり、いろいろな支援をいただきました.
参加者は11月12日午後1時に福島駅に集合しました。小学生の名和桃子さんには、お母さんと別れて鈴木社長の車で放射線量の低い地域をとおり南相馬に向かっていただきました。おとなの参加者は車2台で高放射線地域を経由して、南相馬市に移動しながら空中放射線量を測定し、また所々で道路や側溝の放射線量測定等を行いました。国道399号線沿いで最も高い数値を示したのは,遠くに福島第一原発の高圧鉄塔が見えるところでした.その後,飯舘村役場や南相馬市役所に立ち寄り,放射線量の電光掲示板が設置されているのも見学しました.今回,庄建技術株式会社には参加者のために白い防塵服と積算線量計を用意していただき, 2日間の被曝量も測定しながらの巡検になりました(2日間でだいたい10μSvでしたが,なぜか私の線量計だけその6倍の値でした).
夜は、阿武隈山地での放射線量値の分布,微生物による放射性物質の除染実験および南相馬から相馬にかけての津波被害状況についての学習会を行いました。また香川淳さんに千葉県の湾岸地域の液状化現象の発表をしていただき、2時間を予定した学習会は2.5時間に延長しても終わらず,引きづつき懇親会会場でもいろいろな話題がでてきて24時近くまで交流会が続きました.学習会と懇親会には庄建技術の鈴木社長も参加いただき、3.11後の地元の状況の話を聞くことができました。 2日目は,当初予定では1日目の最後に見学予定であった南相馬市原町区馬場地内の実験田の見学をしました.この実験田は日本地質学会の「東日本大震災対応作業部会報告書に係わる調査・事業プラン応募」で採択された事業プラン「微性物による放射性物質の除染の実証実験」で、庄建技術株式会社が実施しています。その後、南相馬市原町地区から相馬市松川浦にかけての津波被害地域を見学しました。段丘の下まで押し寄せた津波で多くの方が亡くなった老人保健施設ヨッシーランドでは亡くなった方のご供養に井本香如さんがお経を唱え,参加者全員でご冥福をお祈りました.津波から9ヶ月が過ぎて、現地では大量の瓦礫がかたづけられつつあります.夏を過ぎて遠目には草原に見えるところも,近づいてみると9カ月前まで集落があったことがわかって,空中写真等で津波の広範囲な被害を理解してはいても,現地に立つと改めて何とも言えない絶望感を感じました.
最後松川浦大洲海岸では、津波で海岸道路が破壊寸断された堤防沿いを歩きながら、現在復旧状況を見学し,また相馬港に近い原釜地区で1階部分がほとんど全壊した高橋さんのいとこの方の家を見学させていただき,巡検を終了しました.今回は少ない人数だったため,現地では行動しやすい規模ではありましたが,もっと多くの方に現地を見ていただければと思いました.
(山形大学地域教育文化学部 大友幸子)
南相馬巡検に参加して
東北地方太平洋沖地震の日,私はつくばの研究室にいました.揺れはじめの頃は「ああ,ついに大きな地震が来ちゃったね」などど同室の同僚と話をしながらマグカップを押さえたり,崩れそうなものを押さえたりしていました.しかし,揺れは治まらないどころか,本棚からは本や飾ってあった岩石等が降り注ぎ,パソコンやディスプレイもことごとく「飛ぶ」という大揺れに見舞われました.実験仕様の頑丈な机の下に避難しながら,研究所の建物が崩壊するのでは?と,はじめて死を意識しました.その後の原発事故についても,県内におなじ原発を持ち,子どもを放射線量の低くない地域で育てていかなければならない者の一人として,苦慮する日々が続いています.
南相馬巡検には,当事者意識を持って参加させていただきました.1日目午後は,福島駅から川俣町,飯館村を経て南相馬市まで放射線量を計りながら移動するという,まさに体験型の巡検でした.とくに国道114号線から399号線に入ったとたん,それまでの値より二桁急上昇する線量計の数値を見た時には衝撃を受けました.また,犬や猫しか残されていない数々の集落を見るにつけ,目に見えない,匂いもしない,人間の五感で感知できない放射能に対しての恐ろしさを実感せざるを得ませんでした.夜はホテルで学習会が行われ,案内者の田崎さんと高橋さんから巡検コースと除染実験の解説がありました.千葉県環境研究センターの香川さんからは,浦安市内での液状化被害についての研究結果の紹介がありました.
2日目朝は,放射線量の計測と除染実験をされている庄建技術株式会社の実験室を見学した後,除染実験農場を見学しました.まさに試行錯誤を繰り返し,粘り強く実験を続けておられる実験グループの方々の姿に感銘を受けるとともに,科学者としての原点を見る思いでした.午後は相馬市の海岸沿いの津波被害状況を見ました.これまで新聞やテレビ報道,学会等で浸水被害図等を見てはいましたが,現地に行ってみてはじめて,「こんなに海から離れていて,海岸線も見えないほどに街が出来上がっていたら,津波がここまで来るとは思わないのではないか」と思える箇所も多々ありました.また,一緒に参加していた娘と,「ここにいる時に津波が来るとしたら,どちらにどういうふうに逃げるか」と,その場学習することもできました.
他にも天然の岩石のもつ放射線量についての話や福島県北部沿岸域に広く露出している大年寺層についての話,地質コンサルタント会社や海外勤務での経験談等,案内者のみならず,参加者各人からの深く幅広い話題それぞれがとても興味深く,有意義な2日間を過ごすことができました.今回の巡検の企画・運営をして下さった山形大学の大友幸子さん,案内者の田崎和江さん,高橋正則さん,参加者の皆様に厚く篤く御礼申し上げます.また,一人しかいない小学生参加者である娘のために,わざわざ別コースを準備・案内して下さった庄建技術株式会社の鈴木社長に記してお礼申し上げます.最後に,本巡検・研究交流集会と同様の巡検会を再度企画することを提案し,より多くの方々がそれに参加されることをお勧め致します.
(産総研 活断層・地震研究センター 宮下由香里)
飯舘村長泥地区で、道路や路肩の放射線量を測定。
南相馬市原町区の実験田の説明看板
実験田の中の水路を見学中
空中写真を見ながら2日目に見学する津波被害地の説明を聞く
津波で表土がはがされてできた鮮新統大年寺層の露頭と、津波で運ばれてきた瓦礫の一部が下の車道から10mくらいの高さのところに散乱している。道路の向こうは、津波前は相馬市磯部地区の集落だったところ。
津波で破壊された松川浦大洲海岸沿いの道路。写真右側が堤防。道路は左側で、半分以上なくなっている。
→男女共同参画TOP頁にもどる
意見・提言2013
意見・提言2013
「原子炉施設の敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド(案)」に関するコメント
現在,原子力規制委員会の中では「発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる規制基準」の策定が行われております。その中で,添付の「敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド(案)」が策定され、これに対する意見募集が行われました。これに対して、日本地質学会から以下のとおり意見を提出しましたので紹介します。
なお,「原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(案)等に関連する内規に対する意見募集について」の本文については,以下のURLを参照ください.
http://www.nsr.go.jp/public_comment/bosyu130410_02.html
募集案件(37)敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド(案)(PDF)
■日本地質学会より提出した意見書はこちら
(2013年5月13日掲載)
日本地質学会は日本学術会議の提言「地質地盤情報の共有化に向けて」に賛同します
2013年2月5日
一般社団法人日本地質学会 会長 石渡 明
1月31日付けで日本学術会議地球惑星科学委員会より「地質地盤情報の共有化に向けて —安全・安心な社会構築のための地質地盤情報に関する法整備—」との提言がなされました.ボーリングデータをはじめとする地質地盤情報は防災・資源・環境に関わる社会的な諸問題を解決するために必要不可欠であることは,我々地質に関わる者にとって言うまでもありません.しかし地質地盤情報の整備・公開,そして情報の共有化は必ずしも進んでいないのが現状です.日本学術会議の提言では,地質地盤情報が社会にとって極めて重要な情報であること,そして地質地盤情報の整備・公開・共有化を進めるためには,法律の制定,共有化等の仕組みの構築,利用促進と国民の理解向上が必要であることが述べられています.このような具体的な提言が日本学術会議からなされたことは極めて高く評価されるものであり,当学会もこの提言に共感し,賛同するとともに、この提言に沿った地質地盤情報の共有化が実現することを切に願うものです.
これまでボーリングデータ等の地質地盤情報を取り扱うのはむしろ工学分野の専門家が多かったように思います.しかし地層を正確に理解するためには,工学的特性のみならず,地質地盤情報を地層の成因まで立ち戻りながら地質学的に総合的に解釈していく必要があります.そのためには地質の専門家が必要であり,まさにそれは日本地質学会会員の大きな役割のひとつと考えます.また提言では,「地質地盤情報の活用を促進し,地質地盤情報が国民の共有財産であることを国民に周知し,理解向上に努めるべき」としています.そのためには防災・資源・環境等の諸問題を解決するために地質地盤情報が極めて重要であることを実際の活用事例として示すことが重要です.日本地質学会は,地質地盤情報に関する科学的基礎研究をより一層推進するとともに、その利用を促進し,その活用事例の公表・アウトリーチの場を積極的に設け,地質地盤情報の重要性,公共性,そして地質地盤情報が国民の共有財産であることについて,国民の理解向上に努めていく所存です.また法律の制定,情報の共有化等の仕組み構築に関しても,地質を専門とする学会の立場から,可能な限り貢献していきたいと考えております.
日本学術会議による提言:「地質地盤情報の共有化に向けて−安全・安心な社会構築のための地質地盤情報に関する法整備−」
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-t168-1.pdf
(2013年2月5日掲載)
2011年度実施報告(地学情報サービス)
2011年度春季地質の調査研修の実施状況
写真でみる2011年度春季地質の調査研修の実施状況(地学情報サービス株式会社実施)
写真1:初日の林道沿いでのルートマップ作成中の様子(清和県民の森:清澄向斜南翼の清澄層下部分布域).
写真2:初日林道沿いで作成したルートマップの清書後の比較(初日夜).1マス(5mm)は10複歩.作成されたルート図には,凝灰岩鍵層,走向・傾斜,岩相などの情報も記載されている.上方が北(磁北).
写真3:ほぼ100%地層が連続して露出する猪の川(黒滝沢:清澄背斜北翼)沿いでのルートマップ作成中の様子.
写真4:最初一緒に沢沿いを歩きながら確認した主な凝灰岩鍵層には,鍵層名(通称名)の標識がつけられる.
写真5:夜の作業風景.昼歩きながら鉛筆で作成したルートマップのルート図や地質情報を清書(墨入れ)し,その後,岩相の違いなどを色鉛筆で表現する.
写真6:猪の川(黒滝沢)沿いで作成したルートマップの清書後の比較(4日目の夜).左頁のルート図右下端が右頁のルート図の右上端につづく(安野層〜天 津層上部分布域).1マス(5mm)は20複歩.地層の走向方向(東西)方向に猪の川が蛇行しながら伸びる安野層の分布域では,南北性の複数の断層で上下 (南北)方向にずれながらも,走向(東西)方向に鍵層やスランプなどがよく連続することを最初歩きながら確認したが,その様子がそれぞれのルートマップ (左頁)にもよく表現されている.北から南へ順に,安野層・清澄層・天津層が分布する様子も描かれている.また初日のルートマップと比較することによっ て,清澄向斜部と清澄背斜部とでは,清澄層下部の岩相・層厚に顕著な変化があることも確認される.
写真7:東海岸の勝浦市吉尾漁港東方のボラの鼻で,黒滝不整合と再会(5日目午後).ここでは,房総中部の猪の川沿いで黒滝不整合の下に観察された安野層はすべて浸食されて,その下位の清澄層の上部を黒滝不整合が直接覆っていることを確認できる.
写真8:修了証書受領後の記念撮影(勝浦海中公園:5日目午後).参加者には,この他に,土質・地質技術者のための継続教育(CPD)40単位が与えられる.
<参考文献>
徳橋秀一編著(2002)「タービダイトの話(「地質ニュース」復刻版)」実業公報社,252p.
徳橋秀一・石原与四郎(2008)「千葉県清和県民の森周辺の地質図(1万5千分の1)と「同説明書」,産総研地質調査総合センター,特殊地質図 No.39,95p.
徳橋秀一編著(2011)地質ニュース復刻版第2弾「ご地層の話−地層観察・地質調査・露頭保存の重要性を唱えつつ−」実業公報社,203p.
以上
プレスリリース(2013年)
プレスリリース(2013年)
日本地質学会第120年学術大会(仙台大会)(9/9)
発表形態:資料配付
発表先:文部科学省記者会
記事解禁日時:平成25年9月9日
■説明資料(PDF)( 本文 添付資料1 添付資料2 )
■その他資料 ( 情報展 市民講演会 シンポジウム )
日本-ロンドン地質学会学術交流協定を締結(8/8)
発表形態:資料配付
発表先:文部科学省記者会
記事解禁日時:平成25年8月8日
■説明資料(PDF) ■協定書(JPG)
5月10日地質の日第6回事業のご紹介(5/2)
発表形態:資料配付
発表先:文部科学省記者会
記事解禁日時:平成25年5月2日
■説明資料(PDF)( 本文 添付資料1 添付資料2 添付資料3 )
2013-5-13 「原子炉施設の敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド(案)」に関するコメント
「原子炉施設の敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド(案)」に関するコメント
一般社団法人日本地質学会
日本地質学会では,「募集案件(37)敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に関わる審査ガイド(案)」につきまして,「地質・地質構造調査に関わる」とことから内容を確認させていただきました。
内容は,安全審査についてのガイドという観点からは概ね問題はないと思われます。ただし,12ページ〜13ページ 「4.1.2.3 地質調査」の部分は,誤解を生む可能性があると思われますので,ご検討願いたく存じ上げます。
13ページ〔解説〕に「(7) 断層破砕物質の性状に関する知見は、断層の活動性評価に対し、参考にはなるが、現状では決定的な証拠にならないことに留意する必要がある。」という項目がございます。
当該審査ガイド(案)を拝見しますと,この部分だけが「現状では決定的な証拠にならない」という否定的な表現になっており,この文章だけ読んでしまうと破砕物質の調査は行う必要はないと受け取られかねません。ところが,敦賀原発や大飯原発の場合など,敷地内断層の有識者会合においては破砕物質の観察がかなり重要なポイントを占めているため,表現を改めてもよいと考えます。
また,「断層破砕物質の性状に関する知見」とは,何か具体的な性状を念頭において書かれたのかどうか,曖昧に感じられます。念頭においている性状がある場合には,具体的に記述する必要があります。
同ページの〔解説〕「(5) 断層の活動性評価に対し、断層活動に関連した微細なずれの方向(正断層、逆断層、右横ずれ断層、左横ずれ断層など)や鉱物脈あるいは貫入岩等との接触関係を解析することが有効な場合がある。」に記されている内容は,専門的観点から見て,断層の「性状」に含まれます。すなわち,断層破砕物質は,(5) の議論に対しては有効性があります。一方で,(7) の文案は(5) における断層破砕物質の有効性まで否定する可能性があるため,当該審査ガイド内で矛盾を来たすことを危惧いたします。
この様な理由から,「4.1.2.3 地質調査」の〔解説〕 (5) と(7) につきまして,内容を再検討していただくよう,よろしくお願い申し上げます。
募集案件(37)敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド(案)(PDF)
原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(案)等に関連する内規に対する意見募集について
http://www.nsr.go.jp/public_comment/bosyu130410_02.html
(2013年5月13日掲載)
意見・提言2021
意見・提言2021
熱海伊豆山地区土石流についての会長コメント
2021年7月6日
一般社団法人日本地質学会
会長 磯粼行雄
梅雨前線の活発な活動により,2021年7月3日に静岡県熱海市伊豆山地区では土石流が発生し,甚大な被害が生じました.亡くなられた方々にはお悔やみ申し上げるとともに,被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます.本学会としては,この災害の発生および規模の拡大にどのような地質学的な要因があるのかを注視しているところです.会員および関連機関による最新の調査報告について随時学会HPで発信していく所存です.
東日本大震災から10年にあたって
2021年3月2日
一般社団法人日本地質学会
会長 磯粼行雄
2011年3月11日に発生した東日本大震災から間もなく10年となります.未曾有の大災害に対して各地で復興はすすんでいますが,未だ被災者の皆様の心の傷は十分に癒やされていないことでしょう.この10年間を顧みると,地震だけでなく,火山噴火,台風や大雨などによる風水害,土砂災害,大雪による雪害など,個別に挙げるのもためらうくらい多様な災害に見舞われました.さらに,新型コロナウィルスの世界的な蔓延は人間社会に計り知れない影響を与えています.
そんな中,再び2月13日に福島県沖でM7.3の地震が発生し,地域によっては東日本大震災の時よりも大きな被害がでました.防災科学技術研究所によると,宮城県山元町の観測点でこの地震による揺れの加速度が1432ガルを記録しました.これは,2016年4月16日の熊本地震において震度7を観測した熊本県益城町で記録された1362ガルを上回るものでした.今回の福島県沖の地震は東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋沖地震の余震と考えられ,今後これを上回る余震が発生する可能性も否定できません.一人一人の人生のスケールとは違い,自然災害は決して10年で一区切りとはならないことを再認識させられました.
地質学会では,災害が発生する度に地質災害委員会を中心に会員が携わる災害調査,発生原因の研究結果等を取りまとめてホームページに掲載する等の活動を行ってきました.2011年には東日本大震災にかかる「復旧復興にかかわる調査・研究事業」として会員による調査研究事業を支援しました.また,複合災害への対応や異なる研究分野との協働のため,地質学会は防災学術連携体(日本学術会議の協力学術研究団体;自然科学,人文科学,社会科学など多岐に渡る58学会で構成)に参画しています.その中で豊かな知見を全体で共有・活用できるよう各種シンポジウムなどを活発に行っています.今後もこのような社会に貢献する学術活動を進めていくことが,本学会の重要な使命の一つであることを会員の皆様と共有したいと思います.災害に強い社会を作るために互いに協力して頑張りましょう.
令和3年度大学入試共通テストの地学関連科目に関する意見書
2021年2月22日
独立行政法人大学入試センター
理事長 山本 廣基 様
一般社団法人日本地質学会
会長 磯粼行雄
日本地質学会は、ここ数年にわたり、旧大学入試センター試験の地学関連科目の問題作成および得点調整に関わって、意見並びに改善に向けた要望を大学入試センターに申し入れしてきたところです。その要望の主眼は、地学関連科目の平均点が他の理科科目に比べて低くならないようにしていただきたいということでありました。本年度はコロナ禍の中、問題作成に携わった関係各位の努力に敬意を表するとともに、令和3年度大学入試共通テスト(本試験)の地学関連科目に関して、以下のような意見を申し入れ致します。
理科①の「地学基礎」においては基礎的な問題が出題されており、適正 かつ良質な問題であったと考えます。他の科目の平均点と比べて難易度も適正であったと思われます。
理科②の「地学」においても、共通テストの目的に合致した思考力・総合力が試される、良質な問題であったと考えます。しかし、「地学」の平均点は47.06 点で、昨年よりは少し改善されたものの、例年同様、他科目に比べて低い得点となりました。問題・配点等を工夫していただき、平均点が他科目に比べて低くならないようにしていただきたく、さらなる努力をお願い致します。
2013年度春_研修実施報告
2013年度春季地質調査研修実施報告
はじめに
標記の研修を2013年5月27日(月)〜5月31日(金)に実施した.今回の参加者は定員の6名(男性5名,女性1名)であった.その内訳は,地元(千葉県茂原市)の建設系コンサルタント会社(さく井所属)から土質改良出身の参加者が1名(男性)で,他の5名は,いずれも,石油・天然ガスの開発会社(探鉱所属)からの参加者で,地質出身が4名(女性1名),物探(地球物理)出身が1名であった.みなさん,入社2年目から5年目で,年齢的には25歳から29歳の若手技術者であった.講師は,産総研地圏資源環境研究部門客員研究員の徳橋秀一と産総研地質情報研究部門主任研究員の辻野 匠である.
5日間のスケジュール
各日の実施概要は次の通りである.
※それぞれ図の番号をクリックすると、写真へジャンプします。写真からはブラウザのボタン等で戻ってください。
5月27日(月) (曇り)
JR外房線君津駅に午前11時集合後,小糸川上流の清和県民の森に移動.山ヒル対策を実施したのち(第1図),清澄向斜南翼に位置し,清澄層下部の厚いタービダイト砂岩優勢互層が分布する林道沿いで,主な凝灰岩鍵層の観察,クリノメーターを使った層理面の走向・傾斜の測定法,クリノメーターを使ったルート図の描き方などの練習を行った後,ルートマップの作成作業を実施した(第2図).夜は清書などの整理作業を行った後(第3図),互いのルートマップを比較した(第4図).また,研修地域の地質や地層の特徴について,配布したテキストを使って復習と予習を実施した.
5月28日(火) (曇りときどき雨)
清澄背斜北翼に位置し,黒滝不整合発祥の地の小櫃川支流猪の川(通称“黒滝沢”)の黒滝で不整合の状況を観察するとともに,沢歩きになれながら,猪の川沿いに分布する安野層,清澄層,天津層それぞれの岩相の特徴や主な凝灰岩鍵層の確認(第5図),重要な断層についての確認と断層面の走向・傾斜の測定法の習得(第6図)などを行った.特に清澄層と天津層の境界付近では,前日の清和県民の森の林道(清澄層向斜南翼)で,清澄層下部の厚いタービダイト砂岩優勢互層中に上下に分散しながら挟まっていた凝灰岩鍵層が,清澄背斜北翼では,順序良く産出するものの間にタービダイト砂岩が全くなく,上下に密集して産出してその間の厚さが極端に薄くなっていること(地層の背斜軸への収れん現象)を確認した(第7図).夜は,講師の昔の野帳に書かれたルートマップなどを参照するとともに,テキストその他の資料を使いながら,こうしたルートマップづくりや凝灰岩鍵層を利用してこの地域で得られた研究成果について学習した.
5月29日(水) (曇りときどき雨)
猪の川沿いの安野層,清澄層,天津層の分布域のルート図を作成しながら,前日観察し確認したことがら(岩相,鍵層,断層など)を記載してルートマップを作成した(第8図,第9図).夜は清書作業や復習などを実施.
5月30日(木) (雨ときどき曇り)
この日は強い雨が断続的に降るという予報から,林道や遊歩道沿いでの作業に予定を変更した.午前は,清澄背斜軸部近くの南北両翼の天津層と清澄層境界部付近の地層・凝灰岩鍵層を観察するとともに(第10図),北翼の三石山林道沿いでは,猪の川沿いで観察した清澄層のHkタフ(Ky21)を詳しく観察.この後,三石山に行き,三石観音のご神体となっている三石(第11図)など,黒滝不整合直上の凝灰質砂礫層(黒滝層)を観察した.午後は,より新しい時代のより変形の少ない地層を対象に地層の見方を強化する観点から,養老川沿いで,上総層群の大田代層を中瀬遊歩道で,黄和田層を粟又の滝遊歩道で観察した.中瀬遊歩道では,弘文洞跡のところで,タービダイト砂岩表面をたわしでこすった上でバケツで水をかけるなどして,タービダイト砂岩層の堆積構造を浮き彫りにして詳しく観察するとともに(第12図,第13図),粟又の滝遊歩道では,一見泥岩層にみえる地層も詳しく観察するとタービダイト砂岩中の泥岩偽礫の密集体である例がたくさんあることを観察した.夜は,テキストなどを使って,研修地域の地質・地層の特徴とこれまでの研究成果について再度詳しく説明し,理解を深めるようにした.
5月31日(金) (晴れ)
まず,外縁隆起帯をなす嶺岡構造帯(嶺岡山地)を構成し蛇紋岩中に散在する代表的なブロック (層状石灰質チャートと枕状溶岩のブロック)を観察した.その後,東海岸の勝浦海中公園において,猪の川や三石山林道で観察した清澄層中部のHkタフを再度観察し(第14図),凝灰岩鍵層が広域的に連続するとともに前後の岩相が小櫃川流域とは変化していること(同時異相関係)を確認した.そして次に北隣のボラノ鼻に移り, 清澄層上部のタービダイト砂岩優勢互層を直接覆う黒滝不整合を観察し(第15図),猪の川沿いで観察した安野層が,ここでは全部浸食されて存在しなという不整合下での浸食現象を体験的に理解することができた.そしてボラの鼻からもどる途中では,それまで何度かみてきた清澄層上部のタービダイト砂岩層の直上にみられるタービダイト泥岩と非タービダイト泥岩の特徴の違いを識別できるように,観察力強化の訓練を行った.この後,勝浦海中公園の浜辺で,恒例の修了証書の授与を行い(第16図),午後4時前に外房線のJR茂原駅で解散した.
今回の研修の特徴
今回は研修3日目に関東地方が梅雨入りするなど,雨の影響で当初の予定を一部変更した.特に,研修の3日目がときどき雨,4日目が強い雨混じりの天気という予報が出たために,安全と作業内容を考慮して,例年2日目から3日間かけて行っていた猪の川沿いでのルートマップづくりを2日間で終えるようにやり方を一部変更した.代わりに, 雨の日でも実施可能な地層観察用の資料を事前に用意し,4日目は上総層群の代表的な地層を養老川の遊歩道沿いで観察するなど,地層の見方,観察法を充実する形で,雨による影響を最小限にとどめるようにした.
昨年は潮の引きがもうひとつ弱かった上に波が強くて,東海岸のボラの鼻先端の黒滝不整合を真正面から観察することができなかったが,今回は潮の引きもよく,先端部まで行って迫力があることで知られるボラの鼻の黒滝不整合をまじかに観察することができた.また4日目には,三石山山頂(三石観音)付近でも黒滝層を観察するなど,黒滝不整合前後の地層を3ヶ所で観察したことになる.
今回,3日目,4日目は,雨混じりのなかでの作業となったが,雨の中での作業も可能なように,傘と雨合羽を用意しておいたこともあり,それなりの作業を実施することができた.また幸い,風邪を引く人も怪我をする人もなく,無事終了することができた.
山ヒル対策
山ヒルの被害が少しあったので,ここで簡単に言及しておく.昔は清澄寺周辺にしかいなかったシカの分布域が周辺に広がるにつれ,山ヒルも房総のかなり広い範囲に生息するようになった.研修中の山ヒル対策としては,最近は,地元の看板などで推奨されている方法に習って,毎朝長靴とズボンの間をガムテープ(布テープ)でぐるぐるまきつけるとともに,山ヒルが付着しそうな場所での行動に気をつけ,その都度互いにチェックし,付着を発見した際には速やかに塩を振りかけて落とすことが定番となっている.山ヒルは,草むらや湿地のところに好んで潜んでいることから,川の中から林道に上がる際や林道脇で作業する際に長靴に付着しやすく,その都度よくチェックし付着していた際には塩を振りかけて落下させた.このように布テープと塩の準備が大切である.特に布テープによるぐるぐる巻きは,長ぐつの中への山ヒルの侵入防止のみならず,川歩きの際の水の混入防止にも役立つとともに,布テープ同士の継ぎ目のところに山ヒルが閉じ込められトラップされることも多いことから一石三鳥である.また,付着した山ヒルに塩を少し多めにかけるとナメクジと同じく急速に収縮して落下する.山ヒルは雨の日に特に活発化することもあって,今回は塩の出番が多かった.これまで被害者が出てもひとり程度であったが,今回は2人が山ヒルに1ヶ所ずつかまれた.ただ見つけるのが早かったためか,幸いあとに尾を引くことはなかった.このように,事前の準備と必要な注意をしていれば特に怖がることはないといえる.
おわりに
研修実施中は,参加者はルートマップづくりなどの作業に追われ,写真を撮っている時間がないことから,参加者への記録と復習になることを第一に,今回も講師が撮った写真をもとに研修中の出来事を日づけごとにパワーポイントにまとめ,それらに簡単な説明を加えた上で,研修の次の週末には参加者に届くように送った.研修参加者がこれらのファイルを参照して復習していただくならば,また会社での報告などの際に,適宜編集しながら活用していただければ,本研修への理解はさらに広まり深まることが期待される.
本研修実施にあたり,毎回のことながら,研修の主現場として利用させていただいた東京大学千葉演習林の関係者の方々をはじめ,関係機関・関係者の方々に厚くお礼を申し上げたい.今年は秋にも実施予定であり,関心のある方は是非参加を検討していただきたい.
(徳橋秀一・辻野 匠)
写真でみる2013年度春の地質調査研修(2013.5.27〜5.31に実施)の実施状況
第1図 山ヒル対策。長靴とズボンの間の隙間を布製のガムテームでぐるぐる巻きにする。
第2図 清和県民の森の林道沿いでのルートマップ作成。周りの地層は、清澄層下部の滝つぼタフ(Ky8)からバーミューダタフ(Ky7)の間のタービダイト砂岩優勢互層。
第3図 夜の清書作業。昼に鉛筆で書いたルートマップは、夜、極細のペンで清書するとともに、岩相をカラー鉛筆で色づけする。
第4図 清和県民の森の林道沿いで初日の午後作成したルートマップの比較図。ルートマップには、ルート図の他に、岩相の特徴、凝灰岩鍵層の分布、走向・傾斜なども記入されている。
第5図 安野層最下部の凝灰岩鍵層さかさタフ(An1)。確認した特徴的な凝灰岩鍵層には、見落とさないように、チョークで表札をつけていく。
第6図 断層の測定。変移量の大きい断層は、断層面の走向・傾斜を測定する。ここでは、南北性の高角断層によって、安野層の泥岩(左側)と清澄層のタービダイト砂岩優勢互層(右側)が接している。
第7図 猪の川沿いの清澄層と天津層境界付近における滝つぼタフ(Ky8)からバーミューダタフ(Ky7)の間。厚さと岩相に顕著な違いがあることが、第2図との比較で明らか(背斜軸へ向けた地層の収れん現象)。
第8図 猪の川沿いでのルートマップづくりは、黒滝不整合発祥の地の黒滝から開始。
第9図 猪の川沿いでのルートマップ作成の様子。ルート図をつくりながら、岩相、凝灰岩鍵層の位置、地層の走向・傾斜、断層などの情報を記入する。
第10図 片倉ダム近くの清澄背斜南翼の清澄層−天津層境界付近。ここでは、斜交層理の発達した滝つぼタフ(Ky8)の直上から、清澄層の厚いタービダイト砂岩優勢互層が発達している。
第11図 三石山の由来といわれる三つの巨石。三石観音のご神体であり、黒滝不整合直上の凝灰質砂礫層(黒滝層)から構成されている。
第12図 養老渓谷中瀬遊歩道の対岸にある弘文洞跡。崖の大部分は上総層群大田代層上部の泥岩優勢互層であるが、最下部にタービダイト砂岩優勢互層が一部顔を出す。
第13図 弘文洞跡の崖の最下部で、たわしやバケツを使いながらタービダイト砂岩の堆積構造を観察。堆積時の模様が浮かび上がってくる。
第14図 勝浦海中公園の浜辺でみられる清澄層中部のHkタフ(Ky21)。Hkタフの名前は神奈川県の逗子市の東小路に由来。陸上の分布域は東西約70Kmにおよび、その東端がここ勝浦海中公園である。
第15図 東海岸の勝浦ボラの鼻先端部の黒滝不整合。清澄層上部のタービダイト砂岩優勢互層を削り込んで、上総層群最下部の黒滝層が覆う。
第16図 勝浦海中公園をバックにした地質の調査研修修了証書受理後の記念写真。研修参加者には、この他に、技術者継続教育単位(CPD)40単位が与えられる。
2013年秋季研修実施報告
2013年度秋季地質調査研修の実施報告
標記の地質調査研修が、11月18日(月)〜11月22日(金)の4泊5日、房総半島の山中を中心に行われた。どこの会社でも参加できるような若手技術者を主な対象とした地質調査研修を毎年やってほしいという地質関連会社からの要請を受けて2007年に始まった本研修は、毎年実施して今年で7年目になるが、春・秋と年2回実施するのは今年が初めてである。今回は当初申込み状況が芳しくなかったが、締切日近くになって定員の6名に達し、実施の運びとなった。参加申し込みは、都内の石油天然ガス開発会社2社から4名、千葉県の水溶性天然ガス会社から1名、都内の鉱床・地熱等資源会社から1名であった。分野別には、地質出身が4名、物理探査出身が1名、地球化学出身が1名であった。また、第四紀学や堆積学分野で活躍する千葉県立中央博物館学芸員の岡崎浩子氏には、これらの分野の方への広報を兼ねて、オブザーバーとして都合で前半の2泊3日間のみ参加していただいた。講師は、産総研地圏資源環境研究部門客員研究員の徳橋秀一と産総研地質情報研究部門主任研究員の納谷友規である。
※それぞれ文中の図番号をクリックすると、写真へジャンプします。写真からはブラウザのボタン等で戻ってください。
今回は11月後半というこれまでで一番遅い時期での実施となり、寒さや昼時間の短さが懸念されたが、冷たい風が強かった中日水曜日の曇りを除くと、他の日は小春日和の比較的暖かい晴天に恵まれ、併せて、紅葉も楽しむことができた。また、朝晩が冷えるせいか、山ヒルには一度も出会わないなど、好条件がそろった研修となった。ただ、これまでよりも日が暮れるのが早いのだけは避けられなかったので、宿での朝食の時間をいつもより30分早めて6時半からとし、毎朝宿を出る時間を早めるように努めた。このように天候に恵まれた結果、ほぼ予定通りのスケジュールで実施することができた。
初日は、予定通り午前11時に内房線のJR君津駅に集合、昼食を早めに済ませた後、駅近くのホームセンターで必要な人はスパイク付長靴を購入、その後、初日の研修地に向かって移動、途中宿で着替えをしながら目的地には午後1時半に到着した。初日の研修地域は、小糸川上流の清和県民の森のなかの渕が沢林道沿いである。この林道は、ほぼ東西に伸びる清澄向斜の南翼に位置し、清澄層下部のタービダイト砂岩優勢互層の中を蛇行しながらも走向方向にほぼ平行しながら伸びていることから、いくつかの凝灰岩鍵層を何度も観察することが可能である。研修参加者は、林道沿いに露出するこれらの凝灰岩鍵層の特徴を確認するとともに、クリノメーターを使った地層の走向・傾斜の測定法と、やはりクリノメーターを使ったルート図の描き方を練習、その後、早速ある区間のルートマップの作成に挑戦してもらった(第1図)。ルートマップの作成にあたっては、クリノメーターと歩測(複歩)でルート図を描きながら、同時にそこに露頭の分布状況、岩相、走向・傾斜、凝灰岩鍵層の位置などの情報を描くことになるので、最初大変であるが、毎年この方法で実施している。現地では4時45分ころまで作業を行った。墨入れや着色といった清書作業は、夜宿でひとつのテーブルを囲みながら行い(第2図)、作業が一通り終わったところで、各自作成のルートマップを比較し検討を行った(第3図)。
2日目〜4日目までの3日間は、主に清澄背斜北翼に位置し、地層がほぼ100%連続して露出する小櫃川支流猪の川(黒滝沢)上流(東京大学千葉演習林内)において研修を行った。2日目は、初日の研修対象との関係から、まず上流側の清澄層および天津層上部分布域の沢沿いを上流(南方)に向かって歩きながら、岩相、主な凝灰岩鍵層の特徴を観察、確認した(第4図)。特に、初日に清澄層下部のタービダイト砂岩優勢互層中に上下に離れながら挟まれていたKy9からKy5の凝灰岩鍵層が、ここでは上下に密集して産出し、その間にあったタービダイト砂岩などは全く挟まれていないことが確認され(第5図、第6図)、清澄層初期のタービダイト砂岩は向斜部にしか存在しないこと、その結果、向斜部から背斜軸部へ向けての地層の顕著な収れん現象が起きていることを説明した。その後さらに南下して天津層上部の中を歩いたのち、今度は反転し下流(北方)に向かってルートマップを作成しながらその日の出発点まで歩いた(第7図)。この日作成したルートマップも夜清書し、互いに比較しながら検討した。
3日目は、黒滝不整合直上の地層(上総層群黒滝層)の上下方向での変化を観察するとともに、その直下に広がる安野層の分布域の沢沿いを歩きながら、安野層の岩相や凝灰岩鍵層の特徴を観察した。安野層の場合、多数の凝灰岩鍵層が設定されていることから、そのなかでも特に目立つものには河床に落ちている大きめの泥岩礫に鍵層の名前をチョークでつけて鍵層の横において識別できるようにした(第8図)。安野層分布域の猪の川は、走向方向(ほぼ東西方向)に大きく蛇行しながら流れる上に、その流域に多くの南北性の断層が存在することから(第9図)、多くの鍵層が断層でずれながらも、走向方向によく連続することを歩きながら確認した。また、幅数mの破砕ゾーンを伴うような断層の場合には、その両側でのずれが大きいことも鍵層との関係でおおまかに確認することができた。4日目は、3日目に安野層分布域を歩きながら確認したことをルートマップに表現するのが目的で、黒滝不整合発祥の地である黒滝から始めたが(第10図)、夜にはそれを清書し、互いに比較した(第11図)。また、猪の川での作業が終わったのち、3日目には清澄背斜西側延長部での南翼、北翼における清澄層と天津層の境界部の特徴を林道沿いで観察し(第12図)、4日目には、清澄背斜北翼の三石山林道において、清澄層の代表的な凝灰岩鍵層であるKy21タフ(Hkタフ)やKy26タフを三石山林道沿いで観察するとともに、ご神体が黒滝不整合直上の礫層(黒滝層)である三石山頂上近くの三石寺にも参拝した。
最終日の5日目は、まず、清澄山系に分布する安房層群天津層、清澄層、安野層を堆積した清澄海盆の外縁隆起帯を形成していたと思われる嶺岡構造帯の代表的な岩石(蛇紋岩、層状石灰質チャート、枕状溶岩)を嶺岡山地周辺で観察した(第13図、第14図、第15図)。その後、海岸沿いを北上して勝浦海中公園に行き、まずそこの海蝕崖で、猪の川沿いや三石山林道沿いで観察した清澄層中部のKy21タフ(Hkタフ)を再度観察し、20km前後離れていてもよく連続することや、房総半島中央部では、その下位の地層がタービダイト砂岩優勢互層であったのがこの辺りでは泥岩優勢互層に変化していること(同時異相現象)を確認するとともに、大小の共役断層群を観察した(第16図)。その後、東隣の吉尾漁港の東方に突き出した海蝕崖に沿って、清澄層上部のKy26タフを横目にみながら歩き、先端のボラの鼻を目指した(第17図)。しかし、潮の最も引く時間帯に合わせてはいたが、この時期は夜に比べて昼の潮の引きが十分でなかったため、途中の深みを越せずもう少しのところで引き返した。先端部まで行けるとボラの鼻の黒滝不整合として有名な不整合が観察できたが、やむをえず、防波堤から遠望するにとどめた(第18図)。いずれにせよ、ここでは前日三石山林道沿いで観察した清澄層上部のKy26タフの直上まで黒滝不整合が下位層を侵食しており、房総半島中央部の猪の川沿いでルートマップをつくりながら観察した安野層全体が侵食していることを確認し、不整合の下では侵食が起きるという不整合の基本的現象、定義を黒滝不整合を通して体験した。このあと、清澄層上部のタービダイト砂岩の堆積構造や泥岩中にみられるタービダイト泥岩と半遠洋性泥岩の2種類の泥岩の特徴の違いやKy26タフにみられる水抜け構造などを観察した(第19図)。
これで予定していた研修はすべて終わったので、恒例の研修修了証書の授与式を勝浦海中公園で行い、終了後記念写真を撮った(第20図)。この後、車は北上し、途中上総層群分布域の河床でみられる天然ガスの自然湧出現象を見学した後に近くのコンビニで着替え、4時頃に外房線JR茂原駅で解散した。なお研修期間中は、参加者はルートマップの作成などの作業に追われることから、研修中の主な観察対象や研修作業の様子を写真にとり、それを基に簡単な説明も加えたパワーポイントファイルを作成し、研修後できるだけ早い時期に参加者に渡して記録と復習そしてまとめや報告等に活用してもらっていたが、今年も次の週の後半に届けることができた。
最後に、本研修実施にあたり東京大学千葉演習林のご協力を得ました。また、日本地質学会の担当理事の中澤 努氏と学会事務局にいろいろとお世話になりました。最後にお礼を申し上げます。
(徳橋秀一・納谷友規)
写真でみる2013年度秋の地質調査研修(2013.11.18〜11.22)の実施状況
第1図:清和県民の森渕が沢林道沿いでのルートマップづくりの様子(地層は、清澄層タービダイト砂岩優勢互層)(初日)。
第2図:夜、宿の一室での野帳の整理作業(初日)。
第3図:初日午後に作成したルートマップの比較(初日)。1マス5mmは10複歩。
第4図:小櫃川支流猪の川で観察される清澄層第一級の凝灰岩鍵層Ky21(Hk)タフ(2日目)。
第5図:清澄層と天津層の岩相境界付近で、初日に渕が沢林道沿いで観察した清澄層下部の凝灰岩鍵層を探索(2日目)。
第6図:凝灰岩鍵層のKy5タフ(大カゲロウタフ)からKy7(バーミューダタフ)が上下に密集して産出する部分(2日目)。
第7図:猪の川の清澄層(タービダイト砂岩優勢互層)分布域でのルートマップ作成の様子(2日目)。
第8図:安野層の凝灰岩鍵層An28(出べその次郎)と名前を示す表札(3日目)。
第9図:南北性の高角断層の測定練習(3日目)。
第10図:黒滝から猪の川沿い安野層分布域のルートマップ作成の出発(4日目)。
第11図:猪の川沿い安野層分布域のルートマップの比較(4日目)。1マス5mmは20複歩。岩相、凝灰岩鍵層、走向・傾斜の他に、南北性の断層も多数描かれている。
第12図:清澄背斜南翼の天津層と清澄層の境界付近(3日目)。田代林道新道沿い。
第13図:嶺岡構造帯中の蛇紋岩露頭(嶺岡中央林道:5日目)。
第14図:嶺岡構造帯中の層状石灰質チャートブロック(嶺岡山地北鹿の白絹の滝:5日目)。
第15図:嶺岡構造帯中の枕状溶岩ブロック(鴨川青年の家:5日目)。
第16図:清澄層Hk(Ky21)タフ層準にみられる多数の凝灰岩と大小の共役断層群(勝浦海中公園:5日目)。
第17図:ボラの鼻につづく海蝕崖で、清澄層上部のタービダイト砂岩優勢互層が露出。海面近くの白色部はKy26タフ(5日目)。
第18図:防波堤から遠望した海蝕崖先端部のボラの鼻。先端部の上部に、下位層を削る黒滝不整合の境界が観察される。
第19図:凝灰岩鍵層Ky26(ニセモンロータフ)の上半部の山形変形部の中心部にみられる水抜け構造(5日目)。
第20図:研修参加の修了証書をもらった後の記念撮影(勝浦海中公園:5日目)。研修参加者は、この他に技術者継続教育単位CPDを40単位取得する。
意見・提言2014
意見・提言2014
「九州電力株式会社川内原子力発電所1号炉及び2号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案に対する科学的・技術的意見」を提出しました
原子力規制委員会より,九州電力株式会社川内原子力発電所1号炉及び2号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案に対する科学的・技術的意見の募集が実施されました。
地質学会として意見を提出いたしましたので,お知らせ致します。
意見募集の詳細は以下(URL)
https://www.nsr.go.jp/public_comment/bosyu140716.html
日本地質学会より提出した意見(全文)はこちら(PDF)
(2014年8月14日提出)
「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」案への意見提出
文部科学省では「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」案を新たに定めることとなり、そのガイドライン(案)へのパブリックコメント(意見公募手続)が実施されました(7月3日〜8月1日募集)。 日本地質学会からは7月30日に下記の意見を送りましたので、お知らせ致します。
意見募集案件の詳細や「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(案)は以下
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000698&Mode=0
日本地質学会より提出した意見(PDF)
(2014年7月30日提出)
意見募集に対する回答が公開されました。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/__icsFiles/afieldfile/2014/09/03/1351568_03_1.pdf
(2014年9月22日掲載)
「地震に関する総合的な調査観測計画について〜東日本大震災を踏まえて〜 案」に対する日本地質学会の意見提出
政府地震調査研究推進本部(地震本部)では、東日本大震災を踏まえ、今後の地震の調査観測の在り方を示す計画を策定しており,地震本部の調査観測計画部会においてその計画案が取りまとめられました。
この計画案について,7/3〜7/17に意見募集が行われ,日本地質学会から以下のとおり意見を提出しましたので紹介します。
意見募集案件の詳細
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000699
日本地質学会より提出した意見書はこちら↓
「地震に関する総合的な調査観測計画について〜東日本大震災を踏まえて〜」に関する意見(PDF)
(2014年7月16日掲載)
また,日本地質学会を始めとする意見に対する回答がありました
(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000699&Mode=2).
日本地質学会の意見に対する回答は,同pdfファイルの31〜34に掲載されております.
(2014年9月8日掲載)
杉並区立科学館の維持・発展に関する要望書
東京都杉並区の施設再編計画の一環として、杉並区立科学館の廃止が検討されています。
これに対して、日本地質学会から杉並区立科学館の維持・発展に関する要望書を提出しましたので紹介します。
杉並区立科学館の維持・発展に関する要望書(PDF)
(2014年2月25日掲載)
プレスリリース(2014年)
プレスリリース(2014年)
「県の石」:鹿児島県先行決定
発表形態:資料配付(9月12日)
発表先:文部科学省記者会・鹿児島県政記者会
記事解禁日時:設定なし
■ 配布資料:本文(PDF)
日本地質学会第121年学術大会(鹿児島大会):9/9
発表形態:資料配付(9月9日)
発表先:文部科学省記者会・鹿児島県政記者会
記事解禁日時:設定なし
■ 配布資料:本文(PDF)
■ 配布資料:資料1−6(PDF)
「県の石」募集のお知らせ
発表形態:資料配付
発表先:文部科学省記者会
記事解禁日時:設定なし
■説明資料(PDF)
2014年秋季研修実施報告
2014年度秋季地質調査研修の実施報告
はじめに
上記研修が、11月25日(火)〜11月29日(土)にかけて4泊5日で実施された。本研修は、地質関連会社から要請を受けてこれまで毎年実施し、今年で8年目になる。本研修は、定員6名に対して講師2名という小人数指導で、ひとつの地質系統(房総半島中部の清澄山系にゆるやかな褶曲構造を形成しながら分布する新第三系安房層群上部の安野層、清澄層、天津層)を主な対象に、地質調査の経験のない人でも、体(五感)を通して、地質調査法の基本を習得し、それが地質現象の理解・解明に有用であることを理解することを目的に実施している。
今回の参加者は、石油・天然ガス開発関連会社(3社)の新人5名と鉱山開発会社の若手技術者1名の合計6名で、最近では珍しく男性ばかりであった。講師は、産総研の徳橋秀一(地圏資源環境研究部門客員研究員)と工藤 崇(地質情報研究部門主任研究員)が務めた。
※それぞれ文中の図番号をクリックすると、写真へジャンプします。写真からはブラウザのボタン等で戻ってください。
日々の実施内容
<1日目:11月25日(火) :雨のち曇り>
午前11時にJR外房線君津駅に集合後、小糸川上流の清和県民の森に移動、清澄向斜南翼部に位置し、清澄層最下部の厚いタービダイト砂岩優勢互層と凝灰岩鍵層が分布する清和県民の森の渕ヶ沢林道沿いで、タービダイト砂岩層や主な凝灰岩鍵層の特徴を観察した。その後、クリノメーターを使っての走向・傾斜の測定法やルート図の作り方を練習した後、実際のルートマップづくりに挑戦、夜はルートマップの墨入れや色塗りなどの清書作業を行った(写真1〜4)。
<2日目:11月26日(水) :雨>
当初の予定では、清澄背斜北翼に位置する小櫃川支流猪の川(黒滝沢)(東京大学千葉演習林内)で作業をする予定であったが、雨が止む気配がなかったので、同じく清澄背斜北翼に西側に位置する三石山林道沿いで、天津層と清澄層の境界部の特徴、清澄層中の代表的な凝灰岩鍵層であるHkタフ(Ky21)とニセモンロータフ(Ky26)、そして、清澄層タービダイト砂岩中に発達する割れ目構造などを観察した(写真5, 6)。その後、三石山頂上に近い三石寺において、三石山の由来になり、また三石寺のご神体でもある三つの石を構成する黒滝不整合直上の基底礫岩層(黒滝層)を観察した(写真7, 8)。午後は、清澄背斜の南翼に位置する田代林道沿いにおいて、天津層と清澄層境界部の特徴やその前後に挟在する凝灰岩鍵層を観察した。その後宿にもどり、テキスト等を使った講義を午後の後半および夜に実施した。
<3日目:11月27日(木) 晴れ>
小櫃川支流猪の川 (黒滝沢) 沿いの清澄背斜北翼の清澄層、天津層分布域の岩相の特徴や主な凝灰岩鍵層、重要な断層について、上位の清澄層分布域から沢歩きになれるように歩きながら、天津層上部の有名な凝灰岩鍵層であるOkタフ(Am78)の位置まで確認した(写真9)。次に、歩いて確認したルートの沢を歩きながらのルートマップづくりに挑戦した(写真10)。そして同時に、初日に歩いた清澄向斜南翼の清和県民の森渕が沢林道沿いに分布する清澄層最下部のタービダイト砂岩優勢互層中に挟在した凝灰岩鍵層群の産状と猪の川沿いでのこれらの凝灰岩鍵層群の産状の違い、特に、これらの凝灰岩鍵層上下の地層の特徴の大きな変化を確認した(一部層準の地層の背斜軸への顕著な収れん現象)。
<4日目:11月28日(金) 曇り>
前日に続き、小櫃川支流猪の川 (黒滝沢) 沿いにおいて、まず、黒滝不整合の発祥の地となった黒滝で、黒滝不整合とそれを覆う基底礫岩などの堆積物(黒滝層)を観察した(写真11)。そして次に、黒滝不整合の下位に横たわる安房層群最上部の安野層の分布域でルートマップを作成した。黒滝不整合の直下の黒滝の周りには、安野層最上部の硬質の砂質泥岩〜泥質砂岩と凝灰岩層の互層が分布するが(写真12)、猪の川林道と交叉する橋の下をくぐったすぐ東側には、幅4〜5mの破砕帯をともなう南北性の断層があり(写真13)、その断層より上流側には、安野層の上部より下位のシルト岩とタービダイト砂岩の細互層が広く分布する(写真14)。猪の川沿いの安野層分布域では、猪の川が走向方向(ほぼ東西方向)に大きく蛇行しながら伸びることから、安野層の多くの凝灰岩鍵層(写真15など)やスランプ堆積物(写真16)が、大小の南北性の断層によってずれながらも、走向方向に連続し、何度も繰り返し猪の川沿いで観察されることを確認し(写真17)、そのことをルートマップに表現した(写真18)。
<5日目:11月29日(土) 雨ときどき曇り>
まず、安房層群堆積時に外縁隆起帯(バリヤー)をなしていたと考えられる嶺岡構造帯(嶺岡山地)を特徴づける蛇紋岩(写真19)、その蛇紋岩が上昇中に取り込んだ代表的なブロック (層状石灰質チャート、枕状溶岩のブロック)を観察(写真20)。その後、東海岸を北上し、勝浦海中公園東隣りの吉尾漁港の東方に伸びる海蝕崖で、猪の川沿いで観察した安野層の全体を浸食し、三石山林道でみた清澄層上部のニセモンロータフ(Ky26)直上を直接覆う黒滝不整合を防波堤から遠望した(潮位の関係で、黒滝不整合を直接観察できるボラの鼻までは行けなかった)。その後、清澄層上部のニセモンロータフやタービダイト砂岩の特徴を観察した(写真21)。次に、隣の勝浦海中公園において、清澄層第一級の凝灰岩鍵層のHkタフ(Ky21)下位の泥岩優勢互層を観察した。この後、海中公園の浜辺にて、地質調査研修修了証書を参加者に授与し記念写真を撮影した(写真22)。そして、午後2時過ぎにJR外房線の勝浦駅にて解散した。
今回の研修の特徴
今回の研修は、3日目と4日目以外は、雨の降る日が多く、研修の中心地域である猪の川(黒滝沢)沿い(東大千葉演習林内)での作業日数を3日間から2日間に短縮し、その代り、林道沿いでの観察の充実やテキスト等を使った室内での講義に振り替えた。ただ、最も重要な基本作業であるルートマップ作成作業は、やり方を少し変更して実施した結果、当初予定したルート、区間を何とかほぼカバーすることができた。最終日の勝浦海中公園周辺での観察は、潮位の関係で一部の露頭を観察できなかったが、その他の作業は、雨の影響を受けながらも、当初の予定をほぼ実施することができるともに、事故や病気もなく無事終了することができたことは幸いであった。山ヒルについては、2日目の雨の中での林道沿いの草むらでの調査の際に何匹か遭遇したが、それ以外の日は遭遇することはなく、幸い実害はなかった。山ヒル対策として、今年も食塩を持参するとともに、長靴(沢の中での滑り防止のために全員スパイク長靴を使用)とズボンの間を布テープで巻いておいたが、この布テープは、沢の中を歩いている際の水の侵入防止にも大いに役立った(この時期、長靴に水が入ると冷たくまた乾きにくい)。紅葉はちょうど盛りの時期で、林道沿いや沢沿いを歩きながら、各所で見事な紅葉を楽しむことができた。
おわりに
本研修では、参加者は研修中ルートマップの作成などの作業に追われ、あまり写真など撮っている暇がないので、代わって講師の方でその間の写真をできるだけ多く撮り、それを基に、研修の様子や観察した対象物等の写真をパワーポイント上に簡単な説明をつけながら日毎に時系列的に並べたものを、テキストに使った基本的な図面等のファイルの入った資料編ともに、実施記録として毎回作成し参加者に渡してきた。4泊5日にわたる詳細な実施記録の作成は、講師にとっては相当な負担であるが、こうした実施記録をみながら復習してもらうことによって、研修の中身がよりよく理解され身につくことが期待されることから、今回もがんばって作成し、次の週には写真の元データとともにこうした記録ファイルを参加者にお届けし、実施記録として、あるいは、社内での報告や報告書作成の際に役立ててもらっている。また参加者には、毎回研修の内容に関するアンケートに協力してもらっているが、今回も研修の意図を理解し役立った、貴重な経験となったという回答をみなさんから得ている。そのうえで、あともっとこういうこともやりたかったという要望も毎年いくつかいただくが、たとえば、今回身につけたルートマップづくりを、別のルート(支沢や近隣の沢など)で試行錯誤しながら自力で実施したり、特定層準の柱状図づくりを自らやって対比したり、重要な露頭のスケッチを行うなどの経験を一通り行うためには、本当はもう一週間必要である、というのがいつも感じる正直な気持ちである。ただ、実際やるとなると、参加者側にもそれなりの体力(脚力や露頭表面を自ら積極的に削る腕力など)と覚悟(やる気・根気・気力・知力)が必要となろうし、またこれを実施すると、さらに次なる関心や欲求が起きる可能性も高いであろう。
最後に、本研修実施にあたりご協力ご尽力いただいた東京大学千葉演習林、地質学会担当理事の杉田律子氏と前担当理事の中澤 努氏、地質学会事務局など、関係機関、関係者の皆様に厚くお礼を申し上げます。
(徳橋秀一、工藤 崇)
写真でみる2014年度秋季地質調査研修(11月25日〜11月29日実施)の実施の様子
写真1:清和県民の森の林道沿いでの清澄層最下部(タービダイト砂岩優勢互層)の観察(初日)。
写真2:クリノメーターを使った層理面(走向と傾斜)の測定練習(初日)。
写真3:初日午後に作成したルートマップの清書作業(初日の夜)。
写真4:初日午後に作成したルートマップの比較。1マス(5mm)は10複歩。
写真5:清澄層第一級の凝灰岩鍵層であるHkタフ(Ky21:白色部)を三石山林道沿いで観察(2日目)。
写真6:清澄層上部の厚いタービダイト砂岩中の複雑な割れ目の観察(三石山林道:2日目)。
写真7:三石神社裏のご本体(三石のひとつ)を構成する黒滝不整合直上の基底礫岩(黒滝層)の観察(2日目)。
写真8:写真7の黒滝層(基底礫岩層)の一部拡大(2日目)。貝化石などもところどころで観察される。
写真9:天津層第一級の凝灰岩鍵層Okタフ(Am78)(猪の川:3日目)の前でポーズ。
写真10:清澄層のタービダイト砂岩優勢互層の中を歩きながらのルートマップ作成作業(猪の川:3日目)。タービダイト砂岩の河床は、平坦ですべりにくく歩きやすい(猪の川:3日目)。
写真11:黒滝不整合の名前の由来となった黒滝(猪の川:4日目)。不整合直上の基底礫岩は、滝の表面をかするように分布。
写真12:黒滝不整合直下の安野層最上部の硬質砂質シルト岩〜シルト質砂岩と凝灰岩の互層(猪の川:4日目)。
写真13:安野層の最上部と上部のタービダイト砂岩泥岩互層が接する比較的ずれの大きい破砕帯をともなった南北性の断層(猪の川:4日目)。
写真14:安野層のタービダイト砂岩泥岩細互層が猪の川の河床に鬼の洗濯岩状に律動的に分布(4日目)。
写真15:安野層に多数設定された凝灰岩鍵層のひとつであり、軽石質凝灰岩から成るモンロータフ(An16)。直下には付き人が待機(猪の川:4日目)。
写真16:安野層中のスランプ堆積物。スランプ堆積物も凝灰岩鍵層とともによく連続して分布(猪の川:4日目)。
写真17:走向方向に蛇行しながら流れる猪の川沿いに何度も出現する凝灰岩鍵層の確認とルートマップ上への記載(4日目)。
写真18:猪の川の安野層分布域で作成したルートマップの比較(4日目夜)。ルート上には、岩相、凝灰岩鍵層、断層、走向・傾斜が記載されている。1マス(5mm)は20複歩。
写真19:嶺岡山地(嶺岡構造帯)の中心部を東西に伸びる嶺岡中央林道沿いに露出する蛇紋岩露頭(5日目)。
写真20:嶺岡山地の東端部に位置する鴨川青年の家周辺にみられる枕状溶岩(千葉県天然記念物)(5日目)。
写真21:東海岸の勝浦市吉尾漁港東方に伸びる海蝕崖に分布する黒滝不整合直下の清澄層上部のタービダイト砂岩優勢互層(5日目)。
写真22:研修を終えて受け取った修了証書の受領記念写真(勝浦海中公園前:5日目)。研修参加者は、技術者継続教育CPD40単位も取得。
意見・提言2015
意見・提言2015
高等学校理科用『地学』教科書の記述内容に関する意見書
日本地質学会は、現在の高等学校における地学関連科目の履修率の低さについて大いに危機感を持っており、学術団体として地学教育の普及に取り組んでいるところです。この度、その取り組みの一環として、啓林館および数研出版の2社から発行されている高等学校理科用『地学』教科書の記述内容のうち、地質学に関わる部分を学術的に点検し、意見を集約しました。そして、その結果を各出版社へ送付し,あわせて,文部科学省にも送付しました。
2015年12月28日付提出
理科得点調整および地学関連科目に関して,大学入試センターに申し入れ提出
平成27年1月に実施されました大学入試センター試験の理科の得点調整および地学関連科目の内容について受験生の立場にたった申し入れ書を(独)大学入試センター理事長に提出いたしましたので,お知らせいたします.
2015年4月15日付提出
4月16日プレスリリース
要旨:
地 学関連科目の平均点が他分野より低かった.特に「地学」は40.91点と著しく低く,「物理」との間に20点以上もの開きがあったが,得点調整はなされな かった.一部に偏った設問や,複雑な出題・解答形式があった.今回の試験問題を検証し,今後は偏り無く,理解力と考察力を問い,平均点が著しく低くならな いよう努めて頂きたい.受験者数が1万人未満であっても得点調整できる方策を早急に検討して頂きたい.
■ プレスリリース資料:頭書き(PDF) / 本文(PDF)
次期学習指導要領改訂に関する要望書を文科大臣に提出
次期学習指導要領改訂を前に,将来の日本を背負って立つ高校生の立場にたった要望書を文部科学大臣に提出いたしましたので,お知らせいたします。
プレスリリース全文はこちら(PDF)
2015年3月31日付提出
4月2日プレスリリース
地学の知識を減災のソフトパワーに―東日本大震災4年目を迎えて―
東日本大震災から早くも4年目を迎えようとしています。あのような被害を二度と起こさせないためにも、地質学会として標記の声明を発表(プレスリリース)いたしました.地質学の知識が、防災・減災に実際に役立つことを学会としては願ってやみません.
プレスリリース全文はこちら(PDF)
2015年3月2日プレスリリース
2015年度春季研修実施報告
2015年度春季地質調査研修の実施報告
日本地質学会主催、産総研地質調査総合センター共催の上記研修が、5月18日(月)〜5月22日(金)において、4泊5日で実施された。本研修は、誰でも参加できる若手技術者向けの地質調査研修を毎年実施してほしいという要請が、民間地質関連会社から産総研地質調査総合センター(旧工業技術院地質調査所)に出されたことをきっかけに2007年度より始まり、今回で9年目、10回目にあたる。2011年度までは、産総研地質調査総合センターの外部研修プログラムとして、地学情報サービス㈱(当時)の管理運営の下で実施されたが、2012年度からは現在の形で実施されている。今回の研修参加者は、都内の資源・地熱開発会社から男性1名女性1名、都内の石油天然ガス開発会社から男性1名、茂原市の水溶性天然ガス会社から男性1名、千葉市の独立行政法人から男性2名の定員6名であった。講師は、産総研の徳橋秀一(地圏資源環境研究部門の客員研究員)と小松原純子(地質情報研究部門の主任研究員)が務めた。
今回の研修では、研修ルートに関して重要な変更があった。というのは、これまで研修の主要地域であり川沿いでのルートマップ作成コースであった東大千葉演習林内の猪の川(黒滝沢)へ行く猪の川林道沿いで比較的大きな崖崩れがあり、その影響で徒歩での通過も研修開始直前の4月下旬になって禁止となった。このため、猪の川の東側に位置し、猪の川沿いで研修対象としてきた安房層群上部の天津層、清澄層、安野層がやはり同様に分布する七里川(しちりがわ:小櫃川本流の上流部)沿いでのルートマップ作成に急遽変更した。また、4月末〜5月初めの連休の合間に、七里川で現況確認調査を実施した。
研修各日の実施内容は次の通りである。
1日目:5月18日(月) 晴れ
午前11時にJR外房線君津駅に集合後、小糸川上流の清和県民の森に移動した。清澄向斜南翼部に位置し、清澄層最下部の厚いタービダイト砂岩優勢互層と凝灰岩鍵層が分布する清和県民の森の渕ヶ沢林道沿いで、タービダイト砂岩層や主な凝灰岩鍵層の特徴を観察後、クリノメーターを使った層理面の走向・傾斜の測定法、ルート図の作成法を練習後、林道沿いで地質学的ルートマップを作成した(写真1)。夜は、ルートマップの清書作業を行い、結果を比較した(写真2,3)。
2日目:5月19日(火) 雨まじり曇りのち晴れ
まず、小櫃川支流笹川上流片倉ダム周辺の田代林道(清澄背斜南翼)において、天津層と清澄層境界部の特徴を観察した(写真4)。次に、三石山林道の峠部(林道片倉三石線終点)にある三石山神社の周辺(三石山山頂部)に分布する上総層群黒滝層の粗粒堆積物(基底礫岩)を観察した(写真5)。この後、清澄背斜のほぼ軸上に位置する道の駅きみつふるさと物産館において昼食をとり、午後は、片倉ダムから三石山に伸びる三石山林道(林道片倉三石線:清澄背斜北翼)沿いに分布する天津層上部と清澄層の堆積物、主な凝灰岩鍵層を一通り観察した後、もどりながらルートマップを作成した(写真6)。夜は、ルートマップの清書作業を行い、結果を比較した(写真7)。
3日目:5月20日(水) 晴れ
清澄背斜北翼に位置する七里川本流沿いの天津層上部から清澄層の分布域で、これらの地層の堆積物、主な凝灰岩鍵層の特徴を観察するとともに、それらの分布をルートマップで表現した(写真8〜17)。また、前日に観察した清和県民の森渕が沢林道沿い(清澄向斜南翼)の清澄層最下部の特徴と七里川本流における同じ層準の地層の特徴の大きな違い、変化(背斜軸への地層の収れん現象)にも注目し、確認した。夜は、ルートマップの清書作業を行い、結果を比較した(写真18)。
4日目:5月21日(木) 晴れ
夜半に雨が降ったことによる河川の増水の影響も考慮して、午前は、小櫃川の東隣りに位置する養老川(養老渓谷)中瀬遊歩道沿いの上総層群大田代層と梅ヶ瀬層のタービダイト砂岩泥岩互層を観察し、上下方向での岩相の変化や安房層群のタービダイトとの特徴の違いについて観察した(写真19,20)。午後は、七里川沿いで、前日の作業に引き続く形で、安野層分布域のルートマップを作成し、七里川沿いでの黒滝不整合下位の安野層、清澄層、天津層上部分布域でのルートマップを完成させた(写真21〜29)。夜は、ルートマップの清書作業を行い、結果を比較するともに(写真30)、七里川沿いの2日間のルートマップデータを5,000分の1地形図上に描きなおして、全体の配置関係を確認した(写真31)。
5日目:5月22日(金) 晴れ
4日間泊まった鎌田屋旅館に別れを告げ(写真32)、安房層群堆積時に外縁隆起帯をなしていたと考えられる嶺岡構造帯を特徴づける蛇紋岩、その蛇紋岩が上昇中に取り込んだ代表的なブロックの岩石 (層状石灰質チャート、枕状溶岩)を嶺岡山地周辺で観察した(写真33〜36)。
その後、東海岸を北上し、勝浦海中公園東隣りの勝浦市吉尾漁港の東方に伸びる海蝕崖を進みながら(写真37)、先端のボラの鼻で、安野層全体を浸食し、三石山林道や七里川でみた清澄層上部のニセモンロータフ(Ky26)の直上までを浸食する黒滝不整合を観察した(凝灰岩鍵層を通しての不整合下での浸食現象の確認)(写真38)。また、不整合直下の清澄層上部のニセモンロータフやタービダイト砂岩の特徴などを観察した(写真39)。次に、勝浦海中公園において清澄層第一級の凝灰岩鍵層のHkタフ(Ky21)を再度観察するとともに(写真40)、房総の中央部ではタービダイト砂岩優勢互層であったHkタフの下位の層準が、混濁流の下流側にあたるこの地域では泥岩優勢互層に変化していること(同時異相関係)、その結果、各種の凝灰岩鍵層が上下に密集して分布していることを確認した(写真41)。また、この泥岩優勢互層部に発達する共役断層群や生痕化石などを観察し(写真42,43)、研修の締めくくりとした。そして、恒例の地質調査研修修了証書の授与式と記念撮影を海中公園の海岸をバックに行った(写真44)。その後、午後3時半頃にJR外房線勝浦駅で解散し、講師は車(10人乗りハイエース)を夕方までに茨城県のレンタカー屋さんに返すべく、一路北上した。
今回河川でのルートマップづくりの主要ルートとなった七里川沿いは、すぐ隣を県道81号(清澄養老ライン)が通っていることもあって、従来の猪の川(黒滝沢)ルートと比べてアプローチはより容易で移動時間を節約できる点はプラスであるが、小櫃川本流の上流部にあたることから川幅が比較的広くて、U字型の断面を示す支流の猪の川ほどには露頭の連続性がよくないことや雨などによる流量増大の影響をより受けやすい点はマイナスである。地層の露出状況や凝灰岩鍵層の分布状況を比較した場合には、天津層の場合はいずれもほぼ同じであるが、清澄層の場合は七里川の方が、安野層の場合は猪の川の方がより有利であるなど、それぞれ一長一短があるといえる、今回の研修期間中は、夜半に雨が降り、昼は曇りから晴れというパターンが多かったことから、通常よりは水量が少し多いなかでの実施となった。
夜半に雨が降ることが多かった関係で、林道沿いの草むらなどで作業した際には、湿気を好む山ヒルが比較的多く観察されたが、その都度、互いに観察しあって早期発見に努め、発見の度に食塩をかけて振り落した結果、実質的な被害はほとんどなかった。また、長靴(スパイク長靴を使用)とズボンとの間には、毎朝布テープを幾重にも巻いて、山ヒルが長靴の中に入らないように注意したが、この布テームの巻きつけは河川の水が中に入るのを防ぐ意味でも有効であった。
今回は、最終日を除いて、毎日林道沿いか河川沿いでルートマップづくりを行ったために、毎晩そのルートマップの清書作業を共同で行い、その都度野帳を並べて互いに比較した。作成したルートマップの量としては、今回がこれまでで一番多かったといえる。
今後、秋の研修(11月に予定)までに、従来行っていた千葉演習林(猪の川沿い)北口(黒滝口)への林道の改修・復旧が実現した場合は、猪の川沿いでの研修、あるいは、猪の川と七里川を組み合せた研修を実施することになろうが、改修・復旧が間に合わなかった場合は、今回と同じく、七里川沿いでのルートマップづくりが中心となろう。
本研修実施にあたっては、地質学会担当理事の杉田律子氏、産総研地質調査総合センターの関係者、東京大学千葉演習林関係者、地質学会事務局にお世話になった。ここにお礼を申し上げます。
(徳橋秀一・小松原純子)
ページTOPに戻る
写真でみる2015年度春季地質調査研修の様子
写真1:清和県民の森の渕が沢林道沿いの清澄層分布域でのルートマップ作成風景(初日)。
写真2:夜のルートマップ清書作業の様子(初日夜)。
写真3:初日のルートマップの比較。渕が沢林道の清澄層最下部の分布域。
写真4:片倉ダムから東南東に伸びる田代林道沿いの天津層−清澄層境界付近。
写真5:上総層群最下部の黒滝層(基底礫岩)から成る三石山山頂(標高282m)を参拝(2日目).縁結びの祠があることから,その効果を期待したいが?
写真6:片倉ダムから三石山神社へと延びる三石山林道沿いでのルートマップ作成(2日目)。
写真7:三石山林道沿いのルートマップ(天津層上部〜清澄層分布域)の比較(2日目夜)。
写真8:七里川沿いでのルートマップ作成作業の開始(天津層上部のOkタフ付近)(3日目)。
ページTOPに戻る
写真9:天津層第一級の凝灰岩鍵層Okタフ(Am78:名前は三浦半島の大楠山に由来)(3日目)。
写真10:清澄層基底直下の泥岩層に挟在するバーミューダタフ(Ky7)。向斜南翼の渕が沢林道では、バーミューダタフから黒潮タフ(Am98)までの間には、厚さ300m前後のタービダイト砂岩優勢互層が挟在するが、ここ(背斜北翼)では、タービダイト砂岩層はほとんど挟在せず、厚さも10m前後と非常に薄くなっている。
写真11:清澄層基底部付近の厚い小礫岩〜含礫砂岩(タービダイト)。チャンネル堆積部の末端部に位置し、ここでは、滝つぼタフ(KY8)や滝の上タフ(Ky9)は浸食されている(3日目)。
写真12:七里川河床にみられる清澄層中部のタービダイト砂岩優勢互層。凸部が泥岩層で、のっぺりした凹部がタービダイト砂岩層である。凸部の泥岩層の伸長方向は、層裏面の走向方向に一致する(3日目)。
写真13:クリノメーターを使った層理面の走向・傾斜の測定(3日目)。
写真14:七里川の支沢(赤井沢)に入っての鍵層の確認(3日目)。
ページTOPに戻る
写真15;支沢(赤井沢)の入り口付近で見つかったニセモンロータフ(Ky26)(3日目)。
写真16:清澄層とその上位の安野層の境界付近。安野層の基底を特徴づけるサカサタフ(An1)を確認中(3日目)。
写真17:安野層基底のサカサタフ(An1)。どこでも逆級化構造を示すことが名前の由来になっている(3日目)。
写真18:七里川の天津層上部〜清澄層分布域のルートマップ比較(3日目夜)。
写真19:七里川の東隣りを流れる養老川の中瀬遊歩道沿いでの上総層群の地層の見学(3日目)。
写真20:上総層群梅ヶ瀬層最下部のタービダイト砂岩優勢互層(3日目)。
ページTOPに戻る
写真21:七里川の清澄層−安野層境界付近にある吊り橋の下から、安野層分布域のルートマップ作成の再開(3日目)。
写真22:安野層モンロータフ(An16)付近で走向・傾斜を測定(4日目)。
写真23:安野層モンロータフ(An16)の上位にあるタービダイト砂岩優勢互層(4日目)。
写真24:安野層のスランプ堆積物(4日目)。
写真25:安野層みのかさタフ(An32)付近でのルートマップづくり(4日目)。
写真26:安野層最上部付近の露頭の全体の様子(4日目)。
ページTOPに戻る
写真27:安野層最上部付近の露頭の拡大の様子。泥質砂岩と凝灰岩との互層から成り、堆積物全体が粗粒化している。
写真28:七里川の黒滝不整合前後。転石のあるところが不整合付近で、手前は上総層群最下部の黒滝層(凝灰質含礫砂岩)にあたる(4日目)。
写真29:黒滝層の粗粒堆積物に認められる弱い成層構造(4日目)。
写真30:七里川安野層分布域のルートマップの比較(4日目夜)。
写真31:天津層上部〜安野層分布域のルートマップデータを5,000分の1地形図上にまとめて描写した一例。磁北方向(N6°W)の補助線がうすく描かれている(4日目夜)。
写真32:鎌田屋旅館の前で、全員集合写真(5日目)。
ページTOPに戻る
写真33:嶺岡中央林道沿いにみられる蛇紋岩露頭。(5日目)。
写真34:嶺岡山地北麓の白絹の滝を構成する層状石灰質チャート(5日目)。
写真35:東海岸の鴨川青年の家前に露出する枕状溶岩の大ブロック(5日目)。
写真36:枕状溶岩の拡大写真(5日目)。
写真37:鴨川市吉尾漁港の東方に伸びる海蝕崖を構成する清澄層上部のタービダイト砂岩優勢互層(5日目)。
写真38:海蝕崖東端のボラの鼻でみられる黒滝不整合。ここでは、安野層全体のみならず清澄層上部までの浸食現象がみられ、かつてここに海底谷が形成されていたという解釈もある。
写真39:黒滝不整合の直下にあるニセモンロータフ(Ky26)。上部の変形体頂部には、多くの水抜け構造が観察される(5日目)。
写真40:勝浦海中公園の海蝕崖でみられる清澄層第一級の凝灰岩鍵層Hk(Ky21:三浦半島逗子市の東小路に由来)タフ(ゴマシオ状凝灰岩:折尺部分)。1mから2m上位には、黒色のスコリア層(通称、アワオコシタフ)がどこでも観察される。
写真41:Hkタフの下位の泥岩優勢互層。多くの凝灰岩鍵層が上下に密集するとともに、中央部付近では大小の共役断層群が観察される(5日目)。
写真42:大小の共役断層群。中央下部の黒色スコリア層は、Hkタフ直上のアワオコシタフである。
ページTOPに戻る
写真43:Hkタフ下位の泥岩層層裏面にみられる生痕化石群(5日目)。
写真44:地質調査研修修了証書受領記念写真(右後ろにみえるのは、勝浦海中公園の海中展望塔)。研修参加者には、この他に、CPD(技術者継続教育単位)40単位が与えられる。
ページTOPに戻る
2015年度秋季研修実施報告
2015年度秋季地質調査研修の実施報告
日本地質学会主催、産総研地質調査総合センター共催の上記研修が、11月9日(月)〜11月13日(金)において、4泊5日で実施された。本研修は、誰でも参加できる若手技術者向けの地質調査研修を毎年実施してほしいという要請が、民間地質関連会社から産総研地質調査総合センター(旧工業技術院地質調査所)に出されたことをきっかけに2007年度より始まり、毎年1〜2回実施され、今回で9年目(11回目)にあたる。2011年度までは、産総研地質調査総合センターの外部研修プログラムとして、つくば市の地学情報サービス㈱(当時)の管理運営の下で実施されたが、2012年度からは現在の形で実施されている。今回の講師は、産総研の徳橋秀一(地圏資源環境研究部門の客員研究員)と宇都宮正志(地質情報研究部門の研究員)が務めた。研修参加者は、都内の石油開発会社2社からの参加者6名(全員男性)であった。秋季地質調査研修には、この両社からは春に入社した新人が毎年参加されてきたが、今回は両社の新人の数が例年より少し多かったことから、申込み受付開始後すぐに定員の6名に達した。少人数実施制のためやむを得ないとはいえ、他に参加を予定していた会社があった場合は申し訳ない次第でした。
今回の研修は、昨年までの研修の主要地域であり川沿いでのルートマップ作成コースであった東大千葉演習林内の猪の川(黒滝沢)へ行く猪の川林道沿いで比較的大きな崖崩れがあり、その修復の遅れから、林道の通行禁止が解除されなかった。そのため、春季地質調査研修の場合と同じく、沢沿いの研修(ルートマップづくり)は、猪の川の東側に位置する七(しち)里(り)川(小櫃川本流の上流部)沿いで実施された。
研修各日の実施内容は次の通りである。
1日目:11月9日(月) 曇りときどき弱い雨
講師は、朝7時半に、茨城県土浦市のJR常磐線荒川沖駅近くのレンタカー屋で車(トヨタハイエース10人乗り)を借出し、近くで調査用の道具や研修用資料を積み込んだ後、圏央道・東関東自動車道・館山自動車道を経て、集合地点のJR内房線君津駅に向かった。例年11時集合にしていたが、圏央道と東関東自動車道がつながり移動時間の短縮が見込めたことから、集合時間を30分早めたが、予定通りほぼ10時半に到着し、そこで参加者全員と合流した。まず参加者には、例年のことながら、主に室内用と主に野外用のテキストA・Bの2冊(写真1)の他に、首下げ用ひもをつけた野帳、野帳に書いたルートマップなどを作成・清書する際に使うシャープペンシルと黒・赤・青の極細用ペン、ペンケース、それらを収納する名前のついたビニール製の簡易手提げバッグなどを配布した。合流後、近くで昼食を取ったのち、初日午後の研修地である小糸川上流の清和県民の森に向かった。途中その近くにある宿で荷下ろしと着替えをした後、清澄向斜南翼部に位置し、清澄層最下部の厚いタービダイト砂岩優勢互層が分布する清和県民の森の渕ヶ沢林道沿いで、タービダイト砂岩層や主な凝灰岩鍵層の特徴を観察するともに、クリノメーターを使った層理面や断層面の走向・傾斜の測定練習を交替で行うとともに(写真2)、クリノメーターを使ったルート図の作成法を練習した。夜は、テキストを使いながら関連事項の学習を行った。
2日目:11月10日(火) 弱い雨のち曇り
まず、前日ルートマップづくりの練習を行った渕が沢林道沿いに行き、そこを歩きながら確認した清澄層最下部分布域のルートのルートマップ作成を行った。一時的に弱い雨が降ったので、車に積んできたビニール製の傘をさしながらの作業となったが、特に影響はなかった(写真3)。このあと、雨もほぼ上がったなか、小糸川流域から東の小櫃川流域に移り、清澄背斜南翼に位置する小櫃川支流笹川上流片倉ダム周辺の田代林道において、渕が沢林道で見た凝灰岩鍵層の一部と再会しながら、天津層と清澄層境界付近の地層を観察した(写真4)。この後、清澄背斜のほぼ軸上に位置する近くの道の駅「きみつふるさと物産館」において昼食をとった。午後は、清澄背斜北翼に位置し、片倉ダムから三石山に伸びるV字状の片倉−三石林道(三石山林道)沿いに分布する天津層上部から清澄層の地層を観察した。特に片倉ダムのダムサイトが、主に泥岩層から成る天津層とタービダイト砂岩優勢互層から成る清澄層との境界部に建設されていること、天津層の粗粒堆積物(砂質泥岩〜泥質砂岩)にみられる生痕化石(写真5)、清澄層中の代表的な凝灰岩鍵層であるKy21(Hk)タフやKy26(ニセモンロー)タフなどに注目しながら観察を行った(写真6)。この後、安野層分布域を車で通過しながら、林道の峠部(林道片倉−三石線終点)にある三石山観音寺(三石観音)の周辺(三石山頂部含む)に分布する上総層群最下部の黒滝層の粗粒堆積物(基底礫岩)を観察した(写真7)。この後、天津層上部から清澄層が分布する片倉−三石林道のV字ルートでルートマップを作成し(写真8)、三浦半島の逗子市の東小路に由来して名前が付けられたという清澄層第一級の凝灰岩鍵層Hk(Ky21)タフ(写真9)が、V字の東西両側に出てくることや片倉ダムサイト(写真10)が天津層と清澄層の境界部にあることなどをルートマップ上に表現した。夜は、渕が沢林道と片倉−三石林道2つのルートマップの清書作業を行い、結果を比較した(写真11、12、13)。
3日目:11月11日(水) 晴れ (小春日和)
この日は、途中のコンビニで弁当を買ったのち、小櫃川流域で一番東側に位置する七里川に沿って南北に伸びる清澄養老ライン(県道81号線)を南下しながら、札郷トンネルを越えたところに車を止め、ここから清澄背斜北翼に位置する七里川に降り、上流に向かって南下しながら清澄層中部から天津層上部へと移動して、岩相と主要な凝灰岩鍵層を観察した。特に清澄層下部の厚層理礫質砂岩〜小礫岩と天津層の泥岩層との明瞭な境界、その直下の泥岩層部において、向斜南翼の渕が沢林道では、清澄層最下部の厚いタービダイト砂岩優勢互層によって隔てられていた凝灰岩鍵層がここでは上下に超接近し、その間にタービダイト砂岩は全く挟まれていないという事実を観察・確認した(写真14)。その結果、背斜軸に直交する断面では、向斜部と背斜部で、岩相や層厚が大きく異なっているという現象(一部層準の地層の背斜軸への収れん現象)を確認した。この後、三浦半島の大楠山にちなんで名前が付けられたという天津層第一級の凝灰岩鍵層Am78(Ok)タフを確認し(写真15)、そこから再びもどりながら、天津層上部から清澄層中部にかけてのルートマップを作成した(写真16、17)。そして、車のところにもどり昼食をとった。午後は、再び七里川を下流に向かって歩き(写真18)、前日の片倉−三石林道沿いで観察した清澄層中のKy21(Hk)タフやKy26(ニセモンロー)タフの分布を、七里川沿いでも蛇行と地層の走向方向との関係で複数回出現するのを確認しながら(写真19、20)、清澄層を覆う安野層基底の凝灰岩鍵層An1(サカサ)タフが分布するところまでのルートマップを作成した(写真21)。夜は、ルートマップの清書作業を行うとともに、関連資料(図面類)を使っての補足説明を行った。
4日目:11月12日(木) 晴れのち曇り(準小春日和)
4日目は、途中弁当を買った後、前日の清澄養老ラインの札郷トンネルよりは北側に車を置き、そこから七里川に降り、上流に向かって、黒滝不整合付近の安野層最上部の地層から順に安野層の岩相(タービダイト砂岩優勢互層やスランプ堆積物を一部に挟む泥岩優勢互層)や主な凝灰岩鍵層を観察しながら、前日のルートマップ作成終了地点である安野層基底の凝灰岩鍵層An1(サカサ)タフのところまで歩いた。そしてそこから再び下流に向かって歩きながら、安野層分布域のルートマップを作成した(写真22〜26)。最後に、安野層最上部とそれを覆う上総層群最下部の黒滝層との境界付近、すなわち黒滝不整合付近の地層を詳しく観察した(写真27)。この後、川沿いで昼食をとった後、近くで安野層上部のタービダイト砂岩の表面をたわしでこすり布バケツを使って水をかけるなどして、タービダイト砂岩断面の堆積構造を観察した(写真28)。その後、東隣りの養老川沿いに車で移動し、養老渓谷中瀬遊歩道沿いを歩きながら、上総層群中部の代表的なタービダイト互層である大田代層上部と梅ヶ瀬層最下部を観察し(写真29)、安房層群の清澄層や安野層のタービダイトとの特徴の違いについて検討した。夜は、ルートマップの清書作業を行い、2日間のルートマップの結果を比較するとともに(写真30)、天津層上部、清澄層、安野層から黒滝不整合に至る七里川沿いのルートマップデータを5,000分の1地形図上に表現し、全体の配置関係を確認した(写真31)。
5日目:11月13日(金) 曇り
5日目は、宿を去る前に恒例の全員集合写真を撮った後(写真32)、まず、安房層群堆積時に外縁隆起帯をなしていたと考えられる嶺岡構造帯のなかの代表的な岩石ブロック (層状石灰質チャート、枕状溶岩)を嶺岡山地周辺で観察した(写真33、34)。
その後、東海岸を北上し、勝浦海中公園東隣りの勝浦市吉尾漁港の東方に伸びる海蝕崖を進み(写真35)、先端のボラの鼻で、安野層全体を浸食し、半島中央部の三石山林道や七里川でみた清澄層上部のKy26(ニセモンロー)タフの直上までを浸食する黒滝不整合を観察した(凝灰岩鍵層を通しての不整合下での浸食現象の確認)(写真36)。また、不整合直下の清澄層上部のKy26(ニセモンロー)タフやその前後のタービダイト砂岩の特徴などを観察した(写真37)。次に西隣の勝浦海中公園において、清澄層第一級の凝灰岩鍵層であり、地表で東西約70kmにわたって連続追跡されるKy21(Hk)タフの地表東端部での特徴を観察するとともに(写真38)、房総中央部ではタービダイト砂岩優勢互層であったHkタフの下位の地層が、混濁流の下流側にあたるこの地域では泥岩優勢互層に変化していること(同時異相関係)、その結果、Hkタフ下位の各種の凝灰岩鍵層が上下に密集して分布していることを確認した(写真39)。また、この泥岩優勢互層部に発達する共役断層群などを観察した。その後、恒例の地質調査研修修了証書の授与式と記念撮影を海中公園の海中展望塔をバックに行った(写真40)。そして、そこのレストランで昼食をとった後に東海岸を北上し、勝浦市部(へ)原(ばら)海岸北方の崖で、上総層群最下部の勝浦層中のスランプ堆積物を観察した(写真41)。その後、内陸部を北上し、途中睦沢町の瑞沢川西門橋下の川面でみられる上総層群中の天然ガスの活発な自然湧出現象を観察した(写真42)。そして、近くのコンビニの駐車場で着替えなどを行ったのち、再度北上し、JR外房線の茂原駅で午後4時頃に解散した(写真43)。講師陣は、この後一路車で北上し、途中調査道具などを下ろしガソリンを満タンにした上で、例年のことながらぎりぎりの夕方7時前にレンタカー屋に車を返却し、研修を無事終了した。
今回の研修は、前半の月曜日、火曜日と一時的に弱い雨が降ったが、林道沿いでの地層の観察やルートマップ作成作業であったため、実質的な影響はほとんどなかった。七里川でのルートマップ作業がメインであった水曜日と木曜日は、小春日和となるなど天候に恵まれるとともに、川の水量もたいしたことなく、ほぼ順調に実施することができた。最終日の金曜日も曇りがちながら天候に恵まれ、また、この日の一番の目玉である勝浦ボラの鼻の黒滝不整合の観察も、干潮の時間に合わせたとはいえ、この時期としては潮の引きも十分であったために先端まで行って観察できるなど、運にも恵まれ、当初の予定をほぼ実施することができた。
また、今回の研修では、猪の川(黒滝沢)沿いでなく七里川沿いでの研修によって一部浮かせることができた時間を使って、4日目と最終日に、上総層群の地層も代表的な露頭で観察でき、地層の見方を補う上で役立てることができた。また、最終日には、帰路の途中、南関東ガス田の胚胎層として知られる上総層群の分布域で、天然ガスの代表的な自然湧出箇所も見学することができた。これら上総層群関連の見学も、時間の都合がつけば、または強い風雨などによって川沿いでのルートマップ作成作業がむずかしい場合の代替えとして見学するという予定を組んでいたことから、それらの関連資料も参考資料としてテキストに収めておいたが、実際に活用することができた。また、毎晩の夜の学習や整理作業もほぼ順調に実施することができた。
研修前半少し雨が降ったことや比較的暖かったことから、山ヒルの出現が予想されたが、特に多いというわけではなかったが、道沿いの草むらなどで露頭観察作業を行った際には、予想通り山ヒルが長靴を這い上がってくる姿が何回もみられた。対策として、草むらなどで作業した際には、その直後にこまめにお互いの長靴周辺やズボンを観察しあって早期発見と早期駆除に努めた。駆除方法としては、全員に配布しておいた食塩の入った小瓶を使って塩をふりかけ、収縮させて落とした。また毎朝、長靴(川歩きの際に滑って転倒しないように、全員スパイク長靴を使用)とズボンの間をガムテープ(布テープ)で幾重にも巻きつけ、長靴の中に侵入しないようにした。この布テープの巻きつけは、川を歩いている際に、長靴の中に水が浸入するのを防ぐ意味でも大変有効であった。今回被害を受けたのはほぼ一人で、それも1回の被害を受けただけで、特に重症化することもなかった。これは従来の研修とほぼ同じ程度の被害である。
このように今回の研修では、当初天候の影響も心配されたが、その影響はほとんどなく、事前に予定していた内容をほぼ実施することができた。また、交通事故および調査中の事故もなく、無事終了することができた。これは、講師と研修参加者相互の努力・協力の賜物と思われる。
なお、例年、研修終了後の週末から4、5日かけて、研修期間中に講師が撮った多くの写真を日付ごとにパワーポイントに収め、簡単な説明をつけた実施記録を作成し、テキストに使った主な図面のファイル(資料編)とともに、次の週の週末までには参加者に配布してきたが、今回も無事配布することができた。この実施記録は、参加者の場合、研修中はルートマップの作成作業などで忙しく現場の写真を撮る余裕があまりないために、講師が本研修の記録と復習用に作成するものであるが、会社などで研修の実施内容や成果を報告する際にも有効に使ってもらうことも考慮している。また今回は、研修中は地質調査の基本作業としてのルートマップ作成作業に昼夜忙しく、こうした地質調査作業をベースにどのような研究成果が生まれたのか、内容面での説明時間が不足していることから、いくつかの関連文献を指定してその感想文を書いてもらうことを宿題として行ったが、直接接したばかりの地層や凝灰岩鍵層に関連した研究成果の文献だけに、内容面の理解やこうした地質調査法の役割の意義や重要性の理解に大いに役立ったようである。この他、地質調査参加者には、毎回研修終了後アンケートに協力してもらい、その内容をそれ以後の実施内容にできる範囲で反映するように努力している。
本研修実施にあたっては、地質学会担当理事の杉田律子氏、産総研地質調査総合センターの関係者、地質学会事務局にお世話になった。また、東大千葉演習林の関係者にも間接的にお世話になった。ここにお礼を申し上げる。
(徳橋秀一・宇都宮正志)
ページTOPに戻る
写真でみる2015年度秋季地質調査研修の様子
写真1:テキストAとBの表紙。
写真2: Ky8(滝つぼ)タフ直下での層理面の走向・傾斜の測定練習(1日目:清澄向斜南翼の渕が沢林道沿い)。
写真3:清澄層最下部のKy8−Ky7(バーミューダ)タフ間のタービダイト砂岩優勢互層(1日目:清澄向斜南翼の渕が沢奥米林道沿い)。
写真4:清澄背斜南翼の田代林道沿いの天津層−清澄層境界付近の観察(2日目)。
写真5:天津層の粗粒堆積物中の生痕化石(2日目:清澄背斜北翼の片倉−三石林道)。
写真6:清澄層Ky26(ニセモンロー)タフの観察(2日目:清澄背斜北翼の片倉−三石林道)。
写真7:三石観音神社裏で上総層群基底礫岩の黒滝層を観察(2日目)。
写真8:清澄背斜北翼の片倉−三石林道沿いでのルートマップ作成(2日目:清澄層Hkタフ直下のタービダイト砂岩優勢互層付近)。
ページTOPに戻る
写真9:三浦半島の逗子市東小路に由来して名前のついた清澄層第一級の凝灰岩鍵層Hk(Ky21)タフ(2日目)。
写真10:片倉ダムサイトでのルートマップ作成(2日目:清澄背斜北翼の片倉−三石林 道)。
写真11:野帳に書かれたルートマップの清書作業(2日目夜)。
写真12:清澄向斜南翼の渕が沢林道(一部に渕が沢−奥米林道含む)沿いで作成したルートマップの比較(2日目夜)。1マス(5mm)は10複歩。
写真13:清澄背斜北翼の片倉−三石林道沿いで作成したルートマップの比較(2日目夜)。1マス(5mm)は20複歩。
写真14:清澄背斜北翼の七里川沿いの清澄層(手前)−天津層境界付近。天津層最上部付近の凝灰岩鍵層を探索(3日目)。
ページTOPに戻る
写真15:三浦半島の大楠山にちなんで名前のついた天津層第一級の凝灰岩鍵層Ok(Am78)タフ(3日目:清澄背斜北翼の七里川)。
写真16:多数の凝灰岩を挟在する泥岩から成る天津層上部(3日目:清澄背斜北翼の七 里川)。
写真17:清澄層中部付近のタービダイト砂岩優勢互層から成る平坦な河床の上でのルートマップ作成風景(3日目:清澄背斜北翼の七里川)。
写真18:道路沿いでの昼食後、再び川にもどってルートマップづくりを再開(3日目:清澄背斜北翼の七里川)。
写真19:片倉−三石林道でも観察した清澄層Hk(Ky21)タフ(3日目:清澄背斜北翼の七里川)。
写真20:片倉−三石林道でも観察した清澄層Ky26(ニセモンロー)タフ(3日目:清澄背斜北翼の七里川支沢入口付近)。
ページTOPに戻る
写真21:清澄層(タービダイト砂岩優勢互層)とそれを覆う安野層(泥岩優勢互層)との境界付近の凝灰岩鍵層An1(サカサ)タフの観察(3日目:清澄背斜北翼の七里川)。
写真22:安野層最下部付近の泥岩優勢互層分布付近でのルートマップ作成風景(4日目:清澄背斜北翼の七里川)。
写真23:An7(サユリ)タフ付近の安野層(4日目:清澄背斜北翼の七里川)。
写真24:安野層中部に挟在するスランプ堆積物の一部(4日目:清澄背斜北翼の七里川)。
写真25:安野層中部のスランプ堆積物直上の泥岩優勢互層での層理面測定風景(4日目:清澄背斜北翼の七里川)。
写真26:泥質砂岩(〜泥質砂岩)と凝灰岩とが互層する安野層最上部付近(4日目:清澄背斜北翼の七里川)。
ページTOPに戻る
写真27:黒滝不整合直上付近の粗粒堆積物(小礫岩〜礫質砂岩)から成る黒滝層。黒滝層の観察は、三石観音につづいて2度目(4日目:清澄背斜北翼の七里川)。
写真28:表面をタワシでこすりながら安野層上部のタービダイト砂岩の堆積構造の観察(4日目:清澄背斜北翼の七里川)。
写真29:養老川沿いに露出する上総層群梅ヶ瀬層のタービダイト砂岩優勢互層(4日目:養老渓谷中瀬遊歩道)。
写真30:清澄背斜北翼七里川沿いのルートマップ比較(4日目夜)。1マス(5mm)は20複歩。
写真31:ルートマップのデータを七里川沿いの5千分の1地形図に表現した一例(4日目夜)。
写真32:宿の前で、恒例の全員集合写真(5日目)。
ページTOPに戻る
写真33:嶺岡構造帯にブロックとして産出する層状石灰質チャート(5日目:嶺岡山地北鹿の白絹の滝)。
写真34:嶺岡構造帯にブロックとして産出する枕状溶岩(5日目:嶺岡山地東端の鴨川青年の家)。
写真35:勝浦市吉尾漁港東方の海蝕崖に露出する清澄層上部のタービダイト砂岩優勢互層(5日目)。
写真36:吉尾漁港東方の海蝕外東端のボラの鼻にみられる上総層群基底の黒滝不整合。黒滝不整合直上の堆積物(黒滝層)の観察は、片倉−三石林道、七里川につづいて3度目(5日目)。
写真37:清澄層上部の凝灰岩鍵層Ky26(ニセモンロー)タフ上部の変形構造の観察。Ky26タフの観察も、片倉−三石林道、七里川につづいて3度目(5日目)。
写真38:地表東端部にあたる勝浦海中公園に露出する凝灰岩鍵層Hk(Ky21)タフの産状。Hkタフの観察も、片倉−三石林道、七里川につづいて3度目(5日目)。
写真39:勝浦海中公園でみられる清澄層Hkタフ直下の泥岩優勢互層。片倉−三石林道や七里川など、房総中央部ではタービダイト砂岩優勢互層であるが(写真8参照)、ここでは個々のタービダイト砂岩が薄層化するか消滅して泥岩優勢互層に変化する同時異相関係を確認できる(5日目)。
写真40:勝浦海中公園の水中展望塔をバックに恒例の地質調査研修修了証書受領後の記念写真(5日目)。研修参加者は、この他に、技術者教育継続単位(CPD単位)40単位を取得できる。
写真41:上総層群下部の勝浦層中のスランプ堆積物の観察(5日目:勝浦部原海岸北方)。
写真42:上総層群分布域での天然ガス自然湧出現象の観察(5日目:瑞沢川西門橋下)。
ページTOPに戻る
写真43:JR外房線茂原駅にて解散(5日目)。
ページTOPに戻る
意見・提言2016
意見・提言2016
「平成28年(2016年)熊本地震」による地震災害に関する声明
2016年4月14日,16日に発生しました「平成28年(2016年)熊本地震」により,熊本・大分地域の地震災害の犠牲者の方々に心から哀悼の意を捧げ,ご冥福をお祈りすると同時に,被災者の皆様におかれましては,一日も早く静穏な日常生活を取り戻されることをお祈りいたします.
全文(PDF)はこちら
2016年6月11日発表
平成28年度大学入試センター試験の地学関連科目に関する申し入れ
標記申し入れ書を(独)大学入試センター理事長に3月15日付で提出しました.
全文(PDF)はこちら
2016年3月17日発表
参考:理科得点調整および地学関連科目に関して,大学入試センターに申し入れ提出(2015年4月15日付提出)
東日本大震災から5年を迎えるにあたって
日本地質学会(会長 井龍康文)は、東日本大震災から5年を迎えるにあたって、改めて震災に関する記憶の風化を防ぎ、防災意識を一層高めるため、表記の声明を発表(プレスリリース)致しました.
全文(PDF)はこちら
2016年3月4日発表
プレスリリース(2016年)
プレスリリース(2016年)
日本地質学会第123年学術大会(東京・桜上水大会)
発表形態:資料配付(9月8日解禁)
発表先:文部科学記者会・科学新聞社
■ 配布資料:全文(PDF)はこちら
「県の石」発表
日本地質学会は、全国47都道府県について、その県に特徴的に産出する、あるいは発見された岩石・鉱物・化石をそれぞれの「県の石」として選定いたしました。
発表形態:記者会見(文部科学記者会,5月10日13時より),資料配付(5月10日解禁)
発表先:文部科学記者会・科学新聞社・各都道府県県政記者クラブ
■ 配布資料(趣旨文書)
■ 県の石に関する詳細は,こちら(学会ホームページ)
日本の地質を初めて総合的に網羅した「Geology of Japan」が世界で出版されました
地球科学分野において世界で最も歴史ある英国地質学会(The Geological Society, London)と,同じく地球科学分野において日本で最も歴史ある日本地質学会が2013年に学術交流協定を締結しました.そしてこの協定の成果の一つとして日本の地質を世界に紹介する書籍「Geology of Japan」が刊行に至りましたので,ここにお知らせいたします.
発表形態:資料配付(4月5日)
発表先:文部科学記者会・科学新聞社
■ 配布資料:全文(PDF)はこちら
平成28年度大学入試センター試験の地学関連科目に関する申し入れ
標記申し入れ書を(独)大学入試センター理事長に3月15日付で提出し,プレスリリースを行いました.
発表形態:資料配付(3月17日)
発表先:文部科学記者会・科学新聞社
■ 配布資料:全文(PDF)はこちら
東日本大震災から5年を迎えるにあたって
日本地質学会(会長 井龍康文)は、東日本大震災から5年を迎えるにあたって、改めて震災に関する記憶の風化を防ぎ、防災意識を一層高めるため、表記の声明を発表(プレスリリース)致しました.
発表形態:資料配付(3月4日)
発表先:文部科学記者会・科学新聞社
■ 配布資料:全文(PDF)はこちら
地質調査研修中止のお知らせ
地質調査研修中止のお知らせ
地質調査研修中止のお知らせ
日本地質学会では,2012年より実施してきた地質調査研修を,2016年をもって中止することとしました.
これまで,事故もなく,参加者に満足していただける研修が実施されてきたことは,講師の徳橋会員や講師の補助としてご助力頂いた皆様方のご努力のたまものであります.地質学会では,本研修を含めた学会の行事運営の見直しを行っているところですが,万が一の事故に備えた万全の体制を確立し,法と安全を遵守し,より健全な事業運営のためには,相応の費用を負担する必要があります.しかしながら,必要な経費を確保しつつ,これまでの水準の研修を維持することは,現状では困難であり,全面的な見直しが完了するまで,本地質調査研修を中止することとしました.
これまで,地質調査研修にご尽力いただいた徳橋会員はじめ関係者には深く感謝いたします.
2017年3月10日
日本地質学会社会貢献部会
意見・提言2017
意見・提言2017
声明:地質学の知見をもって減災につなげるために 熊本地震から一年を迎えるにあたって
平成28年熊本地震から1年が経とうとしています。この地震は甚大な被害と共に、数多くの地質学的な教訓をもたらしました。本学会は地質学の役割を自ら再認識し、その知見を減災に役立てていくために声明を発表します。
全文(PDF)はこちら
2017年4月10日発表
プレスリリース(2017年)
プレスリリース(2017年)
日本地質学会第124年学術大会(愛媛大会)
発表形態:会見(文部科学記者会,9月8日15時),同日資料配付および解禁
発表先:文部科学記者会・科学新聞社・愛媛番町記者クラブ
■ 配布資料:全文(PDF)はこちら
2017年9月8日発表
声明:地質学の知見をもって減災につなげるために 熊本地震から一年を迎えるにあたって
平成28年熊本地震から1年が経とうとしています。この地震は甚大な被害と共に、数多くの地質学的な教訓をもたらしました。本学会は地質学の役割を自ら再認識し、その知見を減災に役立てていくために声明を発表します。
発表形態:資料配付
発表先:文部科学記者会・科学新聞社
■ 全文(PDF)はこちら
2017年4月10日発表
意見・提言2018
意見・提言2018
「平成30年北海道胆振東部地震」に関する会長談話
2018 年 9 月 6 日未明に発生しました「平成 30 年北海道胆振東部地震」により犠牲になられた 方々に心から哀悼の意を捧げ,ご冥福をお祈りします.同時に,未だ安否不明の方の一刻も早い救出と,被災者の皆様におかれましては,一日も早く日常生活を取り戻されることをお祈りいたします.
平成30年北海道胆振東部地震は,9月6日午前3時7分頃の北海道胆振地方中東部を震源とし,地震の規模はM6.7,震源の深さが37kmの地震です.勇払郡厚真町では,北海道における観測史上初めて最大震度7を観測し,震度6 強を安平町,むかわ町において,また震度6弱を札幌市東区,千歳市,日高町,平取町で観測するなど,胆振・石狩・日高地方を中心に広範囲にわたって強い揺れを観測しました.この強い震動は,厚真町を中心に,火山性堆積物からなる急斜面で数多くの土砂災害を引き起こし,被害を拡大させました.また札幌市東部では大規模な液状化現象が起こりました.さらに苫東厚真発電所の停止による全道にわたる大規模停電が,その後の市民生活に大きな影響を与えております.
平成30年北海道胆振東部地震の地震災害の詳細は,今後の調査・研究結果によりますが,今回の災害の背景に,この地域における地質学的な特徴が反映していることは言うまでもありません.今回の地震の震源域は,石狩低地,夕張山地,日高山脈の接合部にあたり,また西方の支笏・洞爺地方は火山活動の活発な地域にあたります.地殻の構造や断層の配置,加えて表層の地質条件が地震災害に大きく関係します.これらを総合的に理解,解釈することが災害の予測と減災に必要不可欠です.そのためには,基礎となる地質学的研究を精力的に進め,最新の知見を災害の予測と減災に活かす必要があります.日本地質学会は,学術研究の発展と最新の知見の普及・教育を推進し,多くの市民の皆様,そして関係諸機関と共に,最新の地質学的知見を活かして自然災害の予測と防災・減災方策を社会と連携して追求してまいりたいと思います.
今後,今回の地震に関する調査報告や研究成果については,学会公式サイトから,随時,発信してまいります.
一般社団法人日本地質学会
会 長 松田 博貴
PDF版はこちら
2018年9月9日
「チバニアン」に関する声明
昨年6月,日本の22機関32名からなる研究グループが,「千葉セクション」(千葉県市原市田淵の地層露出断面)を『国際標準模式層断面及びポイント』(Global Stratotype Section and Point; GSSPと略記)の「下部−中部更新統境界GSSP」に認定されるよう,GSSPの決定機関である国際地質科学連合(IUGS)に提案しました.これを受けて,IUGSのもとにある,国際層序委員会(ICS)の第四紀層序小委員会(SQS)下部−中部更新統境界作業部会で,提出された申請書が審査されました.そして2017年11月,作業部会における投票の結果,「千葉セクション」がIUGS内の上部の委員会に答申されることになりました.その後,日本の別の団体から申請書の科学的データへの異議がIUGSに出され,IUGSでの認定審査プロセスが本年4月から中断していることが報道されています.
地球科学分野における我が国最大の学会と言える日本地質学会として,今回,研究グループの提案内容を本学会の学術研究部会を中心に検討しました.この声明は,その結果を踏まえ,提案内容の学術的意味の説明と本学会の見解を,ホームページに掲載し表明するものです.
全文(PDF)はこちら(日本語版)
全文(PDF)はこちら(English)
2018年7月1日
平成30年度大学入試センター試験の地学関連科目に関する意見書
独立行政法人大学入試センターへ,平成30年度大学入試センター試験の地学関連科目に関する意見書を提出しました。
全文(PDF)はこちら
2018年3月22日提出
高等学校学習指導要領案へのパブリックコメント
文部科学省では、平成28年12月21日の中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」等を受け、学校教育法施行規則の一部改正及び高等学校学習指導要領の改訂を予定しており,それに伴いブリックコメント(意見募集)が行われました。日本地質学会として意見を提出しました。
全文(PDF)はこちら
学校教育法施行規則の一部を改正する省令案及び高等学校学習指導要領案に対する意見公募手続(パブリックコメント)の実施(募集要項)
2018年3月15日提出
プレスリリース(2018年)
プレスリリース(2018年)
第125年学術大会(2018札幌)
発表形態:会見(道政記者クラブ)および資料配付(9月4日)
発表先:道政記者クラブ・文部科学記者会・科学新聞社
■ 配布資料(PDF)
5月10日「地質の日」第11回事業の紹介
発表形態:資料配付(4月23日)
発表先:文部科学記者会・科学新聞社
■ 配布資料(PDF):本文/添付資料(チラシ)/行事リスト(4/12現在)
意見・提言2019
意見・提言2019
「千葉セクション」に関する声明
2017年6月,日本の22機関32名からなる研究グループが,「千葉セクション」(千葉県市原市田淵の地層露出断面)を『国際境界模式層断面とポイント』(Global Stratotype Section and Point; GSSPと略記)の「下部−中部更新統境界GSSP」に認定されるよう, GSSPの認定機関である国際地質科学連合(IUGS)に提案しました.現在,IUGSによる認定審査プロセスは最終段階に入っております.今回の提案についての学術的説明と意義については,既に2018年7月1日に日本地質学会の見解をホームページに掲載し表明いたしました.
本提案に関わる「千葉セクション」および関連露頭は,地磁気の逆転に関わる研究を含む地質時代の決定に必要な調査研究や,それらに基づいた同地質時代の地球表層環境変動などの研究に関して重要性を有しており,国際的に見てもきわめて貴重な露頭です.今後の地質学の発展のためには,「千葉セクション」および関連露頭が学術的に誰もが自由かつ公平に議論できる環境が維持されることが重要です.日本地質学会は,今後も「千葉セクション」および関連露頭における研究により,地質学がさらなる発展を遂げることを期待しています.
全文(PDF)はこちら
2019年8月15日
東赤石山「赤石山荘」の存続についてに要望書
地質学会は2019年4月6日,安全な研究フィールドの確保と維持を願う学術団体の立場から,新居浜市長と愛媛県知事に対し,赤石山荘管理人 安森 滋氏の陳情受け入れを求める要望書を作成しました.新居浜市長宛の要望書は6月14日,安森氏らと共に新居浜市役所を訪れた西山賢一四国支部長の手で,4359名分の署名と共に直接,石川勝行新居浜市長へと提出されました.また県知事宛の要望書も同日県担当課へ提出されました.
愛媛県知事宛要望書全文(PDF)はこちら
新居浜市長宛要望書全文(PDF)はこちら
2019年6月14日提出
不正研究論文の撤回を受けて
本年3月の地質学関連分野における研究論文の不正問題に関して,5月3日に当該論文が撤回されたとする報道がなされました.本件に関しては,既に4月4日に会長声明を公表しておりますが,ここに改めて遺憾の意を表明し,会員の皆様に,再度,「日本地質学会倫理綱領」ならびに「日本地質学会行動規範」の遵守を呼びかけます.
全文(PDF)はこちら
2019年5月17日
研究論文不正問題を受けて
本年3月,地球科学分野において研究論文の不正問題に関する発表があり,地球科学関連学会である日本地質学会としても大きな衝撃を受けています.
日本地質学会は,2003年に「日本地質学会倫理綱領」を定めるとともに,2011年に「日本地質学会行動規範」を制定し,学会員に対してこれらを遵守することを求めてまいりました.同時に,地質学の成果が与える社会的影響を自覚し,客観的データ・事実に基づき公正,誠実に行動することで,地質学が社会から信頼を得るための不断の努力をしてまいりました.研究不正は,地質学の発展にきわめて深刻な影響を与え,地質学に対する信頼を失墜させることと重く受け止めねばなりません.
全文(PDF)はこちら
日本地質学会倫理綱領 http://www.geosociety.jp/outline/content0010.html
日本地質学会行動規範 http://www.geosociety.jp/outline/content0198.html
2019年4月4日
平成31年度大学入試センター試験の地学関連科目に関する意見書
独立行政法人大学入試センターへ,平成31年度大学入試センター試験の地学関連科目に関する意見書を提出しました。
全文(PDF)はこちら
2019年3月31日提出
プレスリリース(2019年)
プレスリリース(2019年)
第126年学術大会(2019山口)に関して
発表形態:資料配付(9月19日)
発表先:文部科学記者会・科学新聞社・山口県政記者クラブ
■ 配布資料(PDF)
日本地質学会企画の「一家に1枚」ポスター発行
発表形態:資料配付(4月9日)
発表先:文部科学記者会・科学新聞社
■ 配布資料(PDF)
意見・提言2020
意見・提言2020
日本学術会議第25期推薦会員任命拒否に関する緊急声明へ賛同いたしました
現在、日本学術会議の推薦会員の任命を巡っていろいろな報道がなされています。日本地質学会が所属する日本地球惑星科学連合においても、対応について議論がなされました。また他の学術連合においても同様な議論がなされ、それらの結果として、複数の学会連合が共同声明(下記)を出すことになりました。日本地質学会は,日本地球惑星科学連合および自然史学会連合の参加学会として声明に賛同いたしました。
日本学術会議第25期推薦会員任命拒否に関する緊急声明(PDF)
2020年10月10日
会長 磯崎行雄
「令和2年7月豪雨」による災害についての会長談話
令和2(2020)年7月に発生しました「令和2年7月豪雨」災害により犠牲になられた方々に心から哀悼の意を捧げ,ご冥福をお祈りします.被災者の皆様におかれましては,一日も早く日常生活を取り戻されることをお祈りいたします.
一連の豪雨では,熊本県南部,球磨川水系の氾濫により,流域の広い範囲で都市機能が麻痺し市民生活に大きな支障をもたらしたほか,浸水による犠牲者も発生しました.その後も福岡県,大分県,岐阜県,山形県,秋田県などで河川の氾濫が相次ぎ,各地で甚大な被害が生じました.また九州から東北に至る各地で,豪雨による土砂災害が多く発生しました.一部は民家を襲うなどし,多くの尊い人命が失われたことが報道されました.
災害の詳細については,今後の調査・研究結果を待つ段階ですが,災害の背景に,これら地域における地質学的な特徴が反映していることは言うまでもありません.今回,甚大な被害を被った地域は,例外なく過去に大きな水害を経験しています.気象現象はもとより,歴史的に治山治水は地域の地質特性とも密接に関係しており, これらを総合的に理解,解釈することが災害の予測と減災に必要不可欠です.近代・現代に日本列島の地理的・地形的形態が大変化したわけではなく,地質学的時間スケールの中では,同じ地域で同種の自然災害が繰り返し起きてきました.
高知市寺田寅彦記念館 石碑(撮影:坂口有人)
「天災は忘れられたる頃来る」という寺田寅彦の金言は, 地質学会会員の間ではほぼ完全に共有されていますが, 一般市民の間では3世代(国内移住が増えた近年では2世代かもしれません)を越えると過去の経験・記憶が伝達されなくなるのが普通です. 本学会は,学術研究の発展と最新の知見の普及・教育を推進し,多くの市民の皆様,そして関係諸機関と共に,最新の地質学的知見を活かして自然災害の予測と防災・減災方策を社会と連携して追求してまいりたいと思います.
今後,今回の豪雨災害に関する調査報告や研究成果については,学会公式サイト(http://www.geosociety.jp/hazard/) から,随時,発信してまいります.
一般社団法人日本地質学会
会長 磯粼行雄
2020年8月4日
令和2年度大学入試センター試験の地学関連科目に関する意見書
日本地質学会は、過去5年間にわたり、大学入試センター試験の地学関連科目の問題および得点調整に関して、それらが適正に行われているかを検討し、その都度、意見や改善に向けた要望を大学入試センターに申し入れてきました。本年に実施されました令和2年度大学入試センター試験(本試験)の地学関連科目に関して、以下のような意見を申し入れ致します。
全文(PDF)はこちら
2020年2月25日
プレスリリース(2020年)
プレスリリース(2020年)
「コロナ禍での地質学教育に関するサイバーシンポジウム」開催
発表形態:資料配付(9月9日)
発表先:文部科学記者会・科学新聞社
■ 配布資料(PDF)
自宅で地質を楽しんで学べる「地質の日」特設ウェブサイト開設
発表形態:資料配付(4月20日)
発表先:文部科学記者会・科学新聞社
■ 配布資料(PDF)
座談交流会_20210801
日本地質学会 ジェンダー・ダイバーシティ委員会企画
座談交流会 (ジェンダー・ダイバーシティ委員会Workshop)
「地質分野の多様性を増やすには:持続可能で闊達な学会を目指して」
日本地質学は年々会員が減少し、学生会員を含む若手会員数も他学会と比べ少ない傾向にあります。また、女性会員率も決して高いわけではありません。 そこで、若手研究者や女性会員も含め多様な背景を持つ会員が、学会運営に携わる理事達と学会に対する忌憚のない意見を交わし学会の将来を模索していきたいと思います。
日時:2021年8月1日(日)10:00-11:30
開催方法:遠隔開催(Zoom)
参加申込:こちらから
参加申込締切:7月29日(木)*申込された方には、締切後Zoom接続情報を送付します。
スケジュール(予定)
総合司会:堀 利栄(日本地質学会 ジェンダー・ダイバーシティ委員会委員長)
話題提供:10:00-10:40
地質学会ダイバーシティの現状(益田晴恵会員)
若手から見た地質学会(仮)(奥津なつみ氏)
コメント・意見交換:10:40-11:10(コーディネーター:福地里菜会員)
若者から
各理事から
問題提起:11:10-11:20 若手会員や女性会員・幹事を増やすにはどうしたらいいか
最後に:日本地質学会長から
2021業界サポート(実施報告)
2021.11.8 掲載
委員会ページに戻る
第128年学術大会関連行事:
WEBを活用する業界研究サポートサービス
〜地質系企業・団体へのオンライン訪問〜
[実施報告]
「業界研究サポートサービス」は,学術大会の会場において,学生会員が将来就職する可能性のある地質調査業,建設コンサルタント業をはじめとする地質系企業・団体と対面で説明を受け,この業界を研究していただくサポートサービスとして,これまで毎年開催してきました.しかしながら,新型コロナウィルス感染症の拡大により昨年度は学術大会が中止となり,今年も対面ではなくオンラインでの大会となりました.
そこで,今年は地質技術者教育委員会が中心となって,WEBを活用する方法により企画・開催することとなりました.これは,当学会のHPを介して,全国の学生が学術大会会場に行かなくても企業・団体の紹介資料を閲覧し,興味のある企業・団体にオンライン訪問して担当者と直接話ができるというものです.企業・団体にとっても担当者が在社のままで学生に説明ができるメリットがあります.
参加企業・団体は以下の21社で,8月中旬から学会HPに紹介資料を掲載し,全国の40を超える地質系学科を有する大学や土木・建築系の学科のある高等専門学校から会員・非会員を問わず参加募集をおこないました.なお,学会HPには下記の企業・団体の紹介資料を年末まで掲示していますので,ご興味のある方は是非ごらんください(https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/gyokai_support).
参加企業・団体(50音順,*印は賛助会員):アジア航測(株)*/応用地質(株)*/川崎地質(株)*/原子力発電環境整備機構/(株)建設技術研究所*/(株)サクセン/サンコーコンサルタント(株)*/住友大阪セメント(株)/石油資源開発(株)*/太平洋セメント(株)*/(株)ダイヤコンサルタント*/玉野総合コンサルタント(株)/(株)地圏総合コンサルタント*/中央開発(株)*/(株)ドーコン/日鉄鉱業(株)*/(株)日さく*/日特建設(株)/(株)ニュージェック*/(株)パスコ*/(株)レアックス
約2週間の資料閲覧,参加募集期間を経て,2021年9月5日(日)10時から15時(終了は16時)に希望者によるオンライン訪問を行いました.なお,できるだけ多くの学生に参加していただけるように,当日参加も認めるようにしました.
Zoomのブレイクアウトルームを使って15大学43名の学生が,オンライン対応企業・団体18社に対し,延べ154訪問しました.
アンケートの結果は以下のとおりです.アンケートにご協力くださいました学生や企業・団体担当者に感謝申し上げます.
① 参加学生に対するアンケート(43名 回答22名(回答率51%))
※クリックすると大きな画像でご覧いただけます。
② 参加企業・団体に対するアンケート(21社 回答16社(回答率76%))
③ 主なご意見
【学生】
地質系の業界について深く知ることができました.
少人数で色々と話を聞けたのはとてもよかった.
複数の会社を1日で訪問し,比較することができたのでとても良い体験となりました.
この度は貴重な機会を与えてくださり,ありがとうございました.
【企業・団体担当者】
飛び入り参加も可にしたのは,学生側が自由に動けて良かったのではと思います.また,まとまった地球科学系の学生とコンタクトできる良い機会だと思いますので,今後もぜひ開催を検討していただければと思います.
学生は1回の説明に2〜4名程度でしたので,学生側も質問しやすく,適当な人数であると感じました.あらかじめ動画を見て,会社に興味を持った学生が来るのは,全く興味がない学生に説明するのに比べるとお互いに話しやすく,良い取り組みだと思いました.
来年,オンラインではなく対面で開催できる状況だとしても,会社の動画なりPDFを事前に公開するのを続けていただければと思います.
地方の会社としましては,今回のようなオンライン説明会は普段目立たない会社も同列に参加することができる印象があるので,参加してよかったと思いました.今後,対面式の説明会が再開していくと思いますが,オンラインの説明会も並行して行っていただければ幸いです.
一方,運営方法などについてのご指摘や改善点のご提案もあり,次回の企画に参考にさせていただきます.
初めて企画・開催したWEBを使った業界研究サポートサービスでしたので,連絡や当日の運営での不手際がありましたが,概ねよい評価をいただき,企画・開催してよかったと安堵しています.とくに,対面での開催ができるようになっても,紹介資料の学会HP掲示やオンライン説明会も並行して行うことのご意見があったことは大いに参考にさせていただきます.
最後に,ご参加いただいた学生や企業・団体の皆様,学術大会担当の行事委員会,運営担当の地質技術者教育委員会および事務局に厚く御礼申し上げます.
(担当代表 佐々木和彦)
委員会の活動(過去)
地質技術者教育委員会の活動(過去分)
第3回委員会(WEB) 2021年1月19日
JABEE地球・資源分野運営委員会出席 2020年11月24日
JABEEオンラインシンポジウムの詳細広報開始(学会HP他 2020年10月から) 日本機械学会主催のJABEE審査員研修フォーラム(WEB)に本委員が参加 2020年9月14日
学会内のCPD支援策について各支部に連絡 2020年9月12日
第2回委員会(WEB) 2020年7月30日
JABEE地球・資源分野運営委員会出席 2020年7月16日
第1回委員会(WEB) 2020年7月9日
JABEE勉強会(執行理事会、地質技術者教育委員会)2020年2月16日 講師:JABEE専務理事 三田清文氏、 山口大学教授 坂口有人氏
現在のページに戻る
プレスリリース(2022年)
プレスリリース(2022年)
第129年学術大会(2022東京・早稲田大会)に関して
発表形態:資料配付(9月1日)
発表先:文部科学省記者会、科学新聞社
■ 配布資料(PDF)
地質図に関するJIS(日本産業規格):JIS A 0204とJIS A 0205の改正 について
地質図に関するJIS(日本産業規格):JIS A 0204とJIS A 0205の改正 について
川畑大作・斎藤 眞(産業技術総合研究所地質調査総合センター)
本学会の宮下純夫元会長が原案作成委員会の委員長を務めた地質図に関するJIS(日本産業規格):JIS A 0204とJIS A0205 が,2019年に改正された.これまで著者らは原案作成委員会事務局として学会発表の場で紹介したが,以下に地質図に関するJIS規定の経緯と2019年の改正内容を改めて紹介し,利用促進につなげたい.
地質図は地質年代,岩相,地質構造などを表現する図であり,資源,環境,建築,防災などの基本情報となる.地質図の作成は,主に現地調査によって行われ,その歴史は古い.長い歴史の中で,例えば走向傾斜の記号や火山岩のハッチ表現など代表的な記号などは概ね国際標準(ISO)としてある程度決まっている.しかし,地質学の発展に伴い,地質学用語のゆらぎやローカル性が顕著になってきた.また,近年のコンピューターの普及に伴い,地質図の情報を数値処理できるようになってきた.そこで日本で作成する地質図について,2002年に規格準拠の地質図内での用語の統一や記号の統一など品質の保証と信頼度の向上を目指しISOとの整合性を検討しつつ地質図に関するJIS(日本工業規格)として,JIS A 0204「地質図−記号,色,模様,用語及び凡例表示」を規定した.また2008年には普及が進むコンピューターで容易に活用できるようになることまた電子納品への対応を目指して地質年代や岩石名などをコード化した JIS A 0205「ベクトル数値地質図−品質要求事項及び主題属性コード」を規定した.これらによって,JIS制定以前は,地質図の記号等がまちまちだったものが,地質図を作成する側と利用する側が同じルール(言葉)に基づいて地質図の理解が図れるようになった.
第1表 存在確実度と位置正確度に基づく断層の区分
(JIS A 0204解説より引用)
クリックすると大きな画像をご覧いただけます.
JISを規定した2002年以降,規格内での用語の統一や記号の統一は行われたものの,地質学の発展は継続的に続くものであり,JISでも最新の研究成果を反映させる必要がある.JISでは数年単位での見直しが行われることになっており,JIS A 0204 及びJIS A 0205も2008年,2012年に見直しが行われ,改正を行った.改定の経緯については斎藤ほか(2019)で報告している.2012年の改正後,2014年11月に一般社団法人日本結晶学会がOrthorhombicの訳語として,“直方晶系(斜方晶系)”の表記を採用し,日本地質学会もこれを採用した.国際年代層序表では新たに固有の時代名称が与えられ,カンブリア紀が4分割されるなどの変更が行われた.このような名称等の変更に加え,2012年の改正時に不足していたリチウムなど鉱産物の文字記号の項目の追記や,2012年時に断層・地層境界などの存在確実度及び位置正確度を表現する記号を導入した際に規定しなかった岩脈の向きや深成岩の貫入境界面を表す方法の追加など,見直すべき項目が多数生じたため,ちょうどJISが「日本産業規格」に変わった2019年7月にこの規格を改正した.2019年改正内容については川畑ほか(2019)で報告したが,改めて詳細について下記に記す.JIS末尾にある解説には,詳細な経緯や補足説明が記述されおり,利用に際して一読されることをお勧めしている(例えば第1表).また,2022年2月には,普及を目的として,市販のGISソフトウェアやグラフィックソフトウェアで使えるテンプレート試作版を地質調査総合センターで公開した(https://www.gsj.jp/information/standardization/jis/index.html).
2019年版の主な改正内容
JIS A 0204
鉱物の名称の“斜方輝石”を“直方(斜方)輝石”に変更する(これは,直方輝石を推奨するが斜方輝石も使用可の意).
地質学的属性を表現する主な記号の地層・岩体の境界面に,断層面と同様に,境界面の傾斜方向に短線をつけ,傾斜角の値を付けるよう変更する.
鉱産物の種類を表現する主な文字記号にリチウム及びインジウムを追加する.
地質学的属性を表現する主な記号に“立坑”及び“休廃止石材場”を追加する.
変成岩の名称の“黒色片岩”を削除し,“片岩”を追加する.
地質時代の記載を地質年代に統一する.
地質学的属性を表現する主な記号に地層・岩体の内部構造を示す走向傾斜記号や,試料採取地点及び坑口など,線で表現される記号の線種の記述を追加する.
地質学的属性を表現する主な記号に地層・岩体の内部構造を示す走向傾斜記号や,末尾の「その他」に示される試料採取地点や坑口など,線で表現される記号について線種を追加する.
地質学的属性を表現する主な記号の地層・岩体の境界及び断層等の主題属性の説明についての表記を統一する.
JIS A 0205
鉱物コードの“斜方輝石”を“直方(斜方)輝石”に変更する(これは,直方輝石を推奨するが斜方輝石も使用可の意).
鉱物コードにおいて,ナウマン鉱,スピネル族 (10種), タングステン鉱物(3種), マンガン鉱物(3種の追加), リン酸塩鉱物(ゼノタイム),ネソけい酸塩(ブラウン鉱)などを新たに規定する.
地質属性記号コードに“立坑”と“休廃止石材場”を追加する.
堆積岩岩相コードの地層・岩体の境界面の形状について,傾斜境界面,水平境界面及び鉛直境界面の主題属性コードを追加するとともに,水平断層面の主題属性コードを追加する.
最後に注意点について述べておきたい.産業標準化法では国及び地方公共団体にはJISの尊重義務があり,公的機関からの地質図作成依頼は本JISに従う必要があるが,それ以外の状況ではJISに準拠して地質図を作る必要はない.このJISの規定は品質の保証と普及を目的としたものであり,学術の表現手段を限定するものではないためである.しかしながら,地質コンサルタント業界の会員の利便性や,業界に就職する学生・院生の教育を考え,地質学会では,地質学雑誌においても,JISに基づく表現を推奨している.新しい発見に基づく表現手段の多様性はJIS内でもできる限り確保することを目指している.今後も地質学の発展に合わせて最新の研究成果をJISに反映させることを続けていくことによって,地質図が社会で使いやすい状況を構築していくつもりである.
文 献
JIS A 0204 : 2019. 地質図−記号,色,模様,用語及び凡例表示. 日本規格協会.
JIS A 0205 : 2019. ベクトル数値地質図−品質要求事項及び主題属性コード. 日本規格協会.
川畑 大作・斎藤 眞・尾崎 正紀 (2019) 地質図についての日本産業規格(JIS)の改正(2) —2019年版の改正内容につい て—. 日本地質学会学術大会講演要旨. https://doi.org/10.14863/geosocabst.2019.0_275
日本工業標準調査会ホームページ https://www.jisc.go.jp/jis-act/index.html
斎藤 眞・川畑 大作・尾崎 正紀 (2019) 地質図についての日本産業規格(JIS)の改正(1)—JIS A0204とA0205の制定と改正の経緯—. 日本地質学会学術大会講演要旨. https://doi.org/10.14863/geosocabst.2019.0_274
※本記事は,日本地質学会NewsVol. 25, No.3(2022年3月号)にも掲載しています.
学術大会におけるダイバーシティ認定ロゴ(EDI・ESC)
ダイバーシティ認定ロゴ
2024.7.17更新
学術大会におけるダイバーシティ認定ロゴ
「ECS (Early Career Scientist)」
「EDI(Equity, Diversity and Inclusion)」
導入の取り組み
2023年5月
一般社団法人日本地質学会
ジェンダー・ダイバーシティ委員会
委員長 堀 利栄
(セッションに対して)
EDI:Equity, Diversity & Inclusion
(個人に対して)
ECS:Early Career Scientist
日本地質学会は,「ダイバーシティ認定ロゴ」を129年学術大会から導入しています.会員減少傾向が続く本会においては,若手や留学生等を含めた新規入会者への支援,及び多様な会員の積極的な学会活動が必須となってきています.学会活動におけるダイバーシティ(EDI)への貢献を意識し,地質学分野へ新規参画した若手等の研究者(ECS*注1)を学会全体で積極的に支援・応援するために,EDIへの取組みやECS該当者を可視化(「見える化」)し,包括的な支援に繋げることを目的にロゴを導入します. 本取組によって,学会内のダイバーシティ推進や,ECS対象者にはキャリアマッチングなど就職支援につながることが期待されます.また,多様な会員が積極的に学会運営(学術大会等)に関わることを推奨することで,学会全体の活性化をもたらす効果が期待されます.
(1)EDIロゴ
セッションへのダイバーシティ認定ロゴ添付のガイドラインとしては、以下の3項目について、1つでも該当項目がある場合、学術大会開催セッションに対し、EDIロゴを付与いたします。本ロゴは、開催セッションが、多様な背景を持つ会員を包摂し、Early Career Scientistsを応援するものであることを示すものです。
<EDIロゴ対象項目>
世話人が複数の性別で構成されている
世話人にECS (Early Career Scientist)が含まれる
多様な国籍(2国籍以上)の世話人構成または発表者
申請方法:専用申請フォームからお申し込み下さい .
申請できる人:シンポジウム・セッション世話人
(2)ECS ロゴ
学生・院生, また PDの場合は博士号取得後7年以内(ただし公私事由によるキャリア中断年数の加算可)の方で,年齢を問いません.
ECS (Early Career Scientist)に該当する方で,付与を希望される会員の方は,講演画面にECSロゴマークを表示します. 申請は,学会に参加(講演)される該当者ご本人から任意でおこなって頂きます.また,申請した方はECSロゴマークを自由に使うことができます。積極的に、ロゴをご活用ください。ECSである事を示す事で、就職相談や、先輩会員からの研究上の助言など、様々な支援を受け易くなる効果を期待しております。
申請方法:講演要旨投稿の際に,画面入力内容に従って,ロゴ付与の希望をご選択ください(講演申込はこちらから 講演申込:2024年6月26日締切)
申請できる人:学会に参加(講演)する該当者本人
------------------------------------------------
*注1:この取組におけるECS (Early Career Scientist)は,学生・院生, また PDの場合は博士号取得後7年以内(ただし公私事由によるキャリア中断年数の加算可)の方で,年齢を問いません.
この取組が,ECSの方々への応援とご自身のキャリア発展への一助になればと願っております.
2022年 学生のための地質系業界説明会(9/5対面)
■学生のための地質系業界説明会
〜その業界の仕事を知るためのサポートサービス(対面企画)
2022年9月5日(月)11時から16時に、表記企画の対面説明会が、早稲田大学にて開催されました。実に24の企業・団体が参加し、延べ200名を超える学生の訪問がありました。訪問した学生は、地質系の専門職には多様な分野があり、様々な具体的な仕事内容を知ることができたのではないでしょうか。 9月16日(金)13:00〜19:00にはZoomを使ったオンライン説明会を開催します。対面企画に参加しなかった11社を含む32の企業・団体が参加する予定であり、オンラインですから気軽に参加できます。多くの学生が参加されることを期待しています。
※9/16オンライン企画の様子はこちらから
開催前の打合せ
(株)INPEX
応用地質(株)
川崎地質(株)
基礎地盤コンサルタンツ(株)
クニミネ工業(株)
建設技術研究所(株)
原子力発電環境整備機構
興亜開発(株)
国土防災技術(株)
(株)サクセン
(株)三和ボーリング
(株)J-POWER設計コンサルタント
住友大阪セメント(株)
石油資源開発(株)
太平洋セメント(株)
(株)ダイヤコンサルタント
(株)地層科学研究所
中央開発(株)
日鉄鉱業(株)
日特建設(株)
(株)ニュージェック
ハイテック(株)
(株)パスコ
明治コンサルタント(株)
意見・提言2022
意見・提言2021
令和4年度大学入試共通テストの地学関連科目に関する意見書
独立行政法人大学入試センターへ,令和4年度大学入試共通 テストの地学関連科目に関する意見書を提出しました.
2022年3月29日
一般社団法人日本地質学会
会長 磯粼行雄
日本地質学会は,ここ数年にわたり,旧・大学入試センター試験/現・大学入学共通テストの地学関連科目の問題に関する意見並びに改善に向けた要望を大学入試センターに申し入れしてきました.その要望の主眼は,地学関連科目の平均点が他の理科科目に比べて低くならないようにしていただきたいということでありました.本年度もコロナ禍の厳しい環境の中,問題作成に携わった関係各位の努力に敬意を表するとともに,令和4年度大学入試共通テスト(本試験)の地学関連科目に関して,以下のような意見を申し入れ致します.
理科①の「地学基礎」においては基礎的な問題が出題されており,適正 かつ良質な問題であったと考えます.他の科目の平均点と比べて難易度も適正であったと思われます.
理科②の「地学」においても,大学入学共通テストの目的に合致した思考力・総合力が試される,良質な問題であったと考えます.今年度は平均点も高く,難易度も適切であったと考えられます.
「地学」B 地磁気に関する文章において,「この逆転を境界とする地質時代がチバニアンと名付けられた」とありますが,厳密には地磁気の逆転付近にあるByk-Eテフラの下限でチバニアンが定義されるため,「この逆転をはじまりの目安とする地質時代がチバニアンと名付けられた」とする必要があると思われます.出題ミスではありませんが,問題文のより正確な記述を行っていただくようお願いします.
この度の地学関連科目の問題は,毎年課題とされてきた平均点の低さも是正されており,今後も本年同様の努力を維持していただくようお願いいたします.
2022年 学生のための地質系業界説明会(9/16オンライン)
■学生のための地質系業界説明会
〜その業界の仕事を知るためのサポートサービス(オンライン)
2022年9月16日(金)13:00〜19:00にはZoomを使ったオンライン説明会を開催しました。対面企画に参加しなかった10社を含む31の企業・団体にご参加いただきました.
※9/5開催対面企画の様子はこちらから
開始前ミーティング
株式会社INPEX
応用地質株式会社
川崎地質株式会社
基礎地盤コンサルタンツ(株)
クニミネ工業(株)
建設技術研究所(株)
原子力発電環境整備機構
興亜開発(株)
株式会社コスモ建設コンサルタント
(株)サクセン
(株)三和ボーリング
住鉱資源開発株式会社
住友大阪セメント(株)
住友金属鉱山株式会社
石油資源開発(株)
太平洋セメント(株)
(株)ダイヤコンサルタント
株式会社地圏総合コンサルタント
中央開発(株)
株式会社ドーコン
トキワ地研株式会社
飛島建設株式会社
日鉄鉱業株式会社
日特建設株式会社
日本工営都市空間株式会社
株式会社ニュージェック
ハイテック株式会社
株式会社パスコ
株式会社芙蓉コンサルタント
株式会社村尾技建
明治コンサルタント株式会社
プレスリリース(2023年)
プレスリリース(2023年)
5月10日地質の日 第16回事業の紹介(2023年)
5月10日地質の日 第16回事業の紹介(2023年)
発表形態:資料配付(4月28日)
発表先:文部科学記者会・科学新聞社
■ 配布資料(PDF):本文/添付資料(チラシ)/行事リスト(4/28現在)
オンラインシンポジウム 「ジオパーク地域に伝わる伝承と地質学」を開催
市民対象オンラインシンポジウム「ジオパーク地域に伝わる伝承と地質学:古代からの自然館を今に活かす」を開催します
発表形態:資料配付(1月17日)
発表先:文部科学省記者会
■ 配布資料(PDF)
2023年学生のための地質系業界説明会(2023/9/18対面)
■2023年 学生のための地質系業界説明会
〜その業界の仕事を知るためのサポートサービス(対面企画)
2023年9月18日、表記企画の対面説明会が、京都大学にて開催されました。実に32の企業・団体が参加し、延べ200名を超える学生の訪問がありました。
※2023/9/22オンライン企画の様子はこちらから
会場全景
1 (株)アーステック東洋
2 (株)INPEX
3 (株)エイト日本技術開発
4 応用地質(株)
5 川崎地質(株)
6 基礎地盤コンサルタンツ(株)
7 キタイ設計(株)
8 原子力発電環境整備機構
9 (株)建設技術研究所
10 鉱研工業(株)
11 国土防災技術(株)
12 (株)サクセン
13 サンコーコンサルタント(株)
14 三洋テクノマリン(株)
15 三和ボーリング(株)
16 四国建設コンサルタント(株)
17 石油資源開発(株)
18 大日本ダイヤコンサルタント(株)
19 太平洋セメント(株)
20 (株)地圏総合コンサルタント
21 地熱エンジニアリング(株)
22 中央開発(株)
23 (株)日さく
24 日鉄鉱業(株)
25 日特建設(株)
26 (株)日本海技術コンサルタンツ
27 日本工営(株)
28 ハイテック(株)
29 (株)パスコ
30 (株)阪神コンサルタンツ
31 (株)蒜山地質年代学研究所
32 明治コンサルタント(株)
2023年学生のための地質系業界説明会(2023/9/22オンライン)
■学生のための地質系業界説明会
〜その業界の仕事を知るためのサポートサービス(オンライン)
2023年9月22日(金)にはZoomを使ったオンライン説明会を開催しました。35の企業・団体にご参加いただきました.
※9/18開催対面企画の様子はこちらから
1 (株)アサノ大成基礎エンジニアリング
2 応用地質(株)
3 川崎地質(株)
4 基礎地盤コンサルタンツ(株)
5 クニミネ工業(株)
6 原子力発電環境整備機構
7 (株)建設技術研究所
8 鉱研工業(株)
9 国際航業(株)
10 (株)サクセン
11 三和ボーリング(株)
12 四国建設コンサルタント(株)
13 シンワ技研コンサルタント(株)
14 住鉱資源開発(株)
15 住友大阪セメント(株)
16 住友金属鉱山(株)
17 石油資源開発(株)
18 大日本ダイヤコンサルタント(株)
19 太平洋セメント(株)
20 (株)郄田地研
21 (株)地圏総合コンサルタント
22 地熱エンジニアリング(株)
23 中央開発(株)
24 (株)ドーコン
25 トキワ地研(株)
26 (株)日さく
27 日鉄鉱業(株)
28 日特建設(株)
29 日本海洋事業(株)
30 (株)ニュージェック
31 ハイテック(株)
32 (株)パスコ
33 (株)芙蓉コンサルタント
34 明治コンサルタント(株)
35 山北調査設計(株)
意見・提言2023
意見・提言2023
令和5年度大学入試共通テストの地学関連科目に関する意見書
独立行政法人大学入試センターへ,令和5年度大学入試共通 テストの地学関連科目に関する意見書を提出しました.
2023年3月10日
独立行政法人大学入試センター
理事長 山口 宏樹 様
一般社団法人日本地質学会
会長 岡田 誠
日本地質学会は、ここ数年にわたり、旧・大学入試センター試験/現・大学入学共通テストの地学関連科目の問題に関する意見並びに改善に向けた要望を大学入試センターに申し入れてきました。その要望の主眼は、地学関連科目の平均点が他の理科科目に比べて低くならないようにしていただきたいということでありました。本年度もコロナ禍の厳しい環境の中、問題作成に携わった関係各位の努力に敬意を表するとともに、令和5年度大学入試共通テスト(本試験)の地学関連科目に関して、以下のような意見を申し入れ致します。
(1)理科①の「地学基礎」においては基礎的な問題が出題されており、適正 かつ良質な問題であったと考えます。他の科目の平均点と比べて難易度も適正であったと思われます。
(2)理科②の「地学」においても、大学入学共通テストの目的に合致した思考力・総合的理解が試される、良質な問題であったと考えます。今年度の平均点は、昨年の52.72点よりも低い49.85点でした。問題作成にあたっては、平均点が6割程度となるように留意されているかと思いますが、引き続き問題・配点等の工夫により、「地学」の平均点が他科目に比べて低くならないよう今後も努力を継続していただけますようお願いいたします。
意見・提言2024
意見・提言2024
令和6年度大学入試共通テストの地学関連科目に関する意見書
独立行政法人大学入試センターへ,令和6年度大学入試共通 テストの地学関連科目に関する意見書を提出しました.
2024年3月29日
独立行政法人大学入試センター
理事長 山口 宏樹 様
一般社団法人日本地質学会
会長 岡田 誠
日本地質学会は、ここ数年にわたり、旧・大学入試センター試験/現・大学入学共通テストの地学関連科目の問題に関する意見並びに改善に向けた要望を大学入試センターに申し入れてきました。その要望の主眼は、地学関連科目の平均点が他の理科科目に比べて低くならないようにしていただきたいということでありました。本年度も問題作成に携わった関係各位の努力に敬意を表するとともに、令和6年度大学入試共通テスト(本試験)の地学関連科目に関して、以下のような意見を申し入れ致します。
(1)理科①の「地学基礎」においては基礎的な問題が出題されており、適正 かつ良質な問題であったと考えます。他の科目の平均点と比べて難易度も適正であったと思われます。
(2)理科②の「地学」においても、基礎を踏まえた読図問題が多く、大学入学共通テストの目的に合致した思考力・総合的理解が試される、良質な問題であったと考えます。今年度の平均点は、昨年の49.85点よりも高い56.62点でした。問題作成にあたっては、平均点が6割程度となるように留意されているかと思いますが、引き続き問題・配点等の工夫により、「地学」の平均点が他科目に比べて低くならないよう今後も努力を継続していただけますようお願いいたします。
プレスリリース(2024年)
プレスリリース(2024年)
第131年学術大会(2024山形大会)
⽇本地質学会第131 年学術⼤会(2024 ⼭形)
発表形態:資料配付(8月26日)
発表先:文部科学記者会・科学新聞社
■ 配布資料(PDF)
新たに採択された地質遺産サイト(Geoheritage)
後世に語り継ぐべき世界の地質遺産:9 月10 日に説明会開催
発表形態:資料配付(8月26日)
発表先:文部科学記者会・科学新聞社
■ 配布資料(PDF)
5月10日地質の日 第17回事業の紹介(2024年)
「地質の日」のイベントが全国の博物館等で開催
-5月10日地質の日 第17回事業の紹介(2024年)-
発表形態:資料配付(5月1日)
発表先:文部科学記者会・科学新聞社
■ 配布資料(PDF):本文・添付資料(チラシ)・行事一覧(5/1現在)
2024年 学生のための地質系業界説明会(対面)
■2024年 学生のための地質系業界説明会
〜その業界の仕事を知るためのサポートサービス(対面企画)
2024年9月9日、標記企画の対面説明会が、山形大学にて開催されました。実に35の企業・団体にご参加いただきました。
※2024/9/13オンライン企画の様子はこちらから
会場全景
1株式会社アースデザインコンサルタンツ
2株式会社アーステック東洋
3 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング
4 株式会社エイト日本技術開発*
5 応用地質株式会社*
6 株式会社奥村組
7 株式会社開発工営社
8 株式会社開発調査研究所
9 川崎地質株式会社*
10 株式会社建設技術研究所*
11 鉱研工業株式会社
12 国土防災技術株式会社
13 三洋テクノマリン株式会社*
14 三和ボーリング株式会社
15 石油資源開発株式会社*
16 大日本ダイヤコンサルタント株式会社*
17 太平洋セメント株式会社*
18 株式会社郄田地研
19 株式会社田中地質コンサルタント
20 株式会社地圏総合コンサルタント*
21 地熱エンジニアリング株式会社
22 中央開発株式会社*
23 株式会社中部森林技術コンサルタンツ*
24 ドリコ株式会社
25 株式会社日さく*
26 日鉄鉱業株式会社*
27 日特建設株式会社
28 日本海洋事業株式会社*
29 株式会社ニュージェック*
30 日本工営株式会社*
31 株式会社パスコ*
32 株式会社阪神コンサルタンツ
33 明治コンサルタント株式会社*
34 八千代エンジニヤリング株式会社*
35 山北調査設計株式会社*
2024年 学生のための地質系業界説明会(オンライン)
■学生のための地質系業界説明会
〜その業界の仕事を知るためのサポートサービス(オンライン)
2024年9月13日(金)にはZoomを使ったオンライン説明会を開催しました。38の企業・団体にご参加いただきました.
※9/9開催対面企画の様子はこちらから
1 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング
2 応用地質株式会社*
3 株式会社開発調査研究所
4 川崎地質株式会社*
5 クニミネ工業株式会社
6 原子力発電環境整備機構
7 株式会社建設技術研究所*
8 鉱研工業株式会社
9 株式会社サクセン
10 山陰開発コンサルタント株式会社*
11 産業技術総合研究所
12 三和ボーリング株式会社
13 シンワ技研コンサルタント株式会社
14 住友大阪セメント株式会社
15 住鉱資源開発株式会社
16 株式会社大建コンサルタント
17 大日本ダイヤコンサルタント株式会社*
18 太平洋セメント株式会社*
19 株式会社田中地質コンサルタント
20 株式会社地圏総合コンサルタント*
21 中央開発株式会社*
22 株式会社ドーコン
23 飛島建設株式会社
24 ドリコ株式会社
25 株式会社日さく*
26 日鉄鉱業株式会社*
27 日特建設株式会社
28 日本海洋事業株式会社*
29 日本工営都市空間株式会社
30 株式会社ニュージェック*
31 日本工営株式会社*
32 ハイテック株式会社
33 株式会社パスコ*
34 株式会社芙蓉コンサルタント
35 明治コンサルタント株式会社*
36 八千代エンジニヤリング株式会社*
37 株式会社INPEX*
38 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 *
意見・提言2025
意見・提言2025
令和7年度大学入試共通テストの地学関連科目に関する意見書
独立行政法人大学入試センターへ,令和7年度大学入試共通 テストの地学関連科目に関する意見書を提出しました.
2025年4月25日
独立行政法人大学入試センター
理事長 山口 宏樹 様
一般社団法人日本地質学会
会長 山路 敦
日本地質学会は、ここ数年にわたり、旧・大学入試センター試験/現・大学入学共通テストの地学関連科目の問題に関する意見並びに改善に向けた要望を大学入試センターに申し入れてきました。その要望の主眼は、地学関連科目の平均点が他の理科科目に比べて低くならないようにしていただきたいということでありました。本年度も問題作成に携わった関係各位の努力に敬意を表するとともに、令和7年度大学入学共通テスト(本試験)の地学関連科目に関して、以下のような意見を申し入れ致します。
(1)「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」の「地学基礎」においては分野横断型の出題がなされるようになり、工夫された良問が作成・出題されたと評価されます。平均点は昨年より若干落ちたものの、難易度は適正であったと思われます。今後も学習指導要領にある「(1) 地球のすがた」及び「(2) 変動する地球」を意識するとともに、選択科目間の平均得点率に著しい差が生じないように配慮した作題をお願いいたします。
(2)「地学」においては、平均点が昨年から大幅に下がり、他理科科目と比べても極端に低い41点台でした。得点調整の対象にならないことから、「地学」を選択した受験生の中には不公平感を抱く者がいたと考えられます。「地球や地球を取り巻く環境を科学的に探究するために必要な資質・能力を育成する」とした学習指導要領の趣旨を踏まえた作題がなされており、ご尽力が伺えますが、選択科目間の平均得点率に著しい差が生じないように配慮しつつ目標平均点60点を達成できる出題となるよう、更なるご検討・ご尽力をいただければと思います。
プレスリリース(2025年)
プレスリリース(2025年)
⽇本地質学会第132年学術⼤会(2025熊本)
発表形態:資料配付(9月8日)
発表先:文部科学記者会・熊本県政記者クラブ
■ 配布資料(PDF):本文・添付資料
5月10日地質の日 第18回事業の紹介(2025年)
「地質の日」のイベントが全国の博物館等で開催
-5月10日地質の日 第18回事業の紹介(2025年)-
発表形態:資料配付(5月1日)
発表先:文部科学記者会
■ 配布資料(PDF):本文・添付資料(ポスター画像)・行事一覧(5/1現在)
ジオパーク
ジオパーク関連サイト
ジオパーク支援委員会
ジオパーク関連サイト
■ジオパーク連絡協議会
■日本ジオパーク委員会
■地質百選
ジオパーク支援委員会TOP
ジオパーク支援委員会
お知らせ
市民対象オンラインシンポジウム:ジオパーク地域に伝わる伝承と地質学(2023/1/28開催)シンポの内容をYouTubeで公開中です
『私達はどこから来て,どこに行くのか?』を考える:ジオパーク
“ジオパーク”は,46億年の歴史を持つ地球・大地(ジオ)と公園(パーク)を組み合わせた言葉で,大地の公園を意味しています。大地の上で生きている植物や動物を含めた環境の中における私達人間の存在や活動を理解し,地球の未来を考える格好の場所です。『私達はどこから来て,どこに行くのか?』を理解できる場所でもあります。そして,その理解をもとに,地球環境の保護,教育,持続可能な開発を展開することが目的になっています。
日本では,2009年に日本ジオパークネットワーク(JGN)が結成されていらい,2022年5月現在で46地域がJGNに登録されており,その内の9地域がユネスコ世界ジオパークです。また,新しい地域もジオパークの認定を目指して活動しています。 新しいジオパークの開発もさることながら,既存のジオパークの内容の充実も求められています。国際的なレベルでの学術的な価値も担保されなければなりません。日本地質学会は,認定をめざしている地域への学術支援はもとより,新たにジオパークとしてふさわしい地域の開拓,既存のジオパークの質的向上への支援などを視野に入れて今まで活動して来ました。
2021年7月には,地球科学系8学協会の連携によりジオパークを学術的に支援する「日本ジオパーク学術支援連合(JGASU)」が設立されましした。日本地質学会はこの連合の中でも,他学協会と連携してジオパークを強力的に支援していきます。
2022年6月
日本地質学会ジオパーク支援委員会
委員長 天野一男
ジオパーク普及用パンフレット・ポスター
クリックするとPDF版をダウンロードしていただけます。
A2版ポスター
(2023年5月現在)
現在ポスターに掲載されていない地域で,新たにこの地域を開拓してはどうか,というご推薦がございましたら,学会事務局宛に連絡いただければ委員会でも検討させていただきます.以前配布した紙媒体のポスターは,以降のジオパークの認定で情報が古くなっていますり.今後は,上の電子版ポスター(A2印刷用pdf)を適宜更新しますので,もし修正などございましたら,ジオパーク支援委員会(高木秀雄)までお知らせください.
ジオパーク関連サイト
■日本ジオパークネットワーク(JGN)
■日本ジオパーク委員会
■日本ジオパーク学術支援連合(JGASU)(2021年7月設立)
■経済産業省:ジオパークのページ
■地質情報ポータルサイト(地質情報整備活用機構・全地連)ジオパークのページ
■地質百選
■茨城大学学生作成の地質観光マップ
委員会メンバー→こちらから
ユネスコ正式事業化決定に関して(声明)
◆世界ジオパークのユネスコ正式事業化について(JGNのサイトへ)
http://www.geopark.jp/about/datacenter/index.html
ジオパークのユネスコ正式事業化決定に関して
平成27年11月19日
一般社団法人日本地質学会
ジオパークのユネスコ正式事業化決定に関して
2015年11月17日に開催されました第38回ユネスコ総会において、世界ジオパークネットワークの活動が、「国際地質科学ジオパーク計画(International Geoscience and Geoparks Program:IGGP)」として正式にユネスコの事業となりました。これまで活動を進められてこられた世界ジオパークネットワークおよび日本ジオパークネットワークの関係者の方々にとって、今後の活動に向けて大変勇気づけられることであると思います。また、日本のジオパーク活動を支援してきました当学会としても、大変喜ばしいことであります。
世界ジオパークの認定には、地質遺産の保護とともにそれらを資源とし、地域における教育や科学振興、観光事業に活用し、持続可能な地域社会の活性化を図ることが求められています。また、4年毎に再審査が実施され、活動の適正や成果が評価されます。すでに国内では、厳しい審査を乗り越えて洞爺湖有珠山、糸魚川、島原半島、山陰海岸、室戸、隠岐、阿蘇、アポイ岳の8つのジオパークが世界ジオパークに認定されています。今後も国内ジオパークの中から、世界ジオパークが誕生してくることでしょう。
ジオパークは、地質が原点にあります。日本地質学会はそのことを踏まえて、今後も日本ジオパークの活動に対して学術的支援はもちろんのこと、地質学の教育普及、自然災害の観点からも支援を続けて行きます。
ジオパーク活動の益々の発展を願ってやみません。
一般社団法人日本地質学会
会長 井龍康文
地質学会ジオパークワークショップ(2009. 9/5)
地質学会ジオパークワークショップ
ジオパークによる地域活性化をめざして
ー地域と地質学者の連携のあり方をさぐるー
日本地質学会ジオパーク支援委員会は,日本ジオパークネットワークの共催のもと,ジオパークによる地域活性化、地質遺産の保全および地学の普及のために地域の方々と地質学者がどのように連携して活動していけばよいかをさぐるために,ワークショップを開催します。本ワークショップでは,実際にジオパークの運営に携わる人と地質学会員が,各地の実践例の発表をもとに,地域と地質学者の連携のあり方を議論します。ジオパークに関心のある行政担当者,地域の方,研究者などの皆様の参加を期待します。なお,国内初の世界ジオパークネットワーク加盟地域は8月23日には決定する予定です。
日時:9月5日(土)
場所:岡山市デジタルミュージアム4階
(岡山駅西口・リットビル正面のエスカレーターをご利用のうえ,4階へとお上がりください。)
主催:日本地質学会ジオパーク支援委員会
共催:日本ジオパークネットワーク
後援:産総研地質調査総合センター
プログラム(予定)
午前の部 10:00-12:00 日本ジオパーク支援委員によるジオパーク個別相談(事前予約制)
午後の部
第一部 13:00 開会挨拶・趣旨説明 天野一男(日本地質学会ジオパーク支援委員会委員長)
世界ジオパーク申請3地域の実践例(講演20分,質疑5分)
13:05-13:30 糸魚川ジオパーク
13:30-13:55 島原半島ジオパーク
13:55-14:20 洞爺湖・有珠山ジオパーク
14:20-14:30 コメント:世界ジオパークネットワーク現地審査委員が語るジオパーク
−3地域の現地審査に同行して- 渡辺真人
—休憩—
第二部 各地の実践例と情報・アイディアの交換(講演15分,質疑5分)
14:40-15:00 山陰海岸ジオパーク
15:00-15:20 室戸ジオパーク
15:20-15:40 阿蘇
15:40-16:00 隠岐
16:00-16:20 秩父
16:20-16:40 霧島
16:40-17:00 萩・阿武
17:00-17:20 茨城
17:20-17:40 総合討論
17:40-17:45 閉会挨拶 高木秀雄(日本地質学会副会長)
18:00- 懇親会
お問い合わせ先:日本地質学会ジオパーク支援委員会
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル
TEL:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156 e-mail: main@geosociety.jp
ミニシンポ『日本地質学会のジオパークへの学術的貢献』
日本地質学会ミニシンポジウム
2018.3.23掲載
日本地質学会ミニシンポジウム
日本地質学会のジオパークへの学術的貢献
2015年にジオパークがユネスコの事業になった結果、ジオパークのあり方について、いくつかの課題がでてきました。その中で重要なものがジオパークにおける学術的内容の担保があげられます。現在、日本には43のジオパーク(内8つがユネスコジオパーク)がありますが、活動の主体はそれぞれの地域の自治体になっています。これらのジオパークの学術的内容の担保については、学会が中心となって支援することが求められてくる可能性が大きいものと考えられます。地質学会としてどんな貢献ができるかについて、シンポジウムの開催し、今後の可能性について検討します。地質学会員初め、ジオパーク関係者、ジオパークに関心のある皆様に多数ご参加いただき、意見交換したいと思います。
【主催】日本地質学会ジオパーク支援委員会
【日時】2018年5月19日(土) 17:30-20:00
【場所】北とぴあ第2研修室(120名収容可)(東京都北区王子1-11-1)
交通アクセス▶http://www.kitabunka.or.jp/kitaku_info/rlink/summary-map
【世話人】天野一男(ジオパーク支援委員会委員長)・平田大二(日本地質学会ジオパーク担当理事)
【プログラム】
17:30-17:40 趣旨説明−ジオパークへの学術支援−(天野一男:地質学会ジオパーク支援委員長)
17:40-18:00 日本ジオパークネットワークにおける学術支援(平田大二:日本地質学会ジオパーク担当理事)
18:00-18:20 ユネスコジオパークに求められる学術支援(松原典孝:山陰海岸ジオパーク・兵庫県立大学)
18:20-18:30 休 憩
18:30-18:50 研究所による学術支援の可能性(斎藤 眞:産総研地質調査総合センター)
18:50-19:10 博物館による学術支援の可能性(竹之内 耕:糸魚川ユネスコジオパーク・フォッサマグナミュージアム)
19:10-19:30 大学による学術支援の可能性(高木秀雄:早稲田大学)
19:30-20:00 総合討論
オンラインシンポ_ジオパーク地域に伝わる伝承と地質学:古代からの自然観を今に活かす
市民対象オンラインシンポジウム
ジオパーク地域に伝わる伝承と地質学:古代からの自然観を今に活かす
共催:日本ジオパークネットワーク(JGN)・日本ジオパーク学術支援連合(JGASU)
日程:2023年1月28日(土) 10:00〜14:25
開催形態:zoomおよびYouTubeでの配信
※シンポジウムの様子をYouTubeで公開しています.
どなたでもご視聴いただけます.
趣旨
クリックするとA4版チラシPDFがDLできます
本シンポジウムは国内のジオパーク地域に伝わる伝承をとりあげ,そこに古代から伝わる自然観を現在の地質科学の視点から理解することをめざしています.また,地域の伝承が私たちの生活基盤である地質地形と密接な関係のもとにあることを再認識し,地域資源としての活用,自然の保護保全・防災意識などのジオパーク的活動への理解も深めたいと考えています.
2021年に第11回ジオパーク全国大会が島根県松江市と出雲市で開催されたおり,地域の地質地形に関わる伝承を紹介するポスター展示が12ジオパークからありました.このテーマはその他のジオパクでも関心が高いことから,国内ジオパークにおいて共通性のあるテーマといえます.このような観点から,地質学会会員をはじめとして一般市民も対象としたシンポジウムを企画しました.
概要
主催:日本地質学会
共催:日本ジオパークネットワーク(JGN)・日本ジオパーク学術支援連合(JGASU)
日程:2023年1月28日(土) 10:00〜14:25
開催形態:zoomおよびYouTubeでの配信
会員・非会員問わず参加無料.zoom参加者は事前登録制(YouTube視聴の場合は事前申込は不要です.当日どなたでもご視聴いただけます)
※zoom参加者には,申込締切後(1/21以降に),zoomアクセスURLをメールでお知らせいたします.
zoom参加申込:専用申し込みフォーム[こちらから]からお申し込み下さい.
zoom参加申込受付:2022年12月20日(火)〜2023年1月20日(金)
CPD:希望者にはCPD受講証明書を発行します(zoom参加者のみ.Youtube視聴の場合は発行できません.全プログラム参加で3単位予定.(CPDプログラムID:3441)
プログラム
※講演要旨9件分(PDF)のダウンロードはこちらから
開会挨拶…岡田 誠(会長)
趣旨説明… 天野一男(理事・ジオパーク支援委員会委員長)
講 演
Geomythology(地球神話)をジオパーク活動にもっと活かそう…野村律夫(島根半島・宍道湖中海ジオパーク)
アイヌ民族の伝承とジオパーク…大野徹人(アポイ岳ユネスコ世界ジオパーク)
磐梯山に伝わる伝説・昔話…竹谷陽二觔(磐梯山ジオパーク)
大国主命(出雲)と奴奈川姫(古志)の伝説からたどる糸魚川ジオパークの景観 …竹之内 耕(フォッサマグナミュージアム)
日本三大奇勝『妙義山』にまつわる伝説 巨人が射抜いた穴-星穴伝説-…関谷友彦(下仁田ジオパーク)
<昼休み>
バケモノ伝承を科学的視点で読んでみよう…荻野慎諧(恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク)
南紀熊野の地形・地質から読み解く神話伝説…此松昌彦(和歌山大学教育学部)
岡山県新見市に伝わる藁蛇を使用した神事と伝説…先山 徹(NPO 法人地球年代学ネットワーク)
異分野間の対話と連携を目指すジオパークのネットワークの取り組み…山崎由貴子(日本ジオパークネットワーク)
総合討論「テーマ:各地の伝承・神話伝説の扱われ方とジオパーク交流へ向けて」(座長:野村律夫)
問い合わせ先:日本地質学会事務局(main[at]geosociety.jp)※[at]を@マークにして送信してください
普及教育活動
地層命名の手順
地層命名指針
地層命名指針TOP画面に戻る
地層命名の指針VI.地層命名の手順
地層名および層序単元
研究史と背景
模式地の指定
諸模式地における層序単元の記載事項
地層の側方・垂直変化
地質学的意義
対比
地質年代
文献
1.地層名および層序単元
地層の命名は「層(Formation)」を基本単元とする。「層」は「(Subgroup)」・「層群(Group)」・「超層群(Supergroup)」にまとめることができ、「部層(Member)」、「単層(Bed)」および「流堆積物(Flow Deposit)」に細分できる。
地層の命名や再定義の際には、「流堆積物」・「単層」・「部層」・「層」・「亜層群」・「層群」・「超層群」などの単元名を明記する。英語表記の場合は地名、単元名および岩相名の頭文字は大文字とする。
「層」・「亜層群」・「層群」・「超層群」の名称は「地名+単元名」とする。なお、「噴出岩体」や「変成岩体」などを除いて、岩相名を使用すべきでない。
「混在岩体」・「噴出岩体」・「変成岩体」・「貫入岩体」・「二次的移動集積物」などについては、「岩体(rock body)」を基本的に「層」と同格とみなし、単元名には、氷上花崗岩体(Hikami Granite)などのように、「地名+岩相名」を使用してもよい。e) 「複合岩体(Complex)」は、「秩父複合岩体(Chichibu Complex)」などのように、「地名+複合岩体」として命名・使用する。
「複合岩体(Complex)」は、「秩父複合岩体(Chichibu Complex)」などのように、「地名+複合岩体」として命名・使用する。
「部層」については「広瀬川凝灰岩部層(Hirosegawa Tuff Member)」のように、単純で明確な特徴をあらわす岩相名を付し、「地名+岩相名+単元名」で命名する。
「単層」と「流堆積物」は最小単元である。ある「層 (Formation)」中に認められる鍵層などのように特に有用なものは、「単層」として命名して使用することができる。その命名に際しては八戸凝灰岩単層(Hachinohe Tuff Bed)などのように「地名+岩相名+単元名」を連記することを基本とする。また、さらに火山灰単層の場合は十和田八戸軽石凝灰岩単層(Towada-Hachinohe Pumice-Tuff Bed)のように「地名」の前に「供給火山名」を付すこともできる。火砕流のような流れに由来する堆積物は、青葉山火砕流堆積物(Aobayama Pyroclastic Flow Deposit)のように、「地名+由来+堆積物」とし、さらに溶岩流の場合は「流」と「溶岩」を同義語と判断し、草津安山岩溶岩(Kusatsu Andesite Lava)など「地名+岩相名+溶岩」として使用してもよい。これらの「単層名」や「流堆積物」・「溶岩」などの名称は、特に理由があれば、十和田八戸凝灰岩単層(Towada-Hachinohe Tuff Bed)や、草津白根安山岩溶岩(Kusastu-Shirane Andesite Lava)など、火山灰単層のように、由来名などを付けてもよい。
命名に使用する地名は、模式地の名称に由来し、国土地理院発行5万分の1または2。5万分の1地形図に明記されている地名や自然地形(山・河川など)名を使って命名することを基本とする。また、地名にはローマ字表記を付す。
模式地に適切な地名のない場合は、より地域的あるいは広域的地名から選択し、上記の基本に準じた命名を行う。
命名の対象になる単元は、地質図に表現可能で露頭において明確に識別・追跡できる堆積体または岩体である。
同一の地名を異なる単元と組み合わせて使用することは不適切である。
名称変更・再定義の場合は、新称提唱と同様の手続きとともに、名称変更・再定義の学術的な理由を明確に記述することが必要である。
新単元名の命名においては、基本的にホモニム(異物同名)を回避すべきである。
掘削工事に伴う非恒久的露出やボーリングコアに基づく新単元の命名にも本指針を準用の上、国際層序ガイド第2版(1994、 3章B2の特例勧告)に準拠すること。
2.研究史と背景
新単元の記載には、命名の対象となる単元について最初に定義・命名した著者名を明記し、その後の研究者の取り扱いとその評価を層序対照表などで明記する。
3.模式地の指定
模式地は、定義する単元の典型的な露出がある地点またはルートとする。その単元の上下の境界が模式地で設定できない場合は境界模式地を指定することが望ましい。また、複数の岩相が含まれている場合や岩相の側方変化などがある場合は副模式地を指定して記載する。
模式地の露頭が失われた場合には新模式地を指定することができる。また、境界模式地・副模式地・新模式地などの指定は模式地に準ずる。
模式地の指定にあたっては、地形図上の名称・恒久的地形または構築物からの距離・緯度経度など、他の研究者の容易な確認を保証するための情報をもりこむこと。また、できるだけ地形図・地質図・地質構造図・柱状図・層序断面図・露頭写真などの図面情報をできるだけ添える。
4.諸模式地における層序単元の記載事項
新単元の記載にあたっては、その単元の厚さ(層厚)や岩相の特徴について明確に記述する必要がある。さらに、生層序単元など他の層序的特徴・地質構造・堆積構造・地形的特徴・上下あるいは側方に接する他の層序単元との関係・堆積環境(形成環境)など、できるだけ新単元の地質学的諸特徴について記載すること。
5.地層の側方・垂直変化
新単元を提唱する場合は、前項にあげたような諸特徴の側方変化などの地域的・広域的状態をできるだけ記載すること。
6.地質学的意義
新単元について、できるだけその地質学的な意義についての考察を行い、生成過程・続成作用・変質あるいは変成作用などについても可能なかぎり記載すること。
7.対比
新単元は、できるだけ他の関連する岩相層序単元との対比を行うこと。
8.地質年代
新単元の地質年代学的位置づけについて、できるだけその決定根拠となった資料に基づいて議論すること。
地層命名指針TOP画面に戻る
9.文献
新単元について、これに関連した学術的文献を明示する。
地層命名法
地層命名指針
地層命名指針TOP画面に戻る
地層の命名法
2000年3月18日の日本地質学会107年総会(筑波大学)において、下記の「地層命名の指針」が承認されました。2001年1月1日以降に日本地質学会から出版されるものに対して適応されます。基本的には国際地質科学連合(IUGS)の層序小委員会(ISSC)が出版したガイド(参考文献1)に従っていますので参考にして下さい。またEpisodesにガイドの要約版(参考文献2)が掲載されています。
(参考文献)
Salvador, A. ed., 1994, International Stratigraphic Guide 2nd ed. Geol. Soc. America, Inc., 214p.
Murphy, M. A. and Salvador, A., 1999, International Stratigraphic Guide: An Abridged Version. Episodes, vol. 22, no. 4, 255-271.
地層命名の指針
地層命名指針
地層命名の指針1952年2月18日制定2000年4月 1日改訂
本指針は、日本地質学会が採用する岩相層序単元区分に基づく「地層の命名」に関する学術的手続きについての指針である。
本指針は、地層名に関する先取権の尊重を基本原則とし、地層の名称に関する混乱をなくすことが目的で、地質学の自由で闊達な研究を制約するものではない。また将来的に、地質学の発展にあわせた合理的指針となるよう検討を重ねてゆく基本資料でもある。
本指針は、 基本的に国際層序ガイド第2版(1994)に従って作られている。また、岩相層序単元以外の層序単元の命名に関する手続きにも、本指針を適用するよう勧める。
本指針は、1952年制定の「日本地質学会地層命名規約」(地質学雑誌 vol.58, no.678, p112-113, 1952)にかわるものであり、2001年1月1日以降に日本地質学会が編集・発行する出版物に関して適用する。これ以前に命名されたものに関しては、本指針の手続きに沿っていなくても有効な名称と見なすが、著しい不都合が生じる場合は関係する研究者による速やかな再定義が望まれる。また出版物等において慣例的・便宜的に使用するような地層名に関して、何ら規制するものではない。
新たに命名あるいは再定義する層序単元(新単元)は、基本的にVIの1〜9の項目に定める手続きを踏まえて学術的出版物に公表した後、初めて有効な地層名と認められるものとする。
地層命名の手順(詳細はこちら)
地層命名指針TOP画面に戻る
国際惑星地球年(外部リンク)
博物館の地学関連行事
2007年10月〜2008年3月まで 県別 地学関連行事
全国の博物館で行われている行事のうち,地学関連の行事を県別に紹介します。
すべての博物館について網羅はできていませんが、今後充実させていきますので、博物館関係者の方のご協力をいただきたいと思います。
【重要!】
各博物館で行われている行事のうち、申し込みが必要なものについては、申し込み方法などの詳細を、必ず!それぞれの博物館で確かめてください。申し込み締切がすぎていたり、締切や申し込み方法の記入漏れがある可能性もあります。
また、対象年齢や参加費の事などもありますので、ご注意くださ い。主催館とは別の県で行われる場合は、両方の県に記載していますが、出発は主催館である場合もありますので、申し込みをする前に必ず確認してください。
■ 野外観察会など
北海道地方
東北地方
関東地方
中部地方
近畿地方
中国・四国地方
九州・沖縄地方
■ 館内の講座など
北海道地方
東北地方
関東地方
中部地方
近畿地方
中国・四国地方
九州・沖縄地方
■ 特別展示など
北海道地方
東北地方
関東地方
中部地方
近畿地方
中国・四国地方
九州・沖縄地方
【野外観察会】
【岩手県の野外観察会】
第54回地質観察会「岩泉町小本の植物化石と茂師の恐竜産地」
日時:2008年10月14日(日)10:00〜15:00 場所:岩手県岩泉町小本および茂師 主催など:岩手県立博物館・岩泉町教育委員会 内容:年2回県内各地で開催。今回は三陸鉄道小本駅前に集合。白 亜紀の植物化石の採集や日本初の恐竜化石産地の観察をとおして、自然のおい たちを考えます。講師は岩手県立博物館学芸員。 申し込みの要不要:必要。往復葉書また は電子メールで。定員40名。締切りは10月6日(消印有効)。 リンク:紹介ページ
【栃木県の野外観察会】
化石採集教室
日時:2007年10月28日(日) 9:30〜15:00 (雨天中止) 場所:栃木県佐野市内 主催など:葛生化石館 内容:栃木県佐野市内の化石産地にて化石採集を行います。古生 代ペルム紀の化石を見つけることができます。小学校五年生以上の方、親子で の参加歓迎。定員20人。 申し込みの要不要:必要。(申込期間: 10月1日〜10月13日)応募が多数の場合は抽選となります。 リンク:博物館トップ
【茨城県の野外観察会】
10万年前の地層と化石ー繰り返す温暖化・寒冷化—(霞ヶ浦編)
日時:2007年11月18日(日) 8:30〜18:30 場所:茨城県霞ヶ浦地域 (注意:荻窪駅周辺集合・解散.バス移動.定員25名.)
主催など:杉並区立科学館 内容:茨城県霞ヶ浦地域で地層観察と化石採集を行います。産業技術総合研究所地質標本館を見学します。原則として11/24の化石クリーニング体験(於 杉並区立科学館)とセットで参加して下さい(担当 川辺) 。 申し込みの要不要:必要。 リンク:博物館トップ
【千葉県の野外観察会】
10万年前の地層と化石ー繰り返す温暖化・寒冷化—(印旛沼編)
日時:2007年10月21日(日) 12:30〜15:30 場所:千葉県印旛地域 (北総開発鉄道「印旛日本医大」駅前集合・解散.定員25名)
主催など:杉並区立科学館 内容:千葉県印旛地域で地層観察と化石採集を行います.原則として10/27の化石クリーニング体験(於 杉並区立科学館)とセットで参加して下さい(担当 川辺) 。 申し込みの要不要:必要。 リンク:博物館トップ
房総の地形を訪ねる−房総南端の地形−
日時:[事前学習]2007年10月21日(日) 10:00〜16:00、[現地 観察]2007年10月28日(日) 8:00〜18:30" 場所:[事前学習]千葉県立中央博物館 研修室、[現地観察] 千葉県館山市" 主催など:千葉県立中央博物館 内容:房総各地の知られざる地形を訪ね、その特徴や成り立ちを 考えるシリーズ。今回は房総南端の館山市周辺で、特に海岸地形を中心に観察 します。講師当館研究員(八木・吉村)。 申し込みの要不要:必要。2007年10月7日 (日)締切。中央博物館へ往復はがきかファクスで申し込み。交通費(バス代) 実費徴収。 リンク:博物館トップ
秩父地方の地質と化石をめぐって
日時:2007年11月10・11日(土・日) 7:30〜翌17:00 場所:埼玉県秩父地方 主催など:千葉県立中央博物館 内容:秩父地方を巡り、地質と化石の見学・採集を行います。講 師当館研究員(加藤)。 申し込みの要不要:必要。10月27日(土 )締切。中央博物館へ往復はがきかファクスで申し込み。交通費(バス代)・ 宿泊費実費徴収。 リンク:博物館トップ
【埼玉県の野外観察会】
化石探検隊
日時:2007年10月20日(土) 場所:埼玉県小鹿野町 主催など:埼玉県立自然の博物館,小鹿野町共催" 内容:秩父盆地の新第三紀層から山中地溝帯の白亜系の化石産地 などを回ります. 申し込みの要不要:必要(基本的に1ヶ月 〜2週間前に受け付け) リンク:紹介ページ
秩父地方の地質と化石をめぐって
日時:2007年11月10・11日(土・日) 7:30〜翌17:00 場所:埼玉県秩父地方 主催など:千葉県立中央博物館 内容:秩父地方を巡り、地質と化石の見学・採集を行います。講 師当館研究員(加藤)。 申し込みの要不要:必要。10月27日(土 )締切。中央博物館へ往復はがきかファクスで申し込み。交通費(バス代)・ 宿泊費実費徴収。 リンク:博物館トップ
青岩礫岩をしらべる
日時:2008年3月9日(土) 場所:埼玉県寄居町〜深谷市付近(詳細未定) 主催など:埼玉県立自然の博物館,当館友の会共催" 内容:荒川流域に露出する新第三紀層,特に青岩礫岩(結晶片岩 の巨礫を含む特徴的な礫岩)を観察します." 申し込みの要不要:必要(基本的に1ヶ月 〜2週間前に受け付け) リンク:紹介ページ
【神奈川県の野外観察会】
海岸の石ころ探検隊(2)
日時:2007年10月21日(日) 場所:神奈川県小田原市酒匂川河口付近 主催など:神奈川県立生命の星・地球博物館 内容:海岸の石ころの色や模様、形、種類を調べます。 申し込みの要不要:往復はがき、または ホームページから申し込み。締切りは10月2日(消印有効) リンク:紹介ページ
秋の地形地質観察会
日時:2007年11月3日(日) 場所:神奈川県大磯丘陵 主催など:神奈川県立生命の星・地球博物館 内容:大磯丘陵の土台をつくっている地層と、そのまわりの地形 を観察します。 申し込みの要不要:往復はがき、または ホームページから申し込み。締切りは10月16日(消印有効) リンク:紹介ページ
海岸の石ころ探検隊(3)
日時:2007年11月25日(日) 場所:神奈川県二宮海岸付近 主催など:神奈川県立生命の星・地球博物館 内容:海岸の石ころの色や模様、形、種類を調べます。 申し込みの要不要:往復はがき、または ホームページから申し込み。締切りは11月6日(消印有効) リンク:紹介ページ
海岸の石ころ探検隊(4)
日時:2008年1月13日(日) 場所:神奈川県立生命の星・地球博物館 実習実験室 主催など:神奈川県立生命の星・地球博物館 内容:相模湾の海岸で集めた石ころの実物図鑑をつくりながら、 石について学習します。 申し込みの要不要:往復はがき、または ホームページから申し込み。締切りは12月25日(消印有効) リンク:博物館トップ
早春の地形地質観察会
日時:2008年3月2日(日) 場所:神奈川県横浜市戸塚区 主催など:神奈川県立生命の星・地球博物館 内容:多摩丘陵の地層を見学しながら、大地の生い立ちを考えます。 申し込みの要不要:往復はがき、または ホームページから申し込み。締切りは2月12日(消印有効) リンク:博物館トップ
【長野県の野外観察会】
飯田市二ツ山〜水晶山の地質的魅力と昼神断層
日時:2007年10月6日(土) 場所:長野県飯田市西部の山本地区 主催など:伊那谷自然友の会 内容:案内:手塚恒人さん(喬木第一小学校教諭) 申し込みの要不要:申込みは飯田市美術 博物館気付伊那谷自然友の会事務局(0265-22-8118) リンク:博物館トップ
伊那層のテフラと植物化石
日時:2007年10月27日(土) 場所:長野県飯田市川路ほか 主催など:伊那谷自然友の会 内容:案内:小泉明裕さん(飯田市美術博物館学芸員) 申し込みの要不要:申込みは飯田市美術 博物館気付伊那谷自然友の会事務局(0265-22-8118) リンク:博物館トップ
駒ヶ根市の新宮川流域など
日時:2007年11月10日(土) 場所:長野県駒ヶ根市中沢 主催など:伊那谷自然友の会 内容:案内:松島信幸さん(飯田市美術博物館顧問) 申し込みの要不要:申込みは飯田市美術 博物館気付伊那谷自然友の会事務局(0265-22-8118) リンク:博物館トップ
第64回「戸台の化石」学習会
日時:2007年11月4日(日) 場所:長野県伊那市長谷 主催など:「戸台の化石」保存会 内容:野外でアンモナイトなどの化石を採取し、戸台の化石資料 室で整理し保管する。 申し込みの要不要:必要。「戸台の化 石」保存会事務局(0265-98-2009)*詳細は問合せのこと
【静岡県の野外観察会】
体験教室「まるかじり自然体験リレー」
日時:2007年11月3日(土)10:00〜15:30頃 場所:静岡県、朝霧高原周辺(猪之頭〜麓地域) 主催など:奇石博物館 内容:足元の大地をつくる石ころやその上に広がる森や動・植物 たちを通した自然体験を毎年リレー方式で行います。参加費:1000円(資料、 保険料等)。定員30人。 申し込みの要不要:必要。(奇石博物館 に電話にて)、定員になり次第締め切り。 リンク:紹介ページ
自然観察フィールドワーク第1回「三保の魚」
日時:2007年10月14日(日) 場所:静岡県静岡市清水区,三保の海岸ほか" 主催など:東海大学自然史博物館 内容:家族向けの自然観察会です。 申し込みの要不要:必要(10日前までに はがきか電話) リンク:紹介ページ
自然観察フィールドワーク第2回「久能山の化石」
日時:2007年10月21日(日) 場所:静岡市駿河区,久能山" 主催など:東海大学自然史博物館 内容:家族向けの自然観察会です。 申し込みの要不要:必要(10日前までに はがきか電話) リンク:紹介ページ
自然観察フィールドワーク第3回「清水の水−淡水の生きもの」
日時:2007年10月28日(日) 場所:静岡県静岡市清水区,興津川" 主催など:東海大学自然史博物館 内容:家族向けの自然観察会です。 申し込みの要不要:必要(10日前までに はがきか電話) リンク:紹介ページ
【愛知県の野外観察会】
第3回地球教室・河原の石で石包丁をつくろう
日時:2008年10月20・21日 場所:岐阜県各務原市鵜沼の木曽川の河原および名古屋大学博物館 主催など:名古屋市科学館・名古屋大学博物館、協賛:ちゅうで ん教育振興財団" 内容:木曽川の河原で石を採集し、その石で石包丁をつくって料理します。 申し込みの要不要:必要。往復はがき で。2007年10月9日(火)必着" リンク:博物館トップ
学習教室「家族で行く化石採集」
日時:2007年11月25日(日)8:45〜16:30 場所:岐阜県瑞浪市(豊橋市自然史博物館で集合・解散 バス使用) 主催など:豊橋市自然史博物館 内容:1600万年前のサメ・貝化石などを掘り当てよう!雨天の場 合は瑞浪市化石博物館で特別講義を開きます。 申し込みの要不要:必要。往復はがきで 11月14日(水)必着。定員:35名 (小学生以下保護者同伴)。受講料: 1,000円" リンク:博物館トップ
学習教室「三河地学めぐり」
日時:2007年12月1日(土)9:30〜15:30※雨天の場合は12月2日 (日)に順延 場所:愛知県田原市ほか(バス使用) 主催など:豊橋市自然史博物館 内容:渥美半島の成り立ちやかつて海底に生息した貝の化石など を観察します。 申し込みの要不要:必要。往復はがきで 11月14日(水)必着。定員:25名 (小学4年生以上・一般) 。受講料: 300円 " リンク:博物館トップ
第4回地球教室・ナゴヤで化石鉱物を探そう
日時:2008年12月1・2日 場所:名古屋駅周辺・栄地区・中電東桜会館・名古屋大学博物館 主催など:名古屋市科学館・名古屋大学博物館、協賛:ちゅうで ん教育振興財団、協力:蒲郡市生命の海科学館" 内容:化石の断面について学習し、市内の建物に使わせている石 材から化石を さがします。 申し込みの要不要:必要。往復はがき で。平成19年11月20日(火)必着" リンク:博物館トップ
【滋賀県の野外観察会】
多賀の化石観察会
日時:2007年10月14日(日)9:00〜12:00 場所:多賀の自然と文化の館に集合後、移動。 主催など:多賀町立博物館多賀の自然と文化の館 内容:権現谷でいろいろな化石を探してみましょう!! 申し込みの要不要:必要。20〜30日前か ら受付開始、博物館へ連絡。e-mail不可。 リンク:博物館トップ
化石の観察会
日時:2007年10月21日(日) 10:00〜14:00 場所:滋賀県多賀町権現谷 主催など:琵琶湖博物館・多賀の自然と文化の館 (共催) 内容:約2億7千万年前の赤道近くにできたサンゴ礁周辺の化石を 採集します。 申し込みの要不要:10月11日(木)締切. 琵琶湖博物館へ往復はがきで申し込み." リンク:紹介ページ
子どもの森を歩こう「地層の観察」
日時:2007年11月4日(日) 14:00〜15:00 場所:滋賀県甲賀市,みなくち子どもの森園内" 主催など:みなくち子どもの森自然館 内容:毎月第一日曜日は、みなくち子どもの森園内の自然を職員 がご案内します。11月のテーマは園内の地層で、火山灰層などを観察できま す。 申し込みの要不要:無 集合時刻に自然 館前に集まってください" リンク:紹介ページ
【京都府の野外観察会】
テーマ別自然観察会「川原の石ころ」
日時:2007年11月18日(日) 午前10時〜午後3時(雨天中止) 場所:木津川(京都府加茂町) 主催など:大阪市立自然史博物館・NPO大阪自然史センター 内容:内容:「岩石の見分け方がわからない」という声を よく聞きます。たくさんの種類の石ころが観察できる川原で、石の見分け方に チャレンジしてみましょう。 申し込みの要不要:必要。 大阪市立自 然史博物館HPより,申し込めます." リンク:博物館トップ(トップページのイベントをクリック)
【大阪府の野外観察会】
テーマ別自然観察会「川原の石ころ」
日時:2007年11月18日(日) 午前10時〜午後3時(雨天中止) 場所:木津川(京都府加茂町) 主催など:大阪市立自然史博物館・NPO大阪自然史センター 内容:内容:「岩石の見分け方がわからない」という声を よく聞きます。たくさんの種類の石ころが観察できる川原で、石の見分け方に チャレンジしてみましょう。 申し込みの要不要:必要。 大阪市立自 然史博物館HPより,申し込めます." リンク:博物館トップ(トップページのイベントをクリック)
やさしい自然かんさつ会「化石さがし」
日時:2007年12月2日(日) 10時〜15時 場所:大阪府泉佐野市 主催など:大阪市立自然史博物館・NPO大阪自然史センター 内容:化石のねむる山をめざして,みんなで歩こう!ガケの石 や,いろんな化石を見ながら,和泉山脈のヒミツに,せまってみよう." 申し込みの要不要:必要。 大阪市立自 然史博物館HPより,申し込めます." リンク:博物館トップ(トップページのイベントをクリック)
【香川県の野外観察会】
白亜紀の地層見学
日時:2007年10月14日,13:00〜16:00" 場所:香川県まんのう町木戸 主催など:徳島県立博物館 内容:香川県まんのう町(旧琴南町)に分布する白亜紀層の和泉 層群を見学します。馬の蹄に似ていることから「木戸の馬蹄石」とよばれるカ キ化石の密集層(香川県自然記念物)や和泉層群の基盤となっている花崗岩な どを中心に観察します。 申し込みの要不要:往復はがきで申し込 み.10日前必着" リンク:紹介ページ
【徳島県の野外観察会】
白亜紀の地層見学
日時:2007年10月14日,13:00〜16:00" 場所:香川県まんのう町木戸 主催など:徳島県立博物館 内容:香川県まんのう町(旧琴南町)に分布する白亜紀層の和泉 層群を見学します。馬の蹄に似ていることから「木戸の馬蹄石」とよばれるカ キ化石の密集層(香川県自然記念物)や和泉層群の基盤となっている花崗岩な どを中心に観察します。 申し込みの要不要:往復はがきで申し込 み.10日前必着" リンク:紹介ページ
【福岡県の野外観察会】
化石発見!秋吉台周辺3館めぐり!(バスハイク)
日時:2007年11月4日(日) 場所:山口県,秋吉台周辺(北九州市立自然史・歴史博物館前集合,解散) 主催など:北九州市立自然史・歴史博物館(いのちのたび博物館) 内容:太田学芸員と一緒に秋吉台周辺の博物館3館をめぐりま す.化石採集も体験し 申し込みの要不要:必要(詳しくは博物 館まで,申込期間 10月1日〜10月20日) リンク:博物 館トップ
ページトップへ
【講座・講演会・体験イベント】
【北海道の講座など】
恐竜時代のアンモナイト〜北海道のアンモナイトとその古生態〜
日時:2007年11月11日(日) 13:30〜15:30 場所:北海道開拓記念館・講堂 主催など:北海道開拓記念館 内容:約6500万年前の白亜期末まで生きていたアンモナイト。彼 らはいったいどのような生き物だったのでしょうか?実は、謎を解くカギは北 海道にあります。これまでの研究でわかってきたアンモナイトの生態を紹介し ます。(講師・栗原憲一氏(三笠市立博物館))。 申し込みの要不要:必要。10月12日 (金)から受付開始。お電話で受付。 リンク:博物館トップ
アンモナイト掘り出し体験をしよう!
日時:2008年1月13日(日)11:15〜,13:30〜,14:15〜, 15:00〜(各回10名(先着順)) 場所:北海道開拓記念館・講堂 主催など:北海道開拓記念館 内容:北海道はアンモナイトの宝庫!展示場に並ぶ化石は地層か ら掘り出しきれいにしたものです。実際にアンモナイトを岩石から掘り出す体 験をしてみましょう!参加者には貝化石をプレゼント!(講師・北海道化石会 会員)。※参加は1回に限ります。 申し込みの要不要:必要。10月12日 (金)から受付開始。お電話で受付。 リンク:博物館トップ
【岩手県の講座など】
博物館どよう探偵団「偏光顕微鏡で岩石を見る」
日時:2007年10月27日(土)13:00〜15:00 場所:岩手県立博物館 教室 主催など:岩手県立博物館 内容:小学生向けの連続体験イベント。毎月第4土曜で6回連続 (後期分)の第1回目。講師は岩手県立博物館学芸員。 申し込みの要不要:必要。小学校3年生か ら6年生までで3回以上参加できる人。はがきかファックスでただし、9月30日 締切り。 リンク:博物館トップ
秋期博物館セミナー「岩手の化石からカキの進化を探る」
日時:2007年11月11日(日)13:30〜15:30 場所:岩手県立博物館 講堂 主催など:岩手県立博物館 内容:北東北三県共同展関連講座。岩手に産する様々なタイプの カキ化石から、カキの環境への適応や進化のパターンについて考察します。講 師は鎮西清高氏(京都大学名誉教授)。 申し込みの要不要:当日受付、聴講無料。 リンク:"紹介ページ
いわての博物館交流セミナー「早池峰の地質からはじまる岩手 の大地の物語」
日時:2007年12月15日(日)13:30〜15:00 場所:遠野市立図書館博物館視聴覚ホール 主催など:岩手県立博物館・遠野市立博物館 内容:岩手県内の博物館学芸員が相互に交流して実施する講座。 今回は、古生代初期から第四紀にいたるまでの岩手県の自然のおいたちについ て紹介します。講師は岩手県立博物館学芸員。 申し込みの要不要:当日受付、聴講無料。 リンク:博物館トップ、(遠野市立図書館トップ)
県博日曜講座「1896年陸羽地震を見る昔と今」
日時:2008年3月9日(日)13:30〜15:00 場所:岩手県立博物館 講堂 主催など:岩手県立博物館 内容:ほぼ隔週の学芸員による講座。今回は、川舟地震断層を活 動させた陸羽地震から自然災害について考えます。講師は岩手県立博物館学芸 員。 申し込みの要不要:当日受付、聴講無料。 リンク:紹介ページ
博物館どよう探偵団「きみも恐竜発掘探検隊」
日時:2008年3月22日(土)13:00〜15:00 場所:岩手県立博物館 展示室ほか 主催など:岩手県立博物館 内容:小学生向けの連続体験イベント。毎月第4土曜で6回連続 (後期分)の第6回目。講師は岩手県立博物館学芸員。 申し込みの要不要:必要。小学校3年生か ら6年生までで3回以上参加できる人。はがきかファックスで。ただし、9月 30日締切り。 リンク:博物館トップ
【群馬県の講座など】
サイエンス・サタデー「カマラサウルスの歯のレプリカをつく ろう」
日時:2008年2月2日(土)14時〜15時 場所:群馬県立自然史博物館実験室 主催など:群馬県立自然史博物館 内容:自然史博物館に展示されている竜脚類恐竜「カマラサウル ス」の歯のレプリカ作成と簡単な学習を行います。 申し込みの要不要:当日会場で直接申込 (受付開始13:30〜)。小学生以上対象(小3年以下は保護者と参加)、定員 30名(先着順)。 リンク:博物館トップ
サイエンス・サタデー「カマラサウルスの歯のレプリカをつく ろう」
日時:2008年2月9日(土)14時〜15時 場所:群馬県立自然史博物館実験室 主催など:群馬県立自然史博物館 内容:自然史博物館に展示されている竜脚類恐竜「カマラサウル ス」の歯のレプリカ作成と簡単な学習を行います。 申し込みの要不要:当日会場で直接申込 (受付開始13:30〜)。小学生以上対象(小3年以下は保護者と参加)、定員 30名(先着順)。 リンク:博物館トップ
サイエンス・サタデー「カマラサウルスの歯のレプリカをつく ろう」
日時:2008年2月16日(土)14時〜15時 場所:群馬県立自然史博物館実験室 主催など:群馬県立自然史博物館 内容:自然史博物館に展示されている竜脚類恐竜「カマラサウル ス」の歯のレプリカ作成と簡単な学習を行います。 申し込みの要不要:当日会場で直接申込 (受付開始13:30〜)。小学生以上対象(小3年以下は保護者と参加)、定員 30名(先着順)。 リンク:博物館トップ
サイエンス・サタデー「カマラサウルスの歯のレプリカをつく ろう」
日時:2008年2月23日(土)14時〜15時 場所:群馬県立自然史博物館実験室 主催など:群馬県立自然史博物館 内容:自然史博物館に展示されている竜脚類恐竜「カマラサウル ス」の歯のレプリカ作成と簡単な学習を行います。 申し込みの要不要:当日会場で直接申込 (受付開始13:30〜)。小学生以上対象(小3年以下は保護者と参加)、定員 30名(先着順)。 リンク:博物館トップ
サイエンス・サタデー「岩石や鉱物の不思議実験」
日時:2008年3月1日(土)14時〜15時 場所:群馬県立自然史博物館実験室 主催など:群馬県立自然史博物館 内容:岩石や鉱物を使っていろいろな実験をします。 申し込みの要不要:当日会場で直接申込 (受付開始13:30〜)。小学生以上対象(小3年以下は保護者と参加)、定員 30名(先着順)。 リンク:博物館トップ
サイエンス・サタデー「岩石や鉱物の不思議実験」
日時:2008年3月8日(土)14時〜15時 場所:群馬県立自然史博物館実験室 主催など:群馬県立自然史博物館 内容:岩石や鉱物を使っていろいろな実験をします。 申し込みの要不要:当日会場で直接申込 (受付開始13:30〜)。小学生以上対象(小3年以下は保護者と参加)、定員 30名(先着順)。 リンク:博物館トップ
サイエンス・サタデー「岩石や鉱物の不思議実験」
日時:2008年3月15日(土)14時〜15時 場所:群馬県立自然史博物館実験室 主催など:群馬県立自然史博物館 内容:岩石や鉱物を使っていろいろな実験をします。 申し込みの要不要:当日会場で直接申込 (受付開始13:30〜)。小学生以上対象(小3年以下は保護者と参加)、定員 30名(先着順)。 リンク:博物館トップ
サイエンス・サタデー「岩石や鉱物の不思議実験」
日時:2008年3月22日(土)14時〜15時 場所:群馬県立自然史博物館実験室 主催など:群馬県立自然史博物館 内容:岩石や鉱物を使っていろいろな実験をします。 申し込みの要不要:当日会場で直接申込 (受付開始13:30〜)。小学生以上対象(小3年以下は保護者と参加)、定員 30名(先着順)。 リンク:博物館トップ
サイエンス・サタデー「岩石や鉱物の不思議実験」
日時:2008年3月29日(土)14時〜15時 場所:群馬県立自然史博物館実験室 主催など:群馬県立自然史博物館 内容:岩石や鉱物を使っていろいろな実験をします。 申し込みの要不要:当日会場で直接申込 (受付開始13:30〜)。小学生以上対象(小3年以下は保護者と参加)、定員 30名(先着順)。 リンク:博物館トップ
【茨城県の講座など】
謎の絶滅哺乳類 デスモスチルスの復元
日時:2007年10月14日(日)13:30〜14:30 場所:地質標本館 映像室 主催など:地質標本館 内容:デスモスチルス歌登標本の全身骨格標本の研究をてがけ た,犬塚 則久 (いぬづか のりひさ)先生による普及講演会を開催します. 世界中の研究者 が驚いたデスモスチルスの全身復元,すなわち,哺乳類なの に爬虫類のような 側方型に復元した研究をどのようにおこなったかを,わか りやすく解説してい ただきます.演者:犬塚 則久 先生(東京大学) 申し込みの要不要:不要 リンク:紹介ページ
体験学習ワークショップ 砂の科学
日時:2007年10月22日(月)13:30〜16:45 場所:地質標本館 主催など:地質標本館 内容:鳴り砂の体験やペットボトルを使った小型の液状化実験装 置(エキジョッカー)の製作を行い,砂を素材にした簡便な実験方法について 解説を行います.対象は,小中高教員,あるいは博物館などの社会教育機関の 関係者. 申し込みの要不要:必要。 リンク:紹介ページ
化石レプリカ作り
日時:2007年11月10日(土)10:30〜 場所:地質標本館 主催など:地質標本館 内容:アメリカ産デスモスチルス臼歯化石のレプリカを作成します. 申し込みの要不要:不要 リンク:博物館トップ
【千葉県の講座など】
赤土の中の鉱物結晶の観察
日時:2007年11月17日(土)10:00〜15:00 場所:千葉県立中央博物館 研修室 主催など:千葉県立中央博物館 内容:下総台地をつくる関東ローム層には、小さいながらも美し い結晶が多数含まれています。顕微鏡を使ってこれらを観察します。講師当館 研究員(高橋)。 申し込みの要不要:必要。2007年11月3日 (土)締切。中央博物館へ往復はがきかファクスで申し込み。参加無料。 リンク:"紹介ページ
地層のでき方実験
日時:2008年3月22日(土)10:00〜15:00 場所:千葉県立中央博物館 研修室 主催など:千葉県立中央博物館 内容:地層のできかたを実験水路や剥ぎ取り標本を使って説明し ます。講師当館研究員(岡崎)。 申し込みの要不要:必要。2008年3月8日 (土)締切。中央博物館へ往復はがきかファクスで申し込み。参加無料。 リンク:"紹介ページ
【埼玉県の講座など】
化石をきれいにみがいて観察しよう
日時:2007年9月29日(土) 場所:埼玉県立自然の博物館 主催など:埼玉県立自然の博物館 内容:石灰岩に含まれる小さな化石をみがいて、ルーペで観察します。 申し込みの要不要:不要(先着30名)" リンク:"紹介ページ
小石のそのまま図鑑
日時:2008年2月23日(土) 場所:埼玉県立自然の博物館 主催など:埼玉県立自然の博物館 内容:川原で拾った小石を厚紙に貼って,小さな図鑑をつくります." 申し込みの要不要:不要(先着45名)" リンク:博物館トップ
ペインティングストーン
日時:2008年3月8日(土) 場所:埼玉県立自然の博物館 主催など:埼玉県立自然の博物館 内容:川原の小石に絵を描き,色を塗り動物などの飾り物を作ります." 申し込みの要不要:不要(先着45名)" リンク:博物館トップ
【東京都の講座など】
科学講座:「地質時代の先例に学ぶ気候変動(仮)」
日時:2007年10月27日(土)15:30〜17:00 場所:杉並区立科学館 主催など:杉並区立科学館 講師:川辺文久(杉並区立科学館) 申し込みの要不要:不要(定員50名)" リンク:博物館トップ
10万年前の地層と化石ー繰り返す温暖化・寒冷化—(印旛沼編)
日時:2007年10月27日(土)13:00〜15:00 場所:杉並区立科学館第2実験室 主催など:杉並区立科学館 内容:印旛地域産化石をクリーニングし,貝化石群に基づいて古環境復元を行います。 申し込みの要不要:要(定員40名)" リンク:博物館トップ
10万年前の地層と化石ー繰り返す温暖化・寒冷化—(霞ヶ浦編)
日時:2007年11月24日(土)13:00〜15:00 場所:杉並区立科学館第2実験室 主催など:杉並区立科学館 内容:霞ヶ浦地域産化石をクリーニングし,貝化石群に基づいて古環境復元を行います。 申し込みの要不要:要(定員40名)" リンク:博物館トップ
科学講座:「新生代の気候変動と関東平野の成り立ち(仮題)」
日時:2007年11月24日(土)15:30〜17:00 場所:杉並区立科学館 主催など:杉並区立科学館 講師:中島 礼(産業技術総合研究所) 申し込みの要不要:不要(定員50名)" リンク:博物館トップ
科学講座:「温室効果とは(仮題)」
日時:2007年12月15日(土)15:30〜17:00 場所:杉並区立科学館 主催など:杉並区立科学館 講師:茨木孝雄(杉並区立科学館) 申し込みの要不要:不要(定員50名)" リンク:博物館トップ
1億年前の堆積物と化石ー温室地球の姿ー
日時:2007年12月15日(土)13:00〜15:00 場所:杉並区立科学館第2実験室 主催など:杉並区立科学館 内容:国内外の白亜紀堆積物を教材とし構成物質,色,含まれる化石種を比較し,二酸化炭素分圧が現在の10倍ほどあったと推定されている1億年前の地球環境と生命活動を学びます. 申し込みの要不要:要(定員40名)" リンク:博物館トップ
科学講座:
日時:2007年12月22日(土)13:30〜17:00 場所:杉並区立科学館 主催など:杉並区立科学館 内容:過去1億年間の温暖化(仮題).川辺文久(杉並区立科学館)
白亜紀の陸上環境と植物(仮題).斎木健一(千葉県立中央博物館)
白亜紀の海洋環境と生物(仮題).高橋 昭紀(早稲田大学). 申し込みの要不要:不要(定員50名)" リンク:博物館トップ
自然科学ワークショップ「化石の解剖」:実習教室:定員30名(要申込)
日時:2008年3月8日(土)13:00〜15:45 場所:杉並区立科学館実験室 主催など:杉並区立科学館 内容:化石レプリカ作製.化石の研究でレプリカをつくる目的を学びます.
講師:三村麻子(杉並区立科学館) リンク:博物館トップ
日時:2008年3月15日(土)13:00〜15:45 場所:杉並区立科学館 主催など:杉並区立科学館実験室 内容:化石の解剖.アンモナイト化石の断面標本を作製し,殻のつくりを学びます.
講師:川辺文久(杉並区立科学館) リンク:博物館トップ
日時:2008年3月22日(土)13:00〜17:00
場所:杉並区立科学館 主催など:杉並区立科学館実験室 内容:コウイカの解剖.太古の生物を復元するために,今生きている生物の体のつくりを学びます.
講師:佐々木猛智(東京大学准教授)・川辺文久(杉並区立科学館)
リンク:博物館トップ
自然科学ワークショップ「化石の解剖」:特別講演:定員40名(申込不要)
日時:2008年3月8日(土)16:00〜17:00
場所:杉並区立科学館 主催など:杉並区立科学館視聴覚室 内容:アンモナイトはどのような生物であったか?
講師:棚部一成(東京大学教授)
リンク:博物館トップ
日時:2008年3月15日(土)16:00〜17:00
場所:杉並区立科学館 主催など:杉並区立科学館視聴覚室 内容:アンモナイトの系統を復元する.
講師:平野弘道(早稲田大学教授)
リンク:博物館トップ
【神奈川県の講座など】
化石クリーニング教室
日時:2007年11月18日(日) 場所:神奈川県立生命の星・地球博物館 実習実験室 主催など:神奈川県立生命の星・地球博物館 内容:岩石から化石を取り出す体験講座です。 申し込みの要不要:必要。往復はがき、 またはホームページから。締切りは10月2日(消印有効)" リンク:"紹介ページ
岩石プレパラートを作ろう
日時:2007年12月1日(土)、2日(日)(両日)" 場所:神奈川県立生命の星・地球博物館 実習実験室ほか 主催など:神奈川県立生命の星・地球博物館 内容:岩石薄片をつくり、偏光顕微鏡での観察を行い、岩石の種 類や性質を調べます。 申し込みの要不要:必要。往復はがき、 またはホームページから。締切りは11月13日(消印有効)" リンク:博物館トップ
【長野県の講座など】
飯田市二ツ山〜水晶山の地質的魅力と昼神断層
日時:2007年10月4日(木) 午後7時〜9時 場所:飯田市美術博物館科学工作室 主催など:飯田市美術博物館・伊那谷自然友の会 内容:講師:手塚恒人さん(喬木第一小学校教諭) 申し込みの要不要:不要、受講料100円" リンク:"紹介ページ
山と盆地を歩いた54年
日時:2007年11月17日(土) 午後1時30分〜3時30分 場所:飯田市美術博物館講堂 主催など:飯田市美術博物館・伊那谷自然友の会 内容:講師:松島信幸さん(飯田市美術博物館顧問) 申し込みの要不要:不要、受講料100円" リンク:"紹介ページ
茶臼山の化石採集
日時:2007年11月17日(土) 場所:茶臼山自然史館 主催など:茶臼山自然史館 内容:茶臼山で植物化石を掘る 申し込みの要不要:必要。11月7日(水) までに電話で茶臼山自然史館へ。 リンク:"紹介ページ
化石のレプリカ作り
日時:2007年11月24日(土) 場所:茶臼山自然史館 主催など:茶臼山自然史館 内容:化石のレプリカをつくる 申し込みの要不要:必要。 リンク:博物館トップ
世界の屋根からみた日本の屋根9
日時:2008年1月19日(土) 13時30分〜15時30分 場所:飯田市美術博物館講堂 主催など:飯田市美術博物館・伊那谷自然友の会 内容:講師:金澤重敏さん(飯田風越高校教諭) 申し込みの要不要:不要。受講料100円" リンク:"紹介ページ
地層と火山灰からみた伊那谷の生いたち
日時:2008年2月16日(土) 13時30分〜15時30分 場所:飯田市美術博物館講堂 主催など:飯田市美術博物館・伊那谷自然友の会 内容:講師:寺平 宏さん 申し込みの要不要:不要。受講料100円" リンク:"紹介ページ
伊那谷自然史発表会
日時:2008年3月20日(祝) 10時〜17時 場所:飯田市美術博物館講堂 主催など:飯田市美術博物館・伊那谷自然友の会 内容:伊那谷の自然をさまざまな視点から発表し合うと同時に交 流を深める。 申し込みの要不要:発表申込み〆切2008年2月末日。当日の参加自由・無料" リンク:"紹介ページ
【静岡県の講座など】
石ころクラフト教室「石ころ勾玉作り教室」
日時:2008年3月9日(日)AM10:00〜AM15:00(約5時間の予定) 場所:奇石博物館研究学習棟2階教室 主催など:奇石博物館 内容:カットされた大理石の原石から、機械を使わずに穴を開 け、自分の手で磨き、自分だけのオリジナル勾玉を作成します。参加費: 1000円(材料費等)。定員20人。 申し込みの要不要:必要。(奇石博物館 に電話にて)、定員になり次第締め切り。 リンク:"紹介ページ
【愛知県の講座など】
地球工房
日時:2007年10月6日(土)13時〜16時 場所:名古屋市科学館生命館2階 主催など:名古屋少年少女発明クラブ・名古屋市科学館 内容:鉱物など自然素材を使ったテーブルインテリアづくり 申し込みの要不要:不要(材料費200〜 400円徴収)。 リンク:博物館トップ
「カンブリア紀の生物(モンスター)たち なまえとなかまわけ」
日時:2007年10月6日(土) 13時〜14時30分 場所:生命の海科学館 メディアホール 主催など:生命の海科学館・竹島水族館 内容:アノマロカリスやハルキゲニアなど、バージェスモンスタ ーの名前や分類を手がかりに、進化の大爆発「カンブリア爆発」についてご紹 介します。 申し込みの要不要:必要(当日受付もあ ります)/参加無料" リンク:"紹介ページ
サイエンス・トーク「隕石・化石 なまえとなかまわけ」
日時:2007年10月6日(土) 15時〜15時40分ごろ 場所:生命の海科学館 展示室 主催など:生命の海科学館・竹島水族館 内容:科学館展示室で実物標本に触れながら、隕石や化石などの 分類とその意味についてご紹介します。 申し込みの要不要:必要(当日受付もあ ります)/科学館観覧料が必要" リンク:"紹介ページ
地球工房
日時:2007年10月7日(日)11時〜16時 場所:名古屋市科学館生命館2階 主催など:名古屋少年少女発明クラブ・名古屋市科学館 内容:鉱物など自然素材を使ったテーブルインテリアづくり 申し込みの要不要:不要(材料費200〜 400円徴収)。 リンク:博物館トップ
地球工房
日時:2007年10月8日(祝)11時〜16時 場所:名古屋市科学館生命館2階 主催など:名古屋少年少女発明クラブ・名古屋市科学館 内容:鉱物など自然素材を使ったテーブルインテリアづくり 申し込みの要不要:不要(材料費200〜 400円徴収)。 リンク:"紹介ページ
「たいけん★化石発掘!」
日時:2007年10月8日(祝) 10時〜12時ごろ 場所:生命の海科学館 中庭 主催など:生命の海科学館・竹島水族館 内容:化石の発掘にチャレンジしてみよう! 申し込みの要不要:必要(当日受付もあ ります)/無料" リンク:"紹介ページ
地球工房
日時:2007年11月3日(土)13時〜16時 場所:名古屋市科学館生命館2階 主催など:名古屋少年少女発明クラブ・名古屋市科学館 内容:鉱物など自然素材を使ったテーブルインテリアづくり 申し込みの要不要:不要(材料費200〜 400円徴収)。 リンク:博物館トップ
地球工房
日時:2007年11月4日(日)11時〜16時 場所:名古屋市科学館生命館2階 主催など:名古屋少年少女発明クラブ・名古屋市科学館 内容:鉱物など自然素材を使ったテーブルインテリアづくり 申し込みの要不要:不要(材料費200〜 400円徴収)。 リンク:博物館トップ
ひとくちテラス〜ちょっと月まで〜第4回「もしも月から何か 持ち帰るとしたら?」
日時:2007年11月17日(土)午後3時から午後4時 場所:生命の海科学館 屋内テラス 主催など:生命の海科学館 内容:月にちなんだお菓子を頂きながら、月の科学について楽し くご紹介します。 申し込みの要不要:必要(先着順)/参 加料300円(お茶とお菓子代込み)" リンク:"紹介ページ
地球工房
日時:2007年11月23日(祝)11時〜16時 場所:名古屋市科学館生命館2階 主催など:名古屋少年少女発明クラブ・名古屋市科学館 内容:鉱物など自然素材を使ったテーブルインテリアづくり 申し込みの要不要:不要(材料費200〜 400円徴収)。 リンク:博物館トップ
地球工房
日時:2007年11月24日(土)13時〜16時 場所:名古屋市科学館生命館2階 主催など:名古屋少年少女発明クラブ・名古屋市科学館 内容:鉱物など自然素材を使ったテーブルインテリアづくり 申し込みの要不要:不要(材料費200〜 400円徴収)。 リンク:博物館トップ
地球工房
日時:2007年11月25日(日)11時〜16時 場所:名古屋市科学館生命館2階 主催など:名古屋少年少女発明クラブ・名古屋市科学館 内容:鉱物など自然素材を使ったテーブルインテリアづくり 申し込みの要不要:不要(材料費200〜 400円徴収)。 リンク:博物館トップ
地球工房
日時:2007年12月22日(土)13時〜16時 場所:名古屋市科学館生命館2階 主催など:名古屋少年少女発明クラブ・名古屋市科学館 内容:鉱物など自然素材を使ったテーブルインテリアづくり 申し込みの要不要:不要(材料費200〜 400円徴収)。 リンク:博物館トップ
地球工房
日時:2007年12月23日(日)11時〜16時 場所:名古屋市科学館生命館2階 主催など:名古屋少年少女発明クラブ・名古屋市科学館 内容:鉱物など自然素材を使ったテーブルインテリアづくり 申し込みの要不要:不要(材料費200〜 400円徴収)。 リンク:博物館トップ
地球工房
日時:2007年12月24日(祝)11時〜16時 場所:名古屋市科学館生命館2階 主催など:名古屋少年少女発明クラブ・名古屋市科学館 内容:鉱物など自然素材を使ったテーブルインテリアづくり 申し込みの要不要:不要(材料費200〜 400円徴収)。 リンク:博物館トップ
ひとくちテラス〜ちょっと月まで〜第5回「もしも月にタイム カプセルを埋めるとしたら?」
日時:2008年1月19日(土)午後3時から午後4時 場所:生命の海科学館 屋内テラス 主催など:生命の海科学館 内容:月にちなんだお菓子を頂きながら、月の科学について楽し くご紹介します。 申し込みの要不要:必要(先着順)/参 加料300円(お茶とお菓子代込み)" リンク:"紹介ページ
地球工房
日時:2008年2月2日(土)13時〜16時 場所:名古屋市科学館生命館2階 主催など:名古屋少年少女発明クラブ・名古屋市科学館 内容:鉱物など自然素材を使ったテーブルインテリアづくり 申し込みの要不要:不要(材料費200〜 400円徴収)。 リンク:博物館トップ
地球工房
日時:2008年2月3日(日)11時〜16時 場所:名古屋市科学館生命館2階 主催など:名古屋少年少女発明クラブ・名古屋市科学館 内容:鉱物など自然素材を使ったテーブルインテリアづくり 申し込みの要不要:不要(材料費200〜 400円徴収)。 リンク:博物館トップ
自然史講座「鉱物の色」
日時:2008年2月3日(日)14:00〜15:30 場所:豊橋市自然史博物館(豊橋市大岩町字大穴1-238) 主催など:豊橋市自然史博物館 内容:古代から人々を魅了してきた鉱物や宝石の色について紹介 します。小学4年生以上・一般対象、40名(申込順)。 申し込みの要不要:必要。豊橋市自然史 博物館へ電話(0532-41-4747)、FAX:0532-41-8020)またはメールで先着順。 リンク:"紹介ページ
地球工房
日時:2008年2月9日(土)13時〜16時 場所:名古屋市科学館生命館2階 主催など:名古屋少年少女発明クラブ・名古屋市科学館 内容:鉱物など自然素材を使ったテーブルインテリアづくり 申し込みの要不要:不要(材料費200〜 400円徴収)。 リンク:博物館トップ
地球工房
日時:2008年2月10日(日)11時〜16時 場所:名古屋市科学館生命館2階 主催など:名古屋少年少女発明クラブ・名古屋市科学館 内容:鉱物など自然素材を使ったテーブルインテリアづくり 申し込みの要不要:不要(材料費200〜 400円徴収)。 リンク:博物館トップ
地球工房
日時:2008年2月11日(祝)11時〜16時 場所:名古屋市科学館生命館2階 主催など:名古屋少年少女発明クラブ・名古屋市科学館 内容:鉱物など自然素材を使ったテーブルインテリアづくり 申し込みの要不要:不要(材料費200〜 400円徴収)。 リンク:博物館トップ
地球工房
日時:2008年2月16日(土)13時〜16時 場所:名古屋市科学館生命館2階 主催など:名古屋少年少女発明クラブ・名古屋市科学館 内容:鉱物など自然素材を使ったテーブルインテリアづくり 申し込みの要不要:不要(材料費200〜 400円徴収)。 リンク:博物館トップ
地球工房
日時:2008年2月17日(日)11時〜16時 場所:名古屋市科学館生命館2階 主催など:名古屋少年少女発明クラブ・名古屋市科学館 内容:鉱物など自然素材を使ったテーブルインテリアづくり 申し込みの要不要:不要(材料費200〜 400円徴収)。 リンク:博物館トップ
地球工房
日時:2008年2月23日(土)13時〜16時 場所:名古屋市科学館生命館2階 主催など:名古屋少年少女発明クラブ・名古屋市科学館 内容:鉱物など自然素材を使ったテーブルインテリアづくり 申し込みの要不要:不要(材料費200〜 400円徴収)。 リンク:博物館トップ
地球工房
日時:2008年2月24日(日)11時〜16時 場所:名古屋市科学館生命館2階 主催など:名古屋少年少女発明クラブ・名古屋市科学館 内容:鉱物など自然素材を使ったテーブルインテリアづくり 申し込みの要不要:不要(材料費200〜 400円徴収)。 リンク:博物館トップ
地球工房
日時:2008年3月1日(土)13時〜16時 場所:名古屋市科学館生命館2階 主催など:名古屋少年少女発明クラブ・名古屋市科学館 内容:鉱物など自然素材を使ったテーブルインテリアづくり 申し込みの要不要:不要(材料費200〜 400円徴収)。 リンク:博物館トップ
地球工房
日時:2008年3月2日(日)11時〜16時 場所:名古屋市科学館生命館2階 主催など:名古屋少年少女発明クラブ・名古屋市科学館 内容:鉱物など自然素材を使ったテーブルインテリアづくり 申し込みの要不要:不要(材料費200〜 400円徴収)。 リンク:博物館トップ
地球工房
日時:2008年3月8日(土)13時〜16時 場所:名古屋市科学館生命館2階 主催など:名古屋少年少女発明クラブ・名古屋市科学館 内容:鉱物など自然素材を使ったテーブルインテリアづくり 申し込みの要不要:不要(材料費200〜 400円徴収)。 リンク:博物館トップ
地球工房
日時:2008年3月9日(日)11時〜16時 場所:名古屋市科学館生命館2階 主催など:名古屋少年少女発明クラブ・名古屋市科学館 内容:鉱物など自然素材を使ったテーブルインテリアづくり 申し込みの要不要:不要(材料費200〜 400円徴収)。 リンク:博物館トップ
地球工房
日時:2008年3月15日(土)13時〜16時 場所:名古屋市科学館生命館2階 主催など:名古屋少年少女発明クラブ・名古屋市科学館 内容:鉱物など自然素材を使ったテーブルインテリアづくり 申し込みの要不要:不要(材料費200〜 400円徴収)。 リンク:博物館トップ
ひとくちテラス〜ちょっと月まで〜第6回「もしも月より遠く に行けるとしたら?」
日時:2008年3月15日(土)午後3時から午後4時 場所:生命の海科学館 屋内テラス 主催など:生命の海科学館 内容:月にちなんだお菓子を頂きながら、月の科学について楽し くご紹介します。 申し込みの要不要:必要(先着順)/参 加料300円(お茶とお菓子代込み)" リンク:"紹介ページ
地球工房
日時:2008年3月16日(日)11時〜16時 場所:名古屋市科学館生命館2階 主催など:名古屋少年少女発明クラブ・名古屋市科学館 内容:鉱物など自然素材を使ったテーブルインテリアづくり 申し込みの要不要:不要(材料費200〜 400円徴収)。 リンク:博物館トップ
【滋賀県の講座など】
葉っぱの化石を観察してみよう
日時:2008年3月8日(土),13:30〜15:00" 場所:滋賀県立琵琶湖博物館・実習室2 主催など:滋賀県立琵琶湖博物館 内容:植物化石と今の植物をくらべながら観察します。 申し込みの要不要:不要(ただし,当日 13時より受付30名)" リンク:"紹介ページ
葉っぱの化石を観察してみよう
日時:2008年3月22日(土),13:30〜15:00" 場所:滋賀県立琵琶湖博物館・実習室2 主催など:滋賀県立琵琶湖博物館 内容:植物化石と今の植物をくらべながら観察します。 申し込みの要不要:不要(ただし,当日 13時より受付30名)" リンク:"紹介ページ
平成19年度 自然史学会連合 講演会「いきもの・ひと・みず の自然史」
日時:2007年11月25日(日)11時〜16時30分 場所:滋賀県立琵琶湖博物館 ホール 主催など:自然史学会連合、共催:琵琶湖博物館、協賛:ロレッ クス・インスティチュート" 内容:地学や生物分野の10名の研究者が、自然史研究の面白さ についてわかりやすく解説します。(自然史学会連合は、国内38の学協会か らなる研究者の組織です)" 申し込みの要不要:不要。(定員200名)" リンク:"紹介ページ
【大阪府の講座など】
ジオラボ(10月)「ミクロの化石」
日時:2007年10月13日(土) 14時30分〜15時30分 場所:大阪市立自然史博物館 ナウマンホール 主催など:大阪市立自然史博物館 内容:約1億4千万年前の海底にたまった地層から取り出したプ ランクトンの化石を観察します。実体顕微鏡で参加者自身に化石を探してもら い、電子顕微鏡で観察してみます。ジオラボは,第2土曜日の同じ時間で毎月 開催。 申し込みの要不要:不要" リンク:博物館トップ(トップページのイベントをクリック)
ジオラボ(11月)「水槽の中に地層を作る」
日時:2007年11月10日(土) 14時30分〜15時30分 場所:大阪市立自然史博物館 玄関前ポーチ 主催など:大阪市立自然史博物館 内容:崖に出ている地層は大昔の水や波の流れを記録していま す。水槽の中に水の流れでできる砂模様をつくって、地層のできかたを考えま しょう。ジオラボは,第2土曜日の同じ時間で毎月開催。 申し込みの要不要:不要 リンク:博物館トップ(トップページのイベントをクリック)
ジオラボ(12月)「植物の化石」
日時:2007年12月8日(土) 14時30分〜15時30分 場所:大阪市立自然史博物館 ナウマンホール 主催など:大阪市立自然史博物館 内容:ジオラボは,1月以降も第2土曜日の同じ時間で毎月開催します。 申し込みの要不要:不要" リンク:博物館トップ(トップページのイベントをクリック)
自然史オープンセミナー「地学シリーズ1.岩石から何がわか る?」
日時:2007年12月1日(土) 15時〜16時30分 場所:大阪市立自然史博物館 集会室 主催など:大阪市立自然史博物館 内容:12月から3回にわたり,地学シリーズとして岩石・化石・ 地層から何がわかるのか?ということを解説します.第1回目は岩石をとりあ げて,岩石の種類・成因,そして岩石を調べることでどういうことがわかって くるのかと言うことを,解説します." 申し込みの要不要:不要" リンク:博物館トップ(トップページのイベントをクリック)
自然史オープンセミナー「地学シリーズ2.化石から何がわか る?」
日時:2008年1月5日(土) 15時〜16時30分 場所:大阪市立自然史博物館 集会室 主催など:大阪市立自然史博物館 内容:12月から3回にわたり,地学シリーズとして岩石・化石・ 地層から何がわかるのか?ということを解説します.第2回目は化石をとりあ げます." 申し込みの要不要:不要" リンク:博物館トップ(トップページのイベントをクリック)
自然史オープンセミナー「地学シリーズ3.地層から何がわか る?」
日時:2008年2月1日(土) 15時〜16時30分 場所:大阪市立自然史博物館 集会室 主催など:大阪市立自然史博物館 内容:12月から3回にわたり,地学シリーズとして岩石・化石・ 地層から何がわかるのか?ということを解説します.第3回目は地層をとりあ げます." 申し込みの要不要:不要" リンク:博物館トップ(トップページのイベントをクリック)
【徳島県の講座など】
木の葉化石の発掘体験2
日時:2007年12月2日,13:30〜15:00" 場所:徳島県立博物館 実習室 主催など:徳島県立博物館 内容:栃木県の那須塩原には,塩原層群という約50〜30万年前の 湖の地層があります.塩原層群の石を割って植物の葉の化石を探してみません か?" 申し込みの要不要:必要。往復はがきで 申し込み.10日前必着" リンク:"紹介ページ
アンモナイト標本をつくろう
日時:2008年2月10日,13:30〜15:00" 場所:徳島県立博物館 実習室 主催など:徳島県立博物館 内容:実際にアンモナイト標本をつくりながら、その殻の内部構 造を観察します。 申し込みの要不要:必要。往復はがきで 申し込み.10日前必着 リンク:"紹介ページ
【福岡県の講座など】
連続講座「自然史入門〜DNAからフィールドまで」
日時:2007年10月6日(土)〜10月21日(日)までの土日 場所:北九州市立自然史・歴史博物館 主催など:北九州市立自然史・歴史博物館(いのちのたび博物館) 内容:自然史系の学芸員による市民向け連続講座です.第一回目 は,古生物(化石)から見た自然史学(入門編)です." 申し込みの要不要:必要(詳しくは博物館まで) リンク:博物 館トップ
【鹿児島県の講座など】
第13回市民講座「鹿児島湾の生きものたち」
日時:2007年11月10日 (土) 14:30〜16:00 場所:鹿児島大学総合教育研究棟 2F 主催など:鹿児島大学総合研究博物館 内容:鹿児島大学水産学部の3名の教員が、鹿児島湾の動植物の 多様性について講演する。 申し込みの要不要:不要 リンク:博物館トップ
ページトップへ
【特別展示・企画展示など】
【北海道の特別展示など】
第148回テーマ展まるごとアンモナイト展
期間:2007年10月26日(金)〜2008年2月10日(日) 場所:北海道開拓記念館 内容:恐竜時代、世界中の海にはたくさんのアンモナイトがいま した。形は貝ににていますが、実は違う生物です。形も大きさも様々な250個 以上のアンモナイトを通して、その魅力を紹介します。(協力:北海道化石 会) リンク:博物館トップ
【岩手県の特別展示など】
第2回北東北三県共同展「北東北自然史博物館〜大地と生きも のふしぎ旅行〜」
期間:2007年9月22日(土)〜11月11日(日) 場所:岩手県立博物館 特別展示室 内容:青森県立郷土館・秋田県立博物館・岩手県立博物館の自然 史部門(地質・生物)が企画。5億年におよぶ北東北の大地の歴史と豊かな自 然に生きる生物の多様性を紹介しています。展示解説会10月21日(日)、11月 4日(日)14:00〜15:00。 リンク:紹介ページ
【栃木県の特別展示など】
「新着標本展」
期間:2007年12月1日〜2008年3月2日 場所:葛生化石館企画展示スペース(入館無料) 内容:昨年度後半〜今年前半の1年間で市民の方が寄贈してくれた 化石や、化石館で採集した化石を紹介・展示します。 リンク:博物館トップ
【茨城県の特別展示など】
デスモスチルス歌登標本 世界一の全身化石発見から30年
期間:2007年9月26日(水)〜12月2日(日)[9月29日(土)・ 10月7日(日)は 臨時休館] 場所:地質標本館 内容:世界一といえる「デスモスチルス」の全身化石が,北海道 歌登(うたの ぼり)町(現 枝幸町)で発見されてから今秋で30年.今回,こ の標本をはじ めて公開するとともに,謎の多いデスモスチルスの姿を復元し た研究の成果を 紹介します. リンク:
【東京都の特別展示など】
企画展『地下展UNDERGROUND−空想と科学がもたらす闇の冒険』
期間:2007年9月22日(土)〜2008年1月28日(月) 場所:日本科学未来館 企画展示ゾーン 内容:私たちの足元にある地下世界。地下鉄などが埋まるライフ ラインのその先は、宇宙にも匹敵するほどの広大なフロンティアが広がってい ます。現在、その闇の世界について、さまざまな研究やプロジェクトが進行し ています。そこから明らかとなったのは、地下には、地上をしのぐほどの生物 圏が存在し、全生命の祖先は地下に住む生物から発生したのではないかとする 研究結果や、地球環境の歴史、地球の未来に関する結果の数々です。本展で は、そうした最先端科学の研究成果に、神話や小説、哲学など空想豊かに語ら れてきた「地下」の姿を手がかりに、誰も見たことのない闇の世界を描き出し ます。会期中には、地下施設を見学する「地下探検ツアー」やトークイベント 「地下の達人に訊く!」など、さまざまな関連イベントを予定しています。ま た、都営地下鉄の定期券をご持参の方には、割引料金にてご入場いただけま す。 リンク:博物館トップ
企画展『エイリアン展ー モシモシ、応答ネガイマス。』
期間:2008年3月20日(木)〜6月16日(月) 場所:日本科学未来館 企画展示ゾーン 内容:2005年にロンドンで“The Science of Aliens”という名称で初公開されたエイリアン展は、近年の惑星探査や天体観測技術の進歩、最先端の生命科学などによって得られた研究成果をもとに、エイリアンに古くから魅了されてきた人間の心理をひも解きながら、地球外生命が存在する可能性について「科学的」に追求する展覧会です。また同時に、こうした宇宙全体を俯瞰するような研究成果から、地球の現在、そして未来の姿についても考えていきます。 リンク:博物館トップ
【神奈川県の特別展示など】
特別展「ナウマンゾウがいた!温暖期の神奈川」
期間:2007年7月21日〜11月4日 場所:神奈川県立生命の星・地球博物館 特別展示室 内容:神奈川県藤沢市で発掘されたナウマンゾウとこのナウマン ゾウが生きていた当時の様子を紹介しています。 リンク:紹介ページ
【長野県の特別展示など】
茶臼山自然史館22年間の歩みと収集標本
期間:2007年7月14日〜11月25日(日)なお、11月3日から25日ま では、閉館直前で無料開放です。 場所:茶臼山自然史館 内容:館の歴史をふりかえり、寄贈された標本類を展示します" リンク:博物館トップ
特別陳列 骨は語る
期間:2007年11月23日(金)〜2008年2月11日(月) 場所:飯田市美術博物館展示室B 内容:南信州にすむ獣の骨格(現生・化石)を展示し、その機能 的な美を紹介 リンク:博物館トップ
【福井県の特別展示など】
国際恐竜シンポジウム2008「アジアの恐竜研究最前線」
期間:2008年3月22日(土)10:00〜16:00 シンポジウム
3月23日(日) 13:00〜16:00 普及講演、パネルディスカッション 場所:福井県立恐竜博物館 講堂
主催など:福井県立恐竜博物館
内容:中国、韓国、モンゴル、ロシア、タイ、カナダ、日本の第一線の恐竜研究者が一堂に会し、アジアの恐竜研究の最新情報を紹介します。
事前申し込み不要:当日受付、聴講無料。 リンク:紹介ページ
【滋賀県の特別展示など】
第15回企画展示「琵琶湖のコイ・フナの物語〜東アジアの中の 湖と人〜」
期間:2007年7月14日(土)〜11月25日(日) 場所:琵琶湖博物館・企画展示室 内容:7000万年前に誕生して,琵琶湖で人と関係しながら現在に わたるコイ科魚類の物語を紹介します。 リンク:博物 館トップ
【大阪府の特別展示など】
特別展「世界最大の翼竜展」
期間:2007年9月15日〜11月25日まで 場所:大阪市立自然史博物館ネイチャーホール 内容:恐竜時代に大空を支配していた翼竜をテーマにした本格的 な展覧会「世界最大の翼竜展」を開催します。翼を広げた長さが約10メート ルにもなる史上最大の飛行生物ケツァルコアトルスの全身復元骨格をはじめ、 中国で発掘された翼竜化石など約100点を展示し、その生態の謎に迫りま す。 リンク:紹介ページ
【福岡県の特別展示など】
収蔵品展「三池築港」
期間:2008年3月20日(木)〜5月18日(日) 場所:大牟田市石炭産業科学館 企画展示室 内容:今年築港から100年を迎える三池港の100年前を当時の写真を中心に紹介します。◎三池港の昔の写真パネル ◎三池港および大牟田港の様子のわかる地図類 ◎團琢磨のノート ◎三池炭鉱・三池港の絵葉書、その他文献、資料 ◎平成19年度に寄贈された資料 リンク:博物館トッ プ
【鹿児島県の特別展示など】
第7回特別展「鹿児島湾の自然史」
期間:2007年10月15日(月)〜11月15日(木) 場所:鹿児島大学総合教育研究棟プレゼンテーションホール 内容:鹿児島湾に暮らす水生生物の多様性に焦点をあて、最新の 研究成果をわかりやすく紹介します。海藻、有孔虫、プランクトンからエビ、 タコ、魚、イルカまでの様々な生物を生体、標本、映像を用いた多角的な展示 をご覧下さい。リンク:博物館トッ プ
ページトップへ
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2008年9月)
9月のイベント・特別展示カレンダー (2008/09/02〜2008/10/06)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
9月の特別展示
2008/09/02 現在
「ダーウィン展」 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
期間:7/19(土)〜9/21(日)
場所:大阪市立自然史博物館ネイチャーホール
この展覧会では、2009年がダーウィンの生誕200年、「種の起源」発表150年になることを記念して、ダーウィンの生い立ちから、5年に及ぶビーグル号での世界航海、「種の起源」を発表するまでの苦悩と、進化論が当時の世界に与えた影響を紹介します。会場内には、ビーグル号航海の模様を壮大なスケールで展示。ブラジルやアルゼンチン、そして貴重な生物の宝庫として有名なガラパゴス諸島でダーウィンが出会った珍しい生物を剥製や映像で紹介します。また、進化論とは何なのか?について、工夫を凝らした展示でわかりやすく解説します。
「金Gold: 黄金の国ジパングとエル・ドラード展」 (東京都 国立科学博物館)
期間:7/12(土)〜9/21(日)
場所:国立科学博物館
日本は今でも黄金の国です。本展では金形成にいたる地質学を含めた太古の昔から現在に至る金の歴史を実物とともに紹介します。日本の金の歴史,現在の河川でとれた砂金、コロンビアからの金の歴史が見所です。
第31回企画展「きれいで不思議な貝の魅力」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
期間:9/27(土)〜11/24(月)
場所:群馬県立自然史博物館企画展示室
貝の進化や不思議な生態、美しい貝殻など、貝の魅力を多くの標本や生体展示で紹介します。
特別展「箱根火山〜いま証される噴火の歴史〜」 (神奈川県 神奈川県立生命の星・地球博物館)
期間:7/19(土)〜11/09(日)
場所:神奈川県立生命の星・地球博物館 特別展示室
箱根火山の形成モデルは、1950年代に故久野久先生により確立されて以来、半世紀にわたり使われ続き、カルデラ形成史の教科書的存在にもなってきました。また、箱根各所の観光地でもそのモデルの紹介が行なわれています。しかし、近年、詳細なフィールドワークと最新の分析機器の導入により、新しい山体形成モデルが提案され、さらに新たな火山活動などもわかってきました。また、火山ができる前にすでにあった、基盤岩についても、さまざまなことがわかってきました。本特別展示では、箱根地域における基盤の形成から火山体の形成までを、新旧モデルをふまえて紹介します。
企画展「曲げ続けて30年!コンニャク石展」 (静岡県 奇石博物館)
期間:9/01(月)〜1/18(日)
場所:奇石博物館企画展示室
当館常設展示で人気のコンニャク石曲げ実験は1978年より開始されたもので、今年はちょうど30年の節目にあたる。この機会にコンニャク石をはじめとした意外な石たちを一同に集め紹介する。
『どんな生き物だったんだろう?三葉虫展』 (栃木県 葛生化石館)
期間:7/19(土)〜9/28(日)
場所:葛生化石館企画展示室
佐野市葛生地域の石灰岩からは古生代ペルム紀の化石がたくさん見つかっています。その中でも人気の高い三葉虫の化石にスポットをあて紹介します。化石採集教室で見つけた三葉虫も展示します。
第23回特別展「野尻湖遺跡群ー旧石器の狩人が集まった氷河時代の湖ー」 (長野県 野尻湖ナウマンゾウ博物館)
期間:7/19(土)〜11/30(日)
場所:野尻湖ナウマンゾウ博物館3階 特別展示室
野尻湖周辺地域に分布する多くの旧石器時代の遺跡(日向林B遺跡、貫ノ木遺跡、上ノ原遺跡、東裏遺跡、仲町遺跡、杉久保遺跡など)は、日本の氷河時代を代表する遺跡として注目されており、野尻湖遺跡群の全体像を理解していただく資料を展示します。
ぽけっと企画展「地球と生命」 (福岡県 北九州市立いのちのたび博物館)
期間:5/10(土)〜
場所:北九州市立いのちのたび博物館 ポケットミュージアム No. 1
自然の変化に対応してきた、絶えることのない生命の継続性と神秘性を化石や自然史資料を用い紹介します。
9月のイベント
2008/09/02 現在
日付
イベント
9/02
(火)
9/03
(水)
9/04
(木)
9/05
(金)
9/06
(土)
南アルプスの渓流5"小渋川" (長野県 伊那谷自然友の会)
場所:大鹿村小渋川
案内:明石浩司さん
前日までに美術博物館村松へ(0265-22-8118)お申し込み下さい。
9/07
(日)
9/08
(月)
9/09
(火)
9/10
(水)
9/11
(木)
9/12
(金)
9/13
(土)
顕微鏡をのぞいて拡大写真を撮ろう (埼玉県 埼玉県立自然の博物館)
場所:埼玉県立自然の博物館
日本各地の砂を材料に顕微鏡の見方と簡単な写真の撮り方を学びます。
9/14
(日)
追手町小学校化石標本室公開 (長野県 飯田市美術博物館)
期間:9/14(日)
場所:追手町小学校化石標本室(飯田市美術博物館から徒歩14分)
飯田市千代出身の長谷川善和先生が採集した標本を中心に展示
追手町小学校化石標本室公開イベント 化石レプリカ作成 (長野県 飯田市美術博物館)
場所:追手町小学校化石標本室(飯田市美術博物館から徒歩5分)
時間:10:00〜16:00
恐竜の歯やアンモナイトなどの型を作り石膏を流しいれてレプリカを作る。講師:小泉明裕(飯田市美術博物館)
9/15
(月)
敬老の日
ひとはくセミナー (8)サンゴの薄片をつくろう (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:人と自然の博物館・セミナー室
時間:13:30〜15:30
2億6千万年前のサンゴ化石(宮城県気仙沼産)と現世のサンゴ礁(沖縄県国頭)のチップを用意します。それらを研磨、スライドグラスに固定、0.02mmまでの薄くして、顕微鏡下で骨格構造を観察します。 小学生高学年〜一般を対象とした、申込み制、有料のセミナーです。
9/16
(火)
9/17
(水)
9/18
(木)
南アルプスの地形・地質的魅力 (長野県 飯田市美術博物館・伊那谷自然友の会)
場所:飯田市美術博物館
時間:19:00〜21:00
世界遺産登録やジオパーク認定への取り組みがはじまった南アルプスの地形・地質的魅力と課題を探る。講師:村松武(飯田市美術博物館学芸員)
9/19
(金)
9/20
(土)
区民科学講座『化石で学ぶ気候変動』 「第四紀化石のクリーニングと古環境解析」 (東京都 杉並区立科学館)
場所:杉並区立科学館
時間:13:00〜16:30
新生代第四紀の繰り返す温暖化と寒冷化、第三紀中新世の温暖化をテーマにした室内実習教室を実施します。なお、本講座は(独)科学技術振興機構(JST)「地域科学技術理解増進活動・地域活動支援」の助成により実施します。講師は、川辺文久・三村麻子(杉並区立科学館)です。
定員は30名。ハガキに「参加希望講座の名称及び日時、住所、氏名、年齢、電話番号」をご記入の上、郵送。または、専用申込用紙に必要事項をご記入の上、郵送もしくはファックスでお申込みください。締切は9/19(金)です。
9/21
(日)
9/22
(月)
9/23
(火)
秋分の日
9/24
(水)
9/25
(木)
9/26
(金)
9/27
(土)
区民科学講座『化石で学ぶ気候変動』 「第三紀化石の観察とレプリカ作製」 (東京都 杉並区立科学館)
場所:杉並区立科学館
時間:13:00〜15:15
新生代第四紀の繰り返す温暖化と寒冷化、第三紀中新世の温暖化をテーマにした室内実習教室を実施します。なお、本講座は(独)科学技術振興機構(JST)「地域科学技術理解増進活動・地域活動支援」の助成により実施します。講師は、川辺文久・三村麻子(杉並区立科学館)です。
定員は30名。ハガキに「参加希望講座の名称及び日時、住所、氏名、年齢、電話番号」をご記入の上、郵送。または、専用申込用紙に必要事項をご記入の上、郵送もしくはファックスでお申込みください。締切は9/26(金)です。
特別講演会 『地層と化石から復元する太古の秩父の海(仮題)』 (東京都 杉並区立科学館)
場所:杉並区立科学館
時間:15:30〜16:30
本年7月の洞爺湖サミットの主要議案や昨年のノーベル平和賞に象徴されるように、気候変動への社会的関心が年々高まっています。温暖化すると世界はどうなるのか・・・この問いへの実証的な回答は地層と化石に記録されています。本講座では新生代第四紀の繰り返す温暖化と寒冷化、第三紀中新世の温暖化をテーマにした講演会を実施します。なお、本講座は(独)科学技術振興機構(JST)「地域科学技術理解増進活動・地域活動支援」の助成により実施します。
講師は、加藤久佳さん(千葉県立中央博物館)です。定員は50名(先着順)。
9/28
(日)
追手町小学校化石標本室公開イベント 化石クリーニング (長野県 飯田市美術博物館)
場所:追手町小学校化石標本室(飯田市美術博物館から徒歩5分)
時間:10:00〜16:00
阿南町で採取された富草層群の貝やサメの歯などを含む岩塊を割って化石を探す。講師:小泉明裕(飯田市美術博物館)
9/29
(月)
追手町小学校化石標本室公開 (長野県 飯田市美術博物館)
期間:9/29(月)〜9/29(月)
場所:追手町小学校化石標本室(飯田市美術博物館から徒歩15分)
飯田市千代出身の長谷川善和先生が採集した標本を中心に展示
9/30
(火)
10/01
(水)
10/02
(木)
10/03
(金)
10/04
(土)
10/05
(日)
10/06
(月)
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ内のフォームまたはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。随時、情報を更新いたしますので,ご協力をお願いいたします。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
『地質の日』
日本地質学会のイベント情報
はこちらから
地質学会以外
イベント情報
自宅学習に役立つ
デジタルコンテンツ
ポスターDLはこちら
2008年より,5月10日が『地質の日』に制定され,これを記念した多くのイベントが,全国各地の博物館・大学で開催されています。ここでは,全国各地で開催された『地質の日』のイベントの様子をご紹介します。
『地質の日』とは?『地質の日』の由来って何?→地質の日事業推進委員会のサイトへ
地質学会の過去のイベント 一覧
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
街中ジオ散歩 in Kawasaki「多摩丘陵の100万年を歩く」徒歩見学会 ほか
2017年
街中ジオ散歩in Tokyo「国分寺崖線と玉川上水」ほか
2016年
街中ジオ散歩in Tokyo「国会議事堂の石を見に行こう」徒歩見学会
日本地質学会の主催等する各地の『地質の日』イベント
2015年
日本地質学会・日本応用地質学会 街中ジオ散歩in Tokyo「等々力渓谷の地質と人の関わり」徒歩見学会
日本地質学会の主催等する各地の『地質の日』イベント
その他の団体の「地質の日」イベント
2014年
日本地質学会・日本応用地質学会 街中ジオ散歩in Tokyo「下町低地の地盤沈下と水とくらし」徒歩見学会
▶▶▶ 開催報告(2014.6.5)
日本地質学会の主催等する各地の『地質の日』イベント
フィールドワーク「身近な地学1:川原の石—櫛田川—」(主催:三重県総合博物館)5月10日(土)13:30-15:30 場所:三重県多気郡多気町古江 櫛田川右岸河床定員30名(多数の場合は抽選)/参加費無料
2013年
日本地質学会・日本応用地質学会 街中ジオ散歩in Tokyo「石神井川がつくる地形の移り変わりと地質」
日本地質学会の主催等する各地の『地質の日』イベント
2012年
徒歩見学会 街中ジオ散歩 in Tokyo「身近な地層や岩石を知ろう」(5/13)
記念展示 私たちの生活を支える金属鉱床ー札幌周辺の鉱山を例に(4/24-5/27)
2012年『地質の日』くまもと(5/26)
惑星地球フォトコンテスト 展示会○第2回入選作展示日時:2012年4月28日(土)〜5月13日(日)場所:東海大学自然史博物館 ○第3回入選作展示:日時:2012年4月21日(土)〜6月3日(日)場所:千葉県立中央博物館
記念観察会「深海から生まれた城ヶ島」(5/12) PDF
2011年
報告:「紀の松島クルージングセミナー 熊野のジオサイト紀の松島めぐり」 (環境省 近畿地方環境事務所)
日本地質学会の主催等する各地の『地質の日』イベント
2010年
日本地質学会の主催等する各地の『地質の日』イベント 写真家 白尾元理 講演会「地球史46億年を撮る」ほか多数
2009年
特別講演会「火山はすごい!−日本列島の火山をさぐる」(講師:鎌田浩毅さん)(主催 日本地質学会)
2008年
『地質の日』制定記念:サイエンスフェスティバル−化石やきれいな石にさわろう−
(新潟大学・NPO法人ジオプロジェクト新潟・新潟県立自然科学館)
『地質の日』記念講演会・観察会 (埼玉県立自然の博物館)(自然の博物館サーバー)
宮澤賢治ジオツアー(NPO地質情報整備・活用機構)
『地質の日』記念事業 三葉虫をさがせ!化石採集教室(栃木県佐野市葛生化石館)
博物館関係者のみなさまへ
「地質の日」のイベントの様子をぜひご紹介ください。
学会Webページ内のフォームまたはメールにて情報をお寄せ下さい。なお,写真についてはフォームからは送信できませんので,恐れ入りますがメールに添付してお送り下さいますようお願いいたします。
(注:送信の際は、@アットマークは半角にして下さい)
『地質の日』ロゴマーク
■「地質の日」のロゴマークが出来ました!(2009.5)
Geology Dayの「G」をベースに、重なる「地層」を組み合わせ、「地質の日」の広がりを表現しています
2014年地質の日(本部・各支部等)
2014年の「地質の日」
2014年の「地質の日」に関連した日本地質学会の催しをご紹介します。
日本地質学会 4.17 更新
一般社団法人日本地質学会 主催
第5回惑星地球フォトコンテストほか入選作品展示会
日時:5月3日(土)17時〜5月17日(土)13時
場所:銀座プロムナードギャラリー(中央区銀座4丁目地内 東銀座地下歩道壁面)
本年(第5回惑星地球フォトコンテスト)をメインに過去の入選作品も展示します.皆様お誘い合わせの上是非お越し下さい.
http://www.photo.geosociety.jp/
一般社団法人日本地質学会,一般社団法人日本応用地質学会 主催
地質の日記念 街中ジオ散歩in Tokyo「下町低地の地盤沈下と水とくらし」
日時:5月10日(土)9:50-17:00 少雨決行(予定)
場所:東京都江東区清澄白河,住吉,東大島,南砂町界隈(仙台堀川,小名木川)
案内者:中山俊雄氏(元東京都土木技術支援・人材育成センター),小松原純子氏(産業技術総合研究所)
詳しくはこちら
http://www.geosociety.jp/name/content0110.html
一般社団法人日本地質学会 主催
公開講演会「日本の地質学:最近の発見と応用」
日時:5月24日(土)13:00-15:00
会場:北とぴあ第2研修室(東京都北区王子)
プログラム(順番は変わる可能性があります)
・「犯罪捜査と地質学」杉田律子(科学警察研究所)
・「巨大地震の巣を掘る そこから見えてきたもの」坂口有人(山口大学)
・「宇宙からの贈りもの:日本の地層から隕石衝突の証拠を発見」佐藤峰南(九州大学)
・「日本全国の地質情報をあなたへ〜進化する日本シームレス地質図〜」西岡芳晴(産業技術総合研究所)
※それぞれタイトルをクリックすると,講演要旨をダウンロードできます.
本講演会への参加は,CPDの対象となります(CPDH:2単位)
参加費:会員無料,非会員500円.[事前申込不要]
当日は, 第5回惑星地球フォトコンテスト表彰式(11:00〜12:00)予定されています.
※表彰式ならびに審査委員長による講評、入選作品の展示を行います。
▶▶▶入選作品紹介
問い合わせ先(世話人)
斎藤 眞(常務理事)・星 博幸(行事委員長)
e-mail;main@geosociety.jp
北海道支部 4.9更新
クリックするとPDFをダウンロードできます
主催:北海道大学総合博物館・「地質の日」記念企画展示実行委員会
共催:日本地質学会北海道支部ほか
地図の語る多様な世界—地図の過去・現在・未来—
日時:4月22日(火)〜6月8日(日)
会場:北海道大学総合博物館2階企画展示室2
入場無料(月曜休館)
■市民セミナー(総合博物館1階 知の交流コーナー)
1)5月11日(日)13:30〜15:00
山岸宏光:「最近の地図と地理情報システム(GIS)」
2)5月17日(土)13:30〜15:00
国土地理院:「地図と重力」
3)5月24日(土)13:30〜15:00
地徳 力「ライマンはなぜ,開拓峠で道に迷ったか=江戸末期〜明治初期の地形図事情=」
■地質巡検
5月18日(日)13:30〜15:30
「札幌のメムを訪ねる」植物園〜偕楽園〜北大構内
要申し込み、参加費 (保険代 等)大人:500円、 小・中・高:300円
http://www.museum.hokudai.ac.jp/news/article/247/
近畿支部 3.4更新
主催:大阪市立自然史博物館・地学団体研究会・日本地質学会近畿支部
地球科学講演会「プレートの沈み込みと国土形成 −紀伊半島南部のおいたちとジオパーク構想−」
日時:5月25日(日)13:30-15:30
場所:大阪市立自然史博物館 講堂
講師:鈴木博之氏(元同志社大学理工学研究所教授、南紀熊野ジオパーク推進協議会学術専門委員長)
参加費:無料(申し込み不要)
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
西日本支部 4.4更新
主催:熊本県松橋収蔵庫,「地質の日」くまもと実行委員会
共催:日本地質学会西日本支部ほか
「地質の日」企画 “身近に知る「熊本の大地」”
■熊本県松橋収蔵庫 企画展
日時:4月1日(火)〜5月31日(土)(日,祝日を除く)
場所:熊本県宇城市松橋町 熊本県松橋収蔵庫
概要:共催各団体を中心に,松橋収蔵庫展示室にて「熊本の大地」をテーマとした展示を行う。
■体験イベント
日時:5月10日(土)10:00-16:00
場所:熊本県宇城市松橋町 熊本県松橋収蔵庫
概要:松橋収蔵庫学習室にて,展示参加機関等による体験イベントおよび展示説明会を行う。
問い合わせ先:熊本県松橋収蔵庫
Tel (0964)34-3301
三浦半島活断層調査会 4.9更新
クリックするとPDFをダウンロードできます
後援 :一般社団法人日本地質学会
地質情報普及講座 地質の日・記念観察会『深海から生まれた城ヶ島 』
日時:5月10日(土)10:00〜15:00(小雨決行)
集合場所:三浦市城ヶ島
申込締切:4/30 募集人数:50名 参加費:500円(資料代/保険代込)
随時「地質の日」関連の情報を随時ご紹介していく予定です。お楽しみに。
ジオパーク
地質学会はジオパーク、IYPEを積極的に推進しています
地質学会はジオパーク、IYPEを積極的に推進しています
日本地質学会会員の皆さんへ
2008年2月
日本地質学会副会長 伊藤谷生
理事会は,日本地質学会の各支部に対し,学会の事業として最重要課題に位置づけているジオパーク設立推進活動と「地質の日」設置における広報・普及活動への積極的な取り組みを要請いたしました.また,これらの活動が,今年を中心年とするIYPE(国際惑星地球年)への協賛事業ともなるように創意工夫をしていただくことをお願いいたしました. いずれの活動も社会に開かれた一般市民レベルでのものになることと思いますので,各会員におかれましては専門家としてそれぞれのお立場で,これらのとり組みにたいしご理解とご協力をお願いいたします.また,支部の一員として所属支部の支部長・支部幹事会等から提起される諸活動にも積極的に加わっていただき,地質学の普及と振興のためこれらの活動を推進し,盛り上げて下さいますようお願いいたします.以下に各支部宛にお願いしたことがらの要旨を掲載いたします.
1.ジオパークの設立推進について
ジオパークの活動は,地質遺産の保全,それを基にした教育研究普及,さらに地域の経済振興(ジオツーリズムの振興)がその大きな趣旨です.この活動は,地質学に依拠するだけではなく,他の社会的価値といかに結びつけ,地域の発展に寄与・貢献できるかが重要なことです.この活動を推進し発展させることは,地質学者ならびに地質学会の地位向上にも大きく貢献するもので,日本地質学会もその一翼を担う重要な活動です.今年の春には,第三者機関である「日本ジオパーク委員会(仮称)」が立ち上げられる予定です.この委員会では,日本の候補地を世界ジオパークネットワークへ登録するための選定をすることになります.そのための一歩として,日本のジオパークを100程度立ち上げることが当面の目標になりそうです.日本地質学会としては積極的にこの事業に貢献するために,各支部に対し下記の協力要請をいたしました.
1)「地質学会ジオパーク支援委員会(仮称)」への委員の推薦
各支部の代表を中心とした「地質学会ジオパーク支援委員会(仮称)」を新たに理事会の下に設置します.各支部から委員を推薦していただき,具体的な検討を開始いたします.
2)各支部の地域内から,ジオパークの候補地を推薦していただく
候補地の選定は,科学的にもちろんのこと,普及・教育活動を行う場所という点においても重要です.これまで多くの研究者によって蓄積された地域の地質学や資源開発,自然災害や防災,環境問題,生活とサイエンスを結びつける話,資源開発に関わる地元の話を発掘するなど,重要な素材が各地に山積していることでしょう.それらを地質学的現象・地質遺産と絡めて,一般市民の興味をひくストーリーを作ることができるかどうかが,ジオパーク設立への鍵となります.ジオパークは,ジオツーリズムによる普及教育と地域の振興に貢献し,ジオパーク設立支援によって地質学の社会的認知度の向上と地球科学分野の研究発展と人材の確保にもつながることが期待されます.
2.「地質の日」の普及イベント活動について
2007年3月に地質学会や産総研など関係組織が発起人となって,5月10日を「地質の日」とすることを決めました.すでにNews誌等でも案内をしていますのでご覧いただいているものと思います.地質学会をはじめとする「地質の日事業推進委員会」*では,今年の5月10日の「地質の日」に向けて,宣伝のポスター作成や,記念日登録**などの広報活動に取り組んでおります.また,全国の地質関係の博物館などにたいしては,地質の日に関連する行事の企画を呼びかけ,既にいくつかの博物館ではそれに応じた計画が進んでおります.
地質学会としては各支部にたいして「地質の日」の広報・普及活動として,以下のような活動を積極的に行っていただくよう要請いたしました.
*事業推進委員会構成:日本地質学会,日本応用地質学会,日本情報地質学会,日本古生物学会,資源地質学会,日本堆積学会,日本第四紀学会,(独)産総研地質調査総合センター,日本科学未来館,北海道立地質研究所,神奈川県立生命の星・地球博物館,(社)全国地質調査業協会連合会,(社)東京地学協会,(NPO)地質情報整備・活用機構 ,順不同
**すでに記念日登録が完了し,日本記念日協会のWebサイト(http://www.kinenbi.gr.jp/)に掲載されています.
1)5月10日を中心とする,支部としての「地質の日」行事の企画・検討
2)地域の博物館や教育機関からの協力要請にたいしては積極的に応じていただく.
3)地元の博物館や社会教育機関などにたいし,「地質の日」の普及と関連行事等の企画の提案.たとえば,地元の地質百選を活用やジオパークの活動などとセットにした巡検,現場見学,地質相談会,室内での実験.参加型のイベントと合わせた講演会など.
4)「地質の日」の行事企画はWEB(http://www.gsj.jp/geologyday/)や事業推進委員会を通じて紹介.また,独自のサイトがある場合は,地質の日のサイトにリンクを張ることを要請.
3.IYPE事業への参加
国際惑星地球年(International Year of Planet Earth;IYPE)は,国際地質科学連合(IUGS)とユネスコが呼びかけ,2005年12月の国連総会で宣言された,2008年を中心として2007年から2009年を活動期間とするプログラムです.「社会のための地球科学」を標語とし, 災害,資源,健康,気候,地下水,海洋,土壌,地球深部,巨大都市,生命 の10の科学プログラムとアウトリーチプログラムからなります.地質学会も日本IYPE国内委員会に対し,同事業に参加することを表明しました.
各支部に対し,2009年までに実施される支部行事等(ポスター,出版物等)には,IYPEへの参加行事であることを謳い,ポスター,出版物等にはIYPEのロゴマークを積極的に用いることを要請しました.
ロゴマークはWEB(http://www.gsj.jp/iype/index.html)からダウンロードして利用できます.
資 料
■ジオパーク推進活動の現状と今後:日本地質学会ジオパーク設立推進委員会(08.1.21)
■「地質の日」の地域でのイベント企画例:「地質の日」事業推進委員会事務局(07.11.13)
ジオパーク推進活動の現状と今後(08.1.21)
ジオパーク推進活動の現状と今後
2008.1.21
日本地質学会ジオパーク設立推進委員会
ここまでの活動と現状
・ ジオパークの普及活動
➢ 学会:第四紀学会シンポジウム(1月)、地球惑星連合大会ユニオンセッション(5月)、地質学会市民講演会(9月)、日本地理学会シンポジウム(3月予定)
➢ Websiteの整備(日本地質学会Website内)、Q&Aの作成
➢ 新聞取材への対応:朝日新聞科学面(6月)、高知新聞(8月)、北海道新聞(9月)他多数
➢ 地質ニュースジオパーク特集号発行(7月)
➢ 地域のイベントでの講演:山陰海岸(7月)、島原市、有珠洞爺湖(8月)、南アルプス(11月)、島根大学(12月)、高知(1月)、有珠洞爺湖(1月)
・ 興味を示す自治体、博物館などへの情報提供
・ 地域同士の連携を行う連絡協議会の支援(10月4日発起人会、12月26日設立総会GUPIがサポート)
➢ 13地域が連絡協議会に参加
・ 国際会議への出席
➢ 第2回世界ジオパーク会議で発表(06年9月)
➢ アジア太平洋地域ジオパーク会議で発表(07年11月)
➢ ジオパーク国際会議(ドイツ、2008年9月)での各地域の発表を支援
・ 一部地域では具体的な申請に向けた準備を開始
今後の体制
1. 学識経験者、観光業界代表などをメンバーとし、文科省・環境省など関連省庁をオブザーバとする日本ジオパーク委員会の設立
・日本ジオパーク委員会は、ジオパーク候補地域を評価、日本ジオパークネットワーク加盟ジオパークを認定し、世界ジオパークネットワーク申請候補の順位付けを行う予定
2. 地質学会、地理学会、第四紀学会、火山学会などでの支援活動
・ 各学会支援委員会は各ジオパーク、及びジオパークを目指す地域の科学・教育面を支援
3. 連絡協議会の日本ジオパークネットワーク(JGN)への格上げ
・日本ジオパーク委員会が認定した地域が、日本ジオパークとしてネットワークを形成。準備中の地域のオブザーバ参加によるさらなる推進
「地質の日」の地域でのイベント企画例
「地質の日」の地域でのイベント企画例
2007.11.13
「地質の日」事業推進委員会事務局
<巡検・見学会など>
地質百選の見学会
地層見学会の実施(一般向け巡検) (町の中の地学等も含む)
石油,石炭,鉱山,採石場の見学会
建物,構造物を地質の目で見る見学会(ダム・トンネル)(完成,工事中とも)
<体験イベント>
各地の博物館イベント(地質情報展ネタはGSJで助言可能→マニュアル作りが必要か)
→ 化石のレプリカ作り,岩石を割ってみようなど
河原で化石探し
→ 実際に許可を取って地層から掘る場合と河原の礫の中の化石を探す場合等
椀かけによる鉱物探し(ガーネットなど)
→いくつかの強さの違う強力磁石で分離してみるとおもしろい.
お菓子で作る地層・化石・鉱物
塩水の結晶作り(ゆっくりだと日が暮れる,鉱物のでき方)
井戸掘り(ボーリンク?上総掘り?) をやってみる.
→できればボアホールカメラで中を覗くなどもおもしろい
地震を起こしてみよう(油圧プレスによる岩石破壊実験)
紙重ね地質模型を作る
地質鳥瞰図のジグソーパズル
重力計を持って歩く.階段の上り下りで重力が変化することを体験
人工地震で地下を見る(測線を引いてやってみる)
電子顕微鏡で見る微化石(珪藻土)など
砂鉄から(たたら)製鉄
電気石で蛍光灯を光らせる
住宅の地盤の相談会
<出版物>
関連出版物等の発行日を「地質の日」に関連させる
<その他>
全国一斉に同じイベントをやってWEBカメラで中継
記念絵はがきを作り,未来の自分に投稿.10年後に博物館等で開封.
その地域の大きな地質図をはってみる
行ってみよう!! GW・地質の日のイベント特集
行ってみよう!! GW・地質の日のイベント特集
今年から,5月10日が『地質の日』に制定されました。 ゴールデンウィークから「地質の日」にかけて,全国の博物館・大学・関連機関では,地質に関するイベントが盛りだくさん!!
あなたもイベントに参加して,身近な地質を感じてみませんか?
ゴールデンウィーク イベントカレンダー (2008/04/24〜2008/05/11)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
期間中通して行われている特別展示
2008/05/06 現在
地質標本館特別展「青柳鉱物標本の世界」 (茨城県 産業技術総合研究所地質標本館)
期間:3/19(水)〜6/29(日)
場所:産業技術総合研究所地質標本館
すぐれた教育者であった故青柳隆二博士は、学術的にも価値の高い鉱物コレクションを構築されました。そして、このコレクションが青少年や市民に鉱物の楽しみを伝えるために永く活用される事を願い、鉱物学の専門家による標本管理体制をもつ地質標本館に全標本を寄贈されました。青柳博士の生前のご努力と高い志を称え、ここに特別展「青柳鉱物標本の世界」を開催いたします。
ダーウィン展 (東京都 国立科学博物館)
期間:3/18(火)〜6/22(日)
場所:国立科学博物館
ダーウィンの人生をたどりながら、彼が生み出した偉大な業績に迫る展覧会です。会場では、ダーウィンの進化論の着想のもとになったガラパゴス諸島の生物のはく製から、航海に使った「ビーグル号」の模型、航海日誌、身の回りの品々など、様々な資料を展示します。
新市域紹介コーナー「地質図に見る津久井地域の地質」(「地質の日」協賛事業) (神奈川県 相模原市立博物館)
期間:3/22(土)〜7/13(日)
場所:相模原市立博物館常設展示室新市域紹介コーナー
相模原市津久井地域の地質が地質図上でどの様に表現されているのかを地質図を展示して紹介します。
特別展「ようこそ恐竜ラボへ!〜化石の謎をときあかす〜」 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
期間:3/15(土)〜6/29(日)
場所:大阪市立自然史博物館ネイチャーホール
モンゴル科学アカデミーと恐竜共同調査を行っている林原自然科学博物館の全面的な協力を得て、「化石を発掘・調査し、新しい事実を見つけ、復元する」恐竜研究のプロセスに焦点をあて、内容を構成しています。また、日本初公開を含む化石標本・大型植物食恐竜のサウロロフスやコリトサウルス、エドモントニア、肉食恐竜のバリオニクス、アロサウルスの全身骨格化石、デイノニクスの復元模型などを展示します。恐竜研究のプロセスをテーマとした本格的な展覧会は日本で初めてのことです。
丹波恐竜二次発掘速報展 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
期間:4/20(日)〜6/01(日)
場所:兵庫県立人と自然の博物館
2008年1月〜3月に実施された、丹波産恐竜化石発掘のようすと、得られた恐竜化石(実物・レプリカ)を展示します。
部門展示「和泉層群の化石」 (徳島県 徳島県立博物館)
期間:4/01(火)〜7/06(日)
場所:徳島県立博物館部門展示室(常設展示室内)
和泉層群は、中央構造線の北側にそって細長く分布する中生代白亜紀後期(約8000〜7000万年前)の地層です。この地層は主に海底で堆積した礫岩、砂岩、泥岩からなり、ところどころに酸性凝灰岩をはさんでいます。特に北縁部の泥岩が発達する地層からは、アンモナイトや二枚貝、巻貝などの化石が多く産出します。今回の展示では、化石愛好家から寄贈をしていただいた資料を中心に、四国、淡路島、大阪南部と地域別に産出する化石を紹介します。
トピックコーナー:「地質の日」関連展示 地質調査と地質図 (徳島県 徳島県立博物館)
期間:4/01(火)〜6/01(日)
場所:徳島県立博物館トピックコーナー(常設展示室内)
「地質の日」に関連して、徳島およびその周辺地域の地質図を展示するほか、地質調査につかう道具も併せて紹介します。
地質図類パネル展示 (東京都 産総研地質調査総合センター・経済産業省知的基盤課)
期間:4/14(月)〜5/12(月)
場所:経済産業省 本館 ロビー
産総研が100年以上にわたって作成してきた地質図と最新シームレス地質図、化石・鉱物標本の展示。
「地質の日」展 (北海道 日本地質学会北海道支部、日本応用地質学会北海道支部、北海道大学総合博物館)
期間:4/29(火)〜6/1(日)
場所:北海道大学総合博物館3階:札幌市北区北10条西8丁目
ライマンとその弟子たちの活躍を通じて、北海道の地質学および鉱業の発達を紹介するとともに、北海道や札幌周辺の地質と生い立ちを紹介します。
ぽけっと企画展「地球と生命」(福岡県 北九州市立自然史・歴史博物館(いのちのたび博物館))
期間:5/10〜
場所:北九州市立自然史・歴史博物館 ぽけっとミュージアムNo.1
自然の変化に対応してきた,絶えることのない生命の継続性と神秘性を化石や自然史資料を用い紹介します。
期間中のイベント
2008/05/06 現在
日付
イベント
4/24
(木)
4/25
(金)
4/26
(土)
三葉虫をさがせ!化石採集教室 (栃木県 葛生化石館)
場所:佐野市内
葛生石灰岩からは、三葉虫が産出しています。市内の鉱山や山林に行って三葉虫の化石を探します。見つけた三葉虫は夏の企画展で展示予定です。その他古生代ペルム紀の化石も見つかります。たくさん化石を見つけよう。
ホームページで確認の上、電話又はe-mailにてお申込ください。
野外観察と室内実習 「境川遊水地 化石ウォッチング」 (神奈川県 神奈川県立生命の星・地球博物館)
場所:神奈川県立境川遊水地公園(横浜市)と神奈川県立生命の星・地球博物館
1日目は境川遊水地で講義と地層の観察や化石採取をし、2日目は博物館で採取した貝化石の整理をします。貝化石の一部は博物館の標本として保管します。
対象:小学4年生〜中学生と保護者、教員
4/27(日)まで
遠山川の変化・青崩峠の地震跡 (長野県 伊那谷自然友の会)
場所:飯田市南信濃
地震崩れや洪水で変化してきた遠山川の河川環境と、享保遠山地震(1718年)で崩れた青崩峠の痕跡を探る。案内:松島信幸さん
前日までに美術博物館村松へ(0265-22-8118)お申し込み下さい。
企画展「穂別のいろいろ化石展」 (北海道 むかわ町立穂別博物館)
期間:4/26(土)〜5/25(日)
場所:むかわ町立穂別博物館 特別展示室
穂別で見つかった、色々な化石を紹介します。アンモナイトやクビナガリュウのほか、様々な貝化石、ウニ、ウミユリ、サンゴ、スナモグリ、植物の化石などなど。
その他:連休中(4/26、27、29、5/3、4、5、6)と「地質の日」付近(5/10、11)は、学芸員による展示解説を予定しています。
「地質の日」記念事業『地質図』展 (栃木県 葛生化石館)
期間:4/26(土)〜6/01(日)
場所:葛生化石館企画展示室
皆さんは「地質図」という地図があるのをご存知でしょうか?地質学者ライマンらによって日本で最初の地質図が刊行された日を記念して、5月10日『地質の日』が制定されました。化石館でも、これを記念して地質図展を開催します。身近だけど意外と知らない私たちの足元、地面の下をのぞいてみませんか?
収蔵展示「『ナウマンゾウとマンモスゾウ」 (長野県 野尻湖ナウマンゾウ博物館)
期間:4/26(土)〜7/06(日)
場所:野尻湖ナウマンゾウ博物館3階
野尻湖ナウマンゾウ博物館で収蔵しているアラスカ産のマンモスの化石や、長野県を中心とした野尻湖以外のナウマンゾウの化石(レプリカ)を展示します。
追手町小学校化石標本室公開 (長野県 飯田市美術博物館)
期間:4/26(土)〜4/27(日)
場所:追手町小学校化石標本室(飯田市美術博物館から徒歩5分)
飯田市千代出身の長谷川善和先生が採集した標本を中心に展示
4/27
(日)
野尻湖探検−野尻湖自然観察会(ゾウの小道を歩こう)− (長野県 野尻湖ナウマンゾウ博物館)
場所:野尻湖周遊道路
時間:9:00〜15:00
小学生〜一般向けの自然観察。講師は当館学芸員。
はがきかファックス(026-258-2090)で、氏名(よみがな)・学年・保護者名・住所・電話番号を明記の上、お申し込み下さい。
申し込み締め切りは4月26日です。定員になり次第締め切ります。
追手町小学校化石標本室公開イベント 化石クリーニング (長野県 飯田市美術博物館)
場所:追手町小学校化石標本室(飯田市美術博物館から徒歩5分)
時間:10:00〜16:00
阿南町で採取された富草層群の貝やサメの歯などを含む岩塊を割って化石を探す。講師:小泉明裕(飯田市美術博物館)
部門展示「和泉層群の化石」展示解説 (徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島県立博物館部門展示室(常設展自室内)
時間:14:00〜14:30
開催中の「和泉層群の化石」の展示解説を行います。
4/28
(月)
4/29
(火)
昭和の日
4/30
(水)
5/01
(木)
企画展「小僧石大集合」(仮称) (静岡県 奇石博物館)
期間:5/01(木)〜5/31(土)
場所:奇石博物館企画展示室
現地調査において得られた青森県産の結核状の奇石“津軽小僧”の情報を中心に、高師小僧、黄土小僧など「小僧」と名付けられた同様の奇石を集め、それらの成因等に触れながら紹介する。
5/02
(金)
5/03
(土)
憲法記念日
「春の地形地質観察会」 (神奈川県 神奈川県立生命の星・地球博物館)
場所:神奈川県立相模原公園周辺(相模原市)
時間:10:00〜16:00
県立相模原公園周辺を中心に相模原左岸の河岸段丘地形を歩きながら観察します。途中、関東ローム層の観察も行う予定です。
対象:小学生〜大人
城下町飯田の水・道・断層 (長野県 伊那谷自然友の会)
場所:飯田市旧市街地〜上飯田
トレンチサイトの見学と城下町飯田をつくった井水や道を観察する。案内:松島信幸さん
前日までに美術博物館小泉へ(0265-22-8118)お申し込み下さい。
丹波竜フェスティバル2008・展示「丹波竜と過去からのメッセージ」 (兵庫県 NPO西日本自然史系博物館ネットワーク)
期間:5/03(土)〜5/05(月)
場所:兵庫県丹波市山南住民センター
NPO西日本自然史系博物館ネットワークと共催で、7館(人と自然の博物館、大阪市立自然史博物館、和歌山県立自然博物館、徳島県立博物館、きしわだ自然資料館、富山市科学博物館、島根県立三瓶自然館)が協力して恐竜とそれに関係した化石・岩石の展示をします。
サイエンスサタデー「砂と火山灰を観察しよう」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館実験室
時間:14:00〜15:00
砂や火山灰の性質などについて、観察します。
当日会場で直接お申込みください。(受付時間13:30から14:00)
5/04
(日)
みどりの日
追手町小学校化石標本室公開 (長野県 飯田市美術博物館)
期間:5/04(日)〜5/06(火)
場所:追手町小学校化石標本室(飯田市美術博物館から徒歩6分)
飯田市千代出身の長谷川善和先生が採集した標本を中心に展示
やってみよう!さわってみよう!「石を割ってみよう/砂つぶからミニ宝石をさがそう」 (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館1階入り口・1階ホール
時間:10:00〜16:00
岩石ハンマーを使って石を割る体験を行います。また、砂つぶの中から顕微鏡を使ってミニ水晶やミニガーネットを探します。
追手町小学校化石標本室公開イベント 化石レプリカ作成 (長野県 飯田市美術博物館)
場所:追手町小学校化石標本室(飯田市美術博物館から徒歩5分)
時間:10:00〜16:00
恐竜の歯やアンモナイトなどの型を作り石膏を流しいれてレプリカを作る。
講師:小泉明裕(飯田市美術博物館)
5/05
(月)
こどもの日
海の生き物たんけんツアー (愛知県 蒲郡情報ネットワークセンター・生命の海科学館)
場所:生命の海科学館・竹島海岸
時間:10:00〜15:00
化石を観察して進化について学び、野外で生物観察をします。
やってみよう!さわってみよう!「1000万年前のミニ化石を探そう」 (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館1階入り口・1階ホール
時間:10:30〜15:00
1000万年前の海底にたまった岩石から、小さな貝やサメの歯の化石を探します。
追手町小学校化石標本室公開イベント 化石クリーニング (長野県 飯田市美術博物館)
場所:追手町小学校化石標本室(飯田市美術博物館から徒歩5分)
時間:10:00〜16:00
阿南町で採取された富草層群の貝やサメの歯などを含む岩塊を割って化石を探す。
講師:小泉明裕(飯田市美術博物館)
ひとはくセミナー (1)丹波の恐竜化石第二次発掘報告会 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:人と自然の博物館・セミナー室
時間:13:30〜14:30
2006年に丹波市で発見された恐竜の化石は、国内で発見された恐竜化石の中では最も保存が良いものです。巨大な骨格が硬い岩盤の中に埋まっているため、数次にわたる発掘が必要と考えられています。今回は最新の第二次発掘の成果について報告します。
小学生高学年〜一般を対象とした、申込み制、有料のセミナーです。
5/06
(火)
振替休日
追手町小学校化石標本室公開イベント 化石レプリカ作成 (長野県 飯田市美術博物館)
場所:追手町小学校化石標本室(飯田市美術博物館から徒歩5分)
時間:10:00〜16:00
恐竜の歯やアンモナイトなどの型を作り石膏を流しいれてレプリカを作る。
講師:小泉明裕(飯田市美術博物館)
ひとはくセミナー (2)化石のレプリカをつくろう! (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:人と自然の博物館・セミナー室
時間:13:30〜15:30
本物の化石から自分でとった型に石膏を流し込んでレプリカ(複製標本)をつくってみませんか?できたレプリカはお持ち帰りできます。
小学生高学年〜一般を対象とした、申込み制、有料のセミナーです。
5/07
(水)
5/08
(木)
地質調査総合センター 第12回 シンポジウム 〜地下水と岩石物性との関連の解明〜産総研のチャレンジ〜 (東京都 産総研地質調査総合センター)
場所:秋葉原ダイビル 5階カンファレンスフロア5B会議室
時間:13:00〜17:30
受付は終了いたしました。(当日分に若干の余裕があります。詳細はWebページよりお問い合わせ下さい。)
5/09
(金)
5/10
(土)
地質の日
自然観察会「城ヶ島の地層」 (神奈川県 横須賀市自然・人文博物館)
場所:神奈川県三浦市城ヶ島
城ヶ島に見られる地層や断層、堆積構造、地形などを観察しながら、三浦半島の成り立ちと、ダイナミックな地球の姿について考えます。
地質の日記念行事、2008年『国際博物館の日』記念事業、三浦半島活断層調査会共同事業。定員40名。
「地質の日」記念講演会「“日本地質学発祥の地”秩父・長瀞と地質研究史・観察会「岩畳の地質を訪ねる」 (埼玉県 埼玉県立自然の博物館・地質の日推進事業委員会)
場所:埼玉県立自然の博物館+名勝天然記念物「長瀞」岩畳付近
地質の日を記念して講演会と観察会を行います。午前中の講演会は、秩父地域の地質学史について館長が講演します。午後は、岩畳の地質観察を行います。
みんなの観察会「日本の地質百選観察会1 犬吠埼」 (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県銚子市
時間:10:00〜16:00
平成19年に「日本の地質百選」の1つに選ばれた銚子市犬吠埼周辺の地質について観察します。
房総の山の観察会「小糸川を歩く」 (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県君津市
時間:9:00〜16:00
連続の観察会です。小糸川に沿って源流をめざして歩き、周辺の自然や文化を学びます。
地すべり地帯の山と暮らし (長野県 伊那谷自然友の会)
場所:伊那市高頭町芝平
現地に住んでいた方から、三波川帯の高所緩斜面に広がる芝平地区(廃村)の生活をお聞きし、地すべり地帯の暮らしを学ぶ。案内:明石浩司さん
前日までに美術博物館村松へ(0265-22-8118)お申し込み下さい。
ひとはくセミナー 多紀アルプス自然探訪 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:兵庫県篠山市
時間:9:30〜16:00
多紀アルプスの主峰、三嶽・西ヶ嶽の凸凹した稜線を巡ります。シャクナゲの花や多彩な新緑を楽しみながら、地質構成と地質構造の遠望を通して太古のロマンに迫ります。登山の前に栗柄で竹田川と宮田川の谷中分水界にズームイン。健脚向きのコースです。
小学校高学年〜一般を対象とした、申込み制、有料のセミナーです。
トピック展示「『地質の日』制定記念〜日本最古の東北地方地質図〜」 (岩手県 岩手県立博物館)
期間:5/10(土)〜5/25(日)
場所:岩手県立博物館「いわて自然史展示室」
ドイツ人地質学者ナウマンが明治19年に作成した『予察地質図東北部』を紹介します。
「海牛化石のクリーニング作業の公開」 (新潟県 長岡市立科学博物館)
期間:5/10(土)〜5/10(土)
場所:長岡市立科学博物館自然展示室
長岡市立科学博物館では、5月5日〜18日(7日は休館)の期間、「海牛化石速報展」を開催します。これは、平成16年新潟県中越地震による災害復旧工事現場から発掘された海牛の化石についてのこれまでの研究成果を展示・解説するものです。「地質の日」には、この海牛化石のクリーニング作業をご覧頂くことができます。
「日本蝦夷地質要略之図」展示 (茨城県 産総研地質調査総合センター)
期間:5/10(土)〜5/10(土)
場所:産総研つくば 第7事業所 本館 1Fロビー
地質の日の由来となった日本で最初の広域的な地質図「日本蝦夷地質要略之図」(1876年発行)の展示。
つくばフェスティバル ブース展示 〜つくばの地盤と筑波山の地質を知ろう〜 (茨城県 産総研地質標本館(つくば市との共同企画))
期間:5/10(土)〜5/11(日)
場所:つくばセンター
時間:12:00〜17:00
サイエンスサタデー「砂と火山灰を観察しよう」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館実験室
時間:14:00〜15:00
砂や火山灰の性質などについて、観察します。
当日会場で直接お申込みください。(受付時間13:30から14:00)
サイエンスフェスティバル −化石やきれいな石にさわろう− (新潟県 新潟大学・新潟県立自然科学館・NPOジオプロジェクト新潟)
場所:新潟大学理学部前庭〜同サイエンスミュージアム
時間:10:00〜15:00
化石クリーニング、化石レプリカ作成、宝石探し、鉱物展示(販売もあり)、サイエンスミュージアムガイドツアーほか。
入場料:無料(ただし、コーナーによっては、材料費が100円〜200円程度必要です。)
地質の日記念イベント 「黄鉄鉱ひろい」 (茨城県 産総研地質標本館)
場所:地質標本館
時間:10:00〜15:30
白い粘土を水の中で洗い流しその中から金色の黄鉄鉱の結晶をみつけます。小粒ですがきれいな結晶をさがすことができます。
つくばフェスティバル 〜センター街の石を探す探検ツアー・飛び出す火山のペーパークラフトをつくろう〜 (茨城県 産総研地質標本館(つくば市との共同企画))
場所:つくばセンター
時間:12:00〜18:00
見て!触れて!新発見!!海と地球の研究所」JAMSTEC横須賀本部施設一般公開 (神奈川県 独立行政法人海洋研究開発機構(JAMSTEC))
場所:独立行政法人海洋研究開発機構 横須賀本部 (京浜急行 追浜駅下車 無料送迎バス有り)
時間:9:30〜16:00
有人潜水調査船「しんかい2000」コックピット見学会、海洋調査船「かいよう」の体験乗船、海洋調査船「かいよう」一般公開、公開セミナー(国際科学年、地球温暖化、最先端海中ロボット、「ちきゅう」南海掘削報告)、シーサバイバル実演、ロープワーク講習、水中ロボット操縦体験、子ども向け実験など、楽しいイベントをたくさん用意しています。
『第8回研究交流会』 「小笠原諸島 −海洋島の生態系と植物−」 (鹿児島県 鹿児島大学総合研究博物館)
場所:鹿児島大学郡元キャンパス 総合教育研究棟2階
時間:13:30〜16:00
小笠原諸島で、植物多様性の把握や固有種の自生地保全にかかわってきた研究者が、その経験や発見を語ります。
講師:加藤 英寿(首都大学東京助教)、下園文男(元東京大学小石川植物園育成部主任)
地質学講座「地質図入門〜相模野台地編〜」 (神奈川県 相模原市立博物館)
場所:相模原市立博物館実習実験室、道保川公園(相模原市)、県立相模原公園周辺(相模原市)
相模野台地を例に地質図を読みとるために必要な地質学の基礎を学習し、初歩的な地質図の読み取り方、作り方を学習します
参加は原則として相模原市内在住もしくは在勤が条件です。
「地質の日」記念イベント!! (京都府 京都大学総合博物館)
場所:京都大学総合博物館 ミューズ・ラボ
時間:10:00〜15:00
「インドネシア・ジャワ島における鍾乳石研究 〜石から探る、昔の天気」・「瀬戸内海からゾウがでた? 網にかかったナウマンゾウ」などのレクチャーや、ポスター展示と解説を行います。
また、「地質学」を作り上げたライエル、スミス達の古典的名著や地質図など京大所蔵の世界的にも重要な書物も公開します。
「つくばの地質」展示・説明会 (茨城県 産総研地質調査総合センター)
場所:産総研つくば 第7事業所 本館 1Fロビー
時間:9:30〜19:00
つくば市と隣接する地域の地質についての説明会を開催します。地質を知って、安心安全なつくばライフをおくりませんか?産総研の研究者と茨城県地質調査業協会の専門家が地質について分かりやすくご案内いたします。
[主な展示]つくば市とその周辺の大きな地質図と地下を表す断面図。つくば市周辺の平地を作る地層。つくば市の地下を掘って取り出した地層。
第25回地球科学講演会「石油天然ガス資源をめぐる私たちの将来」 (大阪府 大阪市立自然史博物館、地学団体研究会大阪支部、日本地質学会近畿支部、日本堆積学会)
場所:大阪市立自然史博物館 講堂
時間:14:30〜16:30
地質時代の生物遺骸が地下深部の地層中で姿を変えた石油や天然ガスは、近い将来、枯渇する運命にあります。また、今のように使い続ければ地球環境に大きな変化をもたらすでしょう。石油天然ガス資源の成立と利用の実態を概観し、今私たちのおかれている立場について科学的に考えて見ます。
講師:荒戸裕之氏(帝国石油(株)国内本部開発部部長、石油地質学・シーケンス層序学)
地質技術伝承講習会 地質技師長が語る地質工学余話シリーズ 第2回 「海上空港の地質」 (東京都 日本地質学会関東支部)
場所:国立科学博物館 日本館 4階 大会議室
時間:14:00〜16:00
この数十年間,わが国の社会基盤施設(道路・鉄道・空港・都市施設・ダム・地すべり施設など)は著しく整備されてきました。これら施設の建設にあたり,応用地質学もまた大きな役割を果たしてきました。今,これら応用地質学を支えてきた地質技術者から地質技術伝承の講習会を開催いたします。
「知られざるシレトコ‐知床半島の地質‐」 (北海道 日本地質学会北海道支部)
場所:北海道大学高等教育機能開発総合センター S1教室:札幌市北区北17条西8丁目
時間:15:15〜17:00
知床半島の形成史とそこで起こる地質災害、火山災害について、以下の講演を行います。
1.知床半島の生い立ちと世界自然遺産:合地信生(斜里町B&G海洋センター)2.知床の地形にみる斜面の変動と災害:伊藤陽司(北見工業大学) 3.雁行配列した火山列,知床半島‐国後島‐択捉島の火山の地質と災害:中川光弘(北海道大学)
5/11
(日)
活断層を歩くシリーズ3「生駒断層」 (大阪府 大阪市立自然史博物館・NPO大阪自然史センター)
場所:東大阪市方面
生駒山を大阪側から登りながら、活断層がつくる地形と、生駒山の地質を観察します。
ファミリー自然観察会「地質の宝庫:下仁田探検」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:西牧川(下仁田町)周辺
時間:9:30〜12:30
下仁田町で見られる様々な地層や岩石を観察します。
2週間前までに封書で申込み下さい。
新緑の富士山自然観察会 (静岡県 奇石博物館)
場所:富士山西臼塚
富士山西臼塚に整備した自然観察路「自然の小径」を巡りながら、当館が作成したガイドブックを参考に富士山の火山地質や植物の観察を行う。
電話(0544-58-3830 )にて受付いたします。(定員30人)。
5/12(月)まで
みんなの観察会「博物館周辺の地形・地質たんけん」 (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県千葉市
時間:10:00〜15:00
下総台地に見られる地形や地質について、人間による改変も含めて、博物館周辺を例に観察します。
野外自然かんさつ 白亜紀の地層見学(勝浦町) (徳島県 徳島県立博物館)
場所:勝浦郡勝浦町
時間:13:00〜16:00
白亜紀の地層を観察して、化石を発見しよう!
山陰海岸「地質の日」見学会 (兵庫県 日本地質学会近畿支部・山陰海岸ジオパーク推進協議会)
場所:山陰海岸国立公園
時間:9:30集合 16:00解散予定
山陰海岸国立公園が位置する地域で現在ユネスコが認定するジオパークの認証へ向けた準備が進められています.山陰海岸の自然をより理解し,それを多くの方々に伝えるネットワークへと発展できればと考えています.
ひとはくセミナー春の石めぐりハイキング−二上山− (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:奈良県葛城市
時間:10:00〜16:00
奈良と大阪の境にある二上山で、ガーネットの入った安山岩、サヌカイト、凝灰岩などを観察します。
小学校高学年〜一般を対象とした、申込み制、有料のセミナーです。
つくばフェスティバル 〜砂で遊ぼう〜 (茨城県 産総研地質標本館(つくば市との共同企画))
場所:つくばセンター
時間:10:00〜17:00
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ内のフォームまたはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。随時、情報を更新いたしますので,ご協力をお願いいたします。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
「地質の日制定記念 サイエンスフェスティバル−化石やきれいな石にさわろう−」
「地質の日制定記念 サイエンスフェスティバル−化石やきれいな石にさわろう−」速報
栗原 敏之(新潟大学大学院自然科学研究科博士研究員)
新潟大学では、「地質の日」の5月10日(土)に「サイエンスフェスティバル−化石やきれいな石にさわろう−」を開催しました。会場となった理学部には、小学生と保護者を中心とする約450名が詰めかけました。毎年行われている大学祭を除けば、このようなイベントが大学で行われることはまれですが、予想をはるかに上回る人出と子供たちの熱気に正直驚かされました。以下では、会場の催し物の写真を交え、当日の様子を紹介します。なお、アンケート結果などを含めた、より詳しい報告は日本地質学会Newsに投稿する予定です。
写真1:メイン会場の様子.化石のクリーニングやレプリカ作りが行われた会場です.
今回のイベントでは、「地質の日」制定記念イベント実行委員会(委員長:宮下純夫)が実施母体として立ち上げられ、大学内では理学部地質科学科、自然環境科学科、教育学部地学、災害復興科学センターが、学外ではNPO法人ジオプロジェクト新潟、新潟県立自然科学館および地団研新潟班が実施組織として関わりました。当日は、スタッフとして教員、学部生・院生等合わせて約50名が参加しました。
多くの参加者に来てもらうためには、広報活動が重要になってきます。今回は、昨年度から地域連携型の普及事業を通して関係を深めてきた新潟市西区政策企画課の協力を得て、区内18小学校の全生徒約8500名に案内のちらしを配布しました。その他、大学の公式サイトやジオプロジェクト新潟のホームページにも案内が掲載され、それらを見て来場した大学関係者も少なくなかったようです。
会場としては、理学部内のメイン会場のほか、2007年にオープンした理学部サイエンスミュージアムも活用されました。午前10時の開場を待たずして参加者が集まり始め、ピークとなった11時過ぎには、人気ブースの前は長蛇の列となってしまいました。イベントはお昼をはさんで午後3時まで行われましたが、昼食には生協の食堂などが利用され、大学の雰囲気を楽しまれた家族連れの方も多かったようです。
写真2:地球のパズルに挑戦! お兄さんがわかりやすく解説してくれました.
当日行われた催し物は、化石や鉱物など小学生にも親しみやすいものから、地質学の専門的な内容をわかりやすく遊びながら解説しようというもの、さらに中越地震のパネル展示まで、多方面の内容に及びました。例えば、化石のレプリカ作成・クリーニング、恐竜のペーパークラフト・塗り絵、微化石の観察、岩石薄片の観察、プレート運動のパズル、鉱物展示、火山岩変成岩の展示、液状化の実験、生痕の観察、堆積構造形成実験、中越地震のパネル展示、サイエンスミュージアムのガイドツアー、岩石を割ってみよう、などです。これらのいくつかは、地質科学科の学生が運営するグループ(自主ゼミと呼ばれる)によって発案されたもので、学生たちの自由な発想と行動力が存分に発揮されていました。
実のところ、多くても100人というあたりが、開催前の来場者数の予想でした。様々な反省点はあるのですが、なんといっても、子供たち、そして大人たちもが潜在的にもっている地学への興味というものを、400人からが発するパワーとして直に感じられたというのは、きわめて大きな収穫であったと思います。スタッフとして参加した学生・院生からも「地質学の未来は明るいですね!」という声が上がったほどで、子供たちから逆に元気をもらったと言えるのかもしれません。
写真3:石捨て場も宝の山?? 色々な岩石や鉱物を見つけました.
この企画と平行して、新潟県内の地学普及ネットワークの構築を目指した「新潟地学教育・普及連携協議会(仮称)」の設立が進められております。そして来年以降についても、さらなる戦略的な取り組みが検討されています。「地質の日」は確実に私たちの意識を変えました。そして今回の取り組みが、今後どこに波及し、どのような展開へとつながっていくのか、非常に楽しみであります。
宮沢賢治ジオツアー 地質の日イベント
宮澤賢治ジオツアー
釜淵の滝(童話「台川」の舞台).滝の露頭は凝灰岩.
写真1 イギリス海岸近くの北上川河岸での説明.当時は河床に泥岩の露頭があったそうですが,現在は水量が多くて水没している.
写真2 賢治が花巻農学校教員を退職して,農民指導のために設立した羅須地人協会(花巻農業高校内に移築されている)の見学.建物の中も見学できるそうなのですが,たまたま鍵がかかっていて外からの見学になりました.
写真3 羅須地人協会の跡地.現在は「雨ニモマケズ」の詩が刻まれたスレートの詩碑が立つ.葉の白く光っているギンドロ(ウラジロハコヤナギ)の木の説明を聞いているところ.
5月10日の地質の日を記念して,5月17-18日にNPO地質情報整備・活用機構が企画した宮澤賢治ジオツアーに参加して来ました.
旅行の手配は地質ツアー専門の(有)ジオプランニング,案内者は元地質学会副会長で「宮澤賢治の地的世界」の著者である加藤碵一会員です.全28人のうち 案内者・主催者・地質関係者は1/3で,2/3が宮澤賢治ファンの参加者でした.首都圏を中心に,関西や北九州からの参加もあり,賢治ファンの方々は新聞 の行事欄に紹介されたお知らせをみて参加を申し込んだそうです.
第一日目は新花巻駅に集合し,花巻市内を山猫軒(レスト ラン),宮澤賢治記念館,イギリス海岸,羅須地人協会(花巻農業高校),宮澤賢治詩碑を巡り花巻温泉へ(泊).第二日目は花巻温泉近くの釜淵の滝,幣懸 (ぬさがけ)の滝,南昌山,小岩井農場,岩手大学農業資料館,盛岡城址と見学.このように,宮澤賢治に関する学説や著作の中に登場する鉱物・岩石・地質の 説明を聴きながら賢治の足跡をたどり,童話や詩に登場する場所をめぐるという旅行でした.参加者には,賢治の童話にでてくる5種類の岩石の説明とサンプル プレゼントが産総研地質標本館の青木会員からありました,一番人気はメノウでした.宮澤賢治の著作は春と修羅(詩集)しか読んだことのなかった私(それも 30年以上前)にとっては,宮澤賢治ファンの方々との交流はなかなか刺激的な体験でした.
参加者の方の感想等は,地質学会ニュース誌に投稿予定です.
(山形大学 大友幸子)
写真4 写真3の左に見える詩碑.高村光太郎により刻まれたもので,後で間違い部分が修正されている.
『地質の日記念事業 三葉虫をさがせ!化石採集教室』
『地質の日記念事業 三葉虫をさがせ!化石採集教室』(佐野市葛生化石館)
栃木県葛生地域は「地質の日」当日は残念ながら雨となってしまい、化石採集教室は中止となってしまいました。しかし、来館してくれた参加者の方向けにレプリカつくり体験教室を開催。雨にも負けず参加してくれた方たちは一生懸命作った自分だけのレプリカを笑顔で持ち帰って行きました。
地学オリンピック 代表決定
大会派遣代表決定
試験前の控え室風景
実技試験風景(顕微鏡観察)
大会派遣代表決定! 5月31日(日)東京大学で行われた第二次選抜試験は、1名の辞退者を除いた20名で競われ、無事終了いたしました。厳正なる審査(実技と面接)の結果、8月31日-9月8日のフィリピン大会への派遣代表は以下の4名に決定いたしました。
日野愛奈 愛媛県立松山南高等学校 3年
平島崇誠 石川県立金沢泉丘高等学校 2年
森里文哉 香川県立丸亀高等学校 3年
雪田一弥 青森県立青森高等学校 3年
代表生徒は 6−8月の通信研修、8月の合宿研修を経て、国際大会に臨みます。ご声援よろしくおねがいいたします。
なお、来年度の台湾大会の募集は2008年10月1日より12月10日までです。一次試験は12月21日、二次試験は2009年3月29日を予定しております。
地学オリンピック目次に戻る
地学オリンピック目次
日本地質学会地学オリンピック支援委員会
基本情報
地学オリンピックとは
クリックすると大きな画像がご覧いただけます。
国際地学オリンピック(International Earth Science Olympiad; IESO)は、国際地質科学連合(IUGS)の下部組織、Commission on Geoscience Education, Training and Technology Transfer (COGE)がその活動を支援するInternational Geoscience Education Organization (IGEO) の主要活動として創設された高校生のための地学コンペティションです。IGEOには、アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、ドイツ、イギリス、韓国、日本など世界22カ国が加盟しており、国際的な地学教育の普及と向上を主要目標にしています。
(国際地学オリンピック日本委員会より)
日本地質学会の取り組み
地質学会では、平成19年2月からその活動を開始した地球惑星科学連合地学オリンピック小委員会の副委員長に久田理事を選出し、小委員会と地質学会との関係を密にしてまいりました。また地質学会地学教育委員会から推薦を受けました香束小委員会委員が、平成19年10月に韓国で開催されました第1回国際地学オリンピック大会の視察団の一員として参加いたしました。視察団帰国後、国際地学オリンピックに正式参加することは、わが国の将来を担う若人の地球惑星科学的な意識を高めるとともに、国際的な視野を広める上で大変有意義であるとの小委員会の認識と一致し、地質学会は協賛団体として積極的な支援を行うことを決定いたしました。現在小委員会は解散し、国際地学オリンピック日本委員会となっております。同委員会の組織委員会委員には、平元会長、斎藤元会長、木村前会長、佃現副会長が就任しております。また久田理事は運営委員長、伊藤孝会員、萬年会員、小泉会員、田中義洋会員は運営委員に就任しております。
■ 日本地質学会 地学オリンピック支援委員会(2024年6月現在)
本委員会は、2012年8月26日〜9月2日に筑波研究学園都市にて実施された国際地学オリンピック日本大会を始め、毎年開催される日本地学オリンピック大会を支援する目的で発足しました。本支援委員会の活動を通して国際地学オリンピックに関わる地学教育動向を国内に伝えたり日本の動向を発信しています。
問い合わせ先:geo-olympia[@]ml.geosociety.jp(@マークは半角にして下さい)
委員会メンバー→こちらから
■ 地学オリンピック支援委員会_議事録
第20回議事録(2025.3.22実施)NEW
第19回議事録(2024.3.23実施)
第18回議事録(2023.4.1実施)
第17回議事録(2022.3.26実施)
第16回議事録(2021.3.20実施)
第15回議事録(2020.3.29実施)
第14回議事録(2019.3.30実施)
第13回議事録(2018.3.24実施)
第12回議事録(2017.1.9実施)
第11回議事録(2016.5.22実施)
第10回議事録(2016.1.9実施)
第9回議事録(2015.1.10実施)
第8回議事録(2014.1.11実施)
第7回議事録(2013.5.19実施)
第6回議事録(2013.1.12実施)
第5回議事録(2012.9.15実施)
第4回ML議事録(2012.4.8-28実施)
第3回議事録(2012.1.21開催)
第2回議事録(2011.5.22開催)
第1回議事録(2010.12.15開催)
国内選抜・募集
第2回国際地学オリンピック国内選抜実施・募集
第2回国際地学オリンピック(国際大会)の開催が決まりました。
日程:2008年8月31日から9月7日までの8日間
場所:フィリピン共和国
<一次選抜>
募集期間:2月1日から2月29日
対象者: 国際大会に参加可能な高校生・中学3年生および相当学年の生徒
日時: 3月16日(日)(10:00-12:00)
場所: 原則として参加者の所属する高等学校等にて実施
地学オリンピック目次に戻る
参加募集に354名応募!
参加者募集に354名応募!
2008年8月31日から9月7日までフィリピンで開催される第2回国際地学オリンピックに派遣する高校生日本代表団4名を選抜するための試験(国際地学オリンピック日本委員会主催、地球惑星科学連合共催)に、日本全国から354名の応募がありました(25都道府県の44高等学校・中学校)。この354名の中には、中学3年生が15名、チャレンジする中学2年生4名なども含まれています。 地学オリンピック事務局では予想をはるかに上回る応募に嬉しい悲鳴をあげており、参加賞として用意していたボールペンを急遽追加注文することになりました。なお一次選抜として3月16日に在籍高校で筆記試験が実施され約20名が、二次選抜として5月31日に東京大学で実技試験と面接試験が実施され4名が選抜される予定です。そして7月下旬の箱根合宿研修を経て、フィリピン大会に臨みます。日本地質学会は、国際地学オリンピック日本委員会の協賛団体です。
地学オリンピック目次に戻る
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2008年8月)
8月のイベント・特別展示カレンダー (2008/08/05〜2008/09/02)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
8月の特別展示
2008/08/05 現在
「ダーウィン展」 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
期間:7/19(土)〜9/21(日)
場所:大阪市立自然史博物館ネイチャーホール
この展覧会では、2009年がダーウィンの生誕200年、「種の起源」発表150年になることを記念して、ダーウィンの生い立ちから、5年に及ぶビーグル号での世界航海、「種の起源」を発表するまでの苦悩と、進化論が当時の世界に与えた影響を紹介します。会場内には、ビーグル号航海の模様を壮大なスケールで展示。ブラジルやアルゼンチン、そして貴重な生物の宝庫として有名なガラパゴス諸島でダーウィンが出会った珍しい生物を剥製や映像で紹介します。また、進化論とは何なのか?について、工夫を凝らした展示でわかりやすく解説します。
特別展「箱根火山〜新しい箱根火山の形成史〜(仮称)」 (神奈川県 神奈川県立生命の星・地球博物館)
期間:7/19(土)〜11/09(日)
場所:神奈川県立生命の星・地球博物館 特別展示室
箱根火山の形成モデルは、1950年代に故久野久先生により確立されて以来、半世紀にわたり使われ続き、カルデラ形成史の教科書的存在にもなってきました。また、箱根各所の観光地でもそのモデルの紹介が行なわれています。しかし、近年、詳細なフィールドワークと最新の分析機器の導入により、新しい山体形成モデルが提案され、さらに新たな火山活動などもわかってきました。また、火山ができる前にすでにあった、基盤岩についても、さまざまなことがわかってきました。本特別展示では、箱根地域における基盤の形成から火山体の形成までを、新旧モデルをふまえて紹介します。
企画展「印された奇石〜印刷物になった石たち」(仮称) (静岡県 奇石博物館)
期間:7/19(土)〜8/31(日)
場所:奇石博物館企画展示室
切手やポスターなどの印刷物に取りあげられた石たちを展示紹介する。
世界最大の翼竜展―恐竜時代の空の支配者 (東京都 日本科学未来館)
期間:6/28(土)〜8/31(日)
場所:日本科学未来館1階企画展示ゾーンa
恐竜時代に大空を支配していた翼竜をテーマにした展覧会。世界で一番大きい翼竜“ケツァルコアトルス”の全身復元骨格をはじめ、中国で発掘された貴重な化石の数々も公開。さらに翼竜に倣った次世代の飛行技術についても紹介します。
『三葉虫(仮)』展 (栃木県 葛生化石館)
期間:7/19(土)〜9/28(日)
場所:葛生化石館企画展示室
佐野市葛生地域の石灰岩からは古生代ペルム紀の化石がたくさん見つかっています。その中でも人気の高い三葉虫の化石にスポットをあて紹介します。化石採集教室で見つけた三葉虫も展示します。
第23回特別展「野尻湖遺跡群ー旧石器の狩人が集まった氷河時代の湖ー」 (長野県 野尻湖ナウマンゾウ博物館)
期間:7/19(土)〜11/30(日)
場所:野尻湖ナウマンゾウ博物館3階 特別展示室
野尻湖周辺地域に分布する多くの旧石器時代の遺跡(日向林B遺跡、貫ノ木遺跡、上ノ原遺跡、東裏遺跡、仲町遺跡、杉久保遺跡など)は、日本の氷河時代を代表する遺跡として注目されており、野尻湖遺跡群の全体像を理解していただく資料を展示します。
ぽけっと企画展「地球と生命」 (福岡県 北九州市立いのちのたび博物館 )
期間:5/10(土)〜12/31(木)
場所:北九州市立いのちのたび博物館 ポケットミュージアム No. 1
自然の変化に対応してきた、絶えることのない生命の継続性と神秘性を化石や自然史資料を用い紹介します。
8月のイベント
2008/08/05 現在
日付
イベント
8/05
(火)
8/06
(水)
8/07
(木)
伊那谷中部の扇状地礫層が語るもの (長野県 飯田市美術博物館・伊那谷自然友の会)
場所:飯田市美術博物館
時間:19:00〜21:00
伊那谷中部駒ヶ根地域の礫層調査をもとにして、中央アルプス山麓から広がる扇状地の変遷を探る。講師:下平眞樹さん(赤穂中学校教諭)
8/08
(金)
8/09
(土)
みんなの観察会「海岸で石ころをひろおう」 (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県鴨川市
時間:10:00〜15:00
鴨川市の海岸では、千葉県ではめずらしく、海岸に多数の石ころが見られます。いろいろな石ころを採集し、その違いを調べます。
子ども体験教室「化石の模型を作ろう」 (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館研修室
時間:10:00〜15:00
三葉虫、アンモナイト、恐竜の歯など、色々な化石のレプリカづくりにチャレンジします。
室内実習 貝化石標本をつくろう (徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島県立博物館
時間:13:30〜16:00
歯ブラシやハンマー・タガネなどを使って、貝化石を標本に仕上げます。
8/10
(日)
追手町小学校化石標本室公開 (長野県 飯田市美術博物館)
期間:8/10(日)〜8/10(日)
場所:追手町小学校化石標本室(飯田市美術博物館から徒歩12分)
飯田市千代出身の長谷川善和先生が採集した標本を中心に展示
室内実習 化石のレプリカをつくろう (徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島県立博物館
時間:10:00〜11:30
実物の恐竜の歯やアンモナイト、三葉虫の化石から型どりした雌型を使ってレプリカ(複製)をつくりましょう。
ミュージアムトーク 恐竜発掘レポート (徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島県立博物館
時間:13:30〜15:00
福井県立恐竜博物館の学芸員が、最新の恐竜情報をお伝えします。
追手町小学校化石標本室公開イベント 化石クリーニング (長野県 飯田市美術博物館)
場所:追手町小学校化石標本室(飯田市美術博物館から徒歩5分)
時間:10:00〜16:00
阿南町で採取された富草層群の貝やサメの歯などを含む岩塊を割って化石を探す。講師:小泉明裕(飯田市美術博物館)
オープンセミナー(4)蛍石を光らせよう (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:人と自然の博物館・セミナー室
時間:11:00〜15:00
くらやみで光る鉱物を集めた、ルミナスボックスが登場します。時間を決めて、解説と蛍石を暖めて光らせる実験をします。予約無しで参加できる、無料のセミナーです。
8/11
(月)
ひとはくセミナー 地層の見方・調べ方in淡路 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:兵庫県南あわじ市
時間:10:30〜16:30
午前中は室内で地層に関する基礎的な学習を行い、午後青少年交流の家付近に露出する和泉層群などを観察し、地層を観察するときのポイントを学習します。教職員を対象としたを対象とした、申込み制、有料のセミナーです。
8/12
(火)
ひとはくセミナー 教職員対象(1)石の観察と見分け方 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:人と自然の博物館・セミナー室
時間:13:30〜16:30
博物館にある標本を手にとって観察しながら、岩石を見分けるコツをつかみます。わからない石がある人は持って来て下さい。教職員を対象にした、申込み制、有料のセミナーです。
8/13
(水)
ひとはくセミナー 教職員対象(2)兵庫県下の活断層と近未来の大地震 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:人と自然の博物館・セミナー室
時間:9:30〜12:00
山崎断層帯や六甲断層帯など兵庫県内の活断層の地形・地質的な特色や、それらの大地震発生可能性、さらに南海地震について最新の知見を紹介します。職員を対象にした、申込み制、有料のセミナーです。
8/14
(木)
8/15
(金)
8/16
(土)
8/17
(日)
8/18
(月)
ひとはくセミナー 教職員対象(3)地球史から読み解く温暖化問題 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:人と自然の博物館・セミナー室
時間:9:30〜12:30
現在の地球温暖化に警鐘を鳴らすIPCCのメンバーとアル・ゴア氏に、2007年のノーベル平和賞が贈られました。温暖化問題はもはや待ったなしの状態にあります。IPCCの報告書やゴア氏の著書「不都合な真実」が根拠とする地球科学データを解説し、この問題への理解を深めます。教職員を対象にした、申込み制、有料のセミナーです。
ひとはくセミナー 教職員対象(4)地震教材をつくろう (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:人と自然の博物館・セミナー室
時間:13:30〜16:30
地震の揺れ方の実験後、ペットボトルで液状化実験装置を作ります。表面に凹凸のない500mlペットボトルを持参してください。教職員を対象にした、申込み制、有料のセミナーです。
8/19
(火)
ひとはくセミナー 地層の見方・調べ方in丹波 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:兵庫県篠山市
時間:9:30〜16:30
午前中は、丹波地方の地層の中で丹波帯・篠山層群に焦点を当てて、地層や化石に関する基礎的な学習を行います。午後は野外で丹波帯や篠山層群の露頭を観察します。教職員を対象としたを対象とした、申込み制、有料のセミナーです。
やってみよう!さわってみよう!「1000万年前のミニ化石を探そう」 (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館1階入り口・1階ホール
時間:10:30〜15:00
1000万年前の海底にたまった岩石から、小さな貝やサメの歯の化石を探します。
8/20
(水)
ひとはくセミナー 教職員対象(5)学校でできる!やさしい化石レプリカづくり (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:人と自然の博物館・セミナー室
時間:13:30〜16:30
実物のアンモナイトや三葉虫の化石を使って、児童生徒でも扱える材料で楽しくレプリカ(レリーフ)を作成します。教職員を対象にした、申込み制、有料のセミナーです。
8/21
(木)
8/22(金)
もうただの石ころと呼ばせない−石は地球からの手紙− (NECガリレオクラブ)
場所:NEC本社(東京都港区芝5-7-1 多目的ホール)
時間:13:30〜16:00
小学生向けの実験イベントが行われます。当日は、石井輝秋氏(元東京大学海洋研究所)が講師として参加する予定です。対象は小学校4年生〜6年生。定員130名。
8/23
(土)
みんなのイベント「夏休み自由研究相談会」 (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館1階入り口・1階ホール
時間:9:30〜16:00
小・中学生、高校生が夏休みに実施した自由研究に関して、標本同定や研究のまとめ方の相談に応じます。
8/24
(日)
戸台谷の不思議な地形2“巨礫はどこから来た?” (長野県 伊那谷自然友の会)
場所:飯田市長谷戸台谷
案内:明石浩司さん
前日までに美術博物館村松へ(0265-22-8118)お申し込み下さい。
ひとはくセミナー (7)石を知ろう“岩石の見分け方入門” (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:人と自然の博物館・セミナー室
時間:13:30〜15:30
標本を手にとって観察しながら、岩石を見分けるコツをつかみます。わからない石がある人は持って来て下さい。小学生高学年〜一般を対象とした、申込み制、有料のセミナーです。
8/25
(月)
8/26
(火)
「ミニ火山を作ろう」 (神奈川県 神奈川県立生命の星・地球博物館)
場所:神奈川県立生命の星・地球博物館
時間:10:00〜15:00
砂と食用廃油を使っての噴火実験でお好みの火山を作ります。 ※1加熱した油を使いますので小学生以下のお子様には保護者の付き添いが必要です。 ※2持ち物:スプレー缶入りのエアダスターをグループで1本、各自軍手とマスク ※3材料の関係上、作成した火山はお持ち帰りできません。対象:2〜6人までの家族などのグループ
8/27
(水)
8/28
(木)
8/29
(金)
8/30
(土)
8/31
(日)
追手町小学校化石標本室公開 (長野県 飯田市美術博物館)
期間:8/31(日)〜8/31(日)
場所:追手町小学校化石標本室(飯田市美術博物館から徒歩13分)
飯田市千代出身の長谷川善和先生が採集した標本を中心に展示
室内実習 ミクロの世界ー電子顕微鏡で化石を見よう!1 (徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島県立博物館
時間:10:00〜15:30
参加者の方々も電子顕微鏡を操作して、珪藻・有孔虫・放散虫などの小さなサイズの化石を観察します。
追手町小学校化石標本室公開イベント 化石クリーニング (長野県 飯田市美術博物館)
場所:追手町小学校化石標本室(飯田市美術博物館から徒歩5分)
時間:10:00〜16:00
阿南町で採取された富草層群の貝やサメの歯などを含む岩塊を割って化石を探す。講師:小泉明裕(飯田市美術博物館)
9/01
(月)
企画展「曲げ実験30周年記念 コンニャク石とその仲間の意外な石たち」(仮称) (静岡県 奇石博物館)
期間:9/01(月)〜1/18(日)
場所:奇石博物館企画展示室
当館常設展示で人気のコンニャク石曲げ実験は1978年より開始されたもので、今年はちょうど30年の節目にあたる。この機会にコンニャク石をはじめとした意外な石たちを一同に集め紹介する。
9/02
(火)
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ内のフォームまたはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。随時、情報を更新いたしますので,ご協力をお願いいたします。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
地学オリンピック2008年フィリピン大会 銀・銅メダル
地学オリンピック2008年フィリピン大会 おめでとう!
第2回国際地学オリンピック(IESO)が、8月31日から9月8日までフィリピンで開催されました。筆記・実技試験はケソンのフィリピン大学で、フィールドワークは、場所を移して、マヨン火山麓のグラツピで行われました。
登録参加国 は8ヶ国で、実際に参加した生徒は、フィリピン、日本、韓国、台湾、アメリカ、シンガポールからの6ヶ国24名でした。インドネシアはオブザーバのみで生徒の参加はなく、モンゴルは直前のキャンセルでした。
日本チームは、初めてのオリンピック参加にもかかわらず、銀メダル3個、銅メダル1個の素晴らしい成績でした。その内訳は以下のとおりです。
銀メダル
森里文哉(もりさとふみとし:香川県立丸亀高等学校3年)
雪田一弥(ゆきたかずや:青森県立青森高等学校3年)
平島崇誠(ひらしまたかまさ:石川県立金沢泉丘高等学校2年)
銅メダル
日野愛奈(ひのあいな:愛媛県立松山南高等学校3年)
試験風景
式典風景
マヨン火山麓にて
このほか部門賞として森里文哉君は地質・固体地球科学部門で堂々の一位でした。
さらに国際混合チーム(グループ1−4)で競うフィールドワーク・コンテストでは、日野愛奈さんのグループがベストフィールドワーク賞を受賞しました。
なお金・銀・銅メダルの個数は、大会規定により、登録参加国の参加者数(1カ国4名)の10%が金メダル、その2倍が銀メダル、その3倍が銅メダルとなっており、今大会では、それぞれ4個、8個、12個でした。また筆記試験 (3時間;100点満点)は、地質・固体地球科学部門が45%、気象・海洋科学部門が35%、天文・惑星科学部門が20%の構成比となっています。実技試験も同様の3部門で構成され、それぞれ10点が与えられます。金・銀・銅メダルは、この筆記試験と実技試験の合計点で決定します。
フィールドワークでは、マヨン火山麓で、「自然と人間生活」をテーマに、現地での露頭観察や村民へのインタヴューがグループごとに行われました。その記録をもとに、パワーポイントを用いた発表コンテスト形式で、発表内容・構成や成果などの観点で競われました。
なお金メダルは、台湾と韓国からの参加者が2個ずつ受賞しました。第3回は台湾大会となります。
(団長 久田健一郎)
大会参加の印象
地学オリンピックは、各国の高校生・教育者・研究者の国際交流や情報交換を図る上で最適な場でしょう。ただし日本がIESOの運営に積極的に携わることも重要です(地学を創設した国として)。
韓国、台湾の国を挙げての応援に驚きました。
3分野(地質・固体地球科学、気象・海洋科学、天文・惑星科学)の専門家の派遣が必要です。これは問題の選択など様々な場面に少なからず影響するものと思われます。
(団長 久田健一郎)
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2008年10月)
10月のイベント・特別展示カレンダー (2008/10/07〜2008/11/04)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
10月の特別展示
2008/10/09 現在
特別展「箱根火山〜いま証される噴火の歴史〜」 (神奈川県 神奈川県立生命の星・地球博物館)
期間:7/19(土)〜11/09(日)
場所:神奈川県立生命の星・地球博物館 特別展示室
箱根火山の形成モデルは、1950年代に故久野久先生により確立されて以来、半世紀にわたり使われ続き、カルデラ形成史の教科書的存在にもなってきました。また、箱根各所の観光地でもそのモデルの紹介が行なわれています。しかし、近年、詳細なフィールドワークと最新の分析機器の導入により、新しい山体形成モデルが提案され、さらに新たな火山活動などもわかってきました。また、火山ができる前にすでにあった、基盤岩についても、さまざまなことがわかってきました。本特別展示では、箱根地域における基盤の形成から火山体の形成までを、新旧モデルをふまえて紹介します。
第31回企画展「きれいで不思議な貝の魅力」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
期間:9/27(土)〜11/24(月)
場所:群馬県立自然史博物館企画展示室
貝の進化や不思議な生態、美しい貝殻など、貝の魅力を多くの標本や生体展示で紹介します。
企画展「曲げ続けて30年!コンニャク石展」 (静岡県 奇石博物館)
期間:9/01(月)〜1/18(日)
場所:奇石博物館企画展示室
当館常設展示で人気のコンニャク石曲げ実験は1978年より開始されたもので、今年はちょうど30年の節目にあたる。この機会にコンニャク石をはじめとした意外な石たちを一同に集め紹介する。
第23回特別展「野尻湖遺跡群ー旧石器の狩人が集まった氷河時代の湖ー」 (長野県 野尻湖ナウマンゾウ博物館)
期間:7/19(土)〜11/30(日)
場所:野尻湖ナウマンゾウ博物館3階 特別展示室
野尻湖周辺地域に分布する多くの旧石器時代の遺跡(日向林B遺跡、貫ノ木遺跡、上ノ原遺跡、東裏遺跡、仲町遺跡、杉久保遺跡など)は、日本の氷河時代を代表する遺跡として注目されており、野尻湖遺跡群の全体像を理解していただく資料を展示します。
ぽけっと企画展「地球と生命」 (福岡県 北九州市立いのちのたび博物館 )
期間:5/10(土)〜12/31(木)
場所:北九州市立いのちのたび博物館 ポケットミュージアム No. 1
自然の変化に対応してきた、絶えることのない生命の継続性と神秘性を化石や自然史資料を用い紹介します。
日伯交流年事業第23回特別企画展「シーラカンス−ブラジルの化石と大陸移動の証人たち−」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
期間:9/19(金)〜11/16(日)
場所:豊橋市自然史博物館特別企画展示室
世界最大のシーラカンス化石の復元骨格(全長3.8m)やブラジル産の魚類化石の展示とあわせて大陸移動について紹介します。観覧料:大人300円(240円)小・中学生100円(80円)※()内は30名以上の団体料金※この他に、総合動植物公園入園料が必要です
特別展「那賀川平野の貝化石」 (徳島県 徳島県立博物館,阿南市立阿波公方・民俗資料館)
期間:9/25(木)〜10/30(木)
場所:阿南市立阿波公方・民俗資料館(阿南市那賀川町古津339-1)
那賀川平野の地下からは、大規模な土木工事やボーリング調査に伴って、貝などの動物化石が得られることがあります。これらは一見したところただの貝殻にしか見えないため、見過ごされることが多いと思われますが、その多くは今から数千年前の海に生息していた動物の化石です。これらの種類や生態的な特性,時代などを調べることによって,当時の古環境や生物相の変化を知ることができます。この展示では徳島県立博物館が収蔵する那賀川平野産の貝化石と、これらが示す数千年前の古環境について詳しくご紹介いたします。
第4回自然史博物館自由研究展 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
期間:10/11(土)〜11/24(月)
場所:豊橋市自然史博物館自然史スクエアほか
豊橋市内の小中学生が行った地学・生物に関する自由研究の優秀作品を展示します。
企画展示「天神島周辺の地質」 (神奈川県 横須賀市自然・人文博物館)
期間:10/11(土)〜3/29(日)
場所:天神島ビジターセンター
神奈川県横須賀市の天神島から長者ヶ崎にかけては,三崎層や逗子層,立石層,葉山層など,異なった時代の地層が複雑に分布しています.この企画展示では,これらの地層と,地層に見られるさまざまな地質構造について紹介します.
「第8回特別展鹿児島の活火山」 (鹿児島県 鹿児島大学総合研究博物館)
期間:10/21(火)〜11/21(金)
場所:鹿児島大学郡元キャンパス総合教育研究棟2階プレゼンテーションホール(入場無料)
鹿児島県に多く存在する活火山にスポットをあてて解説・展示をいたします。火山のしくみ:マグマの発生メカニズム、噴火のプロセスと規模。火山のめぐみ:温泉、鉱物資源、果物・野菜、火山灰の活用
地震展2008 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
期間:10/25(土)〜12/07(日)
場所:大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール
大阪をおそう地震として、プレート境界地震である南海・東南海地震と、活断層による内陸地震の2種類に焦点を当てて、地震の基礎的な知識から、詳しく紹介します。入館料は大人400円、高・大生300円
富草の化石-近藤コレクションを中心に- (長野県 飯田市美術博物館)
期間:10/25(土)〜2/15(日)
場所:飯田市美術博物館
1800万年前、県南地域に広がった暖かい海の地層からでる化石を紹介します。
10月のイベント
2008/10/09 現在
日付
イベント
10/07
(火)
10/08
(水)
10/09
(木)
10/10
(金)
10/11
(土)
サイエンス・サタデー「アンモナイトのレプリカをつくろう」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:自然史博物館実験室
時間:13:30〜15:00
アンモナイトのレプリカをつくり、どんな生き物だったのかを学びます。
当日会場で直接申込み(先着30名)小学生以上が対象で、参加費は無料です。
ジオラボ(10月)「大阪の地質模型づくり」 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:自然史博物館本館ミュージアムサービスセンター
時間:14:30〜15:30
地質図を見ると、大地がどんな地層や岩石でできているかわかります。立体的な地質模型にすれば、もっとわかりやすくなるかも知れません。かんたんな大阪の地質模型をつくって、大阪の平野や山地の地質のことを調べてみましょう。
地球46億年の歴史を感じよう (神奈川県 神奈川県立生命の星・地球博物館)
場所:生命の星・地球博物館
時間:13:30〜15:30
長い長い地球の歴史の流れを体感しましょう。簡単なレクチャーと展示見学、そして地球46億年ゲームを楽しみます。
小学生と保護者を対象とした申込制の講座です。
中生代の動物たち1 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:丹波市山南住民センター
時間:13:30〜15:00
2006年から2007年にかけて丹波市山南で行われた発掘により、篠山層群からさまざまな恐竜や小型脊椎動物の骨や歯が発掘されました。中生代、とくに篠山層群が出来た前期白亜紀の動物について紹介し、篠山層群の化石の重要性を考えます。
9月20日(土)締め切り。受講料500円。
ミニトーク 「HOME_GROUND地球」第3回 「マグマ!灼熱の石!!」 (東京都 日本科学未来館)
場所:日本科学未来館 1階 屋外 ※雨天時は屋内を予定
時間:14:30〜16:00
地球未踏の深部を目指して掘り進む、統合国際深海掘削計画(IODP)に関わる地球科学者たちの営みが身近に感じられるトーク。毎回、石や土・実験道具などの「モノ」を使いながら、その魅力を紹介します。種類によって溶け方の違う石。流れる溶岩を目の前で見よう!火山の噴火はどうやって起きる?未来館で噴火体験!?
10/12
(日)
特別展示関連ワークショップ〜マグマをあやつるのはキミだ!火山噴火実験 (神奈川県 神奈川県立生命の星・地球博物館)
場所:生命の星・地球博物館
時間:10時30分より、13時30分より〜
「みんなで作ろう箱根火山」と「火山噴火を体験しよう」の2つ火山噴火実験を行います。箱根火山は、浅間山火山と屏風山火山を作ります。
県博日曜講座「地質観察会,その舞台裏〜これから観察会を始めたい人のためのノウハウを含めて〜」 (岩手県 岩手県立博物館)
場所:岩手県立博物館講堂または教室
時間:13:30〜15:00
当館学芸員による講座の中の地質分
中生代の動物たち2 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:丹波市山南住民センター
時間:13:30〜15:00
2006年から2007年にかけて丹波市山南で行われた発掘により、篠山層群からさまざまな恐竜や小型脊椎動物の骨や歯が発掘されました。中生代、とくに篠山層群が出来た前期白亜紀の動物について紹介し、篠山層群の化石の重要性を考えます。
9月20日(土)締め切り。受講料500円。
10/13
(月)
体育の日
特別展示関連ワークショップ〜マグマをあやつるのはキミだ!火山噴火実験 (神奈川県 神奈川県立生命の星・地球博物館)
場所:生命の星・地球博物館
時間:10時30分より、13時30分より〜
「みんなで作ろう箱根火山」と「火山噴火を体験しよう」の2つ火山噴火実験を行います。箱根火山は、小塚山火山と台ヶ岳火山を作ります。
石を通して地域を知るー恐竜がいた頃に日本 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:兵庫県立人と自然の博物館
時間:13:30〜15:30
近畿地方には、中生代ジュラ紀から白亜紀にかけての地層が広く分布していますが、その中で篠山層群以外の地層から見つからないのはなぜか、考えます。
9月23日(火)締め切り。受講料500円(中学生以下300円)。
10/14
(火)
10/15
(水)
10/16
(木)
10/17
(金)
10/18
(土)
川西と猪名川で中・古生代の地層を見る (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:兵庫県立人と自然の博物館
時間:13:30〜15:30
川西市、猪名川町の猪名川流域に分布する丹波帯、超丹波帯の地層を観察します
9月29日(月)締め切り。受講料500円(中学生以下400円)。
サイエンス・サタデー「アンモナイトのレプリカをつくろう」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:自然史博物館実験室
時間:13:30〜15:00
アンモナイトのレプリカをつくり、どんな生き物だったのかを学びます。
当日会場で直接申込み(先着30名)小学生以上が対象で、参加費は無料です。
大人向けおすすめ講座「岩石薄片をつくろう」 (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館研修室
時間:10:00〜16:00
岩石を切ったりみがいたりして薄い切片を作成し、偏光顕微鏡で観察します。
「アラスカ−ツンドラ・永久凍土の自然をめぐる−」 (長野県 飯田市美術博物館)
場所:飯田市美術博物館講堂
時間:16:00〜17:30
氷河・周氷河地形の専門家である小林武彦さん(元富山大学教授)から、国際会議の折、アラスカのツンドラ地帯を旅した報告をしていただきます。
聴講無料
ミニトーク 「HOME_GROUND地球」第4回 「バトル!地球談義!!」 (東京都 日本科学未来館)
場所:日本科学未来館 1階 シンボルゾーン
時間:14:30〜16:00
地球未踏の深部を目指して掘り進む、統合国際深海掘削計画(IODP)に関わる地球科学者たちの営みが身近に感じられるトーク。聞きたかったけど聞けなかった地球のあれこれ。 マグマ学者が一手に引き受けます。
要申込(抽選)。ネットページにある「お申し込みボタン」よりお申し込みください。抽選結果は締め切り後10日以内にご記入のメールアドレスまで当選の可否をご連絡いたします。申込締切2008年10月8日(水)17:00まで
10/19
(日)
総合観察会「秋の橋立川をさかのぼる」 (埼玉県 埼玉県立自然の博物館・埼玉県立自然の博物館友の会)
場所:秩父市浦山付近
時間:10:00〜15:00
秋の橋立川の動物・植物・地質を見学します。
実施日の1ヶ月前から2週間前(当館必着)が申込受付期間です。e-mailまたは往復はがきで受け付けます。
野外自然かんさつ 那賀川上流の地層見学 (徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島県那賀川上流(現地集合・現地解散)
時間:13:00〜16:00
徳島県那賀川沿いは、秩父帯とよばれる地帯区分に含まれ、地質構造が複雑で、古生代、中生代などのさまざまな時代の地層が分布しています。そのため現在でもその成り立ちについては、さまざまな解釈がなされています。この行事では、主に三畳紀やジュラ紀の地層を見学し、それらの地層が堆積した環境や含まれる化石について解説します。
往復葉書に行事名,参加希望者全員の氏名,住所,電話番号を書いて10月9日までにお申し込みください。
特別展示関連ワークショップ〜マグマをあやつるのはキミだ!火山噴火実験 (神奈川県 神奈川県立生命の星・地球博物館)
場所:生命の星・地球博物館
時間:10時30分より、13時30分より〜
「みんなで作ろう箱根火山」と「火山噴火を体験しよう」の2つ火山噴火実験を行います。箱根火山は、早雲山火山と丸山火山を作ります。
トークセッション 「DEEP_GROUND地球」 (東京都 日本科学未来館)
場所:日本科学未来館 1階 シンボルゾーン
時間:14:30〜16:00
独立行政法人 海洋研究開発機構(JAMSTEC)で行っている地球の掘削研究につい て、次期掘削ステージである「伊豆-ボニン-マリアナ弧(IBM=IZU-Bonin-Mariana Arc)」における日本主導研究の中心メンバーとなる研究者5人が、その魅力を語っ ていきます。 巽好幸・小平秀一・田村芳彦・山本啓之(独立行政法人 海洋研究開発機構 地球内部変動研究センター)/沖野郷子(東京大学海洋研究所)
ットページにある「お申し込みボタン」よりお申し込みください。抽選結果は締め切り後10日以内にご記入のメールアドレスまで当選の可否をご連絡いたします。申込締切2008年10月9日(木)17:00まで
10/20
(月)
10/21
(火)
10/22
(水)
10/23
(木)
10/24
(金)
10/25
(土)
古代の生きものを大発見 (埼玉県 埼玉県立長瀞げんきプラザ・埼玉県立自然の博物館)
場所:長瀞町皆野町の荒川
地質見学や化石採集を通じて、自然の成り立ちを学び、自然史学習に対する意欲や探求心を高めます。
実施日の1ヶ月前から2週間前(当館必着)が申込受付期間です。e-mailまたは往復はがきで受け付けます。
10/26(日)まで
東山道神坂峠越と巨大地震 (長野県 伊那谷自然友の会)
場所:阿智村はゝき木館ほか
阿智村東山道・園原ビジターセンター「はゝき木館」の見学と説明。大正13年の巨大地震と園原の環境変化。埋もれ木による天正地震の痕跡
前日までに飯田市美術博物館小泉へ(0265-22-8118)お申し込み下さい。
サイエンス・サタデー「アンモナイトのレプリカをつくろう」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:自然史博物館実験室
時間:13:30〜15:00
アンモナイトのレプリカをつくり、どんな生き物だったのかを学びます。
当日会場で直接申込み(先着30名)小学生以上が対象で、参加費は無料です。
地震展2008・子どもワークショップ「なまちゃんハカセと展示ツアー」 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:自然史博物館ネイチャーホール
時間:11時〜,13時〜,15時〜(3回)〜
特別展会場の中の「なまちゃんキッズパネル」をキーワードに、ハカセがちょっとだけ展示を紹介するよ。大人の方もいっしょにどうぞ。
縄文海進とは何かー海面変動研究の最前線 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:兵庫県立人と自然の博物館
時間:13:30〜15:30
約1万年前に現在の温暖期(間氷期)が始まり、縄文時代の海進を引き起こしました。播磨灘では、縄文海進のピーク時の海面は現在より約1メートル高かったようです。その要因を最新の研究をもとに解説します。
9月23日(火)締め切り。受講料500円
10/26
(日)
現場で学ぶ 石炭基礎講座 掘るだけでは終わらない 第8回『探る』 (北海道 釧路市立博物館)
場所:釧路市阿寒町雄別(雄別炭砿跡;集合は釧路市立博物館)
時間:9:00〜16:30
1970年(昭和45年)に閉山した雄別炭砿発祥の地をたずね、河床の石炭露頭を観察、周辺の地層で地質学の基礎を学びます。あわせて稼行当時の坑口や施設・集落跡を訪ねます。対象は小学生から一般。募集人数30名。保険料等300円。
釧路市立博物館(0154-41-5809)まで電話で申し込んでください。10月1日(水)9:30から受付
火山の不思議(子ども教室地球探検隊) (熊本県 御船町恐竜博物館)
場所:熊本県阿蘇周辺
時間:9:00〜
阿蘇火山の岩石や地層を観察し、火山の仕組みや生い立ちを学びます。
定員は40名。小中学生対象(高校生〜大人の参加も可)参加費2500円(高校生〜大人 3000円)
特別展示関連ワークショップ〜マグマをあやつるのはキミだ!火山噴火実験 (神奈川県 神奈川県立生命の星・地球博物館)
場所:生命の星・地球博物館
時間:10時30分より、13時30分より〜
「みんなで作ろう箱根火山」と「火山噴火を体験しよう」の2つ火山噴火実験を行います。箱根火山は、神山火山と芦之湯火山を作ります。
地震展2008・子どもワークショップ「なまちゃんハカセと展示ツアー」 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:自然史博物館ネイチャーホール
時間:11時〜,13時〜,15時〜(3回)〜
特別展会場の中の「なまちゃんキッズパネル」をキーワードに、ハカセがちょっとだけ展示を紹介するよ。大人の方もいっしょにどうぞ。
追手町小学校化石標本室公開イベント化石レプリカ作成 (長野県 飯田市美術博物館)
場所:追手町小学校化石標本室(飯田市美術博物館から徒歩5分)
時間:10:00〜16:00
恐竜の歯やアンモナイトなどの型を作り石膏を流しいれてレプリカを作る。講師:小泉明裕(飯田市美術博物館)
なし。無料。
自然史講座「日本の天然ダイアモンド」講師:水上知行さん(金沢大学助教) (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市自然史博物館講堂
時間:14:00〜15:00
昨年、日本で初めて発見された天然ダイアモンドについて紹介します。
受講料無料、定員60名(申込順、小学4年生以上・一般対象)豊橋市自然史博物館へ電話(0532-41-4747)、FAX(0532-41-8020)、メール(アドレスはホームページをご覧ください)にて申込み(後日、受講証をお送りします)
10/27
(月)
10/28
(火)
10/29
(水)
10/30
(木)
10/31
(金)
11/01
(土)
みんなの観察会「県外岩石観察会2 阿武隈洞の大理石」 (千葉県・福島県 千葉県立中央博物館)
場所:福島県田村市(JR千葉駅前から貸切バスを使用)
時間:8時集合〜19時解散
福島県中部にある有名な鍾乳洞「阿武隈洞」をつくる大理石や周辺の阿武隈帯の岩石を観察します。
11/02(日)まで
自然史オープンセミナー「地震−2.大阪の地盤と地震」 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:自然史博物館 集会室
時間:15:00〜16:30
大阪の地盤について研究をされている大阪市立大学の三田村宗樹先生が、大阪平野の地盤と地震の関係について講演します。大阪は淀川河口に広がる海岸平野に位置しています。その地の利を活かして大阪の町は発展してきましたが、低地の軟弱な地盤の上に立地しているために、地盤にまつわる災害を被ってもきました。大阪の地盤となっている平野地下に分布する地層は厚く軟弱です。このような厚い地層がどのようにして形成されたのかを紹介し、地震災害との関連について、大阪府が行った地震動解析の結果なども交えながら解説します。
往復はがき、または電子メールに(gyouji@mus-nh.city.osaka.jp)、「地震−2.大阪の地盤と地震に参加希望」と明記の上、参加者全員の氏名、年齢、住所、電話番号、返信用宛名を書いて、10月18日(土)までに届くように、自然史博物館普及係宛に申し込んで下さい。自然史博物館ホームページからも申込みできます。
11/02
(日)
特別展示関連ワークショップ〜マグマをあやつるのはキミだ!火山噴火実験 (神奈川県 神奈川県立生命の星・地球博物館)
場所:生命の星・地球博物館
時間:10時30分より、13時30分より〜
「みんなで作ろう箱根火山」と「火山噴火を体験しよう」の2つ火山噴火実験を行います。箱根火山は、駒ヶ岳火山と陣笠山火山を作ります。
特別展記念講演会「スロー地震とは何か 巨大地震予知の可能性をさぐる」 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:自然史博物館講堂
時間:14:00〜16:00
講師は川崎一朗氏(京都大学防災研究所・地震予知研究センター教授)、 1995年兵庫県南部地震(阪神淡路大震災)が起こったあと、日本国内には高精度・高密度の地震観測ネットワークが整備され、地震に関する基礎的研究が飛躍的に進んでいます。その中の大きなトピックが、南海トラフや日本海溝などのプレート境界型巨大地震が想定される場所での「スロー地震」の発見と、「アスペリティ」という概念の登場です。スロー地震と普通の地震は何が違うの?アスペリティって何?地震予知をめざした研究の最前線の話を伺います。
往復はがき、または電子メールに、「スロー地震とは何か 巨大地震予知の可能性をさぐる講演会に参加希望」と明記の上、参加者全員の氏名、年齢、住所、電話番号、返信用宛名を書いて、10月27日(月)までに届くように、自然史博物館普及係宛に申し込んで下さい。自然史博物館ホームページからも申込みできます。
11/03
(月)
文化の日
特別展示関連ワークショップ〜マグマをあやつるのはキミだ!火山噴火実験 (神奈川県 神奈川県立生命の星・地球博物館)
場所:生命の星・地球博物館
時間:10時30分より、13時30分より〜
「みんなで作ろう箱根火山」と「火山噴火を体験しよう」の2つ火山噴火実験を行います。箱根火山は、神山火山と下二子山火山を作ります。
秋の地形地質観察会 (神奈川県 神奈川県立生命の星・地球博物館)
場所:大磯丘陵(湘南平周辺)
時間:10:00〜15:00
湘南平の周辺を歩きながら、大磯丘陵の土台をつくっている地層とその周りの地形を観察して、大地の歴史を考えます。
小学4年生〜大人を対象とした申し込み制の講座です。
11/04
(火)
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ内のフォームまたはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。随時、情報を更新いたしますので,ご協力をお願いいたします。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2008年12月)
12月のイベント・特別展示カレンダー (2008/12/02〜2009/01/06)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
12月の特別展示
2008/12/02 現在
企画展「曲げ続けて30年!コンニャク石展」 (静岡県 奇石博物館)
期間:9/01(月)〜1/18(日)
場所:奇石博物館企画展示室
当館常設展示で人気のコンニャク石曲げ実験は1978年より開始されたもので、今年はちょうど30年の節目にあたる。この機会にコンニャク石をはじめとした意外な石たちを一同に集め紹介する。
ぽけっと企画展「地球と生命」 (福岡県 北九州市立いのちのたび博物館 )
期間:5/10(土)〜
場所:北九州市立いのちのたび博物館 ポケットミュージアム No. 1
自然の変化に対応してきた、絶えることのない生命の継続性と神秘性を化石や自然史資料を用い紹介します。
企画展示「天神島周辺の地質」 (神奈川県 横須賀市自然・人文博物館)
期間:10/11(土)〜3/29(日)
場所:天神島ビジターセンター
神奈川県横須賀市の天神島から長者ヶ崎にかけては,三崎層や逗子層,立石層,葉山層など,異なった時代の地層が複雑に分布しています.この企画展示では,これらの地層と,地層に見られるさまざまな地質構造について紹介します.
地震展2008 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
期間:10/25(土)〜12/07(日)
場所:大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール
大阪をおそう地震として、プレート境界地震である南海・東南海地震と、活断層による内陸地震の2種類に焦点を当てて、地震の基礎的な知識から、詳しく紹介します。入館料は大人400円、高・大生300円
富草の化石-近藤コレクションを中心に- (長野県 飯田市美術博物館)
期間:10/25(土)〜2/15(日)
場所:飯田市美術博物館
1800万年前、県南地域に広がった暖かい海の地層からでる化石を紹介します。
炭坑(ヤマ)の語り部 山本作兵衛の世界 (北海道 釧路市立博物館 共催:田川市石炭・歴史博物館 後援:NHK釧路放送局・西日本新聞筑豊総局・北海道新聞釧路支局・釧路新聞社)
期間:11/15(土)〜12/21(日)
場所:釧路市立博物館1階マンモスホール
明治以降の日本の近代化を推し進めた石炭。その一大生産地であった筑豊炭田(福岡県)と共に生きた山本作兵衛(1891
01984)は、現在では福岡県指定有形民俗文化財に指定されている膨大な数の炭坑記録画を残しました。そのうち約220点(複製画)の炭坑記録画を展示いたします。この展示会は、田川市石炭・歴史博物館で行われている展示の「交流企画展」として行います。
御船町恐竜アートコンテスト(御船町恐竜博物館開館10周年事業) (熊本県 御船町教育委員会(御船町恐竜博物館開館10周年事業実行委員会))
期間:12/04(木)〜12/26(金)
場所:御船町カルチャーセンター,御船町恐竜博物館
恐竜を題材にしたアート作品(絵画,模型,工芸など)の募集と展示。来場者による投票ならびに主催者および専門家による審査があります。優秀作品の表彰式(12月23日)もあります。
企画展「46億年 地球のしごと〜地質写真家が見た世界の地形〜」 (神奈川県 神奈川県立 生命の星・地球博物館)
期間:12/06(土)〜2/22(日)
場所:神奈川県立生命の星・地球博物館 1階 特別展示室
時間:9:00〜16:30
今回の企画展では、地質写真家 白尾 元理(しらお もとまろ)氏が世界各地で撮影した様々な地形や地質景観の写真 54点に、関連する岩石、化石を加えて紹介します。 地球上には驚いたり、不思議に感じたりする地形や地層、岩石が数多くあります。それらは火山の噴火活動や、大地の隆起や浸食、水や風による運搬や堆積など、地球のさまざまな営みによってできてきたものです。地球が46億年という長い歴史の中でおこなってきた、壮大な「しごと」の数々を、白尾氏撮影の写真と実物標本でお楽しみください。
12月のイベント
2008/12/02 現在
日付
イベント
12/02
(火)
12/03
(水)
12/04
(木)
12/05
(金)
12/06
(土)
第四紀植物と足跡化石 (長野県 伊那谷自然友の会)
場所:阿南町
時間:8:20〜15:00
飯田市山本や下久堅で、植物化石やゾウなどの足跡化石がみられる中-下部更新統を見学し、化石を採集します。採集した化石は各自でお持ち帰り下さい。
前日までに飯田市美術博物館小泉へ(0265-22-8118)お申し込み下さい。
骨のかたちを比べよう〜こども編〜 (神奈川県 神奈川県立生命の星・地球博物館)
場所:生命の星・地球博物館
時間:13:00〜15:00
自分の骨とけものの骨、鳥の骨と恐竜の骨をくらべてみましょう。博物館に展示されている骨格を楽しむコツをお伝えします。
小学1年生〜3年生を対象とした申し込み制の講座です。
12/07
(日)
ふかたん(石めぐり) (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:兵庫県立人と自然の博物館
時間:14:00〜
博物館周辺の深田公園と街の建物の石材を見てまわります。アンモナイトの化石を見つけよう。
12/08
(月)
12/09
(火)
12/10
(水)
12/11
(木)
12/12
(金)
12/13
(土)
12/14
(日)
やさしい自然観察会「化石さがし」 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:泉佐野市
化石のねむる山をめざして、みんなであるこう!ガケの石や、いろいろな化石を見つけて、和泉山脈のヒミツに迫ってみよう。
往復はがき、または電子メール(gyouji@mus-nh.city.osaka.jp)に「化石さがしに参加希望」と明記の上、参加者全員の氏名、年齢、住所、電話番号、返信用宛名を書いて、11月21日(金)までに届くように、自然史博物館普及係宛に申し込んでください。自然史博物館ホームページからも申込みできます。定員150名、申込み多数は抽選、参加は小学3年生以上
県博日曜講座「盛岡地質案内〜ナウマン・賢治から現代へ〜」 (岩手県 岩手県立博物館)
場所:岩手県立博物館講堂または教室
時間:13:30〜15:00
当館学芸員による講座です。
12/15
(月)
12/16
(火)
12/17
(水)
12/18
(木)
12/19
(金)
12/20
(土)
12/21
(日)
ペーパークラフトで学ぶ断層と地震 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:兵庫県立人と自然の博物館
時間:13時より、14時より〜
3種類の断層ペーパークラフトをつくり、断層の動きと地震について学びます。
室内実習 アンモナイト標本をつくろう (徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島県立博物館 実習室
時間:16:30〜15:30
アンモナイトは、カタツムリなどの巻き貝の仲間によく間違われますが、本当はタコやイカなどの頭足類という仲間に含まれます。普通に殻を見る限り、巻き貝にしか見えません。この行事ではアンモナイトの殻を削り、内部の構造が観察できる標本をつくっていきます。そして、なぜアンモナイトが巻き貝の仲間ではないのかという疑問を、いっしょに考えていきましょう!
往復葉書に行事名,参加希望者全員の氏名,住所,電話番号を書いて12月11日までにお申し込みください。
12/22
(月)
12/23
(火)
天皇誕生日
石を通して地域を知るー大陸移動とプレートの運動 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:兵庫県立人と自然の博物館
時間:13:30〜15:30
大陸の移動やプレートの運動がどのようにして証明されたかを示し、その原動力となったプルームテクトニクスについてお話します。
12月3日(月)締め切り。受講料500円(中学生以下300円)
12/24
(水)
12/25
(木)
12/26
(金)
12/27
(土)
12/28
(日)
12/29
(月)
12/30
(火)
12/31
(水)
1/01
(木)
元日
1/02
(金)
1/03
(土)
1/04
(日)
1/05
(月)
1/06
(火)
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ内のフォームまたはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。随時、情報を更新いたしますので,ご協力をお願いいたします。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2009年1月)
1月のイベント・特別展示カレンダー (2009/01/06〜2009/02/03)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
1月の特別展示
2009/01/06 現在
企画展「曲げ続けて30年!コンニャク石展」 (静岡県 奇石博物館)
期間:9/01(月)〜1/18(日)
場所:奇石博物館企画展示室
当館常設展示で人気のコンニャク石曲げ実験は1978年より開始されたもので、今年はちょうど30年の節目にあたる。この機会にコンニャク石をはじめとした意外な石たちを一同に集め紹介する。
コラボ特別展with新潟大学 「頭足類展 アンモナイトとその仲間たち」 (新潟県 フォッサマグナミュージアム、新潟大学)
期間:11/29(土)〜3/31(火)
場所:フォッサマグナミュージアム 展望廊下
アンモナイト、ベレムナイト、オウムガイ、イカ、タコなどの頭足類の分類、生態、進化について、国内・国外の標本により紹介する展示会です。展示標本には学生・院生が研究の過程で採集したものが多く、化石の研究の実例紹介もあります。
企画展示「天神島周辺の地質」 (神奈川県 横須賀市自然・人文博物館)
期間:10/11(土)〜3/29(日)
場所:天神島ビジターセンター
神奈川県横須賀市の天神島から長者ヶ崎にかけては,三崎層や逗子層,立石層,葉山層など,異なった時代の地層が複雑に分布しています.この企画展示では,これらの地層と,地層に見られるさまざまな地質構造について紹介します.
企画展「46億年 地球のしごと〜地質写真家が見た世界の地形〜」 (神奈川県 神奈川県立 生命の星・地球博物館)
期間:12/06(土)〜2/22(日)
場所:神奈川県立生命の星・地球博物館 1階 特別展示室
時間:9:00〜16:30
今回の企画展では、地質写真家 白尾 元理(しらお もとまろ)氏が世界各地で撮影した様々な地形や地質景観の写真 54点に、関連する岩石、化石を加えて紹介します。 地球上には驚いたり、不思議に感じたりする地形や地層、岩石が数多くあります。それらは火山の噴火活動や、大地の隆起や浸食、水や風による運搬や堆積など、地球のさまざまな営みによってできてきたものです。地球が46億年という長い歴史の中でおこなってきた、壮大な「しごと」の数々を、白尾氏撮影の写真と実物標本でお楽しみください。
富草の化石-近藤コレクションを中心に- (長野県 飯田市美術博物館)
期間:10/25(土)〜2/15(日)
場所:飯田市美術博物館
1800万年前、県南地域に広がった暖かい海の地層からでる化石を紹介します。
ようこそ恐竜ラボへ!〜化石の謎をときあかす〜 (宮城県 財団法人斎藤報恩会、NHK仙台放送局、NHKプラネット東北、読売新聞社)
期間:1/10(土)〜3/08(日)
場所:斎藤報恩会自然史博物館
今はいない恐竜たちのことがどうしてわかるんだろう?」化石を発掘して調べ、新しい事実を見つけ出し、恐竜のすがたを明らかにしていく.そんな恐竜研究の世界がわかる展示です。林原自然科学博物館が行っている、モンゴルでの発掘調査や化石のプレパレーションに基づいて、恐竜研究のようすをお伝えします.よみがえった恐竜たち」のコーナーでは、ティラノサウルス他,恐竜の全身骨格を展示しています.これらの標本が経てきた研究の過程も考えながらお楽しみください。
1月のイベント
2009/01/06 現在
日付
イベント
1/06
(火)
1/07
(水)
1/08
(木)
1/09
(金)
1/10
(土)
化石レプリカ教室 (北海道 釧路市立博物館)
場所:釧路市立博物館
時間:13:30〜15:00
浜中町産アンモナイトからとった型に石膏を流し込み、実物を見ながら絵の具で着色します。当日はパレットと絵筆を持参してください。材料費200円
釧路市立博物館(0154-41-5809)まで電話で申し込み。
博物館教室「地層をしらべよう〜地質調査の基礎〜」 (神奈川県 横須賀市自然・人文博物館)
場所:横須賀市自然・人文博物館本館
三浦半島をつくる地層の大部分は深海底でつくられ,約50万年前に陸地になりました.この講座では,これらの地層を調べ,地質図を作成するための基礎的な方法を学びます.室内での作業と野外での実習を行いますが,今年度は特にクリノメーターの使い方を重点的に学習します.定員各10名。
1/11
(日)
1/12
(月)
成人の日
1/13
(火)
1/14
(水)
1/15
(木)
1/16
(金)
1/17
(土)
ミクロの世界(土曜日だ博物館に行こう) (熊本県 御船町恐竜博物館)
場所:御船町恐竜博物館
時間:9:00〜
肉眼で見えない世界を電子顕微鏡や光学顕微鏡で観察します。
当日受付となります。小中学生対象(定員30名) 参加費 無料(ただし、入館料が必要)
1/18
(日)
室内実習 ミクロの世界−電子顕微鏡で化石を見よう!2 (徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島県立博物館 実習室
一見何のへんてつもない泥岩などの堆積岩の中には、奇妙で複雑な形をした小さな(大きさ1mm以下)化石がたくさんうずもれています。この行事では、このような小さなサイズの化石をじっくり観察します。数百倍から数千倍の倍率が出せる走査型電子顕微鏡を使います。参加者には、ピント合わせや倍率の切り替えなどのかんたんな操作や、化石の写真撮影も行ってもらいます。
往復葉書に行事名,参加希望者全員の氏名,住所,電話番号を書いて1月8日までにお申し込みください。
1/19
(月)
1/20
(火)
1/21
(水)
1/22
(木)
六甲山の地形・活断層・上昇過程 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:クラーク記念国際高校芦屋キャンパス
時間:13:10〜14:00
六甲と阪神間の地形と地質構造の解読から、六甲はいつ頃からどうして高くなったのかがわかります。六甲と阪神間の地学環境と生い立ちのアウトラインを紹介。
1月6日(火)締め切り。受講料500円
1/23
(金)
「ミクロの宝石 珪藻」(地学セミナー) (熊本県 御船町教育委員会・御船町恐竜博物館)
場所:御船町カルチャーセンター
時間:(1/23) 19:00〜20:30 (1/24) 13:00〜15:00
講演「ミクロの珪藻化石に記録された気候・環境変動」講師 九州大学大学院 比較社会文化学府 特別研究者 林 辰弥 博士
実習「観察資料作製法と観察」(講義参加者のみ)
対象 大人(高校生以上) 定員 講義50名 実習10名 参加費 無料
参加受付 平成21年1月23日まで ※実習に参加するためには講義への参加が必要。
1/24(土)まで
1/24
(土)
博物館教室「地層をしらべよう〜地質調査の基礎〜」 (神奈川県 横須賀市自然・人文博物館)
場所:横須賀市自然・人文博物館本館
三浦半島をつくる地層の大部分は深海底でつくられ,約50万年前に陸地になりました.この講座では,これらの地層を調べ,地質図を作成するための基礎的な方法を学びます.室内での作業と野外での実習を行いますが,今年度は特にクリノメーターの使い方を重点的に学習します.定員各10名。
「サンゴ礁化石で学ぶ気候変動」 (東京都 杉並区立科学館)
場所:杉並区立科学館
時間:13:00〜15:15
講師:川辺文久・三村麻子(杉並区立科学館)
専用申込用紙(館内で配付 ※ホームページからダウンロード可能)又は、ハガキに「参加希望講座の名称・日時・住所・氏名・年齢・電話番号」を記入の上、開催日前日(必着)までに、科学館へ郵送(〒167-0033 杉並区清水3丁目3番13号)もしくはFAX(03-3396-4393)でお申込み下さい。(定員になり次第締切)
「地質時代の海洋生物地理から読み解く生物進化」 (東京都 杉並区立科学館)
場所:杉並区立科学館
時間:15:30〜17:00
対象は高校生以上。定員は50名(先着順)。参加費無料。講師:伊庭靖弘(東京大学)
直接会場へお越しください
1/25
(日)
1/26
(月)
1/27
(火)
1/28
(水)
1/29
(木)
1/30
(金)
1/31
(土)
いん石をさぐる (神奈川県 神奈川県立生命の星・地球博物館)
場所:生命の星・地球博物館
時間:10:00〜15:00
いん石について常設展示をはじめ博物館にある標本を用いて観察を行い、その特徴を探っていきます。児童・生徒向けの講座です。
小学4年生〜高校生と保護を対象とした申し込み制の講座です。
大人向けおすすめ講座「地層と地形のできかた実験」 (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館研修室
時間:10:00〜15:00
地層のできかたを実験水路や剥ぎ取り標本を使って説明します。
地層と地形のでき方実験 (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館 研修室
時間:10:00〜15:00
水路実験のエキスパート,元筑波大学陸域環境センターの池田 宏先生をお招きしています。水路実験と先生のやさしい解説からいかに地形が形成されるか、また、地層はどうしてできるかを、楽しく学べます。
定員:20名(中学生以上)、締め切りは1月17日(土)、応募者多数の場合は抽選となります。
2/01
(日)
2/02
(月)
2/03
(火)
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ内のフォームまたはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。随時、情報を更新いたしますので,ご協力をお願いいたします。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
2008年フィリピン大会の軌跡
2008年フィリピン大会の軌跡
本大会に備えて
神奈川県生命の星・地球博物館での研修の様子
研修の宿泊所で本大会の発表準備
研修日2日目、岩石標本で復習
特別許可をもらって展示物で走向傾斜の測定練習
いよいよ本大会!フィリピンへ
初日の夜の歓迎会
開会式後の昼食会
各国役員による実技試験の問題作成の様子
試験終了後のロビーでカラオケ大会
フィールドへ
マヨン火山でのフィールドワークへ出発(マニラ空港で)
マヨン火山近くの風景(飛行機から)
マヨン火山をバックに記念撮影(レガスピ空港で)
フィールドワークにはミニバスで
各国混合チームでフィールドワーク
マヨン火山のふもとのジャングルで
ココナツジュースで一息
マヨン火山のふもとの集落
フィールドワーク;地元の人にインタヴュー
日本チームで記念撮影
地熱発電所の見学ひとコマ
地元の小学生による歓迎ダンス
日本チームの面々
フィールドワーク賞と金銀銅メダル
大会参加証明書
出場された代表の皆さん、関係者の皆様ほんとうにお疲れ様でした。初出場にして輝かしい成果を収められたことを心よりお祝い申しあげます。
普及教育活動
普及教育活動
■ 地学教育の取り組み
■ 地質の日
■ 博物館イベント情報
■ ジオパーク
■ 地学オリンピック
■ 地層命名の指針
■ 地震火山地質サマースクール
■ その他
○県の石
地学研究発表会
ジュニアセッション(旧小さなEarth Scientistのつどい):小,中,高校生徒「地学研究」発表会
日本地質学会地学教育委員会では,地学普及行事の一環として,地学教育の普及と振興を図ることを目的として,学校における地学研究を紹介する「地学研究」発 表会を行っています.小・中・高等学校の地学クラブの活動,および授業の中で児童・生徒が行った研究を,年会のポスター会場内の特設コーナーで発表して頂 きます.同時並行で研究者の発表も行われますので,児童・生徒同士のみならず,研究者との交流もできます.この会を通じて生徒,研究者,市民の交流が進 み,地質学,地球科学への理解が深まって,未来を担う生徒たちの学習意欲への良い刺激と励みになることを願っております.なお,参加証とともに,優秀な発 表に対しては審査のうえ,「優秀賞」を授与いたします.
過去の大会報告
※2021年大会以降は,要旨が閲覧できます
2025年熊本大会
2024年山形大会
第22回 ジュニアセッション
2023年京都大会
第21回 ジュニアセッション
2022年早稲田大会
第20回 ジュニアセッション
2021年(WEB)
第19回 ジュニアセッション
2020年(代替企画)
第18回 ジュニアセッション
2019年札幌大会
第17回小さなEarth Scientistのつどい
2018年札幌大会
第16回小さなEarth Scientistのつどい
2017年愛媛大会
第15回小さなEarth Scientistのつどい
2016年東京大会
第14回小さなEarth Scientistのつどい
2015年長野大会
第13回小さなEarth Scientistのつどい
2014年鹿児島大会
第12回小さなEarth Scientistのつどい
2013年仙台大会
第11回小さなEarth Scientistのつどい
2012年大阪大会
第10回小さなEarth Scientistのつどい
2011年水戸大会
第9回小さなEarth Scientistのつどい
2010年富山大会
第8回小さなEarth Scientistのつどい
2009年岡山大会
第7回小さなEarth Scientistのつどい
2008年秋田大会
第6回小さなEarth Scientistのつどい
※学校関係者に本賞の内容とレベルが正しく理解していただけるよう,学会が正式に与える賞であることが誤解なく伝わるように,「日本地質学会ジュニアセッション」に名称変更することなりました.(2019年11月)
教師巡検
教師巡検
日本地質学会地学教育委員会では,年会のたびに教師向けの巡検を行っています。
■2013年仙台大会:「仙台の大地の成り立ちを知る」
■2012年大阪大会:「大阪の津波碑と地盤沈下対策」
■2011年水戸大会:「地層を見る・はぎ取る・作る」
■2010年富山大会:「糸魚川ジオパーク ヒスイ探訪ジオツアー」
■2009年岡山大会:「万成石と文化地質学」
■2008年秋田大会:「地学教育の素材としての男鹿半島」
地学研究発表会(2008秋田)
小さなEarth Scientistのつどい〜第6回小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜(2008秋田)
会場風景
表彰式の様子
秋田大会2日目の9月21日に,日本地質学会地学教育委員会の主催で「小さなEarth Scientistのつどい 〜第6回小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜」(秋田大会の関連行事)がおこなわれた.年会における発表会は5年前の静岡大会からおこなわれており,今回で6回目となった.この発表会の目的は,地学普及の一環として学校における地学研究を紹介することで地学教育の奨励と振興を図ることと,地学を研究する児童・生徒と研究者の交流が進み,地球科学普及の一助となることである.これまでの生徒発表会の経過は,地質学雑誌4月号に掲載された三次・小泉の総説で報告しているので,そちらをご覧頂きたい.
今年も年会のポスターセッション会場の半分程度を発表会場として利用させてもらっていることから,秋田大会2日目に参加されたほとんどの会員の方は発表会場に足を運ばれたことと思う.コアタイムの時間帯には,かわいい児童達が自分たちの研究成果を緊張しながら発表する光景を,多くの会員にご覧いただいたことと思われる.秋田大会では,小学校4校,高等学校6校から,あわせて11件の発表があった.札幌大会に比べて発表件数は減ったが,地元秋田県からの発表が多かったことが特筆できる.このことは,秋田県内の多くの会員が本発表会のためにご尽力頂いたためである.また,2年前より優秀発表に対して優秀賞を授与しており,審査の結果,下に示す2件の発表に対して優秀賞が授与されている.
秋田大会は無事に終了したが,次回発表会への課題として,優秀賞を含めた賞の審査方法や,賞を出すことの必要性などが地学教育委員会内で検討されている.優秀賞を含め本生徒発表会の実施方法にご意見のある方は,学会事務局(main@geosociety.jp)または地学教育委員会担当者にご連絡頂けたら幸いである.
最後となったが,発表会を実施するにあたり後援をいただいた秋田県教育委員会および秋田市教育委員会,会場校である秋田大学と東北支部の関係各位,さらに今回の発表会参加者に謝意を表したい.
優秀賞 能代市立渟城南小学校野発表の様子
優秀賞 加古川東高等学校野発表ポスター
優秀賞を受賞した発表:
1.「マグマ残液流体相と風化変質作用が凝灰岩に与えた影響〜高級石材「竜山石」の成因〜」
:藤本さやか・宮脇彩絵子・原 由洋(兵庫県立加古川東高等学校地学部岩石鉱物班)
2. 「滝ノ間海岸に見られる不思議な穴」:大塚亘恭・藤原佑馬・梅田圭太(能代市立渟城南小学校)
発表会参加校:秋田県立新屋高等学校,秋田県立横手高等学校,八峰町立岩館小学校,八峰町立八森小学校,能代市立渟城南小学校,能代市立渟城西小学校,大阪府立花園高等学校,愛知教育大学附属高等学校,兵庫県立加古川東高等学校,早稲田大学高等学院
(大分大学教育福祉科学部 三次徳二)
教師巡検(2008秋田)
教師巡検(2008秋田)C班:地学教育の素材としての男鹿半島
案内者:藤本幸雄・林信太郎・渡部 晟・渡部 均・栗山知士・小田嶋博・西村隆・阿部雅彦
参加者:松田義章・八島道子・鹿野勘次・小林治朗・小滝篤夫・細谷政夫・大友幸子・中井 均・飯島 力・成田 盛・青木秀則・河本和朗・大串健一・古野邦雄・長澤一雄・大場 總・北沢久和・山本和美・夏井興一・藤原 崇・佐藤和子・佐々木修一・佐々木 衡・佐藤三七(25名)
【案内者報告】
快晴の入道崎にて
晴天に恵まれた中,参加者33名(全国からの会員18名,秋田地学教育学会員7名,案内者8名)が大型バス1台で,地質学の自然博物館といえる男鹿半島を回った.11カ所の見学地点での観察,及びバスの中での解説を通して,東北地方日本海側のおよそ9000万年の地史を代表する地質や地形に触れることができ,たいへんエキサイティングな巡検になった.
最初の見学地点の寒風山では,噴火や火山地形の変遷について,案内者の一人,秋田大学の林教授による解説があった.スケッチブックにクレヨンで描いたイラストを用いた手法は,わかりやすく,しかも風に強いというメリットがあり,参加者一同大喜びしながら見学した.この手法は地元小学生に対する出前授業で使用しているそうで,いろいろな野外観察の際に応用できそうである.
寒風山山頂でスケッチブックを使っての説明。
その後,午前中は安田(あんでん)海岸,西黒沢海岸,入道崎と,時代をさかのぼる順にたどって見学を行った.安田海岸では,高さ20m以上の海食崖が数kmにわたって続く様子に圧倒されながら,第四紀の鮪川(しびかわ)層,潟西層を見学した.ここでは,広域火山灰の発見・同定により,地層の堆積年代が詳しく求められており,例えば海岸の砂浜を数十m(白頭山−男鹿火山灰と阿蘇1火山灰の間)を歩くだけで,20万年分歩いたことになると知り,地質時代のタイムスケールを実感できた.なお,今回の地質学会にあわせ,山形大学のグループが表土を除いていてくださったようで,たいへんよく火山灰層を観察することができた.
男鹿半島の地質見学ポイントには,男鹿市教育委員会による説明看板が設置されており,一般の観光客にも男鹿半島の地質をわかりやすく解説している.今回は入道崎の説明板の前で,参加者全員が仲良く集合して写真撮影した.
午後は男鹿半島西海岸を南下しながら,目潟火山,戸賀火山,海成段丘について,また,門前層や台島層の第三紀火成岩類や化石を含む地層の堆積環境について,最近の研究成果をもとにした解説を聞くことができた.続いて,南海岸を東に向かい,門前,台島,女川(おんながわ),船川,脇本と,代表的地層の模式地を古い方から新しい方へとたどった.鵜ノ崎海岸の波食台では女川層の硬質頁岩を割って魚化石を探したが,時間不足もあってなかなか状態のよい化石がみつからなくて残念だった.その後16時過ぎに男鹿半島での見学を終え,出発地点の秋田大学には17時半に到着した.
本来は2日以上必要な行程を1日で回るというハードな日程であったが,参加者はみんな積極的に見学し,核心をついた質問等も多かった.男鹿半島は地質を学ぶ研究者が一度は見学に来る場所であり,私も何度か訪れていたが,今回の見学会では,最新の研究成果により,地層の年代をはじめ,実に多くの新しい知見に触れることができた.また,地学教育という視点からも,児童生徒への地質現象の見せ方,説明方法など,参考になる点が多く,たいへん有意義な見学会であった.
(秋田中央高校 渡部 均)
【参加者感想】教えてはいけない男鹿半島
秋田地学教育学会への入会申し込みをした翌日に,日本地質学会第115年学術大会見学旅行に参加させていただいたうえ,感想文を書く初仕事を頂戴するなんて…どう表現したらよいのでしょう.林信太郎先生,ありがとうございます.
私は,大学院生であり小学校教員でもあります.ですので,今回の男鹿巡検は二つの視点から考えることができました.この感想文は,形式にとらわれず自由に書いてよいとのことだったので,地質学的に見てずれた意見を述べるかもしれませんが,それは初仕事ということでお許し下さい.
まずは,学生の目から見た男鹿半島です.まさに,男鹿半島は地質の博物館です.学ぶべき点が無数にあります.半島を回るだけで,これだけ連続した地層が観察できるなんて他地域から調査に訪れる方々が多いのもうなづけます.実は,大学院に来るまでこういう事実を知りませんでした.ゴジラ岩も,今回初めて見ました.秋田県民なのに,身近すぎて気づかなかった自分が恥ずかしくもありました.
次に,小学校教員から見た男鹿半島です.これは,もしかしたら「教えてはいけない」半島なのかも知れません.鮪川層の傾斜,亜炭層に挟まれた戸賀の軽石,西黒沢の暖かい海に生息していた生物の化石,何段にも並ぶきれいな段丘面,ツインピークの寒風山…これらに「なぜ」をつけたら,子どもたちは自由に予想や仮説を立て,自分たちなりに調べようとするような気がしました.いつも見ている風景にも,科学的に価値のある謎がある.そんな経験をさせ,そんな眼をした子どもを育てるジオパークに男鹿半島がなったら素敵だなと感じました.
最後に,丁寧なご説明とお世話をしてくださった秋田地学教育学会の諸先生方と,生まれて初めて「学会」というものの雰囲気を味わわせてくださった日本地質学会の皆様にあらためて感謝申し上げ,初仕事を終えさせていただきます.
(秋田大学大学院教育学研究科教科教育専攻理科教育専修 佐々木修一)
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2009年2月)
2月のイベント・特別展示カレンダー (2009/02/03〜2009/03/02)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。
なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
2月の特別展示
2009/02/03 現在
ぽけっと企画展「地球と生命」 (福岡県 北九州市立いのちのたび博物館 )
期間:5/10(土)〜12/31(木)
場所:北九州市立いのちのたび博物館 ポケットミュージアム No. 1
自然の変化に対応してきた、絶えることのない生命の継続性と神秘性を化石や自然史資料を用い紹介します。
ようこそ恐竜ラボへ!〜化石の謎をときあかす〜 (宮城県 財団法人斎藤報恩会、NHK仙台放送局、NHKプラネット東北、読売新聞社)
期間:1/10(土)〜3/08(日)
場所:斎藤報恩会自然史博物館
今はいない恐竜たちのことがどうしてわかるんだろう?」化石を発掘して調べ、新しい事実を見つけ出し、恐竜のすがたを明らかにしていく.そんな恐竜研究の世界がわかる展示です。林原自然科学博物館が行っている、モンゴルでの発掘調査や化石のプレパレーションに基づいて、恐竜研究のようすをお伝えします.よみがえった恐竜たち」のコーナーでは、ティラノサウルス他,恐竜の全身骨格を展示しています.これらの標本が経てきた研究の過程も考えながらお楽しみください。
コラボ特別展with新潟大学 「頭足類展 アンモナイトとその仲間たち」 (新潟県 フォッサマグナミュージアム、新潟大学)
期間:11/29(土)〜3/31(火)
場所:フォッサマグナミュージアム 展望廊下
アンモナイト、ベレムナイト、オウムガイ、イカ、タコなどの頭足類の分類、生態、進化について、国内・国外の標本により紹介する展示会です。展示標本には学生・院生が研究の過程で採集したものが多く、化石の研究の実例紹介もあります。
企画展示「天神島周辺の地質」 (神奈川県 横須賀市自然・人文博物館)
期間:10/11(土)〜3/29(日)
場所:天神島ビジターセンター
神奈川県横須賀市の天神島から長者ヶ崎にかけては,三崎層や逗子層,立石層,葉山層など,異なった時代の地層が複雑に分布しています.この企画展示では,これらの地層と,地層に見られるさまざまな地質構造について紹介します.
企画展「46億年 地球のしごと〜地質写真家が見た世界の地形〜」 (神奈川県 神奈川県立 生命の星・地球博物館)
期間:12/06(土)〜2/22(日)
場所:神奈川県立生命の星・地球博物館 1階 特別展示室
時間:9:00〜16:30
今回の企画展では、地質写真家 白尾 元理(しらお もとまろ)氏が世界各地で撮影した様々な地形や地質景観の写真 54点に、関連する岩石、化石を加えて紹介します。
地球上には驚いたり、不思議に感じたりする地形や地層、岩石が数多くあります。それらは火山の噴火活動や、大地の隆起や浸食、水や風による運搬や堆積など、地球のさまざまな営みによってできてきたものです。地球が46億年という長い歴史の中でおこなってきた、壮大な「しごと」の数々を、白尾氏撮影の写真と実物標本でお楽しみください。
富草の化石-近藤コレクションを中心に- (長野県 飯田市美術博物館)
期間:10/25(土)〜2/15(日)
場所:飯田市美術博物館
1800万年前、県南地域に広がった暖かい海の地層からでる化石を紹介します。
2月のイベント
2009/02/03 現在
日付
イベント
2/03(火)
2/04(水)
2/05(木)
2/06(金)
2/07(土)
博物館教室「地層をしらべよう〜地質調査の基礎〜」 (神奈川県 横須賀市自然・人文博物館)
場所:横須賀市自然・人文博物館本館
三浦半島をつくる地層の大部分は深海底でつくられ,約50万年前に陸地になりました.この講座では,これらの地層を調べ,地質図を作成するための基礎的な方法を学びます.室内での作業と野外での実習を行いますが,今年度は特にクリノメーターの使い方を重点的に学習します.定員各10名。
2/08(日)
2/09(月)
2/10(火)
2/11(水)建国記念の日
2/12(木)
2/13(金)
2/14(土)
2/15(日)
地質図の読み方 (埼玉県 埼玉県立自然の博物館)
場所:埼玉県立自然の博物館
埼玉県地質図を題材に、地質の読み方の基本を学びます。
実施日の1ヶ月前から2週間前(当館必着)が申込受付期間です。e-mailまたは往復はがきで受け付けます。
2/16(月)
2/17(火)
2/18(水)
2/19(木)
2/20(金)
2/21(土)
博物館教室「地層をしらべよう〜地質調査の基礎〜」 (神奈川県 横須賀市自然・人文博物館)
場所:横須賀市自然・人文博物館本館
三浦半島をつくる地層の大部分は深海底でつくられ,約50万年前に陸地になりました.この講座では,これらの地層を調べ,地質図を作成するための基礎的な方法を学びます.室内での作業と野外での実習を行いますが,今年度は特にクリノメーターの使い方を重点的に学習します.定員各10名。
2/22(日)
2/23(月)
2/24(火)
2/25(水)
2/26(木)
2/27(金)
2/28(土)
「アンモナイトで学ぶ気候変動」 (東京都 杉並区立科学館)
場所:杉並区立科学館
時間:13:00〜15:15
講師:川辺文久・三村麻子(杉並区立科学館)
専用申込用紙(館内で配付 ※ホームページからダウンロード可能)又は、ハガキに「参加希望講座の名称・日時・住所・氏名・年齢・電話番号」を記入の上、開催日前日(必着)までに、科学館へ郵送(〒167-0033 杉並区清水3丁目3番13号)もしくはFAX(03-3396-4393)でお申込み下さい。(定員になり次第締切)
「解剖学的復元から探る恐竜類の環境適応」 (東京都 杉並区立科学館)
場所:杉並区立科学館
時間:15:15〜17:00
対象は高校生以上。定員は50名(先着順)。参加費無料。講師: 對比地孝亘(国立科学博物館)
直接会場へお越しください
3/01(日)
早春の地形地質観察会 (神奈川県 神奈川県立生命の星・地球博物館)
場所:生命の星・地球博物館
時間:10:00〜15:30
史跡として有名な石垣山周辺の地層を見学しながら、一夜城公園まで登ります。視界がよければ公園で大磯丘陵の地形スケッチを行います。
小学4年生〜大人を対象とした申し込み制の講座です。
3/02(月)
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ内のフォームまたはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。随時、情報を更新いたしますので,ご協力をお願いいたします。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2009年3月)
3月のイベント・特別展示カレンダー (2009/03/03〜2009/03/31)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
3月の特別展示
2009/03/03 現在
ようこそ恐竜ラボへ!〜化石の謎をときあかす〜 (宮城県 財団法人斎藤報恩会、NHK仙台放送局、NHKプラネット東北、読売新聞社)
期間:1/10(土)〜3/08(日)
場所:斎藤報恩会自然史博物館
今はいない恐竜たちのことがどうしてわかるんだろう?」化石を発掘して調べ、新しい事実を見つけ出し、恐竜のすがたを明らかにしていく.そんな恐竜研究の世界がわかる展示です。林原自然科学博物館が行っている、モンゴルでの発掘調査や化石のプレパレーションに基づいて、恐竜研究のようすをお伝えします.よみがえった恐竜たち」のコーナーでは、ティラノサウルス他,恐竜の全身骨格を展示しています.これらの標本が経てきた研究の過程も考えながらお楽しみください。
コラボ特別展with新潟大学 「頭足類展 アンモナイトとその仲間たち」 (新潟県 フォッサマグナミュージアム、新潟大学)
期間:11/29(土)〜3/31(火)
場所:フォッサマグナミュージアム 展望廊下
アンモナイト、ベレムナイト、オウムガイ、イカ、タコなどの頭足類の分類、生態、進化について、国内・国外の標本により紹介する展示会です。展示標本には学生・院生が研究の過程で採集したものが多く、化石の研究の実例紹介もあります。
企画展示「天神島周辺の地質」 (神奈川県 横須賀市自然・人文博物館)
期間:10/11(土)〜3/29(日)
場所:天神島ビジターセンター
神奈川県横須賀市の天神島から長者ヶ崎にかけては,三崎層や逗子層,立石層,葉山層など,異なった時代の地層が複雑に分布しています.この企画展示では,これらの地層と,地層に見られるさまざまな地質構造について紹介します.
3月のイベント
2009/03/03 現在
日付
イベント
3/03
(火)
3/04
(水)
3/05
(木)
3/06
(金)
3/07
(土)
博物館教室「地層をしらべよう〜地質調査の基礎〜」 (神奈川県 横須賀市自然・人文博物館)
場所:横須賀市自然・人文博物館本館
三浦半島をつくる地層の大部分は深海底でつくられ,約50万年前に陸地になりました.この講座では,これらの地層を調べ,地質図を作成するための基礎的な方法を学びます.室内での作業と野外での実習を行いますが,今年度は特にクリノメーターの使い方を重点的に学習します.定員各10名。
3/08
(日)
入間川にアケボノゾウのふるさとを訪ねる (埼玉県 埼玉県立自然の博物館・埼玉県立自然の博物館友の会)
場所:入間市付近の入間川
時間:13:00〜15:30
入間川沿いに見られる地層と化石の産地を訪ねます。
実施日の1ヶ月前から2週間前(当館必着)が申込受付期間です。e-mailまたは往復はがきで受け付けます。
石を通して地域を知るー地球と大気の歴史 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:兵庫県立人と自然の博物館
時間:13:30〜15:30
46億年前の地球誕生から、現在の地球環境ができるまで、地球・大気の変化は生物を進化させ、生物の進化は地球環境を変化させてきました。このセミナーでは、このような「地球と生命の共進化」について、岩石を観察しながら解説します
2月16日(月)締め切り。受講料500円(中学生以下300円)
3/09
(月)
3/10
(火)
3/11
(水)
3/12
(木)
3/13
(金)
3/14
(土)
3/15
(日)
3/16
(月)
3/17
(火)
3/18
(水)
3/19
(木)
3/20
(金)
春分の日
3/21
(土)
ペインティング・ストーン (埼玉県 埼玉県立自然の博物館)
場所:埼玉県立自然の博物館
時間:13:00〜15:30
川原の小石に絵を描き、色を塗り、動物などの飾り物をつくります。
3/22
(日)
3/23
(月)
3/24
(火)
3/25
(水)
3/26
(木)
3/27
(金)
3/28
(土)
3/29
(日)
3/30
(月)
3/31
(火)
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ内のフォームまたはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。随時、情報を更新いたしますので,ご協力をお願いいたします。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
地質の日特別講演会「火山はすごい」
2009年地質の日(5/10)特別講演会講演会
★5/10:大盛況のうちに講演会は終了いたしました!!★詳しくはコチラ
日本地質学会主催・日本火山学会後援
こどももおとなもみんなで地学をまなびませんか?
火山はすごい!−日本列島の火山をさぐる
カマタ先生のおもしろい火山のお話やQ&Aコーナーもあるよ。質問いろいろ大歓迎!!
講師:鎌田浩毅さん(日本地質学会会員/京都大学人間・環境学研究科 教授)
日時:5月10日(日・地質の日) 15:00-16:45
会場:科学技術館(千代田区北の丸公園2-1 http://www.jsf.or.jp)
会場アクセス:【東京メトロ東西線】「竹橋」1b出口 徒歩7分.「九段下」2番出口 徒歩7分/【東京メトロ半蔵門線】「九段下」2番出口 徒歩7分/【都営地下鉄新宿線】「九段下」2番出口 徒歩7分
定員:90人(小学生から大人まで楽しめます)
参加無料・申込不要(科学技術館を見学される方は、別途入館料が必要となります)
*講演会の前に、新しい「地質の日」ロゴマークの作者(彦根 正さん)の表彰式を予定しています。
■講師紹介■
鎌田先生は、京都大学で教鞭をとられるほか、「科学の伝道師」と言われるほど、地球に関するいろいろな科学的事象をテレビや本で楽しく解説され、私たちに科学の楽しさを伝えてくださいます。今回は、先生のご専門の火山の話について、わかりやすく話していただきます。
<テレビ出演>
NHK総合テレビ「ソクラテスの人事」(第1回)2009年4月2日(木)22:00-22:45
NHK 総合テレビ「課外授業 ようこそ先輩」2009年2月8日
NHK 総合テレビ「爆笑問題のニッポンの教養・京大スペシャル」2008年3月25日
日本テレビ系 全国ネット「世界一受けたい授業」2007年6月16日,2008年7月5日
テレビ朝日系 全国ネット「近未来×予測テレビ ジキル&ハイド」2008年2月3日
<著書>
『地学のツボ』ちくまプリマー新書, 『火山はすごい』PHP新書, 『火山の大研究』PHP研究所(カラー版児童書), 『マグマの地球科学』中公新書,『世界がわかる理系の名著』文春新書 など多数。
HP http://www.gaia.h.kyoto-u.ac.jp/~kamata/
■問い合わせ先■
日本地質学会事務局
電話:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156
e-mail: main@geosociety.jp
*画像をクリックするとA4版チラシのPDFファイルがダウンロードできます。
台湾大会派遣者候補者決定(2009)
台湾大会派遣候補者決定(2009)
2009年3月29日(日曜日)に東京大学にて第3回国際地学オリンピック第二次選抜試験(第1回日本地学オリンピック本選)が行われました。地質・気象・天文の3分野の実技試験と面接の結果、以下の結果になりました。
また、優秀賞・最優秀賞受賞者への表彰式が、5月17日(日)に日本地球惑星科学連合大会会場内にて開催されました。
■最優秀賞 (第3回国際地学オリンピック台湾大会派遣候補者)
冨永 紘平 埼玉県立川越高等学校 3年生
長野 玄 灘高等学校 2年生
槇野 祐大 灘高等学校 2年生
宮崎 慶統 聖光学院高等学校 3年生
■優秀賞
関澤 偲温 栄光学園高等学校 3年生
野田 和弘 広島学院高等学校 2年生
高村 悠介 埼玉県立川越高等学校 2年生
諏訪 敬之 灘高等学校1年生
・通信研修(5月-8月)、合宿研修’7月下旬の2泊3日)の後、9月14日〜22日まで、台湾で開催される第3回国際地学オリンピックに臨みます。
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2009年4・5月)
4・5月のイベント・特別展示カレンダー (2009/04/21〜2009/05/31)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
4・5月の特別展示
2009/04/22 更新
春の特別展 「五百澤智也 山のスケッチとフィールドノート」 (茨城県 産業技術総合研究所 地質標本館)
期間:4/14(火)〜7/05(日)
場所:産業技術総合研究所 地質標本館
地理学者・地図作家である五百澤智也氏は、ヒマラヤや日本の山の精巧なスケッチを数多く制作しています。地質標本館では作品の科学的な側面にスポットをあて、鳥瞰図に描かれた富士山と槍穂高連峰の地形・地質を解説します。また、ヒマラヤの氷河調査で使われたフィールドノートを展示します。
トピックス展示「博物館資料からよみがえった翼竜化石」 (神奈川県 横須賀市自然・人文博物館)
期間:4/11(土)〜7/12(日)
場所:横須賀市自然・人文博物館 1階
このたび、アンモナイトとして収蔵されていた化石資料が、翼竜の化石であることが明らかになりました。ここではその化石を紹介し、中生代の大空を飛んでいた爬虫類である翼竜について解説します。
第32回企画展「わかった!かわった?群馬の自然」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
期間:3/14(土)〜5/06(水)
場所:群馬県立自然史博物館 企画展示室
群馬県立自然史博物館がこれまでに実施した、県内の生物、地質、古生物に関する 調査や研究の成果を紹介します。観覧料は一般600円、高・大学生300円(常設展を含む)
大恐竜展〜知られざる南半球の支配者〜 (東京都 国立科学博物館)
期間:3/14(土)〜6/21(日)
場所:国立科学博物館
日本発上陸のゴンドワナ大陸の恐竜が集まる。
百年前の大震災〜姉川地震に学ぶその備え〜 (滋賀県 滋賀県立琵琶湖博物館・滋賀県防災危機管理局)
期間:4/25(土)〜6/07(日)
場所:琵琶湖博物館 企画展示室
この展示では、100年前におきた姉川地震について、当時の災害写真をもりこみながら解説し、日本の地震がどうやっておきているかなどの自然科学的な解説と、現在の地震防災の取り組みを紹介します。また、ゴールデンウィーク期間中には、地震体験もできます。
“国際博物館の日”記念企画展「石板アートギャラリー」 (静岡県 奇石博物館)
期間:4/25(土)〜7/12(日)
場所:奇石博物館 企画展示室
板状の石を一堂に集め、その美しさや科学的な意味などをご紹介します。
シーラカンス展−ブラジルの化石と大陸移動の証人たち− (徳島県 徳島県立博物館)
期間:4/25(土)〜6/14(日)
場所:徳島県立博物館 企画展示室(1階)
ブラジルから産出するシーラカンスなどの化石は、南アメリカとアフリ カがかつて一つの大陸であったことを示す重要な証人といってよいでしょう。 この企画展では、生きている化石として知られるシーラカンスやブラジル産の 魚類化石を通して、大陸移動や大西洋ができ始めた頃の海の様子、かつて地球 上にパンゲアと呼ばれる一つの大陸があったことをご紹介します。
丹波の恐竜を知ろう −3年間の発掘報告− (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
期間:4/25(土)〜5/31(日)
場所:兵庫県立人と自然の博物館
兵庫県丹波市で見つかった恐竜化石について3年間の発掘成果を展示し、恐竜について、遊びながら学べるいくつかのイベントを実施します。
地質の日記念ミニ展示 地質図を見よう (埼玉県 埼玉県立自然の博物館)
期間:5/01(金)〜5/17(日)
場所:埼玉県立自然の博物館展示室
埼玉県に関係する地質図を展示する
収蔵資料紹介展「足元の地面を探る」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
期間:4/25(土)〜6/14(日)
場所:豊橋市自然史博物館 イントロホール
中央構造線露頭のはぎとり標本やボーリングコアサンプル、巨大な圧力をうけて生じたくいちがい石など、地面の下を探る方法や大地の動きを示す資料等を紹介します。
世界ジオパーク展 −日本最初の認定地をめざす糸魚川− (新潟県 新潟県、糸魚川市教育委員会博物館)
期間:4/25(土)〜
場所:フォッサマグナミュージアム ふるさと展示室
世界ジオパークをめざす糸魚川の多様な大地とそれらが育んだ動植物、文化財などを紹介しています。野外のジオサイトへ出かけて大地の魅力を感じてみてください。
「桐生で発見!古生代の新種腕足類」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
期間:5/09(土)〜6/21(日)
場所:群馬県立自然史博物館エントランス(無料のゾーンです)
4・5月のイベント
2009/04/20 現在
日付
イベント
4/21
(火)
4/22
(水)
4/23
(木)
4/24
(金)
4/25
(土)
山頂の巨石めぐり−阿南町丸山(1484m) (長野県 伊那谷自然友の会)
場所:長野県阿南町
時間:7:00〜16:00
シャクナゲの山として名高い丸山の山頂には巨大な石が群がっている。不思議な山だ。山頂からの展望も良い。登山口から標高差550mをゆっくり登る。
1. 行事名、2. 参加希望者全員の氏名と住所、3. 電話番号を、行事予定日前日までに、飯田市美術博物館気付伊那谷自然友の会事務局(0265-22-8118)まで申し込む。
化石採集教室 (栃木県 佐野市葛生化石館)
場所:佐野市内化石産地
時間:9:30〜15:00
佐野市では化石が豊富に産出する。市内の化石産地に赴き、実際に現場で採集体験を行う。
小学生5年以上、定員20名。保険料として100円。化石館へ直接来ていただくか、電話・メールにて。〆切は4月12日
4/26
(日)
石めぐりハイキング−丹生山地と帝釈鉱山− (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:神戸電鉄箕谷駅前9時30分集合
時間:9:30〜16:00
神戸市北区、丹生山地の地質観察と帝釈鉱山の鉱物採集をします。
4月6日締切。小学校高学年〜大人 30名 参加費:高校生以上500円、中学生以下300円
「地質の日」記念、化石発掘体験 (長野県 飯田市美術博物館)
場所:追手町小学校化石標本室
時間:10:00〜16:00
ハンマー・タガネなどを使って、貝など化石の入った岩塊を崩して化石を取り出します。※化石を探し当てられなかった場合も、お土産を差し上げます。参加費:100円
10:00〜16:00の間に随時受付け
4/27
(月)
4/28
(火)
4/29
(水)
昭和の日
今年こそ!多紀アルプス自然探訪 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:JR「篠山口」駅西口集合
時間:9:30〜16:30
多紀アルプスの主峰、三嶽・西ヶ嶽の凹凸した稜線を巡ります。シャクナゲの花や多彩な新緑を楽しみながら、地質構成と地質構造の遠望を通して太古のロマンに迫ります。
4月10日締切。小学校高学年〜大人 25名 参加費高校生以上600円、中学生以下400円
化石レプリカ作り(地質の日記念) (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
アンモナイトや三葉虫などの化石レプリカ作りを体験する。有料:1個100円
恐竜迫力撮影会(地質の日記念) (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
タルボザウルスに食べられているようなアングルで写真が撮れます。
4/30
(木)
化石レプリカ作り(地質の日記念) (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
アンモナイトや三葉虫などの化石レプリカ作りを体験する。有料:1個100円
恐竜迫力撮影会(地質の日記念) (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
タルボザウルスに食べられているようなアングルで写真が撮れます。
5/01
(金)
化石レプリカ作り(地質の日記念) (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
アンモナイトや三葉虫などの化石レプリカ作りを体験する。有料:1個100円
恐竜迫力撮影会(地質の日記念) (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
タルボザウルスに食べられているようなアングルで写真が撮れます。
5/02
(土)
毛賀沢秘境をたずねる (長野県 伊那谷自然友の会)
場所:長野県飯田市
時間:7:00〜16:00
飯田市内からの丘間を流れる毛賀沢川は、中流部に人が近寄らない秘境がある。新緑の谷を歩いて、最後には念通寺断層の毛賀沢露頭を確かめる。
1. 行事名、2. 参加希望者全員の氏名と住所、3. 電話番号を、行事予定日前日までに、飯田市美術博物館気付伊那谷自然友の会事務局(0265-22-8118)まで申し込む。
サイエンス・サタデー「火山灰から宝石を見つけよう」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 実験室
時間:14:00〜15:00
火山灰の中にある宝石(造岩鉱物)をさがします。定員30人
定員30人、当日会場で直接申し込み[受付13:30〜14:00]、先着順)。対象は小学生以上(小学3年生以下は保護者と参加)、参加費は無料。
化石レプリカ作り(地質の日記念) (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
アンモナイトや三葉虫などの化石レプリカ作りを体験する。有料:1個100円
恐竜迫力撮影会(地質の日記念) (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
タルボザウルスに食べられているようなアングルで写真が撮れます。
ナイトミュージアム(地質の日記念) (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
時間:18:30〜20:15
閉館後の暗くなった館内をめぐり、ナイトミュージアムを体験する。
ホームページ参照
5/03
(日)
憲法記念日
化石レプリカ作り(地質の日記念) (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
アンモナイトや三葉虫などの化石レプリカ作りを体験する。有料:1個100円
恐竜迫力撮影会(地質の日記念) (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
タルボザウルスに食べられているようなアングルで写真が撮れます。
ナイトミュージアム(地質の日記念) (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
時間:18:30〜20:15
閉館後の暗くなった館内をめぐり、ナイトミュージアムを体験する。
ホームページ参照
「地質の日」記念、化石のレプリカをつくろう (長野県 飯田市美術博物館)
場所:飯田市美術博物館
時間:10:00〜16:00
実物の恐竜やアンモナイトなどの化石から型どりした雌型から、超硬石膏でレプリカを作ります。作業時間およそ30分。着色は各自で行いましょう。材料費:1個100円(ネオジム磁石入りは、1個200円)
10:00〜16:00の間に随時受付け
シーラカンス展 展示解説 (徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島県立博物館 企画展示室(1階)
時間:14:00〜14:30
大陸移動の歴史を、シーラカンスやブラジル産の魚類化石を通して、や さしくそして楽しく解説します
5/04
(月)
みどりの日
化石レプリカ作り(地質の日記念) (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
アンモナイトや三葉虫などの化石レプリカ作りを体験する。有料:1個100円
恐竜迫力撮影会(地質の日記念) (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
タルボザウルスに食べられているようなアングルで写真が撮れます。
ナイトミュージアム(地質の日記念) (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
時間:18:30〜20:15
閉館後の暗くなった館内をめぐり、ナイトミュージアムを体験する。
ホームページ参照
「地質の日」記念、化石発掘体験 (長野県 飯田市美術博物館)
場所:追手町小学校化石標本室
時間:10:00〜16:00
ハンマー・タガネなどを使って、貝など化石の入った岩塊を崩して化石を取り出します。※化石を探し当てられなかった場合も、お土産を差し上げます。参加費:100円
10:00〜16:00の間に随時受付け
5/05
(火)
こどもの日
化石レプリカ作り(地質の日記念) (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
アンモナイトや三葉虫などの化石レプリカ作りを体験する。有料:1個100円
恐竜迫力撮影会(地質の日記念) (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
タルボザウルスに食べられているようなアングルで写真が撮れます。
ナイトミュージアム(地質の日記念) (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
時間:18:30〜20:15
閉館後の暗くなった館内をめぐり、ナイトミュージアムを体験する。
ホームページ参照
「地質の日」記念、化石のレプリカをつくろう (長野県 飯田市美術博物館)
場所:飯田市美術博物館
時間:10:00〜16:00
実物の恐竜やアンモナイトなどの化石から型どりした雌型から、超硬石膏でレプリカを作ります。作業時間およそ30分。着色は各自で行いましょう。材料費:1個100円(ネオジム磁石入りは、1個200円)
10:00〜16:00の間に随時受付け
丹波の恐竜化石第三次発掘報告会 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:人と自然の博物館
時間:13:30〜14:30
2006年に丹波市で発見され、その後3年間にわたって発掘がされています。今回は最新の第三次発掘の成果について報告します。
4月15日締切。小学校高学年〜大人 100名 参加費高校生以上500円、中学生以下400円
5/06
(水)
振替休日
化石レプリカ作り(地質の日記念) (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
アンモナイトや三葉虫などの化石レプリカ作りを体験する。有料:1個100円
恐竜迫力撮影会(地質の日記念) (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
タルボザウルスに食べられているようなアングルで写真が撮れます。
石を割ってみよう (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館1階入口前
専用の岩石ハンマーを使って、岩石を割る体験を行います。「地質の日」関連行事
(当日先着順)
化石のレプリカをつくろう! (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:人と自然の博物館
時間:13:30〜15:30
本物の化石から型をとり、石膏を流し込んでレプリカをつくってみませんか?完成したレプリカはお持ち帰りいただけます。
4月14日締切。小学校高学年〜大人 15名 参加費800円
5/07
(木)
5/08
(金)
5/09
(土)
ジオラボ(5月)「火山灰のひみつ」 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:大阪市立自然史博物館 ナウマンホール
時間:10:00〜12:00
その昔、なべの底についたすすを落とすのに、クレンザーの様にして、特別な土が使われていたそうです。その土の正体は、なんと大阪層群の火山灰層です。火山灰が本当にクレンザーのように使えるのか、どうしてなべの底がきれいになるのか、みんなで調べてみましょう。参加費は無料(ただし、博物館入館料が必要)
サイエンス・サタデー「火山灰から宝石を見つけよう」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 実験室
時間:14:00〜15:00
火山灰の中にある宝石(造岩鉱物)をさがします。定員30人
定員30人、当日会場で直接申し込み[受付13:30〜14:00]、先着順)。対象は小学生以上(小学3年生以下は保護者と参加)、参加費は無料。
第26回地球科学講演会「ヒマラヤ山脈の誕生とモンスーン気候の始まり」 (大阪府 大阪市立自然史博物館・地学団体研究会大阪支部・日本地質学会近畿支部)
場所:大阪市立自然史博物館 講堂
時間:14:30〜16:30
★★「地質の日」協賛イベント世界の屋根ヒマラヤはどのようにしてできたのだろう。そしてアジアの気候システムの中核をなすモンスーン気候は、いつ誕生したのだろうか。この2つの研究テーマの解明を目指し、地質学者は様々な障害を乗り越え調査と研究を継続してきました。酸素濃度が半分以下になる5000m以上のエベレスト地域での地質調査や深さ4000mのベンガル扇状地での深海掘削などを通して、これまでの常識を破るヒマラヤ形成史が提唱されています。またヒマラヤ・チベット山塊の誕生によって、モンスーンという気候システムが作られたことも分かってきました。この講演では、ヒマラヤでの地質調査の実体験を交えながら、最近の研究の成果をご紹介します。講師:酒井治孝氏(京都大学大学院理学研究科教授)。参加費は無料(ただし、博物館入館料が必要)
5/10
(日)
地質の日
自然観察会「城ヶ島の地層」 (神奈川県 横須賀市自然・人文博物館)
場所:三浦市城ヶ島
時間:10:00〜15:00
三浦半島の南端に位置する城ヶ島は、地層の露出がよく、さまざまな地層の構造が見られることから、地層の学習には最適な場所の1つです。この観察会では、城ヶ島に見られる地層や断層、堆積構造、地形などを観察しながら、三浦半島の成り立ちと、ダイナミックな地球の姿について考えます。
往復ハガキで申し込む。詳細は博物館ホームページを参照。
ファミリー自然観察会「吾妻峡の岩石と植物」」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:吾妻峡(群馬県長野原町、東吾妻町)
時間:9:00〜12:00
吾妻峡に見られる様々な岩石や植物を観察します。
現地集合、小学生以下は保護者と一緒に参加(高学年以上向け)、参加費50円 (保険料)、2週間前までにハガキで申し込み(観察会タイトル、参加者全員の住所、氏名、年齢、電話番号を記入)。応募者多数の場合は抽選。ハガキは一家族一通でお願いします。
地質の日記念観察会 長瀞・皆野付近の地質を訪ねる (埼玉県 埼玉県立自然の博物館)
場所:長瀞・皆野付近
長瀞〜親鼻橋付近の変成岩と蛇紋岩の観察。
1ヶ月前からメールか往復はがきで申し込む。
地質の日に養老渓谷を歩く (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県夷隅郡大多喜町
平成19年に日本の地質百選の1つに選ばれた養老渓谷周辺の地質について観察します。「地質の日」関連行事
2週間前(4/26)までに、往復はがきかファクスに、参加希望者全員の氏名、年齢、住所、電話番号を記入して、中央博物館までお送りください。応募者多数の場合は抽選となります。(定員30名)
小櫃川をのぼる (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県木更津市・袖ヶ浦市・君津市
2009年5月10日(日)、8月9日、11月15日、2010年2月14日と4回連続の観察会。房総丘陵を源とする小櫃川を河口から源流を目指して歩き、流域の自然や文化を探ります。参加者それぞれが簡単なテーマをみつけそれに基づいて観察します。
初回の2週間前(4/26)までに、往復はがきかファクスに、参加希望者全員の氏名、年齢、住所、電話番号を記入して、中央博物館までお送りください。応募者多数の場合は抽選となります。(定員20名)
地質の日記念「十勝最古の石と最新の石をみよう」 (北海道 足寄動物化石博物館)
場所:足寄動物化石博物館 集合、野外観察は足寄町螺湾
時間:10:00〜14:00
ライマンの地質図ができあがった1876年,米国カリフォルニアではデスモスチルスが発見された。博物館でデスモスチルス研究史をたどり,野外で十勝最古の石(ジュラ紀の枕状溶岩や石灰岩)と最新の石(シオワッカで形成中の炭酸カルシウム鉱物)を観察する。
「地質の日」記念『化石と遊ぼう』 (栃木県 佐野市葛生化石館)
場所:佐野市葛生化石館
時間:10:00〜16:00
「地質の日」を記念して化石模型つくりや、化石探し体験などを開催します。
材料がなくなり次第終了します
シーラカンス展 展示解説 (徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島県立博物館 企画展示室(1階)
時間:14:00〜14:30
大陸移動の歴史を、シーラカンスやブラジル産の魚類化石を通して、や さしくそして楽しく解説します
「地質の日」関連行事「氷河の痕跡を探せ! −北アルプスの氷河地形調査−」 (茨城県 産業技術総合研究所 地質標本館)
場所:地質標本館1階 映像室
時間:13:30〜15:00
北アルプスに残るカールやU字谷などの氷河地形は、いつ、どのようにつくられたのでしょうか。厳しい山岳地での調査エピソードを交えながら、氷河と氷河地形についてご紹介します。講師:長谷川裕彦(明治大学)
5/11
(月)
5/12
(火)
5/13
(水)
5/14
(木)
5/15
(金)
5/16
(土)
篠山層群の観察 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:丹波市山南町下滝 JR福知山線下滝駅集合。
時間:13:00〜16:00
阿草-下滝間の篠山川河床で、含恐竜化石層を含む篠山層群下部層を観察します。地層のみかた・調べ方のポイントを体得します。
4月28日締切。小学校高学年〜大人 15名 参加費 高校生以上500円、中学生以下400円
南あわじで地層を見る (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:南あわじ市 阿万海岸、灘海岸、沼島
時間:10:00〜16:00
淡路島南部の主要な地層、和泉層群、大阪層群、三波川結晶片岩を観察します。
4月27日締切。小学校高学年〜大人 15名 参加費(船代含む) 高校生以上1300円、中学生1100円、小学生700円
サイエンス・サタデー「火山灰から宝石を見つけよう」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 実験室
時間:14:00〜15:00
火山灰の中にある宝石(造岩鉱物)をさがします。定員30人
定員30人、当日会場で直接申し込み[受付13:30〜14:00]、先着順)。対象は小学生以上(小学3年生以下は保護者と参加)、参加費は無料。
博物館教室「地層を調べよう〜地質調査の基礎」 (神奈川県 横須賀市自然・人文博物館)
場所:横須賀市自然・人文博物館1階講堂、付属天神島臨海自然教育園ほか
時間:10:00〜15:00
5月16日、30日、6月13日、27日 (土) 10:00〜12:00、7月11日 (土) 10:00〜15:00に実施。:三浦半島をつくる地層の大部分は深海でつくられ、約50万年前に陸地になりました。この講座では、これらの地層を調べ、地質図を作成するための基礎的な方法を学びます。室内での作業と野外での実習を行います。
往復ハガキで申し込む。詳細は博物館ホームページを参照。
5/17
(日)
眉山の地質ハイキング (徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島県 眉山
時間:13:00〜16:00
徳島市の眉山は、地質学的にも有名な場所です。この行事では山道を数 km歩いて,眉山をつくる結晶片岩などを観察したり,ざくろ石などの鉱物をさ がす予定です。また,途中で目に入る地質学的な現象にも解説を加えていきま す。春の日,ピクニック気分で眉山を歩いて,岩石や鉱物にふれてみましょ う。
往復はがきに 1. 希望行事名 2. 参加希望者全員の氏名と住所 (学生の場合は学年も)3. 電話番号を記入し、行事予定日の1ヶ月前から1 0日前までに届くように徳島県立博物館普及係(〒770-8070 徳島市八万町向 寺山)までお申し込みください。
南あわじで地層を見る (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:南あわじ市 阿万海岸、灘海岸、沼島
時間:10:00〜16:00
淡路島南部の主要な地層、和泉層群、大阪層群、三波川結晶片岩を観察します。
4月27日締切。小学校高学年〜大人 15名 参加費(船代含む) 高校生以上1300円、中学生1100円、小学生700円
5/18
(月)
5/19
(火)
5/20
(水)
5/21
(木)
5/22
(金)
5/23
(土)
自然観察会「三崎の地層」 (神奈川県 横須賀市自然・人文博物館)
場所:三浦市三崎〜浜諸磯
時間:10:00〜15:00
三浦市三崎から浜諸磯の海岸では地層の露出がよく、さまざまな地層の構造が見られ、国や県の天然記念物に指定されている地層もあります。この観察会では、三崎〜浜諸磯の海岸を歩きながら、地層や断層、堆積構造、地形などを観察します。地層の観察から読み取れる大地の動きや、三浦半島の成り立ちについてもご紹介します
往復ハガキで申し込む。詳細は博物館ホームページを参照。
地すべり地帯の山と暮らし②−法華道と御所が池 (長野県 伊那谷自然友の会)
場所:長野県伊那市
時間:7:00〜18:00
伊那市高遠町にある芝平(しびら)は地すべり地帯にあります。現在は廃村ですが、かつては地すべり地形を利用して水田耕作や焼き畑をしていました.法華道は地すべり地形の観察に最適な場所でもあります。芝平はけして「辺境」ではなく、人々の往来がありました。山奥で暮らしが成り立っていた理由を、現地を見て考えます。
1. 行事名、2. 参加希望者全員の氏名と住所、3. 電話番号を、行事予定日前日までに、飯田市美術博物館気付伊那谷自然友の会事務局(0265-22-8118)まで申し込む。
サイエンス・サタデー「火山灰から宝石を見つけよう」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 実験室
時間:14:00〜15:00
火山灰の中にある宝石(造岩鉱物)をさがします。定員30人
定員30人、当日会場で直接申し込み[受付13:30〜14:00]、先着順)。対象は小学生以上(小学3年生以下は保護者と参加)、参加費は無料。
5/24
(日)
教員・観察会指導者向け支援プログラム「火山灰野外編1」 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:「野外編1」泉北・泉南方面、「室内編1」大阪市立自然史博物館
時間:終日〜
理科の地学分野で必ず取り上げられる教材「火山灰」。きれいな鉱物の結晶や火山ガラスを洗い出して顕微鏡で観察すると、その形や色のおもしろさのとりこになるに違いありません。しかし実習の材料の入手方法がわからず、諦めておられる先生もおられるのではないでしょうか。「野外編1」では野外での火山灰層の観察と実習材料の採取を、「室内編1」では室内で火山灰から鉱物粒子の洗い出しや顕微鏡観察、鉱物粒子の同定を行う連続行事です。対象:小・中学校、高校、養護学校の先生、自然観察会の指導をされている方(「野外編1」と「室内編1」両方の参加をお願いします。これまでに教員向けプログラム「火山灰」に参加し、顕微鏡観察のステップアップを希望される方は「室内編1」のみの参加でも結構です)。参加費:「野外編1」100円(自然史博物館友の会会員は無料)、「室内編1」無料
往復はがき、または電子メールに「教師向け火山灰参加希望」と明記の上、参加者全員の氏名、学校名、住所、電話番号、返信連絡先(往復はがきには返信用の宛名)を書いて、5月11日(月)までに届くよう、博物館普及係あてに申し込んで下さい。博物館ホームページからも申し込めます。
「地質の日」記念、化石発掘体験 (長野県 飯田市美術博物館)
場所:追手町小学校化石標本室
時間:10:00〜16:00
ハンマー・タガネなどを使って、貝など化石の入った岩塊を崩して化石を取り出します。※化石を探し当てられなかった場合も、お土産を差し上げます。参加費:100円
10:00〜16:00の間に随時受付け
5/25
(月)
5/26
(火)
5/27
(水)
5/28
(木)
5/29
(金)
5/30
(土)
サイエンス・サタデー「火山灰から宝石を見つけよう」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 実験室
時間:14:00〜15:00
火山灰の中にある宝石(造岩鉱物)をさがします。定員30人
当日会場で直接申し込み[受付13:30〜14:00]、先着順)。対象は小学生以上(小学3年生以下は保護者と参加)、参加費は無料。
5/31
(日)
「地質の日」記念、化石のレプリカをつくろう (長野県 飯田市美術博物館)
場所:飯田市美術博物館
時間:10:00〜16:00
実物の恐竜やアンモナイトなどの化石から型どりした雌型から、超硬石膏でレプリカを作ります。作業時間およそ30分。着色は各自で行いましょう。材料費:1個100円(ネオジム磁石入りは、1個200円)
10:00〜16:00の間に随時受付け
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ内のフォームまたはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。随時、情報を更新いたしますので,ご協力をお願いいたします。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
地学教育の取り組みtop
地学教育の取り組み
地学教育委員会について
本委員会の活動は、主に豊かな自然に恵まれた国土に対する“市民の認識を高める(普及)活動”や“その実践交流”、“教育課程上の位置づけに関する提言”などを目的としています。
・地学教育委員会の活動は日常的にはMLを通じて連絡、情報伝達、討議などをしていきます。
年2回の地質学会の評議員会の開催日には一堂に会し、顔を合わせた会議をおこないます。
更に地質学会年会の時には、全国の会員と協力して下記のような活動をしていきます。
・毎年の年会では、「地学教育・地学史セッション」「教員対象の地質見学会」「公開シンポジウム」「小中高校生の研究発表会」などを開催し、子供たちを含めた市民と共に「日本の地学的自然について学び考える」機会を確保しています。
・日本地質学会の地球惑星科学連合への加盟とともに、地球惑星科学連合のもとに新設された「地学教育委員会」にも参加し、その活動の柱として参加各学会で試みられた地学の授業実践をめぐっての討論会や、「すべての高校生が学ぶべき地球人の科学リテラシー」の標語の元に文部科学省に対して行った全員必修「理科」の提言など、精力的な活動を行っています。
・今年度から高校生の「地学オリンピック」への参加も正式に決まるなど、21世紀に入り地学をめぐる教育情勢は、国際的にも大きく変わってきています。今こそ「地球人としての“科学リテラシー”の高揚」、を目的に、地学教育委員会をベースに活動していきましょう。
2009年4月 地学教育委員会
委員長 中井 均(当時)
委員会メンバーはこちらから
地学教育委員会の最近の活動
2009.04.05:有志にて富士山、青木ケ原に巡検
2009.04.04:地学教育委員会(於 北とぴあ 10:00-12:00)
2009.03.31:リーフレット 屋久島地質たんけんマップ 発行
2009.03.26:地学教育委員会(於 地質学会事務局 13:00-15:00)
学術大会における活動
▶ジュニアセッション(旧小さなEarth Scientistのつどい)小,中,高校生徒「地学研究」発表会
▶教師巡検
▶理科・地学教科書展示解説
その他の活動報告
▶地質の日関連行事:
▶箱根火山たんけんマップ 2007年5月発行
▶屋久島地質たんけんマップ 2009年3月発行
▶城ヶ島たんけんマップ 2010年9月発行
▶青木ヶ原溶岩のたんけん 2014年3月発行
関連情報
パブリックコメント(PDF)
▶高等学校・特別支援学校学習指導要領改訂案について(2009.01.21)
▶小学校学習指導要領案についての意見(2008.03.16)
▶「教育課程部会におけるこれまでの審議のまとめ」への意見(2007.12.05)
各地の活動紹介(準備中)
GSSPとは?(2019.8.21)
GSSPとは何か?
2019年8月20日
日本地質学会学術研究部会
* 全文PDFはこちら
ここでは地質年代(地質時代ともいいます)やその時代を区分する基準となるGSSP (Global Boundary Stratotype Section and Point:国際境界模式層断面とポイント)について,地層の命名や定義などの国際的な取り決めである国際層序ガイド*1に従って解説します.
まず,GSSPを説明するためには,2つの用語「地質年代」と「年代層序」の解説が必要です.「地質年代」とは地球の歴史(以下,地球史)における「時間」を表し,「年代層序」とはある年代に形成された「地層」を表しています.これらは,互いに対応関係をもつ「単元(unit)」に区分されています.この「単元」は,地球上の過去の出来事を国際的に理解するためにつくられた,国際的に共通な時代の区分を意味します.「単元」は,基本となる最も細かい区分をもとに,それらを組み合わせてより大きな区分が設定されるなど,階層構造をもっています.
「地質年代」と「年代層序」は,時間と地層を表す,互いに対応する単元に区分されていると先に説明しましたが,過去の地球の時代区分は,地層から得られた過去の地球史をもとに決められるため,基本的には地層を示す「年代層序単元」が決められ,その地層に対応する時間を「地質年代単元」として表されます.これらを「チバニアン」が提案されている第四紀を例として示すと図1のようになります.
画像をクリックすると大きな画像がご覧いただけます
GSSPは,最も細かい年代層序単元の区分である階 (Stage)の下限を定める境界模式層を意味しています.そして階 (Stage)の下限を規定するために必要なGSSPが世界で一つずつ定められます.GSSPが定められた場合には,そのGSSPが位置する地名にちなんだ階の名称が設定されます*2.「中部更新統/中期更新世」についてはGSSPが決まっていないため,「千葉セクション」がGSSPとして承認されれば,「チバニアン階/期」と命名されます.さらに,現在は77.3万年前とされている中部更新統の下限の年代も「千葉セクション」における研究成果を元に改訂されることになるでしょう.GSSPとして承認されるためにはIUGS (International Union of Geological Sciences:国際地質科学連合) のICS (International Commission on Stratigraphy:国際層序委員会) によって示された8つの条件*3を満たす必要があります.
さて,GSSPは「国際境界模式層断面とポイント」と訳されていることからわかるように境界模式層の一つです.この「境界模式層」が意味する「模式層」とは,模式的に示される地層との意味があります.「模式層」については,国際層序ガイドの第4章で以下の様に定義されており,図2のように示すことができます.
模式層:命名された層状の層序単元または層序単元境界を参照するために,命名時あるいはのちに設定された基準.模式層は特定の地層の特定の区間またはポイントであり,層序単元の定義・特徴づけ,あるいは境界の設定にたいして基準となる.
単元模式層:層序単元の定義・特徴づけのために参照標準として役立つ模式層.完全によく露出している層状の層序単元の場合,単元模式層の上限と下限はその境界模式層となる.
境界模式層:層序単元境界の定義と認定のための基準になる特定のポイントをふくむ,地層の特定の層序範囲.
複合模式層:構成要素模式層とよばれるいくつかの特定の地層区間の組合せにより構成される単元模式層.ある岩相層序単元がどの単一の層序断面にも完全には露出しないことがあり,1つの断面を層序単元の一部分の模式として設定し,ほかの層序断面をその残りの部分の模式として設定する必要が生じるであろう.このような場合はこれら2つのどちらかの層序断面を完模式層,残りを副模式層とするべきである.
画像をクリックすると大きな画像がご覧いただけます
つまり,国際層序ガイドが定義する模式層は大きく分けて「単元模式層」と「境界模式層」の2つの概念からなることと,複数の層序断面(構成要素模式層)からなる単元模式層を特に「複合模式層」と呼ぶことを示しています.層序単元として岩相層序単元を考えると図2のように説明されます。下位からX層、Y層、Z層(いずれも岩相層序単元)が積み重なった層序があるとき、Y層を例に取ると、Y層の模式層(単元模式層)ではY層という岩相層序単元全体が確認できる必要があります.そしてY層の上限境界および下限境界が確認できる地層断面が,それぞれの境界模式層として設定されます.境界模式層は一つの層序断面(通常は地層断面が露出する単一の崖)で構成され,断面上で単元境界を示す点(ポイント)によりその境界が規定されます.
GSSPの場合は,最も細かい年代層序単元である階 (Stage)の下限境界が対象となりますので,その境界が最もよくわかる層序断面および断面上のポイントがGSSPとなります.これを「千葉セクション」を例に説明します(図3参照).
画像をクリックすると大きな画像がご覧いただけます
千葉セクションのGSSP提案は,中部更新統の下限,すなわち中部更新統とその下位にあたる下部更新統との境界である下部―中部更新統境界 (L-M境界)を対象としています.IUGS-ICSの下にある第四紀層序小委員会(SQS)のL-M境界作業部会はL-M境界GSSPの認定条件を以下のように定めました(Head and Gibbard, 2005).
最後の地磁気逆転境界である松山−ブルン(M–B)境界を含むこと
同境界が対応する酸素同位体ステージ(marine oxygen isotope stage; MIS)とその前後1つずつの MIS (MIS19を中心として前後のMIS20およびMIS18をそれぞれ一部含む区間)が見られること
上記2点を満たす陸上に露出した海成層であること
一方,千葉セクションのGSSP提案(千葉セクションGSSP提案チーム, 2019)では,市原市田淵における養老川河岸の崖(千葉セクション)がGSSPとなる層序断面として,さらに断面上で確認できる白尾火山灰層 (Byk-E bed)の基底面上の点が「チバニアン階」の下限境界を規定する点として提案されています.したがって,GSSPとして提案されているのは「千葉セクション」という単一の層序断面となります.しかし先に示されたL-M境界GSSP認定条件にあるMIS区間は,時間にすると少なくとも5万年間以上の区間となります.「千葉セクション」が含まれる上総層群における平均堆積速度が2m/千年 (Kazaoka et al., 2015) であることを考えると,この時間(5万年間)は少なくとも100m程度の層準区間に相当します.GSSP候補となる単一層序断面「千葉セクション」がカバーする層準区間は17m程度 (Nishida et al., 2016など) であるので,養老川を中心に近隣の沢に分布する層序断面を組合せ「千葉複合セクション」としてMIS20後半〜MIS18前半の年代区間をカバーすることで提案されました(千葉セクションGSSP提案チーム, 2019).
注:
*1: 日本地質学会訳編(Translated by the Geological Society of Japan), 2001, 国際層序ガイド(International Stratigraphic Guide). 共立出版(Kyoritsu Shuppan), 238p.
:IUGS (国際地質科学連合)の元にあるICS (国際層序委員会) のISSC (層序区分小委員会) が発行した 「International Stratigraphic Guide, Second Edition; 1994」の全訳である.当ガイドは,世界の地質学の発展と共に年を追うごとに増加してきた層序区分などに関する概念を製理し,国際的な層序学者の合意のもと,国際的に共通の枠組みで使用できる層序区分・用語法・手順の指針を示したものである.
*2: ほとんどの年代層序単元の名称は,年代層序単元の模式層としてGSSPが導入される1976年以前に定められていた.GSSPが未定であるために名称未定の年代層序単元が残っている地質時代は,時代が新しすぎて隆起した海成層が少ない第四紀と,時代が古く地層分布が限られたカンブリア紀のみである.
*3: 国際層序ガイド第9章 9H.3: 年代層序単元の境界模式層の選定にたいする要請
境界模式層は本質的に連続して堆積している断面で選定されなければならない.年代層序単元の境界模式層に関しておこりうる最悪なことは,不整合のところでの選択である.それは年代上の明確な点をしめさないばかりでなく,年代そのものも側方にずらせてゆきがちである.
国際標準年代層序尺度の層序単元の境界模式層は岩相あるいは生物相が上下方向に大きく変化しない海成で化石をふくむ層序断面に存在すべきである.しかし局地的に適用される年代層序単元の境界模式層については非海成の層序断面で選定する必要が生じるかもしれない.
化石含有量はなるべく,豊富で特徴があり,保存がよく,できるだけ広範囲に分布し,多様性に富んでいる動物相あるいは植物相を代表しているべきである.
層序断面は露出がよく,構造的変形,あるいは表層の乱れ,変成作用・続成変質作用(例:いちじるしいドロマイト化)などが最小の地域にあるべきである.選定された境界模式層の上下方向および側方の地層は十分な厚さをもっていることがのぞましい.
国際標準年代層序(地質年代)尺度の層序単元の境界模式層は,自由に調査・試料採集ができ,長期間にわたって保存できることが充分に保証されていて,容易に到達できるような層序断面で選定されることがのぞましい.
選定された層序断面は,調査・試料採集がなるべくよくなされており,研究成果が公表されていることがのぞましい.またその断面から採集された化石が充分な管理のもとに置かれていて,容易に研究に利用することができるような状態になっていることがのぞましい.
国際標準年代層序尺度における年代層序単元の境界模式層の選択には,可能ならば歴史的な先取権と使用を考慮し,伝統的に使用されている境界にちかづけるようにすべきである.
境界模式層は,その受けいれと,可能ならば地球規模の広域での使用を保証するために,できるだけ多くの特定のよい指標層準あるいは遠隔地の年代対比に有益なほかの特徴をふくむように選択されるべきである.たとえば海に広く分布していた特定の化石で特徴づけられた重要な生層序・磁場極性逆転・同位体年代測定法ないしほかの地質年代測定法により正確な数値年代測定ができるような層序区間などである.ことなった岩相および生物相を代表している断面との確実な関係を解明することもまた有益である.そのためには境界模式層をふくむ断面から離れた場所での年代対比をしめす広域的な参照模式層の選定と設定をすることがよいであろう.
参考文献
千葉セクションGSSP提案チーム, 2019, 千葉セクション : 下部-中部更新統境界の国際境界模式層断面とポイントへの提案書(要約).地質雑, 125, 5–22. [GSSP proposal group, 2019, A summary of the Chiba Section, Japan: a proposal of Global Boundary Stratotype Section and Point (GSSP) for the base of the Middle Pleistocene Subseries. J. Geol. Soc. Japan, 125, 5–22.]
Kazaoka, O., Suganuma, Y., Okada, M., Kameo, K., Head, M.J., Yoshida, T., Kameyama, S., Nirei, H., Aida, N., Kumai, H., 2015. Stratigraphy of the Kazusa Group, Central Japan: a high-resolution marine sedimentary sequence from the Lower to Middle Pleistocene. Quat. Int., 383, 116–135. https://doi.org/10.1016/ j.quaint.2015.02.065.
Head, M.J., Gibbard, P.L., 2005. Early–Middle Pleistocene transitions: an overview and recommendation for the defining boundary. In Head, M.J., Gibbard, P.L., eds., Early–Middle Pleistocene Transitions: The Land–ocean Evidence, Geological Society, London, Special Publication, vol. 247, pp. 1–18.
Nishida, N., Kazaoka, O., Izumi, K., Suganuma, Y., Okada, M., Yoshida, T., Ogitsu, I., Nakazato, H., Kameyama, S., Kagawa, A., Morisaki, M., Nirei, H., 2016. Sedimentary processes and depositional environments of a continuous marine succession across the Lower–Middle Pleistocene boundary: Kokumoto Formation, Kazusa Group, central Japan. Quat. Int., 397, 3–15. https://doi.org/ 10.1016/j.quaint.2015.06.045.
(2019.8.21掲載)
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2009年7月)
7月のイベント・特別展示カレンダー (2009/07/07〜2009/08/03)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
7月の特別展示
2009/07/07 現在
トピックス展示「博物館資料からよみがえった翼竜化石」 (神奈川県 横須賀市自然・人文博物館)
期間:4/11(土)〜7/12(日)
場所:横須賀市自然・人文博物館 1階
このたび、アンモナイトとして収蔵されていた化石資料が、翼竜の化石であることが明らかになりました。ここではその化石を紹介し、中生代の大空を飛んでいた爬虫類である翼竜について解説します。
鉱物の魅力−宝石から資源まで− (埼玉県 埼玉県立自然の博物館)
期間:6/27(土)〜10/04(日)
場所:埼玉県立自然の博物館企画展示室
宝石、機械部品、鉱物資源などに利用される身近な鉱物の性質と利用方法を紹介
“国際博物館の日”記念企画展「石板アートギャラリー」 (静岡県 奇石博物館)
期間:4/25(土)〜7/12(日)
場所:奇石博物館 企画展示室
板状の石を一堂に集め、その美しさや科学的な意味などをご紹介します。
第65回特別展「北海道象化石展!」 (北海道 北海道開拓記念館)
期間:7/03(金)〜10/04(日)
場所:北海道開拓記念館 特別展示室
どうして日本では北海道だけマンモスゾウの化石が発見されるの? 忠類で発見されたナウマンゾウ化石はオス?メス? 年齢は? 北海道初となるゾウの足跡化石が最近発見された? 当時北海道には他にどんな動物がいたの? 人間はいた? 今回はこれらに関する化石や最新の研究成果を展示するとともに,普段は収蔵庫にある忠類ナウマンゾウ化石を発見40周年を記念して全て公開します!※総合地球環境学研究所との共催
世界ジオパーク展 −日本最初の認定地をめざす糸魚川− (新潟県 新潟県、糸魚川市教育委員会博物館)
期間:4/25(土)〜11/30(月)
場所:フォッサマグナミュージアム ふるさと展示室
世界ジオパークをめざす糸魚川の多様な大地とそれらが育んだ動植物、文化財などを紹介しています。野外のジオサイトへ出かけて大地の魅力を感じてみてください。
第33回企画展「シーラカンス〜ブラジルの化石と大陸移動の証人たち〜」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
期間:7/11(土)〜8/30(日)
場所:群馬県立自然史博物館 企画展示室
「生きた化石」シーラカンスの進化や生態について、多くの化石標本などの展示で 紹介します。世界最大のシーラカンス化石の復元全身骨格も展示します。観覧料は一般700円、高・大学生400円(常設展を含む)
恐竜のくらした森 - 恐竜は花を見たか? (福井県 福井県立恐竜博物館)
期間:7/10(金)〜10/12(月)
場所:福井県立恐竜博物館3階 特別展示室
現在のわたしたちの世界を取り巻く森の中で85%以上もの圧倒的多数を占めている「花を咲かせる植物」(被子植物)は、恐竜時代の終わり頃に現れ、ごく短い期間に世界を花で被っていったことが分かっている。白亜紀に起こった、この「花のない世界」から「花に被われた世界」への変化は、恐竜をはじめ、植物を食べる地上の動物たちに大きな影響を与えたと考えられている。本特別展では、花の誕生とその進化にスポットをあて、植物化石からわかる被子植物の歴史をひもとき、その進化と繁栄に密接な関係がある昆虫や、恐竜など植物食の動物たちと植物との関わりの歴史を紹介する。観覧料:一般 800円、大学・高校生 600円、小・中学生 400円、70歳以上の方 400円(上記料金で常設展もご覧いただけます)
『リーフ:石灰岩を造った太古の生き物達〜サンゴを中心に〜』 (栃木県 佐野市葛生化石館)
期間:7/11(土)〜10/04(日)
場所:佐野市葛生化石館 企画展示室
石灰岩は様々な種類の生き物が、集まって大きなリーフ(礁)をつくり,その後長い年月かけて形成されたものです。石灰岩を造る生物の化石を紹介する。
デザin Stone (静岡県 奇石博物館)
期間:7/18(土)〜12/23(水)
場所:奇石博物館 企画展示室
石の中に隠されているデザインをクローズアップしてご紹介します。
第4回 私の宝石クラフト作品展 (静岡県 奇石博物館)
期間:8/01(土)〜8/31(月)
場所:奇石博物館 研究学習棟2階教室
併設の宝石探し体験施設で見つけた宝石を使ったクラフト作品を一般公募し展示します。
7月のイベント
2009/07/07 現在
日付
イベント
7/07
(火)
7/08
(水)
7/09
(木)
7/10
(金)
7/11
(土)
シーラカンスの謎と不思議①〜生きた化石の進化と大陸移動〜 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 実験室
時間:13:30〜15:30
講師 籔本美孝(北九州市立自然史・歴史博物館)、参加費無料。
定員100人、一ヶ月前から電話で申し込み、先着順
7/12
(日)
花咲く世界のはじまりを追い求めて -中国初期被子植物研究の最前線- (福井県 福井県立恐竜博物館)
場所:福井県立恐竜博物館3階 講堂
時間:14:00〜15:30
講師 孫革(スン・ガ)氏(中国瀋陽師範大学古生物研究所・所長)。恐竜時代に現れた花咲く植物。その起源について、中国で見つかった植物や昆虫などの化石から分かってきた最新情報を紹介します。 聴講無料。
7/13
(月)
7/14
(火)
7/15
(水)
7/16
(木)
7/17
(金)
7/18
(土)
ナイトミュージアム (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
時間:17:30〜19:15
閉館後の暗くなった館内をめぐり、ナイトミュージアムを体験する。
詳しくはホームページをご覧下さい。
7/19
(日)
ざくろ石をさがそう! (愛媛県 徳島県立博物館)
場所:愛媛県四国中央市土居町 関川河原
時間:13:00〜15:00
大粒(直径1〜2cm)のざくろ石や、変成岩に伴うさまざまな珍しい 鉱物を探しましょう。
往復はがきに 1. 希望行事名 2. 参加希望者全員の氏名と住所 (学生の場合は学年も)3. 電話番号を記入し、行事予定日の1ヶ月前から1 0日前までに届くように徳島県立博物館普及係(〒770-8070 徳島市八万町向 寺山)までお申し込みください。
ナイトミュージアム (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
時間:17:30〜19:15
閉館後の暗くなった館内をめぐり、ナイトミュージアムを体験する。
詳しくはホームページをご覧下さい。
7/20
(月)
海の日
ナイトミュージアム (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
時間:17:30〜19:15
閉館後の暗くなった館内をめぐり、ナイトミュージアムを体験する。
詳しくはホームページをご覧下さい。
7/21
(火)
7/22
(水)
7/23
(木)
7/24
(金)
夏休み企画「自分で作る!化石レプリカ」 (神奈川県 横須賀市自然・人文博物館)
場所:横須賀市自然・人文博物館1階科学教室
時間:13:00〜16:30
大昔の生き物の化石レプリカを作成し、地球や生命の歴史について学習します。作ったレプリカは、おみやげとして持ち帰ることができます。
往復ハガキで申し込む。詳細は博物館ホームページを参照。
7/25
(土)
夏休み企画「自分で作る!化石レプリカ」 (神奈川県 横須賀市自然・人文博物館)
場所:横須賀市自然・人文博物館2階科学教室
時間:13:00〜16:30
大昔の生き物の化石レプリカを作成し、地球や生命の歴史について学習します。作ったレプリカは、おみやげとして持ち帰ることができます。
往復ハガキで申し込む。詳細は博物館ホームページを参照。
ナイトミュージアム (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
時間:17:30〜19:15
閉館後の暗くなった館内をめぐり、ナイトミュージアムを体験する。
詳しくはホームページをご覧下さい。
アンモナイトのレプリカをつくろう!! (北海道 北海道開拓記念館)
場所:北海道開拓記念館 講堂
時間:13:30〜15:30
北海道はアンモナイト化石の宝庫!!実際に北海道から発見されたアンモナイトと石こうを使って、本物そっくりのレプリカ(複製)作りに挑戦!色づけを工夫して、世界で一つだけのアンモナイトも作ってみましょう!講師:添田雄二(北海道開拓記念館学芸員)
2009年6月26日(金)からお電話で受付します。30名(先着順)
化石の調べ方 (埼玉県 埼玉県立自然の博物館)
場所:埼玉県立自然の博物館科学教室
クリーニングの実際とレプリカ作り
1ヶ月前からメールか往復はがきで申し込む。
7/26
(日)
バス見学会 特別展関連化石採集会「化石採集へ行こう!」 (北海道 北海道開拓記念館)
場所:沼田町・滝川市 ※集合場所は記念館入口
時間:9:00〜16:00
北海道では、ラーメンどんぶりのような形をした約500万年前のホタテ貝の化石がみつかります。みんなで巨大ホタテ貝化石を探しに行きましょうー!!そこからは鯨の化石も発見されています・・・大発見があるかも!?講師:添田雄二・山田悟郎(北海道開拓記念館学芸員)
往復ハガキでお申し込みください。あらかじめ復信欄にご自分のご住所をお書きください。1枚のハガキで、ご家族の方に限り4名様までご応募いただけます。全員のお名前をお書きください。 6月12日(金)〜28日(日)必着
ナイトミュージアム (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
時間:17:30〜19:15
閉館後の暗くなった館内をめぐり、ナイトミュージアムを体験する。
詳しくはホームページをご覧下さい。
特別展ツアー「特別展の展示解説」 (福井県 福井県立恐竜博物館)
場所:福井県立恐竜博物館3階 特別展示室
時間:13:00〜14:00
特別展の見どころについて、やさしく解説します。聴講無料。
電話・FAX・E-mailにて。「特別展ツアー(日付)参加希望」と、氏名、住所、電話番号を福井県立恐竜博物館までお知らせ下さい。開催日の一ヶ月前から受付開始し、定員になり次第、〆切とさせていただきます。
7/27
(月)
7/28
(火)
7/29
(水)
夏休み企画「博物館探検 (自然館)」 (神奈川県 横須賀市自然・人文博物館)
場所:横須賀市自然人文博物館自然館
時間:10:00〜12:00
博物館の資料室や展示室の裏側などふだん見られない博物館の舞台裏をご案内します。あわせて博物館資料の作り方、整理や保管の仕方なども紹介します。
往復ハガキで申し込む。詳細は博物館ホームページを参照。
7/30
(木)
7/31
(金)
8/01
(土)
夏休み企画「子ども地震教室」 (神奈川県 横須賀市自然・人文博物館)
場所:横須賀市自然・人文博物館1階科学教室
時間:10:00〜12:00
三浦半島には5つの活断層があり、それらの活断層が動くときには大地震が起こるといわれています。この博物館行事では、地震発生のしくみや地震によって引き起こされる現象を、講義や実験を通して学習します。また、プレートのはたらきなど、地球科学の基礎についても学びます。(小学校低学年向け)
往復ハガキで申し込む。詳細は博物館ホームページを参照。
夏休み企画「子ども地震教室」 (神奈川県 横須賀市自然・人文博物館)
場所:横須賀市自然・人文博物館2階科学教室
時間:13:30〜16:30
三浦半島には5つの活断層があり、それらの活断層が動くときには大地震が起こるといわれています。この博物館行事では、地震発生のしくみや地震によって引き起こされる現象を、講義や実験を通して学習します。また、プレートのはたらきなど、地球科学の基礎についても学びます。 (小学校高学年向け)
往復ハガキで申し込む。詳細は博物館ホームページを参照。
サイエンス・サタデー「三葉虫のレプリカをつくろう」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 実験室
時間:14:00〜15:00
レプリカをつくりながら、三葉虫について学びます。定員30人。
当日会場で直接申し込み[受付13:30〜14:00]、先着順。対象は小学生以上(小学3年生以下は保護者と参加)、参加費は無料。
ナイトミュージアム (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
時間:17:30〜19:15
閉館後の暗くなった館内をめぐり、ナイトミュージアムを体験する。
詳しくはホームページをご覧下さい。
アンモナイトのレプリカをつくろう!! (北海道 北海道開拓記念館)
場所:北海道開拓記念館 講堂
時間:13:30〜15:30
北海道はアンモナイト化石の宝庫!!実際に北海道から発見されたアンモナイトと石こうを使って、本物そっくりのレプリカ(複製)作りに挑戦!色づけを工夫して、世界で一つだけのアンモナイトも作ってみましょう!講師:添田雄二(北海道開拓記念館学芸員)
2009年6月26日(金)からお電話で受付します。30名(先着順)
8/02
(日)
ナイトミュージアム (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
時間:17:30〜19:15
閉館後の暗くなった館内をめぐり、ナイトミュージアムを体験する。
詳しくはホームページをご覧下さい。
アンモナイトの掘り出し体験をしよう! (北海道 北海道開拓記念館)
場所:北海道開拓記念館 正面玄関ホール
北海道の博物館には、きれいな化石やアンモナイトが展示されています。それはどのようにして岩石の中から取り出されたのでしょうか?岩石の中から本物のアンモナイトを掘り出す体験をしてみましょう!講師:千歳化石会会員。当日は5回行います①11:15〜②13:30〜③14:15〜④15:00〜(各回35分)
2009年7月3日(金)からお電話で受付します。各回10名(全4回。先着順)
花はどこから来たのか? (福井県 福井県立恐竜博物館)
場所:福井県立恐竜博物館3階 講堂
時間:13:00〜14:30
講師 山田 敏弘氏(金沢大学理工学域自然システム学系講師)。かつてダーウィンは、花の咲く植物(被子植物)の祖先となった裸子植物について、「(解けなくて)忌々しい問題」と表現しました。それから100年以上が経った現在でも、この謎は解けていません。化石裸子植物からどのように被子植物の祖先を探せば良いのか?私たちのグループが行ってきた祖先探しの取り組みを紹介します。聴講無料。
電話・FAX・E-mailにて、7/2から受講登録を受け付けます。「博物館セミナー(8/2)参加希望」と、住所氏名、電話番号を福井県立恐竜博物館までお知らせ下さい。
シーラカンスの謎と不思議②〜生きた化石の姿にせまる〜 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 実験室
時間:13:30〜15:30
講師 岩田雅光(アクアマリンふくしま)、参加費無料。
定員100人、一ヶ月前から電話で申し込み、先着順
8/03
(月)
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ内のフォームまたはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。随時、情報を更新いたしますので,ご協力をお願いいたします。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2009年6月)
6月のイベント・特別展示カレンダー (2009/06/02〜2009/07/06)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
6月の特別展示
2009/06/02 現在
春の特別展 「五百澤智也 山のスケッチとフィールドノート」 (茨城県 産業技術総合研究所 地質標本館)
期間:4/14(火)〜7/05(日)
場所:産業技術総合研究所 地質標本館
地理学者・地図作家である五百澤智也氏は、ヒマラヤや日本の山の精巧なスケッチを数多く制作しています。地質標本館では作品の科学的な側面にスポットをあて、鳥瞰図に描かれた富士山と槍穂高連峰の地形・地質を解説します。また、ヒマラヤの氷河調査で使われたフィールドノートを展示します。
トピックス展示「博物館資料からよみがえった翼竜化石」 (神奈川県 横須賀市自然・人文博物館)
期間:4/11(土)〜7/12(日)
場所:横須賀市自然・人文博物館 1階
このたび、アンモナイトとして収蔵されていた化石資料が、翼竜の化石であることが明らかになりました。ここではその化石を紹介し、中生代の大空を飛んでいた爬虫類である翼竜について解説します。
百年前の大震災〜姉川地震に学ぶその備え〜 (滋賀県 滋賀県立琵琶湖博物館・滋賀県防災危機管理局)
期間:4/25(土)〜6/07(日)
場所:琵琶湖博物館 企画展示室
この展示では、100年前におきた姉川地震について、当時の災害写真をもりこみながら解説し、日本の地震がどうやっておきているかなどの自然科学的な解説と、現在の地震防災の取り組みを紹介します。また、ゴールデンウィーク期間中には、地震体験もできます。
“国際博物館の日”記念企画展「石板アートギャラリー」 (静岡県 奇石博物館)
期間:4/25(土)〜7/12(日)
場所:奇石博物館 企画展示室
板状の石を一堂に集め、その美しさや科学的な意味などをご紹介します。
大恐竜展〜知られざる南半球の支配者〜 (東京都 国立科学博物館)
期間:3/14(土)〜6/21(日)
場所:国立科学博物館
日本発上陸のゴンドワナ大陸の恐竜が集まる。
シーラカンス展−ブラジルの化石と大陸移動の証人たち− (徳島県 徳島県立博物館)
期間:4/25(土)〜6/14(日)
場所:徳島県立博物館 企画展示室(1階)
ブラジルから産出するシーラカンスなどの化石は、南アメリカとアフリ カがかつて一つの大陸であったことを示す重要な証人といってよいでしょう。 この企画展では、生きている化石として知られるシーラカンスやブラジル産の 魚類化石を通して、大陸移動や大西洋ができ始めた頃の海の様子、かつて地球 上にパンゲアと呼ばれる一つの大陸があったことをご紹介します。
収蔵資料紹介展「足元の地面を探る」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
期間:4/25(土)〜6/14(日)
場所:豊橋市自然史博物館 イントロホール
中央構造線露頭のはぎとり標本やボーリングコアサンプル、巨大な圧力をうけて生じたくいちがい石など、地面の下を探る方法や大地の動きを示す資料等を紹介します。
「桐生で発見!古生代の新種腕足類」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
期間:5/09(土)〜6/21(日)
場所:群馬県立自然史博物館エントランス(無料のゾーンです)
世界ジオパーク展 −日本最初の認定地をめざす糸魚川− (新潟県 新潟県、糸魚川市教育委員会博物館)
期間:4/25(土)〜11/30(月)
場所:フォッサマグナミュージアム ふるさと展示室
世界ジオパークをめざす糸魚川の多様な大地とそれらが育んだ動植物、文化財などを紹介しています。野外のジオサイトへ出かけて大地の魅力を感じてみてください。
鉱物の魅力−宝石から資源まで− (埼玉県 埼玉県立自然の博物館)
期間:6/27(土)〜10/04(日)
場所:埼玉県立自然の博物館企画展示室
宝石、機械部品、鉱物資源などに利用される身近な鉱物の性質と利用方法を紹介
第65回特別展「北海道象化石展!」 (北海道 北海道開拓記念館)
期間:7/03(金)〜10/04(日)
場所:北海道開拓記念館 特別展示室
どうして日本では北海道だけマンモスゾウの化石が発見されるの? 忠類で発見されたナウマンゾウ化石はオス?メス? 年齢は? 北海道初となるゾウの足跡化石が最近発見された? 当時北海道には他にどんな動物がいたの? 人間はいた? 今回はこれらに関する化石や最新の研究成果を展示するとともに,普段は収蔵庫にある忠類ナウマンゾウ化石を発見40周年を記念して全て公開します!※総合地球環境学研究所との共催
6月のイベント
2009/06/02 現在
日付
イベント
6/02
(火)
6/03
(水)
6/04
(木)
6/05
(金)
6/06
(土)
6/07
(日)
石ころクラブ (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:人と自然の博物館
時間:13:30〜15:30
観察会、実験や工作などを皆で計画していきます。最後に2月11日の共生の広場で成果を発表します。
5月18日締切。中学生〜大人 20名 参加費 高校生以上2000円、中学生1000円
シーラカンス展 展示解説 (徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島県立博物館 企画展示室(1階)
時間:14:00〜14:30
大陸移動の歴史を、シーラカンスやブラジル産の魚類化石を通して、や さしくそして楽しく解説します
6/08
(月)
6/09
(火)
6/10
(水)
6/11
(木)
6/12
(金)
6/13
(土)
ジオラボ(6月)「ミクロの化石」 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:大阪市立自然史博物館 ナウマンホール
時間:14:30〜15:00
およそ350万年前の海底にたまった地層から取り出したプランクトンの化石を観察します。実体顕微鏡で観察しながら化石をさがして,それを電子顕微鏡で観察してみましょう.参加費は無料(ただし、博物館入館料が必要)
6/14
(日)
鉱石ラジオ作り体験教室 (静岡県 奇石博物館)
場所:奇石博物館 研究学習棟2階教室
時間:10:00〜15:00
ラジオの仕組みを考えながら、電源を必要としない石を使ったラジオを作り、受信を試します。20名(先着順,定員になり次第締め切り)。料金;1,500円(資料+材料費)
実施日の3日前までに電話にて事前予約を行って下さい。参加される方の氏名、年齢(学年)、住所、電話番号をお知らせ下さい。TEL;0544-58-3830
二枚貝類の分類・同定 (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館研修室
分類の難しい二枚貝類(現生種)を、実際の標本を元に分類・同定します。
2週間前(5/31)までに、往復はがきかファクスに、参加希望者全員の氏名、年齢、住所、電話番号を記入して、中央博物館までお送りください。応募者多数の場合は抽選となります。定員20名
超丹波帯の時代、古生代とは? (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:丹波市・上久下地域づくりセンター
時間:13:30〜15:00
丹波地域に広く分布する超丹波帯が堆積した古生代とはどのような時代だったのか、恐竜の時代である中生代とはどう違うのか、標本をまじえてわかりやすく解説します。
5月25日締切。小学校高学年〜大人 30名 参加費 高校生以上500円、中学生以下300円
6/15
(月)
6/16
(火)
6/17
(水)
6/18
(木)
6/19
(金)
6/20
(土)
現場で学ぶ「石炭基礎講座」掘るだけでは終わらない (北海道 釧路市立博物館)
場所:釧路コールマイン(釧路市興津5丁目)
時間:9:30〜12:00
日本唯一の坑内掘り炭鉱で、アジア各国にも技術移転されている先進的な炭鉱保安(安全対策)について現役炭鉱マンから学びます(坑内には入りません)。
ハガキ受付いたします 受付開始時期はホームページでご案内します。中学生以上を対象、定員20名(申し込み多数の場合は抽選)参加費無料、現地集合/解散です
6/21
(日)
自然史講座「カンブリア紀におきた地球生命史上の大事件」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 実験室
時間:13:30〜15:30
講師 田中源吾(群馬県立自然史博物館)、参加費無料。
定員100人、一ヶ月前から電話で申し込み、先着順
6/22
(月)
6/23
(火)
6/24
(水)
6/25
(木)
6/26
(金)
6/27
(土)
6/28
(日)
教員・観察会指導者向け支援プログラム「室内編1」 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:「野外編1」泉北・泉南方面、「室内編1」大阪市立自然史博物館
時間:終日〜
理科の地学分野で必ず取り上げられる教材「火山灰」。きれいな鉱物の結晶や火山ガラスを洗い出して顕微鏡で観察すると、その形や色のおもしろさのとりこになるに違いありません。しかし実習の材料の入手方法がわからず、諦めておられる先生もおられるのではないでしょうか。「野外編1」では野外での火山灰層の観察と実習材料の採取を、「室内編1」では室内で火山灰から鉱物粒子の洗い出しや顕微鏡観察、鉱物粒子の同定を行う連続行事です。対象:小・中学校、高校、養護学校の先生、自然観察会の指導をされている方(「野外編1」と「室内編1」両方の参加をお願いします。これまでに教員向けプログラム「火山灰」に参加し、顕微鏡観察のステップアップを希望される方は「室内編1」のみの参加でも結構です)。参加費:「野外編1」100円(自然史博物館友の会会員は無料)、「室内編1」無料
往復はがき、または電子メールに「教師向け火山灰参加希望」と明記の上、参加者全員の氏名、学校名、住所、電話番号、返信連絡先(往復はがきには返信用の宛名)を書いて、5月11日(月)までに届くよう、博物館普及係あてに申し込んで下さい。博物館ホームページからも申し込めます。
地球温暖化CO2犯人説はウソか本当か? (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:人と自然の博物館
時間:13:30〜15:00
現在の地球温暖化の原因を人間活動に伴うCO2排出の増加と考え、今後も温暖化が進むとしています。その一方で、CO2の増加がもたらす温室効果はきわめて小さいとする説があります。両者の考え方の違いがどこにあるのかを吟味します。
6月8日締切。高校生〜大人 30名 参加費 500円
6/29
(月)
6/30
(火)
7/01
(水)
7/02
(木)
7/03
(金)
7/04
(土)
太古の化石をさがす (埼玉県 埼玉県立自然の博物館)
場所:高麗川上流、河床
白亜紀の化石の観察
1ヶ月前からメールか往復はがきで申し込む。
特別展オープニングイベント第1弾「忠類ナウマンゾウ発掘物語」 (北海道 北海道開拓記念館)
場所:北海道開拓記念館 講堂
時間:13:30〜15:30
40年前の夏に発見され、翌年に本発掘が行われた忠類ナウマンゾウ。参加者171名という大規模発掘でしたが、予想以上に大変な作業でした。実際に歯の化石を発見した方や発掘に参加した方々がその様子をお話しします。講師:都郷恙寛氏(北海道教育大学札幌校)、赤松守雄氏、山口昇一氏、山田悟郎(北海道開拓記念館学芸員)
2009年6月5日(金)からお電話で受付します。定員:100名(先着順)
7/05
(日)
鳴門の地層見学 (徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島県鳴門市
時間:13:30〜15:30
鳴門周辺に分布している白亜紀後期の地層(和泉層群)の観察を行います。
往復はがきに 1. 希望行事名 2. 参加希望者全員の氏名と住所 (学生の場合は学年も)3. 電話番号を記入し、行事予定日の1ヶ月前から1 0日前までに届くように徳島県立博物館普及係(〒770-8070 徳島市八万町向 寺山)までお申し込みください。
石の見分け方講座−丹波の石を見分けよう (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:丹波市・上久下地域づくりセンター
時間:9:30〜15:30
実物の観察や実験を通して、石の見分け方を学びます。恐竜の出た、丹波地域の石を見分けます。
6月15日締切。小学校高学年〜大人 30名 参加費 高校生以上500円、中学生以下300円
特別展オープニングイベント第2弾「巨象たちがいた頃の日本列島の環境と人々」 (北海道 北海道開拓記念館)
場所:北海道開拓記念館 講堂
時間:13:00〜16:00
日本列島は太古の昔から大型の陸上哺乳類を有する豊かな自然を保ってきました。ここでは巨象たちがいた頃の日本列島の環境と人々との関わりを紹介し、これからの人間と自然との関係を考えます。講師:湯本貴和氏(総合地球環境学研究所)、佐藤宏之氏(東京大学)
2009年6月6日(土)からお電話で受付します。定員:100名(先着順)
7/06
(月)
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ内のフォームまたはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。随時、情報を更新いたしますので,ご協力をお願いいたします。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2009年8月)
8月のイベント・特別展示カレンダー (2009/08/04〜2009/08/31)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
8月の特別展示
2009/08/04 現在
第33回企画展「シーラカンス〜ブラジルの化石と大陸移動の証人たち〜」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
期間:7/11(土)〜8/30(日)
場所:群馬県立自然史博物館 企画展示室
「生きた化石」シーラカンスの進化や生態について、多くの化石標本などの展示で 紹介します。世界最大のシーラカンス化石の復元全身骨格も展示します。観覧料は一般700円、高・大学生400円(常設展を含む)
鉱物の魅力−宝石から資源まで− (埼玉県 埼玉県立自然の博物館)
期間:6/27(土)〜10/04(日)
場所:埼玉県立自然の博物館企画展示室
宝石、機械部品、鉱物資源などに利用される身近な鉱物の性質と利用方法を紹介
デザin Stone (静岡県 奇石博物館)
期間:7/18(土)〜12/23(水)
場所:奇石博物館 企画展示室
石の中に隠されているデザインをクローズアップしてご紹介します。
第4回 私の宝石クラフト作品展 (静岡県 奇石博物館)
期間:8/01(土)〜8/31(月)
場所:奇石博物館 研究学習棟2階教室
併設の宝石探し体験施設で見つけた宝石を使ったクラフト作品を一般公募し展示します。
第65回特別展「北海道象化石展!」 (北海道 北海道開拓記念館)
期間:7/03(金)〜10/04(日)
場所:北海道開拓記念館 特別展示室
どうして日本では北海道だけマンモスゾウの化石が発見されるの? 忠類で発見されたナウマンゾウ化石はオス?メス? 年齢は? 北海道初となるゾウの足跡化石が最近発見された? 当時北海道には他にどんな動物がいたの? 人間はいた? 今回はこれらに関する化石や最新の研究成果を展示するとともに,普段は収蔵庫にある忠類ナウマンゾウ化石を発見40周年を記念して全て公開します!※総合地球環境学研究所との共催
世界ジオパーク展 −日本最初の認定地をめざす糸魚川− (新潟県 新潟県、糸魚川市教育委員会博物館)
期間:4/25(土)〜11/30(月)
場所:フォッサマグナミュージアム ふるさと展示室
世界ジオパークをめざす糸魚川の多様な大地とそれらが育んだ動植物、文化財などを紹介しています。野外のジオサイトへ出かけて大地の魅力を感じてみてください。
『リーフ:石灰岩を造った太古の生き物達〜サンゴを中心に〜』展 (栃木県 佐野市葛生化石館)
期間:7/11(土)〜10/04(日)
場所:佐野市葛生化石館 企画展示室
石灰岩は様々な種類の生き物が、集まって大きなリーフ(礁)をつくり,その後長い年月かけて形成されたものです。石灰岩を造る生物の化石を紹介する。
恐竜のくらした森 - 恐竜は花を見たか? (福井県 福井県立恐竜博物館)
期間:7/10(金)〜10/12(月)
場所:福井県立恐竜博物館3階 特別展示室
現在のわたしたちの世界を取り巻く森の中で85%以上もの圧倒的多数を占めている「花を咲かせる植物」(被子植物)は、恐竜時代の終わり頃に現れ、ごく短い期間に世界を花で被っていったことが分かっている。白亜紀に起こった、この「花のない世界」から「花に被われた世界」への変化は、恐竜をはじめ、植物を食べる地上の動物たちに大きな影響を与えたと考えられている。本特別展では、花の誕生とその進化にスポットをあて、植物化石からわかる被子植物の歴史をひもとき、その進化と繁栄に密接な関係がある昆虫や、恐竜など植物食の動物たちと植物との関わりの歴史を紹介する。 観覧料:一般 800円、大学・高校生 600円、小・中学生 400円、70歳以上の方 400円(上記料金で常設展もご覧いただけます)
夏の特別展「穂別海竜博物館-穂別を泳いでいた海竜たち-」 (北海道 むかわ町立穂別博物館)
期間:7/18(土)〜9/30(水)
場所:むかわ町立穂別博物館 特別展示室
時間:9:30〜4:30
恐竜時代に、海だった穂別を泳いでいた海竜たち(クビナガリュウ、モササウルス、ウミガメ)を紹介。どのような生き物で、どのように泳ぎ、何を食べていたのか、穂別で見つかった化石を見ながら考えよう。
8月のイベント
2009/08/04 現在
日付
イベント
8/04
(火)
石ころクラブ (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:人と自然の博物館
時間:13:30〜15:30
観察会、実験や工作などを皆で計画していきます。最後に2月11日の共生の広場で成果を発表します。
5月18日締切。中学生〜大人 20名 参加費 高校生以上2000円、中学生1000円
2/07(日)まで
化石クリーニング体験 (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館 入口横 「化石の洞窟」
時間:10:00〜15:00
白亜紀の岩石(ノジュール)の中から、アンモナイトや二枚貝イノセラムスを取り出す。幼児用擬似ノジュールもあります。化石は、お持ち帰りいただけます。参加費は無料。
8/05
(水)
1000万年前のミニ化石を探そう (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館1階入口前
福島県から採集した1000万年前の岩石から、小さな貝化石やサメの歯を探します。
(当日先着順100名)
化石クリーニング体験 (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館 入口横 「化石の洞窟」
時間:10:00〜15:00
白亜紀の岩石(ノジュール)の中から、アンモナイトや二枚貝イノセラムスを取り出す。幼児用擬似ノジュールもあります。化石は、お持ち帰りいただけます。参加費は無料。
8/06
(木)
化石レプリカ教室 (北海道 釧路市立博物館)
場所:釧路市立博物館講堂
時間:14:00〜15:30
釧路地方で採集したアンモナイトの型に石こうを流して固めます。固まったら絵の具で本物と同じように着色して完成です。
電話にて受付、受付開始時期はホームページでご案内します。小中学生(定員20名)、参加費200円、パレットと絵筆を持参してください
8/07
(金)
8/08
(土)
海岸で石ころをひろおう (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県富津市
富津市上総湊の海岸でいろいろな石ころを採集し、その違いを調べます。
2週間前(7/25)までに、往復はがきかファクスに、参加希望者全員の氏名、年齢、住所、電話番号を記入して、中央博物館までお送りください。応募者多数の場合は抽選となります。(定員30名)
サイエンス・サタデー「三葉虫のレプリカをつくろう」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 実験室
時間:14:00〜15:00
レプリカをつくりながら、三葉虫について学びます。定員30人。
当日会場で直接申し込み[受付13:30〜14:00]、先着順。対象は小学生以上(小学3年生以下は保護者と参加)、参加費は無料。
貝化石標本のつくりかた (徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島県立博物館
時間:13:30〜16:00
歯ブラシやハンマー・タガネなどを使って、貝化石を標本に仕上げます。
申込詳細:往復はがきに 1. 希望行事名 2. 参加希望者全員の氏名と住所 (学生の場合は学年も)3. 電話番号を記入し、行事予定日の1ヶ月前から1 0日前までに届くように徳島県立博物館普及係(〒770-8070 徳島市八万町向 寺山)までお申し込みください。
アンモナイトのレプリカをつくろう!! (北海道 北海道開拓記念館)
場所:北海道開拓記念館 講堂
時間:13:30〜15:30
北海道はアンモナイト化石の宝庫!!実際に北海道から発見されたアンモナイトと石こうを使って、本物そっくりのレプリカ(複製)作りに挑戦!色づけを工夫して、世界で一つだけのアンモナイトも作ってみましょう!講師:添田雄二(北海道開拓記念館学芸員)
2009年6月26日(金)からお電話で受付します。30名(先着順)
化石クリーニング体験 (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館 入口横 「化石の洞窟」
時間:10:00〜15:00
白亜紀の岩石(ノジュール)の中から、アンモナイトや二枚貝イノセラムスを取り出す。幼児用擬似ノジュールもあります。化石は、お持ち帰りいただけます。参加費は無料。
化石の模型をつくろう (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館研修室
2009年8月8日(土)及び8月14日(金)の2日おこないます。三葉虫やアンモナイト、恐竜の歯などさまざまな化石の模型作りにチャレンジします。8日は製作作業、14日は着色作業を行います(8日のみの参加も可)。
:2週間前(7/25)までに、往復はがきかファクスに、参加希望者全員の氏名、年齢、住所、電話番号を記入して、中央博物館までお送りください。応募者多数の場合は抽選となります。定員20名
いろいろな化石をみる (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:人と自然の博物館
時間:13:30〜14:30
知っている化石、知らない化石、いろいろな化石を見て、大むかしの生きものの世界にいってみよう。
7月19日締切。小学生〜大人 25名 参加費 高校生以上500円、中学生以下300円
8/09
(日)
化石のレプリカをつくろう (徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島県立博物館
時間:13:30〜16:00
実物の恐竜やアンモナイトなどの化石から型どりした雌型からレプリカ (複製)をつくりましょう。
往復はがきに 1. 希望行事名 2. 参加希望者全員の氏名と住所 (学生の場合は学年も)3. 電話番号を記入し、行事予定日の1ヶ月前から1 0日前までに届くように徳島県立博物館普及係(〒770-8070 徳島市八万町向 寺山)までお申し込みください。材料費100円(大学生・一般)、
レプリカづくり (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館 かせき学習館
時間:10:00〜15:00
アンモナイトの石こう模型作り。石こう模型は、お持ち帰りいただけます。参加費は無料。
レプリカ アクセサリーづくり (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館 かせき学習館
時間:13:00〜15:00
アンモナイトストラップかアンモナイトサンダルアクセサリーづくり。参加費は無料。
化石クリーニング実習 (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館 かせき学習館
時間:10:00〜15:00
2時間かけて白亜紀の化石のクリーニングを体験。参加費は100円。
詳細は博物館HPをご覧下さい
8/10
(月)
夏季教職員セミナー 地層の見方・調べ方 in 淡路 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:国立淡路青少年交流の家
時間:10:30〜16:30
午前中は室内で地層に関する基礎的な学習を行い、午後は和泉層群などを観察し、地層を観察するときのポイントを学習します。
6月27日締切。教職員 20名 参加費 1000円
8/11
(火)
夏季教職員セミナー 丹波の恐竜とその頃の日本 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:人と自然の博物館
時間:9:30〜12:30
丹波の恐竜と、その時代の大地について解説します。
6月27日締切。教職員 40名 参加費 500円
8/12
(水)
化石レプリカ作り (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
アンモナイトや三葉虫などの化石レプリカ作りを体験する。有料:1個100円
恐竜迫力撮影会 (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
タルボザウルスに食べられているようなアングルで写真を撮ります。
8/13
(木)
化石レプリカ作り (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
アンモナイトや三葉虫などの化石レプリカ作りを体験する。有料:1個100円
恐竜迫力撮影会 (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
タルボザウルスに食べられているようなアングルで写真を撮ります。
8/14
(金)
化石レプリカ作り (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
アンモナイトや三葉虫などの化石レプリカ作りを体験する。有料:1個100円
恐竜迫力撮影会 (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
タルボザウルスに食べられているようなアングルで写真を撮ります。
8/15
(土)
サイエンス・サタデー「三葉虫のレプリカをつくろう」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 実験室
時間:14:00〜15:00
レプリカをつくりながら、三葉虫について学びます。定員30人。
当日会場で直接申し込み[受付13:30〜14:00]、先着順。対象は小学生以上(小学3年生以下は保護者と参加)、参加費は無料。
化石レプリカ作り (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
アンモナイトや三葉虫などの化石レプリカ作りを体験する。有料:1個100円
恐竜迫力撮影会 (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
タルボザウルスに食べられているようなアングルで写真を撮ります。
アンモナイトのレプリカをつくろう!! (北海道 北海道開拓記念館)
場所:北海道開拓記念館 講堂
時間:13:30〜15:30
北海道はアンモナイト化石の宝庫!!実際に北海道から発見されたアンモナイトと石こうを使って、本物そっくりのレプリカ(複製)作りに挑戦!色づけを工夫して、世界で一つだけのアンモナイトも作ってみましょう!講師:添田雄二(北海道開拓記念館学芸員)
2009年6月26日(金)からお電話で受付します。30名(先着順)
化石クリーニング体験 (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館 入口横 「化石の洞窟」
時間:10:00〜15:00
白亜紀の岩石(ノジュール)の中から、アンモナイトや二枚貝イノセラムスを取り出す。幼児用擬似ノジュールもあります。化石は、お持ち帰りいただけます。参加費は無料。
8/16
(日)
化石レプリカ作り (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
アンモナイトや三葉虫などの化石レプリカ作りを体験する。有料:1個100円
恐竜迫力撮影会 (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
タルボザウルスに食べられているようなアングルで写真を撮ります。
レプリカづくり (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館 かせき学習館
時間:10:00〜15:00
アンモナイトの石こう模型作り。石こう模型は、お持ち帰りいただけます。参加費は無料。
レプリカ アクセサリーづくり (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館 かせき学習館
時間:13:00〜15:00
アンモナイトストラップかアンモナイトサンダルアクセサリーづくり。参加費は無料。
化石クリーニング実習 (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館 かせき学習館
時間:10:00〜15:00
2時間かけて白亜紀の化石のクリーニングを体験。参加費は100円。
詳細は博物館HPをご覧下さい
8/17
(月)
化石レプリカ作り (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
アンモナイトや三葉虫などの化石レプリカ作りを体験する。有料:1個100円
恐竜迫力撮影会 (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
タルボザウルスに食べられているようなアングルで写真を撮ります。
8/18
(火)
夏季教職員セミナー 地層の見方・調べ方 in 丹波 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:篠山市、丹波市の野外
時間:9:30〜16:30
午前中は、丹波帯および篠山層群を中心に、地層や化石に関する基礎的な学習を行います。午後は、野外で丹波帯や篠山層群の露頭を観察し、山南の化石工房や恐竜発掘現場の見学も行います。
6月27日締切。教職員 20名 参加費 1000円
8/19
(水)
夏季教職員セミナー 地震のゆれ方と液状化の実験をしよう (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:人と自然の博物館
時間:9:30〜12:30
「グラリン」を使った振動の実験、ペットボトルを使った「エッキー」「エキジョッカー」づくりなどを行います。表面に凹凸のないペットボトルを持参してください。
6月27日締切。教職員 30名 参加費 1000円
夏季教職員セミナー チョコとココアでおいしい火山実験をしよう (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:人と自然の博物館
時間:13:30〜16:30
お菓子を使って火山噴火の実験をします。もちろん食べられます。
6月27日締切。教職員 20名 参加費 1000円
夏季教職員セミナー 珪化木を観察しよう (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:人と自然の博物館
時間:9:30〜12:30
神戸層群から産出する木の化石について、年輪の見える面をルーペや実体顕微鏡で拡大して、道管の配列や樹脂道を観察してみましょう。
6月27日締切。教職員 20名 参加費 500円
夏季教職員セミナー 恐竜とは何か 〜丹波の恐竜化石の発見と発掘〜 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:人と自然の博物館
時間:13:30〜16:30
現在、日本各地から恐竜化石が発見されています。この講座では、特に丹波から発見されている恐竜化石について勉強します。
6月27日締切。教職員 30名 参加費 500円
夏季教職員セミナー 石の見分け方−兵庫を代表する岩石と鉱物 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:人と自然の博物館
時間:13:30〜16:30
実物の観察を通して、兵庫の意思を題材に、石の見分け方を学びます。
6月27日締切。教職員 30名 参加費 1000円
8/20
(木)
野外での地層の見方講座 (滋賀県 滋賀県立琵琶湖博物館・みなくち子どもの森自然館)
場所:滋賀県甲賀市 みなくち子どもの森
時間:10:00〜14:00
昔の環境情報を保存している地層から、どのように観察すればそれが理解できるのか?について、基礎的な見方を野外にある地層を前に解説します。保険料徴収。
往復ハガキに必要事項をご記入のうえ、琵琶湖博物館へお申し込みください。
8/21
(金)
8/22
(土)
サイエンス・サタデー「三葉虫のレプリカをつくろう」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 実験室
時間:14:00〜15:00
レプリカをつくりながら、三葉虫について学びます。定員30人。
当日会場で直接申し込み[受付13:30〜14:00]、先着順。対象は小学生以上(小学3年生以下は保護者と参加)、参加費は無料。
アンモナイトのレプリカをつくろう!! (北海道 北海道開拓記念館)
場所:北海道開拓記念館 講堂
時間:13:30〜15:30
北海道はアンモナイト化石の宝庫!!実際に北海道から発見されたアンモナイトと石こうを使って、本物そっくりのレプリカ(複製)作りに挑戦!色づけを工夫して、世界で一つだけのアンモナイトも作ってみましょう!講師:添田雄二(北海道開拓記念館学芸員)
2009年6月26日(金)からお電話で受付します。30名(先着順)
化石クリーニング体験 (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館 入口横 「化石の洞窟」
時間:10:00〜15:00
白亜紀の岩石(ノジュール)の中から、アンモナイトや二枚貝イノセラムスを取り出す。幼児用擬似ノジュールもあります。化石は、お持ち帰りいただけます。参加費は無料。
いろいろな化石をみる (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:南あわじ市 ショッピングセンター パルティ
時間:13:30〜14:30
知っている化石、知らない化石、いろいろな化石を見て、大むかしの生きものの世界にいってみよう。
8月2日締切。小学生〜大人 25名 参加費 高校生以上500円、中学生以下300円
「中生代の海生爬虫類 -恐竜時代の海の生き物-」 (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町 穂別町民センター(むかわ町穂別2-1)
時間:13:30〜16:00
「中生代の海生爬虫類」平山 廉(早稲田大学教授)・「穂別の脊椎動物化石」櫻
井 和彦(穂別博物館学芸員)・「穂別のアンモナイト」西村 智弘(穂別博物館普及
員)
8/23
(日)
レプリカづくり (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館 かせき学習館
時間:10:00〜15:00
アンモナイトの石こう模型作り。石こう模型は、お持ち帰りいただけます。参加費は無料。
レプリカ アクセサリーづくり (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館 かせき学習館
時間:13:00〜15:00
アンモナイトストラップかアンモナイトサンダルアクセサリーづくり。参加費は無料。
石の見分け方講座−顕微鏡で見る鉱物と岩石 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:人と自然の博物館
時間:13:30〜15:30
実物の観察や実験を通して、石の見分け方を学びます。きれいな鉱物や薄くした岩石を、実際に顕微鏡で観察します。
9月3日締切。小学校高学年〜大人 30名 参加費 高校生以上500円、中学生以下300円
特別展ツアー「特別展の展示解説」 (福井県 福井県立恐竜博物館)
場所:福井県立恐竜博物館3階 特別展示室
時間:13:00〜14:00
特別展の見どころについて、やさしく解説します。 聴講無料。
電話・FAX・E-mailにて。「特別展ツアー(日付)参加希望」と、氏名、住所、電話番号を福井県立恐竜博物館までお知らせ下さい。開催日の一ヶ月前から受付開始し、定員になり次第、〆切とさせていただきます。
8/24
(月)
8/25
(火)
8/26
(水)
標本の名前を調べる会 (徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島県立博物館
時間:10:00〜16:00
夏休みに採集した植物や動物(昆虫・貝など)、岩石、化石などの名前 を一緒に調べてみましょう。
8/27
(木)
8/28
(金)
8/29
(土)
サイエンス・サタデー「三葉虫のレプリカをつくろう」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 実験室
時間:14:00〜15:00
レプリカをつくりながら、三葉虫について学びます。定員30人。
当日会場で直接申し込み[受付13:30〜14:00]、先着順。対象は小学生以上(小学3年生以下は保護者と参加)、参加費は無料。
化石クリーニング体験 (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館 入口横 「化石の洞窟」
時間:10:00〜15:00
白亜紀の岩石(ノジュール)の中から、アンモナイトや二枚貝イノセラムスを取り出す。幼児用擬似ノジュールもあります。化石は、お持ち帰りいただけます。参加費は無料。
8/30
(日)
レプリカづくり (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館 かせき学習館
時間:10:00〜15:00
アンモナイトの石こう模型作り。石こう模型は、お持ち帰りいただけます。参加費は無料。
レプリカ アクセサリーづくり (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館 かせき学習館
時間:13:00〜15:00
アンモナイトストラップかアンモナイトサンダルアクセサリーづくり。参加費は無料。
石の見分け方講座−ふしぎな岩石と鉱物 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:人と自然の博物館
時間:13:30〜15:30
実物の観察や実験を通して、石の見分け方を学びます。石の持つ不思議な性質を体験します。
8月10日締切。小学校高学年〜大人 30名 参加費 高校生以上500円、中学生以下300円
8/31
(月)
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ内のフォームまたはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。随時、情報を更新いたしますので,ご協力をお願いいたします。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2009年9月)
9月のイベント・特別展示カレンダー (2009/09/01〜2009/10/05)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
9月の特別展示
2009/09/18 現在
鉱物の魅力−宝石から資源まで− (埼玉県 埼玉県立自然の博物館)
期間:6/27(土)〜10/04(日)
場所:埼玉県立自然の博物館企画展示室
宝石、機械部品、鉱物資源などに利用される身近な鉱物の性質と利用方法を紹介
糸魚川ジオパーク展−ヒスイ,化石,断層,見どころいっぱい− (新潟大学旭町学術資料展示館企画展)
期間:9/1(火)〜11/29(日)
場所:新潟大学旭町学術資料展示館
糸魚川産のヒスイ,アンモナイトやサンゴなどの化石,糸魚川から発見された新鉱物などを展示し,新潟大学理学部がこれまでに実施してきた糸魚川地域の研究成果を一般公開しています.理学部のサイエンスミュージアムなどとの間でスタンプラリーも実施中.
デザin Stone (静岡県 奇石博物館)
期間:7/18(土)〜12/23(水)
場所:奇石博物館 企画展示室
石の中に隠されているデザインをクローズアップしてご紹介します。
第65回特別展「北海道象化石展!」 (北海道 北海道開拓記念館)
期間:7/03(金)〜10/04(日)
場所:北海道開拓記念館 特別展示室
どうして日本では北海道だけマンモスゾウの化石が発見されるの? 忠類で発見されたナウマンゾウ化石はオス?メス? 年齢は? 北海道初となるゾウの足跡化石が最近発見された? 当時北海道には他にどんな動物がいたの? 人間はいた? 今回はこれらに関する化石や最新の研究成果を展示するとともに,普段は収蔵庫にある忠類ナウマンゾウ化石を発見40周年を記念して全て公開します!※総合地球環境学研究所との共催
世界ジオパーク展 −日本最初の認定地をめざす糸魚川− (新潟県 新潟県、糸魚川市教育委員会博物館)
期間:4/25(土)〜11/30(月)
場所:フォッサマグナミュージアム ふるさと展示室
世界ジオパークをめざす糸魚川の多様な大地とそれらが育んだ動植物、文化財などを紹介しています。野外のジオサイトへ出かけて大地の魅力を感じてみてください。
『リーフ:石灰岩を造った太古の生き物達〜サンゴを中心に〜』展 (栃木県 佐野市葛生化石館)
期間:7/11(土)〜10/04(日)
場所:佐野市葛生化石館 企画展示室
石灰岩は様々な種類の生き物が、集まって大きなリーフ(礁)をつくり,その後長い年月かけて形成されたものです。石灰岩を造る生物の化石を紹介する。
恐竜のくらした森 - 恐竜は花を見たか? (福井県 福井県立恐竜博物館)
期間:7/10(金)〜10/12(月)
場所:福井県立恐竜博物館3階 特別展示室
現在のわたしたちの世界を取り巻く森の中で85%以上もの圧倒的多数を占めている「花を咲かせる植物」(被子植物)は、恐竜時代の終わり頃に現れ、ごく短い期間に世界を花で被っていったことが分かっている。白亜紀に起こった、この「花のない世界」から「花に被われた世界」への変化は、恐竜をはじめ、植物を食べる地上の動物たちに大きな影響を与えたと考えられている。本特別展では、花の誕生とその進化にスポットをあて、植物化石からわかる被子植物の歴史をひもとき、その進化と繁栄に密接な関係がある昆虫や、恐竜など植物食の動物たちと植物との関わりの歴史を紹介する。 観覧料:一般 800円、大学・高校生 600円、小・中学生 400円、70歳以上の方 400円(上記料金で常設展もご覧いただけます)
夏の特別展「穂別海竜博物館-穂別を泳いでいた海竜たち-」 (北海道 むかわ町立穂別博物館)
期間:7/18(土)〜9/30(水)
場所:むかわ町立穂別博物館 特別展示室
恐竜時代に、海だった穂別を泳いでいた海竜たち(クビナガリュウ、モササウルス、ウミガメ)を紹介。どのような生き物で、どのように泳ぎ、何を食べていたのか、穂別で見つかった化石を見ながら考えよう。
小池コレクション展2 化石の魅力 (長野県 信州新町化石博物館)
期間:9/12(土)〜12/13(日)
場所:信州新町化石博物館 企画展示室
企画特別展「小池コレクション展1」では、当館館外研究員の小池伯一さんが採集した海生哺乳類化石の研究成果を元に紹介いたしました。今回は「化石の魅力」と題して、小池伯一さんが収集した標本の中から、三葉虫・アンモナイト・魚類化石など一般的によく知られている化石を中心に展示し、さらに小池さんが採集され、研究を進めた標本と研究成果についても紹介いたします。 様々な化石を通して、化石の持つ美しさやおもしろさ、生命の歴史などの「化石の魅力」をお楽しみ下さい。
9月のイベント
2009/09/18 現在
日付
イベント
9/01
(火)
9/02
(水)
9/03
(木)
9/04
(金)
9/05
(土)
9/06
(日)
富士山の地学ポイント観察会「幕岩を歩く」 (静岡県 奇石博物館)
場所:富士山南麓の幕岩周辺
時間:10:00〜15:00
富士山宝永火口の南に位置する幕岩と呼ばれる溶岩帯を巡り、富士火山の営みを考えます。定員;30名(先着順,定員になり次第締め切り)。料金;1人500円(資料、保険料)
実施日の3日前までに電話にて事前予約を行って下さい。参加される方の氏名、年齢(学年)、住所、電話番号をお知らせ下さい。TEL;0544-58-3830
化石クリーニング体験 (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館 入口横「化石の洞窟」
時間:10:00〜15:00
白亜紀の岩石(ノジュール)の中から、アンモナイトや二枚貝イノセラムスを取り出す。幼児用擬似ノジュールもあります。化石は、お持ち帰りいただけます。参加費は無料。
9/07
(月)
9/08
(火)
9/09
(水)
9/10
(木)
9/11
(金)
9/12
(土)
9/13
(日)
レプリカづくり (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館 かせき学習館
時間:10:00〜15:00
アンモナイトの石こう模型作り。石こう模型は、お持ち帰りいただけます。参加費は無料。
レプリカ アクセサリーづくり (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館 かせき学習館
時間:10:00〜15:00
アンモナイトストラップかアンモナイトサンダルアクセサリーづくり。参加費は無料。
特別展ツアー「特別展の展示解説」 (福井県 福井県立恐竜博物館)
場所:福井県立恐竜博物館3階 特別展示室
時間:13:00〜14:00
特別展の見どころについて、やさしく解説します。 聴講無料。
電話・FAX・E-mailにて。「特別展ツアー(日付)参加希望」と、氏名、住所、電話番号を福井県立恐竜博物館までお知らせ下さい。開催日の一ヶ月前から受付開始し、定員になり次第、〆切とさせていただきます。
巨象たちがいた頃の北海道 (北海道 北海道開拓記念館)
場所:北海道開拓記念館 講堂
時間:13:30〜15:30
9月13日(日) 13:30〜15:30数万年前、北海道にはたくさんのマンモスゾウやナウマンゾウが生息していました。そして当時生活していた人々の遺跡も発見されています。ゾウ化石と遺跡が語る太古の北海道を紹介します。講師:高橋啓一氏(滋賀県立琵琶湖博物館)、出穂雅実氏(札幌市埋蔵文化財センター)
2009年8月14日(金)からお電話で受付します。定員100名。
9/14
(月)
9/15
(火)
9/16
(水)
9/17
(木)
9/18
(金)
9/19
(土)
9/20
(日)
天神島めぐり「天神島の地層」 (神奈川県 横須賀市自然・人文博物館)
場所:付属天神島臨海自然教育園
時間:10:30〜12:00
天神島や笠島の地層は、およそ500万年前に海底で堆積した三浦層群からできています。この観察会では、天神島の地層に見られる火山豆石や断層、堆積構造などを観察します。
化石クリーニング体験 (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館 入口横「化石の洞窟」
時間:10:00〜15:00
白亜紀の岩石(ノジュール)の中から、アンモナイトや二枚貝イノセラムスを取り出す。幼児用擬似ノジュールもあります。化石は、お持ち帰りいただけます。参加費は無料。
9/21
(月)
敬老の日
レプリカづくり (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館 かせき学習館
時間:10:00〜15:00
アンモナイトの石こう模型作り。石こう模型は、お持ち帰りいただけます。参加費は無料。
レプリカ アクセサリーづくり (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館 かせき学習館
時間:10:00〜15:00
アンモナイトストラップかアンモナイトサンダルアクセサリーづくり。参加費は無料。
石割り化石探し (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館 前庭
時間:15:50〜16:00
7000万年前の白亜紀の本物の石を割って化石を探そう。参加費は無料。
9/22
(火)
国民の休日
化石クリーニング体験 (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館 入口横「化石の洞窟」
時間:10:00〜15:00
白亜紀の岩石(ノジュール)の中から、アンモナイトや二枚貝イノセラムスを取り出す。幼児用擬似ノジュールもあります。化石は、お持ち帰りいただけます。参加費は無料。
石割り化石探し (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館 前庭
時間:15:50〜16:00
7000万年前の白亜紀の本物の石を割って化石を探そう。参加費は無料。
9/23
(水)
秋分の日
レプリカづくり (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館 かせき学習館
時間:10:00〜15:00
アンモナイトの石こう模型作り。石こう模型は、お持ち帰りいただけます。参加費は無料。
レプリカ アクセサリーづくり (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館 かせき学習館
時間:10:00〜15:00
アンモナイトストラップかアンモナイトサンダルアクセサリーづくり。参加費は無料。
石割り化石探し (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館 前庭
時間:15:50〜16:00
7000万年前の白亜紀の本物の石を割って化石を探そう。参加費は無料。
9/24
(木)
9/25
(金)
9/26
(土)
福島県いわき・棚倉地方の化石採集 (福島県 千葉県立中央博物館)
場所:福島県いわき市ほか
福島県いわき市や棚倉地方を巡って、化石の採集を行います。
2週間前(9/12)までに、往復はがきかファクスに、参加希望者全員の氏名、年齢、住所、電話番号を記入して、中央博物館までお送りください。応募者多数の場合は抽選となります。(定員25名)
9/27(日)まで
鉱物に親しもう (埼玉県 埼玉県立自然の博物館)
場所:埼玉県立自然の博物館科学教室
鉱物を砕いたり,磨いたりして遊ぶ
1ヶ月前からメールか往復はがきで申し込む。
微生物が語る水惑星の環境史 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:丹波市・上久下地域づくりセンター
時間:13:30〜15:30
酸素のある大気や現代文明を支える石油をもたらしたのは微生物です。その化石は過去の地球環境の記録者でもあります。その記録を手がかりに明らかにされた気候変動や過去の海水準変動について解説します。
9月7日締切。中学生〜大人 30名 参加費 高校生以上500円、中学生200円
9/27
(日)
アンモナイト探検隊 (北海道 穂別観光協会・むかわ町立穂別博物館・むかわ町穂別地球体験館)
場所:むかわ町立穂別博物館・体験学習用地ほか
時間:9:30〜15:00
中生代白亜紀の終わり(約6500万年前)で永久の眠りについたクビナガリュウ、モササウルス、アンモナイトを、むかわ町穂別で探して掘り起こしましょう。 集合場所から採集地点まではバス送迎。昼食にはイベント限定のアンモナイトバーガーセット。 採集後に博物館と体験館の見学があります。じゃらん9月号にも掲載しています。 料金:中学生以上2,300円、小学生1,500円。
官製はがき、eメール(携帯メールは不可)、FAX 申込内容 1)参加を希望者の氏名、年齢・学年 2)住所 3)電話番号 4)FAX番号 5)eメールアドレス(お持ちの方のみ) はがきの場合 以上の内容をご記入のうえ穂別観光協会まで郵送してください。 eメールの場合 1)から4)の内容を(hakubutukan(at)town.mukawa.lg.jp (at)を@に変更)まで送信してください。折り返し、「申し込み完了」の確認メールを博物館から送信します。数日たっても確認メールが来ない場合は、お手数ですがもう一度改めてメールでご連絡ください。参加していただけるかどうかの最終的なご返事は改めてメールでご連絡します。 申し込み先 官製はがきの場合 〒054-0211 北海道勇払郡むかわ町穂別2番地 穂別観光協会 Eメールの場合 hakubutukan(at)town.mukawa.lg.jp (at)を@に変更して下さい。(むか わ町立穂別博物館) FAX 0145-45-3141(むかわ町立穂別博物館) 締切 9/14(月)必着
レプリカづくり (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館 かせき学習館
時間:10:00〜15:00
アンモナイトの石こう模型作り。石こう模型は、お持ち帰りいただけます。参加費は無料。
レプリカ アクセサリーづくり (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館 かせき学習館
時間:10:00〜15:00
アンモナイトストラップかアンモナイトサンダルアクセサリーづくり。参加費は無料。
9/28
(月)
9/29
(火)
9/30
(水)
10/01
(木)
10/02
(金)
10/03
(土)
10/04
(日)
シンポジウム「北海道のゾウ化石の謎にせまる」 (北海道 北海道開拓記念館)
場所:北海道開拓記念館 講堂
時間:13:30〜15:30
北海道ではたくさんのゾウ化石が見つかっており、最近の研究で様々なことがわかってきました。しかし、同時に新たな謎もいくつかでてきています。その「謎」を通して、北海道のゾウ化石を考えてみます。講師:澤村寛氏(足寄動物化石博物館)、添田雄二・山田悟郎(北海道開拓記念館学芸員)
2009年9月5日(土)からお電話で受付します.
10/05
(月)
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ内のフォームまたはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。随時、情報を更新いたしますので,ご協力をお願いいたします。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2009年10月)
10月のイベント・特別展示カレンダー (2009/10/06〜2009/11/02)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。
なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
10月の特別展示
2009/10/06 現在
第34回企画展「BONES」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
期間:9/19(土)〜11/23(月)
場所:群馬県立自然史博物館企画展示室
「みる きく かぐ たべる うごく ふやす」といった動物の動きをキーワードに、骨から読み解いた動物たちの生活を紹介します。
第17回企画展示『骨の記憶 あなたにきざまれた五億年の時』 (滋賀県 滋賀県立琵琶湖博物館)
期間:7/18(土)〜11/23(月)
場所:滋賀県立琵琶湖博物館
私たちの体に残された五億年の進化の面影やヒトらしさはどこにあるのかを写真、図、解説などで説明した本。骨の楽しみ方も紹介しています。
デザin Stone (静岡県 奇石博物館)
期間:7/18(土)〜12/23(水)
場所:奇石博物館 企画展示室
石の中に隠されているデザインをクローズアップしてご紹介します。
総合国際深海掘削計画アウトリーチ深海底研究最前線「地球をほる?ジョイデス・レゾリューション号の地球を知る旅324」 (東京都 国立科学博物館,日本地球掘削科学コンソーシアム(J-DESC),統合国際深海掘削計画アメリカ実施機関(IODP USIO),協力:海洋研究開発機構(JAMSTEC))
期間:9/08(火)〜11/08(日)
場所:国立科学博物館
地球のことを知るために、地球を直接掘って調べよう!というプロジェクトがあります。私たちの住む星地球には、まだまだ分かっていない環境や歴史があります。これらについて解明するために、海の上から地球を掘っている船があります。世界中からたくさんの研究者が乗り込んで、掘って得られた岩石を調べています。今回の航海で、海底の超巨大火山「シャツキー海台」を目指します。
国会議事堂の石 〜議事堂に使われた阿南市および那賀町産大理石〜 (徳島県 徳島県立博物館、阿南市立阿波公方・民俗資料館)
期間:9/25(金)〜11/05(木)
場所:阿南市立阿波公方・民俗資料館(阿南市那賀川町古津339-1)
大正時代から昭和の初めまで、現在の阿南市や周辺地域では、建築用石材として大理石(石灰岩)が大量に切り出され、全国各地の建築物に使われました。その中で最も有名なものが、大正9年に着工され、昭和11年に落成した国会議事堂です。国会議事堂の内装にはおもに国産の大理石が使われています。県別にみると、内装用石材の中で最も多用されているのが徳島県産のもので、しかも目立つところに特に多く使われています。産地は阿南市の5か所と那賀町の2か所です。この企画展では、国会議事堂に使用されている石材の学術的意義を紹介し、徳島県産の7種類の大理石のそれぞれについて、写真パネルと関連資料を展示します。
世界ジオパーク展 −日本最初の認定地をめざす糸魚川− (新潟県 新潟県、糸魚川市教育委員会博物館)
期間:4/25(土)〜11/30(月)
場所:フォッサマグナミュージアム ふるさと展示室
世界ジオパークをめざす糸魚川の多様な大地とそれらが育んだ動植物、文化財などを紹介しています。野外のジオサイトへ出かけて大地の魅力を感じてみてください。
「糸魚川ジオパーク展 −ヒスイ,化石,断層,見どころいっぱい−」 (新潟県 新潟大学旭町学術資料展示館企画展・新潟大学理学部)
期間:9/01(火)〜11/29(日)
場所:新潟大学旭町学術資料展示館
糸魚川産のヒスイ,アンモナイトやサンゴなどの化石,糸魚川から発見された新鉱物などを展示し,新潟大学理学部がこれまでに実施してきた糸魚川地域の研究成果を一般公開しています.理学部のサイエンスミュージアムなどとの間でスタンプラリーも実施中.
問い合わせ先:新潟大学旭町学術資料展示館(025-227-2260)
小池コレクション展2 化石の魅力 (長野県 信州新町化石博物館)
期間:9/12(土)〜12/13(日)
場所:信州新町化石博物館 企画展示室
企画特別展「小池コレクション展1」では、当館館外研究員の小池伯一さんが採集した海生哺乳類化石の研究成果を元に紹介いたしました。今回は「化石の魅力」と題して、小池伯一さんが収集した標本の中から、三葉虫・アンモナイト・魚類化石など一般的によく知られている化石を中心に展示し、さらに小池さんが採集され、研究を進めた標本と研究成果についても紹介いたします。
様々な化石を通して、化石の持つ美しさやおもしろさ、生命の歴史などの「化石の魅力」をお楽しみ下さい。
恐竜のくらした森 - 恐竜は花を見たか? (福井県 福井県立恐竜博物館)
期間:7/10(金)〜10/12(月)
場所:福井県立恐竜博物館3階 特別展示室
現在のわたしたちの世界を取り巻く森の中で85%以上もの圧倒的多数を占めている「花を咲かせる植物」(被子植物)は、恐竜時代の終わり頃に現れ、ごく短い期間に世界を花で被っていったことが分かっている。白亜紀に起こった、この「花のない世界」から「花に被われた世界」への変化は、恐竜をはじめ、植物を食べる地上の動物たちに大きな影響を与えたと考えられている。本特別展では、花の誕生とその進化にスポットをあて、植物化石からわかる被子植物の歴史をひもとき、その進化と繁栄に密接な関係がある昆虫や、恐竜など植物食の動物たちと植物との関わりの歴史を紹介する。
観覧料:一般 800円、大学・高校生 600円、小・中学生 400円、70歳以上の方 400円(上記料金で常設展もご覧いただけます)
化石は語る〜生物の進化と古環境〜 (長野県 飯田市美術博物館)
期間:10/31(土)〜2/07(日)
場所:飯田市美術博物館 展示室B
美術博物館所蔵の鎮西コレクション、寄託の長谷川コレクションを中心に、貝類や植物などの化石を展示します。クルミの進化、貝などを含む地層の古環境を調べた例も紹介します。
10月のイベント
2009/10/06 現在
日付
イベント
10/06(火)
10/07(水)
10/08(木)
10/09(金)
10/10(土)
ジオラボ(10月)「石になった植物化石」 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:自然史博物館 本館ミュージアムサービスセンター
時間:14:30〜
鉱物に置き換えられて石になった植物の化石を観察します。石になった木の幹、ソテツの幹、木生シダの幹、マツボックリを触ったり顕微鏡で観察してみましょう。
10/11(日)まで
10/11(日)
10/12(月)体育の日
特別展ツアー「特別展の展示解説」 (福井県 福井県立恐竜博物館)
場所:福井県立恐竜博物館3階 特別展示室
時間:13:00〜14:00
特別展の見どころについて、やさしく解説します。
聴講無料。
電話・FAX・E-mailにて。「特別展ツアー(日付)参加希望」と、氏名、住所、電話番号を福井県立恐竜博物館までお知らせ下さい。開催日の一ヶ月前から受付開始し、定員になり次第、〆切とさせていただきます。
10/13(火)
10/14(水)
10/15(木)
10/16(金)
10/17(土)
企画展示講演会「空中写真の撮影と三浦半島」 (神奈川県 横須賀市自然・人文博物館)
場所:横須賀市自然・人文博物館1階 講座室
時間:14:00〜16:30
企画展示「空から見た三浦半島」では、パワードパラグライダーを用いて空撮した三浦半島西岸の写真を展示します。この講演会では、それらの写真を撮影したPPG湘南平塚のメンバーから、パワードパラグライダーの概要や、実際に空から見た三浦半島の様子についてお話いただきます。三浦半島活断層調査会、PPG湘南平塚共同事業。
10/18(日)
ファミリー自然観察会「みかぼ山の地質と植物」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:西御荷鉾山(神流町)
時間:9:00〜12:00
西上州を代表する山である、みかぼ山の自然、特に地質と植物について、観察します。
現地集合、小学生以下は保護者と一緒に参加。参加費50円(保険料)。実施日の2週間前までにハガキで申し込み。参加者全員の住所、氏名、年齢、電話番号を記入。ハガキは一家族一通。応募者多数の場合は抽選。
初めての岩石観察会「伊豆の緑色凝灰岩」 (静岡県 奇石博物館)
場所:伊豆半島
石に記されている地球史ドラマを読み取ります。今年は伊豆の緑色凝灰岩を観察します。地学や岩石のことが分からない方大歓迎です!定員;30名(先着順,定員になり次第締め切り)。料金;1人500円(資料、保険料)
実施日の3日前までに電話にて事前予約を行って下さい。参加される方の氏名、年齢(学年)、住所、電話番号をお知らせ下さい。TEL;0544-58-3830
白亜紀の地層見学(勝浦町) (徳島県 徳島県立博物館)
場所:勝浦郡勝浦町(現地集合・現地解散)
時間:9:30〜13:00
徳島県勝浦町には白亜紀の地層が広く露出しており、たくさんの二枚貝や巻貝の化石が産出します。また、ここからは四国唯一の恐竜化石も発見されています。この行事では、ハイキング気分で山道を歩きながら地層の観察をしていきます。
往復はがきに 1. 希望行事名 2. 参加希望者全員の氏名と住所(学生の場合は学年も)3. 電話番号を記入し、行事予定日の1ヶ月前から10日前までに届くように徳島県立博物館普及係(〒770-8070 徳島市八万町向寺山)までお申し込みください。
山陰海岸国立公園「鳥取砂丘自然観察会」−鳥取砂丘に出かけて、砂丘のなりたちや砂丘植物を学ぼう− (鳥取県 近畿地方環境事務所、財団法人 自然公園財団鳥取支部)
場所:鳥取砂丘市営駐車場 インフォメーション棟集合
自然観察プログラム。鳥取砂丘の散策・自然観察。山陰海岸国立公園「鳥取砂丘自然観察会」−鳥取砂丘に出かけて、砂丘のなりたちや砂丘植物を学ぼう−。
定 員:20名程度(小学生以上。小学生は保護者同伴)。参加費:500円(1人あたり) ※保険代、資料代含む
次のどちらかに電話にて申し込み。
浦富自然保護官事務所TEL:0857-73-1146(金曜日除く平日9:00
017:00)(財)自然公園財団鳥取支部、TEL:0857-23-7652(9:00
017:00)
自然観察フィールドワーク「三保の魚」 (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
三保の浜で地引網を行い、そこにすむ魚など生きものを観察します。
ホームページ参照
10/19(月)
10/20(火)
10/21(水)
10/22(木)
10/23(金)
10/24(土)
ミュージアムナイトツアー (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館展示室
時間:17:30〜19:00
昼間とは違った雰囲気の夜の博物館をミュージアムガイドが案内します。
定員:各回30人。対象は小学生以上、ただし小学生は保護者と参加のこと。回とも実施日の2週間前にハガキ必着。参加希望日は1枚のハガキに一つ記入してください。参加希望者はご家族のみの記入でお願いします。ハガキは一家族一通。応募者多数の場合は抽選(抽選結果はハガキで通知)。
釧路市立博物館 講演会「わたしたちと火山=雌阿寒岳・雄阿寒岳=」 (北海道 釧路市立博物館
(共催:社団法人東京地学協会・釧路市総務部総務課・阿寒行政センター地域振興課・商工観光課、後援:国土地理院北海道地方測量部・気象庁釧路地方気象台・財団法人日本地図センター・NPO法人阿寒観光協会まちづくり推進機構))
場所:釧路市立博物館講堂
時間:13:30〜16:00
美しい景観、安らぐ温泉。火山災害への備え。火山とどうつきあっていくか、考えてみませんか?国土地理院火山土地条件図「雌阿寒岳・雄阿寒岳」刊行を記念してお二人に、分かりやすくお話いただきます。
<講師>奥野 充さん(福岡大学理学部准教授:噴火史研究)、小白井 亮一さん(国土地理院北海道地方測量部長)。 *火山や防災、地図に関する資料の配付やミニ展示もあります。
10/25(日)
日本最古の地層を観察しよう (茨城県 茨城県自然博物館)
場所:日高市
時間:10:00〜15:00
講師は、田切美智雄氏(茨城大学教授)。高校生以上が対象です。定員20名。要参加費。
行事案内のページをご覧ください。
自然観察フィールドワーク「久能山の化石」 (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
久能山で地層や化石を観察して、久能山のおいたちを探ります。
ホームページ参照
10/26(月)
10/27(火)
10/28(水)
10/29(木)
礫層からみた中央アルプス、太田切川流域の地形 (長野県 飯田市美術博物館、伊那谷自然友の会)
場所:飯田市美術博物館 科学工作室
時間:7:00〜9:00
最終氷期〜現在までの千畳敷カールから太田切川流域の地形形成を礫層との関係で見る。講師は下平眞樹さん。
10/30(金)
10/31(土)
地学野外観察会 白河火砕流と白河石・芦野石 (栃木県 千葉県立中央博物館)
場所:栃木県那須町・福島県白河市・西郷村・下郷町
時間:7:30〜
首都圏でもよく使われている石材「白河石」・「芦野石」の供給源である白河火砕流の露頭を観察します.
往復葉書かファクスに行事名と参加希望者全員の氏名・年齢・住所・電話番号を記入し,2週間前までに千葉県立中央博物館あてに申し込みください.定員を越えた場合は抽選となります.
11/01(日)まで
県外岩石観察会3 白河火砕流と白河石・芦野石 (福島県 千葉県立中央博物館)
場所:福島県白河市ほか
首都圏でも使われている石材「白河石」・「芦野石」の供給源である白河火砕流の露頭を観察します。
2週間前(10/17)までに、往復はがきかファクスに、参加希望者全員の氏名、年齢、住所、電話番号を記入して、中央博物館までお送りください。応募者多数の場合は抽選となります。(定員25名)
11/01(日)まで
11/01(日)
土柱周辺の地形と地質のかんさつ (徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島県阿波市阿波町土柱周辺(現地集合・現地解散)
時間:13:00〜16:00
今年5月に「日本の地質百選」のひとつに選ばれた「阿波の土柱」やその周辺の地形と地質を観察します。土柱をつくる土柱層は扇状地の地層で、土石流堆積物や、約100万年前に大分県西部から降ってきた火山灰層などが見られます。この行事では、これらを観察するほか、近年になって急速に進んでいる土柱の埋積についても考えてみたいと思います。
往復はがきに 1. 希望行事名 2. 参加希望者全員の氏名と住所(学生の場合は学年も)3. 電話番号を記入し、行事予定日の1ヶ月前から10日前までに届くように徳島県立博物館普及係(〒770-8070 徳島市八万町向寺山)までお申し込みください。
11/02(月)
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ内のフォームまたはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。随時、情報を更新いたしますので,ご協力をお願いいたします。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
チバニアン提案書の公開と,その引用について(2021年2月)
チバニアン提案書の公開と,その引用について
チバニアン提案書の公開と,その引用について
チバニアンGSSPの提案申請書が,IUGS(国際地質科学連合)の学術誌Episodesに掲載され,ウェブサイトで公開されました.https://doi.org/10.18814/epiiugs/2020/020080
日本発の地質年代名称「チバニアン: Chibanian」の国際的認知度を高めるためにも,論文など出版物中で積極的にチバニアンGSSPに言及し,本提案書を引用してくださいますようお願いいたします.GSSPは10年間のモラトリアム期間が過ぎると再審査が可能になります.チバニアンの国際的認知度の向上が,将来的にチバニアンGSSPを維持することにも繋がりますので,会員の皆様には是非ともご協力をお願いいたします.
2021年2月
日本地質学会学術研究部会
第四紀の下限が変わる(2009.10.1)
拡大地層名委員会
地層命名指針TOP画面に戻る
第四紀の下限が変わる!
2009年10月1日
日本地質学会拡大地層名委員会
この度,国際地質科学連合(IUGS)の理事会は,2009年6月29日に,第四紀・系の下限を2.588 Maとする国際層序委員会(ICS)の提案を批准いたしました.今回,この変更に関する日本地質学会の対応方針の検討が、理事会より地層名委員会に諮問されております.従来の地層名委員会の委員に,専門部会長,研究委員会委員長,理事等を加えた拡大地層名委員会を立ち上げて検討を開始しました.今後,学術会議や関連学協会と連携をとりながら日本としての対応を検討していきます.
問題の背景を理解していただくために,今回このような変更がなされた経緯に関して簡単に紹介します.
1948年のロンドンでの万国地質学会(IGC)において,第四系の基底は,海生動物群の変化に基づいて決定するとされました.その後の検討により,第四系の基底の模式地(GSSP;Global Strato-type Section and Point)として,イタリア地中海沿岸ヴリカのカラブリア層が選ばれ、同系の基底としてオルドバイ正磁極期上限付近のsapropel層であるe層の上面が指定され,1985年に国際地質科学連合(IUGS)で批准されました.しかしその後,古気候や古海洋環境の変遷に関する研究が進展するにつれ,第四紀更新世の始まりは,深海底コアの底生有孔虫化石の酸素同位体比が現在の値より大きくなる時期,北半球高緯度においてIce Rafted Debirsが産出し始める時期(いずれも北半球氷床の形成を示す),中国レスの堆積開始時期等と一致させるべきとの見解が出され,長らく議論が続けられてきました.
今回批准された提案は,この見解に従ったもので,カラブリア期(Calabrian)の前のジェラ期(Gelasian)が第四紀更新世に含められることになりました.新たな第四系の基底(鮮新統・更新統境界),すなわちジェラ階の基底は,シシリー島のモン・サン・ニコラの南斜面にあり,古地磁気層序における松山/ガウス境界の約1m上位に位置します.その年代は2.588Maであり,これは酸素同位体ステージ(Marine Isotope Stage)のMIS103の基底に相当します.この時期は,地球史のうえでは,パナマ地峡が2.7Ma頃に閉塞したために,現在の湾流(Gulf Stream)に相当する海流が成立し,北半球高緯度域に多量の水分がもたらされ氷床が形成されはじめた時期にあたります.これは,深海底コアの底生有孔虫化石の酸素同位体比の変化からも支持されます(第1図).
第1図.過去500万年間の深海底底生有孔虫化石の酸素同位体比変動曲線(Lisiecki, and Raymo, M.E. [2005, Paleoceanography, 20, PA1003, doi:10.1029/2004PA001071]をもとに井龍が作成).2.60M頃を境に,現在の値よりも大きな値を示すようになり,4.1万年周 期のミランコビッチサイクルが顕著になっています.
地層命名指針TOP画面に戻る
地学研究発表会(2009岡山)
小さなEarth Scientistのつどい〜第7回小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜(2009岡山)
会場風景
会場風景
表彰式の様子
岡山大会最終日に,日本地質学会地学教育委員会の主催で「小さなEarth Scientistのつどい 〜第7回小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜」(岡山大会の関連行事)がおこなわれた.年会における発表会は6年前の静岡大会からおこなわれており,今回で7回目となった.この発表会の目的は,地学普及の一環として学校における地学研究を紹介することで地学教育の奨励と振興を図ることと,地学を研究する児童・生徒と研究者の交流が進み,地球科学普及の一助となることである.
今年も年会のポスターセッション会場のうち,8階のほとんどのエリアを発表会場として利用させてもらった.そのため,岡山大会に参加された会員の方は発表会場に足を運ばれ,生徒達の頑張っている姿をご覧いただけたと思われる.岡山大会では,中学校3校,高等学校11校から,あわせて15件の発表があった.昨年の秋田大会に比べて発表件数が増え,地元岡山県からも多くの発表があった.このことは,岡山県内の多くの会員が本発表会のためにご尽力頂いたためであることに加え,岡山県内の地学教育の盛んさを裏付けるものでもある.
なお審査の結果,下に示す4件の発表に対して優秀賞が授与されている.優秀賞の選考については,「研究の動機が明確であり,問題点をはっきりととらえているか」,「観察・実験から導かれたデータを基に,結論が導かれているか」,「ポスターのプレゼンテーションはどうか」,「ポスターに込められた工夫や努力はみとめられるか」の4つの観点で審査を行っており,審査員は学会理事と地学教育委員会の担当者がつとめている.理事の方々については,学会期間中のお忙しい中にもかかわらずご協力頂き,とても感謝している.
岡山大会は無事に終了したが,実施については常に見直すことが必要である.本生徒発表会の実施方法等にご意見のある方は,日本地質学会学会事務局<main@geosociety.jp>または担当者にご連絡頂けたら幸いである.
最後となったが,発表会を実施するにあたり後援をいただいた岡山県教育委員会および岡山市教育委員会,会場校である岡山理科大学と西日本支部の関係各位,さらに今回の発表会参加者に謝意を表したい.
優秀賞を受賞した発表:
1.「堆積物中の二硫化鉄生成の物理化学的検討」:山粼晴香(福岡県立八幡高等学校)
2.「マグマ分化末期の流体相の環境条件を推定する〜凝灰岩の加熱実験から、その赤色化を指標にして〜」:大西のり子,田中佑佳,宮脇彩絵子,小林彩香,藤尾有希,藤本さやか,河合なつみ,岡本裕貴,今村柾美,大西慶子,角山怜祐,窪田みな実,黒田絢香,陳東あかね,沼田聡子,池田志保,井上仁美,梅田剛志,梅田将志,小林愛理,野高緑,原由洋,三木七海,山口航輝,横山朋弘,福本美南,井上紗智,坂本夏奈,十倉麻友子,岩本遙,江草麗子,江籠徳行,近江毅志,角田優貴,田村優季(兵庫県立加古川東高等学校・竜山石班)
3.「磁気治療器を用いた花崗岩の分類—人形峠周辺の場合」:横山雅史(岡山県立林野高等学校)
4.「三重県内の中央構造線未確定区域に関する研究」:中村れいら(伊勢市立五十鈴中学校)
発表会参加校:岡山県立林野高等学校,岡山県立岡山朝日高等学校,岡山県立倉敷天城高等学校,岡山理科大学附属高等学校,岡山市立妹尾中学校,玉野市立日比中学校,早稲田大学高等学院,静岡県立静岡中央高等学校,兵庫県立加古川東高等学校,香川県立三本松高等学校,福岡県立八幡高等学校,伊勢市立五十鈴中学校
(大分大学教育福祉科学部 三次徳二)
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2010年3月)
3月のイベント・特別展示カレンダー (2010/3/01〜2010/04/01)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
3月の特別展示
2010/03/12 現在
北海道アンモナイト図鑑 (北海道 むかわ町立穂別博物館)
期間:2/6(土)から5/30(日)
場所:むかわ町立穂別博物館 特別展示室
北海道産の白亜紀アンモナイト各種の特徴や産出レンジなどについて実物の標本と解説シートで紹介します.これまでに世界で数個体しか見つかっていない種類も含めて,約60種のアンモナイトを紹介します.事前申込不要
ギャラリー展示「鉱物・化石展2010 ぼらくは大地に夢を掘る」 (琵琶湖博物館 企画展示室)
2010年3月20日(土)〜5月9日(日)
場所:琵琶湖博物館 企画展示室
滋賀県やその周辺で活動する鉱物・化石等の愛好家(湖国もぐらの会)が集結して、企画展示室いっぱいに標本を自ら展示する第三弾。今回は採集標本の対象地域を全国に広げて展示します。また、最近はじめたという子ども達の展示を行うなど、新たな試みもあり、展示を通してそのおもしろさをみなさんにお伝えします。事前申込:不要
3月のイベント
2010/03/12 現在
日付
イベント
03/01
(月)
03/02
(火)
03/03
(水)
03/04
(木)
03/05
(金)
03/06
(土)
秩父ジオサイトバスツアー (NPO法人 秩父まるごと博物館)
場所:9:00 西武秩父線 西武秩父駅前集合
時間:9:00〜16:00(雨天決行)
見学地:浦山ダム付近(秩父帯の岩石)〜橋立鍾乳洞(石灰岩と石灰洞)〜/ミューズパーク(高位段丘)〜ようばけ(新第三系)〜前原の不整合等.定員40人(定員を超えた場合は抽選).参加費100円(保険料)
03/07
(日)
03/08
(月)
03/09
(火)
03/10
(水)
03/11
(木)
03/12
(金)
03/13
(土)
03/14
(日)
03/15
(月)
03/16
(火)
03/17
(水)
03/18
(木)
03/19
(金)
03/20
(土)
03/21
(日)
03/22
(月)
03/23
(火)
03/24
(水)
03/25
(木)
03/26
(金)
03/27
(土)
03/28
(日)
03/29
(月)
03/30
(火)
03/03
(水)
03/04
(木)
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ内のフォームまたはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
教師巡検(2009岡山)
教師巡検(2009岡山)万成石と文化地質学
案内者:能美洋介,竹下浩征(万成石研究グループ)
参加者:阿部國廣,大友幸子,矢島道子,岡田浩二,松田義章,飯島 力,細谷正夫,三宅 誠,藤野光裕,行方綾香,野村香織,土屋裕太,大藤貞夫 (13名)
【案内者報告・反省】
写真1 ジオトレイルの恐竜模型の前で
岡山大会期間の中日9月5日(土)の午前中の時間を利用して本巡検が行われた.今回の巡検テーマは,「岡山県南部の花崗岩類(万成石)と文化地質学」として,案内者らが共同研究をすすめている万成花崗岩(万成石)を対象に,その教育利用施設と稼動中の採石場を廻った.
案内者は大部分の参加予定者の顔もわからないような頼りない状況であったが,申込者13名は全員予定時刻までに集合し,初顔合わせのあいさつそこそこにバスに乗り込んで,予定時刻の8時30分ちょうどに岡山駅西口を出発した.
第1目的地は岡山県立児童会館に併設されている「太陽の丘」公園である.ここは岡山市街地の西部にある丘陵地の一部を公園にしたもので,大きな恐竜のモニュメント兼すべり台がランドマークとなっていて,休日は多くの親子連れや子供たちで賑わう.巡検一行は開園直前に到着し,まだ子供たちがいない公園に一番に乗り込んだ.入口の恐竜モニュメント前でやっと今回の巡検の概要を説明し,次いでこの公園の概要を説明した.この公園は少し大きめのすべり台などの遊具がある遊園地だが,その土台を見ると岩石がごつごつと姿を見せているのがわかる.これらは今回の巡検の主役である万成石である.古くは採石場だったらしいこの地では,花崗岩とそれに伴ういくつかの地質学的現象を見ることができる.巡検案内者世話人らは公園内の露頭に看板を設置し,来園した子供たちが遊びの一環として地質学に接することができる地学公園「ジオトレイル」をつくった.ジオトレイルでは看板に設置された文字を順番に集めるとひとつの単語が浮かび上がるようになっていて,地図を見ながら宝探しのように露頭を探し廻ることができる.本巡検では,ジオトレイルの現状と効果,教育利用方法について,看板が設置された露頭を巡り議論した.巡検に参加した地質のプロたちは,最終的に浮かび上がるはずの単語を巡る前に言い当て,案内者としては不調な滑り出しであったが,各露頭の前では説明に使用されている用語の的確性を指摘されたり,小学生を対象としているにしては表現が難しいなどの厳しい意見も寄せられて案内者をたじたじにさせたりの場面もあった.しかし,都市近郊でこのような公園に着目して説明版を設置したことの意義を好意的に評価する意見もあって,案内者としては手に余るほどの成果を持って第1目的地をあとにすることができた.
写真2.万成石の石切り場にて
写真3.伝統的な石切り方法で切れた跡
第2目的地は現在稼動中の(有)浮田石材店の万成石採石場である.この採石場は,岡山市西部の矢坂山山塊の中央部やや西寄りの位置にある.ちなみに,第1目的地のジオトレイルは同山塊の東端にある.採石場では,浮田石材店浮田社長のご好意により,丁場の最前面まで行かせていただき,白く輝く未風化岩盤の切削面に触れることができた.また,その付近に散在している手が切れるようなエッジの岩石片を採集させていただいた.巡検一行はさらに上方に登り,売り物になりにくい岩塊(ズリ)を集めている場所に行ったが,多くの参加者はこちらの石の方が特急品の万成石より目を輝かせて眺めており,ペグマタイトや晶洞を食い入るように観察していた.なお,浮田社長からはズリはいくら叩いても良いという言葉を事前にいただいていたが,個々のズリは巨大であり地質屋のハンマーを受け付けない威容であったため,実際にサンプリングできた人は少なかったように思われる.さらに周辺の細粒花崗岩の貫入露頭や産総研の試掘井などを見学した.その後山を降りて石材加工所の前に集合すると,巨大な石材を割る作業を見せていただけるという.この石割では新旧2通りのやり方を実演していただいたが,石が割れはじめる瞬間の微音に皆が耳をそばだて,瞬間的にクラックが広がる様子に歓声を上げ,割り出し直後の石肌の冷たい感触に触れることができるサプライズイベントとなった.
本巡検は最初から予定した時間が短かったことや,案内者の頼りない説明で参加者間での議論が逆に盛り上がってしまったことなど,主催者としての反省点は誠に多いものであったが,9月初旬の暑い日差しの中にもかかわらず,時間通り行動をしていただき無事に予定コースをまわれた事など,参加者の皆さんのご協力によるところが大きい.最後に案内者といたしまして,巡検を盛り上げていただいた参加者の皆さんと,本巡検の場所を提供していただいた県立児童会館,およびビッグサプライズまでも用意していただきました浮田社長と石割を行ってくれた社員の皆さんにこの場を借りて感謝の意を申し上げます.
(岡山理科大学・万成石研究グループ 能美洋介)
【参加者感想】
今回の教師巡検の参加者は13名(中学教師1、高校教師4、大学教員3、学生・院生3、元教員2)でした。この見学旅行のことは主に地質学会Newsで知った方が多く、その他には学会のホームページや口コミで知られたようです。
岡山理科大学・万成石研究グループの方々の長年の努力のあとを見せて頂きました。ジオトレイルは、コンパクトにまとまっていてよかったです。万成石の石切り場では、市街地に近くてよかった;サンプルも多くでき、石割りも見せていただいて大満足;万成石を以前から見たかったので大満足;石材店の社長さんの説明もよかった;現場での質問に丁寧に答えていただき、ありがたかった等の感想がありました。
全体としては、午前だけの巡検でしたので、半日で少々もの足りない;もう少し時間がとれればよかった、などの感想がありました。また、全体の内容については、全体の地形がみられるところがあるとよかった;花崗岩の成因論の最近の知見も知りたかったし、生活の場への活用についてももう少し説明してほしかったという意見もありました。
教師巡検全体については、案内者の側からは、案内者の一員として、参加者の質問から多くを学んだ;案内者としては、もっと多くの人に見てもらいたかったという感想がありました。参加者側では、生徒にわかりやすく、興味をもって取り組める地学をもっと勉強したいと思った;教員巡検を是非続けてほしい。土日ならば参加できるという感想もありました。次の地質学会でも教師巡検ができるようにしたいです。
(元高校教師 矢島道子)
公開シンポジウム「人類の時代・第四紀は残った」(2010.1.22)
公開シンポジウム「人類の時代・第四紀は残った」
公開シンポジウム「人類の時代・第四紀は残った」
クリックするとpdfファイルをダウンロードで来ます。
主 催:日本学術会議地球惑星科学委員会IUGS分科会・日本学術会議地球惑星科学委員会INQUA分科会
共 催:日本地質学会・日本第四紀学会・日本地球惑星科学連合(予定)
日 時:2010年1月22日(金) 10:00-17:15 <参加無料・事前申込不要>
場 所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木7-22-34)
開催趣旨:2009年6月30日,国際地質科学連合(IUGS)執行委員会は第四紀を正式の地質時代として認め,その始まりを258万8千年前とする新しい定義を批准した.これにより長年,地質時代としての位置づけが不確定であった第四紀が正式な紀/系として認められた.また,その開始時期も,汎世界的な変化を認めることのできない181万年前から,地球規模の寒冷化・環境変動と中緯度地域に達する大規模な氷河の出現が顕著となる時期に変更された.
第四紀は現在も継続する地球規模の激しい環境変動の中で人類が発生して進化してきた最新の地質時代である.地球表層に記録されている第四紀の環境変動に関わる膨大な情報は,近未来の地球環境を合理的に予測するための重要な資料として活用されている.新しい定義を確認し,最新の地質時代の持つ意味を改めて明らかにすることが本シンポジウムの目的の一つである.
またこの新しい定義は,鮮新世の上限を変更し,長年使用されてきた古第三紀・新第三紀の呼称の存続にも関わっている.地学教育や応用地質,地質災害など研究教育と一般社会に広く新しい定義を普及させ,かつ,日本の地質環境に調和した導入と展開を図るための議論も重要な目的の一つである.
プログラム(案)
10:00-10:05 趣旨:地質年代区分の現状と問題. 斎藤靖二(生命の星・地球博)
10:05-10:30 地球生命史からみた新しい時代の意義. 北里 洋(JAMSTEC)
10:30-11:00 第四紀定義問題の歴史. 奥村晃史(広島大)
11:00-11:30 地質時代の決定と第四紀の模式地. 新妻信明(元静岡大)
11:30-12:00 人類進化と第四紀. 海部陽介(国立科博)
12:00-13:00 (休憩)
13:00-13:30 石灰質ナンノ化石からみた本邦の第四系と古海洋. 佐藤時幸(秋田大)
13:30-14:00 日本の第四系—古地磁気・同位体層序から見た房総半島上総層群および千倉層群. 岡田 誠(茨城大)
14:00-14:30 日本の第四系—3.5〜1.5Maの広域テフラ層の層序と給源火山地域.長橋良隆(福島大)
14:30-14:45 (休憩)
14:45-15:15 日本の第四系—応用地質における第四系. 井上大榮(電力中研)
15:15-15:45 地質情報からみる第四紀問題. 尾崎正紀(産総研)
15:45-16:15 アジアの地質にみる第四紀—アジアの大河川とメガデルタ—. 斎藤文紀(産総研)
16:15-17:15 総合討論(教育に関連する話題を中心に)
問い合わせ先:
奥村晃史(kojiok@hiroshima-u.ac.jp)
〒739-8522 東広島市鏡山1-2-3 広島大学大学院文学研究科
電話:082-424-6657
斎藤靖二(saitou@nh.kanagawa-museum.jp)
〒250-0031 小田原市入生田499 神奈川県立生命の星・地球博物館
電話:0465-21-1515 (代)
2025年地質の日
2025年の「地質の日」
ここでは,今年の「地質の日」に関連した日本地質学会主催,共催,後援等の催しをご紹介します。地質学会以外の全国の地質の日イベント情報はこちら
[開催支部・エリア]北海道/東 北/中 部/関 東/近 畿/四 国/西日本/オンライン/その他
日本地質学会 2.27掲載
講演会チラシPDFがDLできます
「地質の日」オンライン一般講演会
「ナウマン来日150年 その功績と足跡を辿る」
日程:2025年5月10日(土)13:30~16:00
*YouTube Liveによるライブ配信(どなたでも視聴可能です).申込不要.無料
*YouTubeのご視聴はこちらから
<オンライン講演会のパブリック・ビューイングを開催しませんか?>当オンライン講演会はYouTubeライブで一般に公開します。博物館やジオパークなどでパブリック・ビューイングを開催いただけます。申請は不要です。開催後、開催した旨を事務局にご報告ください。たくさんの方にご覧いただけるよう,ご協力をお願いいたします。
<プログラム>
13:35-14:35 日本地質学の父 エドムント・ナウマンーお雇い外国人教師ナウマンはフォッサマグナに挑んだ! 矢島道子(東京都立大学非常勤講師) 私たちのよく使う「フォッサマグナ」「中央構造線」「内帯/外帯」などの言葉は1875年に来日したナウマンが提唱しました。帰独した1885年に現在と遜色ない日本の地質図を発表したナウマンは、どうして短時日にこの偉業を達成できたのでしょうか。
14:45-15:05 ナウマンと佐川の人々 森 浩嗣(佐川地質館) 「緑なす山々...」で始まる書をナウマンが記した地・佐川町。この町では、彼のゆかりを各所で見ることができます。また、ナウマンに佐川を案内した高知の化石コレクター・外山矯についても併せてご紹介します。
15:05-15:25 ナウマンの研究したゾウ化石 佐々木猛智(東京大学総合研究博物館) ナウマンは1881年に日本のゾウ化石についての最初の論文を出版しました。ゾウ化石を含む彼の研究標本は現在東京大学総合研究博物館に保存されており、一部を 展示公開しています。関連する収蔵資料について紹介します。
15:25-15:45 火の島に立つ − ナウマンが見た躍動の伊豆大島 臼井里佳(伊豆大島ジオパーク推進委員会事務局) 1877年、ナウマンが訪れた伊豆大島は、安永の大噴火から約100年が経ち、なおも活発に噴火を繰り返す御神火の島でした。若き地質学者はこの躍動の中に何を見たのか。現代の風景と重ねながら、 伊豆大島の魅力をご紹介します。
日本地質学会 2.21掲載
惑星地球フォトコンテスト第16回ほか入選作品展示会
過去の展示の様子
日程:2025年5月13日(火) 午後〜 5月25日(日)14時まで
場所:東京パークスギャラリー(上野グリンサロン内)(台東区上野公園 JR上野駅 公園改札出てすぐ)
入場無料,どなたでもお気軽にお立ち寄り下さい.
入選作品の画像や講評は学会HPに掲載予定です.
問い合わせ先:日本地質学会事務局 main[at]geosociety.jp
(注)[at]を@マークに変えて送信してください。
日本地質学会 3.17掲載
街中ジオ散歩in Chiba
身近な地形・地質から探る稲毛海岸の歴史
※参加申し込み受付は終了しました
主催:(一社)日本地質学会,(一社)日本応用地質学会
日時:2025年5月11日(日)10:00〜13:00ごろ(予定)
見学場所:千葉県千葉市美浜区〜稲毛区 主な見学地点は以下となります.
「海洋公民館跡地(こじま公園)」〜「旧納涼台」〜「漁協解散の記念碑・民間航空発祥之地モニュメント」〜「一の鳥居(稲毛浅間神社)」〜「稲毛浅間神社」〜「稲毛公園」〜「稲毛陸橋と海食崖」
案内者:山中 蛍氏,白井 豊氏,高橋直樹氏(千葉県立中央博物館)
集合及び解散場所・時間:
集合:JR京葉線 稲毛海岸駅南口(人のモニュメント前)
出発:10:00(受付は集合地点で9:45〜10:00)
解散:最終見学地点(JR稲毛駅,京成稲毛駅へ徒歩)13:00ごろ(予定)
会費:大人1,500円,小中学生500円 (保険代含む,小中学生は保護者同伴)
募集人員:20名(定員を超えた場合は,締切後抽選)
募集期間:4月1日(火)〜15日(火)※申し込み受付は終了しました
対象:参加資格は特にありませんが,急坂,階段を含む高低差のある箇所があります.
申込に際しての注意事項(申し込みフォームは4月1日から受付開始いたします):
① 雨天中止,小雨決行とします.② 当見学会では,途中昼食時間を設けておりません.昼食は解散後各自でお願いします. ③ 連絡はメールにて行います.メールでの連絡ができない場合は,申し込みをご遠慮下さい. ④ 一般(非会員)の方を対象とした行事なため,一般申込者を優先とさせていただきます. ⑤ 申込時には保険加入や名簿作成のために必要な情報をお知らせいただきます. ⑥ 申込項目には漏れなく記入して下さい.記入いただけない場合は,受け付けできません. ⑦ 中学生以下の方は保護者同伴でお申し込み下さい(保護者の分も別途申込手続きを行って下さい). ⑧ お申し込みいただいた方は上記事項に同意していただけたものとみなします.
申込方法:上記注意事項をよくご確認のうえ, WEB専用申込フォームから お申し込み下さい(電話では受け付けません).(注)抽選の場合,当選の発表は,4月中にメールにて連絡させていただきます.
問い合わせ先(メールにてお願いします): 日本地質学会関東支部(担当 細矢)mail:hosoya[at]ckcnet.co,jp
関東支部 4.7掲載
2025年度関東支部講演会
日時:2025年4月12日(土)14:00-15:30
場所:北とぴあ第2研修室 JR京浜東北線王子駅北口徒歩3分;東京メトロ南北線王子駅5番出口直結;東京さくらトラム(都電荒川線)王子駅前徒歩5分.
タイトル「潜水船・水中ドローンによる島弧-海溝系の海底露頭観察」
講師:山口飛鳥氏(東京大学大気海洋研究所)
詳しくは,こちらから(関東支部のページへ)
関東支部 4.7掲載
学生・若手会員向け「地質調査の基礎講座」 ー城ヶ島巡検ー
2025年5月31日(土)10:00-16:30 集合場所:白秋碑前バス停.神奈川県三浦市城ヶ島で野外観察・調査
2025年6月1日(日)10:00-15:00 集合場所:会議室(横須賀市産業交流プラザ第一会議室(京急線汐入駅前))で露頭柱状図作成など(室内作業)
参加申込締切:5月23日(金)(定員になり次第締め切り)
詳しくは,こちらから(関東支部のページへ)
近畿支部 3.6掲載
第42回地球科学講演会「地質の日」協賛行事
「関西で考えるべき活断層地震の揺れ」
関西の中心部である大阪平野,京都・奈良盆地などは平野と丘陵(山地)の境に活断層が潜んでいます.長い年月の活断層の動きによってこういった地形ができていると言った方が良いかも知れません.平野や盆地は生活に便利な地形であるが故に人間は現代社会を造ってきました.数千年に1度牙を剥く活断層による地震の揺れにはどういった特徴があるのでしょうか?またその謎解きのためにどういった調査や分析をしているでしょうか?1995年兵庫県南部地震や2016年熊本地震,2018年大阪府北部の地震,2024年能登半島地震などの教訓を踏まえて将来の地震の揺れについて説明します.
日程:2025年5月10日(土)14:00-16:00
場所:大阪市立自然史博物館講堂(YouTubeでの配信も行います)
講師:岩田知孝 氏(京都大学名誉教授)
主催:地学団体研究会大阪支部・日本地質学会近畿支部・大阪市立自然史博物館
対象:講堂での聴講:どなたでも参加できます.
YouTube配信:インターネットに接続できる方.
講堂での聴講の定員:170名(定員を超えた場合は抽選).要申込み.
参加費:無料.ただし博物館講堂での聴講の場合は博物館入館料が必要.
申し込み:自然史博物館ホームページから申し込めます.往復はがき,または電子メール(gyouji@omnh.jp)の場合は,行事名(地球科学講演会),参加希望者全員の氏名と年齢(学年),住所,電話番号および返信用宛名を記入の上,4月25日(金)までに博物館普及係までお申し込み下さい.抽選結果,参加方法は返信でお知らせします.
※YouTube配信での聴講は,申込不要.
その他:YouTubeでの視聴方法:YouTubeの「大阪市立自然史博物館」チャンネル(https://www.youtube.com/c/ 大阪市立自然史博物館/)にアクセスして表題の番組をクリック,開始時間になれば始まります.見逃し配信は6月10日(火)まで.
四国支部 4.18掲載
化石発掘体験〜君も今日から化石博士!!〜
主催:愛媛大学理工学研究科地球科学分野院生会
共催:愛媛大学理学部,日本地質学会四国支部
協賛:愛媛大学理学部地学コース・大学院理工学研究科地球進化学講座,愛媛大学ミュージアム
場所:愛媛大学ミュージアム(オープンテラス)(松山市文京町3 愛媛大学城北キャンパス)
日時:2025年5月10日(土)「地質の日」13:00~16:00
(化石レプリカを用いた発掘体験・発掘した化石レプリカの同定体験を実施予定です)
参加費:無料
事前申し込み:不要(当⽇会場に直接ご来場下さい.13:00-16:00 まで受付)
問い合わせ先:ehime.chishitunohi[at]gmail.com (代表:福井堂子)([at]を@に変えて送信ください。)
電話 089-927-9623(愛媛⼤学理学部地学コース事務室)
三浦半島活断層調査会(日本地質学会後援) 2.21掲載
創立30周年記念 一般公開講座「海底に眠る南下浦断層」
定員になりましたので,募集終了しました(3/24付)
三浦半島活断層調査会では三浦半島活断層群の踏査を幾度か実施しております。今回の目玉は、大潮の干潮時の海底に現れる活断層帯の露頭にあります。当日は、大潮の干潮で朝11時の潮位は-3cmと低いので400mまで断層が確認できると思います。その後、海岸から南下浦中学校まで300m程失われた露頭の確認をします。午後はトレンチ調査跡、断層地形の見学、三崎口駅周辺の開発と活断層について考えます。
主催:三浦半島活断層調査会
後援:日本地質学会,三浦市,横須賀市教育委員会
日時:2025年4月29日(火・祝)小雨決行
集合場所:高抜バス停(京急三浦海岸駅よりバスで約10分、バス停4つ) 三浦海岸駅発 剣崎行8:23または三崎東同行8:45(金田経由)
集合時間:9:00(解散は15:00頃予定)
現地調査コース:高抜バス停〜金田湾(海底の活断層)〜県道215号脇(失われた露頭1)〜高抜バス停横の農道(失われた露頭2)〜南下浦中学校給食棟裏露頭〜菊名丘陵地(三崎面の変形)〜神台(トレンチ調査跡)〜飯森(断層崖)〜三崎口駅下〜(三崎口高架下の露頭と開発)
注意事項:履きなれた靴でご参加を。弁当・飲み物・雨具は各自持参。
申し込み:E-mailまたは往復葉書にて住所・氏名・電話番号をご記入の上、4月20日までに下記の連絡先までお申込みください。(申し込みの受付は先着30名迄とします。)定員になりましたので,募集終了しました.(3/24付)
参加費用:500円(資料代+保険料)
問い合わせ・申込先:三浦半島活断層調査会 事務局(青木厚美方)
鎌倉市大船4-21-5-603
電話:080-1193-5179
メール:atsumi-aoki[at]mcko.jp
第四紀下限変更に伴う諸問題検討に関する報告
第四紀下限変更に伴う諸問題検討に関する報告
日本地質学会拡大地層名委員会
すでに,報道等でお聞き及びと思いますが,第四紀・第四系と更新世・更新統の下限の定義が変更となりました.ここでは,本件に関する日本地質学会の対応を報告します.
日本地質学会地層名委員会は,2009年9月の岡山大会にてランチョンを開催し,第四紀の下限変更に伴う諸問題に対し,従来の地層名委員会に,1)地質学会の研究委員会委員長を加えた拡大地層名委員会を組織して対応すること, 2)2010年の日本地球惑星科学連合大会において,本件に関するシンポジウムを開催することを合意しました.しかしながら,2010年1月22日に,日本学術会議により,シンポジウム「人類の時代—第四紀は残った」が開催されることが決定され,より迅速な対応が求められる状況となりました.このような経緯の中,日本学術会議地球惑星科学委員会 IUGS 分科会,同 INQUA 分科会,日本地質学会,日本第四紀学会,産業技術総合研究所地質情報研究部門有志で,昨年末に,本件に関する合同検討会議を開催し,それ以後,電子メール等にて活発な議論を交わしてきました.その結果,以下に示すような合意文書の作成に至りました.本文書の内容に関しては,1月22日のシンポジウムにて,参加者にも御検討いただき,ほとんどの内容を了承していただきました.今後,この内容は,日本学術会議の「報告」としてまとめられる予定です(「報告」の代表例としては,冥王星が準惑星とされた件があります).
今後,地質学雑誌やIsland Arc等では,第四紀はジェラシアン期を含み,その下限を2.58Maとする年代区分を用います.また,「第三紀・第三系」は正式な用語としては使用できなくなります.
日本地質学会の会員各位におかれましては,本件に関する検討の経緯と結果を御理解いただき,今後国内での普及に御協力下さいますようお願い申し上げます.
これまでの経緯
2010 年1月22日
日本学術会議地球惑星科学委員会 IUGS 分科会
日本学術会議地球惑星科学委員会 INQUA 分科会
一般社団法人 日本地質学会
日本第四紀学会
第四紀と更新世の新しい定義と関連する地質時代・年代層序の用語について
国際地質科学連合(IUGS)は,国際層序委員会(ICS)の決定を受け,2009 年6月30 日第四紀・第四系と更新世・更新統の下限の定義について以下の勧告を発表しました.
1) 更新世・更新統の下限は,更新世・更新統がジェラシアン期・ジェラシアン階を含むように引き下げ,ジェラシアン期・ジェラシアン階の下限が定義されているモンテサンニコラ GSSP をもって定義されること.
2) 第四紀・第四系の下限,すなわち新第三紀・新第三系(注1)と第四紀・第四系の境界はモンテサンニコラ GSSP をもって公式に定義され,それは更新世・更新統およびジェラシアン期・ジェラシアン階の下限に一致すること.
3) 以上の定義に従って,ジェラシアン期・ジェラシアン階は,鮮新世・鮮新統から更新世・更新統に移動する.
日本学術会議地球惑星科学委員会 IUGS 分科会,同 INQUA 分科会,一般社団法人日本地質学会,日本第四紀学会はこの勧告を受けて,日本国内での地球惑星科学における対応を検討してきましたが,以下のような結論を得ましたのでここに報告し,今後国内での普及につとめていきます.
記
1.日本は新しい更新世・更新統,第四紀・第四系の定義を受け入れて,今後これを使用する.
2. 更新世・更新統の細区分については,従来から用いられている後・中・前期更新世および上・中・下部更新統の三分を継承する.前期更新世および下部更新統にジェラシアン期・ジェラシアン階を含め,前期更新世および下部更新統は,カラブリアン期・カラブリアン階と合わせて2つの期・階から構成されるものとする.
3.表に示した年代値は一部検討中(注2)であるが,以上に定義された地質時代・年代層序の定義を用いる場合は,図1に示した年代を上限・下限として用いる(注3).
4.IUGS による英語表記を図1に示したように日本語で表記する.
5.鮮新世の区分は上・下部鮮新統,後・前期鮮新世の二区分とし,IUGS が定義する ザンクリアン期・ザンクリアン階,ピアセンジアン期・ピアセンジアン階に対応させる.
6.これまで新第三紀・新第三系と古第三紀・古第三系を併せた地質時代として用いられてきた,第三紀・第三系は非公式な用語として使用することができるが,学術論文,教科書,地質時代・年代層序表には使用をしない.
7.IUGS が定義する Neogene Period ・Neogene System,Paleogene Period・Paleogene System に対応する日本語として,新第三紀・新第三系,古第三紀・古第三系を従来どおり使用する.従って,新生代・新生界は,第四紀・第四系,新第三紀・新第三系,古第三紀・古第三系に3区分される.
8.ジェラシアン期・ジェラシアン階下限の日本国内の副模式地の選定は現在進行しつつある研究成果をまって決定する.
9.地質時代区分の名称として一部で使用されている沖積世・洪積世の使用は廃し,完新世・更新世を使用することを徹底する(注4).
(注1)Neogene Period・Neogene System に相当する日本語名称として新第三紀・新第三系を用いることは結論7に記されている.
(注2)後・中期更新世および上・中部更新統の名称については,それぞれを タランティアン期・タランティアン階,イオニアン期・イオニアン階がIUGS-ICSで検討されている.
(注3)図1の年代値は,その精度,境界の層位を考慮して,IUGS の年代層序表を一部改めたものである.
(注4)地質時代区分以外にも一部に用いられている『洪積』の使用も廃する.『沖積層』は『沖積世』の地層あるいは完新統ではないことを周知させたうえで使用を継続する.
後記 本報告に議論の過程で出された意見を付帯意見として記録することが,複数の委員より求められましたので,以下に掲載します.
・楡井 久:当然ですが,従来日本の地質層序・命名は,技術社会・経済社会では,日本列島の地質に対応させて使用されてきました.イタリアをはじめEUは,地質家がそれなりに社会的権限を獲得しております.自分達の国で変更することは,世界の学問を修正する観点から,学術文化・政治・経済の戦略的価値はあります.また,国民が理解する素地を持っているように感じます.また,イタリアなどには,日本の新第三紀固有のGreen Tuffなどはありません.Green Tuffは鉱物資源・温泉にとって世界でも稀有な存在です.日本では第三紀に関しては,坐しているのではなく,もう少し発言しても良いと思います.したがって,日本で使用してきた歴史や従来から体系との整合性とを上手に修正にされることを,お願いします.急変ですと,教育会・産業・行政は地学・地質層序(時間軸)から逃げてゆきます.そのような点の配慮を宜しくお願いします.
・小笠原憲四郎:第三・第四を使用しない公式の訳語は,時間をかけて決めれば良いと思います.当面の策として,第三系,第四紀を使用するのに代えて,新生界上部・下部や始新統・中新統,鮮新—更新統などの使用で対応するように勧告するのも,より積極的な調整かも知れません.
・保柳康一:今回の方針で,どのような問題が起こりえるかを考えておく必要があると思います.結論から申し上げますと,なるべく早い時点で,Paleogene, Neogene の訳語に関するコンセンサスをつくり,徐々に古第三紀・新第三紀から移行させた方がよいと思っています.その場合,すでに中国で古近紀,新近紀という語を使っているという点は考慮しなければならないでしょう.
古第三紀,新第三紀を使い続けることで起こりうる問題点として,現時点で次の2点が思いつきます.
1.古第三紀・新第三紀を使い続ける限り第三紀という語を論文などで使用することを禁止できないと思います.すなわち,著者が「古第三紀と新第三紀を合わせて,第三紀と表記する.」と定義してしまえば,編集委員会がダメとは言えないでしょう.第三紀を使えば字数が半分以下になります.論文では無駄を省き印刷ページを節約することは重要な事項とされます.特に,字数制限のある要旨などでは「第三紀」が好まれるでしょう.
2.第三紀・・・という固有の語があるので,なかなかそれを古第三紀・・・,新第三紀・・・とすぐに直すことは難しいでしょう.例えば,「第三紀層地すべり」などはよく使われています.これも,古第三紀,新第三紀が生き残っている以上,使用が無くなることはないと思えます.他にも事例はあると思われます.
このようなことから,Paleogene, Neogene の訳語に関するコンセンサスをなるべく早くつくり,その上で時間をかけて古第三紀,新第三紀を新訳語に移行させるたらよいと思います.しかし,第三紀という語を生き残らせたいという意見が強ければ,古第三紀と新第三紀という語で固定化すれば,私の申し上げた第1の理由で使いたい人は使い続けられるということになると思います.
・新妻信明:新第三紀と古第三紀は日本語として定着しておりますのでそのまま使用するのが,最も混乱が少ないと思います.
もし,変更するとしたら京都学派によって最も古く提唱された「新成紀」と「古成紀」(地質学会ニュース)を採用するのが地質学の先取権の尊重の立場から当然と考えられます.中国の訳語はそれより後だと思われます.先取権の尊重をないがしろにすれば,地層名や学名の命名について混乱は必致です.
・佐藤時幸:標記問題に関して,新妻委員の提案,および先の学術会議合意文書がもっとも適当と思います.また,Neogene, Paleogeneの訳語については,中国の訳語を考慮する事よりあくまでも日本語訳の問題として捉えたほうが良いと思います.その際に考慮すべきは,第四紀を残した事と若干相通じますが,新妻委員が提案された「新第三紀と古第三紀は日本語として定着している」ということかと思います.
・楡井 久:決めごとですので,これまでの決定で結構ですが,小生が保柳委員の意見を理解出来る点は,次の理由からです.
学術英訳の場合には,漢字の文化圏を持つ国家間では,なるべく,同一漢字で統一することが,今後何かと重要になると思います.
IUGS-GEMの常任理事間では,中国とは,地質環境などは,統一しています.ただし,環境の「環」が中国では多少ことなります.中国は,漢字の原型を変形させた活字を使用しています.
現在:国際専門用語になっている
”geopollution”=地質汚染,”strata pollution”=地層汚染,"groundwater pollution"=地下水汚染,"groundair pollution"=地下空気汚染,”man-made strata”=人工地層
を調整中です.medical geology=医療地質学(日本)に関しては,medical geology=医学地質学(中国)かも知れません?この問題は,日本で10年前に,medical geology のworkshop(Buraiton H. 舞浜・千葉)を開催しましたが,それ以来,中国より先に,日本でmedical geology=医療地質学を使用してきた経緯があります.
今後の東アジアの環境地質,地質汚染問題や医療地質学を議論する場合に,これらの作業が重要になるからです.
・平山 廉:日本語の 訳語に関していえば,やはりこれまでの「慣習」や「先取権」を第一義に考えるのが現実的なように思います.一口に漢字文化圏といっても厳密に同じ漢字で表記するのは,無理があるように感じる次第です.
・平野弘道:混乱を防ぐという観点から,合意文書の内容を受け入れる意志でおります
・石渡 明:第三紀がなくなったのに,新第三紀・古第三紀が残っているのは変であり,あくまでも暫定的なものである.研究者による提案や外国の対応などを考慮しながら,なるべく早い時期に,NeogeneとPaleogeneの正式な日本語名を決める必要がある.
・高山俊昭:議論の当初から「第四紀の基底」という表現がしばしば使われていましたが,時間の前後関係と地層の上下関係が混同して表記されるのはいかがなものかと思っていました.同様に「第四紀の下限」という言い方にも違和感を覚えます.「鎌倉時代の下限」という言い方が正しいかということと同じです.
地学術語を同じ漢字文化圏であるという理由から,中国で使われている用語に合わせるという考え方にも,賛同できません.日本従来の用語は,もっと尊重されるべきです.
2010.3.27-28IYPEイベント(秋葉原)
国際惑星地球年(IYPE)終了記念イベント
「惑星地球フォルム2010 in アキバー君たちと考える環境・防災・資源ー」
2010年3月27日(土)〜3月28日(日)
場所:富士ソフトアキバプラザ 6階
詳しくは、 http://www.gsj.jp/iype/be/doc/BE100327A.html
日本地質学会特別協賛企画
■ 早大高等学院の高校生, 四川大地震の記録映画製作者と一緒に語る『大地の変動』
3月27日(土) 15:00〜16:00
早稲田大学高等学院地学クラブの高校生が日頃の研究成果を発表し,日本地質学会司会のもと,四川大地震の記録映画の製作者と一緒に,大地の変動について討論します。
出演:四川大地震記録映画「風を感じて」 制作総指揮・企画:黄 淑柔
早稲田大学高等学院地学クラブ
「風を感じて~四川大地震記録映画~」公式ホームページ
http://www.voiceofchina.jp/kazewokanjite/index_j.html
■ 第1回惑星地球フォトコンテスト表彰式
3月28日(日)10:00-11:00
フォトコンテストサイトはコチラから
http://photo.geosociety.jp/
(コンテスト入選作品は会場内に展示されます)
写真家 白尾元理 講演会「地球史46億年を撮る」
一般社団法人地質学会主催「地質の日」特別イベント
地質学会各支部等でも「地質の日」の催しが予定されています。詳しくはコチラ
一般社団法人 日本地質学会主催「地質の日」特別イベント
写真家 白尾元理 講演会
地球史46億年を撮る
画像をクリックすると、A3版ポスター(PDF)がダウンロード出来ます
日時:2010年5月8日(土)13:30〜15:30
開場13:30 講演会14:00〜15:00
場所:東京大学小柴ホール(東京都文京区本郷)
<会場・小柴ホールへのアクセス>
地下鉄千代田線根津駅より徒歩8分
地下鉄南北線東大前駅より徒歩1分
JR御茶ノ水駅より,学バス利用(学07東大構内行)
JR上野駅より,学バス利用(学01東大構内行)
入場無料・事前申込不要(定員170名)
多少の困難を乗り越えても現地に立ち, 五感を研ぎ澄まして地球の鼓動や悠久の営みを肌で感じること.これが白尾元理さんの写真の原点だそうです.今回は,地球の46億年を,白尾さんご本人に写真で案内していただきます.撮影秘話なども.
講師:白尾元理氏
(写真家・日本地質学会会員)
<講師プロフィール>1953年東京浅草生まれ.東京大学理学系大学院修士課程終了.専門は火山地質学・惑星地質学.現在は写真家・サイエンスライター.著書は『日本列島の20億年』・『世界のおもしろ地形』ほか多数.
ジオ写真展も同時開催:白尾さんの写真と惑星地球フォトコンテスト入賞作品の展示も行います
このほか、地質学会各支部等でも「地質の日」の催しが予定されています。詳しくはコチラ
↑↑「地質の日」とは?↑↑ロゴマークをクリック!
問い合わせ
一般社団法人日本地質学会
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル 6F
TEL 03-5823-1150 FAX 03-5823-1156
E-mail: main@geosociety.jp
2010年地質の日(学会関係)
2010年の「地質の日」
2010年の「地質の 日」に関連した日本地質学会の催しをご紹介します。
日本地質学会:本部イベント企画
写真家 白尾元理 講演会「地球史46億年を撮る」
日時:2010年5月8日(土)13:30〜15:30
場所:東京大学小柴ホール(東京都文京区本郷)
講 師:白尾元理氏(写真家・日本地質学会会員)
入場無料・事前申込不要(定員170名)
ジオ写真展も同時開催:白尾さんの写真と惑星地球フォトコン テスト入賞作品の展示
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/name/content0059.html
北海道支部:「地質の日」・「国際博物館の日」記念展示:
北海道大学総合博物館企画展示「わが街の文化遺 産 札幌軟石」
期間:2010年4月27日(火)〜5月30日(日)10:00〜16:00
会場:北海道大学総合博物館1階「地の統合」 コーナー
関連イベント:
5/1(土)ワークショップ「札幌軟石クラフトに挑戦!」
5/1(土)講演会「札幌軟石 いま・昔」
5/8(土) ミニツアー「札幌軟石ウォッチング」(要申込)
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
関東支部
第2回地質技術伝承講習会:地質技師長が語る地質工学余話
「共生型地下水利用に向けての「育水」の提唱」
日時:2010 年6月6日(日)14:00〜16:30
場所:北とぴあ(東京都北区王子1-11-1) 飛鳥ホール
講師:中村 裕昭氏(株式会社地域環 境研究所)
テーマ:共生型地下水利用に向けての「育水」の提唱
参加費:無料,どなたでも参加できます.
http://kanto.geosociety.jp/
中部支部:「地質の日」記念
サイエンスフェステイバル in 五十嵐キャンパス(新潟大学)
日時:5月16日(日)12:00~15:00
場所:新潟大学理学部
実行委員会:新潟大学理学部・教育学部・災害復興科学センター, 新潟県立自然科学館,NPO法人ジオプロジェクト新潟, 日本地質学会中部支部
近畿支部:「地質の日」協賛行事
第27回地球科学講演会「大阪の温泉は本当に温泉か?−大阪平野の地下水を可視化する−」
地質学会近畿支部では,「地質の日」協賛行事として,地学団体研究会大阪支部と大阪市立自然史博物館との共催で,第27回地球科学講演会「大阪の温泉は本当に温泉か?−大阪平野の地下水を可視化する−」を開催します.「天然温泉」の看板を街の中で見かけることがあります.温泉好きの私たちにとっては,安くて近い息抜きの場です.火山のない大阪になぜ温泉が出るのか,不思議に思ったことはありませんか.平野部にある温泉は,とても深い場所にある地下水なのです.中には変わった泉質を持つものもあります.でも,地下水という点では,上町台地の湧水と同じです.ここでは,目には見えない大阪平野の地下水の流れを話します.地下水とは何か,河川水とどう違うのか,そしてどうつきあえばいいのか,一緒に考えたいと思います.多くの方のご参加をお待ちしております.
日時:2010年5月9日(日)14:30-16:30
場所:大阪市立自然史博物館講堂(大阪市東住吉区長居公園1-23)
講師:益田晴恵氏(大阪市立大学大学院理学研究科教授)
主催:日本地質学会近畿支部,地学団体研究会大阪支部,大阪市立自然史博物館
申込不要.直接会場へお越しください.
参加費:無料.ただし,博物館入館料(大人300円,高校・大学生200円)が要.
西日本支部:後援「地質の日」企画
身近に知る「くまもと の大地」
日時:2010年5月9日(日)「地質の日」 10:00〜16:00
場所:熊本市通町筋上通り入り口 びぷれす広場(熊日ビ ル)
企画:◎おどろきの展示コーナー/◎わくわく体験コーナー/◎なるほど解るコー
ナーなど
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
【国際年代層序表】地質系統・年代の日本語記述ガイドライン(2021.12.2更新)
地質系統・年代の日本語記述ガイドライン
2025年2月17日更新
地質系統・年代の日本語記述ガイドライン
2024年12月改訂版
一般社団法人日本地質学会 執行理事会
国際地質科学連合(IUGS)の国際層序委員会(ICS)が,国際年代層序表の最新版(v 2024/12)を公開しました.v2024/12の改訂は次の通りです.
白亜系/紀の階/期の「バランギニアン」にGSSP(2024年12月28日IUGS承認)が設定された。
GTS2020 (Gradstein et al., 2020) に従い、44件の数値年代を更新された(従来は GTS2012, Gradstein et al., 2012)。ただし、ICS委員会の決定が優先される場合はこの限りではない。
* PDF(Japanese) * PDF(Einglish)
層序表最小区分「階/期」はカンブリア紀以前の年代における最小区分「系/紀」などを含めると全部で117区分です.
GSSP(ゴールデンスパイク)は全部で81箇所あり,チバ二アン時代は74番目のGSSP箇所になります.なお、GSSPが存在する国は,23カ国です(スコットランドをイギリスに,またグリーンランドをデンマークとして数えています).
▷国際層序委員会(ICS)国際年代層序表のページ https://stratigraphy.org/chart
一般社団法人日本地質学会刊行の公式出版物(地質学雑誌等)においては,原則として,上表の年代表記に従って下さいますようお願いいたします.
この日本語版は,IUGSの許諾を得て日本地質学会が作成したもので,年代層序単元の日本語表記はJIS規格に準拠しています.
これまでの年代層序表の改訂履歴はこちら
JISに定められた地質年代の日本語表記
※国際年代層序表は,どなたでも使用可能なもので,地質学会に対する書面による許諾手続きは必要ありません。出典明記の上,適切にご利用ください
キーワード:地質年代表・年代表・時代表・国際年代層序表
街中ジオ散歩in Tokyo
2013年度「地質の日」行事
一般社団法人日本地質学会・ 一般社団法人応用地質学会 主催
◎街中ジオ散歩 in Tokyo「石神井川がつくる地形の移り変わりと地質」
徒歩見学会のご案内(お申込締切ました.大変有難うございました)
日 時:2013年5月12日(日)10時から17時 小雨決行(予定)
国土地理院(2006)「1:25000デジタル標高地形図」(東京都区部)
毎年5月10日は地質の日です.この日は明治9年(1876),ライマンらによって日本で初めて広域的な地質図が作成された日です.また,明治11年(1878)のこの日は,地質の調査を扱う組織(内務省地理局地質課)が定められた日でもあります.近年この地質の日にちなんで様々な機関で記念イベントが開かれており,当学会でも,2012年より日本応用地質学会との共同主催で東京都内の徒歩見学会を開催しています.今回はJR王子駅西側の河川争奪と地形・社会をテーマに実施いたします.皆様,奮ってご参加くださいますようお願いいたします.
共 催:公益財団法人 深田地質研究所
後 援:一般社団法人 東京都地質調査業協会(予定)
協 力:日本地質学会 関東支部
場 所:東京都北区田端・上中里・王子界隈(JR王子駅西側の台地上に発達する石神井川,逆川付近)
案内者:池田宏氏((公財)深田地質研究所,中山俊雄氏((独)防災科学技術研究所)
趣 旨:身近な地質とその地質に由来した地形,それらを利用してきた先人から現在の私たちまでの営みを,春の清々しい空気の中でのんびり歩きながら,ベテラン研究者からの興味深い説明を聞き,楽しく学ぼうという企画です.今回は,石神井川と逆川,谷田川の河川争奪に見る地形の変化と地質,人々の暮らしをテーマに歩きます.
キーワード:地形・地質・土地利用
会 費:一般2,000円, 小中学生500円(予定)保険代を含みます.当日お支払い下さい.昼食は各自でご用意下さい.
注意事項:荒天の場合は中止します.当日朝7時に下記担当者よりご連絡いたします.また昼食は飛鳥山公園内の野外を想定しています.弁当と敷物等をご用意下さい.また昼食時雨天が想定される場合,ご用意いただく昼食は軽食程度でお願い致します.
行 程:10:00 JR田端駅北口前集合→谷田川→中里貝塚→飛鳥山公園(昼食)→逆川→石神井川沿い音無さくら緑地(露頭)→名主の滝公園17:00解散(予定)
(天候等により順序,見学地を変更する場合が有ります)
募集人員:30名程度(お陰様で定員となりました.お申込み有難うございました.)
対 象:一般
申込み:参加資格は特にありません.小学生以上の方でしたらどなたでもお申し込み頂けます.小中学生の方は保護者の方の同伴をお願いいたします.申込みは下記のジオスクーリングネットまたは学会事務局までご連絡先を明記してお申し込み下さい.
申込先:ジオ・スクーリングネット(https://www.geo-schooling.jp/)または下記の学会事務局までFAXまたはメールで、氏名,生年月日,住所,携帯等電話番号,メールアドレスを記して,お申し込み下さい.
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル6F
TEL:03-5823-1150(代表) FAX:03-5823-1156
main@geosociety.jp
日本地質学会事務局 (地質の日担当 緒方)
情報の更新:学会HPおよびジオ・スクーリングネット,および学会事務局にて情報を更新いたします.ご確認下さい.
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2010年6-7月)
6-7月のイベント・特別展示カレンダー (2010/06/01〜2010/07/31)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参 加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
6-7月の特別展示
2010/07/01 現在
アジア恐竜時代の幕開け—巨大恐竜の進化— (福井県 福井県立恐竜博物館)
期間:7/9(金)〜11/7(日)ただし、7/14(水)、9/8(水)、9/22(水)、10/13(水)、10/27日(水)は休館
場所:福井県立恐竜博物館3階 特別展示室
アジア地域は、近年、恐竜研究が最も盛んな地域のひとつである。我々の住むアジアではどのように恐竜が進化してきたのか?ルーフェンゴサウルスやアジア初公開となるエウヘロプスの全身骨格、福井産竜脚類化石などをもとに、タイ、中国、日本へと広がっていったアジアの巨大恐竜「竜脚類」の歴史を紹介する。入場料:一般 1,000円、大学・高校生 800円、小・中学生 600円、70歳以上の方 500円(上記料金で常設展もご覧いただけます)
http://www.dinosaur.pref.fukui.jp/special/
特別展「ようこそ恐竜ラボへ〜化石の謎をときあかす〜」 (岡山県 林原自然科学博物館)
期間:7/10(土)〜8/18(水) *7/12(月)のみ休館
場所:岡山市デジタルミュージアム 4階・5階(岡山市北区駅元町15—1)
ゴビ砂漠での発掘調査について、実物大の発掘現場の写真を見ることができる他、持ち帰った化石を岩石からとりだし、恐竜の姿を復元していくまでの過程を紹介します。新たな発見として最近報道された、タルボサウルスの子どもの化石や新種の鳥類化石などのモンゴル産の実物化石も初展示します。入場料:一般1000円(前売り800円)、高校生・大学生・専門学校生800円、3歳以上・小学生・中学生500円
http://www.city.okayama.jp/okayama-city-museum/kikakuten/dinosaur/dinosaur.html
特別展「キラキラ水晶展」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
期間:7/16(金)〜9/12(日)
場所:豊橋市自然史博物館 特別企画展示室
山梨大学の秘蔵標本を大公開!もっとも身近な鉱物水晶の魅力を紹介します。
http://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/
企画展「よみがえる恐竜と古代生物の世界」 (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
期間:7/17(土)〜8/31(火)
場所:御所浦島開発総合センター(御所浦白亜紀資料館)
恐竜などの古生物を専門とする復元模型作家、徳川浩一氏の手によってよみがえった、太古の生き物たちをメインに展示します。入場料:大人200円、高校生150円、小・中学生100円、幼児無料(同時開催の作品展もご覧いただけます)
同時開催:第12回恐竜会がコンテスト作品展
http://www5.ocn.ne.jp/~g-museum/
6-7月のイベント
2010/07/01 現在
日付
イベント
06/01
(火)
06/02
(水)
06/03
(木)
06/04
(金)
06/05
(土)
06/06
(日)
06/07
(月)
06/08
(火)
06/09
(水)
06/10
(木)
06/11
(金)
06/12
(土)
06/13
(日)
06/14
(月)
06/15
(火)
06/16
(水)
06/17
(木)
06/18
(金)
06/19
(土)
06/20
(日)
「珪化木の魅力」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市自然史博物館 講堂
時間:14:00〜15:00
実物の珪化木にふれながら、石になった木について、種類、でき方などを紹介します。
事前申込:必要・先着順
申込詳細:自然史博物館へ電話(0532-41-4747),FAX(0532-41-8020)またはメール(sizensi@toyohaku.gr.jp)で。
小学4年生以上・一般40名。受講料 無料。
06/21
(月)
06/22
(火)
06/23
(水)
06/24
(木)
06/25
(金)
06/26
(土)
06/27
(日)
06/28
(月)
06/29
(火)
06/30
(水)
07/01
(木)
07/02
(金)
07/03
(土)
07/04
(日)
07/05
(月)
07/06
(火)
07/07
(水)
07/08
(木)
07/09
(金)
07/10
(土)
07/11
(日)
07/12
(月)
07/13
(火)
07/14
(水)
07/15
(木)
07/16
(金)
07/17
(土)
「アジアの恐竜(仮題)」 (福井県 福井県立恐竜博物館)
場所:福井県立恐竜博物館3階 講堂
時間:14:00〜15:30
講師 董 枝明(ドン・ジミン)氏(中国科学院古脊椎動物古人類研究所・教授)。
中国の恐竜研究の歴史や最新情報について紹介します。聴講無料。事前申込:不要
「水晶が面白い」科博コラボ・ミュージアムin豊橋「水晶」(愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市自然史博物館 講堂
時間:14:00〜15:30
講師:国立科学博物館地学研究部長 松原 聰さん
身近な鉱物、水晶の魅力について紹介します
事前申込:必要・先着順
申込詳細:自然史博物館へ電話(0532-41-4747),FAX(0532-41-8020)またはメール(sizensi@toyohaku.gr.jp)で。
小学4年生以上・一般60名。受講料 無料。
07/18
(日)
アンモナイト立体図鑑づくり (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館
時間:10:00〜15:00(最終受付14:30)
アンモナイトの石こう模型を作成する.各種アンモナイトのオリジナル解説シート付き.全15種.1個¥100.
事前申込:不要
07/19
(月)
07/20
(火)
07/21
(水)
07/22
(木)
07/23
(金)
07/24
(土)
07/25
(日)
「山梨の水晶−山から町へ−」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市自然史博物館 講堂
時間:14:00〜15:30
講師:山梨大学准教授 角田謙朗さん
幕末に日本式双晶が発見されてからの山梨の水晶にまつわる特徴と変遷を紹介します。
事前申込:必要・先着順
申込詳細:自然史博物館へ電話(0532-41-4747),FAX(0532-41-8020)またはメール(sizensi@toyohaku.gr.jp)で。
小学4年生以上・一般60名。受講料 無料。
07/26
(月)
07/27
(火)
07/28
(水)
07/29
(木)
07/30
(金)
07/31
(土)
アンモナイト立体図鑑づくり (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館
時間:10:00〜15:00(最終受付14:30)
アンモナイトの石こう模型を作成する.各種アンモナイトのオリジナル解説シート付き.全15種.1個¥100.
事前申込:不要
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ 内のフォームま たはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2010年7-8月)
7-8月のイベント・特別展示カレンダー (2010/07/01〜2010/08/31)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参 加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
7-8月の特別展示
2010/07/20 現在
特別展大恐竜展−陸・海・空の覇者 集結− (栃木県 那須塩原市那須野が原博物館)
期間:6/26(土)〜9/12(日)
場所:那須塩原市那須野が原博物館
恐竜時代の「陸」・「海」・「空」それぞれの環境を支配した覇者にスポットをあて、彼らの繁栄の謎と進化の不思議に迫る。目玉は、ティラノサウルス・レックスの全身復元骨格で、その他全身復元骨格12体、総出展標本135点に及ぶスケール。
http://web.city.nasushiobara.lg.jp/hakubutsukan/
第73回特別展「はっぱときのみ」 (岐阜県 瑞浪市化石博物館)
期間:7/1(木)〜8/31(火)毎週月曜日(7月19日は開館)7月20日、21日は休館
場所:瑞浪市化石博物館
約2億年前から現在までのさまざまな地層から採集された植物化石を展示しています。石の中に貼られたしおりのようなきれいな「はっぱの化石」や、化石とは思えないような綺麗な形を保つ「きのみの化石」などなかなかお目にかかれない化石が沢山あります。また、現在いきている植物の標本や木の実を食べていた動物の化石など様々な標本の展示も行っています。合わせて植物と密接にかかわりあっていた哺乳類の化石も展示しています。
http://www.city.mizunami.gifu.jp/sightseeing/institution/fossil_museum/
アジア恐竜時代の幕開け—巨大恐竜の進化— (福井県 福井県立恐竜博物館)
期間:7/9(金)〜11/7(日)ただし、7/14(水)、9/8(水)、9/22(水)、10/13(水)、10/27日(水)は休館
場所:福井県立恐竜博物館3階 特別展示室
アジア地域は、近年、恐竜研究が最も盛んな地域のひとつである。我々の住むアジアではどのように恐竜が進化してきたのか?ルーフェンゴサウルスやアジア初公開となるエウヘロプスの全身骨格、福井産竜脚類化石などをもとに、タイ、中国、日本へと広がっていったアジアの巨大恐竜「竜脚類」の歴史を紹介する。入場料:一般 1,000円、大学・高校生 800円、小・中学生 600円、70歳以上の方 500円(上記料金で常設展もご覧いただけます)
http://www.dinosaur.pref.fukui.jp/special/
特別展「ようこそ恐竜ラボへ〜化石の謎をときあかす〜」 (岡山県 林原自然科学博物館)
期間:7/10(土)〜8/18(水) *7/12(月)のみ休館
場所:岡山市デジタルミュージアム 4階・5階(岡山市北区駅元町15—1)
ゴビ砂漠での発掘調査について、実物大の発掘現場の写真を見ることができる他、持ち帰った化石を岩石からとりだし、恐竜の姿を復元していくまでの過程を紹介します。新たな発見として最近報道された、タルボサウルスの子どもの化石や新種の鳥類化石などのモンゴル産の実物化石も初展示します。入場料:一般1000円(前売り800円)、高校生・大学生・専門学校生800円、3歳以上・小学生・中学生500円
http://www.city.okayama.jp/okayama-city-museum/kikakuten/dinosaur/dinosaur.html
特別展「キラキラ水晶展」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
期間:7/16(金)〜9/12(日)
場所:豊橋市自然史博物館 特別企画展示室
山梨大学の秘蔵標本を大公開!もっとも身近な鉱物水晶の魅力を紹介します。
http://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/
企画展「よみがえる恐竜と古代生物の世界」 (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
期間:7/17(土)〜8/31(火)
場所:御所浦島開発総合センター(御所浦白亜紀資料館)
恐竜などの古生物を専門とする復元模型作家、徳川広和氏の手によってよみがえった、太古の生き物たちをメインに展示します。入場料:大人200円、高校生150円、小・中学生100円、幼児無料(同時開催の作品展もご覧いただけます)
同時開催:第12回恐竜会がコンテスト作品展
http://www5.ocn.ne.jp/~g-museum/
特別展示「白亜紀ウミガメ化石展界」 (北海道 むかわ町立穂別博物館)
期間:7/17(土)〜10/31(日)
場所:むかわ町立穂別博物館 特別展示室
クビナガリュウやアンモナイトとともに白亜紀の海に生息していたウミガメについて紹介します。特に、模式標本をはじめ穂別で特徴的に発見されている白亜紀のオサガメであるメソダーモケリスを詳しく解説する。カメの分類、骨格の特徴、ウミガメの水中生活への適応についても触れ、2億年を生き抜いてきたカメの秘密に迫ります。
http://www10.plala.or.jp/mukawa/soshiki/hakubutsukan/
日本列島20億年−その生い立ちを探る− (神奈川県 神奈川県立生命の星・地球博物館)
期間:7/17(土)〜11/7(日)
場所:神奈川県立生命の星・地球博物館
日本列島の地質を、できた年代と岩石の性質によって分けると、その分布は帯状となり、まるで箱根の寄木細工のようです。なぜ寄木細工のようになっているのでしょうか。日本列島がいつ、どこで、どのようにして形づくられてきたのか、なぜ帯状の分布をしているのか、その生い立ちの謎について紹介します。入場料:20〜64歳(学生を除く)710円、20歳未満・学生400円、高校生・65歳以上200円、中学生以下無料。
http://nh.kanagawa-museum.jp/
7-8月のイベント
2010/08/10 現在
日付
イベント
07/01
(木)
07/02
(金)
07/03
(土)
07/04
(日)
07/05
(月)
07/06
(火)
07/07
(水)
07/08
(木)
07/09
(金)
07/10
(土)
07/11
(日)
07/12
(月)
07/13
(火)
07/14
(水)
07/15
(木)
07/16
(金)
07/17
(土)
「アジアの恐竜(仮題)」 (福井県 福井県立恐竜博物館)
場所:福井県立恐竜博物館3階 講堂
時間:14:00〜15:30
講師 董 枝明(ドン・ジミン)氏(中国科学院古脊椎動物古人類研究所・教授)。
中国の恐竜研究の歴史や最新情報について紹介します。聴講無料。事前申込:不要
「水晶が面白い」科博コラボ・ミュージアムin豊橋「水晶」(愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市自然史博物館 講堂
時間:14:00〜15:30
講師:国立科学博物館地学研究部長 松原 聰さん
身近な鉱物、水晶の魅力について紹介します
事前申込:必要・先着順
申込詳細:自然史博物館へ電話(0532-41-4747),FAX(0532-41-8020)またはメール(sizensi@toyohaku.gr.jp)で。
小学4年生以上・一般60名。受講料 無料。
恐竜復元に挑戦!「恐竜をつくろう」 (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:天草市立御所浦白亜紀資料館
時間:13:00〜14:30
講師:徳川広和氏
小学生以上対象(小学生は保護者同伴)、材料費¥1500、定員10名、事前申込:必要
07/18
(日)
アンモナイト立体図鑑づくり (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館
時間:10:00〜15:00(最終受付14:30)
アンモナイトの石こう模型を作成する.各種アンモナイトのオリジナル解説シート付き.全15種.1個¥100.
事前申込:不要
恐竜復元に挑戦!「恐竜復元画に挑戦しよう」 (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:天草市立御所浦白亜紀資料館
Aコース:骨格図を元に復元画を描こう 定員35名
時間:11:00〜11:30
講師:徳川広和氏
小学生以上対象(小学生は保護者同伴)、参加無料、事前申込:必要
07/19
(月)
07/20
(火)
天草御所浦ジオパーク島巡りクルージング (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:弁天島 他
時間:11:00〜(1時間半程度)
小学生〜大人(小中学生は保護者同伴)、大人¥1000、小中学生¥500、幼児無料、定員12名、当日申込。
07/21
(水)
天草御所浦ジオパーク島巡りクルージング (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:弁天島 他
時間:11:00〜(1時間半程度)
小学生〜大人(小中学生は保護者同伴)、大人¥1000、小中学生¥500、幼児無料、定員12名、当日申込。
07/22
(木)
07/23
(金)
07/24
(土)
夏休み化石セミナー(前期) (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:天草市立御所浦白亜紀資料館 他
時間:1泊2日、初日11:00集合
トリゴニア砂岩の見られる採石場跡地において、地層や化石の観察や化石採集を楽しみます(学術上貴重な化石以外は持ち帰り可)。
小学生〜大人(小中学生は保護者同伴)、大人¥2500、小中学生¥1500、宿泊代別途、定員35名、先着順、事前申込:前期は7/16、御所浦白亜紀資料館化石セミナー係まで。
伝馬舟体験と化石に逢える島巡りバス (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:御所浦港 他
時間:11:00〜、13:00〜、(1日2回、約1時間)
大人¥400、小中学生¥200、幼児無料、定員15名、当日申込。
07/25
(日)
「山梨の水晶−山から町へ−」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市自然史博物館 講堂
時間:14:00〜15:30
講師:山梨大学准教授 角田謙朗さん
幕末に日本式双晶が発見されてからの山梨の水晶にまつわる特徴と変遷を紹介します。
事前申込:必要・先着順
申込詳細:自然史博物館へ電話(0532-41-4747),FAX(0532-41-8020)またはメール(sizensi@toyohaku.gr.jp)で。
小学4年生以上・一般60名。受講料 無料。
伝馬舟体験と化石に逢える島巡りバス (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:御所浦港 他
時間:11:00〜、13:00〜、(1日2回、約1時間)
大人¥400、小中学生¥200、幼児無料、定員15名、当日申込。
07/26
(月)
07/27
(火)
天草御所浦ジオパーク島巡りクルージング (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:弁天島 他
時間:11:00〜(1時間半程度)
小学生〜大人(小中学生は保護者同伴)、大人¥1000、小中学生¥500、幼児無料、定員12名、当日申込。
07/28
(水)
天草御所浦ジオパーク島巡りクルージング (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:弁天島 他
時間:11:00〜(1時間半程度)
小学生〜大人(小中学生は保護者同伴)、大人¥1000、小中学生¥500、幼児無料、定員12名、当日申込。
07/29
(木)
07/30
(金)
07/31
(土)
アンモナイト立体図鑑づくり (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館
時間:10:00〜15:00(最終受付14:30)
アンモナイトの石こう模型を作成する.各種アンモナイトのオリジナル解説シート付き.全15種.1個¥100.
事前申込:不要
伝馬舟体験とイルカと化石に逢える島巡りバス (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:御所浦港 他
時間:11:00〜、13:00〜、(1日2回、約1時間)
大人¥400、小中学生¥200、幼児無料、定員28名、当日申込。
「御所浦の恐竜化石と天草御所浦ジオパーク」(栃木県 那須塩原市那須野が原博物館)
場所:那須塩原市那須野が原博物館
時間:10:00〜、14:00〜
講師:廣瀬浩司氏(天草市立御所浦白亜紀資料館主査)
恐竜化石発掘のお話と化石のレプリカづくり体験
事前申込:必要。直接 那須野が原博物館へ。定員:親子各回15組(講演のみは、どなたでも)。
08/01
(日)
伝馬舟体験とイルカと化石に逢える島巡りバス (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:御所浦港 他
時間:11:00〜、13:00〜、(1日2回、約1時間)
大人¥400、小中学生¥200、幼児無料、定員28名、当日申込。
室内実習 化石のレプリカをつくろう (徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島県立博物館 3階実習室
時間:10:00〜12:00
実物の恐竜の歯やアンモナイト、三葉虫の化石から型
どりした雌型を使ってレプリカをつくります。事前申込:必要。
申込詳細:往復はがきで、行事予定の1ヶ月前から10日前までに届くようにお申し込みください。
クジラの進化ー化石でたどる5000万年の歴史ー (徳島県 徳島県立博物館、福井県 福井県立恐竜博物館)
場所:徳島県立博物館 3階講座室
時間:13:30〜15:00
講師:一島啓人(福井県立恐竜博物館)
クジラは我々にとても身近なものとして、日常生活の話題にもしばしば上ります。しかし、生物としての側面、とくに起源から現在に到るまでの進化について考える機会は多くないと思います。かつて陸の上で暮らしていたと考えられるクジラが、水中生活に移行するとともに体の様々な特徴を変化させていった過程を話します。申込:不要
08/02
(月)
08/03
(火)
天草御所浦ジオパーク島巡りクルージング (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:弁天島 他
時間:11:00〜(1時間半程度)
小学生〜大人(小中学生は保護者同伴)、大人¥1000、小中学生¥500、幼児無料、定員12名、当日申込。
日本列島の石を探る (神奈川県 神奈川県立生命の星・地球博物館)
場所:神奈川県立生命の星・地球博物館 特別展示室
時間:13:30〜15:30
特別展に展示されてる岩石、化石などの標本類を観察しながら日本列島の生い立ちを探ります。対象:小学4年生〜中学生とその保護者、定員15名、無料、申込締切7/20(火)
08/04
(水)
天草御所浦ジオパーク島巡りクルージング (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:弁天島 他
時間:11:00〜(1時間半程度)
小学生〜大人(小中学生は保護者同伴)、大人¥1000、小中学生¥500、幼児無料、定員12名、当日申込。
08/05
(木)
08/06
(金)
08/07
(土)
アンモナイト立体図鑑づくり (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館
時間:10:00〜15:00(最終受付14:30)
アンモナイトの石こう模型を作成する.各種アンモナイトのオリジナル解説シート付き.全15種.1個¥100.
事前申込:不要
伝馬舟体験と化石に逢える島巡りバス (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:御所浦港 他
時間:11:00〜、13:00〜、(1日2回、約1時間)
大人¥400、小中学生¥200、幼児無料、定員15名、当日申込。
08/08
(日)
伝馬舟体験とイルカと化石に逢える島巡りバス (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:御所浦港 他
時間:11:00〜、13:00〜、(1日2回、約1時間)
大人¥400、小中学生¥200、幼児無料、定員28名、当日申込。
野外自然かんさつ 室戸岬の地質見学 (徳島県 徳島県立博物館)
場所:高知県室戸岬 現地集合現地解散
時間:13:00〜15:00
高知県室戸岬は、地質の見どころがたいへん多い場所です。国内ジオパーク(地質遺産)のひとつ(全国で9箇所)にも選定されています。この行事では、室戸岬の見どころのひとつである、南海地震にともなう隆起地形や化石をおもに観察します。また、同じ場所に見えているはんれい岩などについても簡単に解説します。事前申込:必要
申込詳細:往復はがきで、行事予定の1ヶ月前から10日前までに届くようにお申し込みください。
08/09
(月)
08/10
(火)
天草御所浦ジオパーク島巡りクルージング (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:弁天島 他
時間:11:00〜(1時間半程度)
小学生〜大人(小中学生は保護者同伴)、大人¥1000、小中学生¥500、幼児無料、定員12名、当日申込。
08/11
(水)
天草御所浦ジオパーク島巡りクルージング (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:弁天島 他
時間:11:00〜(1時間半程度)
小学生〜大人(小中学生は保護者同伴)、大人¥1000、小中学生¥500、幼児無料、定員12名、当日申込。
08/12
(木)
08/13
(金)
08/14
(土)
伝馬舟体験とイルカと化石に逢える島巡りバス (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:御所浦港 他
時間:11:00〜、13:00〜、(1日2回、約1時間)
大人¥400、小中学生¥200、幼児無料、定員28名、当日申込。
08/15
(日)
アンモナイト立体図鑑づくり (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:むかわ町立穂別博物館
時間:10:00〜15:00(最終受付14:30)
アンモナイトの石こう模型を作成する.各種アンモナイトのオリジナル解説シート付き.全15種.1個¥100.
事前申込:不要
伝馬舟体験とイルカと化石に逢える島巡りバス (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:御所浦港 他
時間:11:00〜、13:00〜、(1日2回、約1時間)
大人¥400、小中学生¥200、幼児無料、定員28名、当日申込。
08/16
(月)
08/17
(火)
天草御所浦ジオパーク島巡りクルージング (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:弁天島 他
時間:11:00〜(1時間半程度)
小学生〜大人(小中学生は保護者同伴)、大人¥1000、小中学生¥500、幼児無料、定員12名、当日申込。
08/18
(水)
天草御所浦ジオパーク島巡りクルージング (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:弁天島 他
時間:11:00〜(1時間半程度)
小学生〜大人(小中学生は保護者同伴)、大人¥1000、小中学生¥500、幼児無料、定員12名、当日申込。
08/19
(木)
08/20
(金)
08/21
(土)
夏休み化石セミナー(後期) (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:天草市立御所浦白亜紀資料館 他
時間:1泊2日、初日11:00集合
講師:徳川広和氏
トリゴニア砂岩の見られる採石場跡地において、地層や化石の観察や化石採集を楽しみます(学術上貴重な化石以外は持ち帰り可)。
小学生〜大人(小中学生は保護者同伴)、大人¥2500、小中学生¥1500、宿泊代別途、定員35名、先着順、事前申込:後期は8/13、御所浦白亜紀資料館化石セミナー係まで。
伝馬舟体験とイルカと化石に逢える島巡りバス (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:御所浦港 他
時間:11:00〜、13:00〜、(1日2回、約1時間)
大人¥400、小中学生¥200、幼児無料、定員28名、当日申込。
最古の恐竜とカメ (北海道 むかわ町立穂別博物館)
場所:穂別町民センター会議室(むかわ町穂別2番地)
時間:13:30〜15:30
カメ化石の権威であり恐竜についても造詣の深い平山教授(早稲田大学)が、2006年に実施された南米アルゼンチン・イシグアラストでの最古の恐竜化石の調査の様子と、中国で発見された最古のカメ、そしてカメの起源について語ります。
事前申込:不要
08/22
(日)
伝馬舟体験とイルカと化石に逢える島巡りバス (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:御所浦港 他
時間:11:00〜、13:00〜、(1日2回、約1時間)
大人¥400、小中学生¥200、幼児無料、定員28名、当日申込。
08/23
(月)
08/24
(火)
天草御所浦ジオパーク島巡りクルージング (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:弁天島 他
時間:11:00〜(1時間半程度)
小学生〜大人(小中学生は保護者同伴)、大人¥1000、小中学生¥500、幼児無料、定員12名、当日申込。
08/25
(水)
天草御所浦ジオパーク島巡りクルージング (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:弁天島 他
時間:11:00〜(1時間半程度)
小学生〜大人(小中学生は保護者同伴)、大人¥1000、小中学生¥500、幼児無料、定員12名、当日申込。
室内実習 標本の名前を調べる会 (徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島県立博物館 3階実習室・講座室
時間:10:00〜16:00
夏休みに採集した生き物の名前を、講師の方といっしょに調べてみましょう。
名前が分かると生き物への愛着もぐっと増します。対象とするものは植物(コケ・キノコ・海藻を除く)や昆虫・貝などの動物、岩石・鉱物、化石です。
★定員はありません。参加を希望される方は、次の点に留意してご準備ください。
1)おおまかでもかまいませんので、種類ごとに分類しておいてください。
2)まちがっていてもかまいませんので、あらかじめ図鑑で名前を調べてみてください。
3)持ってくる標本の数は、1人30点以内にしてください。
4)分からないところ、質問したいところをはっきりさせておいてください。
事前申込:不要
08/26
(木)
08/27
(金)
08/28
(土)
恐竜復元に挑戦!「恐竜復元画に挑戦しよう」 (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:天草市立御所浦白亜紀資料館
Aコース:骨格図を元に復元画を描こう 定員35名
時間:11:00〜11:30
Bコース:展示物を見て復元画を描こう 定員15名
時間:13:30〜14:30
講師:徳川広和氏
小学生以上対象(小学生は保護者同伴)、参加無料、事前申込:必要
伝馬舟体験と化石に逢える島巡りバス (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:御所浦港 他
時間:11:00〜、13:00〜、(1日2回、約1時間)
大人¥400、小中学生¥200、幼児無料、定員15名、当日申込。
08/29
(日)
「自然のガラス」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市自然史博物館 講堂
時間:14:00〜15:00
海岸や火山灰の中など、身近な場所でみつかる「自然のガラス」を紹介します。
事前申込:必要・先着順
申込詳細:自然史博物館へ電話(0532-41-4747),FAX(0532-41-8020)またはメール(sizensi@toyohaku.gr.jp)で。
小学4年生以上・一般40名。受講料 無料。
恐竜復元に挑戦!「恐竜復元画に挑戦しよう」 (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:天草市立御所浦白亜紀資料館
Aコース:骨格図を元に復元画を描こう 定員35名
時間:11:00〜11:30
Bコース:展示物を見て復元画を描こう 定員15名
時間:13:30〜14:30
講師:徳川広和氏
小学生以上対象(小学生は保護者同伴)、参加無料、事前申込:必要
伝馬舟体験とイルカと化石に逢える島巡りバス (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:御所浦港 他
時間:11:00〜、13:00〜、(1日2回、約1時間)
大人¥400、小中学生¥200、幼児無料、定員28名、当日申込。
08/30
(月)
08/31
(火)
天草御所浦ジオパーク島巡りクルージング (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
場所:弁天島 他
時間:11:00〜(1時間半程度)
小学生〜大人(小中学生は保護者同伴)、大人¥1000、小中学生¥500、幼児無料、定員12名、当日申込。
9月-10月のイベントは --> こちら
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ 内のフォームま たはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
教師巡検(2010富山)
教師巡検(2010富山)日本地質学会 第9回理科教員対象見学旅行
「糸魚川ジオパーク ヒスイ探訪ジオツアー」
案内者:宮島 宏(フォッサマグナミュージアム)
参加者:青木秀則、吾妻惠豊、稲田多恵子、今田耕二、岩崎正夫、岩崎ハルエ、岡田浩二、岡本真琴、岡本真生、小幡喜一、小尾 靖、金 光男、小泉治彦、田中則雄、中井 均、細谷正夫、松田義章、矢島道子、吉岡秋子、渡邊喜美子、渡辺麻友(以上21名)
【参加者感想】
写真1 明星山の岸壁前の展望台で記念写真
写真2 青海川のヒスイ峡にてヒスイの原石を観察
今年の教師向け巡検は、2009年に世界ジオパークに登録された新潟県糸魚川で実施された。参加者は会員およびそのご子息など、総勢21名。フォッサマグナミュージアムの宮島宏氏が案内を担当され、「ヒスイ探訪ジオツアー」というテーマの下、ヒスイと歴史の里、糸魚川を満喫することができた。
当日朝、糸魚川駅に集まった参加者を、ヒスイの巨大な勾玉が出迎えてくれた。まずはバスに乗り込んで、フォッサマグナミュージアムへ。視聴覚ルームで宮島氏のユーモアあふれる柔らかな語り口で、ジオパーク糸魚川と日本最古の宝石であるヒスイ(翡翠)のお話を伺った。東日本と西日本を分けるフォッサマグナに位置する糸魚川市。電流の周波数やお雑煮に入れる餅の形をはじめ、言葉遣いなどいろいろな面で東日本と西日本の境目である糸魚川は、現在、ヒスイとジオパークで町おこしが進んでいる。ジオかつ、ひすいラーメンなどが“開発”されているらしい。また、翡翠はカワセミの意もあるという。「翡」はそのオス、「翠」はメスを指すのだそうだ。
お話の後、館内の展示を自由見学した。古生物分野の展示も充実しているが、やはり圧巻はヒスイの展示である。深い緑色の宝石質のヒスイをはじめ、紫や赤のヒスイなど、様々なヒスイを鑑賞することができた。また、特別に宝石級のヒスイ原石を手に持たせてもらった。さらに、館内には案内者である宮島氏が新鉱物として発見された「糸魚川石」や「蓮華石」などの標本、地質学者ナウマン関連の展示もあり、見学時間はあっという間に過ぎた。
すぐ近くに併設された長者ヶ原考古館に立ち寄った後、一行はバスで石灰岩の岩山である明星山を目指した。ここの石灰岩は石炭紀からペルム紀のもので、下を流れる小滝川から高さ440mもの壮大な岸壁を形作っている。ヒスイでできた岩塊が転がっているという渓流を眼下に眺め(写真1)、一行は昼食に向かった。
午後は、青海自然史博物館を見学。博物館前の広場に据えられている大きなヒスイの原石を前に、宮島氏がヒスイにまつわる新鉱物発見の経緯などを説明した。ご自身が発見したとははっきりおっしゃらない中にも、ちょっとした不注意から新鉱物発見のチャンスを逃した逸話なども盛り込みながら、実感のこもったお話をうかがうことができた。
再びバスに乗り、一行は今回の目玉である青海川のヒスイ峡へと向かった。転がり落ちそうな急坂を下っていくと、急流に洗われる一群の巨岩が目に飛び込んできた。しかも、数トンはありそうな巨岩そのものがヒスイの原石なのだ。その上に立つと感慨もひとしお(写真2)。さらに、周辺には微褶曲が美しい広域変成岩や蛇紋岩など、変化に富んだ岩塊が散らばっている。数億年前にプレートの沈み込み帯深部で起きた地質現象を肌で感じることができた。
今回の巡検では、ヒスイを中心とする鉱物はもちろん、ジオパークとしての糸魚川のバリエーションに富んだ地質と歴史を十分に堪能することができた。ガイドをしてくださった宮島氏に、心から御礼申し上げたい。
(千葉県立我孫子高等学校教諭 小泉治彦)
地学研究発表会(2010富山)
小さなEarth Scientistのつどい〜第8回小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜(2010富山)
会場風景
表彰式の様子
富山大会2日目に,日本地質学会地学教育委員会の主催で「小さなEarth Scientistのつどい 〜第8回小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜」(富山大会の関連行事)がおこなわれた.年会における発表会は7年前の静岡大会からおこなわれており,今回で8回目となった.この発表会の目的は,地学普及の一環として学校における地学研究を紹介することで地学教育の奨励と振興を図ることと,地学を研究する児童・生徒と研究者の交流が進み,地球科学普及の一助となることである.
今回もポスターセッション会場の1つを本企画の会場として利用させて頂いたので,多くの会員の方にご参加頂けたものと思われる.今回は下に示す通り高校生の発表が11件あったが,地元富山県からの発表がなかったことが残念である.富山大学の先生方や,富山県教育委員会の担当者に依頼して,発表できそうな学校を探して頂いたが,結局は参加に至らなかった.富山県においては,高等学校理科で地学を専門とされ,教育,研究にご活躍中の先生もいらっしゃるが,本企画における高校生の発表までは結びつかなかった.隣接領域の研究はあったものの,日本地質学会での企画ということで,研究対象を狭く捉えると参加しづらいものと思われる.
全ての発表を審査した結果,下に示す3件の発表に対して優秀賞が授与されている.優秀賞の選考については,「研究の動機が明確であり,問題点をはっきりととらえているか」,「観察・実験から導かれたデータを基に,結論が導かれているか」,「ポスターのプレゼンテーションはどうか」,「ポスターに込められた工夫や努力はみとめられるか」の4つの観点で審査を行っており,審査員は学会役員と地学教育委員会の担当者がつとめている.役員の方々については,学会期間中のお忙しい中にもかかわらずご協力頂き,とても感謝している.
役員の方々との協議の結果,来年度からは優秀賞の審査の観点を変更し,「高校生らしい研究手法であること」や,「フィールドにおける努力」などを加えることになった.大学や研究所等の最先端の機器を利用することによって多くの成果が得られるが,それに加えて,高校生らしい発想や,フィールドにおける詳細な観察なども評価したいとの意見に配慮したものである.また,今回から優秀賞に加えて,奨励賞の表彰も行うこととなった.奨励賞は,優秀賞としては表彰されないが,今後も研究を頑張ってもらいたい発表に対して,表彰を行うものである.奨励賞は,発表件数の2割程度に,学会役員の投票によって選考される.
来年は,高等学校における地学教育の盛んな地である水戸で大会が実施される.多くの発表があることを,関係者一同期待している.
最後となったが,会場校である富山大学と中部支部の関係各位,行事委員会の皆様,さらに今回の発表会参加者に謝意を表したい.
(地学教育委員会 三次徳二:大分大学教育福祉科学部)
優秀賞を受賞した発表:
1.「金鉱の条痕色は金色」はどのように調べたか〜「条痕色」の定義を考える〜:田村優季・近江毅志・岡島菜穂子(兵庫県立加古川東高等学校 地学部条痕色班)
2.遠州灘海岸の砂の性質と起源〜特にガーネットの起源について〜:佐藤友哉・下谷豪史・鈴木竜成(静岡県立磐田南高等学校)
3.加古川市−高砂市に点在する古墳時代の石棺の鉱物学的研究:井上紗智・友藤 優(兵庫県立加古川東高等学校 地学部石棺班)
奨励賞を受賞した発表:
1.黒曜石の研究 その2:堀内香鈴・三田村愛可・兪珺婷・竹之内翔(大阪府立花園高等学校)
2.岡山県高梁エリアにおけるスカルンの探索:森 祐紀・赤木建斗(岡山県立倉敷天城高等学校理数科)
発表会参加校:静岡県立磐田南高等学校,大阪府立花園高等学校,兵庫県立加古川東高等学校,香川県立三本松高等学校,岡山県立倉敷天城高等学校,岡山県立林野高等学校,熊本県立第二高等学校,明治学園高等学校,早稲田大学高等学院
地質情報展2010とやま
地学オリンピック紹介ポスターを展示しました
2010年9月18日〜19日に、地質情報展2010とやまが開催されました。地質学会コーナーでは、「地学オリンピック−目指せ金メダル!−」と題し、ポスター展示を行いました。本ブースでは、第2回日本地学オリンピック本選で実際に使用した標本をみることができました。また、モニターでは、これまでに撮影した国際地学オリンピックの写真もたくさん紹介しました。
■ 展示ポスター(クリックすると大きな画像がご覧いただけます)
オブザーバーの活動 in インドネシア
オブザーバーの参加報告
2010年9月19日〜28日にかけて開催された第4回国際地学オリンピックインドネシア大会に、日本地質学会地学オリンピック支援委員会から3名がオブザーバーとして参加しました。前年の台湾大会から引き続き参加したのは3名中2名で、残る1名は今回が初めての参加でした。
■ オブザーバーの役割
おもに以下の3つですが、それ以外に写真撮影や日程の記録などをすることもあります。
①生徒の引率
②メンターの補佐(試験問題検討会議への出席/野外調査の下見・現地での問題検討)
③試験問題(英語)の日本語訳作成
①では滞在するホテルは生徒とは別で、開会式後から筆記試験と実技試験が終わるまでは生徒には接触できません。ただし、それ以外は生徒と活動をともにします。また、空き時間には生徒の質問に答えたりもします。
②では英語で質問したり議論したりします。
③ではPCが必要です。その他、専門用語集、教科書や図表などがあると便利です。
②・③は、生徒たちが受験する前までに行います。そのため、開会式直後から2〜3日は睡眠不足の状態が続きます。とにかく体力は必要です。
■ 活動風景
筆記試験の問題検討風景
試験問題翻訳中!
地質野外試験の下見
(問題が妥当かどうかをチェック)
海洋実技試験会場の下見
メンターとオブザーバーのみのムラピ
(メラピ)火山見学
左:晴れていれば写真中央の谷間から山頂がのぞめる.右:避難用シェルター
最後の天文実技後、生徒を慰労
国際野外協力調査を終えた生徒を激励
モデレーション
開会式会場の標本で生徒と最後確認
■ 番外編
インドネシアのお弁当
食事はほとんどバイキング形式
写真で見る軌跡:第4回インドネシア大会への道
本大会に備えて合宿研修
■ 神奈川県立生命の星・地球博物館での研修の様子
齋藤館長からの激励
火山の講義を受講中
偏光顕微鏡やルーペを用い、岩石薄片や岩石を観察する代表選手
夕食後に宿で、事前課題の復習
開館前の空き時間に、前日の復習
■ 聖光学院での研修の様子
移動式プラネタリウムを用いて、インドネシアの夜空を再現
■ 葉山での研修の様子
地層の上下判定
ブラントンコンパスの使い方
いよいよ本大会!インドネシアへ
ジョグジャカルタに到着
開会式前日の歓迎会(自己紹介風景)
開会式での日本選手団
地質野外試験の下見風景
雨天時の地質実技試験場を下見
全ての試験終了後、選手と久々の再会
■ メダルに関わる試験以外の様々な活動
Brivin Caveで実施された国際混合チームで行う国際協力野外調査
国際協力野外調査翌日に行われた調査結果のプレゼンとメンターによる採点風景
ジョグジャカルタの公立高校を訪問(研究発表と意見交換の様子)
世界遺産ボルブドゥール見学
Prof. Dr. Mezak A. RATAG氏による記念講演
■ いよいよ出発のとき・・・
金メダル授与
閉会式後の日本選手団記念撮影
■ 閉会式後
さよならパーティーでの夕食と恒例のアニメソングにのせたダンスの披露
文部科学省表敬訪問
9月29日午後、地学オリンピック日本選手団は郄木文部科学大臣を表敬訪問しました。地学オリンピック日本選手団が文部科学省を表敬訪問したのはこれが初めてです。郄木文部科学大臣から、代表選手ひとり ひとりに文部科学大臣賞が手渡されました。記念撮影の後には、鈴木副大臣と林政務官も同席される中、選手たちはそれぞれに現地でのエピソードや感想などを大臣らに説明しました。
表彰後の記念撮影
郄木大臣との懇談の様子
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2011年5-6月)
5-6月のイベント・特別展示カレンダー (2011/05/01〜2011/06/30)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
5-6月の特別展示
2011/04/05 現在
ミニ展示:モササウルス新規資料展 (北海道 むかわ町立穂別博物館)
期間:第1回 〜5/8(日)[第2回 8/6(土)〜8/21(日)]
場所:むかわ町立穂別博物館 常設展示室
平成21年度に採集したモササウルス類の化石を展示します。本標本は頭骨の半分以上が保存されており、国内でも有数の良好な標本です。詳細な研究は今後の予定ですが、今回はクリーニング作業の進行状況を展示します。※クリーニング作業の進展状況により、標本の状態はかわりますので、第1回と第2回の展示は異なります。
http://www.town.mukawa.lg.jp/1908.htm
石炭館 春の収蔵品展「炭都のくらし」 (福岡県 大牟田市石炭産業科学館)
期間:〜5/15(日)(毎週月曜日休館, 5/2は開館)
場所:大牟田市石炭産業科学館 企画展示室
閉山後10年以上が経過し,いまでは炭鉱の社宅はほとんどなくなりました.しかし炭鉱が栄えていたころは市内各地に社宅があり,そこでは炭鉱のまちならではの暮らしが営まれていました.このたびは石炭館に収蔵されている資料のうち,社宅や暮らしにかかわるものを中心に展示します.
http://www.sekitan-omuta.jp
春季特別展「白亜紀巨大二枚貝 イノセラムス・ホベツエンシス展」 (北海道 むかわ町立穂別博物館)
期間:〜5/29(日)
場所:むかわ町立穂別博物館 特別展示室
主に中生代白亜紀に繁栄した二枚貝イノセラムスとその1種;イノセラムス・ホベツエンシスを詳しく紹介します。
・イノセラムス・ホベツエンシスの模式標本展示(約80年前に穂別地域で採集された標本を初公開)
・日本産イノセラムスの化石層序 ・ふ化後の幼生期浮遊生活
・殻装飾パターンの生成 ・巨大化の謎 ・イノセラムス類の絶滅とその謎
・いのせらたんで学ぶ化石層序 ・いのせらたん名前当てクイズ
・いのせらたんぐるみ
http://www10.plala.or.jp/mukawa/soshiki/hakubutsukan/
春期特別展:深海から生まれた湘南 (神奈川県 平塚市博物館)
期間:〜5/22(日)(毎週月曜日休館)
場所:平塚市博物館
湘南地域(大磯〜平塚〜姥島〜江の島〜三浦)と相模湾を中心として、この地域がかつて相模湾の深海からどのように生まれ、現在に至っているのかという湘南の誕生物語を、陸域と海域の資料から時代を追って紹介します。近年、相模湾に潜航して得られた深海相模湾に関する映像や実物試料を海洋研究開発機構(JAMSTEC)の全面的なご協力のもとに公開し、相模湾が地質的にも生物的にも多様性に富む湾であること、相模湾と湘南地域が地球科学的に密接な深い関係があることを近いしていただければと思います。火山岩の年代測定により、平塚にかつて存在した火山の年代が明らかになったことについても展示します。
http://www.hirahaku.jp/
7月の展示・イベント情報はこちらから
5-6月のイベント
2011/04/05 現在
日付
イベント
05/01
(日)
↓
05/02
(月)
↓
05/03
(火)
↓
05/04
(水)
↓
05/05
(木)
↓
05/06
(金)
↓
05/07
(土)
↓
05/08
(日)
↓
05/09
(月)
↓
05/10
(火)
↓
05/11
(水)
↓
05/12
(木)
↓
05/13
(金)
↓
05/14
(土)
↓
05/15
(日)
特別展展示解説と深海相模湾映像上演(神奈川県 平塚市博物館)
場所:平塚市博物館 特別展示室及び講堂
時間:13:00〜15:00
05/16
(月)
05/17
(火)
05/18
(水)
05/19
(木)
05/20
(金)
05/21
(土)
05/22
(日)
05/23
(月)
05/24
(火)
05/25
(水)
05/26
(木)
05/27
(金)
05/28
(土)
05/29
(日)
05/30
(月)
05/31
(火)
06/01
(水)
06/02
(木)
06/03
(金)
06/04
(土)
06/05
(日)
06/06
(月)
06/07
(火)
06/08
(水)
06/09
(木)
06/10
(金)
06/11
(土)
06/12
(日)
06/13
(月)
06/14
(火)
06/15
(水)
06/16
(木)
06/17
(金)
06/18
(土)
自然史オープンセミナー・大化石展シリーズ:「昆虫化石」 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:大阪市立自然史博物館 集会室
時間:15:00〜16:30
講師:初宿成彦(昆虫研究室)
博物館学芸員が展示内容に関連した内容を紹介します。参加費無料(ただし別途入館料必要)
06/19
(日)
06/20
(月)
06/21
(火)
06/22
(水)
06/23
(木)
06/24
(金)
06/25
(土)
06/26
(日)
06/27
(月)
06/28
(火)
06/29
(水)
06/30
(木)
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ 内のフォームま たはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
特別講演会(山口耕生さん)/フォトコン表彰式
2011年度「地質の日」行事
一般社団法人日本地質学会・神奈川県生命の星・地球博物館 共催
◎第2回惑星地球フォトコンテスト 表彰・展示会
◎講演会「微生物は如何にして地球環境を変えてきたか?〜石から探る地球環境の進化史〜」
日 時:2011年5月14日(土) 13:00〜
会 場:神奈川県立生命の星・地球博物館 ミュージアムシアター(神奈川県小田原市入生田499 )
【アクセス方法はこちら】
入場無料・参加申込不要
プログラム
審査委員長:白尾元理さん
講師:山口耕生さん
13:00〜13:40
「第2回惑星地球フォトコンテスト 表彰・展示会」
審査委員長 白尾元理さん(写真家・サイエンスライター)
13:45〜15:00
記念講演会「微生物は如何にして地球環境を変えてきたか?〜石から探る地球環境の進化史〜」
講師:山口耕生さん(東邦大学准教授・日本地質学会理事)
内容:地球は,46億年という長い歴史の中で,様々な進化を遂げました.地球の内部あるいは外部に起因する様々な環境変動が生命の進化を促し,反対に生命の進化が地球環境を変えてきました.これがまさに「共進化」です.本講演では,地球史初期での「大気と海洋の化学組成」と「微生物の代謝」の進化に関して,最新の知見を交えてお伝えします.地球史初期の岩石試料を実際に触ってもらいながら,研究の興奮をお伝えできればと思います.
講師プロフィール:1969年神奈川県生まれ,東大工学部卒,東大海洋研修士,米国ペンシルヴェニア州立大学大学院博士課程を修了,Ph.D.ウィスコンシン大学マディソン校,海洋研究開発機構を経て現職.NASA Astrobiology Instituteの創立以来のメンバー.専門は地球化学,アストロバイオロジー,安定同位体,元素循環の進化,微生物生命圏の進化など
第1回コンテスト表彰式の様子
第1回コンテスト入選作品の展示の様子
*第2回惑星地球フォトコンテスト入賞作品は,4月16日〜5月29日の期間,神奈川県生命の星・地球博物館特別展示室にて展示されます.
問い合わせ先:日本地質学会
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル6F
TEL 03-5823-1150 FAX 03-5823-1156
E-mail: main@geosociety.jp
2011年地質の日(本部・各支部)
2011年の「地質の日」
2011年の「地質の日」に関連した日本地質学会の催しをご紹介します。
日本地質学会:本部イベント企画
一般社団法人日本地質学会・神奈川県生命の星・地球博物館 共催
◎第2回惑星地球フォトコンテスト 表彰・展示会
◎講演会「微生物は如何にして地球環境を変えてきたか?〜石から探る地球環境の進化史〜」
日時:2011年5月14日(土) 13:00〜
場所:神奈川県立生命の星・地球博物館 ミュージアムシアター(神奈川県小田原市入生田499)
講師:山口耕生(東邦大学理学部化学科)
→詳細はこちらから
北海道支部:2011年度「地質の日」記念展示
「豊平川と私たち —その生いたちと自然—」
場所:北海道大学総合博物館
日時:2011年3月8日(火)〜5月29日(日)
同時開催企画:豊平川の化石〜 化石が語る“札幌の海”
ミニツアー:札幌軟石ウォッチング(要申込)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
今後も、「地質の日」関連の情報を随時ご紹介していく予定です。お楽しみに。
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2011年7-8月)
7-8月のイベント・特別展示カレンダー (2011/07/01〜2011/08/31)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
7-8月の特別展示
2011/07/27 現在
小惑星が衝突した御池山隕石クレーター (長野県 飯田市美術博物館)
期間:〜8/28(日)
場所:飯田市美術博物館 展示室B
飯田市しらびそ高原の御池山で見つかった円形構造が、衝突による隕石クレーターであることが判明しました。衝突の証拠となった物質の他、小惑星が御池山に衝突する様子、世界各地の隕石クレーターや隕石などを紹介します。
http://www.iida-museum.org/
丹波と恐竜を知ろう 2011ー第5次発掘報告 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
期間:〜9/4(日)
場所:人と自然の博物館 3階展示室
第5次発掘の報告、篠山層群や丹波市・篠山市域の成り立ち、恐竜にかかわる丹波市・篠山市の活動などを紹介します。
http://hitohaku.jp/top/kaseki_MIDASInews11.html
「化石のつぶやき展」 (栃木県 葛生化石館)
期間:〜10/18(火)
場所:葛生化石館 企画展示室
この夏、化石がつぶやきます。化石が語る化石のこと。化石のつぶやきに耳を傾けてみませんか?
http://www.city.sano.lg.jp/kuzuufossil/index.html
第42回特別展来て!見て!感激!大化石展 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
期間:7/2(土)〜8/28(日)9:30〜17:00※入館は16:30まで.毎週月曜日休館(休日の場合は翌日)
場所:大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール
本特別展では、巨大なゾウや恐竜の化石から、琥珀に閉じこめられた小さな昆虫の化石まで、化石の魅力を余すところなく紹介し、地球環境の変化とともに生物が移り変わってきた様子を体感していただきます。
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/tokuten/2011kaseki/index.html
平成23年度特別展 新説・恐竜の成長 -The Growth and Behavior of Dinosaurs- (福井県 福井県立恐竜博物館)
期間:7/8(金)〜10/10(月・祝)9:00〜17:00※入館は16:30まで.7/13,9/14,28は休館
場所:福井県立恐竜博物館3階 特別展示室
本展は、モンタナ州立大学付属ロッキー博物館(アメリカ)と(株)ココロ(日本)の共同企画による特別展で、恐竜の成長に焦点を当てた展示。ティラノサウルスやトリケラトプス等の恐竜が成長によりどのようにその姿を変えていき、生活していたのか、ということを実物と複製、最新の恐竜ロボットを駆使して紹介する。
http://www.dinosaur.pref.fukui.jp
第26回特別企画展 おもしろサメ博 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
期間:7/15(金)〜9/11(日)9:00〜16:30※入館は16:00まで.毎週月曜日、7/19は休館(7/18開館)
場所:豊橋市自然史博物館 (観覧料とは別途に総合動植物公園入園料が必要)
会場でのお楽しみ企画◇ド迫力の記念撮影◇史上最大のサメ「メガロドン」の頭部復元模型、巨大なホホジロザメのあご、さけよけの檻などと一緒に記念撮影できます。入場された方ならどなたでも。カメラは各自でご用意ください。◇サメの歯さがし◇本物のサメの歯プレゼント!参加無料。小学生以上 先着10,000名◇サメ型帽子(子ども用)をつくろう◇サメをイメージしたかわいい帽子をつくってみませんか。材料費100円
http://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/
北と南のアンモナイト展 (熊本県 御所浦白亜紀資料館)
期間:7/16(土)〜8/31(水)9:00〜17:00※入館は16:30まで.
場所:御所浦島開発総合センター(御所浦白亜紀資料館)
アンモナイトは「化石の王様」とも言われ、古〜中生代の海で大繁栄し、そして恐竜とともに絶滅した生物です。この化石は、自然の造形美としても、学術的対象としても、非常に人気があります。また、白亜紀のアンモナイトの化石産地としては、北海道は世界有数、ここ天草も国内有数の産地として知られます。本展は、日本化石資料館の協力のもと、“北”の北海道と“南”の九州のアンモナイト化石を中心に展示を行う企画展です。(同時展示:第13回恐竜絵画コンテスト作品)
http://www5.ocn.ne.jp/~g-museum/
黄河大恐竜展 (愛知県 名古屋市科学館)
期間:7/16(土)〜8/31(水)
場所:名古屋市科学館イベントホール
全長27mにもなるアジア最大級の竜脚類ダシアティタンをはじめとする中国甘粛省で発見された恐竜の復元骨格や化石60点以上を展示。
http://www.kouga-kyoryu.com/
15周年記念企画展「よみがえる!謎の巨大恐竜スピノサウルス」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
期間:7/16(土)〜11/20(日)
場所:群馬県立自然史博物館企画展示室ほか
世界最大級の肉食恐竜「スピノサウルス」。1915年にエジプトで発見され、約1世紀の時を経てようやく復元されました。全長17m全高6mの巨大全身骨格と生体モデルを中心に、スピノサウルスの特徴やくらしていた環境、そして肉食恐竜の進化などについて紹介します。
http://www5.ocn.ne.jp/~g-museum/
企画展「石ころから診る環境とエネルギー展」 (静岡県 奇石博物館)
期間:7/16(土)〜12/23(金)
場所:奇石博物館企画展示室「石ころ組合」
国連が定めた2011年“国際森林年”にちなみ、持続可能性が問われることの多い「環境」や「エネルギー」を地球史ドラマが記録された石ころを切り口にご紹介します。
http://www.gmnh.pref.gunma.jp/index.html
地質標本館特別展「世界石紀行」 (茨城県 産業技術総合研究所地質標本館)
期間:7/20(水)〜9/25(日)
場所:産業技術総合研究所 地質標本館
写真家の須田郡司氏は,世界各地の巨石・奇石の写真を通して,自然やそこに根ざした文化を紹介する活動を続けています。「世界石紀行」では,各国の様々な石の写真とともに,写真の石と同じ岩石の標本を展示・解説し,人と関る石の魅力やなりたちを紹介します。
http://www.gsj.jp/Muse/eve_care/eve_care.html
太古からの王者シーラカンス (静岡県 東海大学自然史博物館)
期間:7/24(日)〜2012.3/31(土)
場所:東海大学自然史博物館1階特別展示室
日本で最初に解剖されたシーラカンスのレプリカと、いろいろな種類のシーラカンスの化石を展示。
http://www.sizen.muse-tokai.jp/topics/2011/topics110609.html
むかし・昔の海のいきもの大集合 (静岡県 東海大学自然史博物館)
期間:7/24(日)〜2012.3/31(土)
場所:東海大学海洋科学博物館2階特別展示室
すべては海からはじまった。海の生きものの歴史をさまざまな海の生きものの化石を展示してわかりやすく紹介します。
http://www.umi.muse-tokai.jp/topics/2011/topics110609.html
ミニ展示:モササウルス新規資料展 (北海道 むかわ町立穂別博物館)
期間:第2回 8/6(土)〜8/21(日)
場所:むかわ町立穂別博物館 常設展示室
平成21年度に採集したモササウルス類の化石を展示します。本標本は頭骨の半分以上が保存されており、国内でも有数の良好な標本です。詳細な研究は今後の予定ですが、今回はクリーニング作業の進行状況を展示します。※クリーニング作業の進展状況により、標本の状態はかわりますので、第1回と第2回の展示は異なります。
http://www.town.mukawa.lg.jp/1908.htm
7-8月のイベント
▷▷8月へ ▶▶9-10月へ
2011/07/27 現在
日付
イベント
07/01
(金)
07/02
(土)
07/03
(日)
07/04
(月)
07/05
(火)
07/06
(水)
07/07
(木)
07/08
(金)
07/09
(土)
07/10
(日)
Dinosaur Shapeshifting –変身する恐竜たち- (福井県 福井県立恐竜博物館)
場所:福井県立恐竜博物館3階 講堂
時間:14:00〜15:30
講師:ジャック・ホーナー博士(モンタナ州立大学付属ロッキー博物館)
成長とともにどのように恐竜が変わっていくのか?ジャック・ホーナー博士による最新の学説を紹介します。
07/11
(月)
07/12
(火)
07/13
(水)
07/14
(木)
07/15
(金)
07/16
(土)
子どもワークショップ:ぐるぐる 消しゴム アンモナイト (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール
時間:11:30,13:30,15:30(1回約60分)
対象:小学生以上(定員に余裕のある場合には、小学生未満のお子様もご参加いただけますが、必ず保護者の方が、ご同伴ください。)
ねりけしを コネコネして、はくぶつかんの標本の型に入れて…。ポコッと出したら 消しゴムのできあがり。材料費200円、定員1回10名
自然史オープンセミナー・大化石展シリーズ:「プランクトン化石が語る地球の話」 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:大阪市立自然史博物館 集会室
時間:15:00〜16:30
講師:川端清司(地史研究室)
博物館学芸員が展示内容に関連した内容を紹介します。参加費無料(ただし別途入館料必要)
サイエンス・サタデー「翼竜アンハングエラ型グライダーをつくろう」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 実験室
ブラジルで見つかった翼竜アンハングエラの姿を元にしたグライダーをつくります。
当日、会場で直接申し込み(各回定員30人)。小学生以上(小学3年生以下は保護者と一緒に参加)、参加費無料
07/17
(日)
子どもワークショップ:ぐるぐる 消しゴム アンモナイト (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール
時間:11:30,13:30,15:30(1回約60分)
対象:小学生以上(定員に余裕のある場合には、小学生未満のお子様もご参加いただけますが、必ず保護者の方が、ご同伴ください。)
ねりけしを コネコネして、はくぶつかんの標本の型に入れて…。ポコッと出したら 消しゴムのできあがり。材料費200円、定員1回10名
サメの魅力 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市自然史博物館
時間:14:00〜15:30
講師:田中 彰(東海大学海洋学部教授)
定員60人(小学校4年生以上)事前申込必要0532-41-4747
貝化石標本をつくろう (徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島県立博物館 実習室
時間:11:30〜15:30(1回約60分)
野外で採集したばかりの化石は、そのままでは研究や展示に使えません。化石を標本に仕上げるには、周囲の岩石を落としたり、破損した場所を接着する作業などを行います。これがクリーニングで、標本の良し悪しを決定する大事な作業です。また、テクニックと手先の器用さと根気が必要な、緊張感のある楽しい作業でもあります。この行事でクリーニングを体験してみませんか。初心者むきの材料(新生代の貝化石)を用意しています。できた標本は持って帰ることができます。(事前申込必要)
大鹿村の巨大地すべりで山の動きを探る (長野県 伊那谷自然友の会)
場所:長野県大鹿村鹿塩
大鹿村鹿塩の小塩地区の蛇紋岩地すべり地を歩きます。飯田市美術博物館8時もしくは大鹿村役場9時20分集合。案内:横山裕さん・松島信幸さん
申込必要。二日前までに電話(0265-22-8118)にて。
07/18
(月)
子どもワークショップ:ぐるぐる 消しゴム アンモナイト (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール
時間:11:30,13:30,15:30(1回約60分)
対象:小学生以上(定員に余裕のある場合には、小学生未満のお子様もご参加いただけますが、必ず保護者の方が、ご同伴ください。)
ねりけしを コネコネして、はくぶつかんの標本の型に入れて…。ポコッと出したら 消しゴムのできあがり。材料費200円、定員1回10名
日本一のサメ市場 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市自然史博物館
時間:14:00〜15:00
講師:豊橋市自然史博物館学芸員
定員40人(小学校4年生以上)事前申込必要0532-41-4747
07/19
(火)
07/20
(水)
07/21
(木)
07/22
(金)
07/23
(土)
白亜紀の化石 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:泉佐野市方面
時間:10:00〜14:00 雨天中止
参加費:100円(小学生50円。自然史博物館友の会会員は無料)
対象:小学5年生以上(小学生は保護者の同伴が必要)
中生代白亜紀の化石の観察会を行います。泉佐野市付近に分布する地層から、約7,000万年前の化石を探してみましょう。定員50名(定員を超えた場合は抽選)申込締切 7月12日(火)
子どもワークショップ:ぐるぐる 消しゴム アンモナイト (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール
時間:11:30,13:30,15:30(1回約60分)
対象:小学生以上(定員に余裕のある場合には、小学生未満のお子様もご参加いただけますが、必ず保護者の方が、ご同伴ください。)
ねりけしを コネコネして、はくぶつかんの標本の型に入れて…。ポコッと出したら 消しゴムのできあがり。材料費200円、定員1回10名
サイエンス・サタデー「翼竜アンハングエラ型グライダーをつくろう」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 実験室
ブラジルで見つかった翼竜アンハングエラの姿を元にしたグライダーをつくります。
当日、会場で直接申し込み(各回定員30人)。小学生以上(小学3年生以下は保護者と一緒に参加)、参加費無料
天草御所浦ジオパーク一周クルージング (熊本県 御所浦白亜紀資料館)
時間:11:00,13:30発(1時間40分程度)
内容:天草御所浦ジオツーリズムガイドの案内によるアンモナイト館、および白亜紀の壁や弁天島。京泊(恐竜化石発見地)の見学
1人1,000円(幼児無料) 各便先着12名
地質標本館特別講演 (茨城県 産業技術総合研究所地質標本館)
場所:産業技術総合研究所共用講堂2F大会議室
内容:地質標本館特別講演「世界石紀行−地球の記憶を訪ねる−,講演者:須田郡司氏(写真家)」,「石の造形に見るジオ多様性,講演者:加藤碵一氏(産総研フェロー)」
恐竜ナイトツアー (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
時間:17:45〜19:00
閉館後の誰もいなくなった恐竜ホールで学芸員による解説と、イベントを楽しんでいただきます。暗闇で恐竜が動く?
申込必要(電話にて)
07/24
(日)
アラスカ発、大阪のアンモナイト (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:大阪市立自然史博物館 講堂
時間:13:30〜15:30
講師:重田康成 氏 (国立科学博物館 環境変動史研究グループ研究主幹)
大阪の南にそびえる和泉山脈のふもとは、古くからアンモナイト化石の産地として知られてきました。和泉山脈と同じ中生代白亜紀末(およそ7,000万年前)のアンモナイト化石を研究している重田さんは、北海道やサハリン、アラスカなどの化石と和泉山脈産の化石を比較してその類似性など興味深い成果を出されつつあります。アンモナイトについての基礎的なことから研究の最前線の話まで、フィールドの第一線で活躍する研究者に講演していただきます。 参加費無料(ただし別途入館料必要)
子どもワークショップ:ぐるぐる 消しゴム アンモナイト (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール
時間:11:30,13:30,15:30(1回約60分)
対象:小学生以上(定員に余裕のある場合には、小学生未満のお子様もご参加いただけますが、必ず保護者の方が、ご同伴ください。)
ねりけしを コネコネして、はくぶつかんの標本の型に入れて…。ポコッと出したら 消しゴムのできあがり。材料費200円、定員1回10名
「スピノサウルスの秘密をさぐる」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 学習室
時間:13:30〜15:30
講師:長谷川善和(群馬県立自然史博物館名誉館長)
大型肉食恐竜スピノサウルスの仲間の化石が群馬で発見されました。秘密が多いスピノサウルスの特徴やくらしていた環境について、スピノサウルスの研究をしている長谷川名誉館長が解説します。
対象は小学4年生以上、参加費無料。1ヶ月前から電話で申し込み(先着100名)
天草御所浦ジオパーク一周クルージング (熊本県 御所浦白亜紀資料館)
時間:11:00,13:30発(1時間40分程度)
内容:天草御所浦ジオツーリズムガイドの案内によるアンモナイト館、および白亜紀の壁や弁天島。京泊(恐竜化石発見地)の見学
1人1,000円(幼児無料) 各便先着12名
恐竜ナイトツアー (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
時間:17:45〜19:00
閉館後の誰もいなくなった恐竜ホールで学芸員による解説と、イベントを楽しんでいただきます。暗闇で恐竜が動く?
申込必要(電話にて)
07/25
(月)
07/26
(火)
07/27
(水)
07/28
(木)
先生のための地層と化石入門2011 (神奈川県 神奈川県立生命の星・地球博物館)
場所:生命の星・地球博物館および秦野ビジターセンターほか
時間:28日〜29日,10:00〜15:30
(講座及び野外観察会)地球の営みを博物館展示と野外観察で学ぶ教員向けの講座です。前年と同様、今回も地層や化石が主ではなく、秦野市の水無川を舞台に地域地学素材に注目します。身近な素材を“地球”の実感につなげることを考えます。参加者はレポート提出があります。定員12名(教員・大人)。(事前申込必要)
07/29
(金)
07/30
(土)
子どもワークショップ:ハカセとハッケン!地そうと化石 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール
時間:11:30,13:30,15:30(1回約60分)
対象:小学生以上(定員に余裕のある場合には、小学生未満のお子様もご参加いただけますが、必ず保護者の方が、ご同伴ください。)
大昔からの砂やどろがつもってできた地そうには、いろんな化石がうまっているよ。 ハカセが地そうから化石をほりだすように、化石カードを見つけててんじしつでほんものの化石をさがしてみよう。自分だけの化石標本カードをつくるよ。材料費100円、定員1回10名
サイエンス・サタデー「翼竜アンハングエラ型グライダーをつくろう」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 実験室
ブラジルで見つかった翼竜アンハングエラの姿を元にしたグライダーをつくります。
当日、会場で直接申し込み(各回定員30人)。小学生以上(小学3年生以下は保護者と一緒に参加)、参加費無料
夏休み自然科学教室砂鉄から鉄を作ろう (島根県 奥出雲多根自然博物館)
場所:奥出雲多根自然博物館
時間:10:00,14:00
奥出雲地域でかつて盛んであったたたら製鉄の原理を学び、弓ヶ浜の砂から砂鉄を集め、テルミット反応で鉄を作ります。
申込〜Tel: 0854-54-0003,Fax: 0854-4-0005,E-mail: info@tanemuseum.jp
天草御所浦ジオパーク一周クルージング (熊本県 御所浦白亜紀資料館)
時間:11:00,13:30発(1時間40分程度)
内容:天草御所浦ジオツーリズムガイドの案内によるアンモナイト館、および白亜紀の壁や弁天島。京泊(恐竜化石発見地)の見学
1人1,000円(幼児無料) 各便先着12名
恐竜ナイトツアー (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
時間:17:45〜19:00
閉館後の誰もいなくなった恐竜ホールで学芸員による解説と、イベントを楽しんでいただきます。暗闇で恐竜が動く?
申込必要(電話にて)
07/31
(日)
250万年前の植物化石 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:岸和田市
時間:9:00〜14:00 雨天中止
参加費:100円(小学生50円。自然史博物館友の会会員は無料)
対象:小学生以上(小学生には保護者の同伴が必要)
植物化石の観察会を行います。岸和田市付近に分布する地層から、約250万年前の植物の種子や果実の化石を探してみましょう。定員25名(定員を超えた場合は抽選)申込締切 7月16日(土)
子どもワークショップ:ハカセとハッケン!地そうと化石 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール
時間:11:30,13:30,15:30(1回約60分)
対象:小学生以上(定員に余裕のある場合には、小学生未満のお子様もご参加いただけますが、必ず保護者の方が、ご同伴ください。)
大昔からの砂やどろがつもってできた地そうには、いろんな化石がうまっているよ。 ハカセが地そうから化石をほりだすように、化石カードを見つけててんじしつで ほんものの化石をさがしてみよう。 自分だけの 化石標本カードを つくるよ。材料費100円、定員1回10名
夏休み自然科学教室砂鉄から鉄を作ろう (島根県 奥出雲多根自然博物館)
場所:奥出雲多根自然博物館
時間:10:00,14:00
奥出雲地域でかつて盛んであったたたら製鉄の原理を学び、弓ヶ浜の砂から砂鉄を集め、テルミット反応で鉄を作ります。
申込〜Tel: 0854-54-0003,Fax: 0854-4-0005,E-mail: info@tanemuseum.jp
海岸で石ころをひろおう (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県富津市
富津市上総湊の海岸では、千葉県ではめずらしく、海岸に多数の石ころが見られます。いろいろな石ころを採集し、その違いを調べます。
開催1か月前から2週間前までの間に、氏名、住所、年齢、電話番号を明記の上、往復葉書かFaxで申込みください。
天草御所浦ジオパーク一周クルージング (熊本県 御所浦白亜紀資料館)
時間:11:00,13:30発(1時間40分程度)
内容:天草御所浦ジオツーリズムガイドの案内によるアンモナイト館、および白亜紀の壁や弁天島。京泊(恐竜化石発見地)の見学
1人1,000円(幼児無料) 各便先着12名
サメの解体ショー (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市自然史博物館
時間:14:00〜15:00
本物のサメを解剖して、体の特徴などを観察します。申込不要
恐竜ナイトツアー (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
時間:17:45〜19:00
閉館後の誰もいなくなった恐竜ホールで学芸員による解説と、イベントを楽しんでいただきます。暗闇で恐竜が動く?
申込必要(電話にて)
子ども鉱物教室 (神奈川県 相模原市立博物館)
場所:相模原市立博物館実習実験室
ミョウバン結晶の育成や鉱物の硬さ比べを通して,鉱物についての初歩を学びます。(申込受付終了)
08/01
(月)
08/02
(火)
08/03
(水)
08/04
(木)
海の化石探検隊 (静岡県 東海大学海洋科学博物館)
場所:東海大学海洋科学博物館
日程:8/4〜8/5
(野外観察会・体験イベント)実際に地層を見学して、その中から貝などの化石をとり出し、それを調べて、大昔の海の生きものや海底のようすを考えてみます。(所定の申込書にて申込必要)
「流れる水のはたらき」と「土地のつくりと変化」 (神奈川県 神奈川県立生命の星・地球博物館)
場所:神奈川県立生命の星・地球博物館および酒匂川周辺
日程:8/4〜8/5,10:00〜15:00
(講座および野外観察会)小学校理科5年「流れる水のはたらき」と6年「土地のつくりと変化」に関する野外や屋内での実習、博物館を利用した学習についての解説を行います。定員10名(教員)。(申込必要)
08/05
(金)
2011国際地質学史委員会日本大会(INHIGEO)記念講演会「アフリカの恐竜」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市自然史博物館
時間:15:00〜16:30
近年、恐竜研究者の間で注目されているアフリカの恐竜について、P.タケ(Taquet)さん(フランス国立自然史博物館名誉教授・フランス科学アカデミー副総裁) に紹介していただきます(同時通訳つき)。事前申込:必要(先着順)
08/06
(土)
子どもワークショップ:ハカセとハッケン!地そうと化石 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール
時間:11:30,13:30,15:30(1回約60分)
対象:小学生以上(定員に余裕のある場合には、小学生未満のお子様もご参加いただけますが、必ず保護者の方が、ご同伴ください。)
大昔からの砂やどろがつもってできた地そうには、いろんな化石がうまっているよ。 ハカセが地そうから化石をほりだすように、化石カードを見つけててんじしつで ほんものの化石をさがしてみよう。 自分だけの 化石標本カードを つくるよ。材料費100円、定員1回10名
夏休み自然科学教室化石レプリカを作ろう (島根県 奥出雲多根自然博物館)
場所:奥出雲多根自然博物館
時間:10:00,13:00,15:00
お湯で柔らかくなる樹脂を使って化石から型を取ってレプリカ模型を作ります
申込〜Tel: 0854-54-0003,Fax: 0854-4-0005,E-mail: info@tanemuseum.jp
サイエンス・サタデー「スピノサウルスの歯のレプリカをつくろう」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 実験室
群馬でもその仲間の化石が見つかっている、スピノサウルスの歯のレプリカをつくります。
当日、会場で直接申し込み(各回定員30人)。小学生以上(小学3年生以下は保護者と一緒に参加)、参加費無料
天草御所浦ジオパーク一周クルージング (熊本県 御所浦白亜紀資料館)
時間:11:00,13:30発(1時間40分程度)
内容:天草御所浦ジオツーリズムガイドの案内によるアンモナイト館、および白亜紀の壁や弁天島。京泊(恐竜化石発見地)の見学
1人1,000円(幼児無料) 各便先着12名
恐竜ナイトツアー (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
時間:17:45〜19:00
閉館後の誰もいなくなった恐竜ホールで学芸員による解説と、イベントを楽しんでいただきます。暗闇で恐竜が動く?
申込必要(電話にて)
夏休みお助け石ころ肉眼鑑定会 (静岡県 奇石博物館)
場所:奇石博物館研究学習棟2階教室
時間:9:00,14:00(各回2時間)
夏休みの自由研究のお手伝い、あるいは旅先で見つけた石ころ等々。博物館に持参いただいた石ころの肉眼鑑定を行います。無料。(受付順)
08/07
(日)
子どもワークショップ:ハカセとハッケン!地そうと化石 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール
時間:11:30,13:30,15:30(1回約60分)
対象:小学生以上(定員に余裕のある場合には、小学生未満のお子様もご参加いただけますが、必ず保護者の方が、ご同伴ください。)
大昔からの砂やどろがつもってできた地そうには、いろんな化石がうまっているよ。 ハカセが地そうから化石をほりだすように、化石カードを見つけててんじしつで ほんものの化石をさがしてみよう。 自分だけの 化石標本カードを つくるよ。材料費100円、定員1回10名
天草御所浦ジオパーク一周クルージング (熊本県 御所浦白亜紀資料館)
時間:11:00,13:30発(1時間40分程度)
内容:天草御所浦ジオツーリズムガイドの案内によるアンモナイト館、および白亜紀の壁や弁天島。京泊(恐竜化石発見地)の見学
1人1,000円(幼児無料) 各便先着12名
化石の模型を作ろう (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館研修室
アンモナイトや三葉虫、恐竜の歯などさまざまな化石の模型づくりにチャレンジします。8月7日は製作編で,13日は着色編の2日。
申込必要:開催1か月前から2週間前までの間に、氏名、住所、年齢、電話番号を明記の上、往復葉書かファクスで申込みください。
恐竜ナイトツアー (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館
時間:17:45〜19:00
閉館後の誰もいなくなった恐竜ホールで学芸員による解説と、イベントを楽しんでいただきます。暗闇で恐竜が動く?
申込必要(電話にて)
恐竜ナイトツアー (徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島県立博物館 実習室
時間:13:30〜15:30
実物の恐竜の歯やアンモナイト、三葉虫の化石から型どりした雌型を使ってレプリカをつくります。
申込必要(往復はがきにて・申込詳細はHPにてご確認ください。)
アンモナイト化石をクリーニングしてみよう! (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:人と自然の博物館
時間:13:30〜15:30
人造ノジュールに埋め込んだ小型のアンモナイト化石(実物)を使って化石のクリーニングに挑戦してみませんか?タガネや精密ナイフなどを使ってきれいに仕上げましょう。アンモナイト化石はお持ち帰りできます。
申込必要(博物館HPをご確認ください。)
夏休み特別講演会恐竜は生きている (島根県 奥出雲多根自然博物館)
場所:奥出雲多根自然博物館
最近注目を浴びているは虫類研究家富田京一氏に近年の恐竜研究最前線について語っていただきます。
定員150名。申込〜Tel: 0854-54-0003,Fax: 0854-4-0005,E-mail: info@tanemuseum.jp
戸台構造帯が二児山の双耳峰をつくる (長野県 伊那谷自然友の会)
場所:長野県大鹿村鹿塩
戸台構造帯のナギを観察しながら二児山の山頂まで登ります。健脚向き。飯田市美術博物館8時もしくは大鹿村役場9時20分集合。案内:松島信幸さん
申込必要。二日前までに電話(0265-22-8118)にて。
夏休みお助け石ころ肉眼鑑定会 (静岡県 奇石博物館)
場所:奇石博物館研究学習棟2階教室
時間:9:00,14:00(各回2時間)
夏休みの自由研究のお手伝い、あるいは旅先で見つけた石ころ等々。博物館に持参いただいた石ころの肉眼鑑定を行います。無料。(受付順)
教員・観察会指導者向け支援プログラム「火山灰室内編2」 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:自然史博物館 実習室
時間:10:30〜15:00
火山灰に含まれる鉱物の見分け方を学びます。鉱物の粒を実体顕微鏡下で種類ごとに選り分けて、鉱物見本を作ります。
対象:小・中・高校、特別支援学校の先生、または総合学習や自然観察に関わっている方で、火山灰の実習を実践したことのある方。または当館の教員向け「火山灰」に参加したことのある方(教員志望の大学生、一般の方はご相談ください)。
申込必要。(博物館HPをご確認ください。)
子ども鉱物教室 (神奈川県 相模原市立博物館)
場所:相模原市立博物館 実習実験室
ミョウバン結晶の育成や鉱物の硬さ比べを通して,鉱物についての初歩を学びます.
(申込受付終了)
08/08
(月)
08/09
(火)
あなたのパソコンで地形を知る (神奈川県 神奈川県立生命の星・地球博物館)
場所:生命の星・地球博物館
時間:10:00〜15:00
普段自分が使用しているパソコンで、地形を調べてみましょう。午前中は地図をコンピュータで操り、地形を理解していきます。午後は衛星画像の処理をしていきます。【注】CDドライブ付きのノートパソコン(windows)の持込が条件になります。当館ではパソコンを準備しません。定員20名(高校生から大人・教員)。
(申込受付終了)
教員・観察会指導者向け支援プログラム「学校の地下の地層」 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:生命の星・地球博物館
時間:10:00〜15:00
学校の地下にはどんな地層があるのか、理科の地学分野の教科書に登場するボーリングコアを用いて調べます。また、学校の地下の地層をもとに、大阪平野の生い立ちについてどのような事がわかるか、考えてみます。
対象:小・中・高校、特別支援学校の先生、または総合学習や自然観察に関わっている方で、火山灰の実習を実践したことのある方。または当館の教員向け「火山灰」に参加したことのある方(教員志望の大学生、一般の方はご相談ください)。
申込必要。(博物館HPをご確認ください。)
教職員セミナー:地層の見方・調べ方 in 淡路 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:国立淡路青少年交流の家(南あわじ市)および野外
時間:10:30〜16:30
午前中は室内で地層に関する基礎的な学習を行い、午後青少年交流の家付近に露出する和泉層群などを観察し、地層を観察するときのポイントを学習します。和泉層群は砂岩と泥岩が交互に堆積したわかりやすい地層で、学習素材としては好適なものです。
申込必要。(博物館HPをご確認ください。)
08/10
(水)
08/11
(木)
教職員セミナー:兵庫は石の国、丹波竜・ジオパーク・御影石 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:兵庫県立人と自然の博物館 大セミナー室
時間:13:30〜16:30
昨年10月に世界ジオパークに認定された山陰海岸や丹波で発掘されている恐竜など、兵庫にある石の名所を紹介し、その学術的意義や教材としての価値を紹介します。
申込必要。(博物館HPをご確認ください。)
08/12
(金)
なぜ!?なに?海の化石水族館 (静岡県 東海大学海洋科学博物館)
場所:東海大学海洋科学博物館 1階講堂
時間:10:00〜16:00
海で誕生した生き物の進化と絶滅の歴史にせまります。化石を知って昔の海を見つけよう。
「化石のつぶやきを聞く方法〜子ども用〜」 (栃木県 葛生化石館)
場所:葛生化石館
時間:10:00、13:30
化石について調べると、化石は実におしゃべりです。化石について学ぶ講座です。
小学生以上対象。親子参加可。各回定員15人。申込必要(電話にて)
化石発掘たいけん (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館 1階入口
千葉県内から運んだ岩石を割って、化石探しを体験します。
体験!ナイトミュージアム (島根県 奥出雲多根自然博物館)
場所:奥出雲多根自然博物館
8/12〜8/13。博物館に泊まって夜の博物館の様子を見たり、ピーク近くのペルセウス座流星群の観察、夜の山の中の様子の観察等を行います。
定員20名。申込〜Tel: 0854-54-0003,Fax: 0854-4-0005,E-mail: info@tanemuseum.jp
08/13
(土)
子どもワークショップ:ぐるぐる 消しゴム アンモナイト (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール
時間:11:30,13:30,15:30(1回約60分)
対象:小学生以上(定員に余裕のある場合には、小学生未満のお子様もご参加いただけますが、必ず保護者の方が、ご同伴ください。)
ねりけしを コネコネして、はくぶつかんの標本の型に入れて…。ポコッと出したら 消しゴムのできあがり。材料費200円、定員1回10名
サイエンス・サタデー「スピノサウルスの歯のレプリカをつくろう」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 実験室
群馬でもその仲間の化石が見つかっている、スピノサウルスの歯のレプリカをつくります。
当日、会場で直接申し込み(各回定員30人)。小学生以上(小学3年生以下は保護者と一緒に参加)、参加費無料
天草御所浦ジオパーク一周クルージング (熊本県 御所浦白亜紀資料館)
時間:11:00,13:30発(1時間40分程度)
内容:天草御所浦ジオツーリズムガイドの案内によるアンモナイト館、および白亜紀の壁や弁天島。京泊(恐竜化石発見地)の見学
1人1,000円(幼児無料) 各便先着12名
08/14
(日)
子どもワークショップ:ぐるぐる 消しゴム アンモナイト (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール
時間:11:30,13:30,15:30(1回約60分)
対象:小学生以上(定員に余裕のある場合には、小学生未満のお子様もご参加いただけますが、必ず保護者の方が、ご同伴ください。)
ねりけしを コネコネして、はくぶつかんの標本の型に入れて…。ポコッと出したら 消しゴムのできあがり。材料費200円、定員1回10名
天草御所浦ジオパーク一周クルージング (熊本県 御所浦白亜紀資料館)
時間:11:00,13:30発(1時間40分程度)
内容:天草御所浦ジオツーリズムガイドの案内によるアンモナイト館、および白亜紀の壁や弁天島。京泊(恐竜化石発見地)の見学
1人1,000円(幼児無料) 各便先着12名
泳げ!サメロボット (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市自然史博物館
時間:10:00〜11:00、13:00〜14:00
講師:海洋楽研究所長 林 正道
08/15
(月)
08/16
(火)
教職員セミナー:地形や地層から探る兵庫の自然史〜兵庫県西部編〜 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:兵庫県立人と自然の博物館 中セミナー室
時間:13:30〜16:30
地形や地層の調査からわかった山崎断層帯の活動史や中国山地・瀬戸内海沿岸平野の自然環境の変遷を、調査の方法や問題を含めてお話します。
申込必要。(博物館HPをご確認ください。)
08/17
(水)
教員・観察会指導者向け支援プログラム「岩石の見分け方」 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:高槻市を予定
時間:10:00〜15:00
「石の見分け方がわからない,教材としてどのように扱えばよいかもわかりにくい」というなやみを解決するために、とにかく川原に出かけて,石ころをよく見てみましょう.いろんな種類の石ころが見られます.石ころから,大阪周辺の山々のおいたちもわかってきます.じっくりと,石ころのしらべ方を身につけましょう.周辺で地層や岩石の観察も行う予定です。
対象:小・中・高校、特別支援学校の先生、または総合学習や自然観察に関わっている方。(教員志望の大学生、一般の方はご相談ください)
申込必要。(博物館HPをご確認ください。)
08/18
(木)
教職員セミナー:地層の見方・調べ方 in 丹波 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:丹波竜化石工房(ちーたんの館、丹波市山南町)および野外
時間:9:30〜16:30
午前中は、特に丹波帯および篠山層群に関する基礎的な学習を行います。午後は、野外で丹波帯や篠山層群の露頭を観察し、山南の化石工房や恐竜発掘現場の見学も行います。
申込必要。(博物館HPをご確認ください。)
鉱物の不思議に触れ、見分け方を知ろう (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:兵庫県立人と自然の博物館 大セミナー室
時間:13:30〜16:30
鉱物の持っている不思議な性質を実際の鉱物で体験し、その分類の意味や見分け方のポイントを学びます
申込必要。(博物館HPをご確認ください。)
自然講座「新長野県地質図とエコツーリズム」 (長野県 飯田市美術博物館)
場所:飯田市美術博物館科学工作室
時間:19:00〜21:00
講師:富樫均さん(長野県環境保全研究所)
08/19
(金)
08/20
(土)
子どもワークショップ:ぐるぐる 消しゴム アンモナイト (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール
時間:11:30,13:30,15:30(1回約60分)
対象:小学生以上(定員に余裕のある場合には、小学生未満のお子様もご参加いただけますが、必ず保護者の方が、ご同伴ください。)
ねりけしを コネコネして、はくぶつかんの標本の型に入れて…。ポコッと出したら 消しゴムのできあがり。材料費200円、定員1回10名
自然史オープンセミナー・大化石展シリーズ:「ヤベオオツノジカとヘラジカ」 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:大阪市立自然史博物館 集会室
時間:15:00〜16:30
講師:樽野博幸(地史研究室)
博物館学芸員が展示内容に関連した内容を紹介します。参加費無料(ただし別途入館料必要)
サイエンス・サタデー「スピノサウルスの歯のレプリカをつくろう」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 実験室
群馬でもその仲間の化石が見つかっている、スピノサウルスの歯のレプリカをつくります。
当日、会場で直接申し込み(各回定員30人)。小学生以上(小学3年生以下は保護者と一緒に参加)、参加費無料
夏休みお助け石ころ肉眼鑑定会 (静岡県 奇石博物館)
場所:奇石博物館研究学習棟2階教室
時間:9:00,14:00(各回2時間)
夏休みの自由研究のお手伝い、あるいは旅先で見つけた石ころ等々。博物館に持参いただいた石ころの肉眼鑑定を行います。無料。(受付順)
瀞川渓谷の滝と溶岩ハイキング (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:兵庫県美方郡香美町 道の駅「村岡ファームガーデン」集合
時間:10:00〜16:00
香美町村岡区の道の駅「村岡ファームガーデン」に9時集合。瀞川渓谷を散策し、周囲の岩石や瀞川滝を見学します。
申込必要。(博物館HPをご確認ください。)
天草御所浦ジオパーク一周クルージング (熊本県 御所浦白亜紀資料館)
時間:11:00,13:30発(1時間40分程度)
内容:天草御所浦ジオツーリズムガイドの案内によるアンモナイト館、および白亜紀の壁や弁天島。京泊(恐竜化石発見地)の見学
1人1,000円(幼児無料) 各便先着12名
08/21
(日)
博物館セミナー「ティラノサウルスのなかまが九州にいたー進化の空白をうめる御船の恐竜たちー」 (福井県 福井県立恐竜博物館)
場所:福井県立恐竜博物館2階 研修室
時間:13:00〜14:30
講師:池上直樹博士 (御船町恐竜博物館)
白亜紀後期前半,北米にティラノサウルスが生息していた少し前の時代,当時のアジア大陸の東岸にはどのような恐竜たちがいたのでしょうか?熊本の御船層群から徐々に明かされつつある当時の動物たちの姿を紹介します.聴講無料。
子どもワークショップ:ぐるぐる 消しゴム アンモナイト (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール
時間:11:30,13:30,15:30(1回約60分)
対象:小学生以上(定員に余裕のある場合には、小学生未満のお子様もご参加いただけますが、必ず保護者の方が、ご同伴ください。)
ねりけしを コネコネして、はくぶつかんの標本の型に入れて…。ポコッと出したら 消しゴムのできあがり。材料費200円、定員1回10名
標本の名前を調べようー標本同定会ー (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:自然史博物館(花と緑と自然の情報センター1階からお入りください。)12時〜13時は休み。
時間:10:00〜16:00
夏休み中に野山や海で採集した動物、昆虫、クモ、植物、キノコ、化石、岩石の標本の名前を、各分野の専門家がお答えします。夏休みの自由研究のまとめとしてもご利用ください。採集したものは、まず自分で標本として整理し、できるだけ図鑑などで名前を調べ、わからなかったものをお持ちください。土器や石器などの考古学資料は扱いません。
夏休みお助け石ころ肉眼鑑定会 (静岡県 奇石博物館)
場所:奇石博物館研究学習棟2階教室
時間:9:00,14:00(各回2時間)
夏休みの自由研究のお手伝い、あるいは旅先で見つけた石ころ等々。博物館に持参いただいた石ころの肉眼鑑定を行います。無料。(受付順)
自然教室「恐竜時代のコハクでストラップをつくろう(1)」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 実験室
時間:13:30〜15:30
恐竜時代にできたコハクを材料にして、自分オリジナルのストラップを作ります。
対象は小学生以上(小学3年生以下は保護者と一緒に参加)。参加費1050円(材料費+保険料)。1ヶ月前から電話で申し込み(30人、先着順)
天草御所浦ジオパーク一周クルージング (熊本県 御所浦白亜紀資料館)
時間:11:00,13:30発(1時間40分程度)
内容:天草御所浦ジオツーリズムガイドの案内によるアンモナイト館、および白亜紀の壁や弁天島。京泊(恐竜化石発見地)の見学
1人1,000円(幼児無料) 各便先着12名
08/22
(月)
化石採集教室 (栃木県 葛生化石館)
場所:栃木県佐野市内石灰石鉱山
時間:9:00、13:30
石灰岩の産地として知られる佐野市内の石灰石鉱山内で、古生代ペルム紀の化石を探す化石採集教室です。
小学生以上対象。親子参加歓迎。各回定員20人。申込必要(直接または電話にて)
ミニ火山を作ろう (神奈川県 神奈川県立生命の星・地球博物館)
場所:生命の星・地球博物館
時間:10:00〜15:00
砂と食用廃油を使っての噴火実験で、各グループ1日かけて目標の火山を作ります。【注1】加熱した油を使用しますので、小学生は保護者の付き添いが必要です。【注2】持ち物:汚れても良い服装、スプレー缶入りのエアダスターをグループで1本、各自軍手とマスク。【注3】材料の関係上、作製した火山のお持ち帰りはできません。定員各回10組(小学生以上3〜5人までの家族などのグループ)。
申込必要。(博物館HPをご確認ください。)
08/23
(火)
ミニ火山を作ろう (神奈川県 神奈川県立生命の星・地球博物館)
場所:生命の星・地球博物館
時間:10:00〜15:00
砂と食用廃油を使っての噴火実験で、各グループ1日かけて目標の火山を作ります。【注1】加熱した油を使用しますので、小学生は保護者の付き添いが必要です。【注2】持ち物:汚れても良い服装、スプレー缶入りのエアダスターをグループで1本、各自軍手とマスク。【注3】材料の関係上、作製した火山のお持ち帰りはできません。定員各回10組(小学生以上3〜5人までの家族などのグループ)。
申込必要。(博物館HPをご確認ください。)
08/24
(水)
ミニ火山を作ろう (神奈川県 神奈川県立生命の星・地球博物館)
場所:生命の星・地球博物館
時間:10:00〜15:00
砂と食用廃油を使っての噴火実験で、各グループ1日かけて目標の火山を作ります。【注1】加熱した油を使用しますので、小学生は保護者の付き添いが必要です。【注2】持ち物:汚れても良い服装、スプレー缶入りのエアダスターをグループで1本、各自軍手とマスク。【注3】材料の関係上、作製した火山のお持ち帰りはできません。定員各回10組(小学生以上3〜5人までの家族などのグループ)。
申込必要。(博物館HPをご確認ください。)
標本の名前を調べる会 (徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島県立博物館 実習室・講座室
時間:10:00〜16:00
夏休みに採集した生き物の名前を、講師の方といっしょに調べてみましょう。名前が分かると生き物への愛着もぐっと増します。
対象とするもの〜植物(コケ・キノコ・海藻を除く)、昆虫・貝などの動物、岩石・鉱物、化石。★定員なし。注意 1)種類ごとに分類しておくこと(大まかで可)。2)予め図鑑で名前を調べてみておく(間違っていても可)。3)持ってくる標本の数は、1人30点以内。4)分からないところ、質問したいところをはっきりさせておく。
08/25
(木)
08/26
(金)
08/27
(土)
子どもワークショップ:ハカセとハッケン!地そうと化石 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール
時間:11:30,13:30,15:30(1回約60分)
対象:小学生以上(定員に余裕のある場合には、小学生未満のお子様もご参加いただけますが、必ず保護者の方が、ご同伴ください。)
大昔からの砂やどろがつもってできた地そうには、いろんな化石がうまっているよ。 ハカセが地そうから化石をほりだすように、化石カードを見つけててんじしつで ほんものの化石をさがしてみよう。 自分だけの 化石標本カードを つくるよ。材料費100円、定員1回10名
サイエンス・サタデー「スピノサウルスの歯のレプリカをつくろう」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 実験室
群馬でもその仲間の化石が見つかっている、スピノサウルスの歯のレプリカをつくります。
当日、会場で直接申し込み(各回定員30人)。小学生以上(小学3年生以下は保護者と一緒に参加)、参加費無料
夏休みお助け石ころ肉眼鑑定会 (静岡県 奇石博物館)
場所:奇石博物館研究学習棟2階教室
時間:9:00,14:00(各回2時間)
夏休みの自由研究のお手伝い、あるいは旅先で見つけた石ころ等々。博物館に持参いただいた石ころの肉眼鑑定を行います。無料。(受付順)
天草御所浦ジオパーク一周クルージング (熊本県 御所浦白亜紀資料館)
時間:11:00,13:30発(1時間40分程度)
内容:天草御所浦ジオツーリズムガイドの案内によるアンモナイト館、および白亜紀の壁や弁天島。京泊(恐竜化石発見地)の見学
1人1,000円(幼児無料) 各便先着12名
「化石のつぶやきを聞く方法〜大人用〜」 (栃木県 葛生化石館)
場所:葛生化石館
時間:10:00、13:30
化石を調べるということは、化石の語る言葉を聞くということ。化石の基礎についての講座です。
小学生以上対象。親子参加可。各回定員20人。申込必要(8/2以降電話にて)
08/28
(日)
子どもワークショップ:ハカセとハッケン!地そうと化石 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール
時間:11:30,13:30,15:30(1回約60分)
対象:小学生以上(定員に余裕のある場合には、小学生未満のお子様もご参加いただけますが、必ず保護者の方が、ご同伴ください。)
大昔からの砂やどろがつもってできた地そうには、いろんな化石がうまっているよ。 ハカセが地そうから化石をほりだすように、化石カードを見つけててんじしつで ほんものの化石をさがしてみよう。 自分だけの 化石標本カードを つくるよ。材料費100円、定員1回10名
夏休みお助け石ころ肉眼鑑定会 (静岡県 奇石博物館)
場所:奇石博物館研究学習棟2階教室
時間:9:00,14:00(各回2時間)
夏休みの自由研究のお手伝い、あるいは旅先で見つけた石ころ等々。博物館に持参いただいた石ころの肉眼鑑定を行います。無料。(受付順)
鉱物の不思議を体験しよう (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:兵庫県立人と自然の博物館 大セミナー室
時間:13:30〜15:30
光る石、硬い石、形の変わった石、磁石をひきつける石など、石には不思議な性質をもったものがあります。それらを実際の鉱物で体験し、石の特徴を見つけます。
申込必要。(博物館HPをご確認ください。)
天草御所浦ジオパーク一周クルージング (熊本県 御所浦白亜紀資料館)
時間:11:00,13:30発(1時間40分程度)
内容:天草御所浦ジオツーリズムガイドの案内によるアンモナイト館、および白亜紀の壁や弁天島。京泊(恐竜化石発見地)の見学
1人1,000円(幼児無料) 各便先着12名
08/29
(月)
08/30
(火)
08/31
(水)
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ 内のフォームま たはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
報告:「紀の松島クルージングセミナー 熊野のジオサイト紀の松島めぐり」
報告:「紀の松島クルージングセミナー 熊野のジオサイト紀の松島めぐり」
鎌田 遼(環境省 近畿地方環境事務所 熊野自然保護官事務所)
和歌山県那智勝浦町にて、5月14日(土)に「地質の日」イベント「第4回 地質の日フィールドワーク 紀の松島クルージングセミナー 熊野のジオサイト紀の松島めぐり 〜美しい海岸と温泉をたずねて〜」を開催しました。本イベントでは、日本地質学会会員の後誠介氏を講師に迎え、景勝紀の松島をテーマに、遊覧船でのフィールド講座を実施しました。当日は好天に恵まれた絶好のクルージング日和で、総勢27名の参加者も美しい風景を楽しんでいました。
イベント当日の様子
(2011.5.25受付)
写真で見る軌跡 イタリア大会への道
第3回日本地学オリンピック本選(6月11‐12日:東京大学本郷キャンパスにて)
■ 試験風景
地質実技(岩石・鉱物・化石鑑定)試験
天文実技試験
■ 旅館にて
地学オリンピックOBの自己紹介
OBを囲んでの座談会
国際大会の様子を画像で紹介
■ 東京大学見学ツアー
三四郎池
東京大学博物館
橘先生の講演
■ 表彰式後の記念撮影
■ 表彰式後のピザパーティー
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2011年9-10月)
9-10月のイベント・特別展示カレンダー (2011/09/01〜2011/10/31)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
▶▶11月・12月のイベント
9-10月の特別展示
2011/07/27 現在
「OCEAN!海はモンスターでいっぱい」 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
期間:9/10(土)〜11/27(日)
場所:大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール(花と緑と自然の情報センター2階)
現在、地球上で名前がついている生物は約175万種になります。しかし、実際に生息している生物種は2000万種以上になるとも推定されています。地球上の多様な生物はすべて、今から30数億年前の海の中で誕生した生命の子孫であり、長い時間をかけて進化してきた結果です。本展では、「海にくらす」「6億年海のニュース」の2テーマで構成し、海とそこに棲む生き物たちの多様な姿を、化石と現生標本をつかって紹介しています。6億年のむかしから現在に至る海の生物の「かたち」を通して、それぞれの生物の海中における適応の様子を楽しんでいただき、多くの人が「未来の海」について考えるきっかけになればと考えます。
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
秋の展示「砂のふしぎ」 (千葉県 千葉県立中央博物館)
期間:10/1(土)〜12/4(日)
場所:千葉県立中央博物館 企画展示室
砂はどのようにしてできるのでしょう。どんなふうに動くのでしょう。砂は音を出したりもします。意外と知られていない砂の不思議を紹介します。
http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/
化石集合2011 −ジオパークを彩る化石− (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
期間:10/1(土)〜2012.4/8(日)
場所:人と自然の博物館 3階展示室
篠山層群の恐竜化石のほかに、山陰海岸ジオパークに関連した化石を展示し、ジオパークの見どころや活動を紹介します。
http://hitohaku.jp/
第53回企画展「恐竜発掘−過去からよみがえる巨大動物−」 (茨城県 ミュージアムパーク茨城県自然博物館)
期間:10/8(土)〜2012.1/9(月)
場所:ミュージアムパーク茨城県自然博物館
近年,世界各地から恐竜類,クビナガリュウ類などの海生は虫類,鯨類,束柱類,ゾウ類などの大型脊椎動物化石の発見が相次いでいる。これらの大型動物化石の発掘調査から,その後のクリーニング作業,同定,復元,展示などの数々のステップや研究によって明らかになった新知見などの成果を紹介する。
描かれた地震 (徳島県 徳島県立博物館)
期間:10/21(金)〜11/27(日)
場所:徳島県立博物館 企画展示室
日本列島は世界的にみても地震が際だって多い地域です。日本では地震を避けて生活することはできないため、すでに江戸時代には地震や地震に伴って発生する津波を描いた絵図や瓦版などが多く出版されています。地震は、断層が動くことによって起こる現象です。山地や湖などの地形をつくる大きな要因でもあり、四国山地は数多くの地震によって形づくられたともいえます。この企画展では、地震が起こる原因、地形にみられる地震の痕跡などを紹介するとともに、鯰絵や南海地震の写真など、江戸時代以降の地震に関する絵画や写真の資料を紹介します。なお、今回の企画展は国の「安心こども基金」による「動く大地『地震』こどもワークショップ」と連携して事業を行います。
http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/default.htm
丹波と恐竜を知ろう 2011ー第5次発掘報告 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
期間:〜9/4(日)
場所:人と自然の博物館 3階展示室
第5次発掘の報告、篠山層群や丹波市・篠山市域の成り立ち、恐竜にかかわる丹波市・篠山市の活動などを紹介します。
http://hitohaku.jp/top/kaseki_MIDASInews11.html
第26回特別企画展 おもしろサメ博 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
期間:〜9/11(日)9:00〜16:30※入館は16:00まで.毎週月曜日、7/19は休館(7/18開館)
場所:豊橋市自然史博物館 (観覧料とは別途に総合動植物公園入園料が必要)
会場でのお楽しみ企画◇ド迫力の記念撮影◇史上最大のサメ「メガロドン」の頭部復元模型、巨大なホホジロザメのあご、さけよけの檻などと一緒に記念撮影できます。入場された方ならどなたでも。カメラは各自でご用意ください。◇サメの歯さがし◇本物のサメの歯プレゼント!参加無料。小学生以上 先着10,000名◇サメ型帽子(子ども用)をつくろう◇サメをイメージしたかわいい帽子をつくってみませんか。材料費100円
http://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/
地質標本館特別展「世界石紀行」 (茨城県 産業技術総合研究所地質標本館)
期間:〜9/25(日)
場所:産業技術総合研究所 地質標本館
写真家の須田郡司氏は,世界各地の巨石・奇石の写真を通して,自然やそこに根ざした文化を紹介する活動を続けています。「世界石紀行」では,各国の様々な石の写真とともに,写真の石と同じ岩石の標本を展示・解説し,人と関る石の魅力やなりたちを紹介します。
http://www.gsj.jp/Muse/eve_care/eve_care.html
平成23年度特別展 新説・恐竜の成長 -The Growth and Behavior of Dinosaurs- (福井県 福井県立恐竜博物館)
期間:〜10/10(月・祝)9:00〜17:00※入館は16:30まで.7/13,9/14,28は休館
場所:福井県立恐竜博物館3階 特別展示室
本展は、モンタナ州立大学付属ロッキー博物館(アメリカ)と(株)ココロ(日本)の共同企画による特別展で、恐竜の成長に焦点を当てた展示。ティラノサウルスやトリケラトプス等の恐竜が成長によりどのようにその姿を変えていき、生活していたのか、ということを実物と複製、最新の恐竜ロボットを駆使して紹介する。
http://www.dinosaur.pref.fukui.jp
「化石のつぶやき展」 (栃木県 葛生化石館)
期間:〜10/18(火)
場所:葛生化石館 企画展示室
この夏、化石がつぶやきます。化石が語る化石のこと。化石のつぶやきに耳を傾けてみませんか?
http://www.city.sano.lg.jp/kuzuufossil/index.html
15周年記念企画展「よみがえる!謎の巨大恐竜スピノサウルス」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
期間:〜11/20(日)
場所:群馬県立自然史博物館企画展示室ほか
世界最大級の肉食恐竜「スピノサウルス」。1915年にエジプトで発見され、約1世紀の時を経てようやく復元されました。全長17m全高6mの巨大全身骨格と生体モデルを中心に、スピノサウルスの特徴やくらしていた環境、そして肉食恐竜の進化などについて紹介します。
http://www5.ocn.ne.jp/~g-museum/
企画展「石ころから診る環境とエネルギー展」 (静岡県 奇石博物館)
期間:〜12/23(金)
場所:奇石博物館企画展示室「石ころ組合」
国連が定めた2011年“国際森林年”にちなみ、持続可能性が問われることの多い「環境」や「エネルギー」を地球史ドラマが記録された石ころを切り口にご紹介します。
http://www.gmnh.pref.gunma.jp/index.html
太古からの王者シーラカンス (静岡県 東海大学自然史博物館)
期間:〜2012.3/31(土)
場所:東海大学自然史博物館1階特別展示室
日本で最初に解剖されたシーラカンスのレプリカと、いろいろな種類のシーラカンスの化石を展示。
http://www.sizen.muse-tokai.jp/topics/2011/topics110609.html
むかし・昔の海のいきもの大集合 (静岡県 東海大学自然史博物館)
期間:〜2012.3/31(土)
場所:東海大学海洋科学博物館2階特別展示室
すべては海からはじまった。海の生きものの歴史をさまざまな海の生きものの化石を展示してわかりやすく紹介します。
http://www.umi.muse-tokai.jp/topics/2011/topics110609.html
9-10月のイベント
2011/07/27 現在
日付
イベント
09/01
(木)
09/02
(金)
09/03
(土)
09/04
(日)
09/05
(月)
09/06
(火)
09/07
(水)
09/08
(木)
09/09
(金)
09/10
(土)
ジオラボ(9月)「黒雲母のひみつ」 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:自然史博物館 本館ミュージアムサービスセンター
時間:14:30〜15:30
黒雲母は、博物館の壁をつくっているかこう岩にも含まれる黒っぽい粒で、私たちの身近にある鉱物です。よく観察してみると、六角形で平べったい、薄くぺらぺらとはがれる、酸化したものは金色にぴかぴか光る、など、おもしろい性質を持っています。さわってみたり、顕微鏡で見たりしてみましょう。
09/11
(日)
丹波で地層を見る (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:丹波竜化石工房(ちーたんの館、丹波市山南町)および野外
時間:10:00〜16:30
丹波竜化石工房での1時間程度の講義の後、主に丹波市内で篠山層群、丹波帯、超丹波帯などの地層を観察します。
申込必要(博物館HPをご確認ください。)
09/12
(月)
09/13
(火)
09/14
(水)
09/15
(木)
東山道・御坂峠道と天正地震 (長野県 飯田市美術博物館)
場所:飯田市美術博物館科学 工作室
時間:19:00〜21:00
講師:市沢英利さん(竜丘小学校教諭)
09/16
(金)
09/17
(土)
09/18
(日)
自然教室「恐竜時代のコハクでストラップをつくろう(1)」 (群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 実験室
時間:13:30〜15:30
恐竜時代にできたコハクを材料にして、自分オリジナルのストラップを作ります。
対象は小学生以上(小学3年生以下は保護者と一緒に参加)。参加費1050円(材料費+保険料)。1ヶ月前から電話で申し込み(30人、先着順)
09/19
(月)
千畑層(鋸山)の化石 (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県安房郡鋸南町
千葉県鋸南町の約600万年前の地層(千畑層)で化石採集をします。
申込必要(開催1か月前〜2週間前までの間に、往復葉書かFAX)
09/20
(火)
09/21
(水)
09/22
(木)
09/23
(金)
09/24
(土)
小さな化石の抽出と観察〜前期中新世の有孔虫化石〜 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:人と自然の博物館内
時間:13:30〜16:00
薬品で処理した試料から有孔虫などの小さな化石を取り出してスライドを作製し、観察します。幾何学的な形をした半透明の化石はまるで小さな宝石のようです。作製した スライドはお持ち帰り いただけます。
申込必要(博物館HPをご確認ください。)
09/25
(日)
顕微鏡で見る化石 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:丹波竜化石工房(ちーたんの館、丹波市山南町)および野外
時間:13:30〜16:00
放散虫、コノドント、有孔虫、石灰質ナンノプランクトンなどの、顕微鏡を使わないと見えないような小さな化石を観察します。放散虫化石などのプレパラートを作成します。
申込必要(博物館HPをご確認ください。)
09/26
(月)
09/27
(火)
09/28
(水)
09/29
(木)
09/30
(金)
10/01
(土)
10/02
(日)
砂で遊ぼう−砂絵・ジオパッド (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館 2階ホール
時間:14:30〜15:30
カラーサンドを紙にふりかけて簡単につくる砂絵です。また、小さいカードケースにカラーサンドと水をいれると、砂粒が水の中で自由に動いていろいろな模様を作ります。
白亜紀の地層見学 (徳島県 徳島県立博物館)
場所:阿南市羽ノ浦町(現地集合現地解散)
時間:13:00〜16:30
阿南市羽ノ浦町に分布する白亜紀の地層と、その中に含まれる岩石や化石をかんさつします。申込必要:往復はがきにて
初めての岩石観察会「天竜川の石ころ観察」 (静岡県 奇石博物館)
場所:静岡県浜松市天竜川流域
時間:10:00〜14:00
静岡県西部を流れる天竜川流域に見られる緑色片岩と、その地質体に特徴的に含まれる鉱石「キースラガー」を手に取りながら観察し、その生い立ちなどを分かりやすくご紹介します。
申込必要:定員30名、先着順。参加料500円。電話にて。
10/03
(月)
10/04
(火)
10/05
(水)
10/06
(木)
10/07
(金)
10/08
(土)
ジオラボ(10月)「ハザードマップを作ってみよう」 (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:自然史博物館 ミュージアムサービスセンター
時間:14:30〜15:30
洪水や津波、地震の揺れや土砂崩れ、地滑りなどの危険地域を示した地図をハザードマップと呼びます。各市町村でハザードマップが出されていますが、地形図を読み取ることで、大まかにそれらの災害の及ぶ範囲を知ることができます。地形図を使ってハザードマップを作り、自然災害について考えてみましょう。
10/09
(日)
砂の不思議 (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館 講堂
講師=宮田雄一郎氏(山口大学教授)
浜を歩くと砂がキュキュと鳴くことがあります。砂は水のように動くことがあります。こんな砂の不思議を科学的に解明します。
10/10
(月)
10/11
(火)
10/12
(水)
10/13
(木)
10/14
(金)
10/15
(土)
但馬の化石をさぐる (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:兵庫県美方郡香美町香住区中央公民館
時間:13:30〜14:45
山陰海岸ジオパークに含まれる兵庫県但馬地域からは貝や植物、哺乳類など、さまざまな化石が見つかっています。これらの化石と化石を含む地層について、最新の研究成果を交えながらお話しします。
申込必要(博物館HPをご確認ください。)
10/16
(日)
砂からミニ宝石を探そう (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館 1階ホール
砂を顕微鏡でのぞいて、ざくろ石や石英の結晶を探します。
化石の観察会 (滋賀県 琵琶湖博物館)
場所:滋賀県甲賀市土山町
時間:10:00〜16:00
今から約1500万年前に海でたまった地層(鮎河層)を観察し、その地層に含まれる化石を採取して、当時のようす(環境)を考えてみよう。共催:湖国もぐらの会。申込必要。定員30名、小学生6年生以下は保護者同伴、参加料100円。往復はがきにて。
10/17
(月)
10/18
(火)
10/19
(水)
10/20
(木)
中央アルプスしらび平の氷河堆積物 (長野県 飯田市美術博物館)
場所:飯田市美術博物館科学 工作室
時間:19:00〜21:00
講師:下平眞樹さん(飯島中学校教諭)
10/21
(金)
10/22
(土)
南あわじで地層を見る (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:兵庫県南あわじ市 南淡公民館(予定)および野外
時間:10:30〜16:30
南あわじ市内に分布する白亜紀後期の和泉層群を観察し、化石の採集もおこないます。
申込必要(博物館HPをご確認ください。)
10/23
(日)
星砂を集めよう (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:人と自然の博物館内
時間:13:30〜15:00
奄美大島で取ってきた海岸砂から星砂や他の有孔虫を顕微鏡下で探し出します。集めた星砂はお持ち帰りできます。
申込必要(博物館HPをご確認ください。)
博物館の日 体験教室「砂を顕微鏡で見てみよう」 (神奈川県 相模原市立博物館)
場所:相模原市立博物館 実習実験室
日本各地の砂を顕微鏡で観察します。
星砂を探そう (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館 2階ホール
砂の中から星形の有孔虫化石を探します。
10/24
(月)
10/25
(火)
10/26
(水)
10/27
(木)
10/28
(金)
10/29
(土)
県外岩石観察会5足尾銅山と周辺の岩石 (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:栃木県日光市(千葉県集合)
関東地方有数の銅鉱山であった足尾銅山の跡地を訪ね、坑道跡や資料館、並びに、周辺の岩石を観察します。申込必要:開催1か月前から2週間前までの間に、往復葉書かFAXにて。
公開講演会 恐竜時代の海のモンスター (大阪府 大阪市立自然史博物館)
場所:自然史博物館 講堂
時間:13:00〜15:40
特別展に出展されているクビナガリュウとカメの化石の研究者を招いて、研究の最前線を紹介していただきます。1:00〜「クビナガリュウのいた時代」佐藤たまき氏(東京学芸大学)2:10〜「ウミガメ:大絶滅を生き延びたモンスター」平山廉氏(早稲田大学)
10/30
(日)
光る泥だんごをつくろう (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館 研修室
赤土からピカピカの泥だんごをつくります。申込必要:開催1か月前から2週間前までの間に、往復葉書かFAXにて。
10/31
(月)
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ 内のフォームま たはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
おめでとう金メダル!第5回国際地学オリンピック大会
おめでとう金メダル!第5回国際地学オリンピック大会(イタリア大会表彰式)
色取り取りの国旗や民族衣装に彩られた表彰会場に金メダルを表彰するアナウンスが,「フロムジャポネ ミドリワタナベ!」と響きました.高校一年生の渡辺 翠さんがゆっくりとステージに上がると会場は拍手に包まれました.メダルと賞状を手に,はにかむ彼女の表情からは嬉しさと緊張が伝わってきました.この表彰式に致るまでの9月5日から14日までの10日間に渡って,世界各国から集結した高校生たちは,筆記試験,野外での実技試験,海洋実習,巡検,発表会,被災地の宮城一校との中継交流,地元学校訪問,討論会等の競技をイタリア北部の小さな街モデナ周辺で取り組んできました. その結果,日本代表選手は次の輝かしい成績を残しました.おめでとう.
金メダル
渡辺 翠
(桜蔭高等学校)
銀メダル
浅見 慶志朗
(埼玉県立川越高等学校)
松澤 健裕
(栄光学園高等学校)
銅メダル
松岡 亮
(北海道旭川西高等学校)
選手の皆さんの感想は次のとおりです.
渡辺さん
一時は無理かとあきらめかけた時もあったけど,金メダルが獲れて本当に最高です.ただもう少し英語力があれば,日常会話が楽しめただろうにと思います.そこがもどかしかったので,これからもっと勉強します.
浅見さん
銀メダルが獲れて本当に良かったです.競技の中では,建物の石材を調べるというのがあって,街の中で地質を調べるというのが意外で新鮮でした.それから野外巡検で変成帯にも行ったのですが,日本の長瀞巡検で見た片岩がこちらにもあること,そしてそれが道路の石畳に使われていたことが印象的でした.あとスチューデントサポートの方々がとても親切で,本当に助かりました.機会があればサポートする側の仕事もしてみたいです.
松澤さん
世界中のひとたちと交流できたことが嬉しかったです.17年間でサイコ−でした.フェイスブックのアドレスも交換しました.ぜひ海外の大学に進学したいです.あと銀メダル嬉しかったです.
松岡さん
本当にたいへんなスケジュールで,ハードで長い10日間でした.でも充実してました.楽しめたのでよかったです.世界中に地学が好きなひとがいるんだと思いました.あとこちらに来て驚いたのは,石灰岩の分類が細かいことです.日本では単に石灰岩としか知らなかったのですが,こちらでは本当にいろんな種類があるんです!
選手そして関係者の皆様,本当にお疲れ様でした.来年はアルゼンチン大会です.地学オリンピックが若者たちにとって,地球科学を学びそして世界中の仲間たちと交流するきっかけとしてますます発展していくことを切に願います.
(坂口有人:オブザーバー参加)
図1.表彰式会場の外見
図2.会場の様子
図3.ステージの上で喜び合う渡辺さん(中央)
図4.松岡さんの受賞風景
図5.ステージの上で並ぶ浅見さん(左)と松澤さん(中央)
図6.日本代表チーム.左から松岡さん,浅見さん,渡辺さん,松澤さん
地質情報展2011みと:地学オリンピック
地学オリンピックの紹介をしました
2011年9月10日(土)11日(日)の両日、茨城県水戸市にある塚原運動公園武道館にて、「地質情報展2011みと−未来に活かそう 大地の鳴動−」が開催されました。このイベントは、茨城県及び周辺の地質をはじめとして、最新の地質学の研究成果を分かりやすく体験的に展示・解説するものです。
地質学会地学オリンピック支援委員会では、地質学会コーナーにてポスターを展示し、地学オリンピックの紹介を行いました。
当委員会では今後とも地学オリンピックの支援を行ってまいります。
地質情報展のポスターや地学オリンピックに関するご意見・ご感想などがございましたら、ぜひgeo-olympia(@)ml.geosociety.jp(@マークは半角にして下さい)までお寄せください。
今後とも、地学オリンピックへのご理解・ご協力のほど、よろしくお願い致します。
■ 展示した地学オリンピック紹介ポスター (PDF:約2MB)
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2012年1-2月)
1-2月のイベント・特別展示カレンダー (2012/01/01〜2012/02/29)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
1-2月の特別展示
2011/12/26 現在
第53回企画展「恐竜発掘−過去からよみがえる巨大動物−」 (茨城県 ミュージアムパーク茨城県自然博物館)
期間:〜1/9(月)
場所:ミュージアムパーク茨城県自然博物館
近年,世界各地から恐竜類,クビナガリュウ類などの海生は虫類,鯨類,束柱類,ゾウ類などの大型脊椎動物化石の発見が相次いでいる。これらの大型動物化石の発掘調査から,その後のクリーニング作業,同定,復元,展示などの数々のステップや研究によって明らかになった新知見などの成果を紹介する。
テーマ展「ふくしまの大地をつくる石たち」 (福島県 福島県立博物館)
期間:〜1/29(日)
場所:福島県立博物館収蔵資料展示室
一昨年県立只見高校から福島県の岩石標本が当館に寄贈されました.これはかつて福島県が県内の岩石を網羅的に収集したもの.この岩石標本を紹介し,同時に県土のそれぞれの地域のなりたちを,岩石標本を用いて解説します.
めぐってきました!山陰海岸ジオパーク (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
期間:2/4(日)〜3/11(日)
場所:人と自然の博物館 展示室
ジオ・キャラバンの主な展示や、地元での様子を紹介します。
http://hitohaku.jp/
中生代の化石 (徳島県 徳島県立博物館)
期間:〜2/5(日)
場所:徳島県立博物館常設展示室
http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/default.htm
企画展「箱根ジオパークをめざして―箱根・小田原・真鶴・湯河原の再発見!―」 (神奈川県 神奈川県立生命の星・地球博物館)
期間:〜2/26(日)
場所:神奈川県立生命の星・地球博物館特別展示室
ジオパークは、ユネスコが支援する地球活動の遺産を見所とする自然の公園のことです。小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町の1市3町では、箱根ジオパーク構想を推進しています。この企画展では、箱根地域の地質をはじめとして、その大地の上に生きる動植物や、縄文時代から続く人の歴史まで、幅広い視点で箱根ジオパークの見どころを紹介します。
http://nh.kanagawa-museum.jp/index.html
太古からの王者シーラカンス (静岡県 東海大学自然史博物館)
期間:〜3/31(土)
場所:東海大学自然史博物館1階特別展示室
日本で最初に解剖されたシーラカンスのレプリカと、いろいろな種類のシーラカンスの化石を展示。
http://www.sizen.muse-tokai.jp/topics/2011/topics110609.html
むかし・昔の海のいきもの大集合 (静岡県 東海大学自然史博物館)
期間:〜3/31(土)
場所:東海大学海洋科学博物館2階特別展示室
すべては海からはじまった。海の生きものの歴史をさまざまな海の生きものの化石を展示してわかりやすく紹介します。
http://www.umi.muse-tokai.jp/topics/2011/topics110609.html
化石集合2011 −ジオパークを彩る化石− (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
期間:〜4/8(日)
場所:人と自然の博物館 3階展示室
篠山層群の恐竜化石のほかに、山陰海岸ジオパークに関連した化石を展示し、ジオパークの見どころや活動を紹介します。
http://hitohaku.jp/
1/2月のイベント
2011/10/18 現在
日付
イベント
1/01
(日)
▼
1/02
(月)
▼
1/03
(火)
▼
1/04
(水)
▼
1/05
(木)
▼
1/06
(金)
▼
1/07
(土)
▼
1/08
(日)
▼
1/09
(月)
▼
1/10
(火)
▼
1/11
(水)
▼
1/12
(木)
▼
1/13
(金)
▼
1/14
(土)
▼
1/15
(日)
ミクロの世界—電子顕微鏡で小さな化石を見よう (徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島県立博物館実習室
時間:13:30-15:00
一見何のへんてつもない泥岩などの堆積岩の中には、奇妙で複雑な形をした小さな(大きさ1mm以下)化石がたくさんうずもれています。この行事では、このような小さなサイズの化石をじっくり観察します。数百倍から数千倍の倍率で見ることができる走査型電子顕微鏡を使います。参加者には、ピント合わせや倍率の切り替えなどのかんたんな操作や、化石の写真撮影も行っていただきます。(要申込)
1/16
(月)
▼
1/17
(火)
▼
1/18
(水)
▼
1/19
(木)
▼
1/20
(金)
▼
1/21
(土)
地形を観るための技能講座 (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館研修室
山岳の地形・渓谷の地形の見方を知りたい方のための講座。野外での地形をみるノウハウをお教えします。2012年1月21日(土)・28日(土)・2月18日(土)・25日(土)の連続講座。(要申込)
チョコとココアでおいしい火山実験をしよう (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:兵庫県美方郡香美町香住区中央公民館
時間:13:30-15:30
チョコレートやココアを使って火山が噴火する様子を実験します。もちろん全部食べられます。(要申込)
1/22
(日)
▼
1/23
(月)
▼
1/24
(火)
▼
1/25
(水)
▼
1/26
(木)
▼
1/27
(金)
▼
1/28
(土)
▼
1/29
(日)
▼
1/30
(月)
▼
1/31
(火)
▼
2/01
(水)
▼
2/02
(木)
▼
2/03
(金)
▼
2/04
(土)
▼
2/05
(日)
▼
2/06
(月)
▼
2/07
(火)
▼
2/08
(水)
▼
2/09
(木)
▼
2/10
(金)
▼
2/11
(土)
▼
2/12
(日)
▼
2/13
(月)
▼
2/14
(火)
▼
2/15
(水)
▼
2/16
(木)
▼
2/17
(金)
▼
2/18
(土)
山の学校95化石さがし (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県君津市
清和県民の森に集合し、化石について学びます。
地球の磁石と石に残った磁石 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:香美町村岡区中央公民館
時間:13:30-15:30
日本列島が大陸から分かれたことや地球のもつ磁石が逆転したことなどを教えてくれるのが、古い石に残された磁力です。実際の石を見ながら、地球の磁場について学びましょう。(要申込)
2/19
(日)
▼
2/20
(月)
▼
2/21
(火)
▼
2/22
(水)
▼
2/23
(木)
▼
2/24
(金)
▼
2/25
(土)
南米チリパタゴニアアンデスの自然 (長野県 飯田市美術博物館)
場所:飯田市美術博物館科学工作室
時間:13:30-15:30
講師:金澤重敏さん(風越高校教諭)
2/26
(日)
花粉を見る・調べる (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館研修室
花粉のマカフシギな姿を顕微鏡で観察します。少人数制とし、見どころのポイントを丁寧に講習します。2012年2月26日(日)・3月4日(日)の連続講座。(要申込)
電子顕微鏡で見る化石(全2回) (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
場所:人と自然の博物館内
時間:13:30-16:00
放散虫化石を材料として、1日目に双眼実体顕微鏡下で化石の拾い出しを行い、2日目にその化石を走査型電子顕微鏡で観察します。第1回2012.02月26日(日) 13:30〜16:00 、第2回 2012.03月11日(日)10:30〜16:30(要申込)
2/27
(月)
2/28
(火)
2/29
(水)
2/29
(木)
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ 内のフォームま たはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
街中ジオ散歩in Tokyo
2012年度「地質の日」行事
一般社団法人日本地質学会・ 一般社団法人応用地質学会 共催
◎街中ジオ散歩 in Tokyo「身近な地層や岩石を知ろう」徒歩見学会
*定員になりましたので,参加申込は締切ました。多数のご応募いただきありがとうございました。
日 時:2012年5月13日(日) 10時から16時 雨天決行(予定)
毎年5月10日は地質の日です.5月10日は,明治9年(1876),ライマンらによって日本で初めて広域的な地質図,200万分の1「日本蝦夷地質要略之図」が作成された日です.また,明治11年(1878)のこの日は,地質の調査を扱う組織(内務省地理局地質課)が定められた日でもあります.近年この地質の日にちなんで様々な機関で記念イベントが開かれており,応用地質学会との共催で東京都内の徒歩見学会を開催することになりました.皆様,奮ってご参加くださいますようお願いいたします.
後 援:独立行政法人産業技術総合研究所(GSJ)(予定),一般社団法人東京都地質調査業協会
場 所:東京都千代田区界隈(丸の内,日比谷,三宅坂,永田町,一番町)
案内者:中山俊雄氏((独)防災科学技術研究所),奥村興平氏
趣 旨:身近な地質とその地質に由来した地形についてや,地質と地形を利用してきた先人から現在の私たちまでの営みを,春の清々しい空気の中でのんびり歩きながら,ベテラン案内者からの興味深い説明を聞き,楽しく学ぼうという企画です.
キーワード:地形・地質・地盤沈下・水利用・地中熱利用
会 費:一般2,000円, 小学生500円(予定)保険代を含みます.当日お支払い下さい.昼食は各自でご用意下さい.
行 程:10:00東京駅丸の内南口外集合→旧丸ビル基礎の松杭→三菱1号館歴史資料室→丸の内の地盤沈下跡→稲田花崗岩のビル→伊豆の安山岩の石垣→日比谷図書文化館(千代田区の自然人文地理)(公園内で昼食)→三宅坂の水準原点→黒髪島石(細粒花崗岩)と尾立石(花崗岩)の国会議事堂→玉川上水とお濠の地形水文→一番町の地中熱利用実例ビル見学→東京メトロ半蔵門駅解散15:30頃
問い合わせ先
日本地質学会 事務局
101-0032東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F
TEL:03-5823-1150, FAX:03-5823-1156
E-mail:main@geosociety.jp
地学研究発表会(2011水戸)
小さなEarth Scientistのつどい〜第9回小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜(2011水戸)
会場風景
結果発表を待つ生徒達
水戸大会3日目に,日本地質学会地学教育委員会の主催で「小さなEarth Scientistのつどい 〜第9回小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜」(水戸大会の関連行事)がおこなわれた.年会における発表会は8年前の静岡大会からおこなわれており,今回で9回目となった.この発表会の目的は,地学普及の一環として学校における地学研究を紹介することで地学教育の奨励と振興を図ることと,地学を研究する児童・生徒と研究者の交流が進み,地球科学普及の一助となることである.
今年の発表会もポスターセッション会場の1つを本企画の会場として利用させて頂いたので,多くの会員の方にご参加頂けたものと思われる.比較的奥のほうの会場であったが,多くの会員に足を運んで頂いた.今回は久しぶりに首都圏における開催であり,全国的に見ると,高等学校で地学が多く開講されている茨城県での開催でもあったので,30件程度の発表が集まるのではないかと期待していた.しかし,下に示す通り発表数は昨年と同じ11件あった.これには,東日本大震災と,その後に続く福島の原発事故の影響もあったのではないかと感じている.震災以降,生徒を取り巻く環境が変化し,一部ではあるが生徒の科学研究についても影響が出ているという声がある.また,原発事故が終息していないという状況も,学校の判断に影響を及ぼしたかもしれない.これらとは別に,例年より1週間早い開催のため,学校行事と重なり参加を断念した学校もあったが,その一方で,学校行事とずれたため参加できたという声もある.なお,茨城県内からの参加は2校であった.
今年の特徴として,生徒同士の議論が活発に行われていたことが挙げられる.例年は,自分の学校の発表に集中しているため,他校の成果にまで関心をもつ余裕がないのであるが,今年は他校の発表について質問する場面をしばしばみかけた.このような交流が,盛んになってくることを願っている.
全ての発表を審査した結果,下に示す3件の発表に対して優秀賞が授与されている.優秀賞の選考については,「研究の動機が明確であり,問題点をはっきりととらえているか」,「観察・実験から導かれたデータを基に,結論が導かれているか」,「ポスターのプレゼンテーションはどうか」,「ポスターに込められた工夫や努力はみとめられるか」の4つの観点で審査を行っており,これに「高校生らしい研究手法であること」や「フィールドにおける努力」についても加味している.審査員は学会役員と地学教育委員会の担当者がつとめているが,執行理事の方々については,学会期間中のお忙しい中にもかかわらずご協力頂き,とても感謝している.来年以降は,理事(旧評議員)の希望者にも,審査員を務めて頂く予定にしている.
また,フィールドに根ざして研究している学校への奨励賞の授与が昨年より始まり,下の4件に授与された.
来年は,いよいよ第10回の発表会である.大阪において多くの生徒が集う機会になって欲しい.この発表会は大会の関連行事ではあるものの,大会の一部として定着してきたと感じている.
最後となったが,会場校である茨城大学と関東支部の関係各位,行事委員会の皆様,さらに今回の発表会参加者に謝意を表したい.
(地学教育委員会 三次徳二:大分大学教育福祉科学部)
【優秀賞】
1.金色に輝く黄鉄鉱の粉末はなぜ黒く見えるのか〜鉱物の色を光学で考える〜:村主美佳・小野友生奈(兵庫県立加古川東高等学校地学部条痕色班)
2.ガラス質結晶凝灰岩の「打ち水効果」で都市の気温を下げる〜地元に広く分布する「竜山石」の産業的活用〜:米今絢一郎・竹谷亮人(兵庫県立加古川東高等学校地学部竜山石班)
3.原子核乾板を用いた土壌に含まれる放射性物質の実態調査:森田結香・阿部治奈・井川遥菜・磯部衣里・浦上莉嘉・鈴木菜緒・伊藤正子・小崎菜月(滝学園滝中学校)
【奨励賞】
1.大森浜の海岸浸食と砂の堆積6−イカ看板を襲った悲劇−:海老名朱梨・熊澤果奈・立石美樹・野澤優佳・池垣佳子・池垣理子・小笠原史佳・岡田結衣(遺愛女子中学高等学校地学部)
2.茨城県常陸大宮市大宮地域の詳細な層序及び火山活動と常陸大宮堆積盆の関係について:星加夢輝(水戸葵陵高等学校)
3.茨城県南西部,境町周辺における小河川の分布と地形に関する研究:中山 肇・加藤義樹・木村仁美・岡村桃香・川井裕介・染谷樹生(茨城県立境高等学校科学部)
4.那須烏山ジオパーク構想:熊田共紘・越雲諒汰(那須烏山市立下江川中学校)
【発表会参加校】
茨城県立境高等学校,水戸葵陵高等学校,群馬県立沼田高等学校,早稲田大学高等学院,那須烏山市立下江川中学校,滝学園滝中学校,遺愛女子中学高等学校,兵庫県立加古川東高等学校,香川県立観音寺第一高等学校
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2012年4月-5月)
4-5月のイベント・特別展示カレンダー (2012/04/01〜2012/05/31)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
4-5月の特別展示
2012/04/23 現在
化石集合2011 −ジオパークを彩る化石− (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)
期間:〜4/8(日)
場所:人と自然の博物館 3階展示室
篠山層群の恐竜化石のほかに、山陰海岸ジオパークに関連した化石を展示し、ジオパークの見どころや活動を紹介します。
http://hitohaku.jp/
第64回特別展 クラゲの化石展 (静岡県 月光天文台)
期間:4/1(日)〜7/8(日)
場所:月光天文台 地学資料館
地質年代4紀にわたる軟体生物の化石・7ヶ国から26点
http://www.gekkou.or.jp/
第3回惑星地球フォトコンテスト 入選作品展示会 (千葉県 千葉県立中央博物館)
期間:4/21(土)〜6/3(日)
開館時間 9:00〜16:30(入館は16:00まで)
場所:千葉県立中央博物館
日本地質学会が開催した上記コンテストの入選作品をパネルで展示します.
主催:日本地質学会・千葉県立中央博物館
http://chiba-muse.or.jp/NATURAL/
▶▶6月のイベントはこちら
4-5月のイベント
2012/04/23 現在
日付
イベント
4/01
(日)
▼
4/02
(月)
▼
4/03
(火)
▼
4/04
(水)
▼
4/05
(木)
▼
4/06
(金)
▼
4/07
(土)
▼
4/08
(日)
▼
4/09
(月)
▼
4/10
(火)
▼
4/11
(水)
▼
4/12
(木)
▼
4/13
(金)
▼
4/14
(土)
▼
4/15
(日)
▼
4/16
(月)
▼
4/17
(火)
▼
4/18
(水)
▼
4/19
(木)
▼
4/20
(金)
▼
4/21
(土)
▼
4/22
(日)
▼
4/23
(月)
▼
4/24
(火)
▼
4/25
(水)
▼
4/26
(木)
▼
4/27
(金)
▼
4/28
(土)
▼
4/29
(日)
▼
4/30
(月)
▼
5/01
(火)
▼
5/02
(水)
▼
5/03
(木)
▼
5/04
(金)
石を割ってみよう (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館
時間:10:00〜16:00
専用の岩石ハンマーを使用して岩石を割る体験を行います.
5/05
(土)
本物の化石にさわってみよう (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館
時間:10:00〜15:00
アンモナイトやクジラの骨などの,本物の化石にさわってみます.
5/06
(日)
▼
5/07
(月)
▼
5/08
(火)
▼
5/09
(水)
▼
5/10
(木)
▼
5/11
(金)
▼
5/12
(土)
▼
5/13
(日)
地質の日関連 博物館周辺の地形・地質 (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県千葉市内
時間:10:00〜15:00
下総台地の地形・地質を人間による改変も含めて観察します.
申込詳細:開催日の1ヶ月前から2週間前までに往復葉書かFAX,館Webページにて申込.
5/14
(月)
▼
5/15
(火)
▼
5/16
(水)
▼
5/17
(木)
▼
5/18
(金)
▼
5/19
(土)
地球科学入門 第1回 地形・地質と人間 (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館
時間:13:00〜15:00
私たちが住んでいる土地を地学的に見ていきます.
申込詳細:開催日の1ヶ月前から2週間前までに往復葉書かFAX,館Webページにて申込.
5/20
(日)
▼
5/21
(月)
▼
5/22
(火)
▼
5/23
(水)
▼
5/24
(木)
▼
5/25
(金)
▼
5/26
(土)
上総層群の化石採集会 (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県君津市内
時間:13:00〜15:30
約60万年前の上総層群から産出する貝化石などを採集します..
申込詳細:開催日の1ヶ月前から2週間前までに往復葉書かFAX,館Webページにて申込.
5/27
(日)
▼
5/28
(月)
▼
5/29
(火)
▼
5/30
(水)
▼
5/31
(木)
▼
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ 内のフォームま たはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2012年6月)
6月のイベント・特別展示カレンダー (2012/06/01〜2012/06/30)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
6月の特別展示
2012/04/23 現在
第3回惑星地球フォトコンテスト 入選作品展示会 (千葉県 千葉県立中央博物館)
期間:〜6/3(日)6/17(日)期間延長
開館時間 9:00〜16:30(入館は16:00まで)
場所:千葉県立中央博物館
日本地質学会が開催した上記コンテストの入選作品をパネルで展示します.
主催:日本地質学会・千葉県立中央博物館
http://chiba-muse.or.jp/NATURAL/
第64回特別展 クラゲの化石展 (静岡県 月光天文台)
期間:〜7/8(日)
場所:月光天文台 地学資料館
地質年代4紀にわたる軟体生物の化石・7ヶ国から26点
http://www.gekkou.or.jp/
▶▶7-8月のイベントはこちら
6月のイベント
2012/04/23 現在
日付
イベント
6/01
(金)
▼
6/02
(土)
▼
6/03
(日)
▼
6/04
(月)
▼
6/05
(火)
▼
6/06
(水)
▼
6/07
(木)
▼
6/08
(金)
▼
6/09
(土)
地球科学入門 第2回 地球のすがた (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館
時間:13:00〜15:00
地球全体のすがた・構造などを学習します.
申込詳細:開催日の1ヶ月前から2週間前までに往復葉書かFAX,館Webページにて申込.
6/10
(日)
▼
6/11
(月)
▼
6/12
(火)
▼
6/13
(水)
▼
6/14
(木)
▼
6/15
(金)
本物の化石にさわってみよう (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館
時間:10:00〜15:00
アンモナイトやクジラの骨などの,本物の化石にさわってみます.
6/16
(土)
▼
6/17
(日)
▼
6/18
(月)
▼
6/19
(火)
▼
6/20
(水)
▼
6/21
(木)
▼
6/22
(金)
▼
6/23
(土)
▼
6/24
(日)
▼
6/25
(月)
▼
6/26
(火)
▼
6/27
(水)
▼
6/28
(木)
▼
6/29
(金)
▼
6/30
(土)
▼
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ 内のフォームま たはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2012年7月-8月)
7-8月のイベント・特別展示カレンダー (2012/07/01〜2012/08/31)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
7-8月の特別展示
2012/08/03 現在
第64回特別展 クラゲの化石展 (静岡県 月光天文台)
期間:〜7/8(日)
場所:月光天文台 地学資料館
地質年代4紀にわたる軟体生物の化石・7ヶ国から26点
http://www.gekkou.or.jp/
平成24年度特別展 翼竜の謎−恐竜が見あげた「竜」 (福井県 福井県立恐竜博物館)
期間:7月6日(金)〜10月8日(月・祝)ただし、7月11日(水)、9月12日(水)、26日(水)は休館
時間:9:00〜17:00(入館は16:30まで)
場所:福井県立恐竜博物館3階 特別展示室
翼竜は、初めて空を飛んだ脊椎動物で、史上最大の空を飛ぶ動物を生み出しました。近年の相次ぐ新発見により、翼竜の進化や生態についてさまざまなことが明らかになってきました。多数の世界初公開となる翼竜の実物化石を中心に、翼竜のくらした環境を復元したジオラマや、巨大翼竜の生体復元模型(翼開長10m)などの展示を通じて、翼竜の謎にせまります。
http://www.dinosaur.pref.fukui.jp/
発見された明治三陸津波の古写真 (東京都 杉並区立郷土博物館分館)
期間:7月7日(土)〜9月17日(月)休館日:毎週月曜日と第3木曜日(祝日の場合は開館し翌日休館)
場所:杉並区立郷土博物館分館
区内在住の石黒敬章氏の古写真から明治の写真師中島待乳の遺した明治三陸津波の写真が発見されました。これは新聞等で紹介され大きな反響がありました。本展示では、116年前の災害を伝える展示いたします。
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/histmus/event/index.asp?event=16883
第27回特別企画展「でっかい動物化石」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
期間:7/13(金)〜9/2(日)休館日:7/16、8/13を除く月曜日、7/17
場所:豊橋市自然史博物館
http://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/
企画展示「佐渡の海洋生物展」 (新潟県 新潟大学学術情報基盤機構旭町学術資料館)
期間:7/14(土)〜8/31(金)
場所:新潟大学駅南キャンパス ときめいと
佐渡にかかわる海洋生物について、パネルや標本を展示することにより紹介。現在の佐渡近海に生息する生き物とともに、地層から産出する海洋生物の化石を取り扱う 。
http://www.gekkou.or.jp/
開館15周年特別展「地上の覇者ー恐竜と哺乳類、巨大鳥類ー」 (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
期間:7/14(土)〜9/2(月)
場所:天草市立御所浦白亜紀資料館
中生代、恐竜たちは地球上の覇者として、君臨していました。しかし、6550万年前の大絶滅により姿を消してしまいます。新生代となり、変わって地球上の覇者となったのは、我々人類を含む哺乳類です。その哺乳類の時代にも、哺乳類と、恐竜の子孫である巨大鳥類の地上での覇者争いがありました。今回の特別展はこれらをテーマとしています。
http://www5.ocn.ne.jp/~g-museum/
「石の上にも三億年−生きた化石のキセキ−」 (栃木県 那須野が原博物館)
期間:7/14(土)〜9/17(月)
場所:那須野が原博物館
化石標本と原生標本を比較して展示し,生命進化のデザインとその謎に迫る。また,今年3月に宇都宮市内の鬼怒川河川敷で発掘されたクジラ化石の実物も展示する。
http://web.city.nasushiobara.lg.jp/hakubutsukan/
夏の企画展「旅へと誘う観光列車」 (福岡県 大牟田市石炭産業科学館)
期間:7/21(土)〜8/26(日)
場所:大牟田市石炭産業科学館 企画展示室
http://www.sekitan-omuta.jp/
特別展「石の世界—地球・人類・科学—」 (東京都 東京大学駒場博物館)
期間:7/21(土)〜9/17(月・祝)休館日 火曜日 入場無料
場所:東京大学駒場博物館
http://museum.c.u-tokyo.ac.jp/
成羽の化石再発見!(化石展示室リニューアルオープン記念) (岡山県 高梁市成羽美術館)
期間:7/27(金)〜9/30(日)休館日 月曜日、9/18(ただし8/13、9/17は開館)
場所:高梁市成羽美術館
http://www.kibi.ne.jp/~n-museum/
▶▶9-10月のイベントはこちら
7-8月のイベント
2012/07/13 現在
日付
イベント
7/01
(日)
▼
7/02
(月)
▼
7/03
(火)
▼
7/04
(水)
▼
7/05
(木)
▼
7/06
(金)
▼
7/07
(土)
地球科学入門 第3回 プレートテクトニクス (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館
時間:13:00〜15:00
地球表層の地球科学現象の根本をなすプレートテクトニクスについて学習します.
申込詳細:開催日の1ヶ月前から2週間前までに往復葉書かFAX,館Webページにて申込.
7/08
(日)
翼竜〜中生代の空の王者 (福井県 福井県立恐竜博物館)
場所:福井県立恐竜博物館3階 講堂
時間:14:00〜15:30
講師:呂 君昌 中国地質科学院地質研究所教授
地球表層の地球科学現象の根本をなすプレートテクトニクスについて学習します.
中国の翼竜研究最前線に立つ呂教授が、中国遼寧省の翼竜の多様性、新発見から明らかとなった翼竜の進化や繁殖方法、オス・メスの違いなどについて紹介します。聴講無料。
7/09
(月)
▼
7/10
(火)
▼
7/11
(水)
▼
7/12
(木)
▼
7/13
(金)
▼
7/14
(土)
▼
7/15
(日)
身近な鉱物“雲母” (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市自然史博物館
時間:14:00〜15:00
身近で見られ、使われている鉱物ー雲母の性質を体験学習。
講師:加藤千茶子
定員:40名(小学3年生以上)
申込:電話・FAX・メールにて。
7/16
(月)
▼
7/17
(火)
▼
7/18
(水)
▼
7/19
(木)
▼
7/20
(金)
高校生のための金曜特別講座「風景から見た地球史−石の世界− (東京都 東京大学駒場博物館)
場所:東京大学駒場Iキャンパス18号館ホール
時間:17:30〜(開場 17:00)
講師:東京都市大学知識工学部自然科学科 萩谷 宏
参加無料当日直接会場にお越しください。
7/21
(土)
地球科学入門 第4回 海洋の地球科学 (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館
時間:13:00〜15:00
プレートテクトニクス理論誕生の大きな礎となった海洋域の地球科学探査について見ていきます.
申込詳細:開催日の1ヶ月前から2週間前までに往復葉書かFAX,館Webページにて申込.
生き延びた大昔の生物たち (栃木県 那須野が原博物館)
場所:那須野が原博物館 研修室・企画展示室
時間:14:00〜15:30
講師:栃木県立博物館 柏村 勇二
定員50名、参加費(一般)250円、事前申込必要(博物館へ直接)
天草御所浦ジオパーク島一周クルージング (熊本県 御所浦白亜紀資料館)
時間:11:00,13:30発(1時間40分程度)
内容:天草御所浦ジオツーリズムガイドの案内によるアンモナイト館、および白亜紀の壁や弁天島、京泊(恐竜化石発見地)の見学
1人1,000円(幼児無料) 当日受付 各便先着12名
7/22
(日)
夏休み自由研究相談会(前編) (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館
時間:10:00〜15:00
夏休みの自由研究についての相談を受けます.
天草御所浦ジオパーク島一周クルージング (熊本県 御所浦白亜紀資料館)
時間:11:00,13:30発(1時間40分程度)
内容:天草御所浦ジオツーリズムガイドの案内によるアンモナイト館、および白亜紀の壁や弁天島、京泊(恐竜化石発見地)の見学
1人1,000円(幼児無料) 当日受付 各便先着12名
7/23
(月)
▼
7/24
(火)
▼
7/25
(水)
▼
7/26
(木)
▼
7/27
(金)
成羽の化石ー見どころ解説 (岡山県 高梁市成羽美術館)
場所:高梁市成羽美術館 化石展示室
時間:11:00〜、14:00〜
7/28
(土)
本物そっくりの化石レプリカをつくろう (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市自然史博物館 学習室
時間:10:00〜15:00
化石のレプリカづくりなどを通して化石を調べる方法を学びます。
定員:30名(小学4年生〜中学生)
参加費:300円
申込:往復はがきにて。7/13締切
化石発掘隊【植物編】 (栃木県 栃木県立博物館)
場所:木の葉化石園(旧塩原町)およびその周辺
講師:栃木県立博物館 柏村 勇二氏
定員:100名(小学3年生以上) 参加費(一般):600円(入館料・原石代)
事前申込必要(博物館へ直接)
天草御所浦ジオパーク島一周クルージング (熊本県 御所浦白亜紀資料館)
時間:11:00,13:30発(1時間40分程度)
内容:天草御所浦ジオツーリズムガイドの案内によるアンモナイト館、および白亜紀の壁や弁天島、京泊(恐竜化石発見地)の見学
1人1,000円(幼児無料) 当日受付 各便先着12名
7/29
(日)
ゾウのうんちペーパーをつくろう (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市自然史博物館
時間:13:00〜15:00
ゾウのうんちで紙作りを体験しながら、ゾウの生態や環境について学べます。
講師:植田紘栄志ほか
定員:50名(小学生以上)
参加費:200円
申込:往復はがきにて。7/13締切
天草御所浦ジオパーク島一周クルージング (熊本県 御所浦白亜紀資料館)
時間:11:00,13:30発(1時間40分程度)
内容:天草御所浦ジオツーリズムガイドの案内によるアンモナイト館、および白亜紀の壁や弁天島、京泊(恐竜化石発見地)の見学
1人1,000円(幼児無料) 当日受付 各便先着12名
7/30
(月)
▼
7/31
(火)
▼
8/01
(水)
▼
8/02
(木)
▼
8/03
(金)
▼
8/04
(土)
化石の模型を作ろう1(製作編) (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館
時間:10:30〜15:00
アンモナイト,三葉虫,恐竜の歯などさまざまな化石の模型作りにチャレンジします.8/11との2回連続講座.
申込詳細:開催日の1ヶ月前から2週間前までに往復葉書かFAX,館Webページにて申込.
生きた化石レプリカづくり (栃木県 那須野が原博物館)
場所:那須野が原博物館常設展示室
時間:10:30〜12:00、12:30〜15:30
費用:100円/個(※別途観覧料必要)
天草御所浦ジオパーク島一周クルージング (熊本県 御所浦白亜紀資料館)
時間:11:00,13:30発(1時間40分程度)
内容:天草御所浦ジオツーリズムガイドの案内によるアンモナイト館、および白亜紀の壁や弁天島、京泊(恐竜化石発見地)の見学
1人1,000円(幼児無料) 当日受付 各便先着12名
8/05
(日)
海岸で石ころをひろおう (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県鴨川市内
時間:10:00〜15:00
鴨川市の海岸でいろいろな石ころを観察します.
申込詳細:開催日の1ヶ月前から2週間前までに往復葉書かFAX,館Webページにて申込.
ゾウの歴史をさぐる (豊橋市自然史博物館)
場所:自然史博物館講堂
時間:13:30〜15:20
初期のゾウから現在のゾウまで、ゾウの進化と系統についての細心の研究成果を紹介します。
講師:国立科学博物館/甲能直樹、滋賀県立琵琶湖博物館/高橋啓一 ほか
定員:100名(小学4年生以上) 要申込:電話またはメール等にて
生きた化石レプリカづくり (栃木県 那須野が原博物館)
場所:那須野が原博物館常設展示室
時間:10:30〜12:00、12:30〜15:30
費用:100円/個(※別途観覧料必要)
天草御所浦ジオパーク島一周クルージング (熊本県 御所浦白亜紀資料館)
時間:11:00,13:30発(1時間40分程度)
内容:天草御所浦ジオツーリズムガイドの案内によるアンモナイト館、および白亜紀の壁や弁天島、京泊(恐竜化石発見地)の見学
1人1,000円(幼児無料) 当日受付 各便先着12名
8/06
(月)
▼
8/07
(火)
▼
8/08
(水)
▼
8/09
(木)
▼
8/10
(金)
▼
8/11
(土)
化石の模型を作ろう2(着色編) (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館
時間:10:30〜15:00
アンモナイト,三葉虫,恐竜の歯などさまざまな化石の模型作りにチャレンジします.8/4との2回連続講座.
申込詳細:開催日の1ヶ月前から2週間前までに往復葉書かFAX,館Webページにて申込.
生きた化石レプリカづくり (栃木県 那須野が原博物館)
場所:那須野が原博物館常設展示室
時間:10:30〜12:00、12:30〜15:30
費用:100円/個(※別途観覧料必要)
天草御所浦ジオパーク島一周クルージング (熊本県 御所浦白亜紀資料館)
時間:11:00,13:30発(1時間40分程度)
内容:天草御所浦ジオツーリズムガイドの案内によるアンモナイト館、および白亜紀の壁や弁天島、京泊(恐竜化石発見地)の見学
1人1,000円(幼児無料) 当日受付 各便先着12名
8/12
(日)
でっかい化石 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市自然史博物館
時間:14:00〜15:00
ゾウ、クジラなどでっかい生き物の化石にふれながら紹介。
講師:吉川博章
定員:40名(小学3年生以上)
申込:電話・FAX・メールにて。
生きた化石レプリカづくり (栃木県 那須野が原博物館)
場所:那須野が原博物館常設展示室
時間:10:30〜12:00、12:30〜15:30
費用:100円/個(※別途観覧料必要)
天草御所浦ジオパーク島一周クルージング (熊本県 御所浦白亜紀資料館)
時間:11:00,13:30発(1時間40分程度)
内容:天草御所浦ジオツーリズムガイドの案内によるアンモナイト館、および白亜紀の壁や弁天島、京泊(恐竜化石発見地)の見学
1人1,000円(幼児無料) 当日受付 各便先着12名
8/13
(月)
化石のクリーニング (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館
時間:13:00〜15:30
化石を岩石から取り出してきれいにするクリーニングを学びます.
申込詳細:開催日の1ヶ月前から2週間前までに往復葉書かFAX,館Webページにて申込.
8/14
(火)
成羽再発見〜ふるさとの森を思う (岡山県 高梁市成羽美術館)
場所:成羽総合福祉センター大ホール(美術館隣)
時間:13:30〜15:00
講師:宮脇 昭氏
定員:先着300名 要事前申込 7/14 10時〜 0866-42-4455
8/15
(水)
▼
8/16
(木)
▼
8/17
(金)
▼
8/18
(土)
天草御所浦ジオパーク島一周クルージング (熊本県 御所浦白亜紀資料館)
時間:11:00,13:30発(1時間40分程度)
内容:天草御所浦ジオツーリズムガイドの案内によるアンモナイト館、および白亜紀の壁や弁天島、京泊(恐竜化石発見地)の見学
1人1,000円(幼児無料) 当日受付 各便先着12名
夏休み化石DAYS〜いろいろな化石を見てみよう! (岡山県 高梁市成羽美術館)
場所:高梁市成羽美術館 化石展示室・多目的展示室
時間:11:00〜、13:00〜
講師:林原自然科学博物館スタッフ
化石といっても、もとの生きものや、化石になる過程によってちがった特徴があります。いろいろな化石を観察してみましょう。手にとって観察できるものも用意します。
8/19
(日)
ゾウを復元しよう (豊橋市自然史博物館)
場所:自然史博物館講堂
時間:13:30〜15:30
化石からどのようにして古代ゾウを復元するのか?復元画の方法をプロから学ぶ。
講師:徳川広和
定員:50名(小中学生) 要申込:博物館へ往復ハガキにて
天草御所浦ジオパーク島一周クルージング (熊本県 御所浦白亜紀資料館)
時間:11:00,13:30発(1時間40分程度)
内容:天草御所浦ジオツーリズムガイドの案内によるアンモナイト館、および白亜紀の壁や弁天島、京泊(恐竜化石発見地)の見学
1人1,000円(幼児無料) 当日受付 各便先着12名
夏休み化石DAYS〜いろいろな化石を見てみよう! (岡山県 高梁市成羽美術館)
場所:高梁市成羽美術館 化石展示室・多目的展示室
時間:11:00〜、13:00〜
講師:林原自然科学博物館スタッフ
化石といっても、もとの生きものや、化石になる過程によってちがった特徴があります。いろいろな化石を観察してみましょう。手にとって観察できるものも用意します。
8/20
(月)
▼
8/21
(火)
▼
8/22
(水)
▼
8/23
(木)
▼
8/24
(金)
▼
8/25
(土)
夏休み自由研究相談会(後編) (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館
時間:10:00〜15:00
夏休みの自由研究についての相談を受けます.
生きた化石レプリカづくり (栃木県 那須野が原博物館)
場所:那須野が原博物館常設展示室
時間:10:30〜12:00、12:30〜15:30
費用:100円/個(※別途観覧料必要)
天草御所浦ジオパーク島一周クルージング (熊本県 御所浦白亜紀資料館)
時間:11:00,13:30発(1時間40分程度)
内容:天草御所浦ジオツーリズムガイドの案内によるアンモナイト館、および白亜紀の壁や弁天島、京泊(恐竜化石発見地)の見学
1人1,000円(幼児無料) 当日受付 各便先着12名
成羽の植物化石をプリントしたエコバッグを作ろう〜2億数千年前の植物のカタチを型染めします (岡山県 高梁市成羽美術館)
場所:高梁市成羽美術館 化石展示室・多目的展示室
時間:11:00〜、14:00〜、15:30〜
講師:染色作家 北野静樹氏
各回先着15名、当日開始時間30分前から受付
8/26
(日)
夏休み自由研究相談会(後編) (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館
時間:10:00〜15:00
夏休みの自由研究についての相談を受けます.
生きた化石レプリカづくり (栃木県 那須野が原博物館)
場所:那須野が原博物館常設展示室
時間:10:30〜12:00、12:30〜15:30
費用:100円/個(※別途観覧料必要)
天草御所浦ジオパーク島一周クルージング (熊本県 御所浦白亜紀資料館)
時間:11:00,13:30発(1時間40分程度)
内容:天草御所浦ジオツーリズムガイドの案内によるアンモナイト館、および白亜紀の壁や弁天島、京泊(恐竜化石発見地)の見学
1人1,000円(幼児無料) 当日受付 各便先着12名
8/27
(月)
▼
8/28
(火)
▼
8/29
(水)
▼
8/30
(木)
▼
8/31
(金)
▼
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ 内のフォームま たはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2012年9月-10月)
9-10月のイベント・特別展示カレンダー (2012/09/01〜2012/10/31)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
9-10月の特別展示
2012/08/03 現在
第27回特別企画展「でっかい動物化石」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
期間:〜9/2(日)
場所:豊橋市自然史博物館
http://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/
開館15周年特別展「地上の覇者ー恐竜と哺乳類、巨大鳥類ー」 (熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館)
期間:〜9/2(月)
場所:天草市立御所浦白亜紀資料館
中生代、恐竜たちは地球上の覇者として、君臨していました。しかし、6550万年前の大絶滅により姿を消してしまいます。新生代となり、変わって地球上の覇者となったのは、我々人類を含む哺乳類です。その哺乳類の時代にも、哺乳類と、恐竜の子孫である巨大鳥類の地上での覇者争いがありました。今回の特別展はこれらをテーマとしています。
http://www5.ocn.ne.jp/~g-museum/
発見された明治三陸津波の古写真 (東京都 杉並区立郷土博物館分館)
期間:〜9月17日(月)休館日:毎週月曜日と第3木曜日(祝日の場合は開館し翌日休館)
場所:杉並区立郷土博物館分館
区内在住の石黒敬章氏の古写真から明治の写真師中島待乳の遺した明治三陸津波の写真が発見されました。これは新聞等で紹介され大きな反響がありました。本展示では、116年前の災害を伝える展示いたします。
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/histmus/event/index.asp?event=16883
「石の上にも三億年−生きた化石のキセキ−」 (栃木県 那須野が原博物館)
期間:〜9/17(月)
場所:那須野が原博物館
化石標本と原生標本を比較して展示し,生命進化のデザインとその謎に迫る。また,今年3月に宇都宮市内の鬼怒川河川敷で発掘されたクジラ化石の実物も展示する。
http://web.city.nasushiobara.lg.jp/hakubutsukan/
特別展「石の世界―地球・人類・科学―」 (東京都 東京大学駒場博物館)
期間:〜9/17(月・祝)休館日 火曜日 入場無料
場所:東京大学駒場博物館
http://museum.c.u-tokyo.ac.jp/
「成羽の化石再発見!」(化石展示室リニューアルオープン記念) (岡山県 高梁市成羽美術館)
期間:〜9/30(日)休館日 月曜日、9/18(ただし8/13、9/17は開館)
場所:高梁市成羽美術館
http://www.kibi.ne.jp/~n-museum/
平成24年度特別展 翼竜の謎−恐竜が見あげた「竜」 (福井県 福井県立恐竜博物館)
期間:〜10月8日(月・祝)ただし、9月12日(水)、26日(水)は休館
時間:9:00〜17:00(入館は16:30まで)
場所:福井県立恐竜博物館3階 特別展示室
翼竜は、初めて空を飛んだ脊椎動物で、史上最大の空を飛ぶ動物を生み出しました。近年の相次ぐ新発見により、翼竜の進化や生態についてさまざまなことが明らかになってきました。多数の世界初公開となる翼竜の実物化石を中心に、翼竜のくらした環境を復元したジオラマや、巨大翼竜の生体復元模型(翼開長10m)などの展示を通じて、翼竜の謎にせまります。
http://www.dinosaur.pref.fukui.jp/
▶▶11-12月のイベントはこちら
9-10月のイベント
2012/08/03 現在
日付
イベント
9/01
(土)
天草御所浦ジオパーク島一周クルージング (熊本県 御所浦白亜紀資料館)
時間:11:00,13:30発(1時間40分程度)
内容:天草御所浦ジオツーリズムガイドの案内によるアンモナイト館、および白亜紀の壁や弁天島、京泊(恐竜化石発見地)の見学
1人1,000円(幼児無料) 当日受付 各便先着12名
成羽の化石産地見学会(採取体験) (岡山県 高梁市成羽美術館)
場所:高梁市成羽美術館 化石展示室・成羽町内
時間:10:00〜14:00
講師:岡山大学理学部教授 鈴木茂之氏
定員15名、対象:小学4年〜大人 参加費:500円 往復はがきにて受付 8/10必着 ※雨天中止
9/02
(日)
天草御所浦ジオパーク島一周クルージング (熊本県 御所浦白亜紀資料館)
時間:11:00,13:30発(1時間40分程度)
内容:天草御所浦ジオツーリズムガイドの案内によるアンモナイト館、および白亜紀の壁や弁天島、京泊(恐竜化石発見地)の見学
1人1,000円(幼児無料) 当日受付 各便先着12名
9/03
(月)
▼
9/04
(火)
▼
9/05
(水)
▼
9/06
(木)
▼
9/07
(金)
▼
9/08
(土)
地球科学入門 第5回 地震 (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館
時間:13:00〜15:00
地震とはどのような現象か,その基本を学習します.
申込詳細:開催日の1ヶ月前から2週間前までに往復葉書かFAX,館Webページにて申込.
9/09
(日)
▼
9/10
(月)
▼
9/11
(火)
▼
9/12
(水)
▼
9/13
(木)
▼
9/14
(金)
▼
9/15
(土)
自然科学ワークショップ「生物の形を読み解く」 (東京都 杉並区立科学館)
場所:杉並区立科学館
時間:13:00-14:30 体験講座「化石のレプリカ作製」
講師:杉並区立科学館 職員
:15:00-17:00 特別講演会「"幻の怪獣"デスモスチルスはどこまでわかったか?」
講師:甲能直樹/国立科学博物館 研究主幹
事前申込必要、それぞれ往復ハガキまたはFAXにて
9/16
(日)
▼
9/17
(月)
▼
9/18
(火)
▼
9/19
(水)
▼
9/20
(木)
▼
9/21
(金)
▼
9/22
(土)
▼
9/23
(日)
化石発掘たいけん (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館
時間:13:00〜15:00
恐竜時代の岩石から植物や貝の化石を探します.恐竜が見つかるかも!?.
申込詳細:開催日の1ヶ月前から2週間前までに往復葉書かFAX,館Webページにて申込.
なぜアジアの翼竜足跡化石は翼竜の進化を知るために重要なのか? (福井県 福井県立恐竜博物館)
場所:福井県立恐竜博物館3階 講堂
時間:14:00〜15:30
講師:イ・ユンナム 韓国地質資源研究院地質博物館館長
福井産翼竜足跡化石プテライクヌス・ニッポネンシスをはじめ、アジアの翼竜足跡化石について紹介し、翼竜の進化を理解する上での足跡化石の重要性についてお話します。
9/24
(月)
▼
9/25
(火)
▼
9/26
(水)
▼
9/27
(木)
▼
9/28
(金)
▼
9/29
(土)
自然科学ワークショップ「生物の形を読み解く」 (東京都 杉並区立科学館)
場所:杉並区立科学館
時間:13:00-14:30 体験講座「手羽先の解剖」
講師:杉並区立科学館 職員
:15:00-17:00 特別講演会「トリケラトプスの前肢姿勢復元—ホネの形の意味を探る」
講師:藤原慎一/東京大学総合研究博物館 特任助教
事前申込必要、それぞれ往復ハガキまたはFAXにて
9/30
(日)
▼
10/01
(月)
▼
10/02
(火)
▼
10/03
(水)
▼
10/04
(木)
▼
10/05
(金)
▼
10/06
(土)
▼
10/07
(日)
▼
10/08
(月)
▼
10/09
(火)
▼
10/10
(水)
▼
10/11
(木)
▼
10/12
(金)
▼
10/13
(土)
▼
10/14
(日)
▼
10/15
(月)
▼
10/16
(火)
▼
10/17
(水)
▼
10/18
(木)
▼
10/19
(金)
▼
10/20
(土)
▼
10/21
(日)
▼
10/22
(月)
▼
10/23
(火)
▼
10/24
(水)
▼
10/25
(木)
▼
10/26
(金)
▼
10/27
(土)
▼
10/28
(日)
▼
10/29
(月)
▼
10/30
(火)
▼
10/31
(水)
▼
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ 内のフォームま たはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
教師巡検(2011水戸)
教師巡検(2011水戸)日本地質学会 第10回理科教員対象見学旅行
「地層を見る・はぎ取る・作る」
案内者:伊藤孝(茨城大学)・牧野泰彦(茨城大学)・植木岳雪(産総研)・中野英之(京都教育大学)・小尾 靖(神奈川県立相模原青陵高校)
【参加者感想】
日本地質学会2011年水戸見学旅行J班に参加して
日本地質学会2011年水戸見学旅行J班は「地層を見る・はぎ取る・作る」というテーマで、9月10日に開催された。案内者は伊藤孝(茨城大学)・牧野泰彦(茨城大学)・植木岳雪(産総研)・中野英之(京都教育大学)・小尾 靖(神奈川県立相模原青陵高校)の4名、参加者は合計で17名であった。野外見学は鹿島灘の北端にあたる大洗海岸の現世堆積物、東茨城台地を構成する更新世の海成段丘・河成段丘の地形・地層の観察と地層のはぎ取り標本作製し、室内講義は授業での活用方法の紹介や簡易水路を用いた堆積実験である。
◆見学コースとタイム
8:10 茨城大学発(バス)→9:03〜10:05 STOP1大洗海岸サンビーチ→STOP2 水戸市下入野→10:40〜11:15 STOP3水戸市東前→ 11:30〜13:15 縄文文化財センター前公園で昼食→13:30〜15:00 STOP2で地層のはぎ取り作業→15:00〜16:00 茨城大学研究大会登録→16:00〜17:00 はぎ取り標本を活用した授業報告と簡易水路を用いた地層の堆積実験
◆見学旅行の詳細
主催者側を代表して植木さんから案内者1人1人が個性を発揮して当たることを宣言。その後、参加者それぞれが自己紹介し、この見学旅行にかける期待を語った。
Stop1までは那珂川沿いに下るが、川の堤防沿いにはビニールシートがかけられ、土嚢が積み上げられているところから津波被害を受けたことがわかるという。配られた茨城県の広報誌には大洗海岸に3mの津波が渦を巻いて押し寄せたようすが撮影されている。
Stop1の大洗サンビーチ(36°18′03″N,140°34′10″E)は大洗港の防波堤建設によって砂が堆積する場となっており、現世の海浜の微地形を観察した。前浜では岸沖方向のトレンチを掘って堆積物中に発達する雲母や磁鉄鉱の砂粒子を含んでいるわかりやすい斜交葉理を観察した。今回の観察目的ではないが、津波堆積物は既に取り除かれているが、使用できなくなっているトイレの天井まで水が到達していたことがわかる。
Stop 2の水戸市下入野町(36°18′15″N,140°30′47″E)では最終間氷期(約12.8万年前)の海成段丘(東茨城台地)の露頭があり、谷埋堆積物(見和層上部層=砂礫層→ヒメスナホリムシの生痕化石を含む中粒砂→中粒砂〜砂質シルト層→粘土層)と関東ローム層(ローム層→赤城鹿沼軽石Ag-Kp=4.5万年前)のスケッチをして確認した後、見和層の砂礫層〜砂層のはぎ取り標本の作業に入った。まずは案内者から標本の作製方法の説明を受けた。手順は簡単であるが、2人1組で行う。まず、はぎ取り箇所をなるべく平面にきれいにし、その上に寒冷紗を被せ、ピンで留める。接着剤が目に入るのを防ぐためにゴーグルとビニール手袋は欠かせない。接着剤Hycel(商品名)は原液を水で約3倍に薄める。すぐに固化するので速やかに寒冷紗の上からハケで押しつけるように塗布する。礫層の場合は原液を直接かけてしみこました後に。シュプレーで水をかけてハケで押しつける。という話までしたところで、さあ始めようという段階でハプニング。接着剤が固まっていて使えないという事実が判明、茨城大学に保管してある別の物を取りに行く間に午後の予定のStop3の観察地点に移動観察を再び、昼食後に戻るこの地に戻ることに急遽決定。
Stop 3は水戸市東前の住宅造成地(36°20′33″N,140°31′36″E)で、最終氷期の那珂川沿いの河成段丘である塩ヶ崎面とそれより下位の矢田面を分ける段丘崖である。矢田面は沖積低地と同じ高度にあり、両方の段丘面に鹿沼軽石が被っている。その後、大串貝塚ふれあい公園の縄文文化財センターの外で昼食を取った。
昼食後再びStop2に戻り、礫層や砂礫層の標本作製作業を汗だくになってやった。
Stop 4は(36°24′03″N,140°26′37″E)茨城大学校内の実験室で、地層のはぎ取り標本を活用した授業の体験,および簡易水路を用いた地層の堆積実験のプレゼンを受けた。
◆まとめ
はぎとり標本作業は簡単で自分でもできそうだが、一斗缶単位で接着剤を購入することになるので、できれば一度で使い切る方がいいということがわかった。この研修のスタイルを現職教員や教員養成などで行うことは大変有効な手段だと思う。何よりも今回の見学旅行では砂浜海岸と段丘堆積物の前で皆さんと討論し、地層の質感を残す地層のはぎ取り標本のおみやげを持って帰ることができた。案内者の個性が出た見学会で楽しかったです。大変お世話になり有り難うございました。
相原延光(神奈川県立新羽高校)
2013年地質の日(本部・各支部)
2013年の「地質の日」
2013年の「地質の日」に関連した日本地質学会の催しをご紹介します。
日本地質学会:本部イベント企画 4.15 更新
一般社団法人日本地質学会・一般社団法人応用地質学会 主催
街中ジオ散歩 in Tokyo「石神井川がつくる地形の移り変わりと地質」
日時:5月12日(日)10:00〜16:00 雨天決行(予定)
場所:東京都北区王子界隈(JR王子駅西側の台地上に発達する石神井川、逆川付近)
案内者:池田宏氏((公財)深田地質研究所,中山俊雄氏((独)防災科学技術研究所)
(お陰様で定員となりました.お申込み有難うございました.)
▶▶詳細はこちらから
日本地質学会 4.18 更新
一般社団法人日本地質学会 主催
第4回惑星地球フォトコンテスト 表彰式
日時:5月18日(日)14:15〜15:15(予定)
場所:北とぴあ 第2研修室(東京都北区王子1-11-1)
表彰式ならびに審査委員長による講評、入選作品の展示を行います。
▶▶入選作品はこちらから/
近畿支部 4.15 更新
日本地質学会近畿支部,大阪市立自然史博物館,地学団体研究会大阪支部
地球科学講演会「大阪平野の地盤環境と地盤災害」
日時:5月12日(日)14:00〜15:30
場所:大阪市立自然史博物館 講堂
講師:北田奈緒子氏(一般財団法人地域地盤環境研究所 主席研究員)
大阪平野は、周囲を山地に囲まれた大阪湾に面する海岸平野であり、淀川の河口デルタを中心とする低平地です。大阪平野には、約350万年前以降、断続的に堆積した砂や粘土粒子が厚く堆積し、基盤岩までの層厚は1000mを超える部分もあります。この厚い堆積物の堆積環境は、その時々の気候変化により大きく変わりました。大阪平野の地盤の特性は、その堆積環境の変化によるものです。1960年代の地盤沈下に始まり、近年では地震による液状化現象や長周期地震動などが問題となっていますが、これらの地盤災害の背景には地盤の特性が深く関わります。現在明らかになっている、私たちの大阪平野の地盤の問題点と課題について考えてみたいと思います。
申込:事前申し込みが必要です。往復はがきまたは電子メール(gyouji@mus-nh.city.osaka.jp)、博物館ホームページ(http://www.mus-nh.city.osaka.jp/)のいずれかでお申し込みください。地球科学講演会への参加希望、参加希望者全員の名前、年齢(学年)、往復はがきの場合には、復信はがきに返信用の宛名を明記してください。
申込締切:4月30日(火)
定員:200名(定員を超えた場合には抽選)
その他:手話通訳が必要な方は、申し込みの際にその旨を明記して下さい。
問い合わせ:大阪市立自然史博物館 第四紀研究室 石井陽子 Tel 06-6697-6221(代)、Fax 06-6697-6225
北海道支部「地質の日」記念展示 4.9 更新
「豊平川と共に—その恵みと災い—」
場所:北海道大学総合博物館3階「企画展示室」
日時:4月23日(火)〜6月2日(日)※月曜休館(祝日の場合は翌日休館)
時間:10:00〜16:00(6月以降は9:30〜16:30)
札幌の街は豊平川扇状地に建設され発展してきました。豊平川の恵みとしての河川水・地下水の利用と創成川など運河の開削、およびたびかさなる洪水の歴史を札幌の街の発展に沿って展示します。
組織:北海道大学総合博物館・日本地質学会北海道支部・日本応用地質学会北海道支部・北海道応用地質研究会・北海道地質調査業協会・(独) 産総研地質調査総合センター・(地独) 北海道立総合研究機構地質研究所・札幌市博物館活動センター
協力:(財)宇宙システム開発利用促進機構・北海道大学付属図書館・北海道大学文書館
後援:札幌市・札幌市教育委員会
<関連行事>
市民セミナー:5月11日(土)、26日(日)
市民地質巡検:「札幌のメムを訪ねる」5月18日(土)
http://www.museum.hokudai.ac.jp/news/article/192/
西日本支部
「身近に知る『くまもとの大地』
5月11日(土)10:00〜16:00
場所:熊本交通センター センターコート
主催:「地質の日」熊本実行委員会
共催:日本地質学会西日本支部,熊本大学,熊本市立熊本博物館,(財)阿蘇火山博物館,御船町恐竜博物館,天草市立御所浦白亜紀資料館,熊本県企画部文化企画課,熊本県地質調査業協会,阿蘇ジオパーク推進協議会,天草ジオパーク構想推進協議会 他
企画:おどろきの展示コーナー,わくわく体験コーナー,ジオパークコーナー,博物館・資料館情報コーナー など
三浦半島活断層調査会
一般社団法人日本地質学会 後援
地質情報普及講座 地質の日・記念観察会『深海から生まれた城ヶ島 』
5月11日(土)10:00〜15:00(小雨決行)
集合場所:城ヶ島バス停
申込締切:5/3 募集人数:50名
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//others-pic/2013jogashima-miura.gif
埼玉県立自然の博物館 4.22 更新
一般社団法人日本地質学会 共催
第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品展示
5月25日(土)〜6月9日(日)
博物館観覧料:一般200円(120円)、高校・大学生100円(60円):( )は団体観覧料
*中学生以下、障害者手帳をお持ちの方及び介助者1名は無料
*団体は20名以上
http://www.shizen.spec.ed.jp/
今後も、「地質の日」関連の情報を随時ご紹介していく予定です。お楽しみに。
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2013年5月-6月)
5-6月のイベント・特別展示カレンダー (2013/05/01〜2013/06/30)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
5-6月の特別展示
2013/05/01 現在
春の収蔵品展『石炭と海』 (福岡県 大牟田市石炭産業科学館)
期間:〜5/12(日)休館日:月曜日(月曜が休日の場合は会館、翌日休館)
場所:大牟田市石炭産業科学館 企画展示室
石炭の運搬には、今も昔も主に海が利用されています。江戸時代から明治時代にかけて三池炭は、瀬戸内海の塩田へ多く運ばれていましたが、その運搬を仲介したのは島原の石炭問屋でした。今回の収蔵品展では、昨年度に寄託された島原の石炭問屋山本家の歴史的資料を中心に展示します。主に幕末から明治時代半ばまでの、三池炭運搬の記録を見ることができます。またあわせて三池をはじめ長崎県池島炭鉱など、海の下を採掘した炭鉱の資料を紹介します。 入場料:企画展示は入場無料 常設展示見学の際は別途観覧料が必要
http://www.sekitan-omura.jp
ボラ(軽石)が降ってきた!霧島火山新燃岳の噴火とその恵み (茨城県 産業技術総合研究所 地質標本館)
期間:〜5/31(金)
場所:産業技術総合研究所 地質標本館
日本は火山国であり、その恵みをうけている私たちは、火山と一緒に生活していかなければなりません。そのためには、火山そのものを理解する必要があります。 2011年1月、数百年ぶりの軽石噴火を行った九州の霧島火山新燃岳は、私たちの社会生活に大きな影響を与えました。火山は、ひとたび噴火すると大変な災害を引き起こしますが、噴火のない時期には、私たちに恵みをもたらします。たとえば、霧島はその美しい景色から、日本で最初の国立公園に指定されており、最近では日本 ジオパークにも認定されました。本巡回展は、火山をより理解するため、新燃岳2011 年噴火はどのような噴火であったのかを学び、度重なる噴火でつくられた霧島火山の歴史やその恵みを理解する特別展示です。 ※関連イベント(地質標本館特別講演会)があります。
http://www.gsj.jp/Muse/eve_care/2013/kirishima/index.html
トピックコーナー フランスの化石 (徳島県 徳島県立博物館)
期間:〜6/30(日)
場所:徳島県立博物館 常設展示室 ラプラタ記念ホール内
ヨーロッパは、地質学や古生物学の発祥の地です。特にフランスは、様々な時代の地層が分布し、アンモナイトや二枚貝、巻貝などの化石が多く産出することで知られています。 2010年8月30日〜9月3日にフランス・ディジョン市でアンモナイトなどの化石に関する国際学会(第8回国際頭足類シンポジウム)が開催されました。当館学芸員も学会および、学会後に行われた地質見学会に参加しました。 このトピックコーナーでは、学芸員が、フランスの地質見学会で採集した化石を中心に、化石産地の写真を交えて紹介します。※「地質の日」関連イベント
http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/default.htm
第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品展示会 (埼玉県 埼玉県立自然の博物館)[日本地質学会 共催]
期間:5/25(土)〜6/9(日)
場所:埼玉県立自然の博物館 ※「地質の日」関連イベント
入選作品はこちらから
▶▶7-8月のイベントはこちら
5-6月のイベント
2013/04/24現在
日付
イベント
5/1
(水)
発見!サメの歯化石を掘ろう! (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館 1階ディスカバリールーム
時間:10:00〜12:00、13:00〜15:00
実際のサメの歯化石が埋め込まれたピースを発掘して探します。 ピースは1個500円 。参加費:大人1000円、4歳〜中学生500円 ※地質の日記念イベント
恐竜に食べられる!?恐竜迫力撮影会 (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館 恐竜ホール
時間:11:00〜15:00
タルボサウルスの顔面にせまる迫力ツーショットを撮影できます。 ※地質の日記念イベント
5/2
(木)
発見!サメの歯化石を掘ろう! (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館 1階ディスカバリールーム
時間:10:00〜12:00、13:00〜15:00
実際のサメの歯化石が埋め込まれたピースを発掘して探します。 ピースは1個500円 。参加費:大人1000円、4歳〜中学生500円 ※地質の日記念イベント
恐竜に食べられる!?恐竜迫力撮影会 (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館 恐竜ホール
時間:11:00〜15:00
タルボサウルスの顔面にせまる迫力ツーショットを撮影できます。 ※地質の日記念イベント
5/3
(金)
恐竜ナイトツアー −逃げたタルボを探せ!− (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館 恐竜ホール
時間:17:45〜19:00
閉館後の誰もいなくなった館内をめぐり、ナイトミュージアムの世界を体験しよう。参加費:大人1000円、4歳〜中学生500円
要電話予約、先着順、定員100名 ※地質の日記念イベント
発見!サメの歯化石を掘ろう! (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館 1階ディスカバリールーム
時間:10:00〜12:00、13:00〜15:00
実際のサメの歯化石が埋め込まれたピースを発掘して探します。 ピースは1個500円 。参加費:大人1000円、4歳〜中学生500円 ※地質の日記念イベント
恐竜に食べられる!?恐竜迫力撮影会 (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館 恐竜ホール
時間:11:00〜15:00
タルボサウルスの顔面にせまる迫力ツーショットを撮影できます。 ※地質の日記念イベント
5/4
(土)
石を割ってみよう (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館 1階入口前
時間:10:00〜16:00
専用の岩石ハンマーを使用して岩石を割る体験を行います。
恐竜ナイトツアー −逃げたタルボを探せ!− (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館 恐竜ホール
時間:17:45〜19:00
閉館後の誰もいなくなった館内をめぐり、ナイトミュージアムの世界を体験しよう。参加費:大人1000円、4歳〜中学生500円
要電話予約、先着順、定員100名 ※地質の日記念イベント
発見!サメの歯化石を掘ろう! (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館 1階ディスカバリールーム
時間:10:00〜12:00、13:00〜15:00
実際のサメの歯化石が埋め込まれたピースを発掘して探します。 ピースは1個500円 。参加費:大人1000円、4歳〜中学生500円 ※地質の日記念イベント
恐竜に食べられる!?恐竜迫力撮影会 (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館 恐竜ホール
時間:11:00〜15:00
タルボサウルスの顔面にせまる迫力ツーショットを撮影できます。 ※地質の日記念イベント
5/5
(日)
本物の化石にさわってみよう (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館 1階ホール
時間:11:00〜15:00
アンモナイトやクジラの骨などの本物の化石にさわってみましょう。
恐竜ナイトツアー −逃げたタルボを探せ!− (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館 恐竜ホール
時間:17:45〜19:00
閉館後の誰もいなくなった館内をめぐり、ナイトミュージアムの世界を体験しよう。参加費:大人1000円、4歳〜中学生500円
要電話予約、先着順、定員100名 ※地質の日記念イベント
発見!サメの歯化石を掘ろう! (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館 1階ディスカバリールーム
時間:10:00〜12:00、13:00〜15:00
実際のサメの歯化石が埋め込まれたピースを発掘して探します。 ピースは1個500円 。参加費:大人1000円、4歳〜中学生500円 ※地質の日記念イベント
恐竜に食べられる!?恐竜迫力撮影会 (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館 恐竜ホール
時間:11:00〜15:00
タルボサウルスの顔面にせまる迫力ツーショットを撮影できます。 ※地質の日記念イベント
5/6
(月)
発見!サメの歯化石を掘ろう! (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館 1階ディスカバリールーム
時間:10:00〜12:00、13:00〜15:00
実際のサメの歯化石が埋め込まれたピースを発掘して探します。 ピースは1個500円 。参加費:大人1000円、4歳〜中学生500円 ※地質の日記念イベント
恐竜に食べられる!?恐竜迫力撮影会 (静岡県 東海大学自然史博物館)
場所:東海大学自然史博物館 恐竜ホール
時間:11:00〜15:00
タルボサウルスの顔面にせまる迫力ツーショットを撮影できます。 ※地質の日記念イベント
5/7
(火)
▼
5/8
(水)
▼
5/9
(木)
▼
5/10
(金)
▼
5/11
(土)
銚子ジオパークを訪ねる (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:銚子市(現地集合・解散)
時間:10:00〜16:00
2012年に日本ジオパークに認定された銚子地域の地質を観察します。
事前申込必要:開催日の1ヵ月前から2週間前の間に上記URL(タイトルをクリック)より 定員:30名
5/12
(日)
たのしい地学体験教室「白亜紀の地層見学(勝浦)」 (徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島県勝浦郡勝浦町(現地集合・現地解散)
時間:13:00〜16:00
徳島県勝浦には白亜紀の地層が広く露出しており、たくさんの二枚貝や巻き貝の化石が産出します。また、ここからは四国唯一の恐竜化石も発見されています。この行事では、ハイキング気分で山道(片道5〜6km)を歩きながら、地層の観察をしていきます。
事前申込必要:往復はがきにて
※「地質の日」関連イベント
5/13
(月)
▼
5/14
(火)
▼
5/15
(水)
▼
5/16
(木)
▼
5/17
(金)
▼
5/18
(土)
▼
5/19
(日)
海部自然・文化セミナー「四国南東部の地形と地質 見どころ案内」 (徳島県 徳島県立博物館・海陽町立博物館)
場所:海陽町立博物館
時間:13:30〜15:00
徳島県海部郡から高知県室戸市〜安芸市にかけての地域には、さまざまな地形や地質のみどころが集中しています。このセミナーでは、それらのうち、那佐湾や宍喰浦の漣痕、室戸岬の隆起地形、室戸半島西岸の化石などについて、豊富な写真や図をつかってわかりやすく解説します。
※「地質の日」関連イベント
5/20
(月)
▼
5/21
(火)
▼
5/22
(水)
▼
5/23
(木)
▼
5/24
(金)
▼
5/25
(土)
▼
5/26
(日)
▼
5/27
(月)
▼
5/28
(火)
▼
5/29
(水)
▼
5/30
(木)
▼
5/31
(金)
▼
6/1
(土)
街なかの自然観察2 都の西北−台地と谷と坂道を歩く− (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:東京(小石川〜目白〜早稲田)(現地集合・解散)
時間:9:30〜16:30
小石川植物園や目白〜早稲田周辺の台地と谷、それらを結ぶ坂道を歩きます。
事前申込必要:開催日の1ヵ月前から2週間前の間に上記URL(タイトルをクリック)より 定員:15名
6/2
(日)
那賀川アドベンチャー「那賀川上流の地層見学」 (徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島県那賀町木頭坂州(現地集合・現地解散)
時間:13:00〜15:30
徳島県那賀川沿いには、秩父帯とよばれる地帯区分に含まれ、地質構造が複雑で、古生代、中生代などのさまざまな時代の地層が分布しています。そのため現在でもその成り立ちについては、さまざまな解釈がなされています。この行事では、主に三畳紀やジュラ紀の地層を見学し、それらの地層が堆積した環境や含まれる化石について解説します。最近、国の天然記念物に指定された「坂州不整合」についても解説します。
事前申込必要:往復はがきにて
※「地質の日」関連イベント
6/3
(月)
▼
6/4
(火)
▼
6/5
(水)
▼
6/6
(木)
▼
6/7
(金)
▼
6/8
(土)
▼
6/9
(日)
上総層群の化石採集会 (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:富津市(現地集合・解散)
時間:13:00〜15:30
約60万年前の上総層群から産出する貝化石等を採集します。
事前申込必要:開催日の1ヵ月前から2週間前の間に上記URL(タイトルをクリック)より 定員:30名
6/10
(月)
▼
6/11
(火)
▼
6/12
(水)
▼
6/13
(木)
▼
6/14
(金)
▼
6/15
(土)
▼
6/16
(日)
▼
6/17
(月)
▼
6/18
(火)
▼
6/19
(水)
▼
6/20
(木)
▼
6/21
(金)
▼
6/22
(土)
▼
6/23
(日)
▼
6/24
(月)
▼
6/25
(火)
▼
6/26
(水)
▼
6/27
(木)
▼
6/28
(金)
▼
6/29
(土)
▼
6/30
(日)
▼
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ 内のフォームま たはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2012年11月-12月)
11-12月のイベント・特別展示カレンダー (2012/11/01〜2012/12/31)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
11-12月の特別展示
2012/06/11 現在
▶▶2013年1-2月のイベントはこちら
11-12月のイベント
2012/06/11 現在
日付
イベント
11/01
(木)
▼
11/02
(金)
▼
11/03
(土)
鉱物さがし入門 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市自然史博物館 学習室、西尾市
時間:09:30〜15:30
ガーネット(ざくろ石)の産出地で三河地方の地質や鉱物の観察の仕方などを学びます。
定員:25名(小1以上:低学年要保護者同伴)
参加費:400円
申込:往復はがきにて。7/13締切
11/04
(日)
▼
11/05
(月)
▼
11/06
(火)
▼
11/07
(水)
▼
11/08
(木)
▼
11/09
(金)
▼
11/10
(土)
▼
11/11
(日)
▼
11/12
(月)
▼
11/13
(火)
▼
11/14
(水)
▼
11/15
(木)
▼
11/16
(金)
▼
11/17
(土)
▼
11/18
(日)
家族で行く化石採集 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:岐阜県瑞浪市(自然史博物館集合・解散バス使用)
時間:08:45〜16:30
1600万年前のサメ・貝化石などを掘り当てます。(雨天の場合は瑞浪市化石博物館で特別講義)
定員:40名(小学生以下要保護者同伴)
参加費:1000円
申込:往復はがきにて。7/13締切
11/19
(月)
▼
11/20
(火)
▼
11/21
(水)
▼
11/22
(木)
▼
11/23
(金)
▼
11/24
(土)
▼
11/25
(日)
▼
11/26
(月)
▼
11/27
(火)
▼
11/28
(水)
▼
11/29
(木)
▼
11/30
(金)
▼
12/01
(土)
▼
12/02
(日)
▼
12/03
(月)
▼
12/04
(火)
▼
12/05
(水)
▼
12/06
(木)
▼
12/07
(金)
▼
12/08
(土)
▼
12/09
(日)
▼
12/10
(月)
▼
12/11
(火)
▼
12/12
(水)
▼
12/13
(木)
▼
12/14
(金)
▼
12/15
(土)
▼
12/16
(日)
▼
12/17
(月)
▼
12/18
(火)
▼
12/19
(水)
▼
12/20
(木)
▼
12/21
(金)
▼
12/22
(土)
▼
12/23
(日)
▼
12/24
(月)
▼
12/25
(火)
▼
12/26
(水)
▼
12/27
(木)
▼
12/28
(金)
▼
12/29
(土)
▼
12/30
(日)
▼
12/31
(月)
▼
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ 内のフォームま たはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2013年1月-2月)
1-2月のイベント・特別展示カレンダー (2013/1/01〜2013/2/28)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
1-2月の特別展示
2012/12/03 現在
2011.3.11平成の大津波被害と博物館ー被災資料の再生をめざしてー (岩手県 岩手県立博物館)
期間:1/5(土)〜3/17(日)休館日:月曜日(月曜が休日の場合は会館、翌日休館)
場所:岩手県立博物館 特別展示室
http://h-am.jp/exhibition/index.html
飛騨地方の火山 (岐阜県 光記念館)(日本地質学会後援)
期間:2/27(水)〜12/10(火)10:00〜17:00休館日:水曜日(3/20、5/1.8/14、10/9、10/30、11/6、12/4は開館)
場所:岩手県立博物館 特別展示室
http://www.pref.iwate.jp/~hp0910/exhibition/exhib24/tsunami/tsunami.html
▶▶3-4月のイベントはこちら
1-2月のイベント
2012/12/03 現在
日付
イベント
1/1
(火)
▼
1/2
(水)
▼
1/3
(木)
▼
1/4
(金)
▼
1/5
(土)
2011.3.11平成の大津波被害と博物館 展示説明会 (岩手県 岩手県立博物館)
場所:岩手県立博物館 特別展示室
時間:14:30〜15:30
要入館料
1/6
(日)
▼
1/7
(月)
▼
1/8
(火)
▼
1/9
(水)
▼
1/10
(木)
▼
1/11
(金)
▼
1/12
(土)
▼
1/13
(日)
被災資料を次世代へ伝えていくために〜陸前高田被災資料デジタル化プロジェクトの活動について〜 (岩手県 岩手県立博物館)
場所:岩手県立博物館 当館講堂または教室
時間:13:30〜15:00
当日受付 聴講無料
1/14
(月)
▼
1/15
(火)
▼
1/16
(水)
▼
1/17
(木)
▼
1/18
(金)
▼
1/19
(土)
▼
1/20
(日)
▼
1/21
(月)
▼
1/22
(火)
▼
1/23
(水)
▼
1/24
(木)
▼
1/25
(金)
▼
1/26
(土)
▼
1/27
(日)
平成の大津波で被災した文化財の再生 (岩手県 岩手県立博物館)
場所:岩手県立博物館 当館講堂または教室
時間:13:30〜15:00
当日受付 聴講無料
1/28
(月)
▼
1/29
(火)
▼
1/30
(水)
▼
1/31
(木)
▼
2/1
(金)
▼
2/2
(土)
サザエの解剖ー軟体動物の形をさぐる (東京都 杉並区立科学館)
場所:杉並区立科学館 実験室
サザエを解剖しながら、巻貝の体の構造、機能、生活様式との関係を探ります。(進化的視点も含む予定)
講師:佐々木猛智(東京大学総合研究博物館)
事前申込:必要[往復ハガキ、Eメール、FAXにて、1月19日必着]
申込用紙のPDFはこちらから
2/3
(日)
▼
2/4
(月)
▼
2/5
(火)
▼
2/6
(水)
▼
2/7
(木)
民俗文化財の保護と災害ー陸前高田の漁撈用具の被災・再生を中心にー (岩手県 岩手県立博物館)
場所:岩手県立博物館 当館講堂または教室
時間:13:30〜15:00
当日受付 聴講無料
2/8
(金)
▼
2/9
(土)
▼
2/10
(日)
▼
2/11
(月)
▼
2/12
(火)
▼
2/13
(水)
▼
2/14
(木)
▼
2/15
(金)
▼
2/16
(土)
▼
2/17
(日)
▼
2/18
(月)
▼
2/19
(火)
▼
2/20
(水)
▼
2/21
(木)
▼
2/22
(金)
▼
2/23
(土)
絶滅腕足動物ー機能を追求した奇妙なデザイン (東京都 杉並区立科学館)
場所:杉並区立科学館 実験室
化石観察など実習を交えながら、腕足動物の形が生み出した巧みな生き様を紹介するとともに、その進化や絶滅についてお話しします。
事前申込:必要[往復ハガキ、Eメール、FAXにて、2月9日必着]
申込用紙のPDFはこちらから
2/24
(日)
江戸期の今泉集落と吉田家住宅 (岩手県 岩手県立博物館)
場所:岩手県立博物館 当館講堂または教室
時間:13:30〜15:00
当日受付 聴講無料
2/25
(月)
▼
2/26
(火)
▼
2/27
(水)
▼
2/28
(木)
▼
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ 内のフォームま たはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2013年7月-8月)
7-8月のイベント・特別展示カレンダー (2013/07/01〜2013/08/31)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
7-8月の特別展示
2013/06/28 現在
第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品展示会 (兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館)[日本地質学会 共催]
期間:7/6(土)〜8/4(日)
場所:兵庫県立人と自然の博物館
入選作品はこちらから
第28回特別企画展「はてな?なるほど!ザ・カタツムリ」(愛知県 豊橋市自然史博物館)
期間:7/12(金)〜9/1(日)
場所:豊橋市自然史博物館
http://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/
発掘!発見!1億年の時を越えて 〜福井県恐竜化石発掘25年記念〜 (福井県 福井県立恐竜博物館)
期間:7/12(金)〜10/14(日)
場所:福井県立恐竜博物館 3階特別展示室
福井、中国、タイ。25年の発掘の成果を一堂に公開。
http://www.dinosaur.pref.fukui.jp/
第43回企画展「甦れ!カミツキマッコウ 古代ゾウ〜関東に眠る太古の生きものたち〜」(群馬県 群馬県立自然史博物館)[日本地質学会 後援]
期間:7/13(土)〜9/1(日)
場所:群馬県立自然史博物館 企画展示室
http://www.gmnh.pref.gunma.jp/index.html
特別展「九州にゾウがいた時代」 (熊本県 御所浦白亜紀資料館)
期間:7/13(土)〜9/1(日)
場所:御所浦白亜紀資料館
かつて九州には、ゾウ、サイ、シカ、ワニなどが生息する野生の王国があり、大分県からはゾウの化石や保存の良いシカの化石が発見されています。天草地域からも、古代のゾウ(ナウマンゾウやステゴドン)などの哺乳類の化石が発見されています。かつては、有明海や八代海は、草木が生い茂り、河川の流れる陸地であった時代がありました。
http://www5.ocn.ne.jp/~g-museum/
微化石展−地層の中の小さな芸術品− (新潟県 新潟大学学術情報基盤機構旭町学術資料展示館)[日本地質学会 後援]
期間:7/17(水)〜8/30(金)
場所:新潟大学駅南キャンパス ときめいと
http://www.lib.niigata-u.ac.jp/tenjikan/
大牟田をとりまく鉄道展(福岡県 大牟田市石炭産業科学館)
期間:7/20(土)〜8/25(日)
場所:大牟田市石炭産業科学館 企画展示室
九州新幹線、JR九州鹿児島本線、西日本鉄道天神大牟田線、三井化学専用鉄道と、車両も性格も異なる4つの鉄道が走る大牟田。今回は、大牟田を取りまく身近で多彩な鉄道の、過去から現在までを紹介します。
http://www.sekitan-omuta.jp
▶▶9-10月のイベントはこちら
7-8月のイベント
2013/04/17 現在
日付
イベント
7/1
(月)
▼
7/2
(火)
▼
7/3
(水)
▼
7/4
(木)
▼
7/5
(金)
▼
7/6
(土)
▼
7/7
(日)
▼
7/8
(月)
▼
7/9
(火)
▼
7/10
(水)
▼
7/11
(木)
▼
7/12
(金)
▼
7/13
(土)
▼
7/14
(日)
▼
7/15
(月)
▼
7/16
(火)
▼
7/17
(水)
▼
7/18
(木)
▼
7/19
(金)
▼
7/20
(土)
▼
7/21
(日)
茨城県那珂湊の化石 (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:茨城県ひたちなか市(JR千葉駅前よりバス:実費負担)
時間:7:30〜17:30
茨城県那珂湊の平磯海岸で中生代白亜紀の化石をさがします。
事前申込必要:開催日の1ヵ月前から2週間前の間に上記URL(タイトルをクリック)より 定員:20名
たのしい地学体験教室「化石のレプリカをつくろう」 (徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島県立博物館 実習室
時間:13:30〜15:00
「レプリカ」とは、実物の資料から型どりをした実物にそっくりな複製品のことをいいます。この行事では、実物の恐竜の歯やアンモナイト、三葉虫の化石から型どりした凹型を使ってレプリカをつくります。
事前申込必要:往復はがきにて
7/22
(月)
▼
7/23
(火)
▼
7/24
(水)
▼
7/25
(木)
▼
7/26
(金)
▼
7/27
(土)
地形模型を作ろう (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館 研修室
時間:9:00〜16:00(7/27・8/3・8/18、連続講座)
地形模型の作り方を解説し、自分だけの模型を作ります。
事前申込必要:開催日の1ヵ月前から2週間前の間に上記URL(タイトルをクリック)より 定員:10名
7/28
(日)
エスカルゴ牧場へ行こう! (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:エスカルゴ牧場(三重県松坂市)
時間:9:00〜16:00
エスカルゴ牧場でエスカルゴの養殖を見学し、カタツムリの生態を学びます。参加費:2000円
事前申込必要:往復はがき 定員:25名(小学生以上、低学年は保護者同伴)
7/29
(月)
▼
7/30
(火)
▼
7/31
(水)
▼
8/1
(木)
▼
8/2
(金)
▼
8/3
(土)
地形模型を作ろう (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館 研修室
時間:9:00〜16:00(7/27・8/3・8/18、連続講座)
地形模型の作り方を解説し、自分だけの模型を作ります。
事前申込必要:開催日の1ヵ月前から2週間前の間に上記URL(タイトルをクリック)より 定員:10名
8/4
(日)
自然に学ぶものづくり〜カタツムリと住宅材料〜 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市自然史博物館
時間:14:00〜15:00
カタツムリに学ぶ汚れにくいタイルなど、自然をヒントにした住宅材料の開発について紹介します。
講師:井須紀文氏 定員:100名(小学3年生以上) 参加無料:電話等にてお申込ください
8/5
(月)
▼
8/6
(火)
▼
8/7
(水)
▼
8/8
(木)
▼
8/9
(金)
▼
8/10
(土)
化石の模型をつくろう (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館 研修室
時間:10:00〜15:00(8/10・8/17、連続講座)
アンモナイトや三葉虫、恐竜の歯など、いろいろな化石の模型づくりにチャレンジします。
事前申込必要:開催日の1ヵ月前から2週間前の間に上記URL(タイトルをクリック)より 定員:20名
海岸で石ころをひろおう (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:富津市(現地集合・解散)
時間:10:00〜15:00(8/10・8/17、連続講座)
富津市の海岸でいろいろな石ころを観察します。
事前申込必要:開催日の1ヵ月前から2週間前の間に上記URL(タイトルをクリック)より 定員:30名
貝化石を調べよう1(観察と採集) (徳島県 徳島県立博物館)
場所:高知県安田町唐浜(現地集合・現地解散)
時間:13:00〜15:00
8/11と2回セットの行事です。高知県安田町唐浜(とうのはま)は、新生代第三紀鮮新世後期(約200-300万年前)の貝化石がたくさん産出することで有名な場所です。地層があまり固くなっておらず、化石の保存状態もよいのが特徴です。10日は、現地で観察と採集を行います。
事前申込必要:往復はがきにて
8/11
(日)
貝化石を調べよう2(標本づくり) (徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島県立博物館 実習室
時間:13:00〜15:00
8/10と2回セットの行事です。高知県安田町唐浜(とうのはま)は、新生代第三紀鮮新世後期(約200-300万年前)の貝化石がたくさん産出することで有名な場所です。地層があまり固くなっておらず、化石の保存状態もよいのが特徴です。11日は、室内(徳島県立博物館)で標本に仕上げます。また、標本の名前の調べ方のコツについても伝授します。
事前申込必要:往復はがきにて
8/12
(月)
▼
8/13
(火)
▼
8/14
(水)
▼
8/15
(木)
▼
8/16
(金)
▼
8/17
(土)
化石の模型をつくろう (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館 研修室
時間:10:00〜12:00(8/10・8/17、連続講座)
アンモナイトや三葉虫、恐竜の歯など、いろいろな化石の模型づくりにチャレンジします。
事前申込必要:開催日の1ヵ月前から2週間前の間に上記URL(タイトルをクリック)より 定員:20名
8/18
(日)
地形模型を作ろう (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館 研修室
時間:9:00〜16:00(7/27・8/3・8/18、連続講座)
地形模型の作り方を解説し、自分だけの模型を作ります。
事前申込必要:開催日の1ヵ月前から2週間前の間に上記URL(タイトルをクリック)より 定員:10名
8/19
(月)
▼
8/20
(火)
▼
8/21
(水)
▼
8/22
(木)
▼
8/23
(金)
▼
8/24
(土)
▼
8/25
(日)
自然史トーク「郷土のカタツムリ」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市自然史博物館
時間:14:00〜15:00
豊橋やその周辺のカタツムリについて、昨年行った「カタツムリ調査隊」の結果をまじえて紹介します。
講師:西 浩孝氏 定員:40名(小学3年生以上) 参加無料:電話等にてお申込ください
8/26
(月)
▼
8/27
(火)
▼
8/28
(水)
▼
8/29
(木)
▼
8/30
(金)
▼
8/31
(土)
▼
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ 内のフォームま たはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2014年3月-4月)
3-4月のイベント・特別展示カレンダー (2014/3/01〜2014/4/30)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
3-4月の特別展示
2014/4/10 現在
ミニ・アンモナイト展 (徳島県 徳島県立博物館)
期間:〜4/6(日)
場所:徳島県立博物館 常設展示室
徳島県最南端に位置する海陽町竹ケ島周辺には,砂岩と泥岩の互層(くり返しからなる地層)が分布しており,さまざまな堆積構造や深海性の生痕化石(生物の活動の痕跡)がみられます。これらの地層は露出がよく,いろいろな角度から観察できる利点を持っており,その一部は「竹ケ島生痕化石」として町指定天然記念物に指定されています。しかし一般の方にとっては,必ずしも理解しやすい観察対象ではないと思われます。 このトピックコーナーでは,竹ケ島周辺の地層や生痕化石を,実物の標本と鮮明な写真をもとに紹介し,できるだけわかりやすく解説します。
http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/default.htm
企画展「教授を魅了した大地の結晶−北川隆司鉱物コレクション−」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
期間:4月19日(土)〜6月1日(日)9:00-16:30
場所:豊橋市自然史博物館 イントロホール他
故 北川隆司広島大学教授が収集した美しい鉱物標本を約200点展示。
http://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/03event/h26/index.html
▶▶2014年5-6月のイベントカレンダー
3-4月のイベント
2013/10/23 現在
日付
イベント
3/1
(土)
▼
3/2
(日)
花粉の見わけ方—わざとコツ1 (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館
時間:13:00〜15:30
画像映写器を導入し、花粉観察のコツを初学者にも解りやすく解説します(3/2, 3/9の2回連続講座)
開催日の1ヵ月前から2週間前までにWebサイトより要申込
3/3
(月)
▼
3/4
(火)
▼
3/5
(水)
▼
3/6
(木)
▼
3/7
(金)
▼
3/8
(土)
山を観るための技能講座3 (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館
時間:10:00〜15:00
地形図、地質図、空中写真、カシミールなどを読図して、山の形をその成り立ちから観る見方の理論と実習。観光に役立つ地形 地質学です(2/8, 2/22, 3/8の3回連続受講者を優先)
開催日の1ヵ月前から2週間前までにWebサイトより要申込
3/9
(日)
花粉の見わけ方—わざとコツ2 (千葉県 千葉県立中央博物館)
場所:千葉県立中央博物館
時間:13:00〜15:30
画像映写器を導入し、花粉観察のコツを初学者にも解りやすく解説します(3/2, 3/9の2回連続講座)
開催日の1ヵ月前から2週間前までにWebサイトより要申込
3/10
(月)
▼
3/11
(火)
▼
3/12
(水)
▼
3/13
(木)
▼
3/14
(金)
▼
3/15
(土)
▼
3/16
(日)
アンモナイト標本をつくろう (徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島県立博物館
時間:13:30〜15:30
アンモナイトは、カタツムリなどの巻き貝の仲間によく間違われますが、本当はタコやイカなどの頭足類という仲間に含まれます。普通に殻を見る限り、巻き貝にしか見えません。この行事ではアンモナイトの殻を削り、内部の構造が観察できる標本をつくっていきます。そして、なぜアンモナイトが巻き貝の仲間ではないのかという疑問を、いっしょに考えていきましょう!(大学生と一般は材料費300円が必要)
3月6日までに届くように往復はがきにて要申込:詳細はこちら
3/17
(月)
▼
3/18
(火)
▼
3/19
(水)
▼
3/20
(木)
▼
3/21
(金)
▼
3/22
(土)
▼
3/23
(日)
▼
3/24
(月)
▼
3/25
(火)
▼
3/26
(水)
▼
3/27
(木)
▼
3/28
(金)
▼
3/29
(土)
▼
3/30
(日)
▼
3/31
(月)
▼
4/1
(火)
▼
4/2
(水)
▼
4/3
(木)
▼
4/4
(金)
▼
4/5
(土)
▼
4/6
(日)
▼
4/7
(月)
▼
4/8
(火)
▼
4/9
(水)
▼
4/10
(木)
▼
4/11
(金)
▼
4/12
(土)
▼
4/13
(日)
▼
4/14
(月)
▼
4/15
(火)
▼
4/16
(水)
▼
4/17
(木)
▼
4/18
(金)
▼
4/19
(土)
▼
4/20
(日)
▼
4/21
(月)
▼
4/22
(火)
▼
4/23
(水)
▼
4/24
(木)
▼
4/25
(金)
▼
4/26
(土)
▼
4/27
(日)
▼
4/28
(月)
▼
4/29
(火)
▼
4/30
(水)
▼
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ 内のフォームま たはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
地質情報展2013みやぎ:地学オリンピック
地学オリンピックの紹介をしました
2013年9月15日(日)に行われた日本地質学会「小さな科学者のつどい」ならびに9月14(土)〜16(月)に開催された「地質情報展みやぎ」にて、地学オリンピックの紹介を行いました。
当委員会では今後とも地学オリンピックの活動に対して支援を行ってまいります。
地学オリンピックに関するご意見・ご感想などがございましたら、ぜひgeo-olympia(@)ml.geosociety.jp(@マークは半角にして下さい)までお寄せください。
今後とも、地学オリンピックへのご理解・ご協力のほど、よろしくお願い致します。
■ 展示した地学オリンピック紹介ポスター (PDF:約500KB)
教師巡検(2012大阪)
教師巡検(2012大阪)日本地質学会 第11回理科教員対象見学旅行
「大阪の津波碑と地盤沈下対策」
案内者:三田村宗樹(大阪市立大学)
参加者:飯島 力・池田 碩・石井陽子・磯野 清・岡田浩二・河村教一・北村正信・小幡喜一・小尾 靖・鈴木貴子・鈴木豊久・祖開康彰・竹内靖夫・楠田 隆・都築 宏・中條健次・氷高草多・藤井豊明・古野邦雄・細谷正夫・明海智里・矢島道子・湯川正敏・若林シゲミ(以上24名,50音順)
【案内者報告】
9名の非会員を含む計24名(教員15名,大学3名,博物館2名,一般4名)の参加を得,うす曇りの中の実施となった.JR難波駅13時集合後,道頓堀川沿いに防潮堤,橋の付替え,工業用水道などを見学し,大阪の発展の歴史と地盤沈下経緯の説明を行った.木津川との合流部に建つ大地震両川口津波記を見学,刻まれる記述と東北地方の津波被災との類似点などを話し合い,残される災害碑文を防災教育に生かす工夫の必要性を確認した.南海電鉄汐見橋線経由で木津川防潮水門を見学,落合上渡に乗船し,デルタ地帯の都市の一端を見学した.地盤沈下対策事業の一つである地盤嵩上げ事業が大阪市大正区・港区で行われた経緯を説明すると,他地域では地盤沈下対策として地盤嵩上げ事業の実施はないとのことである.地盤嵩上げが上下水道などを始めからやり直す事業であることを説明.その状況を認識し,参加者は東北地方沿岸部での地殻変動に伴う地表面沈下対策としての地盤嵩上げの難しさを認識した.大正区を甚兵衛渡で港区に移り,予定より1時間超過し,JR弁天町駅にて17時過ぎに無事解散となった.
【参加者感想】
デルタ地帯に発達した大都市大阪における水と市民生活との係わりについて,主に防災の視点に立ってたどる巡検であった.道頓堀川沿いでは,過度な地下水の揚水による地盤沈下の深刻さと,それに伴う防潮堤のかさ上げ工事の歴史を知ることができた.「大地震両川口津浪碑」には,安政南海地震(1854年)のときの津波来襲の有様が記され,後世の人々が津波被害から免れるようにとの思いが込められた碑文に強く胸を打たれた.大型船が航行できるように考案されたアーチ型の木津川防潮水門の開閉の様子を今回は見学できなかったが,またの機会に是非見てみたいと思った.
本巡検で,低平地に発達した大阪の街を水害からいかに守っていくか,行政や地域住民の取り組みの一端をうかがい知ることができた.また,防災教育の大切さも再認識させられた.こと防災に関しては,「備えあれば憂いなし」とはいかず「備えあっても憂いはつきない」という思いを強く抱いた.
最後に,残暑厳しい中,丁寧にご案内いただいた三田村さんに厚く御礼申し上げます.
(茨城県立麻生高等学校 飯島 力)
写真1 大地震両川口津波記での集合写真(飯島力氏撮影)
写真2 木津川防潮水門見学風景(石井陽子氏撮影)
教師巡検(2013仙台)
教師巡検(2013仙台)日本地質学会 第12回理科教員対象見学旅行
「仙台の大地の成り立ちを知る」
案内者:宮本 毅・蟹澤聰史・根本 潤・石渡 明
参加者:浅野俊雄・飯島 力・大友幸子・河合貴之・川辺文久・菊地 真・齋藤洋輔・佐治奈通子・佐藤勇輝・佐野郁雄・菅原 捷・竹下欣宏・中山俊雄・初貝隆行・船引彩子・細谷正夫・松山雅則・松山裕子・矢島道子(以上 地学教育19名) ほかアウトリーチ枠(市民参加)21名(計40名)
【案内者報告】
C班は,会場である東北大学近郊の後期中新世以降の火山噴出物を対象として,大会初日に実施された.年会では初めてのアウトリーチ巡検であったが,正確には地学教育と同時開催された.当日は天候にも恵まれ,晴天の中,巡検を実施することができた.しかし,その反面,徒歩での移動距離も長かったこともあり,熱中症が危惧されるなど,通常以上に気を遣う面も多くあった.
STOP1では三滝玄武岩の溶岩流・火砕岩互層の露頭において,溶岩流の構造の観察をした.STOP2では亀岡層中の高温型石英,竜の口層中の貝化石の産状観察とそれらの採取を行った.親子で参加した小学生らが,篩いで鉱物を熱心にさらう姿が多くみられ,最近ではあまり目にしていなかった1cm大のそろばん型の石英も採取された.昼食後,STOP3,4では広瀬川河岸に露出する広瀬川凝灰岩部層の大露頭と,火砕流によって埋まった埋没林を観察したが,層厚10 mほどの火砕流堆積物を前にして,約350万年前に現在の仙台市街を襲った噴火の大きさについて感心していた方が多くおられた.最後にSTOP5でプリニアン降下軽石である安達愛島軽石を観察し,運搬様式の相違により火山噴出物は多様な特徴をもつことが説明された.各露頭では,参加者から質問が活発にでるなど,大変よい巡検であったと思われるが,STOP6の第四紀火山の遠望観察を時間の都合でスキップすることとなってしまい,時間配分については配慮が必要であった.また,参加者の数に対して案内者の数が十分でなかったなど,通常よりも緻密な計画が必要であったと感じさせられた.
今回の参加者をみると,小中学生から専門家まで非常に多岐にわたったが,結果的に一般の方に向けた内容で説明が行われた.加えて,案内者数の不足から露頭を前にしての議論も活発に行えなかったなど,従来の地学教育での巡検を期待して参加された方には物足りなさを感じさせたかもしれない.そのためこのような異なる2つの枠組みで実施することには困難を感じるところである.しかし,案内者不足に対し,かわって地学教育枠参加者が,一般の方々へ説明を個々に行う場面も多くあった.これはアウトリーチ巡検としては大変意義深いことであり,案内者数が限られることを考慮すると,このような形式も有用であるとも思われた.
今回は初めての試みということもあり,検討すべき点が多く浮き彫りとなった.これらの課題については今後への申し送りをかねて別稿にてご報告する.
[宮本 毅(東北大学)]
写真1 広瀬川河畔大露頭(STOP3)を前に参加者・案内者集合しての記念撮影
写真2 郷六(STOP2)での高温型石英の採取風景
【参加者感想】
今回,小学3年生の息子と一緒に地質学会アウトリーチ巡検に初めて参加させていただき大変感謝致しております.私共のような全くの未経験者でも内容についていけるのかどうか,初めは心配しておりましたが,実際に仙台近郊の地層見学場所を自分たちの足で訪れて,大学の先生方の豊富な知識と経験による丁寧なご説明を伺っているうちに地質学上の専門的な話に自然と引き込まれ,地層に見られる幾つかの特徴が私たちに遠い昔仙台で起きた驚くべき環境変動を教えてくれる目印になるのだという事に深く興味を覚えました.
バスツアーとはいっても,車では入れない場所が多く,思ったより沢山歩いたため日頃の運動不足を痛感しつつ皆さんの歩幅についていくのがやっとでしたが,普段何気なく暮らしている仙台の大地の成り立ちを知るうえで,人間も生まれていない太古の時代に,今は全く姿の見えない火山が仙台の近郊に2つ存在しただろうと思われる火山性生成物の色々な形跡が見られることや,仙山線沿いにかつて玄武岩の石切り場が存在し,仙台城の石垣に用いられたという歴史,また石を運ぶのにかつては牛が使われ,その由来で「牛越橋」という地名が残っているという事など,新しい発見がいっぱいありました.
小学3年生の息子たちは,いかにも子供らしく地層というよりも地層の中に存在する化石や鉱石と,その採掘に興味をもち,研究者の方々に率いられて向かった先々で「どういう化石が取れるのか」という事をしきりに尋ねていました.そして郷六・化石の森に足を踏み入れる際は,さっそうとヘルメットをかぶり手にはお借りしたハンマーを握りしめて,わくわくした様子で靴が泥まみれになるのも気にせず目的地を目指して一生懸命な様子でした.そして川や地層の中に高温型石英と呼ばれる鉱石を見つけると嬉々として収集しておりました.そのあと向かった山の斜面で多くの貝化石を見つけ,夢中になって他の子供たちと一緒にハンマーで掘り出していました.
その後,広瀬川べりの20数メートルにそびえ立つ崖に見られる分厚い凝灰岩層,霊屋の化石林,愛島軽石層を見学し帰途につきましたが,全体を通じて地質学会の皆さんの日頃のご研究の一面に触れ,地質学の学術面,フィールド面,両方の面白さを教えていただき,親子共々大変に貴重な体験となりました.皆様本当にありがとうございました.
[阿部恵美子(仙台市在住:アウトリーチ枠)]
新しい体験を:第120年学術大会(2013年仙台大会):C班アウトリーチ巡検に参加して
久しぶりの暑い夏が戻ってきた.地学教育19名,アウトリーチ21名,退職者から小学生まで計40名が参加した.案内者は蟹澤聰史先生,宮本 毅先生など計6名の案内で始まった.
9時,東北大学萩ホール横の駐車場に集まり,仙台市街を構成する大地をたどっていった.まずは,800万年前の溶岩流三滝層を見学した.国道48号線から入った旧三滝温泉跡で溶岩が塊状から薄い板状の板状節理へと変化している様子が観察できた.また,旧温泉の土台部は集塊岩で硬くなっており滝となっていた.
その後,郷六へ向かった.ここは「化石の森」といわれ,青葉山トンネルの出口付近で,東北自動車道の仙台宮城インターチェンジの付近である.先ほど観察した三滝玄武岩に由来する礫層が観察される.礫岩層直下の凝灰岩に石英が含まれており,そろばん玉状の高温型石英を採集した.さらに,藪をかき分けていくと,竜の口層を見ることができた.ここではアカガイやハマグリなどの化石が取れた.
昼食をはさんで,午後は仙台市評定河原の広瀬川河岸大露頭を見た.対岸からの観察で細かいことはわからなかったが,厚さ8〜9mの350万年前の火砕流堆積物である軽石凝灰岩や向山層上部を見ることができた.ここから20分ほど歩いて,広瀬川下流の河床の化石林に行った.直径が140cmほどもある化石になった樹木の根元の部分が見える.セコイアやメタセコイアで,樹齢800年ほどである.仙台市天然記念物だが保護柵があったが,大部分は河原の土砂や礫に覆われ一時期は見えなくなったが,川の増水で現在は再び見えるようになった.
その後,青葉台からやや東に入った八木山治山の森に行った.ここでは,カミルトン角閃石を含んだ安達−愛島軽石層を見た.この火山灰は,カリウムが少なく,なかなか年代の測定が難しいが,今から5〜8万年前頃に降ったと思われる.
このように,今回の巡検は仙台の足元を800万年前から6〜8万年前とたどった.仙台の中心部から数十分の距離でこのような露頭に恵まれている.子どもたちが多かった理由は,今の子供たちにとって,自分の町の足元を見る機会はほとんどなくなっている.今回,アウトリーチで参加した小学生にとって非常にいい機会が持てたのではないかと思われる.
今回は,学会の巡検で40名の参加者であったが,もう少し人数を減らせば,もっとよく説明が聞けたのではないだろうか.また,交通手段で大型バスを利用したが,駐車の関係で現地まで入ることができず,街中を結構歩いた.もうちょっと,小回りが利く巡検であってもよい.
[地学教育委員会 浅野俊雄]
「仙台の大地の成り立ちを知る」 地学教育・アウトリーチ巡検の総括
1.はじめに
『地学教育・アウトリーチ巡検』は,今年の地質学会で初め て企画・実行されました.この種の企画は,一般市民やこれか らの若い人たちに地質学への関心を高めて頂くうえで,大変有 意義なものと考えます.しかし,企画・内容などを十分練って おかないと,効果が出るかどうか難しい面もあり,また,一般 市民にも参加して頂くという立場に立った場合の責任などを十 分に考えておくべきです.単に行うことが意義のあることだと いうだけでは成功しません.初めての企画を担当・実施して, 今後,実行する上で考えておくべき点を挙げましたので,将来 の参考にして頂ければと思います.
2.巡検案内書に関して
当初,地質学会主催の巡検案内書の書式が地質学雑誌に準拠 するということを,案内者自身が不覚にも知りませんでした. 案内者の一人(SK)は,何回か学会巡検を担当したことがあ りましたが,諸般の事情から査読も必要となったことを後で知 りました.そのため,脱稿後,編集者と執筆者との間で校正の 段階になってから,基本的なことで何度かの往復がありました. このことは,案内書を完璧なものにする上では意義のあること ですが,案内者に十分周知させておく必要があります.
一方で,これがもっとも基本的なことですが,従来の形式の 案内書は,あまりにも専門家向きであって,小学生や一般市民 にはとうてい理解しがたい内容になっています.そのため,今 回は開催の直前に「ジュニア版」を作り,基本的な事項だけを 簡略化して印刷,配布しました.アウトリーチの案内書は,小 学生も含めた一般の人が理解出来るように平易に作る必要があ ります.
3.参加者名簿と広報活動
アウトリーチ参加者名簿を手に入れてまず当惑したのは,大 学の先生,コンサルタントの技術者など地質や古生物のプロか ら,一般の教師,さらに小学生(3〜5年生),中学生,高校 生,それに父兄など,参加者の顔ぶれが非常に多彩であること です.このことは,2で述べた案内書の作成にも関わることで す.また,案内者が,どこを基準にして説明するかが非常に難 しいところです.できるだけ早めに参加者名簿を手に入れたいも のです.
また,募集する際の広報活動をどのように実施するのか,よ く考えておくべきであろうと思います.その方法は地域の「市 民センター便り」や市の広報誌など,あるいは一般紙などに掲 載されることが考えられます.案内者が個人的に「このような 行事がありますので,ぜひご参加下さい」と周辺の一般の方々 に知らせる手もあります.
4.募集上の留意点
参加者を募集するときに,「かなり長い距離を歩きます」な どの注意書きをしておかないと,普段の散歩程度と考えて参加 し,これではハードすぎるという事態も起こりかねませんので, そのあたりを十分注意しておくべきと考えます.CDで会員向 けに配布された巡検案内書には,基本的な注意事項が記載され ていますが,一般市民向けにもこういった注意事項を書くべき で,そのためにも参加者名簿は早めに欲しいものです.幸い, 今回の参加者はそういった心配はなく,一般の方々も非常に熱 心,かつ団体行動に慣れておられるようでした.
5.安全対策
最も注意すべき点は,交通事故,あるいは露頭での事故など です.一般市民をお客さんとして迎え入れる以上は,念には念 を入れておくべきです.そのため,バスから降りて露頭までの 移動に関しては,必ず信号機のある場所で横断する必要があり ます.また,足場が悪い露頭では,一般市民には遠慮願うこと も必要です.
今回は,その点に関してかなり慎重に考え,歩く距離を長く とり,足場の悪い露頭ではヘルメット着用をお願いしました (大学側で用意しました.また,硬い岩石を割る場合も考えて ゴーグルも用意したのですが,これは実際には使用するような 事例はありませんでした).救急箱の用意も必要です.また, 大会本部の巡検担当者にバスの前後を小型車で付き添ってもら い,不測の事態に備えました.院生諸君にも,あらかじめの露 頭整備(草刈,土壌のはぎ取り),資料作成,子供に喜ばれる 鉱物などのお土産準備,当日の交通整理などに多大な協力を願 いました.こういったことも留意すべき点です.
また,悪天候の場合はどうするか,小雨程度ならば決行でき ますが,今年の学会最終日のように台風直撃などがあった場合 にはどうするか,小中学生を含めた一般の人が参加する場合は, あらかじめ考えておかなければならないことです.途中で雨に なった場合は,理学部の自然史標本館の利用を考えていました が,その必要はありませんでした.
6.今回実施した感想・良かった点
幸い,今回の巡検は天候にも恵まれました.また,プロの参 加者の中には,小学生に自ら説明を買って出て下さったことも あり,いろいろな階層の人たちの集まり故の利点もありました. また,参加された小学生などは非常に熱心,かつ付き添いの親 御さんも熱心でした.一般の方々も熱心で,地質学への興味を 持たれている方ばかりだったので,案内者としては,たいへん 満足であったと考えています.しかしながら,時間の関係から 一部の予定を割愛せざるを得なかったこと,安全確保のため,歩 く距離がかなり長くなったことは反省すべき点だろうと思います. 完全にアウトリーチだけにして,学会会員と一般市民とを分 けることも可能ですが,一方で,このようにプロと市民とが一 体になることで,相互の交流を図ることも地質学の何たるかを 理解して頂くためには大きな意味があると思います.別々に巡 検を行えば,説明は簡単でしょうが,プロの間での議論を市民 が聞いて,「なるほど,そういったいろいろな考え方もあるのだ」 といった経験も重要なアウトリーチになるだろうと思います. 時間の関係で,参加者全員に対してのアンケートは実施でき ませんでしたが,できうる限りの感想などを頂ければと考えて います.これはぜひ実施し,次の機会に生かせるようにしたい ものです.また,巡検担当者が,企画の段階から学会運営の会 議に参加する機会を持つべきと考えます.それによって,さら に充実したアウトリーチ巡検ができると思います.
最後に,今回の巡検に積極的に参加し,実施を円滑にして頂 いた東北大学大学院理学研究科の院生諸君に感謝したいと思い ます.
[蟹澤聰史(東北大学)]
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2014年9月-10月)
9-10月のイベント・特別展示カレンダー (2014/9/01〜2014/10/31)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
9-10月の特別展示
2014/6/19 現在
しるしるFOSSIL−とちぎ化石発掘最前線− (栃木県 那須野が原博物館)
期間:〜9月28日(日)9:00-17:00
場所:那須野が原博物館
鬼怒川河川敷で発掘されたクジラの全身骨格を始め、栃木県内で2例しか見つかっていないアンモナイトなど、貴重な化石標本を多数展示します。
http://www2.city.nasushiobara.lg.jp/hakubutukan
スペイン 奇跡の恐竜たち (福井県 福井県立恐竜博物館)
期間:〜10月13日(月・祝)(ただし、9/10、9/24、10/8は休館)
場所:福井県立恐竜博物館3階 特別展示室
スペイン中央部に位置するカスティーリャ=ラ・マンチャ州立科学博物館が所蔵する門外不出の実物化石を用いて、約1億3000万年前のスペインを知っていただき、福井県から産出している恐竜との共通点などを解説します。羽毛の痕跡を残す肉食恐竜コンカベナトール(全長約6m)、歯を持つダチョウ型恐竜ペレカニミムス(全長約2m)を始め、スペイン国外では初めて公開される化石を展示します。
観覧料:一般 1,200円、高校・大学生 800円、小・中学生 600円、70歳以上の方 500円(上記料金で常設展もご覧いただけます)
URL: http://www.dinosaur.pref.fukui.jp/
平成26年度企画展「かごしまに生きた古生物たち」 (鹿児島県 鹿児島県立博物館)
期間:〜9月15日(月)
場所:鹿児島県立博物館
鹿児島県ではアンモナイトや恐竜の化石が続々と発見されています。これらの生物が生きていた頃の鹿児島はどんな様子だったのでしょうか。この企画展では甑島の恐竜化石の最新情報をはじめ,県内で見つかったさまざまな化石をもとに,鹿児島の古生物について紹介します。
https://www.pref.kagoshima.jp/bc05/hakubutsukan/event/extinctorganisms.html
第14回特別展「現代によみがえる生き物たち —種子島にゾウがいた頃—」 (鹿児島県 鹿児島大学総合研究博物館)
期間:9月4日(木)〜9月15日(月)
場所:鹿児島大学総合研究博物館
種子島西之表市住吉、形之山から産出したゾウやイシカワガエル、魚類、植物など極めて保存の良い化石を多数展示し、更新世の種子島と周辺海域の現代とは異なる古環境を再現します。形之山の化石群が本土で公開されるのはこれが初めてです。
http://www.museum.kagoshima-u.ac.jp/
▶▶2014年11-12月のイベントカレンダー
9-10月のイベント
2014/8/11 現在
日付
イベント
9/1
(月)
▼
9/2
(火)
▼
9/3
(水)
▼
9/4
(木)
▼
9/5
(金)
▼
9/6
(土)
▼
9/7
(日)
自然史トーク「東三河の化石」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市自然史博物館講堂
時間:14:00~15:00
東三河で見つかる化石について、実物にふれながら紹介します。
講師:吉川博章(学芸員)
定員40名(小学3年生以上)、参加費無料、要申込(先着順)
9/8
(月)
▼
9/9
(火)
▼
9/10
(水)
▼
9/11
(木)
▼
9/12
(金)
▼
9/13
(土)
とちぎの化石(更新世) (栃木県 那須野が原博物館)
場所:那須野が原博物館
時間:14:00〜15:30
講師:青島睦治(栃木県立博物館名誉学芸員)
参加費無料・定員50人(要、事前申し込み)
9/14
(日)
▼
9/15
(月)
▼
9/16
(火)
▼
9/17
(水)
▼
9/18
(木)
▼
9/19
(金)
▼
9/20
(土)
化石発掘隊木の葉石編 (栃木県 那須野が原博物館)
場所:栃木県那須塩原市木の葉化石園
時間:10:00〜13:00
化石の採集
参加費:入館料、発掘体験費用 ・定員:各回40人 ・申し込み:6月1日(日)より那須野が原博物館にて
自然科学ワークショップ 化石で探る海洋環境(1)特別講演会「海底下の世界−這い痕や巣穴からさぐる底生生物の生き様」 (東京都 杉並区立科学館)
場所:杉並区立科学館
時間:13:30〜16:00
生痕(生物の這い痕や巣穴など)の標本観察を交えながら、海底下に隠された生物の世界についてお話しします。
講師:清家弘治 先生(東京大学大気海洋研究所 助教)
定員40名、参加費無料、要申込(往復ハガキまたはE-mailにて)
9/21
(日)
▼
9/22
(月)
▼
9/23
(火)
▼
9/24
(水)
▼
9/25
(木)
▼
9/26
(金)
▼
9/27
(土)
自然科学ワークショップ 化石で探る海洋環境(2)特別講演会「微化石−小さな化石で探る太古の海」 (東京都 杉並区立科学館)
場所:杉並区立科学館
時間:13:30〜16:30
マリンスノーや深海底の泥の観察を交えながら、微化石に記録された太古の海の話をします。
講師:谷村好洋 先生(国立科学博物館 名誉研究員)
定員30名、参加費無料、要申込(往復ハガキまたはE-mailにて)
9/28
(日)
▼
9/29
(月)
▼
9/30
(火)
▼
10/1
(水)
▼
10/2
(木)
▼
10/3
(金)
▼
10/4
(土)
▼
10/5
(日)
シンポジウム「東三河のジオパークへ向けて」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市自然史博物館講堂
時間:10:00〜12:00
「ジオパーク」が地域社会にどのように貢献しているのか、認定に向けた取組事例を発表します。
演者:高橋 誠さん(静岡県文化・観光部 観光政策課)・田畑朝惠さん(伊豆半島ジオガイド協会会長)
定員60名(小学4年生以上)、参加費無料、要申込(先着順)
ジオツアー2「豊橋ジオサイトめぐり」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市ほか
時間:1300〜16:30
津波で移転した東観音寺跡など、豊橋近辺のジオサイトなどをめぐります。
定員40名(小学4年生以上)、参加費200円、要申込(9/18必着)
白亜紀前期のシルクロード—ヨーロッパと日本の恐竜をつなぐもの— (福井県 福井県立恐竜博物館)
場所:福井県恐竜博物館3階 講堂
時間:14:00〜15:30
講師:ヨウ・ハイルー(中国科学院古脊椎動物・古人類研究所教授)
スペインと日本の恐竜には共通性がみられます。両地域の恐竜をつなぐヒントは、白亜紀のシルクロード、すなわち中国にあります。中国の恐竜を中心に、ヨーロッパとアジアの恐竜の関係を紹介します。
聴講無料
10/6
(月)
▼
10/7
(火)
▼
10/8
(水)
▼
10/9
(木)
▼
10/10
(金)
▼
10/11
(土)
▼
10/12
(日)
▼
10/13
(月)
▼
10/14
(火)
▼
10/15
(水)
▼
10/16
(木)
▼
10/17
(金)
▼
10/18
(土)
▼
10/19
(日)
▼
10/20
(月)
▼
10/21
(火)
▼
10/22
(水)
▼
10/23
(木)
▼
10/24
(金)
▼
10/25
(土)
▼
10/26
(日)
名古屋大学出前授業 in 豊橋「植物プランクトンがクジラを進化させた?〜小さな化石から探る地球環境変動と生物進化〜」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市自然史博物館講堂
時間:14:00〜15:30
名古屋大学が取り組む第一線研究について紹介する一般市民向けサイエンス・トークです。
講師:須藤 斎(名古屋大学環境学研究科准教授)
定員40名(小学4年生以上)、参加費無料、要申込(先着順)
10/27
(月)
▼
10/28
(火)
▼
10/29
(水)
▼
10/30
(木)
▼
10/31
(金)
▼
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ 内のフォームま たはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2014年5月-6月)
5-6月のイベント・特別展示カレンダー (2014/5/01〜2014/6/30)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
5-6月の特別展示
2014/4/10 現在
企画展「教授を魅了した大地の結晶−北川隆司鉱物コレクション−」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
期間:〜6月1日(日)9:00-16:30
場所:豊橋市自然史博物館 イントロホール他
故 北川隆司広島大学教授が収集した美しい鉱物標本を約200点展示。
http://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/03event/h26/index.html
▶▶2014年7-8月のイベントカレンダー
5-6月のイベント
2014/4/10 現在
日付
イベント
5/1
(木)
▼
5/2
(金)
▼
5/3
(土)
▼
5/4
(日)
▼
5/5
(月)
▼
5/6
(火)
▼
5/7
(水)
▼
5/8
(木)
▼
5/9
(金)
▼
5/10
(土)
身近な地学1:川原の石—櫛田川— (三重県 三重県総合博物館)
場所:三重県多気郡多気町古江 櫛田川右岸河床
時間:13:30〜15:30
募集定員30名(多数の場合は抽選)、参加費無料
5/11
(日)
▼
5/12
(月)
▼
5/13
(火)
▼
5/14
(水)
▼
5/15
(木)
▼
5/16
(金)
▼
5/17
(土)
▼
5/18
(日)
▼
5/19
(月)
▼
5/20
(火)
▼
5/21
(水)
▼
5/22
(木)
▼
5/23
(金)
▼
5/24
(土)
▼
5/25
(日)
▼
5/26
(月)
▼
5/27
(火)
▼
5/28
(水)
▼
5/29
(木)
▼
5/30
(金)
▼
5/31
(土)
▼
6/1
(日)
▼
6/2
(月)
▼
6/3
(火)
▼
6/4
(水)
▼
6/5
(木)
▼
6/6
(金)
▼
6/7
(土)
▼
6/8
(日)
▼
6/9
(月)
▼
6/10
(火)
▼
6/11
(水)
▼
6/12
(木)
▼
6/13
(金)
▼
6/14
(土)
▼
6/15
(日)
▼
6/16
(月)
▼
6/17
(火)
▼
6/18
(水)
▼
6/19
(木)
▼
6/20
(金)
▼
6/21
(土)
▼
6/22
(日)
▼
6/23
(月)
▼
6/24
(火)
▼
6/25
(水)
▼
6/26
(木)
▼
6/27
(金)
▼
6/28
(土)
▼
6/29
(日)
▼
6/30
(月)
▼
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ 内のフォームま たはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
街中ジオ散歩in Tokyo2014
2014年 地質の日記念
街中ジオ散歩in Tokyo「下町低地の地盤沈下と水とくらし」徒歩見学会
毎年5月10日は地質の日です.この日は明治9年(1876),ライマンらによって日本で初めて広域的な地質図が作成された日です.また,明治11年(1878)のこの日は,地質の調査を扱う組織(内務省地理局地質課)が定められた日でもあります.近年この地質の日にちなんで様々な機関で記念イベントが開かれており,当学会でも,2012年より日本応用地質学会との共同主催で東京都内の徒歩見学会をご好評の中,開催しています.今回は江東区にて「地盤沈下と内部河川管理と暮らし」をテーマに実施いたします。皆様,奮ってご参加くださいますようお願いいたします.
主催:一般社団法人日本地質学会,一般社団法人日本応用地質学会
協力:東京都江東治水事務所水門管理センター
後援:一般社団法人東京都地質調査業協会(予定)
日時:2014年5月10日(土) 9時50分から17時 少雨決行(予定)
場所:東京都江東区清澄白河,住吉,東大島,南砂町界隈(仙台堀川,小名木川)
案内者:中山俊雄氏(元東京都土木技術支援・人材育成センター),小松原純子氏(産業技術総合研究所)
趣旨:身近な地質とその地質に由来した地形,それらを利用してきた先人から現在の私たちまでの営みを,春の清々しい空気の中でのんびり歩きながら,研究者からの興味深い説明を聞き,楽しく学ぼうという企画です.今回は,東京下町低地の地盤沈下とその対策としての内部河川管理の苦心,人々の暮らしをテーマに歩きます.
今回は東京都江東治水事務所水門管理センターさんのご協力を頂き、内部河川水を排水するポンプ場やパナマ運河のような閘門施設の見学もします。
キーワード:地形・地質・内水管理・地盤沈下
会費:一般2,000円, 小中学生500円(予定)保険代,入場料を含みます.当日お支払い下さい.昼食は各自でご用意下さい.
行程: 9:50 清澄公園西南口集合→東京都水門管理センター・排水機場→清澄庭園→扇橋閘門→住吉駅→(地下鉄利用)→西大島駅→小名木川→仙台堀川→東京都地盤沈下観測所→地盤沈下標柱→南砂町駅17:00解散(予定,天候等により順序、見学地を変更する場合が有ります)
募集人員:25名程度(定員になり次第締め切ります)
対象:一般
申込み:参加資格は特にありません.小学生以上の方でしたらどなたでもお申し込み頂けます.小中学生の方は保護者の方の同伴をお願いいたします.普及事業のため,一般からの申込を優先します.定員に余裕がある場合,会員の方にもご参加頂けます.申込みは下記のジオスクーリングネットまたは学会事務局までご連絡先を明記してお申し込み下さい.
申込先:ジオ・スクーリングネット(https://www.geo-schooling.jp/)または下記の学会事務局までfaxまたはメールで、御氏名,生年月日,住所,携帯等電話番号,メールアドレスを記して,お申し込み下さい.
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル6F
電話:03-5823-1150(代表) FAX:03-5823-1156
<main@geosociety.jp>
日本地質学会事務局 (地質の日担当 緒方)
情報の更新:学会HPおよびジオ・スクーリングネット,および学会事務局にて情報を更新いたします。ご確認下さい.
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2014年7月-8月)
7-8月のイベント・特別展示カレンダー (2014/7/01〜2014/8/31)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
7-8月の特別展示
2014/7/7 現在
第29回特別企画展「大地のめぐみとその魅力」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
期間:7月11日(金)〜8月31日(日)9:00-16:30
場所:豊橋市自然史博物館特別企画展示室
東三河の地形・地質の魅力や、さまざまな宝石等大地の恵みを紹介します。
http://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/03event/h26/tokuten/index.html
しるしるFOSSIL−とちぎ化石発掘最前線− (栃木県 那須野が原博物館)
期間:7月11日(金)〜9月28日(日)9:00-17:00
場所:那須野が原博物館
鬼怒川河川敷で発掘されたクジラの全身骨格を始め、栃木県内で2例しか見つかっていないアンモナイトなど、貴重な化石標本を多数展示します。
http://www2.city.nasushiobara.lg.jp/hakubutukan
スペイン 奇跡の恐竜たち (福井県 福井県立恐竜博物館)
期間:7月11日(金)〜10月13日(月・祝)(ただし、9/10、9/24、10/8は休館)
場所:福井県立恐竜博物館3階 特別展示室
スペイン中央部に位置するカスティーリャ=ラ・マンチャ州立科学博物館が所蔵する門外不出の実物化石を用いて、約1億3000万年前のスペインを知っていただき、福井県から産出している恐竜との共通点などを解説します。羽毛の痕跡を残す肉食恐竜コンカベナトール(全長約6m)、歯を持つダチョウ型恐竜ペレカニミムス(全長約2m)を始め、スペイン国外では初めて公開される化石を展示します。
観覧料:一般 1,200円、高校・大学生 800円、小・中学生 600円、70歳以上の方 500円(上記料金で常設展もご覧いただけます)
URL: http://www.dinosaur.pref.fukui.jp/
新潟のジオパーク展 −糸魚川と佐渡の魅力− (新潟県 新潟大学旭町学術資料展示館,理学部,大学院自然科学研究科)
[日本地質学会ほか後援]
期間:7月12日(土)〜8月29日(金)
会場:新潟大学駅南キャンパス ときめいと
新潟県内のジオパークとしては,糸魚川世界ジオパークと佐渡ジオパークの2つが認定されている。この企画展では,新潟のジオパークの魅力ならびに新潟大学が行っているさまざまな取組を紹介する。また,子どもたちを対象にした体験イベントおよびふれあいトークを行う。さらに,会期中に新潟−糸魚川−佐渡をつなぐスタンプラリーを実施する。
http://www1.niigata-u.ac.jp/tokimate/
変わりゆく鉄道の旅&ミニSLの感動をありがとう 小澤年満さん追悼企画展 (福岡県 大牟田市石炭産業科学館)
期間:7月19日(土)〜8月31日(日)
場所:大牟田市石炭産業科学館企画展示室
石炭館では、毎年夏の企画展として鉄道展を開催しております。今年は時代の変化に伴い姿を変えつつある鉄道の旅について、懐かしい光景も含めて多彩な写真や記念グッズ等を通して紹介します。追悼企画としまして、長年にわたり鉄道展でミニSLを運転していただいてきた蒸気機関車ファンとして知られた故小澤年満さんの写真展も行います。
http://www.sekitan-omuta.jp/
▶▶2014年9-10月のイベントカレンダー
7-8月のイベント
2014/6/19 現在
日付
イベント
7/1
(火)
▼
7/2
(水)
▼
7/3
(木)
▼
7/4
(金)
▼
7/5
(土)
▼
7/6
(日)
化石発掘隊木の葉石編 (栃木県 那須野が原博物館)
場所:栃木県那須塩原市木の葉化石園
時間:10:00〜13:00
化石の採集
参加費:入館料、発掘体験費用 ・定員:各回40人 ・申し込み:6月1日(日)より那須野が原博物館にて
7/7
(月)
▼
7/8
(火)
▼
7/9
(水)
▼
7/10
(木)
▼
7/11
(金)
▼
7/12
(土)
▼
7/13
(日)
スペインの恐竜たち—ドン・キホーテの見た夢— (福井県 福井県立恐竜博物館)
場所:福井県恐竜博物館3階 講堂
時間:14:00〜
講師:ホセ・ルイス・サンス(マドリード自治大学理学部教授)、フランシスコ・オルテガ(スペイン国立通信大学理学部教授)
スペイン中央部に位置するカスティーリャ=ラ・マンチャ州に分布する前期白亜紀の地層から発見された奇跡の恐竜たちを中心に紹介します。
聴講無料
7/14
(月)
▼
7/15
(火)
▼
7/16
(水)
▼
7/17
(木)
▼
7/18
(金)
▼
7/19
(土)
化石発掘隊in葛生 (栃木県 那須野が原博物館)
場所:栃木県佐野市葛生
時間:8:30〜15:00
化石の採集・クリーニング・名前調べ
参加費無料・定員 小学3年生以上30名・申し込み 6月1日(日)より那須野が原博物館にて
7/20
(日)
とちぎの化石(中・古生代) (栃木県 那須野が原博物館)
場所:那須野が原博物館
時間:14:00〜15:30
講師:奥村よほ子(佐野市葛生化石館学芸員)
参加費無料・定員50人(要、事前申し込み)
化石発掘隊in葛生 (栃木県 那須野が原博物館)
場所:栃木県佐野市葛生
時間:10:00〜12:00
化石の採集・クリーニング・名前調べ
参加費無料・定員 小学3年生以上30名・申し込み 6月1日(日)より那須野が原博物館にて
7/21
(月)
▼
7/22
(火)
▼
7/23
(水)
▼
7/24
(木)
▼
7/25
(金)
▼
7/26
(土)
化石発掘隊入門編 (栃木県 那須野が原博物館)
場所:栃木県那珂川町
時間:10:00〜12:00
化石の採集・クリーニング・名前調べ
参加費無料・定員 小学生以上100名・申し込み 6月1日(日)より那須野が原博物館にて
7/27
(日)
化石発掘隊入門編 (栃木県 那須野が原博物館)
場所:栃木県那珂川町
時間:9:30〜16:00
化石の採集・クリーニング・名前調べ
参加費無料・定員 小学生以上100名・申し込み 6月1日(日)より那須野が原博物館にて
7/28
(月)
▼
7/29
(火)
▼
7/30
(水)
ジオツアー1「海から陸から 三河湾周遊ツアー」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市、田原市
時間:8:45〜15:30
海上と陸地から豊橋平野、干潟、三河湾の成り立ちなど、三河湾周辺の地形・地質について学びます。
定員25名(小学4年生以上)、参加費100円、要申込(7/17必着)
7/31
(木)
▼
8/1
(金)
学習教室「化石さがし入門」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:田原市、豊橋市自然史博物館
時間:9:00〜15:00
化石産地を見学したり、カニや貝の化石を砂の中から探したりして 化石の調べ方を学びます。
定員25名(小学4年生〜中学3年生)、参加費500円、要申込(7/17必着)
8/2
(土)
化石発掘隊初級編(1) (栃木県 那須野が原博物館)
場所:栃木県那須烏山市
時間:10:00〜12:00
化石の採集・クリーニング・名前調べ
参加費無料・定員 小学3年生以上60名・申し込み 6月1日(日)より那須野が原博物館にて
8/3
(日)
化石発掘隊初級編(1) (栃木県 那須野が原博物館)
場所:栃木県那須烏山市
時間:午後(時間未定)
化石の採集・クリーニング・名前調べ
参加費無料・定員 小学3年生以上60名・申し込み 6月1日(日)より那須野が原博物館にて
8/4
(月)
▼
8/5
(火)
▼
8/6
(水)
▼
8/7
(木)
▼
8/8
(金)
▼
8/9
(土)
とちぎの化石(中新世) (栃木県 那須野が原博物館)
場所:那須野が原博物館
時間:14:00〜15:30
講師:柏村勇二(栃木県立博物館特別研究員)
参加費無料・定員50人(要、事前申し込み)
8/10
(日)
▼
8/11
(月)
▼
8/12
(火)
▼
8/13
(水)
▼
8/14
(木)
▼
8/15
(金)
▼
8/16
(土)
化石発掘隊初級編(2) (栃木県 那須野が原博物館)
場所:栃木県那須塩原市
時間:9:00〜12:00
化石の採集・クリーニング・名前調べ
参加費無料・定員 小学3年生以上60名・申し込み 6月1日(日)より那須野が原博物館にて
8/17
(日)
8/18
(月)
▼
8/19
(火)
▼
8/20
(水)
▼
8/21
(木)
▼
8/22
(金)
▼
8/23
(土)
化石発掘隊上級編 (栃木県 那須野が原博物館)
場所:栃木県那須烏山市
時間:9:00〜15:00
化石の採集・クリーニング・名前調べ
参加費無料・定員小学5年生以上60名・申し込み 6月1日(日)より那須野が原博物館にて
8/24
(日)
自然史トーク「東三河の大地のめぐみ」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市自然史博物館講堂
時間:14:00〜15:00
東三河の鉱山や温泉など、大地のめぐみを紹介します。
講師:加藤千茶子 (主任学芸員)
定員40名(小学3年生以上)、参加費無料、要申込(先着順)
化石発掘隊初級編(2) (栃木県 那須野が原博物館)
場所:栃木県那須塩原市
時間:(時間未定)
化石の採集・クリーニング・名前調べ
参加費無料・定員 小学3年生以上60名・申し込み 6月1日(日)より那須野が原博物館にて
化石発掘隊上級編 (栃木県 那須野が原博物館)
場所:栃木県那須烏山市
時間:(時間未定)
化石の採集・クリーニング・名前調べ
参加費無料・定員小学5年生以上60名・申し込み 6月1日(日)より那須野が原博物館にて
スペインにも恐竜が?! (福井県 福井県立恐竜博物館)
場所:福井県恐竜博物館2階 研修室
時間:13:00〜14:30
講師:柴田正輝(福井県立大学恐竜学研究所講師・福井県立恐竜博物館研究員)
特別展で展示されている標本を中心にスペインの恐竜について紹介します。
聴講無料
8/25
(月)
▼
8/26
(火)
▼
8/27
(水)
▼
8/28
(木)
▼
8/29
(金)
▼
8/30
(土)
▼
8/31
(日)
▼
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ 内のフォームま たはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2014年11月-12月)
11-12月のイベント・特別展示カレンダー (2014/11/01〜2014/12/31)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
11-12月の特別展示
2014/11/4 現在
特別展「地の宝〜百年を超える眠りからさめる旧制三高・京都帝大時代の秘蔵鉱物コレクション」 (京都府 京都大学総合博物館)
期間:〜11月30日(日) 9:30-16:30[休館日:月・火(平日祝日に関わらず)]
場所:京都大学総合博物館
今100年を超える眠りからさめる秘蔵コレクションを展示し、博物館における鉱物標本のあり方を考えることにしました。
http://www.museum.kyoto-u.ac.jp/
企画展「干支展 アンモーンの石」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
期間:12月20日(土)〜2015年1月18日(日) 9:00-16:30
場所:豊橋市自然史博物館 イントロホール
ヒツジの角を持った古代ギリシアの神アンモーンにちなみアンモナイトの展示を行います。
http://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/03event/h26/index.html
▶▶2015年1-2月のイベントカレンダー
11-12月のイベント
2014/4/10 現在
日付
イベント
11/1
(土)
▼
11/2
(日)
▼
11/3
(月)
▼
11/4
(火)
▼
11/5
(水)
▼
11/6
(木)
▼
11/7
(金)
▼
11/8
(土)
▼
11/9
(日)
ジオツアー3「津具の里に鉱山跡をたどる」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:設楽町ほか
時間:8:45〜16:30
武田信玄の隠し金山と言われた鉱山跡(信玄坑)などをめぐります。
定員25名(小学4年生以上)、参加費800円、要申込(10/23必着)
11/10
(月)
▼
11/11
(火)
▼
11/12
(水)
▼
11/13
(木)
▼
11/14
(金)
▼
11/15
(土)
学習教室「家族で行く化石採集」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:瑞浪市、豊橋市自然史博物館
時間:8:45〜16:30
1600万年前のサメ・貝化石などを掘り当てます。
定員40名(小学生以下は保護者同伴)、参加費1000円、要申込(10/30必着)
11/16
(日)
▼
11/17
(月)
▼
11/18
(火)
▼
11/19
(水)
▼
11/20
(木)
▼
11/21
(金)
▼
11/22
(土)
▼
11/23
(日)
▼
11/24
(月)
名古屋大学出前授業 in 豊橋「炭素を用いた年代測定法」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市自然史博物館講堂
時間:14:00〜15:30
人体にもたくさん含まれている身近な元素である「炭素」を用いた年代測定の紹介をします。
講師:中村俊夫さん(名古屋大学年代測定総合研究センター教授)
定員40名(小学4年生以上)、参加費無料、要申込(先着順)
11/25
(火)
▼
11/26
(水)
▼
11/27
(木)
▼
11/28
(金)
▼
11/29
(土)
▼
11/30
(日)
▼
12/1
(月)
▼
12/2
(火)
▼
12/3
(水)
▼
12/4
(木)
▼
12/5
(金)
▼
12/6
(土)
▼
12/7
(日)
▼
12/8
(月)
▼
12/9
(火)
▼
12/10
(水)
▼
12/11
(木)
▼
12/12
(金)
▼
12/13
(土)
▼
12/14
(日)
▼
12/15
(月)
▼
12/16
(火)
▼
12/17
(水)
▼
12/18
(木)
▼
12/19
(金)
▼
12/20
(土)
▼
12/21
(日)
▼
12/22
(月)
▼
12/23
(火)
▼
12/24
(水)
▼
12/25
(木)
▼
12/26
(金)
▼
12/27
(土)
▼
12/28
(日)
▼
12/29
(月)
▼
12/30
(火)
▼
12/31
(水)
▼
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ 内のフォームま たはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2015年1月-2月)
1-2月のイベント・特別展示カレンダー (2015/01/01〜2015/02/28)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
1-2月の特別展示
2014/4/10 現在
企画展「干支展 アンモーンの石」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
期間:〜1月18日(日) 9:00-16:30
場所:豊橋市自然史博物館 イントロホール
ヒツジの角を持った古代ギリシアの神アンモーンにちなみアンモナイトの展示を行います。
http://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/03event/h26/index.html
▶▶2015年3-4月のイベントカレンダー
1-2月のイベント
2014/4/10 現在
日付
イベント
1/1
(木)
▼
1/2
(金)
▼
1/3
(土)
▼
1/4
(日)
▼
1/5
(月)
▼
1/6
(火)
▼
1/7
(水)
▼
1/8
(木)
▼
1/9
(金)
▼
1/10
(土)
▼
1/11
(日)
▼
1/12
(月)
▼
1/13
(火)
▼
1/14
(水)
▼
1/15
(木)
▼
1/16
(金)
▼
1/17
(土)
▼
1/18
(日)
▼
1/19
(月)
▼
1/20
(火)
▼
1/21
(水)
▼
1/22
(木)
▼
1/23
(金)
▼
1/24
(土)
▼
1/25
(日)
▼
1/26
(月)
▼
1/27
(火)
▼
1/28
(水)
▼
1/29
(木)
▼
1/30
(金)
▼
1/31
(土)
▼
2/1
(日)
日本古生物学会第164回例会 普及講演 「生命38億年の歴史を読む」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市自然史博物館特別企画展示室
時間:13:30〜15:00
生物はなぜこれほど多様なのかという問いに古生物学がどう答えてきたかを紹介します。
講師:渡辺政隆さん(筑波大学教授)
定員40名(小学4年生以上)、参加費無料、要申込(先着順)
2/2
(月)
▼
2/3
(火)
▼
2/4
(水)
▼
2/5
(木)
▼
2/6
(金)
▼
2/7
(土)
▼
2/8
(日)
▼
2/9
(月)
▼
2/10
(火)
▼
2/11
(水)
▼
2/12
(木)
▼
2/13
(金)
▼
2/14
(土)
▼
2/15
(日)
▼
2/16
(月)
▼
2/17
(火)
▼
2/18
(水)
▼
2/19
(木)
▼
2/20
(金)
▼
2/21
(土)
▼
2/22
(日)
▼
2/23
(月)
▼
2/24
(火)
▼
2/25
(水)
▼
2/26
(木)
▼
2/27
(金)
▼
2/28
(土)
▼
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ 内のフォームま たはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2015年3月-4月)
3-4月のイベント・特別展示カレンダー (2015/03/01〜2015/04/30)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
▶▶2015年5-6月のイベントカレンダー
3-4月の特別展示
2015/4/27 現在
春の特別展「地震・噴火・洪水−災害復興の3万年史−」 (兵庫県 県立考古博物館)
期間:4/18(土)〜6/21(日)月曜休館(祝休日の場合は翌平日、5/4は開館、5/7は休館)
場所::兵庫県立考古博物館 特別展示室
兵庫県内で発生した自然災害と人間の歴史的な関係を、遺跡からの出土品によって紹介し、将来発生する災害に備えて私たちは何が出来るのか考えるきっかけを提示します
http://www.hyogo-koukohaku.jp/
平成26年度春期特別展「天変地異〜平塚周辺の自然災害」 (神奈川県 平塚市博物館)
期間:3/11(水)〜5/10(日)休館日:月曜日(5/4は開館)
場所:平塚市博物館
平塚周辺で発生した自然災害に、博物館の自然・人文両分野の目から光をあて、その実態を紹介します。
http://www.hirahaku.jp/
地質の日記念展示 札幌の過去に見る洪水・土砂災害(札幌市資料館)
期間:4/28(火)〜5/31(日)休館日:月曜日(GW中の休館は7日のみ)
場所:札幌市資料館1階
洪水災害を中心に札幌周辺の自然災害について展示・解説し,自然災害への備えの重要性を喚起します。
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
▶▶2015年5-6月のイベントカレンダー
3-4月のイベント
2015/2/26 現在
日付
イベント
3/1
(日)
ジオツアー4「鳳来寺山の基盤をめぐる」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:新城市ほか
時間:8:45〜16:30
馬背岩や寒狭峡など鳳来寺山を形づくる地形、地質をめぐります。
定員25名(小学4年生以上)、参加費500円、要申込(2/12必着)
3/2
(月)
▼
3/3
(火)
▼
3/4
(水)
▼
3/5
(木)
▼
3/6
(金)
▼
3/7
(土)
▼
3/8
(日)
▼
3/9
(月)
▼
3/10
(火)
▼
3/11
(水)
▼
3/12
(木)
▼
3/13
(金)
▼
3/14
(土)
▼
3/15
(日)
▼
3/16
(月)
▼
3/17
(火)
▼
3/18
(水)
▼
3/19
(木)
▼
3/20
(金)
▼
3/21
(土)
▼
3/22
(日)
記念講演会「元禄地震と平塚」 (神奈川県 平塚市博物館)
場所:平塚市博物館 講堂
時間:14:00〜15:30
講師:下重 清氏(東海大学文学部非常勤講師)
参加:自由、先着80名
3/23
(月)
▼
3/24
(火)
▼
3/25
(水)
▼
3/26
(木)
▼
3/27
(金)
▼
3/28
(土)
記念講演会「歴史に学ぶ防災論:関東大震災は語る」 (神奈川県 平塚市博物館)
場所:平塚市博物館 講堂
時間:14:00〜15:30
講師:武村雅之氏(名古屋大学減災連携研究センター教授)
参加:自由、先着80名
3/29
(日)
自然史トーク「地球の歴史をさぐる探検」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市自然史博物館講堂
時間:14:00〜15:00
ロシア、中国、インドネシア、ネパール、日本などの調査から地球環境の変遷をたどります。
講師:松岡敬二(当館館長)
定員40名(小学3年生以上)、参加費無料、要申込(先着順)
3/30
(月)
▼
3/31
(火)
▼
4/1
(水)
▼
4/2
(木)
▼
4/3
(金)
▼
4/4
(土)
▼
4/5
(日)
野外見学会「関東大震災の記念碑をたどる」 (神奈川県 平塚市博物館)
(雨天時は平塚市博物館講堂にて解説)
時間:13:00〜16:00
往復はがきにて要申込、3/20消印有効、定員30名。
4/6
(月)
▼
4/7
(火)
▼
4/8
(水)
▼
4/9
(木)
▼
4/10
(金)
▼
4/11
(土)
野外見学会「巡って学ぶ自然災害と微地形」 (神奈川県 平塚市博物館)
場所:平塚駅〜撫子原〜上平塚(雨天時は平塚市博物館講堂にて解説)
時間:13:00〜16:00
往復はがきにて要申込、3/20消印有効、定員30名。
4/12
(日)
▼
4/13
(月)
▼
4/14
(火)
▼
4/15
(水)
▼
4/16
(木)
▼
4/17
(金)
▼
4/18
(土)
▼
4/19
(日)
シンポジウム「平塚周辺の自然災害を考える」 (神奈川県 平塚市博物館)
場所:平塚市博物館 講堂
時間:13:00〜16:00
講師:博物館学芸員
自由、定員80名。
4/20
(月)
▼
4/21
(火)
▼
4/22
(水)
▼
4/23
(木)
▼
4/24
(金)
▼
4/25
(土)
防災講演会「東日本大震災以降の平塚市の災害対策」 (神奈川県 平塚市博物館)
場所:平塚市博物館 講堂
時間:14:30〜16:00
講師:平塚市災害対策課職員
参加:自由、先着80名
4/26
(日)
▼
4/27
(月)
▼
4/28
(火)
▼
4/29
(水)
▼
4/30
(木)
▼
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ 内のフォームま たはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2015年5月-6月)
5-6月のイベント・特別展示カレンダー (2015/05/01〜2015/06/30)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
5-6月の特別展示
2015/6/25 現在
春の特別展「地震・噴火・洪水−災害復興の3万年史−」 (兵庫県 県立考古博物館)
期間:4/18(土)〜6/21(日)月曜休館(祝休日の場合は翌平日、5/4は開館、5/7は休館)
場所::兵庫県立考古博物館 特別展示室
兵庫県内で発生した自然災害と人間の歴史的な関係を、遺跡からの出土品によって紹介し、将来発生する災害に備えて私たちは何が出来るのか考えるきっかけを提示します
http://www.hyogo-koukohaku.jp/
平成26年度春期特別展「天変地異〜平塚周辺の自然災害」 (神奈川県 平塚市博物館)
期間:〜5/10(日)休館日:月曜日(5/4は開館)
場所:平塚市博物館
平塚周辺で発生した自然災害に、博物館の自然・人文両分野の目から光をあて、その実態を紹介します。
http://www.hirahaku.jp/
地質の日記念展示 札幌の過去に見る洪水・土砂災害(札幌市資料館)
期間:4/28(火)〜5/31(日)休館日:月曜日(GW中の休館は7日のみ)
場所:札幌市資料館1階
洪水災害を中心に札幌周辺の自然災害について展示・解説し,自然災害への備えの重要性を喚起します。
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
企画展「豊橋周辺の第四紀化石」(国際第四紀学連合第19回大会組織委員会・日本第四紀学会・豊橋市自然史博物館)
期間:6/27(土)〜7/19(日)
場所:豊橋市自然史博物館
国際第四紀学連合第19回大会開催記念 一般普及講演会にあわせて、関連した化石を展示紹介します。
▶▶2015年7-8月のイベントカレンダー
5-6月のイベント
日付
イベント
5/1
(金)
▼
5/2
(土)
▼
5/3
(日)
▼
5/4
(月)
▼
5/5
(火)
▼
5/6
(水)
▼
5/7
(木)
▼
5/8
(金)
▼
5/9
(土)
▼
5/10
(日)
▼
5/11
(月)
▼
5/12
(火)
▼
5/13
(水)
▼
5/14
(木)
▼
5/15
(金)
▼
5/16
(土)
▼
5/17
(日)
▼
5/18
(月)
▼
5/19
(火)
▼
5/20
(水)
▼
5/21
(木)
▼
5/22
(金)
▼
5/23
(土)
特別展講演会「地形環境と人のくらし」(兵庫県 県立考古博物館)
場所:兵庫県立考古博物館 講堂
時間:13:30〜15:00(12:50より整理券配付)
内容:講師 青木哲哉(立命館大学非常勤講師)
料金:無料 定員:先着120名 当日受付
事前申込:不要
5/24
(日)
▼
5/25
(月)
▼
5/26
(火)
▼
5/27
(水)
▼
5/28
(木)
▼
5/29
(金)
▼
5/30
(土)
公開シンポジウム「災害考古学の可能性を探る」(兵庫県 県立考古博物館)
場所:兵庫県立考古博物館 講堂
時間:10:00〜16:00(9:30より整理券配付)
コーディネーター:山下史朗(兵庫県教育委員会文化財課副課長)・パネラー:高橋 学(立命館大学環太平洋文明研究センター・歴史都市防災研究所教授)・森永速男(兵庫県立大学防災教育センター教授)・甲斐昭光(当館学習支援課長)・多賀茂治(当館学芸員)
料金:無料 定員:先着120名 当日受付
事前申込:不要
5/31
(日)
▼
6/1
(月)
▼
6/2
(火)
▼
6/3
(水)
▼
6/4
(木)
▼
6/5
(金)
▼
6/6
(土)
特別展講演会「火山災害と金井遺跡群」(兵庫県 県立考古博物館)
場所:兵庫県立考古博物館 講堂
時間:13:30〜15:00(12:50より整理券配付)
講師 桜岡正信((公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団八ッ場ダム調査事務所長)
料金:無料 定員:先着120名 当日受付 事前申込:不要
6/7
(日)
▼
6/8
(月)
▼
6/9
(火)
▼
6/10
(水)
▼
6/11
(木)
▼
6/12
(金)
▼
6/13
(土)
▼
6/14
(日)
▼
6/15
(月)
▼
6/16
(火)
▼
6/17
(水)
▼
6/18
(木)
▼
6/19
(金)
▼
6/20
(土)
▼
6/21
(日)
化石レプリカをつくろう (徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島市八万町向寺山(文化の森総合公園)
時間:13:30〜15:00
「レプリカ」とは、実物の資料から型どりをした実物にそっくりな複製品のことをいいます。この行事では、実物の恐竜の歯やアンモナイト、三葉虫の化石から型どりした凹型を使ってレプリカをつくります。
参加費無料。往復はがきに行事名、参加者全員のお名前、住所、電話番号を記入して、1か月前から10日前までに届くようにお申し込みください。
ジオガイド養成講座「東三河ジオサイトの話題」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市大岩町字大穴1-238(豊橋総合動植物公園内)
時間:14:00〜15:00
「平成27年度に実施するジオツアーの4つのコースを中心に、そのジオサイト解説のポイントを学びます。
定員60名、自然史博物館へ電話(0532-41-4747)、FAX(0532-41-8020)またはメール(sizensi@toyohaku.gr.jp)で先着順。
6/22
(月)
▼
6/23
(火)
▼
6/24
(水)
▼
6/25
(木)
▼
6/26
(金)
▼
6/27
(土)
▼
6/28
(日)
石を顕微鏡で見よう (神奈川県 相模原市立博物館)
場所:相模原市中央区高根3-1-15
時間:10:00〜16:00
相模川の川原の石を偏光顕微鏡で観察します。
事前申込不要
ジオガイド養成講座「ジオツアー 災害の爪痕をたどる―伊勢街道でつなぐ表浜」 (愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市ほか(博物館集合・解散・バス使用)
時間:9:00〜16:00
津波で移転した東観音寺の跡や海食崖など、伊勢街道に沿った表浜のジオポイントを中心にめぐります。
定員:中学生以上25名、参加費:300円、往復はがきで6月11日(木)必着
県博日曜講座「生命史をひも解く−カンブリア紀−」(岩手県 岩手県立博物館)
場所:岩手県盛岡市上田
時間:13:30〜15:00
動物が爆発的に多様化したと言われるカンブリア紀について紹介します。
事前申込不要 当日受付 聴講無料
6/29
(月)
▼
6/30
(火)
▼
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ 内のフォームま たはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
地学研究発表会(2012大阪)
小さなEarth Scientistのつどい〜第10回小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜
(2012大阪)
会場風景
大阪大会2日目に,小さなEarth Scientistのつどい〜第10回小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜がおこなわれた.年会における発表会は9年前の静岡大会からおこなわれており,今回の開催で,節目の10回目を迎えることとなった.この発表会の目的は,地学普及の一環として学校における地学研究を紹介することで地学教育の奨励と振興を図ることと,地学を研究する児童・生徒と研究者の交流が進み,地球科学普及の一助となることである.
今回の発表会もポスターセッション会場の一角を本企画の会場として利用させて頂いたので,多くの会員の方にご参加頂けたものと思われる.今回は久しぶりに関西圏における開催であり,高等学校で地学が多く開講されている地域での開催でもあったので,前回の水戸大会を超える13校(16件)の発表があった.なお,大阪府内の学校からの参加は7校であった.年会を開催する都道府県からの参加校が多いことは,今回の特徴であった.
今回から優秀賞選考の審査基準と審査員が変更となった.審査基準は,「研究の動機が明確であり,問題点をはっきりととらえているか」,「観察・実験から導かれたデータを基に,結論が導かれているか」,「わかりやすいポスターとしてまとめられているか」の3つの観点である.一方で,発表(説明内容)については,加点していない.これまで,生徒が参加して説明を行う学校に優秀賞が授与されることがほとんどであったが,今回から,学校行事等で説明する生徒が参加できなくても,研究そのものがすばらしく,ポスターの説明がしっかりなされていれば,高い評価がなされる仕組みとなった.また,これまで執行理事の方々にお願いしてきた審査員は,今回から理事の方々にお願いしている.任期2年のうち,1回は担当していただけるように,お願いしている.
全ての発表を審査した結果,下に示す4件の発表に対して優秀賞が授与されている.また,フィールドに根ざして研究している学校への奨励賞については,下の3件に授与された.
最後となったが,審査にあたっていただいた理事各位,大阪府内の学校の先生方,行事委員会,会場校である大阪府立大学と近畿支部の関係各位,さらに今回の発表会参加者に謝意を表したい.
【優秀賞】
1.高級石材凝灰岩「竜山石」の特性をリサイクル商品に活かす(兵庫県立加古川東高等学校地学部竜山石班;米今絢一郎・赤松沙耶・榊原 暁・生田恭太郎・伊東万奈瑞・岩本有加・岡本奈緒美・竹谷亮人・松下紗矢香・渡邊有美・五百井悠一郎・石田裕樹・稲岡大悟・長谷川真緒・藤原 奨・若園怜子・玉田梨恵)
2.香川県坂出市のボーリングコアから産出した完新世介形虫化石を指標とする古環境の変化(高松第一高等学校;織田未希・中屋敷彩・西江百加)
3.棚倉断層周辺の新第三系における堆積環境の復元(水戸葵陵高等学校;星加夢輝)
4.白亜紀海底探検〜1億年前,大阪は海の底だった〜(大阪府立清水谷高等学校自然科学部;文山誠友・竹中勇介・中本光玲・佐々木玲奈・竹内瑠希・高木健人・小篠尚之)
【奨励賞】
1.山陽帯フェルシックマグマ分化過程後期におけるマフィックマグマの混染(兵庫県立加古川東高等学校地学部角閃石班:新庄研斗・友藤 優・瓜本拓也・黒田健太・成田花菜・高田真里・藤田優希・大坪榛名・山根綾子)
2.鉱物粉末の大きさによる色相変化の原因(兵庫県立加古川東高等学校地学部条痕色班;蓬莱明日・山本崇広・村主美佳・小松原 啓紀・高田千春・伊東万奈瑞・有働篤人・小野友生奈・石田薫・戎 秀梧・川勝太郎・増井 瑞・増田宗利)
3.愛知県粟代鉱山の黄鉄鉱について(滋賀県立彦根東高等学校;奥 裕輔・河野晋平・上林恵太)
【発表会参加校】
大阪府立岸和田高等学校,大阪府立清水谷高等学校,大阪府立港高等学校,大阪府立堺東高等学校,大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎,城星学園高等学校,大阪市立新北島中学校,兵庫県立加古川東高等学校,滋賀県立彦根東高等学校,高松第一高等学校,早稲田大学高等学院,水戸葵陵高等学校,那須烏山市立下江川中学校
(地学教育委員会 三次徳二)
地学研究発表会(2013仙台)
小さなEarth Scientistのつどい〜第11回小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜
(2013仙台)
会場風景
表彰式の様子
仙台大会2日目に,小さなEarth Scientistのつどい〜第11回小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜がおこなわれた.年会における発表会は10年前の静岡大会からおこなわれており,今回の開催で11回目を迎えることとなった.この発表会の目的は,地学普及の一環として学校における地学研究を紹介することで地学教育の奨励と振興を図ることと,地学を研究する児童・生徒と研究者の交流が進み,地球科学普及の一助となることである.
今回の発表会もポスターセッション会場の一画を本企画の会場として利用させて頂いたので,多くの会員の方にご参加頂けたものと思われる.今回は,特に発表のレベルが上がった印象を受けた.残念なことは,高等学校で地学が多く開講されている宮城県での開催であったため,多くの参加校があるかと期待したが,東北大学の先生方にご尽力いただいたものの,参加校はなかった.その理由は,県内の公立高校は2学期制を導入しており,期末試験前の部活動の禁止期間と重なったことである.それでも,宮城県内の私立高校1校を含め,9校,1団体から16件の発表があった.なお1団体とは,新潟大学理学部が事業主体となっている「未来の科学者を育成する新潟プログラム」であり,そこに参加する中学生2人がそれぞれの研究を発表した.
昨年の報告記事でも紹介したが,前回より優秀賞選考の審査基準と審査員が変更となった.審査基準は「研究の動機が明確であり,問題点をはっきりととらえているか」,「観察・実験から導かれたデータを基に,結論が導かれているか」,「わかりやすいポスターとしてまとめられているか」の3つの観点である.一方で,発表(説明内容)については,加点していない.これまで,生徒が参加して説明を行う学校に優秀賞が授与されることがほとんどであったが,学校行事等で説明する生徒が参加できなくても,研究そのものがすばらしく,ポスターの説明がしっかりなされていれば,高い評価がなされる仕組みとなっている.また,審査員も理事の方々にお願いしており,今回は名簿後半の理事の方々にお願いした.
全ての発表を審査した結果,下に示す3件の発表に対して優秀賞が授与されている.また,研究の進展を期待する発表やフィールドに根ざして研究している学校への奨励賞については,下の3件に授与された.
最後となったが,審査にあたっていただいた理事各位,行事委員会委員,会場校である東北大学と東北支部の関係各位,さらに今回の発表会参加者(生徒と引率の先生方)に謝意を表したい.
【優秀賞】
1.遠州灘鮫島海岸のガーネットサンドの堆積過程と海岸微地形との関係(静岡県立磐田南高等学校 地学部地質班)
2.大森浜の海岸浸食と砂の堆積−イカ看板は埋まり続けるのか−(遺愛女子中学高等学校 地学部)
3.八戸市牛ケ沢(IV)遺跡から産出した縄文土器の胎土分析(青森県立八戸北高等学校 SSH地学班)
【奨励賞】
1.甲府盆地東部の扇状地とその集水域の地質(山梨県立日川高等学校)
2 . 福井県産ジュラ紀アンモナイトPseudoneuqueniceras yokoyamaiの肋の比較(新潟市立中野小屋中学校,未来の科学者を育成する新潟プログラム)
3.佐渡島沢根層から産出する珪藻化石の分類(新潟第一中学校,未来の科学者を育成する新潟プログラム)
【発表会参加校】
明成高等学校(宮城県),青森県立八戸北高等学校,遺愛女子中学高等学校(北海道),群馬県立太田女子高等学校,横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校,早稲田大学高等学院,山梨県立日川高等学校,静岡県立磐田南高等学校,兵庫県立加古川東高等学校,未来の科学者を育成する新潟プログラム(新潟市立中野小屋中学校,新潟第一中学校)
(地学教育委員会 三次徳二)
理科・地学教科書展示(2012大阪)
理科・地学教科書展示
会場の様子
日本地質学会地学教育委員会では大阪大会のトピックセッション「新学習指導要領の実施で地学教育はどのように変わるか?」の開催にあわせ,ポスター会場の一角をお借りして,新旧の高校地学教科書,新旧の小学校・中学校理科教科書,改定された小・中・高校の学習指導要領などを展示しました.いろいろの学校種・学年のさまざまな教科書会社の教科書を比較してみる機会はあまりないと思います.多くの会員の皆様に関心を持ってご覧いただけたようで,展示の準備をしたものとして感謝いたします.また教科書展示についてご理解・ご協力をいただいた大阪大会準備委員会と行事委員会の皆様にお礼申し上げます.
展示会場では「このような教科書類を入手するにはどのようにすればよいか」とのご質問を多数いただきました.この場をお借りして,教科書類の入手方法について紹介させていただきます.
学校で使用する教科書はどこの書店でも購入できるわけではなく,各地方の教科書取次店で購入することになっています.取次店リストなど詳細につきましては一般社団法人全国教科書供給協会のホームページ(http://www.text-kyoukyuu.or.jp/)から,各地方の教科書供給所のホームページに行き,リンクをたどって確認して下さい.一部の教科書取次店は店頭販売や通信販売も行っています.ネットの検索で「検定教科書購入」などのキーワードで検索してみて下さい.
今後もこのような展示を行っていきたいと思いますので,ご意見ご要望がありましたら,地学教育委員会「main@geosociety.jp」までお寄せ下さい.
(地学教育委員会教科書展示担当 中井 均)
「県の石」発表
「県の石」
大切なお願い
各都道府県で岩石・鉱物・化石をそれぞれ1つに絞って認定いたしましたが,これ以外にも各地域には選びきれないほど,すばらしい岩石・鉱物・化石が多々あります.
特に化石・鉱物の産地については,充分な保護が必要です.国立・国定公園、並びに自治体の条例で保護が指定されている地域等ではもちろんのこと,そうでない場所で試料の乱獲や盗掘などはせず,露頭保護を心がけるようお願い致します。
「県の石」関連情報
学会創立125周年記念事業の一環として「県の石図鑑:全国都道府県の岩石・鉱物・化石」を2018年に出版予定です.
「県の石」一覧リストはこちら(日本語/Einglish)
47都道府県各「県の石」詳細(解説・写真など)はこちら
日本地質学会は、全国47都道府県について、その県に特徴的に産出する、あるいは発見された岩石・鉱物・化石をそれぞれの「県の石」として選定いたしました。日本地質学会は来る平成30年(2018年)に創立125周年を迎えますが、都道府県の石の選定をその記念事業のひとつとして実施するものです。
2014年8月に学会のHPやプレスリリースを介して一般にも広く推薦を呼びかけました。それをもとに学会内で各支部から委員を選出して選定委員会(委員長:川端清司(大阪自然史博物館))を構成し、約2年をかけて検討し、選定いたしました。
2014年にこの事業を推進するにあたって調査しましたところ、都道府県の花や樹木、あるいは鳥というのはほぼ全てにありました。しかしながら、各都道府県へのアンケートでは「県の石」あるいはそれに類するものを制定しているという回答はありませんでした。
地元の地質を愛する心は国際共通であり,米国では「州の石」を定めているところもあります.我が国では石や岩などというものは、奇岩や特別な景観の中で愛でることはありますが、産業として成り立っているもの、あるいは一部の愛好家を除いて、日常的にはほとんど意識されていないものだと思います。日本は国土の面積こそ小さいのですが、複雑な地質構造をもつ世界でも特異な場所です。
このような日本列島の北から南までの各都道府県の地域特有の「県の石」を選定することによって、一般市民の方々に大地の性質や成り立ちに関心を持っていただき、大地とうまく付き合っていくことができるようになることを目指しております。
また、各都道府県においては、近年盛んになっております「ジオパーク」への貢献ならびにこの「県の石」をさまざまに活用していただくことを希望しております。
2016年5月10日
一般社団法人日本地質学会
会長 井龍康文
▶ 会長コメント「県の石」選定にあたって(2016.5.10)
(参考)日本の石:日本鉱物科学会は「ひすい(ひすい輝石およびひすい輝石岩)」を国石として選定しました(2016年9月24日).→日本鉱物科学会のサイトへ
街中ジオ散歩in Tokyo2014:開催報告
2014年 地質の日記念イベント!!開催報告
街中ジオ散歩 in Tokyo 「下町の地盤沈下と水とくらし」
1. はじめに
地質の日の街中ジオ散歩も今年で3回目になります.1回目の千代田区,2回目の石神井川に続いて,今回は江東区の地盤沈下と内水管理をテーマに実施しました.
図1 街中ジオ散歩 徒歩ルート
日時:2014年5月10日(土)
参加者数:25名(うち小学生1名)
コース:10:00清澄公園集合→水門管理センター・清澄排水機場→清澄庭園・公園(昼食)→扇橋閘門→地下鉄→小名木川・仙台堀川→南砂地盤沈下観測所→南砂町駅18:00解散(図1)
案内者:中山俊雄氏(東京都土木技術支援・人材育成センター),小松原純子氏(産業技術総合研究所)
幹事:中澤 努,荒井 良祐,細根清治,細矢卓志,緒方信一,長谷川貴志,原 弘
主催:日本地質学会・日本応用地質学会
後援:東京都地質調査業協会
協力:東京都江東治水事務所水門管理センター,東京都土木技術支援・人材育成センター,日本地質学会関東支部
2. 街中ジオ散歩の状況
当日は晴天に恵まれ,参加者一同,楽しく出発しました.午前中は排水ポンプ場を見学しながら,水門管理センターの方々から,江東区三角地帯は地盤沈下のため,きめ細かな内水管理が必要とされるとの説明を受けました(写真1).そして近隣の清澄庭園を見学しました.この庭園は石の博物館とも言われています.午後は,扇橋閘門にて所長さんから,内水管理のために小名木川の水位を調整する必要から,パナマ運河のような水面のエレベータを水門操作で行っていることを学びました(写真2).説明を受ける最中にも多くの船が行き交い,水門の開閉と水位の上昇下降のダイナミックさに圧倒されました.その後,小名木川が周辺の地盤沈下のために天井川となり,堤防の嵩上げを行った跡や,現在の地盤沈下の状況,地盤沈下観測所での実際の観測方法,観測施設自体が大きく浮き上がって観測に苦心したことを学びました(写真3).地盤沈下標柱ではかなり高いところに高水位が示され,標高がマイナスであることを改めて実感しました.
写真1 清澄排水機場で説明を聴く様子
写真2 扇橋閘門での記念撮影
写真3 地盤沈下観測所
3. 参加者の方々の声
今回は少人数グループで行動し,担当スタッフが出来るだけこまめに説明をしたこと,そして徒歩だけでなく地下鉄も利用したという点が昨年までと大きく異なる点です.それでも徒歩距離は7 kmに及び,時間も延長となり,少しタフな見学会でした.
アンケートでは総じて好印象の結果でしたが,グループの列が長くなり最後尾の方々が必ずしも案内者の説明を十分に聴講できなかったこと,徒歩距離が長く説明も多かったため時間が超過したこと,散策道では自転車との交雑での安全管理を改善すべきであることが大きな反省点です.また2,000円の会費についても少し高いのではとの意見が複数有り,今後,あり方の検討が必要と感じました.以下に10人の方々から頂いた声を掲載します.
昨年に続き2回目の参加でしたが,私にとっては今回も大変勉強になる見学会でした.東京の自然について,地形と地質を高校生に指導していて,今年度は低地について少し詳しく学びたいと考えておりました.地盤沈下の実態や,水門管理と水害を防ぐ為の努力などは個人で見て歩くだけでは分からないことを解説して頂いたり,業務の実際を見せて頂くなどして大変興味深く,今回学んだことをぜひ授業に生かしたいと考えております.また低地を流れる川の歴史なども面白く,出来ればそういった資料も添付資料に入れて頂ければなお理解が深まると感じました.
(菊地さん,50代,女性)
下町の地盤沈下なんて今まであまり考えたことがなかったため,今回のジオ散歩で地盤沈下の実態を知ることができて大変有意義でした.また,水門管理センターや扇橋閘門など,普段見る機会のない施設を見学できて楽しかったです.
(森田さん,20代,女性)
江東デルタ地帯の地形と水門管理の実際を見ることができ興味深い見学会でした.現地を歩くと緑も多く高い建物もあるので,海面以下の土地という実感がわきません.耐震護岸と水位低下で守られているのでしょうが,できることなら高い所に住みたいものです.揚水ポンプや水門の見学だけでは地質の香りが乏しいということで,石の解説や清澄庭園の景石の見学も組み込まれていました.見学ポイントの移動に一部地下鉄を利用するなど配慮がありましたが,私には少しきつめのコースでした.
(Fさん,70代,男性)
全体に非常に楽しく見学させていただきました.前から江東三角地帯(江東デルタ)と呼ばれる地域には興味がありましたが,自ら現地見学するわけでもなく,これまで漠然と見過ごしてきましたが,今回は好機到来とばかり参加いたしました.やはり,地域に暮らす方や管理される方から直接お話を聞けるのは,貴重な体験になりました.個人的には仕事柄,山岳地に行く機会が多いため,都内の内水対策について直接話を聞く機会もなかったこともありますが,自分の日頃の無知を自覚するとともに,非常に勉強になったと感じています.改めて企画してくださった学会の関係者に深く感謝いたします.今回吃驚したのは,江東三角地帯の地盤の高さが,東京湾の平均満潮面以下にありながら,水門管理センターを含めて,内水対策として綿密に流域が管理され,住民でもこの管理実態を知らない人がいるかもしれない中,日常的に都民の安全な暮らしを守り続けていることが実感できたことです.センターで働く方も職業的な生きがいを感じておられるのではないでしょうか.江東三角地帯は東側河川と西側河川に大きく区分され,特に東側河川は平常時水位をA.P.-1.0 mに管理されているとのことで,小名木川の扇橋閘門の操作状況も直接観察することができて,仕事などの通行の他に,観光ルートとしても利用していることに,当たり前のように感心しました.また,今回は見学ルートにはありませんでしたが,デルタ地帯東端の旧中川と荒川とを結ぶ荒川ロックゲートの閘門が完成しており,隅田川から荒川にかけての流路が確保され,震災時の救援物資の輸送路としても利用される計画のようです.全体として,見学ルートが徒歩が主体であったため,夕方の終了時にはジョッキングで長距離を走った疲労感がありましたが,満足した1日でした.街中ジオ散歩は,今回で3回目の参加になりますが,参加の度に日頃身近に接している街角なのに,歴史について意外と知らないことを改めて実感するので,これからも機会があれば参加して,住民の暮らしと密着した地域環境や地盤・地下水について確認できればと考えています.
(千田さん,50代,男性)
居住地が近く,今回の話題に非常に興味を持って参加しましたので,とても身になるものでした.
(Nさん,40代,男性)
地盤沈下や厚い沖積層の分布,埋没谷の存在などは,知識として理解してはおりましたが,いざ目で見て説明を受けると,深く理解することができ,また徒歩で見学することにより,そこに住むための努力や工夫を知ることができました.景観を求めて堤防を低くし,水位低下方式を採用した地域においては,美しく整備された水路や,遊具が取り揃えられた多くの公園に出くわし,私自身,ジオ散歩終了後に娘と立ち寄った公園では,同じように遊びに来た親子と楽しく過ごす中で,そこが干潮水位より低い地域であることをうっかり忘れてしまうほどでした.多くの人の努力によって,日々の生活を穏やかな気持ちで過ごすことができるようになった一方,恐怖感は薄れてしまっていくような気がします.だからこそ,今回のような子供も参加できるイベントには,地域の子供達にもっとたくさん参加してもらい,自分たちがどういうところに住んでいるのかを感じ取ってもらいたいと思いました.
(細野さん,30代,女性)
『下町低地の地盤沈下と水とくらし』というテーマのもと地質とどう関係があるのかな?と疑問半分,期待半分で参加しました.下町の地盤沈下量は場所により異なっており,地下水と天然ガス汲み上げ地点周囲の水位低下だけでは説明できず,柱状コア採取や探査,研究により今より100 mも海面低下をしていた氷河期の谷が深い地点ほどその後の軟弱堆積層が厚く,今の地盤沈下量に影響しているということを講師の方々の明快な解説で知ることができ,「地質調査」の重要性を理解できました.川の水位よりも明らかに低い道路地盤面を比較できる橋(白河辺り)があり東京都治水事務所の守人(まもりびと)と,莫大な維持費のお陰で今の生活が享受できている事を午前中に勉強した.堤防と日々の治水管理で守られている事をどれだけの人々が知っているのだろうか.
(滝沢さん,40代,男性)
毎日の通勤下車駅木場に降りて,朝,水路より低い地面ってどういうこと?と思いながら坂の下の事務所に12年通勤しておりました.会に参加して合点できました.ポンプで調整しなければならない運河も,知らずに渡っておりました.会の後は,自分の居る環境をよく見て理解することの大切さを感じつつ,地面下のデリケートなことに思いをはせながら,バランスの大切さを再度確認することができ,今までとは違った見方ができるようになりました.会社のビルの窓から見ている風景も,水門管理センターの方々の制御室での日々に守られていることも良く解り,人は人に守られて日々無事に過ごせていることに感謝しつつ,日中過ごさせていただいております.皆様ありがとうございました.来年もぜひ参加したいと今から楽しみにしております.
(山野辺さん,50代,女性)
東京のこの辺りを東部低地帯というのか?と,なんでも確かめようと歩く日となった.大正12年の関東大震災では中川の軟弱な地盤に多く災害ががでたという,その扇状地帯/江東三角デルタ地域というのか.明治以降は地下水の汲み上げが盛んで地盤沈下していく.何ごとも急激に大規模にとなると大変なことになるのだなぁ.その変化に対応した街は興味深かった.東と西では方針に違いがあり,それが地下鉄移動で街散策した理由だったのか?なんだか歩いて歩いて認識さだかでないところがわたしの感想となった.このあたりに掘られた家庭向けの井戸はすべて打ち込み式でパイプだったのだろうなぁ.掘り抜き丸井戸というわけにはいかない.なにしろ沖積地,というのがその最大の特性である.ハードウォーキングだった.
(60代,女性)
0メートル地帯を初めて実際に歩いて見たが,標高の標識を見て地盤沈下の大きさを感じることができた.排水の設備も見学できてよかったです.
(Kさん,40代,男性)
謝辞:この徒歩見学会の開催にあたって,案内をしてくださった中山俊雄氏,小松原純子氏,並びに一般社団法人東京都地質調査業協会,東京都水門管理センター,土木技術支援・人材育成センターの皆様には多大なご協力を頂き大変お世話になりました.また日本地質学会関東支部幹事会の皆様,日本応用地質学会の幹事の皆様には当日スタッフとして運営にご尽力いただきました.心から感謝申し上げます.
(文責:緒方信一)
第8回国際地学オリンピック2014年スペイン大会
初の金メダル3名受賞!−第8回国際地学オリンピックスペイン大会‐
第8回国際地学オリンピックスペイン大会(8th International Earth Science Olympiad, Santander in Spain、以下スペイン大会と省略)で、以下の通り、日本選手3名が金メダルを、1名が銅メダルをそれぞれ受賞した。金メダルを複数名が授与されたのは今回が初めてで、ゲスト生徒も銀メダル相当の成績を収めた(写真1)。ゲスト生徒はメダル授与の対象外というほかは、他の選手同様に大会に参加できる。2016年の第10回国際地学オリンピック日本大会を三重県内の高校生に広報してもらう目的で、今回初めてゲスト生徒1名を派遣した。
金メダル:
宇野 慎介(灘高等学校3年)
西山 学 (巣鴨高等学校3年)
野村 建斗(筑波大学附属駒場高等学校3年)
銅メダル:
杉 昌樹 (灘高等学校3年)
銀メダル相当:
芝田 力 (高田高等学校2年、ゲスト生徒)
スペイン大会は2014年9月22日〜28日にスペイン北部カンタブリアのサンタンデールで開催された(写真2)。主会場はマグダレナ半島にあるカンタブリア大学の施設。今大会には21ヶ国・地域から82名の高校生が参加した。おもな日程は以下の通りで、( )内は引率者‐メンター・オブザーバー‐の日程。
1日目
登録
2日目
開会式・Sand sculpture・
大学生スタッフによるフラメンコ講習会
(第1回運営会議・試験問題の検討と翻訳)
3日目
見学(第2回運営会議・試験問題の検討と翻訳)
4日目
国際協力野外調査・筆記試験
(試験問題の翻訳・第3回運営会議)
5日目
筆記試験・実技試験(見学)
6日目
国際協力野外調査発表会・伝統舞踊鑑賞
(得点検討会・第4回運営会議・日本大会PR)
7日目
表彰式
試験はこれまでの3部門(地質・固体地球科学部門、気象・海洋科学部門、天文・地球惑星科学部門)による筆記・実技試験ではなく、試験ごとにテーマが設定された分野横断型の5つの試験(筆記試験4、実技試験1)が実施された。
メダルを競う試験とあわせて、国際地学オリンピックの特色ともいえるのが国際協力野外調査(International Team Field Investigation、以下ITFIと省略)である。これは、地球科学分野でもよく行われる共同研究を疑似体験するような活動で、表彰も行われる。今回は一班約10名の国際混合チームが8グループ編成された。大会4日目午前中にはマグダレナ半島対岸の海浜で穴を掘り、剥ぎ取り標本の作成が(写真3)、大会6日目午後には「Sedimentology through Lacquer Peels in Somo Beach」と題し、スライドや実演を交えながら調査結果の発表がそれぞれ行われた(写真4)。日本選手は英語でのやり取りに戸惑いながらも、仲間と協力し合い、以下の賞を受賞した。
ITFI Best Presentation賞
:Group5(西山選手所属チーム)
ITFI Best Scientific Research賞
:Group8(野村選手所属チーム)
ITFI Enthusiasm特別賞
:Group2(芝田ゲスト生徒所属チーム)
このほか、見学日には地元の高校やアルタミラ博物館などを訪れ、夜には伝統舞踊鑑賞・講習が催されるなど、北スペインの魅力にも触れることができた大会であった(スペイン大会の詳細な報告や写真は、地学オリンピック日本委員会のホームページ http://jeso.jp/ にて)。
大会期間中にはメンターとオブザーバーが参加する運営委員会(Jury Meeting)が4回開かれた。第1・2回は試験・イベント運営方針の確認と試験問題の検討、第3回は今大会以降の国際地学オリンピックの活動方針を議論した。大会6日目の第4回運営委員会では、表彰に関する確認の後、第10回国際地学オリンピック日本大会(三重)をメンターとオブザーバーらでPRした。
今大会はアメリカが大会を変更したため、急遽、スペインでの開催となった。試験が地質分野に偏ってしまったことは難点だが、開会式でスペインのGeodiversity紹介映像が流れ、「The Magdalena Gymkhana」と題した地質調査の雰囲気を感じられる実技試験、閉会式でのGeopark関係者のあいさつ、スペイン産アラゴナイトの記念品が参加者全員に贈呈されるなど、地元地質関係者の多大なる協力・支援のおかげと感じた。最後に、円滑に大会を運営してくれた大会実行委員会の尽力に心より感謝申し上げる。
(地学オリンピック支援委員会:渡来めぐみ)
写真1 表彰式直後の日本選手
写真2 参加者全員での記念撮影
写真3 剥ぎ取り標本作成中のグループ2
写真4 ITFI発表会(マイクに向かう日本選手)
(写真提供: NPO法人地学オリンピック日本委員会)
九州・沖縄(県の石)
「県の石」:九州・沖縄
▷「県の石」(大切なお願い/リスト/選定にあたって ほか)
<北海道・東北(青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島)>
<関東(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川)>
<中部・甲信越(新潟・長野・山梨・静岡・富山・石川・岐阜・愛知・福井)>
<近畿(滋賀・奈良・京都・三重・大阪・和歌山・兵庫)>
<四国(徳島・香川・高知・愛媛)>
<中国(岡山・広島・山口・島根・鳥取)>
<九州・沖縄(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)>
福岡県の「県の石」
◆福岡県の岩石
石炭(主要産地:筑豊地域)
展示していある場所:田川市石炭・歴史博物館,直方市石炭記念館
筑豊地域は日本で有数の炭田地域で,日本の近代改革を支えた場所である.石炭は日本海拡大前の約4500万-3000万年前ごろの伸張作用によるハーフグラーベン構造でできた厚い堆積盆中に見られる.筑豊ではヌマスギやメタセコイアなどのヒノキ科の針葉樹が湿地に堆積して厚い石炭層を作る.現在,露頭がほとんどなくなっているが,宅地開発などでできる崖に,河川起源の砂層と互層して真っ黒い石炭層が見られる.石炭層中には珪化木も見つけられる.2020.12.11一部加筆 (撮影:清川昌一)
◆福岡県の鉱物
リチア雲母(主要産地:福岡市長垂)
展示してある場所:北九州市立 いのちのたび博物館,福岡市 九州大学総合研究博物館
リチア雲母(lepidolite)はLiを含む雲母で,紅雲母,鱗雲母とも呼ばれる.紫色〜桃,無色,白色の粒状の集合体をなすことが多いが,六角板状〜柱状結晶,あるいは粗粒の湾曲した鱗片状としても産する.花崗岩質ペグマタイトにリチア電気石などのLi鉱物と共生する.なお,長垂のリチア雲母を含むペグマタイトは昭和9年に「長垂の含紅雲母ペグマタイト岩脈」として国指定天然記念物に指定されている.(写真提供:上原誠一郎(九州大学高標本No1359-1)
◆福岡県の化石
脇野魚類化石群(脇野亜層群産魚類化石群)(主要産地:北九州市,直方市,宮若市)
展示してある場所:北九州市立自然史・歴史博物館(いのちのたび博物館)
約1億3000万年前の前期白亜紀の淡水魚類化石群.
湖成堆積物である脇野亜層群は古くから貝類化石や魚類化石の産出が知られている.北九州市(1976,1977)が行った発掘調査以来これまで,20種を超える淡水魚類化石が発見されている.この化石群は,当時の北部九州の古環境や大陸との関係を知る上で重要な化石となっている.
脇野亜層群から最初に記載されたディプロミスタス コクラエンシス(写真提供:北九州市立自然史・歴史博物館)
このページtopへ戻る
佐賀県の「県の石」
◆佐賀県の岩石
陶石(変質流紋岩溶岩)(主要産地:西松浦郡有田町泉山)
展示してある場所:佐賀県立宇宙科学館・佐賀県立九州陶磁文化館
泉山は日本で初めて磁器が製造された陶磁器発祥の地であり,歴史的意義が大きな陶石鉱床である.泉山陶石鉱床は杵島層群に貫入した直径約200mの岩株状流紋岩体であり,有田流紋岩に相当する.陶石を構成する鉱物は石英・セリサイト・カオリンである.泉山陶石の母岩となった黒雲母流紋岩生成年代は280から270万年前と考えられており,泉山陶石のセリサイトの年代が220から210万年前であるため,流紋岩の貫入から約50万年後に陶石化作用が生じたと推定されている.(写真提供:佐賀県立宇宙科学館)
◆佐賀県の鉱物
緑柱石(主要産地:佐賀市富士町杉山)
展示してある場所:佐賀県立宇宙科学館
杉山の緑柱石は富士町杉山の白石山北斜面,ペグマタイト質石英脈中に産し,昭和18年「佐嘉鉱山」として石英を採掘中に発見された.緑柱石は母岩の黒雲母花崗岩との境界から,石英脈側に10cmの幅で20〜30cmの塊をなして産出したという.
生成年代は母岩である佐賀花崗岩が約9000から8000万年前に形成されたものであるので,緑柱石もこの時期に生成されたものと思われる.(写真提供:佐賀県立宇宙科学館)
◆佐賀県の化石
唐津炭田の古第三紀化石群(主要産地:佐賀県西部)
展示してある場所:佐賀県立宇宙科学館・佐賀県立博物館・多久市郷土資料館
相知層群と杵島層群より産出する化石群,時代は始新世から漸新世(4000万年前〜3000万年前)に相当する.下位の相知層群は,厳木層から海生貝類化石が多産し,芳ノ谷層から植物化石やアミノドン(大型哺乳類)が産出する.上位の杵島層群は,いくつかの層で海生貝類化石が多産し,ヨコヤマオウムガイやサメ,カメ,コペプテリクス(海生鳥類)などが発見されている.(写真提供:佐賀県立宇宙科学館)
長崎県の「県の石」
◆長崎県の岩石
デイサイト(主要産地:雲仙火山(平成新山))
展示してある場所:雲仙岳災害記念館
火山岩は二酸化ケイ素の含有量で分類されており,二酸化ケイ素の少ない方から順に,玄武岩・安山岩・デイサイト・流紋岩と呼ばれている.平成2年から約5年間にわたって活動した雲仙火山は,粘り気の強いデイサイトの溶岩を噴出し,新しい溶岩ドームを作った.溶岩ドームの一部が崩れるとき,火砕流を発生させ44名の命を奪った.デイサイトでできた溶岩ドームはその後「平成新山」と名付けられた.(写真提供:寺井邦久)
◆長崎県の鉱物
日本式双晶水晶(主要産地:長崎県五島市奈留町船廻水晶岳)
展示してある場所:奈留港インフォメーション,長崎市科学館
長崎県五島奈留島船廻にある水晶岳の東側に幅約20 mにわたり水晶が露出している.五島層群中の砂岩泥岩互層に貫入してきた石英脈石による破砕帯にあたる.この中に厚さ数mm〜7cm程度の石英脈が発達し,これに沿って日本式双晶や両錐の水晶が多産する.日本式双晶は透明度の高い平板状の水晶が84.33°で結合しハート型を形成してている.現在は五島市の天然記念物に指定されている.(写真提供:浦川孝弘)
◆長崎県の化石
茂木植物化石群(主要産地:長崎市茂木町)
展示してある場所:長崎市科学館
長崎火山活動の初期(約550万年前(中新世))に噴出した軽石や火山灰が淡水湖に流れ込み,植物の葉などとともに固まってできた地層がある.葉化石が浮き上がった状態で見られることから,水中火砕流ではないかと考えられている.ブナの葉が多く含まれ,棚井敏雅(1976)により,31科40属52種の植物が確認されている.日本の新生代の植物化石の最初の記録となって国際的にも有名であり,昭和54年7月27日に県の天然記念物に指定された.(写真上:ブナ葉化石(茂木植物化石群),下:長崎化石茂木植物化石層 写真提供:山川 続)
このページtopへ戻る
熊本県の「県の石」
◆熊本県の岩石
溶結凝灰岩(主要産地:阿蘇カルデラ周辺)
展示してある場所:阿蘇カルデラ周辺・阿蘇火山博物館(現在休館中 2016.5.12現在)
溶結凝灰岩は,高温の火砕流が堆積した際に,自分自身の重みと熱で圧縮され含まれる火山灰や軽石などが変形し固結してできた岩石.軽石などが押しつぶされて大小様々なレンズ状の形態を示すのが特徴.阿蘇カルデラから噴出した4回の阿蘇火砕流は溶結することが多く,地元では「灰石」と呼ばれている.阿蘇の溶結凝灰岩は加工しやすいため,通潤橋をはじめとする石橋の石材としてよく利用されている.(写真撮影:星住英夫)
(注)展示場所および一部説明文に加筆しました.下線部(2016.5.12 )
◆熊本県の鉱物
鱗珪石(トリディマイトTridymite)(主要産地:熊本市西区島崎の石神山)
展示してある場所:山口大学・理学部・地球科学標本室
鱗珪石(トリディマイト)は,石英(水晶)と同じ化学式SiO2で表されるが,結晶構造が異なり六角板状の形態を示し,石英より高温で安定な鉱物であり珍しい.一般に微細な結晶が多いなか,石神山では安山岩の空隙に1㎝近い大きな結晶を産出したことで有名で,他にクリストバル石や金雲母・パーガス閃石を伴う.石神山は前期更新世の約100万年前の角閃石両輝石安山岩からなり,採石場があったが現在は熊本市の石神山公園となっている.
薄板状透明な1~2㎜程度の結晶(写真提供:山口大学理学部地球科学標本室)
◆熊本県の化石
白亜紀恐竜化石群(主要産地:天草市、御船町)
展示してある場所:天草市立御所浦白亜紀資料館,御船町恐竜博物館
熊本県からは,御船町や天草市(御所浦島や天草下島)などから中生代白亜紀の恐竜やアンモナイトなどの化石が発見されている.1979年に御船町から日本初となる肉食恐竜の歯の化石が,1997年には、天草市御所浦町から九州初の恐竜足跡化石が発見されている.御所浦層群(約1億年前),御船層群(約9000万年前),姫浦層群(約8500万年前・約7500万年前)から,獣脚類,鳥脚類,曲竜類,竜脚類といった恐竜化石が知られ,今後も新たな発見が期待できる地域である.恐竜以外の脊椎動物のほか,貝やアンモナイト,植物などの化石も産出する.(写真左:国内最大級の獣脚類の歯化石(天草市立御所浦白亜紀資料館所蔵),右:御船町恐竜博物館提供)
大分県の「県の石」
◆大分県の岩石
黒曜石(主要産地:姫島)
展示してある場所:大分県立歴史博物館・大分市歴史資料館・離島センター「やはず」(姫島村)
姫島村観音崎の黒曜石は,一般的な黒曜石に比べて色が薄く,乳灰色〜乳白色であることが特徴で,0.2 mmほどのガーネットが含まれている.旧石器時代以降に瀬戸内海や四国,九州各地の広い範囲で石器として使われており,昭和34年に大分県の天然記念物に指定され,平成19年には「姫島の黒曜石産地」として観音崎一帯が国の天然記念物に指定された.(写真提供:おおいた姫島ジオパーク推進協議会)
◆大分県の鉱物
斧石(主要産地:豊後大野市尾平鉱山)
展示してある場所:豊後大野市歴史民俗資料館
尾平鉱山は大分・宮崎の県境近く祖母山麓の奥岳川上流にある.ペルム紀付加体や結晶片岩,蛇紋岩などとそれを覆う中新世の火山岩類に中新世の花崗岩類が貫入して生成された鉱床で,かつて鉱物の巨晶を産出したことで有名.斧石は,マグマ固結の終末期に放出されるホウ素を含むガスと母岩との反応により生成されたスカルン鉱物の一種で,比較的まれな鉱物.尾平鉱山では接触交代鉱床の鉱体ごとに異なる巨晶,美晶の晶群を産出している.(写真提供:豊後大野市歴史民俗資料館)
◆大分県の化石
更新世淡水魚化石群(主要産地:玖珠盆地(九重町野上))
展示してある場所:北九州市立自然史・歴史博物館
玖珠盆地に分布する第四紀更新世の珪藻土層からは,淡水魚の化石が多産し,当時の環境や生物相を理解する上で貴重な情報を提供している.写真はビワマス類似の一種.これは玖珠盆地から最も多く産出する魚類化石で,サケ科に属する.玖珠盆地産のサケ科魚類化石は鱗がビワマスに類似しているが,ビワマスと同種であるかどうかは今後の研究にゆだねられている.(写真提供:北九州市立自然史・歴史博物館)
このページtopへ戻る
宮崎県の「県の石」
◆宮崎県の岩石
鬼の洗濯岩(砂岩泥岩互層)(主要産地:青島海岸(日南海岸))
展示してある場所:日南海岸(青島〜鵜戸神宮)一帯
宮崎県の日南海岸には新生代新第三紀中新世(約700万年前)に堆積した宮崎層群が分布している.洪水等で土砂が供給されると,粒の重さの違う砂と泥の層に分離する.長い年月これを繰り返すと,硬い砂岩とやわらかい泥岩が規則的に積み重なった砂岩泥岩互層ができる.その後,地層は隆起して,傾いた地層を波が水平に洗い,現在の地形ができあがった.鬼の洗濯岩は国や県の天然記念物にも指定されている.(写真:日南海岸戸崎鼻の「鬼の洗濯岩」.写真提供:赤崎広志)
◆宮崎県の鉱物
ダンブリ石(主要産地:土呂久鉱山)
展示してある場所:宮崎県総合博物館
ダンブリ石は米国コネチカット州ダンベリーで最初に見つかった無色透明〜白色で四角柱状の結晶をつくる鉱物で縦方向の筋(条線)が特徴.日本では数カ所でしか産出しない希少な鉱物.ヒ素公害のあった宮崎県の高千穂町の土呂久鉱山は美しい標本が産した.現在は閉山のために採集不能となっている.屈折率が高く美しく輝く性質から,過去には,透明なものがダイヤモンドの代用品としてカットされた時期もあったといわれている.(写真提供:赤崎広志)
◆宮崎県の化石
シルル−デボン紀化石群(主要産地:五ヶ瀬町祇園山)
展示してある場所:宮崎県総合博物館,宮崎県庁本館,五ヶ瀬町自然の恵み資料館
宮崎県五ヶ瀬町鞍岡の祇園山の石灰岩は全国有数の古生代シルル紀〜デボン紀(約4億年前)の化石産出地である.祇園山からは現在のサンゴとは違う構造の床板サンゴやウミユリ,三葉虫など,さまざまな化石が報告されており,特に床板サンゴのハチノスサンゴとクサリサンゴのなかまが代表的.祇園山の石灰岩はかつて石材として使用されており,宮崎県庁本館正面玄関の階段には多数のハチノスサンゴ化石を見ることができる.(写真:祇園山のハチノスサンゴ化石.写真提供:赤崎広志)
鹿児島県の「県の石」
◆鹿児島県の岩石
シラス(主に入戸火砕流堆積物)(主要産地:島嶼部を除くほぼ全域)
シラスという言葉は,南九州で白っぽい火山性の堆積物に対して使われていたが,今日では主に入戸火砕流堆積物の非溶結部を指す.約2万9千年前(後期更新世)に姶良カルデラから噴出した入戸火砕流はシラス台地を形成し,その噴出量は150 km3を超えると報告されている.旧地形によって層厚は変化し,旧谷部では100 mにも達する.入戸火砕流の溶結部は,姶良カルデラの北方から東方の広い地域,薩摩半島の南九州市川辺付近に見られる.同時に噴出した火山灰は関東でも10〜20cmの厚さがある.(写真提供:大木公彦)
(写真左)曽於市にある県指定天然記念物「溝ノ口洞穴」へ至る道路の拡張工事現場.旧谷地形を埋めた入戸火砕流堆積物は,下位より大隅降下軽石層,非溶結部,溶結部,非溶結部が見られます.溶結部の下の非溶結部が地下水によって浸食され「溝ノ口洞穴」ができました.写真の工事現場ではシラスを垂直に切っていますが,このように切った方が雨によって浸食されにくいと考えられています.(写真右)鹿児島市中部に広がる紫原シラス台地の道路建設現場です.工事で植生がはぎ取られシラスが露出すると,雨水によって容易に浸食され,ガリが発達します.
(注)写真を差替えました(2016.7.19)
◆鹿児島県の鉱物
菱刈金山の金鉱石(自然金)(主要産地:菱刈鉱山(住友金属鉱山株式会社))
展示してある場所:鹿児島大学総合研究博物館脇
菱刈鉱山は第四紀の火山活動によって形成された浅熱水性鉱床であり,鉱脈の形成年代も100万年前よりも新しい.普通の金鉱石の品位は数グラム/トンであるが,1981年に発見された菱刈の金鉱石は約50グラム/トンもあり,世界最高の品位を誇っている.菱刈鉱山は国内で稼働しているほぼ唯一の金鉱山であり,その発見は従来あまり注目されなかった島弧の第四紀火山地域における金鉱床の探査を活発化させるきっかけとなった.
(写真:鹿児島大学総合研究博物館の屋外に展示されている金鉱石の大きな塊(横2 m,縦1.4 mで,重量は約4トン).金の含有量はトンあたり約40グラム.金鉱石の標本としては国内最大.)
◆鹿児島県の化石
白亜紀動物化石群(主要産地:甑島、獅子島)
獅子島の約1億年前(後期白亜紀セノマニアン)の御所浦層群からはエラスモサウルス科の長頚竜化石と,植物食のカモハシリュウ類の恐竜化石が,下甑島の約8000万年前(後期白亜紀サントニアン〜カンパニアン)姫浦層群からは肉食性の獣脚類などの恐竜化石や,翼竜,ワニ,カメや魚類化石が産出する.これらの白亜紀脊椎動物化石群集は日本で最も南の産出記録である.
(注)現在,これらの化石は研究中のため,一時的な展示会等以外では展示はされていない
(写真:獅子島での発掘風景(主として高知大学理学部の教員、院生、学生が参加)(撮影:仲谷英夫)
このページtopへ戻る
沖縄県の「県の石」
◆沖縄県の岩石
"琉球石灰岩"(主要産地:県内全域)
展示してある場所:琉球大学付属博物館風樹館
"琉球石灰岩"は第四紀更新世初期から後期更新世に琉球列島の各島々で形成したサンゴ礁複合体堆積物の累積体の俗称で,正式には琉球層群の石灰岩類に相当する."琉球石灰岩"は琉球層群の大部分を占め,サンゴ石灰岩,石灰藻球石灰岩.砕屑性石灰岩,有孔虫石灰岩などに分類される.沖縄県内では建設資材や記念碑等に広く利用されている.特に化学的沈殿を伴う緻密な縞状構造を有する石灰岩は勝連トラバーチンと呼ばれ,国会議事堂の建築材として利用されている.(写真:琉球石灰岩 万座毛1(沖縄県恩納村万座))
(注)字句修正.下線部(2016.5.12)
◆沖縄県の鉱物
リン鉱石(主要産地:沖大東島)
展示してある場所:琉球大学付属博物館風樹館(北大東島産)
沖大東島,北大東島に分布する.生物の骨,海鳥の糞・死骸に含まれるリン成分が下位の石灰岩に染み込んで形成した海成堆積性リン鉱石(有機質リン鉱石)である.北大東島では島の小高い山部と周縁部に散在して分布するが,リン酸三石灰鉱は黄金山にまとまって分布する.1919年から1950年の間に採掘され,閉山までの総採掘量は80万トンと推定されている.現在はリン鉱石貯蔵庫跡が西港に残されている.(写真:燐鉱+りん灰土(右:北大東産燐鉱,左:ラサ島(沖大東)産りん灰土.琉球大付属博物館風樹館所有)
◆沖縄県の化石
港川人(主要産地:八重瀬町字長毛)
展示してある場所:東京大学総合研究博物館(1号,2号保管),沖縄県立博物館(展示物レプリカ:3号,4号保管)
1967〜1970年に沖縄県具志頭村港川の採石場の石灰岩裂罅中(フィシャー)から大山盛保氏によって発見された化石人骨である.四体分の骨格が残っている.化石動物としてリュウキュウシカ,リュウキュウムカシキョンなどを伴う.炭素14年代測定法から1万8000〜1万6000年前の人骨であることが示された.この化石人骨によって末期更新世時代の日本人の祖先の姿が明らかにされた。港川人化石骨格は保存が良く,東アジアの末期更新世における新人の進化を解明する上でも貴重な資料と考えられている.(写真:港川人1号骸骨レプリカ.沖縄県立博物館・美術館所蔵)
県の石リスト(確定版)
県の石リスト
▶「県の石」日本語版リスト
▶「県の石」英語版リスト(解説付):PREFECTURAL STONES OF JAPAN 2017.5.9更新
都道
府県名
岩石
鉱物
化石
支部
岩石名
主要産地
鉱物名
主要産地
化石名
主要産地
北海道
北海道
かんらん岩
様似町
砂白金
北海道中軸部
アンモナイト
北海道中軸部(空知,留萌,日高など)
東北
青森県
錦石(鉄分を含む主に玉髄からなる岩石)
(全域)
菱マンガン鉱
尾太鉱山
アオモリムカシクジラウオ
青森市
岩手県
蛇紋岩
早池峰山
鉄鉱石
釜石市
シルル紀サンゴ化石群
大船渡市樋口沢
秋田県
硬質泥岩
男鹿市船川港女川など,女川層分布地域
黒鉱
北鹿地域
ナウマンヤマモモ
(特定の場所無し)
宮城県
スレート
登米市登米,石巻市雄勝
砂金
のの岳,涌谷
ウタツギョリュウ
南三陸町歌津
山形県
デイサイト凝灰岩
山形市山寺
ソロバン玉石(カルセドニー)
小国町
ヤマガタダイカイギュウ
大江町三郷甲,用地区の最上川川床
福島県
片麻岩
阿武隈高原
ペグマタイト鉱物
石川町
フタバスズキリュウ
いわき市大久町
関東
茨城県
花崗岩
八溝山地南部
リチア電気石
妙見山
ステゴロフォドン
常陸大宮市
栃木県
大谷石(凝灰岩)
宇都宮市大谷町
黄銅鉱
足尾銅山
木の葉石(植物化石)
那須塩原市塩原
群馬県
鬼押出し溶岩(安山岩)
浅間山鬼押出し
鶏冠石
西牧鉱山
ヤベオオツノジカ
富岡市
埼玉県
片岩
長瀞町
スチルプノメレン
長瀞町
パレオパラドキシア
小鹿野町,秩父市大野原
東京都
無人岩
小笠原諸島
単斜エンスタタイト
小笠原諸島
トウキョウホタテ
(特定の場所無し)
千葉県
房州石(凝灰質砂岩・細礫岩)
鋸山
千葉石
房総半島
木下貝層(きおろしかいそう)の貝化石群
印西市木下
神奈川県
トーナル岩
丹沢山地
湯河原沸石
湯河原町
丹沢層群のサンゴ化石群
丹沢山地
中部
新潟県
ひすい輝石岩
糸魚川市青海,小滝
自然金
佐渡金山遺跡
石炭紀−ペルム紀海生動物化石群
糸魚川市青海の青海石灰岩
富山県
オニックスマーブル(トラバーチン)
宇奈月地域
十字石
宇奈月
八尾層群の中新世貝化石群
富山市八尾町
(2016.5.11訂正)
石川県
珪藻土(珪藻泥岩)
能登半島
霰石
能登町恋路
大桑層の前期更新世化石群
金沢市大桑町
福井県
笏谷石(火山礫凝灰岩)
足羽山
自形自然砒
赤谷鉱山
フクイラプトル キタダニエンシス
勝山市北谷
静岡県
赤岩(凝灰角礫岩)
富士火山宝永火口
自然テルル
河津鉱山
掛川層群(大日層)の貝化石群
掛川市,袋井市
山梨県
玄武岩溶岩
富士火山青木ヶ原
日本式双晶水晶
乙女鉱山
富士川層群の後期中新世貝化石群
身延町など
長野県
黒曜石
和田峠
ざくろ石
和田峠
ナウマンゾウ
野尻湖
岐阜県
チャート
木曽川(鵜沼-坂祝),飛水峡,金華山
ヘデン輝石
神岡鉱山
ペルム紀化石群
大垣市赤坂金生山
愛知県
松脂岩
鳳来寺山
カオリン
瀬戸市
師崎層群の中期中新世海生化石群
知多半島
近畿
三重県
熊野酸性岩類
三重県東紀州地域
辰砂
丹生鉱山
ミエゾウ
津市・亀山市・鈴鹿市・伊賀市・桑名市
滋賀県
湖東流紋岩
滋賀県南東部
トパーズ
田上山(大津市)
古琵琶湖層群の足跡化石
湖南市野洲川河床
京都府
鳴滝砥石(前期三畳紀珪質粘土岩)
京都市右京区
桜石(菫青石仮晶)
亀岡市
綴喜層群の中新世貝化石群
宇治田原町
兵庫県
アルカリ玄武岩
玄武洞
黄銅鉱
明延鉱山
丹波竜(タンバティタニス アミキティアエ)
丹波市山南町,篠山川河床
大阪府
和泉石[和泉青石](砂岩)
和泉山脈
ドーソン石
泉南
マチカネワニ
豊中市柴原の待兼山丘陵(大阪大学豊中キャンパス)
奈良県
玄武岩枕状溶岩
玉置山山頂,吉野郡川上村深山の吉野川河床、川上村下多古,十津川村折立など
ざくろ石
二上山
前期更新世動物化石
馬見丘陵(広陵町〜河合町)
和歌山県
珪長質火成岩類
潮岬地域の橋杭岩,古座川弧状岩脈の一枚岩,虫喰岩など
サニディン
太地町
白亜紀動物化石群
有田川流域(有田川町など)
四国
香川県
讃岐石(古銅輝石安山岩)
五色台
珪線石
猫山
コダイアマモ
阿讃山脈
徳島県
青色片岩
眉山-高越地域
紅れん石
眉山
プテロトリゴニア
勝浦川流域(勝浦町,上勝町)
高知県
花崗岩類(閃長岩)
足摺岬
ストロナルシ石
高知市蓮台
シルル紀動物化石群
横倉山(越知町)
愛媛県
エクロジャイト
東赤石山周辺
輝安鉱
市之川鉱山
イノセラムス
宇和島周辺,松山〜四国中央
西日本
鳥取県
砂丘堆積物
鳥取砂丘
クロム鉄鉱
日南町多里
中新世魚類化石群
鳥取市国府町宮下
島根県
来待石(凝灰質砂岩)
松江市宍道町
自然銀
石見銀山
ミズホタコブネ
(県内各地,模式地松江市玉湯町布志名)
岡山県
万成石(花崗岩)
岡山市
ウラン鉱
人形峠
成羽植物化石群
高梁市成羽町
広島県
広島花崗岩
広島県南部
蝋石
庄原市勝光山
アツガキ
三次・庄原地域(備北層群)
山口県
石灰岩
秋吉台
銅鉱石
長登鉱山
美祢層群の植物化石
美祢市
福岡県
石炭
筑豊地域
リチア雲母
福岡市長垂
脇野魚類化石群
北九州市,直方市,宮若市
佐賀県
陶石(変質流紋岩火砕岩)
有田町
緑柱石
富士町杉山
唐津炭田の古第三紀化石群
佐賀県西部
長崎県
デイサイト溶岩
雲仙岳
日本式双晶水晶
奈留島
茂木植物化石群
長崎市茂木町
大分県
黒曜石
姫島
斧石
尾平鉱山
更新世淡水魚化石群
玖珠盆地(九重町野上)
熊本県
溶結凝灰岩
阿蘇山周辺
鱗珪石(トリディマイト)
熊本市島崎の石神山
白亜紀恐竜化石群
天草市,御船町
宮崎県
鬼の洗濯岩(砂岩泥岩互層)
青島海岸
ダンブリ石
土呂久鉱山
シルル紀−デボン紀化石群
五ヶ瀬町祇園山
鹿児島県
シラス(主に入戸火砕流堆積物)
(島嶼部を除くほぼ全域)
金鉱石(自然金)
菱刈金山
白亜紀動物化石群
甑島・獅子島
沖縄県
"琉球石灰岩"
(全域)
リン鉱石
沖大東島
港川人
八重瀬町字長毛
鹿児島県の石
「県の石」
各都道府県の「県の石」については,10.31に募集を締め切り,現在選定作業中です.
鹿児島県の「県の石」
日本地質学会第121年学術大会(2014.9.13-15)が鹿児島市で開催されることを記念して,鹿児島県の「県の石」を下記の通り先行決定いたしました.(2014.9.12決定)
◆鹿児島県の石
シラス(主に入戸火砕流堆積物)
姶良カルデラ噴火で発生した大規模な火砕流や降下物による堆積物で,鹿児島県全体を広く覆っています.一般には“シラス”とも呼ばれ,地形や農産物そして災害など鹿児島県の社会生活に深く関係する堆積物です.
◆鹿児島県の鉱物
菱刈金山の金鉱石(自然金)
菱刈鉱山の金鉱石は品位が世界最高水準であり,また菱刈鉱山から産出された累計産金量も国内歴代一位となっています.菱刈鉱山は名実ともに日本を代表する金山であり,その金鉱石は全国の博物館に展示され,また教科書にも掲載されています.
◆鹿児島県の化石
甑島・獅子島の白亜紀動物化石群
首長竜をはじめアンモナイトやサンカクガイなど白亜紀の海生動物の化石がたくさん産します.特に首長竜の化石は体の多くの部位が見つかっており,全国的にも重要な標本です.
JISに定められた地質年代の日本語表記
JISに定められた地質年代の日本語表記
皆さんは日本語の論文や報告書等で地質年代を記述する場合,どのように表記していますか.国際的な地質年代単元名は,国際地質科学連合(IUGS)の国際層序委員会(ICS)よりInternational Chronostratigraphic Chartとして提示され,“The Geologic Time Scale 2012”(Gradstein et al., eds., 2012a, b)で解説されていることはご存じの方も多いかと思います.International Chronostratigraphic Chartの地質年代は言うまでもないですがもともと英語で表記されています.このような地質年代を和文の報告書等に日本語で記述する場合,これまでは,どのように表記すればよいか困る場合もありました.また,人によって表記法が異なると,意思疎通を妨げ,場合によっては無用な誤解を招くことも考えられます.特に行政機関に納品する地質調査業務報告書や国が出版する報告書では,地質の専門家以外の方が読んでも共通の理解が得られるように,標準的な表記法を定めることが求められます.そのため年代表記を含む地質用語や記号等の指針として2002年に日本工業規格JIS A 0204「地質図—記号,色,模様,用語及び凡例表示」,2008年にはJIS A 0205「ベクトル数値地質図—品質要求事項及び主題属性コード」が制定されました(ともに最新の改定は2012年).これらのJIS規格は,日本地質学会が中心となり,地質関連学協会,研究機関,行政機関が横断的に組織したJIS原案作成委員会が検討し,制定されたものです.しかし日本地質学会会員の皆さんには,このJIS規格をあまり良く知らないという方も多いと思います.そこで今回はJISによって定められた日本語の地質年代表記法の概要をご紹介したいと思います.
JISに定められている地質年代の日本語表記の基本方針は,International Chronostratigraphic Chartにある地質年代単元名の英語読み(英語での一般的な発音)をそのままカタカナ表記にし,末尾に年代単元あるいは層序単元を示す世/統,期/階を添えるという形式です.たとえばBashkirianの場合,年代を示す場合はバシキーリアン期,対応する層序単元を示す場合はバシキーリアン階というようになります.バシュキーリアンとするかバシキーリアンとするかなど,細かいカタカナ表記の問題はありますが,JISではまずは無難と思われる発音(カタカナ表記)を採用しています(地質系統・年代の日本語記述ガイドライン参照).
ところで英語の表記では,年代を示す場合であっても,層序単元を表す場合であっても,単にthe Bashkirianとすることが多いです(Bashkirianは形容詞ですが,theを付すことにより名詞化されます).しかし,これはあくまで簡略形であり,本来はthe Bashkirian ageあるいはthe Bashkirian stageのように「期」「階」に相当するage, stageを末尾に置くのが公式の表記です.JISではこの点について,年代を示しているのか層序単元を示しているのかを明確に区別するため,「期」「階」を必ず付けることにしています.このような表記に違和感を感じる方もおられるようですが,これはあえて年代か層序単元かを明確に区別するための措置です.また,人によっては,年代単元名のもととなった地名そのものを重視し,バシキール期/階というような表記をする方もみかけますが,JISではあくまで原典の地質年代単元名をそのままカタカナ書きにしたバシキーリアン期/階という表記を採用しています.
以上は原則に従った表記ですが,例外もあります.例えば「デボン紀/系」や「石炭紀/系」は古くからよく使われている表記ですが,前述の原則に従うと「デボニアン紀/系」,「カーボニフェラス紀/系」になってしまいます.しかしJISでは長い間使われていて一般に浸透している表記は,それをそのまま踏襲しています.紀レベル以上はほとんどがこの例外に相当します.新生代の世も同様です.なお,Permianは「ペルム紀/系」です.以前は「二畳紀/系」という表記もよくみられました.「二畳紀/系」はもともとDyasという語の訳であるため使用は好ましくないとはよく言われたことですが,JISではこの点は明確に「ペルム紀/系」と表記することと定めています.また,JISでは「沖積世」「洪積世」という地質年代名を公式名として認めていません.もちろんこれに相当する公式の国際的な地質年代単元名もありません.論文で「沖積世」「洪積世」というような表記をされる方はもういないと思いますが,今後も使用は避けるべきです.余談ですが,これに対応する地層の呼び方として「沖積層」「洪積層」が知られています.このうち「洪積層」は現在使用されませんが,「沖積層」は平野部の最終氷期最盛期以降に堆積した地層を指す一般的な用語として使用されています.沖積層は完新統と同義語ではありませんのでご注意を.
また,JISでは地質年代単元を細分する「前期/後期」といった用語の使用法についても定められています.これらの用語は地質時代名を形容する形容詞句として層序単元名の直前に置き,「形容詞句+地質時代名」の形式で記述することになっています.例えば「前期ジュラ紀」といった具合です.年代層序単元の場合もこれと同様で「下部ジュラ系」となります.これをさらに細分する場合,今度は末尾に細分する形容詞句を付けます.
例えば,
late Early Jurassic → 前期ジュラ紀後期
upper Lower Jurassic → 下部ジュラ系上部
となります.これではまぎらわしいと想定される場合は,それぞれ,前期ジュラ紀の後期,下部ジュラ系の上部,のように「の」を付して使用するのもよいでしょう.これまではジュラ紀の前半と後半を,ジュラ紀前期,ジュラ紀後期と記述している例も多かったので,違和感があるかもしれません.しかし,この用法を継いでジュラ紀前期の後半をジュラ紀前期後期,あるいは後期ジュラ紀前期と記述するのも同様に違和感が残ります.いずれの表現を採るにしてもこれといった決め手はなく,後は規則に慣れるしかありません.英語表記に近づけて表現し,さらに細分するときは誤解を避けるために時代名の直後に「形容詞句」を置いたということです.
以上,JISの年代表記法について簡単に解説しました.JISに定められた表記法に関して理解が共有されることにより,日本における地球科学のコミュニティーの中での情報伝達がいっそう正確になると期待されます.すでに国土交通省や自治体等の行政機関に納品される地質調査業務報告書等では,地質年代表記を含む地質用語・記号等はJISに定められた表記法を使用することが義務づけられています.日本地質学会の出版物等でも,地質年代表記を含む地質用語・記号等の使用はJISに準拠することを推奨しています.JIS A 0204及びJIS A 0205は,論文や記事を執筆の際にも,地質用語・記号等の表記法の拠り所となるものですので,会員の皆様も是非ご参照ください.
(JIS・標準担当理事 中澤 努)
【文 献】
Gradstein, F. M., Ogg, J. G., Schmitz, M. D. and Ogg, G. M., eds., 2012a, The Geologic Time Scale 2012, Volume 1. Elsevier, 435p.
Gradstein, F. M., Ogg, J. G., Schmitz, M. D. and Ogg, G. M., eds., 2012b, The Geologic Time Scale 2012, Volume 2. Elsevier, 1144p.
【参考URL】
国際層序委員会(ICS)のチャート/タイムスケール http://www.stratigraphy.org/index.php/ics-chart-timescale
日本工業標準調査会(JIS検索ができます) http://www.jisc.go.jp
JIS A 0204「地質図―記号,色,模様,用語及び凡例表示」
JIS A 0205「ベクトル数値地質図―品質要求事項及び主題属性コード」
*JIS検索でJIS A0204,JIS A0205を検索し,詳細画面を表示することにより内容を閲覧することができます.
(2014.11.17掲載,2016.3.17,2018.1.25 一部修正)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
* International Chronostratigraphic Chart(日本語版)の最新版は下記に掲載しています。
■地質系統・年代の日本語記述ガイドライン(学会サイト内)PDFファイルがダウンロードできます。
この日本語版は,IUGSの許諾を得て日本地質学会が作成したもので,年代層序単元の日本語表記はJIS規格に準拠しています。
2015年地質の日(本部・各支部等)
2015年の「地質の日」
2015年の「地質の日」に関連した日本地質学会の催しをご紹介します。
本部行事 ・ 近畿支部 ・ 北海道支部 ・四国支部NEW・ 三浦断層活断層調査会
日本地質学会 4.6更新
一般社団法人日本地質学会,一般社団法人日本応用地質学会 主催
2015 年地質の日記念 街中ジオ散歩in Tokyo
日時: 5月10日(日)10:00〜15:30 少雨決行(予定)
場所: 東京都世田谷区等々力周辺
詳しくは,http://www.geosociety.jp/name/content0132.html
*定員に達しましたので,申込受付を終了いたしました。
多数のお申込をいただき,ありがとうございました。(4/6現在)
一般社団法人日本地質学会 主催
講演会「日本の地質学:最近の発見と応用2015」
Recent progress in geological science in Japan, 2015
日時:5月23日(土)12:40〜14:40
会場:北とぴあ第1研修室 (東京都北区王子)
プログラム(順番は変わる可能性があります)
・「デジタル岩石物理を用いた新しいアプローチによる地質・水理特性の定量化への試み:実験とシミュレーションの融合に向けて」
辻 健(九州大学)
・「伊豆-小笠原前弧域から採取されたかんらん岩から推測される島弧初期の上部マントル構造」
針金由美子(産業技術総合研究所)
・「島弧の熱構造とエネルギー抽出−超臨界地熱掘削−」
土屋範芳(東北大学)
・「H26年広島土砂災害、土石流災害の実像に迫る−地質屋の役割−」
横山俊治(高知大学)
本講演会への参加は,CPDの対象となります(CPDH:2単位)
参加費:会員無料,非会員500円.[事前申込不要]
当日は,同会場にて以下の行事が予定されています.
・第6回惑星地球フォトコンテスト表彰式(11:00〜12:00)
※作品展示有り▶入選作品紹介(準備中)
・一般社団法人日本地質学会第7回総会(14:50〜15:50)
※正会員は,総会に陪席することができます
問い合わせ先(世話人)
斎藤 眞(常務理事)・竹内 誠(行事委員長)
e-mail:main@geosociety.jp
一般社団法人日本地質学会 主催
第6回惑星地球フォトコンテストほか入選作品展示会
日時:6月13日(土)15:00頃〜6月27日(土)午前中
場所:銀座プロムナードギャラリー(中央区銀座4丁目地内 東銀座地下歩道壁面)
本年(第6回惑星地球フォトコンテスト)をメインに過去の入選作品も展示します.皆様お誘い合わせの上是非お越し下さい.
http://www.photo.geosociety.jp/
近畿支部 2.27更新
共催:日本地質学会近畿支部・大阪市立自然史博物館・地学団体研究会大阪支部
第32回地球科学講演会「阪神淡路大震災以降の近畿の活断層研究」
1995年兵庫県南部地震(M7.3)は死者6400名を越す未曽有の大災害を発生させたが、これは六甲・淡路島断層帯の活動によるものであった。この地震を引き起こした既知の活断層(野島断層)が淡路島北西側沿いに鮮明な断層変位を出現させ、活断層調査の必要性を広く認識させた。これを契機に地震調査研究推進本部が政府に設立されるとともに、基盤的調査観測の活断層として98本(後に110本に追加)が選定され、これらを中心に各種の詳細な活断層調査が実施されてきた。約10数年にわたる調査・研究の成果を総合的に取りまとめて、各活断層(帯)の位置や形状、活動履歴や長期的な発生時期の評価、地震規模、強震動の予測なども公表されてきた。その後も補完的な調査も実施されてきているが、近畿地域における主要活断層の調査研究の成果や残された問題点について紹介する。
日時:5月10日(日)13:30〜15:30 (受付は12:30〜)
場所:大阪市立自然史博物館 講堂
講師:岡田篤正氏(京都大学名誉教授・立命館大学客員研究員)
定員:250名(先着順)申込不要/参加費無料(博物館入館料必要)
問い合わせ先:大阪市立自然史博物館
TEL: 06-6697-6221 FAX: 06-6697-6225
E-mail: monitor@mus-nh.city.osaka.jp
北海道支部 4.8更新
記念企画展示「札幌の過去に見る洪水・土砂災害」
共催:北海道大学総合博物館・日本地質学会北海道支部・産総研地質調査総合センター・道総研地質研究所・北海道博物館・札幌市博物館活動センター・北海道地質調査業協会
札幌は自然災害の少ない街との印象がありますが、過去には大規模な洪水災害、震度6 程度と推定される地震、強烈な台風などがありました。本展では、洪水災害を中心に札幌周辺の自然災害について展示・解説し、自然災害への備えの重要性を喚起します。
期間:4月28日(火)〜5月31日(日) 開館時間 9:00〜17:00
会場:札幌市資料館1階 大通西13丁目
詳しくは,北海道支部のページをご覧下さい。
四国支部 4.20更新
岩石・鉱物鑑定会
地質の日において一般市民の方に,地質・岩石を身近に感じて頂くため,市民の方々から岩石や鉱物を持ち寄って頂き,鑑定を行います.またそれぞれの地質学的な重要性をわかり易く解説します.お持ち帰り用の岩石・鉱物・化石などもご用意します.
日時:2015年5月10日(日)11:00〜16:00
主催:愛媛大学理学部地球科学科・日本地質学会四国支部
会場:愛媛大学ミュージアム中庭(松山市文京町3)(※雨天の場合は,多目的室)
問い合わせ先:
愛媛大学大学院理工学研究科 堀 利栄
電話 089-927-9644 メール shori[at]sci.ehime-u.ac.jp
*ポスター画像をクリックするとPDFファイルがダウンロードできます。
三浦断層活断層研究会 4.8更新
後援:日本地質学会
地質の日記念観察会:深海から生まれた城ヶ島
三浦半島最南端の城ヶ島は風光明娼な観光地として知られています.この自然豊かな城ヶ島には動物・植物ばかりでなく,たくさんの変化に富んだ地形・地質を見ることができます.炎のように舞い上がる火山灰,深海に生活する生物の巣穴,激しい火山爆発によってもたらされた火山豆石やゴマ塩火山灰などなど.城ヶ島には,三浦半島誕生の秘密がたくさん詰まっています.今回は,火山活動と地震活動に焦点をあてて城ヶ島の自然を楽しみます.たくさんの方のご参加をお待ちしています.
開催日:5月23日(土)10:00〜15:00(小雨決行)
集合場所・時間:京急バス城ヶ島バス停(終点) 10:00
場所:三浦市城ヶ島
集合受付:10:00三崎口発城ヶ島行き9:11,9:33(ぎりぎり)
城ヶ島西部灘が崎(10:10)…観光橋(10:30)…長津呂崎(11:30)…昼食(12:00)…馬の背門(13:00)…城ヶ島東部安房崎(14:00)…城ヶ島公圏第二駐車場終了(14:30)…解散(15:00)
帰路のバス停は「白秋碑前」です.三崎口行き14:28,14:58,15:27
募集人数: 50 名
注意事項:海岸の岩場を歩くので,履き慣れた靴をご用意ください.昼食は持参してください.
申し込み:往復はがきあるいはe-mailに住所,氏名,電話番号をご記入の上,4月30 日(木)までに下記三浦半島活断層調査会事務局までお申し込み下さい.
参加費用:500 円(資料代(城ヶ島たんけんマップ等)+保険料
申込先:三浦半島活断層調査会事務局(松崎健一方)
電話 046-825-6665 所在地〒238–0042 横須賀市汐入町3丁目23番地
e-mail:k345matsu[a]yahoo.co.jp
随時「地質の日」関連の情報を随時ご紹介していく予定です。お楽しみに。
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2015年7月-8月)
7-8月のイベント・特別展示カレンダー (2015/07/01〜2015/08/31)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
7-8月の特別展示
2015/8/10 現在
特別展「南アジアの恐竜時代」(福井県立恐竜博物館)
期間:7/10(金)〜10/12(月・祝)
場所:福井県立恐竜博物館3階 特別展示室
アジア南部の恐竜に焦点を当て,タイ産プウィアンゴサウルスや中国・浙江省産アンキロサウルス類(鎧竜類),ラオス国外では初公開となるイクチオベナトール(獣脚類)などを展示し,福井の恐竜との関連性も注目して紹介します.
詳しくはこちら
三池炭坑専用鉄道の歩みと現在(福岡県 大牟田市石炭産業科学館)
期間:7/18(土)〜8/30(日)
場所:大牟田市岬町 大牟田市石炭産業科学館
三池炭坑専用鉄道敷跡は三池炭坑関連施設を構成する資産の1つです.今回は世界遺産登録勧告を記念し,この専用鉄道の歩みと現在の姿をご紹介します。
詳しくはこちら
移動展「見る・さわる 世界の化石」(福島県 福島県立博物館・三春町歴史民俗資料館)
期間:7/18(土)〜8/30(日)
場所:福島県立博物館・三春町歴史民俗資料館
福島県立博物館所蔵の世界の化石の展示。さわって体験できるハンズオン型。
詳しくはこちら
ズバッとアンモナイト展(静岡県 奇石博物館)
期間:7/18(土)〜12/23(水)
場所:奇石博物館本館の企画展示室
ドイツ産のジュラ系アンモナイトのコレクションの一部を紹介します。本コレクションは、ジュラ紀の初期から末期までを網羅したクランツ社製1500点あまりのアンモナイト標本で構成されています。展示では、示準化石としての側面に加え、アンモナイトの生態などにも触れます。
詳しくはこちら
シェルズ −貝類の現在と過去をさぐる−(徳島県 徳島県立博物館)
期間:7/18(土)〜8/30(日)
場所:徳島県立博物館 1階企画展示室
貝類(軟体動物)は、節足動物に次いで種数の多いグループです。その一部は食用として利用されるなど、人間生活とも密接なつながりがあります。また貝化石は、最も普通に産出する大型化石であり、化石記録がたいへん豊富です。この展示では、多様性に満ちた貝類とその化石が示す貝類の現在と過去を、多数の資料や、写真・動画をもとに紹介します。
観覧料無料 詳しくはこちら
第23回企画展示「琵琶湖誕生-地層にねむる7つの謎−」(滋賀県 琵琶湖博物館)
期間:7/18(土)〜11/23(月)
場所:滋賀県草津市(琵琶湖博物館)
広いだけでなく日本一古く、世界でも有数の古い湖である琵琶湖の誕生と400万年の環境変化、生き物の謎について、豊富な化石と地層標本の展示で紹介します。とくに、普段目にすることが少ない、過去の琵琶湖がつくった地層の標本や、現在の日本にはいないゾウやワニなどの生き物の化石がご覧いただけます。
詳しくはこちら
企画展示「殻がつくる世界」(新潟県 新潟大学学術情報基盤機構旭町学術資料展示館)
期間:7/11(土)〜8/28(金)
場所:新潟大学駅南キャンパス ときめいと
生命の痕跡としてだけではなく,生物多様性を知る身近な題材である様々な「殻」を展示します
日本地質学会後援
http://www.lib.niigata-u.ac.jp/tenjikan/
企画展「豊橋周辺の第四紀化石」(国際第四紀学連合第19回大会組織委員会・日本第四紀学会・豊橋市自然史博物館)
期間:6/27(土)〜7/19(日)
場所:豊橋市自然史博物館
国際第四紀学連合第19回大会開催記念 一般普及講演会にあわせて、関連した化石を展示紹介します。
第49回企画展「恐竜時代の海の支配者」(群馬県立自然史博物館)
期間:7/11(土)〜8/31(月)
場所:群馬県立自然史博物館 企画展示室
恐竜時代の海を支配していた、クビナガリュウやギョリュウなどの海生爬虫類の実物やレプリカなどの標本を展示し、それらの進化や特徴的なからだの構造,そして当時の生態系や海洋環境の移り変わりなどを紹介します。
http://www.gmnh.pref.gunma.jp/index.html
第30回特別企画展天空を制した巨大翼竜と鳥たち(豊橋市自然史博物館)
期間:7/10(金)〜8/30(日)
場所:豊橋市自然史博物館 特別企画展示室
史上最大の翼竜ケツァルコアトルス(復元模型)や鳥などの空飛ぶ脊椎動物を紹介。http://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/03event/h27/tokuten/index.html
▶▶2015年9-10月のイベントカレンダー
7-8月のイベント
2015/6/22 現在
日付
イベント
7/1
(水)
▼
7/2
(木)
▼
7/3
(金)
▼
7/4
(土)
サイエンス・サタデー「翼竜アンハングエラ型グライダーをつくろう」(群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 実験室
時間:14:00〜15:00
自然史博物館に展示されている翼竜「アンハングエラ」を元にデザインされたグライダーを作るとともに、中生代の空に君臨した翼竜についても紹介します。
当日申込み、先着30名
7/5
(日)
第69回地質観察会「綱取の地層観察とイワシ化石採集」(岩手県 岩手県立博物館)
場所:北上市和賀川中流の綱取付近
時間:10:00〜15:00
北上市和賀川中流の綱取付近で地層の観察と、菱内川流域でヒシナイイワシの化石採集を行います。
要申込.往復はがきまたは電子メール 詳細は当館HP参照
7/6
(月)
▼
7/7
(火)
▼
7/8
(水)
▼
7/9
(木)
▼
7/10
(金)
▼
7/11
(土)
企画展講演会「フタバスズキリュウ発掘物語」(群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 学習室
時間:13:30〜15:30
講師:長谷川善和(群馬県立自然史博物館名誉館長、横浜国大名誉教授)、日本の中生代爬虫類の中では最も有名であろうフタバスズキリュウやその発掘に関するエピソードについて紹介します。。。
定員100名、博物館に電話申込み(0274-60-1200; 一ヶ月前の9:30から)、対象は小学生以上、小学3年生以下は保護者同伴。
サイエンス・サタデー「翼竜アンハングエラ型グライダーをつくろう」(群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 実験室
時間:14:00〜15:00
自然史博物館に展示されている翼竜「アンハングエラ」を元にデザインされたグライダーを作るとともに、中生代の空に君臨した翼竜についても紹介します。
当日申込み、先着30名
7/12
(日)
▼
7/13
(月)
▼
7/14
(火)
▼
7/15
(水)
▼
7/16
(木)
▼
7/17
(金)
▼
7/18
(土)
サイエンス・サタデー「翼竜アンハングエラ型グライダーをつくろう」(群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 実験室
時間:14:00〜15:00
自然史博物館に展示されている翼竜「アンハングエラ」を元にデザインされたグライダーを作るとともに、中生代の空に君臨した翼竜についても紹介します。
当日申込み、先着30名
学習教室「化石さがし入門」(愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:田原市、博物館学習室(博物館集合・解散・バス使用)"
時間:9:00〜15:00
化石産地を見学したり、カニや貝の化石を砂の中から探したりして化石の調べ方を学びます。
"定員:小4〜中3/25名、参加費:500円、往復はがきで7月2日(木)必着 ※往復ハガキの書き方はホームページ参照、※申込み多数の場合は抽選 "
7/19
(日)
企画展講演会「恐竜時代の海のなか」(群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 学習室
時間:13:30〜15:30
講師:佐藤たまき(東京学芸大准教授)、クビナガリュウの仲間をはじめとする中生代の海生爬虫類について、それぞれの進化やからだの特徴、そして最新の研究動向について紹介します。
定員100名、博物館に電話申込み(0274-60-1200; 一ヶ月前の9:30から)、対象は小学生以上、小学3年生以下は保護者同伴。
7/20
(月)
国際第四紀学連合第19回大会開催記念 一般普及講演会「豊橋周辺の第四紀化石」(愛知県 国際第四紀学連合第19回大会組織委員会・日本第四紀学会・豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市自然史博物館
時間:13:30〜16:00
「豊橋とその周辺の第四紀哺乳類化石」安井謙介(豊橋市自然史博物館 主任学芸員) 「更新世中期渥美層群の化石と研究史」松岡敬二(豊橋市自然史博物館 館長)
定員80名、自然史博物館へ電話(0532-41-4747)、FAX(0532-41-8020)またはメール(sizensi@toyohaku.gr.jp)で先着順。
シェルズ 展示解説(徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島県立博物館 1階企画展示室
時間:13:30〜16:00
特別陳列「シェルズ」の展示解説を行います。
観覧料無料。
7/21
(火)
▼
7/22
(水)
▼
7/23
(木)
▼
7/24
(金)
▼
7/25
(土)
サイエンス・サタデー「翼竜アンハングエラ型グライダーをつくろう」(群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 実験室
時間:14:00〜15:00
自然史博物館に展示されている翼竜「アンハングエラ」を元にデザインされたグライダーを作るとともに、中生代の空に君臨した翼竜についても紹介します。
当日申込み、先着30名
化石標本をつくろう(福島県 福島県立博物館・三春町歴史民俗資料館)
場所:三春町さくら湖自然観察ステーション
時間:14:00〜15:00
上の移動展の関連行事。貝化石の入った岩石ブロックから化石を取り出し、クリーニングをし、化石の名前を調べる体験講座。
先着40名
7/26
(日)
漂着物を探そう!(徳島県 徳島県立博物館)
場所:徳島県南方面
時間:9:00〜17:00
海岸は“宝の山”です!遠い南の島からやって来るヤシの実や色とりどりの浮き。そして、変わった形の流木など、いろいろな面白い漂着物を拾うことができます。海岸で漂着物を探すことは“ビーチコーミング”と呼ばれ、海外でもコレクションと散歩を兼ねた趣味として、たいへん人気があります。 みなさんも夏の想い出づくりに「漂着物=宝!」探しをしてみませんか? 貸し切りバスを使って県南の海岸をご案内します。
貸し切りバス利用、参加費無料。往復はがきに行事名、参加者全員のお名前、住所、電話番号を記入して、1か月前から10日前までに届くようにお申し込みください。
ファミリー自然観察会「川原の石を調べよう−夏休み自由研究教室−」(群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 実験室
時間:9:30〜12:00
夏休みの自由研究のネタとして、河原にある石を実際に観察・分類して調べてみます。
定員30名、博物館に電話申込み(0274-60-1200; 一ヶ月前の9:30から)、対象は4才以上、小学生以下は保護者同伴。保険料として50円が必要。
特別企画展記念講演会「巨大翼竜は飛べたのか―論文発表の反響とその後の進展」(愛知県 豊橋市自然史博物館)
場所:豊橋市自然史博物館
時間:14:00〜15:00
現生鳥類の飛行行動を調べることで、古生物学者も驚く巨大翼竜の生態が判明!巨大翼竜は本当に空を飛べたのか、気鋭の動物行動学者が最新の話題を提供します。
定員60名、自然史博物館へ電話(0532-41-4747)、FAX(0532-41-8020)またはメール(sizensi@toyohaku.gr.jp)で先着順。
7/27
(月)
▼
7/28
(火)
▼
7/29
(水)
▼
7/30
(木)
▼
7/31
(金)
子ども鉱物教室「鉱物のふしぎ」(神奈川県 相模原市立博物館)
場所:相模原市立博物館
時間:14:00〜16:30
ミョウバン結晶の育成実験や鉱物の硬さ比べなどを通して、鉱物についての初歩を学習します。全2回(7/31, 8/7)。
往復はがきに、①保護者を含む参加者全員(1枚につき5名まで)の氏名・学年(代表者に○)、②代表者の住所・電話番号、③返信用の宛名に住所・氏名を記入し、「子ども鉱物教室」係宛に郵送。6月15日〜6月30日必着。
8/1
(土)
石ころ探検隊の夏休みお助け石ころ肉眼鑑定会(静岡県 奇石博物館)
場所:博物館併設の研究学習棟2階教室
時間:9:00-11:00, 14:00-16:00
夏休みの自由研究のお手伝い、あるいは旅先で見つけた石ころ等々、 博物館に持参いただいた石の肉眼鑑定を学芸員が行います。当日の受付順に実施。無料。
サイエンス・サタデー「アンモナイト化石のカラーレプリカをつくろう」(群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:群馬県立自然史博物館 実験室
時間:14:00-15:00
中生代の海を代表する無脊椎動物であるアンモナイトのカラーレプリカを作ります。
当日申込み、先着30名
化石の模型をつくろう(群馬県 群馬県立自然史博物館)
場所:千葉県立中央博物館 研修室
時間:(8/1, 8/8;2回連続講座)10:00〜14:00
アンモナイトや恐竜の歯などいろいろな化石の模型づくりをします。
7月1日〜18日の間に下記URLから申込み下さい(2回分一括申込)。申込が定員を超えた場合は抽選となります。
8/2
(日)
石ころ探検隊の夏休みお助け石ころ肉眼鑑定会(静岡県 奇石博物館)
場所:博物館併設の研究学習棟2階教室
時間:9:00-11:00, 14:00-16:00
夏休みの自由研究のお手伝い、あるいは旅先で見つけた石ころ等々、 博物館に持参いただいた石の肉眼鑑定を学芸員が行います。当日の受付順に実施。無料。
8/3
(月)
▼
8/4
(火)
▼
8/5
(水)
▼
8/6
(木)
▼
8/7
(金)
▼
8/8
(土)
石ころ探検隊の夏休みお助け石ころ肉眼鑑定会(静岡県 奇石博物館)
場所:博物館併設の研究学習棟2階教室
時間:9:00-11:00, 14:00-16:00
夏休みの自由研究のお手伝い、あるいは旅先で見つけた石ころ等々、 博物館に持参いただいた石の肉眼鑑定を学芸員が行います。当日の受付順に実施。無料。
8/9
(日)
石ころ探検隊の夏休みお助け石ころ肉眼鑑定会(静岡県 奇石博物館)
場所:博物館併設の研究学習棟2階教室
時間:9:00-11:00, 14:00-16:00
夏休みの自由研究のお手伝い、あるいは旅先で見つけた石ころ等々、 博物館に持参いただいた石の肉眼鑑定を学芸員が行います。当日の受付順に実施。無料。
8/10
(月)
▼
8/11
(火)
▼
8/12
(水)
▼
8/13
(木)
▼
8/14
(金)
▼
8/15
(土)
▼
8/16
(日)
▼
8/17
(月)
▼
8/18
(火)
▼
8/19
(水)
▼
8/20
(木)
▼
8/21
(金)
▼
8/22
(土)
石ころ探検隊の夏休みお助け石ころ肉眼鑑定会(静岡県 奇石博物館)
場所:博物館併設の研究学習棟2階教室
時間:9:00-11:00, 14:00-16:00
夏休みの自由研究のお手伝い、あるいは旅先で見つけた石ころ等々、 博物館に持参いただいた石の肉眼鑑定を学芸員が行います。当日の受付順に実施。無料。
8/23
(日)
石ころ探検隊の夏休みお助け石ころ肉眼鑑定会(静岡県 奇石博物館)
場所:博物館併設の研究学習棟2階教室
時間:9:00-11:00, 14:00-16:00
夏休みの自由研究のお手伝い、あるいは旅先で見つけた石ころ等々、 博物館に持参いただいた石の肉眼鑑定を学芸員が行います。当日の受付順に実施。無料。
講演会「鳥類の初期進化」(福井県立恐竜博物館)
場所:福井県恐竜博物館3階 講堂
時間:14:00〜15:30
近年,中国遼寧省の熱河層群から多くの原始的な鳥類化石が発見されています.その最新の研究成果をふまえ,中国の鳥類化石研究の第一人者である周博士に,中生代の原始的な鳥類の進化について語っていただきます.
聴講無料.事前申込:不要
8/24
(月)
▼
8/25
(火)
▼
8/26
(水)
▼
8/27
(木)
▼
8/28
(金)
▼
8/29
(土)
石ころ探検隊の夏休みお助け石ころ肉眼鑑定会(静岡県 奇石博物館)
場所:博物館併設の研究学習棟2階教室
時間:9:00-11:00, 14:00-16:00
夏休みの自由研究のお手伝い、あるいは旅先で見つけた石ころ等々、 博物館に持参いただいた石の肉眼鑑定を学芸員が行います。当日の受付順に実施。無料。
8/30
(日)
石ころ探検隊の夏休みお助け石ころ肉眼鑑定会(静岡県 奇石博物館)
場所:博物館併設の研究学習棟2階教室
時間:9:00-11:00, 14:00-16:00
夏休みの自由研究のお手伝い、あるいは旅先で見つけた石ころ等々、 博物館に持参いただいた石の肉眼鑑定を学芸員が行います。当日の受付順に実施。無料。
8/31
(月)
▼
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ 内のフォームま たはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2015年9月-10月)
9-10月のイベント・特別展示カレンダー (2015/09/01〜2015/10/31)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
9-10月の特別展示
2015/10/19 現在
平成27年度展秋期特別展「後世に残したい 相模川流域の地球遺産—相模川をジオパーク—」(平塚市博物館)
期間:10/17(土)〜11/29(日)
場所:平塚市博物館(平塚市浅間町)
詳しくはこちら
▶▶2015年11-12月のイベントカレンダー
9-10月のイベント
2015/3/3 現在
日付
イベント
9/1
(火)
▼
9/2
(水)
▼
9/3
(木)
▼
9/4
(金)
▼
9/5
(土)
▼
9/6
(日)
▼
9/7
(月)
▼
9/8
(火)
▼
9/9
(水)
▼
9/10
(木)
▼
9/11
(金)
▼
9/12
(土)
▼
9/13
(日)
▼
9/14
(月)
▼
9/15
(火)
▼
9/16
(水)
▼
9/17
(木)
▼
9/18
(金)
▼
9/19
(土)
▼
9/20
(日)
講演会「アジア南部における竜脚形類の進化」(福井県立恐竜博物館)
場所:福井県恐竜博物館2階 研修室
時間:13:00〜14:30
講師:当館 関谷 透 研究員.アジア南部の竜脚形類は,タイ・ラオス・中国(南部)などから見つかっています.ジュラ紀の「古竜脚類」と呼ばれる原始的なグループから,白亜紀の進化したティタノサウルス形類まで,進化の道すじをたどってみましょう.
聴講無料.事前申込:不要
9/21
(月)
▼
9/22
(火)
▼
9/23
(水)
▼
9/24
(木)
▼
9/25
(金)
▼
9/26
(土)
▼
9/27
(日)
▼
9/28
(月)
▼
9/29
(火)
▼
9/30
(水)
▼
10/1
(木)
▼
10/2
(金)
▼
10/3
(土)
▼
10/4
(日)
▼
10/5
(月)
▼
10/6
(火)
▼
10/7
(水)
▼
10/8
(木)
▼
10/9
(金)
▼
10/10
(土)
▼
10/11
(日)
▼
10/12
(月)
▼
10/13
(火)
▼
10/14
(水)
▼
10/15
(木)
▼
10/16
(金)
▼
10/17
(土)
10/18
(日)
▼
10/19
(月)
▼
10/20
(火)
▼
10/21
(水)
▼
10/22
(木)
▼
10/23
(金)
▼
10/24
(土)
▼
10/25
(日)
▼
10/26
(月)
▼
10/27
(火)
▼
10/28
(水)
▼
10/29
(木)
▼
10/30
(金)
▼
10/31
(土)
▼
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ 内のフォームま たはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
博物館のイベント・特別展示カレンダー (2015年11月-12月)
11-12月のイベント・特別展示カレンダー (2015/011/01〜2015/12/31)
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展示
イベント
11-12月の特別展示
2015/10/19 現在
平成27年度展秋期特別展「後世に残したい 相模川流域の地球遺産—相模川をジオパーク—」(平塚市博物館)
期間:10/17(土)〜11/29(日)
場所:平塚市博物館(平塚市浅間町)
詳しくはこちら
▶▶2016年1-2月のイベントカレンダー(準備中)
11-12月のイベント
2015/3/3 現在
日付
イベント
11/1
(日)
▼
11/2
(月)
▼
11/3
(火)
▼
11/4
(水)
▼
11/5
(木)
▼
11/6
(金)
▼
11/7
(土)
▼
11/8
(日)
▼
11/9
(月)
▼
11/10
(火)
▼
11/11
(水)
▼
11/12
(木)
▼
11/13
(金)
▼
11/14
(土)
▼
11/15
(日)
▼
11/16
(月)
▼
11/17
(火)
▼
11/18
(水)
▼
11/19
(木)
▼
11/20
(金)
▼
11/21
(土)
▼
11/22
(日)
▼
11/23
(月)
▼
11/24
(火)
▼
11/25
(水)
▼
11/26
(木)
▼
11/27
(金)
▼
11/28
(土)
▼
11/29
(日)
▼
11/30
(月)
▼
12/1
(火)
▼
12/2
(水)
▼
12/3
(木)
▼
12/4
(金)
▼
12/5
(土)
▼
12/6
(日)
▼
12/7
(月)
▼
12/8
(火)
▼
12/9
(水)
▼
12/10
(木)
▼
12/11
(金)
▼
12/12
(土)
▼
12/13br /> (日)
▼
12/14
(月)
▼
12/15
(火)
▼
12/16
(水)
▼
12/17
(木)
▼
12/18
(金)
▼
12/19
(土)
▼
12/20
(日)
▼
12/21
(月)
▼
12/22
(火)
▼
12/23
(水)
▼
12/24
(木)
▼
12/25
(金)
▼
12/26
(土)
▼
12/27
(日)
▼
12/28
(月)
▼
12/29
(火)
▼
12/30
(水)
▼
12/31
(木)
▼
情報をご提供いただいた博物館の皆様,ご協力ありがとうございました。
博物館等 関係者の皆様へ
上記の期間およびそれ以降に実施を予定されている地学関係のイベントがございましたら、是非、学会Webページ 内のフォームま たはメールにて情報をお寄せください。
その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。
イベント種別: (特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
都道府県:
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
内容:
事前申込: (必要・不要 のいずれか)
申込詳細: 必要な場合のみ
URL:
街中ジオ散歩in Tokyo2015
2015年地質の日記念
毎年5月10日は地質の日です.この日は明治9年(1876),ライマンらによって日本で初めて広域的な地質図が作成された日です.また,明治11年(1878)のこの日は,地質の調査を扱う組織(内務省地理局地質課)が定められた日でもあります.近年この地質の日にちなんで様々な機関で記念イベントが開かれており,当学会でも,2012年より日本応用地質学会との共同主催で東京都内の徒歩見学会をご好評の中,開催しています.
定員に達しましたので,申込受付を終了いたしました。
多数のお申込をいただき,ありがとうございました。(4/6現在)
************************************************************************
街中ジオ散歩 in Tokyo
「等々力渓谷の地質と人の関わり」徒歩見学会
主 催:
一般社団法人日本地質学会,一般社団法人日本応用地質学会
後 援:
世田谷区教育委員会,一般社団法人東京都地質調査業協会
日 時:
2015年5月10日(日)10:00〜15:30 少雨決行(予定)
場 所:
東京都世田谷区等々力周辺
案内者:
鈴木毅彦氏(首都大学),中山俊雄氏(元東京都土木技術支援・人材育成センター),寺田良喜氏(世田谷区教育委員会)
趣 旨:
身近な地質とその地質に由来した地形,それらを利用してきた先人から現在の私たちまでの営みを,春の清々しい空気の中でのんびり歩きながら,ベテラン案内者からの興味深い説明を聞き,楽しく学ぼうという企画です.今回は,23 区内でも数少ない自然露頭が残っている等々力渓谷において,東京南部に分布する地質と地形を学びます.また,多摩川の河原に下り現在の河床の石の観察も行います.更に,世田谷区教育委員会の協力を頂き「帆立貝式古墳」として有名な「野毛大塚古墳」の見学もします.
会 費:
一般2,000 円, 小中学生500 円(予定)保険代,入場料を含みます.当日お支払い下さい.昼食は各自ご用意下さい.
見学コース:
10:00 東急等々力駅北側集合(世田谷区玉川支所前)→等々力渓谷(上総層群,東京層,東京軽石,武蔵野礫層)→等々力不動(武蔵野面,立川面)→丸子川(六郷用水)→青少年センター(昼食・説明会)→多摩川(河川敷の石観察)→玉川野毛町公園(野毛大塚古墳)→東急等々力駅解散15:30 頃
(予定,天候等により順序,見学地を変更する場合があります)
募集人員:
30名程度(定員になり次第締め切ります)
対 象:
一般.参加資格は特にありません.小学生以上の方でしたらどなたでもお申し込み頂けます.小中学生の方は保護者の方の同伴をお願いいたします.普及事業のため,一般からの申込を優先します.定員に余裕がある場合,会員の方にもご参加頂けます.
申込受付期間:2015年4月1日(水)〜
[定員になり次第締め切り]
定員に達しましたので,申込受付を終了いたしました。
多数のお申込をいただき,ありがとうございました。(4/6現在)
申込・問い合わせ先:
一般社団法人日本地質学会 事務局(担当 細矢)
電話:03-5823-1150
FAX:03-5823-1156
メール:main@geosociety.jp
2016年地質の日(本部・各支部等)
2016年の「地質の日」
2016年の「地質の日」に関連した日本地質学会の催しをご紹介します。
/北海道/東 北/中 部/関 東/近 畿NEW/四 国/西日本/その他
日本地質学会 3.28 掲載
画像をクリックするとPDFが
ダウンロードできます
2016年地質の日記念 街中ジオ散歩in Tokyo
「国会議事堂の石を見に行こう」
主催:(一社)日本地質学会,(一社)日本応用地質学会
後援:(一社)東京都地質調査業協会
日時:2016年5月14日(土) 1回目 10:00〜11:30/2回目 14:00〜15:30
見学場所:国会議事堂衆議院内(東京都千代田区永田町)
案内者:乾 睦子(国士舘大学),中澤 努(産業技術総合研究所)
趣旨:今年はなかなか見ることのできない,国会議事堂の石の見学会を企画しました.国会議事堂の建設にあたっては日本中から石材が集められ,日本の地質が変化に富んだものであるかを改めて感じることができます.
会費:一般1,500円,小中学生500円 (保険代含む,小中学生は保護者同伴)
募集人員:各回25名(定員を超えた場合は,締切後抽選)
募集期間:4月4日(月)〜15日(金)申込は締切ました。多数のお申込をいただきありがとうございました。
対象:参加資格は特にありません.今回は会員の参加も受け付けます.
申込に際しての注意事項(重要):
1)申込の際に必ず希望の回を明記してください.
2)会員については両主催学会合わせて25名程度を予定しており,募集期間終了後に抽選とさせていただきます.
3)事前に氏名や連絡先等を含む見学者名簿を見学先に提出します.
4)見学会当日は,一部を除いて写真撮影はできません.
5)申込時には保険加入や名簿作成のために必要な情報をお知らせ頂きます.申込項目には漏れなく記入をお願いします.記入頂けない場合は,お申込は受付できません.
6)中学生以下の方は保護者同伴でお申込下さい(保護者の分も別途申込手続きを行って下さい).
7)お申込いただいた方は上記事項に同意していただけたものとみなします.
申込方法:上記注意事項をよくご確認のうえ,FAXまたはWEB専用申込フォームからお申し込み下さい(お電話でのお申込はお受けできません).FAXでお申込の場合は,必ず,1. 参加を希望する回,2. 氏名(ふりなが),3. メールアドレス,4. 連絡先住所,5. 電話番号(緊急連絡先),6. 生年月日,7. 性別 8. 会員,非会員の別 を明記して下さい.
(注)参加者へは,4月中に参加票(ハガキ)をお送りします.抽選の場合,当選の発表は,参加票の発送をもって代えさせて頂きます.
申し込み・問い合わせ先:
日本地質学会(担当 細矢) TEL:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156
▶▶▶専用申込フォームはこちら
第7回惑星地球フォトコンテスト入選作品展示会
● 地質標本館(茨城)(地質標本館2016年春の特別展・第7回惑星地球フォトコンテスト入選作展示会「地球写真の世界」)
日本地質学会・産業技術総合研究所地質調査総合センター 共催
日程:2016年4月19日(火)〜5月22日(日)
場所:地質標本館(茨城県つくば市東1-1-1)入館無料
<表彰式>4月23日(土)13:30〜 1階ホール
<白尾委員長特別講演会>「地球を見た!撮った!」4月23日(土)14:30〜 映像室
>>>詳しくは,こちら
● 銀座プロムナードギャラリー(東京)
日程:2016年6月11日(土)午後〜6月25日(土)12:00
場所:銀座プロムナードギャラリー(中央区銀座4丁目 東銀座地下歩道壁面)
>>>フォトコンテストのサイト>http://www.photo.geosociety.jp/
講演会「日本の地質学:最近の発見と応用2016」
Recent progress in geological science in Japan, 2016
一般社団法人日本地質学会 主催
日時:5月21日(土)11:00〜13:00
会場:北とぴあ 第2研修室 (東京都北区王子)
プログラム(2016.4.5更新:タイトルをクリックするする講演要旨PDFがDLできます)
11:00-11:30
海底堆積物に残された地震・津波の記録:陸上記録との統合的解釈の重要性
池原 研 ・宇佐見和子(産総研)・金松敏也(JAMSTEC)
11:30-12:00
力学情報に基づく断層活動性評価手法−地殻応力と断層姿勢に基づく評価の可能性と意義−
宮川歩夢・大坪 誠(産総研)
12:00-12:30
ツノガイ球状コンクリーションの成因と形成速度
吉田英一(名古屋大)
12:30-13:00
間氷期MIS 19の千年スケールの磁気・気候層序:冷夏―地磁気逆転―猛暑の晩夏
兵頭政幸(神戸大)
本講演会への参加は,CPDの対象となります(CPDH:2単位)
参加費:会員無料,非会員500円.[事前申込不要]
当日は,同会場にて以下の行事が予定されています.
・一般社団法人日本地質学会第8回総会(14:15〜15:15)※正会員は,総会に陪席することができます
問い合わせ先(世話人):斎藤 眞(常務理事)・竹内 誠(行事委員長)
e-mail:main@geosociety.jp
近畿支部 4.11掲載
テーマ別自然観察会「岸和田市南部の地質」 NEW
主催:大阪市立自然史博物館・きしわだ自然資料館・地学団体研究会大阪支部・
日本地質学会近畿支部
岸和田市南部、河合町周辺には、白亜紀の断層活動によって地下10数キロ で
作られた、マイロナイトと呼ばれる変わった岩石が分布します。他にも周辺に
は花こう岩と大阪層群の関係が見られる露頭、1500万年前の火山活動による岩
石など、様々な地質現象を観察することができます。中生代から現在に至る大
地のおいたちを観察してみましょう。
日時:5月29日(日) 終日 雨天中止
場所:岸和田市河合町周辺
講師:奥平敬元氏(大阪市立大学大学院理学研究科)・佐藤隆春氏(大阪市立
自然史博物館外来研究員)ほか
対象:小学生以上(小学生は保護者の同伴が必要)
定員:40名(定員を超えた場合は抽選)
参加費:100円、小学生50円
申込:大阪市立自然史博物館HPのイベントページの申込フォーム、往復はがき
又は電子メールに「岸和田市南部の地質に参加希望」と明記の上、希望者全員
の名前、年齢、住所、電話番号、返信用の宛名を書いて、5月13日(金)までに
届くように、大阪市立自然史博物館普及係宛に申し込んでください。
申込先:
自然史博物館ホームページ:http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
行事申込メールアドレス:gyouji[at]mus-nh.city.osaka.jp
住所(往復はがき申込先):〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園1-23
大阪市立自然史博物館普及係宛
その他:抽選の結果や参加方法などは返信でお知らせします。
問合せ先:大阪市立自然史博物館・中条(TEL: 06-6697-6221)
第33回地球科学講演会「カンブリア大爆発のあとさき」
主催:地学団体研究会大阪支部・日本地質学会近畿支部・大阪市立自然史博物館
5億数千万年前,古生代最初のカンブリア紀と呼ばれる時代の前半には,現在 海洋中で生息する主要な動物の祖先型がすでに出現していました.その時期に生 じた「カンブリア大爆発」と呼ばれる現象はあまりにも有名です.しかし,その 前後での地球生物環境の様子はあまり知られていません.カンブリア紀の前半 に,地球の海洋生物相はどのように移り変わっていったのでしょうか.時代背景 や移ろいを知ることによって,カンブリア大爆発の実像のみならず,その現象 が,後の地球生物環境の変遷に及ぼした影響を正しく評価できるはずです.今回 の講演では,中国やモンゴルでの野外調査のデータも紹介しながら,カンブリア 紀の海洋環境の変遷をわかりやすく紹介します.
日時:5月8日(日)13:30〜15:30 (受付は12:30〜)
場所:大阪市立自然史博物館 講堂
講師:江粼洋一氏(大阪市立大学 大学院理学研究科 地球学科 教授)
申込み:不要
※講演の手話通訳を希望される方は、4月19日(火)までに、博物館までご連絡ください。
問い合わせ先:大阪市立自然史博物館・地史研究室・塚腰
TEL: 06-6697-6221 FAX: 06-6697-6225
E-mail: monitor@mus-nh.city.osaka.jp
北海道支部 4.1掲載
画像をクリックするとPDFが
ダウンロードできます
北海道のジオパーク−地球の営みを体感する−
主催:「地質の日」展 実行委員会
共催:北海道大学総合博物館,日本地質学会北海道支部,産総研地質調査総合センター,道総研地質研究所,北海道博物館,札幌市博物館活動センター,小樽市総合博物館,北海道地質調査業協会
後援:北海道教育委員会,札幌市教育委員会
協力:洞爺湖有珠山ジオパーク,アポイ岳ジオパーク,白滝ジオパーク,三笠ジオパーク,とかち鹿追ジオパーク,十勝岳ジオパーク(美瑛・上富良野エリア)構想,カムイの大地ジオパーク構想,小樽軟石研究会,NPO 法人自然教育促進会
北海道は火山・山岳・湖沼などの地球活動に由来する自然景観に恵まれ,道内には現在「洞爺湖有珠山ジオパーク」や「アポイ岳ジオパーク」など,準備中を含め7か所のジオパークがあります.本展示では,それらの各地のジオパークを紹介することによって,道民・市民の皆さまに道内各地の自然の豊かさや自然の恵みを理解していただくとともに,それらをもたらす地球の営みについて知っていただきたいと思います.
日時:4月26日(火)〜6月5日(日)9:00〜19:00
場所:札幌市資料館 1階展示室(札幌市中央区大通西13丁目)【入場無料】
問い合わせ先: 北大総合博物館(在田)(電話:011-706-2414)
※5/2(月),5/9(月),5/16(月),5/23(月),5/30(月)は休館
関連イベント
● 市民地質巡検「ぶらり 小樽の地質と軟石建造物」
日時: 6月5日 (日) 9:30〜16:30
コース: 小樽軟石採掘跡,小樽運河プラザなど
定員: 約20名(中学生以上,体力に自信のある方)
参加費: 300円(保険代・資料代等込み,当日集金します)
申込方法: 5月20日(金) 消印有効.
往復はがき(1人に付き1枚) に「地質巡検申込み」と明記.返信先(住所)・氏名(フリガナも)・性別・生年月日及び当日連絡可能な電話番号を明記.
申込先: 〒047-0041 小樽市手宮 1丁目 3番 6号 小樽市総合博物館 本館 ※申込み多数の時は抽選
問合せ先: 小樽総合博物館 電話: 0134-33-2523
メール: museum@city.otaru.lg.jp
●市民セミナー「北海道のジオパークを語る」
日時: 5月7日 (土) 13:30〜16:30
場所: 札幌市資料館 2階 研修室
※入場無料(申込不要)
※座席数(54席)を超えた場合は立見となります.
その他 4.1掲載
画像をクリックするとJPEGが
ダウンロードできます
観察会 城ヶ島の関東大震災を体感する
主催:ジオ神奈川 後援:三浦市,日本地質学会
日時:5月7日(土)10:00〜15:00(*雨天の場合は,5/8に延期)
場所:神奈川県三浦市城ヶ島(集合場所:城ヶ島大橋バス停を予定)
参加費:500円
申込締切:5月4日(水)
申込方法:メールもしくは往復はがきで,住所,氏名,電話,年齢(保険用)を記入して下記までお申し込み下さい.申込後集合時間や集合場所等詳細をお知らせします.
申込・問い合わせ先:ジオ神奈川 代表 蟹江康光
〒249-0004 逗子市沼間2-9-4-405
メール:okinaebis@mac.com 電話:046-873-6283
観察会「深海から生まれた城ヶ島」
三浦半島最南端の城ヶ島は,風光明媚な観光地として知られています.この自然豊かな城ヶ島には美しい風景や動物・植物ばかりではなく,たくさんの変化に富んだ地形・地質を見る事が出来ます.炎が舞っているような火山灰の地層や複雑な断層,深海に生活していた生物の痕跡,激しい火山爆発によってもたらされた火山豆石やゴマ塩火山灰などなど.城ヶ島には三浦半島誕生の秘密がたくさん詰まっています.
主催:三浦半島活断層調査会
後援:三浦市(予定)・日本地質学会
日時:5月22日(日)10:00〜15:00 小雨決行
場所:神奈川県三浦市城ヶ島
集合時間・場所:10:00集合,京急バス白秋碑前バス停 城ヶ島公園第二駐車場
(三崎口城ヶ島行きバス 9:11発乗車をおすすめします.9:33ではギリギリ)
参加費:500円(資料,保険代)
募集人員:50名
注意事項:海岸の岩場を歩くので,履き慣れた靴でご参加下さい.飲み物,弁当は各時持参.
申込締切:5月10日(火)
申込方法:メールもしくは往復はがきで,住所,氏名,電話番号を記入して下記までお申し込み下さい.
申込・問い合わせ先:三浦半島活断層調査会事務局(赤須邦夫方)
〒249-0008 逗子市小坪5-16-11
メール:akasu@jcom.zaq.ne.jp
中国(県の石)
「県の石」:中国
▷「県の石」(大切なお願い/リスト/選定にあたって ほか)
<北海道・東北(青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島)>
<関東(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川)>
<中部・甲信越(新潟・長野・山梨・静岡・富山・石川・岐阜・愛知・福井)>
<近畿(滋賀・奈良・京都・三重・大阪・和歌山・兵庫)>
<四国(徳島・香川・高知・愛媛)>
<中国(岡山・広島・山口・島根・鳥取)>
<九州・沖縄(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)>
岡山県の「県の石」
◆岡山県の岩石
万成石(まんなりいし)(主要産地:岡山市)
カリ長石がピンク色を呈すことが特徴の中粒角閃石黒雲母花崗岩.後期白亜紀の火成活動で形成.全体に淡い桃色をなすことから桜御影とも呼ばれる.岡山駅西方の京山,矢坂山周辺に産し,鉄道交通の発達によって明治終わりころから石材(建築材・墓石)として用いられるようになった.ノグチイサムの彫刻や石原裕次郎の墓石などに用いられている.(写真サイズ:縦15cm.写真提供 鈴木茂之)
◆岡山県の鉱物
ウラン鉱(主要産地:苫田郡鏡野町上齋原人形峠)
鳥取県県境に接する人形峠鉱山から産出した。人形石(Ningyoite)や燐灰ウラン石などからなる。約700万年前頃(後期中新世)に堆積した人形峠層の砂岩礫岩中にウラン鉱は形成されている。周辺に分布する花崗岩が風化し、水に溶出した微量なウラン(酸化環境)が、地下水に混じって砂岩礫岩層の隙間を流れた際(還元環境)鉱物として固定されたものである。ウランが散逸せずに鉱物として固定されるメカニズムが核廃棄物処理のヒントになるとして着目されている。(写真:産業技術総合研究所所蔵,登録番号GSJ M18002)
◆岡山県の化石
成羽植物化石群(主要産地:高梁市成羽町,川上町の成羽層群分布域)
展示している場所:高梁市成羽美術館
イチョウ,ソテツなどの裸子植物とシダ植物を主体とする後期三畳紀の植物化石群.これらの多種類の化石群はOishi(1932)によって成羽フローラと定義され,中生代前期型植物の国際的なタイプとなっている.模式標本(北海道大学所蔵)の多くは1930年に設立された成羽地学同好会のメンバーによって採取されたもので,主な化石は現在も成羽美術館で展示されている.
(写真サイズ:縦5cm.写真提供 鈴木茂之)
このページtopへ戻る
広島県の「県の石」
◆広島県の岩石
広島花崗岩(主要産地:広島県南部(瀬戸内海沿岸地域および内陸部))
展示している場所:広島大学総合博物館・理学部サテライト.広島県の瀬戸内海沿岸部のいたるところで観察することができる.
広島花崗岩は,西南日本内帯の山陽帯と称される岩石区に分布する花崗岩を代表するもので,白亜紀末期の8,600万年前頃に貫入した珪長質の深成岩である.一般にカリ長石が淡いピンク色を呈しているが,倉橋島に産するものは色が濃く鮮やかで,国会議事堂の外装に使用されたことから「議院石」と呼ばれている.広島県内の地盤のおよそ40%は広島花崗岩からなっており,経済的恩恵にせよ,災害の要因にせよ,広島県民は広島花崗岩とともにあると言っても過言ではない.(写真提供:早坂康隆)
◆広島県の鉱物
蝋石(主要産地:広島県庄原市勝光山)
展示している場所:広島大学総合博物館・理学部サテライト
蝋石は,葉ろう石(pyrophyllite:Al2Si4O10(OH)2),滑石(talc:Mg3Si4O10(OH)2),カオリナイト(kaolinite:Al4Si4O10(OH)8)などの微細な結晶の集合体でロウのような質感をもつ軟らかい岩石の総称である.庄原市の勝光山鉱山に産するものは葉ろう石成分に富み,優れた耐火煉瓦の原料として,採掘されてきており,現在も操業中である.しばしば青色の微細なコランダムの集合体をともなうのが特徴である.(写真提供:早坂康隆)(2018.1.10一部訂正)
◆広島県の化石
アツガキ(主要産地:広島県庄原市、および三次市周辺の備北層群)
展示している場所:広島大学総合博物館
広島県北部の庄原、三次地域には新第三紀中新世のおよそ2,000〜1,200万年前頃に形成された備北層群とよばれる汽水〜海成の地層が分布し,ヒゲクジラやサメなどの大型化石をはじめとし,様々な種類の化石を産する.中でもアツガキの化石は備北層群の各所に多産し,希に長径30 cmにも達するものがある.牡蠣の養殖が盛んで,牡蠣をこよなく愛する広島県民にとって,アツガキは県の化石としてまことに相応しいものであろう.(写真提供:白石史人)
山口県の「県の石」
◆山口県の岩石
石灰岩(主要産地:秋吉台)
展示している場所:秋吉台
約3億4千万年前のサンゴ礁がプレートとともに移動し,日本列島に付加されて形成された.石灰岩で特徴づけられる秋吉台は,日本最大のカルスト台地であり,日本最大級の洞窟「秋芳洞」が発達する山口県のシンボルであり,国定公園および特別天然記念物,日本ジオパークに指定されている.また,石灰岩はセメント製造や製鉄に欠かせない鉱物資源でもあり,日本の近代化を支えた自給率100%の資源という側面もある.(写真提供:小原北士)
◆山口県の鉱物
銅鉱石(主要産地:長登銅山跡)
展示している場所:長登銅山文化交流館(大仏ミュージアム)
約1億年前,地球規模で火成活動が活発化した時期に,秋吉台の石灰岩にマグマが貫入し,その熱水作用により石灰岩と花崗斑岩の接触部に長登銅山の鉱床が生成された.その後この地域は隆起して陸地となったため,鉱床の露頭は風化によって酸化が進み,褐鉄鉱や孔雀石などからなる酸化鉱帯が生成された.
長登銅山は古代から近代まで断続的に稼働してきた銅山で,奈良の大仏鋳造の際,料銅を産出したことで知られている.古代は地表付近の酸化銅鉱,中世以降はより深い位置にある硫化銅鉱を採掘して,製錬していたと考えられている.また孔雀石などの酸化銅鉱は,古代より顔料として利用されており江戸時代後期には高級画材として高値で取引された.(写真:世界ジオパーク推進課)
◆山口県の化石
美祢層群の植物化石(主要産地:美祢市)
展示している場所:美祢市歴史民俗資料館、美祢市化石館
美祢層群からは約2億3000万年前のシダ類,トクサ,イチョウなどの植物化石が豊富に産出し,中生代三畳紀の植物化石研究において成果をあげてきた.また美祢層群は日本最古の昆虫化石が産出したことでも知られている.これら美祢層群の化石は,ペルム紀末におこった地球史上最大の大量絶滅から生命が再生した象徴ともいえる.美祢層群の植物は大量の石炭(無煙炭)を作り出した.その分布域は日本最大で,無煙炭は明治時代に始まった日本の近代化,戦後の高度経済成長を支えた.(写真:篠田健二)
このページtopへ戻る
島根県の「県の石」
◆島根県の岩石
来待石(きまちいし)(主要産地:松江市宍道町)
展示している場所:モニュメントミュージアム来待ストーン
来待石は約1400万年前の浅海に堆積した大森層の塊状凝灰質砂岩である.来待石は松江市宍道町来待周辺から採掘され,石材として古くは古墳時代の石棺に 始まり,江戸時代には御止石として藩外への持ち出しは松江藩の許可制となるほど重要視された.切り出しや加工がしやすく,新鮮な面では灰色を呈している が,酸化による風化が早いため黄褐色に変化し,趣のある石材として好まれており,現在でも石灯篭などに広く使われている.(写真:モニュメント・ミュージアム 来待ストーンの壁面.撮影:入月俊明)
◆島根県の鉱物
自然銀(主要産地:島根県大田市大森町 石見銀山)
展示している場所:石見銀山資料館
石見銀山は14〜19世紀まで銀を採掘して石見銀山と呼ばれ,19世紀以降は含金銀銅鉱山として大森鉱山と呼ばれた.当地には鉱染鉱床の「福石鉱床」と,鉱脈鉱床の「永久鉱床」がある.銀を多産したのは福石鉱床であるが両鉱床は成因的に関連が深い.銀をもたらした熱水脈跡は幅3mm程の鉉(つる)と呼ばれ,鉉を挟む数10cm幅に自然銀を多く含む「福石」が形成している.(写真:石見銀山資料館の銀鉱石(福石)撮影:亀井淳志)
◆島根県の化石
ミズホタコブネ(主要産地:県内各地(模式地:松江市玉湯町志布名)
展示している場所:島根大学ミュージアム
ミズホタコブネは軟体動物門頭足綱八腕形目アオイガイ科に属す絶滅したタコの仲間で,オウムガイに似た石灰質の殻を持ち,これが化石として残る.殻は薄く殻表には成長線が認められる.殻の内部は空洞で隔壁はない.松江市から新種として記載され,学名(Mizuhobaris izumoensis)に出雲という地名が用いられている.島根県東部に分布する約1300万年前の布志名(ふじな)層の泥岩から保存良好な化石が多産する.(写真:島根大学ミュージアムの展示物.撮影:入月俊明)
鳥取県の「県の石」
◆鳥取県の岩石
砂丘堆積物(主要産地:鳥取砂丘)
鳥取砂丘(鳥取市福部町岩戸〜鳥取市白兎)
鳥取市の千代川河口の東西、福部町岩戸〜白兎までの東西16km、南北2.4kmに広がる鳥取砂丘を構成する石英と長石を主とした風成砂(径0.8mm程度)であって,岩石ではない.砂丘堆積物は約4.5万年前に降灰した大山倉吉軽石層を境に古砂丘砂と新砂丘砂に区分される.砂丘がやや黄褐色をおびているのは粒子表面の汚れ(風化物付着)による.供給源は主として中国山地の山陰帯の花こう岩類(鳥取花こう岩など)である.(写真:鳥取砂丘(鳥取県))
◆鳥取県の鉱物
クロム鉄鉱(主要産地:日南町多里)
展示している場所:鳥取県立博物館(鳥取市東町2丁目124)
クロムを主成分とした酸化鉱物、化学組成は(Fe2+,Mg)(Cr,Al,Fe3+)2O4.多里のクロム鉄鉱は日本有数のクロム鉱床(クロム鉄鉱岩)を構成する鉱物ある.戦前・戦時中には国内生産量の約半分を担った歴史的価値もあり,若松鉱山は「多里地域クロム鉱山」として平成20年度経済産業省「近代化産業 遺産群続33選」に認定された.クロム鉱床は鳥取・広島・岡山県境部の古生代前期の超苦鉄質岩体中に胚胎する.(写真:クロム鉄鉱岩(鳥取県立博物館))
◆鳥取県の化石
中新世魚類化石群(主要産地:鳥取市国府町宮下)
鳥取県立博物館(鳥取市東町2丁目124)
国内の有数の保存のきわめて良好な魚類化石群であり,約1680万年前頃に堆積した栃本頁岩層から,浅い海に生息した10数種類の魚の化石を産出する.ミヤノシタシシャモ,ミヤノシタサッパ,トットリヒラメ,イナバケツギョなど.江戸時代から魚類化石産出の記録が存在する.日本海形成時期の浅海性魚類相の形成を知る上でも貴重であるだけでなく,西太平洋地域の現生浅海性魚類の起原と進化プロセスを知る上で重要である.(写真:イナバケツギョ(鳥取県立博物館))
このページtopへ戻る
四国(県の石)
「県の石」:四国
▷「県の石」(大切なお願い/リスト/選定にあたって ほか)
<北海道・東北(青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島)>
<関東(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川)>
<中部・甲信越(新潟・長野・山梨・静岡・富山・石川・岐阜・愛知・福井)>
<近畿(滋賀・奈良・京都・三重・大阪・和歌山・兵庫)>
<四国(徳島・香川・高知・愛媛)>
<中国(岡山・広島・山口・島根・鳥取)>
<九州・沖縄(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)>
徳島県の「県の石」
◆徳島県の岩石
青色片岩(せいしょくへんがん)(主要産地:眉山(びざん)〜高越(こうつ)地域)
展示してある場所:徳島県立博物館,徳島市立考古資料館,徳島県埋蔵文化財センター,美馬郷土博物館,海陽町立博物館
藍閃石に代表されるNa角閃石を多く含むために濃青色を呈する代表的な低温・高圧型変成岩.白亜紀の海洋沈み込みによって海洋底の玄武岩が地下30〜65kmもの深さに達し,プレート間力の元で構成鉱物が変化して生じた.東西800 kmに渡って延長する三波川変成岩類の中でも,まとまった産出が知られるのは徳島県の眉山-高越地域のみである.弥生時代の徳島県周辺では石庖丁や磨製石斧といった石器の材料として用いられていた.(写真提供:青矢睦月)
◆徳島県の鉱物
紅れん石(こうれんせき)(主要産地:徳島県徳島市眉山)
展示してある場所:徳島県立博物館
紅れん石は桃色〜黄色の多色性を持ち,おおむね長柱状の形態を示している.緑れん石族の鉱物で,3価のマンガンを含む.一般にペグマタイトやマンガン鉱床などに産するが,比較的低温の変成作用によって変成チャート中にも生じる.広域変成作用によって形成した紅れん石の報告は,小藤文次郎によるここ眉山地域の三波川変成岩類(変成年代は後期白亜紀)の例が世界初であった.
紅れん石石英片岩の偏光顕微鏡写真(開放ポーラー,横幅0.5 mm).写真提供:青矢睦月
◆徳島県の化石
プテロトリゴニア(Pterotrigonia pocilliformis)(主要産地:徳島県上勝町・勝浦町)
展示してある場所:徳島県立博物館
三角貝の化石は、中生代の示準化石として理科の教科書に登場する。徳島県勝浦川流域に分布する前期白亜紀の砂岩層(物部川層群傍示層)からは、本種が密集して産出し「菊目石」の愛称で親しまれている。密集層の石材標本は、県内各地の校庭にも展示されており、徳島県を代表する化石といえる。2004年には、上勝町が本種の化石をチョコレートで型取りし、地域紹介に活用、発信したことでも知られる。(写真提供:石田啓祐; 左上スケッチ:大竹 桜)
このページtopへ戻る
香川県の「県の石」
◆香川県の岩石
讃岐石(岩)(古銅輝石安山岩)(主要産地:五色台)
展示してある場所:香川大学博物館(香川県高松市幸町1-1),香川県立五色台自然センター(香川県高松市生島町432番地),高松市こども未来館(平成28年11月開館予定)(香川県高松市松島町1丁目15番1号),さぬき市雨滝自然科学館(香川県さぬき市大川町冨田中515−2)
讃岐石(古銅輝石安山岩)は,中新世の瀬戸内火山岩類を代表する岩石で,黒色緻密でガラス質石基が多い安山岩の一種です.打撃音から讃岐(香川県の旧国名)では古くから「かんかん石」と親しまれてきた.ドイツの地質学者であるヴァインシェンク博士が,東京帝国大学で初めて地質学を教授したナウマン博士がドイツに持ち帰った試料を研究して,代表的な産地である讃岐にちなんでSanukit(英語名はsanukite)と1891 年に命名した.(写真:香川大学博物館所蔵標本(五色台産))
◆香川県の鉱物
珪線石(主要産地:猫山)
香川県まんのう町の猫山には,かつて日本で珍しい珪線石鉱山がありました.珪線石はAl2SiO5で示されるアルミニウム珪酸塩鉱物のうち高温で安定なものです.地学の教科書にもとりあげられています.吉木文平「讃岐國猫山に於ける珪線石礦床に就いて」岩石礦物礦床學 11(3), 103-118, 1934.に詳細な記述があります.(写真:愛媛県総合科学博物館所蔵.展示は行っていない)
◆香川県の化石
コダイアマモ(主要産地:阿讃山脈)
展示してある場所:香川県立五色台自然センター(香川県高松市生島町432番地),高松市こども未来館(平成28年11月開館予定)(香川県高松市松島町1丁目15番1号),さぬき市雨滝自然科学館(香川県さぬき市大川町冨田中515−2)
コダイアマモは,後期白亜紀(およそ7千万年前)の海底に堆積した和泉層群に産出する化石で,かつては海草であるアマモ類の祖先の化石と考えられてきました.しかし,その後,植物学的検討の結果,アマモ類とは系統関係に無いことが指摘されています.最近では,植物化石という考えそのものに疑義が呈されており,海底で泥を食べていた生物がつくった生痕化石であると言う意見が主流になっています.(写真:香川県立五色台自然センター所蔵標本(旧財田町産))
高知県の「県の石」
◆高知県の岩石
花崗岩類(閃長岩)(主要産地:足摺岬)
展示してある場所:高知大学理学部1号館,サイエンスギャラリー
花崗岩は,石材としても使われる身近な岩石である.マグマが地下でゆっくり冷えることで作られ.,足摺岬の花崗岩類は約1300万年前(中期中新世)に形成された.日本列島がアジア大陸から分かれた頃の出来事で,その時代の四国では活発なマグマの活動があった.足摺岬の花崗岩類はナトリウムとカリウムに富む特殊な化学成分をもち,Aタイプ花崗岩とよばれるグループに分類される.また,ラパキビ花崗岩も産する.このような花崗岩類が見られるのは日本で足摺岬だけである.
◆高知県の鉱物
ストロナルシ石(せき)(主要産地:高知県高知市蓮台)
ストロナルシ石(せき)(Stronalsite,SrNa2Al4Si4O16)は,高知県から発見された最初の新鉱物である.ストロナルシ石は長石族の鉱物であり,黒瀬川構造帯内にある高知市蓮(れん)台(だい)の蛇紋岩採石場で,変成苦鉄質岩捕獲岩中に,スローソン石およびペクトライトとともに,白色細脈として見出された.蛇紋岩は高知県の重要な地下資源であり,その代表的な採石場で発見されたことも意義深い.(写真:国立科学博物館所蔵NSM-M24394 (タイプ標本) 左右約2.5cm)
◆高知県の化石
横倉山のシルル紀動物化石群(主要産地:高知県高岡郡越知町横倉山)
展示してある場所:高知県高岡郡越知町立横倉山自然の森博物館,高知県高岡郡佐川町立佐川地質館
越知町横倉山に広く分布する4億年前の古生代シルル紀の地層は,かつて赤道付近に存在したゴンドワナ大陸の一部であったシルル紀の“土佐桜”石灰岩を主とする地層からは,クサリサンゴ,ハチノスサンゴなどの造礁サンゴを始め,三葉虫・直角石等々当時のサンゴ礁に生息していた多種多様の生物群の化石を産する.これらは,日本最古の大型化石で,クサリサンゴの中にオーストラリアとの共通種が認められることは注目に値する.この他,日本唯一の「筆石」化石も見つかっている.(写真提供:安井敏夫)
このページtopへ戻る
愛媛県の「県の石」
◆愛媛県の岩石
エクロジャイト(主要産地:東赤石山周辺)
展示してある場所:愛媛県総合科学博物館
ひすい成分を含む輝石(オンファス輝石)とガーネット(ざくろ石)を構成鉱物とする代表的な高圧型変成岩.産出は希少だが,三波川変成岩類の分布する東赤石山周辺での分布範囲は日本で唯一数km2規模に及ぶ.一般に地下40km以深の高圧条件で形成され,地下深部での地質現象を解明するための重要な研究対象となる.別子地域の瀬場には2001年に新居浜市で開催された第6回国際エクロジャイト会議の記念碑(エクロジャイト製)が建てられている.(写真提供:青矢睦月)
◆愛媛県の鉱物
輝安鉱(主要産地:市之川鉱山)
展示してある場所:愛媛県総合科学博物館, 西条郷土博物館, 愛媛大学ミュージアム
愛媛県市之川鉱山産輝安鉱(stibnite)は,世界的な結晶鉱物として知られており,標本は伊予の国,市之川産として世界各国の名だたる自然史博物館に展示されている.輝安鉱結晶は晶洞に水晶を伴い最長60cmを超える巨晶群として産した.また多くの結晶面を持つ輝安鉱も産出しており,すばらしい結晶図が描かれている.世界的な市之川鉱山産輝安鉱は,日本を代表する鉱物であり,当然「愛媛県の鉱物」に最もふさわしいと断言できる.(写真提供:愛媛大学ミュージアム)
◆愛媛県の化石
イノセラムス(主要産地:宇和島, 松山〜四国中央部)
展示してある場所:愛媛大学ミュージアム, 愛媛県総合科学博物館
ジュラ紀から白亜紀にかけて栄えたイノセラムス科二枚貝の代表的な一属で,殻の外層に方解石からなるプリズム層が顕著に発達するという顕著な特徴を持つ.
分布は汎世界的で,有効な示準化石として用いられてきた.本県では宇和島層群,和泉層群などから数種が知られているが,中でも白亜紀コニアシアン期前半を示唆するInoceramus uwajimensisは,その学名に“宇和島産のイノセラムス”という意味を付与されている.(写真:愛媛大学理学部地球科学科所蔵.撮影:岡本 隆)
このページtopへ戻る
近畿(県の石)
「県の石」:近畿
▷「県の石」(大切なお願い/リスト/選定にあたって ほか)
<北海道・東北(青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島)>
<関東(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川)>
<中部・甲信越(新潟・長野・山梨・静岡・富山・石川・岐阜・愛知・福井)>
<近畿(滋賀・奈良・京都・三重・大阪・和歌山・兵庫)>
<四国(徳島・香川・高知・愛媛)>
<中国(岡山・広島・山口・島根・鳥取)>
<九州・沖縄(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)>
滋賀県の「県の石」
◆滋賀県の岩石
湖東流紋岩(主要産地:滋賀県南東部(東近江市永源寺,近江八幡市安土など))
展示している場所:滋賀県立 琵琶湖博物館,多賀町立博物館
約7000万年前(後期白亜紀)の火山活動によって噴出した溶結凝灰岩で,琵琶湖の南東部に主に分布することからこのように呼ばれている.京都の更新世の地層中にはこの岩石が礫として見つかることから,当時の水系の理解が進んだ.現在の分布している場所は,永源寺や長命寺,安土城といった観光名所周辺にも見られ,その景色の一部を構成している.(写真提供:里口保文)
◆滋賀県の鉱物
トパーズ(主要産地:滋賀県大津市(田上山))
展示してある場所:琵琶湖博物館
トパーズは黄玉という名前でも知られている.滋賀県の田上山のトパーズは,後期白亜紀の花崗岩類中に産し明治20年代には学術論文に記載されている.多量に産出していたらしく,研究者や愛好家によく知られてきた.地元の年配の方からは「昔は山道でもよく見つけられた」との話を聞くが,現在はきれいな形のものは見つけるのが難しくなっている.田上山は,水晶の産地としても,江戸時代にはすでに有名だったことが当時の著書からわかる.(写真:田上山産出のトパーズ.個人蔵)
◆滋賀県の化石
古琵琶湖層群の足跡化石(主要産地:滋賀県湖南市野洲川河床)
展示している場所:滋賀県立 琵琶湖博物館,甲賀市 みなくち子どもの森 自然館,多賀町立博物館(産地が異なるもの)
1988年にこの場所で約260万年前のゾウ類やシカ類の足跡化石が発見され, これを契機として日本の鮮新世〜更新世の地層から多くの足跡化石が調査されるようになった.調査が行われた当時の化石は,川の流れによって削られたが,その後に新しい地層面中の足跡化石が露出し,これまでに,ワニ類,鳥類,サイ類の足跡化石が見つかっている.他の地域の古琵琶湖層群からも多くの足跡化石がみつかっている.(野洲川河床の足跡化石.ゾウ類とシカ類.撮影:岡村喜明)
このページtopへ戻る
奈良県の「県の石」
◆奈良県の岩石
玄武岩質枕状溶岩(主要産地:玉置山山頂,吉野郡川上村深山の吉野川河床,川上村下多古,十津川村折立など)
枕状溶岩は海底火山活動で噴出した溶岩で,多くは玄武岩質である.立体的に見える場合,数十cm程度の径をもつチューブ状である.断面が見える場合,形状は楕円形ないし円形で放射状割れ目が発達する.奈良県内の枕状溶岩は一億年以上前(主に後期三畳紀と前期白亜紀)に形成された後,ぞれぞれプレートによって運ばれてきたものであり,その周辺に分布する堆積岩類とともに大陸の縁にくっついて付加体を構成している.(写真提供:和田穣隆)
◆奈良県の鉱物
ざくろ石(主要産地:二上山)
ざくろ石は赤くきれいな結晶で,二上山の火山岩に含まれているものが有名である.ここのざくろ石はおよそ1㎜大で,濃紅色をした鉄分の多い種類が産する.付近の川底や沖積層には火山岩が風化して,硬いざくろ石だけが取りだされて堆積している.川砂などから採掘したざくろ石は“金剛砂”とよばれ,研磨剤として利用されてきた.(写真提供:佐藤隆春)
◆奈良県の化石
前期更新世動物化石(主要産地:奈良県北葛城郡広陵町〜河合町(馬見丘陵))
展示してある場所:奈良県立橿原考古学研究所附属博物館
馬見丘陵では開墾や宅地開発に伴い,アケボノゾウの臼歯が1点,種類不明の長鼻類の切歯(牙)が4点,ならびにシカマシフゾウの角が1点発掘されている.アケボノゾウとシカマシフゾウは,ともに日本の前期更新世を代表する哺乳類である.アケボノゾウは肩高2m足らずの小さなゾウで,類似の種は大陸で見つかっていない.その祖先が大陸から渡来したあと日本列島が島嶼化したため,日本列島固有種となったと考えられる.(写真提供:奈良県立橿原考古学研究所附属博物館)
京都府の「県の石」
◆京都府の岩石
鳴滝砥石(前期三畳紀珪質粘土岩)(主要産地:京都市右京区)
展示してある場所:梅が畑 平岡八幡宮(原石),宇多野 福王寺神社遍照額(原石)
丹波帯のジュラ紀付加体中の前期三畳紀珪質粘土岩およびその上位に堆積する中期三畳紀チャート−粘土岩互層の細粒泥質部が弱い変成作用を受けた後風化を受けてやや軟質となったもので,刃物を研磨する砥石として活用されている.鎌倉時代より採掘されており,鳴滝砥石または合砥(あわせと)と呼ばれている.主に細粒の石英粒子およびイライトその他の粘土鉱物より構成されていて,鋭利な刃物の研ぎ出し用の砥石として珍重されている.(写真提供:武蔵野 實)
◆京都府の鉱物
桜石(主要産地:京都府亀岡市ひえ田野町柿花、湯ノ花温泉付近)
展示してある場所:益富地学会館、郄田クリスタルミュージアム
三畳紀からジュラ紀の丹波帯の泥質岩が白亜紀の花崗閃緑岩体の接触変成作用を受けたことにより菫青石とインド石(高温型の菫青石)からなる六角柱状結晶が多数生じた.この結晶が外形を残して細粒白色の雲母に変質したものが桜石である.柱状結晶の長軸に垂直な断面(径3〜10mm)は桜の花が開いたように見える.細粒の酸化鉄により桃色を示すものもある.桜石は地元では古くから知られ,桜天満宮境内にみられる桜石は国の天然記念物に指定されている.(写真提供:貴治康夫)
◆京都府の化石
綴喜(つづき)層群の中新世貝化石群(主要産地:京都府綴喜郡宇治田原町)
展示してある場所:宇治田原町総合文化センター,京都教育大学まなびの森ミュージアムなど
京都府綴喜郡宇治田原町の市街地,東西約6km,南北約1.6kmの盆地内には,中期中新世の綴喜層群が広がっている.そこには浅海の暖温帯水から冷温滞水を好んで生息する貝化石群が産出している。貝化石が豊富に含まれることで有名だが,多量に採取され,現在では京都府によって保護すべき対象とされている.(写真上:Dosinia nomuraiとAcila submirabilisの写真,下:Nipponomarcia nakamuraiの貝化石密集写真 写真提供:田中里志)
このページtopへ戻る
三重県の「県の石」
◆三重県の岩石
熊野酸性岩類(主要産地:三重県東紀州地域)
展示してある場所:三重県総合博物館
熊野酸性岩類は約1500万年前(中期中新世)の巨大カルデラ火山活動で生じた火成岩体である.三重県東紀州地域にも分布し,流紋岩質の溶岩や火砕岩(火砕流堆積物),貫入岩を形成している.火砕岩は鬼ヶ城や獅子岩,花の窟神社といった世界遺産のダイナミックな景観を形作っており,貫入岩は楯ヶ崎のような切り立った柱状節理をよく発達させている.一方,それらの険しい地形が土石流災害の要因にもなっている.(写真:楯ヶ崎(熊野市甫母町)提供:後 誠介)
◆三重県の鉱物
辰砂(しんしゃ)(主要産地:丹生鉱山)
展示してある場所:三重県総合博物館(津市),ふるさと交流館せいわ(多気郡多気町)
辰砂は水銀の原料である.古くから丹生の辰砂は有名で,奈良東大寺の大仏造立時の鍍金の際に丹生の水銀が使用された.その後,丹生は水銀座ができるほど水銀の町として知られていた.丹生の水銀鉱床の分布域は中央構造線付近の内帯の領家花崗岩類と外帯の三波川変成岩類の両方に延びている.鉱床ができたのは,新生代新第三紀中新世のころである.また,辰砂を主としているが,まれに黒辰砂を伴う.随伴鉱物としては,鶏冠石などがある.(写真:辰砂(松阪市小片野産),提供:三重県総合博物館)
◆三重県の化石
ミエゾウ(主要産地:三重県津市,亀山市,伊賀市,鈴鹿市,桑名市など)
展示してある場所:三重県総合博物館(全身骨格復元模型,切歯,上顎骨など)
ミエゾウは,およそ350万年前(鮮新世)に生息していた太古のゾウ.学名に Stegodon miensis(ステゴドン・ミエンシス)と種小名に三重の名が付けられている.九州から東北地方にかけて化石が報告されている.特に三重県内に産地が集中し,津市,亀山市,伊賀市などで発見されている.最大で全長8メートル,高さ4メートルあったと推定され,今のところ日本国内から化石の発見された陸上哺乳類としては最も大きい.(写真:全身骨格復元標本.三重県総合博物館展示)
大阪府の「県の石」
◆大阪府の岩石
和泉石[和泉青石](砂岩)(主要産地:和泉山脈)
展示してある場所:大阪市立自然史博物館(大阪市東住吉区長居公園1-23),きしわだ自然資料館(大阪府岸和田市堺町6-5)
和泉石(和泉青石)は,後期白亜紀の和泉層群に産する砂岩を元とした石材である.和泉層群は西南日本の中央構造線に沿って分布する地層で,近畿地方では大阪府・和歌山県の県境の和泉山脈や淡路島などに分布する.和泉山脈の稜線部の和泉層群は砂岩泥岩互層からなり,その中の厚い砂岩が石材(和泉石)として古くから利用されてきた.今でも岸和田城の城壁や大阪府泉南地域の石垣などに用いられているのを見ることができる.(写真提供:大阪市立自然史博物館(左上,左下,右上),きしわだ自然史資料館(右下))
◆大阪府の鉱物
ドーソン石(主要産地:泉南(泉南市,泉佐野市,貝塚市,岸和田市など))
展示してある場所:大阪市立自然史博物館(大阪市東住吉区長居公園1-23),きしわだ自然資料館(大阪府岸和田市堺町6-5)
ドーソン石は,ナトリウムとアルミニウムを主成分とする炭酸塩鉱物NaAl(CO3)(OH)2で,針状結晶が放射状に集合し,白色で絹糸光沢.国内での産出は稀であるが,白亜紀末の化石産地として有名な大阪府南部の和泉層群畦谷泥岩部層分布域からはふつうに産出する.化石をさがして石灰質のジュールを割ると,化石とともにあたかも石の表面に白い花が咲いたようなドーソン石が見つかり,一度に二度おいしい思いができる.(写真提供:大阪市立自然史博物館)
◆大阪府の化石
マチカネワニ(主要産地:大阪府豊中市柴原の待兼山丘陵(大阪大学豊中キャンパス))
展示してある場所:大阪大学総合学術博物館(実物・レプリカ),大阪市立自然史博物館(レプリカ)など
1964年発見.日本で初めて見つかったワニ類の全身骨格化石.頭骨・下顎骨をはじめ,尾椎を除くほとんど全身の骨格が発掘されている.生息時の全長は6.9mから7.7m,体重は1.3tと推定.中期更新世(約50万年前)の地層から産出.最初Tomistoma属の新種で,Tomistoma machikanenenseとされたが,後にToyotamaphimeia machikanensisに改められた.ただし最近の研究では,現生のマレーガビアル(Tomistoma schlegelii)に最も近縁であるとされている.
(写真左:大阪市立自然史博物館レプリカ,写真右:大阪大学総合学術博物館)
(注)年代表記に誤りがありましたので,訂正いたします.(2016.5.11)
(注)文章の補足・修正し,産地の表記をリストと統一しました.下線部(2016.5.16)
和歌山県の「県の石」
◆和歌山県の岩石
珪長質火成岩類(主要産地:潮岬地域の橋杭岩,古座川弧状岩脈の一枚岩,虫喰岩など)
展示してある場所:和歌山県立自然博物館,吉野熊野国立公園宇久井ビジターセンター
県南部の「橋杭岩」・「古座川の一枚岩」・「高池の虫喰岩」などの奇岩群は,1500万年前頃(中期中新世)の珪長質マグマによる巨大カルデラ火山活動の産物である.いずれも流紋岩質で,火砕岩や火山岩が岩脈を形成しているものが多い.特徴的で珍しい景観が風化・浸食により造り出されているが,火砕岩によく発達する虫喰い状の大小無数の洞窟は塩類風化によるものとされ,特異な景観が際立っている.(写真:高池の虫喰岩 (古座川町池野山))
◆和歌山県の鉱物
サニディン(主要産地:太地町)
展示してある場所:和歌山県立自然博物館
サニディンは長石の一種であり,カリウムを多く含むアルカリ長石に属する.一般に花崗岩や流紋岩といった珪長質火成岩類によく含まれている.太地町産のものは1500万年前頃(中期中新世)に形成された熊野酸性岩類の岩脈に含まれる自形斑晶である.板状ないし方柱状で1 cm前後の比較的大きなものの多いことが特徴であるが,風化・変質のため乳白色を呈するものが多く見られる.(写真:サニディン(和歌山県立自然博物館))
◆和歌山県の化石
白亜紀動物化石群(主要産地:有田川流域(有田川町など)
展示してある場所:和歌山県立自然博物館
和歌山県有田郡には白亜紀の海成層が東西に帯状になって分布しており,各地よりアンモナイトや二枚貝などの軟体動物の化石を産出する.これらの化石については大正時代以降多くの研究がなされ,なかには和歌山の地名に由来した種名で記載されたものもある.また,最近では全体の50%以上の骨格が保存されたモササウルス類(海棲爬虫類)の化石が発見されており,注目を集めている.(写真:モササウルス(和歌山県立自然博物館))
兵庫県の「県の石」
◆兵庫県の岩石
アルカリ玄武岩(主要産地:豊岡市赤石・玄武洞)
展示してある場所:玄武洞で見学可能.兵庫県立人と自然の博物館,玄武洞ミュージアムで展示.
豊岡市玄武洞周辺を構成する約160万年前のアルカリかんらん石玄武岩.玄武洞は美しい柱状節理と「玄武岩」という岩石名の由来となったことで,国の天然記念物となっている.また松山基範が地球磁場の逆転を唱えるきっかけとなった場所として国際的にも知られ,山陰海岸世界ジオパークを代表する見学地である.玄武洞はもともと採石場であり,市内各地の伝統的な石積みや漬物石に使用されている.(写真:玄武洞公園(青竜洞))
◆兵庫県の鉱物
黄銅鉱(主要産地:明延鉱山)
展示してある場所:生野鉱物館(生野銀山文化ミュージアム),兵庫県立人と自然の博物館
兵庫県内には白亜紀末〜古第三紀初頭の火山活動に関係する熱水鉱脈鉱床が多数存在している.なかでも生野鉱山は銀,明延鉱山は銅の鉱山として古くから開発され,織田信長・豊臣秀吉の支配を経て江戸時代には幕府直轄領,明治時代には官営の鉱山となり,日本の鉱業を支えてきた.生野・明延鉱山は国内有数のスズの鉱山としても知られたが,両鉱山や兵庫県内の類似の鉱山を代表する鉱物として,黄銅鉱がある.(写真:明延鉱山産黄銅鉱(兵庫県立人と自然の博物館所蔵))
◆兵庫県の化石
丹波竜(タンバティタニスアミキティアエ)(主要産地:丹波市山南町,篠山川河床)
展示してある場所:兵庫県立人と自然の博物館,丹波竜化石工房「ちーたんの館」
2006年に前期白亜紀の篠山層群から発見された竜脚類で,丹波竜はその愛称.その後2014年に新属新種であることが判明し,タンバティタニスアミキティアエ(Tambatitanis amicitiae gen. et sp. nov.)と命名された.この発見がきっかけで,さらに他の恐竜・爬虫類・両生類・ほ乳類化石の発見が相次ぎ,それらを活用した地域の活性化につながるなど,大きな影響を与えた.(写真:タンバティタニスアミキティアエ(Tambatitanis amicitiae gen. et sp. nov.)の尾椎(兵庫県立人と自然の博物館所蔵))
このページtopへ戻る
中部(県の石)
「県の石」:中部・甲信越
▷「県の石」(大切なお願い/リスト/選定にあたって ほか)
<北海道・東北(北海道・青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島)>
<関東(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川)>
<中部・甲信越(新潟・長野・山梨・静岡・富山・石川・岐阜・愛知・福井)>
<近畿(滋賀・奈良・京都・三重・大阪・和歌山・兵庫)>
<四国(徳島・香川・高知・愛媛)>
<中国(岡山・広島・山口・島根・鳥取)>
<九州・沖縄(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)>
新潟県の「県の石」
◆新潟県の岩石
ひすい輝石岩(主要産地:糸魚川市青海,小滝など)
展示してある場所:フォッサマグナミュージアム
ひすい輝石岩は,カンブリア紀のプレート沈み込み帯深部の熱水が関与した変成作用の産物とされ,縄文時代中期に始まる世界最古のヒスイ文化の基本石材である.(写真提供:フォッサマグナミュージアム)
◆新潟県の鉱物
自然金(主要産地:佐渡金山遺跡)
展示してある場所:自然金:佐渡市立佐渡博物館
佐渡島では新第三紀の火山活動により形成された金銀鉱脈が見られる.同島西三川では砂や泥とともに海底に堆積し,砂金となった自然金が見られる.(写真提供:佐渡市)
◆新潟県の化石
石炭紀−ペルム紀海生動物化石群(主要産地:糸魚川市青海,小滝など)
展示してある場所:フォッサマグナミュージアム
青海石灰岩から産する石炭紀からペルム紀の海生動物化石群は、この時代の大洋パンサラッサの古環境を示す我が国屈指の保存状態を誇る化石群である。(写真提供:フォッサマグナミュージアム)
このページtopへ戻る
長野県の「県の石」
◆長野県の岩石
黒曜石(主要産地:和田峠)
展示している場所:黒曜石体験ミュージアム(長野県小県郡長和町大門3670-3)
和田峠の黒曜石は,和田周辺に分布する和田峠火山岩類(更新世)に属する.この黒曜石は岩脈,溶岩の一部,火砕流堆積物の岩片として産出する..良質な黒曜石の岩片は石器として使用され,その広がりから旧石器時代の流通が推察されている.(写真:牧野州明)
◆長野県の鉱物
ざくろ石(主要産地:和田峠)
展示している場所:黒曜石体験ミュージアム(長野県小県郡長和町大門3670-3)
ざくろ石は,赤くてきれいな鉱物である.和田峠火山岩類(更新世)の火道流紋岩中の空孔に産する.和田峠では,ざくろ石の中でも面がよく発達し,マンガンに富む.(写真:牧野州明)
◆長野県の化石
ナウマンゾウ(主要産地:野尻湖)
展示している場所:野尻湖ナウマンゾウ博物館
約35万年〜3万年(中期〜後期更新世)に日本列島で生息していた日本を代表する長鼻類の化石.野尻湖では1962年から発掘が行われており,ナウマンゾウをはじめヤベオオツノジカなど氷河時代を代表する大型脊椎動物化石が産出している.ナウマンゾウは中国大陸から移入してきたが,約3万年前に日本列島から姿を消した.野尻湖は絶滅期におけるナウマンゾウの古生態が解明できる場として注目されている.(写真提供:野尻湖ナウマンゾウ博物館)
山梨県の「県の石」
◆山梨県の岩石
玄武岩溶岩(主要産地:富士火山青木ヶ原)
富士山噴火の中で最大規模の青木ヶ原溶岩は,西暦864年〜866年の2年間にわたって活動した玄武岩溶岩である.この噴火で長尾山・氷穴火口列と石塚火口から相対的に北側に溶岩が流れ,当時富士北麓域に大きく広がっていた“せの海”を埋めて,これを西湖と精進湖に分断し,また本栖湖の一部も埋めた.その後,この溶岩の上に樹木が成長・繁茂したのが青木ヶ原樹海である.(写真:輿水達司)
◆山梨県の鉱物
日本式双晶水晶(主要産地:乙女鉱山)
展示してある場所:山梨県立ジュエリーミュージアム
山梨県北部にそびえる奥秩父連峰を構成する主体は,中新世の花崗岩類である.これら花崗岩の形成に伴う水晶鉱山として,増富鉱山,乙女鉱山などが歴史的にもよく知られている.この中で,乙女鉱山から日本で最初に発見されたと言われる,2つの水晶の接合した日本式双晶が,ドイツ人G. vom Rathによって明治初期に記載された.この水晶は,2枚の平板が双晶面を境に84°33′の角度で接合したハート形(型)の美しい結晶をしている.(写真:輿水達司)
◆山梨県の化石
富士川層群の後期中新世貝化石群(主要産地:身延町小原島など)
展示してある場所:身延町化石公園(写真で示した化石)
身延町小原島付近の道路沿いおよび早川橋付近の河床一帯を中心に,かつて海底に堆積した泥岩・砂岩・礫岩の互層からなる地層が分布している.この地層中に,約600万年前の二枚貝や巻貝などの貝化石群が認められる.同時に,この河床部一帯の地層が70〜80°の急傾斜であることも観察でき,当初地層が水平に堆積し,その後の地層の圧縮変形と陸域化など,地球の大きな営みの歴史についても,この地層の急傾斜から実感できる.(写真:輿水達司)
静岡県の「県の石」
◆静岡県の岩石
赤岩(凝灰角礫岩)(主要産地:富士火山宝永火口(御殿場市))
展示してある場所:宝永山(御殿場市)
赤岩は宝永山を形作る地層で,現在の富士山(新富士火山)を構成する新鮮な噴火堆積物とは異なり,変質が進んで赤褐色を帯びた火山礫と火山灰からなる.かつて古富士火山の山体を構成していた地層の一部が,1707年宝永噴火の際に隆起して地表に露出したと考えられている.(写真提供:小山真人(静岡大学))
(注)説明文書修正(下線部)(2016.5.12)
◆静岡県の鉱物
自然テルル(主要産地:河津鉱山(下田市))
展示してある場所:ふじのくに地球環境史ミュージアム
河津鉱山から産出する鉱物のひとつ.陶器状石英中に微細な結晶の集まりとして見られる.河津鉱山では,他もテルルを含む鉱物が産出し,テルル石や河津鉱など多種多様な鉱物が知られている.なかでも河津鉱は,1970 年に初めて発見され,産出地にちなんで名付けられた新鉱物である.(写真提供: 菅原大助 (ふじのくに地球環境史ミュージアム))
(注)説明文書修正(下線部).写真差替(2016.5.13)
◆静岡県の化石
掛川層群(大日層)の貝化石群(主要産地:掛川市,袋井市)
展示してある場所:ふじのくに地球環境史ミュージアム
掛川層群大日層は,掛川市から袋井市北部にかけて分布する,約200万年前(第四紀前期更新世)に浅海域で堆積した砂層・泥層からなる地層である.この地層には,現生のホタテガイに似た絶滅種であるモミジツキヒガイ等,海生生物化石が多く産出することが知られており,日本を代表する暖流系化石群として,「掛川動物群」と呼ばれている.解説協力:横山謙二氏(NPO法人静岡県自然史博物館ネットワーク)(写真提供: 菅原大助 (ふじのくに地球環境史ミュージアム))
富山県の「県の石」
◆富山県の岩石
オニックスマーブル(トラバーチン)(主要産地:宇奈月町下立)
展示してある場所:黒部市吉田科学館
約1,600万年前の火山性噴出物の上に発達した炭酸塩岩で,「オニックスマーブル」という石材名で呼ばれている.1 mm以下のラミナが発達することから,トラバーチンであると考えられる.国会議事堂建築の際に,その石材の16%にあたる442 tが切り出され,銅像台座・階段壁・階段手摺親柱などに使用されている.また,2014年に開通した黒部宇奈月温泉駅にも使用されている.埋蔵量がごくわずかで,産地は痕跡的にしか残っていない.
◆富山県の鉱物
十字石 (主要産地:宇奈月町内山)
展示してある場所:富山市科学博物館
飛騨変成帯東縁部の宇奈月変成岩類から産する.十字石は,著しい風化で生じる酸化アルミニウムに富む泥岩が,大陸衝突帯深部の温度圧力条件で変成されてできる.宇奈月のものは,約2.5億年前をピークとする南・北中国大陸の衝突に伴い生成した.日本に肉眼で見える大きさの十字石が稀なのは,プレート境界に集積した海成層に富み,風化が起き易い大陸環境起源の地層に乏しく,衝突型変成作用でできた変成岩類も少ないからである.
◆富山県の化石
八尾層群の中新世貝化石群(主要産地:富山市八尾町)
展示してある場所:海韻館・富山市科学博物館・滑川市博物館・黒部市吉田科学館
八尾層群及びその相当層は,日本海形成前後(前期〜中期中新世)の堆積物で,富山県を横断して東西に分布しており,各地で貝化石を豊富に産出する.特に富山市八尾地域では,貝類化石とともにマングローブ植物の花粉化石が見つかったことにより,古環境及び古生物学的研究の発展に大いに貢献した.
(注)産地の誤記を,訂正いたします。(2016.5.11)
このページtopへ戻る
石川県の「県の石」
◆石川県の岩石
珪藻土(珪藻泥岩)(主要産地:能登半島)
展示してある場所:金沢大学で展示予定あり
能登の珪藻土は,新第三紀中新世に堆積した,多様な形態を持つ微小な珪藻化石を大量に含む珪藻質泥岩のことである.七輪などの原料として利用されている.堆積当時,陸源物質の供給が乏しく珪藻が大量に繁茂できる環境が長期間に渡って継続していたことを示す.古環境としては湖から海,海域では開放的な場合から閉鎖的環境まで多様である.特に飯塚層,和倉層は日本海が閉じた状態で循環が悪く酸素欠乏状態になった時期の堆積物である.(写真:珠洲市の珪藻土採掘現場(有限会社丸和工業坑道内).ロバート・ジェンキンズ撮影)
◆石川県の鉱物
霰石(あられいし)(主要産地:能登町恋路)
展示してある場所:金沢大学で展示予定あり
石川県鳳珠郡能登町恋路に産する玄武岩の気泡中に晶出した六角柱状結晶.恋路産の霰石結晶は薄紅色を呈する.気泡内では緑色のセラドン石と共存する.国内の他の産地と比較して,能登町恋路産の結晶は外形の明瞭さ,薄紅色の色彩の美しさにおいて秀でている.(写真:金沢大学保管.奥寺浩樹撮影)
◆石川県の化石
大桑層の前期更新世化石群(主要産地:金沢市大桑町)
展示してある場所:金沢大学で展示予定あり
大桑(おんま)層は第四紀前期更新世のおよそ170万年前から80万年前に日本海の浅海で形成された金沢市大桑(おおくわ)町の犀川沿いを模式地とする地層である.この地層中には主に寒流系種からなる貝化石密集層と暖流系種からなる貝化石散在層が約4万年周期で交互に出現している.これらは第四紀を特徴付ける氷期・間氷期サイクルによる気候変動・海水準変動に対して貝類が鋭敏に反応したことを示す証拠である.(写真:金沢市大桑町犀川の露頭.ロバート・ジェンキンス撮影)
岐阜県の「県の石」
◆岐阜県の岩石
チャート(主要産地:木曽川河畔(各務原市鵜沼,加茂郡坂祝町),飛水峡(加茂郡七宗町),金華山(岐阜市))
展示してある場所:日本最古の石博物館(加茂郡七宗町)
チャートは放散虫というプランクトン化石からなる層状のきれいな地層である.岐阜県の木曽川,長良川沿いには美濃帯のジュラ紀付加体に含まれる三畳紀〜ジュラ紀前期の層状チャートが広く分布する.風化侵食に対する抵抗力が強いため山稜や淵をつくることが多い.岐阜のシンボル金華山もチャートでつくられた山である.特に保存良好な放散虫化石を含むため,精密な形成年代および地質構造の解析が進んだ.美濃帯は海洋プレートの沈み込みによって形成された付加体であることが明らかにされ,日本列島の発達史を明らかにする上で大きな役割を果たした.(写真提供:小嶋 智 飛水峡のチャート)
◆岐阜県の鉱物
ヘデン輝石(主要産地:神岡鉱山(飛騨市神岡町))
展示してある場所:鉱山資料館(飛騨市神岡町)
神岡鉱山は,飛騨片麻岩中に含まれる結晶質石灰岩に花崗岩マグマ起源の熱水が接して形成されたスカルン鉱床からなる.2001年の閉山までの総採掘量は7,500万トンに達し,一時は東洋一の鉱山として栄えた.神岡鉱山から産出する代表的な鉱物がヘデン輝石(灰鉄輝石,CaFeSi2O6)である. (神岡鉱山資料館蔵ヘデン輝石,写真撮影:神岡鉱業(株))
◆岐阜県の化石
ペルム紀化石群(主要産地:赤坂金生山(大垣市))
展示してある場所:金生山化石館(大垣市),岐阜県博物館(関市)
大垣市北部赤坂町の金生山は,古生代中期〜後期ペルム紀の石灰岩からなり,豊富な化石を産する.日本産の最初の化石が記載されたのは,ドイツ人ギュンベルによる金生山産のフズリナ化石と言われており,金生山は「日本の古生物学発祥の地」と呼ばれることもある.フズリナの他にも巻貝,二枚貝,ウミユリ,サンゴなどの化石を多産し,貝類には大型のものが多い. 写真:産業技術総合研究所所蔵(左)巻貝,登録番号GSJ F03579(右)二枚貝,登録番号GSJ F03580(いずれも地質標本登録データベースより)
愛知県の「県の石」
◆愛知県の岩石
松脂岩(主要産地:鳳来寺山)
展示してある場所:新城市鳳来寺山自然科学博物館,名古屋大学博物館,名古屋市科学館
松脂岩は流紋岩質成分でガラス質,松脂のような樹脂状光沢がある.また,英名のピッチストーンはアスファルトのような色と光沢から名づけられている.水分を5%以上含んでいることが特徴で,黒曜岩と区別される.約1500万年前の大規模な火山活動によって形成され,鳳来寺山から棚山にかけて広く分布している.国指定名勝天然記念物の鳳来寺山の象徴である鏡岩は,松脂岩からなっている.(写真:加藤貞亨)
◆愛知県の鉱物
カオリン(主要産地:瀬戸市)
展示してある場所:名古屋大学博物館,名古屋市科学館
瀬戸物として古くから知られる陶業は,愛知県の伝統的産業の一つである.カオリンは陶業の原材料となる粘土である.瀬戸地方の粘土(カオリン)は後期中新世から鮮新世(約700万年から200万年前)に堆積した瀬戸層群の最下部の地層(瀬戸陶土層)から採取される.カオリンは周辺の花崗岩中の長石が風化によって形成された粘土が堆積したり,砂粒として堆積した長石が堆積後風化し粘土化したものである.(瀬戸陶土層とカオリンの電子顕微鏡写真 写真:竹内 誠・サイモン ウォリス・林 誠司(協力:愛知県陶磁器工業協同組合))
◆愛知県の化石
師崎層群の中期中新世海生化石群(主要産地:知多半島(愛知県南知多町山海))
展示してある場所:名古屋大学博物館,名古屋市科学館
約1700万年前(中新世)の地層(師崎層群)が分布する南知多町から,ウミユリ類,ヒトデ類,ウニ類などの棘皮動物,深海魚,二枚貝や巻貝などの軟体動物等,多種の深海性動物化石が発見されている.これだけ多種類の深海性化石群が見つかっているところは日本では師崎層群だけである.さらに特筆すべきは,これらの化石が非常に保存の良い状態で発見されていることで,この化石群を産出する地層は日本を代表する「化石鉱脈*」の例として有名である.(深海性ヒトデの一種 (Hymenodiscus sp.)写真:大路樹生)
*「化石鉱脈」:保存の良い化石が密集して産出する地層
(注)ヒトデ化石学名の誤記を訂正(2021.12.2)
福井県の「県の石」
◆福井県の岩石
笏谷石(火山礫凝灰岩)(しゃくだにいし)(主要産地:足羽山)
展示してある場所:福井市自然史博物館
古来より採掘されてきた青く美しい「笏谷石」は,福井市中心部の足羽山で採掘されたデイサイト質の火山礫凝灰岩に付けられた名称です.水底あるいは一部陸上に流れ出した火砕流堆積物であると考えられており,中新世の糸生層最上部に位置づけられています.層理はほとんどなく塊状で,溶結構造はわずかに認められる程度です.加工しやすい,色が美しいなどの特徴を持っており,福井城の石垣も笏谷石が使われています.(提供:福井市)
◆福井県の鉱物
自形自然砒(主要産地:旧赤谷鉱山(福井市赤谷町;現在は廃鉱))
展示してある場所:福井市自然史博物館
赤谷鉱山では自然砒結晶は変質した面谷流紋岩類(濃飛流紋岩類)中に生じている.大きいものでは,その長径が2㎝に達する.表面は酸化して亜砒酸を生じ,灰白色〜暗灰色になり光沢を失っているが,内部の新鮮な部分では錫白金属光沢がある.本鉱山から産する自然砒結晶は,表面に菱面体結晶の突起が多数突き出ており,そのユニークな形がお菓子の金平糖を連想させるため,“こんぺいとう石”と言われている.写真「ふくい地質景観百選」(2009年,福井市自然史博物館)より
◆福井県の化石
フクイラプトル キタダニエンシス(主要産地:福井県勝山市北谷)
展示してある場所:福井県立恐竜博物館
フクイラプトル キタダニエンシス(Fukuiraptor kitadaniensis)は,アロサウルス上科に属すると考えられる肉食恐竜である.大腿骨から全長4.2mと推定されている.前期白亜紀の手取層群北谷層から,福井県による恐竜化石発掘調査によって発見され,日本で最初に有効な学名がつけられた恐竜であり,また日本で最初に全身骨格が復元された肉食恐竜である.(写真提供:福井県立恐竜博)
このページtopへ戻る
関東(県の石)
「県の石」:関東
▷「県の石」(大切なお願い/リスト/選定にあたって ほか)
<北海道・東北(北海道・青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島)>
<関東(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川)>
<中部・甲信越(新潟・長野・山梨・静岡・富山・石川・岐阜・愛知・福井)>
<近畿(滋賀・奈良・京都・三重・大阪・和歌山・兵庫)>
<四国(徳島・香川・高知・愛媛)>
<中国(岡山・広島・山口・島根・鳥取)>
<九州・沖縄(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)>
茨城県の「県の石」
◆茨城県の岩石
花崗岩(主要産地:八溝山地南部)
展示してある場所:筑波山塊・ミュージアムパーク茨城県自然博物館・地質標本館など
八溝山地南部の主要部をつくる深成岩類で,日本の大地が大陸縁辺部にあった約6000万年前に,地下でマグマが貫入・固結してできたものである。後に侵食を受けて関東平野に突出した筑波山塊の山並みは関東地方一円で親しまれている.
また,稲田・真壁地域では古くから花崗岩は御影石として採掘されており,日本有数の石材産業や地域に根ざした文化が育まれている。この御影石は日本各地で広く利用されている.(写真提供:小池 渉)
(注)展示場所の表示を追加しました.(2016.5.13)
◆茨城県の鉱物
リチア電気石(主要産地:常陸太田市妙見山)
展示してある場所:妙見山・ミュージアムパーク茨城県自然博物館・地質標本館など
リチア電気石は妙見山の中腹に露出するリチウムペグマタイトの主要鉱物の1つで,紅,青,緑などさまざまな色をしたきれいな柱状結晶として多く産する.これはマグマが冷え固まっていくときの残液にリチウム元素が濃集してできた珍しい鉱物で,日本での産出は他に福岡県,岩手県など数カ所に限られている.
リチア電気石を多産する妙見山のリチウムペグマタイトの露頭は,常陸太田市指定の天然記念物として保護されている.(写真提供:ミュージアムパーク茨城県自然博物館)
(注)展示場所の表示を追加しました.(2016.5.13)
◆茨城県の化石
ステゴロフォドン(主要産地:常陸大宮市)
展示してある場所:ミュージアムパーク茨城県自然博物館
ステゴロフォドンは,新生代中新世〜鮮新世に南アジアから日本にかけて生息していた,切歯(牙)を4本もつ古いゾウ類である.2011年に高校生(当時)が常陸大宮市の中新世の地層からその頭蓋化石を発見して,大変話題となった。発見された化石は切歯を含む頭部がほぼ完全に残っており,そのすばらしい保存状態から,ステゴロフォドンの形態やゾウ類の進化過程などを解明する上で極めて重要な標本である.(写真提供:ミュージアムパーク茨城県自然博物館)
このページtopへ戻る
栃木県の「県の石」
◆栃木県の岩石
大谷石(おおやいし)(凝灰岩)(主要産地:宇都宮市大谷町)
展示してある場所:栃木県立博物館,大谷資料館
新第三紀中新世に日本列島が大陸から分かれる際に,いわゆる“グリーンタフ”と呼ばれる海底火山の活動で排出された火山灰・軽石などが固まった岩石である.切断しやすく美しいことから,古墳の石室など古くから石材として用いられてきた.また,旧帝国ホテルに使用され,完成披露当日に起きた関東大震災に耐えたことから,建築資材として全国的に有名になった.
表面には,茶色の“みそ”という軟らかい部分があり,“みそ”が少ないものほど,資材として高品質である.(写真提供:栃木県立博物館)
◆栃木県の鉱物
黄銅鉱(主要産地:足尾銅山)
展示してある場所:栃木県立博物館,足尾銅山観光(要確認)など
かつて国内随一の鉱山であった足尾銅山(中期中新世に形成された銅鉱床)の主要な採掘対象が黄銅鉱であった.銅を製錬する際に排出される二酸化硫黄などが煙害を招いた.長年様々な煙害防除の方策が試みられ,昭和31年の自溶炉導入で解決に至った.自形結晶で出にくい鉱物であるが,晶洞の中には四面体の自形結晶がみられることがある.(写真提供:栃木県立博物館)
◆栃木県の化石
木の葉石(植物化石)(主要産地:那須塩原市塩原)
展示してある場所:木の葉化石園(那須塩原市塩原),栃木県立博物館(宇都宮市),那須野が原博物館(那須塩原市)
約30万年前(第四紀中期更新世)の湖底にたまった塩原湖成層からは,これまでに180種余に上る多数の美しい植物化石が発見されている.稀に,昆虫や魚,ネズミといった動物化石が見つかることもある.この時代における動植物化石の保存状態としては極めて良好で,栃木県を代表する化石といえる.(写真提供:栃木県立博物館)
群馬県の「県の石」
◆群馬県の岩石
鬼押出し溶岩(主要産地:浅間山鬼押出し(吾妻郡嬬恋村))
展示している場所:鬼押出し園
上信国境にある浅間山(標高2568m)を構成する複数の火山体のうち,前掛火山の天明三年(1783年)大噴火で形成された安山岩溶岩である.現在の釜山の火口北側にプリニー式噴火でできた火砕丘が崩れて再流動し,前掛火山北斜面を流下した.火砕成溶岩で3ユニットからなる.上信越高原国立公園の一部であり,日本百名山,日本の地質百選等に選定されている.なお,北麓地域は日本ジオパークに登録申請中である.(撮影 郄耼祐司(於 鬼押し出し園))
◆群馬県の鉱物
鶏冠石(主要産地:西牧鉱山)
展示している場所:群馬県立自然史博物館,下仁田町自然史館
閉山した西ノ牧(西牧)鉱山から産出したものである.本宿層(約600万年前)中の安山岩質凝灰角礫岩をほぼ同時代の安山岩−デイサイト岩脈が貫入してできた低温熱水型の脈状鉱床で形成されたと考えられる,As4S4の化学式を持つヒ素の硫化鉱物.国内では本産地の他に青森県,北海道などで産出が知られる.町全体が日本ジオパークの一つ,下仁田ジオパークである.産地が私有地であるため,基本的に入山できない.(撮影 郄耼祐司 ©群馬県立自然史博物館(GMNH-EM 455))
◆群馬県の化石
ヤベオオツノジカ(主要産地:富岡市上黒岩)
展示している場所:群馬県立自然史博物館
中〜後期更新世の日本にいた,本邦固有の大型絶滅シカ類.同じ固有種のナウマンゾウと共に産出することが多い.中国産の同属の種と比べ①左右の角が外側へ広がらず,ほぼ後ろへ伸びる,②角の先端部に掌状に発達する角冠が小さい,③角の基部から伸びる大きめの眉枝が平たいヘラ状で上へ伸びるなどの特徴がある.化石骨は県指定天然記念物で,日本最古の化石発掘記録となる出土記念碑等3点の発掘関連資料も同記念物附に指定されている.(写真 所蔵 蛇宮神社(富岡市立美術博物館寄託),撮影 群馬県立自然史博物館(郄耼祐司))(17/1/31訂正)
埼玉県の「県の石」
◆埼玉県の岩石
片岩(主要産地:長瀞町など)
長瀞の岩畳に代表される片岩は,片理といわれる板状結晶や柱状結晶の面状配列をもち,平らに剥がれやすい岩石.埼玉県小川町から長瀞町,皆野町,神川町にかけてみられるものは,三波川結晶片岩類と総称される.この岩石は九州東端まで約1000 kmにわたって帯状に分布し,分布地域は三波川帯などとよばる.地下深部で海洋プレート上の堆積物が7000万年前前後(後期白亜紀)に変成作用をうけた広域変成岩.古墳の石室や中世の板石塔婆の石材などにも利用されている.(写真:長瀞の岩畳.2016年4月6日,小幡喜一撮影)
◆埼玉県の鉱物
スチルプノメレン(主要産地:長瀞町上長瀞虎岩など)
埼玉県上長瀞の『虎岩』の成分として有名.『虎岩』はスチルプノメレンの褐色と長石などの白色から縞模様を呈する.この岩は荒川の岸近くにあり,県立自然の博物館前の駐車場の奥にある宮沢賢治の歌碑「つくづくと『粋なもやうの博多帯』荒川ぎしの片岩の色」の脇を通って雑木林を抜け,川原に下りると,見つけることができる.(写真:上長瀞の虎岩にみられるスチルプノメレン(黒褐色).白色の部分は方解石など.2016年4月9日,小幡喜一撮影)
*2017.3.27説明文章修正
◆埼玉県の化石
パレオパラドキシア(主要産地:小鹿野町般若,秩父市大野原)
展示してある場所:埼玉県立自然の博物館
パレオパラドキシア(Paleoparadoxia )は束柱目の絶滅した哺乳類.学名はギリシア語のpalaios(古い)+paradoxos(奇妙)に由来.北太平洋東西両岸の,約2000万年前〜1100万年前の地層から発見されている.束柱目は長鼻目(ゾウの仲間)・海牛目(ジュゴンやマナティーの仲間)と近縁,柱を束ねたような歯,太い胴体と平爪をもった頑丈な四肢をもち,海岸付近を泳いでいたと推定されている.パレオパラドキシアは前歯が発達,スコップのような下あごが特徴.
(写真 埼玉県立自然史博物館に展示されているパレオパラドキシア.
(上)骨格復元模型(左から埼玉県小鹿野町産の般若標本・秩父市産の大野原標本・岐阜県土岐市産の泉標本)と,後方の壁面の産状模型(左から埼玉県小鹿野町産の般若標本・秩父市産の大野原標本).2016年4月9日,小幡喜一撮影.
(下)骨格復元模型(左から埼玉県小鹿野町産の般若標本・秩父市産の大野原標本)と,後方の壁面の産状模型(左から埼玉県小鹿野町産の般若標本).2016年4月9日,小幡喜一撮影.)
千葉県の「県の石」
◆千葉県の岩石
房州石(凝灰質砂岩・細礫岩)(主要産地:鋸山(千葉県富津市,鋸南町))
展示してある場所:鋸山.石材標本は,鋸山ロープウェー石切資料コーナー,千葉県立中央博物館などに展示.石材使用例は東京近郊に多数あり.
黒色のスコリア〜玄武岩片と白色の軽石が縞模様を示す独特の外観を呈する.江戸時代末から明治時代にかけての近代化に伴って石材として産業化が進み,東京,横浜などを中心に首都圏で多量に使用された.昭和60年を最後に切り出しは終了したが,近年になって地元の富津市金谷地区で房州石に着目した町おこしが盛んになり,埋もれた石切場の調査が行われたり,毎年シンポジウムが開催されるなど,首都圏の石材研究の中心地になりつつある.(写真:赤司卓也)
◆千葉県の鉱物
千葉石(主要産地:房総半島)
展示してある場所:千葉県立中央博物館に常設展示(タイプ標本は東北大学総合学術博物館).
2011年に発見された新鉱物.シリカ鉱物の一種で,珪素と酸素がカゴ状の結晶構造を作り,‘カゴ’の内部にメタン,エタンなどの炭化水素分子を1分子ずつ含む珍しい鉱物である.シリカクラスレート(包摂化合物),クラスラシルとも呼ばれる.透明な八面体結晶であるメタンハイドレートのⅡ型と同じ構造を持つ.房総半島南部に分布する前期中新世保田層群の凝灰質砂岩中の石英質脈から発見された.千葉県からの新鉱物の発見は初めてであることから名付けられた.(写真提供:千葉県立中央博物館)
◆千葉県の化石
木下(きおろし)貝層の貝化石群(主要産地:下総台地(印西市木下ほか))
展示してある場所:露頭(国指定天然記念物:印西市木下万葉公園内).標本は印西市立木下交流の杜歴史資料センター,千葉県立中央博物館等に展示.木下貝層は,第四紀後期更新世(約12-13万年前)に,関東平野一円に広がっていた古東京湾で堆積した貝化石層である.内湾棲の貝類・海胆類が密集して産するのが特徴で100種類以上が報告され,バカガイ(Mactra chinensis),キタノフキアゲアサリ(Gomphina neastartoides),クサビザラ(Cadella delta),マメウラシマガイ(Ringicula doliaris)などを多産する.大正時代から数多くの古生物学的・地質学・堆積学的研究があり,平成14年に国指定天然記念物に指定されている.(写真 印西市木下万葉公園南側露頭(提供:千葉県立中央博物館))
このページtopへ戻る
東京都の「県の石」
◆東京都の岩石
無人(むにん)岩(主要産地:小笠原諸島父島など)
“無人(むにん)”とは小笠原の古名で,無人岩はそこから名付けられた岩石名である.無人岩は火山岩の一種で,広義には安山岩に区分されるが,普通の安山岩と比較してマグネシウムの含有量が極めて高いこと,安山岩には普通に含まれる斜長石と呼ばれる鉱物を含まずに,単斜エンスタタイトと呼ばれる鉱物を含むことで特徴づけられる.地球上で極めて稀で,特殊な岩石であり世界的に有名.小笠原諸島の無人岩は,父島列島から聟島(むこじま)列島にかけて分布し,約4800万年前に噴出したものとされている.(写真左上:父島の海岸に露出する無人岩の枕状溶岩の露頭.写真右上:産業技術総合研究所 R57584.写真下:父島釣浜に露出する無人岩枕状溶岩(海野 進提供))
◆東京都の鉱物
単斜エンスタタイト(主要産地:小笠原諸島父島など)
エンスタタイトは,輝石と呼ばれる鉱物の一種で国際鉱物学連合(IMA)主要造岩鉱物のひとつ.単斜エンスタタイトは,エンスタタイトと化学組成は同じであるが,結晶系が単斜晶系である点で区分される.単斜エンスタタイトは,いん石にはよく含まれるが地球上の岩石では珍しい.小笠原諸島は日本で唯一単斜エンスタタイトを産出する場所である.小笠原諸島の単斜エンスタタイトは,無人岩の中に最大10㎝程の結晶として産する.(写真:中央やや右寄りの白色の鉱物が単斜エンスタタイト.神奈川県立生命の星・地球博提供)
◆東京都の化石
トウキョウホタテ(主要産地:特定の場所なし(東京層))
展示してある場所:北区飛鳥山博物館,神奈川県立生命の星・地球博物館
トウキョウホタテ(Mizuhopecten tokyoensis)は,徳永重康博士が1906年に東京都北区王子の東京層から記載した二枚貝化石である.産地の東京にちなみ名がつけられた.ホタテガイに似ているが,別種の絶滅種である.日本各地のほか,台湾などの鮮新世〜更新世の地層からも見つかっている.(写真左:北区西ヶ原産(標本番号KPM-NN4154)写真右:文京区関口(江戸川公園)産(標本番号KPM-NN4108)いずれも神奈川県立生命の星・地球博提供)
神奈川県の「県の石」
◆神奈川県の岩石
トーナル岩(主要産地:神奈川県丹沢山地)
展示してある場所:西丹沢自然教室,神奈川県立生命の星・地球博物館
神奈川県北西部の丹沢山地の中心部に分布する深成岩体.無色から白色の石英や斜長石と黒色の角閃石からなり,白と黒のコントラストが美しい.丹沢山地から流れ出す酒匂川や,酒匂川が注ぐ相模湾の西部では普通に見られる石でなじみ深い.伊豆弧の中部地殻を構成する深成岩体が露出したものと考えられてきたが,最近の年代測定から500〜400万年前(新第三紀鮮新世)にできたことが判明したため,丹沢が本州に衝突してからできた岩体と解釈されている.(写真提供:神奈川県立生命の星・地球博物館)
◆神奈川県の鉱物
湯河原沸石(主要産地:神奈川県足柄下郡湯河原町)
展示してある場所:神奈川県立生命の星・地球博物館
神奈川県西部の湯河原町の不動滝にて,1952年に櫻井欽一博士によって記載された新鉱物で,神奈川県の地名がつけられている唯一の鉱物.箱根火山の一部を構成している凝灰岩に入り込んだ熱水によって二次的にできた鉱物で,脈中に濁沸石などと一緒に産出する.結晶は無色透明で,変形した六角形の薄い板状の結晶をなす.脈中の結晶は,バラバラの向きで集合する.湯河原町指定天然記念物になっている.(写真:中央にある板状で虹色に輝く鉱物が湯河原沸石 提供:神奈川県立生命の星・地球博物館)
◆神奈川県の化石
丹沢層群のサンゴ化石群(主要産地:丹沢山地)
展示してある場所:県立生命の星地球博物館、県立秦野ビジターセンター、県立西丹沢自然教室、平塚市博物館
丹沢山地の中新統・丹沢層群の地層中にサンゴ石灰岩露頭が10地区で30ヶ所在る.その石灰岩は約1500万年前の火山島周辺に発達したサンゴ礁で堆積したものである.造礁サンゴ類、底生有孔虫類,オウムガイ類、石灰藻類化石などが見つかる.フィリピン海プレートに乗って遥々南の海から来て日本列島に付加したことを明示する生物化石が詰まっていて伊豆―小笠原弧の移動方向を教えてくれる.大地の変動を学ぶ良い教材資料である.(写真:人遠・皆瀬川のアオサンゴ群体化石.撮影:門田真人)
このページtopへ戻る
北海道・東北(県の石)
「県の石」:北海道・東北
▷「県の石」(大切なお願い/リスト/選定にあたって ほか)
<北海道・東北(北海道・青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島)>
<関東(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川)>
<中部・甲信越(新潟・長野・山梨・静岡・富山・石川・岐阜・愛知・福井)>
<近畿(滋賀・奈良・京都・三重・大阪・和歌山・兵庫)>
<四国(徳島・香川・高知・愛媛)>
<中国(岡山・広島・山口・島根・鳥取)>
<九州・沖縄(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)>
北海道の「県の石」
◆北海道の岩石
かんらん岩(主要産地:様似町(アポイ岳〜ピンネシリおよび幌満川流域))
展示してある場所:様似町役場前「かんらん岩広場」,アポイ岳ジオパークビジターセンター
日高山脈南端部のアポイ岳のかんらん岩は,「幌満かんらん岩」の名前で世界的に有名である.地下およそ70kmの「上部マントル」の岩石で,約1,300万年前に始まった日高山脈の上昇とともに地表まで持ち上げられた.主に,かんらん石 (オリーブ色)・斜方輝石(濃褐色)・単斜輝石 (エメラルドグリン)と少量のスピネルからなる.アポイ岳ジオパークは, 2015年にユネスコ世界ジオパークに認定された.(写真:新井田清信)
◆北海道の鉱物
砂白金(主要産地:北海道中軸部)
展示してある場所:北海道大学総合博物館,士別市立博物館,地質標本館
北海道の開拓時,全域でゴールドラッシュに湧いた事があった.砂金掘りの際,混在する砂白金は,当初は硬いだけで無価値な邪魔者であった.後に万年筆のペン先に用途が開け,戦前は輸出するほどの世界的産地でもあった.これら砂白金はイリジウム系の白金族元素の合金を主体とし,かつては「イリドスミン」と呼ばれた.起源はマントル由来の蛇紋岩で,産出地も北海道中軸部に沿う河川にほぼ限られている.
写真(上):中川 充.写真は夕張市白金川産.
写真(下):中川 充.幌加内町の雨龍川産で,長辺約 6mm.砂白金,砂金などの重鉱物類.
(注)「北海道博物館」では現在展示は行っていません。お詫びして訂正いたします。(2016.5.11)
◆北海道の化石
アンモナイト(主要産地:北海道中軸部(空知,留萌,日高など))
展示してある場所:三笠市立博物館,むかわ町穂別博物館,中川町エコミュージアムセンター,北海道博物館等
アンモナイトは,約4億年前から6600万年前頃まで生きていた,イカやタコと同じ仲間の生物である.北海道には,アンモナイトが大繁栄した後期白亜紀(約1億年前〜6500万年前)の海の地層が,三笠,穂別,中川などに分布しており,とても保存の良いアンモナイト化石が産出することで知られている.現在までに500種類ほどが発見され,今も新種のアンモナイト化石が毎年のように報告されるなど,1億年前の生命の進化の謎を探る大変貴重な場所となっている.(写真:栗原憲一)
このページtopへ戻る
青森県の「県の石」
◆青森県の岩石
錦石(鉄分を含む主に玉髄からなる岩石)(主要産地:全域)
展示してある場所:青森県立郷土館
津軽地域を中心に産する,磨いて美しい光沢を示す石を錦石と呼んでいる.玉髄・めのう・碧玉を主体とする岩石で,花紋石・玉鹿石(ぎょっかせき)・赤玉石などとも呼ばれている.錦石(玉鹿石)は藩政時代から多くの人々に親しまれてきた歴史をもち,1980年(昭和55)1月24日,青森県天然記念物に指定されている.(写真提供:青森県立郷土館)
(注)主要産地の表記を「五所川原市金木」→「全域」に修正.リストと統一(2016.7.12)
◆青森県の鉱物
菱マンガン鉱(主要産地:西目屋村 尾太鉱山)
展示してある場所:青森県立郷土館
尾太鉱山産の菱マンガン鉱は,きれいな桃色が特徴で,ぶどう状集合体組織の発達が見事であり,世界的に有名.地下深部の熱水によって周囲の岩石と反応して形成される.(写真提供:青森県立郷土館)
◆青森県の化石
アオモリムカシクジラウオ(主要産地:青森市荒川)
展示してある場所:青森県立郷土館.この種の基準となるタイプ標本のため収蔵庫に保管してあり,実物大の写真パネルを展示.
1970年(昭和45)に青森市の堤川上流で発見された深海魚の化石.保存状態が良好で細部まで観察でき,クジラウオ上科アカクジラウオダマシ科の新属新種として2007年12月に発表された.発見された地層は約1500万年前の淡緑色凝灰質泥岩です.本標本はクジラウオ上科の世界初の化石であり,極めて珍しく貴重である上,このなかまの進化の跡を辿る上でも重要な標本である.(写真提供:青森県立郷土館)
秋田県の「県の石」
◆秋田県の岩石
硬質泥岩(主要産地:男鹿市船川港女川など,女川層分布地域)
展示してある場所:秋田大学鉱業博物館,秋田県立博物館など
中新世中期後半から後期にかけて日本海の海底に堆積した,
堅硬かつ緻密な泥岩である.珪藻由来のシリカを多量に含み,板状に割れやすい性質から,珪質頁岩と呼ばれることもある.硬質泥岩中からは,しばしば保存状態の良い魚類や海棲哺乳類の化石が見出される.特に珪質なものはガラスのような質感があり,古代には,石器の材料としてさかんに利用された.日本海側に分布する油田の石油根源岩としてもよく知られている.(写真:秋田市河辺の女川層硬質泥岩の露頭 西川 治)
◆秋田県の鉱物
黒鉱(主要産地:秋田県北鹿地域)
展示してある場所:秋田大学鉱業博物館,秋田県立博物館,小坂町立資料館など
中期中新世の酸性の海底火山活動によって海底に沈殿した,主に方鉛鉱,閃亜鉛鉱,黄銅鉱,重晶石からなる緻密で塊状の黒色鉱石である.銅,鉛,亜鉛に加えて,金,銀や多種類のレアメタルを含んでおり,明治中期から昭和にかけて盛んに採掘された.大規模な鉱床が発達する秋田県北部の北鹿地域で,先進的に開発と鉱床の研究がおこなわれてきたため,「Kuroko」は学術用語として国際的に通用する.(写真:秋田大学鉱業博物館所蔵)
◆秋田県の化石
ナウマンヤマモモ(主要産地:特定の場所無し)
展示してある場所:秋田大学鉱業博物館
学名:Comptonia naumanii.環日本海地域の前期中新世後期の地層中に広く産する台島型植物群の代表的な化石のひとつである.台島型植物群は,常緑・落葉混合の植物群で,現在の本州中部以西太平洋岸に相当する温暖な気候を示す.ナウマンヤマモモは,細長くギザギザに切れ込んだ葉が特徴のヤマモモ科の植物である.本邦では,鮮新世まで近縁種の化石が産出するが,現世では北アメリカに1種のみが認められている. (写真 産地:仙北市下檜木内 秋田大学鉱業博物館所蔵)
岩手県の「県の石」
◆岩手県の岩石
蛇紋岩(主要産地:早池峰山)
展示してある場所:岩手県立博物館
蛇紋岩はかんらん岩を起源とする岩石で,詩人で童話作家の宮澤賢治が特別な親しみを持っていたことでも知られる.蛇紋岩地帯には固有の植物種が成育するため,早池峰山を訪れる登山客にも馴染みが深い.早池峰複合岩類中の中岳蛇紋岩類は,南部北上山地の北縁に位置し,早池峰山周辺に広く分布する.1980年代以降の研究で,南部北上山地の基盤をなすオルドビス紀の島弧オフィオライト(地殻断面の岩石)であると位置づけられるようになった.国定公園,日本ジオパークのジオポイントとして指定されている.(写真:大石雅之)
◆岩手県の鉱物
鉄鉱石(主要産地:釜石市甲子町ほか)
展示してある場所:岩手県立博物館
釜石付近には,石炭紀からペルム紀の石灰岩に前期白亜紀の花崗閃緑岩が接触したことで生成したスカルンが鉱化されてできた鉄鉱床・銅鉱床が分布する.鉄鉱床は,安政年間の日本初の洋式高炉に始まる近代製鉄の礎となり,明治以降日本の経済成長を支え続けて来た.このため,日本の近代製鉄の先駆けとなった橋野鉄鉱山は世界遺産に登録された.この鉄鉱石は磁鉄鉱であり,磁性を持つ.流域の河川では,磁鉄鉱礫(餅鉄 べいてつ)を拾うことができる.(写真:岩手県立博物館(釜石市栗林町産の餅鉄,IPMM 62567))
◆岩手県の化石
シルル紀サンゴ化石群(主要産地:大船渡市日頃市町樋口沢)
展示してある場所:岩手県立博物館・大船渡市立博物館
大船渡市日頃市町樋口沢に分布する石灰岩から,1936年に日石サンゴが発見されたことにより,日本ではじめてシルル紀の岩石であると確認された.以後,西日本や北上山地の他地域でもシルル紀の岩石が見つかった.樋口沢の石灰岩からは,サンゴ・層孔虫・腕足類など多様な化石が産出する.日石サンゴを含む樋口沢のシルル紀化石群は,日本の地史を研究する上で重要な情報を提供しており,国の天然記念物に指定されている.(写真:大石雅之)
山形県の「県の石」
◆山形県の岩石
デイサイト凝灰岩(主要産地:山形市山寺)
芭蕉の「閑さや岩にしみ入る蝉の声」の句が有名な,貞観2年(860年)に慈覚大師によって創建された名刹立石寺(別名山寺)の周辺に分布している山寺層の凝灰岩.主に凝灰角礫岩,火山礫凝灰岩からなる.後期中新世に陸化した奥羽山地ではたくさんのカルデラ火山が形成しており,この地層は奥羽山地西翼のカルデラ火山から噴出された火砕流堆積物である.そそり立つ急崖の表面にタフォニ(雲形浸食)が発達し,虫食い状の特異な景観を作っている.(写真:大友幸子)
◆山形県の鉱物
そろばん玉石(カルセドニー)(主要産地:小国町)
展示してある場所:山形県立博物館,山形大学附属博物館
算盤(そろばん)の玉のような形の石で,玉髄(SiO2)からなる.マグマ中に溶け込んでいたH2OやCO2などの揮発性成分が,マグマが固結する過程で気泡となり,気泡はマグマの流動にともなって円盤状の形になる.流紋岩や安山岩マグマは粘性が大きく,気泡が大きくなりやすい.マグマ固結後に,その空洞を満たしたSiO2に富む熱水から玉髄が晶出し,空洞を充填する.その後,母岩の風化により玉髄が分離したものである.小国町のそろばん玉石は流紋岩中に形成したもので,山形県指定天然記念物である.指定地では現在ほとんど採集できないが,ほかの新第三紀の流紋岩〜安山岩岩体の分布するところでも見つかることがある,(山形大学附属博物館展示 写真:大友幸子)
◆山形県の化石
ヤマガタダイカイギュウ(主要産地:大江町三郷甲,用地区の最上川川床)
展示してある場所:山形県立博物館
1978年に大江町の最上川の河床で二人の小学生が発見した.化石は後期中新世の本郷層橋上砂岩部層から発掘され、海牛の進化の系統を考える上で重要な新種の海牛化石(Dusisiren dewana)であることがわかった.この系列の海牛は、体を大型化させながら、歯と指の骨を消失するという進化をたどった.縮小・退化した「歯」と「指の骨」を持つヤマガタダイカイギュウはその中間的形質をもつ世界的にも貴重な標本で、県の天然記念物に指定されている.(写真提供:山形県立博物館)
このページtopへ戻る
宮城の「県の石」
◆宮城県の岩石
スレート(主要産地:登米市登米,石巻市雄勝)
展示してある場所:東北大学理学部自然史標本館
宮城県北部から岩手県南部にまたがる南部北上山地には,中期〜後期ペルム紀に形成された泥岩が分布する.この泥岩には,圧密作用によりスレート劈開と呼ばれる面構造が生じている.そのような岩石はスレート(粘板岩)と呼ばれ,その面に沿って薄くはがれるため,世界各地で石材として利用されている.宮城県の登米や雄勝で産出するスレートは品質が高く,特に後者は雄勝石と呼ばれ,硯の原料として用いられている.(写真提供:東北大学理学部自然史標本館)
◆宮城県の鉱物
箟岳(ののだけ)、涌谷(わくや)の砂金(主要産地:遠田郡涌谷町涌谷,箟岳)
展示してある場所:涌谷町役場 ※「涌谷町歴史・上」(昭和40年発行)のカラー図版に「黄金沢の砂金」の写真あり.
本邦初の金の産地と考えられてきた.「万葉集」に金の産出が歌われ,「続日本記」には奈良東大寺の大仏鋳造のために黄金900両(約13キロ)が陸奥国府から平城京に届いたという記録が存在する.これらは漂砂型の砂金鉱床であったと考えられる.箟岳丘陵の砂金の多くは金鉱化作用を伴う浅熱水性石英脈鉱床あるいはペグマタイト鉱床を供給源として,それが堆積してできたものだと考えられる. (写真:写真:「涌谷町歴史・上」(昭和40年発行)のカラー図版の「黄金沢の砂金」)
◆宮城県の化石
ウタツギョリュウ(主要産地:本吉郡南三陸町歌津)
展示してある場所:東北大学理学部自然史標本館
学名:Utatsusaurus hataii Shikama, Kamei et Murata
1970年に南三陸町歌津館崎の海岸に分布する前期三畳紀の頁岩(2億4500万〜2億5000万年前)から発見された魚竜(海棲は虫類)の化石である.1978年に鹿間時夫、亀井節夫、村田正文により記載論文が発表され,上記の学名が提唱された.ウタツギョリュウは世界最古の魚竜の1つであり,原始的な形態を有しているとされている.(写真提供:東北大学理学部自然史標本館)
福島県の「県の石」
◆福島県の岩石
片麻岩(主要産地:阿武隈高原)
展示してある場所:福島県立博物館
阿武隈高原南部に分布する阿武隈変成岩は19世紀末から研究が進められ,高温−低圧型の標準的な変成岩として世界的に有名となった.西半部の変成度が高い岩体(竹貫変成岩)の主体をなすのが,黒白の縞状で粗粒な岩石で白亜紀の変成年代をもつ片麻岩である.阿武隈変成岩の原岩については,一部ジュラ紀の付加堆積物が含まれているが,変成帯全体の形成過程については未解決な問題が多く,その解明は日本列島の基盤の成り立ちを探る上で重要である.(写真:阿武隈変成岩中の雲母片麻岩 福島県立博物館蔵)
◆福島県の鉱物
ペグマタイト鉱物(主要産地:石川郡石川町)
展示してある場所:福島県立博物館,石川町歴史民俗資料館
ペグマタイトは,地下深い場所でマグマから花崗岩がつくられた後,残りの揮発成分の多い残留マグマが岩石の割れ目に入り込んで形成されたもので,巨大な鉱物の結晶を含み巨晶花崗岩とも呼ばれる.石川地方のペグマタイト鉱物は,白亜紀の花崗岩から産出し,石英・長石・雲母・電気石などの結晶が特に大きく,また希少元素や放射性元素を含む鉱物を数多く産出することで全国的に有名である.1995年に福島県の天然記念物に指定されている.(写真:石川地方産のペグマタイト鉱物 福島県立博物館蔵)
◆福島県の化石
フタバスズキリュウ(主要産地:いわき市大久町)
展示してある場所:福島県立博物館(全身骨格複製),いわき市石炭・化石館(全身骨格複製)
フタバスズキリュウは,1968年に,いわき市大久町に露出する後期白亜紀(約8500万年前)の玉山層から発見された爬虫類のクビナガリュウ化石である.頭骨・胸骨・四肢骨・骨盤など重要な部分が見つかり,全身の骨格が復元された.全長は約7m.日本で発見されたクビナガリュウの唯一の全身骨格化石である.2006年にプレシオサウルス上科のエラスモサウルス科に属する新属新種Futabasaurus suzukiiとして正式に記載された.
(写真:フタバスズキリュウ全身骨格(複製) 福島県立博物館蔵)
このページtopへ戻る
「県の石」選定にあたって
「県の石」選定にあたって
「県の石」選定にあたって
日本地質学会は、5月10日「地質の日」に、「県の石(岩石・鉱物・化石)」の選考結果を発表しました。2014年8月に公募を開始して以来、1年9ヶ月に渡って進めてきた選考が結実したことは、誠に喜ばしいことです。
「県の石」は、市民の方々に、各地域の岩石・鉱物・化石を身近な存在として捉えていただくことにより、自らが生活する大地の歴史と成り立ちを知っていただき、安全に暮らす一助となればとの強い思いをもって選定しました。
この事業は、学術団体である日本地質学会が、日本全国の地域の意見と学術的な重要性を考慮して選定したものです。諸外国にも例のない事業であり、日本地質学会120有余年の歴史を踏まえて、日本の地球科学の歴史に残るマイルストーンとなるものと評価できると思います。
選定に際しては、市民や会員の方々の岩石・鉱物・化石に対する愛着と強い思いが感じられ、選考は苦渋の選択ともいえるものでした。
今後は、今回選考した県の石を、市民の方々に広く親しんでいただくために、書籍として出版いたします。出版の際には、今回選定した以外にも、候補にあがって残念ながら選にもれた岩石・鉱物・化石も掲載する予定です。
各県におかれては、この機会にぜひ「県の石」をさまざまに活用していただくことを希望いたします。「県の石」が広く市民の皆様に受け入れられ、親しまれることを祈念いたします。
2016年5月10日
一般社団法人日本地質学会
会長 井龍康文
◆「県の石」発表にもどる
◆「県の石」リストはこちらから
◆ 47都道府県 各「県の石」詳細はこちらから
博物館のイベント
博物館イベントカレンダー
イベントの詳細については、リンク先の主催館Webページをご覧ください。 なお、イベントには事前申し込みが必要なもの、対象者・対象年齢に制限があるもの、参加費が必要なものなどがありますので、お出かけの際には、主催する博物館へ詳細をお問い合わせ下さい。
特別展・企画展: イベント 講座・イベント: イベント
(お願い)博物館等 関係者の皆様へ
地学関係のイベントがございましたら、学会Webページ 内のフォームま たはメールにて情報をお寄せください。 その際、以下の内容をまとめてお送り頂けますと助かります。
イベント種別:(特別展示・野外観察会・体験イベント・講演会・講座 のいずれか)
主催館(者):
タイトル:
日時:
場所:
簡単な内容:
事前申込:(必要・不要 のいずれか)
申込詳細:必要な場合のみ URL:
2017年地質の日_学会関連の催し
2017年の「地質の日」
ここでは,2017年の「地質の日」に関連した日本地質学会主催,共催,後援等の催しをご紹介します。
>>イベントカレンダーもご覧下さい(地質学会以外のイベント情報も掲載しています)。
/北海道NEW/東 北/中 部/関 東/近 畿/四 国/西日本/その他
日本地質学会 3.17掲載
(上)真姿の池湧水群.(下)姿見の池
2017年地質の日記念
街中ジオ散歩in Tokyo「国分寺崖線と玉川上水」
申込は締切ました。
多数のお申込をいただき,ありがとうございました。
身近な地質とその地質に由来する地形について,それらを利用してきた先人から現在の私たちまでの営みを,専門研究者の案内で楽しく学ぼうという企画です.今回は,都内でも有数の湧水地として知られている国分寺崖線と江戸時代から現代にいたるまで,生活上水を供給し続けている玉川上水を見学します.また,武蔵国分寺跡も見学し,武蔵国分寺の歴史についても学びます.初夏の清々しい空気の中を,楽しく“ジオ散歩”したいと思います.
主催:一般社団法人日本地質学会,一般社団法人日本応用地質学会
後援:国分寺市,小平市,一般社団法人東京都地質調査業協会
日時:2017年5月14日(日)9:45〜16:00 小雨決行(予定)
見学場所:東京都国分寺市,小平市(国分寺崖線,玉川上水)
案内者:山崎晴雄氏(首都大学東京名誉教授),中山俊雄氏(東京都土木技術支援・人材育成センター)
会費:高校生以上・一般:1,500円,小・中学生:500円(保険代,入場料含む)
(注)参加費は,当日現金をご持参ください.昼食は各自ご用意下さい.途中,一部電車での移動(鷹の台駅→国分寺駅)があります.運賃は各自負担となります.
集合:西武国分寺線 鷹の台駅 9:45 集合
見学コース(予定):10:00 西武国分寺線鷹の台駅(出発)→ 玉川上水(露頭観察)→ ふれあい下水道館(昼食)→ 鷹の台駅→(電車移動)→ 国分寺駅→ 真姿の池湧水群→ 武蔵国分寺跡資料館→ 東山道武蔵路跡→ 姿見の池→ JR西国分寺駅16:00頃 解散
募集人数:30名
対象:小学生以上.ただし,小・中学生の方は保護者の同伴をお願いします.主催団体の会員の申込も可能ですが,本行事は一般向け普及行事ですので,非会員の一般市民の参加を優先します.定員を超えた場合,会員は若干名 とさせていただきます.
申込受付期間:2017年 4月1日(土)〜 4月10日(月)
(申込者多数の場合は抽選を行います.結果は4月中に郵送で全員にお知らせします)
申込は締切ました。多数のお申込をいただき,ありがとうございました。
抽選結果(参加の可否)は,4月中に郵送で全員にお知らせします
(注:グループでの申込場合は,代表者にのみお知らせします)
申込方法:学会HPの申込み専用フォームまたは,FAXにてお申込み下さい.
【WEB申込専用フォーム】http://www.photo.geosociety.jp/geosanpo2017.html(4/1から申込可能)
【FAXの場合】記入事項1〜6をすべて記入願います.メール等がない場合は“なし”とご記入下さい. 1.氏名,2.自宅住所(郵便物を受け取れる住所),3.携帯等電話番号,4.メールアドレス,5.生年月日,6.性別 (注)小・中学生の申込の際は, 1, 5, 6について保護者の情報も明記して下さい.
申込・問い合わせ先:一般社団法人日本地質学会(担当 細矢)
電話:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156
メール:main@geosociety.jp
第8回惑星地球フォトコンテスト表彰式
日程:4月8日(土)12:45〜13:45
会場:北とぴあ901会議室(東京都北区王子)
入選作品の展示も行います!
▶フォトコンテストのサイト http://www.photo.geosociety.jp/
第8回惑星地球フォトコンテスト入選作品展示会
日程:6月10日(土)午後〜 6月27日(土)12:00
場所:銀座プロムナードギャラリー(中央区銀座4丁目 東銀座地下歩道壁面)
▶フォトコンテストのサイト http://www.photo.geosociety.jp/
近畿支部 4.3更新
第34回地球科学講演会「国石になった翡翠について」
主催: 地学団体研究会大阪支部・日本地質学会近畿支部・大阪市立自然史博物館
2016年9月、日本鉱物科学会が日本を代表する石(国石)として翡翠を選びました。なぜ、翡翠が国石になったのでしょうか。最終候補として残った水晶、輝安鉱、自然金、花崗岩などよりも何が高く評価されたのでしょうか。国石になった翡翠について、地球科学と歴史科学の立場からその特徴や価値、いまだに解決されていないさまざまな謎をご紹介します。
日時:2017年5月14日(日)14:00-16:00(13:00より受付)
場所:自然史博物館 講堂
講師:宮島 宏氏(糸魚川市フォッサマグナミュージアム)
参加費: 無料(博物館入館料必要)
参考ホームページ:http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
中部支部 3.21更新
大地のかけらを探せ!!ぼくのわたしの石の標本作り:地質の日 in 白山手取川ジオパーク
主催:金沢大学理工学域自然システム学類地球学コース・白山手取川ジオパーク推進協議会
後援:日本地質学会中部支部
日時:5月13日(土)10:00〜12:00(集合 9:45〜)
集合場所:道の駅しらやまさん(石川県能美市和佐谷町200)
対象:小学校4年生〜高校生の親子(子どものみでも参加可)
定員:20組(先着順) ※申込締切:5月9日(火)17:00
参加費:500円(標本箱代,保険代など)
内容:白山手取川ジオパークは,恐竜の化石が出ることなどで有名です.しかし,その大地は,恐竜が生活するずっと以前にできていました.恐竜が生活する前の大地,恐竜の時代の大地,そして,今私たちの目の前にきらめく白山を作っている大地,それぞれの大地のかけらを河原で探して,自分だけの標本を作りましょう!
申込先・問い合わせ:白山手取川ジオパーク推進協議会
〒924-8688 白山市倉光二丁目1
TEL:076-274-9564 FAX:076-274-9546
E-mail:geopark[at]city.hakusan.lg.jp
WEBサイト:http://hakusan-geo.main.jp
とやまの自然探検「神通川の石ころ観察会」/「常願寺川の石ころ観察会」
後援:日本地質学会中部支部
「神通川の石ころ観察会」
日時:2017年4月29日(土)13:30〜15:30 雨天・増水時中止
「常願寺川の石ころ観察会」
日時:2017年5月13日(土)13:30〜15:30 雨天・増水時中止
主催:富山市科学博物館
いずれも参加無料,要申込
http://www.tsm.toyama.toyama.jp/
長岡市立科学博物館:特別展/企画展
後援:日本地質学会中部支部
・ミニ企画展:アルバートサウルスの前・後肢化石(レプリカ)
日程:2017年4月4日(火)〜23日(日)
・GW特別展示:ハルキゲニア実物化石と生体復元模型2種
日程:2017年4月29日(祝)〜5月7日(日)
・ミニ企画展:パラサウロロフスの下顎化石(レプリカ)
日程:2017年5月10日(水)〜6月4日(日)
http://www.museum.city.nagaoka.niigata.jp/
川の石を比べてジオを知る
主催:黒部市吉田科学館
後援:日本地質学会中部支部
日程:2017年5月14日(日)雨天・増水時は中止
http://kysm.or.jp/
北海道支部支部 4.17更新
地質の日記念展示「北海道のジオサイトに見る化石」
画像をクリックするとポスター画像がダウンロードできます
期間: 2017年 4月28日(金)〜 6月18日(日)
休館日: 月曜日 時間: 10:00 〜 17:00 (6 〜10 月の金曜日は21:00 まで)
会場: 北海道大学総合博物館1 階企画展示室 【入場無料】
主催:地質の日展実行委員会・北海道大学総合博物館
共催:日本地質学会北海道支部・産総研地質調査総合センター・道総研地質研究所・北海道博物館・札幌市博物館活動センター・北海道地質調査業協会
後援:北海道教育委員会・札幌市・札幌市教育委員会
協力:沼田町化石館
問い合わせ先: 北海道大学総合博物館 〒060-0810 札幌市北区北10 条西8 丁目 TEL:011-706-2658
市民セミナー,巡検も予定されています。
詳しくは,北海道支部HPをご参照ください。
その他 3.7掲載
画像をクリックするとJPEGが
ダウンロードできます
観察会 城ヶ島と三崎の地盤隆起:1923年の大正関東地震の地殻変動
主催:ジオ神奈川
後援:日本地質学会,三浦市,三浦市教育委員会
日時:5月13日(土)10:00〜15:00
場所:神奈川県三浦市城ヶ島
参加費:500円
申込締切:5月5日(金)
申込方法:メールもしくははがきで,住所,氏名,電話,年齢を記入して下記までお申し込み下さい.
申込・問い合わせ先:ジオ神奈川 代表 蟹江康光
〒249-0004 逗子市沼間2-9-4-405
メール:okinaebis@mac.com
WEBサイト http://okinaebis.com/
観察会「深海から生まれた城ヶ島」
三浦半島最南端の城ヶ島は,風光明媚な観光地として知られています.この自然豊かな城ヶ島には美しい風景や動物・植物ばかりではなく,たくさんの変化に富ん だ地形・地質を見る事が出来ます.炎が舞っているような火山灰の地層や複雑な断層,深海に生活していた生物の痕跡,激しい火山爆発によってもたらされた火 山豆石やゴマ塩火山灰などなど.城ヶ島には三浦半島誕生の秘密がたくさん詰まっています.
主催:三浦半島活断層調査会
後援:三浦市(予定)・日本地質学会
日時:5月21日(日)10:00〜15:00 小雨決行
場所:神奈川県三浦市城ヶ島
参加費:500円(資料,保険代)
募集人員:50名
注意事項:海岸の岩場を歩くので,履き慣れた靴でご参加下さい.飲み物,弁当は各時持参.
申込締切:5月10日(水)
申込方法:メールもしくは往復はがきで,住所,氏名,電話番号を記入して下記までお申し込み下さい.
申込・問い合わせ先:三浦半島活断層調査会事務局(赤須邦夫方)
〒249-0008 逗子市小坪5-16-11
メール:akasu@jcom.zaq.ne.jp
地質の日イベントカレンダー
地質の日イベントカレンダー
・地質学会の主催,共催,後援などのイベント: イベント
・その他の「地質の日」のイベント: イベント
地学研究発表会(2016東京)
報告:小さなEarth Scientistのつどい〜第14回小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜
日程:2016年9月11日(日) 会場:日本大学文理学部
東京桜上水大会2日目に,小さなEarth Scientistのつどい〜第14回小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜がおこなわれた.年会における発表会は13年前の静岡大会からおこなわれており,今回の開催で,14回目を迎えることとなった.この発表会の目的は,地学普及の一環として学校における地学研究を紹介することで地学教育の奨励と振興を図ることと,地学を研究する児童・生徒と研究者の交流が進み,地球科学普及の一助となることである.
今回の発表会もポスターセッション会場の一画を本企画の会場として利用させて頂いたので,多くの会員の方にご参加頂けたものと思われる.日本大学文理学部3号館の5階に,エスカレータで登った一帯(通路やラウンジなど)で行ったので,東京桜上水大会に参加した多くの会員に気付いていただけただろう.例年のことであるが,若い地球科学者の熱気を帯びた説明で,その一角がさらに蒸し暑くなったことを記憶している.今回は,関東支部地区における開催であり,第2回の千葉大会が非常に多くの学校に参加していただけたので,担当者として期待をしていた.結果として,東京都内の6校(7件)の発表をはじめ,全体としては 16校(22件)の発表となった.学校数,発表件数ともに増加した.また,昨年の長野大会に比べて1週間早いため学校行事と重なったり,あるいは,早くなったため重ならなかったりなど,日程についてはいろいろとご意見をいただいた.学校行事と重なった学校にはコアタイムのみ参加いただいたり,生徒は参加せずにポスターのみを送付していただいたりした.
なお,この発表会では本学会の理事と地学教育委員会委員を中心とした審査員によるポスター審査を行っている.審査基準は,「研究の動機が明確であり,問題点をはっきりととらえているか」,「観察・実験から導かれたデータを基に,結論が導かれているか」,「わかりやすいポスターとしてまとめられているか」の3つの観点である.一方で,発表(説明内容)については,加点していない.「全体的に優れている」発表に対して優秀賞を,「フィールドに根ざして研究を行っており,今後の成果が期待される」発表に対して奨励賞を授与している.今回は名簿前半の理事の方々にお願いし,約半数の方が実際に審査をしていただいた.
全ての発表を審査した結果,下に示す3件の発表に対して優秀賞が授与されている.また,フィールドに根ざして研究している学校への奨励賞については,下の3件に授与された.
最後となったが,審査にあたっていただいた理事各位,東京都内の学校の先生方,行事委員会委員,会場校である日本大学文理学部と関東支部の関係各位,さらに今回の発表会参加者(生徒と引率の先生方)に謝意を表したい.
【優秀賞】
領家帯のアプライト岩脈から推定される応力場(愛知教育大学附属岡崎中学校・星 輝)
芳野層堆積当時の環境変動を探る(熊本県立熊本西高等学校地学部・臼杵秀悟,西本有輝)
【奨励賞】
花崗岩の風化度基準の定量化を目指して(兵庫県立加古川東高等学校・岩本南美,田島春香,田村 笙,東森碧月,中野勝太,中野美玖,尾藤美樹)
皆既月食の研究(鹿児島玉龍高等学校サイエンス部天文班・石原夏葉,竹島侑未,鬼塚瑠奈,江口佳穂,堀切啓奈,橋元季里,鬼丸陽奈)
兵庫県中南部に広がるカルデラ湖の中でどのようなマグマ分化が進行したのか〜凝灰岩の包有岩片中の角閃石から波状累帯構造を発見〜(兵庫県立西脇高等学校地学部マグマ班・田中愛子,石井紗智,田中朱音,戸田亮河,村上 智,神崎直哉,岸本大輝,笹倉瑠那,津田晟俊,福田俊介,藤原宏馬,村上凱星,藤原丈瑠,吉田 葵)
岡山城の石垣石材の種類とその産地の変遷についての考察(岡山理科大附属高等学校普通科進学理大コース・佐野 佑,原且行,西村 隆)
【発表会参加校】
東京学芸大学附属高等学校(2件)
駒場東邦中学高等学校地学部
早稲田高校地学部
早稲田大学高等学院理科部地学班
中央大学附属中学校・高等学校地学研究部
東京都立府中高等学校地学部
群馬県立太田女子高校地学部
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校天文部(化石・岩石班)
法政大学第二中学校科学部(2件)
愛知教育大学附属岡崎中学校
兵庫県立西脇高等学校地学部(3件)
兵庫県立加古川東高等学校自然科学部地学班
学校法人奈良学園奈良学園高等学校
岡山理科大学附属高等学校
鹿児島玉龍高等学校サイエンス部天文班(3件)
熊本県立熊本西高等学校地学部
2018年の「地質の日」
2018年の「地質の日」
ここでは,2018年の「地質の日」に関連した日本地質学会主催,共催,後援等の催しをご紹介します。
>>イベントカレンダーもご覧下さい(地質学会以外のイベント情報も掲載しています)。
/北海道/東 北/中 部/関 東/近 畿/四 国/西日本/その他
日本地質学会 3.15掲載
第9回惑星地球フォトコンテスト展示会
日程:4月28日(土)午後 〜 5月12日(土)12:00
場所:銀座プロムナードギャラリー(中央区銀座4丁目 東銀座地下歩道壁面)
日本地質学会創立125周年記念の特別賞を設けました.
▶入選作品はこちら http://www.geosociety.jp/faq/content0009.html
第9回惑星地球フォトコンテスト表彰式
日程:5月19日(土)11:00〜12:30(予定)
会場:北とぴあ 第2研修室会議室(東京都北区王子)
入選作品の展示も行います!
▶入選作品はこちら http://www.geosociety.jp/faq/content0009.html
2018年地質の日記念 兼 日本地質学会125周年記念事業
街中ジオ散歩 in Kawasaki「多摩丘陵の100万年を歩く」徒歩見学会
身近な地質とその地質に由来する地形について,それらを利用してきた先人から現在の私たちまでの営みを,専門研究者の案内で楽しく学ぼうという企画です.今回は,都心に比較的近い場所で自然露頭が多く残っている川崎市の生田緑地公園を散策し,多摩丘陵の構成層を観察します.公園内では,泥岩層,砂礫層,火山灰層(テフラ層)が観察でき,これら地層を観察することで,この地域がいつどのようにできたのか学ぶこができます.また,公園内にある高台(枡形山)の展望台より関東平野一円を眺め,武蔵野台地,多摩丘陵の成り立ちを学びます.初夏の清々しい空気の中を,楽しく“ジオ散歩”したいと思います.
主催:一般社団法人日本地質学会,一般社団法人日本応用地質学会
後援:川崎市教育委員会,一般社団法人東京都地質調査業協会
日時:2018年5月13日(日)9:45〜16:00 小雨決行(予定)
見学場所:神奈川県川崎市多摩区生田緑地公園内
案内者:山崎晴雄氏(首都大学東京名誉教授),
増渕和夫氏(元かわさき宙と緑の科学館)
会費:高校生以上・一般:2,000円,小・中学生:500円(保険代,入場料含む)
(注)参加費は,当日現金をご持参ください.昼食は各自ご用意下さい.
※やや急な坂や足元の滑る場所が多くある,健脚の方向けのコースです.
集合場所・時間:かわさき宙と緑の科学館(生田緑地公園内)前 9:45集合
見学コース(予定):10:00かわさき宙と緑の科学館見学(剥ぎ取り試料,ボーリングコア)→科学館南側の露頭観察(飯室層,ウワバミテフラ)→不整合の大露頭→昼食(科学館自由観察)→科学館北側の露頭観察(飯室層中の化石,噴砂跡,おし沼砂礫,立川ローム)→枡形山(地形観察)→崩壊地形→横穴古墳→アシカ化石発見露頭前解散16時ごろ
募集人数:30名程度
対象:小学生以上(主催団体の会員の申込も可).ただし,小・中学生の方は保護者の同伴をお願いします.また,本行事は一般向け普及行事ですので,非会員の一般市民の参加を優先します.定員を超えた場合,会員は若干名とさせていただきます.また,夫婦,友人など,グループでの参加希望の場合は,それぞれの備考欄に代表者名を記入してください.グループでの応募は,本人を含め最大4名までとします.
申込受付期間:2018年3月31(土)〜4月10日(火)(申込者多数の場合は抽選を行います.結果は4月中に郵送で全員にお知らせします)
お申込の受付は締切ました
申込・問い合わせ先:一般社団法人日本地質学会(担当 細矢)
電話:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156
メール:main[at]geosociety.jp *[at]を@マークにして下さい
近畿支部 3.29更新
第35回地球科学講演会
「都市大阪を生んだ土地のなりたち―遺跡の地層から読む―」
「大阪南の心斎橋筋は、1500年前は海岸だった」「薬問屋の町、道修町通りは、奈良時代は入江だった」というと、大阪をよく知る方も少なからず驚かれるでしょう。そんなちょっとローカルな土地のなりたちを、上町台地や海岸低地を中心に、都市づくりや気候変化もまじえて、縄文時代から豊臣時代までたどります。
主催:地学団体研究会大阪支部・日本地質学会近畿支部・大阪市立自然史博物館
日時:2018年5月13日(日) 14:00〜16:00
会場:大阪市立自然史博物館 講堂
講師:趙 哲済氏(大阪文化財研究所)
対象:どなたでも参加できます
申込み:不要、直接会場へお越しください(先着250名)
西日本支部 4.23掲載
第10回 身近に知る「くまもとの大地」
主 催:「地質の日」くまもと実行委員会
共 催:日本地質学会西日本支部ほか
日 時:2018年6月2日(土)10:00〜16:00
会 場:びぷれす広場(熊本市通町筋)
概 要:熊本の地質や地形などに関連した展示(熊本の地質や恐竜などの化石、岩石、鉱物など)やパネル、映像(熊本の自然災害、地下水)、実験などの体験型のブースを準備した上での、自然科学分野の普及活動。
北海道支部 18.5.15掲載
地質の日記念展示「北海道のジオサイトに見る岩石」
期間: 2018年 4月27日(金)〜 6月17日(日)
休館日: 月曜日 時間: 10:00 〜 17:00 (6 〜10 月の金曜日は21:00 まで)
会場: 北海道大学総合博物館1 階企画展示室 【入場無料】
主催:地質の日展実行委員会・北海道大学総合博物館
共催:日本地質学会北海道支部・産総研地質調査総合センター・道総研地質研究所・北海道博物館・札幌市博物館活動センター・北海道地質調査業協会
後援:北海道教育委員会・札幌市・札幌市教育委員会
協力:NPO法人北海道総合地質学研究センター
問い合わせ先: 北海道大学総合博物館 〒060-0810 札幌市北区北10 条西8 丁目 TEL:011-706-2658
市民セミナー,巡検も予定されています。
○市民地質巡検 街中ジオ散歩 in Sapporo ジオサイト「藻岩山」を歩く
日時:6月2日(土)10:00〜15:00
参加費:400円(保険代等)
申込締切:5月18日(金)必着
○市民セミナー 「北海道における地質学の調査・研究の事始め〜北海道命名150年によせて〜」
日時:5月26日(土)13:30〜15:00
講師:松田義章(NPO法人北海道総合地質学研究センター)
詳しくは,https://www.museum.hokudai.ac.jp/display/special/13281/
その他 3.14掲載
地質情報普及講座「深海から生まれた城ヶ島」
主催:三浦半島活断層研究会
後援:日本地質学会・三浦市
日程:2018年5月20日(日)10:00 〜15:00(小雨決行)
場所:神奈川県三浦市城ヶ島
火山活動と地震活動に焦点をあてて城ヶ島の自然を楽しみます.
三浦半島最南端の城ヶ島は,風光明媚は観光地として知られています.この自然豊かな城ヶ島には美しい風景や動物・植物ばかりではなく,たくさんの変化に富んだ地形・地質を見ることができます.炎が舞っているような火山灰の地層や複雑な断層,深海に生活していた生物の痕跡,激しい火山爆発によってもたらされた火山豆石やゴマ塩火山灰などなど.城ヶ島には,三浦半島誕生の秘密がたくさん詰まっています.
募集人員:50名
注意:海岸の岩場を歩くので,履き慣れた靴でご参加下さい.飲み物,弁当は各自持参.
参加費:500円(資料代,保険)
申込締切:5月10日(木)
申込方法:往復はがきまたはe-mailにて,住所,氏名,電話番号をご記入のうえ,下記までお申込下さい.
申込先:三浦半島活断層調査会 事務局(赤須邦夫方)
〒249-0008 逗子市小坪5-16-11
電話 0467-24-0935 e-mail: akasu[at]jcom.zaq.ne.jp
その他 3.28掲載
観察会 城ヶ島の高潮・大正関東地震津波・地盤隆起
主催:ジオ神奈川
日時:2018年5月19日(土)10:00〜15:00
場所:神奈川県三浦市城ヶ島
2017年10月23日,台風21号による高潮は,城ヶ島に大被害を与え,島の南部の民宿・食堂は大破しました。長津呂から進入した高潮は7〜8 mと見積もられます.1923年の大正関東地震時は,地盤隆起は断層に挟まれた地塊ごとに隆起量は異なります.地盤隆起で津波被害は減少されましたが.1917(大正6)年の高潮では,大被害を生じました.今回は,自然の防波堤,要塞島であった城ヶ島の地質と高潮被害を観察します.また,1881(明治14)年に開校した旧城ヶ島分校・海の資料館でまとめの学習を行います.
参加費:800円
定員:25名(先着順受付)
申込締切:5月6日(日)
申込方法:メールもしくは往復はがきで,住所,氏名,電話,年齢を記入して下記までお申し込み下さい.
申込・問い合わせ先:ジオ神奈川 代表 蟹江康光
〒249-0004 逗子市沼間2-9-4-405
メール:okinaebis[at]mac.com URL:http://okinaebis.com
地学研究発表会2017(愛媛大会)
報告:小さなEarth Scientistのつどい〜第15回小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜
台風のためプログラム中止→デジタルポスター発表会として実施
台風18号の影響により,17日(日)に予定されていた愛媛大会のプログラムは全て中止となり,「小さなE.S.のつどい」についても,残念ながら中止となった.そのため行事委員会等と協議し,今大会に限り,代替措置としてデジタルポスター発表会という形式を執るとことにした.評価・審査の工程は次の通り.
理事による各ポスターへの評価コメント作成:各校のポスターと講演要旨を学会HP内(要ログインページ)にて閲覧できるようにし,全理事へ感想やコメントの提出を依頼した.
審査委員による審査(評点)作業:工程1の理事からのコメント等を集約したファイルを,審査委員が確認し,採点・評価.審査委員は,竹下 徹,田村嘉之,仲谷英夫,奈良正和,楡井 久,保柳康一,松田達生,三田村宗樹,向山 栄,天野一男,狩野彰宏 の11名の理事に依頼した.
地学教育委員会が審査結果を集計.結果発表.
審査の結果,優秀賞は、高得点を取得した上位4件の発表に決定した。奨励賞は,例年『フィールドワークに根ざした研究を行い、今後の成果が期待される発表』に授与しており,今回は7件の発表に決定した.
児童・生徒が学会に参加する研究者・専門家らと直接交流することは,小さな地球科学者たちの学習意欲への良い刺激と励みなり,本企画の大きなねらいのひとつでもある.残念ながら今回はかなわなかったが,すべての発表に対して,後日参加賞とあわせてデジタル審査のコメント等を送付した.今後の学習・研究の参考にしていただければ幸いである.
今回のデジタル審査のため急遽データ提出等にご対応いただいた各校の皆様,また大会会期後のご多忙のところ,審査にご協力いただいた理事の皆様にあらためて御礼申し上げます.
【優秀賞4件】
ES-17 地下水脈を求めて(奈良学園高等学校:大橋祐輝・篠原つばさ・佐藤若葉)
ES-13 北海道釧路湿原コアの微化石について(群馬県立太田女子高等学校理科研究部:大橋 葵・尾内千花・橋本優里)
ES-15 岩脈調査による応力場変遷の研究(愛知県立岡崎高等学校:星 輝)
ES-9 世界の色を形に (3)〜 砂からつくったガラスの発色に関する考察 〜(東京学芸大学附属高等学校:蒲池美紀・辻 琴里・橋本彩乃・波多柚香里)
【奨励賞7件】
ES-12 武蔵高校標本庫内にあるシカ亜科角化石「Elaphurus wadai」標本の再検討(武蔵高等学校:森北那由多)
ES-20 兵庫県南部加東市の加古川河床からヒカゲノカズラ科(Lycopodiaceae)の化石を発見〜兵庫県南部の形成過程を明らかにする指標として活用〜(兵庫県立西脇高等学校地学部(化石班)石井紗智・田中朱音・戸田亮河・中橋 徹・村上 智・神崎直哉・笹倉瑠那・津田晟俊・西山太一・福田俊介・藤原宏馬・村上凱星・大江華希・友藤奈津歩・西山壮人・松井陵紀・村上由奈)
ES-18 植生による花崗岩体での土砂災害抑制効果と発生予見(兵庫県立加古川東高等学校自然科学部地学班真砂土チーム:中野勝太・中野美玖・羽路悠斗・尾藤美樹・福嶋陸斗・前田菜緒)
ES-1 愛媛県伊予市の更新統郡中層に含まれる唐崎マイロナイト礫(愛媛大学附属高等学校:鳥津 空)
ES-19 安山岩溶岩と玄武岩溶岩の冷却過程で節理に生じる流理構造の比較(兵庫県立西脇高等学校地学部(流理構造班):石井紗智・中橋 徹・村上 智・村上由奈)
ES-14 上越市の揺れ予測(新潟県立高田高等学校理数科:上野詞音・大島 希・加藤大晃)
ES-16 マグマの移動のモデル化について(滋賀県立彦根東高等学校SSH課題研究:吉田尚史・木場健太朗・山岡厚仁・瀧井治貴・村上 快)
【発表会参加校】
愛媛大学附属高等学校
愛媛県立西条高等学校地学部
愛媛県立宇和島東高等学校地学部
愛媛県立今治北高等学校
愛媛県立今治東中等教育学校
香川県立観音寺第一高等学校
東京学芸大学附属高等学校
早稲田大学高等学院理科部地学班
武蔵高等学校中学校
群馬県立太田女子高校理科研究部
新潟県立高田高等学校
愛知県立岡崎高等学校
滋賀県立彦根東高等学校SSH課題研究
学校法人奈良学園奈良学園高等学校
兵庫県立加古川東高等学校自然科学部地学班
兵庫県立西脇高等学校地学部
熊本県立熊本西高等学校地学部
熊本県立天草高等学校科学部
(地学教育委員会 三次徳二)
WEB教材:ボクたちの足もと
WEB教材 ボクたちの”足もと“から地球のことを知ろう
WEB教材 ボクたちの“足もと”から地球のことを知ろう
〜地層と地形が教えてくれるボクたちのルーツとミライ〜
↓↓↓↓↓こちらをクリック↓↓↓↓↓
http://yume-earth.geosociety.jp
日本地質学会では、平成29年度の(独)国立青少年教育振興機構の子どもゆめ基金の助成を受けて、表記のWeb教材の開発制作を行い公開いたしました。この教材は、小学生から中学生の児童・生徒を対象とした内容です。日本各地の地層や地形、身近に観察できる場所などを対象に、広く地学に興味を持つことができる内容と構成になっています。また、この教材は、学校や家庭で子供たちを教える教員及び保護者の皆様にとりましても、有効な教材として、子どもたちと一緒に楽しく学んでいただける内容です。スマートフォンやタブレットなどで見ることができるように構成されていますので、教室や家庭の中だけではなく、野外観察などの屋外での学習に対応できるツールとしても、大いに活用していただきたいと思います。
普及活動へのご協力お願い
この教材開発には、今後3年間にわたる普及活動も含まれており、年度ごとに実績報告が義務となっています。つきましては、会員をはじめ多くの皆様にこの教材をご利用いただき、また普及をしていただければありがたく存じます。普及活動は小規模なものでもかまいませんし、施設にパンフレットやポスターを置いていただくことでも結構です。
この教材を使っての普及活動、イベントや授業、あるいはイベントの中での普及活動、博物館等での普及資料の配布など、ご協力いただける方は、普及活動申請書をダウンロードしていただき、学会事務局までご連絡をお願いいたします。また活用後は簡単な報告書のご提出をお願いしています。
なお、教材はできたばかりですので不備な点があるかもしれません。この教材を育てつつ、ぜひ普及活動にご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。
普及活動申請書
(兼 活動報告書)
PDF: 111kb
Word: 29kb
(注)皆様のご協力によりパンフレットの在庫が無くなりました。A4版パンフレット(A3両面二つ折り)は下記よりご自身でダウンロード,印刷のうえご利用頂きますようお願い致します。ポスター,ハンドブック(ルーペ付)のご用意は可能です。(2019.9.30)
←画像をクリックすると,A4版パンフレット(A3両面二つ折り)(5.1MB)がダウンロードできます。
申請書提出先:一般社団法人日本地質学会
e-mail: main[at]geosociety.jp FAX 03-5823-1156
(注)[at]は半角の@マークに変換して送信して下さい
2018年4月10日
日本地質学会 担当理事 小宮 剛
WEB教材について、気になることがありましたらご連絡ください
教材について間違いや不備な点など、何か気になることがありましたら、ぜひご連絡をお願いします。皆様からのご指摘を参考に、子どもたちにとってより良い教材となるように改善を加えてゆきますので、よろしくお願いいたします。
この教材は,
平成29年度の子どもゆめ基金((独)国立青少年教育振興機構)の助成の交付を受けて
日本地質学会が作成したものです.
非営利目的の青少年教育活動で使用する場合には学会までご連絡下さい.
地質系統・年代の日本語記述ガイドライン_改訂履歴(2021.12.2更新)
地質系統・年代の日本語記述ガイドライン_改訂履歴
>>最新版国際年代層序表はこちらから
2024年12月
国際地質科学連合(IUGS)の国際層序委員会(ICS)が,国際年代層序表の最新版(v 2024/12)を公開しました.v2024/12の改訂は次の通りです. PDF(Japanese)/PDF(Einglish)
白亜系/紀の階/期の「バランギニアン」にGSSP(2024年12月28日IUGS承認)が設定された。
GTS2020 (Gradstein et al., 2020) に従い、44件の数値年代を更新された(従来は GTS2012, Gradstein et al., 2012)。ただし、ICS委員会の決定が優先される場合はこの限りではない。
2023年9月
国際地質科学連合(IUGS)の国際層序委員会(ICS)が,国際年代層序表の最新版(v 2023/09)を公開しました.v2023/09の改訂は次の通りです. PDF(Japanese)/ PDF(Einglish)
原太古世界/代の下限が4031±3 Maに設定された(更新前 ~4000 Ma)[v/2023/09の更新内容]
2023年4月
国際地質科学連合(IUGS)の国際層序委員会(ICS)が,国際年代層序表の最新版(v 2023/4)を公開しました.v2023/4の改訂は次の通りです.PDF(Japanese)/ PDF(Einglish)
新第三系/紀の階/期の「ランギアン」にGSSP(2023年5月31日IUGS承認)が設定され,その下限が15.98 Ma(更新前 15.97 Ma)と定義された.
白亜系/紀の階/期の「バレミアン」にGSSP(2023年3月26日IUGS承認)が設定され,その下限が125.77 Ma(更新前 ~129.4 Ma)と定義された.[v/2023/04の更新内容]
2022年11月
国際地質科学連合(IUGS)の国際層序委員会(ICS)が,国際年代層序表の最新版(v 2022/10)を公開しました.v2022/10の改訂は次の通りです.PDF(Japanese)/ PDF(Einglish)
白亜系/紀の階/期の「カンパニアン」にGSSP(2020年10月5日IUGS承認)が設定された.
冥王界/代が国際標準層序年代(GSSA)として定められ,その下限が4,567.30 ± 0.16 Ma と定義された(2020年10月5日IUGS承認).層序表ではこれまでの「~ 4,600」Maにかわって「4,567」Maと標記.
ジュラ系/紀のすべて階/期の下限が次のように更新された.
------------
チトニアン:149.2 ± 0.7 Ma (更新前 152.1 ± 0.9 Ma )
キンメリッジアン:154.8 ± 0.8 Ma (更新前 1157.3 ± 1.0 Ma )
オックスフォーディアン:161.5 ± 1.0 Ma (更新前 163.5 ± 1.0 Ma )
カロビアン:165.3 ± 1.1 Ma (更新前 166.1 ± 1.2 Ma )
バトニアン:168.2 ± 1.2 Ma (更新前 168.3 ± 1.3 Ma )
バッジョシアン:170.9 ± 0.8 Ma (更新前 170.3 ± 1.4 Ma )
アーレニアン:174.7 ± 0.8 Ma (更新前 174.1 ± 1.0 Ma )
トアルシアン:184.2 ± 0.3 Ma (更新前 182.7 ± 0.7 Ma )
プリンスバッキアン:192.9 ±0.3 Ma (更新前 190.8 ± 1.0 Ma )
シネムーリアン:199.5 ±0.3 Ma (更新前 199.3 ± 0.3 Ma )
ヘッタンギアン:201.4 ± 0.2 Ma (更新前 201.3 ± 0.2 Ma )
------------
太古(累)界/代の下限にあった層序最下位をしめす境界パターンが冥王界/代の下限の位置に移動(冥王界/代の下限が定義されたことによる)
2022年2月
国際地質科学連合(IUGS)の国際層序委員会(ICS)が,国際年代層序表の最新版(v 2022/2)を公開しました.v2022/2の改訂は次の通りです.PDF(Japanese)/ PDF(Einglish)
ペルム系/紀の階/期の「アーティンスキアン」にGSSP(2020年2月3日IUGS承認)が設定された.
カンブリアン系/紀の「フォーチュニアン」の下限が538.8+/-0.2 Ma (Linnemann et al., 2019) に.
白亜系/紀の「アプチアン」の下限が121.4 Ma (GTS2020; Gradstein et al. 2020) に.
2021年12月
国際地質科学連合(IUGS)の国際層序委員会(ICS)が,国際年代層序表の最新版(v 2021/10)を公開しました.v2021/07,v2021/10の改訂は次の通りです.(PDF:Japanese/PDF:English)
ペルム系/紀の統/世の「グアダルピアン」の下限が273.01+/-0.14 Ma (Shen et al., 2020 ESR) に.
ペルム系/紀の階/期の「ウォーディアン」の下限が266.9+/-0.4 Ma (Wu et al., 2020, Paleo-3) に.
ペルム系/紀の統/世の「キャピタニアン」の下限が266.9+/-0.4 Maに (Wu et al., 2020, Paleo-3) に.
ペルム系/紀の統/世の「ローピンジアン」の下限が259.51+/-0.21 Ma (Yang et al., 2018, EPSL) に.
石炭系/紀の亜系/紀の「ペンシルバニア」の色が修正された.
新第三系/紀の中新統/世と鮮新統/世のそれぞれに、上部/後期、中部/中期、下部/前期の標記が追加された。
2021年6月
国際地質科学連合(IUGS)の国際層序委員会(ICS)が,国際年代層序表の最新版(v 2021/05)を公開しました.(PDF:Japanese/PDF:English)
白亜系/紀の階/期の「コニアシアン」にGSSP(2020年5月2日IUGS承認)が設定された.
ジュラ系/紀の階/期の「キンメリッジアン」にGSSP(2020年3月7日IUGS承認)が設定された.
層序表の更新統/世 上部/後期と完新/世の色が修正された.
2020年3月
国際地質科学連合(IUGS)の国際層序委員会(ICS)が,国際年代層序表の最新版(v 2020/01)を公開しました.(PDF:Japanese/PDF:English)
古第三系/紀の階/期の「プリアボニアン」にGSSPが定められ、その下限が37.8 Ma から 37.71 Maに.
2020年1月
国際地質科学連合(IUGS)の国際層序委員会(ICS)が,国際年代層序表の最新版(v 2020/01)を公開しました.(PDF:Japanese/PDF: English)
白亜系/紀の階/期の「オーテリビアン」にGSSPが定められました(2019年12月15日).
市原市の地層断面「千葉セクション」が下部ー中部更新統境界GSSPに承認され、第四系/紀の階/期の中部/中期が「チバニアン」Chibanianと命名されました(2020年1月15日).
2019年5月
前回からの変更点は下記の通りです,(PDF:Japanese/PDF:English)
中期更新世の下限が、78.1万年前から77.3万年前に。
追加:“Meghalayan”の日本語表記を“メガラヤン”としました。(2020.2.16)
2018年7月
2018年7月13日,国際地質科学連合(IUGS)の国際層序委員会(ICS)が,国際年代層序表の最新版(v 2018/07)を公開しました.(PDF:Japanese/PDF:English)
最新版では第四紀の「完新世」Holoceneが後期,中期,前期に細分化され,それぞれ,「メーガーラヤン」 Meghalayan,「ノースグリッピアン」Northgrippian,「グリーンランディアン」Greenlandianと命名されました.それぞれの下限には国際標準模式層断面及び地点(GSSP: Global Boundary Stratotype Section and Point)が定められました.また,カンブリア紀の統/世の「シリーズ 3」Series 3が,「ミャオリンギアン」Miaolingianに改名され,その中の階/期の「ステージ 5」Stage 5が「ウリューアン」Wuliuanに改名され,GSSPが定められました.
日本地質学会では,最新表の日本語版を更新すると同時に,「Archean」の訳語を,従来の「始生代(太古代)」から「太古代(始生代)」に変更しました.「始生代」は既に世界中で使われなくなった「Archeaozoic」の直訳です.一方,現在世界で広く用いられている「Archean」の訳語は「太古代」です.日本でも1990年代から先端の学術論文では「太古代」が使われ始めましたが,いまだに古い用語が用いられている書籍も多く,表現上の混乱を招いています.日本地質学会では,この機会に「太古代」に統一することにしました.ただし,これまでの表現との調整という意味で,しばらくは「太古代(始生代)」と表記することにします.
2016年12月
前回からの変更点は下記の通りです,(PDF:Japanese/PDF:English)
・古第三紀始新世バートニアン期の下限が41.2 Maに.
・ペルム紀の上限(=三畳紀の下限)が251.902 ±0.024 Maに.(2017.3.22 訂正)
・ペルム紀ローピンジアン世ウーチャーピンジアン期の下限が259.1 ±0.5 Ma.
・ペルム紀グアダルピアン世ローディアン期の下限が272.95 ±0.11 Maに.(2017.3.22 訂正)
2015年1月
前回(2014年2月版)からの変更点は下記の通りです,(PDF:Japanese)
1.サーラバリアン階・トートニアン階の境界年代 11.62 Ma → 11.63 Ma
2.バートニアン階・プリアボニアン階の境界年代 38.0 Ma → 37.8 Ma
3.トニアン系・クライオジェニアン系の境界年代 〜850 Ma → 〜720 Ma
2014年10月
下部更新統/世の年代に修正が加えられています
2014年1月
1. サントニアン階の基底を定義するGSSPが設定された.
2. ジュラ紀と白亜紀の境界の年代値が修正された.
3. ラディニアン期とカーニアン期,カーニアン期とノーリアン期の境界の年代値が修正された.
4. ペルム紀の年代値の多くに修正がなされた.
2010年5月
先般の第四紀の下限問題の議論の際に,年代の記述がよく整備されていないことが明らかとなりました.例えば,Calabrian Stage/Ageの場合,カラブリア階/期とカラブリアン階/期という表記が併用されています.また,過去には,地質系統・年代名に関して,どのような訳語を用いるのかとの問い合わせもありました.
そこでガイドラインとして,JIS(ベクトル数値地質図—品質要求事項および主題属性コード;JIS A 0205: 2008)における地質系統・年代の表記を,International Commission on Stratigraphyの発行したInternational Stratigraphic Chartに当てはめた表を準備しました,今後,一般社団法人日本地質学会刊行の公式出版物(地質学雑誌等)においては,原則として,この年代表記に従って下さいますようお願いいたします.
(注)
*1 タランティアン階/期という名称が検討されている.
*2 イオニアン階/期という名称が検討されている.
・更新統/世の区分については,従来から用いられている上・中・下部更新統および後・中・前期更新世の三分を継承する.下部更新統および前期更新世は,それぞれ,ジェラシアン階/期とカラブリアン階/期という2つの階/期から構成されるものとする.
・これまで新第三系/紀と古第三系/紀を併せた地質時代として用いられてきた,第三系/紀は非公式な用語として使用することができるが,学術論文,教科書,地質時代・年代層序表には使用しない.
・オルドビス系/紀およびカンブリア系/紀の階/期の中には,訳語がないものがある.
・カンブリア系/紀の階/期境界の年代値は暫定値である(アルタリスクを付してある).
・GSSPは国際境界模式層断面とポイント(Global Boundary Stratotype Section and Point)の,GSSAは国際標準層序年代(Global Standard Stratigraphic Age)の略語である.
チャレンジ地球2019
2019.9.17掲載
小学生のための地学オリンピック
チャレンジ地球–クイズ30とジオパーク探検—
参加者募集
主催: 一般社団法人日本地質学会
特別後援:NPO法人地学オリンピック日本委員会
事業実施担当:一般社団法人日本地質学会 地学オリンピック支援委員会
後援:日本地学教育学会
関東版
関西版
後援:日本地学教育学会
後援:山陰海岸ジオパーク推進協議会,豊岡市,兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科 日本地学教育学会
1.「ジオパーク探検」(筑波山地域ジオパークの霞ヶ浦湖岸)
実施日:令和元年11月23日(土)
集合:つくばエクスプレス「つくば」駅前駐車場9:00集合(16:00解散)
参加費:保護者同伴2名で3,000円を予定(バス代,保険代を含む)(注)保護者同伴,昼食持参
案内者:久田健一郎先生(筑波大学)
募集人数:先着30名(最大15組)
*最少催行人数:10組20名
1.「ジオパーク探検」(山陰海岸ジオパーク)
実施日:令和元年11月10日(日)もしくは
12月1日(日)(いずれかを選択して下さい)
集合:JR豊岡駅 9:45,兵庫県立コウノトリの郷公園 10:00
目的地:豊岡市コウノトリ文化館,玄武洞,竹野海岸(予定)
解散:JR豊岡駅 15:30,コウノトリの郷公園 15:45
参加費:1名500円前後を予定(保険代・資料代など)(注)兵庫県立大学のバスを使用.保護者同伴.昼食代各自負担
案内者:川村教一先生(兵庫県立大学)
募集人数:両日とも先着24名(6組程度)
2.「クイズ30」(小学校理科「地球分野」の学力を問うクイズ30問)
実施日:令和元年12月15日(日)13:00〜15:00(クイズの時間は60分)
会場:筑波大学東京キャンパス文京校舎
募集人数:先着30名
2.「クイズ30」(小学校理科「地球分野」の学力を問うクイズ30問)
実施日:令和元年12月15日(日)10:00〜12:00
会場:大阪教育大学天王寺キャンパス
募集人数:先着30名
3.対象学年 小学5,6年生
4.表彰 金賞,銀賞,銅賞(全員に表彰状を郵送にて授与,表彰式は行いません.)ただし,表彰対象者は「クイズ30」と「ジオパーク探検」両方の参加者に限ります.
5.申込先:[申込フォームはこちら]
お問い合わせ:日本地質学会事務局 TEL 03-5823-1150
申込締切:令和元年10月31日(木)
6.予習用教材 WEB教材「 ボクたちの“足もと”から地球のことを知ろう」で予習の上参加のこと.
(http://www.geosociety.jp/name/content0161.html)
地学研究発表会2018(札幌大会)
小さなEarth Scientistのつどい〜第16回小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜
札幌大会は9月5日(水)〜7日(金)の平日開催が予定されており,児童・生徒の参加が難しいことが予想されていた.そのため,今回の「小さなESのつどい」は,学会会場における発表に加え,愛媛大会で代替措置として行ったデジタルポスター発表会という形式を執ることを当初から決めていた.
北海道胆振東部地震のため,札幌大会3日目に関連行事として予定されていた「小さなESのつどい」を含め,大会プログラムのすべてが中止となった.悪天候の中,今回の発表会のために札幌入りしていた学校もあったが,行事委員会や学会本部と協議の上,早い段階で「小さなESのつどい」の学会会場での発表会は中止を決定し,デジタルポスター発表会のみでの開催とした.
デジタルポスター発表会の形式は,2017年11月号のニュース誌記事(10-11ページ)をご覧いただきたいが,概要を記すと,2つの段階に大きく分けられる.第1段階では,学会HP内で各校のポスターを閲覧し,理事の方々に感想やコメントを提出いただいた.第2段階では,審査委員による審査であり,第1段階で寄せられた感想やコメントも参考に,審査を行った.最終的には,本行事を担当する地学教育委員会が審査結果を集計し,結果を発表した.なお,審査項目は,「研究の動機が明確であり,問題点をはっきりととらえているか」,「観察・実験から導かれたデータを基に,結論が導かれているか」,「わかりやすいポスターとしてまとめられているか」の3つであり,それぞれ10点満点で評価する.
審査の結果,優秀賞は高得点を取得した上位3件の発表に決定した.奨励賞は例年「フィールドワークに根ざした研究を行い,今後の成果が期待される発表」に授与しており,今回は5件の発表に決定した.
やむを得ない事情で,2年連続して学会会場での発表会は中止となった.児童・生徒が,学会に参加する研究者・専門家らと直接交流することは,小さな地球科学者たちの学習意欲へのよい刺激と励みとなり,本企画の大きなねらいのひとつでもある.特に,大学院生レベルの研究者の存在は,高校生が近い将来に目指す自分たちの姿であり,交流する機会がなかったことは非常に残念である.すべての発表に対して,後日参加賞とあわせてデジタルポスター発表会に寄せられた感想やコメントを送付したが,次回以降の発表会では直接交流が出来ることを期待している.
最後となりましたが,今回の行事に参加いただいた各校の皆様,またご多忙のところ審査にご協力いただいた理事の皆様に,あらためて御礼申し上げます.
(地学教育委員会 三次徳二)
(2019.1.30掲載)
【優秀賞 3件】
ES-1:市立札幌藻岩高等学校フィールドサイエンス部「北海道夕張地域の4000万年前の古植生と陸上古気候」
ES-10:東京学芸大学附属高等学校「三浦半島・三崎層に見られる皿状構造の粒子配列についての考察」
ES-13:長野県長野高等学校定時制科学探究講座「発見!長野高校直下の撓曲」
【奨励賞 5件】
ES-3:北海道旭川西高等学校理数科課題研究地学班「化石のタイムカプセル「ノジュール」の形状解析」
ES-4:遺愛女子中学・高校 地学部「大森浜の海岸浸食と砂の堆積2006-2018 イカ看板は再び出現したのか?」
ES-11:東京学芸大学附属高等学校「相模湾北岸における現生有孔虫の分布の特徴」
ES-14:兵庫県立加古川東高等学校自然科学部地学班「防災的観点で見る放置ため池利用法の提案」
ES-16:兵庫県立西脇高等学校地学部(氷班)「冷却過程における炭酸水と純水の気泡の温度(第3報)―マグマの発泡の基礎研究として―」
参加校(15 校,20 件)
市立札幌藻岩高等学校フィールドサイエンス部
札幌日本大学高等学校
遺愛女子中学校・高等学校(中学校地学部2 件、高等学校地学部1件)
北海道旭川西高等学校理数科課題研究地学班
福島県立福島高等学校
群馬県立太田女子高校理科研究部地学班
早稲田大学高等学院理科部地学班
東京学芸大学附属高等学校(2 件)
東京都立南多摩中等教育学校
長野県長野高等学校定時制科学探究講座
兵庫県立加古川東高等学校自然科学部地学班
兵庫県立西脇高等学校地学部(2 件)
愛媛県立宇和島東高等学校地学部(2 件)
鹿児島玉龍高校サイエンス部天文班
熊本県立天草高等学校科学部
2019年地質の日
2019年の「地質の日」
ここでは,2019年の「地質の日」に関連した日本地質学会主催,共催,後援等の催しをご紹介します。
>>イベントカレンダーもご覧下さい(地質学会以外のイベント情報も掲載しています)。
/北海道/東 北/中 部/関 東/近 畿/四 国/西日本/その他
日本地質学会 3.15更新
第10回惑星地球フォトコンテスト展示会
日程:5月14日(火) 〜 5月19日(日)
場所:東京パークスギャラリー(上野グリンサロン内)(台東区上野公園)
入場無料,どなたでもお気軽にお立ち寄り下さい。
▶入選作品はこちら http://www.photo.geosociety.jp
第10回惑星地球フォトコンテスト表彰式
日程:5月25日(土)11:00〜12:30(予定)
会場:北とぴあ 第2研修室会議室(東京都北区王子)
入選作品の展示も行います!
▶入選作品はこちら http://www.photo.geosociety.jp
街中ジオ散歩 in Hamura
「東京の水インフラと地形・地質〜羽村取水堰とその周辺〜」徒歩見学会
身近な地質とその地質に由来する地形について,それらを利用してきた先人から現在の私たちまでの営みを,専門研究者の案内で楽しく学ぼうという企画です.今回は,玉川上水の取水口である羽村取水堰を見学します。玉川上水及び羽村取水堰は,江戸の人口が増えたため幕府が多摩川の水を江戸に引くために建設されたもので、特に羽村取水堰には,投げ渡し堰,固定堰といったその工法や,堰が作られた位置まで,江戸時代に造られたものが現在まで引き継がれています。また,取水堰周辺には、多摩川で形成された段丘面やその構成層を観察することができ,多摩川及び周辺の地形がどのようにできたのかについても学ぶことができます。更に,郷土博物館では,取水堰の構造を流水によるモデル実験で確認することができ,取水堰が江戸時代から現在まで機能を維持してきた所以を学ぶこともできます。初夏の清々しい空気の中を,楽しく“ジオ散歩”したいと思います.
主催:一般社団法人日本地質学会,一般社団法人日本応用地質学会
後援:羽村市教育委員会,一般社団法人東京都地質調査業協会
日時:2019年5月12日(日)10:00〜15:00 小雨決行(予定)
見学場所:東京都羽村市羽村取水堰周辺
案内者:山崎晴雄氏(首都大学東京名誉教授),
会費:高校生以上・一般:1,500円,小・中学生:500円(保険代を含む)
(注)参加費は,当日現金をご持参ください.昼食は各自ご用意下さい.
集合場所・時間:羽村駅東口まいまいず井戸(西友隣) 10:00集合
見学コース(予定):10:00まいまいず井戸→稲荷神社裏側の露頭観察→羽村導水ポンプ場→取水堰周辺→昼食(取水堰周辺)→牛枠の観察→郷土博物館(モデル実験)→解散15:00ごろ
募集人数:30名程度
対象:小学生以上(主催団体の会員の申込も可).ただし,小・中学生の方は保護者の同伴をお願いします.また,本行事は一般向け普及行事です.会員も申込可能ですが,定員を超えた場合は,非会員の一般市民の参加を優先します.また,夫婦,友人など,グループでの参加希望の場合は,それぞれの備考欄に代表者名を記入してください.グループでの応募は,本人を含め最大4名までとします.
申込受付期間:2019年3月30(土)〜4月10日(水)
(申込者多数の場合は抽選を行います.結果は4月中に郵送で全員にお知らせします)
申込方法:学会HPの申込み専用フォームまたは,FAXにてお申込み下さい.
【申込み専用フォーム】こちらから
【FAXの場合】記入事項1〜6をすべて記入願います.メール等がない場合は“なし”とご記入下さい. 1.氏名,2.自宅住所(郵便物を受け取れる住所),3.携帯等電話番号,4.メールアドレス,5.生年月日,6.性別 (注)小・中学生の申込の際は, 1, 5, 6について保護者の情報も明記して下さい.また,学生の方は学年のご記入をお願いします。
申込・問い合わせ先:一般社団法人日本地質学会(担当 細矢)
電話:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156
メール:main[at]geosociety.jp
近畿支部 3.11掲載
第36回地球科学講演会 OSL年代−砂粒に刻まれた時の記憶」
主催:日本堆積学会・地学団体研究会大阪支部・日本地質学会近畿支部・大阪市立自然史博物館
日時:2019年4月20日(土) 15:00〜16:30
会場:大阪市立自然史博物館 講堂
講師:田村 亨 氏(産業技術総合研究所)
対象:どなたでも参加できます
申込み:不要、直接会場へお越しください(先着150名)
https://www3.mus-nh.city.osaka.jp/scripts/Event.exe?C=0&G=%93%C1%95%CA%83C%83x%83%93%83g
北海道支部 19.4.11掲載
2019年度(第12回)地質の日記念展示「失われた川を尋ねて『水の都』札幌」
都市にはそれぞれの川があります。街は三角州や扇状地のように身近に豊富な水があるところに誕生するからです。札幌は豊平川・琴似川などの扇状地に発達し、川は開拓使時代以前から人々の生活に欠かせないものでしたが、都市化とともにこれらの川は失われてしまいました。本展示では、扇状地の川と泉・北大周辺の「失われた川」を解説し、札幌のかつての自然と風景、そこに暮らした人々について考えます。
https://www.museum.hokudai.ac.jp/contents/calendar/event/14451/
期間:2019年4月27日(土)〜6月16日(日)
場所:北海道大学総合博物館1階 企画展示室(札幌市北区北10条西8丁目)
時間:10:00〜17:00(6月の金曜日は21:00まで)月曜日休館(祝日の場合は翌日休館)入場無料
主催:「地質の日」記念展実行委員会・北海道大学総合博物館
共催:日本地質学会北海道支部・産総研地質調査総合センター・道総研地質研究所・北海道博物館・札幌市博物館活動センター・北海道地質調査業協会
後援:北海道教育委員会・札幌市教育委員会
協力:北海道大学埋蔵文化財調査センター・山の手博物館・サイエンス・コンソーシアム札幌(札幌科学談話会・札幌市中央図書館・札幌市博物館活動研究センター)
<関連イベント>
〇市民セミナー
会場:北海道大学総合博物館1階 「知の交流」ホール
備考:申込不要・入場無料・道民カレッジ連携講座
*第一回「水の都」札幌−コトニ川を尋ねて 5月11日(土)13:30〜15:00 土曜市民セミナー
宮坂省吾(北海道総合地質学研究センター)
*第二回「水の都」その誕生と消滅 〜身近に残る水の痕跡〜 6月9日(日)13:30〜15:00
古沢 仁(札幌市博物館活動センター)
〇市民地質巡検 街中ジオ散歩 in Sapporo 「コトニ川を歩く」
コース:北大正門から西へ→桑園駅東→西11丁目(石山通)→大通西8丁目「鯨の森」
日時:5月25日(土)10:00〜16:00 少雨決行
集合:10:00 北大正門前(札幌市北区北8条西5丁目)
解散:16:00 中央区大通西8丁目
定員:高校生以上20名(先着順)
参加費:500円(資料代・保険代など)
案内人:宮坂省吾(北海道総合地質学研究センター)・内山幸二(山の手博物館)
備考:昼食や飲み物、雨具をご持参ください。ハイキングに適した服装・履物でお越しください。
申込方法:往復はがきに(1)氏名(2)住所(3)年齢(4)電話番号を記入の上、北海道大学総合博物館「巡検係」宛にご郵送ください。5月17日(金)必着
お問い合わせ:北海道大学総合博物館
〒060-0810 札幌市北区北10条西8丁目
TEL:011-706-2658 https://www.museum.hokudai.ac.jp/
2019年度地質の日記念展示「失われた川を尋ねて 『水の都』札幌」
https://www.museum.hokudai.ac.jp/contents/calendar/event/14451/
その他 3.11掲載
地質の日記念講座「三浦半島活断層群主部,北武断層を歩く!」
主催:三浦半島活断層研究会
後援:日本地質学会・横須賀市
日程:2019年5月4日(土)10:00〜15:00小雨決行
集合:千駄ヶ崎バス停10:00
コース:(1)千駄ヶ崎の逗子層(2)北武断層ガウジ(3)葉山層群の年代(4)トレンチ調査跡(5)ボーリング調査跡(6)野比東ノ入公園(断層と開発)
講師:浅見茂雄(三浦半島活断層調査会研究員)
注意事項:履き慣れた靴でご参加を.弁当,飲み物,雨具は各自持参
申込:往復葉書またはE-mailにて住所・氏名・電話番号をご記入の上,4月26日(金)までに下記連絡先までお申込下さい.
参加費:500円(資料代+保険料)
申込先:三浦半島活断層調査会 事務局(赤須邦夫方)
〒249-0008 逗子市小坪5-16-11
電話 0467-24-0935 e-mail: akasu[at]jcom.zaq.ne.jp
その他 4.19掲載
観察会 城ヶ島 火山と地震痕跡を見る
主催:ジオ神奈川
後援:日本地質学会ほか
日時:2019年5月18日(土)10:00〜15:00
場所:神奈川県三浦市城ヶ島
スコリア・火山豆石・So凝灰岩層,1923年大正関東地震の地殻変動
参加費:600円(資料・保険代を含む)
定員:20名(先着順受付)
申込締切:5月13日(月)
申込方法:住所,氏名,電話,年齢を記入して下記までメールでお申し込み下さい.
申込・問い合わせ先:ジオ神奈川 代表 蟹江康光
〒249-0004 逗子市沼間2-9-4-405
電話:046-873-6283
メール:okinaebis[at]mac.com URL:http://okinaebis.com
地震火山地質こどもサマースクール
地震火山地質こどもサマースクール
↓公式WEB サイトはこちら↓
https://kodomoss.jp/
お知らせ
2027年度地震火山地質こどもサマースクール開催地候補募集中(締切延長)
第21回地震火山地質こどもサマースクールin浅間山北麗ジオパーク「浅間のいたずら、鬼のヒミツ」実施報告 (22.12.9)
地震火山地質こどもサマースクールは、、、
研究の最前線にいる専門家が、こどもの視点にまで下りて、地震火山地質現象のしくみ・本質を直接語る。
災害だけでなく、災害と不可分の関係にある自然の大きな恵みを伝える。
の2つの目的のために、日本地震学会と日本火山学会が中心となって、1999年からほぼ毎年夏休みに全国各地で開催してきた恒例行事です。
2008年から、災害と自然の恵みを実感できる「ジオパーク」の運動が国内でスタートしたことを受け、2011年から日本地質学会も加わって、実施しています。
2020年地質の日
2020年の「地質の日」
ここでは,2019年の「地質の日」に関連した日本地質学会主催,共催,後援等の催しをご紹介します。
>>イベントカレンダーもご覧下さい(地質学会以外のイベント情報も掲載しています)。
/北海道/東 北/中 部/関 東/近 畿/四 国/西日本/その他
日本地質学会 5.11更新
第11回惑星地球フォトコンテスト展示会[中止]
日程:5月19日(火) 〜 5月31日(日)
場所:東京パークスギャラリー(上野グリンサロン内)(台東区上野公園)
入場無料,どなたでもお気軽にお立ち寄り下さい。
http://www.photo.geosociety.jp
第11回惑星地球フォトコンテスト表彰式 [中止]
日程:5月23日(土)11:00〜12:30(予定)
会場:北とぴあ 第2研修室会議室(東京都北区王子)
入選作品の展示も行います!
街中ジオ散歩in Yokohama
「身近な地形・地質から探る横浜の発展」徒歩見学会[延期]
新型コロナウィルス感染拡大防止のため
本イベントは開催を延期することにいたしました。
開催時期は今後の状況を見て検討いたします。 (2020.3.30)
身近な地質とその地質に由来する地形について,それらを利用してきた先人から現在の私たちまでの営みを,専門研究者の案内で楽しく学ぼうという企画です。今回は,横浜駅市街地を囲む形で京急神奈川駅から旧東海道を経由し,JR桜木町駅まで反時計回りに歩き,台地と平地(埋立地,干拓地)及び台地平地境界部を散策します。 横浜駅周辺は元々台地が海岸部まで迫っており,横浜駅周辺,みなとみらい周辺の平地の多くは干拓や埋め立てにより造られた歴史があります。前半では台地上にある明治初期の領事館跡をめぐることで,当時の地形と横浜港との関係について学びます。また,台地から平地(横浜駅市街地方面)を眺めることで,地形面の分類・分布状況を学習し,日本で最初に出来た鉄道が当時どのような場所に造られたかについても学びます。横浜市防災センターでは,防災についての学習をするとともに,歴史的な大地震の揺れを体験します。 後半は新田間橋における排水路水面と市街地の高さの対比から横浜市中心部が埋め立てや干拓によって造られたことを学び,桜木町付近の掃部山(かもんやま)周辺では,房州石(千葉県の「県の石」)の石垣を観察するとともに,台地端部からの湧水がかつて蒸気機関車の水源になったことを学びます。初夏の清々しい空気の中を,楽しく“ジオ散歩”したいと思います。
主催:一般社団法人日本地質学会,一般社団法人日本応用地質学会
日時:2020年5月16日(土)9:00〜16:00小雨決行(予定)
見学場所:神奈川県横浜市(旧神奈川宿〜旧東海道〜桜木町周辺)
案内者:笠間友博氏(箱根町立箱根ジオミュージアム)
会費:高校生以上・一般:1,500円,小・中学生:500円(保険代を含む)(注)参加費は,当日現金でお支払い下さい。昼食は各自ご持参下さい。
集合場所・時間:幸ヶ谷公園(京急神奈川駅徒歩3分) 9:00集合
見学コース(予定):9:00幸ヶ谷公園→本覚寺(旧アメリカ領事館)→望欣台(ぼうきんだい)(海上の鉄道盛土)→上台町公園(関東ローム露頭観察)→横浜市防災センター(地震体験・昼食)→沢渡公園露頭(露頭観察)→新田間橋(埋立地・干拓地)→掃部山(かもんやま)一帯(房州石の石垣)→姥岩(桜木町)解散16時ごろ
募集人数:30名程度
対象:小学生以上。ただし,小・中学生の方は保護者の同伴をお願いします。また,本行事は一般向け普及行事です。会員も申込可能ですが,定員を超えた場合は,非会員の一般市民の参加を優先します。また,家族,友人など,グループでの参加希望の場合は,それぞれの備考欄に代表者名を記入してください。グループでの応募は,本人を含め最大4名までとします。
申込受付期間:2020年4月6日(月)〜4月19日(日)(申込者多数の場合は抽選を行います。結果は4月中に郵送で全員にお知らせします)
申込方法:学会HPの申込み専用フォームまたは,FAXにてお申込み下さい。
【お申込みは専用フォームから】準備中
【FAXでのお申し込み】準備中
申込・問い合わせ先:一般社団法人日本地質学会(担当 細矢)
電話:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156
メール:main*geosociety.jp[*を@にして下さい]
近畿支部 2.18掲載
第37回地球科学講演会「地質の日」協賛行事
「北アルプス生成の謎 −マグマと短縮テクトニクスが作り出した北アルプス−」[中止]
新型コロナウィルス感染拡大防止のため
本イベントは中止することにいたしました。(2020.3.31)
地球上に露出する第四紀花崗岩(かこうがん)5岩体のうち、北アルプスには滝谷花崗閃緑岩と黒部川花崗岩の2岩体があります。1990年当時、地球上に第四紀花崗岩が露出しているとは誰も考えていませんでした。厚さ3kmほどの岩盤が侵食され露出するまでには500万年程度はかかると信じられていたためです。第四紀花崗岩がなぜ北アルプスにあるのでしょう?同時代に大噴火を起こしていた巨大カルデラ火山の復元とともに、北アルプスの生い立ちの謎に迫ります。
日時:5月10日(日)15:00〜16:30 開場14:30
場所:大阪市立自然史博物館 本館 講堂
講師:原山 智 氏(信州大学名誉教授・同理学部特任教授)
定員:250名(先着順。事前申し込みは不要です。)
参加費:無料 ただし博物館入館料が必要です。
主催:地学団体研究会大阪支部・日本地質学会近畿支部・大阪市立自然史博物館
問い合わせ先:大阪市立博物館
TEL 06-6697-6221
FAX 06-6697-6225
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
北海道支部
その他
地学研究発表会(2014鹿児島)
小さなEarth Scientistのつどい 〜第12回小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜
鹿児島大会2日目に,小さなEarth Scientistのつどい〜第12回小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜がおこなわれた.年会における発表会は11年前の静岡大会からおこなわれており,今回の開催で,12回目を迎えることとなった.この発表会の目的は,地学普及の一環として学校における地学研究を紹介することで地学教育の奨励と振興を図ることと,地学を研究する児童・生徒と研究者の交流が進み,地球科学普及の一助となることである.
今回の発表会もポスターセッション会場の一画を本企画の会場として利用させて頂いたので,多くの会員の方にご参加頂けたものと思われる.広い体育館の一部を会場として利用したが,若い地球科学者の熱気で,その一角が非常に蒸し暑かったことを記憶している.今回は,はじめての九州における開催である.どの程度,地元からの参加があるか不安であったが,鹿児島県内から4校の発表があった.全体としては 11校(14件)の発表となり,残念ながら前回の仙台大会,前々回の大阪大会を下回った.なお,学校行事が重なったために,当日会場に来ることができなかった学校や,遠方であるためポスターのみを送付していただいた学校もある.
この発表会では理事を中心とした審査員によるポスター審査を行っており,審査基準は,「研究の動機が明確であり,問題点をはっきりととらえているか」,「観察・実験から導かれたデータを基に,結論が導かれているか」,「わかりやすいポスターとしてまとめられているか」の3つの観点である.一方で,発表(説明内容)については,加点していない.「全体的に優れている」発表に対して優秀賞を,「フィールドに根ざして研究を行っており,今後の成果が期待される」発表に対して奨励賞を授与している.今回は名簿前半の理事の方々にお願いし,約半数の方が実際に審査をしていただいた.
全ての発表を審査した結果,下に示す3件の発表に対して優秀賞が授与されている.また,フィールドに根ざして研究している学校への奨励賞については,下の3件に授与された.
最後となったが,審査にあたっていただいた理事各位,鹿児島県内の学校の先生方,行事委員会委員,会場校である鹿児島大学と西日本支部の関係各位,さらに今回の発表会参加者(生徒と引率の先生方)に謝意を表したい.
(地学教育委員会委員長 三次徳二)
【優秀賞】(3件)
兵庫県立西脇高等学校地学部(マグマ班)「本校が立地する兵庫県中部地域の基盤岩の形成史」
京学芸大学附属高等学校「世界の色を形に〜砂からつくったガラスの発色に関する考察〜」
兵庫県立西脇高等学校地学部(都市環境班)「兵庫県南部地震の余震(2013年4月)と加古川市南部の地盤の動き―マンホール周囲の道路面の亀裂に着目して―」
【奨励賞】(3件)
鹿児島玉龍高等学校サイエンス部天文班「月のクレーターの研究」
兵庫県立加古川東高等学校地学部(凝灰岩班)「地元凝灰岩 長石・高室石・竜山石の性質の相違による堆積環境の推定」
北海道札幌あすかぜ高等学校自然科学部地学班「西南北海道,雷電海岸に分布する岩脈について」
【発表会参加校】(11校・14件)
鹿児島玉龍高等学校サイエンス部天文班
鹿児島県立鶴丸高等学校地学部
鹿児島県立錦江湾高等学校理数科3年地学班
鹿児島県立国分高等学校理数科課題研究地学班
北海道札幌あすかぜ高等学校自然科学部地学班
群馬県立太田女子高校地学部
東京学芸大学附属高等学校
早稲田大学高等学院理科部地学班
山梨県立日川高等学校(2件)
兵庫県立加古川東高等学校地学部(2件)
兵庫県立西脇高等学校地学部(2件)
地学研究発表会(2015長野大会)
小さなEarth Scientistのつどい〜第13回小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜
長野大会3日目に,小さなEarth Scientistのつどい〜第13回小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜がおこなわれた.年会における発表会は12年前の静岡大会からおこなわれており,今回の開催で,13回目を迎えることとなった.この発表会の目的は,地学普及の一環として学校における地学研究を紹介することで地学教育の奨励と振興を図ることと,地学を研究する児童・生徒と研究者の交流が進み,地球科学普及の一助となることである.
今回の発表会もポスターセッション会場の一画を本企画の会場として利用させて頂いたので,多くの会員の方にご参加頂けたものと思われる.体育館の一部を会場として利用したが,高校生の声が体育館に響き渡っていたことを記憶している.今回も地元からの参加があるか不安であったが,長野県内から2校の発表があった.全体としては 13校1団体から18件の発表があり,前回大会を上回った.なお,学校行事が重なったために,当日会場に来ることができなかった学校や,遠方であるためポスターのみを送付していただいた学校もある.
この発表会では理事を中心とした審査員によるポスター審査を行っており,審査基準は,「研究の動機が明確であり,問題点をはっきりととらえているか」,「観察・実験から導かれたデータを基に,結論が導かれているか」,「わかりやすいポスターとしてまとめられているか」の3つの観点である.一方で,発表(説明内容)については,加点していない.「全体的に優れている」発表に対して優秀賞を,「フィールドに根ざして研究を行っており,今後の成果が期待される」発表に対して奨励賞を授与している.今回は名簿後半の理事の方々にお願いし,当日都合の付く方に審査をしていただいた.
全ての発表を審査した結果,下に示す3件の発表に対して優秀賞が授与されている.また,フィールドに根ざして研究している学校への奨励賞については,下の4件に授与された.
最後となったが,審査にあたっていただいた理事各位,長野県内の学校の先生方,行事委員会委員,会場校である信州大学と中部支部の関係各位,さらに今回の発表会参加者(生徒と引率の先生方)に謝意を表したい.
【優秀賞】
兵庫県立西脇高等学校地学部(マグマ班)「兵庫県を南北に縦断する地質調査によって明らかにした兵庫県中部〜南部の形成過程(第2報)」
兵庫県立加古川東高等学校地学部「花崗岩の風化が及ぼ 花崗岩の風化が及ぼ す土砂災害 す土砂災害 への影響」
鹿児島玉龍高等学校サイエンス部天文班「月のクレーターを作る」
【奨励賞】
岐阜県立加茂高等学校(自然科学部)「岐阜県美濃加茂市における湧水の特徴」
長野県松本深志高等学校地学会「枕状溶岩を作ろう〜身近なもので再現実験〜」
山梨県立日川高等学校(物理・地学部)「甲府盆地東部における断層研究」
早稲田大学高等学院理科部地学班「自然環境から見た原子力発電所周辺のハザードマップの作成」(その3)
【発表会参加校】(13 校・1団体参加,18 件)
長野県松本深志高等学校地学会
長野県長野西高等学校
岐阜県立加茂高等学校(2件)
山梨県立日川高等学校物理・地学部(2件)
新潟大学理学部未来の科学者養成講座(2件)
群馬県立太田女子高校地学部
千葉県立柏高等学校課題研究Ⅱ受講者
東京学芸大学附属高等学校
早稲田大学高等学院理科部地学班
学校法人奈良学園奈良学園高等学校SS 研究チーム
滋賀県立彦根東高等学校SS 部地学班
兵庫県立西脇高等学校地学部(2件)
兵庫県立加古川東高等学校地学部
鹿児島玉龍高等学校サイエンス部天文班
第18回ジュニアセッション(2020名古屋大会代替企画)
第18回日本地質学会ジュニアセッション 〜小・中・高校生徒地学研究発表会〜
日本地質学会地学教育委員会は,地学普及行事の一環として,地学教育の普及と振興を図ることを目的として,学校における地学研究を紹介する地学研究発表会をおこなっています.昨年までは「小さなEarth Scientistのつどい」と題しておりましたが,2020年より「日本地質学会ジュニアセッション」に名称が変わりました.2020年の地質学会学術大会は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により延期となりましたが,日本地質学会ジュニアセッションを開催し,小・中・高等学校の地学クラブの活動,授業の中で児童・生徒が行った研究,及び児童・生徒の自発的な個人研究の発表を下記の要領にて募集いたしました.ただし,今回は開催地やコアタイムは無く,送付されたポスターの審査のみ実施いたしました.参加校,審査結果は以下の通りです.
審査結果(2020.11.25掲載)
優秀賞(3件)
JS-17 東京工業大学附属科学技術高等学校(佐藤諒弥ほか)
JS-1 兵庫県立姫路東高等学校科学部砂粒班(赤瀬彩香ほか)
JS-12 岐阜県立加茂高等学校自然科学部(山内怜奈ほか)
奨励賞(4件)
JS-2 札幌日本大学高等学校(近 智文ほか)
JS-18 熊本県立宇土高等学校科学部(岩粼議弘ほか)
JS-7 兵庫県立加古川東高等学校理数科課題研究地学班(上笹なつきほか)
JS-5 北海道旭川西高等学校理数科課題研究地学班(北川源樹ほか)
本年の参加校・発表タイトル(16校・18件)
JS-1 兵庫県立姫路東高等学校:石英と長石の砂粒の凹凸系数や体積比は源岩からの距離を推定する指標となる
JS-2 札幌日本大学高等学校:豊平川の古流向を調べる
JS-3 宮城県仙台西高等学校地学部:新第三紀後期に宮城県内にできたカルデラ湖の位置を珪藻化石群集で推定する
JS-4 名古屋中学校自然科学部:PCとネットデータで柱状図−スケール入り現地画像とGoogleマップと地理院地図を利用してPCでつくる柱状図−
JS-5 北海道旭川西高等学校理数科課題研究地学班:実験!! 蛇紋岩作用
JS-6 宮城県仙台第二高等学校地学部:宮城県内の豆石の火口からの距離による比較
JS-7 兵庫県立加古川東高等学校理数科課題研究地学班:縦断形に着目した天井川の形成過程の解明−天井川形成モデル作成にむけて−
JS-8 福井県立若狭高等学校:パイピング現象の防止法
JS-9 福井県立若狭高等学校:放射線を用いた効率的な地質調査とその評価
JS-10 福井県立若狭高等学校:観天望気〜天気の言い伝えは本当か〜
JS-11 群馬県立太田女子高校理科研究部地学班:茨城県阿見町島津の下総層群から産出したクモヒトデ骨片化石
JS-12 岐阜県立加茂高等学校自然科学部:方解石による太陽の方向の特定
JS-13 大阪府立豊中高等学校課題研究地学班:鳴き砂の人工生成の検討
JS-14 中央大学附属中学校・高等学校地学研究部:巨大球形スクリーンによる「ダジック・アース」の有効性
JS-15 兵庫県立西脇高等学校地学部:東条湖の神戸層群の比較 (第2報)〜岩石の特徴から見る凝灰岩層の違い〜
JS-16 宮城学院高等学校自然科学班:丸田沢地層マップ
JS-17 東京工業大学附属科学技術高等学校:水中蛇方ロボットに脚をつけたら蛇足か 古代の化石から生物を再現して実証する
JS-18 熊本県立宇土高等学校科学部:知らない現象(不知火現象)を科学する〜浮島現象の観測などから、不知火現象解明への挑戦〜
問い合わせ:日本地質学会地学教育委員会(担当 三次)
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F
TEL:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156
地学研究発表会2019(山口大会)
小さなEarth Scientistのつどい〜第17回小,中,高校生徒 「地学研究」発表会〜
地学教育委員会 三次徳二
日程:2020年9月23日
会場:山口大学吉田キャンパス
山口大会の1日目に, 小さなEarth Scientistのつどい〜第17回小,中,高校生徒 「地学研究」発表会〜が行われた.年会における発表会は2003年の静岡大会からおこなわ れており,今回の開催で17回目を迎えること となった.この発表会の目的は,地学普及の 一環として学校における地学研究を紹介する ことで地学教育の奨励と振興を図ることと,地学を研究する児童・生徒と研究者の交流が 進み,地球科学普及の一助となることである. この行事は,児童・生徒が参加しやすい日 程に設定されており,本大会では休日である 1日目となった.ただし,大会の各種行事の 都合で,審査や表彰式まで1日で終えること ができない.そのため,今回の「小さなES のつどい」は学会会場における発表を行うも のの,審査については愛媛大会から用いてい るデジタルポスター審査という形式をとっ た.東京・桜上水大会以降,自然災害によるや むを得ない事情で,愛媛大会,北海道大会と 2年連続して学会会場での発表会は中止とな った.今回は当日早朝までの台風の影響で参 加できなかった生徒がいるものの,多くの会 員の方にご覧頂けたものと思われる.児童・ 生徒が,学会に参加する研究者・専門家らと 直接交流することは,小さな地球科学者たち の学習意欲へのよい刺激と励みとなり,本企 画の大きなねらいのひとつでもある.特に, 大学院生レベルの研究者の存在は,高校生が 近い将来に目指す自分たちの姿でもあるの で,大学院生が生徒に積極的に声をかけてい ただいたことは担当者としてとてもありがた かった.また,デジタルポスター審査について概要 を記すと,2つの段階に大きく分けられる. 第1段階では,学会HP内で各校のポスター を閲覧し,理事の方々に感想やコメントを提 出いただいた.第2段階では,審査委員によ る審査であり,第1段階で寄せられた感想や コメントも参考に,審査を行った.最終的に は,本行事を担当する地学教育委員会が審査 結果を集計し,結果を発表した.なお,審査 項目は,「研究の動機が明確であり,問題点 をはっきりととらえているか」,「観察・実験 から導かれたデータを基に,結論が導かれて いるか」,「わかりやすいポスターとしてまと められているか」の3つであり,それぞれ10 点満点で評価する.審査の結果,優秀賞は高 得点を取得した上位3件の発表に決定した.奨励賞は例年「フィールドワークに根ざした研究を行い,今後の成果が期待される発表」に授与しており,今回は4件の発表に決定した.研究者の研究とは違い,高校生の部活動等 のグループ研究において,どのようなテーマを設定するかとても難しい問題である.高校 生にふさわしい研究とはどのようなものか,ポスターをご覧いただいた会員の方々にもご 意見をいただきたいところである.最後となりましたが,今回の行事に参加いただいた各校の皆様,またご多忙のところ審 査にご協力いただいた理事の皆様に,あらためて御礼申し上げます.
【優秀賞 3件】
ES-2:鹿児島県立国分高等学校サイエンス部 地学班(藤田颯太ほか)「貝化石層の堆 積環境から見積もった地殻変動 〜存在 の確実度が上がった鹿児島湾北部の活断 層〜」
ES-8:大阪府立泉北高等学校(泉谷哲平ほ か)「地震発生時におけるニュータウン の危険領域」
ES-5:群馬県立太田女子高校理科研究部地学 班(横堀朝香ほか)「茨城県美浦村馬掛 の露頭から産出したクモヒトデ骨片化石 と介形虫化石(第2報)」
【奨励賞 4件】
ES-4:北海道旭川西高等学校理数科課題研究 地学班(北川 源樹ほか)「実験!蛇紋岩 化作用〜神居古潭帯における超塩基性岩 類の密度と帯磁率の関係〜」
ES-10:兵庫県立姫路東高等学校科学部(高 瀬健斗ほか)「兵庫県南部姫路市−加古 川市の花崗閃緑岩の角閃石から波状累帯 構造を発見」
ES-6:早稲田大学高等学院理科部地学班(廣 瀬 隼ほか)「沖積低地における洪水氾濫 予想地図と神社の立地との関係」
ES-9:兵庫県立西脇高等学校(北口龍河・田 中陽来)「火山岩の貫入岩に見られる、 流理構造の形成過程 〜流紋岩、安山岩、 玄武岩の流理構造の比較〜」
【参加校】(11校13件)
防府市立華陽中学校 理科部
鹿児島県立国分高等学校 サイエンス部地学班
鹿児島玉龍高校 サイエンス部天文班
北海道旭川西高等学校 理数科課題研究地学班
群馬県立太田女子高校 理科研究部地学班
早稲田大学高等学院 理科部地学班
山梨県立日川高等学校 物理・地学部
大阪府立泉北高等学校
兵庫県立西脇高等学校 地学部
兵庫県立姫路東高等学校 科学部
愛媛県立宇和島東高等学校 地学部
2021年地質の日
2021年の「地質の日」
ここでは,今年の「地質の日」に関連した日本地質学会主催,共催,後援等の催しをご紹介します。
>>イベントカレンダーもご覧下さい(地質学会以外のイベント情報も掲載しています)。
開催エリア:北海道/東 北/中 部/関 東/近 畿/四 国/西日本/オンライン企画/
日本地質学会 3.22掲載
惑星地球フォトコンテスト第12回ほか入選作品展示会
日程:2021年5月4日(火) 〜 5月17日(月)
場所:東京パークスギャラリー(上野グリンサロン内)(台東区上野公園 JR上野駅 公園改札出てすぐ)
入場無料,どなたでもお気軽にお立ち寄り下さい.
(注)マスク着用,手指の消毒など感染症対策にご協力をお願いいたします.
入選作品の画像や講評は学会HPに掲載しています.
http://www.geosociety.jp/faq/content0009.html
問い合わせ先:日本地質学会事務局 main[at]geosociety.jp
(注)[at]を@マークに変えて送信してください。
日本地質学会 3.1掲載
地質の日 オンライン一般講演会
日本地質学会は,一般の皆様に最新の地質学研究の成果とその意義について知っていただき,地質学への興味・関心を高めていただくことを目的に,地質の日にあわせて一般講演会をオンラインで開催いたします。今回は,「地質年代チバニアン」と「プレート沈み込み帯地震」のふたつをキーワードに,それぞれの研究で主導的役割を果たしている研究者に一般の皆様向けにわかりやすく解説していただきます。どなたでも無料で参加できます。チャット(YouTube上での書き込み)で質問・コメントもできます。
開催日時:2021年5月9日(日) 9:30開会,12:10閉会予定
開催方法:YouTubeライブ配信 どなたでも視聴可能,申込不要,無料
▷講演会の内容は,YouTubeで公開中です!見逃した方も是非ご覧ください!
<講師と講演タイトル>
9:35〜10:45
岡田 誠(茨城大学理工学研究科教授)「地質年代チバニアンと房総の地質」
研究者情報(researchmap) https://researchmap.jp/read0180444
10:50〜12:00
氏家恒太郎(筑波大学生命環境系准教授)「断層の地質学的研究から読み解くプレート沈み込み帯地震発生の科学」
研究者情報(researchmap) https://researchmap.jp/read0152832
問い合わせ先:日本地質学会事務局 main[at]geosociety.jp (注)[at]を@マークに変えて送信してください。
近畿支部 4.19掲載
普及講演会「ちきゅう」で探る地球のなぞ−海底下に暮らす生命の話−
深海のさらに奥深く、太陽の光がまったく届かない海底下の世界。地球深部探査船「ちきゅう」により、そのような極限的な場所にも膨大な数の小さな生命(微生物)が暮らしていることがわかってきました。それらの生命は、いつ、どこから来たのか? どうやって生きているのか? どのくらい深くまでいるのか? 何かの役に立つのか? 本講演では、「ちきゅう」の科学掘削プロジェクトで明らかにされた最新の知見や展望をご紹介します。
日時 2021年4月25日(日)14時〜16時
会場 大阪市立自然史博物館 講堂
講師 稲垣史生 氏(国立研究開発法人 海洋研究開発機構研究プラットフォーム運用開発部門 マントル掘削プロモーション室・室長、上席研究員)
定員 100名(申し込み多数の場合は抽選)
共催 日本地質学会近畿支部、地学団体研究会大阪支部
申込み 必要。博物館ホームページのイベントページから申し込めます。
申込締切 4月10日(土)必着(締切ました)
※YouTubeでの配信あり。YouTubeでの聴講は申し込み不要です。
詳しくは、http://www.mus-nh.city.osaka.jp/tokuten/2021underground/
特別展普及講演会・地球科学講演会
海洋マントル掘削計画:なぜ? どこで? 何をする?
地球上には、私たち人類を含め、たくさんの生命が暮らしています。生命に必要な液体の水は、実はプレートテクトニクスという他の太陽系の惑星にはない地球だけで見られる現象に支えられています。プレートには、海洋の底を作る海洋プレートと、大陸を作るプレートがあり、海嶺で新しく海洋プレートができ、日本海溝や南海トラフのような場所で大陸プレートに衝突して沈み込んでいます。プレートの深いところにはマントルがありますが、人類はまだマントルを直接調べることができていません。これまでのマントルの研究の経過と、海洋プレートを掘削してマントルを調査する、前人未踏の研究計画についてご紹介します。
日時 2021年5月9日(日)14時〜16時
会場 大阪市立自然史博物館 講堂
講師 森下知晃 氏(金沢大学理工研究域 地球社会基盤学系 地球惑星科学コース 教授)
定員 100名(申し込み多数の場合は抽選)
共催 日本地質学会近畿支部、地学団体研究会大阪支部
参加費 無料(博物館入館料必要)
申込み 必要。博物館ホームページのイベントページから申し込めます。
申込締切 4月25日(日)必着
※YouTubeでの配信あり。YouTubeでの聴講は申し込み不要です。
詳しくは、博物館HP,イベント情報を参照してください.
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/tokuten/2021underground/
2022年地質の日
2022年の「地質の日」
ここでは,今年の「地質の日」に関連した日本地質学会主催,共催,後援等の催しをご紹介します。
2022年の地質の情報はこちら(地質学会以外の全国の地質の日イベント情報)。
開催エリア:北海道/東 北/中 部/関 東/近 畿/四 国/西日本/オンライン企画/その他
日本地質学会 3.9掲載
地質の日 オンライン一般講演会 〜最近の話題をテーマに
日本地質学会は,一般の皆様に最新の地質学研究の成果とその意義についてお知らせし,地質学への興味・関心を高めていただくことを目的に,『地質の日』にあわせ一般講演会をオンラインで開催いたします.今回は, 災害や土地利用にかかわる案外身近な「地質情報の利用」と,最近日本やトンガでおきて注目を浴びている「海底火山噴火」のふたつをキーワードに,それぞれの研究で主導的役割を果たしている研究者に一般の皆様向けにわかりやすく解説していただきます.どなたでも無料で参加できます.チャット(YouTube上での書き込み)による質問・コメントも可能です.
開催方法:YouTube公開中 どなたでも視聴可能,申込不要,参加無料
プログラム(予定)
9:05〜10:15
斎藤 眞(産総研地質調査総合センター・イノベーションコーディネータ)
研究者情報(researchmap) https://researchmap.jp/read0157559
地質が身近にある社会を創る−新しい分野への活用に向けて− 地質図には様々な地質情報が含まれています.地質情報はこれまで地下資源,土木,防災(地震・火山噴火)などに使われてきましたが,斜面災害の規制の面で考慮されていないなど,活用にまだ多くの課題と可能性があります.こうした災害面の課題とともに,農作物の地理的表示(GI)保護制度での活用など,地質を身近なところで活用する新たな取り組みをご紹介します.
10:20〜12:00
鹿野和彦(元鹿児島大学総合研究博物館・教授)
研究者情報(researchmap) https://researchmap.jp/read0005317
海底火山の世界を探る「爆発的海底噴火とその噴出物」 海面下の火山は,直接見ることがむずかしく,謎の多い世界です.それだけにフンガ・トンガや福徳岡ノ場で起こった大規模な噴火を目にすると,海面下の火山でどのようなことが起こっているのか気になりませんか.この講演では,爆発的噴火の噴出物の特徴や潜水調査中に撮影された動画などを紹介し,そこから読み取れる「その何か」を探ります.
問い合わせ先:日本地質学会事務局 main[at]geosociety.jp (注)[at]を@マークに変えて送信してください。
日本地質学会 3.9掲載
惑星地球フォトコンテスト第13回ほか入選作品展示会
過去の展示の様子
日程:2022年5月3日(火・祝) 午後〜 5月15日(日)15時頃まで
場所:東京パークスギャラリー(上野グリンサロン内)(台東区上野公園 JR上野駅 公園改札出てすぐ)
入場無料,どなたでもお気軽にお立ち寄り下さい.
(注)マスク着用,手指の消毒など感染症対策にご協力をお願いいたします.
入選作品の画像や講評は近日学会HPに掲載予定です.
問い合わせ先:日本地質学会事務局 main[at]geosociety.jp
(注)[at]を@マークに変えて送信してください。
日本地質学会 3.15掲載 4.1, 4.6更新
街中ジオ散歩ミニ in Tokyo「国分寺崖線」
主催:(一社)日本地質学会,(一社)日本応用地質学会
日時:2022年5月15日(日)
見学場所:国分寺崖線(東京都国分寺市)
コース:国分寺駅→真姿の池湧水群→東山道武蔵路跡→姿見野池→西国分寺駅
案内者:山崎晴雄氏(首都大学東京名誉教授)
集合場所・時間:JR国分寺駅 午前9時(昼までの3時間程度の行程を予定しています.終了時間は前後する場合があります)
会費:一般1,500円,小中学生500円 (保険代含む,小中学生は保護者要同伴)
募集人員:15名(定員を超えた場合は,締切後抽選)
募集期間:4月8日(金)〜4月18日(月)締切ました【申込み専用フォームはこちらから】
対象:小学生以上(小・中学生の方は保護者の同伴をお願いします)
(重要)申し込みされる方は以下の注意事項をご確認下さい。
参加を希望される方は,付き添いの方も含め,個別に申し込みが必要です.
家族,友人など,グループでの参加希望の場合は,それぞれの備考欄に代表者名を記入してください。グループでの応募は,本人を含め最大4名までとします。
学会員の方へ:一般の方を対象とした行事のため,恐れ入りますが一般申込者を優先とさせて頂きます.
定員15名を超える応募があった場合は抽選とさせて頂きます.
抽選結果は当落関係なく,4月22日(金)までにお知らせします.
連絡はメールで行います.応募はメールで連絡可能な方に限らせて頂きます.
新型コロナの感染状況により中止の可能性があります。中止の場合は,5月6日(金)にメールにて連絡させて頂きます.
<ジオ散歩・新型コロナ対策について>
ワクチン接種をお勧めします。
ジオ散歩当日の朝の体温が 37.5℃以上の場合は参加不可とさせて頂きます。
巡検当日の朝に咳や鼻水、倦怠感、嗅覚異常など感染が疑われる症状がある場合は参加不可とさせて頂きます。
巡検中はマスク着用をお願いします。
開催前2週間(5/1から)の体調を確認するとともに、検温の実施をお願いします。
当日受付時に上記を口頭にて確認させて頂きます。その際、2週間前からの当日までの体調で1日でも37.5度を超える熱(若しくは体調不良)が有った場合は参加不可とさせて頂きます。
参加者から感染者が発生した場合等は必要に応じて保健所等の公的機関へ緊急連絡先の提供をさせて頂く場合があります。
問い合わせ先:日本地質学会(担当 細矢) メール:main[at]geosociety.jp (注)[at]を@マークに変えて送信してください。
近畿支部 3.9掲載
第39回地球科学講演会
日時:2022年5月8日(日)15:00-16:30
主催:地学団体研究会大阪支部・日本地質学会近畿支部・大阪市立自然史博物館
行事形式:講演会およびインターネットによる配信
テーマ:「北アルプス生成の謎 −マグマと短縮テクトニクスが作り出した北アルプス−」
講師:原山 智氏(信州大学名誉教授)
場所:大阪市立自然史博物館講堂(YouTubeを使った同時配信)
定員:聴講150名(定員を超えた場合は抽選)
参加費:無料(博物館での聴講の場合は博物館入館料が必要)
申込み:大阪市立自然史博物館ホームページのイベント情報からお申し込みくだ さい(http://www.mus-nh.city.osaka.jp/)
申込締切:4月25日(日)
※YouTubeを使った配信での聴講をご希望の方は、申込み不要です.
中部支部 4.5掲載 5.9更新
クリックするとPDFがDLできます
「地質の日」特別企画 一般向け特別講演会
<YouTube未配信のお詫び>アカウント不調のため、YouTube配信できませんでした。本講演は未発表資料等を多く含んでいるため動画配信はいたしません。楽しみにされていた全ての皆さまに心よりお詫び申し上げます。(支部長:道林克禎)
日時:2022年5月8日(日)13:00-14:00
演者:高橋 聡会員(名古屋大学准教授)
講演:深海チャートの地層から地球の歴史を解読する
場所:名古屋大学環境総合館レクチャーホール(入場制限有り)及びオンライン配信
(キャンパスマップ)※マップのD2 環境総合館の1階です
(交通アクセス)※地下鉄の場合、1日(24時間)券がお得です
日本列島をはじめとする環太平洋域の付加体地質の中には、世界的に希少な古生代-中生代の時期の深海域を記録した地層が残されています。本講演では、高橋 会員がこれまで取り組まれてきた古生代-中生代境界期の生物大量絶滅事件・環境異変の研究とともに中部日本にも存在する地質資料(秩父帯、美濃帯)とその意義について紹介していただきます。ご興味のある方はご参加ください。
Zoom参加の場合:事前参加申込はこちらから
YouTube視聴はこちらから ※YouTube視聴の場合は,事前申込は不要です。
問い合わせ:道林克禎(支部長)michibayashi[at}eps.nagoya-u.ac.jp
その他 5.10掲載
クリックするとPDFがDLできます
「深海から生まれた城ケ島」 観察会
日時:2022年6月12日(日)10:00-15:00 小雨決行
主催:三浦半島活断層調査会
後援:日本地質学会・三浦市
集合場所:城ケ島京急バス終点(神奈川県三浦市三崎町)
集合時間: 10時 ※三崎口発城ケ島行きバス 9:11発乗車をお勧めします(9:33ではぎりぎり)
コース予定 : バス終点---灘が崎---長津呂---馬の背洞門---安房崎---城ケ島公園(終了・解散)
募集人員 : 30名(申し込み先着順)
注意事項 : 海岸の岩場を歩くので、履きなれた靴でご参加を。飲み物・弁当は各自持参
申し込み : 往復はがき又はE-mailにて 住所、氏名、電話番号をご記入の上6月5日までに下記の三浦半島活断層調査会事務局 までお申込みください。
参加費用 : 500円(資料代【城ケ島探検マップ等】+保険料)
申込先 : 三浦半島活断層調査会 事務局(青木厚美方)
〒247-0056 鎌倉市大船4-21-5-603
電話 080-1193-5179
Eメール:atsumi-aoki@mcko.jp
第21回サマスク(浅間山北麗)実施報告_2022.8.17-18
地震火山地質こどもサマースクール: 実施報告
2022.12.9掲載
第21回地震火山地質こどもサマースクールin浅間山北麗ジオパーク
「浅間のいたずら、鬼のヒミツ」実施報告
地震火山地質こどもサマースクールは、日本地震学会、日本火山学会、日本地質学会の3学会が共同して実施している普及事業である。研究の最前線に立つ専門家がこどもの視点にまで下りて地震・火山・地質の現象のしくみや本質について直接語ること、および災害やそれと不可分の関係にある自然の大きな恵みについてこどもたちに伝えることを目的としている。浅間山北麗ジオパークでの「浅間のいたずら、鬼のヒミツ」は2020年開催予定だったが、新型コロナウイルス感染症の拡大により開催が延期された。社会状況が緩和の方向に向かってきたことに伴い、本年(2022年)8月17日と18日に2日間の日程で開催された。直前まで完全オンライン開催の可能性も検討しながら、現地の救急搬送事情の調査やプログラム中の発熱対応マニュアルを作るなどの準備を重ね、講師陣の一部がオンライン参加、こどもたちは現地参加というハイブリッド形式で開催が実現した。
今回の参加者は、こども24名(小学生14、中学生9、高校生1)、講師・スタッフ34名(うちオンライン3)の合計58名であった。感染対策および会場の収容人数を考慮し、現地参加のこども・スタッフ合計が50人以内になるように計画されるとともに、地元以外のスタッフも可能な限り少なくなるように計画された(しかし結果的に講師・スタッフ数がやや多くなってしまった)。大会実行委員長は高橋正樹・地質学会会員(日本大学)であった。3学会のサマースクール運営委員および現地関係者がこども参加者をさまざまな場面で支援した。初日は開会式、フィールドワーク、実験、オンライン質疑応答などが行われた。2日目は展示物観察、オンラインでの講演聴講と質疑応答、フィールドワーク、フォーラムでの発表会、閉会式などが行われた。終了後のアンケートでは回答者全員から「とても楽しかった」、「楽しかった」という回答が寄せられた。興味深かったプログラムとしては、火砕流や泥流の実験、および宿での宿泊が最多得票であった。
今大会は高橋会員のほか、日本大学の安井真也会員と金丸龍夫会員にも地質学会側講師としてご協力いただいた。また、浅間山北麗ジオパーク関係者をはじめ現地の多くの方々にご協力いただいた。なお、2023年度は神奈川県平塚市で、2024年度は徳島県三好市周辺で開催予定である。地震火山地質こどもサマースクールの詳細については公式ウェブサイトで確認できる(https://kodomoss.jp)。
(地震火山地質こどもサマースクール担当理事 星 博幸)
2023年地質の日
2023年の「地質の日」
ここでは,今年の「地質の日」に関連した日本地質学会主催,共催,後援等の催しをご紹介します。
2023年の地質の情報はこちら(地質学会以外の全国の地質の日イベント情報)
開催エリア:北海道/東 北/中 部/関 東/近 畿/四 国/西日本/オンライン企画/その他
日本地質学会 3.10掲載
「地質の日」オンライン普及講演会:
「日本列島の地質探訪―古生代から新生代まで」
Youtube視聴はこちらから↓
日本地質学会では,広く一般に地質学の魅力と重要性を知っていただくため,毎年,5月10日の「地質の日」を記念した様々な行事を実施しています.本年は,各地のジオパーク拠点博物館に協力いただき,オンラインで各施設の展示や地域の露頭等を紹介することで,聴講者が自宅にいながらにして各地の地質の魅力に“触れ”,日本列島の地質の多様性に“触れる”機会とします.
クリックするとPDFをD Lできます
日程:2023年5月13日(土)9:30〜12:05
主催:日本地質学会
実施方法
オンラインで3施設の登壇者がリレーで講演(1題40分程度).
参加者は,YouTubeライブでご視聴ください(事前登録不要)どなたでもご覧いただけます.(後日オンデマンドでも公開予定です)
スライドでの講演だけでなく,展示室や露頭からの中継なども予定されています.
YouTubeチャット機能を利用した質問も可能です!
スケジュール
9:30~9:35 ご挨拶 岡田 誠(日本地質学会会長)
9:35~9:40 概要説明
9:40~10:20 講演1「四国西予ジオパークと黒瀬川帯」四国西予ジオミュージアム(高橋司館長・榊山匠学芸員)日本最古級の岩石や地層を特徴とする「黒瀬川構造帯」.それらはジュラ紀の付加体である「秩父帯」の中に断続的に細長く分布していますが,その成り立ちについては謎が多く,研究者による見解も分かれています.今回は黒瀬川帯研究発祥の地である西予市から,“黒瀬川帯”をキーワードとして四国西予ジオパークやジオミュージアムを紹介します.
(休憩)
10:30~11:10 講演2「銚子半島をつくった孤独でふしぎな中生代の地層」銚子ジオパークミュージアム(岩本直哉主任学芸員・上田脩郎主任学芸員)犬吠埼灯台で有名な銚子の東海岸.ここには局所的に中生代の付加体,前孤海盆堆積物が露出します.これらの基盤岩の存在により,銚子は半島となり,銚子ならではの風土が形成されました.このように銚子の礎となった中生代の地層や産出する化石を中心に銚子の地質の魅力を銚子ジオパークミュージアムよりご紹介いたします.
(休憩)
11:20~12:00 講演3「糸魚川からフォッサマグナと日本列島誕生の謎に迫る」糸魚川フォッサマグナミュージアム(小河原孝彦学芸員・香取拓馬学芸員・茨木洋介学芸員・郡山鈴夏学芸員)糸魚川ユネスコ世界ジオパークの拠点施設・フォッサマグナミュージアムと,代表的なジオサイトであるフォッサマグナパークから,日本列島の生い立ち,大地の生い立ちと,日本酒など私たちの暮らしの深い関わりを紹介します.断層と日本酒にいったいどんな関係があるのか気になったそこのあなた,ぜひお聞き逃しなく.
12:00~12:05 終わりの挨拶
日本地質学会 3.6掲載
惑星地球フォトコンテスト第14回ほか入選作品展示会
過去の展示の様子
日程:2023年5月16日(火) 午後〜 5月28日(日)14時まで
場所:東京パークスギャラリー(上野グリンサロン内)(台東区上野公園 JR上野駅 公園改札出てすぐ)
入場無料,どなたでもお気軽にお立ち寄り下さい.
入選作品の画像や講評は近日学会HPに掲載予定です.
問い合わせ先:日本地質学会事務局 main[at]geosociety.jp
(注)[at]を@マークに変えて送信してください。
日本地質学会 3.20掲載
街中ジオ散歩in Yokohama「身近な地形・地質から探る横浜の歴史」
主催:(一社)日本地質学会,(一社)日本応用地質学会・神奈川県立生命の星・地球博物館
日時:2023年5月14日(日)
見学場所:横浜市(京急東神奈川〜JR桜木町)
主な見学地点と見どころ:「東神奈川周辺の台地と明治初期の領事館跡」〜「横浜防災センター」〜「横浜市街地の埋め立てと干拓」〜「掃部山周辺の石垣と湧水」
案内者:笠間友博氏(箱根ジオパーク推進協議会事務局)
集合及び解散場所・時間:
集合:幸ヶ谷公園(京急神奈川駅から徒歩4分:スタッフが案内します)9時
解散:JR桜木町駅 16時頃(予定)
会費:大人1,500円,小中学生500円 (保険代含む,小中学生は保護者同伴)
募集人員: 20名(定員を超えた場合は,締切後抽選)
募集期間:4月3日(月)〜4月16日(日)
対象:参加資格は特にありませんが,急坂,階段を含む高低差がある箇所があります.
申込に際しての注意事項:
雨天中止,小雨決行とします.ただし,小雨の場合は昼で打ち切りとさせて頂きます.
お弁当は各自持参でお願いします.昼食を予定している地点(横浜防災センター)は近くに購入するお店はありません.
連絡はメールにて行います.メールでの連絡ができない場合は,申込をご遠慮下さい.
新型コロナの蔓延状況により中止の可能性があります(5月8日(月)に最終決定をさせて頂きます).
一般(非会員)の方を対象とした行事なため ,一般申込者(非会員)を優先とさせて頂きます.
見学会当日のマスクの着用は室内の見学地点を除き任意となります.但し,当日体調が悪い方,発熱が認められた方は参加をご遠慮下さい.
申込時には保険加入や名簿作成のために必要な情報をお知らせ頂きます.申込項目には漏れなく記入をお願いします.記入頂けない場合は,お申込は受付できません.
中学生以下の方は保護者同伴でお申込下さい(保護者の分も あわせて申込手続きを行って下さい).
お申込いただいた方は上記事項に同意していただけたものとみなします.
申込方法:WEB専用申込フォームからお申し込み下さい(お電話でのお申込はお受けできません).
(注)抽選の場合,当選の発表は,4月中にメールにて連絡させて頂きます.
問い合わせ先(メールにてお願いします):
日本地質学会関東支部(担当 細矢)mail:hosoya[at]ckcnet.co.jp ※[at]を@マークにして送信して下さい
近畿支部 3.6掲載
第40回地球科学講演会
「日本海拡大時の日本列島の変動―地質と古地磁気の研究からどこまでわかっているかー」
近畿支部では、地学団体研究会大阪支部・大阪市立自然史博物館と共催で、「地質の日」協賛行事として5月14日(日)に星 博幸氏(愛知教育大学)を講師に迎え、「日本海拡大時の日本列島の変動―地質と古地磁気の研究からどこまでわかっているかー」を開催します。対面での聴講に加え、YouTubeでの配信も予定しています。多くの方のご参加をお待ちしております。
日本海拡大時に、日本列島はどのように大陸から移動してきたのでしょうか。その時、日本列島はどのような変動を受けたのでしょうか。これまで日本海は1500万年前頃に拡大したと考えられていましたが、最近の研究によって拡大はもう少し前に起こり、1500万年前には拡大がほとんど終わっていたことがわかってきました。また、日本海拡大時に日本列島の地殻が広い範囲で変形したことや、拡大直後に西日本太平洋側で一斉にマグマ活動が起こったことなどもわかってきました。本講演会ではこれらの問題について、地質と古地磁気の初歩の解説も交えながら、最新の研究成果を解説します。
主催:地学団体研究会大阪支部・日本地質学会近畿支部・大阪市立自然史博物館
日時:2023年5月14日(日)14:00〜16:00
講師:星 博幸 氏(愛知教育大学 教授)
場所:自然史博物館本館 講堂(YouTubeを使った同時配信も行います)
定員:講堂での聴講:150名(定員を超えた場合は抽選)
対象:講堂での聴講:どなたでも参加できます(小学生以下は保護者同伴)。ただし申込が必要。 ネット配信:インターネットに接続することができる方
申込締切:5月1日(月)
申込方法については、大阪市立自然史博物館ホームページ(http://www.mus-nh.city.osaka.jp/)のイベントページをご覧下さい。※YouTubeを使った配信での聴講をご希望の方は、申込不要です。
配信・接続方法: 【配信方法】YouTubeを使った配信を予定しています。YouTubeの「大阪市立自然史博物館」チャンネル(https://www.youtube.com/c/大阪市立自然史博物館/)にアクセスして表題の番組をクリックしてください。開始時間になれば始まります。
参加費:無料(博物館での聴講の場合は博物館入館料が必要)
その他:6月18日(日)まで見逃し配信を行います。同時配信を見られない人はご覧下さい。
四国支部 4.18掲載
化石発掘体験〜化石レプリカを見つけてみよう!〜
日時:2023年5月13日(土)13:00-16:30
主催:愛媛大学理工学研究科地球進化学コース院生会
共催:日本地質学会四国支部・愛媛大学理学部地学コース,大学院理工学研究科地球進化学講座,愛媛大学ミュージアム
会場:愛媛大学ミュージアム・オープンテラス(愛媛県松山市文京町3 愛媛大学 城北キャンパス)
5月10日は地質学に関する理解を推進させることを目的に制定された「地質の日」である。近年、愛媛県では、道後姫塚で県初の首長竜化石が発掘され、数多くのメディアで取り上げられることにより、古生物学および地質学への関心が高まっています。本企画では、レプリカを用いた化石発掘体験を通して小学生やその保護者に化石および地質や岩石に興味を持ってもらい、地質学に関する理解を深めてもらうことを目的としています。
参加費:無料
事前申込不要 (当日会場に直接ご来場下さい. 13:00-16:00まで受付)
問い合わせ先:
メール:ehime.chishitunohi[at]gmail.com(代表:下岡和也)) ([at]を@に変えて送信ください. )
電話:089-927-9623(愛媛大学理学部地学コース事務室)
西日本支部 4.3掲載
第15回「地質の日」企画 身近に知る「くまもとの大地」
主催:「地質の日」くまもと実行委員会
共催:日本地質学会西日本支部ほか
日時:2023年5月21日(日)10:00〜16:00
場所:熊本博物館 (熊本県熊本市中央区古京町3-2)
内容:2008年から毎年,熊本県内の大学や博物館,民間の地質業協会などの地質関連団体が合同で「地質の日」のイベントを開催しています. 今回は熊本市にある熊本博物館を会場に, 熊本の大地をテーマとした展示や, 地質学に関連する楽しい体験イベントを行います. おどろきの展示コーナー:熊本の地質, 岩石, 火山, 恐竜やアンモナイトなどの化石, 熊本県の自然災害に関する展示./わくわく体験コーナー:化石レプリカづくりやパンニングでの鉱物採集, カルデラ形成実験など, 地学を楽しく学べる体験.
費用:博物館入場料のみ,大人400円(320円), 高・大生300円(240円), 中学生以下200円(160円)※( )は団体料金. 未就学児は無料.
申込不要. 当日直接会場へお越しください.
問い合わせ先:熊本博物館(地質担当:南部靖幸)〒860-0007 熊本市中央区古京町3−2 TEL:096-324-3500 FAX:096-351-4257 E-mail:nambu.yasuyuki[at]city.kumamoto.lg.jp
その他(後援ほか) 3.20掲載
観察会 「観音崎の地層と関東大震災の傷跡をたどる」
※定員を超えましたので,参加受付を終了いたしました.
多数のお申し込みをいただき,ありがとうございました.(2023/5/8)
観音崎は海底に堆積した地層が隆起してできました。その過程でできた傾斜した地層や断層、そして海底地すべりの痕跡など様々な地層があります。これらの観察を通して、大地の成り立ちを学んでいきます。また、関東大震災の傷跡も辿っていきます。
主催:三浦半島活断層調査会
後援:日本地質学会 ほか
令和5年6月4日(日)10:00〜 15:00頃 (小雨決行)
集合場所:観音崎バス停(10時集合)
観察コース:観音崎バス停〜灯台下海岸〜灯台入口〜たたら浜園地 展望園地〜観音崎バス停
募集人員:先着30名
参加費:500 円(資料代・保険代)
持ち物:弁当・飲み物・雨具 歩きやすい靴で ご参加ください。
申込:郵便番号 ・住所・氏名(フリガナ)・年齢・電話番号を記載し、往復葉書 または メール で 5月 20日 までに 下記あてにお申込みください。
申込先:三浦半島活断層調査会 事務局(青木厚美方)〒 247 0056 鎌倉市大船4-21-5-603 電話 080-1193-5179 Eメール atsumi-aoki[at]mcko.jp ※[at]を@マークにして送信して下さい
2024年地質の日
2024年の「地質の日」
ここでは,今年の「地質の日」に関連した日本地質学会主催,共催,後援等の催しをご紹介します。地質学会以外の全国の地質の日イベント情報はこちら
日本地質学会は,令和6年度科学技術週間の協力機関です.
[開催支部・エリア]北海道/東 北/中 部/関 東/近 畿/四 国/西日本/オンライン/その他
日本地質学会 3.22掲載
「地質の日」オンライン一般講演会
令和6年能登半島地震による地殻変動と地盤災害
▶︎視聴者アンケート(概要欄)にご協力をお願いします.*アンケートに回答いただいた方には、地質学会オリジナルのデスクトップ画像をプレゼント*
YouTube概要欄からもアクセスしていただけます.
https://forms.gle/XhtoQUXmt5ZCueFVA
日程:2024年5月12日(日)AM 9:30〜12:05
クリックするとPDFをDLできます
日本地質学会では,広く一般に地質学の魅力と重要性を知っていただくため,毎年,5月10日の「地質の日」を記念した様々な行事を実施しています.本年は,1 月1 日に発生した能登半島地震について,被害のあった能登や新潟市などを長年調査している研究者に登壇いただき,講演会ページ 現地の地形変化や地盤災害の最新情報について解説します.
主催:一般社団法人日本地質学会
開催方法:YouTube ライブ配信.参加無料,事前申込不要.
どなたでも視聴可能です.
<オンライン講演会のパブリック・ビューイングを開催しませんか?>当オンライン講演会はYouTubeライブで一般に公開します。博物館やジオパークなどでパブリック・ビューイングを開催いただけます。申請は不要です。開催後、開催した旨を事務局にご報告ください。たくさんの方にご覧いただけるよう,ご協力をお願いいたします。
「地震がつくった能登半島の大地」 講師:宍倉正展 氏(産業技術総合研究所地質調査総合センター 連携推進室 国内連携グループ グループ長) 能登半島地震では地盤が大きく隆起して海岸一帯が干上がりました.このような現象は,実は過去からくり返し生じていたことが海岸地形からわかります.つまり能登半島は地震のたびに隆起してできた大地なのです.その隆起の実態を日本列島各地にある同様の海岸地形と併せて紹介します.
「能登半島地震による新潟市域の液状化被害」 講師:卜部厚志 氏(新潟大学災害・復興科学研究所 所長・教授) 2024 年能登半島地震では新潟市西区において8000 軒を越える住宅において液状化被害が発生しました.これらの液状化は,1964 年新潟地震による液状化発生地域と重なり,砂丘斜面末端部や旧流路など地形・地盤に特徴がみられます.これら液状化のメカニズムや液状化深度,地盤強度などについて概要を報告します.
日本地質学会 3.5掲載
惑星地球フォトコンテスト第15回ほか入選作品展示会
過去の展示の様子
日程:2024年5月1日(水) 午後〜 5月12日(日)14時まで
場所:東京パークスギャラリー(上野グリンサロン内)(台東区上野公園 JR上野駅 公園改札出てすぐ)
入場無料,どなたでもお気軽にお立ち寄り下さい.
入選作品の画像や講評は学会HPに掲載しています.こちらから
問い合わせ先:日本地質学会事務局 main[at]geosociety.jp
(注)[at]を@マークに変えて送信してください。
日本地質学会 3.15掲載
街中ジオ散歩in Tokyo「身近な地形・地質から探る麻布の歴史と湧水」
主催:(一社)日本地質学会,(一社)日本応用地質学会
日時:2024年5月19日(日)
見学場所:東京都港区麻布(有栖川宮記念公園〜麻布十番駅付近)
主な見学地点と見どころは以下となります.「有栖川宮記念公園」〜「がま池」〜「善福寺」〜「古川・新広尾公園親水テラス」
案内者:宮越昭暢氏(産業技術総合研究所),林 武司氏(秋田大学)
集合:有栖川宮記念公園広尾口(東京メトロ広尾駅から徒歩4分)10:00
解散:古川・新広尾公園親水テラス(東京メトロ麻布十番駅付近)13:00頃(予定)
会費:大人1,500円,小中学生500円 (保険代含む,小中学生は保護者同伴)
定員:20名(定員を超えた場合は,締切後抽選)
対象:参加資格は特にありませんが,急坂,階段を含む高低差のある箇所があります.
申込に際しての注意事項:
雨天中止,小雨決行とします.
当見学会では,途中昼食時間を設けておりません.昼食は解散後各自でお願いします.なお,終了地点付近には多数店舗があります.
連絡はメールにて行います.メールでの連絡ができない場合は,申し込みをご遠慮下さい.
一般(非会員)の方を対象とした行事なため,一般申込者を優先とさせていただきます.
見学会当日のマスクの着用は任意となります.但し,当日体調が悪い方,発熱のある方は参加をご遠慮下さい.
申込時には保険加入や名簿作成のために必要な情報をお知らせいただきます.申込項目には漏れなく記入をお願いします.記入いただけない場合は,お申し込みは受付できません.
中学生以下の方は保護者同伴でお申し込み下さい(保護者の分もあわせて申込手続きを行って下さい).
お申し込みいただいた方は上記事項に同意していただけたものとみなします.
募集期間:2024年4月5日(金)〜15日(月)締切ました.
申込方法:上記注意事項をよくご確認のうえ, WEB専用申込フォーム(こちら)からお申し込み下さい(電話では受け付けません).
(注)抽選の場合,当選の発表は,4月中にメールにて連絡させていただきます.
問い合わせ先(メールにてお願いします):
日本地質学会関東支部(担当 細矢)
mail:hosoya[at]ckcnet.co.jp ※[at]を@マークにして送信して下さい
関東支部 3.7掲載
講演会「デジタル詳細地形データを用いた地表面変位計測で見る地震災害」
日時:2024年4月20日(土)14:00-15:30(13:30から講演会受付開始)
場所:北とぴあ(7階)第2研修室(東京都北区王子)
共催:一般社団法人日本地質学会関東支部・一般社団法人関東地質調査業協会
講師:向山 栄氏(国際航業株式会社 公共コンサルタント事業部)
講演要旨:PDFファイル;支部Webサイトに掲載中.
講演会資料:PDFファイル;支部Webサイトに4月初旬に掲載予定.
講演会の定員:会場100名+オンライン100名(ハイブリッド形式).
参加費:無料
CPD単位:1.5単位取得可
詳しくは,こちら(支部WEBサイト)から
関東支部 5.23掲載
学生・若手会員向け「地質調査の基礎講座」- 城ヶ島巡検
日本地質学会関東支部では,標記の講座を実施します.学生・若手会員向けです.地層・堆積岩の見方を学んで露頭柱状図を作成したり,走向・傾斜の測り方を学んで測定した走向・傾斜をもとに地質構造を推定する講座です.野外地質調査に不慣れな方,堆積岩の見方を勉強したい方,城ヶ島に興味のある方,大歓迎です.また,学生会員には,本会の若手育成事業による学生会員参加費半額補助が適用されます.
日時・場所:
2024年6月8日(土)10:00-15:30 神奈川県三浦市城ヶ島で野外観察・調査(集合場所:白秋碑前バス停)
2024年6月9日(日)13:00-16:45 横須賀市産業交流プラザ第一会議室(京急線汐入駅前)で露頭柱状図作成など(室内作業)
申込締切:6月5日(水)(定員になり次第締め切り)
詳しくは,こちら(支部WEBサイト)から
近畿支部 3.5掲載
第41回地球科学講演会「日本列島の起源と大和構造線」
富山県の神通川沿いに露出する白亜系手取層群,庵谷峠礫岩の露頭
庵谷峠礫岩中の赤色花崗岩礫の研磨面(横幅4cm);日本には全く露出しないこの岩石のルーツが日本列島の起源を解く鍵
日本列島に産する岩石・地層のほとんどは古生代以来の海洋プレート沈み込みで作られたことが20世紀末までにほぼ解明されてきました。しかし、約5億年間にわたってプレートが沈み込み続けた相手の大陸が何者であったのかについては、新生代半ばに日本海が開いてアジア大陸から日本列島が分離してしまったために長く不明のままでした。日本列島の起源について最新の解釈をご紹介します。意外なところにルーツがあった!
日時:2024年5月11日(土)14:00〜16:00
主催:地学団体研究会大阪支部・日本地質学会近畿支部・大阪市立自然史博物館
講師:磯粼行雄(東京大学・名誉教授・元日本地質学会会長)
場所:大阪市立自然史博物館本館 講堂(YouTubeを使った同時配信も行います)
定員:先着170名(先着順・申込不要)
対象:講堂での聴講:どなたでも参加できます(小学生以下は保護者同伴)
配信・接続方法: 【配信方法】YouTubeを使った配信を予定しています。YouTubeの「大阪市立自然史博物館」チャンネル(https://www.youtube.com/c/大阪市立自然史博物館/)にアクセスして表題の番組をクリックしてください。開始時間になれば始まります。
参加費:無料(博物館での聴講の場合は博物館入館料が必要)
その他:見逃し配信は6月16日(日)まで。同時配信を見られない人はご覧下さい。
問合せ:大阪市立自然史博物館 地史研究室 担当:前川 メール:tmaekawa[at]omnh.jp,TEL 06-6697-6221
四国支部 3.18掲載
石の魅力大発見!〜見て・触って・知ってみよう〜
日時:2024年5月11日(土)13:00〜16:30
会場:愛媛大学ミュージアム オープンテラス・多目的室
主催:愛媛大学理工学研究科地球科学分野院生会,
共催:一般社団法人日本地質学会四国支部
協賛:愛媛大学理学部地学コース・大学院理工学研究科地球科学分野,愛媛大学ミュージアム
概要:岩石探し・観察体験イベントおよび,ポスター展示を行います. 岩石探し体験では,砂利を敷き詰めた箱の中から隠されている岩石を探し出し,入手した岩石の同定と含有鉱物の観察を,ルーペを用いて行います.ポスター展示では岩石の種類やなりたちをまとめるとともに,展示試料とその薄片を置き,さまざまな視点から岩石を観察してもいます.
参加費:無料
事前申し込み:不要 (当⽇会場に直接ご来場下さい.13:00-16:00 まで受付)
問い合わせ先:ehime.chishitunohi[at]gmail.com(代表:福井堂子)([at]を@に変えて送信ください。) 電話:089-927-9623(愛媛⼤学理学部地学コース事務室)
西日本支部 3.22更新
第16回「地質の日」企画 身近に知る「くまもとの大地」
日時:2024年5月12日(日)10:00〜16:00
場所:熊本県環境センター(熊本県水俣市明神町55−1)
主催:「地質の日」くまもと実行委員会
共催:日本地質学会西日本支部・熊本県環境センター ・熊本大学大学院先端科学研究部(地球環境科学講座・社会環境工学講座) ・熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター減災型社会システム部門 ・熊本博物館 ・(公財)阿蘇火山博物館 ・御所浦恐竜の島博物館 ・御船町恐竜博物館 ・熊本県博物館ネットワークセンター ・(公財)肥後の水とみどりの愛護基金 ・熊本地学会・NPO法人菊池川自然塾 ・(一社)熊本県地質調査業協会 ・阿蘇ジオパーク推進協議会
内容 2008年から毎年,熊本県内の大学や博物館,民間の地質業協会などの地質関連団体が合同で 「地質の日」のイベントを開催しています. 今回は熊本県の南端,水俣市にある熊本県環境センターを会場に, これまでより活動の範囲を広げた形での取り組みになります.熊本の大地をテーマとした展示や,地質学に関連する楽しい体験イベントを行いますが,水俣という地域の地質の特徴についての講演も用意されています.
おどろきの展示コーナー:熊本の地質, 岩石, 火山, 恐竜やアンモナイトなどの化石, 熊本県の自然災害に関する展示.
わくわく体験コーナー:化石レプリカづくりやパンニングでの鉱物採集, カルデラ形成実験など, 地学を楽しく学べる体験.
特別企画:講演会「みなまた大地のふしぎ」(13:30〜14:30) 会場:熊本県環境センター2階 環境シアター 費用 無料 申込 不要. 当日直接会場へお越しください.
三浦半島活断層調査会(日本地質学会後援) 3.22掲載
観察会「深海から生まれた城ヶ島」地層見学会
定員に達しましたので,募集は締め切りました(5.22)
城ヶ島には美しい風景や動物・植物ばかりでなく,たくさんの変化に富んだ地形・地質を見ることができます.地層が曲げられてできた褶曲や複雑な断層,深海に生活していた生物の痕跡,激しい火山爆発によってもたらされた火山豆石やゴマ塩火山灰など.城ヶ島には,三浦半島誕生の秘密がたくさん詰まっています.
主催:三浦半島活断層調査会
後援:三浦市(予定),日本地質学会
日時:2024年6月2日(日)10:00〜16:00
コース(予定):城ヶ島 灘が粼〜長瀞〜馬の背洞門〜安房崎〜城ヶ島公園
集合場所:京急バス終点「城ヶ島」バス停前10:00
募集人員:30名(申し込み先着順)
注意事項:履きなれた靴でご参加を.雨具は必携。飲み物・弁当は各自持参して下さい.
申し込み:定員に達しましたので,募集は締め切りました(5.22)E-mail又は往復はがきにて 住所,氏名(フリガナ・年齢付記),電話番号をご記入の上5月25日までに下記の三浦半島活断層調査会事務局 までお申込みください.
参加費用:500円(資料代【城ケ島探検マップ等】+保険料)(小学生以上)
問い合わせ・申込先:三浦半島活断層調査会 事務局(青木厚美方)
鎌倉市大船4-21-5-603
電話:080-1193-5179
メール:atsumi-aoki@mcko.jp
e-フェンスター
地球なんでもQ&A:目次
地質学者に答えてもらおう
地球科学に関する疑問質問はありませんか? もしも自分で調べてみてもどうしてもわからない,そんな時は専門家に聞いてみましょう.注意事項をお読みのうえお問い合わせ下さい.
▶▶▶「地質学者に答えてもらおう」の問い合わせフォームへ
▶▶▶ これまでの質問と回答のページへ
地球なんでもQ&A 目次
注:これは地質学会としての統一見解ではなく、読者の理解の一助としてインターネット委員会が整備したものです
地質全般
Q1.なぜ数億年前の出来事がわかるの?
Q2.なぜ高い山脈ができるの?
Q3.アトランティスやムー大陸ってあったの?
Q4.ハワイが毎年日本に近づいている?
Q5.砂や泥が硬い岩石になるのに何年?
Q6.超大陸ってなにが「ちょー」なの?
Q7.底なし沼の下はどうなっているの?
Q8.プレートって何ですか?
Q9.地下水脈に魚はいますか?
Q10.地球内部空洞説って??
Q11.隕石と地球の岩石はどう違いますか?
Q12.隕石ってどれくらいの頻度でぶつかるの?
Q13.クレーターってどうやって見つけるの?
Q14.地球外天体が海に落ちたらどうなるの?
Q15.地球外天体がぶつかったら地震が起る?
Q16.岩石がなかなか割れません.どうすれば?
Q17.鍾乳洞や洞窟は地球の中心まで続いてますか?
Q18.日本のどこで恐竜化石が見つかる?
Q19.日本で発見されている最大の恐竜は何?
Q20.アンモナイトってどんな生き物ですか?
Q21.日本最古の化石はどんなものですか?
Q22.恐竜化石はどんな地層から見つかるの?
Q23.日本で天然のダイヤモンドは採れますか?
Q24.地球の内部は,どうなっているの?
Q25.岩石や鉱物の名前を調べるには?
Q26.鉱物と岩石の違いはなんですか?
Q27.結晶、鉱物、ミネラルって何??
Q28.石綿(アスベスト)について教えて下さい
Q29.恐竜はなぜ巨大だったの? 地球の重力が小さかった?
Q30.化石は大洪水によって埋まったものですか?
Q31.グランドキャニオンとノアの大洪水は関係するの?
Q32.日本近海でメタンを採掘して巨大地震が起きませんか?New
地質災害
Q1.活断層と普通の断層は何が違うのですか?
Q2.活断層はなぜ危険なの?
Q3.中越地震(2006)の山古志村の地盤は?
Q4.史上最大の地震は何?
Q5.地すべりはどのような原因で起こるのですか?
Q6.土石流って何ですか?
Q7.地盤沈下はなぜ起きる?
Q8.津波によって数十トンの石が動くって本当?
Q9.盛土地盤はどんなところ?
Q10.液状化でビルが傾く?
Q11.地層の断面をみることができる?
Q12.GPSで日本の動きがわかる?
地球史
Q1.第四紀の時代区分が変わるってどういうことですか?
Q2.なぜ258万年前なの?
Q3.年代の定義の変更と数値の改訂の違いとは??
Q4.第四紀とはどんな時代なの?
Q5.活断層とは第四紀に動いたものだと聞きました.第四紀の年代が遡ると活断層が増えるのですか? 危険性は?
Q6.法令に「第四紀」は使われているの?
Q7.建築物への影響は?
Q8.第三紀はどうなりますか?
地質全般Q&A
地球なんでもQ&A
注:これは地質学会としての統一見解ではなく、読者の理解の一助として広報委員会が整備したものです
地質全般
Q1、なぜ数億年前の出来事がわかるの?
Q2.なぜ高い山脈ができるの?
Q3.アトランティスやムー大陸ってあったの?
Q4.ハワイが毎年日本に近づいている?
Q5.砂や泥が硬い岩石になるのに何年?
Q6.超大陸ってなにが「ちょー」なの?
Q7.底なし沼の下はどうなっているの?
Q8.プレートって何ですか?
Q9.地下水脈に魚はいますか?
Q10.地球内部空洞説って??
Q11.隕石と地球の岩石はどう違いますか?
Q12.隕石ってどれくらいの頻度でぶつかるの?
Q13.クレーターってどうやって見つけるの?
Q14.地球外天体が海に落ちたらどうなるの?
Q15.地球外天体がぶつかったら地震が起る?
Q16.岩石がなかなか割れません.どうすれば?
Q17.鍾乳洞や洞窟は地球の中心まで続いてますか?
Q18.日本のどこで恐竜化石が見つかる?
Q19.日本で発見されている最大の恐竜は何?
Q20.アンモナイトってどんな生き物ですか?
Q21.日本最古の化石はどんなものですか?
Q22.恐竜化石はどんな地層から見つかるの?
Q23.日本で天然のダイヤモンドは採れますか?
Q24.地球の内部は,どうなっているの?
Q25.岩石や鉱物の名前を調べるには?
Q26.鉱物と岩石の違いはなんですか?
Q27.結晶、鉱物、ミネラルって何??
Q28.石綿(アスベスト)について教えて下さい
Q29.恐竜はなぜ巨大だったの? 地球の重力が小さかった?
Q30.化石は大洪水によって埋まったものですか?
Q31.グランドキャニオンとノアの大洪水は関係するの?
Q32.日本近海のメタンを採掘して巨大地震が起きませんか? New
Q1:なぜ数万年前や数億年前の地球の出来事がわかるの?
A:地層や岩石に地球の過去のことがらが残されているからです.
タイムマシーンがあれば40億年前の岩石のでき方を観察できるかも知れませんが,それはできないので,現在の岩石や地層のでき方を観察したり,実験したり,計算したりして昔の岩石や地層のできた時の条件や過程を推測するのです.
地球は固体惑星ですから,基本的に岩石や地層からできています.地球で最も古い岩石は約40億年前のものが知られています.そのような岩石には岩石ができた時の条件(温度,圧力など)や過程(例えば,マグマが冷えて固まったとか海底で堆積したとか)も記録されています.また,岩石や地層に含まれている化石も重要な情報源です.地球上には様々な岩石や地層があり,それらはすべての時代を通して絶え間なく作られています.このような地道な作業を繰り返すことによって,過去から現在にいたる地球の姿を捉えることができるのです.
(菅森義晃・奥平敬元 大阪市大)
縞状鉄鉱層(オーストラリア,ハマスレー鉱山近くで採集)25〜18億年前に海底で堆積したもの.この様な岩石から当時の酸素量が推定されています。
Q2:なぜ高い山脈ができるの?
A:地殻が厚くなっているからです
軽い地殻が厚くなるおかげで、山は高くなれます。
山が高くなるのには様々な原因がありますが,結局は地殻が厚くなったためです.私たちが住んでいる大地は大陸地殻ですが,この大陸地殻はマントルの上に浮かんでいます.大陸地殻は主に花こう岩質の岩石からできているのに対して,マントルはより重たい(密度の高い)かんらん岩(かんらん石からなる岩石,かんらん石は宝石のペリドットといっしょ)からできていますので,大陸地殻には浮力が働いています.つまり,軽い大陸地殻が厚いほど,マントルから顔を出す部分(標高)が高くなります(これをアイソスタシーといいます).
では,なぜ大陸地殻が厚くなるのでしょうか?その原因の一つは,マントルから大陸地殻へとマグマが供給されるからです.玄武岩質マグマはマントルの一部が溶けてできたものですが,この玄武岩もかんらん岩よりは軽いので,マントル内を上昇し,大陸地殻の底にペタッとひっつきます.日本列島の山脈下ではこのような「底付け作用」が起こっていますので,地殻が厚くなり,標高の高い山脈ができます.もう一つの原因は,大陸と大陸の衝突です.この例は,ヒマラヤ山脈(ユーラシア大陸とインド亜大陸の衝突)やヨーロッパアルプス山脈(ヨーロッパ大陸とアフリカ大陸の衝突,イタリアはアフリカ大陸の一部)です.規模は小さいですが,丹沢山地(本州弧と伊豆・小笠原弧の衝突)もそうです.二つの大陸が衝突したとき,一方の大陸がもう一方の大陸の下に沈み込むことがありますが,この場合大陸地殻の厚さは短期間に倍近くになります.また,大陸同士が衝突した時,非常に強い力がかかるのでその内部に「しわ」ができます.この「しわ」は褶曲とよばれるものでこれによっても大陸地殻は厚くなります.これらのような過程が重なり合って山脈の標高が高くなっていくと考えられています.
(奥平敬元 大阪市大)
Q3:アトランティス大陸やムー大陸ってあったの?
A: 両者は伝説(物語)上の大陸です.
アトランティス大陸はプラトンの著作に登場する,大西洋に存在したと言われる伝説上の大陸のことです.この大陸には世界の覇権を狙っていた王国があったが,ゼウスの怒りに触れ大陸ごと消滅(沈没)させられたと伝えられています.一方,ムー大陸はアメリカの作家ジェームズ・チャーチワードの著作に登場する大陸で,約1万2千年前に太平洋に存在したが,現在は消滅したとされるものです.両大陸とも,その存在には科学的根拠が乏しく,伝説(物語)上の大陸です.
地球の表面は,大陸地殻と海洋地殻からできています.大陸地殻は私たちが住んでいる海面上の大地で,海洋地殻は海の底だと考えてそんなに間違っていません.大陸地殻は主に花こう岩や堆積岩からできているのに対して,海洋地殻は玄武岩からできています.一般に大陸地殻の方が軽く(密度が低い),海洋地殻の方が重い(密度が高い)ので,前者が後者の上に浮いているイメージです.プレート運動によって地殻はマントルへと沈み込んでいきますが,大陸地殻は軽いためなかなか沈み込めません.現在,インド亜大陸がユーラシア大陸に沈み込もうとしていますが,なかなか難しいようです.どうやら,一度できた大陸はなかなか消えてなくなるのは難しいようです.
また様々な海洋地質調査でも、太平洋や大西洋の深海で広大な大陸地殻は見つかっておらず、人類の有史以来ずっと海底だったことがわかっています。
(奥平敬元 大阪市大)
Q4:ハワイが毎年日本に近づいているって本当ですか?
A:本当です.
地球の表面は十数枚のプレートからなっていて,それら各プレートが相対的に動くことによって,いろいろな地質現象が引き起こされるというのが,プレートテクトニクスです.プレートの相対運動によって作られる境界には,大きく分けて2種類あり,それはプレートが近づく「収束境界」と離れる「発散境界」です.日本列島は収束境界に位置しています.日本列島では海側のプレート(太平洋プレート,フィリピン海プレート)が大陸側のプレート(ユーラシアプレート,北米(またはオホーツク)プレート)に対して沈み込んでいます.私たちの日本列島は北米プレートとユーラシアプレート上にあります.ハワイ諸島は太平洋プレート上にあり,太平洋プレートは北米+ユーラシアプレートに対して年間8 cm程度で沈み込んでいますので,毎年8 cmハワイは日本に近づいているわけです.日本ーホノルル間は約4100マイル(約6600 km)ですので,8千万年後には徒歩でハワイに行けるかも知れません.
(奥平敬元 大阪市大)
Q5:砂とか泥が硬い石になるのには何年くらいかかるのですか?
A:1〜2千万年程度はかかるでしょう.
砂とか泥が硬くなって石(岩石)になったものは堆積岩と呼ばれ,砂が固まると砂岩,泥が固まると泥岩になります.砂や泥が厚く堆積すると底の部分には大きな圧力(荷重)がかかります.その様な状態では粒の間の間隙が詰まったりします.これだけだと硬く搾められただけですので,岩石とは呼べません.圧力のかかり方は均質ではなく,あるところでは高く,あるところでは低いといった状態になります.このとき粒の間に水分があると,圧力の高いところでは粒の成分が溶け出し,圧力の低い部分でその成分が沈殿します.この沈殿した成分が接着剤の役目をはたし,最終的には硬い岩石となります(この過程を続成作用といいます).この砂→砂岩,泥→泥岩の変化速度は様々な条件によって違うので一概には言えませんが,日本では 2千万年前よりも新しい地層では岩石とは呼べない「やわい」地層が多いため,砂→砂岩,泥→泥岩の変化にかかる時間は1〜2千万年程度だとされています.
(奥平敬元 大阪市大)
Q6:超大陸ってなにが「ちょー」なんですか?
A:ずばり「大きさ」です.
パンゲア大陸復元図 ウェゲナー著 「大陸と海洋の起源」より)
現在,地球上には大陸が六つ(ユーラシア,アフリカ,北米,南米,オーストラリア,南極)ありますが,この大陸の配置は日々変化しています.かつては地球上の大陸がほぼ1ヶ所に集まり「超大陸」を形成していたとされています.地球と他の太陽系の固体(地球型)惑星との大きな違いの1 つに,大陸地殻のあるなしがあります.実は火星や金星には大陸はありません.そのような地球に特徴的な大陸は主に花こう岩質の岩石からできています.大陸の体積増加パターンには未だ定説がなく,大陸誕生(これ自体もいつなのか議論が分かれるところですが,約40億年前とされています)以降,一定の割合で成長したのか,ある時期にドカッとできたのかはっきりしませんが,10億年前にはほぼ現在の体積(地球の表面積の3割程度)に達したとされています.
その後は,プレートの相対運動にともない,離合集散(バラバラになったり,ひっついたり)を繰り返しています.つまり超大陸とは地球の表面積の3割を占める大陸が1ヶ所に集まった巨大大陸で,「ちょー」は「巨大」という意味です.これまで,様々な地質学的観察から,約2億年前の「パンゲア」,約5億年前の「ゴンドワナ」,約10億年前の「ロディニア」などの超大陸が存在したと言われています.現在はユーラシア大陸を中心にして新たな超大陸が形成されつつあり,それは約2億年後であるとされています.
(奥平敬元 大阪市大)
Q7:底なし沼の下はどうなっているの?
A:岩盤があります.
私たちの暮らしている街や山々の表面、そして海や湖の底には土や砂や泥といった堆積物が広く覆っています。なかには軟らかい泥が厚くたまっている場所もあり、底なし沼と呼ばれたりします。でも、それがずっと続くことはありません。地下深くなると圧力が上がってきて、堆積物中の水分は押し出され、泥も固くしまってきます。堆積物がもっと地下深くまで持ち込まれると、温度も上がり、時間が経つといずれは岩石へと変化します。
水分を豊富に含んだ軟らかい泥が、どこまでも続くことはないのです。私たちの足元の深いところは、すべて岩石なのです。これを岩盤と呼びます。底なし沼も、森の腐葉土も、砂漠の砂も、海底の泥もすべて地球表面を覆っているだけなのです。
(坂口有人 海洋研究開発機構)
Q8:プレートって何ですか?
A:地球表層を覆う、板のような岩石の層です.
地球表層は何枚かのプレートで区分され、プレート同士は互いにいろんな向きにゆっくりと動いています。プレート同士は勝手に動きあうので、その境界では、衝突したり、沈み込んだり、互いに離れあったり(次々生成されたり)、すれちがったりしています。そしてそれによって、地震や火山や造山運動といった重要な地質現象が生じます。プレートの厚さは約100kmで、地殻とマントルの一部からできています。日本周辺にはユーラシアプレート、北アメリカプレート、太平洋プレート、フィリピン海プレートの4つのプレートがひしめき合うという世界でも稀な場所で、実に様々な地質現象が絶え間なく起きています。まるで地球の縮図ですね。
(坂口有人 海洋研究開発機構)
Q9:地下水脈に魚はいますか?
A:いません.
海水浴場の砂浜で穴を掘ったら、地中から水が染み出てきたことはありませんか? あれはある深さまで水に浸っていて、そこまで掘ったので水が出てきたのです。そして水は砂粒と砂粒の間に浸透していて、決して水だけの層があったわけではありません。私たちの街の地下にある地下水も同じで、水が透りやすい層にだけ水が存在しています。そしてそれはある深さならどこでもあるわけではなく、居やすい場所にだけ居るのです。それは地表の川や池と同じですね。地表には水がたくさんありますが、どこにでもあるわけじゃありません。そうして地下水も多く集まったり、ゆっくり、地表の川とは比べ物にならないほどゆっくり流れたりしているのです。こうしたいわば地下の川を水脈と呼んだりします。しかしそれは地表の川とは全く違い、砂や礫の隙間に水が浸みているだけですので、魚が入れるほどのスペースはありません。
(坂口有人 海洋研究開発機構)
Q10:地球内部は空洞だという話は本当ですか??
A:空洞ではありません。
地球の内部は地震波の伝わる様子から推定されています。それはまるでスイカの実の詰まり具合を叩いた音で判別することに似ています。その結果、地球はスカスカではありませんでした。地殻の下には分厚いマントル層、そして液体の外核と固体の内核があることがわかっています。よって地球内部が空洞になっているということはありません。
(坂口有人 海洋研究開発機構)
Q11:隕石(いんせき)と地球の岩石はどう違いますか?
A:隕石の多くは,地球の岩石には含まれない金属鉄を含みます。
隕石には岩石質のもの(石質隕石),鉄のかたまり(隕鉄,鉄質隕石),そして鉄と岩石がほぼ半々に混ざったもの(石鉄隕石)があります.しかし,落下が確認された隕石の90%近くは石質隕石です.そして石質隕石の90%近くは球粒隕石(コンドライト)です.球粒隕石は直径1〜10 mm程度の球形の物体(球粒,コンドルール)を多量に含むことが特徴で,球粒の多くはかんらん石や輝石よりなります.球粒隕石は,地球の岩石の中では「かんらん岩」に似た鉱物組成をもっていますが,地球のかんらん岩には球粒組織は見られません.隕石と地球の岩石の大きな違いは,隕石には金属鉄(実際は少量のニッケルを含む合金)の粒が含まれることです.地球の岩石中では,鉄は珪酸塩,酸化物,硫化物などとして含まれ,金属鉄は非常に稀です.これは隕石が形成された宇宙空間が地球(の表層部)よりも酸素に乏しかったことを示します.金属鉄を含むために,隕石は強い磁力を持ち,隕石を地球の大気中に露出しておくと,金属 鉄が酸化して錆びを生じます.
ところで,製鉄所の熔鉱炉の鉱滓(スラグ)が田畑や道路の整地に使われることがあり,その中に混ざっている鉄のかたまりが隕鉄と間違えられることがよくあります.鉄鉱石から人工的に作り出された鉄のかたまりは,ほとんどニッケルを含みませんが,隕鉄は必ず5〜10%程度のニッケルを含み,特徴的な離溶組織を示します.これによって人工的な鉄と隕鉄を区別できます.石質隕石の少数派である非球粒隕石(エイコンドライト)の中には,最近話題の火星隕石や月から来た隕石が含まれ,それらは玄武岩,斑れい岩,斜長岩,輝石岩といった地球の岩石とよく似ていますが,鉱物の種類や化学組成の違い,微量元素や同位体比の違いによって地球の岩石と区別することができます.なお,落下直後の隕石は,宇宙空間で強い放射線(宇宙線)を浴びていたために,微弱な放射能を持っており,これは隕石であることの証拠になります.
(石渡 明 金沢大)
Q12:地球外天体(隕石など)ってどれくらいの頻度で地球にぶつかるの?
A:小さいサイズは半年に1回、大きいものは1億年に1回くらいです。
地球外天体の地球への衝突頻度は,小さいものほど頻繁に,大きいものほど稀に起きます.例えば,直径7mくらいの天体(10-2Mtほどのエネルギー)の場合,半年に1回くらいの確率で地球にぶつかっています.ただし,この規模の天体は大気圏の上部で燃え尽きてしまうので,地上まで落下してくることはありません.直径250m(103Mtほどのエネルギー)くらいの規模の天体になると,大気圏を通過して地上に衝突し約5kmほどの衝突クレーターを形成すると考えられています.この規模の衝突は1万年に1回くらいの確率で起き,その影響範囲は100km四方くらいに及ぶと推測されています.恐竜絶滅の原因として挙げられている,今から約6500万年前の白亜紀/第三紀(K/T)境界に衝突した天体は直径約10kmです.この規模の天体が地球に衝突する頻度は1億年に1回ほどと極めて稀ですが,ひとたび衝突が起きれば地球規模の大災害が発生します.我々が生きている間にこの規模の衝突に遭遇する確率は非常に低いと考えられますが,46億年の地球の歴史の中では頻繁にこのような巨大衝突が起き,地球や生物の進化に大きな影響を及ぼしたと考えられます.それにも関わらず,K/T境界での衝突以上の規模の衝突が起きたことが確認されているのはわずかに3つしかありません.巨大天体衝突と地球や生命の進化の関係に関する研究は,まだまだこれからです.
(後藤和久 東北大学)
参考文献:
Chapman C. R. and Morrison D. 1994, Impacts on the Earth by asteroids and comets: assessing the hazard. Nature 367, 33-40.
Toon, O, B., Turco, R. P., Covey, C., (1997) Environmental perturbations caused by the impacts of asteroids and comets. Reviews of Geophysics, 35, 41-78.
Q13:天体衝突クレーターってどうやって見つけるの?
A:円形構造を探す→地質調査する→分析→検討→合格!
天体衝突クレーターとは,地球外天体が地球にぶつかることによって地表面または海底面にできる大きな穴のことです.その多くは円形構造(“おわん”のような形)をしており,縁辺部にリムと呼ばれる盛り上がりがあります(アメリカ・アリゾナ州のメテオール・クレーターが代表的です).天体衝突クレーターの可能性がある円形構造は,地質調査や衛星写真・空中写真の解析などで見つかることが多く,現在までに地球上で180個くらいの天体衝突クレーターが確認されています.この数は,長い地球の歴史を考えると驚くほど少ないのですが,天体衝突クレーターの大部分は侵食されていたり,地下に埋没しており,発見することができません.また,衝突クレーターの発見はヨーロッパやアメリカなど,地質調査が盛んに行われている場所に偏っています.今後,アフリカやアジア,中東などで研究が進めば,その数はさらに増えると考えられます.こうした円形構造が見つかると,天体衝突クレーターかどうかの検証が行われます.例えば,円形構造の地形的特徴や衝突起源物質(衝突により溶融した岩石が冷え固まってできた衝突メルトや,衝撃変成石英のように地球外天体衝突時の高温・高圧化でしかできないと考えられる鉱物など)の有無などが調べられ,こうした厳しい検査に合格した円形構造が,晴れて天体衝突クレーターとして国際的に認められます.
(後藤和久 東北大学)
参考文献
Melosh, H.J., 1989. Impact cratering: A geologic process. Oxford University Press, 245 pp.
Q14:地球外天体が海に落ちたらどうなるの?
A:海水の大量蒸発や大津波が起きます
地球外天体が海に落ちる現象を海洋衝突と呼びます.これまでに,海洋衝突クレーターはわずかに20個ほどしか見つかっていません.これは,海底にできた衝突クレーターを見つけることは非常に難しいことと,古い時代のものは海洋プレートの沈み込みとともに地下に沈み込み,消失してしまっていると考えられるからです.見つかっている海洋衝突クレーターに関する研究も,構造の把握や試料採取などが難しく,ほとんど進んでいません.しかし,地球上の約70%が海で覆われていることを考えると,地球外天体の多くは海に落ちていると言っても過言ではなく,今後の研究の進展が期待される分野です.海洋衝突が起きた場合,衝突地点周辺の海水が高温にさらされるため,まず周囲の海水が大量に蒸発します.さらに,巨大津波も発生し,衝突地点からはるかに離れた場所にまで津波の影響が及びます.例えば,白亜紀/第三紀境界の天体衝突は水深〜200mくらいの海洋で起きたと考えられていますが,メキシコ湾沿岸で最大300mもの波高の津波が発生したと考えられています.
(後藤和久 東北大学)
参考文献
Ormo, J., Lindstrom M., 2000, When a cosmic impact strikes the sea bed. Geological Magazine, 137, 67-80.
Matsui, T., Imamura, F., Tajika, E., Nakano, Y., Fujisawa, Y. 2002, Generation and propagation of a tsunami from the Cretaceous-Tertiary impact event. Geological Society of America Special Paper 356, 69-77.
Q15:地球外天体が地球にぶつかったら大きな地震が起きそう.
A:とてつもなく大きな地震が起きます
今から約6500年前の白亜紀/第三紀(K/T)境界の天体衝突(直径10kmの隕石)の規模の場合,すべてのエネルギー(108Mt)が地震波に使われたと仮定すると,マグニチュード12.8にも達する地震が発生すると言われています(Toon et al., 1997).スマトラ島沖で2004年に発生した大地震のマグニチュードは9.1と考えられていますが,マグニチュードが1ずつ増えると地震のエネルギーは32倍ずつになりますから,スマトラ島沖の地震の数十万〜100万倍くらいのエネルギーということになります.ただし,実際には衝突のエネルギーは熱エネルギーなどにも変換されるため,すべてが地震波として使われることはありません.そのため,地震のマグニチュードはもっと小さいと思われます.また,衝突地点から放出された地震波が地球内部で反射を繰り返して地球の裏側(対蹠地)に集中し,火山噴火やホットスポットの形成などを引き起こすという説もあります.Bosloughら(1996)は,K/T衝突当時,衝突地点の対蹠地に現在のデカン高原があった可能性を指摘し,洪水玄武岩(大規模な溶岩台地を形成する玄武岩)の噴出の原因は地球の反対側で起きた天体衝突だったのではないかと主張しています.ただ,この仮説には両者の年代が合わないという問題や位置関係が正確に対蹠地ではないという問題がありますし,K/T境界の衝突のときにこのようなことが実際に起きたかは実証されていません.しかし,火星や月の巨大衝突クレーターの対蹠地には,火山噴火の痕跡や破砕された地形が見つかることが多く,興味深い仮説だといえます.
(後藤和久 東北大学)
参考文献
Boslough, M. B., Chael, E. P., Trucano, T. G., Crawford, D. A., Campbell, D. L., 1996. Axial focusing of impact energy in the Earth’s interior: A possible link to flood basalts and hotspots. Geological Society of America Special Paper 307. 541-550.
Toon, O, B., Turco, R. P., Covey, C., (1997) Environmental perturbations caused by the impacts of asteroids and comets. Reviews of Geophysics, 35, 41-78.
Q16:岩石をハンマーで割って中を見たいと思うのですが,なかなか割れません.どうすればうまく割れますか?
A:専用の岩石ハンマーが必要です.
一般家庭にある釘打ち用のハンマー(トンカチ)は岩石を割るのに適していません.専用の岩石ハンマーが必要です.まず,ハンマーの形ですが,硬い岩石を割るには片方の先が尖り,他方は平らな「ピック型ハンマー」が適しています(軟らかい岩石を削って構造を見るためにはチゼル型ハンマーが適します).持ち運びも考えて,重さ800〜1000 g程度のものがよいでしょう(価格は1本5000〜10000円程度).ただし,大きな岩石を割るには,5ポンド(2.5 kg)〜10ポンド(5 kg)程度のハンマーが必要で,この大きさのものは両側が平らなものが多いです.
野外で岩石を割るには,まず自分自身の安全のために手には軍手(手袋),目にはゴーグル(安全メガネ)をして,周囲数メートル以内に他人がいないことを確かめます.破片が飛んでケガをしますので,他人が近くにいる場合は離れてもらい,ガラス窓や乗用車などからも離れる必要があります.10cm程度の大きさの岩石を割る時は,岩石のできるだけ平らで広い面を上にして,片足でその岩石を押さえ,ピック型(またはチゼル型)ハンマーの平らな面(尖った方ではない)が岩石の平らな面の真ん中に平行に当たるように(ハンマーを足に当てないように注意して)振り下ろします.1回で割れないときは,同じ動作を数回繰り返します.もっと大きい岩石の場合は,真ん中を打っても割れませんので,できるだけ鋭角に割れた角(稜)から5〜10 cm離れた平らな部分にハンマーを当てます.大きいハンマーを使う場合も要領は同じです.ただし,川原の礫のように,大きな丸い石は,大きいハンマーを用いてもなかなか割れません.20〜30 cm大の川原の石を割る最も簡単な方法は,同じくらいの大きさの別の石を両手で頭の上まで持ち上げ,割ろうとする石に向かって投げ下ろすことです.1回で割れなければ,何回か繰り返します.非常に原始的で豪快な方法ですが,これが最も効果的です.ただし,危険を伴うので,ケガをしない(させない)ように注意して行って下さい.
(石渡 明 金沢大)
Q17:鍾乳洞や溶岩洞窟の奥はどこまで続いていていますか?地球の中心まで続いていることがありますか?
A:絶対にありません.
山の中にある鍾乳洞は,基本的に過去の地下河川の跡です.従って上流側に入口があり,下流側に出口があって,入口から出口に向かってゆるく傾斜した(ほぼ水平に近い)洞窟が本洞になっている場合が多く,昔はこの本洞内を川が流れていたわけです(現在も流れていることがあります).そして,地表のドリーネ(凹地)の底から鍾乳洞の本洞まで竪穴が延びていたり,河川の下方浸食の進行によって本洞から下に向かう枝洞ができていたり,下方のほぼ水平なもう一つの洞窟と組み合わさって網目状になっていたりします.しかし,いずれにしても,鍾乳洞は石灰岩が水に溶けやすいためにできるので,石灰岩の地層の中にしかありません.つまり,鍾乳洞の全体は石灰岩の地層の中にすっぽり収まっているわけです.ですから,地質図を見れば鍾乳洞の範囲の限界を知ることができます.石灰岩は浅い海の底に堆積した地層ですから,その広がりには限りがあります.従って鍾乳洞の奥深くが地球の中心まで続いているということは絶対にありません.
溶岩洞窟は,火山の火口から溶岩が流れ,周囲から冷やされて固まりかけた時に,内部のまだ高温のドロドロした部分が,溶岩の傾斜方向に流れ出てしまい,その跡が空洞として残ったものです.従って,溶岩洞窟の全長は1つの溶岩流の中にすっぽり収まります.ですから,溶岩洞窟を探検すると地球の中心まで行けるということは絶対にありません.
(石渡 明 金沢大)
Q18:日本では、どこから恐竜化石が見つかっていますか?
A:北は北海道から南は熊本県まで、15 18の道および県から見つかっています。
発見当時日本の領土であった樺太(現在のロシア連邦サハリン)からニッポノサウルス・サハリネンシスという鳥脚類の化石が発見されており、現在、北海道大学に収蔵されていますが、それを除くと、現在、北は北海道から南は熊本県まで、15の道および県から見つかっています。 かつては、日本から恐竜化石は出ないとも言われていましたが、1978年、岩手県岩泉町から竜脚類の上腕骨の化石(通称:モシリュウ)が発見され、これが日本における最初の恐竜化石の発見となりました。それ以降、各地で発見が相次ぎ、最近では、2006年に兵庫県丹波市から竜脚類のまとまった化石が発見され、現在も発掘調査が続けられています。また、福井県や熊本県などでも継続的に恐竜の発掘調査が続けられているので、今後も発見される恐竜化石の数は確実に増えていくと考えられます。これ以外の地域でも恐竜時代に堆積した地層が全国各地にあり、国内の恐竜産地も増えていくことが予想されます。
追記:
和歌山県からカルノサウルス類と見られる獣脚類の歯の化石が見つかったことが発表されため、現在恐竜化石の発見されている道および県は16となりました。2007.11/2
追記:
2008年に鹿児島県、2012年に長崎県で恐竜化石が発見され、現在恐竜化石の発見されている道および県は18となりました。2012.12/28
(廣瀬 浩司 天草市立御所浦白亜紀資料館)
これは日本の地質百選にも選ばれた熊本県御所浦です。通称白亜紀の壁と呼ばれます。詳しくはこちら。
Q19:日本で発見されている最も大きい恐竜は何ですか?
A:鳥羽市のトバリュウは約16〜18mの大きさです
日本最大級の肉食恐竜の歯。先端部分は欠損していますが、残されている歯の部分の大きさは6.4cmで、復元される歯の大きさは10cmくらいになると推定されます。御所浦層群烏帽子層
日本では歯や骨など部分的な化石が多く、それらから推定された全長で見てみると、三重県鳥羽市で発見された竜脚類(通称:トバリュウ)は約16〜18mと推定されており、兵庫県丹波市の発掘中のもの(通称:タンバリュウ)も同様に10数mはあったと見られています。また、福井県勝山市からも竜脚類と見られる大きな上腕骨の化石が見つかっています。
獣脚類(肉食恐竜)では、熊本県天草市と福岡県宮若市から先端部の欠けた大きな歯の化石(大きさがそれぞれ、6.4cm、5.7cm)が発見されており、どちらも復元すると10cm程度あったと考えられ、10m級の獣脚類であったと推定されます。 ちなみに全身が復元されている日本の恐竜では、フクイラプトル・キタダニエンシスが4.2m、フクイサウルス・テトリエンシスが4.7mです。また、ニッポノサウルス・サハリネンシスの全長は4.1mですが、復元されているものは子供であることが知られ、まだ大きくなったと考えられます。
(廣瀬 浩司 天草市立御所浦白亜紀資料館)
引用文献
三重県立博物館ホームページ http://www.pref.mie.jp/HAKU/HP/
福井県立恐竜博物館ホームページ http://www.dinosaur.pref.fukui.jp
Q20:アンモナイトってどんな生き物ですか?
A:オウムガイやイカ、タコと同じ軟体動物の頭足類です。
古生代シルル紀後期(約4.28〜4.16億年前)にオウムガイから分化し、出現したと考えられています。古生代から中生代に大繁栄し、現在までに1万種以上が報告されています。恐竜などと共に、中生代白亜紀末(約6550万年前)に絶滅しました。
その殻の内側はいくつもの隔壁で仕切られた「気室」からなり、それぞれは細い管でつながっていました。殻口付近は、「住房」と呼ばれ、その部分に軟体部が入っていました。軟体部は、10本程度の腕を持っていたと考えられ、大きなカラストンビ(顎器)を持っていました。また、ドイツのゾルンホーフェンから見つかったものには、腕に吸盤ではなく、小さな鈎爪が残されています。
アンモナイトは形も様々で、一般的な巻きをしている「正常巻き」に対して、「異常巻き」と呼ばれるものもたくさんいます。その形は、クリップ状や螺旋状、棒状、蚊取り線香状などあり、色々な生活様式があったとも考えられています。
(廣瀬 浩司 天草市立御所浦白亜紀資料館)
アンモナイトの化石です。(提供:氏家恒太郎さん)
魚売り場のイカです。
引用文献
早川浩司著.化石が語るアンモナイト,北海道新聞社,pp.253,2003
両角芳郎・辻野泰之著.アンモナイトのすべて,徳島県立博物館, pp.47, 2003
Q21:日本最古の化石はどんなものですか?
A:無顎類の歯化石とされるコノドントです。
岐阜県高山市の地層中から見つかる無顎類の歯化石とされるコノドントで、古生代オルドビス紀中期〜後期(約4.72〜4.39億年前)のものです。 これらは微化石ですが、大型化石としては、古生代シルル紀後期(約4.23〜4.19億年前)のものが高知県横倉山、宮崎県祇園山などから知られ、クサリサンゴやハチノスサンゴなどのサンゴ類、三葉虫、腕足類、ウミユリなどの化石が産出しています。
ちなみに、哺乳類化石で見てみると、日本最古のものは、石川県白山市から中生代白亜紀前期(約1.3億年前)のものが知られ、肉食の小型哺乳類と考えられる三錐歯類(さんすいしるい)ハクサノドン・アルカエウスや、草食の小型哺乳類の多丘歯類(たきゅうしるい)が見つかっています。また、大型哺乳類の化石では、新生代古第三紀始新世 (約5000万年前)のものであり、熊本県天草市からはコリフォドンの仲間やトロゴサスが発見されています。
(廣瀬 浩司 天草市立御所浦白亜紀資料館)
Q22:恐竜化石はどんな地層から見つかりますか?
A:中生代に堆積した地層から見つかります。
お近くの博物館にも行ってみましょう。博物館情報はこちらのページにあります。この写真は熊本の御所浦白亜紀資料館。
恐竜化石は、恐竜の生息していた中生代に堆積した地層から見つかります。日本では、中生代ジュラ紀から白亜紀に堆積した地層から発見されており、その多くが白亜紀のものです。
中でも、恐竜は陸上に棲んでいたため、河川や氾濫原、汽水域(干潟)などといった、陸域ないし陸域に極めて近い場所で堆積した地層中から見つかることが多いのが特徴です。同じく陸域の河川などに棲んでいたカメやワニ、淡水生貝類の化石が一緒に産出することも多く、これらは恐竜化石を探す際の目印にもなります。恐竜の化石を探したい人はまずこれらの地層が分布している場所を調べてみるのが、恐竜発見への近道です。
ただし、陸域から海に流され化石となったと思われるものが、浅海の海成層から産出することもあるので、陸域で堆積した地層がなくても、恐竜時代の地層が分布する地域では、恐竜化石の発見される可能性があるといえます。
(廣瀬 浩司 天草市立御所浦白亜紀資料館)
Q23:日本で天然のダイヤモンドは採れますか?
A:これまでに発見の報告はありません。 発見されました!
中国・山東省蒙蔭のダイヤモンド鉱山.中央部の暗緑色の部分がダイヤモンドを含むキンバレー岩.周囲の白っぽい部分は片麻岩.最も大きいもので約120カラットのダイヤモンドが産出しました。
ダイヤモンドは,石墨(黒鉛)と同様に炭素(C)からできています.そして,マントルと呼ばれる地球深部(120〜150 km以深)の高温・高圧条件下で,炭素原子の配列が変化して形成されます.宝石となるような粗粒のダイヤモンドは,キンバレー岩と呼ばれる特殊な岩石から採掘されています.一方,変成岩の特に高圧で形成されたものからは,顕微鏡を使ってやっと観察できる程度の微細なマイクロ・ダイヤモンドが見つかっています.また,これらダイヤモンドを含む岩石が風化してできた砂・泥やそれが再び固まってできた堆積岩からも発見されています.中国・東部の渤海周辺や大別山−蘇魯大陸衝突帯には,ダイヤモンドを含む岩石が分布しますから,そこから砂や泥と一緒に運ばれてきたダイヤモンドが,日本の堆積岩中で発見される時を待っているかもしれません.また,日本には変成岩が広く分布しており,その一部にはダイヤモンドが安定な深さでできたと考えられるものもあります.これらの岩石を丹念に調べると,ダイヤモンドが見つかるかもしれません.
(榎並正樹 名古屋大)
ところが! 「日本地質学会2007年札幌大会」で、ついに国内でのダイヤモンドの発見報告がありました。驚きました。この画期的な成果の発表資料はプレスリリースのページにあります(編集部 2007.9/18追記)
Q24:地球の内部は,どうなっているのでしょう?
A:地球の内部構造は,しばしば卵にたとえられます。
地球の内部構造は,しばしば卵にたとえられます.卵殻にあたる最も外側の部分(厚さ5〜70 km)は地殻と呼ばれ,主に花崗岩や玄武岩と呼ばれる岩石からできています.卵白に相当するマントル(地殻の下約2,900 kmまで)は,カンラン岩またはそれと似た化学組成の岩石からなっていると考えられています.卵黄にあたる中心部は,金属鉄からできており,液体状態の外側の部分 (深さ2,900〜5,100 km)は外核,それ以深の固体部分は内核と呼ばれています.このような,地球の内部構造は,地震波が伝わる速度の変化の様子を解析して求められました.しかし,地震波データだけからでは,それぞれの部分が,具体的にどんな物質からできているかを決めることは困難です.地球内部の詳しい様子を知るために,地球のような惑星の欠片である隕石や,地殻変動や火山活動などによって地表面にもたらされた地球深部の岩石の研究,地球内部の様子を室内で再現する高圧・高温実験などが行われています.
(榎並正樹 名古屋大)
Q25:岩石や鉱物の名前を調べるにはどうしたらよいですか?
A:まず、色、模様、重さ、硬さなどを調べてください。
三波川変成帯中に産する輝石岩の偏光顕微鏡写真(横幅約1.4 mm).岩石を薄く(厚さ30 µm程度)研磨すると光を通すようになり,顕微鏡で鉱物を観察することができます。
まず,岩石や鉱物の色,模様,重さ(比重)や硬さなどを,調べてください.岩石であれば,それがどんな種類や大きさの鉱物でできているか,どんな場所で採取したかなども,重要な情報となるでしょう.また,鉱物はそれぞれが特有の形をしている場合が多いので,名前を調べるときの助けとなります.岩石や鉱物の特徴がわかったら,図鑑で調べたり,相談できる人がいたら聞いてみたりしてください.
同じ種類の岩石や鉱物であっても,できたときの条件や化学組成のわずかな違いなどによって,見かけが様々に異なる場合があります.一方,互いによく似ているものでも,別の鉱物や岩石である場合もあります.そのため,名前を決めるために偏光顕微鏡や電子顕微鏡で観察したり,X線,電子線やレーザーなどを利用して分析したりすることが必要な場合もあります.自分で調べてみてもよくわからないときは,理学部や教育学部のある近くの大学や,国立科学博物館(http://www.kahaku.go.jp/)・地質調査総合センター(http://www.gsj.jp/HomePageJP.html)などの博物館・科学館に問い合わせてみてください.日本は,「鉱物の博物館」と言われるほど,多くの珍しい鉱物が見つかっています.何だろうと不思議に思ったら,調べてみてください.
(榎並正樹 名古屋大)
岩石の種類をきちんと決めるには,岩石の専門家でも手に取っただけで岩石の種類を正確に決定するのは困難です.しかし,そうは言っても,経験を積んだ地学の先生や研究者は,かなり正確に,しかも即座に岩石の種類を言い当てます.結論として,この質問に対する答えは「経験者に見せるのが一番」ということになりますが,図鑑と見比べながらいろいろ考えるのは楽しいものですし,まずご自分で図鑑と見比べて目星をつけることをお勧めします.「多摩川」,「相模川」など特定の川の石に対象を絞った図鑑は特に有用です.川原や海岸に落ちている岩石は,その地域や川の上流に分布する地層が侵食されたものである場合が多いので,その地域周辺の地質図を見るのも大いに参考になります.産総研のホームページで全国の地質図を見ることができます.
(石渡 明 金沢大)
Q26:鉱物と岩石の違いはなんですか?
A:鉱物の集合体が岩石です。
いくつかの例外はありますが,一般に原子の規則正しい配列(結晶構造)によってできており,ほぼ一定の化学組成をもつものを結晶と呼び,そのうち天然に産出するものが狭い意味の鉱物で,石英,雲母やダイヤモンドなどがその代表です.したがって,結晶構造が同じであっても化学組成が異なれば違う鉱物となり,化学組成が同じでも結晶構造が異なれば別の鉱物とみなされます.たとえば,方解石(CaCO3)とマグネサイト(MgCO3)は,同じ結晶構造ですが,化学組成が違うため,別種の鉱物とみなされます.一方,石墨とダイヤモンドは,ともに炭素(C)からできていますが結晶構造が異なるため,色や硬さなどが異なり,別種の鉱物です.人工的につくられた結晶の種類は多いのですが,そのうち天然に産出が確認され,国際鉱物学連合(IMA)の「新鉱物・命名・分類委員会(CNMNC)によって鉱物として認められているものは,現在のところ3,000種類程度です.そして,毎年数十種類の新鉱物が発見されています.鉱物の中には想像を超えるほど巨大なものがあり,例えば石英の結晶(水晶)には長さ2m, 重さ4 tに達するものが知られています.
鉱物の集合体が岩石です.マグマが固まってできた火成岩,砂や泥などが固まってできた堆積岩,温度や圧力の変化によって岩石が変化してできた変成岩に分けられます.多くの岩石は,複数の鉱物からできていますが,大理石のように一種類の鉱物(方解石)だけからなるものもあります.岩石には,それができたときの条件や含んでいる鉱物の種類によって,様々な色や模様を見せるものがあります.
(榎並正樹 名古屋大)
石墨(左側)とダイヤモンド(右側)の結晶構造.丸い玉ひとつひとつが炭素原子です.石墨では,炭素原子が水平方向につながり,それが重なって何枚もの層をなしています.一方,ダイヤモンドでは,炭素原子が水平・垂直の両方向に,均等につながっているのがわかります.隣り合う炭素原子の間隔は,およそ1オングストローム(1 mmの1千万分の1)です 。
Q27:結晶、鉱物、ミネラルって何??
A:鉱物と結晶はそれぞれ視点が違うことばです
地球の固体部分を構成している岩石,その岩石を形づくっている1つ1つの粒を鉱物と言います.1つの鉱物は物理的・化学的にほぼ均質な天然の無機物質であり,鉱物よりも小さい単位は分子や原子になります.結晶というのは物質の状態の1種で,気体・液体・固体のうちの固体が結晶と非結晶に区分されます.結晶は原子や分子が規則正しく配列している状態(氷や水晶など),非結晶はそれらが(液体と同様に)不規則に配列している状態(ガラスなど)です.従って,鉱物と結晶はそれぞれ「視点が違うことば」であり,例えば水晶(石英)は鉱物であり結晶でもありますが,オパール(ガラス質)は鉱物ですが結晶ではありません.氷砂糖(有機物)は結晶ですが鉱物ではなく,チョコレート(これも有機物)は鉱物でも結晶でもありません. 鉱物と結晶の用語法は,どの言語でもかなり混乱しています.例えばクリスタルガラスというのがありますが,これは結晶ガラスということで,矛盾した言葉です(本当は完全にガラスです).また,鉱物の英語はミネラルですが,この言葉は日常的には人体に必要な栄養素のうち鉱物質の成分(カルシウム,マグネシウムなど)を意味します.人工的に合成した結晶を鉱物と言う場合もあり,鉱物資源と言えば生物の働きで形成された石灰岩や珪藻土なども含まれます.
(石渡 明 金沢大)
Q28:石綿(アスベスト)について教えて下さい
A:繊維状鉱物の集合体です。
壁材中に少量含まれる石綿(中央にある繊維状の結晶)の電子顕微鏡写真. 結晶の太さは1ミクロン(1 mmの千分の1)以下です。
石綿は,繊維状鉱物の集合体で,耐久性,耐熱性,耐薬品性や電気絶縁性などに優れているため,建設資材や電気製品など様々な用途に広く使用されてきました.竹取物語に登場する,火にくべても燃えない「火鼠の皮衣」はこの石綿であったろうと言われています.また,平賀源内が石綿を布状にしたものを,火浣布と名付け幕府に献上しました.このように大変有用な石綿も,体内に吸入されると長い潜伏期間の後に肺がんや中皮腫の病気を引き起こすことが明らかとなり,現在では使用がほぼ全面禁止されています.ILO(国際労働機関)は,石綿(アスベスト)を「蛇紋石と角閃石両グループに属する繊維状の鉱物」と定義して,具体的な鉱物として蛇紋石グループのクリソタイルと角閃石グループのカミングトン閃石−グリューネ閃石(アモサイト),リーベック閃石(クロシドライト),直閃石,トレモラ閃石,アクチノ閃石の6種類の鉱物をあげています.しかし,これら以外にも繊維状の鉱物は数多く存在します.また,石綿の代替品として,ガラス繊維が使用されています.これらの安全性は,早急に検討される必要があります.
(榎並正樹 名古屋大)
Q29:昔の恐竜はなぜ巨大だったの? もしかして当時の地球の重力が小さかったから??
A: 中生代の地球の重力が小さかったという事実は存在しません。
正直言って、恐竜がなぜ巨大化したのか、よくはわからないのです。体が大きい方が有利であることは理解できるのですが、なぜあそこまで巨大になったのかは、不明なのです。地球の重力は、地球の質量と、地球の中心から表面までの距離で決定されます。現在も中生代も、それらは変化していませんから地球の重力は現在も中生代も同じです。中生代の地球の重力が小さかったという事実は存在しません(ちなみに生命発生以降の地球のサイズや直径に変化はありません)。
(瀬戸口烈司 京都大学名誉教授)
Q30:大昔の生物が化石となって見つかりますが、大洪水によって埋まったものですか?
A:化石となる場所は、いろんなところにあります。
地層が堆積しているところに生物の遺骸が運ばれてくると、その生物の体が化石となって残ります。大洪水によって生物の遺骸が運搬されることもありますでしょうが、洪水でなくとも運搬されます。化石となる場所は、いろんなところにあります。
(瀬戸口烈司 京都大学名誉教授)
Q31:グランドキャニオンとノアの大洪水は関係するの?
A:まったく関係はありません。
ノアの洪水というのは、キリスト教の聖書に出てくる概念で、実際におこった現象ではありません。グランドキャニオンの形成とノアの洪水はまったく関係はありません。
(瀬戸口烈司 京都大学名誉教授)
Q32:日本近海にメタンがあるそうですが,海底を掘ることでプレート境界を刺激 して巨大地震が起きませんか?
A: 全く問題ありません(地震発生とメタンハイドレート掘削の間には因果関係はありません)
日本周辺の海底にはメタンハイドレート(包接化合物といいます)というシャーベット状のメタンが,海底から深さ数百m程度の浅い地層のなかに大量に存在する事が知られるようになってきました.一方,プレート境界の巨大地震発生帯は海底から深さ7〜60km程度のはるかに深いところにあります.したがって、地震発生とメタンハイドレートの掘削は全く関係ありません。日本列島の陸上にも多数の活断層があり,地下には多数の地震発生帯が存在すると考えられていますが、地表近くで地下開発(地下街,地下鉄,トンネル,井戸,温泉,地熱,炭鉱,坑道など)が行われてきましたが、そのことによって 活断層が活性化して大きな地震が起きたということはありません.活断層は,私たちの活動に関係なく,何百万年も前から黙々とエネルギーの蓄積と地震発生というサイクルを延々と繰り返し続けています.掘削の物理的影響など全く心配する事はないでしょう。
(坂口有人 広報委員会)
地質学露頭紹介_もくじ
地質学露頭紹介
2021年名古屋大会(オンライン)にて,多くの人に見てほしい,知ってほしい,議論したい露頭の写真を持ち寄り,その地質学的意味について解説・議論するイベントを開催しました.参加者の選りすぐりの露頭紹介をお楽しみください.
なお,今回の企画が好評だったことから,今後も開催したいと考えています.次回はより多くの方から露頭紹介していただけることを期待しています.
(2021.10.25 行事委員長 星 博幸)
※クリックするとそれぞれの露頭紹介と画像をご覧いただけます.
2022年5月29日開催(JpGU2022共同開催)
詳しくはこちらから(YouTubeライブ配信もあります)
2021年9月5日開催(第128年学術大会:名古屋オンライン大会)
中央構造線活断層系 川上断層の露頭:窪田安打(応用地質)
変形構造から読み解くテクトニクス:竹下 徹(北海道大)
関東山地北部秩父帯の褶曲と変成縞:清水以知子(京都大)
蛇紋岩メランジュの蛇紋岩露頭:辻森 樹(東北大)
Wawaの縞状鉄鉱層:大久保英彦(スターミネラルズジャパン)
アイスランドの溶岩断面:星 博幸(愛知教育大)
香川県庄内半島に見られる花崗岩境界:下岡和也(愛媛大)
河川堆積物に見られるHCSのような構造:小松原純子(産総研)
見学や試料採取を行う場合,各自の責任において地権者や関係官庁への連絡と許可の取得の必要があることにご注意下さい.詳しくは,以下のサイトをご覧ください.
http://www.geosociety.jp/publication/content0073.html
(一般社団法人日本地質学会)
地質災害Q&A
地球なんでもQ&A
注:これは地質学会としての統一見解ではなく、読者の理解の一助としてインターネット委員会が整備したものです
地質災害
Q1:活断層と普通の断層は何が違うのですか?
A:新しい時代に活動したものが活断層です
日本のような変動帯では,断層はいくつもの地質時代を通して形成されてきました.私たちは,崖の断面で地層のくい違いとして,断層をみることができます. なかでも最も新しい時代の第四紀(約180万年前以降)に繰り返し活動した断層は,将来も活動する可能性が大きいので,活断層とよばれています.日本の内陸部の活断層は,大部分が数百年から数千年に1回ぐらい間欠的に活動して地震を起こしています.活断層の一度に動く長さが長いほど,大きな地震が発生します。
(リーフレットシリーズ「大地の動きを知ろう—地震・活断層・地震災害—」より)
Q2:活断層はなぜ危険なの?
A:将来、大きな地震が直下で起きるからです。
台湾チェルンプ断層の写真。1999年9月の台湾中部地震で起きた集集地震(M=7.3)の時に活動したチェルンプ断層の写真。断層は川を横切って写真右側が約10mも隆起したため、橋は切断され、川に滝ができました。
地震は、断層が動くことによって生じます。でも、全ての地震で地表の活断層が動くわけではありません。比較的震源が浅く(10km以浅)、地震の規模がマグニチュード5以上の時にだけ、地表に出現します。つまり、活断層があると言うことは、震源が浅く、マグニチュードの大きな地震が起きたことを意味しているのです[1]。
また、断層にはいろいろあり、大昔は活動していたけれども、もはや死んでしまった断層もたくさんあります。地震は地殻に力がかかって、歪が生じて、限界に達すると断層が破壊することで生じます。そのため地殻にかかる力の大きさや向き、地殻の構造や性質といったものによって、どの断層が動くのかが決まります。この地殻にかかる力や構造といったものは、何1000万年という長い地質的時間のうちには、ゆっくりと変化しますが、ここ数100万年くらいの間では、ほとんど変わりません。そのためここ数100万年間のうちに動いたことのある断層は、今後また活動する可能性があります。 ですから、活断層があるということは、震源が浅く、比較的大きな地震が、将来繰り返し起きる可能性があることを意味します[2]。
(坂口有人 海洋研究開発機構)
引用文献
[1] 活断層研究会編. 新編日本の活断層分布図と資料. 東京大学出版会, pp. 440, 1991.
[2] 松田時彦. 活断層. 岩波書店. pp. 242, 1995.
Q3:新潟県中越地震(2006年)で大きな被害を受けた山古志村の地盤はどのような地層からなっているの?
A:地層はただいま変形中
山古志村は新潟県中越地方,東山丘陵(北魚沼丘陵)にあります. 山古志村は,700万年前〜100万年前(新生代中新世〜更新世)の海や陸上でたまった厚い地層でできています。下部は,河川によって陸上でたまった地層(河川成)と海成の地層が半々で、上部になると河川成の地層ばかりになり、次第に浅くなり、陸地になっていった様子が記録されています. 山古志村の地層は地殻変動により褶曲(しゅうきょく:地層が波打って曲がること)が現在進行中です.これを活褶曲といいます.魚沼丘陵は,活褶曲で有名な地域です.河川の浸食の具合によって,地表に露出する地層が違い,尾根には若い地層,谷底ほど古い地層が分布しています. 詳しくはこちら。
(竹内 圭史 産総研 新潟県中越地震(2006年)地質災害調査報告より抜粋)
Q4:史上最大の地震はなんですか?
A:1960年のチリ地震です。
チリ地震は近代的な地震観測が行われるようになって以来最大の地震でマグニチュード(Mw)は9.5でした。これは1923年の関東大震災(M=7.9)、1946年の南海地震(Mw=8.0)[1]、1995年の阪神大震災(Mw=6.9)、2005年の中越地震(Mw=6.6)よりもはるかに大きく、2005年のインド洋大津波のスマトラ島沖地震(Mw=9.0)[2]よりもまだ大きいのです[1]。チリ地震は、それまでの約100年弱の間に地球表層から放出された全地震エネルギーの約1/4をたった1回の地震で占めるほどの大きさでした[3]。震源はチリ海溝の比較的浅い所だったため、巨大な津波が発生し、それは約半日かかってハワイを、そして太平洋を越えて約1日後には、地球の裏側から日本に到達し日本列島の太平洋沿岸にたいへんな被害をもたらしました。
(坂口有人 海洋研究開発機構)
引用文献
[1] 佐藤良輔鮑編. 日本の地震断層パラメータ・ハンドブック, 鹿島出版, pp. 390. 1989.
[2] 東京大学地震研究所ホームページEIC地震学ノート(http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/sanchu/Seismo_Note/)
[3] C.H.ショルツ著, 柳谷 俊訳. 地震と断層の力学, 古今書院, pp. 506, 1993.
Q5:地すべりはどのような原因で起こるのですか?
A: 発生しやすい素因がある斜面に,地下水の上昇などが誘因して起きます.
地すべりが発生するメカニズムは2つの原因があります. 1つは地形や地質,地下の状態(地層の傾きや風化の度合い,断層の有無,地下水など)が地すべりを発生させる条件が整っている(素因と言います)ところです. もう1つは,地すべりを発生させる引き金で,自然現象(梅雨の長雨,雪どけ水,台風などの集中豪雨,地震など)や斜面を掘削したりあるいは土を盛ったり,トンネルの掘削,ダムに水を貯めるなど人為的誘因によって発生します. すなわち,地すべりが発生しやすい地質的条件などの素因がある斜面に,地下水の上昇や地震力などが誘因となって起こります.地震による地すべりを除いて,地すべりが発生する直前には斜面に割れ目ができたり,小さな崩壊が発生したり,湧水が濁るなどの前兆現象が発生することがあります.特に,大雨があったあとや雪どけ水が大量に発生したときなどは注意が必要です.
(上砂正一 明治コンサルタント(株))
Q6:土石流って何ですか?
A:大量の土砂と水が津波のように一気に流れていく現象です
集中豪雨,長雨で山腹の一部が崩壊すると大量の土砂と水が渓流に流れ込み,川底の土石とともに津波のように一気に下流へと流れていく現象です. 土石流の先頭の部分は,大きな岩や流木などが集まってもり上がっています.土石流の速さは,規模,斜面の傾斜によって異なりますが,時速20〜40km の速度になります.土石流は大きな運動のエネルギーを持っているため,土石流の通り道にあたるところは一瞬にして建物や畑を破壊してしまいます. 一般的に,土石流は集中豪雨が原因で起こりますが,地震や地すべりでくずれた土砂が川に流れ込んだり、雪どけ水が土砂とまじったりして起こることもあります.また,雲仙普賢岳に見られたように,火山の噴火でつもった火山灰に雨がふって起こる土石流もあります.
(上砂正一 明治コンサルタント (株))
Q7:地盤沈下はなぜ起きるの?
A:地下水を汲み上げすぎると沈下します。
地下には地下水が多く含まれる層があります。そこには砂や砂利の隙間に水が詰まってて、上の地盤の重さによって高い水圧が生じていることもよくあります。そんな地層にボーリング掘削すると高い水圧によって地下水がこんこんと湧き出してきます。でも、これをくみ上げすぎると、地下の水は減ってしまいます。地下水は上からの重さを支えていたので水圧が高かったのです。その水がなくなったら、重さを支えることができなくなり、砂や砂利の隙間は押しつぶされます。ひとつひとつの隙間は小さいですが、これが多量に失われると、ついには地面が窪んでしまいます。これが地盤沈下です。
(坂口有人 海洋研究開発機構)
Q8:津波によって数十トンの石が動くって本当?
A:本当です.
タイ・カオラックの海岸に堆積している,2004年インド洋大津波によって運搬された巨礫(津波石).
例えば,2004年インド洋大津波によって,タイのカオラックという場所で重さ約〜20トン,直径〜4mの巨礫が数百m内陸に運搬されたことが明らかになっています.同じような巨礫(日本では津波石と呼ばれています)は,日本の石垣島の宮良湾でも見ることができ,古文書記録によれば1771年に起きた明和津波によって運搬されたとされています.最近,世界中の津波リスクが高い国(例えば,アメリカ,ポルトガル,オーストラリア,プエルトリコなど)の沿岸域に同様の巨礫が存在することが相次いで報告されています.巨大岩塊は,大きな津波外力によってのみ移動し,さらに堆積後に人為的に移動されることが少ないので,長期間その場に存在すると考えられます.そのため,過去の津波による痕跡として比較的同定しやすいのが特徴です.しかも,岩塊移動は作用力と軌跡の関係が比較的単純なため,岩塊の移動量から作用力や流速を推定することが可能です。
(東北大学 後藤和久)
引用文献:
後藤和久,S. A. Chavanich,今村文彦,P. Kunthasap,松井孝典,箕浦幸治,菅原大助,柳澤英明,2006, 2004年インド洋大津波によって運搬された”津波石”の起源.月刊地球.Vol. 326, 28, 553-557.
今村文彦,後藤和久, 2007,過去の災害を復元し将来を予測するためのアプローチ-津波研究を事例に-.第四紀研究. (印刷中).
Q9:盛土地盤はどんなところ?
A:人工的に低地や谷を埋め立てた地盤で,地震の時には被害を受けることがあります.
湿地や沼地に土を入れて埋め立てて,住宅地や道路などにした地盤を盛土地盤と呼びます.市街地近郊での宅地開発では,田んぼに土を入れて造成したり,丘陵部の斜面で平らな宅地を作るために,斜面を切り取ったり(切土)土を盛り上げたりするため,結果として多くの盛土地盤が形成されています.また,道路を作るときに横断する谷の部分に土を盛り上げることがあり,道路も盛土の部分が多く見られます.
通常時は特に低地の粘土質な地盤を埋め立てた宅地や道路では不同沈下が起こる可能性があり,地震時はこれに加えて,大きな震動によって盛土部分が崩壊するなどの被害が起こります.
盛土をした宅地の被害は,1978年の宮城県沖地震の際に丘陵部の造成地で多くみられ,以後,1995年の兵庫県南部地震や2004年の新潟県中越地震においても繰り返し発生しました.また,中越地震では山間部を通過する道路の盛土部分で大きな崩壊が多発し,集落が孤立する原因ともなりました.
こうした盛土の部分は,造成や道路が作られる前の地形と比較すると比較的容易に見つけることができます.自分の生活するまわりの地形や地質環境を知り,被害を受けないよう対策をする必要があります.なお,盛土した宅地については2007年に大規模地震時の宅地の耐震性確保のため.宅地造成等規制法が改正され,崩落のおそれのある大規模盛土造成地の耐震性を向上させ,宅地被害の予防を図る新たな取組が始まりました.
(新潟大学 卜部厚司)
宅地盛土の崩壊(2004年新潟県中越地震:卜部厚志撮影)
Q10:液状化でビルが傾く?
A:液状化の対策が十分でないビルや家は傾くことがあります.
沖積層や埋立地などの軟らかい砂の地盤では,普段は砂粒子同士が引っ掛かりながら支えあい,上に載る家やビルの荷重を支えています.しかし,地震が発生するとその引っ掛かりがはずれてしまい,砂粒子はより密な状態になろうとします.このとき,砂粒子が地下水で満たされていると,粒子の隙間の水圧(間隙水圧)が高まり,砂粒子が浮き上がった状態になって,自由に移動できるようになります.この現象が液状化です.間隙水圧が高くなった状態では,より上位の地層や家やビルなどの重さを支えられなくなり,家やビルが沈下したり,砂混じりの水を大量に噴き上げたり(噴砂現象)します.
液状化は,地下水位が高く,粒径 0.1mm〜1.0mm程度の砂を多く含む地盤で,経験的には震度5程度以上の地震の揺れを受けたときに発生することがあります.また,より細かい粒子や礫を含んでいる場合でも起こることがあるので注意が必要です.
液状化は,1964年の新潟地震の際に広い地域で発生し,当時の新潟市街部では道路の亀裂,橋の落下,ビルの倒壊や川岸が川の中に大きくせり出す現象(側方流動)などが起こり注目されました.その後,この地震をきっかけとして多くの研究や対策方法の検討が行われてきました.液状化はその後の各地の地震でもおこり,地盤や構造物の沈下,マンホールの浮き上がり,道路の崩壊,港湾施設沈下などの被害を繰り返してきました.また,古い時代の液状化は,さまざまな時代の遺跡でもみられます.遺跡の調査では,遺物による年代の編年や地層の年代測定によって液状化の編年を行うことができるので,過去の活断層の活動履歴を探る手がかりにもされています.
液状化の発生を予測して災害を軽減するためには,もとの地形(沼地や川の跡)や地層の形成された様子を知り,地層(地盤)をよく調べることが重要です.
(新潟大学 卜部厚司)
液状化によって傾いたビル(1964年新潟地震:若林茂敬氏撮影)
液状化によって落下した橋(1964年新潟地震:若林茂敬氏撮影)
Q11:地層の断面をみることができる?
A:物理探査と呼ばれる方法で,地層の断面をみることができます.
山地や平野の地質構造の断面は,岩石の露出する崖や川での野外地質調査やボーリング調査などの情報によって,直接見えない部分を推定しながら描くことができます.これに対して,人工的な小さい地震などを使って物理的に地下の地層の様子を探り,断面図を描く方法があります.野外調査やボーリング調査に加えて,物理探査と呼ばれる方法を用いるとより詳細な地下の地層の様子を明らかにすることができます.
ここでは,石油探査や丘陵・平野部の活断層の調査に用いられることの多い反射法弾性波探査を紹介します.反射法地震探査は,地表の近くで人工的に発生させた振動(弾性波)が,地層境界面(速度と密度が変化する面)で反射して,再び地表へ戻ってきたところを捉え,データ処理をすることにより,地下の速度構造と地質構造形態(地層の重なり具合)を明らかにすることができます.この方法では,調査対象の深度によって発生させる地震動(P波・S波,震源装置の違い)や受信する仕様(受信する間隔や記録数)を変えることにより,陸上や湖底,海底の地層のさまざまな深さまでの地層を調べることができます.近年の技術では,陸上の探査で深さ5〜6km程度までを調査することができ,石油などの資源探査に加え,内陸での地震発生を探るための大規模な調査が行われています.地質学と組み合わせることにより,より詳細な地質構造やその形成過程が明らかにされようとしています.
(新潟大学 卜部厚司)
Q12:GPSで日本の動きがわかる?
A:高精度のGPS観測網が作られ,日本列島の各地点の動きがわかるようになっています.
GPS衛星は高度2万kmに6つの軌道を持ち,24個の衛星(6軌道×4個)が地球を周回しています.GPSの技術は,現在はカーナビや携帯電話にも使われ小型化と高精度化が進められています.
このGPSの技術を地殻変動の観測に応用するため,国土地理院によって日本全国にGPSの観測網(電子基準点)が整備され,各地点の動きが連続的に観測できるようになりました.この技術による地殻変動観測の成果として,新潟から神戸にかけてひずみが集中していることがわかりました(ひずみ集中帯:Sagiya et al., 2000など).このひずみ集中帯は,海洋プレートの沈み込みによる横方向の圧縮力とその他のプレートから受ける圧縮力も加わってこのような地殻変動が生じていると考えられています.また,このひずみ集中帯では,1995年の兵庫県南部地震,2004年の新潟県中越地震,2007年の新潟県中越沖地震など,過去200年程間に発生した内陸大地震の多くが発生していたことから,ひずみ集中と大地震発生の間に深いつながりがあるものと考えられています.
(新潟大学 卜部厚司)
文献
Sagiya, T., S. Miyazaki, and T. Tada,2000,Continuous GPS Array and Present-day Crustal Deformation of Japan, PAGEOPH, 157, 2303-2322.
geo-flash No.289 プレスリリース「地学の知識を減災のソフトパワーに」!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.289 2015/3/3 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[長野大会]トピックセッションの募集
【2】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(火
【3】中期ビジョン中間報告と意見募集
【4】プレスリリース「地学の知識を減災のソフトパワーに—東日本大震災4年目を迎えて—」
【5】Island Arc からのお知らせ
【6】「理科好きな子に育つ ふしぎのお話365」会員特別割引販売のお知らせ
【7】2015年度春季地質調査研修 参加者募集[受付開始!]
【8】地質の日イベント情報
【9】第35回万国地質学会議(IGC)ほかのご案内
【10】支部情報
【11】その他のお知らせ
【12】公募情報・各賞情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[長野大会]トピックセッションの募集
──────────────────────────────────
日本地質学会行事委員会
第122年学術大会(長野大会)は,中部支部のご協力のもと,信州大学工学部(長野市)をメイン会場として2015年9月11日(金)〜13日(日)に開催されます.
現在,トピックセッションを募集中です.
なお,本大会も前回同様,シンポジウムの一般募集はありません.
※シンポジウムは長野大会実行委員会および学会執行部が企画します.
募集締切:3月16日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0066.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(火)
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は3月31日(火)です.
次年度も割引会費を希望のかたは,忘れずにご提出ください(締切厳守).
※通常の会費払込については,「2015年会費払い込みについて」を参照下さい.
■ 自動引落による納入
昨年12月24日(水)にお届けの金融機関口座より引き落としさせていただきました.通帳記帳等でご確認ください.請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承ください.
■ 郵便振替用紙(またはゆうちょ銀行口座)からのお振り込み2014年12月15日(月)に請求書兼郵便振替用紙を発送しました.地質学会の会費は前納制ですので,お早めにご送金ください.
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/outline/content0135.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】中期ビジョン中間報告と意見募集
──────────────────────────────────
中期ビジョンワーキンググループがこれまでに検討した素案を掲載しています.ご意見,ご助言などをぜひお寄せ下さいますようお願いいたします.
中間報告はこちらから▼▼
http://www.geosociety.jp/outline/content0148.html [後編追加]
意見募集締切:3月15日(日)
送付先:地質学会事務局(main@geosociety.jp)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】プレスリリース「地学の知識を減災のソフトパワーに—東日本大震災4年目を迎えて—」
──────────────────────────────────
東日本大震災から早くも4年目を迎えようとしています.あのような被害を二度と起こさせないためにも,地質学会として標記の声明を発表(プレスリリース)いたしました.地質学の知識が,防災・減災に実際に役立つことを学会としては願ってやみません.
全文はこちらから
http://www.geosociety.jp/engineer/content0040.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■最新号24-1号がオンライン出版されました
通常,無料閲覧は,会員ページにログインしていただいてからとなりますが本号は無料オンライン見本誌となっておりますので,直接ご覧いただけます.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iar.2015.24.issue-1/issuetoc
■日本語要旨掲載ページ
http://www.geosociety.jp/publication/content0084.html
その他の号も,学会webサイトから無料で閲覧出来ます.
ログイン方法はこちらから
https://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】「理科好きな子に育つ ふしぎのお話365」会員特別割引販売のお知らせ
──────────────────────────────────
地質学会も加盟する自然史学会連合監修の書籍が出版されました.
「理科好きな子に育つ ふしぎのお話365」(240×190mm 392頁)
自然史学会連合監修 誠文堂新光社
定価2300円+税→会員特別割引価格1725円+税に.
(※ 9冊以下の場合別途送料が必要.注文用紙参照)
専用注文用紙は,下記学会HP会員のページをご覧下さい.
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】2015年度春季地質調査研修 参加者募集[受付開始!]
──────────────────────────────────
地質調査法の基本技術の修得をめざすとともに,それをベースに得られた過去の調査や研究の成果についても学びます.地質調査の経験のない方でも,地質調査法の基本を体で習得することを目指します.
5月18日(月)〜5月22日(金)4泊5日
研修場所:千葉県君津市及びその周辺地域(房総半島中部域)
募集人数:6名. 参加費:12万円 (CPD:40単位)
募集締切:4月13日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/engineer/content0039.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】地質の日イベント情報
──────────────────────────────────
■近畿支部
第32回地球科学講演会「阪神淡路大震災以降の近畿の活断層研究」
5月10日(日)13:30〜15:30 (受付:12:30〜)
場所:大阪市立自然史博物館 講堂
講師:岡田篤正氏(京都大学名誉教授・立命館大学客員研究員)
定員:250名(先着順)申込不要/参加費無料(博物館入館料必要)
問い合わせ先:大阪市立自然史博物館
TEL: 06-6697-6221 FAX: 06-6697-6225
E-mail: monitor@mus-nh.city.osaka.jp
地質の日イベントの各詳細はこちらから.
http://www.geosociety.jp/name/content0128.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】第35回万国地質学会議(IGC)ほかのご案内
──────────────────────────────────
小川 勇二郎(会員,国際地質科学連合理事)
かねてからご案内の通り,第35回万国地質学会議(IGC; http://www.iugs.org)は,2016年8月27日〜9月4日に南アフリカ共和国のケープタウンの国際コンベンションセンターで開催されるが(http://www.35igc.org/),その準備状況が,本年1月の国際地質科学連合(IUGS)理事会で説明された.主たるテーマは,以下の3つである.
Geoscience for society, Fundamental geoscience, Geoscience in the economy....
続きはこちらから
http://www.geosociety.jp/faq/content0550.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】支部情報
──────────────────────────────────
[東北支部 ]
■2014年度東北支部総会・講演会・シンポジウム
3月7日(土)〜8日(日)
7日(土)13:00〜シンポジウム「東北地方のテクトニクス」,18:00〜懇親会.
8日(日)9:00〜総会・個人講演・ポスター発表コアタイム,15:00頃終了予定
場所:岩手大学工学部(盛岡市上田)
CPD単位あり(当日参加証明書を会場にて希望者に配布予定).
例)・ポスター発表:2単位
・口頭発表:0.4×分(15分の場合:6単位)
問い合わせ先:
支部長:土谷信高 tsuchiya@iwate-u.ac.jp
幹事:越谷 信 koshiya@iwate-u.ac.jp
プログラムの詳細等はこちらから
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
[関東支部 ]
■地学教育サミット・ジオパークと教育〜楽しく元気に大地の公園〜
3月15日(日)10:00〜16:00
場所:神奈川県小田原市生涯学習センター けやき 大会議室
参加費無料,資料代別途1,500円
申込不要.ただし資料準備のため,できるだけ事前連絡を.[3月5日(木)締切]
問合せ先:関東支部幹事長 笠間友博 kasama@nh.kanagawa-museum.jp
■2015年度総会・地質技術伝承講演会
4月18日(土)14:00〜16:45(13:30受付)
場所:北とぴあ 7階 第1研修室(東京都北区王子1-11-1)
14:00〜15:40地質技術伝承講演会[参加費無料,CPD単位(2.0)]
申込・問い合わせ:加藤 潔 kiyoshi.katoh@gmail.com
15:50〜16:45関東支部総会
*支部会員の方で総会へ欠席の方は,委任状をお送り下さい.
関東支部 kanto@geosociety.jp[4月17日(金)午後6時締切]
各行事の詳細,委任状等はこちらから
http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■電中研ニュースNo. 478
http://criepi.denken.or.jp/research/news/index.html?m=150218
■平成27年度技術士試験について
○技術士第一次試験
https://www.engineer.or.jp/c_topics/003/003662.html
申込書配布:6月1日(月)〜7月1日(水)
申込受付期間:6月16日(火)〜7月1日(水)
筆記試験日:10月12日(月・祝)
○技術士第二次試験
https://www.engineer.or.jp/c_topics/003/003660.html
申込書配布:4月1日(水)〜4月27日(月)
申込受付期間:4月6日(月)〜4月27日(月)
筆記試験日:
[総合技術管理部門必須科目]7月19日(日)
[上記部門の選択科目,上記部門を除く技術部門]7月20日(月・祝)
■学術フォーラム「科学を変えるデータジャーナル−科学技術データの共有・再利用の新たなプラットフォーム構築に向けて−」
3月4日(水)10:30〜17:30
場所:日本学術会議講堂
定員:当日先着順300名,事前登録なし
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/208-s-0304.pdf
■Project A 2015 in Korea
日本地質学会ほか 後援
3月4日(水)〜8日(日)
4日オープニング,5日セッション,6〜8日巡検
会場:韓国(大田広域市)
http://archean.jp/
■第4回学生のヒマラヤ野外実習ツアー
日本地質学会等推薦
3月上旬(4日頃)出発,出国から帰国まで15日間
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
■講演会「本邦新生代層序の発展 ー微化石層序学と地質学ー」
3月20日(金)13:30〜17:00
主催:産総研地質情報研究部門
会場:産総研共用講堂1階中会議室
参加登録不要
(ただしCPD希望者はジオスクーリングネットより要申込[3単位])
https://unit.aist.go.jp/igg/ci/update/20150320sympo.pdf
■第172回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
3月27日(金)18:30〜20:30 [事前予約不要]
場所:北とぴあ901会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分)
講師 :高橋正樹氏(日本大学文理学部地球システム科学科 教授)
テーマ :箱根火山の噴火と首都圏都市災害
—もし東京軽石規模の大規模噴火が起こってしまったら—
CPD:2単位
会費:会員,地質学会会員は500円,非会員は1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■日本堆積学会2015年つくば大会
4月24日(金)〜27日(月)
会場:筑波大学大学会館(茨城県つくば市天王台1-1-1)
24日(金):ショートコース
25日(土)・26日(日):個人講演,特別講演ほか
27日(月):日帰り巡検
講演申込・要旨提出・印刷版要旨集購入申込締切:3月13日(金)
(ショートコース,巡検は受付終了)
http://sediment.jp/04nennkai/2015/annai.html
■第52回アイソトープ・放射線研究発表会
日本地質学会ほか 共催
7月8日(水)〜10日(金)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1)
発表申込締切:2月27日(金)
講演要旨原稿締切 :4月10日(金)
http://www.jrias.or.jp/
■第13回微量元素の生物地球化学に関する国際会議
13th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements, ICOBTE 2015 FUKUOKA
日本地質学会 後援
7月12日(日)〜16日(木)
場所:福岡国際会議場
http://www.icobte2015.org/index.html
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
7月27日(月)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1-1)
早期参加登録締切:3月15日(日)まで延長
通常参加登録締切:6月30日(火)
http://inqua2015.jp/
■日本ジオパークネットワークガイドフォーラム
9月15日(火)〜16日(水)
会場:アミティ丹後(京都府京丹後市網野町網野367)
バーチャルジオツアー発表者応募締切:5月29日(金)
参加登録締切:7月31日(金)
http://jgn2015.com/
■第4回アジア太平洋ジオパークネットワーク山陰海岸シンポジウム
日本地質学会ほか 後援
9月16日(水)〜20日(日)
会場:豊岡市民会館(豊岡市立野町20-34)ほか
発表要旨締切:4月30日(木)
早期参加登録締切:4月30日(木)
通常参加登録締切:7月31日(金)
http://apgn2015-jpn.com/
■第10回アジア地域応用地質学シンポジウム
日本地質学会 後援
研究発表会:9月24日(木)〜25日(金)
シンポジウム:9月26日(土)〜27日(日)[その後巡検予定あり]
場所:京都大学宇治黄檗プラザ
http://2015ars.com/
■Arthur Holmes Meeting Tsunami Hazards and Risks: Using the Geological Record
日本地質学会 共催
9月25日(金)
場所:The Geological Society(英・ロンドン)
プレ巡検:9月22日(火)〜23日(水)
http://www.geolsoc.org.uk/ahm15
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0144.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■平成28年度 科学警察研究所:総合職研究職員(4/1〜4/8:国家公務員採用試験)
<業務説明会:霞が関OPENゼミ2015(3/5開催)>
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.004 2007.07/19 geo-Flach
No.004 2007/07/19
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬【geo-Flash】日本地質学会メールマガジン ┴┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.006 2007/08/21 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】新潟県中越沖地震速報
【2】新潟県中越沖地震緊急展示@札幌大会 要旨受付開始
【3】公募情報(横浜国立大学 助教)
【4】ワークショップ申し込み締切延長のお知らせ
【5】国際陸上科学掘削計画(ICDP)に注目!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 新潟県中越沖地震速報
──────────────────────────────────
■新潟大学調査団が緊急調査を開始しています。
http://geo.sc.niigata-u.ac.jp/~070716/
■金沢大学現地調査団
20日から現地被害状況調査を開始します。
■信州大学調査団
今週末より調査開始予定です。
■産業技術総合研究所は緊急現地速報を更新しています。
http://www.gsj.jp/jishin/niigata_070716/index.html
■海洋研究開発機構が遠地実体波を用いた震源破壊過程の解析結果を
報告しています。
http://www.jamstec.go.jp/jamstec-j/maritec/donet/chuetu0707/index.html
その他、会員の方で緊急調査を行っている方、あるいはご予定の方は、
学会事務局までご連絡願います。
ページTOPにもどる
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】 新潟県中越沖地震に関する緊急展示開催 @札幌大会
──────────────────────────────────
講演申し込み終了後、台風4号や新潟県中越沖地震による災害が発生し、
多くの地質学会会員が現場で調査を行っています。
学会活動の一端を広く社会に紹介するとともに、ホットなテーマについて
議論する場を提供するために、災害報告や社会的に影響のある新技術紹介などの
「緊急展示コーナー」を設けます。
ポスター展示を希望する方は、8月23日までに以下の内容で下記の実行委員会にご連絡ください。
1)発表要旨PDF(ニュース誌5月号P12参照) 2)緊急展示の必要性
3)発表代表者と連絡先 4)展示に関わる要望 (2)から4)の様式は自由)
実行委員会は行事委員会と協議し、可否の判断を致します。
希望にはできるだけ応えるようにしますが、
展示方法等については実行委員会の指示に従ってください。
申込先 札幌大会実行委員会 前田仁一郎
メール jinmaeda@mail.sci.hokudai.ac.jp
札幌大会HP http://www.ep.sci.hokudai.ac.jp/~mmgc/GSJ-Sapporo2007/
ページTOPにもどる
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】 公募情報 横浜国立大学
──────────────────────────────────
国立大学法人横浜国立大学では、地球惑星科学分野の特任教員(助教)を
公募しています。詳しくは、、、
http://www.ynu.ac.jp/jinji/jin65.html (日)
http://www.ynu.ac.jp/jinji/jin65_E.html (英)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】 ワークショップ参加申し込み 延期のお知らせ
──────────────────────────────────
Subduction Factory Studies in the Izu-Bonin-Mariana Arc System
Workshop Application DEADLINE EXTENDED to July 22
date: Nov. 7-10, 2007
place: Honolulu, HI
詳しくは、
http://www.nsf-margins.org/IBM07
ページTOPにもどる
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】国際陸上科学掘削計画(ICDP)に注目!
──────────────────────────────────
詳細は・・・・こちら
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3週)配信予定です。原稿は第2・4週金曜日まで
にお送りください。geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
geo-Flash 地質学会メールマガジン
geo-Flash! 日本地質学会公式メールマガジン
geo-Flash(ジオフラッシュ)は、学会活動の改善の一環として、地質学に関わるあるいは学界活動に関する情報をいち早く会員の皆様にお届けすることを目的として発足いたしました。会員の皆様からの情報も積極的に載せていく予定ですので、大いにご活用いただきますようお願い申し上げます。
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬【geo-Flash】日本地質学会メールマガジン ┴┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.001 Since 2007/07/3 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
No.665 2026年度代議員および役員選挙について(告示)
【1】2026年度代議員および役員選挙について(告示)
【2】2026年度学会各賞候補者募集
【3】[2025熊本大会]領収書について
【4】JpGU2026セッション提案募集(地質学会共催)
【5】支部のお知らせ
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
No.664 熊本大会始まりました
【1】熊本大会の様子 熊本大会が始まったんだもん!
No.663 今年は選挙の年です!
【1】今年は選挙の年です!
【2】[2025熊本大会]まもなく講演要旨が公開となります
【3】[2025熊本大会]領収書について
【4】[2025熊本大会]「会員カード」持参して下さい
【5】[2025熊本大会]学生事前予約受付中:地質系業界説明会
【6】[2025熊本大会]学生・若手のための交流会
【7】若手巡検 in 長瀞・皆野地域
【8】Island Arc からのお知らせ
【9】支部のお知らせ
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
【12】災害に関連した会費の特別措置
No.662 (臨時)[2025熊本大会]講演プログラム公開
【1】[2025熊本大会]講演プログラムが公開になりました
【2】[2025熊本大会]事前参加登録はお済みですか?
【3】[2025熊本大会]巡検の催行可否について
【4】[2025熊本大会]緊急展示 受付中
【5】[2025熊本大会]地質系業界説明会:学生参加申込受付中
No.661[2025熊本大会]緊急展示 受付中
【1】[2025熊本大会]事前参加登録はお済みですか?
【2】[2025熊本大会]巡検の催行可否について
【3】[2025熊本大会]緊急展示 受付中
【4】[2025熊本大会]その他の情報
【5】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【6】新刊『大地と人の物語』会員特別販売キャンペーン(8/25まで)
【7】支部のお知らせ
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】災害に関連した会費の特別措置
No.660 2025/8/5[2025熊本大会]巡検申込はお早めに!
【1】[2025熊本大会]全体日程表が公開になっています
【2】[2025熊本大会]巡検も申込受付:まもなく締切です
【3】[2025熊本大会]緊急展示 受付中
【4】[2025熊本大会]その他の情報
【5】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【6】新刊『大地と人の物語』会員特別販売キャンペーン実施中
【7】支部のお知らせ
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.659 2025/7/15[2025熊本大会]巡検申込はお早めに!
【1】[2025熊本大会]大会参加登録受付中
【2】[2025熊本大会]巡検も申込受付中
【3】[2025熊本大会]各種申込を受付中
【4】[2025熊本大会]その他の情報
【5】紹介:漫画・アニメ「瑠璃の宝石」を応援しよう!
【6】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【7】支部のお知らせ
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.658 2025/7/8(臨時)[2025熊本大会]講演申込は明日7/9締切です!
【1】[2025熊本大会]講演申込は明日7/9締切です!
【2】[2025熊本大会]大会参加登録受付中です
【3】[2025熊本大会]巡検9コース実施します
【4】[2025熊本大会]2025年度学生のための地質系業界説明会
【5】[2025熊本大会]その他各種申込受付中です
No.657 2025/7/1 [2025熊本大会]大会参加登録受付開始です
【1】[2025熊本大会]大会参加登録受付開始です
【2】[2025熊本大会]巡検9コース実施します
【3】[2025熊本大会]各種申込を受付中
【4】2025年度会費督促請求に関するお知らせ
【5】新刊紹介『大地と人の物語−地質学でよみとく日本の伝承』
【6】Island Arc からのお知らせ
【7】支部のお知らせ
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】訃報:Richard S. Fiske氏 逝去
No.656 2025/6/17[2025熊本大会]各種申込を受付中です!
【1】[2025熊本大会]各種申込を受付中です!
【2】[2025熊本大会]学生のための地質系業界説明会 出展企業団体募集
【3】2025年度会費督促請求に関するお知らせ
【4】Island Arc からのお知らせ
【5】コラム:中教審の答申「知の総和」とレイトスペシャライゼーションへの対応策
【6】支部のお知らせ
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.655 2025/6/3[2025熊本大会]講演申込受付開始
【1】2025年度代議員総会開催について
【2】[2025熊本大会]講演申込受付開始しました
【3】[2025熊本大会]学生のための地質系業界説明会 出展企業団体募集
【4】[2025熊本大会]広告等協賛企業募集
【5】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【6】支部のお知らせ
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.654 2025/5/20[2025熊本大会]講演申込受付をまもなく開始いたします
【1】2025年度代議員総会開催について
【2】[2025熊本大会]講演申込受付をまもなく開始いたします
【3】2025年「地質の日」行事のご案内
【4】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【5】JpGU2025:地質学会共催セッションにぜひご出席ください
【6】支部のお知らせ
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】訃報:植村 武 名誉会員ご逝去
No.653 2025/5/7 2025年度代議員総会開催について
【1】2025年度代議員総会開催について
【2】2025年「地質の日」行事のご案内
【3】2025年度(第3回)日本地質学会研究奨励金採択結果
【4】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【5】意見・提言2025
【6】支部のお知らせ
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】会員情報に変更があった場合は...
No.652 2025/4/15 第16回惑星地球フォトコンテスト審査結果
【1】第16回惑星地球フォトコンテスト 審査結果
【2】2025年「地質の日」行事のご案内
【3】Island Arc からのお知らせ
【4】第5回JABEEシンポジウム:YouTube公開中
【5】支部のお知らせ
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
【8】会員情報に変更があった場合は...
No.651 2025/4/1 2025年「地質の日」行事のご案内
【1】2025年「地質の日」行事のご案内
【2】地質学雑誌 からのお知らせ
【3】支部のお知らせ
【4】その他のお知らせ
【5】公募情報・各賞助成情報等
【6】会員情報に変更があった場合は...
No.650 2025/3/18 (2025年熊本)トピックセッションまもなく締切
【【1】2025年熊本大会 トピックセッション まもなく締切
【2】2025年「地質の日」行事のご案内
【3】Island Arcからのお知らせ
【4】オーサーシップ・二重投稿等に関するアンケート調査への協力依頼
【5】本の紹介「月面フォトアトラス」
【6】支部のお知らせ
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】会員情報に変更があった場合は...
No.649 2025/3/4今年も「地質の日」始まります!
【1】第132年学術大会(2025年熊本)トピックセッション募集中
【2】2025年「地質の日」行事のご案内
【3】Island Arcからのお知らせ
【4】会員の学術・教育・社会貢献活動
【5】支部のお知らせ
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
No.648(臨時) 2025/3/3 訃報:杉村 新 名誉会員
No.647 2025/2/18(2025年熊本)トピックセッション募集中
【1】第132年学術大会(2025年熊本)トピックセッション募集中
【2】若手野外地質研究者向け研究奨励金募集中
【3】第5回JABEEオンラインシンポ
【4】Island Arcからのお知らせ
【5】本の紹介「噴火した! 火山の現場で考えたこと」
【6】支部のお知らせ
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.646 2025/2/4 (2025熊本)トピックセッション募集開始
【1】第132年学術大会(2025年熊本)トピックセッション募集開始
【2】若手野外地質研究者向け研究奨励金募集中
【3】名誉会員候補者の募集が開始されています
【4】第5回JABEEオンラインシンポ
【5】地質系業界オンライン交流会
【6】Island Arcからのお知らせ
【7】支部のお知らせ
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.645 2025/1/21 地質系業界オンライン交流会 開催します!
【1】若手野外地質研究者向け研究奨励金募集中
【2】名誉会員候補者の募集が開始されています
【3】第16回惑星地球フォトコンテスト応募受付中
【4】地質系業界オンライン交流会 開催します!
【5】Island Arcからのお知らせ
【6】支部のお知らせ
【7】JpGU教育検討委員会よりお知らせ
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.644 2025/1/17(臨時) 祝:伊与原 新さん直木賞受賞!
【1】祝:伊与原 新さん直木賞受賞!
No.643 2025/1/7 謹賀新年 年頭の挨拶
【1】年頭の挨拶(会長 山路 敦)
【2】若手野外地質研究者向けに研究奨励金を支給します
【3】第16回惑星地球フォトコンテスト応募受付中
【4】名誉会員候補者の募集が開始されています
【5】TOPIC:ベニオフ以前に深発地震帯逆断層説を唱えた日本人地質学者
【6】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【7】支部のお知らせ
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.642 2024/12/17 学会各賞候補者募集【締切延長!12/20】
【1】2025年度学会各賞候補者募集【締切延長12/20】
【2】若手野外地質研究者向けに研究奨励金を支給します
【3】2025年度の会費払込について
【4】第16回惑星地球フォトコンテスト応募受付中
【5】地質系若者のためのキャリアビジョン誌2024原稿募集中
【6】2027年度の地震火山地質こどもサマースクール開催地候補募集
【7】支部のお知らせ
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】訃報:小西健二 名誉会員ご逝去
No.641 2024/12/3 学会各賞候補者募集【締切延長!12/20】
【1】2025年度学会各賞候補者募集【締切延長12/20】
【2】若手野外地質研究者向けに研究奨励金を支給します
【3】2025年度の会費払込について
【4】第16回惑星地球フォトコンテスト応募受付中
【5】地質系若者のためのキャリアビジョン誌2024原稿募集中
【6】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【7】支部のお知らせ
【8】会員の学術・教育・社会貢献活動
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
No.640 2024/11/19 2025年度学生会費の申請受付中(12/2締切厳守)
【1】2025年度学会各賞候補者募集受付中(12/2締切)
【2】2025年度の会費払込について
【3】2025年度学生会費の申請受付中(12/2締切厳守)
【4】第16回惑星地球フォトコンテスト応募受付中
【5】地質系若者のためのキャリアビジョン誌2024 原稿募集中
【6】Island Arcからのお知らせ
【7】支部のお知らせ
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.639 2024/11/5 惑星地球フォトコンテスト応募受付中
【1】2025年度学会各賞候補者募集受付中
【2】2025年度の会費払込について
【3】2025年度学生会費の申請受付(12/2(月)締切厳守)
【4】第16回惑星地球フォトコンテスト応募受付中
【5】地質系若者のためのキャリアビジョン誌2024 原稿募集中
【6】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【7】支部のお知らせ
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】訃報 佐藤 正名誉会員ご逝去
No.638 2024/10/17(臨時)JpGU2025セッション提案募集(10/29締切)
【1】JpGU2025セッション提案募集(10/29締切)
No.637 2024/10/15 2025年度会費払込/学生会費の申請受付
【1】2025年度学会各賞候補者募集受付中
【2】2025年度の会費払込について
【3】2025年度学生会費の申請受付(12/2(月)締切厳守)
【4】[2024山形大会]10/11より講演要旨無料公開
【5】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【6】支部のお知らせ
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.636 2024/10/10(臨時)ホフマン博士京都賞受賞記念講演会(東京・駒場)
【1】ポール・ホフマン博士京都賞受賞記念講演会(東京・駒場)
【2】ドローン労働安全セミナーのご案内
No.635 2024/10/1 2025年度学会各賞候補者募集受付開始
【1】2025年度学会各賞候補者募集受付開始
【2】[2024山形大会]学生優秀発表賞ほか決定!
【3】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【4】支部のお知らせ
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
No.634 2024/9/19 (臨時)いわゆる「雇い止め問題」についてのアンケート協力依頼
【1】いわゆる「雇い止め問題」についてのアンケート協力依頼
No.633 2024/9/17 若手巡検 in 愛知県-岐阜県(参加申込受付中)
【1】[2024山形大会]学術大会終了しました
【2】若手巡検 in 愛知県-岐阜県(参加申込受付中!)
【3】第17回日本地学オリンピック:参加申込受付中
【4】支部のお知らせ
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
No.632 2024/9/9 [2024山形大会]大会の写真アップしました
【1】山形大会の写真アップしました
No.631 2024/9/3 [2024山形大会]まもなく開幕!山形大会!
【1】[2024山形大会]「参加者個別認証コード」をお知らせしました
【2】[2024山形大会]大会には「会員カード」持参して下さい
【3】[2024山形大会]領収書をダウンロードしてください(9/30まで)
【4】[2024山形大会]巡検案内書続々公開中!
【5】[2024山形大会]学生事前予約受付中:地質系業界説明会
【6】[2024山形大会]学生・若手のための交流会(9/7開催)
【7】若手巡検 in 愛知県-岐阜県(10/26開催)
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.630 2024/8/20 [2024山形大会]緊急展示:申込受付中(8/29締切)
【1】[2024山形大会]緊急展示:申込受付中
【2】[2024山形大会]プログラム公開中
【3】[2024山形大会]まもなく講演要旨が公開となります
【4】[2024山形大会]学生事前予約受付中:地質系業界説明会
【5】[2024山形大会]学生・若手のための交流会(9/7開催)
【6】若手巡検 in 愛知県-岐阜県(10/26開催)
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.629 2024/8/6 [2024山形大会]プログラム公開&巡検締切延長中
【1】[2024山形大会]巡検締切延長中(8/8締切延長)
【2】[2024山形大会]講演プログラム公開
【3】[2024山形大会]緊急展示
【4】[2024山形大会]学生・若手のための交流会(9/7開催)
【5】[2024山形大会]学生事前予約受付中:地質系業界説明会
【6】Island Arc からのお知らせ
【7】地質学雑誌からのお知らせ
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.628 2024/8/3(臨時)[2024山形大会]巡検締切延長!(8/8締切延長)
【1】[2024山形大会]巡検締切延長!(8/8締切延長)
【2】[2024山形大会]全体日程
【3】[2024山形大会]事前参加登録受付中
【4】[2024山形大会]懇親会予約もお早めに!
【5】[2024山形大会]学生・若手のための交流会(9/7開催)
【6】[2024山形大会]学生事前予約受付中:学生のための地質系業界説明会
【7】[2024山形大会]その他
No.627 2024/7/25(臨時)[2024山形大会]巡検申込お早めに!!
【1】[2024山形大会]巡検申込はお早めに!(締切8/1)
【2】[2024山形大会]全体日程が公開されています
【3】[2024山形大会]事前参加登録受付中
【4】[2024山形大会]懇親会予約もお早めに!
【5】[2024山形大会]学生・若手のための交流会(9/7開催)
【6】[2024山形大会]学生事前予約受付中:学生のための地質系業界説明会
【7】[2024山形大会]その他
【8】文部科学省アンケート調査依頼(7/31まで)
No.626 2024/7/16 [2024山形大会]各種申込受付中
【1】[2024山形大会]事前参加登録受付中
【2】[2024山形大会]懇親会予約はお早めに!
【3】[2024山形大会]巡検:山形を中心に8コースを設定
【4】[2024山形大会]各種申込受付中
【5】Island Arc からのお知らせ
【6】地質学雑誌からのお知らせ
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.625 2024/7/11(臨時) [2024山形大会]事前参加登録受付開始!
【1】[2024山形大会]事前参加登録受付開始しました
【2】第11回ショートコース「微化石」まもなく申込締切です
No.624 2024/7/2 日本地質学会会長就任にあたって
【1】日本地質学会会長就任にあたって(会長 山路 敦)
【2】[2024山形大会]各種申込を受付中です!
【3】[2024山形大会]まもなく事前参加登録受付開始します
【4】第11回ショートコース「微化石」開催します!
【5】Island Arc からのお知らせ
【6】地質学雑誌からのお知らせ
【7】支部のお知らせ
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.623 2024/6/24 [2024山形大会]まもなく講演申込締切です!
【1】[2024山形大会]6/26(水)18時 講演申込締切です!
No.622 2024/6/18 [2024山形大会]講演申込6/26(水)締切です
【1】[2024山形大会]各種申込を受付中です!
【2】[2024山形大会]まもなく事前参加登録受付開始します
【3】第11回ショートコース「微化石」開催します!
【4】2024年度会費督促請求に関するお知らせ
【5】支部のお知らせ
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
No.621 2024/6/4 第11回ショートコース「微化石」開催します!
【1】第11回ショートコース「微化石」開催します!
【2】2024年度代議員総会開催
【3】[2024山形大会]講演申込受付中です!
【4】地質学雑誌からのお知らせ
【5】支部のお知らせ
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
【8】会員ページ一時利用停止のお知らせ(6/12−14)
No.620 2024/5/21 [2024山形大会]講演申込受付中です!
【1】2024年度代議員総会開催
【2】[2024山形大会]講演申込受付中です!
【3】2024年度(第2回)日本地質学会研究奨励金採択結果
【4】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【5】支部のお知らせ
【6】JpGU2024 地質学会共催セッションにぜひご出席ください
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】災害に関連した会費の特別措置
【10】会員ページ一時利用停止のお知らせ(6/12−14)
No.619 2024/5/17 (臨時)山形大会講演申締切:6/26【日程訂正】
【1】[2024山形大会]講演申込受付締切の日程を訂正します
No.618 2024/5/9 (臨時)山形大会講演申込受付開始
【1】[2024山形大会]講演申込受付開始しました
No.617 2024/5/7 2024年度代議員総会開催
【1】2024年度代議員総会開催について
【2】[2024山形大会]講演申込受付をまもなく開始いたします
【3】2024年「地質の日」行事のご案内
【4】Island Arc からのお知らせ
【5】支部のお知らせ
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
【8】災害に関連した会費の特別措置
No.616 2024/4/16 2024年「地質の日」行事 各地で目白押し!
【1】2024年「地質の日」行事のご案内
【2】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【3】支部のお知らせ
【4】その他のお知らせ
【5】公募情報・各賞助成情報等
【6】災害に関連した会費の特別措置
【7】会員情報に変更があった場合は...
No.615 2024/4/2 2024年「地質の日」行事のご案内
【1】2024年「地質の日」行事のご案内
【2】第4回JABEEシンポジウム:YouTube公開中
【3】令和6年度大学入試共通テストの地学関連科目に関する意見書
【4】支部のお知らせ
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
【7】会員情報に変更があった場合は...
No.614 2024/3/19 2024年度理事および監事選挙(結果報告)
【1】2024年度理事および監事選挙(結果報告)
【2】2024山形大会:トピックセッション提案募集中(まもなく締切)
【3】2024年「地質の日」行事のご案内
【4】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【5】コラム 日本周辺の地震西進系列と次の関東・南海地震
【6】支部のお知らせ
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】会員情報に変更があった場合は...
No.613 2024/3/5 山形大会トピックセッション募集中
【1】2024年度理事および監事選挙について
【2】2024山形大会:トピックセッション募集中
【3】Island Arc からのお知らせ
【4】支部のお知らせ
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
【7】会員情報に変更があった場合は...
No.612 2024/2/20 研究奨励金募集中(若手野外地質研究者向け)
【1】2024年度理事および監事選挙について
【2】日本地質学会研究奨励金募集中(若手野外地質研究者向け)
【3】2024山形大会:トピックセッション提案募集
【4】JABEEシンポ:大学縮小危機のなかで、社会の要求にどのように応えるか
【5】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【6】支部のお知らせ
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】会員情報に変更があった場合は...
No.611 2024/2/16(臨時)【締切延長】第10回ショートコース:海底鉱物資源
【1】【締切延長】第10回ショートコース:海底鉱物資源 受講者募集
【2】会長・副会長立候補意思表明者への意向調査(延長)結果報告
No.610 2024/2/6 明日まで!会長・副会長意向調査【期間延長中】
【1】会長・副会長立候補意思表明者への意向調査結果および期間延長について
【2】2024山形大会開催!トピックセッション提案募集
【3】日本地質学会研究奨励金募集(若手野外地質研究者向け)
【4】地質系業界オンライン交流会:開催します
【5】第10回ショートコース:海底鉱物資源 受講者募集中
【6】JABEEシンポ:大学縮小危機のなかで、社会の要求にどのように応えるか
【7】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【8】支部のお知らせ
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
No.609 2024/2/2(臨時)【期間延長中】正副会長立候補意思表明者への意向調査
【1】会長・副会長立候補意思表明者への意向調査結果および期間延長について
No.608 2024/1/30(臨時)まもなく早期締切:2/1(JpGU2024 地質学会共催セッション)
【1】まもなく早期締切:2/1(JpGU2024 地質学会共催セッション)
No.607 2024/1/26(臨時)J-STAGE長期戦略に関しての意見募集のお願い(2/1締切)
【1】J-STAGE長期戦略に関しての意見募集のお願い(2/1締切)
No.606 2024/1/26(臨時)【期間延長中】正副会長立候補意思表明者への意向調査
【1】会長・副会長立候補意思表明者への意向調査結果および期間延長について
No.605 2024/1/19 (臨時)【期間延長】正副会長立候補意思表明者への意向調査
【1】会長・副会長立候補意思表明者への意向調査結果および期間延長について
No.604 2024/1/16 第10回ショートコース:海底鉱物資源 受講者募集
【1】令和6年能登半島地震の関連情報
【2】日本地質学会研究奨励金募集(若手野外地質研究者向け)
【3】第15回惑星地球フォトコンテスト受付中
【4】第10回ショートコース:海底鉱物資源 受講者募集中
【5】JABEEシンポ:大学縮小危機のなかで、社会の要求にどのように応えるか
【6】名誉会員候補者の募集が開始されています
【7】本の紹介「北長門海岸国定公園「青海島」のジオツーリズム」
【8】Island Arc からのお知らせ
【9】支部のお知らせ
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
No.603 2024/1/9 年頭の挨拶/令和6年能登半島地震の関連情報/会長談話
【1】年頭の挨拶(会長 岡田 誠)
【2】令和6年能登半島地震の関連情報/会長談話
【3】正副会長意向調査のお願い<1/10(水)17時まで>
【4】若手野外地質研究者向けに研究奨励金を支給します
【5】第10回ショートコース:海底鉱物資源 開催します
【6】名誉会員候補者の募集が開始されています
【7】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【8】学会HP 会員ページ:引っ越しました(旧会員ページの公開終了)
【9】SPring-8 利用ニーズに関するアンケート調査ご協力のお願い
【10】支部のお知らせ
【11】その他のお知らせ
【12】公募情報・各賞助成情報等
No.602 2023/12/19 若手野外地質研究者向け研究奨励金を支給します!
【1】正副会長意向調査のお願い<1/10(水)17時まで>
【2】若手野外地質研究者向けに研究奨励金を支給します
【3】2024年度の会費払込について(引落は12/25です)
【4】名誉会員候補者の募集が開始されています
【5】第15回惑星地球フォトコンテスト受付中
【6】学会HP 会員ページ:引っ越しました(旧会員ページの公開終了)
【7】2026年度以降地震火山地質こどもサマースクール開催地募集
【8】支部のお知らせ
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
【11】事務局年末年始休業(12/29-1/4)
No.601 2023/12/5 代議員選挙結果& 正副会長意向調査のお願い
【1】2024年度代議員選挙について(正副会長意向調査のお願い)
【2】2024年度の会費払込について(引落は12/25です)
【3】地質系若者のためのキャリアビジョン誌2023 原稿募集中
【4】第15回惑星地球フォトコンテスト受付中
【5】ニュース誌の送本希望の選択
【6】学会HP 会員ページ:引っ越しました
【7】地質学雑誌からのお知らせ
【8】支部のお知らせ
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
No.600 2023/11/21 2024年度学生会費申請(11/30締切)
【1】2024年度各賞候補者募集中(12/1締切)
【2】2024年度の会費払込について(引落は12/25です)
【3】2024年度学生会費の申請受付(11/30締切)
【4】地質系若者のためのキャリアビジョン誌2023 原稿募集中
【5】第15回惑星地球フォトコンテスト受付中
【6】ニュース誌の送本希望の選択
【7】Island Arc からのお知らせ
【8】支部のお知らせ
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
【11】訃報:水野篤行 名誉会員 ご逝去
No.599 2023/11/17 (臨時)代議員選挙11/20(月)17時 立候補締切!
No.598 2023/11/14 (臨時)訃報:志岐常正 名誉会員
No.597 2023/11/13(臨時)訃報:松田時彦 名誉会員
No.596 2023/11/7 2024年度代議員選挙立候補受付中(11/20;17時締切)
【1】2024年度代議員選挙立候補受付中(11/20, 17時締切)
【2】2024年度各賞候補者募集中(12/1締切)
【3】2024年度の会費払込について
【4】2024年度学生会費の申請受付(11/30締切)
【5】地質系若者のためのキャリアビジョン誌2023 原稿募集中
【6】第15回惑星地球フォトコンテスト受付開始
【7】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【8】支部のお知らせ
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
No.595 2023/10/24 (臨時)代議員選挙立候補受付開始
【1】2024年度代議員選挙立候補受付開始
【2】2024年度学生会費の申請受付(11/30締切)
【3】JpGU2024セッション提案募集(11/1締切)
No.594 2023/10/17 10/23より代議員立候補受付が始まります
【1】2024年度各賞候補者募集(12/1締切)
【2】2024年度代議員および役員選挙について
【3】ニュース誌の送本希望の選択について
【4】[2023京都大会]10/20より講演要旨無料公開
【5】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【6】支部のお知らせ
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.593 2023/10/3 ショートコース「応力逆解析法」再び!!
【1】2024年度各賞候補者募集(12/1締切)
【2】2024年度代議員および役員選挙について
【3】第9回ショートコース:応力逆解析法(参加申込受付中)
【4】ニュース誌の送本希望の選択について
【5】2023京都大会「学生優秀発表賞」決定
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
No.592(臨時) 2023/9/23 坂巻幸雄 名誉会員 ご逝去
No.591(臨時)2023/9/18[2023京都大会]会場フォト
No.590(臨時)2023/9/15)[2023京都大会]まもなく学術大会がはじまります!!
【1】[2023京都大会]講演プログラム・講演要旨公開中
【2】[2023京都大会]学生のための地質系業界説明会:オンラインもあります
【3】[2023京都大会]その他(若手会員向けの取り組み/お子様をお連れになる方へ)
【4】[2023京都大会]会場でのマスク着用,換気のお願い
【5】[2023京都大会]大会期間中はSNSをぜひご確認ください!
No.589 2023/9/5 [2023京都大会]まもなく講演要旨公開です
【1】[2023京都大会]講演プログラムが公開しています
【2】[2023京都大会]まもなく講演要旨が公開となります
【3】[2023京都大会]学生のための地質系業界説明会:参加学生申込受付中!
【4】[2023京都大会]その他(ECSロゴのDL/お子様をお連れになる方へ)
【5】本の紹介「高レベル放射性廃棄物処分場の立地選定」
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.588 2023/8/16[2023京都]リアル懇親会【残席僅少】まもなく締切です
【1】[2023京都大会]全体日程表を公開しています
【2】[2023京都大会]各種参加申込受付中
【3】[2023京都大会]若手会員向けルームシェア型宿泊プラン
【4】[2023京都大会]学生のための地質系業界説明会
【5】[2023京都大会]その他
【6】コラム 琉球列島:縄文人が挑んだ遠い島と黒潮
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.587 2023/8/1 [2023京都]巡検のお申し込みはお早めに!!
【1】[2023京都大会]各種参加申込受付中です
【2】[2023京都大会]巡検申込状況:お申し込みはお早めに!!
【3】[2023京都大会]若手会員向けルームシェア型宿泊プラン
【4】[2023京都大会]学生のための地質系業界説明会
【5】[2023京都大会]その他
【6】IGC2024に関する会長メッセージを掲載しました
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】鎮西清高 名誉会員 ご逝去
No.586 2023/7/18 各種参加申込受付中です:巡検!懇親会も!
【1】[2023京都大会]各種参加申込受付中です
【2】[2023京都大会]ジュニアセッション 参加受付中
【3】[2023京都大会]若手会員向けルームシェア型宿泊プラン
【4】[2023京都大会]その他
【5】令和5年7月 九州地方豪雨災害の情報
【6】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.585 2023/7/11 (臨時)明日(7/12;18時)講演申込締切です!
【1】[2023京都大会]明日(7/12;18時)講演申込締切です!
【2】[2023京都大会]各種参加申込受付開始しました
【3】[2023京都大会]ダイバーシティ認定ロゴご活用下さい
【4】[2023京都大会]若手会員向けルームシェア型宿泊プラン
【5】[2023京都大会]ジュニアセッション 参加受付中
【6】[2023京都大会]学生優秀発表賞(新設)について
【7】[2023京都大会]その他の情報
No.584 2023/7/4 講演申込締切まであと1週間です!
【1】[2023京都大会]講演申込受付中です
【2】[2023京都大会]まもなく事前参加登録受付開始します
【3】[2023京都大会]ダイバーシティ認定ロゴご活用下さい
【4】[2023京都大会]若手会員向けルームシェア型宿泊プラン
【5】[2023京都大会]ジュニアセッション 参加受付中
【6】[2023京都大会]学生優秀発表賞(新設)について
【7】支部情報
【8】会員の学術・教育・社会貢献活動
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
No.583 2023/6/20 第8回ショートコース まもなく受付終了です!
【1】第8回ショートコース まもなく受付終了です!
【2】[2023京都大会]講演申込受付中です
【3】[2023京都大会]ダイバーシティ認定ロゴご活用下さい
【4】[2023京都大会]ジュニアセッション 参加受付中
【5】[2023京都大会]学生優秀発表賞(新設)について
【6】会費督促請求に関するお知らせ
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.582 2023/6/6 まだ間に合います!締切延長!若手巡検 in 北海道
【1】新しい会員管理システムの公開・利用について(再掲)
【2】若手巡検・研究集会 in 北海道洞爺湖有珠山ジオパーク地域
【3】第8回ショートコース(参加申込受付中)
【4】2023京都大会ニュース:講演申込受付開始!ほか
【5】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【6】若手巡検・研究集会 in 北海道 洞爺湖有珠山ジオパーク地域
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.581 2023/5/16 新しい会員管理システムの公開・利用について
【1】新しい会員管理システムの公開・利用について
【2】第8回ショートコース(予告)
【3】2023年度(第15回)代議員総会開催について
【4】2023年「地質の日」行事のご案内
【5】2023京都大会ニュース
【6】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【7】若手巡検・研究集会 in 北海道 洞爺湖有珠山ジオパーク地域
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
No.580 2023/5/2 2023年度(第15回)代議員総会開催について
【1】2023年度(第15回)代議員総会開催について
【2】2023年「地質の日」行事のご案内
【3】2023京都大会ニュース
【4】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【5】若手巡検・研究集会 in 北海道 洞爺湖有珠山ジオパーク地域
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.579 2023/4/18 2023年「地質の日」イベント続々準備中!
【1】2023年「地質の日」行事のご案内
【2】今年も地質系業界説明会を開催します!
【3】科学技術系分野における任期付き研究者の雇用問題解決に向けての要望
【4】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【5】地質学雑誌特集号(冊子)販売のお知らせ
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.578 2023/4/4 特集号「球状コンクリーションの科学」全論文公開!
【1】2023年「地質の日」行事のご案内
【2】2023京都大会:トピックセッション採択
【3】第3回JABEEシンポジウム:YouTube公開中
【4】地質学雑誌からのお知らせ
【5】地質学雑誌特集号(冊子)販売のお知らせ
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】学会が主催する対面行事・イベントにおけるマスク着用について
No.577 2023/3/22 今年もはじまるよ!2023年「地質の日」
【1】2023年「地質の日」行事のご案内
【2】第14回惑星地球フォトコンテスト:審査結果発表
【3】第130年学術大会(2023京都)トピックセッションまもなく締切
【4】第3回JABEEシンポジウム:YouTube公開中
【5】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】学会が主催する対面行事・イベントにおけるマスク着用について
No.576 2023/3/7 ショートコース参加申込受付中!お早めに!
【1】第7回ショートコース 参加申込受付中!お早めに!
【2】第130年学術大会トピックセッション募集中
【3】第3回JABEEシンポジウム 開催しました
【4】TOPIC 日本地質学会の国際的プロファイルの向上
【5】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.575 2023/2/21 研究奨励金・学生会員申請 まもなく締切!
【1】2023年度日本地質学会研究奨励金:まもなく締切(2/28締切)
【2】「学生会員」追加申請:まもなく締切(2/28締切)
【3】第3回JABEEシンポジウム「大学ー企業の架け橋教育 ユニークな実例紹介」
【4】第7回ショートコース 開催します
【5】第130年学術大会(2023京都)京都大学吉田南構内にて開催
【6】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】おたずね(古い巡検案内書を探しています)
No.574 2023/2/7 地質系業界オンライン交流会開催します
【1】名誉会員候補者の募集中です(まもなく締切)
【2】2023年度日本地質学会研究奨励金募集
【3】「学生会員」追加申請受付中(2/28締切)
【4】地質系業界オンライン交流会の開催案内
【5】第3回JABEEシンポジウム「大学ー企業の架け橋教育 ユニークな実例紹介」
【6】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.573 2023/1/17 惑星地球フォトコンテストまもなく締切です
【1】名誉会員候補者の募集が開始されています
【2】2023年度日本地質学会研究奨励金募集
【3】「学生会員」追加申請を受付中(2/28締切)
【4】オンラインシンポジウム「ジオパーク地域に伝わる伝承と地質学」
【5】第3回JABEEシンポジウム「大学ー企業の架け橋教育 ユニークな実例紹介」
【6】第14回惑星地球フォトコンテスト受付中
【7】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【8】専門職における旧姓・通称使用に関する実態調査への協力依頼
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
No.572 2023/1/6 謹賀新年*2023
【1】年頭の挨拶
【2】2023年度日本地質学会研究奨励金募集
【3】「学生会員」追加申請を受付中(2/28締切)
【4】2023年度の会費払込について
【5】オンラインシンポジウム「ジオパーク地域に伝わる伝承と地質学」
【6】第14回惑星地球フォトコンテスト受付中
【7】地質学雑誌からのお知らせ
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
【11】訃報 端山好和 名誉会員 ご逝去
【12】新型コロナウィルス感染症に関する学会の対応について
No.571 2022/12/20 若手野外地質研究者向けに研究奨励金を支給します!
【1】2023年度日本地質学会研究奨励金募集
【2】「学生会員」追加申請を受け付けます(12/20-2/28)
【3】2023年度の会費払込について
【4】オンラインシンポジウム「ジオパーク地域に伝わる伝承と地質学」
【5】第3回JABEEシンポジウム「大学ー企業の架け橋教育 ユニークな実例紹介」
【6】第14回惑星地球フォトコンテスト受付中
【7】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
【11】事務局年末年始休業のお知らせ(12/29-1/5)
No.570 2022/12/6 第6回ショートコース 参加申込受付中!
【1】第6回ショートコース:法地質学/付加体地質学 参加申込受付中!
【2】2023年度以降の会費請求と主な変更点
【3】地質系若者のためのキャリアビジョン誌2022 原稿募集中
【4】第14回惑星地球フォトコンテスト受付中
【5】Island Arcからのお知らせ
【6】第3回JABEEシンポジウム「大学ー企業の架け橋教育 ユニークな実例紹介」
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.5697 2022/11/15 第6回ショートコース開催します
【1】第6回ショートコース:法地質学/付加体地質学
【2】2023年度以降の会費請求と主な変更点
【3】学部学生・院生の方へ:「学生会員」申請をお願いします!
【4】2023年度一般社団法人日本地質学会各賞候補者募集中
【5】地質系若者のためのキャリアビジョン誌2022 原稿募集中
【6】第14回惑星地球フォトコンテスト受付中
【7】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【8】(コラム)平安時代の「日本三代実録」の地震・津波・噴火記録
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
No.568(臨時) 2022/11/9 秋山 雅彦 名誉会員 ご逝去
■ 秋山 雅彦 名誉会員 ご逝去
No.567 2022/11/1 学部学生・院生の方へ:「学生会員」申請を!!
【1】2023年度一般社団法人日本地質学会各賞候補者募集中
【2】学部学生・院生の方へ:「学生会員」申請をお願いします!
【3】韓国IGC2024へのサポートレター撤回について
【4】地質系若者のためのキャリアビジョン誌2022 原稿募集開始
【5】第14回惑星地球フォトコンテスト受付開始
【6】JpGU2023セッション提案募集(11/2締切)
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.566 2022/10/18 JpGU2023セッション提案募集(11/2締切)
【1】2023年度一般社団法人日本地質学会各賞候補者募集中
【2】[2022早稲田大会]講演要旨無料公開
【3】JpGU2023セッション提案募集(11/2締切)
【4】第15回日本地学オリンピックの参加申込受付中
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
No.565 2022/10/4 2023年度一般社団法人日本地質学会各賞候補者募集
【1】2023年度一般社団法人日本地質学会各賞候補者募集について
【2】[2022早稲田大会]講演要旨・e-posterの閲覧について
【3】第15回日本地学オリンピックの参加申込受付中
【4】その他のお知らせ
【5】公募情報・各賞助成情報等
No.564 2022/9/22 早稲田大会が終了しました.来年は...
【1】[2022早稲田大会]学術大会が終了しました
【2】[2022早稲田大会]優秀ポスター賞決定
【3】[2022早稲田大会]講演要旨・e-posterの閲覧について
【4】第15回日本地学オリンピックの参加申込受付中
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
No.563(臨時)2022/9/6 [2022早稲田]ラストスパート!
【1】早稲田大会:2日目と3日目の様子
No.562(臨時)2022/9/5 [2022早稲田]帰ってきた対面大会
[2022早稲田大会情報]
【1】早稲田大会 初日の様子
【2】9/4-6対面会場へお越しの皆様へ(会員カードを持参して下さい)
【3】オンラインプログラムの参加方法について
【4】学生のための地質系業界説明会(学生さんの飛び込み参加も歓迎します!
【5】コアタイムの前に「フラッシュトーク」を実施します
【6】ランチョン・夜間小集会(9/4−6対面)のご案内
【7】地質学露頭紹介 やります!(9/11、zoom)
No.561(臨時)2022/9/1 [2022早稲田]会員カードを持って早稲田へGO!
[2022早稲田大会情報]
【1】9/4-6対面会場へお越しの皆様へ(会員カードを持参して下さい)
【2】オンラインプログラムの参加方法について
【3】巡検をお申し込みの皆様へ
【4】参加者・発表者へのメール送信履歴
【5】学生のための地質系業界説明会(9/2まで学生事前申込締切延長)
【6】コアタイムの前に「フラッシュトーク」を実施します
【7】ランチョン・夜間小集会(9/4−6対面)のご案内
【8】地質学露頭紹介 発表者募集!(9/3締切延長)
No.560 2022/8/16 講演プログラム公開中
★★目次 ★★
【1】[2022早稲田]全体日程表・講演プログラム
【2】[2022早稲田]大会参加登録・巡検申込を締め切りました
【3】[2022早稲田]発表者の皆様へ
【4】[2022早稲田]学生のための地質系業界説明会
【5】[2022早稲田]地質学露頭紹介 発表者募集!
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
No.559 2022/8/8(臨時)[2022早稲田]参加登録・巡検まもなく締切!
★★目次 ★★
【1】[2022早稲田]早稲田大会の開催について(再掲)
【2】[2022早稲田]全体日程表・講演プログラム公開
【3】[2022早稲田]大会参加登録,巡検のまもなく締切!
【4】[2022早稲田]発表者の皆様へ
【5】[2022早稲田]学生のための地質系業界説明会
【6】[2022早稲田]地質学露頭紹介 発表者募集!
【7】[2022早稲田]家族巡検「生命の進化を楽しく学ぼう」
No.558 2022/8/2 全体日程表が公開になりました
★★目次 ★★
【1】[2022早稲田]早稲田大会の開催について
【2】[2022早稲田]全体日程表が公開になりました
【3】[2022早稲田]大会参加登録,巡検の申込受付中!
【4】[2022早稲田]企業展示・書籍販売 対面開催します
【5】[2022早稲田]学生のための地質系業界説明会
【6】[2022早稲田]家族巡検「生命の進化を楽しく学ぼう」
【7】[2022早稲田]お子様をお連れになる方へ
【8】トピック:地学に名を轟かした水戸藩の長久保赤水の改正日本輿地路程全図
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
No.557 2022/7/19 大会参加登録,巡検の申込はお早めに!
★★目次 ★★
【1】[2022早稲田]大会参加登録,巡検の申込受付中!
【2】[2022早稲田]ジュニアセッション(e-poster)参加校募集
【3】[2022早稲田]企業展示・書籍販売 対面開催します
【4】[2022早稲田]家族巡検「生命の進化を楽しく学ぼう」
【5】[2022早稲田]お子様をお連れになる方へ
【6】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.556 2022/7/5 新会長挨拶/早稲田大会参加登録受付開始
★★目次 ★★
【0】新会長挨拶(会長 岡田 誠)
【1】[2022早稲田]大会参加登録,巡検の申込受付を開始しました
【2】[2022早稲田]ダイバーシティ認定ロゴ導入の取り組み
【3】[2022早稲田]ジュニアセッション(e-poster)参加校募集
【4】[2022早稲田]企業展示・書籍販売 対面開催します
【5】[2022早稲田]家族巡検「生命の進化を楽しく学ぼう」
【6】[2022早稲田]地質系業界説明会:参加企業・団体募集中
【7】[2022早稲田]お子様をお連れになる方へ
【8】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
【11】訃報:加藤 誠 名誉会員 ご逝去
No.555 2022/6/27 (臨時) [2022早稲田大会情報]講演申込まもなく締切
★★目次 ★★
[2022早稲田大会情報]
【1】講演申込まもなく締切です(6/29:18時)
【2】これから地質学会へ入会される方へお伝えください!
【3】ダイバーシティ認定ロゴ導入の取り組み
【4】ランチョン・夜間小集会募集
【5】ジュニアセッション(e-poster)参加校募集
【6】企業展示・書籍販売 対面開催します
【7】家族巡検「生命の進化を楽しく学ぼう」
【8】地質系業界説明会:参加企業・団体募集中
【9】お子様をお連れになる方へ
No.554 2022/6/21 2022東京・早稲田 講演申込:まずはアカウント登録を!
★★目次 ★★
【1】[2022早稲田]講演申込受付中です
【2】[2022早稲田]ダイバーシティ認定ロゴ導入の取り組み
【3】[2022早稲田]巡検コース紹介掲載しました
【4】[2022早稲田]ランチョン・夜間小集会募集
【5】[2022早稲田]ジュニアセッション(e-poster)参加校募集
【6】[2022早稲田]企業展示・書籍販売 対面開催します
【7】[2022早稲田]家族巡検「生命の進化を楽しく学ぼう」
【8】会費督促請求に関するお知らせ
【9】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【10】(アンケート協力)JST/RISTEX:新規研究開発テーマに関するアンケート
【11】支部情報
【12】その他のお知らせ
【13】公募情報・各賞助成情報等
No.553 2022/6/7 2022東京・早稲田大会情報!!
★★目次 ★★
【1】2022年度(第14回)代議員総会開催について
【2】【重要】学会活性化に関わる会費などの変更について(第2回)
【3】[2022早稲田]講演申込受付中です
【4】[2022早稲田]ダイバーシティ認定ロゴ導入の取り組み
【5】[2022早稲田]巡検コース紹介掲載しました
【6】[2022早稲田]ランチョン・夜間小集会募集
【7】[2022早稲田]ジュニアセッション(e-poster)参加校募集
【8】[2022早稲田]企業展示・書籍販売 対面開催します
【9】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【10】支部情報
【11】(アンケート協力依頼)若手研究者をとりまく評価に関する意識調査
【12】デジタル配列情報(DSI)に関するオープンレターへの署名のお願い
【13】その他のお知らせ
【14】公募情報・各賞助成情報等
【15】訃報:石田志朗 名誉会員 ご逝去
No.552 2022/5/27 (臨時)2022東京・早稲田大会:講演申込開始
★★目次 ★★
【1】2022年東京・早稲田大会:講演申込開始です
【2】地質学露頭紹介 at JpGU2022 5/29は露頭について語りましょう!
No.551 2022/5/17 2022東京・早稲田大会:まもなく講演申込開始です
★★目次 ★★
【1】2022年度(第14回)代議員総会開催について
【2】【重要】学会活性化に関わる会費などの変更について(第2回)
【3】2022年東京・早稲田大会:間もなく講演申込開始です
【4】地質学露頭紹介 at JpGU2022 露頭について、おおいに語りましょう!
【5】日本学術会議シンポジウム:チバニアン,学術的意義とその社会的重要性
【6】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【7】法地質学研究委員会からお知らせ
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
No.550 2022/5/11 地質学露頭紹介 at JpGU2022 発表申込延長します
★★目次 ★★
【1】2022年「地質の日」行事のご案内
【2】日本学術会議シンポジウム?チバニアン,学術的意義とその社会的重要性
【3】地質学露頭紹介 at JpGU2022(発表・参加募集中)
【4】【重要】会費などの変更についてのご提案について
【5】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.549 2022/4/19 シンポ-チバニアン,学術的意義とその社会的重要性-
★★目次 ★★
【【1】【重要】会費などの変更についてのご提案について
【2】2022年「地質の日」行事のご案内
【3】日本学術会議シンポジウム-チバニアン,学術的意義とその社会的重要性-
【4】地質学露頭紹介 at JpGU2022(発表・参加募集中)
【5】地質学雑誌 からのお知らせ
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
No.548 2022/4/5 理事選挙の結果報告
★★目次 ★★
【1】理事選挙の結果報告
【2】【重要】会費などの変更についてのご提案について
【3】2022年「地質の日」行事のご案内
【4】令和4年度大学入試共通テストの地学関連科目に関する意見書
【5】地質学露頭紹介 at JpGU2022(発表・参加募集中)
【6】本の紹介「小説 原子力規制官僚の理一火山リスクに対峙して」
【7】Island Arc からのお知らせ
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
No.547 2022/3/15 第13回惑星地球フォトコンテスト:審査結果
★★目次 ★★
【1】【重要】会費などの変更についてのご提案について
【2】第13回惑星地球フォトコンテスト:審査結果発表
【3】2022年「地質の日」行事のご案内
【4】地質学露頭紹介 at JpGU2022(発表・参加募集中)
【5】2022年度割引申請を忘れずに!(最終締切間近です)
【6】地質学雑誌からのお知らせ
【7】会員の学術・教育・社会貢献活動
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
【11】訃報 木崎甲子郎 名誉会員 ご逝去
No.546 2022/3/1 JABEEシンポ「昔と違う イマドキのフィールド教育」
★★目次 ★★
【1】【重要】会費などの変更についてのご提案について
【2】2022年度理事選挙について
【3】[2022東京・早稲田]トピックセッション提案募集
【4】JABEEオンラインシンポ「昔と違う イマドキのフィールド教育」
【5】地質学露頭紹介 at JpGU2022(発表・参加募集中)
【6】地質学雑誌オンデマンド印刷版年間購読受付のお知らせ
【7】2022年度割引申請を忘れずに!
【8】地質学雑誌からのお知らせ
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
No.545 2022/2/15 【重要】会費などの変更についてのご提案について
★★目次 ★★
【1】【重要】会費などの変更についてのご提案について
【2】2022年度理事選挙について
【3】[2022東京・早稲田]【重要】学術大会セッションの変更について
【4】[2022東京・早稲田]トピックセッション提案募集
【5】JABEEオンラインシンポ「昔と違う イマドキのフィールド教育」
【6】地質学露頭紹介 at JpGU2022(発表・参加募集中)
【7】地質学雑誌オンデマンド印刷版年間購読受付のお知らせ
【8】2022年度割引申請を忘れずに!
【9】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【10】(再掲)地震火山地質こどもサマースクール開催地募集
【11】会員の学術・教育・社会貢献活動
【12】コラム:童謡詩人金子みすゞの地学的側面
【13】支部情報
【14】Mars Ice Mapper計画(MIM)での科学観測に関する意見募集中
【15】(再掲)フィールドワークにおけるセクハラ実態調査アンケート
【16】その他のお知らせ
【17】公募情報・各賞助成情報等
No.544 2022/2/1 【重要】学術大会セッションの変更について
★★目次 ★★
【1】[2022東京・早稲田]【重要】学術大会セッションの変更について
【2】[2022東京・早稲田]トピックセッション提案募集
【3】第2回JABEEオンラインシンポ「昔と違う イマドキのフィールド教育」
【4】会員名簿の発行中止のお知らせ
【5】地質学雑誌オンデマンド印刷版年間購読受付のお知らせ
【6】2022年度会費払込について(割引申請受付中)
【7】名誉会員候補者の募集について
【8】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【9】地震火山地質こどもサマースクール開催地募集
【10】会員の学術・教育・社会貢献活動
【11】支部情報
【12】その他のお知らせ
【13】公募情報・各賞助成情報等
【14】(探しています)事務局からおたずね
No.543 2022/1/18 2022年度代議員選挙(結果報告)
★★目次 ★★
【1】2022年度代議員選挙および会長・副会長意向調査結果報告
【2】会員名簿の発行中止のお知らせ
【3】地質学雑誌オンデマンド印刷版年間購読受付のお知らせ
【4】2022年度会費払込について
【5】名誉会員候補者の募集が開始されています
【6】第13回惑星地球フォトコンテスト受付中
【7】会員の学術・教育・社会貢献活動
【8】フィールドワークにおける性暴力・セクハラに関するアンケート
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
【12】(探しています)事務局からおたずね
No.542 2022/1/6 忘れずに投票しましょう!代議員選挙/正副会長意向調査
★★目次 ★★
【1】年頭のご挨拶
【2】2022年度代議員選挙の投票および会長・副会長意向調査中
【3】会員名簿の発行中止のお知らせ
【4】地質学雑誌オンデマンド印刷版年間購読受付のお知らせ
【5】2022年度会費払込について
【6】名誉会員候補者の募集が開始されました
【7】ニュース誌リニューアルと原稿募集
【8】第13回惑星地球フォトコンテスト受付中
【9】コラム 河川と海岸のデジタル礫形計測:その後の進展
【10】支部情報
【11】その他のお知らせ
【12】公募情報・各賞助成情報等
No.541 2021/12/21 代議員選挙の投票および会長・副会長意向調査中
★★目次 ★★
【1】2022年度代議員選挙の投票および会長・副会長意向調査中
【2】2022年度会費払込について
【3】名誉会員候補者の募集が開始されました
【4】ニュース誌リニューアルと原稿募集
【5】第13回惑星地球フォトコンテスト受付中
【6】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】事務局年末年始休業(12/29-1/5)
No.540 2021/12/7 2022年度代議員選挙の投票および会長・副会長意向調査
★★目次 ★★
【1】2022年度代議員選挙の投票および会長・副会長意向調査
【2】2022年度会費払込について(割引申請受付中)
【3】ニュース誌リニューアルと原稿募集
【4】国際年代層序表(日本語版)の更新(2021年10月改訂版)
【5】第13回惑星地球フォトコンテスト受付中
【6】TOPIC:福徳岡ノ場の噴火
【7】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
No.539 2021/11/16 2022年度代議員選挙:立候補受付まもなく締切
★★目次 ★★
【1】2022年度代議員選挙(代議員立候補まもなく締切)
【2】2022年度学会各賞候補者募集中(12/1締切)
【3】2022年度会費払込について(割引申請受付中)
【4】第13回惑星地球フォトコンテスト受付中
【5】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【6】アンケート協力依頼:第5回科学技術系専門職の男女共同参画実態調査
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】訃報:糸魚川淳二 名誉会員 ご逝去
No.538 2021/11/12 No.538(臨時)代議員選挙:11月18日(木)18時 立候補締切です!
No.537 2021/11/2 地質学露頭紹介のページができました
★★目次 ★★
【1】2022年度代議員選挙立候補受付中!
【2】2022年度学会各賞候補者募集開始(12/1締切)
【3】2022年度会費払込について(割引申請受付中)
【4】地質系若者のためのキャリアビジョン誌(2021版)協賛(締切延長)
【5】地質学露頭紹介のページができました
【6】第13回惑星地球フォトコンテスト受付開始
【7】コラム:“Geomythology(地球神話)“とジオパーク
【8】コラム:中国の月探査機「嫦娥5号」持ち帰り試料の地質学的研究結果
【9】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【10】支部情報
【11】その他のお知らせ
【12】公募情報・各賞助成情報等
No.536 2021/10/27 (臨時)JpGU2022セッション提案募集(11/2締切)
No.535 2021/10/19 2022年度代議員選挙立候補受付開始です!
★★目次 ★★
【1】2022年度代議員および役員選挙(代議員立候補受付開始)
【2】2022年度学会各賞候補者募集開始(12/1締切)
【3】2022年度会費払込について(割引申請受付開始)
【4】京都大学の地球科学分野での研究不正問題について
【5】地質系若者のためのキャリアビジョン誌(2021版)協賛(原稿掲載)募集
【6】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.534 2021/10/5 2022年度の新しい表彰体系について
★★目次 ★★
【1】2022年度の新しい表彰体系について
【2】2022年度学会各賞候補者募集開始(12/1締切)
【3】地質系若者のためのキャリアビジョン誌(2021版)協賛(原稿掲載)募集
【4】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
No.533 2021/9/21第5回ショートコース:申込締切延長
★★目次 ★★
【1】日本地質学会第5回ショートコース:申込締切延長
【2】【2021名古屋】一部行事YouTube公開中/要旨・e-posterの閲覧
【3】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【4】第14回日本地学オリンピックの参加申込受付中
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
No.532 2021/9/15 (臨時)地学オリ国際大会の結果 & IGCインドに関する注意喚起ほか
★★目次 ★★
【1】第14回国際地学オリンピック・オンライン大会の結果
【2】IGCインドに関する注意喚起
【3】(もらってください)地質学雑誌バックナンバー
No.531 2021/9/7 名古屋オンライン大会終了しました
★★目次 ★★
【1】【2021名古屋】オンライン大会終了しました
【2】【2021名古屋】一部行事をYouTubeで公開しています
【3】【2021名古屋】講演要旨・e-poster閲覧について
【4】日本地質学会第5回ショートコース:申込受付中
【5】第14回日本地学オリンピックの参加申込開始
【6】地質学雑誌からのお知らせ
【7】支部情報
【8】全国大学院生協議会:アンケート協力依頼(大学院生対象)
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
No.530 2021/8/17 名古屋大会参加登録まもなく締切!
★★目次 ★★
【1】【2021名古屋】講演プログラム公開
【2】【2021名古屋】大会参加登録を忘れずに!
【3】【2021名古屋】発表者の皆様へ(重要)
【4】【2021名古屋】学生の皆様へ:WEBを活用する業界研究サポートサービス
【5】【2021名古屋】参加しましょう! 名古屋大会追加イベント
【6】【2021名古屋】oVice 懇親会開催します!
【7】日本地質学会第5回ショートコース(予告)
【8】全国大学院生協議会:アンケート協力依頼(大学院生対象)
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
No.529 2021/8/17 (臨時)【2021名古屋】追加イベントにご参加ください!(申込期限あり)
No.528 2021/8/3 名古屋大会参加登録を忘れずに!(8/19締切)
★★目次 ★★
【1】【2021名古屋】全体日程を掲載しています
【2】【2021名古屋】大会参加登録を忘れずに!
【3】【2021名古屋】ジュニアセッション 参加校申込締切延長!
【4】【2021名古屋】参加しましょう! 名古屋大会追加イベント
【5】日本地質学会第5回ショートコース(予告)
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
【8】7月号冊子(ニュース・地質学雑誌)遅延のお詫び
No.527 2021/08/01 (臨時)ジュニアセッション締切延長(2021名古屋大会)
No.526 2021/07/27 (臨時)参加しましょう! 名古屋大会追加イベント
★★目次 ★★
【1】参加しましょう! 2021名古屋大会追加イベント
【2】参加申込受付中!座談交流会 ジェンダー・ダイバーシティ委員会Workshop
No.525 2021/07/20 2021名古屋大会情報(全体日程ほか)
★★目次 ★★
【1】【2021名古屋】全体日程を掲載しました
【2】【2021名古屋】大会参加登録を忘れずに!
【3】【2021名古屋】ジュニアセッション 参加校募集中!
【4】座談交流会 :ジェンダー・ダイバーシティ委員会Workshop
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
No.524 2021/07/12(臨時)若手研究者必聴!第4回ショートコース(7/18開催)受講者募集中!
★★目次 ★★
【1】若手研究者必聴!第4回ショートコース(7/18開催)受講者募集中!
No.523 2021/07/06 名古屋大会 参加登録を忘れずに!
★★目次 ★★
【1】2021名古屋大会情報
【2】2021年度会費督促請求について
【3】支部情報
【4】原子力規制委員会福島第一原子力発電所事故10年動画
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
No.522(臨時) 2021/06/23 第128年学術大会講演申込 間もなく締切です!
★★目次 ★★
【1】講演申込間もなく締切です!(6/30;18時締切)
【2】第128年学術大会(名古屋大会)の「ここがポイント!」
【3】大会参加登録の受付開始します
【4】誌面ブース出展のご案内
【5】トピックセッションT4招待講演者変更
【6】ジュニアセッション参加校募集中
No.521 2021/06/15 名古屋大会講演申込関わるzoom説明会
★★目次 ★★
【1】【2021名古屋】講演申込受付中
【2】【2021名古屋】講演申込関わるzoom説明会:ぜひご参加ください
【3】【2021名古屋】誌面ブース出展のご案内
【4】【2021名古屋】そのほかのお知らせ
【5】2021年度会費督促請求について
【6】第4回ショートコースのご案内
【7】本の紹介: 絶えて存在しなかったかのように
【8】TOPIC:放射性物質を含んでいる福島県太田川河川敷の黒砂中の磁性細菌
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
【12】地質学雑誌127巻5号,一部不達・遅延のお詫び
No.520 2021/06/01 2021年度(第13回)代議員総会開催
★★目次 ★★
【1】日本地質学会2021年度(第13回)総会開催
【2】2021年名古屋大会:講演申込受付中
【3】第4回ショートコースのご案内
【4】令和4年度版学習資料「一家に1枚」の企画募集
【5】研究,教育や社会貢献など,会員の活動成果を学会HPでPRしませんか
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】新型コロナウィルス感染拡大防止に関する学会の対応(2021/6/1)
No.519 2021/05/18 2021年名古屋大会:間もなく講演申込開始です
★★目次 ★★
【1】2021年名古屋大会:間もなく講演申込開始です
【2】第4回ショートコースのご案内
【3】2021年「地質の日」行事のご案内
【4】支部情報
【5】研究,教育や社会貢献など,会員の活動成果を学会HPでPRしませんか
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
No.518 2021/05/07 会員の活動成果を学会HPでPRしませんか
★★目次 ★★
【1】2021年名古屋大会開催のお知らせ
【2】(理事会報告)地質学雑誌完全電子化実施,2022年1月を目標(再掲)
【3】第3回ショートコース「津波堆積物」申込受付中
【4】2021年「地質の日」行事のご案内
【5】支部情報
【6】研究、教育や社会貢献など,会員の活動成果を学会HPでPRしませんか
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】訃報 星野通平 名誉会員 ご逝去
No.517 2021/04/20 学会行動規範の改訂/地雑22年1月より電子化
★★目次 ★★
【1】2021年名古屋大会開催のお知らせ
【2】学会行動規範の改訂について
【3】(理事会報告)地質学雑誌完全電子化実施,2022年1月を目標
【4】第3回ショートコース「津波堆積物」申込受付中
【5】2021年「地質の日」行事のご案内
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】訃報 石井 健一 名誉会員 ご逝去
【10】まん延防止等重点措置実施に関する学会の対応について(2021/4/19付)
No.516(臨時) 2021/04/09 唐木田 芳文 名誉会員 ご逝去
No.515 2021/03/16 ショートコース「津波堆積物」申込受付開始
★★目次 ★★
【1】第3回ショートコース「津波堆積物」申込受付開始
【2】「地質の日」オンライン講演会開催します
【3】地質学雑誌の完全電子化実現に向けて(再々掲)
【4】若手研究者のペーができました!
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
【8】緊急事態宣言解除後の学会の対応について
No.514(臨時) 2021/03/31 三梨 昂 名誉会員 ご逝去
No.513 2021/03/16 21年度割引会費申請(院生・学部生)最終締切です!
★★目次 ★★
【1】「地質の日」オンライン講演会開催します
【2】(名古屋代替)JABEEオンラインシンポを開催しました
【3】地質学雑誌の完全電子化実現に向けて(再掲)
【4】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!(3/31最終締切)
【5】「日本の地質学100年 : 日本地質学会100周年記念」再販セール中
【6】TOPIC “ナホトカ号”の重油流出事故の教訓とモーリシャスでの重油流出事故への責任:24年前の事故現場と今も残る流出被害の痕跡
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.512 2021/03/02 東日本大震災から10年にあたって
★★目次 ★★
【1】東日本大震災から10年にあたって
【2】地質学雑誌の完全電子化実現に向けて
【3】学術大会トピックセッション募集(まもなく締切)
【4】(名古屋代替)JABEEオンラインシンポ
【5】「地質の日」オンライン講演会開催します
【6】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
【7】「日本の地質学100年 : 日本地質学会100周年記念」再販セール中
【8】紹介:プレートテクトニクス・トランプ
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
No.511 2021/02/16 令和3年2月 福島県沖を震源とする地震
★★目次 ★★
【1】地質災害関連情報:令和3年2月 福島県沖を震源とする地震
【2】チバニアン提案書の公開と,その引用について
【3】学術大会トピックセッション募集!
【4】(名古屋代替)JABEEオンラインシンポ
【5】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
【6】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【7】「日本の地質学100年 : 日本地質学会100周年記念」再販セール中
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
【11】事務局からのお知らせ
No.510 2021/02/02 学術大会トピックセッション募集!
★★目次 ★★
【1】学術大会トピックセッション募集!
【2】(名古屋代替)JABEEオンラインシンポ
【3】名誉会員候補者の推薦について
【4】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
【5】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【6】2022年度地震火山地質こどもサマースクール開催地募集
【7】「日本の地質学100年 : 日本地質学会100周年記念」再販セール中
【8】会員の学術・教育・社会貢献活動
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
【11】事務局からのお知らせ
No.509 2021/01/19 名誉会員候補者の募集が開始されています
★★目次 ★★
【1】名誉会員候補者の募集が開始されています
【2】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
【3】第12回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
【4】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【5】2022年度地震火山地質こどもサマースクール開催地募集
【6】「日本の地質学100年 : 日本地質学会100周年記念」再販セール中
【7】研究計画の宣伝(promotion)ビデオの例(参考)
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
【11】訃報:黒田吉益 名誉会員 ご逝去
【12】新型コロナウィルス感染拡大防止に関する学会の対応(1月9日付)
No.508 2021/01/06 謹賀新年
★★目次 ★★
【1】2021年 年頭のご挨拶
【2】名誉会員候補者の募集が開始されました
【3】2021年度会費について
【4】第12回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
【5】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【6】2022年度地震火山地質こどもサマースクール開催地募集
【7】「日本の地質学100年 : 日本地質学会100周年記念」再販セール中
【8】コラム:Pitch vs. Rake
【9】コラム:永瀬清子:宮沢賢治に憧れた女流詩人の地学的側面
【10】支部情報
【11】その他のお知らせ
【12】公募情報・各賞助成情報等
【13】訃報 藤田 崇 名誉会員 ご逝去
No.507 2020/12/15 2021年度会費について
★★目次 ★★
【1】2021年度会費について
【2】第12回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
【3】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【4】2022年度地震火山地質こどもサマースクール開催地募集
【5】「日本の地質学100年 : 日本地質学会100周年記念」再販セール中です
【6】屋久島たんけんマップ 改版しました
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】学会事務局年末年始休業
No.506 2020/12/01 100周年記念誌 再販のお知らせ
★★目次 ★★
【1】2021年度会費について(院生割引会費申請受付中)
【2】第12回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
【3】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【4】「日本の地質学100年 : 日本地質学会100周年記念」再販のお知らせ
【5】コラム:津波と集落
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.505 2020/11/24 第2回サイバーシンポ(YouTube生配信です)
【1】2021年度会費について(院生割引会費申請受付中)
【2】2021年度学会各賞候補者募集中(12/1締切)
【3】第2回コロナ禍での地質学教育に関するサイバーシンポ
【4】第12回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
【6】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【7】論集58号再度販売いたします
【8】支部情報
【9】会員の活動
【10】その他のお知らせ
No.504 2020/11/4 惑星地球フォトコンテスト:作品募集開始
【1】2021年度会費について(学部生・院生割引会費申請受付中)
【2】2021年度学会各賞候補者募集中(12/1締切)
【3】名古屋大会代替企画
【4】第12回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
【6】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【7】論集58号再度販売いたします
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
No.503 2020/10/20 学術会議第25期推薦会員任命拒否に関する緊急声明へ賛同
【1】日本学術会議第25期推薦会員任命拒否に関する緊急声明へ賛同しました
【2】2021年度会費払い込みについて(次年度割引会費申請受付開始)
【3】2021年度学会各賞候補者募集(12/1締切)
【4】名古屋大会代替企画
【5】JpGU2021セッション提案について
【6】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【7】論集58号再度販売いたします
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.502 2020/10/06 2021年度各賞候補者募集(12/1締切)始まります
【1】2021年度学会各賞候補者募集(12/1締切)
【2】名古屋大会代替企画
【3】令和2年7月豪雨災害等地質災害関連情報
【4】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【5】地質学論集58号再度販売いたします
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
No.501 2020/9/24(臨時)地域地質・層序部会合同研究発表会の事前アンケート
【1】名古屋大会代替:地域地質部会・層序部会合同オン ライン研究発表会の事前アンケート
No.500 2020/9/16 名古屋大会代替企画:様々な企画がどんどん進んでいます!
【1】名古屋大会代替企画
【2】令和2年7月豪雨災害等地質災害関連情報
【3】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【4】その他のお知らせ
【5】公募情報・各賞助成情報等
No.499 2020/9/4 (臨時)名古屋大会代替:構造地質部会例会 開催決定!
【1】名古屋大会代替:構造地質部会2020年度オンライン例会開催決定!
No.498 2020/9/1 WEB表彰式・記念講演会ほか9/13配信!
【1】名古屋大会代替:WEB表彰式・記念講演会ほか 9/13配信
【2】令和2年7月豪雨災害等地質災害関連情報
【3】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【4】コラム:柱状節理は低温の発泡膨張,板状節理は高温の流動剪断でできる
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
No.497 2020/8/18 名古屋大会代替企画!様々な企画が進んでいます!
【1】名古屋大会代替企画
【2】令和2年7月豪雨災害等地質災害関連情報
【3】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【4】トピック:昇仙峡は黒富士が造った?(後編)
【5】大学院生を対象にしたアンケート調査:全国大学院生協議会(全院協)
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
No.496 2020/8/4 令和2年7月豪雨災害についての会長談話
【1】令和2年7月豪雨災害についての会長談話
【2】令和2年7月豪雨災害等地質災害関連情報
【3】名古屋大会代替企画
【4】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【5】トピック:昇仙峡は黒富士が造った?(前編)
【6】大学院生を対象にしたアンケート調査:全国大学院生協議会(全院協)
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】訃報 高柳洋吉 名誉会員 ご逝去
【10】訃報 斎藤常正 名誉会員 ご逝去
【11】事務局夏季休業のお知らせ
No.495 2020/7/21 災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
【1】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
【2】令和2年7月豪雨災害等地質災害緊急調査について
【3】令和2年7月豪雨災害に関する情報
【4】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【5】大学院生を対象にしたアンケート調査(全院協)
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
No.494 2020/7/7 令和2年7月 熊本県南部の豪雨災害に関する情報
【1】令和2年7月 熊本県南部の豪雨災害に関する情報
【2】2020年度会費の納入について
【3】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【4】2021年度地震火山地質こどもサマースクール開催地公募結果
【5】JpGUダイバーシティ推進委員会緊急アンケートのお願い
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
No.493 2020/6/16 新会長・新執行理事挨拶
【1】会長就任挨拶/新執行理事挨拶
【2】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【3】2020年度会費督促請求について
【4】大学院生のみなさま:アンケート協力依頼
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
【7】学会事務局からのお知らせ
No.492 2020/6/4 (臨時) 鈴木堯士 名誉会員 ご逝去
■ 鈴木堯士 名誉会員 ご逝去
No.491 2020/6/2
★★目次 ★★
【1】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【2】取材協力(情報提供)
【3】その他のお知らせ
【4】公募情報・各賞助成情報等
【5】学会事務局からのお知らせ
No.490 2020/5/25 (臨時)名古屋大会の開催中止(延期)と代替企画
No.489 2020/5/19 おうちでも!「地質の日」デジタルコンテンツ
★★目次 ★★
【1】2020年度「地質の日」行事のご案内(デジタルコンテンツもあるよ!)
【2】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【3】支部情報
【4】その他のお知らせ
【5】公募情報・各賞助成情報等
【6】学会事務局からのお知らせ
No.488 2020/5/7 防災学術連携体「感染症と自然災害の複合災害に備えて下さい」
★★目次 ★★
【1】日本地質学会2020年度(第12回)総会開催
【2】2020年度「地質の日」行事のご案内(デジタルコンテンツもあるよ!)
【3】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【4】防災学術連携体:緊急メッセージ
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
【8】学会事務局からのお知らせ
No.487 2020/4/21 おうちでも楽しめる!地質のデジタルコンテンツ
★★目次 ★★
【1】2020年度「地質の日」行事のご案内(特設ウェブサイト開設!)
【2】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【3】支部情報
【4】その他のお知らせ
【5】公募情報・各賞助成情報等
【6】学会事務局からのお知らせ
No.486 2020/4/13 (臨時)新型コロナウィルス感染拡大防止に関する学会の対応
■ 新型コロナウィルス感染拡大防止に関する学会の対応 2020年4月13日
No.485 2020/4/7 学術大会要旨電子化アンケート結果報告
★★目次 ★★
【1】学術大会要旨電子化アンケート結果報告
【2】2020年度「地質の日」行事のご案内
【3】Island Arc からのお知らせ
【4】支部情報
【5】国際賞:Moore教授 追悼
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
【8】お知らせ
No.484 2020/3/17 理事および監事選挙(結果報告)
★★目次 ★★
【1】理事および監事選挙(結果報告)
【2】2020名古屋大会:トピックセッション 決定!
【3】2020年度「地質の日」行事のご案内
【4】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
【5】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.483 2020/3/16 (臨時)訃報:諏訪兼位 名誉会員
■ 諏訪兼位 名誉会員 ご逝去
No.482 2020/3/4 (臨時)訃報:石原舜三 名誉会員
■ 石原舜三 名誉会員 ご逝去
No.481 2020/3/3 第11回惑星地球フォトコンテスト:審査結果発表!
★★目次 ★★
【1】第11回惑星地球フォトコンテスト:審査結果発表!
【2】2020年度「地質の日」行事のご案内
【3】令和2年度大学入試センター試験の地学関連科目に関する意見書 提出
【4】2020年度理事選挙開票について(3/11)
【5】2020名古屋大会:トピックセッション募集中
【6】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
【7】地質系統・年代の日本語記述ガイドライン 2020年1月改訂版
【8】Island Arc からのお知らせ
【9】第10回惑星地球フォトコンテスト展示会(一部会期変更)
【10】支部情報
【11】その他のお知らせ
【12】公募情報・各賞助成情報等
【13】訃報:大八木規夫 名誉会員
No.480 2020/3/2 (臨時)訃報:柴田 賢 名誉会員
■ 柴田 賢 名誉会員 ご逝去
No.479 2020/2/18 理事選挙のお知らせ/要旨集電子化アンケート
★★目次 ★★
【1】2020年度理事および監事選挙について
【2】学術大会の講演要旨集の電子化を検討しています:アンケート実施中
【3】2020名古屋大会開催!トピックセッション募集中
【4】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
【5】地質学雑誌/Island Arc からのお知らせ
【6】第10回惑星地球フォトコンテスト展示会
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.478 2020/2/4 要旨集の電子化を検討しています:アンケート実施中
★★目次 ★★
【1】学術大会の講演要旨集の電子化を検討しています:アンケート実施中
【2】2020名古屋大会開催!トピックセッション募集開始!
【3】日本地質学会名誉会員候補者の募集について
【4】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
【5】地質学雑誌からのお知らせ
【6】2021年度地震火山こどもサマースクール開催地募集
【7】第10回惑星地球フォトコンテスト展示会
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
No.477 2020/1/30 (臨時)学術会議マスタープランに地質学会の提案が選定される!
【1】学術会議マスタープランに地質学会の提案が選定される!
No.476 2020/1/21 地質もくわしい!アニメ「恋する小惑星」がスゴイ
★★目次 ★★
【1】正副会長候補者の意向調査(結果)
【2】「GSSPシンポジウム:国際層序の意味と意義」報告
【3】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されています
【4】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
【5】第11回惑星地球フォトコンテスト:締切間近!
【6】2021年度地震火山こどもサマースクール開催地募集
【7】(紹介)「恋する小惑星」を応援しよう!
【8】(会員の活動紹介)地質標本館は「恋アス」を応援しています。
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
No.475 2020/1/17 (臨時)チバニアン認定!
★★目次 ★★
【1】チバニアン認定!
No.474 2020/1/07 謹賀新年 年頭の挨拶
★★目次 ★★
【1】2020年 年頭のご挨拶
【2】正副会長候補者の意向調査(明日締切!)
【3】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されました
【4】2020年からIsland Arcが新しく変わります
【5】2020年度の会費について
【6】第11回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中!
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.473 2019/12/26 お詫び:地質学雑誌発送遅延
★★目次 ★★
【1】お詫び:地質学雑誌発送遅延(1/7頃発送)
【2】会員名簿の訂正・変更受付中:名簿作成アンケート(1/7締切)
【3】正副会長候補者の意向調査実施中
【4】2020年度の会費について
【5】第11回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
【6】事務局年末年始休業(12/27午後からお休みとなります)
No.472 2019/12/17 正副会長候補者の意向調査実施中です
★★目次 ★★
【1】会員名簿の訂正・変更・登録について/名簿作成アンケート
【2】正副会長候補者の意向調査実施中
【3】2020年度の会費について
【4】第11回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
【5】低頻度巨大災害シンポジウム 発表募集
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】事務局年末年始休業(12/27午後〜1/5)訂正
No.471 2019/12/3 会員名簿発行に関するお願い(名簿作成アンケート)
★★目次 ★★
【1】会員名簿の訂正・変更・登録について/名簿作成アンケート
【2】2020年度代議員選挙について(正副会長意向調査のお願い)
【3】2020年度の会費について
【4】第11回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
【5】低頻度巨大災害シンポジウム 発表募集
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.470 2019/11/27(臨時) 訃報:猪郷久義 名誉会員/島津光夫 名誉会員
No.469 2019/11/19 第11回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
★★目次 ★★
【1】第11回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
【2】2020年度代議員選挙について
【3】2020年度学会各賞候補者募集中(12/2締切)
【4】2020年度の会費について
【5】GSSPシンポジウム:国際層序の意味と意義 開催します!
【6】「令和元年台風19号に関する緊急報告会」(仮)発表募集
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.468 2019/11/08 (臨時)2020年度代議員選挙について
No.467 2019/11/05 第11回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
★★目次 ★★
【1】第11回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
【2】2020年度学会各賞候補者募集中(12/2締切)
【3】2020年度の会費について
【4】GSSPシンポジウム:国際層序の意味と意義 開催します!
【5】特集号原稿募集!(投稿のご案内)
【6】「令和元年台風19号に関する緊急報告会」(仮)発表募集
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.466 2019/11/01(臨時)代議員選挙:11月5日(火)18時 立候補届け締切です!
No.465 2019/10/28 (臨時)木村敏雄 名誉会員 訃報
No.464 2019/10/15 2020年度役員選挙立候補受付開始,各賞推薦募集中
★★目次 ★★
【1】2020年度役員選挙(代議員立候補受付中:11/5締切)
【2】2020年度学会各賞候補者募集中(12/2締切)
【3】2020年度の会費について
【4】GSSPシンポジウム:国際層序の意味と意義 開催します!
【5】小学生のための地学オリンピック:チャレンジ地球(参加者募集中)
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.463 2019/10/01 GSSPシンポジウムを開催します!
★★目次 ★★
【1】GSSPシンポジウム:国際層序の意味と意義 開催します!
【2】小学生のための地学オリンピック:チャレンジ地球(参加者募集中)
【3】[2019山口]忘れ物をお預かりしています
【4】[2019山口]CPD参加証明書が必要な方
【5】地質学雑誌からのお知らせ
【6】コラム:海岸礫は河川礫より円くて扁平である
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
No.462 2019/09/24 開幕!山口大会 写真で紹介
★★目次 ★★[2019山口大会関連情報]
【1】山口大会が開幕しました!
【1】普及事業:市民講演会と地質情報展
【2】会場と表彰式
【3】渾身の懇親会
No.461 2019/09/17 まもなく山口大会ですよ!
★★目次 ★★[2019山口大会関連情報]
【1】予約確認書(はがき)を発送しました
【2】懇親会わずかですが当日申込可能です!
【3】会員カードを忘れずに
【4】大会用に臨時バスが運行されます
【5】若手向けルームシェアプラン申込受付中(締切延長)
【6】会場周辺の便利マップができました!
---------------------------------------
【7】チャレンジ地球 参加者募集!
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
No.460 2019/09/03 祝!地オリ2019 日本代表4人全員が金メダル
★★目次 ★★
【1】地学オリンピック2019 日本代表4人全員が金メダル!!
【2】[2019山口]緊急展示申込受付中
【3】[2019山口]若手向けルームシェアプラン(締切延長)
【4】[2019山口]会場周辺の便利マップができました!
【5】[2019山口]会員カードを忘れずに
【6】地質系統・年代の日本語記述ガイドライン 2019年5月改訂版
【7】地質学雑誌からのお知らせ
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
No.459 2019/08/20 2019山口大会:参加登録締切延長!(8/22;15時)
★★目次 ★★
[2019山口大会情報]
【1】[2019山口]事前参加登録締切延長(8/22;15時まで)
【2】[2019山口]緊急展示申込受付中
【3】[2019山口]会員カードを忘れずに
【4】[2019山口]全体日程表・講演プログラム
------------------------------------------------------------
【5】2019年度大学院生の研究・生活実態に関するアンケート調査
【6】第36回万国地質学会議(IGC)のご案内
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.458 2019/08/06 2019山口大会:事前参加登録はお済みですか?
★★目次 ★★
[2019山口大会情報]
【1】[2019山口]全体日程表・講演プログラム公開しました。
【2】[2019山口]事前参加登録はお済みですか?
【3】[2019山口]緊急展示申込受付
【4】[2019山口]会員カードを忘れずに
------------------------------------------------------------
【5】2019年度大学院生の研究・生活実態に関するアンケート調査
【6】本の紹介「The Atom and the Fault」
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.457 2019/07/16 2019山口大会:巡検申込はお早めに
★★目次 ★★
[2019山口大会情報]
【1】大会参加登録受付中:巡検申込はお早めに!
【2】講演要旨集は事前予約をお願いします
【3】小さなEarth Scientistのつどい:参加校募集
【4】宿泊予約の情報
【5】地質関連企業研究サポート:出展企業募集
【6】企業展示・書籍販売・広告掲載 募集
------------------------------------------------------------
【7】地質学雑誌からのお知らせ
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.456 2019/07/03 講演申込締切:本日18時です!
★★目次 ★★
[2019山口大会情報]
【1】講演申込締切:本日18時です!
【2】ランチョン・夜間小集会申込も本日締切
【3】大会参加登録受付中です
【4】小さなEarth Scientistのつどい:参加校募集
【5】宿泊予約の情報
【6】地質関連企業研究サポート:出展企業募集
【7】企業展示・書籍販売・広告掲載 募集
------------------------------------------------------------
【8】地質学雑誌からのお知らせ
【9】Island Arcからのお知らせ
【10】地震火山こどもサマースクール:参加者募集
【11】支部情報
【12】その他のお知らせ
【13】公募情報・各賞助成情報等
No.455 2019/06/28 (臨時)締切まであとわずか!山口大会講演申込
★★目次 ★★
[2019山口大会関連情報]
【1】講演申込 締切まであとわずか!
【2】ランチョン・夜間集会 まもなく締切
【3】事前参加登録受付中です!
【4】地質関連企業研究サポート:出展企業募集
【5】企業展示・書籍販売・広告掲載 募集
【6】宿泊予約の情報
No.454 2019/06/18 地震火山こどもサマースクール参加者募集
★★目次 ★★
[2019山口大会情報]
【1】大会参加登録受付中です
【2】講演申込受付中:まずはアカウント登録を!
【3】ランチョン・夜間集会申込受付中
【4】小さなEarth Scientistのつどい:参加校募集
【5】宿泊予約の情報
【6】地質関連企業研究サポート:出展企業募集
【7】企業展示・書籍販売・広告掲載 募集
------------------------------------------------------------
【8】地震火山こどもサマースクール:参加者募集
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
【12】訂正[2019山口大会]
No.453 2019/06/11 (臨時)山口大会事前参加登録受付開始!
★★目次 ★★
[2019山口大会情報]
【1】大会参加登録受付を開始しました!
【2】講演申込受付中:まずはアカウント登録を!
【3】ランチョン・夜間集会申込受付中
【4】小さなEarth Scientistのつどい:参加校募集
【5】宿泊予約の情報
【6】企業展示・書籍販売・広告掲載 募集
No.452 2019/06/04 山口大会関連情報 ほか
★★目次 ★★
[2019山口大会情報]
【1】講演申込受付中:まずはアカウント登録を!
【2】ランチョン・夜間集会申込受付中
【3】大会参加登録もまもなく受付開始です
【4】小さなEarth Scientistのつどい:参加校募集
【5】宿泊予約の情報
------------------------------------------------------------
【6】2019年地質の日記念行事
【7】本の紹介「新しい地球惑星科学」
【8】支部情報(関東支部サイエンスカフェのご案内 ほか)
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
【11】訃報:武田裕幸 名誉会員 逝去
No.451 2019/05/31(臨時)[2019山口大会]講演申込開始:まずはアカウント登録を!
★★目次 ★★
【1】[2019山口大会]講演申込開始:まずはアカウント登録を!
【2】[2019山口大会]ランチョン・夜間集会申込受付中
【3】[2019山口大会]大会参加登録もまもなく受付開始です
【4】[2019山口大会]小さなEarth Scientistのつどい:参加校募集
【5】[2019山口大会]宿泊予約の情報
No.450 2019/05/21 [2019山口大会]まもなく講演申込開始です!
★★目次 ★★
【1】[2019山口大会]まもなく講演申込開始です!
【2】[2019山口大会]シンポ・セッションが確定しました
【3】[2019山口大会]宿泊予約の情報
【4】日本地質学会第11回総会開催(5/25)
【5】日本地質学会が大型研究計画に提案!
【6】Island Arc:論文投稿ワークショップのご案内
【7】2019年地質の日記念行事
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
No.449 2019/05/07 [山口大会]若手会員向けルームシェア型宿泊プラン
★★目次 ★★
【1】[山口大会関連情報]宿泊予約はお早めに!
【2】[山口大会関連情報]若手会員向けルームシェア型宿泊プラン
【3】日本地質学会第11回総会開催(5/25)
【4】日本地質学会が大型研究計画に提案!!
【5】地質学雑誌からのお知らせ
【6】Island Arcからのお知らせ
【7】2019年地質の日記念行事
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
No.448 2019/04/26(臨時) 地質雑4月号発送遅延[お詫び]
★★目次 ★★
【1】地質学雑誌からのお知らせ
No.447 2019/04/16 [山口大会関連情報]宿泊予約はお早めに!
★★目次 ★★
【1】[山口大会関連情報]宿泊予約はお早めに!
【2】日本地質学会が大型研究計画に提案!!
【3】科学技術週間スタート「一家に1枚 日本列島7億年」配布開始
【4】2019年地質の日記念行事
【5】地質図に関するJIS(日本工業規格)改正に関するお知らせ
【6】意見・提言2019
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.446 2019/04/09(臨時)「一家に1枚」ポスター発行
No.445 2019/04/02 コラム「宋詩にみる石と人の関わり」
★★目次 ★★
【1】2019年地質の日記念行事
【2】地質学雑誌からのお知らせ
【3】コラム「宋詩にみる石と人の関わり」
【4】支部情報
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
No.444 2019/03/19 今年もはじまるよ!2019年地質の日
★★目次 ★★
【1】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
【2】2019年地質の日記念行事
【3】地質学雑誌からのお知らせ
【4】支部情報
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
No.443(臨時) 2019/03/12 吉田 尚 名誉会員 訃報
■ 吉田 尚 名誉会員 ご逝去
No.442 2019/03/05 第10回惑星地球フォトコンテスト:審査結果発表!
★★目次 ★★
【1】[2019年山口大会]トピックセッション募集
【2】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
【3】地質学雑誌からのお知らせ
【4】Island Arc 編集委員会より
【5】第10回惑星地球フォトコンテスト:審査結果発表!
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.441 2019/02/19 山口大会:トピックセッション募集中
★★目次 ★★
【1】[2019年山口大会]トピックセッション募集
【2】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
【3】支部情報
【4】その他のお知らせ
【5】公募情報・各賞助成情報等
No.440 2019/02/05 割引会費(院生・学部生)の申請は忘れずに!
★★目次 ★★
【1】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
【2】[2019年山口大会]トピックセッション募集
【3】日本地質学会名誉会員候補者の募集について(まもなく締切)
【4】紹介「セザンヌの地質学」
【5】JpGU2019:地質学会が共催するJpGUセッション
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.439 2019/01/22 フォトコンテスト締切間近!
★★目次 ★★
【1】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
【2】第10回惑星地球フォトコンテスト:締切間近!!
【3】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されています
【4】2020年度地震火山こどもサマースクール開催地候補募集
【5】コラム 唐詩にみる石と人の関わり:白居易の「青石」考
【6】支部情報
【7】JPGU2019年大会に関するお知らせ
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.438(臨時) 2019/01/16 中沢圭二 名誉会員 訃報
■ 中沢圭二 名誉会員 ご逝去
No.437 2019/01/08 年頭の挨拶
★★目次 ★★
【1】年頭の挨拶(会長 松田博貴)
【2】第10回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
【3】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されます
【4】2020年度地震火山こどもサマースクール開催地候補募集
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
【8】訃報
No.436 2018/12/18 2019年度会費払込について
★目次
【1】2019年度会費払込について
【2】第10回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
【3】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されます
【4】2020年度地震火山こどもサマースクール開催地候補募集
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
【8】事務局年末年始休業(12/29〜1/6)
No.435 2018/12/4 惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
★目次
【1】つくば特別大会終了
【2】第10回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
【3】一家に一枚ポスター:企画提案が採択されました
【4】2019年度会費払込について
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
No.434 2018/11/29(臨時)つくば特別大会最終案内
★目次
【1】つくば特別大会のお知らせ
【2】発表者の方へ(口頭・ポスター)
【3】【会員カード】を忘れずにお持ち下さい
【4】講演プログラム:座長の情報を追加しました
【5】自動車でおいでの方へ
【6】その他のご案内
【7】地質標本館特別展示:開催中
【8】「地質情報展」を実現のためのクラウドファンディングのお願い
No.433 2018/11/20 2019年度各賞候補者募集:まもなく締切!!
★★目次 ★★
【1】つくば特別大会のお知らせ(講演プログラムほか)
【2】2019年度各賞候補者募集:まもなく締切(11/30締切)
【3】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
【4】第10回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
No.432 2018/11/16 (臨時)つくば特別大会:講演プログラム 決定
★★目次 ★★
【1】つくば特別大会:講演プログラム 決定
No.431 2018/11/6 2019年度各賞候補者募集中(11/30締切)
★★目次 ★★
【1】つくば特別大会のお知らせ
【2】2019年度各賞候補者募集中(11/30締切)
【3】2019年度の会費払込について(割引会費申請受付中)
【4】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
【5】第10回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】訃報
No.430 2018/10/31 (臨時)熊井久雄名誉会員 ご逝去
No.429 2018/10/16 つくば特別大会:発表希望等の確認をお願いします
★★目次 ★★
【1】つくば特別大会のお知らせ
【2】つくば特別大会:発表希望等の確認をお願いします(回答期日:10/31)
【3】つくば特別大会:緊急展示の申込について
【4】札幌大会の参加登録費,巡検費用の返金について
【5】第10回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
【6】2018年度各賞候補者募集について
【7】2019年度の会費払込について(割引会費申請受付開始)
【8】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
【9】次期地震火山観測研究計画 パブリックコメント募集
【10】支部情報
【11】その他のお知らせ
【12】公募情報・各賞助成情報等
No.428 2018/10/02 [札幌大会:今後の対応]つくば特別大会実施
★★目次 ★★
【1】[札幌大会:今後の対応]つくば特別大会実施のお知らせ
【2】[札幌大会:今後の対応]参加登録費,巡検費用の返金について
【3】2018年度各賞候補者募集について
【4】2019年度の会費払込について(割引会費申請受付開始)
【5】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.427 2018/09/18 札幌大会:今後の対応について
★★目次 ★★
【1】[札幌大会:今後の対応]参加登録費,巡検費用の返金について
【2】[札幌大会:今後の対応]緊急アンケート実施中
【3】[札幌大会:今後の対応]行事催行中止の証明
【4】[札幌大会:今後の対応]領収書の発行について
【5】[札幌大会:今後の対応]CPD単位の発行について
【6】[札幌大会:今後の対応]忘れ物をお預かりしています
【7】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
【8】一家に1枚ポスター企画案に投票に参加しましょう!
【9】地質学雑誌のあり方についてのアンケート
【10】支部情報
【11】その他のお知らせ
【12】公募情報・各賞助成情報等
No.426(臨時)北海道胆振東部地震 会長声明 & 会員の皆様へ
★★目次 ★★
【1】会長談話
【2】会員の皆様へ
【3】安否確認のお願い
【4】緊急調査のお願い
No.425 2018/9/5 札幌大会スタート!
★★目次 ★★
【1】[2018札幌大会]札幌大会スタート
会場の様子、表彰式の写真など
No.424 2018/9/4 札幌大会まもなく開催(台風21号の対応)
★★目次 ★★
【1】[2018札幌大会]札幌大会まもなく開催(台風21号の対応)
【2】[2018札幌大会]会場変更,講演キャンセルなど
【3】[2018札幌大会]発表者の皆様へ
【4】[2018札幌大会]ポスター会場のご案内
【5】[2018札幌大会]懇親会にご参加下さい
【6】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
【7】一家に1枚ポスター企画案に投票に参加しましょう!
【8】地質学雑誌のあり方についてのアンケート
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
No.423(臨時) 2018/8/27 小林英夫 名誉会員 ご逝去
■ 小林英夫 名誉会員 ご逝去
No.422 2018/8/21 おめでとう地学オリンピック!世界第2位
★★目次 ★★
【1】おめでとう地学オリンピック!歴代最高の成績で世界第2位
【2】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
【3】[2018札幌大会]札幌大会開催まであと2週間です
【4】[2018札幌大会]全体日程表の訂正
【5】地質学雑誌のあり方についてのアンケート
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.421 2018/8/9 発表公募:西日本豪雨災害の緊急報告会
★★目次 ★★
【1】西日本豪雨災害の緊急報告会(9/10開催)への発表公募
No.420 2018/8/7 災害に関連した会費の特別措置
★★目次 ★★
【1】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
【2】国際年代層序表(日本語版)の更新
--------------------------------------------
[2018札幌大会・関連情報]
【3】事前参加登録 まもなく締切です!
【4】懇親会にも是非ご参加下さい
【5】緊急展示のお申込について
【6】全体日程表の訂正(懇親会の時間)
【7】夜間小集会「地質学の大型研究」の案内
【8】会場での受付には「会員カード」を忘れずに!
--------------------------------------------
【9】地震火山子どもサマースクールの2019年度開催地決定
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
No.419 2018/7/18 札幌大会プログラムを公開しました
★★目次 ★★
【1】[2018札幌大会]全体日程表・講演プログラムを公開しました
【2】[2018札幌大会]緊急展示のお申込について
【3】[2018札幌大会]事前参加登録受付中です!
【4】[2018札幌大会]巡検申込状況:申込はお早めに!
【5】[2018札幌大会]若手会員のための地質関連企業研究サポート
【6】[2018札幌大会]宿泊予約もお早めに
【7】[2018札幌大会]会場での受付には「会員カード」を忘れずに!
【8】地質学雑誌のあり方についてのアンケート
【9】大学院生の研究・生活実態に関するアンケート調査ご協力のお願い
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
No.418 2018/7/11 No.418(臨時)台風第7号及び前線等に伴う大雨に関して
★★目次 ★★
【1】[会員各位]台風第7号及び前線等に伴う大雨に関して
No.417 2018/7/3「チバニアン」に関する声明
★★目次 ★★
【1】「チバニアン」に関する声明
【2】地質学雑誌のあり方についてのアンケート
【3】[2018札幌大会]事前参加登録受付中です!
【4】[2018札幌大会]巡検申込状況:申込はお早めに!
【5】[2018札幌大会]若手会員のための地質関連企業研究サポート
【6】[2018札幌大会]宿泊予約もお早めに
【7】[2018札幌大会]会場での受付には「会員カード」を忘れずに!
【8】本の紹介:素敵な石ころの見つけ方
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
No.416 2018/6/19 会長就任挨拶/地質雑あり方アンケート ほか
★★目次 ★★
【1】会長就任挨拶
【2】地質学雑誌のあり方についてのアンケート
【3】[2018札幌大会]事前参加登録受付中です!
【4】[2018札幌大会]巡検申込状況:申込はお早めに!
【5】[2018札幌大会]宿泊予約もお早めに
【6】[2018札幌大会]大会へお子様をお連れになる予定の方へ
【7】125周年記念「ジオルジュ」英語版特別号:配布協力のお願い
【8】地震火山こどもサマースクール in 伊豆大島:参加者募集
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
No.415 2018/6/11 (臨時)締切まであと2日!札幌大会講演申込
★★目次 ★★
【1】[2018札幌大会]講演申込 締切まであと2日!
【2】[2018札幌大会]事前参加登録受付中です!
【3】[2018札幌大会]宿泊予約はお早めに
【4】[札幌大会関連情報]大会へお子様をお連れになる予定の方へ
No.414 2018/6/5 札幌大会:講演申込 締切まであと1週間
★★目次 ★★
【1】[2018札幌大会]事前参加登録受付中です!
【2】[2018札幌大会]講演申込 締切まであと1週間
【3】[2018札幌大会]ランチョン・夜間集会明日(6/6)締切です
【4】[2018札幌大会]宿泊予約はお早めに
【5】地震火山こどもサマースクール in 伊豆大島:参加者募集
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.413 2018/5/15 創立125周年記念式典(5/18)
★★目次 ★★
【1】創立125周年記念式典(5/18)
【2】[2018札幌大会]講演申込受付中!
【2】[2018札幌大会]ランチョン・夜間集会申込受付中!
【4】[2018札幌大会]宿泊予約はお早めに
【5】日本地質学会第10回総会(5/19)
【6】ミニシンポ「日本地質学会のジオパークへの学術的貢献」(5/19)
【7】IAR論文投稿ワークショップ:アクセプトされる論文のヒント
【8】2018年「地質の日」記念行事のご案内
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
【12】訃報:徳永重元 名誉会員 ご逝去
No.412 2018/5/1 札幌大会講演申込受付開始です!
★★目次 ★★
【1】[2018札幌大会]講演申込を開始しました
【2】[2018札幌大会]ランチョン・夜間集会申込受付中
【3】[2018札幌大会]宿泊予約はお早めに
【4】[125周年関連情報]祝賀会参加申込(まだ間に合います)
【5】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【6】日本地質学会第10回総会開催(5/19)
【7】IAR論文投稿ワークショップ:アクセプトされる論文のヒント
【8】2018年「地質の日」記念行事のご案内
【9】「伊豆半島」がユネスコ世界ジオパークに認定!
【10】支部情報
【11】その他のお知らせ
【12】公募情報・各賞助成情報等
No.411 2018/4/17 WEB教材「ボクたちの“足もと”から地球のことを知ろう」が完成しました
★★目次 ★★
【1】[125周年関連情報]祝賀会参加申込(まだ間に合います)
【2】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【3】[札幌大会関連情報]まもなく講演申込を開始します
【4】[札幌大会関連情報]シンポ,セッションが確定しました
【5】[札幌大会関連情報]宿泊予約はお早めに
【6】WEB教材「ボクたちの“足もと”から地球のことを知ろう」が完成しました
【7】2018年「地質の日」記念行事のご案内
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
No.410 2018/4/4 ミニシンポ「日本地質学会のジオパークへの学術的貢献」
★★目次 ★★
【1】[125周年関連情報]祝賀会参加申込のご案内
【2】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【3】ミニシンポジウム「日本地質学会のジオパークへの学術的貢献」
【4】地学教育関連の意見書・パブリックコメントを提出しました
【5】2018年「地質の日」記念行事のご案内
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.409 2018/3/20 今年も5/10は「地質の日」!
★★目次 ★★
【1】[125周年関連情報]祝賀会参加申込のご案内
【2】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【3】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月30日
【4】2017年度版会員名簿発行
【5】2018年「地質の日」記念行事のご案内
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
No.408 2018/3/6 札幌大会トピックセッション募集中
★★目次 ★★
【1】[2018札幌大会情報]トピックセッション募集中
【2】[125周年関連情報]祝賀会参加申込のご案内
【3】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【4】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月30日
【5】第9回惑星地球フォトコンテスト:審査結果発表!
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.407 2018/2/20 2018年度役員選挙(結果報告)
★★目次 ★★
【1】2018年度役員選挙(結果報告)
【2】[125周年関連情報]記念式典のご案内
【3】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【4】[2018札幌大会情報]トピックセッション募集
【5】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月30日
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.406 2018/2/6 2018札幌大会:トピックセッション募集
★★目次 ★★
【1】[125周年関連情報]記念式典のご案内
【2】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【3】[2018札幌大会情報]トピックセッション募集
【4】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月30日
【5】名誉会員候補者の募集について
【6】JpGU2018:地質学会が共催するJpGUセッション
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.405 2018/1/23 大型研究計画ヒアリングに向けて
★★目次 ★★
【1】大型研究計画ヒアリングに向けて
【2】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月30日
【3】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【4】名誉会員候補者の募集が開始されています
【5】コラム:日本ナップ説略史
【6】第20回地震火山こどもサマースクール開催地候補募集
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.404 2018/1/16 (臨時)堀口萬吉 名誉会員 ご逝去
■ 堀口萬吉 名誉会員 ご逝去
No.403 2018/1/9 謹賀新年:いよいよ125周年です
★★目次 ★★
【1】年頭の挨拶(会長 渡部芳夫)
【2】第9回惑星地球フォトコンテスト:まもなく締切!
【3】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【4】名誉会員候補者の募集が開始されています
【5】第20回地震火山こどもサマースクール開催地候補募集
【6】Island Arc からのお知らせ(最新号発行)
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】岡田博有 名誉会員 ご逝去
No.402 2017/12/19 No.402フォトコンテスト締め切りはお正月明けです!
★★目次 ★★
【1】「正・副会長候補者の意向調査」実施中(1/8締切)
【2】2018年度会費払込について
【3】第9回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
【4】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【5】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されます
【6】第20回地震火山こどもサマースクール開催地候補募集
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】事務局年末年始休業(12/29〜1/4)
No.401 2017/12/5 No.401「正・副会長候補者の意向調査」実施中(1/8締切)
★★目次 ★★
【1】「正・副会長候補者の意向調査」実施中(1/8締切)
【2】2018年度会費払込について
【3】会員名簿データを整理中です.住所変更はお早めに!
【4】第9回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
【5】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.400 2017/11/27(臨時)山本高司 副会長 ご逝去
■ 山本高司 副会長 ご逝去
No.399 2017/11/21 各賞候補者募集まもなく締切です
★★目次 ★★
【1】2018年度各賞候補者募集:まもなく締切(11/30締切)
【2】2018年度代議員および役員選挙
【3】会員証(会員カード)をお送りします!(11/25頃)
【4】2018年度会費払込について
【5】会員名簿データを整理中です.住所変更はお早めに!
【6】第9回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
【7】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
No.398 2017/11/10(臨時)2018年度代議員選挙/会員カード発行
★★目次 ★★
【1】2018年度代議員選挙について
【2】会員証(会員カード)をお送りします
【3】2018年度各賞候補者募集中(11/30締切)
No.397 2017/11/7 2018年度学生・院生の割引会費申請受付開始
★★目次 ★★
【1】[愛媛大会]台風によるプログラム中止となった要旨の取り扱い
【2】2018年度会費払込(学生・院生の割引会費申請受付開始)
【3】会員名簿データを整理中です。住所変更はお早めに!
【4】2018年度代議員および役員選挙
【5】2018年度各賞候補者募集中(11/30締切)
【6】第9回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
【7】コラム:地質調査にあたって保護法令などの遵守を
【8】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
No.396 2017/11/2(臨時)代議員選挙:11月6日(月)18時 立候補届け締切です!
No.395 2017/10/17 [愛媛大会]プログラム中止の要旨等の取り扱い
★★目次 ★★
【1】台風18号によるプログラム中止となった講演要旨等の取り扱い
【2】会員名簿データを整理中です。住所変更はお早めに!
【3】2018年度代議員および役員選挙について
【4】2018年度各賞候補者募集について
【5】日本地方地質誌全8巻完結!「2.東北地方」会員特別割引販売中
【6】第9回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
【7】[125周年関連情報]オリジナルクリアファイル完成
【8】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
No.394 2017/10/3 2018年度代議員選挙立候補:まもなく受付開始
★★目次 ★★
【1】2018年度代議員および役員選挙について
【2】2018年度各賞候補者募集について
【3】日本地方地質誌全8巻完結「2.東北地方」会員特別割引販売のお知らせ
【4】第9回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
【5】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【6】日本地球惑星科学連合:代議員選挙投票のお願い
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.393 2017/9/19 2018年度代議員および役員選挙について
★★目次 ★★
【1】2018年度代議員および役員選挙について
【2】2018年度各賞候補者募集について
【3】日本地方地質誌全8巻完結!「2.東北地方」特別割引販売のお知らせ
【4】愛媛大会の忘れ物をお預かりしています
【5】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.392 2017/9/18(臨時)[愛媛大会]最終日
★★目次 ★★
【1】愛媛大会 2日目と最終日の様子
No.391 2017/9/18(臨時)[愛媛大会]台風一過
★★目次 ★★
【1】台風18号接近に伴う対応について
No.390 2017/9/17(臨時)[愛媛大会]17日の全行事中止
★★目次 ★★
【1】台風18号接近に伴う対応について(9月17日12時)
No.389 2017/9/17(臨時)[愛媛大会]17日午前の行事中止
★★目次 ★★
【1】台風18号接近に伴う対応について(9月17日7時)
No.388 2017/9/16(臨時)[愛媛大会]スタート!
★★目次 ★★
【1】愛媛大会:初日の様子(表彰式の写真アリ)
【2】愛媛大会:台風18号接近に伴う対応(既報済)
No.387 2017/9/16(臨時)[愛媛大会]台風18号接近に伴う対応について(
★★目次 ★★
【1】[愛媛大会]台風18号接近に伴う対応について(9月16日15時)
No.386 2017/9/14(臨時)[愛媛大会]台風18号接近に伴う対応について
★★目次 ★★
【1】[愛媛大会]台風18号接近に伴う対応について
No.385 2017/9/5 国際地学オリ金メダル獲得!/愛媛大会情報ほか
★★目次 ★★
【1】国際地学オリンピック:日本代表選手が金メダル2,銀メダル2を受賞
------------------------------------
【2】[愛媛大会情報]予約確認書を発送しました
【3】[愛媛大会情報]講演プログラム公開中です
【4】[愛媛大会情報]発表者の皆様へ
【5】[愛媛大会情報]講演キャンセル,発表者変更希望がある場合
【6】[愛媛大会情報]宿泊地アンケートにご協力ください
------------------------------------
【7】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
【8】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
No.384 2017/8/17[愛媛大会]事前参加登録まもなく締切です!
★★目次 ★★
【1】[愛媛大会情報]事前参加登録まもなく締切です!
【2】[愛媛大会情報]講演プログラム公開中
【3】[愛媛大会情報]緊急展示募集中です(締切:8/31)
【4】[愛媛大会情報]宿泊予約に関する情報
-------------------------------------------------------------
【5】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
【6】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【7】惑星地球フォトコンテスト:まもなく応募受付開始です
【8】コラム:日本地質図百景
【9】その他のお知らせ
No.383 2017/8/1[愛媛大会]講演プログラムを公開しました
★★目次 ★★
【1】[愛媛大会情報]講演プログラムを公開しました
【2】[愛媛大会情報]巡検申込はお早めに
【3】[愛媛大会情報]緊急展示募集中です(締切:8/31)
【4】[愛媛大会情報]事前参加登録受付中:要旨集は事前予約を!
-------------------------------------------------------------------
【5】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
【6】一家に1枚 ポスターの企画案「県の石でわかる 日本の大地のつくり」
【7】地層処分に関わる「科学的特性マップ」が公表されました
【8】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
No.382 2017/7/18 愛媛大会:巡検申込はお早めに
★★目次 ★★
[愛媛大会情報]
【1】巡検申込はお早めに
【2】緊急展示を募集します(締切:8/31)
【3】宿泊希望者受付【学生限定】残りわずか
【4】事前参加登録:受付中
【5】講演要旨集は事前予約をお願いします
-------------------------------------------------------
【6】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.381 2017/7/11(臨時) 平成29年 九州北部豪雨に関して
★★目次 ★★
【1】平成29年 九州北部豪雨に関して
No.380 2017/7/4 愛媛大会演題登録:明日(7/5)18時締切です!
★★目次 ★★
[愛媛大会情報]
【1】演題登録:明日(7/5)18時締切です!
【2】宿泊希望者募集中【学生限定】
【3】事前参加登録:受付中
【4】おもな申込締切
---------------------------------------------------------------
【5】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【6】お知らせ:NHKスペシャル シリーズ 列島誕生 ジオ・ジャパン
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.379 2017/6/30 (臨時)愛媛大会:演題登録締切まで残り5日!
★★目次 ★★
[愛媛大会:臨時号]
【1】演題登録締切まで残り5日! 7月5日(水)18時締切
【2】宿泊希望者募集中【学生限定】
【3】事前参加登録:受付中
【4】おもな申込締切
No.378 2017/6/26 (臨時)愛媛大会:宿泊希望者募集【学生限定】
★★目次 ★★
[愛媛大会情報]
【1】宿泊希望者募集【学生限定】
【2】その他の宿泊情報
【3】まずは演題登録専用のアカウント登録を!
【4】おもな申込締切
No.377 2017/6/20 愛媛大会演題登録:まずはアカウント登録を!
★★目次 ★★
[愛媛大会情報]
【1】事前参加登録:受付中
【2】まずは演題登録専用のアカウント登録を!
【3】ランチョン・夜間小集会:受付中
【4】おもな申込締切
-----------------------------------------------------
【5】2017年度会費督促請求について
【6】[125周年関連情報]寄付のお願い
【7】[125周年関連情報]お願い:会員氏名のローマ字表記について
【8】フォトコンテスト入選作品展示会(in 銀座)開催中
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
No.376 2017/6/6 愛媛大会事前参加登録:受付開始
★★目次 ★★
[愛媛大会情報]
【1】事前参加登録:受付開始しました
【2】まずは演題登録専用のアカウント登録を!
【3】ランチョン・夜間小集会:受付中
【4】企業等団体展示・書籍販売・広告協賛の募集
【5】おもな申込締切
---------------------------------------------------------------
【6】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【7】[125周年関連情報]お願い:会員氏名のローマ字表記について
【8】2017年「地質の日」イベント情報
【9】山形県地質図(10万分の1)割引販売のお知らせ
【10】支部情報
【11】その他のお知らせ
【12】公募情報・各賞助成情報等
【13】訃報 藤井昭二 名誉会員 ご逝去
No.375 2017/5/31 (臨時)愛媛大会演題登録受付開始
★★目次 ★★
[愛媛大会関連情報]
【1】愛媛大会の演題登録受付を開始しました(7/5締切)
【2】ランチョン・夜間小集会:受付中
No.374 2017/5/16 愛媛大会学会専用宿泊予約サイト:申込受付開始
★★目次 ★★
【1】[愛媛大会関連情報]学会専用宿泊予約サイト 申込受付開始
【2】[愛媛大会関連情報]演題登録:まもなく受付開始です
【3】日本地質学会第9回総会開催
【4】[125周年関連情報]お願い:会員氏名のローマ字表記について
【5】Island Arc:論文ワークショップ「アクセプトされる論文の書き方」
【6】2017年「地質の日」イベント情報
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】訃報 相原安津夫 名誉会員 ご逝去
No.373 2017/5/2 日本地質学会第9回総会開催
★★目次 ★★
【1】日本地質学会第9回総会開催
【2】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【3】2017年「地質の日」イベント情報
【4】支部情報
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
No.372 2017/4/17 「巡検時等における車両運行指針」の策定に関して
★★目次 ★★
【1】「巡検時等における車両運行指針」の策定に関して
【2】声明発表:地質学の知見をもって減災につなげるために 熊本地震から一年を迎えるにあたって
【3】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【4】2017年「地質の日」イベント情報
【5】Island Arc:論文ワークショップ「アクセプトされる論文の書き方」
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.371 2017/4/13 (臨時)愛媛大会の宿泊予約に関するお知らせ
★★目次 ★★
【1】愛媛大会の宿泊予約に関するお知らせ
No.370 2017/4/4 125周年:寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
★★目次 ★★
【1】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【2】第8回惑星地球フォトコンテスト:表彰式・展示会
【3】2017年「地質の日」イベント情報
【4】RFG2018:セッション提案募集(5/1締切)
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
No.369 2017/3/21 愛媛大会トピックセッション決定
★★目次 ★★
【1】[2017愛媛大会情報]トピックセッション決定
【2】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【3】第8回惑星地球フォトコンテスト:入選作品
【4】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日
【5】2017年「地質の日」イベント情報
【6】Island Arc編集事務局の連絡先変更
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.368 2017/3/7 第8回惑星地球フォトコンテスト:審査結果発表!
★★目次 ★★
【1】第8回惑星地球フォトコンテスト:審査結果発表!
【2】[2017愛媛大会情報]トピックセッション募集:まもなく締切り!
【3】[125周年関連情報]記念事業の概要/記念事業に対する寄付のお願い
【4】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日
【5】2017年「地質の日」イベント情報
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.367 2017/2/21 愛媛大会トピックセッション募集中
★★目次 ★★
【1】[2017愛媛大会情報]トピックセッション募集中
【2】[125周年関連情報]記念事業の概要/記念事業に対する寄付のお願い
【3】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日
【4】2018年度地震火山こどもサマースクール開催地の公募
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
No.366 2017/2/7第124年学術大会(2017愛媛大会)開催通知
★★目次 ★★
【1】第124年学術大会(2017愛媛大会)開催通知/トピックセッション募集
【2】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日
【3】日本地質学会名誉会員候補者の募集はまもなく締切です
【4】2018年度地震火山こどもサマースクール開催地の公募
【5】コラム:テクタイトの給源クレーター
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.365 2017/1/31(臨時)学会創立125周年記念事業と寄付のお願い
★★目次 ★★
【1】学会創立125周年記念事業の概要とそれを成功させるための寄付のお願い
【2】学会創立125周年記念ロゴについて
No.364 2017/1/17 割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!
★★目次 ★★
【1】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日
【2】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されています
【3】支部情報
【4】その他のお知らせ
【5】公募情報・各賞助成情報等
No.363 2017/1/5 新年あけましておめでとうございます
★★目次 ★★
【1】年頭挨拶:日本地質学会創立125周年を迎えるにあたって
【2】惑星地球フォトコンテスト:まもなく締め切り!
【3】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されます
【4】第3回防災学術連携シンポ熊本地震・一周年報告会(仮)発表募集
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
No.362 2016/12/20 125周年記念特集号の状況
★★目次 ★★
【1】125周年記念特集号の状況について
【2】2017年度会費払込について
【3】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されます
【4】惑星地球フォトコンテスト:締め切り本年度は正月明けです!
【5】第3回防災学術連携シンポ熊本地震・一周年報告会(仮)発表募集
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】事務局年末年始休業(12/29〜1/4)
No.361 2016/12/6 惑星地球フォトコンテスト締め切りは正月明けです!
★★目次 ★★
【1】2017年度会費払込について
【2】惑星地球フォトコンテスト:締め切り本年度は正月明けです!
【3】支部情報
【4】その他のお知らせ
【5】公募情報・各賞助成情報等
【6】訃報:江 博明(JAHN, Bor-ming)教授 ご逝去
No.360 2016/11/15 “各賞候補者募集” まもなく締切です!
★★目次 ★★
【1】2017年度各賞候補者募集中(11/30締切!!)
【2】「院生割引会費」受付中:忘れずに申請して下さい!
【3】惑星地球フォトコンテスト:締め切り本年度は正月明けです!
【4】支部情報
【5】専門部会より
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
【8】訃報:倉沢 一 名誉会員 ご逝去
No.359 2016/11/1 フォトコンテスト:本年度の締切は正月明け!
★★目次 ★★
【1】2017年度各賞候補者募集中(11/30締切!!)
【2】「院生割引会費」受付中:忘れずに申請して下さい!
【3】惑星地球フォトコンテスト:締め切り本年度は正月明けです!
【4】「博士人材追跡調査」の実施について
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
No.358 2016/10/18 2017年度各賞候補者募集中/割引会費申請(忘れずに!)
★★目次 ★★
【1】2017年度各賞候補者募集中
【2】「院生割引会費」受付中:2017年度会費払込について
【3】惑星地球フォトコンテスト:応募受付中
【4】支部情報
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
No.357 2016/10/4 2017年度各賞候補者募集開始
★★目次 ★★
【1】2017年度各賞候補者募集開始
【2】「院生割引会費」受付開始:2017年度会費払込について
【3】『フィールドジオロジー全9巻』電子本の販売が開始されました
【4】惑星地球フォトコンテスト:応募受付中
【5】男女共同参画学協会連絡会大規模アンケートへのご協力のお願い
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.356 2016/9/20 東京・桜上水大会 終了しました!
★★目次 ★★
【1】東京・桜上水大会 終了しました!
【2】惑星地球フォトコンテスト:応募受付中
【3】イタリアのラクイラ地震裁判その後
【4】「The Geology of Japan」正誤表
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
No.355 2016/9/12 東京・桜上水大会]大会最終日!巡検いってらっしゃい
★★目次 ★★
【1】東京・桜上水大会最終日の様子
No.354 2016/9/11[東京・桜上水大会]2日目!大会Go!
★★目次 ★★
【1】東京・桜上水大会2日目の様子
No.353 2016/9/10 (臨時)東京・桜上水大会開幕!
★★目次 ★★
【1】東京・桜上水大会初日の様子
【2】東京・桜上水大会:9月11日(日)の主なイベント
No.352 2016/9/6 [東京・桜上水大会]いよいよ学術大会が始まります!
★★目次 ★★
【1】[東京・桜上水大会]いよいよ学術大会が始まります
【2】[東京・桜上水大会]予約確認書を発送しました
【3】[東京・桜上水大会]「県の石」制定記念「県の酒」開催します
【4】[東京・桜上水大会]学術大会でCPD単位が取得出来ます
【5】[東京・桜上水大会]講演キャンセル・変更など(9/6現在)
【6】[東京・桜上水大会]参加申込に関わるQ & Aもご利用下さい
------------------------------------------------------------------------------
【7】2016年度秋季地質調査研修参加者募集のご案内
【8】惑星地球フォトコンテスト:応募受付中
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
No.351 2016/8/27 (臨時)国際地学オリンピック 金メダルおめでとう!
★★目次 ★★
【1】国際地学オリンピック 金メダルおめでとう!
No.350 2016/8/17[東京・桜上水大会]参加登録締切延長:19日(金)10時
★★目次 ★★
【1】[東京・桜上水大会]事前参加登録締切延長:19日(金)午前10時
【2】[東京・桜上水大会]その他各種申込も受付中です
【3】[東京・桜上水大会]緊急展示申込受付中
【4】[東京・桜上水大会]参加申込に関わるQ & Aもご利用下さい
------------------------------------------------------------------------------
【5】創立125周年記念ロゴデザイン案:WEB投票実施中
【6】惑星地球フォトコンテスト:応募受付中
【7】支部情報
【8】上砂さんを偲ぶ会(日本地質学会理事)
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
No.349 2016/8/2 [東京・桜上水大会]プログラム公開/巡検申込まもなく締切
★★目次 ★★
【1】[東京・桜上水大会]講演プログラム公開しました
【2】[東京・桜上水大会]巡検申込まもなく締切です!
【3】[東京・桜上水大会]緊急展示申込受付中
【4】[東京・桜上水大会]参加申込に関わるQ&Aもご利用下さい
【5】学会創立125周年記念ロゴデザイン案:WEB投票実施中
【6】惑星地球フォトコンテスト:まもなく応募受付開始です
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】お知らせ:事務局夏期休業と次号配信予定
No.348 2016/7/19 [東京・桜上水大会]全体日程表公開しました
★★目次 ★★
【1】[東京・桜上水大会]全体日程表公開しました
【2】[東京・桜上水大会]事前参加登録受付中です
【3】[東京・桜上水大会]参加申込に関わるQ & Aもご利用下さい
【4】学会創立125周年記念ロゴWEB投票(予告)
【5】第1回防災推進国民大会:大規模災害への備え〜過去に学び未来を拓く〜
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.347 2016/7/5 創立125周年記念ロゴデザイン募集中
★★目次 ★★
【1】[東京・桜上水大会]事前参加登録受付中です
【2】[東京・桜上水大会]講演申込を締切ました
【3】[東京・桜上水大会]参加申込に関わるQ & Aもご利用下さい
【4】学会創立125周年記念ロゴ募集中&WEB投票(予告)
【5】「東日本大震災に関する学術調査・研究活動アンケート」への協力願い
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.346 2016/6/27 (臨時)[東京・桜上水大会]講演申込まもなく締切!(延長なし)
★★目次 ★★[東京・桜上水大会]臨時号
【1】講演申込まもなく締切です!6月29日(水)18時締切(延長なし)
【2】講演申込画面(PASREG):入力時の注意
【3】講演予定者で,現在未入会の方へ周知のお願い
【4】ランチョン・夜間小集会のお申込はお済みですか?(6/29締切)
【5】講演/参加申込に関わるQ & Aもご利用下さい
【6】各種申込み締切のお知らせ
No.345 2016/6/21[東京・桜上水大会]講演申込は来週締切りです!
★★目次 ★★
【1】[東京・桜上水大会]講演申込は来週締切りです!
【2】[東京・桜上水大会]講演予定者で,現在未入会の方へ周知のお願い
【3】[東京・桜上水大会]ランチョン・夜間小集会のお申込はお済みですか?
【4】「平成28年(2016年)熊本地震」による地震災害に関する声明
【5】2016年度会費督促請求について
【6】学会創立125周年記念ロゴ募集中
【7】フォトコンテスト入選作品展示会(in 銀座)開催中
【8】第17回地震火山こどもサマースクール参加者募集
【9】紹介:KAGUYA月面図
【10】支部情報
【11】その他のお知らせ
【12】公募情報・各賞助成情報等
No.344 2016/6/15(臨時)[東京・桜上水大会]事前参加登録受付開始
★★目次 ★★
【1】東京・桜上水大会の事前参加登録受付を開始しました
【2】普及・関連行事の受付を開始しました
【3】演題登録・要旨投稿受付中です!
【4】ランチョン・夜間集会の開催申込も忘れずに!
No.343 2016/6/7 東京・桜上水大会 演題登録受付中!
★★目次 ★★
【1】東京・桜上水大会情報
【2】学会創立125周年記念ロゴ募集開始
【3】フォトコンテスト入選作品展示会(in 銀座)
【4】本の紹介:北海道自然探検 ジオサイト107の旅
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
No.342 2016/5/31(臨時)東京・桜上水大会 演題登録受付開始!
★★目次 ★★
【1】東京・桜上水大会の演題登録受付を開始しました(6/29締切)
【2】災害に関連した会費の特別措置
No.341 2016/5/17 まもなく,東京・桜上水大会の演題登録受付開始!
★★目次 ★★
【1】[予告]まもなく,東京・桜上水大会の演題登録受付を開始します
【2】日本地質学会第8回総会開催
【3】学会創立125周年記念ロゴ募集開始
【4】Island Arc 論文投稿ワークショップ「論文構成法を理解しよう(仮)」
【5】2016年「地質の日」イベント情報
【6】「The Geology of Japan」が出版!:会員特別販売のお知らせ
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.340 2016/5/11(臨時)「県の石」発表!
★★目次 ★★
【1】日本地質学会選定「県の石」発表!
【2】Goldschmidt 2016をより充実したものにするために
No.339 2016/5/2 学会創立125周年記念ロゴ募集開始
★★目次 ★★
【1】学会創立125周年記念ロゴ募集開始
【2】日本地質学会第8回総会開催
【3】平成28年熊本地震に関して
【4】「原子力施設等防災対策等委託費事業」の終了に伴う掘削試料の譲渡
【5】2016年「地質の日」イベント情報
【6】「The Geology of Japan」が出版!:会員特別販売のお知らせ
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】ジオルジュ(2015年後期号)の訂正
No.338 2016/4/19 平成28年熊本地震に関して
★★目次 ★★
【1】平成28年熊本地震に関して
【2】2016年「地質の日」イベント情報
【3】「The Geology of Japan」が出版!:会員特別販売のお知らせ
【4】リーフレット 長瀞たんけんマップ 好評発売中!
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
No.337 2016/4/12(臨時)ゆざわジオパーク学術研究等奨励補助金の募集
★★目次 ★★
【1】ゆざわジオパーク学術研究等奨励補助金の募集
【2】2016年「地質の日」イベント情報
【3】公募情報
No.336 2016/4/5 「The Geology of Japan」が出版
★★目次 ★★
【1】「The Geology of Japan」が出版!:会員特別販売のお知らせ
【2】2016年「地質の日」イベント情報
【3】リーフレット 長瀞たんけんマップ 好評発売中!
【4】支部情報
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
【7】訃報:倉林三郎 名誉会員 ご逝去
No.335 2016/3/22(臨時)平成28年度大学入試センター試験の地学関連科目に関する申し入れ
★★目次 ★★
【1】平成28年度大学入試センター試験の地学関連科目に関する申し入れ
No.334 2016/3/15 2016年理事および監事選挙(結果報告)
★★目次 ★★
【1】2016年理事および監事選挙(結果報告)
【2】第7回惑星地球フォトコンテスト:審査結果
【3】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(木)
【4】2016年「地質の日」イベント情報
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
【8】地質マンガ「どっちもポットホール」
No.333 2016/3/1 長瀞たんけんマップ 新発売!
★★目次 ★★
【1】リーフレット 長瀞たんけんマップ 新発売!
【2】2016東京・桜上水大会:トピックセッション募集中
【3】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(木)
【4】日本地方地質誌7。四国地方 2月下旬刊行(会員特別割引販売)
【5】荒川忠彦会員、第47回東レ理科教育賞 受賞
【6】2016年「地質の日」イベント情報
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】地質マンガ「ふん化石のいろいろ」
No.332 2016/2/16 第7回惑星地球フォトコンテスト:締め切り間近です!!
★★目次 ★★
【1】2016年度一般社団法人日本地質学会理事および監事選挙について
【2】第7回惑星地球フォトコンテスト:締め切り間近です
【3】125周年記念地質学雑誌特集号の状況について
【4】2016東京・桜上水大会:トピックセッション募集中
【5】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(木)
【6】日本地方地質誌7.四国地方 2月下旬刊行(会員特別割引販売)
【7】Wiley 東日本大震災3.11から5年 学術論文特集 無料公開中(4/30まで)
【8】本の紹介「巨大地震による複合災害」
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
No.331 2016/2/2 2016東京・桜上水大会:トピックセッション募集中!
★★目次 ★★
【1】2016東京・桜上水大会:トピックセッション募集中
【2】高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する「科学的有望地の要件・基準
に関する地層処分技術WGにおける中間整理」について、専門家からの意見募集
【3】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(木)
【4】名誉会員の推薦が開始されました
【5】第7回惑星地球フォトコンテスト:締切間近です
【6】日本地方地質誌7.四国地方 2月下旬刊行(会員特別割引販売)
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.330 2016/1/25 (臨時)
★★目次 ★★
【1】高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する「科学的有望地の要件・基準に関する地層処分技術WGにおける中間整理」について、専門家からの意見募集
【2】中間整理についての説明会を開催(2月29日)
No.329 2016/1/19 会長・副会長立候補意思表明者にたいする意向調査結果報告
★★目次 ★★
【1】会長・副会長立候補意思表明者にたいする意向調査結果報告
【2】第123年学術大会(2016東京・桜上水大会)開催通知
【3】学術大会に関わるアンケート
【4】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(木)
【5】名誉会員の推薦が開始されました
【6】第7回惑星地球フォトコンテスト:作品募集中
【7】 IGCP608「白亜紀アジア−西太平洋生態系」第4回国際研究集会FirstCircular 配布開始
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
【11】地質マンガ「地質マンガの宿題」
No.328 2016/1/5 平成28年(2016年)第1号!
★★目次 ★★
【1】年頭にあたって(会長 井龍康文)
【2】高レベル放射性廃棄物の最終処分場に関する説明会(1/23)
【3】高等学校理科用『地学』教科書の記述内容に関する意見書
【4】「正・副会長候補者の意向調査」を実施中です(1/9締切)
【5】学術大会に関わるアンケート
【6】名誉会員の推薦が開始されました
【7】第7回惑星地球フォトコンテスト:作品募集中
【8】「日本地方地質誌」完結と「The Geology of Japan」出版
【9】本の紹介 ネパールに学校をつくる:協力隊OBの教育支援35年
【10】支部情報
【11】その他のお知らせ
【12】公募情報・各賞助成情報等
【13】地質マンガ「空から見れば」
No.327 2015/12/15 「正・副会長候補者の意向調査」実施中(1/9締切)
★★目次 ★★
【1】「正・副会長候補者の意向調査」を実施中です(1/9締切)
【2】学術大会に関わるアンケート(1月末締切)
【3】2016年度会費払込のお知らせ
【4】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されます
【5】Island Arcが新しく変わります
【6】2017年度地震火山こどもサマースクール開催地候補募集
【7】第7回惑星地球フォトコンテスト:作品募集中
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
No.326 2015/12/1 第7回惑星地球フォトコンテスト:作品募集中
★★目次 ★★
【1】2016年度会費払込のお知らせ
【2】第7回惑星地球フォトコンテスト:作品募集中
【3】支部情報
【4】その他のお知らせ
【5】公募情報・各賞助成情報等
【6】地質マンガ「GEOって !?」
No.325 2015/11/25 (臨時)勝井 義雄 名誉会員 ご逝去
No.324 2015/11/19 (臨時)ジオパークのユネスコ正式事業化決定!
【1】ジオパークのユネスコ正式事業化決定!
No.323 2015/11/17 各賞候補者募集 11/30締切です!
★★目次 ★★
【1】2016年度各賞候補者募集について(11/30締切)
【2】創立125周年記念事業:地質学雑誌特集号の募集
【3】2016年度会費払込のお知らせ
【4】第7回惑星地球フォトコンテスト:作品募集中
【5】支部情報
【6】専門部会より
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】地質マンガ「大学でも全裸に見えるポーズがあるんです !?」
No.322 2015/11/10 (臨時)2016年度代議員選挙について
★★目次 ★★
【1】2016年度代議員選挙について
【2】2016年度各賞候補者募集について(11/30締切)
No.321 2015/11/5 (臨時)代議員選挙:明日(6日)立候補締切です
No.320 2015/11/2 代議員選挙 まもなく立候補締切です!
★★目次 ★★
【1】2016年度代議員および役員選挙 まもなく立候補締切!
【2】2016年度各賞候補者募集について
【3】「割引会費」申請受付中:2016年度会費払込について
【4】創立125周年記念事業:地質学雑誌特集号の募集
【5】第7回惑星地球フォトコンテスト:作品募集!
【6】支部情報
【7】「県の石」選定作業について
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.319 2015/10/20 2016年度代議員および役員選挙立候補受付開始!
★★目次 ★★
【1】2016年度代議員および役員選挙について
【2】2016年度各賞候補者募集について
【3】「割引会費」申請受付開始:2016年度会費払込について
【4】創立125周年記念事業:地質学雑誌特集号の募集
【5】第7回惑星地球フォトコンテスト:作品募集!
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.318 2015/10/13 (臨時)次期大型研究計画への新規提案についての問合せ
No.317 2015/10/06 2016年度代議員および役員選挙
【1】2016年度代議員および役員選挙について
【2】2016年度各賞候補者募集について
【3】「割引会費」申請受付開始:2016年度会費払込について
【4】創立125周年記念事業:地質学雑誌特集号の募集
【5】第7回惑星地球フォトコンテスト:間もなく応募開始です
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.316 2015/9/25(臨時)小畠郁生 名誉会員 ご逝去
No.315 2015/9/15 長野大会 終了しました!
【1】長野大会 終了しました!
【2】創立125周年記念事業:地質学雑誌特集号の募集
【3】秋季地質調査研修:申込受付始まる!
【4】名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
No.314 2015/9/13 [長野大会臨時号]大会最終日!
【1】長野大会最終日!
No.313 2015/9/12 [長野大会臨時号]大会2日目!
【1】長野大会2日目!
【2】長野大会:9月13日(日)の主なイベント
No.312 2015/9/11 [長野大会臨時号]長野大会スタート!
【1】長野大会初日の様子
【2】長野大会:9月12日(土)の主なイベント
No.311 2015/9/10 [長野大会臨時号]9月11日開催!
【1】いよいよ長野大会が始まります!
【2】特別講演会「地質地盤情報の利活用と法整備」
【3】講演キャンセル・一部プログラム変更のお知らせ(10日17時現在)
【4】地質図を利用した商品「Geological Textile」ICA Map Awardsを受賞
No.310 2015/9/1 [長野大会]いよいよ長野大会が始まります!
【1】[長野大会]いよいよ長野大会が始まります!
【2】[長野大会]講演プログラムを公開しました
【3】[長野大会]予約確認書を発送しました
【4】[長野大会]学術大会でCPD単位が取得出来ます
【5】[長野大会]宿泊の手配はお早めに
【6】創立125周年記念事業:地質学雑誌特集号の募集
【7】秋季地質調査研修参加者募集ご案内(予告編)
【8】2015年度会費およびそれ以前の未納会費がある方へ
【9】名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
【10】支部情報
【11】その他のお知らせ
【12】公募情報・各賞助成情報等
No.309 2015/8/18 [長野大会]事前参加登録:本日8/18(火)18時締切!
【1】[長野大会]事前参加登録:本日8/18(火)18時締切!
【2】[長野大会]緊急展示の申込について
【3】[長野大会]宿泊の手配はお早めに
【4】2015年度会費およびそれ以前の未納会費がある方へ
【5】名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.308 2015/8/6 No.308(臨時)[長野大会]巡検参加申込:明日締切です!
【1】[長野大会]巡検参加申込:明日締切です!(8/7締切)
No.307 2015/8/4 [長野大会]巡検申込まもなく締切(8/7締切!!)
【1】[長野大会]巡検申込まもなく締切です!
【2】[長野大会]緊急展示の申込について
【3】[長野大会]宿泊の手配はお早めに
【4】[長野大会]各種申込み締切のお知らせ
【5】名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
【6】 フォトコンテスト入選作品展示会(in 湯島)
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】訃報
【11】訂正
No.306 2015/7/21 [長野大会]事前参加登録受付中!
【1】[長野大会]全体日程表を公開しました
【2】[長野大会]事前参加登録受付中
【3】[長野大会]宿泊の手配はお早めに
【4】[長野大会]緊急展示の申込について
【5】[長野大会]各種申込み締切のお知らせ
【6】名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
No.305 2015/7/10(臨時)イリノイ州立博物館の閉鎖危機について
No.304 2015/7/7 [長野大会]事前参加登録受付中!
★★目次 ★★
【1】[長野大会]事前参加登録受付中
【2】「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく間接経費措置額の削減割合の基準等について
【3】名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
【4】環境地質部会からのお知らせ
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
No.303 2015/6/29(臨時)[長野大会]講演申込明日(6/30)締切(延長なし)
★★目次 ★★
【1】[長野大会]講演申込明日(6/30)締切です!(延長なし)
【2】[長野大会]講演申込画面(PASREG):入力時の注意
【3】[長野大会]申込に関わるQ & Aもご利用下さい
【4】[長野大会]各種申込み締切のお知らせ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【5】高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する「地層処分技術WGのこれまでの
議論の整理」について、専門家からの御意見を募集します
No.302 2015/6/24(臨時)[長野大会]講演申込:もうすぐ締切です!
★★目次 ★★
【1】[長野大会]講演申込:もうすぐ締切です!
【2】[長野大会]講演申込画面(PASREG):入力時の注意
【3】[長野大会]申込に関わるQ & Aもご利用下さい
【4】[長野大会]各種申込み締切のお知らせ
No.301 2015/6/16 [長野大会]事前参加登録受付開始!・演題登録も受付中
★★目次 ★★
【1】[長野大会]事前参加登録受付開始!・演題登録も受付中
【2】[長野大会]ランチョン・夜間小集会のお申込はお済みですか?
【3】[長野大会]キャンセルした講演の講演要旨の扱いについて
【4】[長野大会]講演予定者で,現在未入会の方へ周知のお願い
【5】2015年度会費督促請求について
【6】名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
【7】フォトコンテスト入選作品展示会(in 銀座)開催中です
【8】環境地質部会:関東地下水盆と人工地層の地質環境巡検
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
No.300 2015/6/2 [長野大会]講演申込受付中です
★★目次 ★★
【1】[長野大会]講演申込受付中です(締切:6/30)
【2】口永良部島火山の噴火に関する情報
【3】知床半島羅臼町で海岸線沿い隆起と地すべり調査報告
【4】2015地震火山こどもサマースクール in 南アルプス参加募集
【5】フォトコンテスト入選作品展示会(in 銀座)
【6】関東地下水盆と人工地層の地質環境巡検:参加募集
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
No.299 2015/5/19 [長野大会]5月25日より講演申込受付を開始
★★目次 ★★
【1】[長野大会]5月25日より講演申込受付を開始します
【2】日本地質学第7回総会開催について
【3】Island Arc:論文ワークショップ開催のお知らせ
【4】コラム:国際学術用語となった“人自不整合”
【5】「地質の日」イベント情報
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】地質マンガ 恋する地質学②「彼女より壁ドン?」
【10】籾倉克幹 名誉会員 ご逝去
No.298 2015/5/7 [長野大会]シンポジウム・セッション決定!
★★目次 ★★
【1】[長野大会]シンポジウム・セッション決定
【2】第35回IGC(万国地質学会議)ケープタウン2016年8-9月のご案内
【3】JAMSTEC船舶で取得された海底地形データの不具合について
【4】「地質の日」イベント情報
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞情報等
No.297 2015/5/5(臨時)ネパール地震のテクトニクスとカトマンズの極軟弱地盤
No.296 2015/4/21 「地質の日」イベント情報満載!
★★目次 ★★
【1】理科得点調整および地学関連科目に関して,大学入試センターに申し入れ提出
【2】日本地質学会第7回総会開催のお知らせ
【3】「3D版ELSAMAP日本全図」へのご案内
【4】「地質の日」イベント情報
【5】Island Arc:論文ワークショップ開催のお知らせ
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞情報等
No.294 2015/4/7 第6回惑星地球フォトコンテスト審査結果
★★目次 ★★
【1】第6回惑星地球フォトコンテスト審査結果
【2】次期学習指導要領改訂に関する要望書を文科大臣に提出
【3】都道府県指定の地質・鉱物天然記念物一覧
【4】地質の日イベント情報
【5】地学オリンピックキャラクターデザインコンテスト入賞作品発表
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞情報等
【9】地質マンガ「彼女のために地質学?」
No.293 2015/3/30(臨時)野沢 保名誉会員 訃報
■ 野沢 保 名誉会員 ご逝去
No.291 2015/3/17 割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!
★★目次 ★★
【1】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(火)
【2】2015年度春季地質調査研修 参加者募集中
【3】Arthur Holmes Meeting Tsunami Hazards and Risks: Using the Geological Record
【4】地質の日イベント情報
【5】紹介:Episodes特集号 "Geohazards in Subduction Zone Environments and their Implications for Science and Society"
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞情報等
No.290 2015/3/12(臨時)トピックセッションの募集(3/16締切!)
★★目次 ★★
【1】[長野大会]トピックセッションの募集(3/16締切!)
【2】中期ビジョン中間報告と意見募集(3/15締切!)
【3】ゆざわジオパークの専門員の募集(3/20締切!)
No.289 2015/3/3 プレスリリース「地学の知識を減災のソフトパワーに」!
★★目次 ★★
【1】[長野大会]トピックセッションの募集
【2】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(火)
【3】中期ビジョン中間報告と意見募集
【4】プレスリリース「地学の知識を減災のソフトパワーに—東日本大震災4年目を迎えて—」
【5】Island Arc からのお知らせ
【6】「理科好きな子に育つ ふしぎのお話365」会員特別割引販売のお知らせ
【7】2015年度春季地質調査研修 参加者募集[受付開始!]
【8】地質の日イベント情報
【9】第35回万国地質学会議(IGC)ほかのご案内
【10】支部情報
【11】その他のお知らせ
【12】公募情報・各賞情報等
No.288 2015/2/17[長野大会]トピックセッション募集中!!(締切3/16)
★★目次 ★★
【1】[長野大会]トピックセッションの募集
【2】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(火)
【3】中期ビジョン中間報告と意見募集
【4】広報委員の募集
【5】平成28年度地震火山こどもサマースクール開催地の公募
【6】第7回日本地学オリンピック予選が全国77会場にて実施!
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞情報等
【10】訃報
No.287 2015/2/3[長野大会]トピックセッションの募集!
★★目次 ★★
【1】[長野大会]トピックセッションの募集
【2】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(火)
【3】日本地質学会名誉会員候補者募集中(2/10締切)
【4】中期ビジョン中間報告と意見募集
【5】広報委員の募集
【6】第6回惑星地球フォトコンテスト:間もなく締め切り!
【7】2015年度春季地質調査研修参加者募集[予告]
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞情報等
No.286 2015/2/2(臨時)千地万造名誉会員 訃報
■ 千地万造 名誉会員 ご逝去
No.285 2015/1/20 日本原子力学会による不適切な情報発信に関して_追記
★★目次 ★★
【1】geo-Flash No.284臨時号の追記について
【2】[長野大会]トピックセッションの募集
【3】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(火)
【4】3rd IGCP608 China 2015 & MTE-12のFirst Circular 配布開始
【5】中期ビジョン中間報告と意見募集
【6】広報委員の募集
【7】第6回惑星地球フォトコンテスト:応募受付中!
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞情報等
No.284 2015/1/12(臨時)日本原子力学会による不適切な情報発信に関して
No.283 2015/1/6 平成27年新年号
★★目次 ★★
【1】年頭にあたって
【2】第122年学術大会開催(2015年9月11日〜13日)/トピックセッションの募集
【3】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(火)
【4】中期ビジョン中間報告と意見募集
【5】広報委員の募集
【6】第6回惑星地球フォトコンテスト:応募受付中!
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞情報等
No.282 2014/12/16 平成25年山口・島根豪雨災害の概要と調査報告
★★目次 ★★
【1】2015年度会費払込のお知らせ:ご送金はお早めにお願いします!
【2】第6回惑星地球フォトコンテスト:応募受付中!
【3】地質学雑誌第12号の遅延のおそれ
【4】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されます
【5】2013年(平成25年)山口・島根豪雨災害の概要と調査報告
【6】2014年度秋季地質調査研修の実施報告
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞情報等
No.281 2014/12/2 第6回惑星地球フォトコンテスト:応募受付中!
★★目次 ★★
【1】2015年度会費払込のお知らせ:割引会費の申請は忘れずに!
【2】第6回惑星地球フォトコンテスト:応募受付中!
【3】支部情報
【4】その他のお知らせ
【5】公募情報・各賞情報等
No.280 2014/11/18 日本地質学会各賞候補者募集中!
★★目次 ★★
【1】2015年度一般社団法人日本地質学会各賞候補者募集について
【2】2015年度会費払込のお知らせ—割引会費の申請は忘れずに!
【3】学会ホームページ会員情報システム一時利用停止のお知らせ
【4】第6回惑星地球フォトコンテスト:応募受付開始しました
【5】JISに定められた地質年代の日本語表記
【6】鹿児島学術大会での国際交流
【7】2014年7月9日南木曽,8月6日岩国,8月17日福知山・丹波における土砂災害
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞情報等
No.279 2014/10/21 ホームページの会員情報システムを一時停止します
★★目次 ★★
【1】2015年度一般社団法人日本地質学会各賞候補者募集について
【2】割引会費申請受付中!—2015年度会費払込のお知らせ—
【3】学会ホームページ会員情報システム一時利用停止のお知らせ
【4】大学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準「地球惑星科学分野」の公表
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞情報等
No.278 2014/10/21「県の石」募集:締切迫る!
★★目次 ★★
【1】2015年度一般社団法人日本地質学会各賞候補者募集について
【2】割引会費申請受付中!—2015年度会費払込のお知らせ—
【3】学会ホームページ会員情報システム一時利用停止のお知らせ
【4】「県の石」募集:締切迫る!
【5】国際第四紀学連合第19回大会における発表募集開始のお知らせ
【6】地学オリンピックキャラクターデザインコンテスト 締切間近!
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞情報等
No.277 2014/10/8(臨時)首藤次男名誉会員 訃報
■ 首藤次男 名誉会員 ご逝去
No.276 2014/10/7 日本地質学会各賞候補者募集
★★目次 ★★
【1】2015年度一般社団法人日本地質学会各賞候補者募集について
【2】割引会費申請の受付開始!—2015年度会費払込のお知らせ—
【3】「研究活動における不正行為...」案の回答公開
【4】「県の石」募集のお知らせ
【5】2014年度秋季地質調査研修:参加者募集締切
【6】防災・減災に関する国際研究のための東京会議ポスター発表のアブストラクト締切延期及びプログラムのお知らせ
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞情報等
No.275 2014/9/30(臨時)御嶽山の噴火 ほか
★★目次 ★★
【1】御嶽山の噴火
【2】国際地学オリンピック:世界トップに
【3】世界ジオパークに阿蘇が
No.274 2014/9/16 鹿児島大会 終了しました!
★★目次 ★★
【1】鹿児島大会 終了しました!
【2】「地震に関する総合的な調査観測計画...」の意見書に対する回答が公開されました
【3】コラム:地質学の復権を念う:GAC/MAC年会 in Fredericton, Canadaにて
【4】「県の石」募集のお知らせ
【5】2014年度秋季地質調査研修:参加者募集
【6】第7回日本地学オリンピック(第9回国際地学オリンピック2015ロシア大会日本代表選抜)参加者募集
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞情報等
No.273 [鹿児島大会臨時号]大会3日目
★★目次 ★★
【1】大会3日目の様子
【2】大会2日目の写真満載(高校生セッション,国際津波シンポ,若手会員業界サポートなど)
No.272 [鹿児島大会臨時号]大会2日目
★★目次 ★★
【1】大会2日目の様子
【2】大会初日の写真満載(表彰式など)
No.271 [鹿児島大会臨時号]大会初日
★★目次 ★★
【1】市民講演会,地質情報展開会,表彰式など
No.270 2014/9/13 No.270 [鹿児島大会臨時号]9月13日開催!
No.269 2014/9/2 No.269 [鹿児島大会]講演プログラム掲載!
★★目次 ★★
【1】[鹿児島大会]講演プログラムを掲載しました
【2】[鹿児島大会]事前参加登録の確認書等を発送しました
【3】[鹿児島大会]地質技術者の皆さん 鹿児島大会でCPD単位が取得出来ます
【4】[鹿児島大会]鹿児島市内の宿泊施設に宿泊される方へ
【5】[鹿児島大会]各種イベント
【6】一般社団法人日本地質学会臨時総会開催について
【7】2014年8月20日広島における土砂災害,特に地質要因
【8】「県の石」募集のお知らせ
【9】2014年度会費およびそれ以前の未納会費がある方へ
【10】今年度の世界ジオパークネットワークへの加盟推薦地域等が決定
【11】2014年度秋季地質調査研修:参加者募集
【12】日本地球惑星科学連合の2015年大会ホームページオープン
【13】防災・減災に関する国際研究のための東京会議:ポスター発表のアブストラクト募集
【14】第10回科学技術予測調査:大規模案アンケート ご協力のお願い
【15】支部情報
【16】その他のお知らせ
【17】公募情報・各賞情報等
No.268 2014/8/19 No.268 [鹿児島大会]事前参加登録:本日申込締切!
★★目次 ★★
【1】[鹿児島大会]事前参加登録:本日申込締切!
【2】[鹿児島大会]緊急展示の申込について
【3】[鹿児島大会]地学教育・アウトリーチ巡検;締切延長!!
【4】「県の石」募集のお知らせ
【5】「九州電力株式会社川内原子力発電所…」に対する意見を提出しました
【6】「平朝彦国際深海科学掘削研究賞」が新設!
【7】2014年度会費およびそれ以前の未納会費がある方へ
【8】2014年度秋季地質調査研修:参加者募集
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞情報等
No.267 2014/8/5 No.267 鹿児島大会:間もなく巡検申込締切!
★★目次 ★★
【1】[鹿児島大会]事前参加登録:間もなく巡検申込締切!
【2】[鹿児島大会]緊急展示の申込について
【3】地質学会会員、GSA Fellow に選出
【4】研究不正ガイドライン案への意見
【5】原子力規制委員会:川内原子力発電所に関する意見募集
【6】The 2nd IGCP608 Waseda 2014のThird Circular(Program) 配布開始
【7】2014年度会費およびそれ以前の未納会費がある方へ
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞情報等
No.266 2014/7/16 (臨時)[鹿児島大会]全体日程が決まりました.
★★目次 ★★
【1】[鹿児島大会]全体日程が決まりました
【2】[鹿児島大会]事前参加登録受付中!
【3】[鹿児島大会]各種申込み締切のお知らせ
【4】「地震に関する総合的な調査観測計画について〜東日本大震災を踏まえて〜 案」に対する日本地質学会の意見提出
No.265 2014/7/15 地震火山こどもサマースクール:参加者募集中!!
★★目次 ★★
【1】[鹿児島大会]事前参加登録受付中!
【2】[鹿児島大会]各種申込み締切のお知らせ
【3】地震火山こどもサマースクール:参加者募集中!!
【4】2014年度会費およびそれ以前の未納会費がある方へ
【5】惑星地球フォトコンテスト入選作品展示会開催中
【6】GSJ地質図幅の電子無償配信スタート
【7】地質災害情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞情報等
No.264 2014/7/4 (臨時)県の岩石・鉱物・化石の出版に向けて
★★目次 ★★
【1】“日本各県の岩石・鉱物・化石”の出版に向けて
【2】意見募集:地震に関する総合的な調査観測計画について
No.263 2014/7/1 惑星地球フォトコンテスト入選作品展示会開催中!
★★目次 ★★
【1】[鹿児島大会]事前参加登録受付中!
【2】[鹿児島大会]各種申込み締切のお知らせ
【3】2014年度会費およびそれ以前の未納会費がある方へ
【4】惑星地球フォトコンテスト入選作品展示会開催中
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞情報等
No.262 2014/6/30 (臨時)[鹿児島大会]講演申込:明日(7/1)締切!(延長なし)
★★目次 ★★
【1】[鹿児島大会]講演申込:明日(7/1)締切です!
【2】[鹿児島大会]講演申込画面(PASREG):入力時の注意
【3】[鹿児島大会]各種申込み締切のお知らせ
No.261 2014/6/24 (臨時)[鹿児島大会]講演申込:締切まであと1週間!
★★目次 ★★
【1】[鹿児島大会]講演申込:締切まであと1週間!
【2】[鹿児島大会]講演申込画面(PASREG):入力時の注意
【3】[鹿児島大会]各種申込み締切のお知らせ
No.260 2014/6/17 井龍会長就任挨拶
★★目次 ★★
【1】会長挨拶:日本地質学会長就任にあたって
【2】[鹿児島大会]事前参加登録受付開始!・演題登録も受付中
【3】[鹿児島大会]講演申込画面(PASREG):入力時の注意
【4】[鹿児島大会]ランチョン・夜間集会申込受付中
【5】[鹿児島大会]講演予定者で,現在未入会のかたへ周知のお願い
【6】2014年度会費督促請求について
【7】惑星地球フォトコンテスト入選作品展示会のお知らせ
【8】地学オリンピックキャラクターデザインコンテスト開催中!
【9】街中ジオ散歩 in Tokyo 開催報告
【10】第4回学生のヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集
【11】支部情報
【12】その他のお知らせ
【13】公募情報・各賞情報等
No.259 2014/6/3 [鹿児島大会]演題登録受付中!
★★目次 ★★
【1】[鹿児島大会]演題登録受付中!
【2】[鹿児島大会]宿泊予約に関するご注意
【3】JST からのお知らせ『サイエンスアゴラ 2014』出展者募集
【4】Island Arcからのお知らせ
【5】[事務局より]会員名簿取り扱いに関する注意喚起
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・教員採用試験情報・各賞情報等
No.258 2014/5/27 (臨時)[鹿児島大会]演題登録受付開始!!
★★目次 ★★
【1】[鹿児島大会]演題登録受付開始しました!!
【2】[鹿児島大会]講演申込を予定しているが、まだ入会手続きをしていない方へ
【3】[訃報]亀井節夫 名誉会員 ご逝去
【4】公募情報・教員採用試験情報・各賞情報等
No.257 2014/5/20 公開講演会「日本の地質学:最近の発見と応用」(5/24)
★★目次 ★★
【1】[鹿児島大会]演題登録は間もなく受付開始です
【2】日本地球惑星科学連合のフェローが発表:地質学会からは8名が選出される!
【3】公開講演会「日本の地質学:最近の発見と応用」
【4】日本地質学第6回総会開催について
【5】平成26年度日本カナダ女性研究者交流 【派遣者募集】
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・教員採用試験情報・各賞情報等
No.256 2014/5/2 5月10日は「地質の日」!
★★目次 ★★
【1】電子書籍「地学を楽しく!」PDF版発売開始
【2】5月10日は地質の日!
【3】日本地質学第6回総会開催について
【4】ジオルジュ 最新号まもなく刊行
【5】The 2nd IGCP608 Waseda 2014のSecond Circular 配布開始
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・教員採用試験情報・各賞情報等
No.255 2014/4/15 地質の日イベントが目白押し!
★★目次 ★★
【1】[鹿児島大会]シンポジウム・セッション決定
【2】日本地質学第6回総会開催について
【3】日本地質学会125周年を迎えるにあたって
【4】5月10日は地質の日!
【5】地質学雑誌規則の大改正
【6】地質学論集58号について
【7】Marjorie Chan教授講演会の案内
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞情報等
No.254 2014/4/1 新発売!「青木ヶ原溶岩のたんけん」
★★目次 ★★
【1】★新発売★ リーフレットたんけんシリーズ4 青木ヶ原溶岩のたんけん
【2】日本地質学第6回総会開催について
【3】[地質の日]公開講演会やジオ散歩など開催予定
【4】日本地質学会初代会長神保小虎小伝
【5】地層処分技術WG中間とりまとめに関するパブリックコメント
【6】2014年度春季地質調査研修参加者募集
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞情報等
No.253 2014/3/18 学部学生・院生の割引会費申請は間もなく締切です
★★目次 ★★
【1】理事選挙結果のお知らせ
【2】連合2014年大会(4月28日〜5月2日)のお知らせ
【3】2014年度春季地質調査研修参加者募集
【4】地球全史スーパー年表:会員特別販売のお知らせ
【5】「割引会費申請」間もなく締め切り!
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
No.252 2014/3/11(臨時)トピックセッション募集 締切間近!!
★★目次 ★★
【1】2014鹿児島大会:トピックセッション募集。締切間近!!〔3月17日(月)〕
【2】産総研地質調査総合センターの出版物に係る閲覧時の注意
No.251 2014/3/4 フォトコン結果速報
★★目次 ★★
【1】第5回惑星地球フォトコンテスト審査結果
【2】地質調査総合センターの出版物に係る誤分析データの記載について
【3】国際地質科学連合(IUGS) 第67回理事会報告および第35回、36回万国地質学会議(IGC)案内
【4】2014年度春季地質調査研修参加者募集
【5】地球全史スーパー年表:会員特別販売のお知らせ
【6】「割引会費申請」忘れずに!
【7】支部情報
【8】科研費助成事業の審査に係る「系・分野・分科・細目表」等への意見募集
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞情報
【11】地質マンガ:地学系よくある勘違い
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
No.1〜No.100 は→→こちら←←
No.101〜No.200 は→→こちら←←
No.201〜No.250 は→→こちら←←
配信希望の方は
geo-Flashは地質学会会員に配信されます。
会員の方はメールアドレスの登録をお願いいたします。オンライン登録システムは現在準備中です。お手数ですがこちらから申し込んで下さい。
非会員の方はこれを機会に入会されませんか。入会案内はこちらです。
geo-flash No.281 第6回惑星地球フォトコンテスト:応募受付中!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.281 2014/12/2 ┬┴┬┴
geo-Flash No.204 学会各賞推薦お待ちしてます!(12/25締切)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.204 2012/12/4 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2013年度日本地質学会各賞候補者募集中:12/25締切
【2】第4回惑星地球フォトコンテスト作品募集中
【3】Island Arc 新名称募集中です
【4】2013年度会費払込のお知らせ
【5】地学オリンピック申し込み1000名突破!
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2013年度日本地質学会各賞候補者募集中:12/25締切
──────────────────────────────────
日本地質学会各賞の自薦,他薦による候補者を募集しています.日本地質学会功労賞・日本地質学会表彰以外は,会員(正会員・名誉会員)であればどなたでも推薦できます.
ご応募いただいた場合には,必ず受取のお返事をお出ししますのでご確認ください.たくさんのご応募をお待ちしております.
下記の賞の候補者を募集中です。たくさんのご応募をお待ちしております。
1.日本地質学会賞
授賞対象:地質学に関する優秀な業績をおさめた本会正会員もしくは名誉会員, またはこれらの会員を代表とするグループ.
2.日本地質学会国際賞
授賞対象:地質学に関する画期的な貢献があり,加えて日本列島周辺域の研究や日本の地質研究者との共同研究などを通じた日本の地質学の発展に関する顕著な功績があった会員及び非会員
3.日本地質学会小澤儀明賞・柵山雅則賞
授賞対象:地質学に関して優れた業績を上げた,2012年9月末日で満37歳以下の会員(研究テーマによって小澤儀明賞・柵山雅則賞のいずれかを授与)
4.日本地質学会研究奨励賞
授賞対象:2010年10月から2012年9月までの過去2年間に地質学雑誌およびIsland Arcに優れた論文を発表した,2012年9月末日で満35才未満の正会員.筆頭著者であれば共著でもよい.
5.日本地質学会論文賞
授賞対象:
1)2009年10月から2012年9月までの過去3年間に「地質学雑誌」発表された優れた論文
2)2009年4号から2012年3号(9月)までの過去3年間に「Island Arc」に発表された筆頭著者が本会会員による優れた論文
6.日本地質学会小藤文次郎賞
授賞対象:2010年10月から2012年9月までの間に重要な発見または独創的な発想を含む論文を発表した会員.
7.日本地質学会功労賞
授賞対象:長年にわたり地質学の発展に貢献のあった本会会員もしくは非会員.またはこれらを代表するグループ.
8.日本地質学会表彰
授賞対象:地質学の教育活動,普及・出版活動,新発見および露頭保全,あるいは新しい機器やシステム等の開発等を通して地質学界に貢献のあった個人,団体および法人.
*2011年から規則が変わり,対象者は会員・非会員を問いません.
応募締切:2012年12月25日(火)必着
選考規則など詳しくは,こちらから(会員によるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第4回惑星地球フォトコンテスト作品募集中
──────────────────────────────────
【こんな作品を大募集!】
・惑星地球の美しい自然
・地層や火山など活きた地球の姿を表す優れた作品
・学術的意義の高い作品(解説文を含む)
・ジオパークに関係する優れた作品
・「ジオ鉄」の優れた作品学術的・教育的な価値のある優れた作品
・そのほか地球科学に関係した作品
締切:2013年1月31日(木)17:00
応募方法など詳しくは,
http://photo.www.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】Island Arc 新名称公募のお知らせ
──────────────────────────────────
応募の締切:2013年1月31日(木)必着
応募方法など詳しくは,
http://www.geosociety.jp/publication/content0005.html#new
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2013年度会費払込のお知らせ
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下さいますようお願いいたします.
■2013年度分会費の引き落とし日:12月25日(火)です.
請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下さい.
■自動引き落とし以外の方(お振り込み)
12月中旬頃までに請求書兼郵便振替用紙をお送りいたします.折り返しご送金くださいますようお願いいたします.
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/outline/content0108.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地学オリンピック申し込み1000名突破!
──────────────────────────────────
第5回日本地学オリンピック大会予選の参加申し込みが、11月15日(木)に締め切られ、過去最高となる1,011名の方々が応募されました! 一次予選は12月16日(日)に行われます。応援しましょう。
http://jeso.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
■西日本支部
西日本支部平成24年度総会・第163回例会
日時:平成25年2月23日(土)
場所:島根大学総合理工学研究科
同日夕刻に懇親会を、前日(2月22日(金))夕刻に幹事会を催す予定です。
他、詳細は追ってお伝えします。
問い合わせ先:西日本支部庶務:宮本知治
e-mail:miyamoto@geo.kyushu-u.ac.jp
■関東支部
地質学会関東支部『地質研究サミット』シリーズ開催について
関東支部が担う予定の第123年学術大会(2016年開催)の成功に向けて多面的な準備を開始しました。その一つが、関東地方の地質に対して鋭い斬りこみを かけている研究グループ群を鼓舞激励しつつ関東地方地質研究の新展開を図り、それを第123年学術大会において披瀝しようとするものです。そのためこれまで1年に一度開催していた支部シンポジウムの形式を改め、各研究グループの中心メンバーが一同に会してホットな研究成果を発表するとともに建設的な議論を 行う場を設定することにしました。名づけて、『地質研究サミット』です。もちろん、この『地質研究サミット』は、“一匹狼”や膨大なデータを蓄積してこら れた諸先輩の参加も大歓迎です。
なお、『地質研究サミット』は、対象が関東地方の地質ではありますが、全国に開かれたものとして運営されます。
★第1回「房総・三浦地質研究サミット」開催のお知らせ及び講演募集
期日:平成25年3月9日(土)・10日(日)
場所:千葉県立中央博物館(千葉市中央区青葉町955−2)
講演申込締切:平成25年1月20日(日)
詳しくは関東支部HP
http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第22回環境地質学シンポジウム
12月7日(金)・8日(土)
場所:産業技術総合研究所共用講堂
主催:地質汚染−医療地質−社会地質学会
共催:日本地質学会環境地質部会ほか
http://www.jspmug.org/envgeo_sympo/22nd_sympo/22nd_sympo.html
■Post Symposium of 4.5-session 1, the 34th IGC, Geopollution,
dust, and man made strata “A flight of stone steps in Brisbane”
“ブリスベーンで見た坂の上の雲”
12月16日(日)13:00〜17:30
主催:国際地質学連合環境地質研究委員会日本支部
共催:日本地質学会環境地質部会ほか
場所:江戸川グリーンパレス(東京都江戸川区)
詳細は,IUGS環境管理研究委員会日本支部
Tel:0478-59-1491 Fax:0478-59-1491
■第13回岩の力学国内シンポジウム
日本地質学会 協賛
(併催:第6回日韓ジョイントシンポジウム)
2013年1月9日(水)〜11日(金)
会場:沖縄コンベンションセンター
事前参加申込締切:12月7日(金)
http://www.rocknet-japan.org/jsrm2013/
■電中研TOPICS 発行
Vol.13「電力システム改革の課題に迫る」
Vol.14「使用済燃料の貯蔵技術」
http://criepi.denken.or.jp/research/topics/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■秋田大学国際資源学部(仮称)教員公募(3件)(1/11締切)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
<ニュース誌表紙写真,特に募集中です!お待ちしてます.>
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
geo-Flash No.203 (臨時)学術会議報告書「高レベル放射性廃棄物について」へのコメント
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.203 2012/11/22 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】日本学術会議より出された報告書「高レベル放射性廃棄物の処分について」に対するコメント(プレスリリース)
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会は、日本学術会議9月11日付け報告書「高レベル放射性廃棄物について」に対して、地球科学界を代表する日本地質学会として積極的に関与し、地質学関連学界が社会に対して果たすべき責務として以下のコメントを公開します。
学術会議報告書での判断と提案は、
〇現時点での科学的知見だけでは地層処分の安全性に対する信頼性を確保できない
〇高レベル放射性廃棄物の回収が可能である方法で数十年〜数百年間の暫定的責任保管を行うべき
ということでした。
しかしながら、「暫定的責任保管」と「地層処分」は、最終的に廃棄物をどのように扱うかという点で異なるだけであり、その実施場所のサイト選定は必須です。
課せられている課題は、もっと確度の高い将来予測を行う研究開発を継続し、同時に安全性に対する社会の懸念を解消することが重要です。
このためには
〇最終的な決断を社会とともに下すために「認識共同体」の構築を進める
・サイト選定の妥当性とその安全性を広く社会で共有する
・社会に対する専門家の説明不足を補うために分野横断的なコミュニケーションをはかる
・理学的、工学的並びに社会学的な学会間の連携により構築する
・透明性を維持し、想定される全ての現象を客観的に議論する
〇その上で我が国が培ってきた放射性廃棄物処分技術の長期的な継承・改良とその重要性の共有化を行うの対応が必要と考えます。
コメント全文はこちらから、、、
http://www.geosociety.jp/engineer/content0018.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
<ニュース誌表紙写真,特に募集中です!お待ちしてます.>
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
地質マンガ 青春の伝説
地質マンガ
青春の伝説
原案:本郷宙軌 マンガ:KEY
戻る|次へ
オーストラリア国立大学に設置されたS/Iタイプ花崗岩ベンチ
オーストラリア国立大学に設置されたS/Iタイプ花崗岩ベンチ
石原舜三(産業技術総合研究所 顧問)
Bruce ChappellおよびAllan Whiteの業績をしのんで、S/Iタイプ花崗岩を用いたベンチが国立大学校内の一隅に設けられ、そのお披露目がBruceの死後6か月に当たる2012年10月19日に行われた。筆者は除幕式に参加し(写真1)、White夫人を含む多数の参加者とその喜びを分かち合った。S/Iタイプは花崗閃緑岩質の岩石が選ばれており、肉眼的にも識別可能な興味深い性質を持っている。大学に立ち寄る機会がある人は是非ともベンチに腰をかけ、岩石を観察してほしい。(Allanには、その功績を讃え2007年に日本地質学会国際賞が贈られた。)
Iタイプ:Bruceのために選ばれたのはNSW州、Middlingbank産のTara花崗閃緑岩である。これは、所によって多くの火成起源包有物を含む中粒のIタイプであり、楕円形状に巨大なSタイプCootralantra花崗閃緑岩複合体に貫入する。ジルコン年代419±4 Ma、構成鉱物は斜長石(50%)、石英(30%)、カリ長石(〜10%)、黒雲母(〜10%)、角閃石(〜5%)。この岩石はメタアルミナス、少量の磁鉄鉱を含み酸化的。Inherited zirconは少量である。87Sr/86Sr初生値は低く(0.7063)、εNdは-3.2である。
Sタイプ:Allanのために選ばれたのは、NSW州にあるJindabyne南方のJillamatong花崗閃緑岩−トナル岩であり、不規則形状の小岩体(〜90km2)が、早期古生代のタービダイトに貫入し、それ自身はIタイプ小岩体の貫入を受ける。ジルコン年代は、南東部オーストラリアのSタイプで一般的な435±4 Ma年代を示す。Inheritedジルコンはさまざまな古い年代を示す。主成分鉱物は石英(30%)、斜長石(25%)、黒雲母(25%)、カリ長石(10%)、白雲母(5%)、菫青石(5%)。この岩石は非常に還元的でアルミナに過剰。特異な性質として石英中の針状ルチル結晶がある。Allanは、この石英にペット名Jilliを与え、特に好んだ。
(2012.11.20)
No.134 2011/4/25 geo-flash(臨時)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.134 2011/4/25 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】解説:人類史上初めて落下の観測とその回収に成功した小惑星
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】解説:人類史上初めて落下の観測とその回収に成功した小惑星
──────────────────────────────────
宮原 正明(東北大学理学研究科地学専攻)
皆さんは,2008年10月6日から7日未明(グリニッジ標準時)にかけて,地球
の裏側で,人類史上初めての劇的な事件が起きていたことをご存じでしょうか
(Jenniskens et al., 2009).事の発端は,米国のある天文台が,名もない小惑
星を発見したことに始まります.後に,この小惑星は“2008 TC3”と名付けら
れます.天文台の研究者が,この小惑星の軌道を計算すると,約20時間後に地球
に衝突することが明らかとなりました.この情報は,即座にNASAに送られ,世界
中の天文台が協力して,その追跡を行いました.そして,.....
続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0307.html
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
昨2010年、小惑星「イトカワ」の物質を地球に持ち帰った「はやぶさ」が話題に
なりましたが,実はその2年前の2008年に、既に発見されていた小惑星が自ら地球
に飛び込んできて,その破片が多数回収されるという事件がありました.しかし,
このことは日本ではあまり報道されず,少数の専門家や天文ファン以外にはあまり
知られていないようです.そこで,Almahatta Sittaと呼ばれるこの隕石の
実物試料を物質科学的に研究している東北大学大学院理学研究科GCOE助教の
宮原正明さんに,この隕石の発見・大気圏突入・回収の経緯と,その興味深い
構成物質について解説を書いていただきました(石渡 明).
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
──────────────────────────────────
本記事は、geo-Flash No.132(4/19号)へ掲載を予定しておりましたが,
編集上の不手際により掲載から漏れておりましたため,臨時号として配信さ
せて頂きました.
関係の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.127 2011/2/15 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.127 2011/2/15 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】衝撃波が発生した新燃岳の爆発的噴火
【2】新燃岳噴火とハザードマップと霧島ジオパーク
【3】2011年度会費/割引申請/災害特別措置
【4】日本地質学第3回(2011年度)総会(代議員総会)開催のお知らせ
【5】支部情報
【6】第34回万国地質学会議(IGC)ブリスベン大会
【7】地学オリンピック関連情報:日本委員会ニュースより(2/14号)
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】衝撃波が発生した新燃岳の爆発的噴火
──────────────────────────────────
後藤章夫(東北大学東北アジア研究センター)
1月19日から始まった新燃岳の噴火活動は,26日には本格的なマグマ噴火へと
移行し,27日からは爆発的な噴火がしばしば発生するようになった.(中略)
2月1日の爆発で被害が出たこともあり,この噴火では,「空振」という言葉が
にわかに注目された.しかし空振は決して珍しい現象ではなく,2004年の浅間
山噴火でもガラス破損などの被害が出ているし,程度の差こそあれ,むしろ
噴火が起これば必ず空振が発生すると思った方がよい.
続きを読む、、、 http://www.geosociety.jp/hazard/content0046.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】新燃岳噴火とハザードマップと霧島ジオパーク
──────────────────────────────────
坂之上浩幸(霧島ジオパーク推進連絡協議会)
平成23年1月26日の噴火に始まった今回の新燃岳の活動は、今後どのような経過
をたどっていくのか、未だ予断を許さない状況で、霧島山周辺の自治体は緊張を
強いられています。ここでは、ここ2年ほどの新燃岳の様子を紹介していきたい
と思います。
続きを読む、、、 http://www.geosociety.jp/hazard/content0045.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2011年度会費/割引申請/災害特別措置
──────────────────────────────────
■2011年度会費払込について
次年度分会費の前納をお願いいたします。自動引き落としを登録されている
方は、2010年12月24日(金)に引き落としを行いました。お振込の方へは、
12月中旬頃に請求書兼郵便振替用紙をお送りいたしました。
詳しくは、 https://www.geosociety.jp/user.php
(会員番号によるログインが必要です)
■2011年度(2011.4〜2012.3)学部学生・院生割引申請受付中
最終締切:2011年3月31日(木)
申請書のダウンロードは、 https://www.geosociety.jp/user.php
(会員番号によるログインが必要です)
■災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
日本地質学会では,災害救助法適用地域で被災された会員の方々のご窮状を
ふまえ,「日本地質学会に届出の住居または勤務地が災害救助法適用地域に
該当する会員のうち,希望する方」は2011年度(平成23年度)会費を免除す
ることといたします.詳しくは、
http://www.geosociety.jp/outline/content0067.html
申請締切:2011年2月25日(金)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】日本地質学第3回(2011年度)総会(代議員総会)開催のお知らせ
──────────────────────────────────
日時 2011年5月21(土)14:00〜15:30
会場 総評会館 201会議室(千代田区神田駿河台3-2-1)
地図はこちら→ http://www.sohyokaikan.or.jp/access/
議事次第等は,後日お知らせいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報
──────────────────────────────────
■北海道支部
支部総会・個人講演会,日本地方地質誌「北海道地方」出版記念行事
日程:2月26日(土)
場所:北海道大学大学院環境科学研究院D棟101室 ほか
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
■西日本支部:第160回支部例会、2010年度総会
日程:2月19日(土)
場所:広島大学理学部(東広島市鏡山)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
■東北支部2009〜2010年度総会,個人講演会と公開シンポジウム
会場:「コラッセふくしま」5階研修室
日程:3月13日(日)(日程を短縮し、13日のみに変更)
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】第34回万国地質学会議(IGC)ブリスベン大会
──────────────────────────────────
第34回IGCが2012年8月5日〜10日にオーストラリア東部の都市ブリスベンで
開催されます.すでに1st. Circular も公開されています.
詳しくは下記をご覧下さい.
http://www.34igc.org
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】地学オリンピック関連情報:日本委員会ニュースより(2/14号)
──────────────────────────────────
日本委員会より、活動内容等を不定期ご連絡いただいてます。一部抜粋して会員の
皆様にご案内いたします。
国際地学オリンピック日本大会(2012)については、下記サイトもご参照ください。
http://ieso2012.jp/infojp/
2月1日より、2012年国際地学オリンピック日本大会開催にかかわる運営資金のオン
ラインによる個人ご寄付の受付を開始いたしました。1口1000円となっています。従
来のゆうちょ銀行・みずほ銀行の払込と合わせてご利用ください。なお、企業ご寄
付につきましては、4月1日をめどに税制優遇を受けられる手続きを進めております。
詳細が明らかになりましたら、再度お知らせいたします。
http://ieso2012.jp/infojp/modules/page/index.php?content_id=8
(NPO法人地学オリンピック日本委員会 http://jeso.jp/)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■平成22年度海洋情報部研究成果発表会
日時:2月25日(金)13:30-18:00 入場無料
会場:海上保安庁海洋情報部7階大会議室(東京都中央区築地)
問い合わせ先:海上保安庁海洋情報部(電話03-3541-3813)
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/
■日本学術会議主催公開講演会
「学術における男女共同参画推進の加速化に向けて」
日時:3月2日(水)13:00〜17:00
会場:日本学術会議講堂(東京都港区六本木)
参加費:無料 定員:300名
https://form.cao.go.jp/scj/opinion-0003.html
■津波防災シンポジウム「津波警報!!そのときあなたは?」
日時:2011年3月10日(木)13:30〜16:00
場所:気象庁講堂(東京都千代田区大手町1-3-4)
参加費:無料(定員200名、事前申込)
・2010年チリ中部地震津波の実態と見えてきた課題:今村文彦
・津波警報の発表に至るまで:横山博文
詳しくは、 http://www.jma.go.jp/jma/press/1102/08b/110310tsunami.html
■第2回ジオ多様性フォーラム
日時:2011年3月28日10:00〜17:00
場所:京都大学東京オフィス(港区港南2-15-1品川インターシティA棟27F)
問い合わせ先:矢島道子 pxi02070@nifty.com
■日本学術会議ニュースNo.284より (2011/2/4)
「若者の就職問題」についての日本学術会議会長談話
本文は次のURLからご覧になれます。
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-21-d10.pdf
■ 日本地球惑星科学連合メールニュースNo.100より (2011/2/10)
新燃岳2011年噴火緊急セッション開催決定
2011年1月から活発化した霧島火山新燃岳噴火に関する研究発表の場として,
連合大会では緊急セッションを開催します.投稿締切等の詳細については決
まり次第,ご連絡申し上げます.なお、緊急セッションはポスター発表のみ
の予定です.
詳しくは、 http://www.jpgu.org/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■高知大学海洋コア総合研究センター全国共同利用研究公募
(前期・通年2/28,後期8/31)
■2011年度地球化学研究協会学術賞「三宅賞」および「奨励賞」候補者の募集
(学会推薦)(6/30学会締切)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.126 2011/2/1 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.126 2011/2/1 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】「はやぶさ」関連プレス発表資料に対する要望書とJAXAからの回答
【2】2011水戸大会ニュース
【3】霧島山新燃岳2011年噴火の情報
【4】地質リーフレット:新発売
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「はやぶさ」関連プレス発表資料に対する要望書とJAXAからの回答
──────────────────────────────────
日本の惑星探査機「はやぶさ」が地球に持ち帰ったカプセルの中に、小惑星
「イトカワ」の微粒子が含まれていたという宇宙航空研究開発機構(JAXA)の
発表は、昨年末の大ニュースでした。しかし、その発表内容については、本
誌13巻12号15頁の記事のように、地球外物質と判断した根拠などについてい
くつか疑問があり、一般向けの発表とはいえ、もう少し科学的な正確さが必
要なのではないかという印象を多くの会員が持ったと思います。そこで、日
本地質学会会長からJAXA理事長に対し、プレス発表に科学的な正確さを確保
するよう求める要望書を郵送しました。この要望書およびそれに対するJAXA
の担当者からの回答文を掲載いたします。
http://www.geosociety.jp/engineer/content0013.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2011水戸大会ニュース
──────────────────────────────────
(1)2011年水戸大会:トピックセッション募集・間もなく締切!
日本地質学会は、関東支部の支援のもと、第118年学術大会を茨城大学をメイ
ン会場として2011年9月9日(金)〜11日(日)の日程で開催します。
トピックセッションの募集は、間もなく締切です。漏れのないよう、お早め
にお申し込みください。(※本大会ではシンポジウムの募集はありません)
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/mito/content0016.html
トピックセッション募集締切:2011年2月14日(月)
(2)見学旅行:各コースの魅力と見どころ紹介
本年9月に行われる水戸大会では、関東支部を中心に多くの会員の協力を得て、
10コースの見学旅行を企画し現在その準備を進めております。水戸大会では、
見学旅行は茨城を中心とした関東周辺地域の地質理解のための重要な行事と
位置付け、参加者に満足していただける特徴的なコース作りを目指しており
ます。正式なコース一覧や参加申込の詳細はニュース誌4月号(4月末頃)で
紹介する予定ですが、それまでに会員の皆様に各コースの魅力や見どころを
詳しく紹介していきたいと思います。
(見学旅行準備委員会 委員長 安藤寿男、副委員長 山本高司)
まずはA〜Fコースのご紹介
http://www.geosociety.jp/mito/content0030.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】霧島山新燃岳2011年噴火の情報
──────────────────────────────────
■産総研・地質調査総合センターによる調査結果
産総研・地質調査総合センターは霧島山新燃岳2011年噴火に対応して,
2011年1月27日から現地噴出物調査(噴出量など)を実施しています.
調査結果は随時公表される予定です。
(産業術総合研究所・火山研究情報のサイト)
http://www.gsj.jp/kazan/kirishima2011/
■霧島山新燃岳2011年噴火:関連リンク
地質学会サイトの「地質災害調査」に関連リンク集を掲載しました。
http://www.geosociety.jp/hazard/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地質リーフレット:新発売
──────────────────────────────────
地質リーフレット4「日本列島と地質環境の長期安定性」
地質環境の長期的利用の観点から、日本の地質環境を分かりやすくまとめた新しい
リーフレットが出来あがりました。最新のデータに基づき、日本列島の断層運動、
火山・マグマ活動等の特徴、そして将来予測の考え方を示しています。多くの方々
に活用して頂けることを願っています。
編集 一般社団法人日本地質学会 地質環境の長期安定性研究委員会
2011年1月刊行 B2版 両面フルカラー印刷
会員頒価500円*20部以上ご注文の場合は割引あり
購入希望の方は、学会事務局まで main@geosociety.jp >
http://www.geosociety.jp/publication/content0037.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報
──────────────────────────────────
■北海道支部
支部総会・個人講演会,日本地方地質誌「北海道地方」出版記念行事
日程:2011年2月26日(土)
場所:北海道大学大学院環境科学研究院D棟101室 ほか
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
■西日本支部
日程:2011年2月19日(土)
場所:広島大学理学部(東広島市鏡山)
講演会申込締切:2月14日(月)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
■東北支部2009〜2010年度総会,個人講演会と公開シンポジウム
会場:「コラッセふくしま」5階研修室
日程:2011年3月12日(土)〜13日(日)
個人講演申込締切:1月26日(水)
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■学術会議シンポ「ヒトの社会と愛〜ラミダス猿人化石からわかること〜」
日時:2月6日(日)14:00〜17:00
場所:東京大学理学部2号館大講堂
主催:日本学術会議基礎生物学委員会・統合生物学委員会合同自然人類学分科会、
日本人類学会、東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻、東京大学総合研究博物
館
事前申込不要・定員200名
詳しくは、 http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf/113-s-2-4.pdf
■講演会「秩父の地質とジオパークへの取り組み」
講師:本間岳史氏(埼玉県立 自然の博物館)
日時:2011年2月13日(日) 13:30〜15:00
場所:埼玉県立川の博物館ふれあいホール
定員:80名(要申込)
詳しくは、 http://www.river-museum.jp/event/event01/post-69.html
■第17回地質調査総合センターシンポジウム
「地質地盤情報の法整備を目指して」
日時:2011年2月28日(月)13時〜17時半
場所:東京大学・小柴ホール
主催:地質調査総合センター・地質地盤情報協議会
定員:170名(要申込・定員になり次第受付終了)
詳しくは、 http://www.gsj.jp/Event/gsjsympo.html
■JABEE事務局ニュース:国際審査員研修会(2011.1.21版ニュースより)
日程:2011年3月7日(月)
会場:東京工業大学大岡山キャンパス
参加受付締切: 2月18日(金)
http://www.jabee.org/OpenHomePage/2011-General_Info.pdf
JABEE http://www.jabee.org/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■産業技術総合研究所:地質情報研究部門 特別研究員(ポスドク)募集(2/4)
■大阪市立大学:大学院理学研究科・理学部地球学教室 特任講師募集(2/9)
■東京大学:大学院理学研究科 地球惑星科学専攻教員募集(准教授)(3/11)
■京都大学:大学院理学研究科 大学院理学研究科地球惑星科学専攻
地質学鉱物学教室(教授)(4/25)
■京都大学:大学院理学研究科附属地球熱学研究施設(研究員)(2/11)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.006 2007.08/21 geo-Flash
【geo-Flash】札幌大会せまる No.006
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬【geo-Flash】日本地質学会メールマガジン ┴┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.006 2007/08/21 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】札幌大会の見所(その3)(海底地すべりとは?)
【2】新潟県中越沖地震&ペルー地震&房総沖群発地震・スロースリップ
【3】新潟県中越沖地震緊急ポスター発表申し込み〆切せまる
【4】今週のキーワード「海底地すべり」
【5】Geo-Flashにアクセス急騰!
【6】京都大学大学院 地球惑星科学専攻地質学鉱物学教室 公募(10/5締切)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 札幌大会の見所(その3)
──────────────────────────────────
■ シンポジウム:「海底地すべり」
日本列島は,険しい地形,激しい気象変動,地震などの頻繁な地盤変動に
よって,地すべり災害が頻発する地域であり,その周辺海底でも地殻変動に
よって,多くの地すべりが生じている.これらの海底地すべりは,津波を引
き起こす要因となることが指摘されているだけでなく,その存在は,メタン
ハイドレートをはじめとする資源の探査における障壁となっている.
このシンポジウムは,日本で初めて学際的に海底地すべりに焦点を当てて
行われるものである.ここでは,近年発生した日本周辺の海底地すべりのみ
ならず,台湾,スマトラ,さらにハワイで生じた海底地すべりの最新の知見
が発表される.そして,それらの発生原因を,海底でのリアルタイム地盤計
測や海底地盤の物性を直接試験した結果から検討している.シンポジウムでは,
これらの成果を海洋国日本の国土防災,資源開発に役立てる方策を探る.
本シンポジウムは,社団法人日本地すべり学会との共催であり,長年の陸
上地すべりの研究の知見を海底地すべり研究に役立てることも目指している.
陸上地すべりの事例としては,北海道内の各地の地すべりの形態・内部構造の
研究,空中写真判読による地形解析の研究が発表される.さらに,地すべりの
滑り面と地震断層との比較研究という新しい視点の研究も発表される.このよ
うな近年の陸上地すべり研究の成果は,海底地すべりの実体を明らかにするこ
とに役立つ.
海底地すべりは,海底活断層と密接な関わり合いを持つとされており,今年
始動する掘削船「ちきゅう」による南海地震発生帯掘削計画でも注目されてい
る.それを砂箱での実験で再現すると,その発生の様子がよくわかる.西南日
本の太平洋側の海底には,南海付加体,と呼ばれる地質体があり,そこには,
多くの活断層があることが知られる.それらの活断層が動くと,断層上盤が崩
壊し,その前縁部に堆積する.もし活断層で長年にわたって,そのようなこと
が生じていたとしたならば,その崩壊堆積物,すなわち海底地すべり堆積物は,
断層の活動履歴を記録していることになる.この研究は,京都大学工学研究科
の山田泰広准教授のグループによって発表される.以下に,関連図を添付する.
用語解説
・メタンハイドレード:メタンの周囲を水分子が囲んだ形の低温かつ高圧で安
定な水和物.日本周辺の水深千〜二千メートルの海底面下,数百メートルに大
量に存在している.次世代エネルギーとして注目されている.
・付加体:海洋プレートの沈み込みにともない,海底に堆積した様々な物質が,
大陸側の斜面の先端部に次々と付け加えられる.このような地層を付加体という.
日本の国土をつくる地層の多くの部分はこの付加体である.
(川村喜一郎 深田地質研究所)
第1図 地質モデルに見られる付加体形成に伴う斜面崩壊. ━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】 新潟県中越沖地震&ペルー地震&房総沖群発地震・スロースリップ
──────────────────────────────────
■ 新潟県中越沖地震 続報
山形大学 川辺研究室 調査報告
■ ペルー地震(Mw=8.1)情報
筑波大 八木研究室(地震概要)
名古屋大学地震火山・防災研究センター(地震概要)
USGS(地震概要)
気象庁(津波観測)
■ 房総沖群発地震・スロースリップ
防災科技研
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】 新潟県中越沖地震緊急ポスター発表申し込み〆切せまる
──────────────────────────────────
■ 緊急展示の申込みについて(再録)
講演申し込み終了後、台風4号や新潟県中越沖地震による災害が発生し、
多くの地質学会会員が現場で調査を行っています。学会活動の一端を広く
社会に紹介するとともに、ホットなテーマについて議論する場を提供する
ために、災害報告や社会的に影響のある新技術紹介などの「緊急展示コー
ナー」を設けます。
ポスター展示を希望する方は、8月23日までに以下の内容で下記の実行
委員会にご連絡ください。
1)発表要旨PDF(ニュース誌5月号P12参照) 2)緊急展示の必要性
3)発表代表者と連絡先 4)展示に関わる要望
(2)から4)の様式は自由)
実行委員会は行事委員会と協議し、可否の判断を致します。
希望にはできるだけ応えるようにしますが、
展示方法等については実行委員会の指示に従ってください。
申込先 札幌大会実行委員会 前田仁一郎
メール jinmaeda@mail.sci.hokudai.ac.jp
ページTOPにもどる
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】今週のキーワード「海底地すべり」
──────────────────────────────────
海底地すべりとは,なんでしょう?わからないので,辞典を引いてみま
しょう.有名な「Glossary of Geology 4th edition(AGI)」には
Submarine sliding という言葉は載っておらず,Subaqueous glidingは
Slumpとあります.しかし,近年の学術論文には,Submarine slide(ing)
やSubmarine landslideという用語は頻繁に見られますので,実際にはまか
り通っているようです.そしてSlumpは陸上地すべりと海底地すべりの2つ
の意味があり,海底地すべりとしては「The sliding-down of a mass of
sediment shortly after its deposition on an underwater slope」と記
されており,より正確には,「Subaqueous slump」とあります.
一方、日本の「地学事典(平凡社及び地学団体研究会)」には「海底地滑り:
海底の堆積物が重力の作用により斜面をすべり落ちる現象」とちゃんと載って
います。堆積物とは,泥や砂,石などのことです.しかし,近年ハワイ諸島や
カナリア諸島の火山島でも海底地すべりの事例が見つかっており,用語もどん
どん進化中のようです。
最後に海底地すべりの重要性について少しだけふれておきます.ハワイ諸島
や北海などで大規模の海底地すべりによって,津波が引き起こされたことがわ
かっています。しかし日本周辺では研究例が多くありません.現在,日本では
海底資源であるメタンハイドレートの開発を押しすすめており,海底地すべり
に対する関心が高まってきています.20世紀中頃には,ミシシッピデルタの
油井プラットフォームの流出事故などの産業構造物に対する被害が社会問題に
なりました.失敗学(http://shippai.jst.go.jp/fkd/Search)ではないですが,
過去に学んで,未来につなげる意味でも,海底地すべり研究は,必要不可欠です.
(川村喜一郎 深田地質研究所)
この写真は,石川県白山南麓にある別当大崩,という地すべり痕です(この写真は,
海底地すべりではありません.あくまでこの記事のイメージです).この地すべり
は山間部にありますが,陸上の地すべりは,移動体の上に人家や田んぼがあること
がめずらしくありません.地すべりによって,地形がなだらかになるからでしょう.
ですから,詳細に動態観測が行われ,その移動体が監視されています.こういった
詳細な観測が活断層でもできたらいいのにな..
地すべりと活断層.一見して関連性が無いように思えますが,百聞は一見にしかず.
今年の日本地質学会第114大会(札幌)で行われる「海底地すべりシンポジウム」
ではそんなトピックスも取り上げられます。ページTOPにもどる
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】 Geo-Flashによるアクセス急騰
──────────────────────────────────
■ 地質学会ホームページは平日が約400人/日くらい、休日は約200人くらい
の訪問者数があります。しかしこの1ヶ月半の統計を見ると、Geo-Fashが
配信される度にアクセスが急騰することがハッキリと見て取れます。
下のグラフは地質学会ホームページの平日のみの訪問者数です。5月は特
に大きなイベントもなく一定数で推移していますが、6月中旬にとても大き
なピークが現れます。これは6/18が学術大会講演要旨〆切(郵送)の1週間
前の月曜だからかもしれません。そして6/25にGeo-Flashの予告号が配信さ
れました。この週は講演要旨申し込みと重なって、ただでさえアクセスが集
中していますが、それでも配信日にはピークがあります。そして講演要旨が
締め切られた後もGeo-Flashが配信された日には必ずアクセスが増加してい
ます!
これはGeo-Flashからリンクをたどってホームページに来た人の数ですから、
メールマガジン中の記事は、これよりもはるかに多い方の目に触れたことで
しょう。地質学会会員にアピールする上でGeo-Flashはきわめて有効な手段で
あると結論づけられます。
ところで、7月下旬以降アクセスが全体的に減ってきていますが、多くの会
員が調査に出てしまうからでしょうか。地質学会のアクティビティが高いゆえ
の現象かもしれません。
(インターネット委員会 坂口有人)ページTOPにもどる
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】京都大学大学院 地球惑星科学専攻地質学鉱物学教室 公募(10/5締切)
──────────────────────────────────
1)採用職名・人員:助教・2名
2)所属講座:地球テクトニクス講座 ・ 地球生物圏史講座 ・ 各1名
3)期待する研究・教育分野:
<地球テクトニクス講座>
同位体を用いて地球変動の研究を行っており、分析手法の開発の経験を有する方。
野外調査の指導のできる方が望ましい。
<地球生物圏史講座>
野外調査にもとづき、堆積学的または構造地質学的研究をしている方。
野外調査の指導ができること。
4)採用予定: 2007年度のできるだけ早い時期
5)必要書類:
イ 履歴書
ロ 業績目録(論文,出版物などのリスト)
ハ 主要論文5編以内の別刷り(又はコピー)各1部、及び内容の簡単な解説
ニ これまでの研究経過(約1,000字以内)
ホ 今後の研究計画と教育の抱負(約1,000字以内)
なお、推薦書は特に必要ありません。
6)適任者の方を御推薦下さる場合は、被推薦者の氏名・所属・連絡先を、
2007年 9月18日(火)までに、文書で教室主任宛お知らせ下さい。
その際、上記の必要書類は不要です。当方で被推薦者に応募の意志の
確認及び必要書類の請求等を致します。
7) 応募締め切り:2007年10月5日(金)必着
8) 書類提出先および問合せ先:
〒606-8502 京都市左京区北白川追分町
京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻 地質学鉱物学教室
教室主任 平島崇男
電話: 075-753-4151・4171 FAX: 075-753-4189
注:封筒の表に「教員公募・応募講座名」又は「教員推薦」と朱書し、郵送の
場合は書留便として下さい。教室段階での選考結果については、
確定次第本人および推薦者に通知いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3週)配信予定です。原稿は第2・4週金曜日まで
にお送りください。geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
巡検情報:目次
巡検情報:学術大会巡検案内書
それぞれの巡検案内書原稿は,2006年以降地質学雑誌に掲載され,J-STAGE上(https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/-char/ja)で公開されていますが,読者の利便性を考慮して,別途Virtual Issueを構成し公開します.
また,アウトリーチ巡検等普及を目的とした一般市民(非専門家)対象の巡検案内書は,現行規則に沿った原稿作成では適さない場合があり(日本語のみの図表の方がわかりやすい等),地質学雑誌本体への掲載が難しいことがあります.そのため補足情報を,学会HP上に掲載し,J-STAGE公開分の案内書と合わせてVirtual Issueを構成します.
2025年(熊本)第132年大会巡検案内書(J-STAGEサイトへ)
2024年(山形)第131年大会巡検案内書(J-STAGEサイトへ)
2023年(京都)第130年大会巡検案内書
2022年(東京早稲田)第129年大会巡検案内書
2021年(名古屋)128年大会巡検案内書
※ 2020年127年学術大会中止.巡検案内書はありません
2019年(山口)第126年大会巡検案内書
2018年(札幌)第125年大会巡検案内書
2017年(愛媛)第124年大会巡検案内書
2016年(東京桜上水)第123年大会巡検案内書
2015年(長野)第122年大会巡検案内書
2014年(鹿児島)第121年大会巡検案内書
2013年(仙台)第120年大会巡検案内書
2012年(大阪)第119年大会巡検案内書
2011年(水戸)第118年大会巡検案内書
2010年(富山)第117年大会巡検案内書
2009年(岡山)第116年大会巡検案内書
2008年(秋田)第115年大会巡検案内書
2007年(札幌)第114年大会巡検案内書
2006年(高知)第113年大会巡検案内書
※2005年(京都)以前の案内書は,デジタル化されていません.複写のご希望は,学会事務局までお問い合わせください.複写のお申し込みはこちらから
見学旅行案内書:2006年(高知)
日本地質学会113年学術大会の際に催された見学旅行の案内書です。
岩井雅夫・村田明広・吉村康隆,2006,見学旅行案内書,地質学雑誌,112,補遺,170pp.
2004年台風10号豪雨で発生した徳島県那賀町阿津江の破砕帯地すべりと山津波
横山俊治・村井政徳・中屋志郎・西山賢一・大岡和俊・中野 浩
中央小出(1955)の定義による破砕帯地すべりは今日の知識からすれば付加体分布地域で多発している.破砕帯地すべりは地すべり性崩壊であると小出(1955)が記述しているように,崩壊時に破壊された地すべり移動体は山津波となって谷を流下し,しばしば末端では河川を堰き止める.見学地である阿津江の事例には,このような破砕帯地すべりの特徴がくまなく現れている.見学は末端部から発生域へと進めていこう.末端部では,坂州木頭川渡った山津波が対岸の斜面を50 mほどの高さまで乗り上げている.ここでは,山津波の流れを記録する樹木に刻まれた流下痕跡を観察し,一旦は斜面に乗り上げた土砂や構造物の大部分を洗い流した強い引きの流れの存在,山津波の一部が坂州木頭川を跳び越えている状況を確認する.発生域では,崩壊頭部のクラック群・緊張した樹根,崩壊壁の地質を,発生源の谷底では新旧の土石流堆積物,破砕帯,断層を観察する.
四国中央部の中央構造線活断層帯の地形・地質・地下構造
岡田篤正・杉戸信彦
中央構造線活断層帯は日本列島で最長の活断層であり,変位地形の規模も大きく明瞭である.断層露頭も見事である.1995年兵庫県南部地震(M7.3)の発生以降も,多くの調査機関や大学(研究者)が各種の活断層調査を実施してきた.とくに,ボーリング・反射法地震探査・トレンチ掘削調査などが各所で行われ,中央構造線活断層帯の性質・活動履歴・地下構造などもかなり詳しく判明してきた.こうした成果に基づいて,地震調査委員会(2003)から長期評価も公表された.四国中央部における中央構造線活断層帯の代表的な活断層地形や断層露頭などを見学するとともに,地下構造調査の成果も紹介し,活断層に関する総合的な考察を行い,残された課題や問題点などについて検討する.
四国中央部三波川変成岩上昇時の変形構造
遅沢壮一・竹下 徹・八木公史・石井和彦
本見学コースでは,三波川変成岩が後退変成作用を受けつつ上昇して来た時に形成された変形構造(D1,D2およびD3時相に形成された構造)を観察する.このうち,著しい東西塑性流動で形成されたD1変形構造と,鉛直の開いた東西方向の褶曲群で特徴付けられるD3変形構造は識別が比較的容易であり,本見学コースで数地点において観察する.一方D2変形構造はこれまで必ずしも明確でなかったが,最近著者らは,その実体や上昇テクトニクスにおける意味を明らかにしつつあり,本見学コースの重要な観察・議論の対象として取り上げる.第1日目では汗見川流域の高度変成岩中に発達する,D2褶曲やスラストおよびデタッチメント正断層が観察の見所となる.第2日目には,中央構造線近傍国領川流域の変形帯で,D2正断層およびそれを転位させるD3褶曲を観察する.ここでは,D2の北北西方向への運動方向を示す石英スリッケンファイバーも観察する.
高知県土佐山田・美良布地域の白亜系とジュラ系白亜系境界
香西 武・石田啓祐・近藤康生
見学コースは,香美市土佐山田町から香美市香北町にかけて分布する黒瀬川帯南帯の地層見学で,田代(1985)による南海層群の模式地とされている地域である.南海層群の地帯帰属を考察するために,南海層群の南側に分布するペルム紀付加体,南海層群基底部礫岩,テチス型二枚貝フォーナとされている二枚貝類の産出地点を観察する.その後,南海層群と断層で接し,ジュラ紀後期から白亜紀最前期の地質年代を持つ美良布層模式地に移動し,Kilinora spiralis 群集,Loopusprimitivus群集,Pseudodictyomitra carpatica 群集の放散虫と海生・汽水生の二枚貝類の産出層準を見学するとともに砕屑岩・石灰岩からなる堆積相を観察する.また,美良布層のジュラ系白亜系境界についても検討する.
沈み込みプレート境界地震発生帯破壊変形と流体移動:高知県西部白亜系四万十帯,興津,久礼,横浪メランジュ
坂口有人・橋本善孝・向吉秀樹・横田崇輔・高木美恵・菊池岳人
四万十帯における構造地質学的調査,温度圧力条件分析等の進展は,四万十帯が沈み込み帯の震源領域で形成されたことを明らかにした.そして四万十帯において典型的な地震性断層岩であるシュードタキライトが次々に発見され,海溝型巨大地震発生メカニズム解明の地質学的アプローチが可能となった.本巡検では,四万十帯に発達する変形構造(沈み込みから底付け作用,アウトオブシークエンススラストおよび地震に関わる変形岩),流体移動の痕跡である鉱物脈の産状等を観察し,室内分析による基礎データ(マップスケール分布,温度・圧力,差応力など)をもとに議論を行う.
室戸岬ハンレイ岩—マグマ分化プロセスの野外での検証
星出隆志・小畑正明・吉村康隆
室戸岬ハンレイ岩体の岩相変化と層状構造.及び壁岩の接触変成部の溶融構造の観察.特に,岩石の産状,鉱物モード組成,全岩化学組成,結晶サイズ,結晶数密度の観点に基づき,急冷周縁相,結晶集積部,結晶成長部,粗粒ハンレイ岩,斜長岩質岩脈といった本岩体の各岩相相互を関連付け,層状構造の発達とマグマの分化プロセスを検証する.
室戸岬,菜生コンプレックスのメランジェと岩脈
遅沢壮一
菜生コンプレックスのメランジェと斑糲岩岩脈,四十寺山層の火山岩礫岩.D1劈開に切られる玄武岩岩脈.シース褶曲と斑糲岩シル. D0正断層とD1境界スラスト.D−(マイナス)1とD1劈開をもつチャート岩塊.時間次第で,手結メランジェなどのオプションあり.
鮮新統唐の浜層群の層序と化石
岩井雅夫・近藤康生・ 菊池直樹・尾田太良
唐の浜層群は数少ない西南日本に点在する鮮新統のひとつで,当時 の黒潮やテクトニクスを探る上で貴重な浅海域の情報をもたらす.甲 藤ほか(1953)は泥岩主体の登層,礫岩主体の奈半利層(=六本松層), 含貝化石砂岩層主体の穴内層を総称し唐の浜層群を定義した.しかし 分布域が広範で露頭が点在することからその層序関係や年代論に関し ては種々見解が飛び交い混沌としてきた.1990年前後になり登層と穴 内層は一部同時異相の関係にあり,それらを不整合に覆う海成段丘堆 積物が六本松層であると理解されるようになったが,公表されたデー タが断片的で年代論に関してはなお見解に相違がみられた.2005年末 〜2006年初頭に相次いで陸上掘削がなされ,年代論に決着をつけ黒潮 の様相を高時間精度で明らかにしようという取り組みが始まった.本 見学コースでは登層模式地,六本松層模式地,穴内層の堆積シーケン スと岩段丘堆積物・海食地形を案内,論争にいざなう.
室戸半島の第四紀地殻変動と地震隆起
前杢英明
高知から室戸岬にかけての土佐湾北東部の海岸に沿って,標高数百m以下に海成段丘がよく発達している.特に室戸岬に近い半島南部では,段丘面の幅が広くな り,発達高度がより高いことから,切り立った海食崖と平坦な段丘面のコントラストが印象的であり,海成段丘地形の模式地として地理や地学の教科書等に頻繁 に取り上げられてきた.本コースの見どころは,室戸沖で発生する地震性地殻変動と海成段丘形成史とのかかわりについて,これまでの研究成果をふまえて,傾 動隆起などを実際に観察できることにある.さらに,ここ数千年間の地震隆起様式について,地形・地質学的証拠と測地・地球物理学的な見解に相違点があるこ とを,現地を見ながら確認できる.
巡検案内:室戸半島の第四紀地殻変動と地震隆起
室戸半島の第四紀地殻変動と地震隆起
Quaternary crustal movement and coseismic uplift along Muroto Peninsula
前杢英明
Hideaki Maemoku
広島大学大学院教育学研究科
Graduate School of Education, Hiroshima
University, Higashi-hiroshima 739-8524, Japan.
概 要
高知から室戸岬にかけての土佐湾北東部の海岸に沿って,標高数百m以下に海成段丘がよく発達している.特に室戸岬に近い半島南部では,段丘面の幅が広くなり,発達高度がより高いことから,切り立った海食崖と平坦な段丘面のコントラストが印象的であり,海成段丘地形の模式地として地理や地学の教科書等に頻繁に取り上げられてきた.本コースの見どころは,室戸沖で発生する地震性地殻変動と海成段丘形成史とのかかわりについて,これまでの研究成果をふまえて,傾動隆起などを実際に観察できることにある.さらに,ここ数千年間の地震隆起様式について,地形・地質学的証拠と測地・地球物理学的な見解に相違点があることを,現地を見ながら確認できる.
Key Words
海成段丘,室戸半島,地震性地殻変動,第四紀,完新世,暖温帯石灰岩
marine terrace, Muroto Peninsula, coseismic crustal movement, Quaternary,
Holocene, warm-temperate limestone
地形図
1: 25,000 「安芸」「奈半利」「羽根」「室戸岬」
見学コース
8:30 高知大(朝倉)出発→はりまや橋→大山岬→行当岬→室戸岬→18:00 高知大(朝倉)解散
見学地点
Stop 1 安芸市大山岬(隆起ベンチ・海食洞,隆起付着カキ).
Stop 2 室戸市国立室戸少年自然の家(H面・M面の模式地,露頭).
Stop 3 室戸市室戸岬展望台(東海岸・西海岸の非対称地形).
Stop 4 室戸市室戸岬(完新世隆起地形,完新世暖温帯石灰岩).
1.はじめに
西南日本外帯は,フィリピン海プレートがユーラシアacプレートの下に沈み込む南海トラフに面しており,南海トラフ付近では,水平圧縮応力による低角逆断層型と推定される巨大地震が(米倉,1976),歴史時代において数多く発生してきたことが,古文書などによって知られている(沢村,1967;宇佐美,1996).
外帯で南海トラフ側に突出した御前崎,潮岬,室戸岬,足摺岬などには,標高数百メートル以下に数段の海成段丘が発達しており,我が国における海成段丘地形の模式地の一つとして知られている.海成段丘とは,緩く海側に傾斜する浅海底面が氷河性海水準変動と地殻変動によって離水した(干上がった)台地状の地形である.このことから,海成段丘の存在は,少なくとも第四紀後半における当該地域の継続的隆起傾向を示唆している.隆起をもたらした地殻変動の様式はそれぞれの地域で異なるが,南海トラフに近接する地域に関しては,巨大地震のたびに陸地が数十cmから数m隆起しており,このような地殻変動が累積することによって,海成段丘が発達したと考えられている(吉川ほか,1964;米倉,1968).海成段丘の形成史には,ここ数十万年間の平均的な地殻変動速度が反映されているので,海成段丘は第四紀後半の地殻変動様式を復元するのにきわめて有効な研究対象であるといえる.
一方,数十万年間の平均的な地殻変動とダイナミックな氷河性海水準変動によって形成された海成段丘に対して,後氷期海進以降の海水準安定期に,エピソディックな地震隆起などによって、海岸線付近で形成された波食面やビーチが離水した,いわばミニ海成段丘も,保存され観察できることがある.室戸岬周辺には,このようにして形成されたと考えられる2〜3段のミニ海成段丘が発達しており,さらにそれらに付随した海岸隆起の生物・地質学的証拠が多数残されている.
2.地形概説
(1)室戸岬およびその周辺の更新世海成段丘南海トラフ沿う地域の中で,室戸岬付近は第四紀後期における隆起速度が最も速く, 最終間氷期極相期(MIS-5e)の旧汀線高度は最高200m付近にまで達する(吉川ほか,1964など).室戸半島における第四紀地殻変動研究は1900年代前半にまで遡る.今村(1930)は歴史記録により,地震時の急性的地殻変動は,室戸岬側が隆起し高知側が沈降する様式であったと述べ,水準測量結果(1895−1929)から明らかにされた地震間の慢性的地殻変動とは変動の向きが異なることを指摘した.三野(1931)は2段の海成段丘面を認定し,同時期に形成された段丘面が北に向かって高度が下がる傾動隆起を認めた.Watanabe(1931)は3群の海成段丘面を認定し,各段丘面はさらに小さな段丘面に細分されることから,地震性地殻変動によって生じた多生的海成段丘面であると述べた.今村(1937)は上下2段の段丘の旧汀線高度から北傾斜の傾動隆起を推定し,地震時の変動と調和することを示唆した.
このような先駆的な研究のさなか,1946年12月26日に南海道地震が発生し,四国沿岸は大きな地震災害を受けた.この地震後に国土地理院によって行われた水準測量から,地震間には岬部がゆっくり沈み逆に高知平野側が隆起,地震時には室戸岬側が急激に隆起し高知平野側が沈降するといった,シーソーのような地盤運動の様式(今村,1930;沢村,1951a,b;1953;1954)が測地学的にも確認された.その後,海成段丘旧汀線高度と地震前後の水準測量による地盤変動の関係について議論されるようになる.渡辺(1948)も段丘高度の北下がりの傾動を認め,地震性地殻変動の累積によって傾動隆起したものとした.
第1図.室戸半島の更新世段丘分類図(吉川ほか,1964を一部改変),位置はルートマップ参照.
第2図.室戸半島に分布する更新世段丘の旧汀線高度(下)と水準点変位量(上)の投影図(吉川ほか,1964)
第3図.室戸半島の地殻変動と海面変化の推移,および両者を複合した結果(吉川ほか,1964).
太い実線:地盤の海抜高度の変化.細い実線:海面変化(Fairbridge,1961による).
細い破線:地殻変動の積算量.
第4図.西南日本外帯の地震性地殻変動区(破線で示されるヒンジラインより南側)と最終間氷期最盛期の海成段丘高度(太田,1968を一部改変).
吉川ほか(1964)はさらに詳細な段丘地形・堆積物の記載を行い,室戸半島に分布する更新世海成段丘を5段に分類した(第1図).段丘堆積物の層厚や地形的な連続性から,M1面段丘をMonastirian期(最終間氷期極相期,MIS-5e),H2面段丘をTyrrhenian期(MIS-7)の段丘に対比した.南海道地震時の変動量分布が,M1面,H2面海成段丘の旧汀線高度の分布傾向に調和することから,南海道地震タイプの変動様式が段丘形成期,すなわち第四紀後期の十数万年前以降現在まで継続していると述べた(第2図).段丘面の高度は地殻変動と氷河性海水準変動量との組み合わせによって説明でき,最終間氷期極相期の年代を9万年前とすると(Fairbridge,1961),室戸岬は平均2 mm/yrで隆起してきたことになり,これは水準測量結果から推定された平均隆起速度に一致するとした(第3図).なお,現在は最終間氷期極相期の年代は約12.5万年前とする考えが一般的であり,この年代から計算すると段丘隆起速度は1.4 mm/yr程度となる.
吉川(1968)は,傾動運動の軸として室戸半島基部を通るほぼ東西方向の境界線(ヒンジライン)を推定し,これより海溝側を地震性地殻変動区とした(第4図).太田(1968)は段丘の高度分布は地震性地殻変動と調和するが,接峰面図から読み取った山地の高度分布とは一致しないとした.
これに対し,須鎗ほか(1971),阿子島・須鎗(1972)および阿子島ほか(1973)は,段丘礫の赤色風化殻の厚さを指標にして室戸半島の海成段丘の対比を行った.その結果,ほぼ水平に隆起した旧汀線分布を復元し,同地域が第四紀後期にはほぼ均等(水平)に隆起してきたという結果を得ている.これは,前述の吉川ほか(1964)に代表される傾動隆起説を否定し,室戸半島は第四紀後期には南海地震時の変動様式とは異なった様式で隆起してきたことを示したものであるが,その後は水平隆起説(須鎗・阿子島説)を支持する他の研究成果は発表されていない.一方、南海トラフの広域的な地質構造や海底地形の発達を説明するには,傾動隆起を考えざるをえないとした
研究が近年多数発表されている(杉山,1989a,b,1991など).例えば岡村(1990)は,南海トラフに沿う海域の音波探査から海底の地質構造を明らかにし,西南日本外帯は第四紀後期に東西圧縮による南北に軸を持つ波状構造と,フィリピン海プレートの北西進による島弧方向の構造をつくる運動が同時に進行していると述べた。その結果,室戸半島の段丘変形は,南下りの島弧方向の変動と南北に軸を持つ背斜構造が合わさって成長している結果だとした(第5図).最近は,海底地震探査によりさらに詳細な南海トラフ沿いの地下構造が解明されつつある(Kodaira et al, 2000;朴ほか,2001など).これらの成果と第四紀の陸域の地殻変動との整合性が検証されるべきであろう.
第5図.海底地質構造から求められた室戸半島の第四紀地殻変動モデル(岡村,1990).
(2)室戸岬およびその周辺の完新世海成段丘室戸半島は,南海トラフに沿う地域の中で第四紀後期の隆起速度が最も速く,完新世の隆起地形・現象の保存が比較的よい地域である.室戸地域の完新世海成段丘および離水波食地形について調査したTakahashi(1974)は室戸岬付近の隆起波食棚を3段に区分し,吉川ほか(1964)による2 mm/yrの隆起速度とFairbridge(1961)の海面変動曲線を用いて形成の時代論を展開した.また金谷(1978)は室戸半島の完新世海成段丘をL1-L3面の3段に分類し,それぞれM1面(最終間氷期最盛期の段丘面)高度に調和した北への傾動隆起が見られることを指摘した.また,金谷(1978)は,L1面を約6000年前の縄文海進に対応すると仮定して,L1面の平均傾動速度を求め,傾動速度を一定とみなしてL2面を3500年前,L3面を1400年前の離水と推定した.地殻変動速度については,完新世において若干隆起速度が速くなるものの,第四紀後半から傾動隆起が継続しているという結果を得ている.
これに対して,完新世海成段丘や離水波食地形の分布や,潮間帯に棲む環虫類の石灰質遺骸の分布と14C年代に基づき,完新世においても均等かつ不等速に隆起してきたとする研究も見受けられる(須鎗・阿子島,1975;甲藤・阿子島,1980;阿子島・甲藤,1984).
前杢(1988)は,室戸半島の完新世段丘や離水波食地形を調査した結果,段丘面区分については金谷(1978)の分類と概ね一致しているが,南海地震の隆起様式の積み重ねで説明した従来の地殻変動論とは違う見解を述べた.
前杢(1988)は,室戸岬付近のヤッコカンザシ棲管の分布高度と14C年代,および海成段丘を含む隆起波食地形の分布高度から,完新世後半における陸地を不動とした時の海面の相対的高度変化を推定した(第6図).これによると,数百年〜千数百年間の海面高度が相対的に安定する時期と,急激に海面が低下する時期が,完新世に数回繰り返された変化が読み取れる.このように急激な海水準の相対的低下は,大地震に伴う陸地の急激な隆起に起因していると推定できる.最近では,一つの化石群体において複数のポイントから年代試料を採取し,少量の試料で測定が可能なAMSによる14C年代測定を行うことによって,さらに詳細な化石群体の成長過程や地殻変動史が明らかにされつつある(前杢,1999a, b,2001;前杢ほか,2005;第7図).
第6図.隆起海岸地形と付着生物化石による室戸岬の最近6,000年間の相対的海水準変化(前杢,1988).破線上のローマ数字は海水準の安定期を,( )内の数字はその高度を表す.横棒のついた○印はヤッコカンザシの採取高度と年代値を,上矢印の先端は試料を採取した化石群体の上限高度をそれぞれ示す.
第7図.コアリングとAMS14C年代から提示さた室戸岬の最近数千年間の相対的海水準変化からみた予察的隆起モデル(前杢,2001).横棒のついた●印はヤッコカンザシの採取高度と年代値を示す.
室戸岬の隆起は,1946年に発生した南海地震のような,プレート境界付近で発生する大地震に伴う地震隆起の単純な累積に起因するという考え方がこれまで一般的であった.これに対して,室戸岬の隆起海岸形成に直接影響を与えている地震は,プレート境界から枝分かれしたより陸地に近い断層の活動によるものではないかとする仮説(島崎,1980;米倉,1979など)が提示された.杉山(1992)は,島弧方向(外縁隆起帯)と南北方向の背斜構造を逆L字型の一連の構造単元と考え,半島海岸の隆起は南北隆起帯の東縁断層が低角右横ずれ断層とともに活動するときに起こるとし,それはプレート間地震の間隔より数倍〜1桁長い間隔で発生すると述べた.
ヤッコカンザシ棲管や隆起波食地形の分布高度から明らかにされた室戸岬の最近数千年間の地殻変動様式および歴史記録から,南海トラフに沿って発生する大地震にはプレート境界付近で発生する地震(境界タイプ)と,プレート境界から枝分かれした(朴ほか,2001),より陸地に近い活断層の活動を伴った地震(内部タイプ)があり,内部タイプの地震が数百年〜千数百年の間隔で発生することが海成段丘などを形成した主たる要因になっていると推定される.また,境界タイプの地震は100年から200年の間隔で発生するが,1回の地震に伴う隆起量が比較的小さいため,地震後数年間の急速な逆戻りや(Okada and Nagata, 1953)地震間の定常的な南下がりの逆向き傾動運動によって,地形学的証拠は残りにくいと考えられる.
3.見学地点
Stop 1 安芸市大山岬(隆起ベンチ・海食洞,隆起付着カキ)
第8図.Stop 1(大山岬)付近の地形図,1:25,000地形図「安芸」を使用.
第9図.Stop 1 付近で見られる典型的離水ベンチとノッチ.
[地形図]1/2.5万「安芸」
[解説]安芸市南部に位置する大山岬では(第8図),底部の標高が7m前後の海食洞,標高4〜5m前後のベンチ・ノッチが発達している(第9図).また,大山岬や下山の岩礁には標高5〜7mにカキ,ボーリングシェル,ヤッコカンザシ,サンゴの群体が付着しており,上限部のカキの14C年代は1290±60(HR-323)〜1515±60 yrBP(HR-215)(いずれも暦年未補正)という値を示した(前杢,1988).隆起ベンチ高度とカキの年代値からは,完新世の平均隆起速度は室戸岬付近と同じくらいになり,大山岬付近のみに限ってみると,一般的な傾動傾向から外れている.この原因は不明である.
Stop 2 室戸市国立室戸少年自然の家(H面・M面の模式地,露頭)
[地形図]1/2.5万「羽根」「室戸岬」
[解説]更新世の海成段丘は,安芸市からさらに南下し,安田,田野,奈半利町に入ってくると段丘面の幅がしだいに広くなり,分布高度が増加する.羽根岬面の模式地である羽根岬(室戸市)以南ではM1面高度が標高100m以上になる.羽根岬から行当岬の間が,更新世海成段丘(H面〜M面)がもっともよく発達する区間であり(第1図),行当岬東方にある室戸市国立室戸少年自然の家の展望所から,この間の海成段丘地形を一望する(第10,11,12図).また,この区間は,室戸半島でもっとも傾動隆起が著しい区間であり,行当岬でM1面高度が標高200m近くに達する(第2図).
第10図.Stop 2(国立室戸少年自然の家)から展望できる吉良川付近の地形図,1:25,000地形図「羽根岬」「室戸岬」を使用.
第11図.吉良川付近のステレオ空中写真,SI-68-5Y(C14-2.3)を使用.
第12図.吉良川付近の斜め空中写真(前杢英明撮影).
Stop 3 室戸市室戸岬展望台(東海岸・西海岸の非対称地形)
[地形図]1/2.5万「室戸岬」
[解説]室戸半島の大部分は,標高200〜1000mの山地からなる.その分水界は半島の東側に遍在しているため,主な河川は土佐湾に流入しており,それらの河口付近,例えば,北部では安芸川,中部では奈半利川,南部では室津川の河口付近に小規模な沖積平野が発達する.東海岸においては,沖積平野は,海部,宍喰付近に分布する程度で,甲浦以南では小規模な河川しかなく,海食崖が直接海に接しているところが多い.海成段丘の発達も,半島の西側に集中しており,東海岸にはほとんど認められない.室戸半島東岸では大陸棚がきわめて狭く,大陸斜面が陸上から前弧海盆に直接落下している。これは半島東部には外縁隆起帯から続く低角逆断層があるため(粟田・杉山,1989)といわれている。室戸岬を1000年〜2000年の周期で隆起させるプレート内部の活断層は,この断層である可能性が高い.活断層研究会(1991)にも,室戸半島東海岸沖から室戸海脚東縁部に延びる海底活断層が記載されている.室戸岬展望台からは半島の両岸が一望でき,東西の非対称的な地形を確認できる(第13,14図).
第13図.室戸岬先端から見た対照的な東西の海岸地形(前杢英明撮影).
第14図.室戸岬付近のステレオ空中写真,SI-68-5Y(C15-2.3)を使用.
Stop 4 室戸市室戸岬(完新世隆起地形,完新世暖温帯石灰岩)
第15図.室戸岬付近の完新世海成段丘分類図.
第16図.Stop 4 付近で見られる典型的な完新世隆起暖温帯石灰岩.
[地形図]1/2.5万「室戸岬」
[解説]室戸岬付近には完新世海成段丘地形が,比較的よく保存されている(第15図).L1面の高度は11m内外である.L1面は,M段丘に至る比高150m前後の急斜面(海食崖)の下部に張り付くように分布しており,内縁部は崖錐に覆われていて汀線アングルの地形は埋没しているところが多い.L2面は比較的連続性がよく,幅100m以下で旧汀線高度は前後8mである.L2面の海側は防波堤・道路擁壁などによって現在の磯や浜と隔てられている.室戸岬の岩礁には,L2面に対比される高度にベンチ(波食棚)などの波食地形が分布する.室戸岬付近のL1面やL2面も基本的にベンチ地形と考えられる.前杢(1988)は,段丘面の離水年代を知るために,段丘地形そのものからではなく,岩礁部において段丘に対比される高度に分布する生物化石を利用して,それを間接的に推定した.
室戸岬沿岸には,潮間帯の岩場に密集して付着するさまざまな生物が分布している(第16図).これらのうち,環虫類のヤッコカンザシ(Pomatoleios kraussii)は,直径数ミリ,長さ数センチの細長い石灰質の棲管を形成する.潮間帯中部の岩場ではそれらが密集して群体を形成し(今島,1979;三浦・梶原,1983;茅根ほか,1987),厚みが数十センチに達することがある.室戸岬の隆起に伴って,このような生物の棲管も岩礁に固着したまま隆起して石灰岩化し,現在では岩陰などに位置して侵食から免れた群体が,標高約9m付近まで分布している.室戸岬の岩礁遊歩道に沿って,隆起ベンチやノッチの地形,および完新世隆起暖温帯石灰岩が数多く分布している.これらを高度帯,年代別に整理しながら見学する.
文 献
阿子島 功・須鎗和巳・細岡秀博,1973,段丘面対比の指標としての“礫の赤色風化殻の厚さ”の統計的研究−四国島海岸平野の形成過程の研究第5報−.徳島大学学芸紀要(社会科学),22,1-9.
阿子島 功・甲藤次郎,1984,室戸半島の沖積世の地殻変動(2).地理予,26,38-39.
阿子島 功・須鎗和巳,1972,“段丘礫の赤色風化殻の厚さ”を指標とした室戸・紀伊両半島の海岸段丘面の対比.徳島大学学芸紀要(社会科学),20,29-41.
粟田泰夫・杉山雄一,1989,南海トラフ沿いの巨大地震に伴う右横ずれ逆断層構造.地震(2), 42, 221-223.
今島 実,1979,付着動物の種類査定法(1)管棲多毛類.付着生物研究,1,29-35.
今村明恒,1930,四国南部の急性的並に慢性的地形変動に就いて.地震,2,357-371.
今村学郎,1937,隆起汀線測量と精密水準測量.科学,7,306-307.
Fairbridge, R.W., 1961, Absolute Chronology of the Last Glaciation. Science, 123, 355-357.
金谷明子,1978,室戸半島の完新世海成段丘と地殻変動.地理評,51,451-463.
活断層研究会,1991,新編日本の活断層.東京大学出版会,439p.
甲藤次郎・阿子島 功,1980,室戸半島の沖積層の地殻変動.平 朝彦・田代正之編,四万十帯の地質学と古生物学−甲藤次郎教授還暦記念論文集−.林野弘済会高知支部,1-15.
茅根 創・山室真澄・松本英二,1987,房総半島南東岸における旧汀線の指標としてのヤッコカンザシ.第四紀研究,26,47-58.
Kodaira, S., Takahashi, N., Nakanishi, A., Miura, S. and Kaneda, Y., 2000, Subducted seamount imaged in the rupture zone of the 1946 Nankaido earthquake. Science, 289, 104-106.
前杢英明,1988,室戸半島の完新世地殻変動.地理評,61A,747-769.
前杢英明,1999a,室戸半島の最近数千年間の隆起様式から推定される新たな南海地震像.月刊地球,号外,24,76-80.
前杢英明,1999b,室戸岬に分布する隆起環虫類化石群体の成長過程.山口大学教育学部研究論叢,49,
23-36.
前杢英明,2001,隆起付着生物のAMS-14C年代からみた室戸岬の地震性隆起に関する再検討.地学雑誌,110,479-490.
前杢英明・前田安信・井龍康文・山田 努,2005,沈み込み帯沿岸の地殻変動を記録する古潮位計としての完新世暖温帯石灰岩に関する予察的研究.地理科学,60,136-142.
三野与吉,1931,高知市四部に於ける侵食面の対比と土佐湾東半部の海岸地形誌(予報).地学雑誌,43,256-267.
三浦知之・梶原 武,1983,カンザシゴカイ類の生態学的研究.日本ベントス研究会誌,25,40-45.
Okada, A. and Nagata, T., 1953, Land deformation of the neighbourhood of Muroto Point after the Nankaido Great Earthquake in 1964. Bull. Earthq. Res. Inst., 15, 169-177.
岡村行信,1990,四国沖の海底地質構造と西南日本外帯の第四紀地殻変動.地質学雑誌,96,223-237 .
太田陽子,1968,旧汀線の変形からみた第四紀地殻変動に関する二・三の考察.地質学論集,2,15-24.
朴 進午・鶴 哲郎・濱嶋多加志・金田義行・平 朝彦・倉本真一,2001,南海トラフ反射法地震探査データのAVO解析.地学雑誌,110,510-520.
沢村武雄,1951a,南海大地震と地殻変動.高知大学研究報告(自然科学),1,20-33.
沢村武雄,1951b,南海地震に伴った四国の地盤変動に関する一考察.地学雑誌,60,190-194.
沢村武雄,1953,西南日本外帯地震帯の活動と四国およびその附近の地質,地盤運動との関係.高知大学学術研究報告,2,46p.
沢村武雄,1954,続,西南日本外帯地震帯の活動と四国
およびその附近の地質,地盤運動との関係.高知大学学術研究報告,3,6p.
沢村武雄,1967,日本の地震と津波.高知新聞社,231p.
島崎邦彦,1980,完新世海成段丘の隆起とプレート内およびプレート間地震.月刊地球,2,17-24.
杉山雄一,1989a,島弧における帯状構造の屈曲とプレートの斜め沈み込み;第1部−西南日本外帯沖の屈曲構造とプレート境界地震−.地質調査所月報,40,533-541.
杉山雄一,1989b,島弧における帯状構造の屈曲とプレートの斜め沈み込み;第2部−西南日本外帯沖の屈曲構造とプレート間相対運動の変遷−.地質調査所月報,40,543-564.
杉山雄一,1991,第二瀬戸内海の右横ずれ沈降盆地.構造地質,36,99-108.
杉山雄一,1992,西南日本前弧域及び瀬戸内区のネオテクトニクス.地質学論集,40,219-233.
須鎗和巳・阿子島 功・栗岡紀子,1971,室戸地域海岸段丘の再検討(第1報).徳島大学教養部紀要(自然科学),4,19-34.
須鎗和巳・阿子島 功,1975,室戸半島の地殻変動について−地殻変動の不等速性について−.徳島大学教養部紀要(自然科学),8,43-49.
Takahashi, T.,1974, Level and age of the planation of emerged platforms near Cape Muroto, Shikoku. Sci. Rep. Tohoku Univ., Ser.7(Geogr.), 24, 47-56.
宇佐美龍夫,1996,新編日本被害地震総覧.東京大学出版会,416p.
米倉伸之,1968,紀伊半島南部の海成段丘と地殻変動.地学雑誌,77,1-23.
米倉伸之,1976,海溝付近の変動地形と地震.地質学論集,12,151-158.
米倉伸之,1979,太平洋諸地域の第四紀後期の海面変
と地殻変動.月刊地球,1,822-829.
吉川虎雄・貝塚爽平・太田陽子,1964,土佐湾北東岸の海成段丘と地殻変動.地理評,37,627-648.
吉川虎雄,1968,西南日本外帯の地形と地震性地殻変動.第四紀研究,7,157-170.
Watanabe,A.,1931,The geomorphology of the coastal
district of southern Shikoku; a contribution to the knowledge of the recent crustal movements of the areaunder discussion. Bull. Earthq. Res. Inst., 10,209-234.
渡辺 光,1948,四国南部の海岸地形とその基盤運動に対する意義.地理調査書報告,1,37-72.
本稿は「岩井雅夫・村田明広・吉村康隆,2006,見学旅行案内書,地質学雑誌,112,補講,170pp」がオリジナルです。
■ オリジナルPDFダウンロード(J-Stageサーバー)
地質フォト:目次
地質フォト:目次
過去の入選作品はこちら(〜2024年:第15回)>>こちら
第16回惑星地球フォトコンテスト
【総評】
今年の応募総数は432点,昨年の2倍以上の応募数となり,レベルの高いコンテストとなりました.伝統ある日本地質学会の専門家によって評価されることが腕試しとしては最高の場と考え,挑戦する応募者が増えたためでしょうか.
入選した12作品中,6点がスマホのカメラで撮影したものでした.1200万画素のスマホならばA4判の印刷でも遜色ありません.高価なカメラでなくとも,着眼点の良さと機動力がスマホの武器となります.いっぽうミラーレス一眼などでは,対象をよく理解した上で,撮影の時間帯・撮影位置・構図などを綿密に計算し,撮影後の画像処理も丹念になされたレベルの高い作品が上位となりました.
応募作品を眺め,講評を書くために関連するサイトを調べていると,自分でも行ってみたい,見てみたいと思わせる作品が多数ありました.読者の皆様も作品を眺め,解説を読み,ジオの世界をお楽しみ下さい.なお5月13日〜25日には東京・上野公園のパークスギャラリーにて入選作品の写真展が開催されます.ぜひお越しください.
審査委員長 白尾元理(写真家・日本地質学会会員)
惑星地球フォトコンテスト第16回入選作品展示会
パークスギャラリー
過去の展示の様子
佐川地質館の展示(現在)
<東京パークスギャラリー>
日程:2025年5月13日(火) 午後〜 5月25日(日)14時まで
場所:東京パークスギャラリー(上野グリンサロン内)(台東区上野公園 JR上野駅 公園改札出てすぐ)入場無料,どなたでもお気軽にお立ち寄り下さい.
<佐川地質館>
展示中:〜2026年春頃まで継続して展示予定です!
場所:佐川地質館(高知県高岡郡佐川町甲360番地)
入選作品
佳作作品
第16回惑星地球フォトコンテスト:最優秀賞
時を閉じ込めた青の世界
写真:ジェシー
悠久の時を経て創り出された氷河の洞窟....(講評や大きな画像はこちら)
第16回惑星地球フォトコンテスト:優秀賞
朝日を浴びて
写真:芝粼静雄
地震による海底地すべりでできたと考えられる欄間石や蜂の巣状の穴がみられます...(講評や大きな画像はこちら)
第16回惑星地球フォトコンテスト:優秀賞
異空間
写真:徳富 豊
世界最大級のカルデラとも言われる阿蘇山の火映と天の川を捉えた一枚です....(講評や大きな画像はこちら)
第16回惑星地球フォトコンテスト:ジオパーク賞
エメラルドブルーの波蝕甌穴群
写真:伊藤裕也
夕暮れの海岸.岩場に空いた丸い穴々の不思議さと,エメラルドブルーの色が印象的でした.....(講評や大きな画像はこちら)
第16回惑星地球フォトコンテスト:日本地質学会会長賞
白亜紀末の断崖
写真:佐藤峰南
シェラン島の東海岸に見られる白亜紀/古第三紀境界の模式地....(講評や大きな画像はこちら)
第16回惑星地球フォトコンテスト:ジオ鉄賞
稜線の美しさがまぶしい開聞岳と時々枕崎線
写真:水口和史
成層火山である開聞岳の昔の噴火ではコラと呼ばれる火山噴出物が薩摩半島南部に堆積した....(講評や大きな画像はこちら)
第16回惑星地球フォトコンテスト:スマホ賞
静寂が語る大地の悪戯
写真:丸山舞
アイシポップ川を降っていくと水流が突然消え,静寂の美しいゴルジュが現れます....(講評や大きな画像はこちら)
第16回惑星地球フォトコンテスト:大学生・大学院生賞
5億5000万年前のデルタ
写真:福山康太
「東南アジア初のジオパーク」そのフレーズに惹かれ,バックパックでマレーシアのランカウイ島に行ってきました.....(講評や大きな画像はこちら)
画面TOPに戻る
第16回惑星地球フォトコンテスト:入選
四倉海岸の砂絵
写真:志賀敏広
いわき市四倉町にある四倉海岸で見た砂模様です....(講評や大きな画像はこちら)
第16回惑星地球フォトコンテスト:入選
雪化粧したフォッサマグナ
写真:名知典之
上空から見たフォッサマグナは,妙高山,黒姫山など個性的な山々や,野尻湖など複雑な地形に富んでいました....(講評や大きな画像はこちら)
第16回惑星地球フォトコンテスト:入選
危峡を貫く
写真:矢粼 煌
吉野川の水蝕や背斜構造,微褶曲や石英脈群,堆積構造が失われた部分など様々な特徴が見られる小歩危峡,「歩危」は古語で川沿いの崖を意味する言葉です....(講評や大きな画像はこちら)
第16回惑星地球フォトコンテスト:入選(中学・高校生部門)
長い時間をかけた鍾乳石
写真:田中孝樹
修学旅行で鍾乳洞に入った時の写真です.....(講評や大きな画像はこちら)
画面TOPに戻る
佳作(注)(計10点・順不同)
* タイトル等をクリックすると各作品画像がご覧いただけます(準備中).
• 長谷川 卓(石川県・日本地質学会会員)楯状火山・テンデュレク山の広がり
• 山口正明(千葉県)びょうぶ岩の夕暮れ
• 橋爪稜翔(埼玉県児)海底大地
• 楮山 武(鹿児島県)牙城桜島
• 水口和史(福岡県)東シナ海の沿岸流が作り出した甑島の奇岩
• 佐々木亮太郎(秋田県)湧水砂模様
• 片平 洋(鹿児島県)桜島の爆発的噴火
• 小池啓高(東京都)潮騒のレリーフ
• 伊藤裕也(福井県)立山の流れ沢を背に
• 古田大樹(東京都)那智の滝
(注)「佳作」惜しくも入選には至らなかったものの,より多くの優れたジオフォト作品を発掘するために「佳作」を設け,作品画像をWEB上で紹介します.またニュース誌や展示会の際に作品タイトルと撮影者氏名の一覧のみ表示します(表彰および作品の展示は行いません).
画面TOPに戻る
2024年(第15回)以前は>>こちら<<
第15回_佳作1-3
第15回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:日本海に一人佇む
写真:宮田敏幸(兵庫県)
撮影場所:石川県珠洲市見附島
【撮影者より】
猛吹雪で何も見えず。待ち時間を利用して宿舎へ朝食に帰る。1時間後に雪は小降りになり、島の姿が現れた。 少し離れて、雪で白くなった海岸の曲線を入れて海に浮かぶ見附島を捉えた。
目次へ戻る
佳作:縞のトンネル
写真:福田倫太郎,(新潟県)
撮影場所:新潟県長岡市芝ノ又川支流
【撮影者より】
後期鮮新世〜更新世初めにかけて形成された魚沼層群の凝灰質な砂岩泥岩互層の露頭写真である。本地域では柔らかい地質によって地すべりが起こりやすく、この地すべりが作る緩やかな地形を使って田んぼが山間部にも多く存在する。このことから、写真のようなトンネルを人工的に掘り、用水路としている場所が多くある。新しい時代の堆積岩が広く露出し、更に稲作が盛んである新潟県ならではの人と自然が作り出した景色である。
目次へ戻る
佳作:タービダイトとフルートキャスト
写真:大森翔太郎(福岡県)
撮影場所:宮崎県日南市下方猪崎鼻キャンプ場付近
【撮影者より】
宮崎県と鹿児島県に巡検で訪れた際に撮影しました。宮崎県で多く見られるタービダイトとその下部に形成されたフルートキャストになります。フルートキャストは当時の水の流れの向きや上位方向を決定するための良い証拠となります。非常に良い保存状態で残されていたため撮影しました。
目次へ戻る
2022東京・早稲田(編集後記)
編集後記:第129年学術大会(2022東京・早稲田)巡検案内書
日本地質学会第129年学術大会は,早稲田大学と地質学会の関東支部が中心となって実施されました.見学旅行の準備ならびに巡検案内書の編集については,関東支部の幹事の皆様に中心になっていただいた上,見学旅行案内書の編集委員会メンバーも務めていただき,大変なご苦労をおかけいたしました. 2022年早稲田大会は,ひさびさの対面を含む大会となり,大いに盛り上がりました.巡検も一件を除き無事に実行され,かつての日常にもどりつつあることを実感できたと思われます.一方で,新型コロナウィルス感染症の流行は収束したわけではありませんので,学術大会よりも密な状況を作り出す可能性がある巡検の実施に当たってはさまざまな注意を払い,対策がとられました.この点,巡検の実施に関わった皆様には,以前の大会よりもはるかに大変な努力をしていただいたことと思います.また,本巡検案内書の編集については,地質学雑誌編集委員長の大藤 茂氏,副編集委員長の小宮 剛氏,星 博幸行事委員長,そして地質学会事務局の皆さんに様々なご意見を頂戴しました.この場をお借りして本巡検案内書作成に関係した全ての方々に御礼申し上げる次第です.
2022年9月
「巡検案内書」担当編集委員会
委員長 亀尾浩司(千葉大学)
委 員 本田尚正(東京農業大学)
委 員 金丸龍夫(日本大学)
委 員 加藤 潔(駒澤大学)
125記念トリビア5:中村弥六
〜2018年日本地質学会創立125周年を記念して〜
トリビア学史 5 中村彌六(1855-1929):地質学に近しい林学者
矢島道子(日本大学文理学部)
写真 中村弥六(1930)より
2012年ころ,山田直利さん(元地質調査所)とナウマン(Edmund Naumann;1854-1927)の日本の地質調査所の業績の報告(1891)を翻訳した.それは地質に関する報告だけでなく,農学に関する業績も扱っている.地質調査所の初期にはリープシャー(Georg Liebscher;1853-1896) やフェスカ(Max Fesca;1845-1917)の率いる農学部門があったからだ.文中に気候学者としてハン(Julius Ferdinand von Hann;1839-1921)やライン(Johannes Justus Rein;1853-1918)のほかに,Nakamuraという日本人の名がでてくる.気候影響の基準に従って日本の森林構成に注目しているNakamura(1883)というドイツ語論文が紹介されている.このNakamuraは誰だろう.調べてみると,かなり地質学に近しい林学者ということがわかってきた.
中村彌六の略歴
中村彌六(1855-1929;写真)は長野県出身の林学者であると同時に政治家で,「義勇・破天荒の政治家」「日本林業の祖」と伝えられているので,その生涯は多く語られている(たとえば信濃毎日新聞社,1967;根岸ほか,2007).信濃国伊那郡高遠城下(現在の長野県伊那市)に儒学者・中村黒水の二男として生まれる.中村家は代々高遠藩の儒学者の家柄.1869(明治2)年,上京し安井息軒に学んだのち,1870(明治3)年に大学南校に入学し,1872(明治5)年に第一番中学生となる.『東京帝国大学五十年史』には中村の若いころの写真が掲載されている.その写真には,穂積陳重(1855-1926),杉浦重剛(1855-1924),志賀泰山(1854-1934)など錚々たる面々が並んでいる.1877(明治10)年に東京大学が創立される前には,大学南校,開成学校などの学校が生まれては消えていった.第一番中学校もその一つだった.
大学卒業後,1876(明治9)年に東京外国語学校(現在の東京外国語大学)の教師になる.1877(明治10)年に大阪師範学校(現在の大阪教育大学)の教師に転じたが,1878(明治11)年に廃校になったため内務省地理局に入り,ここで林業の重要さに開眼する.1879(明治12)年ドイツに私費留学する.1880(明治13)年,現地で大蔵省御用掛に任命され,官費留学生としてミュンヘン大学で勉強できるようになった.中村はミュンヘン大学に入学した初めての東洋人と言われている.1882(明治15)年末に帰国後は一時大蔵省にいたが,1883(明治16)年に農商務省に入り,さらに新設の東京山林学校教授になる.1886(明治19)年に山林学校が東京農林学校になるとそこの教授になり,野外実習を積極的に行い,林学とは何かを日本人によく理解させた.1889(明治22)年に東京農林学校が東京帝国大学農科大学に昇格したのを機会に退職,農商務省に戻る.
1890(明治23)年に施行された第1回衆議院議員総選挙に,郷里の長野県第6区から立候補し当選する.ここから毀誉褒貶の多い政治家としての人生が始まる.第1次大隈内閣では進歩党系となり司法次官となる.1898(明治31)年のフィリピン独立革命でマリアノ・ポンセが支援を求めて訪日した際,日本軍から革命軍への武器払い下げ交渉に尽力した.しかし武器は輸送船「布引丸」の沈没によってフィリピンに届けることができなかった.残った武器を(フィリピン独立派の承認を得た上で)宮崎滔天が興中会による武装蜂起(恵州事件)に転用しようとした時,中村はそれを勝手に売り払い,かつ代金を着服したことが発覚し,多くの非難を浴びた.ただし中村自身は冤罪であることを訴えている.
「何ぞ独り参政の権利を10円以上の納税者のみに制限するの理あらんや……」との理由を付した,日本初の普通選挙案を憲政本党の降旗元太郎・河野広中,無所属の花井卓蔵らとともに衆議院に提出したものの,否決されたこともあった.さらに,1921(大正10)年11月4日,中岡艮一が当時の首相原 敬を暗殺した際,犯行2日後の東京日日新聞(現毎日新聞)に「艮一の大叔父中村彌六氏談」という見出しでコメントが載ったこともあった.
ふたつほど中村と地質学の関係を示す事柄をあげてみる.
大日本山林会
東京朝日新聞1889(明治22)年2月3日の朝刊記事に下記の記事がある.
大日本山林会 本月28日より来月2日迄3日間木挽町厚生館に於いて大日本山林会大集会を開く筈なり.当日の問題は森林に関する気候(寒晴風,雨等)及び土性説にて,演説は,日本の気候(富士谷孝雄),林道及び木材運搬法(志賀泰山),造林法と材質の関係(農林学校教師独逸人マイエル),民林に対し政府が干渉すべき程度(中村彌六),眠林を覚ますの時果たして至るや(高橋琢也),国土保安林の説(松本収),演題未定(高島得三)同(農林学校教師独逸人グラースマン)の諸氏なり.
大日本山林会は1882(明治15)年に創設された林業界の団体で,現在も大日本農会,大日本水産会とともに赤坂の三会堂ビルにある,日本の第1次産業牽引団体である.新聞記事によれば,大日本山林会の講演会で当時の林学者たちが並んでいる.志賀は中村と終生の友人,マイエルやグラースマンはミュンヘン大学の同窓である.発表者の中に,林学者に交じって富士谷孝雄や高島得三などの地質学者の名前がある.富士谷は1882-1884(明治15-17)年東京山林学校で嘱託をしていたし,高島は内務省地理局時代からの仲間であったのだろう.
磐梯の弥六沼
磐梯山ジオパークの裏磐梯湖沼群地域の入り口に弥六沼がある.弥六沼の弥六は中村彌六への献名である.1888(明治21)年磐梯山の噴火によって桧原湖・小野川湖・秋元湖・五色沼といった大小100余りの湖沼群が誕生した.会津若松市の遠藤十次郎(現夢1864-1934)は1907(明治40)年頃,官有地借地の権利を譲り受け,荒地に植林を開始した.その頃,中村彌六と出会った.中村は,荒地に赤松が適していることを遠藤にすすめ,遠藤は弥六沼の西から中の湯までの山麓に13万本の赤松を植林した.弥六沼の名は中村彌六氏への感謝をこめて,遠藤が名付けた.
文 献
信濃毎日新聞社,1967,信州の人脈(下).信濃毎日新聞社.
東京帝国大学,1932,東京帝国大学五十年史・上冊.東京帝国大学.
Nakamura, Y., 1883, Über den anatomischen Bau des Holzes der wichtigsten japanischen Coniferen. Untersuchungen aus dem forstbotanischen Institut zu München, 3, 17-45.
中村弥六(著)川瀬善太郎(編),1930,林業回顧録.大日本山林会.
Naumann, E., 1891, Neuere Arbeiten der kaiserlich japanischen Geologischen Reichsanstalt. Das Ausland, Jahrgang, 64, 18, 356-360; 19, 372-378.
山田直利・矢島道子,2013a,E.ナウマン著「大日本帝国地質調査所の最近の業績」邦訳.地学雑誌,122(3),521-534.
根岸賢一郎ほか,2007,千葉演習林沿革史資料(6):松野先生記念碑と林学教育事始めの人々,演習林,46号,57-121.
第7回フォトコンテスト_最優秀賞
第7回惑星地球フォトコンテスト入選作品
最優秀賞:奇岩越しの世界文化遺産
写真:後藤文義(神奈川県)
撮影場所:三浦市諸磯海岸
【撮影者より】
諸磯の隆起海岸といえば,地震歴史が目の当たりに分かる,海食崖として国の天然記念物に指定されています.この写真は,関東大震災で隆起した波食台が,その前後の激しい浸食作用を受けて,この様な奇岩となったと考えます.
【審査委員長講評】
三浦半島の南西端にある諸磯海岸から冨士山を臨んだ作品です.房総半島や三浦半島の南部には1923年関東地震で隆起した海岸が広く分布します.隆起海岸は平坦面となっている場所が多いのですが,諸磯海岸では地層に硬さや色の違いがあってキノコ岩のような面白い地形になっています.冨士山を入れたので,臨場感がアップしました.
【地質的背景】
三浦半島は1923年の大正関東地震,1703年の元禄地震をはじめ相模湾,房総沖を震源とする地震の際に繰り返し隆起しており,海岸の地層の露出が非常に良好です.諸磯には凝灰質砂岩,凝灰岩と泥岩の互層からなる三浦層群三崎層(中期〜後期中新世)が分布します.露頭中央には共役逆断層が発達し,断層面が完全に癒着していることから,断層の形成が堆積層の固結前であることが分かります.プレート沈み込み,もしくは大規模な地すべりにともなう変形によるものと考えられます.(芦 寿一郎:東京大学)
目次へ戻る
第7回フォトコンテスト_優秀賞1
第7回惑星地球フォトコンテスト入選作品
優秀賞:白亜紀蓋井島花崗岩に記録されたマグマ混交・混合現象
写真:永山伸一(山口県)・解説:今岡照喜(山口県)
撮影場所:山口県下関市蓋井島
【審査委員長講評】
地層の中に円礫が散らばっているように見えますが,説明文を読むと,珪長質マグマと苦鉄質マグマが混合してできた地層ということです.マグマ同士の混合で,こんなに境界がはっきりするは不思議です.地下深くでマグマがどんな挙動をしていたのだろうかと想像力をかき立てます.
【地質的背景】
下関市吉見の北西約10 kmの響灘に浮かぶ小島,蓋(ふた)井島(いじま)の南東海岸には,「幕(まく)紋(もん)岩」と呼ばれる白と黒の斑模様を織りなす岩石が露出しています.この岩は,釣人の間で「斑岩(まだらいわ)」として知られています.白い基質部は花崗岩(珪長質)マグマが,黒い斑は閃緑岩(苦鉄質)マグマが,それぞれ固まったものです.これら2つのマグマが混ざりあいながら,斑模様をつくりだしています.(今岡照喜:山口大学)
目次へ戻る
第7回フォトコンテスト_優秀賞2
第7回惑星地球フォトコンテスト入選作品
優秀賞:赤い惑星
写真:瀬戸口義継(鹿児島県)
撮影場所:宮崎県宮崎市いるか岬
【撮影者より】
宮崎市にある「いるか岬」は水成岩が浸食され他の惑星の様な雰囲気を醸し出しています.夜には満天の星空と街灯(ナトリウム灯)に照らされ地球上では無い様な景色をみせてくれます.まさに赤い惑星の様でした.
【審査委員長講評】
宮崎市最南部のいるか岬で撮影した作品です.起伏に富んだ宮崎層群の上に広がる,冬の天の川がこの作品の魅力です.冬の天の川には明るい星団が多く,シミのように写っています.また右下の地平線の直上には南極老人星(カノープス)が写り,南国宮崎ならではの作品となっています.
【地質的背景】
日南海岸には,日南層群を不整合で覆ってゆるく東傾斜した新第三系の宮崎層群のうち,砂岩泥岩互層からなる"青島相"が分布している.青島相は「鬼の洗濯岩」として有名なタービダイトが主体であるが,ここでは,塊状厚層の砂岩層からなる隆起波食台が平坦な面をなしている.部分的に炭酸塩などで膠結された部分がコアとなって侵食を免れ,キノコ岩に似た形状を示している.このような侵食形状はとりわけ珍しいものではないが,ナトリウム灯の効果と星空とを組み合わせた高度な撮影技術がすばらしい.(宮田雄一郎:山口大学)
目次へ戻る
【geo-Flash】No.336 「The Geology of Japan」出版!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.336 2016/4/5┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】「The Geology of Japan」が出版!:会員特別販売のお知らせ
【2】2016年「地質の日」イベント情報
【3】リーフレット 長瀞たんけんマップ 好評発売中!
【4】支部情報
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
【7】訃報:倉林三郎 名誉会員 ご逝去
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「The Geology of Japan」が出版!:会員特別販売のお知らせ
──────────────────────────────────
2011年に編集計画がスタートした“The Geology of Japan”ですが,ほぼ5年と
いう歳月をかけて,この3月に出版となりました.本書は,日本地質学会と学術
交流協定を締結しているロンドン地質学会の出版物でありますが,その企画段
階から,日本地質学会の会員が主導的な役割を果たして完成しました.
【購入方法】
1.ロンドン地質学会のHPを通じた購入
販売価格:約8,000円(37.50GBP + 送料 13.50GBP)
ロンドン地質学会の会員と同じ特別価格で購入可能です.
2.日本地質学会を通じた購入(6月下旬納品予定)
販売価格:7,000 円(送料込)
(※)注文部数が目標(200冊)に達した場合にはこの金額よりさらに安くなる
予定です.
目標数:200冊 締め切り:5月26日(木)
書籍の詳細や購入申込など詳しくは,
http://www.geosociety.jp/news/n120.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2016年「地質の日」イベント情報
──────────────────────────────────
■■本部行事■■
第7回惑星地球フォトコンテストほか入選作品展示会・表彰式
4月19日(火)〜5月22日(日)[表彰式:4月23日(土)午後]
場所:地質標本館(茨城県つくば市東1-1-1)入館無料
街中ジオ散歩in Tokyo 「国会議事堂の石を見に行こう」
5月14日(土)1回目 10:00〜11:30/2回目 14:00〜15:30
見学場所:国会議事堂衆議院内(東京都千代田区永田町)
募集期間:4月4日(月)〜15日(金)
募集人員:各回25名(今回は会員の参加も受け付けます)
講演会「日本の地質学:最近の発見と応用2016」
5月21日(土)11:00〜13:00
会場:北とぴあ 第2研修室 (東京都北区王子)
*講演要旨をHPにアップしました!
■■近畿支部■■
第33回地球科学講演会「カンブリア大爆発のあとさき」
5月8日(日)13:30〜15:30
場所:大阪市立自然史博物館 講堂
講師:江崎洋一氏(大阪市立大学大学院理学研究科地球学科教授)
■■北海道支部■■
記念展示 北海道のジオパーク−地球の営みを体感する−
4月26日(火)〜6月5日(日)9:00〜19:00
場所:札幌市資料館 1階展示室【入場無料】
関連イベント
・市民地質巡検「ぶらり 小樽の地質と軟石建造物」6月5日(日)
・市民セミナー「北海道のジオパークを語る」5月7日(土)
■■その他■■(地質学会後援)
観察会 城ヶ島の関東大震災を体感する
主催:ジオ神奈川
5月7日(土)10:00〜15:00
場所:神奈川県三浦市城ヶ島
申込締切:5月4日(水)
観察会「深海から生まれた城ヶ島」
主催:三浦半島活断層調査会
5月22日(土)10:00〜15:00
場所:神奈川県三浦市城ヶ島
申込締切:5月10日(火)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/name/content0139.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】リーフレット 長瀞たんけんマップ 好評発売中!
──────────────────────────────────
地質リーフレットたんけんシリーズ5
長瀞たんけんマップー荒川が刻んだ地球の窓をのぞいてみようー
長瀞の岩畳は『ジオパーク秩父』でも重要なみどころのひとつです.長瀞の岩
石はどこでできたのか,地形や地質のおはなし,長瀞の楽しみかたなどが,わ
かりやすく解説されています.観察ポイントごとに写真やイラストが付いてい
ますので,野外での観察にも最適です.教材としても是非ご活用下さい.
編集:日本地質学会長瀞たんけんマップ編集委員会
発行:一般社団法人日本地質学会
仕様:A2版 8折 両面フルカラー印刷 定価:400円(会員頒価 300円)
http://www.geosociety.jp/publication/content0037.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■2016年度支部総会・地質技術伝承会
4月16日(土)14:00〜16:45
場所:北とぴあ 7階 第1研修室
演題「数値解析手法を用いた岩盤斜面の崩壊挙動評価」
講師:萩原育夫氏(サンコーコンサルタント(株)調査技術部 部長)
*総会に欠席される方は委任状お願いします(締切:4月15日).
詳しくは,http://kanto.geosociety.jp/
[四国支部]
■愛媛大学ミュージアム企画展【四国の鉱物展】
共催:日本地質学会四国支部
3月2日(水)〜4月27日(水)
場所:愛媛大学ミュージアム
http://www.museum.ehime-u.ac.jp/
[西日本支部]
■第二回西日本地質講習会(CPD講習会)
<講習会>6月1日(水)10:00〜
場所:山口大学 大学会館2階
<地質巡検>6月2日(木)9:00〜
須佐の地質・岩石と日本海の形成(講師:今岡照喜)
申込締切:5月19 日(木)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■国際地学オリンピック三重大会運営委員会ニュース No.6(4月)
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/name/olymp/kokusai_chiori_news_2016.4.pdf
■高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する「科学的有望地の要件・基準
に関する地層処分技術WGにおける中間整理」について,専門家からの意見募集
<募集期間>1月20日(水)〜4月19日(火)
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/rw/gijutsu-iken.html
*************(以下,関連団体の行事案内です)****************
■第171回深田研談話会
関東平野と長周期地震動リスク
4月15日(金)15:00〜17:00
講師:古村孝志(東京大学地震研究所)
80名(先着順)参加費無料
http://www.fgi.or.jp
■第185回地質汚染イブニングセミナー
4月22日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ902会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分)
講師:高嶋 洋(野田市土木部下水道主査)
テーマ:地下水法制度の更なる検討について
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■日本学術会議主催学術フォーラム
「原子力発電所事故後の廃炉への取組と汚染水対策」
4月23日(土)12:30〜17:30
場所:日本学術会議講堂(参加費無料)
https://ws.formzu.net/fgen/S57675157/
■「科研費審査システム改革2018」説明会
4月26日(火)13:00〜15:00
場所:安田講堂(東京大学本郷キャンパス内)
対象:研究者等(一般公募,先着順)
参加登録:3月11日(金)〜4月15日(金)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/1367693.htm
■第172回深田研談話会(現地)
地質技術者のための露頭写真の撮り方:箱根火山岩類を対象に
5月14日(土)10:00〜17:00
講師:白尾元理(写真家)
申込締切:4月19日(火)
http://www.fgi.or.jp/?p=3296
■日本地球惑星連合2016年大会
5月22日(日)〜26日(木)
会場:幕張メッセ 国際会議場
早期参加登録:5月10日(火)17:00まで
http://www.jpgu.org/meeting_2016/index.htm
■(共)Goldschmidt 2016
6月26日(日)〜7月1日(金)
会場:パシフィコ横浜
http://goldschmidt.info/2016/index
■(共)第53回アイソトープ・放射線研究発表会
7月6日(水)〜8日(金)
http://www.jrias.or.jp/
■国際シンポジウム 地殻ダイナミクス2016:
異なる時空間スケールにおける地殻ダイナミクス過程の統合的理解
7月19日(火)〜22日(金)(19日:巡検)
場所:高山市民文化会館
参加申込・講演要旨:4月15日締切
http://cd.dpri.kyoto-u.ac.jp/iscd2016/index.htm
■IGCP608「白亜紀アジア−西太平洋生態系」第4回国際シンポジウム
8月15日(月)〜17日(水)
場所:ロシア科学アカデミー シベリア支所 トロフィムク石油地質地球物理学
研究所(ロシア・ノボシビルスク)
ポスト巡検:8月18日(木)〜20日(土)ケメロボ地域の白亜系恐竜産出層
参加登録・要旨締切:5月15日(日)
http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/index.php?id=5#aIndex7
■第35回万国地質学会議
8月27日(土)〜9月4日(日)
会場:南アフリカ共和国ケープタウン
http://www.35igc.org/
■第33回歴史地震研究会(大槌大会)
9月11日(日)〜13 日(火)
(注)開催地が被災地であることを考慮し,変則的な内容となっています.
それに伴い,参加申込方法も例年とは異なります.
http://sakuya.ed.shizuoka.ac.jp/rzisin/menu7.html
■(共)第60回粘土科学討論会
9月15日(木)〜17日(土)
会場:九州大学医系キャンパス
講演申込:6月13日(月)〜24日(金)
http://www.cssj2.org/
■Techno-Ocean 2016
10月6日(木)〜8日(土)
場所:神戸コンベンションセンター
http://techno-ocean2016.jp/jp/
■IGCP589「アジアにおけるテチス区の発達」第5回国際シンポジウム
10月27日(木)〜28日(金)
プレ巡検:10月25日(火)〜26日(水)
ポスト巡検:10月29日(土)〜11月2日(水)
場所:Hlaing大学(ミャンマー,ヤンゴン市)
http://igcp589.cags.ac.cn/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0151.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■産業技術総合研究所テニュアトラック型またはパーマネント型研究員募集(5/11)
■北海道立総合研究機構地質研究所(土砂災害を含む地質災害に関する調査研究)採用情報(1名)(6/4)
■第7回(平成28年度)日本学術振興会育志賞受賞候補者の推薦(学会締切5/16)
■2017年〜2018年開催藤原セミナーの募集(学会締切6/30)
■山田科学振興財団国際学術集会助成(4/1–17/2/24)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】訃報:倉林三郎 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
日本地質学会名誉会員 倉林三郎氏(元 日本地質学会事務局長)が,平成27年12月
3日に肺炎のためご逝去されました(享年87歳).
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます.
なお,ご葬儀などは12月7日に執り行われたとのことです.
会員の皆様に,謹んで御連絡申し上げます.
会長 井龍康文
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
第7回フォトコンテスト_ジオパーク賞
第7回惑星地球フォトコンテスト入選作品
ジオパーク賞:巨岩聳える
写真:小林健一(埼玉県)
撮影場所:群馬県甘楽郡下仁田町御堂山,下仁田ジオパーク ジオサイト「じぃとばぁ」
【撮影者より】
群馬県の西上州の山々には奇岩が多く存在しますが,御堂山(878m)の「ジジ岩,ババ岩」もそのひとつです.下仁田ジオパークのジオサイトでは,「じぃとばぁ」という名称で登録されています.突如として山中に現れた不思議な形の巨岩群にとても驚きました.
【審査委員長講評】
2011年に認定された下仁田ジオパークは妙義山,荒船山などを中心としたジオパークです.岩の上に生えた松がスケールとなって巨岩であることがわかりますし,霞んだ谷間に見える家々や遠くの高圧鉄塔から高い場所に登っている感動が伝わってきます.下仁田ジオパークを訪れたくなる作品です.
【地質的背景】
「じいとばあ」の構成岩は後期中新世に堆積した凝灰角礫岩です.本宿第一次陥没盆地(本宿団体研究グループ,1970)内で発生した火山活動で生まれた火山岩類が,その後の浸食で今日の姿になりました.立像の周辺に断層が見あたらないので,岩塊が垂直方向の節理にそって剥ぎ取られて形成された,と推定されます.(ジオパーク下仁田協議会)
(文献)本宿団体研究グループ, 1970,本宿グリーンタフ層の層序学的研究. 地団研専報, no. 16, 1-12.
目次へ戻る
第7回フォトコンテスト_ジオ鉄賞
第7回惑星地球フォトコンテスト入選作品
ジオ鉄賞:海岸線を行く
写真:大宮 知(北海道)
撮影場所:北海道小樽市張碓町の海岸(恵比寿島付近) JR北海道・函館本線(朝里〜銭函)
【撮影者より】
小樽市の海沿いを走るこの鉄路は,北海道で最初に開業した路線であり,雄大な海を眺めながら,乗っても撮っても楽しい区間.こうして上から見てみると,トンネルや橋など大きな土木工事が難しかった時代に,山塊が海へと沈み込む境目のわずかなスペースを巧みに利用して鉄道を敷いた,当時の技術者の苦労が忍ばれる風景とも言えるでしょう.
【審査委員長講評】
鏡のような海面,浅瀬の模様,礫岩からなる海岸,緑鮮やかな山腹,その間にS字を描いて走る赤い列車.ジオ鉄部門で難しいのは,ジオと鉄道の要素の割合です.この写真では鉄道が8割,ジオが2割というところですが,構図や色彩が整理され,清々しい作品なので,ジオ鉄賞としました.
【地質的背景】
石狩湾に面した銭函海岸。新第三紀の火砕岩からなる海食崖の下を、海岸地形に沿うように走る函館本線。地形的制約を受け限られた場所に敷設された線路の特徴を、俯瞰の構図が見事に捉えています。急峻な海食崖を覆う緑と、海底 地形をも写し込む透き通る石狩湾の青、その間を縫うように6両編成でやってきたのは朱色のボディーが映える国鉄型711系電車です。国鉄時代の昭和43年より活躍した711系は平成27年春に営業運転を終えたことからも記憶に残る一枚に。また道内初の開業路線であり当時の難工事を思う撮影者の説明がジオ鉄写真の魅力を一層引き立てています。手宮(現小樽市内)〜札幌間の開業は明治13年。当地は明治大正期に鰊漁が盛んで、鉄道運行が漁の不振原因になるとして論争の絶えない場所でもありました。写真遠方に見える高島岬には現在登録有形文化財の「にしん御殿」が建っています。ジオ鉄のある美しい風景から鉄道開拓時代のエピソードを読み解きたくなる「ジオ鉄賞」に相応しい魅力ある作品でした。(藤田勝代:深田研ジオ鉄普及委員会)
※「ジオ鉄賞」:第6回より深田研ジオ鉄普及委員会より本コンテストに後援を頂き,あらたに「ジオ鉄」賞を創設しました.鉄道と地球の姿を組み合わせた優れた「ジオ鉄」作品を表彰します.
目次へ戻る
第7回フォトコンテスト_スマホ賞
第7回惑星地球フォトコンテスト入選作品
スマホ賞:中生代の水辺
写真:池上郁彦(オーストラリア)
撮影場所:韓国南東部・巨済島(閑麗海上国立公園)北緯34度44分20.8秒 東経128度39分40.2秒
【撮影者より・地質的背景】
湿った土壌が乾燥すると多角形の割れ目が生じる事は,現在の干潟や田畑でも観察することが出来ます.これは「マッドクラック」と呼ばれ,地質からの古環境復元において水辺であったことを示す強い手掛かりとなります.写真は韓国・巨済島の海岸に露出している白亜紀のJindong Formationにおけるマッドクラックです.さり気なく置いてあるマジックから,割れ目の1辺が20 cmほどであることが分かります.スマートフォンでの撮影なので,ジオタグ* 付きです(解説:撮影者本人).* 写真データに付加される追加情報(タグ)で, 緯度と経度の数値を含めたもの
【審査委員長講評】
韓国南部は白亜紀の地層が広く分布し,恐竜足跡の残る多数の島々からなり,その最大の島が巨済島です.マッドクラックを逆光によって強調させて,目立たないようなスケール(写真中央よりやや右下の赤いマジック)の置き方も憎いばかりです.池上さんは毎回入選している地質研究者で,着眼点がしっかりしていれば,スマホでもこれだけの作品が撮れるという好例です.
※「スマホ賞」:ジオフォトがより身近でより親しみやすいものとなるよう,またチャンスを逃さない新たな視点の作品投稿につながるよう,携帯,スマートフォンでの撮影作品を対象に表彰します.
目次へ戻る
第6回フォトコンテスト_佳作1-2
第6回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:大地を引き裂いた証拠:正断層
写真:三木 翼(福岡県)
撮影場所:Mosaic Canyon, Death Valley National Park, CA, US
【撮影者より】
モザイクキャニオンはデスバレーに位置する谷の一つで, 2000万年前以降の引っぱり応力により地殻が引き裂かれて形成した. 茶色っぽい砂や黒っぽい泥といった砕屑物に加え, ベージュ色を帯びた石灰岩からなる. モザイクの名の通り地層のブロックが非常にはっきりしており, デスバレー形成時の引っぱり応力による正断層が教科書のように表れている. この写真の中でも目をこらせば大小様々な規模の正断層を見つけることができる.
佳作の一覧に戻る
佳作:モーリタニア鉄道
写真:宮森庸輔(東京都)
撮影場所:モーリタニア シュム周辺
【撮影者より】
全長最大3kmの長さになるモーリタニア鉄道。シュムを19時頃に出発し、終点ヌアティブまで14時間ほど乗車。最後尾の客室は有料だが、無料の鉄鉱車に乗る。鉄道が動くとパウダー状になった鉄鉱石が舞い、身体が真っ黒になった。羊飼いと羊たちの先とその反対側に延々と車両が続く。日没後は、一気に気温が下がり、ダウンジャケットを着ても寒さが激しく、身体が凍えた。
佳作の一覧に戻る
第6回フォトコンテスト_佳作3-4
第6回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:nisey(ニセイ)
写真:國分麻衣子(北海道)
撮影場所:遠軽町白滝
【撮影者より】
ここは通称「白滝発祥の地」遠軽町白滝地区の地名由来の場所で鉄道ファンにとっては超定番撮影地です.タイトルにしたニセイはアイヌ語で断崖の意味です.当地白滝は黒曜石の産地として日本ジオパークに認定されており,この地を通る石北本線は常紋トンネルに代表される強制労働による死者を多く出し民衆史上重要な路線.この谷を望むたびに先人の苦労をしのびます.
佳作の一覧に戻る
佳作:光跡
写真:高山幹弘(大分県)
撮影場所:豊後大野市清川町岩戸
【撮影者より】
大野川の本流と奥岳川が合流する岩戸の大絶壁は、阿蘇溶結凝灰岩でできています。この岩壁にはトンネルが掘られ、川を渡る鉄橋に直接接続されており、巨大な壁に鉄橋を渡り列車が吸い込まれていく様は、見事の一言につきます。夜は光も少なく、満点の星空の下を列車が走り抜けて行きます。おおいた豊後大野ジオパークを代表するジオサイトの一つです。
佳作の一覧に戻る
第6回フォトコンテスト_佳作5-6
第6回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:夕暮れのくじゅう(スマホ・携帯)
写真:田中雅士(東京都)
撮影場所:大分県竹田市
【撮影者より】
夕日に照らされる大地が光と影によって九重ならではの起伏を映し出しています.左上にはくじゅう連山,右上には大気の安定成層が見えます.グライダーで飛びながらスマホで撮影しました.
佳作の一覧に戻る
佳作:岩にしみ入る波(スマホ・携帯)
写真:玉城義和(沖縄県)
撮影場所:沖縄県恩納村
【撮影者より】
沖縄県恩納村の海岸にて.岩の地層が,太陽の光に照らされ自然の神秘さを感じ写した一枚です.
佳作の一覧に戻る
geo-flash No.290(臨時)トピックセッションの募集(3/16締切!)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.290 2015/3/12 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[長野大会]トピックセッションの募集(3/16締切!)
【2】中期ビジョン中間報告と意見募集(3/15締切!)
【3】ゆざわジオパークの専門員の募集(3/20締切!)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[長野大会]トピックセッションの募集(3/16締切!)
──────────────────────────────────
第122年学術大会(長野大会)は、中部支部のご協力のもと、信州大学工学部(長野市)をメイン会場として2015年9月11日(金)〜13日(日)に開催されます。
トピックセッションの募集は間もなく締切りです。セッション開催を希望される専門部会・グループは、忘れずにお申し込み下さい。
なお、本大会も前回同様、シンポジウムの一般募集はありません。
※シンポジウムは長野大会実行委員会および学会執行部が企画します。
募集締切:3月16日(月)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0066.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】中期ビジョン中間報告と意見募集(3/15締切!)
──────────────────────────────────
中期ビジョンワーキンググループがこれまでに検討した素案を掲載しています。
ご意見、ご助言などをぜひお寄せ下さいますようお願いいたします。
中間報告はこちらから▼▼
http://www.geosociety.jp/outline/content0148.html
意見募集締切:3月15日(日)
送付先:地質学会事務局(main@geosociety.jp)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】ゆざわジオパークの専門員の募集(3/20締切!)
──────────────────────────────────
湯沢市ジオパーク推進協議会では、専門員の募集をしています(任期なし、65歳定年制あり)。
募集締切:3月20日(金)
詳しくは、湯沢市ジオパーク推進協議会のHPをご覧ください。
http://www.yuzawageopark.com/
また、さらに詳しい話を聞きたい場合は、湯沢市ジオパーク推進協議会事務局にお尋ねください。
電話:0183-55-8195
E-mail:geopark@city-yuzawa.jp
その他、学会に寄せられている公募情報は、下記に掲載されています。
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
第2回フォトコン入選作品:入選
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選:「黒曜石の山」
写真:伊藤 建夫(和歌山県) 撮影場所:北海道遠軽町白滝赤石山八号沢上流山頂付近
撮影者より:
今,北海道遠軽町では自然に親しみ,自然に触れ自然から学んで貰おうと「白滝黒曜石遺跡ジオパーク」を目標に町を挙げて取り組んでいます。この遠軽町の黒曜石は世界的規模で国内最大の黒曜石の産地で300万年前の火山活動で誕生したものです。この地は「日本の地質百選」にも選ばれています。写真は私たち「十勝の自然史研究会」の研修で訪れたときのものです。
石器時代から今日に至るまで、多くの人たちを魅了し続けてきた黒曜石。 特に石器時代には道具の原材料として現在の鉄の役割を果たし、一方、その美しさから装飾品として石器時時代から現在に至るまで多くの人たち、特に高価な金銀宝石に縁のなかった庶民の心を虜にしたした黒曜石。その黒曜石の原産地は地球上でも限られた場所にしか存在しない。遠軽町白滝の赤石山山頂付近は山体そのものが黒曜石でできていて、しかも、赤石山の名が示す通り、漆黒の黒曜石ばかりでなく紅筋の花十勝や茶色の花十勝など非常に美しいものや真ん丸な形をした球果を取り込んだ黒曜石が存在し非常に貴重なジオスポットです。
審査委員長講評:
この作品も佐野さんの作品と同じように,北海道遠軽町の黒曜石を題材にしたものです.しかしとらえ方はまったく異なり,黒曜石の美しさそのものに目を向けています.全体に彩度やシャープネスをもうすこし落とした方が落ち着いた作品になると思います.
←戻る 目次 進む→
第2回フォトコン入選作品:最優秀賞
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:最優秀賞
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:最優秀賞: 「カッパドキアの地」
写真:内藤 理絵(東京都) 撮影場所:トルコ
撮影者より:
トルコのカッパドキアで、早朝気球に乗って撮影したもの.
審査委員長講評:
カッパドキアはトルコを代表する名勝地で,この写真は早朝に観光気球に乗って撮影されたものです.数100mからの高度からは,火砕流堆積物の浸食のされ方の違いによってできた尖塔のようすがよくわかります.傾いた地平線は,見る者を気球にのっているような気分にさせる効果があります.もう1点アップの写真を応募されましたが,アップの写真は町の様子までわかって全体を見渡したこの写真を補うものです.2点ともすっきりとしたさわやかな写真で,審査員全員一致で最優秀賞としました.
地質的背景:
トルコのカッパドキア: アフリカとヨーロッパ大陸の衝突に関連する新第三紀の火山 活動によりできた大量の柔らかい火山サイセツ物(火山灰)が,侵食によりキノ コのような不思議な侵食地形を残す世界遺産である.妖精の煙突とよばれギョレメ国立 公園になっている.地理的位置からも後期青銅器時代のヒッタイト軍の本拠地に なり,その後帝政ローマ帝国,オスマントルコの領有など複雑な世界史も経験した場所 でもある.(九州大学 清川昌一)
目次 進む→
第2回フォトコン入選作品:優秀賞
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:優秀賞
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:優秀賞: 「空を翔ける」
写真:菱川 尚駒(東京都) 撮影場所:ボリビア・ウユニ塩湖
撮影者より:
雨期の時期にのみ現れる、空が鏡のように写り込む幻想的な世界。塩の結晶の上を、ゆっくりと四駆が駆けていく。自然が創り出すものは、ただただ惹きつけられてしまう。
審査委員長講評:
ボリビアのウユニ塩湖は,標高3700mにある四国の半分の面積をもつ巨大な塩湖で,最近では世界のリチウム埋蔵量の半分を保有することでも話題になっています.乾期には水分が蒸発して白一色になりますが,雨期には湖一面が水たまりになってこのような風景が出現します.手前の塩の六角形,水面に映る雲,キャラバンを組む4WD,遠くの山並みなどをうまく組合せて,まるで夢の世界にいるようです.
←戻る 目次 進む→
第2回フォトコン入選作品:入選
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選:「新燃岳、緊迫の生中継」
写真:追鳥 浩生(鹿児島県) 撮影場所:鹿児島県霧島市牧園町
撮影者より:
先週突然大噴火した霧島連山の新燃岳とそれを生中継している地元テレビ局の風景です。
霧島連山の新燃岳が突然大噴火しました。噴火・噴煙は桜島の物を毎日のように見ていて慣れているつもりでしたが、この新燃岳の噴火は全く規模が違いました、恐怖を感じました。私の住む町から新燃岳は北東の位置にあるのですが、北東の空は噴煙が低く垂れこめ、山々やふもとの町を覆っていました。車で霧島へ向かうと、新燃岳がなるべく良く見える場所を探しました、その場所には偶然地元テレビ局の中継車がおり、クルーが緊張した面持ちで生中継をしていました。新燃岳は間髪を入れずドーンドーンと地響きを上げながら噴火を繰り返し、真下から見上げるその噴煙は天を覆い尽くさんばかりでした。私は恐怖と興奮の中、夢中でシャッターを押し続けていました。普段とても大人しくとても美しい霧島連山がまさかこのような大噴火を起こすなんて大変驚きました、霧島連山が活火山であることを思い知らされました。それでも私は霧島連山の山々と森と大自然が大好きです。早く沈静化し再び登山ができるようになってほしいです、普段の大人しい霧島連山はそれはもうとてもとても美しく神秘的なのですよ。
審査委員長講評:
2011年1月26日,霧島山新燃岳は本格的な噴火をはじめました.この作品は翌日の27日に撮影されたものです.この日の噴煙は高さ2500m以上にも達し,噴煙の基部では直径数mもの岩塊が飛び散っているのがわかります.バックの荒々しい噴火に比べ,芝生の上で淡々と中継するテレビスタッフのようすが対照的です.
←戻る 目次 進む→
第2回フォトコン入選作品:入選
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選:「光と共に」
写真:大木 晴雄(埼玉県) 撮影場所:栃木県鹿沼市
撮影者より:
古代から共に生きてきた岩と太陽をいっしょにとらえたいと思い考えた構図作りです。
栃木県鹿沼市草久 古峰神社付近 話には聞いていたのですが実際にこの珍しいガラをした石に出会った瞬間,自然の強さと時間の力を感じシャッターを押さずにはいられませんでした.自然界の作る芸術を目の当たりにして人間の小ささを感じました.太古から輝き続ける太陽光と気が遠くなるような時間をかけて作品になっていく石.まだ完成ではないのでしょうが….両方をいっしょに入れて撮りたいと思い考えた構図です.入選して本当に良かったです.皆さんに見ていただきたい石の芸術です.
審査委員長講評:
このトラ皮のような縞模様の岩石は,どのようにしてできるのでしょうか.濡れた岩肌とそれに付着する地衣類,くぼみに溜まった水,そこに写った曇天から顔を出した太陽………….説明的な地質写真ではありませんが,悠然たる時の流れを感じさせます.
←戻る 目次 進む→
第2回フォトコン入選作品:入選
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選:「石鎚山麓」
写真:太田 義将(兵庫県) <高校生以下の部> 撮影場所:JR予讃線 玉之江〜壬生川
撮影者より:
西日本最高峰である石鎚山をバックに一両列車が快走します。
愛媛県西条市石田 踏切を北側に渡った先の所 一日中霞がかかっていましたが夕方の一瞬,石鎚山が姿を現しました.
審査委員長講評:
作者は愛媛県西城市から予讃線のローカル列車とともに四国の最高峰石鎚山(標高1982m)を写しています.全体が夕焼け色に染まり,手前の市外地を走るローカル列車,中景の標高数百mの山並みを配置することによって,画面奧に霞む石鎚山の急峻さや高度感がうまく表現されています.
←戻る 目次 進む→
第2回フォトコン入選作品:入選
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選:「自然が生み出す漆黒の石」
写真:佐野 恭平(北海道) 撮影場所:北海道遠軽町白滝 十勝石沢露頭
撮影者より:
北海道遠軽町白滝で見ることができる,黒曜石路頭。流紋岩質の溶岩噴火により,美しき黒曜石は生み出された。溶岩の断面の一部が黒曜石層となっている。厚さ数mにも及ぶ黒曜石層には思わず見とれてしまう。
日本ジオパークに認定されている北海道遠軽町白滝の黒曜石露頭.約220万年前の溶岩噴火によって,美しき黒曜石は生み出された.厚さ数mにも及ぶ黒曜石層には思わず見とれてしまう.黒曜石の魅力,白滝の魅力が少しでも伝わればと思い,投稿しました.
審査委員長講評:
黒曜石は,流紋岩〜デイサイト質のガラス質火山岩で,割ると鋭利な刃物として利用できることから石器時代には珍重されていました.この作品は日本を代表する黒曜石産地の北海道遠軽町の黒曜石の露頭を写したもので,黒曜石の産状がよくわかります.奧の木々が,露頭の大きさを示すよいスケールとなっています.
←戻る 目次 進む→
第2回フォトコン入選作品:入選
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選:「荒々しき車窓」
写真:太田 義将(兵庫県) <高校生以下の部> 撮影場所:JR高山本線 白川口〜上麻生からの車窓 飛水峡
撮影者より:
高山本線の車窓は穏やかな鏡のような飛騨川と荒々しく奇岩の多い飛騨川と様々な顔を見せてくれます。中でも飛水峡と呼ばれる一帯は甌穴が数多く見ることができ、国の天然記念物にも指定されています。
岐阜県加茂郡七宗町上麻生(飛水峡) 普通列車より飛騨川の車窓 車窓に飛水峡が最も荒々しく映った所を撮影しました
審査委員長講評:
こちらも「石鎚山麓」と同じ作者,太田さんの作品なので四国の大歩危小歩危かと思いましたが,岐阜県の飛水峡でした.飛水峡はジュラ紀の海洋底堆積物チャートからできており,付加帯として海溝に掃き寄せられた堆積物からできています.車窓からでは良い撮影ポイントは一瞬で通り過ぎていましますが,そのポイントを逃さず,また窓枠の入れ方も秀逸です.
←戻る 目次 進む→
第2回フォトコン入選作品:入選
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選:「二つの斜面」
写真:加藤 大佑(神奈川県) <高校生以下の部> 撮影場所:後立山連峰白馬鑓ヶ岳
撮影者より:
白馬鑓ヶ岳から見た杓子岳。この山は北西からの強い季節風により雪が西側斜面(写真左側)から東側斜面(写真右側)へと吹き上げられる。この影響で西側斜面は凍結と融解を毎年繰り返す周氷河作用によりなめらかな斜面に、東側は全層雪崩等により稜線直下が急な斜面が形成される。このような山稜を非対称山稜といい、例としては隣の白馬岳がよく上げられるが東側斜面の崩れ具合等は杓子岳のほうが勇ましい。標高2812m。
岐阜県加茂郡七宗町上麻生(飛水峡) 普通列車より飛騨川の車窓 車窓に飛水峡が最も荒々しく映った所を撮影しました
審査委員長講評:
北アルプスの白馬鑓ヶ岳から杓子岳を望んだ写真で,写真には見えませんがその奥には白馬岳があります.この地域は,左(西)側の緩斜面と左(東)側の急斜面からなる非対称山稜の典型として知られています.解説文にもあるように作者の加藤さんはそのことをしっかり理解して撮影されています.このような知識があると山歩きがいっそう楽しくなります.
←戻る 目次 進む→
第2回フォトコン入選作品:入選
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選:「複成火山の連なり」
写真:小島 一彦(北海道) 撮影場所:岩手県上空(岩手山〜八幡平〜森吉山付近)
撮影者より:
航空機から見下ろす冬景色は、地形が雪にあぶり出されて大変に興味深いものです。雪化粧した岩手山の河口は、その美しさと裏腹に、我々の暮らしのすぐ側にも火山活動があることを思い出させます。
2011/1/27 ANA054便 札幌(千歳)9:30発 東京(羽田)11:10着
この日はとても天気が良く,航空機内からの景色がきれいでした.ひと際目立つ岩手山の白い火口は,人が作ったどの建造物よりも大きく,改めて,火山活動のパワーを思い知らされます.
審査委員長講評:
手前に岩手山(標高2038m),中央右に八幡平(1613m),その向こうに森吉山(1454m),さらに遠方には日本海も見えます.高度1万mを飛行する定期便はこのような広い範囲を撮影するのに適しています.セスナでは高度4000mまでしか上昇できないので,このような写真を撮ることはできません.作者の小島さんは,天候,時間帯,座席に恵まれ,良い作品をものにしました.
←戻る 目次 進む→
研究最前線:目次
研究最前線
シンポジウム&トピックセッションダイジェスト
地質学会で今ホットな研究は何か?! 学術大会で開催されたシンポジウムおよびトピックセッションの目的、内容、成果などをわかりやすく紹介します。
1、南海付加体の実体に迫る:そのミクロ構造とマクロ構造
このシンポジウムでは,潜水船によって採取された岩石や調査船によって得られた海底地形図を使った研究発表が行われました.しかし,私たちの研究の出発点は,海底ではなく,陸上の調査にあります。 詳しくはこちら
川村喜一郎(深田地質研究所)
2、地球史とイベント大事件(3):地球の変化に迫る
地球の歴史は人生の転機ともいうべき大きなイベントがいくつもあって、それ以降の世界を一変させています。このような現在では想像のつかない大事件の歴史が地層には残され含まれており、その痕跡・原因を調べることにより、我々の地球の未来の方向づける重要な指針を明らかにしようとしています。詳しくはこちら。
清川昌一(九州大学)
3、海底地すべり
海底地すべりは,私たちの生活にさまざまな影響を及ぼします.まず,海底ケーブルや海底パイプラインが切断される.さらに,資源開発など海底掘削でのプラットフォームに障害が発生する.また,メタンハイドレートが大規模に融解する,津波が発生するなどです.詳しくはこちら。
川村喜一郎(深田地質研究所)
キーワード
学会でホットなキーワードとそれに関係する研究を紹介します。
1、「大イベント」
2、「カルデラ」
3、「海底地すべり」
データベースとリンク
データベースと外部リンク
リンク集
■学協会(国内)
■学協会(海外)
■大学(国内・海外)
■その他
■官公庁・法人
■賛助会員(企業他)
■博物館
データベース
産業技術総合研究所データベース
地質図Navi
産総研地質調査総合センターから配信される数多くの地質図データを表示するとともに、活断層や第四紀火山などの地質情報を地質図と合わせて表示することが可能な地質情報閲覧システムです.
20万分の1日本シームレス地質図
Webブラウザ上で,ユーザーの環境やニーズに応じて,4通りの方法で各地域の地質図を閲覧可能である.また,必要な地域の画像データをダウンロードして,さまざまな目的に利用していただけます.
地層名検索データベース
産業技術総合研究所(地質調査所.一部は北海道開発庁,北海道立地質研究所)発行の5万分の1地質図幅に用いられている地層名の検索ができます
活断層データベース
文献から忠実に収録された日本の活断層の調査研究結果データ各種,それらを集約したパラメータ代表値,文献情報さらには図表まで情報量豊富.
海と陸の地球化学図
日本全国の海と陸の地球化学図データベース〜有害元素を含む元素濃度分布の全国 マッピング.
第四紀火山岩体・貫入岩帯データベース
“第四紀”に活動した火山岩体および,“第四紀”に貫入・固結し,その後の隆起・侵食作用によって地表に露出した貫入岩体を採録しています.
地質調査総合センターGeoLis検索(文献検索)
地質情報基盤センター アーカイブ室で収集および所蔵している、地質関連の文献資料・地図類をデータベース化.
文 献
国立国会図書館 デジタルコレクション
国立国会図書館で収集・保存しているデジタル資料を検索・閲覧できるサービスです(収集・保存したウェブサイト、CD/DVD等のパッケージソフトは除く)
科学技術情報発信・流通総合システム:J-STAGE
*地質学雑誌バックナンバー検索はこちら
地質学雑誌のオンラインジャーナル(1巻1号より閲覧可),学術大会講演要旨も閲覧できます.
NII論文情報ナビゲータサービス:CiNii
国立情報学研究所電子図書館サービス
石渡 明会員のデータベース
金沢大の旧サイト/東北大のサイト/鉱物鑑定表:ABC順索引
標本・試料ほか
在日本脊椎動物化石標本データベースJAFOV
JAMSTEC航海・潜航データ・サンプル探索システム
船舶・潜水船で得られたデータ、岩石サンプル、堆積物コアサンプルの情報を公開するとともに、関連するデータベースにリンクしています。
国土地理院:地図・空中写真・地理調査
国土地理院の地図・空中写真・基盤地図情報等を提供しています
3D版ELSAMAP日本全図(信州大学山岳科学研究所)
ELSAMAP(Elevation and Slope Angle Map;カラー標高傾斜図)は傾斜量図と高度段彩図を重ね合わせた、地形表現図.地形の特徴を際立たせて表現した地図を「鳥瞰図」として、日本全国どこでも、好きな視点から自由自在に眺めることがでます.
ページTOPに戻る
リンク集
■学協会(国内)
■学協会(海外)
■大学(国内・海外)
■その他
■官公庁・法人
■賛助会員(企業他)
■博物館
学協会(国内)
日本応用地質学会
岩の力学連合会
日本海洋学会
日本火山学会
日本鉱物科学会
日本機械土工協会
日本古生物学会
日本活断層学会
日本地震学会
日本自然災害学会
日本情報地質学会
日本水文科学会
砂防学会
資源地質学会
自然史学会連合
地すべり学会
地盤工学会
水文・水資源学会
石油技術協会
Oil Survey(石油関連検索エンジン及びリンク集)
砂防・地すべり技術センター
日本測地学会
日本堆積学会
日本第四紀学会
日本地下水学会
日本地学教育学会
日本地球化学会
日本地形学連合
日本地熱学会
日本地理学会
日本地理教育学会
日本洞窟学会
地学団体研究会
地球電磁気・地球惑星圏学会
東京地学協会
土木学会
日本粘土学会
日本物理学会
日本有機地球化学会
日本陸水学会
歴史地震研究会
富士学会
物理探査学会
地質汚染−医療地質−社会地質学会
日本地球惑星科学連合
(社)全国地質調査業協会連合会
北海道地質調査業協会
東北地質調査業協会
関東地質調査業協会
中部地質調査業協会
関西地質調査業協会
中国地質調査業協会
四国地質調査業協会
九州地質調査業協会
ページTOPに戻る
学協会(海外)
The Geological Society of America
Geological Society of Australia
Austrian Geological Society
Brazilian Geological Society
Bulgarian Geological Society
Geological Society of China
Czech Geological Society
Geological Society of Denmark
Nederlandse Geologische
Vereniging
Deutschen Geologischen Gesellschaft(Germany)
Iceland meteorological office
Geological Society of India
Israel Geological Society
Geological Society of Jamaica
Geological Society of Malaysia
Nepal Geological Society
Geological Society of New Zealand
Geological Society of the Philippines
Saskatchewan Geological Society(Canada)
Geological Society of South Africa
Swiss Geological Society
The Geological Society of Trinidad and Tobago
Geological Society of Zambia
Geological Association of Canada
Irish Geological Association
The Geological Society of Korea
■ The Geology Society of Mongolian
■ The Geological Society of Thailand
■ The Geological Society, London
■ Geological Society Located in Taipei
■は学術交流協定締結団体
大学(国内・海外)
北海道・東北
北海道大学大学院地球環境科学研究科
北海道大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻
北海道大学大学院理学研究院付属地震火山研究観測センター
北海道教育大学
室蘭工業大学
弘前大学理工学部地球環境学科
秋田大学教育文化学部地学研究室
秋田大学工学資源学部地球資源学科
東北大学理学部地球科学系
東北大学大学院理学研究科地学専攻
東北大学大学院理学研究科宇宙地球物理学科・地球物理専攻
宮城教育大学理科教育講座
山形大学理学部地球環境学科
山形大学地域教育文化学部生活総合学科
福島大学共生システム理工学類環境システムマネジメント専攻(地球環境科学)
関東
群馬大学教育学部自然情報系・理科専攻(地学)
茨城大学理学部地球環境科学コース
茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター
筑波大学地球科学系
宇都宮大学教育学部理科教育(地学)
埼玉大学工学部建設工学科
千葉大学理学部地球科学科
東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻
東京大学大学院工学系研究科地球システム工学専攻
東京大学大学院総合文化研究科宇宙地球部会
東京大学地震研究所
東京大学大気海洋研究所
東京大学生産技術研究所
東京工業大学地球惑星科学科
首都大学東京地理学教室
日本大学文理学部地球システム科学教室
早稲田大学教育学部地球科学教室
早稲田大学人間科学部人間環境科学科
慶應義塾大学理工学部応用化学科(地球化学)
横浜国立大学教育人間学部(地球環境課程)
中部・甲信越
新潟大学災害復興科学センター
新潟大学理学部地質科学教室
新潟大学理学部自然環境科学科
上越教育大学理科地学教室
富山大学理学部地球科学教室
福井大学教育地域科学部
金沢大学理工学域自然システム学類地球学コース
山梨大学教育人間科学部
信州大学理学部地質科学科
信州大学理学部物質循環学科
岐阜大学教育学部地学教室
岐阜大学工学部社会基盤工学科(地質)
静岡大学理学部生物地球環境科学科
静岡大学教育学部総合科学教育課程(地球科学系)
東海大学海洋学部
愛知教育大学地学教室
名古屋大学理学部地球惑星科学教室
名古屋大学大学院環境学研究科
名古屋大学大学院環境学研究科付属地震火山防災研究センター
近畿・四国・中国
滋賀大学教育学部自然科学系(地学)
京都大学理学部地質学鉱物学教室
京都大学理学部地球物理学教室
京都大学総合人間学部自然環境学科生物地球圏環境論講座地球科学分野
京都大学防災研究所
大阪大学大学院理学研究科宇宙地球科学専攻
大阪府立大学理学部物理科学科(地球科学)
大阪市立大学理学部地球学科
大阪教育大学理科教育講座(地学)
神戸大学理学部地球惑星科学科
兵庫教育大学自然系コース(地学)
兵庫県立大学理学部
和歌山大学教育学部
三重大学教育学部
岡山大学理学部地球科学科
岡山大学地球物質科学研究センター
岡山理科大学自然科学研究所
山口大学理学部地球圏システム科学科
広島大学文学部地理学研究室
広島大学理学部地球惑星システム学科
島根大学総合理工学部地球環境資源学科
鳥取大学教育地域科学部地域環境学科
鳴門教育大学地学教室
香川大学工学部安全システム建設工学科(地質学)
徳島大学総合科学部自然システム学科
愛媛大学理学部地球科学科
高知大学理学部地球科学
高知大学海洋コア総合研究センター
九州
九州大学理学府地球惑星科学
九州大学大学院理学研究院 附属地震火山観測研究センター(島原)
大分大学教育福祉学部理科教育課程
佐賀大学文化教育学部・学校教育課程理科選修
熊本大学理学部地球環境
福岡教育大学教育学部理科教育講座
福岡大学理学部地球圏科学科
長崎大学環境科学部環境科学科環境保全設計学系
長崎大学教育学部
宮崎大学教育学部地学講座
鹿児島大学理学部地球環境科学科
琉球大学理学部物質地球科学科地学系
海外
Open University Geological Society (London Branch)
Department of Earth Sciences University of Oxford
(2011年2月現在)
ページTOPに戻る
官公庁・法人:
文部科学省
地震調査研究推進本部(地震本部ニュース)
環境省
原子力規制委員会
国土交通省
国土地理院
地理院地図/GSI Maps
気象庁
気象庁気象研究所
経済産業省
外務省
農林水産省
海上保安庁海洋情報部
日本海洋データセンター
特許庁
日本学術会議
産業技術総合研究所地質調査総合センター
防災科学技術研究所
地震ハザードステーション
国立極地研究所(NIPR)
国立環境研究所
国立情報学研究所(NII)
科学技術振興機構(JST)
国立国会図書館
土木研究所(PWRI)
建築研究所
北海道立総合研究機構
環境・地質研究本部地質研究所(旧:北海道立地質研究所)
北海道開発土木研究所
神奈川県温泉地学研究所
新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)
海洋研究開発機構(JAMSTEC)
日本地球掘削科学コンソーシアム(J-DESC)
日本原子力研究開発機構
エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)
MH21-S 研究開発コンソーシアム
水資源機構
国際協力機構(JICA)
宇宙航空研究開発機構
電力中央研究所
鉄道総合技術研究所
深田地質研究所
高速道路技術センター(EXTEC)
河川情報センター
リモート・センシング技術センター(RESTEC)
日本建設情報総合センター(JACIC)
テクノオーシャン・ネットワーク
--------------------------------------------
賛助会員:(2025年10月現在)
※学会の目的に賛同し,学会の事業を賛助する個人,法人および団体(定款第2章第6条より)
<企業>
■ 旭鉱末資料合資会社
■ アジア航測(株)
■ 株式会社INPEX
■ (株)エイト日本技術開発
■応用地質(株)
■ 関東天然瓦斯開発(株)
■ 川崎地質(株)(事業本部)
■ 川崎地質(株)(西日本支社)
■ 基礎地盤コンサルタンツ(株)
■ (株)建設技術研究所
■ 興亜開発(株)
■ 国際航業(株)
■ サンコーコンサルタント(株)
■ ENEOS Xplora(株)旧・JX石油開発(株)
■ 石油資源開発(株)
■ 総合地質調査(株)
■ 大平洋セメント(株)
■ 大日本ダイヤコンサルタント(株)
(23.7月名称変更)
■ (株)地圏総合コンサルタント
<博物館>
■北九州市立自然史・歴史博物館(いのちのたび博物館)
■中央開発(株)
■ 日鉄鉱業(株)
■(株)日さく
■日本工営(株)
■(株)ニュージェック
■(株)パスコ
■明治コンサルタント(株)
■日本海洋事業(株)
■四国建設コンサルタント(株)
■山北調査設計(株)
■三洋テクノマリン(株)
■八千代エンジニヤリング(株)
■共立工営(株)
■ (株)中部森林技術コンサルタンツ
■山陰開発コンサルタント(株)
■Nanjing Binzhenghong Instrument Co., Ltd
■ (株)地球科学総合研究所
■(株)アーステクノ
■八洲開発(株)
■明大工業(株)
博物館:
<北海道>
旭川市博物館
足寄動物化石博物館
虻田町立火山科学館
えりも町郷土資料館・水産の館
斜里町立知床博物館
石炭の歴史村夕張市石炭博物館
忠類ナウマン象記念館
沼田町化石館
日高山脈館
北海道開拓記念館
北海道大学総合博物館
三松正夫記念館(昭和新山資料館)
むかわ町立穂別博物館
札幌市博物館活動センター
士別市立博物館
中川町エコミュージアムセンター
三笠市立博物館
<東北>
青森県立郷土館
秋田県立博物館
秋田大学付属鉱業博物館
岩手県立博物館
東北大学総合学術博物館
仙台市科学館
地底の森ミュージアム(仙台市富沢遺跡保存館)
久慈琥珀博物館
山形県立博物館
福島県立博物館
磐梯山噴火記念館
唐桑半島ビジターセンター・津波体験館
石と賢治のミュージアム 太陽と風の家
宮沢賢治記念館
陸前高田市海と貝のミュージアム
陸前高田市立博物館
龍泉新洞科学館
<関東>
群馬県立自然史博物館
鬼押出し浅間園 浅間火山博物館
神流町恐竜センター
ミュージアムパーク茨城県自然史博物館
地質標本館(産業技術総合研究所)
稲田石資料館 石の百年館
埼玉県立自然史博物館
千葉県立中央博物館
国立科学博物館
東京大学総合研究博物館
府中市郷土の森博物館
科学技術館
相模原市立博物館
平塚市博物館
神奈川県立生命の星・地球博物館
横須賀市自然博物館
川崎市青少年科学館
<甲信越・北陸>
新潟県立自然科学館
フォッサマグナミュージアム
長岡市科学博物館
青海自然史博物館
出雲崎石油記念館
野尻湖ナウマンゾウ博物館
信州新町化石博物館
戸隠村地質化石館
ミュージアム鉱研地球の宝石箱
松本市四賀化石館
大鹿村中央構造線博物館
立山カルデラ砂防博物館
富山市科学博物館
福井市自然史博物館
福井県立恐竜博物館
山梨宝石博物館・河口湖
山梨県立富士ビジターセンター
<東海>
東海大学自然史博物館
(財)石の博物館(奇石博物館)
名古屋市科学館
豊橋市自然史博物館
鳳来寺山自然科学博物館
蒲郡情報ネットワークセンター・生命の海科学館
瑞浪市化石博物館
中津川市鉱物博物館
美濃加茂市民ミュージアム・みのかも文化の森
岐阜県立博物館
日本最古の石博物館
博石館
三重県立博物館
<近畿>
みなくち子どもの森自然館
多賀町立博物館
滋賀県立琵琶湖博物館
京都大学総合博物館
(財)益富地学会館 石ふしぎ博物館
京都市立青少年科学センター
大阪市立自然史博物館
きしわだ自然資料館
和歌山県立自然博物館
兵庫県立人と自然の博物館
玄武洞ミュージアム
史跡生野銀山と生野鉱物館
阪神淡路大震災記念 人と防災未来センター
北淡震災記念公園(野島断層保存館)
香芝市二上山博物館
<中国・四国>
日本化石資料館
笠岡市立カブトガニ博物館
鳥取県立博物館
(財)奥出雲多根自然博物館
島根県立三瓶自然館サヒメル
石見銀山資料館
秋吉台科学博物館
美祢市化石館
徳島県立博物館
香川県立五色台少年自然センター自然科学館
ラピス大歩危石の博物館
愛媛県総合科学博物館
龍河洞博物館
横倉山自然の森博物館
佐川地質館
<九州・沖縄 >
北九州市立自然史・歴史博物館 いのちのたび博物館(賛助会員)
大牟田市石炭産業科学館
御船町恐竜博物館
阿蘇火山博物館
御所浦白亜紀資料館
宮崎県総合博物館
鹿児島県立博物館
桜島国際火山砂防センター
雲仙岳災害記念館
沖縄県立博物館
その他
■ 日本技術者教育認定機構(JABEE)
■ 地球・資源分野JABEE委員会
■ 地震火山地質こどもサマースクール
■ 地質地盤情報の活用と法整備を考える会
■ 地域巡検的WEB教材「川崎ジオポイント」
------- 川崎ジオポイントcafé-@nifty-
------- 川崎ジオポイントcafé-@facebook
------- かわさきジオポイントcafé-live doorblog-
【geo-Flash】No.388(臨時)[愛媛大会]スタート!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.388 2017/9/16 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】愛媛大会:初日の様子
【2】愛媛大会:台風18号接近に伴う対応(既報済)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】愛媛大会 初日の様子
──────────────────────────────────
愛媛大会が開幕しました!
それでは大会の様子を写真でご覧ください.
■大会スタート
さあ、始まります
スタートダッシュ
初日から大盛り上がり
熱い議論
■地質情報展
愛媛大学ミュージアムで開催中。ぜひ見に行きましょう。
水流実験
断面模型
巨大地質図
大看板
大人気の石割
好きな石を割ろう
メディアも駆けつけ
噴火実験
重力異常を起こそう
地震を起こそう
断層の音
フォトコン展示
■ 表彰式が開かれました。
南加記念ホール
会長挨拶
愛媛大学副学長
名誉会員証
鈴木博之会員
波田重煕会員
大場忠道会員
永年会員
岡田昭明会員
地質学会賞
ウォリス会員
国際賞
Dr. Richard S. Fiske
柵山雅則賞
平内健一会員
Island Arc賞
纐纈佑依会員
地質学会論文賞
野崎篤会員
小藤文次郎賞
佐藤活志会員
研究奨励賞
三田村圭祐会員
功労賞
大和田朗会員
学会表彰
NHKブラタモリ制作チーム
■懇親会
かんぱーい
大会委員長
さあ!どうぞ
伝説のみかん蛇口
瀬戸内のタイ
揚げたてジャコ天
坊ちゃん登場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】台風18号接近に伴う対応について(既報済)
──────────────────────────────────
・小さなEarth Scientist の集い は中止が決定しました。
・愛媛大学生協は9月17日の終日営業中止が決定しました。
・その他の行事が中止される場合は下記の時刻に決定されます。
17日午前の行事は当日朝7時に決定されます。
17日午後の行事は当日11時に決定されます。
17日夜の行事は夕方4時に決定されます。
中止情報はホームページ、会場受付に掲示されます。
こまめにチェックして頂けますようお願いします。
学会サイト http://www.geosociety.jp/
大会専用サイト https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
第6回フォトコンテスト_最優秀賞
第6回惑星地球フォトコンテスト入選作品
最優秀賞:太古の足跡
写真:鶴田重房(鹿児島県)
撮影場所:屋久島宮浦シーサイドホテル屋久島下の海岸
【撮影者より】
屋久島在住の中川正二郎氏によって2003年1月発見されたズーフィコス化石です.ユムシ類の摂食,排泄の跡という事ですが,大変保存状態が良く,今は天然記念物に指定されています.撮影した日は生憎の空模様.海風が強く飛沫に苦労しました.
【審査委員長講評】
左半分には海沿いの切り立った堆積岩層を,右半分に明るく照明を当てた生痕化石ズーフィコスを配置させることによって,わかりやすく美しい作品に仕上げています.撮影場所は屋久島宮之浦港の近くにあり,行きやすいので,実際に訪れて生痕化石ズーフィコスを残した太古の深海底での生物の営みを感じたくなります.
【地質的背景】
ズーフィコス(Zoophycos)は,カンブリア紀以降の海成堆積物から産出する生痕化石です.白亜紀以降は深海堆積物から産出します.円盤状でシート状の構造(スプライト)が,層理面に垂直な中心軸の周りを螺旋状に取り巻く特徴的形を示します.中心軸内で一生を過ごす形成者は,海底面上で摂食を行い,中心軸周囲の堆積物中に糞を規則的に排泄してスプライトを作ります.極めて大型で複雑な立体構造のため,露頭面で全体像を見ることは難しく,写真のような一巻き分のスプライトが観察できるのは大変珍しい例です.(小竹信宏:千葉大学)
目次へ戻る
第6回フォトコンテスト_優秀賞1
第6回惑星地球フォトコンテスト入選作品
優秀賞:等高線の台地
写真:岩田尊夫(東京都)
撮影場所:ロシア,クラスノヤルスク地方,中央シベリア高原北西部上空
【撮影者より】
ヨーロッパへの出張の途中,シベリア上空でたまたま窓の日よけを上げたら,まさに等高線のような模様が印象的な台地が目の前に広がっていたので,コンパクトデジカメで撮影しました.出張後にインターネットで調べたら,大量絶滅が起こったP-T境界期に噴出したシベリア台地玄武岩からなることがわかり,さらに印象を深くしました.
【審査委員長講評】
見た瞬間は風紋かと思いましたが,飛行機の窓とエンジンが写っているので,定期便から撮影したスケールの大きな作品であることがわかります.シベリア洪水玄武岩は,シベリア・トラップとも呼ばれていますが,トラップとはスウェーデン語で階段のこと.浸食された溶岩断面が太陽光に照らされて輝き,トラップと呼ばれるゆえんがよくわかります.
【地質的背景】
被写体は約2億5000万年前にシベリア東部に噴出したシベリア洪水玄武岩.面積250万平方km,体積200万立方㎞で,デカン洪水玄武岩と並んで顕生代最大の洪水玄武岩です.噴出時期が古生代/中生代境界に重なるために,この洪水玄武岩による大量の火山ガスが地球最大規模の大量絶滅を引き起こした原因とする説が有力です.(審査委員長 白尾元理)
目次に戻る
geo-Flash No.296「地質の日」イベント情報満載!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.296 2015/4/21 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】理科得点調整および地学関連科目に関して,大学入試センターに申し入れ提出
【2】日本地質学会第7回総会開催のお知らせ
【3】「3D版ELSAMAP日本全図」へのご案内
【4】「地質の日」イベント情報
【5】Island Arc:論文ワークショップ開催のお知らせ
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】理科得点調整および地学関連科目に関して,大学入試センターに申し入れ提出
──────────────────────────────────
平成27年1月に実施されました大学入試センター試験の理科の得点調整
および地学関連科目の内容について受験生の立場にたった申し入れ書を(
独)大学入試センター理事長に提出いたしましたので,お知らせいたしま
す.
http://www.geosociety.jp/engineer/content0041.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】日本地質学会第7回総会開催のお知らせ
──────────────────────────────────
2015年5 月23日(土) 14:50〜15:50
会場 北とぴあ 第1研修室
総会議案はこちらから
http://www.geosociety.jp/outline/content0152.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】「3D版ELSAMAP日本全図」へのご案内
──────────────────────────────────
新しい地形観察方法を提供します
http://science.shinshu-u.ac.jp/~geol/ttelsa/index.html
ELSAMAP(Elevation and Slope Angle Map;カラー標高傾斜図)は傾斜量
図と高度段彩図を重ね合わせた,地形表現図です.
このたびELSAMAPの特許権,商標権をもつ国際航業(株)の許可を得て日本
全国のELSAMAP(10mメッシュDEMを使用)を作成し,Google Earthで閲覧
できるようにしました.地形の特徴を際立たせて表現した地図を「鳥瞰図」
として,日本全国どこでも,好きな視点から自由自在に眺めることがでま
す.今まで見落としていたような地形の特徴もありありと見えてきます.
このような地図は他にはありませんので,ぜひお試しください.
(信州大学山岳科学研究所 津金達郎)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】「地質の日」イベント情報
──────────────────────────────────
[本部]
■街中ジオ散歩in Tokyo「等々力渓谷の地質と人の関わり」徒歩見学会
5月10日(日)10:00〜15:30 少雨決行(予定)
【定員に達しましたので,申込受付を終了しました】
■講演会「日本の地質学:最近の発見と応用2015」
5月23日(土)12:40〜14:40
会場:北とぴあ第1研修室 (東京都北区王子)
■第6回惑星地球フォトコンテストほか入選作品展示会
6月13日(土)〜27日(土)午前中
場所:銀座プロムナードギャラリー(中央区銀座4丁目地内 東銀座地下歩道壁面)
[北海道支部]
■記念企画展示「札幌の過去に見る洪水・土砂災害」
開催期間:4月28日(火)〜5月31日(日)
会場:札幌市資料館1階 大通西13丁目
[近畿支部]
■第32回地球科学講演会「阪神淡路大震災以降の近畿の活断層研究」
5月10日(日)13:30〜15:30 (受付:12:30〜)
場所:大阪市立自然史博物館 講堂
[四国支部]
■岩石・鉱物鑑定会
5月10日(日)11:00〜16:00
主催:愛媛大学理学部地球科学科・日本地質学会四国支部
会場:ミュージアム中庭(雨天の場合は,多目的室)
[三浦半島活断層調査会](日本地質学会 後援)
■地質の日記念観察会:深海から生まれた城ヶ島
5月23日(土)10:00〜15:00(小雨決行)
★参加申込締切★4月30日(木)
地質の日イベントの各詳細はこちらから.
http://www.geosociety.jp/name/content0128.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】Island Arc:論文ワークショップ開催のお知らせ
─────────────────────────────────
Island Arcの出版社であるWileyでは,下記論文投稿ワークショップを企
画しています.連合大会に参加される会員の方は,是非本ワークショップ
にもご参加下さい.
「論文投稿ワークショップ −論文構成法と査読プロセスを理解しよう」
(Tips on Structuring Your Article & the Peer Review Process)
Island Arc編集委員長およびGeochemistry, Geophysics, and
Geosystems編集委員による講演
日時:2015年5月25日(月)17:20〜18:10
会場:幕張メッセ国際会議場(日本地球惑星連合2015年大会内)3階301B
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/publication/content0085.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
─────────────────────────────────
[中部支部]
■2015年支部年会
6月13日(土)
年会会場:黒部市吉田科学館(富山県黒部市吉田574-1)
地質巡検(6月14日):富山県北東部の中生界(定員15名程度予定)
参加申込:6月6日(土)までに
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地震本部ニュース平成27年度春号
http://www.jishin.go.jp/main/p_koho04.htm
■電中研ニュースNo.479
「雷から電子機器を守るための電磁界解析プログラム『VSTL REV』を開発」
http://criepi.denken.or.jp/research/news/index.html?m=150410
■第166回深田研談話会 世界遺産富士火山の自然と防災
5月15日(金)15:00〜17:00 参加費無料
会場:深田地質研究所 研修ホール
講師:小山真人(静岡大学教授)
申込期間:4月20日〜5月13日(定員80名,定員になり次第締切)
http://www.fgi.or.jp/
■日本地球惑星科学連合2015年大会
5月24日(日)〜28日(木)
会場:幕張メッセ
http://www.jpgu.org/meeting/
■第52回アイソトープ・放射線研究発表会
日本地質学会ほか 共催
7月8日(水)〜10日(金)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1)
http://www.jrias.or.jp/
■第13回微量元素の生物地球化学に関する国際会議
13th International Conference on the Biogeochemistry of Trace
Elements, ICOBTE 2015 FUKUOKA
日本地質学会 後援
7月12日(日)〜16日(木)
場所:福岡国際会議場
http://www.icobte2015.org/index.html
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
7月26日(日)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区)
通常参加登録締切:6月30日(火)
http://inqua2015.jp/
■日本ジオパークネットワークガイドフォーラム
9月15日(火)〜16日(水)
会場:アミティ丹後(京丹後市網野町)
バーチャルジオツアー発表者応募締切:5月29日(金)
参加登録締切:7月31日(金)
http://jgn2015.com/
■第59回粘土科学討論会
日本地質学会 共催
9月2日(水)〜 5日(土)
会場:山口大学理学部・人文学部
講演申込期間:6月15日(月)〜 7月10日(金)
http://www.cssj2.org/
■第4回アジア太平洋ジオパークネットワーク山陰海岸シンポジウム
日本地質学会ほか 後援
9月15日(火)〜20日(日)
会場:豊岡市民会館(豊岡市立野町20-34)ほか
発表要旨締切:4月30日(木)
早期参加登録締切:4月30日(木)
通常参加登録締切:7月31日(金)
http://apgn2015-jpn.com/
■第10回アジア地域応用地質学シンポジウム
日本地質学会 後援
研究発表会:9月24日(木)〜25日(金)
シンポジウム:9月26日(土)〜27日(日)[その後巡検予定あり]
場所:京都大学宇治黄檗プラザ
http://2015ars.com/
■Arthur Holmes Meeting Tsunami Hazards and Risks: Using the Geological
Record
日本地質学会 共催
9月25日(金)
場所:The Geological Society (Burlington House)(英・ロンドン)
プレ巡検:9月22日(火)〜24日(木)
http://www.geolsoc.org.uk/ahm15
■国際シンポジウム「沈み込み帯堆積盆地のリソスフェア・ダイナミクス」
日本地質学会 後援
10月5日(月)〜7日(水)(10月8日〜9日:地質巡検)
会場:東京第一ホテルシーフォート(品川区東品川)
講演要旨締切:7月15日
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/ILP2015/
■第8回アジア海洋地質会議(ICAMG-8)
10月5日(月)〜10日(土)(巡検を含む)
場所:韓国済州島,JEJU GRAND HOTEL
ホスト:KIGAM & KIOST
講演要旨締切:5月31日
http://icamg-8.kigam.re.kr/ICAMG/index.jsp
■IGCP589「アジアにおけるテチス区の発達」第4回国際シンポジウム
10月26日(月)〜27日(火)
ポスト巡検:10月28日(水)〜11月1日(日)
場所:チュラロンコン大学(タイ王国バンコク市)
http://www.igcp589bangkok.org/
■ 第31回ゼオライト研究発表会
日本地質学会 協賛
11月26日(木)〜27日(金)
会場:とりぎん文化会館(鳥取市尚徳町101-5)
講演申込締切: 7月24日(金)
要旨原稿締切:10月30日(金)
http://katalab.org/31zeolite/
■第5回学生のヒマラヤ野外実習ツアー
日本地質学会 推薦
暫定日程:2016年3月5日〜20日の16日間
参加申込受付期間:2015年5月1日〜11月30日
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0144.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■産業技術総合研究所研究職員(地質分野)募集(5/27)
■住友財団2015年度研究助成(基礎科学研究助成・環境研究助成)(6/16)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
▶▶予告▶▶次回の定期配信は祝日のため,5月7日(金)配信予定です.
第6回フォトコンテスト_優秀賞2
第6回惑星地球フォトコンテスト入選作品
優秀賞:干潮の橋杭岩
写真:鈴木文代(和歌山県)
撮影場所:和歌山県串本町橋杭岩
【撮影者より】
昨年,南紀熊野ジオパークに認定されました「橋杭岩」です.干潮時には,岩の傍まで行くことが出来ます.少し残った海水に,橋杭岩が映り込んだり,砂紋を見ることが出来ます.2014年12月22日大潮の干潮時にそばまで行って撮影しました.
【審査委員長講評】
橋杭岩は,𠮷野熊野国立公園の中にあり,風景写真として数多くの写真が撮影されていますが,この写真では手前のリップルマーク(漣痕)が存在感を示しています.斜光によってリップルマークが強調されるとともに,青空をバックに陰影に富んだ橋杭岩が印象的です.
【地質的背景】
橋杭岩は,中新世熊野層群の泥岩に貫入した石英班岩が,差別侵食により,切り立った岩列をなすようになったもので,国指定天然記念物の名勝です.潮間帯の元で波食棚をなす平坦な泥岩の上には,橋杭岩からもたらされた無数の石英班岩の巨礫が散らばっており,これらが南海トラフ巨大地震による津波石であるという指摘もなされています.作品で見られる波食棚上の砂紋は,潮汐のたびに形を変えて様々な模様を見せてくれます.(産業技術総合研究所:宍倉正展)
目次へ戻る
No.108 2010/09/7 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.108 2010/9/7 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】富山大会関連情報いろいろ
【2】本の紹介:「地殻進化学」堀越 叡 著
【3】支部情報
【4】その他のご案内
【5】公募・各賞助成 情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】富山大会関連情報いろいろ
──────────────────────────────────
■見学旅行:追加募集
申込・問い合わせは各案内者へお願い致します。
B班 跡津川断層(1-2名)
竹内 章 <takeuchi@sci.u-toyama.ac.jp>
I班 糸魚川ジオパーク ヒスイ楽(若干名)
宮島 宏<hiroshi.miyajima@city.itoigawa.niigata.jp>
各コースの見どころはこちら
http://www.geosociety.jp/toyama/content0032.html
■参加・講演をキャンセルされる場合(変更も含む)は,早めにご連絡をお願い
致します。
参加登録料ほかのキャンセル料は下記の通りです。ご注意ください。
9/15まで:キャンセル料50%
9/16以降:キャンセル料100%
■富山大会就職支援プログラム
学生・院生・教官のみなさまへ。民間企業・団体、研究機関と相互に情報交換
を行う就職支援プログラムが開催されます。ぜひご参加ください。
日時:2010年9月19日(日)14:00-17:00(*時間帯は若干変更になる場合があります)
場所:富山大学 五福キャンパス 共通教育等E棟
参加費:無料
参加予定企業・団体(敬称略・8/10現在):
株式会社クレアリア,石油資源開発株式会社,ジーエスアイ株式会社,
株式会社ダイヤコンサルタント,明治コンサルタント株式会社,
(独)産業技術総合研究所,川崎地質株式会社
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/toyama/content0006.html
■託児室・学童ルーム
富山大会期間中、9/18(土)〜9/20(月)に開設されます。
ご利用希望の方は、9月10日(金)までにお申し込みください。
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/toyama/content0014.html
■地質情報展2010とやま —海・山ありて富める大地—[先行イベント]
富山大会前日の17日に地質情報展開会式に引き続き、先行してイベントを
開催します(13:00〜16:30)。入場無料です。ぜひ御参加ください。
本番は、9月18日(土)〜19日(日) 9:30-16:30(19日は16:00まで)です。
場所:富山市民プラザ
地質情報展詳細は↓
http://www.gsj.jp/Info/event/2010/johoten_2010/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】本の紹介:「地殻進化学」堀越 叡 著
──────────────────────────────────
東京大学出版会,2010年8月20日発行344ページ,横書
15.5 x 21.5 x 2.5 cm, ハードカバー,定価6,400円+税
ISBN978-4-13-060747-6 C3044
本書は,昨年10月16日に亡くなった堀越 叡氏の校正刷りの遺稿を,鎮西清高・
島崎英彦・大藤 茂の3氏が編集したもので,世界のプレカンブリア剛塊地域(ク
ラトン)とカレドニア・ヴァリスカン両造山帯に関する地質学の教科書である.
章立ては,第1章 造山論の概念,第2章 地殻の誕生,第3章 グリーンストン・
花崗岩帯,第4章 楯状地堆積物,第5章 剛塊の成長,第6章 プレカンブリア時
代の終焉,第7章 アパラチア・カレドニア造山帯,第8章 ヴァリスカン造山帯,
第9章 超大陸パンゲア,第10章 生命の多様性と絶滅,となっている.これら各
章の末尾には充実した引用文献・概説書リストがあり,最後に索引と最新の地質
年代表がついている.図や写真が多く,複雑な地質図なども著者がすべて整理・
簡略化して描き直している.
序文によると,著者が専門とする鉱床学は「地質学の中でももっとも総合的な学
問である.悪く言えば雑学である.したがって,多分に手前味噌だが,鉱床学の
専門家は何をやらせてもそれなりにこなすことができる」.そこで1978年の富山
大学着任時に,Brian F. Windleyの“The Evolving Earth” をタネ本として「地
殻進化学」の講義を始めたが,10年も続けると「当初のウィンドレイ色はほとん
どなくなった」そうである.編集者の「本書刊行の経緯」によると,この講義の
ノートと,学生に配布した私家版の教科書をもとに拡張発展させたものが本書で
ある.著者が遺した目次によれば,さらに第11章 アルプスとヒマラヤ,第12章
北米コルディレラ,第13章 東アジアの形成,第14章 日本列島の萌芽,第15章
日本島弧と続くはずであったが,著者の急逝によってこれらの章が完成されなかっ
たのは残念である.
第1章には興味深いエピソードが満載である.250年以上前のドイツのヴュルツブ
ルグ大学のベリンガー教授は,学生が露頭に埋め込んでおいた太陽の化石,星の
化石などを「発見」して論文を書いたが,自分の名前が彫ってある化石を掘り出
して,さすがに悪戯であることに気がつき,出版物の買い戻しに奔走したという
有名な話があるが,当時の裁判記録によると,真犯人は学生ではなく大学の地理
の教授と図書室係であったこと,化石に彫られていたのは教授の名前ではなく「
エホバ」の文字だったことが本章の冒頭で語られ,面白い話には換骨奪胎がつき
ものであることを知る.「一般地質学(または地質学原理)」を書いたロンドン
大学のライエルの講義には,着飾った女性たちが押し寄せたが,ライエルは女性
の聴講を拒否し,地質学会への女性の出席の是非をめぐる論争になったという話
も興味深い.この章ではこうしたエピソードを交えながら,地向斜,ナップ,大
陸漂移説,海底拡大説,プレートテクトニクス,そしてプルームテクトニクスま
でが説明される.プレートテクトニクスの創立者の一人であるルピションが「海
洋底拡大説に反対したという点では関係者の記憶が一致している.彼は1966年に
海洋底は動かないという趣旨の論文で博士号を得ている.しかしその2年後,彼は
プレートテクトニクスと呼ばれる地球変動の枠組みを完成した」という記述には
目が点になった.確かに,ルピションの著書「極限への航海」(岩波書店,1990)
の40頁を見ると,「1966年4月にストラスブール大学でドクター論文の公開審査を
受けていた頃・・・熱量の食い違いは,私がハリー・ヘスの海洋更新仮説を退け
るべき主要論拠となっていたのである.しかし,私は自己の非を悟るに手間取り
はしなかった(加賀野井秀一訳)」と書いてある.第2章では,隕石,年代測定法,
地球最古の岩石,地球最古の化石などについて述べられている.第3章は世界各地
のグリーンストン・花崗岩帯の説明であるが,世界最古の硫酸塩鉱床,正マグマ
性ニッケル鉱床,中熱水性金鉱床(最近は「中熱水性」と言わず「造山性」とい
う:Goldfarb et al. (2001) Ore Geol. Rev., 18, 1-75),黒鉱型鉱床などにつ
いても詳しい.第4章は縞状鉄鉱層,巨大貫入岩体,隕石孔などを扱っているが,
ザ・グレートダイク,スティルワーター,サドバリーなど著者独特のカタカナ英
語表記が目立つ.第5章ではオーストラリア,バルト楯状地,北米などの原生代造
山帯が扱われ,縞状鉄鉱層,堆積性噴気鉱床(鉛・亜鉛・銀),堆積岩内銅鉱床
(ホワイトパイン)などについても説明されている.第6章はロディニア超大陸の
形成と分裂,氷結地球,エディアカラ化石群,原生代/古生代境界問題,気圏・
水圏の進化などの話であるが,ここでもザンビア,ザイールの世界最大の堆積岩
内銅鉱床,北米の堆積性噴気鉱床などについて述べている.第7章は北米東岸,英
国北部,ノルウェーの地域地質とアパラチア・カレドニア造山運動のテクトニク
スを概説している.ローレンシア(Laurentia), ローラッシャ(Laurussia),ロー
レイジア(ローラシアLaurasia)はそれぞれ範囲が違うので注意が必要である.
第8章では,まずヴァリスカン造山帯の岩石は露出が悪いためプレートテクトニク
スの解明が遅れたことを指摘し,英国南部,ドイツ,「ボヘミアマッシーフ」,
スペイン,ポルトガルなどの地質を概説してテクトニクスを論じているが,ここ
でも「石炭紀の石炭」について述べるのを忘れない.第9章はカンブリア紀の生物
進化の爆発に始まり,北米・中欧・東欧などの卓状地堆積物,ウラル造山運動と
パンゲアの形成,そしてパンゲアの分裂までを述べている.ミシシッピヴァレー
型炭酸塩岩内鉛・亜鉛鉱床についての説明もある.第10章では顕生代の生物5大絶
滅期について述べているが,北海油田,イリジウム異常,チチュルブ隕石孔などK
/T境界に関するトピックも詳しい.大規模火山岩類のところで,シベリア・トラッ
プ(洪水玄武岩)の話があり,トラップという語が「階段」を意味するスウェー
デン語(溶岩台地の末端が溶岩1枚ごとの階段状になっている)に由来すること
を初めて知った.なお,本書には「まとめ」や「あとがき」はない.
以上のように,本書の背骨を貫くのは,鉱床の性質や成因を,地球進化の大きな
枠組みの中で解き明かそうとする著者の強い意志だと思う.そして本書の至ると
ころに,著者の幅広い知識,深い洞察,批判的精神の発露をみることができる.
その結果,本書は地球史とグローバルテクトニクスに関する学部学生・大学院生
向けのこの上ない教科書となっており,同時に地球科学の諸分野に広い関心をも
つ研究者にも有用な,示唆に富む記述が盛り沢山である.著者は序文で「本書に
は多くの鉱床地質が引用されている.これを我田引水とは考えないでほしい.ほ
かの地域とは地質解明の精度が極度に違うのである」.「世界の地質が鉱床地域
と同じくらいの精度で明らかになれば,地球の歴史は変わるであろう」と述べて
いる.著者の鉱床研究者としての矜持が輝いている.著者には「地向斜征伐のす
すめ」(マグマ発生の時間的空間的分布(GDP), 1, 119-122, 1973)に代表される
戦闘的イメージが強いが,本書を読めばその学識・経験の豊かさ,奥深さがよく
わかる.本書を読んで,著者にいろいろ質問し,ご教示いただきたいと思うが,
もうそれは叶わないのが寂しい限りである.なお,本誌13巻3号20頁に速水 格・
大藤 茂両氏による追悼文がある.拙稿を校閲していただいた小西健二先生に感
謝する.
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】支部情報
──────────────────────────────────
■日本地質学会関東支部2010年秋季シンポジウム
「関東盆地の地下地質構造と形成史」
>開催日:2010年11月20(土),21(日)
場所:日本大学文理学部3号館5階
詳しくは、http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】その他のご案内
──────────────────────────────────
■ 日本学術会議回答「大学教育の分野別質保証の在り方について」の公表
日本学術会議は、8月17日(火)、会則第2条に基づき表出する政府及び関
係機関等への回答として、日本学術会議回答「大学教育の分野別質保証の在り方
について」(平成22年7月22日開催の第100回幹事会了承案件)を公表し、
同日、文部科学省への手交を行いました。本回答は次のURLからご覧になれます。
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-21-k100-1.pdf
■The 7th International Conference on Asian Marine Geology (ICAMG-7)
日程:2010年10月11日〜14日
会場: National Institute of Oceanography (CSIR), Goa, INDIA
Deadline of session proposal: 31 January 2011
Deadline of abstract submission: 31 July 2011
http://icamg7.nio.org
■日本の活断層・フォトコンテスト:作品募集中
日本活断層学会では,活断層に関する教育・普及活動の一環として
「日本の活断層・フォトコンテスト」を実施しています.変動地形や活断層露頭
写真に,簡単な説明と撮影場所の地図を添えて,ご応募下さいますようお願い致
します.(締切は9月末日).11月末頃発表予定.詳しくは,
http://danso.env.nagoya-u.ac.jp/jsafr/fotocontest01.html
■産総研オープンラボのご案内(地質分野)
日時:2010年10月14日(木)・15日(金)(参加無料)
場所:産総研つくば
産総研のこれまでの研究の成果や実験装置・共用設備等の研究リソースを、企業
の経営層、研究者・技術者、大学・公的機関の皆様に広くご覧いただくための催
しです。
地質分野の展示内容は、
G-02 20万分の1日本シームレス地質図講習会
G-20 地質調査業務に役立つ粒子径計測技術ワークショップ など
ラボツアー予約〆切:10月4日(月)まで
来場者登録〆切:10月12日(火)まで
詳しくは、http://www.aist-openlab.jp/
■平成22年度 東濃地科学センター 地層科学研究 情報・意見交換会
日時:平成22年10月19日(火)12:45〜17:00
場所:瑞浪市地域交流センター「ときわ」(定員:約150名)
「瑞浪超深地層研究所 深度300m水平坑道見学会」
日時:平成22年10月20日(水)9:30〜11:30
場所:瑞浪超深地層研究所(定員:約40名)
※入場無料(事前の申込が必要です)
詳しくは、http://www.jaea.go.jp/04/tono/index.htm
■第1回地質リスクマネジメント事例研究発表会
日時:2010年9月24日(金)9:30-16:30
会場:飯田橋レインボービル
詳細:http://www.georisk.jp/2010/0924georisk.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】公募・各賞助成 情報
──────────────────────────────────
■(地独)北海道立総合研究機構研究職員募集:環境・地質(地下水)(9/13締切)
■熊本大学理学系地球環境科学講座地球惑星物質科学分野女性教員公募(10/8締
切)
■海のフロンティアを拓く岡村健二賞(9/21締切)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
第1回フォトコン入選作品:IYPE名誉会長賞
第1回惑星地球フォトコンテスト入選作品:IYPE名誉会長賞
第1回惑星地球フォトコンテスト入選作品:IYPE名誉会長賞:「地底へ続く道」
写真:蓮村 俊彰(東京都) 撮影場所:中国新疆ウイグル自治区庫車県天山神秘大渓谷
撮影者より:
新疆ウイグル自治区の秘境、何層にも積み重なった地層の底をゆく。
審査委員長講評:
新疆ウイグル自治区は,中国北西部にある乾燥地域です.写真は,クチャ(庫車)郊外の大峡谷を撮影したものです.このような高さ数百mにも達する狭い大峡谷は,一部にしか太陽光があたらずに残りは影となるため,撮影の非常に難しい場所です.作者は縦位置に構えて峡谷の高さを,的確な露出で峡谷の奥行きを,下端の人物によって峡谷の大きさをうまく表現しています.クチャは三蔵法師玄奘が1600年前に訪れた場所,玄奘もこのような大峡谷を見たのでしょうか.
地質解説:
この渓谷は、タリム盆地を構成する小プレートが北方に移動・衝突した際に隆起してできた天山山脈の南端に位置する。この激しい隆起運動のために形成された山地が河川によって浸食され、このような深い渓谷が形成された。露出している岩石は漸新世後期のSuweiyi層と中新世前期のDijike層の赤色砂岩泥岩互層である。(京都大学工学研究科 山田泰広)
No.066 2009/6/8 geo-flash
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.066 2009/06/08 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 加納 博 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
日本地質学会名誉会員、加納 博 秋田大学名誉教授は平成21年6月6日(土)
にご逝去されましたので、謹んでお知らせいたします。これまでの故人の功績を
讃えるとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
なお、通夜、ご葬儀は下記のとおり執り行われますので併せてお知らせ申し上げ
ます。
記
(通 夜)平成21年6月8日(月)午後 6 時
(ご葬儀)平成21年6月9日(火)午前11 時
(喪 主) 加納 直 様(ご長男)
(場 所) ベルコシティホール広面
秋田市広面字糠塚107-1
電話018-884-7979
会長 宮下純夫
──────────────────────────────────
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質フォト:ホボロ島の生物浸食作用
地質フォト:瀬戸内海中部、芸予諸島、ホボロ島の生物浸食作用
写真:沖村雄二・土岡健太・船越雄治(東広島市自然研究会)
解説:沖村雄二・後藤益巳・矢原大和(広島県立教育センター)
写真1
写真2
写真3
解説:
広島県東広島市安芸津町赤碕の沖にある小さな島,ホボロ島は,ここ数十年の間にみるみる小さくなり,若いころに遊んだ島の面影は全くなくなったと語る老年の方々は少なくない.台風のたびに目だって小さくなるし,どうしてこの島だけが急速に小さくなるのだろうか?と,理由がわからないまま,ホボロを売るという民話ともあいまって,わびしく見守られてきた.明治30年と大正14年に測図され,昭和3年と31年に発行された2万5千の分地形図,三津図幅では,この島の高さは21.9mと標記され,長径が120m+と読み取れるが,現在,高潮位時の海面上に見られる部分は,高さ6m・幅が8m×3mに足りない搭状の岩石が島の西端に一つあるにすぎない(写真1).ちなみに周辺の島の規模はほとんど変化していない.島がなくなるのではと言われる中,安芸津町木谷小学校5年生の環境学習テーマとして島の自然がとりあげられ,コスモ石油エコカード基金(学校の環境教育プロゼクト)と父兄の助けを借り,海浜の生態系を中心に調べる上陸作戦がおこなわれた.筆者らは,同行の機会をいただいて,地質調査を行った.構成岩石は,デイサイト溶結結晶凝灰岩(松浦,2001)で,赤色化の激しい風化作用のために軟岩化がすすみ,島全域の潮間帯に無数の穴があることに気がついた.調査がすすむにつれて,10mm±くらいの“ダンゴムシ”よう生物がこの穴に棲んでいることが確認され,その頻度は表面積の50%以上(写真2)にたっし,明らかに生物侵食作用であることを伝えた.潮間帯上部では穴がこわれて連続して巻貝やカニの棲みかとして利用され,波のエネルギーによるムシの棲みかの崩壊が容易に考えられる.それによって引き起こされる潮間帯の軟岩の崩壊が,上位の岩石の崩落をまねき,島が小さくなる大きな原因であることは間違いない.実際に潮間帯の穿孔穴が発達する軟岩化した基盤岩の上には,風化作用を受けていない巨〜小礫岩が散在している.詳しくは,本誌に発表する作業をすすめているが,このムシが,凝灰岩に穿孔することが知られている「ナナツバコツブムシ」(写真3)であることを,北九州自然史博物館,下村通誉学芸員に鑑定していただいた.生物侵食作用(bioerosion)という学術用語は知られているが,ほとんどが生痕として観察・記載されたもので,島が消失するという規模とその速度からして,この島の現象はきわめて異質であり報告する(2007,2,10,日本地質学会西日本支部例会でポスター発表)
地質フォト:平成19年度能登半島地震 写真速報
地質フォト:平成19年度能登半島地震 写真速報
写真提供 石渡 明(金沢大学)
解説
3 月25 日9時42 分頃,能登半島沖の深さ11km を震源とするマグニチュード(M)6.9(暫定値)の地震が発生し,石川県の七尾市,輪島市,穴水町で震度6強を,石川県の志賀町,中能登町,能登町で震度6弱を観測した.(金沢地方気象台HPより)
写真上段左:氷見漁港の突堤の陥没と液状化による砂の噴出跡.
写真上段右:能登有料道路の盛土部分の損壊.
写真中段左:関野鼻の崩落の様子.関野鼻では崩落によって海水が濁っており,この付近は今回の地震によって40 cm程度隆起した.
写真下段右: 龍ヶ崎の崩落の様子.
(以上が,共同通信社の取材に同行してヘリコプターから撮影)
写真中段右:輪島市門前町,総持寺祖院亀山墓地の惨状.
写真下段左 旧門前町中心部,家屋の被害.
※なお,石渡グループはじめ,能登半島地震の現地調査報告は,日本地質学会地質災害委員会のページに随時公開されている.
地質フォト:隠岐島後時張山累層の火山豆石
地質フォト:隠岐島後時張山累層の火山豆石
写真:大友幸子(山形大学教育学部)
解説:
日本地質学会107年学術大会(松江)の見学旅行B-8班隠岐島後コースに参加して撮影したもの.沢田ほか(2000)によると,時張山累層は日本海の形成過程の中の陸弧時代に形成された地層として位置づけられている.写真は布施浄土ヶ浦の砂岩泥岩凝灰岩互層の観察時に,凝灰岩層の火山豆石濃集部を撮影したもの.
文献
沢田順弘ほか,2000,隠岐島後.日本地質学会第107年学術大会見学旅行案内書(松江).115-134.
地質フォト:南アフリカのSwaziland系(32億〜35億年前)
地質フォト:南アフリカのSwaziland系(32億〜35億年前)
Swaziland System (3.2〜3.5Ga-old) in South Africa
写真:諏訪兼位 Kanenori Suwa
写真1
写真2
解説:
写真1: Barberton山地のOnverwacht層群中位のKomati層(34億年前).この写真では,6つのflow unit がみられる.ひとつのflow unitは10~20m厚さである.Flow unitの下位はkomatiiteで,弱い変成作用をうけ,角閃石などの変成鉱物を生じているため,ごつごつとした岩肌を呈する.中位はkomatiitic basaltで,スムーズな表面をもち,芝生のような見掛けを呈する.上位は縞状鉄鉱層でグリュネル角閃石(grunerite)珪岩が存在する.(1992年1月18日撮影).
写真2: Barberton 山地のOnverwacht層群中・上位のKromberg層(33億年前).見事なpillow lavaがみられる.(1992年1月20日撮影).
始生代早期・中期のSwaziland系は,Barberton山地(Kaapvaal剛塊東部)にもっともよく露出している.Barberton山地は,19世紀半ば頃から金の産出で知られ,古くから地質調査も行われていた.ここのgreenstone帯は,長さ100kmを超え,Swaziland系(層厚22km)の火山岩や堆積岩からできている.低温の変成作用をうけた火山性岩石は緑色を呈するので,greenstone帯とよばれる.
Swaziland系は下部のOnverwacht層群(33億〜35億年前),中部のFig Tree層群(32億年前),上部のMoodies層群(32億年前)の3つに分けられる. Onverwacht層群(層厚15.2km)は,下位より上位へ,Sandspruit層,Theespruit層,Komati層,Hooggenoeg層,Kromberg層,Swartkoppie層の6層よりなる.下位には超塩基溶岩のコマチ岩(komatiite)が多く,中位には塩基性溶岩が,上位には中性・酸性の溶岩とチャートが多い.
Fig Tree層群(層厚2.1km)は主に,チャート,グレイワッケ,頁岩からなり,縞状鉄鉱層をわずかに含む.Moodies層群(層厚4.3km)は主に,礫岩,粗粒砂岩,珪岩,頁岩からなり,縞状鉄鉱層をわずかに含む. これらをとりかこんで,26.9億〜35.1億年前の時代を異にするいくつかの花こう岩体が分布する.
地質フォト:台湾北投温泉の地獄谷
地質フォト:台湾北投温泉の地熱谷
写真・文 貴治康夫(大阪府立箕面東高等学校)
解説:
台北の中心から鉄道で北へ約40分の郊外に北投(Beitou)温泉がある.周辺は国家公園に指定され,大屯(Datun)山をはじめ,標高1000mを超える10以上の火山からなる大屯火山群(Datun volcano group)が分布する.地質は角閃石安山岩や輝石安山岩を主体とし,鮮新世後期から火山活動が活発であった.
北投地域は17世紀ころから硫黄の採掘がさかんであり,1894年,ドイツ人によって温泉の存在が確認された.大阪商人,平田源吾が金鉱脈探査中に負った傷をこの地で癒したことがきっかけとなり,台湾初の温泉旅館を開いたのが1896年のことである.日本の統治時代には一大温泉街として発展した.
北投温泉は北投石(Hokutolite)の産地として有名である.北投石は独立した鉱物ではなく,Baの一部をPbに置換した重晶石が沈殿したもので白色〜淡褐色の縞状構造を示す(写真左上、右中段).色の淡い部分がRaを多く含み,放射能が強い.すでに1898年,日本の秋田県渋黒温泉(現,玉川温泉)で同様の沈殿物が採取されていたが,本格的な研究は1905年に台湾総督府鉱物課技師・岡本要八郎が北投温泉「瀧の湯」で重い沈殿物を発見したことに始まる.当時,世界的に放射能鉱物に対する関心が高かったことや温泉医学的な見地から,この沈殿物が注目された.1912年11月,東京帝国大学教授・神保小虎により新鉱物「北投石」として報告された.
北投温泉にある地熱景観公園内の窪地(地熱谷)が泉源になっており,水温80〜100℃,pH1.2~1.6の強酸性緑礬泉が小さな池を形成し,湯煙を上げている.かつては自由に温泉卵をつくることができたこの池も現在は立ち入り禁止になっており(写真下段),学術的に貴重な北投石が保護されている.
地質フォト:「平成18年7月豪雨」での長野県岡谷市における災害発生地の状況
「平成18年7月豪雨」での長野県岡谷市における災害発生地の状況
写真・文:大塚 勉(信州大学,全学教育機構)・信州大学自然災害科学研究会・信州大学山岳科学総合研究所
写真1
写真2
解説:
活発な梅雨前線の活動による「平成18年7月豪雨」において,7月15日から19日にかけて長野県で降り続いた雨は,県中部を中心とする地域に土砂災害をもたらし,9名の犠牲者を含む甚大な被害が生じた.7月17日未明から19日正午までの連続累積降水量は,辰野町で約400mm,諏訪市で約360mmに達していた.信州大学の上記の組織のグループによる,災害発生直後からの調査の結果,今回の災害の地質学的な発生要因の概要が明らかになった.
災害発生地域は,諏訪湖の南部から南西部にわたる地域である.ここには,主として輝石安山岩の角礫を多量に含む凝灰角礫岩からなる下部更新統塩嶺累層が広く露出している.塩嶺累層は,基質・角礫ともに風化が著しく,粘土化が進行している.
岡谷市の湊地区小田井沢川左支(写真1)では,7月19日午前5時頃土石流が発生し,7名の犠牲者を出すこととなった.ここでは,被災地から標高差約200m上の稜線付近において,塩嶺累層の変質した凝灰角礫岩(写真2の1段)を覆う火山灰質の表土が崩壊し,多量の水が一気に谷を流れ下った.途中,谷底に存在していた角礫混じりの土壌を洗掘し,洗い出した礫を伴って被災地に押し寄せた.
同市の川岸東地区の志平川(犠牲者1名)・本沢川でもほぼ同時に土砂災害が発生した.いずれの例でも,稜線直下に存在する表土が崩壊し(写真2の2段),多量の水がはき出されたらしい.塩嶺累層を覆う表土中には,災害数日後でも水を排出するパイプが観察された(写真2の3段).多量の水は一気に谷を流れ下り,途中,谷底に存在していた角礫層・黒色土壌を洗掘し,洗い出された礫を伴って被災地に押し寄せた.とくに志平川では,河床の洗掘は下流部に限られ,上流部では泥水が通過したのみである(写真2の4段).
岡谷市における災害は,変質した塩嶺累層の凝灰角礫岩をを被覆する多孔質の風化火山灰を含む表土が,多量の水を支えきれなくなって崩壊したことが引き金となっている.崩壊発生地から被災地までの距離が長い例では,崩壊土砂が主体となって直接下流を襲うことは少なく,崩壊を機に表土からはき出された多量の水が,河川水と一体となって河床を洗掘した.下流を襲ったのは,洗掘された土砂を含む多量の泥水であり,岡谷市での災害は洪水流に近いタイプであったと判断される.
写真1:泥水が流れ下った小田井沢川左支.遠方に諏訪湖を望む.
写真2の1段:塩嶺累層の変質した凝灰角礫岩.
写真2の2段:谷頭部における表土の崩壊.志平川.
写真2の3段:風化した塩嶺累層(写真右下)と表土(写真左上)中に形成されたパイプ.本沢川.
写真2の4段:洪水流によって草本がなぎ倒された志平川上流部.
地質フォト:南アフリカのダイヤモンド鉱山
南アフリカのダイヤモンド鉱山:Diamond mine in South Africa
写真・文 諏訪兼位 Kanenori Suwa
写真1
写真2
写真3
解説:
写真1:Kimberley diamond鉱山のBig Hole Kimberley (Cape州北部)では,1871年にキンバリー岩のパイプ(Big Hole,直径450m)が発見され,露天掘りの採掘がはじまった.露天掘りは深さ360mまでつづいた.1889年以降,キンバリー岩のパイプの外側に縦坑を下ろし,順次,深いレベルで横坑を掘って,キンバリー岩を採掘するようになった.縦坑の深さが1200mになると,キンバリー岩中のダイヤモンド含量が激減した.そのため1915年に閉山した.稼行40余年で1450万カラット(2.9トン)のダイヤモンドを採掘した.現在は博物館になっている.Big Holeの彼方にキンバリーの町が見える.(1973年9月19日撮影).
写真2:Premier diamond鉱山
Premier鉱山(Transvaal州)は1902年に発見され,ついで1905年に,世界最大のダイヤモンド「カリナン」(約3000カラット)が発見された.キンバリー岩のパイプの大きさは,地表で860m×400m.毎日2万トンのキンバリー岩が採掘され,7500カラットのダイヤモンドが集められている.(1970年3月11日撮影).
写真3:キンバリー岩の露頭(Dutoispan diamond鉱山)
Dutoispan鉱山はKimberley鉱山の近くに位置する.この露頭写真の左右は約1m.大量の火山ガスを含み,高速で上昇するキンバリー岩は,地下深部の岩塊を運び上げ,地表に達すると火山ガスを爆発的に放出する.周囲の岩石は破砕され,キンバリー岩自体も,写真のように,はげしく破砕されている.(1973年9月18日撮影).
アフリカ大陸はダイヤモンドの宝庫である.全世界の年間生産額1億2200万カラットのうち,アフリカ大陸から7080万カラット産出する.
最近,南アフリカのダイヤモンドの生成年代がわかってきた.29億年前である.ダイヤモンド結晶中の硫化鉱物の微細包有物を,レニウム・オスミウム法で精密測定した結果である.
こうして地下深部でできたダイヤモンドを運んでくる岩石が,キンバリー岩である.南アフリカのキンバリー岩の大部分は,1億年前に集中的に,地下深部から地表に向かって噴き上げてきた.ちょうど,アフリカ大陸と南アメリカ大陸が分裂した時期である.なお,例外もある.Premier diamond鉱山のキンバリー岩は,17.5億年前に噴出したものである.
地質フォト:グランドキャニオンの巨大クロスベッド
グランドキャニオンの巨大クロスベッド
写真提供:渡部芳夫(産業技術総合研究所)
解説:
この斜交層理砂岩は,サハラ砂漠などの砂漠の砂丘構造に似ており,陸上の堆積物だと現在は考えられているようです.砂丘の砂が岩石になるには,砂粒を固めるセメント材が必要ですが,この砂岩にはココニノ石(Coconinoite)と呼ばれる鉱物が知られているように,鉄やアルミとウランが燐やケイ素と一緒に酸化して固結している事が知られています.
過去には水の流れによるものとの強い意見もありましたが,それはノアの箱船の洪水と関係があります.実際,グランド・キャニオン(Grand Canyon)国立公園のビジターセンターでは,グランド・キャニオンはノアの箱船の大洪水によって創られたと説明している「Grand Canyon: A Different View」という本が置かれています.
『旧約聖書』の『創世記』では,洪水は40日40夜続き,地上に生きていたものを滅ぼしつくした,そして水は150日の間,地上で勢いを失わなかったとされています.
現在のグランドキャニオンの谷地形は,コロラド高原がコロラド川の侵食作用によって削り出されたもので,一般には4,000万年程かけて現在の1,800mに及ぶ浸食に至ったものです.従って,現在のグランドキャニオンの谷そのものが,旧約聖書にある大洪水で造られたとはピンと来ません.地形に残る浸食は,洪水が流れとして働くときにのみ生じると思われるからです.しかしながら,谷地形にそって大洪水が進んできたとすれば,何らかの記録が洪水堆積物として残されていても良さそうです.
その時の洪水が押し寄せる流れで堆積した砂が,このココニノ砂岩だという見解では,広さ32万平方キロに100mの厚さで溜まった砂が,海からの大洪水の流れによって数日間でもたらされたと主張されています.堆積学的な条件から,斜交層理ができるためには,海流の速度は毎秒1.65m程度未満の必要がありますから,流速はかなり小さい見込みで,これもピンと来ません.
これに対して,多くの地質学的論文が反論を提出してきました.たとえば,水流での斜交層理の角度は10度以上に傾くことは稀ですが,ココニノの斜交層理は25度にも達する事,リップルマークや砂丘構造の配列から,砂の移動は北からであって,当時西にあった海岸からではないこと,そして層理面に陸上動物の足跡等が残されている事などです.これらによって,陸上の砂丘堆積物との理解が広がっています.
これらの論戦は,双方が科学的根拠だけでなく,宗教的な確信等も含めて交わされてきているもので,それを思いながらグランドキャニオンの渓谷を眺めると,地質自体のスケールの大きさに気づきます.
地質フォト:蒜山高原の珪藻土層
蒜山高原の珪藻土層
写真:公文富士夫(信州大学理学部)
写真1
写真2
解説:
松江市で行われた第四紀学会2005年大会の帰途,8月29日に蒜山高原にある昭和化学工業(株)岡山工場の珪藻土採石場を見学させていただきました.この珪藻土層は蒜山原層と名付けられており,縞状のラミナの周期性が有名です(石原・宮田,1999).
石原・宮田(1999)で報告された露天掘りの位置よりも500mほど東側の新しい露天掘りの露頭でしたが,明瞭な縞模様の見える珪藻土層を観察することができました.縞模様は1-3mmの厚さをもつ淡緑色と暗緑色の層からなり,明瞭な下限境界をもつ暗色層から明色層までは1セットで1年に対応すると考えられています.
珪藻土層の上位には3,4mの厚さの砂礫層が重なり,その上部にATテフラが確認できました.ATテフラの上に1mほどの厚さの砂層と細礫層があり,そのローム層と黒色の土壌層が見られる.
参考文献:
石原与四郎・宮田雄一郎,1999,中期更新統蒜山原層(岡山県)の湖成縞状珪藻土層に見られる周期変動.地質雑,105,461-472.
蒜山原団体研究グループ,1975,岡山県蒜山原の第四系.地球科学,29,153-160,227-237.
シンポジウム2006(1)南海付加体の実体に迫る
1)南海付加体の実体に迫る:そのミクロ構造とマクロ構造
私たちは,海底の調査をしています.このシンポジウムでは,潜水船によって採取された岩石や調査船によって得られた海底地形図を使った研究発表が行われました.しかし,私たちの研究の出発点は,海底ではなく,陸上の調査にあります.ちょっと遠回りをしますが,まず,陸上での地盤調査について話します.
唐突ですが,トンネルは,どうやって設計するかわかりますか.それは,地盤調査に基づいて行われます.では,地盤調査とはなんでしょう.それは,現在,3つの方法からなっています.それは,1)物理探査,2)ボーリング調査,3)地表踏査,です.物理探査とは,電気や地震波,電磁波などを使って地下を調べる方法です.地盤の大まかな構造を調べることができます.「この半径数mの範囲に亀裂がたくさんありそうだ」というような予測ができます.ボーリング調査は,地盤に直接孔を掘って,地盤の土や岩石を見ることです.さきほどの物理探査の予測を確かめることができます.最後の地表踏査は,トンネルを掘る地盤の上を直接歩いて,地表に見えている土や岩石を調べることです.山全体も歩きますが,特に山の急斜面や川沿い,海岸など,山の内部の岩石が出ていそうなところを重点的に調べます.このように,物理探査で,大まかな構造(マクロ構造)を調べ,ボーリング調査と地表踏査によって,それらを検証しながら,地盤調査は行われるのです.細かな構造(ミクロ構造)を調査するボーリング調査と地表踏査とは,その性格が少し違います.ボーリング調査は,孔を掘るので,垂直(もしくは水平)の一直線の地下構造がわかります.孔の直径は,10cm程度です.一直線の地下構造を「面」の地下構造に再構築するのが,地表踏査です.このようにして,3つの手法がうまく協力しあいながら地盤調査は進められます.言い方を変えると,それぞれの手法は,それぞれの「限界」を持っている,とも言えます.
しんかい6500(天竜海底谷調査を終えて)
しんかい6500内部
では,海の底で地盤調査をやろうと思うとどうでしょうか.石油やメタンハイドレートなどの海底資源などの目的で海底の地盤が調べられています.特に,今年2007年から数年に渡って,南海地震の発生源に向けて掘削が行われることになっています.
海底での地盤調査は,主に,1)物理探査,2)ボーリング調査,の2つです.これによって,「マクロ構造」と「ミクロ構造」を調べることができるとされています.しかし,海底では,「地表踏査」はできないと思われていました.当然です.どんなに強い人間といえども,水深数百mも潜って地表を調べることなどできないからです.しかし,日本には,「しんかい6500」という潜水調査船があります.水深6500mまで潜って作業をすることができます.これを使えば,海底でも「地表踏査」できそうです.しかし,そんなに,簡単ではありません.なぜでしょうか.
みなさん,マリンスノー,というものをご存じでしょうか.海に降る雪.海では,プランクトンの死骸などが,深海底に向けてどんどん落ちているのです.落ちて,海底に降り積もります.こう考えると,海底は,いつでも豪雪地帯ですね.しかも真っ暗.これでは調査できません.なぜならば,海底には「雪」ばかりがつもっていて,地盤を作っている「土」や「石」が見えないからです.でも,「雪」がいつも吹き飛ばされている場所があることをみなさん知っていますか?
海底で,海水が流れているところです.そんなところあるのでしょうか?答えは「たくさんあります」です.特に,私たちは,海底谷,を重点的に調査しています.静岡県にある天竜川は,海底にもつながっています.天竜海底谷,と言います.
天竜海底谷と潮岬海底谷の位置
台風などで土砂が天竜川を流れ下ると,その土砂はこの天竜海底谷に沿って海底まで運ばれます.このときの流れはとても強いと思われ,ここならば,「雪」だけではなく,海底の岩も削ってしまうでしょう.実に,天竜海底谷は,その海底斜面を最大で1000mも削っているのです.同様に,紀伊半島と四国の間の紀伊水道からも,潮岬海底谷が海底に向かって伸びています.これらの海底谷は,海底斜面を削っていて,海底谷の両側には,数百mもの巨大な崖があります.この崖には,海底の地盤がむき出しになっていました.
天竜海底谷,水深約3000mに広がる地層
私たちは,海底谷に沿って,「しんかい6500」を潜航させ,海底の「地表踏査」を行っています.潜水船による海底谷の調査は,いままで不可能だと思われてきたことでした.その崖には,私たちが今までに見た事のない海底地盤がありました.このシンポジウムでは,その未知の海底地盤調査でどのような成果が上がったのか,についての多くの研究発表がありました.現在,それらの成果をまとめており,近々,研究論文として発表されます.
さまざまな手法には,それぞれの限界があります.その限界は,それぞれの手法によって補うことができれば,限界は限りなくゼロになると信じています.
川村喜一郎 (深田地質研究所)
講演プログラム
シンポジウム「南海付加体の実体に迫る:そのミクロ構造とマクロ構造」は2006年9月に第113年学術大会(高知大会)において以下の講演が行われました。
潜水船で明らかになった天竜海底谷沿いの南海付加体の地質構造,変形組織,物性,力学特性(川村喜一郎・小川勇二郎・安間 了Yildirim Dilek・横山俊治・川上俊介Gregory Moore・YK05-08Leg2乗船研究者)
潮岬海底谷に沿って露出する南海付加体の地質断面(安間 了・小川勇二郎グレゴリームーア・川村喜一郎・川上俊介佐々木智之・YK05-08Leg2乗船研究者YK06-02乗船研究者)
天竜海底谷,東海スラスト上盤側で発見された千枚岩質頁岩の被熱温度:スラストの鉛直運動量の推察(原 英俊・川村喜一郎小川勇二郎・YK05-08およびYK06-02乗船研究者)
アナログモデル実験による付加体の形態と形成過程(山田泰広・長村直樹馬場 敬・松岡俊文)
(招待講演)様々な震源インバージョンによって得られる震源モデルの違いについて(八木勇治)
天竜海底谷の西側斜面に発達しているテクトニック・ノンテクトニック変動地形(横山俊治佐々木智之・YK05-08Leg2乗船研究者一同)
放散虫生層序と海溝陸側斜面堆積盆の層序学〜南海トラフと南房総との対比〜(川上俊介)
沈み込み帯海側斜面に発達する海底地すべり−房総半島南部,西川名を例として− (道口陽子)
断層の微細構造を手がかりにした堆積物物性の抽出(鈴木清史・千葉達朗)
南海付加体の2つの海底谷からスレート劈開の発見:劈開2方向問題とexhumation問題再燃(小川勇二郎・川村喜一郎安間 了・原 英俊)
No.003 2007.07/17 geo-Flash
No.003 2007.07/17
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬【geo-Flash】日本地質学会メールマガジン ┴┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.003 2007/08/21 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】緊急 新潟県中越沖地震情報
【2】緊急提案:渋谷温泉施設爆発
【3】世界遺産登録記念:石見銀山の地質と鉱床
【4】生物侵食の島(ニュース誌表紙写真ダウンロード開始)
【5】札幌大会の見所 (その2)
【6】今週のキーワード 「大イベント」「カルデラ」
【7】シンポジウム案内
【8】公募情報(秋田大学工学資源学部 ポスドク 8/31〆切)
【9】札幌大会関連プレスリリース日程変更
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 新潟県中越沖地震緊急情報
──────────────────────────────────
平成19年7月16日10:13頃発生した新潟県中越沖地震(M6.6)に
関して、様々な速報が出ています。まだ余震が続いていますので、
被災地の方々、現地緊急調査の方々、くれぐれもお気をつけ下さい。
地質学会では札幌大会で緊急調査速報を展示する予定です。
詳細は後日発表します。
産業技術総合研究所発表の震央位置と地質図
http://www.gsj.jp/jishin/niigata_070716/index.html
防災科学技術研究所発表の地震メカニズムなど
http://www.hinet.bosai.go.jp/topics/niigata070716/
気象庁発表情報
http://www.jma.go.jp/jp/quake/
東京大学地震研究所発表情報
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/index-j.html
国土地理院発表情報
http://www.gsi.go.jp/BOUSAI/H19-nigata/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】 東京都渋谷区の温泉施設の'07.06.19爆発と緊急提案
──────────────────────────────────
正会員 中野啓二(Terra-Fluid Systems)
(1)「爆発」のあらまし(2)危険の広域性と原因(3)今後の爆発防
止と日本の温泉文化の発展のために
http://www.geosociety.jp/organization/hazard/07shibuya-gas.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】 世界遺産登録記念:石見銀山の地質と鉱床 (産総研)
──────────────────────────────────
世界遺産に登録された「石見銀山」は,仙山(せんのやま)とその周辺
の地下に分布する銀主体の鉱床を採掘した鉱山で,いまなお多数の坑口が
確認できます.石見銀山の鉱床がどのようにしてできたかについては幾つ
か議論がありますが、、、 詳細は、
http://www.gsj.jp/Gtop/topics/iwami-ginzan/
ページTOPにもどる
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】 生物侵食の島報道記念
──────────────────────────────────
今月のニュース誌(Vol. 10, No. 6)に掲載された広島県のホボロ島が報道されました。
これを記念して表紙写真ダウンロードを先行開始します。
新聞報道:
http://www.asahi.com/science/update/0711/TKY200707110129.html
表紙写真ダウンロード
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】 札幌大会の見所 (その2)シンポジウムの見所
──────────────────────────────────
大規模カルデラ火山 ─構造・噴火-堆積プロセス・長期予測─」
三浦大助(電力中央研究所)
陥没カルデラは,火山噴火の巨大エネルギーが造った凹地である.カルデ
ラ噴火が起これば,現代文明社会に深刻なダメージを与える事は間違いない.
その全容を明らかにするために,横断的な議論が必要な時期である.
本シンポジウムは,カルデラ火山の準備・噴火・終息過程について,以下の
視点からアプローチする.
(1)構造:カルデラは,火山噴火の巨大なエネルギーが地殻を破壊した結果
である.したがって,その構造は,マグマ溜りの深さや火道の分布など噴火
の場を反映していると考えられている.
(2)噴火?堆積プロセス:カルデラ噴火はしばしば大規模な火砕流を伴う.
噴火−堆積プロセスを正しく知ることは,影響の種類や範囲を理解することに
繋がる.また,構造と噴火プロセスの関係も重要である.
(3)長期予測:カルデラ噴火は,長期にわたる噴火休止期の後に発生すると考
えられている.長期予測を試みるには,噴火休止期を正しく把握することが重
要である.巨大噴火の周期性や後カルデラ火山活動の特徴などから,長期予測
の可能性をさぐる.
ページTOPにもどる
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】 今週のキーワード 「大イベント」「カルデラ」
──────────────────────────────────
「大イベント」
過去の地質現象は現在の自然現象と同じ作用で起きたとする斉一観は、
地質学にとって重要な概念である。しかし地球史を詳しく研究すると、現
在では全く考えられないようなイベントがたびたび起きており、それがま
た重要なターンニングポイントとなっていることがある。
地球の歴史は、ある意味で冷えていく歴史であるが、その冷え方は一定
でなく、時々地球内部から巨大な熱が出てきたり、地球外部からのエネル
ギーインプット(たとえば隕石落下)などがある。そんなイベントの痕跡
はローカルな地質に潜んでおり、これを具体的に暴いていくことで思いが
けない真の歴史が紐解かれる。真実の多くはまだまだ地層中に閉じこめら
れたままである。
清川昌一(九州大学)
「カルデラ」
カルデラとは,ポルトガル語で「大鍋」の意味を持ち,火山に見られる巨
大な凹みである.巨大とは概ね直径2km以上のものを指す.隕石が衝突して
できたクレーターとは明瞭に区別される.地下からマグマが一斉に噴出する
ことで,地表が陥没するものを「陥没カルデラ」と呼ぶ.巨大噴火でできる
カルデラは,陥没カルデラであることが多い.言い換えれば,カルデラの存
在は,火山が過去に巨大噴火を起こしたことの証明である.陥没カルデラを
造るような巨大噴火は,日本列島では1万年に1回ぐらいの割合で起こってい
る.日本で見られる陥没カルデラ火山は,北海道〜東北と九州で圧倒的に多い.
その噴火の影響は日本列島全体に及んだことが,堆積物の証拠から分かって
いる.一方,2000年の三宅島噴火のような玄武岩質火山では,マグマの噴出
が少なくても,陥没カルデラを生じることがある.この時のマグマは多くが地
下を移動したため,地表に出てこなかったと考えられている.
三浦大助(電力中央研究所)
写真:北東側から見た屈斜路カルデラ.後方は雄阿寒岳.
ページTOPにもどる
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】 シンポジウム案内
──────────────────────────────────
東京大学海洋研究所共同利用研究集会
「南海トラフ巨大地震発生帯の掘削科学」
8月8日(水)10:00〜17:30
会場:東京大学海洋研究所講堂
http://www.ori.u-tokyo.ac.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】 公募情報
──────────────────────────────────
研究機関研究員(ポスドク)の公募
1.採用予定人数:1名
2.研究分野:環境問題または資源開発に関連する地球科学。
3.担当業務等:基本的に応募者自身の研究テーマに専念してもらいますが、
実験補助等の依頼もあります。
4.応募資格:博士の学位を有すること。
5.採用予定日:平成19年10月1日
6.雇用期間:平成20年3月31日まで(半年間、ただし審査の上、半年に限って延長可)
7.提出書類:
(1)履歴書:学歴は高校卒業以降を記載し、調査・研究歴も明記すること
(2)研究業績目録:原著論文(査読の有無を区別すること)、総説、報告書、
著書、学会等での講演に分けて記載すること
(3)主要論文3編以内の別刷(コピーも可)
(4)これまでの研究内容の概要(1000字以内)
8.公募期間:平成19年8月31日(金) まで
9.提出先:
〒010-8502秋田市手形学園町1-1
秋田大学工学資源学部附属環境資源学研究センター 村上英樹
提出書類は「書留」とし、封筒に「研究機関研究員応募書類在中」と朱書すること。
10.問い合わせ先:
〒010-8502秋田市手形学園町1−1
秋田大学工学資源学部附属環境資源学研究センター 村上英樹
TEL:018-889-2446 E-mail:hidekim@cges.akita-u.ac.jp
その他:本公募は、半年間の雇用で、条件的にあまり良くありません。従いまして、応募者
のご希望に、できるだけ応えられる様にしたいと思います。ご質問などは、随時受け
付けますので、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
ページTOPにもどる
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】 札幌大会関連プレスリリース日程変更
──────────────────────────────────
札幌大会および札幌大会の講演内容について、日本地質学会からプレス発表を
2007年8月24日(金)に行う予定です(News誌6月号掲載の日程を変更)。
地質学会からのプレスリリー スを希望する方は、8月13日(月)までに、
学会事務局(main@geosociety.jp)にご連絡ください。
個人でプレスリリースを行う方も、2007年8月24日(金)以降に行うよう
ご協力願います。
ページTOPにもどる
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3週)配信予定です。原稿は第2・4週金曜日まで
にお送りください。geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.001 2007.07/03 geo-Flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬【geo-Flash】日本地質学会メールマガジン ┴┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.001 2007/08/21 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】創刊のごあいさつ (会長 木村 学)
【2】講演申し込み締切延長 (7月4日に変更)
【3】札幌大会はホテル不足?! (お早めに!)
【4】札幌大会セッションの見所 (その1)
【5】地質学雑誌に新しいカテゴリー追加 (要チェック!)
【6】シンポジウム案内
【7】今週のコラム 「北海道に地質の風を吹かそう!」の巻
【8】geo-Flash配信アドレスの追加・変更および停止
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 創刊のごあいさつ
──────────────────────────────────
日本地質学会の発する公式メールマガジンgeo-Flash第1号をお届けします。
このgeo-Flashは、学会活動の改善の一環として、地質学に関わるあるいは
学界活動に関する情報をいち早く会員の皆様にお届けすることを目的として
発足いたしました。会員参加型へのホームページの大幅充実(9月刷新予定)
に先んじてお届けするものです。会員の皆様からの情報も積極的に載せていく
予定ですので、大いにご活用いただきますようお願い申し上げます。
木村 学(地質学会長)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】 講演申し込み締切が1日延長されました
──────────────────────────────────
9月の札幌大会講演申し込み締め切りは1日延長されました。詳細は、、、
http://www.ep.sci.hokudai.ac.jp/~mmgc/GSJ-Sapporo2007/
ページTOPにもどる
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】 札幌大会はホテル不足?!
──────────────────────────────────
9月の札幌大会期間中に「北海道マラソン」が札幌市で開催されます。
札幌のホテルや航空券予約はお早めにお願いします。詳しくは、、、
http://www.ep.sci.hokudai.ac.jp/~mmgc/GSJ-Sapporo2007/GSJ-Inform1.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】 札幌大会トピックセッションの見所(その1)
──────────────────────────────────
地球史とイベント大事件3:地球の変化に迫る コンビナー: 清川昌一(九州大学)
地球史におけるイベント
18世紀末、J.ハットンの斉一説を解き、地質学教室ではかならず覚えさせられた記憶
がある。つまり、過去の地質現象は現在の自然現象と同じ作用で一様に行われた!とす
る考え方である。もちろん、侵食・堆積作用・化学反応など現在と同様に起こるのだ
が、地球の歴史は現在の状態とはかけ離れた状態を経てきているのである。この現在
では考えられないような事件を紐解き、そのときの地球のリアクションを考えていく
ことが、科学的に面白く、かつ今後の地球を考えていく上で重要なのである。
これは、子供(大人も)が恐竜を見て、興奮するのと同じである。
本セッションは、1)初期地球(太古代・原生代)の地球復元・大陸成長、2)雪玉地球
やPT/KT(KPg)境界などの生物繁栄・絶滅、3)温暖地球・寒冷地球の変動(たとえば、白
亜紀・石炭紀など) 4)テクトニクスに関連した地球イベント、5)地球内部活動vs地球
外インパクトなどによる揺れ動く地球の理解、を目標にしている。テクトニクス、層序・
古生物学、分析系などさまざまな分野から、またローカル地質から引き出される一般化への
トライが望まれる。
今週のキーワード: 「大イベント」
過去の地質現象は現在の自然現象と同じ作用で起きたとする斉一観は、地質学にとって重要な
概念である。しかし地球史を詳しく研究すると、現在では全く考えられないようなイベントがた
びたび起きており、それがまた重要なターンニングポイントとなっていることがある。
地球の歴史は、ある意味で冷えていく歴史であるが、その冷え方は一定でなく、時々地球内部から
巨大な熱が出てきたり、地球外部からのエネルギーインプット(たとえば隕石落下)などがある。
地球表層では複雑な事件が繰り広げられている。そんなイベントの痕跡はローカルな地質に潜んで
おり、これを具体的に暴いていくことで思いがけない真の歴史が紐解かれる。まだまだ、ベールの
多くは地層中に閉じこめられたままである。
ページTOPにもどる
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】 地質学雑誌に新しいカテゴリーが加わりました
──────────────────────────────────
地質学雑誌に「報告(Report)」という新しいカテゴリーが加わりました。
制限ページ数は6ページです。詳しくは編集規約・投稿規定(PDF)をご覧下さい。
毎年,全国の地学系の教室で取り組まれている卒業研究や修士論文の数は,相当数に昇るものと
思われます.それらの中には,一次データとしては大変貴重なものが多数含まれています.しかし,
それらの多くは各大学や指導教員のもとに保管されているのみで,全く日の目をみないで死蔵されて
いる例が多いのではないでしょうか.また,以前には多くの大学で発行されていた紀要が,廃止され
ている例も多く,そうした一次データを公表する場も少なくなっている様に思われます.新潟大学でも
和文の研究報告は廃止されています.重要な露頭の記載や,ルートマップ,岩石の分析値や化石の記載
など,膨大な貴重なデーターが公表されずに眠り続けているとしたら,大変残念な事態です.
地質学雑誌に,データの報告を主としたカテゴリーを加えることによって,そうした一次データの
公表の場を提供する事が出来るのではないかということで,編集委員会企画部会で現在検討を進めて
いるところです.この議論は,全国の地学系の教室で行われている膨大な卒業研究や修士論文によっ
て得られている,貴重なデータの公表の場を設けるという趣旨で発想されています.会員の皆様から
の積極的なご意見をお待ちしています(地質学雑誌113巻 5月号 編集後記より).
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】 シンポジウムのご案内
──────────────────────────────────
「公共財としての地質地盤情報 -ボーリングデータの整備と活用-(仮)」
地質調査総合センター第8回シンポジウム
http://www.gsj.jp/Event/070725sympo/
ページTOPにもどる
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】 今週のコラム 「北海道に地質の風を吹かそう!」
──────────────────────────────────
巷では、年金問題や格差社会問題などが騒がれている。
さて、13年振りに札幌で開催される地質学会では、
地質学会に加えて地質関連の諸行事が前後していくつか
企画されており,「ジオウイーク」として協力・共同して
進めることとなっている。ところで,北海道の人口は
ほとんど変化していないが、札幌だけは人口増加が続いており、
200万の大台に近づきつつある(現在189万人)。
札幌駅周辺の変容振りに驚く人も多いのではないだろうか。
とりわけ札幌駅の雑踏振りは東京を思わせるが、その札幌駅で
今回のジオウイークに関連した展示がなされるとのことである。
一方,北海道の負の側面として全国に名を響かしている
夕張を舞台として、2つの巡検が企画されている。それに
歩調を合わせて夕張近郊の炭坑町出身の木村 学地質学会長
による現地での講演会も企画されている。これら全体を成功
させ、北海道に地質の風を吹かせたいと思っている。
おいしいビールを札幌で、そして各巡検地で飲み交わし、
熱く議論を交わしたいものである。
宮下純夫(地質学会情報特任理事)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】 geo-Flash配信アドレスの追加・変更および停止
──────────────────────────────────
9月のホームページリニューアル以降は、オンラインでの変更が可能になり
ます。それまでの間はお手数ですが、配信アドレスの追加・変更および停止は、
事務局(journal@geosociety.jp)へご連絡ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今週のキーワード
今週のキーワード
大イベント
過去の地質現象は現在の自然現象と同じ作用で起きたとする斉一観は、地質学にとって重要な概念である。しかし地球史を詳しく研究すると、現在では全く考えられないようなイベントがたびたび起きており、それがまた重要なターンニングポイントとなっていることがある。
地球の歴史は、ある意味で冷えていく歴史であるが、その冷え方は一定でなく、時々地球内部から巨大な熱が出てきたり、地球外部からのエネルギーインプット(たとえば隕石落下)などがある。そんなイベントの痕跡はローカルな地質に潜んでおり、これを具体的に暴いていくことで思いがけない真の歴史が紐解かれる。真実の多くはまだまだ地層中に閉じこめられたままである。
清川昌一(九州大学)
カルデラ
カルデラとは,ポルトガル語で「大鍋」の意味を持ち,火山に見られる巨大な凹みである.巨大とは概ね直径2km以上のものを指す.隕石が衝突してできたクレーターとは明瞭に区別される.地下からマグマが一斉に噴出することで,地表が陥没するものを「陥没カルデラ」と呼ぶ.巨大噴火でできるカルデラは,陥没カルデラであることが多い.言い換えれば,カルデラの存在は,火山が過去に巨大噴火を起こしたことの証明である.
陥没カルデラを造るような巨大噴火は,日本列島では1万年に1回ぐらいの割合で起こっている.日本で見られる陥没カルデラ火山は,北海道〜東北と九州で圧倒的に多い.その噴火の影響は日本列島全体に及んだことが,堆積物の証拠から分かっている.一方,2000年の三宅島噴火のような玄武岩質火山では,マグマの噴出が少なくても,陥没カルデラを生じることがある.この時のマグマは多くが地下を移動したため,地表に出てこなかったと考えられている.
三浦大助(電力中央研究所)
写真:北東側から見た屈斜路カルデラ.後方は雄阿寒岳.
海底地すべり
海底地すべりとは,なんでしょう?わからないので,辞典を引いてみましょう.有名な「Glossary of Geology 4th edition(AGI)」にはSubmarine sliding という言葉は載っておらず,Subaqueous glidingはSlumpとあります.しかし,近年の学術論文には,Submarine slide(ing)やSubmarine landslideという用語は頻繁に見られますので,実際にはまかり通っているようです.そしてSlumpは陸上地すべりと海底地すべりの2つの意味があり,海底地すべりとしては「The sliding-down of a mass of sediment shortly after its deposition on an underwater slope」と記されており,より正確には,「Subaqueous slump」とあります.
一方、日本の「地学事典(平凡社及び地学団体研究会)」には「海底地滑り:海底の堆積物が重力の作用により斜面をすべり落ちる現象」とちゃんと載っています。堆積物とは,泥や砂,石などのことです.しかし,近年ハワイ諸島やカナリア諸島の火山島でも海底地すべりの事例が見つかっており,用語もどんどん進化中のようです。
最後に海底地すべりの重要性について少しだけふれておきます.ハワイ諸島や北海などで大規模の海底地すべりによって,津波が引き起こされたことがわかっています。しかし日本周辺では研究例が多くありません.現在,日本では海底資源であるメタンハイドレートの開発を押しすすめており,海底地すべりに対する関心が高まってきています.20世紀中頃には,ミシシッピデルタの油井プラットフォームの流出事故などの産業構造物に対する被害が社会問題になりました.失敗学(http://shippai.jst.go.jp/fkd/Search)ではないですが,過去に学んで,未来につなげる意味でも,海底地すべり研究は,必要不可欠です.
(川村喜一郎 深田地質研究所)
巡検案内:鮮新統唐の浜層群の層序と化石
鮮新統唐の浜層群の層序と化石
Overview of stratigraphy and paleontology of Pliocene Tonohama Group, Kochi Prefecture, southwest Japan
岩井雅夫1 近藤康生1
菊池直樹1 尾田太良2
Masao Iwai 1, Yasuo Kondo 1,
Naoki Kikuchi 1, and Motoyoshi Oda2
1.高知大学理学部自然環境科学科
Department of Natural Environmental Science, Faculty of Science, Kochi University,
Kochi 780-8520, Japan
2.東北大学大学院理学研究科地圏環境科学科
Faculty of Science, Tohoku University,
Aoba-ku, Sendai 980-8578, Japan
Corresponding author: M. Iwai
概 要
唐の浜層群は数少ない西南日本に点在する鮮新統のひとつで,当時の黒潮やテクトニクスを探る上で貴重な浅海域の情報をもたらす.甲藤ほか(1953)は泥岩主体の登層,礫岩主体の奈半利層(=六本松層),含貝化石砂岩層主体の穴内層を総称し唐の浜層群を定義した.しかし分布域が広範で露頭が点在することからその層序関係や年代論に関しては種々見解が飛び交い混沌としてきた.1990年前後になり登層と穴内層は一部同時異相の関係にあり,それらを不整合に覆う海成段丘堆積物が六本松層であると理解されるようになったが,公表されたデータが断片的で年代論に関してはなお見解に相違がみられた.2005年末〜2006年初頭に相次いで陸上掘削がなされ,年代論に決着をつけ黒潮の様相を高時間精度で明らかにしようという取り組みが始まった.本見学コースでは登層模式地,六本松層模式地,穴内層の堆積シーケンスと岩段丘堆積物・海食地形を案内,論争にいざなう.
Key Words
登層,穴内層,六本松層,高知県,堆積サイクル,軌道要素年代
Nobori Formation, Ananai Formation, Ropponmatsu Formation, Kochi Prefecture, sedimentary cycle, astronomical time scale.
地形図
1: 25,000 「羽根」「安芸」(「奈半利」「土佐土居」)
見学コース
8:30 高知大(朝倉)集合→11:00 登→12:00 羽根岬(昼食)→13:30 奈半利(六本松層模式地)→15:00 唐の浜(駅北方の穴内層)→16:30 伊尾木洞(穴内層海食洞)→18:00 高知大(朝倉)解散見学地点
Stop 1 登層模式地(浮遊性微化石・耳石産地).
Stop 2 六本松層模式地(挟亜炭層).
Stop 3 唐の浜駅北方の穴内層(堆積サイクルと段丘礫).
Stop 4 伊尾木洞(穴内層浅海相,海食洞,シダ植物群落).
1.はじめに
第1図.唐の浜層群分布図.日本の地質「四国地方」編集委員会(1991)より
高知県東南部の土佐湾沿岸には,多種多様な軟体動物化石・微化石等を含む鮮新世の唐の浜層群(甲藤ほか,1953)が点在している(第1図). 唐の浜層群は四国で唯一の海成正常堆積物からなる鮮新統で,静岡の掛川層群や九州の宮崎層群,沖縄の島尻層群などとともに,4万年ないし2 万年サイクルが卓越する当時(Tiedemann et al., 1994;Shackleton et al., 1995ほか)の黒潮やテクトニクスを探る上で重要な情報源となり得る.
これまでの研究により,鮮新統唐の浜層群は(1)浮遊性有孔虫(甲藤ほか,1953;Takayanagi, 1953;Takayanagi and Saito, 1962;Uchio, 1967;Kurihara,1968),放散虫(中世古・菅野,1973;Sugiyama et al.,1992),石灰質ナンノプランクトン(Nishida, 1971,1979;Takayama, 1969, 1980;甲藤ほか,1980;甲藤,1990),珪藻(Koizumi and Ujiie, 1976)の浮遊性微化石主要4タクサがそろって産出すること,(2)氷期−間氷期サイクルに相当すると考えられる堆積サイクルの存在が知られていること(近藤,2005;近藤ほか,1997, 2006)から,軌道要素年代(岡田,1998)を確立する上で好条件をそろえた地質体である.
本稿ではまず層序と年代に関する議論に絞って研究史を振り返り問題点を整理する.次に現在進行中の陸上掘削の概要(岩井ほか,2006)をかいつまんで紹介する.浅海域の堆積物で軌道要素年代層序を確立することにより,我々は化石層序の高精度化をはかるとともに,黒潮の消長やアジアモンスーンに関連した沿岸水の発達史をひもとく作業を開始した(岩井ほか,2006;Kondo etal., 2006;近藤ほか,2006).今回の見学旅行が,古くて新しい層序問題の議論から進化古生態学・古海洋生物学論議に発展することも期待したい.
2.研究史
第2図.研究者別層序対照表(岩井原図).
古くから土佐湾沿岸には大型化石を含む比較的新しい時代の堆積物が存在することが知られていた(Yokoyama, 1926, 1929;Suzuki, 1930).戦後甲藤ほか(1953)は泥岩主体の登層,礫岩主体の奈半利層,含貝化石砂岩層主体の穴内層を識別,それらを総称し唐の浜層群と呼んだ.そののち基盤の奈半利川層と紛らわしいとの理由で,奈半利層を六本松層と改称した(甲藤ほか,1960).Uchio(1967)はその改称を不要としたが,一般に六本松層が広く用いられてきた(Kurihara, 1968;日本の地質「四国地方」編集委員会編,1991;甲藤・増田,1993).しかし分布域が広範で露頭が点在することからその層序関係や年代論に関しては種々見解が飛び交い混乱してきた(研究者別層序対照表参照;第2図).甲藤ほか(1953)は,登層の上位に奈半利層(=六本松層)が不整合で重なり,奈半利層を一部不整合で穴内層が覆うと考えた.ところが甲藤・尾崎(1955)では唐の浜層群から登層を除外し,甲藤ほか(1960)ではさらに六本松層をはずして,穴内層と足摺地域の越層を対比,総称として唐の浜層群を用いた.Takayanagi and Saito(1962)が浮遊性有孔虫化石から登層が中新統であることを示唆したこと,ならびに六本松層と他の地層との岩相上の差違や“不整合”の評価が揺れ動いたことによると思われる.
第3図.Kurihara(1968)による唐の浜層群地質図.4桁の数字は第1表の有孔虫分析試料採取地点を示す.
第4図.Kurihara(1968)による唐の浜層群岩相対比図.1.泥岩,2.泥質砂岩,3.細粒砂岩,4.中粒砂岩,5.粗粒砂岩,6.砂岩−礫岩互層,7.礫岩,8.亜炭層,9.石灰質物質,10.軟体動物化石,11.生痕化石,A.穴内,B.新浜,C.高台寺,D.沢ノ平,E.久保田,F.伊尾木,G.唐の浜,H.城,I.大野,J.高田,K.野友,L.郷,M.六本松,N.羽根.
第1表.Kurihara (1968)による底棲有孔虫化石産出リストに,底棲有孔虫の産出頻度小計ならびに長谷川ほか(1989)にもとづく指標種の古水深を加えた.
軟体動物化石群を比較したTsuchi(1961)は穴内層と登層の化石群の共通性から,それほど大きな年代ギャップはなく一連の堆積体であると考えた.底生・浮遊性有孔虫化石を再検討したUchio(1967)も,登層を中新28 岩井雅夫・近藤康生・菊池直樹・尾田太良Supplement, Sept. 2006統とするTakayanagi and Saito(1962)の解釈に異議をとなえTsuchi(1961)を支持,さらに穴内層と奈半利層(六本松層)は整合的であるとの考えを示した.またUchio(1967)は底生有孔虫群集の違いは堆積場の違いによるもので,穴内層は内部−中部陸棚,登層は外部陸棚ないし内部陸棚斜面で堆積したと主張した.いずれも重要な指摘であったが,基礎となる観察データの提示は不十分であった.Kurihara(1968)は主たる唐の浜層群分布域の地質図(第3図)・柱状図(第4図)とともに底生有孔虫の産出リスト(第1表)を提示し,Uchio(1967)とほぼ同じ結論を導いている.Kurihara (1968)は登層から(1)“シルト岩部層群集”(登層主部に分布)および(2)“砂岩部層群集”(登層下部),穴内層から(3)千福相(穴内層東部域)および(4)伊尾木相(穴内層西部)を識別し,現世群集と比較して(1)を上部陸棚斜面,(2)と(3)を中部陸棚,(4)を上部陸棚の堆積環境を示唆するものと解釈した(第1表).登層下部と穴内層東部の群集に共通性が認められることなどから唐の浜層群に年代のギャップをともなうような不整合はないとの考えを示した.
第1表
有孔虫・貝化石による年代論争に引きずられ,層序に関する見解が混迷する中,1970年代になると有孔虫以外の浮遊性微化石で年代を決定しようとする動きが活発となる(甲藤ほか,1980参照).石灰質ナンノ化石ではNishida(1971, 1979),Takayama(1969, 1980)が詳細な検討を行っているほか,甲藤ほか(1980)や甲藤(1990)などで予察的な記述・図示が認められる.また珪質微化石は,珪藻化石についてKoizumi and Ujiie(1976)が,放散虫化石について中世古・菅野(1973)およびSugiyama et al.( 1992) が報告している.Matubara(2004)は唐の浜層群産化石標本のカタログを作成した際,微化石層序データも整理し,登層の堆積年代を前期鮮新世の後期から後期鮮新世初期(4.20−3.21 or 3.12Ma),穴内層の堆積年代は後期鮮新世後期(2.78 or 2.73−1.97Ma)とした.しかし甲藤ら(甲藤,1990;甲藤・増田,1993)は登層と穴内層を同時異相とみなし,登層の最上部がむしろ穴内層より新しい年代を示すことを図示している(根拠となった石灰質ナンノプランクトン化石のデータは未公表;岡村眞,私信).甲藤ほか(1980)はこうした唐の浜層群の年代・層序の問題を解決すべく,羽根産業採石場内標高19.36mの地点で65.8mの陸上掘削を行い,連続した柱状試料を得た.しかし予察結果(甲藤ほか,1980)公表以降,この柱状試料の解析結果は公表されていない.
第5図.唐の浜付近の穴内層に認められる堆積サイクル(近藤,2005を一部改変).
満塩・安田(1989)は登層と穴内層は一部同時異相の関係にあり,それらを不整合に覆う海岸段丘堆積物(従来の六本松層)を芸西層群和食層に対比した.加賀美ほか(1992)は六本松層模式地周辺を再調査し,従来の六本松層模式地と同じ地域を模式地とした奈半利層を再定義した.また満塩・安田(1989)の指摘を支持し,奈半利層を芸西層群安芸層に対比し下部更新統と考えた.安田(1999)は,穴内層と登層が同時異相であること,南海トラフで継続的な付加作用が進む中,海成層−非海成層−成層と重なることは矛盾があることから,六本松層の存在を認めながらも「礫層は登層・穴内層の上位に位置し,第四紀礫層に覆われる」との見解を示している.甲藤(1990)も登層と穴内層の一部は同時異相であるとの考えには同調したが,六本松層の年代については花粉化石を根拠に更新世ではなく鮮新世との考えを譲らず,六本松層は従来どおり穴内層・登層とともに唐の浜層群としてあつかった(甲藤・増田,1993).Matsubara(2004)は公表された微化石データを最新の地質年代尺度(Berggren et al., 1995;Yanagisawaand Akiba, 1998)に照らしあわせて再評価した.その結果登層を前期鮮新世後期から後期鮮新世初期(4.2−3.21 or 3.12 Ma),穴内層を後期鮮新世(2.78 or 2.73−1.97 Ma)に形成された堆積物とみなし,両者の間に横たわる約40万年の間に奈半利層(=六本松層)が形成されたと考えた.Matsubara(2004)はUchio(1967)や甲藤(1990)が示した同時異相の考えを否定している.その後近藤ら(近藤ほか,1997;近藤,2005)は別な観点(シーケンス層序学)から穴内層の層序を見直し,氷期−間氷期サイクルに呼応すると考えられる堆積サイクルの存在を見いだした(第5図).近藤らは数メートルオーダーの堆積サイクルが4万年サイクルないし2万年サイクルの海水準変動に対応すると考え,そのことを確かめるとともに,唐の浜層群形成時の堆積場を復元,化石生物の古生態研究を推進しようと陸上掘削を計画した.2005年末〜2006年初頭に穴内層・登層の掘削が実現し,年代論に決着をつけ黒潮圏の様相を高時間精度で明らかにしようという取り組みが始まった(岩井ほか,2006;Kondo et al., 2006;近藤ほか,2006).
3.地層各説
第6図.登層の泥岩と,挟在する貝化石含有砂岩薄層.
登層
[命名]甲藤ほか(1953)
[模式地]高知県室戸市羽根町登
[分布]長く登周辺に限定的とされてきた(甲藤ほか,1953, 1980)が,室戸市向江付近(甲藤・増田,1993)や行当岬付近元川流域(満塩ほか,1990)にも分布することが知られるようになってきた.
[岩相]塊状泥岩を主体とし,貝化石や緑色角礫を含む砂岩薄層が挟在する(第6図).甲藤ほか(1980)は羽根産業採石場内標高19.36mの地点で65.8mの陸上掘削を行い,連続した柱状試料を得た.主体は灰白色シルト岩ないし砂質シルト岩で白色凝灰岩薄層や緑色・白色の角礫状軽石や貝化石,褐鉄鉱ノジュールなどを挟有,30m以深では砂がちとなり,56m以深では砂岩の角礫が基底礫(65m付近)まで続くとされている.30〜40mには小規模な断層の存在も記載されている.
緑色粒子は緑泥石を主体とし,スメクタイト,イライトなどの粘土鉱物を含む(高知大学・東正治教授,私信)が,コンデンスセクションにしばしば見つかる海緑石(Kitamura, 1998)は確認されていない.[産出浮遊性微化石ならびに年代]主要浮遊性微化石4タクサの浮遊性有孔虫化石( 甲藤ほか, 1 9 5 3 ;Takayanagi, 1953;Takayanagi and Saito, 1962;Uchio,1967),石灰質ナンノ化石(Takayama, 1969, 1980;Nishida, 1971, 1979;甲藤ほか, 1980;甲藤, 1990),珪藻化石(Koizumi and Ujiie, 1976),放散虫化石(中世古・菅野,1973;Sugiyama et al., 1992)がそろって産する.Matsubara (2004)は既存の微化石データを整理し,Cande and Kent (1995)の古地磁気年代を採用した古地磁気— 微化石複合層序( Berggren et al., 1995;Yanagisawa and Akiba, 1998)に対比, 4.20−3.21 or3.12Maとした.しかし穴内層と同時異相と考える甲藤ら(甲藤,1990;甲藤・増田,1993;安田,1999)は石灰質ナンノプランクトン化石帯NN14−19に対比し,最上部は鮮新世−更新世境界付近に届くことを図示している.
甲藤ほか(1980)によれば,登層の平均堆積速度は5〜10cm/k.y.と見積られている.
[その他化石ならびに堆積環境]底生有孔虫化石(甲藤ほか,1953;Uchio, 1967;Kurihara, 1968;甲藤,1990),花粉化石(甲藤ほか,1953),軟体動物化石や耳石化石( 満塩ほか, 1990; Majima and Murata, 1992;Matsubara, 2004;三本・中尾,2004など),珊瑚(甲藤・尾崎,1955),甲殻類(三本,2001),鮫の歯や脊椎(上野ほか,1975;田中・三本,1991;三本,2002)等が報告されている.陸棚縁辺から陸棚斜面上部の海盆で堆積したと解釈されている(甲藤ほか,1953;Uchio,1967;Kurihara, 1968;第1表).
第7図.穴内層とそれを不整合で覆う海岸段丘堆積物.
穴内層
[命名]甲藤ほか(1953)
[模式地]高知県安芸市穴内
[分布]穴内・新浜・江川・伊尾木・唐の浜および安田付近に分布.
[岩相]主体は石灰質シルト岩〜中粒砂岩で,下部には円礫層が認められる.中・上部では,砂質シルトあるいはシルト質砂を基軸とし,細粒化と粗粒化を繰り返し,一つの堆積サイクルを形成している(第5,7図).堆積サイクルを形成する堆積相としては,粒度・堆積構造・含有大型化石から以下の堆積相I〜IVが認識される;
堆積相 I :化石密集層を含む細粒砂相貝類を中心とした大型化石の密集層(厚さは最大で10 cm )を挟む細粒砂層である.化石密集層は上に凸のレンズ状形態を呈し,低角の斜交層理砂岩に覆われることがある.暴風時堆積物のハンモック状堆積物であると見なされる.
堆積相 II:貧化石砂質シルト相堆積物の粒度は均質で,化石に乏しい,淘汰がよいシルト岩からなる.暴風時の堆積作用により懸濁状態となった堆積物のうち比較的粗粒のものが堆積したもので,下部外浜から内側陸棚への漸移部にあたると考えられる.
堆積相 III:砂質シルト相化石を豊富に含み,生物攪拌の著しい不均質な砂質シルトで,ほとんどが生息時の姿勢を保った状態で見つかるClementia vatheleti(フスマガイ)と,大型で殻の薄い腹足類Stellaria exutus(キヌガサガイ) がめだつ.暴風時の堆積作用の影響が比較的少ない安定した海底環境を表しており,ベントスの深度分帯では上部浅海帯,堆積学的には内側陸棚に相当する.
堆積相 IV:泥岩相やや砂混じりの不均質な泥岩で,Glycymeris rotunda(ベニグリ)が優占する.Paphiaschnelliana, Clementia vatheletiなどが混じり,KeenaeasamaringaeやVenus foveolataなど,下部浅海帯に分布する貝類が含まれる.暴風時の堆積作用の影響が砂質シルト相の場合よりさらに少ない外側陸棚の堆積物であると考えられる.
含まれる貝化石群はすべて暖水種で,寒水種は全く出現しないが,穴内層上部に見られる堆積サイクルは大桑
第8図.穴内層掘削コア試料(ANA)模式柱状図(近藤原図).
唐の浜.層中部の海進海退サイクル(Kitamura et al., 1994)とよく似た特徴を示す.
唐の浜駅北方農免道路沿いの陸上セクションでは10の海進−海退サイクルが認定されている(近藤,2005;第5図).唐の浜駅北方の丘陵で掘削されたコア試料では,総計17の堆積サイクルが認定され(Kondo et al., 2006;第8図),岩相対比により,コアの堆積サイクル13は,近藤(2005)のサイクル6に対比される.
[産出浮遊性微化石ならびに年代]石灰質ナンノ化石(Nishida, 1971, 1979; 甲藤,1990;甲藤・増田,1993)および花粉化石( 中村, 1 9 5 2 ) の報告がある.Matsubara(2004)は,浮遊性微化石の既存公表資料をBerggren et al.,(1995)の地質時間尺度によみかえて2.78 or 2.73−1.97Maとし,登層より40万年程度以上新しい堆積物とした.甲藤ら(甲藤,1990;甲藤・増田,1993)の石灰質ナンノ化石登層とは同時異層であるとしている.
[ その他化石ならびに堆積環境] 軟体動物化石(Yokoyama, 1926, 1929;Nomura, 1937;満塩ほか,1990;柴田・氏原,1990;近藤,1999;Tomida and Kitao, 2002;三本・中尾,2004;Matsubara, 2004など),耳石(門部・近藤,2005)貝形虫化石(Ishizaki, 1979, 1983;Ishizaki andTanimura, 1985),花粉(中村,1952)などが報告されている.Ishizaki(1983)はCallistocythereananaiensis, C. kattoi, Cytherella japonicaなど7種を新種記載している.
甲藤ほか(1953)およびKurihara(1968)は底生有孔虫化石群集から,穴内層分布域西部(伊尾木)で浅く,東部(千福)ではやや深くなる一般的傾向を示した.Ishizaki and Tanimura(1985)は,貝形虫化石群集のQモード主成分分析を行い,4つのバリマックス群集(公海陸棚群集,黒潮系群集,湾口群集および沿岸流系群集)を認定した.粒度分析の結果と比較し,貝形虫の群集変化は堆積学的要因とは独立し,古海洋環境を反映したものと見なせることも示した. Ishizaki andTanimura(1985)は,主成分因子の時空間変動の様相から,穴内地域が最も開放的陸棚の影響化にあり,西部の穴内や伊尾木は湾口部の堆積場にあったことを明らかにしている.六本松層[命名]甲藤(1960).甲藤ほか(1953)で記載された際には奈半利層と命名され,不整合で登層をおおい,穴内層には覆われる関係と見なされた.その後奈半利川層との混乱を嫌い甲藤ほか(1960)は六本松層と改称した.Uchio(1967)はその改称を不要と考えたが,その後使われ続けている(甲藤・増田,1993ほか).加賀美ほか(1992)は層序再検討に際し,奈半利層を再定義し使用している.
第9図.六本松層の礫岩,泥岩と挟亜炭層.安芸市六本松.
[模式地]高知県安芸郡奈半利町六本松.
[分布]奈半利町六本松・車瀬・加茂,田野町大野台,および室戸市羽根.
[岩相]礫岩を主体とし,一部成層した泥岩・亜炭・砂岩が挟在する(第9図).礫種としては室戸層群起源と思われる砂岩,泥岩,チャート等からなる.
[産出化石ならびに年代・堆積環境]木片や花粉化石のAlnus, Taxodiaceae (Metasequoia+Sequoia), Gramineae,Fagus, Ulmus, Liquidamberなどが報告されている(Nakamura, 1951;甲藤ほか,1953).海成堆積物であることを示唆する化石は見つかっておらず,陸水性堆積物とされている.満塩・安田(1989)は羽根岬周辺の層序調査結果と周辺地域との岩相対比を元に,下部更新統であると考えた.加賀美ほか(1992)は模式地周辺の六本松層を調査し,同じく下部更新統とみなし,六本松層をもとの奈半利層に改めて改称・再定義した.しかし甲藤・増田(1993)では,花粉化石を根拠に鮮新統であるとの考えを崩していない.Matsubara(2004)は,登層・穴内層の産出微化石は年代ギャップがあると考え(同時異相との考えを否定),そのギャップすなわち後期鮮新世前期が六本松層の形成年代とみなしている.
第10図.登層掘削コア試料(NOB)模式柱状図(近藤原図).
4.陸上掘削
甲藤ほか(1980)によって採取された登層掘削柱状試料は,その後高知大学理学部や佐川地質館(初代館長:甲藤次郎)などを転々とし,最後は甲藤高知大学名誉教授私設の倉庫に保管されていた(岡村眞・松岡裕美,私信)とされるが,甲藤先生ご逝去後倉庫を確認した第二著者近藤はその所在を確認していない.現在は所在不明の状態である.そこで平成17年度高知大学学長裁量経費「200万年前の土佐湾:海洋生物相と気候変動の復元」(代表:近藤康生)ならびに科学研究費基盤研究A(一般)「高品質の層序データ提供と若手育成のための浮遊生微化石統合データバンクの構築」(代表:尾田太良)の資金援助をうけ,2005年末から2006年初頭にかけて相次いで穴内層・登層の陸上掘削を実施した(岩井ほか,2006;近藤ほか,2006).
穴内層掘削コア(ANA)は掘進長70mで回収率は96.0%,登層掘削コア(NOB)は掘進長63.3mで回収率は99.3%であった.いずれも完全に基盤を確認することはできなかったものの,穴内層・登層のおおむね全層準を連続した柱状試料として回収することができた(第8,10図).セクション長1mのコア試料は,種々計測や試料分割の前にまず地球深部探査船「ちきゅう」船上で残留磁気測定が行われた.暫定的ながら古地磁気層序があきらかになり,さらに穴内層コア試料では地磁気逆転時の磁気変動の詳細が明らかになった(小玉ほか,2006;Kodama et al., 2006).しかし石灰質ナンノ化石の予察分析(亀尾浩司,私信)とは一致した結論を得るには至っておらず今後の精査が待たれる.これまでに,帯磁率やCT画像等,海洋コアセンターの大型機器を利用したデータが取得され,各種微化石や酸素同位体の分析が進行中である.詳細は別途報告することにし,ここでは岩相の記載概要(観察者:近藤)の記述にとどめる.
穴内層掘削コア(第8図)
唐の浜層群穴内層の最下部を除く大部分をカバーしており,陸上では露出不良のため不明であった同層下部の層序が明らかとなった.唐の浜における層序は,下位より,石灰質砂岩(最下部:掘削層準よりも下位),砂質貝殻密集層と化石散在層(あるいは貧化石層)の互層(下部:層厚20m),厚層細礫泥質貝殻層と化石散在層の互層(中部: 層厚7.5m),細礫貝殻層と貝殻散在層の互層(上部:層厚17.5m),貝殻散在層と無化石層の互層(最上部: 層厚18.3m)である.以上が穴内層に相当し,礫質の段丘堆積物に覆われる.少なくとの17の堆積サイクルが認定でき,それらの一部は従来の露頭観察で認定されていた海進海退サイクル(気候変動に伴うミランコビッチサイクルと推定される)に対比することができた.
登層掘削コア(第10図)
表層60cmは採土作業過程で埋め戻した人為改変堆積物であるが,以下〜63mまで連続した試料が得られた.最上部(0.6〜13.3m)の泥岩には緑色粒子は目立たず,長谷・近藤(1999)が,海綿骨針を集めて殻をつくる膠着質有孔虫と解釈したMakiyamaが密集または散在する.13.3〜28.8mのコア上部では,おなじく泥岩層を主体とするが,緑色粒子と貝殻の密集層が繰り返し出現する.Makiyamaは密集または散在.岩相変化に周期性が認められる.掘削コア中部(28.8〜41.9m)では,緑色粒子・貝殻は,コア上部のように密集せず,広い層準に散在する.Makiyamaは密集または散在するが,24〜28mの間は産出が欠落する.コア下部(41.9〜60.1m)ではやや粒子が粗くなり,化石は乏しく,緑色粒子はみあたらない.この区間の最上部では,炭質物薄層やタービダイトを挟み,下位に漸移する.Makiyamaは区間中下部では見あたらない.コア試料の流動化のため,一部岩相・層序が不明.最下部の60.1〜63.3mには細粒砂岩の角礫岩が認められる.
層序関係の明瞭な連続した柱状試料を,穴内層・登層のほぼ全層準をカバーするように採取することをめざした掘削は,いずれも基盤にこそ達しなかったものの,ほぼ全層準をカバーする連続試料の採取に成功し,軌道要素年代学確立に必要な,古地磁気層序・同位体層序・微化石層序の分析試料を供した.
Geologic Time Scale (GTS) 2004(Gradstein et al.,2004)の中でLourence et al.(2004)は古地磁気層序の再評価を行うとともに,微化石層序の基準面と酸素同位体ステージ(MIS)等軌道要素変動に起因した反応特性を示す物理化学情報とを対応づけ,新生代の高精度層序= 軌道要素年代尺度( Astronomically TunedNeogene Time Scale;ATNTS)の確立を提言している.高精度層序の確立により,これまで等時性が維持されていると考えられてきた化石層序学的基準面においても地域差の存在が明らかにされてきており,進化生態学的評価検討が可能な時間精度で議論できる環境が整備されつつある.
穴内層・登層より得られたコア試料は,従来の混乱要因を明らかにして高精度微化石層序を確立することに最適であり,それにより黒潮圏の古海洋学的・進化古生態学的研究を推進することが期待される.
第11図.見学地点位置図.A .登層模式地(Stop 1).星印付近で柱状試料NOBを採取.B.六本松層模式地(Stop 2).C.唐の浜駅周辺(Stop 3).○は穴内層柱状試料(ANA)掘削地点.D.伊尾木洞(海食洞とシダ群落;Stop 4).
5.見学地点
Stop 1 登層模式地(浮遊性微化石・耳石産地)
[地形図]1/2.5万 「羽根」
[位置]室戸市羽根町羽根産業採石場(第11図A)
[解説] 2.5万分の1地形図に示された鳥居印付近にわずかに露頭が残るほか,周辺に露頭が点在(実在する社の位置は北に40m程ずれているので注意).
浮遊性有孔虫化石Globorotalia tosaensisの模式地(Takayanagi and Saito, 1962)として知られるが,底生有孔虫化石ではSpiroloculina akiensis,Trifarina shikokuensis, Quadrimorphina akiensis(Kurihara, 1968)が,石灰質ナンノ化石ではReticulofenestra japonica (Nishida) emend.N i s h i d a が, 放散虫化石では,Pseudodictyophimus hexaptesimus, Bathropyramis(?) pyrgina, Eucyrtidium leneが(Sugiyama et al.,1992)この地で記載されている.残念ながらKurihara(1968)やNishida(1979)等で試料採取された河川床の露頭は護岸工事等で消滅してしまっている.
採石場あとや途中の進入路では雨水に洗い出された耳石化石(径数mm程度)を拾うことができるが,山頂付近の平坦地は採土の埋め戻しが行われている(羽根産業社,私信)ので注意.
Stop 2 六本松層(奈半利層)模式地
[地形図]1/2.5万 「羽根」
[位置]六本松にある旧貯木場付近,国道55号の北側(第11図B).
[解説]国道の北側ゴルフ練習場入り口付近を最上部に,作業道沿いに下位層準を観察.100mほど入ると亜炭層が少なくとも3層準で認められる露頭に至る.地層はおよそ海岸線に向かって緩く傾斜.この付近で穴内層や登層との関係は不詳.
Stop 3 唐の浜駅北方の穴内層(堆積サイクルと段丘礫)[地形図]1/2.5万 「安芸」
[位置]第三セクター土佐くろしお鉄道の唐の浜駅から北方約200m(第11図C),農免道路沿いに連続露出.一部はすでに壁面保護されている.
[解説]Stop 3周辺における地層の走向はN30゜W,傾斜は南西に10゜程度.農道入り口近くの露頭はこれまで認定されている最上位層準にあたり,貝殻が多数散らばっているが,そのほとんどはベニグリ(Glycymerisrotunda)と呼ばれる二枚貝である.ベニグリは,本州,四国,九州,東シナ海の水深30〜300mに分布している(黒田ほか,1971).
第12図.伊尾木洞(Stop 4).
Stop 4 伊尾木洞
[地形図]1/2.5万 「安芸」
[位置]土佐くろしお鉄道伊尾木駅から東北東約7分.国道55号からやや北(第11図D).海食洞窟への入口付近には子供の塑像と標識がある.
[解説]Stop 3で見られる穴内層にくらべ粗粒で,チャネルを充填する礫岩薄層もみられる.層理面の走向はおおむね海岸線にそっており,海岸に向かってゆるく傾斜する.洞穴(第12図)を抜けると,穴内層がつくる渓谷壁面にはぎっしりとシダが生い茂る.国の天然記念物として指定されているシダ植物群落(大正15年10月20日指定)で,暖地性シダ類7種が共生繁殖するとされている.沢の奥に突き進むと礫岩が卓越するようになり,四万十帯の砂岩泥岩互層と断層で接する露頭が見られる.
謝 辞
千葉大学亀尾浩司博士ならびに徳島大学村田明広博士には原稿の校閲をしていただいた.登層模式地における調査・巡検は(株)羽根産業の好意により実現した.感謝する次第である.
文 献
Berggren, W.A., Kent, D.V., Swisher, C.C., III and Adbry,M.-P., 1995, A revised Cenozoic geochronology andchronostratigraphy. In Berggren, W.A., Kent, D.V.,Aubry, M.-P. and Hardenbol, J., eds., Geochronology,Time Scales and Global Stratigraphic Correlation, SEPMSpec. Publ., no.54, 129-212.
Cande, S.C. and Kent, D.V., 1995, Revised calibration of thegeomagnetic polarity time scale for the Late Cretaceousand Cenozoic. Jour. Geophys. Res., 100 (B4), 6093-6095.
Gradstein, F.M. Ogg, J.G. and Smith, A.G, 2004, A geologicTime Scale 2004. 588pp., Cambridge Univ. Press.
長谷宏司・近藤康生,1999, Makiyama の分類場の位置:元素マッピングと骨針の形態分析に基づく再検討.日本古生物学会1999年年会(仙台)講演予稿集,102.長谷川四郎・秋本和實・北里 洋・的場保望,1989,底生有孔虫にもとづく日本の後期新生代古水深指標.地質学論集, no.20, 241-253.Ishizaki,
K., 1979, Study of Ostracoda from the PlioceneAnanai Formation, Shikoku, Japan-a step towarddistinguishing the sedimentary environments-.Taxonomy, Biostratigraphy and Distribution ofOstracodes, Proceedings of the VII InternationalSymposium on Ostracodes, 197-205.
Ishizaki, K., 1983, Ostracoda from the Pliocene AnanaiFormation, Shikoku, Japan -description-. Trans. Proc.Palaeont. Soc. Japan, N.S., no.131, 135-158.
Ishizaki, K. and Tanimura, Y., 1985, Ostracoda from thePliocene Ananai Formation, Shikoku, Japan -faunalanalyses-. Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan, N.S.,no.137, 50-63.
岩井雅夫・近藤康生・小玉一人・尾田太良・亀尾浩司,2006,唐の浜層群陸上掘削プロジェクト概要.黒潮域における古気候・古海洋変動ワークショップ(2006年3月13-14日,高知大学海洋コア総合研究センター)要旨集,23.
門部洋章・近藤康生,2005, 鮮新統唐ノ浜層群穴内層の魚類耳石化石群とそのタフォノミー.第5回日本地質学会四国支部会総会・講演会(予稿集),O-8.加賀美秀雄・満塩大洸・野沢繁,1992, 高知県東南部の奈半利川付近にみられる第四系.城西大学研究年報(自然科学編),16, 1-13.
甲藤次郎, 1990. 第三章地質.田野町史, 高知県田野町,21-76.甲藤次郎・小島丈児・沢村武雄・須鎗和巳, 1960,20万分の1高知県地質鉱産図.
甲藤次郎・増田孝一郎, 1993, “安芸の喰はず貝”の伝説で名高い唐ノ浜層群の貝化石.佐川地質館展示解説特集,佐川地質館, 高知県佐川町, 51pp.
甲藤次郎・中村純・高柳洋吉, 1953, 唐ノ浜層群の層序と微古生物的考察. 高知大学学術研究報告, 2, no.32, 1-15.
甲藤次郎・尾崎博, 1955, 高知県の中新世「登層」について. 高知大学学術研究報告, 4, no.1, 1-7.
甲藤次郎・高柳洋吉・増田孝一郎・平朝彦・岡村真,1980, いわゆる“唐ノ浜層群”の再検討−予報−.四万十帯の地質学と古生物学. 甲藤次郎教授還暦記念論文集, 27-36.
Kitamura, 1998,Glaucony and carbonate grains as indicatorsof the condensed section: Omma Formation, Japan.Sediment. Geol. 122, no.1, 151-163.
Kitamura, A., Kondo, Y., Sakai, H. and Horii, M., 1994,Cyclic changes in lithofacies and molluscan content inthe early Pleistocene Omma Formation, central Japanrelated to the 41,000-year orbital obliquity. Palaeogeogr.Palaeoclimatol. Palaeoecol., 112, 345-361.
小玉一人・三島稔明・岩井雅夫・近藤康生,2006,唐の浜層群穴内層掘削試料から得られた鮮新世後期の地磁気逆転と逆転移行期.黒潮域における古気候・古海洋変動ワークショップ(2006年3月13-14日,高知大学海洋コア総合研究センター)要旨集,24.
Kodama, K., Mishima, T., Iwai, M. and Kondo, Y., 2006,Late Pliocene polarity reversals and transitions from anon-shore drilled core of the Ananai Formation insoutheast Shikoku, Japan. 地球惑星関連学会合同大会(2006年5月17日)講演要旨集.
Koizumi, I. and Ujiie, H., 1976, On the age of the NoboriFormation, Shikoku, Southwest Japan-particularly basedon diatoms. Mem. Natl. Sci. Museum, no.9, 61-70.
近藤康生,1999,黒潮域の貝類群とその200万年の歴史.くろしお(高知大学黒潮圏研究所所報), no.14, 24-34.
近藤康生,2005,鮮新統唐の浜層群穴内層の海進海退サイクル:安田町唐の浜での野外観察.高知地学研究会会報,no.29, 4-8.
Kondo, Y., Iwai, M. and Kodama, K., 2006, Muroto Project:Scientific Drilling of the late Pliocene forearc basindeposit on the west coast of Muroto Peninsula, Shikoku,Japan. Scientific Drilling, no.3, 42-43.
近藤康生・岩井雅夫・小玉一人・亀尾浩司,2006,陸上ボーリング試料からみた上部鮮新統唐の浜層群穴内層の層序と土佐湾の古環境.日本地質学会第113年学術大会講演予稿集.
近藤康生・菊池直樹・広瀬浩司,1997,鮮新世後期の陸棚成堆積サイクルと底生動物化石群の古生態:高知県安田町唐の浜層群穴内層.日本古生物学会第146回例会講演要旨集,20.
Kurihara, K., 1968, Notes on the benthonic foraminifera ofthe Tonohama Group, Shikoku, Japan. Trans. Proc.Palaeont. Soc. Japan, N.S., no.70, 267-283.
黒田徳米・波部忠重・大山 桂,1971,相撲湾産貝類.丸善,489pp.
Lourens, L., Hilgen, F., Shackleton, N.J., Laskar, J. andWilson, D., 2004, The Neogene Peroiod. In Gradstein,F.M., Ogg, J.G. and Smith, A., eds., A Geologic TimeScale 2004. Cambridge Univ.Press,409-440.
Majima, R. and Murata, A., 1992, Intraspecific variation andheterochrony of Phanerolepida pseudotransenna Ozaki(Gastrapoda: Turbinidae) from the Pliocene NoboriFormation, Pacific side of southwestern Japan. Trans.Proc. Palaeont. Soc. Japan, N.S., no. 165, 1024-1039.
Matsubara, T., 2004, Catalogue of the Pliocene Molluscafrom the Tonohama Group in Kochi Prefecture, Shikoku,Japan. Nature and Human Activities, no.8, 49-95.
三本健二,2001,高知県の鮮新統登層産タカアシガニ属及びその他の甲殻類.地学研究,50,no.3,131-135.
三本健二,2002,高知県の鮮新統唐浜層群から産出した板鰓類Parotodusの歯, 地学研究,50,no.4,211-213.
三本健二・中尾賢一,2004,高知県の鮮新統唐ノ浜層群の浮遊性貝類.徳島県立博物館研究報告,no.14,15-25.
満塩博美・吉川 治,1977,高知・室戸間の第四系.日本地質学会地質巡検案内書.満塩大洸・安田尚登,1989,室戸半島羽根岬付近の地質.高知大学学術研究報告(自然科学),38, 217-224.
満塩大洸・小林哲之・三本健二,1990, 室戸半島行当岬付近の鮮新−更新統.高知大学学術研究報告(自然科学),39, 89-98.
Nakamura, J., 1951, Fossil pollen in the Nahari Lignite. Rep.Kochi Univ., Nat. Sci., no.1. 1-11.中村 純,1952,土佐穴内産亜炭の花粉分析,植物生態学会報,1,no.3, 9-11.
中世古幸次郎・菅野耕三, 1973. 日本新第三紀の化石放散虫分帯. 地質学論集, 8, 23-33.日本の地質「四国地方」編集委員会編,1991,四国地方.日本の地質,8, 共立出版.266pp.
Nishida, S., 1971, Nannofossils from Japan IV. Calcareousnannoplankton fossils from the Tonohama Group,Shikoku, Southwest Japan. Trans. Proc. Palaeont. Soc.Japan, N.S., no.83, 143-161.
Nishida, S., 1979. Restudies of calcareous nannoplanktonbiostratigraphy of the Tonohama Group, Shikoku, Japan.Bull. Nara Univ. Edu. Nat. Sci., 28 , no.2, 97-110.
Nomura, S., 1937. The molluscan fauna from the Pliocene ofTosa. Japan. Jour. Geol. Geogr., 14, no.3-4, 67-90.
岡田 誠,1998,用語解説「Astrochronology(軌道要素年代学)」.堆積学研究,no.47, p.113-118.
Shackleton, N.J., Hall, M.A. and Pate, D., 1995, Pliocenestable isotope stratigraphy of Site 846. In Pisias, N.G.,Mayer, L.A., Janecek, T.R., Palmer-Julson, A., and vanAndel, T.H. eds., Proc. ODP, Sci. Results, 138: CollegeStation, TX (Ocean Drilling Program), 337-355.
柴田 博・氏原 温,1990,日本の新生代翼足類相.瑞浪市化石博物館専報告,no.7, 61-82.Sugiyama, K., Nobuhara, T. and Inoue, K., 1992. Preliminaryreport on Pliocene radiolarians from the NoboriFormation, Tonohama Group, Shikoku, Southwest Japan.Jour. Earth Planet. Sci. Nagoya Univ., no.39, 1-30.
Suzuki, T., 1930, 1/75,000 geological map “Muroto” withan explanatory textbook. Geol. Surv. Japan.
Takayama, T., 1969, Discoasters from the Lamont Core V21-98. Natl. Sci. Mus. Bull., 12 (2), 431-450.
Takayama, T., 1980. Geological age of the Nobori Formation,Shikoku, Japan; calcareous nannofossil evidence. Prof.Kanno Mem., 365-372.
Takayanagi, Y., 1953, New genus and species of foraminiferafound in the Tonohama Group, Kochi Prefecture,Shikoku, Japan. Short Papers, Inst. Geol. Paleont.,Tohoku Univ., no.5, 25-36.
Takayanagi, Y. and Saito, T., 1962, Planktonic foraminiferafrom the Nobori Formation, Shikoku, Japan. Sci. Rep.Tohoku Univ., Ser.2, Spec. no.5, 67-106.
田中 猛・三本健二,1991,高知県唐ノ浜層群(鮮新世)産板鰓類化石について.地学研究,40,143-154.
Tiedemann, R., Sarnthein, M. and Shackleton, N., 1994,Astronomic timescale for the Pliocene Atlantic δ18O anddust flux records of Ocean Drilling Program Site 659.Paleoceanography, 9, no.4, 619-638.
Tomida, S. and Kitao, F., 2002, Occurrence of Hartungia(Gastropoda: Janthinidae) from the Tonohama Group,Kochi Prefecture, Japan. Bull. Mizunami Fossil Mus., no.29, 157-160.
Tsuchi, R., 1961. On the late Neogene sediments andmolluscs in the Tokai region, with notes on the geologichistory of the Pacific coast of southwest Japan. Japan.Jour. Geol. Geogr., 32, no.3-4, 437-456.
Uchio, T., 1967. Is the Geologic age of the Nobori Formation,Shikoku, Japan, Miocene or Pliocene? Trans. Proc.Palaeont. Soc. Japan, N.S., no.67, 114-124.
上野輝彌・鹿島愛彦・長谷川善和, 1975, 四国産白亜紀及び第三紀のサメ類化石.国立科学博物館専報,no.8,51-56.
Yanagisawa, Y. and Akiba, F., 1998, Refined Neogenediatom biostratigraphy for the northwest Pacific aroundJapan, with an introduction of code numbers for selecteddiatom horizons. Jour. Geol. Soc. Japan, 104, 395-414.
安田尚登,1999,田野町の地形と地質について.土佐の自然, no.78, 5-8.
Yokoyama, M., 1926, Tertiary shells from Tosa. Imp. Univ.Tokyo, Fac. Sci., Ser. II, 1, no.9, 365-368.Yokoyama, M., 1929, Pliocene shells from Tonohama, Tosa.Imp. Geol. Surv., Japan. Rept., no.104, p.9-17.
本稿は「岩井雅夫・村田明広・吉村康隆,2006,見学旅行案内書,地質学雑誌,112,補講,170pp」がオリジナルです。
■ オリジナルPDFダウンロード(J-Stageサーバー)
No.009 2007.09/14 geo-Flash(臨時)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬【geo-Flash】日本地質学会メールマガジン ┴┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.009 2007/09/14 臨時号 ┬ <*)++<< ┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】「かぐや」打ち上げ成功!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「かぐや」打ち上げ成功! 月の地質調査始まる!
──────────────────────────────────
■「宇宙航空研究開発機構(JAXA) は9月14日10時31分に月周回衛星
「かぐや」を搭載したH-IIAロケットの打ち上げに成功し、打ち上げ約45分
後に「かぐや」を分離することに成功しました。この「かぐや」は月の地質調査を
行うことをミッションとしており、地質学の新たな地平を切り開いたと言えます。
これからますます地質学、地球科学の重要性が認識され、貢献が期待される
ことになるのは自明です。学会としても惑星地質学の普及、教育にも務めて
いくことは急務であり、責務と思います。
「かぐや」については、
http://www.jaxa.jp/countdown/f13/index_j.html
を参照ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.008 2007.09/04 geo-Flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬【geo-Flash】日本地質学会メールマガジン ┴┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.008 2007/09/04 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】第114年学術大会(in 札幌)迫る!
【2】札幌大会口頭発表:プログラム一部訂正
【3】コラム:「間違いだらけの発音選び」(気をつけなきゃ)
【4】同志社大学工学部 環境システム学科専任教員公募(10/10締切)
【5】JABEE講習会のご案内(10/13 開催)
【6】院生評議員・代議員より「博士の将来」アンケート作成中
【7】9月9日(日)新HPついに公開(予定)!!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 札幌大会迫る!
──────────────────────────────────
■札幌大会実行委員会を代表して、皆様にご挨拶申し上げます。
暑さも一段落した札幌では、日本地質学会第114年学術大会へ皆様をお迎え
する準備が着々と進んでおります。657件にもおよぶ個人講演やシンポジウム
に加え、教育・普及事業、就職支援プログラム(企業説明会)など、様々な
新たな試みが予定されています。参加者数もここ数年では最大規模になる
ことが予想されています。地質学の重要性が見直されつつある社会風潮の
なかで、皆様の最新の成果や話題提供など有意義な討論がなされますことを
心よりお願い申し上げます。皆様のお越しをお待ち申し上げます。
札幌大会実行委員長 岡田 尚武
■緊急PDプログラム公開:我が国の防災立地に対する地球科学からの提言-平成19年新潟県中越沖地震にあたって-
主催:日本地質学会理事会、同構造地質専門部会
日時:9月10日午後6時〜9時
場所:日本地質学会第114年学術大会 N2会場
1)挨拶と趣旨説明 木村 学 日本地質学会会長
2)地震・災害の状況と地震震源断層等に関する報告
1.(独)防災科学技術研究所 青井 真
2.日本地質学会緊急調査団 小林健太(新潟大学)
3.東京大学地震研究所 佐藤比呂志
4.国土地理院 飛田幹男
5.(独)産業技術総合研究所 杉山雄一
3)国の安全審査の現状 佃 栄吉 日本地質学会副会長
4)今後の防災立地に向けて(パネルディスカッション)
1.京都大学防災研究所 飯尾能久
2.(独)防災科学技術研究所 青井 真
3.東京大学地震研究所 佐藤比呂志
4.国土地理院 飛田幹男
5.(独)産業技術総合研究所 杉山雄一
6.日本地質学会災害委員会 天野一男
7.日本地質学会構造地質専門部会 高木秀雄
モデレーター 伊藤谷生 日本地質学会副会長
5)終わりの挨拶 高木秀雄 日本地質学会構造地質専門部会長
ページTOPにもどる
■ 札幌大会就職支援プログラム 開催!!
卒業後就職を考えている学生諸君,ならびに多くの学生を指導していらっしゃる
先生方を対象に,年会前日の午後からのプログラムとして企画いたしました.
地球科学関連の知識・技術をベースに、社会基盤整備に関わる調査・計画・設計・施工・維持管理、ソフトウェアやハードウェアの開発、および資源開発などを行う企業の紹介いたします.ぜひ多くの方の参加をお待ちしております.
日程 2007年9月8日(土) 13〜17時まで
場所 北海道大学札幌キャンパス,高等教育機能開発総合センターE214・E218会場
協賛 全国地質調査業協会連合会
参加企業 (株)日さく・(株)ニュージェック・応用地質(株)・国際航業(株)
石油資源開発(株)・北海道土質コンサルタント(株)・(株)ジーエスアイ
■ 院生・学生の皆さん 懇親会で会いましょう!
懇親会への多数の参加申し込みどうもありがとうございます! 皆さまとお
会いし,交流できることを楽しみにしております.交流を広げる機会ですの
でまだ参加申し込みしていない方も当日参加お待ちしております!!
(針金由美子 院生評議員)
■ 地質情報展の日程に注意!
今年の地質情報展の開催日は9月7日(金)〜9日(日)です.
札幌大会の初日9月9日(日)が最終日です.
今年は,北海道大学クラーク会館(メイン)と札幌駅サテライトの2カ所開催.
地質情報展2007北海道−探検!熱くゆたかなぼくらの大地−
会場:北海道大学クラーク会館(9:00〜17:00)・札幌駅サテライト(9:00〜18:00)
http://www.gsj.jp/Info/event/2007/johoten_2007/
■ ぞくぞくメディアに登場しています!
<北海道新聞>
8月30日(木)夕刊1面(学術講演 重野 他の内容)
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/environment/46561.php
<北海道建設新聞>
http://e-kensin.net/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=1351ページTOPにもどる
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】プログラム一部訂正
──────────────────────────────────
ニュース誌8月号掲載の札幌大会口頭発表プログラムの中で、一部
発表時間の記載に誤りがありましたので、訂正致します。
正しくは下記の通りです。
■定番セッション:岩石・鉱物の破壊と変形
9月9日(日) 9:00-15:00 E301会場
O-124 9:00 熱水・天水の変質作用を受けた断層岩中の破砕粒子の特徴
滝沢 茂・小澤佳奈
O-125 9:15 異なる粉砕機構で粉砕した黒雲母・石英粒子の形状特徴
小澤佳奈・滝沢 茂
O-126 9:30 石英圧痕周辺の残留超高応力
増田俊明・三宅智也・榎並正樹
O-127 9:45 硬い粒子と柔らかい粒子が混在している岩石の弾性変形について
阪口 秀・坂口有人
O-128 10:00 カルサイト双晶密度による岩石の応力解放後の見かけ弾性歪み推定法
坂口有人・阪口 秀・中谷正夫・吉田慎吾
ページTOPにもどる
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】 コラム 「間違いだらけの発音選び」
──────────────────────────────────
■ 筆者は,かつて「間違いだらけの発音選び」なる内容の一文を,地質学
雑誌のニュース誌に投稿したが,反響はほとんどなかった。その後も,内外
の学会やシンポジウムで,気になる発音や使用法に気を止めていたが,一向
に改善の兆しが見られない。著名な研究者が,間違い発音を繰り返すので,
学生や若手が,直そうとしないのは,当たり前である。最近でも,日本人若
手研究者の大発見の記者会見で,某著名な研究者が,正しい発音を使うよう
にとの意図は,某官庁の指示で,実現されなかったという。それは,
lithosphereを正しくリソスフィアと使うことが,認められなかったのである。
「間違い発音を使え」と,国家が統制しているのである。
以下,若干の重複をおそれず,この際,皆様に今一度ご一考願いたい。
最初に,教訓。
1.ほとんどの英語の用語が間違って発音されている。
2.しかも,その多くが,外来語化されてしまっており,修正はもはや困難か
とも思われるが,間違い発音を使わざるを得ない場合でも,少なくとも,
間違い発音が,正しい英語発音ではないと承知の上で,使うべきである。
3.どんな発音も辞書にあたるべきである。しかし,辞書に載っていない場合や,
英語使用研究者間でも,各種の発音が入り乱れている場合もある。たとえば,
著名な研究者である某Moore氏は,自分の名前は,ムーアではなく,モーアで
ある。と言っている。そうなのであろう。
4.日本語文の中で,日本で慣用とされている発音をカタカナ表記で使用する場
合があろうが,あまりにも間違った発音を使うのは,考え物である。たとえ
外来語化していようとも,使うべきではない。たとえば,reservoirを
リザーバーとする類である。(正しくは,レザヴォア,アクセントはレにある)
5.少なくとも,英語で発表する講演やポスターでの説明には,心して,正しい
発音,正しいアクセントを使うように心がけたい。
ページTOPにもどる
例
スペリング
1.Lithosphere
2.Reservoir
3.Seismic
4.Trough
5.Southampton
6.Frontier
7. Stratigraphy
8.Microbial
9.Oceanic
10.Review
間違い発音
リソスフェア
リザーバー
サイスミック
トラフ
サザンプトン
フろンティア
マイクロバイアル
おシアニック
レビュー
より好ましい発音(アクセントをひらがなで表記)
リソスふぃア
れザヴォア
さイズミック
(ただし,Seismicityは、サイズみシティー)
トろフ
サウさンプトン
フロンてぃア (アクセントは てぃ)
ストラてぃグラフィー
(アクセントは てぃ にある!ただし,
形容詞では,グらフィックの ら にある)
マイクろうビアル (アクセントは ろう)
オシあニック (アクセントは あ)
動詞も名詞もアクセントはビューにある。
あまりにも簡単な言葉に関しては,辞書を引かないことが多いが,すべてあた
るべきである。これは,ホノルルなどのアクセントにも当てはまる。成田のア
ナウンスでも,英語なのにもかかわらず,平板なホノルルと発音していた。お
かしいと思う。ただし,地名,人名は,一般にどう発音していいか,分からな
いことが多く,いちいちあたる必要がある。しかも,人,場所によって異なる。
小川勇二郎(筑波大)
次号につづく。
ページTOPにもどる
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】 同志社大学工学部 環境システム学科専任教員公募(10/10締切)
──────────────────────────────────
募集人員 教授または准教授 1名
専門分野 地域環境学(都市環境,気候学,環境変遷学,地理情報システムや
遠隔探査などを含む).特に,グローバルな変動に対し,特定地域の環境につい
ての教育と研究を行う.
担当予定科目 地域環境学,都市環境学,環境システム基礎実験,環境システム
応用実験,卒業論文など.学部初年度生を対象とした地球環境科学,プログラ
ミング,物理学などの専門基礎科目,全学共通教養教育科目を分担していただく
ことがあります.
応募資格 博士の学位を有し,専門分野において優れた研究業績があり,学部の教育に熱意を持つ,着任時49歳までの方.
着任時期 2008年4月1日
提出書類
履歴書(写真添付)/研究業績一覧(著書,学術論文,国際会議論文,その他)/
主要論文の別刷り(10編以内)/着任後の教育と研究に関わる抱負(A4用紙2枚程度)
/推薦書,または本人について所見を求めることができる方の氏名と連絡先
応募締切 2007年10月10日(水)必着
書類送付・問い合わせ先
〒610-0321
京田辺市多々羅都谷1-3
同志社大学工学部環境システム学科
教務主任 林田 明
Tel:0774-65-6680,E-mail:ahay@mail.doshisha.ac.jp
その他
応募書類は簡易書留とし,「環境システム学科教員応募書類在中」
と朱書してください.
審査後,応募書類の返却を希望される方は,郵便番号・住所・氏名を記載し,
郵便切手を貼った返信用封筒を同封してください.
ページTOPにもどる
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】 JABEE講習会のご案内(10/13 開催)
──────────────────────────────────
JABEE地球資源分野では下記のような講習会を計画しています.
JABEEへの理解を深めていただくためにも一人でも多くの会員の方に参加いただきたいと存じます.
今後認定申請を予定されているプログラム所属の方にも,ぜひ参加をお願いいたします.
ご希望の方は,日本地質学会JABEE委員会委員長の天野(kazuo@mx.ibaraki.ac.jp)に,9月18日午後5時までに申し込んでください.
なお,この講習会に参加するとJABEEの認定審査のオブザーバー参加資格が得られます.地質学会では,JABEEの審査員の資格を持った方は非常に少数です.地質学会としてJABEEを盛り上げていくためにも,審査員候補者を増やしていくことが必要です.
この意味でも,関心のある方には参加をお願いいたします.本講習会参加実績の賞味期限は5年間となっており,以前受講された方々も,是非,再度受講していただきたいと存じております.
開催日時: 10月13日(土),9:30〜18:00(詳細未定)
開催場所: 早稲田大学理工学部62号館E棟1階中会議室
(http://www.sci.waseda.ac.jp/campus/index.html)
プログラム等の詳細は追ってご連絡させていただきます.
ページTOPにもどる
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】 院生評議員・代議員より「博士の将来」アンケート作成中
──────────────────────────────────
現在作成中ですが,博士の将来についての意識調査を行いたいと思っておりま
す.完成次第,メールマガジンなどを通して改めて連絡致しますので皆さまご
協力お願いします!
質問・意見はどんどん受け付けますので院生評議員・代議員へ申し出てくださ
い.よろしくお願いします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】9月9日(日)新HP公開(予定)!!
──────────────────────────────────
インターネット委員会を中心として、地質学会の新ホームページを立ち上げるべく
作業がすすめられてきましたが,ついに9月9日(日)に現HPから新HPに移行されます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.010 2007.09/18 geo-Flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬【geo-Flash】日本地質学会メールマガジン ┴┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.010 2007/09/18 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】「ちきゅう」による南海トラフ掘削開始間近!
【2】月周回衛星「かぐや(SELENE)」による地質調査
【3】日本初の天然ダイアモンド発見!
【4】地学教育公開授業
【5】日高山脈地質くらぶ"千栄の家"存続にご協力を!
【6】コラム「間違いだらけの発音選び」その2(全3回)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「ちきゅう」による掘削開始間近!
──────────────────────────────────
■ 南海トラフ地震発生帯掘削計画(NanTroSEIZE: Nankai Trough
Seismogenic Zone Experiment なんとろさいず)は、いよいよ「ちきゅう」
を用いたIODP (Integrated Ocean Drilling Program: 統合国際深海掘削計画)
の計画として、9月21日に和歌山県新宮港を出港し、掘削を開始します。
「ちきゅう」は来年2月5日まで無寄港で掘削作業を続ける予定で、その間
3つのエクスペディション(研究航海)が予定されています。
10年以上にわたる科学計画の立案から実施までの集大成の幕開けです。
「ちきゅう」による掘削は、最終的にプレート境界の巨大地震発生帯まで掘削
するにはまだ数年はかかる予定だそうですが、壮大な地球科学プロジェクトの
開始であります。詳しくは、、、
http://www.jamstec.go.jp/chikyu/jp/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】月周回衛星「かぐや(SELENE)」による地質調査
──────────────────────────────────
先週,種子島からH-IIロケットにより,月周回衛星「かぐや(SELENE)」が打ち
上げられた.このプロジェクトの地質学との関わりについて,簡単に紹介する.
この探査機は,月の両極の上空を通る,高度約100kmの軌道を約1年間にわたっ
て周回するリモートセンシング衛星であり,多種類かつ詳細なグローバルマッ
ピングをすることが,「かぐや」のスローガンである.それにより,月の起源
と進化にせまる.
地質学的に興味深い研究対象が,月にはいろいろある.衛星とはいえ,月は半
径が約1700kmと,ガス惑星を除き,太陽系では地面のある天体のうち,比較的
大きな部類に属する.そのため,インパクト・クレータリングなどの外的地質
過程はもちろん,テクトニクス・火成活動・風化・侵食・堆積というように,
様々な地質過程を経験している.そしてそれらの産物が,多様な地質体として
残されている.しかし,内的過程を駆動した熱源が地球ほど多くなかったため,
表層の地質を改編する主要な活動は,20〜30億年前にほぼ終息した.そして,
地球ほど速やかな侵食は起こらないため,地球でいえば太古代の様々な情報を,
月面あるいは表層地質から読み取ることができる.マグマオーシャンや隕石重
爆撃の時代は,地球型惑星の最初期の重要な時代であるが,それらの地質学的
な手がかりが地球ではおおかた消去されているのに対し,月では表層地質や地
形にそれが残されている.月はロゼッタストーンなり,というわけである.ま
た,多様な地質過程があったとはいえ,月は地球に比べれば単純な系であり,
表層地質からも,グローバルな応力場変遷やその原因としてのグローバル熱史,
そしてまた月・地球系の起源や軌道進化について,制約を与えることができる
ものと期待されている.また,ジャイアント・インパクト説が正しかったかど
うか,正しかったとすればどんな様子だったのか,というたぐいの問題につい
てである.詳しくは地質学論集第50号の拙文をご覧いただきたい.
「かぐや」は月周回軌道に入って定常的周回軌道を目指して徐々に高度を落と
し,10月後半頃から本格的観測を開始する予定である.1年間の観測期間の後,
データは順次公開されることになっている.それには,地質学者が扱うべきも
のが大量に含まれている.詳しくは適宜,宇宙航空研究開発機構(JAXA)のホー
ムページに掲示されるはずである.
山路 敦 (京都大学)/ 山口 靖(名古屋大学)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本初の天然ダイアモンド発見プレス発表報告
──────────────────────────────────
■ ご存知の方もお多いと思いますが、札幌大会直前でしたが本件のプレス
発表を行いました。大きな反響を巻き起こしましたが、今後学術的な検討
が進むことと、露頭の保護や、天然ダイアモンドの存在する意義の社会教育
など、学会として社会に発信していかなければならないことなど、おおくの
問題が提起されました。地質学の面白さや、重要さに触れてもらう需要な機
会を作ってくれました。
ちなみに本件のプレス発表後、学会HPには1日で約5万件以上のアクセスが
ありました。これはこれまでのアクセス件数の約1年分に匹敵します。
プレス発表の資料はプレスリリースのページから閲覧できます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地学教育公開授業
──────────────────────────────────
■ 学会内外で地学教育に情熱を注いでこられた阿部国広 会員の研究授業
が9月27日に開催されます。国民の素養としての地学(地球惑星科学教育)
の普及と定着を目指して、関係者の方々のご協力により公開授業として開催
されることになりました。
授業単元は、「流れる水の働き」〜川は平野を作り出す〜(5年)です。参加希望者の方は、下記まで一報ください。日本地球惑星科学連合 教育問題検討委員会 瀧上(takigami.yutaka@nifty.com)詳しくはこちら 詳細資料(PDF)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】日高山脈地質くらぶ"千栄の家"存続にご協力を!
──────────────────────────────────
日高山脈地質くらぶ(くらぶ設立の折には、地質ニュース内においても紹
介.また,日高町による「日高山脈館の運営および調査活動の支援」は地質
学の普及および発展に大きく貢献しているということで、2004年に日本地質
学会として表彰)からのお知らせです.(メルマガ編集部)
みなさまご存知の通り、日高山脈地質くらぶ「千栄の家」は、故・樋掛鉄也
氏の"資金的に苦しい学生・院生たちのへの援助""学生同士の交流""交流の輪
を生かして日高山脈館を一緒に盛り立てていく"という信念のもとに生まれ
ました。日高山脈全域および日高町にかかわる地質帯を調査している若手
研究者のために利用しやすい料金体系を設定し、フィールドの宿舎として、
また若手研究者の支援、交流の促進を目的として運営が行われています。
これまでに200名を越える学生・研究者の利用があり、絶大なる支持と感謝
をいただいてまいりました。運営費(賃料、光熱費、修繕費など)は、すべ
て会費やカンパによって賄われています。これまで、多くの方のご協力をい
ただいて活動を維持してきました。しかし、数年前に大雪のための大幅な修
繕を行なったほか、日高地方へ長期の調査で訪れる研究者が減る傾向もある
ようで、運営費が底をつく勢いです。これまでの数年分の会計報告ファイル
を閲覧希望の方は
hmc@town.hidaka.hokkaido.jp
にご連絡いただければ,添付ファイルでお送りいたします.
今なお、日高に訪れる学生・研究者(とくに若手)は、千栄の家を利用し、
成果を上げています。設立の信念からしましても、若手の研究者が千栄の家
を必要としている限り、ここで千栄の家を閉じるわけにはいきません。そこ
で、これまでご協力いただいてきたみなさまに、重ねましてのお願いです。
千栄の家の運営存続にご協力いただけないでしょうか。「千栄の家」は会員
制となっています。これまで、現地事務局(小野)が直接お会いした方々を
中心に、引き続いての会費納入のお願いをしてきました。毎年1万円の納入を
お願いするのも心苦しいものがありましたので、管理に協力いただいている
会員さんとも協議して『夏のオリンピックイヤーに1万円(つまり4年に1回1
万円)の会費納入をお願いする』形を取ってきました。しかし、会費をいた
だく来年度まで存続し得ない状態に陥っています。オリンピックイヤーにか
ぎらず、会費を受け付けます。また、カンパは一口一万円から受付いたしま
す。ご一報の上、下記口座までお振込下さい。余剰分は次年度以降に繰越し
て使用させていただきます。今後のよりよい運営を目指して;・ご協力やご
利用いただいた方の中でも連絡先(メールアドレス)不明の方が複数いらっ
しゃいますので、連絡先把握につとめます。同じ職場にいらっしゃる方のア
ドレスをお尋ねすることなどが出てくると思いますので、その際はどうぞご
協力お願いいたします。
・9/9から札幌で開かれる地質学会で、PRとカンパの呼びかけを行います。
・これまで数回メールマガジンを流してきましたが、皆様に運営や活動状況
をお伝えしきれる状態ではありませんでした。ホームページの設置も含め
て、情報伝達の方法を検討します。何卒、よろしくお願い申し上げます。
(なお私事ですが、現地事務局の小野は一身上の都合で3月末に退職しまし
た。「千栄の家」の現地事務局は、後任として山脈館に着任した東に一任し
ています。今年以降も運営管理体制は継続していますので、どうぞご安心く
ださい。)
<振込先>
苫小牧信用金庫 日高支店 (普)117494日高山脈地質くらぶ「千栄の家」
小野昌子
(注;担当者名(小野昌子)は9月中旬を目処に変更の予定です。口座番号
は変更ありません。)
<連絡先>
日高山脈館 東 豊土(4月より、小野に代わり着任いたしました。)
〒055-2306 北海道沙流郡日高町本町東1-297-12
電話&FAX 01457-6-9033
hmc@town.hidaka.hokkaido.jp
臼杵(小野)昌子、東 豊土
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】コラム 「間違いだらけの発音選び」その2(全3回)
──────────────────────────────────
その道の研究者が自分の分野名の発音を間違えていることがある。Burial を
バリアル(本当はベリアル),warmingをワーミング(正しくはウォーミン
グ),Neogeneをネオズィーン(正しくはニ(ネ)オジーン;アクセントは
ニ,またジーにも第二アクセントあり),Albianをアルビアン(アクセント
はアにおくべきで,ルにおいてはいけない(ありえない))。schistをスィ
ストなどと発音すると,この人は本当にシストを研究しているのか,と疑わ
れ,低く見られる。Analysisをアナらいシスとする人もいる。アなリシスで
ある。Drill: これは,アクセントはシラブル(母音を含む)にしかないはず
だから,どリルなどと発音するはずはない。アクセントはリ以外考えられな
い。(つくばにあるビルのCreoも,皆 くレオと発音しているが,英語とし
てはありえないのである。日本語の宿命なのであろうか?) (もっともバ
カらしいのは、あるクリニックのCMで、クーリニックとクーにアクセント
をおいているのだ。英語人が、どれほど日本を馬鹿にするかが、わかる。シ
ラブルもない子音にアクセントを置くなんて(また、それがために長音にな
るなんて)、あり得ない中のあり得ない、なのである。正しくは、当然、リ)。
そのほか。日常用語的になっていて,もはや修正が難しいのも多い
が,英語として発音するときは,正しく行うべきである。たとえば,
channelは(チャンネルなどではなく、チャヌルまたはチャヌー(的
に)),acousticはアコ(またはアコー)スティックではなく,アクース
ティック(アクセントはクー;ともかくアクセントのあるシラブルの発音は
正確に,がモットーである)。また,hammockyは はマキ,faciesはファ
シースではなく,フェイシーズである。labelはラベルではなく,レイ
ボー,sampleはサンポー,などのほうが通じやすい。stickerはステッカーで
はなく,スティッカー,digitalはデジタルと新聞、放送、一般に使われてい
るが、ディジトー(デズニーと発音すると、いかにも田舎くさい)。
volunteerはボランティアー(アクセントはティ),matureはともかくメイ
チャーなどではなく,マチュア。また,majorはメジャーリーグなどで使わ
れるが,もちろんメイジャーである。Measureの発音は難しく,メザーとメ
ジャーの間くらいである。
そのほか,思いつくままにあげると,patternは,99%の日本人が,パターン
とターにアクセントを置くが,もちろん,パタンであって,アクセントはパ
である。plumeは,日本でも以前は正しくプルームと書かれていたが,いつ
の日からか,プリュームとされるようになり,岩波も,そう使うことがある
ようである.しかし,これは,イギリスでも,アメリカでも,プルームであ
る。Diameterはダイアミター、アクセントはア(ダイアマター的)。また,
英語と米語の発音の差は,日本人にとっては,気にしていたらきりがなく,
区別して行うこともないとは思うが,彼らは結構気になっているようである。
(差別社会のせいかもしれない)。againは英語ではアゲインだが,米語では
アゲンである。こうした,ちょっとした違いは非常に多い。
小川勇二郎(筑波大)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.011 2007.10/02 geo-Flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬【geo-Flash】日本地質学会メールマガジン ┴┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.011 2007/10/02 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2008年度代議員および役員選挙のお知らせ
【2】博物館イベント情報100連発!(こんなにも!)
【3】「ちきゅう」掘削開始!
【4】院生割引申請受付開始 (毎年更新です。お忘れなく!)
【5】コラム「間違いだらけの発音選び」(最終回)
【6】コラム「2秒であなたは何をします?」
【7】「地質の調査」に関わる研修 受講者募集
【8】日本土地環境学会 2007 年シンポジウム(日本地質学会 協賛)
【9】札幌大会の出版物や忘れ物のお知らせ
【10】女性研究者の星、猿橋勝子氏 逝く。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2008年度代議員および役員選挙のお知らせ
──────────────────────────────────
<<立候補受付期間:2007年10月1日(月)〜10月31日(水)>>
日本地質学会会則ならびに運営細則・選挙細則に基づいて,代議員および役員選挙
を実施いたします.
<会長・副会長・監事および代議員選挙>
<理事選挙>
<評議員選挙>
選挙実施要領・立候補届け書式等、詳しくは、
http://www.geosociety.jp/news/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】博物館イベント情報100連発(生涯教育委員会より)
──────────────────────────────────
■ 2007年10月〜2008年3月までの地学関連行事
全国の博物館で行われている行事のうち,地学関連の行事を地方別に紹介します。
すべての博物館について網羅はできていませんが、今後充実させていきますので、
博物館関係者の方のご協力をいただきたいと思います。
詳しくは、、
http://www.geosociety.jp/name/content0007.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】「ちきゅう」掘削開始!
──────────────────────────────────
■ 地球深部探査船「ちきゅう」は9月21日、16:00に新宮港を
出港しました。毎日の作業の様子や、レポートが報告されています。
http://www.jamstec.go.jp/chikyu/jp/Expedition/NantroSEIZE/exp314.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】院生割引申請受付開始
──────────────────────────────────
■ 日本地質学会では,2001年より会費の院生割引制度が設けられています.
<注意>毎年更新となりますので,今年度の割引を受けている方で,次年度も
該当する方は改めて申請して下さい。詳しくは、、
http://www.geosociety.jp/news/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】コラム「間違いだらけの発音選び」最終回(全3回)
──────────────────────────────────
Quite a few クワイタフュー 「少し」という意味ではない。正しい意味
はmany. また,発音に関しては,ともかくR とLを,きっちりと区別する。L
が文頭にあるときは,極端に舌を突き出す。また,単語の最後にある時は,る,と
いわないようにして,無視する。ジンゴーベー,イーゴー(eagle)などである。
全体的に,私もそうだが,発声方法(あごの動かし方や口,舌などの使い方)が,
英語と日本語では根本的に違うので, physicalな面でもあえて英語的に変えない
と,なかなか通じない。一つの方法は,高い声を出して発音することである。
疲れるが有効である。私が手本としている人は,オウコウチ氏である。あえて
言わせていただく。ただし,彼らは残念ながら,オークチと呼んでいるが。。。
(今度は,彼らに日本語発音を学ばせる番か?)
事項が達成できたかどうかを示すのに,×,○,△は使わないようにする。
(欧米では,Vや×は,yes, OK,できた,済み,などの意味に使われる。
つまり日本の○として使われることが多い。○や△は,めったに使われない。)
話し方の対処療法:和文英訳をしながら頭で文章を作りながら話をすると,
つい硬くなる。Jeremy Leggett氏から教わった話し方は,枕を用意しておき
(たとえば,As far as I know, To tell the truth, In this case, I may sayなど),
それを言っている間に,次の文章を考えるとよい。
福音:日本人の寡黙さ,謙虚さは,美徳でもあろうが,誤解をも招きかねない。
彼らは,くだらないことでも,聞き返したり,一言余計にしゃべったりしている。
また,確認を頻発する。この方が,あとあと面倒にならず,また相手の考えのレベ
ルが相互に分かって,コミュニケーションにはふさわしい。どうであろうか?
(その他;関係ないかもしれないが,かなり気になること:タバコはやめよう。
著名な研究者や教授クラスの方でも,平気でタバコをふかすのが日本の学界である。
恥ずかしさを通り越している。自らの周囲の環境をも守れないのである。)
(おあとがよろしいようで。みなさん,がんばってください。)(以上)
(補遺)
ともかく、新しく外来語になる用語の発音表記には、気をつけるべきである。
責任ある立場にあるのは、放送局, 大新聞、それにリーディング・リサーチャー
特に大学教授である。
小川勇二郎(筑波大)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】2秒であなたは何をしますか?(IODPと緊急地震速報)
─────────────────────────────────────────
■ IODP(統合国際深海掘削計画)南海掘削が科学掘削船「ちきゅう」によって開
始された。現在,IODPにプロポーザルを提出中の「相模湾—房総沖掘削計画
(KAP:関東アスペリティ計画)」も地震発生帯を探ろうとするものだ。本日,10月1日
から,「緊急地震速報」も作動開始である。(緊急地震速報は地震の発生直後に,
震源に近い地震計でとらえた観測データを解析して震源や地震の規模(マグニ
チュード)を直ちに推定し,これに基づいて各地での主要動の到達時刻や震度を推
定し,可能な限り素早く知らせる情報です。)
地下で地震が発生すると,P波(縦波)とS波(横波)となって,地表を揺らす。S波の
揺れが大きいと,大地震を引き起こすことになる。世界中の地震計のP波とS波の記
録がたくさん蓄積され,地球内部のことが分かってきたことは20世紀以後の人類の
偉業の一つだ。日本の地震学の開祖,大森房吉は,P波とS波の速度から震源地ま
での距離を推測する公式を見出した:
震源までの距離(km) = (P波の平均の速さkm/秒 X S波の平均の速さkm/秒)
/ (P波の平均の速さkm/秒 − S波の平均の速さkm/秒)X( P波が到達した瞬
間からS波の震動までの初期微動の秒数)
ここで,P波の平均の速さを5.5 km/秒,S波の平均の速さを3.3 km/秒と仮定する
と,震源までの距離(km)は,8.25 X 初期微動の秒数 となる(距離が1000km以
内ならあまり誤差はない)。なぜ,震源地がすぐ報道されるのかは,初期微動の秒数
が地震計でただちに読み取れるからである。
関東大震災を引き起こした大正地震は,三浦半島先端部から相模湾北部の地下10km
で発生したと考えられている。横浜からは約15km,東京中心部からは約65kmの距
離である。
同じ場所で地震が発生するとしたら,上記,大森の公式から逆算して,東京は7.9秒
(65/8.5)後,横浜は何と1.8秒(15/8.5)後に大地震に見舞われることになる。
「緊急地震速報」があったとき,横浜にいるあなたは2秒間で何が準備できるだろうか?
KAPは,大正地震クラスの巨大地震が何処で発生するか,その地震の巣である「アス
ペリティ」の位置や性質を直接掘削して調べてみようとするプロジェクトである。
巨大地震は本当に繰り返して起きるものか?今後,起きると考えられる巨大地震の位
置は何処か?「緊急地震速報」の活用と,南海掘削や相模房総沖掘削には大きな関
連があるのだろう。
(鈴木宇耕 地球深部探査センター/海洋研究開発機構)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】「地質の調査」に関わる研修 受講者募集
──────────────────────────────────
(独)産総研地質調査総合センターでは、産総研法第11条の四にある「技術指導及
び成果の普及を行うこと」に則り、第2期研究戦略(平成19年度版)地質分野におい
て、「今後は民間コンサルタント会社の技術者を対象とした技術研修」を実施し、
「高度な知識や技術を兼ね備えた外部人材の育成」に重点を置くこととしています。
この方針に沿って、国内随一の公的地質の調査・研究機関である産総研地質調査
総合センターでは、関連業界等における人材の総合的な技術向上をめざし、
1)社会からの人材育成のための要請に的確に答え
2)その育成結果についての技術水準を社会に保証することとします.
具体的には、人材育成の技術研修要請への組織的対応、ならびに地質調査総合
センターが認定する民間研修事業へのカリキュラム編成援助や技術移転自体への
職員の派遣を実施し、認定事業等の修了者に対しては、地質調査総合センター代表
名での修了証の発行と、CPD(技術者継続教育単位)認定を行うこととします。
地質調査総合センターが認定した外部の研修事業は、当総合センターのHPに掲
載します。第1号は地学情報サービス(株) によって10月22日(月)〜26日(金)に
行われます。ふるってご参加ください。
独立行政法人産業技術総合研究所
地質調査情報センター地質調査企画室
斎藤 眞
【基礎コース】
日程: 10月22日(月)〜26日(金) 4泊5日
場所: 千葉県君津市及びその周辺地域
主任講師:徳橋秀一(産総研地圏資源環境研究部門主任研究員)
講師: 滝沢文教(元地質調査所地質部長・応用地質(株)社外顧問・予定)
費用: 13万円(消費税込み)、宿泊代、昼食代は別途精算。現地までの交通費は各自負担。
内容: 地質調査の初心者が、自分の力で地質調査を行い、簡単な地質図が描けるまで。
募集人数: 6名
詳細は以下の通り.
http://www008.upp.so-net.ne.jp/gsis/gykensyu.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】日本土地環境学会 2007 年シンポジウム(日本地質学会 協賛)
──────────────────────────────────
『土壌汚染対策の現状と今後 —法政策と不動産鑑定の視点から—』
日程 2007 年11 月10 日(土) 15:00〜17:00
会場 明治大学和泉校舎 和泉メディア棟 3階 M306 (東京都杉並区永福1-9-1)
シンポジウム参加費:3000円 のところ、協賛学会員は、1000円となります(資料代含む).
詳しくは、 http://www.j-lei.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】札幌大会の出版物や忘れ物のお知らせ
──────────────────────────────────
■ 第114年学術大会(札幌大会)での忘れ物をお預かりしています。
お心当たりのある方は、学会事務局までお問い合わせ下さい。
例えば
・レーザーポインター
・講演要旨
・ノート
■ 札幌大会見学旅行案内書・講演要旨について、わずかですが残部があります。
購入をご希望の方は、お早めに学会事務局までお申し込み下さい。詳しくは、、
http://www.geosociety.jp/news/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】女性研究者の星、猿橋勝子氏 逝く。
──────────────────────────────────
女性研究者の育成にご尽力されてきた猿橋勝子さんがお亡くなりになりました。
女性研究者の育成にどれだけご尽力されたか計り知れません。
ご冥福をお祈り致します。
http://mainichi.jp/select/science/news/20071002k0000m040182000c.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.0012 (臨時)2007/10/5 geo-Flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬【geo-Flash】日本地質学会メールマガジン ┴┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.012 2007/10/05 臨時号 ┬ <*)++<< ┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】討論会 「日本海沿岸褶曲・断層帯の形成・成長と地震活動」開催
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「日本海沿岸褶曲・断層帯の形成・成長と地震活動」
参加申込締切:10月20日
──────────────────────────────────
1995年兵庫県南部地震以降,日本海側で大きな内陸地震が頻発し,甚大な被害 を
もたらしています。また,新潟県中越沖地震では,柏崎刈羽原発が被災しました。
地質学会構造地質部会では,理事会との共催で札幌地質学会での緊急パネルディスカッション
:「我が国の防災立地に対する地球科学からの提言− 平成19年 新潟県中越沖地震にあたって−」
を開催し,原発立地問題とからみ,断層を含む地質構造のより精密な調査が社会的要請として
重要であることが示されました。このPDをキックオフとし,次の企画として,活構造 とから
んだ原発の立地問題を睨みつつ,討論会を新潟大学で開催することになりました.そこで,
構造地質−地震地質専門家として,地質構造や当該地域の活断層に関連する研究をなさっている
方々に声をかけ,下記のようなプログラムを組みました。
つきましては,この討論会に参加,またはこのテーマに関連した発表をなさりたい方は,
10月20日までに下記申し込み欄を送信欄にペーストしていただき,構造地質部会事務局
重松紀生(n.shigematsu@aist.go.jp)宛に電子メールでお申し込み下さい。
また,討論会の時間的制約から,口頭発表は特に希望される方に限り,発表は原則として
ポスターでお願いします。ポスター(50枚まで可能)の掲示可能サイズ(ボード本体)は
112 cm×112 cmです.これに長さ67cmの脚 がついていますので,一枚ものであれば幅112cm,
長さ179cmが上限です(下部はぶらさがりとなります).とくに,院生や学部生,若手の
研究者の参加を大歓迎します。
なお,プログラムの詳細は10月末にお知らせ致します。
会場:新潟大学五十嵐キャンパス・大学院自然科学研究科(管理・共通棟)大会議室
主催:日本地質学会構造地質部会
問い合わせ先:高木秀雄(hideo@waseda.jp)
日程
・11月24日(土) プレ巡検 「新潟堆積盆地の標準層序と活断層」
案内 小林健太 (新潟大学) ・大坪 誠 (産総研) ・栗田裕司 (新潟大学)
JR長岡駅に集合(9時30分の予定:詳細は決定次第連絡します),
貸し切りバスで西へ移動.
鳥越断層の地形と露頭〜中央油帯と海岸付近で標準層序(魚沼・灰爪・西山・椎谷 ・寺泊層)
〜海岸沿いに北上,新潟大へ 夜懇親会(学内の松風会館)
・11月25日(日) 討論会「日本海沿岸褶曲・断層帯の形成・成長と地震活動」
プログラム 9:00〜17:00(12:00〜14:00ポスター発表)の予定
趣旨説明 伊藤谷生(千葉大)
1. 2004中越・2007中越沖地震
(1) 羽越沿岸域の地質構造とその形成史
小林健太(新潟大)新潟地域の地質構造と活断層−中越沖地震に対する影響と反映
立石雅昭(新潟大)北部フォッサマグナ新生界標準層序と地質構造
(2) 地震・測地学的諸データの提示と解釈
酒井慎一(東大地震研究所)・2007年中越沖地震合同余震観測グループ:複雑な2007
年中越沖地震の余震分布
山田泰広(京大)・葛岡成樹(ImageOne社)ほか:中越地域におけるPSInSAR解析に
よる地表変動解析とモデル実験の比較
(3) 地震探査諸成果からみる地殻構造と地震活動
佐藤比呂志・加藤直子(東大地震研究所):日本海沿岸褶曲〜逆断層帯における震源断
層の問題について
岡村行信(産総研):日本海東縁の地質学的歪み集中帯と震源断層
長 郁夫 (産総研):活断層のモデルと大地震連鎖のシミュレーション
2.北陸〜山陰沿岸域の地質構造とその形成史(レビュー)
竹内 章 (富山大)北陸〜北信越の地質構造とその形成史
山本博文(福井大)若狭湾周辺地域の地質構造
沢田順弘(島根大)山陰沿岸域の地殻構造とテクトニクス
3. リフト形成期〜反転期の力学的条件と堆積盆の発達過程
山路 敦(京大)日本海のリフティング
竹下 徹(北大) 大陸地殻のレオロジーに基づく地震再来周期の一つのモデル:
何故,ノーマークの活断層で地震は頻発するのか?
山田泰広(京大):アナログモデル実験による堆積盆発達過程の知見(コメント)
4.地震活動と断層および断層岩
藤本光一郎(東京学芸大学):震源断層掘削研究の成果と到達点:野島断層とチェルン
プ断層を例として
金折裕司(山口大):山口−出雲地震帯と地質断層の再活動性
総合討論 (30分)
***************************************************************************
講演・参加申し込み欄(n.shigematsu@aist.go.jp)宛
---------------------------------------------------------------------------------------------
11月24日(土) 巡検に参加 (する・しない)
懇親会に参加 (する・しない)
11月25日(日) 討論会に参加 (する・しない)
ポスター発表 (する・しない)
講演予定題目:
その他ご希望:
所属:
氏名:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.0013 2007/10/16 geo-Flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┴┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.013 2007/10/16 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2008年度代議員および役員選挙のお知らせ
【2】IYPE(国際惑星地球年)学生コンテスト開催!
【3】天然記念物(地質鉱物編)めぐり
【4】地球惑星科学連合のメールニュースおよびセッション締め切り
【5】「ちきゅう」2地点目掘削中!
【6】信州大学大学院テニュアトラック助教 公募
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2008年度代議員および役員選挙のお知らせ
──────────────────────────────────
<立候補受付期間:2007年10月1日(月)〜10月31日(水)>
<投票期間:2007年11月15日(木)〜12月15日(土)>
日本地質学会会則ならびに運営細則・選挙細則に基づいて,代議員および役員選挙
を実施いたします.
・会長・副会長・監事および代議員選挙
・理事選挙
・評議員選挙
選挙実施要領・立候補届け書式等、詳しくは、、、
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】IYPE(国際惑星地球年)学生コンテストでフランスへ!
──────────────────────────────────
■ 国際惑星地球年日本では、「社会のための地球科学」を掲げる国際惑星地球年の
10テーマに焦点をあてた創造的な作品を募集しています。作品は、エッセイ、
俳句、絵、写真、コミックなど、あなたの得意な方法で表現してください。
優秀な作品の作成者は、来年2月12日〜13 日の2日間にわたりユネスコ本部
(パリ)で開催される IYPE Global Launch Event(国際惑星地球年2008式典)
に招待されます。
詳しくは、、、
https://www.geosociety.jp/news/index.php?page=article&storyid=19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】天然記念物(地質鉱物編)めぐり
──────────────────────────────────
■ われわれは広い意味での地質学の研究に携わっているため、地質学というも
のを身近に感じているが、一般の市民が地質学に触れる機会はほとんどない。本邦
には、国および都道府県が指定した天然記念物があるが、このような天然記念物は
市民が地質学をより身近に感じるための格好の題材であり、地質学野外博物館(佐
藤,1992,地質ニュース435号(5月号))として、活用できたら素晴らしいのではな
いであろうか。 奥平 敬元 (大阪市大)
詳しくは、、、
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】 地球惑星科学連合もメールニュース開始、そしてセッション締め切り
──────────────────────────────────
■ 地球惑星科学連合メールニュースが開始されました。連合の一翼を担う地質
学会としても注目です。来年度大会に向けてのセッション締め切りが近づいています。
詳しくは、、
http://www.jpgu.org/publication/mailnews/071010.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】「ちきゅう」2地点目掘削中!
──────────────────────────────────
■ 「ちきゅう」がIODP航海として初めて出港してから、もうすぐ1ヶ月に
なります。様々な苦難を乗り越え、今日も掘削を続けています。毎日のレポート
に加え、毎週のまとめ、写真などが掲載されています。
詳しくは、、、
http://www.jamstec.go.jp/chikyu/jp/Expedition/NantroSEIZE/exp314.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】信州大学大学院テニュアトラック助教 公募
──────────────────────────────────
職名および人員 テニュアトラック助教 1名
専門分野 地質学.専門分野のキーワード:フィールド地質学,山岳科学,地殻物質科学
<テニュアトラックとは>本公募により採用される教員には5年の任期が付けられます.
この期間は,優れた研究者・教員への準備期間として位置づけられ,専門分野における研究,
教育の経験を積みます.4年後にテニュア審査が行われ,合格後はテニュア教員(定年65歳)
に採用されます.テニュア後の職位は原則として准教授です.
応募締切: 2007年12月10日 (月) 17時
詳しくは
http://www.wakate-shinshu.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
天然記念物(地質鉱物編)めぐり
◇各地の天然記念物◇
TOP 秋田県編 滋賀県編 京都府編 和歌山県編 福岡県編
天然記念物(地質鉱物編)めぐり
奥平 敬元(大阪市大)
われわれは広い意味での地質学の研究に携わっているため,地質学というものを身近に感じているが,一般の市民が地質学に触れる機会はほとんどない.本邦には,国および都道府県が指定した天然記念物があるが,このような天然記念物は,市民が地質学をより身近に感じるための格好の題材であり,地質学野外博物館(佐藤,1992,地質ニュース435号(5月号))として,活用できたら素晴らしい.
筆者はこのような観点と個人的な興味から,天然記念物(地質鉱物)の現地での現状把握を目的として,フィールドワークを不定期に行なうことにした.今後,随時,そのフィールドワークの結果を報告していく予定である(第1回は滋賀県を予定,取材済み).
なお,書店で手に入る参考資料としては,「日本の天然記念物(6)地質鉱物」(1984年,渡部景隆編,講談社,230p)や「自然紀行 日本の天然記念物」(2003年,講談社,399p)などがある.また,1992年の地質ニュース(5月号,6月号)において,天然記念物特集が組まれているので,興味のある方はこちらも是非参照して頂きたい.
天然記念物(地質鉱物)についての基礎知識を以下にまとめたので,先ずはこちらを読んで頂きたい.
記念物には以下の3つのカテゴリーがある.
(1)貝塚,古墳,都城跡,城跡旧宅等の遺跡で我が国にとって歴史上または学術上価値の高いもの
(2)庭園,橋梁,峡谷,海浜,山岳等の名勝地で我が国にとって芸術上または鑑賞上価値の高いもの
(3)動物,植物及び地質鉱物で我が国にとって学術上価値の高いもの
国は,これらの記念物のうち重要なものをこの種類に従って,「史跡」,「名勝」,「天然記念物」に指定し,これらの保護を図っている.そのうち特に重要なものについては,それぞれ「特別史跡」,「特別名勝」,「特別天然記念物」に指定している(文化庁HPより).
史蹟名勝天然記念物は,文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき,文部科学大臣が指定し,文化庁が所管する.戦前は,史蹟名勝天然記念物保存法(大正8年法律第44号,勅令第499号)により指定されていたが,文化財保護法がこれを引き継いだ.地質鉱物関係では現在(2007年3月1日),222件指定されており,そのうち20件が特別天然記念物である(文化庁HPより).
文部科学省による,地質鉱物での天然記念物・特別天然記念物の指定基準は以下の通りである(昭和26年文化財保護委員会告示第二号).
(1)
岩石,鉱物及び化石の産出状態
(2)
地層の整合及び不整合
(3)
地層の褶曲及び衝上
(4)
生物の働きによる地質現象
(5)
地震断層など地塊運動に関する現象
(6)
洞穴
(7)
岩石の組織
(8)
温泉並びにその沈殿物
(9)
風化及び侵蝕に関する現象
(10)
硫気孔及び火山活動によるもの
(11)
氷雪霜の営力による現象
(12)
特に貴重な岩石,鉱物及び化石の標本
1922年から指定が行なわれているが,1945年までの指定が全体の78%(173件)におよぶ.戦後,指定件数は徐々に減少し,1980年代は10年間で2件しか指定されていない.2000年以降は15件指定され,1990年代以降増加に転じている(図1左).
図1)指定件数の推移(左)と指定基準の分布(右)
指定基準は「(1)岩石,鉱物及び化石の産出状態」が最も多く全体の27%を占め,次に「(9)風化及び侵食に関する現象」(21%),「(6)洞穴」(13%),「(7)岩石の組織」(10%),「(5)地震断層など地塊運動に関する現象」(10%)と続く(図1右).2000年以降も1番多い指定基準は「(1)岩石,鉱物及び化石の産出状態」である.
文化庁HPより各県別にピックアップした天然記念物(地質鉱物)を表として以下に示す.なお,地質・鉱物関係の天然記念物の指定のない都道府県は,北から山形県,茨城県,東京都,大阪府,鹿児島県である.
都道府県
指定年
指定規準#1
#2
#3
#4
市区町村
北海道
昭和新山
1951
10
特別
有珠郡壮瞥町
名寄鈴石
1939
1
7
名寄市緑丘
名寄高師小僧
1939
1
4
名寄市有利里
根室車石
1939
7
根室市花咲港
エゾミカサリュウ化石
1977
12
三笠市幸町立公民館分室
夕張岳の高山植物群落および蛇紋岩メランジュ帯
1996
3
夕張市空知郡南富良野町
オンネトー湯の滝マンガン酸化物生成地
2000
1
4
8
足寄郡足寄町
青森県
仏宇多(仏ヶ浦)
1941
1
9
下北郡佐井村
岩手県
根反の大珪化木
1936
1
特別
二戸郡一戸町
夏油温泉の石灰華
1941
8
特別
北上市和賀町
焼走り溶岩流
1944
5
10
特別
岩手郡西根町
厳美渓
1927
9
一関市厳美町
蛇ヶ崎
1936
4
6
陸前高田市小友町
碁石海岸
1937
4
6
9
11
大船渡市末崎町
岩泉湧窟およびコウモリ
1938
6
下閉伊郡岩泉町
館ヶ崎角岩岩脈
1939
1
7
大船渡市末崎町
崎山の潮吹穴
1939
6
9
宮古市鍬ヶ崎
崎山の蝋燭岩
1939
1
9
宮古市鍬ヶ崎
姉帯小鳥谷根反の珪化木地帯
1941
1
二戸郡一戸町
浪打峠の交叉層
1941
2
二戸郡一戸町
葛根田の大岩屋
1943
6
9
岩手郡雫石町
樋口沢ゴトランド紀化石産地
1957
1
大船渡市日頃市町
安家洞
1975
3
6
下閉伊郡岩泉町
宮城県
鬼首の雌釜および雄釜間歇温泉
1933
8
特別
玉造郡鳴子町
球状閃緑岩
1923
1
白石市白川・犬卒都婆・大鷹沢大町
姉滝
1934
9
仙台市太白区秋保町
小原の材木岩
1934
7
9
白石市小原
歌津館崎の魚竜化石産地および魚竜化石
1975
1
12
本吉郡歌津町
秋田県
玉川温泉の北投石
1922
1
8
特別
仙北郡田沢湖町
■(ジ)状珪石および噴泉塔
1924
1
8
雄勝郡雄勝町
象潟
1934
5
由利郡象潟町
筑紫森岩脈
1938
1
10
河辺郡河辺町
千屋断層
1995
3
5
仙北郡千畑町
鳥海山獅子ヶ鼻湿原植物群落及び新山溶岩流未端崖と湧水群
2001
10
由利郡象潟町
男鹿目潟火山群一ノ目潟
2007
1
10
秋田県男鹿市
山形県
なし
福島県
入水鍾乳洞
1934
6
田村郡滝根町
見彌の大石
1941
1
9
耶麻郡猪苗代町
塔のへつり
1943
1
9
南会津郡下郷町
鹿島神社のペグマタイト岩脈
1966
1
郡山市西田町
茨城県
なし
栃木県
湯沢噴泉塔
1922
8
塩谷郡栗山村
名草の巨石群
1939
1
足利市名草上町
群馬県
浅間山溶岩樹型
1940
2
7
10
特別
吾妻郡嬬恋村
岩神の飛石
1938
1
5
前橋市昭和町
生犬穴
1938
6
多野郡上野村
川原湯岩脈(臥龍岩および昇龍岩)
1934
1
9
吾妻郡長野原町
上野村亀甲石産地
1938
1
7
多野郡上野村
吹割渓ならびに吹割瀑
1938
1
4
9
利根郡利根村
三波石峡
1957
1
群馬県多野郡鬼石町・埼玉県児玉郡神泉村
埼玉県
御岳の鏡岩
1940
1
5
特別
児玉郡神川町
長瀞
1924
1
3
7
9
秩父郡長瀞町・皆野町
千葉県
犬吠埼の白亜紀浅海堆積物
2002
1
2
4
銚子市犬吠埼
木下貝層
2002
1
2
4
印西市大字木下
東京都
なし
神奈川県
諸磯の隆起海岸
1928
5
三浦市三崎町諸磯
新潟県
笹川流
1927
5
9
岩船郡山北町
佐渡小木海岸
1938
1
5
9
佐渡郡小木町
平根崎の波蝕甌甌穴群
1940
9
佐渡郡相川町
清津峡
1941
1
7
9
南魚沼郡湯沢町・中魚沼郡中里村
小滝川硬玉産地
1956
1
糸魚川市小滝
青海川の硬玉産地及び硬玉岩塊
1957
1
12
青海川の硬玉産地及び硬玉岩塊
田代の七ツ釜
1937
7
9
中魚沼郡津南町・中里村
富山県
魚津埋没林
1936
1
5
特別
魚津市釈迦堂
薬師岳の圏谷群
1945
11
特別
上新川郡大山町
飯久保の瓢箪石
1941
1
7
氷見市飯久保
猪谷の背斜・向斜
1941
1
3
婦負郡細入村
横山楡原衝上断層
1941
5
富山県上新川郡大沢野町・富山県婦負郡細入村・岐阜県吉城郡神岡町
立山の山崎圏谷
1945
11
中新川郡立山町
称名滝
1973
9
中新川郡立山町
真川の跡津川断層
2003
3
5
・岐阜県
石川県
岩間の噴泉塔群
1954
8
特別
石川郡尾口村
山科の大桑層化石産地と甌穴
1941
1
9
金沢市山科町
曽々木海岸
1942
1
9
輪島市町野町
手取川流域の珪化木産地
1957
1
石川郡白峰村
福井県
東尋坊
1935
7
9
坂井郡三国町
山梨県
鳴沢溶岩樹型
1929
6
10
特別
南都留郡鳴沢村
富岳風穴
1929
6
西八代郡上九一色村
富士風穴
1929
6
西八代郡上九一色村
本栖風穴
1929
6
西八代郡上九一色村
鳴沢氷穴
1929
6
南都留郡鳴沢村
大室洞穴
1929
6
南都留郡鳴沢村
神座風穴 附 蒲鉾穴および眼鏡穴
1929
6
南都留郡鳴沢村
船津胎内樹型
1929
6
10
南都留郡河口湖町
龍宮洞穴
1929
6
南都留郡足和田村
吉田胎内樹型
1929
6
10
富士吉田市上吉田
雁ノ穴
1932
6
10
富士吉田市上吉田
忍野八海
1934
10
南都留郡忍野村
燕岩岩脈
1934
1
10
甲府市御岳町
新倉の糸魚川—静岡構造線
2001
3
5
南巨摩郡早川町
長野県
白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石
1922
8
特別
南安曇郡安曇村
高瀬渓谷の噴湯丘と球状石灰石
1922
1
7
大町市大字平
渋の地獄谷噴泉
1927
8
下高井郡山ノ内町
中房温泉の膠状珪酸および珪華
1928
7
8
南安曇郡穂高町
横川の蛇石
1940
1
7
上伊那郡辰野町
四阿山の的岩
1940
1
7
小県郡真田町
岐阜県
根尾谷断層
1927
5
特別
本巣郡根尾村
根尾谷の菊花石
1941
1
7
特別
本巣郡根尾村
鬼岩
1934
1
9
可児郡御嵩町・瑞浪市日吉町
傘岩
1934
9
恵那市大井町
美濃の壺石
1934
1
7
土岐市土岐津町土岐口
飛水峡の甌穴群
1961
9
加茂郡七宗町
福地の化石産地
1962
1
吉城郡上宝村
静岡県
湧玉池
1944
10
特別
富士宮市宮町
駒門風穴
1922
6
10
御殿場市駒門
万野風穴
1922
6
10
富士宮市山宮
印野の熔岩隧道
1927
6
10
御殿場市印野
手石の弥陀ノ岩屋
1934
5
6
賀茂郡南伊豆町
地震動の擦痕
1934
5
田方郡伊豆長岡町
丹那断層
1935
5
田方郡函南町
堂ヶ島天窓洞
1935
5
6
9
賀茂郡西伊豆町
白糸ノ滝
1936
9
10
富士宮市原・上井出
愛知県
鳳来寺山
1931
1
7
南設楽郡鳳来町
猿投山の球状花崗岩
1931
1
7
豊田市加納町
阿寺の七滝
1934
1
9
南設楽郡鳳来町
乳岩および乳岩峡
1934
1
6
7
9
南設楽郡鳳来町
馬背岩
1934
1
南設楽郡鳳来町
三重県
熊野の鬼ケ城 附 獅子巖
1935
5
9
熊野市木本町
月出の中央構造線
2002
3
5
飯南郡飯高町
滋賀県
石山寺硅灰石
1922
1
大津市石山寺辺町
綿向山麓の接触変質地帯
1942
7
蒲生郡日野町
鎌掛の屏風岩
1943
1
蒲生郡日野町
別所高師小僧
1944
1
4
蒲生郡日野町
京都府
稗田野の菫青石仮晶
1922
1
7
亀岡市稗田野町
郷村断層
1929
5
京丹後市網野町
東山洪積世植物遺体包含層
1943
1
4
京都市東山区今熊野南日吉町
琴引浜
2007
9
京丹後市網野町
大阪府
なし
兵庫県
玄武洞
1931
7
豊岡市赤石竹栗
觜崎ノ屏風岩
1931
1
10
揖保郡新宮町龍野市神岡町大住寺
但馬御火浦
1934
7
9
美方郡浜坂町・城崎郡香住町
神戸丸山衝上断層
1937
1
3
5
神戸市長田区明泉寺町
鎧袖
1938
1
9
城崎郡香住町
野島断層
1998
5
津名郡北淡町
奈良県
屏風岩、兜岩および鎧岩
1934
1
9
宇陀郡曽爾村
和歌山県
橋杭岩
1924
9
東牟婁郡古座町・西牟婁郡串本町
瀞八丁
1928
1
和歌山県東牟婁郡熊野川町・三重県南牟婁郡紀和町・奈良県吉野郡十津川村
白浜の化石漣痕
1931
1
3
西牟婁郡白浜町
白浜の泥岩岩脈
1931
1
3
西牟婁郡白浜町
高池の虫喰岩
1935
1
9
東牟婁郡古座川町
神島
1935
1
9
田辺市(湾内
門前の大岩
1935
1
日高郡由良町
鳥巣半島の泥岩岩脈
1936
1
7
9
田辺市新庄町
栗栖川亀甲石包含層
1937
1
西牟婁郡中辺路町
古座川の一枚岩
1941
1
東牟婁郡古座川町
鳥取県
浦富海岸
1928
1
5
7
9
岩美郡岩美町
鳥取砂丘
1955
9
鳥取市浜坂岩美郡福部村
島根県
大根島の溶岩隧道
1931
6
10
特別
八束郡八束町
鬼舌振
1927
9
仁多郡仁多町
潜戸
1927
5
9
松江市
立久恵
1927
9
出雲市乙立町
石見畳ヶ浦
1932
1
5
7
9
浜田市国分町
多古の七ツ穴
1932
6
松江市
岩屋寺の切開
1932
9
仁多郡横田町
築島の岩脈
1932
7
9
松江市
隠岐知夫赤壁
1935
1
9
隠岐郡知夫村
大根島第二熔岩隧道
1935
6
10
八束郡八束町
波根西の珪化木
1936
1
大田市久手町波根西
唐音の蛇岩
1936
1
益田市西平原町
隠岐白島海岸
1938
1
9
隠岐郡西郷町
隠岐海苔田ノ鼻
1938
1
9
隠岐郡西郷町
隠岐国賀海岸
1938
6
9
隠岐郡西ノ島町
松代鉱山の霰石産地
1959
1
大田市久利町松代
三瓶小豆原埋没林
2004
1
10
大田市
岡山県
草間の間歇冷泉
1930
10
新見市草間
羅生門
1930
6
9
新見市草間
象岩
1932
9
倉敷市下津井
大賀の押被
1937
3
5
川上郡川上町
白石島の鎧岩
1942
1
9
笠岡市白石島
広島県
船佐・山内逆断層帯
1961
3
高田郡高宮町三次市畠敷町庄原市山内町
久井・矢野の岩海
1964
9
御調郡久井町甲奴郡上下町
押ヶ垰断層帯
1965
5
山県郡戸河内町廿日市市下山大畑
雄橋
1987
5
6
9
比婆郡東城町
山口県
秋芳洞
1922
6
9
特別
美祢郡秋芳町
秋吉台
1961
1
3
6
9
特別
美祢郡秋芳町・美東町
景清穴
1922
6
9
美祢郡美東町
大正洞
1923
6
9
美祢郡美東町
中尾洞
1923
6
9
美祢郡秋芳町
青海島
1926
1
2
3
5
長門市仙崎・通
石柱渓
1926
7
豊浦郡豊田町
俵島
1927
1
7
大津郡油谷町
須佐湾
1928
1
7
阿武郡須佐町
岩屋観音窟
1934
6
7
玖珂郡美川町
万倉の大岩郷
1935
1
9
美祢市伊佐町奥万倉
吉部の大岩郷
1935
1
9
厚狭郡楠町
須佐高山の磁石石
1936
1
阿武郡須佐町
徳島県
阿波の土柱
1934
9
阿波市
宍喰浦の化石漣痕
1979
1
海部郡宍喰町
香川県
屋島
1934
1
10
高松市屋島東町・中町・西町・高松町
円上島の球状ノーライト
1934
1
10
観音寺市伊吹町
絹島および丸亀島
1940
1
6
9
大川郡大内町
鹿浦越のランプロファイヤ岩脈
1942
2
大川郡白鳥町
愛媛県
八釜の甌穴群
1934
9
特別
上浮穴郡柳谷村
砥部衝上断層
1938
1
3
5
伊予郡砥部町
八幡浜市大島のシュードタキライト及び変成岩類
2004
1
5
愛媛県八幡浜市大島
高知県
龍河洞
1934
6
香美郡土佐山田町
唐船島の隆起海岸
1953
5
土佐清水市清水
千尋岬の化石漣痕
1953
1
5
7
土佐清水市三崎
大引割・小引割
1986
3
5
9
高岡郡仁淀村・東津野村
福岡県
長垂の含紅雲母ペグマタイト岩脈
1934
1
7
福岡市西区長垂
千仏鍾乳洞
1935
6
北九州市小倉南区大字新道寺
鷹巣山
1941
9
福岡県田川郡添田町・大分県下毛郡山国町
平尾台
1952
1
6
9
北九州市小倉南区大字新道寺
青龍窟
1962
6
9
京都郡苅田町
芥屋の大門
1966
1
6
9
糸島郡志摩町
水縄断層
1997
5
久留米市山川町
佐賀県
屋形石の七ツ釜
1925
9
唐津市屋形石
八藤丘陵の阿蘇4火砕流堆積物及び埋没林
2004
1
10
佐賀県三養基郡上峰町
長崎県
七釜鍾乳洞
1936
6
西彼杵郡西海町
斑島玉石甌穴
1958
9
北松浦郡小値賀町
平成新山
2004
10
長崎県島原市、南高来郡小浜町
熊本県
妙見浦
1935
5
7
9
天草郡天草町
龍仙島(片島)
1935
1
9
牛深市牛深町
大分県
小半鍾乳洞
1922
6
南海部郡本匠村
風連洞窟
1927
6
大野郡野津町
狩生鍾乳洞
1934
6
佐伯市狩生
耶馬渓猿飛の甌穴群
1935
9
下毛郡山国町
大岩扇山
1935
1
7
玖珠郡玖珠町
姫島の黒曜石産地
2007
1
10
大分県東国東郡姫島村
宮崎県
五箇瀬川峡谷(高千穂峡谷)
1934
9
西臼杵郡高千穂町
関の尾の甌穴
1928
9
都城市関之尾町
七折鍾乳洞
1933
6
西臼杵郡日之影町
青島の隆起海床と奇形波蝕痕
1934
1
5
7
9
宮崎市大字折生迫
柘の滝鍾乳洞
1933
6
西臼杵郡高千穂町
鹿児島県
なし
沖縄県
塩川
1972
9
国頭郡本部町
下地島の通り池
2006
6
7
9
宮古島市
e-フェンスターとは?
みなさまへ
e-フェンスターとは?
フェンスターとは、低角の衝上断層(逆断層)の下盤が浸食作用によって地表に露出している部分を指す地質用語です。地窓もしくはテクトニックウィンドウとも呼ばれ、そこではぽっかりと下位の地質体が顔を出しており、地球深部の様子を垣間見せてくれます。
e-フェンスターは、インターネットにおける地窓になることを願って名付けられました。必要な情報を、的確に見つけられるようにしたいと思います。みなさまの地球を知るための窓になりましたら幸いです。
倉本真一・坂口有人
巡検案内:四国中央部三波川変成岩上昇時の変形構造
四国中央部三波川変成岩上昇時の変形構造
Exhumation-related deformation structures of the Sambagawa metamorphic rocks, central Shikoku,Japan
遅沢壮一1 竹下 徹2八木公史3 石井和彦4
Soichi Osozawa 1, Toru Takeshita 2,Koshi Yagi 3, and Kazuhiko Ishii 4 受付:2006年6月30日
受理:2006年8月18日
1.東北大学大学院理学研究科地学専攻
Department of Earth Sciences, GraduateSchool of Science, Tohoku University, Sendai,980-8578 JapanE-mail: osozawa@mail.tains.tohoku.ac.jp
2.北海道大学大学院理学院自然史科学専攻
Department of Natural History Sciences,Graduate School of Sciences, Sapporo, 060-0810JapanE-mail: takesita@ep.sci.hokudai.ac.jp
3.(株)蒜山地質年代学研究所
Hiruzen Institute for Geology & ChronologyCo. Ltd., Okayama, 703-8248 Japan
4.大阪府立大学大学院理学系研究科物理科学専攻
Department of Physical Science, GraduateSchool of Sceiences, Osaka PrefectureUniversity, Gakuen-cho, Sakai, 599-8531 Japan
概 要
本見学コースでは,三波川変成岩が後退変成作用を受けつつ上昇して来た時に形成された変形構造(D1,D2およびD3時相に形成された構造)を観察する.このうち,著しい東西塑性流動で形成されたD1変形構造と,鉛直の開いた東西方向の褶曲群で特徴付けられるD3変形構造は識別が比較的容易であり,本見学コースで数地点において観察する.一方D2変形構造はこれまで必ずしも明確でなかったが,最近著者らは,その実体や上昇テクトニクスにおける意味を明らかにしつつあり,本見学コースの重要な観察・議論の対象として取り上げる.第1日目では汗見川流域の高度変成岩中に発達する,D2褶曲やスラストおよびデタッチメント正断層が観察の見所となる.第2日目には,中央構造線近傍国領川流域の変形帯で,D2正断層およびそれを転位させるD3褶曲を観察する.ここでは,D2の北北西方向への運動方向を示す石英スリッケンファイバーも観察する.
Key Words
Sambagawa metamorphic rocks, exhumation, extrusion wedge, Asemigawadetachment fault, D2 normal and reverse faults, north and south vergences,D2 asymmetric fold.
地形図
1:25,000「本山」「佐々木連尾山」「別子銅山」
見学コース
[1日目]8:00 高知大(朝倉)正門前集合→伊野IC→大豊IC→本山町早稲田→草原→東浦→桑の川→竜王の淵→竜王林道→さめうら荘(泊)
[2日目]さめうら荘→大豊IC→新居浜IC→新居浜市板の本→渡瀬→足谷川→13:30頃JR新居浜駅→15:30頃高知空港
見学地点
[汗見川](汗見川本流)
Stop 1 本山町早稲田,緑泥石帯.D1およびD2の重複.
Stop 2 本山町草原,ガーネット帯と緑泥石帯境界.D2逆断層境界と,ガーネット帯のD1伸長線構造を曲げる
D2褶曲の逆転翼.(桑ノ川林道)
Stop 3 本山町桑ノ川,灰曹長石−黒雲母帯と曹長石−黒雲母帯境界.角閃石片岩基底付近のD2逆断層境界と南フェルゲンツのD2非対称褶曲群,逆転翼での非対称ブーディン.
Stop 4 本山町桑ノ川,灰曹長石−黒雲母帯.互いに直交する,角閃石片岩のD1伸長線構造とD2細密褶曲.
Stop 5 本山町桑ノ川,灰曹長石−黒雲母帯.D2の汗見川デタッチメント断層と構成するアクチノライト片岩.
(汗見川本流)
Stop 6 本山町汗見川,曹長石−黒雲母帯.南フェルゲンツのD2非対称褶曲に参加するアクチノライト片岩.
Stop 7 本山町汗見川,曹長石−黒雲母帯.南フェルゲンツのD2非対称褶曲の逆転翼に生じたD2逆断層.
Stop 8 本山町汗見川,灰曹長石−黒雲母帯(角閃石片岩)と曹長石−黒雲母帯境界のD2逆断層.Stop 3の東方延長.
Stop 9 本山町汗見川,汗見川デタッチメント断層より北側の灰曹長石−黒雲母帯.北フェルゲンツのD2非対称褶曲.(竜王林道)
Stop 10 本山町竜王林道,汗見川デタッチメント断層より北側の灰曹長石−黒雲母帯.北フェルゲンツのD2非対称キンク褶曲.
Stop 11 本山町竜王林道,灰曹長石−黒雲母帯と曹長石−黒雲母帯境界.D2の汗見川デタッチメント断層と構成する,アクチノライト片岩.Stop 5の東方延長.
Stop 12 本山町竜王林道,汗見川デタッチメント断層より南側の灰曹長石−黒雲母帯.角閃石片岩の南フェルゲンツのD2非対称褶曲と,角閃石片岩を限るD4横ずれ断層.
(汗見川本流)
Stop 13(オプション)本山町汗見川,汗見川デタッチメント断層より北側の曹長石−黒雲母帯と灰曹長石黒雲母帯のD2正断層境界.
(佐々連尾山林道)
Stop 14(オプション)本山町佐々連尾山林道,汗見川デタッチメント断層より北側の曹長石−黒雲母帯.北フェルゲンツの非対称褶曲を伴う正断層とチャート外来岩塊.[国領川]
Stop 15 新居浜市板ノ本国領川河床,D2正断層,運動方向およびD3褶曲(その1).
Stop 16 新居浜市渡瀬国領川河床,D2正断層,運動方向およびD3褶曲(その2).
Stop 17 新居浜市足谷川,東平緑れん石角閃岩中に発達するD1褶曲.
1.はじめに
第1図.四国中央部三波川帯地質図(東野, 1990)と汗見川および国領川セクションの位置図.
第2図.逆転温度構造を説明する既存の3モデルとウェッジエクストルージョンモデル.
四国中央部の三波川変成岩(第1図)のエクスヒュームプロセスについては,逆転温度構造の成因が関連していようことは予想されていたが(Wallis, 1998),その成因には諸説があり,確定していなかった.逆転温度構造は,これまで,横臥褶曲(Banno et al., 1978)か,ナップの集積(スラスティング;Hara et al., 1992)で説明されている(第2図).
横臥褶曲については,褶曲が南に閉じている(Bannoet al., 1978)と北に閉じている(Wallis et al., 1992)の2説がある.Banno et al.(1978)の南に閉じた横臥褶曲は,そもそも逆転温度構造を説明するために考えられたモデルであり,それ以外に根拠があった訳では無い.一方, Wallis et al.(1992)の北に閉じた横臥褶曲は,温度構造の中軸部を挟んで,南北での褶曲のフェルゲンツの相違に基づいており,それなりに構造地質学的根拠のある,より妥当なモデルと思われる.しかし,Wallis(1990)以来,D1時相の東西伸張・剪断と,東西方向の露頭規模の褶曲は同時形成とされているので,地質図規模の大褶曲である横臥褶曲もこれらと同時の形成ということになる.つまり,横臥褶曲は西に閉じた巨大なシース褶曲の南北断面を観察していると見なし得るが,運動方向やエクスヒューメイションとの関連を含めた,これらについての議論は無く,疑問の余地が残されている.つまり,微小構造の研究は数多いが,それと中〜大構造との関連,あるいは中〜大構造自体の検討が不十分と思われた.
一方,Hara et al.(1992)のナップについては,肝心のナップ境界(鉱物帯の境界)の逆断層の記載が無く,その点で不十分なモデルであり,Wallis(1998)などでも疑問視される一因となっている.さらに,Hara et al.(1992)の述べる主要なナップ境界は,上昇するより高度の変成岩類が,沈み込むより低度の変成岩類と接合する際に出来たとされるものであり(例えば彼らのTable 2),D1時相に形成された.一方,本見学旅行の主題となるD2は東西流動(D1)後に形成された,南フェルゲンツの横臥褶曲・ナップあるいはスラストで従来定義されていた(例えばFaure, 1983).したがって,D2断層はHara et a(l. 1992)の主要なナップ境界形成後に,それらを切って形成されたことに注意されたい(例えば,D2断層は彼らの大生院メランジュの基底断層,Fig. 15に相当する).つまり,後述するD2スラストあるいは正断層は,Hara et a(l. 1992)のナップ境界とは異なる断層である.
Kawachi(1968)の汗見川セクションにおける大構造(スラスト等)の推定は,後述するD2大構造を構造地質学的に推定した先駆的な研究であった.しかし,本案内書で遅沢が提唱するD2大構造(後述)は,主要な褶曲軸や断層の位置が彼のものと異なる.
第3図.汗見川セクションの地質図および見学地点位置図(左)と地質断面図(右;ウェッジエクストルージョンそのものである).
第4図.汗見川セクションにおけるD2の正断層(太線は汗見川デタッチメント断層と鉱物帯境界断層)・逆断層(破線は鉱物帯境界断層)のステレオプロットと,それらを形成した古応力場(およその最大(σ1)および最小(σ3)主応力軸方位が示される).Yamaj(i 2000)の多重逆解法ソフトウェアを使用して作成.
高圧低温型変成岩はウェッジエクストルージョンでエクスヒュームしているという考えがあり(Maruyamaet al., 1996; Wintsch et al., 1999),別子と大歩危ユニットの関係について近年,適用されている(Wallis, 1998).Yagi and Takeshita(2002)およびTakeshita and Yagi(2004)は,エクスヒューム時におけるデタッチメント正断層の重要性を指摘している.汗見川セクションには逆転温度構造のみならず,その上盤側の正常の温度構造も良好に保存されているため,大構造の復元に適しており,ウェッジエクストルージョンを考慮して,精査を進めた.その結果,温度構造の中軸部(灰曹長石−黒雲母帯の軸部)に汗見川デタッチメント断層を見出した(第2, 3図).この断層構成岩は東西に伸張したアクチノライトからなる片岩で,灰曹長石−黒雲母帯に出現すること自体が特異である.さらに,このデタッチメント断層より北側では北フェルゲンツの非対称褶曲を密接に伴う正断層群を,南側では南フェルゲンツの非対称褶曲を密接に伴う逆断層群を見出した(第3図).この南北地域での断層や褶曲の出現様式には,一切の例外は認められなかった.また,各鉱物帯の境界は北側では正断層,南側では逆断層で,これらの関係を露頭で初めて確認した.これらの事実に基づき,遅沢は,第2図に示した様なウェッジエクストルージョンが四国中央部三波川変成岩の高変成度部(別子ユニット)のエクスヒューメーションを説明する最も妥当なモデルであることを提唱する.このモデルが既存のモデルと異なる重要な点は,逆転温度構造がウェッジエクストルージョンによって作られたとする点である.なお,以上の断層・褶曲はエクスヒュームに関連したD2の南北圧縮および伸張応力場で生じており(第4図;ただし,後述するように第2著者の竹下らによって得られたD2正断層形成の応力場はこれと少し異なる),それより先の,片理形成時の,D1の東西性伸張・剪断とは明瞭に区別される.従って,D1とD2が一連とするWallis (1990)の変形時相区分には再検討が必要で,従来通りの原ほか(1977)やFaure(1983,1985)の区分をむしろ踏襲すべきである.変成岩は,地下深部でこそ温度が高いために流動的であるが,地殻上部レベルまで上昇し,温度が低下して来ると,流動的でなくなり簡単に動けなくなる.最近,Beaumont et a(l. 2004)は,ヒマラヤ変成岩の上昇過程の数値モデリングを行い,流動する中部地殻の変成岩が最終的にどのような様式でレオロジカルに硬い上部地殻を突き破って(unroofing)上昇するかについて,様々な可能性(多雨による著しい侵食,上部地殻中の断層形成,変成岩のドーミング等)を示した.以下に述べるように,D2変形は脆性―塑性転移点付近の条件で生じている.そのような脆性―塑性転移点の温度および深度は,三波川変成岩のレオロジーが石英のそれに支配されると仮定し,また,変成場の地温勾配が20℃/km程度であったとすると,約300℃,15kmの上部地殻の基底に相当する条件であったと推察される.したがって,D2褶曲・断層活動はこれまで殆ど注目されることはなかったが,三波川変成岩の最終的な上部地殻への上昇(unroofing)を示す重要な活動であり,Beaumontモデルを検証する材料を提供していると考える.なお,四国中央部の三波川変成岩については実際の所,膨大な数の研究論文が存在するが,本見学旅行案内書でそれらをすべてレヴューする余裕はなく,引用は本見学旅行と関連する研究のみに留めることを御理解いただきたい.
2.地質概説
三波川変成岩はジュラ紀あるいはジュラ紀以前の沈み込み帯で形成された付加体を原岩とする(Isozaki andItaya, 1990; Faure et al., 1991).放射年代に基づくと,四国における三波川変成岩の高変成度部は白亜紀前期(120-110 Ma, Okamoto et al., 2004)にピークの変成作用を被り, 白亜紀後期( 80Ma前後, Itaya andTakasugi, 1988; Takasu and Dallmeyer, 1990)に上部地殻のレベルまで上昇,冷却したと推察される.三波川帯は点紋片岩と呼ばれる斜長石斑状変晶を産する高度変成岩を含む部分があり,四国中央部にはそのような高度変成岩が典型的に露出している.高度変成岩は灰曹長石−黒雲母帯,曹長石−黒雲母帯,ガーネット帯に区分され,周囲を緑泥石帯が取り巻いている(東野,1990;第1図).
本巡検の調査地域の1つである汗見川セクションには, 中軸部に最高変成度部の灰曹長石− 黒雲母帯(T=600℃, P=10 kb, Enami et al., 1994)が位置し,その上・下流,南・北に向かって,順に,曹長石−黒雲母帯,ガーネット帯が分布しており,最も下流域である南側に緑泥石帯の分布がある(第1, 3図).三波川帯のフォリエーションは北傾斜であるので,中軸部より下流・南では,温度構造が逆転していることになる(東野,1990).
汗見川セクションでは,変形時相をD0,D1,D2,D3の4時相に区分した. D0は泥質片岩の斜長石変晶内に鏡下で観察される圧力溶解劈開を曲げる非対称の微小褶曲で,東への一定のフェルゲンツをもっている.この変形時相は三波川帯のピーク変成作用の前に当たり,おそらく沈み込み過程の途中で被った変形を表している.D1は,東西走向の片理,西に向かう剪断を伴う伸長線構造,西に閉じたシース褶曲であり,上昇時の大歪の塑性変形で特徴付けられる時相である.D2は今回発見された汗見川デタッチメント断層と正・逆断層群,これらに密接に伴う北・南フェルゲンツの非対称褶曲群であり,上昇・冷却時に脆性−塑性転移点付近の条件(準緑色片岩相,T=300℃前後)で形成された。D2褶曲はD1片理を曲げていることでそもそも定義されるが,D1伸長線構造も明らかに曲げている.また,D1褶曲の軸面はD1時に晶出した白雲母の底面に当たるのに対し,D2褶曲の軸面は圧力溶解劈開である.さらに以下に述べるアクチノライト片岩の存在もこの区分が妥当であることを示している. D3はD2褶曲や断層を曲げる正立褶曲である(第3図).
温度構造の中軸部は東西から北北西−南南東に延び,汗見川の灰曹長石−黒雲母帯は,別子や本巡検のもう1つの調査地域である国領川セクションのエクロジャイトや灰曹長石−黒雲母帯に連続するものである(第1図;D3の褶曲軸とは無関係).従って,国領川セクションの灰曹長石−黒雲母帯についても,汗見川デタッチメント断層に相当するD2のデタッチメント正断層や逆断層の発見が期待される.国領川セクションや猿田川セクション(第1図)にはD3の強い影響があり,調査は容易では無いが,実際,汗見川デタッチメント断層などを構成するアクチノライト片岩と全く同一岩相の構成岩をもつ正断層が発見されている(Yagi and Takeshita, 2002; 竹下・八木,2003; 本見学旅行案内書).
本見学旅行で主眼となるD2変形は,秀(1972;長浜横臥褶曲),原ほか(1977),塩田(1981;辻ナップ),Faure(1983)などによって記載されて来た.これらの文献に記載されているD2変形は,基本的に南フェルゲンツのスラストやナップ(あるいは横臥・転倒褶曲)である.一方,Hara et a(l. 1992)および原ほか(1995)は,D2(彼らの大洲時相)を三波川メガユニット(パイルナップ構造)の崩壊と位置付け,従来の大洲時相を北に向かう変位成分を持つ正断層運動の生じた早期(辻時階,前述)と南フェルゲンツの構造群の形成を伴う正断層運動の生じた後期(大洲時階)に区分している.また,本見学旅行で観察する国領川の変形帯(Hara et al., 1992の大生院メランジュ帯)は彼らによると辻時階に形成されたとされる.D2については,この様な大構造の記載がある一方,露頭規模の構造(例えばtransposition構造;Hara et al., 1992)の記載は数少ない.本見学旅行では,露頭規模のD2構造が四国中央部三波川高度変成岩類に広く発達することを示す.
なお,汗見川セクションのD2褶曲・断層構造については,遅沢は国際誌に投稿中の論文中の記載や,原図を含む多くの図をほぼそのまま用いて,以下の見学地点を説明している.汗見川デタッチメント断層もその論文で命名・記載されている.一方,第2著者の竹下は,現段階で逆転温度構造がウェッジエクストルージョン(第2図)で作られたとする遅沢のモデルに同意していない.つまり,逆転温度構造がD1横臥褶曲やナップによって形成されたことを否定する根拠は何もないことを指摘しておく.また,現段階では最終的なエクスヒューメーションの様式が,ウェッジエクストルージョンなのか正断層形成によるもの(例えばRing et al., 1999)なのか,判定する根拠に欠けると竹下は考えている.さらに,竹下とその共同研究者はD2正断層について,遅沢とは少し異なる結果を得たので,以下に別項を設けて述べる。
第5図.汗見川流域東岸,白髪―竜王林道沿いの灰曹長石―黒雲母帯中に発達する共役正断層.(a)条線を持つ正断層と条線(矢印)のステレオ投影.(b)断層データ(a)に,Angelier(1979)法を適用して得られた古応力場.PおよびTは圧縮軸および伸張軸の方位を示す.白色部と陰影部は,短縮および伸張領域をそれぞれ示す. Takeshita and Yag(i 2004)から引用
3.D2正断層についての新知見(竹下)
Takeshita and Yag(i 2004)は,汗見川流域の白髪林道および竜王林道の灰曹長石−黒雲母帯に,共役正断層が顕著に発達することを認めた(第5図).共役正断層は,北東―南西ないし東西走向で北傾斜のもの(Group A)と北北西―南南東走向・東傾斜のもの(Group B)から構成される.これらの正断層の一部では条線が明瞭であり,条線の方位(上盤の移動方向)を断層面の方位とともに第5図aに示す.Group AおよびGroup Bの断層は,正断層変位成分のほかに,それぞれかなり大きな左ずれおよび右ずれ変位成分を持っていることがわかる.重要な事実は,断層面の方位はばらつくが,条線の方位は西北西―東南東方向で良く揃っていることである.この断層データについてAngelier(1979)法を用いて古応力場を求めた結果,圧縮軸(P)はこの地域の平均的片理面(N80゜W,30゜N)に垂直な方向に一致し,伸長軸はN60゜W〜S60゜E,水平と求められた(第5図b).
第6図.国領川板ノ本付近のルートマップと片理面極の等面積投影図.等面積投影図には,最適大円(実線)の極(π-axis,褶曲軸)が白丸で示される.数値は,褶曲軸の沈下方向とプランジ角を示す.+印は,露頭で観察される個々の褶曲軸方位を示す.国領川の位置は第1図を見よ.竹下作成.
本地域の岩石は,津根山向斜(汗見川最上流部のD3正立褶曲,第1図)の南翼を構成する.先に述べた圧縮軸方向が片理面に垂直な方向と一致する事実は,正断層は地層が褶曲する前の水平な状態で,鉛直な圧縮軸のもとで形成されたことを示唆するのかもしれない.この考え方が正しいと,正断層はD3褶曲である津根山向斜の形成以前に形成されたD2正断層であると推測される.実際の所,西北西―東南東方向の条線の方位は,中間主応力軸方位とほぼ垂直である(第5図).つまり,圧縮軸が鉛直,中間主応力軸が水平の状態でこれらの共役正断層が形成されたと考える方が,上記した断層面上の横ずれ変位成分が殆どなくなるため合理的である.
新居浜地域の国領川に分布する曹長石(あるいは灰曹長石)−黒雲母帯の泥質片岩は,著しい断層および褶曲運動を被って乱れており,Hara et a(l. 1992)によって大生院メランジュ帯と呼ばれた.先に述べた様に,彼らによると大生院メランジュ帯は,D2の早期(辻時階)に形成されたとされる.我々は最近,国領川においてルートマップを作成する他,詳細な構造解析を行った(El-Fakharani and Takeshita,論文準備中).竹下によって作成されたStop 15,板ノ本付近のルートマップを第6図に示す.この図を見て明らかな様に,D1片理面は多数の断層に切断されているほか(第6図中には主要断層のみ示される),西―東ないし北西―南東方向,西に低角でプランジする軸について波長数10m以内で褶曲している.ここで,断層と褶曲のどちらが先に形成されたかが問題となるが,詳細な構造解析により,断層面が褶曲により転位していることが明らかとなった(竹下,2006; 竹下ほか,2006).この付近の褶曲は,翼が開いた鉛直褶曲であり,D3褶曲と推測される.したがって,断層はD2期に形成されたことになる.また,断層面の方位,断層に沿う地層の変位,および断層面上に観察される石英スリッケンファイバーによって示される岩盤の移動方向から,これらの断層の殆どは正断層であり,かつ,汗見川地域と同様の共役正断層系と判定出来る(El-Fakharani and Takeshita,論文準備中).なお,このD2正断層と先に述べたD2スラスト形成の時間的前後関係は,現段階では明らかではない.
最後に,国領川地域の2ヶ所(板ノ本と渡瀬付近)に発達する断層運動の方向を示す石英スリッケンファイバーの方位を,断層面の方位とともに示す(第7図).石英スリッケンファイバーの方位は,第7図以外に周辺地域も含めて非常に多数のデータが取得出来ている(総数=117条).それらのデータに基づくと,石英スリッケンファイバーの方向は西北西―東南東から北―南方向まで変化するが,北北西―南南東方向が優勢であり,かつ,上盤が北北西に向かう変位が圧倒的に優勢である.したがって,断層は全体として上盤北北西ずれの剪断変形を解消したと考えられる.また,これらの断層データにAngelier(1979)法を適用すると,圧縮軸がほぼ鉛直,伸張軸が北北西―南南東ないし北―南方向・水平という結果が得られた(第7図,およびEl-Fakharani andTakeshita,論文準備中).
第7図.国領川板ノ本および渡瀬付近における(a)断層面と石英スリッケンファイバー(striationと等価)のステレオ投影と,(b)断層解(第5図の説明を見よ).断層データ取得位置は,第6図枠内の位置図を見よ.竹下測定.
4.見学地点
Stop 1 汗見川ルートの緑泥石帯におけるD1およびD2の重複
[地形図]1/2.5万「本山」
[位置]本山町早稲田,緑泥石帯.通称,亀岩の露頭を観察する.汗見川河床に下りるのは容易である.[解説]砂質と泥質片岩中のD1およびD2の重複を観察する.D1片理(S1)は,軸面が東西走向で北に傾斜する,南フェルゲンツのD2褶曲を形成している.D2細密褶曲劈開(S2)は比較的広い間隔で形成されており,そのマイクロリソンやD1との交差線構造の認識は容易である.
Stop 2 ガーネット帯と緑泥石帯境界
[地形図]1/2.5万「本山」
[位置]本山町草原,ガーネット帯と緑泥石帯境界. 小沢に架かる橋の横に駐車スペースがある.北側の別の小沢を登る.一番上の露頭の左部分は緑色片岩の転石であるので,その下方,下流側の断層露頭を観察する.
[解説]D2逆断層境界と,ガーネット帯のD1伸長線構造を曲げるD2褶曲の逆転翼を観察する.Hara et al.(1992)のナップ境界に,明確な境界逆断層の記載は無いが,境界断層の1つとして認定できる.
車を降りた道路沿いの露頭では,緑泥石帯の岩石は紅簾石を産する石英片岩を含んでいる.また,緑泥石帯では例外的な斜長石の変晶が認められる.D2非対称褶曲のフェルゲンツは見かけ上,北であり,これは付近が一次オーダーの南フェルゲンツ非対称褶曲の逆転翼に相当するためである.
第8図.Stop 2.A:逆断層と上盤の逆転翼の非対称褶曲.B:非対称褶曲で曲げられるD1伸長線構造のステレオプロット.
小沢では,石英脈を伴う幅1〜2mの破砕帯が認められ,部分的にガウジを伴い,ガウジの断層面には,断層の走向と直交する条線が観察される(第8図A).
上盤は鏡下でガーネットが確認できる泥質片岩で,軸面がD1フォリエーションより緩くて,また,見かけ上,北フェルゲンツのD2非対称褶曲が認められ,ここでも一次オーダーの非対称褶曲の逆転翼を観察していることになる(第8図A).さらに,褶曲したD1フォリエーション面上には,褶曲軸と高角で交差して褶曲に参加して曲げられているD1伸長線構造が観察される(第8図B).
第9図.Stop 3.A:泥質片岩逆転翼の二次オーダーの非対称褶曲.キンクである.B:泥質片岩内のリーデル剪断を伴う逆断層.C:アクチノライト片岩からなる逆断層.D:逆転翼での石英脈の非対称ブーディン.E:2条の逆断層を含む露頭スケッチ.
Stop 3 灰曹長石−黒雲母帯と曹長石−黒雲母帯境界
[地形図]1/2.5万「本山」
[位置]本山町桑ノ川,灰曹長石−黒雲母帯と曹長石−黒雲母帯境界.桑ノ川林道で,赤滝を見る位置に駐車して,歩く.
[解説]一連の露頭で,角閃石片岩基底付近のD2逆断層境界と南フェルゲンツのD2非対称褶曲群,逆転翼での非対称ブーディンを観察する.
赤滝の滝見台では,泥質片岩中に,D2非対称褶曲の逆転翼に当たる,見かけ上北フェルゲンツの小褶曲が観察される(第9図A).
カーブを曲がった先の小沢には,上盤・下盤とも泥質片岩であるが,幅15cmの剪断帯をもち,下盤との境界にガウジや石英脈を伴う断層が観察される(第9図B,E).剪断帯のリーデル剪断や断層面の傾斜方向にある条線から,逆断層である.なお,D1の伸長線構造は条線と直交した,別の線構造である.次に述べる断層が曹長石−黒雲母帯と灰曹長石−黒雲母帯境界断層であろうが,この断層が境界断層である可能性もある.
10m北方には,別の断層が認められ,断層構成岩はアクチノライト片岩である(第9図C,E).アクチノライトの結晶は細粒であるが,Stop5,6と特にStop 11で述べる粗粒のアクチノライト片岩と,アクチノライトを含むことで共通している.ここの条線も断層面の傾斜方向にプランジしており,これと直交するD1伸長線構造と区別される.下盤は泥質片岩である.一方,上盤は南フェルゲンツの2背斜・1向斜があり,逆転翼には二次オーダーの小褶曲を伴う(第9図E).また,上盤は厚い角閃石片岩であるが,この断層近傍では,上位に泥質片岩を伴っており,共に上記の1背斜・1向斜に参加している(第9図E).なお,この角閃石片岩はTakeshita andYagi(2004)で鍵層として図示されている.
この角閃石片岩は西に向かう林道沿いにずっと露出している.カーブを曲がって南に向かうと,境界断層上盤の逆転翼が再び露出している.この泥質片岩は見かけ上,北フェルゲンツの二次褶曲を伴っているが,非対称の石英脈ブーディンも観察され(第9図D,E),その剪断センスは北落ちで,褶曲の北フェルゲンツと調和的である.この先,境界断層が期待されるが,露頭が欠如している.
第10図.Stop 4.A:D2褶曲の南翼.B:D2細密褶曲軸と直交するD1伸長線構造.C:D2褶曲で曲げられるD1伸長線構造のステレオプロット.
第11図.Stop 5.A:汗見川デタッチメント断層のスケッチ.断層構成岩は主にアクチノライト片岩.B:北フェルゲンツで非対称褶曲した石英脈を含むアクチノライト片岩.C:泥質片岩と共に非対称褶曲したアクチノライト片岩.褶曲した石英脈を含む.
Stop 4 互いに直交する,角閃石片岩のD1伸長線構造とD2細密褶曲
[地形図]1/2.5万「本山」
[位置]本山町桑ノ川,灰曹長石−黒雲母帯.小沢の橋を渡った後,林道カーブに駐車する.[解説]互いに直交する,角閃石片岩のD1伸長線構造とD2細密褶曲が角閃石片岩に観察できる.厚い角閃石片岩は,基底付近で泥質片岩を伴っているが,西方に連続して露出している.角閃石片岩に認められるD1の伸長線構造は,多くの露頭では,D2褶曲軸とほぼ平行で,わずかに斜交しているのが観察される程度である.しかし,Stop4では,南フェルゲンツの非対称褶曲の南翼で,系統的に伸長線構造と褶曲軸がほぼ直交しており,曲げられている(第10図A,B).この褶曲軸は三次オーダーの細密褶曲の軸として認識できる(第10図B).ステレオプロットからも(第10図C),細密褶曲は線構造を曲げていることが分かる.Wallis(1990)はD1とD2を同一時相としているが,このStop 4の例からも,D1とD2は明確に区分されるべき別の変形時相である.
Stop 5 D2の汗見川デタッチメント断層と構成するアクチノライト片岩
[地形図]1/2.5万「本山」(北端は「佐々連尾山」を含む)
[位置]本山町桑ノ川,灰曹長石−黒雲母帯中軸部.谷沿いに土石流〜地滑りがあり,地滑りの北側壁岩を観察する.落石に注意.
[解説]比較的大きな露頭で,D2の汗見川デタッチメント断層と構成するアクチノライト片岩が観察できる.上盤の泥質片岩と断層,断層構成岩からなる露頭である(第11図A).断層は全体として下方に凸な円弧状を呈する(第11図A).断層構成岩は細粒のアクチノライト片岩を主体とするが,粗粒部もあり,また上盤付近には泥質片岩,また石英脈を含んでいる(第11図B,C).これらには,断層直上の泥質片岩を含めて,北フェルゲンツの非対称褶曲が認められる(第11図).断層条線は断層や片理の走向と高角にプランジしているが,低角プランジで,平行なD1伸長線構造と対照的である.上盤の泥質片岩は林道沿いに露出しているが,単に北に緩く傾斜しているのみで,非対称褶曲はここでは認められない.
第12図.Stop 6,7.A:D2非対称褶曲しているアクチノライト片岩.B:一次オーダーのD2非対称褶曲の逆転翼に生じたD2逆断層(アンチセティック).
Stop 6 南フェルゲンツのD2非対称褶曲に参加するアクチノライト片岩
[地形図]1/2.5万「本山」
[位置]本山町汗見川,曹長石−黒雲母帯.竜王の淵,手前の小屋のあるスペースに駐車して戻る.
[解説]南フェルゲンツのD2非対称褶曲に参加するアクチノライト片岩を含む露頭(第12図A).一次オーダーの南フェルゲンツの非対称褶曲が泥質片岩にあるが,その軸部は粗粒のアクチノライト片岩からなっている.アクチノライト片岩は,ここでも,東西方向の鉱物伸長線構造をなしているが,褶曲はこれを曲げて形成されている.この褶曲は,曹長石−黒雲母帯の変成条件から,さらにアクチノライトが生成される条件に温度・圧力が低下した後に生じており,D1とは明確に区別されるD2であることが明らかである.また,D1の間に,三波川帯は既にエクスヒュームを開始していることを意味する.
Stop 7 南フェルゲンツのD2非対称褶曲の逆転翼に生じたD2逆断層(アンチセティック)
[地形図]1/2.5万「本山」
[位置]本山町汗見川,曹長石−黒雲母帯の泥質片岩.道路幅が広い,直線部があり,駐車し,本流に下りる.
[解説]南フェルゲンツのD2非対称褶曲の逆転翼に生じたD2逆断層が観察できる(第12図B).
逆断層はガウジを伴い,面上には,断層の走向に高角な条線とほぼ平行なD1伸長線構造が認められる.逆断層に切られる泥質片岩には,一次オーダーの南フェルゲンツ非対称褶曲の逆転翼に当たっており,二次オーダーの,見かけ上,北フェルゲンツの非対称小褶曲となって逆断層に切られている.
Stop 8 灰曹長石−黒雲母帯(角閃石片岩)と曹長石−黒雲母帯境界のD2逆断層
[地形図]1/2.5万 「佐々連尾山」
[位置]本山町汗見川,灰曹長石−黒雲母帯(角閃石片岩)と曹長石−黒雲母帯境界.竜王林道方面からの枝沢を渡る,大きなヘアピンカーブのある橋の下流側.[解説]Stop 3の東方延長であるD2逆断層が観察される.泥質片岩にある逆断層は厚さ6cmのガウジを伴う厚さ15cmの剪断帯からなり,条線とD1線構造との関係はこれまでと同じである.上盤の泥質片岩には1向斜があり,その南翼で南フェルゲンツの二次褶曲を伴っている.その北翼では,下位に角閃石片岩を伴っていて,さらにヘアピンカーブ側には,南フェルゲンツの一次オーダーの非対称背斜が観察される.Stop 3で観察されるアクチノライト片岩からなる逆断層は,露頭崩壊のため確認できていない.
Stop 9 灰曹長石−黒雲母帯中の北フェルゲンツのD2非対称褶曲
[地形図]1/2.5万「佐々連尾山」
[位置]本山町汗見川,汗見川デタッチメント断層より北側の灰曹長石−黒雲母帯.竜王林道入り口手前.
[解説]北フェルゲンツのD2非対称褶曲.汗見川デタッチメント断層上盤は,下盤と対照的に,北フェルゲンツのD2非対称褶曲で特徴付けられる.そのような褶曲はより上流側に広く認められるが, Stop9でも観察可能である.軸面の傾斜はD1片理より当然ながら緩い.また,しばしば北落ちの正断層を密接に伴っているが,竜王林道入り口の最初のヘアピンカーブでも,このような正断層が観察できる.この正断層は北フェルゲンツの引きずり褶曲を伴う厚さ20cmのフォリエイティドガウジからなっており,条線は北にプランジしている.
第13図.Stop 11.A:鏡下でのD1シース褶曲.軸面に平行に黒雲母の底面が配列するが,黒雲母の全体的な分布が褶曲を定義している.B:アクチノライト片岩からなる汗見川デタッチメント断層.C:北フェルゲンツの非対称褶曲に参加するアクチノライト片岩.D:鏡下でのアクチノライト片岩.黒雲母と緑泥石を伴う
Stop 10 灰曹長石−黒雲母帯中の北フェルゲンツのD2非対称キンク褶曲
[地形図]1/2.5万「佐々連尾山」
[位置]本山町竜王林道,汗見川デタッチメント断層より北側の灰曹長石−黒雲母帯.次のヘアピンカーブを過ぎた沢のところに駐車して歩く.
[解説]北フェルゲンツのD2非対称キンク褶曲.この北フェルゲンツの褶曲は,D2褶曲としては例外的にキンク褶曲である.実際,褶曲面上には,褶曲軸と直交したフレキシュアルスリップによる条線が観察される.
Stop 11 灰曹長石−黒雲母帯内の汗見川デタッチメント断層
[地形図]1/2.5万 「佐々連尾山」
[位置]本山町竜王林道,灰曹長石−黒雲母帯と曹長石−黒雲母帯境界.道路が南から東にカーブする手前で,目印の石積みを通過したところ.[解説]D2の汗見川デタッチメント断層と構成するアクチノライト片岩が観察される.Stop 5の東方延長に当たる.なお,本流の道路沿いでも,汗見川デタッチメント断層は観察可能であるが,金網のため露出不良である.また,ここで,D1シース褶曲(第13図A)の露頭も失われた.
上盤は砂質片岩,下盤は泥質片岩である.断層構成岩であるアクチノライト片岩は厚さ50cmである(第13図B).アクチノライトは粗粒で,c軸は東西であり,D1の伸長線構造をなしている.北プランジの条線をもった剪断面が上盤と下盤境界それぞれと,内部に3条あり,アクチノライトは北フェルゲンツの非対称褶曲に参加している(第13図C).アクチノライト以外にレリックと思われる黒雲母,黒雲母起源の緑泥石が含まれていて(第1表),鏡下では黒雲母にキンクが認められる.条線と平行に切った薄片では,北落ちの非対称剪断構造は認められなかった(第13図D).
第1表.Stop 11,アクチノライト片岩のアクチノライト,黒雲母,緑泥石のEDSでの化学組成.
Stop 12 灰曹長石−黒雲母帯角閃石片岩中の南フェルゲンツのD2非対称褶曲
[地形図]1/2.5万「佐々連尾山」
[位置]本山町竜王林道,汗見川デタッチメント断層より南側の灰曹長石−黒雲母帯.小沢を2つ越えた後の露頭.また,この2つ目の小沢を登る.
[解説]角閃石片岩の南フェルゲンツのD2非対称褶曲と,角閃石片岩を限るD4横ずれ断層が,それぞれ観察される.
2つ目の小沢までは,泥質片岩が露出しているが,この沢を越えると,同じ東西の走向であるにもかかわらず,鍵層の角閃石片岩が現れる.角閃石片岩にはD2の南フェルゲンツの非対称褶曲が複数観察されるが,いずれも軸面はやや曲面であり,軸もやや曲線である.2つ目の小沢には,泥質片岩が露出し,東側の角線石片岩との直接の境界は確認できないが,断層の走向がN45゜,E70゜NW,条線のプランジがS60゜,W35゜SWの横ずれ断層が観察できる.ここでは,この系統の横ずれ断層で,Takeshita and Yagi(2004)が指摘した通り,東方の角閃石片岩の分布が断たれることになる.なお,このような横ずれ断層は,Osozawa(1993)が四万十帯白亜系の牟岐コンプレックスで報告した横ずれ断層に相当し,D4と区分できる.Osozawa(1993)はこの断層を正断層としているが,実際に正断層であることが確実な菜生コンプレックス(本巡検案内書参照)と異なり,圧力溶解劈開を切っていることを指摘しているので,傾動後に活動した横ずれ断層と見なされる.このような横ずれ断層は,共役断層として,小規模であるが,次の大きな枝沢でも観察される.一方,竹下はこれらの方位の断層はGroup Aに属し,片理面と平行の断層と同様に一連のD2正断層と推察している.
Stop 13 曹長石−黒雲母帯と灰曹長石−黒雲母帯のD2正断層境界
[地形図]1/2.5万「佐々連尾山」
[位置]本山町汗見川,汗見川デタッチメント断層より北側の曹長石−黒雲母帯と灰曹長石−黒雲母帯の境界.玉取山林道の汗見川を渡る橋の下の露頭.橋の東側から河床に下りる.渇水期にのみ,徒渉して露頭観察可能.
[解説]境界に当たるD2正断層が観察される.剪断帯は幅1mで,北フェルゲンツの非対称褶曲を伴っている.剪断帯の上下境界はガウジである.条線はここでもD1の伸長線構造と直交している.
Stop 14 曹長石−黒雲母帯中の北フェルゲンツの非対称褶曲を伴う正断層とチャート外来岩塊
[地形図]1/2.5万「佐々連尾山」
[位置]本山町佐々連尾山林道,汗見川デタッチメント断層より北側の曹長石−黒雲母帯.この林道は入り口が荒れており,車の進入不可で,ひたすら歩く.多数の正断層や北フェルゲンツの非対称褶曲が観察される.
[解説]北フェルゲンツの非対称褶曲を伴う正断層とチャート外来岩塊を1つの露頭で観察できる.汗見川デタッチメント断層より北側では,正断層や北フェルゲンツの非対称褶曲を除けば,構造は単純に北に緩く傾動しているに過ぎない.泥質片岩の斜長石変晶には,D0の非対称褶曲が鏡下で明瞭に観察できる.
正断層のガウジは1mmに過ぎないが,北フェルゲンツの非対称褶曲を密接に伴っている.ここでも北プランジの条線は明瞭であるが,付近の露頭では,正断層に北落ちステップ構造も観察される.この露頭の上半分には,厚さ2.5m以下のチャート(珪質片岩)の外来岩塊が泥質片岩に含まれる.つまり初生的な付加体メランジェが保存されている.泥質片岩のD1片理とチャートとの境界,およびチャートの層理面は斜交している.チャート内部にはこれとほぼ直交する節理が認められ,節理はさらに変形している.
Stop 15 国領川ルートにおけるD2正断層,運動方向およびD3褶曲(その1)
[地形図]1/2.5万「別子銅山」
[位置]新居浜市板ノ本付近の国領川河床.
[解説]この地点を構成する泥質片岩は,東野(1990)によると灰曹長石−黒雲母帯に属する.地層は一見ばらばらの方位を向いており,無数の断層によって切られていることが明らかである.この地帯は,Hara et al.(1992)によって大生院メランジュ帯と命名されている.しかし,この様な一見ばらばらな方位を向いている地層(片理面)の走向・傾斜を密な間隔で測定し,ステレオネットに極を投影して見ると,ばらついてはいるが確実に1つの大円に載り,D3褶曲を形成していることがわかる(第6図).橋のすぐ西の右岸に波長20mで,西北西―東南東方向・ほぼ水平の軸を持つ見事なアンチフォームとシンフォームのセットが観察される.この地点では,断層は片理面の走向と平行な西北西―東南東ないし北西―南東走向のものが多い(第6図).ただし,断層に沿う変位のセンスや大きさは殆どわからない.断層の多くは,破砕帯幅の小さい断層であるが,いくつかの断層に沿っては10cm以上の幅の破砕帯が存在し,その様な断層の1つを見学旅行で観察する.その断層に沿っては,蛇紋岩起源と思われるアクチノライト岩がへい入している.さらに,一見四万十帯で良く観察される様なblockin matrixの産状を示す,メランジュ様の破砕帯が存在する.これらの破砕帯は沈み込み過程で出来た付加体特有のメランジュである可能性もあるが,四国中央部三波川帯他地域ではメランジュの存在は知られていないので,やはりD2断層に伴う大規模破砕帯であると解釈している.D2断層が実際に露頭でD3褶曲により曲げられているかどうかは,この見学地点では殆ど判定することが出来ない.さらに,この地点では,ほぼ南北方向の石英スリッケンファイバーが断層面上に観察される.
Stop 16 国領川ルートにおけるD2正断層,運動方向およびD3褶曲(その2)
[地形図]1/2.5万「別子銅山」
[位置]新居浜市渡瀬付近の国領川河床.
[解説]この見学地点もHara et a(l. 1992)の大生院メランジュ帯に属するが,先の見学地点と比較すると地層の乱れの程度は小さい.この地点は曹長石−黒雲母帯(東野, 1990)の砂質片岩および泥質片岩で構成されている.結晶片岩は西北西―東南東ないし北西―南東走向で北に高角で傾斜するが,場合によって逆転して南に高角傾斜する場合もある.Stop 15と同様,多数のD2断層が発達しているが,殆ど東西ないし西北西―東南東走向で北あるいは南に高角傾斜するGroup Aに属する断層である(第5, 7図).これらの断層は,石英スリッケンファイバーの方位,地層のドラッグ,およびマーカー層の変位から,左横ずれ成分を持つ正断層であることが明らかである.石英スリッケンファイバーの方位は,一様に北西―南東ないし北北西―南南東方向である(第7図).露頭の北側には,かなり延性的な東西方向の鉛直褶曲が発達している.この褶曲の形成時相は,鉛直褶曲であることを根拠にD3と推察する.しかし,褶曲している片理面にD2マイクロリソンで認識されるS2面は認められなかったので,D2褶曲である可能性もある.
Stop 17 足谷川における東平緑れん石角閃岩中に発達するD1褶曲
[地形図]1/2.5万「別子銅山」
[位置]新居浜市足谷川右岸を通る旧道横の露頭
[解説]この見学地点はこれまで東平緑れん石角閃岩(変はんれい岩)とマッピングされているが(例えば東野,1990),岩石はかなり珪質であるほか,一部に石灰岩が挟まれる.したがって,原岩ははんれい岩ではなく,付加体の堆積岩であると推察される.同様の観察と解釈は,最近Miyagi and Takasu(2005)でもなされている.露頭では一見して著しい褶曲構造が明瞭である.褶曲は折りたたまれており,測定された褶曲軸面(N71゜W,45゜N)は片理面(N73゜W,50゜N)とほぼ平行である.また,測定された褶曲軸(N69゜E,40゜E)は,線構造方向(N70゜E,27゜E)とほぼ平行である.したがって,片理と同化したこの褶曲はD 1 褶曲である. オーダー(Ramsay, 1967)の異なる褶曲があることにも注意されたい.初日の汗見川流域の灰曹長石―黒雲母帯にもD1褶曲は多数発達するが,今回の見学旅行では本地点でのみD1褶曲を観察する.
文 献
Angelier, J., 1979, Determination of the mean principaldirections of stresses for a given fault population.Tectonophysics, 56, 17-26.
Banno, S., Higashino, T., Otsuki, M., Itaya, T.and Nakajima,T., 1978, Thermal structure of the Sanbagawametamorphic belt in central Shikoku. Jour. Physics of theEarth, 26, 345-356.
Beaumont, C., Jamieson, R. A., Nguyen, M. H. andMedvedev, S., 2004, Crustal channel flow: 1. Numericalmodels with applications to the tectonics of theHimalayan-Tibetan orogen. Jour. Geophys. Res., 109,B06406, doi:10.1029/2003JB002809.
Enami, M., Wallis, S. R. and Banno, Y., 1994, Paragenesis ofsodic pyroxene-bearing quartz schists: implications forP-T history of the Sambagawa belt. Contrib. Mineral.Petrol., 116, 182-198.
Faure, M., 1983, Eastward ductile shear during the earlytectonic phase in the Sanbagawa belt. Jour. Geol. Soc.Japan, 89, 319-329.
Faure, M., 1985, Microtectonic evidence for eastward ductileshear in the Jurassic orogen of SW Japan. Jour. Struct.Geol., 7, 175-186.
Faure, M., Iwasaki, M., Ichikawa, K. and Yao, A., 1991, Thesignificance of Upper Jurassic radiolarians in highpressure metamorphic rocks of SW Japan. Jour.Southeast Asian Earth Sci., 6, 131-136.
原 郁夫・秀 敬・武田賢治・佃 栄吉・徳田 満・塩田次男,1977,三波川帯の造構運動.秀 敬編「三波川帯」,広島大学出版研究会,309-390.
Hara, I., Shiota, T., Hide, K., Kanai, K., Goto, M., Seki, S.,地質雑 112(補遺) 四国中央部三波川変成岩上昇時の変形構造115
Kaikiri, K., Takeda, K., Hayasaka, Y., Miyamoto, T.,Sakurai, Y. and Ohtomo, Y., 1992, Tectonic evolution ofthe Sambagawa schists and its implications in convergentmargin processes. Jour. Sci. Hiroshima University, Ser.C, 9, 495-595.
原 郁夫・塩田次男・秀 敬・武田賢治・竹下 徹・関幸代・金井賢次・榊原信夫・中村夫佐裕・田上雅彦・鈴木靖子・川口小由美・直本啓祐・榎木美奈・
田中健吾,1995, 四国中央部三波川帯の岩石構造とテクトニクス.日本地質学会第102年学術大会 見学旅行案内書,1-29.
秀 敬,1972,四国西部長浜大洲地方三波川変成帯における二つの横臥褶曲構造の発見と意義.広島大教養部紀要,III, 5, 35-51.
東野外志男,1990,四国中央部三波川帯の変成分帯.地質学雑誌,96,703-718.
Isozaki, Y. and Itaya, T., 1990, Chronology of Sanbagawametamorphism. Jour. Metamorphic Geol. 8, 401-411.Itaya, T. and Takasugi, H., 1988, Muscovite K-Ar ages of theSanbagawa schists, Japan and argon depletion duringcooling and deformation. Contri. Mineral.Petrol., 100,281-290.
Kawachi, Y., 1968, Large-scale overturned structure in theSambagawa metamorphic zone in central Shikoku,Japan. Jour. Geol. Soc. Japan, 74, 607-616.Maruyama, S., Liou, J., Terabayashi, M., 1996, Blueschistsand eclogites of the world and their exhumation. Intern.Geol. Review, 38, 485-594.
Miyagi, Y. and Takasu, A., 2005, Prograde eclogites from theTonaru epidote amphibolite mass in the SambagawaMetamorphic Belt, central Shikoku, southwest Japan.Island Arc, 14, 215-235.
Okamoto, K., Shinjoe, H., Katayama, I., Terada, K., Sano, Y.and Johnson, S., 2004, SHRIMP U-Pb dating of quartzbearingeclogite from the Sanbagawa Belt, south-westJapan: implications for metamorphic evolution ofsubducted protolith. Terra Nova, 16, 81-89.
Osozawa, S., 1993, Normal faults in accretionary complexformed at trench-trench-ridge triple junction, as anindicator of angle between the trench and subductedridge. Island Arc, 2, 142-151.
Ramsay, J. G., 1967, Folding and Fracturing of Rocks.McGraw-Hill, Inc., New York, 568p.
Ring, U., Brandon, M. T., Willett, S. D. and Lister, G. S.,1999, Exhumation processes. In Ring, U., Brandon, M.T., Lister, G. S. and Willett, S. (eds) ExhumationProcesses: Normal Faulting, Dductile Flow and ErosionGeol. Society. London, Spec. Publ., 154, 1-27.
塩田次男,1981,四国東部池田−三加茂地方三波川結晶片岩の構造地質学的および岩石学的研究.徳島大学学芸紀要,自然科学,32, 29-65.
Takasu, A. and Dallmeyer, R. D., 1990, 40Ar/39Ar mineralage constraints for the tectonothermal evolution of theSambagawa metamorphic belt, central Shikoku, Japan: aCretaceous accretionary prism. Tectonophysics, 185,111-139.
竹下 徹,2006,四国中央部三波川変成岩黒雲母帯における広域的な上昇時断層活動.日本地球惑星科学連合2006年大会講演要旨.
竹下 徹・八木公史,2003,四国中央部三波川変成岩上昇時の正断層活動.月刊地球, 25, 186-191.
Takeshita, T. and Yagi, K., 2004, Flow patterns duringexhumation of the Sambagawa metamorphic rocks, SWJapan, caused by brittle-ductile, arc parallel extension. In:Grocott, J., MCaffrey, K. J. W., Taylor, G. and Tikoff,B.(eds) Vertical Coupling and Decoupling in theLithosphere, Geol. Soc. London, Spec. Publ., 227, 279-296.
竹下 徹・El-Fakharani,A-H・八木公史,2006,四国中央部三波川変成岩を最終的に上部地殻レベルに上昇させたD2断層活動について:汗見川東方および国領川の黒雲母帯に発達するD2断層の詳細解析.日本地質学会第113年年会講演要旨.
Wallis, S., 1990, The timing of folding and stretching in theSambagawa Belt: the Asemigawa region, centralShikoku. Jour. Geol. Soc. Japan, 96, 345-352.
Wallis, S., 1998, Exhuming the Sanbagawa metamorphic belt:The importance of tectonic discontinuities. Jour.Metamorphic Geol., 16, 83-95.
Wallis, S., Banno, S., and Radvanec, M., 1992. Kinematics,structure and relationship to metamorphism of the eastwestflow in the Sanbagawa Belt, southwest Japan.Island Arc, 1, 176-185.
Wintsch, R. P., Byrne, T. and Toriumi, M., 1999, Exhumationof the Sanbagawa blueschist belt, SW Japan, by lateralflow and extrusion: evidence from structural kinematicsand retrograde P-T-t paths. In: Ring, U., Brandon, M. T.,Lister, G. S. and Willett, S. D. (eds.) ExhumationProcesses: Normal Faulting, Ductile Flow and Erosion.Geol. Soc. London, Spec. Publ., 154, 129-155.
Yagi, K. and Takeshita, T., 2002, Regional variation inexhumation and strain rate of the high-pressureSambagawa metamorphic rocks in central Shikoku,south-west Japan. Jour. Metamorphic Geol., 20, 633-647.
Yamaji, A., 2000, The multiple inverse method: A newtechnique to separate stresses from heterogeneous faultslipdata. Jour. Struct. Geol., 22, 441-452.
本稿は「岩井雅夫・村田明広・吉村康隆,2006,見学旅行案内書,地質学雑誌,112,補講,170pp」がオリジナルです。
■ オリジナルPDFダウンロード(J-Stageサーバー)
No.0014(臨時) 2007/10/26 geo-Flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┴┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.014 2007/10/26 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】札幌大会緊急パネルディスカッション報告UP!
【2】日本学術会議より募集がありました
【3】「日本列島ジオサイト—地質—百選」が出版されました!
【4】2008年連合大会セッション提案締切延長(30日まで)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】札幌大会緊急パネルディスカッションの報告がUPされました!
──────────────────────────────────
■ 札幌大会中に緊急開催されたパネルディスカッション、「わが国の防災
立地に対する地球科学からの提言」(9/10)の開催報告が公表されました。
発表資料も一部公開されていますので、ご覧下さい。なお、資料の引用は、
日本地質学会並びに発表者の許可を得ることが必要です。
またこの会の提言を受けて、討論会(「日本海沿岸褶曲・断層帯の形成・
成長と地震活動」11月24−25日)が開催されますので、是非そちらも
ご覧下さい。
パネルディスカッション報告はこちらから
討論会「日本海沿岸褶曲・断層帯の形成・成長と地震活動」はこちら
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】H19代表派遣会議及び派遣候補者の追加募集(締切間近)
──────────────────────────────────
■ 日本学術会議は代表派遣会議及び代表派遣候補者の追加募集を行っています。
学会からの推薦を受け、代表派遣会議及び代表派遣候補者を次の1)、2)の
基準により検討されます。
1) 国際学術団体の議決を伴う総会、理事等役員会に該当する会議
2) 日本学術会議の活動として代表派遣が必要とされる会議
ご興味のある方は、学会事務局までご連絡願います。学術会議への締切は、
11月2日です。
日本学術会議について知りたい方は、、、
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】「日本列島ジオサイト—地質—百選」が出版されました!
──────────────────────────────────
■ 全国地質調査業協会連合会、地質情報整備・活用機構共編 で、
『日本列島ジオサイトー地質ー百選 』(ISBN : 978-4-274-20460-9)が
オーム社より発行されました。オールカラーの181p、2,940円 (税込)です。
「日本の地質百選」に選定されたジオサイト(全83箇所)について、
その特徴や見どころを解説しています。現場カラー写真を豊富に用いつつ、
地質学的な特質や、見学・観光のための諸情報などを見開き2ページ区切りで
わかりやすくまとめてあります。「地質を学べる博物館、日本の地質百選
現地の博物館・展示施設」も収録してあります。「日本の地質百選」を見て
歩くためのよきガイドブックとなるでしょう。
書店店頭でちょっと変わったガイドブックとして手にとって頂ければ、
地質学の魅力の糸口になると思います。 (矢島道子)
http://ssl.ohmsha.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?ISBN=978-4-274-20460-9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2008年連合大会セッション提案締切延長(10月30日まで)
──────────────────────────────────
■ 2008年連合大会セッション提案の締切が、10月30日(火)、15:00まで
延長されました。
セッション提案の具体的な方法など、詳細につきましては下記をご覧下さい。
大会ホームページ:http://www.jpgu.org/meeting/
セッション提案ページ:http://www.jpgu.org/meeting/program.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
巡検案内:室戸岬,菜生コンプレックスのメランジェと岩脈
室戸岬,菜生コンプレックスのメランジェと岩脈*
Melanges and dikes of the Miocene Nabae complex, MurotoPeninsula, Shikoku, Japan
遅沢壮一
Soichi Osozawa
東北大学大学院理学研究科地学専攻
Department of Earth Sciences, Graduate
School of Science, TohokuUniversity,
Sendai, 980-8578 Japan.
E-mail: osozawa@mail.tains.tohoku.ac.jp
概要
菜生コンプレックスのメランジェと斑糲岩岩脈,四十寺山層の火山岩礫岩.D1劈開に切られる玄武岩岩脈.シース褶曲と斑糲岩シル. D0正断層とD1境界スラスト.D−(マイナス)1とD1劈開をもつチャート岩塊.時間次第で,手結メランジェなどのオプションあり.
Key Words
Nabae complex, melange, asymmetric shear, gabbro and basalt dikes, block in matrix, debris flow, recycle
地形図
1: 25,000 「室戸岬」「佐喜浜」「手結」
見学コース
7:15 JR高知駅前集合→9:00 室戸市街→三津(丸山)海岸→六ガ谷海岸→室戸岬(昼食)→芝碆→石ノ碆→
菜生漁港→室戸市街→行頭岬→大山岬→手結→18:00 JR高知駅前解散.
見学地点
Stop 1 室戸市三津.菜生コンプレックスのメランジェと斑糲岩岩脈,四十寺山層の火山岩礫岩.
Stop 2 室戸市六ヶ谷.D1劈開に切られる玄武岩岩脈.
Stop 3 室戸市室戸岬.シース褶曲と斑糲岩シル.
Stop 4 室戸市津呂芝碆.D0正断層とD1境界スラスト.
Stop 5 室戸市津呂石ノ碆.D−(マイナス)1とD1劈開をもつチャート岩塊.
Stop 6 室戸市佐喜浜町遅越.佐喜浜メランジェ(オプション).
Stop 7 芸西村十代.手結(てい)メランジェ(オプション).
1.はじめに
メランジェはブロックインマトリックス組織を持つ混在岩に対して,むしろ成因を問わない記載用語として用いられている(例えばCowan, 1985).四国四万十帯のメランジェについても,かつては,含有される海洋性岩石が海溝外側斜面から重力崩壊で海溝軸にもたらされたオリストストロームと考えられていた(平ほか,1980a).筆者も,四万十帯を含む奄美大島の付加体を土石流などの地辷り堆積物起源と見なしていた(Osozawa, 1984).しかし,Needham(1987)以来,四万十帯の多くの混在岩から,普遍的かつ一定センスの剪断変形作用が確認されている.剪断は構造的であるので,そのような剪断作用を被った混在岩をテクトニックメランジェとして扱うのが,近年の付加体研究の主流となっている(例えばOnishi and Kimura, 1995).テクトニックメランジェはアンダープレーティングで定置し,デュープレックスをなすと解釈され,この観点に立った研究が進められている(例えばHashimoto and Kimura, 1995).さらに,テクトニックメランジェは地震発生帯に対応する可能性がある岩石とも見なされており,注目されている(例えばIkesawa et al., 2005).そして,最終的には,ブロックインマトリックス組織あるいは混在岩の成因としても,構造的な剪断作用が“想定”されている(例えば脇田,2000).ただし,狩野・村田(1998)や木村(2002)のレビューや,上記のいずれの論文においても,混在岩形成,特に海洋性岩石が基質中に混在するに至った具体的なプロセスが明記されている訳では無い.
第1図.菜生コンプレックスの位置と地質図.Osozawa(1993)のFigs. 1と2による.
第2図.菜生コンプレックス(Stop 1〜5)見学地点の位置図.
菜生コンプレックスは中新統で,四万十帯では最も若い付加コンプレックスの1つであり,また室戸岬の斑礪岩シルが存在するなど,特異な付加コンプレックスである(第1,2図).しかし,菜生コンプレックスに含まれるメランジェは,ブロックインマトリックス組織を持ち,また全域で一定の向きの剪断変形を被っていることから,例えば木村(2002)に従えば,典型的なテクトニックメランジェに当る.
本巡検では,菜生コンプレックスのテクトニックメランジェやブロックインマトリックス組織に関する露頭を観察予定である.観察結果は以下のように要約される.1.中新世に菜生コンプレックスが付加する以前に形成された,別の,より古期の圧力溶解劈開がチャートや砂岩の外来岩塊や岩片内に認められる,2.岩脈は付加に伴う剪断作用が働く以前に貫入しているが,岩脈が被った剪断変位はわずかで,玄武岩など外来岩塊を基質中にもたらすために期待される大きな剪断・断層変位を超え難い,3.土石流堆積物であると1の事実からも判断される地層がメランジェに挟在され,またメランジェは半遠洋性と陸源堆積物との間の層準を占め,いわゆる海洋プレート層序の一部をなしている(Osozawa, 1993).これらの観察結果から,菜生コンプレックスのブロックインマトリックス組織は本来,土石流堆積物の堆積構造で,それ自体にはテクトニックな成因を持たないことが示唆される.また,剪断作用による混在岩化というテクトニックメランジェプロセスを菜生コンプレックスにそのまま適用するのは困難であると思われる.さらに,菜生コンプレックスの海洋性岩石は付加プリズムでのリサイクルの結果,含有されていると考えられる.
菜生コンプレックス以外のいくつかの付加コンプレックスについて,混在岩化は剪断によらないことの,もう1つの理由をあげることができる.それは,剪断作用とブロックインマトリックス組織の有無は互いに無関係であることである.奄美大島の湯湾コンプレックス(Osozawa and Yoshida, 1997)など,ブロックインマトリックス組織をもつにもかかわらず,スレート劈開のみが発達し,剪断を伴わない付加体の例が少なからずある.また,逆に,菜生コンプレックスの岬アセンブレッジもその1例ではあるが,沖縄の名護変成岩など,ブロックインマトリックス組織が無いにもかかわらず,D1の剪断帯をなす例(Schoonover and Osozawa, 2004)が少なからず存在する.
第3図.佐喜浜メランジェ(Stop 6),手結メランジェ(Stop 7)の見学地点位置図.
菜生コンプレックスのメランジェに含まれるチャートや玄武岩の外来岩塊は,佐喜浜メランジェ(平ほか,1980b)に由来する可能性が高く,見学地点6として,記載した.また,上記1の現象は佐喜浜メランジェに加えて,さらに横浪メランジェ(平ほか,1980a)でも観察できた.本巡検ではそれに対比され,四万十帯では著名なメランジェの1つである手結メランジェ(平ほか,1980a)についてもオプションとして見学地点7に加えている(以上,第3図).
2.地質概説(菜生コンプレックス)
四国室戸半島の先端は室戸岬である.菜生コンプレックスは室戸岬一帯に分布しており,第三系が分布する四万十帯南帯の南縁を占めている(第1図).菜生コンプレックスの年代は,四万十帯でも最も新期である中新統である(平ほか,1980b).
菜生コンプレックスは,Hibbard et al.(1992)により,北西側から南東側に,日沖メランジェ,津呂アセンブレッジ,坂本メランジェ,岬アセンブレッジに区分されている(第1図).いずれのメランジェも下位側に半遠洋性泥岩を伴っている(Osozawa,1993).津呂アセンブレッジは下位の半遠洋性泥岩と上位の砂岩泥岩互層であるタービダイトからなっているが,これらの境界部にコンタクトメランジェ(Hibbard et al., 1992)が挟まれている.岬アセンブレッジはタービダイトであるが,これも基底に半遠洋性泥岩を伴っている.以上を貫いて斑糲岩と玄武岩のシルや岩脈があり,Hibbard et al.(1992)により丸山貫入スウィートと呼ばれている.日沖メランジェは,さらに前弧盆堆積物としての四十寺山層に覆われている(Hibbard et al., 1992).
変形時相をD−(マイナス)1,D0,D1,D2,D3の5時相に区分した.D−1はメランジェのチャート岩塊や砂岩岩塊内に限って認められる圧力溶解劈開である.D0は正断層で,斑糲岩や玄武岩岩脈の正断層に沿う貫入を含める.D1は圧力溶解劈開で,整然層,メランジェとも非対称褶曲の軸面劈開となっている.メランジェに認められるスラストで,右ずれセンスの非対称剪断構造もD1に含まれる.D2は室戸コンプレックスとの境界断層(椎名−奈良師断層;Hibbard et al., 1992;奈良師北東2kmの谷で観察できる)であるが,菜生コンプレックスでは,露頭でのD2褶曲は極めて稀である.室戸屈曲(Hibbard et al., 1992)は上記の境界断層も曲げており,D3に当たる.
3.見学地点
Stop 1
[地形図]1/2.5万 「室戸岬」
第4図.Stop 1の日沖メランジェ.A:チャートや砂岩の外来岩塊.B:玄武岩岩片とD1圧力溶解劈開.海綿骨針や微化石も含まれる.C:メランジェに挟在される土石流堆積物.D:この土石流堆積物中の,D−1劈開をもった砂岩岩片.E:海食台の上空からの写真.斑礪岩岩脈にはD1剪断でのずれは認められない.F:四十寺山層の火山角礫岩.
[位置]室戸市三津にある高知県海洋深層水研究所の北方の海食台.駐車場スペースと海岸に下りる階段あり.[解説]日沖メランジェの好露出がある.このメランジェは黒色の泥岩基質中に,直径数10cm以下の鮮やかな緑色のチャート岩片を含むことで特徴付けられる(第4図A).このチャートは,白亜紀のチャートに比べて軟質であるなど,佐喜浜メランジェに含まれる恐らく曉新世(後述)のチャート岩塊に,岩相上,類似している.このような緑色チャートからは始新世を示すとされる放散虫化石が報告されている(平ほか,1980b).メランジェはチャート以外に,鏡下ではしばしば玄武岩の岩片も含んでいる(第4図B).また,酸性凝灰岩や砂岩の岩塊を大量に含むことも特徴的である.
メランジェ,整然層とも,D1の圧力溶解劈開を伴っている.この劈開は,より古期の,例えば始新統の室戸コンプレックスに比べて,ラフでスペーストな,またアナストモージングな劈開である(第4図B).劈開は,また,非対称褶曲の軸面劈開をなしている.メランジェにおいては,この褶曲は非円筒褶曲で,極端な場合,シース褶曲である.メランジェはプレッシャーシャドウなど,非対称の剪断構造も伴っている.以上のD1の変形は,Stop 1の日沖メランジェでも,良く観察される.日沖メランジェの走向(D1の圧力溶解劈開の走向)は北東−南西で,南東に高角で傾斜している.この走向と平行に,厚さ1.5mの礫岩が挟まれているのが観察される(第4図C, E).この礫岩は平ほか(1980b)の第4図Aにも示されている.最大直径30cmで,亜円礫の砂岩岩塊が砂岩基質中に,基質保持で認められる.大きい岩塊は基底と上部に配列しているが,上部の岩塊が一番大きい.個々の岩塊は時計回りに,右ずれセンスで回転しているように観察される.砂岩岩塊は鉱物組成や粒径が異なり,また花崗岩や変成岩,さらに放散虫化石を含む岩片もあるなど,起源は多様である.そして,個々の岩塊と岩片の接触部には,D1劈開が認められるのに対し,内部には種々の向きのD−1劈開(一部は片理)が認められる(第4図D).D−1劈開は,D1褶曲を基質とともに被っているチャート岩塊にも,認められる.日沖メランジェを貫いて3条の斑糲岩岩脈とシルが認められる.高知県海洋深層水研究所から,西方の神社を経て,途中で消失するが,四十寺山方面に至る東西走向の斑糲岩がシルで,他に海食台には東北東-西南西走向の岩脈と,これらと交差し,海岸線と平行な北北東-南南西走向の岩脈がある(第4図E).次のStop 2でも述べるように,メランジェファブリックをなすD1剪断は,特にこれと高角で交わる北北東−南南西走向の斑糲岩の貫入後に起っているが,この岩脈自体に大きなずれは認められない.
Stop 1から北西に望まれる,同じ標高のピークが2つある山は四十寺山から続く山塊である.四十寺山層は砂岩からなるが,その基底は玄武岩類で,これは前弧盆としてはかなり異質な岩相である.北方の大碆などにある枕状溶岩も,四十寺山層の玄武岩分布域から海岸にもたらされた巨大な転石である.Stop 1の海食台の北端にも(Stop 1b),火山角礫岩の転石が認められる.岩片は輝石玄武岩やドレライトで,玄武岩岩片には発泡があり,また緑泥石とぶどう石の二次鉱物も認められる(第4図F).
Stop 2
[地形図]1/2.5万 「室戸岬」
[位置]室戸市六ヶ谷の海食台.国道から海岸に向かって水田の畦を歩き,堤防の階段を下りる.
第5図.Stop 2の坂本メランジェと玄武岩岩脈.A:D1劈開と直交して貫入している玄武岩岩脈.B:玄武岩のローブ. C:メランジェ,急冷縁,岩脈を貫くD1劈開.D:オープンニコルでの急冷縁.泥の注入がここでも認められる.E:クロスニコルでの急冷縁.なお,C〜EはOsozawa(1993)のFig. 7 と同じ薄片を用いている.
[解説]坂本メランジェを貫く玄武岩岩脈が観察される.坂本メランジェも,岩片サイズではあるが,チャートや玄武岩の外来岩塊を含み,また剪断されており,木村(2002)の定義に従えば,典型的なテクトニックメランジェである.岩脈は1条では無いが,特に南端の北北西-南南東走向の岩脈が劈開と完全に直交しており,劈開や剪断との前後関係を観察するのに適している(第5図A,B).Osozawa(1993)でも報告したが,D1劈開は母岩の泥岩,急冷ガラス,玄武岩のすべてを切っており(第5図C),玄武岩の貫入はメランジェファブリック形成前である.また,急冷ガラスには泥が注入しており(第5図C),玄武岩は未固結状態の泥に貫入している.なお,この急冷ガラスは変質を免れており(第5図D,E),日本の付加体としては例外的に初生的な化学組成を保持していると考えられるので(Osozawa andYoshida, 1997参照),検討中である.
Stop 3
[地形図]1/2.5万 「室戸岬」
[位置]室戸市室戸岬.駐車場から岬方面への遊歩道.
第6図.Stop 3の岬アセンブレッジと岩脈群.A:タービダイトにある,D1の軸面劈開を伴うアイストラ
クチャー.B:斑礪岩シル北東端の玄武岩岩脈群.後方の建物はホテル明星.
[解説]室戸岬一帯は岬アセンブレッジの褶曲したタービダイトからなる.この褶曲は東南東フェルゲンツの非対称褶曲で,D1の圧力溶解劈開を軸面劈開としている.褶曲軸のトレンドや軸面の走向は北北東-南南西で,良くそろっている.これらの褶曲は酒井(1981)により,スランプ褶曲とされたが,このような軸面劈開の存在から否定されている(Hibbard and Karig,1987).シース褶曲はHibbard and Karig(1987)により,発見された.シースと言っても,上記のような軸面劈開が定義でき,シースは北北東に閉じている(第6図A).剪断センスが他地域と逆になっているが,いずれにせよ,岬アセンブレッジはこのような剪断変形を伴っている.
斑糲岩シルは,室戸岬西側から,ホテル明星(あけのほし)の海岸まで,分布しているが,この海岸が分布の北西端で,消失している.この北西端の露頭では(Stop3b),斑糲岩シルは走向を北北西に変えた岩脈群となっている(第6図B).シル本体とその北西側のタービダイトの境界はホテル明星南方のビシヤゴ碆などで観察される.タービダイトは熱変成作用を被って,赤鉄鉱などを生じている.斑糲岩全岩と黒雲母のRb/Sr比から,14.4Maの年代が得られている(浜本・酒井,1987).放散虫化石は,この海岸の半遠洋性泥岩から,Cyltocapsella tetrapera を検出している(Osozawa,1993;水谷哲也の東北大学卒業論文による).
Stop 4
[地形図]1/2.5万 「室戸岬」
[位置]室戸市津呂芝碆.階段から海岸に下りる.
第7図.Stop 4の津呂アセンブレッジの正断層と基底のスラスト.A:正級化のある酸性凝灰岩を切る共役正断層群.B:酸性凝灰岩を変位させている正断層を貫く圧力溶解劈開.なお,Osozawa(1993)のFig. 6 と同じ薄片を用いている. C:放散虫化石の圧力溶解.D:基底スラスト.スラストも不透明鉱物(劈開)からなる.
[解説]津呂アセンブレッジ基底の半遠洋性泥岩が好露出している.北西側上位で級化した白色の酸性凝灰岩を挟んでいることが特徴的である(第7図A).地層は一般に南東に急傾斜しているので,津呂アセンブレッジも全体として逆転している.この逆転はD3に当たる室戸屈曲(Hibbard et al., 1992)の一表現である.これら半遠洋性泥岩は共役のD0正断層に頻繁に切られている(第7図A).正断層は傾動補正によっており,補正しない場合は横ずれ断層である.Osozawa(1993)により,正断層の中間主応力軸として北西−南東が得られている.層理面について変位のある正断層はD1の圧力溶解劈開に明瞭に切られている(第7図B).また,正断層は石英・方解石脈で満たされているが(第7図B),これら脈上には条線や正断層センスのステップが観察される.正断層は次のStop 5では,砂岩脈に充填されていた.なお,D1劈開は圧力溶解劈開であるが,剪断を伴っていない(第7図C)
D1スラストが南東側の坂本メランジェとの境界となっている.このスラストには,圧力溶解劈開や石英・方解石脈が認められ(第7図D),ガウジは存在しない.この付近の坂本メランジェからN4の浮遊性有孔虫化石が報告されているが(Saito,1980),次に述べるように,この年代は放散虫化石の示すそれより古い.
Stop 5
[地形図]1/2.5万 「室戸岬」
第8図.Stop 5のコンタクトメランジェとチャート岩塊.A:砂岩の非対称D1褶曲.玄武岩の外来岩塊を含む.B:非対称プレッシャーシャドウ.C:基質とともにD1褶曲に参加したチャート岩塊.D:チャート岩塊に注入した泥岩岩脈.E:チャート内のD−1劈開を切る流動組織をもった泥岩岩脈.F:D1褶曲したチャートのD−1劈開.
[位置]室戸市津呂石ノ碆.新室戸岬漁港の北端に駐車して,その北側の古い堤防から海岸に降りる.[解説]北方の菜生漁港に至る海食台には,津呂アセンブレッジの下位の半遠洋性泥岩と上位のタービダイトがD1スラストで繰り返して露出し,覆瓦構造をなしている.タービダイトはディスタル・タービダイトで,北西上位である.ここでも津呂アセンブレッジは全体として,逆転している.現在は漁港建設に伴い露頭は失われているが,砂岩脈を伴う半遠洋性泥岩から,Stycocolys cf.wolffii やCalocycletta sp.が検出されている(Osozawa,1993;水谷哲也の東北大学卒業論文による).また,この失われた露頭には,半遠洋性泥岩の同時礫を角礫で含む,厚さ1.5mの土石流堆積物が半遠洋性泥岩に挟まれているのが観察できた.なお,菜生漁港では,フジツボ化石の破片からなる(Sakai, 1987)タービダイト(Osozawa, 1993)が観察される.
観察地点では,例外的に,Hibbard et al. (1992)によるコンタクトメランジェが半遠洋性泥岩とタービダイトの間に挟在されている.このメランジェは,Hibbardet al.(1992)でも報告されているように,直径50cm前後の複数の玄武岩と,長径15mのチャートの岩塊を含んでいる(第8図A;現在はその一部が観察できる).津呂アセンブレッジではこのメランジェに限って認められるD1の剪断変形などは,日沖メランジェのそれらと共通している(第8図A,B).チャート岩塊は基質の泥岩とともに非対称に褶曲して,向斜をなしており,またD1の圧力溶解劈開がその軸面劈開となっている(第8図C).このチャートには,さらに,泥岩が注入している(第8図D).鏡下では,この泥岩には,砕屑岩脈と泥岩との境界に平行に発達する,粒界滑りによる流動組織が観察される(第8図D).一方,この泥岩岩脈はチャートの層理面を切っているが,その層理面と平行に,D1劈開とは異なる,別のD−(マイナス)1の圧力溶解劈開が観察される(第8図E).含有放散虫化石もこの劈開と平行に押し潰されている(第8図E).また,このD−1劈開はD1褶曲を重複して被っている(第8図F).
Stop 6
[地形図]1/2.5万 「佐喜浜」
第9図.Stop 6の佐喜浜メランジェ.A:玄武岩を覆うチャートの外来岩体.B:玄武岩を覆うチャート.C:境界には強いD1圧力溶解があるが,ガラスが残存している.D:D−1とD1の新旧2つの劈開.いずれも白雲母を晶出.E:放散虫化石
[位置]室戸市佐喜浜町遅越.近隣では現在も稼働しているが,採石場跡地にある露頭で,現在は失われている可能性が強い.このため,Stop 6は遠距離にあることも考慮して,オプションとしている.[解説]菜生コンプレックスに含まれるチャートや玄武岩の外来岩塊は,年代や岩相が類似しているため,佐喜浜メランジェ(平ほか,1980b)に含まれるこれらの外来岩体に由来する可能性がある.佐喜浜メランジェは砂岩泥岩基質に玄武岩の岩塊・岩体を含むが,チャートの岩塊も見いだしている.このチャートは,四国に限らず,四万十帯南帯の古第三系から知られる唯一の例である(Osozawa, 1992).
採石場跡地の大露頭には,下位の厚さ10m以上あり,逆転していない玄武岩枕状溶岩と,上位の厚さ18mのチャートからなる巨大岩体がD2断層で切断されてはいるが,砂岩泥岩基質中に認められる(第9図A).溶岩とチャートの接触部は(第9図B),基質にも認められるD1の圧力溶解劈開を被っているが,部分的に枕状溶岩のガラスが残存している(第9図C).このチャートにも,チャートの層理面と平行なD1とは異なっている,基質には存在しない,別のD−1の圧力溶解劈開が鏡下で観察される(第9図D).なお,これらの変形時相の区分は,これまで述べた菜生コンプレックスでの区分と同じになっているが,例えばそれぞれのD1の年代は全く異なっていることに注意されたい.なお,菜生コンプレックスのチャートがこの岩体に由来するとすれば, Stop5のチャートにはさらにD−2の劈開が観察されるはずである.
2度の圧力溶解劈開を被って,それぞれの面と垂直に押し潰されているにも拘らず,チャートに含まれる放散虫化石の保存は極めて良い(第9図E).筆者にとって,瀬戸川コンプレックスの石灰岩を塩酸処理して検出した放散虫化石(Osozawa et al., 1990)に次ぐ保存の良さであった.1992年当時の酒井豊三郎教授による鑑定結果は,連続試料を検討し,全体として曉新世−始新世初期を示すと思われるが,放散虫はほとんどすべてが新種で,より詳細な年代を限定することはできないとのことであった.
Stop 7
[地形図]1/2.5万 「手結」
第10図.チャートと砂岩岩片を含む横浪メランジェ.岩片内にD−1劈開(これも白雲母晶出),基質と岩片にD1劈開.
[位置]芸西村十代.国道から西分漁港に下りる道路は,国道の海側にある緑のネットがあるパークゴルフ場が良い目印である.漁港の拡張工事により,平ほか(1980a)やTaira et al.(1988)の報告した露頭はかなり破壊されたが,漁港の東海岸の露頭は健在である.室戸からの帰りに,時間が余った場合のオプションとして用意した.[解説]漁港の西側は泥岩卓越のタービダイトで(整然層;ただしD1剪断あり),この下位に手結メランジェが分布している.両者の境界は整合とされているが(平ほか,1980a),実際はD2断層で,漁港の谷で,かつては観察できた.なお,平ほか(1980a)やTaira et al.(1988)はこの断層とは別に,より上位の砂岩卓越タービダイトの境界を断層としている.手結メランジェの特徴は基質の砂岩・泥岩が少ないことで,ほとんどが枕状溶岩を含む玄武岩,石灰岩,チャート,および大量の半遠洋性泥岩(平ほか,1980の多色互層)の外来岩塊・岩体からなっている.さらに,メランジェには基質とは区別される砂岩の岩塊も含まれる.これらがD1の剪断を含む複雑な変形を被っている.手結メランジェの薄片は作成していないが,ここでは土佐湾の対岸にあって互いに対比できる(Taira et al.,1988)横浪メランジェの薄片を示す.チャートや砂岩の外来岩片には,基質から岩片内部に連続するD1劈開以外に,岩片内部に限られるより古期のD−1劈開が明瞭に観察される(第10図).手結メランジェでも同様な現象が期待できるので,今後の薄片観察が肝要である.
文 献
Cowan, D. S., 1985, Structural styles in Mesozoic andCenozoic melanges in the western Cordillera of NorthAmerica. Geol. Soc. Amer. Bull., 96, 451-462.
浜本礼子・酒井治孝,1987,室戸岬ハンレイ岩に伴う文象斑岩のRb-Sr年齢.九州大学理学部研究報告(地質),15,131-135.
Hashimoto, Y. and Kimura, G., 1999, Underplating processfrom melange formation to duplexing: Example from theCretaceous Shimanto Belt, KiiPeninsula, southwestJapan. Tectonics, 18, 92-107.
Hibbard, J. and Karig, D., 1987, Sheath-like folds andprogressive fold deformation in Tertiary sedimentaryrocks of the Shimanto accretionary complex, Japan.Jour. Struct. Geol., 9, 845-857.
Hibbard, J., Karig, D. and Taira, A., 1992, Anomalousstructural evolution of the Shimanto accretionary prismat Murotomisaki, Shikoku Island, Japan. Island Arc, 1,133-147.
Ikesawa, E., Kimura, G., Sato, K., Ikehara-Ohmori, K.,Kitamura, Y., Yamaguchi, A., Ujiie, K. and Hashimoto,Y., 2005, Tectonic incorporation of the upper part ofoceanic crust to overriding plate of a convergent margin:An example from the Cretaceous-early Tertiary MugiMelange, the Shimanto Belt, Japan. Tectonophysics, 401,217-230.
狩野謙一・村田明広,1998,構造地質学.朝倉書店,298p.
木村 学,2002,プレート収束帯のテクトニクス.東京大学出版会,271p.
Needham, D. T. 1987, Asymmetric extensional structures andtheir implications for the generation of melanges. Geol.Mag., 124, 311-318.
Onishi, C. T., and Kimura, G., 1995, Change in fabric ofmelange in the Shimanto Belt, Japan: Change in relativeconvergence? Tectonics, 14, 1273-1289.
Osozawa, S., 1984, Geology of Amami Oshima, centralRyukyuIslands, with special reference to effect ofgravity transportation on geologic structure. TohokuUniv. Sci. Rep. 2nd Ser. (Geol.), 54, 165-189.
Osozawa, S., 1992, Double ridge subduction recorded in theShimanto accretionary complex, Japan, and platereconstruction. Geology, 20, 939-942.
Osozawa, S., 1993, Normal faults in accretionary complexformed at trench-trench-ridge triple junction, as anindicator of angle between the trench and subductedridge. Island Arc, 2, 142-151.
Osozawa, S., Sakai, T. and Naito, T., 1990, Miocenesubduction of an active mid-ocean ridge and origin of theSetogawa ophiolite, central Japan. Jour. Geol., 98, 763-771.
Osozawa, S., and Yoshida, T., 1997, Arc-type and intra-platetype ridge basalts formed at trench-trench-ridge triplejunction, implication for the extensive sub-ridge mantleheterogeneity. Island Arc, 6, 197-212.Saito, T., 1980, An early Miocene (Aquitanian) planktonicforaminiferal fauna from the Tsuro Formation, theyoungest part of the Shimanto Supergroup, Shikoku,Japan. In Taira, A. and Tashiro, M., eds., Geology andPaleontology of the Shimanto Belt, Selected Papers inHonor of Prof. Jiro Katto, Rinnyakosaikai Press, Kochi,227-234.
酒井治孝,1981,室戸半島南端部四万十帯のオリストストロームとメランジェ.九州大学理学部研究報告(地質),14,81-101.
Sakai, H., 1987, Storm barnacle beds and their deformation inthe Muroto-misaki olistostrome and melange Complex,Shikok. Jour. Geol. Soc. Japan, 93, 617-620.Schoonover, M. and Osozawa, S., 2004, Exhumation processof the Nago subduction-related metamorphic rocks,
Okinawa, Ryukyu island arc. Tectonophysics, 393, 221-240.
Taira, A., Katto, J., Tashiro, M., Okamura, M. and Kodama,K., 1988, The Shimanto Belt in Shikoku, Japan-Evolution of Cretaceous to Miocene accretionary prism.Modern Geol., 12, 5-46.
平 朝彦・岡村真・甲藤次郎・田代正之・斉藤靖二・小玉一人・橋本光男・千葉とき子・青木隆弘,1980a,高知県四万十帯北帯(白亜系)における“メランジェ”の岩相と時代.平朝彦・田代正之編,四万十帯の地質学と古生物学,甲藤次郎教授還暦記念論文集,林野弘済会高知支部,179-214.
平 朝彦・田代正之・岡村 真・甲藤次郎,1980b,高知県四万十帯の地質とその起源.平朝彦・田代正之編,四万十帯の地質学と古生物学,甲藤次郎教授還暦記念論文集,林野弘済会高知支部,319-389.脇田浩二,2000,美濃帯のメランジュ.ジュラ紀付加体の起源と形成過程,地質学論集,55,145-163.
本稿は「岩井雅夫・村田明広・吉村康隆,2006,見学旅行案内書,地質学雑誌,112,補講,170pp」がオリジナルです。
■ オリジナルPDFダウンロード(J-Stageサーバー)
巡検案内:室戸岬ハンレイ岩―マグマ分化プロセスの野外での検証
室戸岬ハンレイ岩—マグマ分化プロセスの野外での検証*
Múrotomisaki Gabbroic Complex − Field observations of magmatic differentiation processes
星出隆志1 小畑正明1吉村康隆2
Takashi Hoshide 1, Masaaki Obata 1 and Yasutaka Yoshimura 2
受付:2006年6月30日
受理:2006年8月14日
*日本地質学会第113年学術大会(2006年・高知)見学旅行(D班)案内書
1.京都大学大学院理学研究科地質学鉱物学教室Department of Geology and Mineralogy,Graduate School of Science, Kyoto University,Kyoto 606-8502, Japan.
2.高知大学理学部自然環境科学科Department of Natural EnvironmentalScience, Kochi University, Kochi 780-8520,Japan.Corresponding author:T. HoshideE-mail: hoshide@kueps.kyoto-u.ac.jp
概 要
室戸岬ハンレイ岩体の岩相変化と層状構造.及び壁岩の接触変成部の溶融構造の観察.特に,岩石の産状,鉱物モード組成,全岩化学組成,結晶サイズ,結晶数密度の観点に基づき,急冷周縁相,結晶集積部,結晶成長部,粗粒ハンレイ岩,斜長岩質岩脈といった本岩体の各岩相相互を関連付け,層状構造の発達とマグマの分化プロセスを検証する.
Key Words
層状貫入分化岩体,結晶分化,結晶沈積,結晶成長,クリスタルマッシュLayered igneous complex, crystall;gation differentiation, crystal setting, crystal growth, crystal mush
地形図
1: 25,000 「室戸岬」
1: 2,500 室戸市都市計画平面図9
見学コース
8:30 高知大(朝倉)正門前集合→大山岬→室戸岬ハンレイ岩体→大山岬→高知空港→高知駅→18:00 高知大(朝倉)解散.
見学地点
Stop 1 結晶集積部(岩体底部から0−40 m:下部急冷周縁相,ピクライト質ハンレイ岩,カンラン石ハンレイ岩下部).
Stop 2 結晶成長部(岩体底部から40−100 m:カンラン石ハンレイ岩,斜長岩脈,波状ペグマタイト脈).
Stop 3 粗粒ハンレイ岩
Stop 4 マグマ貫入による接触変成と部分溶融,及び上部カンラン石ハンレイ岩中の角閃石クロットの分布.
Stop 5 ハンレイ岩体先端部の玄武岩質岩脈群.
第1図.室戸岬ハンレイ岩体の地質図.1:急冷周縁相,玄武岩〜細粒ドレライト.2:ピクライト質ハンレイ岩.3:カンラン石ハンレイ岩.4:粗粒ハンレイ岩.5:母岩(主に砂岩泥岩互層).Hoshide et al.(2006a)に加筆・修正.
第2図.室戸岬斑れい岩体の岩相とモード組成の鉛直変化.LCM,下部急冷周縁相.LPG,下部ピクライト質斑れい岩.LOG,下部カンラン石斑れい岩. CG,粗粒斑れい岩.UOG,上部カンラン石斑れい岩.UPG,上部ピクライト質斑れい岩.UCM,上部急冷周縁相.WPV,波状ペグマタイト脈. AnV,斜長岩質脈.Ol,カンラン石.Pl,斜長石.Aug,普通輝石.Opq,不透明鉱物.Oth,その他の鉱物.Hoshide et al.(2006a)に加筆.
1.はじめに
層状貫入分化岩体の研究は,マグマの結晶分化機構の解明に重要である.深成岩のマクロからミクロな構造はマグマ溜りプロセスの結果であるから,その構造の解析からマグマ溜りプロセスに関して多くの情報を得ることができる.実際スケアガード貫入岩体を筆頭に世界の層状貫入分化岩体の研究は火成岩岩石学の進歩に大きく貢献してきた(たとえばWager and Brown, 1968).一般に,重力場で冷却しつつあるマグマ溜りでは,結晶作用という化学変化と,結晶の重力沈積,マグマの対流といった流体力学的なプロセスが,様々な程度に相伴って連結して起こり,複雑で多様な空間構造が形成される(例えばMcBirney and Noyes, 1979).マグマ溜りは熱的,化学的,力学的プロセスが競合する複雑なシステムである.これらの素過程の相対的な重要度は岩体の規模によって異なるであろう.ここに,異なった規模の岩体の比較研究が重要になる理由がある.規模の大きな岩体は冷却に時間がかかり,それゆえに結晶分化はより大きく進行しうる.またマグマ対流も重要な役割を果たすであろう.逆にシルのように小規模な岩体の場合は比較的早く冷却するので,あまり分化が起こらないであろう.
Wagerらのスケアガード貫入岩体の古典的な研究以来,天然の実験室という観点から深成岩体比較研究の重要性は今日でも薄れることはない.むしろ実験的,理論的研究の進歩により,新しいコンセプト(例えば組成対流,Tait and Jaupart, 1989; 境界層分化, Langmuir, 1989)が導入され,新しい視点からの記載研究の重要性は今日ますます増大してきているといえよう.
本巡検の対象である室戸岬ハンレイ岩体は,我が国の代表的な塩基性深成岩体として古くから良く知られたものであり,これまで繰り返し多くの研究が行われてきた(Yoshizawa, 1953, 1954;Yajima, 1972a, 1972b;赤塚ほか,1999).本岩体は比較的小規模な岩体にもかかわらず,岩相変化に富み,明瞭な層状構造が発達することから,研究者の注目を集めてきた.岩体の形状がシンプルであるため全体構造が容易に把握でき,海岸沿いは露出も良く詳細な野外観察にも適していることから,学生向き巡検コースとしても良く取り上げられている.しかしその成因に関しては,ごく最近までは古典的なイメージ,すなわちスケアガード貫入岩体の研究(Wager andBrown, 1968)の延長線から大きく外れるものではなかったのではないだろうか.例えば,初期の研究によって,本岩体は結晶の重力沈積による分別結晶作用で形成されたことが明らかにされており,岩体下部に発達するカンラン石に富むハンレイ岩層はカンラン石の重力沈積によって形成されたことはYajima(1972a, b)の先駆的研究ですでに明らかになっていた.しかしその後の研究により,カンラン石に富む層が複数存在する事が確認され,これらがすべてカンラン石の集積によって出来たのかどうか疑問視されるようになった(赤塚ほか,1999).我々は最近,本岩体を,岩石組織,全岩化学組成の点から再検討し,従来考えられていなかった新たなマグマプロセスを見出した(Hoshide et al., 2006a, b).このことにより結晶分化作用の実態を従来よりも明確に,より具体的に把握することが出来るようになった.特に重要な新知見は,(1)本岩体中に複数存在するカンラン石に富む層を,カンラン石結晶の沈積・集積によって出来た部分(カンラン石結晶集積部)と,カンラン石結晶数は始めよりも減少したが,マグマの冷却過程で結晶が成長するにつれてカンラン石のモードが増えた部分(カンラン石結晶成長部)とに峻別することに成功したこと,(2)「カンラン石結晶成長部」では,結晶成長に伴ってカンラン石モードが増加したが,これは斜長石に富むマッシュ状のマグマが分離したためであるということ,(3)浮力で上昇した斜長岩質マッシュ(マグマ)は,上方すなわち岩体中央部に残存していた未分化なマグマと混合し,結晶沈積とは異なる「マグマ混合トレンド」を形成したということである(Hoshide et al., 2006b).これらの知見から,従来漠然としかとらえられていなかった「結晶分化作用」の実態が,物理過程としてより明確に把握できるようになってきた.カンラン石の結晶成長,斜長岩質マッシュの分離と上昇は,固結しつつあるマグマ溜りのいわゆる境界層で生じたものである.この「境界層分化」というプロセス概念は,1990年頃から主として火山岩の解析により提唱されてきたものであるが(例えばLangmuir,1989;Kuritani, 1998),このプロセスが実際に起こっていることが深成岩で確認された事例としては室戸岬ハンレイ岩の研究が世界初である.本巡検は,我々が現在見出しつつある新しいマグマプロセスを野外で検証することをテーマの中心に据えて,本岩体の主要な岩相とそれらの野外での産状,相互の関係を観察することを主眼とするものである.なお,本案内書の見学コースは一日の巡検を想定して組まれてある.
2.地質概説と岩体の層状構造
室戸岬ハンレイ岩体は高知県室戸半島南端部の四万十累層群中に貫入したシル状の火成岩体である(第1図).本岩体は最大幅約220m,長さ約1800mのくさび状の形態をなし,現在は周りの堆積岩の地層と共に全体として急角度で北に傾斜しているが,形成時はほぼ水平であった地層(砂泥互層)にマグマが調和的に貫入し,固化したものであるといわれている(Kodama and Koyano,2003).岩体の南東側が重力的に下位であったことは岩体内部に分布する波状ペグマタイト脈や斜長岩質岩脈の産状から推定されている(Yajima, 1972a).また周囲の堆積岩の堆積構造も南東側が下位であることと調和的である(三宅,1983).海岸沿いの露出部は,シルの底部から天井部および壁岩までを連続的に観察でき,マグマプロセスの観察・研究に適している.貫入年代は,岩体上部周縁部に分布する母岩の融解に由来する石英長石質の岩脈から,14.4±0.4 MaというRb-Sr黒雲母−全岩アイソクロン年代(浜本・酒井,1987)が得られている.13〜15 Maという火成作用の年代は同じ「外縁帯」(高橋,1986)に分布する潮岬火成複合岩体,足摺岬複合貫入岩体などでも得られており,本岩体形成プロセスの解明は,一連の西南日本弧の中新世中期火成活動の一環として,日本海拡大に伴う四国海盆沈み込みに関連付けて議論されることの多い,テクトニクスの問題としても興味深い位置付けにある(Hibbard et al., 1992;Shinjoe,1997;新正ほか,2003).
第3図.室戸岬ハンレイ岩体の各種データの鉛直変化.(a)岩相変化,(b)カンラン石モード組成,(c)カンラン石の平均結晶サイズ,(d)カンラン石の結晶数密度,(e)全岩MgO量,(f)カンラン石のFo値,(g)斜長石のAn値.図(d)の点線は結晶数密度の岩体全体での平均値を,図(e)の点線は全岩MgOの岩体全体での平均値を示す.AC,結晶集積部.GR,結晶成長部.その他の略称は,図2に同じ.Hoshide et al. (2006a)より.
本岩体の鉱物モード組成の鉛直変化を第2図に示す.本岩体は全体としてハンレイ岩質である.主要な構成鉱物はカンラン石,普通輝石,斜長石で,少量のハイパーシン,ホルンブレンド,黒雲母,イルメナイトを含む.カンラン石の量は,鉛直方向に繰り返し増減の変化があり,複数のピークが認められる(第3図のO1, O2, O3,O4).本岩体中最も粗粒な「粗粒ハンレイ岩」は,主として普通輝石と斜長石からなり,カンラン石は含まない.第3図は本岩体の各種データのシル鉛直方向変化をまとめたものである.カンラン石の結晶サイズと結晶数密度(単位体積あたりの結晶数)は,薄片(2次元)での結晶サイズ分布をもとに確率論に基づき3次元における真のサイズ分布を推定したものである(Hoshide, et al.,2006a).下部40m部はカンラン石モードが多く,結晶数も多いが,結晶サイズは急冷周縁相部とほとんど変わらない.一方,その直上,40mから100mの部分はカンラン石モードの増減は見られるが,結晶数は著しく少なく,しかし結晶サイズは増大しているという特徴がある.これらのデータから,Hoshide et al.(2006a)は,下部のカンラン石に富む層を,カンラン石斑晶が重力沈積・集積してモードが増加した部分であるという意味で「結晶集積部」と呼び,上部のカンラン石結晶サイズが大きい層を,結晶数は減少したが結晶が大きく成長したためにモードが増加した,という意味で「結晶成長部」(底部から40−100m)と呼んで区別した.全岩でのMgO量の増加は両ゾーンで見られる.後で述べるように,「結晶集積部」でのカンラン石モード増加はカンラン石の結晶沈積によるものであるが,「結晶成長部」でのモード増加はカンラン石結晶の集積に帰することはできない.結晶成長部のカンラン石ハンレイ岩中には斜長岩質脈や波状ペグマタイト脈が散在する.これらがマグマの分化に重要な役割を果たしたことを以下に示す.
第4図.室戸岬ハンレイ岩体の全岩化学組成の鉛直変化.影の付いた部分の組成点は,粗粒ハンレイ岩相に含まれるカンラン石ハンレイ岩のものである. Fe2O3*は,全鉄を3価として計算した値.FeO*/MgOのFeO*は,全鉄を2価で計算した値.岩相名の略称は図2に同じ.赤塚ほか(1999)を改変.
第5図.CaO-Fe2O3*-MgO全岩組成変化図.Fe2 O3*は,全鉄を3価として計算した値.AC zone,結晶集積部.GR zone,結晶成長部.岩相名の略称は図2に同じ.Hoshide et al.(2006b)より.
第6図.カンラン石ハンレイ岩部(底部から60−80 m付近)に発達する斜長岩質脈.(A)露頭写真.(B)脈の内部構造のスケッチ.Hoshide et a(l. 2006a, b)より.
3.全岩化学組成—結晶集積トレンドと結晶成長トレンド
赤塚ほか(1999)により報告されている全岩化学組成のシル鉛直方向変化図を第4図に示す.さらにFeO,CaO量について,MgO量を横軸にとった変化図を図5に示す.
第5図において,結晶集積部の全岩化学組成は,貫入時の初期メルト組成(=急冷周縁部の全岩化学組成から,斑晶のコア部の組成を差し引いて求めた;赤塚ほか,1999)から急冷周縁部に含まれるカンラン石斑晶組成(Fo83)方向に伸びるほぼ直線的なトレンドを示す.このトレンドは,初期メルトとカンラン石斑晶の機械的混合によって説明でき,貫入時にマグマ中に存在していたカンラン石斑晶の重力沈積説に調和的である.従って,このトレンドを「結晶集積トレンド」と呼ぶ.
一方結晶成長部の組成は,その多くが結晶集積トレンドから外れ,異なる傾きを持つ別トレンドを形成しているように見える.興味深いことに,結晶成長部の層序的上位に位置する粗粒ハンレイ岩や上部カンラン石ハンレイ岩の組成は,この結晶成長部が形成するトレンドの延長線上,初期メルトを挟んで結晶成長部の組成点と反対側(Mgに乏しい側)にプロットされる.このトレンドを全体として「結晶成長トレンド」と呼ぶことにする.これら傾きの異なる2つの直線的なトレンドは,初期メルトの組成点付近で互いに交わる.Hoshide et al.(2006b)は結晶成長部に分布する斜長岩質脈の組成が,この結晶成長トレンド上の最もMgに乏しい端にあることに注目し,斜長岩質脈が結晶成長部の形成に重要な役割を果たしたと考えた(第5図).そこで次の章では,結晶成長部に発達する斜長岩脈と「波状ペグマタイト脈」の産状について述べる.
第7図.カンラン石ハンレイ岩に発達するさまざまな構造.(A)底部から40−45 m付近に発達するリズミック層状構造.白い部分は斜長石に富む.スケールは20 cm.(B)底部から40−45 m付近に見られる波状ペグマタイト脈.スケールは20 cm.(C)同波状ペグマタイト脈の内部構造のスケッチ.脈上部の優白質部分の斜長石結晶は長軸が2〜4 mm,脈下部の優黒質部分の斜長石結晶は1〜1.5 cm.(D)波状ペグマタイト脈の優白質部分に発達するプリューム状構造.
4.結晶成長部の斜長岩質脈と波状ペグマタイト脈
結晶成長部には,斜長岩質脈(第6図)や,上部が斜長岩質で下部がマフィック鉱物に富む「波状ペグマタイト脈」(wavy pegmatitic vein;Yajima, 1972a)(第7図)が多数分布している.特に斜長岩質脈は,結晶成長部の中でもカンラン石に富む層に特徴的に分布する.Yajima(1972a)は,これらの脈がマグマの冷却固結過程最末期の残液が固結したものであると考えた.しかしHoshide et al.(2006b)は,以下に述べるように,これらの脈が本岩体のマグマ分化において重要な役割を果たしていたことを主張している.
斜長岩質脈は厚さ数10cm−1mで,下面は平坦で上境界面は波状を呈するという上下非対称な形状を示す(第6図-A).露頭での斜長岩質脈の占める割合は10%以下である.場所によっては,脈の波状構造がさらに発達しプリューム状構造を呈するものもある.脈の内部では斜長石結晶が脈の上面に沿うように配列しており,脈が流動していた時には既に斜長石結晶が多量に存在していたことを示唆する(第6図-B).斜長岩質脈は鏡下で,自形の斜長石(粒径0.5〜1.0cm)を大きな他形の普通輝石が包有するオフィティック組織を呈する.
第8図.斜長岩質マッシュの分離,浮上によるマグマ分化モデル.Fe2O3*は,全鉄を3価として計算した値.計算で得られたメルト組成変化を示す線上の数字は,結晶化度を示す.AC trend,結晶集積トレンド.GR trend,結晶成長トレンド.岩相名の略称は図2に同じ.Hoshide eta(l. 2006b)より.
5.「結晶成長トレンド」の形成
Hoshide et al.(2006b)は斜長岩質脈の産状と内部構造の観察から,結晶集積部の直上からマグマ溜り上方内側へとマグマの冷却固結が進行していく際に,固液境界層から斜長岩質物質が分離し,それが浮力によりダイアピル状に上昇していたと考えた.斜長岩質物質が抜けた部分は,相対的にFeやMgに富み,カンラン石成分に富む結晶成長部となる(第3図).一方,ダイアピル的に上昇した斜長岩質物質は,上方に位置していた未分化なメルト(貫入時以来組成変化していないメルト=初期メルト)と合体し混合したであろう.つまり第5図において,結晶成長トレンドのMgに富む側は,斜長岩質物質をはき出してできた残渣トレンドであり,Mgに乏しい側は,下から上昇してきた斜長岩質物質と未分化なメルトの混合トレンドを表していると考えるのである.Hoshide et al.(2006b)は,観察されるような斜長岩質物質が本岩体のマグマの結晶作用の過程で生じうるかどうかを調べるために,相平衡計算ソフト「PELE」(「MELTS」のWindows版:Boudreau, 1999)を用いて境界層での結晶作用のモデル計算を行った.結晶作用開始時のメルト組成は初期メルト組成(赤塚ほか,1999),すなわち急冷周縁相の全岩化学組成から斑晶分を差し引いたものとし,メルトの初期含水量は1 . 0 w t %(McBirney, 1993),酸素フュガシティーをQFMバッファー,結晶作用の圧力を1 kb(Yajima et al., 1977)とし,平衡結晶作用を仮定して計算した.図8にその計算結果を示す.
はじめに晶出するのはカンラン石で,続いて斜長石が晶出,結晶化が進むにつれてメルト組成はMgOが減少し,FeOが増加する.およそ30%結晶化したところでメルトは普通輝石に飽和するが,メルトのFeOはさらに増加していく.60%程度結晶化が進むと,磁鉄鉱が晶出しはじめるため,メルトのFeOは減少に転ずる.こうして見積もられる分化メルトの組成トレンドは,結晶成長トレンドから大きく外れ,斜長岩質脈の組成点を通過しない.従って,斜長岩質脈はどのステージのメルト組成をも表していないことがわかる.しかしながら斜長岩質脈の組成は,およそ30%結晶化が進行した時の分化メルトの組成と,それと平衡共存する斜長石結晶(An71〜72)の組成を結ぶ連結線上に乗る.つまり斜長岩質脈は,分化メルトと斜長石結晶との混合物が固化したものと考えることができる.全ての元素を考慮して,計算で得られる分化メルト+斜長石結晶の混合物の組成が実際の斜長岩質脈組成に最も近づく時の分化メルトと斜長石結晶の混合比を求めたところ,分化メルト:斜長石結晶=6:4が最適であることがわかった.この割合で混合したメルトと結晶の混合物は,カンラン石や普通輝石に富んだマトリックスから分離することができるほど十分流動的であると考えられる.この計算結果は,斜長岩質脈がメルトと斜長石結晶の混合物,すなわちクリスタルマッシュであるという考えを支持するものである.上の計算結果から,斜長岩質脈は,およそ30%結晶化が進んだ固液境界層に由来する分化メルトと,それに平衡な斜長石結晶の混合物(斜長岩質マッシュ)が固化したものとして説明できることがわかった.このような斜長岩質マッシュが固液境界層から分離した結果,その残渣は相対的にカンラン石成分に富み(結晶成長部の形成),逆にその上部のマグマは斜長岩質マッシュの供給を受け混合が起こり,その結果全体として,結晶集積トレンドと異なる傾きを持つトレンドが形成されたと考えられる(第5図).
第9図室戸岬ハンレイ岩体のマグマ分化過程の模式図.AC,結晶集積部.GR,結晶成長部.Hoshide et al. (2006a) を改変.
6.まとめ
以上のことから,本岩体のマグマ分化過程は以下のようにまとめられる(第9図).1)マグマ貫入後早期に,貫入マグマにもともと含まれていたカンラン石結晶の大部分は底部に沈降集積し,厚さ約40mの結晶集積部を形成した.この過程では,カンラン石結晶は実質上成長しなかった.この時間スケールは数年のオーダーである(赤塚ほか,1999).2)カンラン石結晶沈積終了後,結晶集積部直上に発達した固液境界層から斜長岩質マッシュが分離し,その残渣は相対的にカンラン石成分に富んでいった.このプロセスは上の結晶沈積よりも遙かにゆっくりしたプロセスであり,カンラン石の結晶成長はこの時期に起こったものであろう.その上方では,未分化マグマと下方から上昇してきた斜長岩質マッシュプリュームとの混合が起こり,その部分が結晶化して粗粒ハンレイ岩となった(第8図).
斜長岩質マッシュの分離と浮上は,カンラン石の結晶沈積と同程度に,室戸岬ハンレイ岩体のマグマ分化に重要な役割を果たしたと考えられる.この過程は,Langmuir(1989)によって提案された「境界層分化」に似ているが,上昇した物質が分化メルトではなく,相当量の斜長石結晶を含んだ「クリスタルマッシュ」である点が異なっている.「結晶成長トレンド」は,(a)境界層における斜長岩質マッシュの分離によってできた残渣トレンドと,(b)未分化なメルトと上昇してきた斜長岩質マッシュとの混合によって生じた混合トレンド,とが組み合わさってできた一つの複合トレンドである.斜長岩質マッシュの分離と,それが直上のマグマと混合するメカニズムの詳細については今後の課題であり,またこのようなプロセスが他の岩体においてどの程度普遍的に起こっているのかということは,マグマ混合のメカニズムとしても興味深いテーマである.
7.見学地点
第10図.Stop 1〜3付近の地形図.1/2500「室戸市都市計画平面図9」の一部に加筆.
第11図.室戸岬ハンレイ岩体の代表的な岩石の薄片写真.(A)下部急冷周縁相(壁岩との接触部)(B)下部急冷周縁相(底部から2.2 m)(C)下部ピクライト質ハンレイ岩(底部から15 m)(D)下部カンラン石ハンレイ岩(底部から36 m)(E)下部カンラン石ハンレイ岩(底部から49 m)(F)下部カンラン石ハンレイ岩(底部から62 m)(G)下部カンラン石ハンレイ岩(底部から83 m)(H)上部ピクライト質ハンレイ岩(底部から209m).Ol:カンラン石,Pl:斜長石,Aug:普通輝石,Chl:緑泥石.Hoshide et a(l. 2006a)より.
Stop 1 結晶集積部(岩体底部から0−40m:下部急冷周縁相,ピクライト質ハンレイ岩,カンラン石ハンレイ岩下部)
[地形図]1/2.5万「室戸岬」及び1/2500「室戸市都市計画平面図9」
[位置]結晶集積部(下部急冷周縁相,ピクライト質ハンレイ岩,カンラン石ハンレイ岩)は,岬突端の中岡慎太郎像前から車道を離れて南へと下った海岸付近(月見が浜)に露出する(第10図).
[解説]下部急冷周縁相は,露頭で茶褐色の概観を呈する.層厚は3m以上であるが,直上のピクライト質ハンレイ岩層への遷移部は侵食により失われて明らかでない.鏡下では,壁岩との接触部から数cmまでは,カンラン石と斜長石の斑晶と細粒緻密な基質からなる玄武岩質の斑状組織が認められる(第11図-A).さらに岩体内側へ向かうと普通輝石が晶出しはじめ,斑状組織(玄武岩)→インターグラニュラー→オフィティック組織へと移り変わる.急冷周縁玄武岩と壁岩の境界部は大局的に見てシャープであるが,所々玄武岩と壁岩が指交状に互いに入り組んでいることや,壁岩から玄武岩に向かって直径1cm程度のプリュームが上昇したような構造が観察される(第12図).また急冷周縁相の岩片が壁岩に包有されていることもある.
ピクライト質ハンレイ岩は本岩体中最もカンラン石に富み,その量は40vol%にも達する.鏡下では,粒径0.1〜0.3mmのカンラン石が斜長石や普通輝石に取り囲まれるポイキリティック組織を呈する(第11図-C).
第12図.下部急冷周縁相と壁岩の境界部付近の構造(Stop 1).写真の白色部が壁岩.(A)〜(C)の矢印は岩体の上方向を示す.
Stop 2 結晶成長部(岩体底部から40−100m:カンラン石ハンレイ岩,斜長岩質脈,波状ペグマタイト脈)
[地形図]1/2.5万「室戸岬」及び1/2500「室戸市都市計画平面図9」
[位置]Stop 1から北西へ30m程進むと,大小さまざまな斜長岩質脈〜波状ペグマタイト脈が発達するカンラン石ハンレイ岩(結晶成長部)の露頭が分布する(第10図).
[解説]「結晶成長部」は,岩体底部から40−100 mの部分のカンラン石ハンレイ岩で,「結晶集積部」に比べて結晶粒が大きくなる.主要な構成鉱物は斜長石,カンラン石,普通輝石であるが(第11図-E,F,G),これらの量比は「結晶成長部」内で大きく変化する(第2図).その他少量のハイパーシン,ホルンブレンド,黒雲母,チタン磁鉄鉱,硫化鉱物を伴う.「結晶成長部」の最下部(底部から40−45m付近)では,斜長石と普通輝石,カンラン石の量比が約10cmの周期で変化するリズミカルな層状構造が観察できる(第7図).斜長石に富む層では,斜長石結晶が層状構造に平行に定向配列する.層状構造が認められるあたりから,厚さ平均5cm,横幅平均20cm程度の小さな「波状ペグマタイト脈」が次第に出現しはじめ,岩体内部に向かうにつれそのサイズが大きくなっていく.「波状ペグマタイト脈」は3次元的にはレンズ状をしており,脈の上部は斜長石に富む優白質部,下部は普通輝石とカンラン石に富む優黒質部で構成される(第7図).優白質部と優黒質部の比率は一定ではなく,優白質部を有さずほぼ優黒質部のみで構成されるものもある.また脈の優白質部がプリューム状構造をしたものも認められる.我々はこうした産状から,先に述べた斜長岩質脈だけでなく,波状ペグマタイト脈からも斜長岩質マッシュがプリュームとして上昇していたと考えている.
カンラン石ハンレイ岩の中部(底部から60−80m付近)になると,カンラン石は粗大化し,かつモードも増加する(第3図).このあたりでは,先の波状ペグマタイト脈はあまり見られなくなり,代わりにシルの層構造にほぼ調和的に厚さ10cm〜1mの斜長岩質脈が分布する(第6図).斜長岩脈は,下面が平坦で上面が波状構造をしており,脈内の斜長石結晶が脈の外形に沿って定向配列する.鏡下では斜長石と普通輝石のオフィティック組織を呈し,カンラン石は認められない.さらに岩体の内部へ向かうと再び波状ペグマタイト脈が多く分布するようになる.しかし底部から40−45m付近に分布しているものと比べるとそのサイズは大きい.
Stop 3 粗粒ハンレイ岩
[地形図]1/2.5万「室戸岬」及び1/2500「室戸市都市計画平面図9」
[位置]室戸岬突端の中岡慎太郎像前から国道55号を西に約150m進み,北西へ右折するカーブに差し掛かった所から車道を離れ海岸へ向かって南に下ると,粗粒ハンレイ岩が分布する(第10図).
第13図.粗粒ハンレイ岩Ⅰの露頭写真(Stop 3).
第1表室戸岬ハンレイ岩体の代表的な岩石の全岩化学組成.Fe2O3*は,全鉄を3価として計算した値.岩型名(Rock type)の略称は第2図に同じ.データは赤塚ほか(1999)より.
[解説]粗粒ハンレイ岩は本岩体中最も分化した岩石(第1表)で,岩体の中央部(底部から100−180m)に位置する.本岩相は,Yajima(1972a, b)や赤塚ほか( 1 9 9 9 )の「ハンレイ岩質ペグマタイト( G a b b r opegmatite)」に相当する.粗粒ハンレイ岩は主として斜長石と普通輝石からなり,その他少量のホルンブレンド,黒雲母,アパタイト,及び磁鉄鉱を含むが,カンラン石は認められない.粗粒ハンレイ岩は岩石組織により2つのサブタイプ−粗粒ハンレイ岩Ⅰ,Ⅱ−に分けられる.粗粒ハンレイ岩Ⅰは岩体底部から120−180mの位置に露出し,1〜2cm大の自形の斜長石を普通輝石が取り囲むオフィティック組織を呈する.粗粒ハンレイ岩Ⅰの風化面には,直径5〜10cm程度の窪みが斑点状に分布する(第13図).この窪みの部分は,その周囲より普通輝石やホルンブレンドに富む.
粗粒ハンレイ岩Ⅱは底部から110−120m付近に転石としてのみ見出される.周囲の岩相との関係は露頭状況が悪く不明である.0.5〜3cm大の自形の普通輝石の粒間を,1〜2cm大の他形の斜長石が埋める組織を呈する.本岩相中の普通輝石は双晶をなすことが普通である.
第14図.Stop 4, 5付近の地形図.国土地理院発行1/2.5万地形図「室戸岬」の一部に加筆.
第15図.上部急冷周縁相に見られるドレライトブロックのスケッチ(Stop 4).上から俯瞰している.
第16図.岩体天井部付近(上部境界から4m)のカンラン石ハンレイ岩中に分布する角閃石のクロット(Stop 4).ハンマー左側のクロットを一部縁取りしてある.
Stop 4 マグマ貫入による接触変成と部分溶融,及び上部カンラン石ハンレイ岩中の角閃石クロットの分布[地形図]1/2.5万「室戸岬」及び1/2500「室戸市都市計画平面図9」
[位置]室戸岬突端から東海岸に沿って国道55号を700−800m程進んだところに,空海が若い頃に篭もって修行したと伝えられている洞窟「御み蔵くろ洞ど」がある.この御蔵洞前から海沿いの乱礁遊歩道に入り北へ50 m程歩いた所に,本岩体天井部と壁岩の境界(上部境界)が露出している(第14図).その他に岬東海岸のコビシャゴ岩,ビシャゴ岩付近や,岬西海岸(月見が浜)にも上部境界が露出する.
[解説]上部境界では,下部境界のように急冷周縁玄武岩と壁岩が指向状に入り組んだ構造は見られず,境界はマクロにはシャープである.しかし,壁岩から本岩体に向かって,幅数10cm〜1m程の優白質岩脈が貫入する.この岩脈は,石英長石質の完晶質粗粒な岩石で,微文象構造を呈するものもある.また上部境界でも下部境界と同様,急冷周縁相の岩片が壁岩に多数包有されている(第15図).Yajima(1972a)はこの産状から,玄武岩質マグマの貫入により壁岩が溶融したが,花崗岩組成の壁岩は融点の高い玄武岩質マグマが固結した後も流動的であったために,先に固結した急冷周縁相の破壊によって生じた岩片を取り込むことができたと考えた.また上部急冷周縁相〜上部カンラン石ハンレイ岩には,直径数mm〜3cm程度の青緑色球体(クロット)が多数分布する(第16図).この球体を鏡下で観察すると,淡緑色のホルンブレンド〜アクチノ閃石が放射状に集合している.マグマ分化時の水の存在と上方移動を示唆する興味深い組織である.
Stop 5 ハンレイ岩体先端部の玄武岩質岩脈群
[地形図]1/2.5万「室戸岬」及び1/2500「室戸市都市計画平面図9」
[位置]本ハンレイ岩体から分かれた多数の玄武岩質岩脈群が,御蔵洞から国道55号を北へ400mほどの所にある,ホテル明星あけのほし横の海岸に分布する(第14図).
[解説]多数の玄武岩質岩脈が堆積岩に板状に貫入している(第17図-A).岩脈の厚さは10〜30cm程度で,急冷縁と流理構造が認められる.本岩脈周囲の堆積岩や,ハンレイ岩体上下境界近傍の堆積岩中には,直径数cm大の球状の団塊が特徴的に分布している(第17図-B).
第17図(A)ハンレイ岩体先端部の玄武岩質岩脈群の堆積岩への貫入(Stop 5).スケールの折れ尺は長さ20cm(B)下部急冷周縁相周辺の堆積岩中に分布する球状団塊(Stop 1,5).
謝 辞
室戸岬ガブロの研究成果の多くは,赤塚貴史氏(地熱エンジニアリング株式会社)との共同研究に負っている.村田明広教授(徳島大学)には原稿を校閲していただいた.室戸市役所観光深層水課,高知県安芸土木事務所,高知県文化環境部自然共生課の方々には,現地での試料採取許可申請手続きの際に大変お世話になった.現地では民宿室戸荘の方々にお世話になった.以上の方々と関係機関各位に感謝します.
文 献
赤塚貴史・小畑正明・横瀬久芳,1999,室戸岬ハンレイ岩体の層状構造,特にピクライト質ハンレイ岩層の成因について—結晶の集積・分別効果の定量的検討—.地質雑,105,__________771-788.
Boudreau, A.E., 1999, PELE - A version of the MELTSsoftware program for the PC platform. Comp. Geosci.,25, 21-203.
浜本礼子・酒井治孝,1987,室戸岬ハンレイ岩体に伴う文象斑岩のRb-Sr年令.九大理研報(地質),15,131-135.
Hibbard, J., Karig, D. and Taira, A., 1992, Anomalousstructural evolution of the Shimanto Accretionary Prismat Murotomisaki, Shikoku Island, Japan, Island Arc, 1,133-147.
Hoshide, T., Obata, M. and Akatsuka, T., 2006a, Crystalsettling and crystal growth of olivine in the magmaticdifferentiation - the Murotomisaki Gabbroic Complex,Shikoku, Japan -. Jour. Mineral. Petrol. Sci., 101, 223-240.
Hoshide, T., Obata, M. and Akatsuka, T., 2006b, Magmaticdifferentiation by means of segregation and diapiricascent of anorthositic crystal mush- the MurotomisakiGabbroic Complex, Shikoku, Japan. Jour. Mineral.Petrol. Sci., in press.
Kodama, K. and Koyano, T., 2003, Paleomagnetism andmagnetic fabric of a mafic intrusive body andsurrounding sedimentary rocks in the shimanto belt,southwest japan: structural evolution of an accretionaryprism recorded in magnetization of fore-arc intrusiverocks. IUGG 2003 Scientific Program.
Kuritani, T., 1998, Boundary layer crystallization in a basalticmagma chamber: evidence from Rishiri Volcano,northern Japan. Jour. Petrol., 39, 1619-1640.
Langmuir, C., 1989, Geochemical consequences of in situcrystallization. Nature, 340, 199-205.
McBirney, A.R. and Noyes, R.M., 1979, Crystallization andlayering of the Skaergaard intrusion. Jour. Petrol., 20,487-554.
三宅康幸,1983,前弧堆積盆内に形成された室戸岬斑レイ岩体.Magma,69,10-14.
Shinjoe, H., 1997, Origin of the granodiorite in the forearcregion of southwest Japan: Melting of the Shimantoaccretionary prism. Chem. Geol., 134, 237-255.
新正裕尚・角井朝昭・折橋裕二,2003,西南日本弧の海溝寄り地域における中新世中期火成活動:熱い四国海盆沈み込みとの関連.月刊地球号外,no.43, 31-38.
Tait, S. and Jaupart, C., 1989, Compositional convection inviscous melts. Nature, 338, 571-574.
高橋正樹,1986,日本海拡大前後の島弧マグマ活動,科学,56,103-111.
Wager, L.R. and Brown, G.M., 1968, Layered Igneous Rocks.588 pp., Oliver and Boyd, Edinburgh.Yajima, T., 1972a, Petrology of the Murotomisaki gabbroiccomplex. Jour. Japan. Assoc. Min. Pet. Econ. Geol., 67,218-241.
Yajima, T., 1972b, Petrochemistry of the Murotomisakigabbroic complex. Jour. Japan. Assoc. Min. Pet. Econ.Geol., 67, 247-261.
Yajima, T., Kajima, M. and Nagamura, Y., 1977, On the roleof igneous activities in the tectonic movement, withspecial reference to the Muroto peninsula igneous zone.Jour. Geol. Soc. Japan, 83, 395–09.
Yoshizawa, H., 1953, On the gabbro of the Muroto, Shikokuisland, Japan. Part Ⅰ. Mem. Coll. Sci., Univ. Kyoto., Ser.B, 20, no.4, 271-284.
Yoshizawa, H., 1954, On the gabbro of the Muroto, Shikokuisland, Japan. Part Ⅱ. Mem. Coll. Sci., Univ. Kyoto., Ser.B, 21, no.2, 193-212.
本稿は「岩井雅夫・村田明広・吉村康隆,2006,見学旅行案内書,地質学雑誌,112,補講,170pp」がオリジナルです。
■ オリジナルPDFダウンロード(J-Stageサーバー)
巡検案内:沈み込みプレート境界地震発生帯破壊変形と流体移動:高知県西部白亜系四万十帯,興津,久礼,横浪メランジュ
沈み込みプレート境界地震発生帯破壊変形と流体移動:高知県西部白亜系四万十帯,興津,久礼,横浪メランジュ*
Seismogenic fault-rock and fluid flow in ancient subduction zone: Field guide of Okitsu, Kure andYokonami Melanges, Cretaceous Shimanto accretionary complex, Shikoku, Japan
坂口有人1 橋本善孝2向吉秀樹3 横田崇輔2高木美恵2 菊池岳人2
Arito Sakaguchi 1, Yoshitaka Hashimoto2,Hideki Mukoyoshi 3, Sosuke Yokota2, Mie Takagi 2, and Taketo Kikuchi 2
受付:2006年7月14日 受理:2006年8月7日
*日本地質学会第113年学術大会(2006年・高知)見学旅行(E班)案内書
1.独立行政法人海洋研究開発機構地球内部変動研究センター
Institute for Research on Earth Evolution,Japan Agency for Marine-Earth Science andTechnology
2.高知大学理学部自然環境科学科
Department of Natural EnvironmentalScience, Faculty of Science, Kochi University
3.株式会社マリン・ワーク・ジャパン
Marine Works Japan Ltd.Corresponding author: A. Sakaguchi,E-mail: arito@jamstec.go.jp
概 要
四万十帯における構造地質学的調査,温度圧力条件分析等の進展は,四万十帯が沈み込み帯の震源領域で形成されたことを明らかにした.そして四万十帯において典型的な地震性断層岩であるシュードタキライトが次々に発見され,海溝型巨大地震発生メカニズム解明の地質学的アプローチが可能となった.本巡検では,四万十帯に発達する変形構造(沈み込みから底付け作用,アウトオブシークエンススラストおよび地震に関わる変形岩),流体移動の痕跡である鉱物脈の産状等を観察し,室内分析による基礎データ(マップスケール分布,温度・圧力,差応力など)をもとに議論を行う.
Key Words
付加体,断層岩,シュードタキライト,流体,沈み込み帯
accretionary complexes, fault rocks, pseudotachylyte, fluid, subduction zone
地形図
1: 25,000 「窪川」「久礼」「土佐高岡」
見学コース
1日目午前:興津断層午後:久礼メランジュ,久礼OST
2日目終日:横浪メランジュ
見学地点
Stop 1 興津メランジュ.
Stop 2 久礼OST系.
Stop 3 久礼メランジュ.
Stop 4 横波メランジュ.
1.はじめに
1980年代に四万十帯が付加体であることが示されて以来(平ほか,1980),年代学,構造地質学,岩石学,古地磁気学,地球化学,その他数多くの分野から研究され,その形成プロセスが詳細に議論されるようになってきた.とりわけ四万十帯研究のユニークな点として,南海トラフをはじめとする現世付加体の海洋調査と共に発展してきたことが挙げられよう.
四万十帯は当初,斜面海盆堆積体や付加体先端の浅い部分が露出しているものと漠然と想像されてきた(平ほか,1980など).しかしながら構造地質学的解析が進むに連れて,付加プリズム先端で剥ぎ取られたユニット(Ujiie et al., 1997),大規模なデュープレックス構造に代表される底付けされたユニット(村田,1991;Kanoet al., 1991; Onishi and Kimura, 1995;Hashimoto andKimura, 1999;Ujiie et al., 2000)などが区分され,詳細な形成プロセスが議論されるようになった.また,付加プリズムの厚化に大きく貢献していると考えられている,アウトオブシーケンススラスト(Out of SequenceT h r u s t ,以下O S T )も認識されるようになり(Underwood et al., 1993;木村,1998),四万十帯には付加プリズムの比較的深い部分も露出していることが示された.また,四万十帯の温度圧力条件に関しては,緑色岩の鉱物組み合わせ(Toriumi and Teruya, 1988),ビトリナイト反射率(Mori and Taguchi, 1988; Ohmoriet al., 1997),曹長石化グレード(公文,1992),イライト結晶度(Awan and Kimura, 1996),流体包有物(Sakaguchi, 1996, 1999; Hashimoto et al., 2002, 2003;Matsumura et al., 2003),イライト/雲母b0値(Underwood, et al., 1993)などの手法による分析がなされ,四万十帯が少なくとも150℃以上,高い部分では300℃以上の温度領域で形成されたことが明らかになった.この地質温度計と構造地質学的手法とを組み合わせて,上盤/下盤の温度差から,OSTの中でも累積変位が特に大きい断層が注目されるようになった(Ohmoriet al., 1997; 木村,1988; Kondo et al., 2005; Mukoyoshiet al., 2006).
一方,南海トラフの海側延長である南海トラフ付加体における詳細な構造探査が進展するに連れて,1944年の東南海地震,1946年の南海地震の破壊領域の上限付近は,底付け付加が開始される深度であり,かつ大規模なOSTが発達している領域であることが示されるようになった(Park et al., 2002).そして1944年の東南海地震時の地震波および津波の逆解法による断層破壊エリアは(Ichinose et al., 2003; Baba and Cummins, 2005),熊野灘沖の大規模なOSTの分布と一致し,このOSTが震源断層であると考えられている(Baba and Cummins,2005).また南海トラフ沿いの巨大地震発生帯の上限と下限の分布が,プレート境界面における150℃から350℃の等温線と一致し,沈み込み帯断層の非地震性・地震性すべりの遷移は温度に依存するものと考えられるようになった(Hyndman et al., 1993; Moore and Saffer, 2001).この地震発生帯の温度領域とテクトニックセッティングは,まさに四万十帯の構造と温度領域と一致する.そのため,四万十帯に沈み込み帯地震発生帯の上限付近が露出しているであろうと考えられるようになった(木村,1997;狩野,1999).
こういった背景の中,地震性高速すべりを典型的な証拠とされているシュードタキライト(Sibson, 1975など)が,沈み込み帯としては初めて四国西部四万十帯の興津メランジュにおいて発見された(Ikesawa et al., 2003).そしてこれを皮切りに同四国西部の久礼メランジュ(Mukoyoshi et al., 2006),四国東部の牟岐メランジュ(Kitamura et al., 2005),そして九州の延岡構造線(Kondo et al., 2005)においても次々と報告され,四万十帯は沈み込み帯の地震発生領域という新しい視点で研究されるようになった.
断層岩の研究は,これまで内陸断層を中心に長年にわたって実に数多くの研究が成されてきた(Sibson, 1977など).それに対して付加体における沈み込み帯型の断層岩研究は,まさに途に就いたところである.しかし付加体の断層は,構造,構成鉱物,そして豊富な流体の存在など内陸断層とは異なる特徴も多い.本巡検では,地震発生帯としての四万十帯の深部構造,変形組織,流体移動の痕跡,そして震源断層の産状などを紹介する.
第1図.白亜系四国四万十帯の大正層群.付加体の変形・流体移動様式が典型的に露出する横浪メランジュ,沈み込み帯の震源断層が露出する興津メランジュ,久礼メランジュ周辺を観察する.図下方に断面と熱構造を図示した.ビトリナイト反射率はBTLから南へ上昇し,久礼OSTで急低下する.この熱構造パターンは付加年代・変形・岩相とは一致しない.興津メランジュは周辺層よりも高い温度を受けた.そしていずれの地域であっても南海トラフで考えられている地震発生領域の温度条件の範囲内にある.
2.地質概説
四国の白亜系四万十帯は北は仏像構造線によってジュラ系の秩父帯と接し,南は安芸構造線によって第三系四万十帯と接しており,白亜紀前期に付加した新荘川層群と後期に付加した大正層群から構成される.コニアシアンからマーストリヒチアンの大正層群は厚いタービダイト相(下津井,野々川,中村,有岡層)と,それに挟み込まれるように分布するメランジュ相(横浪,久礼,興津メランジュ)から構成される(平ほか,1980)(第1図).大正層群のタービダイト相は,一般に砂岩優勢の砂岩泥岩互層からなるが,一部に多色頁岩を含み,おおむね北東走向で北に急傾斜する.有岡層を除けば,露頭スケールの変形は比較的少ない.横波,久礼,興津の3つのメランジュ相は葉片状鉱物が配列する鱗片状劈開と圧力溶解によるスレート劈開が発達する黒色頁岩を基質として,玄武岩,チャート,多色頁岩等の遠洋性から半遠洋性の岩体がブロック状に含まれることで特徴づけられる.四万十帯から秩父帯のメランジュは,これまでに微化石年代および古地磁気学的手法によって,形成時の海洋底層序や玄武岩の噴出緯度が詳細に議論されている.それによると玄武岩の噴出から付加までの堆積年代差,すなわちプレートの移動時間は秩父帯から四万十帯南帯にかけて徐々に短くなっていることを意味し(Taira etal., 1988),白亜紀後期から始新世にかけて,かなり若いプレートが沈み込んでいたものと解釈されている.メランジュは,概ね1km程度の厚さで,比較的変形の弱いタービダイト相に挟まれるように産する.一般に剪断された黒色頁岩を基質にし,鱗片状もしくはスレート劈開が発達しており,その表面には条線が多く見られる(Shibata and Hashimoto, 2005).様々なスケールで非対称な褶曲構造やブーディン構造が発達しており,他の地域の四万十帯では,これらの非対称変形組織からメランジュ形成期における剪断センスが復元され,古プレートモーションとの対比も試みらている(Kano et al.,1991; Onishi and Kimura, 1995など).また,一部には泥の注入脈や未固結変形に特徴的な粒界すべりによる変形組織が観察される一方で,脆性破壊を伴う断層や,圧力溶解変形による岩塊の回転組織なども産し,付加体浅部から深部にかけて累進的に変形作用を被ってきたことを示唆する.
ビトリナイト反射率(Ro)地質温度計による熱構造分析の結果,この地域の四万十帯の被熱温度は北から南へ15kmほどの間にRo=1.0%(約150℃)からRo=2.2%(約230℃)へと緩やかに上昇し,特定の断層でRo=1.0%(約150℃)に急低下して再び南へ緩やかに上昇するという,ノコギリ刃のパターンを示すことが示されている(第1図)(坂口ほか,1992).熱構造パターンが,新荘川層群と大正層群といった付加年代の違いや,メランジュとタービダイト相といった岩相・変形の違いから独立していることは特筆されるべきことである.四国東部の四万十帯では,フィッショントラックによる熱史が検討されており,そこでも堆積年代や岩相とは独立に,四万十帯が広範囲に白亜紀後期以降のエピソディックな熱年代が示されている(Hasebe et al., 1993; Tagami et al.,1995).また粘土鉱物のK-Ar年代では始新世の被熱年代が示されている(Agar, 1989).坂口ほか(1992)やSakaguchi et al.(1996)は,一連の熱構造に新荘川層群の堂ヶ奈路層といった前弧海盆堆積相までも高い温度を受けていることから,エピソディックな埋没・隆起作用というよりも,沈み込み帯の地殻熱流量の変化によるもので,白亜紀後期から始新世にかけての若いプレートの沈み込みにその原因を求めた.
以上のように本地域には,比較的若いプレートの沈み込みに伴う,付加体の先端から地震発生帯に至る深さまでの変形過程が記録されており,そのテクトニックな特徴は,若い四国海盆が沈み込んでいる現世南海トラフ地震発生帯の特徴とよく似ている.
3.見学地点各説
第2図.デュープレックス構造を有する興津メランジュの地質図.ルーフスラスト,底付けユニットの上部にシュードタキライトを含む震源断層が発達する.
第3図.模式的テクトニックセッティング.興津断層はデュープレックス構造のルーフスラストに相当し,付加体底付けユニットの上部に位置する.久礼OST系は,浅部のスプレー状に分岐している部分を見ているものと考えられる.
Stop 1
[地形図]1/2.5万 「窪川」
[位置]小鶴津の北東の道路分岐に駐車.海岸へ降りて南西へ徒歩10分程度.
[解説]興津メランジュは,北の野々川層と南の中村層に挟まれた幅約1kmに分布し,チャートに乏しく,緑色岩が多量に産することで大正層群の他のメランジュと区別される.黒色頁岩を基質とし,ブロック状に遠洋性岩体が含まれる.黒色頁岩には若干の凝灰岩層や砂岩層がレンズ状に含まれ,露頭スケールでは分断されて連続性が良くない.しかしながら地質図スケールでは,玄武岩層や黒色頁岩優勢の部層は側方に連続的に追跡可能であり,厚さ数10m〜数100mの海洋底層序が少なくとも5回覆瓦状に繰り返される大規模なデュープレックス構造が描き出される.
興津メランジュと北側の野々川層とを境する興津断層(新称)は,シュードタキライトを産する震源断層として特徴づけられる.断層は地質図スケールのデュープレックス構造のルーフ断層に相当する(第2,3図).断層は,高知県四万十町小鶴津周辺に模式的に露出し,平均方位はN55°E,80°Nとメランジュの面構造の平均方位N55°E,70゜Nとほぼ平行で,南西の興津集落付近まで追跡できる.傾斜は露頭によって北に中傾斜から垂直近くまであるが,地質図上は地形に左右されることなくほぼ北東走向に分布するので,大局的には垂直に近い.断層は砂岩優勢の野々川層とスレート劈開が発達した黒色頁岩優勢の興津メランジュとの境界にあり,断層沿いに玄武岩のブロックが散在するが,メランジュ中の他の玄武岩よりも変質している.断層変形帯の厚さは,断層沿いに10数mから数10cmまで変化する.断層表面には多くの条線やS-C状組織等の非対称組織が数多く見られ,複合面構造によるスラストの衝上センスはN20°E,40°Nである.
興津断層は,東端の小鶴津周辺の海岸において長さ30mにわたって非常に良く露出している(第4図).この露頭においては傾斜は北に約45°で,断層帯は変形変質が特に著しい幅5〜6mの断層コアと,主断層に平行な小断層と層平行剪断に伴う褶曲構造などが上盤側の野々川層に約10mにわたって見られる.下盤は興津メランジュになるが,断層変形よりも古いメランジュ形成ステージの変形構造が卓越し,断層はこれと一部斜交している.しかし断層と関連する変形は不明確で,断層コアを挟んで上盤側にだけ変形が顕著に見られる.
第4図.興津断層のルートマップ.図2の地質図東端の海岸に,シュードタキライトを多く含む部分が露出している.断層コアは変質した玄武岩ブロックと変形集中帯から成り,その下部にシュードタキライトが多産する.上盤側に主断層に平行な断層や断層に伴う褶曲(矢印A),変形が発達する.断層は一部メランジュファブリックと斜交する(矢印B).している部分を見ているものと考えられる.
第5図.(A)震源断層の露頭全景.(B)変形集中帯.カタクレーサイトと鉱物脈が多産し,それらは圧力溶解によって塑性的な変形を被り,S-C状変形組織をなす.(C)そういった断層岩をシュードタキライト(写真中央の黒い筋)が切る.(D)シュードタキライトの薄片写真.シュードタキライト断層脈沿いに融解に伴う湾入構造や注入脈が見られる.矢印は古いシュードタキライトを新しいシュードタキライト注入脈が切っている部分を指す.
断層コアは,シュードタキライトを含むカタクレーサイト,著しく変質した玄武岩ブロック,石英およびアンケライト鉱物脈が多産することで特徴づけられる.特に鉄・マンガンに富むドロマイトのアンケライトの風化のために露頭全体が赤茶けた様相を呈する(第5図A, B).断層コアには幅約20〜30cm程度の変形集中帯が少なくとも4層発達しており,玄武岩ブロックを挟んで,分岐もしくは合流して産する.この変形集中帯は,カタクレーサイト,岩片,鉱物脈がS-C変形組織状に配列している.鏡下ではS面に岩片や鉱物脈中に不溶性物質が縫合線状に濃集するスタイロライトフォリエーションが発達しており,圧力溶解機構による塑性変形によって非対称変形組織が形成されたものと考えられる(第5図C, D).C面と平行にシュードタキライト断層脈は産し,古いシュードタキライトや鉱物脈を切るシュードタキライト注入脈が認められており,地震性すべりが繰り返されたことを示している(第5図D).
変形集中帯にはアンケライトと石英の鉱物脈が多産する.石英とアンケライトの鉱物脈には,同一脈のある部分では石英が,またある部分ではアンケライトが自形を持ち,他方が他形を持つという産状を示すものがある.これは,双方が過飽和にあり,同じ時期に沈殿したためと考えられている(坂口,2003).また,鉱物脈にはジグソーパズル組織の岩片も含まれ,破砕岩片が基質の脈鉱物によって支持されているものもある.これはいわゆるimplosion breccia (Sibson, 1986)と解釈され,水圧破砕と急速な沈殿が生じたものと考えられる(坂口,2003).また,断層沿いの玄武岩は著しく変質しており,その平均モード組成は炭酸塩鉱物類が約62%,粘土・沸石類が約7%,緑泥石鉱物類が約16%,不透明鉱物約4%,石英・その他が約3%であり,斜長石類や輝石類などの源源岩鉱物は約8%しか残されていない.急冷組織や産状から玄武岩であったものと考えている.また鉱物脈沿いにはブドウ石・パンペリー石が産し,ビトリナイト反射率Ro=3.2%(約270℃)(Sakaguchi, 1996)と調和的な温度を示す.また,イライト結晶度では,断層付近はIC値0.33-0.38と,周辺層の0.35-0.44よりも高い値であり,断層沿い高温の流体が移動していたものと考えられる.それはおそらくCO2に富み,そのために玄武岩は炭酸塩優勢の変質作用を被ったのであろう.断層帯の透水率は,約10-15m2〜10-16m2程度であるが,封圧105-140MPa,250℃で10時間保持したところ約1桁も低下することが報告されている(Kato et al., 2004).これは鉱物の溶解沈殿作用に起因するものと解釈されており,それらが空隙率や間隙水圧をはじめ,力学挙動に影響する可能性がある.
第6図.久礼メランジュ周辺の地質図.久礼OSTは,複数のスラストからなり,下津井層,久礼メランジュ,野々川層と斜交し雁行状に配列する.付加体後期形成されたスラストであり、熱構造解析に基づく累積変位量は、周辺の他のスラストよりもとりわけ大きく、OSTと解釈されている(Mukoyoshi, etal., 2006).圧縮場における杉型の雁行状配列であることから左横ずれセンスを伴ったものであろう.ビトリナイト反射率は,この久礼OST系を挟んでRo=2.2%からRo=1.0%へと大きく低下する.久礼南方の大津崎周辺に断層は典型的に露出し,岬南部の海岸の断層露頭でシュードタキライトが見出された.
Stop 2
[地形図]1/2.5万 「久礼」
[位置]清水と若瀬の間の農道を東へ.海岸付近の球場手前に駐車.
[解説]久礼OST系(Mukoyoshi et al., 2006)は,久礼メランジュとその周辺層と斜交して発達している.下津井層,久礼メランジュ,野々川層が概ね東西から東北東走向,北に急傾斜に配列しているのに対して,久礼OST系は北東走向,北中程度に傾斜しており,下津井層,久礼メランジュそして野々川層のいずれとも低角に切っており,これら地質体定置後に発達した後期の断層であることを示している.OST系は,幅約1kmの範囲内に雁行状に配列し,小断層まで含めるとかなりの数の断層が発達している(第6図).
ビトリナイト反射率による熱構造解析においても,BTLから約15kmかけてRo=1.0%(約150℃)から2.1%(約230℃)まで上昇してきたビトリナイト反射率が,幅1km弱のOST系を挟んでRo=1.0にまで急減する(第1図).このような熱構造パターンは,最高被熱後に,断層を挟んで上盤側が衝上した累積変位が,周辺の他の断層よりもはるかに大きいことを意味している.類似の熱構造パターンは,安芸構造線や延岡構造線とった四万十帯の他の地域でも報告されている(Mori and Taguchi,1988; Ohmori et al., 1997; Kondo et al., 2005).久礼OST系は,他のOSTと比較して段階的にRoが低下することで特徴付けられる.例えば延岡構造線は,わずか数10cmの厚さの破砕帯を境して急変するが(Kondo et al.,2005),久礼OST系は雁行状に配列する個々の断層が少しづつの変位によって,断層系全体として大きな変位が認められる(Mukoyoshi et al., 2006).また,逆断層の下盤の埋没深度は,断層形成深度の下限を意味し,久礼OST系の下盤のRo=1.0%(約150℃)の被熱温度は,四万十帯でも最も低い温度に相当するため,他の地域のOSTよりも浅いことを示す.また,複数の断層系に分岐していることも一般的な断層浅部の様式と対比できるため,久礼OST系は津波を伴うような海底浅部の断層を見ていると解釈されている(第3図)(Mukoyoshi etal., 2006).
第7図.(A)シュードタキライトを含む,久礼OSTの露頭全景.断層は緩傾斜で,周辺層と斜交する.(B)断層は幅数10cm程度のカタクレーサイトと黒色の薄いシュードタキライトからなる.(C)反射電子像では,基質ガラス中に白雲母成分の晶出鉱物が見られる.(D)斜長石の岩片が部分溶融している.
久礼OST系は,中土佐町久礼南方の大津崎周辺に典型的に露出している.各断層は,幅は概ね1m程度の破砕帯を有し,その中心部には幅数mm程度に変形が局所化したものもあり,そのうちの一つからはシュードタキライトが確認されている.シュードタキライトは幅数10cmの砂岩のカタクレーサイト中にシャープで薄い断層脈として産する.鏡下においては透明のガラスに黒色の微小粒子が散在する基質と,円礫状の岩片が観察される.電子顕微鏡観察では,部分融解組織のアルバイトやカリ長石,気泡,晶出した針状の白雲母などが観察され(第7図),石英やアノーサイトには融解組織がないことから,摩擦加熱の到達温度は650〜1100℃と推測されている(Mukoyoshi et al., 2006).
Stop 3
[地形図]1/2.5万 「久礼」
[位置]高知県中土佐町土佐久礼漁港の南西.ホテル「黒潮本陣」の真下に位置する海岸.
[解説]久礼メランジュは南北に約1km程度の幅を持つ.断層を境にして,北に下津井層,南に野々川層といった砂泥互層を主体とするコヒーレント層に挟まれている(第1図)年代はチャートからアルビアンからセノマニアン,陸源性堆積物からカンパニアンと報告されている(Taira et al., 1988).久礼メランジュは主に砂岩ブロックが泥岩マトリックスに取り囲まれる,陸源性堆積物主体のメランジュからなり,稀に玄武岩,凝灰岩,チャート,多色頁岩を含む.泥岩マトリックス中には強く発達した面構造が見られ,非対称ブロックや複合面構造などが観察されることから,メランジュ組織を示すブロック化の成因は構造性と考えられる.面構造の走向傾斜はおよそEW,80°Sである.ビトリナイト反射率から推定された過去の最高被熱は約230℃程度と報告されている(Mukoyoshi et al., 2003 ).
第8図に海岸域のルートマップを示す.ほぼ中央に海没する場所があり,北部と南部は別の入り口から入る必要がある.北部と南部は砂岩泥岩からなるメランジュで,稀に凝灰岩を含む.本地域に見られる玄武岩は陸源性堆積物を挟んで4回繰り返し,それぞれBK1,2,3,4と呼ぶことにする. BK-1の北端は断層で砂岩泥岩からなるメランジュと接している.BK-2の南端は玄武岩,チャート,泥岩が複雑に混合した変形帯をなしており,底付け付加時に玄武岩基底が泥岩に逆断層で乗り上げた際に下盤の泥岩やチャートが混合したものと考えられる.この解釈は後述する変形構造に伴う鉱物脈からの温度圧力条件と矛盾しない.この変形帯は後に詳述する.BK-3の北端では,チャート,遠洋性堆積物が玄武岩の北側に露出しており,海洋底層序の堆積関係を示している.一方,BK-3の南端は数mm〜数cmの玄武岩と泥岩の薄層の互層をなしており,やはり,底付け剪断時の混合を示す.一方,BK4は北端も南端も断層関係である.また,BK-4の南部にはおよそ10m程度に渡って数mmから数cmの砂岩円レキからなるメランジュ様の泥質岩が露出している.これらは,伸びた非対称ブロックを特徴的に示す構造性メランジュとは明らかに異なる産状であり,海底地滑りなどを起源とするものである可能性も考えられる.BK-1の南端およびBK-2の北端は,挟在する岩石が複雑に混合しており,不明瞭である.
第8図.久礼メランジュ海岸域のルートマップ.
底付け剪断帯(BK-2南端)
BK-2南端には顕著な底付け剪断帯が露出している.構成岩石は玄武岩,チャート,泥岩であり,複雑に混合している.玄武岩はブロック状であるが,玄武岩質な細粒マトリックスをなしているものも見られる.基本的にマトリックスはこの玄武岩質な細粒物からなる.チャートは鮮やかな赤色で,熱水性チャートと考えられる.泥岩は玄武岩質な細粒マトリックスと波状に接しており,全体として定向配列し,縦横比が大きい.玄武岩やチャートのブロックは大きいもので50cm程度の長軸を持ち矩形をなすものから,直径約数cmの小さなものまで様々である.形状は亜角礫である.全体として非常に激しく変形しているものの,大きく見ると,変形帯南部に玄武岩,チャート,北部に泥岩が走行方向に分布している.
第9図.久礼地域における鉱物脈の産状.横の行:Underthrustingは砂岩泥岩からなる構造性メランジュ中の鉱物脈.Underplatingは第11図における底付けせん断帯における鉱物脈.縦の列:open crackveinは引っ張り割れ目を埋める鉱物脈.Shear veinは小断層に沿って発達する鉱物脈.写真には鉱物脈の微細構造を記している.詳細は本文を参照のこと.
鉱物脈の産状
鉱物脈はメランジュ中に稀に観察される一方,底付け剪断帯などには比較的よく集中している.構成鉱物は石英と方解石である.鉱物脈は,1)面構造の走向に直行する引っぱり割れ目,と2)面構造に斜交あるいは平行な剪断面に発達するものの二つに大きく分けられる.これらの鉱物脈は,構造性メランジュ中にも,底付け剪断帯中にも見られる(第9図).砂岩泥岩からなる構造性メランジュ中の引っぱり割れ目は久礼地域では非常に稀であるが,一般に砂岩ブロックのみを切っており,泥質マトリックスに切られている.このような産状はこのような引っぱり割れ目がメランジュ形成時期と同時期であったことを示唆している.底付け剪断帯では,2)の鉱物脈が複雑な切断関係にあり,複数の発達ステージがあったことが推定される.最終ステージで全体を切るようなNW-SE走向の断層には非常に厚い(数cm)の鉱物脈が付随する.また,底付け剪断帯中にはブロック化した鉱物脈も含まれており,鉱物脈の沈殿と断層帯の活動,およびその後の小断層の形成など,変形と流体からの沈殿が複雑に繰り返している事を示している.このような2)の鉱物脈の切断関係はメランジュ中では認められない.これは鉱物脈の密度が小さいために関係を示す証拠が少ないことに起因していると考えられる.微細組織にも2種類認められた.一つはelongate blockyな組織で多くは壁岩に細流な石英があり,内部により粗流な方解石が一つの脈に混合している(第10図A).もう一つは石英粒子がdisaggregateしたと見られる隙間を方解石がセメントのように埋めている組織で(第10図B),本論ではcalcite cemented textureと呼ぶ事にする.このようなcalcite cemented textureは底付け剪断帯の剪断面に伴う鉱物脈のみが有しており,メランジュ中の2種類の鉱物脈と底付け剪断帯中の引っぱり割れ目を埋める鉱物脈はelongate blockyな組織を示す(第9図).
第10図.鉱物脈の微細構造の薄片写真.(A)Elongate blocky texture,(B)Calcite cemented texture.
流体包有物による温度圧力の推定
四万十帯の鉱物脈中に捕獲された流体包有物は水とメタンの包有物からなる.この共存関係は水がメタンに飽和していた仮定を設けることができる(Vrolijik et al.,1988).この仮定の上で,両者の均質化温度から温度圧力を一義的に得る事ができる.
本調査地域では上述した鉱物脈の分類に則って,それぞれ温度圧力を推定した.すなわち,砂岩泥岩からなるメランジュ帯における引っぱり割れ目を埋める鉱物脈と,小断層に沿う鉱物脈,また,底付け断層帯における引っぱり割れ目を埋める鉱物脈と,底付け剪断帯を切る小断層に沿った鉱物脈である.底付け剪断帯を切る小断層に沿った鉱物脈は二つ測定し,他はそれぞれ1つずつ測定した.
砂岩泥岩からなるメランジュ中の引っぱり割れ目を埋める鉱物脈では,捕獲温度および圧力は182℃,171MPaであった.以下同様に,砂岩泥岩からなるメランジュ中の小断層を埋める鉱物脈から,186℃,199MPa,底付け剪断帯中の引っぱり割れ目を埋める鉱物脈では188℃,126MPa,最後に底付け剪断帯中の小断層を埋める鉱物脈からは187℃,171MPaと207℃,184MPaの結果が得られた.
異常間隙圧比を0.9とし,岩石密度を2.7g/cm3とすると形成深度はおおよそ5.2km〜8.2kmであり,地温勾配は引っぱり割れ目を埋める脈ではおおよそ34℃/km程度,小断層に沿った脈ではおおよそ25℃/km程度となる.
Stop 4
[地形図]1/2.5万 「土佐高岡」
[位置]宇佐大橋を渡って南西へ.明徳義塾高校をすぎた急な登り坂の終点付近左手に車止めあり.
[解説]横波メランジュ
横浪メランジュは,高知県横浪半島に東西幅2kmの帯状に分布し,北に砂岩・泥岩主体の須崎層,南に同じく砂岩・泥岩主体の下津井層で共に断層によって境されている(Taira et al., 1988)(第11図).そのなかでも横浪半島の東端に位置する五色ヶ浜地域には南北海岸線によく露頭が露出している.放散虫化石年代ではチャートからバランギニアン(131〜138Ma),赤色頁岩からセノマニアン(91.0〜97.5Ma)からチェロニアン(88.5〜91.0Ma),泥岩からコニアシアン(87.5〜88.5Ma)からカンパニアン(73.0〜83.0Ma)群集が報告されている(岡村, 1980).
本調査地は,インコンピーテントな黒色頁岩が基質を成しており,コンピーテントな砂岩,石英質泥岩,石英質凝灰岩,チャート,赤色頁岩,緑色岩などをブロックとして含む.ブロック・イン・マトリックス構造に密接に関連して複合面構造が発達していることから剪断変形を成因とする構造性メランジュである(第11, 12図).地質情報と鉱物脈分布を対応させるため,須崎断層との境界を0mとし南へ約530mの柱状図を作成した(第13図).これは,露頭の面構造と直行する方向に1m間隔で岩相分布を記録したものである.
調査範囲529.6mのうち,露頭は466.6mであった.須崎断層から約230mまでは泥岩・砂岩・砂質泥岩が繰り返している.この中で,16mと33mから多色頁岩が見られる.232mと260mからは,5m程度の赤色・多色頁岩が見られ,260mの手前には14m程度の砂岩が続いていた.265〜400mまでは,再び泥岩・砂岩・砂質泥岩が繰り返す.414mからは約25mの砂岩が現れ,その後510m付近まで泥岩が続き,その後約10mの砂岩が現れる.524mには玄武岩が現れる.この玄武岩は,測定範囲では0.6mであったがその少し南側では3.6mの範囲に分布していた(第11, 12および13図).
第11図.(A)五色が浜の位置図.(B)五色が浜地域の広域的なルートマップ.
北部境界断層
横波メランジュの北端は断層によって北部の泥岩砂岩主体の須崎層と接している.五色が浜地域の北位にこの境界断層が露出している(第12図).このようなメランジュ帯の北端に位置するコヒーレント層との境界断層は,興津メランジュにおいても,牟岐メランジュにおいても四万十帯で見つかったシュードタキライトのセッティングと,同等の位置づけになる.横波メランジュ北端における境界断層からは,シュードタキライトが報告されていないが,現在調査中である.露頭観察においては,シュードタキライトが見つかった他のメランジュ帯における北端の境界断層と類似している点が多々ある.
第12図.五色が浜地域のルートマップ.
第13図.五色が浜地域における柱状図.鉱物脈分布は10mごとに測定し,左から頻度,鉱物脈の合計厚さおよび鉱物脈の平均厚さを示す.鉱物脈分布図中のラインは平均値.色の濃い部分は平均値よりも高い場所を示す.
横波メランジュにおける北端の境界断層は幅約2-3mの脆性破砕帯からなる(第14図A).構成岩石はほぼ泥質岩であり,横波メランジュを構成する岩石が破砕されている.注意深く観察すると,先に形成された横波メランジュの面構造が後から切る脆性破砕面によって乱雑に乱されていることが分かる.そのような破砕帯はおよそ数cmの厚さである.このような破砕帯がネットワーク状に発達し,取り囲まれた内部は周囲のメランジュと同等の構造が残っている.場所によっては非常に連続性のよい破砕帯が見られ,その中心部には非常に薄いシャープな断層面が見られる(第14図B).この断層面は1mm程度であり,内部に非常に細粒な物質が詰まっている.このようなシャープで連続性の良い断層は,他のメランジュ帯で見られたシュードタキライトを含む断層の特徴である.このようなシャープな断層が,周囲により厚い破砕帯とセットで観察される事も類似している.全体として破砕帯の厚さは,牟岐メランジュと同程度であり,興津メランジュに比べると約20%の厚さである.
第14図.横波メランジュ北端境界断層の露頭写真.(A)全体.(B)シャープで連続性のよい断層.
鉱物脈の産状
本調査地域である五色ヶ浜地域の鉱物脈の産状は様々で,露頭の表面を覆うものやスリッケンラインのついたもの,連続性が良く他の脈を切るものや逆に他の脈に切られた連続性の悪いもの,脈の厚さについては1mm以下の非常に薄いものから数cmもある厚いものまで多種多様である(第15図).また,鉱物脈の形状が周りのメランジュ中のブロックの形状とよく似たものも見られる.鉱物脈は,一般的に石英とカルサイトの混合物からなっており(第16図),石英主体の脈とカルサイト主体の脈がある.これらの鉱物脈は,切る・切られるの関係によって,大きく2つのステージに分けることができる.1つ目は,メランジュブロックのみに発達する引っぱり割れ目を埋める鉱物脈で,泥質マトリックスに切られている.この産状は横波メランジュ中によく見られる.このような鉱物脈はメランジュ形成時の鉱物脈であると考えられる.2つ目は,メランジュ構造を切るかあるいは平行な比較的連続性の良い脈である.これはメランジュ形成後にできた鉱物脈である可能性が高い.図13には,比較的連続性の良い鉱物脈の頻度分布を示している.調査範囲529.6m(露頭466.6m)のうち,鉱物脈の頻度は計1523本,厚さは計4533.5mmで,今回測定した最も厚い脈は192〜193mの22.0mmであった.鉱物脈の3要素(頻度・合計の厚さ・平均の厚さ)の分布には,共に約100mの増減の波がある.また,この3要素と岩相の依存性については,砂岩に鉱物脈が少ないとは言えそうだが,他の岩相については関連がないように思われる(第13図).
詳しく見ていくと,まず頻度で平均値は32.6本/10mとなり,平均値以上の地点は全範囲の43.4%を占めている.最も高いのは50〜60m地点の73本で,これを含む30〜70mでピークが見られた.次に,合計の厚さで平均値は97.2mm/10mとなり,平均値以上の地点は全範囲の3 4 . 0 %を占めている.最も厚いのは1 7 0 〜 1 8 0 m の255.7mmで,これを含む160〜220mの範囲で顕著に突出しているのが分かる.ここで,頻度と合計の厚さの平均値は露頭466.6mでの平均とした.平均の厚さの場合,平均値は全体の厚さ(4533.5mm)と全体の頻度(1523本)を用いて求め,その値は2.98mm/本となった.平均値以上の地点は全範囲の26.4%を占めている.最大値は170〜180mの6.91mm/本で,合計の厚さと同じく160〜220mで突出している.したがって,相対的に30〜70mの範囲では脈の数が多く,160〜220mの範囲では厚さの厚い脈が多く分布していることが分かる.また,3要素とも平均値以上の地点は北側に集中しているように思われる.
第15図.鉱物脈の露頭写真.(A)ネットワーク状の鉱物脈.一部砂岩ブロックにのみ発達する引っ張り割れ目を埋める鉱物脈も見られる.(B)面構造に平行な鉱物脈.(C)鉱物脈面の写真.(D)鉱物脈面上のスリッケンライン.
第16図.鉱物脈の顕微鏡写真.(A)elongate blocky texture.周辺部に細粒な石英が見られ,中心部に粗粒な方解石が見られる.方解石にはツインが発達している.(B)複雑な産状の方解石.(C)細密な方解石ツイン.(D)比較的密度の低い方解石ツイン.�
謝 辞
流体包有物測定では高知大学海洋コア総合研究所の村山雅史助教授はじめ関係者の方々に便宜を図っていただいた.ここに感謝の意を表する.
文 献
Agar, S.M., Cliff., I.R. and Rex, D.C., 1989, Accretion anduplift in the Shimanto Belt, SW Japan, Jour. Geol. Soc.,146, 893-896.
Awan, A. and Kimura, K., 1996, Thermal structure anduplift of the Cretaceous Shimanto Belt, Kii Peninsula,Southwest Japan : An illite crystallinity and illite bolattice spacing study. Island Arc, 5, 69-88.
Baba, T. and Cummins, P.R., 2005, Contiguous rupture areasof two Nankai Trough earthquakes revealed by highresolutiontsunami waveform inversion, Geophy. Res.Lett., 32, L08305, doi:10.1029/2004GL022320.
Hasebe, N., Tagami, T. and Nisimura, N., 1993, Evolution ofthe Shimanto accretionary complex. A fission-trackthermochronologic study. In Underwood, M. B., ed.,Thermal Evolution of the Tertiary Shimanto Belt,Southwest Japan: An Example of Ridge-TrenchInteraction. Geol. Soc. Amer. Spec., 273, 121-136.
Hashimoto, Y. and Kimura, G., 1999, Underplating processfrom melange formation to duplexing: Example from theCretaceous Shimanto Belt, Kii Peninsula, southwestJapan. Tectonics, 18, 92-107.
Hashimoto, Y., Enjoji, M., Sakaguchi, A. and Kimura, G.,2002, P-T conditions of cataclastic deformationassociated with underplating: An example from theCretaceous Shimanto complex, Kii Peninsula, SW Japan,EPS, 54, 1133-1138.
Hashimoto, Y., Enjoji, M., Sakaguchi, A. and Kimura, G.,2003, In-situ Pressure Temperature condition of amelange: Constraints from fluid inclusion analysis ofsyn-melange veins, Island Arc, 12, 357-365.
Hyndman, R. D., Wang, K. J., Yuan, T. and Spence, G. D.,1993, Tectonic sediment thickening, fluid expulsion, andthe thermal regime of subduction zone accretionaryprisms the Cascadia margin off Vancouverisland. Jour.Geophy. Res., 98, 21865-21876.
Ikesawa, A., Sakaguchi, A. and Kimura, G., 2003,Pseudotachylyte from an ancient accretionary complex:Evidence for melt generation during seismic slip along amaster decollement? Geology, 31, 637-640.
狩野謙一,1999,付加体における震源域物質科学,月刊地球,no.21,38-44.
Kano, K., Nakaji, M. and Takeuchi, S., 1991, Asymmetricalmelange fabrics as possible indicators of the convergentdirection of plates: a case study from the Shimanto Beltof the Akaishi Mountains, central Japan. Tectonophysics,185, 375-388.
Kato, A., Sakaguchi, A., Yoshida, S., Yamaguchi, H. andKaneda, Y., 2004, Permeability structure around anancient exhumed subduction-zone, Geophys. Res. Lett.,31, L06602, doi:10.1029/2003GL019183.
木村 学,1997,プレート沈み込み帯におけるMassFluxとSeismogenic Zone−OD21に期待する科学目標−.月刊地球 号外21世紀の深海掘削への展望−ODPからOD21へ−,no.19,227-232.
木村克己,1988,付加体のout-of-sequence thrust,地質学論集,no. 50,131-146.
Kitamura, Y., Sato, K., Ikesawa, E., Ikehara-Ohmori, K.,Kimura, G., Kondo, H., Ujiie, K., Onishi, C.T.,Kawabata, K., Hashimoto, Y., Mukoyoshi, H. andMasago, H., 2005, Melange and its seismogenic roofdecollement: A plate boundary fault rock in thesubduction zone?An example from the Shimanto Belt,Japan, Tectonics, 24, TC5012, doi:10.1029/2004TC001635.
Kondo, H., Kimura, G., Masago, H., Ohmori-Ikehara, K.,Kitamura, Y., Ikesawa, E., Sakaguchi, A., Yamaguchi,A. and Okamoto, S., 2005, Deformation and fluid flowof a major out-of-sequence thrust located at seismogenicdepth in an accretionary complex: Nobeoka Thrust in theShimanto Belt, Kyushu, Japan. Tectonics, 24, TC6008,doi:10.1029/2004TC001655.
公文富士夫,1992,四国東部の四万十累帯白亜系の砂岩における斜長石粒子の曹長石化.地質学論集,no.38,281-290.
Matsumura, M., Hashimoto, Y., Kimura, G., Ohmori-Ikehara,K., Enjoji, M., and Ikesawa, E., 2003, Depth of oceaniccrust underplating in subduction zone -inference fromfluid inclusion analysis of crack-seal veins-, Geology, 31,1005-1008.
Moore, J. C. and Saffer, D., 2001, The updip limit of theseismogenic zone in the accretionary prism of SW Japan:An effect of diagenetic/low grade metamorphicprocesses and declining fluid pressure. Geology, 29 183-186.
Mori K. and Taguchi, K., 1988, Examination of the low-grademetamorphism in the Shimanto Belt by vitrinitereflectance, Modern Geology, 12, 325-339.Mukoyoshi, H., Sakaguchi, A. and Otsuki, K., 2003, EosTrans. AGU, 84 (46), Fall Meet. Suppl., Abstract T52C-0281
Mukoyoshi, H., Sakaguchi, A., Otsuki, K., Hirono, T., andSoh, W., 2006, Co-seismic frictional melting along anout-of-sequence thrust in the Shimanto accretionarycomplex. Implications on the tsunamigenic potential ofsplay faults in modern subduction zones, Earth andPlanet. Sci. Lett. 245, 330〜343.
村田明広,1991,九州四万十帯,内ノ八重層の作るデュープレックス構造と内ノ八重クリッペ,地質学雑誌,97,39-52.
Ohmori, K., Taira, A., Tokuyama, H., Sakaguchi, A.,Okamura, M. and Aihara, A., 1997, Paleothermalstructure of the Shimanto accretionary prism, Shikoku,Japan: Role of an out-of-sequence thrust, Geology, 25,327-330.
岡村 眞,1980,高知県四万十帯北帯(白亜系)の放散虫化石.四万十帯の地質学と古生物学−甲藤次郎教授還暦記念論文集−,平 朝彦・田代正之編,林野弘済会高知支部,153-178.
Onishi, C. T. and Kimura, G., 1995, Change in fabric ofmelange in the Shimanto Belt, Japan: Change in relativeconvergence? Tectonics, 14, 1273-1289.
Park, J. O., Tsuru, T., Kodaira, S., Phil, R. C. and Kaneda,Y., 2002, Splay Fault Branching Along the NankaiSubduction Zone, Science, 297, 1157-1160.
Rowe, K. J. and Rutter, E. H., 1990, Paleostress estimatingusing calcite twinning: experimental calibration andapplication to nature, Jour. Struct. Geol. 12, 1-17.
Sakaguchi, A., 1996, High geothermal gradient with ridgesubduction beneath Cretaceous Shimanto accretionaryprism, southwest Japan. Geology, 24, 795-798.
Sakaguchi, A., 1999, Thermal maturity in the Shimantoaccretionary prism, southwest Japan with the thermalchange of the subducting slab: Fluid inclusion andvitrinite reflectance study. Earth and Planet. Sci. Lett.,173, 61-74.
坂口有人,2003,四万十付加体興津メランジュの震源断層の特徴と流体移動に伴うセメンテーションによる固着すべりのアナログ実験,地学雑誌,112,885-896.
坂口有人・大森琴絵・山本浩士・相原安津夫・岡村真,1992,輝炭反射率から見た四国四万十帯北帯の熱構造−高知県西部域を例にして−.高知大学学術研究報告,41,29-47.
Shibata, T. and Hashimoto, Y., 2005, Deformation style ofslickenlines on melange foliations and change indeformation mechanisms along subduction interface:example from the Cretaceous Shimanto Belt, Shikoku,Japan. Gondwana Res., 8, 433-442.
Sibson, R.H., 1975, Generation of pseudotachylyte by ancientseismic faulting. Geophys. Jour. Royal AstronomicalSoc., 43, 775-794.
Sibson, R.H., 1977, Fault rocks and fault mechanics. J. Geol.Soc., 133, 191-213.
Tagami, T., Hasebe, N. and Shimanda, C., 1995, Episodicexhumation of accretionary complexes: Fission-trackthermochronologic evidence from the Shimanto Belt andits vicinities, southwest Japan. Island Arc, 4, 209-230.Taira, A., Katto, J., Tashiro, M., Okamura, M. and Kodama,K., 1988, The Shimanto Belt in Shikoku, Japan -Evolution of Cretaceous to Miocene accretionary prism.Modern Geology, 12, 5-46.
平 朝彦・田代正之・岡村 眞・甲藤次郎,1980,高知県四万十帯の地質とその起源.平 朝彦・田代正之編,四万十帯の地質学と古生物学-甲藤次郎教授還暦記念論文集,林野弘済会出版,319-389.
Toriumi, M. and Teruya, J., 1988, Tectono-metamorphism ofthe Shimanto Belt. Modern Geology, 12, 303-324.Ujiie, K., 1997, Off-scraping accretionary process under thesubduction of young oceanic crust: The Shimanto Belt ofOkinawa Island, Ryukyu Arc. Tectonics, 16, 305-321.Ujiie, K., Hisamitsu T. and Soh, W., 2000, Magnetic andstructural fabrics of the melange in the Shimantoaccretionary complex, Okinawa Island: Implication forstrain history during decollement-related deformation.Jour. Geophys. Res., 105, 25729-25742.
Underwood, M. B., Laughland, M.M. and Kang, S.M., 1993,A comparison among organic and inorganic indicators ofdiagenesis and low-temperature metamorphism, TertiaryShimanto Belt, Shikoku, Japan, In Underwood M. B. ed.Thermal Evolution of the Tertiary Shimanto Belt,Southwest Japan: An Example of Ridge-TrenchInteraction. Geol. Soc. Amer. Spec., 273, 45-61.
Vrollijk P., Myers G. and Moore J. C., 1988, Warm fluidmigration along tectonic melanges in the KodiakAccretionary Complex, Alaska, Jour. Geophys. Res., 93,10313-10324. �
本稿は「岩井雅夫・村田明広・吉村康隆,2006,見学旅行案内書,地質学雑誌,112,補講,170pp」がオリジナルです。
■ オリジナルPDFダウンロード(J-Stageサーバー)
巡検案内:高知県土佐山田・美良布地域の白亜系とジュラ系白亜系境界
高知県土佐山田・美良布地域の白亜系とジュラ系白亜系境界
Jurassic-Cretaceous boundary and Cretaceous formations in the Tosayamada-Birafu area, KochiPrefecture
香西 武1 石田啓祐2近藤康生3
Takeshi Kozai 1, Keisuke Ishida 2 andYasuo Kondo 3
受付:2006年6月30日
受理:2006年8月21日
* 日本地質学会第113年学術大会(2006年・高知)
見学旅行(F班)案内書
1.鳴門教育大学自然系(理科)教育講座
Faculty of Science Education, NarutoUniversity of Education, Tokushima 772-8502,Japan.E-mail: kozai@naruto-u.ac.jp
2.徳島大学総合科学部地球物資科学教室
Laboratory of Geology, Faculty of IntegratedArts and Sciences, Tokushima University,
3.高知大学理学部自然環境科学科
Department of Natural EnvironmentalScience, Kochi University, Kochi 780-8520,Japan.
概 要
見学コースは,香美市土佐山田町から香美市香北町にかけて分布する黒瀬川帯南帯の地層見学で,田代(1985)による南海層群の模式地とされている地域である.南海層群の地帯帰属を考察するために,南海層群の南側に分布するペルム紀付加体,南海層群基底部礫岩,テチス型二枚貝フォーナとされている二枚貝類の産出地点を観察する.その後,南海層群と断層で接し,ジュラ紀後期から白亜紀最前期の地質年代を持つ美良布層模式地に移動し,Kilinora spiralis 群集,Loopusprimitivus群集,Pseudodictyomitra carpatica 群集の放散虫と海生・汽水生の二枚貝類の産出層準を見学するとともに砕屑岩・石灰岩からなる堆積相を観察する.また,美良布層のジュラ系白亜系境界についても検討する.
Key Words黒瀬川帯,白亜系,ジュラ系,放散虫,二枚貝
地形図
1: 25,000 「土佐山田」「美良布」
見学コース
8:30 高知大(朝倉)集合→9:30 土佐山田町油石・神母ノ木→13:00 香北町美良布→18:00 高知大(朝倉)解散
見学地点
Stop 1 香美市土佐山田町油石,女夫池周辺.物部川層群と南海層群を区分する杉田構造線.南海層群基底部礫岩.
Stop 2 香美市土佐山田町神母ノ木橋下の物部川右岸.ペルム紀付加体雪ヶ峰層.
Stop 3 香美市土佐山田町佐野,雪ヶ峰牧場付近の露頭.神母ノ木層;南海層群に特徴的な二枚貝類の産出地点.
Stop 4 香美市香北町小川.美良布層A2部層Kilinora spiralis 群集産出地点.
Stop 5 香美市香北町西ノ川.美良布層A3部層Loopus primitivus 群集産出地点.
Stop 6 香美市香北町西ノ川.美良布層B1部層二枚貝産出地点とその岩相.
Stop 7 香美市香北町西ノ川.美良布層B2部層Pseudodictyomitra carpatica 群集産出地点.
はじめに
西南日本外帯黒瀬川帯には,大型化石を伴うジュラ−白亜系が広く分布する.それらの中で四国中央部には,杉田構造線を境として北側に物部川層群が分布し,南側に南海層群及び坂州層群・竹ヶ谷層群相当層が分布する(Kozai et al., 2005).杉田構造線以北の物部川層群はペルム系を不整合に覆う白亜系から構成されるが,杉田構造線以南では,ジュラ紀から白亜紀初期の堆積物がみられる.
香美市土佐山田町から香北町にかけて分布するジュラ−白亜系については古くから注目され,多くの層位・古生物学的研究がなされてきた.伊木(1897)は香北町西川について調査を行い,ジュラ系鳥巣層の石灰岩,白亜系の石灰岩の存在,アンモナイト,二枚貝や植物化石の産出を報告した.その中のアンモナイトに関しては,Kobayashi and Fukada(1947)によりKimmeridgianを示すAtaxioceras kurisakenseとして記載されている.蔵田ほか(1941)は白亜系石灰岩中の化石を検討し,ジュラ系鳥巣統から産するものと異なることを明らかにし,この石灰岩を含む地層を白亜系領石統に位置づけ,三宝山帯の鳥巣統と区別した.甲藤・須鎗(1956)は土佐山田町に分布する杉田構造線の南側の白亜系について研究し,それら白亜系を船谷層,萩野層と命名し,西川沿いにもそれらが分布するとした.田代(1985)はこれらの地層を,杉田構造線の北側に分布する物部川層群から区別し,南海層群として記載した.森野ほか(1989)は,西川流域の露頭から二枚貝および放散虫化石を検出し,香北町西川下流域を模式地として美良布層を設定し,それを南海層群に含めた.地質年代に関しては,産出する放散虫及び二枚貝から,late Valanginian〜Barremianとした.その後,香西ほか(2004)は美良布層から二枚貝類及び放散虫化石を検出し,その地質年代をOxfordian〜Berriasianとした.
美良布層の砕屑岩に挟まれる石灰岩層の岩相と生物相について,森野(1993)は詳しく報告しており,下位から,植物の根を含む淡水成層,汽水生二枚貝類を含む汽水成層,海成層の石灰岩が順に重なっていると述べた.このことにより,砕屑岩と石灰岩が一連の海進によって形成されたことが明らかとなった.また,大賀・井龍(2004)は石灰岩中に見られるウーイドを分析し,初生的には高マグネシウム方解石であったが,その後の続成作用によって,より安定な低マグネシウム方解石になったと推定している.
杉田構造線以南の白亜系の地帯帰属に関しては,美良布層および南海層群の帰属を黒瀬川帯とする考え(香西・石田,2000)と三宝山帯とする考え(田代・川村,1995)とがある.
今回の巡検コースでは,四国中央部黒瀬川帯ジュラ−白亜系のうち,土佐山田−美良布地域に分布するジュラ−白亜系及びそれに関連する地層について見学する.
地質概説
第1図.土佐山田地域の地質図.
今回の巡検の対象は,高知県香美市土佐山田町から香美市香北町に分布する黒瀬川帯ジュラ−白亜系である.白亜系分布域の北側には, ペルム系白木谷層群(Suyari, 1961)が分布し,白亜系とは不整合もしくは御在所山スラストによって境される(第1図).南側は,上韮生川断層により四万十帯の地層群と接する(伊熊,1980).ジュラ−白亜系は杉田構造線を境に北側に下部白亜系物部川層群が,南側に南海層群,美良布層及び鳥巣層群が分布する(甲藤・須鎗,1956;田代,1985;須鎗・桑野,1986;森野ほか,1989;香西ほか,2004など).土佐山田町杉田−香北町美良布間では物部川層群と南海層群の間には,ペルム紀のフズリナを含有する石灰岩塊を有するペルム系が分布する(甲藤・須鎗,1956).美良布以東では杉田構造線を境に,物部川層群と南海層群もしくは美良布層が接する.杉田構造線は,時に蛇紋岩を伴い北傾斜の低角度断層である.南海層群の南側は,ペルム系の雪ヶ峰層と断層で境される(香西・石田,2000).また雪ヶ峰層は香北町北岩改北方では,南海層群と美良布層の間に,北岩改南方では美良布層と三宝山帯鳥巣層群の間に分布する.
見学地点案内
第2図.Stop 1-3 の位置図(2万5千分の1地形図「土佐山田」).
1 土佐山田地域(第2図)
第3図.南海層群と物部川層群との境界にみられる蛇紋岩.船谷層に低角度で蛇紋岩体が衝上している.
第4図.船谷層下部層中の緑色凝灰岩礫から産出した放散虫化石.1-3:Devoniglanus unicus Wakamatsu, Sugiyama and Furutani.
Stop 1 香美市土佐山田町油石,女夫池周辺(杉田構造線と南海層群下部礫岩)
[地形図]1/2.5万「土佐山田」
[位置]見学地点は,国道195号線土佐山田から,北方にある土佐山田ゴルフ場方面に市道を入り,ゴルフ場手前油石から東に未舗装の作業道を女夫池方向に入った所.
[解説]本観察地では,南海層群船谷層最下部がみられる.船谷層は層厚約180mで下部層と上部層に区分される.女夫池付近でみられる下部層は層厚約160m.北縁は,断層で杉田構造線の蛇紋岩と接するが,女夫池北側では,境界付近が崩壊土に覆われその関係を見ることができない.しかし,観察地手前の市道沿いの切り通しでは, 蛇紋岩と船谷層の砂岩がN80゜E,45゜Nで接するのが確認できた(第3図).船谷層下部層の下半部は泥岩と礫岩とが繰り返し,上方に礫岩が厚層化する.女夫池で確認できる下部層最下部は泥岩で,暗緑色を呈し,タマネギ状風化がみられる.その上位は,小〜中礫の亜角〜亜円礫からなる淘汰の悪い礫岩が重なる.礫はチャート,砂岩が主体で,まれに緑灰色凝灰岩礫を含む.この凝灰岩礫からは,放散虫Devoniglanssus unicusWakamatsu, Sugiyama and Furutaniが検出された(第4図).同種は横倉山G4層準下部の凝灰質砂岩より報告され,同名の群集の特徴種であり,デボン紀前期を示すと考えられている(Wakamatsu et al., 1990).岩質と産出化石の同一性から,この礫が黒瀬川帯のシルル−デボン系に由来する可能性を示している.礫岩は頻繁に泥質砂岩部をレンズ状に含むが,成層構造は明瞭でない.
上半部は下半部に比べ,礫岩層が優勢である.比較的淘汰の良い小〜中礫で,亜円〜円礫が多くみられる.礫種は下半部と同じくチャート,砂岩礫が優勢で,希に凝灰質砂岩礫,石灰岩礫を含む.本層の礫種構成は杉田構造線北側に分布する物部川層群の基底部,領石層及び立川層の礫岩と類似するが,杉田−喰田構造線南側に分布する菖蒲層とは花崗岩類の礫含まない点で異なる.Stop 1では,南海層群と物部川層群を境する蛇紋岩及び南海層群下部のシルル−デボン系に由来すると考えられる礫を含む礫岩を観察する.
第5図.雪ヶ峰層から産出したペルム紀放散虫化石.1: Nazarovella sp. チャートブロックより産出.2: Albaillella sp. チャートブロックより産出.3: Follicucullus sp. チャートブロックより産出.4: Follicucullus sp. 泥岩より産出.
Stop 2 香美市土佐山田町神母ノ木橋下の物部川右岸(ペルム紀付加体雪ヶ峰層)
[地形図]1/2.5万「土佐山田」
[位置]国道195号線土佐山田町から大栃方面に行く途中にある神母ノ木橋下(物部川右岸).
[解説]雪ヶ峰層は南海層群の南に分布し,同層群とは断層で接する.地層の一部は,チャートや石灰岩塊を伴う砂泥質岩相で,石灰岩塊からNeoschwagerina craticulifra(Schwager)が検出されたことから,ペルム系高岡累層とされた(沢村・甲藤,1961).しかしながら,高岡累層が模式的に見られる佐川地域において高岡累の一部はジュラ系であることが明らかとなり(松岡,1985),年代と地層の帰属については再検討を要するものと考えられるようになった.観察地点である神母ノ木橋付近の物部川河床は,これまで,宮ノ口層ないし,高岡累層とされてきた.劈開の発達した黒色泥岩層,砂岩泥岩の細互層が分布しており,数mの砂岩層を挟在し,淡緑色層状チャートの大小レンズ状岩塊ならびに石灰岩の小岩塊を伴う.黒色泥岩層より放散虫のFollicucullus sp.,層状チャート岩体からはNazarovella sp.の梯子状の腕,ならびにAlbaillella sp., Follicucullus sp.が産出した(第5図).これらの放散虫化石に基づき,本層はペルム紀付加体であることが明らかとなったことから,いわゆる高岡累層と区別し,雪ヶ峰層と命名されている(香西・石田,2000).南海層群分布域の南側にペルム紀付加体が分布することは,南海層群が黒瀬川帯に帰属することを示している.Stop 2では,ペルム紀放散虫化石の産出地点を紹介する.
第6図.雪が峰牧場下(Stop 3)付近の神母ノ木層の柱状図.×:神母ノ木層から記載された二枚貝類の模式標本の産出
第7図.美良布地域地質図(香西ほか,2004を改変).
第8図.美良布層の岩相と放散虫化石,二枚貝化石の産出層準(香西ほか,2004).
Stop 3 香美市土佐山田町佐野,雪ヶ峰牧場付近の露頭(神母ノ木層)
[地形図]1/2.5万「土佐山田」
[位置]Stop 2から物部川右岸を上流約500mの地点を左折し,雪ヶ峰牧場に入る.牧場の建物下の露頭.
[解説]本観察地点は,神母ノ木層の模式地分布域にあり,上部にあたる(Tashiro and Kozai,1984;香西・石田,2000).層厚約250m.本層は牧場中央部の谷付近に向斜軸をもつ向斜構造を示し,観察地点はその南翼にあたる.牧場建物付近では断層の北側に,アレナイト質砂岩,砂岩優勢の砂岩泥岩互層が分布し,砂岩と泥岩との境界面に植物片を含こともある.この砂岩は,側方では礫岩に移化することもあり,物部川河床では,花崗斑岩など酸性火成岩礫の円礫を含む礫岩が観察される.この砂岩からは,Pterotrigonia sp., Astarte (Nicaniella) makibaensisTashiro and Kozaiなどの二枚貝を産出する.さらに上位は,一部に砂岩優勢の砂岩泥岩互層があるものの全体的に上方細粒化の堆積サイクルを示し,上部では厚い黒色泥岩となる(第6図).帯緑色細粒砂岩からは, Brachidontes igenokiensisTashiro and Kozai, Mesomiltha japonica Tashiro andKozai, Anthonya igenokiensis Tashiro and Kozai,Leptsolen amabilis Tashiro and Kozai, Granocardiummulticostata Tashiro and Kozai, Linearia nankaianaTashiro and Kozai, Scittila dericatostriata Tashiro andKozai, Isocyprina japonica Tashiro and Kozai, I.igenokiensis Tashiro and Kozai などが記載され,Eburneopecten miyakoensis(Nagao), Xcenocardita amanoiHayami, Protocardia amanoi Tashiro and Matsuda,Isocyprina aliquantula(Amano)などの多様な二枚貝類が産出する.これらの二枚貝フォーナは物部川層群からのフォーナとは種構成が異なる.また二枚貝類とともにCheloniceras sp.が産出する.
第9図.Stop4〜7の位置図(2万5千分の1地形図「美良布」).
2 美良布地域
(1)美良布層の概要北縁は,土佐山田町間から香北町熊淵にかけてはペルム系雪ヶ峰層と断層で接し,熊淵から西川にかけては南海層群萩野層と断層で接する.それ以北では,物部川層群日比原層と断層で接する.南縁は,土佐山田町間から香北町清水ヶ森北方付近まではペルム系雪ヶ峰層と断層で接し,それ以北では三宝山帯鳥巣層群と断層で接する(第7図).
美良布層の模式地は高知県香美郡香北町小川の西川沿いの河床で,層厚は約600mである.本層は岩相から,6部層に区分される(第8図).本層最下部のA1部層は,断層で物部川層群日比原層泥岩と接し,黒色泥岩及び泥岩優勢の砂岩泥岩互層からなる.化石は未発見である.A2部層は,暗灰色中粒砂岩,泥質砂岩,砂質泥岩からなる.泥質砂岩には,貝殻片を含む部分もある.泥岩にはレンズ状の酸性凝灰岩を含み,凝灰岩直下の泥岩からKilinora spiralis 群集帯の放散虫が見いだされた.A3部層は砂質泥岩及び黒色泥岩からなる.最上部付近の凝灰岩と接する泥岩からLoopus primitivus 群集帯の放散虫が検出された.B1部層は,砂岩,石灰岩,黒色泥岩で構成される.砂岩は,有機物や泥質物を含み淘汰の悪い砂岩と石灰質砂岩からなる.有機物含有砂岩からは,海生及び非海生の巻き貝,二枚貝などが産出する.石灰岩層は,それぞれ下部ほど砕屑性粒子に富み,上部にはサンゴ,層孔虫などの化石を含む(森野,1993).石灰岩を覆う黒色泥岩は淘汰が良く,化石をほとんど含まない.B2部層は,砂岩,黒色泥岩,砂岩泥岩互層,石灰質砂岩,石灰岩からなる.下部の砂岩は淘汰の良い,中粒砂岩である.泥岩には,まれに酸性凝灰岩をレンズ状に含み,凝灰岩の上位からPseudodictyomitra carpatica 群集帯の放散虫を産出する.上部の砂岩は,時に石灰質となる.C部層は,主に泥岩,砂岩泥岩互層から成り,下位の泥岩には酸性凝灰岩の薄層が観察される.
(2)見学地点(第9図)
第10図.放散虫化石と二枚貝化石産出地点.
第11図.Kilinora spiralis 群集産出付近の柱状図(Stop 4).
Stop 4 香美市香北町小川の南西(美良布層A2部層Kilinora spiralis 群集産出地点)
[地形図]1/2.5万「美良布」
[位置]国道195号線香北町小川から西川沿いに上流へ約800mの河床.
[解説]Stop 4は,美良布層A2部層最上部にあたる.中粒砂岩,有機物に富み,淘汰の悪い泥質砂岩,砂岩泥岩互層,細粒砂岩からなる.砂岩泥岩互層と砂岩の間に挟まれるレンズ状の酸性凝灰岩直下の泥岩(loc.32601R)からKilinoraspiralis 群集帯の放散虫が見いだされた(第10,11図).
放散虫産出地点が多くないため, Kilinoraspiralis 群集帯の上下限を特定することはできていない.loc.32601RからはKilinora spiralis 群集帯の特徴種であるKilinora spiralis(Matsuoka)の産出とともに, Hsuum maxwelli Pessagno,Stichocapsa robusta Matsuoka, Tethysettadhimenaensis (Baumgartner), Tricolocapsa conexaMatsuoka, およびTricolocapsa cf. parvipora Tanが豊産する.Archaeodictyomitra amabilis Aita,Cinguloturris carpatica Dumitrica, Eucyrtidiellumnodosum Wakita, Mirifusus guadalupensisPessagno, Ristola procera(Pessagno), Stylocapsatecta Matsuoka, Tricolocapsa plicarum Yao も普通に産する. 美良布層の模式セクションにおけるKilinora spiralis 群集帯は,Matsuoka and Yao(1986)のKilinora spiralis 帯に対比され,上部ジュラ系下部(Oxfordian)に相当する.なお,A2部層最上部の泥岩( l o c . 3 2 6 0 1 R ) からはEucyrtidiellum ptyctum(Riedel & Sanfilippo)とKilinora spiralis が共産することから,この層準はHull(1997)のSubzone 2γ(Oxfordian中部)に属するものと推測する.また,美良布層に対比される徳島県栗坂層の模式セクションからもKilinora spiralis 群集帯を示す放散虫群集が報告されている(Ishida., 1997).
第12図.Loopus primitivus 群集産出地点(Stop 5).
Stop 5 香美市香北町小川の南西(美良布層A3部層Loopus primitivus 群集産出地点)[地形図]1/2.5万「美良布」[位置]Stop 4の約100m上流,西川左岸の小道沿い.[解説]A3部層は砂質泥岩及び黒色泥岩からなる.最上部付近には,黒色泥岩中に酸性凝灰岩のレンズ状岩体を含む部分があり,その凝灰岩と接する泥岩(loc.32602R)からはLoopusprimitivus 群集帯の放散虫が検出される(第12図).その放散虫群集はレンズ状岩体周辺では豊産するが,それ以外の場所ではあまり産出しないために,本帯の上下限は特定されていない.Loopus primitivus 群集帯はLoopus primitivus( Matsuoka and Yao)の産出とともに,Cinguloturris carpatica, Dumitrica, Protunumajaponicus Matsuoka and Yao, Ristola altissima(R?st),Svinitzium depressum(Baumgartner), Svinitzium mizutaniiDumitrica, Svinitzium pseudopuga DumitricaとXitusgifuensis Mizutaniの豊産で特徴づけられる.本帯から産出し始める放散虫としては,Archaeodictyomitraapiarium(R?st), Archaeodictyomitra broweri(Tan),Archeodictyomitra minoensis(Mizutani), Loopus doliolumDumitrica, Loopus primitivus(Matsuoka and Yao), Loopusyangi Dumitrica, Neorelumbra kiesslingi Dumitrica,Pantanellium lanceola(Parona), Protunuma japonicus,Matsuoka and Yao, Solenotryma(?)ichikawai Matsuokaand Yao, Svinitzium mizutanii Dumitrica, Svinitziumpseudopuga Dumitrica, Tethysetta boesii(Parona),Tethysetta pygmaea Dumitrica, Xitus gifuensis などがある.下位から引き続き産するものとしては,Eucyrtidiellumptyctum(Riedel and Sanfilippo)がある.Hsuum maxwelliPessagno およびPseudodictyomitra carpatica(Lozyniak)は,どちらもloc. 32602R からは産しない.これらのことから,loc. 32602Rから産出する放散虫群集はMatsuoka(1995)のLoopus primitivus 帯に対比され,最上部ジュラ系(Tithonian)に相当する.
第13図.B1, B2 部層の岩相と産出する二枚貝化石(香西ほか,2004).
Stop 6 香美市香北町小川の南西(美良布層中部二枚貝産出地点)
[地形図]1/2.5万「美良布」
[位置]Stop 5から河床におり,上流約20m-200m付近
[解説]美良布層模式ルートである西川沿いには,石灰岩層と砕屑岩層が繰り返す,美良布層B1部層が特徴的に露出している.このルートでは明らかな断層も数カ所認められるが,おおむね一連の層序を示すものとみられる.砕屑岩からその上位の石灰岩への漸移的な岩相変化に対して,石灰岩とその上位の砕屑岩との間には明瞭な境界がみられるので,これを岩相層序の境界として,B1部層は,サブユニットⅠ−Ⅶに細分され,またそれぞれのサブユニットの特徴から,サブユニットⅠ−Ⅲ(下部),Ⅳ・Ⅴ(中部),Ⅵ−Ⅶ(上部)にまとめられている(香西ほか,2004;第13図).以下,このルートで観察されるB1部層の層序,堆積環境,および産出する二枚貝化石の特徴について簡単に紹介する.
B1部層下部では,下位から順に,下位の泥岩を覆う貝化石を含む砕屑岩,ネリネアを含む石灰質砂岩,ウーイドを多量に含む石灰岩, そして再び泥岩に覆われるというサイクルが3回認められる.それぞれのサブユニットでは,砕屑性粒子の割合が上位に向かって減少し,石灰岩の上部で最小となり,明瞭な境界を介して砕屑性堆積物(泥岩)に覆われる,というパタンが認められ,このパターンはそれぞれのサブユニットに共通する.最下部のサブユニットⅠは,より下位の厚い泥岩から連続しているため,便宜的に石灰岩直下の貝化石層から,石灰岩の上限までとする.下位から順に,貝類遺骸を含み,植物片を大量に含む泥質砂岩,石灰質砂岩,ウーイド・ペロイド・グレインストン,ウーイド・グレインストンと重なり,再び石灰質砂岩をはさんだ後,砕屑性粒子の多いウーイド・グレインストン〜パックストンに移り変わる.最上部は,径1cm前後の藻類被覆殻を持つ球状体を含む薄い石灰質泥岩を経て,サブユニットⅡの黒色泥岩に覆われる.サブユニットⅡとⅢは断層で接しているため完全な層序はわからないが,石灰岩の堆積相とその累重パタンから見て,サブユニットⅠと同様の層序であると推定される.
B1部層中部はサブユニットⅣとⅤの2サイクルで構成される.B1部層中部では石灰岩の厚さも,サイクルの厚さも下部に比べて薄いのが特徴である.石灰岩直下の貝化石層, 特にサブユニットⅤ の貝化石層には,Aguilerella nagatoensis-Corbula imamurae 群集で特徴づけられる美良布層で最も豊富な汽水性貝類群集が含まれている.B1部層中部の石灰岩は露頭の制約のため,詳細な岩相変化は不明であるが,ウーイドを多量に含む石灰岩であり,B1部層下部の石灰岩と共通の変化パタンが一部に認められる.森野(1993)により研究された,西川ルート南斜面の石灰岩体は斜面崩壊の跡地で観察されたもので,現在は崩壊地が修復されているために観察できない.しかし,その層相変化はB1部層中部のサブユニットに認められる堆積サイクルと非常によく似ており,位置関係から見てサブユニットⅣの石灰岩と対比される可能性が高い.
B1部層上部は,サブユニットⅤの石灰岩の上位に重なる,全体として上方に粗粒化する砕屑岩(層厚約80m)に始まる.サブユニットⅥは,下位から順に,砂質泥岩と極細粒砂岩の互層,石灰質砂岩と粗粒のウーイドからなる.サブユニットⅦは,下位から順に,砂岩,細粒石灰質砂岩,バウンドストンが重なる.
二枚貝類は,石灰岩が特徴的に分布するB1及びB2部層から産出する.B1-Ⅰの砂岩層からは,汽水生のAguilerella nagatoensis(Ohta)とともに, 海生のGrammatodon takiensis Kimura, Pterotrigonia toyamai(Yehara), Miltha japonica Tashiro, Isocyprina japonicaTashiro and Kozai, Ctenoides tosana(Kurata andKimura)などが産出する.Pterotrigonia toyamai (Yehara)は,Yehara(1923)によって本層からの標本をもとに記載されたもので,B1-Ⅰの砂岩層からのみ産出するが,保存状態は良くない.B1-Ⅱの砂岩からは, Isocyprinajaponica Tashiro and Kozai, Corbula globosa Tamuraの他,汽水生のCorbula imamurae Hase, Caestocorbulamorinoi Tashiro and Kozaiなどが産出する.ほかにも多数の巻き貝を共産し,中には10cmを越えるネリネアも含まれる. また石灰岩上部の石灰質砂岩部からはGrammatodon takiensis Kimura が産出する.石灰岩を覆う泥質岩からは大型化石,微化石ともに検出ができていない.B1-Ⅲの砂岩からは,Eomiodon nipponicus Ohta,Corbula imamurae Haseなどの汽水生二枚貝類が産出する.B1-Ⅳの砂岩からは,海生のCtenoides tosana (Kurataand Kimura), Parvamussium habunkawense(Kimura),Miltha japonica Tashiro, Isocyprina japonica Tashiro andKozai, Eomiodon kumamotoensis Tamura, Corbula globosaTamura などの他,汽水生のAguilerella nagatoensis(Ohta), Eomiodon nipponicus Ohta, Caestocorbula morinoiTashiro and Kozaiが産出する.B1-Ⅴの砂岩からは産出化石は少ないが,海生のFalcimytilus sp., Limatula sp.が産出する. B 1 - Ⅵ の砂岩からは,Crenotrapesiumkitakamiense Hayami, Aguilerella nagatoensis(Ohta),Eomiodon nipponicus Ohta, Eomiodon kumamotoensisTamura, Corbula imamurae Haseが産出する.B1-Ⅶからは化石の産出は確認できていない.B1部層の全ての泥岩層からそれぞれ5個の放散虫検出用サンプルを採取し処理を行ったが,微化石は検出できなかった.B2部層からの大型化石は, Parvamussium habunokawense(Kimura)が1個体得られたのみであるが,放散虫化石は凝灰岩の周辺から豊富に産出する.
B1部層からの二枚貝類は,海生種と汽水生種の混在で特徴づけられる.それら非海生二枚貝と海生二枚貝の産出頻度は,B1-Ⅰ及びB1-Ⅱでは海生二枚貝の割合が約90%であるのに対して,B1-Ⅳ及びB1-Ⅵでは非海生二枚貝類の産出頻度が約40%とB1-Ⅰ,Ⅱより高い値を示す.森野(1993)が検討した層準はB1-Ⅳに対比され,B1-Ⅳの砂岩−石灰岩の形成が汽水環境から浅海環境へと変化する中で形成されたことを指摘している(森野,1993).B1-Ⅶからは,大型化石は産出していない.このことは,B1-Ⅵが形成された後,その堆積の場が沿岸からさらに沖合へとシフトした可能性がある.
以上,二枚貝の産出状況から,B1部層は細かなサイクルを繰り返しながら全体として沿岸から汽水域へと環境が変化した後,沖合へと堆積環境が変化したと考えられる.
Stop 7 香美市香北町小川の南西(美良布層上部Pseudodictyomitra carpatica 群集産出地点)
[地形図]1/2.5万「美良布」
[位置]西川,陰ノ谷川合流地点から下流へ約100mの地点.
[解説]B2部層は,砂岩,黒色泥岩,砂岩泥岩互層,石灰質砂岩,石灰岩からなる.下部の砂岩は,淘汰の良い,中粒砂岩である.泥岩は,酸性凝灰岩をレンズ状に含み,そこから放散虫化石を産出する.西川ルートのB2部層においてはloc.32604R から放散虫群集が産出し,C部層も含め,より上位の層準からは散在的に放散虫化石が産出する.B2部層のloc. 32604RからはPseudodictyomitra carpatica 群集帯に属する放散虫化石を産出する.
Pseudodictyomitra carpatica(Lozyniak)とともにArchaeodictyomitra mitra Dumitrica, Archaeodictyomitrapseudomulticostata(Tan), Sethocapsa kaminogoensis Aita,Sethocapsa pseudouterculus Aita ならびにTethysettac o l u m n a ( R ? s t ) の初産出が認められる.Archaeodictyomitra apiarium(R?st), Archaeodictyomitramitra Dumitrica, Loopus doliolum Dumitrica, Loopusyangi Dumitrica, Neorelumbra kiesslingi Dumitrica,Pantanellium lanceola(Parona), Svinitzium depressum(Baumgartner), Svinitzium mizutanii DumitricaとSvinitzium pseudopuga Dumitricaは当群集帯からは普通ないし豊富に産する.Archaeodictyomitra broweri(Tan),Archeodictyomitra minoensis(Mizutani), Mirifususmediodilatatus(R?st), Tethysetta boesii(Parona), Tethysettapygmaea DumitricaとTethysetta usotanensis (Tumanda)は,少数ながら本群集帯から産する. 当群集帯の下部(B2部層)からは,下位層に引き続いてCinguloturriscarpatica Dumitrica, Eucyrtidiellum ptyctum (Riedel andSanfilippo), Loopus primitivus Matsuoka and YaoとSolenotryma(?)ichikawai Matsuoka and Yaoが産する.Pseudodictyomitra carpatica 帯(Matsuoka,1995; 松岡,2004)ならびにDitrabs sansalvadorensis 帯(Aita andO k a d a , 1 9 8 6 ) は, T i t h o n i a n − 白亜系最下部(Berriasian - Lower Valanginian)とみなされている.当セクションでは,Sethocapsa pseudouterculus AitaとS.kaminogoensis Aita がPseudodictyomitra carpatica(Lozyniak)と共に群集帯のほぼ最下部から出現する.松岡(2004)はPseudodictyomitra carpatica(Lozyniak)のFAB はTithonian前期であるとしている.またAita andOkada(1986)は,Sethocapsa pseudouterculus Aita の出現が, Ditrabs sansalvadorensis 帯のほとんど基底であり,J/K 境界のわずかに下位であるとしている.しかしながら,S. kaminogoensis Aita は,同じBreggia Riversection においてJ/K 境界以後に出現するとされる.加えてDumitrica et al(. 1997)はArchaeodictyomitra mitraDumitrica, Archaeodictyomitra pseudomulticostata(Tan)やTethysetta columna(R?st)をBerriasian 以降から報告している.このような状況から,筆者らは美良布層の模式セクションにおけるPseudodictyomitra carpatica 群集帯の始まりはBerriasianであり,J/K 境界はB2部層より下位であると見なしている.
地質雑 112(補遺) 高知県土佐山田・美良布地域の白亜系とジュラ系白亜系境界97上限に関しては, Dumitrica et al(. 1997)はArchaeodictyomitra tumandae Dumitrica, Becus rotulaDumitrica, Cinguloturris cylindra Kemkin and RudenkoやPseudodictyomitra altiturris Dumitricaの産出がB e r r i a s i a n - V a l a n g i n i a nであるとしている.またMatsuoka and Yang( 2000)によれば, Cecropsseptemporatus(Parona)のEFAB はCecrops septemporatus帯の下底であり,その年代はValanginianとされている.当セクションからはCecrops septemporatus (Parona)は未検出であり,C部層の最上部は依然Pseudodictyomitracarpatica 群集帯にあり,その年代はValanginian後期には及ばないと考えている.
美良布層のJ/K境界美良布層からは,ジュラ系からのみ報告されている二枚貝類,ジュラ−白亜系最下部から報告されている二枚貝類,白亜系からのみ報告されている二枚貝類が産出する.二枚貝類の産出層準は,Loopus primitivus 群集帯とPseudodictyomitra carpatica 群集帯の間にあり,ジュラ紀最後期から白亜紀最前期の範囲内にある.産出二枚貝類とその産出層準に関しては,第13図に示す.
今まで,ジュラ系からのみ知られていた二枚貝類は,Pterotrigonia toyama(i Yehara),Ctenoides tosana(Kurataand Kimura)で,Pterotrigonia toyamai(Yehara)はB1-Ⅰからのみ産出し,Ctenoides tosana(Kurata andKimura)は,B1-Ⅳからも産出する.一方,従来白亜系のみから知られるAguilerella nagatoensis( Ohta),Isocyprina japonica Tashiro and Kozai, Miltha japonicaTashiro などもB1-Ⅰから産出する.このように,B1部層における二枚貝類は,ジュラ紀型,白亜紀型の混在が特徴である.ジュラ紀後期の二枚貝類は,白亜紀最前期までのレンジを持つものが多いが,白亜紀型の二枚貝類に関しては,ジュラ系からの報告はない.従って,白亜紀型二枚貝類が産するB1-Ⅰの地質年代は白亜紀最前期と考えられ,J/K境界は,A3部層最上部でLoopus primitivus 群集が産するloc.32602Rの泥岩層とB1部層基底部の石灰質砂岩層の間にある可能性が高い.
第14図Pseudodictyomitra carpatica 群集産出地点(Stop 7).
謝 辞
本調査にあたって,大野正宏氏,遠藤浩氏,斉藤誠氏には高知大学在学中に卒論などの研究で得られた二枚貝類のサンプル及び産出層準に関する情報をいただいた.また,新潟大学松岡篤教授および徳島大学村田明広教授からは有益な示唆をいただき,原稿が大幅に改善された.これらの方々に厚くお礼申し上げます.
文 献
Aita, Y. and Okasa, H., 1986, Radiolarians and calcareousnannofossils from the uppermost Jurassic and LowerCretaceous strata of Japan and Tethyan regions.Micropaleontology, 32, 97-128.
Dumitrica, P., Immenhauser, R. and Dumitrica-jud, R., 1997,Mesozoic radiolarian biostratigraphy from MasirahOphiolite, Sultanate of Oman, part I: Middle Triassic,uppermost Jurassic and Lower Cretaceous Spumellariansand multisegmented Nassellarians. Bull. Natn. Mus.Natn, Sci., 9, 1-106.
Hull D. Meyerhoff., 1997, Upper Jurassic Tethyan andsouthern Boreal radiolarians from western NorthAmerica. Micropaleontology, 43, supplement 2, 1-202.
伊木常誠,1897,土佐のジュラ及び白亜紀層.地質雑,4,411-421.
伊熊俊幸,1980,高知県領石・物部地域の秩父累帯白亜紀層の変形.地質雑,86, 389-407.
Ishida, K., 1997, Stylocapsa(?) spiralis Assemblage(Radiolaria) from the Kurisaka Formation of theTorinosu Group in Shikoku, SW Japan. NOM, Spec.Vol., 10, 193-203.
Kobayashi, T. and Fukada, A1947, A new species ofAtaxioceras in Nippon. Japan. Jour. Geol. Geogr., 20,45-48.
甲藤次郎・須鎗和己,1956,物部川盆地の再検討 (四国秩父累帯の研究−Ⅶ).高知大学学術研究報告,5,1-11.
香西 武・石田啓祐,2000,高知県中部,土佐山田地域に分布する南海層群の層序及び物部川層群との対比.鳴門教育大学研究紀要,自然科学編,15,13-25.
香西 武・石田啓祐・近藤康生,2004,四国中央部黒瀬川帯美良布層の放散虫年代と二枚貝群集.大阪微化石研究会誌,特別号,no.13,149-165.
Kozai,T., Ishida, K., Hirsch, F., Park, S.O. and Chang, K.H.,2005, Early Cretaceous non-marine mollusk faunas ofJapan and Korea. Cretaceous Res., 26, 97-112.
蔵田延男・青地清彦・深澤恒雄,1941,物部川盆地中部の地質(概報).地質雑, 48, 384-390.
松岡 篤,1985,高知県佐川地域秩父累帯南部の中部ジュラ系毛田層.地質雑, 91, 411-420.
松岡 篤,2004,ジュラ期末の放散虫古生物地理−Vallupus群集とEucyrtidiellum群集の認定.日本地質学会第111年学術大会講演要旨,35.
Matsuoka, A., 1995, Radiolaria-based Jurassic/Cretaceousboundary in Japan. Proc. 15th Symposium of KyungpookNational Univ., 219-232.
Matsuoka, A. and Yang Q., 2000, A direct correlationbetween North American and Japan-Pacific radiolarianzonal schemes for the Upper Jurassic. GeoResearchForum, no. 6, 119-128.
Matsuoka, A. and Yao, A., 1986, A newly proposedradiolarian zonation for the Jurassic of Japan. MarineMicropaleontology, 11, 91-106.
森野善広,1993,高知県物部地域の下部白亜系鳥巣式石灰岩の生成環境.地質雑,99,173-183.
森野善広・香西 武・和田 貴・田代正之,1989, 高知県物部地域の鳥巣式石灰岩を含む下部白亜系美良布層について.高知大学学術研究報告,38,73-83.大賀博道・井龍康文,2004,下部白亜系美良布層中の石灰岩に含まれるウーイドの特徴と成因.堆積学研究,59,27-37.
沢村武雄・甲藤次郎,1961,高知県地質鉱産図説明書,高知県,129p.Suyari, K., 1961, Geological and paleontological studies incentral and eastern Shikoku, Japan-Part 1, geology. Jour,Gakugei, Tokushima Univ., Nat. Sci., 11, 11-76.
須鎗和己・桑野幸夫,1986,鳥巣層群の放散虫年代 その2 −高知県香美郡香北町久保川の鳥巣層群−.徳島大学教養部紀要,19,37-43.
田代正之,1985,四国秩父帯の白亜系−下部白亜系の横ずれ断層について−.化石, no.38, 23-35.田代正之・川村喜一郎,1995, 秩父帯南帯(三宝山帯)の解釈.高知大学学術研究報告, 44, 11-25.
Tashiro, M. and Kozai, T., 1984, Bivalve from the typeMonobegawa Group (Part 1). Res. Rep. Kochi Univ., 32,259-293.
Wakamatsu, H., Sugiyama, K. and Furutani, H., 1990,Silurian and Devonian Radiolarians from theKurosegawa Tectonic Zone, Southwest Japan. Jour.Earth Sci. Nagoya Univ., 37, 157-192.
Yehara, S., 1923, Cretaceous Trigoniae from South-westernJapan. Japan. Jour. Geol. Geogr., 2, 59-84.
本稿は「岩井雅夫・村田明広・吉村康隆,2006,見学旅行案内書,地質学雑誌,112,補講,170pp」がオリジナルです。
■ オリジナルPDFダウンロード(J-Stageサーバー)
No.0015 2007/11/06 geo-Flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┴┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.015 2007/11/06 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2008年度役員選挙:選挙活動期間についてのお知らせ
【2】韓国地質学会との学術協定調印!
【3】2008年度日本地質学会各賞候補者募集 開始!
【4】日・タイ/日・モンゴル/日・フィリピン 交流委員募集
【5】天然記念物めぐり 滋賀編(4つ紹介!)
【6】ジオパーク大図解シリーズ 発売
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2008年度役員選挙:選挙活動期間についてのお知らせ 選挙管理委員会
──────────────────────────────────
■ 選挙活動の期間は11月6日から12月15日までです。
立候補者あるいは会員の方は、期間中、特定の立候補者への投票をお願い
することができます。投票用紙は,11月14日発送予定です。
HPの会員のページには,立候補者名簿が掲載されています。
マニフェストも近日中に会員のページに掲載される予定です。
会員の皆さまには,選挙活動ルールの再確認(選挙活動について)を
お願い申し上げます。
選挙活動ルール・ 立候補者名簿は【会員のページ】をご覧下さい
(会員番号によるログインが必要です)
選挙管理委員会
2007年11月5日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】日韓学術協定 調印! 新たなパートナーシップの始まり!
──────────────────────────────────
■ 2007年10月25日、日韓学術協定の調印式が開催されました。その報告
が届きました。これからの両国の地球科学の発展のために、協力して様々な
学術協力が期待されます。会員の皆様にも、是非この機会を活用していただき
たいと思います。異なる文化での地質学会の雰囲気もレポートされています
ので、是非ご一読ください。
レポートは、、、
http://www.geosociety.jp/science/content0008.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2008年度日本地質学会各賞候補者募集 開始!
──────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして,研究の援助・奨励および研究
業績の表彰を行っています(会則第3条).具体的には,運営細則第11条お
よび各 賞選考に関する規約(本号別途掲載)に,表彰の種別や選考の手続きを
定めています.これらにしたがい,下記の賞の自薦,他薦による候補者を募集
いたしま す.
日本地質学会功労賞・日本地質学会表彰以外は,会員(正会員・名誉会員)で
あればどなたでも推薦できます.論文賞・研究奨励賞・小藤賞の対象論文リスト
については,本ページよりダウンロードいただくか,または,
地質学会事務局までお問い合わせください.
応募の締切は、2007年12月25日(火)です.
詳しくは、こちら
http://www.geosociety.jp/outline/category0011.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】日・タイ/ 日・モンゴル/ 日・フィリピン 交流委員募集
──────────────────────────────────
■■日・タイ地質学会の交流のための委員を募集致します■■
平成19年10月の地質学会理事会で、日・タイ小委員会設立が承認されました。
これは、理事会の下にある国際交流委員会の中に国・地域毎に小委員会を組織し,
小委員会が中心となって交流活動を展開させようという趣旨によるものです.
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/news/n22.html
■■日・モンゴルおよび日・フィリピンの地質学会との交流のための委員を募集します■■
これは韓国やタイに対応した小委員会と同じ趣旨のものです.
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/news/n23.html
国際交流委員会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】天然記念物めぐり 滋賀編(4つ紹介!)
──────────────────────────────────
■ 滋賀には国指定の天然記念物が4つある.
(1)石山寺硅灰石(1922年指定),大津市石山寺辺町石山寺
(2)綿向山麓の接触変質地帯(1942年指定),蒲生郡日野町音羽綿向山麓
(3)鎌掛の屏風岩(1943年指定),蒲生郡日野町鍵掛滝谷川左岸
(4)別所高師小僧(1944年指定),蒲生郡日野町別所字真窪
詳しくは、、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0041.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】ジオパーク大図解シリーズ 発売中
──────────────────────────────────
■ 日本の地質遺産を図や写真をたくさん使って紹介した大図解が東京新聞から
出版されました。新聞見開き2ページ、あるいは学校教育用にはA3版で、
かなりお安く手に入れる事ができます。
詳しくは、、、
http://www.tokyo-np.co.jp/daizukai/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
トピックセッション2007 地球史とイベント大事件3:地球の変化に迫る
地球史とイベント大事件(3):地球の変化に迫る 2007年トピックセッションより
地質学の大きな魅力は、「地球が経てきた歴史を理解する」ことを地球表層に岩石や堆積物として残された証拠から紐解くことができることにあります。特に過去の地球に起こった真実があきらかになることは、我々をまるでタイムマシーンに乗って過去の地球に連れて行ってくれることに他ありません。近年の年代測定技術の進歩で、非常に精度の高い時代解像度で研究が行われるようになり、地球におけるイベント的な変化が詳細に明らかになってきています。
本セッションでは、このような地球上に起こっていた変化の記録の解明についての最先端の研究を集結し、ここの時代の変化を詳細に明らかにするとともに、別の時代における変化との共通点や違いなどを学ぶことを目標におこなっております。
ここで地球の歴史のおさらいをしましょう。
地球の歴史(45才の働き盛りのおじさんにたとえると。)
冥王代(45.6億年—40億年):地球上に記録がない時代:人間も生まれたときから5才ぐらいまではほとんど記憶がないですね。そのころの地球の歴史は月にのこされたクレーターや岩石の痕跡から類推しています。ちなみに最古の鉱物は 西オーストラリア・ジャックヒルというところにおいて、変成した砕屑岩(砂岩)中に含まれるジルコン(ZrSiO2) という鉱物から44億400万年前 (たとえば、Wilde et al., 2001, Cavosie et al, 2006)が報告されています.
太古代の露頭 Barberton greenstone belt South Africa. 枕状溶岩上に珪質堆積物がたまっている。約35億年前の枕状溶岩
太古代(40億年—25億年前)(小学生から二十歳ぐらいまで)
この時代は地球がとても多感な頃です。小学生から二十歳ぐらいになるでしょうか。体力がついて、骨格もしっかりしてきます。記録も鮮明になってきます。
地球も同様で、このときにほかの太陽系惑星にない大陸地殻が形成されるのです。この時代は我々が住むことができる大陸を作っていった時代と行っても過言ではないでしょう。また、生物の発生もこの時代に始まります。どんな環境で・いかなる生物が住んでいたのかまだまだ謎の多い時代です。
雪玉(全球凍結)仮説のナミビアのダイアミクタイト露頭
原生代(25億年—5億4500万年前)(二十歳から四十歳)
人間的にはこの時代社会に入って、人間世界を思い知る時代でしょうか。人間社会のなかでも就職・結婚・倒産・破局・家を造る・出産・など様々なことが起こる時代です。
地球上でも超大陸の形成・分裂・地球環境の暴走と収束(スノーボールアース事件)・巨大生物の時代への移行期と実はいろいろなことが起こっております。それぞれのところで、いろいろな出来事が起こっているようですが、その全貌はまだまだ謎です。
顕生代(5億4500万年前—現在) (おじさんの時代)
地球の歴史を考える上で、二十年前まではこの時代までが地球の歴史で、それ以前を先カンブリア時代と呼んでいました。顕生代は古生代・中生代・新生代と分かれており、三つの時代の境界はPT, KT境界と呼ばれ生物の大量絶滅がおこっています。また、古生代の後半は世界的な寒冷化におそわれており、白亜紀は世界中が急激な温暖化を起こしています。特に、ジュラ紀後期以降(約18000万年)より新しい時代では海洋底にも地質証拠が残っており、格段に精度の良い歴史復元が可能になっています。
KT境界層(中生代/新生代境界、いわゆる恐竜大絶滅)。ユカタン半島 Belize (Kiyokawa et al., 2006 地質学会口絵より)のイジェクター堆積物。
地球の歴史は人生の転機ともいうべき大きなイベントがいくつもあって、それ以降の世界を一変させています。このような現在では想像のつかない大事件の歴史が地層には残され含まれており、その痕跡・原因を調べることにより、我々の地球の未来の方向づける重要な指針を明らかにしようとしています。
清川昌一(九州大学)
本トピックセッションは現在まで3年間おこなっており、以下のようなテーマの発表がおこなわれています。
1) 太古代の地球:大陸の成長・初期生物・環境:
2) 酸化的地球への移行問題(太古代—原生代境界)
3) スノーボールアース時代と原生代後期—カンブリア時代への移行(原生代—顕世代境界)
4) PT境界(古生代—中生代境界問題)
5) OAE問題(海洋無酸素状態事件)
6) KT境界(白亜紀—第三紀境界問題)
文献
G. Brent Dalrymple's, The Age of the Earth, published by the Stanford University Press (Stanford, Calif.) in 1991 (492 p.)
A.J. Cavosie, J.W. Valley, S.A. Wilde, 2006. Correlated microanalysis of zircon: Trace elemnet, d18O, and U^Th-Pb sotopic constraints on the igneous origin of complex >3900Ma detrital grain. Geochimica Cosmo. Acta 70 5601-5616.
K. Condie and R. Sloan, Origin and Evolution of Earth, Principles of Historical Geology, published by the Prentice-Hall, Inc. in 1997 (498p.)
S.A. Wilde, Valley, J.W., Peck W.H., Graham, C.M., 2001. Evidence form detrital zircons for the existence of continental crust and oceans on the Earth 4.4 Gyr ago. Nature 409, 175-178.
講演プログラム
トピックセッション「地球史とイベント大事件3:地球の変化に迫る」は2007年9月に第114年学術大会(札幌大会)において以下の講演が行われました。
北海道東部に分布する根室層群仙鳳趾層から得られた上部白亜系マストリヒチアン階の高解像度安定炭素同位体比層序(荷福 洸・池原 実・成瀬 元)
アプチアンの海洋無酸素イベント堆積物の炭素・鉛・オスミウム同位体から読み取る火山活動の記録(黒田潤一郎・谷水雅治・鈴木勝彦・TejadaMarissa・小川奈々子・CoffinMillard・柏山祐一郎・大河内直彦)
ペルム紀中期から三畳紀初期にかけての深海底における酸素レベルの変動−放散虫チャート化学分析値の再評価(角和善隆)
古生代/中生代遷移期の始まりと上村事件(磯崎行雄)
太古代の海底環境:ピルバラ海岸グリーンストーン帯,32億年前のクリバーベル層群について(清川昌一・高下将一郎・伊藤 孝・池原 実・北島富美雄・山口耕生)
ピルバラ海岸グリーンストーン帯,デキソンアイランド層黒色チャート部層の岩相および炭素含有量の側方変化(高下将一郎・清川昌一・北島富美雄・伊藤 孝・池原 実・山口耕生)
南アフリカ, バーバートン帯中のマサウリチャートの岩相・層序について(稲本雄介・清川昌一・北島富美雄・山口耕生・伊藤 孝・池原 実)
南アフリカ,ポンゴラ超層群の4種硫黄同位体分析による約30億年前の大気酸素濃度の推定(鶴岡 昴・上野雄一郎・小宮 剛・吉田尚弘・丸山茂徳)
宮崎県高千穂町上村地域におけるペルム系Guadalupian統石灰岩のフズリナ化石帯区分(糟屋晃久・磯崎行雄)
南中国・四川省朝天におけるペルム紀G-L境界の層序(予報)(斎藤誠史・磯闢行雄・小林儀匡・姚建新・紀戦勝)
英国ウェールズ州アングルシー島の後期原生代−古生代イアペタス海起源遠洋性石灰岩・チャート(佐藤友彦・磯崎行雄・川井隆宏・丸山茂徳・WindleyB.F.)
豊浦層群西中山層の黒色頁岩中に記録されたPliensbachian-Toarcian期の長期的貧酸素環境(石浜佐栄子・松本 良)
日本全国天然記念物めぐり(滋賀県編)
◇各地の天然記念物◇
TOP 秋田県編 滋賀県編 京都府編 和歌山県編 福岡県編
日本全国天然記念物めぐり(滋賀県編)
滋賀には国指定の天然記念物が4つある.
(1)石山寺硅灰石(1922年指定),大津市石山寺辺町石山寺
(2)綿向山麓の接触変質地帯(1942年指定),蒲生郡日野町音羽綿向山麓
(3)鎌掛の屏風岩(1943年指定),蒲生郡日野町鍵掛滝谷川左岸
(4)別所高師小僧(1944年指定),蒲生郡日野町別所字真窪
このうち,石山寺境内にある硅灰石は保存状態およびアクセスに関して検証する必要はないと考え,他の3つを目指して,現地に向かった.一般市民の目線で天然記念物を探し見学するという主旨であるため,道路マップおよび現地観光協会の観光マップに出きるだけ頼るようにした.また,ネットでの下調べは行なっていない.ただし,虎の巻として石原(1992, 地質ニュース, 454, p.6-14「近畿地方の天然記念物」)は携帯した(取材日:9月16日(日)).
石山寺硅灰石以外の天然記念物は,全て蒲生郡日野町にあり,町の観光マップ(図1)にも綿向山麓の接触変質地帯と鎌掛の屏風岩は載っている.別所高師小僧は載っていないが,これには理由がある(後述).
図1)日野町観光マップ(日野のまち,日野観光協会)の抜粋.綿向山麓の接触変質地帯と鎌掛の屏風岩の位置を赤丸で示した.
名神高速を八日市I.C.で降り,国道307号線を南下,先ずは鎌掛の屏風岩を目指す.筆者愛用の「昭文社マップルリング関西道路地図」には「屏風岩」として載っている.県道182号の道端に見過ごしそうなほど小さな標識が出ている(図2).
図2)屏風岩の存在を示す標識
この看板に従い進むが10mほどで舗装道路(農道)が終わり,山道となる.車から降り山道を進むと道が二手に分かれているが,当然のように屏風岩の在りかを示すものはない.虎の巻の石原(1992)に,滝谷川左岸と記載されているので,谷沿いの山道を進むと屏風岩を発見(図3).車から降りて5分とかからない距離であり,ルートも分かってしまえば簡単であるが,一般市民はおそらく,舗装道路の終わるところで引き返してしまうだろう.屏風岩は秩父帯のチャートの露頭であり,層理面と直交する節理が交互にみられるため屏風状を呈するもの(石原, 1992)とされているが,屏風には見えなかった(図3).なお,チャートは秩父帯ではなく美濃・丹波帯のものである.見学ポイントには,滋賀県教育委員会と日野観光協会(?)の説明碑がある(図4).
図3)屏風岩全景
図4)滋賀県教育委員会の説明碑(上)と日野観光協会(?)の説明碑(下)
次に,綿向山麓の接触変質地帯に向かう.「昭文社マップルリング関西道路地図」には記載されていないので,日野町観光マップ(図1)を頼りに綿向山の登山口を取りあえず目指す.綿向山登山道の入り口には,登山道のガイドマップがあり,登山道が良く整備されている様子が伺える(図5).このガイドマップに接触変質帯の所在が記されていた.このガイドマップ以外に,天然記念物の在りかを示すものは認められなかった.このガイドマップに従い,駐車場から登山道を歩いて10分くらいで,接触変質帯の露頭に到着した(図6).
図5)綿向山ガイドマップ.接触変質帯の位置を赤丸で示した.
図6)接触変質帯全景
綿向山の接触変質帯は,秩父帯の石灰岩に花崗岩が貫入し,それによりスカルン鉱物(珪灰石,透輝石,ベスブ石,ザクロ石)が形成され,両者の接触部も観察されるようである(石原, 1992).筆者は,一般市民として天然記念物を観察するという立場であるので,ハンマーや鎌等は持参しなかったが,9月中旬頃の露頭は草木が繁茂し,気軽に露頭に近づいて観察することは出来なかった.日野観光協会・西大路公民館および滋賀県教育委員会の説明碑がそれぞれあるが,両者の内容は微妙に異なる(図7).ここでも秩父帯となっているが,現在の知見では美濃・丹波帯とすべきであろう.
図7)日野観光協会・西大路公民館の説明碑(上)と滋賀県教育委員会の説明碑(下)
最後に,別所高師小僧に向かう.これは「昭文社マップルリング関西道路地図」にも日野町観光マップにも載っていないため,取りあえず別所の集落を目指す.そこで,真窪という字を探すが見当たらず住民に尋ねると,親切にも直接案内して頂けた.高師小僧は古琵琶湖層群中にあると予想していたので,丘陵地に連れていかれると思ったが,そこは田んぼの真ん中であった(図8).そこに至るまでは,当然のように案内板など存在しなかった.ちょうど稲の収穫後だったので,分かってしまえば遠方からでも確認できるが,刈り取り前だったら全く分からないであろう.
図8)別所高師小僧の所在地(国道307号線より撮影.写真中央に高師小僧の記念碑があるはず)
現地では,高師小僧は存在せず,石碑だけがあった(図9).高師小僧自体は現在,南比都佐公民館に保存されているようである.おそらくこのため,別所高師小僧は観光マップにも載っていないのであろう.事実,天然記念物ツアー(後述)には,別所ではなく南比都佐公民館がそのルートに含まれている.
図9)別所高師小僧記念碑
後日,ネット(滋賀報知新聞オンライン)で検索した結果,日野町と日野町グリーン・ツーリズム推進協議会は,日野町内5つの天然記念物を巡る「秋の自然を満喫!日野の天然記念物めぐりツアー」(2006年11月)や「親子で巡ろう!日野の天然記念物ツアー」(2007年8月)などを開催していることが分かった.このツアーには,ここで紹介した3つの地質鉱物の天然記念物も含まれている(他の2つは植物).今年は8月に開催したようであるが,参加者の意見が聞きたいところである.
最後に,今回滋賀県の記念物めぐりをした感想は,「オリエンテーリング的には楽しい」(筆者は,大学の時オリエンテーリング部だった)であって,地質鉱物学的に楽しいかどうかは判断できなかったし,少なくとも感動はしなかった(別所高師小僧はある意味感動したが..).良い悪いは別として,これが天然記念物の現状である.今後も,随時,天然記念物の現状把握(と物見遊山)のために,少なくとも近畿の天然記念物はめぐる予定である.近畿以外の天然記念物めぐりを記事として書いて頂ける方は,奥平までご連絡いただければ幸いである.
No.0016 2007/11/20 geo-Flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.016 2007/11/20 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2008年度役員選挙についてのお知らせ(マニフェスト有)
【2】海外だより(ドイツから北村さんより)
【3】トピックセッションより:地球史とイベント大事件
【3】2008年度日本地質学会各賞候補者募集中!
【4】1/20万 日本シームレス地質図詳細版のお知らせ(これは使える!)
【5】大阪市立大学理学研究科・理学部地球学教室 特任講師の募集
【6】日本学術会議 平成20年度代表派遣会議及び派遣候補者の推薦募集
【7】第9回Project Aシンポジウム「五島列島で考える地球史」 参加者募集
【8】代議員選挙(地方区),立候補者リストの訂正とお詫び
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2008年度役員選挙:選挙活動期間についてのお知らせ
──────────────────────────────────
選挙活動の期間は11月6日から12月15日までです。
立候補者あるいは会員の方は、期間中、特定の立候補者への投票をお願いするこ
とができます。投票用紙は,11月14日発送予定です。HPの会員のページには,立
候補者名簿が掲載されています。マニフェストも近日中に会員のページに掲載さ
れる予定です。会員の皆さまには,選挙活動ルールの再確認(選挙活動について)
をお願い申し上げます。
立候補者名簿はHP会員のページをご覧下さい(HP画面右下、会員番号によるログ
インが必要です)
https://www.geosociety.jp
会長・副会長 候補者マニフェスト(カラー版PDF)についてはHPをぜひご覧
下さい.ログインの必要はありません.
https://www.geosociety.jp/outline/content0043.html
選挙活動ルールは、、、
www.geosociety.jp/outline/content0031.html
2007年11月5日
選挙管理委員会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】海外便り(1)北村有迅(IFM-GEOMAR)その1
──────────────────────────────────
海外で生活する会員から,研究環境や生活の様子などを紹介していただく<海外便りc第1回は,キール(ドイツ)の北村さんに書いていただきました.今号と次号に掲載致します.これを読んでいる海外在住の方!ぜひ原稿書いてください!海外生活の様子をご紹介いただける内容を自由に書いてください.ぜひぜひ!!原稿は地質学会事務局へ.(メルマガ編集部)
──────────────────────────────────
海外便り(1)IFM-GEOMARの紹介と来欧来独情報
北村有迅(IFM-GEOMAR, The Leibniz Institute of Marine Sciences at the University of Kiel)
はじめに
今回は筆者の所属するIFM-GEOMARとドイツの研究事情について紹介したい.IFM-GEOMAR(イーエフエム・ゲオマー)はドイツ最北の州, Schleswig-Holstein(シュレスヴィヒ・ホルシュタイン)の州都Kiel(キール)にある海洋科学の研究所である.
Kielについて
Kielは第二次世界大戦時にUボートの基地として知られたバルト海沿岸の港町で,現在でも造船や海運が盛んである.緯度は高いものの海洋性の気候のお陰 で冬でも南ドイツほど寒くはならない.戦災が酷かったこと,港湾都市であること,古くから大学があることなど複合的な要因でドイツ国内でも非常にリベラル な町であるそうで,黒人を含む移民比率が多い一方で治安は日本より良いと感じられるほどに安定している.
研究所沿革
IFM-GEOMARはKielにあった二つの海洋系研究所,IfMとGeomarが2004年に統合され設立された.Leibniz科学協会の研究所連 合の一員であり約400人の職員を擁する.Leibniz連合は全国84の研究所から成り,その研究成果は連邦・州政府の政策決定に関わるという使命を 持っており,それゆえ両政府からの補助を受けている.研究所名にKiel大学(正式名Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)の名が入っているが,附属しているわけではなく緊密な協力関係ということになっている.未だに筆者にはその確たる位置付けが分からないが, IFM-GEOMARの教授はKiel大学の教授も兼任しており,給与は大学から支払われている.一方で我々スタッフサイエンティストは研究所から雇われ ている.
ドイツ科学協会(DFG: Deutsche Forschungsgemeinschaft)
DFGは日本の学術振興会に相当する機関である.IFM-GEOMARは所謂ソフトマネー研究所であるので,筆者も含めポストに研究費がついていない. 従って着任時にまずやることは資金獲得である.DFGが学振と異なるのは,提出期限も申請金額の上限も無いことである.いつでも好きな金額の研究計画を立 てて申請できる.和文履歴書や科研費申請書のように決められた枠もない.書くべき事の章立ては決められているが,かなり自由な書式である.その代わり行き 当たりばったり的な要素を排し,“この測定をやればこれが分かる”と,もう結果さえあれば論文になるような書き方をしなければならないのが大きな違いであ る.筆者からするともう少し模索的余地がないと創造的研究が出来ないのではないかと思うのだが.申請書はレビューされ,研究規模や実績,スタートアップ資 金が必要な若手であることなどを考慮して審査される.
DFGにはSFB(Sonderforschungsbereich:特別研究領域)と呼ばれるプログラムがある.これは異分野の研究者が一つの大きな学 際的テーマに取り組むもので,2度の中間審査を経て最長12年に渡って研究資金が提供される.IFM-GEOMARとKiel大学は2つのSFBを獲得し ている(SFB460: Dynamics of Thermohaline Circulation Variability; SFB574: Volatiles and Fluids in Subduction Zones).SFBによって多くの研究者,博士課程の学生が雇われており,我がグループは直接雇用の研究者よりSFBメンバーの方が多い.
研究グループ構成
IFM-GEOMARには4つの研究部門(FB1〜4)がありそれぞれ,海洋循環・気候ダイナミクス,海洋生物地球科学,海洋生態学,海洋底ダイナミクス となっている.筆者の所属するFB4にはジオダイナミクス(GDY)とマグマ熱水システム(MUHS)のグループがある.GDYは教授3,ハードマネー研 究員6(筆者含む),ソフトマネー研究員22(13),SFB研究員10(8),学部生1,技官2(括弧:大学院生内数)からなる.グループ44人中研究 所から直接雇われているのは6人だけであるということや,大学院生が皆研究員として給与を貰っていることなどが特徴的であろう.学部生でも授業料は無料で ある.またドイツは教授ポストが非常に少ないことも見てとれると思う.MUHSもほぼ同規模である.
研究環境
研究室はDr.は個室,学生は2,3人でシェアしている.筆者の研究室も日本なら学生7人くらいは詰め込まれているだろう.ゼミはGDYグループで週1回 10時から行われている.海洋研究という性格上常に誰かが航海中であり,ゼミに集まるのは20人強といったところである.発表は基本的に10-20分,1 時間もやったら顰蹙である.クルーズレポートや研究の進捗状況などを徒然に発表しているようだ.ゼミの最後に翌週発表する人を募る.指名されることはない が発表者がないということもあまりない.それで回っているのが不思議だ.7-8割はドイツ人であるがゼミは英語である.国籍構成について教授に聞いたとこ ろ,考えたこともないという答えが返ってきたことがある.知る限りではGDYにはオーストリア,フランス,クロアチア,チリ,ロシア,タイ,中国からの学 生がいる.
GDYは基本的に地球物理屋が中心でほぼ皆が音波探査をやっている.そこに構造地質を専門とする教授がグループ長として赴任し,筆者を含め3人の地質屋を 採用して学際的研究グループとなることを目論んでいる.MUHSは分析系の研究者が多いのだが,それでも地球科学系の研究施設としては驚いたことに岩石薄 片作成設備が無い.このような点からも,資金をまず設備に投資する日本と,人材に投資するドイツの違いが感じられる.
言語
研究所では英語のみでもやっていける.ゼミは英語で行われ,皆一様に流暢である.筆者はパリ第六大学の大学院の野外実習に1週間ほど参加した経験がある が,フランスの学生はエリートと言われるパリ大学でもかなりレベルにばらつきがある.先に述べたDFGの研究資金も英語で申請でき,その他様々なウェブサ イトが英語で提供されている.あるロシア人学生曰く英語は“Sinplified German“だ,というのも頷けるほどに,集団に一人でも外国人が居れば英語で話す.時として途中からドイツ語になったり,通訳している最中に筆者に向 かってドイツ語で,相手に英語で話したりと混同する程違和感なく使っているようである.しかし科学者はそうであっても一般人はドイツ語のみの人も多いの で,生活には多少のドイツ語が必要である.これが国境を越えてデンマーク,スウェーデンへ行くと,町の誰もが英語を話すから驚きである.
しかし,IFM-GEOMARが必ずしも典型とは限らず, Kiel大学の別の学部のある研究室ではゼミも全てドイツ語で,それなりに話せないと発表機会も与えられないという話を聞いた.筆者は研究所の正規の研究 員ということで内部の予算会議などにも出席する.そのようなときはさすがに全員ドイツ人なのでドイツ語で行われる.各種メールもドイツ語がほとんどであ る.従って赴任前に数ヶ月のインテンシブコースを受講しておくべきだったと若干後悔している.仕事があるとなかなかまとめて勉強できないものである.
学生・ポスドクとしての来欧来独のチャンス・奨学金
いざ海外に出たいと思ってもなかなかそのための情報を得にくいものである.そこでその端緒となる情報にアクセスできるウェブサイトをいくつか紹介する.ドイツの大学は授業料が無料であったのだが,昨今では有料化の流れとなっている.これは大学によって異なる.
◇欧州全般◇
The European Researcher's Mobility Portal
http://ec.europa.eu/eracareers/index_en.cfm
ヨーロッパ中のファンドを検索出来る.
さらに各国版があり、そのドイツ版 http://www.eracareers-germany.de/
Seventh Research Framework Programme (FP7) (2007 - 2013) http://cordis.europa.eu/fp7/
EU の主導する科学助成プログラムの第7期FP7の中にMarie Curie Incoming International Fellowshipsがある.このMarie Curie IIFは申請書で書く量が多い上に、受け入れ側教員にも沢山書いてもらわねばならずかなりの労力を強いられる.その分、これさえ書いてしまえば他の申請書へいくらでも転用出来る.CV(履歴書)などもこの機会に作ってしまうと後々楽である.よく知った受入先と事前のコンタクトを取り、早め早めに申請を.
エラスムス・ムンドゥス(修士課程)http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html
EU版COE.EU域外からの修士課程へのサポートあり.それぞれの大学のプログラムに直接応募.
◇ドイツ◇
フンボルト財団 (Alexander von Humboldt Foundation)
Humboldt Research Fellowships
http://www.humboldt-foundation.de/en/programme/stip_aus/index.htm
ドイツ学振(DFG)
http://www.dfg.de/en/
ドイツ学術交流会(DAAD)
http://www.daad.de/en/index.html
様々なファンドが提供されており、しかも全て英語. DAADの奨学金検索ページではたとえば(地球科学、日本人向け、博士持ち)といった条件で検索できる.
DAAD東京支部
http://tokyo.daad.de/japanese/jp_index.htm
申請書の書き方まで日本語で解説.
ライプニッツ協会
http://www.leibniz-gemeinschaft.de/extern/englisch/positions/index.html
各種奨学金へのリンクもあり.
(次号に続く)
ページtopに戻る
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】トピックセッションより:地球史とイベント大事件
──────────────────────────────────
地球の歴史は人生の転機ともいうべき大きなイベントがいくつもあって、
それ以降の世界を一変させています。このような現在では想像のつかない
大事件の歴史 が地層には残され含まれており、その痕跡・原因を調べる
ことにより、我々の地球の未来の方向づける重要な指針を明らかにしよう
としています。 清川昌一(九州大学)
詳しくは、研究最前線のページ
https://www.geosociety.jp/faq/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2008年度日本地質学会各賞候補者募集中!
──────────────────────────────────
2008年度の賞の自薦,他薦による候補者を募集いたします.ご応募いただいた候補
者を,各賞選考委員会(委員は評議員の互選と職責により選出)が選考し,4月の
評議員会で受賞者を決定します.
日本地質学会功労賞・日本地質学会表彰以外は,会員(正会員・名誉会員)で
あればどなたでも推薦できます.
応募の締め切りは各賞とも,2007年12月25日(火)必着です.
日本地質学会各賞選考委員会
くわしくは、こちらから
https://www.geosociety.jp/outline/category0011.html
ページtopに戻る
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】20万分の1日本シームレス地質図 詳細版の公開のお知らせ
──────────────────────────────────
11月1日より,20万分の1日本シームレス地質図の詳細版を以下のURLで公開しまし
た。
http://riodb02.ibase.aist.go.jp/db084/index.html
従来の地質図は,基本版とし,同じHPで,基本版と詳細版が閲覧できます。
詳細版では,従来の基本版の凡例数193から,凡例数384に増えました。特に付加
体, 変成岩,花崗岩類及び完新世の凡例が詳細化されました。四国などでその違
いが明瞭です。
詳細版の画像ダウンロードも11月6日から可能になっています。基本版については,
以下のURLにおいて,ベクタ形式のデータのダウンロード が可能になっています。
統合地質図データベース http://iggis1.muse.aist.go.jp/ja/top.htm
是非ご利用ください。
産業技術総合研究所 地質情報研究部門
ページtopに戻る
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】大阪市立大学理学研究科・理学部地球学教室 特任講師の募集
──────────────────────────────────
1.募集人員:特任講師 1名
2.所 属:大阪市立大学大学院理学研究科・理学部 地球学教室
地球学教室に関する情報は,ホームページ(http://www.sci.osaka-cu.ac.jp)を
ご参照ください.
3.資 格 等:博士の学位を有し,野外実習・地質調査法の指導ができる方(30歳
前後が望ましい).
4.募集分野:環境地球学講座の分野
野外調査に基礎をおき,環境地球学分野の教育・研究を積極的に推進する意欲の
ある若手研究者.
5.職務内容:教育および研究
地質調査法や地球学野外実習などの野外実習関連科目,および地球学入門や建設
地学,地球学実験などの全学共通科目を分担または担当.
6.任 期:平成20年4月1日から1年
7.必要書類:
(1) 履歴書 (2) 論文・著書のリストおよび最近5年間の学会発表リスト (3) 論
文の別刷りあるいはコピー (4) 研究・教育に関するこれまでの経過と今後の抱
負(2000字以内)
8.締 切:平成19年11月30日(金) 必着
9.そ の 他:封筒に「特任講師応募」と朱書きし,書留で郵送して下さい.選
考結果は,平成19年12月下旬に本人にのみ通知します.他の方々には応募書類を
返却します.選考の過程で必要に応じて面接を行う場合があります.この場合,
交通費等は応募者の負担となります.
10.宛 先:〒558-8585 大阪市住吉区杉本3-3-138 大阪市立大学大学院理学研究
科・理学部
地球学教室 教室主任 升本 眞二 宛
11.問い合わせ:電話 (06)6605-3178 電子メール masumoto@sci.osaka-cu.ac.jp
(教室主任)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】日本学術会議 平成20年度代表派遣会議及び派遣候補者の推薦募集
──────────────────────────────────
日本学術会議より、依頼がありましたので、関係書類と合わせて転送します。
推薦を希望される会員は、必要書類を整えて12月20日までに理事会にお申し出下
さい。
締切:平成19年12月20日(木)
選考決定:平成20年3月 幹事会(学術会議国際委員会審議後)
派遣対象となる会議の開催期間は、平成20年4月〜平成21年3月
★ ご注意
代表派遣候補者の推薦は、地球惑星科学委員会国際対応分科会に所属する分科会・
小委員会が受け付け、地球惑星科学委員会を通じて国際委員会に届けられます。
推薦の締切は平成20年1月11日(金)ですが,理事会での手続きの関係上、学会締
切は12月20日となります.ご注意下さい.
問い合わせ先・連絡先
内閣府日本学術会議事務局(国際業務担当)付国際業務総括
朽木、小島
東京都港区六本木7-22-34
電話03-3403-5731 FAX 03-3403-1755
mail:i252@scj.go.jp mailto:i252@scj.go.jp
必要書類は下記からダウンロードして下さい。
1.平成20年度代表派遣会議及び代表派遣候補者の推薦(依頼)
2.留意事項
3.平成20年度代表派遣会議推薦書(様式3)
4.平成20年度代表派遣会議調書(様式4)
5.平成20年度代表派遣会議候補者推薦書(様式7)
6.代表派遣実施計画等に係るスケジュール(予定)参考1
7.日本学術会議の行う国際学術交流事業の実施に関する内規(抄)参考2
8.旅行代金概算見積書
ページtopに戻る
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】第9回Project Aシンポジウム「五島列島で考える地球史」 参加者募集
──────────────────────────────────
1地球の歴史を様々な角度からとりあげ、フィールドにおいて議論する地質学の重
要性を大前提に活発な意見交換を行います。特に五島列島の成因・背弧拡大また、
地球史について議論が予定されています。若手研究者・大学院生の交流の場とし
て最適です。日本列島が最後に中国と分かれた痕跡をのぞいてみませんか?ふるっ
てご参加ください。
日程:2008年3月7日(金)18時頃〜10日(月)
3月7日(金)一般講演会「五島列島で考える地球史」(福江)共催 五島教育委員会
3月8日(土)シンポジウム・巡検 海岸線の船による地質巡検(玉之浦)
3月9日(日)シンポジウム・巡検 (玉之浦)
3月10日(月)富江—福江地域・巡検 午後解散
参加申込締め切り:12月7日(金)
***テーマ****
1)五島列島の形成史
2)日本海・沖縄トラフ・背弧海盆の形成 伸展テクトニクス
3)太古代の海底環境や地球史イベントについて
3)アピールしたい最新の話題(古海洋・テクトニクス・年代学・古地磁気etc)。
(詳細なスケジュールは参加者決定後送ります。)
ぜひ、身近な方々にお声をおかけください。日本最西端の断崖絶壁に残された日本列島が中国大陸から分離する最後の痕跡が残る壮大な地質が皆様をお待ちしております。
————————————————
***対象:若手研究者、PD、院生およびやる気のある学部生。(参加者全員発表を行う。)人数制限がありますので、お早めにご連絡ください。一般講演は無料。
***参加方法
1)名前・所属・専門
2)講演題目
3)アブスト A4 1ページ:(下記の宛先までe-mailで添付してください。)
***交通手段
(飛行機)
12月前後で3月ごろの超割切符が発売されます。ぜひこれを購入してください。長崎空港まで行き、長崎港からフェリーが便利です。
(フェリー)
行き方
A: 3月6日 夜11:30分発博多港発 太古 9:00福江着
B: 3月7日(金曜日) 昼12:00発長崎港発 4:30分福江着
帰り方
C: 3月10日 午後4:30分 福江発 午後8時 長崎港着 (東京方面などはこれでは帰れないので、もう1泊ということになります。)
***参加費 (予算:参加費:3食・巡検・船・福江島内での車代込み)
学生・大学院生 5000円 寝袋持参(及び貧乏若手研究者)
教官・研究者 10000円 寝袋持参
一般講演のみの参加は無料です。
宿泊は公民館的なところになりますが、個室ご希望の方は近くの民宿・ホテルを予約しますので、ご連絡ください。
Project A 代表 清川昌一
問い合わせ (E-mail のみの対応とさせていただきます)
九州大学地球惑星科学部門 M2 長谷川孝宗
E-mail haseg@geo.kyushu-u.ac.jp
ページtopに戻る
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】代議員選挙(地方区),立候補者リストの訂正とお詫び
──────────────────────────────────
代議員選挙(地方区)の無投票当選者リストに一部誤りがありましたので,訂正
いたします.
【代議員選挙の地方区(中部)】
石田 桂会員の所属
中部 8 石田 桂 信州大学
学会ホームページに最初に公開され,郵送された立候補者リストでは,岐阜大学
となっておりましたが,正しくは「信州大学」の誤りでした.
立候補者のかたにはたいへん申し訳ございませんでした.この場をお借りしてお
詫び申し上げます.
2007年11月19日
日本地質学会 選挙管理委員会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.0017 2007/12/4 geo-Flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.017 2007/12/04 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】投票はお済ですか?
【2】2008年度日本地質学会各賞候補者募集中
【3】海外だより(ドイツキール大の北村さんより 後編)
【4】日本全国天然記念物めぐり(京都府編)
【5】ホットな地球惑星科学連合の最近について
【6】「ジオパーク」最近の動き
【7】第6回地球システム・地球進化ニューイヤースクールのご案内
【8】討論会「日本海沿岸褶曲・断層帯の形成・成長と地震活動」報告
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2008年度会長・副会長・全国区代議員選挙 投票締め切り間近!
──────────────────────────────────
投票〆切:12月15日(土)必着
例年,出し忘れや締め切りを過ぎてから到着するものがあります.候補者名簿を
よくご覧になって,お早めに投函されますようお願いいたします.開票結果は学
会ホームページ,ニュース誌1月号に掲載いたします。
選挙の詳細は学会HP会員のページをご覧下さい。
(ログインID・パスワードが必要です)
https://www.geosociety.jp/members/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2008年度日本地質学会各賞候補者募集中
──────────────────────────────────
応募の締切:12月25日(火)必着
日本地質学会功労賞・日本地質学会表彰以外は,会員(正会員・名誉会員)で
あればどなたでも推薦できます.論文賞・研究奨励賞・小藤賞の対象論文リスト
については,学会HPご覧いただくか,または,
学会事務局<main@geosociety.jp>までお問い合わせください.
詳細は,https://www.geosociety.jp/news/n21.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】海外便り 北村有迅さん@ドイツキール大学 後編
──────────────────────────────────
海外で生活する会員から,研究環境や生活の様子などを紹介していただく<海外
便り>第2回は,キール(ドイツ)の北村さんの後編です.これを読んでいる海外
在住の方!ぜひぜひ!!海外生活の様子を書いてください(内容は自由).原稿
は地質学会事務局へ.
──────────────────────────────────
風土の違い
北村有迅(IFM-GEOMAR, The Leibniz Institute of Marine Sciences at the Uni
versity of Kiel)
ドイツと日本は似ているという人もいるが,大いに異なると感じられる.日本人
にとって馴染みやすい,生活しやすいのは確かである.双方とも先進国と括られ
るが,時としてどうにもドイツが先進国とは思えないこともある.あまつさえ先
進的であろうとしていない様にも見える.これはドイツの個としての発展に対し
て,日本が集団として発展しているからかも知れない.言い換えればドイツが人
間中心的発展なのに対し,日本は社会・経済中心的発展をしているように見える.
では人間的である方がいいかと言えば,裏を返すとわがままで自己主張が強いの
である.だからあらゆる些細なことまでルールを作っているのである.例えば筆
者のアパートの契約書には毎日5分換気をすること,という条項がある.このルー
ルが日本人には心地良いのかも知れないが,いざルールが無い事柄になるともう
お手上げである.チャランポランかつ自己中心的な南欧人と大差ない(語弊のな
いよう言うと,筆者は幼少期をフランスで過ごしており愛着がある).ドイツで
特に感じるのは“個”である.他人にあまり干渉しないし,日本人から見るとド
ライな人間関係である.どの職業の人に聞いても同僚とあまり飲みには行かない
ようである.研究所でも月に1回のコロキウムの後はビールパーティーがあるが,
皆早々に散っていく.多国籍なパーティーで12時を過ぎて残っているのは日本人
だけということもあった.
仕事以外の生活面は充実している.まず労働時間が短い.夏は夜11頃まで明るい
ので,皆仕事を早く切り上げる.逆に冬は4時には日没なので暗くなる前に帰る.
出勤時間は8~9時が多いだろうか.筆者の労働契約も週37.8時間というものである.
IFM-GEOMARのような高々400人規模の研究所にも保育所がある.子育てや家族との
時間を取るなら圧倒的に良い環境である.教育に関しては日本の方がいい気もす
るが,日本は落ちる一方であろう.ドイツはゆとり教育の失敗に気付いて転換し
たが,ピーク世代が今30歳前後だそうだ.日本はこれからである.
最も異なるのは科学者の位置付けや待遇であろう.こちらでは博士はエリートで
あり高給取りであり,博士課程の学生はその卵である.学生時代から将来を嘱望
され,投資され,ポスドクになれば一人前の研究者と見なされる.日本では時と
してポスドクは学生の延長のような半人前扱いを受ける.学生も往々にして管理
された状態である.しかし一方でドイツでは,先に述べたとおりプロジェクトの
予算申請は子細に書かれているので,学生に与えられるテーマはやるべき事が決
まっており,ほとんどマシンとなればいいのである.日本の学生の方が自由な研
究ができているかも知れない.にもかかわらず個としての尊厳が守られているド
イツの学生をみるにつけ文化の違いだと感じるところである.
ドイツで最もがっかりしたことは給料が45%も天引きされることだ.フィンランド
の友人でさえ驚いていたのだが,独身は搾り取られることを覚悟しなくてはなら
ない.旅行などもグループ割引が異常なまでに利くので,友達も家族もいないと
極めて金のかかる国である.
よく日本とドイツどちらがいいかと問われるが,メリットデメリットは常に交錯
して一概に言えない.日本は街が清潔で,研究設備は整っていて,天引きも少な
く,何事もきっちりしていてトラブルが少なく,同僚と飲みに行けて,食事がお
いしい.かたやドイツは街並みが美しく,空間に余裕があり,人件費を惜しまず,
余暇が多く,物価が安い.
未知を既知とすることで人類が成長してきたのであるから,異文化を知ることは
一科学者を多少なりとも成長させていると信じつつ.
(氷点間際のキールにて 北村有迅)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】日本全国天然記念物めぐり(京都府編)
──────────────────────────────────
(1)稗田野の菫青石仮晶(1922年指定),亀岡市稗田野町桜天神(桜天満宮)境内
(2)郷村断層(1929年指定),京丹後市網野町,樋口断層,小池断層(郷小学校),
生野内断層
(3)東山洪積世植物遺体包含層(1943年指定),京都市東山区今熊野南日吉町
正法寺境内
(4)琴引浜(2007年指定),京丹後市網野町琴引浜
(大阪市立大学 奥平敬元)
詳しくに読む。https://www.geosociety.jp/faq/content0047.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】ホットな地球惑星科学連合の最近について
──────────────────────────────────
日本地球惑星科学連合は発足して2年半が経過しました。いま連合では、これま
でのように春に関連学協会が合同で大会を開くという活動と、学術会議対応で関
連学協会の統一的窓口となるというところから更に発展して、地球惑星、地球環
境などに関わる共通した課題に取り組むコミュニティーとして前進しようとして
おります。それに当たっての基本的方向として、学協会の発展と連合の発展を車
の両輪として進めるということが連合の将来構想委員会中間答申で打ち出されま
した。更に引き続き検討が進行しています。
http://www.jpgu.org/publication/mailnews/071112/masterplan1023.html
また、社会に関わる連合の活動の1つとして、地学教育に関わる様々な課題に関
しては目覚ましい活動が展開されております。文字通りの統一されたコミュニ
ティーとして、相次ぐ文部科学省、中央教育審議会への申し入れと会談など、重
要な社会的影響力を発揮して来ております。
:www.jpgu.org/education/index.html
地質学会会員はそこで主導的役割りを果たしております。 日本地質学会はこの
連合において、日本気象学会に次ぐ規模であり、連合登録者数においては最大の
日本地震学会と並ぶ最大の規模となっております。連合への登録は誰でも無料と
なっておりますので、関心をお持ちの方はウエブ上で簡単にできます
: http://www.jpgu.org/meeting/entry.html
いますぐ登録し、めまぐるしく動いているホットな地球科学関連情報が手元に配
信される環境を構築しましょう。
(会長 木村 学)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】「ジオパーク」最近の動き
──────────────────────────────────
日本地質学会ジオパーク設立推進委員会 渡辺真人(産総研)
確実に浸透しているジオパークの活動
日本地質学会ジオパーク設立推進委員会は2005年に設立され、以来日本におけ
るジオパーク活動を推進してきています(ジオパークの詳細に関しては日本地質
学会のwebsiteをご覧下さい)。5月に当委員会が中心となって地球惑星科学連合
大会でジオパークに関するユニオンセッションを開催し、それをきっかけに6月に
ジオパーク推進の動きが朝日新聞科学面に報道されました。それ以来、各地から
問い合わせ、地域でのシンポジウムなどでの講演依頼が当委員会あてに多数来る
ようになり、地方紙などにジオパークに関する記事が何度も掲載されました。た
とえば、8月には、当委員会岩松氏の雲仙岳災害記念館での講演が地元で大きく報
道されましたし、地質学会札幌大会の前後には、壮瞥町での有珠・洞爺湖ジオパー
ク構想に関するフォーラムでの当委員会委員長の佃氏の講演、地質学会市民講演
会、アポイ岳をジオパークにという様似町の動きなど、ジオパークの話題が何度
も北海道新聞をはじめとする地元紙の紙面を飾りました。ジオパークの知名度は
最近半年ほどの間に飛躍的に上がってきており、多くの地域でジオパークによる
地域振興計画が始まりました。
地域はジオパーク連携協議会設立へ ー国内体制の確立へ向けてー
これらの各地での盛り上がりを受けて、10月4日に、世界ジオパークネットワー
ク(GGN)参加を目指す12地域の代表(主に自治体関係者)がNPO法人地質情報整
備・活用機構(GUPI)に集まり、ジオパーク連絡協議会を設立することで合意し
ました。現在も設立に向けて参加資格や規約、活動内容に関して話し合いが続い
ており、12月26日に連絡協議会が設立される予定です。10月4日の会議に参加した
地域は、白滝黒曜石遺跡、アポイ岳、有珠・洞爺湖地域、五浦海岸周辺、箱根・
小田原地域、糸魚川、山陰海岸、四国(四国運輸局予算で地域選定を含めた調査
中)、霧島、島原半島、天草市御所浦、計12地域です。さらに、石見銀山(大田
市)、南アルプス(伊那市、大鹿村など)にもジオパーク設立に向けた動きがあ
ります。
ジオパーク設立推進委員会としては、今後関連学会・関連省庁の人をメンバー
とする日本ジオパーク委員会を設立し、GGN申請候補の選定と国内版のジオパーク
の認定を行いたいと考えています。また上記の連絡協議会をベースとして、国内
版ジオパークが加盟する日本ジオパークネットワークを設立し、日本のジオパー
ク活動の支援と広報活動などを行いたいと考えています。ジオパークを認定する
日本ジオパーク委員会と、実際の活動を支援する日本ジオパークネットワークの
両輪でジオパークを振興する体制を作ることを当委員会は目指しています。
アジア・太平洋地域ジオパークネットワーク設立への動き
先月11月13-15日に、マレーシア・ランカウイ島でアジア・太平洋地域ジオパー
ク会議が開催されました。日本からは渡辺と、糸魚川フォッサマグナミュージア
ムの竹之内耕氏が参加し発表しました。日本では博物館などを中心として地球科
学の教育・普及活動の実績があること、それをベースにジオパークの活動が進ん
でいることがユネスコジオパーク委員に好感を持って受け止められ、申請に向け
て良い足がかりとなったと思います。会議中、アジア太平洋ジオパークネットワー
ク(APGN)の設立が提案されました。日本としてアジア・太平洋地域のジオパー
ク活動が高いレベルで盛り上がっていくよう、APGNに協力していく必要がありま
す。そのためにも、上に述べたような日本の国内体制を早急に整備し、日本第一
号のGGN加盟申請をできるだけ早く実現したいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】第6回地球システム・地球進化ニューイヤースクールのご案内
──────────────────────────────────
テーマ 「新しい切り口から地球を探る」
開催日: 2008年1月5日(土)〜6日(日)
開催場所: 国立オリンピック記念青少年総合センター(東京・代々木)
参加費: 3000円(懇親会費込み)
申込期間: 2007年11月5日(月)〜12月7日(金)
スクールホームページ(申込・詳細情報はこちらから)
http://quartz.ess.sci.osaka-u.ac.jp/~earth21/school/2007/index.html
新しいアプローチやアイデアを武器に新しい研究領域を切り開いてこられた研究
者の方々による講演です。研究に取り組むにあたり、どのような問題意識を持ち、
どのような着眼点、アイデア、アプローチでその問題に取り組んでこられたか、
について簡単なレビューを踏まえてお話していただきます。この他にもさまざま
なイベントを企画しています!
講演者:
- 小川勇二郎先生 筑波大学
- 高井 研 先生 海洋研究開発機構
- 谷 篤史 先生 大阪大学
- 平田 岳史 先生 東京工業大学
- 平野 直人 先生 東京大学
- 安田一郎 先生 東京大学
- 横山 祐典 先生 東京大学
Ex. レクチャー講演者:
科学に携わる様々な職種の方々による講演です。
- 高山 英男 博士 NHK新潟放送局
- 干場 真弓 博士 日本科学未来館
- 向吉 秀樹 博士 (株)マリンワークジャパン
主催:21世紀の地球科学を考える会
http://quartz.ess.sci.osaka-u.ac.jp/~earth21/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】討論会「日本海沿岸褶曲・断層帯の形成・成長と地震活動」報告
──────────────────────────────────
11月25日に,新潟大学において表記の討論会が構造地質部会主催・新潟大学後援
で開催された.また,それに先立ち,24日に小林健太・大坪 誠・栗田裕司氏の
案内で新潟県中越沖地震を起こした断層との関係が注目されている鳥越断層の地
形と露頭〜中央油帯と海岸付近で新潟のNeogeneの標準層序(魚沼・灰爪・西山・
椎谷・寺泊の各層)の見学を実施した.プレ巡検の模様は河本和朗氏により記載
されるので,ここでは討論会の記録を記す・・・・・。
(構造地質部会長 高木秀雄)
さらに読む。https://www.geosociety.jp/science/content0012.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
日本全国天然記念物めぐり(京都府編)
◇各地の天然記念物◇
TOP 秋田県編 滋賀県編 京都府編 和歌山県編 福岡県編
日本全国天然記念物めぐり(京都府編)
京都府には国指定の天然記念物が4つある.
(1)稗田野の菫青石仮晶(1922年指定),亀岡市稗田野町桜天神(桜天満宮)境内
(2)郷村断層(1929年指定),京丹後市網野町,樋口断層,小池断層(郷小学校),生野内断層
(3)東山洪積世植物遺体包含層(1943年指定),京都市東山区今熊野南日吉町正法寺境内
(4)琴引浜(2007年指定),京丹後市網野町琴引浜
前回の滋賀県編では,道路マップおよび地元の観光マップを頼りにめぐったが,今どきはやはり事前にネットで調べるのが常識と一部の読者から指摘されたため,簡単な下調べをネットで行なうことにした.前回同様,市民として物見遊山が基本である(10月の連休に取材).
稗田野の菫青石仮晶
先ずは,「稗田野の菫青石仮晶」を目指した.菫青石や接触変成作用は著者の専門にも近いし,桜石自体も有名であるので大いに期待した.また,稗田野の町には「さくら石」というお菓子も販売しており(図1,残念ながら購入できず),テンションも自ずと上がる(この後,すぐに下がることになるが..).
図1)銘菓「さくら石」
ネットで調べると「亀岡市稗田野町桜天神(桜天満宮)境内」となっているが,石原(1992, 地質ニュース, 454, p.6-14「近畿地方の天然記念物」)では「亀岡市街西方,大谷タングステン鉱山南方の山林」となっていることが不安材料であったが,とりあえず桜天満宮を目指す.国道372号沿いに石碑(図2左)と標識が出ていたので,それに従い左手の側道に入る.側道から山手に登るのであろうと予想して気をつけていたが,なかなか入り口を見つけることが出来ず,結局,地元の方に教えて頂いた(図2右).いつものことながら,なぜ直前の標識がないのか不思議である.細い砂利道をしばらく行くと,突然整備された参道が現れ(図3左),古刹と呼ぶにふさわしいお寺(積善寺)に到着(図3右).
図2)(左)さくら天神の石碑と標識.ただし,標識には「積善寺(桜天満宮)」とあり,左の側道を行けとある.(右)側道沿いの桜天神(桜天満宮)および積善寺参拝道口.白いトラックの停めてある細い砂利道を登っていく.
図3)(左)積善寺参道.この左奥に桜天満宮がある.(左)積善寺山門.
図4)(左)桜天神(桜天満宮).(右)桜石と桜天満宮の碑文.
山門をくぐり,お寺の境内のすぐ左手に鳥居を発見.その前に天然記念物の存在を告げる碑があった(図4).境内をそれなりに探したが,露頭らしきものは真砂化した花崗岩だけであり,泥質接触変成岩の露頭はなかった.泥岩の転石がいくつかあったので観察したが,桜石は含まれていなかった.ここは「京都の自然二百選」,「亀岡の自然百選」に選ばれている(図4左)ため,「稗田野の菫青石仮晶」の所在地で間違いはないと思うが,石原(1992)の記述とは所在地が異なり,実際に桜石を含む接触変成岩の露頭は見当たらなかったし,天然記念物の石碑も認められなかった.碑文に「(前略)"桜石"は盗掘のため現在残り少なっているので,文化財保護のため丁重な見学を希望します.(後略)」とあるので,盗掘により露頭自体が消失してしまったのかもしれない.ご存知のように,天然記念物は文化財保護法(第196条 史跡名勝天然記念物の現状を変更し,又はその保存に影響を及ぼす行為をして,これを滅失し,き損し,又は衰亡するに至らしめた者は,五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する)により,その採集は禁止されている.稗田野の桜石に関して,情報をお持ちの方にご連絡いただければ幸いである.
東山洪積世植物遺体包含層
次に「東山洪積世植物遺体包含層」を目指した.事前のGoogle検索では,なんと「じゃらんネットの旅行・観光:おでかけガイド」がトップヒットだった.マップも掲載されていた.今さらながらネットにおける情報量の多さに感心しつつ,セカンドヒットの「全国たび相談(全国地域観光情報センター)」に詳細なマップが掲載されていたので,念のために印刷しておいた.マップに従い現地に到着したが,その位置には正法寺というお寺があった.石原(1992)に境内とあったのでお邪魔し,境内を探したが見当たらず(結局20分くらい境内を含め周辺を探した),結局,お寺の方に伺いその所在を教えて頂いた.そこはお寺のプライベートな空間の奥にあり(図5左),観光客が気軽に見つけ出すということは不可能である.露頭自体は1×3メートル程度の大阪層群の泥層であり,保存条件は良好であった.天然記念物を示すものはひっそりとたたずむ記念碑(図5右)のみであり,説明文の掲示等はなかった.京都市内の住宅地で,このような露頭が存在し得るというのは,やはり天然記念物の威光というものを実感した.しかし,「東山洪積世植物遺体包含層」という名称は,いかがなものであろうか.洪積世と言われても,地質系大学の低学年でもいつの時代の地層なのか分かるのであろうか?(現在は,洪積世を更新世と習うはずだからである).植物遺体も生々しい.なお,文化財保護法第196条の2に「前項に規定する者が当該史跡名渉天然記念物の所有者であるときは,2年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金若しくは科料に処する」とあるので,おそらく土地の所有者であろうお寺さんは,消極的か積極的か係わらず,保護の義務を負っているのであろう.
図5)(左)東山洪積世植物遺体包含層の露頭.(右)天然記念物碑.
郷村断層
次に,京丹後市網野町の「郷村断層」を目指した(翌日).旧郷村内の3ヶ所が天然記念物として指定されている.ここは素晴らしかった.先ず,3ヶ所のうち2ヶ所(樋口断層,小池断層)で府道に大きな案内板が出ていた(図6左,図9左上)ので,迷うことなく現地に着けたのは嬉しかった.
図6)(左)郷村断層(樋口断層)の案内板.(右)樋口断層保存建屋.奥に駐車場あり.
樋口断層の保存建屋はまだ新しく,普通車5台程度の整備された駐車場が隣接していた(図6右).また,京丹後市教育委員会の説明碑(図7左)は詳細であるばかりでなく,QRコードが表示されており(図7右),コードリーダーで読むとネットにちゃんと繋がった.ネットでの情報はそれほど詳細なものではないが,結構楽しい.
図7)(左)京丹後市教育委員会の説明碑と天然記念物碑.説明碑の左下にQRコード(右)がある.
保存建屋には大きなガラス窓があり,中の様子を観察することができるようになっている(前日の雨のためか,ガラス窓が曇っていて,あまり観察できなかった)(図8).保存建屋内は,小さな断層崖が保存されているようである.扉には鍵がかかっており,通常は保存のため,建屋内には入れないようになっているのであろう.
図8)保存建屋内の様子.
小池断層は,変位地形が残されている(図9右上).右横ずれ変位の様子がよくわかり,素晴らしい.京丹後市教育委員会の説明文も詳細で,地震発生当時の写真も掲載されている(図9右下).
図9)(左上)郷村断層(小池断層)の案内板.すぐ後ろに郷小学校がある.(右上)断層による変位(右横ずれ)によって道路が食い違っている様子が観察で きる.断層位置に碑が建っている.(左下)京丹後市教育委員会の説明碑と天然記念物碑.(右下)説明碑のクローズアップ.
生野内断層は,府道からの案内板がないので,若干迷うが樋口断層の説明文に掲載されている地形図を参考にすれば辿着くことが出きる.車をおりて200メートルほど歩くと草に埋もれた標識があり(図10右,この標識の存在は帰りしな気がついた),生野内断層の保存建屋が見えてくる(図11左上).
図10)郷村断層(生野内断層)の所在を告げる標識(2ヶ所).
ここにも,京丹後市教育委員会の説明碑と天然記念物の石碑がある.他の2ヶ所にはなかった,「京都の自然二百選」の碑がなぜかここにある.保存建屋の扉には鍵はかかっておらず,中に入ることが出きる.中にはいくつかの掲示があり,生野内老人会による丁寧な説明文もあった(図11左下).このような掲示は,地元の方々が天然記念物を身近に感じていることの表れのように感じた.建屋内には断層変位を物語る断層崖が保存されていた.
図11)(左上)生野内断層の保存建屋.(右上)天然記念物碑と京丹後市教育委員会の説明文.京都の自然二百選の碑もある.(左下)建屋内の生野内老人会による説明文.(右下)建屋内に保存されている断層崖.
琴引浜
郷村断層の取材が効率的に終わったので,気を良くしながら琴引浜に向かった.琴引浜は2007年7月に指定されたばかりで,地元はこれを観光資源として活用しようと盛り上がっていた(図12).
図12)天然記念物指定を祝う横断幕.
琴引浜は,もともと鳴砂で有名である(図13左).一時期は海岸環境の悪化が言われていたが,地元住民らの努力により,琴引浜の鳴砂は清浄に保たれている.鳴砂は,石英の砂粒が充分洗浄され,表面の摩擦係数が極端に大きくなった結果として,外部から力を受けた時にスティックスリップを起こすことにより音が出るものであるらしい(琴引浜ガイドブック,京丹後市網野町).鳴砂の必要条件として,常時,流動的な砂浜海岸において,鳴砂の主成分となる石英砂が供給され,常時,微粒子等の付着が発生する砂浜海岸において砂を洗浄するシステムが機能していることが挙げられている(鳴砂の浜をまもる,(財)日本ナショナルトラスト,2006年).これにより,指定基準は「(9)風化及び侵蝕に関する現象」となっている.石英粒は高温型とされており,実体顕微鏡で観察すると確かにそろばん玉の形状を示したものが認められる.琴引浜の後背地には,白亜紀珪長質火成岩類として,矢田川層群や宮津花崗岩が分布しているので,高温石英は矢田川層群に由来するのであろう.なお,天然記念物に指定されたため,琴引浜の鳴砂採集すると罰せられる(先述,文化財保護法第196条)のでご注意あれ(図13右).
図13)(左)琴引浜.(右)鳴砂の採集を禁ずる掲示.
琴引浜から徒歩20分程度の所に「ヘリテイジセンター琴引浜鳴き砂文化館」があり,そこでは鳴砂に関する展示や鳴砂を通した環境保護の展示がなされており,大変参考になる.採集が禁じられた鳴砂は,この文化館のお土産としてちゃっかり販売している.
今回の京都府の天然記念物は,亀岡市・京都市と京丹後市にあるため,2日かけてめぐることになった.保存状態の悪いものが散見される中,郷村断層のように地元の方々や教育委員会が保存と展示に力を入れているものを目の当たりにすると,安堵し嬉しくなるのは正直なところである.また,琴引浜は最近天然記念物に指定されたが,これも地元住民の継続的な努力の結果であり,どれほど地質学的な意義が認識されているかは不明であるが,市民と地質学のひとつの接点のあり方として,希望を感じた.
シンポジウム2007 海底地すべり
海底地すべり 2007年シンポジウムより
図1 アスファルト地すべり?
図2 白山山麓の「別当大崩れ」
地すべりは,大雨のとき裏山が崩れたり,大規模に田畑や山が崩れたり,とニュースで聞きますよね(図1と2).海底にも,そんな地すべりがあります.ただ,海底なので,大雨や田畑はないですが.
では,海底の地すべりはどうやって起きるのでしょう.浅い場所ならば,風浪が考えられますが,もっと深く水深数百mではどうでしょう.実際に多くの海底地すべりが見つかっています.深いところでは,水深4000mを超えます.
海底地すべりの誘因として,まず,地震動が上げられます.2004年の中越地震では,多くの山や斜面で地すべりが発生したことは記憶に新しいと思います.地震が発生すると,揺れによる加速度で斜面が安定性を失い,海底の斜面だったとしても崩壊します.
地震動の他に,メタンハイドレートの崩壊も海底地すべりの発生誘因として考えられています.例えば,氷河期などで大規模に海水準が低下する(氷河期では海水準が200mも下がったとされています)と,現在メタンハイドレートがある海底の水深が浅くなります.そうすると,水圧が減少するため,メタンハイドレートは安定性を失い融解します.メタンハイドレートが斜面にある場合,海底地すべりが発生するとされています.
このような誘因によって発生した海底地すべりは,私たちの生活にさまざまな影響を及ぼします(図3).まず,海底ケーブルや海底パイプラインが切断される.さらに,資源開発など海底掘削でのプラットフォームに障害が発生する.また,メタンハイドレートが大規模に融解する,津波が発生する(漫画では波高の高い津波が沖合に描いてありますが実際には沿岸で水深が浅くなり減速して波高が高くなります).です.
海底地すべりは,このように大変重要な調査,研究課題ですが,「海底」という目視が難しい環境のため,謎ばかりです.ですから,私たちは今年多くの分野の研究者とともにシンポジウムを行いました.みなさんも興味を感じるところがあったならば,一緒に調べていきましょう.
図3 海底地すべりとその影響
川村喜一郎・藤田勝代(深田研),目代邦康(産総研)
講演プログラム
シンポジウム「海底地すべり」は2007年9月に第114年学術大会(札幌大会)において以下の講演が行われました。
シンポジウム開催にあたって(川村喜一郎)
潜水船調査から明らかにされた南海付加体の海底地すべりの特徴(川村喜一郎・横山俊治)
地質モデルに見られる付加体形成に伴う斜面崩壊(山田泰広・大島祐介・宮川歩夢・松岡俊文)
地すべり移動体の内部構造と微地形:北海道の陸上の例から(田近 淳)
堆積岩山地斜面上に見られる大規模崩壊の前兆現象(目代邦康・手打啓一郎)
なぜ同じ地点からすべり始めるのか?〜動態観測とすべり開始点のコア分析〜 (坂口有人・横山俊治・橋本善孝・氏家恒太郎・山田知成・吉村典宏)
(招待講演)サーボ型加速度計を用いた海底地層変位モニタリングシステムの開発(横山幸也・斉藤秀樹・亀谷裕志)
ハイパードルフィンによる深海底表層地盤におけるコーン貫入試験と地震時安定性評価(阪口 秀・渦岡良介・泉 典洋・木戸ゆかり)
台湾海底ケーブル断線記録から読み取る地震直後の深海底混濁流イベントと斜面崩壊(徐 垣・町山栄章)
(招待講演)深海巡航AUVを用いた海底地すべり調査の可能性(笠谷貴史・月岡 哲・山本富士夫・木下正高・金松敏也)
(招待講演)ハワイ諸島における巨大海底地すべり(横瀬久芳)
ハワイ島海底山麓のAlikaデブリアバランシェによってもたらされたタービダイト層の特徴(藤本悠太・横瀬久芳・金松敏也・石井輝秋・村山雅史)
地震が誘発する巨大海底地すべりとその内部構造(山本由弦・鈴木清史)
アンダマンースマトラ沖における調査航海中に見られた海底地滑り:MD149およびSO189-2航海の概要(金松敏也・山口はるか)
おわりに:これからの地すべり研究(大八木規夫)
No.0018 2007/12/18 geo-Flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.017 2007/12/04 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】発表!2007年 地質重大ニュース(勝手に選びましたっ)
【2】2008年度日本地質学会会長、副会長,代議員選挙結果
【3】2008年度日本地質学会各賞候補者募集中(来週締切!)
【4】シンポジウムダイジェスト「 海底地すべり」
【5】専門部会再登録のお願い
【6】2008年度会費の払込・院生割引申請について
【7】シンポジウム「新潟の自然と科学教育の素材」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】発表!2007年 地質重大ニュース
──────────────────────────────────
今年もあとわずかになりました。2007年を振り返り、地質関連の重大ニュースを
編集部で勝手に選んでみました。こうしてみると地質学関連のニュースがたくさん
報道されています。来年も良い意味で地質学のニュースが多くあることを願います。
新潟県中越沖地震
渋谷ガス爆発事故(産総研地質情報センターのHPにアクセス殺到?)
能登半島地震
天然ダイアモンド国内初発見
(地質学会HPにアクセス殺到。サーバーパンク寸前に)
ちきゅう運航開始
学術大会メディアリリース開始(6紙、3局で報道)
学会HPリニューアル
ジオフラッシュ創刊
地下資源高騰
「地質の日」制定
地球温暖化問題がクローズアップ(ノーベル平和賞がIPCCとゴア氏に)
南極観測船しらせが最後の航海に出向(建造中の新南極観測船の名前も“しらせ”に)
恐竜化石発見ラッシュ
熊本県 天草市立御所浦白亜紀資料館
恐竜化石の発見が相次いだことに関して熊本県御所浦白亜紀資料館の廣瀬浩司学
芸員からコメントを頂きました。
Q1 今年は恐竜化石発見のニュースが相次ぎました。主要なニュースについて
教えて下さい。
A.
1 今年一番の国内の恐竜関係のニュースは、なんと言っても丹波竜です。
鳥羽国内昨年発見、今年1月にマスコミ発表され、現在も発掘中のものですが、
全長10数mで、推定16〜18mの鳥羽竜と並び、国内最大級の恐竜です。しかも、
日本産で、複数の部位がいくらかまとまったものとしても、ニッポノサウルス(
旧日本領樺太産)、フクイリュウ、フクイラプトル、御所浦の鳥脚類(クリーニ
ング中)などが知られていますが、これもそうで公表されている尾椎のなどの産
状は、国内で前例のない関節がつながった部分もあり、非常に状態の良いもので
す。
さらに、脳函(頭骨の一部)も見つかっており、今後の調査次第では他の部分が
見つかる可能性も高く記載や全身の復元も期待できるものだと思います。
2 福井で見つかった皮膚痕は、同化石としては2例目、体の表皮の部分として
は、国内で初めて公表されたもので、非常に貴重な発見です。
特に、皮膚痕は、細かい模様であるため、残される環境が限定されます。しかも
その痕を削らずに上に堆積物が堆積しないといけなく、さらに人の目に触れるま
で、侵食や変動、破壊などによる消失を免れないといけないので、骨や歯、足跡
以上に、化石として残る可能性は低いものです(少し前にアメリカで恐竜のミイ
ラ発見の報道がありましたが・・)。通常、皮膚は残らず腐敗することから、そ
の痕跡であっても、恐竜の復元において重要なもので、詳細な復元に役立つ希少
な資料です。
3 熊本県御船のハドロサウルス類の化石は国内からいくつか知られていますが、
御船のものは、福島県のものと並び、ハドロサウルス類としては国内最古級のも
のです。
これらの化石は、北アメリカやアジアなどから化石が多く見つかりますが、約830
0万年以前のものは世界でも発見例が少ないということです。白亜紀の鳥脚類は、
前期のイグアノドン類、中頃のプロバクトロサウルス類、そして、後期のハドロ
サウルス類へと変化しており、この内、初期のハドロサウルス類という意味でも
貴重な発見です。
4 このほかに和歌山で、同県初となる恐竜化石が発見されています。
獣脚類の歯で、その特徴からカルノサウルス類で、大きさから3〜4mの大き
さのものであったと推定されています。獣脚類としては中央構造線より太平洋側
では3例目だそうです。ちなみに、兵庫の丹波竜の産地で、他に獣脚類や鳥脚類
の歯の化石、福井で、竜脚類の大腿骨(竜脚類の大腿骨としては国内2例目)や
前脚、歯、肋骨なども発見されています。
Q2.これだけ相次いだ年は珍しいですか?
A 1997年は御所浦だけで3件、他にも福井や御船などのものがニュースになってい
たりするので、発見の数の公表数では、過去にも多い年はあります。
今年も多いと思いますが、さらに丹波や福井での発見では、調査状況の進み具合
に応じて、新知見が得られた毎にその内容を発表していたりするので、国内の恐
竜化石について、話題に挙がる回数としても多かった年と言える思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2008年度日本地質学会会長、副会長,代議員選挙結果
──────────────────────────────────
12/17に、2008年度役員および代議員選挙の開票を行いました。
選挙結果は会員のページへのログインして下さい。
日本地質学会選挙管理委員会
注意!会員のページにログインするには、ID/パスワードが必要です。
ログイン方法の詳しい説明はこちら
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2008年度日本地質学会各賞候補者募集 来週締め切り
──────────────────────────────────
応募の締切:12月25日(火)必着
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして,研究の援助・奨励および研究業
績の表彰を行っています(会則第3条).具体的には,運営細則第11条および各
賞選考に関する規約(本号別途掲載)に,表彰の種別や選考の手続きを定めていま
す.これらにしたがい,下記の賞の自薦,他薦による候補者を募集いたします.ご
応募いただいた候補者を,各賞選考委員会(委員は評議員の互選と職責により選
出)が選考し,4月の評議員会で受賞者を決定します.
日本地質学会功労賞・日本地質学会表彰以外は,会員(正会員・名誉会員)で
あればどなたでも推薦できます.
詳細は募集ページをご覧いただくか,または学会事務局までお問い合わせください.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】シンポジウムダイジェスト「 海底地すべり」
──────────────────────────────────
地質学会で今ホットな研究は何か?! 学術大会で開催されたシンポジウムおよ
びトピックセッションの目的、内容、成果などをわかりやすく紹介します。
-----------------------------------------------------
■札幌大会シンポジウム「 海底地すべり」■
地すべりは,大雨のとき裏山が崩れたり,大規模に田畑や山が崩れたり,とニュー
スで聞きますよね(図1と2).海底にも,そんな地すべりがあります.ただ,海
底なので,大雨や田畑はないですが.では,海底の地すべりはどうやって起きる
のでしょう.
・・・・続きを読む.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】専門部会再登録のお願い
──────────────────────────────────
これまでは専門部会名簿も整備されていませんでしたが,会員管理システムに部
会情報を入力することができるようになりました.これまで部会に参加されてい
た方も,改めて登録をしていただきますようお願いいたします.
専門部会に所属するための条件は,特にありません.会員であれば専門によって
希望する部会に,自由な意思で参加することができます.複数の部会(とりあえ
ずは3つまで)に参加することも可能です.
登録書式・各部会紹介など詳しくは、、、
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】2008年度会費の払込・院生割引申請受付中!!
──────────────────────────────────
<2008年度会費の払込>
会則により,次年度分(2008年4月〜2009年3月)の会費を前納下さいますよう
お願いいたします.
1.自動引き落としを登録されている方の引き落とし日は12月25日(月)です.
2.お振り込みの方には,12月中旬頃までに請求書兼郵便振替用紙をお送りいた
しました.
<院生割引申請受付中!!>
定収のない院生(研究生)については,本人の申請により院生割引会費が適用さ
れます.申請の最終締切は、2月29日(金)です.
*注意*毎年更新となりますので,今年度の割引を受けている方で,次年度も該
当する方は改めて申請して下さい(来年3月まで院生(研究生)の方も申請すれ
ば適用).
詳しくは,http://www.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】シンポジウム「新潟の自然と科学教育の素材」
──────────────────────────────────
日時:2007年12月25日(火)10:00〜16:00
会場:新潟大学自然科学研究棟2階大会議室
主 催:新潟大学教育人間科学部
事務局:新潟大学教育人間科学部自然情報講座(准教授)藤林 紀枝
fujib@ed.niigata-u.ac.jp, tel/fax 025-262-7156
プログラム
1. あいさつ 10:00 - 10:05
森田 龍義(新潟大学教育人間科学部 学部長)
2. 糸魚川のジオパーク構想 10:05 - 10:45
竹之内 耕(糸魚川市フォッサマグナミュージアム)
3. 日本海東縁の地質構造と地震 10:45 - 11:10
小林 健太(新潟大学理学部)
4. 2004年中越地震の市街地における建物被害と地盤の関係 11:10 - 11:35
坂東 和郎(株式会社興和)
5. 中越沖地震における地盤液状化を「エッキー」で再現する 11:35 - 12:00
和泉 薫(新潟大学災害復興科学センター)
6. 2004年中越地震を地域素材として活用した「地震の伝わり方」の授業 13:00
- 13:25
結城 義則(新潟大学教育人間科学部附属長岡中学校)
7. 金銀鉱床のタイプと生成場 13:25 - 13:50
久保田 喜裕(新潟大学理学部)
8. 佐渡金銀山とその文化的景観 13:50 - 14:20
若林篤男(佐渡市教育委員会世界遺産・文化振興課)
9. 新潟県の砂丘湖環境 14:35 - 15:00
福原 晴夫(新潟大学教育人間科学部)
10. 地域の素材を活かした野外授業の一例 −主として、河川環境と水
生昆虫− 15:00 - 15:25
富樫 繁春(元村上養護学校)
11. 総合討論 15:25 - 16:00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.0019 2008/1/8 geo-Flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.019 2008/01/08 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】会長より新年のご挨拶
【2】理事選挙立候補受付中(1月11日締切)
【3】2009年地質学雑誌表紙デザイン一新計画 デザイン募集(予告)
【4】中国の大別蘇魯(ターピエ・スールー)衝突帯の東方延長に新説!
【5】「ちきゅう」の科学者に聞いてみよう! *質問募集中*
【6】NUMO技術開発成果報告会開催
【7】消防防災科学技術研究推進制度平成20年度研究開発課題の募集
【8】静岡大学理学部地球科学科教員(助教)公募
【9】日本ジオパーク連携協議会 発足
【10】AOGS 2008 in 釜山 のお知らせ
【11】北海道大学2008テニュア・トラック・ポストの特任助教の公募
【12】産総研ポスドク公募
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】会長より新年のご挨拶 <一歩、そしてまた一歩前へ>
──────────────────────────────────
一歩、そしてまた一歩前へ ー2008年の年頭にあたってー
日本地質学会会長・木村 学 (東京大学・大学院理学系研究科)
皆様、あけましておめでとうございます。現在、南海トラフ掘削のため、「ちきゅう」上におります。洋上から一言、新年のご挨拶を申し上げます。
めまぐるしく発展する科学とそれを取り巻く社会や経済的変化はこの新しい年にはどのようになるのでしょうか。 日本地質学会はどのような見通しと方向をめざして活動をすすめればよいのでしょうか。
【加速する地質学への期待】
いま地質学の重要性が再び広く認識されようとしております。たとえば、いま私の乗船している「ちきゅう」での掘削の科学目的は、地震や津波発生帯としての 生きているプレート沈み込み境界を直接観察・観測し、これまでの「こと」の理解としての地震を「もの」としての理解と結合し、「知の飛躍」を計ろうという ものです。そこには20世紀的意味での地球物理学や地質学の垣根はもはやありません。ただ同じ知りたい対象に対する得手不得手があるだけです。それらの共 同が共通の目的達成のために不可欠です。
同じことは、今年北海道洞爺湖で開催予定サミットの大テーマでもある、地球温暖化・地球環境問題についても言えます。産業革命以降の産業発展、そして20 世紀以降の爆発的人口増加よるエネルギー消費が、地球温暖化や環境問題を引き起こし、資源エネルギー枯渇、水食料枯渇に直面し、このままでは人類が「地球 を食い尽くす」ことは明らかです。しかし、それは不可能なことであり、結末は人類の大量死へとつながるとの危惧は21世紀、現実を持って迫っています。 この温暖化・環境問題ももはや個別の科学の域をはるかに超えていることも明らかです。10年や100年スケールはもちろんのこと、10万年や100万年、 億年スケールに至るまでの変動の歴史や、固体地球を含めた全地球における物質エネルギー循環の理解なくしての環境問題への対処両方だけでは、人類の生存を 賭けた未来への科学戦略構築としては極めて脆弱です。
このような時であるからこそ、私たちは地質学会設立の理念を思い起こさねばなりません。すなわち、地質学と地球に関わる科学の振興をはかり、それを広く社 会へと還元する活動を大胆に展開することであります。 地球を最も良く知ると自負する私たちは、この地球の未来を指し示すことの出来る、そしてしなければ ならない重要な立場にあります。それが私たちの科学のもつ、根本的な社会貢献であると思います。そのことを強く意識して一層旺盛な学術活動を展開すること の必要な時代となっております。
【情報革命を突き抜ける学会の構築を】
この科学とそれをもってして行う社会貢献に関して、いま進行している人類史上未曾有の情報革命に対する理解とそれを担うとの強い意思の確立は極めて重要で す。20世紀末に始まったネット社会の構築、ウェブ時代の到来は、国境の壁、既存科学の分野の壁、大組織の壁、などを次々と突き崩しつつあります。「パブ リックでオープンでフリー」の理念で一気に広がる情報革命は、あらゆる場面で「群衆の叡智」を最大限引き出し、はっきりとした意思を持った個人や集団なら ば誰でも自由に新しい「知のフロント」へ突入できることを示しています。そして、10年程度以内には、この情報革命の担い手達が科学を、社会を、そして世 界をリードすることとなることも明らかです。
さて、このような情勢にあって、日本地質学会が時代を突抜け、広い裾野をもった共同体として発展するためには、今何をなすべきなのでしょうか? その基軸 は、梅田望夫氏の言葉を借りれば、広く社会へ向けて「パブリックでオープンでフリー」な地球科学・地質学の情報を多角的に発信する「知の高速道路」を構築 することです。それは、国際社会をも広く見通したものでなければなりません。押し寄せる地球科学・地質学への期待は日本国内にとどまるものではありませ ん。勃興するアジア諸国などに対し適切で緻密な情報の発信は、日本の地質学会が果たすべき国際的使命でもあります。この間に押し進めてきた学会サイトの刷 新、電子ニュースの配信の充実にとどまらず、その完全国際化、基軸となるジャーナルの充実、会員の自発的意思にもとづく大規模な情報発信交流システムの構 築支援などは時代をリードする上で欠かす事ができません。情報システムによる会員サービスの充実も当然のことです。春の連合大会、秋の関連学会合同と協力した学術大会の開催を活動のリズムとして定着させ、新しい時代を突き抜けるための前進を計らなければなりません。
【2008年、一歩、そしてまた一歩前へ】
2008 年、具体的にはどのような活動を展開して、この着実な前進を計るのでしょうか?今年は国際惑星地球年の中心的年であります。また、新たに「地質の日」が設 定された最初の年です。秋には新生鉱物科学会との初の同時開催の大会が秋田で開かれます。その大会では協定を結んだ日韓による国際シンポジウムも企画され ています。若者を対象とした、就職支援、同窓会活動の一層の充実を図られる予定です。
また、これらの活動を推進するための学会組織の強化と社会的認知と組織の透明性確保のために、長年の懸案であった法人化をいよいよ実現させる年となります。
これらの活動を通して一歩ずつ、しかし着実に前進する、若者がこの学会に未来をみつけて多いに集う、そして時代を突き抜ける。そんな夢を、一歩、そしてまた一歩前へとすすんで、共に実現しようではありませんか。
キーワード:加速する地質学への期待、情報革命を突き抜ける学会の構築
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】理事選挙立候補受付中
──────────────────────────────────
理事選挙の選挙権、被選挙権及び選出定員・任期は以下の通りです。
立候補の受付はe-mailまたは郵送による文書でお願いします。
1)2008年度ー2009年度、新理事選挙:定員7名、任期2年
選挙権:2007-2008及び2008-2009年度任期全代議員
被選挙権:2008-2009年度(新選出)代議員
締切は1月11日(金)18時です。
2)2008年度、理事欠員補充選挙:定員2名、任期1年
選挙権:2006-2007及び2007-2008年度任期全代議員
被選挙権:2007-2008年度任期代議員
締切は1月18日(金)18時です。
選挙管理委員会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2009年地質学雑誌表紙デザイン一新計画 デザイン募集(予告)
──────────────────────────────────
現在の地質学雑誌の体裁は、1994年にB5版からA4版に変更になり、その後
表紙のデザインは、一部特集号で内容に見合った写真や図を用いた他は、同じ
デザインが用いられています。この間に何度か表紙デザインの改訂の声があが
りましたが、実現していませんでした。電子ジャーナルとしての性格が強く
なってきたこの機会に、2009年1月号からデザインを一新することで、評議会、
理事会で合意されました。
表紙デザイン案(PDFファイル)を大募集いたします。伝統ある「地質学雑誌」
の文字デザインはなるべく活かしていただいて、ロゴも入れていただきます。
表紙デザインの細かな規定は近日中に学会ホームページに掲載いたしますので、
是非ご覧になって、ご応募ください。締切は3月7日(予定)です。
地質学雑誌編集委員長 狩野 謙一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】中国の大別蘇魯(ターピエ・スールー)衝突帯の東方延長に新説(論文紹介)
──────────────────────────────────
石渡会員(金沢大学理学部)より、一押し論文をご紹介してもらいました。
それは、超大陸ロディニア及びゴンドワナの形成・分裂の歴史を踏まえて
東アジアの地質構造発達史を総括的に論じた論文だそうで、日本の中ー古生代
研究にも大きなインパクトがありそうです。
論文紹介 中国の大別蘇魯(ターピエ・スールー)衝突帯の東方延長に新説
Oh, Chang Whan and Kusky, Timothy (2007)
The late Permian to Triassic Hongseong-Odesan collision belt in South Korea, and its tectonic correlation with China and Japan
International Geology Review, 49(7), 636-657. (ISSN: 0020-6814/07/942/636-22)
呉 昌桓,ティモシー・クスキー (2007)
南朝鮮のペルム紀後期〜三畳紀の洪城−五台山衝突帯,そして中国・日本との構造対比
1980 年代末から1990年代にかけて,日本,米国,トルコなどと中国との共同研究により中国東部の大別(Dabie)山地(湖北省・安徽省)及び蘇魯 (SuLu)地域(江蘇省・山東省)から相次いでコース石やダイヤモンドを含むエクロジャイトが発見され,北中国(中朝)地塊と南中国(揚子)地塊の間の 衝突帯に超高圧変成帯の存在が明らかになった.その後の同位体年代測定によりこの超高圧変成作用の年代は約250 Maであると決定された.つまり,古生代末〜三畳紀にかけて,この地域で大規模な大陸衝突型造山運動があったことが確実になった.大別蘇魯超高圧変成帯の 東方延長がどこに続くかは朝鮮半島や日本の地質研究者にとっても非常に身近な興味ある問題である.これまで様々な提案がなされてきたが,それらはどれも朝 鮮半島におけるデータが十分でなかったために決め手を欠いていた.このたび,韓国の呉 昌桓氏が米国のTimothy Kusky氏と共著で韓国内のデータをまとめ,中国や日本との地質のつながりを論じた総説を発表したので,ここに紹介する.
まず,この総説で紹介されている従来の提案を概説する.Yin and Nie (1993)は蘇魯超高圧変成帯が朝鮮半島中部の臨津江(Imjingang)帯につながると考え,左横ずれの●廬(TanLu)断層と右横ずれの湖南 (Honam)断層(沃川Okcheon帯と嶺南Yongnam地塊を境する)の間の部分が北へ動いて沈み込んだとする「食い込み (indentation)モデル」を提唱した.Ree et al. (1996)は臨津江帯の変成作用の年代が249 Maであることを報告し,蘇魯帯と臨津江帯を結ぶ説を支持したが,この変成作用は中圧型であって超高圧の証拠はない.Ernst and Liou (1995)はこの衝突帯が更に日本の三郡変成帯に延びるとし,Zhang (1997)はこの衝突帯が北東に延びて中国東北部の延吉(Yanji)帯に達すると提案し,延吉ではペルム紀前期に衝突が始まり,衝突は次第に西方に 移って三畳紀後期まで続いたと考えた.しかし,Ishiwatari and Tsujimori (2003)は大別蘇魯衝突帯が朝鮮を迂回し,八重山諸島石垣島の高圧変成帯を経て直接西南日本内帯の高圧変成帯につながると提案した.
Oh and Kusky論文の要旨は次の通りである.著者らは南朝鮮京畿(Gyeonggi)地塊の洪城(Hongseong)地域(韓国中西部)の三畳紀中期(約 230 Ma)エクロジャイトが中国の大別蘇魯衝突帯に対比できることを新たに提案する.また,京畿地塊東部の五台山(Odesan)地域(韓国北東部)に貫入す るペルム紀(約257 Ma)のマンゲライトは大陸衝突帯に特徴的な化学組成を示し,このことは洪城衝突帯が五台山地域まで延びること暗示する.一方,西南日本の肥後変成帯では サフィリンを含むグラニュライトとそれに関連する高度変成岩が約245 Maの超高温変成作用の存在を示している.この変成作用は五台山地域の地域のスピネルグラニュライトについて見積もられた245±10 Maの超高温変成作用とよく対応しており,大別蘇魯変成帯が洪城五台山帯を経て肥後帯に続くこと,そして西南日本の古生代沈み込み帯が大別蘇魯衝突帯の東 の延長であることを示している.日本の古生代沈み込み帯は更に北中国地塊東縁に沿う石炭紀〜ペルム紀の沈み込み帯である延吉(Yanji)帯に続くのだろ う.これらのデータは北中国地塊周縁部の顕生代の沈み込み及び北中国地塊と南中国地塊の間の衝突が大別−蘇魯−洪城−五台山−肥後−延吉帯を形成したこと を示す.温度圧力条件を推定すると,この衝突帯では東から西へ地温勾配が低下し,削剥速度が大きかったことがわかる.この結果として,朝鮮の五台山地域と 日本の肥後地域では超高温変成帯が,朝鮮の洪城地域では高圧変成帯が,そして大別−蘇魯帯では超高圧変成帯が形成され,地域ごとに異なる地温勾配が記録されている.
この論文の結論は次の3つである.(1)中国の大別−蘇魯衝突帯は朝鮮の洪城−五台山帯に続く.(2)北中国地塊と南中国地塊の衝突はペルム紀前期 (297-268 Ma)に朝鮮で始まり,258-225 Maの間に西へ伝播して,左ずれの●廬断層を形成した.(3)北中国地塊周辺の顕生代の沈み込み及び北中国・南中国地塊の衝突が大別−蘇魯−洪城−五台山 −肥後−飛騨−延吉帯を形成した.
私としては,(1)洪城地域のエクロジャイト(飛鳳Bibong)やざくろ石グラニュライト(白銅Baekdong)が超高圧変成帯の延長を代表し得るか (コース石はまだ発見されておらず,飛鳳, 白銅,維鳩Yugu等の超苦鉄質岩体からもまだざくろ石かんらん岩は発見されていない),(2)超高温変成帯が超高圧変成帯の延長と言えるか(なぜ同じ衝 突帯の延長上で一部が超高圧になり一部が超高温になるのか.古典的な「対をなす変成帯」のモデルと矛盾する),(3)朝鮮半島南部が南中国地塊に属するこ との論証は十分か(特に古生界の層序の問題),などの疑問は残るが,この総説は超大陸ロディニア及びゴンドワナの形成・分裂の歴史を踏まえて東アジアの地 質構造発達史を総括的に論じた気宇壮大な論文であり,日本の地質研究者に一読をお勧めする.
なお,上の3つの疑問を直接著者に伝えたところ,(1)と(2)については,造山帯延長方向での衝突時期の差による沈み込むスラブの破断の有無によって説 明可能であり,それについての論文を執筆中とのことだった.また,(3)については,Wang, Z.-H. et al. (2007)を示して,南朝鮮のオルドビス紀のコノドントは北中国タイプだが,南中国の一部(江西省や江蘇省北部)にも北中国タイプのコノドントが出るこ とがある(p. 838)ので,化石からも南朝鮮は南中国地塊の一部と考えてよいという返答を得た.
韓国の地名の漢字表記の一部を調べていただいた町 澄秋氏に感謝する.
Wang, Z.-H., Qi, Y.-P., Bergstrom, S.M. 2007. Ordovician conodonts of the Tarim Region, Xinjiang, China: Occurrence and use as palaeoenvironment indicators. JAES, 29, 832-843.
(金沢大学理学部 石渡 明)
【追記】
大 別蘇魯超高圧変成帯の東方延長について2007年11月に中国のグループが次の論文を公表した.Zhai, M.G., Guo, J.H., Zhong L., Chen, D.Z., Peng, P., Li, T.S., Hou, Q.L. & Fan,Q.C. (2007) Linking the Sulu UHP belt to the Korean Peninsula: Evidence from eclogite, Precambrian basement, and Paleozoic sedimentary basins. Gondwana Research, 12, 388-403. この論文は基本的にIshiwatari & Tsujimori (2003)らの説を支持し,蘇魯帯は朝鮮半島を横断せず,朝鮮半島の西岸に沿って黄海を南下するとしている.ただし,洪城地域のエクロジャイトを含む片 麻岩だけは揚子地塊の黄海突出域の先端の蘇魯帯の一部が露出したものと考えている.なお,洪城地域のエクロジャイトについて,Oh & Kusky論文では2003年のノルウェーでのエクロジャイト会議におけるOh et al.の発表を最初の報告としているが,Zhai et al.論文ではこれを引用せず,2004年のGuo et al.のGondwana to Asia International Workshop(韓国開催)の発表が最初としている.また論文発表も,Oh & Kusky論文ではOh et al. (2005)のJournal of Geologyの論文を引用し,Zhai et al.論文ではZhai & Guo (2005) のMitteilungen der Osterreichischen Mineralogischen Gesellschaftの論文を引用している.国際的な共同研究は(国内でも?),現地調査の段階では仲良くやっていても,発表の段階でトラブルになる ことがよくあるので,その例かもしれない.
(金沢大学理学部 石渡 明)
注:「●廬(TanLu)断層」の「●:タン」は、「炎」に「おおざとへん」です.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】「ちきゅう」の科学者に聞いてみよう! *質問募集中*
──────────────────────────────────
IODP(統合国際深海掘削計画)は、現在「ちきゅう」に乗船している科学者
にいろいろな質問をする普及・広報・教育プログラムを展開しています。
小・中・高校生を対象にしたもので、世界中の子供たちからの質問を受け付け
ています。ぜひご紹介ください。
http://www.jamstec.go.jp/chikyu/jp/CHIKYU/ask.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】NUMO技術開発成果報告会開催
──────────────────────────────────
原子力発電環境整備機構では,高レベル放射性廃棄物を地層処分する実施主体と
して,事業を安全・確実に実施するための技術開発に取り組んでおり,2004年6月
には,地層処分に関する技術的基礎にかかる技術報告会を開催しております.
日 時:2008年1月17日(木)13:10〜17:20(受付12:30〜)
場 所:東京国際交流館 プラザ平成 国際交流会議場(お台場)
詳しくは,http://www.numo.or.jp/what/news2007/news_071219.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】消防防災科学技術研究推進制度平成20年度研究開発課題の募集
──────────────────────────────────
「消防防災科学技術研究推進制度」は,消防防災科学技術の振興を図り,安心・
安全に暮らせる社会の実現に資する研究を,提案公募の形式により幅広く募り,
優秀な提案に対して研究委託し,より革新的かつ実用的な技術へ育成するための
制度です.
募集締切 平成20年1月31日(木)
公募要領及び申請書類等詳しくは,
消防庁のホームページへ http://www.fdma.go.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】静岡大学理学部地球科学科教員(助教)公募
──────────────────────────────────
募集人員 助教1名
専門分野 固体地球科学
授業担当科目 学部及び大学院の地球科学の実験,実習,演習など.
資 格 着任時に博士の学位を有すること
着 任 日 平成20 年4月1日
応募締切 平成20 年1月25 日(金)必着
■ 問い合わせ先 狩野謙一
Tel: 054-238-4786 Fax: 054-238-0491
e-mail: sekkano@ipc.shizuoka.ac.jp
詳細は、学会HP・公募欄をご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】日本ジオパーク連携協議会 発足
──────────────────────────────────
2007年12月26日に、ジオパーク設立を希望する自治体や組織による
「日本ジオパーク連携協議会」が発足しました。本会の総会では日本から
世界ジオパークネットワークへの申請を行うため、「日本ジオパーク委員会」
を早急に設立するように要請文が決定され、地質学会に渡されました。
http://www.geosociety.jp/geopark/content0014.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】AOGS 2008 in 釜山 のお知らせ
──────────────────────────────────
AOGS(Asia Oceania Geosciences Society) は、アジアの地球科学関連
学会の結集を目指して活動しています。今年の年会は6月に韓国の釜山(プサン)
で開催されます。要旨投稿締切は1月24日(木)です。
http://www.asiaoceania.org/aogs2008/index.asp━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【11】北海道大学2008テニュア・トラック・ポストの特任助教の公募──────────────────────────────────公募締切: 2008年2月4日(月) 必着北海道大学2008テニュア・トラック・ポストについては、「若手リーダー育成ステーション」(L−Station)のホームページ(http://www.cris.hokudai.ac.jp/l-station/)に説明があります。この制度により、当分野では「層位・古生物学」または「鉱物学」の研究領域を専門とする特任助教を募集することになりました。当該分野の教育研究をさらに発展させるとともに、当テニュア・トラック・ポストの目的を理解し,その達成に向かって意欲的に取り組む優秀な人材を募集いたします。なお、当ポストへの応募者の選考は、第一段審査を当「ホスト部局人材選考委員会」で行い、総合力審査を全学の「リーダー推進委員会」で行います。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【12】産総研ポスドク公募──────────────────────────────────公募締切: 2008年2月16日(金) 必着任期は最大2年募集区分 特別研究員(1号) 研究内容または業務内容 :地震発生機構解明のため,当所所有の高温高圧実験装置を用いて、弾性波速度・電気伝導度などの断層深部物性の測定手法の開発を行い,また活断層深部の応力状態や物質推定手法の開発を行う. 応募資格 :岩石物性または地震学に関して知識と能力を有し、物性測定実験に対する強い意欲を有すること。採用時において博士号取得後7年以内であること 詳細は(http://unit.aist.go.jp/igg/ci/recruit/index.html)をご覧ください。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
日本全国天然記念物めぐり(和歌山県編)
◇各地の天然記念物◇
TOP 秋田県編 滋賀県編 京都府編 和歌山県編 福岡県編
日本全国天然記念物めぐり(和歌山県編)
和歌山県にある以下の国指定天然記念物のう ち、(1)〜(6)と(8)について、石井和彦(大阪府立大学)が報告します。多くは(6、8以外) 初めていく場所ではないので(というより、単に報告者の性格の違いのた め)、前2回の記事とはかなり趣が異なると思います。
(1)橋杭岩(1924年指定)東牟婁郡串本町
(2)高池の虫喰岩(1935年指定)東牟婁郡古座川町
(3)古座川の一枚岩(1941年指定)東牟婁郡古座川町
(4)白浜の化石漣痕(1931年指定)西牟婁郡白浜町
(5)白浜の泥岩岩脈(1931年指定)西牟婁郡白浜町
(6)鳥巣半島の泥岩岩脈(1936年指定)田辺市
(7)神島(1935年指定)田辺市
(8)栗栖川亀甲石包含層(1937年指定)田辺市
(9)門前の大岩(1935年指定)日高郡由良町
(10)瀞八丁(1928年指定)和歌山県新宮市・三重県熊野市・奈良県吉野郡十津川村
(1)橋杭岩、(2)高池の虫喰岩、(3)古座川の一枚岩
これらはすべて、中期中新世に貫入した酸性火成岩脈です。(1)はNNW方向に貫入した石英斑岩で、(2)と(3)は東西方向に貫入した凝灰岩と花崗斑岩からなる古座川弧状岩脈の一部で、指定された部分はどちらも凝灰岩岩脈のようです。
20万分の1日本シームレス地質図データベース 2005年2月1日版、産業技術総合研究所地質調査総合センター (編) を利用(承認番号 第63500-A-20080115-002号)。
(1)橋杭岩
橋杭岩は、天然記念物だけでなく名勝にも指定されている有名な観光地で、ほとんどの地図に載っており、かつ幹線道路(国道42号)に面していることから、迷うことはありません。また、案内板による簡単な解説もあります。
手前は熊野層群の泥岩
写真をクリックすると拡大されます。(以下同様)
(2)高池の虫喰岩
虫 喰岩の載っている地図は少なく、道路沿いの案内表示も私が見つけたのは、町内の何ヶ所かにある観光案内板(写真)を除くと、古座川町役場から虫喰岩に向か う道路沿い(県道227田原古座線)のガードレール(写真)の一ヶ所だけでした。現地に天然記念物という表示はありますが、とくに説明はありません。
観光案内板の一例。
赤線枠は右図の範囲
(3)古座川の一枚岩
一 枚岩は、たいていの地図に載っており、道路案内表示も分かりやすく容易に辿り着けます。国道42号の高富から国道371号を北上(写真)、あるいは上記の 古座川町役場から古座川沿いに行くこともできます。道路沿いに一枚岩観光物産センターがあり、河原ではキャンプなどもできるようです。しかし、天然記念物 であることを示す表示は見つけられませんでした。
観 光パンフレットをみると、串本町は、「本州最南端」潮岬や「ラムサール条約」にも登録されたサンゴ群集をはじめとする沿岸生態系、古座川町は、「清流」古 座川のカヌーや奇岩奇石(一枚岩・虫喰岩以外にもたくさんあります)にまつわる伝説などをウリにしているようです。橋杭岩・一枚岩・虫喰岩を個別に扱うだ けでは物語性がなく、民話・伝説にかないません。地質に関する簡単な解説、とくに紀伊半島全域の火成岩類の分布を含めた全体の文脈(昔、このあたりに大き なカルデラがあって大規模な噴火をしたことなど)を含む解説が観光パンフレットや現地の案内板などにあると、少しは身近に感じてもらえるのではないでしょ うか。
(4)白浜の化石漣痕、(5)白浜の泥岩岩脈、(6)鳥巣半島の泥岩岩脈
観光案内板や観光地図には、これらに関する記載はありません。また、道路案内表示もないので、前もって位置を調べて行くか、偶然立ち寄ることになるかと思います。
(4)白浜の化石漣痕
白浜温泉の中心部に近く、マリンスポーツなど観光客の多い場所です。ただ、下記のように案内板と露頭の位置が離れているので一般の人には見つけられないかもしれません。
これらの案内板は江津良浜の西端にあり、露頭(右図)は、浜の東端(約200m東)にある
天然記念物を示す石碑と露頭。背景は江津良浜。
左図の右下の部分の拡大
(5)白浜の泥岩岩脈
白浜温泉の中心部、白砂で有名な白良浜の北、権現崎北岸にあり、白良浜から続く遊歩道もあるので、立ち寄る人は多いと思います。
案内板の露頭は干潮時にしか観察できない。
遊歩道沿いの露頭。
(6)鳥巣半島の泥岩岩脈
田辺市と白浜町の境界に近い位置ですが、半島の先にあるので、立ち寄る人は少ないのではないかと思います。岩脈は、この付近一帯にあるようですが、観察には潮が大きく引く春から夏が良いようです。
ここから約100m右図
天然記念物を示す石碑。背景は国指定天然記念物の神島。
上から見下ろしている。
南 紀白浜は、温泉を中心とする近畿地方有数の観光地で、温泉以外にも多くの観光スポットがあり、天然記念物を地図やパンフレットに載せる余裕はないようで す。白浜周辺では、上記以外にも多くの場所で泥岩岩脈やさまざまな堆積構造を観察することができます。とくに円月島の対岸と千畳敷は多くの観光客が立ち寄 る場所で、いろいろな堆積構造が観察できるので、お薦めです。何の説明もありませんが、地層の中のいろいろな幾何学模様が楽しめます。
(8)栗栖川亀甲石包含層
国 道311号を白浜方面から10数km行ったところの山腹にあり、インターネット(マピオン)から印刷した地図をもって探しましたが、何の手がかりもありま せん。幸運にも、戦後すぐの子供の頃、調査に来た京大教授といっしょに現地に行った経験があるという方に現地まで案内してもらいました。以前は案内表示が あったそうですが、今は何もないそうです。また、亀甲石が見つかることは、今ではほとんどないそうです。なお、インターネットで検索してみると、亀甲石は もともと海藻の化石と考えられてコダイアミモと名付けられたが、現在では原生動物の一種と考えられているようです。
案内してもらった場所の露頭(成層した砂岩)
このあたり(旧中辺路町、2005年田辺市に合併)は、観光と言えば、世界遺産に登録された「熊野古道」一色のようです。
後日、インターネットで検索していたら、和歌山県立自然博物館のホームページに「和歌山の珍石」というコーナーがあり、そこで亀甲石と梅干し石(天然記念物「門前の大岩」に含まれるウニのトゲの化石)を紹介していました。
geo-Flash No.294 第6回惑星地球フォトコンテスト審査結果
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.294 2015/4/7 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】第6回惑星地球フォトコンテスト審査結果
【2】次期学習指導要領改訂に関する要望書を文科大臣に提出
【3】都道府県指定の地質・鉱物天然記念物一覧
【4】地質の日イベント情報
【5】地学オリンピックキャラクターデザインコンテスト入賞作品発表
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞情報等
【9】地質マンガ「彼女のために地質学?」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】第6回惑星地球フォトコンテスト審査結果
─────────────────────────────────
応募作品全417作品のうち,上位入選作品等が決定いたしました.入選作品の画像
や詳細情報は近日公開の予定です.
なお,入選作品については,5月23日に東京都北区「北とぴあ」にて表彰式を開催
し,各地で入選作品の展示を予定しています.今回も多数のご応募を頂き,あり
がとうございました.
第6回惑星地球フォトコンテスト審査委員会
【入選作品の表彰式】2015年5月23日(土)11時より
会場:北とぴあ 第1研修室(東京都北区王子)
詳しくは,http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】次期学習指導要領改訂に関する要望書を文科大臣に提出
──────────────────────────────────
次期学習指導要領改訂を前に,将来の日本を背負って立つ高校生の立場
にたった要望書を文部科学大臣に提出いたしましたので,お知らせいたし
ます.
要望書の全文(PDF)はこちらから
http://www.geosociety.jp/engineer/content0040.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】都道府県指定の地質・鉱物天然記念物一覧
──────────────────────────────────
現在,選定作業が進められている「県の石」に関連して,辻森会員が都道府県
指定の地質・鉱物天然記念物一覧を作成されました.地質学会ホームページの
e-フェンスター「天然記念物(地質鉱物編)めぐり」に掲載いたしましたので,
ぜひご覧ください.
一覧はこちらから
http://www.geosociety.jp/faq/content0558.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地質の日イベント情報
──────────────────────────────────
[本部]
■街中ジオ散歩in Tokyo「等々力渓谷の地質と人の関わり」徒歩見学会
(主催:一般社団法人日本地質学会,一般社団法人日本応用地質学会)
5月10日(日)10:00〜15:30 少雨決行(予定)
場所:東京都世田谷区等々力周辺
【定員に達しましたので,申込受付を終了しました】
■講演会「日本の地質学:最近の発見と応用2015」
Recent progress in geological science in Japan, 2015
5月23日(土)12:40〜14:40
会場:北とぴあ第1研修室 (東京都北区王子)
会費:会員無料,非会員500円[CPDH:2単位]
■第6回惑星地球フォトコンテストほか入選作品展示会
6月13日(土)15:00頃〜6月27日(土)午前中
場所:銀座プロムナードギャラリー(中央区銀座4丁目地内 東銀座地下歩道壁面)
[近畿支部]
■第32回地球科学講演会「阪神淡路大震災以降の近畿の活断層研究」
(共催:日本地質学会近畿支部・大阪市立自然史博物館・地学団体研究会大阪支
部)
5月10日(日)13:30〜15:30 (受付:12:30〜)
場所:大阪市立自然史博物館 講堂
講師:岡田篤正氏(京都大学名誉教授・立命館大学客員研究員)
申込不要/参加費無料(博物館入館料必要)
地質の日イベントの各詳細はこちらから.
http://www.geosociety.jp/name/content0128.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地学オリンピックキャラクターデザインコンテスト入賞作品発表
──────────────────────────────────
地学オリンピック日本委員会では,日本地質学会との共催で中学生・高校
生を対象としたキャラクターデザインコンテストを実施しました.応募総
数43作品のうち,入賞作品1点が決定いたしました.またこのほか,一次
審査を通過した12作品を佳作として表彰しました.
<入賞作品の応募者>
萱野真子さん 三重県立桑名高校 2年(学年は応募受付時点)
キャラクター画像など詳しくは.日本委員会HPをご覧下さい.
http://jeso.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
─────────────────────────────────
[関東支部 ]
■2015年度総会・地質技術伝承講演会
4月18日(土)14:00〜16:45(13:30受付)
場所:北とぴあ 7階 第1研修室(東京都北区王子1-11-1)
14:00〜15:40地質技術伝承講演会[参加費無料,CPD単位(2.0)]
申込・問い合わせ:加藤 潔 kiyoshi.katoh@gmail.com
15:50〜16:45関東支部総会
*支部会員の方で総会へ欠席の方は,委任状をお送り下さい.
関東支部 kanto@geosociety.jp[4月17日(金)18時締切]
各行事の詳細,委任状等はこちらから
http://kanto.geosociety.jp/
[中部支部]
■2015年支部年会
6月13日(土)
年会会場:黒部市吉田科学館(富山県黒部市吉田574-1)
地質巡検(6月14日):富山県北東部の中生界(定員15名程度予定)
参加申込:6月6日(土)までに
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■電中研 TOPICS Vol.19「微量PCB汚染大型変圧器の洗浄技術」
http://criepi.denken.or.jp/research/topics/index.html?m=150402
■シンポジウム:環境資源システムを支えるジオサイエンス
5月8日(金)9:30〜17:00
場所:早稲田大学理工キャンパス63号館2F(03会議室)
会費:無料(要登録)
https://sites.google.com/site/geosciencetokyo/home
■科学上のブレークスルーに関するグローバルシンポジウム
5月26日(火)9:30〜15:00
場所:ホテルオークラ東京 別館地下2階 アスコットホールII(東京都港区虎ノ門
2-10-4)
言語:英語(日英同時通訳有)
参加費無料/要申込/先着順
http://grc2015tokyo.jp
■三朝国際インターンプログラム2015
7月1日(水)〜8月7日(金)
場所:岡山大学地球物質科学研究センター
応募条件:学部3・4年生または修士課程相当大学院生
募集人数:各部門それぞれ5名程度
旅費・滞在費全額負担,詳しくは,
分析地球化学部門(4/29締切)
http://intern.misasa.okayama-u.ac.jp/pml2015/?lang=ja
実験地球物理学部門(4/26締切)
http://www.misasa.okayama-u.ac.jp/~misip/intern_j.php
■第52回アイソトープ・放射線研究発表会
日本地質学会ほか 共催
7月8日(水)〜10日(金)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1)
講演要旨原稿締切 :4月10日(金)
http://www.jrias.or.jp/
■第13回微量元素の生物地球化学に関する国際会議
13th International Conference on the Biogeochemistry of Trace
Elements, ICOBTE 2015 FUKUOKA
日本地質学会 後援
7月12日(日)〜16日(木)
場所:福岡国際会議場
http://www.icobte2015.org/index.html
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
7月26日(日)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1-1)
通常参加登録締切:6月30日(火)
http://inqua2015.jp/
■日本ジオパークネットワークガイドフォーラム
9月15日(火)〜16日(水)
会場:アミティ丹後(京都府京丹後市網野町網野367)
バーチャルジオツアー発表者応募締切:5月29日(金)
参加登録締切:7月31日(金)
http://jgn2015.com/
■第4回アジア太平洋ジオパークネットワーク山陰海岸シンポジウム
日本地質学会ほか 後援
9月15日(火)〜20日(日)
会場:豊岡市民会館(豊岡市立野町20-34)ほか
発表要旨締切:4月30日(木)
早期参加登録締切:4月30日(木)
通常参加登録締切:7月31日(金)
http://apgn2015-jpn.com/
■第10回アジア地域応用地質学シンポジウム
日本地質学会 後援
研究発表会:9月24日(木)〜25日(金)
シンポジウム:9月26日(土)〜27日(日)[その後巡検予定あり]
場所:京都大学宇治黄檗プラザ
http://2015ars.com/
■Arthur Holmes Meeting Tsunami Hazards and Risks: Using the Geological
Record
日本地質学会 共催
9月25日(金)
場所:The Geological Society (Burlington House)(英・ロンドン)
プレ巡検:9月22日(火)〜24日(木)
http://www.geolsoc.org.uk/ahm15
■第8回アジア海洋地質会議
10月5日(月)〜10日(土)(巡検を含む)
場所:韓国済州島,JEJU GRAND HOTEL
ホスト:KIGAM & KIOST
講演要旨締切:5月31日
http://icamg-8.kigam.re.kr/ICAMG/index.jsp
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0144.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■海洋研究開発機構高知コア研究所:同位体地球化学研究グループ(研究員もし
くは技術研究員)(5/15)
■横浜国立大学大学院:環境情報研究院(自然環境と情報部門)教員公募(5/15)
■名古屋大学大学院:環境学研究科地球環境科学専攻地球化学講座教員公募(6/1)
■平成27年度山陰海岸ジオパーク学術奨励研究事業の募集(5/15)
■平成27年度島原半島ジオパーク学術研究奨励事業の募集(6/26)
■平成27年度 地域防災対策支援研究プロジェクト:地域の防災力向上に資する人
材育成を含む研究成果を活用した防災・減災対策の検討(火山災害に対して)
(5/15)
■第6回(平成27年度)日本学術振興会育志賞受賞候補者の推薦(6/10〜6/12 学
会締切5/15)
■山田科学振興財団国際学術集会助成(4/1〜2016/2/26)
■コスモス国際賞受賞候補者推薦募集(4/30 学会締切4/20)
■2016〜2017年開催藤原セミナーの募集(7/31 学会締切6/30)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】地質マンガ 「彼女のために地質学?」
──────────────────────────────────
「彼女のために地質学?」
原案:本郷宙軌 マンガ:Key
http://www.geosociety.jp/faq/content0555.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
No.0020 2008/1/22 geo-Flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.020 2008/01/22 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】「地質学雑誌」表紙デザイン公募要領発表
【2】第115年学術大会(秋田大会)トピックセッション,シンポジウム募集
【3】日本全国天然記念物めぐり(和歌山編)
【4】宮沢賢治と鉱物に関するコラム
【5】国際地学オリンピック 国内選抜実施・募集のお知らせ
【6】第3回IGCP507 「東アジアの白亜紀古気候」シンポジウムとモンゴル巡検のお知らせ
【7】広島大学大学院理学研究科地球惑星システム学専攻準教授公募
【8】高知大学海洋コア総合研究センター研究員(非常勤職員)の募集
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「地質学雑誌」の表紙デザイン公募開始!
──────────────────────────────────
公募締切:2008年3月31日(月)
「地質学雑誌」は2009年1月号から表紙のデザインを一新する予定です。
つきましては会員、非会員のみなさまから、学会の新しいイメージを反映した
斬新なデザインを公募します。採用デザインには、賞金5万円を進呈します。
たくさんのご応募、お待ちしております。
応募の詳細は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0050.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第115年学術大会(秋田大会)トピックセッション,シンポジウム募集
──────────────────────────────────
募集締切:2008年3月17日(月)
2008年9月20日(土)〜22日(月)秋田大学で開催予定の第115年学術大会のトピッ
クセッションとシンポジウムの募集を行います.トピックセッションは,学会
内の領域をカバーし,これから新分野になりそうなトピック的な内容で,定番セッ
ションと同様な形式の発表となります.シンポジウムは,多数の学会員が関心を
持つ(あるいは持ちそうな)内容・学会外と関係した新分野の内容など,地質学
会として重要視すべき研究内容を取り上げます.
なお,秋田大会より招待講演の取り扱いが変わります.会員,非会員にかかわら
ず,トピックセッション,シンポジウムで招待講演を行うことができます.
詳しくは、、
http://www.geosociety.jp/outline/content0051.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本全国天然記念物めぐり(和歌山編)
──────────────────────────────────
和歌山県にある以下の国指定天然記念物のう ち、(1)〜(6)と(8)について、
石井和彦(大阪府立大学)が報告します。多くは(6、8以外)初めていく場所で
はないので(というより、単に報告者の性格の違いのため)、前2回の記事とは
かなり趣が異なると思います。
(1)橋杭岩(1924年指定)東牟婁郡串本町
(2)高池の虫喰岩(1935年指定)東牟婁郡古座川町
(3)古座川の一枚岩(1941年指定)東牟婁郡古座川町
(4)白浜の化石漣痕(1931年指定)西牟婁郡白浜町
(5)白浜の泥岩岩脈(1931年指定)西牟婁郡白浜町
(6)鳥巣半島の泥岩岩脈(1936年指定)田辺市
(7)神島(1935年指定)田辺市
(8)栗栖川亀甲石包含層(1937年指定)田辺市
(9)門前の大岩(1935年指定)日高郡由良町
(10)瀞八丁(1928年指定)和歌山県新宮市・三重県熊野市・奈良県吉野郡十津
川村
詳しくは、http://www.geosociety.jp/faq/content0051.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】コラム 「宮澤賢治に学ぶ地質」 加藤碵一・青木正博
──────────────────────────────────
宮澤賢治が、盛岡高等農林学校地質及び土壌教室在籍時に授業の一環として
級友らと盛岡付近の地質調査をした際の報告書(大正6年)に次の一文があ
ります。
『地質学は吾人の棲息する地球の沿革を追求し、現今に於ける地殻の構造を
解説し、又地殻に起る諸般の変動に就き其原因結果を闡明にす、即ち我家の
歴史を教へ其成立及進化を知らしむものなるを以て、苟も智能を具へたるも
のに興味を与ふること多大なるは辯を俟たずして明なりとす』
前半は、実に簡潔に地質学をあますところなく説明しています。さて後半部
ですが、いやしくも知能を備えた人は現今でも多々いるはずですが地質学に
関心を持っているのはどれくらいでしょうか。より一層の普及啓蒙活動が
要されます。というわけで賢治作品を鉱物と色の観点から紐解いて地質学
への関心をいささかでも高めようと「賢治と鉱物」の連載を開始しました。
ご一読ください。
(加藤碵一・青木正博)
http://www.kousakusha.co.jp/planetalogue/kenji/kenji.html━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【5】国際地学オリンピック 国内選抜実施・募集のお知らせ──────────────────────────────────主催:国際地学オリンピック日本委員会 共催:日本地球惑星科学連合●第二回国際地学オリンピック(国際大会)日程: 2008年8月31日ー9月7日までの8日間場所: フィリピン共和国派遣対象者: 2008年7月1日で19才未満の高校生 4名 (費用は主催者負担)(ただし,高等専門学校1-3年生,中等教育学校4-6年生などの高等学校に対応する学校の生徒も含む)第一回大会の様子はIESOのHP(http://2007ieso.or.kr/)で見ることができます.また,日本地球惑星科学連合地学オリンピック小委員会による視察の報告は連合のHP(http://www.jpgu.org/education/1stIESOreport.htm)に載っています.●第二回国際地学オリンピック(国内選抜)a) 一次選抜募集期間: 2月1日 — 29日対象者: 国際大会に参加可能な高校生・中学3年生および相当学年の生徒日時: 3月16日(日)2時間(10:00-12:00)場所: 原則として参加者の所属する高等学校等にて実施b)二次選抜日時: 5月31日(土)(9:00-15:00)場所: 東京大学(予定) (交通費等の補助はありません)内容: 実技試験(詳細な内容は検討中.例:地質断面図作成)面接時に英語で2-3分の簡単な自己および自校紹介.参加申込等詳細は、http://www.jpgu.org/ieso/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【6】第3回IGCP507 「東アジアの白亜紀古気候」シンポジウムとモンゴル巡検のお知らせ──────────────────────────────────IGCP507(Paleoclimates in Asia during the Cretaceous: their variatins, causes, and biotic and environmental responses)の次回のシンポジウムが下記のとおりモンゴル国で開催されます.巡検も企画され,有名な恐竜化石産地などの訪問が計画されています.現地研究者による解説をいただきながら通常立ち入ることのできない発掘現場の視察を行うことのできる絶好の機会です.モンゴル側では許可申請のため早めに参加者を確定したい模様です.参加希望者は至急下記までご連絡ください.主催:モンゴル科学アカデミー古生物学センター日程:2008年8月15日〜20日(シンポジウム:8月15,16日;巡検8月17〜20日)シンポジウム開催地:ウランバートル市費用:(予定,宿泊と食費を含む):シンポジウムのみ:USD$ 250 巡検:USD$ 300巡検予定:8/17-20の日程で、モンゴル南部の南ゴビ県の中央部に位置する,バヤンザク,ツグリキンシレ,アブドラントヌルの3地点(モンゴルの白亜系は全て陸成層からなり,大局的には前期白亜紀の湿潤気候下にあったことを特徴付ける湖成層(Barremian?-Aptian)や石炭層(Albian)と,後期白亜紀の乾燥気候を特徴付ける砂漠堆積物及び河川成層(主に赤色岩:Cenomanian?-middle Maastrichtian)により構成されています.本巡検では,このモンゴル地域の前期白亜紀から後期白亜紀にかけての顕著な気候変動の記録を見ることができると期待されます).巡検場所は砂漠地域ですが,8月下旬(17-20日)は幸い, 7月下旬から8月中旬の最も暑い時期から次第に冷涼になる時期ですので,日中は暑すぎず夜も寒すぎず,比較的過ごしやすい時期になります.ビザ:モンゴルはビザが必要になります.発効日より3ヶ月が有効です.入手所要日数は1週間程度,申請先は,駐日モンゴル国大使館の他,在大阪モンゴル国名誉領事館と在札幌モンゴル国名誉領事館があります.申し込み期限:3月1日(シンポジウムの講演タイトルも同時提出)連絡先:IGCP507国内コーディネータ: 長谷川卓(金沢大学自然研):jh7ujr@kenroku.kanazawa-u.ac.jp現地責任者:Dr.Khand Yo.(モンゴル科学アカデミー古生物学センター):Khandyo@yahoo.com━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【7】広島大学大学院理学研究科地球惑星システム学専攻準教授公募──────────────────────────────────本地球惑星システム学専攻では、この度下記の要領で教員を募集いたします。この募集では、新しい地球惑星科学の教育・研究を通じ、当専攻の発展を担う意欲と実績を備えた方の応募を期待致します。 職種および人員:准教授1名専門分野: 中期計画の目標 「地球惑星進化素過程の解明と地球環境の将来像の予測」に沿い、地球惑星システムにおける資源地球科学に関連した分野応募締切り: 平成20年2月29日(金)必着詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【8】高知大学海洋コア総合研究センター研究員(非常勤職員)の募集──────────────────────────────────職名:研究員募集人員:若干名勤務場所:高知大学海洋コア総合研究センター業務内容:(1)地球掘削科学に関連する諸分野(岩石学、堆積学、地球化学、古地磁気学、微古生物学、岩石物性など)に関する研究 (2)センターの研究・教育活動業務の補助 (3)機器保守の補助雇用期間:平成20年4月1日〜平成21年3月31日(1年)応募締め切り:平成20年1月28日(月)必着詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
ハロー「ちきゅう」から
私はこのたび、地球深部探査船「ちきゅ う」による南海トラフの研究航海・IODP Expedition 316 (NanTroSEIZE Stage1) に乗船研究者として参加する機会に恵まれました。日程も残り少なくなり、コアの記載や下船後の研究に関するミーティングなどで慌しい日々が続いている船上 の様子を少しご紹介します。
・船上生活について
船上の夜明け
「ちきゅう」はほんとうに大きな船です。居住区画は9階建て、研究区画も4階建てで、居住区画の中にはシネマルームや茶室、ジャグジーまであります。
居 室は1人部屋で非常に快適!トイレとシャワーがついていて、毎日ベッドメイキングや洗濯をやってくれます。そして、食事も大変美味。補給船が来るので生の野菜やくだものも食べられるし、日替わりでスイーツもあります。クリスマスやお正月には、七面鳥の丸焼き、塊のローストビーフ、カニ、ロブスターなどの特別メニューが食卓に並びました。
お酒が飲めないことと、1ヶ月を過ぎると少々飽きてくることとを除けば、非常に快適な生活を送ることができます。
・作業の流れ
structural geology groupのメンバー。左からChun-Feng Li, Frederick M. Chester, 氏家恒太郎, Olivier Fabbri, 山口飛鳥
船上では、採取したコアの記載・分析を乗船研究者全員で手分けして行います。作業は12時間交代で休みなく行われ、私は0:00-12:00の夜シフトに配属されています。
全体の作業の流れとしては、船上に上がってきたコアをまずCTスキャナにかけて内部の構造を観察し、それから地球化学者や微生物学者が間隙水や微生物用の whole roundサンプルを抜き取ります。そのあとコアを半裁し、Archive halfは岩相の記載ののち永久保存、Working halfは変形構造の記載・物性の測定後にサンプリングが行われます。サンプリングは半裁したコア(Working half)の横に各自の採取箇所を示す旗を立ててから行われます。重要な箇所には数cmおきにたくさんの旗が立ってなかなか壮観です。
私はstructural geologistとして乗船しているので、コアの構造の記載と方位測定(あとで古地磁気のデータを使って真の方位を復元することができます)が主な仕事 です。非変形の地層は記載事項が少なく作業も比較的楽なのですが、断層帯は記載することが多くて残業が続くこともしばしばです。そのぶん、やり甲斐がある のはもちろんですが。
・IODPについて
直径7cm弱のコアは陸上の全面露頭と比べるといかにも貧弱です。しかし「現世の連続サンプリング」というその威力は強大です。科学が前に進むまさにその瞬間に自分が立ち会っていることを実感します。新しいデータやサンプルを前に、鳥肌が立つことすらあります。
多様なバックグラウンドをもつ10カ国・26人の研究者が、それぞれのデータを持ち寄って考え、公の場で全て議論する。この船の中では、科学の意思決定プロ セスが早送りで進められているように感じます。昼夜のシフトチェンジの時間に開かれるミーティングでは、議論に熱中するあまり食事の時間を逃してしまうこ ともしばしばですが、全く苦になりません。
このメールマガジンが配信される日には「ちきゅう」は新宮に入港します。今回、乗船の機会を与えていただいたことに感謝するとともに、船上・陸上を問わず、たくさんの方々のご支援のもとに私たちの研究が成り立っていることに改めて感謝申し上げる次第です。
多くの方々、特に若い学生・院生の皆さんにとって、IODPの乗船研究は必ず有意義なものになると信じています。この貴重な経験を共有される方が今後ますます増えることを祈りつつ、筆を置きたいと思います。
2008年2月 熊野沖洋上にて
<写真タイトルバック:デリック(掘削やぐら)の頂上から眺めたヘリデッキ。船内ツアーにて>
No.0021 2008/2/5 geo-Flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.021 2008/02/05 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2008年度日本地質学会 理事・評議員選出結果
【2】第2回国際地学オリンピック国内選抜実施・募集
【3】地質学会はジオパーク、IYPEを積極的に推進しています!
【4】「地質の日」が記念日協会に登録されました
【5】「ちきゅう」南海掘削Stage 1A終了
【6】コラム ハロー「ちきゅう」から(山口飛鳥)
【7】地質調査総合センター第11回シンポジウム
【8】関東アスペリティ・プロジェクト(KAP)国際ワークショップ開催
【9】日本堆積学会2008年弘前大会のご案内と講演募集
【10】J-DESCコアスクール「コア解析基礎コース」開催
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2008年度日本地質学会 理事・評議員選出結果
──────────────────────────────────
選挙細則ならびに選挙内規に基づき,新理事(08〜09年度)・補充理事(08年
度のみ)選挙ならびに新評議員(08〜09年度)選出を実施いたしましたので,ご
報告いたします.
選出結果は,学会HP【会員のページ】にログインし
て下さい.
注意!!
・【会員のページ】へのログインには,ID/パスワードが必要です.
・ログイン方法の詳しい説明はこちら
2008年1月30日
日本地質学会 選挙管理委員会
委員長 加藤 潔
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第2回国際地学オリンピック国内選抜実施・募集
──────────────────────────────────
第2回国際地学オリンピック(国際大会)の開催が決まりました。
日程:2008年8月31日から9月7日までの8日間
場所:フィリピン共和国
<一次選抜>
募集期間:2月1日から2月29日
対象者: 国際大会に参加可能な高校生・中学3年生および相当学年の生徒
日時: 3月16日(日)(10:00-12:00)
場所: 原則として参加者の所属する高等学校等にて実施
詳しくは、http://www.jpgu.org/ieso/ をご参照下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】地質学会はジオパーク、IYPEを積極的に推進しています!
──────────────────────────────────
ジオパークという言葉は皆さん聞かれたことがあるかと思いますが、いよいよ
本格的に活動が開始されます。今春には第三者機関である「日本ジオパーク
委員会(仮称)」が立ち上がり、具体的な場所の選定も始まる予定です。
地質学会は積極的にこの活動を支援するために、支部の活動と一丸となって
対応します。また5月10日の「地質の日」(今年が第1回目)やIYPE
(国際惑星地球年:今年は活動のピーク年です)にちなんだ活動も企画中です。
2008年は地質関連の特別な年になりそうです。会員の皆さんのご協力をお願い
いたします。
詳しくは、http://www.geosociety.jp/name/content0008.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】「地質の日」が記念日協会に登録されました
──────────────────────────────────
昨年3月に、地質学会をはじめとする地質関係の組織・学会が発起人となって定め
られた「5月10日:地質の日」を記念日協会に申請し、登録されました。
記念日協会HP
http://www.kinenbi.gr.jp/
地質の日HP
http://www.gsj.jp/geologyday/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】「ちきゅう」南海掘削Stage 1A終了
──────────────────────────────────
昨年9月21日から始まったIODPによる熊野灘沖南海トラフでの科学掘削
計画(南海トラフ地震発生帯掘削計画:NanTroSEIZE)の第1段階の掘削
を終了し、「ちきゅう」は新宮港に帰港します(2月5日)。138日間
無寄港で、3つのExpeditionを完了しました。日報、週報などは以下の
サイトから見れます。また科学成果のPreliminary Reportは、順次IODPの
サイトから見れる予定です。
「ちきゅう」の日報、週報に関しては、
http://www.jamstec.go.jp/chikyu/jp/index.html
IODPのPreliminary Reportは、
http://www.iodp.org/scientific-publications/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】コラム ハロー「ちきゅう」から 山口飛鳥(東大D2)
──────────────────────────────────
IODP Expedition 316 (Thrust Faults)に乗船研究者として参加しました。
コアの記載や下船後の研究に関するミーティングなどで慌しい日々が続いて
いる船上の様子を少しご紹介します。
http://www.geosociety.jp/faq/content0053.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】地質調査総合センター第11回シンポジウム
──────────────────────────────────
「地下水のさらなる理解に向けて〜産総研のチャレンジ〜」
開催趣旨:
地球上における水循環の一端を担う地下水は、従来の資源的側面に加えて、
近年は環境因子として、特に物質を運ぶ媒体としてその役割の重要性が
再認識されている。また、地震発生、断層活動、火山活動などの地質現象を
考える上でも、地下水の挙動のさらなる理解が不可欠であると認識されつつ
ある。産総研では、これらの重要かつ新しいテーマを解決すべく、さまざまな
分野の研究者が異なる視点や手法に基づいて地下水研究に取り組んでいる。
本シンポジウムでは、産総研における地下水研究の最新成果を紹介すると
ともに、「持続可能な社会」「安全・安心な社会」の構築のために担うべき
産総研の役割を議論する。
日時:2008年3月19日(水)13:00-17:30
場所:秋葉原ダイビル 5階カンファレンスフロア5B 会議室
(東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル 5F)
主催:(独)産業技術総合研究所地質調査総合センター
HP:http://www.gsj.jp/Event/080319sympo/index.html
定員:100名
参加費:無料
参加登録:上のHPからご登録下さい。
お問い合わせ:(独)産業技術総合研究所地質調査総合センター
シンポジウム事務局 gsjsympo11@m.aist.go.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】関東アスペリティ・プロジェクト(KAP)国際ワークショップ開催
──────────────────────────────────
(3rd International Workshop on the Kanto Asperity Project)
日時:2008年2月16日(土)〜19日(火)
場所:千葉大学けやき会館(巡検は房総半島)
主催:関東アスペリティ・プロジェクト・グループ
千葉大学地球科学研究グループ
言語:英語
本計画は、相模トラフ沿いで起きた1703年元禄関東地震と1923年大正関東地震の
アスペリティと、近接するスロースリップ発生域の物性とメカニズムを解明する
ために、相模湾と房総沖での掘削とその掘削孔を使った地球物理学的モニタリン
グを行う深海掘削プロポーザルである。これらはIODPにおいて科学立案評価パネ
ルや科学計画委員会で評価され、この8月には複合掘削計画 (CDP) として承認さ
れた (707-CDP, 707A, 707B)。本ワークショップでは、既存のプロポーザルの改
訂と、新たなプロポーザルの作成を念頭に、プロジェクトに関連する最新の研究
成果に関する議論と最近行われた事前調査の報告を行う。
・Kanto Asperity Projectワークショップ巡検(2/18-19:in房総半島)も開催
されます。
詳しくは、
http://www.j-desc.org/oshirase/events/workshop/KAP_IWS080216.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】日本堆積学会2008年弘前大会のご案内と講演募集
──────────────────────────────────
2008年4月25日(金)〜 29日(火・祝)
25日(金):ショートコース
26日(土):個人講演,総会議事,懇親会
27日(日):個人講演,表彰,堆積学トーク・トーク
28・29日(月・火):巡検
会場:弘前大学創立50周年記念館
例会参加費 (講演要旨集込み):
一般会員 3,000円,学生・院生会員 2,000円
非会員一般 4,000円,非会員学生・院生 2,500円
個人講演募集(口頭講演とポスター):
講演申込締切:2008年3月14日(金)
講演要旨締切:2008年3月21日(金)17:00
ショートコース:「石油探鉱データを使用した地下地質堆積環境イメージング」
4月25日(金)13:00〜18:00,弘前大学教育学部
講師:中西健史(国際石油開発)
効率のよい石油探鉱をすすめる上で,地下地質の堆積環境を把握することは重要
です.それは石油を蓄えている貯留岩の性状とその堆積環境とに密接な関係があ
るためです.本ショートコースは参加者に石油探鉱で取得される坑井データ及び
地震探鉱データを用いた地下の堆積環境のイメージングエクササイズを通じて,
堆積学の石油探鉱への適用,地下地質の不確実性,地下地質解釈の実践的アプロー
チを体感してもらうものです.
巡検:下北半島の更新統田名部層(バリアー島堆積物や氷河性海水準変動に伴う
開析谷とその埋積物など)
集合:4月28日(月)〜29日(火)
案内者:鎌田耕太郎・小岩直人(弘前大学)ほか
青森県むつ市周辺の更新統田名部層(バリアー島堆積物や氷河性海水準変動に伴
う開析谷とその埋積物など)を見学します.
詳しくは,
堆積学会HP<http://sediment.jp/04nennkai/2008/annnai.html>
をご参照下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】J-DESCコアスクール「コア解析基礎コース」開催
──────────────────────────────────
ピストンコア、深海掘削コア、陸上掘削コアを研究材料としている(もしくはこ
れから研究する)学部生、大学院生、研究者を対象とした実習形式のスクールです。
受講すればコア記載やコア解析の基礎がわかります!
開催日程: 2008年3月15日(土)〜18日(火)の4日間
開催場所: 高知コアセンター(高知大学物部キャンパス内)
参加費: 9,000円程度を予定(宿泊費,懇親会費等込み、交通費別)
(※J-DESC会員機関所属の学生、院生に旅費援助あり)
申込締切: 2008年2月29日(金)
申込方法やスクールの詳細はコアセンターHPまで
http://www.kochi-core.jp/eando/2007/coreschool-basic/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
コラム-目次
コラム
中教審の答申「知の総和」とレイトスペシャライゼーションへの対応策
正会員 坂口有人
中央教育審議会から「我が国の「知の総和」向上の未来像 〜高等教育システムの再構築〜 (答申)」が2月21日に公表された(以下,今回の答申と呼ぶ).今回の答申の特徴は,学生一人一人の能力を高める質の向上,18歳人口減に伴う大学規模適正化,高等教育へのアクセス確保などがあり,それらを実現する手段として文理融合のレイトスペシャライゼーション(以降LSと呼ぶ)が強調されている.本稿はこのLSを中心に論じる.続きはこちらから
旧石器人の琉球列島への航海(後編)
正会員 高山信紀
旧石器人が用いた舟は,草束舟,竹筏舟,丸木舟による実験航海の結果より丸木舟と考えられる.なお,フィリピンや台湾から漂流して琉球列島に生存してたどり着く可能性は極めて小さいことが漂流ブイの実験から示されている.続きはこちらから
旧石器人の琉球列島への航海(前編)
正会員 高山信紀
琉球列島の沖縄本島,伊江島,久米島,宮古島,石垣島から旧石器人骨が発見されている.これらのうち,ミトコンドリアDNA分析が行われた港川フィッシャー遺跡の約2万年前の人骨は,縄文時代,弥生時代,現代の集団の直接の祖先ではないことが示唆されたが,現代の日本列島人集団の祖先のグループに含まれるか非常に近いものであり,白保竿根田原洞穴遺跡の約2万年前の人骨は中国南部や東南アジアに起源をもつ可能性があると考えられている.本稿では,時代を4万年前と2万年前に設定し,いくつかの文献をもとに旧石器人の琉球列島への移動経路を考えてみた.続きはこちらから
ベニオフ以前に深発地震帯逆断層説を唱えた日本人地質学者
正会員 石渡 明
現在では,環太平洋式の造山帯は深発地震を伴う海洋プレートの沈み込みによって形成されるということは常識になっている.これは,深発地震の存在を初めて確認した和達清夫と,深発地震帯は大陸/大洋境界の逆断層であり海溝はこの断層の運動によってできると喝破したベニオフの貢献とされ,深発地震帯は和達−ベニオフ帯(Wadati-Benioff zone)と呼ばれる.続きはこちらから
日本周辺の地震西進系列と次の関東・南海地震
石渡 明(正会員 原子力規制委員会)
石渡(2019)は最近360年間の日本周辺の大地震について,「南海トラフ巨大地震を中心に,M≧7.5地震が北海道から台湾へ西進する傾向が見られ(中略)これを「地震系列」と名付ける」と述べ,南海トラフ地震発生時の年号により各系列を宝永,安政,昭和と命名した.小論では現在東北地方から西進しつつある最新地震系列の特徴を過去3系列と比べて論じ,今後の推移を考察する.続きはこちらから
琉球列島:縄文人が挑んだ遠い島と黒潮
正会員 高山信紀
喜界島で福徳岡ノ場2021年8月噴火のものと見られる漂着軽石を見た話を 友人にしたとき,「喜界島から屋久島は見えるか?」と聞かれた.本稿は, これをきっかけに,九州から台湾の間の島々について隣の島が見えるか 計算式により確認するとともに,縄文時代の航海への黒潮の影響と当時の 航海の限界を考えてみたものである. 続きはこちらから、、、
平安時代の「日本三代実録」の地震・津波・噴火記録:地震西進系列の白眉
正会員 石渡 明
日本地震周期表(石渡,2019)は最近約360年間の日本の被害地震の時空分布をまとめ,大地震(≧M7.5)が東北日本から関東甲信越・西南日本を経て琉球・台湾へと110〜180年かけて西進すること,その地震系列が約120年周期で繰り返すことを示した.そして,南海トラフ地震の年号により,各西進系列を宝永,安政,昭和,最新と名づけた.例えば,1677延宝三陸・房総沖−1703元禄関東−07宝永南海トラフが宝永系列を代表する地震であり,1793寛政仙台沖−1847弘化長野善光寺−54安政南海トラフが安政系列を代表し,1896明治三陸−1923大正関東−44・46昭和南海トラフが昭和系列を代表する.続きはこちらから、、、
地学に名を轟かした水戸藩の長久保赤水の改正日本輿地路程全図
正会員 石渡 明
伊能忠敬(1745-1818)は幕府の命により全国を実地測量して精密な地図を作った が,伊能図(大日本沿海輿地全図:文政 4(1821)年完成)は秘密とされ一般人 は使用できなかった.それに対し,長久保 赤水(1717-1801)が作ったのは10里 が1寸の縮尺約130万分の1)の1枚刷り全国図で,経緯線が入り,郡や村,道路, 山川,古跡名勝等が詳しく示され,国別の色分 けも美しく,安永9(1780)年 に大坂で初版を出版して以来, 明治の初めまで約100年間にわたって版を重ね, 国内はもちろん国外でも,正確で実用的な日本地図として重宝された. .続きはこちらから、、、
童謡詩人金子みすゞの地学的側面
正会員 石渡 明
2011年3月11日の東日本大震災からしばらくの間,AC ジャパン(公共広告機構)が金子みすゞの「こだまでしょうか」という詩をラジオやテレビで流し続けたので,仙台で被災者生活を送った私などは,その詩が未だに耳に残って離れない.この詩人の哲学的,宗教的側面については既に論じられているが(後述),小論ではその地学的側面について述べる.続きはこちらから、、、
河川と海岸のデジタル礫形計測:その後の進展
正会員 石渡 明
石渡ほか(2019)は文献調査と実際の礫のデジタル画像の計測によって河川礫と海岸礫では形が明瞭に異なることを数値で示した。原子力発電所の敷地や敷地周辺の調査では、断層の活動性評価において、断層の上載層(多くは段丘堆積物)が河成か海成か判断する必要が生じることがあり、いくつかの原子力事業者が石渡ほか(2019)の方法による礫形計測を実施した。続きはこちらから、、、
中国の月探査機「嫦娥5号」持ち帰り試料の地質学的研究結果
正会員 石渡 明
中国の月探査機「嫦娥5号(Chang’e-5)」(チャンオー、eはE表記も)は 2020年12月1日に嵐の大洋(兎が餅を搗く臼の部分)の北部、Rümker (リュムカー)山の北東約170km、露の入江に近い北緯43.06度、西経51.92度 に着陸し、地質試料の採集などを行って、2020年12月16日に内モンゴルの 沙漠に帰還した。月からの試料回収は1976年のソ連のルナ24号以来44年ぶり である。2021年10月にこれらの試料の分析結果が発表されたので、その概要 を紹介する。 続きはこちらから、、、
“Geomythology(地球神話)“とジオパーク
正会員 野村律夫
第11回ジオパーク全国大会が10月3日〜5日にかけて島根県松江市 と出雲市で開催された.昨年から続くコロナ禍のため1年延期となった が,637名が参加するオンライン開催であった.パソコンのモニター越し に伝わる静かな雰囲気の大会ではあったが,発言のしやすさなど学ぶこ とも多かったように思う. さて,どのジオパークにもシンボル的な自然がある.大会に向けて, 島根半島・宍道湖中海ジオパークはなんだろうかと問い直してみた. 半島と湖が醸し出す広大な景観は美しい.また,そこは古代からの歴史 という空気で満たされた不思議な自然である.少し抽象的な表現になった が,このジオパークは新第三紀中新世の変動地質と第四紀の平野形成と いった学術価値のみではなく,古事記や出雲国風土記にある神話・伝説 が大地に深く根付いているということだ. 続きはこちらから、、、
放射性物質を含んでいる福島県太田川河川敷で発見した黒砂中の磁性細菌
正会員 田崎和江ほか
2011年3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生し,地震と津波による被害が生じた. さらに, 東京電力福島第一原子力発電所のある福島県では,原子炉の損傷により放射性物質が飛散し,広範囲に被害が及んだ.2020年3月11日に福島県南相馬市双葉町の避難困難区域は解除となったが,多くの住民は安心して帰宅することはできず,いまだに不安を抱えている.続きはこちらから、、、
“ナホトカ号”の重油流出事故の教訓とモーリシャスでの重油流出事故への責任:24年前の事故現場と今も残る流出被害の痕跡
正会員 田崎和江ほか
1997年1月2日,2時41分頃,ロシア船籍タンカー“ナホトカ号(13,157トン)”の船首部が脱落して,同後部が島根県隠岐島北北東106kmに沈没した.この事故で乗務員32名(全員ロシア人)のうち31名が救出されたものの,船長は死亡した.そして,折からの秒速30m前後の強い西風にあおられ,1月6日には船首部分が福井県三国町安東沖に座礁した.続きはこちらから、、、
永瀬清子:宮沢賢治に憧れた女流詩人の地学的側面
正会員 石渡 明
筆者は2016年8月21日に岡山県赤磐市で開催された「じぇーじーねっと地質学講座」に招待され,「東アジアの地質 赤磐市の海底岩石とのつながり」の題で講演した.翌月25日,読売新聞日曜版に掲載された永瀬清子(1906〜1995)の特集(名言巡礼:文・松本由圭,写真・林陽一)を読み,宮沢賢治に憧れて「雨ニモマケズ」詩の「発見」の現場にも立ち会ったこの女流詩人が,戦後ずっと赤磐市で農婦として働きながら詩作を続けていたことを初めて知った.つづきはこちらから、、、
Pitch vs. Rake
正会員 高木秀雄
pitch(rake)とは,断層面上の条線や,砂岩の底面のソールマークなどのように,傾斜した面構造上に線構造が存在する 時の面構造の走向と線構造とのなす角度を面上で測定したもので,線の傾きを鉛直面上で求めた沈下角(plunge)と区別される.
つづきはこちらから、、、
津波と集落
正会員 高山信紀
あと数ヶ月で東日本大震災から10年となる.この間,様々な分野で調査・研究が行われ,復興が進められ,膨大な画像や文献が公開されている.本記事では,筆者が訪れたことがあるいくつかの津波被災地の思い出と,このたびインターネットで調べたこれら被災地の津波被害と復興の一端を述べてみたい.つづきはこちらから、、、
柱状節理は低温の発泡膨張,板状節理は高温の流動剪断でできる
正会員 石渡 明
地学事典は,溶岩・岩脈・岩床等に見られる柱状節理(columnar joint) について,「岩体の冷却時の体積収縮によって形成され」,「柱状節理 の間隔(spacing)は冷却速度に比例し,ゆっくり冷えれば間隔が大きく なると考えられている(Spry, 1962)」と記し,板状節理(platy joint) も「冷却時に形成される」と記している(平野・横田, 1996).
つづきはこちらから、、、
昇仙峡は黒富士が造った?:「地質図Navi」と「地理院地図」で楽しむ四次元の旅(後編)
正会員 高山信紀
「前編」に引き続き,後編では,「旧荒川」,「旧板敷川」のルートと縦断面,大滝,仙娥滝の成り立ちについて検討した内容を述べる.
つづきはこちらから、、、
昇仙峡は黒富士が造った?:「地質図Navi」と「地理院地図」で楽しむ四次元の旅(前編)
正会員 高山信紀
本記事は,山梨県甲府市北部に位置する昇仙峡,野猿谷, 大滝と仙娥滝の成り立ちについてのアイデアとそれに基づいて机上で検討した内容を述べたものである.
つづきはこちらから、、、
海岸礫は河川礫より円くて扁平である
正会員 石渡 明ほか
河川と海岸で礫(れき)(小石,石ころ)の形に違いがあるかどうかという問題は,小学校や中学校の夏休みの自由研究のテーマのように聞こえるが,両所の礫形の違いについてはっきり述べた教科書はなく,公表された研究結果も少ない.しかし,きちんと計測すれば海岸礫は河川礫より円くて扁平であることが,文献調査と実測により明らかになったので報告する.
つづきはこちらから、、、
コラム 宋詩にみる石と人の関わり
正会員 石渡 明
前回は中国唐代(618-907)の詩について白居易の青石を中心に石と 人の関わりを考えたので (http://www.geosociety.jp/faq/content0818.html),今回は宋代 (960-1279)のいくつかの詩について考えることにする.宋代は日 本の平安時代中期から鎌倉時代に当たる.吉川幸次郎(1962)は「 宋詩概説」(中国詩人選集第二集第一巻,岩波書店)で宋詩の特徴 として,叙述性,生活への密着,連帯感,哲学(論理)性,悲哀か らの離脱を挙げ,平静さが最大の特徴だとして,唐詩は酒,宋詩は 茶だと述べている.また吉川は,欧陽脩(六一居士,1007-72)が従 来の仏教または道教の優位に対して儒教の優位を確立し,この転換 が約900年後の清末まで中国文化を規制したとも述べている.続きをよむ
コラム 唐詩にみる石と人の関わり:白居易の「青石」考
正会員 石渡 明
唐詩にみる石と人の関わり:白居易の「青石」考唐詩において,石は自然(山水)を代表する点景として用いられることが多い.詩仏と呼ばれる盛唐の王維(701?-761)の「香積寺を過る」には,「泉声は危石に咽び,日色は青松に冷ややかなり」という,谷川の急流が切り立った岩に当たる音と,松林に差し込む落ち着いた日光の色を対置した,非凡な対句がある.香積寺は唐の首都長安(陝西省西安)南方にあったが,唐朝の高級官僚だった彼は長安東方40kmの藍田に広大な別荘をもち(輞川荘),敷地内の各所に鹿柴,竹里館などと名づけて詩友裴迪とともに遊歩し絶句を賦した(輞川集).「空山人を見ず 但だ人語の響くを聞く 返景深林に入り 復た青苔の上を照らす」(鹿柴),「独り坐す幽篁(竹やぶ)の裏琴を弾じ復た長嘯 深林人知らず 明月来たって相照らす」(竹里館)などの名詩はここで作られた.近くには藍田山があり,古くから玉を産した.続きをよむ
学会創立125周年記念 トリビア学史 16 東京大学の演説会
矢島道子(日本大学文理学部)
「演説」という行為は明治時代には,大変重要だった.福澤諭吉の訳と言われている.明治15年には「演説する女」も現れた(関口,2014).特に自由民権運動における演説は有名であるが,本トリビアはそういう意味ではない.
東京大学は明治10年に創立されたが,『東京日日新聞』の記事を読んでいくと,創立当初から一般の人向けに講演会がおこなわれていたようなのだ.この講演会は演説会あるいは演舌会と言われていた.東京帝国大学五十年史(1927)には,これらの記載が一切ない.進化論を一般向けの講演会で演説したモースの『日本その日その日』にも大学の講演会は一言も触れられていないので,現在,わかり始めたことだけ記す. 続きをよむ
コラム:日本ナップ説略史
正会員 石渡 明
米国地質学会の情報誌GSA Today最新号の表紙と冒頭に,ギリシャ・ペロポネ ソス半島のゼウス霊場は,古成(古第三)系暁新統にジュラ・白亜系が衝上す るクリッペの上にあったという文理融合研究の報告が載っている(Davis, 201 7).スイス中部シュヴィッツ(Schwyz)州のヘルベチア帯北縁部の白亜系にペ ンニン帯のジュラ系石灰岩が衝上するミューテン(ミーテンMythen)クリッペ もゲーテが感動した「神話の山」であり,米国モンタナ州ロッキー山脈の白亜 系に先カンブリア系が衝上するチーフ(Chief)山クリッペ(現地語名は Ninaistako)も雷神が住む聖山だという.
続きを読む
学会創立125周年記念 トリビア学史 15 客死した鉱山学者ヘルマン・リットル
矢島道子(日本大学文理学部)
明治初期,開成学校に優秀な鉱山学者ヘルマン・リットル(Hermann Ritter 1827–1874)がいた.ところがリットルは天然痘で1874(明治7)年に死亡し,後任の地質学の教授が必要になった.良く知られている通 り,1875(明治8)年エドムント・ナウマン(1854–1927)がやってきて,東京大学地質学教室の初代教授に就任した.地質学史上ナウマンが,日 本に地質学をもたらしたことになっている.歴史に「もし」はないけれど,リットルが生きていたら,ナウマンは日本に来なかったかもしれない.
詳しくはこちら
学会創立125周年記念 トリビア学史 14 京都の鉱物学者‐比企忠(1866−1927)
矢島道子(日本大学文理学部)・浜崎健児(Ultra Trex(株))
日本で最初にノーベル賞を受賞した湯川秀樹(1907−1981)の父親である地質学者小川琢治(1870−1941)は,京都大学理学部地質学教室の創設者であることもよく知られている.…(中略)…実は,京都大学には,小川琢次よりも前に,すなわち,1897(明治30)年から,地質学・鉱物学者比企忠(ひきただす)が工学部のほうに赴任していた.京都大学総合博物館に所蔵されている鉱物標本の多くは比企忠の蒐集物である
詳しくはこちら
地質調査にあたって保護法令などの遵守を
正会員 小滝篤夫・鈴木寿志
近年,研究者の国立公園など法的に保護された区域での試料採取が問題になっています.日本地質学会でも2008年に理事会名で『野外調査において心がけたいこと』を公表し,そのなかで「史跡・名勝・天然記念物においては,文化庁や地元自治体などへの必要な手続きなしには露頭をハンマーでたたいて岩石試料を採取するなどの破壊を伴う調査はもちろん,転石の採取もできません....
詳しくはこちら
学会創立125周年記念 トリビア学史 13 地方で生きる:福井県の場合
矢島道子(日本大学文理学部)・浜崎健児(Ultra Trex(株))
日本の地質学の歴史を調べていると,話はどうしても東京や京都などの都市中心になる.基本的には東京大学で地質学者が育てられ,地質調査所で調査にはげみ,地質学会で議論するという構図で,日本の地質学は始まったので,致し方がないのかもしれない.ただ,目を凝らして見ていけば,いろいろな地方の動きも見えてくる.福井県を一例として報告してみたい.
詳しくはこちら
学会創立125周年記念 トリビア学史 12 誤りは早く直しましょう
矢島道子(日本大学文理学部)
『日本の地質学100年』(日本地質学会,1993)の,中国関連の記述に誤りがあると中国科学史家・武上真理子氏(元京都大学人文科学研究所)より指摘を受けた.戦前の中国での地質学研究の記述である.上記100周年記念本を所持されていたら,訂正してほしい.
詳しくはこちら
学会創立125周年記念 トリビア学史 11 新島襄と地質学
矢島道子(日本大学文理学部),林田 明(同志社大学理工学部)
新島襄(1843-1890)は同志社を創設したキリスト者であるが,地質学に親しかったことはすでに知られている(島尾,1986,1989;八耳,2001など).同志社大学は2017年5月16日(火)〜7月9日(日)に,ハリス理化学館同志社ギャラリーにて,第12回企画展「新島襄が感じた地球」を開催した.同志社大学の文化系公認団体である地学研究会が2017年に創立50周年を迎えたのを機に,同志社における地学の意義を考える企画展であった.このとき初めて新島旧邸にある化石及び岩石鉱物標本の肉眼鑑定が実施され,その成果の一部も公開された.
詳しくはこちら
日本地質図百景
正会員 石渡 明
産業技術総合研究所地質調査総合センター(以下「地調」。旧通商産業省工業 技術院地質調査所)の地質図は、1/20万図が北方領土を除く全国122区画(110 図幅、うち2区画合体図幅が12)を、1/5万図が全国の約6割(1274区画のうち7 60)をカバーし、凡例を統一した1/20万全国シームレス地質図も提供されてい る。北海道については、国土交通省北海道局(旧北海道開発庁)及び北海道立 総合研究機構地質研究所(旧地下資源調査所)による地質図も含めると、全道 のほとんどの1/5万図が出版済みである(未出版は7区画)。そしてこれらのす べての地質図とその説明書が、地調のホームページにて無料で閲覧・ダウンロー ドできる(https://www.gsj.jp/Map)。これらの地質図は学校や社会における 地学教育にも非常に有用であるが、どの地質図がどのようなテーマの教材とし て役立つかを示したガイドが、これまで無かったように思う。私は仕事柄全国 の地質図を見る機会が多いので、その経験に基づいてテーマごとに地質図の「 見どころ案内」を試みる。
詳しくはこちら
学会創立125周年記念 トリビア学史10 韃靼の地質調査—榎本武揚,オッセンドフスキ
矢島道子(日本大学文理学部)
司馬遼太郎の最後の小説『韃靼疾風録』を知っている人も少 なくなった.韃靼といっても,もうほとんど通じないかもしれ ない.モンゴル付近に住んでいる(いた)タタール人のことを 韃靼という.戦前は,韃靼ということばはある程度知られてい た.日本で間宮海峡といわれている地名は,世界的にはタター ル海峡(韃靼海峡)と呼ばれている.
詳しくはこちら
学会創立125周年記念 トリビア学史 9 1893(明治26)年吾妻山爆発にともなう地質学者の殉難
矢島道子(日本大学文理学部)
火山はときに大爆発をし,人間の社会生活に甚大な被害を与 えることがある.1893年には会津の吾妻山が爆発し,地質学者 が殉難した.地質学が日本に芽生えてから初めて起きた事件だ ったので,東京地学協会報告や鉱山雑誌等によく記録された. 佐藤(1985)によく再録されているが,当時の新聞等を入手し たので,社会的な影響についても報告したい.
詳しくはこちら
学会創立125周年記念 トリビア学史8 傍系の地質学者 篠本二郎(1863-1933)
矢島道子(日本大学文理学部)・浜崎健児(Ultra Trex(株))
鉱床学者,木下龜城(1896-1974)が1933年,『我等の礦物』誌に篠本二郎の追悼文を書いている.略歴も著述目録も詳しく載っている.にもかかわらず,巷では生没年不詳となっているものが多い.本人も自伝のようなものを書かず,木下のほかには評伝や弔辞を書かなかったことが,そうなっている原因だと言えそうだ.こう紹介すると篠本の名は歴史から消えかかっているように思えるが,彼の交友関係は思いのほか広い.
詳しくはこちら
学会創立125周年記念 トリビア学史7 地質学者宮沢賢治研究の嚆矢?
矢島道子
地質学の歴史を調べていくときに,戦争中の地質学者の動きは重要である.日本地質学会は創立60周年記念誌でかなり詳細に記録しているが,まだ知られてい ない資料は多い.資料が散逸しないうちに記録されるべきであろう.東京大学の地質学教室の戦時中の歴史を調べているうちに,おもしろい資料を発見したの で,公開する.
詳しくはこちら
学会創立125周年記念 トリビア学史6 女性地質研究者の嚆矢
矢島道子
2015(平成27)年発行の日本地質学会・会員名簿では,3851名の会員中,女性は373名で1割弱である.地質学会で女性を初めて見かけるようになったのは,1943(昭和18)年のことであるが,実は,その前に日本の化石を研究した外国人女性と日本人女性がいる.概略を記したい.
詳しくはこちら
学会創立125周年記念 トリビア学史5 中村彌六(1855-1929):地質学に近しい林学者
矢島道子
2012年ころ,山田直利さん(元地質調査所)とナウマン(Edmund Naumann;1854-1927)の日本の地質調査所の業績の報告(1891)を翻訳した.それは地質に関する報告だけでなく,農学に関する業績も扱っている.地質調査所の初期にはリープシャー(Georg Liebscher;1853-1896) やフェスカ(Max Fesca;1845-1917)の率いる農学部門があったからだ.文中に気候学者としてハン(Julius Ferdinand von Hann;1839-1921)やライン(Johannes Justus Rein;1853-1918)のほかに,Nakamuraという日本人の名がでてくる.
詳しくはこちら
学会創立125周年記念 トリビア学史4 不思議に満ちた白野夏雲(1827-1899)
矢島道子
明治の初め,地質学を志した日本人の第1 世代は,ほとんどが欧米から学んだ.榎本武揚のように明治以前に欧米に行って学んだ者や,明治になってからお雇い外国人のコワニエ,ライマン,ナウマンな どに習った者などである.地質学そのものが日本で生まれたのではなく,欧米で生まれた学問だから当たり前のことかもしれない.ところが,今回とりあげる白 野夏雲(文政10年‐明治32年)は欧米人に習った形跡も,大学で教育を受けた経験もない.にもかかわらず,白野の地質学的業績はかなり秀でている.
詳しくはこちら
テクタイトの給源クレーター
石渡 明
日本地質学会が執筆協力したThe Geology of Japanが2016年4月にロンドン地質学会から出版された(Nowell, 2016).このシリーズにThe Geology of Thailandがあり,その第21章がテクタイト(tektite)の記述にあてられている(Howard, 2011).また同シリーズのThe Geology of Central Europe(McCann, 2008)の下巻にもテクタイト(モルダバイト)とそれを生じたリース・クレーターに関する記述がある.一方,2016年8〜9月に第35回万国地質学会議(IGC)が南アフリカのケープタウンで開催され,そこで配布されたアフリカの地質ガイドブックにもテクタイトとその給源クレーター(Bosumtwi)の記述がある(Reimold and Gibson, 2016).日本にテクタイトは分布しないが,松田(2008)や下ほか(2010)の優れたまとめがあり,本学会でも林・宇田(1997)の報告がある.ここでは,テクタイトの給源クレーターに関する最近の地質学的知見を中心に略述する.
詳しくはこちら
学会創立125周年記念 トリビア学史 3 富士谷孝雄(? – 明治26(1893))はどこへ消えたか
矢島道子
富士谷孝雄は生年がいまだ不明だが,東京大学理学部地質学科を明治14(1881)年に卒業した,3回目の卒業生である.初代教授ナウマンと一緒に移っている写真は有名である.ナウマンが日本人と一緒に移っている写真は大変珍しい.おそらく富士谷だけであろう.ところが,富士谷はその後の地質学史からほとんど消えている.どうしたのだろうか…
詳しくはこちら
学会創立125周年記念 トリビア学史 2 日本にライエルの孫が来た?ビーグル号が来た?
矢島道子
チャールズ・ライエル(Charles Lyell 1797-1875)は『地質学原理』の著者として,(『地質学原理』を読んだことがなくても)地質学を志した人ならば誰でも知っている.その孫が日本に来たという話がある.
詳しくはこちら
学会創立125周年記念 トリビア学史 1 地学会編集『本邦化石産地目録』(1884)
矢島道子
2018年に日本地質学会は創立125周年を迎える.これまでに50周年,60周年,100周年に記念誌を出版してきた.125周年には各分野の100周年から125周年のレビューを地質学雑誌に特集号として掲載予定である.この動きとは別に,これまでの記念誌に掲載されてこなかった学史的な資料がときどき発見されることがある.また,科学史全体の趨勢として,事実解釈が変更されてきているものもある.125周年が終われば,記念誌の編纂は150周年まで試みられないだろう.最近発見されたことがらは風化して消失してしまう可能性も高い.それで,今号から数回にわたって,「トリビア学史」として,小さいけれど,地質学の歴史で重要になるかもしれないことがらをまとめていきたい.第1回は1884年発行の『本邦化石産地目録』についてお送りする.
詳しくはこちら
「日本地方地質誌」完結と「The Geology of Japan」出版:日本地質学発展のランドマーク
石渡 明・井龍康文・ウォリス サイモン
地質学の研究者や学生が,日本のある地域の地質を少し詳しく知ろうと思った時,最初に手に取る書物はその地方の地質誌である.また,ある外国の地質を知ろうと思えば,まずその国の地質誌に目を通すことになる.2016年度中に日本地質学会(以下「本学会」)編,朝倉書店発行の「日本地方地質誌」が全巻完結予定,また英国地質学会(The Geological Society of London)から「The Geology of Japan」が刊行予定である.ここでは地方地質誌の歴史と現状を略述して,その意義を明らかにしたい.
詳しくはこちら
国際学術用語となった“人自不整合”
上砂正一(環境地質コンサルタント、NPO法人日本地質汚染審査機構副理事長)
5年前の日本地質学会富山大会の夜間小集会「都市地質学全国協議会」で、地質汚染などで問題となっていた自然地層と人工地層との境界“人自不整合”について、地質学用語の提唱とその重要性が指摘された。
詳しくはこちら
日本地質学会初代会長神保小虎小伝
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
筆者は日本地質学会会長の任期を終えるに当たり、初代会長神保小虎(1867-1924)の小伝を記してその心意気を会員諸兄諸姉に伝え、本学会の今後の発展の一助としたい。
詳しくはこちら
日本地質学会の60, 75, 100周年記念誌を読む:125周年に向けて
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
893年の創立から今年で121年になるが(ただし1934年までは「東京地質学会」)、本学会は60、75、100周年に記念誌を刊行してきた。この他、1985年に地質学論集25号「日本の地質学—1970年代から1980年代へ」、1998年に同49号「21世紀を担う地質学」と50号「21世紀の構造地質学にむけて」の総説集を刊行した。ここでは、これらを読んで簡単な感想を述べ、125周年に向けての一歩としたい。敬称を略すことをお許し願いたい。
詳しくはこちら
「日本からみつかった巨大隕石衝突の証拠」発表までの道のり
佐藤峰南(九州大学大学院理学府 博士課程2年)
三畳紀層状チャートの露頭で有名な岐阜県坂祝(さかほぎ)町の木曽川河床では,隕石衝突により堆積した粘土岩が観察されます(図1).2013年9月16日,この粘土岩についてオスミウム同位体分析を行った著者らの研究成果がNature Communications誌に掲載されました(Sato et al., 2013).本稿では,多くのメディアに取り上げていただきましたこの研究のきっかけや経緯につきまして,自身の経験談を中心にご紹介させていただきます.なお詳しい研究の内容は,プレスリリース資料(http://www.sci.kumamoto-u.ac.jp/~onoue/press.pdf)に掲載してあります.
詳しくはこちら
福島原発大事故に伴う福島県の放射性物質汚染 —汚染地域の住民から見た汚染の実態—
千葉茂樹(福島県立小野高校平田校)
著者は,事故当時「福島市渡利」に居住していた.本稿では,汚染地域「福島市渡利」に居住していた人間の視点から汚染の実態を報告する.著者は今までに汚染の状況を報告してきた(千葉ほか2013など)が,本稿ではそれも含め,新たに「8.森林における放射性物質の濃集—楯状高放射線量土—」も記載する.この内容は,著者が知る限りにおいては報告例がなく初めての報告と思われる.発見の経緯なども含め詳しく記載する.
詳しくはこちら
鳥が首岬の謎
高山信紀((株)JPビジネスサービス)
以前、米国ユタ州サンファン川(San Juan River)の「Gooseneck」や、愛媛県を流れる肱川中流の「鳥首」を訪れたことがあるが、いずれも地名は河川の蛇行を鳥の首に例えたことに由来する。鳥が首岬は、新潟県上越市西方(糸魚川市寄り)に位置し、全国的にはそれほど有名では無いが国土地理院発行の20万分の1地形図や2万5千分の1地形図にはその名が記載されている。鳥が首岬の地名は何に由来するのだろう?
詳しくはこちら
東海道五十三次と地震・津波・噴火
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
江戸時代のはじめ、参勤交代制の開始(1635年)とともに整備された東海道五十三次は、橋のない川や厳しい関所などの問題はあったが、当時としては世界で最も安全・快適に旅行できるハイウェー・システムであった。しかし、この道はいくつかの場所で海岸沿いを通り(図1)、そこではしばしば自然災害に襲われてきた。この地域は相模トラフや南海トラフのプレート境界に沿っていて地震・津波の被害があり、また多くの台風が直撃して高潮、洪水、山崩れなどの被害があった。そして巨大な活火山である富士山がこの街道の間近にそびえている。ここでは、東海道の宿駅の歴史を概観して、この地域の自然災害について一考する。
詳しくはこちら
丹那断層と丹那トンネル難工事と二つの大地震
正会員 服部 仁
提案の目的:丹那盆地は,地殻変動の活発な伊豆半島北端に位置し,徑約1㎞の環状地形をなしている.東縁には南北性丹那断層が通り,北縁の地下約150 mには東西方向に日本の幹線鉄道の丹那トンネルおよび新丹那トンネルが貫いている.両トンネルは盆地中頃において丹那断層とほぼ直交する.
その1はこちら
その2はこちら
その3はこちら
上町断層によって撓曲した大阪層群の貴重な露頭が消失の危機に
中条武司(大阪市立自然史博物館)・廣野哲朗(大阪大学)
閑静な住宅地に囲まれた大阪府豊中市西緑丘に,佛念寺山断層(上町断層)の活動によりほぼ直立に撓曲した大阪層群の露頭があります(写真).この学術的にも教育的にも貴重な露頭が開発により失われようとしています.この問題について広く地質学会学会員の方に報告し,露頭保存のあり方について一考いただければと思います.
詳しくはこちら
地震雲についての雑感
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
半年前,あるニュース社からの取材を受け,世間でよく言われる地震の前兆現象の中で科学者として信じられるものはどれか,というアンケートに○△×で答えたことがある(石渡,2012).動物の異常行動,前震,鳴動,地盤の隆起と沈降,井戸水や温泉の異常(水量やラドン含有量の変化を含む),電磁気異常,発光現象などには△をつけたが,地震雲だけは×をつけた.地震学者が書いた前兆現象に関する従来の論文や書籍を見ても,地震雲についてはほとんど取り上げられていない。そこで,地震雲についての書籍を読んで勉強してみたので,その感想を述べて会員の皆様の参考に供する.
詳しくはこちら
日本で唯一のモホ面露頭の保全について
日本地質学会会長 石渡 明
福井県大飯郡おおい町の大島半島には夜久野(やくの)オフィオライトが分布しており,県道241号線(赤礁(あかぐり)崎公園線)の大島トンネル北口から約200m北西の浦底(うらぞこ)地内の露頭には,そのモホ面(モホロビチッチ不連続面,地殻とマントルの境界)が露出しています.これは,道路沿いで容易に観察できるモホ面の露頭としては日本国内で唯一のものであり,かんらん岩・輝石岩・斑れい岩からなる層状構造が露出しています.
詳しくはこちら
オーストラリア国立大学に設置されたS/Iタイプ花崗岩ベンチ
石原舜三(産業技術総合研究所 顧問)
Bruce ChappellおよびAllan Whiteの業績をしのんで、S/Iタイプ花崗岩を用いたベンチが国立大学校内の一隅に設けられ、そのお披露目がBruceの死後6か月に当たる2012年10月19日に行われた。
詳しくはこちら
新潟および関東地方の天然ガスの起源と賦存状態について
金子信行(産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門)
新潟県は、わが国の有数の石油・天然ガス地帯である。また、南関東ガス田はわが国の天然ガス生産量の10%程度を占め、数百年分の埋蔵量を誇るガス田である。最近は原子力発電所の停止により輸入液化天然ガス(LNG)が注目されているが、国内にも貴重な石油・天然ガス鉱床は存在する。資源ナショナリズムの問題もあり、国産資源に目を向ける動きもあるが、資源の研究に従事する者としては、爆発事故等が起きる度に、一時的に国内の天然ガス資源が注目されることを悲しく感じる。
詳しくはこちら
世界のM9地震と地質学の課題
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
マグニチュード(M)9.1(ここでは国立天文台(2011)に基づくモーメント・マグニチュード(Mw)を用いる)の2011年東北地方太平洋沖地震とそれに伴う津波および原子力発電所の事故による東日本大震災が発生してから1年になる。体に感じる余震はまだ頻発しているが,ここ数ヶ月間は被害を伴う地震の発生はない。今後の地震災害について考えるために,地球上で過去にM9クラスの超巨大地震が発生した地域における,その前後の地震活動の推移を知ることが大切だと思い,それらの地域における最近の大地震の時空分布を簡単にまとめてみた。そして,我々地質研究者の当面の課題について考えてみたい。
詳しくはこちら
英語クロスワードのすすめ
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
英語がなかなか上達しないというのが私を含めて多くの日本人研究者の悩みである.私はパズルが好きなので,外国に行くと英字新聞のパズルを解いてみるのだが,どこの国でも数独(Sudoku)は何とか解けるのに,クロスワードは歯が立たないことが多い.その国の三面記事に通じていないという事情もあるが,やはり基本的な単語力が弱いためである.クロスワードは完成した時に何とも言えない達成感があり,多少わからない単語があっても完成できるので,楽しみながら単語力をつけるのに最適のパズルであるが,邦字紙には英語のクロスワードが滅多に載っておらず,英字紙のクロスワードは難しすぎる.そこでネット書店で探してみたところ,文末のリストのような学習者向けの英語クロスワードの本があることがわかったので,自分で解いてみた感想を含めて紹介する.
詳しくはこちら
糸魚川-静岡構造線新倉露頭の断層上盤側の崩落
狩野謙一(静岡大学理学部)
日本を代表する逆断層露頭として有名な糸魚川-静岡構造線 (以下,糸静線)の新倉(あらくら)露頭(別称:新倉断層)の断層上盤側 が,2011年9月の台風に伴う豪雨によって崩落し,露頭状況が一変した.この露頭の2011年12月末時点での状況について報告する.図1は崩落以前, 図2は崩落後の状況である.いずれも露頭の全容が把握しやすい落葉後の写真を採用した.
詳しくはこちら
水星の地質について
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
太陽系惑星で最も内側の軌道を回る水星の探査は、1974〜75年のマリナー10号以来30年以上途絶えていた。そのため、地球型惑星の地質学・物質科学においては,水星を軽視する傾向があった(例えば武田2009)。2004年に打ち上げられた米国のMESSENGER (Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry, and Ranging)探査機は、2008〜10年の間に3回ほど水星近傍を通過して観測を行い、2011年3月18日には水星周回軌道に入って連続観測を行っており、その高解像度写真やX線、γ線などによる化学組成分析データに基づき新知見が続々と公表されつつある。ここでは,それらを簡単にまとめて地質学会会員諸氏の参考に供する。
詳しくはこちら
中国と日本のジオパーク
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
国際地質科学連合(IUGS)の機関誌Episodesの最新号に中国のジオパークについての記事が出た(Yang et al. 2011).これは非常に内容の濃い,示唆に富む優れたまとめであり,表と写真を交互に参照しながら読みふけってしまった.中国と日本のジオパークを比べて,感じたこと,気がついたことを述べてみたい.
詳しくはこちら
アメリカ合衆国ユタ・コロラド州境界、ダイノソー・ナショナル・モニュメントとユインタ山系の地質概略(紹介)
小川勇二郎(ユタ州プロヴォ、ブリガム・ヤング大学)
ダイノソー・ダイアモンドという名称をご存じだろうか?まだあまり人口に膾炙していないかもしれないが、ユタ州とアリゾナ州にまたがる国立公園めぐりのメッカ、グランド・サークルの向こうを張った、ユタ州とコロラド州の一部を主とする、ダイノソーめぐりの新しい観光ルートのキャンペーンなのである。以下に、その北東部の、ダイノソー・ナショナル・モニュメントとユインタ山系の地質を中心として、若干の観察を交えて、見学の概略を紹介したい。
詳しくは、こちらから(前編)、(後編)
磁鉄鉱系・チタン鉄鉱系花崗岩の帯磁率の境界値:鬼首カルデラ周辺の例
石渡 明1・佐藤勇輝2・久保田 将2・濱木健成(1東北大学東北アジア研究センター,2東北大学理学部地球惑星物質科学科)
東花崗岩の野外調査に帯磁率計が役立つことは30年以上前からよく知られている(Ishihara, 1979).磁鉄鉱系花崗岩は帯磁率が高く,チタン鉄鉱系花崗岩は帯磁率が低い.帯磁率を表すのに,かつてはcgs単位系のemu (electro-magnetic unit)という単位が使われていたが,現在はmks単位系のSIユニット(Système International d'Unités; 国際単位系)に統一されている.我々が使用しているチェコのGeofyzika社製のKAPPAMETER KT-6も,測定値はSIユニットで表示される.地学団体研究会編「新版地学事典」(平凡社, 1996)の磁鉄鉱系花崗岩とチタン鉄鉱系花崗岩の説明文(石原舜三氏執筆)には,磁鉄鉱系とチタン鉄鉱系の花崗岩の帯磁率の境界として「100×10-6 emu (30×10-3 SI)」という値が与えられている.
詳しくはこちら
地質年代表における年代数値—その意味すること
兼岡一郎(前学術会議地質年代小委員会委員長、元IUGS国際地質年代小委員会副委員長)
IUGS (国際地質学連合)では、ICS(国際層序委員会 )から提案されていたInternational Stratigraphic Chart(地質系統・地質年代表)における Quaternary(第四紀)の始まりの境界を、GelasianとPiacenzianとすることを2009年6月に承認した。その境界の年代数値としては2.588Maとされており、 以前にQuaternary境界として割り当てられていたCalabrian底部の年代数値よりは約78万年古くなっている。わが国でもこの経緯を踏まえて、地質年代 関連分野の各学協会から推薦された委員によって構成された委員会で、国際規約に沿ったQuaternaryの定義などを受け入れることを決め、その件に関して周知徹底が計られた(奥村, 2010など)。しかし、その過程において、地質年代表における年代数値の意味の詳細についての理解が、わが国の研究者間で必ずしも同じではない様子が見受けられた。さらにそうしたことが要因となって生じたと考えられる事例を、私自身の周囲でも経験することになった。そのため、10年前まではICSの中の小委員会のひとつとして存在していたSOG(国際地質年代小委員会)に在籍したことのある立場から、ISCに付された年代数値を利用する人たちが、それらについて的確な取り扱いをされるようにその意味を説明しておきたい。
詳しくはこちら
花崗岩類からの放射線量
石原舜三(産業技術総合研究所)
東日本大震災以降、放射線量への関心が急速に高まっており、花崗岩の放射線量についての執筆依頼を編集部から受け、筆をとった。筆者と放射 線との出会いはこれが2回目である。最初は広島の原爆である。小学校6年生の1945年8月6日朝、爆心地から6km東方の小学校の2階で、B29を目視追跡 していた私は爆裂の閃光を真正面から浴びた。当時、それが原子爆弾によるものとは知る由もなく、5万トンくらいの爆弾であろうかと友達と話しあっ た。その2日後に行方不明者を探しに近所の老婆の手を引いて広島市内に入り、瓦礫を掘り起こした。広島市内は焼け野原であったから、放射性埃など を吸い込む内部被曝の可能性は少なかったであろうが、残留放射能下を歩き続けたことは明らかである。
このような事故的なことを除くと、我々が浴びる自然界の放射能は空から来る宇宙線に由来するものと、地殻の諸岩石の放射性元素(K, Th, U)に起因 するものとに大別される 。
詳しくはこちら
ネガフィルムからポジ画像をデジカメで簡単に作る方法
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
中年以上の研究者は、デジカメ普及以前に撮影したフィルムやプリントの写真を多量にお持ちだと思う。それらをプレゼンなどで使用したい場合、プリントであればスキャナで取り込むのが最も簡単で、高画質のデジタル画像が得られる。しかし、昔のカラープリントは年数の経過とともに褪色・変色していることがあり、もとのネガがあればそれから直接デジタル化した方が美しい画像になる。
詳しくはこちら
人類史上初めて落下の観測とその回収に成功した小惑星
宮原 正明(東北大学理学研究科地学専攻)
皆さんは,2008年10月6日から7日未明(グリニッジ標準時)にかけて,地球の裏側で,人類史上初めての劇的な事件が起きていたことをご存じでしょうか(Jenniskens et al., 2009).事の発端は,米国のある天文台が,名もない小惑星を発見したことに始まります.
詳しくはこちら
新鉱物「千葉石」の発見
高橋直樹(千葉県立中央博物館)
「千葉石(chibaite)」という名前の新鉱物が誕生しました.2011年2月15日付けで論文が公表され(Momma et al., 2011),晴れて世界に認められることになりました.新鉱物の発見自体はそれほど珍しいことではなく,世界では年に約100件,国内でも年に1,2件は発見・記載されていますが,今回は,「千葉石」という名前のためか,新聞やテレビのニュースでも取り上げられ話題になっていることもあり,ここで紹介させていただくことになりました.
詳しくはこちら
日本最古の鉱物 〜37億5000万年前の痕跡〜
堀江憲路(国立極地研究所)
富山県黒部市宇奈月地域の花崗岩中に「日本最古の鉱物」が含まれることが,国立極地研究所・広島大学及び国立科学博物館を中心とする研究グループにより発表された.宇奈月地域は,飛騨帯の東縁部に位置し,含十字石結晶片岩に代表される中圧型変成作用を経験した地域として知られており,また日本列島と韓半島や中国大陸との関係を探る上で鍵となる地域である.
詳しくはこちら
最近、太陽黒点が少ないことについての雑感
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
太陽黒点については、ガリレオ以来すでに約400年の観測の歴史があり、黒点の数は太陽活動の活発さを表す指標として重視されている。黒点数は約11年を周期として増減を繰り返してきた(黒点周期)。黒点数は、多い時(極大期)には100〜200に達するが、少ない時(極小期)はゼロに近くなる。(中略)私は晴天の休日には小さな望遠鏡で黒点観測をしているが、近頃も黒点数ゼロの日が多い。
詳しくはこちら
「はやぶさ」が持ち帰った小惑星「イトカワ」の微粒子分析結果についての雑感
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
2010年11月16日,宇宙航空研究開発機構(JAXA)は,同年6月13日にオーストラリアで回収した小惑星探査機「はやぶさ」のカプセルに含まれていた微粒子1500個以上のほとんどが,小惑星「イトカワ」由来のものであることを確認したとしてプレス発表を行い,大々的に報道された.発表資料によると,確認された鉱物の組合せは,かんらん石,輝石,斜長石,硫化鉄,その他微量鉱物となっていて,普通コンドライト(球粒隕石)のものと一致する. (中略)
しかし,今回の微粒子のSEM-EDS分析結果をプロットした発表資料中のグラフ(図1)については,いくつか問題があるように思う.
詳しくはこちら
地質調査中のトラブル体験記と危険回避術(後編)
広島大学大学院地球惑星システム学科
日本勤労者山岳連盟会員 大橋聖和
調査期間後半ともなると日数を稼ごうと無理をしてしまいがちであるが,悪天候時は安全なルートに変更したり,停滞してデータの整理に当てるなどの余裕が必要である.宿を出る前にはその日の天気予報を必ずチェックしておく........
続きはこちら
地質調査中のトラブル体験記と危険回避術(前編)
広島大学大学院地球惑星システム学科
日本勤労者山岳連盟会員 大橋聖和
先日,日本地質学会富山大会での懇親会で地質調査中の苦労話を紹介させていただいたところ,News誌編集委員長の坂口さんに情報共有のために寄稿してもらえないかと依頼を受けた.個人的にも調査時の安全管理の重要性を近年特に認識するようになったため,適任者かどうか不安もあるが快諾した次第である.以下では,私の調査中のトラブル体験談とともに,小トピックごとに一般的な山での安全術を紹介する.特に地質調査を始めたばかりの学生を対象とするが,ベテランの先輩方にも今一度安全対策を思い直すきっかけになれば存外の幸せである.地質調査のリスクを十分に把握した上で,安全且つ高度な地質調査を目指したい.
続きはこちら
ギリシャ式地震予知に関するEOS誌上での最近の討論について
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
地電流観測に基づくギリシャ式地震予知法は,その創始者3名(P. Varotsos, K. Alexopoulos, K. Nomicos)の頭文字をとってVAN法と呼ばれている.VAN研究グループは,1984年にその地震予知法を世界に公表して以来,現在までギリシャ国内の観測網を維持し,観測と予知を続けてきた.最近,米国地球物理連合(AGU)の連絡誌EOSでVAN法についての討論があったのでここに紹介する.
続きはこちら
アメリカ、アイダホ州Craters of the Moon National Monument and Preserve 完新世火山地帯紹介
小川勇二郎(東電設計)ほか
筆者らは、Maley (2005)のField geology illustratedという書物で、実に美しい火山岩の露頭がアイダホ州にあることを知り、かねがね訪問を策していたが、今回ここを訪ねることができた。日本ではあまり紹介されていない上に、一見の価値があると考え、以下に簡単に紹介する。
続きはこちら
世界自然遺産推薦地「小笠原諸島」
海野 進(金沢大学地球学教室)
小笠原諸島は東京の南1000 kmに点在する古第三紀の火山岩類と活火山を含む第四紀火山からなる島嶼群である.小笠原は「屋久島」,「白神山地」,「知床」に続く4番目の世界自然遺産候補としてユネスコの世界遺産委員会に推薦され,2010年7月に国際自然保護連合(IUCN)の専門家による現地視察が行われた
続きはこちら
宮澤賢治の地的背景を示す地質学史資料
金 光男・山田直利・鈴木尉元・加藤碵一・盛岡科学史資料調査団
2009年7月「予察地質図」ほかの図幅類と多くの貴重な古書籍群が,国 立大学法人岩手大学に所蔵されることが明らかとなった.それらの発見に至るまでの経緯と意義について簡単に報告する.
続きはこちら
ニュージーランドのウェリントン断層 巡検参加報告
川村喜一郎(財団法人深田地質研究所)
ウェリントン市は,ニュージーランドの首都で,北島の南端に位置しており,アルパイン断層は市のすぐ北の海底を通っています.去年,2009年7月15日のニュージーランドのMw = 7.8の地震は,アルパイン断層の南西の南島の南端のFiordlandで発生しています....
続きはこちら
オマーンジオサイトツアー報告
宮下純夫(新潟大学)
新年も明けてまもない2010年1月7日(木),オマーンオフィオライトのワジ・ジジ地域におけるジオサイトツアーが,在オマーン日本大使館とオマーン・日本友好協会の主催の下に開催された.
続きはこちらから
IGCP-511 海底地すべり会議に参加して
川村喜一郎(財団法人深田地質研究所)
11月7から12日にテキサス大学オースチンで,IGCP-511(IUGS-UNESCO's Internat ional Geoscience Programme 511:IGCPは国際地質学会とユネスコの共同国際プログラムにあたる)の第4回国際会議に参加した.
続きはこちらから
赤崩と大井川ー池田宏氏による井川ジオツアーの報告−
川村喜一郎(財団法人深田地質研究所)
写真は,「赤崩(あかくずれ)」と呼ばれる四万十帯の白亜紀の砂岩泥岩互層(写真2)に見られる斜面崩壊である.崩壊斜面は,北斜面に発達しており,地層は南傾斜である.すなわち,崩壊斜面は,受け盤である.受け盤の地層が岩盤クリープによって傾動し,崩壊が進行している.崩壊は数千年以上の長期間に渡って進行していると考えられており,現在も崩壊は進んでいる.崩れた後に赤い水がでることから,「赤崩」と呼ばれているらしい.
続きはこちらから
地球の体温を測って,地球に電気を流す〜海洋研究開発機構,深海調査研究船「かいれい」KR08-10日本海溝航海
川村喜一郎(財団法人深田地質研究所)ほか
平成20年8月18日〜9月11日まで,海洋研究開発機構の深海調査研究船「かいれい」による日本海溝での調査航海(KR08-10)が行われた.この航海では,日本海溝周辺の海底で地殻熱流量を測定することが主な目的であった.さらに,「かいれい」に搭載されている無人探査機「かいこう7000II」を用いて,海底に人工電流を流し,それを海底電位差計で受信する,いわゆる人工電磁探査を海底で行うための実験も行った.
続きはこちらから
有志にて富士山・青木ヶ原巡検
矢島道子(NPO 地質情報・活用整備機構)
2009年4月4日(土)、数日前の天気予報では雨天の情報も出ていたが、久しぶりの好天に恵まれて、日大の高橋正樹さん、金丸龍夫さんを講師に地学教育 委員3名は、富士山・青木ヶ原に巡検にでかけた。地質学会で発行している「たんけんマップ」の第3弾制作を考えての巡検である。
続きはこちらから
南海トラフ地震発生帯掘削計画の国際会議に参加して
宮川歩夢(京都大学大学院工学研究科 博士課程後期2年)
航海後に一堂に会する初めての会議で、日本はもちろんアメリカ・ヨーロッパ ・アジアの各国から研究者が参加し、参加者は総勢78名に上りました.
続きはこちらから
海外便り 台湾より:変成岩の大渓谷巡検
川端訓代(中央大学地球物理研究所・博士後研究員)
台湾東部花蓮には変成岩の渓谷が存在し,こちらは観光地ともなっており,地質を観察する事が容易となっています.昨年,国立中央大学の陳維民先生が学生用に行われた台湾北東部花蓮巡検に参加しました. 巡検の様子を写真を中心にお届けします.
続きはこちらから
第7回地球システム・地球進化ニューイヤースクール参加体験談
宮川和(名古屋大学大学院環境学研究科 博士課程後期1年)
皆さん,ニューイヤースクール(NYS)をご存知でしょうか? NYSは地球科学に関して幅広く見識を深める場として毎年1月に開催されています.学部生や大学院生,若手研究者の集いの場としては,夏の学校や若手会などが良く知られていると思います.NYSは歴史こそ浅いものの,それらとはまた違った,様々な分野の交流の場または広い学問的視野を養う場として大変有意義な機会になっています.本稿では,NYSの紹介を交えながら,私が参加したNYS-7 (2009年1月10日〜11日,東京・代々木)の体験談をご紹介します.
続きはこちらから
淡青丸KT-08-30次航海と鹿児島での火山灰採取
伊藤拓馬(信州大学)
平成20年11月13日から17日にかけて,淡青丸KT-08-30次航海が行われた.本航海の主な研究目的は,遠州灘と熊野灘を調査域として,沿岸域から深海底までの砕屑物の運搬過程を明らかにすることであった.
本航海は,東京台場港を出港して遠州灘と熊野灘で試料採取を済ませた後,鹿児島港に帰港した.また,私たちは下船後に鹿児島市周辺に分布する火山灰の試料を採取した.ここでは,淡青丸航海と鹿児島における火山灰採取の様子の一部を紹介する.
続きはこちらから
アメリカ・カルフォルニア州Panoche Hill巡検に参加して
田阪美樹(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻修士2年)
2008年12月20日,アメリカ・カルフォルニア州Panoche Hillsでカリフォルニア州立大学サンタクルズ校教授. Casey Moore博士案内の巡検が行われました.この巡検は昨年房総・三浦半島で行われた付加体巡検のお返しにAGUミーティング後Casey氏が開いて下さったものです.今回の巡検は天気にも恵まれ,壮大でダイナミックなアメリカの地質を満喫することができました.
続きはこちらから
三陸津波の痕跡と防災〜田老の防潮堤を見学して〜
川村喜一郎(財団法人深田地質研究所)・南澤智美(日本海洋事業)
海洋研究開発機構の深海調査研究船「かいれい」によるKR08-10日本海溝航海が8月18日〜9月11日まで行われた.9月1日〜2日朝にかけて,乗船研究者の入れ替えと荷物の積み込みのために岩手県の宮古港に寄港した.筆者は,少し足を伸ばし,三陸鉄道北リアス線に乗り,宮古駅から3つ目の駅の田老駅で下車した.
田老の街には,巨大な砦を連想させる防潮堤が縦横無尽に張り巡らされているそれらの防潮堤は,二度にわたる巨大な津波が田老の街に押し寄せたことに深く関わっている.
続きはこちらから
ロンドン地質学会「Gravitational Collapse at Continental Margins」に参加して
川村喜一郎(財団法人深田地質研究所)・小川勇二郎(筑波大学)
日本では重力崩壊というと,陸上で見られるような地すべりを初めとして,その規模は,海底においても,数km程度のものが多く,また,それらは現在進行形 のものである.しかし,ContinentalMarginsでの事例は,近年急速に情報がもたらされつつあり,規模が数百kmで,白亜紀に活動したもの が保存されている事例も知られてきた.
続きは、こちらから
手動式ポイントカウンターとエクセルの計数マクロの紹介
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
岩石学、火山学、堆積学などの分野では、岩石薄片の顕微鏡観察により、鉱物(斑晶)、ガラス(石基)、気泡、砕屑粒子などの量比をポイントカウンティングにより計測する作業が普通に行われる.自動式の方が作業は楽だが、経済性と能率を重視し労力を惜しまないに人は手動式も有用である.私はマイクロソフト社の表計算ソフト「Excel」を用いた12成分カウンターのマクロ(Visual BASICプログラム)を作成してみた.
詳しくは、こちら
■マクロのダウンロードとオンラインマニュアルはこちら
MARGINS SEIZE 2008 workshop参加報告 2008.10.7UP
氏家恒太郎(海洋研究開発機構 地球内部変動研究センター)
MARGINS SEIZE 2008 workshop(以下WS)が2008年9月22日〜9月26日に米国オレゴン州のMt. Hoodにおいて開催された。参加者は米国を中心に80名余り。日本からも6名が参加した。このWSは非常にプロダクティブかつ有意義で、日本の地質学関 係者にも多少参考になるかもしれないと感じたので、簡単ではあるが紹介させて頂きたい。
詳しくは、こちら。
学会ホームページにアクセス集中!2008.9.2UP
昨年9月にがらりとリニューアルして以来、たいへんアクセス数が伸びており、皆様には感謝感謝です。ここ最近は1日平均1300人ほどの来訪者があります。これは年間50万人(ページビューなら200万ページ)という勢いです。おそらく地球科学系で国内トップクラスのメディアに成長していると言っても過言ではないでしょう。広報委員会と致しましては、会員の皆様に情報発信プラットフォームとして大いに活用頂けることを強く願っております。
詳しくはコチラから。
坂口有人(広報委員長)
海外便り 〜ウィスコンシン州立大学マディソン校より〜 2008.8.5UP
現在私は日本学術振興会海外特別研究員として、ウィスコンシン州立大学マディソン校に派遣されております。去年の春から2年の予定で、早いものですでに1 年と3ヶ月が過ぎました。
詳しくはコチラから。
橋本善孝
(日本学術振興会海外特別研究員)
ジオパークと “Rock” “Green” “Café”
理事・矢島道子(地質情報整備・活用機構)
日本国内にもジオパークをつくろうという動きが,あちらこちらで少しずつ見られるようになってきました.日本地質学会の中にもジオパーク支援委員会ができました.ジオパークの「ジオ」の部分をよく知悉していて,その知識・情報をジオパーク成立に役立てるのは地質学会会員の仕事と思われます.詳しくはこちら。
三浦・房総半島の付加体巡検に参加して 2008.2.19UP
2月13日から15日にかけて,Kanto Asperity Projectワークショップ参加のため来日したJ. Casey Moore教授(カリフォルニア州立大学サンタクルズ校)をむかえ,ワークショップに先立ち三浦・房総半島の付加体巡検が行われました.詳しくはこちら。
原 勝宏
(静岡大学大学院理学研究科修士課程1年地球科学専攻)
ハロー「ちきゅう」から 2008.2.9UP
IODP Expedition 316 (Thrust Faults)に乗船研究者として参加しました。コアの記載や下船後の研究に関するミーティングなどで慌しい日々が続いている船上の様子を少しご紹介します。詳しくはこちら。
山口 飛鳥
(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻D2)
三浦・房総半島の付加体巡検に参加して
三浦・房総半島の付加体巡検に参加して 2008.2.19UP
静岡大学大学院理学研究科修士課程1年
地球科学専攻 原 勝宏
2月13日から15日にかけて,Kanto Asperity Projectワークショップ参加のため来日したJ. Casey Moore教授(カリフォルニア州立大学サンタクルズ校)をむかえ,ワークショップに先立ち三浦・房総半島の付加体巡検が行われました.案内者は山本由弦さん(産総研),参加者はJ. Casey Moore教授ほか,山口はるかさん(JAMSTEC),平内健一さん(筑波大学),山口飛鳥さん(東京大学),北條愛さん(東京大学),辻智大さん(愛媛大学),原(静岡大学)の7名.
三浦・房総半島南部は伊豆孤の衝突に伴う急激な上昇により,陸上に見られる付加体としては最も若く(6Ma〜4Ma),埋没深度の浅い(1〜2km)部分を見ることのできる世界的に見ても珍しい地域です.三浦・房総半島の付加体は剥ぎ取り付加型で,付加時のデタッチメントスラストの周囲にはスラストユニットと呼ばれる変形帯,その上位は整然層と乱堆積層からなる,という構造が特徴的なスラストシートの積み重なりを見ることができます.今回の巡検は埋没深度の浅い部分から深い部分へ堆積物の変形や物性がどのように変化していくのかを見ることを主なねらいとして,1日目から2日目にかけてはまず,三浦・房総それぞれで見られる埋没深度1kmのスラストユニットを観察し,3日目に房総半島の埋没深度2kmのスラストユニットを観察する,というコースでした.
見学地点ごとに,露頭での産状に加え,定方位サンプルの研磨面,顕微鏡写真の観察,堆積物中の間隙率の変化,磁性鉱物の配列の特徴など様々なデータに基づいた解説がなされ,熱い議論が巻き起こりました.私が特に強い印象を受けたのは,埋没深度によるスラストユニット中の変形の違いです.深度1kmのスラスト沿いでは剪断による非対称な組織が見られますが,それに伴う粘土鉱物の配列が不明瞭です.それに対し,深度2kmのスラスト沿いでは異常なほどの粘土鉱物の定向配列が見られます.そして,スラストに沿って今まさにでき始めた,いわゆる「生メランジュ」を見ることができます.私の研究地域は美濃帯のジュラ紀付加体であり,厚さ1kmを超えるメランジュが主体です.これほど厚い混在岩相がどのような過程で形成されるのかいつも不思議に思っています.ここで見られる「生メランジュ」の幅は非常に薄いものですが,変形組織は美濃帯,また白亜紀付加体である四万十帯などに見られるメランジュそのものです.これほど浅い埋没深度,薄い幅でメランジュができ始めているということは私の研究を進めていく上でも非常に興味深く,房総半島の付加体はまだまだ謎の多いメランジュの形成過程の解明に向けて大きな期待が持てる場所なのだと感じました.
また,今回の巡検で,案内者の山本さんの研究に強い衝撃をうけた思いです.広域かつ詳細なマッピング,丁寧なサンプル採取と処理,様々な分析データ,それらから組み立てられる緻密かつダイナミックな考察.そして参加された皆さんと白熱した議論をする姿勢.驚かされるばかりでした.それと同時に自分の未熟さを痛感しました.しかし,だからこそ私はこの巡検に参加できて本当によかったと感じます.今後の研究に向けて,大きな刺激になりそうです.
今回の巡検は最高の天気に恵まれ,様々な角度から望む富士山にも感動の連続でした.三浦半島で見た海の向こうの富士山を背景とした見事なデュープレックス構造はまさに日本を代表する露頭風景だったのではないでしょうか.そして2日目の夜は,山本さんおすすめの居酒屋での楽しい宴会となりました.実はこのお店に来るのが楽しみで巡検に参加された方もいらっしゃったようですが・・・,なるほど,本当に美味しい料理の数々,私も含めて皆さん感動の連続でした.本当にまた来たいと思ってしまいます.研究に訪れる地域でその土地の味を楽しむことも研究の醍醐味.山本さんのそんな姿勢にも感銘を受けました.
あっという間の3日間でしたが,私の人生において実り多い旅になったと感じています.この道に進んだことに誇りを持ち,もっともっと地球科学を楽しみたいと思います.最後に,今回案内して頂いた山本さん,そして参加された皆さん,本当にお世話になりました.心から感謝申し上げます.
写真:巡検参加者(左から辻智大,山口飛鳥,原勝宏,J. Casey Moore,山口はるか,山本由弦,平内健一)
地質マンガ-目次
地質マンガ
マンガをクリックすると4コママンガが閲覧できます。
「どっちもポットール」
(原案:chiyodite マンガ:KEY)
「地質マンガの宿題」
(原案:chiyodite マンガ:KEY)
「ふん化石のいろいろ」
(原案:chiyodite マンガ:KEY)
「GEOって!?」
(原案:土岐知弘 マンガ:KEY)
「空から見れば」
(原案:chiyodite マンガ:KEY)
恋する地質学②「彼女より壁ドン?」
(原案:本郷宙軌 マンガ:KEY)
「大学でも全裸に見えるポーズがあるんです!?」
(原案:土岐知弘 マンガ:KEY)
恋する地質学①
「彼女のために地質学?」
(原案:本郷宙軌 マンガ:KEY)
「地学系よくある勘違い」
(原案:本郷宙軌 マンガ:KEY)
「楽しみのリサイクル」
(原案:chiyodite マンガ:KEY)
「ハンマーの行方」
(原案:chiyodite マンガ:KEY)
「デジタル派vsアナログ派」
(原案:chiyodite マンガ:KEY)
「青春の伝説」
(原案:本郷宙軌 マンガ:KEY)
「統合国際深海掘削計画IODPで活躍するプラットフォームたち」
(原案・マンガ:黒田潤一郎)
「包丁は必要」
(原案:川村喜一郎 マンガ:KEY)
「ルーツ」
(原案:坂口有人 マンガ:key)
「水戸大会に行こう」
(原案:星 博幸 マンガ:KEY)
「無酸素じゅげむ」
(原案・マンガ:黒田潤一郎)
「タイムスケール」
(原案・マンガ:黒田潤一郎)
「やるやる さぎ」
(原案・マンガ:key)
「巡検 あるある」
(原案・マンガ:黒田潤一郎)
「巡検に行こう!」
(原案:星 博幸 マンガ:key)
「学会に行ってみると」
(原案:坂口有人 マンガ:key)
「ロトウに迷う」
(原案:chiyodite マンガ:key)
「富山大会に行こう!」
(原案:星 博幸 マンガ:key)
「晴れ男」
(原案:川村喜一郎 マンガ:key)
「雨男」
(原案:川村喜一郎 マンガ:key)
「卒論練習」
(原案:橋本善孝 マンガ:key)
「調査後のカニの味は」
(原案:木村 学 マンガ:key)
「スケールプロトラクター」
(原案:川村喜一郎 マンガ:key)
「選挙管理委員会」
(原案:川村喜一郎 マンガ:key)
「地すべり調査」
(原案:坂口有人 マンガ:key)
「人間行動学的古生物学」
(原案:川村喜一郎 マンガ:key)
「津波は大丈夫かね」
(原案:川村喜一郎 マンガ:key)
「鬼の洗濯板」
(原案:本郷宙軌 マンガ:key)
「ギョーカイ岩って」
(原案:千代田厚史 マンガ:key)
「穿孔貝って」
(原案:chiyodite マンガ:key)
「テストの日」
(原案:坂口有人 マンガ:key)
「木目とクロスラミナ」
(原案:川村喜一郎 マンガ:key)
「食べられません」
(原案:木村英人 マンガ:key)
「岩石の色」
(原案:川村喜一郎 マンガ:key)
「海には危険がいっぱい」
(原案:木村英人 マンガ:key)
「エアロゾルってなに?」
(原案:古谷浩志・鄭進永・川村喜一郎 マンガ:key)
「船酔いはつらいよ」
(原案:川村喜一郎・不破裕司 マンガ:key)
「ラップ百万回」
(原案:吉田弘和・川村喜一郎 マンガ:key)
「薄片道」
(原案:向吉秀樹 マンガ:key)
「地質学は理系?文系?」
(原案:川村喜一郎 マンガ:Key)
「小学生の会話」
(原案:山口耕生 マンガ:key)
「新婚旅行」
(原案:向吉秀樹 マンガ:Key)
「巡検初参加」
(原案:本郷宙軌 マンガ:key)
「ある日の海外調査」
(原案:RSH猫 マンガ:key)
「生痕」
(原案:川村喜一郎・金松敏也 マンガ:key)
「調査日和」
(原案:清川昌一 マンガ:key)
「遭遇したくないもの」
(原案:山口はるか マンガ:key)
「地質学の彼氏を持つと」
(原案:山口飛鳥 マンガ:key)
「学会に行こう」
(原案:柴田伊廣 マンガ:key)
「何の調査?」
(原案:柴田伊廣 マンガ:key)
「そして帰港」
(原案:坂口有人 マンガ:key)
「ハンマーのためなら」
(原案:某Y大学教授 マンガ:key)
「正月のごちそう」
(原案:坂口有人 マンガ:key)
「船なのに」
(原案:坂口有人 マンガ:key)
「ちきゅうはゆれない」
(原案:坂口有人 マンガ:key)
「サンプルリクエスト」
(原案:坂口有人 マンガ:key)
「ちきゅうに乗りたい」
(原案:坂口有人 マンガ:Key)
「乗船」
(原案:坂口有人 マンガ:Key)
「堆積岩」
(原案:山口はるか・マンガ:Key)
「変成岩」
(原案:山口はるか・マンガ:Key)
「フィールド調査」
(原案:坂口有人・マンガ:Key)
「巡検」
(原案:坂口有人・マンガ:Key)
「geo-flash*の正しい使い方」
(原案:倉本真一・マンガ:Key)
「geo-flash*とんだ間違い」
(原案:倉本真一・マンガ:Key)
*geo-flash:地質学会会員専用のメールマガジン
この4コママンガの原原案を募集中です。投稿はこちらから。
【geo-Flash】No.438(臨時)中沢圭二 名誉会員 訃報
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.438 2019/1/16┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 中沢圭二 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
中沢圭二 名誉会員(日本地質学会元副会長,京都大学名誉教授)が、平成31
年1月15日(火)早朝にご逝去されました(97歳)。
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
通夜ならびに告別式は、下記のとおり執り行われますので併せてお知らせ申し
上げます。なお,御香典,御供花,御供物の儀はご辞退されるとのことです。
お通夜:1月17日(木)午後6時より
告別式:1月18日(金)午前10〜11時
場 所:公益社 北ブライトホール
〒603-8158 京都市北区紫野宮西町34 Tel: 075-414-0420
喪 主:小林純子様(長女)
会長 松田博貴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
*************************************************************************************
[追記]メルマガ配信後,ご葬儀については「家族葬」にて執り行われ
るというご連絡ありましたので,追記させていただきます。(2019/1/17追記)
地質マンガ 恋する地質学① 彼女のために地質学?
地質マンガ
恋する地質学①
彼女のために地質学?
原案:本郷宙軌 マンガ:KEY
解説文
鹿児島県喜界島(きかいじま)はチョウの「オオゴマダラ」や「アサギマダラ」などで有名ですが,この島は年平均2mmの速度で隆起したサンゴ礁で出来ており,地学的にとても興味深いところです.標高約200mの百之台(ひゃくのだい)では最終間氷期(約12.5万年前)のサンゴの化石などが産出し(大村1988,写真1).標高数mの海岸には数千年前のサンゴなどが良好な状態で保存されています(写真2).また,隆起速度が大きいので,海水準が数十m低下していた氷期の頃のサンゴも露頭にて観察することができます.ウラン系列年代と電子スピン共鳴(ESR)年代によって40万年前の化石も産出することが明らかとなっています(例えば,大村1988).そのため,これまで多くの研究者がこの島を訪れ,様々な研究(例えば,地震の履歴復元や海面変動復元,古水温復元など:南條ほか2013など)が行なわれてきました.
今年の夏は喜界島の露頭を観察しに行ってみましょう.地質学に興味が無かった学生の皆さんも観察に行ってみましょう.きっと,面白い!
写真1 百之台からみた離水サンゴ礁.
写真2 化石サンゴ(テーブル状)
引用文献
大村明雄(1988)地質学論集 29:253‒268
南條貴志, 佐々木 圭一, 松田博貴(2013)地質学雑誌 119:155‒170
geo-Flash No.292(臨時)杉並区立科学館実質閉館に
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.292 2015/3/27 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】杉並区立科学館が実質閉館に!
【2】ジャーマンウィングス航空機が墜落したアルプス山中
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】杉並区立科学館が実質閉館に!
──────────────────────────────────
東京都杉並区立科学館が、行政改革の一環で4月から指導員不在となり、
事実上「閉館」となることが決まりました。同科学館は、学校外の科学教
育の先駆けとなったことで有名で、ノーベル物理学賞受賞者の小柴昌俊さ
んが名誉会長を務めています。
区民や学術団体からは存続を求める声が多く寄せられ,地質学会から
も「杉並区立科学館の維持・発展に関する要望書」(2014年2月提出)を出
しましたが、区としては老朽化などを理由に2015年度末で施設を廃止し、
跡地に特別養護老人ホームの整備を検討しているとのことです。
学会が提出した要望書は,HPに掲載しています。
http://www.geosociety.jp/engineer/content0036.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】ジャーマンウィングス航空機が墜落したアルプス山中
─────────────────────────────────
テレビ・新聞等のマスコミによる報道でご存知の方も多いと思いますが、
フランス南東部のアルプス山中でドイツのジャーマンウィングス航空の旅
客機が墜落しました。生存者の見込みはないということで、乗員・乗客の
皆様のご冥福をお祈りいたします。
テレビの映像で見ると、真っ黒い岩石が露出する急峻な山の斜面に墜落
したようで残骸が散乱しています。場所は、Digne-les-Bainsと
Barcelonetteのほぼ中間地点とのことです。この黒い地層は、当地域に詳
しい研究者によると恐らくTerres noires(テル・ノアール、黒土)と呼
ばれるジュラ紀のBathonian–Oxfordianの泥灰岩(石灰質泥岩)であろう
ということです。地質学会員の皆様の中には、ご興味を持たれる方もおら
れるかということでお知らせ致します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
地質マンガ 巡検
地質マンガ
「巡検」
作:坂口有人 画:Key
地質巡検とは、地表に顔を出している地層や岩体(露頭と呼びます)を実際に見に行く野外実習のことです。良く調査されていて、わかりやすく、すばらしい露頭に案内してもらえるので感動です。でも授業の一部なのです。
戻る|次へ
地質マンガ geo-flashとんだ間違い
地質マンガ
(作:倉本真一・画:Key)
戻る|次へ
地質マンガ geo-flashの正しい使い方
地質マンガ
(作:倉本真一・画:Key)
次へ
No.0022 2008/2/19 geo-Flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.022 2008/02/19 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】地質学雑誌新表紙デザイン 募集中!
【2】地質マンガ:「巡検」・「フィールド調査」
【3】コラム:三浦・房総半島の付加体巡検に参加して
【4】学生・院生・ポスドク就職支援WGメンバー募集中!
【5】IODP DRILLS in 東大 (セミナーのお知らせ)
【6】IGCオスロのアブストラクト締め切りが2月末に延長!
【7】第4回IGCP516「東南アジアの地質学的解剖:東テーチスの古地理と古環境」
【8】平成20年度高知大学海洋コア総合研究センター全国共同利用研究公募
【9】地質調査総合センター第10回シンポジウム
【10】地震予知総合研究振興会 嘱託職員(非常勤)募集
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】地質学雑誌新表紙デザイン 募集中!
──────────────────────────────────
公募締切:2008年3月31日(月)
「地質学雑誌」は2009年1月号から表紙のデザインを一新する予定です。
つきましては会員、非会員のみなさまから、学会の新しいイメージを反映した
斬新なデザインを公募します。採用デザインには、賞金5万円を進呈します。
たくさんのご応募、お待ちしております。
応募の詳細は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0050.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】地質マンガ:「巡検」・「フィールド調査」
──────────────────────────────────
詳しくは、http://www.geosociety.jp/faq/content0057.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】コラム:三浦・房総半島の付加体巡検に参加して
──────────────────────────────────
2月13日から15日にかけて,Kanto Asperity Projectワークショップ参加のため
来日したJ. Casey Moore教授(カリフォルニア州立大学サンタクルズ校)をむか
え,ワークショップに先立ち三浦・房総半島の付加体巡検が行われました.
原 勝宏( 静岡大学大学院理学研究科修士課程1年地球科学専攻)
詳しくはhttp://www.geosociety.jp/faq/content0056.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】学生・院生・ポスドク就職支援WGメンバー募集中!
──────────────────────────────────
地質学会では、学生就職支援活動の第一歩として、昨年の札幌大会において企業
説明会を開催したところ、大変好評でした。そして説明会のおかげで就職の話が
まとまったとの報告も受けています。そこで地質学会理事会としては、就職支援W
Gを設置し、就職支援活動を学会大会時だけでなく、日常的な取り組みとして多面
的に進めることにしました。しかし、理事会だけでは人材不足です。学生・院生・
ポスドクの就職支援には、どうしても若手の会員諸氏の御協力が必要です。パー
マネントな職を得ている若手会員の皆さん、同じ世代の仲間達や後輩のためにWG
のメンバーになってください。メンバーとなって下さる方は、電子メールのSubje
ctに「就職支援」と書いて、地質学会事務局(main@geosociety.jp)にご連絡願
います。第1回目のWGは参加メンバーの御都合をうかがった上で3月中に開催す
る予定です。ぜひ会員による、会員のための活動、特に若手へのご支援をお願い
申し上げます。
就職支援担当: 伊藤谷生(副会長)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】DRILLS セミナー 日本で開催!
──────────────────────────────────
DRILLS (Distinguished Researcher & International Leadership Lecture
Series)はIODPが主催する講師派遣型のレクチャーシリーズです。
今回はミシガン大学名誉教授のTed Moore博士(古海洋・堆積学)が来日され、
海底掘削から見えてくる地球の気候変動の歴史と未来予測をテーマにした講義が
東大で行われます。また、昨年秋に開始した地球深部探査船「ちきゅう」による
南海掘削について、下船されたばかりの木村学教授(理学研究科)にお話いただ
きます。
日時 3月6日(木) 15時〜
場所:理学部3号館320号室
http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_06_03_e.html
プログラム
15:00 開催あいさつ
15:10-16:10 Ted Moore氏講義 "The Warm Earth as We Know It"
16:10-16:25 IODP関連ビデオ上映
break
16:30-17:10 木村学氏講義"ちきゅう深部への夢に駆り立てられてー南海地震発生帯掘削ー
17:10 終了
17:30~19:00 懇親会
ウェブサイト:http://ofgs.ori.u-tokyo.ac.jp/~ofgs/IODP_DRILLS/
問い合わせ先:東大海洋研 沖野(okino@ori.u-tokyo.ac.jp)
Ted Moore博士によるDRILLSセミナーは、東大以外でも開催されます。
日程:
3月1-2日:北海道大学(IODPキャンペーンと同時開催)
3月4日:九州大学
3月9-10日:京都大学(IODPキャンペーンと同時開催)
詳しくは以下のサイトをご覧下さい。
http://www.j-desc.org/oshirase/events/DRILLS.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】IGC(オスロ)のアブストラクト締め切りは2月末(締め切り延長)!
──────────────────────────────────
オリンピックの年に開催される第33回万国地質学会(International geologic Con
gress).今年はオスロで,日程8月6日-14日です.
今回の大会の巡検は,スカンジナビア半島を中心に,アイスランド,グリーンラ
ンド,ウクライナ 等まで!
abstract submissions 締め切り 2月29日(金) 24:00
(たぶん,日本時間ではないと思います)発表1件あたり40ユーロ.
Registration:4月15日までなら560ユーロ(全日程),410ユーロ(前半又は後半).
(学生はそれぞれ160,110ユーロ)4月15日以降は少し高くなります.
詳細および申し込みは,http://www.33igc.org/coco/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】第4回IGCP516「東南アジアの地質学的解剖:東テーチスの古地理と古環境」シン
ポジウム
──────────────────────────────────
IGCP516 (Geological Anatomy of East and South Asia: Paleogeography and
Paleoenvironment in Eastern Tethys)の第4回シンポジウムが,タイ国のバンコ
クで行われます.今回は,チュラロンコン大学理学部地質学教室創立50周年シン
ポジウムと共催で行われ,東南アジアにおける層序・テクトニクス・構造地質・
堆積学・鉱床学・古地磁気学・古地理学・古生物・古海洋学・環境地質など,幅
広い分野のトピックを募集しています.またタイとカンボジアの古生界や付加体,
昨年11月にオープンした東南アジア最大の恐竜博物館(Sirindhorn Museum:地質
NEWS vol. 10, no. 10, p. 10に紹介記事掲載あり)への巡検が計画されています.
日程:2008年11月20日〜12月1日
プレ巡検:11月20〜23日
A1:タイ西部の先カンブリア系〜第三系とAkara金鉱床.
A2:タイ北東部コラート高原の中生界と恐竜博物館(Sirindhorn Museum).
シンポジウム:11月24日〜26日.
ポスト巡検:11月27日〜12月1日
B1:タイ東部とカンボジアの古生界と付加体.
アブストラクトの締め切り:8月15日
連絡先:
IGCP516事務局:原 英俊(産総研)
e-mail: hara-hide@aist.go.jp
タイの事務局:Dr. Thasinee Charoentitirat(Chulalongkorn University)
e-mail: ctitima2005@yahoo.com
詳しくは、http://staff.aist.go.jp/hara-hide/igcp516
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】平成20年度高知大学海洋コア総合研究センター全国共同利用研究公募
──────────────────────────────────
高知大学海洋コア総合研究センターは、海洋コアの総合的な解析を
通じ、地球掘削科学に資する研究を推進するため、センターの施設・
設備を共同利用に供します。この度、平成20年度に実施する研究
課題を公募しますので、皆様にお知らせいたします。
公募要領、申請書様式、主要設備一覧等、詳しくは下記ウェブペー
ジ内に掲載しておりますのでご参照下さい。
高知大学海洋コア総合研究センターホームページ:
http://www.kochi-u.ac.jp/marine-core/index.html
申請書提出期限:平成20年2月29日(金)
申請書提出・お問い合わせ先:
高知大学海洋コア総合研究センター 全国共同利用事務局
ADDRESS: 〒783-8502 高知県南国市物部乙200
TEL: 088-864-6712 FAX: 088-864-6713
E-MAIL: core-kyodo@kochi-u.ac.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】地質調査総合センター第10回シンポジウム
──────────────────────────────────
地質リスクとリスクマネージメント—地質事象の認識における不確実性とその対
応—
開催趣旨:地質調査においてはボーリングの本数や各種調査の量は有限であり、
そのため地質事象の認識における不確実性が存在し、様々なリスクの要因となる。
石油や鉱物資源探査分野では資源探査の経済性評価の点から、そのような地質リ
スクを定量的、定性的に取り扱うリスクマネージメントが行われている。トンネ
ル工事等における応用地質分野でも地質に起因するリスクの議論が活発になって
いる。今回、全地連の地質リスク海外調査の成果と地質に関連するリスクマネー
ジメントの現状を議論し、さらに地質リスク逓減に貢献する地質情報整備の意義
を討論する。
日時:2008年3月11日(火)13:00-17:15
場所:秋葉原ダイビル5階カンファレンスフロア 5B会議室
主催:産総研地質調査総合センター・産学官連携部門、
(社)全国地質調査業協会連合会、地質地盤情報協議会
定員:130名 参加費:無料
お問い合わせ:(独)産業技術総合研究所地質調査総合センターシンポジウム事
務局 gsjsympo10@m.aist.go.jp
http://www.gsj.jp/Event/080311sympo/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】地震予知総合研究振興会 嘱託職員(非常勤)募集
──────────────────────────────────
地震予知総合研究振興会では嘱託職員(非常勤)を募集しています。
資格は地球物理学、構造地質学、地理学等の履修者で
出勤日は週に2日〜3日で、業務は活断層関係の会議の議事録作成や資料作成等です。
詳細は下記のホ−ムペ−ジを参照して下さい。4月1日からの採用を予定しています。
(応募締め切りは2月15日となっていますが、現在も募集中です)。
http://www.adep.or.jp/ERCBoshu/boshu080124.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質マンガ フィールド調査
地質マンガ
「フィールド調査」
作:坂口有人 画:Key
大学の卒業論文などでは学生が自分でプランを立てて調査に行くことができます(教室の方針によりますが)。駆け出しの学生であっても調査段階から自分でアレンジできるというのはたいへんな魅力です。新発見の予感に引き寄せられて出かけてしまいます。
戻る|次へ
No.0023 2008/3/4 geo-Flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.023 2008/03/04 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】東レ科学技術研究助成に加藤泰浩氏(東大)決定!
【2】第2回国際地学オリンピック参加者募集に354名応募!
【3】シンポ「五島列島と地球の歴史」 自然に残されたタイムカプセルの探求
【4】「カタカナ英語本」の紹介
【5】地質マンガ「堆積岩」「変成岩」
【6】ノーザン・イリノイ大学銃乱射事件に学ぶ日本の危機管理
【7】地質学雑誌 表紙デザイン応募状況
【8】地質の日関連行事:宮澤賢治ジオツアー
【9】国際恐竜シンポジウム2008「アジアの恐竜研究最前線」
【10】地域連携シンポジウム:茨城県の湖沼環境をめぐって
【11】8th International Scientific Conference SGEM2008
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】東レ科学技術研究助成に加藤泰浩氏(東大)決定!
──────────────────────────────────
本会から推薦された加藤泰浩 会員(東大)が、東レ科学技術研究助成を受領
することが決定しました。研究課題は、「同位体を指標とする固体地球の応
答の解明」です。
授賞式は3月17日に開催される予定です。以下に研究の抱負を加藤会員から
いただきました。
日本地質学会からご推薦いただき、東レ科学
技術研究助成を受けることになりました。こ
の助成は,物理、生物(医学)、化学などの
あらゆる研究分野から推薦された研究者間で
争われるものであり、今回受賞できたことは
研究者として非常に光栄なことです。私の研
究テーマは,「大気CO2濃度の上昇に対する
固体地球の応答の解明」というものです。百
万年を超えるタイムスケールでは、大陸地殻
を構成するケイ酸塩鉱物の化学的風化作用が
大気CO2濃度をコントロールしていると考え
られていますが、それよりも短いタイムスケ
ールでも固体地球の応答が起こっている可能
性があります。1万年ー10万年で寒冷と温暖を繰り返した第四紀の海底堆積物中
のOs (オスミウム)同位体比組成を解析することにより、固体地球の応答のタイ
ムスケールを解明できると考えています。それにより、大気CO2問題に対して我
々人類が対処すべきタイムスケールが明らかになるはずです。
加藤泰浩(東京大学)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第2回国際地学オリンピック参加者募集に354名応募!
──────────────────────────────────
2008年8月31日から9月7日までフィリピンで開催される第2回国際地学オリンピッ
クに派遣する高校生日本代表団4名を選抜するための試験(国際地学オリンピッ
ク日本委員会主催、地球惑星科学連合共催)に、日本全国から354名の応募があ
りました(25都道府県の44高等学校・中学校)。この354名の中には、中学3年
生が15名、チャレンジする中学2年生4名なども含まれています。
地学オリンピック事務局では予想をはるかに上回る応募に嬉しい悲鳴をあげて
おり、参加賞として用意していたボールペンを急遽追加注文することになりま
した。なお一次選抜として3月16日に在籍高校で筆記試験が実施され約20名が、
二次選抜として5月31日に東京大学で実技試験と面接試験が実施され4名が選抜
される予定です。そして7月下旬の箱根合宿研修を経て、フィリピン大会に臨み
ます。日本地質学会は、国際地学オリンピック日本委員会の協賛団体です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】「五島列島と地球の歴史」 自然に残されたタイムカプセルの探求
──────────────────────────────────
Projact A 第9回シンポジュームin Goto Island
公開講演会 「五島列島と地球の歴史」 自然に残されたタイムカプセルの探求
日時 3月7日 18:30-20:30
場所 五島市福江文化会館 3F 展示室
参加料 無料 (中学生・高校生・一般の方々)
共催 九州大学掘削研究リサーチコア・五島市教育委員会
(講演)
1)「地球科学からみた「日本で暮らす」ということ」
茨城大学教育学部 准教授 伊藤孝 (NHK教育テレビ高校講座講師)
2)「五島列島の生い立ち」
九州大学地球惑星科学部門 修士2年 長谷川孝宗
3)「深海掘削船 ちきゅう」乗船と五島列島の地質から学んだこと
マリンワークジャパン 海洋観測船研究支援員 安永 雅
4)「五島列島は何歳ですか?:地球の「人生」を考えよう」
九州大学地球惑星科学部門 講師 清川昌一
お問い合わせは、
清川昌一(九州大学地球惑星科学部門)
Tel. 092-642-2666
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】 カタカナ英語本の紹介
──────────────────────────────────
金沢大学理学部 石渡 明
このメルマガの1〜3号で,筑波大学の小川勇二郎先生が国際学会などにおける
英語の話し方について,とてもタメになるお話を書かれていますが,今年になっ
て,日本人特有の訛りがある「カタカナ英語」でも,十分に通じさせることがで
きる話し方の要領を,懇切丁寧に説明した本がブルーバックスから出ました.こ
れから世界で活躍しようとする日本の若い地質家に役立つ内容の本だと思うので,
ここに紹介します.
池谷裕一
「怖いくらい通じるカタカナ英語の法則 ネイティブも驚いた画期的発音術」
講談社ブルーバックス,B-1574.2008年1月20日第1刷発行.
1,000円+税.
そこでまずクイズですが,カッコ内の状況で次のように発音すると米国人によく
通じるそうです.さて,何と言っているのでしょうか.答えはすぐ下にあります.
(1)(知人に出会った時) はぜ(鯊)ゴン!【ハゼゴン】
注:相手は怪獣? 魚の化け物? 単なるニックネーム?
(2)(隣席の友人に) 悪酔い天下暴れ!【ワルユーテンカバウレッ】
注:酒癖が悪い迷惑者には勇気を持って直言しましょう.
(3)(ちょっと失礼する時) 赤ブラ目熱 【アカプラメネツ】
注:凝視するとセクハラになります.でもその色はちょっと・・・
(4)(動物園で係員に) 春愛月と万桁魚 【ハルアイゲットゥマンケタウオ】
注:土産物のお菓子とオモチャを探している?
(5)(観光地で他人に) 健乳帝 河白猪 【ケニュテイカワペクチョ】
注:胸が立派な外国の女帝ですが,水浴好きのある動物のような・・・
(「白」は韓流に発音します)
以上ですが,おわかりになりましたか.(1)と(2)はこの本にそのまま出て
いますが,(3)〜(5)はこの本の内容をもとにして,私が漢字表記などを考
えました.状況や注は私がつけたものです.正答は以下の通りです.
(1)How is it going? (元気かい?)
(2)What do you think about it ? (どう思う?)
(3)A couple of minutes. (ちょっと待ってて)
(4)How do I get to Monkey Tower? (サル山へはどう行きますか?)
(5)Can you take our picture? (写真を撮ってくれませんか?)
要するに,学校式発音でスペル通りに棒読みしても通じず,自分が発する言葉を
理解してもらうにはリズムや気合い・間合いが大切ということだと思います.
この本の著者は脳科学者で,米国に行って言葉が通じずにご自身が大変苦労され
た経験に基づいて,この本を執筆されたそうです.絶望の中に一条の光を見た軌
跡(奇跡?)とのことです.単行本は3年前に出たそうですが,今回それが新書
になりました.発音練習用の8 cm CD付きです.著者の奥さんとネイティブの女性
が録音しています.日本人はなぜ英語ができないかという問題に関する脳科学的
解説もあります.是非ご一読をお勧めします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質マンガ:「堆積岩」・「変成岩」
──────────────────────────────────
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/faq/content0057.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】ノーザン・イリノイ大学銃乱射事件に学ぶ日本の危機管理
──────────────────────────────────
アメリカ、イリノイ州デカルブにあるノーザン・イリノリ大学で2月14日午後
3時(日本時間15日午前6時)に元学生による銃乱射によって、学生5名が死亡、
16名が負傷、犯人は自殺という、痛ましい事件が報道されました。この事件は
地質学の講義中に発生した事件で、地質学を学ぶ若き命が無惨にも銃という武
器によって、突然絶たれてしまったことは、痛恨の極みであります。同大学地
質学教室は私がポストドクで3年過ごした所で地質学関係の知り合いが何人か
おり、これまでに伺った状況を報告させていただくと同時に、被害に遭われた
方々やそのご家族へのお悔やみ、再発防止、精神的な支援の必要な方々へのお
見舞いといたします。
事件は「地質学104」の授業が大教室で行われていた時に起こりました。講義
をしていたのは地質学教室の大学院生、TAも同じく地質の大学院生でした。
講師の院生は肩から上腕部を撃たれたが、大事に至っていません。TAは複数
回撃たれたが意識を失うことなく自力で大講義室から歩いて出たそうです。幸
い2人とも回復の見込みですが、地質学の講義を受けていた学生が5名亡くなっ
たのは報道された通りです。地質学教室の教室主任,Jonathan Berg教授(変成
岩岩石学,南極調査など)は、学生からの電話連絡を受け、半信半疑で現場に
かけつけ、頭から血を流して道路にしゃがみ込んでいる学生を見つけて、連絡
が嘘でなかったことを知りました。その時点で既に救急車とパトカーが到着し、
数十分後に彼が現場から教室に戻る時にはパトカーが100台は集結したそうです。
副学長や他の教員もすぐに現場に現れ、学生を避難させ、カウンセリングを開
始したと聞き、対応が素早く、かつ適切に行われたと感じました。当時,地質
学教室事務室は安否を尋ねる学生でごった返していたそうですが、携帯メール
のリレーが安否確認に役立ったということです。教職員は翌週火曜日に仕事に
戻り、精神的な問題を抱えた学生をどのように対処するかという実習を受け、2
月の最後の週から再開する授業に備えたようです。教室主任のBerg教授のもと
には全国から労りのメールが殺到し、同州の大学教員からは授業を代わって教
えて良いという申し出までもあったそうです。
昨年4月16日に銃乱射事件で33名が亡くなったバージニア工科大学からのもの
を始め、数多くのメールに励まされたといいます。危機管理体制については今
後の評価にゆだねるとしています。社会状況は異なりますが、日本の大学での
危機管理方策について、あらためて考えさせられる出来事でありました。
長谷中利昭(熊本大学)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】地質学雑誌 新表紙デザインの投稿状況
──────────────────────────────────
「地質学雑誌」の新表紙デザインを募集中です。今月末が締切ですが、現在ま
での応募数はまだ数点のみです。会員、非会員のみなさまから、学会の新しい
イメージを反映した斬新なデザインを募集します。採用デザインには、賞金5万
円を進呈します。たくさんのご応募、お待ちしております。なお2009年1月号
から表紙のデザインを一新する予定です。
応募の詳細は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0050.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】地質の日関連行事:宮澤賢治ジオツアー
──────────────────────────────────
GUPIでは地質の日を記念して、宮澤賢治ツアーを企画しました。
主催 (NPO) 地質情報整備・活用機構(GUPI)
日程 2008年5月17日(土)〜18日(日)(定員になり次第締切)
案内 加藤碵一(産業技術総合研究所)
詳しくは、http://www.gupi.jp/kenji/kenji-tour.pdf
GUPIの宮澤賢治ジオツアーのページもご参照下さい。
http://www.gupi.jp/kenji/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】国際恐竜シンポジウム2008「アジアの恐竜研究最前線」のお知らせ
──────────────────────────────────
福井県立恐竜博物館では、中国、韓国、モンゴル、ロシア、タイ、カナダ、
日本から第一線の研究者を招き、シンポジウム「アジアの恐竜研究最前線」を
開催いたします。皆様の御参加をお待ちしております。
主 催:福井県立恐竜博物館
日 程:2008年3月22日(土) 10:00〜16:00 シンポジウム
23日(日) 13:00〜16:00 普及講演、パネルディスカッション
会 場:福井県立恐竜博物館 講堂
(福井県勝山市村岡町寺尾51-11 URL: http://www.dinosaur.pref.fukui.jp/)
発表者:董枝明、季強、呂君昌、金幸生、彰光照、李大慶、 Yuong-Nam Lee、
Rinchen Barsbold、Ivan Bolotsky、 Varavudh Suteethorn、Philip Currie、
Eva Koppelhus、冨田幸光、藤田将人、東洋一、柴田正輝
参加費:無料
申 込:不要
その他:日本語と英語での同時通訳を提供します。
問合先:福井県立恐竜博物館
野田芳和 y-noda@dinosaur.pref.fukui.jp
一島啓人 hiroto.ichishima@dinosaur.pref.fukui.jp
詳しくは、http://www.dinosaur.pref.fukui.jp/sympo/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】茨城大学・霞ヶ浦環境科学センター地域連携シンポジウム
──────────────────────────────────
茨城県の湖沼環境をめぐって
ー市民とともに考える霞ヶ浦の環境の保全と利用ー
日時:2008年3月18日(火)13:00〜16:30
場所:茨城県立図書館 視聴覚ホール
茨城大学・茨城県霞ケ浦環境科学センター・茨城県立図書館・茨城新聞社
協賛:IYPE日本(国際惑星地球年日本)・日本地質学会関東支部・NPO法人 地質
情報整備・活用機構
プログラム
1.あいさつ :菊池龍三郎(茨城大学学長)
2.趣旨説明 :天野一男(茨城大学理学部教授)
3.2007年度連携活動報告
・茨城大学:田切美智雄ほか
・茨城県霞ケ浦環境科学センター:山本哲也ほか
・産業技術総合研究所:納谷友規
4.市民とともにめざす霞ケ浦の環境の保全と利用
(1)茨城大学と茨城県霞ケ浦環境科学センター連携による教育活動の可能性:前
田 修(茨城県霞ケ浦環境科学センター・センター長)
(2)自然を生かした地域活性化へのチャレンジ−茨城大学学生地域参画プロジェ
クトの成果−:小峯慎司(茨城大学理学部4年)・松原典孝(茨城大学理工学研究
科博士後期過程3年)・地質情報活用プロジェクトチーム
(3)地域から世界への情報発信−ジオパークと霞ケ浦大学構想−:天野一男(茨
城大学理学部教授)
(4)霞ヶ浦の環境保全と地元紙の役割:沼田安広(茨城新聞水戸支社編集部長)
(5)農業・地域と結ぶ霞ケ浦:太田寛行(茨城大学農学部教授)
5.総合討論(司会:天野一男)
6.閉会の辞:前田 修
問い合わせ先
茨城大学理学部地球環境科学コース
TEL:029-228-8390(天野一男)FAX:029-228-8405
e-mail:kazuo@mx.ibaraki.ac.jp
茨城県霞ケ浦環境科学センター
TEL:029-828-0963(水環境研究室) FAX:029-828-0963
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】8th International Scientific Conference SGEM2008
──────────────────────────────────
日程 2008年6月16日(月)〜20日(金)
場所 Albena Complex Bulgaria
参加登録 3月15日までに登録するとで5%割引になります。
詳しくは、http://www.sgem.org/index_eng.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質マンガ 堆積岩
地質マンガ
「堆積岩」
(作:山口はるか 画:Key)
戻る|次へ
地質マンガ 変成岩
地質マンガ
「変成岩」
(作:山口はるか 画:Key)
戻る|次へ
間違いだらけの発音選び
間違いだらけの発音選び
筆者は,かつて「間違いだらけの発音選び」なる内容の一文を,地質学雑誌のニュース誌に投稿したが,反響はほとんどなかった。その後も,内外の学会やシンポジウムで,気になる発音や使用法に気を止めていたが,一向に改善の兆しが見られない。著名な研究者が,間違い発音を繰り返すので,学生や若手が,直そうとしないのは,当たり前である。最近でも,日本人若手研究者の大発見の記者会見で,某著名な研究者が,正しい発音を使うようにとの意図は,某官庁の指示で,実現されなかったという。それは,lithosphereを正しくリソスフィアと使うことが,認められなかったのである。「間違い発音を使え」と,国家が統制しているのである。 以下,若干の重複をおそれず,この際,皆様に今一度ご一考願いたい。
最初に,教訓:
1.ほとんどの英語の用語が間違って発音されている。
2.しかも,その多くが,外来語化されてしまっており,修正はもはや困難かとも思われるが,間違い発音を使わざるを得ない場合でも,少なくとも,間違い発音が,正しい英語発音ではないと承知の上で,使うべきである。
3.どんな発音も辞書にあたるべきである。しかし,辞書に載っていない場合や,英語使用研究者間でも,各種の発音が入り乱れている場合もある。
たとえば,著名な研究者である某Moore氏は,自分の名前は,ムーアではなく,モーアである。と言っている。そうなのであろう。
4.日本語文の中で,日本で慣用とされている発音をカタカナ表記で使用する場合があろうが,あまりにも間違った発音を使うのは,考え物である。たとえ外来語化していようとも,使うべきではない。たとえば,reservoirをリザーバーとする類である。(正しくは,レザヴォア,アクセントはレにある)
5.少なくとも,英語で発表する講演やポスターでの説明には,心して,正しい発音,正しいアクセントを使うように心がけたい。
アクセント
スペリング
1.Lithosphere
2.Reservoir
3.Seismic
4.Trough
5.Southampton
6.Frontier
7. Stratigraphy
8.Microbial
9.Oceanic
10.Review
間違い発音
リソスフェア
リザーバー
サイスミック
トラフ
サザンプトン
フろンティア
マイクロバイアル
おシアニック
レビュー
より好ましい発音(アクセントをひらがなで表記)
リソスふぃア
れザヴォア
さイズミック
(ただし,Seismicityは、サイズみシティー)
トろフ
サウさンプトン
フロンてぃア (アクセントは てぃ)
ストラてぃグラフィー
(アクセントは てぃ にある!ただし,
形容詞では,グらフィックの ら にある)
マイクろうビアル (アクセントは ろう)
オシあニック (アクセントは あ)
レびゅー 動詞も名詞もアクセントはビューにある。
あまりにも簡単な言葉に関しては,辞書を引かないことが多いが,すべてあたるべきである。これは,ホノルルなどのアクセントにも当てはまる。成田のアナウンスでも,英語なのにもかかわらず,平板なホノルルと発音していた。おかしいと思う。ただし,地名,人名は,一般にどう発音していいか,分からないことが多く,いちいちあたる必要がある。しかも,人,場所によって異なる。
発音:
その道の研究者が自分の分野名の発音を間違えていることがある。
Burial をバリアル(本当はベリアル)
warmingをワーミング(正しくはウォーミング)
Neogeneをネオズィーン(正しくはニ(ネ)オジーン;アクセントはニ,またジーにも第二アクセントあり)
Albianをアルビアン(アクセントはアにおくべきで,ルにおいてはいけない(ありえない))
Schistをスィストなどと発音すると,この人は本当にシストを研究しているのか,と疑われ,低く見られる。
Analysisをアナらいシスとする人もいる。アなリシスである。
Drill: これは,アクセントはシラブル(母音を含む)にしかないはずだから,どリルなどと発音するはずはない。アクセントはリ以外考えられない。ドりル
(つくばにあるビルのCreoも,皆 くレオと発音しているが,英語としてはありえないのである。日本語の宿命なのであろうか?)
(もっともバカらしいのは、あるクリニックのCMで、クーリニックとクーにアクセントをおいているのだ。英語人が、どれほど日本を馬鹿にするかが、わかる。シラブルもない子音にアクセントを置くなんて(また、それがために長音になるなんて)、あり得ない中のあり得ない、なのである。正しくは、当然、り)。
そのほか。日常用語的になっていて,もはや修正が難しいのも多いが,英語として発音するときは,正しく行うべきである。たとえば
channelは(チャンネルなどではなく、チャヌルまたはチャヌー(的に))。
acousticはアコ(またはアコー)スティックではなく,アくースティック
(アクセントはくー;ともかくアクセントのあるシラブルの発音は正確に,がモットーである)。
hammockyは はマキ。
faciesはファシースではなく,フェイシーズである。
labelはラベルではなく,レイボー。
Sampleはサンポー,などのほうが通じやすい。
Stickerはステッカーではなく,スティッカー
Digitalはデジタルと新聞、放送、一般に使われているが、ディジトー
(デズニーと発音すると、いかにも田舎くさい)。
Volunteerはボランティアー(アクセントはティ)
Matureはともかくメイチャーなどではなく,マチュア。
また,majorはメジャーリーグなどで使われるが,もちろんメイジャーである。
Measureの発音は難しく,メザーとメジャーの間くらいである。
そのほか,思いつくままにあげると,
patternは,99%の日本人が,パターンとターにアクセントを置くが,もちろん,ぱタンであって,アクセントはぱである。
Plumeは,日本でも以前は正しくプルームと書かれていたが,いつの日からか,プリュームとされるようになり,岩波も,そう使うことがあるようである.しかし,これは,イギリスでも,アメリカでも,プルームである。
Diameterはダイあミター、アクセントはあ(ダイアマター的)。
また,英語と米語の発音の差は,日本人にとっては,気にしていたらきりがなく,区別して行うこともないとは思うが,彼らは結構気になっているようである。(差別社会のせいかもしれない)。
Againは英語ではアゲインだが,米語ではアゲンである。こうした,ちょっとした違いは非常に多い。
Quite a few クワイタフュー 「少し」という意味ではない。正しい意味はmany.
また,発音に関しては,ともかくR とLを,きっちりと区別する。Lが文頭にあるときは,極端に舌を突き出す。また,単語の最後にある時は,る,といわないようにして,無視する。ジンゴーベー,イーゴー(eagle)などである。全体的に,私もそうだが,発声方法(あごの動かし方や口,舌などの使い方)が,英語と日本語では根本的に違うので, physicalな面でもあえて英語的に変えないと,なかなか通じない。一つの方法は,高い声を出して発音することである。疲れるが有効である。私が手本としている人は,オウコウチ氏である。あえて言わせていただく。ただし,彼らは残念ながら,オークチと呼んでいるが。。。(今度は,彼らに日本語発音を学ばせる番か?)
そのほか:
事項が達成できたかどうかを示すのに,×,○,△は使わないようにする。(欧米では,Vや×は,yes, OK,できた,済み,などの意味に使われる。つまり日本の○として使われることが多い。○や△は,めったに使われない。)
話し方の対処療法:
和文英訳をしながら頭で文章を作りながら話をすると,つい硬くなる。Jeremy Leggett氏から教わった話し方は,枕を用意しておき(たとえば,As far as I know, To tell the truth, In this case, I may sayなど),それを言っている間に,次の文章を考えるとよい。
福音:
日本人の寡黙さ,謙虚さは,美徳でもあろうが,誤解をも招きかねない。彼らは,くだらないことでも,聞き返したり,一言余計にしゃべったりしている。また,確認を頻発する。この方が,あとあと面倒にならず,また相手の考えのレベルが相互に分かって,コミュニケーションにはふさわしい。どうであろうか?(その他;関係ないかもしれないが,かなり気になること:タバコはやめよう。著名な研究者や教授クラスの方でも,平気でタバコをふかすのが日本の学界である。恥ずかしさを通り越している。自らの周囲の環境をも守れないのである。)
(おあとがよろしいようで。みなさん,がんばってください。)(以上)
(補遺)ともかく、新しく外来語になる用語の発音表記には、気をつけるべきである。責任ある立場にあるのは、放送局, 大新聞、それにリーディング・リサーチャー特に大学教授である。
小川勇二郎(筑波大)
No.0024 2008/3/18 geo-Flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.024 2008/03/18 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】地質学雑誌の新表紙デザイン締め切り間近!
【2】北海道・関東・近畿・四国・西日本支部 イベント案内
【3】コラム:関東アスペリティ計画第三回国際ワークショップと巡検に参加して
【4】地質マンガ「ちきゅうに乗りたい」・「乗船」
【5】地球科学関係の最近10年間の引用数トップ10
【6】第6回国際アジア海洋地質学会議のお知らせ
【7】『岩石物性入門』著者割引販売のお知らせ
【8】国際惑星地球年日本 Newsletter No.3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】地質学雑誌の新表紙デザイン締め切り間近!
──────────────────────────────────
応募締切:2008年3月31日(必着)
募集詳細については、http://www.geosociety.jp/outline/content0050.html
をご参照ください。
応募締切まで数日ありますが、現時点で複数点の応募をいただいております。
ご応募の際には、デザインについての趣旨やコメント等(A4・1ページ程度)をあ
わせてお送り下さい.審査の際の参考にさせていただきます。
■応募例・・・・
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】北海道・関東・近畿・四国・西日本支部 イベント案内
──────────────────────────────────
■北海道支部■
2008年総会・個人講演会・地質学講演会のお知らせ
日時 2008年5月10日(月) 10:30-17:00
場所 北海道大学高等教育機能開発総合センター
参加申込締切:4月25日(金)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
■関東支部■
1)地質技術伝承講習会:地質技師長が語る地質工学余話シリーズ
日時:2008年4月19日(土) 14:00〜16:00
会場:国立科学博物館 日本館4階大会議室
参加申込:定員になり次第締切
2)第2回研究発表会「関東地方の地質」
日時:2008年6月8日(日)10:00分〜17:00
会場:早稲田大学国際会議場 第1会議室
講演申込締切:年3月31日(月)
3)箱根火山見学会のお知らせ
日時:2008年5月17(土)〜18日(日)1泊2日
参加申込締切:4月18日(金)
詳しくは、http://kanto.geosociety.jp/
■近畿・四国・西日本支部■
近畿・西日本・四国 三支部合同例会
日程:2008年 6 月 29 日(日)
会場:兵庫県立人と自然の博物館
ポスター発表申込締切: 6月2日(月) 必着
詳しくは、http://kinki.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】コラム:関東アスペリティ計画第三回国際ワークショップと巡検に参加して
──────────────────────────────────
2/16-17に、相模湾/房総沖掘削計画である「関東アスペリティプロジェクト」の
第三回国際ワークショップが千葉大学にて行われ、引き続き2/18-19には南房総半
島にて巡検が行われました。参加された千葉大学の院生の山本修治氏から参加報
告をご投稿頂きました。
詳しくは
http://www.geosociety.jp/faq/content0070.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地質マンガ「ちきゅうに乗りたい」・「乗船」
──────────────────────────────────
詳しくは、http://www.geosociety.jp/faq/content0057.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地球科学関係の最近10年間の引用数トップ10
──────────────────────────────────
金沢大学理学部地球学科 石渡 明
Thomson Scientificが世界の地球科学関係の最近10年間の引用数の順位を学術雑
誌,研究者個人,研究機関について昨年末に公表したので,以下に紹介します.
具体的なデータは次のサイトにアクセスして確認して下さい.
http://scientific.thomson.com/press/2007/8402215/
1.地球科学関係雑誌,引用数トップ10 (1996-2007)
雑誌ではGeophysical Research Lettersが群を抜いてトップで,次が米国地質学
会のGeology, それら以外はどれも似たような引用数です.分野を見ると地球物理,
地質,水文,鉱物,古生物,第四紀,海洋,生化学,岩石など,地球科学全体を
代表する幅広い分野の雑誌が10位以内に入っています.
2.世界の地球科学研究者,引用数トップ10 (1996-2007)
研究者個人では,上位10人中に岩石・鉱物関係が6人も入っており,他は宇宙科学
が3人,古生態学が1人です.10番目にアジア人としてただ1人,Island Arcの編
集顧問でもあるJ.G. Liou氏が入っているのは立派です(彼は岩石学者です).
3.世界の研究機関,引用数トップ10 (1996-2007)
研究機関では,米国地質調査所が1位,NASAが2位なのはさもありなんと思いま
すが,3位にコロラド大学が来ています.4位はロシア科学院,5位が中国科学
院で,6位がワシントン大学です.米国の地方大学2校が上位に入っているのが
注目されます.フランスのCNRS(国立科学研究センター)が10位に食い込んでい
ますが,残念なことに日本の研究機関は10位までに顔を出していません.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】第6回国際アジア海洋地質学会議のお知らせ
──────────────────────────────────
第6回国際アジア海洋地質学会議(6th International Conference on Asian Mar
ine Geology: ICAMG VI)が高知工科大学にて開催されます.ICAMGは、アジア周
辺海域の海洋地質学を研究する研究者が約4年毎に開催する学術会議です.現在 2
nd circular を公開中,アジアを含む世界各国から研究者が集い最新の研究成果
を発表する機会ですので,皆様奮ってご参加ください.大学院生の参加支援プロ
グラムも用意されています.
会期:平成20年8月29日(金)〜9月1日(月)
事前参加登録&講演要旨投稿締め切り 2008年4月10日
参加費用:
事前申し込み(全日程)25,000円(学生;15,000円)(※4月10日まで)
当日申し込み 全日程:30,000円,一日:10,000円
詳しくは下記公式ウェブサイトをご覧ください(日本語概要も閲覧できます).
http://ofgs.ori.u-tokyo.ac.jp/ICAMG6/
問い合わせ先:第6回国際アジア海洋地質学会事務局
TEL/FAX :088-864-6705/088-878-2192
Email:icamg_6@jamstec.go.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】『岩石物性入門』著者割引販売のお知らせ
──────────────────────────────────
シュプリンガー・ジャパンから『岩石物性入門』
(Y. ゲガーン・V. パルシアウスカス著、西澤 修
・金川久一訳、A5版348頁、税込み定価3,990円)
が出版されました。岩石物性を体系的に記述した
入門書で、物理探査に関係する方々には有用と思
います。詳細は下記HPを参照下さい。
http://www.springer.jp/japan/astronomy/j71200.html
著訳者割引(税込み3,192円)による購入が可能です。
購入を希望される方は、氏名と送付先を明記の上、
<kyu_kanagawa@faculty.chiba-u.jp>までお申し込み
下さい。シュプリンガー・ジャパンから直接郵送され
ます(送料無料です)。支払いは現品到着後の後払い
(請求書類一式・郵便振込用紙同封)で、クレジット
カードでの支払いも可能(同封書類に記入欄あり)だそうです。
注文は随時受け付けますが、毎週金曜日にまとめて出版社に発注しますので、注
文されてから本が届くまで3~10日間ほどかかることをご了承下さい。
(千葉大学 金川久一)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】国際惑星地球年日本 Newsletter No.3 (2008.3.18)
──────────────────────────────────
詳しくは、http://www.gsj.jp/iype/at/jp/eNL/n03.html
●●目次●●
【1】IYPE日本部会委員の募集
【2】I*Yシンポジウムのご案内
【3】Y.E.S. Congress 2009のご案内
【4】韓国でのIYPEイベント
【5】4月の協賛イベント
【6】地質の日 関連イベント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.0025 2008/4/1 geo-Flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.025 2008/04/01 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】日本地質学会第115年総会開催のお知らせ
【2】地質学雑誌表紙デザイン締め切る
【3】2008年度会費引き落としのご連絡(6/23)
【4】関東支部箱根巡検・近畿支部山陰海岸地質見学会
【5】木村会長とロンドン地質学会会長との懇談のリポート
【6】地質マンガ「ちきゅうはゆれない」
【7】三朝国際インターンプログラム2008の案内
【8】高知大学理学部理学科地球科学コース准教授・助教公募
【9】千葉大学大学院理学研究科地球科学コース准教授公募
【10】地質調査総合センター第12回シンポジウム
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】日本地質学会第115年総会開催のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地質学会第115年総会を次の次第により開催いたします.
2008年5月25日(日) 17:30〜19:00
会場 幕張メッセ 国際会議場(3F 303会議室)
1. 開会
2. 議長選出
3. 議案
1号議案 2007年度事業経過報告
2号議案 2007年度決算報告
3号議案 選挙結果の報告
———新旧役員の交代———
4号議案 2008年度事業計画について
5号議案 2008年度予算案について
6号議案 名誉会員の推薦について
4. 閉会
詳しくはこちら、
http://www.geosociety.jp/outline/content0054.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】地質学雑誌表紙デザイン締め切る
──────────────────────────────────
たくさんのご応募ありがとうございました。3月31日、17:00に
応募を締め切りました。会員、非会員の方々から、全25作品の応募が
ありました。今後会長により審査委員会が招集され、厳正な審査の上、決定
される予定です。選考結果は5月25日の地質学会115年総会(幕張)で
発表される予定です。乞うご期待!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2008年度会費次回引き落としのご連絡(6/23)
──────────────────────────────────
2008年4月〜2009年3月の会費をご請求しています.未納の方には督促請求書を送
付いたしますが,早急にご送金をお願いいたします.督促請求は5月末頃の予定で
す.なお、次回は,6月23日(月)に引き落としの予定です(2008年およびそれ以
前の会費が未入金の方対象).
正会員の「院生割引申請者」は、大学院に在籍し,定収のない方で所定の申請を
された方のみに適用します.2008年度(本年度)分までの申請受付は終了しまし
た.
詳しくはこちら、
http://www.geosociety.jp/outline/content0052.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】関東支部箱根巡検・近畿支部山陰海岸地質見学会
──────────────────────────────────
■関東支部箱根巡検■
日時 2008年5月17日(土)〜18日(日)(1泊2日)
費用 一般会員20000円,学生会員10000円(非会員はそれぞれ5000円増)
講師 高橋正樹(日本大学文理学部)
募集人員 20名 (先着順)
応募受付期間 3月18日(火)〜4月18日(金)まで
詳しくは、関東支部HPへ
■近畿支部山陰海岸地質見学会■
主 催:日本地質学会近畿支部・山陰海岸ジオパーク推進協議会
日程:2008年5月11日(日)
見学内容:遊覧船にて浜坂-香住間の海岸線の地形・地質見学
(花崗岩類・北但層群八鹿-豊岡累層,海食洞・柱状節理など)ほか
案内者:古山 勝彦(大阪市立大学 大学院理学研究科),
三木武行 (八鹿高校教諭) ほか
参加費:無料
申込締切:4月25日(金)(必着)
詳しくは、近畿支部のHPへ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】木村会長とロンドン地質学会会長 懇談リポート
──────────────────────────────────
ロンドン地質学会会長のリチャード・フォーティ氏がダーウィン展開催を記念し
て、来日された。忙しい日程の中、3月19日、木村学地質学会会長と小一時間ほど、
親しく懇談できた。(理事 矢島道子)
詳しくはこちら、
http://www.geosociety.jp/science/content0013.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質マンガ「ちきゅうはゆれない」
─────────────────────────────────
好評★地質マンガ連載中!!
「地質学会がマンガをはじめたって」
「まじで? フツーしなくない」
「学会のマンガってどーよ?」
「やべえ おもしれえよぉ!」
http://www.geosociety.jp/faq/content0057.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】三朝国際インターンプログラム2008の案内
──────────────────────────────────
実施期間:7月1日(月)〜8月8日(金)(約6週間)
国際的な研究・教育の推進を目的に、国内外からの学部3 ・4年生並びに修士課程
学生(国籍は問わない)を対象として2005年より継続的に開催されています。。
参加者はそれぞれ教員並びにその研究グループによる指導のもと、当研究センター
が推進している、
1. 地球惑星化学・年代学)/ 2. 高圧実験科学・鉱物物理学/ 3. 結晶化学・マ
グマ学
に関する最先端研究プロジェクトに実際に参加していただきます。プログラム終
了時には、英語による研究成果発表の実施を予定しています。このプログラムを
通して、高度な実験・分析技術に触れるのみでなく、研究者としての経験や最先
端研究への情熱が育まれることを期待しています。
募集人員:15名程度
応募締切:2008年4月15日(木)必着
詳しくは、http://www.misasa.okayama-u.ac.jp/MISIP/2008/index_j.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】高知大学理学部理学科地球科学コース准教授・助教公募
──────────────────────────────────
公募人員:高知大学理学部理学科地球科学コース 准教授または助教1名。着任後、
資格審査の上、大学院修士課程も担当していただきます。なお、助教として採用
する場合には、任期は5年(再任可)となります。
専門領域:古生物学・古環境学
資格条件:
(1) 博士の学位を有すること/(2) 地質調査の指導ができること
予定主要担当科目:地球科学コース専門科目(地史学、野外調査実習など)のほ
か、共通教育科目を担当していただきます。
採用時期:平成20年8月1日(予定)
提出期限:平成20年5月16日(金)17:00必着
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】千葉大学大学院理学研究科地球科学コース准教授公募
──────────────────────────────────
職名・人数:准教授1名
公募分野:野外において地球科学的手法を用いた調査・観測・実験に基づいて,
学際的で新しい視点から地球表層の水圏・地圏でおこる過去から現在までの環境
変動に関する研究を行い,その成果を将来予測に活かそうと試みている
方。地球表層科学講座の教員と連携した共同研究や学内外での共同研究プロジェ
クトを積極的に推進する意欲のある方を希望します。
応募締切り:2008年 6月 6日(金)必着
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】地質調査総合センター第12回シンポジウム
──────────────────────────────────
独立行政法人 産業技術総合研究所
地質調査総合センター第12回シンポジウム
地下水と岩石物性との関連の解明〜産総研のチャレンジ〜
日時:2008年5月8日(木)13:00-17:30(12:30開場,ポスター閲覧可能)
場所:秋葉原ダイビル5F 5B会議室
主催:産総研地質調査総合センター
入場無料
定員:100名
参加お申込み:地質調査総合センターのシンポジウムwebサイトからお申し込みく
ださい.
http://www.gsj.jp/Event/080508sympo/
お問い合わせ:
地質調査総合センター gsjsympo12@m.aist.go.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質マンガ ちきゅうに乗りたい
地質マンガ
「ちきゅうに乗りたい!」
戻る|次へ
地球深部探査船「ちきゅう」は掘削ポイントに何ヶ月も無寄港で滞在します。その間の人員交代はヘリコプターや連絡船で行われます。そのためヘリ脱出訓練は必須項目です。海洋調査では避難訓練は重要ですから。下の写真はヘリに模したシミュレータです。シートベルトに固定されてプールでひっくり返されます。「窓を外して水面に脱出せよ!」 (たいへんそうですが、結構わくわくする訓練です)
写真:Harold J. Tobin( ウィスコンシン大学マディソン校)
【geo-Flash】No.332 第7回惑星地球フォトコンテスト:締め切り間近です!!
【geo-Flash】No.332 第7回惑星地球フォトコンテスト:締め切り間近です!!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.332 2016/2/16┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2016年度一般社団法人日本地質学会理事および監事選挙について
【2】第7回惑星地球フォトコンテスト:締め切り間近です
【3】125周年記念地質学雑誌特集号の状況について
【4】2016東京・桜上水大会:トピックセッション募集中
【5】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(木)
【6】日本地方地質誌7.四国地方 2月下旬刊行(会員特別割引販売)
【7】Wiley 東日本大震災3.11から5年 学術論文特集 無料公開中(4/30まで)
【8】本の紹介「巨大地震による複合災害」
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2016年度一般社団法人日本地質学会理事および監事選挙について
──────────────────────────────────
2月8日に役員の立候補が締め切られました.選挙管理委員会で確認した理事お
よび監事の立候補者をHPに掲載しています.
1)理事選挙
◆全国区代議員(定数43名):定数内につき,無投票当選となります.
◆地方支部区代議員(定数7名:各地方支部区から1名ずつ):中部支部区は理
事選挙を行います.他の地方支部区は定数内につき,無投票当選となり投票は
ありません.
2)監事選挙
監事については会員から1名,理事会推薦から1名,計2名の立候補届出がありま
したが,会員からの候補者は定数内のため,監事の投票は行いません.
候補者名簿など,詳しくは,(要会員ログイン)
http://sub.geosociety.jp/members/content0089.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第7回惑星地球フォトコンテスト:締め切り間近です
──────────────────────────────────
ジオフォトの最高峰の写真コンテスト!今年も作品を募集しています.
★★★応募締切:2016年2月22日(月)17時★★★
近年の応募数は,会員からの割合が極端に低くなっています. 会員の皆様にお
いては,地質の美しさ,素晴らしさを表現した渾身の作品を是非ご投稿下さい.
お待ちしています.
詳しくは, http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】125周年記念地質学雑誌特集号の状況について
──────────────────────────────────
昨年の11月末を〆切としていた地質学会125周年記念地質学雑誌特集号には多
くの申し込みを頂きました.特集号としては10件,個別総説論文としては2件の
申し込みがありました.これらの内容について企画委員会で検討を重ねてきま
したが,現時点での状況について会員の皆様へお知らせします.10件の特集号
の申し込みのうち,下記の9件の特集号が企画委員会として採択されています.
1件については保留となっており,再提案を受けて再度検討することとなってい
ます.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/125th/content0003.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2016東京・桜上水大会:トピックセッション募集中
─────────────────────────────────
本大会では,多くのセッション開催を可能にするよう,必要十分数の会場(部
屋)を確保する予定です.ポスター会場については,近年のポスター発表重視
の方向を満たすスペースを確保します.
「第123年学術大会(2016東京・桜上水大会)」
2016年9月10日(土)〜12日(月) 会場:日本大学文理学部
★トピックセッション募集:3月14日(月)締切★
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0068.html
開催通知はこちら,http://www.geosociety.jp/science/content0069.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(木)
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は,3月31日(木)です.
次年度も割引会費を希望のかたは,忘れずにご提出ください(締切厳守).
割引会費申請や2016年度の会費払込について,
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0164.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】日本地方地質誌7.四国地方 2月下旬刊行(会員特別割引販売)
─────────────────────────────────
日本地方地質誌7.四国地方(700頁,口絵8頁)が2月下旬に刊行になります.
定価:29,160円,会員特別割引価格:25,600円
*専用申込書はニュース誌1月号または,学会HPからダウンロードして頂けます.
http://sub.geosociety.jp/members/content0026.html
(会員番号・パスワードによるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】Wiley 東日本大震災3.11から5年 学術論文特集 無料公開中(4/30まで)
──────────────────────────────────
学会公式欧文誌 Island Arc を出版するWiley社では,東日本大震災に関する
論文123報を科学・医学・社会科学分野から選び,2016年4月30日までオンライ
ンで無料公開しています.
詳しくは,
http://news.wiley.com/311GlobalJapan?elq_mid=8126&elq_cid=1993432
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】本の紹介「巨大地震による複合災害」
──────────────────────────────────
「巨大地震による複合災害:発生メカニズム・被害・都市や地域の復興」
八木勇治・大澤義明(編著)
筑波大学出版会、2015年11月、210ページ、2900円+税、ISBN978-4-904074-38-1
本書は、2011年3月11日に起きた東北沖地震と、関連する災害(東日本大震災)と、そこからの復興に関しての自然科学・工学からのみならず、社会・人間科学分野の多くの専門家によって書かれた、文科省の特別経費研究プロジェクトの成果物である。と同時に、序にあるように、大学の学部1,2年学生の講義のために書かれた総合的教科書でもある。内容は、多くの図・グラフ・写真などを使用し、専門的な事象を比較的平易に説明しているほか、随所により深く知りたい方々や専門家をも満足させるようなコラムも設けられており、コンパクトながら高度な書物となっている。
巨大地震発生後、すでに5年が経過し、地震のメカニズムと震災(ほとんど津波による被害)の実態に関しては、多くの科学論文やそれに基づく報告書、普及書などが出版されているが、本書の特徴は、それらとはやや異なり、自然災害そのものと復興に際しての社会や人間活動へも及ぶ複合災害の諸現象とその実態や考え等に関しても、豊富な生データとともに紹介しており、多くの視点から書かれた社会に広く役立つ書物である。
構成は、全10章からなっており、第1章は巨大地震・津波の発生メカニズム、第2章は地震被害、第3章は津波の実態と対策、第4章は液状化と斜面崩壊、第5章は建物被害の特徴、第6章は建築物崩壊のメカニズム、第7章は社会インフラの被害と対策、第8章は原発事故による放射性物質の挙動、第9章は物質的な被害が発生した後の人間行動や社会的影響、第10章は大震災後の社会的な影響の精査と復興を円滑に行うために必要な合意形成について、それぞれ取り扱っている。(これらには地質学分野の読者にも身近に感じられる内容が多く含まれ、また社会に生きるすべての人々が関心を持つべき内容でもある)。これら広範囲におよぶ災害関連の諸現象や考え方を一つの書物にまとめるには、編集上の苦労があったことと想像される。なお、八木氏は、著名な若手の理論地震学者であり、大澤氏は社会工学の研究者である。総計20名に及ぶ各章の著者は、主として筑波大学大学院の生命環境系と情報システム系に属する研究者である。
今や市民(読者)には、現在および将来の自らの生命や財産などを守ることが重要だとの意識が広がっている。そのためには、自然界と人間活動のすべての現象の原理や事実と、その信ぴょう性を確実なものとすることが求められている。それには、極めて高い意識をもって、現在最高レベルの学問からの知識を日常的に絶えず整理し、取り込むことが重要だというのが、一読した後の筆者の感想である。本書は、その実現に近づいたものと思う。
本書は、上に述べた章立てにもあるように、自然科学・工学研究者が地球の諸現象と社会生きる人間とその諸活動とどう関係するかという観点から見た取り組み方と、それとは逆の、人間活動を主眼とする社会科学・人文科学分野の研究者が自然とどう付き合うか(理解、改善、征服、妥協、服従などの言葉が思い浮かぶが)の両方に関して、読者に問いかけている。今日、人間活動(主として技術と経済の発展に伴う)の高度化と複雑化によって、我々人間を取りまく状況は、極めて多面的で、かつ完全な理解が難しい状況になっている。21世紀に入って、それはまた人間の精神的な活動にも影響を与え(国際政治についてもしかり)、相互の全体的な理解がないとその困難を乗り越えることはできないところまで来ている。そのための試みとして、気候変動枠組条約締約国会議(COP)や、社会科学者が提案し国際的な議論を呼び起こしている気候変動政府間パネル(IPCC)などがある。2015年3月仙台において開かれた国連防災会議(UN WCDRR)や同時に開かれた関連するさまざまな集会も、類似の方向を目指している。国際科学会議(ICSU)の中での一大テーマであるFuture Earthも、人類生き残りをかけての国際的な科学運動の一つに含まれる。我々の地質学あるいは地球惑星科学分野でも、さまざまな取り組みが行われているのは衆知の通りである。
自然災害は、気候変動によるものと(特に異常気象(干ばつや洪水など)と海水準変動)とその他の固体地球科学的要因(地震、火山、津波、斜面崩壊など)によるものとに分けられようが、多くは相互に深い関係がある))、それらは人間にマイナスの効果を与えるもの(災害、ディザスター)の地球の3次元、いや4次元的現象としてとらえるべきものである(その多くが、地質的現象を含むものであることを留意すべきである)。しかし、一般に、そのメカニズムやプロセスは複合的で、ますます複雑化している。近年の自然災害の巨大化は、上に述べたようなハザード(災害要因)やリスク(危険度)に対応した現象と、それに人類の増加とその活動の高度化・集中化が関係している。一方、災害のリスクの高い箇所に人口や活動が集中するということは、人間の居住や活動要素による複合化した相乗効果(synergy)として理解されるだろう。
自然災害の多くは、アジア・環太平洋諸国などで特に顕著である。実際、多くの人々が活動する大都市が、大河川のデルタ地帯や活断層の上などに集中する。日本の大都市を見れば明らかである。人間の多くが、自然災害のリスクの大きいところにあえて住んでいるのではないか?との危惧すら感じられる。そこが多くの利便性を提供するからである。そこにいったん災害が起きると、その被害は極めて複合化しかつ巨大化し、復興には時間と巨額の資金が必要である。さらに、近代科学が150年程度の歴史しか持たない状況から、各方面での研究者の努力はあるものの、ハザードに関しての十分精度や確度のよいデータは依然として完全とは言えない。我々は、高いリスクのあるハザードに満ちた地域に、あえて住んでいるのである。我々の周辺の事象の将来予測は手探りであるといえる。実際、自然災害が起きることを予測した準備(preparedness)によりも、起きた場合のための救援、避難、その後の復興などへの経済的支出がずっと多額を占めるとも聞く。これらの自然科学的、社会科学的、人間科学的諸問題を乗り越えるには、本書にあるように、すべての分野を通した一貫した意識のもとに、基本的なすべての事項を整理して、どこがポイントかを抑えて、より詳しい検討を続け、全体の理解や行動を皆で考えて、時期を失せずに行動を起こす以外、ないものと思われる。(我々、4Dでの考察を得意とする地球惑星科学分野の出番である、と思うのは、筆者の手前味噌であろうか?)
本書は、これから社会活動の中枢を担うべき大学生や講義を担当する教官ばかりでなく、立法・行政に携わる方々(decision maker)や産業活動、教育に携わる方々、さらに一般市民の方々(これらすべてを含めてstakeholderと呼ぶようである)にも、大いに役立つ画期的な書物と考え、多くの方々に推薦したい。そして、世界の人々が、自然災害に関してどのように向き合うかを、日常的に話題にできるようにしたいものと考える。(小川勇二郎)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】支部情報
──────────────────────────────────
[北海道支部]
■北海道支部平成27年度(2015年度)総会
2月27日(土)14:30〜16:30
場所:北海道大学理学部6号館2階 6-204室
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[関東支部]
■2016年度支部総会・地質技術伝承会
4月16日(土)14:00〜16:45
場所:北とぴあ 7階 第1研修室
伝承会演題(予定)「落石,斜面崩壊の岩盤斜面安定解析(数値)」
講師:萩原育夫氏(サンコーコンサルタント(株)調査技術部 部長)
*総会に欠席される方は委任状お願いします.
■支部幹事の選出 立候補期間:3月1日(火)〜11日(金)
■ 矢川地すべり巡検参加者募集
4月23日(土)
巡検場所:群馬県甘楽郡下仁田町大字西野牧字徳若山国有林内(矢川地すべり
地域)
集合:8:00 解散:18:00頃 JR大宮駅西口
募集人数:25人 参加費:6,000〜7,000円程度(人数により変動)
参加申込締切:3月23日(水)
詳しくは,http://kanto.geosociety.jp/
[西日本支部]
■西日本支部平成27年度総会・第167回例会
2月20日(土)9:00〜 例会終了後 懇親会
場所:熊本大学黒髪南キャンパス理学部2号館
★講演プログラムPDFを公開しました★
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する「科学的有望地の要件・基準
に関する地層処分技術WGにおける中間整理」について、専門家からの意見募
<募集期間>1月20日(水)〜4月19日(火)
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/rw/gijutsu-iken.html
*中間整理についての説明会も開催が予定されています(2月29日開催,参加申込2/19締切)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/news/n119.html
■公開講演会「強靭で安全・安心な都市を支える地質地盤の情報整備−あなた
の足元は大丈夫?−」(2016/1/23開催)*日本地質学会 後援
講演要旨集が公開されています。
http://janet-dr.com/01_home_calendaer/201601/20160123chishitujiban_youshi.pdf
■地震本部ニュース冬号
調査研究レポート:津波遡上の即時予測を目指して〜SIP 防災「津波被害軽減
のための基盤的研究」〜 ほか http://www.jishin.go.jp/herpnews/
*************(以下,関連団体の行事案内です)****************
■JAMSTEC2016(平成27年度海洋研究開発機構研究報告会)
3月2日(水)13:00〜17:00
場所:東京国際フォーラム ホールB7
参加費無料(事前登録制)
http://www.jamstec.go.jp/j/pr/event/jamstec2016/
■(後)愛媛大学ミュージアム企画展【四国の鉱物展】
共催:日本地質学会四国支部
3月2日(水)〜4月27日(水)
場所:愛媛大学ミュージアム
http://www.museum.ehime-u.ac.jp/
■平成27年度海洋情報部研究成果発表会
3月7日(月)13:10〜18:00
場所:海上保安庁海洋情報部10階大会議室
参加費無料(事前申込不要)
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/
■ブルーアース2016
3月8日(火)〜9日(水)10:00〜17:40(9:30開場)
場所:東京海洋大学 品川キャンパス
入場無料(事前申込不要)
http://www.jamstec.go.jp/maritec/j/blueearth/2016/program.html
■(共)原子力総合シンポジウム「福島第一原発事故から5年を経て」
3月16日(水)13:00〜17:30
場所:日本学術会議講堂(地下鉄千代田線乃木坂駅徒歩2分)
入場無料
http://www.aesj.net/events/symp20160316
■第184回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
3月25日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:張 銘(産総研地圏環境リスク研究グループ長)
テーマ:中国の土壌・地下水汚染状況と動向
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■海洋と地球の学校2016
3月26日(土)〜27日(日)
場所:オーエンス泉岳自然ふれあい館(講義)
3月28日(月)仙台平野(巡検)
参加申込締切:2月21日(日)
*参加者が30名に達し次第募集を終了します。
http://kaiyotochikyunogakko-2016.jimdo.com/
■日本地球惑星連合2016年大会
5月22日(日)〜26日(木)
会場:幕張メッセ 国際会議場
最終締切: 2月18日(木)12:00
http://www.jpgu.org/meeting_2016/index.htm
*学生を対象とした旅費補助制度が新設設されました
詳細はこちら,http://www.jpgu.org/meeting_2016/to_student.html
■(共)Goldschmidt 2016
6月26日(日)〜7月1日(金)
会場:パシフィコ横浜
要旨受付:1月1日(金)〜2月26日(金)
http://goldschmidt.info/2016/index
■(共)第53回アイソトープ・放射線研究発表会
7月6日(水)〜8日(金)
発表論文の申込締切:2月26日(金)
http://www.jrias.or.jp/
■第35回万国地質学会議
8月27日(土)〜9月4日(日)
会場:南アフリカ共和国ケープタウン
要旨締切:2月29日(月)*締切が延長されました*
http://www.35igc.org/Verso/211/Submit-an-Abstract
IGCサイト>http://www.35igc.org/
■(共)第60回粘土科学討論会
9月15日(木)〜17日(土)
会場:九州大学医系キャンパス
講演申込:6月13日(月)〜24日(金)
http://www.cssj2.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0151.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■アディスアベバ科学技術大学(学部長・教授)公募(2/20)
■高知大学農林海洋科学部海洋資源科学科海底資源環境学コース教員(講師ま
たは助教)公募(3/18)
■桜島・錦江湾ジオパーク推進協議会嘱託職員(ジオパーク国際推進員)(2/
29)
■恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク推進協議会(ジオパーク専門員)(2/29)
■高知大学海洋コア総合研究センター平成28年度(前期・後期)全国共同利用研
究課題 (2/29)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
地質マンガ 乗船
地質マンガ
「乗船」
戻る|次へ
「ちきゅう」は、統合国際掘削計画(IODP)の主力船として活躍しています。このIODPとは日本と米国が主導する地球環境変動、地球内部構造及び地殻内生物圏の解明を目的とした国際的な海洋科学掘削計画で、2003年10月に発足しました。日本の地球深部探査船「ちきゅう」と米国が提供するジョイデス・レゾリューション号、欧州が提供する特定任務掘削船(MSP)の複数の掘削船により科学研究航海を実施しています。世界中の様々な分野の研究者が誰でも参加できます。
関連リンク:
IODP(英語)
CDEX(地球深部探査センター:IODP日本実施機関)(日本語・英語)
J-DESC(日本地球掘削科学コンソーシアム、乗船申し込みはこちら)(日本語・英語)
関東アスペリティ計画第三回国際ワークショップと巡検に参加して
コラム
関東アスペリティ計画第三回国際ワークショップと巡検に参加して 08.3.18UP
千葉大学大学院 修士二年 山本 修治
去る2月16・17日に関東アスペリティ計画(KAP)の第三回国際ワークショップが千葉大学けやき会館にて開催されました.また,続く18・19日には房総半島南部の地質・変動地形の巡検が行われました.以下では,それぞれについて簡単にご報告したいと思います.
KAPは相模トラフ沿いで生じるプレート間巨大地震(例えば1703年元禄関東地震・1923年大正関東地震)のアスペリティ領域の掘削と坑内観測を最終目的とする科学掘削計画で,現在各種プロポーザルがIODPに提出されています.今回のワークショップでは海外から5名の研究者をお招きし,地質学・地震学・測地学・変動地形学の各方面の最新の研究成果が発表され,南関東のテクトニクスに関する学際的な議論が行われました.二日目の午後には掘削やモニタリングのためのサイトサーベイに関する具体的な計画や今後拡充すべきデータ,掘削により得られるであろう成果とその意義について,熱い議論が交わされました.
(WS1日目:撮影者:早川信(千葉大))
ワークショップでは講演者の発表一つ一つに対して緻密な討論が行われた.
(WS2日目:撮影者:武本真和(千葉大))
国内外から主に房総半島を研究対象とした様々な成果が報告された.
筆者は,房総半島南部の海陸地域で行われた反射法地震探査の成果について,修士論文の内容をまとめたものをポスター発表させて頂きました.研究内容は,沈み込むフィリッピン海プレート上面に関連する断層構造を含めた房総半島南部の上部地殻構造と,南東沖の浅海地質調査を目的とした高分解能反射法地震探査の結果とその解釈から読み取る第四紀地殻変動の空間分布に関するものです.南海トラフや世界の他の沈み込み帯に比べ,相模トラフ沿いでは科学目的の反射法地震探査の実例は質・量ともに少なく,貴重なデータを扱わせていただいたことにより国内外を問わず著名な研究者の方々と反射断面の解釈や構造発達といった深い内容について語り合うことができました.特に世界の付加体研究をリードしてこられたJ. C. Moore先生(UCSC)とは,プレートの沈み込みとデコルマゾーンの関係について議論することができました.また,Nicholas W. Hayman先生(テキサス大オースティン校)とは,臨海尖角が前弧域沈み込み帯にも適用可能かどうかについてお話しました.これらの議論やワークショップ全体を通じてこの地域のもつテクトニックな特異性と複雑性,それが故の本プロジェクトの重要性を強く感じました.そして,これまでの研究では未解明であった様々な地学現象(例えば,アスペリティのもつ物理化学的な実体・プレート三重会合点付近のテクトニクス・歴史地震の痕跡を残す乱堆積物など)が本プロジェクトにより解明されると期待され,それらがもつインパクトに大きな希望を持つに至りました.ワークショップの口頭発表や質問はすべて英語で行われ,あたかも海外の学会にいるかのような雰囲気さえ感じられました.また,参加人数が30〜50人という規模であったこともあり,このプロジェクトに直接関わらずとも一つ一つの研究成果・発表に対して濃密な議論の時間が費やされていたと感じました.また,初日にはレセプション・パーティーも開かれ,研究者同士のふれあいの場に同席できたことも嬉しく思うところです.
巡検初日に野島崎にて撮影した集合写真(撮影者:筑波大村岡諭)
上段左から・・・小林励司(鹿児島大),三宅弘恵(東大地震研),Daniel Curewitz(JAMSTEC−CDEX),木戸ゆかり(JAMSTEC),Kurtis Burmeister(パシフィック大),Nicholas W. Hayman(テキサス大オースティン校),J. Casey Moore(カリフォルニア大サンタクルズ校),Wayne Thatcher(USGSメンローパーク),道口陽子(筑波大),大坪誠(産総研),宍倉正展(産総研),田村慎太朗(東大理),纐纈一起(東大地震研),横田裕輔(東大理),丸山岳朗(東大理)(敬省略)
下段左から・・・早川信(千葉大),山本修治(千葉大),山本由弦さん(産総研),川村喜一郎さん(深田研),村岡諭(筑波大)
18・19日に行われた巡検では,筑波大学の小川勇二郎教授・産総研の山本由弦博士・同宍倉正展博士の案内により,房総半島南部の地質・地形についての解説がなされました.
一日目の午前は,元禄タイプ・大正タイプそれぞれの完新世離水段丘を徒歩で実感し,旧汀線指標となるヤッコカンザシを観察しました.ここでは早くも段丘面の認定と年代決定の精度について宍倉博士と海外の研究者の方との間で議論がなされ,海外の研究者の方のKAPに対する関心の強さを感じました.午後は,まず野島崎付近にて千倉層群白浜層の付加体への帰属問題について白熱した議論が交わされました.この日は快晴で見晴らしがよく,富士山が非常にきれいに見えたほか,大島・三宅島も眺望することができました.昼食後,小川教授による南関東のプレートテクトニクスについての説明が行われ,文字通りこれら伊豆・小笠原弧の島々を背景としたご説明の分かりやすかったことが非常によく思い出されます.一日目の最後は産総研の山本博士により最近報告された,過去の地震に伴う液状化と海底地すべりの痕跡を残す露頭の紹介が行われました.その露頭はご本人曰く,雨天後撮影された写真に比べると不鮮明であったとのことですが,山本博士の丁寧な説明と分かりやすい写真とスケッチによりその痕跡の重要性と不思議さが強く心に強く残りました.
宿泊は国民休暇村館山で行われ,房総の刺身舟盛と美味しいビール,そして普段の研究とは一線離れたくだけた会話が,一日の疲れを癒してくれました.
(小川先生の解説・・・撮影者:早川信(千葉大))
鴨川漁港弁天島で枕状溶岩の姿勢について解説される小川勇二郎先生(筑波大)
二日目の午前は見物にて元禄タイプ・大正タイプの典型的な段丘露頭を観察した後,西川名の海岸沿いの後期中新世の三浦付加体(西岬層)を観察しました.ここでは埋没・剥ぎ取り付加と伊豆・丹沢ブロックの衝突に伴う構造回転の研究についての説明が,山本博士によりなされました.山本博士によるマッピングの精緻さにただ驚くしかありませんでした.その後,筑波大学博士課程の道口陽子さんによるこの地域での重力性地すべりに関する研究の成果が説明され,議論の的となりました.午前の最後は布良付近の津波堆積物の観察を行いました.午後は有名な鴨川漁港の弁天島で嶺岡帯中のオフィオライトコンプレックスを観察しました.ここでは小川教授の詳細なマッピングに基づくこれらの岩体のエンプレイスメントに関する説明がなされました.最後は小湊付近の海岸ベンチにて,元禄地震の際の沈降に関する宍倉博士の見解が述べられました.
著者は修士の二年間,主として反射法地震探査の立場から,房総半島南部の地質構造を眺めてきました.この巡検を通して,本地域の構造の骨格を追体験し,自分の研究手法とは異なったフィールドジオロジーによる構造観に触れられたと感じています.反射法によってしか解明されない部分も多分にあるものの,地質学的時間スケールに比べてミクロな事象についての研究は,やはり実際に野外調査をすることによってしか解明することができないということを再認識させられました.
今回の二日間の巡検に一貫するテーマは,『地質・地形に記録される過去の地震イベントの抽出』であったといえると思います.巡検には東京大学地震研究所纐纈一起教授をはじめ強震動予測などの地震学を専門としておられる方々も参加され,そこにある地質・地形と過去の地震現象との関係が盛んに議論に挙がっていました.とりわけ,付加体や海溝陸側斜面堆積物に残されている過去の地震と関連する地質現象の解釈は,これまで知られていなかったものがほとんどであり,地質学者と地震学者の融合的研究とモデル実験による実証可能性についての新たな研究領域が拓かれつつあると感じました.これらの研究が進展し,詳細な時間目盛の刻まれた地表地形・地質の研究と,今後遂行されるKAPでの海洋掘削により,南関東で発現するプレート間巨大地震の防災・リスク評価のみならず,テクトニクス研究についても飛躍的な発展が遂げられるものと期待させるような4日間でした.
最後にこの場をお借りして本ワークショップ・巡検の準備と進行に関わられたすべての方に感謝申し上げたいと思います.
地質マンガ 『ちきゅう』はゆれない
地質マンガ
「『ちきゅう』は揺れない」
戻る|次へ
「ちきゅう」は、統合国際掘削計画(IODP)の主力船として活躍しています。このIODPとは日本と米国が主導する地球環境変動、地球内部構造及び地殻 内生物圏の解明を目的とした国際的な海洋科学掘削計画で、2003年10月に発足しました。日本の地球深部探査船「ちきゅう」と米国が提供するジョイデ ス・レゾリューション号、欧州が提供する特定任務掘削船(MSP)の複数の掘削船により科学研究航海を実施しています。世界中の様々な分野の研究者が誰で も参加できます。
関連リンク:
IODP(英語)
CDEX(地球深部探査センター:IODP日本実施機関)(日本語・英語)
J-DESC(日本地球掘削科学コンソーシアム、乗船申し込みはこちら)(日本語・英語)
ジオパークと “Rock” “Green” “Cafe”
ジオパークと “Rock” “Green” “Café”
理事・矢島道子(地質情報整備・活用機構)
1.はじめに
日本国内にもジオパークをつくろうという動きが,あちらこちらで少しずつ見られるようになってきました.日本地質学会の中にもジオパーク支援委員会ができました.ジオパークの「ジオ」の部分をよく知悉していて,その知識・情報をジオパーク成立に役立てるのは地質学会会員の仕事と思われます.しかし,ジオパークは少し新しい概念を含んでいたため,UNESCOで考案している段階からIUGSやUNESCOといろいろな議論をへて現実化してきた事情もあり,ジオパークとはどういうものかをイメージすることはなかなか難しいところがあるように思います.2008 年1 月,四国ジオパークモデル地域調査に,世界ジオパークの生みの親で前UNESCO 地球科学部長のウォルフガンク・エダーさんが来日されました.そのとき,私は通訳として,エダーさんと地域調査をともにしました.調査を通して,ジオパークについてそれなりの理解をえました.日本地質学会のより多くの会員の方にジオパークを理解していただきたいと思い,3月の四国の報告会で報告した内容を本誌で整理してみようと思います.
2.ジオサイトとは
ジオパークの説明の際に必ず,図1のように,いくつかのジオサイトをジオパークという名前でひとつに括った図がでてきます.この図は抽象的なもので,理解はちょっと難しいです.まずスケールがありません.
図1 ジオサイトとジオパーク
これはジオパークとして様々な広さが考えられるからです.そして,ジオパークとして括るためには,ある考え=コンセプトが必要なのです.どういう考えでジオパークという傘を広げるかが問題となります.そして,ジオサイトとは,名称にジオがついているけれど,地質学的なことに限らないと私は思うようになりました.
3.“Rock” “Green” “Café”
エダーさんと一緒に高知から室戸に向かう途中で,海のよく見えるコーヒー屋さんに入りました.そのコーヒー屋さんは「ROCK GREEN CAFE」という名前で,入り口に赤地に白のペンキで店の名前が書いてありました.この看板にエダーさんは大変興味をもって,写真を撮っておられました.私は,英語としてもフランス語としても,文法的にも誤りだらけで,とても恥ずかしい感じがしていました.また,エダーさんがなぜ興味をもったのか,その時はわかりませんでした.4日間,一緒に旅をして,ジオパークを考えるときに,この“Rock” “Green” “Café”は重要であると気がつきました.そして,図2のような三重構造のモデルを考えるようになりました.
「ROCK GREEN CAFE」の看板
図2 “Rock” “Green” “Café”の3層構造.写真は上から池川のお神楽,室戸岬亜熱帯樹林,日沖の枕状溶岩
4.“Rock”のいろいろ
“Rock”はまさにジオパークのベースです.地質学的におもしろい事象のことです.エダーさんとともに訪ねたのは,地質学的なところでは,日沖の枕状溶岩,室戸岬斑レイ岩など,地理学的なところでは,長者地すべり地形,仁淀川の川筋などでした.また,高知大学海洋コア総合研究センターも訪問しましたが,エダーさんはそこで大変感激され,是非とも高知大学海洋コア総合研究センターがジオパークの中に含まれることを希望されました.つまり,高知大学海洋コア総合研究センターをジオサイトのひとつとすることです.
“Rock”はジオパークの基本的な構成要素です.図2のようにジオパークの基盤です.そして,“Rock”は単に岩石ではなく,あるいは地質事象だけではなく,地理学的な事象,すなわち地形,河川,地下水等あらゆるものを含んでいます.と同時に,高知大学海洋コア総合研究センターに代表されるような上質の科学で研究されていることも重要な要素です.四国で訪問した地域では,説明版がもう少し配備されれば立派なジオサイトになると,エダーさんは感想を述べられていました.
5.“Green”のいろいろ
立ち寄った「ロックグリーンカフェ」は,海岸にはりだした大きな岩の上に,こんもりした木が生い茂っていて,緑が夕日の赤い海に映えてとても美しいところでした.エダーさんのイメージする“Green”は“Rock”の上に生活している植物,動物など,あるいはそれをひっくるめたエコロジーとか里山などの概念や,運動や,エコツーリズムなどをさします.四国では,室戸岬亜熱帯樹林および海岸植物群落を見学しました.サボテン,リュウゼツランなどが生い茂り,ブーゲンビリアも咲いていました.まだ春浅かったので,蝶は飛んでいませんでしたが,鳥は何種類も飛んでいて,鳴き声で何の鳥かわかるものもいました.
私たちは,何気なく町を歩いていても,沈丁花の香りで春を知り,家の前の小さな植え込みに植えられた草花を愛でています.野山に入れば,美しい花,にぎやかな昆虫たちに眼を奪われます.花の名前を知りたいと思います.できたら,窓辺で花を咲かせたいと思います.動植物は,私たちに身近です.
“Green”を愛でることは比較的普通に行います.でも“Green”から“Rock”に眼を移すことはあまりやりません.四国の報告会には高知県立牧野植物園の研究員が見えられ,「植物は動けないから,その生えている“Rock”に大きく影響されます.たとえば,蛇紋岩地域には特有な植物相があります.この研究は四国が発祥の地です.」と話されました.蛇紋岩地域の植生が他地域と違うことは,蛇紋岩地域の研究者は知っていますが,蛇紋岩を研究していないとあまり知りません.山登りを趣味としている人は,同じ高山でもコマクサの生えているところと生えないところがあることを知っています.でも,その違いが山を形成している岩石に基づいているらしいことを知っている人は数多くありません.あるいは,高山植物がよく見られるのは,崖錘の多い地形だということを知っている人は多くありません.
観光関係の方からはエコツーリズムはすでにビジネス段階に入っているという説明がありました.植物や動物が好きで山歩き,里歩きをしている人は増えてきたということです.この人たちにもっと「ジオ」を知ってもらいたいと思います.“Green”から“Rock”にもっと眼を向けさせる必要があるようです.
6.Caféのいろいろ
私たちは四国の「ロックグリーンカフェ」にお茶を飲むために入りました.Caféは楽しいところで,休むところです.Caféはもっと意味を拡大できます.誰でも楽しいと思うところです.四国では司牡丹など美味しいお酒のテースティングをしました.カツオ料理も楽しみました.吉良川では町並みを見学し,お蔵を利用したコーヒー屋さんでロック音楽を楽しみました.長者地域ではお神楽を楽しみました.もちろん四国を代表する八十八箇所の一つである最御崎寺にも行きました.途中でカヌーの発着所やハングライダーの基地があることも教わりました.ジオパークにもCaféが必要なのです.
Caféはもっとも卑近な食・芸術・スポーツ・町並み・宗教・文学等さまざまな分野に広がります.Caféとは楽しいところ,知的なところを意味します.池川のお神楽をみて,なぜここに,こんな文化が残っているか考えました.四国の特殊な歴史が思い浮かびました.その後,長者地すべり地を見学しました.非常に興味深い文化を見ました.なぜ地すべり地に高い文化が残っているのかを考えました.
四国の宗教もCaféと考えます.八十八箇所のひとつである最御崎寺では,お寺の独自の歴史の説明を聞きました.お経も聞かせていただきました.お寺自身がとてもおもしろい存在に感じました.空海が銅などの鉱山開発をよくしていたことを知っていましたが,その説明が不要なほど,お寺への坂道を歩く効果がありました.なんだか癒されるのです.ああ,「ジオパークへ行くと癒される」と多くの人が感じることが1番大切のように思いました.ジオパークで癒されて楽しいと思えば,リピーターになります.リピーターになって,何度も通ううちに「ジオ」の意味がわかってくればいいのではないかと思うようになりました.Caféはジオパークの入り口です.まずは,人々がジオパークにやってこなければ始まらないと思いました.
7.“Rock” “Green” “Café”を結びつけるのは
ジオパークにやってくる人々は地質学者たちではありません.素晴らしい“Rock”があっても,そんなに簡単に地質巡検はできません.まずは“Café”でジオパークを楽しみ, “Café” から“Green”を通して “Rock”へだんだんと近づいていくのでいいのではないでしょうか(図3).これは,誰か手引きしてくくれる人が必要です.ガイド,あるいは,最近の言葉ではインタプリターの力の見せ所です.でも無理にジオに結び付けないでください.折角ジオパークを訪れた人が「なんだかわからない」「なんだかとても難しい」と思われたら,二度とジオパークには近づいてくれないかもしれません.ジオを“Rock”をほんとうに愛している人が,その理解しているところをわかりやすく説明することが是非とも必要です.あるいは,ジオパークを訪れている人が“Green”や“Café”のレベルで知的なものを欲しているかもしれません.これらの要求に応えて,その上で,ジオの魅力を語っていく必要がありそうです.
図3 “Rock” “Green” “Café”を結ぶのはガイドの力
8.活動のベースは博物館
おそらく,ジオパークができたときには,ジオパークの中にある自然史系博物館がジオパーク運動のベースになるのではないでしょうか.四国の見学した地域には,横倉山自然の森博物館と佐川地質館がありました.ジオパークを訪れる人は,まずは博物館にいって,少し説明を聞き,博物館を通して,ガイドさんを紹介してもらって,ジオパークの楽しみ方を習っていくのではないでしょうか.こういった活動は博物館にとっても,博物館の質の向上にずいぶん役に立つように思います.
9.日本型のジオパークをめざして
現在世界中で53箇所以上のジオパークが存在し,活動しています.日本はこれからです.ヨーロッパや中国の先達のジオパークをよく学んで,新しい,質の高い,日本型のジオパークを模索していきたいと思います.日本地質学会の会員の皆様,ジオパーク運動に一肌脱いで見ませんか.ジオパークのガイドは日本地質学会の会員がもっとも適しているように思います.“Rock”を知悉している会員が自ら“Green”と“Café”を学んで,ジオパークを最も楽しむ人になったらよいと思うのです.
地質マンガ 「サンプルリクエスト」
地質マンガ
「サンプルリクエスト」
戻る|次へ
解説
ボーリング採取された掘削コア(柱状試料)は、船上で基本的な分析と
記載が行われ、そして個別分析のためにサンプリングされます。各研
究者は少しでも良いサンプルを持ち帰ることが至上命題です。たいてい
は専門分野によってうまく棲み分けるのですが、本当に重要な部分(断
層帯や地層境界など)はみんなのリクエストが激突します! コアには
リクエストのフラッグが立ち並び緊張感が走ります。研究チームは分裂
の危機に!?
No.0026 2008/4/15 geo-Flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.026 2008/04/15 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】日本地質学会第115年総会開催のお知らせ
【2】ジオパークと“Rock”・“Green”・“Café”
【3】日本地質学会各支部イベント案内(中部支部・関東支部)
【4】2008年度会費払込(次回引き落としについて)
_____________________________________________________
【5】地質マンガ「サンプルリクエスト」
【6】第52回粘土科学討論会講演申込(地質学会共催)
【7】第6回国際アジア海洋地質学会議:締め切り延長のお知らせ
【8】産業技術総合研究所地質調査総合センター第12回シンポジウム
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】日本地質学会第115年総会開催のお知らせ
──────────────────────────────────
2008年5月25日(日) 17:30〜19:00
会場 幕張メッセ 国際会議場(3F 303会議室)
会則により,本総会は役員ならびに代議員による総会となります.ただし,
正会員は総会に出席し,意見を述べることができます.
詳しくはこちら、
http://www.geosociety.jp/outline/content0054.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】ジオパークと“Rock”・“Green”・“Café”
──────────────────────────────────
理事・矢島道子(地質情報整備・活用機構)
ジオパークとはどういうものかをイメージすることはなかなか難しいところがあ
るように思います.ジオパークとして括るためには,ある考え=コンセプトが必
要なのです.どういう考えでジオパークという傘を広げるかが問題となります.
そして,ジオサイトとは,名称にジオがついているけれど,地質学的なことに限
らないと私は思うようになりました.
詳しくは、http://www.geosociety.jp/faq/content0073.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本地質学会各支部イベント案内(中部支部・関東支部)
──────────────────────────────────
■■中部支部■■
年会シンポジウムの案内と個人講演受付
日時:2008年6月28日(土)
会場:新潟大学五十嵐キャンパス:自然科学研究科棟大会議室
シンポジウム「ひずみ集中帯とフォッサマグナ」
地質見学会「中越東頸城丘陵の地形と地質構造」
案内:小林健太・豊島剛志・立石雅昭
日程:2008年6月29日(日)
懇親会 6月28日(土)18:00-20:00
会場 新潟大学五十嵐キャンパス構内
個人講演・見学会・懇親会等申込締切:5月30日(金)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
■■関東支部■■
第2回研究発表会「関東地方の地質」・支部総会(委任状をご提出ください)
6月8日(日)に「関東地方の地質」に焦点をあてた研究発表会を開催いたし
ます. なお当日は,研究発表会に引き続き2008年度支部総会も予定されて
おります.
あわせてご出席のほどよろしくお願い申し上げます.支部会員の方で総会に
欠席される方は委任状をお願いいたします.
日 時:2008年6月8日(日)10:00〜17:00
会 場:早稲田大学 国際会議場
詳しくは、http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2008年度会費払込(次回引き落としについて:6/23)
──────────────────────────────────
2008年4月〜2009年3月の会費をご請求しています.未納の方には督促請求書を送
付いたしますが,早急にご送金をお願いいたします.督促請求は5月末頃の予定で
す.なお、次回は,6月23日(月)に引き落としの予定です(2008年およびそれ以
前の会費が未入金の方対象).
まだ会費を未入金の方で今後自動引き落としを希望される方は,「自動払込利用申
込書」(ニュース誌巻末掲載)をご利用の上,5月12日(月)までにお申し込み下
さい.
なお、2008年度(本年度)分までの「院生割引申請者」申請受付は終了しました.
次回引き落とし予定:6月23日(月)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0052.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質マンガ「サンプルリクエスト」
──────────────────────────────────
好評★地質マンガ連載中!!
「地質学会がマンガをはじめたって」
「まじで? フツーしなくない」
「学会のマンガってどーよ?」
「やべえ おもしれえよぉ!」
http://www.geosociety.jp/faq/content0057.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】第52回粘土科学討論会講演申込(地質学会共催)
──────────────────────────────────
会 期:2008年9月3日(水)〜5日(金)
会 場:沖縄ポートホテル(沖縄県那覇市西1-6-1,TEL. 098-868-1118)
申込受付期間:2008年5月13日(火)12:00〜6月10日(火)必着です.
参加登録料:会員(共催学会員を含む)3,000円,学生会員 1,000円,
非会員 5,000円
講演要旨締切:2008年7月25日(金)必着
懇親会:9月3日(水)18:30〜(於 沖縄ポートホテル)
見学会:9月5日(金)工業技術センター,やちむんの里−読谷,美ら海水族館,
万座毛(ノジュール)(予定)会費:未定
詳しくは、http://wwwsoc.nii.ac.jp/cssj2/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】第6回国際アジア海洋地質学会議:締め切り延長のお知らせ
──────────────────────────────────
平成20年8月29日(金)〜9月1日(月)の4日間,高知工科大学にて開催
される第6回国際アジア海洋地質学会議(6th International Conference
on Asian Marine Geology: ICAMG VI)の事前参加登録および講演要旨
投稿の締め切りが,大幅に延長されました.
新しい締め切りは,6月25日です(登録料の早期割引も6月25日まで延長).
皆様,奮ってご参加ください.
詳しくは下記公式ウェブサイトをご覧ください(日本語概要も閲覧可).
http://ofgs.ori.u-tokyo.ac.jp/ICAMG6/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】産業技術総合研究所地質調査総合センター第12回シンポジウム
──────────────────────────────────
「地下水と岩石物性との関連の解明〜産総研のチャレンジ〜」
日時:2008年5月8日(木)13:00-17:30(12:30開場,ポスター閲覧可能)
場所:秋葉原ダイビル5F 5B会議室
入場無料 定員:100名
詳しくは,http://www.gsj.jp/Event/080508sympo/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。geo-Flashは
送信用であり、返信はできません。
No.0027 2008/4/24 geo-Flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.027 2008/04/24 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】第1回「地質の日」迫る
【2】博物館GWスペシャル
【3】野外調査の季節到来 でもちょっとこんなことにも気をつけて!
【4】国際地学オリンピック日本委員会組織委員会が発足
_____________________________________________________
【5】IYPE日本 Newsletter(NO.4) (NO.5) より
【6】日本地質学会 各支部の5-6月のイベント
【7】北海道洞爺湖サミット・「地質の日」記念シンポジウム『洞爺湖・有珠山との共生』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「地質の日」とは?
──────────────────────────────────
5月10日は、第一回目の「地質の日」です。
なぜこの日なの?どうして?・・・ちょっとWEBサイトを覗いてみて下さい。
はは〜ん!これって今ならトリビア。
http://www.gsj.jp/geologyday/
イベントもたくさん開催されます。皆さんの力で盛り上げましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】行ってみよう!! GW・「地質の日」のイベント特集
──────────────────────────────────
ゴールデンウィークは、全国の博物館・大学・関連機関で、地質の日に関
連したイベントが盛りだくさん。あなたもイベントに参加して、身近な地質
を感じてみませんか?
ゴールデンウィーク イベントカレンダー
http://www.geosociety.jp/name/content0011.html
なお,紹介するイベントの中には事前申し込みが必要なもの,対象者・対象年齢に制限
があるもの,参加費が必要なものなどがありますので,お出かけの際には,主催する博物
館へ詳細をお問い合わせ下さい.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】安全な野外調査の心得
──────────────────────────────────
野外調査のシーズン到来ですが、安全は何にも勝る重要なことです。
1)調査計画を事前に第三者へ連絡していますか?
2)無理の無い計画になっていますか?
3)安全装備は十分ですか?
「野外調査」や「安全」をキーワードにインターネットで検索してみて下さい。
いろいろなノウハウや事例をみることができます。自分だけは大丈夫という
ことは、けしてありません。皆さんの安全にたいする取り組みや事例など、
geo-Flashへお知らせください。あなたの体験が、皆さんの安全に貢献します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】国際地学オリンピック日本委員会組織委員会が発足
──────────────────────────────────
現在第1次選抜(参加者319名、通過者22名(中学生チャレンジャー1名を含む))
を終え、5月31日の第2次選抜(実技・面接)の準備を進めている日本委員会は、4
月19日に正式に組織委員会を立ち上げました。組織委員会は、濱野洋三委員長、
藤井敏嗣副委員長、上田誠也委員、木村学委員、久城育夫委員、斎藤靖二委員、
平朝彦委員、佃栄吉委員など総勢14名で構成されています。また同時に運営委員
会も25名の委員で発足しました。今年度は2次選抜通過者4名を8月31日から9月7日
のフィリピンでの第2回オリンピックに派遣します。また、2009年8月末から1週間
(予定)台湾で開催予定の第3回オリンピックに向け、2008年10月1日〜12月10日
に参加者募集、12月21日(日)に国内第1次選抜(筆記)、2009年3月29日(日)
に国内第2次選抜(実技・面接)が予定されています。
国際地学オリンピックについては、http://www.jpgu.org/ieso/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】IYPE日本 Newsletter(NO.4)(NO.5) より
──────────────────────────────────
国際惑星地球年日本事務局から配信されるNewsletterの中から、地質学会に関連
する内容をご紹介いたします。
Newsletter No.4 (2008.4.15配信)
【3】第1回「地質の日」...2008.5.10
http://www.gsj.jp/iype/at/jp/eNL/n04.html
Newsletter No.5 (2008.4.22配信)
【1】ユネスコ写真コンテスト
【2】IYPEの横断幕,つくば駅近くの陸橋に
【3】ポスターやパンフレットの提供
http://www.gsj.jp/iype/at/jp/eNL/n05.html
国際惑星地球年日本 事務局:http://www.gsj.jp/iype/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】日本地質学会 各支部の5-6月のイベント
──────────────────────────────────
■■北海道支部■■
総会・個人講演会・地質学講演会
日時:2008年5月10日(土)(地質の日) 10:30〜17:00
場所:北海道大学高等教育機能開発総合センター
地質学講演会「知られざるシレトコー知床半島の地質ー」
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
■■関東支部■■
地質技術伝承講習会:地質技師長が語る地質工学余話シリーズ
第2回:建設に伴う活断層調査をささえた地質技術屋のはなし
講師 豊蔵 勇氏(ダイイヤコンサルタント 技師長)
日時:2008年5月10日(土)(地質の日)14:00〜16:00
会場:国立科学博物館 日本館4階大会議室
申込方法:ジオ・スクーリングネット(GSネット)にて
詳しくは、関東支部HP http://kanto.geosociety.jp/
■■中部支部■■
年会シンポジウムの案内と個人講演受付
日時:2008年6月28日(土)
会場:新潟大学五十嵐キャンパス:自然科学研究科棟大会議室
シンポジウム「ひずみ集中帯とフォッサマグナ」
すべての申込締切:5月30日(金)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
■■近畿・西日本・四国■■
近畿・西日本・四国三支部合同例会
日時: 2008年 6 月 29 日(日)10:30〜
会場: 兵庫県立人と自然の博物館
公開講演会「丹波の恐竜化石発掘」
シンポジウム「篠山層群周辺の地質発達史」
個別ポスター発表申込締切:6月2日
詳しくは、http://kinki.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】北海道洞爺湖サミット・「地質の日」記念シンポジウム『洞爺湖・有珠山との共生』──────────────────────────────────
北海道洞爺湖サミット・「地質の日」記念シンポジウム
『洞爺湖・有珠山との共生』平成20年 北海道立地質研究所 調査研究成果報告会
日時:2008年5月13日(火)10:00-16:15(9:30開場)
場所:札幌エルプラザ 3階ホール(札幌市北区北八条西3丁目)
入場無料(定員300名)
事前に参加申し込みをお願いします。
詳しくは、http://www.gsh.pref.hokkaido.jp/topics/chishitsunohi/chishitsun
ohi_event.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.0028 2008/5/9 geo-Flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.028 2008/05/09 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】地質の日(5/10)関連イベント 盛りだくさん!!
【2】5月の博物館イベント・特別展示カレンダー
【3】地質技術伝承講習会:地質技師長が語る地質工学余話シリーズ
【4】化石チョコレート発売開始!(化石のチョコレートではありません)
【5】広島大学大学院理学研究科地球惑星システム学専攻助教公募
【6】地質マンガ2本立て! 「船なのに」&「正月のごちそう」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】地質の日(5/10)関連イベント 盛りだくさん!!
──────────────────────────────────
明日、5月10日は、いよいよ「地質の日」です。
地質の日は、人々が地質への理解を推進する日として、制定されました。さまざ
まなイベントや日常の活動を通じて、地質をより身近に感じて下さい。
地質学会では5月1日に「地質の日」関連イベントのプレス発表を行いました。
地質の日の関連イベントが各地で催されています。
詳しくは、http://www.gsj.jp/geologyday/event.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】 5月の博物館イベント・特別展示カレンダー
──────────────────────────────────
今月から、全国各地の博物館で開催されるイベント・特別展示を、カレンダー形式で
ご紹介します。
楽しい体験イベントや野外観察会はもちろん、貴重な展示や講演会も盛りだくさん!!
みなさん,ご家族やお友達といっしょに出かけてみませんか。
詳しくは、5月の博物館イベント・特別展示 カレンダーでcheck!!
http://www.geosociety.jp/name/content0012.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】 地質技術伝承講習会:地質技師長が語る地質工学余話シリーズ
──────────────────────────────────
第2回 「海上空港の地質」
主催:日本地質学会関東支部
日時:2008年5月10日(土)14:00〜16:00
場所:国立科学博物館日本館4階大会議室
内容:この数十年間,わが国の社会基盤施設(道路・鉄道・空港?都市施設・ダム・
地すべり施設など)は著しく整備されてきました.これら施設の建設にあたり,
応用地質学もまた大きな役割を果たしてきました.今,これら応用地質学を支え
てきた地質技術者から地質技術伝承の講習会を開催いたします.
事前申込:不要
詳しくは、http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】 化石チョコレート発売開始!(化石のチョコレートではありません)
──────────────────────────────────
産総研監修の化石レプリカ・チョコレートが発売されました。解説書付きです。
国立科学博物館、千葉県立中央博物館、名古屋市科学館などで好評発売中。
ぜひ博物館の思い出にいかがですか?通販はされていませんので、レアものです。
今回特別に5月25日からの日本地球惑星科学連合大会で販売されますので、
ぜひゲットして下さい!
詳しくは、、、 http://www.geobox.jp/ まで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】 広島大学大学院理学研究科地球惑星システム学専攻助教公募
──────────────────────────────────
1. 職種および人員: 助教 1名
2. 採用条件: 任期5年、1回更新可能
3. 専門分野: 本専攻の中期計画の目標 「地球惑星進化素過程の解明と地球環
境の将来像の予測」に沿い、地球惑星システムにおける地球環境,地球古環境変
遷,生命の進化に関連した分野
4. 応募資格等:
(1) 博士の学位を有すること (2) 本専攻の現研究分野グループ(地球環境進化
学、地球造構学、資源・地球惑星物質学、地球惑星内部物理学、同位体地球惑星
科学、表層環境地球化学)を基盤として意欲的に研究にあたり、専攻の発展に大
きく貢献しうること (3) 学部および大学院の授業を担当し、学部生・大学院生
の教育と研究指導に意欲的であること (4) 本専攻で実施している「大学院教育
改革支援プログラム:世界レベルのジオエキスパートの養成 」に積極的に貢献し
うること
5. 応募締切り: 平成20年6月20日(金)必着
詳しくは、
http://www.geol.sci.hiroshima-u.ac.jp/~info/COM/koubo.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質マンガ2本立て! 「船なのに」&「正月のごちそう」
──────────────────────────────────
今回は2二本立て。さてどんなかな?
投稿お待ちしています。絵が描けない人はアイディアだけでもOK!
http://www.geosociety.jp/faq/content0057.html
地質マンガ 船なのに
地質マンガ
「船なのに」
戻る|次へ
地質マンガ 正月のごちそう
地質マンガ
「正月のごちそう」
戻る|次へ
地質フォト:南アフリカのTransvaal系(20.5〜23.5億年)
南アフリカのTransvaal系(20.5〜23.5億年) Transvaal System(20.5〜23.5Ga-old)in South Africa
写真:諏訪兼位
写真1
写真2
解説:
写真1. Blyde River CanyonのTransvaal系.
南アフリカの首都Pretoriaは,海抜1400mのTransvaal高原の町である.Pretoriaの東方約200kmのBlyde River Canyonでは,Tranvaal系の地層がGrand Canyonさながらの景観を呈する.(1970年3月7日撮影).
写真2. Drakensberg断層崖のTransvaal系.
Transvaal高原は東へ向かって高くなり,Drakensberg山脈に達する.山脈の東側は急崖になっており,Transvaal系の地層が見事に露出している.(1970年3月7日撮影).
Transvaal系は,第1図に示すように,東西900kmにわたって広がり,50万km2の分布域を示す.Transvaal系の全層厚は15,000mで4層群が識別される.下位から,Wolkberg層群(苦鉄質溶岩・グレーワッケ・珪岩),Chuniespoort層群(Black Reef珪岩・苦灰質石灰岩・縞状鉄鉱層),Pretoria層群(珪岩・頁岩・アルコース・火山岩・漂礫岩・ストロマトライト質炭酸塩岩),Rooiberg層群(珪長岩)と重なる.
Chuniespoort層群中に胚胎する大規模な縞状鉄鉱層の最大層厚は2,000mに達する.この縞状鉄鉱層は1,000kmにわたってつづいている.
大陸の位置を,中生代の大陸移動以前に復元すると,オーストラリア,アフリカ,南米,北米,ロシアの縞状鉄鉱層地帯はよく連続し,ひとつのベルトをつくる.いずれも20億から25億年前に形成されたものである。
地質フォト:ジローナ(スペイン)のカテドラルの貨幣石石灰岩
ジローナ(スペイン)のカテドラルの貨幣石石灰岩:Nummulites limestone ovserved in the Catedral de Gerona, Catalunya,Spain
写真:大友幸子(山形大学) Yukiko Ohtomo (Univ. Yamagata)
写真1
写真2
解説:
10年以上前にバルセロナでのある時のお茶会で日本人マダムから,「ジローナのカテドラルのところにアーモンドの化石がたくさんはいっているのよ」という話を聞いた.「はて??アーモンドの化石とは???」と疑問に思いさっそく見学に行った.
ジローナはバルセロナの北東約100kmに位置する町である.小高い丘の一番高いところに11〜18世紀にかけて造られたカテドラルがあり、中世の雰囲気を残す旧市街がそれを取り囲んでいる.駅からカテドラルめざして旧市街の坂をのぼっていくと,バロック様式の正面の前には長い階段が続いていた.階段を登りながら足元を見ると全面貨幣石である(スケール直径約2.5cm).「ああ,これをアーモンドの化石と思ったのか」と妙に納得.カテドラルの周辺を歩くと坂の一角に露頭が顔を出していて,カテドラルは貨幣石石灰岩の小高い丘に建っているようである.始新世にカタルーニャ地方北部から内陸に侵入した海の石灰岩である.
地質フォト:愛媛県八幡浜大島のシュードタキライト
愛媛県八幡浜大島のシュードタキライト:Psudotachylite in Yawatahama-Oshima, Ehime Prefecture
写真・解説:宮下由香里 Yukari Miyashita
写真1
写真2
写真3
写真4
解説:
四国西部に位置する八幡浜大島には,南から真穴層,大島変成岩,三波川南縁帯片岩および三波川変成岩がスラストで接して分布している.これらは転倒背斜や断層により,複雑な地質構造を呈する.
大島変成岩は主として火成岩起源の変成岩から構成され,少量の堆積岩起源の変成岩を挟む.これらは下部地殻(地震学的にも地質学的にも)からの上昇過程において,運動方向の異なる4回のマイロナイト化作用を受けている.
シュードタキライトを含む断層帯は,大島変成岩中に3帯認められる.面構造の切断関係の解析から,シュードタキライトはマイロナイト化作用III(角閃岩相〜緑色片岩相)後,同IV(緑色片岩相)の前に形成されたことが明らかとなった.なお,八幡浜大島西岸に分布する変成岩類(シュードタキライトを含む)は,2004年に国の天然記念物に指定されました.
写真1.剪断面に高角な割れ目に注入するシュードタキライト.主剪断面よりも,二次剪断面沿いの注入脈が目立つ.
写真2.シュードタキライト脈の周縁にはより濃い黒色の急冷相が見られる.
写真3.幅5cmに達するシュードタキライト脈.複数条のシュードタキライト脈がステップし,プルアパート状に開いた部分と考えられる.
写真4.シュードタキライト形成後にマイロナイト化作用を受けた部分.互層状の片状岩に見える.このマイロナイト化作用IVは,三波川南縁帯との境界付近にのみ見られる.
参考文献
小松正幸,宮下由香里,米虫 聡,1997,四国西部,八幡浜大島のシュードタ キライト.地質雑,Vol.103, No.8, XXV-XXVI
小松正幸,宮下由香里,米虫 聡,1998,八幡浜大島シュードタキライト見学案内書,pp.37.
地質フォト:ピレネー東部のRoses花崗閃緑岩体の不均質延性剪断帯
ピレネー東部のRoses花崗閃緑岩体の不均質延性剪断帯:Inhomogeneous ductile shear zones in the Roses granodiolite, eastern Pyrenees
写真:大友幸子(山形大学) Yukiko Ohtomo (Univ. Yamagata)
写真1
写真2
解説:
ピレネー東部のマイロナイト帯の東端,地中海に 面して分布するRoses花崗閃緑岩体中にはNW-SE方向の主に左横ずれの小規模な 剪断帯が無数に発達している.
写真2の横方向に見える黒い筋の部分がすべて剪断帯.アプライト 脈が左横ずれ変位している.
(写真2右)海岸沿いの露頭.黒い筋に見えるところが剪断帯.
地質フォト:千鳥が滝の中新統川端層とソールマーク
千鳥が滝の中新統川端層とソールマーク
千鳥が滝の中新統川端層とソールマーク:
Miocene Kawabata Formation and sole marks at the Chidori-ga-taki (Chidori Falls), Yubari, Hokkaido
写真:川村信人(北海道大学理学院自然史科学専攻
解説:川村信人・川上源太郎(北海道立地質研究所)
写真1
解説:
『千鳥が滝』は,夕張市滝の上公園内にある夕張川河床の段差地形である.写真(上)は2005年10月撮影.下流部が滝つぼ状にやや深くなっており,千鳥が淵とも呼ばれる.
北海道では有数の地層の大規模露頭であり,良い巡検場所ともなっている.なお,この河床平坦面が自然侵食面なのか,あるいは人工的なものかは不明である. 千鳥が滝周辺を含む夕張山地に分布する新第三系中新統川端層は,軸流方向の重力流によって形成された全層厚3,000 mに達する地層であり,島弧衝突に伴うフォアランド堆積盆(フォアディープ)を埋めたconfined turbidite systemであると考えられる.千鳥が滝付近では,走向NNW,傾斜60Wでほぼ同斜構造をなす.写真に写っている地層の厚さは100 m程度である. 千鳥が滝の地層は,シルト岩・細粒葉理砂岩・粗粒タービダイトの互層からなる.葉理砂岩には,単層上面にやや不規則なリップルマークを持つものもある.粗粒タービダイトは含礫極粗粒砂〜細粒砂岩の級化層で,単層上部にシルト片を含む場合が多い. タービダイトの単層底部には,頻繁にソールマークが認められる.写真(中・下)は,デジタルカメラにより撮影した9枚の写真(2001年6月撮影)をパノラマ合成したもので,掲載の都合上その中央部で2分割した.全景写真(上)のほぼ中央部にあるこの露頭は,2005年頃の春先の雪どけ増水で崩落し,現在はそのほとんどが失われている.ソールマークはフルートキャストを主体とし,グルーブキャストが混在している.無方向・団瘤状のものはロードキャストであり,フルート・グルーブキャストも未固結時変形により形状が改変されているものが多い.古流向を判定できるものでは,写真の右→左方向であり,NNW→SSE方向となる.川端層の全体的な傾向として北→南の古流向が卓越しているので,それに整合的である.
古文書によると,有名なB.Sライマンが日本人助手たちとともに舟で夕張川を遡った時,この千鳥が滝に進路を阻まれて断念し,後日あらためて陸路で上流へ調査の歩みを進めたとされている.またその際川岸で採取した石炭の転石が,後の夕張炭田の発見につながったとも伝えられている.
地質フォト:モンゴルのゲルと果てしなく広がる大地
モンゴルのゲルと果てしなく広がる大地
写真:後藤晶子(名古屋大学年代測定総合研究センター)
解説:後藤晶子・高橋亮平(北海道大学大学院理学研究院)・久田健一郎(筑波大学大学院生命環境科学研究科)
写真1
写真2
解説:
Eurasian Geological Seminar 2007(EGS 2007:モンゴルにて開催)にともなっておこなわれたフィールド巡検では,モンゴルの自然や文化を十分に堪能することができた.巡検の途中に現地の人の生活空間であるゲルを何度か突撃訪問したが,快く迎え入れ馬乳酒やチーズをご馳走になった.また,なだらかな山の麓までまっすぐにのびる道ではモンゴルの大地の雄大さを感じることができた.
写真1:ウランバートル近郊でのゲルの風景.ゲルの周辺では馬やヤギ,羊などが飼われている.ゲルの屋根の上ではチーズが天日干しされている.このチーズは少し硬くパサパサしている.いたるところでバイクを見かけ交通手段としてバイクが重宝されていることが伺える一方で,小学生ぐらいの子供が颯爽と馬を走らせている光景が見られる.
写真2:ザーマル(Zaamar)からボロー(Boroo)への草原を貫く道.ひたすら続く道を数時間走り続けるのが普通で,運転手の気分に応じて草原をショートカットすることは日常茶飯事である.貴重な(?)岩場を見つけて休憩となったが,炎天下の中に逃げ場がなく非常に暑かった.休憩の度にジュースや果物,お菓子が振舞われる.
地質フォト:セントヘレンズ山巡検
IODPジオハザードワークショップとセントヘレンズ山巡検
IODPジオハザードワークショップとセントヘレンズ山巡検
IODP Geohazard Workshop and Field excursion to Mt. St. Helens IODP Geohazard Workshop and Field excursion to Mt. St. Helens
写真:川村喜一郎(深田地質研究所),山田泰広・宮川歩夢(京都大学))
写真1:セントヘレンズ山(Johnston Ridge観測所から)
写真2 :爆風によってなぎ倒された森林
写真3:爆風でなぎ倒された森林(拡大)
写真4
解説:
8月26日から31日までの6日間,米国オレゴン州ポートランドの宿泊施設McMenamins Edgefieldにて,IODPジオハザードワークショップが開催された.このワークショップには60名を超える参加があり,海洋における今後のジオハザード,特に海底地すべりに関する様々な課題が議論された.海底地すべりは,沈み込み帯で発生するもの,非活動的縁辺部で発生するもの,その他(主として火山体崩壊によるもの)の3つに分類される.まずハワイ島周辺海域やエトナ火山を例とした火山体崩壊に伴う海底地すべりの可能性について議論された.日本にも多くの山体崩壊の事例やそれに伴う津波の発生の事例がある.特に,寛政4年の雲仙普賢岳周辺の眉山の崩壊とそれに伴う津波の発生は,島原大変として絵図に記録されており,今後のこのような研究において重要な物証であると考えられる.次に非活動的縁辺部の例として,大西洋沿岸での大規模海底地すべりの発生要因(主として海水準低下に伴うメタンハイドレートの崩壊)やその発生頻度,発生間隔などが議論された.海底地すべりが小規模であったとしても,その運動速度や発生水深によって津波が増幅される可能性があることが議論された.日本周辺などの沈み込み帯でも,海山衝突に伴う付加体の巨大崩壊が考えられているが,話題の中心ではなかった.しかし,海底活断層の活動頻度などを議論する上で,最近,沈み込み帯での小規模海底地すべりが注目されており,招待講演者の一人である山田のモデリング結果を例にして活発な議論がなされた.参加を通じて,日本から発信できる海底地すべりの情報は多い,と感じた. 28日には会場近くのセントヘレンズ山を巡検し,噴火に伴う山体崩壊地形と崩壊堆積物を観察した.セントヘレンズ山は,1980年に大規模な山体崩壊を引き起こしたことで世界的に有名である.まず同年3月中旬頃,地震が観測されはじめ,3月27日に最初の噴火が山頂部で発生した.その後,5月18日午前8時32分にM5.1の地震が発生し,山体北側が3回に分けて大規模に崩壊した.山体を構成していた岩石は岩なだれ(debris avalanche)となって流下し,爆風によって周囲の森林がなぎ倒されたとの説明があった.
片や陸上,片や海底.しかし両者は地すべりであり,空気と海水で媒質は異なるが,共通するところも多い.我々は陸海を越えてお互いに学ぶ必要があり,それこそが未知の,そして謎の多い海底地すべりへの最善のアプローチであると信じている.
参考文献
須藤茂,2007,セントヘレンズとフッドーポートランド近辺の火山.地質ニュース,636,10-34.
地質フォト:ハワイ島巡検
IODP Exp.303&306の2nd post-cruise meetingのハワイ島巡検
IODP Exp.303&306の2nd post-cruise meetingのハワイ島巡検 :
Field excursion at Island of Hawaii in 2nd post-cruise meeting of the IODP Exp.303&306
写真:川村紀子(産業技術総合研究所)、川村喜一郎((財)深田地質研究所)
写真1:ハワイ島キラウエア,プウオオベントの溶岩
写真2:プウオオベント周辺ナパウトレイルで見られるピットクレーター
写真3:プウオオベント周辺ナパウトレイルで見られる溶岩樹
写真4:Chain of Craters Roadで見られる溶岩流
解説:
2007年5月12日にハワイ島ヒロからキラウエア,Chain of Craters Roadを巡る巡検が行われた.巡検のホストは,ハワイ大学Roy H. Wilkens博士で,日本からは川村喜一郎(深田地質研究所),川村紀子(産業技術総合研究所)が参加した.ワイピオ・ルックアウトは,巡検前日にレンタカーで行った.ヒロから,レンタカーで1時間で行ける. 写真で見られるように,ハワイ島は,マグマの噴出によって山体が成長している一方,ワイピオ・ルックアウトのように,浸食,崩壊が進行しているところもある.
写真1 ハワイ島キラウエア,プウオオベントの溶岩
写真2 プウオオベント周辺ナパウトレイルで見られるピットクレーター
写真3 プウオオベント周辺ナパウトレイルで見られる溶岩樹
写真4 Chain of Craters Roadで見られる溶岩流
地質フォト:ライマン「日本蝦夷地質要略之図」彩色指定稿
ライマン「日本蝦夷地質要略之図」彩色指定稿
ライマン「日本蝦夷地質要略之図」彩色指定稿:The B.S.Lyman’s Color Index Manuscript‘Geological Sketch Map of the Island of Yesso,Japan’(10th May,1876)
北海道大学附属図書館 所蔵
解説:金 光男(自然地質環境研究所
写真1
写真2
写真3
写真4
解説:
日本地質学の偉大な恩人B.S. Lyman(Benjamin Smith Lyman:1835.12.11-1920.8.30;以下ライマンとする)は,1873(明治6)年1月17日来日(副見1990)すると,東京 芝に創設されたばかりの開拓使仮学校(札幌農学校−北海道大学の前身)において教鞭をとる.それから間もない同年4月17日,彼は当時未開地とされた蝦夷(北海道)へ向け横浜を出航すると,以後門弟たちとともに言語に絶する艱難辛苦を重ねている(今井1966,Suzuki & Kim 2003,金・菅原2007など).
3年におよぶ北海道全島調査は,その名目こそ地質調査であったが,地形測量すなわち地図作成という難行をともなう“道無き道を進む”苛烈なものだった.多くの困難を乗り越え彼らはそれを完遂すると,新生明治日本の将来に順風を送る幌内炭田群(石狩炭田)の発見報告などとともに,1876(明治9)年5月10日,日本最初の広域地質図幅「日本蝦夷地質要略之図」を刊行して日本地質学史に金字塔をうちたてる.
本図発刊日である5月10日は,2007年3月13日をもって「地質の日」に制定された. 本地質図について,今井(1963)は「それぞれの分布はきわめて大まかで,いろいろと問題はあるが,限られた踏査路線から複雑な北海道の地質の大勢をよく把握していることに感心させられる」と評価した.
2005年12月,筆者は北海道大学に残されるライマン資料を調査し,日本蝦夷地質要略之図の彩色指定稿が残されることを見出した.北海道大学附属図書館に日本蝦夷地質要略之図は全9葉保存される.その中には福士成豊の所有していたものなど希少資料が含まれる. 日本蝦夷地質要略之図は「日本の地質学100年」(日本地質学会1993)に,ライマンと彼の門弟たちの集合写真とともに掲載されるが,この機会に,このたび撮影した新画像(写真1)を,ライマンの彩色指定稿(写真2)と併せ紹介する.
ライマン彩色指定稿の台紙は39cm×48cm大,刊行された地質図の台紙よりひとまわり小さいが,図そのものの大きさは変わらない.台紙の紙質は粗悪で,薄く,縦横方向にそれぞれ三折にされる.英文個所は全て空白.黒色インクにより印刷された原図に,ライマンが手描き彩色している.多くの部位において彼の筆タッチが見てとれる. 本稿の発見により黒色版が和文・英文の計二刷あったことが明らかとなった.日本蝦夷地質要略之図は層序表記のため七色使用されることから,少なくとも九刷という,かなり複雑な工程を経て印刷されたものであることが想定される.
日本には多色刷り地質図を作成した実績がなかったため,ライマンは当初米国での印刷を希望していたが,試し刷りが届けられ,維新後石版印刷に登用されていた“最後の浮世絵師”たちの仕事振りを実見し,彼は大いに驚かされたのでなかろうか.ライミンは試し刷り原図に彩色指示を入れると,英文原稿をあわせて,いそぎ印刷所に送った.和英併記による微細な地名印刷を黒インク二度刷りにより精確に仕上げた職人たちこそ,かつて髪の毛一本までをも彫り,そして刷りあげた,江戸−明治期異色技能者たちだったのである.
日本蝦夷地質要略之図発刊後,本稿は開拓使に返却され,それが開拓使仮学校→札幌農学校→北海道帝国大学→北海道大学とリレーされ奇跡的に保存された.その間携わったであろう多くの図書館司書の皆様に,ひとりの科学史研究者として深甚なる謝意を贈りたい. 日本蝦夷地質要略之図タイトルの部分画像を紹介する(写真3).「Geological Survey of Hokkaido」の記載にライマンのプライドが輝く.彼が成果を独り占めすることなく全ての調査者を明記したことは,まさにライマンの人柄を示す史実だろう.筆者が米国で初めて本図を手にしたとき,余りの美しさに一瞬にして心奪われたことを思い出す.浮世絵師たちの精緻な仕事振りもさることながら,ライマンの地質記載,とりわけブレーク,パンペリー,アンチセル,モンローらの文献を丁寧に並べ,未開地北海道を調査した先達に対する真摯な表敬記載(写真4)にも心打たれるものがある.
本稿作成に当たりご指導いただいた大森昌衛名誉会員に深謝する.
文 献
副見恭子(1990)ライマン雑記.地質ニュース,427,54-57.
今井 功(1963)地質調査事業の先覚者たち(4)炭田・油田開発の貢献者−ライマン−.地質ニュース,101,29-35.
今井 功(1966)黎明期の日本地質学.ラティス社(丸善),193p.
金 光男・菅原明雅(2007)ライマン鹿角を行く.秋田県博研究紀要,32,1-18.
日本地質学会(1993)日本の地質学100年.706p.
Suzuki & Kim(2003)Lyman’s Contributions to Japan….JAHIGEO Newsletter.5,2-5.
地質フォト:地震が作り出した芸術:巨大乱堆積物
地震が作り出した芸術:巨大乱堆積物
地震が作り出した芸術:巨大乱堆積物:
Artistic outcrop showing earthquake-induced chaotic sediment
写真:山本由弦(産業技術総合研究所)・坂口有人(海洋研究開発機構)
写真1
解説:
まるで絵に描いたように奇妙で,大規模な乱堆積物露頭.
上部鮮新統〜更新統の千倉層群畑(はた)層中に発達するこの露頭は,2007年度初頭に房総半島南部の農業道路建設現場において発見された(Yamamoto et al., 2007 in press).約200万年前の地震によって,砂層が液状化し,剪断強度を失ったそれらが古斜面上を移動したものと結論される(いわゆるliquefied sediment flow).岩体の厚さは約20 mにおよぶ(写真は全体の半分程度しか写っていない).この露頭は,下底面・上端境界を含む岩体全体を運動方向に対してほぼ真横から観察できることから,地震が誘発した海底地すべりの内部構造を把握する上で非常に貴重な資料である.地震動によって液状化・地すべりを起こした岩体は,東西5 km以上におよんでいることから,巨大な津波を引き起こした可能性もある.現在調査を進めている.
この露頭は,現在工事中のため立ち入りが規制されている.地質学的に重要な露頭であることから,工事発注元である(独)緑資源機構によって保存が検討されている. この露頭の詳細については,下記Island Arc誌16巻を参照されたい(Online で閲覧可能).
文献
Yamamoto, Y. Ogawa, Y., Uchino, T., Muraoka, S., and Chiba, T., 2007. Large-scale chaotically mixed sedimentary body within the Late Pliocene to Pleistocene Chikura Group, Central Japan, Island Arc, 16, 2007 505-507, in press.
巡検情報:四国 中央構造線 活断層帯の地形・地質・地下構造
四国中央部の中央構造線活断層帯の地形・地質・地下構造
Geomorpholgy, geology and subsurface structure of the Median Tectonic Line active fault zone inthe central part of Shikoku
岡田篤正1 杉戸信彦2
Atsumasa Okada 1 andNobuhiko Sugito 2
受付:2006年6月30日
受理:2006年8月17日
* 日本地質学会第113年学術大会(2006年高知)見学旅行(H班)案内書
1.立命館大学COE推進機構(歴史都市防災研究センター)
Center for Promotion of the COE(ResearchCenter for Disaster Mitigation of UrbanCultural Heritage), Ritsumeikan University,Kyoto.603-8341, Japan.
2.名古屋大学大学院環境学研究科附属地震火山・防災研究センター
Research Center for Seismology, Volcanologyand Disaster Mitigation, Graduate School ofEnvironmental Studies, Nagoya University.Nagoya464-8601. Japan.
概 要
中央構造線活断層帯は日本列島で最長の活断層であり,変位地形の規模も大きく明瞭である.断層露頭も見事である.1995年兵庫県南部地震(M7.3)の発生以降も,多くの調査機関や大学(研究者)が各種の活断層調査を実施してきた.とくに,ボーリング・反射法地震探査・トレンチ掘削調査などが各所で行われ,中央構造線活断層帯の性質・活動履歴・地下構造などもかなり詳しく判明してきた.こうした成果に基づいて,地震調査委員会(2003)から長期評価も公表された.四国中央部における中央構造線活断層帯の代表的な活断層地形や断層露頭などを見学するとともに,地下構造調査の成果も紹介し,活断層に関する総合的な考察を行い,残された課題や問題点などについて検討する.
Key Words
Median Tectonic Line, Active fault (zone), Tectonic geomorphology, Faultoutcrop (geology), Subsurface structure, Long-term prediction.
地形図
1:25,000 「伊予小松」「西条」「新居浜」「別子銅山」「東予土居」「伊予三島」「讃岐豊浜」「伊予新宮」「阿波池田」「辻」
見学コース
[1日目]8:00 高知大(朝倉)出発→高速道伊予小松IC→西条市湯谷口→新居浜市川口→中萩低断層崖→畑野(四電開閉所付近)→平山→阿波池田泊
[2日目]8:30 池田町白地付近の見学→池田低断層崖→昼間→三野町芝生→16:00 JR土讃線阿波池田駅解散
見学地点
Stop 1 湯谷口の断層露頭(西条市丹原町(旧丹原町)湯谷口).
Stop 2 川口の断層露頭(新居浜市大生院川口).
Stop 3 中萩低断層崖と地層抜き取り調査・トレンチ掘削調査地点(新居浜市中萩).
Stop 4 畑野付近の活断層地形と断層露頭・トレンチ掘削調査地点(四国中央市土居町畑).
Stop 5 西金川〜平山付近の活断層地形とトレンチ掘削調査地点(四国中央市金田町西金川〜半田平山).
Stop 6 阿波池田付近の活断層地形と地質(三好市池田町(旧池田町)市街地).
Stop 7 昼間の断層露頭(東みよし町(旧三好町)昼間).
Stop 8 芝生の活断層地形と断層露頭(三好市三野町(旧三野町)芝生).
1.はじめに
中央構造線は,九州地方から関東地方まで1000km以上延びる第一級の大断層であり,紀伊半島中央部より東では領家変成岩類と三波川変成岩類との境界断層として認定される.しかし,四国では領家変成岩類の南縁に沿って厚層の和泉層群(上部白亜系)が分布しており,北側の和泉層群と南側の三波川変成岩類を境する地質境界断層として中央構造線は認定される.
こうした地質境界の中央構造線,およびこれに近接して並走もしくは雁行する新旧の断層群が形成されており,中央構造線断層系を構成する(岡田,1968,1973aなど).このうち,第四紀に繰り返し活動してきた断層群は中央構造線活断層帯(系)とよばれ,明瞭な活断層地形を伴う(岡田,1970b,1973bなど).
1995年兵庫県南部地震(M7.3)の発生以降,活断層はとみに注目され,地形や地質調査のみならず,ボーリングや反射法地震探査などの調査も各所で実施され,中央構造線沿いの地下構造もかなり判明してきた.とくに,愛媛県や徳島県の活断層調査,産業技術総合研究所活断層研究センター(旧地質調査所)や大学(研究者)などによって,各種の活断層調査が行われ,活断層の性質や活動履歴の解明に向けて努力されてきた.とりわけトレンチ掘削やジオスライサーによる調査事例は倍増し,活動時期や地表近くの断層位置・構造などが詳しく解明されてきた.こうした成果をふまえて,地震調査研究推進本部地震調査委員会(2003)は金剛山地東縁から伊予灘にかけての中央構造線活断層帯の長期評価を行い,大地震の発生場所・規模・時期の予測を公表した.
本見学旅行では,四国中央部における中央構造線活断層帯を対象として,代表的な活断層地形や断層露頭などを見学するとともに,主な既存研究を紹介したり,活断層調査場所を訪ねたりして,本活断層帯の地形・地質・地下構造や最近の活動および研究成果について検討を行う.以下では,前半で中央構造線活断層帯の概要をまとめ,後半で各見学地点の要点を述べる.なお,日本地質学会第98年学術大会が愛媛大学で開催された際に,中央構造線のネオテクトニクスと題するシンポジュウムが企画された.その後に,同名の現地巡検が行われ,見学旅行案内書(岡田・長谷川,1991)が作成されているが,主要な見学地の説明は一部で重複する.しかし,本見学ではその後に得られた数多くの調査成果も取り入れて,重要な地点の観察を行う計画であり,最新データを大幅に導入して本稿の解説を試みた.
2.四国の中央構造線活断層帯の概要
第一表.四国の中央構造線付近の地質層序(岡田,1972を一部改変).
1)地質概要(岡田・長谷川,1991を一部改変;第1図,第1表)
領家変成岩類および花崗岩類領家変成岩類は高縄半島の基部に分布している.本変成岩類は砂質,泥質,石灰質,塩基性のホルンフェルス〜片麻岩からなる.泥質のホルンフェルスから,三畳紀〜ジュラ紀の放散虫化石が発見されている(鹿島・増井,1985).白亜紀後期の花崗岩類は四国の瀬戸内海に面した高縄半島と讃岐半島の主部を占めて広く分布している.大部分は,領家変成作用に関与した領家花崗岩類である.領家花崗岩類は中〜粗粒の花崗閃緑岩を主体とし,片麻状構造が発達しているところもある.領家変成岩類および花崗岩類は南縁部で和泉層群に不整合に覆われている.
三波川変成岩類三波川変成岩類は愛媛県の佐田岬半島から徳島市にかけて,中央構造線の南側に分布している.分布幅は南北方向に最大30kmに達し,四国の脊梁山地を形成している.三波川変成岩類は,主として泥質片岩,塩基性片岩および砂質片岩から構成されている.四国中央部から東部にかけて泥質片岩が,四国西部では塩基性片岩(緑色片岩)が広く分布している.三波川変成岩類は,波長数kmの東西性の複背斜や複向斜を随伴している.中央構造線に隣接する三波川変成岩類は,複背斜の北翼に当たり,片理面は一般に東西走向であり,北傾斜している.
和泉層群白亜紀最後期の和泉層群は讃岐山脈から松山南西部まで幅10数kmの細長い地帯に,領家帯と三波川帯とに挾まれて分布している.本層群は領家変成岩類および領家花崗岩類を不整合に被覆している.不整合面付近には,礫岩あるいは,石英長石質砂岩が細長く東西方向に分布している.この基底礫岩相の南には,泥岩を主体とする泥岩相,さらにその南には砂岩・泥岩の互層を主とするタービダイト相が分布している(例えば,須鎗・阿子島,1973).和泉層群は東にプランジした軸をもつ向軸構造を形成し,各岩相は東が開いた馬蹄型の分布をなす.向斜軸は和泉層群分布域の南部にあり,中央構造線はその南翼を切っている.和泉層群では,東ほど時代の新しい地層が堆積し,かつ東ほど埋没続成深度が浅くなり,これは向斜構造と調和している(西村,1984).和泉層群中の地層の擾乱は小さく,一般に整然とした成層構造がみられる.ところが,讃岐山脈南麓の丘陵性山地(切幡丘陵)には著しい擾乱を受けた和泉層群が分布する.これらは,中央構造線の断層運動による破砕帯と考えられていたが,更新世前期〜中期に発生した重力滑動岩塊の可能性が指摘されている(長谷川,1988,1990).久万層群久万層群は後述の石鎚層群と共に石鎚山第三系を構成し,石鎚山脈を取り巻くように分布している.大部分の地域では三波川変成岩類を,一部では和泉層群を不整合に被覆している.本層群は始新世中期の二名層と始新世後期の陸成の明神層とに区分され,両者は不整合関係にあるとされてきた(永井,1972).しかし,両層は完全に上下関係にあるのではなく,同時異相のところもあるようである(甲藤・平,1979;木原,1985).二名層は外帯の三波川変成岩類からの砕屑物,明神層は主として内帯の和泉層群などからの砕屑物を源岩とする礫岩,砂岩および泥岩からなる.久万層群はほぼ水平であり,褶曲構造は形成されていない(高橋,1986).久万層群基底面の高度は分布域東端の瓶ヶ森付近では,約1,800mに達するが,西端に近い砥部町岩家付近では約100mとなる.これは,堆積以後に東高西低の地殻運動を受けたと解されている.西条市市之川に分布する,いわゆる「市之川礫岩」は明神層に対比されている(高橋,1981).
第1図.A:北四国における活断層と主要地質構造線分布図(岡田,1973b).基図は岡山(1953)による接峰面図で等高線間隔は100m.B:北四国の地質略図(岡田,1973b).地質調査所発行の20万分の1地質図などを編集し簡略化した.1:沖積層,2:更新世層,3:瀬戸内火山岩類(中新世〜鮮新世),4:黒雲母安山岩,5:石鎚層群(両輝石安山岩),6:石鎚層群,7:久万層群,8:四万十層群,9:和泉層群,10:外和泉層群,11:ジュラ紀層,12:二畳(ペルム)紀〜三畳紀,13:かんらん岩〜蛇紋岩,14:御荷鉾緑色岩類(斑レイ岩〜角閃岩),15:領家帯花崗岩類,16:領家変成岩類,17:三波川変成岩,18:断層,19:活断層.
石鎚層群ほか石鎚層群は久万層群を不整合で覆うとともに,松山市南方では和泉層群を不整合に被覆し,中央構造線を覆って内帯と外帯の両域に分布している(永井・堀越,1953).また,中央構造線の断層破砕部に貫入している酸性〜中性火山岩類も本層群に対比されている(堀越,1964).火山砕屑岩類としては,凝灰岩および凝灰角礫岩,火山角礫岩などがあり,基底部に礫岩を伴うことがある.これらは植物や淡水性の魚類化石を産出する湖成層であり,流紋岩−安山岩質の大規模な火砕流堆積物の存在も明らかにされている(吉田,1970).火山岩としては,流紋岩,斜方輝石安山岩,黒雲母安山岩,讃岐岩(サヌカイト),讃岐岩質安山岩などがある.中央構造線の断層破砕部に貫入している酸性〜中性火山岩類から約15MaのK-Ar年代が報告されている(田崎ほか,1990).西条市域以西の中央構造線に貫入した酸性〜中性火山岩類は貫入および冷却後には,顕著な断層運動を受けていない.
第二瀬戸内累層群中央構造線に隣接する平野の縁辺部では,メタセコイア植物群によって特徴づけられる鮮新世後期〜更新世前期の河成〜湖成層が分布し,丘陵を形成している.これらは,松山平野では郡中層,道前平野では岡村層,徳島平野では森山(粘土)層とよばれている(Saito,1962;高橋,1958;須鎗ほか,1965).また,メタセコイア化石は産出しなかったが,これらの地層と密接に関連し,同じく丘陵を構成する扇状地および土石流堆積物が分布している.これらは,八倉層(松山平野),大谷池礫層(道前平野),土柱(礫)層(徳島平野)とよばれている.最近になり,これらの地層中からメタセコイアの産出,あるいは火山灰層のFT年代が報告され,更新世前期(〜中期)の地層と判明してきた(山崎,1985;水野,1987;阿子島・須鎗,1989).すなわち,平野の縁辺部には鮮新世後期〜更新世中期にわたる第二瀬戸内累層群の相当層が普遍的に分布している.これらの第二瀬戸内累層群は沖積平野の地下にもぐり,瀬戸内海の海底下にも広く分布している(斎藤ほか,1972;緒方,1975).
段丘堆積物平野の周辺部には,砂礫層からなる扇状地性の河成段丘面群が形成されている.これらは一般に高位,中位,低位の各段丘に区分される(岡田,1973a).そして,高位段丘が多摩面(15〜50万年前)に,中位が下末吉面(10〜15万年前)に,低位が武蔵野面(6〜8万年前),立川面(1.5〜3万年前)等に概ね相当すると考えられた.広域火山灰などによって時代が確認された段丘は従来少なかったが,近年その発見が各所で続いており,低位段丘については年代がほぼ確立してきた(岡田・堤,1990).
高位段丘堆積物は分布の幅が狭い.本層は地表付近には赤色風化殻が形成され,クサリ礫を多く含んでいる.中位段丘堆積物は普遍的に分布し,地表付近に薄い赤色風化殻が形成され,全体として赤黄色を呈し,クサリ礫も含む.低位段丘堆積物は現河床沿いや沖積平野の周辺部に広範囲に分布する.全体に黒褐色〜黄褐色を呈し,新鮮な礫からなり,風化をほとんど受けていない.段丘面は堆積原面をよく残し,開析度が低い.
2).中央構造線活断層帯の活動史
四国北西部では三波川帯と領家帯(和泉層群を含む)とを境する地質境界の中央構造線と,これにほぼ並走する活断層があり,これらは中央構造線断層帯を形成している.地質(構造)から判読できる活断層帯の発現時期や運動様式を以下にまとめる.
石鎚層群の火山活動中(中新世中期)に,既存の割れ目である地質境界の中央構造線に沿って,安山岩質の岩脈が貫入した.これは破砕をほとんど受けておらず,しかも,併走する活断層帯(伊予・郡中・川上・小松・岡村の各断層)にはほとんど貫入していない.したがって,地質境界の中央構造線は砥部時階の運動までにほぼ形成され,以後の活動は停止している.一方,活断層帯は岩脈の貫入後に位置をやや異にして誕生したとみなされる(岡田,1973b,2004).
四国山地北西部に分布する小起伏面(皿ヶ嶺面や犬寄面など)は,鮮新世後期頃までに中央構造線や石鎚層群を切って形成されているが,この形成期に郡中層が堆積したとされる(永井,1973).すなわち,全般的に地殻運動の緩やかな時代とされている,中新世後期から鮮新世にかけて,中央構造線の活動はほとんどなく,この地殻運動の休止期間に平坦化が進行したとみなされる(岡田,1973b,2004).
3).活断層の分布形
四国山地北麓や讃岐山脈南麓域では,地質境界の中央構造線のほかに,これにほぼ平行ないし雁行状に配列するいくつかの断層が分布する.これらの大半は少なくとも第四紀後半でも右ずれが卓越した活断層であり,断層線の走向や断層面の傾斜もほとんど同じ傾向を示す.こうした一連の右ずれ断層群を中央構造線活断層帯とよぶ(岡田,1973b)が.これに属する断層も,変位地形が明瞭で第四紀後期にも変位を繰り返している断層と,変位地形が不明瞭で第四紀後期には変位が少ないか,認められない副次的な断層とに分けられる.前者に属するものとして,西方より東方へ,伊予・重信・川上・岡村・石鎚・畑野・池田・三野・井口・父尾・神田・鳴門南などの活断層があり,変位が各々の活断層へ受け継がれて連なる.これら活断層帯全体として,N75。Eの方向へ延び,変位速度もほぼ等しい.
各活断層の平面形は直線状ないし多少湾曲を伴う場合も滑らかな曲線を画いて連続する.しかし,活断層の両端では,一般走向に対して多少方向を変えることが多く,東西ないし北東偏りに曲がる傾向がある.雁行状に配列する活断層が,次の活断層へ移る場所,例えば,三好市三野町芝生(旧三野町芝生)や美馬市美馬町(旧美馬町)東端の坊僧山,美馬市脇町(旧脇町)北西方などでは,北東方向へ偏って延びる分岐断層が数本認められる.こうした接合部付近では各断層に沿った横ずれ地形はあまり明瞭でなく,むしろ縦ずれが卓越するようである(岡田,1970b,1973a;後藤,1998;後藤・中田,2000).変位地形が不明瞭なものとしては,三野町芝生の芝生衝上断層・土柱断層・切幡南・引野などの断層がある.南側へ凸状に湾曲したり,断層線がかなり湾曲したりしている.多くの露頭では,北側の山地から南側へ突き上げた逆断層状を呈する.また,活断層線の北側を併走する活断層がいくつかあり,讃岐山脈南麓では箸蔵断層(池田断層の北側)や鳴門断層(鳴門南断層の北側)が挙げられるが,これらの変位量は相対的に小さく,第四紀後期では変位が少ない副次的な断層とみなされる.愛媛県東温市(旧川内町)南部から西条市丹原町湯谷口(旧丹原町湯谷口)にかけて中央構造線は一般走向に対して大きくS字状に約10km湾曲している.この屈曲に対して,小林(1950)は桜樹屈曲と名付けたが,犬寄峠付近でも規模はやや小さい約3kmの湾曲が認められる.活断層としての川上断層もここで大きく湾曲する.川上断層の存在とその湾曲は新しい応力場のもとで既存の屈曲した中央構造線(の深部の剪断面)に規制されて,一部では新しい破断面を,一部では古い断層面を利用して形成された.この付近での最大圧縮軸は屈曲部の川上断層の走向とほぼ直交するので,純粋な逆断層型の運動が期待されるが,以西の伊予断層や川上断層西半分での右横ずれ運動の影響を受け,右横ずれの卓越した逆断層120 岡田篤正・杉戸信彦Supplement, Sept. 2006となっている.高縄山地側では西方から移動してきた物質が屈曲部で詰まるような状態となり,高縄山地の曲隆がもたらされたと考えられる.この物質過剰による曲隆が,山地東縁の川根断層や北縁を円弧状に取り巻く断層をも随伴させたとみなされる.また,中央構造線以南では,石鎚山脈部が右横ずれ運動の累積によって圧縮されるので,より隆起する位置に当たるとみられる(岡田,1973b).
前述したように,桜樹屈曲部以西の中央構造線沿いでは,石鎚層群に相当する火山岩類が噴出・貫入している.これらは時には地質境界の中央構造線を越して分布するが,主な分布は活断層帯以南である.この時の噴出・貫入の多少や隆起量などが,中央構造線の屈曲をもたらした可能性も指摘されている(池田ほか,2003;長谷川・大野,2006).
上述のように,桜樹屈曲の概形は砥部時階の後で活断層運動の発生前,すなわち中新世から鮮新世までの期間に形成されたとみなされる.また,桜樹屈曲の成因は形状からみても,屈曲部だけの隆起とみるより,それ以東の石鎚山脈部が以西に比べて相対的に隆起し,北斜する中央構造線の更に深部が削剥低下により露出して,大きく湾曲した.石鎚山方向に急上昇するような運動は石鎚山第三系(久万層群と石鎚層群)の分布高度にも明瞭に現れている(岡田,1972,1973b).
4).大規模地すべりと断層との関係
中央構造線沿いは,断層崖斜面を伴う山地と平野との地形境界をなし,斜面の基部には幅広い断層破砕帯が形成されている.また,活断層運動に伴って,強震動が生成され,上下変位も引き起こされるので,地すべりが形成されやすい地形・地質環境となっている.讃岐山脈南麓では,和泉層群からなる地すべり移動地塊が山麓部に数多く見られ,低角度の逆断層状の露頭が観察される.また,一部は活断層を乗り越えて平野側へ移動し,第四紀堆積物に挟まれたり,覆ったりしている.比較的小規模の地すべりは各所に見られ,枚挙に暇が無いので,ここでは省略し,規模の大きな地すべりについてのみ検討する.
三好市池田町(旧池田町)シンヤマにおける事例は径約1kmに達し,1集落を乗せるほど規模も大きい.山麓の斜面物質・土石流堆積物・古吉野川河床礫を取り込みながら南側へ滑動し,吉野川を一時的に堰き止めた(岡田,1968).三好市池田町白地では中位段丘2面を被覆し,シンヤマでは約5.7万年前の材を含む堆積物に地すべり物質(和泉層群)がのし上げる.地すべり移動地塊上面の南側山麓部のみに赤色土壌を乗せるが,これは南側上方斜面からの匍行による被覆とみなされる.移動地塊上面の地形はあまり開析されておらず,ここでは赤色土壌を乗せないので,約5.7万年前頃に発生したと考えられる(岡田,2004).
吉野川北側の讃岐山脈南斜面には,馬場・洞草・西山の集落を乗せる地すべり地形が見られる(岡田,1968;後藤ほか,1999a)が,東部の西山のものが吉野川近くまで徐々に南斜し,滑落崖を伴う輪郭が明瞭な移動体をなす.シンヤマの地すべり物質である和泉層群は一部が角礫化し,数多くの開口節理を伴い,全体として成層構造を保存しているので,比較的緩やかな滑動であったとみなされる.したがって,西山を起源とする地すべりと認定され,その場合流下後に約1.5kmの右横ずれ,数10m以上の北上がりの断層変位を受けたと推算される.長谷川(1992,1999)はこの地すべりの年代がさらに古く,発生場も東方の鮎苦谷川出口とみなしているが,地形・地質の情報からみて,上に述べた見解が妥当である.また,讃岐山脈東部南麓に当たる阿波市(旧阿波町)の土柱地域や旧市場町・旧土成町域の切幡丘陵にも大規模な地すべり移動岩体を指摘している.しかし,これらは活断層の平面的な分布形や地質配置からみて,別の見解も可能であるが,池田の事例は典型例で貴重である.
5).断層面の傾斜
浅部讃岐山脈南麓では,北側から南側への低角度の衝上断層が古くから記載・報告されてきた(今村ほか,1949;中川・中野,1964a,b;槇本ほか,1968,1969).それらのうち,表層で観察された露頭の一部では,地すべりや匍行による断層面や破砕帯の低角度化によるものがある(岡田,1968,1970b).また,須鎗ほか(1965)で指摘された事例のように,活断層に近接した場所では,小規模の低角度衝上状の断層が観られることがある.しかし,断層露頭の多くやトレンチ掘削調査では,ほとんどの場所で垂直ないし北側へ高角度で傾斜した断層面が観察される(ただし,熊谷寺東南トレンチでは,最新期の断層面でも北側へ傾斜していたが,この場所は活断層の屈曲部近くに位置している).
深部讃岐山脈南麓域から石鎚山脈北麓・松山平野域で,P波による反射法地震探査が数ヶ所で実施されてきた.以下,主な成果を西側から紹介する.愛媛県(1999)が実施した松山平野中部(重信断層の西端部)域では,ほぼ直立する断層面が約1km以浅の部分で求められている.
西条市宮の下付近の中位段丘面が南側へ逆傾斜することから,その北縁に活断層が推定されている(岡田,1973;水野ほか,1993;中田ほか,1998).一方,これを横切る西条市新兵衛から伊予氷見北方に至る長さ0.6kmの南北測線(愛媛県,1999)では,川上断層北東延長部や宮の下北縁の推定断層は探査された断面に断層を示唆する構造が明瞭には現れていない.
堤ほか(2003)は新居浜市西部で岡村断層と中央構造線を横切るP波反射法地震探査を実施し,約35゜Nで傾斜する地質境界の中央構造線を明瞭に捕えた.この北傾斜する断面は岡村断層の下でも深部へ延長するので,次の2つの解釈が出された.1)岡村断層は地質境界断層から地下約1kmで分岐し,高角度となって地表に達する.2)岡村断層は地下深部まで高角度であり,地質境界断層を地下約1kmで切断・変位させているが,上下変位量が小さいので,反射面には明瞭な食違いとして認定できない.どちらの解釈が妥当かはなお未解決である.伊藤ほか(1996)は,讃岐山脈中部を南北方向(徳島県美馬市脇町の曽江谷川沿い)に横断して,P波反射法地震探査を実施した.この探査結果によると,深さ約5km以浅では地質境界の中央構造線は30〜40。Nで傾斜していると推定されるが,地表で追跡される活断層(父尾断層)直下の解像度はあまりよくない.讃岐山脈東部南縁では,佃・佐藤(1996)により反射法弾性波探査が実施され,断層面の傾斜は深さ500m以浅では北傾斜約40。と推定される.
さらに東方の鳴門市里浦町〜撫養町でのP波測線(長さ1.5km)では,北側傾斜の断層が推定される.鳴門市段関付近を南北方向に横切るS波測線とボーリングで求められた浅部(70m以浅)では,約70。Nで傾斜する活断層面(鳴門南断層)が確認され,これは地質境界の中央構造線にほぼ相当する(森野ほか,2001).
以上述べてきたように,地質境界の中央構造線は北側傾斜であるが,高角度から30〜40。Nとやや低角度とみなす見解がある.場所や手法,探査時期などによる相違もあり,現段階では断層面の角度を一義的には決められない.とくに活断層と地質境界の中央構造線との関係も場所による相違が顕著であり,詳細な構造解明は今後の重要な課題として残されている.
6).断層破砕帯
地質境界の中央構造線は幅10m以上に達する断層ガウジ帯とその両側に広がる破砕帯を伴う.結晶片岩類に由来する破砕帯は青灰色〜灰白色を呈し,縞模様が発達して粘土化が顕著である.しかし,和泉層群では黒褐色で断層角礫やブーダン構造を伴い,断層ガウジは相対的に幅が狭く,粗粒物質で構成される.両者は見かけ上すぐに区別され,鉱物組成も大きく異なる.
このような断層ガウジ・破砕帯の接触面は,平面でも断面でも両者が指交(interfinger)関係で接したり,紡錘状〜岩脈状に取り込まれたりすることが.三野町芝生や美馬市脇町東田上などで観察された.
活断層や中央構造線を横断する方向で,断層破砕帯の全てが観察されることはまず無いので,場所による相互の比較は容易ではない.限られた露頭での観察であるが,断層線が屈曲・分岐し,他の断層へ乗り換える場所(例えば,三好市三野町芝生北部)で,とくに顕著な断層破砕帯が発達している.
7).断層面におけるすべりの方向
三好市池田町佐野瀬戸谷では,断層破砕帯に取り込まれた材が断層面にほぼ平行に延びていた(岡田,1968).また,阿波市井出口では,断層破砕帯に取り込まれた材が断層面に斜交し切断され,材面にほぼ水平の明瞭な条線が何本も観察された(岡田,1970b).阿波市土柱においては,破砕帯に落ち込んだ礫の表面にほぼ水平の条線が観察された(岡田,1970b;岡田,1992).これらの現象はいずれも,水平変位成分が卓越していることを示す.したがって,讃岐山脈南麓域では断層運動は北上がりで右横ずれを示唆する.
8).第四紀後期の活動性
平均変位速度岡田・堤(1997)は,岡田(1970a,b)が求めた阿波市市場町の父尾断層による段丘崖の水平変位量と段丘崖の形成年代を再検討し,右ずれ変位量を約50m,その形成年代を約8,000年前とした.これらの数値から右横ずれ変位速度を求めると約6mm/yrとなる.また,岡田(1970b)は,美馬市美馬町の三野断層で,形成年代を約2.5万年前よりも新しいと推定した扇状地面を開析する河谷の右横ずれ屈曲量を200〜230mとして,右横ずれ変位速度は8〜9mm/yrに達するとした.さらに,岡田(1968)が14C年代値をもとに推定した段丘礫層下の不整合面の形成年代(約3万年前)と,断層による右横ずれ変位量(約200m)を用いて,三好市池田町の池田断層における右横ずれ変位速度を7mm/yr以上とした.
岡村断層のトレンチ調査は西条市飯岡地区で数回にわたって実施されたが,壁面に現れた礫層中の特異な礫の供給源を指標として,Tsutsumi et al.(1991)は右横ずれ変位速度を5〜8mm/yrと求めた.岡田ほか(1998)はその後に行われた調査も取り入れて再考察し,右横ずれの変位速度を5〜6mm/yr程度と見積もった.1回の横ずれ変位量岡田・堤(1997)は阿波市上喜来の父尾断層付近で表土を剥いだ自然堆積層のほぼ上面を写した写真を分析し,断層を挟んで約6m弱右横ずれ変位しているとし,これを最新活動時の横ずれ変位量とした.また,Tsutsumi and Okada(1996)は,同地点における水田の畦の屈曲を断層活動によるものとして,その屈曲量から最新活動に伴う父尾断層の右横ずれ変位量を6.9ア0.7mとした.また,同地域で別の畦で12.9mの横ずれが認められることについて,これが最新活動及び1回前における活動との2回分の変位が累積したと解釈した.
上述の岡村断層飯岡でのトレンチ調査では,断層の南北を挟んで地層中の特異層を比較して,最新活動期に約5.7mの右ずれが認定された(Tsutsumi et al.,1991).最新活動時期当域の活断層帯は有史以後に大地震を伴った変位の記録がないとみられていた(岡田,1973b,1980など).しかし,阿波市上喜来のトレンチ掘削調査で16世紀頃の活動が指摘されて以来(岡田ほか,1991;岡田,1992;Tsutsumi and Okada,1996;岡田・堤,1997),中央構造線活断層帯の詳しい調査が実施され,同じ頃に活動した地質学的な証拠が各地で判明してきた.たとえば,伊予断層の伊予市市場大道寺トレンチでは14世紀以降(後藤ほか,2001),重信断層では後藤ほか(1999b)および愛媛県(1999)の調査をまとめると,11世紀以後に活動したとされる.西条市土居町で行われた川上断層北東部でのトレンチ掘削調査からも,飛鳥時代から江戸時代までの間に活動したとされる(堤ほか,2000).
後藤ほか(2003)は畑野断層において3次元的なトレンチ調査を実施し,最新活動時期が西暦1520〜1660年(暦年較正:ア1σ)または西暦1480〜1670年(ア2σ)と求めた.すなわち,16世紀を挟んだ140〜190年間に最新活動が限定されるとした.
岡田(2006)は古地震学的調査と歴史地震資料の発掘を総合的に判断して,中央構造線活断層帯の最新活動時期が1596年頃とみなした.すなわち,9月1日四国中央部122 岡田篤正・杉戸信彦Supplement, Sept. 2006に最初の活動(慶長伊予国地震)があり,9月4日に別府湾で慶長豊後地震が発生し,9月5日に四国中央・東部から淡路島東部を経て,有馬−高槻断層帯へ至る活断層が連動的に動いたと推定した.有馬−高槻断層帯は慶長伏見地震の震源断層であるが,この時に四国の中央構造線も活動した可能性を指摘した.個々の地震の活動範囲・地震規模などの詳細は今後の課題とした.
最新活動以前の活動時期と活動間隔地震調査研究推進本部地震調査委員会(2003)は中央構造線活断層帯の長期評価を公表している.以下の2項目(活動時期と活動間隔・長期評価)についてはこれを要約して解説する.鳴門南断層から石鎚断層に至る区間の1回前の活動は概ね2,000年前頃であったと推定される.さらに,2回前の活動時期は少なくとも板野断層の川端地点などで認められるが,この時の活動がどの範囲まで及んだかの特定は困難である.鳴門南断層から石鎚断層では,父尾断層で右横ずれ変位速度が6mm/yr,1回の活動に伴う右横ずれ変位量が6〜7mと求められ,平均活動間隔は約1,000〜1,200年となる.一方,本区間の最新活動は16世紀頃であり,1回前の活動が約2,000年前頃であることから,この間の活動間隔は1,500〜1,600年となる.このように2つの方法により求められた数値は整合しないが,前者は用いた平均変位速度及び1回の活動に伴う変位量の数値の信頼度が高いとはいえず,一方,後者も過去2回の活動時期から得られた活動間隔であり,信頼度が高くない.したがって,ここでは両者の数値から,本区間の平均活動間隔を約1,000〜1,600年とする.
長期評価鳴門南断層から石鎚断層に至る区間の平均活動間隔は約1,000〜1,600年,最新の活動以後の経過時間は約400〜500年である.したがって,平均活動間隔に対する現在における地震後経過率は0.3〜0.5となり,地震調査研究推進本部地震調査委員会(2001)に示された手法によると,今後30年以内,50年以内,100年以内,300年以内の地震発生確率は,それぞれ,ほぼ0〜0.3%,ほぼ0〜0.5%,ほぼ0〜2%,0.03%〜20%となる.また,現在までの集積確率は,ほぼ0〜0.2%となる.
3.見学地点の説明
Stop 1 湯谷口の断層露頭(中央構造線・川上断層)[地形図]1/2.5万「伊予小松」,中田ほか(1998):都市圏活断層図 1/2.5万「西条」
[位置]愛媛県西条市丹原町(旧丹原町)湯谷口
第2図.湯谷口付近の地形・地質(岡田作成原図).基図は丹原町作成1:2,500地形図.等高線間隔は2m.1:沖積谷,2:低位段丘面,3:中位段丘面,4:中位−高位段丘面(切断曲流跡),5:和泉層群,6:川上断層と露頭,7:中央構造線と露頭.
第3図.湯谷口の中山川河床でみられる中央構造線の地質断面(岡田,1972を修正).位置は第2図のLoc.1〜4.
[解説]西条市丹原町湯谷口には中央構造線の見事な断層露頭があり,天然記念物として保護されている(第2図のLoc.1〜3;第3図;Saito,1962).露頭は中山川の河床両岸にある.ここでは南側の結晶片岩類と北側の和泉層群が断層で接し,接触部には幅5〜6mの変質両輝石安山岩が岩脈として貫入している.そのK-Ar年代は約21Maと測定されている(田崎ほか,1990,1993).岩脈の上・下面の断層面は走向N70〜80。E,傾斜25〜35。Nである.断層下面沿いには幅数10cm以下の断層ガウジ〜破砕物質がみられるが,それはごく軽微であり,しかも固結している.また下盤の結晶片岩はほとんど破砕や擾乱を受けていない.一方,上盤の和泉層群の破砕が著しく,10数m北方まで断層角礫帯となっている.
この露頭の下流約80mの中山川左岸には,南側の和泉層群断層破砕帯と北側の新期礫層が接する断層露頭があった(第2図のLoc.4,第3図;岡田,1972;岡田・長谷川,1991ほか).この露頭は川上断層のトレース上に位置する.断層北側の礫層のうち,下位の礫層は和泉層群の亜角〜亜円礫からなる扇状地礫層で,やや固結している.こうした岩相からみて,中位段丘礫層あるいはそれよりやや古いものと推定される.上部には厚さ数m以下の沖積礫層が不整合状に分布する.含まれる礫の種類は現河床の礫層とほぼ同じである.この沖積礫層も明らかに断層変位を受け,偏平礫が直立し,断層ガウジが礫と混在する.断層面は走向N74。E,ほぼ垂直である.断層ガウジ帯幅は5〜6mで,それ以南には層理が乱された和泉層群が中央構造線の露頭までみられる.この断層露頭は1980年代の終わりごろまでみられたが,コンクリート護岸壁が建設され,現在では観察できない.
しかし最近の洪水で河床が削られ,下流側延長部が広く観察できるようになった(森野ほか,2002).ここでは幅数10cmの礫層部分(偏平礫の直立帯)がN74。E方向へ河床面で長く認められる.礫の長軸が水平に近く,横ずれ変位の卓越が示唆される.前者の地質境界の露頭で観察される断層面は北傾斜である.したがって,後者でみられるほぼ垂直な断層面とは地下浅所で合流するはずである.
Stop 2 新居浜市川口の断層露頭(石鎚断層)
[地形図]1/2.5万「別子銅山」,堤ほか(1998):都市圏活断層図 1/2.5万「新居浜」
[位置]愛媛県新居浜市大生院川口
第4図.中萩低断層崖付近の地形(岡田,1973bに追記).上図:岡村断層に沿う中萩低断層崖の立面形(村田,1971,一部改変).影部分が低断層崖.下図:中萩断層崖付近の詳細地形図(岡田,1973b).等高線は1:5,000国土基本図からを抽出したもので間隔は5m.間隔2.5mの間曲線も抽出.
第5図.川口の小河谷川谷壁にみられる断層露頭(岡田,1973a).位置は第4図のLoc.1.
[解説]この断層露頭は,新居浜市大生院川口の小河谷川山麓出口左岸・右岸にあり,石鎚断層のトレース上に位置する(第4図のLoc.1,第5図).この付近では中央構造線自体が活動的であり,石鎚断層とよばれる.露頭下部に幅約2mほどの断層ガウジが見られ,安山岩質岩脈が破砕された灰白色の粘土状物質として含まれる.低位段丘礫層も明らかに切断されているが,西側の低位段丘面には低断層崖は認められない.断層面の走向はN75〜85。E,傾斜は35〜45。Nであり,断層面の一部には35。東下りの条線が認められる.南岸や右岸にみられる露頭でも同様のことを観察できる(岡田,1973a).この下流数10m付近には,細粒でやや固結した砂礫層(岡村層相当)が段丘礫層下に不整合関係で露出している.これらの露頭は崩落土砂で被覆されたり,侵食で露出したりして,随時状況が異なる.
Stop 3 新居浜市中萩低断層崖と各種の調査地点
[地形図]1/2.5万「新居浜」,堤ほか(1998):都市圏活断層図 1/2.5万「新居浜」
[位置]愛媛県新居浜市大生院岸ノ下・萩生・中萩
[解説]中萩低断層崖(岡村断層) 新居浜市萩生〜中萩には,見事な低断層崖(中萩低断層崖)が約3kmにわたって連続する(第4図).この低崖地形は辻村・淡路(1934)によって最初に指摘された.その後も,永井(1955),Kaneko(1966),村田(1971)らによって低断層崖の検証や扇状地面の分類がなされ,いずれも開析扇状地面を切断する低断層崖と認定されている.この低断層崖は岡村断層を構成する代表的な変位地形で,石鎚断層の北側1.5kmを並走する.
この付近には石鎚断層崖下に発達した合成合流扇状地がみられ,その北端近くを中萩低断層崖が切断している.この北側に沿っては沖積扇状地群が分布し,低断層崖の南北両側で地形面が異なる.中萩低断層崖では古い段丘面ほど高い位置にある(第4図上図).それらの比高を列記すると,沖積面を切断するもので3m,低位段丘下位(L2)面で6m,低位段丘上位(L1)面で13〜14m,中位段丘面で23mである.北之坊阿弥陀寺(第4図のLoc.2)の北側での低断層崖は低位段丘(L1)面で比高10〜11m,その北東側では約14mである.北之坊の西側の開析谷基部では,L1面構成層の中(地表下約6.5m)に泥炭層(層厚10〜15cm)が挟まれている.その14C年代値は,23,400ア750yrBP(GaK-3368)と27,040+1,040-920yrBP(HR-543)である(岡田,1973a;岡田・堤,1990).この試料の花粉分析では草地的な環境が示唆され,古気候は温帯から冷温帯と考えられる.これらの資料から,L1面構成層は最終氷期最寒冷期(2万数千年前)頃に形成されたとみなされる.したがって,この付近にひろがるL1面を基準とすると,比高最大16mで,平均上下変位速度の最小値は0.7mm/yr程度と求められる.岸ノ下地区地層抜き取り調査・トレンチ掘削調査の結果(岡村断層) 岸ノ下付近の低断層崖基部の沖積面上で,地層抜き取り調査(後藤ほか,2001)と2つのトレンチ掘削調査(愛媛県,1999)が実施された(第4図のLoc.3).
この付近では,中萩低断層崖は小谷によって開析されて南側にやや後退しているが,その谷底面にも比高2.2〜2.4mの低断層崖がみられる.この低断層崖東方延長部の谷底東端でジオスライサーによる地層抜き取り調査が実施された(後藤ほか,2001).この後に行われた岸ノ下西トレンチ(愛媛県,1999)のすぐ東側である.岸ノ下東トレンチ(愛媛県,1999)は岸ノ下西トレンチの約80m東方に位置する.
第6図.岸ノ下地区地層抜き取り調査の結果(後藤ほか,2001).位置は第4図のLoc.3.
第7図.A:岸ノ下西トレンチの西壁面(愛媛県,1999),B:岸ノ下東トレンチの東壁面(愛媛県,1999).位置は第4図のLoc.3.A・Bの断層南側には岡村層が露出している.
地層抜き取り調査では,幅1.3m,長さ3m,厚さ0.15mのジオスライサーによって地層断面が3枚得られた(第6図;後藤ほか,2001).その結果,ほぼ直立する4条の断層が認められ,16世紀以後に最新活動があったと推定された.
愛媛県(1999)は岸ノ下西トレンチ掘削調査を実施して,南に高角度で傾斜し,南側隆起の数条の断層を確認した(第7A図).これらの断層は耕作土直下の地層まで変位を与え,少なくとも3回の活動が認定された.すなわち,最新活動時期は960〜1,090yrBP(9世紀以後14世紀以前),1回前の活動時期は2,230〜4,530yrBP(約5,300年前以後約2,200年前以前),2回前の活動時期は4,910yrBP以前(約5,000年前以前)と求められた(カッコ内の値は地震調査研究推進本部地震調査委員会(2003)による暦年補正後の値).
さらに愛媛県(1999)は岸ノ下東トレンチ調査を実施して,南に高角度で傾斜し,南側隆起を示す断層を,西壁面に1条,東壁面に2条確認し(第7図A),沖積層中に少なくとも3回の活動を解読している.すなわち,最新活動時期は760〜1,820yrBP(2世紀以後),1回前の活動時期は2,040〜8,190yrBP(約9,700年前以後1世紀以前),r2回前の活動時期は8,530〜8,600yrBPと求められた(カッコ内の値は地震調査研究推進本部地震調査委員会(2003)による暦年補正後の値).
以上述べたように,岸ノ下地区では地層抜き取り調査と岸ノ下西トレンチ掘削調査による最新活動時期とは整合しない.しかしながら,両調査地点は非常に近接しており,各地層の層相も類似することから,別の活動を捉えているとは考えにくい.両地点の最新活動は同時に発生したものであり,年代値の矛盾は測定された年代値の誤差や採取された層準の相違等によると考えられる.地震調査研究推進本部地震調査委員会(2003)は,両地点から得られた最新活動の年代値を総合して,岸ノ下地点における最新活動時期は9世紀以後であり,それより古い活動として約5,300年前以後約2,200年前以前と約5,000年前以前の2つの活動が認められるとしている.
Stop 4 四国中央市土居町畑野付近の活断層地形と断層露頭・トレンチ掘削調査地点
[地形図]1/2.5万「東予土居」,堤ほか(1998):都市圏活断層図 1/2.5万「新居浜」
[位置]愛媛県四国中央市土居町畑野(四国電力東予開閉所付近)
第8図.上野〜畑野付近の地形・地質(岡田,1973aを一部改変).等高線は1: 5,000 国土基本図から抽出したもので間隔は10m.
第9図.畑野付近の地形・地質断面図(南北方向)(岡田,1985を一部改変).
第10図.畑野の浦山川左岸にみられる断層露頭(平面図)(松田・岡田,1977).位置は第8図のLoc.2.
[解説]活断層地形(畑野断層・石鎚断層) この付近(四国中央市土居町(旧土居町)上野〜畑野)における畑野断層沿いの断層鞍部や横ずれ尾根・河谷は,中央構造線活断層帯の中でもとくに明瞭である(第8,9図).丘陵性台地(段丘)を横切る河谷では,断層線上で系統的な右横ずれが認められる(岡田,1973a).かつて連続していたと思われる河谷を,いろいろな可能性を考慮して断層線を挟んだ下流側に求めてみると,第8図に英字で記したように推定される.畑野断層では,A−A'・A''・B−B'・C(C)−C',D−D',E−E'と河谷の系統的な右横ずれがみられ,尾根筋の連続でもほぼ同様の屈曲が認められる.これらから,平均150〜200mの右ずれ量が求められる.畑野断層の西方への追跡は不明瞭となるが,東方の浦山川左岸では,低位段丘(L3)面や沖積段丘(L3〜L4)面が上下方向に4.5m,2.4m切断されている(岡田,1973a).
南方の石鎚断層上でも,L−L',M−M'のやや小規模の屈曲がみられ,Mの北には南側に向いた比高数mの逆向き新期低断層崖がある.Mの谷は広い風隙を通って,M''の広い谷に連続していたとみなされる.西谷川は低位段丘面形成時までは,畑野集落付近を北東流し,その後西方の和泉層群よりなる丘陵を貫通して現流路をとるようになったと考えられる.西谷川が形成したと思われる側方侵食崖がO'・O''・P''とあるが,古いものほど変位量が大きくなっている.低位段丘面の形成前に,現西谷川の位置を流れていた河谷上流は,谷の規模がやや小さいが,Nないし(N)に求められる.また,畑野の南方では,P−P'のはっきりした屈曲が断層線上でみられ,屈曲部から東方へ開く風隙状地形がある.前述の地形のうち,もっとも明瞭なものをあげると,畑野断層沿いの150〜200mと,中央構造線に沿う550〜600mの計700〜800mが,高位段丘面形成以降の右横ずれ量と推算される.この付近の高位段丘は堆積原面を残している.地表面には厚さ1.5m+の赤色土壌層(色調:5YR,5〜4/8)がみられ,礫層は全体にかなりクサリ礫化している.この高位段丘堆積物や地下構造がかなり詳しく判明してきたが,高位段丘面の形成年代に関する直接的な値はまだ得られていない.なお,この高位段丘面上では深いボーリング調査が実施されている(第8図のLoc.1;金折ほか,1980).
浦山川河床露頭浦山川河床では,中央構造線(石鎚断層)とその両側の地質がよく観察された(第8図のLoc.2,第10図;岡田,1973a;松田・岡田,1977).安山岩質の岩脈が和泉層群側に貫入し,この一部は破砕して白色の粘土帯となり,走向N56。E・傾斜67。Nの断層面で,結晶片岩の断層破砕帯と接する.断層破砕帯中の剪断面は走向N50〜90。E・傾斜40。N〜75。Sと不規則であるが,第四紀後期に活動し,軟弱な断層ガウジ帯を伴う断層面の傾斜は70〜80。N(一部では75。S)と高角度である.とくに擾乱の著しい部分の破砕帯幅は10数m以内であり,黒灰色の断層ガウジ帯を伴う部分は幅約7mである.南側の三波川変成岩類はあまり破砕を受けておらず,その破砕帯幅は数m以下であり,すぐ南側に堅硬な岩石が露出している.柴田ほか(1989)によって,断層ガウジのK-Ar年代測定が行われている.
第11図.上野地区トレンチ掘削調査の位置(長谷川ほか,1999を一部改変).
第12図.上野地区トレンチ掘削調査の壁面(Cトレンチ東壁面)(長谷川ほか,1999を一部改変).位置は第11図参照.
上野地区トレンチ掘削調査(畑野断層) 上野にある四国電力(株)東予開閉所内では数多くのトレンチ調査が行われてきた(第11,12図;長谷川ほか,1999).確認された断層面は,全体としてほぼ東西の走向を示し(N80。E〜87。W),南または北へ高角度で傾斜する.みかけの隆起側も一定していない.
活動時期に関しては,谷底堆積物を変位させるCトレンチとSK-2掘削の成果が,年代測定値が多く得られたためとくに重要である.当地区での全ての調査から活動履歴をまとめた長谷川ほか(1999)によれば,最新活動時期は625ア80〜770ア75yrBP,1回前の活動時期は1,055ア80〜3,750ア100yrBP,2回前の活動時期は3,980ア130〜4,500ア130yrBPである.最新活動と2回前の活動の間隔は誤差を考慮すると約3,000〜4,000年であるため,平均値を取ると活動間隔が約1,500〜2,000年と算出される.ただし,調査は幅の狭い谷底で行われたので,堆積物が連続的に堆積していない可能性もあり,すべての活動が地層に記録されているとは限らない.したがって,求められた活動間隔は活動時期に比べると信頼性は低い(長谷川ほか,1999).
地震調査研究推進本部地震調査委員会(2003)は長谷川ほか(1999)の記載と暦年補正値を考慮して以下のように述べた.すなわち,上野地区で行われた複数のトレンチ掘削調査結果によれば,SK-2トレンチでは9世紀以後に最新活動が認められた.これに対し,Gトレンチでは最新活動は3世紀以前であった可能性があり,最新活動の時期が矛盾する.SK-2地点では,断層を覆う地層からほぼ同じ年代値が得られており,他の地層から得られた年代値もこれとほぼ整合する.しかし,Gトレンチでは概ね2世紀の年代値が得られた地層からはさらに古い年代値(約3,700年前)が1つ得られているのみであり,これら以外には年代値が得られていない.このため,年代値データが豊富で,その信頼度が相対的に高いと推定されるSK-2トレンチの年代値のデータを重視し,9世紀以後15世紀以前,または9世紀以後17世紀以前に最新活動があったと判断する.周辺の調査結果を考慮すると後者が妥当と判断される.
Stop 5 四国中央市西金川〜平山付近の活断層地形とトレンチ掘削調査地点(池田断層)
[地形図]1/2.5万「伊予三島」,堤ほか(1999):都市圏活断層図 1/2.5万「伊予三島」
[位置]愛媛県四国中央市金田町平山
第13図.平山付近の地形・地質(岡田作成原図).等高線は50m間隔.1:池田断層と露頭,2:風隙,3:河谷変位,4:低位段丘層,5:中位段丘層,6:高位段丘層,7:中古期第四系,8:和泉層群,9:結晶片岩類.
第14図.金川付近の模式鳥瞰図と地質断面(永井,1973を一部改変).鳥瞰図は西北西上空から見たもの.断面の位置は第13図参照.1:沖積層,2:段丘礫層,3:崖錐堆積層,4:角礫層,5:和泉層群,6:結晶片岩類.
第15図.高知自動車道法皇トンネル北坑口付近の地形と地質(岡田,1994).1:沖積面(=層)・三波川変成岩類,2:和泉層群,3:沖積扇状地〜崖錐,4:新期地すべり(滑落崖と堆積域),5:古期地すべり,6:横ずれ河谷,7:池田断層.
[解説]活断層地形四国中央市金田町(旧川之江市金田町)西金川〜東金川には,池田断層に沿って広い沖積面が続き,ここから2つの河谷が北方へ流下している(第13図).1つは西金川から北東へ流れて,四国中央市(旧川之江市)正地に至るものであり,他の1つは三星ゴルフ場東側から,東金川の北方へと流下する河谷である.これら河谷地形から,約1kmに及ぶ右横ずれが推定される.この河谷の変位は北西側の尾根部を構成する礫層の堆積以後に形成されたものである.岡田(1973a)はこれを高位段丘礫層とみなしたが,水野ほか(1993)は岡村層に対比している.
西金川〜東金川の低地の北側と南側に沿って,断層が推定される(第13図).これらは明瞭な地形変換線を伴っている.この低地を南北方向に横切って水路トンネルが掘削された結果,断層の存在が地質的にも確認された(第14図;永井,1973).これによると低地の両側が正断層状の高角な断層で限られた地溝である.池田断層では右横ずれ成分が卓越するが,平面的な分布形と考え併せると,西金川〜東金川の低地は小規模なプルアパート盆地(pull-apart basin)とみなされる(後藤・中田,2000).金田町半田平山には明瞭な風隙地形があり,そこには層厚7m以上の河成礫層がみられる(第13図).かつての上流を断層以南の山地側に求めると,少なくとも350m西方の谷(堀切峠から平山へ北流する谷)となるが,このようにして推定される旧河谷は東流して金生川と合流する.平山にある249mの丘は,地すべりあるいは土石流堆積物(中古期第四系)で構成されるが,その堆積以後に約2kmの右横ずれをした可能性が指摘できる.
平山地区トレンチ掘削調査平山の幅狭い沖積低地でトレンチ掘削調査が行われた(愛媛県,2000).この地点は開析谷の中に認められる比高1〜2mの逆向き低断層崖の西方延長上にある.トレンチ掘削調査の結果,3条の断層が認められた.これらはいずれも南側へ高角度で傾斜している. 愛媛県( 2 0 0 0 ) は, 最新活動時期を1,120ア70yrBP前後(AD765〜1,025年),1回前の活動時期を1,120ア70yrBP〜2,930ア120yrBPとした.また,地層の流動化跡から190ア70〜610ア50yrBPに強い地震動を受けた可能性を示唆した.地震調査研究推進本部地震調査委員会(2003)は,本地点における最新活動は9〜14世紀,流動化をイベントとした場合には14世紀以後であり,周辺の調査結果を考慮すると,後者が妥当と判断した.また,1回前の活動時期を約3,300年前以後11世紀以前としている.
なお,このトレンチ壁面に現れた断層は地質境界の中央構造線ではなく,すぐ北側を併走する和泉層群内の活断層であり,中央構造線との関係を解明する必要がある.高知自動車道法皇トンネル北坑口付近の地形・地質四国中央市川滝町(旧川之江市川滝町)領家の西端に,中央構造線(池田断層)を貫く高知自動車道法皇トンネルが掘削された(第15図).坑口周辺に新旧の地すべり地形が分布するが,池田断層はこうした地形を切断している.
北坑口付近を中央構造線が通過するが,詳しい地質は岸(1990)や出口ほか(1990)で報告されている.北坑口から南側へと厚い崖錐堆積物中を通過すると,約120m付近で中央構造線に伴う幅広い断層破砕帯(約60m)に遭遇する.中央構造線の北側には古期の崖錐堆積物があり,これは断層破砕帯と接し,断層面は南へ47。で傾斜している.また,古期崖錐堆積物を覆う新期の崖錐堆積物も破砕帯の北側で,急に厚さを増すので,断層破砕帯とは断層で接している可能性が高い.断層破砕帯は全体として粘土化の顕著な泥質片岩であるが,下盤側(北坑口側)では砂礫状であり,和泉層群の破砕帯状の岩石を挟む.上盤側に向かって次第に粘土・シルト分を含む砂礫となり,結晶片岩との境界では,完全な断層ガウジ帯となっている.この部分は遮水層となっているらしく,山地側から多量の湧水がある(出口ほか,1990).
Stop 6 三好市池田町付近の活断層地形と地質(池田断層)
[地形図]1/2.5万「阿波池田」,後藤ほか(1999a):都市圏活断層図1/2.5万「池田」
[位置]徳島県三好市池田町白地・シンヤマ・阿波池田市街地
第16図.三好市阿波池田付近の地形・地質(Okada,1980を一部修正).等高線は1:5,000国土基本図からを抽出したもので間隔は5m.★は古池ボーリング地点,_Cは露頭位置.
第17図.三好市阿波池田付近の河成段丘面群の模式断面(岡田,2004).
[解説]活断層地形三好市池田町(旧池田町)の市街地付近には日本を代表する見事な変位地形が発達している(第16図).市街地がある段丘面にはほぼN70。E方向に連なる南向きの低断層崖がみられる.崖の比高は西部で約30m,東部で約20mである.この低崖は吉野川の東方および西方までほぼ一直線に延びて新旧の段丘面を変位させ,これ沿いに断層露頭や破砕帯が確認される(岡田,1968,1970b;Okada、1980;水野ほか,1993;後藤ほか,1999).
池田上位面(上野ヶ丘)は東方に17パーミルの勾配で傾斜し,現河床面や池田下位面に比べてやや急である.低断層崖の比高は前述のように東西で異なっており,相対的な隆起量に差がある.上位面の堆積物は池田小学校北側で厚さ4〜5m,諏訪神社南側で1〜2mと薄い.この段丘礫層は径1mに達する粗大礫を含む吉野川本流のもので,風化はすすんでいない.上位面は層厚数m以下と全般に薄く,侵食段丘の性格をもつ.
池田下位面東縁にある比高約20mの段丘崖はすべて段丘礫層よりなり,基盤岩石は露出していないが,市街地南部の開析谷底には硬い結晶片岩がみられる.第16図に_Cで示した位置の露頭では,段丘礫層は上部礫層と下部礫層に2分される.下部礫層の上部に,厚さ約1.2mの灰色シルト〜粘土層がみられ,その中に多数の埋もれ木が含まれていた.この14C年代は,27,700ア600yrBP(TK-39)と測定された.よって低位段丘堆積物基底の不整合面は約3万年頃に形成されたとみなされる.池田市街地西方の池田下位面背後の侵食崖は約200m右横ずれておりし,段丘堆積物基底面も約40m北上がりに変位している(岡田,1968).平均右横ずれ変位速度は約6 . 6 m m / y r , 平均上下変位速度は北上がり約1.3mm/yrと求められた.
池田町白地付近における河成段丘面池田町白地から池田市街地付近にかけて,吉野川が形成した河成段丘面群がよく発達する(第17図;岡田,2004).白地の旧「かんぽの宿」付近から,周辺に見られる段丘面群を展望し,それらの堆積物との関係や形成年代について議論する.古池におけるボーリング調査 池田町市街地西部の古池(現在ではほとんど埋め立てられて工場や体育館が建設されている)で実施されたボーリング(第16図の星印)では,厚さ約10mの段丘堆積物の下方に,厚さ約60mの未固結堆積物がみられた.これはシルト層を含む土石流状の湖沼性堆積物であり,三波川変成岩類から供給された砕屑物を主体とし,メタセコイアの化石を含む.メタセコイアは大阪層群のMa3層準以降で消滅しているので,当域でもほぼ同じとみなせば,この堆積時期は更新世前期(約85万年)以前となる.こうした湖沼性堆積物が内陸の河谷底でみられることは意外であるが,中央構造線が通る馬路川河谷でも同じような堆積物が確認される.これらは当域の発達史を考察する上で貴重な事実であり,中央構造線に沿う東西方向の河谷に鮮新世後期−更新世前期の湖沼性低地が出現したことを意味している(水野,1992).また,池田西方のシンヤマは開口割れ目や不規則な破断面を伴う「和泉層群」の地すべり移動岩塊である(岡田,1968)が,この下位にも第四紀前半の堆積物が露頭やボーリング調査で確認されている.なお,古池ボーリングでは三波川変成岩類は60m以深に存在することが判明している.
Stop 7 東みよし町昼間の断層露頭(中央構造線)
[地形図]1/2.5万「阿波池田」,後藤ほか(1999):都市圏活断層図1/2.5万「池田」
[位置]徳島県三好郡東みよし町昼間
第18図.東みよし町昼間付近の詳細地形図(岡田・長谷川,1991を一部改変).
第19図.東みよし町昼間の小川谷川沿いに見られた断層露頭(平面図)(岡田,1968).位置は第18図の_印.
[解説]東みよし町昼間(旧三好町昼間)付近には,比高数mの南向き低断層崖がほぼ東西方向に延びている(第18図;岡田,1968).この池田断層に沿う低断層崖は小川谷川西方に見られる比高約10mの南向き低断層崖へと連続する.これらを結ぶ直線と小川谷川が交わる付近の河床において,中央構造線の断層露頭が広く平面的に観察された(第19図;岡田,1968).北側に黒褐色を呈する和泉層群断層破砕帯がみられ,相当破砕された和泉層群が破砕度を減少しつつ,数100m以上北東まで見られた.南側に淡緑色を帯びた灰色〜灰白色の縞模様をなす三波川変成岩類が分布し,境界部には変成岩類起源の断層ガウジが発達する.和泉層群と三波川変成岩類の境界はinterfinger状の差違え構造をしており,断層ガウジが発達する.断層面の個々の接触部や,破砕帯内の剪断面の走向・傾斜はかなり相違がある.しかし,和泉層群断層破砕帯と結晶片岩との境界をなす断層面の全体的な走向・傾斜はN82。E,70。Nである.このような構造は,その接触状態からみて,主として,右横ずれの断層運動の凸部が砕波時の波形のように楔状に取込まれて,さらに延張されて形成されたと解される.
Stop 8 三好市三野町芝生の活断層地形と断層露頭(中央構造線・三野断層)
[地形図]1/2.5万「辻」,後藤ほか(1999):都市圏活断層図 1/2.5万「池田」
[位置]徳島県三好市三野町芝生
第20図.三好市三野町芝生付近の地形(岡田・堤,1990).等高線は1:5,000国土基本図からを抽出したもので間隔は5m.二点鎖線は中央構造線,破線は活断層線を示す.
第21図.三好市三野町芝生付近の地形・地質断面図(南北方向)(岡田,1973b).
[解説]三好市三野町太刀野(旧三野町太刀野)から芝生北方にかけては,東北東方向に走る数本の断層がみられるが,活断層帯が大きく屈曲・湾曲する場所に位置している(第20図;岡田,1970b).これら断層のうち,変位地形がとくに明瞭で活動的と思われるのは南端の三野断層であり,太刀野山のL1段丘面を切断して,比高10〜12mの低断層崖が形成されている.第20図東部の三野断層に沿う尾根や河谷は系統的な右ずれ屈曲をなすので,三野断層は右ずれが卓越し,北上がりの上下変位成分を伴う活断層と認定される.
この低断層崖のまさに東北東延長部に当たる,河内谷川東岸側には,三野断層沿いの大規模な破砕帯が露出している(第20図のLoc.F11).ここは高速道建設前から大規模な土砂採取地となり,三野断層周辺から北方約200mの範囲にかけて,和泉層群の破砕状況がよく観察できてきた.
この南端部では,今村ほか(1949)や中川・中野(1964a)により,「芝生衝上」と名付けられた低角度(30。N)の断層が指摘されたが,採掘地でも和泉層群の破砕帯が南側にある礫層に衝上する様子がよく観察された.
南端部の芝生衝上の北側に,上記の三野断層が認められた.この位置が第20図のLoc.F11であり,かつて明瞭な断層鞍部が存在したが,現在では取り除かれた.この三野断層の位置で,和泉層群が破砕されている状況が南北方向の断面でよく観察された.とくに,破砕が顕著であり,断層ガウジ帯を含む細粒物質が幅広く認められた場所は鞍部付近であった.そこでは,破砕度Ľ(断層角礫帯;松田・岡田,1977)〜Ś(断層粘土帯)の幅は8m以上におよび,この南北両側に破砕度Ł〜Ľ(原岩の堆積構造不明)が数m以上の幅で広がる.中心部をなす断層粘土主体の破砕帯の中には,何本もの剪断面がみられ,それらは走向:N80。E,傾斜:Vで,相互にほぼ平行している.和泉層群の破砕帯は黒褐色から灰黒色を呈し,破砕から免れた砂岩の角礫を多く挟む.断層面ないし剪断面に沿って,灰白ないし青灰色の三波川結晶片岩に由来した,紡錘形ないし脈状の破片が細長く取り込まれていた.工事の進捗によって,幅1m強の青灰色や淡緑色を呈する縞状模様の入った明瞭な断層粘土帯がブーダン状に挟まれる.こうした和泉層群と三波川結晶片岩類の破砕帯が差し違えて産出する状況は讃岐山脈南麓沿いの何カ所か観察された(岡田,1970b)が,淡路島南部でも確認されている(金折ほか,1982).この破砕物は泥質片岩からなり,明瞭な剪断面を伴わず,流動したように和泉層群の破砕帯内に取り込まれている.破砕物の面構造はN80。Eの走向で,ほぼ鉛直である.しかし,この面に沿って鏡肌が形成されているので,断層面に相当する.ほぼ垂直に近い三野断層の地下には,三波川変成岩類の破砕帯が存在する.北傾斜の芝生衝上の北側を併走するので,両者は地下浅所で合流しており,中央構造線の断層帯を形成しているとみなされる(第21図;岡田・長谷川,1991).
文 献
阿子島 功・須鎗和巳,1989,中央構造線吉野川地溝の形成過程.地球科学,43,428-442
出口政昭・黒田義樹・鈴木 徹,1990,四国横断自動車道法皇トンネル建設工事.土木施工,31,12,17-26.愛媛県,1999,平成10年度地震関係基礎調査交付金中央構造線断層帯(愛媛県北西部・石鎚山脈北縁)に関する調査成果報告書.416p.
愛媛県,2000,平成11年度地震関係基礎調査交付金中央構造線断層帯(愛媛北西部・石鎚山脈北縁・讃岐山脈南縁)に関する調査成果報告書.421p.
後藤秀昭,1998,吉野川北岸における中央構造線活断層の再検討.第四紀研究,37,299-313.
後藤秀昭・中田 高,2000,四国の中央構造線活断層系—詳細断層線分布図と資料—.総合地誌研研究叢書,35,広島大学総合地誌研究資料センター,144p.
後藤秀昭・中田 高・岡田篤正・堤 浩之・丹羽俊二・小田切聡子,1999a,1:25,000都市圏活断層図「池田」.
国土地理院技術資料・日本地図センター.
後藤秀昭・中田高・奥村晃史・池内啓・熊原康博・高田圭太,1999b,中央構造線活断層系・重信断層の変位地形と活動履歴.地理学評論,72A,267-279.
後藤秀昭・中田 高・堤 浩之・奥村晃史・今泉俊文・
中村俊夫・渡辺トキエ,2001,中央構造線活断層系(四国)の最新活動時期からみた活断層系の活動集中期.地震II,53,205-219.
後藤秀昭・堤 浩之・遠田晋次,2003,中央構造線活断層系畑野断層の最新活動時期と変位量.地学雑誌,112,531-543,口絵写真4.
長谷川修一,1988,古期重力滑動岩塊の地質構造.第27回地すべり学会研究発表会講演集,36-39.
長谷川修一,1990,中央構造線沿いの巨大重力滑動岩塊−徳島県切幡丘陵の例−.第2回地すべり学会研究発表会講演集,80-83.
長谷川修一,1992,讃岐山脈南麓における中央構造線沿いの大規模岩盤すべりと第四紀断層運動.地質学論集,40,143-170.
長谷川修一,1999,中央構造線沿いの大規模地すべり−その特徴と地盤工学上の問題点−.地盤工学会誌,47,21-24及び口絵写真.
長谷川修一・岡田篤正・田村栄治・川上裕史・大野裕記・永峰良則,1999,愛媛県土居町における中央構造線系畑野断層のトレンチ調査.四国電力・四国総合研究所研究期報,73,50-67.
長谷川修一・大野裕記,2006,活断層の分布形態を規制する中期中新世火成岩体.月刊地球号外,54,50-58.堀越和衛,1964,四国西部(愛媛県)における中央構造線に沿う地帯に分布する火山岩類について.愛媛大学紀要II,5,7-16.
池田倫治・大野一郎・大野裕記・岡田篤正,2003,四国北西部地域の中央構造線活断層系の地下構造とセグメンテーション.地震II,56,141-155.
今村外治・中野光雄・岩本昇海,1949,讃岐山脈南北両側に発達する衝上断層について(予報)(演旨),地理学評論,22,130.
伊藤谷生・井川 猛・足立幾久・伊勢崎修弘・平田直・浅沼俊夫・宮内崇裕・松本みどり・高橋通浩・
松澤進一・鈴木雅也・石田啓祐・奥池司郎・木村学・國友孝洋・後藤忠徳・澤田臣啓・竹下 徹・仲谷英夫・長谷川修一・前田卓哉・村田明広・山北聡・山口和雄・山口 覚,1996,四国中央構造線地下構造の総合物理探査.地質学雑誌,102,346-360.
金折裕司・佐竹義典・猪原芳樹,1980,中央構造線の分布・性状と活動性−四国北東地域における断層露頭の調査および解析− . 電力中央研究所報告,3800041-153.
金折裕司・佐竹義典・猪原芳樹・妹尾正晴・神田淳男,1982,淡路島最南部付近における三波川結晶片岩類起源の断層粘土の確認とその意義.地質学雑誌,88,701-704.134 岡田篤正・杉戸信彦Supplement, Sept. 2006Kaneko, S., 1966, Transcurrent displacement along theMedian Line, southwestern Japan. New ZealandJour. Geol. Geophys., 9, 45-59.
鹿島愛彦・増井 芽,1985,四国高縄半島,領家変成岩の地質時代.地質学雑誌,91,233-234.甲藤次郎・平 朝彦,1979,久万層群の新観察.地質ニュ−ス,293,12-21.
木原茂樹,1985,愛媛県中央部,久万町周辺の始新統久万層群の層序と堆積環境.立石雅昭・中村和善・卯田 強編,スランプ相の形成とテクトニクス−未固結堆積物の変形に関する諸問題−,構造地質研究会砕屑性堆積物研究会,133-144.
岸 寛,1990,中央構造線を貫く法皇トンネルの施工.土木技術,45,58-67.
小林貞一,1950,日本地方地質誌「四国地方」.朝倉書店,271p.
槇本五郎・中川 典・中野光雄,1968,徳島県美馬郡脇町でみられる中央構造線.地質学雑誌,74,479-484.
槇本五郎・中川 典・中野光雄,1969,徳島県美馬郡内の「中央構造線」.地理科学,11,31-38.
松田時彦・岡田篤正,1977,断層破砕帯の破砕度階級−野外観察による分類試案−.MTL(中央構造線),2,117-125.
水野清秀,1987,四国及び淡路島の中央構造線沿いに分布する鮮新・更新統について(予報).地質調査所月報,38,171-190.
水野清秀,1992,中央構造線に沿う第二瀬戸内期の堆積場−その時代と変遷.地質学論集,40,1-14.
水野清秀・岡田篤正・寒川 旭・清水文健,1993,中央構造線活断層系(四国地域)ストリップマップ及び説明書.構造図8,地質調査所,63p.
森野道夫・岡田篤正・中田 高・松波孝治・日下雅義・村田明広・水野清秀・能見忠歳・谷野宮恵美・池田小織・原 郁夫,2001,徳島平野における中央構造線活断層系の活動履歴.地質学雑誌,107,681-700.
森野道夫・塩田次男・原 郁夫・池田小織・田中義浩・市原 健・森川倫人・森山 豊・谷野宮恵美・窪田安打,2002,中央構造線活断層系川上断層の断層露頭.地質学雑誌,108,III-IV.
村田貞蔵,1971,断層扇状地の純形態学的研究.扇状地−地域的特性−,古今書院,318p,1-54.
永井浩三,1955,東予の中央構造線に沿う地帯の最近の地殻運動.愛媛大学紀要II,2,71-84.
永井浩三,1972,四国,始新統久万層群.愛媛大学紀要,7,1-7.
永井浩三,1973,愛媛県の中央構造線.杉山隆二編,中央構造線,東海大学出版会,401p,197-207.
永井浩三・堀越和衛,1953,愛媛県伊予郡砥部町附近の第三紀層.愛媛大学紀要,1,119-132.
中川 典・中野光雄,1964a,讃岐山脈中部南麓に発達する「中央構造線」.地質学雑誌,70,52-58.中川 典・中野光雄,1964b,四国阿波池田町西部の「中央構造線」.地質学雑誌,70,580- 585.
中田 高・後藤秀昭・岡田篤正・堤 浩之・丹羽俊二,1998,1:25,000都市圏活断層図「西条」.国土地理院技術資料・日本地図センター.西村年晴,1984,四国西部の上部白亜系和泉層群の堆積盆解析.地質学雑誌,90,157-174.
緒方正虔,1975,佐多岬半島北岸海域の地質構造−音波調査による海底地質の考察−.電力中央研究所報告,37506,35p.
岡田篤正,1968,阿波池田付近の中央構造線の新期断層運動.第四紀研究,7,15-26.
岡田篤正,1970a,四国東部における中央構造線の第四紀変位速度(演旨).地質学雑誌,76,104.
岡田篤正,1970b,吉野川流域の中央構造線の新期断層運動.地理学評論,43,1-21.
岡田篤正,1972,四国北西部における中央構造線の第四紀断層運動.愛知県立大学文学部論集(一般教育編),23,68- 94.
岡田篤正,1973a,四国中央北縁部における中央構造線の第四紀断層運動.地理学評論,46,295-322.
岡田篤正,1973b,中央構造線の第四紀断層運動について.杉山隆二編,中央構造線,東海大学出版会,49-86.
Okada, A., 1980, Quaternary faulting along the MedianTectonic Line of Southwest Japan. Mem. Geol. Soc.Japan, 18, 79-108.
岡田篤正,1980,中央日本南部の第四紀地殻運動−地殻運動の変化と場の移動−.第四紀研究,19,263-276.
岡田篤正,1985,横ずれ断層地形−石鎚山脈北麓の中央構造線活断層系.写真と図でみる地形学,東京大学出版会,162-163.
岡田篤正,1992,
巡検情報:徳島県那賀町阿津江の破砕帯地すべりと山津波
2004年台風10号豪雨で発生した徳島県那賀町阿津江の破砕帯地すべりと山津波
Fractured zone landslide and debris flow at Azue, Naka Town, Tokushima Prefecture,induced by the heavy rainfall of Typhoon Namtheun in 2004
横山俊治1 村井政徳2中屋志郎3 西山賢一4大岡和俊5 中野 浩6
Shunji Yokoyama 1, Masanori Murai 2,Shirou Nakaya 3, Ken-ichi Nishiyama 4,Kazutoshi Ohoka 5 ,and Hiroshi Nakano 6
受付:2006年6月27日
受理:2006年7月28日
* 日本地質学会第113年学術大会(2006年・高知)見学旅行(I班)案内書
1.高知大学理学部自然環境科学科
Department of Natural EnvironmentalScience, Kochi University, Kochi 780-8520,Japan.
2.高知大学大学院黒潮圏海洋科学研究科黒潮圏海洋科学専攻
Division of Kuroshio Science, Graduate Schoolof Kuroshio Science, Kochi University,Nankoku 783-8502, Japan.
3.京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻
Division of Earth and Planetary Sciences,Graduate School of Science, Kyoto University,Kyoto 606-8502, Japan.
4.徳島大学総合科学部自然システム学科
Department of Mathematical and NaturalSciences, Faculty of Integrated Arts andScience, The University of Tokushima,Tokushima 770-8502, Japan.
5.株式会社サンブレーン・プラン
Sun Brain Plan Co., Ltd., Tokushima 771-1156,Japan.
6.株式会社創研技術
Soken Engineering Co., Ltd, Tokushima 770-
概 要
小出(1955)の定義による破砕帯地すべりは今日の知識からすれば付加体分布地域で多発している.破砕帯地すべりは地すべり性崩壊であると小出(1955)が記述しているように,崩壊時に破壊された地すべり移動体は山津波となって谷を流下し,しばしば末端では河川を堰き止める.見学地である阿津江の事例には,このような破砕帯地すべりの特徴がくまなく現れている.見学は末端部から発生域へと進めていこう.末端部では,坂州木頭川渡った山津波が対岸の斜面を50 mほどの高さまで乗り上げている.ここでは,山津波の流れを記録する樹木に刻まれた流下痕跡を観察し,一旦は斜面に乗り上げた土砂や構造物の大部分を洗い流した強い引きの流れの存在,山津波の一部が坂州木頭川を跳び越えている状況を確認する.発生域では,崩壊頭部のクラック群・緊張した樹根,崩壊壁の地質を,発生源の谷底では新旧の土石流堆積物,破砕帯,断層を観察する.
Key Words
Typhoon Namtheun, fractured zone landslide‘, Yamatsunami’, debris flowdeposits, greenstone
地形図
1: 25,000 「雲早山」
見学コース
[1日目]8:00 高知大(朝倉)→別府峡(休憩)→11:00 那賀町符殿→(昼食)→15:40 阿津江→18:00 鷲敷青少年野外活動センター(泊)
[2日目]7:00 鷲敷青少年野外活動センター→8:30 那賀町阿津江→14:00 JR徳島駅→14:30 徳島空港→17:00 高知龍馬空港
用語解説
1.山津波と土石流
第1図.分野別にみた土石流関係用語の変遷(西本,2006).
第1図は分野別に見た土石流関連の用語の変遷である(西本,2006).ここでは,用語「土石流」と用語「山津波」について検討してみる.それは,現在の学術用語が「土石流」であることを承知の上で「山津波」をこの見学案内書で使用している理由を説明することでもある.用語「土石流」の使用は研究分野で最も早く,それは1916年のことである(西本,2006).行政がそれに続き,社会(新聞報道など)と言語(辞書)で用語「土石流」が使用されるようになったのは1970年代である(第1図参照).
一方,用語「山津波」が研究分野で使用されたのは1950年の中頃であるが,定着しなかった(西本,2006).しかし,1889年には国語辞典に用語「山津波」が掲載されている.国語辞典への掲載は当時の一般社会では用語「山津波」の使用頻度が高くなって日本語として認知されたことを示している.一般社会と報道関係との大きな時期的ずれ(第1図参照)は,1960 年頃まで,土石流関連の災害が報道の舞台に登場しなかったということであろう.
西本(2006)によれば,用語「山津波」は,土石流の実態がよく分かっていなかった時代に生まれたもので,津波のように押し寄せてくるイメージを感覚的・比喩的に表現されたものであるという.これに対して,用語「土石流」は“物(土と石)”と“流れる”という物理現象を表現する用語であり,土石流を表現するには最も理にかなった用語である(西本,2006)としている.ここで問題にしたいのは,実在の土石流の構成物が土と石だけなのかということである.もちろん,水の存在を忘れていると言うつもりはない.水の存在を自明のこととして扱っているのであろう.問題は水の量である.村井ほか(2006)は,2004年台風15号による大川村の土石流災害で,谷を流下する土石流の水位が土石流堆積物の数倍にもなることを明らかにしている.実在の土石流における水の量は土石の間に含まれている程度として片隅においておけるようなものではない.さらに,同時に多量の流木が流れる.土石だけに目を奪われていたら,その実態を見失うことになる.ちなみに,土石流を表現する英語は「debris flow」(砂防学会編,2004)で,語彙の意味するところは日本語の用語「土石流」と同じである.ここでは,土石と流木と水からなる混合流体物を指す用語として「山津波」を用いる.土石の定置・堆積したものは「土石流堆積物」と呼ぶことにする.
2.破砕帯地すべりと破砕帯
破砕帯地すべり(英訳はfractured zone landslide;日本地すべり学会地すべりに関する地形地質用語委員会編,2004)の特徴は小出(1955)の「日本の地辷り」の記述にしたがって要約すると以下のようになる.破砕帯地すべりは崩壊に近い一次地すべりで,地すべり移動体は崩壊と同時に流動化し,発生域を離れて遠くまで移動し,しばしば河川に突っ込んで天然ダムをつくる.これが荒廃河川の原因になる.崩壊後の斜面は安定性が高く,地すべり移動体の構成物は砂礫質であるために傾斜畑として利用されることが多い.すなわち,破砕帯地すべりは徐動性の地すべりではないという点がまず重要である.
破砕帯地すべりのもうひとつ重要な特徴は帯状分布にある.それは帯状分布を示す破砕帯の構造規制を受けて地すべりが発生したことを意味する.小出(1955)は「岩石が破砕されている限りでどんな地質や岩石のところでもおこる.」としているが,破砕帯地すべりの多くが付加体で発生しているという事実は,素因となっている破砕帯の形成が付加体の地質構造と密接に関係していることを示唆している.
「断層そのものはむろん破砕帯ではない.このような破砕岩(断層角礫岩や断層粘土を指す;著者ら注記)が,たとえ幅20〜30 mにわたった断層であっても,それだけではむろん破砕帯ではないし,破砕帯と呼ぶ資格もない.」と小出(1955)が述べているように,小出のいう用語「破砕帯」は今日一般に破砕帯と呼んでいるもの(地学団体研究会編,1996)とは異なる.この点がまず重要であるが,今日まで用語「破砕帯地すべり」は,上記小出の破砕帯の内容と地すべり性崩壊であることの2点を無視してしばしば使われている.
小出(1955)は破砕帯を「地殻変動で歪力をうけ,壊された地帯」,あるいは「自然にあるがままの状態で歪力をうけ,もまれるための破砕作用で,その結果をみると,岩石が徹底的にこわされることがあり,細粒化,ブロック化という程度にこわされることもある.」と定義し,解説している.しかし,この定義・解説では小出のいう破砕帯の実態は捉えにくい.「日本の地辷り」の中で小出は破砕帯の典型例として蛇紋岩の構造を挙げている.その特徴は,無数の剪断面の発達によって,角礫状あるいは片状を呈すること,剪断面は輝く鏡肌を呈し,粘土脈を挟在しないことである.いわゆる黒瀬川帯の蛇紋岩ではこういった破砕帯が岩体の全体に及んでいるが,いわゆる黒瀬川帯の蛇紋岩を地学団体研究会編(1996)の定義による破砕帯として記載する習慣はこれまでになかった.後述するように,今回の見学地の阿津江や大用知では,緑色岩が蛇紋岩と同様の破砕帯構造をもっていることが明らかになった.
しかし,小出(1955)が破砕帯と記載している地帯のあるもの,例えば瀬戸川層群や大井川層群の破砕帯では地すべり性崩壊が発生し,地すべり性崩壊発生前の地質体は“破砕”しているが,その破砕帯(破砕岩)は地学団体研究会編(1996)の定義による破砕帯とも蛇紋岩の破砕帯とも異なっていて,重力による岩盤クリープ変形に起因したものである( C h i g i r a , 1 9 9 2 ; 千木良,1998;横山・柏木,1996).このような破砕帯は小出(1955)の破砕帯の定義から外れるが,小出(1955)が認定したほかの破砕帯でも岩盤クリープから地すべり性崩壊に至る斜面変動が発生しているのが確認されている(横山,2003参照).このタイプの破砕帯地すべりも付加体の斜面変動を特徴づけるものである.
2004年台風10号災害の概要
1.気象・降雨状況
第2図.阿津江に近い気象観測所の降水量の変化(櫻井ほか,2006).
第3図.阿津江周辺の等雨量線図(2004/7/30-8/2,4日間雨量)(櫻井ほか,2006).
2004年7月25日に南鳥島の西海上で発生した台風10号(ナムセーウン)は,31日夕方に高知県西部に上陸し,四国・中国地方を通過して日本海へ抜け,8月1日には日本海で弱い熱帯低気圧に変わった.台風の接近・通過に伴い,徳島県南部の那賀川流域では7月30日の夜から雨が降り始め,台風通過後も長時間にわたって豪雨が継続した.那賀町海川の雨量計では,8月1日の日雨量が,同じ那賀町木頭で1976年に観測された日本記録を200 mm以上更新する1,317mmを記録した(7月30日〜8月2日までの総雨量は2,050mm).
見学地に近い気象観測点での降水量の時間変化(櫻井ほか,2006)を第2図に示す.図のように,降雨は8月1日の午後から夜にかけてピークに達しており,主な災害は8月1日の夜に発生した.7月30日〜8月2日にかけての総雨量コンター図(櫻井ほか,2006)を第3図に示す.7月30日〜8月2日にかけての総雨量が1,400mm以上に達したのは,那賀川支流の海川谷川および坂州木頭川に沿った南北約20数km,東西5 〜10数km程度の狭い領域である(櫻井ほか,2006).
2.地形・地質概要ならびに過去の災害履歴
那賀川上流域は四国山地の南東部にあたり,剣山(1,955 m)の南側に位置する.この地域は標高230 〜1,955 mの山地からなり,全般に急峻な地形を呈する.稜線と谷底の比高は,数100 m〜1,000 mにも達し,山腹斜面の傾斜も30°〜40°と急傾斜であるが,一部の谷壁を除くと裸地の断崖絶壁は少ない.那賀川と大きな支流である坂州木頭川には滝などの傾斜変換点はほとんど存在しないが,それらに合流する支流にはしばしば存在する(例:那賀町沢谷の大轟の滝).
第4図.阿津江周辺の地質図(村田,2003).
第5図.阿津江周辺における崩壊分布図(西山ほか,2005a).
今回の見学地である阿津江を含む那賀川上流・木沢地域の地質に関しては,最近ではTominaga(1990),富永(1990),山北(1998),四国地方土木地質図編纂委員会(1998),石田・香西(2003),村田(2003),石田ほか(2005)などの研究があるが,地質構造のみならず,地帯構造区分の所属・名称,形成時代(付加の年代,変成作用の年代)も研究者によって見解が異なっている.ここでは,これらの研究成果を踏まえ,2004年に発生した斜面崩壊の分布地域を中心にその概要を述べる.なお,地質図は村田(2003)を第4図に示す.2004年に発生した崩壊のうち,那賀町の大用知,加州,阿津江,沢谷(嫁ヶ滝)の崩壊が発生した地域は,ほぼ秩父(累)帯中帯(四国地方土木地質図編纂委員会,1998など)あるいは中部秩父帯(山北,1998など)と呼ばれる地帯に所属していて,ジュラ紀付加体の分布地域である.大用知の崩壊地と阿津江の崩壊地から山津波の流下域にかけては玄武岩組織を明瞭に残すペルム紀の緑色岩が分布している.一方,大用知の集落付近や阿津江の崩壊地の南の地域には時代未詳の蛇紋岩が分布しており,加州や沢谷(嫁ヶ滝)には泥質・砂質・凝灰岩質の準片岩が分布している.さらに,阿津江の崩壊地の東側の尾根には礫岩が分布している.蛇紋岩や準片岩類,白亜系礫岩は黒瀬川帯(四国地方土木地質図編纂委員会,1998)と呼ばれる地帯を特徴づける岩石である.
海川1号と海川2号の崩壊は,秩父(累)帯南帯(四国地方土木地質図編纂委員会,1998など)あるいは南部秩父帯(山北,1998など)に属する三宝山帯あるいは三宝山ユニット(松岡ほか,1998)のジュラ紀付加体分布域で発生しており,三畳紀の石灰岩・チャートや,ジュラ紀の砂岩頁岩互層などが関与している.海川1号の崩壊地の地質は砂岩頁岩互層,海川2号のそれは石灰岩・チャートである.
山地斜面にはしばしば地すべり地形が認められるが,四国山地の地すべり密集地帯(三波川帯・御荷鉾帯)と比較すると少ない(寺戸,1986).
尾根には,しばしば線状凹地が認められる(例:那賀町源蔵ノ窪など).この種の微地形は,山体の重力変形に伴う地形と考えられており,大規模な崩壊地の周辺に付随して認められることがあるため,崩壊前兆地形とも考えられている(例えば,千木良,1995).四国山地各地でも同様の微地形が分布しており(古谷,1979;寺戸,1986;加藤,2002;布施・横山,2003),高知県室戸市の加奈木崩れのように,南海トラフを震源とする大地震により大崩壊を起こした斜面も知られている(甲藤,1980;寺戸,1986;千木良ほか,1998).
那賀川上流域は日本屈指の多雨地域でもあり,これまでにも豪雨による斜面災害を繰り返し受けてきた.1892年には,那賀町大戸の高磯山北斜面で大崩壊が発生し,約400万m3もの崩壊土砂が2つの集落を完全に埋没させるとともに,那賀川本流を堰き止めて天然ダムを形成し,2日後に決壊して大洪水を引き起こした(寺戸,1970;井上ほか,2005).1976年台風17号豪雨に伴い,那賀町木頭の新九郎山東斜面で発生した大崩壊は,崩壊土砂量が約100万m3と推定されており,崩壊土砂の堆積により下流域の河床が数10m上昇し,土石流段丘を形成した(寺戸,1977).このほか,四国山地南東部では,1701年に発生したと推定される徳島県上勝町山犬岳の崩壊,1788年に発生したと推定される高知県香美市物部町の窪田海の崩壊,那賀町・高磯山崩壊と同日に発生した徳島県海陽町保瀬の崩壊などの事例が知られている(寺戸,1975;井上ほか,2005).
3.2004年の崩壊分布と豪雨域との関係
今回の見学地である阿津江周辺における崩壊分布図(西山ほか,2005a)を,第5図に示す.これらの崩壊が発生した地点は,日雨量が1,000 mm以上を記録した豪雨域とほぼ一致する.ただし,崩壊発生密度は1km2当たり最大でも10個以下であり(西山ほか,2005a;櫻井ほか,2006),記録的な雨量の割には斜面崩壊の発生数が少ない.その原因としては,1976年豪雨をはじめとする豪雨常襲地帯であるため,斜面の表層風化帯はすでに取り除かれ,斜面はほとんどが硬質で風化に対する抵抗性が高い堆積岩からなっていて,いわゆる「崩壊の免疫性」を獲得していることが考えられる(西山ほか,2005b)が,今後より詳細な検討が必要である.
見学地のみどころ
STOP 1 符殿集落
符殿集落は国道193号線三田口バス停脇の林道を約1kmいったところである.大用知集落から加州谷を経て行くこともでき,大用知集落からは約4.5 kmである.符殿集落では,地すべり性崩壊発生域から山津波の流下経路の全体を遠望することができる.
STOP 2 符殿トンネル北側坑口付近
緑色岩の破砕帯構造を観察できる.山津波で持ち上げられた現河床堆積物由来の礫,樹木に刻まれた各種流下痕跡を観察できる.
STOP 3 坂州木頭川の左岸斜面
坂州木頭川左岸へは右岸から川の中を歩いて渡ることになる.坂州木頭川は比較的水量が少ないときでも浅いところで膝くらいまで水位があるので,十分な注意が必要である.左岸斜面は山津波によって露出したF1断層面に沿って登る.断層面には山津波の流下による削痕が多数刻まれている.
標高400 m程度まで斜面を登ると,ルートAおよびBの山津波の流下経路を遠望することができる.
STOP 4 旧木沢村風車前
風車は国道193号線から町道黒滝寺線を約4km行ったところで,木頭名集落を通り抜けてすぐのところにある.風車前には展望デッキが設置されており,大用知および加州で発生した山津波を遠望することができる.また,道路切土斜面には蛇紋岩が露出している.展望デッキからの眺めは大変よく,晴天の日にはここで昼食を摂られることをお勧めする.
STOP 5 加持久保神社〜黒滝寺
風車前で道路は黒滝寺と阿津江集落へと二手に分かれる.加持久保神社は風車から約1km,そこからさらに1km行くと黒滝寺に至る.
阿津江の破砕帯地すべり発生域の変動地形および道路や構造物の地すべり変状を観察することができる.地すべり発生域のクラックの破断面には風化した緑色岩が露出しており,クラックを跨ぐように伸びる緊張した樹根がある.この緊張した樹根の方位からは変動域側の地盤の移動方向を推定することができる.
STOP 6 阿津江集落
第6図.阿津江で発生した山津波の全景
風車前から阿津江集落までは1.3kmである.道路はここで行き止まりとなり,阿津江山津波によって全壊した家屋がある.ここから山津波が流下した谷へ下りることができ,土石流堆積物やF1,F2断層の断層ガウジを観察できる.
阿津江の破砕帯地すべりと山津波本章では,本見学地の阿津江の破砕帯地すべりと山津波(第6図)について記述する.なお,見学地点との関係を明確にするために,適宜【STOP番号】を文末等に記した.
1.災害地名「阿津江」
第7図.見学地点位置図(国土地理院発行1/25,000地形図「雲早山」に加筆).
小川(1995)によると,「阿津江」という地名は,古語「アズヘ」で崖崩れの上,崖崩れの辺りを意味しているらしい.楠原・溝手編(1983)の地名用語語源辞典では,「アヅ」は崩壊,久豆礼とあり,「エ」は上の転訛,動詞ヱル(彫)の語幹で「掘られたような地形」,動詞ヱル(笑)の語幹で「ほころびる.割れる」といった意味があるようである.
また,阿津江にある竜王山黒滝寺(第7図)には,その昔,弘法大師が悪竜を退治して寺の池に封じ込めたという伝説が残っている.大師が退治した「悪竜」とはおそらく山津波を指していると考えられる.このように,自然地名や当地に伝わる伝説からも阿津江では過去に地すべりが発生したであろうことが読み取れる.
2.古い変動地形・過去の土石流堆積物
第8図.阿津江山津波発生域付近の地質図.(横山ほか,2005を修正)
上述の悪竜を封じ込めたという池は現在空池であるが,1582年に長曽我部元親の軍勢が黒滝寺に攻め上った時には池の水が血で染まったと伝えられている【STOP5】.この池は開口クラックに起因した線状凹地である可能性が高く,池の水が涸れたのは斜面変動に伴ってクラックが再び開口したことが原因と考えられる.池の位置は後述する破砕帯地すべりAの崩壊壁背後に広がる準変動域(大八木,1992)(変動域A‐1)を画するクラック群の北方延長上に当たる.線状凹地は準変動域の背後の尾根にも存在する【STOP 5】.尾根の裾には段差地形が認められ,準変動域を画するクラック群の一部は段差地形に沿っている【STOP 5】.
破砕帯地すべりAの滑落崖の北半部には成層構造を有する土石流堆積物が露出している【STOP 6】(第8図).今回の山津波が流下した谷の右岸壁にも削剥によって過去の土石流堆積物が露出した【STOP 6】.また,今回山津波が乗り上げた対岸斜面にも過去の土石流堆積物が露出した.これらの事実は,この谷で複数回の山津波が発生したことを示唆している.
3.基岩の地質
第9図.F2断層の断層ガウジ.
阿津江の破砕帯地すべりの発生域から山津波の末端まで,基盤にはペルム紀の緑色岩が広く分布している【STOP 2,3,5,6】(第8図).岩石名は緑色岩であるが,地表付近に露出している緑色岩のほとんどは赤紫色を呈していて,雨が降ると赤紫色の水が流れ出てくる.緑色岩には無数の微小断層群が網目状に発達し,個々の断層面は非常に磨かれた鏡肌になっているのが特徴である【STOP 2,3,6】.このような破砕構造を有する地質を小出(1955)は破砕帯と呼んでいる.
この緑色岩の中には局部的に石灰岩や砂岩の薄層が挟在している.坂州木頭川沿いの緑色岩中で挟在している石灰岩は褶曲したり,小断層によってずれていたりするが,全体としては緩やかに北に傾斜している.山津波による削剥で河床に露出した石灰岩と緑色岩の境界面の走向・傾斜はN40°E,16°NWと緩傾斜である【STOP 3】.尾根付近に存在する砂岩の分布形態も緩傾斜である.第4図の地質図は高角度の地質構造が読めるが,阿津江周辺地域の地質構造は緩傾斜である可能性が高い.阿津江の破砕帯地すべりの発生域から山津波の流下した谷の出口にかけて,走向はN60°E〜N65°Eで傾斜は30°程度北落ちのF1断層が走っている【STOP 6】.谷の出口付近の左岸谷壁には,F1断層面が露出している【STOP 3】.この断層面には山津波の流下による削痕が多数刻まれている.破砕帯地すべり発生域には走向N52°W〜N60°Wで傾斜32〜62°SのF2断層が右岸谷壁に沿って走っている【STOP 6】.F1 断層とF2 断層を地下に延ばすと地下で交わることになり,両断層とも幅1m前後の粘土質の断層ガウジを伴っているために遮水層になりうると考えられる(第9図).
4.阿津江の破砕帯地すべり発生域の斜面変動
第10図.阿津江の破砕帯地すべりの分布図(横山ほか,2005を修正).
変動領域A‐1のa〜e領域クラック群の形態.
阿津江の破砕帯地すべりは谷頭部付近と支谷の左岸側の標高480 m付近で発生した(第10図).それぞれ,破砕帯地すべりA, Bと記号を付け,さらに破砕帯地すべりAは記載の便宜上A‐1〜A‐5の5つの変動領域に区分した.
(1)破砕帯地すべりA
1)変動領域A‐1【STOP 5】変動領域A‐1は破砕帯地すべりAの滑落崖背後に広がる準変動域で,その頭部を画すクラック群と変動領域A‐2の滑落崖と変動領域A‐3の滑落崖に挟まれた領域を指す.ただし,変動領域A‐1はこれらのクラック群によって完全に閉じているわけでない.クラック群はクラックの分布形態や方向によってa〜eの5つの領域に分けることができる(第11図).このうち,a領域からc領域に至るクラック群は変動領域A‐1の頭部を画するもので,d領域のクラック群は変動領域A‐2の滑落崖の背後に,e領域のクラック群は変動領域A‐3の滑落崖の背後に分布している.
a領域a領域のクラックは局部的に湾曲しているが平均方向N65°Wで約100 m連続し,変動域A‐1の頭部の北端の頭部を画している.クラックの南南西側(変動領域側)が約100 cm下がり,多くの場所で50 cm程度開口している.破断面には風化した緑色岩が露出している.クラックを跨いで伸びる緊張した樹根の方位から推定した変動域側の地盤の移動方向は南西である.
b領域b領域は,N25°Eに延びる帯状の領域に,長さ2〜36 mで北西から南北に延びる多数のクラックが雁行状に分布している.a領域に続くが,クラックの方向は大きく変化している.全てのクラックで南西側(変動領域側)が20〜250 cm下がる.開口幅の狭いクラックが多いが,80cm開いているところもある.破断面には風化した緑色岩か岩屑が露出している.緊張した樹根の方位は,クラックの走向に直交する方向に対して,反時計回りに10〜40 度斜交している.これは,クラック群の雁行状配列パターンから推定される変位センスと調和的で,左横ずれを示している.緊張した樹根の方位から推定した変動域側の地盤の移動方向は西南西である.c領域c領域には N58°E〜N50°Eに延びる長さ約70mのクラックが分布している.クラックの南西側(変動領域側)が80〜220 cm下がり,開口幅は狭い.破断面には新鮮な緑色岩が露出しているところが多い.緊張した樹根の方位から推定した変動域側地盤の移動方向は西南西である.
d領域d領域はc領域のクラックと変動領域A‐2の滑落崖とに囲まれた領域で,加持久保神社の境内にあたる.複数のクラックが発達しているが,西側に発達する長さ約25 mでN23°E〜NS方向に延びるクラックに沿ってクラックの東側(境内側)が20〜60 cm下がっているので,このクラックとc領域のクラックに囲まれた領域は陥没していることになる.そのほかのクラックはNS〜N30°Eで落差を伴わない開口クラックで,上記の連続性の良いクラックの東側に分布している.
e領域e領域は変動領域A‐3の滑落崖の背後に位置している.長さ10 m以下のクラックが複数分布する.ひと続きのクラックであっても折れ曲がり,クラック群の方向はN22°W〜N50°Eと変化が著しい.クラックの北側(変動領域側)が下がるものとその反対側が下がるものとがあるが,落差は20〜80 cmで差はない.破断面には風化した緑色岩か岩屑が露出している.緊張した樹根の方位はばらつく.e領域のクラック群は変動領域A‐3の変動に関係して形成された可能性があり,クラックのあるものは変動領域A‐3の滑落崖に連続しているが,あるものはクラックに直交する滑落崖に切られている.2)変動領域A‐2【STOP 5,6】
変動領域A‐2は破砕帯地すべりAの中央部の南側に当たり,地すべり移動体は緑色岩からなり,一部砂岩層を挟在する.地すべり移動体そのものは大部分が発生域に残っている.樹木の傾動から地盤の動きを読み取ることができる.頭部滑落崖は加持久保神社の前の道路の西端に沿って走り,落差2 m程度の崖をつくっている.崖には風化した緑色岩が露出し,その中に地表部ほど広く開口したクラックが発達している.地すべり移動体の左岸側部の上方は非変動岩盤と接し,下方は破砕帯地すべりBと接している.後者では,境界に沿って断層ガウジの絞り出しが認められることから,左岸側部に沿って,支谷の左岸側を走るF1断層が延びている可能性が高い.地すべり移動体の右岸側部は変動領域A‐3の左岸側方崖で切られている.
地すべり移動体の中央部にも段差の明瞭な滑落崖が発生し,それより下流の地すべり移動体は回転すべりを起こし,樹木は山側に傾動している.そしてさらに地すべり移動体の末端では岩塊・岩片が堆積している.これは地すべり移動体内で分離した岩塊・岩片が樹根の繁茂している表層を残して流れ出して堆積したもので,地すべり性崩壊の特徴が一部に現れている.
3)変動領域A‐3【STOP 5,6】
変動領域A‐3は破砕帯地すべりAの中央部から下部にあたる.現在は地すべり移動体のほとんどが発生域から移動し,山津波となって流下している.右岸側方崖の上部10〜20 mは過去の土石流堆積物からなり,その下部には緑色岩が分布している.緑色岩の崖の下部の一部には,谷の右岸側を走るF2断層が顔を出している.頭部滑落崖と左岸側方崖は緑色岩が露出している.また,発生域の下流部谷底には過去の土石流堆積物が崩壊せずに残っている.したがって,変動領域A‐3の地すべり移動体はその上部が緑色岩で,中央部から下部にかけては過去の土石流堆積物でできていたものと推定している.
4)変動領域A‐4【STOP 6】
変動領域A‐4は変動領域A‐3の崩壊後,不安定になって崩壊し,山津波となって流下した.地すべり移動体は旧土石流堆積物からできていたものと考えている.
5)変動領域A‐5【STOP 6】
砂岩層からなる南北方向の滑落崖をもつ古い地すべり移動体の右半部が変動したもので,東西方向の開口クラックが民家の下を走ったために民家は大きく傾き,ねじれている.クラック内の緊張した樹根の方位から推定される地すべり移動体の移動方向は北北西である.地すべり移動体の北側は変動領域A‐3の左岸側方崖に切られている.
(2)破砕帯地すべりB
地すべり移動体の地表には樹木が残っていて,地すべり移動体から崩れでた岩塊・岩片は山津波となって流下し,後述するルートCの山津波の主体となった.
(3)斜面変動の順序
破砕帯地すべりAの各変動領域の間で斜面変動の順序を検討した.
変動領域A‐1は大局的には南西から西南西方向に移動しており,変動領域A‐2や変動領域A‐3の移動方向(西北西)とは異なっている.さらに,頭部クラック群に沿う変動領域の移動方向はa領域と,b領域とc領域との間で異なっている.また,a領域の北の端から変動領域A‐2の滑落崖までは大きく離れている.以上のことから,変動領域A‐1の地下にひと続きのすべり面が形成されていると考えるのは疑問である.破断面に現れた条線の落とし方向は近傍の緊張した樹根の方向と調和的で,条線の落とし方向も領域毎で異なり,しかも落とし角は高角である.その落とし角を地下に延ばすとすべり面は地下深く潜り込んでしまう.このことからもひと続きのすべり面で滑動している可能性は低い.また,変動領域A‐1の中央部で掘削した掘進長75 mのボーリングコアにもすべり面であることが確実な構造は観察されていない.
変動領域A‐1の頭部のクラック群に沿う移動方向は変動領域A‐3の滑落崖の方向と大きく斜交しているので,変動領域A‐3の崩壊で不安定化して変動領域A‐1が動いたとは考えにくい.斜面変動A‐1と斜面変動A‐3との関係,斜面変動A‐2と斜面変動A‐3との関係も同様に考えることができる.すなわち,破砕帯地すべりAでは,変動領域A‐1,A‐2,A‐3,A‐4あるいはA‐5の順に変動したと考えている.
5.山津波の運動像
(1)山津波の流下痕跡
阿津江の破砕帯地すべりでは,山津波が流下したことを示すさまざまな証拠(流下痕跡)が得られている.以下に流下痕跡の種類と特徴を述べる.
1)土石流堆積物と現河床堆積物由来の礫土石流堆積物が山津波の流下経路を示す証拠であることはその通りであるが,阿津江では破砕帯地すべりの発生域から山津波の先端まで,基岩は緑色岩で構成されているため,斜面に分布する岩屑が今回の山津波の産物であることを示すには,ある程度の厚さの岩屑が地表面を被覆していることが示されないと難しい.今回山津波が乗り上げた坂州木頭川の右岸側斜面では,山津波が坂州木頭川を渡るときに巻き上げた現河床堆積物由来の礫が重要な証拠になった.砂岩や石灰岩の円〜亜円礫は現河床堆積物由来の礫である【STOP 2】.
第12図.樹幹切断部のささくれの傾動現象(中屋ほか,2006).矢印はささくれの傾動方位を示す.ささくれの間には礫がはさまっていて,根元には番線を含む流下物が巻き付いている.
第13図.樹皮の剥げ落ち現象(中屋ほか,2006).矢印は剥げ落ち部の最上位を示している.
第14図.礫の突き刺さり現象.(a)樹皮の剥げ落ち部に突き刺さった緑色岩の粗礫.やや下方より上向きに突き刺さっている様子がうかがえる.(b)樹皮の剥げ落ち部に突き刺さっている緑色岩の中礫群.樹幹のめくれ上がりの範囲と中礫がジグソーパズルのようにかみ合っていることから粗礫が衝突後に粉砕したものと思われる.(c)樹皮の剥げ落ち部に斜め上方から突き刺さった痕跡を残す緑色岩の中礫.土石流の乗り上げ方向とは逆方向から突き刺さっているため,土砂が斜面に衝突した際に礫がその衝撃で飛散したことをうかがわせる.
第15図.スギ立木の樹幹に残された流下痕跡の一例.
第16図.樹幹への流下物の巻き付き現象(中屋ほか,2006).巻き付いたものの多くは枝葉や樹根であり,番線や電線などもみられた.また,現河床礫が流下物の中に挟まってこともある.
第17図.符殿橋の橋脚の鉄筋の折れ曲がり.鉄筋の曲がり方向は山津波の引きの流れ方向と一致している.
2)樹木に刻まれた流下痕跡【STOP 2】山津波発生後の空中写真をみると,山津波が流下したところは樹木が失われている(日浦ほか,2004;Hiuraet al.,2005;Wang et al.,2005;橋本ほか,2006).樹木の流出は山津波の流下経路を示す重要な流下痕跡である.
流出していない樹木もさまざまなダメージを受けており,それらは山津波の水位や流下方向が推定できる流下痕跡である(村井ほか,2006;中屋ほか,2006).阿津江では,樹幹の切断,樹皮の剥げ落ち現象,礫の突き刺さり現象,流下物の樹幹への巻き付き現象が観察されている(中屋ほか,2006).
樹幹の切断樹幹の切断には,ほぼ樹幹の根元付近で切断され,切断面が縦に裂けてジグザグにささくれたもの(第12図)と,地表から数メートルの所でかなり鋭利な面で切断されたものの二通りが見られた.いずれの場合にも切断面に礫が挟まっている.第12図では,ささくれが一方向に折り曲げられているが,折り曲げられた方向は流下方向を示すものと考えられる.
樹皮の剥げ落ち現象流下物が樹幹へ衝突したことによって樹皮の一部分が剥げ落ちている現象(第13図)で,剥がれた部分の向きが山津波の流下方向を示していると考えている.
礫の突き刺さり現象礫の突き刺さり現象は台風15号によって高知県大川村で発生した山津波でも,山津波が通過した渓流内の樹木で観察された(村井ほか,2006).上流側から突き刺さっている礫が多いことから,それは山津波の流下方向を示しているものと考えられた.阿津江では山津波が乗り上げた斜面に植わっている樹木で多数観察された(第14図,第15図).礫は樹皮が剥げ落ちた部分に突き刺さっていることが多く,礫径は数mmから数cmで,ほとんどが緑色岩であるが,現河床礫もある.後述するように,礫の突き刺さり現象からは複数の流下方向が推定される.流下物の樹幹への巻き付き現象流下物の樹幹への巻き付き現象は河川で橋脚に漂流物が上流側から巻き付くのと同じ現象で,流下方向が推定できる重要な指標である(第16図).
3)構造物に刻まれた流下痕跡さまざまな流下痕跡が観察されるが,後述するように,阿津江では駐車してあった車両の移動方向や符殿橋の橋脚の鉄筋の曲がり方向(第17図)が山津波の流下方向を示す貴重な流下痕跡となった.
第18図.阿津江で発生した山津波の流下経路.(横山ほか,2005を修正)
第19図.阿津江で発生した山津波の末端部の被災直後の様子.
第20図.阿津江で発生した山津波の流下・到達範囲.(横山ほか,2005を修正)
(2)山津波の流下経路
樹木の流出範囲から推定される山津波の流下経路はルートA〜Cの3ルートである【STOP 1】(第18図).
1)ルートAの山津波
ルートAの山津波は支谷の中央を流れて坂州木頭川まで達した後,坂州木頭川を堰き止め,対岸に乗り上げた山津波である.この山津波は河床に堆積していた過去の土石流堆積物を削りながら流下するとともに,流路の右岸側では,過去の土石流堆積物の地表面を流れている.一方,左岸側では,山津波の一部が低い尾根をのり越えて,ルートCの谷にも流れ込んでいる.
坂州木頭川に達した山津波による土石流堆積物は坂州木頭川河床を上流および下流に広がっている.河床の土石流堆積物の分布から山津波の上流方向の広がりはかなり正確に推定できるが,下流方向の広がりは土石流堆積物の流失により不明である.山津波の本体は川幅180 mの河床を渡り,対岸にぶつかった山津波は道路上を上流方向および下流方向に流れている.上流方向に流れた土石流堆積物はガードレールに捕捉されて,坂州木頭川に落ち込むことなく,道路上を上流に向かって流れている(第19図).一方,下流方向に流れた山津波は符殿トンネル内に流れ込み,長さ350 mのトンネルの反対側に出ている(第20図).トンネル内には土石と共に流木や車両が流れ込み,トンネルの天井のライトを破壊している.この山津波が対岸の正面斜面および符殿トンネル上方の斜面に乗り上げたことは樹木の流失から明らかであるが,乗り上げたはずの土石流堆積物や流木がほとんど残っていないのが特徴である.坂州木頭川を渡った山津波の先端部の運動像はさまざまな流下痕跡から読み取った.
山津波が乗り上げた斜面では,樹幹を切断された樹木が分布する範囲よりもさらに斜面上方に向かって約10〜20 mの範囲に,樹皮の剥げ落ち現象や,礫の突き刺さった樹木,現河床堆積物由来の礫が分布している.山津波の真正面に当たる対岸では,平均勾配約40°の斜面を標高350 mの高さまで山津波が到達している.
山津波が乗り上げた坂州木頭川右岸側の斜面は湾曲していて,符殿トンネルを境に,トンネルの坑口に向かって右側斜面が南北方向に延び,左側斜面が東西方向に延びている.山津波が乗り上げてきた方向は,樹皮の剥げ落ちの方向や樹幹に突き刺さっている礫の方向から斜面にほぼ直交する方向であると推定される(第20図).乗り上げてきた山津波の流れの方向は,土石流堆積物の分布から推定される山津波の流れの方向と調和的である.主要な山津波の乗り上げとは別に,トンネルの坑口に向かって左側斜面では,樹幹に突き刺さっている礫の方向からは西から東への流れも読み取れる.
一方,山津波の主要な乗り上げの方向とは正反対の流れが樹木切断部のささくれの方向と流下物の樹幹への巻き付き現象から斜面全域に読み取れる.一旦乗り上げた山津波が同じ斜面を流れ下っていく引きの流れである.土石流堆積物や流木,さらには一部の橋脚を残してほとんど失われた符殿橋の流失はこの強い引きによるものと思われる.破壊された符殿橋の橋脚の鉄筋の曲がりも引きの流れの方向と一致している(第17図).
2)ルートBの山津波
ルートBの山津波は支谷の出口に近いところでルートAの山津波から分岐したもので,坂州木頭川からの比高が約50 mの尾根に乗り上げている.山津波が尾根に乗り上げたのは,支谷の谷底をそのまま下流に延ばすと尾根の稜線に続いているからである.
尾根に駆け上がった後のルートBの山津波の挙動はどのようなものであったであろうか.ルートBの山津波は尾根の樹木をことごとく根こそぎなぎ倒しているが,坂州木頭川の左岸壁に植わっている樹木にはほとんど損傷を与えていない.しかし,次に述べる現象はルートBの山津波が対岸に到達したことを示唆している.
gあるいはhの地点にあった重機運搬車とcあるいはdの地点にあったダンプカーの一台が道路上に東から西にトンネルのところまで運ばれ,その後トンネル内に持ち込まれている(第21図).これらの車両はルートAの山津波の流れによって運搬されたのなら,運搬の方向は西から東で,東から西への運搬は不可能である.しかし,ルートBの山津波なら東から西への車両運搬は可能であるだけでなく,ルートBの山津波の流れなくして,車両は東から西へは運ばれない.ルートBの山津波によってトンネルの前まで運ばれてきた車両がルートAの山津波によってトンネル内に運び込まれたものと解釈している.ただし,ルートBの山津波が坂州木頭川の河床を渡ったとは考えにくい.上述した坂州木頭川の左岸壁の樹木の破損状況に加え,右岸側の尾根に植わっている複数の樹木が地表から数mの高さで鋭利に切断されていること,ルートAの山津波より先に対岸に到達していなければならないことから,ルートBの山津波のかなりの量が坂州木頭川を跳び越えて対岸に達したと考えている.
第21図.阿津江で発生した山津波によって移動した建設重機の位置図(横山ほか,2005を修正).
3)ルートCの山津波
ルートCの山津波は,破砕帯地すべりCから発生した土石流で,ルートAの支谷(南側の小さな谷)を流れている.このルートの山津波は対岸には到達せず坂州木頭川に流れ込んでいる.
(3)山津波先端部の到達時刻の推定
山津波が乗り上げた坂州木頭川右岸斜面の直上にある符殿地区住民は8月1日23時頃に「ドシーン」や「ゴォー」といった大きな音を聞いている.また,家やガラス戸の揺れなどを体感している.
証言に共通している「大きな音」は山津波が坂州木頭川を渡ってから対岸に乗り上げるまでの音であり,「瞬間的な揺れ」は山津波が対岸に衝突したときの衝撃と考えられる.よって,山津波が対岸に到達した時刻は8月1日23時頃と推定される.
旧木沢村役場の加集一夫氏は,山津波が坂州木頭川河床に流入した地点から約500 m上流にある名古ノ瀬橋での河川水位の記録から,土石流堆積物による天然ダムの形成とその決壊の時刻を次のように推定している.河川水位の記録は,8月1日22時50分に5.89 mであったものが23時00分に6.38 m(0.49 m上昇)となり,その後同23時10分の6.38 mから23時50分の6.08 m(0.30 m下降)へと変動したことを示している.このことから,23時00分の水位上昇は土石流堆積物による堰き止め,23時10分からの水位低下は土石流堆積物からなる天然ダムの決壊によるものと解釈している.土石流堆積物による堰き止め時刻は符殿地区の住民の証言と調和的であり,山津波が到達した時刻は23時の少し前と推定される.坂州木頭川の河床勾配と波高を考慮すると,天然ダムの高さは7 mくらいになっていたものと推定される.その後起こった天然ダムの決壊は河川の越流による浸食の可能性が高い.
文 献
地学団体研究会編,1996,新版地学事典.平凡社,東京,1443p.
Chigira, M.,1992,Long-term gravitational deformation ofrocks by mass rock creep.Eng. Geol.,32,157-184.千木良雅弘,1995,風化と崩壊.近未来社,名古屋,204p.
千木良雅弘,1998,岩盤クリープと崩壊−構造地質学から災害地質学へ.地質学論集,no.50,241-250.
千木良雅弘・長谷川修一・村田明広,1998,四国の四万十帯にある加奈木崩れの地質・地形特性.日本応用地質学会平成10年度研究発表会講演論文集,61-63.
古谷尊彦,1979,四国山地のGravitational Slideの予察的研究 ‐三嶺・天狗塚・綱附森・京柱峠付近の空中写真判読を例に‐.千葉大学教養部研究報告,B-12,63-68.
布施昌弘・横山俊治,2003,四国島の線状凹地の分布と特徴.第43回日本地すべり学会研究発表会講演集,561-564.
橋本英俊・佐藤威臣・山田正雄・小島健・久積崇広,2006,阿津江地すべりの地すべり機構.日本地すべり学会誌,42,no.6,37-42.
日浦啓全・海堀正博・末峯章・里深好文・堤大三,2004,2004年台風10号豪雨による徳島県木沢村と上那賀町における土砂災害緊急調査報告(速報).砂防学会誌,57,no.4,39-47.
Hiura, H., Kaibori, M., Suemine, A., Yokoyama, S. andMurai, M.,2005,Sediment related disasters generatedby Typhoons in 2004.In Senneset, K., Flaate, K. andLarsen, J.O., ed., Landslides and avalanches ICFL2005Norway, 157-163.
井上公夫・森 俊勇・伊藤達平・我部山佳久,2005,1892年に四国東部で発生した高磯山と保瀬の天然ダムの決壊と災害.砂防学会誌,58,no.4,3-12.
石田啓祐・香西武,2003,四国東部秩父累帯の地帯区分と層序.徳島大学総合科学部自然科学研究,16,11-41.石田啓祐・元山茂樹・吉岡美穂・岡本治香・西山賢一・橋本寿夫・森江孝志・中尾賢一・小澤大成・香西武・辻野泰之,2005,徳島県木沢村地域の秩父-黒瀬川帯海底火山噴出物の組成と随伴層の微化石年代.阿波学会紀要,51,9-16.
加藤弘徳,2002,中央構造線南側の四国法皇山脈の山体変形.日本応用地質学会平成14年研究発表会講演論文集, 321-324.
甲藤次郎,1980,南四国(外帯)の山地災害とその対応.四万十帯の地質学と古生物学−甲藤次郎教授還暦記念論文集−,121‐146.
小出博,1955,日本の地辷り:その予知と対策.東洋経済新報社,東京,259p.
楠原佑介・溝手理太郎編,1983,地名用語語源辞典.東京堂出版,東京,661p.
松岡篤・山北聡・榊原正幸・久田健一郎,1998,付加体地質の観点に立った秩父累帯のユニット区分と四国西部の地質.地質雑,104,634-653.
村井政徳・横山俊治・中屋志郎・佐々浩司・日浦啓全,2006,流下痕跡による土石流の洪水位の推定:2004年台風15号豪雨によって発生した高知県嶺北地方の
土石流災害の例.日本地すべり学会誌,42,no.6,31-36.
村田明広,2003,徳島県木沢地域の黒瀬川帯北縁部の地質構造.徳島大学総合科学部自然科学研究,17,7-17.
中屋志郎・佐々浩司・横山俊治・村井政徳,2006,樹木に残された流下痕跡による阿津江土石流の流下方向の推定.日本地すべり学会誌,42,no.6,43-49.
日本地すべり学会地すべりに関する地形地質用語委員会編,2004,地すべり地形地質的認識と用語.社団法人日本地すべり学会,東京,318p.
西本晴男,2006,土石流に関する表現方法の変遷についての一考察.砂防学会誌,59,no.1,39-48.
西山賢一・石田啓祐・村田明広・岡田憲治,2005b,2004年台風10号に伴う豪雨により徳島県那賀川流域で発生した斜面崩壊の地質・地形的特徴.徳島大学総合科学部自然科学研究,19,49-61.
西山賢一・寺戸恒夫・石田啓祐・村田明広・岡田憲治,2005a,2004年台風10号に伴う豪雨で発生した木沢村の斜面災害と地すべり地形.阿波学会紀要,51,1-8.
小川豊,1995,自分で学べる防災の知恵崩壊地名.山海堂,東京,279p.
大八木規夫,1992,土砂災害.荻原幸男編:災害の事典.朝倉書店,東京,177-252.
砂防学会編,2004,砂防学用語集.山海堂,東京,432p.櫻井正明・内藤洋司・前川峰志・佐保昇児,2006,2004年集中豪雨により四国山地に発生した崩壊地の特性.日本地すべり学会誌,42,no.6,19-30.
四国地方土木地質図編纂委員会,1998,四国地方土木地質図解説書.財団法人国土開発技術センター,859p.
寺戸恒夫,1970,徳島県高磯山崩壊と貯水池防災.地理科学,14,22-28.
寺戸恒夫,1975,四国東部における大規模崩壊.阿南工業高等専門学校研究紀要,11,91-100.
寺戸恒夫,1977,大規模崩壊による山地地形の変化.地理科学,28,17-27.
寺戸恒夫,1986,四国島における大規模崩壊地形の分布と地域特性.地質学論集,no. 28,221-232.
富永良三,1990,四国東部秩父帯北部のジュラ紀付加体.地質雑,96,505-522.
Tominaga, R.,1990,Tectonic development of ChichibuBelt, Southwest Japan.Jour. Sci. Hiroshima Univ., Ser.C,9,377-413.
Wang, G., Suemine, A., Furuya, G., Kaibori, M. and Sassa,K.,2005,Rainstorm‐induced landslides at Kisawavillage, Tokushima Prefecture, Japan, August 2004.Landslides,2,235-242.
山北 聡,1998,北部秩父帯とはどの範囲か −北部秩父帯と黒瀬川帯をめぐる地帯区分上の問題−.地質学雑誌,104,623-633.
横山俊治,2003,小出(1955)の破砕帯地すべりと三波川帯の斜面変動.日本応用地質学会中四国支部平成15年度研究発表論文集,87-94.
横山俊治・柏木健司,1996,安倍川支流関の沢流域の瀬戸川層群に発達する斜面の傾動構造の運動像.応用地質,37,no.2,102-114.
横山俊治・村井政徳・中屋志郎・佐々浩司・日浦啓全,2005,2004年台風10号の豪雨によって徳島県那賀町阿津江で発生した破砕帯地すべりの運動像の復元.地盤災害・地盤環境問題論文集,5,31-40.
No.0030 2008/5/21geo-Flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.030 2008/05/21 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
□ 四川大地震に関しての緊急情報
【1】四川大地震に関する情報
【2】地質背景(緊急寄稿)
【3】会員からの情報
□ ミュンマーサイクロン災害に関しての緊急情報
【4】ミャンマーサイクロン災害に関する情報
【5】被災状況
□ 未曾有の災害に対する学会の対応に付いて
【6】地質学会の対応について
【7】地球惑星科学連合大会での緊急発表
【8】緊急人道支援に関して
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】関東支部 第2回研究発表会「関東地方の地質」・支部総会(6/8)
【10】堆積学スクールOTB2008(6/18-20)
【11】第7回産学官連携推進会議(6/14 日本学術会議 主催)
【12】サマー・サイエンスキャンプ 2008参加者募集
【13】第21回国際ミネラルフェア(6/6-6/10)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】四川大地震に関する情報
──────────────────────────────────
発生日:2008年5月12日(月)
発生時間:14:28(現地時間), 15:28 (日本標準時間)
震源地:中華人民共和国 四川省、北緯31度01分5秒、東経103度36分5秒
震源の深さ:19km
マグニチュード:7.9 -> 8.0 (5月18日修正)
関連断層:龍門山断層
USGS Earthquake Center:速報および地震概説、過去の記録などがまとめられています。
産総研:震源地域の地質、構造、過去の地震、文献などがあります。
東京大学地震研究所:震源解析(暫定解その2)や簡単なテクトニクス解説があります。
名古屋大学NGY地震学ノート:震源解析と解説があります。
筑波大学西村直樹・八木勇治さん:震源解析の図とアニメーションおよび解説があります。
JAXA:陸域観測技術衛星「だいち」による地震前後の地形変化
日本建築学会:各種情報が網羅されている
GUPI(地質情報整備・活用機構)
政府の対応(外務省発表)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】 地質背景 (池田会員による地震直前の調査結果から緊急寄稿)
──────────────────────────────────
私たちは,数年前から中国地震局と共同で,チベット高原南東部の康定断層帯
(Kangding Fault Zone;鮮水河-小河断層帯 Xianshuihe-Xiajiang Fault
Zone とも呼ぶ;付図参照)の研究を行ってきました。今年もついひと月前迄
現地調査を行い成都を経由して帰国したばかりのところに、突然飛び込んだ
大地震の知らせ でした。正直に告白すると、龍門山断層帯がこのように大きな
地震を起こすとは,私は予想していませんでした・・・
続きは・・・http://www.geosociety.jp/hazard/content0025.html
池田安隆(東京大学)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】会員からの情報
──────────────────────────────────
地球惑星科学連合大会で地質学会会員からは下記3件の報告がなされます。
(5月26日、幕張)
1)寺岡易司・奥村公男・神谷雅晴
2)奥村公男・寺岡易司・神谷雅晴
3)神谷雅晴 ・寺岡易司・奥村公男
東アジアの地質図,鉱物資源図等を用いて、被災地域の地質を説明いたします。参考資料は、
http://www.gsj.jp/jishin/china_080512/index.html
静岡大学 林 愛明 教授の緊急現地調査報告は【7】をご参照ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】 ミャンマーサイクロン災害に関する情報
──────────────────────────────────
サイクロン名:ナルギス(Nargis)
5月2日にミャンマー上陸
最大瞬間風速:72 m/s
5月11日現在の国連人道問題調整事務所の発表によると、
「行方不明者は22万人、死者数は6万3000〜10万人、救援が必要な
被災者は122万 〜192万人」と推計。
国連人道問題調整事務所
JAXA:陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)による緊急観測(1)
JAXA:陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)による緊急観測(2)
土木学会:緊急現地調査報告
日本建築学会
政府の対応(外務省発表)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】被災状況
──────────────────────────────────
入国VISAなどの問題もあり、国際人道支援や現地調査なども遅れている
ようです。そのなか(社)土木学会の緊急現地調査報告によると(上記URL参照)、
河口から90km上流の支流にも高潮が押し寄せ、浸水被害をもたらしている
ことなどが19日に発表されました。被災された方々は、いまだに浸水した
場所での生活を余儀なくされ、生活環境の悪化による感染病などの蔓延など、
二次災害が懸念されています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質学会の対応
──────────────────────────────────
地質学会会員の皆様
ミャンマーのサイクロン、中国四川省の大地震と、アジアで尊い多くの命が
奪われる大規模な自然災害が立て続けに発生いたしました。命を落とされた
人々のご冥福をお祈りし、困難に立ち向かっている方々の奮闘をお祈りした
いと思います。
これらの災害に対して、地質学はその科学的な解明に寄与し、災害を小さく
するために貢献することが求められています。すでに日本地質学会会員によ
る現地調査、あるいはこれまで関連する研究をされて来た会員などによる説
明等、多くの情報が寄せられております。それらを学会のサイトに公開、
リンクを形成いたしました。
日本地質学会は、中国地質学会に対し、お見舞いのメッセージと、今回の地
震に私たちがどのように対応したいと考えているかを説明するメッセージを
発信することといたしました。
私たちの職業的使命の一つはこれらの自然災害の対策と研究であります。地
質学を学びつつある学生、大学院生諸君の社会的使命の一つもまたこれらの
自然災害の対策と研究です。こうした使命に鑑み前例にないことではありま
すが、学会のサイトに人道支援の募金を実施している権威ある組織へのリン
クを形成いたしました。多くの方々による支援を呼びかけたいと思います。
日本地質学会・会長 木村 学
日本地質学会・理事会
お見舞いメッセージは学会HPをご覧ください(中文、英文)。
http://www.geosociety.jp/hazard/content0026.html
現地調査などを予定されている方は、ぜひ学会事務局までご一報願います。
地質学会では、他学会との連絡を行い、現地での混乱や救援活動に支障の無いよう支援していきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】地球惑星科学連合大会での緊急発表
──────────────────────────────────
緊急ポスターセッション
5月26日 場所:ポスター会場
掲示時間: 10:00-19:30
コアタイム: 17:15-18:45
ミャンマーサイクロン
水文水資源学会、気象学会合同:7件
四川省地震
地震学会:14件
測地学会:4件
地質学会:3件
緊急現地調査報告会
5月26日12時50分ー13時30分 場所:303号室
静岡大学 林 愛明 教授が現地調査結果を速報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】緊急人道支援に関して
──────────────────────────────────
お近くのコンビニ、銀行など、あるいはインターネットによる募金が可能です。
募金には各団体の活動趣旨にご留意ください。
日本赤十字社
ドラえもん募金
カンガルー募金
Yahoo!ボランティア
イーココロ:各種ショッピングポイントによる寄付
日本ユニセフ協会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】関東支部 第2回研究発表会「関東地方の地質」・支部総会(6/8)
──────────────────────────────────
日 時:6月8日(日)12時30分〜17時20分
会 場:早稲田大学 国際会議場
参加費:無料(ただし講演資料集は有料) どなたでも参加できます.
支部会員で総会に欠席される方は、委任状んご提出をお願いいたします。
委任状フォーム・プログラム等詳細は、関東支部HPをご参照ください。
http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】堆積学スクールOTB2008(6/18-20)
──────────────────────────────────
「タービダイトと海底扇状地のダイナミクス」
日程:集合は18日夜,講義・巡検は7月19日(土)午前8時から
7月 21日(月)午後12時まで
講演会場・宿泊先
北海道立厚岸少年自然の家
〒088-1113 北海道厚岸郡厚岸町愛冠6番地
Tel:(0153)52-1151
http://www-es.s.chiba-u.ac.jp/geolo/naruse/OTB2008.html
申し込み締切;6月25日(水)までにメールで申し込んで下さい.
問い合わせ先:
日本堆積学会行事委員会
成瀬 元(千葉大学大学院理学研究科 naruse@faculty.chiba-u.jp)
横川美和 (大阪工業大学情報科学部 miwa@is.oit.ac.jp)
堆積学会HPもご参照ください。http://sediment.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】第7回産学官連携推進会議(6/14-15)
──────────────────────────────────
福田内閣府特命担当大臣(科学技術政策)による基調講演、産・学を代表する有
識者による特別講演に加え、個別の課題について、分科会ごとに分かれて、パネ
ルディスカッション方式で掘り下げた議論を行っていただく他、産学官連携の成
功事例についての発表会・表彰式を行います。さらに、各大学・研究機関・TL
O・民間企業等による産学官連携の事例紹介、研究成果・試作品の展示やワーク
ショップの開催も予定。
日時:6月14日(土) 10:00〜18:45
15日(日) 9:00〜12:30
場所:国立京都国際会館(京都市左京区宝ヶ池)
参加者:産学官の第一線のリーダーや実務者・専門家等
詳細、参加申込等については、
http://www.congre.co.jp/sangakukan/top.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】サマー・サイエンスキャンプ 2008 参加者募集
──────────────────────────────────
先進的な研究施設や実験装置等を有する日本各地の大学・公的研究機関・民間企
業49会場)が夏休みに高校生等を受け入れ、第一線で活躍する研究者・技術者等
から直接講義や実習指導が受けられる科学技術体験合宿プログラムです。
2008年7月22日〜2008年8月30日の夏休み期間中の2泊3日
参加費:無料(自宅から会場までの往復交通費は参加者負担)
応募締め切り:6月25日(水) <必着>
主催:独立行政法人 科学技術振興機構
サイエンスキャンプ事務局:財団法人 日本科学技術振興財団
問い合わせ TEL:03-3212-2454 FAX:03-3212-0014
詳しくは、http://spp.jst.go.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】第21回東京国際ミネラルフェア(6/6-6/10)
──────────────────────────────────
主催 東京国際ミネラル協会
6月6日(金)〜10日(火)
会場 新宿第一生命ビル1Fスペースセブンイベント会場
チケット 一般 1000円(公式ガイドブック付)
チケットぴあ・ファミリーマート・サンクスで発売中
無料講習会
6月7日(土)「始祖鳥の故郷ゾルンホーフェンの化石」
6月8日(日)仮題「ゾルンホーフェンの化石と歴史」
この他、無料鉱物鑑定会,「恐竜折紙」の世界等企画展も満載です.
http://www.tima.co.jp/tima/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質マンガ そして帰港
地質マンガ
「そして帰港」
戻る|次へ
No.0031 2008/6/3geo-Flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.031 2008/06/03 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】新会長あいさつ
【2】秋田大会情報! 申し込み受付開始
【3】地質の日イベント報告 各地で大盛況
【4】6月の博物館イベント情報
【5】地質学雑誌新表紙コンテスト結果
【6】四川大地震現地体験報告
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】海洋基本法制定一周年記念シンポジウム
【8】産業技術総合研究所地質分野:H21年度採用予定研究員募集
【9】資源地質学会第58回年会シンポジウム
【10】日本学術会議・北海道大学主催公開シンポジウム
【11】第24回ゼオライト研究発表会
【12】地質マンガ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】新会長あいさつ
──────────────────────────────────
地球環境問題のさらなる深刻化が人類の未来に暗雲を投げかけている今,
地質学・地球科学に関する研究をさらに発展させ,地球に関する理解の重要性と
地質学の意義,そして地質学会自体を強化していくことが求められています.
地質学会の新しい理事会一同,力を合わせてその先頭に立って努力する所存です.
また,こうした壮大な事業の推進・成功のためには,広範な会員の理解と協力が
必要です.ともに力を合わせてがんばりましょう.(宮下純夫)
全文はこちら
http://www.geosociety.jp/outline/content0002.html
学会の顔(2008年度理事紹介)はこちらから
http://www.geosociety.jp/outline/content0003.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第115年学術大会(2008 秋田大会)情報
──────────────────────────────────
参加登録、講演申し込み、見学旅行などなど受付開始!
webからの講演申込締切:7月10日(木)18:00
詳しい情報は下記へ
http://www.geosociety.jp/science/content0014.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】全国各地で大盛況!! 『地質の日』のイベントの様子をご紹介
──────────────────────────────────
今年から制定された、5月10日 『地質の日』には、全国各地の博物館・大学など
でイベントが開催され、どこも大にぎわい。イベントの様子が報告されています
ので,その様子をご紹介します。
■「地質の日制定記念 サイエンスフェスティバル
−化石やきれいな石にさわろう−」 速報
栗原敏之(新潟大学大学院自然科学研究科博士研究員)
新潟大学では、「地質の日」の5月10日(土)に「サイエンスフェスティバル−
化石やきれいな石にさわろう−」を開催しました。会場となった理学部には、小
学生と保護者を中心とする約450名が詰めかけました。毎年行われている大学祭を
除けば、このようなイベントが大学で行われることはまれですが、予想をはるか
に上回る人出と子供たちの熱気に正直驚かされました。
続きは、 http://www.geosociety.jp/name/content0015.html で
■「宮澤賢治ジオツアー」
NPO地質情報整備・活用機構が企画した宮澤賢治ジオツアーに参加して来ました.
案内者は元地質学会副会長で「宮澤賢治の地的世界」の著者である加藤碵一会員
です.首都圏を中心に,関西や北九州からの参加もあり,賢治ファンの方々は新
聞の行事欄に紹介されたお知らせをみて参加を申し込んだそうです.
続きは、 http://www.geosociety.jp/name/content0016.html で
■「地質の日記念講演会・観察会」
埼玉県立自然の博物館で行われた、講演会と・観察会の様子です。
詳細は、埼玉県立自然の博物館Webページへ
http://www.shizen.spec.ed.jp/event/e_repo/2008/20080510gioday.html
■「地質の日記念事業 三葉虫をさがせ! 化石採集教室」
栃木県葛生地域は「地質の日」当日は残念ながら雨となってしまい、化石採集教室は
中止となってしまいました。しかし、来館してくれた参加者の方向けにレプリカつくり
体験教室を開催。雨にも負けず参加してくれた方たちは一生懸命作った自分だけのレプ
リカを笑顔で持ち帰って行きました。
続きは、 http://www.geosociety.jp/name/content0017.html で
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】 6月も博物館へGO!!
──────────────────────────────────
関東甲信地方まで梅雨入りしましたが,梅雨にも負けず博物館はがんばりますよ。
野外観察会はもちろん,室内での体験イベントも充実です。
晴れても,雨が降っても,博物館へいらっしゃい〜!!
詳しい情報は
http://www.geosociety.jp/name/content0013.html でCheck!!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】 地質学雑誌新表紙コンテスト結果
──────────────────────────────────
多数のご応募ありがとうございました。その中から選考作品を1点決定しました。
以下選考結果をお知らせします。今後最終選考作品をもとに新デザインを作成し、
来年115巻1月号から新表紙デザインで地質学雑誌を皆様にお届けする予定です。
<最終選考作品:1件>
小柴雅樹
<佳作:2件>
萬年一剛・内田省吾
2008年5月 地質学雑誌新デザイン選考委員会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】四川大地震現地体験報告
──────────────────────────────────
地熱学会会員の宮崎眞一さん(四川大学)から、中国・成都での地震時の様子を
お知らせ頂きましたので、皆様にご紹介します。
-------------------------------------------------
四川大地震を成都で体験したので報告します。
私は日本地熱学会会員で地熱地質が専門です。今、四川大学に語学留学していま
す。
(1) 地震の時の様子
地震の時、私は成都の市街地にある四川大学で授業中でしたが、先生の一声でみ
な4階の教室から急いで下の緑地に降りました。校舎の外壁が少しはがれて落ちて
きて緊迫しましたが、皆無事に外に出ました。震度は3から4未満程度で、日本で
ならあわてて外に飛び出すほどではなかったように思います。揺れ方はドンドン、
ガンガンというものではなく、ユラリユラリと2分間くらいかなり長く続いたよう
です。
中国人や外国人は皆恐怖に怯えていましたが、日本人のみが平静でした・・・。
続きは、学会HPで
http://www.geosociety.jp/hazard/content0028.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】海洋基本法制定一周年記念シンポジウム
──────────────────────────────────
海洋新時代における海洋新産業の振興に向けて
日時 2008年6月27日(金)13:00-17:30
場所 東京大学安田講堂
主催 海洋技術フォーラム
お問い合わせ・お申し込みは、
下記ホームページから(プログラムも掲載されています)
http://blog.canpan.info/mt-forum/archive/346
海洋技術フォーラム事務局
電話:03-5841-6505 FAX:03-3815-8364
Email:ocntechf2008@gmail.com(お申し込み先)
Email:ocntechf@gmail.com(お問い合わせ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】産業技術総合研究所地質分野:H21年度採用予定研究員募集
──────────────────────────────────
地圏資源環境研究部門 地質特性研究グループ
■ 採用予定数:1名 産業技術人材育成型任期付研究員または中堅採用
■ 応募締切日:平成20年6月20日(金)
■ 採用予定時期:平成21年4月1日
■ 雇用期間:5年(平成26年3月31日まで)または任期の定めのない定年制
■ 問い合わせ先: 伊藤一誠,電話: 029-861-3977
地質情報研究部門 島弧堆積盆研究グループ
■ 採用予定数:1名 産業技術人材育成型任期付研究員または中堅採用
■ 応募締切日:平成20年6月20日(金)
■ 採用予定時期:平成21年4月1日
■ 雇用期間:5年(平成26年3月31日まで)または任期の定めのない定年制
■ 問い合わせ先:igg-saiyo20@m.aist.go.jp
詳しくは、http://unit.aist.go.jp/humanres/ci/02koubo/5_geological.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】資源地質学会第58回年会シンポジウム
──────────────────────────────────
ウランとレアメタル−資源確保,探査および研究
日時:2008年6月24日(火) (10:25〜17:40)
場所:東京大学小柴ホール(本郷キャンパス)
参加費:2,000円(講演要旨代を含む)
資源地質学会第58回年会学術講演会シンポジウム「ウランとレアメタル−資源確
保,探査および研究」では,学会内外の方々による下記13講演が予定されており
ます.関連諸分野の皆様にご参加頂き,ウランとレアメタル資源の利用,探査,
地質などについて活発にご討論頂ければ幸いです.
58回年会学術講演会:6月24日(火)〜26日(木)
プログラム・詳細は、
http://www.kt.rim.or.jp/~srg/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】日本学術会議・北海道大学主催公開シンポジウム
──────────────────────────────────
「地球温暖化 —科学者からのメッセージ」
人口増加、エネルギー消費の拡大等に伴う地球温暖化等、人為起原の地球環境の
問題は、21世紀の今、明らかに顕在化しており、生物圏と人間社会へ大きな影響
を与え始めている。その解決には、未曾有の気候変化の監視、それを防ぐための
対策と社会構造の変革、そして持続的社会の規範を支える教育等の分野の総合的
な対策を推進しなければならない。本年7月開催されるG8サミット(北海道洞
爺湖)でもこのような全球的環境問題への抜本的対策が重要課題の一つになって
いる。日本学術会議では、「地球温暖化等、人間活動に起因する地球環境問題に
関する検討委員会」において、地球温暖化等の地球環境問題について検討してお
り、その一環として、関係機関等と協力して一般公開シンポジウムを開催し、市
民とともに、大きな社会的な関心を呼んでいるこの問題について考える。
日 時:平成20年6月25日(水)13:30〜16:30
会 場:北海道大学学術交流会館(札幌市北区北8条5丁目)
定 員:300名、参加無料
詳細については、以下のURLを御覧ください。
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf/55-s-3-1.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】第24回ゼオライト研究発表会
──────────────────────────────────
主催:ゼオライト学会
協賛: 日本地質学会ほか
日時:2008年11月26日(水)〜11月27日(木)
会場:タワーホール船堀(東京都江戸川区船堀4-1-1)
テーマ:ゼオライト,メソ多孔体,およびその類縁化合物に関連した研究の基礎
から応用まで
講演申込締切:7月28日(月)
予稿原稿締切:11月5 日(水)
問い合わせ先:
窪田好浩(横浜国立大学大学院工学研究院)
Tel: 045-339-3926, Fax: 045-339-3941, e-mail: kubota@ynu.ac.jp
詳しくは、
http://www.jaz-online.org/event/kenkyukai.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】地質マンガ 「そして帰港」
──────────────────────────────────
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/faq/content0094.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質マンガ ハンマーのためなら
地質マンガ
戻る|次へ
No.0032 2008/6/18geo-Flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.032 2008/06/18 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】岩手・宮城内陸地震の地質学的背景
【2】岩手・宮城内陸地震(M=7.2)の調査に行かれる方へ
【3】書評:英語の会議に出る前に読む本
【4】国際地学オリンピック 大会派遣代表決定!
【5】韓国科学フェスティバルに学生派遣
【6】ジオパークの募集始まる
【7】G8北海道洞爺湖サミットに向けた各国学術会議の共同声明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】「Prof. Gregory Mooreさん、ありがとうミニシンポジウム」開催のお知らせ
【9】構造地質部会夏の学校 「反射法地震探査のための夏期集中講義・実習」
【10】第12回尾瀬賞募集
【11】第2回「科学の芽」賞募集
【12】平成20年度文部科学大臣表彰:科学技術賞/若手科学者賞候補者推薦
【13】柏崎刈羽原子力発電所敷地内の地質調査現場見学会
【14】地質マンガ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】岩手・宮城内陸地震の地質学的背景
──────────────────────────────────
佐藤比呂志・加藤直子(東京大学地震研究所)
阿部 進((株)地球科学総合研究所)
2008年岩手・宮城内陸地震(Mj7.2)は、「餅転(もちころばし)ー細倉構造帯」北部
の活断層としては記載されていない断層の深部延長の破壊によって発生した。中
新世の正断層の逆断層としての反転運動によって引き起こされたと推定される。
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/hazard/content0031.html
岩手・宮城内陸地震のページ
http://www.geosociety.jp/hazard/category0008.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】岩手・宮城内陸地震(M=7.2)の調査に行かれる方へ
──────────────────────────────────
「岩手・宮城内陸地震」に関連して多くの会員から現地調査の速報など様々な
情報をお寄せ頂いております。今後も調査などを予定されている方は、ぜひ学
会事務局までご一報願います。地質学会では、他学会との連絡を行い、現地で
の混乱や救援活動に支障の無いよう支援していきます。MLの立ち上げなども支
援できますので、ぜひご一報願います。
地質災害委員会 委員長 藤本光一郎(担当理事)
岩手・宮城内陸地震の関連情報はこちら
http://www.geosociety.jp/hazard/category0008.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】書評:英語の会議に出る前に読む本
──────────────────────────────────
東北大学東北アジア研究センター 石渡 明
ある国際会議の議長に選出され、大変な重責を背負うことになってしまった。
その会議の目的などを概説した2ページの文書には、「この会議の議事進行はロバー
ト議事規則(Robert’s Rules of Order)に基づく」と書いてある。そんな規則は
聞いたことがないが、議長をやる以上「知らない」では済まされないので、ネッ
トの本屋で探して読んでみた。これは、19世紀後半に米国のロバート将軍がある
会議の議長に指名され、最初はどうしてよいかわからず自然の進行に任せるしか
なかった(the Assembly would behave itself)が、そうした試行錯誤の経験の中
から編み出した、万人が納得する合理的な議事規則をまとめて出版したところ大
成功となり、その後多くの人によって添削・推敲され現在に伝えられているもの
で、最近の版には電子会議のやり方も入っている。詳しいものから簡略なものま
で色々な版があるが、私が読んだのは最も簡略なDoris P. Zimmerman (2005)の”
Robert’s Rules in Plain English, Second Edition” Collins, 171 p. ($7.95
)であり、”A Readable, Authoritative, Easy-to-use Guide To Running Meetin
gs”というキャッチフレーズがついている。この訳本、ドリス・P・ジマーマン著、
立木茂雄監訳、「民主主義の文法」(市民社会組織のためのロバート議事規則入
門)萌書房, 128 p. (¥1,600)も出版されていて、「会議の効率化のために!自治
会やマンションの管理組合、ボランティア団体をはじめとするNPOやNGOなど、す
べての地域組織・市民活動団体の民主的意思決定のために!」という帯がついて
いる。
会議は開会宣言(Call to Order、定足数quorumの出席確認を含む)から始まり、
前回の議事録の承認(Approval of the Minutes)、今回の議事次第(議程表)の承
認(Approval of the Agenda)、役員報告(Reports of the Officers)、会計報告(T
reasurer’s Report)、委員会報告(Committee Reports)、継続(積み残し)議案
の審議(Unfinished (Postponed) Business)、新規議案の審議(New Business)、連
絡・催し物など(Announcements, Program, etc.)、閉会(Adjournment)といった順
序で進み、それぞれの場面で議長がどう発言すべきか、具体的な例文が載ってい
る。挙手riseして発言を許されたり動議motionの審議が認められたりすることをf
loorと言い(I have the floor, The motion on the floorなど)、議長が持つハン
マーのことをgavel(「やたらに叩くな」という注意があるが、国際会議では使わ
ない)、票を数える人をteller、動議について審議することをdebateと言い、表
決voteのやり直しを求める場合はDivision!と叫ぶなど、日本の学校英語では習わ
ないような独特の会議用語が使われる。表決は一般に過半数で決定されるが、構
成員の権利を制限または取り上げる場合、あるいは既に決まっていることを覆す
場合は2/3の賛成を必要とするという原理が明確に述べられており、ロバート議事
規則では棄権abstention(動詞はabstain)は表決の母数に算入しない。構成員個
人による動議(“I move that….”と提案する)は、すぐに他の人が支持(second)
しなければ審議されない、など、日本ではしばしば混乱のもとになる動議に対す
る処置方法もきちんとしている。この議事規則は、「組織の権利は構成員1人1人
の権利にまさる」という原則に基づいており、「議事手続は意思決定を円滑に進
めるために使われるべきで、それを妨げるために使用すべきでない」という倫理
を前提としている。可能な限り全会一致の表決(拍手など)を用いるとか、沈黙
は同意を意味するとか、修正案にかこつけて無関係の新しい審議事項を加えさせ
てはいけないといった、会議をスムースに進めるための技術やヒントも豊富に用
意されている。これから英語の会議に出ようという人には、原本と訳本の両方を
読むことをお勧めする。また、地質学会の理事や評議員は少なくとも訳本を読ん
でおく必要があると思う。ただし、この本の議事次第の例では、開会宣言の直後
に実は「神への祈り」、「神と国家への忠誠の誓い」という項目があり(これら
は当然国際会議では省略されるが「物故者への黙祷」は行われる)、そういう国
における「民主主義の文法」だということを頭に入れておく必要がある。
「民主主義の文法」(市民社会組織のためのロバート議事規則入門)、
ドリス・P・ジマーマン著、立木茂雄監訳、萌書房, 128 p. (¥1,600)
http://www3.kcn.ne.jp/~kizasu-s/pages/kikanzenbu/shakai.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】国際地学オリンピック 大会派遣代表決定!
──────────────────────────────────
5月31日(日)東京大学で行われた第二次選抜試験は、1名の辞退者を除いた20名
で競われ、無事終了いたしました。厳正なる審査(実技と面接)の結果、8月31日-9
月8日のフィリピン大会への派遣代表は以下の4名に決定いたしました。
日野愛奈 愛媛県立松山南高等学校 3年
平島崇誠 石川県立金沢泉丘高等学校 2年
森里文哉 香川県立丸亀高等学校 3年
雪田一弥 青森県立青森高等学校 3年
ご声援よろしくおねがいいたします。なお、来年度の台湾大会の募集は2008年10
月1日より12月10日までです。一次試験は12月21日、二次試験は2009年3月29日を
予定しております。
国際地学オリンピック日本委員会 新HP http://jeso.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】韓国科学フェスティバルに学生派遣
──────────────────────────────────
韓国IYPE国内委員会よりIYPE日本委員会に対し,今年の8月1日から6日にかけて光
州広域市で開催される韓国科学フェスティバルに日本の学生の招待がありました.
地質学会へも推薦するよう要請があり,代議員等のメールを通じて全国的に推薦を
呼びかけました.その結果,国内から地球科学関連の学生合計5名の派遣が決定さ
れました。
大川恵理 京都大学大学院工学研究科(ジオフィジクス)
木本健太郎 東京大学大学院新領域創成科学研究科自然地理学・地形学)
細井 淳 茨城大学理学部理学科地球環境科学コース(地質学)
宮田真也 早稲田大学大学院創造理工学研究科(古生物学)
山田哲史 早稲田大学大学院創造理工学研究科(構造地質学)
韓国科学フェスティバル
http://festival.scienceall.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】ジオパークの募集始まる
──────────────────────────────────
IYPE日本のトップページでもお知らせしていますが,日本ジオパーク委員会では
日本ジオパーク認定地域および世界ジオパークネットワーク申請候補地域の募集
を開始しました。応募要項や申請書など必要書類は日本ジオパーク委員会のウェ
ブサイトから入手することができます。それぞれの締切は,世界ジオパークネッ
トワーク申請候補地域が2008年7月18日,日本ジオパーク認定地域が2008年8月29
日です。
IYPE期間中に日本にジオパークが生まれ,また世界ジオパークネットワーク加盟
が達成されるのは大変素晴らしいことです。地域からの応募に関して,IYPE日本
参加の機関・団体・学協会等に所属されている皆さまも是非ご協力お願いいたし
ます。
日本ジオパーク委員会
http://www.gsj.jp/jgc/indexJ.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】G8北海道洞爺湖サミットに向けた各国学術会議の共同声明
──────────────────────────────────
〜日本学術会議ニュース・メール No.131 2008/06/10 より〜
日本学術会議は、平成20年7月7〜9日に北海道洞爺湖サミットで開催
されるG8サミットに向け、G8サミット各国及び関係5ヵ国(ブラジル、
中国、インド、メキシコ、南アフリカ)のアカデミーと共同で、本年のG
8サミットの議題である「気候変動」と「Global Health」について、サミッ
ト参加国指導者に対する提言を取りまとめました。 取りまとめられた提言
は、同年6月10日、我が国において、金澤会長から福田総理に手交すると
ともに、世界同日に公表されました。
共同声明や本件に関する会長コメントは次のURLからご覧になれます。
http://www.scj.go.jp/ja/int/g8/index.html
【お問い合わせ先】
内閣府日本学術会議 国際業務総括担当
Tel:03-3403-5731 Fax:03-3403-1755 E-mail:i252@scj.go.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】Prof. Gregory Mooreさん、ありがとうミニシンポジウム
──────────────────────────────────
長年、南海トラフなどの付加体研究をされ、三年ほど前から米国を離れて
海洋研究開発機構に勤務されていたGregory Mooreさんがこの7月、
ハワイ大学へ戻ることとなりました。南海トラフの研究に多くの足跡を残し、
また現在進行中の南海トラフ地震発生帯掘削においても中心的に貢献いただ
いております。日本の研究コミュニティー発展のためにも多大な力を尽くし
ていただきました。
この間の貢献に感謝し、今後の活躍を祈念して、ささやかではありますが、
「ありがとうミニシンポジウム」を企画いたしました。シンポジウムの後には
「感謝会パーティー」を開催いたします。親交のありました方のみならず、
多くの方々が気軽に参加いただけますよう呼びかける次第です。
発起人
海洋開発研究機構、理事 平朝彦
海洋開発研究機構、理事 末広潔
筑波大学 教授 小川勇二郎
東京大学 教授 徳山英一
東京大学 教授 木村 学
開催日時:6月27日(金)、14:30〜
場所:東京大学海洋研究所 講堂 (http://www.ori.u-tokyo.ac.jp/map/index.html)
<プログラム>
14:30~15:00 Gregory Moore教授の軌跡と南海トラフ
平朝彦・末広潔
15:00~16:00 Nankai accretionary prism and life in Japan
Gregory Moore
16:00~16:15 休憩
16:15~17:15 南海地震発生帯掘削計画の現状と今後の展望
木下正高・木村学
17:15~17:30 Gregさんとの思い出
小川勇二郎・芦 寿一郎
17:45~ 感謝会パーティー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】構造地質部会夏の学校「反射法地震探査のための夏期集中講義・実習」
──────────────────────────────────
このたび構造地質部会では以下の予定で,千葉大学大学院理学研究科地殻構造
学研究室と共同して平成20年度の夏の学校を開催します.奮ってのご参加をお
願いします.なお,準備のため,受講人数を把握する必要があります.7月2
0日までに,担当事務局員の山田泰広(yamada@earth.kumst.kyoto-u.ac.jp)
まで連絡をください.受講希望人数が40名に達した場合にはその段階で締め
切ることを予めご了承下さい。
日本地質学会構造地質部会長 竹下 徹
-----------平成20年度構造地質部会夏の学校------------------------
「反射法地震探査のための夏期集中講義・実習」
日時:2008年8月21日(木)〜23日(土)
場所:千葉大学理学部4号館301、自然科学研究科1号棟702
内容:
石油天然ガス開発など資源探査のために開発・発展してきた反射法地震探査
は、今や世界的には構造地質学、堆積学などをはじめとする地質学の基本手法
の一つとして広く用いられています。しかしながら我が国においては反射法地
震探査が十分には普及していないという現実があります。そこで構造地質部会
の夏の学校として、反射法地震探査の講義と実習を行ないます.特に若手研究
者と学生・院生の参加を歓迎します.
スケジュール:
1日目 午前:講義「反射法の基礎」 午後「反射法演習」
2日目 終日:解釈演習(2D震探8測線程度を用いて,Horizon解釈しマップを
書く.マップの解釈を発表しあう)
(夕方:懇親会 千葉大構内「けやき会館」)
3日目 千葉大油圧インパクターによる現場実験,千葉大学構内既存データの
解析演習、反射法処理システムのデモと演習など
講師:賛助会員石油資源開発株式会社と(株)
地球科学総合研究所から派遣していた だくことができる予定です。
参加費用:資料代・実習費(実費)
参加登録・懇親会参加申し込み締め切り:2008年7月20日
参加登録方法:
参加登録と懇親会参加のご連絡を京都大学工学研究科・山田泰広
(yamada@earth.kumst.kyoto-u.ac.jp)
までお送りください.なお、宿泊場所についての相談がある場合には急ぎご連
絡下さい。
今後のお知らせについて:詳細につきましては決まり次第,構造地質部会ホー
ムページに掲載しますので,こちらをご覧ください.
http://www.geosociety.jp/organization/bukai/struct/struct-index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】第12回尾瀬賞募集
──────────────────────────────────
主催:財団法人尾瀬保護財団
目的 「湿原」に関する学術研究を顕彰することにより,この分野の学問的・学
際的研究の伸展を図るとともに,環境保護に関する関心を高めることを目的とし
ます.
候補者の対象・資格
・応募者は泥炭湿原の保全に関わる基礎的研究において,優れた業績を上げた個
人・グループとします.
・研究対象は,「主として泥炭を有する湿原及びそこを生活の場とする生物」
とします.なお,対象とする湿原は尾瀬ヶ原に限りません.
・応募者は昭和33年4月2日以降生まれの人(平成20年4月2日現在50歳未満)
とします.特に若手研究者の応募を歓迎します.など
募集期間 平成20年4月1日〜10月31日(当日の消印有効)
詳しくは,
http://www.oze-fnd.or.jp/main/banner/oze_prize/oze_prize1.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】第2回「科学の芽」賞募集
──────────────────────────────────
筑波大学では,本学の前身の東京教育大学の学長を務めるなど,本学にゆかりの
あるノーベル物理学賞受賞者の朝永振一郎博士の功績を称え,それを後続の若い
世代に伝えていくために,小・中・高校生を対象に自然や科学への関心と芽を育
てることを目的としたコンクールを行い「科学の芽」賞を授与します。なお日本
地質学会は本事業を後援しています。
応募資格:全国の小学校3学年〜中学校・高等学校(高等専門学校3年次までを
含む.),中等教育学校,特別支援学校の個人もしくは団体「小学生部門」,
「中学生部門」,「高校生部門」に分けて公募します.
応募期間:平成19年8月20日(月)〜9月30日(日)〔消印有効〕
詳しくは、
http://www.gakko.otsuka.tsukuba.ac.jp/Site/start_files/kagakunome.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】平成20年度文部科学大臣表彰:科学技術賞/若手科学者賞 候補者推薦
──────────────────────────────────
文部科学省では,科学技術に関する研究開発,理解増進等において顕著な成果
を収めた者について,その功績を讃えることにより,科学技術に携わる者の意欲
の向上を図り,もって我が国の科学技術水準の向上に寄与することを目的とする
科学技術分野の文部科学大臣表彰を定めております.
(1) 科学技術賞:1)開発部門 2)研究部門 3)科学技術振興部門 4)技術
部門 5)理解増進部門
(2)若手科学者賞: 萌芽的な研究,独創的視点に立った研究等,高度な研究開
発能力を示す顕著な研究業績をあげた40歳未満の若手研究者個人
学会推薦締切:2008年6月30日(月)必着
注意*本表彰は,文科省が推薦依頼を出した機関からの推薦のみ受付となります.
個人からの募集は行っておりません.推薦を希望される方は、学会事務局までお
申し出ください.
詳しくは文部科学省HPをご参照ください.
http://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/2008/08050813.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】柏崎刈羽原子力発電所敷地内の地質調査現場見学会
──────────────────────────────────
日本地質学会関東支部 主催
2007年新潟県中越沖地震に関連し柏崎刈羽原子力発電所敷地内で実施されている
断層調査の現場見学会を開催します。
日時:平成20年7月9日(水)10:20 JR長岡駅集合
申し込み方法は関東支部HPを参照下さい。
http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【14】地質マンガ
──────────────────────────────────
「ハンマーのためなら」
作:某Y大学教授 画:Key
http://www.geosociety.jp/faq/content0096.html
地質マンガは原作を募集しています。文字だけでもラフスケッチでも清書
して仕上げます。投稿はこちらから
http://www.geosociety.jp/publication/content0009.html#toko4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回の地震災害に関しまして、緊急に多くの方々にご尽力頂きまして、たいへんあ
りがとうございました。(編集部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
日本全国天然記念物めぐり(秋田県編)
◇各地の天然記念物◇
TOP 秋田県編 滋賀県編 京都府編 和歌山県編 福岡県編
日本全国天然記念物めぐり(秋田県編)
秋田県には現在,国指定の天然記念物が7つある.
(1)玉川温泉の北投石(1922年指定,特別),仙北市玉川温泉
(2)じ状(魚卵状)珪石および噴泉塔(1924年指定),湯沢市雄勝
(3)象潟(1934年指定),にかほ市象潟
(4)筑紫森岩脈(1938年指定),秋田市河辺
(5)千屋断層(1995年指定),美郷町
(6)鳥海山獅子ヶ鼻湿原植物群落及び新山溶岩流未端崖と湧水群(2001年指定),にかほ市象潟
(7)男鹿目潟火山群一ノ目潟(2007年指定),男鹿市
2008 年の地質学会秋田大会の巡検案内を秋田大学工学資源学部の西川 治氏と行うことになり,その巡検地の下見と打ち合わせを行うため,ゴールデンウィーク(5 月1日〜3日)に秋田に出張した.その時,西川氏と2ヶ所(+1)の天然記念物をめぐったので,ここに報告する.実際に現地を訪れたのは,千屋断層と筑紫森岩脈の2ヶ所であり,玉川温泉の北投石は展示資料を観察しただけである.千屋断層と筑紫森岩脈は,両者とも20万分の1地形図に記載されており(市販の道路マップでは確認していない),現地までは西川氏に案内して頂いたのでスムーズに行くことができたが,いつものように幹線道路に案内標識が出ているわけではないので,一般の方は迷うかもしれない.
玉川温泉の北投石
図1)秋田大学工学資源学部鉱業博物館所蔵の北投石.左が台湾北投温泉のもので,右が玉川温泉のもの.*クリックすると大きな画像がご覧頂けます
北投石は温泉沈殿性重晶石のことであり,1922年に天然記念物に指定され,その後(1952年)に特別天然記念物となった.西川氏によると,玉川温泉に行っても北投石が大規模に沈殿しているところは見ることができないとのことだったので,氏の所属する鉱業博物館所蔵の展示資料を見せて頂いた.博物館にはその名称の由来となった,台湾台北市の北投温泉の重晶石も展示してあった(図1).なお,西川氏によれば,玉川温泉の温泉水には,電子顕微鏡スケールの重晶石が含まれているとのことであった.
千屋断層
千屋断層は横手盆地東縁断層帯の一部であり,1896年の陸羽地震の際に出現したものである.1984年に県指定の天然記念物となり,その後(1995 年)に国指定の天然記念物となった.国指定の露頭は,東大地震研究所などによる活断層調査(1982年)のトレンチ露頭であり,現在は保存のため土嚢が敷き詰められていた(図2左上).露頭自体の観察は出来ないが,詳細な露頭スケッチ(図2右上)と説明文が展示されていた(図2左下).西川氏によると,この露頭は美郷町による保存観察施設設置に向けて協議が行なわれているため,現状維持のため土嚢が積まれているとのことであった(図2右下).この説明板にあるように,教育委員会または千畑交流センターに行くと,千畑断層観察ロードマップを入手する事ができる.
図2)国指定のトレンチ露頭(左上)とそのスケッチ(右上).旧千畑町教育委員会による説明板(左下).右下は,千畑断層保存観察施設設置のため,トレンチ露頭を保存する目的で土嚢が積まれ,現在は観察できないことを告げる説明板(美郷町教育委員会).*クリックすると大きな画像がご覧頂けます
このトレンチ露頭の北の赤倉川の河岸にも断層露頭があり(図3),町の教育委員会の説明板がある.こちらの露頭も国指定の断層露頭であるらしい(ただし,石碑等はない).遠目ではよくわからないが,図の点線の位置に東傾斜の衝上断層がありそうである.また,千屋断層は直線的な高さ1mほどの断層崖をともなっており,その断層崖に沿って何箇所か,陸羽地震に関連した説明板が立っている(図4).これらの説明板は,千畑断層観察ロードマップに記載されている.
図3)赤倉川河岸露頭(左)とその説明板(右).明瞭な断層崖が形成されている.*クリックすると大きな画像がご覧頂けます
図4)陸羽地震に関連した地震被害を伝える説明板.先述の千畑断層観察ロードマップにその位置が記載されている.
*クリックすると大きな画像がご覧頂けます
筑紫森岩脈
筑紫森岩脈は,第三紀中新世の黒雲母流紋岩による溶岩円頂丘である.遠景で岩尖の様子が観察できるほか,ハイキングコースも整備されているので,山頂まで約30分ほどで行くことができる(図5).途中までは,普通のハイキングコースであるが,天然記念物の説明板(図6左上)からは,横臥柱状節理の発達した流紋岩の岩場となっている(図6右上).往復1時間のコースであるが,最近はやりの俗っぽい名前の症候群の方には辛いかもしれない.
図5)秋田市教育委員会による筑紫森への案内板(左上・右上),右上の案内図は山頂までのハイキングコースと途中の見せ場が記載されている.筑紫森岩脈の遠景(左下),溶岩円頂丘がはっきり確認できる.今回は表参道を行った(右下).*クリックすると大きな画像がご覧頂けます
図6)天然記念物の案内板(左上).この地点から横臥柱状節理の発達した流紋岩の岩場が続く(右上).山頂付近は,節理がほぼ水平に発達し,さながら階段のようである(左下).筑紫森山頂の筑紫森神社(推定,右下),神社には天然記念物としての解説文が掲げられている.*クリックすると大きな画像がご覧頂けます
今回は,時間の都合上,2ヶ所(+1)しかめぐれなかったが,後は西川氏が取材してくれるとのことであったので,それに期待して今回は簡単に紹介するにとどめた.
地質マンガ 学会に行こう
地質マンガ
戻る|次へ
地質マンガ 何の調査?
地質マンガ
戻る|次へ
No.0032 2008/7/1geo-Flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.033 2008/07/01 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2008年岩手・宮城内陸地震続報:墓石転倒率調査ほか
【2】秋田大会で岩手・宮城内陸地震関連の講演
【3】秋田大会の要旨締め切り迫る(7/10)
【4】7月の博物館イベント情報 もうすぐ夏休み!
【5】日本全国天然記念物めぐり(秋田県編)北投石、千屋断層、筑紫森岩脈!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】柏崎刈羽原発見学会の日程変更と再募集のお知らせ(7/11)
【7】平成21年度研究船利用課題公募
【8】猿橋賞候補者推薦依頼
【9】第30回(平成20年)沖縄研究奨励賞推薦応募
【10】平成20年度東レ科学技術賞および東レ科学技術研究助成の候補者推薦
【11】地質マンガ
【12】geo-Flash創刊1周年によせて
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2008年岩手・宮城内陸地震続報
──────────────────────────────────
岩手・宮城内陸地震 墓石転倒率分布調査 結果所見
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)ほか
この調査は、今回の地震による揺れの強さの詳しい分布を明らかにすることを目
的として、地震後10日〜15日の期間に4日間行った。
続きは、http://www.geosociety.jp/hazard/content0032.html
そのほか以下の現地調査団が活動中です。
■秋田大学教育文化学部調査班
調査対象:土砂災害,地震動調査
当面の調査場所:中心は秋田県湯沢市,東成瀬村,
6/18に宮城県側をヘリコプターで調査予定
当面の調査期間:6/16-6/28
班長:林 信太郎(秋田大学教育文化学部)
■山口大学 地形・地質班
調査対象:斜面崩壊、地表断層
当面の調査場所:奥州市から栗原市
当面の調査期間:7/1-7/5
班長:金折裕司(山口大学理学部)
班員:福塚康三郎(八千代エンジニアリング(株))
■茨城大学班
調査対象:地形・地質,斜面崩壊
当面の調査場所:栗原市および奥州市
当面の調査期間:6/29(日)-6/30(月)
班長:天野一男(茨城大学理学部)
班員:藤縄明彦(火山学),本田尚正(自然災害),松原典孝(グリーンタフ地質学),
天野一男(構造地質学),所属は全員茨城大学理学部理学科地球環境科学コース
詳しくは、こちら
http://www.geosociety.jp/hazard/content0029.html
今後も調査などを予定されている方は、ぜひ学会事務局までご一報願います。地質
学会では、他学会との連絡を行い、現地での混乱や救援活動に支障の無いよう支援
していきます。MLの立ち上げなども支援できますので、ぜひご一報願います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】秋田大会で「岩手・宮城内陸地震」関連の講演を
──────────────────────────────────
会員の皆様
秋田大会での講演の検討をされていることと思います.行事委員会でセッションの確
定等を行ってから,四川地震,岩手・宮城内陸地震が発生し,それらをどのセッション
に発表しようか迷っておられる方もおられるかと思います.
行事委員会としては,現在すでに起こっている事象につきましては,通常のセッション
の枠内で対応する予定でおります.応用地質一般,地域地質・地域層序,ノンテクトニ
ック,テクトニクス,環境地質,情報地質等のセッションが該当するかと思います.その
際,聴衆にインパクトのあるように,申込状況に臨機応変に対応し
1)セッション内でサブセッションを作る等,プログラム上も見える形にする
2)セッション間で講演をやりとりして関係講演をまとめる
等の対応を行い,プレス等にもアピールしたいと思います.
つきましては,備考欄に四川地震,岩手・宮城内陸地震などとご記入の上,講演申し
込みをお願いいたします.数多くの発表をお待ちしております.
なお今後これらの地震災害に関連して新たに発生した事象については別途対応を検討
するものと致します.
行事委員長 斎藤 眞
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】秋田大会の要旨締め切り迫る(7/10)
──────────────────────────────────
講演申込・要旨投稿締切:2008年7月10日(木)17時
(郵送の場合は、7月7日必着)
講演申込画面 はこちら↓
http://proc.jstage.jst.go.jp/proceedings/service/geosocabst/newregistration/
J-STAGEのシステムの都合上、申込手続きは締切日の0時ではなく、夕方の17時で
締め切られます。締切時間のお間違いのないように、ご注意下さい。
例年締切間際に申込が集中しますが、なるべく早めのお申し込みをお願いいたしま
す。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】もうすぐ夏休み 博物館はイベントがいっぱい!!
──────────────────────────────────
いよいよ夏休みも近づいてきました。博物館では,体験イベントや野外観察会など
を用意して,みなさんのお越しをお待ちしています。
夏休み中のイベントは混雑が予想されますので,イベントカレンダーで早めにチェッ
クして申し込みはお早めに。
7月の博物館イベント情報は
http://www.geosociety.jp/name/content0019.html
で!!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】日本全国天然記念物めぐり(秋田県編)
──────────────────────────────────
奥平敬元(大阪市立大)
秋田県には現在,国指定の天然記念物が7つある.
(1)玉川温泉の北投石(1922年指定,特別),仙北市玉川温泉
(2)じ状(魚卵状)珪石および噴泉塔(1924年指定),湯沢市雄勝
(3)象潟(1934年指定),にかほ市象潟
(4)筑紫森岩脈(1938年指定),秋田市河辺
(5)千屋断層(1995年指定),美郷町
(6)鳥海山獅子ヶ鼻湿原植物群落及び新山溶岩流未端崖と湧水群(2001年指定),
にかほ市象潟
(7)男鹿目潟火山群一ノ目潟(2007年指定),男鹿市
続きは、
http://www.geosociety.jp/faq/content0098.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】柏崎刈羽原発見学会の日程変更と再募集のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地質学会関東支部 主催
2007年新潟県中越沖地震に関連し柏崎刈羽原子力発電所敷地内で実施されている
断層調査の現場見学会を開催します。
先にご案内した上記見学会は、北海道サミットに関連し原子力発電所のテロ対策
として7月10日まで発電所への立ち入りが制限去れることになりました。
つきましては、下記日程に変更させていただき、新たに参加希望者を募集します。
変更日時:平成20年7月11日(金) 10:20 JR長岡駅集合
申し込み方法は関東支部HPを参照下さい。
http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】平成21年度研究船利用課題公募
──────────────────────────────────
海洋研究開発機構では、平成20年に2月に制定した「海と地球の研究5ヶ年指針」
に基づく研究の推進を行うため、所有する研究船「みらい」、「なつしま」、「よこすか」、
「かいれい」等を利用する課題を募集いたします。
募集期間:平成20年6月26日(木)〜7月22日(火)
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】猿橋賞候補者推薦依頼
──────────────────────────────────
対象:推薦締切日に50才未満で,自然科学の分野で,顕著な研究業績を収めて
いる女性科学者
表彰内容:賞状,副賞として賞金30万円,1件(1名)
応募方法:所定の用紙(当会のホームページからダウンロード)に,推薦者
(個人・団体,自薦も可)・受賞候補者の略歴,推薦対象となる研究題目・推薦
理由(800字程度),及び主な業績リスト(指定は1頁です.やむを得ない場合で
も追加は1頁までです)を記入して,主な論文別刷10編程度(2部ずつ)を添え,
推薦書類をお送り下さい.
締切日:平成20年11月30日
詳しくは,http://www.saruhashi.net
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】第30回(平成20年)沖縄研究奨励賞推薦応募
──────────────────────────────────
沖縄研究奨励賞は,沖縄の地域振興及び学術振興に貢献する人材を発掘し,育
成することを目的としています.
本奨励賞は,沖縄を対象とした将来性豊かな優れた研究(自然科学,人文科学又
は社会科学)を行っている新進研究者(又はグループ)の中から, 受賞者3名以
内を選考し,奨励賞として本賞並びに副賞として研究助成金50万円を贈り表彰す
るものです.
応募資格は,学協会,研究機関若しくは実績のある研究者から推薦を受けた50
歳以下(平成20年7月15日現在)の方で,出身地及び国籍は問いません.
応募締切:平成20年9月30日(当日消印まで有効)
詳細は, http://homepage3.nifty.com/okinawakyoukai/index.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】平成20年度東レ科学技術賞および東レ科学技術研究助成の候補者推薦
──────────────────────────────────
推薦締切期日:平成20年10月10日(金)(学会締切9月10日必着)
1.東レ科学技術賞(概要)
候補者の対象:貴学協会が関与する分野で,下記に該当するもの/学術上の業績が
顕著なもの/学術上重要な発見をしたもの/重要な発明をして,その効果が大きい
もの/技術上重要な問題を解決して,技術の進歩に大きく貢献したもの
2.東レ科学技術研究助成(概要)
候補者の対象:学協会が関与する分野で国内の研究機関において自らのアイディ
アで萌芽的基礎研究に従事しており,今後の研究の成果が科学技術の進歩,発展
に貢献するところが大きいと考えられる若手研究者(原則として推薦時45才以下)
詳しくは、
http://www.toray.co.jp/tsf/info/inf_004.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】地質マンガ
──────────────────────────────────
「学会に行こう」「何の調査?」
作:柴田伊廣 画:Key
http://www.geosociety.jp/faq/content0057.html
地質マンガは原作を募集しています。文字だけでもラフスケッチでも清書
して仕上げます。投稿はこちらから
http://www.geosociety.jp/publication/content0009.html#toko4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】geo-Flash創刊1周年によせて
──────────────────────────────────
geo-Flashは、地質学会の会員間情報共有ツールとして、昨年7月3日に
第1回の配信がなされました。早いものであれから1年、今回で33号の配信
になりました。ご愛読ありがとうございます。この間、学会HPの大幅更新、
様々なホットな話題の提供、イベント情報など、沢山の情報をなるべく早く
会員の皆様に届けることを目的に編集、配信して参りました。多くの分野の
会員を抱える学会としては、様々な分野の情報を網羅することと、会員の年齢
構成も念頭に、やや「くだけた」感じのところもあったかと存じますが、なる
べく多くの会員に興味を持ってもらえるような体裁を念頭に編集にあたってき
ました。
地球科学に対する社会の期待は、災害/防災だけでなく、地球環境問題や資源
そして純粋な科学的興味や教育問題まで、ますます大きくなっていると感じる
今日この頃です。情報の共有はその基礎をなすものです。法人としての学会も
間もなくスタートします。我々が貢献できること、我々でしか貢献できないこ
と、今後の学会の礎を皆さんで築いていきましょう。geo-Flashはそんな
会員間のコミュニケーションツールでもあるのです。
倉本真一(geo-Flash前編集長)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質マンガ 遭遇したくないもの
地質マンガ
戻る|次へ
No.0034 2008/7/15geo-Flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.034 2008/07/15 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2008年岩手・宮城内陸地震続報:茨城大学班調査ほか
【2】韓国科学フェスティバル目前 IYPE日韓交流学生訪問団
【3】2008秋田大会:各種申込受付中!!
【4】日本学術会議提言「地球環境の変化に伴う水災害への適応」の公表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第111回深田研談話会のご案内
【6】3rd INTERNATIONAL IGBP PAGES FOCUS- V (old) LIMPACS CONFERENCE
【7】講演会「海洋法条約に基づく大陸棚限界延長−NZの申請の経験から−」
【8】島原市職員公募(8/22)
【9】静岡大学防災総合センター教員募集(7/31)
【10】新潟大学教育研究院自然科学系教員公募(9/16)
【11】広報委員募集
【12】地質マンガ「遭遇したくないもの」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2008年岩手・宮城内陸地震続報:茨城大学班調査ほか
──────────────────────────────────
天野一男(班長)・藤縄明彦・本田尚正・松原典孝(茨城大学理学部理学科地球
環境科学コース)
[調査日]2008年6月29日(日)・30日(月)
[調査対象]荒砥沢ダム上流部および冷沢流域における地表変状及び大規模崩落.
[地質の概要]通産省資源エネルギー庁(1976)によれば,荒砥沢ダム上流部付
近及び冷沢上流部付近には火砕流起源で一部溶結した軽石質凝灰岩を主体とする
上部中新統の小野松沢層が分布し,その上位に一部第四系北川層及び新期安山岩
類が分布する.本調査地域は,後期中新世〜鮮新世に形成された栗駒南麓のコー
ルドロン北東部に相当する、、、、、、.
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/hazard/content0033.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】韓国科学フェスティバル目前 IYPE日韓交流学生訪問団
──────────────────────────────────
国際惑星地球年(IYPE)に関連して,8月1日
から6日にかけて韓国光州広域市で韓国科学フェ
スティバルが開催されます。韓国IYPE国内委
員会より日本の学生の招待があり、全国から
5名の代表学生が決定されましたのは先月既報の
通りです(geo-flash no.32:6/18号)。
出発を目前に控えた7/12に派遣学生が日本地質
学会を訪問してくれました。この日は理事会が開
かれていましたので、会長および理事からは激励
が、そして派遣学生からは力強い抱負とフェスティ
バルへの期待が熱く語られました。
9月の秋田大会では韓国地質学会会長も来日され、日韓合同深海掘削シンポジウムも開催
されます。ますます両国の学術交流が深まることが期待されます。なお訪問団は、高木
秀雄 日韓交流小委員会委員長が引率されます。
韓国科学フェスティバル
http://festival.ksf.or.kr/2008/index.jsp#
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2008秋田大会(9/20-22):各種申込受付中!!
──────────────────────────────────
■事前参加登録:8月8日(金)締切
http://www.knt.co.jp/ec/2008/science/index.html
見学旅行・懇親会には限りがあります。お申し込みはお早めに!
■小,中,高校生徒「地学研究」発表会;参加校募集:7月25日(金)締切
http://www.geosociety.jp/science/content0019.html
■就職支援プログラム:出展企業募集中:8月8日(金)締切
http://www.geosociety.jp/science/content0023.html
そのほか秋田大会の情報はコチラ↓
http://www.geosociety.jp/science/content0014.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】日本学術会議提言「地球環境の変化に伴う水災害への適応」の公表
──────────────────────────────────
地球惑星科学委員会・土木工学・建築学委員会合同国土社会と自然災害
分科会が、提言「地球環境の変化に伴う水災害への適応」を公表いたしま
した。
平成19年5月30日に公表した対外報告「地球規模の自然災害の増大に対す
る安全・安心社会の構築」及び、国土交通大臣からの地球規模の自然災害
に関する諮問に対して行った答申に基づき、地球規模での気候変動や我が
国の社会構造の変化を踏まえ、特に水災害についてより具体的な災害対策
のあり方を検討し、適応策の推進や国際社会への貢献について提言を行い
ました。
提言全文は、日本学術会議HPの以下のURLで御覧いただけます。
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/index.html
【お問い合わせ先】
日本学術会議事務局参事官(審議第二担当)付
Tel:03-3403-1056 Fax:03-3403-1640
E-mail:s253@scj.go.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】 第111回深田研談話会のご案内
──────────────────────────────────
テーマ:石油・天然ガスの成因ー生物起源か、非生物起源か?ー
講師: 林 雅雄 氏((独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構,元出光石油開
発(株)取締役開発部長)
日時: 2008年9月12日(金)15:00〜17:00
会場: (財)深田地質研究所研修ホール(東京都文京区本駒込2-13-12)
参加費無料
<講演内容>石油や天然ガスの有用性が認識されて150 年が経過したが、その成
因について科学者達が論争を始めたのは、実用開始より100 年も前のことであり、
今でも論争が繰り返されている。最近の原油価格の急上昇が日常生活に深刻な影
響を与えるようになったことから、この古くて新しいテーマに対して、一般の方
々も大きな関心を寄せているように見受けられる。本講演では、有機起源説と無
機起源説という対立する二つの成因説について、アニメ図面を駆使して判り易い
解説を行い、石油探査30年の実務経験に基づいて、どちらの説が妥当かの判定を
試みる。
申込先: 財団法人深田地質研究所
TEL:03-3944-8010 FAX:03-3944-5404
E-mail:fgi@fgi.or.jp
URL:http://www.fgi.or.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】3rd INTERNATIONAL IGBP PAGES FOCUS- V (old) LIMPACS CONFERENCE
──────────────────────────────────
3rd INTERNATIONAL IGBP PAGES FOCUS- V (old) LIMPACS CONFERENCE
“HOLOCENE LAKES: CLIMATE INSTABILITY AND SALINIZATION”
日程:2009年3月5日〜8日
会場:VENUE: GOLDEN JUBILEE HALL, PANJAB UNIVERSITY CAMPUS, CHANDIGARH, 1
60 014, INDIA
スケジュール
Last date of submitting pre-registration:7月31日
Last date of abstract submission :9月15日
Final announcement:10月15日
Submission of manuscripts:2009年 3月5日
問い合わせ先
B. S. Kotlia
Convener, 3rd LIMPACS conference, E mail: limpac3@yahoo.com
www.himclimate.in
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】講演会「海洋法条約に基づく大陸棚限界延長−NZの申請の経験から−」
──────────────────────────────────
主催:海洋政策研究財団
日時:平成20年7月25日(金) 14:30〜16:30 参加費無料
場所:東京都港区虎ノ門1-15-16 海洋船舶ビル 10階ホール
講師:レイ・ウッド氏(ニュージーランド 地質・核科学研究所海洋探査部長)
申込締切:7月22日(火)
使用言語:英語【逐次通訳で行います】
席の関係で参加不可能な場合のみ、当方から連絡させていただきます。連絡がな
い場合は、当日会場へお越しください。
【お問合せ先】
海洋政策研究財団 海技研究グループ 玉眞 洋
TEL:03-3502-1881 FAX:03-3502-2033
E-mail:h-tamama@sof.or.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】島原市職員公募(8/22)
──────────────────────────────────
職種および採用人数:地質火山調査業務 若干名
受験資格:大学卒業程度の学力を有し、昭和44年4月2日以降に生まれた人で、
大学等で主に地質又は火山に関する課程を専攻した人.採用後は市内に居住できる人
受付期間:平成20年7月22日(火)〜8月22日(金)まで
第一次試験
・体力試験 平成20年9月20日(土)
・学力試験 平成20年9月21日(日)
第二次試験
一次試験合格通知の際にお知らせします.
そのほか詳しい募集要項は以下のURLを参照してください
http://www.city.shimabara.lg.jp/section/shiko/bosyu2008/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】静岡大学防災総合センター教員募集(7/31)
──────────────────────────────────
募集人員:准教授 又は 助教 2名
募集分野:自然科学系1名、人文社会科学系1名
いずれも静岡地域における防災に関する教育、研究及び地域連携に意欲と関心を
持って取り組める方
採用時期:平成20年10月1日(水)(予定)
任期:平成24年3月31日まで
応募資格: (1) 博士の学位を有する方、又はそれと同等以上の能力を有する方
(2) 静岡市又は静岡市近隣地域に居住できる方
応募期限:平成20年7月31日(木)(当日消印可)
応募書類送付先及び問合せ先
静岡大学防災総合センター
電話054-238-4253
E-mail : matsu-e@adb.shizuoka.ac.jp 〔担当 松梨〕
応募書類等詳しくはhttp://www.shizuoka.ac.jp/guide/20080710.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】新潟大学教育研究院自然科学系教員公募(9/16)
──────────────────────────────────
担当予定科目 大学院:自然構造科学演習など/学部:地質科学科の野外実習・地
質調査法など
担当分野 地球科学分野
職種・人員 助教 1名
採用予定日 平成20年12月1日以降のなるべく早い時期。
任期 採用時から5年間。 再任なし。
応募資格 (1)博士の学位を有すること。なお,着任時までに取得見込みの者を
含む。(2)野外地質調査に基づく地質図作成の実績があり,野外実習の指導ができ
ること。
応募の締切 平成20年9月16日(火)必着
問合せ先
新潟大学大学院自然科学研究科自然構造科学専攻 教授 松岡 篤
電話 025-262-6376(直通)
E-mail:matsuoka@geo.sc.niigata-u.ac.jp
詳しくは、
http://www.gs.niigata-u.ac.jp/~scitech/koubo/koubo080710.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】広報委員募集
──────────────────────────────────
日本地質学会広報委員会は、2008-2009年期の委員をを募っております。学会の活
動内容を広く網羅し会内外に知らせるために、会員の皆様からの応募をお待ちし
ています。
広報委員会の活動目的:
ニュース誌、メールマガジン(geo-Flash)、ホームページ の運営を主として、
学会の活動内容を会内外に広く知らせ、会員相互の意思疎通および情報交換の場
を提供して社会と学会の発展に寄与する。
委員と活動内容:
研究分野のアウトリーチに理解があり、年に数回程度の記事の担当、および学会
の情報環境の改善に力を貸して頂ける方。
任期:2年
応募締切:8月8日(金)
申込先:main@geosociety.jp (事務局担当 細川)
広報担当理事 坂口有人/情報特任理事 倉本真一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】地質マンガ「遭遇したくないもの」
──────────────────────────────────
「遭遇したくないもの」
作:山口はるか 画:Key
http://www.geosociety.jp/faq/content0102.html
地質マンガは原作を募集しています。文字だけでもラフスケッチでも清書
して仕上げます。投稿はこちらから
http://www.geosociety.jp/publication/content0009.html#toko4
──────────────────────────────────
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.0035 2008/7/22geo-Flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.035 2008/07/22 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】夜間小集会追加募集!
【2】プレス発表希望者は早めに連絡を!
【3】2008秋田大会:各種申込受付中!!(8/8締切)
─────────────────────────────────
【4】構造地質「2008年夏の学校」“反射法地震探査:基礎・演習・実習”
【5】古気候・古環境研究の推進のための多分野横断型メーリングリストへの参加のお誘い
【6】地質学雑誌:編集規約一部修正について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】夜間小集会追加募集
──────────────────────────────────
行事委員会では、セッションの申し込み等すべて終了し、現在プログラム
編成もほぼ終了し、講演要旨の印刷、8月号News誌へのプログラムの掲載等
の準備を進めております。
現在、夜間小集会については、若干の余裕がありますので、再募集いたします。
募集期間は7/22-25正午までです。
希望者は、行事委員会(事務局気付け main@geosociety.jp )までお申し込
み下さい。
行事委員会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】プレス発表を希望される方へ
──────────────────────────────────
秋田大会での講演や行事について、9月上旬にプレス発表を行う予定です。
昨年の札幌大会では多数のメディアに取り上げられ、会員の皆様の研究成果が
多いに注目されました。秋田大会で発表される予定の案件で、学会からの
プレス発表をご希望の方は、8月25日(月)までに学会事務局
(journal@geosociety.jp)にご連絡願います。全ての案件をプレス発表
することはできませんが、社会への情報発信として特筆すべき成果は積極的に
公表して行きたいと考えております。会員の皆様におかれましては、プレス
リリース解禁日をお守りいただき、公平かつ効果的な情報発信にご協力願い
ます。不明な点は学会事務局までお問い合わせ願います。
登録締切:8月25日(月)
プレス発表(投げ込み):9月5日(金)
現地説明会(解禁日):9月12日(金)(予定)
情報特任理事 倉本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2008秋田大会:各種申込受付中!!(8/8締切)
──────────────────────────────────
■事前参加登録:8月8日(金)締切
http://www.knt.co.jp/ec/2008/science/index.html
見学旅行・懇親会には限りがあります。お申し込みはお早めに!
■小,中,高校生徒「地学研究」発表会;参加校募集:7月25日(金)締切
http://www.geosociety.jp/science/content0019.html
■就職支援プログラム:出展企業募集中:8月8日(金)締切
http://www.geosociety.jp/science/content0023.html
そのほか秋田大会の情報はコチラ↓
http://www.geosociety.jp/science/content0014.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】構造地質「2008年夏の学校」“反射法地震探査:基礎・演習・実習”
──────────────────────────────────
反射法地震探査は石油探鉱の方法として発展してきたものですが、いまや広く資源探査、地質・地殻構造解明、堆積盆解析、地震断層解析など構造地質学の基本的ツールとなっています。そこで日本地質学会構造地質部会は千葉大学大学院理学研究科地球科学コース地殻構造研究室と共同で、反射法地震探査の基礎から応用まで、演習や実習を折り込みながら学ぶ『夏の学校』を以下の要領で開校します。特に若い学生諸君の積極的な受講を期待しています。
日本地質学会構造地質部会長 竹下 徹
I.スケジュール
8月21日(木)午前9時30分〜8月23日(土)午後5時
II.会場
1〜2日目:千葉大学理学部4号館301号室
3日目:理学部敷地内+自然科学研究科第1号棟702室
(http://www.chiba-u.ac.jp/general/about/map/nishichiba.html)
III.カリキュラム
1日目:21日(木)
午前9時30分受付開始
午前10時開講
講師:西木 司さん(石油資源開発(株) 探鉱本部)
午前:《講義》「反射法の基礎」
・反射法地震探査のデータ取得
・処理と解釈
・振幅情報を用いた地下の物性推定
・3次元・4次元地震探査
午後:講義続き
・データ処理の重要ステップ
《演習》
(1) コンボリューションとデコンボリューション(簡単なウェーブレットによる
デコンボリューションの計算など)
(2) 速度解析(例えば速度解析のパネルを用意し実際に速度を読み取り、区間速
度を計算する。読み取った速度を変化させるとNMOカーブがどう変化するか、など)
(3) マイグレーション:Map Migration(反射面が、上方に急ディップに移動する
様子、スマイルがなぜできるか、回折波がなぜ1点に集まるのか、など)、
(4) (1)のコンボリューションモデルとの関連から、合成地震記録の作成など
2日目:22日(金)講師:中神康一さん(石油資源開発(株) 探鉱本部)
《解釈演習》反射断面上で解釈訓練
(1)紙の断面で解釈(各自)
(2)断面の解釈をマップに落とす(ふたり1組)
(3)マップをコピー(主催者)
(4)マップ上にコンターを書く(各自)
(5) 品評会
夜:懇親会(けやき会館内コルサ)
3日目:23日(土)講師:須田茂幸さん(㈱地球科学総合研究所研究開発部)、
西木 司さん、菊池伸輔さん(石油資源開発(株))
午前の早い時間から震源=油圧インパクター、探鉱器=DAQを用いてデータ取得作
業の練習。早めの弁当をたべ、ただちに教育用ソフト(ActiveSeis)を用いてノー
トPC上で処理の練習を行う。処理訓練用データは、1993年千葉大学構内で取
得したものを使用する。
IV.参加者が準備するもの
(1)文房具類:定規(50cm以上)、鉛筆(シャープペンシル)、色鉛筆(赤を含む最低3
色)、鉛筆削り、ボールペンまたは極細サインペン、消しゴム、分度器
(2)関数付電卓
(3)可能であれば、Windows2000、同XP以上のノートパソコンを持参していただけるとありがたい
(4)3日目の作業が可能な服装
V.受講費 一般3000円、学生・院生1000円
VI.懇親会費 一般4000円、学生・院生2000円
VII.申し込み方法
京都大学工学部山田泰広まで以下の事項を明記した上でメール(yamada@earth.ku
mst.kyoto-u.ac.jp)で申し込んでください(これらの情報は部会事務局で管理し、
「夏の学校」運営目的以外には使用しません。また「夏の学校」終了後すべて廃
棄します)。定員30名になったところで締め切らせていただきます。
氏名 所属 学生/一般
連絡方法(メール+携帯電話)
◎宿泊についての希望がある場合は可能な限り世話したいと思いますので申し込
みの際にその旨ご記入下さい。
◎受講確定者には、追って詳細な実施要項をメールにてお送りいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】古気候・古環境研究の推進のための多分野横断型MLへの参加のお誘い
──────────────────────────────────
日本学術会議・IGBP分科会・PAGES小委員会では、日本における古気候・古環境
研究の益々の発展を図るため、関連する様々な学会・研究会等に呼びかけて、
多分野横断型のメーリングリスト(Japan-PAGESリスト)を、新たに立ち上げる
ことに致しました。
【趣旨】
PAGES(Past Global Change)は、IGBP(国際地圏・生物圏研究プログラム)の下
で、地球環境問題の解決と気候・環境の将来予測に資するための、古気候・古
環境研究の国際的なコーディネートを行うために、1991年から活動を続けてい
る国際的な研究 者組織(http://www.pages.unibe.ch/)であり、日本学術会議
には、当初か ら、その国内対応のためのPAGES小委員会が設けられ、国内外の
研究状況の交 流・分析が行われています。PAGESが対象とする分野は、第四紀
の様々な時間スケール(更新世、完新世、歴史時代、前世紀など)における、
グローバルからローカルスケールの気候や海洋、生物地球化学、生態系プロセ
ス、生物多様性、そして人間活動との関連です。
日本国内では、これまで、多くの分野で古気候・古環境に関する研究が活発に
行われてきた反面、研究立案や成果にかかる交流が個別の分野内にとどまり、
必ずしも広く交流されて来なかったため、気候・環境変動メカニズムの総合的
な理解にむけた議論が広く行われにくいことや、分野横断型の新たな学際的研
究の展開にむけた分野間・研究者間の調整が進みにくいといった弱点がありまし
た。
そこで、PAGES小委員会では、分野間の交流と連携の推進を目的とした、以下の
メーリングリストを作成することに致しました。
【名称】
Japan-PAGESメーリングリスト
【目的】
1.地質学、地球化学、古生物学、地理学、第四紀学、古海洋学、雪氷学、木
材学、歴史学、考古学、花粉学等々の古気候・古環境復元に関係する全ての分
野、及び、気象学、気候学、海洋学、生態学等々の直接観測するデータに基づ
いて近過去〜現在の気候・環境変動やその将来予測研究を行っている全ての分
野から、研究者の参加を得ること。
2.グローバル〜ローカルスケールの気候・環境変動の総合的な理解とそのメ
カニズムの解明や、分野横断型の学際的共同研究の立ち上げ等のための、多分
野にまたがる日常的な議論と情報交換を行うこと。
3.定期的に開催される関連学会等(地球惑星連合大会など)に向け た、「古
気候・古環境関連セッション」の企画立案・講演募集・相互調整を行うこと。
4.PAGESその他、国内外の古気候・古環境研究の学問的・制度的・予算的状況
についての、国内の関連研究者に対する迅速かつ正確な情報伝達を行うこと。
【参加方法】
pages-j-pub@geos.ees.hokudai.ac.jp という名前の、「メンバーのみ投稿可」
のメーリングリストを作成します。このメーリングリストに登録希望の方は、
PAGES小委員会のメーリングリスト担当委員である、北大・地球環境の入野さん
あて(irino@ees.hokudai.ac.jp)に、「氏名・メールアドレス・所属・専門分
野(研究・専攻内容など)」の情報を、お送りださい。尚、いただいた情報に
ついては、メールアドレスをメーリングリストに登録するために用 いるだけ
で、決して公開などはしません。
メーリングリストの趣旨にご賛同頂ける、多くの関連研究者(学生・院生を含
む)の皆さまの参加をお待ちしております。
井内美郎(早稲田大学人間科学学術院人間科学部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質学雑誌:編集規約一部修正について
──────────────────────────────────
地質学の研究・教育に関わるより多くの方に論文や情報・アイデアをお寄せいた
だくために,いくつかの編集規約,投稿規定を改訂・改善したいと考えています.
その一つとして,カテゴリー「報告」の規約を少し改訂することになりました.
「議論を含まない」ことを記して他のカテゴリーとの区別を明確にし,本来の主
旨(卒論・修論等に掲載されたオリジナル・データ業務等の中で得られたデータ
を公開する)を実現しやすいようにいたします.奮ってご投稿ください。
現行)
e.報告 (Report) :卒論・修論等に掲載されたオリジナル・データや業務等の中
で得られたデータで,地質学上有意義なデータの報告.
改訂後)
e.報告 (Report) :卒論・修論等に掲載されたオリジナル・データや業務等の
中で得られた地質学上有意義なデータの紹介で,議論等を含まない.*注記1
*注記1) 7月12日に,「報告」の内容について,上記のような改訂案の提示があ
りました.この改訂案の提示以前に投稿された原稿および8月11日までに投稿され
た原稿に関しましては,この改訂案に従うものではありません.なお,改訂規約は
2008年8月12日以降に投稿された「報告」原稿より,適用するものとします.
(地質学雑誌編集委員会)
──────────────────────────────────
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.0036 2008/7/29 geo-Flash
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.036 2008/07/29 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
本学会、ならびにこれまで地質学への多大な貢献をなされてきた方々が
相次いでご逝去されました。突然の悲報に接し、誠に痛惜の念でいっぱい
です。あらためて、故人の方々の功績を讃えるとともに、謹んでご冥福を
お祈り申し上げます。
会長 宮下純夫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 都城 秋穂 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
米ニューヨーク州立大名誉教授、地質学会名誉会員であられた、
都城秋穂先生が、不慮の事故により7月24日ご逝去されました。享年87歳。
NY州のオルバニー近郊の森林公園で崖から転落事故にあわれたとのことです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 八木 健三 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
北海道大学名誉教授、東北大学名誉教授、地質学会名誉会員であられた、
八木健三先生が、7月18日午前、慢性心不全のためご逝去されました。
享年93歳。葬儀、告別式はご親族のみで7月21日に行われました。
「八木健三先生 お別れの会」のお知らせ
札幌藻岩山にシナノキの花が香る7月18日、北海道大学・東北大学名誉
教授 八木健三先生がご逝去されました。享年93歳でした。過日、ご家族
・近親者による密葬が無宗教にて滞りなく執り行われました。
先生は,東北大学・北海道大学・北星学園大学における永年の教育・研究
活動はもとより,日本学術会議会員など国内外の学会の役員として岩石学
鉱物学の発展に寄与されました。また、北海道大学ワンダーフォーゲル部
顧問としてご尽力され,さらに北海道のみならず日本の自然保護運動にき
わめて大きな足跡を残されました。
つきましては、関係者が相計らい、生前お世話になった方々、また、ご親
交のあった方々にご参会いただき、下記のとおりお別れの会を行うことに
致しました。ご多用中恐縮に存じますが、ご臨席賜りますようご案内申し
上げます。
まずは略儀ながら、ご挨拶かたがたお願い申し上げます。
記
日時 2008年9月6日(土曜日)正午 〜 午後1時半(開場午前11時半)
場所 札幌後楽園ホテル地下2階ピアリッジホール
(〒060-0042 札幌市中央区大通西8丁目、
電話011-261-0111、fax011-261-5105)
「八木健三先生 お別れの会」世話人会代表 在田 一則
(元北海道大学大学院教授・(社)北海道自然保護協会副会長)
*当日は平服でご参加頂くようお願いいたします。
お問合せ先
北海道大学理学研究院、 三浦裕行、011-706-2727、hiro@mail.sci.hokudai.ac.jp
(社)北海道自然保護協会、福地郁子、011-251-5465、nchokkai@polka.ocn.ne.jp
北海道大学工学研究科、 平沖敏文、011-706-6640、hiraoki@eng.hokudai.ac.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
──────────────────────────────────
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質マンガ 地質学の彼氏を持つと
地質マンガ
戻る|次へ
No.0037 2008/8/5geo-Flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.037 2008/08/05 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】秋田大会各種申込み8/8締切! 巡検もまだ余裕あります
【2】続報 岩手・宮城内陸地震 山形大学・千葉県地質環境センター
【3】海外便り
【4】夏休みだー 博物館へGo!! 8月の博物館イベント情報
【5】紹介:「地質学者が見た風景:坂 幸恭著」/「プレートテクトニクスの拒絶と受容:泊 次郎著」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募:京都教育大学新潟大学/東北大学東北アジア研究センター
富山市科学博物館/統合国際深海掘削計画中央管理組織
【7】地質マンガ「地質学の彼氏を持つと」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】秋田大会各種申込み:8/8 18時締切
──────────────────────────────────
■秋田大会の参加登録の締切が迫っています。忘れずにご登録をお願いいたします。
また、講演申込をされた方も忘れずに別途事前参加登録(Knt申込フォームから)
を行って下さい!
■ 見学旅行空き状況(8/5 13:00現在の残数)*見学旅行の申込みページに表示されます.
A班<男鹿半島火山岩相>3(定員20)
B班<男鹿−能代>9(定員20)
C班<地学教育>11(定員20)
D班<出羽丘陵>6(定員14)
E班<鳥海火山>6(定員20)
F班<地熱>19(定員20)
G班<非金属鉱床>8(定員10)
H班<黒鉱鉱床>0(定員14)受付終了
I班<北部北上帯>7(定員20)
J班<根田茂帯>11(定員20)
K班<アダカイト>7(定員20)
■懇親会定員約200名のところ、すでに170名以上のお申し込みを頂いております。当
日参加はお受けできない可能性がありますので,参加希望の方はお早めにお申し込み
ください。
懇親会費:(一般)5000円・(名誉・院割・準会員ほか)2000円
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/science/content0014.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2008年岩手・宮城内陸地震 荒砥沢ダム上流地すべり調査報告
──────────────────────────────────
荒戸沢上流部の地すべりについて現地での地質調査と空中写真および地形図の
解析によって,地すべりが古い地すべりの再活動であったことを明らかにした.
また,地すべりの発生が強震動にあることは間違いないが,その前提として,
古い地すべり末端付近で開析が進んで比較的深い谷が形成されていたことによ
る可能性を示した.
川辺孝幸(山形大学地域教育学部)
風岡 修・香川 淳・楠田 隆・酒井 豊・古野邦雄・吉田 剛(千葉県環境地質センター)
詳しくは、、、
http://kei.kj.yamagata-u.ac.jp/kawabe/www/2008iwtmyg/aratozawa/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】海外便り(2) マディソン郡のはっしー
──────────────────────────────────
ウィスコンシン州はミシガン湖の西部に位置しており、北海道とほぼ同緯度です。
冬は札幌に比べると雪は少ないですが、気温はかなり低くなります。昨冬はマ イ
ナス24℃を経験しました。素手が外気に耐えられないことは初めてでした。長い冬
は厳しいですが、そのおかげで春の訪れに対する感動は倍増します。夏は 札幌
同様短く、夏の空が異常にきれいなところも似ています。今はその短い夏を満喫し
ているところです。
橋本善孝(高知大学・日本学術振興会海外特別研究員)
詳しくは、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0108.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】夏休みだー 博物館へGo!!
──────────────────────────────────
いよいよ、夏休みも本番。博物館では、今月もたくさんのイベントを用意してみなさま
のお越しをお待ちしています。
貴重な夏休みの思い出を、博物館でつくりませんか。
8月の博物館イベント情報は
http://www.geosociety.jp/name/content0023.html
でチェック!!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】紹介「地質学者が見た風景:坂 幸恭著」/「プレートテクトニクスの拒絶と受容:泊 次郎著」
──────────────────────────────────
■地質学者が見た風景 (会員割引有り)
坂 幸恭 著. 築地書館,2008年5月20日発行,横型B5判,255ページ,ISBN 978-4-8067-1368-5
定価5,600円+税,日本図書館協会選定図書
右は,本(B5判横型)の表紙,「海洋に堆積した順序2」と題された三重県南伊勢町海岸の海洋プレート層序を示す露頭の画の一部で,本文中に画の全体が掲載され,詳しく解説されています.そのほか,本文中の画の2例を図2,3に掲げました.画の説明はそれぞれに記されています.
図2.仏像構造線
図3 マッターホルン
著者が写真を基にした水彩画を作成された動機は,著者のすばらしい絵心に加えて,「露頭・風景等の写真では特定の対象が全体のなかに埋没して判かりづらくなる一方,スケッチは観察者の意図を十分に反映するがたいへんな時間を要する.写真を眺めてスケッチを起こせば,両者の特性を活かせるのではないかと考えた」ことだそうです.フィールドでの観察・撮影時に記された簡略スケッチの4例と掲載された画を眺めていると,確かにそのとおりと納得できます.
全体的に,このような意図のもとに描かれた画は,写真とは違う面で,作者の意図・見方,感じ方ないし心情を読者に伝達しているので親しみを持つことができ,また筆の運び方を楽しむこともできて,見飽きることがありません.もっとも,知っている風景や露頭については,部分的には「自分ならば少し違う描き方をするかもしれないな」というところが,何箇所かには見られますが.
画の題材は,著者の訪問先に限られています.とはいえ,海外ではアフリカ大陸(とくに東アフリカ・リフトバレー),アイスランド(ギャオほか),トルコ(アナトリア断層ほか),イギリス,大陸欧州,中国,東南アジア,米国に及んでいます(約180点).また,国内では秋吉台,野島断層,中央構造線,仏像構造線,北海道の火山ほか多数箇所の地形・地質が採り上げられています(約40点).なかでも,道路工事中の切り割りに現れた仏像構造線のすばらしい露頭(図2)はその後コンクリートによって覆われて,その画が貴重な記録となっています.
本は上記のような画を主体としていますが,冒頭には,海外の画の作成地点の索引地図などのほか,16ページにわたって「解説」が掲載されています.一般地質学の解説ですが,とくに多くの画が描かれている地域(アフリカ大陸,アイスランド,トルコ)をはじめとして,国内外の作成地域の構造地質学的な特徴や地球の内成・表成過程全般が説明されており,画の地質学的理解を助けています.
本書は,著者自身の水彩画による記録史です.と同時に,必ずしも網羅的ではありませんが,国内外を問わず地形・地質紀行誌として大いに楽しめる画集です.それだけでなく,地質屋(フィールドジオロジスト)が露頭や自然景観を見て何を感じ,何を考えるか,またどのような見方をすれば地質学に迫ることができるのか,などが全体を通じて示唆されており,小中高・大学を通じてよい教材として活用でき,一般の人びとに対するよい普及書でもあると思います.
出版元の築地書館のご好意により,日本地質学会会員は会員番号・住所・氏名・電話番号を明記の上,9月末日までに下記宛に申し込めば,定価の2割引,築地書館送料負担で購入できます.それぞれの会員番号は毎月送付される雑誌の封筒宛先面に記載されています.申し込み先は,築地書館(〒104-0045東京都中央区築地7-4-4-201)受注担当 川上 e-mail:eigyo@tsukiji-shokan.co.jp 電話03-3542-3731 FAX 03-3541-5799
(水野篤行)
■「プレートテクトニクスの拒絶と受容 戦後日本の地球科学史」
泊 次郎 著.東京大学出版会 A5, 258ページ ISBN978-4-13-060307-2 \3,800+税
2008年6月2日発行
出張帰りの新幹線の車内で「週刊文春」を見ていたら,作家の池澤夏樹氏による「地学論争」と題する「私の読書日記」が目にとまった(2008年7月17日号136ページ).地団研,地向斜造山説,歴史法則主義,プロレタリア科学,スターリン主義,ルイセンコ生物学などという,およそ一般向けの週刊誌ではまずお目にかからない,しかし私の脳裏に複雑な反応を引き起こす言葉が散りばめられたこの丸1ページの読書日記は,帰宅後すぐにネット書店でこの本を探して「カートに入れる」ボタンをクリックさせるのに十分なインパクトがあった.
私は著者の泊氏と面識がなく,この本の内容を部分的にでも見聞きしたことはそれまで一度もなく,この本に私の名前が登場するわけでもないので,その限りでは「客観的な読者」であるが,私は地団研の活動に長年参加してきて北陸支部長を務めたこともあり,しかし一方では学生時代からプレートテクトニクスの枠組みを「受容」した研究をしてきたため,この本が研究対象としている地学関係者の末席を汚してきたわけで,その意味で私はこの紹介文を「当事者」の感慨抜きに書くことはできない.泊氏は1944年生まれで私より一回り年上であり,東京大学理学部で地球物理学を学び,その後ずっと朝日新聞に勤務していたが,2002年に東京大学大学院総合文化研究科科学史・科学哲学講座博士課程に入学し,昨2007年博士(学術)の学位を得た.この本はその学位論文に「大幅な改訂を加えたもの」とのことである.
この本の章題を列挙すると,序章 プレートテクトニクスと日本の科学史,第1章 大陸移動説からプレートテクトニクスへ−地球科学の革命,第2章 戦前の日本の地球科学の発展とその特徴,第3章 戦後の日本の民主主義運動と地学団体研究会,第4章 「2つの科学」と地学団体研究会,第5章 日本独自の「地向斜造山論」の形成,第6章 プレートテクトニクスの登場と日本の地球科学,第7章「日本列島=付加体」説の形成とプレートテクトニクスの受容,終章 プレートテクトニクスの受容とそれ以降の日本の地球科学,となる.
作家の池澤氏の感想は「この冷静な科学史の研究書はおもしろかった」であり,確かにこの本の各章末には引用文献や注釈が数ページずつ添付されていて非常に丁寧な労作の研究書である.20人ほどの関係者に直接取材したそうであるが,聞き書きを避け,徹底した文献調査に基づいている.ただし,文献の中には自費出版の主観的な回想録なども含まれる.ところで,この本の構成や論述の進め方は,学術誌に掲載される「科学論文」よりも,むしろジャーナリスティックなドキュメントに近い.科学史研究のケーススタディとして,この研究の結論が何なのか,また新発見や独創的なアイデアは何なのか,いま一つはっきりしない.例えば,本書の序章ではクーンの「科学革命」やパラダイムの概念が紹介され,「うわぁ難しい本だな」という印象を与えるが,研究対象とする日本のケースについて,序章で示されたテーマに沿ってデータを示しながら議論を行い,終章の結論に導くという,通常の科学論文の構成にはなっていない.終章は「そくほう」の「おわび」問題や「都城賞」否決問題など最近の動きを紹介し,「残された課題」として「政治と科学の問題」,特に「地団研の運動が当時の社会の動きとどのように結びついていたか」を十分に明らかにできなかったという反省を述べて終わっている.この本は一般向けの普及書なので,学問的な議論については博士論文を読まなければいけないのかもしれない.
本書では全く触れられていないが,私が1980年にオフィオライト会議参加のためイタリアを訪れた時に見聞したところでは,その頃のイタリアにも地団研によく似た性格の地質学者集団があったようで,同じ第2次世界大戦の敗戦国で,国内資源に乏しく,戦後の一時期に左翼が優勢で,ドイツのように分断国家にはならなかった等の点で日本と社会状況が似ており,本書で触れられているロシアや中国よりは,イタリアの方がこの種の比較研究に適しているかもしれない.ただし,イタリアでプレートテクトニクスの受容が遅れたという話は聞かない.
本書はよく推敲・校閲されていて誤りは少ない.しかし,19ページに「海洋底を構成する岩石(シマと呼ばれた)にはマグネシウムなどの重い金属が多く含まれ」とあるが,マグネシウムはアルミニウムよりも「軽い」金属である.
ともあれ,我々以上の世代にとってはまだ生々しい戦後日本の地球科学史を,豊富な資料を駆使して読みやすい文章で上手に描き出したのは本書の功績である.私のような「当事者」でも,科研費配分の話や日米科学協力の話など,「ああそうだったのか,そんなことがあったのか」と感心するような記述は多く,一方で過去の経緯を何も知らない現在の学生にとっては,格好の地球科学の入門書(または年輩の指導教員と共通の話題を仕入れるためのネタ本)になるだろう.地団研に反対する立場の人たちの論説の誤りや問題点も指摘しており,公平を心がけていることにも好感が持てる.この労作は日本の地球科学界をより成熟した風通しのよいコミュニティにし,地質学会がその中でより大きな役割を果たしていくことに貢献すると思う.会員各位のご一読をお勧めする.
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募:京都教育大学/新潟大学/東北大学東北アジア研究センター
富山市科学博物館学芸員(岩石)/統合国際深海掘削計画中央管理組織
──────────────────────────────────
■京都教育大学「理科教育」担当教員公募
職名及び人員 講師または准教授 1名
担当分野 理科教育
応募資格 年齢:着任時40歳以下
学歴等:修士または博士の学位を有する者/専門等:理科教育に関する研究業績を
有し,中学校理科第2分野の内容に関する研究をバックグラウンドにする者
応募期限:平成20年 9 月17 日(水)17:00必着
http://www.kyokyo-u.ac.jp/KOUHOU/saiyou/saiyou.htm
■新潟大学教育研究院自然科学系教員(助教)公募
所属:新潟大学教育研究院自然科学系 自然構造科学系列
担当分野:地球科学分野
職種・人員:助教 1名
任期:採用時から5年間. 再任なし.
応募の締切:平成20年9月16日(火)必着
http://www.gs.niigata-u.ac.jp/~scitech/koubo/koubo080710.html
■東北大学東北アジア研究センター教員の公募
公募分野:東北アジア研究センター 基礎研究部門 地球化学研究分野
職名・人員:助教1名(任期3年,再任可,再任は任期2年,2回を限度とする)
専門分野:岩石学, 地質学,火山学,地球化学,鉱物学,鉱床学など.日本を
含む東北アジア地域を研究対象とする野外研究の実績及び今後の計画があること.
当該分野のスタッフ(下記参照)との共同研究が可能な者.
応募締切日:平成20年9月30日(火)必着
http://www.geosociety.jp/outline/content0062.html
■富山市科学博物館学芸員(岩石学)
受験資格:昭和53年4月2日〜昭和62年4月1日に生まれた人
学芸員資格は不問ですが、採用後に取得が必要.
受験案内と申込書は、富山市のホームページの下記のURLを開き、上級試験(学
芸員)からPDFをダウンロードしてください。
http://www7.city.toyama.toyama.jp/pr/v_useful/index.html
申込期間:8/11-8/22(必着)
*昨年「富山市科学文化センター」から「富山市科学博物館」に名称変更しました.
**当館は文部科学大臣による「研究機関」の指定を受けていますので、大学など
と同様に「科学研究費補助金」の申請をすることができます.
■ 統合国際深海掘削計画中央管理組織
統合国際深海掘削計画(IODP)の中央管理組織である、IODPマネジメント・インター
ナショナル社(IODP-MI)のPresident/CEO ポストの公募情報です。
詳細はこちらをご覧ください。
http://www.iodp.org/employment-opportunities/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】地質マンガ「地質学の彼氏を持つと」
──────────────────────────────────
「地質学の彼氏を持つと」
作:山口飛鳥 画:Key
http://www.geosociety.jp/faq/content0106.html
地質マンガは原作を募集しています。文字だけでもラフスケッチでも清書
して仕上げます。投稿はこちらから
http://www.geosociety.jp/publication/content0009.html#toko4
──────────────────────────────────
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
海外便り 〜ウィスコンシン州立大学マディソン校より〜
海外便り 〜ウィスコンシン州立大学マディソン校より〜 2008.8.5UP
日本学術振興会海外特別研究員 橋本善孝
現在私は日本学術振興会海外特別研究員として、ウィスコンシン州立大学マディソン校に派遣されております。去年の春から2年の予定で、早いものですでに1 年と3ヶ月が過ぎました。ウィスコンシン州はミシガン湖の西部に位置しており、北海道とほぼ同緯度です。冬は札幌に比べると雪は少ないですが、気温はかな り低くなります。昨冬はマイナス24℃を経験しました。素手が外気に耐えられないことは初めてでした。長い冬は厳しいですが、そのおかげで春の訪れに対す る感動は倍増します。夏は札幌同様短く、夏の空が異常にきれいなところも似ています。今はその短い夏を満喫しているところです。マディソンはウィスコンシ ン州の州都で、人口は周辺の連続する町を含めて30万人程度です。州政府と大学しかない街と言われています。街は芝生と街路樹で覆われており、グーグル マップで見ると森の中に住宅街があるように見えます。州最大の街はミラービールやハーレーダビットソンで有名なミルウォーキーで、東へ車で1時間半程度で す。州をまたいでイリノイ州シカゴまで車で3時間程度の所に位置します。極稀にラーメンを食べに行きます。
私はこちらで 堆積物の弾性波速度の測定と堆積物の組織についての研究を行っております。タイミングよく昨年末に南海トラフ掘削プロジェクトに参加することができ、そこ で取られた堆積物を対象にしています。実際に測定を開始したのは今春からでした。というのも、タイミングの悪いことに私の受け入れ教員が本大学に異動した ばかりだったので、測定器のセットアップをほぼ一から行わなければならず、これが意外と大変でした。圧力容器をはめる穴をテーブルに空けるところから始ま り、機器をセットアップして、機器から送られてくる電気信号のデータ処理プログラムまで一通り経験することになりました。当初はなかなかデータを取る段階 までたどりつけず焦っていましたが、逆にいえばそういう機器のセットアップに関わるチャンスもなかなかないので、かえってよかったのではないかと今は思い ます。米国の名だたる大学は同様なのかもしれませんが、日本でいうところのテクニシャン(技師)が豊富に揃っており、機器のセットアップについては金属加 工技師や電気技師に大変お世話になりました。また、サンプル処理についても、いわゆる薄片技師と相談しながら私専用のルーチンを立ち上げてもらいました。 電子顕微鏡の使用についても専門技師のお世話になっております。実質的な現場作業はこのような技師なしでは回らないというほど重要な存在です。皆プロ フェッショナル意識が強く、彼らなしでは教授陣の研究が進まないことをお互いに自覚しています。このような技師のおかげで、教授陣は比較的多く研究につい て考えられるようになっています。私も彼らのおかげで順調にデータを取得しつつあり、幸せな日々を送っております。
私の 受け入れ教員の研究室には正規の学生は3名です。一人は非常に優秀で、機器のセットアップはほとんど彼がやって僕はほぼ横にくっついていただけという状態 でした。もう一人は逆に全く仕事が遅い問題児です。最後の一人は新入りで未知数ですができそうなオーラを感じます。現在は定期的なゼミなどはありません。 これまで不定期に勉強会や輪読会を研究室で行ってきました。時々構造地質グループのゼミや、極稀に開かれる不定期セミナーなどに参加します。学期中には毎 週金曜日にゲストスピーカーによる講演会があり、興味のあるものに出たりしていました。自由の国らしく日本よりもかなり縛りの弱い活動をしています。4月 に年に一度だけの学生による研究発表会がありますが、去年と今年と比べてみるとあまり変わっていない学生が多くいました。こちらでは学生に強制するものが あまりないようで、相当なレベルで自律しないとなかなか一人前にはなれないのではないかと感じます。一方でほとんどの学生は教授の研究費から授業料やとき に給料までも出してもらっており、自律を促すような仕組みになっているとも言えます。
こちらには妻と娘が一緒で、家事に ついては全くもって助かっています。マディソンに日本食材屋があり、家ではほぼ日本と変わらぬ食事をしています。とはいっても全く日本と同じというわけに はいかず、ご飯の味のちょっとした違いなどが最初は気になって仕方なかったのですが、今となってはどんな違いだったか思い出せないほどです。来た当初は まったく食べなかったまるまる一本のピクルスも、今はホットドックにものすごく合う食べ物だと思うようになりました。慣れというのはすごいですね。
言葉の問題で否が応でもマイノリティー意識を感じざるを得ないことがありますが、民主党の候補者選挙のときにバラク・オバマさんの講演を聞きに行き、個人 情報を提供したところ、選挙日の前日に後援会から電話がかかって来て、明日の選挙よろしくと言われたときは、何か米国国民の仲間入りをさせてもらったよう な気持ちになってありがたく感じたと同時に無用な仕事をさせてしまって申し訳ない気持ちになりました。
週末は、お祭りや パレードを見に行ったり、州立公園を回ったり、農場にピクニックピッキングに行ったり、いろいろ楽しんでいます。日本にいた頃とは比べるべくもないアク ティブさです。明日はエアーショウ、来週はウィスコンシンフェスタ、再来週はイリノイ州鉄道博物館にトーマス電車に乗りに行き、さらに次の週はメジャー リーグベースボールの観戦でミルウォーキーに行く予定です。今年度一杯で帰国する予定ですので今のうちにできるだけ楽しんでおかないともったいないと思う ばかりです。
家族を連れて来たことで余計なプレッシャーがありましたが、妻も娘も日本人の友達を早々に見つけて、順調に 馴染んでくれました。今夏から娘のプレスクールが始まり、妻は先生との連絡の必要性から教会主催の無料英会話クラスを以前より熱心に受けているようです。 ネタで周囲からはすぐに娘に英語を教えてもらえると言われます。確かに最近娘が英語をしゃべりだしましたが、幼児語なので大人は使ってはいけないという注 意もよく聞きます。
後半はまったく個人的な話で一体何のためにこれを書いているのかよくわからなくなってきましたが、将来海外で自分を試してみたいという若者がいて、そういう若者にこの文章が少しでも参考になれば幸いです。
No.0038 2008/8/12geo-Flash
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.038 2008/08/12 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
中川久夫名誉会員の突然の悲報に接し、驚愕しております。先生の地質学会
に残されたご功績を偲び、心からご冥福をお祈りいたします。
会長 宮下純夫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 中川 久夫 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
東北大学教授であられた中川久夫 名誉会員が、肺がんご療養中の
8月5日にご逝去されました。慎んで会員の皆様にお知らせいたします。
享年82歳でありました。
中川久夫先生におかれましては、2008年8月5日早朝にご逝去されました。
享年82歳でした。あまりに突然のお知らせに関係者一同大いに驚き、悲しみ
の極みであります。
中川先生は、昭和2年に東京でお生れになり、昭和23年に岡山の旧制第六
高等学校理科甲類をご卒業の後、東北大学理学部地質学古生物学教室に進学さ
れました。同教室を昭和28年にご卒業後、昭和34年に東北大学理学部教務
員として奉職され、同年東北大学理学部助手となられ、昭和36年に理学博士
の学位を取得されました。以後、34年の永きに亘り研究と教育に専念され、
平成3年に東北大学を退官されました。この間に、第三紀古地磁気層位学や琉
球列島における第四紀地質学の分野で国際的な業績をあげられ、多くの卒業生
を世に送り出されました。
中川先生は、学会活動でもご活躍され、昭和37〜45年および昭和58年
〜平成3年には日本第四紀学会の評議員を務められ、さらに日本地質学会など
におかれましても多数の要職・役員を歴任されました。
中川久夫先生は、地球科学の研究にとどまらず、研究地域の文化にも造詣を
深くされました。特に、沖縄や奄美の島々では地酒と歌謡に深いご理解を示さ
れ、酒宴の席で三線に併せて舞われる姿は今も鮮やかに脳裏に刻まれておりま
す。アトラスの東縁を吹き抜けた砂漠の風が中川先生の愛されたメッシナの海
に春をもたらします。その先チレニアの海を渡る風はボルカノの雲を払い,ス
トロンボリを一望にします。中川先生の生き様は,エオリアの春の一陣の風の
ごとく,我々に大らかさと力強い希望を与えるものでした。
中川久夫先生のご厚恩に改めてお礼を申し上げると共に、万感を込めここに
心よりご冥福をお祈りいたします。
(箕浦幸治・中森 亨)
東北大学地質学古生物学教室
同窓会係り 島本昌憲
──────────────────────────────────
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.0039 2008/8/19geo-Flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.039 2008/08/19 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】会員情報の確認・修正がオンラインでスタート!便利じゃん
【2】秋田大会見学旅行追加募集
【3】新!地質学会広報誌 準備中!乞うご期待!
【4】コラム:庭石から地球科学を考える
【5】秋田大会・夜間小集会「地質学会若手の集い」のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】群馬県立自然史博物館学芸員募集
【7】国際シンポのご案内 "Efficient Groundwater Resources Management"(in タイ)
【8】地質研修のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】会員情報の確認・修正がオンラインでスタート! 便利じゃん
──────────────────────────────────
平素は学会ホームページにご活用ありがとうございます.昨年9月に新装開店
し,やや作業が遅れていました会員情報のオンライン編集機能が使用可能となり
ました.からアクセスして頂き,会員ページにログインしますと住所,メールア
ドレス,専門部会などなど皆様ご自身の登録情報の確認と更新ができます.大変
便利です.なお従来の郵送やメールでの変更サービスも継続しております.どう
ぞご利用下さい.なおセキュリティのためにもログインパスワードの管理(定期
変更など)をどうぞよろしくお願いいたします.
今後ますます使いやすい環境にしていく予定ですが,会員皆様のご意見,ご要
望をお待ちしております.
会員ページへのログインはこちら
(ログインの際には、会員番号こうからなるIDとパスワードが必要です)
https://www.geosociety.jp/user.php
(2008年8月 広報委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】秋田大会見学旅行追加募集します
──────────────────────────────────
秋田大会見学旅行参加者を再募集いたします.
申し込む方は8月31日までに,下記項目を明記の上,
大友幸子<yukiko@e.yamagata-u.ac.jp>にお申し込みください.
申込者には,8/25以降に必ず“受付”メールを返信します(返信がない場合,不
着の可能性がありますので再度連絡ください.8/20-24は不在です).なお,受付
は先着順です.
●申込事項:氏名,よみ仮名,年齢,所属,E-mailアドレス,電話番号
A(9/23-24)男鹿半島の火山岩相:始新世〜前期中新世火山岩と戸賀火山 2名
B(9/23-24)男鹿半島−能代地域の地形と第四系 6名
C(9/20:大会初日です)地学教育の素材としての男鹿半島 8名
D(9/23)秋田県沿岸ー出羽丘陵新第三系に発達する変形構造 4名
F(9/23)秋田県南部小安秋の宮地域の地熱地質 6名(参加費3000円に変更予
定)
G(9/23)秋田県の珪藻土,パーライト,ゼオライト鉱床 4名
I(9/23-24)安家-久慈地域の北部北上帯ジュラ紀付加体 5名
J(9/23-24)北上山地前期石炭紀付加体「根田茂帯」の構成岩相と根田茂・南部
北上帯境界 6名
K(9/23-24)北上山地に分布する古第三紀アダカイト質流紋岩〜高Mg安山岩と前
期白亜紀アダカイト質累帯深成岩体 6名
*E鳥海火山とH小坂元山黒鉱鉱床・・は定員に達しておりますので再募集しま
せん.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】地質学会から新たな広報誌を配布します!
──────────────────────────────────
広報委員会をリニューアルし、新たな試みとして、会員外の人にも読んで
もらえるような広報誌の配布を計画しています。記事は思わず訪ねてみたく
なるような景観(あえて露頭とは申しませんが)の紹介と、そこに隠された
自然の営みや歴史などの紹介。身近な地球のQ&Aや最近の地球科学ニュース
など、様々な視点から多くの人が興味を持っているようなことを取り上げます。
お試し号を、秋田大会で配布する予定です。乞うご期待。
雑誌のタイトルは・・・まだ秘密です。
(広報委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】コラム:もう一つの東京の石の博物館 -清澄庭園と六義園に見られる
庭石から地球科学を考える-
──────────────────────────────────
清澄庭園は, 都営大江戸線清澄白河駅から歩いて数分のところにあり,
名石には,その産地と石の種類が書かれた立て札が立っており,石の
いわれが簡単にわかる.庭園を一周するころには,北は泥岩の仙台石
から,南は変成岩の伊予青石まで,観察することができる.
(川村喜一郎 深田地質研究所)
詳しくは、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0111.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】夜間小集会「地質学会若手の集い」のご案内
──────────────────────────────────
2008年9月20日〜22日に秋田大学で開催される地質学会秋田大会において,夜間小
集会「地質学会若手の集い」を企画しています.
日時:9月21日(日)18:00〜20:00
会場(予定):工資-321教室
世話人:大坪 誠(産総研)・山口飛鳥(東大)・山口直文(京大)・山岡香子
(東大)・大橋聖和(広島大)・池田昌之(東大)
この小集会では,「地球科学研究の今とこれから」について考えます.地球科
学には現在,多種多様な専門分野が存在しますが,「地球を知る」ということを
目的にした学問であることに変わりはありません.人類共通財産である学問とし
ての地球科学を発展させるために,いま力を入れるべきことは何か?障害となっ
ているのは何か?社会から求められていることは何か?などについて参加者全員
で議論し,その上で地質学のこれからについて考えていきたいと思います.
今回の小集会における特徴は,10人程度のグループで行うワーク形式で進めて
いくことです.参加者一人一人が意見を述べ,参加者間で考えを共有し,そこか
ら新たなアイデアを模索することができる小集会を目指しています.
若手と銘打っていますが,年齢は問いません.また,鉱物科学会の皆様の参加
も歓迎します.意欲ある多くの皆様のご参加をお待ちしています.
問い合わせ先
世話人代表 大坪 誠(産総研)
Tel: 029-861-3934 e-mail: otsubo-m@aist.go.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】群馬県立自然史博物館学芸員募集
──────────────────────────────────
分野・・・・地質、岩石・鉱物
採用時期・・平成20年12月1日
任期・・・・平成20年12月1日〜平成25年3月31日
応募期限: 平成20年9月19日(金) 17:00必着
応募書類:
・履歴書
・小論文「関東山地形成における時代論の変遷に関して知るところを述べなさ
い」2,000字以内
・研究実績(今までの研究の目的、成果、今後の抱負を1,200字程度にまとめたも
の)/業績リスト/主要論文等の別刷またはコピー
・証明書類(学位記の写し/卒業(修了)証明書/学業成績証明書(学部・大学院
発行のもの)/語学(英語)技能検定合格証などの証明書類(任意)
応募・問合せ先:
〒371−8570
群馬県前橋市大手町1−1−1
群馬県生活文化部文化振興課
電話 027−223−1111(内線2595)
FAX 027−223−3984
詳しくは、こちらから
http://www.geosociety.jp/outline/content0063.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】国際シンポのご案内 "Efficient Groundwater Resources Manage
ment"(in タイ)
──────────────────────────────────
IGS-TH2009
日程:2009年2月16日〜21日
場所:タイ・バンコク
事前参加登録 2009年1月15日〆切
問い合わせ先
IGSTH 2009 secretariat
Department of Groundwater Resources, Ministry of Natural Resources and En
vironment
49 Soi 30 Rama VI Road , Phayathai, Bangkok 10400 , Thailand
Tel : +662-299-3967 Fax : +662-299-3926
http://www.igsth2009.com/home.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】地質研修のご案内
──────────────────────────────────
独)産業技術総合研究所地質調査総合センターは,「地質の調査」に関する研修
制度の認定プログラム として,地質調査の研修を行います.この研修は地質調査
総合センターの職員またはOBを講師とし,民間企業の若手技術者を対象とした地
質調査の研修です.今回は「基礎コース」として基本的地質調査技術を学び,独
自で地質調査を行うことのできるノウハウの習得を目指します.
この地質調査の研修を受講された方には,産総研地質調査総合センター代表から
修了証とCPD40単位の認定が受けられます.
詳しくは,
http://www008.upp.so-net.ne.jp/gsis/gykensyu.htmをご覧下さい.
日程: 2008年10月6日(月)〜10日(金)4泊5日
場所: 千葉県君津市及びその周辺地域
費用: 13万円(消費税込み),宿泊代,昼食代,現地までの交通費は各自(会
社)負担が必要です.
募集人数: 5名前後
申込〆切: 2008年9月5日(金)
問合わせ・申込先:
地学情報サービス株式会社 担当:佐藤
〒305-0045 つくば市梅園2-32-6
Tel. 029-856-0561 Fax. 029-856-0568
E-mail: gsis-smg@abox.so-net.ne.jp/gsis@kb3.so-net.ne.jp
──────────────────────────────────
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
もう一つの東京の石の博物館 -清澄庭園と六義園に見られる
もう一つの東京の石の博物館−清澄庭園と六義園に見られる庭石か ら地球科学を考える−2008.8.19UP
深田地質研究所 川村喜一郎
清澄庭園は, 都営大江戸線清澄白河駅から歩いて数分のところにあり,入園料,大人150円の石の博物館である.この庭園は,一説には,紀伊国屋文左衛門の屋敷跡と伝え られており,享保のころに,現在の庭園の基礎が形造られた.明治に入り,岩崎彌太郎が所有し,全国各地から名石を取り寄せ,現在,東京都の名勝として至っ ている.庭園に入ると,55個の全国各地の名石に出会える.それらの名石には,その産地と石の種類が書かれた立て札が立っており,石のいわれが簡単にわか る.庭園を一周するころには,北は泥岩の仙台石から,南は変成岩の伊予青石まで,観察することができる.
*画像をクリックすると大きな画像をご覧頂けます。
写真1 生駒石(一覧表では花崗岩系となっている),清澄庭園.
写真2 秩父青石(一覧表では変成岩系となっている),清澄庭園.
写真3 紀州青石(一覧表では変成岩系となっている),清澄庭園.
写真4 伊豆網代磯石(一覧表では安山岩系となっている),清澄庭園.
写真5 伊豆式根島石(一覧表では礫岩系となっている),清澄庭園.
さらに,サービスセンターに尋ねると,ガリ版刷りの清澄庭園の銘石一覧表を渡してくれた.この一覧表には,石の産地,由来,庭石としての程度,岩石の種類(花崗岩系,安山岩系,変成岩系,礫岩系,泥板岩系(おそらく粘板岩系のあやまり)が書かれている.庭園を回る前に入手しておくと,庭石を詳しく観察できる.東京のど真ん中の公園にも,このようなすばらしい石の野外展示がなされていることは驚きである.
同様に,東京都の名勝である駒込の六義園にも庭石がある.六義園の六義は,和歌の六体である,そえ歌,かぞえ歌,なぞらえ歌,たとえ歌,ただごと歌,いわい歌に由来する.庭石には和歌が詠まれており,庭石一つ一つに歴史が感じられる.都営三田線千石駅もしくはJR山手線駒込駅から歩いて数分のところにあり,入園料は300円である.私の勤務している研究所のすぐ近くにあり,春先にはしだれ桜でにぎわう.
写真6 伊予青石(一覧表では変成岩系となっている),清澄庭園.
写真7 武州三波青石(一覧表では変成岩系となっている),清澄庭園.
写真8 カモメ橋のたもとにある石.この石は江戸時代の書物の六義園記に記される桜波石と同じ場所にある.しかし,残念ながら,これが桜波石であるかは不明.
こちらの庭石には,清澄庭園のような解説が園内にはないが,サービスセンターで石の由来について親切に教えてくれる.さらに,東京都公園協会監修の東京公園文庫19六義園という本(森守著,1982,郷学舎)に,六義園記という江戸時代の書物に記されている石の由緒について詳しく書かれている.その中に,今現存するか不明であるが,カモメ橋のたもとに,桜波石(おうはせき)があるとされる(確かに,その位置にはそれらしい石がある).この石には「余りあれは桜とそおもふ春風の吹き上げはまにたてるしらなみ」と句が詠まれている.しだれ桜の咲く頃に,この石を見る事ができれば,六義園で「岩石」を通して春を感じることができるだろう.
いずれにせよ,どちらの庭園も日曜日の散歩コースとして,ふさわしい石の博物館であると思う.このような庭園が好きな方々(私が見受ける限り,家族連れやご年配の方々が多い)にとって,日常気軽に触れる事ができる,もしくは,休日という生活の一部に浸透している地球科学だろう.このような歴史や文学と融合した「石の博物館」は,私たちの手の届くところにある地球科学の一端であると思う.
(*同記事はニュース誌2008年6月号p.11 TOPICに掲載)
No.040 2008/08/20 geo-flash (臨時号)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.040 2008/08/20 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
本学会、ならびに地質学,岩石学への多大な貢献をなされてきた坂野昇平先生が
ご逝去されました.突然の悲報に接し、誠に痛惜の念でいっぱいです。坂野先生
は相平衡岩石学,変成岩岩石学,三波川変成帯などに関する研究で多大の功績
を上げられ,また多くの人材を育てられました.坂野先生の功績を讃えるとともに、
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
会長 宮下純夫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 坂野昇平 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
お知らせ
京都大学名誉教授 坂野 昇平 殿(75歳)におかれましては、8月19日(火)
午前10時07分ご逝去されましたので、謹んでお知らせいたします。
なお、通夜、告別式は、仏式にて下記のとおり執り行われます。ご遺族より
ご香典・供花につきましては辞退したい旨お申し出がありましたことを申し添えます。
記
日時
(通 夜)平成20年8月20日(水)18:00〜19:00
(告別式)平成20年8月21日(木)12:00〜13:00
場所 公益社 南 ブライトホール
京都市南区西九条池ノ内町60番地
電話 075−662−0042
喪主 坂野 節(ばんの みさお*)(妻)
(*訂正・お詫び)
メール送信の記事では、奥様のお名前が「ばんの せつ」様となっておりました.
正しくは、「ばんの みさお」様です。
ここに訂正し,お詫び申し上げます。(2008/8/19 編集事務局)
──────────────────────────────────
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質マンガ 生痕(せいこん)
地質マンガ
戻る|次へ
海底や湖底の軟らかい地層を柱状の採泥機で取ることができます。この試料をコア試料と呼び、縞々の地層から過去の記録を読み取ることができます。マンガに出てきたのは、このコア試料です。写真はピストンコアと呼ばれる採泥機です。(写真:木戸ゆかり JAMSTEC)
引き上げられたコア試料は詳細に調べられます。
あなたのアイデアがマンガになります!
例えば次のような文章で投稿されたものがこんなマンガに清書されます。
■ 投稿された原作
■ 完成品
「地質学者の彼氏を持つと」
1.今日は二人でお買いもの。久しぶりの銀座デート♪
2.二人同時にショーウィンドウを指さして「あっ!」
3.女「ねーねーこの服すごくかわいい!値段もそんなに高くないし」
4.男、壁にはりついて「うぉー大理石の中にアンモナイトが」
女、呆れて「そっちかい…」
地質学会のメールマガジンで連載中の「地質マンガ」は
みなさま(原作)+イラストレータKeyさん(画)
により作られています。地質の魅力を伝える作品を募集しています。現在ストックゼロで即時掲載の状態です。ゆくゆくは英語化して世界の地質学を席巻する予定です!?どうぞご協力をお願い致します。いけてる作品をぜひ!
投稿はこちらから
地質学会ホームページにアクセス集中!
地質学会ホームページにアクセス集中!
年間50万人・200万ページビューのペース!
いつも地質学会ホームページをご利用下さいまして、ありがとうございます。昨年9月にがらりとリニューアルして以来、たいへんアクセス数が伸びており、皆様には感謝感謝です。ここ最近は1日平均1300人ほどの来訪者があります。これは年間50万人(ページビューなら200万ページ)という勢いです。おそらく地球科学系で国内トップクラスのメディアに成長していると言っても過言ではないでしょう。広報委員会と致しましては、会員の皆様に情報発信プラットフォームとして大いに活用頂けることを強く願っております。
基礎データと用語の説明
インターネットのサーバーには訪問者数、閲覧ページ、検索語とったログデータが記録されており、マーケティングに広く使われております。地質学会サーバーでも自動的に統計処理され、生データは順次削除されております。ここから地質学会ホームページの読者像をうかがい知ることができます。今回使いましたデータは、ページビュー、訪問者数、検索語です。
ページビューはhtmlファイルのヒット数です。たとえ複数の画像ファイルが含まれるページであっても、一つのhtmlファイルであればカウントは1となります。何ページ読まれたかを指します。
訪問者数は、のべ読者数を指します。ただし設定によって変化するので目安として使われます。それは例えば、一度に何十ページも立て続けにアクセスする場合は、一人とカウントされるべきですし、一方、毎朝見に来るファンは毎朝1人とカウントされるべきでしょう。グレーゾーンはありますが、必要な指標のひとつです。
図1.1日あたりの訪問者とページビューの変遷。2007年9月のダイアモンド報道は桁違いのアクセスのためグラフから振り切られています。2007年8月のデータ空白は、サーバー切り替えに伴うデータ欠損です。
訪問者数とページビュー
図2.1日あたりの訪問者数を月間平均したもの。連休等による短期変動がならされ、アクセスが右肩上がりに伸びていることがよくわかる。
毎日の訪問者数とページビューを図1に示します。2005年から2007年夏のホームページリニューアルまでは、おおむね300人(1800ページ)/日で一定しており、学術大会の締め切り月などにアクセスが増えています。短周期のアクセス低下は週末に相当します。ゴールデンウィークや正月には大きく低下します。多くの読者が平日のビジネスアワーに来訪していることに起因します。
2007年7月にメールマガジン「geo-Flash」が開始されアクセス数が増加し始めました。そして9月8日に現在のホームページに切り替わり、その直後に水上会員のダイヤモンド国内発見の報がメディアリリースされました。このニュースは人気サイトYahoo!のトップに掲載され、地質学会のQ&Aページ「Q.日本で天然のダイヤモンドは採れますか? A.これまでに発見の報告はありません」にリンクが貼られ、爆発的なアクセス集中が発生しました。業者は地質学会ホームページがDOS攻撃を受けていると勘違いをしたほどでした。このアクセス集中は日をまたいで起きたので統計上は最高31025人/日となっていますが、実際は深夜から次の日の夜までの24時間で53000人ほどのアクセスがあったものと考えられます。
突発的な影響をならして中期的な傾向を見るために訪問者数の月平均を図2に示します。2007年9月のホームーページリニューアルを境に訪問者数が大きく伸びていることが明瞭にわかります。リニューアルから4月までの累計訪問者数は28万0901人で、このペースであれば2008年度は年間50万人・200万ページビューに達すると予想されます。
人気ページと人気検索語
検索語ランキング(リニューアル以降)
順位
ページ
回
1
地質学会 等
17487
2
地質(日本の地質)等
3141
3
ジオパーク 等
3115
4
地質学雑誌
1422
5
地層
337
6
Island Arc
270
7
vocanlos park
200
8
岩石
163
9
地質学論集
153
10
化石
140
11
地質の日
138
12
地学オリンピック
100
人気ページランキング(リニューアル以降)
順位
ページ
ページビュー
%
1
トップページ
106981
6.5
2
e-フェンスター目次
88472
5.4
3
地質学会とは
42258
2.6
4
出版物 目次
14219
0.9
5
ジオパーク 目次
12269
0.7
6
Q&A 目次
11639
0.7
7
Q&A 地質全般
10511
0.6
8
会長選挙資料
10242
0.6
9
会員入り口
8568
0.6
10
ニュース
7923
0.5
リニューアル以降に最もアクセスされたページと、また検索サービス(Yahoo!、Googleなど)からどのような検索語で導かれて来たのかを図3に示します。アクセス1位はトップページで、検索語トップは「日本地質学会、地質学会など」学会名関連語でした。学会名が検索語トップになっていますが、これはホームページのURLをブックマークせずに、毎回サイト名で検索するのが最近の読書スタイルなので、その影響かもしれません。e-フェンスターやQ&Aといった一般向けコンテンツが上位にあがっています。リニューアル以降のアクセスの急上昇は、やはり一般読者が増えているからと推測できます。また、ページランキングおよび検索語ランキングでもジオパークが上位に入っていることは注目に値します。
また特筆すべき点として、上位10ページの総ページビューが全体に占める割合が非常に少ないことが挙げられます。1位のトップページでも全体の6.5%にすぎず、10位までの総計でも全体の19%にすぎません。つまり特定の人気コンテンツが全体のアクセスを引っ張るのではなく、各ページが少しずつ稼いだ結果としてトータルのアクセスが急増していることを意味します。
まとめ
地質学会ホームページは外部向けメディアとなるためにリニューアルされ、急激にアクセス数を伸ばしています。今年度は50万人・200万ページビューが見込まれます。アクセス急増は一般読者から様々なページが広く読まれた結果と推測されます。今後も高いアクセス数を維持するためには、幅広い分野のページの充実が望まれます。会員皆様の情報発信プラットフォームとしてどしどしご活用下さい。
広報委員長 坂口有人
No.041 2008/09/2 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.041 2008/09/02 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
<秋田大会関連ニュース>
【1】地質災害現地報告会 開催
【2】日本学術振興会事業に関する説明会 開催
【3】就職支援プログラム
【4】秋田大会 講演プログラム公開しました
-------------------------------------------------------------------------
【5】スズメバチは2度目にご注意 フィールド体験談
【6】ホームページのアクセス急増中! 年間50万人ペース
【7】新広報誌「ジオルジュ」スタート
【8】9月の博物館イベント情報
-------------------------------------------------------------------------
【9】第33回IGCの環境成果報告会
【10】平成20年度東濃地科学センター地層科学研究 情報・意見交換会
【11】地質マンガ「生痕」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】地質災害現地報告会 開催
──────────────────────────────────
5月の中国四川大地震,6月の岩手・宮城内陸地震をはじめとして今年は地震が目
立つ年となっております.特に後者の地震は地質学会を開催する秋田県の隣県で
発生したもので地元の関心も高いと思われます.日本地質学会では,四川大地震,
岩手・宮城内陸地震について現地で調査を行ってきた会員による報告会および一
般発表を下記のように開催することにいたしました.
(日本地質学会地質災害委員会)
■プログラム(暫定版)
1.2008年四川大地震について
現地報告 林愛明 (静岡大)
2.2008年岩手・宮城内陸地震について
地質学的背景 佐藤比呂志(東京大地震研)
地下水と地震 大槻憲四郎(東北大)
地表断層 越谷信(岩手大)
地盤災害など 大場司・林信太郎(秋田大)ほか
福塚康三郎(八千代エンジニヤリング)・金折裕司(山口
大)ほか
天野一男(茨城大)ほか
川辺孝幸(山形大)ほか
■一般発表
「応用地質学一般」セッションの中でサブセッションとして7編(口頭4編,ポス
ター発表3編)まとめて以下の通り行われます.
口頭発表:9月22日(月)午後2時30分〜3時30分
ポスター発表:9月22日(月)午後1時〜2時
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】日本学術振興会事業に関する説明会(日本地質学会・鉱物科学会 共催)
──────────────────────────────────
日時 9月21日(日)17:00-18:30
場所 合同セッション会場2-101
演題「科学研究費補助金制度について −審査システムを中心として−」
演者 独立行政法人日本学術振興会研究事業部研究助成第一課長 岡本和久氏
そのほか,学術システムセンター研究員の榎並正樹氏(名古屋大学大学院教授)に
よるシステムセンターの紹介も予定しています.
科研費の選考システム,学振特別研究員等の説明がありますので,申請等に関わ
る方はぜひご参加ください.
なお,講演者の都合のため,17時以降のセッションや18時より始まる夜間小集会
と重なることをお詫びいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】就職支援プログラム
──────────────────────────────────
日時:2008年9月21日(日)14:00〜
場所:秋田大学VBL・総合研究棟 2Fポスター会場
内容:主催者等 挨拶・紹介、参加各社による数分のプレゼンテーション、参加
各社の個別説明会
参加対象:秋田大会に参加する学生・院生および大学教官等の会員・秋田大学の学
生・院生および教官等
参加申し込み:事前の申し込みは不要です.
参加費:無料
参加企業 (株)日さく 北信越支社・応用地質(株)・明治コンサルタント(
株)・太平洋セメント(株) ジーエスアイ(株)・国際航業(株)など
学生,院生ならびに教員のかたがたの多数のご参加をお待ちしています!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】秋田大会 講演プログラム公開しました
──────────────────────────────────
詳しくは、秋田大会HPをご覧下さい。
http://www.geosociety.jp/science/content0014.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】コラム:スズメバチは2度目にご注意
──────────────────────────────────
鳥海光弘(東大新領域、JAMSTEC)
著者の研究室では毎年7月末から8月はじめにかけていろいろな大学の友人らと
四国、中国、九州の変成岩巡検をおこなっている。ことしは7月30日から8月
3日まで九州の天草と長崎変成岩の巡検を行った。この際貴重な経験をしたので
ご報告する。8月1日2時ごろ西彼杵半島南部の三重近傍の海岸に出ようと斜面
の藪を約10人ほどで下っていたところ、突然私の肩に激痛が走った。
後ろの宇野君が、「スズメバチがたくさんたかっています」と叫んでいた。振り
向くと4,5匹の5cmほどもあるスズメバチがブーンブーンといいながら肩に
尻尾を立てていた。パニック状態で帽子を取って叩いていてもなかなか逃げない。
かがみ込みながら後退し、胸にたかって刺そうとしている一匹を握りつぶし、腹
いせに足でつぶしつつ藪から脱した。ついで、全員に撤収をたのみ、ほかには誰
も被害にあっていないことでほっとしつつ、これはしばらくするとショック状態
になるかもと思い、至急救急車の手配と今後の予定を北九州博物館の森さんと西
上原君に頼み、救急車で長崎市内の病院へいった。幸いなことにはショック状態
には陥らずに、無事対抗剤を注射し、事なきを得た。
結局、5箇所キイロスズメバチに刺された。6年ほど前に家で巨大なクロスズメ
バチの巣を壊したが、その仕返しをされた思いである。さて、問題はこれ以後で
ある。医者から深刻に注意されたのは、2度目になるときわめて危険であるとの
こと。それはご存知のように抗体が形成されてそれに蜂毒が入ると過剰反応のた
め全身に強いアレルギー反応が起き、ショック状態に陥り、死に至る。これはほ
ぼ10分以内らしい。これを避けるにはスズメバチに刺されないこと、ただし、
他の種類の蜂は多分大丈夫らしい。もうひとつは緊急のアドレナリン自己注射キッ
トを持ち歩くこと。
著者は、大学の保健センターに相談して、近隣の内科病院でエピペンというキッ
トを購入した。8月20日から25日にかけて学生実習のため一週間室戸岬で調
査したときに常備し、安心して実習に当たることができた。ただし、これは緊急
措置であり、かならず救急病院にいかねばならぬらしい。
スズメバチはきわめて攻撃的であり、巣の近隣を通過するときにはしばしば襲う。
そしてこれも知られたことであるが、黒い服や黒髪が目標となること。基本的に
は集団で襲う。一匹で採餌行動のときは襲わないようである。などなどスズメバ
チの習性を野外研究者には知っておく必要があるようだ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質学会ホームページにアクセス集中! 年間50万人ペース!
──────────────────────────────────
昨年9月のホームページリニューアル以降、たいへんアクセス数が伸びてい
ます。年間50万人(200万ページ)という勢いです。おそらく地球科学系で
国内トップクラスのメディアに成長していると言っても過言ではないでしょう。
詳しくは、http://www.geosociety.jp/faq/content0114.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】新広報誌「ジオルジュ」の準備号を秋田で配布
──────────────────────────────────
地質学会が新しく刊行する広報誌の名前が「ジオルジュ」と決まりました。
これはgeology+concierge(コンシェルジュ)の造語です。地質学の魅力や知見を広める案内人として。そしてこれまでにない全く新しいものに成長して欲しいという願いを込めてあります。
皆様からご意見を頂けますよう秋田大会に向け準備号を編集中です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】9月の博物館イベントカレンダー
──────────────────────────────────
今月は連休がたくさんありますので、皆さんお出かけの機会も多いかも。お出かけ
のついでに,ちょっと博物館へ足をのばしてみませんか。もちろん、秋田大会へ参
加の行き帰りにもお立ち寄りください。
今月のイベントは
http://www.geosociety.jp/name/content0024.html でチェック!!
博物館等のみなさまへ
イベントカレンダーに掲載するイベント情報を募集しています。今後、実施を予定され
ている地質関係のイベントがございましたら情報をお寄せください。
詳しくは、http://www.geosociety.jp/name/content0024.html#info
をご覧ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】第33回IGCの環境成果報告会
──────────────────────────────────
「オスロ(ノルウェー)からの道-地球の地質汚染の正しい調査と浄化に向けて-」
The Road from Oslo to Brisbaneを踏まえて、国際地質科学連合(IUGS)環境管
理研究委員会(GEM)は、ポスト・シンポジウム「The Road from Oslo, Norway」
が開催されます。環境科学にかかわる国際性を高める観点からも会員の皆様は是
非ご参加くださるようお願い申し上げます。
国際地質科学連合(IUGS)環境管理研究委員会(GEM)常任理事
日本地質学会環境地質部会長
地質汚染診断士 楡井 久
日時 2008年9月8日 10:00〜15:00
会場 ホテル・プラザ菜の花(千葉市中央区)http://www.plazananohana.com/
参加費 無料
参加対象者 研究者・国際性が求められる地質汚染診断士、国内の各土壌調査資
格者、廃棄物・水質環境事業担当者、環境行政担当者、事業場の環境担当技術者
等
内容
1.日本チームによる地質汚染科学の強化
2.Geo-stratigraphic Investigation Methodの世界的普及と更なる研究推進
3.MGH-2 session では、日本側の参加者が Opening Address, Chair Person,
Oral presentations, Poster presentationsといったように、各立場で活躍され
ました。
また、各委員会への出席といった具合に多忙を極め、日本チームによるすばらし
い世界的貢献を行った総体的姿が、各自で把握できなかったと存じます。次回のB
risbaneにおける34IGCに向けての相互理解を深め、さらに世界貢献をする仲間を
増やす必要があります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】平成20年度東濃地科学センター地層科学研究 情報・意見交換会
──────────────────────────────────
東濃地科学センターでは、当センターが実施する地層科学研究を適正かつ効率
的に進めていくため、研究開発の状況や成果、さらに今後の研究開発の方向性に
ついて、大学、研究機関、企業等の研究者・技術者等に広く紹介し、情報・意見
交換を行うことを目的として、「平成20年度 東濃地科学センター地層科学研究
情報・意見交換会」を下記の通り開催します。
日程 平成20年10月16日(木) 10:30〜17:00
「平成20年度 東濃地科学センター 地層科学研究 情報・意見交換会」
10月17日(金) 10:00〜12:00
「瑞浪超深地層研究所 深度200m水平坑道見学会」
場所 瑞浪市地域交流センター「ときわ」
プログラム・参加申込はこちらから
(参加申込締切:9月26日(金))
http://www.jaea.go.jp/04/tono/topics/topics0808_1/0808_1.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】地質マンガ 「生痕」
──────────────────────────────────
地質マンガ「生痕」作:川村喜一郎・金松敏也 画:key
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/faq/content0113.html
──────────────────────────────────
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質マンガ 調査日和
地質マンガ
戻る|次へ
あなたのアイデアがマンガになります!
例えば次のような文章で投稿されたものがこんなマンガに清書されます。
■ 投稿された原作
■ 完成品
「地質学者の彼氏を持つと」
1.今日は二人でお買いもの。久しぶりの銀座デート♪
2.二人同時にショーウィンドウを指さして「あっ!」
3.女「ねーねーこの服すごくかわいい!値段もそんなに高くないし」
4.男、壁にはりついて「うぉー大理石の中にアンモナイトが」
女、呆れて「そっちかい…」
地質学会のメールマガジンで連載中の「地質マンガ」は
みなさま(原作)+イラストレータKeyさん(画)
により作られています。地質の魅力を伝える作品を募集しています。現在ストックゼロで即時掲載の状態です。ゆくゆくは英語化して世界の地質学を席巻する予定です!?どうぞご協力をお願い致します。いけてる作品をぜひ!
投稿はこちらから
No.042 2008/09/16 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.042 2008/09/16 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
<秋田大会関連ニュース>
【1】大会プレスリリース
【2】口頭発表講演データ取り扱いについて 演者はご注意を!
【3】秋田大会:一部会場の変更について
【4】普及事業・就職支援プログラムのご案内
-------------------------------------------------------------------------
【5】専門部会への登録のお願い
【6】地学オリンピック 日本は銀と銅メダル! ぱちぱちぱち
【7】地質の日のポスター・ロゴ募集
-------------------------------------------------------------------------
【8】学術会議提言「新しい理工系大学院博士後期課程の構築に向けて−科学・技術
を担うべき若い世代のために−」
【9】地質マンガ「調査日和」
【10】スズメバチは2度目にご注意 フィールド体験談
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】大会プレスリリース
──────────────────────────────────
第115 年学術大会(秋田大会)関連のシンポジウム、報告会、トピックスの
プレスリリースが行われました。
詳しくは、、
http://www.geosociety.jp/engineer/content0007.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】口頭発表講演データ取り扱いについて
──────────────────────────────────
セッションの講演データは、主催者側の学会のやり方で取り扱うことになります
ので,講演者の皆様は、その旨ご了解下さい。とくに鉱物科学会主催の合同セッ
ション( 該当セッション:「岩石・鉱物・鉱床一般」)で講演される地質学会
会員の方は、ご注意下さい。
●地質学会主催のセッション
基本的に半日前(午前の場合は前日午後から)からセッション開始30分前まで
試写室(大学会館2F)でデータを受付けます。
なお、9/20(初日)午前中の口頭発表で使用するファイルのについては、
試写室にて[9月19日16:00-17:00、9月20日8:00-8:30]で受付けます。
余裕を持って、講演前にあらかじめご対応頂きますようお願いいたします。
●鉱物科学会主催の合同セッション
該当セッション:「岩石・鉱物・鉱床学一般」
セッション前に直接会場に行って、設置してあるPCにデータを入れるか,自分
のパソコンをつなぎ替えることになります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】秋田大会:一部会場の変更について
──────────────────────────────────
会場準備の都合により、プログラムでお知らせしておりました一部会場が下記の
通り変更となります。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、当日はお間違いの
ないよう会場にお越し下さい。
●就職支援プログラム:VBL・総合研究棟 2Fポスター会場(9/20、14時)
●夜間小集会「南海トラフ地震発生帯掘削」:般2-103号室(9/21、18時)
●書籍等販売コーナー:般1-208
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】普及事業・就職支援プログラムのご案内
──────────────────────────────────
多くの皆様のご参加をお待ちしています!
<普及事業>
■地質情報展2008あきた−発見・体験!地球からのおくりもの−
(注意:開催期間が学術大会とは一部異なります)
9月19日(金)〜21日(日)9:00〜17:00 (入場無料)
会場:秋田市民交流プラザ「ALVE」1階「きらめき広場」
■市民講演会
「大地の成り立ちと人びとの生活・歴史—男鹿半島・大潟村・豊川油田をジオパークに」
9月20日(土)13:00〜15:00(入場無料)
会場:秋田大学手形キャンパス 教育文化学部3号館大講義室
■小さなEarth Scientistのつどい〜第6回小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜
9月21日(日) 9:00〜15:00
会場:日本地質学会年会ポスター会場(秋田大学)
<就職支援プログラム>
就職に関心のある学生・若手研究者集まれ!
就職を希望する学生,若手研究者と民間企業・団体,研究機関等との情報交換を
目的として,昨年度から始まった新しい取り組みのひとつで,各企業等からのブー
ス出展と説明会形式の紹介プレゼンテーションに参加していただくプログラムで
す.
9月21日(日)14:00〜 入場無料
場所:秋田大学VBL・総合研究棟 2Fポスター会場(注意:会場が変更になりました!)
秋田大会HPはこちら↓
http://www.geosociety.jp/science/content0014.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】専門部会への登録のお願い
──────────────────────────────────
地質学会には下記の13の専門部会があります.その活動は部会によって様々
ですが,年会の折にランチョンの開催,行事委員会に部会代表委員を出して
年会プ ログラムの編成,部会として各賞の推薦なども行っています.また,
各部会のメーリングリストでは,より専門性の高い議論や,シンポジウム・
巡検案内などの 様々な情報がタイムリーに交換されています.今後は,専門
的な学術活動を担う組織としてさらなる充実が期待されています.
会員情報の変更がネットで可能になり,専門部会への登録情報の確認や更新
もできるようになりました.今までも会員の皆様へ部会への登録をよびかけ
てきましたが,名簿やメーリングリストが整備されていないなどの状況があ
り,取り組みが遅れ気味になっておりました.これを機会に会員の皆様が専
門部会の活動に関心を持ち,積極的に参加されるようお願いいたします.
■ 現在活動中の専門部会は以下の13です.
岩石部会
層序部会
第四紀地質部会
海洋地質部会
情報地質部会
構造地質部会
古生物部会
環境地質部会
堆積地質部会
現行地質過程部会
応用地質部会
火山部会
地域地質部会
■ 各専門部会の紹介は,こちら
http://www.geosociety.jp/outline/content0018.html
■ 会員ページへのログインは,こちら
(ログインの際には、会員番号からなるIDとパスワードが必要です)
https://www.geosociety.jp/user.php
(日本地質学会理事会 担当理事 藤本光一郎)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】国際地学オリンピック 日本は銀と銅メダル! おめでとう
──────────────────────────────────
日本チームは、初めてのオリンピック参加にもかかわらず、銀メダル3個、
銅メダル1個の素晴らしい成績でした。
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/name/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】地質の日のポスター・ロゴ募集
──────────────────────────────────
地質の日事業推進委員会
委員長 中尾征三
1. 地質の日のポスター・ロゴ募集の趣旨
「地 質の日」は、明治9年(1876) 5月10日に日本で初めて広域の地質図(北海道)
が作成された日にちなみ、2007年3月13日に地質に関係した学会・機関が発起人と
なって定められた記念日です(日本記念日協会登録済み)。地質の日には、人々
の安全・安心で豊かな暮らしのために重要である「地質」への興味と理解を拡大
する事への期待が込められています。
この「地質の日」を盛り上げるため、本年5月10日には、第1回「地質の日」事業
が全国で盛大に行われ、多くの方の参加を得ることができました.
地質の日事業推進委員会では、2009年5月10日を中心に、第2回「地質の日」事業
として全国で数多くのイベントを行います.このため、第2回「地質の日」事業な
いしそれ以降に使用するポスターとロゴを募集します.条件は以下の通りです.
数多くの応募をお待ちしています.
2. 応募要項
1) 応募資格:どなたでも応募できます.関係学会・機関構成員に限りませ
ん.
2) 応募点数:点数の規定はありません.個人、グループで何点でも応募で
きます.
3) サイズ:ポスターはA2版以上で印刷されることを想定してデザインして
ください.ただし、審査の際に必ずしも大きな紙の作品または、大きなサイズの
ファイルを送っていただく必要はありません.A4サイズを目安にして作成してい
ただいてけっこうです。ロゴについてはバナーとしても利用されることを想定し
てください。
4) 作品は他の機関などに投稿あるいは公表していないオリジナル作品に限
ります。Web等に掲載されることを考えて、著作権法の規定を著者の責任で守って
ください。
5) 採用された作品の著作権は著者に帰属するものとします。ただし、「地
質の日」事業の目的に合致している使用法については、あらゆる二次利用を含め
て、著者は著作財産権、著作人格権を行使しないこととします。
6) 採用された作品のデザインを修正して使用することがあります。
7) 応募された作品(紙、データ)の返却は行いません。データの場合、応
募者の責任で事前にバックアップ等をとることをお勧めします。
8) また当募集において得た個人情報はこの募集の目的以外には使用いたし
ません。
3. 応募方法
手書き、印刷等の紙作品については、下記の宛先にお送りください。
データの場合、PDFもしくはJPEGなどの一般的な画像ファイルとして(ただしファ
イルサイズが2MBを超えない範囲を目安)、地質の日事業推進委員会事務局に電子
メールで送ってください。宛先:geologyday-jimu@m.aist.go.jp、subjectは「ポ
スター応募」ないし「ロゴ応募」としてください。電子メールで送れないサイズ
のファイルである場合は、別途CD-ROMにて下記の宛先に送付をお願いします。な
お、採用された場合、作品のオリジナルファイル(tiff、bmp、psd形式等が好まし
い)は別途送っていただきます。
作品の趣旨を簡単に説明する文章を添えていただくと良いと思います。
宛先:〒305-8567 茨城県つくば市東1-1-1 中央第7 産総研地質調査総合セン
ター内「地質の日」事業推進委員会事務局 宛
4. 締め切り 2008年10月20日(月)、17:00必着
5. 賞品等
採用作品提供者には、賞状と記念品を進呈します。また「地質の日」Webサイト、
並びに地質の日事業推進委員会加盟学会・機関の広報誌等に公表し、その栄誉を
称えます。
6. 審査方法
応募作品の中から「地質の日」事業推進委員会(委員長:中尾征三)で決定しま
す。なお、また送付されたデジタル作品に対して、追加のデータの送付をお願い
することがあります。
審査結果は地質の日事業推進委員会Webサイトで公表し、事業推進委員会加盟学会・
機関を通じても公表いたします。
7. その他
全ての問い合わせは、「地質の日」事業推進委員会事務局 (産総研地質調査総合
センター、担当:原、斎藤) にお願いいたします。
〒305-8567 茨城県つくば市東1-1-1 中央第7
TEL:029-861-9122 FAX:029-861-3672
E-mail:geologyday-jimu@m.aist.go.jp
http://www.gsj.jp/geologyday/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】学術会議提言「新しい理工系大学院博士後期課程の構築に向けて
−科学・技術を担うべき若い世代のために−」
──────────────────────────────────
我が国の未来の科学・技術を牽引する役割を果たすべき博士号取得者の
育成に関して、我が国の現状は、理工系大学院博士(後期)課程への進学
者の減少、ポスドク研究者の就職問題、大学院教育の国際競争力への不安
などの課題が山積し、急速に危機的ともいえる状況に陥りつつあります。
そこで、大学院博士課程の新しい理念と制度の下に、博士課程の教育と
研究の体制とそれを取り巻く環境を改革すべく、大学、政府、及び産業界
など社会の各関係部門に向けて、以下の提言を行いました。
(1)大学は、育成すべき人材像を明確に示しつつ、新たな時代に相応しい
博士号取得者の育成を構想するべきである。
(2)国際的な競争力を持つ、多彩で魅力ある大学院教育体制を構築すべき
である。
(3)大学院の学生定員制度の柔軟化を図るべきである。
・・・・etc
提言全文は、日本学術会議HPの以下のURLで御覧いただけます。
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/index.html
【お問い合わせ先】
日本学術会議事務局参事官(審議第二担当)付
Tel:03-3403-1056 Fax:03-3403-1640 E-mail:s253@scj.go.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】地質マンガ 「調査日和」
──────────────────────────────────
「調査日和」作:清川昌一 画:Key
詳しくは、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0116.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】スズメバチは2度目にご注意 フィールド体験談
──────────────────────────────────
鳥海光弘(東大新領域、JAMSTEC)
著者の研究室では毎年7月末から8月はじめにかけていろいろな大学の友人らと
四国、中国、九州の変成岩巡検をおこなっている。ことしは7月30日から8月
3日まで九州の天草と長崎変成岩の巡検を行った。この際貴重な経験をしたので
ご報告する。8月1日2時ごろ西彼杵半島南部の三重近傍の海岸に出ようと斜面
の藪を約10人ほどで下っていたところ、突然私の肩に激痛が走った。
続きは、こちら、、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0115.html
前号ではリンクが切れていました。申し訳ありませんでした。
再掲載させて頂きます(編集部)。
──────────────────────────────────
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.043 2008/09/30 geo-flash(臨時)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.043 2008/09/30 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】名誉会員 「中川久夫先生を偲ぶ会」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】名誉会員 「中川久夫先生を偲ぶ会」のお知らせ
──────────────────────────────────
仙台の夏祭りが始まろうとする8月5日、地質学を信念の拠り所とされ教室の
地質学教育に多大に尽力された中川久夫先生が他界されました。突然の訃報に
接し、教室の同窓一同も大いに驚いた次第です。享年82才でした。
先生の謦咳に接した我々にとって、この訃報は、時を超えた取り留めの無い記憶
を呼び起こしました。在りし日々の追憶を共有し、先生が求められた地質学の
研究と教育に思いを馳せ、ここに「中川久夫先生を偲ぶ会」を企画致しました。
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。
日時: 平成20年10月10日(金) 午後5時〜7時
会場: アークホテル仙台 (仙台市青葉区大町2-2-10・旧ワシントンホテル
電話:022-222-2111)
会費: 8000円
参加をご希望される方は、10月6日(月)までに、下記宛にご連絡いただければ幸いです。
FAX番号: 022−795−6634
電話番号・メールアドレス:
中森 亨 022−795−6617 (nakamori@dges.tohoku.ac.jp)
同窓会窓口(木幡)022−795−6635 (kohata@mail.tains.tohoku.ac.jp)
島本昌憲 (東北大学総合学術博物館)
──────────────────────────────────
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質マンガ 巡検初参加
地質マンガ
戻る|次へ
あなたのアイデアがマンガになります!
例えば次のような文章で投稿されたものがこんなマンガに清書されます。
■ 投稿された原作
■ 完成品
「地質学者の彼氏を持つと」
1.今日は二人でお買いもの。久しぶりの銀座デート♪
2.二人同時にショーウィンドウを指さして「あっ!」
3.女「ねーねーこの服すごくかわいい!値段もそんなに高くないし」
4.男、壁にはりついて「うぉー大理石の中にアンモナイトが」
女、呆れて「そっちかい…」
地質学会のメールマガジンで連載中の「地質マンガ」は
みなさま(原作)+イラストレータKeyさん(画)
により作られています。地質の魅力を伝える作品を募集しています。現在ストックゼロで即時掲載の状態です。ゆくゆくは英語化して世界の地質学を席巻する予定です!?どうぞご協力をお願い致します。いけてる作品をぜひ!
投稿はこちらから
MARGINS SEIZE 2008 workshop参加報告
MARGINS SEIZE 2008 workshop参加報告 2008.10.7UP
氏家恒太郎(海洋研究開発機構 地球内部変動研究センター)
MARGINS SEIZE 2008 workshop(以下WS)が2008年9月22日〜9月26日に米国オレゴン州のMt. Hoodにおいて開催された。参加者は米国を中心に80名余り。日本からも6名が参加した。このWSは非常にプロダクティブかつ有意義で、日本の地質学関係者にも多少参考になるかもしれないと感じたので、簡単ではあるが紹介させて頂きたい。
MARGINSとは全米科学財団(NSF)の所有するプログラムで、RCL (Rupturing Continental lithosphere)、S2S (Source-to-Sink)、SEIZE(Seismogenic Zone Experiment)、SubFac(Subduction Factory)の4つに大別される。今回のWSはSEIZEに関連するもので、タイトルは”The next decade of the Seismogenic Zone Experiment”。つまり今後10年間の沈み込み帯における地震発生帯研究のありかたを探り議論する(特に米国にとって)重要なWSである。
SEIZEの重点研究対象地域は、南海トラフと中米コスタリカである。これらはそれぞれ付加型、造構性浸食型沈み込み帯の代表として捉えられており、対照的な造構環境下での地震の特徴を理解するうえで重要である。WSでは、まず南海トラフ、コスタリカにおける研究レビューがなされ、続いて非重点研究対象地域(スマトラ、カスカディアなど)での研究成果が紹介された。そして、これまでの研究成果をふまえたうえで、新たな研究手法・戦略が示された。南海トラフは統合国際深海掘削計画(IODP)のもと深海掘削船“ちきゅう”による掘削が既に成功裏にスタートしており、また日本の充実した地震・測地観測網のもとプレート境界に沿った非火山性微動や付加体内部における超低周波地震など最新の知見が次々と出されている。コスタリカもIODPによる掘削実現に向けて探査・観測が進んでおり、研究進展が著しい。一方、非重点研究対象地域での研究紹介も(WS議論項目に重点研究対象地域の変更・追加の可能性が盛り込まれていたこともあり?)熱のこもった魅力的なものであった。WSの詳細内容・報告は、ホームページ(http://nsf-margins.org/SEIZE/2008/)にそれぞれ掲載済み・掲載予定なので、興味のある方は参考にして頂きたい。ここではWSで印象に残った研究アップデートだけ簡単に紹介しておく。
(1) 南海トラフのような付加型沈み込み帯において、粘土鉱物のスメクタイトからイライトへの変化が地震発生・固着域の上限を規定している、という仮説は崩れ去ったとみてよいであろう。新たな別の要因(例えば間隙水圧減少、セメンテーション・圧力溶解による岩石化など)を提示し、それを検証しつつあるのが現状である。
(2) 南海トラフにおいて、少なくとも浅い深度(〜1 km)では、分岐断層を挟んで応力状態が劇的に変化する(分岐断層陸側は正断層型応力状態に対し海側は横ずれないし逆断層型応力状態)。
(3) コスタリカでは、微小地震・測地学的に求められた固着域の上限深度が走向方向に変化しており、沈み込むプレートの年代の変化とよく対応している。沈み込むプレートからの熱的影響(例えば含水鉱物の脱水深度の変化)が微小地震・固着域の分布を左右しているかもしれない。
(4) 沈み込むプレートの起伏が地震の規模・頻度に影響を与えていそうである。例えば起伏の少ない滑らかなプレートが沈み込むニカラグア沖ではM6.5–N7.5の地震が50-75年間隔で発生するのに対し、海山など起伏に富むプレートが沈み込むコスタリカ中部沖ではM6.5が上限の地震が数年間隔で発生する。
(5) コスタリカでは、固着域の上限側でゆっくり地震や非火山性微動が検出された。
(6) プレート境界先端域に設置・実施されている長期孔内計測において、パルス的な間隙水圧変化が観測され、南海トラフでは超低周波地震と時期的に対応している。
さて、今回は実質3日間、雪を頂くカスケード山脈の素晴らしい眺望のもと、ロッジの中に設置された会場で集中的に議論・意見交換が行われたのであるが、実にinterdisciplinary, interactive, interestなWSであった。規模・参加人数・専門分野のバランスもちょうどいい。今後10年間の米国における地震発生帯研究戦略を知るうえで大変参考になると同時に、ここが足りないと実感・把握することもでき非常に有意義であった。日本列島には、地震発生深度で発達したプレート境界断層・順序外断層、ゆっくり地震や非火山性微動の発生する深度で形成された変成岩、沈み込み帯に衝突・付加した海山が露出しており、地質学的側面から地震発生帯研究を推進していくうえ最適のフィールドである。一方で、回転式高速せん断摩擦試験機、摩擦発熱の地質学的証拠検出、密な地震観測・測地網など優れた技術・手法を兼ね備えている。明らかに日本は地震発生帯研究を推進するうえで恵まれた状況にあるし、そこで日本の地質学が果たす役割は今後益々大きくなると思われる。今回のような多分野の研究者・これからを担う大学院生らが特定の場所に集結して、これまでの研究を総括しつつ、問題点を浮き彫りにして、斬新な研究プランの提示・実行に向けて徹底的に議論を重ねていくWSがもっと日本にあっていいと感じた次第である。
No.044 2008/10/07 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.044 2008/10/07 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】 野外調査において心がけたいこと
【2】コラム:MARGINS SEIZE 2008 workshop参加報告
【3】「地球を救う みんなの知恵」講演会のお知らせ
【4】産総研オープンラボのご案内
【5】10月の博物館イベント情報
【6】第3回国際地学オリンピック台湾大会の国内選抜参加者募集
【7】JST平成21年度地球規模課題対応国際科学技術協力事業研究提案募集
【8】アサヒビール学術振興財団2009年度学術研究助成募集
【9】京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻地質学鉱物学教室教員公募
【10】公立大学法人首都大学東京 教員募集要項
【11】「日本石紀行」会員割引のお知らせ
【12】地質マンガ「巡検初参加」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 野外調査において心がけたいこと
──────────────────────────────────
秋風が心地好い季節になりました。会員の皆様も調査や実習等で野外に出ら
れる機会も多いことと思います。ベテランの皆様は、今更と思われるかもしれ
ませんが、あらためて国立・国定公園や史跡・名勝・天然記念物、あるいは一
般的な露頭における調査上の注意を喚起させて頂きます。地質学会員が模範と
なって、節度ある行動を示していただければ幸いです。
■ 国立・国定公園、並びに自治体の条例で保護が指定されている地域等で調査
する場合は、事前の許可が必要です。まず、調査を行う地域がどのような保
護地区を含んでいるか、事前に確認しておきましょう。特別保護区などの範
囲は、自治体や環境省等のHPで確認できる場合が多いですし、必要な手続
きもオンラインで申請できますので、必ず手続きをしてから現地に入るよう
にしましょう。
<国立公園特別地域内における行為の許可>
■ 史跡・名勝・天然記念物においては、文化庁や地元自治体などへの必要な
手続きなしには露頭をハンマーでたたいて岩石試料を採取するなどの破壊を伴
う調査はもちろん、転石の採取もできません。やむを得ず研究上必要な場合は
許可申請の手続きを行い、必要最低限の採取に留めることが重要です。許可を
得ておくことによって、その成果を公表することも可能になります(その際に
は謝辞に許可のことを触れておくとよいでしょう)。
■ 世界遺産については、世界遺産保護条約によって保護・保全が定められてい
ますので、国の保護計画の不備が認められた場合は登録が抹消されることもあ
ります。高い保全意識を持って慎重に行動する必要があります。
これらの地域の巡検の際にはハンマーを持ち歩かないなど「李下に冠を正さず」
といった節度ある態度を心がけましょう。
法的な保護が為されていない貴重な露頭においても、同様に露頭の保護を心
がけたいものです。不必要なサンプルの採取、削剥はもちろん慎み、あらかじ
め地権者や地元自治体への連絡などを行っておくことにより、トラブルを未然
に防げます。コア抜きは坑が大変目立ち、また半永久的に残りますので、場所
をよく選ぶよう心がけることが大切です。また、露頭面にペイントやマーカー
で記号等を派手に書き込む行為も、その後きれいに消していくようなマナーが
必要です。
このほか些細なことのようですが、地元の方々と良好な関係を保つというこ
とは、思いのほか重要なことです。貴重な露頭が、将来はジオパークの中の有
力なジオサイトになるかもしれません。
地球を愛する者として、社会から地質調査の有用性や公益性が認められ、末
永く地質調査を行える環境作りには、上記のような調査に当たっての心がけが
必須ですので、地球科学分野の研究者の全員の協力でこれを進めましょう。
(日本地質学会 理事会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】コラム:MARGINS SEIZE 2008 workshop参加報告
──────────────────────────────────
氏家恒太郎(海洋研究開発機構 地球内部変動研究センター)
MARGINS SEIZE 2008 workshop(以下WS)が2008年9月22日〜26日に米国オレゴ
ン州のMt. Hoodにおいて開催された。参加者は米国を中心に80名余り。日本から
も6名が参加した。このWSは非常にプロダクティブかつ有意義で、日本の地質学関
係者にも多少参考になるかもしれないと感じたので、簡単ではあるが紹介させて
頂きたい。
続きはこちら、、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0121.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】「地球を救う みんなの知恵」講演会のお知らせ
──────────────────────────────────
日本学術会議・国際惑星地球年日本(IYPE日本)主催の公開講演会、
「地球を救う みんなの知恵」が、下記の要領で開催されます。小中学生を
対象にしたやさしい講演会で、地球環境問題や地震・津波に関する講演が行
われます。
日時:平成20年11月2日(日)、13:00-15:40
場所:日本科学未来館 7F みらいCANホール (参加無料)
プログラム
ご挨拶・・・小玉 喜三郎(IYPE日本 会長)
第1部
地球深部探査船「ちきゅう」でみつけた地球の姿
高校生による「ちきゅう」乗船体験レポート
第2部
地球はどうなっているの?
「海からさぐる地球の歴史」・・・平 朝彦 (海洋研究開発機構 理事)
「南極で氷を掘って過去の地球環境変動をさぐる」
・・・東 久美子 (国立極地研究所 准教授)
「地球はこれからどうなるの? 人間が変えつつある地球環境」
・・・江守 正多 (国立環境研究所 室長)
第3部
地震を知り、地震にそなえる
人形劇 「稲むらの火」・・・人形劇団 わにこ
「耐震人形劇」・・・幸田 眞希(聖徳大学短期大学部 教授)
「地震・津波の発生のしくみと予測」
・・・佐竹 健治 (東京大学地震研究所 教授;
産業技術総合研究所 上席研究員)
【参加申し込み】
講演会名、お名前、連絡先をメイル(sympo@scj.go.jp)、あるいは
FAX (03-3403-6224)にて、日本学術会議事務局企画課公開講演会担当
までお申し込みください。
詳細は、
http://www.scj.go.jp/ja/event/index.html あるいは、
http://www.gsj.jp/iype/be/doc/BE081102A.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】産総研オープンラボのご案内
──────────────────────────────────
産総研では、産業界、大学、公的研究機関等の皆様向けの催しとして「産総研オー
プンラボ」(10/20-21;於 産総研つくばセンター)を開催することとなりました。
産総研オープンラボでは、研究者自らが装置・設備の紹介を含めながら研究成果
の内容をご説明し、議論の場を設けます。また、個別の具体的な連携のご相談や、
ご質問にもお答えいたします。地質分野からは29件の出展のほか,「地質情報の
新たな利活用」と題した技術講演会を催します。
なお、産総研オープンラボの参加は無料ですが、事前の登録が必要です。ご来
場登録は下記ウェブサイトにて受け付けております。
ご参加を心よりお待ちしております。
産総研オープンラボ・ウェブサイト:http://www.aist-openlab.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】 10月の博物館イベント情報
──────────────────────────────────
博物館では、来週の連休や週末を中心に特別展示や体験イベントを多数用意して、
みなさまのお越しをお待ちしています。調査のついでにもぜひお立ち寄りください。
今月のイベントは↓↓↓
http://www.geosociety.jp/name/content0026.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】第3回国際地学オリンピック台湾大会の国内選抜参加者募集
──────────────────────────────────
国際地学オリンピック日本委員会から 2009年9月14日〜22日に台湾で
おこなわれる第3回国際地学オリンピックの国内予選(第1回日本地学
オリンピック)の参加者募集が10月1日より始まりました。
多数の生徒の参加が今後の地学オリンピックの推進の鍵となりますので、
ご支援よろしくお願いいたします。
国内選抜大会(第1回日本地学オリンピック大会)
募集期間 2008年10月1日(水)〜12月10日(水)
対象者;国際大会に参加可能な高校生・中学3年生および相当学年の生徒
日時;2008年12月21日(日曜日)2時間(10:00〜12:00予定)
問い合わせ先
日本地球惑星科学連合気付 国際地学オリンピック日本委員会事務局
詳しくは、http://www.jeso.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】JST平成21年度地球規模課題対応国際科学技術協力事業研究提案募集
──────────────────────────────────
事業の趣旨
本事業は,開発途上国等(途上国等)のニーズを基に,地球規模課題を対象とし,
将来的な社会実装の構想を有する国際共同研究を政府開発援助(ODA)と連携
して推進し,地球規模課題の解決及び科学技術水準の向上につながる新たな知見
を獲得することを目的としています.また,その国際共同研究を通じて途上国等
の自立的研究開発能力の向上と課題解決に資する持続的活動体制の構築を図りま
す.
本年9-11月の間,環境・エネルギー,防災,感染分野における地球規模課題の解
決に資する国際共同研究「地球規模課題対応国際科学技術協力事業」の平成21年
度研究提案を募集いたします.
事業ホームページをご参照下さい.
締切 平成20年11月19日(水)
【お問い合わせ先】
独立行政法人 科学技術振興機構
国際部 地球規模課題国際協力室
詳しくは,http://www.jst.go.jp/global/koubo.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】アサヒビール学術振興財団2009年度学術研究助成募集
──────────────────────────────────
助成対象
日本の大学・研究所等に所属する研究者,または学識があると認められる個人・
グループで主として食にかかわる生活科学,生活文化(人文・社会科学分野)及
び生活環境科学に関する研究を計画し,完成後に優れた成果が期待できるもの.
募集期間
2008年10月1日(水)〜11月6日(木) [消印有効]
本件関する問い合わせ,申請書申込み,応募先は下記までお願いします.
〒130-8602 東京都墨田区吾妻橋1-23-1
財団法人アサヒビール学術振興財団
http://www.asahibeer.co.jp/csr/philanthropy/ab-academic/boshu.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻地質学鉱物学教室教員公募
──────────────────────────────────
採用職名: 教授
所属講座: 地球生物圏史講座
期待する研究・教育分野:生物圏を含む地球表層の成り立ちや進化・変動に関す
る研究をフィールド
応募締切:2008 年10 月31 日(金)必着
詳しくは、
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news_data/b/b5/news3/2008/081031_1.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公立大学法人首都大学東京 教員募集要項
──────────────────────────────────
募集職位:教授又は准教授 1名
所属及び勤務地:都市環境学部 地理環境コース
専門分野:自然地理学
担当予定科目:学部・大学院における自然地理学関連の科目
提出期限:平成20年 11月14 日(金)必着
詳しくは、
http://www.tmu.ac.jp/kikaku/employ/tmu_teacher.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】「日本石紀行」会員割引のお知らせ
──────────────────────────────────
国連提唱の国際惑星地球年IYPEへのささやかな貢献(ロゴマーク使用)として、ま
た尾池和夫(京大総長・日本ジオパーク委員会委員長)氏のご推薦(帯)をいた
だき以下の書籍を刊行しました。
「日本石紀行」(加藤碵一・須田郡司)みみずく舎、232p.2200円
東京都新宿区百人町1-22-23 新宿ノモスビル4F
電話 03-5330-2441 ファックス03-5389-6452
なお、地質学会会員の方には以下のメールアドレスでお申し込みいただければ、
著者割引(2割引)かつ送料無料で配本いたします。
(izumi@mimizukusha.co.jp)
内容は、加藤(産総研フェロー)と石の写真家須田との共同で、各地のさまざま
な石や岩塊を
1. 常世から現世へ石と道連れ、2. 神宿り,神籠もるところ、3. ありがたき
仏のおわすところ 4. 恐れ戦く怪力乱神、5. 人の世の移り変わりと縁、
6. 進化の流れに沿って 7. 海陸の王である巨獣、8. 弱肉強食の猛獣の世界、
9. 人類の良き友—ペットや家畜に因んで
写真と文でそれらの俗称、いわれと地質学的見解などをおもしろく順に紹介する
ものです。
ぜひご一読いただき機会あれば他の方々へもご紹介をよろしくおねがいいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】地質マンガ 「巡検初参加」
──────────────────────────────────
「巡検初参加」
作:本郷宙軌 画:Key
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/faq/content0120.html
──────────────────────────────────
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.045 2008/10/21 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.045 2008/10/21 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】日本地質学会2008年臨時総会(11/30)
【2】世界ジオパークへの国内推薦決定!!
【3】【岩手・宮城内陸地震】
地理情報システムを用いた地震災害とカルデラ構造との関連の検討
【4】平成21年度役員ならびに代議員選挙の実施(告示)延期について
【5】2009年岡山大会トピックセッション,シンポジウム募集
【6】2009年度日本地質学会各賞候補者募集
【7】2009年度院生割引申請受付開始! 院生注目!
-------------------------------------------------------
【8】日本地方地質誌 3. 関東地方 会員特別割引販売のお知らせ
【9】秋田大会見学旅行案内書,残部あります.
【10】深田研談話会:第112回(現地)・第113回(大阪)のご案内
【11】第7回地球システム・地球進化ニューイヤースクール NYS-7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 日本地質学会2008年臨時総会(11/30)
──────────────────────────────────
2008年11月30日(日)14:00〜16:00
会場 学士会館 (210会議室)
本学会は公益法人化を目指して準備を進めているところです.準備作業等につき
ましては9月の秋田年会前の評議員会にて基本的に了承いただき,12月1日に予定
している一般社団法人日本地質学会の登記に向けた諸作業を,理事会・法人化作
業委員会では進めております.
このたび,一般社団法人日本地質学会の登記にかかる定款案,関連諸規則,な
らびに代議員と役員の選挙に係る手続き等について,最終的に総会の場で承認い
ただくために,別紙の通り臨時総会を招集いたします.現在の任意団体の日本地
質学会が公益法人となる第1段階を迎えるに当たり,この総会ならびに引き続き予
定いたします懇親会には,多くの代議員並びに会員の方のご出席を希望します.
(2008年10月6日 会長 宮下純夫)
議事次第は、会員のページをご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】世界ジオパークへの国内推薦決定!!
──────────────────────────────────
日本ジオパーク委員会は、日本から初めてユネスコが支援する世界ジオパーク
ネットワークに加盟申請を行う地域を「洞爺湖有珠山」「糸魚川」「島原半島」
にすると発表しました。
詳しくは、
http://www.gsj.jp/jgc/pressrelease.html
日本地質学会ジオパーク支援委員会
http://www.geosociety.jp/geopark/content0017.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】【岩手・宮城内陸地震】
地理情報システムを用いた地震災害とカルデラ構造との関連の検討
──────────────────────────────────
布原啓史(株)テクノ長谷),吉田武義,山田亮一(東北大・理)
筆者らは,産学官連携プロジェクトとして,自然由来の土壌汚染や水質汚濁の原
因解明に資する目的で,デジタル化された地質図上に,様々な地質・地形・地圏
環境に関する情報を統合化しつつある.1),2)これまでに公表した具体的なコン
テンツとして,東北地方における地すべり地形,活断層分布及び河川の重金属バッ
クグランドなど,また,全国レベルとして,鉱山や変質帯分布図,独自の土壌や
岩石分析値などがある.今般,これらを土台として,東北地方のカルデラ構造3),
4)分布および大規模斜面崩壊地点分布などを統合し,今回の地震災害と地質構造
との関係を検討した.
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/hazard/content0035.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】平成21年度役員ならびに代議員選挙の実施(告示)延期について
──────────────────────────────────
会則第48条ならびに選挙細則第5条により来年度の役員並びに代議員選挙の告示を
する時期でありますが,このことに関し会員の皆様にご連絡とお願いを申し上げ
ます.
詳しくは、会員のページをご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2009年岡山大会トピックセッション,シンポジウム募集
──────────────────────────────────
日本地質学会は,西日本支部の支援のもと岡山理科大学ほかにおいて第116年学術
大会(岡山大会)を2009年9月4日(金)〜6日(日)の日程で開催致します.つき
ましては,トピックセッションとシンポジウムの募集を下記の要領で行います.
シンポジウムの募集締切:2008年12月19日(金)
トピックセッションの募集締切:2009年2月13日(金)
詳しくはこちら、、、
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】2009年度日本地質学会各賞候補者募集
──────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして,研究の援助・奨励および研究業績
の表彰を行っています(会則第5条).具体的には,運営細則第11章および各賞選
考に関する規約に,表彰の種別や選考の手続きを定めています.これらにしたが
い,下記の賞の自薦,他薦による候補者を募集いたします.
応募の締め切りは各賞とも,2008年12月25日(木)必着です.
詳しくはこちらから
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】2009年度(2009.4〜2010.3)院生割引申請受付開始!
──────────────────────────────────
日本地質学会では,会費の院生割引制度が設けられています.定収のない院生(
研究生)については,本人の申請により院生割引会費が適用されます.
<注意>毎年更新となりますので,今年度の割引を受けている方で,次年度も該
当する方は改めて申請して下さい(今年3月まで院生(研究生)の方も申請すれ
ば適用).
請求書発行前締切:2008年11月19日(水)
申請書式は、こちらから
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】日本地方地質誌 3. 関東地方 会員特別割引販売のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地質学会編集 日本地方地質誌 <全8巻,函入上製本>
3. 関東地方 592頁,口絵8頁 (10月刊行)
編集委員長:佐藤 正
定価27,300円(税込)を会員特別割引価格24,000円(税・送料込)
申込用紙をHPより、ダウンロードの上、FAXまたは郵送でお申し込み下さい。
詳しくはこちら、、、、
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】秋田大会見学旅行案内書,残部あります.
──────────────────────────────────
2008年秋田大会見学旅行案内書について残部があります.購入をご希望の方は,
お早めに学会事務局までお申し込み下さい.(昨年札幌大会の案内書もわずかで
すが残部があります)
e-mail: main@geosociety.jp
・秋田大会(2008)見学旅行案内書 2500円+送料
・札幌大会(2007)見学旅行案内書 2400円+送料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】深田研談話会:第112回(現地)・第113回(大阪)のご案内
──────────────────────────────────
■第112回深田研談話会(現地)
テーマ:「関東山地東部の黒瀬川帯巡検」
講 師: 久田健一郎 氏(筑波大学大学院准教授)
日 時: 2008年11月15日(土)10:00〜16:00
巡検地: 東京都西多摩郡日の出町水口周辺
参加費: 1,000円(資料代、保険料)現地交通費は自己負担、昼食はご持参下さい。
申込み締切り日: 11月12日(水)
定 員: 30名(定員になり次第締め切ります)
■第113回深田研談話会(大阪)
テーマ:「上町断層 −どこまで判っているのか−」
講 師: 横田 裕 氏(株式会社阪神コンサルタンツ代表取締役社長)
竹村恵二 氏(京都大学大学院教授)
日 時: 2008年11月28日(金) 15:00〜17:00
会 場: マイドームおおさか 8階/第3研修会議室
大阪市中央区本町橋2−5 TEL06-6947-4321
参加費: 無 料
申込み方法: 参加ご希望の方は、E-mailか FAXまたはハガキでお申込み願います。
その際、氏名・所属・連絡先(住所・電話番号)をお知らせ下さい。
●申込み先: 財団法人 深田地質研究所
〒113ー0021 東京都文京区本駒込2ー13ー12
TEL:03-3944-8010 FAX:03-3944-5404
E-mail:fgi@fgi.or.jp
詳しくはこちら
http://www.fgi.or.jp/FGIhomepage/index-j.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】第7回地球システム・地球進化ニューイヤースクール NYS-7
──────────────────────────────────
テーマ: 地球科学をとりまく研究の進化と発展
今回も様々な分野を代表する第一線の研究者に講演していただきます。
毎回好評のEXレクチャーやサイエンスディスカッションを今回も企画しておりま
す。
開催日時: 2009年1月10日(土)-1月11日(日)
開催場所: 国立オリンピック記念青少年総合センター(東京・代々木)
参加費:一律3000円を予定(懇親会費込み)、割引企画を検討中(学生)
受付:2nd circular(10月下旬頃を予定)にて詳細を配信
問い合せ: 井上麻夕里(東大・海洋研) mayuri-inoue@ori.u-tokyo.ac.jp
詳しくは、
http://quartz.ess.sci.osaka-u.ac.jp/~earth21/school/2008/index.html
──────────────────────────────────
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
今号はボランティアイラストレータKEYさん多忙につきマンガはお休みです。
申し訳ありません。
No.046 2008/10/30 geo-flash(臨時)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.046 2008/10/30 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】IODP計画更新に向けたテーマ別国内ワークショップ 参加者募集開始
【2】故 中川久夫 名誉会員を偲ぶ会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 IODP計画更新に向けたテーマ別国内ワークショップ 参加者募集開始
──────────────────────────────────
統合国際深海掘削計画(IODP)では、2001年に作成されたIODP初期科学計画の更
新および2013年以降のIODPサイエンスを考えることを目的として、来年9月にドイ
ツ・ブレーメンにてINVEST会議を開催します。
日本のIODPナショナルオフィスであるJ-DESCでは、これに先駆けて「DomesticINV
EST会議」と称しまして、まずは国内において専門テーマ別に5つのワークショッ
プを開催し、国内コミュニティからボトムアップの意見を集める準備を行ってお
ります。以下の5つのテーマ別ワークショップの参加者を募集します。
【Domestic INVEST テーマ別ワークショップ】
◯Geohazard
対象分野:Seismology, Tectonics and others
日時:12月1日(月)〜3日(水)
◯Earth's Interior
対象分野:Petrology, Geochemistry, Paleomagnetism, Tectonics,Seismology,
etc.
日時:12月5日(金)〜 6日(土)
◯Paleoenvironment
対象分野:Paleoceanography, Paleontology, Sedimentology,Geochemistry and
others
日時:12月4日(木)〜6日(土)
◯Deep Biosphere and Sub-seafloor Aquifer
対象分野:Microbiology, Geochemistry, Hydrogeology and others
日時:12月12日(金)〜13日(土)
◯Technology development
対象分野:Ultra Deep Drilling and Monitoring, and others
日時:12月6日(土)〜7日(日)
募集締切:2008年11月4日(火)17:30 必着
お問い合わせ
J-DESC事務局 : info@j-desc.org
Tel : 045-770-5359 / Fax :045-770-5360
詳しくは、J-DESCのホームページをご確認ください。
http://www.j-desc.org/m3/INVEST_DWSs.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】故 中川久夫 名誉会員を偲ぶ会
──────────────────────────────────
故 中川久夫 名誉会員を偲ぶ会が東京で開催されます。
期 日:平成20年11月14日(金)19:00〜21:00
場 所:虎ノ門パストラル(港区虎ノ門4−1−1) TEL:03-3432-7261
地下鉄日比谷線神谷町駅4b出口から徒歩2分
会 費: 7,000円
なお、出席のご返事は11月11日までに、下記までご連絡くださるよう
お願い致します。(当日の参加も歓迎します)
IGPS在京同窓会 幹事有志
樋口 雄、斎藤 靖二、高嶋 克典、中山 一夫
斎藤 庸、驫木 俊夫、圓入 敦仁
<出席通知先> メールは、CCをつけて両方に送信願います。
e-mailの場合:中山 一夫kazuo.nakayama@japex.co.jp
圓入 敦仁a.ennyu@itochuoil.co.jp
FAXの場合: 03(6268)7303 中山(石油資源開発)まで
──────────────────────────────────
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
手動式ポイントカウンターとエクセルの計数マクロの紹介
岩石学、火山学、堆積学などの分野では、岩石薄片の顕微鏡観察により、鉱物(斑晶)、ガラス(石基)、気泡、砕屑粒子などの量比をポイントカウンティングにより計測する作業が普通に行われる.従来は英国Swift社製のポイントカウンターが世界各国で使われていたが、これは高価で(1式60万円程度)、自動的なステージ移動はX方向片道のみ、しかも数年前の同社の倒産により新製品の入手が困難になった.この状況に対応するため、日本では2005年に茨城大学の田切美智雄先生を中心に、パソコンと接続してX・Y方向のステージ移動を自動で行う装置が開発され、Swift社製品と同程度の価格で注文生産されている(有限会社アクティブコンピュータ(代表取締役 鈴木宏治氏)製、製品名:Micro Topper 偏光顕微鏡用X-Yステージコントロールシステムhttp://blog.livedoor.jp:80/active_computer/archives/50946615.html).
メイジテクノ社製のポイントカウンターつきメカニカルステージを偏光顕微鏡に取り付けた様子.手前の0.1と書かれた黒いつまみを付属の他のつまみと交換すれば、0.2, 0.5 mm刻み及び無段階(連続移動)に変更できる.岩石薄片の大きさは48 x 28 mm.
しかし、昔から顕微鏡取り付け用の手動式ポイントカウンターは存在しており、現在もメイジテクノ社から販売されている(製品番号MA954, 製品名 ポイントカウンター付メカニカルステージ.2008年の定価は121,000円)(第1図).この製品は手でつまみを回すと、クリックの感覚により、X・Y方向に0.1, 0.2, 0.5 mm刻みに一定間隔で(または無段階に)動かすことができ、48 x 28 mmの岩石薄片や生物用の細長い薄片を載せることができる.この製品はメイジテクノ社製の顕微鏡にはそのまま取り付け可能だが、他のメーカーの顕微鏡の場合はステージの下面に出ている2つの留めピンの位置が合わない.しかし、2つの留めピンをネジ回しで外せば、1つの留めネジだけで取り付けることも可能であり、実用上はこれで差し支えない.ただし、顕微鏡の機種によってはネジ径(4 mm)が合わないものもあるので、購入前にチェックが必要である.手動式の利点は反対方向のステップ移動も可能なことで、X方向に薄片の端まで数えたら、少しY方向にずらして逆向き(−X方向)に折り返して(または渦巻き式に)計数することができ、一方向にしかステップ移動ができない自動式に比べて計数時間を短縮できる.もちろん自動式の方が作業は楽だが、経済性と能率を重視し労力を惜しまないに人は手動式も有用である.
パソコンを用いた計数プログラムは、BASICなどのプログラム言語を知っている人なら簡単に組むことができるが、私はマイクロソフト社の表計算ソフト「Excel」を用いた12成分カウンターのマクロ(Visual BASICプログラム)を作成してみた.このマクロはWindowsでもMacでも問題なく動く.このマクロはキーボードのM, J, K, L, U, I, O, P, 7, 8, 9, 0の12個の計数キーのいずれかを押すと、それぞれのキーに対応するエクセルのセルの値が1ずつ増加するもので、全ての計数キーは右手だけで操作できるので左手は同時にステージ移動操作ができ、かなり早打ちしても正確に計数できる.常に総数も表示され、任意の時点でCキーを押せば%値が表示され(もう一度押せば%値は消える)、間違えた場合はXキーを押してからいずれかの計数キーを押せばその値が1だけ減少するようになっている.1成分を除外した%値(Vキー)や全数消去(Zキー)機能もついている.エクセルの表なので、計数結果はそのまま別のシートあるいは他のワープロソフトなどにコピーできる.
12成分ポイントカウンター用エクセル・マクロの画面表示(石渡作成).計数中なのでいくつかの「カウント」欄に数値が入っている.「成分」欄には任意の鉱物名を記入できる.Cキーを押すと「%」欄に%値が表示される.詳しくは本文と図中の説明を参照.
この12成分ポイントカウンター用マクロつきエクセルファイルは地質学会のホームページ(HP)からダウンロードできる(ダウンロードとオンラインマニュアルはこちら).これを開くと、通常のエクセル画面に計数表と注意書きが表示され(その前に「マクロを有効にする」をクリックしなければならないこともある)、CrtlキーとAキーを同時に押すと赤字で「計数中」と表示されて計数を開始できる(第2図).エクセル画面の色やセルの大きさ、文字のフォントなどは、セルの位置(セル番号)を変えない限り、自分の好みに合わせ改変して差し支えない.ただし、行や列の挿入・削除などを行ってセルの位置を変更するとプログラムに不具合が生じる.セキュリティーの関係などでマクロがうまく動かない場合は、エクセルのマクロのセキュリティーを最低レベルに設定し、HP上にあるテキスト形式で書かれたマクロプログラムをコピーして自分のエクセルのマクロに貼り付けるとよい.また、他人からもらったエクセルのファイルには、悪意を持ったプログラムがマクロに書き加えられている可能性もあるので、必ず地質学会のHPから自分で直接ダウンロードしたものを使っていただきたい.なお、昔のNECパソコンなどで使われていたN88BASIC用のプログラムも用意してあるので、必要な人は著者にご連絡いただきたい.(有)電脳組のBASIC/98ソフトを用いればWindows上でN88BASICを動かすことができる(現在はWindows Vista対応のVer. 5.1が販売中http://www.dennougumi.co.jp/).
Micro Topperについてご教示いただいた金沢大学フロンティアサイエンス機構の森下知晃准教授に感謝する.わかりやすいオンラインマニュアルを作成していただいた(独)海洋研究開発機構地球内部変動研究センターの坂口有人博士に感謝する.
手動式ポイントカウンターとエクセルの計数マクロのダウンロードとマニュアル
手動式ポイントカウンターとエクセルの計数マクロのマニュアル
このマクロは
このマクロは石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)会員により作成・提供されたものです。詳しくはこちらを参照
ダウンロード
下記からエクセルマクロがダウンロードできます。
■手動式ポイントカウンター用エクセルの計数マクロV2(Windows版・サウンド有)
■手動式ポイントカウンター用エクセルの計数マクロV1(Mac & Windows版・サウンド無し)
使い方
(1)ファイルを開き、マクロを有効にして下さい。
(2)表の「成分」の各欄に鉱物名を入力して下さい.計数を始める前に日本語入力をOFFにして下さい.(サンプル番号などを記入する場合はN8セル(右上の空欄)やA8〜A11セル(左の項目欄)を利用して下さい.)
(3)開始前に左上のA1セルをクリックして下さい.CtrlキーとAキーを同時に押すと計数を開始できます(「計数中」と表示).
(4)1〜12番に対応するキーを1回押す毎にその成分の数値が1だけ加算されます.早押ししても大丈夫です.
(片手で迅速に計数できる配列にしました.1〜6の数字キー,F1〜F12キー,Num Lock,テンキーは使いません).
(5)目標値に達すると音がします(V2のみ).初期値は1000です.自由に書き換えて下さい.
(5) Cキーを押すと%を表示します.もう一度押すと%の値は消えます.何度でも繰り返せます.計数時は消して下さい.
(6) Vキーを押すと12番(Mキー)を除いて%を算出します.算入しない成分は12番(Mキー)に割り当てましょう.%欄は99と表示されます.
(7)結果を保存する場合は必ず別のファイル名で保存して下さい.もとのファイルに上書きしてしまうと原状回復が大変です.
トラブルシューティング
成分の入力を間違えた場合.
Xキーを押してから1〜12番に対応するキーを押すと-1だけ減算されます.
作業中に表のどこかに不要な文字を入力してしまった場合
ESCキーを数回押しA1セルをクリックして下さい.再開できます. (それでもだめなら,もう一度Ctrl+Aを押して下さい((3)参照).これまでのカウント数から再開します)
No.048 2008/11/18geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.048 2008/11/18 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】臨時総会(11/30)法人申請・登記に向けて!
【2】コラム:ロンドン地質学会「Gravitational Collapse at Continental
Margins」に参加して
【3】日韓地質学会学術交流協定調印記念式典 報告
【4】2009年度日本地質学会各賞候補者募集中
【5】2009年岡山大会トピックセッション,シンポジウム募集中
【6】The International Groundwater Symposium 2009 (IGS-TH 2009)
【7】第54回日本水環境学会セミナー
【8】平成20年度国土技術政策総合研究所(国総研)講演会
【9】深田研談話会(113,114回)と講演会のお知らせ
【10】第55回「海洋フォーラム」
【11】第45回の霞ヶ関環境講座・第36回の三宅賞受賞者記念講演
【12】各賞・研究助成情報
【13】公募情報
【14】地質マンガ「小学生の会話」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】日本地質学会2008年臨時総会
──────────────────────────────────
2008年11月30日(日)14:00〜15:30
会場 学士会館 210会議室(東京都千代田区神田錦町)
12月初旬に予定される一般社団法人の申請・登記に向けた総会です.懇親の
場も予定しておりますので,代議員以外の会員の方々もぜひご出席下さいま
すようお待ちいたしております.
※懇親会は総会終了後,引き続き同会場にて懇親会を行います.
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/members/content0029.html
(会員のページへログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】コラム:ロンドン地質学会「Gravitational Collapse at Continental
Margins」に参加して 川村喜一郎(財団法人深田地質研究所)
──────────────────────────────────
日本では重力崩壊というと,陸上で見られるような地すべりを初めとして,
その規模は,海底においても,数km程度のものが多く,また,それらは現在
進行形のものである.しかし,ContinentalMarginsでの事例は,近年急速に
情報がもたらされつつあり,規模が数百kmで,白亜紀に活動したものが保存
されている事例も知られてきた.
詳しくは、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0131.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日韓地質学会学術交流協定調印記念式典 報告
──────────────────────────────────
2007年10月25日に韓国地質学会学術大会で締結された日韓地質学会学術交流協定
調印を記念し,日本地質学会第115年学術大会(秋田2008)に招待された韓国地質
学会会長の Lee, Hyun Koo (李 鉉具) 忠南大学教授の講演が9月20日の各賞授与
式で行われました.
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/science/content0039.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2009年度日本地質学会各賞候補者募集中
──────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして,研究の援助・奨励および研究業績
の表彰を行っています(会則第5条).具体的には,運営細則第11章および各賞選
考に関する規約に,表彰の種別や選考の手続きを定めています.これらにしたが
い,下記の賞の自薦,他薦による候補者を募集いたします.
応募の締め切りは各賞とも,2008年12月25日(木)必着です.
詳しくはこちらから
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
(会員のページへログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2009年岡山大会トピックセッション,シンポジウム募集中
──────────────────────────────────
日本地質学会は,西日本支部の支援のもと岡山理科大学ほかにおいて第116年学術
大会(岡山大会)を2009年9月4日(金)〜6日(日)の日程で開催致します.つき
ましては,トピックセッションとシンポジウムの募集を下記の要領で行います.
シンポジウムの募集締切:2008年12月19日(金)
トピックセッションの募集締切:2009年2月13日(金)
詳しくはこちら、、、
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
(会員のページへログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】The International Groundwater Symposium 2009 (IGS-TH 2009)
──────────────────────────────────
日程:2009年2月16日〜21日
会場:タイ・バンコク
http://www.igsth2009.com/home.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】第54回日本水環境学会セミナー
──────────────────────────────────
「水道水質管理に関する最近の話題」
期日:2009年1月23日(金)9:45〜16:45
場所:自動車会館 大会議室(東京都千代田区九段南)
参加費:会員7,000円 非会員14,000円 学生会員3,000円
http://www.jswe.or.jp/kais/jour/event.html#eve5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】平成20年度国土技術政策総合研究所(国総研)講演会
──────────────────────────────────
日時:12月2日(火)10:00-16:50
場所:九段会館(千代田区九段南1-6-5)
特別講演「土地と人間の生活」 曽野綾子(作家)ほか
http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/kouenkai/kouenkai2008.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】深田研談話会(113,114回)と講演会のお知らせ
──────────────────────────────────
■第113回深田研談話会(大阪)
「上町断層 -どこまで判っているのか-」
講師:横田 裕 氏(株式会社阪神コンサルタンツ代表取締役社長)/竹村
恵二氏(京都大学大学院教授)
日時:11月28日(金)15:00〜17:00
会場:マイドームおおさか8階/第3研修会議室(大阪市中央区)
参加費:無料
■第114回深田研談話会
「京都 地下に眠る千年の地下水脈 -歴史都市と地下水-」
講師:楠見晴重 氏 (関西大学 工学部長・教授)
日時:12月 5日(金)15:00〜17:00
会場:深田地質研究所 研修ホール
参加費: 無料
日本酒試飲会(参加費 1,000円):講演終了後、京都伏見の地下水で醸した
日本酒の試飲会を開催します。
■深田地質研究所:岩盤工学特別講演会2008
「地盤・岩盤工学における最近の技術開発トピックス」
日時:12月12日(金) 14:00 〜 17:00
会場:財団法人 深田地質研究所 研修ホール
詳しくは、http://www.fgi.or.jp/FGIhomepage/index-j.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】第55回「海洋フォーラム」
──────────────────────────────────
1.日 時:平成20年11月28日(金)17:00〜18:30
2.場 所:東京都港区虎ノ門1−15−16 海洋船舶ビル10階ホール
3.テーマ:“21世紀型”海の事故・事件の分析と考察
4.講 師:大貫 伸 氏((社)日本海難防止協会 研究統括本部部長 上席
研究員)
5.参加費:無 料
【お問合せ先】
海洋政策研究財団(シップ・アンド・オーシャン財団)
詳しくは、http://www.sof.or.jp/jp/forum/all.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】第45回の霞ヶ関環境講座・第36回の三宅賞受賞者記念講演
──────────────────────────────────
講座:「アジア陸域生態系の炭素動態」及川武久氏(筑波大)
受賞記念講演:「海洋大気中の有機エアロゾルの起源と長距離輸送に関する
研究」河村公隆氏(北海道大低温科学研)
日時:2008年12月6日 (土)14:30〜
場所:霞ヶ関ビル33階 東海大学校友会館
参加費:賛助会員および学生は無料、一般1,000円(資料代を含む)
詳しくは、http://wwwsoc.nii.ac.jp/gra/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】各賞・研究助成情報
──────────────────────────────────
■第50回科学技術映像祭参加作品募集
応募締切:2009年1月30日(金)
詳しくは、http://ppd.jsf.or.jp/filmfest
■第50回藤原賞募集
応募締切:2009年1月31日(金)
http://www.fujizai.or.jp/J-p-jigyo.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】公募情報
──────────────────────────────────
■北海道大学大学院理学研究院自然史科学部門地球惑星システム科学分野特任
教員および博士研究員の公募
締切:2008年12月24日(水)必着
■愛媛大学大学院理工学研究科(理学系)教員公募
締切:2009年1月16日(金)必着
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【14】地質マンガ
──────────────────────────────────
「小学生の会話」
作:山口耕生 画:KEY
詳しくは、http://www.geosociety.jp/faq/content0130.html
──────────────────────────────────
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質マンガ ある日の海外調査
地質マンガ
戻る|次へ
あなたのアイデアがマンガになります!
例えば次のような文章で投稿されたものがこんなマンガに清書されます。
■ 投稿された原作
■ 完成品
「地質学者の彼氏を持つと」
1.今日は二人でお買いもの。久しぶりの銀座デート♪
2.二人同時にショーウィンドウを指さして「あっ!」
3.女「ねーねーこの服すごくかわいい!値段もそんなに高くないし」
4.男、壁にはりついて「うぉー大理石の中にアンモナイトが」
女、呆れて「そっちかい…」
地質学会のメールマガジンで連載中の「地質マンガ」は
みなさま(原作)+イラストレータKeyさん(画)
により作られています。地質の魅力を伝える作品を募集しています。現在ストックゼロで即時掲載の状態です。ゆくゆくは英語化して世界の地質学を席巻する予定です!?どうぞご協力をお願い致します。いけてる作品をぜひ!
投稿はこちらから
No.047 2008/11/4 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.047 2008/11/04 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2009年度日本地質学会各賞候補者募集(12/25締切)
【2】コラム:手動式ポイントカウンターとエクセルの計数マクロの紹介
【3】「有殻原生生物プランクトン研究はどこに向かうのか」研究会
【4】「京都 地下に眠る千年の地下水脈 −歴史都市と地下水−」談話会
【5】ZMPC2009国際会議のお知らせ
【6】11月の博物館特別展示・イベント情報
【7】日台科学技術交流の各種事業応募者募集
【8】大阪市立大学理学研究科・理学部地球学教室特任講師募集
【9】東京工業大学大学院理工学研究科地球惑星科学専攻教員募集
【10】地質マンガ「ある日の海外調査」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2009年度日本地質学会各賞候補者募集(12/25締切)
──────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして,研究の援助・奨励および研究業績
の表彰を行っています(会則第5条).具体的には,運営細則第11章および各賞選
考に関する規約に,表彰の種別や選考の手続きを定めています.これらにしたが
い,下記の賞の自薦,他薦による候補者を募集いたします.
応募の締め切りは各賞とも,2008年12月25日(木)必着です.
詳しくはこちらから
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】コラム:手動式ポイントカウンターとエクセルの計数マクロの紹介
──────────────────────────────────
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
岩石学、火山学、堆積学などの分野では、岩石薄片の顕微鏡観察により、鉱物(
斑晶)、ガラス(石基)、気泡、砕屑粒子などの量比をポイントカウンティング
により計測する作業が普通に行われる.従来は英国Swift社製のポイントカウンター
が世界各国で使われていたが、これは高価で(1式60万円程度)、自動的なステー
ジ移動はX方向片道のみ、しかも数年前の同社の倒産により新製品の入手が困難に
なった.
続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0126.html
手動式ポイントカウンターとエクセルの計数マクロのマニュアル
はこちらから、、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0127.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】 「有殻原生生物プランクトン研究はどこに向かうのか」
──────────────────────────────────
琉球大学熱帯生物圏研究センター共同利用研究会のお知らせです。
主 催: 琉球大学熱帯生物圏研究センター・新潟大学自然史科学会
後 援: 形の科学会・日本地質学会・日本古生物学会
日 時: 2008年11月28日(金)・11月29日(土)
会 場: 沖縄県本部町産業支援センター・モトブリゾートホテル
内 容:
放散虫を中心とした海洋プランクトンの取り扱いや観察の仕方を講習するた
めのワークショップ(沖縄放散虫ツアー)を1997年に開始してから、2007年に
は9回を数えた。この間、延べ100名以上の研究者・学生がワークショップに参
加した。10回目の節目にあたり、ワークショップにあわせて研究会を開催する
ことを企画した。
研究会では,これまでに瀬底実験所での研究により得られた直接の成果だけ
でなく、ワークショップの経験を原生生物分類学、進化学、微古生物学、古海
洋学、地質学、宇宙工学などへと応用した内容の発表も含まれる。有殻原生生
物プランクトンの研究が、「海」だけでなく「宇宙」へ「未来」へ、さらにど
こへ向かうことを目指すのかを議論したい。
お問い合わせ: 新潟大学理学部地質科学科 松岡 篤
〒950-2181 新潟市西区五十嵐2の町8050
e-mail: matsuoka@geo.sc.niigata-u.ac.jp
Tel/Fax: 025-262-6376
プログラム
2008年 11月28日(金) 本部町産業支援センター
9:00-12:30
松岡 篤:現生放散虫研究:18 年の軌跡と今後の展望
新免 浩太郎:放散虫 Acantharea 綱の殻構造および寄生体の研究
大塚 雄一郎:Acantharea 綱に寄生する藻類の分子系統解析
湯浅 智子:放散虫に共生もしくは寄生する藻類の多様性
辻 彰洋:珪藻を用いたメソポタミア文明への塩害の影響評価
13:30-17:30
高橋 修:Hexacontium pachydermum Jorgensen の分子系統
大金 薫:盤状放散虫の形態進化と分子系統の融合へむけて
鈴木 紀毅:球状放散虫の仮足活動
堀 利栄:愛媛県愛南町における珪質殻プランクトンの研究
栗原 敏之:日本海表層水における放散虫群集の季節変化と対馬暖流との関係:これまでの成果と今後の展望
木元 克典:東シナ海−対馬海峡の浮遊性有孔虫の空間分布:対馬暖流の有殻動植物プランクトン研究への助走
2008年 11月29日(土) モトブリゾートホテル
9:00-12:30
伊藤 剛:岡山県芳井地域の芳井層群より産出したペルム紀放散虫化石
石田 直人:放散虫化石群集の変遷から考えるジュラ紀新世の古海洋環境
相田 吉昭:ニュージーランド研究(1987-2007)の到達点と今後の展開
吉野 隆:放散虫骨格形成の数理モデル
岸本 直子:マルチスケールデザイン学の構築:プランクトンから宇宙構造物まで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】 第114回深田研談話会のご案内
──────────────────────────────────
◆テーマ: 「京都 地下に眠る千年の地下水脈 −歴史都市と地下水−」
◆講 師: 楠見晴重 氏 (関西大学 工学部長・教授)
◆日 時: 2008年12月 5日(金) 15:00〜17:00
◆会 場: 深田地質研究所 研修ホール
◆談話会参加費: 無 料
◆日本酒試飲会(参加費 1,000円):
講演終了後、京都伏見の地下水で醸した日本酒の試飲会を開催します。
試飲会への参加を希望される方は、談話会申込時にその旨お知らせください。
◆講演内容:
古都 京都は、なぜ、世界でほとんど例がないと言っても過言ではないほど、
1200年もの長い間、都として栄えることができたのか?・・・それが、
「地下水」にあることを科学的に解き明かします。
一般に、文化・文明が栄える土地は大河を伴っていますが、京都にはさしたる
大きな川はありませんでした。これまで20年以上にわたって、京都盆地の地下
水に関する実証的ならびに解析的な研究を続けてきましたが、そこで明らかと
なった研究成果と2002年にNHKと共同で行なった研究での興味深い結果を基に
して、本講演ではとくに、京都盆地の豊富な地下水と京の街の発展、京の雅、
さらに京の伝統産業と地下水の濃密な関わりに焦点をあてながら考察します。
●申込み方法: 参加ご希望の方は、E-mailか FAXでお申込み願います。
その際、氏名・所属・連絡先(住所・電話番号)をお知らせ下さい。
●申込み先: 財団法人 深田地質研究所
〒113ー0021 東京都文京区本駒込2ー13ー12
TEL:03-3944-8010 FAX:03-3944-5404
E-mail:fgi@fgi.or.jp URL:http://www.fgi.or.jp/
川村喜一郎(財団法人深田地質研究所)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】ZMPC2009国際会議のお知らせ
──────────────────────────────────
International Symposium on Zeolites and Microporous Crystals 2009
主催:ゼオライト学会
日 時:2009年8月3日(月)〜8月7日(金)
開 催 地:東京都新宿区 早稲田大学
セッション:1. Mineralogy and Crystallography, 2. Synthesis, 3. Post-synt
hetic Treatment, 4. Characterization, 5. Ion Exchange, 6. Catalysis, 7. A
dsorption and Diffusion, 8. Membranes and Films, 9. Computational Chemist
ry, 10. Layered Materials, 11. New Porous Materials, 12. Novel Applicatio
ns, 13. Industrial Applicationsなどゼオライト,ミクロ・メソポーラス物質,
層状化合物に関する研究発表(口頭およびポスター)を広く募集する.
締切:2008年12月31日(水).
発表申込はホームページhttp://www.zmpc.org/からオンラインで,
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】 11月の博物館特別展示・イベント情報
──────────────────────────────────
秋といえば、スポーツの秋、読書の秋、食欲の秋とさまざまな秋がありますが、
忘れてはいけないのが文化の秋。博物館では文化の秋を応援する、特別展示や
イベントが盛りだくさんです。特別展示では、今月で終了してしまうものも多くありま
すので、お見逃しのないようイベントカレンダーをチェックしてくださいね。
11月の博物館イベントカレンダーは↓↓↓
http://www.geosociety.jp/name/content0027.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】日台科学技術交流の各種事業応募者募集
──────────────────────────────────
財団法人交流協会では,科学技術分野(※)につき,日本と台湾の共同研究開
発や人材育成の一助として,次の事業を実施しております. 現在,平成21年度
事業の応募者の募集を行っております.(※)主に先端技術(IT分野,生命科学,
新素材等),環境・エネルギー,医療・福祉及び防災.
1.若手研究者交流:日本の大学院で研究活動を行っている大学院生とその指導
教官対象.
2.セミナー・シンポジウム:日本または台湾で開催する日台合同セミナーやシ
ンポジウムに開催経費や参加者の旅費等を支援します.
3.共同研究:台湾の研究機関等と共同研究を行う大学等研究機関に研究経費を
支援します.
応募締切:2008年12月25日(木)締切
問い合わせ先
〒106-0032 東京都港区六本木3丁目16番33号青葉六本木ビル7階
TEL: 03(5573)2600(代表) FAX: 03(5573)2601
詳しくは,http://www.koryu.or.jp/をご参照下さい.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】大阪市立大学理学研究科・理学部地球学教室 特任講師募集
──────────────────────────────────
募集分野および職務内容については以下のHPをご覧下さい
http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/grad/BIOGEO/koubo.html
応募締切: 2008年11月28日(金) 必着
問い合わせ先:
大阪市立大学大学院理学研究科・理学部 地球学教室
主任 江崎 洋一(E-mail:ezaki@sci.osaka-cu.ac.jp)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】東京工業大学大学院理工学研究科地球惑星科学専攻教員募集
──────────────────────────────────
募集人員:地球惑星科学専攻教授あるいは准教授1名
応募締切:2008年12月19日(金)必着.宅配便にて送付してください.
提出書類の送付先:〒152-8551 東京都目黒区大岡山2-12-1
東京工業大学大学院理工学研究科地球惑星科学専攻209号室 専攻秘書室気付
問い合わせ先:高橋栄一 (etakahas@geo.titech.ac.jp)
Tel: 03-5734-2338
詳しくは,
http://www.geo.titech.ac.jp/koubo/koubo2008/koubo2008.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】地質マンガ「ある日の海外調査」
──────────────────────────────────
「ある日の海外調査」
作:RSH猫 画:Key
詳しくは、http://www.geosociety.jp/faq/content0128.html
地質学会のメールマガジンで連載中の「地質マンガ」は
「みなさま(原作)+イラストレータKeyさん(画)」
により作られています。地質の魅力を伝える作品を募集しています。現在ストッ
クゼロで即時掲載の状態です。ゆくゆくは英語化して世界の地質学を席巻する予
定です!?どうぞご協力をお願い致します。いけてる作品をぜひ!
投稿はこちらから
http://www.geosociety.jp/publication/content0009.html#toko4
──────────────────────────────────
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質マンガ 小学生の会話
地質マンガ
戻る|次へ
あなたのアイデアがマンガになります!
例えば次のような文章で投稿されたものがこんなマンガに清書されます。
■ 投稿された原作
■ 完成品
「地質学者の彼氏を持つと」
1.今日は二人でお買いもの。久しぶりの銀座デート♪
2.二人同時にショーウィンドウを指さして「あっ!」
3.女「ねーねーこの服すごくかわいい!値段もそんなに高くないし」
4.男、壁にはりついて「うぉー大理石の中にアンモナイトが」
女、呆れて「そっちかい…」
地質学会のメールマガジンで連載中の「地質マンガ」は
みなさま(原作)+イラストレータKeyさん(画)
により作られています。地質の魅力を伝える作品を募集しています。現在ストックゼロで即時掲載の状態です。ゆくゆくは英語化して世界の地質学を席巻する予定です!?どうぞご協力をお願い致します。いけてる作品をぜひ!
投稿はこちらから
No.052 2009/1/6 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.052 2009/01/06 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2009年の年頭に当たって 会長 宮下純夫
【2】コラム:アメリカ・カルフォルニア州Panoche Hill巡検に参加して
【3】第157回西日本支部例会および平成2008年度支部総会のご案内
【4】構造地質部会2008年度例会のご案内
【5】男女共同参画委員会:金沢ワークショップご案内
【6】公募情報(2件)
【7】1月の博物館特別展示・イベント情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2009年の年頭に当たって
────────────────────────────────────────────────
日本地質学会会長・代表理事 宮下純夫
新しい年2009年が始まりました.地質学会理事会を代表して会員の皆様に年頭の
ご挨拶を申し上げます.昨年は洞爺湖サミットで地球環境問題・温暖化問題が大
きく取り上げられ,社会の関心が大きく高まりました.しかし,石油価格の大高
騰に引き続く世界経済の大混乱と石油価格の急落,円の急騰,世界恐慌ともいえ
る深刻な経済危機の状況が続いています.このご挨拶が皆様の手元に届く頃には
少しでも改善の兆しが見えていることを願っています.
全文はこちら、http://www.geosociety.jp/outline/content0002.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】コラム:アメリカ・カルフォルニア州Panoche Hill巡検に参加して
────────────────────────────────────────────────
東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻修士2年 田阪美樹
2008年12月20日,アメリカ・カルフォルニア州Panoche Hillsでカリフォルニア州
立大学サンタクルズ校教授. Casey Moore博士案内の巡検が行われました.この巡
検は昨年房総・三浦半島で行われた付加体巡検のお返しにAGUミーティング後Case
y氏が開いて下さったものです.今回の巡検は天気にも恵まれ,壮大でダイナミッ
クなアメリカの地質を満喫することができました.
続きは、http://www.geosociety.jp/faq/content0139.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】第157回西日本支部例会および平成2008年度支部総会のご案内
────────────────────────────────────────────────
第157回日本地質学会西日本支部例会および平成2008年度支部総会を開催致します.
奮ってご参加下さいますようお願いいたします.
(西日本支部 支部長 大木公彦)
日時:
2009年2月14日(土)
9:00〜18:00(予定) 西日本支部例会(口頭・ポスター発表)・総会
(終了後懇親会を予定しています。)
会場:西日本支部例会・総会:九州大学国際ホール(九州大学箱崎キャンパス内)
講演申し込み方法:
講演申込:
講演題目
講演者(所属)
講演方法 口頭発表(15分を予定)またはポスター発表
使用機材(液晶プロジェクター・OHP)
発表者の連絡先
懇親会申込:
参加者氏名
各申込希望者は,上記項目を下記(西日本支部事務局庶務)まで郵送・ファック
スあるいはメールして下さい.なお,すべての申し込みの期限は1月30日(金)必
着までとします.また講演をされる方は,地質学会の講演要旨原稿フォーマット
に沿って作成した講演要旨を1月30日(金)必着で,下記まで「郵送」にてお送り
下さい.
問い合わせ先:
〒860-8555 熊本市黒髪2-39-1
熊本大学大学院自然科学研究科 地球環境科学講座
松田博貴
電話:096-342-3424,FAX:096-342-3411,
e-mail: hmat@sci.kumamoto-u.ac.jp
注:宿泊は各自手配をお願いします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】構造地質部会2008年度例会のご案内
────────────────────────────────────────────────
日本地質学会構造地質部会では,この度「構造地質学と応用地質学の接点」をテー
マにし,下記の日程で2009年(2008年度)例会を行う予定です.
3/14(土) 普及講演 会場:長岡市中央公民館大ホール(宿泊:湯元館)
3/15(日) シンポジウム及び例会(一般講演)
会場:長岡市民営国民宿舎悠久山湯元館(宿泊:湯元館)
3/16(月) 例会(一般講演) 会場:長岡市民営国民宿舎悠久山湯元館
シンポジウムのテーマは下記の通りです.
1.放射性廃棄物地層処分及びCO2地下貯留関連
2.活断層のモデリング
3.石油探査と構造地質学
今回の例会は,その趣旨から従来の例会とは異なり,特にシンポジウムのテーマ
を主な業務として研究されている各研究機関,コンサルタント業界や石油業界の
方々の発表を歓迎致します.大学・研究機関の方々の発表も歓迎するのは従来通
りです.(下記 URL 参照)
http://struct.geosociety.jp/topics.html
参加申し込み等の期限と方法を下記のようにさせて頂きたいと存じます.
(1)参加及び講演申し込み:2009年1月末日迄
(2)宿泊(湯元館)申し込み:2009年1月末日迄
(3)講演要旨提出:2009年2月20日迄
(1)と(2)は下記のフォーマットに記入してメールにて松田までお送り下さい
(mtatsuo@bosai.go.jp)
-----------------------------------------------------
2009年(2008年度)構造地質部会春の例会参加申込書
氏名:
性別:
参加希望日:3/14,15,16(例)
宿泊希望日:3/14,15(例)
(宿泊:http://www.sky.sannet.ne.jp/yumoto/)
講演希望:有 or 無
(有の方は,講演題目及び講演希望セッションもご記入下さい.セッションは3つ
のシンポジウムと一般講演の4つです.発表形式は原則口頭発表ですが,一般講演
についてはポスター発表も可能です.その場合,ポスター発表希望と明記して下
さい.)
(3) の講演要旨は,地質学会の年会と同じように作成して下さい.作成方法は,
今年の地質学会 News 誌 5月号にも掲載されておりますし(P.13, 14)ホームペー
ジにも掲載されております.http://www.geosociety.jp/science/content0021.html
作成した PDF ファイルを,メールに添付して同様に松田までお送り下さい.なお,
不明な点等ございましたら,お気軽にお尋ね下さい.特に長い講演要旨が必要と
いう場合には,その旨ご連絡下さい.検討させて頂きます.
多くの皆様のご参加をお待ちしております.
問い合わせ先
松田達生
防災科学技術研究所地震研究部
Tel:029-863-7616 Fax:029-863-7610
E-mail:mtatsuo@bosai.go.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】男女共同参画委員会:金沢ワークショップご案内
────────────────────────────────────────────────
「燃える温泉と地滑りのメッカ ー地質学と町おこしー」に参加しませんか?
日時:2009年3月29日(日)〜30日(月)
場所:金沢&石川県能登半島周辺
日本地質学会男女共同参画委員会主催
お子様連れでも参加できます。春休みにぜひご一緒に!
幼・小学生には下記特別プログラムが用意してあります。もちろん中学生以上も
大歓迎!
GeoKids応援プログラム「忍者ハットリくんのからくり時計とすべらない神社のな
ぞを探検しよう!」
特典:すべらないお守りが手に入ります。
参加申込・問い合わせ先
堀 利栄 shori@sci.ehime-u.ac.jp
Tel: 089-927-9644 Fax: 089-927-9630
申込はなるべく早めにお願いします
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募情報
────────────────────────────────────────────────
■東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教員公募
公募人員 教授もしくは准教授1名
公募分野 生命地球科学およびその関連分野
応募資格 学位(博士)を有し,大学院前期・後期課程での生命地球科学分野の研
究教育ができる方.着任後は,理学部地球惑星環境学科の講義,実習を兼担して
頂くことになります.
応募・推薦締切 2009年2月28日(土)(消印有効)
詳しくは, http://www.eps.s.u-tokyo.ac.jp/
■新潟大学教育学部 地学准教授公募
所属 人文社会・教育科学系
専攻領域 理科教育(地学)
担当科目 学 部:生活地圏環境形成論、生活圏地形地質環境論、生活地圏環
境セミナーA、地学演習A、地学基礎実習、地域地質実習、地殻科学実習、
理科教育法(中等)IV、小学校理科,総合演習など
大学院:地質学特論、地質学演習I、II、地学課題研究I、 IIなど
応募締切 2009年1月30日(金)必着
詳しくは、http://www.ed.niigata-u.ac.jp/modules/news/index.php?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】1月の博物館特別展示・イベント情報
────────────────────────────────────────────────
明けましておめでとうございます。今年も博物館では、たくさんの特別展示やイベ
ントをご用意してみなさまのお越しをお待ちしております。
寒いこの季節は、室内の講座や体験イベントが充実しています。事前申し込みが
必要なものもありますので、カレンダーやWebページをご確認の上お早めにお申し
込み下さい。
1月の博物館イベント情報は↓↓↓
http://www.geosociety.jp/name/content0029.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
急募!マンガの原稿を募集しています。文だけでもマンガにします(編集部)
http://www.geosociety.jp/faq/content0137.html
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
ロンドン地質学会「Gravitational Collapse at Continental Margins」に参加して
ロンドン地質学会「Gravitational Collapse at Continental Margins」に参加して
川村喜一郎(財団法人深田地質研究所)・小川勇二郎(筑波大学)
写真1 会議のアブストラクトの表紙(付加体先端と見まごうばかりのデュープレックス構造.実はナミビア沖の非活動的大陸縁という.)
写真2 ロンドン地質学会(The Geological Society)バーリントンハウスの入り口.
*画像をクリックすると、大きな画像をご覧頂けます。
10月28日,29日にかけて,ピカディリーのバーリントンハウスのロンドン地質学会で,Gravitational Collapse at Continental Margins会議が開催された.主催者は,バーミンガム大学のジョナサン・ターナー博士とアバディーン大学のロバート・バトラー教授で,主に大西洋沿岸 における大規模重力崩壊現象について討論がされた(写真1,写真2).日本から,筑波大学の小川勇二郎教授と私が参加し,ほとんど全員 Continental Marginsの中,Convergent Marginsの発表を行った.
日本では重力崩壊というと,陸上で見られ るような地すべりを初めとして,その規模は,海底においても,数km程度のものが多く,また,それらは現在進行形のものである.しかし, ContinentalMarginsでの事例は,近年急速に情報がもたらされつつあり,規模が数百kmで,白亜紀に活動したものが保存されている事例も 知られてきた.事例の中心は,ナイジェリア沖,ブラジル沖,アマゾンファン,北海のストレッガスライドなどであり,巨大な地すべりについて3D地震探査を 駆使して研究されている.それらのデータはStatoilHydroなどの石油会社から石油とは関係ない領域のデータとして提供されたものである(日本に このようなシステムがあるとは聞いたことがない,うらやましい限りである).これらの中には,あまりに規模が大きいために,その下部では,付加体とほとん ど同じ構造が形成されていることが知られてきた.地震探査で確認できるほどの規模のデュープレックス構造も観察される.デコルマン帯は,明瞭なものとそう でないものがあり,それらは頁岩か岩塩によって構成されている.どうやら,それらの岩石が流動変形することにより,重力崩壊は進行しているようである.そのように考えると,日本に見られる付加体と考えられている構造も,このような重力崩壊によって形成された可能性もありうる,と思わせる.これは根本的な問 題であり,日本だけ,大西洋だけで見ているとその違いは明瞭であるように思えるが,両者の事例を比較して見ると,真実はまだ完全には解決していないように 思われてくる.今回の集会は非常に良い刺激になった. 大西洋の事例は,3D地震探査が主であり,掘削や潜水船を用いた直接的な観察,研究が立ち後れてい るようである.その点は我々Convergent Marginsは,総合力で上回っているのかもしれない.我々は掘削を通して,直接デコルマン帯を観察しており,地層の変形構造を直接潜水船を用いて観察 することもできる.また,地震時に惹起されるものも多い.これらの分野では日本が圧倒的に優勢であると感じた.この分野において「地質学」が日本でイニシ アチブを発揮できるように思う.我々はIODPでのサイエンティフィックな掘削を提案したが,反応はこれからのようである.
写真3 バーリントンハウスの会場内,40名ほどが議論に参加した.
写真4 ワークショップ終了後に訪れたハートランドキーに見られる石炭紀層のCrackington Formationの座屈褶曲.
写真5 更新世のティライト層(暗色)が鉛直の褶曲軸面を持つ等斜褶曲をして,最後期白亜紀のチョーク層(白色)よりスラストアップされている.デュープレックス構造の一部と考えられている.
しかし,何より,このような 時流のトピックをワークショップ形式で議論して,それを意欲的にまとめていこうとする姿勢は,見習うべきところがあると思った.今回の事例は,ロンドン地 質学会特集号として,世界に発信されることであろう.このようないち早い対応は,学問を大いに発展させるだけでなく,グループとしてのスタンスを早い時期 に明確にできる面もある.彼らの研究,議論,成果の発表などからは,大いに学ぶべきものがあることを感じた. 海底地すべりや海底斜面変動は,日本の地質 学会ではあまり注目されない分野かもしれないが,メタンハイドレートをはじめとする海底資源開発で実際に掘削作業する際の懸念される問題であるはずであ る.また,断層運動によって津波が発生するとされているが,海底地すべりによって誘発される津波現象の詳細についてはほとんどわかっていないと言わざるを 得ない.このような海底での現象によるGeo-hazardをどのように予測していくのかは,これからの日本産業界だけでなく,科学掘削における重要な テーマであると思われる.
ところで,川村は,ロンドンの集会のあと,イングランド,ウェールズに行き,さまざまな地質構造を見学した.小川は,ドイツ北 東部のグライフスヴァルト大学のマーティン・メシェーデ教授を訪ねた.氏はNbを頂点に取る玄武岩のダイアグラムの考案者として有名であるが,現在は oceanicridge, convergent marginのテクトニクスの研究者として,プレートテクトニクスの教科書(まもなく英訳版が出版されるという)の著者でもある.同大学の共同研究者ら と,Jasmund国立公園の海食崖に露出する地質構造を見学する機会があった.ここでは氷河の引きずりによって更新世のティライト層(最後期白亜紀の チョーク層に平行不整合で載る)が,何とともにデュープレックス構造になっている.これはロンドンで馴染みになった付加体先端と同じような重力テクトニク スそのものであり,このような構造が氷河によっても形成されるらしいことを知り,新たな感激を持った.
三陸津波の痕跡と防災
三陸津波の痕跡と防災〜田老の防潮堤を見学して〜
川村喜一郎(財団法人深田地質研究所)・南澤智美(日本海洋事業)
写真1 三陸鉄道リアス線の切符と駅に置いてあるスタンプ.上のスタンプには田老で見られる三王岩が描かれている.
写真2 田老に張り巡らされた防潮堤.高さは約10メートル,総延長は2.4キロにも達する.
*画像をクリックすると、大きな画像をご覧頂けます。
海洋研究開発機構の深海調査研究船「かいれい」によるKR08-10日本海溝航海が8月18日〜9月11日まで行われた.9月1日〜2日朝にかけて,乗船研究者の入れ替えと荷物の積み込みのために岩手県の宮古港に寄港した.筆者は,少し足を伸ばし,片道440円を払って三陸鉄道北リアス線に乗り,宮古駅から3つ目の駅の田老駅で下車した(写真1).
田老の街には,巨大な砦を連想させる防潮堤が縦横無尽に張り巡らされている(写真2).それらの防潮堤は,二度にわたる巨大な津波が田老の街に押し寄せたことに深く関わっている.明治29年6月15日の午後8時過ぎ,三陸海岸に津波が押し寄せ,全体で死者6477人の被害を出した.田老には15メートル近くの津波が押し寄せ,村民の7割以上の命が奪われた.その36年後の昭和8年3月3日の午前2時過ぎには,昭和三陸津波が襲来した.このとき,田老には10メートル近くの津波が押し寄せ,972人の死者を出した.これらの津波被害を二度と出さないために,昭和三陸津波の翌年の昭和9年に防潮堤の建設に着手した.その防潮堤は,戦争で工事が一時中断したものの,昭和33年に完成した.まさに街を津波から守る「砦」と言ったところであり,現在の総延長は2.4キロ,海面からの高さは約10メートルである.
田老駅を降りて,駅舎で尋ねると近隣の地図がもらえる.駅を出て,左手の坂を上り,小高い国道45号線に出ると,すぐに防潮堤が見える(写真3).防潮堤の上は歩けるようになっており,そこを伝って,景勝地で有名な三王岩まで行くことができる.30分の散歩道と言ったところである.三王岩までの防潮堤の道のりでは,道路や河川を通すための鉄の門が幾つも見られ,物々しさが感じられる(写真4).海岸の崖には明治29年と昭和8年の津波の波高が記録されており,周辺の建物を凌駕するその高さに圧倒される(写真5).
写真3 田老の防潮堤.手前の道路が国道45号線で,奥に見えるコンクリートの壁が防潮堤.
写真4 防潮堤にある鉄の門.道路や河川と交差する箇所に設置されている.左には非常用階段が見える.
田老を訪れた日は,9月1日で,偶然ではあるが,防災の日だった.大正12年9月1日の正午,東京をマグニチュード7.9の地震が東京周辺を襲い,火災によって,十万人を超える方々が亡くなった.このときの地震でも津波が観測されており,房総半島南部,三浦半島から伊豆半島で数m〜十数mであったとされる.津波は,本震から約5分後に神奈川県の沿岸に到達し,根府川地区では,5〜6メートルの津波が押し寄せたとされる.首都近辺でこのような地震が再び生じると,その被害は甚大なものになると予想されており,地震予知は未だ難しい領域であるにしても,その地震のメカニズムについて少しでも理解するための試みがなされている.その中でも,東京近辺の海底を掘削する「関東アスペリティープロジェクト(略称KAP)」が現在進行中である.今年12月のアメリカ地球物理学連合のFall meetingやその後の日本での学会などで,関連の発表やイベントの案内を見る機会があるだろう.このようなプロジェクトによって,地震学やそれに基づいた地震防災が少しでも進歩するのならば,我々地球科学者はそれに取り組まなければならないのかもしれない.
近年,スマトラ地震に代表されるように,地震に伴う巨大な津波によって,多くの被害が生じている.防災対策に対して,関心が高まっている時期でもあると言える.田老を訪れると,津波が頻繁に日本に押し寄せたことを,身をもって理解することができる.田老は,街全体で津波に対する防災を実感,体感できる場所であり,過去の記憶を伝承する上でも重要な街である.
写真5 明治29年の津波波高(上の印,15メートル)と昭和8年の津波波高(下の印,10メートル).手前の自動車と比べてもその高さ如何に高いかがよくわかる.
文献
釜石市ホームページ,津波災害について.
武村雅之,2007,1923(大正12)年関東大震災ー揺れと津波による被害ー.広報ぼうさい,39,20-21.
東北地方整備局,2005,東北歴史探訪 田老万里の長城.東北コミュニケーションマガジン,28.
No.049 2008/12/02geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.049 2008/12/02 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】速報!ついに法人設立へ
【2】岡山大会シンポジウム申し込み(12/19締切)
【3】コラム:三陸津波の痕跡と防災〜田老の防潮堤を見学して〜
【4】大学教育の分野別質保証の在り方検討委員会(第3回)会議について
【5】第33回フィッショントラック研究会のご案内
【6】JAMSTECデータ検索ポータル」の提供開始
【7】12月の博物館特別展示・イベント情報
【8】東京大学地震研究所技術職員 公募
【9】次期南極観測計画を募集中(1/15締切)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】速報!ついに法人設立へ
──────────────────────────────────
日本地質学会の臨時総会が11月30日に開催され、法人設立のための議案が了承さ
れました(詳細な議事録はおってニュース誌にてお知らせいたします)。引き続
いて社団法人日本地質学会の設立時社員及び設立時役員による会議が開催され、
定款に定められている通り宮下純夫理事を代表理事に選任しました。翌12月1
日に東京法務局に登記申請を行い、一般社団法人日本地質学会が設立されました!
これによって当面の間は任意団体と社団法人の二つの地質学会が存在すること
になります。従来の学会事業と会員サービスは、これまで通り任意団体の地質学
会が行います。今回設立されました社団法人の地質学会は、将来の公益法人の母
体であり、公益法人になるための活動を担います。今回の社団法人設立は公益法
人になるためのプロセスにすぎません。しかし長い公益法人化の道のりの重要な
マイルストーンと言えるでしょう。
臨時総会の様子(於 学士会館)
総会資料や、一般社団法人日本地質学会定款は、会員のページからご覧頂けます。
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
(会員のページへログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】岡山大会シンポジウム申し込み(12/19締切)
──────────────────────────────────
第116年学術大会(岡山大会)を2009年9月4日(金)〜6日(日)のトピック
セッションとシンポジウムの募集を行っています.
シンポジウムの募集締切:2008年12月19日(金)
トピックセッションの募集締切:2009年2月13日(金)
詳しくはこちら、、、
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
(会員のページへログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】コラム:三陸津波の痕跡と防災〜田老の防潮堤を見学して〜
──────────────────────────────────
川村喜一郎(財団法人深田地質研究所)・南澤智美(日本海洋事業)
海洋研究開発機構の深海調査研究船「かいれい」によるKR08-10日本海溝航海が8
月18日〜9月11日まで行われた.9月1日〜2日朝にかけて,乗船研究者の入れ替え
と荷物の積み込みのために岩手県の宮古港に寄港した.筆者は,少し足を伸ばし,
三陸鉄道北リアス線に乗り,宮古駅から3つ目の駅の田老駅で下車した.
田老の街には,巨大な砦を連想させる防潮堤が縦横無尽に張り巡らされているそ
れらの防潮堤は,二度にわたる巨大な津波が田老の街に押し寄せたことに深く関
わっている.
続きはこちらから
http://www.geosociety.jp/faq/content0056.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】大学教育の分野別質保証の在り方検討委員会(第3回)会議について
──────────────────────────────────
(日本学術会議メールニュースより)
日本学術会議は、11月6日に大学教育の分野別質保証の在り方検討委員会の
第3回会議を開催しました。
第3回会議では、「理工系分野における大学教育の状況」について、小
林信一委員(筑波大学ビジネス科学研究科教授)から、「大学教育と仕事
との関係性」について、本田由紀氏(東京大学大学院教育学研究科比較教
育社会学コース准教授)から、それぞれご講演いただき、議論を行いまし
た。
当日の議事要旨を作成し、会議資料は以下のURLからご参照下さい。
http://www.scj.go.jp/ja/info/iinkai/daigaku/index.html
【問い合わせ先】
日本学術会議事務局審議第一担当 廣田、川上、古橋
Tel:03-3403-6289 Fax:03-3403-1640 E-mail:s248@scj.go.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第33回フィッショントラック研究会のご案内
──────────────────────────────────
日時:2009年1月9日(金)〜10日(土)
場所:金沢大学角間キャンパス自然科学研究科 図書館棟G15室
連絡・問い合わせ先
長谷部徳子<hasebe@kenroku.kanazawa-u.ac.jp>
Tel&Fax: 076-264-6529
研究会HP http://wwwsoc.nii.ac.jp/ftrgj/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】JAMSTECデータ検索ポータルの提供開始
──────────────────────────────────
このサービスは、データの種類を選択すると地図上に取得位置が表示され、マ
ウスで範囲を指定することでそこに含まれるデータのリストが表示される、とい
うものです。検索結果に含まれるデータ公開ページへのリンクをクリックする
と、データの詳細を確認したりダウンロードもできます。
JAMSTECが「JAMSTEC観測航海データサイト」を始め各種データサイト、データ
ベースで公開しているデータやサンプルを海域から探したい場合にご利用頂けます。
このサイトは、
http://www.jamstec.go.jp/dataportal/からアクセスできます。
ご利用の際は画面右上のabout this siteから説明ページをご覧ください。
本システムに関するご意見は<dmo@jamstec.go.jp>へ。
なお、本サービスはWindowsではInternet Explorer 7、MacではFirefox 3での
動作を確認しています。またポップアップブロックを有効にしていると検索結果
画面が表示されませんのでご注意ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】12月の博物館特別展示・イベント情報
──────────────────────────────────
早いもので今年も残すところあと1か月となりました。寒くはなりましたが野外観察会
を含めたイベントをご用意。もちろん、室内での特別展示やイベントも充実です。
師も走る何かと忙しい月ですが、博物館ではみなさまのお越しをお待ちしております。
なお、年末年始は多くの館が休館となりますので、お立ち寄りの際には各博物館の
Webページにて開館スケジュールをご確認の上お越し下さい。
12月の特別展示・イベントのチェックは ↓↓↓
http://www.geosociety.jp/name/content0028.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】東京大学地震研究所技術職員 公募
──────────────────────────────────
募集職種:技術職員(1名)
応募資格:4年制理工系大学卒業以上の学歴を有し、大学や国・自治体・企業等
の研究機関で蛍光X線、X線マイクロプローブ及びICP質量分析計等を用いた
機器分析の経験を2年以上有すること。ただし、大学院等における研究歴は資格
要件の職務経験に含みます。
応募期限:2008年12月25日(木)午後5時 必着
詳しくは、
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/recruit/H20/gijutu_koubo201225new.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】次期南極観測計画を募集中(1/15締切)
──────────────────────────────────
国立極地研究所は、南極観測事業第VIII期計画(2010-2015年度)に実施する「一般研
究観測」「萌芽研究観測」の公募を行っています。
地質関係の計画をお持ちの方は、南極地質研究委員会(廣井美邦委員長、千葉大、
または、本吉洋一幹事、国立極地研究所)にお問い合わせください
締切:2009年1月15日(木)
募集要項等の詳細は以下のサイトをご覧ください。
http://www.nipr.ac.jp/info/notice/H22_research/index.html
──────────────────────────────────
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.050 2008/12/05geo-flash
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.050 2008/12/05 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 藤田和夫 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
日本地質学会名誉会員、藤田和夫 大阪市立大学名誉教授におかれましては、
12月1日、18時30分に肺炎のため、神戸市の病院でご逝去されました。
享年89歳でありました。これまでの故人の功績を讃えるとともに、謹んで
ご冥福をお祈り申し上げます。
なお、通夜・告別式はそれぞれ3日・4日に行われました。
会員の皆様に、謹んで御連絡申し上げます。
会長 宮下純夫
──────────────────────────────────
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.051 2008/12/16 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.051 2008/12/16 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】日本地質学会の新たな出発:一般社団法人のスタートにさいして
【2】地質学雑誌 新表紙デビュー!!
【3】岡山大会シンポジウム申し込み(12/19締切)
【4】2009年度会費について(災害関連特別措置・院生割引ほか)
【5】日本ジオパークに7ヶ所が申請
【6】「地質の日」ロゴが決定しました!
【7】日本の地質百選 第二次選定追加募集中(1/30締切)
【8】国際地学オリンピック参加応募締め切り;昨年の倍増!83校686名
【9】構造地質部会例会「構造地質学と応用地質学の接点」のご案内(3/14-16)
【10】第46回アイソトープ・放射線研究発表会発表論文募集(2/28)
【11】消防防災科学技術研究推進制度平成21年度研究開発課題募集(1/30締切)
【12】12月の博物館特別展示・イベント情報
【13】地質マンガ 新婚旅行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】日本地質学会の新たな出発:一般社団法人のスタートにさいして
──────────────────────────────────
2008年12月1日,一般社団法人日本地質学会がスタートしました.今回の社団法人
地質学会の設立は,長い歴史の日本地質学会の中でも画期的な意義を持つもので
す.
詳しくは、一般社団法人日本地質学会HPへ
http://geosociety.sakura.ne.jp/jgs/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】地質学雑誌 新表紙デビュー!!
──────────────────────────────────
地質学雑誌の表紙デザインを変更することを理事会で決定してから,約1年の
時間を費やし,表紙デザインを広く公募し,選考委員会による一次,二次審査を
経て,基本デザインとなった作品を決定した(2008年5月).その後,理事会を中
心に,編集出版委員会部会長,広報委員会部会長とのデザインの修正を議論し最
終案を作成した.
新デザインのコンセプトは,本学会のポリシー(「地球を知る」,「地球を守
る」,「地球と歩む」)に掲げられている「地球」を相手に,新しい科学の手法
により料理していく,あるいは既成概念にとらわれることなく,常に斬新なアイ
ディアのもとに地球史を理解し,現在そして将来の人類に貢献していくことをジ
グソーパズルに例えて表現したものです.
国内はもとより,世界をリードしていけるようなアイディア,知識を我々の地
質学雑誌から発信していくことを願い,新たな表紙デザインとして決定しました.
末永く皆様に愛される表紙になることを願います.
情報特任理事(表紙デザイン選考委員会幹事) 倉本真一
新しい表紙はこちら、、http://www.geosociety.jp/publication/content0002.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】岡山大会シンポジウム申し込み(12/19締切)
──────────────────────────────────
第116年学術大会(岡山大会)を2009年9月4日(金)〜6日(日)のトピック
セッションとシンポジウムの募集を行っています.
シンポジウムの募集締切:2008年12月19日(金)
トピックセッションの募集締切:2009年2月13日(金)
詳しくはこちら、、、
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
(会員のページへログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2009年度会費について(災害関連特別措置・院生割引ほか)
──────────────────────────────────
■2009年度会費について
会則により、次年度分会費の前納をお願いいたします。自動引き落としを登録さ
れている方の引き落としは、12月24日(水)です。お振込の方へは、12月中旬頃
までに請求書兼郵便振替用紙をお送りいたしました。
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/outline/content0066.html
■2008年岩手・宮城内陸地震等の災害に関連した会費の特別措置
2008年中に災害により被害を受けられた皆様に,心よりお見舞い申し上げます.
日本地質学会では,災害救助法適用地域で被災された会員の方々のご窮状をふ
まえ,「日本地質学会に届出の住居または勤務地が災害救助法適用地域に該当す
る会員のうち,希望する方」は2009年度(平成21年度)会費を免除することといた
します.
締切:2009年2月13日(金)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0067.html
■2009年度(2009.4〜2010.3)院生割引申請受付中!
最終締切:2008年2月27日(金)
申請書等野ダウンロードは、http://www.geosociety.jp/members/content0034.html
(会員番号によるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】日本ジオパークに7ヶ所が申請
──────────────────────────────────
日本ジオパーク委員会は、アポイ岳、洞爺湖有珠山、糸魚川、南アルプス(中央構
造線)、山陰海岸、室戸、島原半島以下の申請を認められました。認定された地域
は今後設立される予定の日本ジオパークネットワーク(2009年2月20日設立予定)
への加盟を認められ、ジオパークを名乗ることができるようになります。
詳しくは、http://www.gsj.jp/jgc/indexJ.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】「地質の日」(5月10日)のロゴが決定しました!
──────────────────────────────────
作者は彦根 正さん(東京都)です。
Geology Dayの「G」をベースに、重なる「地層」を組み合わせ、「地質の日」の
広がりを表現された作品です。全国の「地質の日」に関連した行事、印刷物に 広
くお使いください.
(地質の日事業推進委員会)
地質の日のHP>http://www.gsj.jp/geologyday/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】日本の地質百選 第二次選定追加募集中(1/30締切)
──────────────────────────────────
日本全体から,地質現象のよくわかるところを百箇所選び出し,そのユニークさ
を顕彰し,広く知っていただきたいと思います。
第二次選定募集締切:2009年1月30日(金)
詳しくは、地質情報整備活用機構(GUPI)へ
http://www.gupi.jp/geo100/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】国際地学オリンピック参加応募締め切り;昨年の倍増
──────────────────────────────────
12月10日に来年9月に開催される第3回国際地学オリンピック台湾大会の参加者の
応募が締め切られました。応募者は全国83校686名で、前回の358名のほ
ぼ2倍の数となりました。12月21日に全国各地の大学・高校で一斉に一次試
験である筆記試験が行われ、2月に結果発表、そして3月29日(場所は東京大
学の予定)の2次試験である実技試験・面接に望みます。なお今回の選抜試験は、
第1回日本地学オリンピック大会を兼ねます。
詳しくはhttp://www.jeso.jp/をご覧ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】構造地質部会例会「構造地質学と応用地質学の接点」のご案内
──────────────────────────────────
会期:2009年3月14日(土)〜16日(月)
3/14(土)普及講演 会場:長岡市中央公民館大ホール(宿泊:湯元館)
3/15(日)シンポジウム及び例会(一般講演)
会場:長岡市民営国民宿舎悠久山湯元館(宿泊:湯元館)
3/16(月)例会(一般講演) 会場:長岡市民営国民宿舎悠久山湯元館
シンポジウムのテーマ
(1)放射性廃棄物地層処分及びCO2地下貯留関連
(2)活断層のモデリング
(3)石油探査と構造地質学
詳しくは、構造地質部会HP>http://struct.geosociety.jp/topics.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】第46回アイソトープ・放射線研究発表会発表論文募集
──────────────────────────────────
会期 2009年7月1日(水)-3日(金)
会場 日本科学未来館(東京都江東区青海2-41)
内容:それぞれの研究分野において,その専門的な成果を得た放射性同位体,安
定同位体や放射線の利用研究,およびこれら利用の基礎となる研究.少なくとも
一部に未発表の部分が含まれていること.
発表者の資格:発表者の一人が本発表会の主・共催学・協会の会員であること(
共催 日本地質学会ほか).
申込締切:2009年2月28日(土)
参加費:2,000円(学生は無料)要旨集 3,000円(消費税含む)
詳しくは、http://www.jrias.or.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】消防防災科学技術研究推進制度平成21年度研究開発課題募集
──────────────────────────────────
◯対象となる研究開発
消防防災に係る課題の解決にとって、実用的な意義が大きいものであり、かつ、
消防防災への波及効果が具体的に想定される、科学技術(自然科学及び人文・社
会科学)を利活用した研究開発を対象としています。
・現場ニーズ対応型研究開発 /・テーマ設定型研究開発 /・その他消防防災分野
を対象とする研究開発
◯研究費の額
・直接経費で、年間100万円以上400万円を上限とする額(A区分)
・直接経費で、年間400万円を超え2,000万円を上限とする額(B区分)
募集締切 平成21年1月30日(金)
詳しくは、http://www.fdma.go.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】12月の博物館特別展示・イベント情報
──────────────────────────────────
早いもので今年も残すところあと1か月となりました。寒くはなりましたが野外観察会
を含めたイベントをご用意。もちろん、室内での特別展示やイベントも充実です。
師も走る何かと忙しい月ですが、博物館ではみなさまのお越しをお待ちしております。
なお、年末年始は多くの館が休館となりますので、お立ち寄りの際には各博物館の
Webページにて開館スケジュールをご確認の上お越し下さい。
■新着情報■
フォッサマグナミュージアム:コラボ特別展with新潟大学「頭足類展」/
葉県立中央博物館:地層と地形のでき方実験(講座)など
12月の特別展示・イベントのチェックは ↓↓↓
http://www.geosociety.jp/name/content0028.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】地質マンガ 「新婚旅行」
──────────────────────────────────
「新婚旅行」
作:向吉秀樹 画:Key
詳しくは、http://www.geosociety.jp/faq/content0137.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質マンガ 新婚旅行@スイス
地質マンガ
戻る|次へ
あなたのアイデアがマンガになります!
例えば次のような文章で投稿されたものがこんなマンガに清書されます。
■ 投稿された原作
■ 完成品
「地質学者の彼氏を持つと」
1.今日は二人でお買いもの。久しぶりの銀座デート♪
2.二人同時にショーウィンドウを指さして「あっ!」
3.女「ねーねーこの服すごくかわいい!値段もそんなに高くないし」
4.男、壁にはりついて「うぉー大理石の中にアンモナイトが」
女、呆れて「そっちかい…」
地質学会のメールマガジンで連載中の「地質マンガ」は
みなさま(原作)+イラストレータKeyさん(画)
により作られています。地質の魅力を伝える作品を募集しています。現在ストックゼロで即時掲載の状態です。ゆくゆくは英語化して世界の地質学を席巻する予定です!?どうぞご協力をお願い致します。いけてる作品をぜひ!
投稿はこちらから
アメリカ・カルフォルニア州Panoche Hill巡検
アメリカ・カルフォルニア州Panoche Hill巡検に参加して
東京大学大学院 理学系研究科 地球惑星科学専攻
修士2年 田阪美樹
(写真1)Panoche Hillsの露頭の様子(撮影者:坂口有人氏)
(写真2):チューブワームの化石群
*画像をクリックすると、大きな画像をご覧頂けます。
2008年12月20日,アメリカ・カルフォルニア州Panoche Hillsでカリフォルニア州立大学サンタクルズ校教授J. Casey Moore博士案内の巡検が行われました.この巡検は昨年房総・三浦半島で行われた付加体巡検のお返しにAGUミーティング後Casey氏が開いて下さったものです.房総三浦半島の巡検については静岡大学の原君が報告していますのでそちらを参照ください.今回の巡検は天気にも恵まれ,壮大でダイナミックなアメリカの地質を満喫することができました.
巡検地はCasey氏が長年研究されている場所で,前孤海盆の堆積層とそれを貫く巨大な砂岩岩脈群,流体移動の痕跡が見られます.つまり,現在海面下にある前孤域の表層で起こっている様々な現象を陸上でまるごと観察できる世界的にも貴重な場所です.
午前中は前弧海盆を覆う堆積層と,そこに貫入している砂岩の岩脈群を観察しました.堆積層は下位から厚さ数kmに及ぶ砂岩層,厚さ約700mの泥・シルト岩層,炭酸塩岩のコンクリーションやマウンドを含む厚さ数10mの砂岩層からなり,白亜紀後期〜暁新世初期にかけて形成された一連の層序として見ることができます.岩脈は水圧破砕により生じたクラックに最下位の砂がメタンなどの炭化水素を含む流体とともに上位の堆積層に注入したもので,厚さは平均数10cm,厚いものでは最大数mに達します.この辺りは丘陵地で見渡す限り新鮮な露頭が露出し,高台に立つと数キロ先まで見渡せる巨大岩脈群は息をのむほどの光景でした(写真1).
午後からは,炭酸塩岩のコンクリーションやマウンドを含む層を中心に観察しました.この層の下部では至る所に流体の通り道であった大小のチューブ状の構造が見られ,地下からの流体の供給量の多さを感じ驚きました.コンクリーションやマウンドは海洋底表層で,海水中のカルシウムや酸素と地下からの流体に含まれる炭化水素が反応して形成されたものです.マウンドの中には,チューブワームや白ウリ貝など現世の海底で確認される熱水噴出孔の生物と同様の化石が見られました.チューブワームの化石はアラゴナイトで置換されており10cmほどの輪切りのチューブワームが固まりになっていました.Casey氏に見せていただいた現在の海底下に生育するチューブワームの産状と露頭で見える化石群が大変よく似ており,まるで海底下の熱水活動をその場で観察しているようで圧巻でした(写真2).
私はこれらの構造を見るのは初めてでしたが,Casey氏はアメリカンサイズの大きなピックアップトラックから,アメリカンサイズの大きなパネルを取り出し,論文の図や地質図を大変分かりやすく説明して下さいました.Casey氏の丁寧な説明と綺麗な露頭で,前孤海盆における流体の移動について自分なりにイメージをつかめたことは大きな収穫でした.
巡検終了後はCasey氏お勧めのレストランにてみんなで夕食会をしました.次から次へと大量の料理が出てきてどれもおいしく,自然と会話もはずみました.Casey氏はとても温和な方で私のつたない英語の質問にも丁寧に答えて下さり,とても楽しい時間を過ごすことができました.
この巡検は山田泰広さん,辻健さん,宮川歩夢さん,山本由弦さん(京都大)植田勇人さん(弘前大)坂口有人さん(JAM)平内健一さん(広島大)原勝宏さん(静岡大)田阪美樹(東京大)およびJ. Casey Moore博士,合計10人で行われました(写真3).案内して下さったCasey氏,巡検に誘って下さった山本さん,素人の私に丁寧に専門用語の説明して下さった参加者の皆様,粗稿を丁寧に読んでくださった原勝宏さんに心よりお礼申し上げます.またこのような巡検があれば参加したいと思います.
(写真3)アメリカ・カルフォルニア州Panoche Hillsにて撮影した集合写真(撮影者:坂口有人氏)上段左から・・・山本由弦さん,坂口有人さん,辻健さん,植田勇人さん,平内健一さん,下段左・・・田阪美樹,原勝宏さん,J. Casey Moore博士,山田泰広さん,宮川歩夢さん
地質マンガ 薄片道
地質マンガ
戻る|次へ
あなたのアイデアがマンガになります!
例えば次のような文章で投稿されたものがこんなマンガに清書されます。
■ 投稿された原作
■ 完成品
「地質学者の彼氏を持つと」
1.今日は二人でお買いもの。久しぶりの銀座デート♪
2.二人同時にショーウィンドウを指さして「あっ!」
3.女「ねーねーこの服すごくかわいい!値段もそんなに高くないし」
4.男、壁にはりついて「うぉー大理石の中にアンモナイトが」
女、呆れて「そっちかい…」
地質学会のメールマガジンで連載中の「地質マンガ」は
みなさま(原作)+イラストレータKeyさん(画)
により作られています。地質の魅力を伝える作品を募集しています。現在ストックゼロで即時掲載の状態です。ゆくゆくは英語化して世界の地質学を席巻する予定です!?どうぞご協力をお願い致します。いけてる作品をぜひ!
投稿はこちらから
No.053 2009/1/20 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.053 2009/01/20 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2009年度役員ならびに代議員選挙の実施(告示)延期の決定について
【2】地球惑星科学連合の個人会員登録について
【3】岡山大会ニュースNO.2 シンポ・見学旅行の企画などなど
【4】写真で見る軌跡 地学オリンピック2008年フィリピン大会の道
【5】第116回深田研談話会のご案内
【6】日本堆積学会2009年京都枚方大会のご案内と講演募集
【7】地質調査総合センター第13回シンポジウム(2/26)
【7】公募情報
【8】1月の博物館特別展示・イベント情報
【9】地質マンガ 「薄片道」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2009年度役員ならびに代議員選挙の実施(告示)延期の決定について
──────────────────────────────────
2009年1月9日
日本地質学会理事会
ニュース誌2008年12月号に掲載の臨時総会議事録でご報告しましたように,11月3
0日の臨時総会において,3議案(一般社団法人日本地質学会定款案,代議員およ
び役員選挙について,一般社団法人としての各種規則案)の提案が承認されまし
た.
この中の第2号議案の代議員および役員選挙については,10月21日付けの日本地
質学会メールマガジン 【geo-Flash】No.045においてもお知らせしましたように,
2008年度末に任期を終える任意団体日本地質学会の代議員・評議員・理事・監事
の任期を,移行段階の措置として1年間延長することとし,本年度の選挙は実施
しないという内容であることを,改めてお知らせいたします.
なお,今後の選挙は,学会のすべてが完全に法人へ移行した後に一般社団法人
の地質学会の中で実施することといたします.また,新しい選挙においては,こ
れまでの半数改選のルールを改め,全役員,全代議員の一斉改選を行う方針が決
まっております.それまでに法人の定款に沿った選挙規則などの整備を行い,会
員の皆様にも十分な共通理解を得たうえで,新法人での選挙を実施いたしたいと
考えております.なお,役員,代議員選出の構造については,概ね以下の図のよ
うに想定しております.
任期延長および継続任期の代議員・評議員の皆様には,当面は,これまでどお
りの任意団体と新しい一般社団法人が並行して存在し,日本地質学会が実質的に
任意団体から法人に移行する大事な時期を担っていただくことになります.これ
までにも増してご協力のほどよろしくお願いいたします.また,会員の皆様にも
改めてご理解とご協力をお願いいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】地球惑星科学連合の個人会員登録について
──────────────────────────────────
日本地質学会理事会
2009年1月9日より地球惑星科学連合の個人会員登録が始まりました(連合URL:
http://www.jpgu.org/ 参照).
昨年12月1日に一般社団法人となりました地球惑星科学連合は,本学会と同じく
公益法人をめざしているところですが,学術会議との連携や政策決定者への適切
な提言・パブリックコメントの対応など,地球惑星科学分野からの統一的な発信
を有効に推進するため,引き続き日本地質学会は同連合の主要な構成団体として
積極的に関わっていく方針でおります.
そのためには,本学会より会員各位が連合の個人会員として登録いただき,会
員の皆様の活動の場と可能性を広げつつ,積極的な連合でのご活動をいただく事
が必須と考えております.地質学会員の登録区分は下記の「4.固体地球科学」を
はじめ,「2.大気海洋・環境科学」,「3.地球人間圏科学」,「5.地球生命科
学」,など幅広い分野にわたると思いますので,各々のセクションにおいて地質
学会員の皆様に重要な役割を担っていただくためにも,できる限り多くの方に連
合の個人会員登録をお願いする次第です.
【登録区分】
(学術研究活動推進の場としてのセクション区分は,下の1〜5に限られます.)
1.宇宙惑星科学:太陽系の諸天体(太陽,惑星,小天体)の起源と進化の解明,
現在の状態(内部構造,表層環境,大気・プラズマ環境)とダイナミクスの理解,
さらには宇宙空間及び系外惑星の探求を目指す研究分野.
2.大気海洋・環境科学:現在及び過去の大気・海洋・表層環境とその変動(気象
現象から古気候変動ま で)のメカニズムを解明し,将来の地球環境の変動の予測
に向けて,大気,海洋,陸水,雪氷,土壌,植生とそれらの相互作用の理解を目
指す研究分野.
3.地球人間圏科学:地球表層空間における自然と人間の相互作用とそれに起因す
る諸問題(自然災 害,農村・都市環境,土地・資源・エネルギー利用など)を,
調査・観測,デ —タ分析,モデルにより多面的に研究する分野.
4.固体地球科学:固体地球(地殻,マントル,中心核)の構造と物性,進化と変
動の歴史,現在 のダイナミクスを,地球物理学的,地質学的,物質科学的,地球
化学的な手法 を用いて,総合的かつ統一的に解明する研究分野.
5.地球生命科学:地球上の生物を対象に,その起源と進化,絶滅の原因とプロセ
ス,形態や生態 の多様性を,地球環境の進化・変動との関わりという視点に立っ
て,地球惑星科学及び生物学の両側面から理解を目指す研究分野.
6.地球惑星科学総合:他の5つの区分にはなじまない,広く地球惑星科学全般に
関心のある教育関係者,ジャーナリスト,官公庁・民間企業の関係者,一般市民
の方々等を対象としたものであり,「総合的あるいは分野横断的な学術分野とし
ての区分」という意味ではありませんのでご注意ください.
【参考】
なお,連合の組織上の大きな変更点の概要をご参考までに以下にご説明します.
1. 個人会員制および連合を構成する学協会の団体会員制を新たに設ける.
2. 将来を見据えた学術研究活動の推進のために,これまでの学協会の分野の枠組
みを超えた5つの分野からなるセクション制を導入する.
連合の個人会員(年会費一般2000円,院生1000円)になれば,連合および希望
セクションからの様々な情報サービスや会員特典が受けられることになります.
また,連合大会の登録料が個人会員では2000円安く設定されるため,連合大会参
加者は実質上従来と出費は変わりません.一方,非会員のまま連合大会に参加す
る場合は,参加登録費が会員より5,000円高くなります.連合総会の代議員を選ぶ
権利を有する登録区分は,6つの登録区分のうちの1つを選択することとなりま
すが,情報配信,活動を実施するセクションへは複数登録が可能です.詳しくは,
JGL1月号,連合メールニュースならびに連合URLをご覧ください.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】岡山大会ニュースNO.2
──────────────────────────────────
岡山大会では,シンポジウムやそれに対応した見学旅行を企画しています.これ
までに公募などで提案のあったシンポジウム及び見学旅行や地学教育関連企画及
び市民講演会について紹介します.
■企画中のシンポジウム
「坂野昇平追悼シンポジウム」/「都城秋穂追悼シンポジウム」*/「高Mg安山岩
とアダカイト」*/「日本列島構造発達史」*/「3次元地質モデルの構築手法と利
活用」/「中国地方における第三系の諸問題」/「科学を文化に—学校教育・地学
分野のこれから—」/「「ちきゅう」による南海トラフ地震発生帯掘削計画ステー
ジ1と2の成果(総括)*」(*印は、見学旅行とのセット企画)
http://www.geosociety.jp/members/content0036.html
(会員のページへログインが必要です)
■トピックセッションの募集締切:2009年2月13日(金)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
(会員のページへログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地学オリンピック2008年フィリピン大会の軌跡
──────────────────────────────────
写真で見る軌跡「地学オリンピック2008年フィリピン大会への道」がアップ
されました。
詳しくは、、、
http://www.geosociety.jp/name/content0030.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第116回深田研談話会のご案内
──────────────────────────────────
◆テーマ: 「関東地震の断層を探る」
◆講 師: 小林励司 氏 (鹿児島大学 准教授)
◆日 時: 2009年 2月27日(金) 15:00-17:00
◆会 場: 深田地質研究所 研修ホール
◆談話会参加費: 無料
◆講演内容: 南関東は陸側のプレートの下に太平洋プレートとフィリピン海プ
レートが沈み込んでおり、島弧−島弧衝突帯でもあるという複雑な構造になって
いる。フィリピン海プレートの沈み込みにともなって、相模トラフ沿いでは1703
年元禄地震、1923年関東地震といった巨大地震が起き、首都圏に甚大な被害をも
たらしている。講演では、これらの巨大地震の断層を探る研究をレビューし、現
在立案を進めている深海掘削計画「関東アスペリティ・プロジェクト」について
紹介する。
●申込み方法: 参加ご希望の方は、E-mailか FAXでお申込み願います。
その際、氏名・所属・連絡先(住所・電話番号)をお知らせ下さい。
詳しくは、http://www.fgi.or.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】日本堆積学会2009年京都枚方大会のご案内と講演募集
──────────────────────────────────
日程:2009年3月27日(金)〜 30日(月)
27日(金):ショートコース(1)「漂砂流砂系における堆積物動態と地形変化の
とらえ方」,(2)「石油探鉱データを使用した地下地質堆積環境イメージング」
28日(土):個人講演(基調講演含む),総会議事,懇親会
29日(日):個人講演(基調講演含む),最優秀口頭・ポスター発表の表彰,堆
積学トーク・トーク
30日(月):巡検
会場:大阪工業大学情報科学部枚方キャンパス
講演申込締切:2009年2月13日(金)
講演要旨締切:2009年2月20日(金)17:00
巡検申し込み締切:2009年2月13日(金)
ショートコース申し込み締切:2009年3月6日(金)
詳しくは,http://sediment.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】地質調査総合センター第13回シンポジウム(2/26)
──────────────────────────────────
「海域・沿岸域の資源・環境・防災—持続的発展に向けた海洋地質研究—」
日時 平成20年2月26日(木) 13:00-17:45
会場 秋葉原ダイビル コンベンションホール(東京都千代田区外神田)
参加費 無料
詳細および参加登録・CPD登録は以下のサイトから、
http://www.gsj.jp/Event/090226sympo/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報
──────────────────────────────────
■高知大学海洋コア総合研究センター技術職員募集
職種および人員 技術職員(常勤職員) 1名
応募資格 4年制理工系大学卒業以上の学歴を有し、大学や国・自治体・企業等
の研究機関で質量分析計やX線機器などの機器分析の経験を2年以上有すること。
ただし、大学院等における研究歴は資格要件の職務経験に含みます。
応募期限 平成21年2月16日(月)17時必着
http://www.kochi-u.ac.jp/marine-core/
■広島大学大学院理学研究科地球惑星システム学専攻教授公募
職種および人員: 教授 1名
専門分野: 本専攻の中期計画の目標 「地球惑星進化素過程の解明と地球環境の
将来像の予測」に沿い、地球惑星システムにおける地球環境化学に関連した分野
応募締切り: 平成21年2月16日(月)必着
http://www.hiroshima-u.ac.jp/top/saiyo_syusyoku/kyoinkobo/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】1月の博物館特別展示・イベント情報
──────────────────────────────────
1月も博物館では、たくさんの特別展示やイベントをご用意してみなさまのお越し
をお待ちしております。 寒いこの季節は、室内の講座や体験イベントが充実し
ています。事前申し込みが必要なものもありますので、カレンダーやWebページを
ご確認の上お早めにお申し込み下さい。
(新着情報:杉並区立科学館/財団法人斎藤報恩会 など)
1月の博物館イベント情報は↓↓↓
http://www.geosociety.jp/name/content0029.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】地質マンガ 「薄片道」
──────────────────────────────────
「薄片道」 作:向吉秀樹 画:Key
http://www.geosociety.jp/faq/content0140.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
シンポや巡検の報告を掲載しませんか? 現在ストックゼロです。(編集部)
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.054 2009/1/29 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.054 2009/01/29 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┬┴──
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★ 目次
【1】IODP米国主催 スクール・オブ・ロック2009参加募集のご案内
【2】学術会議シンポジウム:第3回GEOSSアジア太平洋シンポジウム
【3】 秋田大学東京セミナー 「男鹿半島と私とジオパーク構想」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】IODP米国主催 スクール・オブ・ロック2009参加募集のご案内
──────────────────────────────────
IODPアメリカ実施機関は、IODP科学掘削船のひとつである「ジョイデス・レゾ
リューション号」の船上で、教育関係者を対象にしたスクールを開催します。ア
メリカ国内からの参加者に加えて、IODP国際枠として日本から2名の教育関係者が
参加することができます。
■募集対象:小中高校の理科教諭、博物館・科学館の学芸員、大学の地球科学系
の教員など
■募集人数:日本から最大2名が参加できます。
応募多数の場合は選考が行われます。
■実施期間:2009年6月23日から7月5日までの13日間(船上)
■スクール実施場所:
科学掘削船「ジョイデス・レゾリューション号」船内
乗船場所:サンディエゴ(カリフォルニア州・アメリカ)
下船場所:ビクトリア(ブリティッシュコロンビア州・カナダ)
■実施海域:東太平洋沿岸部のファン・デ・フーカ海域
ファン・デ・フーカ海域は太平洋北東部、バンクーバー沖に位置します。ここで
は、ファン・デ・フーカ海嶺と呼ばれる中央海嶺が発達しており、太平洋の海洋
地殻が生成され、年間速度4cm程度で海底が拡大しています。この海域では海底の
玄武岩でできた海洋地殻の高まりから数十度の熱水が湧出していることが知られ
ています。IODPでは、2004年に、IODP発足初の航海である第301次航海「ファン・
デ・フーカ海嶺東翼部の玄武岩質海洋地殻の水理地質学的構造」を実施しました。
詳細は下記URLのページよりご覧ください。
http://www.j-desc.org/m2/expeditions/exp301.html
■スクール内容:海底下から採取した地質試料(コア試料)や掘削孔内長期流体
観測装置(CORK)を用いた地層内の流体挙動などファン・デ・フーカ海嶺の地質
について、航海を体験しながら船上の研究ラボで学ぶことができます。
■第1次参加申込締切:2009年2月4日(水)
■お問い合わせ:
IODP日本実施機関である地球深部探査センター
お問い合わせください。
電話:045-778-5647 FAX:045-778-5704
電子メール:cdex@jamstec.go.jp
■注意事項
・本スクール参加にかかる旅行費用等は参加者の負担となります。
・本スクールは英語で実施されます。
・乗船にあたり、IODPアメリカ実施機関との乗船手続きが必要となります。
・参加者は、スクール参加経験を授業や展示イベントなどに活用することが求め
られます。
・本スクールは、洋上での研究航海中に実施されます。研究計画の変更などに伴
い、スケジュールの変更や開催が中止される可能性があります。
・本スクールの実施主体は、IODPアメリカ実施機関(Consortium for Ocean Lead
ership)となります。日本地球掘削科学コンソーシアムと地球深部探査センター
では、参加希望者への情報提供などをサポートします。
■主催者
Deep Earth Academy
Consortium for Ocean Leadership
1201 New York Avenue, NW, 4th Floor
Washington, DC 20005 USA
Attn: Sharon Cooper
Or Fax: 202-462-8754; email: scooper@oceanleadership.org
School of Rock 2009」ウェブサイト
http://www.oceanleadership.org/learning/school_of_rock/09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】学術会議シンポジウム:第3回GEOSSアジア太平洋シンポジウム
──────────────────────────────────
昨年7月のG8北海道洞爺湖サミットにおいて、「気候変動及び水資源管理
に関し、観測、予測及びデータ共有を強化することにより、全球地球観測
システム(GEOSS)の枠内の努力を加速化する」ことが合意されるなど、地
球観測が果たすべき役割がますます高まっております。この度アジア太平
洋地域におけるGEOSSへの取組強化の一貫として「分野横断のための観測
データの共有」をテーマとした標記シンポジウムを開催しますので、お知
らせします。
日時:平成21年 2月4日(水)〜2月6日(金)
場所:京都リサーチパーク(京都府京都市下京区中堂寺粟田町93)
主催:地球観測に関する政府間会合(GEO)事務局
プログラム等、詳細については以下のURLをご覧下さい。
http://www.prime-intl.co.jp/geoss/
参加登録:参加無料。上記URLよりお申し込み下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】 秋田大学東京セミナー 「男鹿半島と私とジオパーク構想」
──────────────────────────────────
日時:平成21年2月10日(火)16:00〜17:00
(交流会 17:00〜18:30)
会場:キャンパスイノベーションセンター 2階多目的室2
東京都港区芝浦3−3−6(JR山手線田町駅東口徒歩1分)
講師: 秋田大学工学資源学部 地球資源学科教授 白石 建雄
演題: 「男鹿半島と私とジオパーク構想」
参加申込締切:平成21年2月6日(金)
※セミナー修了後,意見交歓・親睦のため簡単なパーティーをいたします。
(交流会に参加費:3,000円を当日受付にて申し受けいたします。)
申込先:秋田大学工学資源学部広報・企画係
TEL:018−889−2318
FAX:018−889−2300
E-mail:kokoki@jimu.akita-u.ac.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
シンポや巡検の報告を掲載しませんか? ご投稿をお待ちしています。(編集部)
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質マンガ 地質学は理系か文系か?
地質マンガ
戻る|次へ
地質学は体育会系..大学のとき,私の先輩が言った言葉は,確かにその通りでした.しかし,野外調査は大変な事ばかりではありません.自然と直にふれあいながら,地層を見て,さまざまな問題に取り組むことによって,室内では学ぶことのできない観察力を身につけることができますし,それに基づいた応用力も身に付きます. このマンガで,先輩と後輩は,山の中の谷や沢に沿って調査しています.このような場所は,川によって地面が深く削りこまれているので,土の下の岩盤を調べることに適しています.また,崖や海岸なども,地面の下の地層の重なりを調べることに適しています. このように野外を歩いて地層調査することを,地表踏査,と言い,地層が露出している場所を,露頭,と言います.地表踏査は,18世紀から行われている古い調査手法ですが,今でも地質図作りなどで大変重要な作業ですし,最近は,海底でもこのような試みがなされています. (調査に行くときは,装備をきちんと用意して,なるべく複数人数で行くように).
あなたのアイデアがマンガになります!
例えば次のような文章で投稿されたものがこんなマンガに清書されます。
■ 投稿された原作
■ 完成品
「地質学者の彼氏を持つと」
1.今日は二人でお買いもの。久しぶりの銀座デート♪
2.二人同時にショーウィンドウを指さして「あっ!」
3.女「ねーねーこの服すごくかわいい!値段もそんなに高くないし」
4.男、壁にはりついて「うぉー大理石の中にアンモナイトが」
女、呆れて「そっちかい…」
地質学会のメールマガジンで連載中の「地質マンガ」は
みなさま(原作)+イラストレータKeyさん(画)
により作られています。地質の魅力を伝える作品を募集しています。現在ストックゼロで即時掲載の状態です。ゆくゆくは英語化して世界の地質学を席巻する予定です!?どうぞご協力をお願い致します。いけてる作品をぜひ!
投稿はこちらから
淡青丸KT-08-30次航海と鹿児島での火山灰採取
淡青丸KT-08-30次航海と鹿児島での火山灰採取
信州大学大学院総合工学系研究科(理学)山岳地域環境科学専攻
伊藤拓馬
写真1 マルチプルコアの採取風景.
写真2 グラビティーコアラーの引き揚げ風景.
写真3 遠州灘と熊野灘で採取された試料の剥ぎ取り標本.海底タービダイトの堆積構造が明瞭に観察できた絶好の機会であった.
平成20年11月13日から17日にかけて,淡青丸KT-08-30次航海(主席研究員は東大の白井正明博士)が行われた.本航海の主な研究目的は,遠州灘と熊野灘を調査域として,沿岸域から深海底までの砕屑物の運搬過程を明らかにすることであった. 本航海は,東京台場港を出港して遠州灘と熊野灘で試料採取を済ませた後,鹿児島港に帰港した.また,私たちは下船後に鹿児島市周辺に分布する火山灰の試料を採取した.ここでは,淡青丸航海と鹿児島における火山灰採取の様子の一部を紹介する.
1.淡青丸航海の様子
陸域で生産された砕屑物が陸棚以深の深海底まで運搬されるには,タービディティーカレントが重要な役割を担う.タービディティーカレントの発生には,嵐や洪水といった気象的なイベントや,地震による海底斜面の崩壊といったものが関係するとされる.このように形成されたタービディティーカレントは,深海底まで流れ下り,最終的にタービダイトとして海底に保存される.本航海では,熊野トラフおよび遠州トラフに流れ込む海底谷において,過去約100年間のタービダイトの堆積履歴を明らかにし,陸棚上から深海底までの砂質粒子の運搬履歴をタービダイトや陸棚堆積物の分析を通して推定すること,また可能ならばタービダイトが深海底環境に及ぼす影響を明らかにすることが目的であった.
11月13日の天候は晴天.絶好の航海日和となり,淡青丸は最初の試料採取地点のある遠州灘へと移動した.翌日14日に採取地点に到着して,朝7時から採泥が始まった.採泥には,船上から海底にパイプを突き刺して採泥する“マルチプルコアラー”と“グラビティーコアラー”と呼ばれる柱状採泥器が用いられた.マルチプルコアラーは,軟らかい海底表層の堆積物を連続的に採泥することができ,一度に最大8本の柱状試料を採泥できるという点で優れているが,採泥できる試料の長さが40cm程度と短い(写真1).一方,グラビティーコアラーは,マルチプルコアラーでは貫入が難しい砂質堆積物を採取することが可能だが,採取される柱状試料は一度に1本と限られる(写真2).このような両者の利点をうまく使い分けて採泥作業が進められた.
遠州灘では,約10cmの厚さを持ち,上方細粒化を示すタービダイトが採取された.順調に採泥作業を進め,淡青丸は次の採取地点がある熊野灘へと移動を始めた.移動中は,ひたすら採取された試料の処理に明け暮れた.柱状試料を半割して,岩相記載,色調や帯磁率といった基礎的なデータを取った後,粒度組成,有機物,元素組成,帯磁率異方性といった分析の目的に応じて試料を取り分けた.
翌日15日には,熊野灘で採泥が行われ,遠州灘と同様に試料の基礎的なデータを取り,試料を取り分けた.このような日程で,遠州灘および熊野灘で水深100m程度の陸棚から水深2000m程度の海底盆までの試料を採取することができた.
今回は,保存用の試料として剥ぎ取り標本を作製した.私自身,剥ぎ取り標本の作製は初めての経験であり,良い勉強になった.親水性樹脂で不織布に貼り付けた剥ぎ取り標本は,タービダイトの堆積構造を観察する絶好の材料となると共に,剥ぎ取った後の柱状試料の半裁面の観察・記載を容易にする.船上では剥ぎ取り標本を採取地点ごとに机上に並べて,乗船研究者皆でタービダイトの形成過程やタービダイト形成の原因となる災害イベントに関する議論を行った(写真3).
採泥日数は,14日と15日の2日間と限られていたが,天候に恵まれたこともあり,予定されていた地点で多くの採泥が成功した.熊野トラフ西縁斜面では,1度のマルチプルコア採取で得られた試料でも,柱状試料ごとに挟まれるタービダイトの枚数や層位が異なり,斜面における流路分布の複雑さを垣間見た.今後,タービダイト内の粒度組成などの解析を行い,深海底までの堆積粒子の運搬過程の解明に役立てる予定である.
2.鹿児島での火山灰採取
16日の下船後,私たちは鹿児島大学で開催されていた特別展「鹿児島の活火山」を見学した.ここには,多くの岩石標本や火山灰の剥ぎ取り標本が展示されており,鹿児島の火山の歴史や人と火山との関わりを学ぶことができた.この特別展では,翌日の火山灰採取の基礎知識を仕入れることができた.火山灰採取の際は,首都大学東京の大石雅之博士が現地案内をして下さった.
桜島は,北岳・南岳火口を中心とする成層火山であり,山腹に側火山を配する.桜島誕生時から約5000年前までは主に北岳を中心に活動し,その後,南岳の活動が主になった.現在,南岳火口とその側火山の昭和火口が主に噴煙を上げる.鹿児島湾は,約29000年前の巨大噴火により形成された姶良カルデラの名残であり,姶良カルデラ南部に約26000年前に後カルデラ火山として形成されたのが桜島である.約29000年前の巨大噴火は,見かけの体積で500km3以上の火砕流や降下軽石を産み,南九州全域を埋め尽くし,シラス台地を形成したらしい.桜島は,過去に少なくとも17回の噴火を繰り返しており,記録に残る噴火は,764年の天平宝字噴火,1471年の文明噴火,1779年の安永噴火,1914年の大正噴火,1946年の昭和噴火がある.
18日は,午前中は桜島で活火山の様子と1914年の大正噴火の噴出物を見学した.午後は姶良火砕噴火の噴出物を見学し試料採取を行った.最初に立ち寄った袴腰では,大正噴火で流出した溶岩流が鹿児島湾に流入した場所を見学した.熱い溶岩流が海水に突入し,冷却されてできた黒色でガラス質の表面が認められた.また,冷却節理の発達した枕状溶岩のような形態を示すものもあった.烏島は,大正噴火前までは海に浮かぶ島であったが,噴火時に溶岩流がこの島を埋め立てたという歴史がある場所である.このように海を隔てた島が埋め立てられる噴火は,火山史上でも珍しいことらしく,かつての烏島上に記念碑が建立されていた.また,この噴火は,桜島と大隅半島は陸続きにした.この噴火の噴出物の総量は,約0.8km3と見積もられている.大正噴火の威力を肌で知ることができる場所であった.
写真4 赤生原の露頭で観察できる降下軽石(下位)と溶岩流(上位)との層位関係.
写真5 鹿児島県指定文化財に指定されている埋没鳥居.自然の猛威を後世に伝えるために保存されている.
写真6 大隅降下軽石(下位)と妻屋火砕流(上位)の境界.
写真7 入戸火砕流堆積物.
赤生原(あこうばい)にある露頭は,大正噴火の降下軽石と溶岩流との層位関係を知る上で重要であり,降下軽石が溶岩流に覆われる様子が観察できた(写真4).湯之平展望所では,現在は活動していない北岳火口,大正の割れ目噴火の谷地形を望めた.黒神にある鹿児島県指定文化財となっている埋没鳥居も,大正噴火の噴出物によるもので,かつて高さが3mもあった鳥居が今はわずかに地表に顔を出すに過ぎない(写真5).
桜島の見学を終えた午後には,シラス台地を形づくる姶良火砕噴火における一連の噴出物の露頭を観察した.それらは,春山原(はるやまばい)に向かう林道沿いの露頭で観察することができた.下位から大隅降下軽石,妻屋火砕流,亀割坂角礫層,入戸火砕流堆積物という層位関係にある.大隅降下軽石と妻屋火砕流の境界を見ることができた(写真6).入戸火砕流の下位に濃集する亀割坂角礫層は,入戸火砕流噴出初期に岩盤が吹き飛ばされて形成されたものらしい.入戸火砕流(写真7)のco-ignimbrite ashとして,姶良丹沢テフラ(AT火山灰)が噴出したとされている.この露頭の大きさや,角礫の大きさを見て,巨大な噴火であったことやAT火山灰層が日本全国に広く分布しており鍵層の1つとなったのも納得できる.AT火山灰層は,陸域や海域で重要な年代面を提供する.日本全域に分布するAT火山灰層を生んだ入戸火砕流を観察でき,試料採取ができたことは,海底柱状試料でATを認識し年代面を挿入する上で重要なことである.入戸火砕流の試料採取が成功し,今回の鹿児島で火山灰を採取するという目的は充分に果たされた.
鹿児島での火山灰採取の巡検は,火山噴出物の観察や試料採取のみならず,火山と人々の生活の関わりについても学ぶことができた.桜島は日本でも有数の活火山であり,土石流の発生頻度が日本一と伺った.土石流は山麓に扇状地を作り出す.扇状地は,水はけが良く果樹園や畑に適した土地として住民に利用される.ここで作られる桜島大根や桜島小みかんといった地方名産物は,火山と深く関わっている.先人達は,火山のもつ二面性と上手く付き合ってきた.鹿児島は,火山と上手く共生している町であるといえる.
3.乗船研究者
淡青丸には,地質学,地理学や生物学を専門とする研究者が乗船した.乗船研究者(敬称略)は,主席の白井正明(東大),亀尾桂(東大),大村亜希子(東大),川村喜一郎(深田地質研究所),大石雅之(首都大),若林徹(東大),南雲直子(東大),丹羽雄一(東大),嶋永元裕(熊本大),北橋倫(熊本大),吉田和弘(マリンワークジャパン),清野船長を始めとする淡青丸乗組員の皆様,そして筆者の伊藤拓馬(信州大)であった.
白井正明さん,大村亜希子さん,大石雅之さん,川村喜一郎さんには,原稿を読んで頂き,多くのご意見を頂いた.淡青丸では多くのことを学んだ.ここで学んだこと糧として,今後の研究に生かしていきたい.お世話になった方々,本当にありがとうございました.
No.055 2009/2/3 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.055 2009/02/03 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】コラム 淡青丸KT-08-30次航海と鹿児島での火山灰採取
【2】2月の博物館特別展示・イベント情報
【3】「地球なんでもQ&A」活用術: アピールに使おう!
【4】関東支部イベント案内
【5】日本ジオパーク記念式典
【6】IYPE日本:ポータルサイト「惑星地球の扉」試験運用
【7】学術会議主催:公開シンポジウムのお知らせ
【8】J-DESCコアスクール 2コース 参加申込受付中!
【9】地惑連合大会 J-DESCセッション「地球掘削科学」のお知らせ
【10】9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference &
EXPO SGEM2009
【11】地質マンガ 「地質学は理系か、文系か?」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】コラム 淡青丸KT-08-30次航海と鹿児島での火山灰採取
──────────────────────────────────
伊藤拓馬(信州大学)
平成20年11月13日から17日にかけて,淡青丸KT-08-30次航海が行われた.本航海
の主な研究目的は,遠州灘と熊野灘を調査域として,沿岸域から深海底までの砕
屑物の運搬過程を明らかにすることであった.
本航海は,東京台場港を出港して遠州灘と熊野灘で試料採取を済ませた後,鹿児
島港に帰港した.また,私たちは下船後に鹿児島市周辺に分布する火山灰の試料
を採取した.ここでは,淡青丸航海と鹿児島における火山灰採取の様子の一部を
紹介する.
続きは、コチラから
http://www.geosociety.jp/faq/content0056.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2月の博物館特別展示・イベント情報
──────────────────────────────────
まだまだ寒い日が続きますが、博物館では暖かい室内での特別展示と室内
講座をご用意して、みなさまのお越しをお待ちしています。
詳しくはこちらから
http://www.geosociety.jp/name/content0037.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】「地球なんでもQ&A」活用術: アピールに使おう!
──────────────────────────────────
地質学会ホームページをご活用頂きありがとうございます。ホームページはリ
ニューアル以降たいへんアクセスが伸びており、毎日1000人以上の読者が訪れる
人気サイトとなっております。これもひとえに皆様のおかげです。特に「地球な
んでもQ&A」というコーナーの人気が高く、約6万8千人以上の読者数となっており
ます。このコーナーは会員の皆様が作る想定問答集です。「問 AはBですか?」
「答 いいえCです」といった明瞭簡潔な解説がポイントです。一般によく誤解さ
れやすい事項の解説でもよいですし、執筆者ご自身が関係する分野をネタにして、
読者にアピールすることも可能です。どうぞご活用くださいますようお願いしま
す。
「地球なんでもQ&A」http://www.geosociety.jp/faq/content0001.html
「投稿案内」http://www.geosociety.jp/publication/content0009.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】日本地質学会関東支部イベント案内
──────────────────────────────────
■地質技師長が語る地質工学余話〜地質技術伝承講演会
昨年2008年4月から6月にかけて3回の講演会を催し,ご好評をいただきましたが,
今年も計3回実施することとなりました.
近年,プレート論で代表されるように日本のアカデミズム地質学は大きな進展を
とげてまいりましたが,同時に,わが国の社会基盤整備の状況を見ると,応用地
質学もまたこの分野において大きな役割を果たし,アカデミズム地質学に勝ると
も劣らない進歩があったと思っています.
いわゆる2007年問題を迎えて,これら日本の応用地質技術を支えた団塊の世代の
方々が次々と一線を退かれています.そこで,関東支部ではこれら団塊世代の会
員の方々から地質技術のノウハウを伝授していただくための企画として,下記の
ような一般向けの講演会を行います.
日程:
第4回目 4月11日(土)14:00-16:00 国立科学博物館日本館大会議室
テーマ「農業の有する多面的機能と地質技術者の役割(仮)」
講演者 山本昭夫
第5回目 5月10日(日)(地質の日)14:00-16:00 国立科学博物館日本館
第6回目 6月6日(土)10:00-12:00 国立科学博物館新宿分館
(なお,6月6日は支部発表会を同会場にて引き続き行います)
参加費:無料(日本館での開催の場合は別途入館料がかかります)
参加申込:ジオスクーリングネットまたはFAX(学会事務局)にて
共催予定:独立行政法人 国立科学博物館
協賛予定:(社)全国地質調査業協会連合会 関東地質調査業協会
連絡先:
日本地質学会事務局内 関東支部
電話:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156
担当幹事 緒方信一(中央開発(株))
■地質見学会:茨城県平磯海岸
この見学会は,地質学・地学の普及を目的とするとともに,ジオパークにおける
ジオツアーの実験的試みとして行うものです。詳細は次号にてお知らせいたしま
す。
日時 2009年5月9日(土)9:30 JR常磐線勝田駅集合,16:00 鹿島臨海鉄道大洗駅
解散
費用 大人 3000円程度(貸切バス代,保険代,資料代含む)
中学生以下 1500円程度(小学生以下の参加は要保護者同伴。)
昼食は各自持参
見学場所 茨城県平磯海岸(茨城県ひたちなか市)
平磯海岸周辺では白亜紀に形成した「那珂湊層群」をみることができます。ここ
では「異常巻きアンモナイト」や「翼竜」の化石が産出しました。見学会当日は
「大潮」(予定)です。アンモナイトが産出した露頭が広く露出し,老若男女だ
れもが地層観察できます。
平磯海岸の詳しい地質情報につきましては,茨城大学地質情報活用プロジェクト
のホームページ(http://geotourde.gozaru.jp/)をご覧下さい。
募集人員 40名
案内人 茨城大学地質情報活用プロジェクトメンバー(茨城大学理学部学生)お
よび茨城大学理学部教員
応募方法 下記連絡先にメールまたは往復ハガキでお申し込み下さい。
○メールの場合は必ず件名「地質見学会申し込み」を明記して下さい。
○日本地質学会会員の有無に関わらず,誰でも申し込みできます。
○申込には,住所,氏名,所属または学校名,年齢,性別,連絡先を明記して下
さい。
○応募者数が募集人員を超えた場合は,抽選により参加者を決定します。
○申込締切:2009年4月10日(金)(ハガキの場合は当日消印有効)
申し込み先・連絡先 地質見学会担当幹事 本田尚正
〒310-5812 茨城県水戸市文京2-1-1 茨城大学理学部地球環境科学コース
TEL&FAX 029(228)8396 E-mail nhonda@mx.ibaraki.ac.jp
■第3回研究発表会「関東地方の地質」一般講演募集
この研究発表会では,特に学生・若手研究者・若手技術者への発表の場の提供を
考えています.この場合,学会員の有無を問いません.卒論・修論の内容や土木
地質の調査結果などを是非この機会に発表し,意見交換や交流の場としてはいか
がでしょうか.もちろんベテラン研究者・技術者の方の発表も歓迎いたします.
研究発表会では関東地方の地域地質研究の発表を歓迎しますが,地質学に広く関
係する内容ならばそれ以外のテーマも受け付けます.
当日は地質技術伝承講演会,地方地質誌「関東地方」刊行記念シンポジウム,
支部総会も同時開催されます.
日時:2009年6月6日(土)13:00〜17:00
会場:国立科学博物館 新宿分館(予定)
講演申込要領
講演内容:関東地方の地質研究を歓迎しますが,地質学に関係する内容ならば全
て可.
申込資格:学会員(連名の場合はどなたか一人が学会員ならば可),ただし学生
および若手研究者・技術者(35歳未満)は学会員でなくとも可.
投稿・発表料:無料
講演方法:今回はポスターのみとさせていただきます.
講演申込方法:発表者(氏名・所属・責任者連絡先E-mail),発表タイトルを下
記担当幹事宛に電子メールかファックスでお知らせください.
担当幹事:中澤(産総研),E-mail:t-nakazawa@aist.go.jp,FAX029-861-3591
講演申込締め切り:平成21年4月6日(月)
講演要旨締め切り:平成21年5月8日(金),様式は後日お知らせします.
上記案内は関東支部ホームページhttp://kanto.geosociety.jp/ にも掲載されま
す.ご参照ください.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】日本ジオパーク記念式典
──────────────────────────────────
第一回目の日本ジオパーク設立を期して,ジオパークを広く社会にアピ
ールすると共に今後の活動指針を示唆することを目的として,日本ジオ
パーク記念式典が開催されます。
主催:日本ジオパーク委員会
後援:日本地質学会ほか
日時:2009年2月20日(金) 12:00〜17:00
場所:東京大学小柴ホール
対象:一般,関連官庁,地方自治体,企業,マスコミ
参加費無料,先着順200名程度
ポスター展示:各日本ジオパークの紹介など
詳しくは、
http://www.gsj.jp/jgc/event/20090220.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】IYPE日本:ポータルサイト「惑星地球の扉」試験運用
──────────────────────────────────
IYPEアウトリーチの一助として,地学関連の展示や催しがある博物館・科学館,
ジオパークをはじめとする自然公園や各種遺産,調査研究機関
や大学など,あるいは教材のヒントがあるウェブサイトやIYPE日本参加会員の皆
さんが用意されているQ&Aやキッズのページなどを掲示
したポータルサイト「惑星地球の扉」を試験運用しています。是非とも,ご意見
やご提案などをIYPE日本事務局までお寄せ下さい。
ポータルサイト「惑星地球の扉」
http://www.gsj.jp/iype/portal.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】学術会議主催:公開シンポジウムのお知らせ
──────────────────────────────────
「アジアにおける持続可能な水資源管理
(Sustainable Water Resources Management in Asia)」
アジアの水問題は今、経済発展と急速な都市化・工業化に加え、気候変
動という新たな課題に直面している。
本シンポジウムでは、アジア学術会議(SCA)加盟国等から水資源管理に
係わる気鋭の研究者を招いて、アジア地域における持続可能な水資源管理
に向けた取組を紹介するとともに、急速に変化する社会、経済、環境条件
下で水資源をいかに安定的、持続的かつ安全に利用していくか、それに向
けた学術的・政策的課題について考える。
日 時 平成21年2月27日(金) 9:30〜18:00
場 所 日本学術会議講堂(東京都港区六本木7−22−34)
主 催 日本学術会議国際委員会
定 員 200名 同時通訳付き
参加費 無料(事前申込制)
詳細は、以下のホームページを御覧ください。
http://www.env.t.u-tokyo.ac.jp/swm/index.html
問い合わせ先
「アジアにおける持続可能な水資源管理シンポジウム」事務局
Tel & Fax: 03-5841-6244
E-mail: swmsympo09@env.t.u-tokyo.ac.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】J-DESCコアスクール 2コース 参加申込受付中!
──────────────────────────────────
J-DESCではコア解析のスキルを学んでもらういくつかのコースをもうけていま
す.現在,コア解析基礎コースの参加申込を受け付けておりますのでぜひご応募
ください.
期間:2009年3月14日(土)〜17(火)
場所:高知コアセンター
対象:ピストンコア(海洋,湖沼など)およびODP/IODPなどの深海掘削コア,ICD
Pなどの陸上掘削コア等を主な研究材料としている(もしくは,これから研究しよ
うとしている)学生,大学院生,研究者など
※ 博士課程院生以上の方には,実習グループのリーダー役をお願いする場合があ
ります.
募集人数:18名
申込〆切:2009年2月10日(火)
※定員に達し次第、募集を締め切らせて頂きます.
※詳細は下記URLをご参照下さい。
http://www.j-desc.org/m3/coreschool/basic.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】地惑連合大会におけるJ-DESCセッション「地球掘削科学」のお知らせ
──────────────────────────────────
これまでスペシャルセッションだった「地球掘削科学」は、今年からレギュラー
セッションとして認められました。
本セッションは、統合国際深海掘削計画(IODP)/国際陸上科学掘削計画
(ICDP)に関わるこれまでの成果報告や技術開発に関する発表を広く募集してい
ます。またIODPに関しましては、2013年から次のフェーズを迎え、そのための科
学目標策定会議(INVEST)開催も来年に迫っています。そこで、 IODPの次のフェ
イズに向けたサイエンスプランへの提案およびNew Scienceに関する発表も歓迎
致します。
レギュラーセッション1年目の今年、より多くの方にご参加頂き、セッションを
盛り上げていければと思っています。
予稿集原稿投稿締切:2月6日(金) 12:00 最終締切
大会HP: http://www.jpgu.org/meeting/
また、昨年に引き続き、J-DESCタウンホールミーティングも開催致しますので、
こちらもみなさんお誘い合わせの上ご参加下さい。ご参加をお待ちしています。
問い合わせ先:
セッション代表コンビーナ・井上麻夕里(mayuri-inoue@ori.u-tokyo.ac.jp)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO SGEM2009
──────────────────────────────────
日程:2009年6月14日(日)〜19日(金)
会場:Bulugaria Alnena Resort
締切:Early Registration:2009年2月28日
Abstract Submission:2009年3月31日
詳しくは,http://www.sgem.org/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】地質マンガ 「地質学は理系か文系か?」
──────────────────────────────────
「地質学は理系か文系か?」 作:川村喜一郎 画:Key
http://www.geosociety.jp/faq/content0143.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
シンポや巡検の報告を掲載しませんか? 現在ストックゼロです。(編集部)
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.056 2009/2/9 geo-flash
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.056 2008/02/09 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
日本地質学会名誉会員、松本達郎 九州大学名誉教授におかれましては、
2月7日心不全のため、福岡市の病院でご逝去されました。享年95歳であり
ました。本学会、ならびにこれまで地質学への多大な貢献をなされてきた
故人の功績を讃えるとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
会員の皆様に、謹んで御連絡申し上げます。
会長 宮下純夫
────────────────────────────────
なお、通夜は8日に行われ、松本家と九大地球惑星科学教室の合同葬が
9日に行われます。
合同葬 2月9日 (月) 午前11時から
場 所 積善社 福岡斎場
福岡市中央区古小烏町(ふるこがらすまち)70−1
TEL.092−522−0789
喪 主 南部すみ子 (長女)
────────────────────────────────
同じく加藤磐雄名誉会員が、昨年12月27日にご逝去されていたことがわかりまし
たので、あわせてお知らせいたします。
──────────────────────────────────
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質マンガ 船酔いはつらいよ
地質マンガ
戻る|次へ
船に乗るとき,一番不安なのは,船酔いです.船酔いは,つらいものですが,そんなに長く続くモノでもなく,峠を越えると,徐々に慣れてくるものです(と信じている).久しぶりに乗船すると,船のプロの船員さんですら船酔いになるそうです. マンガでは,冷蔵庫が船の動揺で,中に入れてある食品をはき出してしまっていますが,冷蔵庫などの扉はマジックテープなどで固定されていて,多少の揺れでは開かないように工夫されています.マンガの揺れはものすごかったのですね.そして,船に備え付けてあるものは,冷蔵庫を含めて頑丈に固定されていて,簡単には動かないようになっています. 研究用に荷物を船に持ち込むときも,やはり揺れで動かないようにひもなどで固定します.これを固縛(こばく)と言います.これを行わないと,重要な研究用の装置や物品が,揺れて飛んでいって,壊れてしまいますし,けがのもとにもなります.船ではロープワークが必須です.
あなたのアイデアがマンガになります!
例えば次のような文章で投稿されたものがこんなマンガに清書されます。
■ 投稿された原作
■ 完成品
「地質学者の彼氏を持つと」
1.今日は二人でお買いもの。久しぶりの銀座デート♪
2.二人同時にショーウィンドウを指さして「あっ!」
3.女「ねーねーこの服すごくかわいい!値段もそんなに高くないし」
4.男、壁にはりついて「うぉー大理石の中にアンモナイトが」
女、呆れて「そっちかい…」
地質学会のメールマガジンで連載中の「地質マンガ」は
みなさま(原作)+イラストレータKeyさん(画)
により作られています。地質の魅力を伝える作品を募集しています。現在ストックゼロで即時掲載の状態です。ゆくゆくは英語化して世界の地質学を席巻する予定です!?どうぞご協力をお願い致します。いけてる作品をぜひ!
投稿はこちらから
No.058 2009/3/3 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.057 2009/03/03 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】杉山了三会員 文部科学大臣賞!
【2】2009岡山大会関連情報
【3】関東支部からのご案内
【4】本の紹介「科学を志す人びとへ 不正を起こさないために」
【5】2009年度日本地球化学会年会のご案内(地質学会共催)
【6】雄大な北米ロッキーでのフィールドキャンプへ参加しよう
【7】日本学術会議主催講演会「学術分野における男女共同参画促進のために」
【8】3月の博物館イベント情報
【9】東レ科学技術賞および東レ科学技術研究助成候補者推薦
【10】富山大学極東地域研究センター教員公募
【11】地質マンガ「船酔いはつらいよ」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】杉山了三会員 文部科学大臣賞!
──────────────────────────────────
東レ科学振興会主催 東レ理科教育賞(後援:文部科学省)に,本会会員の
杉山了三さん(盛岡一高)が、最高の理科教育賞文部科学大臣賞(1名)に
選ばれました。 題目は「地域を生かした生徒自作標本による岩石・鉱物学習」
です。
詳しくはhttp://www.toray.co.jp/tsf/rika/rik_020.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2009岡山大会関連情報
──────────────────────────────────
■4/28から、講演申込が開始となります。
講演申込期間:2009年4月28日(火)〜6月23日(火)17時締切
(郵送での申込の場合は、6月16日(火)必着)
講演申込,要旨送付とも同日の締切です。
昨年同様、J-STAGEの講演申込システムを利用の予定で、現在2009年版の申込画面
を準備中です。webサイトから24時間いつでもお申し込み頂けます。
講演を予定されているの方は、早めの準備をお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】関東支部からご案内
──────────────────────────────────
■地質見学会:茨城県平磯海岸
日時 2009年5月9日(土)9:30 JR常磐線勝田駅集合
費用 大人 3,000円程度
見学場所 茨城県平磯海岸(茨城県ひたちなか市)
募集人員 40名
案内人 茨城大学地質情報活用プロジェクトメンバー(茨城大学理学部学生)
および茨城大学理学部教員
申込締切:2009年4月10日(金)
http://kanto.geosociety.jp/
■第3回研究発表会「関東地方の地質」一般講演募集
日時:2009年6月6日(土)13:00〜17:00
会場:国立科学博物館 新宿分館
講演内容:関東地方の地質研究を歓迎しますが,地質学に関係する内容ならば全
て可.
申込資格:学会員(連名の場合はどなたか一人が学会員ならば可),ただし学生
および若手研究者・技術者(35歳未満)は学会員でなくとも可.
講演申込締切:2009年4月6日(月)
http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】本の紹介「科学を志す人びとへ 不正を起こさないために」
──────────────────────────────────
科学倫理検討委員会編(執筆者:黒川 清,浅島 誠(代表),御園生 誠,松
本三和夫,笠木伸英,札野 順,佐藤 学,猿田享男,池内 了,北澤宏一,池
勝智恵美)
2007年10月20日発行.(株)化学同人.152 p. 1800円+税.ISBN978-4-7598-11
39-1
2005年10月に組織を刷新した日本学術会議は,2006年10月3日に声明「科学者の行動規範」を発表したが,これとは別の形で「科学者とはいかにあるべきか」を若者たちに伝えるために,学術会議の検討委員会での討議内容と化学同人の原案をもとに本書を作成したという.
本書の章立てと各章の執筆者は次のようになっている.序章 科学研究を担う人たちへ(黒川),第1章 科学とは何か(浅島),第2章 科学者の評価と不正(御園生),第3章 社会における科学の位置(松本),第4章 科学者の行動規範(笠木),第5章 不正を防止するために(札野),第6章 科学者の倫理と教育(佐藤),第7章 実例から学ぶ(猿田ほか),第8章 若い学生・研究者へ!困ったときのQ&A(池内・北澤・池勝ほか).
序章は談話調である.「データも見ず議論もしないで論文に名前をつけたがる教授などは,みっともないし,問題外である」.「捏造のプロセスを検証し,誰が悪いとか,『魔女狩り』のようなことをしても建設的ではない.もっと根っこの問題を研究者自身が自発的に改革していくことこそが求められている」.「学術雑誌を発行するのも(学会の)大事な活動であろうが・・・研究者を育てることこそが,最も大事な使命であろう」.「なぜか大学でも研究者は内向き,鎖国マインドである」.「日本は若手研究者の層が薄いし,独立していない・・・『力が足りない』,『実体験が少ない』,『修羅場をくぐっていない』,『ひ弱だ』と一般的に感じるのは筆者だけではあるまい」.
第1章以後は講義調になる.「科学者にとっては・・・名誉や富はあくまで付属物であり,重要なことは『科学的知識の体系にどのような新しい貢献をなしえたか』という点である」.「科学研究に対して正しい判断を行えるよう,科学者自らが自分の研究をよく理解し,他者にわかるように説明を行う必要がある」.「科学研究費を適切に使用するに当たっては,単に適切に使用したというだけでなく,その適切性を第三者に説明できるよう,証拠となる書類を作成し,保管する義務がある」(研究ノートの励行も強調している).「インパクトファクターや被引用回数での比較は,簡便で定量的ではあるが,その特徴を理解して利用しなければ正当な評価とはいえない」.
科学者の代表的な不正行為はFFP,つまり捏造(Fabrication),改ざん(Falsification),盗用(Plagiarism)である.不正行為の一覧表(p. 80)には,(1)データの捏造,(2)データの改ざん(矛盾データの恣意的削除),(3)研究成果やアイデアの盗用,論文の剽窃,(4)不適正なオーサーシップ(著者の構成と順番),(5)個人情報の不適切な扱い,プライバシーの侵害,(6)研究資金の不正使用,(7)論文の多重投稿,(8)研究成果の紹介や研究費申請における過大表現,(9)研究環境でのハラスメント,(10)研究資金提供者の圧力による研究方法や成果の変更,(11)利益相反(の不申告や利益誘導?)がリストアップされている.ただしこの表には,「はじめの3項目は,合理と実証に基づく科学を根底から揺るがす行為といえるが,一方その他の項目に関しては,前提なしに不正行為と判定することが困難な場合もある」という注が付いている.過去5年間に日本で発生した科学者の不正行為の種類と件数の表(p. 109)によると,論文の二重投稿(83件),研究の盗用・論文の剽窃(26),プライバシー侵害(14)が上位を占める.そしてFFPと「責任ある研究活動Responsible Conduct of Research」との間には「疑わしい行動Questionable Research Practice」があり,それらは虚偽記載Misrepresentation,不正確Inaccuracy,偏向Biasなどであると指摘されている.
誤りや誇張と不正との関係については,「いくら誠実に研究を行っても誤りを犯すことはあり・・・誤りそのものを不適切な行為とはいわない.ただし,誠実に研究を行ったうえでの誤りであるか否かは問われよう.また,誤りとわかった後の対応が誠実でなければ,不適切な行為として糾弾されることになる」,「マスメディアに発表するときに,誇張した表現(『世界初』など)や誤解を生みやすい表現(『実用化に道を開く』など)を多用することも好ましくない」と述べている.そして,「科学者の反省材料」として,誤った論文に端を発した常温核融合の研究ブーム(1989-1992年)における論文数の推移と常温核融合を肯定した論文の割合のグラフを提示している.
一方で,倫理や社会貢献を過剰に振り回す危険についても第3章で述べられている.「研究という営みのもつ性質を多面的に理解することなく,倫理によってすべてを律するのは,やや性急といえよう」.「『科学ヒューマニスト』と呼ばれる一群の科学者たちによって,1930年代のイギリスで草の根的に行われた「市民のための科学」運動は,第二次大戦の勃発と前後して戦時における科学動員へとつながっていったことが知られている」.日本でも戦前・戦中には科学技術動員を目的とした国民的な理科振興が高らかにうたわれた.また,科学研究費獲得競争の否定的側面について,「問題は,基礎研究を目標志向研究の基準で評価し,それによって一律に予算配分をしようとする点にある.さながら,一般道でレーシングカーを走らせて競争させるようなもので,やがて事故(不正)が起こることは目に見えている」と述べている.
不正防止に果たす学会の役割は大きい.「ピアレビュー(査読)は,同業者の利益を守るために部外者を排除する仕組みではない.研究最前線の知見を判断できる専門能力を備えた研究者同士の率直な相互批判によって,知の品質を保つための仕組みである」と述べ,韓国の黄寓錫(ファン・ウソク)教授のクローン牛疑惑事件を例に出しながら「科学研究の成果は,ピアレビューを経た論文というかたちで,学界の認知を得たうえで社会的な評価を得なければならない」,「科学が科学者の自立的な営みであるためには,社会の動向とは独立した自浄能力をもっている必要がある」と述べている.そして不正防止の実効的な方針として,「米国の研究公正局が90年代初頭に行った「規制強化」が失敗に終わった事実からも,『不正行為を取り締まる』という消極的かつ性悪説的な姿勢ではなく,『責任ある研究活動を奨励する環境をどのようにして整備するか』という前向きで性善説に基づく取り組みが必要」ということが強調されている.
本書は日本学術会議の「科学者の行動規範」の内容解説,NASAの「倫理プログラム」,日本医師会の「医の倫理綱領」などの資料も充実し,参考文献や解説がどのページにも欄外に付記されていて,読者に親切な構成になっている.特に有用なのは第8章の充実したQ&Aである.「予想外の実験データが出たときにはどう扱えばよいか」,「論文数を増やすために細切れに発表してもいいか」,「研究成果を2つの雑誌に出すとき,どうすれば二重投稿にならないか」,「ある先生から『私の論文が引用されていない』と抗議されたがどう対処すればよいか」,「教授から与えられたテーマで研究して論文にする段階になったが,著者構成や順番をどうすべきか」,「同僚の研究データに不自然な感じを持っているが,誰に相談すればよいか」,「新聞社から科学的なコメントを求められたがどう対応すればよいか」,「2つの商業雑誌から原稿を依頼されたが,同じ原稿を渡してもよいか」,「国の研究費で得た科学的成果で本を執筆し商業出版してよいか」などの現実的かつ深刻な問題に一応の解答が与えられている.
地質学会も学術会議の「行動規範」に先んじて2003年に「倫理綱領」を制定したが(会員名簿の冒頭に掲載),共同研究上のトラブルによる除名申請,著者と査読者の間のトラブルによる抗議沙汰,二重投稿,禁止区域での標本採集への社会的批判などが発生している.我々の倫理についてより実践的に考えるために,会員諸氏に是非本書の一読をお勧めする.関連して,米国ベル研究所の事件を扱った松村 秀「論文捏造」(中公新書ラクレ)も一読されたい.
(石渡 明)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2009年度日本地球化学会年会のご案内(地質学会共催)
──────────────────────────────────
会期:2009年9月15日(火)〜17日(木)
会場:広島大学理学部
共催:日本地質学会ほか
参加費用 (予定)
予約申込:会員5000 (3000)円 会員外7000 (4000)円(括弧内学生)
当日受付:会員6000 (4000)円 会員外8000 (5000)円
懇親会費:予約5000 (3000)円 当日6000 (4000)円
*共催学会会員は日本地球化学会会員と同等
関連イベント(予定):公開講座「放射線と宇宙」(9月13日)
問い合わせ:
広島大学大学院理学研究科地球惑星システム学専攻内
e-mail: GSJ2009@hiroshima-u.ac.jp
http://www.geochem.jp/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】雄大な北米ロッキーでのフィールドキャンプへ参加しよう
──────────────────────────────────
Yellowstone Bighorn Research Association (YBRA)では毎年、主としてアメリ
カの学部学生を対象にしたフィールドキャンプをやっています(参加学生の男女
比は年によって違いますがほぼ1に近い)。これは大変伝統のあるフィールドト
レーニングで、長い間、プリンストン大学が担ってきました。その後1992〜2007
年はペンシルバニア大学、2008年以降はヒューストン大学が主管となって、毎夏2
回にわたって5週間ぶっ続けで行われます。千葉大学では修士1年の大学院生が90
年代の終わりからほぼ毎年1-2名参加しています。アメリカでは主として学部学生
対象ですが、語学の問題もあり、日本からの参加は大学院生となっていた方がよ
いと思われます。もちろん日本の大学から遠路来たとなると大いに歓迎されます
から躊躇する必要はありません。これまでの参加者は異口同音に、非常に勉強に
なるだけでなく、地球に関する世界観が変わり、しかも国境を越えた友情がひろ
がると語っています。下に案内のURLを載せておきますので、興味のある方は、是
非、ご参加ください。
http://www.trinity.edu/departments/geosciences/YBRAFieldCampBrochure2009.
pdf
締切は3月15日(日)ですので希望者は至急手続きをしてください。ご不明な
点がありましたら、千葉大学の伊藤谷生<tito@earth.s.chiba-u.ac.jp>までお問
い合わせください。
(千葉大学理学研究科 伊藤谷生)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】日本学術会議主催講演会「学術分野における男女共同参画促進のために」
──────────────────────────────────
日時:2009年3月2日(月)13:00-17:30
会場:日本学術会議 講堂
趣旨:日本学術会議では、学術分野における男女共同参画の現状と課題を明らか
にするため、国・公・私立大学を対象とした初めての大規模なアンケート調査を
平成19年に実施しました。この調査 の分析結果と学術分野における状況改善の
ために平成20年7月に公表した提言を基に、市民に対する意識啓発と具体的な活動
のための提案を行います。
プログラム(予定)【敬称略】
基調講演 1)猪口邦子(衆議院議員)/2)板東久美子(内閣府男女共同参画局長)
パネルディスカッションほか
参加費:無料 定員:300名
プログラム等詳細は、こちら
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf/70-t-1.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】3月の博物館イベント情報
──────────────────────────────────
まだ寒い日が続いていますが,少しずつ春が近づいているのが感じられるように
なってきました。博物館では、春を感じられる野外観察会も各地でスタートします。
詳しい日程はイベントカレンダーでご確認下さい。
博物館イベントカレンダーはこちら
http://www.geosociety.jp/name/content0038.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】平成21年度東レ科学技術賞および東レ科学技術研究助成候補者推薦
──────────────────────────────────
■東レ科学技術賞
候補者の対象 貴学協会が関与する分野で,下記に該当するもの/学術上の
業績が顕著なもの/学術上重要な発見をしたもの/重要な発明をして,その効果が
大きいもの/技術上重要な問題を解決して,技術の進歩に大きく貢献したもの
推薦締切期日 2009年10月9日(金)弊会必着(学会締切:9/10必着)
■東レ科学技術研究助成
候補者の対象 貴学協会が関与する分野で国内の研究機関において自らのア
イディアで萌芽的基礎研究に従事しており,今後の研究の成果が科学技術の進歩,
発展に貢献するところが大きいと考えられる若手研究者(原則として推薦時45才
以下)
推薦締切期日 2009年10月9日(金)弊会必着(学会締切:9/10必着)
各推薦書用紙・詳細等は,ホームページから
http://www.toray.co.jp/tsf/index.html
学会推薦の件数には制限がありますので、お早めにお申し出下さい
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】富山大学極東地域研究センター教員公募
──────────────────────────────────
募集職名及び人員:准教授または講師 1名
専門分野:北東アジアにおける環境変動に関わる分野(理系)
授業担当等:当センター以外の部局(理学部および大学院理工学教育部等)におい
て専門分野に関する授業及び教養科目を担当していただくことになります.
応募条件:博士課程を修了またはそれと同等の能力を有する者
採用年月日:2009年10月 1日
応募締切日:2009年6月30日(火)当日消印有効
詳しくは、
http://www.u-toyama.ac.jp/jp/employ/pdf/fes_20090630.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】地質マンガ
──────────────────────────────────
「船酔いはつらいよ」作:川村喜一郎 画:Key
http://www.geosociety.jp/faq/content0147.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年度末のシンポジウム等の報告を掲載しませんか?すぐに掲載できます(編集部)
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
第7回地球システム・地球進化ニューイヤースクール参加体験談
第7回地球システム・地球進化ニューイヤースクール(参加体験談
名古屋大学大学院環境学研究科 博士課程後期1年
宮川和也
写真1:活き活きと講義を聴く参加者
写真2:坂口先生の実験の様子
写真3:懇親会での1コマ
【はじめに】
皆さん,ニューイヤースクール(NYS)をご存知でしょうか?NYSは地球科学に関して幅広く見識を深める場として毎年1月に開催されています.学部生や大学院生,若手研究者の集いの場としては,夏の学校や若手会などが良く知られていると思います.NYSは歴史こそ浅いものの,それらとはまた違った,様々な分野の交流の場または広い学問的視野を養う場として大変有意義な機会になっています.本稿では,NYSの紹介を交えながら,私が参加したNYS-7 (2009年1月10日~11日,東京・代々木)の体験談をご紹介します.
NYSでは毎年各分野の最先端で活躍されている講師の方々や地球科学を取り巻く業界の方々が招かれ,2日間で10コマほどの講演が行われます.1コマ1コマが大学院の集中講義の様であり,とても内容の濃い時間を過ごすことができます.私はこれまでにNYS-5, 6, 7と3年間,参加をしました.自身の研究生活(学生生活)では1年間の大半を所属する大学の研究科の中で過ごします.日常的に他の人の研究の話を聞いたり,論文を読んだりしていますが,研究スタイル等の環境の多くは名古屋大学の影響を強く受けていると思います.そんな中で,他大学の方や他の研究機関の方の話を直に聴けて,ディスカッションができるという機会はとても貴重であると感じています.私が毎年のNYSを楽しみにしている一番の理由は,この点にあります.
【NYS-7の様子】
NYSの参加者層は学部生から研究者まで様々です.NYS-7では学部生33名,修士32人,博士17人,非常勤講師・PD11人,常勤講師21人,その他2人の合計116人の方が参加していました.学部生が多いことが特徴的です.進学や就職が間近に控えている学部生や大学院生にとって,研究の面白さを発見する場であり,また地球科学に関連する職業の選択肢を発見する場にもなっている様です.私は修士1年生の時に,博士課程後期への進学に関する悩みを抱えながらNYS-5に参加しました.そのときに多くの方と話をし,相談をできたことが大変励みになり,頑張ってみようという思いのきっかけを得ることができました.
参加者の専門分野も様々です.地質学,岩石学,古気候・古環境・古生物学,地球物理学,火山学,雪氷学,地球化学,地震学など,地球惑星科学連合の中でやや地球寄りの分野の方が多く集まります.会場では参加者の方は名札をつけているので,誰がどんな研究を専攻されているのかが分かり易くなっています.
NYS-7の講義は通常のレクチャー(60分)とEXレクチャー(30分)から成ります.60分レクチャーは各講師の方が,研究に関して各々の専門分野を分かり易く説明する基礎レクチャーです.一方, EXレクチャーは少し視野を広げて,地球科学やサイエンス一般に広く共通する話題や職業に関するレクチャーです.今回は伊賀公一さん(カラーユニバーサルデザイン機構)の「バリアフリープレゼンテーションの仕方」,土屋健さん(株式会社ニュートンプレス,ニュートン編集室)の「地球科学を武器にメディアで働く」,中井紗織さん(国立科学博物館)の「みんなで広げるサイエンスコミュニケーションの輪!」という3つのEXレクチャーを聴きました.このEXレクチャーで聴ける講演は,普段なかなか聴く機会が無いがとても興味深い講演という点において,NYSの大きな魅力であると感じています.
NYS-7では次の講師の方々の講義を聴きました.橘省吾さん(東大・理学研究科),竹内望さん(千葉大・理学研究科),坂本天さん(JAMSTEC),武岡英隆さん(愛媛大・沿岸環境科学研究センター),長久保定雄さん(JOGMEC),坂口有人さん(JAMSTEC),青矢睦月さん(AIST),磯崎行雄さん(東大・総合文化研究科)の8名です.太陽系形成から雪氷学,地球温暖化,沿岸環境,メタンハイドレート,断層力学,変成岩,大学人の理科離れについてなど,多種多様な話を聴きながら,また,同時に自身の研究との接点を探したり考えたりしていました.
NYS-5, 6, 7を通して何度か実験の実演によるレクチャーがありました.NYS-7では坂口有人さんがバネとおもりをスライドさせて,沈み込み帯における地震の発生サイクルに関する実験を実演されました.文献等で何度か読んでいて知っていた実験なのですが,実際に目にすると少し感動があります.NYSで講演される実験は,十分に誰でも再現可能なものなので,ここで得た知識はいつか学部生に対するセミナー等で活用できます.面白いことを知ったという思いから,ここでもNYSに来て良かったと感じます.
初日(1月10日)は午前10時半に開会し,午後4時半まで休憩を挟みながら講義が行われました.その後,その日の講師の方々と参加者が個々に集まり,議論を交わすという「サイエンスディスカッション」の時間が1時間程ありました.この時間は,各講師の方に対して質問したいことがあるが質疑応答の時間に聞くことができなかった,という様なことをじっくりと話し合える良い機会です.しかし,多数の参加者がいるために時間内ではディスカッションが終わらないことがあります.この場で終わらない話はそのままその後の夕食・懇親会・ポスターセッションの時間にすることができます.夕食・懇親会・ポスターセッションの時間では旧知の方とつもる話をすることもありますが,昼間の講演で得た新たな知見を共通の話題として,必ず新たに多くの方と知り合いになります.こういった場の大切さは改めて言うまでもないでしょうが,多様な研究仲間と知り合えることを一言で表現すると,「嬉しい」です.
二日目(1月11日)は午前9時に始まり,午後3時40分まで休憩を挟みながら講義が行われました.その後に再び「サイエンスディスカッション」の時間があり,午後5時過ぎに閉会となりました.閉会後に今後のNYSの運営に関わりたい方が集まり,話し合いが行われました.NYSは有志の方が事務局を構成し,運営を行っています.NYS-7が終わり,私がこれまでに参加してきた3回のNYSの運営を行って来た事務局は,来年度から新たなメンバーに変わります.これに伴いNYSもまた新たに生まれ変わると思います.
【今後のNYS】
来年度に向けた新たな事務局によるNYSの動きは既に始まっています.地球科学コミュニティの移り変わりに伴い,今一度「何のための会なのか」を明確にすることから出発しています.これまでの様な分野の多様性を生かし,質の高いレクチャーという伝統を保ちつつ,新たな方向性を模索しています.参加者も聞き手に準じるだけではなく,主体的になれる会を考えています.また,これまでのNYSの様子は下記のURLから見ることができます.
http://quartz.ess.sci.osaka-u.ac.jp/~earth21/school/gakkou/gakkou.html
【おわりに】
最後になりましたが,この素敵な場を企画・運営して下さったNYS-5, 6, 7の事務局の方にこの場をお借りしてお礼を申し上げます.本当にありがとうございました.
No.057 2009/2/17 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.057 2008/02/17 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】「ジオパーク」がいよいよ日本でも始まります
【2】コラム:地球システム・地球進化ニューイヤースクール参加体験談
【3】「地質の日」新しいポスターが出来ました!
【4】2009年岡山大会関連情報
【5】北海道支部総会・個人講演会・日本地質学会長講演会
【6】都市問題研究シンポジウム 「沖積平野の地盤・環境特性」
【7】信州大学山岳科学総合研究所シンポジウム
【8】Blue Earth'09 の開催のご案内
【9】石油技術協会 第2回特別見学会のご案内
【10】The 2nd International Conference of Natural Resources in Africa on Sustainable Development in the Nile Basin Countries (ICNRA)のご案内
【11】高知大学海洋コア総合研究センター全国共同利用研究公募
【12】北海道大学大学院地球環境科学研究院准教授公募
【13】地質マンガ「船酔いはつらいよ」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「ジオパーク」がいよいよ日本でも始まります
──────────────────────────────────
「ジオツーリズム」を楽しむ場所「ジオパーク」がいよいよ日本でも始まります
国際惑星地球年(IYPE) の活動の最後になる今年は,日本のジオパークの活
動にとっても記念すべき年となります.
2月20日には日本ジオパークに認証された7箇所の認証式と記念式典が開催さ
れ,5月中旬にはこれまでの日本ジオパーク連絡協議会が発展的に解消し,新
たに日本ジオパークネットワークがスタートする予定です.また,今年後半に
は,国内初の世界ジオパークネットワーク加盟地域が決定します.
地質学会ジオパーク支援委員会では,ジオパーク認定地域,認定を目指して
いる地域への学術的支援はもとより,新たにジオパークとしてふさわしい地域
の開拓も視野に入れて,活動しています.地質学会会員の皆様にもジオサイト
の情報提供などのご協力をお願いすることもあるかと思いますが,ご支援のほ
どよろしくお願い申し上げます.ジオパーク支援委員会では一般向けのパンフ
レットを作りましたが,現在そのパンフレットに掲載されていない地域で,新
たにこの地域を開拓してはどうか,というご推薦がございましたら,学会事務
局宛に連絡いただければ委員会でも検討させていただきます.パンフレットは
地質学会ジオパーク支援委員会のホームページ
http://www.geosociety.jp/geopark/content0017.html
からpdfファイルでダウンロードできますのでご覧下さい.
なお,5月16日(土)から幕張メッセで開催される地球惑星連合大会でも,
一般公開プログラム(参加費は無料)としてジオパークのセッション(A004)
が開かれますので,ご参集いただければ幸いです.
地質学会ジオパーク支援委員会
委員長 天野一男
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】コラム:第7回地球システム・地球進化ニューイヤースクール
(New Year School 7)の参加体験談
──────────────────────────────────
名古屋大学大学院環境学研究科 博士課程後期1年 宮川和也
皆さん,ニューイヤースクール(NYS)をご存知でしょうか?NYSは地球科学に関
して幅広く見識を深める場として毎年1月に開催されています.学部生や大学院
生,若手研究者の集いの場としては,夏の学校や若手会などが良く知られている
と思います.NYSは歴史こそ浅いものの,それらとはまた違った,様々な分野の交
流の場または広い学問的視野を養う場として大変有意義な機会になっています.
本稿では,NYSの紹介を交えながら,私が参加したNYS-7 (2009年1月10日~11日,
東京・代々木)の体験談をご紹介します.
続きは、コチラ
http://www.geosociety.jp/faq/content0056.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】「地質の日」新しいポスターが出来ました!
──────────────────────────────────
今年も5月10日(日)が地質の日です.
新たにポスターを作成しました.地質の日事業推進委員会では,これから印刷して各博物館等にお送りしますが,WEBサイトにはpdfファイルをおいてありますので,ご自由にお使いください.
http://www.gsj.jp/geologyday/
今年も,昨年にまして見学会等イベントを行いましょう!
(地質の日事業推進委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2009年岡山大会関連情報
──────────────────────────────────
本年の地質学会岡山大会と連動して行われる地質情報展のタイトルが決まりまし
た.
「地質情報展2009おかやま−ワクワク,発見,瀬戸の大地−」
日時 9月5日(土)・6日(日)
場所 岡山駅西口デジタルミュージアム
大会会場の岡山理科大学へのバスの乗り場の正面です.地質学会も展示,ワーク
ショップを行いますので,ぜひご協力をお願いいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】北海道支部総会・個人講演会・日本地質学会長講演会
──────────────────────────────────
日程:2009年5月30日(土)13:30〜(予定)
場所:北海道大学理学部7号館7-310号室(予定)
個人講演申込締切:2009年4月3日(金)
タイトル,発表者名,所属,連絡先を明記し,申込ください.
〒060-0819 札幌市北区北19条西12丁目 北海道立地質研究所内
日本地質学会北海道支部事務局 (担当:高清水まで)
TEL/FAX:011-747-2475/737-9071
E-Mail:yasu@gsh.pref.hokkaido.jp
日本地質学会長講演会 「オマーンから日高—マントルと海洋地殻を見る-」宮
下純夫会長による講演を予定
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】都市問題研究シンポジウム 「沖積平野の地盤・環境特性」
──────────────────────────────────
主催:大阪市立大学複合先端研究機構・大阪市立大学都市研究プラザ
後援:日本地質学会近畿支部・日本応用地質学会関西支部
月日 :2009年3月7日(土)10:00〜17:30
会場 :大阪市立大学文化交流センター大ホール
参加費:無料
問い合わせ先:
日本地質学会近畿支部:三田村宗樹(大阪市立大学)
TEL:06-6605-2592 FAX:06-6605-2522
E-mail: mitamura@sci.osaka-cu.ac.jp
詳しくは、http://kinki.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】信州大学山岳科学総合研究所シンポジウム
──────────────────────────────────
「登山道の安全を考える」
北アルプス白馬大雪渓を中心に、観光利用と登山者の安全等について、地形学や
地質学の研究者、行政(国、県、村)、観光事業者等が一同に会して話し合う画
期的なシンポジウムといえますので、ご紹介します。
主催 信州大学山岳科学総合研究所・白馬村
日程:2009年2月21日(土) 10:00〜17:00
会場:信州大学理学部 C棟2階大会議室
入場無料、申込不要
http://ims.shinshu-u.ac.jp/symposium.html#090221
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】Blue Earth'09 の開催のご案内
──────────────────────────────────
独立行政法人海洋研究開発機構では保有する海洋研究船及び有人潜水調査船等の
深海調査システムを活用して得られた研究の成果発表を目的としてBlue Earth'09
を開催いたします。
日時:2009年3月12日(木)〜13日(金)
場所:立教大学 池袋キャンパス 7号館
〒171-8501 東京都豊島区西池袋3-34-1
入場無料です。事前申込の必要はありません。
http://www.jamstec.go.jp/jamstec-j/maritec/rvod/blue_earth/2009/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】石油技術協会第2回特別見学会のご案内
──────────────────────────────────
「地震探査データ取得機器の見学会」
開催日:2009年3月13日(金)
場所:(株)地球科学総合研究所・嵐山研究センターおよび工業団地管理センター
(埼玉県)
対象:学生・院生及び同行する教官 ※定員に余裕がある場合は一般の参加も可
参加費:1,000円(昼食代込み)
申込期限:2009年3月6日(金)
詳細は石技協HP(http://www.japt.org/)「最新情報」を参照下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】The 2nd International Conference of Natural Resources in Africa on Sustai
nable Development in the Nile Basin Countries (ICNRA)のご案内
──────────────────────────────────
The 2nd International Conference of Natural Resources in Africa on Sustai
nable Development in the Nile Basin Countries (ICNRA)
日程2009年5月11日-12日
会場:Egypt, Cairo University
詳細 はこちら(PDF)
申込用紙(word)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】高知大学海洋コア総合研究センター全国共同利用研究公募
──────────────────────────────────
高知大学海洋コア総合研究センターは、海洋コアの総合的な解析を
通じ、地球掘削科学に資する研究を推進するため、センターの施設・
設備を共同利用に供します。この度、平成21年度に実施する研究
課題を公募しますので、皆様にお知らせいたします。
公募要領、申請書様式、主要設備一覧等、詳しくは下記ウェブペー
ジ内に掲載しておりますのでご参照下さい。
http://www.kochi-u.ac.jp/marine-core/cooperations/zenkyo_index.html
申請書提出期限:2009年2月28日(土)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】北海道大学大学院地球環境科学研究院准教授公募
──────────────────────────────────
所属:地球圏科学部門環境変動解析学分野 准教授
(大学院環境科学院 地球圏科学専攻 物質循環・環境変遷学コースに参画の予定)
専門分野:地球環境変動に関連し、陸域および水域における温室効果ガスや そ
の挙動を支配する物質の循環機構の解明に取り組む方を募集し ます。フィール
ドワークと地球化学的・生物地球化学的手法に基づき、研究・教育を推進してい
ただける方を希望します。
公募締切:2009年4月30日(必着)
詳細は、http://www.ees.hokudai.ac.jp/をご覧下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】地質マンガ
──────────────────────────────────
「船酔いはつらいよ」 作:川村喜一郎 画:Key
http://www.geosociety.jp/faq/content0147.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ワークショップやシンポジウムの報告を掲載しませんか? 即掲載可です(編集部)
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質マンガ ラップ百万回
地質マンガ
戻る|次へ
あなたのアイデアがマンガになります!
例えば次のような文章で投稿されたものがこんなマンガに清書されます。
■ 投稿された原作
■ 完成品
「地質学者の彼氏を持つと」
1.今日は二人でお買いもの。久しぶりの銀座デート♪
2.二人同時にショーウィンドウを指さして「あっ!」
3.女「ねーねーこの服すごくかわいい!値段もそんなに高くないし」
4.男、壁にはりついて「うぉー大理石の中にアンモナイトが」
女、呆れて「そっちかい…」
地質学会のメールマガジンで連載中の「地質マンガ」は
みなさま(原作)+イラストレータKeyさん(画)
により作られています。地質の魅力を伝える作品を募集しています。現在ストックゼロで即時掲載の状態です。ゆくゆくは英語化して世界の地質学を席巻する予定です!?どうぞご協力をお願い致します。いけてる作品をぜひ!
投稿はこちらから
海外便り 台湾より:変成岩の大渓谷巡検
海外便り 台湾より:変成岩の大渓谷巡検
台湾の地質図(http://140.115.123.30/earth/shade/twgeomaps.htm).西側のポイント1がTaroko,2がTienhsian,3が最後の海岸露頭.詳しい地質図はこちら
台湾は小さい島ですが,フィリピン海プレートとユーラシアプレートの衝突によって形成されたと考えられる3000mの高峰が連なる中央山脈を初め,躍動的な地質地形を観察する事ができます.台湾東部花蓮には変成岩の渓谷が存在し,こちらは観光地ともなっており,地質を観察する事が容易となっています.昨年,国立中央大学の陳維民先生が学生用に行われた台湾北東部花蓮巡検に参加しました.
巡検の様子を写真を中心にお届けします.
太魯閣(taroko)国家公園
Tananao metamorphic complexはPalezoicからMesozoicのSchist. 主にGreenschist, Psammic schist, Black schist, Marble, Gneissからなります.
■Changchun Shrine付近.
Changchun Shrineは台湾の中央横断道路建設時に亡くなった方の為に建てられた神社(廟?)だそうです.この神社のそばに断層が走っており,断層の中心部で岩石が崩落している.断層は写真を写している方(手前)へ伸びています.
国家公園内なのでもちろんハンマーの使用はできません.でも川岸に下りて近づく事は可能でした(公式に大丈夫かどうかは分かりません).
ananao Schist. 褶曲の構造を観察.スケールが大きい褶曲からmmスケールの褶曲まで観察可能.
■Tienhsian 付近. Changchun Srineより更に西に進んだポイント
Metamorphosed m四ange. Melange内には主にタフ,砂岩様のブロックが観察される.ブロックは非対称変形をしている.
同Tananao metamorphic complexですが,国家公園ではなく,ハンマーのふるえる川にての観察.(立ち入るには許可証が必要でした).川が西から東に流れており,それをさかのぼって観察して行きました.
Metabasalt.枕状の構造が観察できます.
スケールが大きいので転石まで大きい.転石かどうか注意しなければ露頭と間違えてしまいそうでした.ここは国家公園内ではないので,岩石の持ち帰りは自由な様で,切り取られた転石をいくつも見ました.写真の手前と奥の不自然に平な岩石がそれ.切り取り方もスケールが大きい.おかげで変成岩の美しい縞状の構造を観察する事ができました.
こでもTaroko国家公園と同じく褶曲が発達しており,数十mスケールからmmスケールまで観察が可能です.
最後に,東の海岸沿いに露出するMioceneのagglomerate.中には柱状節理が取り込まれている露頭も.この層順の形成場所,形成過程等は様々な議論があるそうです.
おまけ
巡検の始まり:台湾にて初めての巡検で出発を楽しみにしていたけれど,2台で出発する予定の1台の停車していたバスに原付がつっこむという衝撃的な始まりでした.台湾では事故に会うと,その日にはその厄(?)を落とす為かこの写真の用に豚肉が入った麺を食べるそうです.
Taroko渓谷にて
あちこちで見かける落石注意の看板.地震時などやはり時々落ちてくる様です.
やはりこのような渓谷に道を作るのは並大抵の仕事ではなかった様です.
川沿いでは温泉がある事も.露頭に行くために温泉を通過して行くのですが,ずかずか乗り越えて行くのが少し心苦しく感じたりしました(日本人だから?).といいつつ写真は撮っていたり.
No.059 2009/3/17 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.059 2009/03/17 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】海外便り 台湾より:変成岩の大渓谷巡検!
【2】支部情報
【3】日本地方地質誌 5.近畿地方 会員特別割引販売のお知らせ
【4】学術会議報告「地球温暖化問題解決のために—知見と施策の分析、
我々の取るべき行動の選択肢」の公表
【5】2009年度日本地球化学会年会(地質学会共催)
【6】藤原賞50回記念講演会
【7】TV情報
【8】日本学術振興会特別研究員/-RPD 平成22年度採用分募集
【9】電力中央研究所地球工学研究所研究職募集
【10】ニュース誌の表紙写真急募!
【11】地質マンガ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】海外便り 台湾より:変成岩の大渓谷巡検! 川端訓代
──────────────────────────────────
台湾東部花蓮には変成岩の渓谷が存在し,こちらは観光地ともなっており,
地質を観察する事が容易となっています.
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/faq/content0152.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】支部情報
──────────────────────────────────
■関東支部:第3回研究発表会「関東地方の地質」一般講演募集
日時:2009年6月6日(土)13:00〜17:00
会場:国立科学博物館 新宿分館
講演申込締切:2009年4月6日(月)
講演要旨締切:2009年5月8日(金)
詳しくは、http://kanto.geosociety.jp/
■北海道支部:総会・個人講演会・日本地質学会長講演会
日程:2009年5月30日(土)13:30〜(予定)
場所:北海道大学理学部7号館7-310号室(予定)
個人講演申込締切:2009年4月3日(金)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
■中部支部:2009年年会のお知らせ
6月13日(土)、総会・シンポジウム・懇親会
6月14日(日) 地質巡検
会場:山梨大学教育人間科学部講義棟
シンポジウム:「フォッサマグナ地域の地殻変動現象と中部地方の最新情報」
詳細は後日お知らせいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本地方地質誌 5.近畿地方 会員特別割引販売のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地質学会編集 「日本地方地質誌 5.近畿地方」
(472頁,口絵8頁)が刊行されました。会員の皆様に,
特別割引価格で販売をいたします.専用申込用紙にて、
直接朝倉書店ご注文下さい.
■■会員特別割引価格20,500円(定価23,100円)■■
詳しくは、
https://www.geosociety.jp/user.php
(会員のページへログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】学術会議報告「地球温暖化問題解決のために—知見と施策の分析、
我々の取るべき行動の選択肢」の公表
──────────────────────────────────
第72回幹事会(2/26開催)において、標記の報告が承認され、3/10公表しま
した。(地球温暖化問題に関わる知見と施策に関する分析委員会)
本報告は、我が国および世界の重要な課題になっている地球温暖化現象
の把握とその対策について、日本学術会議に設置された「地球温暖化等、
人間活動に起因する地球環境問題に関する検討委員会」(第20期課題別委
員会)及び「地球温暖化問題に関わる知見と施策に関する分析委員会」
(第21期課題別委員会)において審議を重ね、地球温暖化問題に関して現
在得られている科学的知見を精査し、それに基づいた現実的な行動の選択
肢を示しております。報告全文は、
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-21-h72-1.pdf
【問い合わせ先】 日本学術会議事務局参事官(審議第二担当)付
Tel:03-3403-1056 FAX:03-3403-1640 E-mail:s254@scj.go.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2009年度日本地球化学会年会(地質学会共催)
──────────────────────────────────
2009年9月15日(火)〜17日(木)
会場:広島大学理学部(東広島市鏡山1−3−1)
共催:日本地質学会ほか
参加費用 (予定)
予約申込:会員5000 (3000)円 会員外7000 (4000)円 (括弧内学生)
*共催学会会員は日本地球化学会会員と同等
http://www.geochem.jp/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】藤原賞50回記念講演会
──────────────────────────────────
本講演会は、若い人たちに科学の楽しさを知ってもらい、科学の裾野を広げ、
将来の科学者を育てる一助となるように、中学生、高校生が科学に関心をもち、
親しめるような内容を織り込みながら、多くの方々にも満足してもらえる内容と
いたします。
日時:2009年4月25日(土) 1:30PM〜4:50PM 無料・要申込
場所:よみうりホール(千代田区有楽町1-11-1)
・基調講演
飯島澄男氏(名城大学教授)【カーボンナノチューブのふしぎ】
岡田典弘 氏(東京工業大学教授)【哺乳類進化のなぞに迫る】
・ミニコンサート:シャンソン 松本かずこ 氏
曲目“愛の讃歌”“水に流して”ほか全4曲予定
・パネルディスカッション:テーマ“研究者を目指す人たちへ”
詳しくは、http://www.fujizai.or.jp/J_koenkai.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】TV情報
──────────────────────────────────
鎌田浩毅会員が下記の大学生向けの教育番組に出演されます.
NHKテレビBS1「ガッチャン!〜世界につながる!学生チャンネル」
放送日2009年3月20日(金)23:10-23:55(45分)
NHK総合テレビ「ソクラテスの人事」
放送日2009年4月2日(木)22:00-22:45(45分)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090304-00000610-san-ent
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】日本学術振興会特別研究員/-RPD 平成22年度採用分募集
──────────────────────────────────
■日本学術振興会特別研究員 平成22年度採用分募集
申請受付期間 平成21年6月3日(水)〜5日(金)(必着)
詳しくは、http://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_boshu_f.htm
■日本学術振興会特別研究員-RPD 平成22年度採用分募集
申請受付期間
平成21年5月13日(水)〜15日(金)(必着)
詳しくは、http://www.jsps.go.jp/j-pd/rpd_boshu_f.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】電力中央研究所地球工学研究所研究職募集
──────────────────────────────────
職種および人員:研究職 1名
専門分野:構造地質学.特に断層岩の解析などに基づく活断層抽出手法の開発や,
地質構造指標と断層破壊挙動を考慮した活断層連動性評価手法の開発に取り組む
方.地質調査を基本としつつ,物質科学や破壊力学等の知識を導入して,新たな
震源断層評価手法の開発に積極的に取り組む意欲を有する方.
応募資格:平成22年3日末時点,修士又は博士課程修了者(新卒・既卒いずれも可)
着任時期:平成22年4月1日
応募締切:決定次第締切
詳しくは、
http://criepi.denken.or.jp/jp/recruit/10/saiyo/kadai.html#06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】ニュース誌の表紙写真急募! 4月号のストックがありません
──────────────────────────────────
日頃のフィールドワークなど,皆様が撮影された自慢の写真をニュース誌の表
紙として紹介してみませんか.国内外を問わず,露頭や地形(風景写真)・鉱物・
化石などなど様々なテーマの写真を受け付けています.
表紙写真以外の記事も随時募集中です.
ご応募をお待ちしています.<journal@geosociety.jp>まで.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】地質マンガ
──────────────────────────────────
「ラップ100万回」作:吉田和弘・川村喜一郎 画:Key
http://www.geosociety.jp/faq/content0150.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年度末のシンポジウム等の報告を掲載しませんか?すぐに掲載できます(編集部)
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
マンガ 海には危険がいっぱい
地質マンガ
戻る|次へ
あなたのアイデアがマンガになります!
例えば次のような文章で投稿されたものがこんなマンガに清書されます。
■ 投稿された原作
■ 完成品
「地質学者の彼氏を持つと」
1.今日は二人でお買いもの。久しぶりの銀座デート♪
2.二人同時にショーウィンドウを指さして「あっ!」
3.女「ねーねーこの服すごくかわいい!値段もそんなに高くないし」
4.男、壁にはりついて「うぉー大理石の中にアンモナイトが」
女、呆れて「そっちかい…」
地質学会のメールマガジンで連載中の「地質マンガ」は
みなさま(原作)+イラストレータKeyさん(画)
により作られています。地質の魅力を伝える作品を募集しています。現在ストックゼロで即時掲載の状態です。ゆくゆくは英語化して世界の地質学を席巻する予定です!?どうぞご協力をお願い致します。いけてる作品をぜひ!
投稿はこちらから
マンガ エアロゾルってなに?
地質マンガ
戻る|次へ
エアロゾルってなになに?
研究船「みらい」に搭載しているエアロゾル研究のための装置.突き出た煙突のような部分からエアロゾルを吸い込み,フィルターでエアロゾルを回収する.
エアロゾルとは、簡単にいうと大気中を漂う“ちり”ですが、火山からの噴煙、工場の煙突や車のテールパイプから出てくる煙、たばこや焚き火の煙、ひいては空をただよう雲や霧、これらも全てエアロゾルです。この意外に身近なエアロゾルですが、地球の気候変動や海洋での微生物の活動に大きな関わりがあることが明らかになっています。
例えば、春の風物詩である「黄砂」現象。中国奥地の砂漠から砂が大気中に巻き上げられて、西風にのって“エアロゾル”として運ばれてきたもので、日本だけでなく、太平洋を越え遠くアメリカ大陸まで到達することが知られています。この黄砂“エアロゾル”は、海では不足がちな大切な栄養分を含んでおり、海の微生物にとって陸の恵みを海へ運んでくれる大切な“運送屋さん”です。またエアロゾルは地面に届く太陽光を遮るため、温室効果ガスとは逆に、地球の大気を“冷やす”作用があると言われています。例えば、雲が空を覆う曇の日、霧のかかった日(雲も霧も水滴状のエアロゾル)を想像してください。太陽の光が地面には届かず寒くなりますね。これと同じ事が、工場や車から出てくるエアロゾルが増えたため、地球全体でも起こっていることが明らかとなっています。また頻繁に観測される、南極や北極のオゾンホールですが、これも氷のエアロゾルが引き起こす特殊な化学反応が引き金となっています。
このように、エアロゾルは現在問題となっている地球環境の変動に大きく関わっており、地球環境の将来を考える上で最も重要な課題の1つです。そして、海洋大気観測船を使った広範囲にわたるエアロゾル観測は(今回の航海では地球半周分、MR08-06「みらい」による研究航海:首席,原田尚美)、陸上では得られない貴重なデータを私たちにもたらしてくれます。
古谷浩志・鄭進永(東京大学海洋研究所),川村喜一郎(財団法人深田地質研究所)
コラム 南海トラフ地震発生帯掘削計画の国際会議に参加して
NanTroSEIZE Stage 1 のSecond Post-Expedition Meeting (以下PEM)が2009年4月15日〜4月17日に京都大学にて行われました。本稿では、PEMでの体験を紹介します。
NanTroSEIZEとは、Nankai Trough Seismogenic Zone Experiments(南海トラフ地震発生帯掘削計画)の略語で、統合国際深海掘削計画(IODP)のプログラムの一つとして現在も進行中です。NanTroSEIZEの目的は、南海トラフに沿って存在する地震発生帯を掘削することによって岩石の取得・計測・長期観測をおこない、地震発生帯で何がおきているのかを明らかにすることです。そのために地球深部探査船「ちきゅう」により水深2000メートル・海底下6000メートルの震源断層固着域まで掘削することになります。計画達成には数年、あるいは十年以上の時間が必要であるため、掘削計画を4つの段階(Stage)に分けており、各Stageがそれぞれ複数の航海で構成されています。最初のStage1では3回の航海が行われ、それぞれExpedition 314,315,316と呼ばれています(この番号はIODPの航海毎につけられる番号です)。
本PEMはNanTroSEIZE Stage1研究者が航海後に一堂に会する初めての会議で、日本はもちろんアメリカ・ヨーロッパ・アジアの各国から研究者が参加し、参加者は総勢78名に上りました(そのうち乗船研究者は61名参加し、それ以外にも航海で取得されたデータや岩石サンプルを使用して研究するShore-based scientistsも参加しました)。会議の目的は、Stage1における研究成果と進捗を関係研究者間で共有し、より大きな成果を生み出すことでした。会議は各航海のリーダーであるCo-chief、研究者のまとめ役であるExpedition Project Manager、そして研究計画を通して科学的手法毎に研究をとりまとめるSpecialty coordinatorを中心に進められました。内容は地球物理学・地質学・岩石学・地球化学・微生物学など多岐にわたり、各研究者の研究状況を簡単に報告するだけでも丸一日かかる様な大がかりなものになりました。また、PEMでは現状報告だけでなく、科学目標毎に分科会を設定し今後達成すべき目標の確認と、100人近い研究者が地震発生帯の理解という一つの目的に向うことによって生じる研究内容の重複を整理し、研究成果を多角的かつ最大にするためにそれぞれがどのような貢献をすべきかを話し合いました。同時に、研究内容に漏れが無いかを確認し、それを補うために何をするべきかが話し合われました。
私はNanTroSEIZE Stage1におけるExpedition 314に乗船研究者として参加し、その時取得された物理検層データを基に、熊野海盆におけるメタンハイドレートの産状を研究しています。この研究成果は、熊野海盆におけるメタンガスをともなう流体の流れがどのようなものかを明らかにし、付加体における流体移動の理解につながると考えています。今回のミーティングの中では、他の航海で取得された同じ地点の岩石コアから得られた情報がどのようなものであったかを確認し、それらは自分の研究にどう反映できそうかなどを、他の研究者と議論することができました。
本PEMにおける科学的な議論はとても真面目な内容でしたが、会議はジョークを交えた終始おだやかな雰囲気でした。多くの研究者は同じ船上で研究を行った他の研究者との再会を喜び、コーヒーブレークや懇親会では参加者が楽しそうに会話をしているのが印象的でした。私自身も2ヶ月間おなじ船上で研究をおこなったフランスの研究者と1年半ぶりに再会し、お互いの近況について報告ができたことがとても嬉しかったです。
本PEMの締めくくりでは、今後行われるStage2以降での掘削計画についての紹介が行われ、今後の進展についてとても楽しみであると同時に、それに関わっている自分の責任の重さを再確認しました。
NanTroSEIZEへの参加そして本PEMを通して、多くの研究者が一つの科学目標に向かって研究をすることの重要性とその難しさを感じました。地震発生帯では地質スケールの時間・空間の中で、数秒あるいはもっと短い時間に断層面で滑り現象がおきており、それらを引き起こす原因には岩石の物性や地中の流体あるいは鉱物の化学反応などいろいろな要素が関わっていると考えられます。そのため、様々な分野の研究者が集いその理解に向かうことが必要になります。しかし、それらの研究は個々に行われるのではなく、自分の研究分野とは異なる分野のことも頭に入れながら、それぞれの研究が地震発生帯を理解するためにどのような意味があるのかを理解し上で行われなければなりません。今までは自分の研究に一生懸命でしたが、今後は自分の研究がさらに大きな科学の中でどのような位置づけにあるのか、どのような貢献ができるのかを考えながら取り組まなければならないと思い至りました。
最後にこの場をお借りして本PEMの準備と進行に関わられたすべての方に感謝申し上げたいと思います。
宮川歩夢(京都大学大学院工学研究科 博士課程後期2年)
写真提供:J-DESC
No.060 2009/4/7 geo-flash
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.060 2009/04/07 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
本学会、ならびに地質学への多大な貢献をなされてきた本学会名誉会員の勘米良
亀齢先生がご逝去されました.突然の悲報に接し、誠に痛惜の念でいっぱいです。
勘米良先生は沈み込み帯の研究で先駆的な功績を上げられ,また多くの人材を育
てられました.
勘米良先生の功績を讃えるとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
会長 宮下純夫
勘米良先生の御葬儀
喪主 勘米良興子(かんめら おきこ) 様(奥様)
通夜 4月7日(火)18:00〜
葬儀 4月8日(水)11:00〜
場所 ベルコ シティホール博多
福岡市博多区博多駅前3-18-21
電話 092-452-4242
FAX 092-452-4255
No.061 2009/4/7 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.061 2009/04/07 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】地質の日(5/10)特別講演会「火山はすごい!」
【2】報告書等の作成に関して—知っておくべきこと—
【3】「地質の日」イベント情報を掲載しませんか?
【4】支部情報
【5】HOPEミーティング参加者募集
【6】三朝国際インターンプログラム2009の案内
【7】2010〜2011年開催藤原セミナー募集
【8】公募情報
【9】地質マンガ「海には危険がいっぱい」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】地質の日(5/10)特別講演会「火山はすごい!」(日本地質学会主催)
──────────────────────────────────
5月10日は「地質の日」です.日本地質学会主催・日本火山学会後援で特
別講演会「火山はすごい!−日本列島の火山をさぐる− 講師:鎌田浩毅会員」
を科学技術館(東京都千代田区北の丸公園2-1)にて開催します.
皆様お誘い合わせの上ご参加下さい.
詳細はこちら、(イベントのポスターPDFもダウンロードできます)
http://www.geosociety.jp/name/content0039.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】報告書等の作成に関して—知っておくべきこと—
──────────────────────────────────
日本地質学会理事会・法務委員会
知的財産基本法が制定されそれに伴い著作物等の保護について厳格に法規制さ
れておりますことは周知の事実でありますが,地質学会においてもコンプライア
ンス面からも,知的財産基本法を遵守しております.
研究成果の報告書を作成に当たり地質学雑誌等の論文を複製・転載する場合は
必ず学会の許諾を取っていただく必要があります.以下に報告書等の作成に当た
り必要な手続きについてお知らせいたします.
http://www.geosociety.jp/outline/content0071.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】「地質の日」イベント情報を掲載しませんか?
──────────────────────────────────
5月10日は「地質の日」です(2008年制定)。
昨年も全国で様々なイベントが開催されました.今年も学会特別講演会をはじめ
多方面でイベントが予定されています( http://www.gsj.jp/geologyday/)。
皆様の周辺(所属機関,支部,専門部会,コミュニティ)でイベントを開催する
予定がありましたら是非ご紹介下さい.メルマガやニュース誌で全国の開催情報
が流れることが「地質の日」の盛り上がりにつながります。
(地質の日事業推進委員会・日本地質学会広報委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】支部情報
──────────────────────────────────
■関東支部:技術伝承講習会/研究発表会「関東地方の地質」
日時:2009年6月6日(土)10:00〜17:30
午前の部>技術伝承講習会
午後の部>研究発表会
会場:国立科学博物館 新宿分館
詳しくは、 http://kanto.geosociety.jp/
■北海道支部:総会・個人講演会・日本地質学会長講演会
日程:2009年5月30日(土)13:30〜(予定)
場所:北海道大学理学部7号館7-310号室(予定)
プログラム等詳細は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
* ■「地質の日」記念展示『支笏火山と私たちのくらし』も開催中
■中部支部:2009年年会のお知らせ
6月13日(土)、総会・シンポジウム・懇親会
6月14日(日) 地質巡検
会場:山梨大学教育人間科学部講義棟
シンポジウム:「フォッサマグナ地域の地殻変動現象と中部地方の最新情報」
http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】HOPEミーティング参加者募集
──────────────────────────────────
HOPEミーティングは、アジア太平洋地域の若手科学者を一同に集めて、ノーベ
ル賞科学者を交えた交流の機会を提供するという合宿形式のイベントです。
今年のHOPEミーティングは「化学(および物理学・生物学を含む関連分野)」
をテーマに、9月27日〜10月1日の間、箱根で開催されます。
講演者は、野依 良治博士、田中 耕一博士他、ノーベル賞受賞者を中心に予定。
募集期間:2009年4月13日(月)〜4月24日(金)
開催日時: 2009年9月27日(日)〜10月1日(木)
会場: ザ・プリンス箱根
テーマ: Art in Science
対象分野: 化学及び関連分野(物理学、生物学等)
主催:(独)日本学術振興会
募集要項等詳しくは、
http://www.hopemeetings.jp/howto-app/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】三朝国際インターンプログラム2009の案内
──────────────────────────────────
実施期間:7月2日(木)〜8月11日(火)(約6週間)
国際的な研究・教育の推進を目的に、国内外からの学部3 ・4年生並びに修士課程
学生(国籍は問わない)を対象として2005年より継続的に開催されています。参
加者はそれぞれ教員並びにその研究グループによる指導のもと、当研究センター
が推進している、1)地球惑星化学・年代学、2)高圧実験科学・鉱物物理学、3)
マグマ学・結晶化学に関する最先端研究プロジェクトに実際に参加していただき
ます。プログラム終了時には、英語による研究成果発表の実施を予定しています。
このプログラムを通して、高度な実験・分析技術に触れるのみでなく、研究者と
しての経験や最先端研究への情熱が育まれることを期待しています。
募集人員:10名程度
応募締切:2009年4月30日(木)午前10時
詳しくは、 http://www.misasa.okayama-u.ac.jp/MISIP/2009/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】2010〜2011年開催藤原セミナー募集
──────────────────────────────────
科学技術の振興に寄与することを目的として,「藤原セミナー」の開催を希望す
る研究者から,申請を受け,選考の結果採択を決定したものについて,セミナー
開催に必要な経費を援助いたします.
対象分野:自然科学の全分野
応募資格:わが国の大学等学術研究機関に所属する常勤の研究者
セミナーの要件: セミナー開催対象期間は,2010年1月〜2011年12月末日/セミ
ナーの開催地は,日本国内であること.(原則として北海道苫小牧市或いは旭川
市で開催)等
申請受付期間:2009年4月1日(水)〜7月31日(金)(必着)
詳しくは、(財)藤原科学財団 http://www.fujizai.or.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報
──────────────────────────────────
■京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究施設教員公募
職種・人員: 京都大学大学院理学研究科教授 (1名)
専門分野: 地熱流体論研究分野
着任地・時期:地球熱学研究施設,主な勤務地は地球熱学研究施設本部(別府)
採用決定後,できるだけ早い時期
応募締切:2009 年5月22日(金)必着
詳細は,
http://www.vgs.kyoto-u.ac.jp/japan/koubo20090325.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】地質マンガ「海には危険がいっぱい」
──────────────────────────────────
「海には危険がいっぱい」作:木村英人 画:Key
http://www.geosociety.jp/faq/content00154.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新年度のイベント等を掲載しませんか?すぐに掲載できます(編集部)
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.062 2009/4/21 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.062 2009/04/21 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】日本地質学会第116年総会および一般社団法人2009年度定時総会 開催
【2】地学オリンピック!台湾大会派遣候補者決定
【3】コラム:南海トラフ地震発生帯掘削計画の国際会議に参加して
【4】「地質の日(5/10)」イベント情報
【5】地質学雑誌PDFカラー図表の差替えサービスを始めます!
【6】国立公園リーフレットシリーズ 屋久島地質たんけんマップ 新発売!
【7】4・5月の博物館 特別展示・イベント情報
【8】第6回(平成21年度)日本学術振興会賞受賞候補者推薦募集
【9】採用試験情報(北海道警察科学捜査研究所)
【10】地質マンガ「エアロゾルって何?」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】日本地質学会第116年総会および一般社団法人2009年度定時総会 開催
──────────────────────────────────
■日本地質学会第116年総会
2009年5月17(日) 17:45-18:45
会場 幕張メッセ 国際会議場(3F 302議室)
■一般社団法人日本地質学会2009年度定時総会
2009年5月17(日) 18:45-19:45
会場 幕張メッセ 国際会議場(3F 302議室)
議案等詳しくは、http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
(会員のページへログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】地学オリンピック:台湾大会派遣候補者決定
──────────────────────────────────
2009年3月29日(日)に東京大学にて第3回国際地学オリンピック第二次選抜試験
(第1回日本地学オリンピック本選)が行われました。地質・気象・天文の3分野
の実技試験と面接の結果、第3回国際地学オリンピック台湾大会派遣候補者が決定
しました。
詳しくは、http://www.geosociety.jp/name/content0040.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】コラム:南海トラフ地震発生帯掘削計画の国際会議に参加して
──────────────────────────────────
宮川歩夢(京都大学大学院工学研究科 博士課程後期2年)
航海後に一堂に会する初めての会議で、日本はもちろんアメリカ・ヨーロッパ
・アジアの各国から研究者が参加し、参加者は総勢78名に上りました.
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/faq/content0156.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】「地質の日(5/10)」イベント情報
──────────────────────────────────
■特別講演会「火山はすごい!−日本列島の火山をさぐる」
講師に鎌田浩毅さんを迎え、子供から大人まで楽しめる一般向け特別講演会を企
画しています。
2009年5月10日(日・地質の日)15:00-16:45
会場 科学技術館
詳しくは、http://www.geosociety.jp/name/content0039.html
この他、各支部でもさまざまな催しが企画されています。
■関東支部:技術伝承講習会
第5回 講師 安間 恵氏
テーマ「海底探査(海底調査)の魅力-海洋地質学の基礎を学ぶ-」
5月10日(日)14:00-16:00(地質の日)
会場 国立科学博物館日本館4階大会議室
参加無料(ただし、入館費500円かかります)
第6回 講師 大島 洋志氏
テーマ「トンネルの地下水問題にどう取り組んできたか(仮題)」
6月6日(土)10:00-12:00
会場 国立科学博物館新宿分館 参加無料(入館費も無料)
6月期は、午後から「関東地方」出版記念シンポおよび研究発表会も行います。
併せてぜひご参加下さい。
詳しくは、関東支部HP<http://kanto.geosociety.jp/>をご覧下さい。
■北海道支部: 記念展示『支笏火山と私たちのくらし』
展示期間:4月28日(火)-5月31日(日)ただし5/7,11,18,25は休館.
展示場所:北海道大学総合博物館1階「知の統合」コーナー
開館時間:10:00-16:00(入場無料)
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
■西日本支部(後援):「地質の日」企画:身近に知る「くまもとの大地」
5月10日(日・地質の日)10:00-16:00
場所:熊本市通町筋上通り入り口 びぷれす広場(熊日ビル)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質学雑誌オンライン用PDFカラー図表の差替えサービスを始めます!
──────────────────────────────────
地質学雑誌に掲載する図はカラーにすることも可能です.しかし,そのためには
かなりの費用が必要です(投稿規定参照).その金額を聞いてカラーの図を掲載
することを断念した著者も多いのではないでしょうか? そこで,冊子体の図は
白黒のままで,現在、冊子発行3ヶ月後にオンラインで無料公開されているJ-STAG
E<http://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/-char/ja/>上のPDFファイルはカ
ラー版に差替えるサービスを5月号から開始することにしました.料金は,図の点
数に関係なく,1論文につき5,000円とたいへんお値打ちになっています.ぜひお
試しください.
実施方法等続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/publication/content0002.html
2009年4月 地質学雑誌編集委員会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】国立公園リーフレットシリーズ2 屋久島地質たんけんマップ 新発売!
──────────────────────────────────
屋久島地質たんけんマップー洋上アルプスは不思議がいっぱいー
編 著:日本地質学会地学教育委員会・屋久島地学同好会
A2版 12折 両面フルカラー印刷 会員頒価 300円
かわいいキッキくんとシカノスケ博士が屋久島の地質をわかりやすく紹介してく
れます。裏面は、地図で示した観察ポイントごとに写真やイラスト付きでわかり
やすく解説。ハンディタイプで、野外での観察にも最適。教材としても是非ご活
用下さい。シリーズ1「箱根火山たんけんマップ」も好評発売中。
購入希望の方は、学会事務局<main@geosociety.jp>まで
詳しくは、http://www.geosociety.jp/publication/content0004.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】4・5月の博物館 特別展示・イベント情報
──────────────────────────────────
いよいよ今年も地質の日が近づいてきました。全国の博物館では、地質の日に合わ
せた特別展示や体験イベント,野外観察会を開催し、地質の日を盛り上げていきま
す。
なお、各館が行う体験イベントや野外観察会の中には、事前申し込みが必要なもの
がありますので、イベントカレンダーからご確認の上、お申し込み下さい。
4・5月の博物館イベントは↓↓↓でチェック
http://www.geosociety.jp/name/content0041.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】第6回(平成21年度)日本学術振興会賞受賞候補者推薦募集
──────────────────────────────────
対象分野 人文・社会科学及び自然科学にわたる全分野
受付期間 2009年5月26日(火)〜28日(木)必着
(学会推薦受付締切:5月14日(木)学会推薦です.自薦はありません)
推薦書類の提出先及び問い合わせ先
独立行政法人 日本学術振興会
総務部 研究者養成課 「日本学術振興会賞」担当
TEL 03-3263-0912 FAX 03-3222-1986
http://www.jsps.go.jp/jsps-prize/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】採用試験情報(北海道警察科学捜査研究所)
──────────────────────────────────
北海道警察科学捜査研究所化学科で2名募集が出ています.
(地質学系学科も適する専攻にはいってます)
受付期間;2009年4月9日(木)〜5月8日(金)必着
http://www.police.pref.hokkaido.jp/info/keimu/saiyou/h21-kasouken.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】地質マンガ「エアロゾルって何?」
──────────────────────────────────
「エアロゾルって何?」作:古谷浩志・鄭 進永・川村喜一郎 画:Key
http://www.geosociety.jp/faq/content00155.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地質の日などイベント情報をおよせください.すぐに掲載できます(編集部)
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
富士山・青木ヶ原に巡検
有志にて富士山・青木ヶ原に巡検
溶岩がどんなふうに流れてきたか説明を受けています。場所は西湖の近くです。
溶岩標本はどんな鉱物が見えるか観察しています。
まさに青木が原樹海の中です。1200年前は、ハワイの溶岩のように真っ赤だったのかあと感心しました。
(写真撮影:小尾 靖)
2009年4月4日(土)、数日前の天気予報では雨天の情報も出ていたが、久しぶりの好天に恵まれて、日大の高橋正樹さん、金丸龍夫さんを講師に地学教育 委員3名は、富士山・青木ヶ原に巡検にでかけた。地質学会で発行している「たんけんマップ」の第3弾制作を考えての巡検である。最近の知見では、今から 1000年前、青木ヶ原溶岩が噴出した頃、まるで、ハワイの火山の様相を呈していたというのである。ほんとうであろうか。桜上水に9時に集合し、中央道を 西に向かった。途中小休止をして、鳴沢の鉱物博物館には11時に着いた。東京から大変近い。道路もそんなに混んでいなかった
鉱物博物館の入り口には世界中から集めた美しい大きな結晶が並んでいる。「富士山のものではないよ」「いいんじゃない」いろいろ意見が出る。恐竜が溶岩に 飲まれて助けを呼んでいる展示物にも賛否両論がでる。目的は博物館ではなかった。その裏にある黒っぽい石の壁のようなところである。これは博物館を作ると きに少し手を入れてあるものの、純然たる溶岩露頭であった。ここで高橋講師から溶岩の観察ポイントを教わる。ハワイのアアとパホイホイの溶岩の構造が見ら れるという。なるほどすべすべしてホイホイと歩きやすいところがパホイホイ、ごつごつザラザラして歩くのが「ああ大変」なところがアア溶岩のようである。
昼食をはさんで、溶岩が一面に観察できるところに行く。だんだんと、ほんとうに溶岩の上を歩いているような感じになってくる。その後、コウモリ穴を見てか ら、青木ヶ原の樹海に行く。1000年以上前の溶岩が流れているようである。レーダーなどの最近の技術の発達を如実に感じる。最後は精進湖で、50年前の 久野久先生の解釈が変わってきたことを知る。ドキドキしてきた。最後は少し自然渋滞に巻き込まれたが、1日の巡検で青木ヶ原の溶岩について十分に理解でき た。この感動を「たんけんマップ」でどのように表現したら、多くの人に伝わるだろうか。私たちの力量が問われている。
地質マンガ 食べられません
地質マンガ
戻る|次へ
化石ハンマーの一種だそうです.通称「魚沼」と呼ぶそうですが,今回の投稿で初めて知りました.ありがとうございました.(編集部)
No.063 2009/5/12 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.063 2009/05/12 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】総会案内
【2】第116年岡山大会:講演申込/事前参加申込受付開始
【3】地質の日 各地でイベント開催!
【4】地球惑星科学連合の会員登録を!
【5】研究を進める上で支障となっている事項調べ(日本学術会議事務局)
【6】支部情報 「北海道地質百選」
【7】原子力総合シンポジウム2009
【8】科学情報の活用に関するワークショップ開催
【9】日本地下水学会50周年記念講演会
【10】茨城大学理学部理学科地球環境科学領域教員の公募
【11】第4回「科学の芽」賞募集
【12】5月以降の博物館 特別展示・イベント情報
【13】地質マンガ「食べられません」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】総会案内
──────────────────────────────────
■日本地質学会第116年総会
2009年5月17(日) 17:45-18:45
会場 幕張メッセ 国際会議場(3F 302議室)
■一般社団法人 日本地質学会2009年度定時総会
2009年5月17(日) 18:45-19:45
会場 幕張メッセ 国際会議場(3F 302議室)
議案等詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
(会員のページへログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第116年岡山大会:講演申込/事前参加申込受付開始
──────────────────────────────────
岡山大会のシンポジウム・一般発表の申込受付が開始されました。
講演申込は、今年もJ-STAGE演題登録システムを利用いたします。講演申込締
切は、6月23日(火)です(郵送の場合は6/19)。
また、事前の参加登録は、(株)日本旅行岡山支店が窓口となります。
いずれもお早めのお申し込みをお願いいたします。
岡山大会のHPは、、、
http://www.geosociety.jp/okayama/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】地質の日 各地でイベント開催
──────────────────────────────────
■特別講演会火山はすごい!−日本列島の火山をさぐる」開催
(日本地質学会主催・日本火山学会後援)
5/10(日)地質の日普及イベントとして,地質学会会員の鎌 田浩毅氏(京都大)
を講師に迎え,一般普及向けの特別講演会「火山はすごい!−日本列島の火山を
さぐる」 を科学技術館(千代田区北の丸公園内)にて開催した.
定員90名の会場は,開場とともにすぐに席が埋まり,立ち見がでるほどの盛況ぶ
りであった.休日ということもあり,小学生の親子連れの姿なども見かけること
ができた.
講演は,各地の火山を例にあげて,火山のでき方や噴火のメカニズムなどを紹介
しながら,自然災害と火山の恵みなど、話題の豊富な内容であった. また,
専門家としていかに一般の人々に科学を伝えていくか,鎌田氏の現在のライフワー
クの一つであるアウトリーチについても熱心にお話いただいた.氏はTV出演や講
演の機会も多く,時折笑いをとりいれた,わかりやすくて楽しい講演であった.
長時間の講演にも関わらず,参加者は時間を忘れて聞き入っていた.
後半のQ&Aコーナーでは,火山に関する専門的なものから,鎌田氏の奇抜なファッ
ションに関するものまで,参加者から様々な質問が寄せられ,氏が時間のある限
りひとつひとつに丁寧に回答する様子が印象的であった.
日本地質学会では,今後も一般の方々にわかりやすいアウトリーチ活動をめざし
て,いろいろな催しを企画していきたいと思います.
(担当理事 藤林紀枝)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地球惑星科学連合の会員登録を!
──────────────────────────────────
いよいよ16日から地球惑星科学連合大会が開催されます.連合に参加される
方は連合の個人会員登録をして下さい.これまでの連合大会の登録者数でみる
と,地質学会は1867名に対してまだ683名の登録者数です.法人化した連合の
代議員数は,登録区分別に比例配分されます.連合大会という場でより魅力の
あるセッションを組み立てていただくためにも,また,地球惑星科学の中での
地質学の意義を広く認知していただくためにも,多くの地質学会会員による連
合の会員登録が期待されています.
http://www.jpgu.org/meeting/entry.html
日本地質学会理事会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】研究を進める上で支障となっている事項調べ(日本学術会議事務局)
──────────────────────────────────
4月21日の第80回総合科学技術会議本会議において、将来の成長に向けた科
学技術政策上の重要課題について議論する中で、甘利規制改革担当大臣から「研
究の現場で研究を進める上で隘路となっている制度上、運用上の問題を総合科学
技術会議が把握し、一つずつ解決していくことが必要」との趣旨の発言があり,
これを受けた日本学術会議より,日本地質学会は,学会の立場で把握している範
囲での以下の点について回答を求められました.
【研究の現場において研究を進める上で支障となっており、その改善が図られれ
ば、よりスムーズな研究ができると思われる事項(例えば、研究費等経費の使用
の不便さの解消、施設・設備の目的外使用の緩和など、できるだけ多くの研究者
に共通するような事項)があれば、別記様式により、事項ごとに一葉として、で
きるだけ具体的に記述する】
ご多忙中と存じますが,5月29日までに回答をとりまとめるところですので,ご意
見をいただける方は,下記の様式に記述を御願いします.回答は5月25日月曜日中
に御願いします.いただいた資料を学会としてとりまとめて回答する予定です.
なお,ご報告いただいた事項については、日本学術会議事務局が整理した上で、
総合科学技術会議有識者議員でもある金澤日本学術会議会長から、総合科学技術
会議有識者議員会合に説明され,その後の解決に向けた作業の契機とされると聞
いております.
以上よろしく御願いします.
・締め切り:5月25日昼12時
・送り先:comment@geosociety.jp (5月25日までの専用アドレス)
---研究を進める上で支障となっている事項調べ様式(日本学術会議事務局)---
1.研究費等経費の使用に関する事項
2.施設・設備などの使用に関する事項
3.その他の制度上・運用上支障となっている事項
(個別の制度の改善では対応が困難な構造的・複合的な事項を含む。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
■北海道支部「北海道地質百選」のwebサイト更新しました
北海道支部では「北海道地質百選」の活動を行ってきました.今回,2009年
地質の日を期してwebサイトを全面的に更新しました.北海道の魅力ある地質・
地形を紹介しています.ぜひご覧になって下さい.
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
■関東支部:技術伝承講習会/研究発表会「関東地方の地質」
日時:2009年6月6日(土)10:00〜17:30
午前の部>技術伝承講習会 午後の部>研究発表会
会場:国立科学博物館 新宿分館
詳しくは、 http://kanto.geosociety.jp/
■中部支部:2009年年会のお知らせ
日時:2009年6月13日(土)-14日(日)
会場:山梨大学教育人間科学部講義棟
シンポジウム:「フォッサマグナ地域の地殻変動現象と中部地方の最新情報」
http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】原子力総合シンポジウム2009
──────────────────────────────────
共催 日本地質学会ほか
主調テーマ「原子力の将来展開 〜変革期の社会の中で〜」
2009年5月27日(水)〜28日(木)
会 場 日本学術会議講堂(東京都港区六本木7-22-34)
参加費無料
詳しくは、http://www.aesj.or.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】科学情報の活用に関するワークショップ 開催
──────────────────────────────────
計量書誌学は論文の価値を評価する一つの方法として知られています。評価部で
は、今後の評価システム構築の参考とするために、最近の計量書誌学の動向につ
いて、当分野において著名な皆様にご講演いただく機会を設定しました。さらに
これに合わせて、(独)物質・材料研究機構ならびに地質調査情報センター提供
によるデジタルアーカイブに関する企画展示、エルゼビア・ジャパン(株)なら
びにトムソン・ロイター(株)提供による科学論文データベースを用いた調査・
分析のトライアルを実施いたします。
日時:2009年6月1日(月) 10:00-17:00
場所:産業技術総合研究所つくばセンター共用講堂
参加費無料,但し,事前申込が必要(産総研外の研究者・研究支援者も参加可能).
申込・問い合わせ先:評価部 七山・岡
電話:029-862-6096, メール:eval-ws2009@m.aist.go.jp
詳しくは、
産業技術総合研究所評価部 http://unit.aist.go.jp/eval/ci/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】日本地下水学会50周年記念講演会
──────────────────────────────────
2009年5月29日(金)14:00〜
場所 日本科学未来館みらいCANホール
祝賀パーティー:同日18:00〜 於有明ワシントンホテル
詳しくは、
http://homepage2.nifty.com/jagh_gyouji/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】茨城大学理学部理学科地球環境科学領域教員の公募
──────────────────────────────────
職名・人数: 助教1名 (任期付きではありません)
所属: 理学部理学科地球環境科学領域
応募締切: 2009年6月30日(火)必着
詳しくは、
http://www.sci.ibaraki.ac.jp/02info/koubo.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】第4回「科学の芽」賞募集
──────────────────────────────────
趣旨:筑波大学の前身の東京教育大学の学長を務めるなど,本学にゆかりのある
ノーベル物理学賞を受賞した朝永振一郎博士の功績を称え,それを後続の若い世
代に伝えていくとともに,小・中・高校生を対象に自然や科学への関心と芽を育
てることを目的としたコンクールを行い「科学の芽」賞を授与します.
応募期間:2009年8月20日(木)〜9月30日(水)〔消印有効〕
詳しくは,
http://www.tsukuba.ac.jp/community/kagakunome/oubo.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】5月以降の博物館 特別展示・イベント情報
──────────────────────────────────
■豊橋市自然史博物館
収蔵資料紹介展「足元の地面を探る」
期間:4月25日(土)〜6月14日(日)
■群馬県立自然史博物館
「桐生で発見!古生代の新種腕足類」
期間:5月9日(土)〜6月21日(日)
■フォッサマグナミュージアム
「世界ジオパーク展−日本最初の認定地をめざす糸魚川−」
期間:4月25日(土)〜秋
博物館イベントは↓↓↓でチェック
http://www.geosociety.jp/name/content0041.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】地質マンガ「食べられません」
──────────────────────────────────
「食べられません」 作:木村英人 画:Key
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/faq/content0162.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
記事をいつでも募集中.さくっと投稿すぱっと配信(編集部)
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.64 2009/5/19 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.064 2009/05/19 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】総会が終了いたしました。
【2】地学オリンピック・表彰式
【3】研究を進める上での支障はありませんか? コメント募集
【4】岡山大会:講演申込/事前参加申込受付中
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】総会が終了いたしました
──────────────────────────────────
議事録等の総会報告は、ニュース誌・HP で後日公開予定です。
■日本地質学会第116年総会
2009年5月17(日) 17:45-18:45
会場 幕張メッセ 国際会議場(3F 302議室)
■一般社団法人 日本地質学会2009年度定時総会
2009年5月17(日) 18:45-19:45
会場 幕張メッセ 国際会議場(3F 302議室)
議案等詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
(会員のページへログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】地学オリンピック・表彰式
──────────────────────────────────
3月に行われた第3回国際地学オリンピック第二次選抜試験(第1回日本地学オリ
ンピック本選)での最優秀賞・優秀賞受賞者への表彰式が、先日5月17日に日本地
球惑星科学連合大会会場内にて開催されました。
http://www.geosociety.jp/name/content0040.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】研究を進める上での支障はありませんか? コメント募集
──────────────────────────────────
前号でもお知らせ致しましたが,再度送らせて頂きます.
日本学術会議より,日本地質学会は,学会の立場で把握している範囲での
以下の点について回答を求められました.
【研究の現場において研究を進める上で支障となっており、その改善が図ら
れれば、よりスムーズな研究ができると思われる事項(例えば、研究費等経
費の使用の不便さの解消、施設・設備の目的外使用の緩和など、できるだけ
多くの研究者に共通するような事項)があれば、別記様式により、事項ごと
に一葉として、できるだけ具体的に記述する】
地質学会取りまとめ窓口:comment@geosociety.jp
締切:5月29日(金)正午
詳細:http://www.geosociety.jp/faq/content0163.html#geo-flashno.62-5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第116年岡山大会:講演申込/事前参加申込受付中
──────────────────────────────────
岡山大会のシンポジウム・一般発表の申込受付中です。
講演申込は、今年もJ-STAGE演題登録システムを利用いたします。講演申込締
切は、6月23日(火)です(郵送の場合は6/19)。
また、事前の参加登録は、(株)日本旅行岡山支店が窓口となります。
いずれもお早めのお申し込みをお願いいたします。
岡山大会のHPは、、、
http://www.geosociety.jp/okayama/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつでも記事を募集中.さくっと投稿すぱっと配信(編集部)
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.65 2009/6/2 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.065 2009/06/02 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2009岡山大会ニュース *講演申込:6/23締切です
【2】支部の情報
【3】日本の地質百選2次選定決まる
【4】深田研ジオフォーラム 2009/第120回深田研談話会
【5】第14回GSJシンポジウム「地質リスクとリスクマネジメントその2」
【6】第13回尾瀬賞募集
【7】公募情報(2件)
【8】6月の博物館特別展示・イベント情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2009岡山大会ニュース *講演申込:6/23締切です
──────────────────────────────────
■講演申込・事前参加登録受付中!!
岡山大会の講演申込・事前参加登録の申込受付中です。
講演申込締切は、6月23日(火)です(郵送の場合は6/19)。
早めのお申し込みをお願いいたします。
岡山大会ホームページ
http://www.geosociety.jp/okayama/content0001.html
■一部シンポジウムは英語での発表・議論を推奨することになりました。
・日本列島構造発達史(世話人:磯崎行雄・丸山茂徳)
・坂野昇平追悼シンポジウム(世話人:平島崇男・榎並正樹)
上記2件のシンボジウムについて、世話人からの希望により、外国人招待講演者が,
自己以外の発表・議論に参加できるようにするため英語での発表・議論を推奨す
ることとなりました。しかし講演申込開始後の変更となるため、日本語での発表
を希望されておられた方に対しては個別に世話人がご相談させていただきますの
で、よろしくお願いいたします。
各シンポジウムの詳細は、http://www.geosociety.jp/okayama/content0019.html
■理科教員対象見学旅行:参加者募集中
実施日:2009年9月5日(土)8:30集合
テーマ:岡山県南部の花崗岩類(万成石)と文化地質学
申込締切:申込者数が定員に達し次第,申込を終了させていただきます.
詳しくは、http://www.geosociety.jp/okayama/content0007.html#field-trip
■小さなEarth Scientistのつどい:参加校募集中
申込締切:2009年7月7日(火)
http://www.geosociety.jp/okayama/content0007.html#earth-scientist
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】支部情報
──────────────────────────────────
■関東支部:総会およびシンポ・講習会
6月6日(土)10:00-17:40
場所:国立科学博物館 新宿分館
10:00-12:00
第6回地質技術伝承講習会 講師:大島洋志(国際航業株式会社)
「トンネルの地下水問題にどう取り組んできたか」
詳しくは,http://kanto.geosociety.jp/kousyuukai/2009/kousyuukai_2009new.h
tml
13:00-17:40
日本地方地質誌「関東地方」刊行記念シンポジウム
「関東地方の地質:研究の進展と今後の課題」
<シンポ終了後に支部総会が開催されます>
関東支部会員で欠席の方は委任状をお願いいたします.
詳しくは,http://kanto.geosociety.jp/koen/2009-06yokoku2.html
■中部支部:2009年年会のお知らせ
6月13日(土)、総会・シンポジウム・懇親会
6月14日(日) 地質巡検
場所:山梨大学教育人間科学部講義棟
シンポジウム:「フォッサマグナ地域の地殻変動現象と中部地方の最新情報」
http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本の地質百選2次選定決まる
──────────────────────────────────
地質百選は2007年5月10日に83箇所を選定しました.それから2年,各地から地
質百選への推薦(自己推薦を含む)がありました.そこで,2009年3月31日で推薦
を締め切り,地質百選選定委員会で慎重に議論を重ねました.
その結果,2009年5月10日(地質の日)に37箇所の選定を発表いたしました.ま
た2007年の選定箇所の1部を変更します.これで,地質百選は120箇所の選定をもっ
てまずは終了とします.
詳しくは,http://www.gupi.jp/geo100/index.htmlをご覧下さい.
(日本の地質百選選定委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】深田研ジオフォーラム 2009 ,第120回深田研談話会
──────────────────────────────────
※いずれも技術士CPD(継続教育)履修実績として申請できます。
■深田研ジオフォーラム 2009
テーマ: 花崗岩とそれに関連する資源の話
講 師: 石原舜三 氏 (産業総合技術研究所 特別顧問)
日 時: 2009年6月20日(土) 10:00〜16:00
会 場: 財団法人深田地質研究所 研修ホール
参加費: 一般 5,000円 学生 1,000円 (昼食代を含む)
申込み締切り日: 6月17日(水)
定 員: 50名(定員になり次第締切ります)
講演要旨:
花崗岩は大陸地殻を構成する主な岩石であるから、私達は
花崗岩、そのマグマ分泌物−鉱床、風化物と共に生きていると
言っても過言ではない。花崗岩は40億年前頃に初めて地球上
に現れ、現在も島弧の火山の下では生まれつつある。
そんな花崗岩を全地球史的に概観し日本の特色について述べ、
私たちの生活における有用性について解説する。
■第120回深田研談話会
テーマ: 地球の過去・現在・未来 −特に人類史について−
講 師: 丸山茂徳 氏 (東京工業大学大学院 教授)
日 時: 2009年7月10日(金) 15:00〜17:00
会 場: 財団法人深田地質研究所 研修ホール
参加費: 無 料
◆講演概要:
人類史1万年の中で、資源(地球の貯金)の利用を思いついた人類の大躍進のいきさつを
解説する。更に、科学の発展の3段階を述べて、おぼろげながら見え始めた人類の未来を
概観しよう。人類は、2020年から人類史の黄金時代の終末期に突入する。人類のサバイ
バルの方策も併せて議論する。
●申込み方法: 参加ご希望の方は、E-mail か FAXでお申込み願います。
その際、氏名・所属・連絡先(住所・電話番号)をお知らせ下さい。
●申込み先: 財団法人 深田地質研究所
〒113ー0021 東京都文京区本駒込2ー13ー12
TEL:03-3944-8010 FAX:03-3944-5404
E-mail:fgi@fgi.or.jp URL:http://www.fgi.or.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第14回GSJシンポジウム「地質リスクとリスクマネジメントその2」
──────────────────────────────────
地質調査においては、ボーリングの本数や各種調査量の制約から、地質事象の
把握における不確実性が存在し、それが様々なリスクの要因となることがある。
石油や金属鉱物の資源探査分野では、資源の経済性評価の点から、地質リスクを
定量的、定性的に取り扱うリスクマネジメントが行われている。また、トンネル
工事等における応用地質分野でも地質に起因するリスクのマネジメントに関する
議論が活発化してきている。こうしたことから、平成20年3月の第10回シンポジウ
ムでは、様々な分野で取り扱われている「地質リスク」の事例について紹介し、
討論を行った。また近年、ジオリスク(Geo Risk)やジオハザード(Geohazard)
という言葉は、各国の地質調査機構の役割を議論する上で重要なキーワードとなっ
ており、ジオリスクマネジメントに関する議論が国外でも多くなされている。今
回のシンポジウムでは、前回のシンポジウムの成果を基に、地質や地盤工学に関
連するリスクとリスクマネジメントの海外事例の紹介を行った上で、国内での新
たな取り組みの内容と今後の活動の方向性について議論することを目的とする。
日時:2009年6月15日(月) 9:45〜16:40(受付9:15〜)
場所:東京大学小柴ホール
http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_00_25_j.html
主催:(独)産総研・地質調査総合センター,(社)全国地質調査業協会連合会
後援:地質地盤情報協議会
参加費:無料 定員:150名
詳しくは、http://www.gsj.jp/Event/090615sympo/index.html
をご参照ください.また,継続教育としてのCPD6単位が認定されます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】第13回尾瀬賞募集
──────────────────────────────────
主催:財団法人尾瀬保護財団
目的:「湿原」に関する学術研究を顕彰することにより,この分野の学問的・学
際的研究の伸展を図るとともに,環境保護に関する関心を高めることを目的とし
ます.
募集期間 2009年10月31日(土)(消印有効)
詳しくは,
http://www.oze-fnd.or.jp/main/banner/oze_prize/oze_prize1.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報
──────────────────────────────────
■財団法人地球科学技術総合推進機構契約職員公募
仕事の内容 掘削地球科学(地質学、地球物理学、地球化学、海洋学、微生物学
など)に関する国際共同研究プロジェクトの総合推進業務をサイエンスコーディ
ネーターとして行う。
勤務地 (独)海洋研究開発機構横浜研究所内
応募締切 急募につき、決定次第締め切り
詳しくは、http://www.aesto.or.jp/pdf/koubo090528.pdf
■山形大学理学部地球環境学科教員公募
職種・人員 准教授 1 名(任期制なし)
所属部局 山形大学理学部地球環境学科(講座制なし)
専門分野 地層,化石,構造地質,テクトニクスなどに関連する分野
書類締切 2009 年8 月28 日(金)必着
詳しくは、
http://ksgeo.kj.yamagata-u.ac.jp/info_application.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】6月の博物館特別展示・イベント情報
──────────────────────────────────
全国の博物館で特別展示・イベントが目白押しです。まもなく終了予定の特別展
示もありますので、イベントをカレンダーをチェックして、お見逃しなく!!
今月の博物館イベントは↓↓↓でチェック
http://www.geosociety.jp/name/content0043.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつでも記事を募集中.さくっと投稿すぱっと配信(編集部)
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質マンガ テストの日
地質マンガ
戻る|次へ
地質マンガ 岩石の色
地質マンガ
戻る|次へ
色を定量的に表す指標はいろいろありますが(色だけに),L*a*b* もそんな表色系のひとつです.色彩計測機器を使えば変色しやすい地質試料の色合いも迅速かつ定量的に記録できます.
地球の体温を測って,地球に電気を流す
〜海洋研究開発機構,深海調査研究船「かいれい」KR08-10日本海溝航海
川村喜一郎(財団法人深田地質研究所),濱元栄起,山野誠(東京大学地震研究所),後藤忠徳(海洋研究開発機構),馬場聖至(東京大学地震研究所),原田誠(東海大学海洋研究所),川田佳史,桜井紀旭(海洋研究開発機構),羽入朋子(総合研究大学院大学),南澤智美(日本海洋事業株式会社),畠山映,富樫尚孝,宗輝(マリン・ワーク・ジャパン株式会社),KR08-10乗船研究者
写真1(←)かいこう7000II.かいこうは,ランチャー(上半分)とビークル(下半分)からなっており,不幸にもビークルが2003年の亡失事故で失われた.その後,UROV 7Kをビークルとして復活し,改良を加えて,現在の形になった.
写真2 OBE:海底電位差測定装置.4本の腕につけた電極で海底の電位差を測定する装置.時代とともに,小型化した.1つ玉が最新型.
平成20年8月18日〜9月11日まで,海洋研究開発機構の深海調査研究船「かいれい」による日本海溝での調査航海(KR08-10)が行われた.この航海では,日本海溝周辺の海底で地殻熱流量を測定することが主な目的であった.さらに,「かいれい」に搭載されている無人探査機「かいこう7000II」を用いて,海底に人工電流を流し,それを海底電位差計で受信する,いわゆる人工電磁探査を海底で行うための実験も行った.
これまでの研究により,日本海溝海側の海域では,沈み込む海洋プレートの年齢から推定されるよりも高い地殻熱流量が観測されることがわかってきた.その原因として,近年発見されたプレート亀裂に伴う新しい火山活動,いわゆるプチスポットによる熱的な影響や,海溝海側に発達する正断層に沿った流体活動の影響を想定して,航海は実施された.海底電位差計での観測・探査は,その原因の深さを推定するための第一歩となる.
新しい火山活動の痕跡は,この「かいれい」に搭載されていた「かいこう」によって初めて発見された.1997年に第56回潜航が行われ,「かいこう」は,日本海溝の海溝軸部の海側斜面の水深7300 m付近から比較的新しい年代に噴出した玄武岩からなる崖を発見した.そして,それはこの海域での新しい地球科学の足がかりになった.「かいこう」は,2003年に不幸にも亡失事故によって行方不明になったが,この無人探査機の功績はすばらしかった.
それまでは有人探査船「しんかい6500」により,水深6500 mまでの海底の様子はわかっていたが,この「かいこう」は,それよりも深い場所を観察することを可能にし,そして,新しい地球科学の発見に導いた.私たちにはまだ知らない領域が多くあり,きっと,それらは,新しい技術によって知りうることができる,ということを,先の「かいこう」の例は指し示している.
今回の航海では,新旧問わず,さまざまな海洋観測装置が用いられた.研究者によるそれらの観測装置の新規開発に加え,観測技術員,探査船運航チーム,船長をはじめ船員の方々の船上での操船,操作技術によって,未知の領域に光が灯されるのだろう.
写真3 自己浮上式海底熱流量計:温度センサーが付いている槍を海底に突き刺して,海底下の温度分布を測定する.長期間測定を行った後,海面からコマンドを音波として送信し,重りを切り離して記録部分を浮上させ,回収する.
写真4 自己浮上式海底水温計:海底に温度計を付けた切り離し装置を設置し,長期間の海底の水温を測定する.水深が約二千メートルよりも浅い海域では,海底面における水温変動が大きく海底堆積物中の温度分布を乱す.このため熱流量を求めるには,長期的な海底水温の変動を測定して影響を補正する必要がある.この装置や自己浮上式海底熱流量計は,その長期測定のための装置である.
写真5 深海用地殻熱流量測定装置:海底堆積物に温度センサーを取り付けた槍を突き刺して,堆積物中の温度勾配を測定する装置.温度センサーに熱パルスを発生させて,その後の温度変化を測定することにより,堆積物の熱伝導率を求めることもできる.測定過程や槍の姿勢は音波で送信され,それを船上で受信することにより,海底での測定の状況をリアルタイムで知ることができる.
写真6 ヒートフローピストンコアラーと自己記録式小型温度計:ピストンコアラーという柱状採泥器のパイプの外側に,複数の自己記録式小型温度計を取り付けたもの.採泥を行うとともに,海底下の温度勾配を測定することができる.
写真7 ピストンコアラーによって採取された柱状採泥試料を半割し,熱伝導率の測定を船上で行っている様子.半割した試料面にアイロンのような形状のセンサーを置く.このセンサーに熱を発生させ,その熱による堆積物の温度上昇過程から熱伝導率を求める.熱伝導率と温度勾配から地殻熱流量を計算することができる.
No.067 2009/6/16 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.067 2009/06/16 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2009岡山大会ニュース あっ来週締切だ!
【2】地質学雑誌:文献英文併記と図表・キャプションの英文化を
【3】コラム:地球の体温を測って,地球に電気を流す
【4】2009年度日本地球化学会年会(共催:日本地質学会他)
【5】第15回GSJシンポジウム
【6】3rd International Tsunami Field Symposium(in 仙台)
【7】公募・各賞助成(各2件)
【8】地質マンガ「岩石の色」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2009岡山大会ニュース *講演申込:6/23締切です
──────────────────────────────────
■講演申込:もうすぐ締切です!!
岡山大会の講演申込締切まで後1週間です。
講演申込締切は、6月23日(火)です(郵送の場合は6/19)。
早めのお申し込みをお願いいたします。
岡山大会ホームページ
http://www.geosociety.jp/okayama/content0001.html
■岡山大会に関連したプレス発表を希望される方へ
岡山大会で発表される予定の案件で,学会からのプレス発表をご希望の方は,8月
10日(月)までに学会事務局にご連絡願います.全ての案件をプレス発表するこ
とはできませんが,社会への情報発信として特筆すべき成果は積極的に公表して
行きたいと考えております.会員の皆様におかれましては,プレスリリース解禁
日をお守りいただき,公平かつ効果的な情報発信にご協力願います.不明な点は
学会事務局までお問い合わせ願います.
登録締切:8月10日(月)
プレス発表(投げ込み):8月21日(金)
現地説明会(解禁日):8月28日(金)(予定)
連絡先:日本地質学会事務局<journal@geosociety.jp>
■理科教員対象見学旅行:参加者募集中
実施日:2009年9月5日(土)8:30集合
テーマ:岡山県南部の花崗岩類(万成石)と文化地質学
申込締切:申込者数が定員に達し次第,申込を終了させていただきます.
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/okayama/content0007.html#field-trip
■小さなEarth Scientistのつどい:参加校募集中
申込締切:2009年7月7日(火)
http://www.geosociety.jp/okayama/content0007.html#earth-scientist
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】文献英文併記と図表・キャプションの英文化をお願いします
──────────────────────────────────
これまでもニュース誌等でお知らせして参りました通り,日本地質学会の法人
化に伴い,学会諸規則の整備が行われ,その中の一つとして,従来の編集規約,
投稿規定などの編集に関わる規則を一本化,内容も一部改訂し,新しい編集規則
を作成いたしました.
従来からの大きな変更点は,引用文献リストや図表およびキャプションの英文
化です.これは,インパクトファクターの附帯化,国際的な相互引用化をめざす
ためにも必要不可欠なものです.地質学雑誌の更なる充実・地位向上のため会員
の皆様のご協力をお願いいたします.
具体的には,2009年9月1日以降,新規に投稿される投稿原稿全てに新規則が適
用されます.また,また第115卷9号(2009年9月号)以降の掲載論文に関しても適
用となりますので,既にご投稿中の著者にも随時修正をお願いする次第です.
新しい編集規則は,学会ホームページまたは地質学雑誌巻末をご参照ください.
http://www.geosociety.jp/publication/content0038.html
2009年6月 地質学雑誌編集委員会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】コラム:地球の体温を測って,地球に電気を流す
──────────────────────────────────
川村喜一郎(財団法人深田地質研究所)ほか
会議の様子平成20年8月18日〜9月11日まで,海洋研究開発機構の深海調
査研究船「かいれい」による日本海溝での調査航海(KR08-10)が行われた.この
航海では,日本海溝周辺の海底で地殻熱流量を測定することが主な目的であった.
さらに,「かいれい」に搭載されている無人探査機「かいこう7000II」を用いて,
海底に人工電流を流し,それを海底電位差計で受信する,いわゆる人工電磁探査
を海底で行うための実験も行った.
続きはこちらから、、http://www.geosociety.jp/faq/content0056.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2009年度日本地球化学会年会(共催:日本地質学会他)
──────────────────────────────────
会期:2009年9月15日(火)-17日(木)
会場:広島大学理学部(東広島市鏡山1-3-1)
講演申込、講演要旨原稿受付:7月13日(月)14時まで受付。
参加予約申込:8月28日(月)14時まで受付。
年会事務局:
〒739-8526 東広島市鏡山1-3-1
広島大学大学院理学研究科地球惑星システム学専攻内
e-mail:GSJ2009@hiroshima-u.ac.jp
大会HP:http://www.wdc-jp.biz/geochem/2009
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第15回GSJシンポジウム
──────────────────────────────────
「古地震と現在の地殻活動から地震を予測する—産総研 活断層・地震研究セン
ターが目指す地震研究—」
日時:2009年7月2日(木) 13:00〜17:35(受付12:30〜)
場所: 秋葉原ダイビルコンベンションホール
主催:(独)産総研・地質調査総合センター
参加費:無料 定員:300名
詳しくは,http://www.gsj.jp/Event/090702sympo/index.html
継続教育としてのCPD5単位が認定されます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】3rd International Tsunami Field Symposium(in 仙台)
──────────────────────────────────
東北大学では,2010年4月10−11日に,津波の国際シンポジウム
(3rd International Tsunami Field Symposium)を開催するこ
とになりました.シンポジウム後には,仙台,三陸,沖縄(石垣
島)での巡検も企画しております(三陸・沖縄はオプション).
参加登録,要旨投稿などの情報は,8月末公開予定のSecond Circularでお知
らせする予定です.宜しくお願いいたします.
詳細は
http://www.tsunami.civil.tohoku.ac.jp/hokusai3/E/itfs2010/
3rd International Tsunami Field Symposium実行委員会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募・各賞助成(各2件)
──────────────────────────────────
■東京工業大学大学院理工学研究科地球惑星科学専攻教員(助教)公募
募集人員 地球惑星科学専攻専任助教 1名(任期5年,再任1回3年)
専門分野: 地球惑星物質科学
応募締切:2009年7月17日(金)必着
詳しくは、http://www.geo.titech.ac.jp
■山口大学大学院理工学研究科(地球科学分野)教員公募
専門分野:地球科学(特に鉱物資源科学分野)
公募人員:准教授、講師又は助教 1 名
応募締切:2009年8月28日(金)(必着)
詳しくは、http://www.sci.yamaguchi-u.ac.jp/geo/index.html
■第13回尾瀬賞
目的:「湿原」に関する学術研究を顕彰することにより,この分野の学問的・学
際的研究の伸展を図るとともに,環境保護に関する関心を高めることを目的とし
ます.
募集締切:2009年10月31日(土)(消印有効)
詳しくは,
http://www.oze-fnd.or.jp/main/banner/oze_prize/oze_prize1.html
■2009年度信州フィールド科学賞募集
「信州フィールド科学賞」山岳地域におけるフィールド・ワークを基本として研
究している若手研究者(2009年度末で35才以下).研究対象や分野は問いません.
「信州フィールド科学奨励賞」 Ⅰ種:陸域の自然・文化を対象にフィールド・ワー
クを行っている高校生.Ⅱ種:「山」におけるフィールド・ワークに基づいてま
とめられた大学等の(過去3年間に提出された)卒業論文.
募集締切:2009 7月31日(金)必着
詳しくは、http://ims.shinshu-u.ac.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】地質マンガ 「岩石の色」
──────────────────────────────────
岩石の色 作:川村喜一郎 画:Key
詳しくはhttp://www.geosociety.jp/faq/content0167.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今月も記事を募集中. 皆様の声をお届けしたい!(編集部)
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
赤崩と大井川−池田宏氏による井川ジオツアーの報告−
赤崩と大井川−池田宏氏による井川ジオツアーの報告−
川村喜一郎(財団法人深田地質研究所)
写真1 赤崩
写真1は,「赤崩(あかくずれ)」と呼ばれる四万十帯の白亜紀の砂岩泥岩互層(写真2)に見られる斜面崩壊である.崩壊斜面は,北斜面に発達しており,地層は南傾斜である.すなわち,崩壊斜面は,受け盤である.受け盤の地層が岩盤クリープによって傾動し,崩壊が進行している.崩壊は数千年以上の長期間に渡って進行していると考えられており,現在も崩壊は進んでいる.崩れた後に赤い水がでることから,「赤崩」と呼ばれているらしい.
これらの撮影地点は,池田宏氏(財団法人深田地質研究所)の地形学習会「井川ジオツアー」で案内された場所である.この学習会は,平成21年7月4日〜5日に行われ,総勢20名の地形学,堆積学,人文地理学,海洋地質学の学生・研究者が参加した.
7月4日に静岡から安倍川を上り,井川ダム,赤石ダムからさらに上流の赤石沢川(写真3)を回り,筑波大学農林技術センターで宿泊した.夕食後,10名が自分の研究について各人15〜20分間ほど話した.翌日は大井川の河川の地形や堆積構造を観察しながら静岡まで戻ってきた.その間,蛇行の成因や発達過程,さらに,それらの過程と河川での堆積作用との因果関係などについて野外で議論を交わした(写真4).
このような有意義な会は,久しぶりだった.現地案内をしてくださった池田先生や筑波大学農林技術センターをはじめ,多くの関係者には,感謝すると共に,今後もこのような会を是非続けて頂きたいと心から願っている.
写真2 赤石沢上流域で観察された四万十帯の砂岩泥岩互層.上の砂岩と河床の間に挟まれた領域はデュープレックスのようにみえる.
写真3 赤石沢にかかる吊り橋.渡るときはちょっとどきどき
写真4 蛇行する大井川
クリックすると大きな画像をご覧頂けます。
No.068 2009/06/22 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.068 2009/06/22 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2009岡山大会ニュース 講演申込締切24時間延長!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2009岡山大会ニュース *講演申込締切24時間延長!
──────────────────────────────────
■講演申込締切24時間延長!
少しでも多くの方々に講演していただくために、
岡山大会講演申込締切を24時間延長いたしました。
まだお申し込みでない方は、至急申し込み手続きを行ってください。
また別途、事前参加登録も忘れずに行ってください。
最終締切:6月24日(水)17時
↓講演(要旨投稿)申込はこちらから↓
http://proc.jstage.jst.go.jp/proceedings/service/geosocabst/newregistrati
on/
↓大会参加登録はこちら↓
https://apollon.nta.co.jp/chishitsu/perl/jouhou.pl?&mode=top
2009年6月22日 日本地質学会行事委員会
■岡山大会に関連したプレス発表を希望される方へ
岡山大会で発表される予定の案件で,学会からのプレス発表をご希望の方は,8月
10日(月)までに学会事務局にご連絡願います.全ての案件をプレス発表するこ
とはできませんが,社会への情報発信として特筆すべき成果は積極的に公表して
行きたいと考えております.会員の皆様におかれましては,プレスリリース解禁
日をお守りいただき,公平かつ効果的な情報発信にご協力願います.不明な点は
学会事務局までお問い合わせ願います.
登録締切:8月10日(月)
プレス発表(投げ込み):8月21日(金)
現地説明会(解禁日):8月28日(金)(予定)
連絡先:日本地質学会事務局<journal@geosociety.jp>
■理科教員対象見学旅行:参加者募集中
実施日:2009年9月5日(土)8:30集合
テーマ:岡山県南部の花崗岩類(万成石)と文化地質学
申込締切:申込者数が定員に達し次第,申込を終了させていただきます.
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/okayama/content0007.html#field-trip
■小さなEarth Scientistのつどい:参加校募集中
申込締切:2009年7月7日(火)
http://www.geosociety.jp/okayama/content0007.html#earth-scientist
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.070 2009/07/21 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.070 2009/07/21 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】快挙!Island Arc のIFが再び1.0越え
【2】フォトコンテストを開催します.良い写真をぜひ!
【3】岡山大会ニュース:プログラム決定
【4】Neogene/第四紀 境界 IUGSで批准
【5】惑星地球リスボン式典2009 派遣学生推薦募集
【6】ダーウィン生誕200年記念シンポジウム
【7】公募情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】快挙!Island Arc のIFが再び1.0越え
──────────────────────────────────
先月6月に発表されました2008年度インパクトファクターについて、Wiley-Blackw
ell社から報告がありました。
下記の通り、Island Arc誌におきましては2008年IF [1.038]が発表されました。2
007年度は[0.837]でしたので(+0.201)の上昇です。
なお、2008年Island Arc 報告については、ニュース誌で詳しく掲載の予定です。
■Journal Impact Factor
Cites in 2008 to items published in:
2007 =44
2006 =39
Sum:83
Number of items published in:
2007 =40
2006 =40
Sum:80
Calculation:Cites to recent items 83=1.038
Number of recent items 80
Island Arc誌はGEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARYにインデックスされており、
90/137(2007)→89/143(2008)ににランクしています。
Island Arc無料閲覧は、学会HP 会員のページから(ログインが必要です)
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】惑星地球フォトコンテストを開催します
──────────────────────────────────
IYPE(国際惑星地球年)と地質学会の主催で惑星地球フォトコンテストを開
催します.惑星地球に関する芸術的もしくは学術教育的写真を募集します.
上位入賞作品は,3月のIYPE記念イベントにて展示表彰いたします.会員の
皆様には奮ってご応募下さいますようお願いいたします.11/30締切.
詳しくは,,http://photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】岡山大会プログラム決定
──────────────────────────────────
■講演プログラム決定
第116年学術大会(岡山大会:2009.9.4-9/6)の講演プログラムが確定いたしまし
た。各講演者にはすでにお知らせした通りです。
たくさんの会員の皆様のご参加をお待ちしています。
web事前参加登録締め切り:8/17(月)18:00
■難問に挑戦!大会ポスター岩石名・地層名当てクイズ
http://www.geosociety.jp/okayama/content0003.html#news0721
岡山大会HP:
http://www.geosociety.jp/okayama/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】Neogene/第四紀 境界 IUGSで批准
──────────────────────────────────
第四紀・系の下限を2.588 Maとする国際層序委員会(ICS)の提
案が,国際地質科学連合(IUGS)の理事会(6/29)にて批准され
ました.かねてより議論されております新しい時代区分の国内
対応に,日本地質学会は関係機関・団体と協議し,主導的役割
を果たしていく所存です.(日本地質学会理事会)
関連情報<http://www.quaternary.stratigraphy.org.uk/>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】惑星地球リスボン式典2009 派遣学生推薦募集
──────────────────────────────────
国際惑星地球年(IYPE)2007-2009のファイナルイベントとして,ポルトガル政府の
協力のもと,2009年11月20日・ 21日の両日,リスボンで「惑星地球リスボン式典
2009(Planet Earth Lisbon Event 2009)」が開催されます。式典は IYPE3ヶ年
の活動を総括し,またポストIYPEプロジェクトに光 を当てるものです。あわせて,
展示会や科学者・政治家・産業界首 脳 による「再生可能エネルギー」「持続可
能な土地および水管理」 「海洋」に関する会議も計画されています。
本式典に対し、各国から学生を招待することとなり、IYPE日本委員会より日本
地質学会に対して派遣学生1名の推薦依頼がありました。推薦候補者の資格や条件
等は下記の通りです。応募者の中から理事会で1名の候補者を決定し、IYPE日本委
員会に推薦いたします。
(日本地質学会理事会)
締切:2009年8月10日(月)12 時まで
宛先:日本地質学会<main@geosociety.jp>
必要項目:
氏名,所属,住所(和英併記,氏名は旅券標記と同じとすること)
電話番号,FAX番号,eメールアドレス,旅券番号,発行場所,発行年月日,有効
期間満了日
資格:
1)日本国籍を有する18才以上の学生・大学院生(30才未満が望ましい)。
2)日本地質学会会員,もしくは指導教官が日本地質学会会員である者。
3)国際惑星地球年(IYPE)についての知識を有していること。
条件:
1)本年11月20日・21日,ポルトガルのリスボンで開催される式典に参加可能なこ
と(式典主催者による指定航空路および日程で参加)。
2)少なくとも簡単な英会話ができること。
3)地球科学関連分野を専門としていること。
4)帰国後,参加報告書を提出すること。
備考:
航空券(東京成田〜リスボン往復)および現地宿泊経費は式典主催者が負担しま
す。国内交通費(集合・解散場所は東京成田国際空港を予定)やパスポート取得,
旅行保険,そのほか参加に必要となる 費用は自己負担です。
参考 http://www.planetearthlisbon2009.org/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】ダーウィン生誕200年記念シンポジウム(ご案内)
──────────────────────────────────
公開シンポジウム「ダーウィンを超えて−21世紀の進化学」
2009年は、進化論を唱えたチャールズ・ダーウィン(Charles R. Darwin)の
生誕200年にあたり、さらに、自然選択による進化論を展開した『種の起源』
(初版1859年刊)の出版150周年にもあたる。
このため、日本学術会議進化・系統学分科会、ならびに日本進化学会、日本
動物学会では、生物学・進化学におけるダーウィンの業績を称え、進化学の
普及のために、中高生・一般向けに『ダーウィン生誕200年記念シンポジウム
ダーウィンを超えて −21世紀の進化学』を開催する。
日時:平成21年8月22日(土)13:00〜17:00
場所:東京大学安田講堂(文京区本郷7−3−1)
講演:
○第一部 講演 21世紀の進化学の最前線とその教育
・「植物になる進化」井上勲
・「ダーウィンを超えて植物進化を解く」長谷部光泰
・「共生と生物進化」深津馬
・「脊索動物の起源と進化」佐藤矩行
・「ゲノムからみた脳・神経系の起源と進化」五條堀孝
・「危機から生まれた哺乳類:脳進化」岡田典弘
・「迅速な適応性:昆虫の学習と進化ゲーム」嶋田正和
・「中高生にどのように進化を教えるか?」中井咲織
○第二部 パネルディスカッション 進化教育と生物多様性条約の動き
進行:嶋田正和、中井咲織
パネラー:井上勲、長谷部光泰、深津武馬、佐藤矩行、五條堀孝、
岡田典弘、伊藤元己
【問い合わせ先】 日本学術会議事務局第二部担当 小川
Tel:03-3403-1091
詳しくは、http://www.darwin-200th.net/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報
──────────────────────────────────
以下の公募のお知らせがあります。
詳しくは、学会HP http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html >をご
参照下さい。
■東京大学地震研究所地球化学分野教授公募(9/14締切)
■東北大学学術資源研究公開センター(総合学術博物館)教授公募(9/30締切)
■千葉工業大学 惑星探査研究センター 常勤研究員公募(8/31締切)
■名古屋大学大学院環境学研究科地球環境科学専攻教授または准教授公募(8/31)
■名古屋大学グローバルCOEプログラム特任教員公募(8/31)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
マンガ原作を募集します.ぜひ!(編集部)
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.069 2009/07/07 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.069 2009/07/07 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2009岡山大会ニュース:「保証及び著作権譲渡等同意書」への返信を!
【2】コラム:赤崩と大井川−池田宏氏による井川ジオツアーの報告−
【3】7月の博物館特別展示・イベント情報
【4】海底地形名称の提案募集
【5】堆積学スクールOTB2009 in 沖縄
【6】公募情報
【7】地質マンガ「テストの日」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2009岡山大会ニュース
──────────────────────────────────
■「保証及び著作権譲渡等同意書」への返信をお願いします。
岡山大会講演申込WEB画面の保証及び著作権譲渡等同意書へのリンクが切れており、
保証及び著作権譲渡等同意書に同意していただかないまま,講演申込を受け付け
てしまいました.
このため,申込者の皆様には保証及び著作権譲渡等同意書 http://www.geosociet
y.jp/okayama/content0024.htmlをご覧いただき,同意いただいてうえ、6/27付け
送信の『【重要】要返信 保証及び著作権譲渡等同意書』メールにご返信頂きま
すようお願いいたします.
受信されたメールに対して、そのまま返信頂ければ結構です。お手数をおかけし
大変申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
*講演番号・プログラムは7/中頃に各講演者にメール等でお知らせいたします。
また、ニュース誌7月号(7月末配布)に掲載されます。
■講演要旨集広告協賛の募集:締切延長しています。
地質関係機関・関連企業のご活躍を広く地質学会員に広報いただくべく,大会開
催にあわせ発行されます講演要旨集・見学旅行案内書において,広告協賛を募集
致しております。要旨集印刷日程にあわせて,締切を延長いたしましたので是非
ご検討ください。
最終締切:7月31日(金)
詳しくはこちらから。
http://www.geosociety.jp/okayama/content0016.html#09koukoku
■岡山大会に関連したプレス発表を希望される方へ
岡山大会で発表される予定の案件で,学会からのプレス発表をご希望の方は,8月
10日(月)までに学会事務局にご連絡願います.
登録締切:8月10日(月)
プレス発表(投げ込み):8月21日(金)
現地説明会(解禁日):8月28日(金)(予定)
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/okayama/content0003.html#news0619
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】コラム:赤崩と大井川−池田宏氏による井川ジオツアーの報告−
──────────────────────────────────
川村喜一郎(財団法人深田地質研究所)
「赤崩(あかくずれ)」とは、四万十帯の白亜紀の砂岩泥岩互層に見られる斜面
崩壊である.崩壊斜面は,北斜面に発達しており,地層は南傾斜である.すなわ
ち,崩壊斜面は,受け盤である.受け盤の地層が岩盤クリープによって傾動し,
崩壊が進行している.崩壊は数千年以上の長期間に渡って進行していると考えら
れており,現在も崩壊は進んでいる.崩れた後に赤い水がでることから,「赤崩」
と呼ばれているらしい.
続きを読む、、、http://www.geosociety.jp/faq/content0056.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】 7月の博物館特別展示・イベント情報
──────────────────────────────────
いよいよ、夏休みまでもう少し。博物館では、特別展示とイベントを用意してみな
さまのお越しをお待ちしています。
今月のイベントは、事前に申し込みが必要なものが多くあります。カレンダーをご
確認の上ご参加下さい。
詳しくはこちらから
http://www.geosociety.jp/name/content0044.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】海底地形名称の提案募集
──────────────────────────────────
海上保安庁では,海図や海底地形図などに記載する海底地形の名称を決定する「
海底地形の名称に関する検討会」を開催します.開催にあたり,関係学会等に広
く海底地形名称を募集することとしましたのでお知らせします.
同検討会で決められた海底地形名は,海上保安庁海洋情報部のホームページで紹
介しております.
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KOKAI/ZUSHI3/topographic/topographic.htm
「海底地形の名称に関する検討会」
日時:2009年7月6日(月)15:00から
場所:海上保安庁海洋情報部会議室
主な議題:海洋調査機関などから提案された日本列島周辺の海底地形名称の検討
問い合せ先:
海上保安庁海洋情報部航海情報課
主任海図編集官 細萱(ほそがや)
電話 03-3541-4201 FAX 03-3541-4388
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】堆積学スクールOTB2009 in 沖縄
──────────────────────────────────
「第四紀サンゴ礁堆積物の層序,堆積相,化石相」
日本堆積学会では,今年も恒例の堆積学スクール・オン・ザ・ビーチを開催いた
します.今年は炭酸塩堆積物に焦点を当てたスクールです.堆積学の2本柱のひ
とつである炭酸塩堆積学について,沖縄のサンゴ礁堆積物をじっくりと見学しな
がら学びます.このスクールは,堆積学の普及とレベルアップを目的とした学習
の場です.地層や地形に興味のある方,川や海が好きな方,地質学をこれから学
ぼうとしている方,地球科学系の理科教育に携わっていらっしゃる方,堆積研究
にこれから邁進してみたいと思っている方などなど,多方面からの参加をお待ち
しています.詳しくは、
日本堆積学会のHP(http://sediment.jp/04nennkai/2009/school.html)
地質学会の皆様の参加をお待ちしております.
講師:井龍康文(名古屋大),藤田和彦(琉球大),浅海竜司(琉球
大),Marc Humblet(東大・海洋研)
日程:8月4日(火)〜6日(木) 4日8:00 パレットくもじ集合.
* 8月4日 巡検 沖縄本島南部で島尻層群,知念層,琉球層群を観察
* 8月5日 巡検 沖縄本島で琉球層群を観察
* 8月6日 レクチャー:1 )琉球列島の新生代地史 2 )琉球列島および大東諸
島の炭酸塩堆積物(ドロマイト化作用を含みます) 3 )造礁サンゴの古生物学
(英語でのレクチャーとなります) 4 )大型有孔虫の生物学・古生物学 5 )
造礁サンゴから古環境を読む
定員:40名(先着順.定員に達し次第締め切ります)
参加費:15,000円巡検費用,テキスト,懇親会代を含みます.
問い合わせ先:
日本堆積学会行事委員会
横川美和(大阪工業大学 miwa@is.oit.ac.jp)
堆積学スクールOTB2009 in 沖縄 世話人
井龍康文(名古屋大学 iryu.yasufumi@a.mbox.nagoya-u.ac.jp)
浅海竜司(琉球大学 asami@lab.u-ryukyu.ac.jp)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募情報
──────────────────────────────────
以下の公募、各賞・研究助成等のお知らせがあります。
詳しくは、学会HP<http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html>をご参
照下さい。
■平成22年度研究船利用公募課題の募集(7/20)
■山口大学大学院理工学研究科(地球科学分野)教員公募(8/28)
■福井県職員(古生物学)募集(9/11)
■第30回猿橋賞の推薦の募集(11/30)
■2009年度「朝日賞」候補者推薦依頼(8/14)
■第31回沖縄研究奨励賞推薦応募(9/30)
■平成21年度東レ科学技術賞および東レ科学技術研究助成の候補者推薦(9/10)
( )は締切日です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】地質マンガ 「テストの日」
──────────────────────────────────
マンガ「テストの日」 作:坂口有人 画:Key
詳しくは,http://www.geosociety.jp/faq/content0171.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎年夏は記事が少ないです. 皆様の声をお届けしたい!(編集部)
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質マンガ ギョーカイ岩って
地質マンガ
戻る|次へ
No.072 2009/08/18 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.072 2009/08/18 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】岡山大会関連情報:緊急展示募集ほか
【2】一般社団法人日本地質学会の代議員および役員の選挙実施について
【3】日本地質学会ジオパークワークショップ開催(9/5)
【4】日本地方地質誌「中国地方」刊行と割引販売のお知らせ
【5】韓国地質学会:日韓合同英語セッション開催
【6】IGCP507第4回シンポジウムのご案内
【7】南海トラフ地震発生帯掘削計画タウンホールミーティング のご案内
【8】第26回東海地震防災セミナー2009のお知らせ
【9】公募情報
【10】地質マンガ 「ギョーカイ岩って」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】岡山大会関連情報:緊急展示募集ほか
──────────────────────────────────
■緊急展示募集中!!
学会活動の一端を広く社会に紹介するとともに,ホットなテーマについて議論
する場を提供するために,災害報告や社会的に影響のある新技術紹介などの「緊
急展示コーナー」を設けます.ポスター展示を希望する方は,8月21日(金)まで
に以下の内容でお申し込みください.
1)発表要旨PDF(ニュース誌4月号参照) 2)緊急展示の必要性 3)発表代表者
と連絡先 4)希望枚数(1枚:幅90×180cm) 5)展示に関わる要望(2〜5の様
式は自由)
実行委員会は行事委員会と協議し,可否の判断を致します.希望にはできるだ
け応えるようにしますが,展示方法等については実行委員会の指示に従ってくだ
さい.
申込先 main@geosociety.jp
締切 2009年8月21日(金)
担当 鈴木茂之(岡山大会実行委員会)・上野将之(行事委員会)
■理科教員対象見学旅行:参加者募集中!!
実施日:2009年9月5日(土)8:30集合
テーマ:岡山県南部の花崗岩類(万成石)と文化地質学
申込締切:申込者数が定員になり次第締切.
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/okayama/content0007.html#field-trip
■構造地質・若手の集い合同夜間小集会
9月5日(土)の18:00〜20:00に,「構造地質学の今後の課題」と
「地質学会若手の集い」の夜間小集会を合同で開催します(会場55).
講演「ナウマンに導かれて(高橋雅紀氏,産総研)」に引き続いて,構造地質
を含む日本の地質学の展望について参加者で議論します.たくさんの会員の
皆様のご参加をお待ちしています.
(世話人 松田達生・大坪 誠・山口飛鳥・山口直文・大橋聖和・池田昌之)
■岡山大会HP:
http://www.geosociety.jp/okayama/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】一般社団法人日本地質学会の代議員および役員の選挙実施について
──────────────────────────────────
今年度末で任意団体を解散し,2010年度から全面的に法人として活動を行なう計
画でおりますが,それに先立ち,法人として初めての,代議員および役員の選挙
を今秋10月から来年2月にかけて実施いたすことになりました.詳細は選挙管理委
員会により,来月号のNews誌およびWebサイト に告示されます.
会員各位におかれましては,ご留意のうえよろしくご協力くださいますようお願
いいたします.
なお,選挙管理委員会の構成は次のとおりです.
委員長:松田達生
委 員:太田 亨・川上俊介・川村喜一郎・中島 礼
2009年8月10日
一般社団法人日本地質学会執行理事会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本地質学会ジオパークワークショップ開催(9/5)
──────────────────────────────────
日本地質学会ジオパーク支援委員会は,日本ジオパークネットワークの共催の
もと,ジオパークによる地域活性化、地質遺産の保全および地学の普及のために
地域の方々と地質学者がどのように連携して活動していけばよいかをさぐるため
に,ワークショップを開催します。本ワークショップでは,実際にジオパークの
運営に携わる人と地質学会員が,各地の実践例の発表をもとに,地域と地質学者
の連携のあり方を議論します。ジオパークに関心のある行政担当者,地域の方,
研究者などの皆様の参加を期待します。なお,国内初の世界ジオパークネットワー
ク加盟地域は8月23日には決定する予定です。
日時:9月5日(土)10:00-
場所:岡山市デジタルミュージアム4階
(岡山駅西口・リットビル正面のエスカレーターをご利用のうえ,4階へとお上
がりください。)
主催:日本地質学会ジオパーク支援委員会
共催:日本ジオパークネットワーク
後援:産総研地質調査総合センター
詳しくはhttp://www.geosociety.jp/geopark/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】日本地方地質誌「中国地方」刊行と割引販売のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地質学会編集 日本地方地質誌
第4回配本 6.中国地方 560頁,口絵8頁(9月上旬刊行)
定価26,250円(税込)を会員特別割引価格22,500円(税・送料込)
日本地質学会会員の皆様に,日本地方地質誌を特別割引価格で販売をいたします.
お申し込みは,専用申込用紙にて直接朝倉書店までお願いいたします.
(日本地質学会「日本地方地質誌」刊行委員会)
詳しくは、HP会員のページへ(ログイン情報が必要です)
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】韓国地質学会:日韓合同英語セッション開催
──────────────────────────────────
昨年,秋田で合意された日韓の地質学会年会の相互乗り入れについて,今年の
韓国地質学会(GSK)の英語セッションの案内が届きましたのでご紹介します.今
年のGSK大会は10月末に済州島で開催されますが,その中で10月29日(木)に,日
本人も発表できる英語セッションを設けていただきました.とくに日本海(East
Sea)のテクトニクスや活断層などは,盛り上がるテーマだと思いますので,ふるっ
てご参加ください.済州島は火山岩だけではなく堆積構造も面白い場所のようで,
韓国の中でジオパークに最も熱心な場所でもあると聞いています.
未だ申し込み方法,巡検等については未だ決まっていないようですが,岡山大
会から間もないことでもあり,とりあえず日程だけお知らせしておきます.詳細
がわかり次第,再度ご案内いたします.巡検の参加も歓迎とのことです.
(日韓交流小委員会 高木秀雄)
韓国地質学会
日時:10月29日(木)9:00〜12:00 日韓合同英語セッション(主催はK-IODPであ
るが,発表のテーマは問わない)
場所:済州島
全体の日程は以下の通り.
Itinerary of 2009 KJOD Symposium
10/28 Wed. Full day: *Field Excursion provided by Geological Soc
iety of Korea (GSK)
10/29 Thu. Morning: IODP Session of GSK
10/30 Fri. 09:00-12:00: KJOD Symposium organized by K-IODP/J-DESC
13:00-18:00: KJOD Workshop for OT (Okinawa Trough) dril
ling
Afternoon: *Field Excursion provided by GSK
10/31 Sat. 09:00-12:00: KJOD Workshop for OT drilling
Full day: *Field Excursion provided by GSK
以下,主催者のLee, Young-Joo氏からのメール(8月12日)です.
This is Young-Joo Lee working for KIGAM.
As we agreed during GSJ(Geological Society of Japan) meeting at Akita las
t year,
Korea IODP(K-IODP) will open a international session during GSK (Geologic
al Society of Korea) meeting (Oct. 28-31) at Jeju Island.
I'll briefly explain each sessions;
1. IODP session of GSK: Morning of 29th Oct.
: It is kind of English session in GSK. K-IODP will handle this session,
however, themes are not limited IODP & Ocean Sciences. We really welcome
Japanese scientists to present their scieitific papers in this session wi
th more broad themes.
2. 4th KJOD (Korea Japan Ocean Drilling) Session : Morning of 30th Oct.
:This session is more focused on Ocean Drilling activities & sciences,
however, the theme has wide ranges
as IODP does.
3. KJOD Workshop for OT (Okinawa Trough) drilling: Afternoon of 30th & Mo
rning of 31st Oct.
: This session is more focused on collaborative work on drilling proposa
l in Okinawa Trough. As you may know, Japanese & Korean scientists are pr
eparing new drilling proposal targeting OT region. Even this session is
more dedicated to OT drilling, anyone who have interests can join in & di
scuss.
For more detailed information such as logistics & registration, please co
ntact Dr. Seung Il Nam (sinam@kigam.re.kr).
以下,上記の Seung Il Nam氏からのメール(8月14日)です.
-------------------------------------------------------------------------
many thanks for your kind coordination for helping a special session for
Korea-Japan IODP scientists in the morning of 29th Oct.
But, we have still not any detailed information about the schedule of re
gistration of this joint session.
I think the GSK (Geological Society of Korea) will soon inform us about t
he detailed schedule of the GSK meeting.
As I know there will be two one-day field trips, i.e. pre (28th)- and pos
t (31st) filed trips around Jeju Island. These field trips will be very e
xciting for Japanese scientists. I hope many of them will join those fiel
d trips. Now, I'm also looking for a nice accommodation Hotel for all par
ticipants and if the hotel will be decided I will inform you for the hote
l reservation of Japanese scientists.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】IGCP507第4回シンポジウムのご案内
──────────────────────────────────
「白亜紀のアジアの古気候とそれらの国際的な比較」
日時:12月1日(火)〜3日(木),プレ野外巡検(御所浦・姫浦層群)
12月4日(金)〜5日(土),シンポジウム
12月6日(日),ポスト野外巡検(御船層群)
会場:熊本大学大学院自然科学研究科「工学部100周年記念館」
主催:UNESCO & IUGS,共催:熊本大学・御船町恐竜博物館
講演および野外巡検への参加申込と講演要旨の締切:2009年9月15日(火)
問合せ先:熊本大学大学院自然科学研究科 小松俊文
TEL: 096-342-3425, FAX: 096-342-3411
e-mail: IGCP507@sci.kumamoto-u.ac.jp, komatsu@sci.kumamoto-u.ac.jp
詳しくはhttp://igcp507.kopri.re.kr
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】 南海トラフ地震発生帯掘削計画タウンホールミーティング のご案内
──────────────────────────────────
IODP南海トラフ地震発生帯掘削計画は,一昨年のステージ1を皮切りに着実に進行
しており,現在はステージ2が実施中です.来たるステージ3における大深度掘削を
控えて,地質学会学術大会(岡山)に合わせてタウンホールミーティングを開催いた
します.また、あわせて今年度より発足する新学術領域「超深度掘削が拓く海溝型
巨大地震の新しい描像」(代表研究者 木村学)の公開説明会を開催いたします。
関係者のみならず関心ある皆様にはご来場頂けますようお願いいたします.
[日時] 9月5日 18時〜
[場所] 岡山国際交流センター 3階研修室
http://www.opief.or.jp/oicenter/index.html
[問い合わせ先]
海洋研究開発機構 坂口有人(arito@jamstec.go.jp)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】第26回東海地震防災セミナー2009のお知らせ
──────────────────────────────────
日 時:2009年11月11日(水)13:30−16:00
会 場:静岡商工会議所会館5階ホール(JR静岡駅北口西側)
テーマ:東海地震に備える
座長:静岡大学理学部地球科学科 静岡大学防災総合センター 教授 里村 幹夫
1. インド洋大津波の災害実態
静岡大学防災総合センター 准教授 林 能成
2. 地震学の発展で実現した地震防災−緊急地震速報−
東京大学地震研究所 准教授 束田 進也
主 催:東海地震防災研究会
連絡先:〒422-8035静岡市駿河区宮竹1-9-24
土研究事務所 土 隆一
Tel.:054-238-3240 Fax:054-238-3241
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報
──────────────────────────────────
■東京大学大学院理学系研究科地殻化学実験施設教員公募(9/25締切)
■大阪市立大学大学院理学研究科・理学部地球学教室教員公募(A)(10/16締切)
■大阪市立大学大学院理学研究科・理学部地球学教室教員公募(B)(10/16締切)
--------------------------
■日本原子力研究開発機構平成22年度「先行基礎工学研究」募集(11/16締切)
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】地質マンガ
──────────────────────────────────
「ギョーカイ岩って」 作:千代田厚史 画:Key
http://www.geosociety.jp/faq/content0177.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
岡山でお会いしましょう(編集部)
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質マンガ 木目とクロスラミナ
地質マンガ
戻る|次へ
No.071 2009/08/04 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.071 2009/08/04 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】岡山大会 事前参加登録を!8/17日締切(FAX:8/10締切)
【2】惑星地球リスボン式典2009 派遣学生推薦募集
【3】惑星地球フォトコンテスト;作品募集中
【4】アジア留日経験研究者データベース(JARC-Net)のご案内
【5】IGCP507シンポ「白亜紀のアジアの古気候とそれらの国際的な比較」
【6】8月の博物館特別展示・イベント情報
【7】公募情報
【8】地質マンガ
【9】お知らせ(J-STAGEサービス一時停止/事務局夏期休業)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】事前参加登録を!8/17日締切(FAX:8/10締切)
──────────────────────────────────
■事前参加登録を!8/17日締切(FAX:8/10締切)
当日会場受付での混雑緩和のため,事前に参加登録申込をお願いします。大会参
加登録およびそれに伴う参加費は,全ての参加者(見学旅行のみの場合も)に必
要な基本的なお申込です.ただし,会員が同伴する非会員の配偶者ならびに子供
については必要ありません。講演予定の方は参加登録をお忘れなく!
web参加登録画面(日本旅行)<https://apollon.nta.co.jp/chishitsu>
(注:締切まで、申込内容の確認・変更も可能です)
■理科教員対象見学旅行:参加者募集中!!
実施日:2009年9月5日(土)8:30集合
テーマ:岡山県南部の花崗岩類(万成石)と文化地質学
申込締切:申込者数が定員になり次第締切.
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/okayama/content0007.html#field-trip
■岡山大会に関連したプレス発表を希望される方へ
岡山大会で発表される予定の案件で,学会からのプレス発表をご希望の方は,8月
10日(月)までに学会事務局にご連絡願います.
・登録締切:8月10日(月)
・プレス発表(投げ込み):8月21日(金)
・現地説明会(解禁日):8月28日(金)(予定)
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/okayama/content0003.html#news0619
岡山大会HP:
http://www.geosociety.jp/okayama/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】惑星地球リスボン式典2009 派遣学生推薦募集
──────────────────────────────────
国際惑星地球年(IYPE)2007-2009のファイナルイベントとして,ポルトガル政府の
協力のもと,2009年11月20日・ 21日の両日,リスボンで「惑星地球リスボン式典
2009(Planet Earth Lisbon Event 2009)」が開催されます。式典は IYPE3ヶ年
の活動を総括し,またポストIYPEプロジェクトに光 を当てるものです。あわせて,
展示会や科学者・政治家・産業界首 脳 による「再生可能エネルギー」「持続可
能な土地および水管理」 「海洋」に関する会議も計画されています。
本式典に対し、各国から学生を招待することとなり、IYPE日本委員会より日本
地質学会に対して派遣学生1名の推薦依頼がありました。推薦候補者の資格や条件
等は下記の通りです。応募者の中から理事会で1名の候補者を決定し、IYPE日本委
員会に推薦いたします。(日本地質学会理事会)
締切:2009年8月10日(月)12 時まで
宛先:日本地質学会<main@geosociety.jp>
詳しくはこちら、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0174.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】惑星地球フォトコンテスト;作品募集中
──────────────────────────────────
IYPE(国際惑星地球年)と地質学会の主催で惑星地球フォトコンテストを開
催します.惑星地球に関する芸術的もしくは学術教育的写真を募集します.
上位入賞作品は,3月のIYPE記念イベントにて展示表彰いたします.会員の
皆様には奮ってご応募下さいますようお願いいたします.11/30締切.
詳しくは,, http://photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】アジア留日経験研究者データベース(JARC-Net)のご案内
──────────────────────────────────
アジア留日経験研究者データベース(英語名称:Japan-Asia Research Community
Network、略称:JARC-Net)は、日本への留学・滞在研究の経験を持つアジアの研
究者やアジアとの研究協力に関心を持つ日本人研究者等の情報を集めたデータベー
スです。JARC-Netは、アジアの同僚とのネットワークの維持や新たな共同研究の
パートナーの発見の機会を提供することで、日本とアジアとの長年の研究交流に
より培われた人的ネットワークの維持と強化に貢献すること目的としています。
本データベースは登録制となっています。是非ご登録のうえ、ご活用ください。
<対象>日本での留学・滞在研究の経験のあるアジア人研究者/日本との研究協力
に関心があるアジア人研究者/アジアとの研究協力に関心がある日本人研究者この
他にも、大学院生、大学・研究機関職員、企業関係者、政策担当者等などアジア
との研究協力に関心をもつ方々の登録を歓迎します。またアジア地域以外の国・
地域の方も登録可能です。
詳しくは、http://www.jsps.go.jp/j-astrategy/11_jarc-net.html
問い合わせ
日本学術振興会国際事業部地域交流課戦略交流係
TEL 03-3263-1742 FAX 03-3234-3700
jarc-net@jsps.go.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】IGCP507シンポ「白亜紀のアジアの古気候とそれらの国際的な比較」
──────────────────────────────────
韓国のソウル大学を中心に進めているIGCP507「白亜紀におけるアジアの古気候」
の第4回シンポジウムと野外巡検が,熊本大学と熊本県下のフィールドで行われま
す.
日時:2009年12月1日(火)-3日(木),プレ野外巡検(御所浦・姫浦層群)
12月4日(金)-5日(土),シンポジウム
12月6日(日),ポスト野外巡検(御船層群)
会場:熊本大学大学院自然科学研究科「工学部100周年記念館」
主催:UNESCO & IUGS
講演申込・参加申込・講演要旨の締切:9月15日(火)
参加費:シンポジウム(ポスト巡検を含む)一般参加者18,000円,学生10,000円
プレ野外巡検 一般・学生参加者 43,000円
問合せ先:〒860-8555 熊本県熊本市黒髪2−39−1
熊本大学大学院自然科学研究科 小松俊文
TEL: 096-342-3425, FAX: 096-342-3411
e-mail: IGCP507@sci.kumamoto-u.ac.jp,
komatsu@sci.kumamoto-u.ac.jp
詳しくは、http://igcp507.kopri.re.kr
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】 8月の博物館特別展示・イベント情報
──────────────────────────────────
いよいよ夏休みも本番。博物館では充実した特別展示や体験イベントをご用意して
みなさまのお越しをお待ちしております。
特に今月は事前申込が不要の体験イベントが盛りだくさんですので、いまからでも
間に合いますよ。
スケジュールは今すぐ↓↓でチェック!!
http://www.geosociety.jp/name/content0045.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報
──────────────────────────────────
■東京工業大学新学術領域「地殻流体」(領域提案型)特任助教公募(8/21)
■東京工業大学グローバルCOE「地球から地球たちへ」特任准教授公募(8/20)
----------------------
■高知大学海洋コア総合研究センター全国共同利用研究公募(8/31)
■平成22年度笹川科学研究助成の募集(10/1-10/15)
■第17回日産科学賞候補者募集(学会締切:9/1)*学会推薦です
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】地質マンガ
──────────────────────────────────
「木目とクロスラミナ」 作:川村喜一郎 画:Key
http://www.geosociety.jp/faq/content0175.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】お知らせ いろいろ
──────────────────────────────────
◇J-STAGEシステムメンテナンス・サービス一時停止のお知らせ
(投稿・査読システム・公開・Journal@rchive)
8月29日(土) 10:00 〜 8月30日(日) 20:00
詳しくは、http://www.geosociety.jp/news/n51.html
◇学会事務局:夏期休業のお知らせ
8/13(木)・8/14(金)
事務局営業カレンダーはこちらから、
http://www.geosociety.jp/outline/content0026.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
マンガ原作を募集します.ぜひ!(編集部)
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.081 2009/11/04 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.081 2009/11/04 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】日韓交流:友情の楯
【2】2010年度代議員および役員選挙 立候補受付中!
【3】名簿作成アンケート実施中!
【4】惑星地球フォトコンテスト;作品募集中
【5】コラム:山手線と山の手台地
【6】学術会議関連:お知らせ
【7】その他お知らせ
【8】11月の博物館特別展示・イベント情報
【9】公募情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】日韓交流:友情の楯
──────────────────────────────────
大韓地質学会より,宮下会長に日韓地質学会交流記念の楯が,高木副会長に日韓
地質学者交流促進による感謝の楯が授与されました.
2009年10月29日〜30日に済州国際コンベンションセンターにて開催された韓国の
秋季地質科学連合大会における大韓地質学会第64回定期総会にて,大韓地質学会
李鉉具会長より,宮下純夫会長に日韓地質学会交流記念の楯が授与されました(
写真左).宮下会長からは,最近の地質学会の活動,とくにジオパークや地学オ
リンピックの促進,韓国,タイ,モンゴルなどの学術交流協定に基づき,来年富
山で開催される地質学会でアジアの方たちを招くセッションを開催する予定であ
ることなどが紹介されました.
友情の楯
感謝の楯
また,高木秀雄副会長には,1998年から始まった日韓の構造地質関係者をはじ
めとする学術交流を促進したことに対して,感謝の楯(写真右)が授与されまし
た.高木副会長からは,ソウル,様似,デジョンで開催された過去3回の構造地
質日韓合同大会は韓国のメンバーの多大な協力なくしてはなし得なかったこと,2
007年に締結された日韓学術交流協定に基づく活動が韓国地質学会からの協力によ
り着実に進んでいることに対する謝辞が述べられ,来年8月に高知で第4回構造地
質日韓合同大会を開く予定であることが紹介されました.
なお,この大会と同時に開催されたIODP日韓シンポジウムや巡検および済州島
“ジオパーク”の可能性については,後日参加者によりニュース誌に投稿される
予定です.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2010年度代議員および役員選挙 立候補受付締切迫る!!
──────────────────────────────────
代議員の立候補受付締切まであと1週間程となりました.11月12日(木)必着です.
今度の選挙は,日本地質学会が一般社団法人となって初めての大変重要な選挙で
す.今後の学会の趨勢を担うものですので,多くの会員の皆様に立候補して頂き
たいと存じます.皆様,是非とも宜しくお願い申し上げます.
代議員立候補受付締切:11月12日(木)(必着)
投票期間:11月30日(月)〜1月9日(土)
詳しくは、(ログインID・パスワードが必要です).
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
(選挙管理委員会 委員長 松田達生)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】名簿作成アンケート実施中!
──────────────────────────────────
2009年度版会員名簿発行(12月末発行予定)にあたり、会員情報の変更、また会
員名簿(冊子)への掲載についての確認を会員ページからにログインしてご自身
の情報を確認・訂正・変更してください.
会員情報Web画面更新締切日:2009年11月6日(金)
詳しくは、(ログインID・パスワードが必要です)
http://www.geosociety.jp/members/content0044.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】惑星地球フォトコンテスト;作品募集中
──────────────────────────────────
IYPE(国際惑星地球年)と地質学会の主催で惑星地球フォトコンテストを開
催します.惑星地球に関する芸術的もしくは学術教育的写真を募集中です.
上位入賞作品は,3月のIYPE記念イベントにて展示表彰いたします.会員の
皆様には奮ってご応募下さいますようお願いいたします.(11/30締切)
詳しくは、http://photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】コラム:山手線と山の手台地
──────────────────────────────────
川村喜一郎(財団法人深田地質研究所)
我々の研究所は、山の手台地にある。山の手台地は、武蔵野台地の東側にあたり、
武蔵野台地と言っても良いらしい。
ここから、自転車で10分程度行くと、山手線田端駅がある。この田端駅から駒
込駅に向かうとき、山手線は坂を登り、崖の上に出る。ご存知だろうが、この坂
は、東京低地と山の手台地を境する崖にあたる。
地図で山手線の通っているところをよく見ると、東側は、台地の麓に沿って走っ
ていることがわかる。上野駅から田端駅までの間の山手線の西側には、比高10m
程度の崖が南北に、山手線に沿って伸びている。これが山の手台地と東京低地の
境である。この崖は、約6000年前の縄文時代の海進によって作られた海食崖
である。このような海食崖には貝塚が作られた。中学校の理科で勉強して、知っ
ている方々も多いだろう。私の出身地の目黒にも東山貝塚公園なるものがあり、
竪穴式住居や昔の人を模した人形が公園内にあったことを今でも覚えている。
東京低地は、海食崖が作られた縄文前期に作られた。当時、台地の縁まで海が侵
入してきて、海成堆積物が堆積し、その後河川堆積物が覆い、それが今の東京低
地である。弥生時代には、東京低地で稲作が行われていたそうだ。
一方、武蔵野台地の段丘面は、それよりももっと前、今から約10万年〜3万年
前の後期更新世の中頃に作られた。その当時、多摩川によって運搬、堆積した礫
層や砂層が広大な、今の武蔵野面を作ったとされている。ただし、田端のあたり
の山の手台地は、荒川によって作られたとされている。そして、この武蔵野面は、
その後の富士山などの噴火によって、数メートルの厚さの関東ローム層によって
覆われている。
田端には、車両基地があり、新幹線や機関車などの各種鉄道車両がある。また、
山手線は、今年で100周年を迎え、復刻の茶色い車両が走っている。田端で、
めずらしい鉄道を見て、遠くに見える台地の縁を眺めると、都会にある鉄道とジ
オロジーの融合、すなわち「ジオ鉄」を感じることができるかもしれない。
今、日本地質学会とIYPEが、惑星地球フォトコンテストを開催している。このフォ
トコンテストでは、先の「ジオ鉄」にまつわる写真も募集している。500万画
素で撮影して、今すぐ応募しよう。全国の「田端」が君を待っている。
田端車良基地。電気機関車や奥にはさまざまな新幹線も見られる。その奥には、山の手台地の崖がある。
東京低地から山の手台地をめざして登る山手線。田端駅—駒込駅の富士見橋から撮影。次は茶色いのを撮りたいのだが。
参考文献:東京都地学のガイド編集委員会編(貝塚監修)1997、地学のガイドー
東京都の地質とそのおいたちー、コロナ社、276p。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】学術会議関連:お知らせ
──────────────────────────────────
■日本学術会議主催公開講演会
「大学教育の分野別質保証に向けて:日本学術会議からの報告」開催のご案内
日時:11月23日(月・祝)13:30-17:00
会場:東京大学安田講堂(東京大学本郷キャンパス)
要申込(11/6締切)・参加費無料
http://www.asahi.com/edu/scj/
■市民対象 公開講演会
「地域資源の活用を図り、地域と共に知を育み生かす学習〜国や地方公共団体等
が取り組む、自然フィールドを使った体験学習を通じた、人間力の向上と実社会
との連携〜」
日時:12月3日(木)13:00-17:00
場所:宇部全日空ホテル(山口県宇部市相生町8−1)
参加申込不要・参加費無料
詳細は、
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf/83-s-2-1.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他お知らせ
──────────────────────────────────
■巡検+勉強会 第11回Project A 春期ミーティング 伊豆大島
日程:3月4日-7日(4,5日:シンポジウム/6日:巡検/7日朝解散)
場所:海のふるさと村(東京都大島町泉津字原野2-1)
会費:学生 8000円・ 一般 16000円
申込締切 12月10日(木)
詳しくは
http://archean.jp/modules/pico/index.php?content_id=7
■第55回日本水環境学会セミナー「水辺の再生」
水辺空間は,人々の憩いの空間,子供の遊び場所として重要な役割をはたしてい
る.しかしながら都市域の河川をはじめとする水辺の多くは,未処理の生活雑排
水が流入したり,排水処理過程で除去ができない物質が流入し,有機物・有害化
学物質などにより汚染され,生き物の減少や種の単純化が起こっている.このよ
うな背景のもと,中小河川,身近な水辺である水路,ため池,濠のさらなる水質
改善および多様な生き物が生育・生息する場としての保全・再生が必要とされて
いる.本セミナーでは水辺の再生の方向性,生物・物理化学的手法による水辺環
境の保全・再生技術についてご講演いただきます.
主 催: (社)日本水環境学会
期 日: 2010年1月22日(金)9:55 –16:45
場 所:自動車会館 大会議室(東京都千代田区九段南4-8-13)
参加費: 会 員/7,000円 非会員/14,000円 学生会員/3,000円
定 員: 180名
申込方法:
FAX,E-mail,またはハガキに①参加者氏名(フリガナ),②会員・非会員の別,
③会員の場合は会員番号,④連絡先(所属団体名,住所および電話・FAX番号)を
ご記入の上,下記宛てお申し込み下さい,また,参加費を1月15日までにお振り込
み下さい.入金を確認後,参加証(ハガキ)をお送りいたします.
参加費振込先: 三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店 (普通)0754950
(社)日本水環境学会セミナー口
シャ)ニホンミズカンキョウガッカイセミナーグチ
申し込み・問い合わせ先
(社)日本水環境学会 セミナー係
〒135-0006 東京都江東区常盤2-9-7 グリーンプラザ深川常盤201号
Tel.03-3632-5351 Fax.03-3632-5352
E-mail: yamamoto@jswe.or.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】11月の博物館特別展示・イベント情報
──────────────────────────────────
博物館では文化の秋を応援する、特別展示やイベントが盛りだくさんです。特
に今月は、週末のイベントが充実しています。
また、特別展示がまもなく終了するものもありますので、お見逃しのないよう
イベントカレンダーをぜひチェックして見てください。
11月の博物館イベントカレンダーは↓↓↓
http://www.geosociety.jp/name/content0050.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報
──────────────────────────────────
■平成22年度東京大学海洋研究所共同利用公募(11/30締切)
■第51回藤原賞受賞候補者募集(10/01/30締切)
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.073 2009/08/24 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.073 2009/08/24 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】祝!日本の3地域が世界ジオパークに認定
【2】世界ジオパーク認定関連行事の案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】祝!日本の3地域が世界ジオパークに認定
──────────────────────────────────
2009年8月22日に中国泰安市で開催された世界ジオパークネットワーク事務
局会議において、洞爺湖有珠山、糸魚川、島原半島の3地域が世界ジオパーク
ネットワーク加盟のジオパークとして認定されました。
詳しくは
http://www.gsj.jp/jgc/news/ggn2009.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】世界ジオパーク認定関連行事の案内
──────────────────────────────────
「日本地質学会第116年学術大会(岡山)」および「地質情報展 2009 おか
やま」にて関連行事が開催されます.
■緊急展示:
日本地質学会第116年学術大会(岡山理科大)において世界ジオパーク認定
3地域のポスターを緊急展示いたします.
■「地質学会ジオパークワークショップ」の開催
ジオパークによる地域活性化をめざして
−地域と地質学者の連携のあり方をさぐる-
日本地質学会ジオパーク支援委員会は,日本ジオパークネットワークの共催の
もと,ジオパークによる地域活性化、地質遺産の保全および地学の普及のために
地域の方々と地質学者がどのように連携して活動していけばよいかをさぐるため
に,ワークショップを開催します。本ワークショップでは,実際にジオパークの
運営に携わる人と地質学会員が,各地の実践例の発表をもとに,地域と地質学者
の連携のあり方を議論します。ジオパークに関心のある行政担当者,地域の方,
研究者などの皆様の参加を期待します。
日時:9月5日(土)10:00-
場所:岡山市デジタルミュージアム4階
(岡山駅西口・リットビル正面のエスカレーターをご利用のうえ,4階へとお上
がりください。)
主催:日本地質学会ジオパーク支援委員会
共催:日本ジオパークネットワーク
後援:産総研地質調査総合センター
詳しくはhttp://www.geosociety.jp/geopark/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.074 2009/09/01 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.074 2009/09/01 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】岡山大会関連情報いろいろ
【2】地質学雑誌:文献英文併記と図表・キャプションの英文化を
【3】日本地方地質誌「中国地方」刊行と割引販売のお知らせ
【4】平成21年度 東濃地科学センター 地層科学研究情報・意見交換会
【5】Conference of the Association of Korean Geoscience Societies,
Autumn-2009
【6】バングラデシュの環境問題を考えるシンポジウム
【7】9月の博物館特別展示・イベント情報
【8】公募情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】岡山大会関連情報 いろいろ
──────────────────────────────────
■見学旅行:追加募集します。
見学旅行の一部コースについて追加募集を行います。定員になり次第締切となり
ます。申込希望の方は、お早めに学会事務局<main@geosociety.jp>
または電話:03-5823-1150 まで.
◯B班「四万十帯牟岐メランジェにみる沈み込み帯地震発生帯の変形と流体移動」
(残7名分)
日程:9月7日(月)〜8日(火)(1泊2日)
◯G班「成羽層群の炭層地すべり群」(残2名分)
日程:9月7日(月)日帰り
◯H班「岡山県東部周辺の舞鶴帯と超丹波帯」(残り5名分)
日程:9月7日(月)日帰り
詳しくは、http://www.geosociety.jp/news/n52.html
■大会専用直通バスについて(注意!9/4(金)のみの運行)
通常、岡山駅西口バス乗場から岡電バス(岡山大学経由岡山理科大学正門行)が
運行しており、7:55〜8:45 は5分間隔でバスが出発しますが,附属高校の通学時
間(7:55〜8:20)と重なり混雑が予想されます.そこで学会専用直行バスを3台運
行いたします。どうぞご利用ください。
運行日時:9/4(金)08:00発
乗り場:JR岡山駅西口出て、ANAホテル前バス乗り場
講演者優先、運賃200円、会場までの直行便です(途中どこにも停まりません)
■新型インフルエンザ等の対応について
日本地質学会は、新型インフルエンザ予防対策として、会場に手洗い用の消毒薬
を用意します.その他はご自身のご判断で、マスク等各自でご用意願います.
なお、38度以上の発熱や呼吸器症状のある方、新型インフルエンザの感染者(疑
似症患者を含む)及び濃厚接触者は、会場への入場を自粛されるようお願いいた
します.
会期中またはその後に、38度以上の発熱や呼吸器症状の出た方は、必ず事前に
医療機関に電話連絡し、受診方法等について指示を受け、マスクを着用したうえ
で受診してください。新型インフルエンザを含む感染症法の対象となる疾病と診
断された場合は、学会本部にもその旨、必ずご連絡をお願いいたします。
連絡先は、こちら
http://www.geosociety.jp/okayama/content0003.html#0831news02
■シンポジウム「科学を文化にー学校教育・地学教育のこれから」
9月6日(日)9:00-12:00 会場:講演会場43
興味のある学生さんの多くの参加をお待ちしています。
学習指導要領の改訂を機に、地域の山野を愛で,大地のなりたちや環
境保全の大切さを「身近な自然科学」として生徒が身につけるような、
「成熟した社会における地学教育」を議論します。新鮮な感性のご意見
をお待ちしてまーす!(世話人代表:藤林紀枝)
■構造地質・若手の集い合同夜間小集会
9月5日(土)の18:00〜20:00に,「構造地質学の今後の課題」と
「地質学会若手の集い」の夜間小集会を合同で開催します(会場55).
(注:構造地質部会の会場42ではなく,若手の方の会場55です!)
講演「ナウマンに導かれて(高橋雅紀氏,産総研)」に引き続いて,構造地質
を含む日本の地質学の展望について参加者で議論します.たくさんの会員の
皆様のご参加をお待ちしています.
(世話人 松田達生・大坪 誠・山口飛鳥・山口直文・大橋聖和・池田昌之)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】地質学雑誌:文献英文併記と図表・キャプションの英文化を
──────────────────────────────────
これまでもニュース誌等でお知らせして参りました通り,日本地質学会の法人
化に伴い,学会諸規則の整備が行われ,その中の一つとして,従来の編集規約,
投稿規定などの編集に関わる規則を一本化,内容も一部改訂し,新しい編集規則
を作成いたしました.
従来からの大きな変更点は,引用文献リストや図表およびキャプションの英文
化です.これは,インパクトファクターの附帯化,国際的な相互引用化をめざす
ためにも必要不可欠なものです.地質学雑誌の更なる充実・地位向上のため会員
の皆様のご協力をお願いいたします.
具体的には,2009年9月1日以降,新規に投稿される投稿原稿全てに新規則が適
用されます.また,また第115卷9号(2009年9月号)以降の掲載論文に関しても適
用となりますので,既にご投稿中の著者にも随時修正をお願いする次第です.
新しい編集規則は,学会ホームページまたは地質学雑誌巻末をご参照ください.
http://www.geosociety.jp/publication/content0038.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本地方地質誌「中国地方」刊行と割引販売のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地質学会編集 日本地方地質誌
第4回配本 6.中国地方 560頁,口絵8頁(9月上旬刊行)
定価26,250円(税込)を会員特別割引価格22,500円(税・送料込)
日本地質学会会員の皆様に,日本地方地質誌を特別割引価格で販売をいたします.
お申し込みは,専用申込用紙にて直接朝倉書店までお願いいたします.
(日本地質学会「日本地方地質誌」刊行委員会)
詳しくは、HP会員のページへ(ログイン情報が必要です)
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】平成21年度 東濃地科学センター 地層科学研究情報・意見交換会
──────────────────────────────────
■平成21年度 東濃地科学センター 地層科学研究情報・意見交換会
日時;10月27日(火)12:30〜17:00
場所;瑞浪市地域交流センター「ときわ」
※入場無料(事前の申込が必要です)
詳しくは、http://www.jaea.go.jp/04/tono/index.htm
■瑞浪超深地層研究所 深度300m水平坑道見学会
日時;10月28日(水)10:00〜12:00
場所;瑞浪超深地層研究所
※入場無料(事前の申込が必要です)
詳しくは、http://www.jaea.go.jp/04/tono/index.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】Conference of the Association of Korean Geoscience Societies,
Autumn-2009
──────────────────────────────────
日程:10月29日-30日
会場:韓国・済州島
講演要旨締切:9月15日(火)
1st Circularはこちらか(word)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】バングラデシュの環境問題を考えるシンポジウム
──────────────────────────────────
日時:平成21年9月3日(木)18:30-20:00
場所:北九州国際協力協会
主催:BEN(バングラデシュ環境ネットワーク) 日本分科会
参加費:無料 使用言語:英語/日本
詳しくは、こちらから(PDF)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】9月の博物館特別展示・イベント情報
──────────────────────────────────
すっかり秋らしくなってきました。博物館では、週末を中心に特別展示や体験イベ
ントを多数用意して、みなさまのお越しをお待ちしています。
特別展示では、今月で終了してしまうものも多くありますので、お見逃しのないよ
うイベントカレンダーをチェックください。
9月の特別展示・イベントカレンダーは↓↓↓
http://www.geosociety.jp/name/content0046.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報
──────────────────────────────────
■新潟大学教育研究院自然科学系教員公募(10/26締切)
■平成22年度学術研究船淡青丸・白鳳丸共同利用公募(9/18締切)
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.075 2009/09/03 geo-flash(臨時)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.075 2009/09/03 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 羽鳥謙三名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
羽鳥謙三名誉会員が平成21年9月2日(水)にご逝去されましたので、謹んでお知
らせいたします。これまでの故人の功績を讃えるとともに、謹んでご冥福をお祈
り申し上げます。
なお、通夜、ご葬儀は下記のとおり執り行われますので併せてお知らせ申し上げ
ます
記
喪主 羽鳥洋一 様
■通夜:9月5日(土)18時から
■告別式 6日(日)11時〜12時
場所:東福寺武蔵野斎場(JR西国分寺駅下車徒歩約5分)
(国分寺市西恋ヶ窪1−39−5 tel 042−321−1046)
会長 宮下 純夫
──────────────────────────────────
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.076 2009/09/08 geo-flash(臨時)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.076 2009/09/08 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次★★
【1】岡山大会:盛況のうちに終了しました
【2】韓国地質学会:日韓合同セッション 修正・追加情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】岡山大会:盛況のうちに終了しました
──────────────────────────────────
去る9/4-6(注:見学旅行は9/7-8実施)に岡山理科大学で開催された日本地質学
会第116年学術大会は、連日30度を超える厳しい残暑の中にも関わらず、800名近
い参加者があり、盛況のうちに幕を閉じました。詳しくは近日中に学会News誌やH
Pでご報告する予定です。お楽しみに。
また、見学旅行案内書(1部 2800円+送料)がわずかですか残部がありますので、
ご希望の方はお早めに学会事務局まで<main@geosociety.jp>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】韓国地質学会:日韓合同セッション 修正・追加情報
──────────────────────────────────
韓国地質学会済州島大会特別セッション1st. circularの追加・修正情報
今月1日のgeo-Flashでお送りした韓国地質学会(GSK)済州島大会1st.
circularについて,韓国側のDr. Nam氏から一部訂正の情報が入りましたの
で,取り急ぎお知らせします.
<主な修正点>
1. ホテル
日本人参加者の宿泊は,Seogwipo KAL Hotelに (情報の共有と歓迎パ
ーティー等のため).そこで,ホテルの情報を入れ替えた1st circular
を添付致しますので,宿についてはこちらに申込いただくよう,お願いし
ます.すでに申込をされた方は,大変恐れ入りますが変更いただければ幸
いです.
予約締切は9月30日.
2.巡検申込期日:9月15日(火)
要旨・巡検申込先 Prof. Chun (sschun55@hanmail.net, sschun@jnu.
ac.kr) にメール添付で(1st.circular 7ページに登録用紙があります).
参加予定の方は,恐れ入りますが遅くとも今週11日までに高木<hideo@
waseda.jp>までご一報いただければ幸いです.
日本からの参加人数の把握を急いでいます.
現在の為替レートで1,000ウォンは約80円ですので,日本円に換算して参
加登録料約8,000円(学生約4,000円),巡検参加費約2,400円(10月10日
までの早割料金)となります.韓国では通常部屋に料金がかかりますので,
1部屋で2名泊まると格安になります.
詳細は,
韓国側の問い合わせ先:Dr. Seung-Il Nam (sinam@kigam.re.kr +82-42-
868-3384, KIGAM)にお願いします.
2nd.(final) circular は9月末に参加申込者に送られます.
また,以下のようにK-IODP/J-DESC主催のKJODシンポジウム(日本側世話
人は琉球大学 松本剛氏:tak@sci.u-ryukyu.ac.jp)も同時開催されますの
で,それに参加される方で巡検を申し込まれる方は,B以外を選択してく
ださい.
済州島大会1st. circular 全文(MS Word)はこちらからダウンロード出来ます。
こちらから。
-------------------------------------------------------------------
10/28 Wed. Full day: *Field Excursion A provided by GSK
(プレ巡検)
10/29 Thu. Morning: IODP Session of GSK
(日本人向け英語セッション)
10/30 Fri. 09:00-12:00: KJOD Symposium organized by K-IODP/
J-DESC
13:00-18:00: KJOD Workshop for OT (Okinawa
Trough) drilling
Afternoon: *Field Excursion B provided by GSK
10/31 Sat. Full day: *Field Excursions C1, C2, C
3 provided by GSK
-------------------------------------------------------------------
すでにお知らせしました通り,この大会は2007年の日韓地質学会学術交流協
定締結をふまえて,お互いの学会に相互乗り入れできるようにしようという
2008年秋田大会での合意を受け,初めて試みられるものです.日本人が発表
できる英語のセッションは,IODPのセッションとして10月29日午前に開催さ
れます.発表内容は問いませんが,(環)日本海に関連するテーマは盛り上
がると思います.この「日韓(+)セッション」は,来年の富山大会に引き
継ぎげれば,と考えています.
また,これとは別に,構造地質部会では2010年夏に,高知で9年ぶりに日韓
合同大会を開催する予定です.
日韓交流小委員会 高木秀雄
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質マンガ 穿孔貝とは
地質マンガ
戻る|次へ
【解説】
穿孔貝(boring shell)は、岩石や材に穿孔するという習性をもつ貝のことで、 二枚貝が多いことから「穿孔性二枚貝」と呼ばれることもある。自ら岩石等の内 部に埋没するように穿孔し、その中で成長する。その結果、穴の開口部(入口) は貝殻よりも小さく、外部に出るようなことはない。そこをとらえて「墓穴を掘 る貝」と揶揄する人もいる。
現生のカモメガイ(神奈川県観音崎)シルト岩から取り出したもの
カモメガイの仲間の巣穴化石(埼玉県秩父盆地)
現生のフナクイムシと巣穴(千葉県野島崎灯台:漂着)
No.077 2009/09/15 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.077 2009/09/15 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】大河内会員 講談社科学出版賞 受賞
【2】会員名簿データを整理中です。住所変更はお早めに!
【3】岡山大会:関連情報
【4】学会オリジナルフィールドノート:新しくなりました。
【5】地質学雑誌:文献英文併記と図表・キャプションの英文化を
【6】日本地方地質誌「中国地方」割引販売のお知らせ
【7】北海道地質百選シンポジウム「北海道の地質魅力発見!」
【8】9月の博物館特別展示・イベント情報
【9】公募情報
【10】地質マンガ:「穿孔貝って」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】大河内会員 講談社科学出版賞 受賞
──────────────────────────────────
大河内 直彦会員著「チェンジング・ブルー 気候変動の謎に迫る」(岩波書店刊)
が第25回講談社科学出版賞を受賞しました.贈呈式・祝賀会は9月4日(金)
に行われました.
詳しくは
http://www.kodansha.co.jp/award/nonfiction-essay.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】会員名簿データを整理中です。住所変更はお早めに!
──────────────────────────────────
本年12月に会員名簿を発行予定です。
住所・所属など会員情報に変更のある方はできるだけ早めに、学会事務局<main@g
eosociety.jp>にご連絡いただくか、学会HP会員のページから会員情報の更新を
行って下さい。
会員ページへのログインはこちら、、、(ログイン情報が分からない場合は事務局
にご連絡ください)
https://www.geosociety.jp/user.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】岡山大会:関連情報
──────────────────────────────────
■岡山大会見学旅行案内書:残部僅少!
見学旅行案内書(9コース、152ページ、1部 2800円+送料)がわずかですか残部が
あります(講演要旨は売り切れました)。
ご希望の方はお早めに学会事務局まで<main@geosociety.jp >
■会場での忘れ物をお預かりしています
・カラビナ/・鍵
お心当たりの方は学会事務局まで<main@geosociety.jp >
詳しくは, , http://www.geosociety.jp/news/n54.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】学会オリジナルフィールドノート:新しくなりました。
──────────────────────────────────
皆様からご好評いただいております、学会オリジナルフィールドノートが新しく
なりました。
表紙がビニールコーティングになり、今までよりもさらに水や摩擦・衝撃にも強
くなりました。野外調査に最適です。本体の紙は従来と同じくレインガード紙を
使用しています。ぜひご活用ください。
サイズ:12×19cm(従来と同じです).
カバー:ハードカバー,ビニールコティング,金箔押し.
色:ラセットブラウン(小豆色)
会員頒価:500円
ご希望の方は学会事務局まで<main@geosociety.jp>
詳しくは、、、
http://www.geosociety.jp/publication/content0040.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質学雑誌:文献英文併記と図表・キャプションの英文化を
──────────────────────────────────
本年6月に従来の編集規約,投稿規定などの編集に関わる規則を一本化,内容も一
部改訂し,新しい編集規則を作成いたしました.
従来からの大きな変更点は,引用文献リストや図表およびキャプションの英文
化です.これは,インパクトファクターの附帯化,国際的な相互引用化をめざす
ためにも必要不可欠なものです.地質学雑誌の更なる充実・地位向上のため会員
の皆様のご協力をお願いいたします.
具体的には,2009年9月1日以降,新規に投稿される投稿原稿全てに新規則が適
用されます.また,また第115卷9号(2009年9月号)以降の掲載論文に関しても適
用となりますので,既にご投稿中の著者にも随時修正をお願いする次第です.
新しい編集規則は,学会ホームページまたは地質学雑誌巻末をご参照ください.
http://www.geosociety.jp/publication/content0038.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】日本地方地質誌「中国地方」割引販売のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地質学会編集 日本地方地質誌
第4回配本 6.中国地方 560頁,口絵8頁(9月上旬刊行)
定価26,250円(税込)を会員特別割引価格22,500円(税・送料込)
日本地質学会会員の皆様に,日本地方地質誌を特別割引価格で販売をいたします.
お申し込みは,専用申込用紙にて直接朝倉書店までお願いいたします.
(日本地質学会「日本地方地質誌」刊行委員会)
詳しくは、HP会員のページへ(ログイン情報が必要です)
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】北海道地質百選シンポジウム「北海道の地質魅力発見!」
──────────────────────────────────
日時:2009年10月17日(土)13:00-17:00(13:00開場)
会場:かでる2・7(札幌市中央区北2条西7丁目)・入場無料
日本地質学会北海道支部では,北海道地質百選候補の募集と公開を行っています
(http://www.geosites-hokkaido.org/).
このシンポジウムでは,さまざまな分野の専門家や立場から,おすすめの,隠れ
た,重要な,知られざるジオサイトの紹介とその保護・活用について語っていた
だき,北海道地質百選を充実・発展させたいと思います.奮ってご参加ください.
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】9月の博物館特別展示・イベント情報
──────────────────────────────────
すっかり秋らしくなってきました。博物館では、週末を中心に特別展示や体験イベ
ントを多数用意して、みなさまのお越しをお待ちしています。
特別展示では、今月で終了してしまうものも多くありますので、お見逃しのないよ
うイベントカレンダーをチェックください。
★★新着★★
新潟大学旭町学術資料展示館企画展(9/1-11/29)
「糸魚川ジオパーク展 −ヒスイ,化石,断層,見どころいっぱい−」
9月の特別展示・イベントカレンダーは↓↓↓
http://www.geosociety.jp/name/content0046.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募・助成情報
──────────────────────────────────
■広島大学大学院理学研究科地球惑星システム学専攻教員公募(11/6締切)
■日本原子力研究開発機構平成22年度「先行基礎工学研究」募集(11/16締切)
■日本学術会議:平成21年度日本・カナダ女性研究者交流事業派遣者募集(9/30締切)
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】地質マンガ 「穿孔貝って」
──────────────────────────────────
「穿孔貝って」 作:chiyodite 画:key
詳しくは
http://www.geosociety.jp/faq/content0183.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.078 2009/09/25 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.078 2009/09/25 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次★★
【1】地学オリンピック 日本チーム銀メダル4個という快挙で無事終了
【2】会員名簿データを整理中です。住所変更はお早めに!
【3】公募情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】地学オリンピック 日本チーム銀メダル4個という快挙で無事終了
──────────────────────────────────
2009年9月14日から9月22日まで台湾において第3回国際地学オリンピックが開催
されました.参加国14カ国50名+3カ国のオブザーバーの参加で、台北周辺で
メダル対象の筆記試験と実技試験が行われ、国際混合チームによる野外調査コン
テストが台中の地震断層で行われました。日本チームも世界の代表らと叡智を競
い,銀メダル4個という輝かしい成果を挙げました.
銀メダル 冨永 紘平 さん (埼玉県立川越高等学校3年)
銀メダル 長野 玄 さん (私立灘高等学校2年)
銀メダル 槇野 祐大 さん (私立灘高等学校2年)
銀メダル 宮崎 慶統 さん (私立聖光学院高等学校3年)
また正式種目ではありませんが,参加生徒による人気ナンバーワンに日本からの
参加生徒が選ばれるなど,日本チームは、各国選手の間に溶け込んでいたとのこ
とです。なお日本チームの団長は、上田誠也東大名誉教授が務めました。
日本地学オリンピック委員会ウェブサイト<http://jeso.jp/>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】会員名簿データを整理中です。住所変更はお早めに!
──────────────────────────────────
本年12月に会員名簿を発行予定です。住所・所属など会員情報に変更のある方は
できるだけ早めに、学会事務局<main@geosociety.jp>にご連絡いただくか、
学会HP会員のページから会員情報の更新を行って下さい。
会員ページへのログインはこちら↓↓↓↓
https://www.geosociety.jp/user.php
(ログイン情報が分からない場合は事務局にご連絡ください)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】公募情報
──────────────────────────────────
■麻布中学校・高等学校専任教員募集(10/14締切)
■筑波大学生命環境科学研究科・地球進化科学専攻教授募集(10/30締切)
■東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻准教授募集(11/19締切)
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質マンガ 津波は大丈夫かね
地質マンガ
戻る|次へ
【解説】
マンガのように地表が3mも隆起するようなら,海底の変動はもっと大きいかもしれません.しかも深海で起きた津波は,沿岸に近づくと一段と大きくなるので,隆起したからといって安心するのは間違っているでしょう...
さて,マンガにあるような海底活断層による地震と津波と地盤の隆起の典型例を関東地震にみることができます.1923年(大正12年)9月1日正午に関東近辺を襲ったM7.9の関東地震の震源域は、神奈川県西部の小田原周辺直下と考えられています。そこから破壊を開始し、北側は現在の川崎市の地下35km、南は千葉県館山市の地下5km、東は房総半島先端の野島崎付近に延びる実に長さ130km、幅70kmにもおよぶ断層が動き、大きい所で5m、平均でも2.1mのずれを生じました。地震の数分後には、太平洋沿岸〜伊豆諸島にかけて津波が襲いました(熱海で12m、房総半島で9mを記録)。この地震で生じた海岸段丘崖が、千葉県館山近くの見物海岸で見ることできます。海面から1.5mと4.5mの高さに平らな面が残っています。低い方は、大正関東地震時に急激に隆起して陸上に顔を出し、波の浸食で洗われて平らな面となり、高い方はそれより220年前の1703年の元禄地震で生じた隆起痕です。
写真1. 宍倉ら2003より、千葉県館山市見物海岸の2つの関東地震の隆起痕。
写真2:関東大地震時の地震断層が地表に表れている千葉県館山市延命寺。赤矢印部は右横ずれ断層によりずれを生じている。
写真3:関東大地震時の地震断層が地表に表れている千葉県岩井駅前。赤矢印部では、2m程度の鉛直方向のずれを生じている。
房総半島の館山湾から3-4km内陸に入った延命寺では、境内の小道が断層の影響でずれて、大きな断層面が地面に顔を出した所です(写真2)。よくアニメで地震時に地面の割れ目が出来て、人が落っこちて両手を挙げて助けを求める描写がありますが、ここでは、本当に割れ目に子供が落ちて亡くなったそうです。地震に伴う全ての自然現象、決して侮ってはいけません。この4コマ漫画のように揺れが治まれば無事、ということは決してありません。運が悪ければ、瞬時に亀裂にはまり、海岸周辺では大波に押し流され、飲み込まれてしまいますよ。
関東周辺は3000万人という人口密集地であり、政治経済の中心地ですが、200-400年という間隔で巨大な地震に見舞われています。過去の記録を読み解くと同時に、地下の断層が動いた時の被害を想定し、地盤に合った都市開発計画に反映させることが急務ですが、地震波伝搬モデルの構築には、地下の速度や密度構造を知らねばなりません。しかし、関東平野の地下構造はたいへん複雑です。海側プレートが陸側プレートの下に沈み込む、といった単純なモデルでは、諸現象を説明できません。関東の下に相模湾から北西方向へ沈み込むフィリピン海プレートは、10km程の深さに存在し、くさび型を呈しています。そのフィリピン海プレートの下に東から沈み込む太平洋プレートは、さらに数km下をくの字型に屈曲した状態で沈み込んでおり、さらにもう一枚別のプレートも存在する、というように、にわかにはイメージしづらい入り組んだ立体構造になっていることを微小地震による解析結果が示しています。このように関東平野直下には大地震の巣が根付いていて、地震の発生層が厚いのです。大きな揺れが来た際にどのように揺れるのか、強震動予測や建築物の耐震性などを吟味するために、関東近辺に観測網を張り巡らし、モニターをしようという計画があります。国際統合深海掘削計画(IODP)に提案された実験計画の概要は、相模湾と房総沖の海底数カ所に、1000〜6000m長の孔を掘りながら物理計測を行い、得られる柱状試料は、地質学、生物学、土質実験等に用い、掘削孔には長期地震計、傾斜計等、地殻変動を探る機器を設置し、陸上の観測網(関東近辺の小学校300カ所に設置中)と併せて、関東周辺の強震動予測を行おうとする試みです。関東地震の際に大きく揺れた領域(アスペリティといいます)を掘抜こうという計画なので、「関東アスペリティ掘削計画(Kanto Asperity Project、略してKAP)」と呼んでいます。
写真4:千倉の海底乱泥流痕にて、画面右は山本由弦氏(IFREE,JAMSTEC)、山本ほか2007より
実は、房総半島南部の千倉には、有史以前300万年もの昔に遡りますが、とんでもない大地震の痕が残っているのが発見されました(写真4、山本ら2007より)。ここでは、数m分の地層のブロックが破断され、横に斜めにひっくり返されて再堆積している様子が見えます。道路建設の際にここの地層が露になり、偶然にも巡検時の地質学者に発見され、その後、貴重な記録として一部が保存されることになりました。ここまでカタストロフィックな大地の変動があったら、掘削試料が得られても何が何だかパズル合わせもできないかもしれません。変動帯にある狭い国土の日本列島には途方もない大地の変動の記録が残されているものですね。
(木戸ゆかり(独)海洋研究開発機構/地球深部探査センター/IODP推進・科学支援室)
No.083 2009/11/17 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.081 2009/11/17 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】惑星地球フォトコンテスト:作品募集中
【2】2010年度会費払込:学部生・院生割引会費申請を忘れずに!!
【3】日本地質学会2010年度各賞候補者募集中
【4】「地質の日」関連イベントの最終集計が出ました!!
【5】コラム IGCP-511 海底地すべり会議に参加して
【6】その他 お知らせ
【7】地質マンガ 鬼の洗濯板
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】惑星地球フォトコンテスト:作品募集中
──────────────────────────────────
IYPE(国際惑星地球年)と地質学会の主催で惑星地球フォトコンテストを開
催します.惑星地球に関する芸術的もしくは学術教育的写真を募集中です.
上位入賞作品は,3月のIYPE記念イベントにて展示表彰いたします.会員の
皆様には奮ってご応募下さいますようお願いいたします.(11/30締切)
詳しくは、http://photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2010年度会費払込:学部生・院生割引会費申請を忘れずに!!
──────────────────────────────────
来年度(2010年度)からは学部学生・院生(研究者)については,本人の申請
によりそれぞれ割引会費が適用されます.次年度(2010年度)の会費についてた
だ今申請受付中です.毎年更新となりますので,次年度会費について該当する方
は,申請書を提出してください(郵送に限る).
書式等詳しくは,ニュース誌10月号または学会ホームページをご覧下さい.
お振込の方へは、12月中旬までに請求書兼振り替え用紙をご送付致します。
会費口座引落:12月24日(予定)
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/outline/content0052.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本地質学会2010年度各賞候補者募集中
──────────────────────────────────
応募締切:2009年12月25日(金)必着
詳しくはも、会員のページをご参照下さい(ログインID・パスワードが必要です).
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】「地質の日」関連イベントの最終集計が出ました!!
──────────────────────────────────
事業推進委員会の集計によると、本年度(第2年次)は、全国60の機関及び団体
が総計98のイベントを開催しました。その結果、参加者総数は 260,433人 に達し
ました。昨年度は、40機関及び団体が74のイベントを開催し、参加者総数は72,34
5人でした。これにくらべると、本年度は4倍に近い数の参加者を得たことになり
ます。
来年の5月に向けても,各支部,機関、団体で、さらに大きな輪となるよう参加
者を広げて行きましょう。
(地質の日事業推進委員会)
詳しくは、http://www.gsj.jp/geologyday/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】コラム IGCP-511 海底地すべり会議に参加して
──────────────────────────────────
川村喜一郎(財団法人深田地質研究所)
11月7から12日にテキサス大学オースチンで,IGCP-511(IUGS-UNESCO's Internat
ional Geoscience Programme 511:IGCPは国際地質学会とユネスコの共同国際プ
ログラムにあたる)の第4回国際会議に参加した.
続きは、http://www.geosociety.jp/faq/content0193.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他お知らせ
──────────────────────────────────
■北淡国際活断層シンポジウム2010
会期 2010年1月17日--21日
会場 兵庫県淡路市・北淡震災記念公園セミナーハウス
研究発表受付締切:12月27日締切
参加登録と宿泊等予約締切:12月17日締切
http://home.hiroshima-u.ac.jp/kojiok/hokudan2010.html
■第46回の霞ヶ関環境講座/第37回三宅賞受賞者の受賞記念講演
日時:2009年12月5日 (土)14:30〜
場所:霞ヶ関ビル35階 東海大学校友会館
http://wwwsoc.nii.ac.jp/gra/
■平成21年度国土技術政策総合研究所講演会
日時:12月2日(水)10:00-16:50
場所:日本教育会館一ツ橋ホール
http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/kouenkai/kouenkai2009/kouenkai2009.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】地質マンガ 鬼の洗濯板 作:本郷宙軌 画:Key
──────────────────────────────────
詳しくは
http://www.geosociety.jp/faq/content0191.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
活動報告,書評,ニュース表紙写真,マンガ原作,随時募集中!
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
日本全国天然記念物めぐり(福岡県編)
◇各地の天然記念物◇
TOP 秋田県編 滋賀県編 京都府編 和歌山県編 福岡県編
日本全国天然記念物めぐり(福岡県編その1)
今回は乾睦子(国士舘大学)が,福岡県の平尾台をルポします.
福岡県の天然記念物(地質鉱物)は下記のように7件ありますが,石灰岩台地としての(4)平尾台の他に,個別に指定されている(2)と(5)の鍾乳洞も平尾台の中にあります.(その他の4か所を取材する計画は立っていません.どなたかお願いします,の意味を込めて本稿は「その1」).
(1) 長垂の含紅雲母ペグマタイト岩脈(1934年指定)福岡市西区長垂
(2) 千仏鍾乳洞(1935年指定)北九州市小倉南区大字新道寺
(3) 鷹巣山(1941年指定)福岡県田川郡添田町・大分県下毛郡山国町
(4) 平尾台(1952年指定)北九州市小倉南区大字新道寺
(5) 青龍窟(1962年指定)京都郡苅田町
(6) 芥屋の大門(1966年指定)糸島郡志摩町
(7) 水縄断層(1997年指定)久留米市山川町
はじめに,このシリーズの主な目的であるところの「天然記念物の現状把握」という点について視察した結果です.ペルム紀の付加体中にある礁性石灰岩台地,平尾台は,日本有数の石灰岩台地のひとつです.白亜紀の火成作用を受けたため,ほぼ全体が大理石だそうです.この平尾台,私が短期間で見聞きした限り.地域における知名度は十分高く,道案内もきちんとされていましたし,子供の頃に遠足で行ったという声も聞かれるなど,地域での存在感を保っていました.観光洞になっている「千仏鍾乳洞」では,入り口付近や入場券に天然記念物である旨がきちんと記載されていました.
写真1.カルスト台地に散らばる羊達(石灰岩の).
写真2.「千仏鍾乳洞」の入場券表.天然記念物との記載.
写真3.同裏.入り口から1km程度に照明が設置されている.
写真4.「千仏鍾乳洞」内.後半は川なので,足を取られないよう意外と真剣に歩かねばならなくなる.
写真5.大理石の青い岩肌.建築石材として用いられたこともある.
現在では「福岡県平尾台自然観察センター」(2000年オープン)や「北九州市平尾台自然の郷」(2003年オープン)などのビジター施設も備わっています.今回は「平尾台自然の郷」に行ってきましたが,カルスト地形の簡単な解説などがある他,もうひとつの天然記念物である「青龍窟」(通常は入れない)も予約すればケービングさせていただけるとのことでした.様々なイベントが開催(最近では日食も見えたよう)されている他,ウェブサイトも完備.観察対象の保存だけでなく積極的に情報発信も行われています.天然記念物が地域の貴重な自然資産として申し分なく活用されているように見えます.
写真6.平尾台自然の郷 入り口ゲート.
写真7.平尾台の大理石が展示されている.
写真8.ドリーネを見下ろす展望台も.
以上が現状です.ところが,担当者にお話をうかがったところ,平尾台がかなり泥臭い歴史を背負っていることを教わりました.そもそも平尾台が天然記念物に指定された経緯からして,地域社会の大紛争の中で行われたことだというのです.
紛争というと,現在であれば「保護vs観光」といった図式がすぐに思い浮かびます(実際,今現在の平尾台の問題としてそれはあるようです)が,戦後すぐからの平尾台を巡る対立はもっと切実で複雑,農業vs鉱業(石灰石採掘)vs観光の三つ巴の土地争いだったようです.「天然記念物に指定する」ということも「観光(=カルスト台地の景観保護)」側であった小倉市が打った手の一つです.指定後に,さらに鉱区指定を巡ってかなり緊迫した応酬があったとのこと.
詳しい経緯はこちらにまとめられています(お話をうかがった「平尾台自然の郷」の久下さんのブログ.「平尾台の歴史」というカテゴリーでまとめて見ることができます).
最終的には,平尾台の半分が保護地域,半分が産業的採掘が可能な地域とされ,「観光」と「産業」が共存する形になりました.そして近年,逆に「産業」側が積極的に提案する形で緩衝地帯に「自然の郷」がつくられたそうです.今は,平尾台の自然をどうしたら活用できるかを「産業」と「観光」が協力して模索している段階と言っていいのかもしれません.
写真9.企画のひとつ,採掘後の洞窟で熟成した限定醸造の焼酎.オーナーになれます!
岩石は地下資源.岩石と人との関わりも,生活と無関係ではいられないことを考えさせてくれました.
No.079 2009/10/06 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.079 2009/10/06 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2010年度代議員および役員選挙について
【2】2010年度各賞候補者募集開始
【3】一般社団法人日本地質学会の公益法人認定申請について
【4】地球惑星科学連合の代議員選挙のお知らせ-連合に参加しよう-
【5】会員名簿データを整理中です。住所変更はお早めに!
【6】天然記念物めぐり:福岡県編
【7】日本堆積学会からのご案内
【8】第2回日本地学オリンピック大会参加募集
【9】10月の博物館 特別展示・イベント情報
【10】公募情報
【11】地質マンガ:「津波は大丈夫かね」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2010年度代議員および役員選挙について
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会定款ならびに選挙規則・選挙細則に基づいて,法人と
して初めての代議員および役員(監事,理事)選挙を実施いたします.
詳しくは,News誌9月号または学会HP会員のページ(ログインID・パスワードが必
要です)をご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
■代議員選挙
立候補締切日:11月12日(木)
投票期間:11月30日(月)〜1月9日(土)
■理事・監事選挙
立候補締切:2月12日(金)
投票期間:2月22日(月)〜3月8日(月)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2010年度各賞候補者募集開始
──────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして,研究の援助・奨励および研究業績
の表彰を行っています.応募要項をご参照の上,各賞選考委員会(学会事務局)
あてご応募下さい.期日厳守にて,たくさんのご応募をお待ちしております.
応募締切:12月25日(金)必着
詳しくは,News誌9月号または学会HP会員のページ(ログインID・パスワードが必
要です)をご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】一般社団法人日本地質学会の公益法人認定申請について
──────────────────────────────────
昨年12月に一般社団法人日本地質学会が設立され,今年度は法人への移行期間と
して,一般社団法人と従来の任意団体の二つの地質学会が並存しています.法人
化作業委員会では,任意団体日本地質学会の事業・会員・財産などについて,一
般社団法人日本地質学会が公益認定されてから一気に法人側に移すという方針で
公益認定の準備作業を進めて参りました.しかしながら本年4月の任意団体評議
員会や法人理事会,5月の法人総会で審議していただいたように,公益認定につ
いて不明な点が多いこと,二つの団体の並存期間が長引くことは運営上の面から
も好ましくないとの判断から,理事会としてはできるだけ早期に任意団体事業活
動の主体を法人側に移すこととし,今年度末には任意団体日本地質学会を解散し,
全ての事業・会員・財産を一般社団法人日本地質学会に移す方向で準備を進めて
いるところです.....
続きは,News誌9月号または学会HP会員のページ(ログインID・パスワードが必
要です)をご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地球惑星科学連合の代議員選挙投票のお願い-連合に参加しよう-
──────────────────────────────────
10月1日より,昨年12月に日本地球惑星科学連合が一般社団法人化されて最初の代
議員選挙の投票が開始されています.日本地球惑星科学連合の個人会員(正会員)
より選ばれた代議員(社員)の方々はセクションプレジデントならびに理事の被
選挙者となるとともに,団体(学協会)会員とともに,定時・臨時社員総会にお
いて,役員の選出,事業計画の承認,その他の連合の運営に関わる諸事項につい
ての決議を行なうこととなります.
代議員を選出する選挙の投票は,ホームページ上で行なわれますが,代議員選挙の
投票締切日(10月30日)までに会員登録をされた個人会員(正会員)の方は,ご
自分が登録した登録区分の候補者のなかから,5名(あるいはそれより少ない人数)
を選んで,投票することができます.
連合の会員登録されている地質学会員の皆様はもちろんですが,まだ登録されて
いない方はぜひともこの機会に会員登録をしていただき,地質学会員の候補者に
ご支援いただきますよう,よろしくお願い致します.ちなみに連合の年会費は2,0
00円で,連合大会の参加登録料が会員は非会員に比べ7,000円安くなるほか,ニュー
スレター(JGL)も受け取ることができます.
連合の代議員選挙に立候補している登録区分別地質学会員は以下の通りです.ご
支援をよろしくお願いします.立候補者全員の名簿は下記URLをご覧ください.
・宇宙惑星(1):永原裕子
・大気海洋・環境(2):公文富士夫,多田隆治
・地球人間圏(5):奥村晃史,坂本正徳,鈴木毅彦,福冨幹男,渡部芳夫
・固体地球(28):石渡 明,磯崎行雄,板谷徹丸,伊藤谷生,岩森 光,ウオ
リスサイモン,小山内康人,木村 学,木村純一,斎藤 眞,酒井治孝,佐藤比
呂志,高木哲一,高木秀雄,竹下 徹,巽 好幸,田村芳彦,趙 大鵬,佃 栄吉,
富樫茂子,中田節也,西山忠男,久田健一郎,藤井敏嗣,藤本光一郎,丸山茂徳,
山崎俊嗣,吉田武義
・ 地球生命(6):井龍康文,大河内直彦,川端穂高,北里 洋,北村晃寿,西
弘嗣
・地球惑星総合(4):加藤泰浩・芝川明義・中井睦美・山本高司
[選挙日程] 2009年
9月17日(木)代議員選挙,立候補受付締切
10月1日(木)代議員選挙,投票開始
10月30日(金)代議員選挙,投票締切
11月6日(金)代議員選挙,開票,結果報告
[投票]
個人会員ログインページよりログイン後,「代議員選挙投票」をクリックして行っ
てください https://secure.jtbcom.co.jp/jpgu/
[新規会員登録]
投票締切日(10月30日)までに正会員登録されると代議員選挙に投票できます
http://www.jpgu.org/touroku/entry_new.html
[代議員候補者名簿]
http://www.jpgu.org/whatsnew/090924_daigiinlist.pdf
一般社団法人日本地質学会執行理事会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】会員名簿データを整理中です。住所変更はお早めに!
──────────────────────────────────
本年12月に会員名簿を発行予定です。
住所・所属など会員情報に変更のある方はできるだけ早めに、学会事務局 main@g
eosociety.jp>にご連絡いただくか、学会HP会員のページから会員情報の更新を
行って下さい。
会員ページへのログインはこちら、、、(ログイン情報が分からない場合は事務局
にご連絡ください)
https://www.geosociety.jp/user.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】天然記念物めぐり:福岡県編
──────────────────────────────────
今回は乾睦子(国士舘大学)が,福岡県の平尾台をルポします.
福岡県の天然記念物(地質鉱物)は下記のように7件ありますが,石灰岩台地とし
ての(4)平尾台の他に,個別に指定されている(2)と(5)の鍾乳洞も平尾台の中にあ
ります.(その他の4か所を取材する計画は立っていません.どなたかお願いしま
す,の意味を込めて本稿は「その1」).
続きは、、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0187.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】日本堆積学会からのご案内
──────────────────────────────────
国際堆積学会/国際地球化学会・前会長Dr.ジュディス・マッケンジ講演旅行
国際堆積学会前会長(ISC2006 FUKUOKA開催時)のJudith McKenzie博士が来日さ
れるのを機に,東京,名古屋,広島,福岡の4会場においてセミナーを開催しま
す.McKenzie博士のMicrobial Carbonates(微生物源炭酸塩)に関する講演の他,
国内の研究者の講演もプログラムされております. 各セミナーとも一般公開で,
参加無料です.お近くの会場へ足をお運び下さい.
■東京大学地球惑星科学セミナー「炭酸塩堆積学と地球化学の最前線」
11月10日(火)13:00〜17:00
場所 理学部1号館小柴ホール
■海洋研究開発機構「生命圏領域セミナー」
11月12日(木)14:00〜17:00
場所 海洋研究開発機構
■第3回広島大学・海洋研究開発機構合同シンポジウム
「海底下の環境と地下生命圏研究の最前線-地下生命と堆積環境の相互作用-」
11月16日(月)13:00〜17:00
場所 広島大学中央図書館ライブラリーホール
■「新たな生命地球科学の構築ー炭酸塩からのアプローチ」
11月19日(木)13:00〜17:00
場所 九大箱崎キャンパス国際ホール
詳しくは,
http://sediment.jp/01member/nos0284.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】第2回日本地学オリンピック大会参加募集
──────────────────────────────────
兼 2010年第4回国際地学オリンピック・インドネシア大会日本代表選抜
募集締切 2009年11月30日(月)
予選の概要ならびに募集要項は、http://jeso.jp/
問い合わせ先:
特定非営利活動法人地学オリンピック日本委員会
TEL 03-3815-5256
E-Mail esolympiad@yahoo.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】10月の博物館 特別展示・イベント情報
──────────────────────────────────
全国の博物館で開催されている特別展示と、開催予定のイベントのご紹介です。
今月は、2館で特別展示がはじまります。また、イベントも野外観察会を中心に、秋
を満喫できる充実したイベントが盛りだくさんです。
中には、事前に申し込みが必要なものもありますので、詳細は下の特別展示・イ
ベントカレンダーでチェックしてください。
10月の博物館 特別展示・イベント情報カレンダー ↓↓↓
http://www.geosociety.jp/name/content0047.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報
──────────────────────────────────
■島根大学総合理工学部地球資源環境学科教員募集(11/20締切)
■平成22年度「とやま賞」候補者推薦募集(11/10学会締切)
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】地質マンガ 「津波は大丈夫かね」
──────────────────────────────────
「津波は大丈夫かね」 作:川村喜一郎 画:key
詳しくは
http://www.geosociety.jp/faq/content0186.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.080 2009/10/20 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.080 2009/10/20 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】第四紀の下限が変わる!
【2】国際交流:モンゴルへの交流協定締結
【3】2010年連合大会:旧レギュラーセッション提案お願い
【4】2010年度会費請求・学部生/院生割引申請受付開始!
【5】名簿作成アンケート実施中:会員情報変更締切 11/6(金)
【6】来年は富山大会です:日本地質学会第117年学術大会
【7】その他お知らせ
【8】公募情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】第四紀の下限が変わる!
──────────────────────────────────
この度,国際地質科学連合(IUGS)の理事会は,2009年6月29日に,第四紀・系の
下限を2.588 Maとする国際層序委員会(ICS)の提案を批准いたしました.今回,
この変更に関する日本地質学会の対応方針の検討が、理事会より地層名委員会に
諮問されております.従来の地層名委員会の委員に,専門部会長,研究委員会委
員長,理事等を加えた拡大地層名委員会を立ち上げて検討を開始しました.今後,
学術会議や関連学協会と連携をとりながら日本としての対応を検討していきます.
問題の背景を理解していただくために,今回このような変更がなされた経緯に関
して簡単に紹介します.
1948年のロンドンでの万国地質学会(IGC)において,第四系の基底は,海生動物
群の変化に基づいて決定するとされました.その後の検討により,第四系の基底
の模式地(GSSP;Global Strato-type Section and Point)として,イタリア地
中海沿岸ヴリカのカラブリア層が選ばれ、同系の基底としてオルドバイ正磁極期
上限付近のsapropel層であるe層の上面が指定され,1985年に国際地質科学連合(
IUGS)で批准されました.しかしその後,古気候や古海洋環境の変遷に関する研
究が進展するにつれ,第四紀更新世の始まりは,深海底コアの底生有孔虫化石の
酸素同位体比が現在の値より大きくなる時期,北半球高緯度においてIce Rafted
Debirsが産出し始める時期(いずれも北半球氷床の形成を示す),中国レスの堆
積開始時期等と一致させるべきとの見解が出され,長らく議論が続けられてきま
した.
今回批准された提案は,この見解に従ったもので,カラブリア期(Calabrian)の
前のジェラ期(Gelasian)が第四紀更新世に含められることになりました.新た
な第四系の基底(鮮新統・更新統境界),すなわちジェラ階の基底は,シシリー
島のモン・サン・ニコラの南斜面にあり,古地磁気層序における松山/ガウス境
界の約1m上位に位置します.その年代は2.588Maであり,これは酸素同位体ステー
ジ(Marine Isotope Stage)のMIS103の基底に相当します.この時期は,地球史
のうえでは,パナマ地峡が2.7Ma頃に閉塞したために,現在の湾流(Gulf Stream)
に相当する海流が成立し,北半球高緯度域に多量の水分がもたらされ氷床が形成
されはじめた時期にあたります.これは,深海底コアの底生有孔虫化石の酸素同
位体比の変化からも支持されます(第1図).
第1図.過去500万年間の深海底底生有孔虫化石の酸素同位体比変動曲線(Lisiecki, and Raymo, M.E. [2005, Paleoceanography, 20, PA1003, doi:10.1029/2004PA001071]をもとに井龍が作成).2.60M頃を境に,現在の値よりも大きな値を示すようになり,4.1万年周期のミランコビッチサイクルが顕著になっています.
2009年10月1日
日本地質学会拡大地層名委員会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】国際交流:モンゴルへの交流協定締結
──────────────────────────────────
日本地質学会とモンゴル地質学会の交流協定の調印式が、10月14日モンゴル地質
学会のモンゴル地質調査70周年記念学術大会の際に行われました。
モンゴル地質学会からの招待を受け、地質学会からは、宮下会長と石渡理事(国
際交流担当)及び地質学会日・モンゴル小委員会の高橋裕平会員・坂巻幸雄会員
にご出席頂きました.
調印式のほかモンゴル訪問の様子を石渡理事よりご報告頂きましたのでお伝えし
ます。
詳しい報告は、こちら、、、
http://www.geosociety.jp/science/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2010年連合大会:旧レギュラーセッション提案お願い
──────────────────────────────────
2010年大会では、現在、10月30日(月)17時締切として、セッション提案を募集
中です。
旧レギュラーセッションの「提案」お願い
●セッション構成上、昨年度までのレギュラーセッション・スペシャルセッショ
ンの区別がなくなったため、旧レギュラーセッションもふくめて、すべてのセッ
ションは通常の「セッション」としての「提案」が必要です。
(これまで昨年度コンビーナーやプログラム委員に対し行ってきたレギュラーセッ
ション継続について、連合側からの確認・問い合わせは今年はありません。)
●Webからのセッション提案時に、過去のレギュラーセッション実績についての入
力項目がありますので、ご入力ください。
セッション採択・編成作業ではこれまでのレギュラーセッションとしての開催
実績を十分考慮していきたいと思います。
●事務局からも、過去のコンビーナへ別途よびかけをしていきますが、どうか、
ご所属の学会から提案のセッションなど、お心当たりの旧レギュラーセッション
について、セッション提案の促すご連絡を急ぎお願いもうしあげます。
●学協会の共催・後援など、未確定の情報がある場合も、後日採択されたセッショ
ンについてWebで再入力いただく機会があります(11月中〜下旬を予定)ので、現
段階で確定していない状態でセッション提案いただいた場合も、それまでに確定
くだされば結構です。(トラブルを避けるため、少なくても提案時には、先方に申
し入れはしておいていただくようお願いします。)
セッションは以下のWebサイトからお申し込みいただけます。
<http://www.jpgu.org/meeting/regist01_session.html>
●旧スペシャルセッション、新規セッション提案
また同様に、過去のスペシャルセッションなど、「レギュラーでない」トピッ
クスや全く新しいテーマなどの セッションについても、もちろん多くのご提案
をお待ちしております。
●連合大会を通じた国際的な交流、国際的な活動を促進するため、国際セッショ
ン(すべての講演を英語で行う)の募集も あわせて推進中です。よろしくお願
いいたします。
セッション構成・システムなどの変更のため、混乱されることもあるかと思いま
す。こちらの説明が十分でない部分についてはお詫び申し上げます。
セッション提案についてご不明の点がありましたら、ぜひ、下記の事務局までご
相談いただけるよう、ご助言いただければ幸いです。
村山泰啓:2010年大会プログラム委員長
一般社団法人 日本地球惑星科学連合事務局
〒113-0032 東京都文京区弥生2-4-16
学会センタービル4階
Tel: 03-6914-2080 Fax: 03-6914-2088
Email: office@jpgu.org
URL: http://www.jpgu.org/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2010年度会費請求・学部学生も割引申請書の提出が必要になります!
──────────────────────────────────
去る5月の総会において日本地質学会は,来年度(2010年4月)から任意団体日本地
質学会を解散し,事業の全てを一般社団法人日本地質学会へ移行することを決め
ました.会員も2010年度からは法人の会員ということになります.
つきましては,本年末に徴収のご案内をいたします会費は,一般社団法人日本地
質学会2010年度会費ということになります.また,2009年度およびそれ以前に会
費の未納がある場合には,全財産を引き継ぐ法人の会費として督促請求をいたし
ますので,なにとぞご了承ください.
院生および学部学生にはこれまでと同金額の割引会費があります.学部学生も所
定の書式で申請していただいた方に限り,学部学生割引が適用されることになり
ます.
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0052.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】名簿作成アンケート実施中:会員情報変更締切 11/6(金)
──────────────────────────────────
日本地質学会では,学会員相互の交流と親睦を図る目的で,2年ごとに会員名簿
を発行することを会則にうたっております.2009年はその発行年にあたり,本年1
2月末日発行の予定で準備を行っております.
会員情報の変更、また会員名簿(冊子)への掲載についての確認を会員ページか
らにログインしてご自身の情報を確認・訂正・変更してください.
Web画面更新締切日:2009年11月6日(金)
詳しくは、(ログインID・パスワードが必要です)
http://www.geosociety.jp/members/content0044.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】来年は富山大会です:日本地質学会第117年学術大会
──────────────────────────────────
来年、日本地質学会第117年学術大会は、富山で開催されます。シポジウムの募集
など今後順次広報して行く予定です。多くの会員の皆様のお越しをお待ちしてい
ます。
■日本地質学会第117年学術大会
日程:2009年9月18日(土)〜20日(月・祝)
メイン会場:富山大学(富山市五福)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他お知らせ
──────────────────────────────────
■2010年度各賞候補者募集中
応募締切:2009年12月25日(金)必着
■2010年度代議員および役員選挙 立候補受付中
代議員立候補受付締切:11月12日(木)(必着)
投票期間:11月30日(月)〜1月9日(土)
いずれも、会員のページをご参照下さい(ログインID・パスワードが必要です).
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報
──────────────────────────────────
■北見工業大学工学部社会環境工学科教員公募(12/22締切)
■平成22年度環境研究・技術開発推進費及び地球環境研究総合推進費の新規課題
公募(11/10締切)
■日台科学技術交流の各種事業応募者募集(12/25締切)
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.084 2009/11/20 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.084 2009/11/20 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】行政刷新会議のこれまでの事業仕分けについての意見書
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】行政刷新会議のこれまでの事業仕分けについての意見書
──────────────────────────────────
会員 各位
理事会は、現在、内閣府行政刷新会議によって行われているいわゆる事業仕分け
に関し、刷新会議議長ならびに文部科学大臣に対し、添付のような意見書を先ほ
ど提出しました。
11月18日に出された2事業、科学界全体が関わる若手研究者育成事業や本学会が深
く関連する地球科学分野の事業の仕分け結果に関しては、危機感を強く持ちまし
た。
意見書の内容はこちらから
http://www.geosociety.jp/engineer/content0008.html
会員各位におかれましても、ぜひ個人的な立場で結構ですので、文科省あてに意
見表明をしていただきますよう、お願いいたします。
宛先:<nak-got@mext.go.jp>
担当 文部科学省副大臣 中川正春・政務官 後藤斎
注:12月15日まで。様式自由、必ず「件名(タイトル)」に事業番号、事業名を
記入してください。
事業仕分けの詳細は文部科学省HPをご参照下さい。
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/sassin/1286925.htm
No.085 2009/11/27 geo-flash(臨時)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.085 2009/11/27 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 市川浩一郎 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
市川浩一郎 名誉会員(享年87歳)が平成21年11月25日(水)午前10時30分にご
逝去されましたので、謹んでお知らせいたします。これまでの故人の功績を讃え
るとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
なお、通夜、ご葬儀は下記のとおり執り行われますので併せてお知らせ申し上げ
ます。
記
■喪主:市川喬子(きょうこ)様 (ご令室)
■通夜:11月28日(土)18時30分から
■告別式:11月29日(日)午前10時15分から
■場所:博全社 蘇我儀式殿(千葉市中央区南町2-3-18)
(tel 043-268-4444 JR蘇我駅東口 徒歩3分)
会長 宮下純夫
──────────────────────────────────
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質マンガ 地すべり調査
地質マンガ
戻る|次へ
【解説】
のどかな風景です。
すべり面の水頭、傾斜、歪などが常時観測されています。
すべり面に水抜きボーリングを行い、間隙水圧を下げるといった様々な対策も施されます。
「良い所なんだぁ」というのはさすがに言い過ぎでしょう。しかし地すべり地帯の中には、壊滅的な山崩れを起こさないものも多数あります。普段は停止していますが、春の融水や豪雨の時に地下水位が上昇し、ほんの数ミリ〜数センチだけクリープして、そして再び停止するというパターンを繰り返すものも珍しくありません。こういったタイプの地すべりは、長い年月のうちに緩やかにすべり続け、やがて安定化していきます。おかげで急峻な山地に貴重な平坦面を提供してくれます。しかも地下水位が高く、水量も豊富なため(それゆえにすべるのですが)、昔から段々畑や棚田として利用されてきました。こういった地すべり地帯は、いくつかの大きなブロックに分かれてすべることがあります。このブロックの境界では食い違いや亀裂が生じますが、それ以外では家の立て付けが悪くなることも、田んぼの水が抜けることもありません。ブロックに乗って徐々に高度が下がっていくのみです。
とはいえ、ブロックがすべっていくのですから、長期的には道路や線路が断ち切られるといった被害が生じます。河川を堰き止めたり、高速道や新幹線を断ち切るようなことになれば、きわめて深刻な災害に発展するでしょう。そもそもこのクリープが大規模な斜面崩壊を誘発する可能性もあるかもしれません。やはり十分な地質調査と長期的な観測、それに基づいた対策が講じられなければならないのは言うまでもありません。
坂口有人(海洋研究開発機構)
No.086 2009/12/1 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.086 2009/12/01 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】学会ホームページ2年3ヶ月で100万人突破!
【2】2010年度一般社団法人日本地質学会代議員選挙:投票受付中
【3】日本地質学会2010年度各賞候補者募集中
【4】2010年度会費払込:学部生・院生割引会費申請を忘れずに!!
【5】行政刷新会議仕分け作業結果へのパブリックコメント受付中!
【6】リーフレット企画を募集します。
【7】12月博物館特別展示・イベント情報
【8】その他 お知らせ
【9】地質マンガ
【10】今年の地質重大ニュース募集
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】学会ホームページ2年3ヶ月で100万人突破!
──────────────────────────────────
地質学会のホームページは、2007年9月のリニューアル以降の訪問者数がつい
に100万人(565万ページビュー)を超えました。1年当たりにしますと、44万人読者
(251万ページビュー)という膨大な数字になります。学会ホームページは会員のみ
ならず一般読者が数多く訪れる外部向けメディアに成長したと言えるでしょう。これも
ひとえに会員皆様のご協力のおかげあり心から感謝申し上げます。人気ページや検
索ワードといったログ解析の詳細をニュース誌12月号にて報告する予定です.これか
らも学会ホームページをご利用・ご活用下さいますようお願いいたします.
(広報委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2010年度一般社団法人日本地質学会代議員選挙:投票受付中
──────────────────────────────────
投票締切:2010年1月9日(土)必着
定款,選挙規則および選挙細則に基づき,法人として初めての代議員選挙を実施
いたします.
全国区については定数未満ですので,全員が無投票当選となり投票は行いません.
地方支部区においては,立候補者が定数を超えた支部区はありませんので,全員
が当選となりますが,支部枠理事の選出がありますので,投票を行います.
また,この選挙と同時に,会長・副会長への立候補意思表明者に対する会員の意
向調査を実施いたします(定数:会長1名,副会長2名).詳細は投票用紙ととも
に参考書類を別途お送りしましたのでご覧ください.投票はお早めに,多くの会
員が投票していただきますようご協力をお願いします.なお、立候補者名簿・マ
ニフェストなどはHPでもご覧いただけます。
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
(ログインID・パスワードが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本地質学会2010年度各賞候補者募集中
──────────────────────────────────
応募締切:2009年12月25日(金)必着
詳しくは、会員のページをご参照下さい(ログインID・パスワードが必要です).
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2010年度会費払込:学部生・院生割引会費申請を忘れずに!!
──────────────────────────────────
来年度(2010年度)からは学部学生・院生(研究者)については,本人の申請
によりそれぞれ割引会費が適用されます.次年度(2010年度)の会費についてた
だ今申請受付中です.毎年更新となりますので,次年度会費について該当する方
は,申請書を提出してください(郵送に限る).
お振込の方へは、12月中旬までに請求書兼振り替え用紙をご送付致します。
会費口座引落:12月24日(予定)
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/outline/content0052.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】行政刷新会議仕分け作業結果へのパブリックコメント受付中!
──────────────────────────────────
行政刷新会議の仕分け作業結果を受けて、地質学会はコメントを11月20日に文
部科学大臣(川端大臣)、行政刷新会議議長(鳩山 総理大臣)宛に送りました。
文部科学省は皆さんからの意見をホームページで受け付けております。ぜひ将来
の科学技術の発展、そして教育の充実のために、皆様のご意見をお送りください。
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/sassin/1286925.htm
日本地質学会の意見書(2009.11.20付)はこちら
http://www.geosociety.jp/engineer/content0008.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】リーフレットの企画を募集します。
──────────────────────────────────
日本各地の地質を専門家や一般の方々,そして子供達にわかりやすく紹介するリー
フレットを募集します.大地に関する地質研究の成果を積極的に社会に還元しま
しょう.手続きは下の図のようになります.企画に関わる細則と必要書類は,学
会ホームページをご参照下さい。
詳しくは、http://www.geosociety.jp/publication/content0044.html
(リーフレット企画出版委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】12月博物館特別展示・イベント情報
──────────────────────────────────
早いもので,冬の便りも届く季節になりました。寒くはなりましたが野外観察会を含
めたイベントをご用意してみなさまのお越しをお待ちしております。
なお、年末年始は多くの館が休館となりますので、お立ち寄りの際には各博物館の
Webページにて開館スケジュールをご確認の上お越し下さい。
12月の特別展示・イベントのチェックは↓↓↓
http://www.geosociety.jp/name/content0052.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他お知らせ
──────────────────────────────────
■「ちきゅう」乗船スクール2010開催のご案内
対象:若手研究者、教育関係者等
地球深部探査船「ちきゅう」は、海底下7,000mという世界最高レベルの掘削能力と
船上研究設備を持つ最新鋭の科学掘削船です。日米が主導し、世界24カ国が参加
する統合国際深海掘削計画(IODP)において、巨大地震発生のメカニズムや海底下
に広がる地下生命圏、地球規模の環境変化や地殻変動の解明といった地球科学の
革新的な飛躍を目指して研究を行っています。本スクールでは、「ちきゅう」に乗船し、
掘削技術や研究手法を学ぶほか、研究区画において、実際のコアサンプルを用いた
試料処理、各種計測の操作実習、海洋科学掘削研究の意義や研究トピックなどを、
船内生活を通じて学ぶことを目的とします。将来の乗船研究者を目指して、また乗船
体験や実習の成果を授業等で活用するために、「ちきゅう」に乗り込んでみませんか?
http://www.jamstec.go.jp/chikyu/jp/education/school.html
■2010年度IODP掘削航海乗船者募集中!
○テーマ:ファン・デ・フーカ海嶺東翼部の玄武岩質海洋地殻の水理地質学的構造2
>航海予定期間:2010年7月〜9月
○テーマ: 南太平洋環流における微生物学(仮題)
>航海予定期間:2010年10月〜12月
○テーマ:ルイスビル海山列の進化モデルの検証(仮題)
>航海予定期間: 2010年12月〜2011年2月
詳しくは、http://www.j-desc.org/modules/tinyd0/rewrite/expeditions.html?PHPSESSID=tjisaasd4ag86hmgh4dbcbuc94
■第8回地球システム・地球進化ニューイヤースクール
開催日:2010年1月9日(土)〜10日(日)
開催場所: 国立オリンピック記念青少年総合センター(東京・代々木)
参加費:3500円(懇親会費込み)
申込締切:2009年12月10日(木)
詳しくは、
http://quartz.ess.sci.osaka-u.ac.jp/~earth21/school/gakkou/gakkou.html
■北淡国際活断層シンポジウム2010開催案内
会期:2010年1月17日--21日
会場:兵庫県淡路市・北淡震災記念公園セミナーハウス
詳しくは、http://home.hiroshima-u.ac.jp/kojiok/hokudan2010.html
■学術会議シンポジウム「学術コミュニティと知的財産」
日時:2009年12月14日(月)15:00〜18:00
場所:日本学術会議 講堂(東京都千代田区六本木)
主催:日本学術会議 科学者委員会 知的財産検討分科会
詳しくは、http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf/83-s-1.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】地質マンガ 「地すべり調査」作:坂口有人 画:Key
──────────────────────────────────
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/faq/content0196.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】今年の地質重大ニュース募集
──────────────────────────────────
本年も残り1ヶ月となりました.皆様にとりましてどのような1年だったでしょうか.
次号では恒例の地質重大ニュースを選び,今年1年を振り返ってみたいと思います.
皆様からの推薦をお待ちしております.どうぞご応募ください.
https://www.geosociety.jp/modules/liaise/2.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
マンガの原作募集中!もうストックがありません.テキストで原案を投稿下さいますと
マンガ化いたします.「マンガ+解説」で研究紹介にもご活用下さい.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質マンガ 鬼の洗濯板
地質マンガ
戻る|次へ
【解説】
宮崎県日南海岸には鬼の洗濯板と呼ばれる平滑な地形が観察できます.このような平滑な地形は潮間帯において形成され,地学用語で「波食棚」と呼ばれています.
波食棚は岩石海岸の基本的な地形の特徴であり世界各地で観察することができます.また,波食棚は潮間帯を示す特徴であることから,隆起した波食棚に残された穿孔性生物の化石などを組み合わせることで過去の相対的な海面の位置を復元することができます.
*「津波は大丈夫かね」の解説で紹介されている房総半島南端でも観察できます.
さて,マンガにでてくる波食棚(鬼の洗濯板)は砂泥互層によって構成されています.水平に堆積した砂泥互層は褶曲の影響を受け,現在は15〜20度前後の緩い傾斜をもっています.緩い傾斜をもった砂泥互層は,潮間帯において絶えず浸食の影響を受けるため,浸食に強い砂岩と弱い泥質岩によって凹凸が形成されます.この凹凸によって洗濯板のように見えます.
この砂泥互層は有孔中などの化石記録から,後期中新世から鮮新世に堆積した宮崎層群に区分されている.粒子のサイズや層厚の変化に加えて貝類が産出することから,堆積環境の変化(外洋性・内湾性)が論じられ,古くから重要な地質サイトのひとつです.
IGCP-511 海底地すべり会議に参加して−
IGCP-511 海底地すべり会議に参加して−
川村喜一郎(財団法人深田地質研究所)
平成21年11月7−12日にテキサス大学オースチンで,IGCP-511(IUGS-UNESCO's International Geoscience Programme 511:IGCPは国際地質学会とユネスコの共同国際プログラムにあたる)の第4回国際会議に参加した.このプログラムは,主として海底地すべりについて検討するものである.会議は,総勢約130名の,主としてアメリカ,カナダ,ヨーロッパ(特にドイツとイギリス)の理学,工学,エンジニアが参加し,シェルやフグロなどの石油,掘削関連の会社がスポンサーとして参加している.
この会議では,海底地すべりに関わる論文を集めて,Springerから書籍を出版し,その内容を発表し合うという形式のものであった.全般的に書籍に書かれている内容の発表であったために,あまり目を引くような内容の発表は少なかった.このような形式のシンポジウムは,成果として残っていくのだろう.
この会議で網羅されている海底地すべりの事例は世界的で,目を引くものがある.北海,大西洋全般(カナダ沖,スペイン沖,ブラジル沖,ナイジェリア沖,ナミビア沖などなど),オーストラリア,スマトラ,チリ,日本周辺をはじめ太平洋全般,南極周辺,当然北アメリカは陸上海底さまざまな海底地すべりが紹介されていた.今まで参加した海底地すべり関連の集まりの中で最大級のものであった.このコミュニティーが急速に世界的に拡大していることを物語っている.日本からは,私とJAMSTECの山本由弦氏の2名が参加し,日本の海底地すべりをアピールした.
その研究スタイルはおおよそ1)地震探査,2)地形調査,3)コアリング,という従来のツールに集約される.これらを組み合わせて,海底地すべりの形状の把握,発生年代の特定を行うことが中心であり,記載的なものがまだ多い.しかし,一部の革新的な研究者は,海底での斜面安定解析や斜面崩壊のシミュレーションに挑戦している.私は,この会議でも潜水船調査に基づいた海底地すべりの観察事例について紹介した.このような研究スタイルは世界的にもまだ珍しいようで,コミュニティーにそれなりに受け入れられている,と実感している.次の機会は,ぜひ今進行している斜面安定解析を公表したい.
写真1 テキサス大学内BEGの発表会場.
写真2 たった2人の日本人.山本由弦氏と発表ポスター
ポスターセッションもあり,そこで北海の海底地すべりの研究者と話をした.最近の知見では,北海をはじめとした大西洋に存在する海底地すべりの発生原因はよくわからないという結論に達しているようである.北海にはストレッガスライドと呼ばれる第四紀最大の海底地すべりがあることが知られており,長年,それはメタンハイドレート層の分解によって引き起こされたとされていた.しかし,その発生年代は,8000年〜5000年であり,メタンハイドレート層の分解ではうまく説明できないようである.すなわち,メタンハイドレート層は海水準の低下による水圧の減少によって分解され,それによって海底地すべりが大量に発生すると考えられてきた.しかし,8000年は海水準が高い時期にあたり,このロジックではうまく説明できない.今考えられているもっともらしい海底地すべりの発生原因は,地震だそうである.氷期が終わり,スカンジナビア半島を覆っていた大陸氷床がなくなり,それにより,アイソスタシーバランスで半島は隆起する.このとき,マグニチュード6〜7程度の地震が発生するらしいのである.この地震が海底地すべりを引き起こしたと考えられているようである.2年前の2007年のオレゴンで行われたジオハザードワークショップでは,このような説明は聞かず,すべてメタンハイドレート原因説で済まされていた.この分野の知見はすざまじい速度で進展しているようだ.
あまりに急速に進展しているため,現在のところ,すべての事象を一括して海底地すべりと称している感があるが,一見する限り,それらの大部分は,いわゆるスランプかフロー,一部スライドに属すると思われる(海底地すべりという用語としては,最近は,「submarine landslide」が主流で定着しつつあるようである,しかし,gravitational collapse, submarine slide,さらには debris avalancheと呼んでいる研究者もいる.Stregga slideのように呼称でslideというものもごく一般的である.そして,これらの結果堆積したものは,mass-transport deposit: MTDがよく使われており,mass-transport complex, mass-wasting depositも同様に見受けられる.採取されたコアを用いて,このMTDをslide, slump,debris flowに細分して,その分布を調べている研究者もいる).今後,堆積学的な用語の「クリープ,スライド,スランプ,フロー」と併せて,海底地すべりの用語を整理していかないといけないのだろう.それはおそらく今後,数年でまた急速に進展するのだろうが.
このIGCP511は,今年で終わりで来年へ向けて新しいIGCPを提案することになっており,私もその協力者として混ぜてもらっている.この提案されているIGCPが採択されれば,次のこのような国際会議は2年後になる.めざましい進歩についていくために,また参加したい.
地質マンガ 人間行動学的古生物学
地質マンガ
戻る|次へ
【解説】
天草御所浦ジオパークの「白亜紀の壁」. 「白亜紀の壁」では河川流域や浅海で堆積した地層が見られますが,化石が多く見れる層から見られない層まであります.
「トリゴニア砂岩」.暴風時に貝殻が掃き寄せられてできた化石層で,化石が密集した状態で見られます.
横から見た「トリゴニア砂岩」.横から見ると,化石の多いのは一面だけで,他は少ない部分からなっています.
一般に誰もが化石とわかるような大型化石が出てくる地層の多くは,河川流域や海などで堆積した堆積物です.これらの地層を探せば,化石が見つけることができます.しかし.化石の多いところから,化石がほとんど出てこない場所まであり,様々です.
では,効率的に化石を見つける方法は,どのような方法でしょうか.それは,化石の出ている場所を文献で調べる,人に教えてもらうなどの方法があります(最近はインターネットなど,ウェブ上で紹介されていることもありますが…).しかし,文献などでは,化石の出てくるピンポイントまではわかりにくいものです.そのような場合,丁寧に探していく方法はもちろんですが,マンガにあるような人が掘った跡のあるところ探す方法があります.化石が多く出てくるところなどは,台風のような暴風などといったイベント,干潟など多くの生物が生息している場所で堆積した地層中に見られ,同時期や同じ環境でたまった地層中に層状に広がり,化石を多く含む“化石層”を作ることがしばしばあります.その層を掘れば,たくさんの化石が得られます.このような場所に集中して人が掘るので,その場所が人為的に掘削されていることがよくあります.そこを探せば,効率的に化石が探せるという訳です.
しかし,化石採集には人の土地だったり,法などで保護されて場所であったり,採集すると問題となる場所も多くありますので,必ず地権者や管理者の許可を得てから化石採集することが,トラブルを防ぐ上で重要です.また,崩れやすくなっていることもありますので,事故に気をつけるとともに,景観破壊とならないよう十分気をつけて下さい.
天草市立御所浦白亜紀資料館 廣瀬浩司
WEBサイト→http://www5.ocn.ne.jp/~g-museum/
No.087 2009/12/15 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.087 2009/12/15 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】公開シンポジウム「人類の時代・第四紀は残った」
【2】2010年度一般社団法人日本地質学会代議員選挙:投票受付中
【3】日本地質学会2010年度各賞候補者募集中(12/25締切)
【4】2010年度会費払込:学部生・院生割引会費申請を忘れずに!!
【5】フィールドジオロジー第6巻新発売:会員特別割引販売のお知らせ
【6】その他 お知らせ
【7】地質マンガ
【8】今年の地質重大ニュース発表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】公開シンポジウム「人類の時代・第四紀は残った」
──────────────────────────────────
国際地質科学連合(IUGS)執行委員会は第四紀を正式の地質時代として認め,そ
の始まりを258.8万年前とする新たな定義を批准した.これにより,長年,地質区分
として不確定であった第四紀が正式な紀/系として認められ, 激しい環境変動と人
類の出現・進化を特徴とする,最新の地質時代が誕生した.本シンポジウムでは,
今回批准された新たな定義を確認し,第四紀の持つ重要性を再認識するとともに,
研究教育や産業活動に及ぼす影響を議論する.
主 催: 日本学術会議地球惑星科学委員会IUGS分科会・日本学術会議地球惑星科
学委員会INQUA分科会
共 催:日本地質学会・日本第四紀学会・日本地球惑星科学連合(予定)
日 時:2009年1月22日(金) 10:00-17:15
場 所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木7-22-34)
詳しくは、学会webサイトをご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/name/content0053.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2010年度一般社団法人日本地質学会代議員選挙:投票受付中
──────────────────────────────────
投票締切:2010年1月9日(土)必着
定款,選挙規則および選挙細則に基づき,法人として初めての代議員選挙を実施
いたします.
全国区については定数未満ですので,全員が無投票当選となり投票は行いません.
地方支部区においては,立候補者が定数を超えた支部区はありませんので,全員
が当選となりますが,支部枠理事の選出がありますので,投票を行います.
また,この選挙と同時に,会長・副会長への立候補意思表明者に対する会員の意
向調査を実施いたします(定数:会長1名,副会長2名).詳細は投票用紙ととも
に参考書類を別途お送りしましたのでご覧ください.投票はお早めに,多くの会
員が投票していただきますようご協力をお願いします.なお、立候補者名簿・マ
ニフェストなどはHPでもご覧いただけます。
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
(ログインID・パスワードが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本地質学会2010年度各賞候補者募集中(12/25締切)
──────────────────────────────────
応募締切:2009年12月25日(金)必着
詳しくは、会員のページをご参照下さい(ログインID・パスワードが必要です).
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2010年度会費払込:学部生・院生割引会費申請を忘れずに!!
──────────────────────────────────
来年度(2010年度)からは学部学生・院生(研究者)については,本人の申請
によりそれぞれ割引会費が適用されます.次年度(2010年度)の会費についてた
だ今申請受付中です.毎年更新となりますので,次年度会費について該当する方
は,申請書を提出してください(郵送に限る).
お振込の方へは、12月中旬までに請求書兼振り替え用紙をご送付致します。
学部生・院生割引申請最終締切:2010年3月31日
会費口座引落:12月24日(予定)
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/outline/content0052.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】フィールドジオロジー第6巻新発売:会員特別割引販売のお知らせ
──────────────────────────────────
第6巻 「構造地質学」 天野一男・狩野謙一 2009年12月23日発売
B6判・約200頁・定価2,100円⇒会員特別割引価格1,900円(税込)
日本地質学会会員を対象に、特別割引価格での販売をいたします。手続きは、共
立出版に直接扱っていただきますので予約申込みは、専用申込用紙をご利用くだ
さい(HP・ニュース誌掲載)
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
(ログインID・パスワードが必要です)
日本地質学会フィールドジオロジー刊行委員会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他 お知らせ
──────────────────────────────────
■第124回深田研談話会
2010年1月15日(金)午後3-5時
講師:中谷正生氏(東京大学地震研究所)
会場: 財団法人深田地質研究所 研修ホール
テーマ:南アフリカの大深度金鉱山における半制御地震発生実験
■第125回深田研談話会
2010年2月19日(金)午後3-5時
講師:林 雅雄氏(石油天然ガス・金属鉱物資源機構)
会場: 財団法人深田地質研究所 研修ホール
テーマ:次世代の国産エネルギー候補「メタンハイドレート」ー資源量評価研究
の最前線ー
「深田研談話会」は技術士CPD(継続教育)履修実績として申請可です。
■International Field Conference and Workshop on Tephrochronology, Volcan
ism and Human Activity: Active Tephra in Kyushu, 2010(火山灰編年・火山活
動・人間活動に関する国際野外集会およびワークショップ「アクティブテフラ九
州2010」)
2010年5月9日(日)〜17日(月)
会場:鹿児島県霧島市霧島市役所および九州内での野外巡検
http://www.ris.ac.jp/intav-jp/index.html
■第47回アイソトープ・放射線 研究発表会発表論文募集
会期:2010年7月7日(水)〜9日(金)
会場:日本科学未来館(東京都江東区青海2丁目41番)
共催:日本地質学会ほか
申込締切:2010年2月28日(日)
講演要旨原稿締切:2010年4月15日(木)
http://www.jrias.or.jp/index.cfm/1,html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】地質マンガ「人間行動学的古生物学」 作:川村喜一郎 画:Key
──────────────────────────────────
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/faq/content0057.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】発表!今年の地質重大ニュース
──────────────────────────────────
今年も残すところあとわずかになりました.地質に関する重大ニュースを勝手に選
んでみました.地質学関連に絞ってもいろんなことがありました.こうして振り返っ
てみると,地質学と社会との向き合い方を考えさせられます.
世界ジオパークに国内3地域認定
地質学の巨星の訃報あいつぐ
国連気候変動枠組条約COP15会議始まる
かぐや月探査成功
国内で皆既日食
篠山市で角竜類の化石発見
新「しらせ」(4代目南極観測船)出航
地球科学分野の事業仕分け.意見書提出
来年も地質学とそして皆様にとってよい年でありますよう願っております.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本年も本当にありがとうございました.来年もまたどうぞよろしくお願いします.
<*事務局年末年始休業のお知らせ:12月29日から1月5日まで*>
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質マンガ スケールプロトラクター
地質マンガ
戻る|a href="http://www.geosociety.jp/faq/content205.html">次へ
【解説】
「透けるからスケプロ!」ではありません。 Scale(定規)+Protractor(分度器)だからスケールプロトラクターなのです。言われてみれば、わかりやすいネーミングですね。
野外踏査では、地層や断層、様々な構造、岩石の分布などをマップに記載していきます。この時にマップに記入しながら、未調査のエリアに何があるのかを推測します。調査地域のアウトラインを考えつつ調査するのはとても重要です。この時にマップに正しく記載しなければ、とんでもない推測にたどりついてしまいます。だから分度器と定規をちゃんと使って、できるだけ正確に書く必要があります。
もちろん普通の分度器と定規を使ってもいいのですが、野外には机もペン立てもありません。風も吹けば雨も降ります。そして小さなボードの上で作業するには文房具は多くない方が便利です。というわけで定規と分度器が一体化したスケールプロトラクターを使うのです。
この便利さがわからなければ「こんなプラスチック定規がなぜこんなに高いの?!」と、言ってしまうのです(私も学生のとき、そう思いました)。
(スケプロ+ルートマップ提供:氏家恒太郎)
海洋研究開発機構 坂口有人
No.088 2010/01/06 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.088 2010/1/6 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2010年の年頭に当たって
【2】公開シンポジウム「人類の時代・第四紀は残った」
【3】日本地質学会2010年度各賞候補者:締切延長(1/12まで)
【4】2010年度一般社団法人日本地質学会代議員選挙:投票受付中
【5】2010年度会費払込:学部生・院生割引会費申請を忘れずに!!
【6】Island Arc vol18 Issue4 公開されました
【7】支部情報(関東支部/西日本支部)
【8】フィールドジオロジー第6巻新発売:会員特別割引販売のお知らせ
【9】公募情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2010年の年頭に当たって
──────────────────────────────────
会長 宮下純夫
新しい年2010年が始まりました.地質学会理事会を代表して会員の皆様に年頭
のご挨拶を申し上げます.昨年と同様にオマーンからこの挨拶をお送りしていま
す
続きは、、、、
http://www.geosociety.jp/outline/content0002.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】公開シンポジウム「人類の時代・第四紀は残った」
──────────────────────────────────
国際地質科学連合(IUGS)執行委員会は第四紀を正式の地質時代として認め,そ
の始まりを258.8万年前とする新たな定義を批准した.これにより,長年,地質区分
として不確定であった第四紀が正式な紀/系として認められ, 激しい環境変動と人
類の出現・進化を特徴とする,最新の地質時代が誕生した.本シンポジウムでは,
今回批准された新たな定義を確認し,第四紀の持つ重要性を再認識するとともに,
研究教育や産業活動に及ぼす影響を議論する.
主 催: 日本学術会議地球惑星科学委員会IUGS分科会・日本学術会議地球惑星科
学委員会INQUA分科会
共 催:日本地質学会・日本第四紀学会・日本地球惑星科学連合(予定)
日 時:2010年1月22日(金) 10:00-17:15
場 所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木7-22-34)
詳しくは、学会webサイトをご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/name/content0053.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本地質学会2010年度各賞候補者:締切延長(1/12まで)
──────────────────────────────────
12/25で締切となりました募集ですが、さらに多くのご推薦等を頂きたく締め切り
を延長致しました。多くのご応募をお待ちしております。
応募締切延長しました:2010年1月12日(火)
詳しくは、会員のページをご参照下さい(ログインID・パスワードが必要です).
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2010年度一般社団法人日本地質学会代議員選挙:投票締切間近!!
──────────────────────────────────
投票締切:2010年1月9日(土)必着
代議員選挙投票はまもなく締切です!また,この選挙と同時に,会長・副会長へ
の立候補意思表明者に対する会員の意向調査を実施いたします(定数:会長1名,
副会長2名).多くの会員が投票していただきますようご協力をお願いします.な
お、立候補者名簿・マニフェストなどはHPでもご覧いただけます。
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
(ログインID・パスワードが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2010年度会費払込:学部生・院生割引会費申請を忘れずに!!
──────────────────────────────────
来年度(2010年度)からは学部学生・院生(研究者)については,本人の申請
によりそれぞれ割引会費が適用されます.
学部生・院生割引申請最終締切:2010年3月31日
会費口座引落:12月24日
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/outline/content0052.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】Island Arc vol.18 Issue 4 公開されました
──────────────────────────────────
Vol.18 Issue 4
1. Ramin Arfania and Sohrab Shahriari:イランに分布するザグロス造山帯の構
造的発達における南東部Sanandaj-Sirjan帯の役割
2. 丹羽正和ほか:中部日本の阿寺断層における断層破砕帯の発達過程の復元
3. James Hawkins, 石塚 治:パラオ諸島における初期島弧のマグマ進化
4. Deniz Cukur et al;3次元震探データおよび検層データに基づくバルバドス付
加プリズム北部の構造,変形様式,流体挙動
5. 氏家良博:不整合,断層および接触変成作用に関連した北日本の堆積岩における
「統計的熱変質指標(stTAI)」とビトリナイト反射率との関係
会員無料閲覧は下記からログインしてください.
https://www.geosociety.jp/user.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報(関東支部/西日本支部)
──────────────────────────────────
■関東支部:ジオパークをめざして! 秩父地域の観察会と講演会
・ジオサイト観察会「長瀞の岩畳」
日時:2010年2月13日(土)10:30〜12:00(雨天決行)
申込締切:2月6日(土)
・ジオパーク講演会
日時:2月13日(土)13:00〜16:00
会場:埼玉県立自然の博物館 2階講堂
申込締切:2月6日(土)
・秩父ジオサイトバスツアー
日時:3月6日(土)9:00〜16:00(雨天決行)
申込締切:2月24日(水)
詳しくは、http://kanto.geosociety.jp/
■西日本支部
第158回日本地質学会西日本支部例会および2009年度支部総会のご案内
日程:2010年2月13日(土)
会場:西日本支部例会・総会:福岡大学18号館1824教室
参加・講演申込締切:2010年2月1日(月)必着
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】フィールドジオロジー第6巻新発売:会員特別割引販売のお知らせ
──────────────────────────────────
第6巻 「構造地質学」 天野一男・狩野謙一 2009年12月23日発売
B6判・約200頁・定価2,100円⇒会員特別割引価格1,900円(税込)
日本地質学会会員を対象に、特別割引価格での販売をいたします。予約申込みは、
専用申込用紙をご利用ください(HP・ニュース誌掲載)
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
(ログインID・パスワードが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報
──────────────────────────────────
■東京工業大学大学院理工学研究科特任助教(1名)
締切:2010年 1月 25 日(月) 必着
■東北大学大学院理学研究科地学専攻准教授(1名)公募
締切:2010年1月末日 必着
■広島大学大学院理学研究科地球惑星システム学准教授(1名)公募
締切:2月15日(月)必着
■東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻准教授(1名)公募
締切:2010年2月26日(金)
■北海道大学大学院理学研究院自然史科学部門地球惑星システム科学分野教授(1
名)公募
締切:2010年3月31日(水)必着
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
あけましておめでとうございます.本年もどうぞよろしくお願いします.
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地球史Q&A
地球史Q&A
注:これは地質学会としての統一見解ではなく、読者の理解の一助として広報委員会が整備したものです
地球史に関するQ&A
Q1.第四紀の時代区分が変わるってどういうことですか?
Q2.なぜ258万年前なの?
Q3.年代の定義の変更と数値の改訂の違いとは??
Q4.第四紀とはどんな時代なの?
Q5.活断層とは第四紀に動いたものだと聞きました.第四紀の年代が遡ると活断層が増えるのですか? 危険性は?
Q6.法令に「第四紀」は使われているの?
Q7.建築物への影響は?
Q8.第三紀はどうなりますか?
Q1.第四紀の時代区分が変わるってどういうことですか?
A.旧来の鮮新世の一部まで第四紀になります
これまで新第三紀 鮮新世に入れられていたジェラ期(中生代のジュラ紀ではありません)が,第四紀の更新世に含まれることに変更されました.これは,新生代末期の顕著な寒冷化および数万年周期の氷期・間氷期の繰り返しが.ジェラ期には既に始まっていたことがはっきりしたためです.また,松山逆磁極期の始まり(258万年前)をもって第四紀の始まりとすることになりました. 2009年6月30日、国際地質科学連合(IUGS)執行委員会は長年、地質区分として不確定であった第四紀を正式な紀/系として認め、その始まりをこれまでの181万年前から258万年前に変更する新たな定義を批准しました。日本においてもこの新しい定義を受け入れ,普及させる必要があります.
ちなみに松山逆磁極期とは,松山基範先生(1884-1958)が,地質時代において地球磁場が逆転していたことを世界で初めて発見し,その2功績からが名づけられたものです。これがひとつの指標となったということは,日本の地球科学にとって嬉ばしいことです.
Q2.なぜ258万年前なの?
A.各時代区分は,それぞれその時代を特徴づける現象によって区切られています.
第四紀は,地球が全体的に寒冷化に向かった時代です.古気温の指標である酸素同位体比は,鮮新世から更新世にかけて大きく変動しつつも,この時代から明らかに現在のレベルよりも下がっていきます.そしてそれ以降,氷期と間氷期の4.1万年の周期性が明瞭に表れてきます.かつガウス正磁極期から松山逆磁極期への逆転の時期に当たるので,これを凡世界的な境界として使うことができます.
Q3.年代の定義の変更と数値の改訂の違いとは?
A.分析技術の進展により,年代の数値が変わることはたびたびあります.
しかし時代区分の定義の変更はめったにありません.しかも私たちが生活している第四紀という時代の区分が変更されるというのは,他の時代区分とは全く違った意味を持っています.
Q4.第四紀とはどんな時代なの?
A.寒冷化と人類が進化した時代です.
地球規模で寒冷化がすすみ,中緯度地域に達する大規模な氷河の出現が顕著となり,現在も継続する地球規模の激しい環境変動の中で人類が発生して進化してきた最新の地質時代です.人類の出現はもっと以前ですが,ホモ属が世界各地に拡散・多様化し,現代人に至る進化を行ってきた時代です.また,氷床の拡大・縮小、氷期・間氷期等のサイクルが明瞭で,気候変動・環境変動に関わる膨大な情報が残されており,近未来の地球環境を合理的に予測するための重要な資料として活用されています.こういった特徴が第四紀を他の時代と画する重要な特徴です.
Q5.活断層とは第四紀に動いたものだと聞きました.第四紀の年代が遡ると活断層が増えるのですか? 危険性は?
A.時代区分が変更されたからといって急に危険性が増したりはしません.
活断層とは,最近の時代に活動した断層で,将来も動く可能性がある点が重要です.基本的には個々の断層において,トレンチ調査等によって再来周期と最新イベントを認定し,それを基づいて活動度評価がなされます.つまり,いつ,どれくらいの地震が繰り返されたか,という前歴を明らかにして,そこから将来を推測するのです.それに対して,断層が第四紀の地層・地形を切っているかどうか,というのは大まかな目安とすぎません.調査の最初のステップとして,第四紀の地層を切っているかとうかというのは注目されますが,最近では特に後期更新世以降の地層を切っているかどうか(すなわちここ10万年くらいの活動)が重要視されるようになっていますので,今回の変更により活断層の調査や評価が大きく変わるものではありません.
Q6.法令に「第四紀」は使われているの?
A.使われています.
たとえば 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年八月三十一日通商産業省令第百五十一号)です.詳しくは電子政府のホームページから閲覧できます.ここからリンク
Q7.建築物への影響は?
A.ありません
大きな構造物の建設が検討される場合に、地盤の目安として第四紀の地層の有無が、大まかな目安として使われる場合があります。しかしこれはあくまでも第四紀より古い地層は固まっているだろうという、便利な目安にすぎません。実際に建設する場合には地盤の力学試験に基づいて安全評価が行われます。第四紀の定義が変更されるからといって、既存の構造物の安全性が損なわれるものではありません.
Q8:第三紀はどうなりますか?
A: 用語としては国際的には使われなくなっています.
アメリカと日本を除き,国際的なスタンダードとして Tertiaryは すでに 使われていませんので,国内でもそれに従い今後「第三紀」は使うべきではな いと話し合われています.それに代わり,Paleogene, Neogene の和訳として,今の所は従来の和訳(古第三紀,新第三紀)を踏襲するという提案がなさ れています.いずれにせよ,新学習指導要領に則った高等学校の地学教科書の 改訂のこともありますので,地質学会の方針を早めに決定し,速やかに広報す る予定です.
No.089 2010/01/19 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.089 2010/ 1/19 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2010年度代議員選挙の結果報告
【2】公開シンポジウム「人類の時代・第四紀は残った」(時代区分の定義が変わります)
【3】ハイチ地震情報
【4】ハイチ地震に対して
【5】ハイチ地震情報・救援関係 リンク集
【6】支部情報いろいろ
【7】その他のご案内
【8】地質学会ニュース誌 “百名山の地質(仮)”執筆者募集
【9】会員特別割引販売のご案内:地学読本
【10】公募情報
【11】地質マンガ「スケールプロトラクター」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2010年度代議員選挙の結果報告
──────────────────────────────────
選挙規則ならびに選挙細則に基づき,標記選挙を実施いたしましたのでご報告い
たします.
2010年1月16日
一般社団法人日本地質学会 選挙管理委員会委員長 松田達生
開票立会人 佐野貴司・竹内圭史
詳しくは、http://www.geosociety.jp/members/content0048.html
(会員番号・パスワードによるログインが必要です)
*監事立候補受付中です(締切:2/12)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】公開シンポジウム「人類の時代・第四紀は残った」
──────────────────────────────────
主 催: 日本学術会議地球惑星科学委員会IUGS分科会・日本学術会議地球惑星科
学委員会INQUA分科会
共 催:日本地質学会・日本第四紀学会・日本地球惑星科学連合(予定)
日 時:2010年1月22日(金) 10:00-17:15
場 所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木7-22-34)
詳しくは、学会webサイトをご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/name/content0053.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】ハイチ地震の解説: ヒスパニョーラの地質とテクトニクス
──────────────────────────────────
ヒスパニョーラの地質とテクトニクス(ハイチの地震に寄せて)
小川勇二郎 (東電設計株式会社)
今回のハイチ地震は、とても他人事ではない。丁度、阪神淡路大地震15周年の
行事や放送が行われていた時であったから、なおさらである。筑波大学の八木勇
治准教授によると、くしくも今回の地震は阪神と類似のメカニズム、規模である
ようだ。続きはこちら、、、
http://www.geosociety.jp/hazard/content0036.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】ハイチ地震に対して
──────────────────────────────────
2010年1月13日6時53分(日本時間)にカリブ海の島国であるハイチ共和国南部でM7.
0の地震が発生しました.この地震は北米プレートとカリブプレートのプレート境
界近傍の内陸断層の活動による直下型地震と考えられています.人口の密集する
首都の直下が震源となったために,多くの家屋が倒壊し,数十万人規模の死者が
予想されるなど甚大な被害が出ています.くしくも兵庫県南部地震から15年が経
過して多くの報道や番組放映などがされたこともあり,突然襲う地震災害の恐怖
を,人々に改めて感じさせることになりました.続きはこちら、、、
http://www.geosociety.jp/hazard/content0037.html
2010年1月18日
日本地質学会地質災害委員会委員長 藤本光一郎
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】ハイチ地震情報・救援関係 リンク集
──────────────────────────────────
地震情報
USGS
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/us2010rja6.php#details
NGY地震学ノート
http://www.seis.nagoya-u.ac.jp/sanchu/Seismo_Note/2010/NGY24.html
東大地震研特設ページ
http://outreach.eri.u-tokyo.ac.jp/2010/01/201001_haiti/
募金情報
お近くのコンビニ、銀行など、あるいはインターネットによる募金が可能です。
募金には各団体の活動趣旨にご留意ください。
日本赤十字社
http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00001446.html
中央共同募金会(赤い羽根)
http://blogs.yahoo.co.jp/kyodobokin/50043305.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報いろいろ
──────────────────────────────────
■関東支部
・ジオサイト観察会「長瀞の岩畳」
2月13日(土)10:30-12:00(雨天決行)集合:秩父鉄道長瀞駅10:30
申込締切:2月6日(土)
・ジオパーク講演会
2月13日(土)13:00-16:00(雨天決行)
会場:埼玉県立自然の博物館2階講堂
申込締切:2月6日(土)
・秩父ジオサイトバスツアー
3月6日(土)9:00-16:00(雨天決行)集合:西武秩父線西武秩父駅前
申込締切:2月24日(水)
詳しくは、http://kanto.geosociety.jp/
■西日本支部支部
第158回西日本支部例会および2009年度支部総会
2010年2月13日(土)
会場:福岡大学18号館1824教室
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
■北海道支部
支部総会・個人講演会
2010年3月20日(土)13:30-17:30
場所:北海道大学理学部6号館 6-204-02教室
申込締切:2月12日(金)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他の案内
──────────────────────────────────
■第125回深田研談話会
日 時:2010年2月19日(金)15:00〜17:00(受付開始時間14:30)
会 場:財団法人深田地質研究所 研修ホール
講 師:林 雅雄 氏 ((独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構,元 出光石油開
発(株)取締役開発部長)
演 題:次世代の国産エネルギー候補「メタンハイドレート」−資源量評価研
究の最前線−
講演概要:メタンハイドレートという物体をご存知ですか?これが次世代(将来)
のエネルギー資源候補として研究対象に取り上げられて以来、新聞や雑誌、時に
はテレビで報道されるようになりましたが、多くの方々にとっては実体が判らな
いというのが実情かもしれません。そこでメタンハイドレートの資源量評価分野
に関するわが国の研究成果を簡潔に紹介し、併せて日頃その恩恵に浴している天
然ガスについて、日本が世界でどのような状況に置かれているかをお伝えします。
・「深田研談話会」は技術士CPD(継続教育)履修実績として申請することができ
ます。
・参加費無料
参加ご希望の方は、E-mail・FAX・ハガキの何れかでお申込みください。
その際、氏名・所属・連絡先(住所・電話番号)をご記入ください。
※申込み多数の場合は、お断りさせて頂く場合がございます。
(財)深田地質研究所
〒113-0021 東京都文京区本駒込2−13−12
TEL 03-3944-8010 FAX 03-3944-5404
URL http://www.fgi.or.jp/ E-mail fgi@fgi.or.jp
■第4回 海洋と地球の学校開催のご案内(5日間巡検含む)
多様性を科学する〜海洋と地球のツアー〜
「海洋と地球の学校」は、大学生と大学院生対象に、海洋と地球の知識を、講義
と体験を通して取得させることで、将来の海洋研究を担う人材を育成することを
目的としています。
主催;海洋研究開発機構
後援;文部科学省
協力;新江ノ島水族館、葉山しおさい博物館、(社)海洋産業研究会
横須賀市博物館天神島臨海自然教育園 (順不同)
期日;2010年3月15日(月)〜19日(金)
場所;海洋研究開発機構横須賀本部、横浜研究所、三浦半島の生物地質巡検
応募資格;大学生及び大学院生(短大、高等学校専攻科を含む)
募集人数;宿泊参加24名、通い参加約6名
*各講義の聴講生はお問い合わせください。
応募締切;2010年2月26日(金)
参加費;約23,000円(4泊宿泊、交流会など)、通い参加者は約10,000円
*講義内容と講師などの詳細と参加申込みは、海洋研究開発機構のホームページを
ご覧下さい。 http://www.jamstec.go.jp
問合せ先 海洋研究開発機構 海洋と地球の学校 学長 藤岡換太郎
事務局 田中惠子・萱場うい子TEL:045-778-5446
事務長 設楽文朗 TEL:046-867-9062
事務局E-mail:admin-kcg@jamstec.go.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】地質学会ニュース誌 “百名山の地質(仮題)”執筆者募集
──────────────────────────────────
今春から地質学会ニュース誌で,“百名山の地質(仮題)”の企画をはじめたい
と思います.内容は,地質全般の解説以外に,たとえば登山ルート上の見所や地
学教育や歴史解説地学教育などをもりこんで一般向けでも読める原稿(写真込み
でニュース誌1〜2p)の執筆者を募集します.執筆していただける方は,下記にご
連絡お願いします.
広報委員会 大友幸子(山形大学): yukiko@kescriv.kj.yamagata-u.ac.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】会員特別割引販売のご案内:地学読本
──────────────────────────────────
『地学は何ができるか─宇宙と地球のミラクル物語─』
日本地質学会 監修 地学読本刊行小委員会 編集
A5判,総376頁(本文368頁,カラー口絵 8頁)2009年12月25日刊行
本体価格:2,800円(税別)→ 割引価格:2,400円(税・送料込み)
次代を担う若者たちの多くが,「このままでは地球は壊れる」という誤った悲
観論に囚われて未来への夢を失っている.現状を打破するには,宇宙・地球・生
き物・人間・社会そして未来,を総合的に考える「地学教育」の振興が不可欠で
ある.
大学や高校で地学教育に携わる人々と現代文明の行く末を危惧する人々を念頭
において編まれた本書は,明るい未来を切り拓くための強力な知的武器となろう.
(地学読本刊行小委員会)
割引申込書(PDF)はこちら、、、
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
(会員番号・パスワードに寄るログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報
──────────────────────────────────
■平成22年度三内丸山遺跡特別研究募集(締切:2/26)
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】地質マンガ 「スケールプロトラクター」
──────────────────────────────────
「スケールプロトラクター」作:川村喜一郎 画:Key
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/faq/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
オマーンジオサイトツアー報告
オマーンジオサイトツアー報告
宮下純夫(新潟大学)
新年も明けてまもない1月7日(木),オマーンオフィオライトのワジ・ジジ地域におけるジオサイトツアーが,在オマーン日本大使館とオマーン・日本友好協会の主催の下に開催された.このツアーには,森元大使を初めとした大使館員とその家族や在留日本人に加えて,オマーン人も10名ほどが参加した,案内者は現地で地質調査を行っていた新潟大学の宮下研究室のメンバー10名があたり,総勢で50名以上,マイクロバスを含めて車13台を連ねた壮観な見学会となった(写真1).
写真1.シート状岩脈群の前での記念集合写真
このジオサイトツアーは,一年前の現地での調査の折りに宮下が日本大使館を訪問して森元大使とオマーンの地質資源・景観の素晴らしさやジオパークに関する話をしたところ,大使が深く興味を示され,オマーンの人々との交流推進も合わせて,大使館としてジオサイトツアーを企画することとなったものである.ツアーの数日前には現地の英語新聞にも予告が掲載された.
今回のツアーでは,マイクロバスや乗用車も参加するとのことで,舗装道路すぐ近くのサイトを中心に4ヶ所を回った.参加者は早朝に首都マスカットを出発し,集合地のソハール近郊のホテル前に到着したのは午前10時すぎであった.
第1見学地点としては「枕状溶岩の巨大露頭:一億年前の深海底に噴出したマグマの化石」と題して,地質学雑誌の表紙を飾ったこともある海洋地殻上部の溶岩層の大露頭に案内した.この露頭はジオタイムズに掲載された事から有名となってジオタイムズユニットと呼ばれるようになったいわく付きの露頭で,「ここを訪問する地質研究者は一億年前に海底に流出したとはとても思えないほど生々しい枕状溶岩層の美しさにため息をつく!」と案内書に記したのだが,地質とは全く縁のない大使館員や商社の方々にとっても,この露頭の生々しさは驚きであったようである.枕状構造の垂れ下がりや溶岩の流走方向の判定などにかんしても解説し,こうした露頭から読み取れるマグマの流動の様子などをイメージしてもらった.
第2見学地点は第1地点から1 kmほど離れた場所に露出している,溶岩層のマグマを供給した通路の化石ともいえるシート状岩脈群で,海洋底拡大説と大陸移動説とが合わさってプレートテクトニクスが提唱され,地球科学界が騒然たる状況となったときに,海洋底拡大の証拠を示している現場として世界中の地質科学界から注目を集めた場であることを解説した.ここでは,地殻が引っ張られて海嶺軸と平行に割れ目が周期的に形成され,板状の岩脈が形成され続けて100%岩脈群となったことや,マグマが冷却・固結するときの様子を観察した.この観察地点では,橋の下の日陰で主催者の準備した軽食や飲み物などをとり,日本人参加者同士やオマーン人との交流も行われた.
写真2.マントルかんらん岩と地殻下部(層状斑れい岩)の境界部,モホ不連続面の遠景.右側の斜面上方には層状斑れい岩が,その下側にはマントルハルツバージャイトが露出している.手前側にはオフィオライトの下盤側のハワシナ層もここでは見られる.
第3見学地点は地殻—マントルの境界であるモホ不連続面と,衝上したオフィオライトの前面にあった著しく褶曲したチャート層からなるハワシナ層の遠望を観察した.オマーンの普通の集落のすぐ裏山に,我々の足下に存在している地球の成層構造の第一級の不連続面の実体が露に見れること,そして,海洋底の深部にあったモホ不連続面が出現するまでの地球のダイナミックな運動に思いを馳せてもらった(写真2).
第4見学地点は,オマーンの考古学にとっても重要な遺跡であるラセイル鉱山を訪れた.古代メソポタミアの碑文に,「マガンという地に産出する銅・・・」という一文があり,そのマガンとは現在のオマーンのラセイル鉱山付近と見られている.ここでは古代の採掘時に用いられていた坑道の入り口が記念にアーチ状に残されており,その周辺には古代の精練による鉱滓が散在している(写真3).ここでは,1990年代に銅の採掘が大規模に行われたことによって形成された巨大な陥没穴や,激しい熱水循環によって毒々しい赤や黄色などに変色した変質帯(ゴッサン)を見学した,参加者は古代文明までさかのぼるオマーンの歴史に思いを馳せたことであろう.なお,このラセイル鉱山の近くにある同様な鉱山からは世界で初めてチューブワームの化石が報告されている.
写真3.ラセイル鉱山の西暦前2000年頃の採掘時の坑道入り口を残したアーチ
ツアーは午後2時半に終了したが,多くの参加者からは,オマーンの各地を旅行する際の目が大きく変化したことや,壮大な露頭に秘められている過去の変動を感じとれたなどの感想が寄せられていた.このツアーの様子はオマーンの英語新聞Oman Tribuneにも写真付きで紹介された.また,オマーン人への説明を買って出てくれたのは,オマーン商工省鉱物局のDurair博士である.
最後にオマーンという国について少し紹介しょう.オマーンが近代国家として歩み始めたのは1970年に現在の国王が即位してそれまでの鎖国を解いてからで,それまでは未開の地であった.例えば,その当時オマーン全土に学校は3つしかなく,満足な道路やテレビ放送なども全くなかった.いわば,中世から脱却して以来まだ40年しか経ていない.国土面積は日本よりも少し小さいが,そこに外国人労働者も含めて230万人程度の人口しかいない.国土の大半が砂漠や岩砂漠であり,荒涼とした風景はまさにアラビア半島の厳しい自然環境を表しているが,世界遺産となっているファラージシステム(灌漑システム)がワジ(枯れ川)にそって張りめぐされている.興味深いことに,マントルと地殻の境界部付近には泉が湧出していることが多く,緑豊かなオアシスとなっており,その付近には集落も多い.首都マスカットや北部の拠点都市であるソハールは,近代的な向上やビル,新しい高速道路や空港の建設など,劇的な変貌が現在も進行している.オマーンには石油の産出量はそれほど多くはないが,脱石油を掲げて様々な産業振興や観光産業の育成に努めている.高級ホテルの建設ラッシュも続いており,アラビア半島の情緒を味わえる中近東ではもっとも安全な地として欧米人を中心とした旅行者に人気を集めている.
今回のジオサイトツアーはオフィオライトを中心に行なったが,近隣の山岳地帯にはオフィオライトの下盤に露出するプレカンブリアンの地層や,その上を不整合に覆う二畳紀から白亜紀の陸棚堆積層,高圧変成帯などが壮大に全面露出している.地質学徒にとって素晴らしい研究・巡検地場であるばかりでなく,一般旅行客にとっても地球の魅力的な場所となる可能性を秘めている.
本ジオサイトツアーの報告は下記の在オマーン日本大使館のホームページにも掲載されている.
http://www.oman.emb-japan.go.jp/japanese/20100107geoparktour_j.htm
大使短信: http://www.oman.emb-japan.go.jp/japanese/5-003-013_j.htm
地質マンガ 選挙管理委員会
地質マンガ
戻る|次へ
選挙舞台裏,すべて見せます!—選挙管理委員が見た代議員選挙—
川村喜一郎(財団法人深田地質研究所)・中島礼(産総研)・川上俊介(アースアプレイザル)・太田亨(早稲田大学)・松田達生(防災科研)(選挙管理委員長)
いきなり問題です.下の写真はなんでしょう? こたえは,投票用紙の入っていた封筒を開封したときの切りくずです.1月16日(土)は,代議員選挙の開票日でした. 今回は,この開票作業や私たち選挙管理委員の活動について紹介して,選挙の裏側,選挙の意外な素顔を,全部,お見せしちゃいます. 大晦日の紅白歌合戦の舞台裏を見せる企画として,紅白の裏側全部見せます! なんていう特番が組まれて,あんなスターの思いがけない素顔が見られますよね.この記事を読めば,あなたも選挙の素顔がわかりますよ.
封筒の切りくず.
私たち選挙管理委員の活動は,6月から始まりました.6月下旬に第一回目の選挙管理委員会が行われ,そのときに,委員長として松田さんが選出され,選挙告示の文章が作られました.その後,9月10日に選挙告示,10月から11月に立候補届が受け付けられました.11月上旬に第二回目の会議がありました.そこでは,立候補者の確認,投票用紙のチェックが行われました.
11月下旬には,みなさんのところに,投票用紙が送られましたよね.その後,1月9日まで投票期間.その間,年末にかけて,川上さんが投票数を頻繁にチェックして,本日,1月16日,めでたく開票日となりました.
開票日には,立会人として,佐野貴司さん(科博)と竹内圭史さん(産総研)がお忙しい中,開票時間の朝の9:00から夕方の16:00くらいまで,同席されました.
みなさんの一票一票の選挙結果が近日中に,公示されます.要チェック!(掲載と後先になり申し訳ありません.選挙結果は会員ページに公示してあります.ログインしてみてください:編集部)
開封作業中の中島さん.封筒を開封する前にとんとんして,投票用紙を封筒の下に落としてから開封します.そうしないと,投票用紙も一緒に切ってしまうことがあるからです.
開封が終わった封筒と立会人の竹内さん
これだけの封筒が開封されました.みなさんの投票は,一票ですが,これだけそろうとすごいですね.
投票用紙を仕分けしています.一枚一枚は,みなさんの一人一人の投票です.左奥には立会人の佐野さんがいます.
最後に投票用紙をバーコード読み取り機に入れます.重要な作業は,委員長の松田さんのお仕事.奥には学会事務局の堀内さんがいます.読み取り機は,事務局の方々の多大なるお手伝いがないと動かせません.
バーコード読み取りが終わって,出てきた数字を集計しています.右奥から二番目の太田さんが数字を読んで,それを松田さんがチェックしています.選挙管理委員に必要なのは,数を正確に記録する,ことです.簡単に思えますが,結構緊張しますよ.
バーコード読み取り機が無効票とした投票用紙を再度,チェックします.不安そうに見つめる事務局の細川さん..
開票作業が終わって,一安心.みんなで撮影.選挙に関わる仕事は,地味ですが,学会活動の裏側がわかって,勉強になりますよ.委員会活動の中では,比較的負担の少ないものだと思いますので,学会活動には興味があるけれど,忙しい,という方は,是非! さらに,委員会活動を通じて,みんな仲良くなれます.楽しい仲間ができますよ.
委員会前のイメージ
活動後のイメージ
No.090 2010/02/02 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.090 2010/ 2/2 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2010年富山大会:シンポジウム・トピックセッション募集のお知らせ
【2】報告:シンポジウム「人類の時代・第四紀は残った」
【3】一般社団法人日本地質学会2010年度監事立候補受付中
【4】コラム:オマーンジオサイトツアー報告
【5】支部情報いろいろ
【6】宮崎県総合博物館より情報提供のお願い
【7】その他のご案内
【8】公募情報いろいろ
【9】J-STAGEサービス一時停止のお知らせ
【10】地質マンガ「選挙管理委員会」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2010年富山大会:シンポジウム・トピックセッション募集のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地質学会は,中部支部の支援のもと,富山大学(五福キャンパス)において
第117年学術大会(2010年富山大会)を2010年9月18日(土)〜20日(月)の日程
で開催致します.
つきましては,トピックセッションとシンポジウムの募集を行います.
トピックセッションは,学会内の領域をカバーしこれから新分野になりそうなト
ピック的な内容で,定番セッションと同様な形式(15分間の口頭発表あるいはポ
スター発表)の発表となります.シンポジウムは,多数の学会員が関心を持つ(
あるいは持ちそうな)内容・学会外と関係した新分野の内容など,地質学会とし
て重要視すべき研究内容を取り上げます.招待講演の取り扱いは,例年通りです.
募集締切:2010年3月15日(月)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/science/content0043.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】「人類の時代・第四紀は残った」の報告
──────────────────────────────────
公開シンポジウム「人類の時代・第四紀は残った」が1月22日に日本学術会
議講堂にて開催されました.150名を超える参加者が集まり,国内外の時代
区分の問題が討議され,その一部は新聞等にも報道されました.とりわけ第
四紀に関する簡単なQ&Aを準備いたしましたので,ご活用ください.時代
区分の問題は重要ですので,より詳細な資料を準備しております.準備が整
い次第,geo-FLash・ニュース誌にてお知らせいたします.
第四紀Q&Aはこちら
http://www.geosociety.jp/faq/content0203.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】一般社団法人日本地質学会2010年度監事立候補受付中
──────────────────────────────────
監事立候補締切:2月12日(金)(必着)
(*選挙人は今回の選挙で当選した代議員,被選挙人は会員および非会員)
立候補届の書式等詳細は,下記をご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
(会員番号・パスワードによるログインが必要です)
*2010年度代議員選挙の結果報告は、
http://www.geosociety.jp/members/content0048.html
(会員番号・パスワードによるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】コラム:オマーンジオサイトツアー報告
──────────────────────────────────
宮下純夫(新潟大学)
新年も明けてまもない1月7日(木),オマーンオフィオライトのワジ・ジジ地域
におけるジオサイトツアーが,在オマーン日本大使館とオマーン・日本友好協会
の主催の下に開催された.このツアーには,森元大使を初めとした大使館員とそ
の家族や在留日本人に加えて,オマーン人も10名ほどが参加した,案内者は現地
で地質調査を行っていた新潟大学の宮下研究室のメンバー10名があたり,総勢で5
0名以上,マイクロバスを含めて車13台を連ねた壮観な見学会となった.
続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0056.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報いろいろ
──────────────────────────────────
■西日本支部支部
第158回西日本支部例会および2009年度支部総会
2010年2月13日(土)
会場:福岡大学18号館1824教室
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
■北海道支部
支部総会・個人講演会
2010年3月20日(土)13:30-17:30
場所:北海道大学理学部6号館 6-204-02教室
申込締切:2月12日(金)
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
■関東支部
・地質技術伝承講演会:地質技師長が語る地質工学余話(第1回)
日時:2010年4月18日(日)13:30〜16:00
場所:北とぴあ(東京都北区王子1-11-1)7階第1研修室
講師:千葉達郎氏 (アジア航測株式会社)
テーマ:赤色立体地図による新しい地質調査技術
・2010年度関東支部総会
日時:2010年4月18日(日)16:00〜16:30
場所:北とぴあ(東京都北区王子1-11-1)7階第1研修室
詳しくは、 http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】宮崎県総合博物館より情報提供のお願い
──────────────────────────────────
宮崎県総合博物館では,県内の地質情報の集約に努めておりますが,思うに任せ
ない状況です.
近年,新たに決められた新第三紀-第四紀境界の存在が宮崎層群内に想定され,そ
の調査のためなどに県外の研究者のみなさんが調査に来られているとの話も耳に
するようになってきました.
当方としては,宮崎県下の地質情報を集約し,博物館活動に活用したいと考えて
おります.このため宮崎県内を調査されるみなさんとはぜひコミュニケーション
を図りたいと思っております.
また,当方で知っている情報で参考にしていただけることがあるかもしれません.
来県の際は,ぜひお気軽に御来館下さい.どうぞよろしくお願いいたします.
連絡先 宮崎県総合博物館 学芸課地質担当 赤崎・松田
〒880-0053 宮崎市神宮2-4-4 電話:0985-24-2071 FAX:0985-24-2199
e-mail:akazaki-hiroshi@pref.miyazaki.lg.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のご案内
──────────────────────────────────
■平成21年度海洋情報部研究成果発表会
日時:平成22年2月16日(火)13:30〜17:45
場所:海上保安庁海洋情報部7階大会議室(東京都中央区築地5-3-1)
入場無料.事前予約不要.
詳しくは、http://www1.kaiho.mlit.go.jp/
■平成21年度海洋研究開発機構研究報告会:JAMSTEC2010
ー地球システムの解明に果たすJAMSTECの役割ー
日時:平成22年2月24日(水)13:00〜17:30
場所:東京国際フォーラム ホールB5
詳しくは、http://w3.jamstec.go.jp/j/index.html
■日本堆積学会2010年茨城大会
日程:2010年3月26日(金)〜29日(月)
会場:茨城大学水戸キャンパス茨苑会館
個人講演募集
申込締切:2月12日(金)/要旨締切:2月19日(金)17:00
詳しくは,http://sediment.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報いろいろ
──────────────────────────────────
■鳥取県教育委員会職員募集:学芸員(地学担当)
募集締切:2010年2月22日(月)
詳しくは、http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=123953
■(財)電力中央研究所研究職員(常勤)募集<随時受付中>
募集研究分野:火山活動評価技術(火山学)
http://criepi.denken.or.jp/jp/recruit/11/saiyo/kadai.html
■2010年度地球化学研究協会学術賞「三宅賞」および「奨励賞」候補者募集
締切日:2010年8月31日(火)
詳しくは、http://wwwsoc.nii.ac.jp/gra/
その他の公募情報はこちら、、、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】J-STAGEサービス一時停止のお知らせ
──────────────────────────────────
定期メンテナンスのため次の期間サービスがご利用頂けません。ご迷惑をおかけ
致しますが、ご了承下さい。 2010年2月20日(土) 10:00 〜2月22日(月) 02:00
[対象] 地質学雑誌;投稿・査読システム
地質学雑誌:閲覧 等々
ご不明な点などがありましたら、下記までお問い合わせください。
独立行政法人 科学技術振興機構 研究基盤情報部 電子ジャーナル課
e-mail:contact@jstage.jst.go.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】地質マンガ「選挙管理委員会」
──────────────────────────────────
地質マンガ「選挙管理委員会」
作:川村喜一郎 画:Key
http://www.geosociety.jp/faq/content0205.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
宮澤賢治の知的背景を示す地質学史資料
宮澤賢治の知的背景を示す地質学史資料
金 光男・山田直利・鈴木尉元・加藤碵一・盛岡科学史資料調査団
第1図.岩手大学図書館の所蔵する古図幅類
2009年10月「予察地質図」ほかの図幅類と多くの貴重な古書籍群が,国立大学法人岩手大学に所蔵されることが明らかとなった.それらの発見に至るまでの経緯と意義について簡単に報告する.
宮澤賢治の作品中にあらわれるハイレベルな地質学的・鉱物学的知識体系が盛岡高等農林学校時代に構築されたことはほぼ確実であろうと誰もが考えることであるが,他方においてその根拠をわれわれは示せずにいた.このたび,盛岡高等農林学校の後身である岩手大学の書庫内から,貴重な科学史資料が再発見されるに至った.そしてそれらは賢治の知的背景を裏付けるものばかりだったのである.
予察地質図については極めて重要な最近の発見があった.故 今井 功本会名誉会員は,1998年の秋,それまで誰も見たことのなかった「予察地質図東北部(英文版)」が岩手県の釜石鉱山に保管されていることを知り,その特徴と意義について詳報した(今井, 1999a,b,c).
今井 功博士は日本地質調査所(現 産総研地質調査総合センター)の地質部に永年在籍し,“地質調査所が発行したすべての縮尺の地質図の作成者として名を連ねた唯一の図幅調査者”として知られる(金2007).その今井が岩手大学に出向した後,そのまま盛岡に居住したことにより,初めて「予察地質図東北部(英文版)」が発見されるに至った.「予察地質図東北部(英文版)」は100年ものあいだその姿を隠し,自らの真の価値を理解する人の訪れを心待ちにしていたのであろう.
予察地質図については山田(2008,2009,2010)が詳しい.山田(2008)によれば,『…予察地質図は発行元の産総研地質調査情報センター地質資料管理室にも全部は揃っていない…今井は「予察東北部地質図」が岩手県釜石鉱山に所蔵されていることを知ってそれを実見し,ナウマンが「日本全土の地質図の一部であることを意識して,地質時代と岩質による客観的な区分をした」と述べている…20万分の1地質図幅作成に先行して進められた予察地質図の作成は,日本列島主要部の地質を縮尺40万分の1の地図5葉に分割,図示しようとするものであり,その第1号「東北部」がナウマン自身の調査旅行に基づいて作られたことは特筆すべきことである…本図によって,東北地方の東半部(北上山地)が中・古生界および深成岩類から,西半部(奥羽山脈・出羽丘陵)が第三系および火山岩類からなるという基本的な帯状構造が明らかにされた…のちに「東北弧」が非火山性外弧と火山性内弧からなる典型的な島弧として認識される予兆は,本図の中にあった…』と概説される.
明治年間,しばしば発生した凶作によって東北の農村が著しく荒廃し,その克服が大きな社会問題となっていた頃,明治政府が冷害に打ち克つ新たな農業の基礎をつくり地域の農業指導者を育成することによって東北の農業を振興させることが広い意味での日本農業の底辺拡大につながる道であると考え,1902(明治35)年日本最初の農業専門学校すなわち官立盛岡高等農林学校が創設された.これが岩手大学の前身のひとつとなる.
その盛岡高等農林学校に宮澤賢治(1896-1933)が入学し,東京帝国大学農科大学を卒業した 関 豊太郎教授(1868-1955)から地質学・鉱物学・土壌学などの指導を受けたことは良く知られる史実である.地学者としての賢治についての論考はこれまで少なからず発表されてきた.最近,加藤碵一会員(産総研)が『宮澤賢治の地的世界』(2006)を上梓し,賢治の作品中にあらわれる鉱物(学)・地質(学)に関する記述について,当時の日本地質学界の情況を明らかにすることによって賢治の時代における鉱物学・地質学知識に基づいて再検討するという新たな手法により,賢治作品を正しく解釈しようとした.
第2図.岩手大学図書館の所蔵する古書籍群(一部)
これまでの,主に文学者たちによる賢治研究には,地学や外国語についての基本的な知識がないままになされたため数多くの誤りが内在していた.例えば,賢治が作品中においてカタカナ表記した鉱物や物質が一体何であったのか? それを正確に確認しないまま彼らは賢治の作品についてしばしば誤った評価を下した.科学知識の欠如による弊害ともいえるだろう.それは学問的に間違っているとされる以前に,賢治の多用した地学的・物質的隠喩を吟味する上でも重大な障害として残された.加藤会員はその障害を取り除くべく,地質学者として賢治作品に肉薄したのである(金,2010; Kato, 2010).
『宮澤賢治の地的世界』を上梓した頃,加藤会員は岩手大学の農業教育資料館(重要文化財 盛岡高等農林学校本館)を訪れた.賢治が直接採集したとされる岩石標本を見学し,その発見者である溝田智俊岩手大学農学部教授に会うためだった.その折,当時の農業教育資料館 若尾紀夫館長から,賢治らが学んだ岩石鉱物標本類が未整理状態になっているが人手も専門知識もないまま放置されていると聞かされ,後日改めて産総研地質標本館 青木正博館長(当時)らと再訪し,標本のクリーニングと整理にあたった.そこにはかつて賢治が在籍した(旧農学部農学科)土壌学教室を1970〜1980年代において主導した故井上克弘教授の夫人が勤務していて,夫人は加藤に盛岡高等農林学校時代に所蔵され,現在は岩手大学情報メディアセンター図書館(以下,岩手大学図書館とする)に移管された古い蔵書目録を示した.加藤はその中に「予察地質図」や貴重古書籍が含まれることを見出し,さっそく2009年6月に開催された地質学史懇話会の2009年例会において,山田直利会員が「予察地質図 (1886-1895)を読む−ナウマンから原田・巨智部へ−」と題して講演した際,討論の場において報告した.
2009年10月14日,地質学史懇話会より鈴木尉元本会名誉会員,山田直利本会名誉会員,加藤碵一本会会員,日本地質学会地質学史アーカイブス委員会より金 光男,さらに岩手県立博物館より大石雅之学芸第一課長,吉田裕生学芸第二課長の6名が盛岡駅に集合して「盛岡科学史合同調査団」を組織し,岩手大学図書館へと向かった.調査団には現地において同大農学部土壌学教室溝田智俊教授のほか,農業教育資料館より亀井 茂,さらに同大教育学部地学教室土谷信高会員が合流した.
調査団は,多くの図幅類と古書籍類を実見した.現在それは研究の途上にあるが,図幅類30葉以上(第1図),和書80冊以上(第2図右),洋書110冊以上(第2図左)の存在がこれまでに確認されている.古書籍には原田豊吉の“Die Japanischen Inseln”(1890 明治23年刊)をはじめとする,明治期〜大正期の地質学〜地球科学に関する貴重書籍が含まれる.
第3図.「予察地質図」を精査する 山田直利 加藤碵一 土谷信高会員
岩手大学に保存されていた「予察地質図」は3葉(東北部,東部,中部)で,同図の改訂版は7葉に及んだ(第3図). いっぽう,古書籍には稀少本が多数含まれ,「玉利」の印の押されるものがある.これは 玉利喜造(1856−1931)初代校長の蔵書印に他ならない.盛岡高等農林学校の開校当時,土壌学教室を主導した関 豊太郎教授は,自らがドイツ留学時代に購入したクランツ社製鉱物標本や専門書,さらに偏光顕微鏡などを学校に寄贈して学生の指導にあたったとされる.岩手大学図書館に保管される古書をみる限り,関教授とともに玉利校長が当時貴重とされた内外の専門書を,多数,学校に寄贈したことが推定されよう.宮澤賢治に代表される当時の学生たちは,玉利と関の献身に強い感銘を受け,猛勉強を展開したとされる.
盛岡は震災や戦争による空襲を被験しなかった幸運に恵まれ,これらの貴重史料はほとんど痛むことなく長期間保存された.東京にあった地質調査所や東京大学などは,いずれの災難をも被むり,貴重資料を次々と失った苦い歴史を有する.かつてこの世から失われたのではないかと考えられていた「予察地質図東北部(英文版)」は今井 功の手により,1998年,岩手の地で奇跡的に発見された.そしてこのたびの,岩手大学科学史資料の出現である.調査団のメンバーたちは,このような貴重史料が『古い学校があって,空襲と震災を履歴していない土地』,たとえば大学や旧制高校・高等専門学校のあった,松本・金沢・新潟・山形・秋田・弘前・札幌などに代表されるような,地方の拠点都市などに,人知れず所蔵されているのではないかと想像している.
これら科学史資料は,今後,岩手を代表する素晴らしい社会遺産となるであろう.そして今後の宮澤賢治研究に多大な影響を与える貴重資料となるであろう.「盛岡科学史資料」についての詳細は,Kato(2010)および金(2010)を参照されたい.
【文献】
今井 功(1999a)ナウマンの足跡 最古の東北地方地質図.河北新報,1999年3月13日〔(1)地質学的貢献〕,同14日〔(2)予察地質図(上)〕,同17日〔(3)予察地質図(下)〕,同18日〔(4)釜石鉱山〕.
今井 功(1999b)日本最古の東北地方地質図.地質学史懇話会会報.no.12,13.
今井 功(1999c)ナウマンの東北地方地質図〔1/40万予察地質図「東北部」(1886)〕.地質学史懇話会会報.no.13,11-14.
加藤碵一(2006)宮澤賢治の地的世界.愛智出版.142p.
Kato, H.(2010) Kenji MIYAZAWA –A fusion of Literature and geology. JAHIGEO Newsletter, no.12, 2-7.
金 光男(2007)名著『黎明期の日本地質学』(ラティス,1966).地質学史懇話会会報.no.29,11-13.
金 光男(2010)2009年10月 盛岡科学史資料調査(予報).地質学史懇話会会報.no.34, 32-39.
山田直利(2008)ナウマンの「予察東北部地質図」—予察地質図シリーズの紹介 その1—.地質ニュース,no.652,31-40.
山田直利(2009)原田豊吉編「予察東部地質図」—予察地質図シリーズの紹介 その2—.地質ニュース,no.660,32-47.
山田直利(2010)原田豊吉編「予察中部地質図」—予察地質図シリーズの紹介 その3—.地質ニュース,no.668,15-28.
No.091 2010/02/16 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.091 2010/ 2/16 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】コラム:ニュージーランドのウェリントン断層
【2】2010年富山大会:シンポジウム・トピックセッション募集中 ぜひ!
【3】支部情報いろいろ
【4】その他のご案内
【5】公募情報いろいろ
【6】J-STAGEサービス一時停止のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】コラム:ニュージーランドのウェリントン断層
──────────────────────────────────
ウェリントン市は,ニュージーランドの首都で,北島の南端に位置しており,アルパイン
断層は市のすぐ北の海底を通っています.去年,2009年7月1日のニュージーラン
ドのMw = 7.8の地震は,アルパイン断層の南西の南島の南端のFiordlandで発生
しています....
川村喜一郎(深田地質研究所)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/faq/content0249.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2010年富山大会:シンポジウム・トピックセッション募集中 ぜひ!
──────────────────────────────────
日本地質学会は,中部支部の支援のもと,富山大学(五福キャンパス)において
第117年学術大会(2010年富山大会)を2010年9月18日(土)〜20日(月)に開催
いたします。
魅力あるシンポジウムとセッションが盛会の鍵です。とっておきの提案をお待ち
しています。
募集締切:2010年3月15日(月)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/science/content0043.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】支部情報いろいろ
──────────────────────────────────
■北海道支部
支部総会・個人講演会
2010年3月20日(土)13:30-17:30
場所:北海道大学理学部6号館 6-204-02教室
個人講演会プログラム等詳しくは、
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
■関東支部
・ジオパークを目指して!秩父ジオサイトバスツアー
日時:3月6日(土)9:00-16:00 集合:西武秩父線西武秩父駅前
申込締切:2月24日(水)
・地質技術伝承講演会:地質技師長が語る地質工学余話(第1回)
日時:2010年4月18日(日)13:30〜16:00
場所:北とぴあ(東京都北区王子1-11-1)7階第1研修室
講師:千葉達郎氏 (アジア航測株式会社)
テーマ:赤色立体地図による新しい地質調査技術
・2010年度関東支部総会
日時:2010年4月18日(日)16:00〜16:30
場所:北とぴあ(東京都北区王子1-11-1)7階第1研修室
詳しくは、 http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】その他のご案内
──────────────────────────────────
■平成21年度京都大学防災研究所研究発表講演会
日時:平成22年2月23日(火)・24日(水)
場所:京都大学宇治キャンパス(京都府宇治市五ヶ庄)
詳しくは、http://www.dpri.kyoto-u.ac.jp
■海洋研究開発機構・Blue Earth’10
日時:平成22年3月2日(火)〜3日(水)9:30〜18:00
場所:東京海洋大学品川キャンパス
入場料:無料(事前登録不要)
詳しくは,
http://www.jamstec.go.jp/jamstec-j/maritec/rvod/blue_earth/2010/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】公募情報いろいろ
──────────────────────────────────
■平成22年度高知大学海洋コア総合研究センター全国共同利用研究公募要領
申請書の締切:
[前期/前期及び後期]平成22年2月28日(日)
[後期]平成22年8月31日(火)
詳しくはこちら、、、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】J-STAGEサービス一時停止のお知らせ
──────────────────────────────────
定期メンテナンスのため次の期間サービスがご利用頂けません。ご迷惑をおかけ
致しますが、ご了承下さい。
[期間] 2010年2月20日(土) 10:00 〜2月22日(月) 02:00
[対象] 地質学雑誌;投稿・査読システム
地質学雑誌:閲覧 等々
ご不明な点などがありましたら、下記までお問い合わせください。
独立行政法人 科学技術振興機構 研究基盤情報部 電子ジャーナル課
e-mail:contact@jstage.jst.go.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質マンガ 卒論練習
地質マンガ
戻る|次へ
No.092 2010/03/02 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.092 2010/ 3/2 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】チリ地震津波とチリのテクトニクス
【2】理事選挙および監事選挙結果
【3】2010年富山大会:シンポジウム・トピックセッション募集中 ぜひ!
【4】第1回惑星地球フォトコンテスト審査結果
【5】2010年度学部学生割引・院生割引会費受付:まもなく終了です
【6】紹介:「日本列島 動く大地の物語」(NHK総合:1982-1983年)
【7】支部情報
【8】その他のご案内
【9】地質マンガ「卒論練習」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】チリ地震津波とチリのテクトニクス
──────────────────────────────────
「海水がふくれ上がって、のっこのっことやって来た」 三陸沿岸で夜明けの
海を見つめていたある漁師は、吉村昭の取材に対してこんな言葉で1960年チ
リ地震津波の襲来を伝えたという。これほどドラマティックではなかったにせ
よ、2010年2月28日に我々が見た光景も、まさにこのようなものであった。
安間 了(筑波大学生命環境科学研究科)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/hazard/content0038.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】理事選挙および監事選挙結果
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会選挙規則ならびに選挙細則に基づき,理事選挙および
監事選挙を実施いたしましたので,下記のとおりにご報告いたします.
一般社団法人日本地質学会
選挙管理委員会 委員長 松田達生
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
(会員番号・パスワードによるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2010年富山大会:シンポジウム・トピックセッション募集中 ぜひ!
──────────────────────────────────
日本地質学会は,中部支部の支援のもと,富山大学(五福キャンパス)において
第117年学術大会(2010年富山大会)を2010年9月18日(土)〜20日(月)に開催
いたします。
魅力あるシンポジウムとセッションが盛会の鍵です。とっておきの提案をお待ち
しています。
募集締切:2010年3月15日(月)
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/science/content0043.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第1回惑星地球フォトコンテスト審査結果
──────────────────────────────────
この度は、第1回惑星地球フォトコンテストに多数ご応募いただき、誠にありがと
うございました。厳正なる審査を行い、応募作品全436作品のうち,14の入賞作品
が決定いたしました.
詳しくは、コチラ
http://photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2010年度学部学生割引・院生割引会費受付まもなく終了
──────────────────────────────────
◯学部学生も院生同様に割引申請が必要になります
◯毎年更新となりますので,次年度会費について該当する方は,必ず申請してく
ださい.申請が無い場合は、通常正会員の会費額のご請求となります。
最終締切: 2010年3月31日(水)
書式等詳しくは、、、
http://www.geosociety.jp/outline/content0052.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】紹介:「日本列島 動く大地の物語」(NHK総合:1982-1983年)
──────────────────────────────────
NHK総合テレビ1982〜1983年放送
こ れはNHK総合テレビで1982年(続編は1983年)に放送された30分番組計10回のシリーズである.1987年放送の「地球大紀行」よりも5年前 に,世界各地の取材映像も交えながら,日本列島の地質をプレートテクトニクスの観点からかなり詳しく紹介した科学番組である.放送から30年近く経過した 現在の時点で見ると,今は水戸黄門役も演じる司会の石坂浩二さん(そして全ての登場人物)が非常に若いのはさておいて,これは現在に続く日本地質学の方向 性が定まった最初の時点で制作された番組だと感じる.この番組には平 朝彦さんも登場するが,まだ「付加体」という語は使われていない.出てくる深海掘削 船は「グロマー・チャレンジャー」であり,「ちきゅう」はもちろん「ジョイデス・レゾリューション」も登場しない.その代わり,当時一世を風靡した「パシ フィカ大陸」や「テレーン説」が大きく扱われており,飛騨帯の片麻岩は先カンブリア代とされている.
現在,ちょうど日本地質学会編の「日本地方地 質誌」が出そろってきたところでもあり,そろそろ最近30年間の成果を組み込んで新たな日本の地質のシリーズ番組を作る時期に来ているように思う.私 は,1982〜1983年はフランスに留学していたために,この番組が放送されたことを全く知らなかった.たまたま,今年2月に金沢大学を訪問した際,同 大学の奥寺浩樹准教授(鉱物学)が学生時代に録画していたビデオを見せていただき,これは現時点で紹介する価値があると判断した.1980年頃は地質学会 の会員数が毎年増加を続けていて,特に1979〜1982年は学生会員の加入者数が多かった時期である.この時代の地質学界のハツラツとした雰囲気がこの番組 に登場する学生たち(今は教授クラス)の様子によく出ている.本学会の会員数は1994〜1999年頃をピークとしてその後は低落傾向にあるが,このよう な番組が新たに放送されれば,起死回生の妙薬になるかもしれない.以下に各回のタイトル,主な出演者(○,敬称略),キーワード(●)などを列挙する.
「日本列島 動く大地の物語」(NHK総合テレビ)1982年8月16〜20日放送
(1)フィリピン沖からきた島 伊豆半島 1982年8月16日
○奈須紀幸 石坂浩二 伊藤和明 R.ウォーレス,M.チャーキン 坂田俊文
●1974 年伊豆半島沖地震 国府津—松田断層 海嶺 アルビン号 メキシコ沖ブラックスモーカー 沈み込み帯 有珠山噴火 ニュージーランドのルアペフ火山 ワイ ラケイ地熱地帯 ホワイトアイランド火山 サンアンドレアス断層 伊豆半島衝突による本州中部の地質構造の屈曲
(2)流されてきた巨大海山 秋吉台 1982年8月17日
○奈須紀幸 石坂浩二 太田正道
●石灰岩 カルスト台地 秋芳洞 高知県鳥形山 サンゴ礁 ハワイ島 カウアイ島 ミッドウェー島 ニイハウ島 海上保安庁昭洋丸 音波探査
(3)陸にのしあげた深海底 四国 1982年8月18日
○奈須紀幸 石坂浩二 平朝彦 岡村真 D.ジョーンズ M.ソールズベリ 西脇親雄
●中央構造線 四万十帯 高知県五色ノ浜 放散虫化石 チャート 枕状溶岩 赤道付近から動いてきた深海底 グロマーチャレンジャー号 スクリップス海洋研究所
(4)衝突している島 北海道 琉球弧 1982年8月19日
○奈須紀幸 石坂浩二 小松正幸 宮下純夫 番場光隆 小山内康人 豊島剛志 大和田正明 小西健二 キャサリン・ミュージック
●日高山脈 静内川 グラニュライト ポロシリ岳 カール地形 かんらん岩 喜界島の隆起サンゴ礁段丘 大東島・奄美海台の沈み込み 海底ボーリング
(5)火山列島のゆくえ 環太平洋 1982年8月20日
○奈須紀幸 石坂浩二 伊藤和明 西脇親雄 T.マホン M.チャーキン D.ジョーンズ 上田誠也
●黒部峡谷 16億年前の岩石 アジア大陸の古い地盤 太平洋プレート フィリピン海プレート 海山 海洋底 「火の輪」と膨大な資源 ブーゲンビル銅鉱山 ニュージーランド・ワイラケイの地熱発電 アラスカの海底油田開発 日本列島は将来10倍の広さになる
「続 日本列島 動く大地の物語」 NHK総合テレビ 1983年8月22〜26日放送
(続1)海底火山がつくった大地・東北日本 1983年8月22日
○奈須紀幸 石坂浩二 熊倉一雄 天野一男 ポール・イムスランド 伊藤和明
●仙台 広瀬川 グリーンタフ 海底火山活動 ニュージーランド 沈み込みの変化 1500万年前の巨大割れ目噴火 同和鉱山小坂鉱業所 黒鉱 インジウム ガリウム 石油・天然ガス地帯
(続2)海にできた大平原・関東平野 1983年8月23日
○奈須紀幸 石坂浩二 熊倉一雄 伊藤和明 平山次郎 ユーリー・ブリーゲル
●関東大地震 野島崎の隆起 関東平野は3000mの深海底だった 三国山地・谷川岳の隆起 深海に大量の土砂が堆積 アルプス山脈 イタリア ロンバルジア平野 ヒマラヤは平野づくりに失敗
(続3)緑野をつくった巨大噴火・南九州 1983年8月24日
○荒牧重雄 町田洋 新井房夫 ザビエル・ル・ピション ジョージ・ウォーカー 宇井忠英 奈須紀幸 石坂浩二 熊倉一雄
●鹿児島の最大級の火山噴火 姶良カルデラ 鹿児島湾 桜島火山観測所 エーゲ海 サントリーニ島 巨大カルデラ 広域火山灰
(続4)大陸が裂けてできた海・日本海 1983年8月25日
○奈須紀幸 石坂浩二 熊倉一雄 西脇親雄 星野光雄 李大声 金玉準 イゴール・ルーペキン
●アジア大陸と陸続きの日本列島 大陸からの分裂 日本海の形成 エチオピア ケニア 東アフリカ・リフトバレー 大地溝帯 奥飛騨の7億年前の片麻岩 神岡鉱山 隠岐片麻岩 韓国の片麻岩
(続5)赤道上からきた巨大大陸・アジア,日本 1983年8月26日
○奈須紀幸 上田誠也 石坂浩二 熊倉一雄 濱田隆士 郭令智 平朝彦 坂田俊文 ジェームズ・モンガー
● メキシコ サンフランシスコ アラスカ 日本列島の地学的兄弟 チベット タクラマカン カナダのロッキー山脈 フズリナ テーチス型 岐阜県福地 貴州サンゴ 北米西岸のテレーン説 カシェクリーク パシフィカ 宮城県気仙沼 岩手県
(石渡 明)
*本番組は,現在のところ,NHK公開ライブラリーやオンデマンドサービスで視聴することはできません.
学会より視聴サービスの要望を出しておきました.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
■北海道支部
・支部総会・個人講演会
2010年3月20日(土)13:30-17:30
場所:北海道大学理学部6号館 6-204-02教室
個人講演会のプログラム等はこちら
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
■関東支部
・地質技術伝承講演会:地質技師長が語る地質工学余話(第1回)
日時:2010年4月18日(日)13:30〜16:00
場所:北とぴあ(東京都北区王子1-11-1)7階第1研修室
講師:千葉達朗氏 (アジア航測株式会社)
テーマ:赤色立体地図による新しい地質調査技術
・2010年度関東支部総会
日時:2010年4月18日(日)16:00〜16:30
場所:北とぴあ(東京都北区王子1-11-1)7階第1研修室
詳しくは、 http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のご案内
──────────────────────────────────
■公開シンポジウム「若手アカデミーとは何か」
日時:2010年3月4日(木)13:30〜
場所:大阪大学中之島センター佐治敬三メモリアルホール(10F)
主催:日本学術会議 若手アカデミー委員会
参加費無料、登録不要
詳細は http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf/90-s-1.pdf
■21世紀モホール計画:掘削候補地点絞り込みのための国際ワークショップ
日程:2010年6月3日〜5日
場所:石川県金沢市文化ホール
共催:金沢大学,日本地球掘削科学コンソーシアム,国際統合深海掘削計画,日
本海洋研究開発機構,インターリッジ
詳しくは、http://earth.s.kanazawa-u.ac.jp/~Mohole/
■シンポジウム「地殻流体活動としてみた松代群発地震」
日時:2010年3月25日(木)13:30-17:45
会場:産業技術総合研究所第7事業所別棟大会議室(7-3C211)
主催:文部科学省科学研究費補助金 新学術領域研究「地殻流体」
詳しくは、http://www.geofluids.titech.ac.jp/sub9.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】 地質マンガ 「卒論練習」
──────────────────────────────────
「卒論練習」 作:橋本義孝 画:Key
詳しくは、http://www.geosociety.jp/faq/content0209.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質マンガ 調査後のカニの味は
地質マンガ
戻る|次へ
【解説】
これは遠い昔話。
以来私は小さな醤油を持ち歩くことにしている。
お弁当につけるあの小さな1回使い捨て醤油。
それだけで世界の食はたちどころに日本食となる。
醤油は偉大だ!
木村 学(東京大学)
木村研究室ホームページはこちら
No.094 2010/03/16 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.094 2010/ 3/16 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】第四紀下限変更、そして第三紀は非公式用語に
【2】国際惑星地球年(IYPE)終了記念イベント
【3】韓日地質学会室戸合同大会開催のお知らせ
【4】2010年度学部学生割引・院生割引会費受付まもなく終了
【5】Island Arc vol.19 Issue1 発行
【6】その他のお知らせ
【7】3月の博物館特別展示・イベント情報
【8】公募情報
【9】地質マンガ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】第四紀下限変更、そして第三紀は非公式用語に
──────────────────────────────────
すでに,報道等でお聞き及びと思いますが,第四紀・第四系と更新世・更新統の
下限の定義が変更となりました.ここでは,本件に関する日本地質学会の対応を
報告します.
(日本地質学会拡大地層名委員会)
続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/name/content0057.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】国際惑星地球年(IYPE)終了記念イベント
──────────────────────────────────
「惑星地球フォルム2010 in アキバー君たちと考える環境・防災・資源ー」
(2010年3月27日(土)〜3月28日(日)富士ソフトアキバプラザ 6階)
に、こぞってご参加ください。
詳しくは、http://www.gsj.jp/iype/be/doc/BE100327A.html
■日本地質学会も特別協賛団体として協賛企画します。
3月27日(土) 15:00〜16:00
「早大高等学院の高校生, 四川大地震の記録映画製作者と一緒に語る『大地の変
動』」
(早稲田大学高等学院地学クラブの高校生が日頃の研究成果を発表し,日本地
質学会司会のもと,四川大地震の記録映画の製作者と一緒に,大地の変動につい
て討論します。)
3月28日(日)10:00-11:00
「第1回惑星地球フォトコンテスト表彰式」
(コンテスト入選作品は会場内に展示されます)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】韓日地質学会室戸合同大会開催のお知らせ
──────────────────────────────────
今年の夏(8月23日〜25日)構造地質部会が主体となり(主催は日本地質学会)韓
国地質学会のご協力も得て,下記の大会を開催いたします.
韓日地質学会室戸合同大会
日程:2010年8月23日〜25日
会場:国立室戸青少年自然の家
大会webサイト:http://struct.geosociety.jp/koreajapangs2010/
今後,詳細が決まり次第,上記のホームページを随時更新いたします.なお,ポ
スターはご自由にダウンロードして頂き,ご興味のありそうな方に配布して頂け
ますと幸いです.
ぜひ,多くの皆様に参加して頂ければと存じます.宜しくお願い申し上げます.
構造地質部会 庶務 松田達生
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2010年度学部学生割引・院生割引会費受付まもなく終了
──────────────────────────────────
◯学部学生も院生同様に割引申請が必要になります
◯毎年更新となりますので,次年度会費について該当する方は,必ず申請してく
ださい.申請が無い場合は、通常正会員の会費額のご請求となります。
最終締切: 2010年3月31日(水)
書式等詳しくは、、、
http://www.geosociety.jp/outline/content0052.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】Island Arc vol.19 Issue1 発行
──────────────────────────────────
Island Arc 最新刊が発行されました。
特集号:Thematic Section:Fluid-rock interaction in the bottom of the
inland seismogenic zone
Guest Editors : Masaru Terabayashi, et al
ほか
日本語要旨は学会ホームページからご覧いただけます。
http://www.geosociety.jp/publication/content0046.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■「2010年春季地質の調査研修」参加者募集のお知らせ
本研修は、(独)産業技術総合研究所(産総研)地質調査総合センター
(Geological Survey of Japan)認定の研修プログラムとして、資源系、土木・
建設 系、環境系を問わず、地質関連企業に勤務する主に若手技術者を対象にした
現場での 研修事業(4泊5日:月曜日〜金曜日)として、2007年以来実施していま
す。本研修参 加者には、地質調査総合センター長名の修了証書と、技術者専門継
続教育(CPD)40点 の加点ポイントを取得する資格が授与されます。
実施期間:2010年5月31日(月)〜6月4日(金)
主な研修場所:千葉県君津市とその周辺(房総半島中部域)
募集人数:5名前後
申込締切:2010年4月23日(金)
本研修の実施内容、参加費用、申込方法などの詳細は、地学情報サービス?のホー
ム ページ(http://www008.upp.so-net.ne.jp/gsis/gsis-J.htm)地質調査研修の
項目 をご参照ください。関連図面の他、過去の研修の様子を示した写真なども多
数掲載しています。
■STRATI 2010
日程:2010年8月30日〜9月2日
会場:University Pierre et Matie Curie Paris6
http://paleopolis.rediris.es/STRATI2010
■Zeolite 2010
8th International Conference on the Occurrence,
Properties, and Utilization of Natural Zeolites
日程:2010年7月10日〜18日
場所:Kempinski hotel Zografski Sofia, Bulgaria
www.zeolite2010.org
■第126回深田研談話会のご案内
「地下における「水」の主要循環系と貯留」
講師: 籾倉克幹 氏 (元農林水産省地質官 現基礎地盤コンサルタンツ(株)顧問・
技師長)
日時: 4月23日(金)15:00〜17:00
会場: 財団法人 深田地質研究所 研修ホール 参加費無料
◆ 講演概要:地球の表層は大きく水圏,大気圏,土壌・岩石圏に分けられている.
水は液体−気体−固体−液体と相を変えながらこれら三圏に またがっ て循環し
ている.したがって,水を使用あるいは保全しようとする場合には 水が循環資源
であることをわきまえ,循環系に損傷を与え ないよう系全体の 構造規制を洞察
することが肝要である.今回は,「阿 蘇カルデラ火山の西麓 から熊本平野への
地下水の流動と貯留」のほか演 者がこれまでに歩いてみてきた内外の事例から,
土壌・岩石圏の水循環経路を制約している構造要素を ピックアップし,それぞれ
の地下水盆が 抱えている水保全上の課題を紹介する.
詳しくは、http:// www.fgi.or.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】3月の博物館特別展示・イベント情報
──────────────────────────────────
博物館では春休み〜GWかけて、特別展示やイベントが予定されています。
3月の博物館イベントカレンダーは↓↓↓
http://www.geosociety.jp/name/content0052.html
■琵琶湖博物館:ギャラリー展示「鉱物・化石展2010 ぼらくは大地に夢を掘る」
■大阪市立自然史博物館:特別展「大恐竜展〜知られざる南半球の支配者〜」
・・・・など
各地の博物館の情報を是非編集部までお寄せ下さい。随時HPにアップいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報いろいろ
──────────────────────────────────
■日本学術振興会特別研究員-RPD平成23年度採用分募集
申請受付 平成22年5月12日(水)〜14日(金)(必着)
http://www.jsps.go.jp/j-pd/rpd_boshu_f.html
■日本学術振興会特別研究員平成23年度採用分募集
申請受付 平成22年6月2日(水)〜4日(金)(必着)
http://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_boshu_f.htm
■平成22年度東レ科学技術賞および東レ科学技術研究助成候補者推薦
推薦締切期日 平成22年10月8日(金)弊会必着
(学会締切9月10日必着)
※学会推薦となります.推薦をご希望の方は,必要書類等をご準備の上,期日ま
でに学会事務局にお申し出ください.
*各推薦書用紙は,ホームページからもダウンロードできます.
http://www.toray.co.jp/tsf/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】地質マンガ
──────────────────────────────────
「調査後のカニの味は」
作:木村 学 画:Key
http://www.geosociety.jp/faq/content0211.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.093 2010/03/05 geo-flash
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.093 2010/03/05 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 古川和代 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
日本地質学会名誉会員、古川和代氏(元明治コンサルタント株式会社)は平成22
年3月4日(木)にご逝去されました。
ここに謹んでお知らせ致します。これまでの故人の功績を讃えるとともに、謹ん
でご冥福をお祈り申し上げます。
なお、通夜、ご葬儀は下記のとおり執り行われますので併せてお知らせ申し上げ
ます。
記
通 夜:3月5日(金)18時〜
告別式:3月6日(土)11時〜
喪 主:古川恭子 様(奥様)
場 所:ハートプラザ・立花
福岡県糟屋郡新宮町夜臼6丁目9−17
電 話:092-963-1000
会長 宮下純夫
──────────────────────────────────
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
第1回フォトコン入選作品:地質学会長賞
第1回惑星地球フォトコンテスト入選作品:日本地質学会長賞
第1回惑星地球フォトコンテスト入選作品:日本地質学会長賞:「麦圃生山・植生回復」
写真:松山 幸弘(福井県) 撮影場所:有珠山ロープウェイ 有珠山頂駅付近
撮影者より:
麦圃生山(ばくほせいざん)とは昭和新山のこと,50年前に見た山の裾野は深い緑で覆われていました。撮影:平成21年7月3日
審査委員長講評:
昭和新山は1943年〜45年の火山活動によって,かつては麦畑だった場所が隆起してできた潜在溶岩ドームです.噴火から60年以上も経つと中腹までは植生に覆われていますが,作者は50年ぶりにこの地を訪れ,有珠山の展望台から見下ろすようなアングルで白煙をあげる昭和新山の現在をうまくとらえています.手前に昭和新山をどっしり置き,遠方には人家を配置するなど構図も秀逸で,写真の質も高く,学会長賞としました.
第1回フォトコン入選作品:審査委員長特別賞
第1回惑星地球フォトコンテスト入選作品:審査委員長特別賞
第1回惑星地球フォトコンテスト入選作品:審査委員長特別賞:「作者は、地球。」
写真:中西 康治(沖縄県) 撮影場所:沖縄県石垣市大浜の海岸
撮影者より:
石垣島大浜の海岸にある岩の天然アート。
審査委員長講評:
石垣島南部の大浜海岸で撮影したものです.この地層は始新統(3400〜56万年前)の宮良川層で砂岩・泥岩などからできおり,その中に含まれる球状のノジュールとともに色鮮やかに撮影しています.地層の奧にはサンゴ礁の穏やかな海が広がり,さらにその向こうには白雲の点在する青空,それらを対角魚眼レンズによってとらえています.撮影したのは影のもっとも少なくなる正午頃でしょうか.作者の中西さんは地元の方です.身近にある対象を的確なレンズ,天候,時刻を選んで撮影し,見ている人を明るい気持ちにさせてくれます.
第1回フォトコン入選作品:優秀賞(A部門)
第1回惑星地球フォトコンテスト入選作品:優秀賞(A部門)
第1回惑星地球フォトコンテスト入選作品:優秀賞(A部門):「石の木」
写真:北川 太郎(兵庫県) 撮影場所:ボリビア・ウユニ塩湖近郊
審査委員長講評:
ボリビア南西部にあるウユニ塩湖(海抜3700m)の近郊で撮影したものです.砂の侵食によって地表に近いほど激しく侵食されるので,このようなキノコのような地形ができます.周囲を何回もまわり,視線の高さを調整して,ベストのポジションから撮影したのでしょう.陰影の具合,周囲に散在した岩石の配置,背景などがよく整理されています.
地質的背景:
撮影ポイントは、ペルー南東部からボリビア西部にかけて広がる標高4,000m(±)の高原アルティプラノの南端付近に知られている「El Árbol de Piedra」(岩の木)と呼ばれる奇岩です。名のとおり、あたかも地中から岩石が伸びて広がったように見えます。高さ5m余りで、火山岩が強風により侵食され残留したものです。この北約150kmには、最近リチウム資源で有名になった世界最大の塩湖、ウユニ塩湖があります。(中山 健)
第1回フォトコン入選作品:優秀賞(B部門)
第1回惑星地球フォトコンテスト入選作品:優秀賞(B部門)
第1回惑星地球フォトコンテスト入選作品:優秀賞(B部門): 「支笏湖湖底」
写真:荒木 一視(山口県) 撮影場所:北海道千歳市支笏湖
撮影者より:
空気に触れる水面上には何も残っていません.支笏湖の水面下には朽ちずにかつての大木の根の部分が残っています.写真は水深2m弱のところから水中カメラ(ニコノス)で撮影したものですが,水面に根の部分が反射しています.ただし水面に顔を出すと何もありません.湖畔から離れた浅い水底に不思議な湖底の森林が広がっています.
審査委員長講評:
当初は選者全員が富山県魚津の海底埋没林だと思っていましたが,タイトルを見て支笏湖にもこのような湖底林があることを初めて知りました.ポジフィルムと水中カメラを使い,根の広がりや水面をうまく配置して,湖底林を見事にとらえています.このような写真は地学の知識,ダイビングの技術,カメラの技術がそろっていないとなかなか撮影できません.
第1回フォトコン入選作品:入選01
第1回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第1回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選:「赤い岩」
写真:佐藤 忠(東京都) 撮影場所:アメリカアリゾナ州北部ナホバ族居留地
審査委員長講評:
アメリカ合衆国アリゾナ州のアンティロープクリークでの作品です.ここは砂岩でできた高さ数十m・長さ数百mの谷で,写真愛好家には人気の場所だけに作品は類型的になりがちです.今回は3名の方から応募がありました.佐藤さんは望遠レンズを使い,見上げるようなアングルで,砂岩のパターンと耐乾性植物を独自の視点で切りとりました.赤のグラディエーションが豊かです.
地質的背景:
水の流れのような印象的な模様を見せるのは斜交層理の発達する砂岩。ナバホ砂岩と呼ばれるこの地層は、ジュラ紀前期の砂丘で堆積したものと考えられ、アリゾナ州北部に広く分布します。水の流れがナバホ砂岩に刻み込んだ峡谷「アンテロープキャニオン」では、狭い谷間に差し込む光に彩られ、ジュラ紀の堆積模様が浮かび上がります。(内藤一樹 産業総合研究所)
第1回フォトコン入選作品:入選02
第1回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第1回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選:「エンルム岬」
写真:加藤 幸雄(北海道) 撮影場所:北海道様似郡様似町会所町
審査委員長講評:
エンルム岬は,北海道様似町漁港のすぐ南に延びた陸繋島で,70mの高さがあります.白亜紀の砂岩・泥岩が露出し,日本ジオパークに認定されているアポイ岳ジオパークの一部をなしています.手前にあるのは地層ではなく,日高昆布を干しているところです.この写真が本コンテストにふさわしいものであるかどうかで迷いましたが,独特の雰囲気があり入選としました.
第1回フォトコン入選作品:入選03
第1回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第1回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選:「祝 洞爺湖有珠山ジオパークGGN登録!」
写真:横山 光(北海道) 撮影場所:北海道有珠郡壮瞥町 昭和新山山頂にて
撮影者より:
昭和新山山頂から見下ろす洞爺湖。GGN正式登録を祝して虹が架かりました。
審査委員長講評:
洞爺湖と有珠山一帯は,島原半島・糸魚川とともに2009年8月,世界ジオパークに認定されました.この写真は,昭和新山山頂から北方の虹がかかった洞爺湖を撮影したもので,地元壮瞥町の横山さんの作品です.地元の喜びが伝わってきます.おめでとうございます.
地質的背景:
洞爺湖は、今から約11万年前の巨大噴火によってできたカルデラ湖です。湖中に浮かぶ島は「中島」と呼ばれ、カルデラ形成後(約5万〜2万年前)にできた、これも立派な火山です。中島の形成に引き続いて、洞爺湖南縁(撮影地点側)に有珠山・昭和新山が成長し、現在に至ります。
ちょうど10年前の、2000年3月末に起きた有珠山の噴火は、記憶に新しいところではないでしょうか? そしてこのたびのGGN正式登録を祝して、洞爺湖に虹が架かりました。 (長谷川 健 茨城大学)
第1回フォトコン入選作品:入選04
第1回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第1回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選:「山河」
写真:横山 栄治(神奈川県) 撮影場所:岡山県上空
審査委員長講評:
石川県小松空港〜沖縄の定期便の窓から鳥取・岡山県境付近の中国山地を撮影したものです.定期便は高度10,000m以上を飛行することが多く,大地形を的確に捉えられることがあります.この作品では,モノトーンの山並みがはるか彼方まで続き,光る川面や山間の霧がよいアクセントとなっています.
第1回フォトコン入選作品:入選05
第1回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第1回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選:「奇跡のアーチ」
写真:渡辺修二(神奈川県) 撮影場所:神奈川県三浦市城ヶ島馬の背洞門
撮影者より:
「馬の背の洞門」三浦半島の先端に位置する城ヶ島の赤羽根崎の突端にある海食洞門。これは自然が作った海蝕洞穴で、長い年月をかけて波浪、風雨等に侵蝕されてこのような見事な形となったものです。 地層は第三紀層、鮮新統、三浦層群に属し、土質は凝灰質砂礫岩という軟かい岩質です。高さ8メートル、横6メートル、厚さ2メートルで、土地の人は「馬の背の洞門」のほか、「めぐりの洞門」、「眼鏡の洞門」などど呼んでいます。
審査委員長講評:
三浦半島先端にある城ヶ島の「馬の背の洞門」を撮影したものです.城ヶ島は首都圏から1時間余りで行ける場所で,海岸沿いにはいくつもの地質の見どころがあります.作者の渡辺さんは横須賀市にお住まいです.遠方の房総半島がくっきり見える透明度の良い日を狙って撮影したのでしょう.真っ青な空が地層を引き立てています.欲をいえば,左側の人物が『馬の背の洞門」の方を見ていればさらに良かったと思います.
第1回フォトコン入選作品:入選06
第1回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第1回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選:「羊蹄の朝」
写真:菅野 照晃(東京都) 撮影場所:北海道虻田郡倶知安町峠下 JR函館本線北四線踏切
撮影者より:
「ジオ鉄」撮影地 JR函館本線 倶知安〜小沢
審査委員長講評:
羊蹄山は蝦夷富士とも呼ばれる火山で,雪がほどんど溶けた新緑の美しい5月末頃に撮影した作品でしょうか.羊蹄山山頂を上端ぎりぎりに置き,列車の曲がりを計算してシャッターを切り,隙のない構図となっています.「ジオ鉄」のもう1つの入選候補は,江ノ電と上総層群の組み合わせを広角レンズでとらえた作品で,「羊蹄山の朝」とは対照的な作品でした.今回はすがすがしさが感じられるこちらの作品を入選としました.
ジオ鉄提唱者より:
朝もやの平原を走りゆく列車。夏の訪れを待つ北の鉄路の一コマである。行く手の車窓からは,青葉生い茂る木々の切れ間に,残雪を湛えた巨大な山容が浮かび上がることであろう。美しい裾野を従えるその姿は,火山が作り上げた大自然の芸術だ。のんびりと列車に揺られながら,大地の活動と季節の移ろいを感じたい,そんな思いに浸る作品である。
走り去る車両は,遠く本州からやってきた臨時検測列車。普段この路線では目にすることができない「珍客」である。このようなイレギュラーな組合せを期待するのも,ジオ鉄撮影家の楽しみの一つだ。(加藤 弘徳(株)荒谷建設コンサルタント)
第1回フォトコン入選作品:入選07
第1回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第1回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選:「北米−カリブプレート境界の蛇紋岩」
写真:辻森 樹(鳥取県) 撮影場所:グアテマラ共和国バハ・ベラパス県ラ・エスタンシア・デ・ガルシア地区
撮影者より:
中米グアテマラ・モタグア断層帯の蛇紋岩採石場(ワイヤーソーで切り出した面に水をかけている様子).写真の濃緑色の岩石が蛇紋岩.北米−カリブプレート境界に沿って高圧変成岩や翡翠を含むアンチゴライト蛇紋岩が広く露出する.この蛇紋岩はトランスフォーム断層による急速なマントル物質の上昇や地震活動を読み解く地質素材というだけでなく,マヤの時代から現在に至るまで良質の宝石や石材として人々の生活に関与している.
審査委員長講評:
最初は何の写真だろうと思いますが,よく見ると右側にいる人物が水をかけているようすから巨大な採石場であることがわかります.グアテマラの蛇紋岩採石場での撮影です.雑多な採石場と周囲の森の写り込みが美しい切断面が対照的で,作品に広がりを与えています.作者は地質研究者で,詳しい解説が写真をいっそう引き立てています.
第1回フォトコン入選作品:入選08
第1回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第1回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選:「重力」
写真:岡田 治(和歌山県) 撮影場所:和歌山県西牟婁郡すさみ町口和深 国道42号線すさみ町
撮影者より:
和歌山県西牟婁郡すさみ町にある褶曲である。学術的な事は私には不明であるが、近くのフェニックスの大褶曲は近年発見され知られているが、同様の褶曲が幾重にもあり、これはその中の一つである
審査委員長講評:
撮影したのは四万十帯の砂泥互層の褶曲構造で,海洋プレートの沈み込みによる付加帯に特徴的に見られます.今回モノクロフィルムでの応募は数が少なかったので審査員一同の目を引きました.赤フィルターを使っているのでしょうか,空のトーンを落とし,広角レンズで地層の褶曲を強調して格調高い作品となっています.
第1回フォトコン入選作品:入選09
第1回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第1回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選:「阿波の土柱」
写真:三木 万理子(徳島県) 撮影場所:阿波市阿波町桜ノ岡(土柱高越県立自然公園)
撮影者より:
私の住んでいる徳島県には世界3大土柱の1つ,阿波の土柱があります。残りはアメリカのロッキー山脈とイタリアのティロル地方にあるそうです。先日,父に初めて連れて行ってもらいましたが,とても不思議な光景でした。また,すごい年月がかかって作られていることを知り,想像すると気が遠くなりそうでした。ただ,頂上まで歩いていきましたが,くずれないかと思い怖かったです。何万年かたったらもっと増えているのかな?
審査委員長講評:
高校生部門からの入選です.作者の三木さんは地元徳島県の中学生で,阿波の土柱をそつなく写しています.阿波の土柱は観光地になっており,数多くの写真が発表されていますから,新鮮な印象の写真を撮るのは難しい場所でもあります.地元にお住まいですから,季節や天候,アングルなどをいろいろと工夫して,さらに魅力的な阿波の土柱を撮影してください.
地質マンガ 晴れ男
地質マンガ
戻る|次へ
地質マンガ 雨男
地質マンガ
戻る|次へ
No.096 2010/04/06 geo-flash 春爛漫号
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.096 2010/ 4/6 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】 第4回 国際地学オリンピック(インドネシア大会):日本代表決定!
【2】2010年の「地質の日(5/10)」は?
【3】第1回惑星地 球フォトコンテスト入選作品
【4】ジオ・スクーリングネットをご活用ください!
【5】本の紹介:「固体惑星物質進化」
【6】支部情報
【7】その他のご案内
【8】公募情報・各賞助成
【9】マンガ2本立て!「晴れ男」「雨男」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 第4回 国際地学オリンピック(インドネシア大会):日本代表決定
──────────────────────────────────
非営利活動法人地学オリンピック日本委員会(理事長:濱野洋三(海洋研究開発
機構))は、第4回国際地学オリンピック大会に参加する日本代表生徒4名を3月
26日に決定しました。
第4回国際地学オリンピック大会は、インドネシアにおいて2010年9月19日から
28日までの10日間に渡って開催されます。
3月24日から26日に行われた国内二次選抜大会(第2 回日本地学オリンピック
本選「グランプリ地球にわくわく」)(主催:特定非営利活動法人地学オリンピッ
ク日本委員会、特別共催:一般社団法人日本地球惑星科学連合、特別協賛:独立
行政法人科学技術振興機構、後援:文部科学省)で選ばれた4名の日本代表(第
2回日本地学オリンピック大会最優秀賞)は以下の通りです。
第4回国際地学オリンピック大会日本代表(第2回日本地学オリンピック大会
最優秀賞)
氏名、ふりがな、学年(平成22年3月現在)、高等学校名
大西 泰地(おおにし たいち)高1 白陵高等学校
川島 崇志(かわしま たかし)高2 静岡県立磐田南高等学校
武内 健大(たけうち けんた)高2 聖光学院高等学校
野田 和弘(のだ かずひろ)高2 広島学院高等学校
第2回日本地学オリンピック大会優秀賞4名は以下の通りです。
丸山 純平(まるやま じゅんぺい)中3 聖光学院中学校
高村 悠介(たかむら ゆうすけ)高2 埼玉県立川越高校
橋本 敏明(はしもと としあき)高2 慶應義塾高等学校
諏訪 敬之(すわ たかし 高1 灘高等学校
国内選抜(第2回日本地学オリンピック大会)一次予選(筆記試験;2009年12月
20日実施)には、日本各地から682名の生徒が応募し、全国の大学や高校会場に
て受験しました。
二次選抜試験(実技試験、面接;2010年3月24日から26日までつくば研究学園
都市で「グランプリ地球にわくわく」として実施)には、一次で選ばれた24名の
生徒 が参加し、4名の最優秀賞者と4名の優秀賞者が選考されました。この最優
秀賞者4名が国際大会日本代表となります。代表生徒は5月から8月の通信研修、
8月下旬の合宿研修(神奈川県立生命の星・地球博物館にて)を経て、9月の国
際大会に臨みます。
なお、「グランプリ地球にわくわく」は、独立行政法人産業技術総合研究所地質
調査総合センター、気象庁気象研究所、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独
立行政法人国立環境研究所、茨城県、つくば市の共催、一般社団法人日本地球惑
星科学連合の特別共催、独立行政法人科学技術振興機構の特別協賛、文部科学省、
茨城県教育委員会、つくば市教育委員会の後援で開催され、茨城県知事賞、つく
ば市長賞、地質調査総合センター賞も授与されました。
茨城県知事賞(総合成績1位)
大西 泰地(おおにし たいち)高1 白陵高等学校
つくば市長賞(女性部門総合成績1位)
渡辺 翠(わたなべ みどり)中2 桜蔭中学校
地質調査総合センター長賞(地質実技試験優秀者)
石井 彰吾(いしい しょうご)高1 灘高等学校
大西 泰地(おおにし たいち)高1 白陵高等学校
川島 崇志(かわしま たかし)高2 静岡県立磐田南高等学校
橋本 敏明(はしもと としあき)高2 慶應義塾高等学校
松岡 亮(まつおか りょう)高1 北海道旭川西高等学校
なお、2012年8月には第6回国際地学オリンピック日本大会がつくば学園都市で
開催される予定です。
問い合わせ先
特定非営利活動法人地学オリンピック日本委員会
113-0032 東京都文京区弥生2-4-16 学会センタービル4F
日本地球惑星科学連合気付
TEL 03-3815-5256, E-mail esolympiad@yahoo.co.jp
担当者 瀧上豊、村瀬公胤
(原則として、月曜日以外の電話は瀧上の携帯へ転送)
担当者 瀧上豊、村瀬公胤
(原則として、月曜日以外の電話は瀧上の携帯へ転送)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】 2010年の「地質の日(5/10)」は?
──────────────────────────────────
2010年の「地質の 日」に関連した学会の催しをご紹介します。
■日本地質学会:本部イベント企画
・写真家 白尾元理 講演会「地球史46億年を撮る」
日時: 2010年5月8日(土)13:30〜15:30
場所: 東京大学小柴ホール(東京都文京区本郷)
講師: 白尾元理氏(写真家・日本地質学会会員)
入場無料・事前申込不要(定員170名)
・ジオ写真展: 白尾さんの写真と惑星地球フォトコンテスト入賞作品の展示
■北海道支部:「地質の日」・「国際博物館の日」記念展示:
北海道大学総合博物館企画展示「わが街の文化遺産 札幌軟石」
期間: 2010年4月27日(火)〜5月30日(日)10:00〜16:00
会場: 北海道大学総合博物館1階「地の統合」 コーナー
関連イベント:
5/1(土)ワークショップ「札幌軟石クラフトに挑戦!」
5/1(土)講演会「札幌軟石 いま・昔」
5/8(土) ミニツアー「札幌軟石ウォッチング」(要申込)
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
■ 関東支部
第2回地質技術伝承講習会:地質技師長が語る地質工学余話
「共生型地下水利用に向けての「育水」の提唱」
日時: 2010 年6月6日(日)14:00〜16:30
場所: 北とぴあ(東京都北区王子1-11-1) 飛鳥ホール
講師: 中村 裕昭氏(株式会社地域環 境研究所)
テーマ: 共生型地下水利用に向けての「育水」の提唱
参加費: 無料,どなたでも参加できます.
http://kanto.geosociety.jp/
■ 近畿支部:「地質の日」協賛行事
第27回地球科学講演会「大阪の温泉は本当に温泉か?−大阪平野の地下水を可視
化する−」
地質学会近畿支部では,「地質の日」協賛行事として,地学団体研究会大阪支
部と大阪市立自然史博物館との共催で,第27回地球科学講演会「大阪の温泉は
本当に温泉か?−大阪平野の地下水を可視化する−」を開催します.
「天然温泉」の看板を街の中で見かけることがあります.温泉好きの私たちに
とっては,安くて近い息抜きの場です.火山のない大阪になぜ温泉が出るのか,
不思議に思ったことはありませんか.平野部にある温泉は,とても深い場所にあ
る地下水なのです.中には変わった泉質を持つものもあります.でも,地下水と
いう点では,上町台地の湧水と同じです.ここでは,目には見えない大阪平野の
地下水の流れを話します.地下水とは何か,河川水とどう違うのか,そしてどう
つきあえばいいのか,一緒に考えたいと思います.多くの方のご参加をお待ちし
ております.
日時: 2010年5月9日(日)14:30-16:30
場所: 大阪市立自然史博物館講堂(大阪市東住吉区長居公園1-23)
講師: 益田晴恵氏(大阪市立大学大学院理学研究科教授)
主催: 日本地質学会近畿支部,地学団体研究会大阪支部,大阪市立自然史博物館
申込不要.直接会場へお越しください.
参加費: 無料.ただし,博物館入館料(大人300円,高校・大学生200円)が要.
■ 西日本支部:後援「地質の日」企画
身近に知る「くまもと の大地」
日時: 2010年5月9日(日)「地質の日」 10:00〜16:00
場所: 熊本市通町筋上通り入り口 びぷれす広場(熊日ビ ル)
企画: ◎おどろきの展示コーナー/◎わくわく体験コーナー/◎なるほど解るコー
ナーなど
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】 第1回惑星地球フォトコンテスト入選作品
──────────────────────────────────
厳正なる審査を行い、応 募作品全436作品のうち,14の入選作品が決定し、3/28
IYPEイベント会場で表彰式が行われました。
表彰式の様子や各作品の講評など詳細は、、、http://photo.geosociety.jp/
(惑星地 球フォトコンテスト審査委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】ジオ・スクーリングネッ トをご活用ください!
──────────────────────────────────
ジオ・スクーリングネット(土質・地質技術者の生涯学習ネット)は,2001年10月
から運用中です
特徴
1)土質・地質に係る技術者のための関連情報をインターネットで提供しています
2)オープン・フリー制で“どなたでも無料でご利用いただけます”各種証明書発
行も無料
機能
1) 講習会情報の検索と参加申込みができます
2)技術者継続教育(CPDH)の自己学習の記録が管理できます
http://www.geo-schooling.jp/
今すぐのアクセスをお待ちしております.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】本の紹 介:「固体惑星物質進化」
──────────────────────────────────
「固体惑星物質進化」武田 弘 著
株式会社現代図書(神奈川県相模原市)、2009年
2月15日発行,131ページ,横書
20.9×29.7×0.8cm, ソフトカバー、定価 5238円+税
ISBN987-4-86299-006-8
本書は,最も未分化な原始太陽系物質とされる一種の 炭素質隕石から,普通コンドライト,エイコンドライトや鉄隕石,月の岩石や月隕石,火星表面の岩石や火星隕石,金星表面に推定される 岩石 を経て,最も分化した地球表層の岩石まで,太陽系固体惑星物質の46億年間の進化について,カラフルな260葉以上の写真や図表を 用い て,最新の知識を親しみやすくわかりやすい文章で系統的に解説した教科書である.「岩石鉱物科学」の38巻2号40ページ(2009)に境 毅氏 による本書の紹介文があるので,ここでは特に興味深い点と問題点を指摘したい.著者の武田弘先生は日本ソムリエ協会の名誉ソムリ エでもあ り,本書2ページにはその片鱗が表れている.それは,1492年の隕石落下の様子を記録した木版画を図柄としたアルザスワイン のエチケッ ト(ラベル)である(図1-2-2).本題の話は,球粒が少なく微細な蛇紋石やサポナイトを主とし,最も未分化な炭素質隕石とされ るオル ゲイユ隕石(1864年,フランスに落下)から始まる.次に普通コンドライトの話になるが(第2章),多くの普通コンドライト(例えば L4〜L6 型)では一つの隕石中のかんらん石などの固溶体組成がほぼ均質であるのに,稀に鉱物の化学組成が非常に大きなバラツキを示す 「非平衡普通 コンドライト」(例えばL3型)があり,その球粒の中に球粒の前駆物質と思われる「しん(芯)」が最近発見されたという. これは球粒が, ガスからの凝縮ではなく,前駆固体物質の再溶融でできたことを示唆する.一方,変成作用が最も進んだL6型などより更に温度が 上がり,部 分的に溶融したコンドライト(例えばLL7型)があることも示されている.また,第3章では,普通コンドライトと同じスペクトルを示す小惑星は,隕 石の故郷と言われる火星と木星の間の小惑星帯では少数派であり,多数派のS型スペクトルを示す小惑星に対応する隕石は, 地球への落下数が少ない, 部分溶融したコンドライト(球粒は含まず深成岩組織を示す)の可能性があると述べている.そのような隕石から は,表紙の写真(縦幅 13mm)のようにNaに富む斜長石と両輝石・かんらん石などからなる深成岩組織の部分(化学的には高Mg安山岩質)も報告されている. 母天体中での金属鉄(鉄隕石)の分布に関する「ゆで卵モデル」と「ぶとうパンモデル」の話も面白い.第4章は地球のマントルか んらん岩に よく似た組織を示すエイコンドライトの一種,ユレイライト隕石について述べ,その珪酸塩鉱物の粒間を埋めるグラファイト中に 含まれるダイアモンド の成因として,天体衝突による超高圧説と気相成長説を検討している.第5章は小惑星ベスタを構成していると考えら れるHED隕石(エイコ ンドライトの一群,境氏によると武田先生が名付け親)の話であり,母天体における部分溶融と結晶分化作用が論じ られている.第6章は月の 陸地の岩石及び月隕石の記載と成因論であり,月の初期地殻の成長モデルとして岩山説(早期に固結した岩石が氷山のよう にマグマ大洋に浮か ぶ.「がんざん」と読む?)が紹介されている.輝石・かんらん石のMg#と斜長石のAn値の図(図6-5-2)にお ける月の深成岩のMg主系列と 斜長岩系列の位置関係は,それぞれ地球の海嶺玄武岩と島弧玄武岩から晶出する鉱物の関係に似ている.第7 章は月の海の溶岩の話であり, 「盆地周辺より火の噴水のようにふき出し,中心部に向かって流れたらしい」という記述は興味深い.第8章は火星 起源のSNC隕石と火星探 査機が分析した火星表面の岩石の化学組成と鉱物組合せについて述べている(詳細は後述).第9章はロシアの着陸船が分 析した金星表面の岩 石の化学組成と,それから導かれる可能な鉱物組合せについて述べていて,マイクロクリン,紅柱石,菫青石など地球の 岩石屋に親しみ深い鉱物名が列挙されている.最後の第10章は地球表層物質について述べ,地球特有の鉱物の代表として雲母を挙げている (同じく含水鉱物である角閃石は 火星隕石にも含まれる).また,「金が採掘可能なほどに濃集するというのは,隕石母天体や月では考えら れないことである」と述べている.
以 上のように,本書は固体惑星物質科学分野の最新の知識を系統的に説明した教科書として優れた内容と 構成を持っているが,残念なことに,高価な書籍 であるにもかかわらず,以下のような不備や誤りが目立つ.まず,解像度が極端に悪い写真 が16葉ある.図の説明と本文が矛盾する場合があ り,例えば物質分布図(P.20, 図2-7-3)の説明では小惑星「エロス」となっているのに,本文(P. 20左段中程)では小惑 星「イトカワ」として説明されている.33ページの右段では「エロスの表面には物質の不均質分布は確認されていない」と述べられているので,こ の分布図はイトカワのものなのだろう.本書には組織の特徴をよく表現した美しい偏光顕微鏡写真が多いが,「左側の列は普通の平行光,右側の列は 偏 光で見たもの」(P. 36, 図4-1-2)という説明は,例えば「左側の列は単ニコル,右側の列は直交ニコルで見たもの」のよう にす べきである.左側の列の写真も偏光で見ているはずで,「普通の平行光」ではない.図のラベルの誤りや記入漏れもある.52ページの 図 5-2-5では, 図の説明に対応する記号が図の中に示されていない.96ページの図8-3-4では, 縦軸の最下部のラベルの数値が間違っている.96ページの図8-3-5では, 図の右上部の2つのドットに同じ「カリウム」というラベルがつい ている.その一つは「ガリウム」の誤りかもしれない.53ページ図5-3-1の右上の写真は「太陽系中最古の溶岩」とのことだが,このようなオ フィチック組織の岩石は,確かに厚い溶岩流の中心部の可能性があるものの,地下で固結した岩脈や岩床の可能性も大きい.「溶岩」(マグ マ が地表に噴出して固結した岩石)と断定する根拠がよくわからない.77ページの図6-7-7の説明では,「青が低い値,赤が高く,黄 色は 中間」とのことだが,色の変化を見ると,どうも青が低い値,黄色〜白色が高い値で,赤色はその中間を示しているように見える.102ページ の表 8-6-1と103ページ左段の記述によると,火星探査車スピリットが分析したアディロンダックという岩石はカリウムやナトリウム に富むアルカリ 岩とのことだが,表8-6-1に示された化学分析値を見るとK2Oの量はわずか0.08%であり,しかもNa2Oの量が 示されていないの で,アルカリ玄武岩かどうか判断できない.図8-6-4を見ると,Na2O+K2Oの量の合計が3%程度になってお り,Na2Oが多いのだと思う が,Na2Oの分析値を表8-6-1に示してほしい.また,102ページ本文と図8-6-4ではグーセフ・ クレーターと書いてある が,103ページではグスタフ・クレーターになっている.122ページ図10-2-3の地球の写真は裏焼きで,アフリカ 大陸の東西(この図では 上下)が逆である.本文の文章は全体にわかりやすいが,例えば72ページ以後の本文で,同じ意味の語に創世記, 創世期,創生期,創成期など様々な 漢字が使われるなど,よくこなれていない文章があり,校閲が不足していると言わざるをえない.参考文 献のリストはあるが,用語索引も欲し いところである.とはいえ,今年6月に日本の惑星探査機「はやぶさ」が小惑星「イトカワ」の表面 物質を携えて(?)地球に帰還すること になっており,現在日本では惑星物質への興味が高まりつつある.地質学会の会員諸氏には,是非この時期に 本書の一読をお勧めする.なお, 昨年の本誌12巻2号3ページ(火星)と12号3ページ(惑星地質)で紹介した関連書籍も参照されたい.
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】 支部情報
──────────────────────────────────
■関東支部
・地質技術伝承講演会:地質技師長が 語る地質工学余話(第1回)
日時:2010年4月18日(日)13:30〜16:00
場所:北とぴあ(東京都北区王子1-11-1)7階 第1研修室
講師:千葉達朗氏(アジア航測株式会社)
テーマ:赤色立体地図による新しい地質調査技術
・2010年度関東支 部総会
日時:2010年4月18日(日)16:00〜16:30
場所:北とぴあ(東京都北区王子1-11-1)7階第1研修室
・ 2010年関東支部幹事立候補受付中
立候補締切:2010年4月15日(木)
詳しくは、 http://kanto.geosociety.jp/
■近畿・四国・西日本三支部合同
「ジオ・シンポジア2010 in 北九州」(日本地質学会近畿・四国・西日本支部三
支部合同例会)
本大会では,ジオパークの活動に代表されるジオの視 点を取り入れた地域活動
に関する公開シンポジウムとジオツアーを計画しております.多数の方々のご参
加をお待ちしております.
シ ンポ「ジオ・シンポジア2010 in 北九州」〜環境を考える新しいキーワードGEO〜
ジオの視点を取り入れた地域振興とジオパークの活動
日 時 2010年7月18日(日)13:30〜
場所 北九州市立自然史・歴史博物館(いのちのたび博物館)ガイド館
ジオツアー「ジ オ・サイト 曽根干潟,間島」
主な見学予定地点:日本一のカブトガニ生息地・消えかけた砂嘴 ・
島の古墳群・小倉城石垣(花崗岩)の石切 り場・恒見の石灰岩大露頭
実施日 2010年7月19日(月・祝)海の日
*事前予約受付: 5月31日(月)(必着)
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html#2010geo
* この他にも各支部で「地質の日」関連の催しが予定されています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】 その他のお知らせ・ご案内
──────────────────────────────────
■学術会議提言「日本の展望—学術から の提言2010」等の公表
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/tenbou/teigen.html
■ 三朝国際インターンプログラム2010
実施期間: 2010年7月1日(木)〜8月11日(水)(約6週間)
国際的な研究・教育の推進を目的に,国内外からの学部3 ・4年生並びに修士課程
学生(国籍は問わない)を対象として2005年より継続的に開催されています.参
加者は各研究部門(分析地球化学部門,実験地球物理学部門)の教員並び研究者
による指導のもと当研究センターが推進している最先端研究プロジェク トに実際
に参加していただきます.プログラム終了時には,英語による研究成果発表の実
施を予定しています.
このプログラムを通して, 高度な実験・分析技術に触れるのみでなく,研究者と
しての経験や最先端研究への情熱が育まれることを期待しています.
募集人員: 10名程 度
応募締切: 2010年5月9日(日)
詳しくは, http://intern.misasa.okayama-u.ac.jp/misip2010/
■IODP掘削航海(3航海)乗船研究者募集
2011年に JOIDES Resolutionにて実施予定の掘削航海(3航海)の乗船研究者を募
集いたします.詳細は各航海のページをご覧ください.いずれの募集も5月15日が
締め切りとなっておりますので,奮ってご応募ください.
◇Costa Rica Seismogenesis Project (CRISP)
(IODP重点研究カテゴリ:地震発生体の包括的理解)
航海予定期間:2011年3月15日〜4月16日
>http://www.j-desc.org/m2/expeditions/CRISP.html
◇Superfast Spreading Rate Crust 4
(IODP重点研究カテゴリ:巨大海台,海洋地殻,大陸縁の形成と進化の解明)
航海予定 期間:2011年4月16日〜5月19日
>http://www.j-desc.org/m2/expeditions/superfast4.html
◇Mid-Atlantic Microbiology
(IODP重点研究カテゴリ:地下生物圏の探査)
航海予定期間:2011年9月中旬〜11月中旬
>http://www.j-desc.org/m2/expeditions/mid_atlantic_microbio.html
■ 米国地質学会国際大会(in トルコ・アンカラ)
「テクトニクスの十字路:ユーラシア・アフリカ・アラビアの造山帯発達史」
日程: 2010年10月3日(日)〜8日(金)
場所: トルコ・アンカラ
締切: Abstracts deadline: 2010年5月10日
Standard registration deadline: 2010年8月23日.
Registration cancellation deadline: 2010年8月30日
詳しくは、
http://www.geosociety.org/meetings/2010turkey/
■ 深田研地形学習会のご案内
今回の地形学習会は「富士山」をとり上げました。現地での学習会と室内での実
験観察会をセットで開催します。
参加を希望される方は下記要領をご確認の上お申込みください。
※「深田研地形学習会」は技術士CPD(継続教育)履修実績として申請できます。
◆ テーマ:富士山の地形の謎を探ろう!
◆講師: 池田 宏 氏 (元筑波大学 深田地質研究所客員研究員)
◆開催概要
●1日目 【富士山一周ジオツアー】
・日時: 2010年5月15日(土)10:00〜17:00終了予定
・集合・解散場所: 小田原駅前
・ 学習内容:富士山麓をバスで一周します。富士山の地形をよく見て、みんなで
謎を見つけよう!(天候不良の場合は「生命の星・地球博物館」等の関連施設を
見学)
●2日目 【富士山の地形実験観察会】
・日時: 2010年5月22日(土)13:00〜16:00
・会場: 深田地質研究所 研修ホール
・学習内容: 1日目のジオツアーで見つけた謎を探る実験観察会を行います。キー
ワードは「富士山の傾斜角」「広い裾野」「大沢崩れ」「吉田大沢」「宝永山」
「富士五湖」 etc.
◆ 募集要項
・対象者: 富士山の地形に関心のある方で、原則として二日とも参加できる方。
・定 員: 30名程度(申込み多数の場合は抽選とします)。
・参加費: 5,000円(バス代、資料代、保険代として)。集合場所までの往復
の交通費は別途各自で負担願います。
・申込み締切り日: 4月25日(日)。参加の可否(抽選の結果)は4月28
日までに通知します。参加者には別途詳細を連絡します。
◆申込み方法: 参加ご希望の方は、E-mailもしくはFAXでお申込み下さい。
その際、氏名(ふりがな)・生年月日・所属・連絡先(住所・電話番号)をお
知らせ願います。
※生年月日は保険をかけるために必要となります。
◆申込み先: 財団法人 深田地質研究所
〒 113ー0021 東京都文京区本駒込2ー13ー12
TEL:03-3944-8010 FAX:03-3944-5404
E- mail:fgi@fgi.or.jp URL:http://www.fgi.or.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】 公募情報・各賞助成
──────────────────────────────────
公募
■三重県職員(学芸員または学芸 技師)の募集(生物学・古生物学) (締切4/16)
■広島大学大学院理学研究科地球惑星システム学専攻教員公募(教授) (締切5/31)
■ 筑波大学生命環境科学研究科地球進化科学専攻教員公募(助教) (締切5/1)
各賞助成
■第7回(平成22年度)日本学術振興会賞 受賞候補者推薦募集
(学会推薦受付締切: 5月7日(金)学会推薦です.自薦はありません.)
■2011〜2012年開催藤原セミナー募集 (締切7/31必着)
■2010 年度「信州フィールド科学賞」募集 (締切6/30)
詳しくは、こちら
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】 マンガ2本立て!「晴れ男」「雨男」
──────────────────────────────────
晴れ男 原案:川村喜一郎/ マンガ:Key
http://www.geosociety.jp/faq/content0228.html
雨男 原案:川村喜一郎 /マンガ:Key
http://www.geosociety.jp/faq/content229.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報 告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
ま でに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.097 2010/04/20 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.097 2010/ 4/20 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】 日本開催決定!ジオパーク国際ユネスコ会議
【2】日本地質学会第117年総会/(一社)日本地質学会第2回総会
【3】報告:理事会推薦監 事立候補者について
【4】2010年の「地質の日(5/10)」は?
【5】富山大会:シンポ・トピック・定番セッションが決まりました!
【6】 韓日地質学会ー室戸合同大会ー ファーストサーキュラー公開
【7】2010年度会費督促請求について
【8】その他のご案内
【9】 公募情報
【10】新事務局員のご紹介
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】日本開催決 定! ジオパーク国際ユネスコ会議
──────────────────────────────────
2年に1度開催されているジオ パーク国際ユネスコ会議(第4回:マレーシア
・ランカウイ)の閉会式において、次回2012年(第5回)の開催地が島原半
島ジオパークに 決定したとのことです。 奇しくも国際地学オリンピック日本
開催と同じ年です.2012年は地質学の年になりそうです.
(ジオパーク支援委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】 日本地質学会第117年総会/(一社)日本地質学会第2回総会
──────────────────────────────────
2010 年5月23日(日)18:00〜
会場 幕張メッセ 国際会議場(3F 304会議室)
任意団体および一般社団法人日本地質学会の 総会を開催いたします.議事次第等
詳しくは下記をご参照下さい.
<任意団体>
http://www.geosociety.jp/outline/content0079.html
<一 般社団法人>
http://geosociety.sakura.ne.jp/jgs/#sokai_2010
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】 報告:理事会推薦監事立候補者について
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会 選挙規則ならびに選挙細則に基づき会員以外からの理
事会推薦監事候補者として、山本正司氏の立候補届および推薦承諾書を受理しま
した。な お、本立候補届については、届け出期限を過ぎるという手続き上の間違
いがありました。しかしながら、会員外の監事立候補者については、実際上、代
議 員による投票は行われない仕組みであることと、監事の選任は総会の議決事項
でありますので、当選挙管理委員会においては、候補者としての有効性に 問題は
ないと考えます。よって下記の通り、選挙結果として追加ご報告いたします。
【理事会推薦監事立候補者=当選者 1名】
1. 山本正司 山本司法書士事務所所長
一般社団法人日本地質学会
選挙管理委員会委員長 松田達生
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2010年 の「地質の日(5/10)」は?
──────────────────────────────────
2010年の「地質の日」に関連 した学会の催しをご紹介します。
■日本地質学会:本部イベント企画
・写真家 白尾元理 講演会「地球史46億年を撮る」
日 時:2010年5月8日(土)
■北海道支部:「地質の日」・「国際博物館の日」記念展示:
北海道大学総合博物館企画展示「わが街 の文化遺産 札幌軟石」
期間:2010年4月27日(火)〜5月30日(日)
■ 関東支部
第2回地質技術伝承講習会:地 質技師長が語る地質工学余話
「共生型地下水利用に向けての「育水」の提唱」
日時:2010 年6月6日(日)
■中部支 部:「地質の日」記念
サイエンスフェステイバル in 五十嵐キャンパス(新潟大学)
日時:5月16日(日)12:00~15:00
場 所:新潟大学理学部
■ 近畿支部:「地質の日」協賛行事
第27回地球科学講演会「大阪の温泉は本当に温泉か?−大阪平野の地下 水を可視
化する−」
日時:2010年5月9日(日)
■ 西日本支部:後援「地質の日」企画
身近に知る「くまもと の大地」
日時:2010年5月9日(日)
それぞれの詳しい情報は、、、
http://www.geosociety.jp/name/content0060.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】 富山大会:シンポ・トピック・定番セッションが決まりました!
──────────────────────────────────
今年第117年学術大会(富山大会:9月18日〜20日開催)では下記のシンポジウ
ム・トピックセッション等を予定しております.このほかにも特 別講演会や,地
質情報展はじめ多数の普及行事も企画・準備中です.募集・予告記事は、次号
ニュース誌5月号で掲載予定です.また,講演申 込や参加登録は5月頃受付開始予
定です.(日本地質学会行事委員会)
セッション内容等詳しくはコチラ
http://www.geosociety.jp/science/content0044.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】 韓日地質学会ー室戸合同大会ー ファーストサーキュラー公開
──────────────────────────────────
2010年8月23-25日に予定されております韓日地質学会ー室戸合同大会ーのファー
ストサーキュラーが公開されました。
韓日地質学 会室戸合同大会では、韓国と日本における地質学の最新の研究成果
に関する情報交換や、地質学を学ぶ若者の交流を目的としています。学生サポー
ト もありますので学生さんにはふるって参加いただきたいと思います。
詳しくは、こちら
http://struct.geosociety.jp/koreajapangs2010/
竹下徹・橋本善孝(韓日地質学会室戸合同大会事務局)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】 2010年度会費督促請求について
──────────────────────────────────
—2010年度およびそれ以前 の会費が未入金の方へ—
1.次回の自動引き落とし日は6月23日(水)です.2010年度会費が未入金の方で
6月23日の自動引 落をご希望される方は,News誌4月号(月末発送予定)の巻末頁
に掲載される「預金口座振替依頼書」をご利用の上,5月12日(水)までにお申 込
み下さい.
2.郵便振替用紙によるお振り込みの方には,督促請求書(郵便振替用紙)を送
付いたします.お手元に届きま したら,早急にご送金くださいますようお願いい
たします.督促請求書の発送は5月末頃を予定しております.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】 その他のご案内
──────────────────────────────────
■地球惑星連合2010年大会:パブリックセッ ション/スペシャルレクチャー
パブリックセッション
日時:2010年5月23日(日)9:45〜(国際会議室ほか)
・高校生によ るポスター発表
・ジオパーク
・地球・惑星科学トップセミナー「地球史における大変動」
http://www.jpgu.org/meeting/public_sessions_2010.html
ス ペシャルレクチャー
研究分野を越えて学生・若手に贈る地球惑星科学の特別講義シリーズ!『スペシャ
ルレクチャー』を企画しました.毎日お 昼休みに開催します.
24日(月) 地球生命科学:山岸明彦 (東薬大)
25日(火) 地球人間圏科学:中川毅(Newcastle University)
26日(水) 固体地球科学:長谷川昭 (東北大)
27日(木) 大気海洋・環境科学:T. N. Krishnamurti (Florida State Univ)
28日(金) 宇宙惑星科学:井田茂 (東工大)
2010 年大会webサイト
http://www.jpgu.org/meeting/index.htm
■日本学術会議 公開シンポジウム「IPCC(気候変動に関する政府間パネル)問
題の検証と今後の科学の課題」
日時:平成22年4月30 日(金)13:00〜17:00
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木)
開催趣旨:IPCC(気候変動に関する政府間パネル)をめぐ る問題(Climate-gate,
IPCC-gates)について、科学的観点から事実関係を明らかにし、その情報と認識
を共有する こと、そして、今後このような問題が生じないためのIPCCの科学的作
業の在り方、社会と政策への情報提供の倫理性、科学者の行動規範などについ て
討議する。
問い合わせ先 岩澤 康裕 日本学術会議第三部長
電気通信大学大学院情報理工学研究科
Tel: 042-443-5921 e-mail: iwasawa@pc.uec.ac.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】 公募情報
──────────────────────────────────
■東京大学地震研究所教員公募:ナノスケール地球科学分 野(6/14締切)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】 新事務局員のご紹介
──────────────────────────────────
事務局では,4月1日より阿南晶子(あなん あきこ)さんを新メンバーに迎え,
計4名で業務にあたっています.阿南さんの主な担当は,Island Arc編集事務をは
じめ庶務全 般です.皆様どうぞよろしくお願い致します.
温泉王国?大分県出身です.大学時代の専攻は建築でしたので,これまで地質
とはあ まりご縁はありませんでしたが,これからどうぞよろしくお願い致します
(阿南).
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報 告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
ま でに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.098 2010/05/06 geo-flash アイスランド解説
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.098 2010/ 5/6 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】 アイスランドの噴火と噴煙(解説)
【2】地質の日までカウントダウン!
【3】2010年度会費督促請求について
【4】支部情報
【5】 日本地質学会第117年総会/(一社)日本地質学会第2回総会
【6】その他のご案内
【7】公募情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 アイスランド火山の噴火と噴煙(解説)
──────────────────────────────────
4月中旬に起こったアイス ランドでの噴火はヨーロッパの約30カ国の空港を一時閉
鎖に追い込み,経済的にも大きな損害を与えた.日本国内でも,桜島で千mに達す
る 噴煙を出すような噴火がほぼ毎日起こっていて,噴煙災害はけっして対岸
の火事ではない. 鈴木雄治郎(海洋研究開発機 構)
詳しくは、、、
http://www.geosociety.jp/hazard/category0009.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】 地質の日までカウントダウン!
──────────────────────────────────
今年もまもなく地質の日 (5/10)です。2010年の「地質の日」に関連した学会の
催しをご紹介します。
■日本地質学会:本部イベント企画
写 真家 白尾元理 講演会「地球史46億年を撮る」
日時:2010年5月8日(土)
■北海道支部:「地質の日」・「国際博物館の 日」記念展示:
北海道大学総合博物館企画展示「わが街の文化遺産 札幌軟石」
期間:2010年4月27日(火)〜5月30日(日)
■ 関東支部
第2回地質技術伝承講習会:地質技師長が語る地質工学余話
「共生型地下水利用に向けての「育水」の提唱」
日 時:2010 年6月6日(日)
■中部支部:「地質の日」記念
サイエンスフェステイバル in 五十嵐キャンパス(新潟大学)
日 時:5月16日(日)12:00~15:00
場所:新潟大学理学部
■ 近畿支部:「地質の日」協賛行事
第27回地球科 学講演会「大阪の温泉は本当に温泉か?−大阪平野の地下水を可視
化する−」
日時:2010年5月9日(日)
■ 西日本支部:後援「地質の日」企画
身近に知る「くまもとの大地」
日時:2010年5月9日(日)
それぞれの詳しい情報 は、、、
http://www.geosociety.jp/name/content0060.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】 2010年度会費督促請求について
──────────────────────────────────
—2010年度およびそれ以前 の会費が未入金の方へ—
1.次回の自動引き落とし日は6月23日(水)です.2010年度会費が未入金の方で
6月23日の自動引落をご希 望される方は,News誌4月号(月末発送予定)の巻末頁
に掲載される「預金口座振替依頼書」をご利用の上,5月12日(水)までにお申込
み 下さい.
2.郵便振替用紙によるお振り込みの方には,督促請求書(郵便振替用紙)を送
付いたします.お手元に届きましたら,早急 にご送金くださいますようお願いい
たします.督促請求書の発送は5月末頃を予定しております.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】 支部情報
──────────────────────────────────
■中部支部:2010年支部年会
日時:2010 年7月24日(土)
会場:福井県立恐竜博物館 3階 ガイダンスルーム
(参加者は無料で博物館(常設展)を見学できます)
シンポ ジウム 「ジオパークと野外現場を生かした教育普及活動」
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
■ 北海道支部:支笏湖ビジターセンター出前展示「わが街の文化遺産 札幌軟石」
期間:2010年6月3日(木)〜6月30日(水)
会場:支 笏湖ビジターセンター レクチャールーム
現在進行中の「地質の日」記念行事『北海道大学総合博物館企画展示「わが街の
文化遺産 札幌軟 石」』に引き続いて、6/3〜6/30の間、自然公園財団支笏湖支部
と千歳市のご協力を得て、サテライト展示(出前展示)を行ないます。
詳 しくは、
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】 日本地質学会第117年総会/(一社)日本地質学会第2回総会
──────────────────────────────────
2010 年5月23日(日)18:00〜
会場 幕張メッセ 国際会議場(3F 304会議室)
任意団体および一般社団法人日本地質学会の総会を 開催いたします.議事次第等
詳しくは下記をご参照下さい.
<任意団体>
http://www.geosociety.jp/outline/content0079.html
<一 般社団法人>
http://geosociety.sakura.ne.jp/jgs/#sokai_2010
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】 その他のご案内
──────────────────────────────────
■原子力総合シンポジウム2010
原子力 平和利用技術が目指すもの〜国際動向をふまえた現状と将来像〜
日時 5月26日(水)-27日(木)
場所 日本学術会議講堂
事前 登録必要(5/20まで)
詳しくは、http://www.aesj.or.jp
<訂正>
ニュース誌4月号 CALENDAR掲載欄で、日程の記載に誤りがありました。正しくは以
下の通りです。
◯地質学史懇話会
6月20日 (日)13:30-17:00
場所:文京区シビックセンター4階シルバーセンター内会議室A
加藤碵一「宮澤賢治論の地的背景」/菊池真一 「水路図の歴史」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報
──────────────────────────────────
■ 福岡大学理学部地球圏科学科助教公募:地史・環境変動系(5/28締切)
詳細およびその他 の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報 告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
ま でに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質マンガ ロトウに迷う
地質マンガ
戻る|次へ
No.099 2010/05/18 geo-flash もうすぐ100号!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.099 2010/ 5/18┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】 地質系統・年代の日本語記述ガイドライン
【2】日本地質学会第117年総会/(一社)日本地質学会 2010年度総会
【3】2010年度 会費督促請求について
【4】韓日地質学会 室戸合同大会ファーストサーキュラー公開中
【5】まもなく富山大会の申込受付開始です!
【6】 その他のご案内
【7】公募情報
【8】地質マンガ ロトウに迷う
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 地質系統・年代の日本語記述ガイドライン
──────────────────────────────────
先般の第四紀の下限問題 の議論の際に,年代の記述がよく整備されていないこと
が明らかとなりました.過去には,地質系統・年代名に関して,どのような訳語を用
い るのかとの問い合わせもありました.そこで、、、
続きを読む
http://www.geosociety.jp/name/content0062.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】 日本地質学会第117年総会/(一社)日本地質学会 2010年度総会
──────────────────────────────────
2010 年5月23日(日)18:00〜
会 場 幕張メッセ 国際会議場(3F 304会議室)
任意団体および一般社団法人日本地質学 会の総会を開催いたします.議事次第等
詳 しくは下記をご参照下さい.
<任意団体>
http://www.geosociety.jp/outline/content0079.html
<一 般社団法人>
http://geosociety.sakura.ne.jp/jgs/#sokai_2010
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】 2010年度会費督促請求について
──────────────────────────────────
■■■2010年度およびそ れ以前の会費が未入金の方へ■■■
1.次回の自動引き落とし日は6月23日(水)です.2010年度会費が未入金の方で
1月から5月上旬 までの間に自動引落の手続きをされた方は6月23日に引き落とし
がかかります.引き落とし不備にならぬよう,残高の確認をお願いします.
2. 郵便振替用紙によるお振り込みの方には,督促請求書(郵便振替用紙)を送
付いたします.お手元に届きましたら,早急にご送金くださいますようお願 いい
たします.督促請求書の発送は5月末頃を予定しております.
※7月上旬頃までに入金確認が取れない場合には,7月号の雑誌か ら発送停止
となります.定期的に雑誌をお受け取りになりたい方は,お早めにご送金くださ
いますよう,よろしくお願いいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】 韓日地質学会 室戸合同大会ファーストサーキュラー公開中
──────────────────────────────────
2010年8月23-25日に予定されております韓日地質学会−室戸合同大会−のファー
ストサーキュラーが公開中です.
韓日地質学会室 戸合同大会では,韓国と日本における地質学の最新の研究成果
に関する情報交換や,地質学を学ぶ若者の交流を目的としています.学生サポー
ト もありますので学生さんにはふるって参加いただきたいと思います.
詳しくは,こちら
http://struct.geosociety.jp/koreajapangs2010/
韓 日地質学会室戸合同大会事務局
竹下 徹・橋本善孝
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】 まもなく富山大会の申込受付開始です!
──────────────────────────────────
第117年学術大会(富山 大会:9/18-20)の各種申込がまもなく開始となります
(5月末受付開始予定)。
今年は、「高度差4000mの地質学」をキャッチフ レーズに,富山大学を中心に中
部支部の会員にご協力をいただき、シンポジウム・トピックセッション・普及行
事などなど、たくさんの企画を ご用意しています。
詳しくは、ニュース誌5月号及び次号メルマガ等でご案内の予定です。
■主な締切の予定(WEB)
講演 申込・要旨投稿締切:7月7 日(水)
参加登録締切:9月3日(金)
(日本地質学会行事委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のご案内
──────────────────────────────────
■ 地球惑星科学連合若手の集いのご案内
テーマ:地球惑星科学研究,私たちに今出来ることは何か?(今やらなくて
いけないのは何か?)
日 時: 2010年5月25日(火)18:15〜20:15
会場: 幕張メッセ連合大会会場202室
主催: 地球システム・地球進化ニューイヤースクール(NYS)事務局
http://quartz.ess.sci.osaka-u.ac.jp/~earth21/school/gakkou/gakkou.html
趣 旨: この夜間小集会では,様々な分野の若手研究者〜学部生が主体とな
り,地球惑星科学研究の今後を考えることを目的としています.「自分たち自 身
に今後何が出来るかを見つめ直す」ことを目指しており,世代別でのグループワー
クを通じて,参加者が自ら意見を出す場にしたいと考えて います.
夜間小集会に関する問い合わせは,
NYS事務局(代表 産総研・大坪earth21-nys8th@m.aist.go.jp) まで.
■日本学術振興会による科研費・特別研究員制度に関する説明会
日本学術振興会では、地球惑星科学連合大会の期間中に、科研 費制度および特別
研究員制度の説明会を開催します。
科研費制度をめぐる昨今の状況、基盤研究・若手研究を中心とした科研費、PD・D
C を中 心とした特別研究員制度の申請・採択に関する昨今の状況、学術システムセ
ンターの役割などを説明いたします。特に、地球惑星科学をめぐる状 況につ いて
も紹介します。
日時:2010年5月25日(火) 17:15-19:15
会場:幕張メッセ国際会議場 国際会議 室(2階)
■海底地形名称の提案募集
海上保安庁では,海図や海底地形図などに記載する海底地形の名称を決定する
「海底 地形の名称に関する検討会」を下記のとおり開催します.開催にあたり,
関係学会等に広く海底地形名称を募集することとしましたのでお知らせしま す.
同検討会で決められた海底地形名は,海上保安庁海洋情報部のホームページで紹
介しております.
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KOKAI/ZUSHI3/topographic/topographic.htm
■IODP 普及講演会:地球深部への挑戦深海掘削におけるサイエンスとテクノロジー
の最前線
日時:2010年5月22日 (土)13:30〜16:30
場所:東京海洋大学越中島キャンパス・越中島会館(江東区越中島)
対象者:海洋科学・技術を学ぶ大学生と関 連分野の教員および、海洋科学に関
心のある一般の方々・100名(参加費無料、事前登録不要)
詳しくは、
http://www.j-desc.org/modules/tinyd0/rewrite/index_j.html
■ 日本学術会議主催 公開講演会
「高レベル放射性廃棄物の処分問題解決の途を探る」
日時:平成22年6月4日(金)13:00〜18:30
会 場:日本学術会議 講堂
参加費:無料・予稿集:2,000円・定員:300名
詳しくは、http://www.scj.go.jp/ja /event/pdf/92-k-1.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報
──────────────────────────────────
■ 高知大学海洋コア総合研究センター研究員(非常勤職員)(6/7締切)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】 地質マンガ
──────────────────────────────────
ロトウに迷う
原案:chiyodite マン ガ:Key
http://www.geosociety.jp/faq/content0233.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報 告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
ま でに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.100 2010/06/01 geo-flash 法人へ完全移行 geo-Flashも100号!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.100 2010/ 6/1 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】 法人へ完全移行(任意団体117年の歴史に幕)
【2】富山大会:講演申込・参加登録 受付開始しました。
【3】科学技術基本政策パブリッ クコメント 声を送ろう
【4】韓日地質学会 室戸合同大会 学生さん注目
【5】支部情報いろいろ
【6】その他のお知らせ
【7】 geo-Flash 100号!記念アンケート ご協力お願いします
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 法人へ完全移行(任意団体117年の歴史に幕)
──────────────────────────────────
geo-Flash100号と一般社団法人日本地質学会の新たな出発に際して
地球惑星科学連合大会初日の5月23日に開催された第117年地質学会総会
において,任意団体としての日本地質学会はその幕を下ろしました.その全ての
活動や資産は2008年12月に設立された一般社団法人日本地質学会に委譲さ
れ,名実共に一般社団法人としての新体制がスタートしました.これまで,諮問
委員会的役割を果たしてきた評議員会は,一般社団法人の理事会として新しい役
割を果たして行くことになります.理事会は社団法人の日常的な業務について意
思決定を行うとともに,学会活動を大いに担って行くことになるでしょう.
同日に開催された一般社団法人の第1回理事会においては,昨年の学会役員選
挙の結果に基づいて,学会長(理事長)と2名の副会長(副理事長)が選出され
ました.また,常務理事,副常務理事を含む15名の執行理事が選出されました.
執行理事の詳細な役割分担は近日中に決まる予定です.今回の執行理事会には6名
の方が新たに加わっており,年齢構成や所属上のバランスが取れた若々しい執行
理事会となったと感じています.
このように,2010年は,117年の長い歴史を持つ日本地質学会がその歴史を閉じ,
一般社団法人日本地質学会としてその実質的なスタートを切る歴史的な年度にな
りました.一般社団法人日本地質学会は,何にもまして,日本における地質学の
研究・教育のレベルを向上させるために尽力し,日本における地球科学関連学会
の中で中心的な役割を担っていく所存です.また,地質学に関する産学官の連携
を深める努力を継続・発展させます.
現在,地球環境問題の深刻化,資源の枯渇とエネルギー問題,異常気象や頻発
する地震・火山による大規模自然災害問題など,地質学が果たすべき社会的役割
はますます重要になっています.しかし,例えば高校での理科3科目選択制の開
始がまぢかに迫っていますが,高校地学教師は「絶滅危惧種」に例えられるくら
い,現状では圧倒的に多数の都道府県で長期間にわたって採用が全くありません
(地質ニュース2010年5月号:特集「地学教育問題の現状と課題」参照).一方,
明るいニュースとしては,ジオパーク運動が巨大な前進を始めており,関連自治
体での学芸員・専門員などの採用の動きのニュースも届き始めています.地質学
会はこれらの問題・課題に強力に取り組み,地質学の社会的地位の向上を図りま
す.
また,2012年には目覚ましく発展しつつある国際地学オリンピックがつくばを
舞台として開催されます.そしてユネスコ国際ジオパーク会議が島原で 開催され
ることも決定しており,これらが地質学に対する大きな社会的関心を惹起する機
会となることは間違いありません.本学会はこれらの成功のために大いに力を発
揮する所存です.
今年9月18-20日に富山大学で開催される地質学会学術大会では,これらの現状
打開やさらなる発展に向けて,学術活動の一層の発展とともに,地質学が今こそ
その役割にふさわしい社会的地位を獲得するための大きな第一歩を歩みだす場と
なるよう,大いに力を発揮しましょう.
一般社団法人日本地質学会 会長 宮下純夫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】 富山大会:講演申込・参加登録 受付開始しました。
──────────────────────────────────
日本地質学会 第117年学術大会(富山大会)−高度差4000m地質学−
日程:2010年9月18日(土)〜20日(月・祝)
会場:富山大学五福 キャンパス ほか
2010年日本地質学会年会は,「高度差4000mの地質学」をキャッチフレーズに,
富山大学を中心に中部支部 の会員にご協力をいただき開催いたします.講演申込
および事前参加登録を開始致しました。多く方々のご参加をお待ちしています。
講演申込 締切:7月7日(水)(郵送の場合は7月2日)
詳しくは、大会HPをご覧下さい。
http://www.geosociety.jp/toyama/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】 科学技術基本政策パブリックコメント 声を送ろう
──────────────────────────────────
日本学術会議よ りパブリックコメントの案内がありました.
会員の皆様のご協力をお願い致します.
総合科学技術会議では、現在、第4期科学技術基 本計画の策定に向けての
検討を進めているところです。
このたび、同計画の骨格となる「科学技術基本政策策定の基本方針(案)」
が 取りまとめられ、5月27日(木)より、パブリックコメント手続が開
始されました(パブリックコメントの期間は、6月7日(月)まで)。
本 パブリックコメントの詳細、意見提出様式等につきましては、以下の
URLから参照できるようになっておりますので、その旨お知らせさせて
い ただきます。
上記基本方針に対する御意見等を提出される場合には、以下のURLより、
直接内閣府(科学技術政策担当)あてに御提出くださ いますようお願い申
し上げます。
パブリックコメントURL
http://www8.cao.go.jp/cstp/pubcomme/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】韓日地質学会 室戸合同大会 登録受付中 学生さん注 目!
──────────────────────────────────
韓日地質学会−室戸合同大会−のファーストサーキュラーが公 開中です.
韓日地質学会室戸合同大会では,韓国と日本における地質学の最新の研究成果
に関する情報交換や,地質学を学ぶ若者の交流を目的 としています.学生サポー
ト もありますので学生さんにはふるって参加いただきたいと思います.
間もなく受け付け締切です!
日 時:8月23日(月)-25日(水)
場所:室戸青少年自然の家および室戸ジオパーク
参加登録締切:6月11(金)
詳しくは,こちら
http://struct.geosociety.jp/koreajapangs2010/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】 支部情報
──────────────────────────────────
■ 関東支部:地質技術伝承講演会〜地質技師長が語る地質工学余話(第2回)
講師:中村 裕昭氏(株式会社地域環境研究所)
テーマ:共生型地 下水利用に向けて「育水」の提唱
日時:6月6日(日)14:00-16:30
場所:北とぴあ 飛鳥ホール(東京都北区王子 1−11−1)
参加費:無料
申込等詳細は、関東支部HP<http://kanto.geosociety.jp/>
■ 中部支部:2010年支部年会
日時:7月24日(土)
会場:福井県立恐竜博物館 3階 ガイダンスルーム
(参加者は 無料で博物館(常設展)を見学できます)
シンポジウム 「ジオパークと野外現場を生かした教育普及活動」
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
■ 北海道支部:支笏湖ビジターセンター出前展示「わが街の文化遺産 札幌軟石」
期間:6月3日(木)-6月30日(水)
会場:支 笏湖ビジターセンター レクチャールーム
6/3〜6/30の間、自然公園財団支笏湖支部と千歳市のご協力を得て、サテライト展
示(出前展 示)を行ないます。
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】 その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■科学・技術フェスタ in 京都−平成22年度産学官連携推進会議−
日時:年6月5日(土) 9:30-16:30
場所:国立京都国 際会館(京都市左京区宝ヶ池)
http://www.kagakugijutsu-festa.jp/program.html
■ 学校教育で地学は生き残れるか?:学会と教育現場との連携に向けて
日時:6月19日(土) 13:00-18:00
場所:早稲田大学22 号館202教室
主催:日本第四紀学会 後援:日本地質学会ほか
http://wwwsoc.nii.ac.jp/qr/event/qr.html#sympo0619
■ 資源地質学会第60回年会シンポジウム
「リチウム・トリウム -資源とその利用-」
日時: 6月23日 (水) (10:55-17:50)
場所:東京大学小柴ホール(本郷キャンパス)
http://www.kt.rim.or.jp/~srg/
■IGCP507(白 亜紀のアジア古気候)第5回国際シンポジウム(インドネシア)
◎シンポジウム(口頭発表・ポスター発表)
日時:10月7日(木)-8日 (金)
場所:ヨグヤカルタ市
講演申込・要旨締切:7月16日(金)
◎巡検日時:10月9日(土)
場所:ジャワ島中部 Luk Uloのテクトニックメランジェ
不明な点は国内コーディネーター(金沢大・長谷川卓)まで.
http://igcp507.grdc.esdm.go.id/
■ 第26回ゼオライト研究発表会
日時:2010年12月2日(木)-3日(金)
会場:タワーホール船堀(東京都江戸川区船堀)
テー マ:ゼオライト,メソ多孔体,およびその類縁化合物に関連した研究の基礎
から応用まで
協賛:日本地質学会ほか
講演申込締切:7月 26日(月)
http://www.jaz-online.org/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】 geo-Flash 100号!記念アンケート ご協力お願いします
──────────────────────────────────
geo- Flashも2007年7月創刊以来おかげさまでついに100号になりました。今後とも
皆様にお役にたつgeo-Flash(そしてニュース誌、 ホームページ)であるために皆様の
ご意見をお聞かせ下さい。下記にアンケートを準備いたしました。ご協力をお願いいた
します(締め切り6 月末)。
http://www.geosociety.jp/cgi_enq/enq.cgi?id=geoflash
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報 告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
ま でに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.103 2010/06/30 geo-flash(臨時) 講演申込:7月7日(水)17時締切 来週です!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.103 2010/ 6/30┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
----------------------
富 山大会関連情報
【1】講演申込:7月7日(水)17時 締切です!
【2】ランチョン・夜間集会 間もなく申込締切です
【3】就職支援プログラム参加企業募集
【4】地学教育関連情報
【5】富山大 会に関連したプレス発表を希望される方へ
----------------------
【6】火山ガス災害が発生した酸ヶ湯温泉付近の地質について
【7】支部情報
【8】JABEE事務局ニュース
【9】学術会議シンポ「21世紀日本における学術の展望」
【10】気候変動に関心のある皆様へ:学術会議地球惑星科学委員会声明文
【11】公募情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】富山大会:講演申込:7月7日(水)17時締切です!
──────────────────────────────────
日本地質学会第 117年学術大会(富山大会)−高度差4000m地質学−
講演申込等各種申込受付中です。講演申込の締 切が近づいてきました。締切間際
はアクセスが集中し、繋がりにくくなる状況も予想されます。お早めにお申し込
み下さい。またシステムの都合上、締切日の夕 方17時に申し込み画面は閉じられ
ます。くれぐれもご注意ください。
講演申込(要旨投稿)締切:7月7日 (水)17:00厳守(郵送の場合は、7月2日必着)
詳 しくは、大会HPをご覧下さい。
http://www.geosociety.jp/toyama/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】 富山大会:ランチョン・夜間集会 間もなく申込締切です
──────────────────────────────────
富山大会のランチョン・夜間集会は間もなく 申込締切です。
会合を 予定されている世話人の方は、忘れずにお申し込み下さい。
ランチョン・夜間集会申込締切:7月2日(金)
詳細は、下記を ご参照ください。
http://www.geosociety.jp/toyama/content0012.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】就職支援プログラム参加 企業募集
──────────────────────────────────
本 年も「就職支援プログラム」を開催することになりました。本プログラムは、
学会に参加される学生・院生および大学教官の会員、ならびに富山大学の 学 生・
院生・関係者らを対象に、本会賛助会員をはじめとする関連会社との相互の情報
交換を行う場を提供しようというものです是非、ご参 加下さい。
日程 2010年9月19日(日)14-17時(*時間帯は若干変更になる場合があります)
参加無料
参加申込締切:8 月10日(火)(必着)
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/toyama/content0006.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地学教育関連
──────────────────────────────────
■ 小さなEarth Scientistのつどい
〜第8回 小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜参加校を募集中です。
日時 2010年 9月19日(日) 9:00〜15:30
後援 富山県教育委員会・富山市教育委員会(予定)
参加対象
・小,中,高校地学 クラブならびに理科クラブ等の活動成果の発表
・小,中,高校の授業における研究成果の発表
・活動,研究内容は地学的なもの(地質や気象な どの地球科学・環境科学,天文
など)
申込締切:7月20日(火)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/toyama/content0005.html
■第9回理科教員対象見学旅行:参加者募集中
実施日:9月20日(月・祝日)
テー マ:「糸魚川ジオパーク:ヒスイ探訪ジオツアー」
日本を代表するヒスイの産地,新潟県糸魚川市を訪ねます.地学的な見どころだ
けでなく, ヒスイと日本人との関係をさまざまな視点(考古学や宝石としてのヒ
スイなど)から考える,そのような見学旅行です.
定員:25名
費 用:5,000円(バス代・保険代・昼食代・見学資料代)
申込期限:7月31日(土)
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/toyama/content0005.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】富山大会に関連したプ レス発表を希望される方へ
──────────────────────────────────
富山大会での講演や行事について,8月下旬にプレス発表を行う予定です.
昨年の岡山大会でも多数のメディアに取り上げられ,会員の研究成果が多 いに
注目されました.富山大会で発表される予定の案件で,学会からのプレス発表を
ご希望の方は,8月10日(火)までに学会事務局にご連 絡願います.全ての案件を
プレス発表することはできませんが,社会への情報発信として特筆すべき成果は
積極的に公表して行きたいと考えて おります.会員の皆様におかれましては,プ
レスリリース解禁日をお守りいただき,公平かつ効果的な情報発信にご協力願い
ます.不明な点は 学会事務局までお問い合わせ願います.
登録締切:8月10日(火)
プレス発表(投げ込み):8月下旬
現地説明会 (解禁日):8月下旬
連絡先:日本地質学会事務局<journal@geosociety.jp>
プレス発表に関するQ&Aなども↓↓↓
http://www.geosociety.jp/toyama/content0031.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】火山ガス災害が発生した酸ヶ湯温泉付 近の地質について
──────────────────────────────────
火山ガス災害 (2010年6月20日)が発生した酸ヶ湯温泉付近の地質について
(産業術総合研究所・火山研究情報のサイト)
http://www.gsj.jp/HomePageJP.html
http://www.gsj.jp/kazan/hakkouda/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
■北海道支部企画野外巡検
「夕張市・白金川流域の地質—砂金・化石の 産状と白亜紀海洋無酸素事変層準
の観察—」
2010年9月4日(土)・5日(日)
定員:30名
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline /content0023.html
■関東支部顕彰制度制定へ(感謝状贈呈者推薦のお願い)
推薦は、8/20(金)まで
詳しくは、http://kanto.geosociety.jp/
■ 中部支部:2010年支部年会
日時:7月24日(土)
会場:福井県立恐竜博物館 3階 ガイダンスルーム
シンポジウム「ジオパークと野外現場を生かした教育普及活動」
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
■ 近畿・四国・西日本三支部合同
「ジオ・シンポジア 2010 in 北九州」
(日本地質学会近畿・四国・西日本支部三支部合同例会)
日時 7月18日(日)13:30〜
場所 北九州市立自然史・歴史博物館(いの ちのたび博物館)ガイド館
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】JABEE事務局ニュース No.4
──────────────────────────────────
社員(正会員)・賛助会員をはじめとする JABEEご関係の皆様へ、情報のより広い
共有をめざして「JABEE事務局ニュース」を発信されています。是非ご覧下さい。
JABEE事務局ニュース No.4 (2010.6.18)
http://www.jabee.org/OpenHomePage/jabee_e-news_4_100618.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】学術会議シンポ「21世紀日本におけ る学術の展望」
──────────────────────────────────
「日本の展望−学術からの提言2010」の 内容のエキスを日本の展望委員会のメン
バーが報告し、日本の学術の今後をともに語り合うことを目的にして開催します。
奮ってご参加下さい。
日 時 平成22年7月3日(土) 13:00〜17:00
場 所 専修大学(神田キャンパス)7号館 731号室
主 催 日 本の展望委員会
専修 大学社会科学研究所、同今村法律研究室、同法学研究所
詳細は日本学術会議事務局ホームページ
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf/97-s-k-1.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】気候変動に関心のある皆様へ:学術会議地球惑星科学委員会声明文
──────────────────────────────────
2005年までの過去100年間、大気CO2濃度は 280ppmから380ppm へ
と増加した。この濃度の上昇は、人為起源のCO2の排出、すなわち化石燃料の消費
にその原因を求めるこ とができる。一方、全球平均気温は、同期間に、約0.7
℃上昇した。この地球温暖化の原因について、2007年11月に発表されたIPC
C(気 候変動に関する政府間パネル)の第四次評価報告書(例えばhttp://www.data.
kishou.go.jp/climate /cpdinfo/ipcc/ar4/index.htmlを参照)では、人為起源の
温室効果ガスによってもたらされた可能性が非常に高いという 結論を出した。
最近になり、IPCCにおける作業の公正さや、一部のデータの確実性などについ
て疑問を呈する見解が見られるようにな り、これに対して国際科学会議(ICSU)か
ら、声明文が提出された。私たち、日本学術会議地球惑星科学委員会の有志は、
国際科学会議の 声明に賛同するものであり、さらに今後の対応のあり方などにつ
いて、以下に声明を表するものである。
平成22年6月23日
日本学 術会議地球惑星科学委員会有志一同
続きを読む、、、http://www.jpgu.org/whatsnew /100623ipcc.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報
──────────────────────────────────
■東邦大学理学部化学科非常勤講師(7/7 締切)
■北海道大学大 学院理学研究院自然史科学部門地球惑星システム科学分野特任助期
教(女性に限る)(7/30締切)
■神戸大学大学院理学研究科 地球惑星科学専攻教授(8/31締切)
■平成23年度研究船利用公募課題の募集「みらい」「なつしま」「よこすか」
「かいれい」等(7/20締切)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿 募集中です.
geo- Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信は できません。
No.106 2010/08/03 geo-flash 世界自然遺産推薦地「小笠原諸島」
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.106 2010/8/3 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】解説:世界自然遺産推薦地「小笠原諸島」
【2】院生・ポスドクの皆さん、学会に行きましょう!
【3】富山大会見学旅行申込受付中
【4】7月に発生した豪雨・土砂災害の地質情報
【5】第2回惑星地球フォトコンテスト作品募集
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報
【8】8月博物館特別展示・イベント情報
【9】地質マンガ
【10】企画アンケート「ポスター会場でのビール販売はどう?」中間報告付
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】解説:世界自然遺産推薦地「小笠原諸島」
──────────────────────────────────
海野 進(金沢大学・地球学教室)
小笠原諸島は東京の南1000 kmに点在する古第三紀の火山岩類と活火山を含む
第四紀火山からなる島嶼群である.小笠原は「屋久島」,「白神山地」,「知床」に
続く4番目の世界自然遺産候補としてユネスコの世界遺産委員会に推薦され,
2010年7月に国際自然保護連合(IUCN)の専門家による現地視察が行われた.
これまでの3つの世界自然遺産がいずれも生態系や動植物で登録されている
のに対し,小笠原諸島は「生態系」「生物多様性」に加えて「地形・地質」が重要な
遺産価値として挙げられており,もし登録されれば日本で最初の「地形・地質」の
世界自然遺産が誕生することになる.
続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0056.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】院生・ポスドクの皆さん、学会に行きましょう!
──────────────────────────────────
今回の富山大会では、8件のシンポジウムと26件のセッション(6件のトピックセッ
ションを含む)に、560件を超える発表申し込みがありました。世界最先端を切り
開く研究から、地域地質の詳細な調査報告まで、実にさまざまな発表が行われる
予定です。いい刺激を受けてください!
院生・ポスドクの皆さんに特にオススメなのは...
■「就職支援プログラム」… 地質関連会社による説明会が開催される予定です。
業界の方と直接話ができる絶好の機会です!
■「見学旅行(巡検)」… 本大会のスローガン(高度差4000mの地質学)にふさわし
い9件ものコースが用意されています。その道のプロの案内で、重要な露頭を観
察することができます。また、自分のボス以外の研究者の考えや着眼点を知るこ
ともできます(これ、重要です)。受付中です!
■「懇親会」… 個人的に強くお勧めします。私が院生だった頃、地質学会の何が
強く印象に残っているかというと、この懇親会です(単に私が酒好きということも.
..)。「この人が○○さんか」「○○さんって、すごい酒飲みだな」と、興味深い
観察事実を得ることができます(笑)。また、先生や知っている研究者に頼んで自
分を紹介してもらうのもいいでしょう。受付中です!
連合大会とは違う雰囲気を、ぜひ楽しみましょう。皆さんの参加をお待ちしてお
ります。
星 博幸(行事委員長, 愛知教育大学)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】富山大会見学旅行申込受付中
──────────────────────────────────
いずれのコースもまだ充分申込可能です.たくさんのご参加をお待ちしています.
各コースのみどころはこちらから↓↓↓
http://www.geosociety.jp/toyama/content0032.html
■教官のみなさま、これからの地質学を担う若手に,その道の専門家の案内によ
り地質観察を経験させる絶好のチャンスです!ぜひ指導学生・院生・PD等に参加
を呼び掛けてください。
申込締切:9月3日(金)18時
http://www.geosociety.jp/toyama/content0027.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】 7月に発生した豪雨・土砂災害の地質情報
──────────────────────────────────
7月には各地で豪雨・土砂災害が発生しましたが、災害の発生した地域の地質の特
徴についての解説が産総研地質調査総合センターのHPに掲載されています。
地質調査総合センターのHP:
■2010年7月15日に発生した岐阜県南部の集中豪雨災害地域の地質情報
http://www.gsj.jp/Gtop/topics/gifu/index.html
■2010年7月16日に発生した広島県庄原市北部の土砂災害地域の地質
http://www.gsj.jp/Gtop/topics/syoubara/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第2回惑星地球フォトコンテスト作品募集
──────────────────────────────────
このコンテストはユネスコおよび国際地質科学連合による国際惑星地球年(2007-
2009年)を契機に始められたものです。私たちの惑星「地球」をテーマにした写真
を公募し、優秀な作品を表彰するとともに、広報、普及、教育活動を通じて地球
科学に対する理解を深め、学術の振興と社会の発展に寄与・貢献することを期待
するものです。
応募締切:2011年1月31日(月)
応募方法・第1回コンテストの様子など詳しくは、http://photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】 その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■世界石油会議カタール大会講演募集
2010年4月1日、世界会議(World Petroleum Council: WPC)は、2011年
12月4日(日)〜8(木)ドーハ(カタール)で開催する第20回世界石油会議
第における技術プログラムのフォーラム(Forum)の論文募集を開始しました。
締切:2011年1月31日
要約提出に当たり国内委員会としても、希望される場合には無償にて提出要約の
英文作成にご協力させていただきます.
詳しくは、http://www.wpcjnc.jp
■2010年秋季地質の調査研修
研修期間:2010年10月4日(月)〜10月8日(金)(4泊5日)
研修場所:房総半島中部域(千葉県君津市とその周辺)
募集人員:5名前後
申込締切:2010年8月27日(金)
詳しくは、http://www008.upp.so-net.ne.jp/gsis/gykensyu.htm
■若手アカデミー活動検討分科会の委員候補者の募集
日本学術会議では、現在、若手の研究者によるアカデミー活動の振興を重要な課
題として位置付け、そのための取組みを進めて います。その一環として、下記の
要領で委員候補者を公募することとしました。多くの方からのご応募を期待して
います。
募集締切:8月20日(金)
詳しくは、http://www.scj.go.jp/
■高橋孝三会員が、第3回海洋立国推進功労者表彰(内閣総理大臣賞)を受賞
表彰対象:【海洋に関する顕著な功績分野(海洋に関する科学技術振興部門)
「海洋における気候変動研究」】
詳細は以下に掲示されています
https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji09_hh_000029.html
■地球システム・地球進化 秋の学校 in 関西 2nd circular
テーマ:「融合から発展する地球惑星科学」地球惑星科学内外での分野の融合に
よって新たに切り開かれる研究について,第一線の研究者の方々に講演をしてい
ただきます.また,受講者同士がグループに分かれて議論できる場を設ける予定
です.
日時: 2010年10月9日(土)
場所:大阪大学豊中キャンパス理学部D501教室
参加登録締切:9/10(金)あるいは定員(100名程度)に達し次第終了.
詳しくは、
http://quartz.ess.sci.osaka-u.ac.jp/~earth21/school/2010/index.html
(各講演内容の紹介も見ることができます)
■日本の活断層のフォトフォトコンテスト:作品募集中
日本活断層学会では,活断層に関する教育・普及活動の一環として「日本の
活断層・フォトコンテスト」を実施しています.
変動地形や活断層露頭写真に,簡単な説明と撮影場所の地図を添えて,ご応募
下さいますようお願い致します.(締切は9月末日).11月末頃発表予定.
詳しくは, http://danso.env.nagoya-u.ac.jp/jsafr/fotocontest01.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報
──────────────────────────────────
■第13回大学婦人協会守田科学研究奨励賞受賞候補者募集 (11/30締切)
■首都大学東京都市環境学部地理学教室(地理環境科学域)教員公募(9/21)
■東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教員公募(9/24)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】8月博物館特別展示・イベント情報
──────────────────────────────────
全国各地で、夏休み特別展・企画展開催中!
詳しくは↓↓↓
http://www.geosociety.jp/name/content0064.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】地質マンガ
──────────────────────────────────
「巡検に行こう!」
原案:星 博幸 マンガ化:Key
www.geosociety.jp/faq/content0240.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】企画アンケート「ポスター会場でのビール販売はどう?」中間報告付
──────────────────────────────────
海外の学会ではポスター会場等でビールやワインをたしなみつつ議論に花咲かせ
ている風景をよく目にします.
地質学会のポスター会場でビール等が販売されたら皆さんはどう思いますか?
●回答はこちらから
http://www.geosociety.jp/cgi_enq/enq.cgi?id=kikaku01
<中間報告>
盛り上がるのでよい (74.2%) 23pt
飲み過ぎ防止策があればよい (9.7%) 3pt
アルコールはよくない (6.5%) 2pt
どちらでもよい (6.5%) 2pt
飲食はよくない(3.2%) 1pt
計31pt
●集計結果はこちらから
http://www.geosociety.jp/cgi_enq/enq.cgi?id=kikaku01&mode=result
どうぞよろしくお願いします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.102 2010/06/15 geo-flash 「はやぶさ」はきっとジオロジスト
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.102 2010/ 6/15┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】小惑星探査機「はやぶさ」の帰還に関して声明
【2】富山大会:講演申込・参加登録 受付中。
【3】コラム:宮澤 賢治の地的背景を示す地質学史資料
【4】科学技術基本政策へコメントを送りました
【5】高等学校理科地学担当教員の増員に関する要望書を 提出しました
【6】文科省「政策創造エンジン 熟議カケアイ」に声を送ろう
【7】 支部情報いろいろ
【8】第9回理科教員対象見学旅行 参加者募集
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報
【11】6-7 月博物館特別展示・イベント情報
【12】geo-Flash 100号!記念アンケート継続中 (中間報告付)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】小惑星探査機「はやぶさ」の帰還に関して声明
──────────────────────────────────
小惑星探査機「はやぶさ」が小惑星イトカワでの探査を終えて地球に帰還
し,試料回収カプセルが無事回 収された快挙に,日本地質学会から祝意を表
します.「はやぶさ」が,小惑星イトカワの構造や表面状態について多くの
興味深い知見をもたら し,様々な技術的困難を乗り越えて地球に帰還したこ
とは,関係者の粘り強い心血を注いだ努力の賜物です.今回の探査に携わら
れた多くの関 係者の皆さまの労をたたえます.
地球上の変動やこれまでの変遷過程を理解する上で,直接的なサンプルが
果たしてきた役割は大きなものが あります.地質学の発展はまさにそうした
直接的なサンプルやフィールドでの観察によって支えられてきました.月か
ら得られた岩石試料が, 月のみならず,地球の生成・発展の解明にとっても
大きな役割を果たしたことは,よく知られています.
今後も始原天体などへのサンプルリ ターン探査がおこなわれ,地球・惑星・
生命の起源と進化に関する解明が進むことを期待しますとともに,日本地質
学会としてもそうした先端 的・学際的な研究の発展のために力を尽くす所存
です.
日本地質学会 会 長 宮下純夫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】富山大会:講演申込・参加登録 受付中。
──────────────────────────────────
日本地質学会第 117年学術大会(富山大会)−高度差4000m地質学−
講演申込等各種申込受付中です。
日程:2010年9月18日(土)〜 20日(月・祝)
会場:富山大学五福キャンパス ほか
講演申込締切:7月7日(水)(郵送の場合は7月2日)
詳しく は、大会HPをご覧下さい。
http://www.geosociety.jp/toyama/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】 コラム:宮澤賢治の地的背景を示す地質学史資料
──────────────────────────────────
金 光男・山田直 利・鈴木尉元・加藤碵一・盛岡科学史資料調査団
2009年7月「予察地質図」ほかの図幅類と多くの貴重な古書籍群が,国立大学法人
岩 手大学に所蔵されることが明らかとなった.それらの発見に至るまでの経緯と
意義について簡単に報告する.
続きを読む、、、 http://www.geosociety.jp/faq/content0207.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】 科学技術基本政策策定の基本方針(案)にコメント送付
──────────────────────────────────
前号の geo-Flashにてご案内いたしましたように,総合科学技術会議が検討
を進めている第4期科学技術基本計画の骨格となる「科学技術基本政策策 定
の基本方針(案)」に対してパブリックコメントが募集されておりました.
6月7日に学会としてのコメントを送付いたしましたのでご報告 いたします.
詳細な送付コメント
http://www.geosociety.jp/engineer/content0013.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】 高等学校理科地学担当教員の増員に関する要望書を提出しました
──────────────────────────────────
今般の学習指導要領の改訂にともなう平成24年度からの高等学校理科の先行実
施に関し,本学会は文部科学大臣,各都道府県教育委員会教育長,政令 指定都市
教育委員会教育長に対して下記のような要望を提出し,高等学校地学教員の増員
を直接お願いすることにいたしました.なお,同様の 要望書は,お送りいたしま
した.
要望書の内容
http://www.geosociety.jp/engineer/content0013.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】文科省「政策創造エンジン 熟議カケアイ」に声を送ろう
──────────────────────────────────
文 部科学省が現場対話型の政策形成新機軸として「政策創造エンジン 熟議
カケアイ」というネッ ト上での討議を試みています.
・国立大学法人の課題(6/17締切)
・我が国の 研究費を使いにくくしている問題点は何か?(6/30締切)
など多くの皆様に関係する議題もあります.ご参加下さいますようお願い します.
http://jukugi.mext.go.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】 支部情報
──────────────────────────────────
■ 中部支部:2010年支部年会
日時:7月 24日(土)
会場:福井県立恐竜博物館 3階 ガイダンスルーム
(参加者は 無料で博物館(常設展)を見学できます)
シンポジウ ム「ジオパークと野外現場を生かした教育普及活動」
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
■ 北海道支部:支笏湖ビジターセンター出前展示「わが街の文化遺産 札幌軟石」
期間:〜6月30日(水)まで
会場:支笏湖ビジターセンター レクチャールーム
自然公園財団支笏湖支部と千歳市のご協力を得て、サテライト展示(出前展示)
を開催中です。
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
■ 近畿・四国・西日本三支部合同
「ジオ・シンポジア 2010 in 北九州」
(日本地質学会近畿・四国・西日本支部三支部合同例会)
本 大会では,ジオパークの活動に代表されるジオの視点を取り入れた地域活動
に関する公開シンポジウムとジオツアーを計画しております.多数の方々の ご参
加をお待ちしております.
日時 7月18日(日)13:30〜
場所 北九州市立自然史・歴史博物館(いのちのたび博物館) ガイド館
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】 第9回理科教員対象見学旅行 参加者募集
──────────────────────────────────
「糸魚川ジオパーク:ヒ スイ探訪ジオツアー」
恒例となりました理科教員対象見学旅行を,富山大会の最終日に開催いたしま
す.富山大会への参加申し込みをしなく てもこの行事に参加できますので,お気
軽にお申し込みください.
実施日:9月20日(月・祝日)8:45糸魚川駅前集合,観光バ ス使用
申込期限:7月31日(土)
詳しくは、富山大会HP
http://www.geosociety.jp/toyama/content0005.html#teacher
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】 その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■日本学術会議中部地区会議学術講演会
日 時:7月9日(金)13:00-16:00 参加無料
場所:福井大学文京キャンパス総合研究棟113階会議室
・「日本学術会議の新しい動 向」金澤一郎(日本学術会議会長)
・「原子力の安全、核不拡散の保障措置と核セキュリティを巡る動向について」
広瀬研吉(福井 大学特命教授)
・「福井大学での原子力教育と研究」竹田敏一(福井大学附属国際原子力工学研
究所長)
お問合せ先:日本学術会議中 部地区会議事務局
TEL:052-789-2039 FAX:052-789-2041
E- mail:kenkyo@post.jimu.nagoya-u.ac.jp
又は、福井大学総合戦略部門研究推進課
TEL:0776-27-8880 FAX:0776-27-9742
■堆積学スクール2010参加者募集
テーマ 未固結変形構造と脱水構造
申込締切:7 月15日(木)
日程:8月9日(月)夕方集合〜12日(木)
詳しくは,
http://sediment.jp/index.html
■ 深田研ジオフォーラム2010
テーマ: 岩盤動力学の現状と今後の展開
日時:7月31日(土)10:00-17:00
会場:財団 法人 深田地質研究所研修ホール
定員:50名(定員 になり次第締め切ります)
詳しくは,http://www.fgi.or.jp/
■2010 年秋季地質の調査研修参加者募集
実施期間:10月4日(月)〜8日(金)
主な研修場所:千葉県君津市とその周辺(房総半島中部域)
募 集人数:5名前後
申込締切:8月27日(金)
http://www008.upp.so-net.ne.jp/gsis/gsis-J.htm
■ 地球システム・地球進化 秋の学校 in 関西 1st circular
テーマ:融合から発展する地球惑星科学
日程:10月9日(土)
場 所:大阪大学豊中キャンパス理学部D501教室
詳しくは、
http://quartz.ess.sci.osaka-u.ac.jp/~earth21/school/gakkou/gakkou.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】 公募情報
──────────────────────────────────
■東京都市大学非常勤講師の公募(古生物学・進化生物 学)(7/6締切)
■平成23年度科学技術分 野の文部科学大臣表彰科学技術賞および若手科学者賞受
賞候補者の推薦(7/16;学会推薦 のみ)
■日本学術振興会育志賞推薦の募集 (7/29-8 /2;学会推薦のみ)
■第 14回尾瀬賞募集 (8/31)
■第31 回猿橋賞の推薦の募集(11/30)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】 6-7月博物館特別展示・イベント情報
──────────────────────────────────
夏休みを目前に控えて、各 地で特別展等が開催されています。
みなさまのお越しをお待ちしております。
6-7月の特別展示・イベントのチェックは↓↓↓
http://www.geosociety.jp/name/content0063.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】 geo-Flash 100号!記念アンケート ご協力お願いします(継続中)
──────────────────────────────────
geo- Flashも2007年7月創刊以来おかげさまでついに100号になりました。今後とも
皆様にお役にたつgeo-Flash(そしてニュース誌、 ホームページ)であるために皆様の
ご意見をお聞かせ下さい。
中間報告
ニュース誌に関して
よく読む 43%
表紙写真好き 20%
書評好き 13%
geo-Flashに関して
よく読む 71%
解説好き 15%
HTML化歓迎 71%
ホームページに関して
時々読む 57%
地質フォト好き14%
全 般
気軽な雰囲気なら書きたい 29%
アンケートにご協力お願いいたします(6月末締切)。
http://www.geosociety.jp/cgi_enq/enq.cgi?id=geoflash
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報 告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
ま でに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.101 2010/06/08 geo-flash(臨時) 韓日地質学会@室戸 学生パワーのアップを!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.101 2010/ 6/8 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】韓日地質学会@室戸 学生パワーのアップを!
──────────────────────────────────
韓日地質学会室戸合同大会は,両国の地質学に関わる研究者と
学生の交流を目的としています.
韓国からは学生のみなさんがぞくぞくと参加を申し込んでいます!
にもかかわらず日本からは心もとない状況です...
周囲の学生の方にお声をかけてくださいますようお願いいたします.
日韓両国の地質学に関わる研究者と学生の交流を目的として開催いたします.
室戸ジオパークの美しい地質・地形(新生代の四万十帯、前弧火成活動のハン
レイ岩、浸食と地震隆起による海岸段丘など)の巡検も目玉です。
学生のポスター発表も歓迎いたします。ポスター発表賞を企画しております。
韓日地質学会室戸合同大会
日時:8月23日(月)ー8月25日(水)
場所:室戸青少年自然の家および室戸ジオパーク
日程:8月23日 レセプション
8月24日 セッション
8月25日 室戸ジオパーク巡検
参加費:4500円(食事代、宿泊費込み)
学生補助:15000円(参加費含まず)レセプションは無料
参加締め切り:6月11日(金) 今週末!
申込み方法:フォームに記入して kjmuroto@gmail.comに送付
http://struct.geosociety.jp/koreajapangs2010/
詳細はホームページをご覧下さい.
http://struct.geosociety.jp/koreajapangs2010/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質マンガ 富山大会に行こう!
地質マンガ
戻る|次へ
院生・ポスドクの皆さん,学会に行きましょう!
今回の富山大会では,8件のシンポジウムと26件のセッション(6件の トピックセッションを含む)に,560件を超える発表申し込みがありま した.世界最先端を切り開く研究から,地域地質の詳細な調査報告まで, 実にさまざまな発表が行われる予定です.いい刺激を受けてください!
院生・ポスドクの皆さんに特にオススメなのは...
「就職支援プログラム」… 地質関連会社による説明会が開催される予定です.業界の方と直接話ができる絶好の機会です!
「見学旅行(巡検)」… 本大会のスローガン(高度差4000mの地質学)にふさわしい9件ものコースが用意されています.その道のプロの案内で,重要な露頭を観察することができます.また,自分のボス以外の研究者 の考えや着眼点を知ることもできます(これ,重要です).受付中です!
「懇親会」… 個人的に強くお勧めします.私が院生だった頃,地質学会の何が強く印象に残っているかというと,この懇親会です(単に私が酒好き ということも...).「この人が○○さんか」「○○さんって,すごい酒飲みだな」と,興味深い観察事実を得ることができます(笑).また,先生や知っている研究者に頼んで自分を紹介してもらうのもいいでしょう.受付中です!
連合大会とは違う雰囲気を,ぜひ楽しみましょう.皆さんの参加をお待ちして おります.
星 博幸(行事委員長,愛知教育大学)
No.104 2010/07/06 geo-flash 講演申込締切延長 7/8(木)昼12時
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.104 2010/7/6┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】富山大会講演申込:締切延長 7/8(木)昼12時
【2】支部情報
【3】その他のお知らせ
【4】公募情報
【5】7-8月博物館特別展示・イベント情報
【6】 広報関連アンケート集計結果
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】富山大会講演申込:締切延長 7/8(木)昼12時
──────────────────────────────────
日本地質学会第 117年学術大会(富山大会)−高度差4000m地質学−
多くの方々にご講演いただくため、講演申込の締切を延長いたしました。
お申し込 みをお待ちしています。(日本地質学会行事委員会)
講演申込締切:7月8日(木)昼12時(郵送分は締切ました)
詳しく は、大会HPをご覧下さい。
http://www.geosociety.jp/toyama/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】 支部情報
──────────────────────────────────
■北海道支部企画野外巡検
「夕張市・白金川流域 の地質—砂金・化石の産状と白亜紀海洋無酸素事変層準
の観察—」
2010年9月4日(土)・5日(日)
定員:30名
詳し くは、 http://www.geosociety.jp/outline /content0023.html
■関東支部顕彰制度 制定へ(感謝状贈呈者推薦のお願い)
推薦は、8/20(金)まで
詳しくは、 http://kanto.geosociety.jp/
■ 中部支部:2010年支部年会
日時:7月24日(土)
会場:福井県立恐竜博物館 3階 ガイダンスルーム
シンポジウム「ジオ パークと野外現場を生かした教育普及活動」
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
■ 近畿・四国・西日本三支部合同
「ジオ・シンポジア 2010 in 北九州」
(日本地質学会近畿・四国・西日本支部三支部合同例会)
日 時 7月18日(日)13:30〜
場所 北九州市立自然史・歴史博物館(いのちのたび博物館)ガイド館
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】 その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■科学技術ポータルサイ ト:SciencePortal
(独)科学技術振興機構では、科学技術振興策の一環として、インターネットで科
学技術情報を総合的に提 供する科学技術ポータルサイト
「SciencePortal (サイエンスポータル)」http://scienceportal.jp/
を 運営しています。ご活用下さい。
日本地質学会 学術大会情報も掲載されています↓
http://scienceportal.jp/events/index.php?option=com_spjgevcal
■ 地殻流体研究会・サマースクール
主催:新学術領域研究「地殻流体」
日程:2010年9月10日(金)〜13日(月)
会場:ラ フォーレ修善寺(静岡県伊豆市)
参加費:一般 4万円程度を予定(3泊4日)(院生・学生:3万円程度を予定)
ただし参加費には、登録 料、宿泊代と全ての会議食費(8食分)が含まれています。
院生・学生の旅費を最大20名程度一部補助する予定です。
申し込み締切:7月 31日
研究集会・サマースクールの詳細やプログラムは以下をご覧下さい。
http://www.geofluids.titech.ac.jp/summerschool_2010.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】 公募情報
──────────────────────────────────
■東邦大学理学部化学科教員公募(9/21締切)
■高知大学海洋コア総合研究センター教員公募(8/6締切)
■東北大学学術資源研究公開センター(総合学術博物館)教員公募(8/15締切)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】 7-8月博物館特別展示・イベント情報
──────────────────────────────────
夏休みシーズンに入り、各 地で特別展・企画展等が開催されています。
みなさまのお越しをお待ちしております。
7-8月の特別展示・イベントのチェックは ↓↓↓
http://www.geosociety.jp/name/content0064.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】 広報関連アンケート集計結果
──────────────────────────────────
6月のgeo-Flash配信100 号を記念して,ニュース誌,geo-Flash,ホームページに
関するアンケートを実施いたしました.皆様ご協力ありがとうございました.こ
こ に集計結果を報告いたします.回答者数が19名でしたので,数値や順位を厳密
に考察するのは無理があるかもしれませんが,大まかな傾向は見れると 思います.
これらの結果を参考に,今後とも広報活動を進めてまいります.どうぞご協力を
お願いいたします.
(広報委員会)
広報関連アンケート集計結果
実施期間:2010年6月1日〜6月30日
回答者数:19名
図1.ニュース誌に関する項目です.ニュース誌は比較的読まれているようです.また大会案内への注目が高いようですが,アンケート時期がちょうど大 会要旨締め切り前だったことが影響した可能性もあります.それ以外はおおむね同じくらいの人気のようです.
図2.geo-Flashに関する項目です.geo-Flashも比較的読まれているようです.こちらも様々な記事がありますが,いずれも同じくら いの人気のようです.ただし地質災害の解説だけは特に関心が高いようです.
図3.geo-FlashのHTMLメール化に関する項目です.おおむね賛成という結果です.
図4.ホームページに関する項目です.ニュース誌やgeo-Flashに比べて,ホームページは会員の皆様にそれほど人気のメディアではないようです.し かし実際には地質学会ホーム−ページは59万人読者/年(253万ページビュー)とたいへんなアクセス数がありますので,これはホームページが一般の読者 が主体のメディアであることを意味していると思われます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報 告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.105 2010/07/20 geo-flash [解説]鹿児島土石流災害
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.105 2010/7/20 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】 解説:鹿児島県南大隅町で発生した土石流
【2】富山大会関連情報
【3】運営費交付金削減に関する共同声明
【4】日本学術振興会科 研費細目見直しに関する意見募集
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報
【8】企画アンケー ト: 今月のお題 「ポスター会場でのビール販売はどう?」
【9】地質マンガ 富山大会に行こう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 解説:鹿児島県南大隅町で発生した土石流
──────────────────────────────────
井村隆介(鹿児島大学・大学院理工学研究科)
2010年7月4日から5日にかけて,鹿児島県南大隅町の船石川で土石流が発生した.
流 出土砂は,既設の砂防ダムにトラップされ,大浜集落の数百メートル手前で止
まった.町は5日,集落の50世帯91人に避難勧告を出した(7月20 日現在継続中).
続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/hazard/content0041.html
[関連情報] 鹿児島県南大隅町で起こった斜面崩壊(土石流)の地質学的背景
(産業術総合研究所・地質調査総合センターのサイト)
http://www.gsj.jp/HomePageJP.html
http://www.gsj.jp/Gtop/topics/kagoshima/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】 富山大会関連情報
──────────────────────────────────
<事前参加登録締切>
オンライン:9月 3日(金)18:00 FAX/郵送:8月31日(火)必着
■見学旅行
富山大会では会期前後に、「高低差4000mの地質学」 にふさわしい豊富な9コース
が企画されています。いずれのコースもまだまだお申し込み可能です。多くの方
々のご参加をお待ちしています。
各 コースの紹介は、
http://www.geosociety.jp/toyama/content0027.html
■緊急展 示の申し込みについて
学会活動の一端を広く社会に紹介するとともに,ホットなテーマについて議論
する場を提供するために,災害報告や社 会的に影響のある新技術紹介などの「緊
急展示コーナー」を設けます.ポスター展示を希望する方は,9月3日(金)まで
に以下の内容で下記 の実行委員会にご連絡ください.
1)発表要旨PDF(ニュース誌4月号参照) 2)緊急展示の必要性 3)発表代表者
と連絡先 4)希望 枚数(1枚:幅90×180cm) 5)展示に関わる要望(2〜5の様
式は自由)
実行委員会は行事委員会と協議し,可否の判断を致しま す.希望にはできるだ
け応えるようにしますが,展示方法等については実行委員会の指示に従ってくだ
さい.
申込 先:<main@geosociety.jp>
担当:大籐 茂(富山大会実行委員会)・上野将之(行事委員会)
■富 山大会に関連したプレス発表を希望される方へ
富山大会での講演や行事について,8月下旬にプレス発表を行う予定です.富山大
会で発表され る予定の案件で,学会からのプレス発表をご希望の方は,8月10日(
火)までに学会事務局にご連絡願います.
登録締切:8月10日 (火)
プレス発表(投げ込み):8月下旬
現地説明会(解禁日):8月下旬
連絡先:日本地質学会事務 局<journal@geosociety.jp>
富山大会の詳細情報は,大会HPをご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/toyama/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】 運営費交付金削減に関する共同声明
────────────────────────────────── 国の人材を育成するための大学の運営費交付金がさらに削減されるという
動きがあり ます。地質学に関する研究教育にも大きな影響が出る恐れがあり、
地質学会としても見過ごすことはできません。 ■32大学理学部長会議緊急声明(7/10)
“人財”養成と学術研究の中心である 大学への支出は我が国の繁栄を実現
するために必須
http://www.s.u-tokyo.ac.jp/info/statement.html
■ 国立大学生協・私立大学団体連合会連名(7/14)
「新成長戦略」の原動力は「強い大学」 http://www.janu.jp/active/txt5/yosan100714.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】 日本学術振興会科研費細目見直しに関する意見募集
──────────────────────────────────
日本学術振興会 では、文部科学省科学技術・学術審議会の依頼を受け、
平成25年度公募から適用する「系・分野・分化・細目表」の改正に向け
検討を行って おります。
詳しくは...http://www.geosociety.jp/news/n65.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】 支部情報
──────────────────────────────────
■北海道支部企画野外巡検
「夕張市・白金川流域 の地質—砂金・化石の産状と白亜紀海洋無酸素事変層準
の観察—」
2010年9月4日(土)・5日(日)
定員:30名
詳し くは、 http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
■ 関東支部顕彰制度制定へ(感謝状贈呈者推薦のお願い)
推薦は、8/20(金)まで
詳しくは、 http://kanto.geosociety.jp/
■シンポジウム「関東盆地の地下地質構造と形成史」
日時:2010年 11月20日(土)・21日(日)の両日開催
場所:日本大学文理学部3号館5階
1日目「首都直下のプレート地殻構造と地震発生」
2 日目「関東平野の形成と進化の新しい見方」
<一般講演の募集>
シンポジウムに併せて、一般講演(ポスターのみ)の募集をおこないます。
関 東地域の地質に関する幅広い発表をお待ちしております。
講演要旨〆切:2010年9月10日(金)必着
詳しくは、 http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】 その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■京大防災研究所一般研究集会「地学教育の現状 とその改革−防災知識の普及に向けて−」
2010年9月1日(水)〜2日(木)
会場:京都大学宇治キャンパス
http://www.dpri.kyoto-u.ac.jp/web_j/index_topics.html
■ 第19回日本水環境学会市民セミナー
2010年8月27日(金) 10:00 -15:50
「食糧と水—私たちが生きていくために—」
場 所 東京会場:地球環境カレッジホール(いであ(株)内)
大阪会場:いであ(株)大阪支社 ホール
http://www.jswe.or.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】 公募情報・各賞助成情報
──────────────────────────────────
■東北大学大学院理学研究科地学専攻教授 公募(9/30締切)
----------------------------------------
■「科学の芽」賞募集 (9/30)
■「朝日賞」候補者の推薦 (8/31; 学会推薦のみ)
■平成22年度 第51回東レ科学技術賞・第51回東レ科学技術研究助成 (10/8;学会
推薦)
■第32回(平成22年度)沖縄研究奨励賞の推薦 (7/15-9/30;学会推薦)
■日本学術振興会育志賞推薦の募集 (7/29-8 /2;学会推薦)
詳細およびその他の公募 情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】 企画アンケート 今月のお題 「ポスター会場でのビール販売はどう?」
──────────────────────────────────
海 外の学会ではポスター会場等でビールやワインをたしなみつつ議論に花咲かせ
ている風景をよく目にします.
地質学会のポスター会場でビール 等が販売されたら皆さんはどう思いますか?
回答はこちらから
http://www.geosociety.jp/cgi_enq/enq.cgi?id=kikaku01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】 地質マンガ
──────────────────────────────────
富山大会に行こう!
原案:星 博幸 マンガ 化:Key
http://www.geosociety.jp/faq/content0240.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中ですgeo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。 geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
ニュージーランドのウェリントン断層 巡検参加報告
ニュージーランドのウェリントン断層:巡検参加報告
川村喜一郎(財団法人深田地質研究所)
統合国際掘削計画(IODP)の科学諮問機関(Science Advisory Structure)の一つ,事前調査委員会(Site Survey Panel)の会合で,ニュージーランド,ウェリントンに来ています.会合は,2010年1月27日〜29日までです.10日前には,IODPのジョイデス・レゾリューション号もウェリントンに停泊していました.現在は南極航海中のようです(詳しくは:http://www.j-desc.org/modules/tinyd0/rewrite/expeditions/wilkes_land.html).
我々の会合の前日にGNSサイエンスのスチュアート・ヘンリーさんがウェリントン断層を案内してくれるということで,前日入りしました.それでは,さっそく,ウェリントン断層に....という,その前にニュージーランドとウェリントンの地質学的な位置関係について,ちょっとだけ説明します.
GNSサイエンスのウェブサイトに掲載されている巡検コース
ニュージーランドは,北西側がインドーオーストラリア・プレート,南東側が太平洋プレートに属している,北島と南島に分かれた島国です.それらの島を縦断するように,中央構造線やアルパイン断層が北東—南西に走っています.ウェリントン市は,ニュージーランドの首都で,北島の南端に位置しており,アルパイン断層は市のすぐ北の海底を通っています.去年,2009年7月15日のニュージーランドのMw = 7.8の地震は,アルパイン断層の南西の南島の南端のFiordlandで発生しています.
ウェリントン断層は,ウェリントン市内を北東—南西にアルパイン断層に平行に通っており,南島の北端付近でアルパイン断層と合流します.ウェリントン断層は,300〜400年前に動いたと考えられており,600〜1000年周期でマグニチュード7.5程度の地震を発生させるのではないか,と考えられているようです.運動センスは,左横ずれです.ごく最近の地震イベントは,ウェリントン断層の南にほぼ平行に走るパイララパ断層の1855年の地震で,このときもウェリントン市は大きな被害が出たようです.
説明はここまでにして,今回の観察ポイントを順次示して行きます.我々一行は,まず[9]のワイヌイオマタの丘に行き,そこで断層崖を外観しました.まずは,おおつかみの地形を見る,というのは,木を見て森を見ず,にならないためにも重要です.そして,その次に,[8]のPetone浜を見ました.Petone浜は,地震の度に隆起し,先のパイララパ地震でも突然隆起しました.次に向かったのは,[6]のトーンドン陸橋でした.ここは,陸橋が断層の直上を通っており,阪神淡路大震災後,陸橋の橋脚を補強したようです.また,橋脚が壊れても下に落ちないように落下防止柵も取り付けたようです.橋脚の下には,列車が通っているためです.その後,[1]のTe Papaを自動車で回り,[13]のハーコート公園に行きました.[1]から[13]まで20〜30分のドライブでした.ここでは,地震断層の断層崖が公園内を通っており,また,その断面を川沿いの露頭で観察することもできます.ウェリントン断層は,南に急傾斜した断層であることが,露頭からもよくわかります.そして,最後に,[12]の川沿いに発達したテラスを横切るウェリントン断層を観察しました.このテラスの形成年代がある程度わかるので,どのテラスが切られたかによって,断層の活動年代をある程度推定することができるようです.
[9]のワイヌイオマタの丘で見られる断層崖
[8]のPetone浜.奥にウェリントン断層崖がある.
[6]のトーンドン陸橋.説明する中央のスチュアートさん.橋脚は補強されている.
ウェリントンは港町.倉庫群に見つけた日本の香り.日本食レストランも多い.
[13]のハーコート公園のウェリントン断層.まるでジオパークのよう.
[13]のハーコート公園の断層活動で持ち上がった河川堆積物.やはり,まるでジオパークのよう.
まずい.写真ばっかり撮っていると置いて行かれる.待ってくれー.
公園内のハット川.この川に沿って,ほぼウェリントン断層が見られる.
この草むらを抜けると...
これがウェリントン断層の露頭.どうやらウェリントン断層は,写真中央やや右の縦の亀裂様の地点.
道すがら.タンポポ発見.その他,ススキやハルジオン,アサガオのような花がたくさん見られる.日本っぽい.
このなだらかな斜面もウェリントン断層.毎年ここで地震探査やGPSなどの測量の実習が行われるらしい.
[12]の河岸段丘.写真ではちょっとわかりにくいけど,ここに河岸段丘があって,その段丘がずらされている.どこでもそうですが,説明書の写真だとわかりやすいんですけどね.
ここまでで,午後1時にホテルを出発し,午後5時くらいにホテルで解散でした.こういった手軽な巡検コースが,わが町にもあれば良いのにな,と思い,ちょっと作ってみたくなりました.まるまる一日連れてってくれたGNSサイエンスのスチュアートさん,ありがとうございました.最後にちょっとだけ立ち寄ったGNSは,Geological and Nuclear Sciencesの略だそうです.
【参考文献】
東京大学地震研究所ウェブサイト ニュージーランド
GNSサイエンスウェブサイト
世界自然遺産推薦地「小笠原諸島」
世界自然遺産推薦地「小笠原諸島」
海野 進(金沢大学地球学教室)
第1図.母島御幸浜の含貨幣石礫岩を観察するIUCN評価委員と筆者(左端).
小笠原諸島は東京の南1000 kmに点在する古第三紀の火山岩類と活火山を含む第四紀火山からなる島嶼群である.小笠原は「屋久島」,「白神山地」,「知床」に続く4番目の世界自然遺産候補としてユネスコの世界遺産委員会に推薦され,2010年7月に国際自然保護連合(IUCN)の専門家による現地視察が行われた.これまでの3つの世界自然遺産がいずれも生態系や動植物で登録されているのに対し,小笠原諸島は「生態系」「生物多様性」に加えて「地形・地質」が重要な遺産価値として挙げられており,もし登録されれば日本で最初の「地形・地質」の世界自然遺産が誕生することになる.
世界自然遺産登録への歩み
小笠原諸島は2003年に環境省,林野庁主催の検討会において世界遺産候補に選定され,2006年に設置された各分野の専門家による科学委員会の検討を経て,2010年1月26日に小笠原諸島を世界遺産一覧表に記載するための推薦書がユネスコの世界遺産センターに提出された.これを受けて世界遺産委員会の諮問機関である国際自然保護連合(IUCN)に推薦書(日本政府, 2010)が送付され,2010年7月3日から14日にかけてIUCNによる現地調査が行われた.筆者は小笠原諸島世界自然遺産候補地科学委員会委員の一人として他分野の科学委員とともにIUCNの現地視察に同行し,小笠原諸島の世界遺産としての「地質学上の遺産価値」の紹介にあたった(第1図).IUCNの現地評価委員はシドニー大学で動植物学を専攻し,オーストラリアのニュー・サウス・ウェールズ州国立公園におけるレンジャー,監督官を経てバンコクにあるIUCNアジア事務所のCo-ordinatorを勤めるPeter Shadie氏と,グリフィス大学環境応用科学部で学位を取得して現在Seychelles Islands FoundationのResearch Officerとして勤務するNaomi Doak氏の2名である.残念ながら地質学の専門家の派遣はなかったが,10日余りの滞在を通じて両氏には小笠原諸島がもつ地質学上の遺産価値について本質的な点はご理解いただけたものと思う.
この現地評価報告書と外部専門家による評価をもとに,2011年夏の世界遺産委員会において世界遺産一覧表への記載の可否が審議される.
世界遺産に登録されるためには
世界自然遺産に登録されるためには次の4つの評価基準のうち1つ以上に合致しなくてはならない:(vii) 自然景観,(viii) 地形・地質,(ix) 生態系,(x) 生物多様性.小笠原は自然景観を除く3つの評価基準について普遍的価値を有するものとして,ユネスコに推薦された.このうち地質学に携わる者として関心が高い地形・地質の評価基準とは次のようなものである:「生命進化の記録,重要な進行中の地質学的・地形形成過程あるいは重要な地形学的自然地理学的特徴を含む,地球の歴史の重要な段階を代表する顕著な見本であること」.では,小笠原における「現在進行中の地球史の段階を代表する顕著な見本」とはどのようなものであろうか.
「小笠原諸島」がもつ世界自然遺産としての地質学上の価値
プレートの沈み込みがどのようにして始まり,沈み込み帯が確立していくかという問題は,大陸地殻の形成やプレートテクトニクスの起源にも通じる地球科学上の第一級のテーマであり,統合深海掘削計画(Integrated Ocean Drilling Project)の第一期科学計画(2003〜2012年)にも取り上げられている(Initial Science Plan; http://www.iodp.org/about/).伊豆−小笠原−マリアナ島弧−海溝系は,その発生から現在に至るまでの島弧の成長過程を解明するのに最適のフィールドとして精力的に研究され,地球上で最も理解が進んでいる海洋性島弧といえよう.伊豆−小笠原−マリアナ弧はおよそ5,000万年前に太平洋プレートがフィリピン海プレートの下に沈み込みを開始したことによって誕生した若い島弧である(Ishizuka et al., 2006).プレートの沈み込み開始とともに,海溝沿いの広範囲に無人岩をはじめとする高Mg安山岩マグマやソレアイト質マグマを生じた.無人岩は地球上で唯一クリノエンスタタイトを含有し,斜長石を含まず古銅輝石を主要構成物とするガラス質の高Mg安山岩である(第2図).沈み込みの継続とともにマグマの組成は海溝から離れた,より深いマントルで生じた玄武岩質のものとなり,それとともに噴火様式や火山の分布,生物の棲息環境等も変化していった.沈み込み開始からおよそ800万年を経て,現在あるような形の沈み込み帯が確立したと考えられる(海野ほか, 2009).
第2図.聟島のクリノエンスタタイト(白色結晶)を含有する無人岩(左)と偏光顕微鏡写真(右).Cen: clinoenstatite, Brz: bronzite, Ol: olivine
島弧形成初期の無人岩類からなる海底火山噴出物は伊豆−小笠原−マリアナ前弧に沿って広く分布するが,これらの大部分は水深3,000 mを越える海底下にあり,容易に目にすることはできない.しかし,小笠原海台とそれに先行する海山群の衝突によって伊豆−小笠原前弧の一部は持ち上げられ,本来深海にあるべき始新世の海底火山噴出物を陸上で観察することが可能となった.これが父島,母島をはじめとする小笠原群島である(海野・石渡, 2006; 海野ほか, 2007, 2009).小笠原群島では発達した海食崖が露出する地層の記録から,無人岩の海底噴火に始まり母島の火山島形成に至る,島弧マグマと火山活動の変遷を一望することができる.とりわけ高さ300 mの断崖が連なる父島の千尋岩は圧巻である(第3図).父島や母島では大規模な崩壊と浸食によって火山体の中心部が広く露出し,多くの側火口跡や火山体の内部構造を覗かせている.高粘性の溶岩としては珍しいデイサイトや流紋岩の枕状溶岩が火口縁を越えて流下する様子や,火口直上の塊状硫化鉱床などの海底熱水活動の生々しい痕跡が見られる.また,火山活動終息後の浅瀬にはサンゴや底生有孔虫などが棲息するリーフが発達した(Matsumaru, 1996).最終氷期にカルスト台地を造った石灰岩は後氷期に冠水し,沈水カルストとなって父島南崎〜南島一帯に広がり,日本最大のカタツムリであるニュウドウカタマイマイの化石などを産出する.マイマイ属は著しい種分化を遂げ,適応放散の代表例として世界自然遺産の価値のひとつに挙げられている(日本政府, 2010).
このように小笠原諸島は,プレートの沈み込み開始から沈み込み帯の確立に至る,海洋性島弧の進化過程を記録した地層が大規模に陸上に露出し,火山活動の様子や生物を取り巻く環境の変化を目の当たりにできる世界でも類い希な価値を有するものとして,世界遺産に推薦された.
第3図.父島南岸の千尋岩の断崖.無人岩枕状溶岩(下位)とデイサイト枕状溶岩及びハイアロクラスタイト(上位)に挟在される凝灰角礫岩を鍵層として,100 mを越える断層の落差がわかる.
世界遺産登録と地質学
小笠原諸島は開発の歴史が浅く,固有の生態系等が比較的よく残されてはいるものの,外来種や開発による擾乱を受けている.そこで,小笠原本来の生態系をどのようにして守り,あるいは再生していくかなどの課題について,管理計画と具体的なアクションプランをもとに関係行政機関と島民等が連携・協力した取り組みが進められている.また,東京都が実施する自然ガイド認定講習その他のプログラムを通じて,小笠原の動植物や生態系,地形地質等についての教育・普及活動も実施されている.筆者も数年来現地で地質解説等を行っているが,世界遺産登録へ向けた活動もあることから “郷土の地質”に対する受講者の関心も高く,毎回聴講される熱心なリピーターもいる.地質学は一般になじみが薄く,高校の理科教育においても疎外された感がある.小笠原諸島が日本初の「地形・地質」の世界自然遺産として登録されることをきっかけとして,地質学に対する一般社会の認知度と関心が高まり,理解が深まらんことを切に願う.
なお,小笠原諸島の世界自然遺産登録へ向けた動きと自然環境の保全・再生への取り組みについては,環境省の小笠原自然情報センターのホームページに詳しい説明がある: (http://ogasawara-info.jp/index.html)
【文献】
Ishizuka, O., Kimura, J., Li, Y.B., Stern, R.J., Reagan, M.K., Taylor, R.N., Ohara, Y., Bloomer, S.H., Ishii, T., Hargrove, U.S.III and Haraguchi, S.(2006) Early stages in the evolution of Izu.Bonin arc volcanism: New age, chemical, and isotopic constraints. Earth Planet. Sci. Lett., 250, 385 - 401.
Matsumaru, K. (1996) Tertiary Larger Foraminifera (Foraminiferida) from the Ogasawara Islands, Japan. Paleontological Soc. Japan Spec. Papers, 36, 239 p.
日本政府 (2010) 世界遺産一覧表記載推薦書「小笠原諸島」.http://ogasawara-info.jp/isan_value.html
海野 進・石渡 明 (2006) 日本地質学会(編)中部地方,第11章.日本地方地質誌, 4, 朝倉書店(株),東京,564p.
海野 進・中野 俊 (2007) 父島列島地域の地質.地域地質研究報告(5万分の1地質図幅)小笠原諸島(20) No. 2 NG-54-8-13・14. 産業技術総合研究所地質調査総合センター,71p.
海野 進・中野 俊・石塚 治・駒澤正夫 (2009) 20万分の1地質図幅「小笠原諸島」.産業技術総合研究所地質調査総合センター.
地質マンガ 巡検に行こう!
地質マンガ
戻る|次へ
院生・ポスドクの皆さん,露頭で議論しましょう!
地質学会年会は,3日間の発表会が終わると必ず見学旅行(巡検)があります.
院生・ポスドクの皆さんに,私は巡検への参加を強くお勧めします.
富山大会では9つものコースが用意されています.その道のプロが重要露頭を厳選して案内してくれます.こんなチャンスは滅多にありません! 自分の研究あるいは専門分野に関連するコースに参加するものよし,あえて専門外のコースに参加するのもよし.参加すれば必ず得るものがあります.
学会巡検では,しばしば露頭の前で議論が交わされます.案内者は当然,自分のデータや解釈に基づいて参加者を案内しますが,参加者は地質屋としての習性(?)から,そうしたデータや解釈を鵜呑みにせず,自己の観察によって検証しようとします.いったん誰かが異論を唱えると,そこから激論が始まります.これが面白い! 議論では済まず,皆で時間を忘れて証拠探しをすることもあります.こうした行動は案内者,参加者の両方にとってたいへん重要です.宿泊を伴う巡検では,夕食後に酒の力を借りて(笑)さらに激論を交わすこともしばしば.
こうした議論の経験は,自分の研究に必ずプラスに働くはずです.わずか1日か2日の巡検に参加するだけで,その地域またはその分野の研究到達点や問題点がわかるのです.知り合いを増やすこともできます.これは大きなチャンス
ですよ!
星 博幸(行事委員長,愛知教育大学)
アメリカ、アイダホ州 クレーターズ・オブ・ザ・ムーン国定公園 完新世火山地帯紹介
アメリカ、アイダホ州Craters of the Moon National Monument and Preserve 完新世火山地帯紹介
小川 勇二郎(東電設計)、安間 了、小室 光世(以上筑波大学)
藤内 智士(産総研)、村岡 諭(東大大気海洋研)
はじめに
筆者らは、Maley (2005)のField geology illustratedという書物で、実に美しい火山岩の露頭がアイダホ州にあることを知り、かねがね訪問を策していたが、今回ここを訪ねることができた。日本ではあまり紹介されていない上に、一見の価値があると考え、以下に簡単に紹介する。
図1. 都城(1979)によるアメリカの第四紀火山岩の分布。今回の場所は本図のBの付近である。
アメリカ大陸を旅行していると、新生代の火山や火山岩が意外に多いことに気づく。特に、第四紀の火山は西海岸以外にも、グランドキャニオンの南のサンフランシスコピークスを初め、所々にある。図1はそれらの分布を示したものである(都城、1979)。これを見ると、島弧性のもの以外にもそれぞれに方向性やドメインがあり、それらは何らかのテクトニクスを反映しているようである。
一方、イエローストンホットスポットの軌跡には屈曲があって、それが示す時代が北アメリカプレートの進行方向の変化の19.5 Maに一致するかどうか、屈曲や洪水玄武岩の原因が果たしてインパクトによるのかが焦点である(Price, 2001)。もしそうだとすると、洪水玄武岩の起源、ホットスポットそのものやプレート運動方向の成因よりも、インパクトが上位に置かれることになり、従来の考えに大幅な変革をもたらす(詳細はPriceの書物を参照されたい)。
それはさておき、コロンビアリバーとその上流のスネークリバーには、洪水玄武岩の分布や中新世から第四紀にかけてのカルデラがある。安山岩から流紋岩質のカルデラはプルームと地殻の混合(再溶融を含む)によるものとのことであり、スネークリバープレーン(Snake River Plain)の東半分に集中している(図2)イエローストンはその最東縁部に相当する。このスネークリバープレーンはベイスンアンドレインジ(Basin and Range)の範疇にあって、ほぼ東西引っ張りの場である。このほぼ中央部に、南北ないし北西—南東方向のグレート・リフト(Great Rift)と呼ばれる裂け目があって、そこからごく最近の地質時代に玄武岩を主とする膨大な溶岩が噴出している(図3)。これが今回紹介するCraters of the Moon National Monument and Preserveである。アメリカ本土では随一の第四紀完新世の玄武岩の噴出であるそうだ。その第四紀火山岩の総量は1600 km2, 30 km3であるという。
図2.スネークリバープレーンにおける巨大カルデラの分布と年代。今回の場所は、本図のPicabo Caldelaの北西部にある。Maley (2005)から引用。
図3. 東部スネークリバープレーン周辺の東西伸張を示す図。Alt and Hyndman (1989)による。
アクセス
このクレーターズオブザムーンを訪ねるには、イエローストンかコロンビアリバーバソールト(Columbia River Basalt)などの見学との組み合わせが便利である。イエローストンからは、南西方へおよそ300 kmほどある(図2)。Idaho Fallsから20号線を西方へ入り、Arcoを過ぎてしばらく行くと、スネークリバープレーンの中に、黒色の累々たる新鮮な玄武岩が現れる(43° 27'N, 113° 34'W)。
また、オレゴン州のポートランドからコロンビア川(河岸はほとんどコロンビアリバーバソールト(洪水玄武岩の一種)が分布していて、それらを見ながらのドライブも壮観である。これほどの量ではあるが、洪水玄武岩としては世界最小規模であるという。)に沿って84号線を東へ走り、Boise(ボイーズ)で1泊してから、その東のMountain Homeから20号線に入り(途中でIdaho Batholithの一端を見ることができる)、さらに200 kmほど走ると目的地に達する。また、84号線のGoodingから26号線に入り、Shoshone(ショウション)経由で93号線に入ってもよい。このショウションはショショナイトのタイプロカリティーではない。ショウション(ショショニー、ショショネとも発音するらしい)という地名はアメリカ中西部には多く、タイプロカリティーはワイオミング州のショウションリバーである。)、Caryを過ぎて50 km東進すると公園に入る。
なお途中の景色はすばらしいが、一般の路肩には車を駐車しないようにしたい。ビスタポイント、レストエリア(レストとあると、トイレがあるという意味である)に限って駐車するように。(有料のこともあるので、注意。)
図4.ほぼ中央部の黒い部分(86の西)がCraters of the Moon (Google Earthから)
図5.Craters of the MoonのNW-SEに伸びるリッジが明瞭である。図の東西幅は約30 km。
図6.図5に相当する個所の地質図(Kuntz et al., 1994)。東西幅約30 km。NW-SEに伸びるリッジは、最新の活動。赤矢印は流れの方向。どこから噴出したかが分かる。
クリックすると大きな画像がご覧頂けます。
公園の見学
ビジターセンターには各種の展示や出版物が置かれているので、マップなどを購入して、公園内へ車で乗り入れる。もし人を見かけたら、極力ゆっくりと走ろう。彼らは制限速度を絶対に超えない。マイル表示ではあるが、日本での感覚とは異なるので注意。およそ1,2時間ですべてを見て回れる。所々にパーキングがあって、そこからは徒歩で各クレーターやコーンに登ることができる。なお、トレイル以外には絶対に足を踏み入れないように。阿蘇の米塚のようなものであるが、草はほとんど生えていない。そこここに溶岩(ラバ)や噴出物のさまざまな形態、表面構造、流れの方向などが学べるであろう。小丘(コーン)に登ると、全体の有様を理解することができる。小規模な火山体には様々な種類があり、ラバの粘性やガスの噴出程度などによって、各種のタイプのクレーターやコーンができるのであろう。火山灰中心ならばアッシュコーン、火山餅(ペイ)ならばスパッターコーン、そのほかシンダーコーン、スコリアコーンなどもある。岩石の種類は、図7のように、SiO2 が45%から 64%程度までに及び、またトータルアルカリが3% から9%までに及ぶので、ほぼピクライトから、バソールト、ハワイアイトをへてラタイトまである。
図7.ハーカーダイアグラム。Kuntz et al. (2007)による。
図8.観察地点。1から6までの直線距離は約4.5 km。公園で渡されるリーフレットから。
(クリックすると大きな画像がご覧頂けます)
露頭、景色の写真:(クリックすると大きな画像がご覧頂けます)
一般道路にあるパーキングからの観察。ラバが滝のように流れたためにできた縦の筋模様。縄のれんのようである。
図8の2付近。パホエホエ様ラバの末端。一方、粘性の低いものは水平に近い。
ラバが縦方向に割れて正断層状にずれている。
ある種の縦割れ目からは、マグマが絞り出されている。このような説明はとても教育的で親切である。
図8の3から見た7付近。コーンがグレートリフトに沿って一直線状に並んでいるのが分かる。
図8の3から見た7付近。拡大。コーンにはスパッター状の部分もある。
図8の3から見た7付近。スパッターが溶結してagglutinateとなっている。
図8の5付近。ラバ・トンネル状となっている。
岩石はほとんどが急冷のガラス質であるため、それらの詳細は肉眼で見分けることはできない。しかし、ほとんどが玄武岩である。
これらの噴出は、1万1千年前から間欠的に、ごく最近の2000年前まで続いたという。AからFまでの6つのピリオドに区分されている。先住民族の種族も(おそらくショショニー族)、ラバカーテンが吹き上がる様子や、コーンのできる様子、粘性の低いラバがとろとろと流れる様子などを見届けたであろうことは想像に難くない。グレートリフトゾーンと呼ばれる北西—南東方向の亀裂に沿って大半が噴出したようで、クレーターやコーンの多くはその方向に並んでいる。多くのラバもそのリフトゾーンから流れ出たことが、地質図(図6)の矢印の追跡から分かる。なお、この周辺には第四紀の火山地形やビュートと呼ばれる山体や、さまざまな年代(480 Ma-4.2 Maに及ぶ)を示す岩石が知られている。これらの岩石のメイジャー化学組成やC-14年代などは、Kuntz et al. (2007)に網羅されている。また、グレートリフトの玄武岩から流紋岩のTh, Pb同位体にもとづく成因(イェローストンプルームと地殻との関係など)はReid (1995)に、さらにイエローストンホットスポットトラックの岩石のSr, Ndの同位体にもとづく総合的な検討は、McCurry and Rodgers (2009)に詳しい。これらによると、基本的にはプルーム起源であるが、地殻物質の汚染やそれとの交代作用で説明できるという。
このように、コロンビアリバーの上流、スネークリバープレーンの一地方に、驚くべきことに完新世の巨大な量を誇る玄武岩の噴出をみる。それは直線的なリフト(裂け目)からのアルカリ岩系のものである。なぜ、このホットスポット地帯に時代を経て完新世にアルカリ岩系の玄武岩類が噴出したのかは、ここがベイスンアンドレインジの東西伸張場にあり、プルームからのマグマはリソスフィア下底面付近に用意されており、それが下部地殻と反応しつつ、上昇の機会をうかがっていた。その裂け目に沿って比較的深部から部分溶融の小さな玄武岩類が割れ目噴火したとのおおよその類推が成り立とう(Reid, 1995)。つまり10 Ma前後にカルデラを作ったホットスポットが去った後にも、リソスフィアの底におかゆ状の玄武岩質マグマが残存し、それが最近になって亀裂を契機に、噴出したのであろう。
図9.Reid (1995)によるホットスポット以降のアルカリ岩の上昇モデル。
ホットスポット起源の海洋島でも、最初の活動からかなり後になって再活動する例(多くはアルカリ岩)はハワイ・オアフ島のダイアモンドヘッドの例を見るまでもないが、その他にもアルゼンチン沖のトリスタン島や、マリアナ沖のジュラ紀海底火山(Hirano et al., 2002)などの例が知られている。上記のReid (1995), McCurry and Rodgers (2009)の2論文には、それらの詳細がアイソトープにもとづいて検討されており、Reidの論文には図9のようなモデルも紹介されている。そのモデルは、近年日本の沖合で見出された「プチスポット」のセッティング(Hirano et al., 2006)と類似し、今後比較検討の材料となりうるだろう。
クレーターズオブザムーンでは火山岩の噴出のさまざまな様式を観察することができるだけでなく、アメリカの地質の一端を知るためにも、一見の価値があるものとして紹介した次第である。なお、公園内はサンプリングは絶対禁止である。ハンマーなどは、たとえスケールにしたくても持ち歩かないこと。また、トレイル以外には足を踏み入れないように。
【参考文献】
Alt, D. D. and Hyndman, D. W. (1989) Roadside geology of Idaho. Mountain Press Pub. Co., MO, 393pp.
Hirano, N. et al. (2002) Long-lived early Cretaceous seamount volcanism in the Mariana Trench, Western Pacific Ocean. Marine Geology, 189, 371-397.
Hirano, N. et al. (2006) Volcanism in response to plate flexure. Science, 313, 1426-1428.
Kuntz M.A. et al. (1994) Preliminary geologic map of the Craters of the Moon, 30' x 60' Quadrangle, Idaho. USGS Map I-2330.
Kuntz M.A. et al. (2007), Geologic Map of the Craters of the Moon, 30' x 60' Quadrangle, Idaho. USGS, Scientific Investigations Map 2969.
Maley, S. T. (2005), Field geology illustrated. Mineral Land Publications, Boise, ID, 704pp.
McCurry, M. and Rodgers, D.W. (2009) Mass transfer along the Yellowstone hotspot track I: Petrologic constraints on the volume of mantle-derived magma. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 188, 86-98.
都城秋穂 (1979) 北アメリカの地質.世界の地質.岩波書店.
Price, N. (2001) Major impacts and plate tectonics, Routledge, London, 354pp.
Reid, M.R. (1995) Processes of mantle enrichment and magmatic differentiation in the eastern Snake River Plain: Th isotope evidence. EPSL, 131, 239-254.
(2010.8.7)
ギリシャ式地震予知に関するEOS誌上での最近の討論
ギリシャ式地震予知に関するEOS誌上での最近の討論について
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
地電流観測に基づくギリシャ式地震予知法は,その創始者3名(P. Varotsos, K. Alexopoulos, K. Nomicos)の頭文字をとってVAN法と呼ばれている.VAN研究グループは,1984年にその地震予知法を世界に公表して以来,現在までギリシャ国内の観測網を維持し,観測と予知を続けてきた.この方法の概要と予知の成果を紹介した長尾 (2001) によると,予知が成功したかどうかの判断基準を (1) 震央の位置の誤差100 km 以下,(2) マグニチュードの誤差0.7以下,(3)前兆検知の数時間後〜1ヶ月後に地震が発生,の3つの条件をすべて満たした場合とすると,1984年から1998年までの15年間にギリシャで発生したマグニチュード5.5以上の地震12個のうち,VAN法は8個の予知に成功し,1個は一応予知できたものの基準から大きく外れ,3個は予知できなかった.つまり地震数当たりの予知成功率は2/3であった.また,予知情報を出した回数当たりの予知成功率も2/3程度とのことである.
筆者は1995年に長尾年恭氏や河野芳輝氏とともにギリシャ国内各地のVAN観測地点を訪問し,それらの地形・地質状況を調査したことがある(石渡, 1996).我々が訪問した8ヶ所の観測点の中には,地震前兆電磁気信号(SES)に対して感度が良い地点と良くない地点があり,その違いが地形や地質と関係しているかどうかを調べるのが筆者の現地調査の目的であった.地質との対応関係ははっきりしなかったが,地形的には,特に感度がよい2つの地点はいずれも内陸の大きな湖の近くにあり,湖とその周囲の盆地下の帯水層の存在が電磁気信号を増幅する役割をしているのかもしれないと考えた.筆者は地震や地震予知の専門家ではないが,このような経験があるので,VAN法には少なからぬ興味を持っている.最近,米国地球物理連合(AGU)の連絡誌EOSでVAN法についての討論があったのでここに紹介する.
Papadopoulos et al. (2009) によると,2008年はギリシャでマグニチュード6以上の地震が6回発生し,近来になく地震活動が盛んな年だった.Uyeda and Kamogawa (2008) は,このうち2つの地震についてVAN法が予知に成功したこと,予知の時間精度が向上したと述べた.それによると,2月14日にペロポネソス半島南方のイオニア海で起きた地震については,Varotsosらが,1月14日に新しいSESを同半島西部のPirgosで観測したこと,地震の発生が予想される地域は同半島西方から南方にかけての約250km四方の地域であることを, 2月1日にデータベース上に発表した.2月10日のギリシャの新聞は,この地域で近くマグニチュード6程度の地震が発生するかもしれないという記事を第1面に載せた.そしてその4日後に予想された地域内で予想された規模の地震が発生した.このUyeda and Kamogowa (2008)の記事に対して,Papadopoulos (2010) は反論を発表し,まず,この「予知」は「ギリシャ地震災害危険度評価常設特別科学委員会」に報告されなかったので予知として認められないと述べた後,新聞記事には時間や規模についての記述がなかったこと,2月4日にペロポネソス半島北部の都市Patras付近で起きたマグニチュード5程度の2回の地震について,VANグループがこれらを予知したと新聞紙上で発表していたこと(つまり,1月14日のSESは,2月4日と14日のどちらの地震の前兆なのかわからないという疑問),2つ目の成功例が示されていないことを述べて,予知は成功しておらず,却って新聞報道による社会不安が起こったことを指摘し,最後は「警察がウワサを広めた張本人を捜索している」という脅し文句で結んでいる.これに対し,Uyeda and Kamogawa (2010) の返答は,2008年2月4日のPatras地震の前兆のSESは1月10日に記録されたていたこと,6月8日のPatras西方の地震についても,VANグループの研究者が5月29日に予知情報をデータベース上に出していたことを示して反論した.VANグループの予知情報は米国コーネル大学のデータベース上で発表されているという.
今回の討論から判断すると,既に25年以上の伝統があるギリシャのVAN地震予知法も,まだギリシャの学界や政府が広く認めるところとはなっていないようである.地震から2年後の今年になって,予知情報が事前に出されていたか,いなかったかについて,国際的な学会誌で討論が行われるということ自体,予知情報の配信システムがきちんとしていないことを示している.VANの予知情報は「必要があれば政府機関および地方の出先機関,軍隊,地方自治体の防災関係者に伝えられ,情報が一般大衆に公表されることはほとんどない」(長尾, 2001)はずなのに,今回はいきなり新聞の第1面で公表されてしまったことは,予知が「成功」だったとしても,VAN法のシステムの危うさを示している.VAN法に関するこのような混乱はこれが初めてではなく,初期に外国の研究者にも予知情報を流していたところ,当時のフランスの防災大臣(有名な火山学者,故人)が「ギリシャで地震が発生するかもしれない」と発言し,ギリシャ国内が大騒ぎになったことや,1995年の地震の予知情報を政府が受け取っていたか,いなかったかで大問題となり,防災担当大臣は当初「受け取っていない」と言っていたのに,後で「秘書が止めていた」と訂正し,これを野党は倒閣の材料に使ったこと,などがある(長尾, 2001).
日本では,地震予知に関して,まだ予知情報を出すところまで研究が進んでいないが,火山噴火予知に関しては,有珠山の2000年噴火の際に,噴火が切迫しているという情報を火山研究者が公表し,それに応じて自治体の判断で噴火開始前に住民が避難し,人的被害を出さずに済んだ例があるが,デマの流布や避難拒否など多少の問題は発生した(北海道新聞社編, 2002).また,同じ2000年の三宅島噴火による全島避難は,解除が2005年まで持ち越され,避難者の苦労と不安が長期間続いたことは記憶に新しい.一方,昨2009年4月6日にイタリア中部のラクィラ(L’Aquila)で発生したマグニチュード6.3の地震では, 6万人以上が被災し300人以上の死者が出たが,この地震の3ヶ月前から顕著な群発地震活動があったにも関わらず,地震学者も参加していた災害対策委員会や防災当局が有効な地震情報を出せなかったことに対して,過失致死罪または殺人罪を視野に入れた刑事事件として捜査が行われており,これに対して世界の関連学会が抗議するという事態になっている.この背景には,現地のある技師がラドン観測データから本震の1ヶ月前に大地震の発生を予知してインターネットで発表したが,「市民の不安を煽る」という理由で地震発生前に当局によって発表を削除され,警察に告発されたという事件がある.この技師は昨年12月にAGUの学術大会で研究発表を行ったが,帰国後イタリア政府は彼に予知情報の公表を禁じたという(以上L’Aquila地震関連の話はWikipedia英語版に基づく).群発地震は大地震につながることもあるが,そのまま終息してしまうこともあり,予知は難しい.
ギリシャでは,上述のように,既に四半世紀にわたるVAN法の実践の中で,地震予知の成功と失敗,予知情報のリークと混乱などの社会的な経験が蓄積されており,今後はギリシャの地震予知法を理学的に研究するだけでなく,社会科学的に研究することも重要になると思う.法人化された地質学会が社会との関わりを深めて行けば,当然このような問題に直面することになるので,他人事ではない.例えば,日本の緊急地震速報システムは,減災効果は少ないかもしれないが,科学に対する市民や行政の信頼を獲得する上で大きな心理的効果を挙げていると思う.地震予知に限らず,斜面災害,地層処分,地質汚染,地球温暖化など,本学会が関わる様々な問題について,専門の人はあきらめずに粘り強く研究を進め,専門外の人も関心を持ち,基礎知識を社会に普及し,研究成果を社会に還元する活動を,学会全体として地道に行っていくことが求められている.
【文献】
北海道新聞社編 (2002) 2000年有珠山噴火.北海道新聞社.
石渡 明 (1996) ギリシャ,VAN観測地域の地質.平成6〜7年度科学研究費補助金国際学術研究(共同研究)研究成果報告書(河野芳輝:自然電位観測によるギリシャ式地震予知法の基礎と日本への適用.No. 06044085),35-62.
長尾年恭 (2001) 地震予知研究の新展開.近未来社.209 p.
Papadopoulos, G.A. 2010: Comment on "The prediction of two large earthquakes in Greece". EOS Trans. AGU, 91(18), 162.
Papadopoulos, G.A., Karastathis, V., Charalampakis, M., Fokaefs, A. 2009: A storm of strong earthquakes in Greece during 2008. EOS tans. AGU, 90(46), 425-426.
Uyeda, S., Kamogawa, M. 2008: The prediction on two large earthquakes in Greece. EOS. Trans. AGU, 89(39), 363.
Uyeda, S., Kamogawa, M. 2010: Reply to comment on “the prediction of two large earthquakes in Greece”. EOS trans. AGU, 91(18), 163.
(2010年8月17日)
No.107 2010/08/17 geo-flash 行かんまいけ!富山
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.107 2010/8/17 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】アメリカ、アイダホ州 Craters of the Moon National Monument and Preserve
完新世火山地帯紹介
【2】ギリシャ式地震予知に関するEOS誌上での最近の討論について
【3】巡検へ行こう!各コースの見どころ紹介
【4】富山大会:事前参加登録もうすぐ締切です!
【5】現地報告:7/15に発生した岐阜県可児市の集中豪雨災害
【6】その他のご案内
【7】公募・各賞助成 情報
【8】学会事務局8月のお休み
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】アメリカ、アイダホ州 Craters of the Moon National Monument and Preserve
完新世火山地帯紹介
──────────────────────────────────
小川勇二郎(東電設計)、安間了、小室光世(以上筑波大学)、藤内智士(産総
研)、村岡諭(東大大気海洋研)
筆者らは、Maley (2005)のField geology illustratedという書物で、実に美しい
火山岩の露頭がアイダホ州にあることを知り、かねがね訪問を策していたが、今
回ここを訪ねることができた。日本ではあまり紹介されていない上に、一見の価
値があると考え、以下に簡単に紹介する。
続きを読む、、、 http://www.geosociety.jp/faq/content0246.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】ギリシャ式地震予知に関するEOS誌上での最近の討論について
──────────────────────────────────
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
地電流観測に基づくギリシャ式地震予知法は,その創始者3名(P. Varotsos, K.
Alexopoulos, K. Nomicos)の頭文字をとってVAN法と呼ばれている.VAN研究グルー
プは,1984年にその地震予知法を世界に公表して以来,現在までギリシャ国内の
観測網を維持し,観測と予知を続けてきた.(中略)最近,米国地球物理連合(AG
U)の連絡誌EOSでVAN法についての討論があったのでここに紹介する.
続きを読む、、、 http://www.geosociety.jp/faq/content0247.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】巡検へ行こう!各コースの見どころ紹介
──────────────────────────────────
富山大会の見学旅行、各コースの魅力と見どころを写真付きで紹介しています。
この機会でないと見学できない対象が多数ありますので、多くの皆様の参加
をお待ちしています。
参加申込み締切: 9/3(金)WEB (FAX・郵送は8/31締切)
見学旅行:各コースの魅力と見どころはこちらから↓
http://www.geosociety.jp/toyama/content0032.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】富山大会:事前参加登録もうすぐ締切です!
──────────────────────────────────
事前参加登録締切:9/3(金)WEB (FAX・郵送は8/31締切)
★注意★講演をされる方は、忘れずに、別途事前参加登録も行って下さい!
全体日程表も公開されています。
http://www.geosociety.jp/toyama/content0003.html
富山大会HPはこちらから↓
http://www.geosociety.jp/toyama/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】現地報告:7/15に発生した岐阜県可児市の集中豪雨災害
──────────────────────────────────
7月15日に発生した岐阜県可児市の集中豪雨災害の現地の状況報告が産総研
地質調査総合センターのHPに掲載されています。
地質調査総合センターのHP:
■2010年7月15日に発生した可児市土田の集中豪雨災害の現地報告 (2010.8.16)
http://staff.aist.go.jp/saito-mkt/geohazard/kanigawa.html
■2010年7月15日に発生した岐阜県南部の集中豪雨災害地域の地質情報 (2010.7.23)
http://www.gsj.jp/Gtop/topics/gifu/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のご案内
──────────────────────────────────
■NPO日本汚染審査機構第19回地質汚染調査浄化シンポジウム
イタイイタイ病からの土壌環境基準とは
ー健康環境基準?経済環境基準?土壌汚染問題発祥地から問うー
日時 2010年9月16日(木)午後1時から6時30分
場所 富山国際会議場大手町フォーラム多目的会議室203号
詳しくは、 http://www.npo-geopol.or.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募・各賞助成 情報
──────────────────────────────────
■京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻教員公募(10/21締切)
■東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻准教授公募(進化古生物学分野)
(9/30締切)
■大阪市立大学大学院理学研究科・理学部地球学教室教員公募(10/18締切)
------------------------------------
■平成23年度笹川科学研究助成の募集(10/1-15)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】学会事務局 8月のお休み
──────────────────────────────────
土日・祝日以外に8月は下記の通りお休みとなりなす。
8/30(月):振替休日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.113 2010/10/19 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.113 2010/10/19 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2011年度学会各賞募集開始
【2】2011年度会費払込/学部学生・院生割引申請受付開始!
【3】第34回IGC ブリスベン大会のプロモーション
【4】支部情報
【5】連合大会2011年大会のセッション提案にご注意下さい
【6】惑星連合 大気海洋・環境セクション名称変更に関するご連絡
【7】「科学技術に関する基本政策について」のパブリックコメントについて
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2011年度学会各賞募集開始
──────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして、研究の援助・奨励および研究業
績の表彰を行っています(定款第3条)。
本年も各賞の自薦、他薦による候補者を募集いたします。期日厳守にて、たくさん
のご応募をお待ちしております。
応募締切:2010年12月24日(金)必着
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
(会員番号・パスワードによるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2011年度会費払込/学部学生・院生割引申請受付開始!
──────────────────────────────────
■2011年度会費払込について
次年度分会費の前納をお願いいたします。自動引き落としを登録されている方の
引き落としは、12月24日(金)です。お振込の方へは、12月中旬頃までに請求書
兼郵便振替用紙をお送りいたします。
詳しくは、https://www.geosociety.jp/user.php(会員番号によるログインが必要です)
■2011年度(2011.4〜2012.3)学部学生・院生割引申請受付中
最終締切:2010年11月17日(水)
申請書のダウンロードは、
https://www.geosociety.jp/user.php(会員番号によるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】第34回IGC ブリスベン大会のプロモーション
──────────────────────────────────
日本地質学会会員各位
2012年8月に第34回万国地質学会議(IGC)がオーストラリアのブリスベンで開催さ
れます.同大会事務局長のIan Lambert氏が2010年11月9-10日に来日し,同大会の
プロモーション活動を行います.日本からは毎回かなりの人数がIGCに参加してお
り,前回の2008年オスロ大会ではノルウェー(960名),ロシア(505名),米国(394名),
中国(376名),イタリア(267名),ドイツ(261名),英国に次ぐ参加者数(150名程度?)
でした.今回は大洋州での開催なので日本人参加者が増加すると思われます.
国際地質科学連合(IUGS)の主要な会議もIGCの会期中に行われます.この会議
における日本のプレゼンスを高めるためにも,今回の事務局来日の機会を最大限
に利用すべきと思いますので,関連諸学会の関係者の皆様には,9日または10日
の説明会のどちらかに,奮ってご参加いただきますよう,ご案内申し上げます.
参加申し込みは,9日・10日それぞれ担当者が異なりますので,お間違えのない
よう,10月22日(金)までにご連絡下さい.
斎藤靖二
日本学術会議IUGS分科会委員長
石渡 明
日本地球惑星科学連合国際学術委員会委員長
日本地質学会学術研究部会国際交流担当理事
記
第34回IGCブリスベン大会のプロモーション開催日時および会場
Date: Tuesday, 9 Nov. 2010
Time: 15:00 - 17:00
Place:Japan Agency for Marine Science and Technology
(JAMSTEC) Tokyo Office
Hibiya Central Bld. 6th Floor, Nishi-shimbashi 1-2-9, Minato-ku,
Tokyo, 105-0003 Japan
Tel: +81-3-5157-3900 Fax: +81-3-5157-3903
http://www.jamstec.go.jp/e/about/access/tokyo.html
Correspondence:
Dr. Arito Sakaguchi (坂口有人)<arito@jamstec.go.jp>
Date: Wednesday, 10 Nov. 2010
Time: 10:00 - 12:00
Place: Geological Survey of Japan
The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
(AIST) 1-1-1, Higashi, Tsukuba , 305-8567, Japan
phone: +81-29-861-3750/3751 fax:-3746
http://www.gsj.jp/Muse/eng/index.html
Correspondence:
Dr. Yutaka Takahashi(高橋 浩)<takahashi-yutaka@aist.go.jp>
資料
1.Ian Labmert氏の略歴とプロフィール/2.第34回IGCの概要(要旨)/3.オース
トラリアの地球科学の現状と展望(要旨)
http://www.cneas.tohoku.ac.jp/labs/geo/ishiwata/IGC34promotion.htm
なお,10月13日に34th IGCのFirst Circularが発行されました.
https://mymail.ezemsgs.com/ch/8781/2ddswr8/1331640/9d98811z4g.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】支部情報
──────────────────────────────────
■日本地質学会関東支部2010年秋季シンポジウム
「関東盆地の地下地質構造と形成史」
日程:2010年11月20(土),21(日)
場所:日本大学文理学部3号館5階
懇親会予約:件名を「懇親会予約」とし,ご予約する旨,お名前,ご連絡先を書
いて<kanto@geosociety.jp>に,送信して下さい.予約締切:11/12(金)
詳しくは、 http://kanto.geosociety.jp/
■2010年度近畿支部総会・シンポジウム
日時:2010年11月20日(土)
11:00〜12:00(総会)・ 13:00〜16:30(シンポジウム)
場所:神戸大学滝川記念学術交流会館
シンポジウム「中央構造線の発生と改変:白亜紀から新第三紀にかけて」
問い合わせ先:近畿支部幹事 三田村宗樹
TEL:06-6605-2592 FAX:06-6605-2522
e-mail: mitamrm@sci.osaka-cu.ac.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】連合大会2011年大会のセッション提案にご注意下さい
──────────────────────────────────
来年(2011年)の日本地球惑星科学連合大会から学会主催のレギュラーセッション
は廃止され、すべてのセッションが公募になっております。セッション提案を予定
している場合は、お忘れのないよう申込手続きをお願いします。
締切は、10/26(火)です。
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/faq/content0255.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】惑星連合 大気海洋・環境セクション名称変更に関するご連絡
──────────────────────────────────
大気海洋・環境セクションに関係する学協会の皆様
地球惑星連合における当セクション名に関してかねてより「水」関係の学協会か
ら名称変更の要望が出ておりました。そのためセクションとして、花輪バイスプ
レジデントを代表とする「名称変更検討ワーキンググループ」を今年度立ち上げ、
名称変更の検討を行ってまいりました。その検討結果がまとまりましたのでお知
らせいたします。
検討結果は以下のサイトからダウンロードできます。
http://www.kaiyo-gakkai.jp/main/2010/10/post-129.html
WGからの答申について何かご意見がありましたら
御寄せください(10月末日まで)。個人のご意見でも、学協会としてのご意見で
もかまいません。宜しくお願いいたします。
大気海洋・環境セクションボード幹事:川合義美(海洋研究開発機構)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】「科学技術に関する基本政策について」のパブリックコメントについて
──────────────────────────────────
総合科学技術会議では、平成23年度からの新たな第4期科学技術基本計画の策定
に向けて検討を進めており、本年12月に答申を予定しています。
このたび、答申に向けて「科学技術に関する基本政策について」がまとめられ、
10月18日(月)よりパブリックコメントが開始されました。
締切は、11月8日(月)です。
詳細、意見提出様式等につきましては、以下のウェブサイトをご覧下さい。ご意
見等は、以下のウェブサイトから、直接内閣府(科学技術政策・イノベーション
担当)あてにご提出いただきますようお願いいたします。
http://www8.cao.go.jp/cstp/pubcomme/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■21世紀の地学教育を考える大阪フォーラム
第11回こどものためのジオ・カーニバル
会場: 大阪市立科学館
日時: 11月6日(土)〜7日(日)
参加費: 無料
http://geoca.org/
■米国土壌・地下水浄化先端技術セミナー
「土壌対策法改正に向けたアメリカの新技術紹介」
アメリカの事例に学ぶ土壌・地下水浄化のありかた
主催: US Remediation Partners
後援: 米国大使館商務部ほか
11月8日(月) 東京 米国大使館 講堂
11月9日(火) 名古屋 在名古屋米国領事館 会議室
11月10日(水) 大阪 在大阪・神戸米国総領事館 多目的ホール
11月12日(金) 福岡 福岡アメリカン・センター・ホール
参加費:無料
http://www.buyusa.gov/japan/ja/remediation.html
■産総研地質調査総合センター第16回シンポジウム
「20万分の1地質図幅完全完備記念シンポジウム
−全国完備後の次世代シームレス地質図を目指して−」
開催日時: 2010年11月16日 (火) 13:00〜17:50
場所: 秋葉原ダイビル コンベンションホール
詳しくは,http://www.gsj.jp/Event/101116sympo/index.html
■JSTシンポジウム:グリーンイノベーションと社会実験
日時 2010年11月17日(水) 13:00〜17:30
場所 江戸東京博物館ホール(東京都墨田区)
主催 (独)科学技術振興機構(JST)
定員 400名(参加 無料・要事前登録)
http://www.jst.go.jp/pr/sjsympo2010.html
■第2回惑星地球フォトコンテスト 【作品募集中】
主催: 一般社団法人 日本地質学会
応募締切: 2011年1月31日(月)
賞および賞金: 最優秀賞 1点 賞金5万円/優秀賞数点賞金3万円ほか
詳しくは、 http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■埼玉県立自然の博物館学芸員公募(10/26)
■第28回とやま賞募集(11/22)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
【第2回惑星地球フォトコンテスト】作品募集中!<http://www.photo.geosociety.jp/>
地質マンガ 学会に行ってみると
地質マンガ
戻る|次へ
No.109 2010/09/21 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.109 2010/9/21 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】富山大会は盛会のうちに無事終了しました。
【2】速報:写真で見る富山大会
【3】プレス発表! 富山大会
【4】支部情報
【5】その他のご案内
【6】公募・各賞助成 情報
【7】地質マンガ「学会に行ってみると」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】富山大会は盛会のうちに無事終了しました。
──────────────────────────────────
富山大会(9/18-20:富山大学ほか)は盛会のうちに無事3日間の会期を終了致し
ました。
参加者は,事前登録・当日登録あわせて約800名。
初日の懇親会には200名近い方にご参加いただきました。
また今日から、会期後の見学旅行も各コースがスタートしました。
学術大会の様子は、近日学会News誌やHPでご報告いたします。
来年は、水戸大会(2011年9月2日-4日:茨城大学ほか)でお会いしましょう!
■忘れ物をお預かりしています
・講演要旨 1冊(表紙に自署あり・書込み/黄色の付箋多数) http://www.geosociety.jp/toyama/content0002.html#0921
■富山大会講演要旨および見学旅行案内書にわずかですが、残部があります。
ご購入希望の方は学会事務局まで<main@geosociety.jp>ご注文ください。
会員価格(いずれも送料別)
・講演要旨 4000円
・見学旅行案内書 2800円
なお、事前注文された方には、近日中に冊子を発送致しますので、しばらくお待
ちください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】速報:写真で見る富山大会 表彰式ほか
──────────────────────────────────
大会会場,表彰式,懇親会の様子などを写真でご紹介します.
この熱気!伝わるでしょうか.
富山駅での歓迎
大会会場入口
表彰式会場
Prof. Ochir Gerel モンゴル地質学会国際関係・高等教育理事,IUGS副会長
西頭富山大学学長
来賓の皆様
藤田 崇 新名誉会員
町田 洋 新名誉会員
石原舜三 新名誉会員
50年会員顕彰 加藤祐三会員
50年会員顕彰 蟹江康光会員
国際賞 Juhn G. Liou 米国スタンフォード大学名誉教授
日本地質学会小澤儀明賞 後藤和久会員
日本地質学会論文賞 菅原大助会員
日本地質学会論文賞 宮田雄一郎会員
日本地質学会研究奨励賞 大橋聖和会員
日本地質学会研究奨励賞 川上 裕会員
学会功労賞 杉山了三会員
学会表彰 山口県(二井関成知事 代理 山口県農林水産部大井陽一氏)
学会表彰 地球システム・地球進化ニューイヤースクール事務局
9/18優秀ポスター賞 入月俊明会員
9/18優秀ポスター賞 細井 淳会員
懇親会会場その1
懇親会会場その2
懇親会会場その3
懇親会会場その4
懇親会会場その5
小さなEarth Scientistの集い 表彰式
9/19優秀ポスター賞 川村喜一郎会員
9/19優秀ポスター賞 畑中雄太会員
9/20優秀ポスター賞 伊藤 光会員
9/20優秀ポスター賞 本田豊也会員
9/20優秀ポスター賞 滝本春南会員
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】プレス発表! 富山大会
──────────────────────────────────
日本地質学会第117年学術大会(富山大会)に関して,文部科学省記者会,
富山県県庁記者クラブ,科学新聞社より記者発表を行いました.学術大会や
関連行事のほかに特筆すべき学術報告として下記の三点を発表いたしました.
・肉食恐竜,もっと低い姿勢.従来の復元姿勢に変更を迫る
・温暖な地球と寒冷な地球の移行期を知る手掛かり
・津波警報・被害評価の死角
http://www.geosociety.jp/engineer/content0015.html
おかげさまで全国紙・地方紙等多くのメディアから報道されました.
関係者の皆様にはご尽力頂きまして本当にありがとうございました.
今後もプレス向け広報活動を積極的に行いますので,ご協力頂けますよう
どうぞよろしくお願いいたします.
広報委員会・行事委員会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】支部情報
──────────────────────────────────
■日本地質学会関東支部2010年秋季シンポジウム
「関東盆地の地下地質構造と形成史」
開催日:2010年11月20(土),21(日)
場所:日本大学文理学部3号館5階
詳しくは、http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】その他のご案内
──────────────────────────────────
■The 7th International Conference on Asian Marine Geology (ICAMG-7)
「第7回アジア海洋地質会議」
日程:2011年10月11日〜14日
会場: National Institute of Oceanography (CSIR), Goa, INDIA
Deadline of session proposal: 31 January 2011
Deadline of abstract submission: 31 July 2011
http://icamg7.nio.org
■日本の活断層・フォトコンテスト:作品募集中
締切10/15まで延長しました。
詳しくは、
http://danso.env.nagoya-u.ac.jp/jsafr/fotocontest01.html
■The KJOD/IODP Workshop for Okinawa Trough Drilling in 2010
2010年10月11日(月)-12日(火)
会場 琉球大学
http://www.j-desc.org/modules/tinyd0/rewrite/events/101011_KJOD_ws.html
■国土地理院「古地理に関する調査」成果公開のお知らせ
「中部地方の古地理に関する調査業(狩野川・安倍川・大井川)」について、平
成22年中に以下より公表予定です
当面、中部地方の古地理調査報告書を公開する予定です。その他の地域について
は、順次公開する予定です。現在、天竜川・木曽川等公開中。
http://www1.gsi.go.jp/geowww/paleogeography/index.html
■第129回深田研談話会(高知)
ジオ鉄&自然を楽しむ鉄道旅行のススメ
日 時: 2010年11月5日(金)18:00-20:00
会 場: 高知市文化プラザかるぽーと 2階 小ホール
参加費: 無 料
申込み締切:10月31日(日)
■第130回深田研談話会(現地・四国)
ジオ鉄−自然を楽しむ鉄道旅行(土讃線)
日 時: 2010年11月6日(土)
対象者:ジオ鉄の活動に関心のある中学生以上の方で(中学生は保護者同伴)、
鉄道の運行ダイヤおよび安全運行に支障を来さない行動管理のできる方
定 員: 25名 (定員を越えた場合は抽選)
参加費: 参加費: 3,000円 (資料代および保険代)
申込み締切:10月12日(火)
詳しくは、
http://www.fgi.or.jp/
■第5回 SPARC Japan セミナー 2010の開催案内
「日本の学術情報流通 10年後を見据えて」
主催:社団法人 日本動物学会/国際学術情報流通基盤整備事業(SPARC Japan)
後援:日本学術会議
2010年9月24日(金)9:00〜11:30
東京大学駒場キャンパス
参加費: 無料
http://www.nii.ac.jp/sparc/event/2010/20100924.html (SPARC Japan HP)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募・各賞助成 情報
──────────────────────────────────
■広島大学大学院:理学研究科地球惑星システム学専攻女性教員公募(11/1)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】地質マンガ
──────────────────────────────────
「学会に行ってみると」 原案:坂口有人 マンガ:Key
http://www.geosociety.jp/faq/content0251.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.110 2010/09/28(臨時) geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.110 2010/9/28 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 祝!国際地学オリンピック 初めての金メダル!
──────────────────────────────────
2010 年9 月19 日から9 月28 日までインドネシアで開催された第4回国際
地学オリンピックに日本代表生徒4 名が派遣され,以下の成績を挙げられました.
銀メダル 大西 泰地 私立白陵高等学校(岡山県) 2年生
銀メダル 川島 崇志 静岡県立磐田南高等学校 3年生
銀メダル 武内 健大 私立聖光学院高等学校(神奈川県)3年生
金メダル 野田 和弘 私立広島学院高等学校(広島県)3年生
(天文・惑星科学部門トップ賞も同時受賞)
(五十音順)
今回の第4回のインドネシア大会は参加国17カ国63名の高校生の参加で、ジョグ
ジャカルタ周辺で筆記試験と実技試験が行われ、日本の結果は金メダル1個、銀メダル
3個で、さらに金メダルを受賞した野田君は天文・惑星科学部門トップ賞も受賞しました。
参加国はルーマニア、フィリピン、アメリカ、ウクライナ、タイ、日本、ロシア、カン
ボジア、スリランカ、イタリア、インド、台湾、韓国、クウェート、モルディブ、ネパ
ール、インドネシアで、フランスがオブザーバーで参加しました。
部門トップ賞と総合最優秀賞について
筆記試験・実技試験は、原則として、地質・固体地球科学部門、気象・海洋科学部門、天文・
惑星科学部門の3部門に分かれています。筆記試験では、3部門の配点が、この順番で45%、
35%、20%になっています。そして実技試験と筆記試験の配点比率は7:3となっています。
部門トップ賞は、それぞれの部門の筆記試験・実技試験の合計得点1位者に与えられます。また
総合最優秀賞は、3部門の合計得点1位者に与えられます。
念願の金メダルを獲得ということで、選手の皆さんの活躍に心から祝福したいと思います。
そしてこれを契機に再来年の国際地学オリンピック日本大会に関心を持ってもらればと思います。
久田健一
より詳細な情報は
地学オリンピック日本委員会 http://jeso.jp/
第4回国際地学オリンピック http://www.ieso2010.ugm.ac.id/ie/index.php?p=berita
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.111 2010/10/05 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.111 2010/10/05 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】「山陰海岸ジオパーク」が世界ジオパークに認定!
【2】第2回惑星地球フォトコンテスト 作品募集
【3】Island Arc 日本語要旨 Vol.19 Issue3
【4】支部情報
【5】学術の大型研究計画に関する調査(平成22年度)について
【6】緊急連絡「元気な日本復活特別枠」のパブリックコメントについて
【7】平成23年度概算要求に関する国立極地研究所長声明
【8】その他のご案内
【9】公募・各賞助成 情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「山陰海岸ジオパーク」が世界ジオパークに認定!
──────────────────────────────────
ヨーロッパジオパークネットワーク会議に参加中の渡辺真人さんから
「山陰海岸ジオパーク」世界ジオパーク認定の速報が届きました→
山陰海岸ジオパークが、世界ジオパークネットワーク(GGN)に加盟を認めら
れました。昨年12月1日にGGNに申請書を提出、今年4月にIUGSとGGNによる
書類審査を通過、8月に現地審査を受け、10月1〜3日にギリシャレスボス島で
開催されたヨーロッパジオパークネットワーク会議と平行して行われたGGN
Bureau meetingでGGN加盟が認められたものです。
山陰海岸ジオパークは鳥取市から兵庫県日本海側を経て京丹後市までを含む
地域です。GGNの審査では、次のような点が評価されました。
・地形・地質の多様性と重要性。
・ガイドツアー、遊覧船でのガイド、様々なイベントなどにより一般市民向
けの普及活動が広く行われている。
・教育・普及活動の拠点があり、野外にわかりやすい解説版がある。
・広い範囲にわたる自治体・各種団体がうまく協力して運営している。
・コウノトリと湿地の関係は、地形・地質と生態系の関係の良い例であり、
湿地の保全とコウノトリの保護が地域の活性化と両立していることは、
地形・地質・生態系の多様性と人との共生を示す良い例である。
今回新たに加盟を認められた地域は下記の通りです。
・Basuque Coast Geopark, スペイン
・Parco Nazionale del Cliento e Vallo di Diano, イタリア
・Rokua Geopark, フィンランド
・Tuscan Mining Park, イタリア
・Vikos-Aoos Geopark, ギリシャ
・Dong Van Karst Plateau Geopark, ベトナム
・Jeju Island Geopark(済州島), 韓国
・Leye-Fengshan Geopark, 中国広西チワン族自治区
・Ningde Geopark, 中国福建省
・山陰海岸ジオパーク, 日本
・Stonehammer Geopark, カナダ
渡辺真人(産総研 地質調査総合センター)
累計で25ヶ国77地域が世界ジオパークネットワーク加盟になったとのことです。
詳細は、、、http://www.geopark.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第2回惑星地球フォトコンテスト 作品募集
──────────────────────────────────
このコンテストはユネスコおよび国際地質科学連合による国際惑星地球年(2007-
2009年)を契機に始められたものです。私たちの惑星「地球」をテーマにした写真
を公募し、優秀な作品を表彰するとともに、広報、普及、教育活動を通じて地球
科学に対する理解を深め、学術の振興と社会の発展に寄与・貢献することを期待
するものです。
今年も多数のご応募をお待ちしています!!
主催 一般社団法人 日本地質学会
応募締切 2011年1月31日(月)
賞および賞金 最優秀賞 1点 賞金5万円/優秀賞数点賞金3万円ほか
詳しくは、http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】Island Arc 日本語要旨 Vol.19 Issue3
──────────────────────────────────
特集号:Thematic Section: Bridging the gap separating geological studies
and disaster mitigation countermeasures for earthquakes and tsunami
(地震・津波堆積物研究の最前線−防災への貢献を目指して)
後藤和久,藤原 治,藤野滋弘
日本語要旨はこちら(ログイン不要です)
http://www.geosociety.jp/publication/content0048.html
全文無料閲覧(英語)はこちら(会員ページへのログインが必要です)
https://www.geosociety.jp/user.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】支部情報
──────────────────────────────────
■日本地質学会関東支部2010年秋季シンポジウム
「関東盆地の地下地質構造と形成史」
開催日: 2010年11月20(土),21(日)
場所: 日本大学文理学部3号館5階
詳しくは、http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】学術の大型研究計画に関する調査(平成22年度)について
──────────────────────────────────
—大型研究計画マスタープランの改訂— (締切11/15)
日本学術会議科学者委員会学術の大型計画検討分科会において昨年行った大型研
究に関する調査を,今年も行うことが決定されました.
この中で,今年3月に発表された43計画の改訂と新たに新規提案の第3回目調
査を行います.締め切りは本年12月22日であり,来年3月までに素案を作り,
10月の総会で承認する予定です.
第3回調査のご案内:
http://www.jpgu.org/whatsnew/100926scjchosa1.pdf
43計画の改定のご案内:
http://www.jpgu.org/whatsnew/100926scjchosa2.pdf
http://www.jpgu.org/whatsnew/100926scjchosa3.pdf
これを受けて,日本学術会議地球惑星科学委員会企画分科会では,日本地球惑星
科学連合理事会と調整して,次のタイムスケジュールで,大型計画の提案につい
て,調査の取りまとめと全体の調整を行うこととしました.
(1) 11月15日までに連合下記専用フォームにてご提案を提出ください.
<日本学術会議へ直接送ることはしないで下さい>
回答専用フォーム:http://don.jp/ezform107/17367/form.cgi
提案は,第1回目,第2回目に提案したかどうか,また,現在,43計画の中に
含まれているかどうかに関係なく,新たに提案をして下さい.これは,前回の調
査が不徹底であったとの反省から,今回は,再び,コミュニティーの考えをすべ
てを網羅したいと考えるからです.
(2) 11月15日までの提案をもとに,地球惑星科学委員会では連合のサイエン
スボードと連携して,全体の調整を行い,提案者の皆様へフィードバックを行い
ます.その検討を通じて,12月22日の締め切りに間に合うように,全体調整
案を作ります.調整は,3月の提言にあるクライテリアを基として,判断して行
きます.
学術会議の大型研究計画マスタープランは,次第に種々の局面で重要性が増して
おります.地球惑星科学分野においても,しっかりこれをフォローする必要があ
ります.どうぞよろしくご協力願います.
日本学術会議地球惑星科学委員長 平 朝彦
日本地球惑星科学連合会長 木村 学
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】緊急連絡「元気な日本復活特別枠」のパブリックコメントについて
──────────────────────────────────
政府の平成23年度予算概算要求につきましては、標記「元気な日本復活
特別枠」が設けられ、この特別枠に対する各府省の要望事業に対する、国民から
のパブリックコメントの受け付けが9月28日(火)から開始されました。締切
りは10月19日(火)午後5時までとされております。
日本学術会議では、本年4月に、「日本の展望—学術からの提言2010」を取り
まとめ、我が国の学術と社会が目指すべき方向について、幅広い提言を行いまし
た。
今回の特別枠に対する各府省の要望事業には、学術研究や大学教育に関するもの
など、日本の展望で提言したことに関わるものも含まれており、日本の科学者コ
ミュニティを構成する一人一人が、積極的に意見を送ることが重要であると考え
ます。
具体的には、首相官邸の以下のウェブサイトにアクセスして下さい。そして、
「分野別」もしくは「府省別」に、関連する要望事業をご確認下さい。「府省別」
で要望事業をご確認いただく場合は、さらに「要望事業一覧を見る」をクリック
して頂くことにより、御意見を入力することが可能になります。お一人で意見を
付すことができる事業の数に制限はありません。
官邸ウェブサイト http://seisakucontest.kantei.go.jp/
意見を入力するためには、ユーザー登録を行い氏名等を入力して頂く等の手続
きが必要です。皆様大変お忙しい中、お手数とは存じますが、今回のパブリック
コメントが、今後の学術研究や大学教育等に重要な影響を与えることも考えられ
ますところ、できるだけ多くの方が御意見を送信いただきますとともに、この
ニュースメールを、広くお知り合いの方にも転送いただきますことを御期待申し
上げます。
(日本学術会議会長 金澤一郎)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】平成23年度概算要求に関する国立極地研究所長声明
──────────────────────────────────
現在、政府では、平成23年度概算要求における「元気な日本復活特別枠」要望に
関するパブリックコメント〜政策コンテスト〜を実施しています。
このパブリックコメントの対象事業の中には、
事業番号1905 事業名「強い人材」育成のための大学の機能強化イニシアティブ
が取り上げられています。
この事業の中には、国立大学及び大学共同利用機関の根幹を支える国立大学法人
運営費交付金が含まれており、特別枠で要望している国立極地研究所の「南極地
域観測事業」の経費はその一部をなしています。
言うまでもなく、南極地域観測事業は、地球システムの探求、とりわけ地球環境
問題という国民生活にも直結する重要な研究を推進しているものであり、また、
国家事業として国民の支持を得て50年余にわたり継続実施しているものです。
しかしながら、来年度の予算の状況によっては、南極地域観測事業の継続実施が
困難になるのではないかと、大変危惧しております。
ついては、このパブリックコメントは、今後実施される優先順位付けの際の参考
となるものですので、是非、皆様のご理解のもと、今後の研究・教育の進展のた
め、数多くのコメント(締め切りは、10月19日(火)17:00)を出していただけま
すよう、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
平成22年10月4日
情報・システム研究機構 国立極地研究所長 藤井 理行
http://www.nipr.ac.jp/announce/20101004.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のご案内
──────────────────────────────────
■深田研一般公開 2010
日時:10月16日(土) 10:00-16:00
場所:深田地質研究所
参加費:無料
講演「パパは南極へ行った—第48次南極観測隊 486日間の越冬生活—」
講師:新井直樹氏 (独)電子航法研究所
時間:14:00-15:30
http://www.fgi.or.jp/index.html
■石油技術協会平成22年度秋季講演会
資源探求フロンティアー新しいエネルギー資源を求め続けて
日時:10月27日(水)10:30〜17:20
会場:東京大学本郷キャンパス 小柴ホール
参加費:
・正会員、賛助会員、協賛団体(所属者) 2,000円
・学生無料、非会員4,000円
詳しくは、http://www.japt.org/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募・各賞助成 情報
──────────────────────────────────
■北海道大学大学院工学研究院環境循環システム部門資源循環工学分野教員公募
(2011/1/7締切)
■平成23年度学術研究船淡青丸/白鳳丸共同利用(10/8締切)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(
geo-flash@geosociety.jp
)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.112 2010/10/13 geo-flash(臨時)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.112 2010/10/13 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】連合大会2011年大会のセッション提案にご注意下さい
──────────────────────────────────
来年(2011年)の日本地球惑星科学連合大会でセッション開催を予定している
専門部会及び会員の皆様へ
来年(2011年)の大会から学会主催のレギュラーセッションは廃止され、
すべてのセッションが公募になっております。セッション提案を予定
している場合は、お忘れのないよう申込手続きをお願いします。
締切は10/26です。
地質学会主催または共催の形(地質学会を提案母体にする形)でセッション
提案を予定している専門部会及び会員は、次のような手続きをお願いします。
・最も関連する(または従来母体となってきた)専門部会の行事委員を通じて
行事委員会に報告し、承認を得たら申込手続き。
・関連する専門部会がない場合は,コンビーナーが行事委員会(学会事務局)
に直接報告し、承認を得たら申込手続き。
すでに地質学会主催あるいは共催の形で提案を済ませた専門部会あるいは
会員は、今回に限り事後の報告でも構いませんので、必ずお知らせください。
ご協力よろしくお願いします。
(執行理事会)
現在提案済みのセッションは下記のwebにリストアップされています.
https://secure.jtbcom.co.jp/jpgu/session/DisplaySessionProposalStat.asp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質調査中のトラブル体験記と危険回避術(後編)
地質調査中のトラブル体験記と危険回避術(後編)
広島大学大学院地球惑星システム学科
日本勤労者山岳連盟会員 大橋聖和
気象
調査期間後半ともなると日数を稼ごうと無理をしてしまいがちであるが,悪天候時は安全なルートに変更したり,停滞してデータの整理に当てるなどの余裕が必要である.宿を出る前にはその日の天気予報を必ずチェックしておく.特に夏場は午後から天気が崩れる場合が多いので,午後の予報を注視する.また,低気圧や前線の接近も頭の中に入れておくと天気の移り変わりが予想できる.急な雨に備えてザックの中には常に折り畳み傘かレインスーツを用意しておきたい.特に雨に濡れた状態で風に吹かれると夏場でも驚くほど体温が低下するので(低体温症になる),軽視は禁物である.長雨の際には土砂崩れや落石にも十分注意する(雨が上がってからも数日間は危険性の高い状態が続く).
筆者は一度非常に怖い思いをして以来,雷にはかなり敏感になっている.そのときは朝から雨模様で入山前に一回だけ雷鳴を聞いたのだが,続かないようだし大丈夫だとそのまま入山してしまった.昼頃に下山するときになって雷鳴が何度か続くようになり,稜線上で激しく鳴り出した.雷が落ちてから次までの間に15秒ほど走って次の窪地を見つけ体をかがめる…の繰り返しでようやく稜線を通過したが,生きた心地がしなかった(この時は20〜30秒ほどの間隔で落雷が続いていた).これは前線に伴う雷を甘く見たことにあった.夏場の積乱雲に伴う雷は30分から1時間程度で通過(あるいは消滅)する一過性のものであるが,前線に伴う雷はそれに比べて長時間・広範囲におよぶ(一方で積乱雲による雷の場合は発達が非常に速いことに注意する).この時の雷は後者のもので,当時前線がかかっていることは分かっていたのだが,雷鳴が一度聞こえたにもかかわらず入山し,稜線沿いの道を選んだのは完全に判断ミスであった.
実際に雷に遭遇し,雷鳴が近い場合や周囲に落雷している場合は,下山を急がずに窪地で体勢を低くしてやり過ごさなければならない.また,落雷時にはその地点から半径2〜4 mの範囲内にも影響が及ぶので,高い樹木などからは離れておく必要がある.稜線上や平地などの隠れる場所がない場合,次の落雷までの間隔を利用して移動する手もあるが,平均間隔は10秒〜15秒というデータもある一方でほぼゼロの場合もあり,絶対安全というわけではないらしい.逃げ場のないところで雷に遭遇するようなシチュエーションを作らないというのが最善の策であろう.
一方で,夏場の晴天時は熱中症に注意が必要である.特に炎天下の採石場や海岸などでは照り返しにより恐ろしいほど気温が上がる.斜面にいるときに意識を失い,滑落・負傷した事例もあった.炎天下では直射日光から身を守る工夫と水分補給を徹底したい.
沢での安全
沢沿いで調査を行う人も多いと思うが,沢歩きは危険度の高い登山行為であることを認識しなければならない.ヘルメットは必須であり,足回りもフェルト底の地下足袋+脚絆が好ましい(登山・釣り具店で入手可能).ズボンは綿素材のものは避け,水切れがよく体温を低下させない化繊素材のものがよい.ジーパンは重く,足上げが困難になるため不適である.沢歩きは,登りよりも下りの方が危険性が高い.
筆者は,滝を高巻き(斜面の樹林帯を迂回する)して下りるときに滑落して痛い目にあったことがある.これは下山時であったが,サンプルで重量が増えたザックを背負って,登りと同じ踏み跡をたどったのが原因であった.下りのすべりやすさと重量増加を考慮し,登りよりも安全な道を選ばなくてはならなかった.特にフェルト地下足袋は土や植生のついた斜面ではほとんどグリップしないので注意が必要である(適宜下山用の軽登山靴を持つと良い).
大きな滝を越えるようなルートでは,登攀技術やロープワークを覚えることで安全性は大きく向上する.これについては,地質ニュース597号の37-46ページに長森英明氏によって詳しく書かれているので参考にされたい.ただし,登攀技術は見よう見まねで習得できるものではないため,志のあるものは経験者に指南を乞うか山岳会などでしっかりと身に付けてほしい.
万が一,サンプルを背負った状況で滝壺に落下した場合は,ザックを水中で脱ぐことが重要である.また,渦を巻く水流によって滝直下に引き込まれてしまうため,下流側に力強く泳いで脱出しなければならない.
両側が岸壁状の沢では,急激な増水時に逃げ場を失うため,気象状況の見極めは重要になる.また,北海道や中部山岳地帯の奥地を調査する者は,雨が降っていなくても天然ダムやスノーブリッジの崩壊によって急激な増水があることも頭に入れておく必要がある.いくらフェルト底地下足袋を履いていても,膝以上の徒渉は非常に不安定になり,腰以上になると水流が遅くても流されかねないため,増水時には特に注意する.
万が一の遭難に備えて
非常用装備品の例.可能な限り準備しておきたい.① ヘッドランプ,②非常食(高カロリーのものや飴など),③ライター(ジップロック等に入れておく),④ホイッスル&オリエンテーリングコンパス,⑤雨具(セパレートタイプ),⑥ビバークツェルト,細ロープ
「遭難」というと大げさな響きがするが,山中で足を骨折したり,現在位置を見失ってビバーク(用意なく山中で野宿すること)しようものならその時点で立派な遭難であり,その危険性は地表踏査の至る所に転がっている.これまで述べたのはいわば遭難しないための注意点であるが,実際遭難した際に早期発見するにはどうしたらよいだろうか.以下では遭難者と捜索者の視点から重要と思われる点を述べる.ちなみに調査中のビバーク事例は狩野謙一氏の「野外地質調査の基礎」(古今書院)にも書かれている.
遭難者側: 道迷いなどでその日のうちに下山できそうにない場合,日没前に安全にビバークすることを考える(ヘッドライトを持っていたとしても,暗闇の中歩き回るのは非常に危険である).雨具を着込み,薮や岩陰などに隠れて夜露をしのぐ.空にしたザックを寝袋のようにして足を入れているだけでも落ち着く.この際,ツェルト(簡易テント.収納時の大きさは350ml缶程度.一万円弱)やヘッドライトを持っていると非常に心強いので,是非ザックの片隅に入れておきたい.
沢歩きが得意な人であっても,遭難時の下山は谷(沢)には下りてはいけないのが基本である(その沢を安全に登ってきた場合を除く).状況の分からない谷への下山は,転・滑落の危険性が極めて高いからである.
尾根沿いに林道まで下りたら,すぐに安全が確保された旨の連絡を入れる.負傷して自力下山が見込めない場合,携帯電話の電波が入るかどうかを確かめる(携帯電話は防水の為必ずジップロック等に入れておく).電波状況が悪く電話が繋がらなくても,メールは送れる場合もある.また,尾根まででも登れれば,電波は入りやすくなる.
落石・増水の危険性のある場所からは身を遠ざけ,なるべく発見されやすい場所で待機する.近くに登山道がある場合や捜索の気配を感じたときは,ホイッスルやハンマーで音を立てるとよい.夏場,遭難から1週間以上たって無事発見された例はいくつもあるので,忍耐強く救助を待つ.無理な自力下山は逆に命取りになりうる.飴やカロリーの高い保存食を非常用にザックにしのばせておくことも重要である.
捜索者側: 通常の山岳遭難と同じであるが,むやみに人海戦術的に捜索をかけるのは二重遭難を引き起こす可能性があるので避けるべきである.まずは早急に対策本部を作り,どこで遭難した可能性が高いか推理する.この時,当日の調査範囲の情報があると非常に強力であるが,ない場合は知人との調査に関する会話や宿に置いてあるベースマップなどから居そうな場所を推理する.
自家用車で調査を行っている場合は,車がどこにおいてあったかが大きな手がかりとなる.現場での捜索時は,遭難者の足取りをたどるように探すのがポイントである(間違えやすい登山道の折れ曲がりや危険な滝など.遭難者の力量を鑑みながら).
また,調査の痕跡(踏み跡,ハンマー痕,露頭清掃の痕)からも居そうな場所を推定する.捜索者側からも,ホイッスルを鳴らしたり名前を呼びかける.発見した遭難者が自力下山不可能な場合は捜索者らでセルフレスキューが可能かどうか検討し,不可能であれば消防に救助要請をする.警察・消防,地元の山岳会などに捜索協力を要請した場合,いかに正確な情報を共有できるかが発見の鍵となる.地質屋の習性や遭難者の性格・技量を正しく伝えないと,見当はずれな場所を捜索してしまう可能性もある.
いずれにせよ,遭難となると大学関係者のみならず警察や消防にも多大な迷惑をかけてしまう上,莫大な救助費用が請求される可能性もある.十分な安全対策と絶対に遭難を起こさない気構えが必要である.情報伝達の不手際による「遭難騒ぎ」にも十分注意したい.
おわりに
以上,可能な限り調査時の危険事例と対策を書いたが,もし実際に事故が生じたり,ヒヤリ・ハットなどの事故の萌芽があった場合には,関係者でその原因について考察,反省し,第三者にも情報を共有させることが再発防止上重要である.決して「武勇伝」や「自慢話」として扱ってはいけない.是非大学などでも事例を文章化し,同じ事例を繰り返さないような活用が望まれる.
[参考ホームページ]
http://www.arito.jp/oth_sonan.shtml(坂口有人氏のビバーク体験)
http://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/~oyo/accident.html(岩松暉氏による事故防止Tips)
地質調査中のトラブル体験記と危険回避術(前編)
地質調査中のトラブル体験記と危険回避術(前編)
広島大学大学院地球惑星システム学科
日本勤労者山岳連盟会員 大橋聖和
先日,日本地質学会富山大会での懇親会で地質調査中の苦労話を紹介させていただいたところ,News誌編集委員長の坂口さんに情報共有のために寄稿してもらえないかと依頼を受けた.個人的にも調査時の安全管理の重要性を近年特に認識するようになったため,適任者かどうか不安もあるが快諾した次第である.以下では,私の調査中のトラブル体験談とともに,小トピックごとに一般的な山での安全術を紹介する.特に地質調査を始めたばかりの学生を対象とするが,ベテランの先輩方にも今一度安全対策を思い直すきっかけになれば存外の幸せである.地質調査のリスクを十分に把握した上で,安全且つ高度な地質調査を目指したい.
調査予定届けの重要性
各トラブル事例の前に最も重要なことを書いておきたい.それは,その日どこに調査に向かうか,どの沢や林道に入る予定であるかを第三者に知らせておくことである.これは特に単独調査の場合は極めて重要であるが,複数人であっても知らせておくべきである.家族,友達,指導教官,あるいは宿の人でも構わない.どうしても知らせられない場合は,宿や車の中に今日の予定のメモ書きを残すだけでもよい.この情報が,実際に大きなトラブルが生じたときに助けになるのである.調査終了時には無事終了した旨も伝えたい.
野生動物との遭遇
地質調査中の野生動物との遭遇は不可避である.特に近年ではツキノワグマが中山間地や平地にまで下りてくる事例が相次いでいるため,特にツキノワグマの対策について書きたいと思う.よく,ツキノワグマはヒグマに比べて“安全”などと言われるが,格闘すれば重傷は免れず,場合によっては死亡するため決して甘く見てはいけない.また,「熊に出会ったときの対処法」という一問一答を見かけるが,「熊に出会った時」と十把一絡に考えるのは好ましくなく,熊対策は3つの段階に分けて考えなければならない.つまり,(1) 熊に会わないためにどうするか(遭遇前),(2) 遠距離で熊にあったらどうするか,そして(3) 近距離で熊にあったらどうするか,である.
私の遭遇経験などからすると,人間は熊に出会うとまず冷静な判断が出来なくなる.したがって,(1) 熊に遭遇しないためにどうするか,が極めて重要となる.まず調査前にしておかなければならないのは,その地域にどのくらいの熊が棲息しているかを調べることである.本州・四国におけるツキノワグマ,北海道におけるヒグマの分布はインターネット上で調べられる上,頻出地域の自治体のホームページでは出現日時や場所まで詳しく報告されているので事前に調べておく.また,夏以降は木の実の作況などからその後の出現動向が予想されるので,参考にしたい(今年の10月以降の大量出没は9月から予測されていた).
不運にして調査地域が熊の生息地であった場合,現地では熊注意の看板や,糞・爪痕などの熊の気配(生活痕)の有無に気を配り,熊目撃の防災無線なども聞き漏らさないように注意する.調査は断続的に大きな音を立てて人間の存在を知らせながら行う.ツキノワグマは本来臆病な性格なので人の気配を察すると向こうから逃げてくれる.ここで気をつけたいのは如何にして音を立てるかである.よく登山用品店などで売っている「熊鈴」は登山道では良いが,沢では水の音にかき消されて経験上ほとんど役に立たない.また,基本的に歩いているときにしか音が出ないのも盲点である.筆者はハンマーの側面を堅い転石に叩き付けて音を出している.これは「キーン,キーン」と非常に通る音を発するので都合が良い.未固結岩地域ではホイッスルが有効である(転石のない沢の源頭部や立ち止まっているときにも有効.数100mは音が通る).これまで筆者が熊に遭遇したのはいずれも十分な音を出していなかったときであり,ハンマーを鳴らしていたときには一度も出会っていないことを考えると,やはり大きな音で存在を知らせることが一番有効であると感じる.
さて,次に遠距離(お互いに冷静さを保っていられる距離:約30m以上と言われている)で熊にあったらどうするかであるが,相手に気づかれていないようであれば,そのまま後ずさりで距離を広げ,その日の調査はそこから少なくとも数km離れた所に変更する.相手に気づかれたとしてもこの距離から襲ってくるケースは少ないので,冷静に相手の様子を見ながら後ずさりで退却する.安全な場所にすぐに到達できる場合などを除いては、走って逃げるなどして不要な刺激をクマに与えてはいけない.
一方で近距離(約30m以内)で熊にあったらどうするかであるが,冷静さを保てるように努力することがまず先決である.熊の様子を見ながら、「お前何してるんだ.向こうに行きなさい」などと話しかけるのも,自らを落ちつかせるためにいいようである.特に10m以内の至近距離の場合,多くの人は体が凍り付いたようになるとともに,力が入らなくなるだろう(腰が抜ける手前.筆者や知人は実際にこれに近い状況を体感している).突発的な行動さえしなければ,襲われる可能性は小さい.襲われた際の対処法は書籍やインターネット上で見ることも出来るが,抵抗(格闘)した方がいいという一方で,抵抗すると熊を逆上させるという意見もあるなど読めば読むほど一筋縄ではいかないようである.ケースバイケースで正解はなく,実際の体験談を元に判断するしかないだろう.
インターネット上にもいくつか体験記があるので,もしものときの判断材料にされたい.また,子育て期の親熊は非常に過敏になっているので,小熊を見た際は十分に注意が必要である.熊対策は,いくら知識を詰め込んでも「これで大丈夫」ということはなく,むしろ本当に冷静に対処できるだろうかと不安になる.結局のところ,熊の生活圏にいることを常に意識し「熊に遭わないようにする」のが対策上の神髄だといえる.
筆者の卒論時の体験を話そう.熊に遭遇したのは富山−岐阜県境の飛騨高地と呼ばれる場所であり,調査地域の中でも特に険しい谷であった.時期は秋口の9月30日のことである.遡行開始点に車を止め,堰堤を4つほど越えた約900m上流まで調査を行った時,前方で木の折れるバキッという音に気がついて顔を上げた.目に飛び込んできたのは,約20m前方の斜面にいるツキノワグマであった.向こうは立ち姿勢で大の大人ぐらいの大きさに見え,既にこちらを凝視していた.瞬間的に筆者は凍り付き,全身の血の気が引いたように感じた.直後にどうしたかというと,踵を返して一目散に来た沢を走って下ったのである.ほとんど本能的であったが,この時頭の中には「さっき越えた堰堤を下れば逃げられる!」という考えがあった.遭遇地点から約30m下流側にあった最も近い堰堤を落ちるように下ったが,後ろの様子を確認する余裕はなく,ようやく立ち止まって確認できたのはその後さらに2つの堰堤を越えた後だった.追ってくる様子はなく,やっと生きた心地が戻ってきたが,車に戻っても体の震えが残る状態だった.
ここにはいくつかの反省すべき点がある.まず,この時ほとんどハンマー音を出していなかったことである.思い返すと,調査期間後半の慣れと気のゆるみが原因であったことは明らかであった.もう一つは遭遇時に冷静さを失い,走って逃げたことである(この時が人生初の熊との遭遇であった).堰堤を下れば逃げられるという判断が正しかったかどうかわからないが,それにしても走って逃げるという行為は熊の本能的習性により追われるリスクをかなり高める.恐らく熊にとっては堰堤脇の急斜面などいとも簡単に(むしろ人間より早く)下りられたであろう.結果的に襲われずに済んだが,よくよく考えると運が良かっただけであった.堰堤を下るにしろ,相手の状況を見つつゆっくりと下りる必要があった.
ヒグマの場合も遭遇しないための対策は基本的に同じである.道庁や各振興局のホームページから最新の情報を仕入れておくことと,過去の事故事例をよく読んでおくことが必要である.特にカムイエクウチカウシ山での福岡大ワンゲル部の事件は教訓として生かさなければなるまい.
他に注意が必要な野生動物は毒ヘビや蜂などである.毒ヘビはこちらから危害を与えない限り攻撃することは少ないが,岩場や林道によく現れるので,誤って踏まないように注意する.マムシは判別できるように特徴(形と背中の斑紋)を覚えておいた方がよい.スズメバチとの遭遇については昨年東大の鳥海光弘氏が体験談を寄せている(地質学会メールマガジンNo.41)ので是非参考にしていただきたい.
車のトラブル
意外と忘れられがちであるが,調査中の車の事故やトラブルは,初歩的なトラブル事例として頻繁に耳にする.
林道走行時に注意する点は,落石,車体底部の接触,パンクなどであるが,当然フィールドまでの道でも居眠り運転やスピード超過に注意する(特に免許取り立て〜2年以内の学生は要注意).自家用車で長期間の調査に出かける際は,タイヤの空気圧,ウォッシャー液の量,スペアタイヤの状態を今一度確認したい.車高の低い車で林道を走行する際は轍にはまらないようなライン取りが必要であるが,轍から無理に出ようとしてタイヤの側面を岩角に引っ掛けてパンクする例もよく見る.タイヤの側面は強度が低く,パンク修理剤でも直せないので要注意である.また,勢いよく車体底部をぶつけてオイルパンに穴をあけた例も聞いたことがある.
私自身,林道で車をぶつけたりヒヤッとしたこともあるが,いずれも同乗者がいるときであり,知らず知らずのうちに注意力が散漫になっていたことに気づかされた.同乗者も積極的にナビ役に徹するとか,話をして運転者の眠気をさますなどの配慮が必要である.また,林道のカーブでオフロードバイクが突然現れて驚いたこともあった.最近は廃道・酷道マニアなども多いらしい.偶然開いていたゲートが帰りになって閉じられる場合もあるため,災害や工事に伴う林道の規制状況も毎年調べておく必要がある.
その他,林道でバッテリー上がりの車を助けたこともあったが,逆に脱輪を助けてもらったこともあった.ブースターケーブルや牽引ロープの重要性を痛感した.ガス欠で3時間かけて徒歩で下山した話や,鍵の閉じ込みを偶然通りかかった車に助けてもらった話もある.町中ではなんでもない車の故障が,勾配のきつい道や携帯電話の圏外,人里離れた場所では命取りにもなりかねないことを認識したい.
一方で,山中に車を停めていると地元住民に不審がられたり,遭難などと勘違いされて通報される可能性もある.私の場合,ダッシュボードの上に「地質調査中」と書いた紙を置くようにしている(所属と緊急連絡先も書いている).近隣住民の理解のためにもあった方が良いのではと思う.
次回後編では,気象,沢での安全,万が一の遭難にスポットを当て紹介させていただきます.
No.120 2010/12/16(臨時)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.120 2010/12/16 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 深田淳夫 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
日本地質学会名誉会員,深田淳夫氏(応用地質(株)名誉顧問,深田地質研究所名
誉会長)が平成22年12月10日(金)にご逝去されました(享年88歳).
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます.
なお,ご葬儀は既に近親者のみで執り行われており,後日「お別れの会」を行う
予定とのことです.
「お別れの会」
日程未定:来年1月末〜2月上旬を予定
お問い合わせ先:応用地質(株)社長室 電話03-3234-0811(代)
会長 宮下純夫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.118 2010/12/14(臨時)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.118 2010/12/14 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】地球惑星科学「夢ロードマップ」へのご意見募集!<追加・補足>
──────────────────────────────────
地球惑星科学「夢ロードマップ」へのご意見募集ということで【geo-Flash】
No.117 (臨時)号を発行しましたが、会員の方から ”PPC資料を見ただけ
では的確なコメントが出せないのでは、補足的説明がほしい、”というご意見
がありました。
連合から各学協会長に対し出された文書と、上記意見に対して改めて連合
会長からいただいたコメントを以下に掲載したします。
会員各位におかれましては、これらをご参考に、地質学会あてにご意見
をお寄せください。それらをもとに、地質学会としての意見をまとめて
提出したいと思いますので、みなさまのご意見をお待ちしております。
地質学会事務局への意見提出の〆切は、12/20(月)とさせていただきます。
また、地質学会事務局の〆切に間に合わない場合でも、地惑連合のホーム
ページでは12/31(金)まで意見を受け付けています。
・「夢ロードマップ」案
http://www.jpgu.org/whatsnew/101208roadmap.pdf
<連合木村会長コメント>----------------------
経過にありますように、文書といえば、「日本の展望2010」があるだけ
です。その作成に学術会議は1年以上の時間をかけたものです。Pptの説明
文各A41枚程度のものとしてまとめるようにとの学術会議からの要請により、
作業がいま行われているところです。Pptも分野において1枚というのが、
学術会議からの要請であり、そのポイントは時系列の中で、どのコミュニ
ティーから見てもキーワードが落ちないようにと配慮するかでした。その
作業では大局的な科学技術展望とその中での個別的分野の位置を如何に
織り込むのかが焦点です。A41枚の説明文は更に難しく、大変苦労して
いるところです。 それについては、1月28日の学術会議までに第1次案
作成の予定です。それについても改めて公開し、意見を求める方針です。
すべてをそろってから意見を聞けとおしかりを受けそうですが、一方で
短い期限が定められ、一方でコミュニティーの意を尽くすようにとの要請
の両者を成り立たせるためには、進捗に応じた逐一の公開により、意見を
反映させて行くしかないことをご了解いただければと思います。
学術会議の見解は、政府の政策を動かすほどに大きくなって来ており、
コミュニティーのマイペースだけで議論が出来ないことをご理解いただけ
ればと思います。
従って、文書としては当面「日本の展望」を取り合えずは参照していただ
き、地質学会独自の視点から見て、改定、修正すべきところがあればお願
いしたいというのが主旨です。
・「日本の展望―学術からの提言2010 報告 地球惑星科学分野の展望―
地球の未来予測への挑戦―」
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-21-h-3-4.pdf
「夢ロードマップ」に関わって重要なことは、各学協会長への依頼文にも
記しましたが、連合作成中のものについてのご意見をいただくとともに、
それぞれの学協会が、それぞれの分野の科学・技術の将来展望を持つことの
推奨です。先の学協会長会議にてすべての学会が会員数において右肩下がり
であることが明らかとなりました。団塊世代が抜けて行くということもあり
ますが、若者の参加が鈍いということもあります。
それらを打開するためには、それぞれの分野がそれぞれの科学・技術発展の
将来展望を持ち、それを基軸吸引力として組織的発展の戦略を練る。そして、
より広い地球惑星科学分野の中で「戦略的互恵関係」を計りながら全体の
発展をめざすことが必要です。それが連合の立場です。地質学会は連合に
おいても今や間違いなく基軸学会の1つですね。
学術会議は、理工系、生命系、そして人文系も含めて更に広い分野でそれ
をはかろうとしているとことだと思います。 よろしくお願い致します。
--------------------------------------------
加盟学協会長各位
日本地球惑星科学連合では,先の学協会長会議にて紹介致しました通り,
日本学術会議との連携作業として,「夢ロードマップ」作成作業を,企画
委員会と各サイエンスセクションボードを中心として開始しております.
学協会各位におかれましては,現段階での素案に関するご意見をお寄せい
ただければ幸いです.
この作業の位置づけは,学術会議から発行された「日本の展望―学術から
の提言2010」のそれぞれの分野の充実を計り,国民による一層の科学・技
術への理解の促進,国の長期的科学・技術政策への反映を図るためのもの
です.「日本の展望」作成時と大きく異なるのは,それぞれの分野の科学
者コミュニティーがより深く,広く,かつ主体的に作成をすすめることが
奨励されている点です.
これを受けて,日本地球惑星科学連合は,地球惑星科学に関連する科学・
技術者・教育者,加盟学協会と日本学術会議との連絡調整窓口としての任
務を果たすべく,地球惑星科学分野全体をカバーする体系的な「夢ロード
マップ」の作成を,企画委員会と各サイエンスセクションボード中心とし
て開始しているところです.その素案をHPにアップいたしました.
この素案に対する「修正案・改定案」を募集致します.以下のURLから,
お寄せください.
http://www.jpgu.org/whatsnew/101208roadmap.html
学術会議のスケジュールの都合上,本年末12月31日(金)までにお寄せ
いただければ幸いです.ご協力のほど,よろしくお願い申し上げます.
日本地球惑星科学連合は,今後,この「夢ロードマップ」に関して,日本
学術会議地球惑星科学委員会と連携し,大型研究に関する検討と合わせて,
2011年5月に開催予定の連合大会ユニオンセッションとして議論すること
を予定しております.また,学術会議においては,2011年3月18日に理工
系全分野の夢ロードマップ会議,そして8月24日には,広く国民へ紹介す
る第三部主催シンポジウム「科学・技術の過去・現在・未来」を予定して
います.
なお,各学協会におかれましても,これを機に改めてそれぞれの中・長期
を展望した将来ビジョンに関する議論を活性化していただくことをお願い
申し上げます.加盟学協会と連合が共に協力しながら将来ビジョンに関す
る議論を深めることは,日本の地球惑星科学分野の発展にとって極めて重
要です.
よろしくお願い申し上げます.
日本地球惑星科学連合 会長 木村学
日本地球惑星科学連合,企画委員会 中村正人
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.119 2010/12/16(臨時)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.119 2010/12/16 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2011年度学会各賞募集中:12月24日(金)締切!!
──────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして、研究の援助・奨励および研究業
績の表彰を行っています(定款第3条)。本年も各賞の自薦、他薦による候補者を
募集中です。正会員の皆様なら、どなたでも推薦できます。
締切間近ですが、期日厳守にて、たくさんのご応募をお待ちしており
ます。
応募締切:2010年12月24日(金)必着
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
(会員番号・パスワードによるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
★「第2回惑星地球フォトコンテスト」作品募集中!
http://www.photo.geosociety.jp/
No.117 2010/12/13(臨時)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.117 2010/12/13 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】地球惑星科学「夢ロードマップ」へのご意見募集!
──────────────────────────────────
地球惑星科学「夢ロードマップ」が日本地球惑星科学連合のもとで作成され
ています。これは、地球惑星科学分野の将来像をまとめ、物理・化学など他
の学術分野も含めた国の長期的科学・技術政策への反映を図るための重要な
資料となるものです。
現在、「夢ロードマップ」案に対する修正案・改定案の募集が行われており、
地質学会としては、会員のみなさまから広く寄せていただいた意見を基に地
質学会としての意見書を提出することとしました。
そこで、会員のみなさまには、ぜひ「夢ロードマップ」案をご確認いただき、
意見・要望などを日本地質学会事務局( main@geosociety.jp )までお寄せくだ
さるようお願いします。
・地球惑星科学「夢ロードマップ」案に関する修正案・改定案 ご意見募集
http://www.jpgu.org/whatsnew/101208roadmap.html
・「夢ロードマップ」案
http://www.jpgu.org/whatsnew/101208roadmap.pdf
取りまとめの都合上、地質学会事務局への意見提出の〆切は、12/20(月)
とさせていただきます。
また、地質学会事務局の〆切に間に合わない場合でも、地惑連合のホーム
ページでは12/31(金)まで意見を受け付けています。
みなさまのご意見お待ちしております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.121 2010/12/21 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.121 2010/12/21 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】コラム:最近、太陽黒点が少ないことについての雑感
【2】国際地学オリンピック日本大会が公認されました!
【3】JSEC2010表彰式報告:地学関係者の活躍目立つ!
【4】2011年度学会各賞募集中:12月24日(金)締切!!
【5】2011年度会費払込/2011年度学部・院生割引申請書受付中!
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報
【9】事務局年末年始休業のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】コラム:最近、太陽黒点が少ないことについての雑感
──────────────────────────────────
太陽黒点については、ガリレオ以来すでに約400年の観測の歴史があり、黒点の数
は太陽活動の活発さを表す指標として重視されている。黒点数は約11年を周期とし
て増減を繰り返してきた(黒点周期)。黒点数は、多い時(極大期)には100〜200
に達するが、少ない時(極小期)はゼロに近くなる。(中略)
私は晴天の休日には小さな望遠鏡で黒点観測をしているが、近頃も黒点数ゼロの日
が多い。
続きを読む、、、http://www.geosociety.jp/faq/content0056.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】国際地学オリンピック日本大会が公認されました!
──────────────────────────────────
2012国際地学オリンピック日本大会に関わる最新情報:
地学オリンピック日本委員会では、文部科学省に国際地学オリンピック日本大会の
支援の要請を行いました。これに対し「文部科学省として、地学オリンピックを生
物や化学などのオリンピックと同様な扱いをする。国際大会に関しても、国際生物
オリンピック日本大会や化学オリンピック日本大会と同様な支援をする。」という
回答をいただきました。これにより、国際地学オリンピック日本大会が国から公式
に認められたことになります。
NPO法人地学オリンピック日本委員会
http://jeso.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】JSEC2010表彰式報告:地学関係者の活躍目立つ!
──────────────────────────────────
副会長 久田健一郎
第8回ジャパン・サイエンス&エンジニアリング・チャレンジ(JSEC2010) / 高校生“科学技術”チャレンジ(主催 朝日新聞社, 後援 日本地質学会、内閣府、文部科学省など)の表彰式が12月12日に日本科学未来館で行われました。今年は全国から122件の応募があり、数回に及ぶ 審査後30件がファイナリストとして参加しました。ファイナリスト30件のうち、カテゴリー地学は4件、カテゴリー地球宇宙科学は3件と、地学関係者の活 躍が目立っていました。
本大会では、最も優秀な研究に最高賞のGrand Awardが授与されます。Grand Awardには、文部科学大 臣賞、科学技術振興機構賞、科学技術政策担当大臣賞の3賞があり、優れた研究がそれぞれ一件ずつ選ばれます。他にも優れた研究に対し協賛社賞、朝日新聞社 賞、審査員奨励賞が与えられます。本年の文部科学大臣賞は「折り紙を用いた多面体の切断・分割と空間の充填」(立命館中学校・高等学校、女子生徒1名) に、科学技術振興機構賞は「プレゼンテーションの時の「あがり」感の心拍・皮膚電気伝導度への影響と皮膚電気伝導度のSCR指標の色表示によって「あが り」感を抑制するバイオフィードバックシステムの構築」(早稲田大学高等学院、男子生徒2名)が受賞しました。そして科学技術政策担当大臣賞は、「桜島の 噴火に従う火山雷の発生メカニズムの解明を目指して〜桜島における大気電場観測と火山雷の光学・電波観測〜」(鹿児島県立錦江湾高等学校、男子生徒3人) に授与されました。また審査委員奨励賞(3件)は、「遠州灘海岸の砂に含まれるガーネットの性質とその起源の推定」(静岡県立磐田南高等学校、男子生徒3 人)に授与されました。
さらに、すぐれた研究指導を行った先生に贈られる賞にインテル賞(1件)があります。本大会では、静岡県立磐田南高等学校青島 晃先生(日本地質学会会員)が受賞しました。
静岡県立磐田南高等学校は、生徒・先生が共に受賞するというダブル快挙を成し遂げました。同校は今年の9月に行われた第4回国際地学オリンピックインドネシア大会でも銀メダル1個を受賞しています。
Grand Award受賞の3件と、協賛社賞3件、朝日新聞社賞1件が来年5月アメリカ・ロサンゼルスで開催されるIntel ISEF Fairに派遣されます。そのうち3件が、Intel ISEF Fairのコンテストに参加することになりますが、その3件は後日発表されるとのことです。
なお「ISEF」は、「International Science and Engineering Fair」の略で、「国際学生科学技術フェア」「国際学生科学技術博覧会」などと和訳されています。世界中40ヶ国以上から集まる1500人をこす高校生 (9-12grade)が自分たちの研究を披露しあう科学研究コンテストで、いわば「科学のオリンピック」です。半世紀以上も続いている伝統あるフェア で、毎年5月にアメリカの都市で開催されます。運営主体はワシントンにある非営利団体のサイエンスサービス「Society for Science & the Public」で、1997年よりインテル社がメインスポンサーとなり「インテル国際学生科学フェア(Intel ISEF)」となりました。(http://www.isef.jp/ より)
写真1 インテル賞を受賞した青島晃氏
写真2 受賞者・関係者で記念撮影
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2011年度学会各賞募集中:12月24日(金)締切!!
──────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして、研究の援助・奨励および研究業
績の表彰を行っています(定款第3条)。本年も各賞の自薦、他薦による候補者を
募集中です。正会員の皆様なら、どなたでも推薦できます。
締切間近ですが、期日厳守にて、たくさんのご応募をお待ちしております。
応募締切:2010年12月24日(金)必着
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
(会員番号・パスワードによるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2011年度会費払込/2011年度学部・院生割引申請書最終受付中!
──────────────────────────────────
■2011年度会費払込について
次年度分会費の前納をお願いいたします。自動引き落としを登録されている方の
引き落としは、12月24日(金)です。お振込の方へは、12月中旬頃までに請求書
兼郵便振替用紙発送いたしましたので、折り返しご送金をお願いいたします。
■2011年度学部・院生割引申請書最終受付中!
最終締切は、2011年3月31日(木)です.この期日までに申請書を必ずご提出く
ださい.なお,これまで(〜2010年度)の院生割引会費についての申請受付は終了
していますので,2011年度分の申請のみ適用となります.
詳しくは、https://www.geosociety.jp/user.php
(会員番号によるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
■北海道支部総会・個人講演会
日程:2011年2月26日(土)
場所:北海道大学大学院環境科学研究院D棟101室
個人講演会申込締切:1月21日(金)
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
■西日本支部例会のお知らせ
日程:2011年2月19日(土)
場所:広島大学理学部(東広島市鏡山)
講演会申込締切:2月14日(日)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
■東北支部2009〜2010年度総会,個人講演会と公開シンポジウム
会場:「コラッセふくしま」5階研修室
日程:2011年3月12日(土)−13日(日)
公開シンポジウム「東北地方におけるジオパークへの取り組み(仮題)」
個人講演申込締切:2011年1月26日(水)
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■平成22年度東京大学大気海洋研究所共同利用研究集会
「日本列島周辺域に分布するテフラのデータベース整備にむけて」
日本第四紀学会 テフラ・火山研究委員会は,上記の研究集会を開催いたします.
ふるってご参加下さい.
火山国である日本周辺には,爆発的噴火の産物であるテフラが多数分布します.過
去に噴出し堆積物中に保存されているテフラは,第四紀編年,古環境復元,地形変
化史,火山噴火史,考古編年など様々な分野で指標として用いられています.日本
のテフラの研究史は長く,日本列島における上記研究分野の特徴となっています.
ところで,各種地球科学分野のデータベースが急激に整備されつつあるにもかかわ
らず,テフラ研究分野では紙媒体で研究が進められているのが現状です.一方で,
個人研究レベルで,テフラのデータベース化が試みられている場合もあります.本
研究集会では,テフラのデータベース化に関する情報交換を行い,本格的なテフラ
のデータベース整備を模索します.
日時:2011年1月11日(火)〜12日(水)
場所:東京大学柏キャンパス大気海洋研究所講堂
アクセス:http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/about/j/map.html
プログラム:次のURLから閲覧できます.
http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/news/j/index.cgi?mode=art_view&id=321&lang=ja
参加費無料,事前登録は必要ありません.直接会場においで下さい.
初日の夕方,懇親会(大気海洋研究所内)開催を予定しています.
懇親会参加費:4000〜5000円(一般) 2000円程度(院生・学生)
※懇親会参加希望者は,1月5日までに,suzukit@tmu.ac.jpまで.
当日空きがありましたら当日受付も致しますが,事前のご連絡をお願いします.
■中・下部更新統境界国際模式地に関する国際シンポジウム
日時:2011年1月15日(土)-16日(日)(16日は現地見学)
場所:サンプラザ市原(千葉)
参加費:一般1000円、学生500円(予稿集込み)
詳細は会田まで<aida.nobuyuki@taupe.plala.or.jp>
■第48回 アイソトープ・放射線 研究発表会
会期:2011年7月6日(水)〜8日(金)
会場:日本科学未来館7階(東京都江東区青海2-3-6)
申込締切:2011年2月28日(月)
共催(予定):日本地質学会ほか
詳しくは、http://www.jrias.or.jp/index.cfm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■高知大学海洋コア総合研究センター研究員ほか募集(締切2/1)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】事務局年末年始休業のお知らせ
──────────────────────────────────
12月29日(水)〜1月4日(火)まで事務局はお休みを頂きます。
年始1月5日より通常通り営業いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
★「第2回惑星地球フォトコンテスト」作品募集中!
http://www.photo.geosociety.jp/
No.114 2010/11/2 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.114 2010/11/2 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】コラム:地質調査中のトラブル体験記と危険回避術(前編)
【2】2011年度学会各賞募集開始
【3】2011年度会費払込/学部学生・院生割引申請受付中!
【4】新トピックセッション「地質情報の利活用」の提案
【5】第34回IGC ブリスベン大会のプロモーション
【6】支部情報
【7】日本地方地質誌「北海道地方」特別割引販売のお知らせ
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】コラム:地質調査中のトラブル体験記と危険回避術(前編)
──────────────────────────────────
広島大学大学院地球惑星システム学科
日本勤労者山岳連盟会員 大橋聖和
先日,日本地質学会富山大会での懇親会で地質調査中の苦労話を紹介させてい
ただいたところ,News誌編集委員長の坂口さんに情報共有のために寄稿してもら
えないかと依頼を受けた.個人的にも調査時の安全管理の重要性を近年特に認識
するようになったため,適任者かどうか不安もあるが快諾した次第である.以下
では,私の調査中のトラブル体験談とともに,小トピックごとに一般的な山での
安全術を紹介する.特に地質調査を始めたばかりの学生を対象とするが,ベテラ
ンの先輩方にも今一度安全対策を思い直すきっかけになれば存外の幸せである.
地質調査のリスクを十分に把握した上で,安全且つ高度な地質調査を目指したい.
続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0056.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2011年度学会各賞募集開始
──────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして、研究の援助・奨励および研究業
績の表彰を行っています(定款第3条)。
本年も各賞の自薦、他薦による候補者を募集いたします。期日厳守にて、たくさん
のご応募をお待ちしております。
応募締切:2010年12月24日(金)必着
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
(会員番号・パスワードによるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2011年度会費払込/学部学生・院生割引申請受付中!
──────────────────────────────────
■2011年度会費払込について
次年度分会費の前納をお願いいたします。自動引き落としを登録されている方の
引き落としは、12月24日(金)です。お振込の方へは、12月中旬頃までに請求書
兼郵便振替用紙をお送りいたします。
詳しくは、https://www.geosociety.jp/user.php(会員番号によるログインが必要です)
■2011年度(2011.4〜2012.3)学部学生・院生割引申請受付中
最終締切:2010年11月17日(水)
申請書のダウンロードは、
https://www.geosociety.jp/user.php(会員番号によるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】新トピックセッション「地質情報の利活用」の提案
──────────────────────────────────
地域地質部会・情報地質部会
これまで地質学会では,人類の地質への理解を進展させるためのさまざまな研
究成果が発表されてきた.しかし,野外で地質情報を取得し,それらを意味のあ
る地質情報へと変換し,社会での地質情報の利活用を推進する,という流れを持っ
た研究成果の発表例は少ない.情報処理技術が発展した昨今,野外で取得した地
質情報をデジタルデータとして整理・処理・管理する環境はほぼ整った.インター
ネットを通じて地質情報のデジタルデータを共有・利活用する環境も整いつつあ
る.また,近年,ジオパーク活動が盛んになるにともない,これまで地質学とは
つながりが薄かった一般社会でも,地質情報を利活用しようという機運が高まっ
ている.本年の富山大会でのトピックセッション「地学巡検・地学名所とガイド
ブック」もこの流れのうちと言える.
地域地質部会・情報地質部会では,このような地質学会の現状,および,世相
の変化を受けて,地質情報の取得から利活用までの流れの中にある研究の成果を
発表する場として,表記トピックセッションを計画する.
現在,地域地質部会は,毎年の大会において定番セッションとして地域地質・
地域層序を層序部会と共同で運営し,地域地質の研究成果を発表する場となって
いる.また,情報地質部会は,地質情報を処理するための理論・技術の開発,お
よび,それらの地質学分野への応用などの成果を発表する場となっている.そこ
で,本トピックセッションでは,社会での地質情報の利活用に焦点をあて,
・特定地域から得られた地質情報の利活用,および,その問題点や比較検討
・地質情報の利活用に向けた情報取得方法
・ジオパークや博物館等における地質情報の利活用
を具体的発表テーマとする.
来年度,トピックセッションに応募して活動を開始し,将来的には両部会が共
同で行う定番セッションを目指す.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第34回IGC ブリスベン大会のプロモーション
──────────────────────────────────
日本地質学会会員各位
2012年8月に第34回万国地質学会議(IGC)がオーストラリアのブリスベンで開催さ
れます.同大会事務局長のIan Lambert氏が2010年11月9-10日に来日し,同大会の
プロモーション活動を行います.日本からは毎回かなりの人数がIGCに参加してお
り,前回の2008年オスロ大会ではノルウェー(960名),ロシア(505名),米国
(394名),
中国(376名),イタリア(267名),ドイツ(261名),英国に次ぐ参加者数(15
0名程度?)
でした.今回は大洋州での開催なので日本人参加者が増加すると思われます.
国際地質科学連合(IUGS)の主要な会議もIGCの会期中に行われます.この会議
における日本のプレゼンスを高めるためにも,今回の事務局来日の機会を最大限
に利用すべきと思いますので,関連諸学会の関係者の皆様には,9日または10日
の説明会のどちらかに,奮ってご参加いただきますよう,ご案内申し上げます.
斎藤靖二
日本学術会議IUGS分科会委員長
石渡 明
日本地球惑星科学連合国際学術委員会委員長
日本地質学会学術研究部会国際交流担当理事
記
第34回IGCブリスベン大会のプロモーション開催日時および会場
Date: Tuesday, 9 Nov. 2010
Time: 15:00 - 17:00
Place:Japan Agency for Marine Science and Technology
(JAMSTEC) Tokyo Office
Hibiya Central Bld. 6th Floor, Nishi-shimbashi 1-2-9, Minato-ku,
Tokyo, 105-0003 Japan
Tel: +81-3-5157-3900 Fax: +81-3-5157-3903
http://www.jamstec.go.jp/e/about/access/tokyo.html
Correspondence:
Dr. Arito Sakaguchi (坂口有人)<arito@jamstec.go.jp>
Date: Wednesday, 10 Nov. 2010
Time: 10:00 - 12:00
Place: Geological Survey of Japan
The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
(AIST) 1-1-1, Higashi, Tsukuba , 305-8567, Japan
phone: +81-29-861-3750/3751 fax:-3746
http://www.gsj.jp/Muse/eng/index.html
Correspondence:
Dr. Yutaka Takahashi(高橋 浩)<takahashi-yutaka@aist.go.jp>
資料
1.Ian Labmert氏の略歴とプロフィール/2.第34回IGCの概要(要旨)/3.オース
トラリアの地球科学の現状と展望(要旨)
http://www.cneas.tohoku.ac.jp/labs/geo/ishiwata/IGC34promotion.htm
なお,10月13日に34th IGCのFirst Circularが発行されました.
https://mymail.ezemsgs.com/ch/8781/2ddswr8/1331640/9d98811z4g.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
■日本地質学会関東支部2010年秋季シンポジウム
「関東盆地の地下地質構造と形成史」
日程:2010年11月20(土),21(日)
場所:日本大学文理学部3号館5階
懇親会予約:件名を「懇親会予約」,お名前,ご連絡先明記の上
<kanto@geosociety.jp>まで.予約締切:11/12(金)
懇親会会費:一般 5,000円,学生 1,000円
詳しくは、 http://kanto.geosociety.jp/
■2010年度近畿支部総会・シンポジウム
日時:2010年11月20日(土)
11:00〜12:00(総会)・ 13:00〜16:30(シンポジウム)
場所:神戸大学滝川記念学術交流会館
シンポジウム「中央構造線の発生と改変:白亜紀から新第三紀にかけて」
問い合わせ先:近畿支部幹事 三田村宗樹
TEL:06-6605-2592 FAX:06-6605-2522
e-mail: mitamrm@sci.osaka-cu.ac.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】日本地方地質誌「北海道地方」特別割引販売のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地方地質誌 1.北海道地方
664頁,口絵8頁 (11月下旬刊行)
会員特別割引価格24,000円(税・送料込)(定価27,300円)
日本地質学会会員の皆様に日本地方地質誌を特別割引価格で販売をいたします.
お申し込みは,HP会員のページの専用申込用紙にて直接朝倉書店までお願いいた
します.
https://www.geosociety.jp/user.php(会員番号によるログインが必要です)
お問い合せ
〒162-8707 東京都新宿区新小川町 6-29
朝倉書店編集部:千葉 Tel.03-3260-1967
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■東北大学素材工学研究懇談会
「マグネシウム合金の現状と新しいアプローチ」
日時:11月17日(水)〜18日(木)
場所:東北大学さくらホール
詳しくは、http://www.tagen.tohoku.ac.jp/
■海洋調査技術学会第22回研究成果発表会
11 月25日(木)〜26日(金)
会場:海上保安庁海洋情報部7階大会議室(中央区築地5-3-1)
詳しくは、http://www.soc.nii.ac.jp/jsmst/
■自然史学会連合会講演会
「東北の豊かな自然〜ワンダー イン イーハトーブ」
日時:11月28日(日)
場所:岩手県立博物館講堂 入場無料(要予約)
詳しくは、http://www.pref.iwate.jp/~hp0910/
■第2回惑星地球フォトコンテスト 【作品募集中】
主催: 一般社団法人 日本地質学会
応募締切: 2011年1月31日(月)
賞および賞金: 最優秀賞 1点 賞金5万円/優秀賞数点賞金3万円ほか
詳しくは、 http://www.photo.geosociety.jp/
■オフィオライト・シンポジウムのお知らせ.
環太平洋北部地域のオフィオライトと海洋底の類似岩石
日時:2011年2月7〜8日*
東北大学東北アジア研究センター 4階436会議室
980-8576仙台市青葉区川内41 事務室Tel: 022-795-6009
センターURL: http://www.cneas.tohoku.ac.jp/
シンポジウム英語URL:
http://www.cneas.tohoku.ac.jp/labs/geo/ishiwata/SendaiSympo1.htm
*引き続き,2011年2月9-10日に房総半島のオフィオライト見学旅行を行います.
講演申し込み数によっては8日のみになる可能性もあります.
世話人:
石渡 明・平野直人(東北大学東北アジア研究センター)
早坂康隆(広島大学自然科学研究科地球惑星システム科学科)
町 澄秋(金沢大学自然科学研究科地球学科)
S.D.ソコロフ・G.V.レドネバ(ロシア科学アカデミー地質研究所,
モスクワ)Sergey D. Sokolov, Galina V. Ledneva (Geological Institute, Rus
sian Academy of Sciences, Moscow)
趣旨
日露共同研究「アジア北東端のオフィオライトと随伴岩類:北極圏東部の岩石,
構造,広域地質対比」(日本側代表:石渡 明,参加者:早坂康隆・町 澄秋,
ロシア側代表:Sergey D. Sokolov)の最終ワークショップ・シンポジウムを2011
年2月7-8日に東北大学東北アジア研究センターで行います.9-10日には房総半島
のオフィオライト見学旅行もあります.ロシア及び米国からも計5〜6人が参加
する見込みです.関連研究者の皆様,奮ってご参加下さい.申し込み締め切りは2
010年12月10日です.申し込みはシンポジウム・見学旅行それぞれの参加・不参加
を明記し,メールで石渡まで.
E-mail: geoishw@cneas.tohoku.ac.jp
URL: http://www.cneas.tohoku.ac.jp/labs/geo/ishiwata/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■平成23年度東京大学大気海洋研究所共同利用公募(11/30締切)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
【第2回惑星地球フォトコンテスト】作品募集中!
<http://www.photo.geosociety.jp/>
No.116 2010/12/7 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.116 2010/12/7 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【0】第118年学術大会(2011水戸大会)開催日程決定!
【1】コラム:地質調査中のトラブル体験記と危険回避術(後編)
【2】コラム:「はやぶさ」が持ち帰った小惑星「イトカワ」の微粒子分析結果についての雑感
【3】各賞にどしどし推薦しよう! (12/24締切)
【4】2011年度会費払込/2011年度学部・院生割引申請書受付中!
【5】地学オリンピック日本委員会ニュース(11月25日号)
【6】支部情報
【7】Island Arc Vol.19 Issue 4号 日本語要旨
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【0】第118年学術大会(2011水戸大会)開催日程決定!
──────────────────────────────────
日程:2011年9月9日(金)〜11日(日)
会場:茨城大学ほか
来年の学術大会は、
「日本地質学会第118年学術大会・日本鉱物科学会2011年年会合同学術大会」(水戸大会)
として、日本鉱物科学会ほかとの共催で、茨城大学をメイン会場として開催されます。
詳細は近日お知らせいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】コラム:地質調査中のトラブル体験記と危険回避術(後編)
──────────────────────────────────
大橋聖和(広島大学大学院地球惑星システム学科・日本勤労者山岳連盟会員)
調査期間後半ともなると日数を稼ごうと無理をしてしまいがちであるが,悪天候時
は安全なルートに変更したり,停滞してデータの整理に当てるなどの余裕が必要で
ある.宿を出る前にはその日の天気予報を必ずチェックしておく........
続きはこちら、、、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0056.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】コラム:「はやぶさ」が持ち帰った小惑星「イトカワ」の微粒子分析結果についての雑感
──────────────────────────────────
2010年11月16日,宇宙航空研究開発機構(JAXA)は,同年6月13日にオーストラリ
アで回収した小惑星探査機「はやぶさ」のカプセルに含まれていた微粒子1500個以
上のほとんどが,小惑星「イトカワ」由来のものであることを確認したとしてプレ
ス発表を行い,大々的に報道された.
しかし,今回の微粒子のSEM-EDS分析結果をプロットした発表資料中のグラフ(図
1)については,いくつか問題があるように思う.......
詳しくはこちら、、、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0056.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】各賞にどしどし推薦しよう! (12/24締切)
──────────────────────────────────
日本地質学会各賞の推薦締め切りが迫っています。
正会員の皆様なら、誰でも推薦できます。
・分野をリードしてきたあの方に! 学会賞、国際賞
・最近イケてるあの若手に! (掲載誌問わず) 小澤賞、柵山賞
・グッときた学会誌の論文に! 論文賞、小藤賞、研究奨励賞
・長年お世話になったあの方に! 功労賞、
・地質学に貢献したあの方に! (非会員) 学会表彰
応募締切:2010年12月24日(金)必着
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
(会員番号・パスワードによるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2011年度会費払込/2011年度学部・院生割引申請書受付中!
──────────────────────────────────
■2011年度会費払込について
次年度分会費の前納をお願いいたします。自動引き落としを登録されている方の
引き落としは、12月24日(金)です。お振込の方へは、12月中旬頃までに請求書
兼郵便振替用紙をお送りいたします。
■2011年度学部・院生割引申請書受付中!
最終締切は、2011年3月31日(木)です.この期日までに申請書を必ずご提出く
ださい.なお,これまで(〜2010年度)の院生割引会費についての申請受付は終了
していますので,2011年度分の申請のみ適用となります.
詳しくは、https://www.geosociety.jp/user.php
(会員番号によるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地学オリンピック日本委員会ニュース(11月25日号)
──────────────────────────────────
地学オリンピック日本委員会
第4回国際地学オリンピック(IESO: International Earth Science Olympiad)
インドネシア大会(2010年9月19日〜28日)結果報告
・はじめて金メダル1個を獲得しました。
・参加国が過去最高17カ国になりました。(6カ国→14カ国→)(ルーマニア、フィ
リピン、アメリカ、ウクライナ、タイ、日本、ロシア、カンボジア、スリランカ、
イタリア、インド、台湾、韓国、クウェート、モルディブ、ネパール、インドネシ
ア)
・本大会の結果は、朝日、毎日、読売、日経の各紙に取り上げられました。また金
メダリストは9月30日のフジテレビのめざましテレビに電話インタヴュー出演しまし
た。
・帰国当日29日に、郄木文部科学大臣に帰国報告を行いました。これははじめての
文部科学省訪問となりました。また文部科学広報第132号、文教ニュース第2106号に
大臣表彰受賞の模様が掲載されました。
第5回国際地学オリンピックイタリア大会国内一次選抜
(日本地学オリンピック大会予選:2010年12月19日全国各地で実施)
11月15日に募集が締め切られ、869名の応募がありました。この数字は過去最高で
す(358名→689名→682名→)。
第5回国際地学オリンピックイタリア大会国内二次選抜
(日本地学オリンピック大会本選:別名 グランプリ地球にわくわく)
(2011年3月24日〜26日筑波研究学園都市で実施)
2010年とほぼ同様な内容で実施されます。
第6回国際地学オリンピック日本大会(2012年8月26日〜9月2日)
の準備状況
・本年6月に開催された顧問委員会の答申を受けて、現在募金活動の見直しをしてい
ます。企業募金については、税制優遇が受けられるように特定公益増進法人と交渉
中。個人募金については、クレジットカード決済できるように会社と交渉中。上記
2件については、2011年3月からの運用開始を目指しています。
・特定公益増進法人との交渉過程で発生した日本大会組織委員会の体制見直しを検
討しています。合わせて、組織委員会規約の作成を行っています。
・筆記・実技試験会場となる筑波大学(共催)が、学内支援体制作りを始めました
(地球学類地学オリンピック支援委員会)。
・日本地質学会地学オリンピック支援委員会、日本地学教育学会地学オリンピック
支援委員会が設置されました。また気象学会教育と普及委員会でも支援活動を行い
ます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
■北海道支部総会・個人講演会
日程:2011年2月26日(土)
場所:北海道大学大学院環境科学研究院D棟101室
個人講演会申込締切:1月21日(金)
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
■西日本支部
日程:2011年2月19日(土)
場所:広島大学理学部(東広島市鏡山)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
■東北支部2009〜2010年度総会,個人講演会と公開シンポジウム
会場:「コラッセふくしま」5階研修室
日程:2011年3月12日(土)−13日(日)
公開シンポジウム「東北地方におけるジオパークへの取り組み(仮題)」
個人講演申込締切:2011年1月26日(水)
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】Island Arc Vol.19 Issue 4号 日本語要旨
──────────────────────────────────
特集号:Thematic section: Paleoclimates in Asia during the Cretaceous:
Their variations, causes, and biotic and environmental responses (IGCP
Project 507) Part 1
Guest Editors : Yong Il Lee and Helmut Weissert
白亜紀におけるアジア古気候:多様性,原因および生物と環境の反応(IGCP
project 507),その1 ほか
詳しくは、http://www.geosociety.jp/publication/content0049.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■日本学術会議主催国際会議:持続可能な社会のための科学と技術に関する国際会議
2010「生物多様性の保全と持続可能な利用
日時 12月16日(木)ー17日(金)
場所 石川県 ホテル金沢(石川県金沢市堀川新町1-1)
入場無料・日英同時通訳あり
詳細は、http://www.scj.go.jp/ja/int/kaisai/jizoku2010/ja/index.html
■ジオ多様性研究会の創立と第1回フォーラムのご案内
私たちは,ジオ多様性研究会を以下の趣旨で創立し,フォーラムを行うことにし
ました.実は,ジオパークというのは,ジオ多様性を守っていく意味をこめて考え
られました.どうぞフォーラムに奮ってご参加いただき,みなさんで日本に「ジオ
多様性」の大切さをひろめていこうではありませんか.
(ジオ多様性研究会事務局 矢島道子)
趣旨説明:ジオ多様性研究会の創立にあたって
生態系に依存して生きる私たちにとって,生物多様性という概念がとても大切で
あることは自明になりつつある.ところが,生物多様性が地球表層圏(岩石圏・大
気圏・水圏)における多様性すなわちジオ多様性の上になりたっていることは,ほ
とんど認識されていない.ジオ多様性とは何か,具体的にどのようなジオ多様性が
あるのか,ジオ多様性と生物多様性とは具体的にどんな関係にあるのか,ジオ多様
性は人類にどのように貢献するのか,ジオ多様性は保全等のどんな問題をかかえて
いるのか等の重要な問題もほとんど議論されておらず,また普及していない.
私たちはジオ多様性研究会を発足させ,ジオ多様性に興味関心をいだいているで
きるだけ多くの関連分野の研究者とともに協議討論して,ジオ多様性にかかわるさ
まざまな問題を協議検討し,その重要性を明らかにしていきたい.
ジオ多様性研究会発起人
尾池和夫(代表)
加藤碩一・小泉武栄・白山義久・原田憲一・矢島道子(事務局)・吾妻 直
■第1回フォーラム「ジオ多様性とは何か,その重要性を問う」
月日:2011年1月14日(金)・15日(土)
場所:国際高等研究所(近鉄京都駅から急行で約30分,新祝園駅からタクシーで97
0円)http://www.iias.or.jp/access/access.html
1月14日(金)15:00-17:30
司会 原田憲一
開会挨拶 尾池和夫
・ 渡辺悌二(北海道大学)「ジオ多様性:いま,関係者が取り組むべきこと」・
高井 研(JAMSTEC)「知られざる深海熱水環境のジオ多様性:微生物生態系の生物
多様性の決定的要因」・白山義久(京都大学)「深海はなぜ生物多様性が高いのか?」
懇親会
1月15日(土)9:30-午前中
・小泉武栄(東京学芸大学)「生物多様性の基盤環境としての地形・地質と自然
史」・佃栄 吉(産総研)「さらなるジオ時空間可視化の必要性」
・ 木村克巳(産総研)「ボーリングデータ解析による地下構造の3次元可視化
とジオ多様性」・加藤碵一(産総研)「ジオ多様性とは?−日本・アジア・ヨーロッ
パを跨いで
昼食
* 基本的に発表者は30分,討議は10分,休憩(余裕)5分
問い合わせ先
ジオ多様性研究会事務局
矢島道子
pxi02070@nifty.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■東京工業大学大学院:総合理工学研究科環境理工学創造選考教員募集(1/14締切)
■広島大学大学院:理学研究科地球惑星システム学専攻教員募集(1/21締切)
■東京大学大気海洋研究所:古環境変動研究分野教員募集(1/11締切)
■山田科学振興財団 2011年度研究援助(学会推薦)(3/1学会締切)
■三菱財団 第42回自然科学研究助成(2/2締切)
■「第52回科学技術映像祭」参加作品の募集(1/31締切)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
★「第2回惑星地球フォトコンテスト」作品募集中!
http://www.photo.geosociety.jp/
No.115 2010/11/16 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.115 2010/11/16 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】祝!探査機「はやぶさ」回収の微粒子、小惑星起源と確認(解説付)
【2】2011年度学会各賞募集中
【3】2011年度会費払込について
【4】支部情報
【5】日本地方地質誌「北海道地方」特別割引販売のお知らせ
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】祝!探査機「はやぶさ」回収の微粒子、小惑星起源と確認
──────────────────────────────────
小惑星探査機「はやぶさ」が地球に持ち帰ったカプセルに入っていた微粒子が 小惑星イトカワ起源のものと確認されたと発表されました。地質学の発展は、直 接的なサンプル分析やフィールドでの観察に支えられてきました.今後もサンプ ルリターン探査がおこなわれ,地球・惑星・生命の起源と進化に関する解明が進 むことを期待します。
6/16に日本地質学会会長より出されたはやぶさ帰還に関する声明
http://www.geosociety.jp/faq/content0236.html
宇宙航空研究開発機構(JAXA)報道資料
「はやぶさカプセル内の微粒子の起源の判明について」
http://www.jaxa.jp/press/2010/11/20101116_hayabusa_j.html
──────────────────────────────────
解説とコメント: 今回採取された試料がどのような組成なのか、全貌を早く知りたいところです。微 粒子とは言え、1000個以上もあれば、かなりのことがわかるはずです。鉱物組合せ は、かんらん石、輝石、斜長石、硫化鉄、その他微量鉱物となっていて、普通コン ドライト(球粒隕石)のものと一致します。武田弘氏の「固体惑星物質進化」によ ると、イトカワは長軸535mの「ラッコ型」の形をした角礫岩質の小惑星で、密度1. 9g/cm3、化学組成はLLコンドライトに類似するとのことです。LLコンドライトのか んらん石のFo値は72〜67程度のはずですが、今回の報道資料(上記)のグラフから 読み取るとFo値70程度なので、普通コンドライトの一種であるLLコンドライトと矛 盾しません。
石渡 明(東北大学)
今後の詳細な分析を待たねばならないが、今回採取された試料の中に小惑星本体 のみならず表層に降り積もった原始太陽系星雲からの凝縮物が含まれていること を期待している。例えばより鉄の多いカンラン石が見つかれば、星雲ーカンラン 石相互作用における温度とガス化学組成の変化がわかるだろう。低温の含水鉱物 が見つかれば、当時の揮発成分の状況を知る手がかりになるだろう。さらに鉱物 の化学組成変化や酸素同位体組成等の分析によって原始太陽系星雲と惑星の形成 プロセスが詳細にわかるに違いない。
鳥海光弘(東京大学名誉教授)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2011年度学会各賞募集中
──────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして、研究の援助・奨励および研究業 績の表彰を行っています(定款第3条)。本年も各賞の自薦、他薦による候補者を 募集いたします。期日厳守にて、たくさんのご応募をお待ちしております。
応募締切:2010年12月24日(金)必着
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
(会員番号・パスワードによるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2011年度会費払込について
──────────────────────────────────
■2011年度会費払込について 次年度分会費の前納をお願いいたします。自動引き落としを登録されている方の 引き落としは、12月24日(金)です。
お振込の方へは、12月中旬頃までに請求書 兼郵便振替用紙をお送りいたします。
詳しくは、https://www.geosociety.jp/user.php (会員番号によるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】支部情報
──────────────────────────────────
■日本地質学会関東支部2010年秋季シンポジウム
「関東盆地の地下地質構造と形成史」約500kmの反射測線プロファイルを一挙展示
日時:2010年11月20(土),21(日)両日,10:00ー17:00.
場所:日本大学文理学部3号館5階(一般2,000円,学生 1,000円).
懇親会:11月20日(土)17:30−.学内カフェテリアチェリーにて.
懇親会会費:一般 5,000円,学生 1,000円(当日参加可能)
詳しくは、 http://kanto.geosociety.jp/
■2010年度近畿支部総会・シンポジウム
日時:2010年11月20日(土) 11:00〜12:00(総会)・13:00〜16:30(シンポジウム)
場所:神戸大学滝川記念学術交流会館
シンポジウム「中央構造線の発生と改変:白亜紀から新第三紀にかけて」
問い合わせ先:近畿支部幹事 三田村宗樹
TEL:06-6605-2592 FAX:06-6605-2522 e-mail: mitamrm@sci.osaka-cu.ac.jp
■東北支部2009〜2010年度総会,個人講演会と公開シンポジウム
会場:「コラッセふくしま」5階研修室
日程:2011年3月12日(土)−13日(日)
公開シンポジウム「東北地方におけるジオパークへの取り組み(仮題)」
個人講演申込締切:2011年1月26日(水)
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】日本地方地質誌「北海道地方」会員特別割引販売のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地方地質誌 1.北海道地方 664頁,口絵8頁 (11月下旬刊行)
会員特別割引価格24,000円(税・送料込)(定価27,300円)
お申し込みは,HP会員のページの専用申込用紙にて直接朝倉書店までお願いいた します.
https://www.geosociety.jp/user.php(会員番号によるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第47回の霞ヶ関環境講座(第38回の三宅賞受賞者の受賞記念講演)
日時:2010年12月4日 (土)14:30〜
場所:霞ヶ関ビル35階東海大学校友会館
講座「生物多様性の起源を探る: 分子系統学の挑戦」 西田 睦先生(東京大学大気海洋研究所所長・教授)
受賞記念講演 「窒素同位体およびリモートセンシングを用いた海洋物質循環の先駆的研究」 三宅賞受賞者 才野敏郎博士(海洋研究開発機構地球環境変動領域物質循環研究プ ログラムディレクター)
詳しくは、http://wwwsoc.nii.ac.jp/gra/
■「サイエンスアゴラ2010」
日時: 11/19(金)〜11/21(日)10:00〜17:00
場所: 国際研究交流大学村(東京・お台場)
参加費:無料 主催 :独立行政法人科学技術振興機構(JST)
共催 :日本学術会議、独立行政法人産業技術総合研究所、国際研究交流大学村
詳しくは、 http://scienceagora.org/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■九州大学大学院理学研究院教員公募(女性限定)(1/5)
■神戸大学大学院理学研究科地球惑星科学教員公募(12/3)
■第38回「環境賞」(1/21)
詳細およびその他の公募情報は、 http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です. geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日 までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。 geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
【第2回惑星地球フォトコンテスト】作品募集中! http://www.photo.geosociety.jp/
「はやぶさ」が持ち帰った小惑星「イトカワ」の微粒子分析結果についての雑感
「はやぶさ」が持ち帰った小惑星「イトカワ」の微粒子分析結果についての雑感
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
図1.微粒子の分析値.JAXAプレス発表資料「はやぶさカプセル内の微粒子の起源の判明について」より.
http://www.jaxa.jp/press/2010/11/20101116_hayabusa_j.html#at01
2010年11月16日,宇宙航空研究開発機構(JAXA)は,同年6月13日にオーストラリアで回収した小惑星探査機「はやぶさ」のカプセルに含まれていた微粒子1500個以上のほとんどが,小惑星「イトカワ」由来のものであることを確認したとしてプレス発表を行い,大々的に報道された.発表資料によると,確認された鉱物の組合せは,かんらん石,輝石,斜長石,硫化鉄,その他微量鉱物となっていて,普通コンドライト(球粒隕石)のものと一致する.武田弘著(2009)「固体惑星物質進化」(現代図書)によると,イトカワは長軸535 mの「ラッコ型」の形をした角礫岩質の小惑星で,密度1.9 g/cm3,化学組成はLLコンドライトに類似するとのことである.LLコンドライトのかんらん石のFe/(Fe+Mg)モル%(以後Fe#と表記)は28〜33程度のはずであるが,今回の報道資料のグラフ(図1)から読み取るとFe#30程度なので,普通コンドライトの一種であるLLコンドライトと矛盾しない.斜長石があることから,かなり変成度の高いタイプであるらしく,始原的な炭素質コンドライトなどに由来する粒子は未発見のようである.
しかし,今回の微粒子のSEM-EDS分析結果をプロットした発表資料中のグラフ(図1)については,いくつか問題があるように思う.
この図は,例えば武田弘・北村雅夫・宮本正道編(1994)「固体惑星物質科学の基礎的手法と応用」(サイエンスハウス)のp. 216に載っている,普通平衡コンドライト(E, H, L, LL)の分類によく使われる図で,かんらん石のFe#と輝石のFe#を各軸にとったXY図である.この教科書にはモル%と明記されているが,発表資料では省略されている.しかし,重量%でプロットすると結果が大きく違ってくるので,モル%であることを明記すべきである.
隕石中の輝石には単斜輝石と斜方輝石があるが,発表資料では単に「輝石」となっていて,その種類が明示されていない.上述の教科書では,本文の記述やプロットされている隕石の種類から,これが斜方輝石であることは推察できるが,発表資料では何も手がかりがないので,輝石の種類を明記する必要がある.例えばL6型の根上隕石の場合,斜方輝石の Fe#は21だが単斜輝石は15で,かなり異なる(因みに,根上隕石のかんらん石のFe#は24.石渡ほか(1995)地球科学49, 71-76, 179-182).
この図には,リモートセンシングによって推定されたイトカワ表面物質の組成範囲と,地球のマントル岩石の輝石・かんらん石の組成範囲が示されていて,今回測定された微粒子の化学組成が前者と一致し,後者とは大きく異なっていているから,微粒子は地球外物質と判断した,という説明がなされている.しかし,はやぶさの地球出発前または地球到着後に地表や実験室で混染(コンタミ)が起きた可能性を考えると,マントルの岩石が紛れ込む可能性 はあまりないが,地表付近に多量に存在する火山岩中 のかんらん石や輝石が何らかの原因で混じる可能性はある.従って,それらの組成範囲もプロットしないと,「地球外のもの」という判断に説得力がない.ところが,それらをプロットすると,完全に今回の分析値をカバーしてしまう.例えば,島根県隠岐島後のアルカリ玄武岩中のかんらん石のFe#は13〜49の範囲でばらつく(Xu, 1988; Sci. Rep. Tohoku Univ., Ser. 3, 17, 1-106).従って,この図だけから,地球の岩石の破片ではない,という結論を導くことはできない.とは言え,地球の物質が混入したのなら,石英などのシリカ鉱物や雲母などの含水鉱物あるいは火山岩片などが多く含まれていてもよいが,それらはみつかっていないようなので,地球外物質であることは確かなのだろう.今後の斜長石,輝石,硫化物などの分析結果を注視したい.
この図は隕石研究の分野でよく使われる図だとしても,今回の分析結果をこの図にプロットすることが適当かどうかは疑問である.かんらん石と輝石が必ず1つの微粒子中で共存しているのならともかく,単独の場合は個々の組成をこの図にプロットできない.かんらん石と輝石それぞれの平均値を点1つでプロットしてあるが,これでは分析値の範囲がどの程度の広がりをもつのか不明である.この図を使うにしても,標準偏差を十字線で表すなどの工夫があるとよかった.測定されたかんらん石のFe#のヒストグラムを,普通コンドライトの各タイプのもの,地球のマントルや地殻の岩石のものなどと比較しながら示せば,なおよかったと思う.
そもそも,隕石も地球・月の岩石も含めて,あらゆる岩石のかんらん石と斜方輝石は,化学平衡が成り立っていれば,この図の原点を通る傾斜約1の直線付近にプロットされるので,このXYプロットを行う意味はあまりない.ただし,著しい非平衡の存在の有無を判断するには有効な図かもしれない.
また,今回の地球外物質の持ち帰り確認は,月より遠い天体では初という報道が一部でなされたが,2006年に米国の探査機スターダストがヴィルト第2彗星からコマの粒子を既に持ち帰っている.多額の費用をかけた高水準の科学を,冷静に見守りたいものである.
最近、太陽黒点が少ないことについての雑感
最近、太陽黒点が少ないことについての雑感
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
太陽黒点については、ガリレオ以来すでに約400年の観測の歴史があり、黒点の数は太陽活動の活発さを表す指標として重視されている。黒点数は約11年を周期として増減を繰り返してきた(黒点周期)。黒点数は、多い時(極大期)には100〜200に達するが、少ない時(極小期)はゼロに近くなる。組織的な太陽観測が始まった1750年から数えて第23番目の黒点周期は、1996年頃の極小期に始まり、2000年頃に極大期(黒点数は120程度)となり、 2007〜2008年頃の極小期で終わった。2010年末の現在は、次の第24周期が始まってから既に2〜3年経過しており、通常であればそろそろ極大期にさしかかる頃だが、黒点数はまだ少ないままである。私は晴天の休日には小さな望遠鏡で黒点観測をしているが、近頃も黒点数ゼロの日が多い。また、「マウンダーの蝶形図」としてよく知られているように、新しい黒点周期の開始と同時に高緯度地域に黒点が出現し、極大期を経て次の極小期まで、黒点の出現緯度が次第に低緯度に移る傾向がどの周期でも顕著に見られるが、今回の周期では高緯度の黒点がやっと今年になってから出現し始めた。
NASAの今後の黒点数予想によると、第24周期の極大は2013年頃(平均的な周期より約2年遅れ)、黒点数のピークは60程度と見積もられている。この予想が正しいとすると、極大が1805年頃の第5周期(黒点数40程度)と1816年頃の第6周期(50程度)(この時期をダルトン極小期という)、そして1907年頃の第14周期(60程度)に匹敵する黒点数の少なさになり、約100年ぶり(または約200年ぶり)の低水準となる(図1)。黒点観測の記録がある最近 400年間では、1958年頃を極大とする第19周期の黒点数が最も多く(約190)、第21, 22周期もかなり多かったが(約150)、上述のように第23周期はやや少なく、現在の第24周期は非常に少ないことが予想される。黒点数の増減周期も長くなる傾向にあり、これは長期的な極小期の特徴であるという。このようなことから、1600年代に黒点が非常に少ない時期が70年近く続いた「マウンダー極小期」(1645年頃〜1715年頃、図1)が再来する可能性も取り沙汰されている。
黒点数と地球の平均気温との関係は、1年毎あるいは1周期毎のそれぞれの平均値をプロットするとほとんど相関がなく、1958年をピークとする第19周期以後は太陽黒点が減少傾向にあるのに地球の気温の上昇が続いていることから、両者の間には全く相関がないとする意見もある。しかし、もっと長期的に見ると、マウンダー極小期から1800年頃までは小氷期と呼ばれ、ロンドンのテムズ川が氷結し日本でも飢饉が頻発するなど地球全体の気温が低かったが、1780年頃を底として、太陽活動の活発化とともに気温の上昇が続いてきた(図1)。つまり、太陽活動の長期的な極小期(中心は1680年頃)から約100年後まで地球の気温は低下を続けたことになる。
図1.最近400年間の太陽黒点の各極大期の平均数(NASAの公表データに基づく。ただし1750年以前のデータは少ない)と地球の平均気温(理科年 表)及び北極海の島の氷床コアの酸素同位体比から推定される北極地方の気温の変化(Fritzsche, 2005)。黒点数は11年周期の各極大期の平均値。地球平均気温は1971〜2000年の平均値を250とし、平均値との温度差を100倍した値。酸素 同位体比はδ18O値(負の値)を20倍して700を加えた値。酸素同位体比の変化を100年前に移動したものを点線で示す。これは黒点数の変化とかなり よく対応する。つまり黒点数の変化に表れた太陽活動の強弱が100年後の気温の変化に反映していると考えられる。そこで、これまでの黒点数の変化を100 年後に移動したものを破線で示す。これは将来の気温の変化傾向を示す可能性がある。地球の気温の機器観測データが揃っているのは最近100年ほどにすぎな いことも注意すべきである。
さて、地球には海があり、海水は大気よりもはるかに多量の熱を蓄え、しかも温まりにくく冷めにくい。我々は巨大な湯たんぽ(海洋)を入れた布団(大気)の中で生活しているようなものである。地球の気温が海水温に支配され、海水の循環が地球全体の気候に大きく影響することは、数年毎に繰り返されるエルニーニョ現象とラニーニャ現象がよく示している。海洋全体の水平・鉛直方向の大循環は、大西洋の北部で海洋表層から深海に潜り込んだ冷たく塩分の高い海水が大西洋南部を経てインド洋南部を通り(一部はインド洋北部で表層に出る)、オーストラリア東方で北上して北太平洋で海洋表層に出るという流れになっており、表層には逆向きの流れがある(ブロッカーのコンベアベルト)。この循環の1サイクルには約2000年を要する。言い換えれば、海洋全体を温める(冷ます)のに 1000年以上を要し、海洋の比較的浅部のより小規模な循環にも相当の年数を要するので、太陽活動の変化(つまり受熱量の変化)に対する地球の海洋の温度変化の応答(レスポンス)に100年以上の遅れがあるとしても不思議ではない。因みに、私は一時期地震予知をめざして段丘崖の湧水の温度と水量の観測を3年間続けたことがある。段丘面の地下約10 mの層を流れる地下水の温度変化は、位相が気温の変化より約半年遅れており、冬に最高温度になる。このことからも、平均4500 mの深さがある海洋の、気候に直接影響を与える部分の水温変化の位相が100年以上遅れることは想像がつく。このように考えると、1960年頃の長期的な黒点極大期の後50年を経た現在でも、まだ気温が上昇傾向にあることの原因が、人為的なCO2の排出による温室効果の増大だけとは言い切れないように思えてくる。1960年頃をピークに太陽活動が長期的な低下傾向に転じたとすれば、この約100年のレスポンスの遅れを考えると、今世紀の中頃(2060年頃)を温暖化のピークとして、それ以後地球の気温は長期的な寒冷化に転じる可能性がある(図1の破線)。しかし、最近400年間の黒点数の変化を見ると、太陽活動は100年程度の周期で活発な時期と不活発な時期を繰り返してきたようにも見えるので、現在の太陽活動の低下は一時的なもので、底が深くならないうちにまた活発化する可能性もあり、今後の推移を見る必要がある。
拙稿を校閲してコメントをいただいた井龍康文博士に感謝する。
【参考文献】
Fritzsche, D., Schütt, R., Meyer, H., Miller, H., Wilhelms, F., Opel, T., Savatyugin, L.M. (2005) A 275 year ice-core record from Akademii Nauk ice cap, Severnaya Zemlya, Russian Arctic. Annals of Glaciology, 42, 361-366.
東山正宣 (2010) 太陽まもなく「冬眠」.朝日新聞,2010年3月19日科学面.
http://news.sciencemag.org/sciencenow/2010/09/say-goodbye-to-sunspots.html
http://sidc.oma.be/sunspot-index-graphics/sidc_graphics.php
http://solarscience.msfc.nasa.gov/SunspotCycle.shtml
http://www.skepticalscience.com/solar-activity-sunspots-global-warming.htm
http://www.dailytech.com/NASA+Study+Acknowledges+Solar+Cycle+Not+Man+Responsible+for+Past+Warming/article15310.htm
石渡 明 (2010) 羽鳥先生の「資源と環境」に学ぶ.地学教育と科学運動, 64, 35-40.
(原稿受付 2010年12月21日)
No.122 2011/1/5 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.122 2011/1/5 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】年頭にあたって:会長挨拶
【2】2011年水戸大会:トピックセッション募集開始
【3】締切迫る!惑星地球フォトコンテスト
【4】2011年度会費払込/2011年度学部・院生割引申請書受付中! 学生注目!
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報
【8】故 深田淳夫名誉会員 お別れの会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2011年の年頭にあたって:会長挨拶
──────────────────────────────────
会長 宮下 純夫
あけましておめでとうございます.
日本は年末−年始と大荒れのお天気でしたが,昨年の夏の記録的な猛暑のことを
考えあわせると,最近の地球の気候変動の振幅の大きさが気になります.地球自体
のもつリズムによる気候変動幅の大きさと周期について,もっともよく理解してい
るのは地質学を中心とした地球を相手にする科学者です.地球を理解することの重
要性や意義を広めていく上で,日本地質学会が担っている役割は極めて大きいもの
があります.
続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/outline/content0089.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2011年水戸大会:トピックセッション募集開始
──────────────────────────────────
日本地質学会は,関東支部の支援のもと,第118年学術大会を茨城大学をメイン会場
として2011年9月9日(金)〜11日(日)の日程で開催します.本大会は日本鉱物科
学会との共催で「日本地質学会第118年学術大会・日本鉱物科学会2011年年会 合同
学術大会(水戸大会)」となります.
トピックセッションの募集を行います.本大会はシンポジウムの募集はありません.
詳しくは、http://www.geosociety.jp/mito/content0016.html
トピックセッション募集締切:2011年2月14日(月)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】締切迫る!惑星地球フォトコンテスト
──────────────────────────────────
このコンテストはユネスコおよび国際地質科学連合による国際惑星地球年(2007〜
2009年)を契機に始められたものです。私たちの惑星「地球」をテーマにした写真
を公募し、優秀な作品を表彰するとともに、広報、普及、教育活動を通じて地球
科学に対する理解を深め、学術の振興と社会の発展に寄与・貢献することを期待
するものです。
★今年も多数のご応募をお待ちしています★
応募締切: 2011年1月31日(月) 締切迫る!!
賞および賞金: 最優秀賞 賞金5万円/優秀賞 賞金3万円ほか
詳しくは、http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2011年度会費払込/2011年度学部・院生割引申請書最終受付中!
──────────────────────────────────
■2011年度会費払込について
次年度分会費の前納をお願いいたします。自動引き落としを登録されている方は、
12月24日(金)に引き落としを行いました。お振込の方へは、12月中旬に請求書
兼郵便振替用紙発送いたしましたので、折り返しご送金をお願いいたします。
■2011年度学部・院生割引申請書最終受付中!
最終締切は、2011年3月31日(木)です.
この期日までに申請書を必ずご提出ください.なお,これまで(〜2010年度)の院
生割引会費についての申請受付は終了していますので,2011年度分の申請のみ適用
となります.
詳しくは、https://www.geosociety.jp/user.php
(会員番号によるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報
──────────────────────────────────
■北海道支部総会・個人講演会
日程:2011年2月26日(土)
場所:北海道大学大学院環境科学研究院D棟101室
個人講演会申込締切:1月21日(金)
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
■西日本支部
日程:2011年2月19日(土)
場所:広島大学理学部(東広島市鏡山)
講演会申込締切:2月14日(月)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
■東北支部2009〜2010年度総会,個人講演会と公開シンポジウム
会場:「コラッセふくしま」5階研修室
日程:2011年3月12日(土)〜13日(日)
個人講演申込締切:1月26日(水)
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■JABEE事務局ニュース
2010.12.27版ニュース(PDF)
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/geoFlash_img/no.122_jabee.pdf
JABEE WEBサイト<http://www.jabee.org/>
■パネル展 『神宿る熊野 〜魂を昇華させる地質遺産〜』
世界遺産『熊野の霊場と参詣道』を、地質の切り口から取り上げた
パネル展が開催されます。(第4回熊野学フォーラムと平行開催)
期間: 2011年1月11日(火)〜22日(土)
会場: 明治大学アカデミーコモン1階ホール
http://www.kumanogenki.com/event/kumanogaku4/
■日本堆積学会2011年長崎大会のご案内と講演募集
日程:2011年3月17日(木)〜 22日(火)
17日(木)〜18日(金):ショートコース「オート層序学実験セミナー」
19日(土)〜20日(日):個人講演(基調講演含む)など
21日(月・祝)〜22日(火):巡検(1泊2日)
会場:長崎大学文教キャンパス総合教育研究棟3階 他
講演申込締切:2月4日(金)
詳しくは,http://sediment.jp/
■第7回アジア海洋地質学会議:7th International Conference on Asian Marine
Geology
場所:インド(ゴア)
日程:2011年10月11日(火)〜14日(金)
http://icamg7.nio.org/index.php?body=1
以下のトピックスについて議論が行われます。2011年1月31日(月)までセッション
の受付が行われています。ぜひご一読ください。
1) Gas hydrate: recent development in exploration and experiments
2) Asian monsoon: land-ocean & tectonic-climate linkages
3) Tsunami – Understanding the past records –
4) Sea level changes in Asian coasts and shelves
5) Tectonics, stratigraphy, and evolution of the continental shelf & slope
6) Marine Sedimentology: Source-to-sink sediment dynamics
7) Paleoceanography in Asian waters
8) Marine tectonics in Asia
9) Tectonics, Rifting Processes, Deep-Sea
10) Marine Minerals
11) Sediment and pore-water geochemistry
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■産総研 活断層・地震研究センター特別研究員(ポスドク)募集(締切1/19)
■平成23年度三内丸山遺跡特別研究募集(締切2/28)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】故 深田淳夫名誉会員 お別れの会
──────────────────────────────────
故 深田淳夫名誉会員(平成22年12月10日逝去 享年88)のお別れの会が下記の通
り行われます。
日時:平成23 年1月27 日(木)、午前11 時30 分〜午後1時
場所:ホテルニューオータニ、ザ・メイン(本館)1階 「芙蓉の間」
(東京都千代田区紀尾井町4番1号)
http://www.newotani.co.jp/tokyo/info/access/index.html
お別れの会では、随時献花をしていただきますので、ご都合の良い時間に平服にて
お越しください。なお、誠に勝手ながら、ご香典ご供花ご供物の儀は、固くご辞退
申し上げます。
問合せ先:応用地質株式会社 社長室 電話 03-3234-0811(代)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.123 2011/1/11(臨時)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.123 2011/01/11 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 大森昌衛 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
日本地質学会元会長・名誉会員大森昌衛氏(麻布大学名誉教授)が、平成23年1月3
日(月)にご逝去されました(享年91歳).
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます.
なお,ご葬儀は1月7日に近親者のみで執り行われており,後日「お別れの会」を
行う予定とのことです.
会長 宮下純夫
──────────────────────────────────
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日までに
事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.124 2011/1/18 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.125 2011/2/1 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2011年水戸大会:トピックセッション募集中 ぜひ!
【2】締切迫る!惑星地球フォトコンテスト
【3】2011年度会費払込/2011年度学部・院生割引申請書最終受付中!
【4】2011年春季地質の調査研修の募集始まる!
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2011年水戸大会:トピックセッション募集中 ぜひ!
──────────────────────────────────
日本地質学会は,関東支部の支援のもと,第118年学術大会を茨城大学をメイン
会場として2011年9月9日(金)〜11日(日)の日程で開催します.本大会は日本
鉱物科学会との共催で「日本地質学会第118年学術大会・日本鉱物科学会2011年
年会 合同学術大会(水戸大会)」となります.
現在トピックセッションを募集中です。ご提案お待ちしています。
(※本大会ではシンポジウムの募集はありません)
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/mito/content0016.html
トピックセッション募集締切:2011年2月14日(月)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】締切迫る!惑星地球フォトコンテスト
──────────────────────────────────
(このコンテストはユネスコおよび国際地質科学連合による国際惑星地球年(2007-
2009年)を契機に始められたものです。私たちの惑星「地球」をテーマにした写真
を公募し、優秀な作品を表彰するとともに、広報、普及、教育活動を通じて地球
科学に対する理解を深め、学術の振興と社会の発展に寄与・貢献することを期待
するものです。
★今年も多数のご応募をお待ちしています★
応募締切 2011年1月31日(月) 締切迫る!!
賞および賞金 最優秀賞 賞金5万円/優秀賞 賞金3万円ほか
詳しくは、 http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2011年度会費払込/2011年度学部・院生割引申請書最終受付中!
──────────────────────────────────
■2011年度会費払込について
次年度分会費の前納をお願いいたします。自動引き落としを登録されている方は、
昨年12月24日(金)に引き落としを行いました。お振込の方へは、12月中旬に請求
書兼郵便振替用紙発送いたしましたので、折り返しご送金をお願いいたします。
■2011年度 学部・院生割引申請書最終受付中!
最終締切は、2011年3月31日(木)です.
この期日までに申請書を必ずご提出ください.なお,これまで(〜2010年度)の院
割引会費についての申請受付は終了していますので,2011年度分の申請のみ適用
となります.
詳しくは、 https://www.geosociety.jp/user.php
(会員番号によるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2011年春季地質の調査研修の募集始まる!
──────────────────────────────────
産総研地質調査総合センター認定の研修プログラムの一環として、上記の研修
が今年の5月16日(月)〜20日(金)に企画され、参加者の募集が始まりました。
本研修参加者には、産総研地質調査総合センター長名の修了証書が授与される
とともに、CPD(土木・地質技術者のための継続教育)制度の40単位を取得する
資格が与えられます。
詳細は、 http://www008.upp.so-net.ne.jp/gsis/gsis-J.htm をご参照ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報
──────────────────────────────────
■北海道支部総会・個人講演会
日程:2011年2月26日(土)
場所:北海道大学大学院環境科学研究院D棟101室
個人講演会申込締切:1月21日(金)
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
■西日本支部
日程:2011年2月19日(土)
場所:広島大学理学部(東広島市鏡山)
講演会申込締切:2月14日(月)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
■東北支部2009〜2010年度総会,個人講演会と公開シンポジウム
会場:「コラッセふくしま」5階研修室
日程:2011年3月12日(土)〜13日(日)
個人講演申込締切:1月26日(水)
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■学術会議公開シンポジウム「科学の社会的責任」
日時: 2011年2月1日(火)13:00〜16:00
場所: 日本学術会議講堂(東京都港区六本木・事前申込不要)
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf/113-s-2-3.pdf
■オフィオライト・シンポジウム
「環太平洋北部地域のオフィオライトと海洋底の類似岩石」
日時:2011年2月7日(月)14:00-18:00, 8日(火)9:00-17:30
場所:東北大学東北アジア研究センター4階436会議室
シンポジウム・プログラム英語URL:
http://www.cneas.tohoku.ac.jp/labs/geo/ishiwata/SendaiSympo2.htm
*2月9-10日:房総半島のオフィオライト見学旅行実施.
http://www.geosociety.jp/faq/content0258.html#sympo
■第1回アジア太平洋大規模地震・火山噴火リスク対策ワークショップ
First Workshop of Asia-Pacific Region Global Earthquake and Volcanic
Eruption Risk Management
日時: 2011年3月14日(月)〜15日(火)
場所: 産業技術総合研究所つくば中央共用講堂
http://www.gsj.jp/Event/AsiaPacific/
■日本地学オリンピック:とっぷレクチャー聴講生募集
日時:2011年3月24日(木)13:00〜16:30
場所:産業技術総合研究所共用講堂
定員:250名先着順,要申込,参加費無料
詳しくは, http://jeso.jp/
もしくは、 http://www.geonet-tsukuba.jp/event_calendar/317.html
■日本地球惑星科学連合2011年大会
日時: 2011年5月22日(日)〜27日(金)
会場: 幕張メッセ国際会議場(千葉市美浜区中瀬2-1)
*1/11(火)より,WEBでの申込受付開始
早期(割引)投稿締切: 2011年1月31日(月) 17:00
最終投稿締切: 2011年2月4日(金) 12:00
http://www.jpgu.org/meeting/
■IGCP-581第二回シンポジウム「アジア河川系の変遷:テクトニクスと気候」
日時: 2011年6月11日(土)〜12日(日)
場所: 北海道大学大学院地球環境科学研究院(札幌市北区)
セッション:
1)アジア河川系の現在プロセスと地球化学サイクル
2)アジアモンスーン変動に対する河川系の応答と縁海への影響:陸上・海洋記録
3)アジア河川・大陸棚と新生代テクトニクス・気候変化との関連
巡検: 2011年6月13日〜14日
発表申し込み: 2011年2月15日(火)締切
web site: http://geos.ees.hokudai.ac.jp/581/
問い合わせ先: IGCP-581 LOC 山本正伸( myama@ees.hokudai.ac.jp)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■産業技術総合研究所:ポスドク(イノベーションスクール)20名募集(2/6)
■産業技術総合研究所:若手型任期付研究職員募集(一次2/28, 二次3/15)
公募課題名:
1) 国土及び周辺域の地質基盤情報の整備
・重要地域(陸域)の地質調査及び地質図作成/・地球物理情報の整備/・衛星情報
と地質情報の統合化技術の開発
2) 地圏の環境と資源に係る評価技術の開発
・未固結層の広域・長期応力変化評価手法開発/・沿岸域の物理探査データ解析評価
技術の開発/・レアメタル鉱床の野外調査・分析技術開発/・海底鉱物資源の探査及
び技術開発/・地下水及び地中熱エネルギー利用技術の開発
3) 地質災害の将来予測と評価技術の開発
・高温高圧下の断層構成物質評価技術の開発/・火山岩の年代測定技術の開発
■筑波大学:生命環境科学研究科 地層学分野教員募集(教授)(2/28)
■筑波大学:生命環境科学研究科 岩石学分野教員募集(助教)(2/28)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flash 地質学会メールマガジンNo.1〜No.100
geo-Flash! 日本地質学会公式メールマガジン
geo-Flash(ジオフラッシュ)は、学会活動の改善の一環として、地質
学に関わるあるいは学界活動に関する情報をいち早く会員の皆様にお届
けすることを目的として発足いたしました。会員の皆様からの情報も積極的に
載せていく予定ですので、大いにご活用いただきますようお願い申し上げます。
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬【geo-Flash】日本地質学会メールマガジン ┴┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.001 Since 2007/07/3 ┴┬┴┬ <*)++<< ┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
最新号,No.101〜はこちらから
No.100 2010/06/01
★★目次 ★★
【1】法人へ完全移行(任意団体117年の歴史に幕)
【2】富山大会:講演申込・参加登録 受付開始しました。
【3】 科学技術基本政策パブリックコメント 声を送ろう
【4】韓日地質学会 室戸合同大会 学生さん注目
【5】支部情報いろいろ
【6】 その他のお知らせ
【7】geo-Flash 100号!記念アンケート ご協力お願いします
No.99 2010/05/18
★★目次 ★★
【1】地質系統・年代の日本語記述ガイドライン
【2】日本地質学会第117年総会/(一社)日本地質学会 2010年度総会
【3】2010年度会費督促請求について
【4】韓日地質学会 室戸合同大会ファーストサーキュラー公開中
【5】 まもなく富山大会の申込受付開始です!
【6】その他のご案内
【7】公募情報
【8】地質マンガ ロトウに迷う
No.98 2010/05/06
★★目次 ★★
【1】アイスランドの噴火と噴煙(解説)
【2】地質の日までカウントダウン!
【3】2010年度会費督促請求について
【4】支部情報
【5】日本地質学会第117年総会/(一社)日本地質学会第2回総会
【6】その他のご案内
【7】公募情報
No.97 2010/04/20
★★目次 ★★
【1】 日本開催決定!ジオパーク国際ユネスコ会議
【2】日本地質学会第117年総会/(一社)日本地質学会第2回総会
【3】報告:理事会推薦監 事立候補者について
【4】2010年の「地質の日(5/10)」は?
【5】富山大会:シンポ・トピック・定番セッションが決まりました!
【6】 韓日地質学会ー室戸合同大会ー ファーストサーキュラー公開
【7】2010年度会費督促請求について
【8】その他のご案内
【9】 公募情報
【10】新事務局員のご紹介
No.94 2010/03/16
【1】第四紀下限変更、そして第三紀は非公式用語に
【2】国際惑星地球年(IYPE)終了記念イベント
【3】韓日地質学会室戸合同大会開催のお知らせ
【4】2010年度学部学生割引・院生割引会費受付まもなく終了
【5】Island Arc vol.19 Issue1 発行
【6】その他のお知らせ
【7】3月の博物館特別展示・イベント情報
【8】公募情報
【9】地質マンガ
No.92 2010/03/02
★★目次 ★★
【1】チリ地震津波とチリのテクトニクス
【2】理事選挙および監事選挙結果
【3】2010年富山大会:シンポジウム・トピックセッション募集中 ぜひ!
【4】第1回惑星地球フォトコンテスト審査結果
【5】2010年度学部学生割引・院生割引会費受付:まもなく終了です
【6】紹介:「日本列島 動く大地の物語」(NHK総合:1982-1983年)
【7】支部情報
【8】その他のご案内
【9】地質マンガ「卒論練習」
No.91 2010/02/16
★★目次 ★★
【1】コラム:ニュージーランドのウェリントン断層
【2】2010年富山大会:シンポジウム・トピックセッション募集中 ぜひ!
【3】支部情報いろいろ
【4】その他のご案内
【5】公募情報いろいろ
【6】J-STAGEサービス一時停止のお知らせ
No.90 2010/02/02
★★目次 ★★
【1】2010年富山大会:シンポジウム・トピックセッション募集のお知らせ
【2】報告:シンポジウム「人類の時代・第四紀は残った」
【3】一般社団法人日本地質学会2010年度監事立候補受付中
【4】コラム:オマーンジオサイトツアー報告
【5】支部情報いろいろ
【6】宮崎県総合博物館より情報提供のお願い
【7】その他のご案内
【8】公募情報いろいろ
【9】J-STAGEサービス一時停止のお知らせ
【10】地質マンガ「選挙管理委員会」
No.89 2010/01/19
★★目次 ★★
【1】2010年度代議員選挙の結果報告
【2】公開シンポジウム「人類の時代・第四紀は残った」(時代区分の定義が変わります)
【3】ハイチ地震情報
【4】ハイチ地震に対して
【5】ハイチ地震情報・救援関係 リンク集
【6】支部情報いろいろ
【7】その他のご案内
【8】地質学会ニュース誌 “百名山の地質(仮)”執筆者募集
【9】会員特別割引販売のご案内:地学読本
【10】公募情報
【11】地質マンガ「スケールプロトラクター」
No.88 2010/01/06
★★目次 ★★
【1】2010年の年頭に当たって
【2】公開シンポジウム「人類の時代・第四紀は残った」
【3】日本地質学会2010年度各賞候補者:締切延長(1/12まで)
【4】2010年度一般社団法人日本地質学会代議員選挙:投票受付中
【5】2010年度会費払込:学部生・院生割引会費申請を忘れずに!!
【6】Island Arc vol18 Issue4 公開されました
【7】支部情報(関東支部/西日本支部)
【8】フィールドジオロジー第6巻新発売:会員特別割引販売のお知らせ
【9】公募情報
No.87 2009/12/15
★★目次 ★★
【1】公開シンポジウム「人類の時代・第四紀は残った」
【2】2010年度一般社団法人日本地質学会代議員選挙:投票受付中
【3】日本地質学会2010年度各賞候補者募集中(12/25締切)
【4】2010年度会費払込:学部生・院生割引会費申請を忘れずに!!
【5】フィールドジオロジー第6巻新発売:会員特別割引販売のお知らせ
【6】その他 お知らせ
【7】地質マンガ
【8】今年の地質重大ニュース発表
No.86 2009/12/1
★★目次 ★★
【1】学会ホームページ2年3ヶ月で100万人突破!
【2】2010年度一般社団法人日本地質学会代議員選挙:投票受付中
【3】日本地質学会2010年度各賞候補者募集中
【4】2010年度会費払込:学部生・院生割引会費申請を忘れずに!!
【5】行政刷新会議仕分け作業結果へのパブリックコメント受付中!
【6】リーフレット企画を募集します。
【7】12月博物館特別展示・イベント情報
【8】その他 お知らせ
【9】地質マンガ
【10】今年の地質重大ニュース募集
No.85 2009/11/27(臨時)
【1】市川浩一郎名誉会員 訃報
No.84 2009/11/20(臨時)
【1】行政刷新会議のこれまでの事業仕分けについての意見書
No.83 2009/11/17
★★目次 ★★
【1】惑星地球フォトコンテスト:作品募集中
【2】2010年度会費払込:学部生・院生割引会費申請を忘れずに!!
【3】日本地質学会2010年度各賞候補者募集中
【4】「地質の日」関連イベントの最終集計が出ました!!
【5】コラム IGCP-511 海底地すべり会議に参加して
【6】その他 お知らせ
【7】地質マンガ 鬼の洗濯板
No.82 2009/11/09
【1】代議員および役員選挙:立候補届受領書をご確認下さい!!
No.81 2009/11/04
★★目次 ★★
【1】日韓交流:友情の楯
【2】2010年度代議員および役員選挙 立候補受付中!
【3】名簿作成アンケート実施中!
【4】惑星地球フォトコンテスト;作品募集中
【5】コラム:山手線と山の手台地
【6】学術会議関連:お知らせ
【7】その他お知らせ
【8】11月の博物館特別展示・イベント情報
【9】公募情報
No.80 2009/10/20
★★目次 ★★
【1】第四紀の下限が変わる!
【2】国際交流:モンゴルへの交流協定締結
【3】2010年連合大会:旧レギュラーセッション提案お願い
【4】2010年度会費請求・学部生/院生割引申請受付開始!
【5】名簿作成アンケート実施中:会員情報変更締切 11/6(金)
【6】来年は富山大会です:日本地質学会第117年学術大会
【7】その他お知らせ
【8】公募情報
No.79 2009/10/06
★★目次 ★★
【1】2010年度代議員および役員選挙について
【2】2010年度各賞候補者募集開始
【3】一般社団法人日本地質学会の公益法人認定申請について
【4】地球惑星科学連合の代議員選挙のお知らせ-連合に参加しよう-
【5】会員名簿データを整理中です。住所変更はお早めに!
【6】天然記念物めぐり:福岡県編
【7】日本堆積学会からのご案内
【8】第2回日本地学オリンピック大会参加募集
【9】10月の博物館 特別展示・イベント情報
【10】公募情報
【11】地質マンガ:「津波は大丈夫かね」
No.78 2009/9/25
★★目次★★
【1】地学オリンピック 日本チーム銀メダル4個という快挙で無事終了
【2】会員名簿データを整理中です。住所変更はお早めに!
【3】公募情報
No.77 2009/9/15
★★目次★★
【1】大河内会員 講談社科学出版賞 受賞
【2】会員名簿データを整理中です。住所変更はお早めに!
【3】岡山大会:関連情報
【4】学会オリジナルフィールドノート:新しくなりました。
【5】地質学雑誌:文献英文併記と図表・キャプションの英文化を
【6】日本地方地質誌「中国地方」割引販売のお知らせ
【7】北海道地質百選シンポジウム「北海道の地質魅力発見!」
【8】9月の博物館特別展示・イベント情報
【9】公募情報
【10】地質マンガ:「穿孔貝って」
No.76 2009/9/8(臨時)
★★目次★★
【1】岡山大会:盛況のうちに終了しました
【2】韓国地質学会:日韓合同セッション 修正・追加情報
No.75 2009/9/3
■ 羽鳥謙三名誉会員 ご逝去
No.74 2009/9/1
★★目次 ★★
【1】岡山大会関連情報いろいろ
【2】地質学雑誌:文献英文併記と図表・キャプションの英文化を
【3】日本地方地質誌「中国地方」刊行と割引販売のお知らせ
【4】平成21年度 東濃地科学センター 地層科学研究情報・意見交換会
【5】Conference of the Association of Korean Geoscience Societies,
Autumn-2009
【6】バングラデシュの環境問題を考えるシンポジウム
【7】9月の博物館特別展示・イベント情報
【8】公募情報
No.73 2009/8/24
★★目次 ★★
【1】祝!日本の3地域が世界ジオパークに認定
【2】世界ジオパーク認定関連行事の案内
No.72 2009/8/18
★★目次 ★★
【1】岡山大会関連情報:緊急展示募集ほか
【2】一般社団法人日本地質学会の代議員および役員の選挙実施について
【3】日本地方地質誌「中国地方」刊行と割引販売のお知らせ
【4】韓国地質学会:日韓合同英語セッション開催
【5】IGCP507第4回シンポジウムのご案内
【6】南海トラフ地震発生帯掘削計画タウンホールミーティング のご案内
【7】第26回東海地震防災セミナー2009のお知らせ
【8】公募情報
【9】地質マンガ 「ギョーカイ岩って」
No.71 2009/8/4
★★目次 ★★
【1】岡山大会 事前参加登録を!8/17日締切(FAX:8/10締切)
【2】惑星地球リスボン式典2009 派遣学生推薦募集
【3】惑星地球フォトコンテスト;作品募集中
【4】アジア留日経験研究者データベース(JARC-Net)のご案内
【5】IGCP507シンポ「白亜紀のアジアの古気候とそれらの国際的な比較」
【6】8月の博物館特別展示・イベント情報
【7】公募情報
【8】地質マンガ
【9】お知らせ(J-STAGEサービス一時停止/事務局夏期休業)
No.70 2009/7/21
★★目次 ★★
【1】快挙!Island Arc のIFが再び1.0越え
【2】フォトコンテストを開催します.良い写真をぜひ!
【3】岡山大会ニュース:プログラム決定
【4】Neogene/第四紀 境界 IUGSで批准
【5】惑星地球リスボン式典2009 派遣学生推薦募集
【6】ダーウィン生誕200年記念シンポジウム
【7】公募情報
No.69 2009/7/7
★★目次 ★★
【1】2009岡山大会ニュース:「保証及び著作権譲渡等同意書」への返信を!
【2】コラム:赤崩と大井川−池田宏氏による井川ジオツアーの報告
【3】7月の博物館特別展示・イベント情報
【4】海底地形名称の提案募集
【5】堆積学スクールOTB2009 in 沖縄
【6】公募情報
【7】地質マンガ「テストの日」
No.68 2009/6/22
★★目次 ★★
【1】岡山大会講演申込締切24時間延長!
No.67 2009/6/16
★★目次 ★★
【1】2009岡山大会ニュース あっ来週締切だ!
【2】地質学雑誌:文献英文併記と図表・キャプションの英文化を
【3】コラム:地球の体温を測って,地球に電気を流す
【4】2009年度日本地球化学会年会(共催:日本地質学会他)
【5】第15回GSJシンポジウム
【6】3rd International Tsunami Field Symposium(in 仙台)
【7】公募・各賞助成(各2件)
【8】地質マンガ「岩石の色」
No.66 2009/6/8
■ 加納 博 名誉会員 ご逝去
No.65 2009/6/2
★★目次 ★★
【1】2009岡山大会ニュース *講演申込:6/23締切です
【2】支部の情報
【3】日本の地質百選2次選定決まる
【4】深田研ジオフォーラム 2009/第120回深田研談話会
【5】第14回GSJシンポジウム「地質リスクとリスクマネジメントその2」
【6】第13回尾瀬賞募集
【7】公募情報(2件)
【8】6月の博物館特別展示・イベント情報
No.64 2009/5/19
★★目次 ★★
【1】総会が終了いたしました。
【2】地学オリンピック・表彰式
【3】研究を進める上での支障はありませんか? コメント募集
【4】岡山大会:講演申込/事前参加申込受付中
No.63 2009/5/12
★★目次 ★★
【1】総会案内
【2】第116年岡山大会:講演申込/事前参加申込受付開始
【3】地質の日 各地でイベント開催!
【4】地球惑星科学連合の会員登録を!
【5】研究を進める上で支障となっている事項調べ(日本学術会議事務局)
【6】支部情報 「北海道地質百選」
【7】原子力総合シンポジウム2009
【8】科学情報の活用に関するワークショップ開催
【9】日本地下水学会50周年記念講演会
【10】茨城大学理学部理学科地球環境科学領域教員の公募
【11】第4回「科学の芽」賞募集
【12】5月以降の博物館 特別展示・イベント情報
【13】地質マンガ「食べられません」
No.62 2009/4/21
★★目次 ★★
【1】日本地質学会第116年総会および一般社団法人2009年度定時総会 開催
【2】地学オリンピック!台湾大会派遣候補者決定
【3】コラム:南海トラフ地震発生帯掘削計画の国際会議に参加して
【4】「地質の日(5/10)」イベント情報
【5】地質学雑誌PDFカラー図表の差替えサービスを始めます!
【6】国立公園リーフレットシリーズ 屋久島地質たんけんマップ 新発売!
【7】4・5月の博物館 特別展示・イベント情報
【8】第6回(平成21年度)日本学術振興会賞受賞候補者推薦募集
【9】採用試験情報(北海道警察科学捜査研究所)
【10】地質マンガ「エアロゾルって何?」
No.61 2009/4/7
★★目次 ★★
【1】地質の日(5/10)特別講演会「火山はすごい!」
【2】報告書等の作成に関して—知っておくべきこと—
【3】「地質の日」イベント情報を掲載しませんか?
【4】支部情報
【5】HOPEミーティング参加者募集
【6】三朝国際インターンプログラム2009の案内
【7】2010〜2011年開催藤原セミナー募集
【8】公募情報
【9】地質マンガ「海には危険がいっぱい」
No.60 2009/4/7
■勘米良亀齢先生 名誉会員 訃報
No.59 2009/3/17
★★目次 ★★
【1】海外便り 台湾より:変成岩の大渓谷巡検!
【2】支部情報
【3】日本地方地質誌 5.近畿地方 会員特別割引販売のお知らせ
【4】学術会議報告「地球温暖化問題解決のために—知見と施策の分析、
我々の取るべき行動の選択肢」の公表
【5】2009年度日本地球化学会年会(地質学会共催)
【6】藤原賞50回記念講演会
【7】TV情報
【8】日本学術振興会特別研究員/-RPD 平成22年度採用分募集
【9】電力中央研究所地球工学研究所研究職募集
【10】ニュース誌の表紙写真急募!
【11】地質マンガ
No.58 2009/3/3
【1】杉山了三会員 文部科学大臣賞!
【2】2009岡山大会関連情報
【3】関東支部からのご案内
【4】本の紹介「科学を志す人びとへ 不正を起こさないために」
【5】2009年度日本地球化学会年会のご案内(地質学会共催)
【6】雄大な北米ロッキーでのフィールドキャンプへ参加しよう
【7】日本学術会議主催講演会「学術分野における男女共同参画促進のために」
【8】3月の博物館イベント情報
【9】東レ科学技術賞および東レ科学技術研究助成候補者推薦
【10】富山大学極東地域研究センター教員公募
【11】地質マンガ「船酔いはつらいよ」
No.57 2009/2/17
【1】「ジオパーク」がいよいよ日本でも始まります
【2】コラム:地球システム・地球進化ニューイヤースクール参加体験談
【3】「地質の日」新しいポスターが出来ました!
【4】2009年岡山大会関連情報
【5】北海道支部総会・個人講演会・日本地質学会長講演会
【6】都市問題研究シンポジウム 「沖積平野の地盤・環境特性」
【7】信州大学山岳科学総合研究所シンポジウム
【8】Blue Earth'09 の開催のご案内
【9】石油技術協会 第2回特別見学会のご案内
【10】The 2nd International Conference of Natural Resources in Africa on Sustainable Development in the Nile Basin Countries (ICNRA)のご案内
【11】高知大学海洋コア総合研究センター全国共同利用研究公募
【12】北海道大学大学院地球環境科学研究院准教授公募
【13】地質マンガ「船酔いはつらいよ」
No.56 2009/2/9(臨時)
■松本 達郎 名誉会員 訃報
■加藤 磐雄 名誉会員 訃報
No.55 2009/2/3
★★目次 ★★
【1】コラム 淡青丸KT-08-30次航海と鹿児島での火山灰採取
【2】2月の博物館特別展示・イベント情報
【3】「地球なんでもQ&A」活用術: アピールに使おう!
【4】関東支部イベント案内
【5】日本ジオパーク記念式典
【6】IYPE日本:ポータルサイト「惑星地球の扉」試験運用
【7】学術会議主催:公開シンポジウムのお知らせ
【8】J-DESCコアスクール 2コース 参加申込受付中!
【9】地惑連合大会 J-DESCセッション「地球掘削科学」のお知らせ
【10】9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference &
EXPO SGEM2009
【11】地質マンガ 「地質学は理系か、文系か?」
No.54 2009/1/29(臨時)
★ 目次
【1】IODP米国主催 スクール・オブ・ロック2009参加募集のご案内
【2】学術会議シンポジウム:第3回GEOSSアジア太平洋シンポジウム
【3】秋田大学東京セミナー「男鹿半島と私とジオパーク構想」
No.53 2009/1/20
【1】2009年度役員ならびに代議員選挙の実施(告示)延期の決定について
【2】地球惑星科学連合の個人会員登録について
【3】岡山大会ニュースNO.2 シンポ・見学旅行の企画などなど
【4】写真で見る軌跡 地学オリンピック2008年フィリピン大会の道
【5】第116回深田研談話会のご案内
【6】日本堆積学会2009年京都枚方大会のご案内と講演募集
【7】地質調査総合センター第13回シンポジウム(2/26)
【7】公募情報
【8】1月の博物館特別展示・イベント情報
【9】地質マンガ 「薄片道」
No.52 2009/1/6
★★目次 ★★
【1】2009年の年頭に当たって 会長 宮下純夫
【2】コラム:アメリカ・カルフォルニア州Panoche Hill巡検に参加して
【3】第157回西日本支部例会および平成2008年度支部総会のご案内
【4】構造地質部会2008年度例会のご案内
【5】男女共同参画委員会:金沢ワークショップご案内
【6】公募情報(2件)
【7】1月の博物館特別展示・イベント情報
No.51 12/16
★★目次 ★★
【1】日本地質学会の新たな出発:一般社団法人のスタートにさいして
【2】地質学雑誌 新表紙デビュー!!
【3】岡山大会シンポジウム申し込み(12/19締切)
【4】2009年度会費について(災害関連特別措置・院生割引ほか)
【5】日本ジオパークに7ヶ所が申請
【6】「地質の日」ロゴが決定しました!
【7】日本の地質百選 第二次選定追加募集中(1/30締切)
【8】国際地学オリンピック参加応募締め切り;昨年の倍増!83校686名
【9】構造地質部会例会「構造地質学と応用地質学の接点」のご案内(3/14-16)
【10】第46回アイソトープ・放射線研究発表会発表論文募集(2/28)
【11】消防防災科学技術研究推進制度平成21年度研究開発課題募集(1/30締切)
【12】12月の博物館特別展示・イベント情報
【13】地質マンガ 新婚旅行
No.50 12/5(臨時)号
■ 藤田和夫 名誉会員 ご逝去
No.49 12/2号
★★目次 ★★
【1】速報!ついに法人設立へ
【2】岡山大会シンポジウム申し込み(12/19締切)
【3】コラム:三陸津波の痕跡と防災〜田老の防潮堤を見学して〜
【4】大学教育の分野別質保証の在り方検討委員会(第3回)会議について
【5】第33回フィッショントラック研究会のご案内
【6】JAMSTECデータ検索ポータル」の提供開始
【7】12月の博物館特別展示・イベント情報
【8】東京大学地震研究所技術職員 公募
【9】次期南極観測計画を募集中(1/15締切)
No.48 11/18号
★★目次 ★★
【1】臨時総会(11/30)法人申請・登記に向けて!
【2】コラム:ロンドン地質学会「Gravitational Collapse at Continental
Margins」に参加して
【3】日韓地質学会学術交流協定調印記念式典 報告
【4】2009年度日本地質学会各賞候補者募集中
【5】2009年岡山大会トピックセッション,シンポジウム募集中
【6】The International Groundwater Symposium 2009 (IGS-TH 2009)
【7】第54回日本水環境学会セミナー
【8】平成20年度国土技術政策総合研究所(国総研)講演会
【9】深田研談話会(113,114回)と講演会のお知らせ
【10】第55回「海洋フォーラム」
【11】第45回の霞ヶ関環境講座・第36回の三宅賞受賞者記念講演
【12】各賞・研究助成情報
【13】公募情報
【14】地質マンガ「小学生の会話」
No.47 11/4号
★★目次 ★★
【1】2009年度日本地質学会各賞候補者募集(12/25締切)
【2】コラム:手動式ポイントカウンターとエクセルの計数マクロの紹介
【3】「有殻原生生物プランクトン研究はどこに向かうのか」研究会
【4】「京都 地下に眠る千年の地下水脈 −歴史都市と地下水−」談話会
【5】ZMPC2009国際会議のお知らせ
【6】11月の博物館特別展示・イベント情報
【7】日台科学技術交流の各種事業応募者募集
【8】大阪市立大学理学研究科・理学部地球学教室特任講師募集
【9】東京工業大学大学院理工学研究科地球惑星科学専攻教員募集
【10】地質マンガ「ある日の海外調査」
No.46 10/30号(臨時)
★★目次 ★★
【1】IODP計画更新に向けたテーマ別国内ワークショップ 参加者募集開始
【2】故 中川久夫 名誉会員を偲ぶ会
No.45 10/21号
★★目次 ★★
【1】日本地質学会2008年臨時総会(11/30)
【2】世界ジオパークへの国内推薦決定!!
【3】【岩手・宮城内陸地震】
地理情報システムを用いた地震災害とカルデラ構造との関連の検討
【4】平成21年度役員ならびに代議員選挙の実施(告示)延期について
【5】2009年岡山大会トピックセッション,シンポジウム募集
【6】2009年度日本地質学会各賞候補者募集
【7】2009年度院生割引申請受付開始! 院生注目!
-------------------------------------------------------
【8】日本地方地質誌 3. 関東地方 会員特別割引販売のお知らせ
【9】秋田大会見学旅行案内書,残部あります.
【10】深田研談話会:第112回(現地)・第113回(大阪)のご案内
【11】第7回地球システム・地球進化ニューイヤースクール NYS-7
No.44 10/7号
★★目次 ★★
【1】 野外調査において心がけたいこと
【2】コラム:MARGINS SEIZE 2008 workshop参加報告
【3】「地球を救う みんなの知恵」講演会のお知らせ
【4】産総研オープンラボのご案内
【5】10月の博物館イベント情報
【6】第3回国際地学オリンピック台湾大会の国内選抜参加者募集
【7】JST平成21年度地球規模課題対応国際科学技術協力事業研究提案募集
【8】アサヒビール学術振興財団2009年度学術研究助成募集
【9】京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻地質学鉱物学教室教員公募
【10】公立大学法人首都大学東京 教員募集要項
【11】「日本石紀行」会員割引のお知らせ
【12】地質マンガ「巡検初参加」
No.43 9/30(臨時)号
■名誉会員 「中川久夫先生を偲ぶ会」
No.42 9/16号
★★目次 ★★
<秋田大会関連ニュース>
【1】大会プレスリリース
【2】口頭発表講演データ取り扱いについて 演者はご注意を!
【3】秋田大会:一部会場の変更について
【4】普及事業・就職支援プログラムのご案内
-------------------------------------------------------------------------
【5】専門部会への登録のお願い
【6】地学オリンピック 日本は銀と銅メダル! ぱちぱちぱち
【7】地質の日のポスター・ロゴ募集
-------------------------------------------------------------------------
【8】学術会議提言「新しい理工系大学院博士後期課程の構築に向けて−科学・技術
を担うべき若い世代のために−」
【9】地質マンガ「調査日和」
【10】スズメバチは2度目にご注意 フィールド体験談
No.41 9/2号
★★目次 ★★
<秋田大会関連ニュース>
【1】地質災害現地報告会 開催
【2】日本学術振興会事業に関する説明会 開催
【3】就職支援プログラム
【4】秋田大会 講演プログラム公開しました
-------------------------------------------------------------------------
【5】スズメバチは2度目にご注意 フィールド体験談
【6】ホームページのアクセス急増中! 年間50万人ペース
【7】新広報誌「ジオルジュ」スタート
【8】9月の博物館イベント情報
-------------------------------------------------------------------------
【9】第33回IGCの環境成果報告会
【10】平成20年度東濃地科学センター地層科学研究 情報・意見交換会
【11】地質マンガ「生痕」
No.40 8/20(臨時)号
■ 坂野昇平 名誉会員 ご逝去
No.39 8/19号
【1】会員情報の確認・修正がオンラインでスタート!便利じゃん
【2】秋田大会見学旅行追加募集
【3】新!地質学会広報誌 準備中!乞うご期待!
【4】コラム:庭石から地球科学を考える
【5】秋田大会・夜間小集会「地質学会若手の集い」のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】群馬県立自然史博物館学芸員募集
【7】国際シンポのご案内 "Efficient Groundwater Resources Management"(in タイ)
【8】地質研修のご案内
No.38 8/12号(臨時号)
■中川久夫 名誉会員 訃報
No.37 8/5号
【1】秋田大会各種申込み8/8締切! 巡検もまだ余裕あります
【2】続報 岩手・宮城内陸地震 山形大学・千葉県地質環境センター
【3】海外便り
【4】夏休みだー 博物館へGo!! 8月の博物館イベント情報
【5】紹介:「地質学者が見た風景:坂 幸恭著」/「プレートテクトニクスの拒絶と受容:泊 次郎著」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募:京都教育大学/新潟大学/東北大学東北アジア研究センター
富山市科学博物館/統合国際深海掘削計画中央管理組織
【7】地質マンガ「地質学の彼氏を持つと」
No.36 7/29号臨時
■ 都城 秋穂 名誉会員 ご逝去
■ 八木 健三 名誉会員 ご逝去
(八木健三先生 お別れの会 案内)
No.35 7/22号臨時
【1】夜間小集会追加募集!
【2】プレス発表希望者は早めに連絡を!
【3】2008秋田大会:各種申込受付中!!(8/8締切)
─────────────────────────────────
【4】構造地質「2008年夏の学校」“反射法地震探査:基礎・演習・実習”
【5】古気候・古環境研究の推進のための多分野横断型メーリングリストへの参加のお誘い
【6】地質学雑誌:編集規約一部修正について
No.34 7/1号
【1】2008年岩手・宮城内陸地震続報:茨城大学班調査ほか
【2】韓国科学フェスティバル目前 IYPE日韓交流学生訪問団
【3】2008秋田大会:各種申込受付中!!
【4】日本学術会議提言「地球環境の変化に伴う水災害への適応」の公表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第111回深田研談話会のご案内
【6】3rd INTERNATIONAL IGBP PAGES FOCUS- V (old) LIMPACS CONFERENCE
【7】講演会「海洋法条約に基づく大陸棚限界延長−NZの申請の経験から−」
【8】島原市職員公募(8/22)
【9】静岡大学防災総合センター教員募集(7/31)
【10】新潟大学教育研究院自然科学系教員公募(9/16)
【11】広報委員募集
【12】地質マンガ「遭遇したくないもの」
No.33 7/1号
★★目次 ★★
【1】2008年岩手・宮城内陸地震続報:墓石転倒率調査ほか
【2】秋田大会で岩手・宮城内陸地震関連の講演
【3】秋田大会の要旨締め切り迫る(7/10)
【4】7月の博物館イベント情報 もうすぐ夏休み!
【5】日本全国天然記念物めぐり(秋田県編)北投石、千屋断層、筑紫森岩脈!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】柏崎刈羽原発見学会の日程変更と再募集のお知らせ(7/11)
【7】平成21年度研究船利用課題公募
【8】猿橋賞候補者推薦依頼
【9】第30回(平成20年)沖縄研究奨励賞推薦応募
【10】平成20年度東レ科学技術賞および東レ科学技術研究助成の候補者推薦
【11】地質マンガ
【12】geo-Flash創刊1周年によせて
No.32 6/18号
★★目次 ★★
【1】岩手・宮城内陸地震の地質学的背景
【2】岩手・宮城内陸地震(M=7.2)の調査に行かれる方へ
【3】書評:英語の会議に出る前に読む本
【4】国際地学オリンピック 大会派遣代表決定!
【5】韓国科学フェスティバルに学生派遣
【6】ジオパークの募集始まる
【7】G8北海道洞爺湖サミットに向けた各国学術会議の共同声明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】「Prof. Gregory Mooreさん、ありがとうミニシンポジウム」開催のお知らせ
【9】構造地質部会夏の学校 「反射法地震探査のための夏期集中講義・実習」
【10】第12回尾瀬賞募集
【11】第2回「科学の芽」賞募集
【12】平成20年度文部科学大臣表彰:科学技術賞/若手科学者賞候補者推薦
【13】柏崎刈羽原子力発電所敷地内の地質調査現場見学会
【14】地質マンガ
No.31 6/3号
★★目次 ★★
【1】新会長あいさつ
【2】秋田大会情報! 申し込み受付開始
【3】地質の日イベント報告 各地で大盛況
【4】6月の博物館イベント情報
【5】地質学雑誌新表紙コンテスト結果
【6】四川大地震現地体験報告
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】海洋基本法制定一周年記念シンポジウム
【8】産業技術総合研究所地質分野:H21年度採用予定研究員募集
【9】資源地質学会第58回年会シンポジウム
【10】日本学術会議・北海道大学主催公開シンポジウム
【11】第24回ゼオライト研究発表会
【12】地質マンガ
No.30 5/21号
★★目次 ★★
□四川大地震に関しての緊急情報
【1】四川大地震に関する情報
【2】地質背景(緊急寄稿)
【3】会員からの情報
□ミュンマーサイクロン災害に関しての緊急情報
【4】ミャンマーサイクロン災害に関する情報
【5】被災状況
□未曾有の災害に対する学会の対応に付いて
【6】地質学会の対応について
【7】地球惑星科学連合大会での緊急発表
【8】緊急人道支援に関して
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】関東支部 第2回研究発表会「関東地方の地質」・支部総会(6/8)
【10】堆積学スクールOTB2008(6/18-20)
【11】第7回産学官連携推進会議(6/14 日本学術会議 主催)
【12】サマー・サイエンスキャンプ 2008参加者募集
【13】第21回国際ミネラルフェア(6/6-6/10)
No.028 5/9号
★★目次 ★★
【1】地質の日(5/10)関連イベント 盛りだくさん!!
【2】5月の博物館イベント・特別展示カレンダー
【3】地質技術伝承講習会:地質技師長が語る地質工学余話シリーズ
【4】化石チョコレート発売開始!(化石のチョコレートではありません)
【5】広島大学大学院理学研究科地球惑星システム学専攻助教公募
【6】地質マンガ2本立て! 「船なのに」&「正月のごちそう」
No.027 4/24臨時号
【1】第1回「地質の日」迫る
【2】博物館GWスペシャル
【3】野外調査の季節到来 でもちょっとこんなことにも気をつけて!
【4】国際地学オリンピック日本委員会組織委員会が発足
_____________________________________________________
【5】IYPE日本 Newsletter(NO.4) (NO.5) より
【6】日本地質学会 各支部の5-6月のイベント
【7】北海道洞爺湖サミット・「地質の日」記念シンポジウム『洞爺湖・有珠山との共生』
No.26 4/15号
【1】日本地質学会第115年総会開催のお知らせ
【2】ジオパークと“Rock”・“Green”・“Café”
【3】日本地質学会各支部イベント案内(中部支部・関東支部)
【4】2008年度会費払込(次回引き落としについて)
【5】地質マンガ「サンプルリクエスト」
【6】第52回粘土科学討論会講演申込(地質学会共催)
【7】第6回国際アジア海洋地質学会議:締め切り延長のお知らせ
【8】産業技術総合研究所地質調査総合センター第12回シンポジウム
No.25 4/1号
★★目次 ★★
【1】日本地質学会第115年総会開催のお知らせ
【2】地質学雑誌表紙デザイン締め切る
【3】2008年度会費引き落としのご連絡(6/23)
【4】関東支部箱根巡検・近畿支部山陰海岸地質見学会
【5】木村会長とロンドン地質学会会長との懇談のリポート
【6】地質マンガ「ちきゅうはゆれない」
【7】三朝国際インターンプログラム2008の案内
【8】高知大学理学部理学科地球科学コース准教授・助教公募
【9】千葉大学大学院理学研究科地球科学コース准教授公募
【10】地質調査総合センター第12回シンポジウム
No.024 3/18号
★★目次 ★★
【1】地質学雑誌の新表紙デザイン締め切り間近!
【2】北海道・関東・近畿・四国・西日本支部 イベント案内
【3】コラム:関東アスペリティ計画第三回国際ワークショップと巡検に参加して
【4】地質マンガ「ちきゅうに乗りたい」・「乗船」
【5】地球科学関係の最近10年間の引用数トップ10
【6】第6回国際アジア海洋地質学会議のお知らせ
【7】『岩石物性入門』著者割引販売のお知らせ
【8】国際惑星地球年日本 Newsletter No.3 (2008.3.18)
No.023 3/4号
★★目次 ★★
【1】東レ科学技術研究助成に加藤泰浩氏(東大)決定!
【2】第2回国際地学オリンピック参加者募集に354名応募!
【3】シンポ「五島列島と地球の歴史」 自然に残されたタイムカプセルの探求
【4】「カタカナ英語本」の紹介
【5】地質マンガ「堆積岩」「変成岩」
【6】ノーザン・イリノイ大学銃乱射事件に学ぶ日本の危機管理
【7】地質学雑誌 表紙デザイン応募状況
【8】地質の日関連行事:宮澤賢治ジオツアー
【9】国際恐竜シンポジウム2008「アジアの恐竜研究最前線」
【10】地域連携シンポジウム:茨城県の湖沼環境をめぐって
【11】8th International Scientific Conference SGEM2008
No.022 2/19号
★★目次 ★★
【1】地質学雑誌新表紙デザイン 募集中!
【2】地質マンガ:「巡検」・「フィールド調査」
【3】コラム:三浦・房総半島の付加体巡検に参加して
【4】学生・院生・ポスドク就職支援WGメンバー募集中!
【5】IODP DRILLS in 東大 (セミナーのお知らせ)
【6】IGCオスロのアブストラクト締め切りが2月末に延長!
【7】第4回IGCP516「東南アジアの地質学的解剖:東テーチスの古地理と古環境」
【8】平成20年度高知大学海洋コア総合研究センター全国共同利用研究公募
【9】地質調査総合センター第10回シンポジウム
【10】地震予知総合研究振興会 嘱託職員(非常勤)募集
No.021 2/5号
【1】2008年度日本地質学会 理事・評議員選出結果
【2】第2回国際地学オリンピック国内選抜実施・募集
【3】地質学会はジオパーク、IYPEを積極的に推進しています!
【4】「地質の日」が記念日協会に登録されました
【5】「ちきゅう」南海掘削Stage 1A終了
【6】コラム ハロー「ちきゅう」から(山口飛鳥)
【7】地質調査総合センター第11回シンポジウム
【8】関東アスペリティ・プロジェクト(KAP)国際ワークショップ開催
【9】日本堆積学会2008年弘前大会のご案内と講演募集
【10】J-DESCコアスクール「コア解析基礎コース」開催
No.020 1/22号
【1】「地質学雑誌」表紙デザイン公募要領発表
【2】第115年学術大会(秋田大会)トピックセッション,シンポジウム募集
【3】日本全国天然記念物めぐり(和歌山編)
【4】宮沢賢治と鉱物に関するコラム
【5】国際地学オリンピック 国内選抜実施・募集のお知らせ
【6】第3回IGCP507 「東アジアの白亜紀古気候」シンポジウムとモンゴル巡検のお知らせ
【7】広島大学大学院理学研究科地球惑星システム学専攻準教授公募
【8】高知大学海洋コア総合研究センター研究員(非常勤職員)の募集
No.019 1/8号
【1】会長より新年のご挨拶
【2】理事選挙立候補受付中
【3】2009年地質学雑誌表紙デザイン一新計画 デザイン募集(予告)
【4】中国の大別蘇魯(ターピエ・スールー)衝突帯の東方延長に新説!
【5】「ちきゅう」の科学者に聞いてみよう! *質問募集中*
【6】NUMO技術開発成果報告会開催
【7】消防防災科学技術研究推進制度平成20年度研究開発課題の募集
【8】静岡大学理学部地球科学科教員(助教)公募
【9】日本ジオパーク連携協議会 発足
【10】AOGS 2008 in 釜山 のお知らせ
【11】北海道大学2008テニュア・トラック・ポストの特任助教の公募
【12】産総研ポスドク公募
No.018 12/18号
【1】発表!2007年 地質重大ニュース(勝手に選びましたっ)
【2】2008年度日本地質学会会長、副会長,代議員選挙結果
【3】2008年度日本地質学会各賞候補者募集中(来週締切!)
【4】シンポジウムダイジェスト「 海底地すべり」
【5】専門部会再登録のお願い
【6】2008年度会費の払込・院生割引申請について
【7】シンポジウム「新潟の自然と科学教育の素材」
No.017 12/4号
【1】投票はお済ですか?
【2】2008年度日本地質学会各賞候補者募集中
【3】海外だより(ドイツキール大の北村さんより 後編)
【4】日本全国天然記念物めぐり(京都府編)
【5】ホットな地球惑星科学連合の最近について
【6】「ジオパーク」最近の動き
【7】第6回地球システム・地球進化ニューイヤースクールのご案内
【8】討論会「日本海沿岸褶曲・断層帯の形成・成長と地震活動」報告
No.016 11/20号
【1】2008年度役員選挙についてのお知らせ(マニフェスト有)
【2】海外だより(ドイツキール大の北村さんより)
【3】トピックセッションより:地球史とイベント大事件
【4】2008年度日本地質学会各賞候補者募集中!
【5】1/20万 日本シームレス地質図詳細版のお知らせ(これは使える!)
【6】大阪市立大学理学研究科・理学部地球学教室 特任講師の募集
【7】日本学術会議 平成20年度代表派遣会議及び派遣候補者の推薦募集
【8】第9回Project Aシンポジウム「五島列島で考える地球史」 参加者募集
【9】代議員選挙(地方区),立候補者リストの訂正とお詫び
No.015 11/6号
★★目次 ★★
【1】2008年度役員選挙:選挙活動期間についてのお知らせ
【2】韓国地質学会との学術協定調印!
【3】2008年度日本地質学会各賞候補者募集 開始!
【4】日・タイ/日・モンゴル/日・フィリピン 交流委員募集
【5】天然記念物めぐり 滋賀編(4つ紹介!)
【6】ジオパーク大図解シリーズ 発売
No.014 10/26(臨時)号
★★目次 ★★
【1】札幌大会緊急パネルディスカッション報告UP!
【2】日本学術会議より募集がありました
【3】「日本列島ジオサイト—地質—百選」が出版されました!
【4】2008年連合大会セッション提案締切延長(30日まで)
No.013 10/16号
★★目次 ★★
【1】2008年度代議員および役員選挙のお知らせ
【2】IYPE(国際惑星地球年)学生コンテスト開催!
【3】天然記念物(地質鉱物編)めぐり
【4】地球惑星科学連合のメールニュースおよびセッション締め切り
【5】「ちきゅう」2地点目掘削中!
【6】信州大学大学院テニュアトラック助教 公募
No.012 10/05(臨時)号
★★目次 ★★
【1】討論会 「日本海沿岸褶曲・断層帯の形成・成長と地震活動」開催
No.011 10/02号
★★目次 ★★
【1】2008年度代議員および役員選挙のお知らせ
【2】博物館イベント情報100連発!(こんなにも!)
【3】「ちきゅう」掘削開始!
【4】院生割引申請受付開始 (毎年更新です。お忘れなく!)
【5】コラム「間違いだらけの発音選び」(最終回)
【6】コラム「2秒であなたは何をします?」
【7】「地質の調査」に関わる研修 受講者募集
【8】日本土地環境学会 2007 年シンポジウム(日本地質学会 協賛)
【9】札幌大会の出版物や忘れ物のお知らせ
【10】女性研究者の星、猿橋勝子氏 逝く。
No. 010 9/18号
★★目次 ★★
【1】「ちきゅう」による南海トラフ掘削開始間近!
【2】月周回衛星「かぐや(SELENE)」による地質調査
【3】日本初の天然ダイアモンド発見!
【4】地学教育公開授業
【5】日高山脈地質くらぶ"千栄の家"存続にご協力を!
【6】コラム「間違いだらけの発音選び」その2(全3回)
No. 009 9/14(臨時)号
★★目次 ★★
【1】「かぐや」打ち上げ成功!
No. 008 9/4号
★★目次 ★★
【1】第114年学術大会(in 札幌)迫る!
【2】札幌大会口頭発表:プログラム一部訂正
【3】コラム:「間違いだらけの発音選び」(気をつけなきゃ)
【4】同志社大学工学部 環境システム学科専任教員公募(10/10締切)
【5】JABEE講習会のご案内(10/13 開催)
【6】院生評議員・代議員より「博士の将来」アンケート作成中
【7】9月9日(日)新HPついに公開(予定)!!
No. 006 8/21号
★★目次 ★★
【1】札幌大会の見所(その3)(海底地すべりとは?)
【2】新潟県中越沖地震&ペルー地震&房総沖群発地震・スロースリップ
【3】新潟県中越沖地震緊急ポスター発表申し込み〆切せまる
【4】今週のキーワード「海底地すべり」
【5】Geo-Flashにアクセス急騰!
【6】京都大学大学院 地球惑星科学専攻地質学鉱物学教室 公募(10/5締切)
No. 004 7/19号
★★目次 ★★
【1】新潟県中越沖地震速報
【2】新潟県中越沖地震緊急展示@札幌大会 要旨受付開始
【3】公募情報(横浜国立大学 助教)
【4】ワークショップ申し込み締切延長のお知らせ
【5】国際陸上科学掘削計画(ICDP)に注目!
No. 003 7/17号
★★目次 ★★
【1】緊急 新潟県中越沖地震情報
【2】緊急提案:渋谷温泉施設爆発
【3】世界遺産登録記念:石見銀山の地質と鉱床
【4】生物侵食の島(ニュース誌表紙写真ダウンロード開始)
【5】札幌大会の見所 (その2)
【6】今週のキーワード 「大イベント」「カルデラ」
【7】シンポジウム案内
【8】公募情報(秋田大学工学資源学部 ポスドク 8/31〆切)
【9】札幌大会関連プレスリリース日程変更
No. 001 7/3号
★★目次 ★★
【1】創刊のごあいさつ (会長 木村 学)
【2】講演申し込み締切延長 (7月4日に変更)
【3】札幌大会はホテル不足?! (お早めに!)
【4】札幌大会セッションの見所 (その1)
【5】地質学雑誌に新しいカテゴリー追加 (要チェック!)
【6】シンポジウム案内
【7】今週のコラム 「北海道に地質の風を吹かそう!」の巻
【8】geo-Flash配信アドレスの追加・変更および停止
配信希望の方は
geo-Flashは地質学会会員に配信されます。
会員の方はメールアドレスの登録をお願いいたします。オンライン登録システムは現在準備中です。お手数ですがこちらから申し込んで下さい。
非会員の方はこれを機会に入会されませんか。入会案内はこちらです。
No.125 2011/1/21(臨時)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.123 2011/01/11 ┴┬┴┬ <*)++<< ┬┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 濱田隆士 会員 ご逝去
──────────────────────────────────
濱田隆士会員が1月19日にご逝去されました(享年77歳).
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます.
通夜・ご葬儀の日程と会場は次の通りです.
通 夜 :1月27日(木)18時より
葬儀告別式 :1月28日(金)11-12時
場 所 :吉祥院(神奈川県足柄郡湯河原町吉浜13)
http://www.kichijyo.com/access.html
*供花・花輪等はお受けしていただけるとのこと。お申し込みはゆがわら式典へご
連絡ください。
*お身内の方がいらっしゃらないこともあり、お香典・弔電はご辞退されるとのこ
とです。
*供花等申込先:ゆがわら式典
http://www.sougi-bon.com/kanagawa/sougisha/14587/
TEL 0465−63−4949 FAX 0465−63−3939
会長 宮下純夫
──────────────────────────────────
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日までに
事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
第2回フォトコン入選作品:優秀賞
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:優秀賞
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:優秀賞:「クレーター」
写真:亀田きようかず(和歌山県) 撮影場所:和歌山県太地
撮影者より:
月面のクレーターに似ていると思って写した.太地の海岸で見つけた岩.この海岸にはこのような岩が多く有ります.
審査委員長講評:
この写真は,亀田さんが和歌山県太地海岸で見つけた月面のクレーターのような地層を写されたものです.同じようなクレーター状の地層は写真の左奥にも見られます.このような形がどうやってできるのでしょうか.彩度の低い青色が基調となった写真で,独特の雰囲気があります.
地質的背景:
和歌山県太地町周辺には中新世の四万十帯が分布しています.四万十帯はプレートの沈み込み作用によって,海底の堆積物が陸側に押しつけられてできた付加体です.白亜紀の四万十帯と違って,始新世から中新世の四万十帯は砂岩がとても多いことが特徴です.地震隆起による岩礁地帯には砂岩がごつごつとそびえています. (海洋研究開発機構 坂口有人)
←戻る 目次 進む→
No.128 2011/3/1 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.128 2011/3/1 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】解説:ニュージーランド・クライストチャーチ地震の地質学的側面
【2】コラム:日本最古の鉱物 〜37億5000万年前の痕跡〜
【3】コラム:新鉱物「千葉石」の発見
【4】林原生物化学研究所の地質学・古生物学研究に関する要望書
【5】日本地質学第3回(2011年度)総会(代議員総会)開催のお知らせ
【6】2011水戸大会見学旅行:各コースの魅力と見どころ紹介
【7】本の紹介:「石と人間の歴史 地の恵みと文化」蟹澤聰史 著
【8】2011年度会費/学部学生・院生割引申請受付中(3/31締切)
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】故 大森昌衛名誉会員を偲ぶ会 お知らせ
【12】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】解説:ニュージーランド・クライストチャーチ地震の地質学的側面
──────────────────────────────────
小川勇二郎
2011年2月24日現地時刻12時51分43秒(23日23:51 43.0 s UTC)にニュージー
ランド南島クライストチャーチ近郊でM6.3の地震が起きた。震源の深さは
約5kmとされている。この地震は、2010年9月4日に約70km西方で起きたM7.0
のDarfield地震(右水平ズレ)の余震域の東端に位置し、余震の一つと考
えられる。
続きを読む、、、 http://www.geosociety.jp/hazard/content0047.html
追加情報:
なお地震の発震機構は下記より見ることができます。
右横ずれ成分のある逆断層のようです。
http://www.geonet.org.nz/news/feb-2011-christchurch-badly-damaged-by-magnitude-6-3-earthquake.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】コラム:日本最古の鉱物 〜37億5000万年前の痕跡〜
──────────────────────────────────
堀江 憲路(国立極地研究所)
富山県黒部市宇奈月地域の花崗岩中に「日本最古の鉱物」が含まれることが、
国立極地研究所・広島大学及び国立科学博物館を中心とする研究グループに
より発表された。
続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0280.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】コラム:新鉱物「千葉石」の発見
──────────────────────────────────
高橋 直樹(千葉県立中央博物館)
「千葉石(chibaite)」という名前の新鉱物が誕生しました.2011 年2月15日付け
で論文が公表され(Momma et al., 2011),晴れて世界に認められることになりま
した.
続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0281.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】林原生物化学研究所の地質学・古生物学研究に関する要望書
──────────────────────────────────
新聞報道などでご存知と思いますが、株式会社林原の経営破綻により、複数
の本学会会員を含む地質・古生物系職員の研究活動、恐竜化石を中心とする
貴重な標本や文献の管理、国際的な学術協力関係などに支障が出る可能性が
懸念されます。そこで地質学会会長から同社社長と管財人あてに、これらの
事項に関する要望書を発送しました。
続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/engineer/content0018.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】日本地質学第3回(2011年度)総会(代議員総会)開催のお知らせ
──────────────────────────────────
日時 2011年5月21日(土)14:00〜15:30
会場 総評会館 201会議室(千代田区神田駿河台3-2-1)
地図はこちら→http://www.sohyokaikan.or.jp/access/
議事次第等は、後日お知らせいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】2011水戸大会見学旅行:各コースの魅力と見どころ紹介
──────────────────────────────────
水戸大会では、見学旅行は茨城を中心とした関東周辺地域の地質理解のため
の重要な行事と位置付け、参加者に満足していただける特徴的なコース作り
を目指しております。正式なコース一覧や参加申込の詳細はニュース誌4月号
(4月末頃)で紹介する予定です。
全コースの紹介を掲載しました。
http://www.geosociety.jp/mito/content0030.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】本の紹介:「石と人間の歴史 地の恵みと文化」蟹澤聰史 著
──────────────────────────────────
中公新書2081,2010年11月発行,257ページ, 定価820円+税,ISBN978-4-12-102081-9
本書は、「文学を旅する地質学」(古今書院、2007年)に引き続くこの著者の岩石・鉱物エッセー集であり、帯には「石、あってこそのホモ・サピエンス」、「地球の歴史に思いを馳せる世界岩石紀行」というキャッチフレーズがついている。本書は、序「石とは何だろう」、第Ⅰ部「古い大陸とその周辺の石」、第Ⅱ部「テチス海の石—地中海沿岸諸国」、第Ⅲ部「アジアの古い大陸とテチス海の石」、第Ⅳ部「新しい活動帯の石—トルコ、イタリア、北米、日本」、第Ⅴ部「天から降ってきた石と地の底から昇ってきた石」という構成になっており、あとがきと引用・参考文献リストがついている。
序ではまず「石の定義」があり、広辞苑の「岩より小さく、砂より大きい鉱物質のかたまり」から始まって火成岩、堆積岩、変成岩の説明があり、あれ、教科書かなと思いきや、すぐにゲーテが絡む水成論と火成論の対立、ギリシャ・ローマ神話や聖書の中の石と岩(聖ペテロの名は「石」の意)、十和田火山噴火と八郎太郎伝説、そして地球の年齢を求める科学者の苦闘の歴史が語られ、完全に著者のペースにはまってしまう仕掛けになっている。
第Ⅰ部ではスウェーデンの銅鉱床、ノルウェーのオスロリフトのカーボナタイト、イングランドの巨石文化を廻り、宮澤賢治のイギリス海岸に到着する。1950年にイギリスで起きた「即位の石」事件や、賢治の「銀河鉄道の夜」のプリオシン海岸で発掘していた大学士は早坂一郎氏だったことなど、興味深いエピソードもある。賢治の詩や童話には月長石、トルコ石、藍銅鉱、サファイアなど青い鉱物がよく登場し、作品が地学的で「青」を基調とする点で、同じく夭折したドイツのロマン主義詩人ノヴァーリスと共通点が多い、という指摘は含蓄に富む。
第Ⅱ部の話は、ギリシャ・アテネのアクロポリスの丘の地質から始まり、イタリアの大理石(ローマの円形劇場はトラバーチン製)、中欧諸国の石と建物(赤色砂岩など)、エジプトのピラミッド(大型有孔虫化石を含む始新世石灰岩)、そしてエジプトを舞台とするモーツアルトの「魔(ま)笛(てき)」とフリーメーソンの関係に発展する。ミロのビーナス像は本来トルコに行くはずだった、デルポイの神託は活断層から出てくるエチレンなどのガスを吸って恍惚(こうこつ)となった巫女(みこ)の口から発せられた、などのエピソードも興味深い。
第Ⅲ部は一転してモンゴルのオボー(石塚)や亀趺(きふ)(亀形の石)の話から始まり、カンボジアのアンコールの石材、北中国の万里の長城の石、南中国の太湖石(奇妙な形の石灰岩の庭石)を廻り、チベット高原・ヒマラヤに行きつく。南中国の蘇州近くの太湖が衝突クレーターであるという説が紹介されているが、どの程度確かなのだろうか。
第Ⅳ部はトルコのパムッカレの石灰華から始まり、ヴェスヴィオ火山とポンペイ遺跡(ゲーテの訪問記も紹介)、アメリカのコロラド高原の火山地帯(バイアスカルデラなど)を廻って日本の石文化(石器、ヒスイ、環状列石、城壁、野仏、磨崖仏など)に戻る。教科書の大幅書き直しに発展した日本の石器捏造(ねつぞう)事件には触れていない。日本の国会議事堂の石材は国内で調達したが、都庁の石材は全て輸入品、という記述はワサビが効いている。
第Ⅴ部では、まず世界最古の落下が目撃された隕石は日本にあることが述べられ、生物大量絶滅の隕石衝突説、「サッドベリー」岩体の隕石衝突成因説、聖書に記された隕石シャワー、次に地下深部から来たマントル捕獲岩とダイヤモンド、そして最後は最近日本で発見されたダイヤモンドの話で結んでいる(発見者の氏名や文献を明記すべきだと思う)。
本書は、著者が専門としてきた岩石学の該博な知識と、在職中及び退職後の精力的な海外旅行や幅広い読書が融合して成立した本だと思う。著者は「あとがき」で、「美術史、歴史学、民俗学、あるいは宗教学などに関しては未知の世界で、これらの文献や解説書を読むのは至福の一時であり、こんなにも面白い考え方があったのかと、あらためて自由な時間の楽しさを味わった」と述べている。
本書とよく似た内容の本として中山 勇氏の「新・石の文明と科学」(啓文社、1990年)がある。読み比べてみると、蟹澤氏の本は「文化」の香りが高く、ゲーテや宮澤賢治などの詩人を頻繁に登場させ、一般の人にはなかなか伝えにくい石に関する科学的知識を、文学的教養に包んで普及しようという意図が感じられる。一方、中山氏の本は、石と「文明」の関わりを記述しながら、科学者の精神を問題にしていて、プリニウス、アグリコラ、そしてソ連のダイヤモンド調査隊(遭難して帰らなかった)が残した文章などから、あるべき科学者の人柄、思想、心を説こうとしている。どちらの本も石と人間の関わりを古今東西にわたって詳しく記述している点では共通するが、方向はかなり異なっている。
本書に誤りは少ないが、例えば73ページの「ギリシャは多神教で、多くの神々が宿るところである」は、主語を「古代ギリシャ」として過去形にすべきだろう。現代ギリシャは一神教の正教の国である。また、石は学習や遊び(硯(すずり)、石盤(せきばん)、蝋(ろう)石(せき)、碁石(ごいし)、カーリング)、料理(焼石、砥石(といし))など昔は日常生活でよく使われ、貨幣として使われた地域もあった(ヤップ島など)。こういう身近な話題も加えたら、より親しみやすくなるのではないかと思う。
この教養あふれる世界岩石紀行が新書版で楽しめるのはありがたく、本書によって多くの読者が著者の「至福の一時」のおこぼれにあずかることができると思う。
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】2011年度会費/学部学生・院生割引申請受付中(3/31締切)
──────────────────────────────────
■2011年度会費払込について
次年度分会費の前納をお願いいたします。自動引き落としを登録されている
方は、2010年12月24日(金)に引き落としを行いました。お振込の方へは、
12月中旬頃に請求書兼郵便振替用紙をお送りいたしました。
詳しくは、 https://www.geosociety.jp/user.php
■2011年度(2011.4〜2012.3)学部学生・院生割引申請受付中
最終締切:2011年3月31日(木)
申請書のダウンロードは、https://www.geosociety.jp/user.php
(いずれも会員番号によるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】支部情報
──────────────────────────────────
■北海道支部:2011年度「地質の日」記念展示
「豊平川と私たち —その生いたちと自然—」
場所:北海道大学総合博物館
日時:2011年3月8日(火)〜5月29日(日)
同時開催企画:豊平川の化石〜 化石が語る“札幌の海”
ミニツアー:札幌軟石ウォッチング
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
■東北支部2009〜2010年度総会,個人講演会と公開シンポジウム
会場:「コラッセふくしま」5階研修室
日程:3月13日(日)(日程を短縮し、13日のみに変更)
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
■2011年関東支部総会および地質技術伝承講習会
【地質技術伝承講習会】
日時:2011年4月24日(日)14:00〜16:00
場所:大田区産業プラザ(大田区蒲田1-20-20)特別会議室
テーマ:トンネル事前調査の課題と物理探査
参加費:無料、どなたでも参加できます。
【支部総会】
日時:2011年4月24日(日)16:00〜16:30
場所:上記講習会と同会場
申込方法・総会委任状等、詳しくは、http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■気候変動適応研究推進プログラム平成22年度研究成果報告会
文部科学省は、気候変動適応に関する研究水準の大幅な底上げ、適応策検討
への科学的知見の提供、気候変動による影響に強い社会の実現に貢献すること
を目的として平成22年度から「気候変動適応研究推進プログラム」を開始しま
した。
日時:2011年3月18日(金) 13:30〜17:00
場所:東京ステーションコンファレンスサピアタワー5階
詳しくは、http://www.mext-isacc.jp/article.php/event_result_report2011
■日本学術会議 公開講演会
「自然災害軽減のための国際協力のあり方を考える」
日時:2011年3月22日(火)13:00〜17:00
会場:日本学術会議講堂(東京都港区六本木)
参加費:無料
Web(申込フォーム)によりお申込み下さい。
https://form.cao.go.jp/scj/opinion-0003.html
■JABEE 事務局ニュース No12(2011/2/22版)
JABEE事務局ニュースは社員(正会員)、賛助会員、理事、監事、顧問、委員会
委員宛に配信されています。情報のより広い共有のため、会員の皆様にもご転送
いたします。
2011/2/22版ニュース PDFはこちら
JABEEホームページ
■2011年春季 地質の調査研修:参加者募集中
産総研地質調査総合センター認定の研修プログラムの一環として、上記の研修
の参加者募集中です。
日程:2011年5月16日(月)〜20日(金)4泊5日
場所:千葉県君津市及びその周辺地域(房総半島中部域)
申込締切: 2011年4月11日(月)
詳細は、 http://www008.upp.so-net.ne.jp/gsis/gykensyu.htm
■IGCP507国際シンポジウム(北京)
日程: 2011年8月15〜20日(15,16:シンポジウム,17〜20:巡検)
開催地: 中国地質大学・北京校
シンポジウム内容: 一般セッション(IGCP507の趣旨に関連するテーマ全般)
およびテーマ・セッション「前期白亜紀の中国Jehol Biota」 (半日)
巡検:西部遼寧の白亜系非海成層(Jehol Biotaを含む露頭など西部遼寧省の
層序や堆積環境などの観察)
http://igcp507.kopri.re.kr/(近日中にサーキュラーアップ予定)
IGCP507国内コーディネーター:長谷川卓(金沢大)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】故 大森昌衛名誉会員を偲ぶ会 お知らせ
──────────────────────────────────
故 大森昌衛名誉会員(平成23年1月3日逝去 享年91)の偲ぶ会が下記の通り
行われます。詳しい内容ついては下記にお問い合わせください。参加希望の方
には詳細をお送りします。
日時:2011年4月16日(土)13:30〜16:30(予定)
場所:東京ガーデンパレス
※旧私学会館(東京都文京区湯島1-7-5,最寄りJR御茶ノ水駅)
http://www.hotelgp-tokyo.com/map/index.html
問い合せ先:真野勝友 TEL/FAX:042-546-5723
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■日本学術振興会特別研究員-RPD平成24年度採用分募集 (5/11〜13)
■日本学術振興会特別研究員平成24年度採用分募集 (6/6〜8)
■平成23年度東レ科学技術賞および東レ科学技術研究助成候補者の募集(学会推薦)
(9/2学会締切)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
日本最古の鉱物〜37億5000万年前の痕跡〜
日本最古の鉱物 〜37億5000万年前の痕跡〜
堀江憲路(国立極地研究所)
富山県黒部市宇奈月地域の花崗岩中に「日本最古の鉱物」が含まれることをが,国立極地研究所・広島大学及び国立科学博物館を中心とする研究グループにより発表された.宇奈月地域は,飛騨帯の東縁部に位置し,含十字石結晶片岩に代表される中圧型変成作用を経験した地域として知られており,また日本列島と韓半島や中国大陸との関係を探る上で鍵となる地域である.
本地域の調査の一環として,宇奈月地域の変成岩に貫入する花崗岩から,〜0.2 mm程度の大きさのジルコン(化学式ZrSiO4)を多数取り出した.1つの花崗岩試料中には,角ばったジルコンとともに,丸みを帯びたジルコンが多数存在した.ジルコンは放射性元素であるウランを含んでおり,ウランが一定のペースで鉛に変化(壊変)していくことを利用することにより,ジルコンが形成した年代を決定することが可能である.そこで個々のジルコンについて,国立極地研究所と広島大学に設置されている高感度高分解能イオンマイクロプローブ(SHRIMP II)を用いてウラン−鉛年代測定を行った.SHRIMPは〜0.2 mm程度のジルコンに対して,0.01〜0.02 mm程度の領域の分析が可能である.角ばったジルコンは,花崗岩が形成する際に結晶化したものと考えられ,つまり2億5600万年前に花崗岩が形成したことを示している.一方,丸みを帯びたジルコンは外来性の粒子であり,全て34億5000万年よりも古く,最古のものは37億5000万年前という年代を示した.これまで報告されていた「日本最古の鉱物」は,岐阜県の天生峠から採取した飛騨片麻岩中のジルコンから得られた33〜34億年前のものであった.したがって,今回発見された37億5000万年前のジルコンは「日本最古の鉱物」となる.
ジルコンは物理化学的に安定な鉱物であり,つまり風化作用や変質作用の影響を受け難く,古い大陸の情報を保持することがあることが知られている.36億年以前の大陸の情報はジルコンから報告されており,カナダやグリーンランド,オーストラリア,東南極で発見されているが,東アジア地域では中国北東部からしか発見されていない.かつて中国大陸は北部と南部で別の小大陸であったが,約2億5000万年前に衝突し1つの大陸になったと考えられている.日本列島の大部分は,南中国大陸の縁でプレートが沈み込む際に巻き込まれた南中国大陸起源の物質から形成されたと考えられている.宇奈月花崗岩中に含まれる37億5000万年前のジルコンは,花崗岩を形成したマグマが,宇奈月地域の地下深部に存在していた北中国大陸由来の岩盤を貫くときに取り込まれたことを示唆する.このことは花崗岩形成時期の宇奈月地域の地理的位置を解明する手掛かりとなるであろう.
参考サイト:
国立科学博物館ホットニュース(2010.8.10):http://www.kahaku.go.jp/userguide/hotnews/theme.php?id=0001287564615961
(原稿受付 2011年2月5日)
新鉱物「千葉石」の発見
新鉱物「千葉石」の発見
高橋直樹(千葉県立中央博物館)
「千葉石(chibaite)」という名前の新鉱物が誕生しました.2011年2月15日付けで論文が公表され(Momma et al., 2011),晴れて世界に認められることになりました.新鉱物の発見自体はそれほど珍しいことではなく,世界では年に約100件,国内でも年に1,2件は発見・記載されていますが,今回は,「千葉石」という名前のためか,新聞やテレビのニュースでも取り上げられ話題になっていることもあり,ここで紹介させていただくことになりました.
千葉石は変わった特徴を持つ鉱物です.主成分は石英と同じ二酸化珪素(シリカ)ですが,それらが‘かご’状の結晶構造をつくり,その‘かご’の中にメタン,エタンなどの炭化水素ガスの分子を1個ずつ含みます(シリカクラスレート:シリカ包摂化合物).‘かご’の直径は1 nm程度という微小なものです.
図1.千葉石の結晶構造の模式図.図中の多面体が,ケイ素(Si)と酸素(O)からなるいろいろなサイズの‘カゴ’
化学式はSiO2•n(CH4,C2H6, C3H8,C4H10);(nmax=3/17)と表現されます.これは,次世代のエネルギー資源として期待されているメタンハイドレートと同じ構造なのです.こちらはシリカではなく水(H2O)が‘かご’状の結晶構造をつくっています.天然ガスハイドレートは,これまで3つの異なる結晶構造をもつタイプが知られており,それぞれ,I 型(等軸晶系),II 型(等軸晶系),H型(六方晶系)と呼ばれています.この順に,よりサイズの大きな炭化水素を含みます.シリカクラスレート鉱物は,天然ではこれまで「メラノフロジャイト」1種が知られていました.これは天然ガスハイドレートI 型に対応する構造をもつ鉱物です.今回発見された千葉石は,天然ガスハイドレートII 型に相当する鉱物で,炭化水素としてメタンのほかエタン,プロパン,イソブタンまで含まれます.さらに,同じ場所から天然ガスハイドレートH型に相当する鉱物も微小ながら確認されていますが,まだ正式な鉱物種の認定までには至っていません.メラノフロジャイト仮像と思われる結晶も同じ場所から見つかっており,ここでは3種のシリカクラスレートが同一環境下で形成されたことが示唆されるという貴重な場所となっています.
千葉石の結晶の外形は水晶とはまったく異なり,一見すると六角板状に見えます(図2a).しかし,詳しく調べるとこれらは等軸晶系に一般的な正八面体を基本としてそれに正六面体の面が少し現れているもので(図2b),特に正八面体の1つの面{111}面が大きく発達し,さらにその{111}面を境に双晶をなしているものが多く,その結果,六角板状に見えるのです(図2c).
図2:千葉石の結晶の外形.a 千葉石結晶の拡大写真(本間千舟氏所蔵:門馬綱一氏撮影).
b 千葉石単結晶の理想的な形態の模式図(高田雅介氏作成).c 一般的に観察される千葉石の形態の模式図(bの点線で囲まれた部分の双晶)(高田雅介氏作成).
このような性質を持つ千葉石はいつどのような環境でできたのでしょうか.メタンだけではなくエタン,プロパン,イソブタンという大きな炭化水素分子を含むことから,その生成には生物分解だけではなく熱分解作用が進行する必要があります.そのことから,通常のメタンハイドレート( I 型)の形成環境より深い場所で,やや高い温度のもとで形成されたことが示されます.
千葉石が産出したのは,房総半島南部に分布する前期中新世(約1800万年前頃)の「保田(ほた)層群」と呼ばれる堆積岩層です.千葉石は層理面と斜交する幅数cmの石英質の脈の空隙部分に成長しています.母岩の保田層群には,クモの巣状構造,皿状構造など水圧破砕によって形成された構造が見られ,付加体的な特徴を示します.堆積後に(あるいは同時進行で)超苦鉄質岩類などを含む「嶺岡オフィオライト」の固体貫入(プロトルージョン)を受けており,プレート境界近傍での形成が類推されます.
特筆すべきは,同じ露頭からシロウリガイ類,オウナガイ類,キヌタレガイ類などの化学合成生物群の化石が産出している点です.堆積当時,メタンなどに富む冷湧水が存在したことが想定され,地層の性質と合わせて考えると,逆断層が発達する沈み込み帯近傍の海溝陸側斜面の環境が推測されます.内部にメタンなどの炭化水素ガスを含む千葉石は,このような環境で形成された可能性があります.ただ,時代としては,四国海盆の拡大末期で,かつ日本海が拡大しつつある時期であり,当時のこの場所の構造的位置については議論が分かれるところでしょう.保田層群の岩相が凝灰質な砂岩・泥岩であることから,伊豆前弧の堆積物が海溝で付加したものとも考えられますが,当時の房総半島と伊豆弧の位置関係などが明確ではなく,推定の域を出ません.千葉石を含む脈があまり断層に切断されずに連続する傾向にあることから,脈の形成は地層の堆積よりもだいぶ後の時代である可能性もあります.このように千葉石形成の地質学的環境については,さらに詳細な調査が必要です.
千葉石発見のきっかけになった鉱物が発見されたのはだいぶ前の1998年です.アマチュアの化石・鉱物研究家本間千舟氏(千葉県館山市在住)が発見したその鉱物は,結晶の形は千葉石そのものだったのですが,内部は石英に変質してしまっていました(仮像).透明感のない白く濁った結晶です.しばらくは原鉱物の正体がわかりませんでしたが,2007年に別のアマチュア鉱物研究家西久保勝己氏(千葉県市川市在住)が,同じ場所から変質していない無色透明な結晶を発見し,(独)物質・材料研究機構の門馬綱一氏が中心となりその結晶を分析した結果,新鉱物であることが判明したのです.変質した千葉石仮像は単結晶で長径が最大5 mm程度のものが見られますが,千葉石は最大でも2 mm程度であり,肉眼ではなかなか見えません.当初は大きな仮像結晶が目立ったことから,千葉石に気が付くまでに時間がかかったのです.それでも,様々な段階でかかわった方々の勘や執念によって探求が継続され,ついに新鉱物の誕生に至ったと言えるでしょう.
なお,千葉石の実物標本は,現在,千葉県立中央博物館で展示中です.6月12日までは関連資料とともにトピックス展を開催し,その後は規模を縮小して常設展示に追加する予定です.この風変わりな鉱物を,ぜひご覧いただければと思います.
[千葉石記載論文]
Momma, K., Ikeda, T., Nishikubo, K., Takahashi, N., Honma, C., Takada, M., Furukawa, Y., Nagase, T. and Kudoh, Y. (2011) New silica clathrate minerals that are isostructural with natural gas hydrates. Nature Communications, 2, Article number: 196.
(原稿受付 2011年2月26日)
No.129 2011/3/15 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.129 2011/3/15 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】東日本を襲った超巨大地震に関して
【2】会員の皆様へ(事務局より)
【3】その他のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】東日本を襲った超巨大地震に関して
──────────────────────────────────
2011年3月11日に発生した日本の観測史上最大であるマグニチュード9の超巨大
地震「2011年東北地方太平洋沖地震」は,甚大な被害をもたらしました.
なかでも大津波の襲来により,多くの人命が失われたことは痛惜の思いです.
被害に遭われた方々へお見舞いを申し上げます とともに,亡くなられた方々
への哀悼の意を表します.
今回の地震は,長期間にわたって強い余震が発生する事が予想されています.
また,日本列島全域にわたって地震活動が活発化しており, 更なる災害を
警戒する必要がありますが,そうした災害が起こらない事を願っています.
地質学は,地層や岩石などに刻印された過去の様々な変動の歴史を読み取り
ますが,過去の履歴を精密に解析することによって,将来起こ りうる事変を
予測することが出来ます.実際に,今回のような超巨大地震が1000年毎位に
発生していたこと,そしてそうした超巨大地震が 迫っている可能性も最近
明らかにされ始めていましたが,残念ながら今回の事態には間に合いません
でした.
日本地質学会は,今回の超巨大地震に関する地質学的観点からの調査や,津波
堆積物などに記録された過去の超巨大地震の履歴研究などの 推進に努めると
ともに,復興をはじめとして,長期的な防災・減災対策にそれらの研究の
成果を生かせるように努力する所存です.
会長 宮下純夫
学会ホームページにはその他関連情報へのリンクを掲載しています.
http://www.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】会員の皆様へ(事務局より)
──────────────────────────────────
3月11日に発生いたしました東北地方太平洋沖地震により,学会事務局の室内
および事務機器の破損や事務局員の出勤も一部困難となっているため,執行理事会の判
断により,学会事務局の業務を一時停止させていただきます.何とぞご容赦を頂きます
よう,お願いいたします。 (2011.3.15)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■日本堆積学会2011年長崎大会の延期のお知らせ
今回の震災を受け,3月17-22日に予定されていました日本堆積学会2011年
長崎大会が延期されることになりました.ショートコース・巡検も同時に
延期もしくは中止の予定です.詳しくは,http://sediment.jp/をご覧ください.
※お知らせにつきましては、緊急と判断されるもののみ掲載いたしました.
その他の情報につきましては,次号以降にてご案内予定です.
ご了承ください.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.130 2011/3/25 geo-flash(臨時)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.130 2011/3/25 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】安否確認のお願い
【2】事務局業務再開のお知らせ
【3】関連情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】安否確認のお願い
──────────────────────────────────
日本地質学会では、現在、支部や大学などを通じて会員の安否確認に努めて
いますが、まだすべての会員の安否を確認するには至っておりません。
そこで、大変な状況とは存じますが安否確認にご協力をお願い申し上げます。
災害安否連絡フォーム: http://www.geosociety.jp/anpi.html
ご自身だけでなく、周囲の方の安否についてもご連絡いただければ幸甚です。
投稿していただいた内容は、今回の地震に関する安否確認及びそれに関連
する業務のみに使用し、日本地質学会プライバシーポリシーに従って管理
されます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】会員の皆様へ(事務局より)
──────────────────────────────────
地震の影響により学会事務局の業務を一時休止させていただいておりましたが、
3月22日(火)より、事務局業務を再開しました。
しばらくの間、交通事情や停電により業務に影響が出ることも考えられますが、
ご理解とご協力をお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】関連情報
──────────────────────────────────
学会のホームページ(トップページ)に今回の地震に関するサイトへのリンク
をまとめています。
http://www.geosociety.jp/ (随時更新しています。情報もお寄せください。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.132 2011/4/19 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.132 2011/4/19 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】解説:日本の自然放射線量
【2】東日本大震災に関する現地調査について
【3】「東日本大震災 情報マップ」で震災関連投稿情報を公開
【4】第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品が決定!
【5】2011年度「地質の日」行事のお知らせ
【6】構造地質部会書籍企画「日本の地質構造百選」候補地・写真大募集
【7】被災会員の会費減免申請について
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞情報
【11】訃報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】解説:日本の自然放射線量
──────────────────────────────────
今井 登 (産業技術総合研究所 地質情報研究部門)
われわれの身の回りにはもともと宇宙線や大地、建物、食品などに由来する
放射線があり、この値が異常であるかどうかは自然状態の放射線量と比較し
て初めて知ることができる。このような自然放射線量は場所によって大きく
異なっており、これを知るには実際にその場所に行って線量計で測定しなけ
ればならないが、これを大地のウランとトリウムとカリウムの濃度から計算
によって求める方法がある。
続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/hazard/content0058.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】東日本大震災に関する現地調査について
──────────────────────────────────
2011年3月11日の震災から1か月たち、復興の声が出始めました。一方で福島県
浜通り南部では、直下型の地震が頻発しています。地質学会としては、この復
興に資するため、会員による「日本地質学会緊急調査団」を条件付きで認めた
いと思います。
詳しくは、、、
http://www.geosociety.jp/news/n81.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】「東日本大震災 情報マップ」で震災関連投稿情報を公開 ──────────────────────────────────
東日本大震災に関して、会員の皆様から投稿していただいた報告や情報を
取りまとめて情報マップとして公開を始めました。
今回の地震による様々な地質に関する事象を記録することで、多くの人々に
地震に関する地質現象を知っていただけるよう、情報マップを充実させてい
きたいと思います。
まとまった報告でなくても構いませんので、レポートや解説付きの写真など
皆様からの投稿をお待ちしております。
■「東日本大震災 情報マップ」
http://www.geosociety.jp/hazard/content0056.html
■投稿はこちらから、、、「地質災害 情報マップ報告フォーム」
http://www.geosociety.jp/geohazard_report2.html
■東日本大震災に関する会員からの投稿情報
http://www.geosociety.jp/hazard/content0057.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品が決定! ──────────────────────────────────
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品が決定しました。最優秀賞の
「カッパドキアの地」(内藤理絵さん:東京都)を含め、18点の作品が
選ばれました。
講評と作品の紹介はこちらから、、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0009.html
5月14日(土)13:00より神奈川県立生命の星・地球博物館(小田原市)で
表彰式が行われます。
また同館にて入選作品の展示が、4月16日(土)から5月29日(日)まで
開催されています。
展示の様子
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2011年度「地質の日」行事のお知らせ
──────────────────────────────────
■日本地質学会: 本部イベント企画
日本地質学会・神奈川県生命の星・地球博物館共催で2011年度「地質の日」
行事が行われます。
◎第2回惑星地球フォトコンテスト 表彰・展示会
◎講演会「微生物は如何にして地球環境を変えてきたか? 〜石から探る
地球環境の進化史〜」 講師:山口耕生(東邦大学理学部化学科)
日時:2011年5月14日(土)13:00〜
場所:神奈川県生命の星・地球博物館 ミュージアムシアター
入場無料・参加申込不要
詳しくは、、、
http://www.geosociety.jp/name/content0075.html
■北海道支部: 2011年度「地質の日」記念展示
◎「豊平川と私たち −その生いたちと自然−」
場所:北海道大学総合博物館
日時:2011年3月8日(火)〜5月29日(日)
◎同時開催企画:豊平川の化石〜 化石が語る“札幌の海”
場所:札幌市博物館活動センター
日時:2011年5月7日(土)〜7月30日(土)
◎ミニツアー:札幌軟石ウォッチング
日時:2011年5月7日(土)10:00〜15:00(要申込)
詳しくは、、、
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】構造地質部会書籍企画「日本の地質構造百選」候補地・写真大募集
──────────────────────────────────
構造地質部会では、「日本の地質構造百選」と題した書籍を企画しております。
本書籍は写真を中心とし、手短な説明文とアクセスマップからなる、ハンド
ブック形式のものになる予定です。
つきましては、この書籍に載せるべき候補地および写真そのものを広く地質学会
員のみなさまから大募集いたします。
みなさまの提案や写真が書籍になるかもしれません!
受付はホームページより行っております。
(「日本の地質構造百選」編集委員会ホームページ)
http://struct.geosociety.jp/JSGBook2011/Top.html
また、掲示板も用意いたしました。みなさまの意見交換にご利用ください。
(「日本の地質構造百選」編集委員会掲示板)
http://jsgbook2011.1616bbs.com/bbs/
奮ってご応募お願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】被災会員の会費減免申請について
──────────────────────────────────
日本地質学会では、災害救助法適用地域で被災された会員の方々のご窮状を
ふまえ、会費については減免の措置を取らせていただいており、今回の災害
においても対象となる会員の方から、申し出があった場合には適用いたします。
詳細: http://www.geosociety.jp/outline/content0093.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
──────────────────────────────────
■2011年関東支部総会および地質技術伝承講習会
【地質技術伝承講習会】
日時: 2011年4月24日(日)14:00〜16:00
場所: 大田区産業プラザ(大田区蒲田1-20-20)特別会議室
講師: 三木 茂氏(基礎地盤コンサルタンツ株式会社 保全・防災センター)
テーマ: トンネル事前調査の課題と物理探査
共催:(社)全国地質調査業協会連合会 関東地質調査業協会
参加費: 無料、どなたでも参加できます。
【支部総会】
日時: 2011年4月24日(日)16:00〜16:30
場所: 上記講習会と同会場
申込方法・総会委任状等、詳しくは、
http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第52回科学技術映像祭 入選作品発表会
日時: 2011年4月21日(木)・22日(金)(表彰式:4/22 13:00〜15:00)
場所: 科学技術館サイエンスホール(千代田区北の丸公園2-1)
問い合わせ先: 科学技術映像祭事務局 03-3212-8487
http://ppd.jsf.or.jp/filmfest/52/pdf/52jyouei.pdf
■日本学術会議主催学術フォーラム「東日本大震災からの復興に向けて」
日時:2011年4月26日(火)13:20〜17:20
会場:日本学術会議 講堂
趣旨:東日本大震災の被災地は、極めて広域に及んでおり、震災復興の考
え方と道筋は、国土・地域の在り方を根底から問い直すものとなる。
日本学術会議は、3月25日の第一次緊急提言に始まり、この間、原子
力発電所、放射能問題、被災者救援、復興支援、震災廃棄物対策など、
様ざまの提言を発してきた。
このフォーラムは、このうち、震災復興に焦点を絞り、日本における
震災復興の経緯をレヴューし、東日本大震災の被災状況を踏まえて、
復興に向けた理念と主軸について、論議を深めることを目的とする。
参加費:無料(事前申込み)
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf/h-110426.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■2011年度「信州フィールド科学賞」募集(6/30)
■藤原セミナー開催希望者募集(学会選考)(6/30 学会締切)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】訃報
──────────────────────────────────
■小高民夫名誉会員 ご逝去
────────────────────────────
日本地質学会名誉会員 小高民夫氏(東北大学名誉教授)が、
平成23年4月12日(火)にご逝去されました(享年86歳)。
これまでの故人の功績を讃えるとともに、謹んでご冥福を
お祈り申し上げます。
なお、ご葬儀の日程は未定です。日程が分かりましたら、
改めてご連絡いたします。
────────────────────────────
■玉木賢策会員 ご逝去
────────────────────────────
日本地質学会会員 玉木賢策氏(東京大学教授)が、
平成23年4月6日(水)にご逝去されました(享年61歳)。
ニューヨーク出張中、突発的なご病気のため、入院先の病院
におきましてお亡くなりになられたとのことです。
これまでの故人の功績を讃えるとともに、謹んでご冥福を
お祈り申し上げます。告別式の日程と会場は次の通りです。
日時:平成23年4月25日(月)14:00〜
(12:30より受付開始、開場は13:30)
場所:神田一ツ橋学士会館
〒101-8459
東京都千代田区神田錦町3丁目28番地
TEL 03-3292-5936
http://www.gakushikaikan.co.jp/
喪主:玉木くに様(ご令室)
<お問い合わせ先>
東京大学大学院工学系研究科
システム創成学専攻 山冨二郎
エネルギー・資源フロンティアセンター 佐藤光三
TEL: 03-5841-0243
E-mail: hatanaka@frcer.t.u-tokyo.ac.jp
会員の皆様に、謹んで御連絡申し上げます。
会長 宮下純夫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
地質フォト:目次-2010
地質フォト:目次(過去のフォトコンテスト入選作品)
最新版はこちら
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回
第15回惑星地球フォトコンテスト
【総評】 今年は審査員全員がこれだという作品がなかったために,残念ながら最優秀賞は該当なしとしました.スマホの性能が向上したために,気軽にほどほどの地質写真が撮れるようになったのは良いことですが,優れた地質写真と残そうとする意気込みを感じさせる作品が少なかったように思います.その中で最終選考では撮影者の意気込みを感じさせる作品が残りました. 今年の応募総数は208点,昨年よりも151点の減少となりました.減少した原因は,インスタグラムなど自分自身で画像を発信できる環境が増えたことも一つの要因かも知れません.しかし,日本地質学会のような伝統ある学会で専門家によって評価された作品の存在意義は重要だと考えます.今後は若い審査員を増やすなどして,新しい視点からも良い地質写真を選んでいきますので,よろしくお願いします.(審査委員長 白尾元理)
入選作品
佳作作品
第15回惑星地球フォトコンテスト:優秀賞
道東太平洋岸の特異な地質と固有のナガコンブ
写真:平野直人
玄武岩が海底堆積物(後期白亜系の砂泥互層)を覆っています...(講評や大きな画像はこちら)
第15回惑星地球フォトコンテスト:優秀賞
龍うねる 写真:門脇正晃
島根半島・宍道湖中海ジオパークに属する島根半島の鹿島町手結にあるスランプ褶曲です...(講評や大きな画像はこちら)
第15回惑星地球フォトコンテスト:ジオパーク賞
切通し 写真:島村哲也
8月20日(日)晴れ.夜行船で伊豆大島に来島...(講評や大きな画像はこちら)
第15回惑星地球フォトコンテスト:日本地質学会会長賞
空撮で捉えた付加体の覆瓦構造 写真:木村克己
空撮は大峰山脈北部の大普賢岳(写真中央)から山上ヶ岳(写真右)にいたる険しい大峯奥駈道を捉えています...(講評や大きな画像はこちら)
第15回惑星地球フォトコンテスト:ジオ鉄賞
夜明けの大山 写真:藤森俊多
澄み切った秋の朝,空に大山のシルエットが美しく浮かび上がりました...(講評や大きな画像はこちら)
第15回惑星地球フォトコンテスト:スマホ賞
離島の夏 写真:澤 健二
島根県の隠岐諸島,中ノ島の海士町にある明屋海岸.隠岐諸島はユネスコ世界ジオパークの認定地のひとつ...(講評や大きな画像はこちら)
第15回惑星地球フォトコンテスト:大学生・大学院生賞
草千里 写真:古田大樹
阿蘇・草千里ヶ浜に訪れた際に撮影しました....(講評や大きな画像はこちら)
画面TOPに戻る
第15回惑星地球フォトコンテスト:入選
大地の目覚め 写真:村上 真
この写真は岩手県八幡平市にある「焼走り溶岩流」で撮影しました...(講評や大きな画像はこちら)
第15回惑星地球フォトコンテスト:入選
未来に残したい惑星地球の情景 写真:水口和史
鬼の洗濯岩で有名な宮崎市の青島周辺から日南海岸にかけては浸食で変わった表情をした海岸が見られます...(講評や大きな画像はこちら)
第15回惑星地球フォトコンテスト:入選
南中国の褶曲 写真:余 金霏
雄大な断層と褶曲があり,それは雲南省の省都昆明市の東川区に位置し...(講評や大きな画像はこちら)
第15回惑星地球フォトコンテスト:入選(中学・高校生部門)
褶曲 写真:福本朝陽
地元の方にもあまり知られていないという,御座の褶曲....(講評や大きな画像はこちら)
画面TOPに戻る
佳作(注)(計8点・順不同)
* タイトル等をクリックすると各作品画像がご覧いただけます(準備中).
宮田敏幸(兵庫県) 日本海に一人佇む
福田倫太郎(新潟県) 縞のトンネル
大森翔太郎(福岡県) タービダイトとフルートキャスト
朝永武志(長崎県) 迫り出す地層
指田丈二(茨城県) 神様のお遊び
三浦大輝(新潟県) 分水嶺
法橋尚宏(兵庫県) 噴火の再現ドラマのような鬼岳の野焼き
永岡正行(島根県) 宍道湖畔を駆ける最後の国鉄型特急
(注)「佳作」惜しくも入選には至らなかったものの,より多くの優れたジオフォト作品を発掘するために「佳作」を設け,作品画像をWEB上で紹介します.またニュース誌や展示会の際に作品タイトルと撮影者氏名の一覧のみ表示します(表彰および作品の展示は行いません).
画面TOPに戻る
第14回惑星地球フォトコンテスト
【総評】今年の応募総数は359点,3年間続いたコロナ禍のため,応募はほとんどが国内で撮影された作品となりました.また今回は3年ぶりのリアルでの審査会となりました.全体的にレベルが上がり,また適切な解説付の作品が増えいます.解説によってジオフォトの作品がより生きてきます.ドローンで撮影した作品も増えてきましたが,世の中にはドローンの映像が溢れています.見る側の目も肥えてきたので,応募作品は気合いを入れて撮影することが望まれます.1000万画素以上のカメラ付スマホの応募も増えてきました.気軽に撮影できるのがスマホの良い点ですが,構図や露出等に細心の注意を払いながら撮影してほしいと思います. ジオフォトはまだ未開拓な要素が多く,大きな可能性を秘めているはずです.来年もより地質や地形に愛を感じられるレベルの高い作品の多数の応募を期待します.
(審査委員長 白尾元理)
入選作品
佳作作品
第14回惑星地球フォトコンテスト:最優秀賞
古代の双六 写真:朝永武志(長崎県)
この作品はドローンを使って柱状節理を撮影したものです....(講評や大きな画像はこちら)
第14回惑星地球フォトコンテスト:優秀賞
大西洋と砂漠 写真:近藤 洋(兵庫県)
ナミブ砂漠はナミビア西海岸に広がる大砂漠で,大きな砂丘は高さ300mもあります....(講評や大きな画像はこちら)
第14回惑星地球フォトコンテスト:優秀賞
Lingshed Village 写真:佐藤竜治(静岡県)
撮影地はインド最北部でパキスタン・中国との国境間近,ヒマラヤ山系のインダス川源流に近い秘境です....(講評や大きな画像はこちら)
第14回惑星地球フォトコンテスト:ジオパーク賞
個性豊かな,まぁ〜るい畑写真:高場智博(長崎県)
五島列島ジオパークは昨年1月に認定されたばかりのジオパークで,このジオパークを撮影した多くの作品が集まりました....(講評や大きな画像はこちら)
第14回惑星地球フォトコンテスト:日本地質学会会長賞
屋根瓦のような重なり
写真:大坪 誠(茨城県)
この作品は10cm足らずの地層間の変形構造を撮影したものです....(講評や大きな画像はこちら)
第14回惑星地球フォトコンテスト:ジオ鉄賞
日南海岸の洗濯岩 写真:礒部忠義(福岡県)
宮崎県南部を走るJR日南線(内海−小内海間)の車窓には.......(講評や大きな画像はこちら)
第14回惑星地球フォトコンテスト:スマホ賞
スナヘビの大群 写真:高場智博(長崎県)
写真とタイトルを見て一瞬,何だろうと思わせるのがこの作品の魅力です.(講評や大きな画像はこちら)
第14回惑星地球フォトコンテスト:大学生・大学院生賞
離島の断崖 写真:福永拓真(神奈川県)
壱岐島は博多から高速船で1時間余り,そこから辰ノ島へは遊覧船で気軽に行ける場所のようです....(講評や大きな画像はこちら)
画面TOPに戻る
第14回惑星地球フォトコンテスト:入選
太古の覗き穴 写真:佐藤 孝(新潟県)
評者は甌穴(ポットホール)が川の流水によってできるものだと思っていました...(講評や大きな画像はこちら)
第14回惑星地球フォトコンテスト:入選
刻々と 写真:新垣隆吾(沖縄県)
新垣さんは2年前の当コンテストで『地底の世界』(ルーマニア)で最優秀賞を授賞された方です....(講評や大きな画像はこちら)
第14回惑星地球フォトコンテスト:入選
一期一会の姿 写真:藤倉聖也(群馬県)
新島の東海岸にある白ママ断崖を望遠レンズで南に向けて撮影した作品です...(講評や大きな画像はこちら)
第14回惑星地球フォトコンテスト:入選(中学・高校生部門)
真夏の断崖 写真:新宅草太(熊本県)
ジオパーク下甑島の鹿島断崖は付近から竜脚類の歯が発見されて有名になっています...(講評や大きな画像はこちら)
画面TOPに戻る
佳作(注)(計11点・順不同)
* タイトル等をクリックすると各作品画像がご覧いただけます.
朝永武志(長崎県)断崖と白亜の灯台
横江憲一(北海道)地球の吐息
宮田敏幸(兵庫県)湖底の朝
市谷和也(埼玉県)吸い込まれそう
遠藤悠一(茨城県)迫り上る大地
後藤文義(神奈川県)湘南好日
石原孝陽(神奈川県)遼遠の時を経て
福村成哉(和歌山県)波にも負けず
坂内愛莉(長崎県)朱、一点
加藤慶彦(秋田県)厳冬の岩脈
荒木英里(神奈川県)連なる漢字の所以
第13回惑星地球フォトコンテスト
【第13回コンテスト総評】
今年もコロナ禍が続き,6人の審査員によるリモートでの審査会となりました.審査員の着眼点はそれぞれで,候補作が30点以下に絞られるとそれからは喧々囂々.4時間もかかりましたが作品を楽しみながらの審査会となりました.
2年間のコロナ禍のため,応募のほとんどは国内で撮影された作品となりました.いままで見逃していた身近な地質や地形を見直す良い機会になっています.しかし一方では,パキスタン最北部のカラコルム山脈で撮影された作品があるのには驚きました.
この10年でデジタルカメラと画像の処理技術の進歩は驚くばかりですが,類型的な作品が多く,審査員一同がびっくりするようなアイデアの作品は僅かです.顕微鏡やマクロレンズを用いた作品や組写真による対象に肉迫するような作品など,まだまだジオフォトには多くの可能性があるはずです.来年には冒険的な表現の作品にも期待します.
(審査委員長 白尾元理)
入選作品
佳作作品
第13回惑星地球フォトコンテスト:最優秀賞
宝永火口岩脈群 写真:露木孝範(静岡県)
富士山の宝永第1火口岩脈群は五合目から撮影されることが多いのですが,作者はぐっと近づいた宝永山山頂からの撮影なので迫力があります...(講評や大きな画像はこちら)
第13回惑星地球フォトコンテスト:優秀賞
3つのStream 写真:加藤順子(東京都)
評者はこの作品で初めて関西には3つの川が合流する場所があることを知りました...(講評や大きな画像はこちら)
第13回惑星地球フォトコンテスト:優秀賞
恐怖の石段写真:高木 嶺(東京都)
撮影地はパキスタン最北部の7000m峰が連なるカラコルム山脈です...(講評や大きな画像はこちら)
第13回惑星地球フォトコンテスト:ジオパーク賞
大海に注ぐ湧水 写真:大場建夫(秋田県)
パターンが美しい作品です...(講評や大きな画像はこちら)
第13回惑星地球フォトコンテスト:日本地質学会会長賞
ミニチュアテラス
写真:金子敦志(福島県)
この作品は山形県の広河原温泉の小規模な石灰華テラスを撮影したものです...(講評や大きな画像はこちら)
第13回惑星地球フォトコンテスト:ジオ鉄賞
たまゆらの中の洗濯岩 写真:落合文登(宮崎県)
日豊本線(宮崎〜南宮崎間)で有名な鉄道撮影スポットとして知られる大淀川橋梁....(講評や大きな画像はこちら)
第13回惑星地球フォトコンテスト:スマホ賞
島山島のシマシマ 写真:安永 雅(長崎県)
五島列島は2022年1月,日本ジオパークに認定された地域で,そのためか今回は五島列島から多くの作品が寄せられました.(講評や大きな画像はこちら)
第13回惑星地球フォトコンテスト:入選
4億年の記憶 写真:中川達郎(愛媛県)
四国西予ジオパークは愛媛県にある東西に細長いジオパークで,その海岸部に位置するのが須崎海岸です...(講評や大きな画像はこちら)
画面TOPに戻る
第13回惑星地球フォトコンテスト:入選
Inside the Volcano 写真:金井雄亮(東京都)
スリーヌカギガルはアイスランドの首都レイキャビクの南15kmにあるスコリア丘で,山頂からマグマが退いた火山の深部を覗ける人気の観光スポットになっています...(講評や大きな画像はこちら)
第13回惑星地球フォトコンテスト:入選
大荒れ橋杭岩 写真:福村成哉(和歌山県)
橋杭岩は毎年応募作品があります...(講評や大きな画像はこちら)
第13回惑星地球フォトコンテスト:入選
ぽっかり 写真:笠井 忠(奈良県)
蓬莱岩は海岸に露出した岩場で,観光名所になっています...(講評や大きな画像はこちら)
第13回惑星地球フォトコンテスト:入選(中学・高校生部門)
広がる世界 写真:谷川七海(長崎県)
福江島にはいくつかの単成火山群からなり,,,(講評や大きな画像はこちら)
画面TOPに戻る
佳作(注)(計19点・順不同)
* タイトル等をクリックすると各作品画像がご覧いただけます.
DHAKAL BISHAL(大分県) 坊主の入浴
福永拓真(茨城県) 銅色の湖
安永 雅(長崎県) 山に包まれる
中吉剛彦(宮崎県) 鬼の洗濯
片岡雅子(兵庫県) 後退する氷河
小川智教(岩手県) 険しき山
糸賀一典(千葉県) 魅惑の川廻し洞窟
紱本陽士(長崎県) 崖の前の赤灯台
河野 潔(埼玉県) サメの口の中
鈴木文代(和歌山県) 筏下り
草田栄久(千葉県) 阿蘇の大地と春の天の川
明野敏行(兵庫県) 日本三奇石 生石神社
小澤 宏(神奈川県) 褶曲の丘
原口孝和(千葉県) ガンガラ岩と五能線列車
木下 滋(和歌山県) 岩模様
峯田翔平(山口県) 阿蘇カルデラ
井上克幸(長崎県) 石灰藻球三千三百万年の旅
川邉竜也(愛知県) 逆層スラブ、穂高岳の溶結凝灰岩
白井里奈(愛知県) ブロモ山噴火口
(注)「佳作」惜しくも入選には至らなかったものの,より多くの優れたジオフォト作品を発掘するために「佳作」を設け,作品画像をWEB上で紹介します.またニュース誌や展示会の際に作品タイトルと撮影者氏名の一覧のみ表示します(表彰および作品の展示は行いません).
第12回惑星地球フォトコンテスト
【総評】 今年の応募点数は435点,昨年よりも61点増えました.この1年はコロナ禍のため,応募作品はほとんどが国内で撮影されたものとなり,入選は海外が2点,国内が10点となりました. 近年,さまざまなフォトコンテストの受賞作がウェブサイトで見られるようになってきました.日本地質学会の惑星地球フォトコンテストでも第1回からの入選作品が見られ,腕自慢の人達が本コンテストの趣旨にあった作品を応募するようになったので年々レベルが高くなってきました.その一方で類型的な作品が多くなる傾向があります.選者たちを驚かせるような奇抜な発想の作品も期待したいものです. コロナ禍で海外はもちろんのこと,日本国内も自由に移動できないうっとうしい日々が続いています.入選作品の解説をたよりにグーグルアースやウェブサイトで検索すると,その作品の背景にある地形,地質,歴史,人々の暮らしなどを巡ることができます.入選作品をゆっくりとお楽しみください. (審査委員長 白尾元理)
入選作品
佳作作品
第12回惑星地球フォトコンテスト:最優秀賞
地底の世界 写真:新垣隆吾(沖縄県)
この作品を一瞬見たときは何が写っているだろうと迷います...(講評や大きな画像はこちら)
第12回惑星地球フォトコンテスト:優秀賞
大地の鼓動 写真:横江憲一(北海道)
日本最大のカルデラと言われる屈斜路・摩周カルデラの中央部にあるアトサヌプリ(硫黄山)は溶岩ドームで周辺には噴気地帯が発達しています.....(講評や大きな画像はこちら)
第12回惑星地球フォトコンテスト:優秀賞
コジラの背 写真:中吉剛彦(東京都)
房総半島の南端,南房総市の屏風岩は撮影スポットして有名です...(講評や大きな画像はこちら)
第12回惑星地球フォトコンテスト:ジオパーク賞
不思議な空間 写真:長谷 洋(和歌山県)
浦神半島は「那智の滝」や「勝浦温泉」が有名な和歌山県那智勝浦町にある長さ3㎞程の半島です.(講評や大きな画像はこちら)
第12回惑星地球フォトコンテスト:日本地質学会会長賞
上五島で新たに見出された海底地滑り構造
写真:川原和博(長崎県)
巨大な採石場を撮影した作品で,その大きさは右下のパワーショベルからよくわかります.(講評や大きな画像はこちら)
第12回惑星地球フォトコンテスト:ジオ鉄賞
古の海洋堆積物から見上げて 写真:藤岡比呂志(岐阜県)
岐阜県の美濃太田駅(美濃加茂市)と北濃駅(郡上市)を72.1kmで結ぶ長良川鉄道.美濃帯のダイナミックな付加体構造をほぼ南北に縦断しながら走ります....(講評や大きな画像はこちら)
第12回惑星地球フォトコンテスト:スマホ賞
断層を塞ぐ人工の防風堤 写真:岩田晃一(長崎県)
五島列島の土台である大きな5つの島は,大規模な正断層で分かれています.(講評や大きな画像はこちら)
第12回惑星地球フォトコンテスト:入選(中学・高校生部門)
奇跡の小岩 写真:石谷樹莉(長崎県)
五島列島福江島で最も有名な観光スポットである大瀬崎灯台での作品です....(講評や大きな画像はこちら)
画面TOPに戻る
第12回惑星地球フォトコンテスト:入選
カルスト台地 写真:百崎礼治(福岡県)
福岡県の平尾台は山口県の秋吉台,四国カルストと並んで日本を代表するカルスト台地です.(講評や大きな画像はこちら)
第12回惑星地球フォトコンテスト:入選
catastrophe 写真:峯田翔平(広島県)
撮影地点の「礁の鼻」は地元では有名な朝日・夕日スポットのようです.(講評や大きな画像はこちら)
第12回惑星地球フォトコンテスト:入選
地の造形 写真:佐藤悠大(福岡県)
「くぐり岩」はいくつもの海食洞に削られた存在感のある岩です.、、、(講評や大きな画像はこちら)
第12回惑星地球フォトコンテスト:入選
柱状節理 写真:本田 誠(神奈川県)
レイニスフィヤラはアイスランド南端近くにあり,カトラユネスコジオパークのジオサイトのひとつです..(講評や大きな画像はこちら)
画面TOPに戻る
佳作(注)(計14点・順不同)
* タイトル等をクリックすると各作品画像がご覧いただけます.
「せめぎ合い」登坂直紀(北海道)
「斜里岳従えて」糸賀一典(千葉県)
「貫通甌穴ごしにアイコンタクト(長瀞)」本間岳史(埼玉県)
「大量の枕」金子敦志(福島県)
「秘境の先の聖地」薄葉友貴(東京都)
「富士噴火の堆積地層」齋藤敏雄(神奈川県)
「そそり立つ立岩へ」笠井 忠(奈良県)
「太古の記憶」 横江憲一(北海道)
「和深のタービダイト」木下 滋(和歌山県)
「柱状節理」本田 誠(神奈川県)
「大陸の裂け目」林 正彦(兵庫県)
「タイムトンネル」瀧しま修じ(埼玉県)
「龍鱗郷の造形美」来栖旬男(山口県)
「ヴァトナヨークトル氷河」加藤 歩(神奈川県)
(注)「佳作」惜しくも入選には至らなかったものの,より多くの優れたジオフォト作品を発掘するために「佳作」を設け,作品画像をWEB上で紹介します.またニュース誌や展示会の際に作品タイトルと撮影者氏名の一覧のみ表示します(表彰および作品の展示は行いません).
画面TOPに戻る
第11回惑星地球フォトコンテスト
【総評】今年の応募点数は374点で,昨年よりも26点増えました.昨年の入選は12点のうち6点が夜の作品で,さらに増えたら星景写真コンテストになると心配しましたが,今年は夜の写真の入選は1点のみで本来の姿に戻った形です. 今年の入選作の特徴は,単なる風景写真の延長ではなく,地質をよく理解して撮影された力作が増えたことです.また作者の解説文も充実したものが多く,作品と合わせて読むと地質への理解が深まります.本コンテストは今年で11回目を迎えますが,ようやく普通の風景写真コンテストとは異なる,本コンテストの趣旨が深く理解されつつあることを嬉しく思います. 最優秀賞の「鷹島」,優秀賞の「橋杭岩」は地質をよく理解された上で写真の技術レベルも高く,国内の身近な場所にも素晴らしい地質があることを私たちに教えてくれます.来年以降の応募者にとっても良い指針になるでしょう. (審査委員長 白尾元理)
入選作品
佳作作品
第11回惑星地球フォトコンテスト:最優秀賞
鷹島の奇岩 写真:佐藤悠大(福岡県)
鷹島は第三紀砂岩層を基礎としその上に玄武岩の溶岩台地が載っている..(講評や大きな画像はこちら)
第11回惑星地球フォトコンテスト:優秀賞
Cosmic Blue 写真:根岸桂子(富山県)
初めて橋杭岩に来て,太古の昔より侵食されてきた岩柱がそそり立つ光景は迫力がありました....(講評や大きな画像はこちら)
第11回惑星地球フォトコンテスト:優秀賞
褶 曲 写真:西出 琢(千葉県)
ドロミテの山々をトレッキング.山全体に褶曲の痕跡があり驚きました. (講評や大きな画像はこちら)
第11回惑星地球フォトコンテスト:ジオパーク賞
巨人のげんこつ 写真:長谷 洋(和歌山県)
白浜町南紀熊野ジオパークエリア内の海食アーチの片側だけを撮り,天に伸びる岩をイメージしました.(講評や大きな画像はこちら)
第11回惑星地球フォトコンテスト:日本地質学会会長賞
迷子石 写真:川又基人(東京都)
日本の南極観測基地である昭和基地から約80 km離れたパッダ島で撮影した一枚(講評や大きな画像はこちら)
第11回惑星地球フォトコンテスト:ジオ鉄賞
滝上を走る列車 写真:細谷正夫(茨城県)
新第三紀の地層を削る龍門の滝の上を走るJR烏山線の列車 ...(講評や大きな画像はこちら)
第11回惑星地球フォトコンテスト:スマホ賞
風と波の合作 写真:加藤聡一郎(愛知県)
台湾北部の野柳公園の風化によってできた奇岩を小山の上から撮影しました(講評や大きな画像はこちら)
第11回惑星地球フォトコンテスト:入選
混成の美 写真:辻森 樹(宮城県)
露カレリア共和国の見事なミグマタイト(混成岩)の露頭写真です...(講評や大きな画像はこちら)
画面TOPに戻る
第11回惑星地球フォトコンテスト:入選
活火山のある暮らし 写真:迫 勇(鹿児島県)
2019年11月12日23時07分,南岳山頂火口噴火により赤く染まる桜島です(講評や大きな画像はこちら)
第11回惑星地球フォトコンテスト:入選
Chocolate Box 写真:長谷川裕二(長崎県)
「九十九島」は長崎県北西部,北松浦半島の西岸に散在する208の島からなる小島群です(講評や大きな画像はこちら)
第11回惑星地球フォトコンテスト:入選(中学・高校生部門)
幸(さち)を育む海と大地と,そして空 写真:奥野由寿(長崎県)
長崎県の五島市岐宿にある城岳展望所から望む溶岩台地は、、、(講評や大きな画像はこちら)
第11回惑星地球フォトコンテスト:入選(中学・高校生部門)
ゴジラの爪 写真:田邊はるか(大阪府)
室戸岬の灯台です.室戸の大地の大部分は氷河期時代の終わりに太平洋の深海で堆積した層でできています.(講評や大きな画像はこちら)
画面TOPに戻る
佳作(注)(計13点・順不同)
* タイトル等をクリックすると各作品画像がご覧いただけます.
「ウェブロック」 原澤 宏 (埼玉県)
「芥屋の柱状節理」 小松原純子 (茨城県)
「白いコウモリ」 島村直幸 (福岡県)
「人々の営みを支える、息づく大地」 八田章光 (高知県)
「滝雲」 三浦光 (大分県)
「湖底出現」 都筑和雄 (愛知県)
「巨大エイリアン」 長谷 洋(和歌山県)
「波の舞」 伊藤修二 (茨城県)
「竜串海岸」 加藤昭七 (奈良県)
「御輿来海岸の砂紋」 松浦 寛 (福岡県)
「断崖絶壁の絶景」 藤田文子 (滋賀県)
「断崖絶壁」 野波和音 (東京都)
「異国情緒」 永井秀和 (千葉県)
画面TOPに戻る
2019年(第10回)
2019年上野グリンサロンでの展
示の様子(2019年5月)
【総評】このコンテストは今年で10年目を迎えました.今年の応募点数は338点,うち一般310点,中・高校生28点,ジオ鉄9点,スマホ41点でした.応募点数は昨年の590点よりも減少して内容低下が心配でしたが,実際には数多く力作が寄せられており,審査会では応募作品を楽しみながら選出することができました. 今年の入選作の特徴は,12点のうち6点が夜の作品だったことです.10数年前までは夜の撮影では10分以上の露出時間が必要でしたが,最近では数十秒の露出時間で済み,撮影結果を見てから撮り直しもできるようになりました.とはいうものの暗い中での構図取りやカメラ操作,現地までのアクセスなどは困難を伴うものです.それにもかかわらず,夜のジオをテーマにしたレベルの高い作品がこれだけ集まったことを嬉しく思います.(総評:審査委員長 白尾元理)
入選作品
佳作作品
第10回惑星地球フォトコンテスト:最優秀賞
月下の大噴煙 写真:横江憲一(北海道)
2018年11月17日は,オンネトー国設野営場から雌阿寒岳を目指して登山しました..(講評や大きな画像はこちら)
第10回惑星地球フォトコンテスト:優秀賞
月明りのメテオラの谷 写真:川口雅也(神奈川県)
ギリシャのテッサリア平原が尽き,ピンドス山脈が始まる境にカルスト台地が浸食をうけた「メテオラ」がある...(講評や大きな画像はこちら)
第10回惑星地球フォトコンテスト:優秀賞
枕と星屑と 写真:森田康平(東京都)
小笠原父島.一度も陸続きになっていない海洋島です.…(講評や大きな画像はこちら)
第10回惑星地球フォトコンテスト:ジオパーク賞
新緑の六方の滝 写真:齋藤敏雄(神奈川県)
湯河原の新崎川の上流,沢沿いに登っていくと紫音の滝が現れます.(講評や大きな画像はこちら)
第10回惑星地球フォトコンテスト:日本地質学会会長賞
ルービックキューブ 写真:島村哲也(茨城県)
四角い形状とモザイク状の割れ目が面白くてシャッターを切りました(講評や大きな画像はこちら)
第10回惑星地球フォトコンテスト:ジオ鉄賞
川底を抜けて 写真:桑田憲吾(東京都)
沖積平野の上に細長く伸びる地形とその下を潜る短いトンネル,そしてそこには「大沙川」の文字...(講評や大きな画像はこちら)
第10回惑星地球フォトコンテスト:スマホ賞
大地のグラデーション 写真:加古原恵(東京都)
砂漠を抜けた先に広がるのは,鮮やかな絶景.自然の造形美に目を奪われます.(講評や大きな画像はこちら)
第10回惑星地球フォトコンテスト:入選
キラウエア火山の溶岩湖 写真:田中信彦(東京都)
キラウエア火山山頂の火口では,2018年4月末〜5月初に溶岩水位が上昇し,ジャガーミュージアム前の展望台から溶岩湖表面が観察できました...(講評や大きな画像はこちら)
画面TOPに戻る
第10回惑星地球フォトコンテスト:入選
雷光のヴィーナス 写真:白山健悦(青森県)
北海道胆振東部地震発生の7時間前の2018.9.5,午後8時撮影です.(講評や大きな画像はこちら)
第10回惑星地球フォトコンテスト:入選
風雅 写真:佐藤悠大(長崎県)
海岸には玄武岩の柱状節理が広がっていました(講評や大きな画像はこちら)
第10回惑星地球フォトコンテスト:入選
巨岩砲 写真:長谷 洋(和歌山県)
南紀熊野ジオパーク,エリア内の奇岩です.(講評や大きな画像はこちら)
第10回惑星地球フォトコンテスト:入選(中学・高校生部門)
地球を削る 写真:荒岡柊二郎(東京都)
東京都西多摩郡奥多摩町にある海沢三滝の一つ「ねじれの滝」を撮影しました.(講評や大きな画像はこちら)
画面TOPに戻る
佳作(注)(計4点・順不同)
* タイトル等をクリックすると各作品画像がご覧いただけます.
「大陸分裂の始まりか−ビクトリアの滝」−横山俊治(東京都)
「デビルズタワーに昇る夏の大三角」川口雅也(神奈川県)
「屏風岩の夕景」武藤達郎(千葉県)
「歴史(とき)の彫刻」佐藤悠大(福岡県)
(注)「佳作」惜しくも入選には至らなかったものの,より多くの優れたジオフォト作品を発掘するために「佳作」を設け,作品画像をWEB上で紹介します.またニュース誌や展示会の際に作品タイトルと撮影者氏名の一覧のみ表示します(表彰および作品の展示は行いません).
2018年(第9回)
【総評】 このコンテストは今年で9年目を迎え,昨年とほぼ同数の590点(内ジオ鉄20点,スマホ92点)の応募がありました.応募数がこのように安定してきたのは,地学愛好者だけではなく,広く一般の写真愛好者にもジオフォトの分野が認められてきたからでしょう.一般の写真愛好者からの応募も本コンテストの趣旨をよく理解された力作が多く集まり,今年は特に地元の人の頑張りが目立ちました. 今年の入選や佳作作品では,適度なHDRなどの画像補正をおこなって自然に見える作品が増えました.またスマホ作品のクォリティの高さも目立ちます.スマホはコンパクトデジカメと性能では見劣りがせず,卓越した機動性,位置や撮影時刻などの記録性ではもっともすぐれたカメラとなっています.スマホでは普段は気軽に,そして時には気合いを入れての作品づくりを目指していただきたいと思います.(総評:審査委員長 白尾元理)
入選作品
佳作作品
第9回惑星地球フォトコンテスト:最優秀賞
神の彫刻 写真:白山健悦(青森県)
巨岩・奇岩が連なる景観の仏ヶ浦,上部にそそり立っている巨岩をアクセントに撮影しました.(講評や大きな画像はこちら)
第9回惑星地球フォトコンテスト:日本地質学会創立125周年記念賞
月に浮かぶ大瀬崎南火道 写真:露木孝範(静岡県)
週末はダイバーで賑わう大瀬崎.外海のダイビングポイントから少し南に歩いた場所に伊豆半島ジオパークを構成する地形があると知り,月夜に撮影に向かいました.(講評や大きな画像はこちら)
第9回惑星地球フォトコンテスト:優秀賞
混 濁 写真:小山悠太(長野県)
三波川帯の泥質起源の結晶片岩.微褶曲がきれいだったのでそこに注目しました.…(講評や大きな画像はこちら)
第9回惑星地球フォトコンテスト:優秀賞
異様な光景 写真:長谷 洋(和歌山県)
南紀熊野ジオパーク,ジオパークサイトの滝の拝のポットホールです.…(講評や大きな画像はこちら)
第9回惑星地球フォトコンテスト:ジオパーク賞
新燃岳 写真:山田宏作(鹿児島県)
6年ぶりに噴火した新燃岳が,高千穂峰を背景に火口から噴気を上げている様子を撮影してみました.(講評や大きな画像はこちら)
第9回惑星地球フォトコンテスト:日本地質学会会長賞
ワディの河床 写真:佐藤由理(大分県)
スーダン国東部のカッサラ州を流れるワディ,ガシ川は,隣国エリトリアを源流とし同州内で消滅します.(講評や大きな画像はこちら)
第9回惑星地球フォトコンテスト:ジオ鉄賞
悠久の想い 写真:門脇正晃(千葉県)
秩父長瀞は岩畳の景観で知られており,荒川沿いに河原を歩くと結晶片岩が広く露出しています.(講評や大きな画像はこちら)
第9回惑星地球フォトコンテスト:スマホ賞
流 写真:石田英俊(高知県)
水流により時流が削り出され風流と為す.私たちの生活する惑星地球は,悠久とも思える時の流れを地質に重ね上げ現(うつつ)の姿を現しています.(講評や大きな画像はこちら)
第9回惑星地球フォトコンテスト:入選
尖塔エギュー・ドゥ・ミディ 写真:高木 嶺(東京都)
この写真はフランスシャモニーの観光地,エギュー・ドゥ・ミディです.氷河が削った2つのU字谷の間が鋭く尖っている様子を超広角レンズで撮影しました.(講評や大きな画像はこちら)
画面TOPに戻る
第9回惑星地球フォトコンテスト:入選
昔 何もなかった頃 写真:矢野根滋明(石川県)
軽石凝灰岩が波に浸食された海岸です.(講評や大きな画像はこちら)
第9回惑星地球フォトコンテスト:入選
風吹く夜に 写真:西 眞史(東京都)
2017年8月に,ベトナム北部ニンビンにて撮影しました.数日間滞在していたロッジ裏にあった岩山を撮影しました.(講評や大きな画像はこちら)
第9回惑星地球フォトコンテスト:入選
日が暮れる 写真:高橋広太郎(福岡県)
夏の終わりが近づくころの夕陽を,平尾台の特徴的な岩と共に撮影しました.(講評や大きな画像はこちら)
第9回惑星地球フォトコンテスト:入選(中学・高校生部門)
切り立った断崖 写真:越智優心(神奈川県)
日本三名瀑のひとつに数えられる華厳滝は,男体山から流れ出した溶岩などが川をせき止めて中禅寺湖を作り,あふれた水が溶岩壁から流れ落ちてできたと言われています.(講評や大きな画像はこちら)
画面TOPに戻る
佳作(注)(計12点・順不同)
* タイトル等をクリックすると各作品画像がご覧いただけます.
「星空に吠える」堀内 勇(和歌山県)
「恐竜」島村直幸(福岡県)
「斜光に浮かぶ柱状節理」大谷 景(北海道)
「塩見岳の美岩」西出 琢(千葉県)
「断崖の記憶から来た人」曳地正刀(福島県)
「富士山型泥火山」木田敦男(福島県)
「蛇石の流れ」古屋 治(長野県)
「幽岩」三橋俊之(神奈川県)
「大地の迷路」黒田朋花(岐阜県)
「美しい宮崎の自然美」野村奈保美(福岡県)
「貌(かお)」若山拓也(岩手県)
「リアス海岸の恵み」久保田修(兵庫県)
2017年
【第8回惑星地球フォトコンテスト:総評】このコンテストは今年で8年目を迎えましたが,喜ばしいことに昨年の約2倍,過去最高の650点(内ジオ鉄18点,スマホ53点)の応募がありました.応募 数の増加は,地学愛好者だけではなく,雑誌などで広く一般の写真愛好者にこのコンテストを宣伝したためかと思います.一般の写真愛好者からの応募も本コン テストの趣旨をよく理解された力作が多く,審査会では寄せられた優秀な作品の中からあえて12点の入選作品を選ばなければならないのに苦労しました.今回 の入選や佳作作品では,撮りっぱなしではなく,撮影後もHDRなどの画像補正を行い,作品にメリハリを付けている作品が増えたことです.デジタルカメラや 画像処理ソフトの進歩,そして撮影者の斬新な視点によって今まで見ることのできなかった「地球」が見られるようになる.なんと楽しいことではありません か.入選作品を存分にお楽しみください.(審査委員長 白尾元理)
入選作品
佳作作品
第8回惑星地球フォトコンテスト:最優秀賞
「毘沙門海岸の奇岩」 写真:田中健以(神奈川県)
自然が創りあげたとは思えない奇妙な外観に美しさを感じ、撮影しました(講評や大きな画像はこちら)
第8回惑星地球フォトコンテスト:優秀賞
「火星」 写真:西村礼能留(青森県)
写真を撮りに行くたびにここは天候により色々な色に変化して不思議な場所です.…(講評や大きな画像はこちら)
第8回惑星地球フォトコンテスト:優秀賞
「奇妙な宇宙(SORA)」 写真:渡辺昌也(和歌山県)
国の天然記念物「虫喰岩」を夜撮影しました.…(講評や大きな画像はこちら)
第8回惑星地球フォトコンテスト:ジオパーク賞
「波間のプロムナード」写真:古矢さつき(神奈川県)
堂ヶ島の美しい断層を見ながら,海の上を散歩できる遊歩道....(講評や大きな画像はこちら)
第8回惑星地球フォトコンテスト:日本地質学会会長賞
「安山岩の細胞分裂」写真:牧野帆乃香(福岡県)
琉球列島の中の久米島という離島から橋で渡れる距離にある小さな島、奥武島....(講評や大きな画像はこちら)
第8回惑星地球フォトコンテスト:ジオ鉄賞
「あまちゃんの歌が聞こえる」 写真:吉村 誠(奈良県)
昨年のゴールデンウィークにみちのく旅行に出かけました,...(講評や大きな画像はこちら)
第8回惑星地球フォトコンテスト:スマホ賞
「競う曲線美」 写真:伊藤正顕(静岡県)
田舎に住んで十余年、赤ん坊だった娘も、気が付けば1人の女性になっていた...(講評や大きな画像はこちら)
第8回惑星地球フォトコンテスト:入選
「大ヤスリを見下ろす山並み」 写真:三浦雅哉(神奈川県)
奥秩父山脈の最西端に位置する瑞牆山。...(講評や大きな画像はこちら)
画面TOPに戻る
第8回惑星地球フォトコンテスト:入選
「渓谷の歴史」 写真:寺田百合(東京都)
Fjadrargljufur Canyonは,深さ100 m,全長2 km を誇る巨大な渓谷である.(講評や大きな画像はこちら)
第8回惑星地球フォトコンテスト:入選
「太平洋のヘソ」 写真:滝 玲名(愛知県)
イースター島は、不思議な歴史を持つ「モアイ像」で有名な、太平洋に浮かぶ孤島です(講評や大きな画像はこちら)
第8回惑星地球フォトコンテスト:入選
「太古からの流れ」 写真:木下 滋(和歌山県)
和歌山県すさみ町に「まだら岩」と呼ばれている地層があります(講評や大きな画像はこちら)
第8回惑星地球フォトコンテスト:入選
「モエラキボールダー」 写真:蛯子 渉(沖縄県)
ニュージーランド南島の東海岸にある奇石です。(講評や大きな画像はこちら)
画面TOPに戻る
佳作(注)(計10点・順不同)
* タイトル等をクリックすると各作品画像がご覧いただけます.
「活」小野祐介(愛知県)
「冬晴れ」山内崇司(北海道)
「beautiful FUJIYAMA」本多礼子(東京都)
「夕暮れの海金剛」松元澄夫(奈良県)
「咆哮」辰巳 功(東京都)
「大理石の芸術」佐藤 瞳(宮城県)
「時が創った渓谷」乗松賢二(愛媛県)
「天国の洞窟」中尾圭志(神奈川県)
「火山の恵み」越智優心(神奈川県)
「大地の記憶」早川 満(兵庫県)
2016年
第7回惑星地球フォトコンテスト<総評>
惑星地球コンテストは今年で7年目を迎えました.今回は273点の応募があり,このコンテストの趣旨にそった力作が多く集まり,審査会では熱心に議論を重ねて入選作品を選ぶことができました.
今 回は,地質研究者やジオパーク関係者など地質専門家の作品が数多く入選しました.地質現象をわかりやすく,興味深く,楽しく伝えるのは,ジオフォトの重要 な要素です.専門家の中にも,一般の人々が注目するようなジオフォトを撮ろうという意欲のある人が増えたのは嬉しいことです.
スマホの応募数は 29点でした.スマホ賞の「中生代の水辺」は,他の入選作品と比べても遜色のないものです.現在のスマホは,30年前の高級カメラ以上の性能があ り,GPSによる位置情報が得られるのも便利です.普段は気軽に,そして時には気合いを入れて高いレベルの作品をものにできます.来年は,より多くのスマ ホ写真の応募も期待します.
講評:審査委員長 白尾元理
入選作品
佳作作品
第7回惑星地球フォトコンテスト:最優秀賞
「奇岩越しの世界文化遺産」 写真:後藤文義(神奈川県)
三浦半島の南西端にある諸磯海岸から冨士山を臨んだ作品です.(講評や大きな画像はこちら)
第7回惑星地球フォトコンテスト:優秀賞
「白亜紀蓋井島花崗岩に記録されたマグマ混交・混合現象」 写真:永山伸一(山口県)
地層の中に円礫が散らばっているように見えますが,…(講評や大きな画像はこちら)
第7回惑星地球フォトコンテスト:優秀賞
「赤い惑星」 写真:瀬戸口義継(鹿児島県)
宮崎市最南部のいるか岬で撮影した作品です.…(講評や大きな画像はこちら)
第7回惑星地球フォトコンテスト:ジオパーク賞
「巨岩聳える」小林健一(埼玉県)
2011年に認定された下仁田ジオパークは妙義山,荒船山などを中心としたジオパークです.(講評や大きな画像はこちら)
第7回惑星地球フォトコンテスト:ジオ鉄賞
「海岸線を行く」 写真:大宮 知(北海道)
鏡のような海面,浅瀬の模様,礫岩からなる海岸,...(講評や大きな画像はこちら)
第7回惑星地球フォトコンテスト:スマホ賞
「中生代の水辺」 写真:池上郁彦(オーストラリア)
韓国南部は白亜紀の地層が広く分布し,恐竜足跡の残る多数の島々からなり...(講評や大きな画像はこちら)
第7回惑星地球フォトコンテスト:入選
「ハート型の礫 写真:」辻森 樹(宮城県)
大したことのないようでも,よく見ると凄いということがあります...(講評や大きな画像はこちら)
画面TOPに戻る
第7回惑星地球フォトコンテスト:入選
「造形美」 写真:大矢 学(東京都)
スカイ島は,太古代の片麻岩から新生代の火山岩まで多様な岩石が露出します.(講評や大きな画像はこちら)
第7回惑星地球フォトコンテスト:入選
「朝陽輝く幾何学模様の干潟」 写真:谷山誠四郎(東京都)
作品の選考は,作品自身の素晴らしさに加えて,類似した作品の有無,学術的な価値,意外性などの視点からも評価されます.(講評や大きな画像はこちら)
第7回惑星地球フォトコンテスト:入選
「大地の息吹を感じて」 写真:岡本芳隆(神奈川県)
室堂から撮影した立山です.紅葉や青空に浮かぶ絹雲も印象的(講評や大きな画像はこちら)
第7回惑星地球フォトコンテスト:入選
「親子で地底湖探検〜龍泉洞第三地底湖」 写真:熊谷 誠(岩手県)
洞窟は狭くて暗いため,一昔前までは最も困難な撮影対象でした.(講評や大きな画像はこちら)
第7回惑星地球フォトコンテスト:入選
「海上の城壁」 写真:小林健一(埼玉県)
屏風ヶ浦の崖下に下りられる場所は数カ所しかなく,撮影場所は定番ポイントとなっています.(講評や大きな画像はこちら)
第7回惑星地球フォトコンテスト:入選
「リーセフィヨルドの説教壇」 写真:上砂正一(大阪府)
ノルウェー西海岸には多数のフィヨルドがありますが,代表的な観光地がプレーケストーレン(説教壇)です.(講評や大きな画像はこちら)
画面TOPに戻る
佳作(注)(計20点・順不同)
*各作品タイトルをクリックすると画像,撮影者コメント等をご覧いただけます.
佳作「青空と砂岩泥岩互層」藤原寛仁(高知県)
佳作「神の島」林 昌尚(福井県)
佳作「プトラナ台地の洪水玄武岩・トラップ・フィヨルド」奥村晃史(広島県)
佳作「プトラナ台地のシベリアトラップ」奥村晃史(広島県)
佳作「自然のオブジェ」山内佳子(北海道)
佳作「南米の大地」 長谷川宗也(神奈川県)
佳作「自然が産んだ宝物」松原大翔(岩手県)
佳作「渓間のローカル線」斉藤宏和(北海道)
佳作「俵島の玄武岩の柱状節理 」永山伸一(山口県)
佳作「岩礁の道筋」神藤貴之(神奈川県)
佳作「室戸のタービダイト層」 雪本信彰(高知県)
佳作「銀河への定期便」山田宏作(鹿児島県)
佳作「太古の大波」 米岡克啓 (神奈川県)
佳作「天高く」大矢 学(東京都)
佳作「自然のコントラスト」森 祐紀(福岡県)
佳作「躍動は時を越えて」福原春輔(神奈川県)
佳作「マチュピチュ遺跡と花崗岩の造形」 横山俊治(高知県)
佳作「The Bean」池上郁彦(Australia)
佳作「地球は生きている」長山武夫(神奈川県)
佳作「極彩色の世界」長山武夫(神奈川県)
(注)「佳作」惜しくも入選には至らなかったものの,より多くの優れたジオフォト作品を発掘するために「佳作」を設け,作品画像をWEB上で紹介します.またニュース誌や展示会の際に作品タイトルと撮影者氏名の一覧のみ表示します(表彰および作品の展示は行いません).
2015年
第6回惑星地球フォトコンテスト<総評>
このコンテストは今年で6年目を迎え,応募数は417点,昨年の294点を大きく上回りました.応募者の約80%は日本地質学会の会員以外で,ジオフォトが一般の人々にも受け入れるようになったのは嬉しいことです.
今 年の最優秀賞は鶴田重房氏の「太古の足跡」です.生痕化石というあまり一般にはなじみの薄い分野の作品でしたが,一般の人にも生痕化石が理解してもらえる ように工夫された画面構成が評価されました.優秀賞の岩田尊夫氏の「等高線の台地」は定期便からシベリア洪水玄武岩をとらえた作品です.評者は今までこれ ほどはっきりとシベリア洪水玄武岩をとらえた作品を知りません.偶然に撮影されたとのことですが,作者の頭に洪水玄武岩の位置や形状などが頭にしっかり 入っており,執念深く狙っていたかのような素晴らしい作品です.
今年からはスマホ賞を新設し,簡単に応募できるようにしましたが,スマートフォンからの応募はわずか24点で低調でした.スマートフォンカメラの性能向上によって高品質の写真が撮れるようになったので,来年はもっと気軽に応募してほしいものです.
講評:審査委員長 白尾元理
入選作品
佳作作品
第6回惑星地球フォトコンテスト:最優秀賞
「太古の足跡」 写真:鶴田重房(鹿児島県)
屋久島在住の中川正二郎氏によってい発見されたズーフィコスという化石です…(講評や大きな画像はこちら)
第6回惑星地球フォトコンテスト:優秀賞
「等高線の台地」 写真:岩田尊夫(東京都)
ヨーロッパへの出張の途中,シベリア上空でたまたま窓の日よけを上げたら…(講評や大きな画像はこちら)
第6回惑星地球フォトコンテスト:優秀賞
「干潮の橋杭岩」 写真:鈴木文代(和歌山県)
昨年,南紀熊野ジオパークに認定されました「橋杭岩」です.…(講評や大きな画像はこちら)
第6回惑星地球フォトコンテスト:ジオパーク賞
「太古の跡の砂滑り」 写真:竹之内範明(静岡県)
南伊豆の海水浴場で穴場的存在である田牛には,サンドスキー場があり,砂滑りが楽しめます…(講評や大きな画像はこちら)
第6回惑星地球フォトコンテスト:ジオ鉄賞
「ロートホルン登山鉄道」 写真:吉田 宏(神奈川県)
写真はスイス・ブリエンツから出発するロートホルン登山鉄道です…(講評や大きな画像はこちら)
第6回惑星地球フォトコンテスト:スマホ賞
「灼熱の谷」 写真:三浦雅哉(神奈川県)中学・高校生部門より
2014年秋に箱根ロープウェイから撮影しました.…(講評や大きな画像はこちら)
第6回惑星地球フォトコンテスト:入選
「海上の多面体」 写真:八木英雄(宮城県)
造化の妙としか言いようのない形,芸術作品を鑑賞するように…(講評や大きな画像はこちら)
画面TOPに戻る
第6回惑星地球フォトコンテスト:入選
「雲」 写真:野口絵未(東京都)中学・高校生部門より
夏休みに秋川でバーベキューをした帰りにふと上を見たら…(講評や大きな画像はこちら)
第6回惑星地球フォトコンテスト:入選
「千畳敷」 写真:山代大木(岩手県)中学・高校生部門より
釜石湾と大槌湾を仕切るのように太平洋に突き出た御箱崎半島にある千畳敷にて…(講評や大きな画像はこちら)
第6回惑星地球フォトコンテスト:入選
「柱状節理」 写真:永友武治(宮崎県)*組写真
霧島連山の西に位置するところに飯盛山(標高846m)があります.…(講評や大きな画像はこちら)
第6回惑星地球フォトコンテスト:入選
「自然の造形」 写真:山本和恵(福岡県)
阿蘇火口付近の撮影後,下って行くと自然の造形美と思われる場所を発見…(講評や大きな画像はこちら)
第6回惑星地球フォトコンテスト:入選
「宝永山火口」 写真:平井健司(静岡県)
江戸期宝永の年に富士山大爆発によってできた大火口で,異空間の世界を作っています…(講評など詳しく読む)
第6回惑星地球フォトコンテスト:入選
「立ち上る白煙」 写真:岡本芳隆(神奈川県)
大涌谷は箱根の代表的な観光スポットです.…(講評や大きな画像はこちら)
画面TOPに戻る
佳作(注)(計16点・順不同)
*各作品タイトルをクリックすると画像,撮影者コメント等をご覧いただけます.
佳作「大地を引き裂いた証拠:正断層」三木 翼(福岡県)
佳作「モーリタニア鉄道」宮森庸輔(東京都)
佳作「nisey(ニセイ)」國分麻衣子(北海道)
佳作「光 跡」高山幹弘(大分県)
佳作「夕暮れのくじゅう」田中雅士(東京都)
佳作「岩にしみ入る波」玉城義和(沖縄県)
佳作「バッド・ウォーター」渡瀬正章(和歌山県)
佳作「伊豆石と街並」蓑和雄人(静岡県)
佳作「中綱湖畔の春」横山俊治(高知県)
佳作「半化石の浜」天沼 彩(神奈川県)
佳作「異なる食材を使った地層の変形実験」藤内智士(高知県)
佳作「悠久の時を語る岩達」伊良部描理(沖縄県)
佳作「大空を映して」藤松政春(佐賀県)
佳作「自然の造形」佐藤 忠(東京都)
佳作「漂礫岩堆積物の山」加藤智津子(東京都)
佳作「大自然の造形」荒井俊明(京都府)
(注)「佳作」惜しくも入選には至らなかったものの,より多くの優れたジオフォト作品を発掘するために「佳作」を設け,作品画像をWEB上で紹介します.またニュース誌や展示会の際に作品タイトルと撮影者氏名の一覧のみ表示します(表彰および作品の展示は行いません).
画面TOPに戻る
2014年
第5回惑星地球フォトコンテスト<総評>
このコンテストは今年で5年目を迎え,今回は294点で昨年とほぼ同数の応募がありました.コンテストの趣旨も広く理解されてきたようで,一般的な風景写真の応募は少なくなり,地球や地質と関わりの深い作品が集まりました.
3 月初旬の選考会では,入選作品とそれ以外の作品に力の差を感じました.全体のレベルを上げるためには,多くの人々からの応募が必要です.入選されれば日本 地質学会News誌の表紙を飾れますし,全国の科学館などの巡回写真展で多くの人々に見てもらえるチャンスも生まれます.来年はより多くの応募作品がある ことを期待します.
今回のコンテストで出色だったのは,モーターパラグライダーから空撮を野心的に進めているプロカメラマンの山本直洋さんの最優秀賞と入選の作品です.時代ともに新しい撮影機材が出現し,それによって今まで見ることができなかった世界が広がる.今後の活躍が楽しみです.
講評:審査委員長 白尾元理
第5回惑星地球フォトコンテスト:最優秀賞
「Earthscape of Japan」(組写真)
写真:山本直洋(埼玉県)
「Earthscape」と題して,地球を感じる写真をテーマに作品を撮り続けています.、、、(講評など詳しく読む)
第5回惑星地球フォトコンテスト:優秀賞
「地層風景」
写真:増見芳隆(東京都)
国道163のモニュメントバレーからアーチーズ国立公園を結ぶあたりにこの地層が、、、(講評など詳しく読む)
「枕状溶岩とアオウミガメの産卵」
写真:後藤文義(神奈川県)
2013/5/10日の早朝,宿近くの小港海岸出かけたところ,砂上にウミガメの、、、(講評など詳しく読む)
画面TOPに戻る
第5回惑星地球フォトコンテスト:ジオパーク賞
「活火山桜島」
写真:山田宏作(鹿児島県)
火山活動が活発な桜島は,夜になると火山雷を伴った噴火を繰り返して、、、(講評など詳しく読む)
第5回惑星地球フォトコンテスト:入選
「東京砂漠」
写真:鈴木正人(静岡県)
初夏に初めて家族で出かけた神津島は島の海岸沿いの景色にも圧倒されましたが、、、(講評など詳しく読む)
「海底土石流の名残」
写真:竹之内範明(静岡県)
伊豆下田市須崎海岸の小さな島「恵比須島」には,東西の海岸に二つの、、、(講評など詳しく読む)
「Floating Alps」
写真:山本直洋(埼玉県)
ロフォーテン諸島は,アルプス山脈が海に浮かんでいるような景観と、、、(講評など詳しく読む)
「火山湖のある風景」
写真:森井悠太(千葉県)
火山活動によって生じた湖を題材にしました.火山活動の影響を強く受けた、、、(講評など詳しく読む)
画面TOPに戻る
「原生代の谷」
写真:池上郁彦(福岡県)
(講評など詳しく読む)
「タイムアーチ」
写真:糸満尚貴(大分県)
竜串一帯では砂岩と泥岩の層が波や風に侵食され,数多くの、、、(講評など詳しく読む)
「台湾燕巣泥火山」
写真:田中郁子(兵庫県)
学部時代に留学していた台湾に思いを馳せ,金沢大の後輩の台湾一周大巡検に、、、(講評など詳しく読む)
「王冠形態をつくる岩片インパクト」
写真:椎野勇太(東京都)
雨天続きで調査が難航しつつ,ようやく晴天に恵まれたある日、、、(講評など詳しく読む)
「Face」
写真:平山 弘(和歌山県)
和歌山県白浜町にある「いそぎ公園」(通称:チャボ公園)を抜け、、、(講評など詳しく読む)
「桜島火山雷」
写真:永友武治(宮崎県)
桜島噴火の火山雷の撮影です.毎日数回の噴火を繰り返しています.、、、(講評など詳しく読む)
2013年
第4回惑星地球フォトコンテスト<総評>
惑星地球フォトコンテストは今年で4回目を迎えました。応募総数は昨年の321点くらべて205点と減少しましたが、「地球」が主役であるジオフォトの理解が深まったためか、コンテストの趣旨にそった応募作品が多く、とくに上位の50点は力作が目立ちました。
その中で特に注目されたのは海洋研究開発機構の坂口有人氏の作品「深い海底の流れ」です。海岸沿いのだれでも行ける露頭ですが、注意深い観察力と優れた写真技術によって露頭に秘められた物語を見事に引き出しています。
一方、国立極地研究所の菅沼悠介氏の作品「東南極セール・ロンダーネ山地の巨大岩峰」は、ごく限られた研究者しか近づけない世界を私たちに教えてくれます。過酷な環境での撮影ですが、このような写真を見て胸をときめかせる少年もいるでしょう。
風景写真的なアプローチからの力作が堀内勇氏の作品「ホイールストーン」です。デジタルカメラの特性を生かした作品で、坂口氏の作品と最優秀賞を争いました。
ジオフォトには、さまざまなアプローチがあって良いと思います。来年も選者たちをあっと驚かすような力作や意外性のある作品を期待します。
講評:審査委員長 白尾元理
最優秀賞「深い海底の流れ」写真:坂口有人(神奈川県)(講評など詳しく読む)
優秀賞「ホイールストーン」写真:堀内 勇(和歌山県)(講評など詳しく読む)
優秀賞「地層模様」写真:細井 淳(茨城県)(講評など詳しく読む)
優秀賞「空気砲」写真:大江雅史(愛知県)(講評など詳しく読む)
ジオパーク賞*「活躍するボランティアガイド」写真:本多優二(群馬県)(講評など詳しく読む)
入選「静けさ」写真:檜山貴史(北海道)(講評など詳しく読む)
入選「1934-35昭和硫黄島」写真:池上郁彦(福岡県)(講評など詳しく読む)
入選「マグマの上で」写真:高橋伸輔(秋田県)(講評など詳しく読む)
入選「火山の造形」写真:坪田敏夫(神奈川県)(講評など詳しく読む)
入選「地層のデザイン」写真:坂口有人(神奈川県)(講評など詳しく読む)
入選「東南極セール・ロンダーネ山地の巨大岩峰」写真:菅沼悠介(東京都)(講評など詳しく読む)
入選「輝く岩山」写真:佐藤 忠(東京都)(講評など詳しく読む)
*新設:「ジオパーク賞」第 4回フォトコ ンテストでは,ジオパークの作品が前回より大幅に増えました.そこで,今回より優秀賞の枠の一つを使い,ジオパーク賞を設けることになりました.なお,こ の賞では,ジオパークの風景を撮影したすぐれた作品とは別に,ジオパークの重要なテーマである「ジオと人との関わり」が表現されている作品を重要視しま す.
2012年
[お知らせ]第3回惑星地球フォトコンテストの入選作品が、「月刊日本カメラ」8月号(7月20日発売)(p.298-299)に紹介(掲載)されました。お近くの書店でお求めください。
第3回惑星地球フォトコンテスト<総評>
最近10年間でジオフォトと呼ばれる写真分野は確立し、雑誌、書籍、ウェブサイトで優れた作品が頻繁に発表されるようになりました。ジオフォトが、一般の人々にも地質が身近に感じさせることに大きな役割を果たしているのは喜ばしいことです。
惑星地球フォトコンテストは今年で3回目を迎えました。作品の応募総数は1回目、2回目がそれぞれ436点、426点だったのに対して今回は321点とやや少なく、選考会で溜息が漏れるような作品が少なかったのは残念でした。
応 募作品の中で注目されたのは地質研究者の清川昌一氏の作品で、最優秀賞と入選となっています。いずれも簡単には行けない場所での撮影で、何を見せたいかを 客観的に判断してすばらしい作品に仕上げています。いまや日本の地質研究者は世界をまたにかけて調査する時代ですから、ぜひ自分の研究分野の自信作を応募 してほしいものです。
また少し残念に思ったのは、デジタルカメラの進歩によって撮影対象や表現方法は大きく広がったのに、応募作品にはそれが 生かされていません。見なれた露頭でも冒険的なアングルから撮影するとか、画像処理によっていままで見えなかった地質現象を表現するとか、ジオフォトの可 能性を広げる作品を見たいものです。
審査委員長:白尾 元理
最優秀賞「27億年前の鉄鉱山」写真:清川 昌一(福岡県)、(講評など詳しく読む)
優秀賞「ある惑星にて」写真:公文 俊朗(愛知県)(講評など詳しく読む)
優秀賞「自然の威力」写真:永友 武治(宮崎県)(講評など詳しく読む)
優秀賞「新燃岳の噴火と火山雷」写真:中馬辰紀(宮崎県)(講評など詳しく読む)
入選「渓谷を行くSL」写真:竹内 久俊(東京都)(講評など詳しく読む)
入選「しらひげの滝 (青い池の上流には滝があった)」写真:宇津木 圭(北海道)(講評など詳しく読む)
入選「尖塔」写真:林 孝信(東京都)(講評など詳しく読む)
入選「初めてのジオパーク」写真:高橋 伸輔(秋田県)(講評など詳しく読む)
入選「よろい岩」写真:中桐 晴己(大阪府)(講評など詳しく読む)
入選「凍土の星」写真:兼子 昌根(千葉県)(講評など詳しく読む)
入選「夜来たる」写真:公文 俊朗(愛知県)(講評など詳しく読む)
入選「柱状節理」写真:辰巳 功(東京都)(講評など詳しく読む)
入選「27億年前の海台1(枕状溶岩)」写真:清川 昌一(福岡県)(講評など詳しく読む)
入選「地球の記憶」写真:柳瀬 真(新潟県)(講評など詳しく読む)
入選「チョコレート・ボンボン」写真:吉田 宏(神奈川県)(講評など詳しく読む)
入選「褶曲」写真:平山 弘(和歌山県)(講評など詳しく読む)
2011年
第2回惑星地球フォトコンテスト<全体講評>
今回も426点という多数の応募をいただき,ありがとうございました.今回は第2回目なので,コンテスト趣旨への理解が深まり,地質的な要素がうまく組み 込まれた写真が増えたのは嬉しいことです.入選作品にはやや長めの解説文がつけられた作品が多く,作者それぞれの撮影意図がはっきりと読み取れました.
し かし,撮影対象の魅力を1枚の写真で表現するのが難しいこともあります.最優秀賞「カッパドキアの地」の内藤さんのように広角と望遠によって,また作者は 異なりますが北海道遠軽町の黒曜石を石としてとらえた伊藤建夫さんと露頭としてとらえた佐野恭平さんの作品のように組み合わせると対象をより的確に表現で きことがあります.来年以降は組写真での応募にも期待いたします.
審査委員長 白尾 元理
最優秀賞「カッパドキアの地」写真:内藤理絵 (東京都)(講評など詳しく読む)
優秀賞「空を翔ける」写真:菱川尚駒(東京都)(講評など詳しく読む)
優秀賞「クレーター」写真:亀田きようかず (和歌山県)(講評など詳しく読む)
入選「黒曜石の山」写真:伊藤建夫(北海道)(講評など詳しく読む)
入選「新燃岳、緊迫の生中継」写真:追鳥浩生 (鹿児島県)(講評など詳しく読む)
入選「光と共に」写真:大木晴雄 (埼玉県)(講評など詳しく読む)
入選「石鎚山麓」写真:太田義将 (兵庫県)<高校生以下の部>(講評など詳しく読む)
入選「荒々しき車窓」写真:太田義将 (兵庫県) <高校生以下の部>(講評など詳しく読む)
入選「二つの斜面」写真:加藤大佑 (神奈川県) <高校生以下の部>(講評など詳しく読む)
入選「複成火山の連なり」写真:小島一彦(北海道)(講評など詳しく読む)
入選「自然が生み出す漆黒の石」写真:佐野恭平 (北海道)(講評など詳しく読む)
入選「燃える桜島」写真:堂元久志(鹿児島県)(講評など詳しく読む)
入選「晩秋の嵐」写真:中野 優 (新潟県)(講評など詳しく読む)
入選「幻想」写真:滑方芳江 (千葉県)(講評など詳しく読む)
入選「懐深き山」写真:西田真魚 (東京都)(講評など詳しく読む)
入選「予感」写真:浜口恵美 (和歌山県)(講評など詳しく読む)
入選「吹割の滝」写真:山崎 泰 (栃木県)(講評など詳しく読む)
入選「秋の清津峡」写真:山崎 泰(栃木県)(講評など詳しく読む)
2010年
第1回惑星地球フォトコンテスト
IYPE名誉会長賞「地底へ続く道」写真:蓮村俊彰 (東京都)(講評など詳しく読む、、、)
日本地質学会会長賞「麦圃生山・植生回復」写真:松山幸弘(福井県)(講評など詳しく読む、、、)
審査委員長賞「作者は、地球。」写真:中西康治 (沖縄県)(講評など詳しく読む、、、)
優秀賞A部門「石の木」写真:北川太郎(兵庫県)(講評など詳しく読む、、、)
優秀賞B部門「支笏湖湖底」写真:荒木一視 (山口県)(講評など詳しく読む、、、)
入選「赤い岩」写真:佐藤 忠 (東京都)(講評など詳しく読む、、、)
入選「エンルム岬」写真:加藤幸雄 (北海道)(講評など詳しく読む、、、)
入選「祝 洞爺湖有珠山ジオパークGGN登録!」写真:横山 光 (北海道)(講評など詳しく読む、、、)
入選「山河」写真:横山栄治 (神奈川県)(講評など詳しく読む、、、)
入選「奇跡のアーチ」写真:渡辺修二(神奈川県)(講評など詳しく読む、、、)
入選「羊蹄の朝」写真:菅野照晃 (東京都)(講評など詳しく読む、、、)
入選「北米−カリブプレート境界の蛇紋岩」写真:辻森 樹(鳥取県)(講評など詳しく読む、、、)
入選「重力」写真:岡田 治 (和歌山県)(講評など詳しく読む、、、)
入選「阿波の土柱」写真:三木万理子 (徳島県)(講評など詳しく読む、、、)
2008年
IODPジオハザードワークショップとセントヘレンズ山巡検
写真:川村喜一郎(深田地質研究所),山田泰広・宮川歩夢(京都大学))
米国オレゴン州ポートランドの宿泊施設McMenamins Edgefieldにて,IODPジオハザードワークショップが開催された.会場近くのセントヘレンズ山を巡検し,噴火に伴う山体崩壊地形と崩壊堆積物を観察した.セントヘレンズ山は,1980年に大規模な山体崩壊を引き起こしたことで世界的に有名である.まず同年3月中旬頃,地震が観測されはじめ,3月27日に最初の噴火が山頂部で発生した.その後,5月18日午前8時32分にM5.1の地震が発生し,山体北側が3回に分けて大規模に崩壊した.山体を構成していた岩石は岩なだれ(debris avalanche)となって流下し,爆風によって周囲の森林がなぎ倒された、、、(詳しくは、、)
モンゴルのゲルと果てしなく広がる大地
写真:後藤晶子(名古屋大学年代測定総合研究センター) 解説:後藤晶子・高橋亮平(北海道大学大学院理学研究院)・久田健一郎(筑波大学大学院生命環境科学研究科)
Eurasian Geological Seminar 2007(EGS 2007:モンゴルにて開催)にともなっておこなわれたフィールド巡検では,モンゴルの自然や文化を十分に堪能することができた.巡検の途中に現地の人の生活空間であるゲルを何度か突撃訪問したが,快く迎え入れ馬乳酒やチーズをご馳走になった.また,なだらかな山の麓までまっすぐにのびる道ではモンゴルの大地の雄大さを感じることができた、、、(詳しくは、、)
2007年
ライマン「日本蝦夷地質要略之図」彩色指定稿
北海道大学附属図書館 所蔵
解説:金 光男(自然地質環境研究所)
日本地質学の偉大な恩人B.S. Lyman(Benjamin Smith Lyman:1835.12.11-1920.8.30;以下ライマンとする)は,1873(明治6)年1月17日来日(副見1990)すると,東京芝に創設されたばかりの開拓使仮学校(札幌農学校−北海道大学の前身)において教鞭をとる.それから間もない同年4月17日,彼は当時未開地とされた蝦夷(北海道)へ向け横浜を出航すると,以後門弟たちとともに言語に絶する艱難辛苦を重ねている(今井1966,Suzuki & Kim 2003,金・菅原2007など). 3年におよぶ北海道全島調査は,その名目こそ地質調査であったが,地形測量すなわち地図作成という難行をともなう“道無き道を進む”苛烈なものだった.、、、(詳しくは、、)
地震が作り出した芸術:巨大乱堆積物
写真:山本由弦(産業技術総合研究所)・坂口有人(海洋研究開発機構)
まるで絵に描いたように奇妙で,大規模な乱堆積物露頭. 上部鮮新統〜更新統の千倉層群畑(はた)層中に発達するこの露頭は,2007年度初頭に房総半島南部の農業道路建設現場において発見された(Yamamoto et al., 2007 in press).約200万年前の地震によって,砂層が液状化し,剪断強度を失ったそれらが古斜面上を移動したものと結論される(いわゆる liquefied sediment flow)、、、(詳しくは、、)
IODP Exp.303&306の2nd post-cruise meetingのハワイ島巡検
川村喜一郎((財)深田地質研究所)(写真提供)・川村紀子(産業技術総合研究所)
ハワイ島は,マグマの噴出によって山体が成長している一方,ワイピオ・ルックアウトのように,浸食,崩壊が進行しているところもある.、、、(詳しくは、、)
千鳥が滝の中新統川端層とソールマーク
写真:川村信人(北海道大学理学院自然史科学専攻)
解説:川村信人・川上源太郎(北海道立地質研究所)
『千鳥が滝』は,夕張市滝の上公園内にある夕張川河床の段差地形である.写真(上)は2005年10月撮影.下流部が滝つぼ状にやや深くなっており,千鳥が淵とも呼ばれる.北海道では有数の地層の大規模露頭であり,良い巡検場所ともなっている、、、(詳しくは、、)
瀬戸内海中部、芸予諸島、ホボロ島の生物浸食
写真:沖村雄二・土岡健太・船越雄治(東広島市自然研究会)
解説:沖村雄二・後藤益巳・矢原大和(広島県立教育センター)
広島県東広島市安芸津町赤碕の沖にある小さな島,ホボロ島は,ここ数十年の間にみるみる小さくなり,若いころに遊んだ島の面影は全くなくなったと語る老年の方々は少なくない.台風のたびに目だって小さくなるし,どうしてこの島だけが急速に小さくなるのだろうか?と,理由がわからないまま,ホボロを売るという民話ともあいまって,わびしく見守られてきた、、、(詳しくは、、)
平成19年(2007年)能登半島地震写真速報
写真:石渡 明
3 月25 日9時42 分頃,能登半島沖の深さ11km を震源とするマグニチュード(M)6.9(暫定値)の地震が発生し,石川県の七尾市,輪島市,穴水町で震度6強を,石川県の志賀町,中能登町,能登町で震度6弱を観測した、、、(詳しくは、、)
隠岐島後時張山累層の火山豆石
Pisolites in Tokihariyama Formation, Oki-Dogo
写真:大友 幸子
日本地質学会107年学術大会(松江)の見学旅行B-8班隠岐島後コースに参加して撮影したもの.沢田ほか(2000)によると,時張山累層は日本海の形成過程の中の陸弧時代に形成された地層として位置づけられている.(詳しくは、、)
南アフリカのSwaziland系(32億年〜35億年)
Swaziland System(3.2〜3.5Ga-old)in South Africa
写真:諏訪 兼位
始生代早期・中期のSwaziland系は,Barberton山地(Kaapvaal剛塊東部)にもっともよく露出している.Barberton山地は,19世紀半ば頃から金の産出で知られ,古くから地質調査も行われていた.ここのgreenstone帯は,長さ100kmを超え,Swaziland系(層厚22km)の火山岩や堆積岩からできている.(詳しくは、、)
2006年
台湾北投温泉の地獄谷
Hokutolite (radioactive plumbous barite) reservation area, Hot spring valley, Beitou, north Taiwan
写真:貴治 康夫(大阪府立箕面東高等学校)
台北の中心から鉄道で北へ約40分の郊外に北投(Beitou)温泉がある.周辺は国家公園に指定され,大屯(Datun)山をはじめ,標高1000mを超える10以上の火山からなる大屯火山群(Datun volcano group)が分布する.地質は角閃石安山岩や輝石安山岩を主体とし,鮮新世後期から火山活動が活発であった.(詳しくは、、)
「平成18年7月豪雨」での長野県岡谷市における災害発生地の状況
写真:大塚 勉(信州大学,全学教育機構)・信州大学自然災害科学研究会・信州大学山岳科学総合研究所
活発な梅雨前線の活動による「平成17年7月豪雨」において,7月15日から19日にかけて長野県で降り続いた雨は,県中部を中心とする地域に土砂災害をもたらし,9名の犠牲者を含む甚大な被害が生じた.7月17日未明から19日正午までの連続累積降水量は,辰野町で約400mm,諏訪市で約360mmに達していた.信州大学の上記の組織のグループによる,災害発生直後からの調査の結果,今回の災害の地質学的な発生要因の概要が明らかになった.(詳しくは、、)
南アフリカのダイヤモンド鉱山
Diamond mine in South Africa
写真・文 諏訪兼位 Kanenori Suwa
Kimberley (Cape州北部)では,1871年にキンバリー岩のパイプ(Big Hole,直径450m)が発見され,露天掘りの採掘がはじまった.露天掘りは深さ360mまでつづいた.1889年以降,キンバリー岩のパイプの外側に縦坑を下ろし,順次,深いレベルで横坑を掘って,キンバリー岩を採掘するようになった.縦坑の深さが1200mになると、、(詳しくは、、)
グランドキャニオンの巨大クロスベッド
Huge cross bed structures at the Grand Canyon
写真提供:渡部芳夫(産業技術総合研究所)
この写真は,グランドキャニオンを中心にユタ州からモンタナ州にかけて32万平方キロ以上に広がっている,2億6千万年前の二畳紀のCoconino砂岩と名付けられた乳白色の砂岩です.渓谷の絶壁で真っ白に映えるこの砂岩は,広く対比されています.ここグランドキャニオン・サウスリムでの断面では,台地面の直下,つまり渓谷の頂部の高さにほぼ水平に露出しており,壁面全体にトラフ型の大型斜交層理が見えています.(詳しくは、、)
岡山県,蒜山原高原の珪藻土層
Laminated diatomaceus bed of middle Pleistocene Hiruzenbara Formation, Hiruzenbara, Okayama Prefecture, Japan
公文富士夫(信州大学理学部)
松江市で行われた第四紀学会2005年大会の帰途,8月29日に蒜山高原にある昭和化学工業(株)岡山工場の珪藻土採石場を見学させていただきました.この珪藻土層は蒜山原層と名付けられており,縞状のラミナの周期性が有名です(石原・宮田,1999).
石原・宮田(1999)で報告された露天掘りの位置よりも500mほど東側の新しい露天掘りの露頭でしたが,明瞭な縞模様の見える珪藻土層を観察することができました.(詳しくは、、)
2005年
南アフリカのTransvaal系(20.5〜23.5億年)
Transvaal System(20.5〜23.5Ga-old)in South Africa
諏訪兼位
南アフリカの首都Pretoriaは,海抜1400mのTransvaal高原の町である.Pretoriaの東方約200kmのBlyde River Canyonでは,Tranvaal系の地層がGrand Canyonさながらの景観を呈する.Transvaal系は,東西900kmにわたって広がり,50万km2の分布域を示す.Transvaal系の全層厚は15,000mで4層群が識別される
(詳しくは、、)
愛媛県八幡浜大島のシュードタキライト
Psudotachylite in Yawatahama-Oshima, Ehime Prefecture
宮下由香里
大島変成岩は主として火成岩起源の変成岩から構成され,少量の堆積岩起源の変成岩を挟む.これらは下部地殻(地震学的にも地質学的にも)からの上昇過程において,運動方向の異なる4回のマイロナイト化作用を受けている. シュードタキライトを含む断層帯は,大島変成岩中に3帯認められる.(詳しくは、、)
ジローナ(スペイン)のカテドラルの貨幣石石灰岩
Nummulites limestone ovserved in the Catedral de Gerona,Catalunya,Spain
大友幸子(山形大学)
10年以上前にバルセロナでのある時のお茶会で日本人マダムから,「ジローナのカテドラルのところにアーモンドの化石がたくさんはいっているのよ」という話を聞いた.「はて??アーモンドの化石とは???」と疑問に思いさっそく見学に行った.(詳しくは、、)
ピレネー東部のRoses花崗閃緑岩体の不均質延性剪断帯
Inhomogeneous ductile shear zones in the Roses granodiolite, eastern Pyrenees
大友幸子(山形大学)
ピレネー東部のマイロナイト帯の東端,地中海に面して分布するRoses花崗閃緑岩体中にはNW-SE方向の主に左横ずれの小規模な 剪断帯が無数に発達している.(詳しくは、、)
No.131 2011/4/5 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.131 2011/4/5 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】東日本大震災に関する地質学からの提言
【2】速報:津波被災地現地報告
【3】2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震による仙台地域の墓石転倒率について
【4】震災関連情報の投稿のお願い
【5】被災会員の会費減免申請について
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞情報
【9】訃報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】東日本大震災に関する地質学からの提言
──────────────────────────────────
一般社団法人 日本地質学会 会長 宮下 純夫
2011年3月11日は,日本の歴史にとって忘れえない日となった.マグニチュー
ド9の東日本を襲った超巨大地震と大津波による甚大な被害,そして原子力発
電所の被災によって,日本はこれまでに経験した事がない困難な時期を迎えて
いる.破滅的な被害からの復旧・復興のグランドデザインを考える上で,また,
今後の防災・減災対策を講じていくために地質学的観点からの提言を行う.
続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/hazard/content0051.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】速報:津波被災地現地報告
──────────────────────────────────
大石雅之(岩手県立博物館)
岩手県沿岸の津波被災地を訪れ、予備的調査を行ったので、速報として報告し
ます。(中略)地質学会会員の中でも被災地に近い場所に居住する者として、
いちはやく現場に向かいたかったのですが、地震当初のライフライン寸断と
ガソリン不足のために、初動が遅れてしまいました。そしてやっと、3月25日
と29日に当館同僚の吉田充とともに岩手県沿岸の一部の地域に行くことができ
ました。ここではその報告を行います。結果的には、災害発生直後では道路
事情が悪く、通行規制もあったので、2週間後の行動で妥当だったように思わ
れます。以下に当初関係者に電子メールで報告したものをベースに時系列で
記述します。
続きを読む、、、
■津波被災地現地報告(その1)
http://www.geosociety.jp/hazard/content0052.html
■津波被災地現地報告(その2)
http://www.geosociety.jp/hazard/content0053.html
■宮古市重茂半島川代の津波コマ撮り写真と姉吉の最大遡上高
http://www.geosociety.jp/hazard/content0054.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震による仙台地域の墓石転倒率について
──────────────────────────────────
石渡 明・宮本 毅・平野直人(東北大学東北アジア研究センター)
主な結論
(1)今回の巨大地震による墓石転倒率は1978年宮城県沖地震より低い。
(2)墓石の転倒率が高い地域は沿岸部と内陸部の2列になっている。
仙台地域の墓地129ヶ所において、2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震
(M9.0)による墓石の転倒率を3月13日から4月4日にかけて調査し、1978年
6月12日の宮城県沖地震による墓石転倒率分布と比較した。
続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/hazard/content0055.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】震災関連情報の投稿のお願い
──────────────────────────────────
東北地方太平洋沖地震に関する各地の状況を記録することは、学会として
とても重要なことと考えています。
そこで、今回の地震に関する様々な情報を会員の皆様から投稿していただける
ようお願い申し上げます。投稿いただいた情報はできる限りHPやニュース誌
などで掲載できるように取りまとめていきたいと思います。
レポートや解説付きの写真など、形式は自由です。
分かる範囲で結構ですので、投稿情報の場所の情報(町名や緯度経度など)
が有りましたら添えていただけるようお願いします。
投稿先: journal@geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】被災会員の会費減免申請について
──────────────────────────────────
日本地質学会では、災害救助法適用地域で被災された会員の方々のご窮状を
ふまえ、会費については減免の措置を取らせていただいており、今回の災害
においても対象となる会員の方から、申し出があった場合には適用いたします。
詳細: http://www.geosociety.jp/outline/content0093.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
■2011年関東支部総会および地質技術伝承講習会
【地質技術伝承講習会】
日時: 2011年4月24日(日)14:00〜16:00
場所: 大田区産業プラザ(大田区蒲田1-20-20)特別会議室
講師: 三木 茂氏(基礎地盤コンサルタンツ株式会社 保全・防災センター)
テーマ: トンネル事前調査の課題と物理探査
共催:(社)全国地質調査業協会連合会 関東地質調査業協会
参加費: 無料,どなたでも参加できます.
【支部総会】
日時: 2011年4月24日(日)16:00〜16:30
場所: 上記講習会と同会場
申込方法・総会委任状等、詳しくは、
http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■日本学術会議公開シンポジウム「新しい高校地理・歴史教育の創造
−グローバル化時代を生き抜くために−」
日時:2011年4月23日(土)14:00〜17:00
場所:日本学術会議講堂
問い合わせ先:日本学術会議事務局第一部担当 小林03-3403-5706
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf/116-s-1-1.pdf
■地質学史懇話会
6月25日(土)13:30〜
会場:北とぴあ701号室(北区王子1-11-1)
小澤健志「金澤藩鉱山教師E.デッケンの生涯について」
後藤和久「宮古−八重山諸島を襲った 1771 年明和津波の歴史学的・地質学的証拠」
■JABEE 事務局ニュース No. 13(2011/4/4版)
JABEE事務局ニュースは社員(正会員)、賛助会員、理事、監事、顧問、
委員会委員宛に配信されています。
情報のより広い共有のため、会員の皆様にもご転送いたします。
2011/4/4版ニュース PDFはこちら、、
http://www.jabee.org/OpenHomePage/jabee_e-news_13_110404.pdf
JABEEホームページ http://www.jabee.org/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■新潟大学:教育研究院自然科学系環境科学系列(教授)(5/31)
■岡山大学地球物質科学研究センター:共同利用研究員の追加公募(随時)
東北地方太平洋沖地震で被災された研究者及び大学院生(学部卒論生も含む)
の皆様の研究・教育活動の支援のために、追加申請を受け付けます。
■岡山大学地球物質科学研究センター:三朝国際インターンプログラム2011
参加学生募集(5/9)
■第8回(平成23年度)日本学術振興会賞受賞候補者推薦募集(学会推薦)(5/6)
■第2回(平成23年度)日本学術振興会 育志賞受賞候補者推薦募集(学会推薦)(5/31)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】訃報
──────────────────────────────────
────────────────────────────
■松本ゆき夫名誉会員 ご逝去
────────────────────────────
日本地質学会名誉会員 松本ゆき夫氏(山口大学名誉教授)が,
平成23年3月30日(水)にご逝去されました(享年82歳).
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福を
お祈り申し上げます.
なお,通夜・告別式はそれぞれ3月31日・4月1日に執り
行われました.
※「ゆき」=行にんべんに「正」の字2つ.
────────────────────────────
■須鎗和巳名誉会員 ご逝去
────────────────────────────
日本地質学会名誉会員 須鎗和巳氏(徳島大学名誉教授)が,
平成23年4月2日(土)にご逝去されました(享年85歳).
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福を
お祈り申し上げます.
なお,通夜・告別式はそれぞれ4月2日・3日に執り
行われました.
会員の皆様に,謹んで御連絡申し上げます.
会長 宮下純夫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
第2回フォトコン入選作品:入選
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選:「燃える桜島」
写真:堂元 久志(鹿児島) 撮影場所:鹿児島市黒神
撮影者より:
県都鹿児島市からわずかな距離にある活火山桜島。H22は900回近い噴火を繰り返し,地球の息づかいを肌身に感じた。その模様をとらえたいと連日通い,やっと夢が叶った。地元であったことが幸いした一瞬であった。火映現象を間近に見られ,しかも写真におさめることができた。地球に感謝の一年であった。
審査委員長講評:
桜島では2008年2月から昭和火口での噴火が活発になり,最近では毎日のように爆発的噴火をしています.昼間は黒煙をもくもくとあげる爆発的噴火ですが,夜見ると赤熱した岩塊を噴き上げているのがよくわかります.連日通ったということですが,地元の人ならではの作品といえるでしょう.
←戻る 目次 進む→
第2回フォトコン入選作品:入選
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選:「晩秋の嵐」
写真:中野 優(新潟県) 撮影場所:JR信越本線の米山駅ー笠島駅間 新潟県柏崎市米山町.聖ヶ鼻にある展望広場.
撮影者より:
米山駅を見下ろす高台からの撮影です.この地は,地すべり多発地帯として有名です.また,彼方には,妙高の山々を望むことができます.
国道8号の旧道にある展望広場にて,カメラを三脚にセットし,列車が来るのを待っていました.当日は暴風警報が出されており,強風が吹き荒れていました.しばらく待っても列車が来ないため,携帯電話で調べたところ,案の定「強風のため運休」とのこと.あきらめてカメラを片付けようとしたところ,短編成の貨物列車がノロノロとやってきました.凍えながら撮った写真です.
審査委員長講評:
信越本線の米山駅付近を東側の高台から撮影した作品です.悪天候で撮影が大変だったとありますが,雲間からの一瞬の光,白波が立つ海面など悪天候でなければ撮影できない写真です.このような逆光では従来のフイルムカメラでは手前が露出アンダーでまっ黒になってしまいますが,最近のデジタルカメラだからこそ撮れた写真ともいえます.
←戻る 目次 進む→
第2回フォトコン入選作品:入選
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選:「幻想」
写真:滑方芳江(千葉県) 撮影場所:千葉県旭市飯岡
撮影者より:
海と陸との戦いも一休み。飯岡・屏風ヶ浦に穏やかな月の出を写させて頂いた。
千葉県旭市飯岡(漁港より) 黒潮流れる九十九里海岸の東端.海と陸の戦いにて生まれた東洋のドーバーとも呼ばれる屏風ヶ浦.月を写した一枚です.
審査委員長講評:
この写真は日没直後の残照を利用して千葉県の屏風ヶ浦を撮影しています.崖の上半分は陸成層の関東ローム層,下半分は砂泥互層の海成層の飯岡層で,両者の境界は植生の違いによっても明瞭です.満月がよいアクセントになっています.
←戻る 目次 進む→
第2回フォトコン入選作品:入選
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選:「懐深き山」
写真:西田 真魚(東京都) 撮影場所:韓国ソウル北漢山山頂付近
撮影者より:
ソウルという都会のすぐそばにある、約79.9Km2に及ぶ広大な面積と、いくつもの巨大な花崗岩の岩峰を誇る、北漢山。その威風堂々とした山の姿とは、うらはらに人々は、この山で憩い、愛用し、安らぎを頂く。年平均500万人が訪れており、「面積当たり最も多くの人が訪れる国立公園」ということでギネス記録を持つ。
審査委員長講評:
韓国の北漢山の花崗岩を,見下ろすようなアングルで撮影しています.ぱっと見ると岩の節理ばかりが目立ちますが,よく見ると下の方には登山客がいることから巨岩であることがわかります.遠くに低い山々が霞んで映っています.私はソウル近郊にこのような国立公園があるのを,この写真で初めて知りました.
地質的背景:
首都ソウルを守護する玄武の山・北漢山(ブッカンサン)は、韓国に広く分布す るジュラ紀大宝(デボ)花崗岩類に属し、カリ長石に富むことからピンク色を呈 するのが特徴的です。韓国の花崗岩山地でよく見かける間隔の広い節理も発達し ており、切り立った見事な絶壁を造り上げています。(江川浩輔 産総研メタン ハイドレート研究センター)
←戻る 目次 進む→
第2回フォトコン入選作品:入選
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選:「予感」
写真:浜口 恵美(和歌山県) 撮影場所:和歌山県東牟婁郡串本町くじの川・橋杭岩
撮影者より:
串本から大島に向かって、大小約40個の奇岩が850メートルに渡って並んでいます。国の名勝・指定天然記念物に指定されています。この奇岩群「橋杭岩」は、県内で唯一、日本の地質百選に選ばれている「古座川弧状岩脈」の一つで、1400万年前ごろ、地層の割れ目に沿って珪長質マグマが上昇してできたとされます。 夏の時期、日の出前や岩の向こうから太陽が昇る時間には、神秘的な光景が広がります。
審査委員長講評:
橋杭岩は,泥岩中に流紋岩の岩脈が貫入し,その後周囲の泥岩が侵食によって取り除かれたためにできた地形です.干潮時には周囲の土地も干上がってしまいますが,満潮時で周囲が海水で満たされた早朝にこの作品を撮影されています.空や海面のグラディエーションが美しい.
←戻る 目次 進む→
第2回フォトコン入選作品:入選
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選:「吹割の滝」
写真:山崎 泰(栃木県) 撮影場所:群馬県片品村
撮影者より:
河床の岩盤が大きく割れた吹割の滝。白く輝く水と岩盤のコントラストが見事。午後の低い光線が虹をかけた。
群馬県沼田市利根町片品川にある片品渓谷(吹割渓谷)にある滝で,東洋のナイアガラとも呼ばれている.河床の岩を大きく切り開いたような岩盤と数々の滝がすばらしい.
審査委員長講評:
吹割の滝は落差7mですが,U字型に奥行きが30mも削られているので滝幅があって見応えがあります.対岸の観瀑台から全体を俯瞰する構図の写真が多いのですが,山崎さんは反対にローアングルから滝の水がうまく重なる位置を選んで撮影しています.
←戻る 目次 進む→
第2回フォトコン入選作品:入選
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選:「秋の清津峡」
写真:山崎 泰(栃木県) 撮影場所:新潟県清津峡
撮影者より:
谷川が永年かけて刻み込んだ岩の造形。柱状節理が見事。
新潟県十日町市にある信濃川の支流である清津川が形成した渓谷.清津峡温泉から上流に温泉があり,3ケ所の展望台がある.晩秋であるが,見事な柱状節理に圧倒された.
審査委員長講評:
清津峡は中新世の迸入岩体からなり,かつては秘境でしたが平成8年に峡谷にそって清津峡渓谷トンネルが完成しました.現在では4つの見晴らし台から,みごとな柱状節理をながめることができます.いままであまり紹介されていない対象を撮影されたということで入選としました.
←戻る 目次
No.133 2011/4/22 geo-flash(臨時)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.133 2011/4/22 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】5月10日は「地質の日」
【2】その他のお知らせ
【3】連休中のgeo-Flashはお休みです
【4】訃報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】5月10日は「地質の日」
──────────────────────────────────
5月10日の「地質の日」を中心に講演会や野外観察会などのイベントが全国
各地で開催されます。一般の人々が地質への理解を深め身近なものと感じら
れるように、全国の博物館や大学などの研究機関で様々な講演会や野外観察会
などが企画されています。
今年のゴールデンウィークは地質の日イベントで地質に親しんでみませんか?
みなさまのご参加をお待ちしております。
■日本各地で開催されるイベントはこちらから、、、
http://www.gsj.jp/geologyday/2011/event.html
■地質学会主催のイベントはこちらから、、、
http://www.geosociety.jp/name/content0076.html
■地質の日事業推進委員会:
http://www.gsj.jp/geologyday/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■saveMLAKイベント
東日本大震災によって被災した博物館・美術館(Museum)、図書館(Library)、
文書館(Archive)、公民館(Kominkan)の関係者及び支援者の有志団体による、
saveMLAKによるシンポジウムが開催されます。
緊急討議「東日本大震災 被災支援とMLAK−いまわたしたちにできることは」
日時:2011年4月23日(土)13:00〜14:30
場所:学習院大学(目白) 南3号館203教室 (東京都豊島区目白1-5-1)
http://savemlak.jp/wiki/saveMLAK:Ev/20110423
以下のサイトで各地の博物館の被災状況・救援情報が集約されています。
saveMLAK:
博物館・美術館、図書館、文書館、公民館(MLAK)の被災・救援情報サイト
http://savemlak.jp/
■海底地形名称の提案募集のお知らせ
海上保安庁では、海図や海底地形図などに記載する海底地形の名称を決定する
「海底地形の名称に関する検討会」を7月1日に開催します。
開催にあたり、関係学会等に広く海底地形名称を募集することとしましたので
お知らせします。
提案地名がある場合は、以下の問い合せ先にご連絡いただければ提案書を
送付致します。提案期限は随時とし、今回の検討会に間に合わない場合は
次回検討会に提案いたします。
問い合せ先:海上保安庁海洋情報部航海情報課 主任海図編集官 今井義隆
電話: 03-3541-4201, FAX: 03-3541-4388
検討会で決められた海底地形の名称の紹介:
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KOKAI/ZUSHI3/topographic/topographic.htm
■JABEE 事務局ニュース No. 14(2011/4/21版)
JABEE事務局ニュースは社員(正会員)、賛助会員、理事、監事、顧問、
委員会委員宛に配信されています。
情報のより広い共有のため、会員の皆様にもご転送いたします。
2011/4/21版ニュース PDFはこちら、、
http://jabee.org/OpenHomePage/jabee_e-news_no14_110421.pdf
JABEEホームページ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】連休中のgeo-Flashはお休みです
──────────────────────────────────
次号geo-Flash定期配信日は連休中のため配信をお休みとさせて頂きます。
次回配信は5月17日を予定しておりますので、よろしくお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】訃報
──────────────────────────────────
■ 中世古幸次郎 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
日本地質学会名誉会員、中世古幸次郎氏((財)災害科学研究所 理事)
が平成23年4月21日(木)にご逝去されました(享年86歳)。
これまでの故人の功績を讃えるとともに、謹んでご冥福を
お祈り申し上げます。
なお、通夜、ご葬儀は下記のとおり執り行われますので併せて
お知らせ申し上げます。
記
通 夜:4月23日(土)18時00分〜
ご葬儀:4月24日(日)12時30分〜14時00分
喪 主:中世古 博幸 様
場 所:公益社 千里会館(吹田市桃山台5-3-10)
電 話:06-6832-0034
FAX:06-6831-7984
*ご香典・ご供物の儀はかたくご辞退申し上げますとのことです。
*お問い合わせは、公益社千里会館へご連絡ください。
会長 宮下純夫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flashは送信用であり、返信はできません。
No.137 2011/5/30 geo-flash(臨時)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.137 2011/5/30 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】<水戸大会> 講演申込:6月7日(火)17時締切です!
【2】<水戸大会> オンライン参加登録スタート
【3】geo-Flash No.136 の記事の訂正
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】<水戸大会> 講演申込:6月7日(火)17時締切です!
──────────────────────────────────
オンライン「発表申込」(演題登録)締切は6月7日(火)17時です!
残り10日を切りました。
発表を予定されている方は、期日までに必ず申し込んで下さい。
(郵送での申込みは6月1日(水)必着です)
オンライン水戸大会講演申込:
http://www.geosociety.jp/mito/content0018.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】<水戸大会> オンライン参加登録スタート
──────────────────────────────────
参加登録がオンラインでできるようになりました
2011水戸大会事前参加登録ほか申込:
http://www.geosociety.jp/mito/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】geo-Flash No.136 の記事の訂正
──────────────────────────────────
6月4日(土)開催されるシンポジウム「人工改変地と東日本大震災」の
開催場所が誤っておりました。
正しくは、「明海大学 浦安キャンパス第2研究棟」です。
関係の皆様にご迷惑をおかけしたこと、お詫び申し上げます。
■シンポジウム「人工改変地と東日本大震災」
災害に強いまちづくりをめざして
−房総半島の液状化・津波被害に係わる緊急報告−
日時: 2011年6月4日(土)9:30〜12:45
場所: 明海大学 浦安キャンパス第2研究棟
参加費: 無料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
人類史上初めて落下の観測とその回収に成功した小惑星
昨2010年、小惑星「イトカワ」の物質を地球に持ち帰った「はやぶさ」が話題になりましたが、実はその2年前の2008年に、既に発見されていた小惑星が自ら地球に飛び込んできて、その破片が多数回収されるという事件がありました。しかし、このことは日本ではあまり報道されず、少数の専門家や天文ファン以外にはあまり知られていないようです。そこで、Almahatta Sittaと呼ばれるこの隕石の実物試料を物質科学的に研究している東北大学大学院理学研究科GCOE助教の宮原正明さんに、この隕石の発見・大気圏突入・回収の経緯と、その興味深い構成物質について解説を書いていただきました。
(石渡 明)
人類史上初めて落下の観測とその回収に成功した小惑星
宮原 正明(東北大学理学研究科地学専攻)
皆さんは,2008年10月6日から7日未明(グリニッジ標準時)にかけて,地球の裏側で,人類史上初めての劇的な事件が起きていたことをご存じでしょうか(Jenniskens et al., 2009).事の発端は,米国のある天文台が,名もない小惑星を発見したことに始まります.後に,この小惑星は“2008 TC3”と名付けられます.天文台の研究者が,この小惑星の軌道を計算すると,約20時間後に地球に衝突することが明らかとなりました.この情報は,即座にNASAに送られ,世界中の天文台が協力して,その追跡を行いました.そして,計算通り,その小惑星はスーダン北部の大気圏に突入し,地球へ落下を始めました.幸いにも,この小惑星は,地表に到達する前に空中で爆発し,その破片がサハラ砂漠南東端部(ヌビア砂漠)に降り注ぎました.落下直後から,小惑星の破片の探索が始まり,多くの破片が回収されました.そして,それらは隕石として“Almahatta Sitta 2008 TC3”と呼ばれ,人類史上初めて,落下の観測とその回収に成功した小惑星となりました.
地球近傍には無数の大小様々な小惑星が存在しており,その一部は地球に接近・衝突する可能性があります.カタリナ天文台(米国・アリゾナ州)はそうした危険な小惑星の観測を行っており,2008年10月6日6時39分に小惑星“2008 TC3”を発見しました.発見後,直ぐにその軌道の簡易計算が行われ,地球への衝突コースにあると判明しました.この情報は直ぐにNASAへ送られ,より正確な軌道計算が行われ,10月7日2時45分にスーダン北部、ナイル川東側のヌビア砂漠に落下すると予想されました.また,その小惑星の大きさは2〜5 m程度と見積もられました.この落下情報は,米国だけでなく各国に“警報”として送られ,世界中の天文台や天文家によりその追跡が始まりました.そして,計算通り,7日2時45分40秒にスーダン北部の大気圏に西から突入し,5秒後に北緯20.8度,東経32.2度,高度37kmで爆発し,その東方の広い範囲に落下しました.その爆発は人工衛星と付近を飛行していた国際線のパイロットにより目撃されました.爆発の規模は1キロトン程度と見積もられています.落下後から,スーダン大学とNASAを中心とした探索チームが編成され,小惑星の破片の探索が始まりました.その結果,多くの破片(約4 kg)が回収されました.破片が回収された地域には,鉄道駅以外にこれといったランドマークがなかったため,そのアラビア語での駅名(Almahatta Sitta = 第六鉄道駅)がその破片(=隕石)の名前となりました.
回収された隕石の一部は,世界各国の研究者へ配分され,その岩石・鉱物・化学的特徴が調べられました(例えば,Bischoff et al., 2010; Zolensky et al., 2010).その結果,小惑星“2008 TC3”は主として,エコンドライトの一種であり超苦鉄質岩,ユレイライトで構成されていることが分かりました.より厳密には,異なる組成の砕屑岩の混合物で構成される,ポリミクトユレイライトです.ですので,試料ごとにその岩石学的・鉱物学的特徴が大きく異なっています.また,一般的なユレイライトの空隙率は9 %程度なのですが,“2008 TC3”のユレイライトの空隙率は25−37 %と非常に高く,いわば,“すかすかな惑星”だったことが分かります.ユレイライト以外にも,少量のHやEタイプのコンドライトが発見されており,“2008 TC3”の構造が不均質であることを物語っています.もっとも,長期間宇宙空間を漂って小惑星が形成される訳ですから,この不均質性こそが小惑星のあるべき姿であるとも考えられます.小惑星“2008 TC3”の成り立ちは,各国の研究者が目下研究中ですが,元々あったユレイライト母天体が他の天体の衝突によって破壊され,その破片と別の天体(EやHタイプコンドライトの母天体)起源の破片が一緒に再集積したのではないかと推測されています.
図1.粗粒なユレイライトの電子顕微鏡写真.オリビン(Ol)の粒間にグラファイト(Gra)とダイアモンド(Dia)が存在する.その周囲は,鉄に枯渇したオリビン,エンスタタイト(En)と金属鉄(Fe)が分布している.
さて,私は幸運にも,“2008 TC3”の破片の一部を入手することができました.私が入手したのは,ユレイライトとEH6,EL6及びH5タイプコンドライトです.ユレイライトは粗粒なものと細粒なものに分けられ,前者は深成岩,後者は砕屑岩に似た岩石組織を示しています.現在,私が重点的に調べているのは,粗粒なユレイライトです.粗粒なユレイライトを構成する鉱物は主に粒径が1 mm程度のFa18−20のオリビンです.その他には,エンスタタイト,ピジョン輝石,硫化鉄や金属鉄も僅かに含まれています.ユレイライトの特徴の1つは,炭素質コンドライト同様に,かなりの量の炭素を含むことにあります.走査型電子顕微鏡を用いて,オリビンの粒間や割れ目等を観察すると,粒状或いはブックレット状の炭素質物質が見つかりました(図1).さらに,レーザーラマン分光法で,これらの炭素質物質を調べたところ,グラファイトとダイアモンドが存在していることが分かりました.炭素質物質が存在する周囲では,オリビン中のFa成分が枯渇しており(Fa2-4),細粒のエンスタタイト(Fs2-5)と金属鉄が晶出していました.オリビンのFa成分は,炭素質物質から離れるに従って元の値(Fa18−20)に戻っていき,エンスタタイトと金属鉄は観察されなくなります.これは,おそらく,オリビンが炭素質物質により還元され,エンスタタイトと金属鉄に分解された結果であると予想しています.このようなユレイライト中でのオリビンの還元分解は古くから知られていますが,その分解メカニズムは未だに解き明かされていません.また,グラファイトやダイアモンドの成因についても,母天体深部胚胎説,衝撃波説や化学気相成長(CVD)説など複数の説があり,結論は得られていません.
図2.(上)当研究室に導入されている収束イオンビーム(FIB)加工装置,(下)加工(薄膜化)途中の試料.
ユレイライト中のオリビン還元組織,グラファイトやダイアモンドはマイクロメートルオーダーの大きさであり,その鉱物学的特徴を調べるのも一苦労です.そこで,私は現在,収束イオンビーム加工装置(FIB)と透過型電子顕微鏡(TEM)を利用し,オリビンの還元分解メカニズムとグラファイトやダイアモンドの成因をナノスケールで明らかにする試みを行っています.FIBは細く絞ったガリウムイオンビームを試料上で走査し,試料内の数ミクロンの特定部位を切り出す(薄膜化)ことができます.すなわち,FIBを使用することで,TEMにより観察したい部位を確実に取り出すことが可能となります. 私は,こうしたナノテク機器を駆使することで,原始太陽系で起きた,惑星内部での炭素質物質の物質進化や循環,そしてそれがもたらした惑星の進化過程を解き明かすことが出来ると考えています.また,ユレイライトから得られた知見が,近年,大きな問題となりつつある地球内部での炭素の大循環の謎を解き明かす手掛かりともなると考えています.
【参考文献】
[1] Jenniskens P. and 34 authors. (2009) The impact and recovery of asteroid 2008 TC3, Nature, 458, 485-488.
[2] Bischoff A., Horstmann M., Pack A., Laubenstein M., and Haberer S. (2010) Asteroid 2008 TC3-Almahata Sitta: A spectacular breccia containing many different ureilitic and chondritic lithologies. Meteoritics & Planetary Science, 45, 1638-1656.
[3] Zolensky M. and 24 authors. (2010) Mineralogy and petrography of the Almahata Sitta ureilite. Meteoritics & Planetary Science, 45, 1618-1637.
(原稿受付 2011年4月7日)
【お詫びと訂正】 初出時にヌビア砂漠の名称を誤って表記しておりました.お詫びして訂正させていただきます.
ネガフィルムからポジ画像をデジカメで簡単に作る方法
ネガフィルムからポジ画像をデジカメで簡単に作る方法
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
1.はじめに
中年以上の研究者は、デジカメ普及以前に撮影したフィルムやプリントの写真を多量にお持ちだと思う。それらをプレゼンなどで使用したい場合、プリントであればスキャナで取り込むのが最も簡単で、高画質のデジタル画像が得られる。しかし、昔のカラープリントは年数の経過とともに褪色・変色していることがあり、もとのネガがあればそれから直接デジタル化した方が美しい画像になる。カラーのネガフィルムやポジ(スライド)フィルムをデジタル化したい場合は、フィルムスキャナ(最近の機器の多くはプリントのスキャナとしても使える)を用いるのが一般的である。しかし、多量のフィルムをデジタル化するならともかく、当面必要な数枚の画像をデジタル化するのに、わざわざフィルムスキャナを購入するのは不経済であるし、あまり使用頻度の高くない機械を抱え込むことになりかねない。ここでは、手持ちのデジタルカメラで簡単にネガフィルムから美しいポジ画像を作る方法を紹介する。必要なものは、図1に示すように、デジカメ(できれば一眼レフ)、クローズアップレンズ、フィルムを垂直に保持できる台(不要なプラスチックケースなどを加工して自作)とクリップ、白い紙を貼った厚紙(反射板として使用)、カメラの高さを調節するための適当な厚さの本、そして昼色光の蛍光灯(電球型のものがよい)である。ところで、一眼レフを含めて普通のデジカメには、ネガをポジに反転する機能がついていない。しかし、ネガの画像をデジカメで撮影すれば、ウィンドウズに標準で付属している画像処理ソフトで、この反転操作を容易に行うことができる。この技術ノートの要点は、デジカメを用いたフィルム接写撮影のテクニック、ネガポジ反転に適したカメラの設定、および汎用画像処理ソフトによる反転の方法であり、詳細は以下の通りである。
2.カメラとレンズ
図1.デジタルカメラを用いたフィルム接写の様子。カメラは適当な厚さの本の上に置いてあり、レンズの前部にNo. 10のクローズアップレンズが取り付けてある。被写体のフィルムはプラスチックケースを加工して自作した保持台にクリップで取り付けてある。画面上部に光源があり(消灯)、奥にザラザラの白紙を厚紙に貼った反射板が斜めに置いてある。 レンズとフィルムに上から直接光が当たらないよう遮光した方がクリアな画像になる。
デジタル一眼の場合、中間リング、ベローズ、スライドコピアなどの接写システムを用いれば収差のない高画質の画像が得られるが(図2a)、そのようなシステムがなくても、レンズの前にねじ込み式で取り付けるクローズアップ(拡大)レンズを購入すれば、実用上問題ない画質の接写撮影ができる。例えば、デジタル一眼に附属している18〜55 mmの標準ズームの場合、No. 10(焦点距離100mm)のクローズアップレンズを取り付けて望遠側(55 mm)で撮影すれば、36×24 mmのフィルム画像を画面いっぱい(ないしそれ以上)に拡大できる。絞りをF8〜F11に絞って撮影すれば、周辺までピントが合った、比較的収差の少ない画像が得られる。若干の糸巻き型(内側に凸)の歪曲収差と色収差が周辺部で認められるが、あまり目立たない(図2b)。もちろん、自分が使っているカメラのレンズと同一直径のクローズアップレンズを選ぶ必要がある。例えばケンコー社のNo. 10レンズは49〜58 mmφの各サイズがあり、直径によって値段が異なる(定価5200〜6500円)。クローズアップレンズはフィルムの接写以外にも、野外や室内で岩石(後述するように薄片全体の偏光撮影にも適する)、鉱物、化石、動植物などの手軽な拡大撮影に利用でき、用途が広い。接写用交換レンズ(マクロレンズ)を利用すればもっと高画質の接写ができるが、かなり高価である。また最近は、一眼レフでなくても、本体だけで等倍以上の接写が可能な安価のデジカメがあるので、それを用いる手もあるが、樽型(外側に凸)の歪曲収差が顕著な画像になるので、注意が必要である(図2c)。
図2.(a)接写専用のシステム(ベローズ、スライドコピア)に取り付けたデジタル一眼レフ(レンズは焦点距離80 mm)で撮影した格子模様。画面の周辺部でも歪曲収差がない。
(b)接写システムを使用せず、焦点距離55 mmのレンズにNo. 10クローズアップレンズを取り付けたデジタル一眼レフ(図1)で接写した格子模様。若干糸巻き型の歪曲収差があるが、目立たない。
(c)通常の接写機能つき小型デジカメで撮影した格子模様。クリアな画像ではあるが、樽型の歪曲収差が顕著である。線の間隔はいずれも5 mm。
3.フィルム保持台と光源および反射板
例えば図1にあるような、机の上に原版フィルムを垂直に立てられるように工夫したフィルム保持台を、不要なプラスチックケースを加工するなどして自作する。レンズの前面にクローズアップレンズを取り付けたカメラを適当な厚さの本の上に置き、フィルムがカメラレンズに対して垂直になるように配置して画像の位置を調整する。電球型の昼光色蛍光灯などを光源とし、白い紙に反射させた光を裏からネガに当てて接写撮影する。できれば、フィルムの前面やカメラのレンズに直接光源からの光が当たらないように厚紙などで覆う方がよいが、それがなくても画質への影響は少ない。図1では覆いを設置していない。
これは机の上にカメラ、被写体、光源を横に並べるやり方であるが、蛍光灯ライトボックスの上にフィルムやスライドを乗せ、三脚に固定したカメラで上から撮影する縦方向の配置でもよい。
4.カラーバランスと露出補正の設定
カラー用のネガフィルムはオレンジ色なので、この影響を除去するため、カメラのホワイトバランス(WB, 色温度)を2000〜2500Kに設定する。その設定ができない場合は「電球色」(3000K程度)でもよいが、反転するとやや青っぽくなる。この場合、レンズに青フィルターをつけて撮影するか、または撮影後に画像処理ソフトで赤と緑を明るくするように色を調整する。カメラの露出補正を+1.0〜+1.3程度にして、やや薄いネガ画像を撮影する。自分のカメラで最良の設定を見出すためには、多少の試行錯誤が必要である。
5.撮影モードの設定
撮影モードを「絞り優先」(「A」)に設定し、絞りをF8〜F16にして撮影する。絞り開放またはF4以下で撮影すると周辺部で暗くなったりピントが甘くなったりする。デジカメが露出時間を自動調節するので、シャッター速度はあまり気にしなくてよいが、光源が暗いと露出時間が長くなり、振動による画像のブレが生じやすくなる。12〜20Wの昼色光電球型蛍光灯を用いれば問題ない。
6.ソフトウェアによるネガポジ反転処理
撮影したネガ画像のJPEGファイルを画像処理ソフトで読み込んで色反転する。例えばウィンドウズの「アクセサリー」に標準で附属している「ペイント」の場合、読み込んでから、「変形」→「色の反転」とクリックするとネガからポジへの反転ができる。「ペイント」では明るさ、コントラスト、色調などの調整はできないが、カメラの色温度や露出の設定を上のように行えば、反転しただけで大体良好な明るさと色調の美しいポジ画像が得られる。ポジ画像をディスクに書き込み、それをやはり標準でウィンドウズに装備されている「フォトギャラリー」で開くと、明るさ、コントラスト、色温度、色の濃淡、色の鮮やかさなどを調整でき、画像の回転やトリミングもできる。ただしフォトギャラリーでは色の反転はできない。画像のネガポジ反転と明るさなどの調整が同時にできる無料ソフトとしてJTrim(著作権所有:WoodyBells)があり、処理速度も速くて便利である。また、白黒フィルムのポジ画像も同様の要領で作成できる。ポジのスライドをそのままデジタル画像にするのはもっと簡単である(反転処理の必要がない)。さらに、振動方向が直交するように重ねた(暗く見える)2枚の偏光板の間に岩石薄片を挟んで、上と同様にクリップで保持台に固定して撮影すれば、手軽に薄片全体の直交ニコル(偏光板1枚なら単ニコル)の偏光画像を撮影できる(これも反転の必要はない)。
以上、手持ちのデジカメで手軽にネガからポジに反転する方法を述べた。この拙文が大震災後のネガティブな雰囲気をポジティブに反転する一助になれば幸いである。初稿を読んで貴重なコメントをいただいた住鉱資源開発株式会社の二ノ宮淳氏と長尾尚顕氏、株式会社地圏総合コンサルタントの棚瀬充史氏に感謝する。
(原稿受付 2011年5月12日)
No.135 2011/5/17 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.135 2011/5/17 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】水戸大会の講演申込(J-STAGE)受付開始
【2】コラム:ネガフィルムからポジ画像をデジカメで簡単に作る方法
【3】電子書籍スタート! 日本地質学会から出版しませんか
【4】フォトコンテスト表彰式開催
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】20万分の1日本シームレス地質図 スマートフォン版公開:産総研
【8】NYSより若手研究者へのアンケートのお願い
【9】地質の日イベント記事募集!
【10】公募情報・各賞情報
【11】geo-Flash No.134 の記事の訂正
【12】訃報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】水戸大会の講演申込(J-STAGE)受付開始
──────────────────────────────────
大会予告記事(ニュース誌4月号)でお知らせしましたように、5月10日より講演申込が始まっております。オンラインの締切は【6月7日(火)17時】です。
今大会の地質学会担当セッションでは、次の新ルールが適用されます。
1) 発表者=発表申込者とするが、発表者が筆頭著者である必要はない(筆頭者に会員・非会員等の条件なし)。例えば,非会員の卒業生をファーストにして、指導教員(会員)がセカンド以下で発表することが可能。
2) 複数著者の場合、講演要旨には発表者に○(マル印)をつける。
3) 1人最大2題発表できる(発表負担金の支払い必要)。
詳細については大会予告記事(ニュース誌4月号)をご確認下さい。これらの新ルールを踏まえて、多くの会員の皆様に講演申込をしていただきたく、お願い申し上げます。
行事委員会
オンライン講演申込はこちらから、、、
http://www.geosociety.jp/mito/content0018.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】コラム:ネガフィルムからポジ画像をデジカメで簡単に作る方法
──────────────────────────────────
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
中年以上の研究者は、デジカメ普及以前に撮影したフィルムやプリントの写真を多量にお持ちだと思う。それらをプレゼンなどで使用したい場合、プリントであればスキャナで取り込むのが最も簡単で、高画質のデジタル画像が得られる。しかし、昔のカラープリントは年数の経過とともに褪色・変色していることがあり、もとのネガがあればそれから直接デジタル化した方が美しい画像になる。(中略)ここでは、手持ちのデジタルカメラで簡単にネガフィルムから美しいポジ画像を作る方法を紹介する。
続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0308.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】電子書籍スタート! 日本地質学会から出版しませんか
──────────────────────────────────
ここ最近の電子書籍関連サービスの急速な発展は目を見張るものがあります。
電子書籍はパソコン、専用端末,携帯電話等に保存・閲覧する書籍であるため、カラー写真や動画をふんだんに盛り込むことができ,本棚のスペースをとらず、色あせることもありません。また出版する側にとっても、印刷費、輸送費、在庫リスクが極めて低いというメリットがあるため、採算性は低くとも重要な書籍を出版することができます。また絶版になるリスクもほとんどありません。このように電子書籍は専門書にとって大きな可能性があります。
そこで日本地質学会では、新たに電子書籍出版サービスを開始いたします。例えば、調査報告書、研究プロジェクト総括、地学教科書、地学実験ノート、巡検ガイド、普及教育書、など地質学に関する幅広い原稿を募集いたします。
詳細は、、、http://www.geosociety.jp/news/n82.html
企画出版担当理事
山口耕生
広報担当理事
坂口有人・内藤一樹
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】フォトコンテスト表彰式開催
──────────────────────────────────
5月14日(土)に神奈川県立生命の星・地球博物館にて行われた「地質の日」イベント内にて、フォトコンテストの表彰式が行われました。
最初に審査委員長である白尾元理さんから、各入選作の講評をいただきました。30分という限られた時間の中、作品の地質的背景や入選としたポイント等について解説していただきました。
当日は入選者のうち優秀賞の菱川尚駒さん、入選の伊藤建夫さんが出席され、審査委員長の白尾元理さんから表彰状と賞金が手渡されました。写真の構図やタイミングが絶妙だと講評を受けた菱川さんは「ただの旅好きなのですが、とても嬉しいです。ありがとうございます。」と喜びを語られました。応募時にジオパークについてもコメントを寄せて頂いていた伊藤さんは、北海道からお越し下さいました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報
──────────────────────────────────
■北海道支部: 2011年度「地質の日」記念展示
「豊平川と私たち ―その生いたちと自然―」
場所: 北海道大学総合博物館
日時: 2011年3月8日(火)〜5月29日(日)
同時開催企画: 豊平川の化石〜 化石が語る“札幌の海”
場所: 札幌市博物館活動センター
日時: 2011年5月7日(土)〜7月30日(土)
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
■中部支部:2011年支部年会
場所:名古屋大学東山キャンパス環境総合館1階レクチャーホール
日程:2011年6月11日(土)〜12日(日)
http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■IGCP-507第6回国際シンポジウム(北京)
「白亜紀のアジア古気候:その多様性,原因および生物と環境の反応」
2011年8月15日(月)〜16日(火)
テーマセッション「熱河生物群と熱河層群」および一般セッション
場所: 中国地質大学・北京校
2011年8月17日(水)〜20日(土):巡検
場所: 熱河生物群産地ほか遼寧省の非海成白亜系分布地
問い合わせ先: IGCP-507国内コーディネーター 長谷川卓(金沢大)
E-mail: jh7ujr@kenroku.kanazawa-u.ac.jp
■石油技術協会−海洋研究開発機構 共催シンポジウム
「地下圏微生物と石炭起源の炭化水素資源」
― 西太平洋沿岸海域におけるエネルギー資源と生成メカニズム ―
近年,地下生命圏研究の進展により,海底下深部環境での微生物の果たす役割が次々と明らかになっています.当シンポジウムでは,炭化水素資源と微生物の関係について議論し,その全体像モデルを参加者全員で共有することを目的としています.
日 時:2011年6月6日(月)午後1時〜5時
場 所:東京大学本郷キャンパス 小柴ホール
東京都文京区本郷7-3-1(理学部1号館2階)
共 催:石油技術協会,海洋研究開発機構
後 援:日本地球掘削科学コンソーシアム(J-DESC)
参加費:無料(事前申込み不要)
プログラム等,詳細は以下のURLでご確認ください.
http://www.japt.org/news/2011/files/h23_kaiyoukenkyu.pdf
問い合わせ先:森田澄人(産総研)
Email: morita-s@aist.go.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】20万分の1日本シームレス地質図 スマートフォン版公開:産総研
──────────────────────────────────
産業技術総合研究所地質調査総合センターが公開している20万分の1日本シームレス地質図にスマートフォン、iPad用のページが加わりました。
スマートフォン片手に巡検など、いろいろな使い方ができそうです。
『20万分の1日本シームレス地質図 スマートフォン版』
http://riodb02.ibase.aist.go.jp/db084/
(Internet Explorerには対応していません。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】NYSより若手研究者へのアンケートのお願い
──────────────────────────────────
■東日本大震災に関する地球惑星科学系若手研究者へのアンケートの実施
このたびの東日本大震災に際して、地球惑星科学に携わる若手研究者・学生の皆さんが現在抱えている問題や不安、必要な支援を調査するためのアンケートを実施します。
『東日本大震災に関する地球惑星科学系若手研究者へのアンケート』
http://enq-maker.com/iFL17iN
問い合わせ先:地球システム・地球進化ニューイヤースクール(NYS)
事務局アンケート係
Email: earth21-311earthquake@m.aist.go.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】地質の日イベント記事募集!
──────────────────────────────────
各支部で行われた地質の日イベントの様子をニュース誌などで紹介していく予定です。イベントの報告や、また、会員の皆さんが各イベントを訪れた時の感想や写真等を事務局(geo-flash@geosociety.jp)までお寄せください。
(5月末締切)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■新潟大学:教育研究院自然科学系環境科学系列(准教授)(7/19)
■広島大学大学院:理学研究科地球惑星システム学専攻(助教)(7/15)
■大阪市立大学大学院:理学研究科・理学部地球学教室(特任講師)(5/13)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】geo-Flash No.134 の記事の訂正
──────────────────────────────────
geo-Flash No.134臨時号の解説記事「人類史上初めて落下の観測とその回収に成功した小惑星」に、著者の責任による誤りがありました。謹んでお詫びいたしますとともに、下記の通り訂正させていただきます。
【誤】
1段落目8行目 その破片がナミビア砂漠に降り注ぎました.
2段落目5行目 スーダン北部のナミビア砂漠に落下すると予想されました.
2段落目8行目 大気圏に突入し,その5秒後に高度37 kmで爆発しました.
【正】
1段落目8行目 その破片がサハラ砂漠南東端部(ヌビア砂漠)に降り注ぎ
ました.
2段落目5行目 スーダン北部、ナイル川東側のヌビア砂漠に落下すると
予想されました.
2段落目8行目 大気圏に西から突入し,5秒後に北緯20.8度,東経32.2度,
高度37kmで爆発し,その東方の広い範囲に落下しました。
宮原正明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】訃報
──────────────────────────────────
────────────────────────────
■柴田松太郎名誉会員 ご逝去
────────────────────────────
日本地質学会名誉会員 柴田松太郎氏が、平成23年4月3日(日)にご逝去されました(享年85歳)。
これまでの故人の功績を讃えるとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
なお、ご葬儀はすでに執り行われたとのことです。
会員の皆様に、謹んで御連絡申し上げます。
会長 宮下純夫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.136 2011/5/25 geo-flash(臨時)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.136 2011/5/25 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】シンポジウム「人工改変地と東日本大震災」開催 (6/4)
【2】公開シンポジウム「緊急集会:被災した自然史標本と博物館の復旧・
復興にむけて−学術コミュニティは何をすべきか?」開催 (6/6)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】シンポジウム「人工改変地と東日本大震災」開催 (6/4)
──────────────────────────────────
日本地質学会環境地質部会他の主催によるシンポジウム「人工改変地と
東日本大震災」が来週(6/4)に急遽開催される運びとなりました。
震災直後からの千葉県内の調査を中心とした、液状化に関する講演が予定
されています。
■シンポジウム「人工改変地と東日本大震災」
災害に強いまちづくりをめざして
−房総半島の液状化・津波被害に係わる緊急報告−
日時: 2011年6月4日(土)9:30〜12:45
場所: 明治大学 浦安キャンパス第2研究棟
参加費: 無料
<内容>
1. 人工地層の出来方と液状化−流動化被害: 1987年千葉県東方沖地震での
被害との比較も含めて(千葉県環境研究センター 風岡 修)
2. 浦安地区における液状化-流動化調査から
(千葉県環境研究センター 香川 淳)
3. 土地液状化による市民意識の変化と不動産取引時における地圏域説明の
必要性(明海大学 本間 勝)
4. 環境地質からみた地層の液状化防止対策
(環境地質コンサルタント 上砂 正一)
5. 東北太平洋沖地震発生メカニズムの疑問と房総を襲った津波
(茨城大学名誉教授 楡井 久)
詳しくは、、、
http://www.jspmug.org/envgeo_sympo/2011sympo/sympo110604.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】公開シンポジウム「緊急集会:被災した自然史標本と博物館の復旧・
復興にむけて−学術コミュニティは何をすべきか?」開催 (6/6)
──────────────────────────────────
東日本大震災で被災した自然史標本と博物館を救うために何が出来るのかを
話しあう公開シンポジウムが開催されます。
■公開シンポジウム「緊急集会:被災した自然史標本と博物館の復旧・
復興にむけて−学術コミュニティは何をすべきか?」
日時:2011年6月6日(月)13:30〜17:10
場所:日本学術会議 6階会議室 6-C(1〜3)(分科会・控室として会議室1室を使用)
主催:統合生物学委員会自然史・古生物学分科会
共催:自然史学会連合
後援:日本古生物学会、日本人類学会、日本植物分類学会、生物多様性JAPAN
分科会の開催:分科会開催予定
開催趣旨:東日本大震災による自然史標本及びその収蔵施設被害の状況を
把握し、迅速な救済を支援するとともに、将来にわたり標本と施設を激甚
災害から守るための対策を学術会議として提言するために、情報収集と
意見交換を行う。
<内容>
第一部:13:30-16:10:いまを知る
13:30-13:35:開催あいさつ
西田治文(日本学術会議連携会員・中央大学理工学部教授)
13:35-13:45:緊急集会の趣旨について
真鍋 真(日本学術会議連携会員・国立科学博物館主任研究員)
13:45-14:05:文化財レスキューについて(六川真五:東京文化財研究所)
14:05-14:25:岩手県の状況報告(大石雅之:岩手県立博物館)
14:25-14:45:宮城県の状況報告(佐々木理:東北大学総合学術博物館)
14:45-15:05:福島県の状況報告(竹谷陽二郎:福島県立博物館)
15:30-15:50:水族館の事例報告(岩田雅光:アクアマリンふくしま)
15:50-16:10:岩手県山田町に寄贈した海藻標本について(吉崎誠:元東邦大学)
第二部:16:10-17:00:具体的なアクションプランを作るために、これからを考える
進行:西田治文・真鍋真
登壇者:第一部の報告者に加えて、文科省社会教育局及び文化庁担当者
などパネリストによる討論。
17:00-17:10:結語
斎藤靖二(日本学術会議連携会員・神奈川県立生命の星・地球博物館館長)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.152 2011/9/14 geo-flash(臨時) 日本代表 金メダル!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.152 2011/9/14 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】地学オリンピック:日本代表 金メダル!
【2】水戸大会アンケート募集!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】地学オリンピック:日本代表 金メダル!
──────────────────────────────────
第5回国際地学オリンピック大会が、イタリアのモデナ周辺にて開催されま
した.世界26ヶ国104名の高校生が9月5日から14日までの10日間に渡って
地球科学の祭典に参加しました.
その結果日本代表は下記の輝かしい成績を残しました.
金メダル:
渡辺 翠 (桜蔭高等学校)
銀メダル:
浅見 慶志朗 (埼玉県立川越高等学校)
松澤 健裕 (栄光学園高等学校)
銅メダル:
松岡 亮 (北海道旭川西高等学校)
選手の皆さんは15日に帰国します.暖かいご声援ありがとうございました.
来年はアルゼンチンです!どうぞよろしくお願いします.
帰国後 文科省 神本美恵子 文部科学大臣政務官を表敬訪問しました.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】水戸大会アンケート募集
──────────────────────────────────
水戸大会の思い出も鮮やかなうちに、水戸大会アンケートに是非ご協力下さい。
学術大会・見学旅行・関連行事をより良くするために、会員の皆様の声が必要です!
水戸大会 Webアンケート
ご協力よろしくお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
花崗岩類からの放射線量
花崗岩類からの放射線量
石原 舜三 (産業技術総合研究所)
東日本大震災以降、放射線量への関心が急速に高まっており、花崗岩の放射線量についての執筆依頼を編集部から受け、筆をとった。筆者と放射線との出会いはこれが2回目である。最初は広島の原爆である。小学校6年生の1945年8月6日朝、爆心地から6km東方の小学校の2階で、B29を目視追跡していた私は爆裂の閃光を真正面から浴びた。当時、それが原子爆弾によるものとは知る由もなく、5万トンくらいの爆弾であろうかと友達と話しあった。その2日後に行方不明者を探しに近所の老婆の手を引いて広島市内に入り、瓦礫を掘り起こした。広島市内は焼け野原であったから、放射性埃などを吸い込む内部被曝の可能性は少なかったであろうが、残留放射能下を歩き続けたことは明らかである。
このような事故的なことを除くと、我々が浴びる自然界の放射能は空から来る宇宙線に由来するものと、地殻の諸岩石の放射性元素(K, Th, U)に起因するものとに大別される (Wollenberg and Smith, 1990)。富士山頂のように高度が大きく岩石が玄武岩で放射性成分に乏しい特殊な個所を除けば後者により大きく左右され、地殻物質では広義の花崗岩類が特に重要な放射線源であると、一般に解釈されている(古川, 1993; 湊, 2006; 今井, 2011)、しかし花崗岩研究者からみると、それほど単純ではなく、花崗岩の種類によって大きく異なる。
花崗岩の名称は狭義と広義に用いられており、狭義には石英20%以上、斜長石/カリ長石=2/1〜1/9の粗粒な深成岩であり、広義にはこれに、より斜長石や苦鉄鉱物に富む花崗閃緑岩・トナル岩・石英閃緑岩などを含めた深成岩に対して、“花崗岩類”として用られる。またアルカリ量比によってアルカリ岩/カルクアルカリ岩、酸化度の違いによって磁鉄鉱系/チタン鉄鉱系、起源物資の違いによってS/Iタイプ、アダカイトなどにも分けられる。
第1図.西南日本の岩株型、強放射能花こう岩類 (早瀬、1961に加筆)。
ある種の花崗岩類がγ線を多く出すことは、1955年からの日本のウラン調査でジープに放射線測定装置を積んだカーボーン調査、地質家がガイガー・シンチレーション カウンターなどを持ち歩き測定する“マンボーン”調査などにより直ちに明らかにされた。早瀬(1961)は花崗岩中の微量ウランの研究過程において、山陽帯のストック状岩体が特に強放射性であることを発見し(第1図)、花崗岩の産状と放射線量との関係を指摘した。私達の現在の知識では、放射線量は産状よりも起源物質による規制が大きい。ここではその1例を紹介してみたい。
花崗岩質マグマは高熱流量変動帯である島弧に最も多く貫入し、その起源は沈み込む海洋底地殻から大陸地殻最下部、更には大陸地殻中部と様々である。したがって起源物質も初生の玄武岩・斑れい岩から古期花崗岩・変成岩類まで変化に富んでいる。北上山地の花崗岩類は海洋底地殻の溶融物と考えられるアダカイトを含み、低いSr初生値などから海洋底地殻と大陸地殻下部の苦鉄質岩が溶融したものと考えられる。北上山地で最大規模の遠野岩体(630 km2)は山地全体の花崗岩類の平均的な性質を持つものと思われるが、そのK2O, Th, U含有量は極めて低いものに属する(第2図)。これよりさらに低レベルの岩体に、神奈川県の丹沢、甲府岩体の芦川型などがある。
第2図.花崗岩マグマ起源の相違に基づく放射性元素量。遠野岩体は金谷(1974)、土岐-苗木岩体はIshihara and Murakami (2006)ほかによる。
一方、岐阜県土岐-苗木地方に露出する山陽帯の花崗岩類は土岐岩体の一部で花崗閃緑岩質であるのみであり、全体的に花崗岩質である。これら花崗岩類は磁鉄鉱を含まないチタン鉄鉱系に属し、そのSr初生値は高く、そのマグマ起源は大陸地殻内の堆積岩や古期花崗岩類と考えられる。このように対称的に異なる起源を持つ花崗岩類は平均値として下記の放射線元素量を持つ。
遠野岩体:
K2O 2.17 %,
Th 6.07 ppm,
U 1.98 ppm
(n=37)
土岐-苗木岩体:
K2O 4.49 %,
Th 27.8 ppm,
U 7.3 ppm
(n=14)
これらの値からMinato (2005)に従って、地上1mにおける線量率 (D) = 5.4CU + 2.7CTh + 13.0CK を求めると、両者には3.1倍の開きが生じ、同一種岩石から得られる放射線量としては大きな違いである。花崗岩類に見られるこの様な地域差はウラン鉱床の生成にも関係している。
日本のウラン鉱床探査では二つの大規模鉱床が発見された。最大の鉱床は東濃地方の中新世瑞浪層群基底部の土岐きょう炭累層に胚胎する堆積型の鉱床で、基盤の土岐花崗岩(第1図)の風化面の直上に産出する。ウランに富む土岐花崗岩の風化によって流出したウランが中新世母岩に固定されたものである。しかしその多くがゼオライトや粘土鉱物に吸着されているために、ウランを経済的に取り出すことが困難である難点がある。この性質は、現在、福島原発で放射性物質除去に使われている。第2位の人形峠鉱床(第1図)は、我が国で最初に発見された堆積型ウラン鉱床であり、かつU-REE-Caリン酸塩鉱物である人形石を産することで著名である。ここでもウランに富む風化花崗岩直上の鮮新世の旧河川沿いに鉱化作用が何箇所かで生じ、その起源は花崗岩中の微量のウランと推定されている。
このように私達が浴びる放射線量は地質、岩石の種類によって数倍以上は簡単に異なる。岩石名は主成分によって付けられるから、岩石名がわかっても詳しく調べなければ放射線量の多少はわからない。1950-60年代の岐阜県苗木地方では、花崗岩やペグマタイトに由来する放射性鉱物を集めて腕輪にはめ込み、健康バンドとして販売していた。近傍にはラジウム鉱泉も存在し、人々が愛用した。筆者は土岐-苗木花崗岩に近い性質を持つ広島花崗岩体の風化土壌の上で遊び育ち、かつ花崗岩やウラン鉱床の研究に従事したから同期生よりも多くの放射線を受け、未だに元気であると思っている。
【文献】
古川雅英(1993) 日本列島の自然放射線レベル. 地学雑誌、v. 102, 868-877. [Journal@rchive]
早瀬一一(1961) 花こう岩中のウランの存在状態. ウラン、その資源と鉱物. 朝倉書店.p. 190-199.
今井 登 (2011) 日本の自然放射線量. 日本地質学会 News, v. 14, 6-7.
Ishihara, S. and Murakami, H. (2006) Fractionated ilmenite-series granites in Southwest Japan: Source magma for REE-Sn-W mineralizations. Resource Geology, v. 56, no. 3, 245-256.
金谷 弘 (1974) 北上山地の白亜紀花崗岩類のカリウム・トリウム・ウラン及び帯磁率. 地質調査所報告, 251, 91-120.
Minato, S. (2005) Uranium, thorium and potassium concentrations in Japanese soils. Radioisotopes, 54, 509-515. [Journal@rchive]
Wollenberg, H.A. and Smith, A.R. (1990) A geochemical assessment of terrestrial γ–ray absorbed dose rates. Health Physics, v. 58, 183-189. [Abs.]
(原稿受付 2011年6月21日)
No.138 2011/6/7 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.138 2011/6/7 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
------------------------------
水戸大会関連情報
【1】講演申込:締切延長 6/8(水)17時!
【2】ランチョン・夜間小集会 間もなく申込締切です
【3】プレス発表会へのご協力のお願い
【4】市民向けポスター展示・説明会に参加しませんか?
------------------------------
【5】東日本大震災対応の取り組みについて
【6】地質学雑誌の「短報」がなくなりました!
【7】IGCP585 第5回 国際シンポジウム「海底地すべりとその影響」
【8】「日本の地質構造百選」候補地・写真大募集:締切6月末
【9】本の紹介:「ゆかいな理科年表」スレンドラ・ヴァーマ著
【10】地質の日イベント報告
【11】第34回万国地質学会議(IGC)ブリスベン大会: Second Circular公開
【12】支部情報
【13】その他のお知らせ
【14】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】<水戸大会> 講演申込:締切延長 6/8(水)17時!
──────────────────────────────────
日本地質学会第118年学術大会・日本鉱物科学会2011年年会合同学術大会(水戸大会)「いま,地球科学に何ができるか?」
多くの方々にご講演いただくため、講演申込の締切を延長いたしました。
お申し込みをお待ちしています。(日本地質学会行事委員会)
オンライン講演申込締切:6月8日(水)17時厳守(郵送分は締切ました)
詳しくは,大会HPをご覧下さい。
http://www.geosociety.jp/mito/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】<水戸大会> ランチョン・夜間小集会 間もなく申込締切です
──────────────────────────────────
水戸大会でのランチョン・夜間小集会の開催を希望する方は、行事委員会まで申し込んでください。
申込締切が 6/10(金)に迫りましたので、お忘れなく!
詳しくは、、、
http://www.geosociety.jp/mito/content0035.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】<水戸大会> プレス発表会へのご協力のお願い
──────────────────────────────────
平素より日本地質学会の活動にご協力頂きましてありがとうございます。
日本地質学会では、学術大会の際に、学術大会や地質情報展の開催案内、そして「特筆すべき研究成果」等を開催地および文科省の記者クラブに情報提供してまいりました。特に開催地での記者会見には、例年多くの報道機関の方が来場され、TV、新聞等で取り上げてもらっております。
本年も水戸大会においてプレス発表会を開催する予定です。会員皆様の学術活動が広く報道されることは、地質学全体にとってプラスになることですから、この機会に会員皆様の成果を「特筆すべき研究成果」としての発表くださりますようお願いいたします。皆様からの推薦をもとに、会見にマッチした資料を準備いたしますので、支部、部会、会員皆様からの自薦・他薦等、幅広い情報をお待ちしております。
詳しくは、、、
http://www.geosociety.jp/mito/content0043.html
プレス発表についてのQ&Aも準備いたしました。
http://www.geosociety.jp/mito/content0043.html#QA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】<水戸大会> 市民向けポスター展示・説明会に参加しませんか?
──────────────────────────────────
秋の学術大会では、いつも開催地のホットなエリアで市民向けの地質情報展が催されています。この地質情報展は、それぞれの地方新聞やローカルニュースでも積極的に取り上げられ、多くの皆様がご来場くださり、そして地球科学に関心の高い市民の皆様と専門家との交流の場として成長しています。そこでアウトリーチに関心のある会員の皆様に、情報展のスペースを活用して頂き、地球科学の一段の普及に役立てて欲しいと考えております。そこで下記のポスター展示を募集します。「自分の研究成果を市民に少しでも伝えたい・知ってほしい」という方、ぜひご応募下さい。
詳細・応募方法は、、、
http://www.geosociety.jp/mito/content0044.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】東日本大震災対応の取り組みについて
──────────────────────────────────
1.今後の東日本大震災への取り組み
5月21日の総会で承認された2011年度事業計画においては東日本大震災に対して以下の取り組みが提起され、それらに関連して200万円の震災関連事業費が予算に計上されている。
1.被災会員、被災地域の大学や研究機関などに対する支援
2.災害に関する知識や情報の提供・発信
1)水戸大会でのシンポジウム
2)緊急リーフレットの準備
3)HPの活用
3.地質学的観点からの災害調査と大規模自然災害に対する学術研究の推進
4.提言など
学術会議、政府機関、一般社会に向けた提言
すでに環境地質部会で6月4日にシンポジウム「人工改変地と東日本大震災」を開催したほか、独自の企画をしている専門部会もある。会員各位や各専門部会におかれては、地質学会にふさわしい事業を積極的に提案していただきたい。また、9月の水戸大会では、「大規模災害のリスクマネージメント―東北日本太平洋沖地震に学ぶ―」と題するシンポジウムが企画されているほか、震災に関連する活動の成果や経験を交流する場として夜間集会を持つ予定である。
続きはこちらから、、、
http://www.geosociety.jp/hazard/content0060.html
東日本大震災対応作業部会報告:
http://www.geosociety.jp/hazard/content0059.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質学雑誌の「短報」がなくなりました!
──────────────────────────────────
地質学雑誌編集委員長 小嶋 智
地質学雑誌の「短報」と「論説」の違いは、ページ制限があるかどうか、日本語要旨をつけるかどうか、アブストラクトの制限文字数の多寡という3点のみで、「短報」というジャンルを設ける本質的な意味はほとんどなくなっていました。そこで、地質学雑誌編集委員会では「短報」を廃止することを検討してきましたが、「小藤賞」との関連もあり、簡単には廃止できませんでした。この問題を執行理事会で検討して頂いた結果、(1)「短報」を廃止すること、(2)「小藤賞」は「小藤文次郎賞」と名称を変更し、地質学雑誌掲載論文に限らず広く重要な発見または独創的な発想を含む論文を対象に表彰することが決定されました。(中略)
「短報」が廃止されたからといって、地質学雑誌は、これまでの「短報」のような内容の論文の受付を拒否するものではありません。今後も、新しい発見を「短い論説」として、ぜひ地質学雑誌にご投稿下さい。お待ちしています!
「4ページの論説」の投稿をお待ちしています!
詳しくは、、、
http://www.geosociety.jp/publication/content0002.html#TANPO
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】IGCP585 第5回 国際シンポジウム「海底地すべりとその影響」
(5th International Symposium on Submarine Mass Movements and Their
Consequences; ISSMMTC)
──────────────────────────────────
IGCP585として国際シンポジウム「海底地すべりとその影響」が開催されます。
これは、アジアで初めての海底地すべり国際研究集会であり、京都で開催します。海底変動は通信回線や資源開発へのダメージのみならず、津波など深刻な被害をもたらすことが予測されています。また堆積物の大規模な運搬と堆積は、堆積学やテクトニクスにとっても重要なテーマです。活動的縁辺域における海底地すべり作用は、新しい研究分野であり、世界から精鋭の研究者が集って議論します。
主催:第五回ISSMMTC国内委員会(委員長:山田泰広,京都大学)
共催:日本地質学会
場所:京都大学 芝欄会館
日時:2011年10月24日(月)〜26日(水)
23日と27−28日には野外巡検を企画しています。
ポスター要旨投稿・登録締切:9月1日(木)
詳細:http://landslide.jp
テーマ:
・津波と海底地すべりの関係
・目撃された海底斜面崩壊
・沈み込み帯における斜面削剥メカニズム
・斜面の安定性と流体問題
・トリガーとダイナミクス
・ポスト崩壊プロセス
・海底地すべりは環境変動をトリガーするか?
・大規模崩壊の堆積変形構造
・堆積物物性と斜面安定アセスメント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】「日本の地質構造百選」候補地・写真大募集:締切6月末
──────────────────────────────────
構造地質部会の企画する書籍「日本の地質構造百選」に掲載する候補地と写真の応募締め切りが6月末に迫りました。
みなさまの提案や写真が書籍になるチャンスです!
ホームページに挙がっている候補地の写真をお持ちの方は、ぜひご応募下さい。
候補地リストの写真だけでなく、身近な変形構造の投稿もお待ちしております。
候補地リストと応募はこちらから、、、
http://struct.geosociety.jp/JSGBook2011/Top.html
掲示板も用意しております。みなさまの意見交換にご利用ください。
(「日本の地質構造百選」編集委員会掲示板)
http://jsgbook2011.1616bbs.com/bbs/
奮ってご応募お願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】本の紹介:「ゆかいな理科年表」スレンドラ・ヴァーマ著
──────────────────────────────────
ちくま学芸文庫 筑摩書房
スレンドラ・ヴァーマ著、安原和見訳、2008年、397ページ
ISBN978-4-480-09175-8 C0140 \1,300+税
この本は、インド生まれの科学ジャーナリスト、サイエンス・ライターのヴァーマ氏が、理科、数学、工学の広い分野にわたる科学史上の重要な発明・発見や興味深いエピソード190話をそれぞれ2ページにまとめ、紀元前1700年から2007年まで年代順に書き並べたものである。
第1話は円周率πの話で、神秘的な呪文のような英語の覚え方があるのを始めて知った。私は「身一つ世一つ、生くに無意味、曰く泣く身」と覚えていたのだが、この本の訳者注は少し違っている。最近でもコンピュータで何桁まで計算したというのがニュースになるが、ニュートンが小数点以下15桁まで計算して、「何桁まで計算したなどとお話しするのも恥ずかしいかぎりです。このころはほかになにもすることがなかったものですから」と友人に書き送っているという話は、無意味さを自覚しながら計算しないではいられない学者の気持ちが出ていて面白い。覚え方に関するもう一つの話題に「ピザからナチョへ」がある(p. 394)。My Very Educated Mother Just Served Us Nine Pizzasというのが2006年以前の太陽系惑星の英語での覚え方だったのだが、この年に冥王星が惑星から外されたので、この「9枚のピザ」をメキシコ料理のNachosにするよう国際天文学連合が推奨したというのである。しかし、「非常に教育のあるお母さん」なら、子供に9枚もピザを出したりナチョを出したりせず、もっと健康的なNattos(納豆)にしたらよいと思う。
この本には、科学に関する大ウソや大失敗についての逸話も多い。1835年にニューヨークの新聞が有名な天文学者ハーシェルの名を騙って月に「コウモリ人間」がいるというデマを書きたてた話、1903年にナンシー大学の教授が新しい放射線を発見し、大学の頭文字をとってN線と名付け発表したが、実験がメチャクチャであったことが発覚して「科学史最大の欺瞞」になり、却って大学の不名誉になってしまった話、1912年に発見されたピルトダウン(ドーソン)原人の化石が全くの偽物だったという話、1925年にテネシー州の当時の法律「神による人間の創造を否定する学説を教えてはならない」に違反したとして進化論を教えた高校の生物教師が「サル裁判」にかけられ、有罪となって罰金100ドルを科せられた話(ただし1年後、同州最高裁判所はこの判決を覆した)、1962年ロシア発で10年以上にわたり世界的研究ブームになった「ポリウォーター」(超冷却水、これが外部に漏れたら自然の水を取り込んで自己増殖し地球全体を凍らせてしまうと言われた)の話、1978年のカナダの化学関係の雑誌に載ったリットル(体積の単位)に関する冗談(おまけに従来の小文字lを大文字Lに変更するという)を世界の多くの学者やマスコミが真に受けて大混乱になった話(p. 113)、そして1989年から数年間にわたって世界的な研究ブームになった(が何の成果も得られなかった)常温核融合の話などである。「えせ科学」に関するまとめは1952年のガードナーの項目にあり、我々科学を志す者の常に心すべきことが書いてある。
科学者の人生を考えさせる話題もある。原子番号と特性X線の波長に関する法則で名高いモーズリーはわずか4年間であの仕事を成し遂げ、第1次世界大戦に従軍して27歳で戦死したという話、核分裂の発見で1944年にノーベル賞を受けたハーンは、研究上重要な助言・指導を仰いだユダヤ人女性科学者マイトナーの名前を論文に出さず、彼女が共同研究者として受賞できなかった(ただし、その後109番元素に彼女の名前がつけられた)という「ノーベル賞の失点」と題する話などである。
元素周期表のメンデレエフのことも載っているが、彼が長年ロシアのアルコール局に勤めていたこと(一般のロシア人の間では、ウォッカが40度なのは彼が決めたことになっている)、その後大学の教授になったが、学生の授業料値上げ反対運動に同調したためクビになったこと、などのよく知られたエピソードは書かれていない。しかし、この本には次のような良質のユーモアが至るところにある。絶対温度目盛を創始したケルビン卿(トムソン)が22歳でグラスゴー大学の教授になり、50年以上教授を務めたが、ある日Professor Thomson will not meet his classes todayという休講通知を貼りだしたところ、学生がcの字を消すイタズラをした。すると教授は翌日講義に来た時に、次のlの字を消しただけで学生を叱らなかったという話は、いかにもイギリス的なウィットに富んでいて面白い。
この「年表」は広い分野にわたって取材しており、地球科学に関連する分野でも、プリニウス、ダーウィン、モホロビチッチ、ウェーゲナー、パターソン(隕石の放射年代)、ビャークネス(エルニーニョ・南方振動)、ジョハンソン(人類化石)などが扱われている。モホロビチッチの項目の「地層を解明する」という表題は不適当で、「地球の層構造を解明する」としてほしかったし、ウェーゲナーの大陸移動説の項目でプレートテクトニクスまで済ましてしまおうというのは端折り過ぎだと思うが、数字ばかりで無味乾燥な本物の「理科年表」と異なり、古代から現代まで、表側と裏側を行き来しながら知的刺激に富む文章で科学史を概観できる「ゆかいな」本であり、会員各位にご一読をお勧めする。
東北大学東北アジア研究センター 石渡 明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】地質の日イベント報告
──────────────────────────────────
■報告:「紀の松島クルージングセミナー 熊野のジオサイト紀の松島めぐり」
5月14日(土)に「地質の日」イベント「第4回 地質の日フィールドワーク紀の松島クルージングセミナー 熊野のジオサイト紀の松島めぐり 〜美しい海岸と温泉をたずねて〜」を開催しました。本イベントでは、日本地質学会会員の後誠介氏を講師に迎え、景勝紀の松島をテーマに、遊覧船でのフィールド講座を実施しました。当日は好天に恵まれた絶好のクルージング日和で、総勢27名の参加者も美しい風景を楽しんでいました。
写真入りの記事はこちらから、、、
http://www.geosociety.jp/name/content0078.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】第34回万国地質学会議(IGC)ブリスベン大会: Second Circular公開
──────────────────────────────────
Second Circular が公開されています。
詳しくは下記をご覧ください。
34IGC Website: http://www.34igc.org
34th IGC Second Circular:
http://www.34igc.org/FileLibrary/34igc_second_circular_v9.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】支部情報
──────────────────────────────────
■中部支部:2011年支部年会
場所:名古屋大学東山キャンパス環境総合館1階レクチャーホール
日程:2011年6月11日(土)〜12日(日)
http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
■北海道支部・遠軽町共催「白滝ジオパーク地質見学会・講演会」
○地質見学会『白滝の地質と黒曜石』
日時:2011年6月25日(土)〜26日(日)
25日:支湧別川ルート(案内者:加藤孝幸ほか)
26日:赤石山ルートほか (案内者:和田恵治ほか)
参加費:一般 10,000円 学生・院生 6,000円
定員:30名
申込先:支部幹事 川上源太郎 (道総研 地質研究所)
Tel:011-747-2447 Email: kawakami-gentaro@hro.or.jp
○講演会『ジオパークとは何だ!?−遠軽の大地の遺産』
日時:2011年6月25日(土)15:00〜17:30
場所:遠軽町白滝支所 国際交流センター
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■SELENE-2着陸候補地点に対する説明・討論会について
「かぐや」に続く次期月探査計画として、宇宙航空研究開発機構(JAXA)
では、月着陸探査SELENE-2を検討しております。
今回以下の通り、着陸候補地点に対する説明・討論会を行い、着陸地点
の優先順位付けを、行うことになりました。
ご興味のある方は是非ご参加ください。
<SELENE-2着陸地点検討会全体会議>
日時: 2011年6月14日(火) 11:00〜16:00
場所: 宇宙科学研究所 A棟2F本会議場(神奈川県相模原市)
内容: SELENE-2着陸地点候補に関する議論
詳細は以下のURLをご覧ください。
http://astrosis.ess.sci.osaka-u.ac.jp/selene2_public3/
■日本学術会議主催 学術フォーラム「「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポ」
日時:2011年6月11日(土)10:00〜16:45
会場:日本学術会議 講堂
参加費:無料(要申込)
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf/123-s-0611.pdf
■公開シンポジウム「若手研究者の考える,震災後の未来― 学術に
何ができるのか」の開催について(ご案内)
日時:2011年6月26日(日)13:00〜18:00
会場:日本学術会議 講堂
主催:日本学術会議若手アカデミー委員会若手アカデミー活動検討分科会
参加費:無料
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf/123-s-0626.pdf
■一般社団法人日本応用地質学会平成23年度シンポジウム
「応用地質学の変遷と将来展望」
日時:2011年6月17日(金)13:00〜17:30
場所:日本大学文理学部 百周年記念館国際会議場
主催:一般社団法人日本応用地質学会
費用(予定):一般会員2,000円,学生会員500円(非会員は+500円)
URL: http://wwwsoc.nii.ac.jp/jseg/00-main/H23_symposium.html
問合せ先:一般社団法人日本応用地質学会事務局
〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台2-3-14 お茶の水桜井ビル7F
Tel: 03-3259-8232,Fax: 03-3259-8233
E-mail:KYW04560@nifty.com
■JABEE 事務局ニュース No. 15(2011/6/2版)
JABEE事務局ニュースは社員(正会員)、賛助会員、理事、監事、顧問、
委員会委員宛に配信されています。
情報のより広い共有のため、会員の皆様にもご転送いたします。
2011/6/2版ニュース PDFはこちら、、
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/geoFlash_img/no138/jabee_e-news_14_110602.pdf
JABEEホームページ http://www.jabee.org/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【14】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■東京都市大学:知識工学部自然科学科 等(非常勤講師)(7/20)
■平成23年度山陰海岸ジオパーク学術研究奨励事業募集(6/24)
■第15回尾瀬賞募集(8/31)
■平成24年度科学分野の文部科学大臣表彰科学技術賞及び
若手科学賞受賞候補者募集(推薦)6/30:学会締切)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
地質マンガ 巡検あるある
地質マンガ
戻る|次へ
オックスフォード大学 学部生地質巡検同行紀
イギリスでは、大学の地質学教室の多くは、年度が切り替わる10月に学部生巡検をおこないます。今回、オックスフォード大学のSteve Hessalbo教授、Hugh Jenkyns博士の御好意で、オックスフォード大学の巡検に同行させてもらいました。オックスフォード大学では、例年イングランド南海岸、Weymouthの東西約30 kmに広がるジュラシックコーストを1週間かけて巡検します。ここでは、三畳紀の河川性・湖沼性堆積物、ジュラ紀の浅海堆積物、白亜紀のチョークなど、さまざまな堆積物を見ることができます。参加する学生は新2年生、ほとんどが10代の若人で、元気いっぱいです。
写真1.Lulworthの褶曲露頭をスケッチする学生。
巡検は、まずLulworthの褶曲露頭での地質スケッチから始まります(写真1)。スケッチを皆で廻し読みし、他の人たちがどのようなスケッチを描いているのか、どこにポイントを置いて描けばいいのかを学びます。その後、古い三畳系から若い白亜系まで年代を追って観察していきます。その間、学生は露頭の観察方法、柱状図の描き方、走向傾斜の測定、上下判定などを学びます。海岸露頭はどこも素晴らしく、さまざまな堆積構造や豊富な化石を見ることができます。圧巻はLyme Regis近くの波食台です(写真2)。層理面が露出し、一面にアンモナイトが!ここではアンモナイトの詳細な観察や、サイズの測定をおこないます。なお、露頭から許可なくアンモナイトを採取することはできません。今回の巡検では、化石を多産する露頭の一つが、冬の間の嵐のため礫に覆われてしまうという不運がありました(4コマまんがのネタ)。しかし、Lyme Regis 周辺には、アンモナイトやベレムナイトを多産する露頭が続きます。運が良ければ、アラゴナイトの殻がそのまま残っているアンモナイトが見つかることも!
写真2.Lyme Regis 近くの露頭。層理面には大量のアンモナイト化石が。
学生はみんな好奇心旺盛で、露頭を前に議論が絶えません。引率の講師陣にはどんどん質問し、とても活気がありました。夜は講師陣の講義があり、一日のレビューをします。その後学生は幾つかのグループに分かれ、巡検に関連したテーマ(生痕化石、Sr同位体層序、テクトニクスと石油など)についてディスカッションし、皆の前で発表します。学生が書いた野帳は、毎晩講師陣がチェックします。講師陣も学生も休む暇はありません。私も数名の学生の野帳をチェックしましたが、実によく書けていました。スケッチや柱状図は日に日に上達し、露頭での説明や講義もしっかりメモを取っていて、驚かされました。最終日には途中で立ち寄った古城跡でなぜか学生対講師陣の鬼ごっこが始まり、みんな子供のようにはしゃいでいました。最終日の夜は講義もほどほどに、近所のパブで大宴会。オックスフォード大学の巡検は、よく歩き、よく観察し、よく議論し、よく学ぶ。それに加えてよく遊び、よく飲む、というのが伝統のようです。
地質マンガ やるやるさぎ
地質マンガ
さて,構想1年の力作はこちらから!
戻る|次へ
No.141 2011/7/5 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.141 2011/7/5 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】共同声明「自然災害に向き合う強い日本社会の復興のために」
【2】水戸大会:発表申込800件超え!ここ10年で最大規模に
【3】水戸大会:東日本大震災関連ポスター展示におけるポスター募集について
【4】3/11地震・津波前兆現象アンケート調査のお願い
【5】東日本大震災に係る復旧・復興に関連する事業プランの募集(継続)
【6】構造地質部会書籍企画「日本の地質構造百選」 追加募集中!
【7】オマーンにおける国際会議の紹介:http://www.geoman2012.com
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞情報
【11】地質マンガ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】共同声明「自然災害に向き合う強い日本社会の復興のために」
──────────────────────────────────
6月30日に,地球惑星科学連合学会に参画している学協会44による共同声明
が公表されました.本共同声明作成に当たっては,幹事学会が募集されまし
たが,地質学会は積極的に幹事学会に名乗りを挙げ,渡部副会長が作成に関
与しました.その背景としては,4月5日には「東日本大震災に関する地質学
からの提言」,5月21日には大震災対応作業部会による詳細な総括と課題の提
起を行っていた事が挙げられます.
6月30日に幹事学会である地質学会,地震学会,気象学会,地球化学会会長
あるいは代理などの参加のもとに記者会見を行い,連合の木村 学会長から
今回の共同声明に関する説明が行われました.その際に,地質学会は独自の
資料を準備して,今回の震災への対応を説明しました.記者からは特に博物
館関係の被災状況について質問がありました.会見終了後の記者との懇談で
は,津波災害遺跡の保存やジオパークとの関わりや,地学教育の危機的な現
状に関しても,話題に上りました.
共同声明の内容はこちらから、、、
http://www.jpgu.org/whatsnew/110630_311state.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】水戸大会:発表申込800件超え!ここ10年で最大規模に
──────────────────────────────────
水戸大会(日本鉱物科学会との合同学術大会)は、発表申込数が800件を超え、
ここ10年間で最大規模の大会になる見込みです。
見学旅行は、最近注目を集める日立古生層をはじめ、魅力的なフィールドを
多数用意。地質情報展は、毎年好評の実演に加えて、新企画「市民向けポス
ター展示説明会」や「震災展示」も。市民講演会と特別講演会は、会員の皆
様にも時間の許す限り聞いてほしい話が満載。
さあ、行きましょう、日本最大の「地質学の祭典」へ!
行事委員長 星 博幸
■大会参加申込は8月5日(金)18時まで。まだ申し込んでいない方は、お早めに。
http://www.geosociety.jp/mito/content0026.html
■市民向けポスター展示説明会は、大きなポテンシャルを秘めた新企画です。
「自分の研究を市民にわかりやすく伝えたい」という会員に発表スペースを
提供します。市民からのフィードバックも期待できます。
http://www.geosociety.jp/mito/content0044.html
■企業・研究機関等による展示(ブース設置)は、ポスター会場と融合した
配置にし、効果的に宣伝できる場を提供します。募集中です。
http://www.geosociety.jp/mito/content0037.html
■見学旅行は、参加申込が順調です。参加ご希望の方は、お早めに。
http://www.geosociety.jp/mito/content0030.html
■技術者の皆様、CPD単位の対象となります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】水戸大会:東日本大震災関連ポスター展示におけるポスター募集について
──────────────────────────────────
東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)により,東北から関東に至る広い
地域が被災しました.今大会開催地である茨城県においても,護岸部・平野
部の液状化,山間地の斜面災害,さらには原発に伴う海域汚染など多くの被
害が報告されています.そこで,震災において発生した様々な被災状況に関
して,地質学的視点から広く社会に紹介する場を計画しました.
茨城県内の市民に向けて,県内の被災状況,さらには近隣を含めた広範囲
な震災情報を「東日本大震災関連ポスター展示」として発信したいと考えて
います.ぜひ,震災調査に関わっている多くの会員の応募をお願いいたしま
す.東日本大震災関連ポスター展示は,これまでの緊急展示と異なり,「地
質情報展」会場(茨城大より徒歩数分)で開催し,一般市民向けといたしま
す.
市民の皆様に理解していただくために,以下の点についてご考慮ください.
・写真や図表を多用し,文章は少なくする.
・平易な表現で,『です・ます』調の文体とする.
申し込み方法など詳細は、
http://www.geosociety.jp/mito/content0046.html
<申込締切:8月22日(月)17時>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】3/11地震・津波前兆現象アンケート調査のお願い
──────────────────────────────────
3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震と大津波は,未曽有の東日本大震災
をもたらしました.犠牲になられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとと
もに,ご遺族の方々にお悔やみを申し上げます.また,長期にわたりご不便
な避難生活を送っていらっしゃる方々,行方不明のご家族を捜索中の方々,
被災によるケガや病気で療養中の方々にお見舞いを申し上げます.そして被
災地の復興にご尽力されている方々に敬意を表します.
今回の地震について,様々な視点からの記録を,できるだけ多く残すことが
将来の人たちのために大切であると痛感しております.皆さまのご協力を得
て,今回の地震・津波の前兆現象について,アンケート調査を行いたいと思
います.明治・昭和の三陸地震津波を含め,従来の大地震については,様々
な前兆現象が報告されています.ところが,今回の大地震に関しては,その
2日前に発生した震度5強の前震以外は,顕著な前兆現象の話をあまり聞きま
せん.それは,微弱な光や音を認知しにくい昼過ぎの時間帯に,従来の地震
に比べて陸地から遠い深海底で今回の地震が発生したためかもしれません.
しかし,予断をもつことなく,まずデータを集めることが必要です.
つきましては,もし何らかの地震・津波の前兆と思われる現象に気づかれた
方は,過去に観察された地震の前兆現象についての簡単なまとめをお読みい
ただいた上で,アンケートの質問にお答えいただくよう,お願い申し上げま
す.
【趣旨説明・アンケート項目・回答送付方法など】
http://www.cneas.tohoku.ac.jp/labs/geo/ishiwata/Precursor1.htm
【過去に観察された前兆現象に関する簡単なまとめ】
http://www.cneas.tohoku.ac.jp/labs/geo/ishiwata/PrecursorExpl.htm
皆さまからの貴重な情報をお待ちしております.
東北大学東北アジア研究センター 石渡 明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】東日本大震災に係る復旧・復興に関連する事業プランの募集(継続)
──────────────────────────────────
6月21日のgeo-Flashでお伝えしました東日本大震災に係る復旧・復興に関連
する事業プランの募集に多くのご応募ありがとうございます.これまでのと
ころ2件が採択され2件が審議中です.さらに会員の皆様からの積極的なご
提案をお待ちしております.どうぞよろしくお願いいたします.
採択プラン
「歌津魚竜館大型標本レスキュー事業」(代表:永広 昌之,佐々木 理)
「放射性セシウムに汚染された水田土壌のカヤツリグサ科マツバイによる
ファイトレメディエーション」(代表:榊原正幸・佐野 栄)
応募先
http://www.geosociety.jp/hazard/content0061.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】構造地質部会書籍企画「日本の地質構造百選」 追加募集中!
──────────────────────────────────
「日本の地質構造百選」は,120程度の想定候補地の中から50項目の写真が
集まりつつあります.そこで7月末まで写真の〆切を延長することにしまし
た. 皆様の写真がアトラスとして掲載されるかもしれません!
ぜひとも投稿をよろ しくお願いします.プリント版またはスライド版で
良い写真をお持ちの方は,高木宛にお送りください.なお,すでに投稿頂い
ている方には,後日レイアウト案 を送りますので,説明やキャプション等
をお願いいたします.ぜひとも投稿をよろしくお願いします.
「日本の地質構造百選」編集委員長 高木秀雄 (hideo@waseda.jp)
投稿ページ
http://struct.geosociety.jp/JSGBook2011/Top.html
足りない地域等はこちら(エクセルファイル)
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/geoFlash_img/no141_strct100list.xls
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】オマーンにおける国際会議の紹介:http://www.geoman2012.com
──────────────────────────────────
宮下純夫(新潟大学)
オマーンにおける国際会議(International Conference on the Geology of
the Arabian Plate and the Oman Mountains)が2012年1月7-9日に開催され
る.この時期は平均気温が25度前後でもっとも快適な季節である.オマーン
における国際会議は1990年に初めて開催され,日本からは4名が参加した.
2001年には2回目となる国際会議が開催され,大勢の日本人研究者が参加し
たが,そこでは1996年頃から本格的に開始された日本隊による成果が多数報
告され,大いに注目を引いた.今回で3回目となる国際会議は,ほぼ10年毎に
開催されていることとなる.今回の国際会議では,オフィオライトを中心と
した海嶺プロセスに関連するセッションは当然ながら,それ以外にも魅力的
な数多くのセッションが予定されている.詳細は冒頭のURLを参照されたい.
アブストラクトの締め切りは8月1日である.
巡検も,オフィオライトを始め,高圧変成岩,堆積岩などに関して9コースが
準備されている.手前味噌ではあるが,この10数年間の日本隊を中心とした
成果を問う巡検も予定されている.オマーンはオフィオライトが有名であり,
数多くの研究がなされているが,その下盤側の古生代―中生代の堆積層や,
プレカンブリアンと古生代との大不整合や,エクロジャイトなどの高圧変成
岩類なども壮大に露出している.オマーンは,全面露出する海洋地殻-マント
ルの断面を始め,壮大な古生代―中生代の連続露出など,地球史を本当に実
感できる素晴らしいジオサイトであり,地質学に関わる多くの方々に是非お
勧めしたい場所である.
最後にオマーンの国情に関してコメントする.最近,アラビア半島を始め,
イスラム諸国の治安状況が不安視されているが,オマーンに関しては,ごく
小規模なデモはあったものの,現在は完全に平静な状況に復帰している(在
オマーン日本大使館HP参照:http://www.oman.emb-japan.go.jp/japanese/index_j.htm).
現地の人々の日本に対する感情は大変良く,治安に関する不安は殆どない.
また,首都マスカットや北部の中心都市ソハールの近代的な発展には目を見
張らされるものがある.多くの日本人研究者が,今回の国際会議に参加し,
オマーンの壮大な露頭を楽しまれることを期待している.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
──────────────────────────────────
■第161回西日本支部例会(九州考古学会との合同大会)
日程:2011年7月9日(土)・10日(日)
場所:九州大学・西新プラザ(福岡市早良区西新2-16-23)ほか
講演申込締切:7月4日(月)
○ポスターセッション
○シンポジウム「考古学と地球科学の融合研究の最前線」
・基調発表(敬称略)
(1)地球科学精密分析手法の考古学への応用(小山内康人・九州大学)
(2)ストロンチウム分析と先史社会研究(田中良之・九州大学)
(3)西南日本沿岸湖沼に残された地震津波記録を解読する(岡村 眞・高知大学)
(4)青銅器鋳型の岩石学的分析(足立達朗・九州大学)
・シンポジウムポスター発表(敬称略)
黒曜石研究(隅田祥光・明治大学)、磨製石器の化学分析(角縁進・佐賀大学)、
鋳型の原産地同定(田尻義了・九州大学)、LA-ICP-MSを用いた考古学資料解析
(中野伸彦・九州大学)、胎土分析の新展開(石田智子・九州大学)、青銅器
研究(岩永省三・九州大学)、など
○野外巡検:八女市青銅器鋳型・原石露頭、吉野ヶ里遺跡
プログラム等、詳細は、、、
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第48回アイソトープ・放射線研究発表会
日時:2011年7月6日(水)〜7月8日(金)
場所:日本科学未来館 7階(江東区青梅2-3-6)
○特別講演:
温暖化が及ぼす極付近の氷の危機(石井吉之、北海道大学低温科学研究所)
冷反水素を用いた反物質研究の現状(山崎泰規、理化学研究所)
患者貢献度から医療被曝を考える(大野和子、京都医療科学大学医療科学部)
○パネル討論:
重粒子線加速器の生物・医学研究への応用
○緊急公開講座:
放射線から人を守る―福島原発事故の健康影響を正しく理解するために―
○緊急公開セッション
福島原子力発電所から放出された放射能の環境影響、社会生活への影響
:我々科学者の仕事は何か?
プログラム:
http://www.jrias.or.jp/index.cfm/6,15522,c,html/15522/file1_program.pdf
詳細は、
http://www.jrias.or.jp/index.cfm/6,15522,103,212,html
■日本学術会議中国・四国地区会議公開学術講演会「愛媛大学の先端研究
−拠点化の歩み−」の開催について
日時:2011年7月23日(土) 14:00〜17:00
場所:愛媛大学構内 南加記念ホール(松山市文京町3番)
趣旨:愛媛大学は研究戦略として、世界レベルの先端研究を行うため、各部
局に散在している関連分野の研究者を集約して研究センターを作ってきた。
国立大学法人前に3つのセンターを開設し、また、法人化後には更に3つの研
究センターに加えて社会貢献を視野に入れた地域貢献型の研究センターを立
ち上げてきた。これのうち、2つのセンターではグローバルCOEプログラムに
採択され、また他の何れのセンターも各々の分野で成果を挙げて高い評価を
得ており、大学の戦略は成功したように思われる。今回は、大学の研究戦略
を概説するとともに、各研究センターの活動の概要を紹介したい。
詳細については、
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf/123-s-0723t.pdf
■ The 7th International Conference on Asian Marine Geology (ICAMG)
11-14 October 2011
National Institute of Oceanography (CSIR), Goa, India.
Conference webpage: http://icamg7.nio.org
Flyer is available from: http://icamg7.nio.org/Flyer-ICAMG-7.pdf
Deadline of registration and abstract submission: 31st July 2011
■ 第20回市民セミナー「水辺の環境調査−水辺の生物多様性と水環境総合指標−」
日時:2011年8月3日(水)9:40〜16:20
場所:東京会場・地球環境カレッジホール(東京都世田谷区駒沢)
大阪会場・いであ(株)大阪支社 ホール(大阪市住之江区南港北)
参加費:無料(要申込、先着300名)
http://www.jswe.or.jp/event/seminars/
問い合わせ先:(社)日本水環境学会セミナー係 山本、窪田
E-mail: kubota@jswe.or.jp
■山陰海岸ジオパーク国際学術会議「城崎会議」
"ジオパーク活動"のアジアにおける知の拠点化をめざすとともに、山陰海岸
ジオパークを国内外に大きくアピールするため、 山陰海岸ジオパーク国際
学術会議「城崎会議」が開催されます。
期日:2011年10月29日(土)〜31日(月)
場所:城崎温泉 西村屋ホテル 招月庭(兵庫県豊岡市城崎町湯島1016-2)
主催:山陰海岸ジオパーク国際学術会議「城崎会議」実行委員会
参加登録など詳細は、、、
http://sanin-geo.jp/modules/news/index.php?page=article&storyid=51
■第6回「海洋と地球の学校」
日時:2011年8月29日(月)〜9月3日(土)
場所:青森県内(むつ市、八戸市及び周辺地域)
テーマ:災害を越えて未来を切り拓く〜地球システムと自然災害科学〜
対象:大学生及び大学院生(短大、高等学校専攻科を含む)
(応募者数により一般社会人の参加も可能)
趣旨:(独)海洋研究開発機構では、海洋科学技術の最先端のテーマを設定し、
大学生及び大学院生を対象に、21世紀の海洋科学技術の研究・開発を担う人材
育成に資することを目的として、「海洋と地球の学校」を開催しています。
カリキュラムは宿泊型の研修形式とし、研究者による講義と研究施設の見学等
のほか、野外実習等を実施することで、大学の講義では得られない海洋科学に
関する総合的な学習の場を提供することを目指します。
詳細は、、、
http://www.jamstec.go.jp/j/pr/school/006/
問い合わせ先:(独)海洋研究開発機構 広報課 海洋と地球の学校 事務局
E-mail:kaiyo-gakko@jamstec.go.jp
■第2回シンポジウム「海洋教育がひらく防災への道」
日時:8月27日(土)13:00-17:20
場所:東京大学農学部 弥生講堂
対象:小・中・高等学校教諭、学生、教育関係者、一般
参加費:無料ただし、以下のURLから事前登録が必要。定員300名。
https://www.webmasters.co.jp/RCME/symp/ (参加登録フォーム)
または http://www.oa.u-tokyo.ac.jp/RCME/
問い合わせ先:】東京大学理学部経理課海洋リテラシー事務 小山 ・ 太田
E-mail: literacy_jimu@oa.u-tokyo.ac.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■北海道大学大学院:自然史科学部門 地球惑星システム科学分野(准教授)(7/15)
■広島大学大学院:理学研究科地球惑星システム学専攻(特任助教)(8/12)
■2011年度「朝日賞」候補者推薦(8/19学会締切)
■第33回(平成23年度)沖縄研究奨励賞推薦応募(8/31学会締切)
■第32回猿橋賞募集(11/30)
■東レ科学技術賞および東レ科学技術研究助成候補者募集(8/31学会締切)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】地質マンガ 無酸素じゅげむ
──────────────────────────────────
無酸素じゅげむ
(原案・マンガ化:黒田潤一郎)
解説:海洋無酸素事変Oceanic Anoxic Events OAEs
http://www.geosociety.jp/faq/content318.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.139 2011/6/21 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.139 2011/6/21 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
------------------------------
水戸大会関連情報
【1】[緊急]東日本大震災に係る復旧・復興に関連する事業プランの募集
【2】水戸大会関連のお知らせ
・【鉱物科学会担当セッション】発表受付中!
・企業・研究機関等のブース募集
・その他の水戸大会関連の締切
【3】コラム:花崗岩類からの放射線量
【4】第5回 国際地学オリンピック(イタリア大会)の日本代表が決定!
【5】東北地方太平洋沖地震を受けたパブリックコメント(内閣府)
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞情報
【9】地質マンガ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[緊急]東日本大震災に係る復旧・復興に関連する事業プランの募集
──────────────────────────────────
東日本大震災に関しまして、2011年5月21日に日本地質学会東日本大震災作業部
会の報告書が提出されました(http://www.geosociety.jp/hazard/content0059.html)。
報告書では災害対応への地質専門家の積極的な参画が求められています。この報
告書の提案を具現化するために、学会として取り組むべき事業プランを募集しま
す。プランは会員が直接に取り組むもののみならず、間接的な協力事業を含みま
すが、報告書に対応して学会として実施されることが基本となります。
募集要項
(1)東日本大震災対応作業部会報告書に係る復旧・復興に関連する研究・調
査・事業のプラン
(2)1件あたり30万円(上限の目安).ただし,設備備品や分析器具などの購
入費は除く.
(3)申請書類に必要事項を記入し,地質学会事務局(main@geosociety.jp)に送付
(4)2011年6月21日より募集開始
(5)緊急性に応じて随時審査し、採択され次第実施
(6)調査・研究期間:2012年3月末まで
(7)応募資格:申請者は正会員であること
(8)研究終了後の報告義務:収支報告書とともに成果報告概要をニュース誌に掲載する.
また,2012年地質学会年会(大阪)で発表(2件目の発表を可とする).
一般社団法人日本地質学会執行理事会
災害復旧事業部会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】水戸大会関連のお知らせ
──────────────────────────────────
■【鉱物科学会担当セッション】発表受付中!
地質学会会員は、鉱物科学会担当セッションでも発表できます。
トピックセッション T1〜T8
定番セッション R1〜R5
(セッション一覧: http://wwwsoc.nii.ac.jp/jams3/11session.htm)
締切:6月30日(木)14:00
詳しくは鉱物科学会ホームページをご覧下さい。
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jams3/
■ 企業・研究機関等関係団体による展示会の出展募集
地質関係機関・関連企業のご活躍を広く地質学会員に紹介していただくため,会期中,
企業展示会を開催致します.企業紹介・業務紹介・研究成果・新技術・特許などご自
由に展示内容を構成いただけます.奮ってご出展のお申込をいただきますようお願い
申し上げます.
申込締切 第1次募集締切:6月28日(火) 最終募集締切:7月22日(金)
詳細はこちら
http://www.geosociety.jp/mito/content0037.html
■ その他の水戸大会関連の締切
・市民向けポスター展示・説明会申込み:7月22日(金)17時
http://www.geosociety.jp/mito/content0044.html
・プレス発表「特筆すべき研究成果」の推薦:7月22日(金)17時
http://www.geosociety.jp/mito/content0043.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】コラム:花崗岩類からの放射線量
──────────────────────────────────
石原舜三(産業技術総合研究所)
東日本大震災以降、放射線量への関心が急速に高まっており、花崗岩の
放射線量についての執筆依頼を編集部から受け、筆をとった。筆者と放射
線との出会いはこれが2回目である。最初は広島の原爆である。小学校6年
生の1945年8月6日朝、爆心地から6km東方の小学校の2階で、B29を目視追跡
していた私は爆裂の閃光を真正面から浴びた。当時、それが原子爆弾による
ものとは知る由もなく、5万トンくらいの爆弾であろうかと友達と話しあっ
た。その2日後に行方不明者を探しに近所の老婆の手を引いて広島市内に入
り、瓦礫を掘り起こした。広島市内は焼け野原であったから、放射性埃など
を吸い込む内部被曝の可能性は少なかったであろうが、残留放射能下を歩き
続けたことは明らかである。
このような事故的なことを除くと、我々が浴びる自然界の放射能は空から
来る宇宙線に由来するものと、地殻の諸岩石の放射性元素(K, Th, U)に起因
するものとに大別される 。
続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0313.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第5回 国際地学オリンピック(イタリア大会)の日本代表が決定!
──────────────────────────────────
第5回国際地学オリンピック大会は、イタリアにおいて2011年9月5日から14日までの
10日間に渡って開催されます。
国内選抜(第3回日本地学オリンピック大会)一次選抜(筆記試験;2010年12月19日
実施)には、日本各地から869名の生徒が応募し、全国の大学や高校会場にて受験
しました。二次選抜試験(筆記・実技試験、面接;2011年6月11日から12日まで東京
大学本郷キャンパスで実施)には、一次で選ばれた27名の生徒が参加し、4名の
最優秀賞者と4名の優秀賞者が選考されました。この最優秀賞者4名が国際大会
日本代表(前掲)となります。代表生徒は6月から8月の通信研修、8月中旬の合宿
研修(神奈川県立生命の星・地球博物館にて)を経て、9月の国際大会に臨みます。
次の4名の方が日本代表です。皆さん応援しましょう.
浅見 慶志朗 (埼玉県立川越高等学校)
松岡 亮 (北海道旭川西高等学校)
松澤 健裕 (栄光学園高等学校)
渡辺 翠 (桜蔭高等学校)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】東北地方太平洋沖地震を受けたパブリックコメント 内閣府
──────────────────────────────────
東北地方太平洋沖地震を受けて、総合科学技術会議が第4期科学技術基本計画策定
に向けた答申の再検討を行っています。その見直し案に対するパブリックコメント
が募集されています.下記よりお送り下さい.
内閣府共通意見等登録システム
https://form.cao.go.jp/cstp/opinion-0020.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
■北海道支部・遠軽町共催「白滝ジオパーク地質見学会・講演会」
○地質見学会『白滝の地質と黒曜石』
日時:2011年6月25日(土)〜26日(日)
25日:支湧別川ルート(案内者:加藤孝幸ほか)
26日:赤石山ルートほか (案内者:和田恵治ほか)
参加費:一般 10,000円 学生・院生 6,000円
定員:30名
申込先:支部幹事 川上源太郎 (道総研 地質研究所)
Tel:011-747-2447 Email:kawakami-gentaro@hro.or.jp
○講演会『ジオパークとは何だ!?−遠軽の大地の遺産』
日時:2011年6月25日(土)15:00〜17:30
場所:遠軽町白滝支所 国際交流センター
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
■第161回西日本支部例会(九州考古学会との合同大会)
日程:2011年7月9日(土)・10日(日)
場所:九州大学・西新プラザ(福岡市早良区西新2-16-23)ほか
講演申込締切:7月4日(月)
○ポスターセッション
○シンポジウム「考古学と地球科学の融合研究の最前線」
・基調発表(敬称略)
(1)地球科学精密分析手法の考古学への応用(小山内康人・九州大学)
(2)ストロンチウム分析と先史社会研究(田中良之・九州大学)
(3)西南日本沿岸湖沼に残された地震津波記録を解読する(岡村 眞・高知大学)
(4)青銅器鋳型の岩石学的分析(足立達朗・九州大学)
・シンポジウムポスター発表(敬称略)
黒曜石研究(隅田祥光・明治大学)、磨製石器の化学分析(角縁進・佐賀大学)、
鋳型の原産地同定(田尻義了・九州大学)、LA-ICP-MSを用いた考古学資料解析
(中野伸彦・九州大学)、胎土分析の新展開(石田智子・九州大学)、青銅器
研究(岩永省三・九州大学)、など
○野外巡検:八女市青銅器鋳型・原石露頭、吉野ヶ里遺跡
プログラム等、詳細は、、、
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■日本学術会議会長談話「放射線防護の対策を正しく理解するために」
日本学術会議は6月17日、日本学術会議会長談話「放射線防護の対策を正しく
理解するために」を発出しました。
本文は、、、 http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-21-d11.pdf
■公開シンポジウム「フォーラム:東日本大震災による生態系や生物多様性
への影響−どれだけの影響があったのか、回復に向けて何を考えるべきか−」
日時:2011年6月28日(火)13:00〜17:00
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木7-22-34)
主催:日本学術会議統合生物学委員会生態科学分科会、
環境学委員会自然環境保護保全再生分科会
後援:日本生態学会
参加自由・事前申し込み不要
詳細は、、、 http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf/125-s-2-2.pdf
■日本学術会議緊急講演会「放射線を正しく恐れる」
東日本大震災後、放射能や放射線に関する様々な情報が大量に発信され、多く
の国民は放射線の身体への影響等に関する漠然な不安を日々感じている。
本緊急講演会は、放射線に関する第一線の研究者の講演並びにパネル討論によ
り、国民へ現時点での正しい情報を伝え、国民の不安の解消を図るとともに、国
民の放射線へのリテラシーの向上を図ることを目的とする。
日時:2011年7月1日(金)10:00〜12:30
場所:日本学術会議 講堂
主催:東日本大震災対策委員会
参加費:無料(要申込)
詳細は、、、 http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf/126-s-3-1.pdf
■日本学術会議中国・四国地区会議公開学術講演会「愛媛大学の先端研究−拠
点化の歩み−」の開催について(ご案内)
日時:平成23年7月23日(土) 14:00〜17:00
場所:愛媛大学構内 南加記念ホール(松山市文京町3番)
主催:日本学術会議中国・四国地区会議、愛媛大学
共催:日本学術協力財団
後援:愛媛県、愛媛県教育委員会、松山市、東温市、愛媛新聞社、
NHK松山放送局、南海放送、テレビ愛媛、あいテレビ、愛媛朝日テレビ
趣旨:愛媛大学は研究戦略として、世界レベルの先端研究を行うため、
各部局に散在している関連分野の研究者を集約して研究センターを作っ
てきた。国立大学法人前に3つのセンターを開設し、また、法人化後
には更に3つの研究センターに加えて社会貢献を視野に入れた地域貢
献型の研究センターを立ち上げてきた。これのうち、2つのセンター
ではグローバルCOEプログラムに採択され、また他の何れのセンタ
ーも各々の分野で成果を挙げて高い評価を得ており、大学の戦略は成
功したように思われる。今回は、大学の研究戦略を概説するとともに、
各研究センターの活動の概要を紹介したい。
詳細については、
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf/123-s-0723t.pdf
■第48回アイソトープ・放射線研究発表会
日時:2011年7月6日(水)〜8日(金)
場所:日本科学未来館7階(江東区青梅2-3-6)
http://www.jrias.or.jp/
■山陰海岸ジオパーク国際学術会議「城崎会議」
"ジオパーク活動"のアジアにおける知の拠点化をめざすとともに、山陰海岸
ジオパークを国内外に大きくアピールするため、 山陰海岸ジオパーク国際
学術会議「城崎会議」が開催されます。
期日:2011年10月29日(土)〜31日(月)
場所:城崎温泉 西村屋ホテル 招月庭(兵庫県豊岡市城崎町湯島1016-2)
主催:山陰海岸ジオパーク国際学術会議「城崎会議」実行委員会
参加登録など詳細は、、、
http://sanin-geo.jp/modules/news/index.php?page=article&storyid=51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■北海道立総合研究機構:平成24年度採用の研究職員採用試験(6/30)
■北海道大学大学院:自然史科学部門 地球惑星システム科学分野(准教授)(7/15)
■平成23年度「みらい」航海(MR11-08)の追加公募(6/28)
■第33回(平成23年度)沖縄研究奨励賞推薦応募(8/31学会締切)
■第32回猿橋賞募集(11/30)
■東レ科学技術賞および東レ科学技術研究助成候補者募集(8/31学会締切)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】地質マンガ やるやる さぎ & 巡検あるある
──────────────────────────────────
やるやる さぎ(原案・マンガ:KEY)
http://www.geosociety.jp/faq/content0315.html
巡検 あるある(原案・マンガ:黒田潤一郎)
http://www.geosociety.jp/faq/content0314.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.140 2011/6/28 geo-flash(臨時)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.140 2011/6/28 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
------------------------------
水戸大会関連情報
【1】[構造地質部会書籍企画「日本の地質構造百選」候補地・写真応募締切迫る
【2】<水戸大会>【鉱物科学会担当セッション】講演申込締切迫る
【3】<水戸大会>巡検コースの見学順等の変更について(D班・I班)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】構造地質部会書籍企画「日本の地質構造百選」候補地・写真応募締切迫る
──────────────────────────────────
<<<< 6月下旬 締切迫る >>>>
構造地質部会では、「日本の地質構造百選」と題した書籍を企画しております。
本書籍は写真を中心とし、手短な説明文とアクセスマップからなる、ハンド
ブック形式のものになる予定です。
つきましては、この書籍に載せるべき候補地および写真そのものを広く地質
学会員のみなさまから大募集いたします。
みなさまの提案や写真が書籍になるかもしれません!
一般の方々からの応募もいただいており、大変うれしく思っております。
その締め切りの6月下旬が迫っております!
まだまだ大募集中ですので、どんどんご投稿お願いいたします。
受付はホームページより行っております。
■「日本の地質構造百選」編集委員会ホームページ
http://struct.geosociety.jp/JSGBook2011/Top.html
また、掲示板も用意いたしました。みなさまの意見交換にご利用ください。
■「日本の地質構造百選」編集委員会掲示板
http://jsgbook2011.1616bbs.com/bbs/
奮ってご応募お願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】<水戸大会>【鉱物科学会担当セッション】講演申込締切迫る
──────────────────────────────────
水戸大会鉱物学会担当セッションの講演申込は 6月30日(木)14:00 締切りです。
みなさま、講演申込みお忘れなく!!
トピックセッション T1〜T8
定番セッション R1〜R5
(セッション一覧: http://wwwsoc.nii.ac.jp/jams3/11session.htm)
地質学会会員は、鉱物科学会担当セッションでも発表できます。
詳しくは鉱物科学会ホームページをご覧下さい。
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jams3/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】<水戸大会>巡検コースの見学順等の変更について(D班・I班)
──────────────────────────────────
見学旅行については、5/27参加申込の開始以来、各班とも順調に申し込み
いただいております。
以下の班におきましては、準備状況等により見学順等の変更をいたしますので
お知らせします。
■D班 常磐地域の白亜系〜新第三系と前弧盆堆積作用(9/12-13)
原発事故の影響により、第1日目と第2日目の日程を逆にして、第1日目に北茨
城市を見学し、宿泊先を平潟温泉(北茨城市)に変更します。見学予定地につい
てはいずれも再度下見を行い、露頭状況・放射線量等について大きな問題なく
実施できることを確認しております。
また、海岸付近や見学地間の移動では、震災(特に津波被害)やその後の復興
状況について紹介することも予定しています。なお、状況によっては第2日目(い
わき市内ほか)の見学地の変更の可能性(代替見学地検討済)があることをあら
かじめご承知おき下さい。その場合はできるだけ早くお知らせします。
■I班:伊豆弧衝突の最前線ー関東のテクトニクスの応用地質(9/12-13)
見学予定地について再度下見を行い、露頭状況や時間割等を再検討しました
ところ、当初予定しておりましたコースを下記のとおり変更いたします。
1日目 小田急小田原線新松田駅集合(10:00)
1.国府津−松田断層:松田町松田山からの俯瞰
2.日向断層:山北町日向の断層露頭
3.平山断層:山北町平山の断層露頭
4.畑火道角礫岩:山北町谷ヶの採石場 (山北町泊)
2日目
5.塩沢断層系、塩沢層の礫岩:山北町塩沢
6.小山火砕岩層:小山町生土、鮎沢川左岸の露頭
JR御殿場線 駿河小山駅(15:30)、小田急新松田駅(16:30)、
JR小田原駅(17:30)解散
予備見学地(雨天,時間調整など):諸淵のカキ礁、生命の星・地球博物館及び
温泉地学研究所の施設見学
定員:15名(レンタカーによる見学のため定員を変更いたします)
皆様のふるっての申込・参加をお待ちしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
地質マンガ 無酸素じゅげむ
地質マンガ
戻る|次へ
海洋無酸素事変Oceanic Anoxic Events OAEs
太陽光は海面から約300m程度しか届かないため、深海では光合成は行われません。現在の海では、海水が大循環しているので、表層の酸素が数千mの深海底まで行き届いているのです。しかし地質時代においては、海洋の大部分が無酸素状態に陥ってしまう"イベント"が起きてきたことがわかっています。
海洋無酸素事変は、海洋底に有機炭素に富む泥(黒色頁岩)が広く堆積するイベントです。中生代のジュラ紀や白亜紀に繰り返し起こったことが報告されています。初めて海洋無酸素事変という概念が提唱されたのは、1970年代のことです。Schlanger and Jenkyns (1976)が、白亜紀Cenomanian-Turonian境界で異常に有機炭素濃度が高い堆積物が世界各地に存在することを指摘し、OAEの概念を提唱したのが始まりです(1)。その後、Jenkyns (1980)は白亜紀のBarremian-Aptian-AlbianとCenomanian-Turonianの2回(+より小規模なBoniacian-Santonian)のOAEを提唱し、白亜紀OAE研究の基本的枠組みを築きます(2)。その後の調査が進むにつれて、Barremian-Aptian-AlbianのOAEはさらにOAE-1aからOAE-1dの4つのイベントとして認識されるようになりました(3)。白亜紀OAEでは、黒色頁岩の堆積は主に大西洋、テチス海や北米Interior Seawayなどが中心ですが、OAE-1aや-1dでは、太平洋の海山や海台でも黒色頁岩が堆積しており、グローバルイベントであったことが示唆されます。
写真1.イタリア中部、Gubbio近くのContessa 採石場
1980年代後半〜1990年代前半にかけて、「無酸素環境の出現か、海洋基礎生産の増大か」という論争が流行しました。要するに、有機物が保存されるためには、有機物がたくさん作られたことが重要か、保存される環境があったことが重要か、という論争です。この論争は、結局明確な決着がつかないまま、OAE研究は次のフェーズを迎えます。1990年代後半〜2000年代になると、先の海洋無酸素 vs. 基礎生産という構図から、より具体的な古環境像が描かれるようになりました。一つの大きな進展が、バイオマーカーによる有機物の起源生物の推定です。バイオマーカーの情報から、シアノバクテリアが重要な基礎生産者であったことが明らかになりました(4,5)。これは、単に基礎生産の増減ではなく、海洋表層のエコシステムの変化がOAEと深く関連していることを示しています。また、光合成硫黄細菌のバイオマーカーが北大西洋から見つかり、当時の北大西洋は、有光層に硫化水素が存在する異常な状況となっていたことがわかりました(6,7)。さらに、微生物研究により黒色頁岩をエサとして現在生きているバクテリアの存在も明らかになってきました(8)。
2000年代後半になると、マルチコレクター型誘導結合プラズマ質量分析計や表面電離質量分析計の発展とともに、重元素の同位体組成が簡易に測定できるようになり、OAEの古環境解析にも応用されるようになりました。堆積岩のオスミウムや鉛の同位体比を測定することで、海洋無酸素事変とほとんど同時期にマントル由来のオスミウムや鉛が海洋に放出されたことが明らかになります(9-11)。これは、OAEとほぼ同時に巨大海台形成に伴う大規模な火山活動が起こったことを示唆していて、地球内部変動が表層環境変動に強くリンクしていることを示しています。また、数値シミュレーションによる古環境復元も盛んに進められ、無酸素状態を作るのに最も重要な要素が何か、が明らかになってきました。これによると、大規模噴火による二酸化炭素放出により、大陸地殻風化速度が上昇してリンの供給が増加することが、海洋無酸素化をもたらす一つの要素になります(12)。また、表層堆積物からのリンの水柱への再供給も非常に重要であることがわかってきました(13)。
海洋無酸素事変の研究は、今後さらに発展していくものと期待しています。それは、新たな掘削や地質調査による、黒色頁岩の時間空間分布の解明(特に、これまで情報の空白域であった太平洋の研究(14))、分析技術の発展による新しい古環境指標の応用、そしてモデリングによるアプローチなどが、今後重要になって行くことでしょう。
黒田潤一郎(海洋研究開発機構)
引用文献
1. Schlanger, S.O., Jenkyns, H.C. (1976) Geol. Mijnb. 55, 179-184.
2. Jenkyns, H.C. (1980) J. Geol. Soc. London 137, 171-188.
3. Leckie R.M. et al. (2002) Paleoceanography 17, 1041.
4. Ohkouchi, N. et al. (2006) Biogeosciences, 3, 467-478.
5. Kashiyama, Y. et al. (2008) Org. Geochem., 39, 532-549.
6. Damste J.S.S., Koster, J. (1998) Earth Planet. Sci. Lett. 158, 165-173.
7. Oba, M. et al. (2011) Geology 39, 519-522.
8. Inagaki, F. et al. (2005) Astrobiology 5, 141-153.
9. Kuroda, J. et al. (2007) Earth Planet. Sci. Lett. 256, 211-223.
10. Turgeon, S.C., Creaser, R.A. (2008) Nature 454, 323-326.
11. Tejada, M.L.G. et al. (2009) Geology 37, 855-858 12. Misumi, K. et al. (2009) Earth Planet. Sci. Lett. 286, 316-323.
13. Ozaki, K. et al. (2011) Earth Planet. Sci. Lett. 304, 270-279.
14. Takashima, R. et al. (2011) Nature Comm. 2, 234, doi:10.1038/ncomms1233
地質マンガ タイムスケール
地質マンガ
戻る|次へ
No.142 2011/7/19 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.142 2011/7/19 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】まもなく地惑連合の選挙!会員登録の更新を忘れずに。
【2】水戸大会関連情報
【3】「日本の地質構造百選」写真投稿、さらに募集中!
【4】東日本大震災に係る復旧・復興に関連する事業プランの募集(継続)
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞情報
【7】地質マンガ「タイムスケール」
【8】geo-Flash No.141 の記事の訂正
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】まもなく地惑連合の選挙!会員登録の更新を忘れずに。
──────────────────────────────────
今年は日本地球惑星科学連合の運営に関わる重要な選挙が予定されています。
地質学会員の皆様にも選挙を通じた連合の運営への積極的な参加をお願いします。
選挙に先立ち連合の会員登録の更新を忘れていないかどうか、ぜひご確認下さい。
会員登録と確認は以下のページから。会員の登録区分の変更などもできます。
日本地球惑星科学連合の個人会員登録ページ: http://www.jpgu.org/touroku/
日本地質学会は「固体地球科学」と「地球生命科学」のセクションを中心として
連合の活動に貢献しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】水戸大会関連情報
──────────────────────────────────
■水戸大会に関する各種の締切が迫っています。ご確認下さい。
○プレス発表会「特筆すべき研究成果」の推薦のお願い【締切 7/22(金)】
水戸大会においてプレス発表会を開催します。会員皆様の学術活動が広く
報道されることは、地質学全体にとってプラスになります。この機会に会員
皆様の成果を「特筆すべき研究成果」として発表くださいますようお願いい
たします。皆様からの推薦をもとに、会見にマッチした資料を準備いたしま
すので、支部、部会、会員皆様からの自薦・他薦等、幅広い情報をお待ちし
ております。
応募・推薦締切:7月22日(金)17時
申込先:学会事務局(journal@geosociety.jp)
http://www.geosociety.jp/mito/content0043.html
○「市民向けポスター展示」【締切 7/22(金)】
水戸大会に合わせて「地質情報展2011みと―未来に活かそう 大地の鳴動―」
が水戸市武道館で開催されます。これまで全国各地で開催されてきた地質情
報展は、子供からお年寄りまで多くの市民で賑わい、地質の専門家とたっぷ
り話をして地質の理解を深めることができると好評です。
今年は会員の皆様に情報展のスペースを活用して頂き、地球科学の普及に役
立てていただきたいと考えています。「自分の研究成果を市民に少しでも伝
えたい・知ってほしい」という方、ぜひご応募下さい。
申込締切:7月22日(金)17時
申込先:行事委員会(main@geosociety.jp)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/mito/content0044.html
○広告協賛の募集【締切 7/22(金)】
講演要旨集・見学旅行案内書への広告協賛の募集をいたします。
企業紹介・業務紹介・研究成果・新技術・特許などの広報活動のご一環として、
奮ってお申込をいただきますようお願い申し上げます。
申込締切:7月22日(金)
申込先:現地事務局(e-mail: mito2011@academicbrains.jp; 担当:田中)
http://www.geosociety.jp/mito/content0037.html#11koukoku
○企業・研究機関等関係団体による展示会の出展募集【締切 7月末】
募集締切:7月末まで延長しました
申込先:現地事務局(e-mail: mito2011@academicbrains.jp; 担当:田中)
http://www.geosociety.jp/mito/content0037.html#11tenji
○書籍・販売ブースご利用の募集【締切 7月末】
募集締切:7月末まで延長しました
申込先:現地事務局(e-mail: mito2011@academicbrains.jp; 担当:田中)
http://www.geosociety.jp/mito/content0037.html#11book
■所属区分により参加登録費に含まれる講演要旨集の組み合わせが異なります。
合同学術大会となる水戸大会の講演要旨集はA,B,Cの3冊に分かれています。
参加登録費の発生するかた(一部を除く)には、大会プログラムやシンポジウム
を収録した講演要旨集(A)と、所属する学会の講演要旨集(BまたはB・C)が
必ず付きます。冊子の組み合わせは所属区分によって異なります。
・日本地質学会所属として登録した方:冊子(A)(B)
・日本地質学会,日本鉱物科学会両学会所属として登録した方:冊子(A)(B)(C)
※注1)講演要旨集A,B,Cについて
(A)プログラム,シンポジウム(3件),索引,広告等を収録
(B)日本地質学会が扱うセッションを収録
(C)日本鉱物科学会が扱うセッションを収録
※注2)講演要旨集は既に事前参加登録費に含まれていますので、登録の際に
追加講演要旨を申し込まれる方は、ご注意下さい。
参加登録費の詳細は、、、
http://www.geosociety.jp/mito/content0028.html
■見学旅行、好評受付中。この機会をお見逃しなく!
各コースの魅力と見どころはこちらから、、、
http://www.geosociety.jp/mito/content0030.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】「日本の地質構造百選」写真投稿、さらに募集中!
──────────────────────────────────
構造地質部会が企画しています「日本の地質構造百選」は,〆切を今月末
まで延ばしましたが,未だ40件ほどの写真が不足しています.
露頭の写真はある程度集まりつつあり,また期待される写真の想定される
持ち主には声もかけていますが,とくに次の構造の写真はいまのところ宛て
がありません.
もし良い写真をお持ちの方は,ぜひとも投稿くださるよう,あらためてお
願いします.
薄片スケールの写真も歓迎します.
なお,掲載される予定の露頭の保護・保全については,充分注意を喚起す
るようにしたいと考えています.
・糸魚川ー静岡構造線(早川の露頭)
・双葉断層
・露頭スケールのデコルマ
・露頭スケールのブロック回転
・スレートへき開(とくに牡鹿半島や対州層群のものなど)
・石灰岩中のスタイロライト
・節理面の羽状構造
・ブーダン構造
・マリオン構造
・食い違い礫
・複褶曲
など.
「日本の地質構造百選」編集委員会委員長 高木秀雄(hideo@waseda.jp)
投稿ページ
http://struct.geosociety.jp/JSGBook2011/Top.html
足りない地域等はこちら(エクセルファイル)
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/geoFlash_img/no142_strct100list.xls
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】東日本大震災に係る復旧・復興に関連する事業プランの募集(継続)
──────────────────────────────────
6月21日のgeo-Flashでお伝えしました東日本大震災に係る復旧・復興に関連
する事業プランの募集に多くのご応募ありがとうございます.これまでのと
ころ7件のご応募があり,5件が採択されました.今少し余裕がございますの
で,さらに会員の皆様からの積極的なご提案をお待ちしております.
どうぞよろしくお願いいたします.
採択プラン(7月19日現在)
・「歌津魚竜館大型標本レスキュー事業」(申請者:永広 昌之)
・「放射性セシウムに汚染された水田土壌のカヤツリグサ科マツバイによる
ファイトレメディエーション」(申請者:榊原正幸・佐野 栄)
・「微生物による放射性物質の除染の実証試験」(申請者:高橋正則)
・「関東平野内陸部の住宅地での盛土材質の相違による液状化要因の解明」
(申請者:卜部厚志)
・「陸前高田市立博物館地質標本救済事業」(申請者:大石雅之)
応募先
http://www.geosociety.jp/hazard/content0061.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■ INHIGEO 国際地質学史委員会日本大会
日時:2011年8月2日(火)〜10日(水)
場所:愛知大学(愛知県豊橋市)
3rd Circular:
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/geoFlash_img/no142_Inhigeo3rd2011.pdf
プログラム:
http://www.inhigeo-jp.org/program_inhigeo2011japan.pdf
INHIGEO 2011 Japan 36th Conference 公式ページ
http://www.inhigeo-jp.org/index.html
■ 日本学術会議 公開講演会「科学・技術の過去、現在、未来
−夢・ロードマップ−」
日時: 2011年8月24日(水) 13:00〜17:30
場所: 日本学術会議 講堂(東京都港区六本木7-22-34)
主催: 日本学術会議第三部
・特別講演 「戦後の科学・技術の発展をささえたもの(仮題)」小林 誠
・講演 「第4期科学技術基本計画」泉 紳一郎
「理学・工学分野における科学・夢ロードマップ」後藤 俊夫
・パネルディスカッション
詳細は、、、
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf/125-s-3-2.pdf
■ 2011年秋季地質の調査研修
産総研地質調査総合センターの「地質の調査」に関わる研修制度の外部プロ
グラムの一環として2011年秋季地質の調査研修が実施されます。
実施期間:2011年10月24日(月)〜10月28日(金) 4泊5日
実施場所:千葉県君津市及びその周辺地域(房総半島中部域)
申込締切:2011年9月16日(金)
詳細は、、、
http://www008.upp.so-net.ne.jp/gsis/gykensyu.htm
■ Indian Ocean IODP Workshop in October 2011
日時:2011年10月17日(月)〜18日(火)
場所:Goa, India
詳細は、、、
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/geoFlash_img/no142_IndianOceanIODP_ws.pdf
■ 2011年 PERC 惑星地質学フィールドシンポジウム
惑星探査,惑星地質学の最先端研究を行っている研究者と地質学者が情報交
換をできる場として,千葉工業大学惑星探査研究センターでは,11月初旬に,
北九州国際会議場で「2011年 PERC惑星地質学フィールドシンポジウム(2011
PERC Planetary Geology Field Symposium)」を開催します.会議では,惑
星地質学に関連した発表に限らず,惑星地質学者にとって地球の地質を知る
場でもあります.そのため,分野を問わず,ぜひ地球上での地質研究のご発
表をお願いできればと思います.また,欧米の惑星探査計画,惑星地質学の
中心的研究者を複数名招く予定で,日本では聞くことができない最先端の研
究成果を聞くこともできます.
シンポジウムに引き続き,別府,阿蘇,雲仙などで現地巡検を行います.通
常の地質巡検とは異なり,惑星探査を見据えた比較惑星地質学が焦点となり
ます.例えば,阿蘇山での惑星探査ローバーの走行テストなども実施する予
定です.
日程:シンポジウム 2011年11月5日(土)〜6日(日),巡検 11月7〜9日
シンポジウム開催場所:北九州国際会議場
参加費:シンポジウム 一般8000円,学生5000円
巡検 35,000円(定員40名)
(学生旅費支援の申込みを受け付けています.詳細はweb siteに.)
アブストラクト,登録〆切:2011年8月31日
ご意見・ご質問:pgfs2011@perc.it-chiba.ac.jp
詳細は、、、
http://www.perc.it-chiba.ac.jp/meetings/pgfs2011/
■JABEE 事務局ニュース No. 16(2011/7/8版)
JABEE事務局ニュースは社員(正会員)、賛助会員、理事、監事、顧問、
委員会委員宛に配信されています。
情報のより広い共有のため、会員の皆様にもご転送いたします。
2011/7/8版ニュース PDFはこちら、、
http://www.jabee.org/OpenHomePage/jabee_e-news_16_110708.pdf
JABEEホームページ http://www.jabee.org/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■東京工業大学大学院:理工学研究科 地球惑星科学専攻(助教)(9/30)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】地質マンガ 「タイムスケール」
──────────────────────────────────
タイムスケール
(原案・マンガ化:黒田潤一郎)
http://www.geosociety.jp/faq/content0320.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】geo-Flash No.141 の記事の訂正
──────────────────────────────────
geo-FlashNo.141(7/5号)の【7】に誤りがありましたので、
下記の通り訂正させていただきますと共に謹んでお詫び申し上げます。
申し訳ございませんでした。
【7】オマーンにおける国際会議の紹介
1段落 2行目
2011年1月7-9日に開催 --> 2012年1月7-9日に開催
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
地質年代表における年代数値―その意味すること
地質年代表における年代数値―その意味すること
兼岡一郎(前学術会議地質年代小委員会委員長、
元IUGS国際地質年代小委員会副委員長)
1.はじめに
IUGS (International Union of Geological Sciences; 国際地質学連合)では、ICS(International Commission on Stratigraphy; 国際層序委員会 )から提案されていたInternational Stratigraphic Chart(地質系統・地質年代表; 以後ISCと略記)におけるQuaternary(第四紀)の始まりの境界を、GelasianとPiacenzianとすることを2009年6月に承認した。その境界の年代数値としては2.588 Ma(1 Maは100万年前を意味する)とされており、以前にQuaternary境界として割り当てられていたCalabrian底部の年代数値よりは約78万年古くなっている。わが国でもこの経緯を踏まえて、地質年代関連分野の各学協会から推薦された委員によって構成された委員会で、国際規約に沿ったQuaternaryの定義などを受け入れることを決め、その件に関して周知徹底が計られた(奥村, 2010など)。しかし、その過程において、地質年代表における年代数値の意味の詳細についての理解が、わが国の研究者間で必ずしも同じではない様子が見受けられた。さらにそうしたことが要因となって生じたと考えられる事例を、私自身の周囲でも経験することになった。そのため、10年前まではICSの中の小委員会のひとつとして存在していたSOG(Subcommission on Geochronology、国際地質年代小委員会)に在籍したことのある立場から、ISCに付された年代数値を利用する人たちが、それらについて的確な取り扱いをされるようにその意味を説明しておきたい。
2.地質年代表につけられた年代数値とは?
図1.International Stratigraphic Chart(国際地質系統・地質年代表)(ICS2009)中、 Holocene からLower Cretaceousまでの部分。(International Commission on Stratigraphy, 2009)
GSSP(Global boundary Stratotype Section and Point; 国際標準模式層断面及び地点)の欄で鋲型の印がついているのは、各地質境界においてGSSPが定義されている部分。
ここでは、ICSが2009年に発行したISC(ICS2009と表記)に基づいて解説することにする(ICS, 2009)。
図1には、ICS2009のうちLower Cretaceous(下部白亜紀)から Holocene(完新世)までの部分、図2では、Precambrian(先カンブリア時代)の部分を示している。これらの図を注意してみると、(a)Neogene(新第三紀)からHolocene(完新世)までの期間、(b)Paleogene(古第三紀)以前でCambrian(カンブリア紀)までの期間(図1ではJurassic(ジュラ紀)以前は示していない)、(c)Cambrianより古いPrecambrianの期間で、それぞれ年代数値の表示の仕方が異なっていることが分かる。(b)については多くの年代数値に±の値が付けられているが、(a)と(c)の数値にはそれがつけられていない。そのことは、それぞれの数値が推定されている方法が異なり、数値自体が示す意味も異なっていることを反映している。すなわち同じ地質年代表の中でそれにつけられている年代数値の意味が異なるということで、そのことを考慮せずに与えられている数値をそのままの形で細かい議論などに用いると、無用の混乱を生じかねない。内容としては、(a)は天文年代に基づいた値、(b)は放射年代データに基づいた値、(c)では年代数値自体が各地質境界を定義している。
(a)で採用されている天文年代は、ユーゴスラビアの地球物理学者M. Milankovitchが20世紀初めに提唱したモデルを基本としている。彼は地球の気候変化は北緯65度における日射量の変化と対応し、それは地球の公転軌道の離心率、地軸の傾き、地軸歳差運動の変動周期の組み合わせに支配されているとした(Milankovitch cycle)。その後、地球の軌道要素の変化に関しては、地球と月や他の惑星などの影響を考慮してさらに詳細に調べられてきた。一方、1970年以降に詳しく研究されるようになった海洋堆積物中の底生有孔虫の殻などの酸素同位体比から推定された過去の海水温度変化などと、Milankovitch cycleがよい対応をすることが明らかになってきた(例、Shackleton et al. 1990)。その対応関係を利用することにより、海洋堆積物から推定される地質年代の境界の年代値を推定することができる。これが天文年代を利用した手法であり、ICS2009のNeogeneより新しい地質年代に対しては、この方法により推定された年代数値が採用されている。この方法では年代数値は地球軌道要素の計算値で与えられ、数値としては非常に細かい年代値を与えることができる。しかし、天文年代は地表での周期的な気候変化はMilankovitch cycleのみによることを前提としており、誤差のつかないモデル年代と考えるべきである。
図2.ICS2009中で、Precambrianに相当する部分。(International Commission on Stratigraphy, 2009)
GSSP, GSSA(Global Standard Stratigraphic Age; 国際標準層序年代)の欄で時計印がつけられているのは、数値年代で定義された部分。
これに対して(b)では、できるだけGSSP(Global boundary Stratotype Section and Point: 国際標準模式層断面および地点)ないしそれに相当する場所において、各層序境界を挟む上下の地層から岩石・鉱物・火山灰など放射年代測定が可能な試料を採取して年代測定を行い、それらの値を内挿して層序境界の年代を推定している。各層序の地質年代は示準化石などによって定義されているが、一般的には化石そのもので放射年代測定をすることは難しいので上記のような手法をとらざるを得ない。年代測定値は誤差を伴うと共に複数のデータを扱うので、それらをあわせた誤差が算出される。現在こうした手法によって得られた年代の誤差としては、その年代が数億年の古さをもつものでも0.1〜0.2 %以下におさえることはかなり難しい。また図1において(b)の範囲にあるものでも、±がつけられないままの年代値しか与えられていない境界がある。それらはその境界での年代値を推定するために、放射年代測定を行うために適した試料が十分に得られなかったことなどにより、上下の境界の年代値を考慮して推定した概算値である。
こうした地質年代表において、年代数値に誤差が付けられるようになったのはそれほど古いことではなく、また一般的なことでもない。筆者の知る限りにおいては、かつて国際地質年代小委員会の委員長だったG. Odinが私案として報告している年代表(Odin, 1994)で採用しているのが、最も早い例である。それ以前に提案されていた地質年代表(例, Harland et al. 1990)に与えられている年代数値についても放射年代などのデータを基に推定されていたはずだが、その当時は基になるデータ数などが限られていて統計誤差を算出するまでに至らなかったか、あるいは地質年代表に用いる年代数値に誤差をつける意義を認めなかったことがその理由かも知れない。実際、アメリカ地質学会から2009年に発行された地質年代表でも、各地質境界に与えられている年代数値は高々3桁の有効数字しか表示されておらず、誤差はつけられていない(Walker and Geissman, 2009)。
一方、Precambrianに相当する(c)においては、Proterozoic(原生累代)末期を除くと大型化石そのものが存在しない。そのため地質年代表が作成され始めた頃には、化石の代わりに類似した岩相の比較によって対比などがされてきたが、異なった大陸間などでそれらを同定することは容易でなく、また同じ岩相をもった岩体が存在する必然性もない。そのため現在の地質年代表におけるPrecambrianの地質年代は、GSSA(Global Standard Stratigraphic Age; 国際標準層序年代)による数値年代で定義されており(Plumb and James, 1986)、年代数値に誤差は生じない。しかし図2にあるHadean(冥王累代)は、現時点では非公式な名称であり、その上限境界の年代値4000 Maも暫定的なものである。
3.異なった基準での年代数値が採用されている理由
地質年代表ICS2009において、なぜ年代区分の違いによってこのような異なった基準に基づいた年代数値が採用されているのだろうか。それにはICSを構成する小委員会の事情が関係している。
ICSには各地質年代ごとに対応する小委員会とそれ以外の小委員会があるので、それらの数はかつて20を超えていた。10年ほど前までは、放射年代を手法として年代数値などを検討するSOG(国際地質年代小委員会)も存在していて、地質年代全体を通して各年代層序の境界の年代数値を検討し、放射年代測定に用いる核種の壊変定数の妥当性などについて検討する役割を担ってきた。しかし、IUGS執行部からICSが小委員会の数が多過ぎるのでその数を減らすことを勧告された際、当時のICS執行部はSOGを廃止することにした。そのためSOGが2002年に廃止されて以降は、年代層序の境界の年代数値を定める役割は、各地質年代に対応するそれぞれの小委員会に任されるようになったのである。
Precambrianに関しては、上記とは異なる経緯がある。もともと各地質年代はその特徴を代表する示準化石などによって区分されているのに対し、Precambrianにおいてはそのような示準化石を手段として用いることができない。そのためICSのSPS(Subcommission on Precambrian Stratigraphy; 先カンブリア時代層序小委員会)では、年代数値によって層序境界を区分することにした。その提案は1989年にSPSおよびICSで承認され、1990年にはIUGSでも批准されていた。
一方、Neogene以後については、1970年代頃から海洋底掘削プロジェクト(DSDP, ODP)によって回収された連続した海洋底掘削コア試料などを分析することにより、地質、微化石、地磁気逆転などに基づいて細分化された層序年代が得られるようになった。そのため、それぞれの層序を区分するために高分解能をもった年代数値が求められるようになり、それに対する試みもされるようになった。例えば地磁気層序に対するCande and Kent(1995)による表(CK)では、その区分を0.001 Ma単位とし、年代区分数値としてJurassicなどでは6桁の年代数値を与えている。この表を作成するためには基準となる9点を選び、それらの年代数値は放射年代および一部天文年代などで調整した値に基づいて推定されている。その際、これらの値には誤差がないものとし、それぞれの間における地磁気逆転の年代を統計的な手法で内挿して数値を与えている。しかし規準として用いられた放射年代は測定値であるので当然測定誤差を含んでおり、しかも3桁の有効数字しか有していない。したがって(CK)での年代数値の有効数値は3桁程度の信頼性しかなく、それ以上に細分化した年代数値は地磁気層序における相対年代を示すことには意味を有しても、他の方法によって得られた年代数値との細かい差異を検討することは不適当である。同様のことは、微化石層序表などにつけられた年代数値でも生じている。そもそもNeogene以後の年代に対しては、放射年代値として0.2〜0.3 %以下の測定確度を得ることは非常に難しい。一方、海洋性堆積物に含まれる底生有孔虫などに対する酸素同位体比の変動から作成されたMarine isotope stageとMilankovitch cycleに基づいて計算された気温変化を結び付けて得られた天文年代は、年代数値としては非常に高い分解能をもつとされた(例、Shackleton et al. 1995)。そのため従来の放射年代測定に代わり、少なくともNeogene以後におけるMarine isotope stageに示される気温変化はMilankovitch cycleに支配されているという前提のもとに、Neogene以後の地質年代に対しては天文年代によって地質年代表への年代数値を与える試みが当時のICS執行部の意向によって提案された(ICS, 2004)。この案は、結局Quaternaryの定義の改訂と共に、2009年の新しい地質年代表ISCとしてIUGSで承認された。
しかし、それ以前の地質年代に対しては、Cretaceous-Paleogene(K-T)境界で隕石衝突によってもたらされた急激な気候変化が示されているように、明らかにMilankovitch cycleとは異なる要因によっても気温変化が生じていることが認められていることもあり、従来通り放射年代のデータに基づいた年代数値が与えられている。このことは、これらの地質年代を扱う各小委員会の年代数値に対する対応が、Neogene以後を対象とする小委員会とは異なっているためと考えられる。
4.地質年代表における年代数値について注意すべきこと
これまで述べてきたように、ICS2009の地質年代表につけられている各境界の年代数値は、Neogene以後とそれ以前、さらにPrecambrianの各地質年代でその意味が異なっている。
図1に見られるように、Neogene以後の地質年代境界に対する年代数値は、1 Maまでの境界は3桁、1 Maより古い年代に対しては4桁ないし5桁の数値で与えられ、±はつけられていない。前述したとおり、これらの年代数値は、Milankovitch cycleに基づいた天文年代に基づいている。天文年代は気候変動の周期性は全てMilankovitch cycleによって支配されていることを前提としており、本来この前提自体については放射年代などとの詳細な比較・検討によってその妥当性が保証される必要がある。気候変動に関する要因としては、これまでも太陽活動やそのほか多くの可能性が挙げられてきており、研究者によってそれぞれに対する見解は分かれている。また、その年代数値を推定する際には、酸素同位体比の周期的変動とMilankovitch cycleなどをうまく対応させるための調整(tuning)が必要であるが、それは一義的に定まるわけでなく、統計的に意味のある不確定さを見積もることも困難である。
Quaternryの境界区分として、GelasianとPiacenzianを区分する年代数値として2.588 Maが与えられているが、放射年代測定値としては、この年代範囲で4桁の有効数値を与える精度は得られない。たとえば、従来Quaternaryの境界とされていたCalabrian とGelasianに対してICS2009では1.806 Maが与えられているが、Odin(1994)では1.75±0.05 Maと表示されている。またGelasian とPiacenzianは、地磁気層序ではMatuyama Reversed Epoch(松山逆磁極期)と Gauss Normal Epoch(ガウス正磁極期)との境界に相当するとされていて、そのことも第四紀の境界を定義するための有力な要因のひとつとなったことが考えられる。しかし、実際は両者が全く同じ地層に対して定義されているわけではなく、地磁気層序ではMatuyama Reversed Epochと Gauss Normal Epochとの境界は天文年代を基にして2.581 Maと推定されている(Ogg and Smith, 2004)。
Milankovitch cycleを前提として求める天文年代にしても、研究者の推定手法によってその数値にも異同が生じる。こうした理由から、Quaternaryに与えられた2.588 Maという年代数値はモデル年代としてそのまま引用するのが最も妥当であるが、丸めた数値を用いる際には他の境界の年代数値と同じ基準に基づいて取り扱うべきであろう。もし概数として取り扱う際には、アメリカ地質学会で採用している2.6 Maの数値(Walker and Geissman, 2009)などを用いた方が、自然現象との対応に関しての年代数値としては問題が少ないと考えられる。
一方、Paleogene以前の地質年代に対して放射年代データを基に与えられている年代数値は、用いられている放射年代値がきちんとそれぞれの年代測定法の前提条件を満足している限り、現在からの年代数値を直接示すはずである。実際には、年代区分の値を得るためには、境界をはさんだ試料の年代測定の数値からの内挿によって求められ、またそれぞれの年代測定値には誤差を伴うので推定された境界の値にも誤差がつく。年代測定に伴う誤差は、方法や試料の種類・年代範囲にもよるが、0.2〜0.3 %以下の分析精度・確度を得ることは容易でない。また各放射壊変定数自体にも不確定さが残っており、各年代測定法における固有の問題と共に、今後さらに検討される必要がある。しかし、同じ対象に対して異なった年代測定法によってクロスチェックすることにより、測定確度としての誤差範囲をある程度まで見積もることができる。そのため、放射年代値を用いて求めた地質年代の境界値の年代数値に誤差を伴うことは避けられないが、特定のモデルとは独立して、年代数値そのものが意味をもつ。このことは、Milankovitch cycleに準拠して与えられているNeogene以後の年代数値とは、原理的に異なる意味を持つ。
Precambrianの年代数値は、数値そのものが地質年代区分に用いられているので数値としての曖昧さはない。
5.最後に
上述したように、ICS2009の地質年代表で与えられている地質年代境界の年代数値は、Neogene以後、PaleogeneからCambrian、Precambrianの各期間では、それぞれ年代数値の推定の仕方が異なっている。そのため、それらの年代数値はそれぞれの意味をきちんと把握した上で用いることが非常に大切である。異なった前提に立った数値を混同すると科学的な議論にまで影響を及ぼす恐れがあるので、十分に注意して欲しい。またこれらの数値年代は、今後も適宜改訂されていく余地があることも念頭においておくことが大切である。
【謝辞】
本稿は、天野一男氏、星 博幸氏などとの会話を通じて得た示唆、および斎藤靖二氏からのお勧めもあって執筆することにした。さらに天野氏と斎藤氏には原稿を読んでいただき、その改善のために有益なご指摘をいただいた。これらの方々にお礼の言葉を申し上げます。
【文献】
Gradstein, F.H., Ogg, J.G., Smith, A.G. (ed.) (2004), A Geologic Time Scale 2004. Cambridge University Press.
Harland, W.B., Armstrong, R.L., Cox, A.V. et al. (1990) A Geologic Time Scale 1989. Cambridge University Press.
ICS(International Commission on Stratigraphy) (2009), International Stratigraphic Chart 2009, (http://www.stratigraphy.org/).
Odin, G. S. (1994) Geologic time scale. Comptes rendus de l’Academie des Sciences de Paris, Serie II, 318, 59-71.
奥村晃史、第四紀の新しい定義:人類の未来を拓く鍵として、JGL, 6(2), 1-3.
Plumb, K.A. and James, H.I. (1986) Subdivision of Precambrian time: recommendations and suggestions by the Subcommission on Precambrian Stratigraphy. Precambrian Research, 32(1), 65-92.
Shackleton, N.J., Berger, A. and Peltier, W.A. (1990), An alternative astronomical calibration of the lower Pleistocene time scale based on ODP Site 677. Transaction of the Royal Society of Edinburgh, Earth Sciences, 81, 251-161.
Walker, J.D. and Geissman, J.W. (compilers) (2009), Geologic Time Scale. Geological Society of America, doi: 10.1130/2009.CTS004R2C.
(原稿受付 2011年7月6日)
地質マンガ ルーツ
地質マンガ
戻る|次へ
No.143 2011/7/28 geo-flash(臨時)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.143 2011/7/28 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】水戸大会:まもなく参加登録締切です!
【2】見学旅行へ行こう! 見学旅行申込も締切間近!
【3】市民向けポスター展示の募集 締切延長!(8/22〔金〕まで)
【4】市民向け:東日本大震災関連ポスター募集
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】水戸大会:まもなく参加登録締切です!
──────────────────────────────────
関東支部から会員の皆さまに向けて水戸大会参加を呼びかけるメッセージが
届いています。皆さんの参加で水戸大会を成功させましょう!
-----------------------------------
日本地質学会の皆様
蒸し暑い日々が続き、今年は節電で部屋の温度も一段と高く、扇風機で
しのいでいる会員の方も少なくないことと思います。
ご案内の通り、2011年水戸大会の参加申し込みの期限も近づいてきました。
会員が多く参加することが大会の成功の鍵となります。ぜひ、事前参加
登録・見学旅行申込みを積極的に行い水戸大会を盛り上げましょう。
【事前参加登録】
申込締切:オンライン 8月5日(金)18:00、
FAX/郵便 8月1日(月)必着
詳細は http://www.geosociety.jp/mito/content0026.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】見学旅行へ行こう! 見学旅行申込も締切間近!
──────────────────────────────────
見学旅行のお申し込みも締切間近です.
この機会でないと見学できない対象が多数ありますので, 多くの皆様の参加
をお待ちしています.
(FAX/郵送:8月1日,オンライン:8月5日18:00)
まだの方はお早めにお申し込みください.
既に学会参加登録された方で見学旅行のお申し込みをされていない方,追加
で見学旅行参加申込ができます(FAX/郵送,オンラインの両方で可).
この機会に是非お申し込みください.
--------------------------
コース名
A班:日本最古の地層-日立のカンブリア系変成古生層(9/12-13)
B班:筑波山周辺の深成岩・変成岩(9/12日帰り)
C班:磐梯・吾妻・安達太良−活火山ランクBの三火山(9/12-13)
D班:常磐地域の白亜系〜新第三系と前弧盆堆積作用(9/12-13)
E班:棚倉断層のテクトニクスと火山活動・堆積作用(9/12-13)
F班:栃木の新第三系−荒川層群中部の層序と化石および大谷地域の応用地質(9/12日帰り)
G班:常陸台地の第四系下総層群の層序と堆積システムの時空変化(9/12日帰り)
H班:鬼怒川低地帯の第四紀テフラ層序−火山噴火史と平野の形成史(9/12-13)
I班:伊豆衝突帯の最前線−関東のテクトニクス(9/12-13)
J班:地層を見る・はぎ取る・作る(9/10)
--------------------------
見学旅行:各コースの魅力と見どころはこちらから↓
http://www.geosociety.jp/mito/content0030.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】市民向けポスター展示の募集 締切延長!(8/22〔金〕まで)
──────────────────────────────────
市民向けポスター展示・説明会に参加しませんか?
アウトリーチに関心があり、「自分の研究を市民にわかりやすく伝えたい」
という会員の皆様に、情報展のスペースを活用していただき、発表スペース
を提供いたします。
応募締め切りは8月22日(金)17時まで延長いたします。
普及教育に関心のある方は、ぜひ展示をご検討・ご応募下さい!
詳しくは、、、
http://www.geosociety.jp/mito/content0044.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】市民向け:東日本大震災関連ポスター募集
──────────────────────────────────
東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)により,東北から関東に至る広い
地域が被災しました.今大会開催地である茨城県においても,護岸部・平野
部の液状化,山間地の斜面災害,さらには原発に伴う海域汚染など多くの被
害が報告されています.そこで,震災において発生した様々な被災状況に関
して,地質学的視点から広く社会に紹介する場を計画しました.
茨城県内の市民に向けて,県内の被災状況,さらには近隣を含めた広範囲
な震災情報を「東日本大震災関連ポスター展示」として発信したいと考えて
います.
ぜひ,震災調査に関わっている多くの会員の応募をお願いいたします.
申込締切:8月22日(月)17時 (←締切延長しました)
詳細は http://www.geosociety.jp/mito/content0046.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.145 2011/8/5 geo-flash(臨時)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.145 2011/8/5 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】水戸大会見学旅行の申込締切を延長します(8/12まで)!是非この機会に!
【2】その他のお知らせ
【3】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】水戸大会見学旅行の申込締切を延長します(8/12まで)!是非この機会に!
──────────────────────────────────
水戸大会見学旅行には多くの方から参加申込をいただきました。ありがとう
ございます。
定員までまだ少々余裕のあるコースがありますので、8/12(金)まで締切を延
長し、見学旅行の参加申込のみ受け付けることにいたしました。魅力的なコ
ースをたくさん用意していますので、是非この機会に見学旅行にご参加くだ
さい。多くの皆様の参加をお待ちしています。
参加希望の方は学会事務局(main@geosociety.jp)までご連絡ください。
(オンラインでの受付は終了しています)
申込締切:8月12日(金)15時
ただし、各コース、定員に達した時点で申込を締め切らせていただきます。
--------------------------
コース名
A班:日本最古の地層-日立のカンブリア系変成古生層(9/12-13)
B班:筑波山周辺の深成岩・変成岩(9/12日帰り)
C班:磐梯・吾妻・安達太良−活火山ランクBの三火山(9/12-13)
D班:常磐地域の白亜系〜新第三系と前弧盆堆積作用(9/12-13)←☆空き残り僅か,お早めにお申し込みを
E班:棚倉断層のテクトニクスと火山活動・堆積作用(9/12-13)←☆空き残り僅か,お早めにお申し込みを
F班:栃木の新第三系−荒川層群中部の層序と化石および大谷地域の応用地質(9/12日帰り)
G班:常陸台地の第四系下総層群の層序と堆積システムの時空変化(9/12日帰り)
H班:鬼怒川低地帯の第四紀テフラ層序−火山噴火史と平野の形成史(9/12-13)
I班:伊豆衝突帯の最前線−関東のテクトニクス(9/12-13)←★定員に達しましたので,追加募集はいたしません
J班:地層を見る・はぎ取る・作る(9/10)←☆空き残り僅か,お早めにお申し込みを
--------------------------
見学旅行:各コースの魅力と見どころはこちらから↓
http://www.geosociety.jp/mito/content0030.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究センター第2回シンポジウム
「海洋教育がひらく防災への道」
東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。一日
も早い復興をお祈り申し上げます。
今、学校教育での防災教育の重要性が再確認されています。海がもたらす
災害を子どもたちがどのように学ぶのか。災害からどのように身を守ったら
よいのか。一方で、海は怖いばかりではなく、漁業や海運などのように私た
ちへの恵みの場であることを学ぶことも大事です。学校での海の防災教育に
ついて考えるため、東京大学海洋教育促進研究センターと日本財団は共同で
シンポジウムを開催いたします。学校教育の現場の先生方をはじめとして、
多くの方々の参加をお待ちします。
日時:2011年8月27日(土)13:00〜17:20
場所:弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1 東京大学農学部構内)
対象:小・中・高等学校教諭、学生、一般
参加費:無料(要申込)
プログラム詳細はこちらから、、、
http://www.oa.u-tokyo.ac.jp/RCME/information/201108symp.html
参加申込みはこちらから、、、
https://www.webmasters.co.jp/RCME/symp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■平成24年度研究船利用課題の募集(8/22)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.146 2011/8/23 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.146 2011/8/23 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】水戸大会:茨城大学アクセスお得情報
【2】報告:津波で墓石が丸くなった!岩手県大槌の墓石の津波による侵食について
【3】東日本大震災に対する学会員の声を募集します
【4】地惑連合:代議員立候補の受付が始まっています
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】水戸大会:茨城大学アクセスお得情報水戸大会:茨城大学アクセスお得情報
──────────────────────────────────
関東支部から茨城大学アクセスお得情報が届きました。
【東京から茨城大学へのアクセスお得情報】
○高速バス 東京駅八重洲南口のりばからの水戸線茨大ルートがお得.
ツインチケットで3700円.ツインチケットは2枚つづりの回数券で1人で往復
利用でも2人で片道利用でもOK.茨城大学前まで約1時間37分.
○JR東日本+バスの場合 お一人様の場合,「ひたち往復きっぷ」が7000円
でお得.上野駅から水戸駅まで約1時間10分.特急列車普通車指定席利用可能
で4日間有効. 他に回数券もありますがチェックしてみてください.
バスは,水戸駅北口7番のりば・5番のりば(約25分;320円).
○自家用車等 水戸へは多人数で乗るとお得.ただし,茨大へは茨大周辺の
駐車場を利用するしかありません.東京から茨大へ直接行く場合,常磐高速
自動車道水戸北スマートICで降りると近いです.ただし,ETC車載器とETC
カードが必要です.また,福島方面からお越しの方は,上り車線から降りら
れませんのでご注意ください.
○ツアー,その他 ツアーがあるかもしれませんが,インターネット上で
ホテル等の予約をしても大してかわらないかもしれません.いずれにしても
予約はお早めに.
○学部生の場合 登録料が要らないのでお得です.学会はいいですよ.来てください.
○院生の場合 登録料が割引になるのでお得です.
【水戸駅周辺の駐車情報】
水戸駅周辺にお泊まりの場合でホテル駐車場がご利用できない場合,以下の
大規模駐車場があります.
①パラカ水戸駅前第1 \700/日
②アップルパーク水戸駅前パーキング \800/日(旧 西武パーキング)
③NPC24H水戸駅南口パーキング \1000/日
①,③についてはgoogle検索で場所が表示されます.
②については検索できませんが,google地図上で水戸駅北方約200m付近で
施設名が確認できます.
また、9/10,11(土・日)の期間で,地質情報展等の見学で県立堀原武道館へ
行かれる方は,堀原運動公園の駐車場(夜9時以降は閉鎖)を利用することが
できます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】報告:津波で墓石が丸くなった!岩手県大槌の墓石の津波による侵食について
──────────────────────────────────
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
2011年7月12日の朝日新聞朝刊1面に,「震災4ヶ月,手を合わせ」という題
の小さな記事が写真入りで掲載された.この写真には,岩手県大槌の江岸寺
の墓前で手を合わせる家族の姿が写っている.そして,この家族の周囲では,
全ての墓石が倒れているように見える.しかし,私たちの墓石転倒率調査の
結果によると,震源からの距離が同程度の仙台付近でも転倒率は7.8%(墓地
128ヶ所の平均)と低く,なぜ100%近い墓石が倒れているのか疑問だった.
津波で水没した仙台平野の海岸部の墓地でも,津波で倒された墓石は少数だ
った.この疑問を解決するため,7月31日に現地調査を実施した.その結果,
驚くべき被害の実体がわかったので報告する.
続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/hazard/content0062.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】東日本大震災に対する学会員の声を募集します
──────────────────────────────────
今回の大震災では、原発の被災問題も含めて、日本史上、歴史的な瞬間に
我々は今立たされています。地質学会としては、これまでに提言の発出など
の活動を行なってきましたが、今回の震災に対する会員の皆様からの声を集
めて学会HPに掲載していくことで、学会内での意見や情報の共有を進めてい
きたいと考えています。
皆様からの声をお寄せください。
学会事務局(journal@geosociety.jp)まで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地惑連合:代議員立候補の受付が始まっています
──────────────────────────────────
日本地球惑星科学連合の代議員選挙が8月3日公示され、立候補受付が8月15日
から始まっています。会員の皆様の積極的な立候補をお願いします。
代議員選挙の公示:
http://www.jpgu.org/whatsnew/110803daigiin_kouji.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第61回東レ科学講演会(地質学会後援)
「科学技術と知の文化」
1. 科学・技術はどこまで信頼できるか(村上 陽一郎)
2. 大災害と科学者・技術者の倫理(阿部 博之)
日時:2011年9月16日(金)17:00〜20:00
場所:有楽町朝日ホール(千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン11階)
入場無料(定員630名:当日会場先着順)
http://www.toray.co.jp/tsf/info/inf_006.html
■原子力総合シンポジウム2011「原子力安全の再構築―東日本大震災を踏まえて―」
中長期的視点から福島第一原子力発電所事故の状況,今後の地域復興にかか
わる進め方の提示,原子力安全にかかわる再構築等について,日本学術会議と
関連学協会が協力し,各界の識者を交えて総合的に議論する。
日時:2011年10月19日(水)
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木7-22-34)
主催:日本学術会議 総合工学委員会
プログラム案など詳細は、、、
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/geoFlash_img/no146_2011AtomEnergySympo.pdf
■第11回放散虫研究集会(松山) ―中世古先生追悼集会―
おりしも第1回放散虫研究集会(1981年)が開催されてから30年、中世古先生
の追悼として「特別セッション」を設け、海外研究者や生物学分野の方々の
特別講演やWorkshop[微化石骨格と理論形態学]など、盛りだくさんの企画を
用意して多数の方々のご参加をお待ちしております。
日時:2011年10月29日(土)・30日(日)
場所:愛媛大学理学部総合研究等4階共通会議室486(場合により302講義室に変更)
参加費:無料
参加&講演申込:9月末まで
詳細は、、、
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/geoFlash_img/no146_11radiolaria.pdf
お問い合わせ&申込み: 愛媛大学大学院理工学研究科(理学系)地球科学
堀 利栄(shori@sci.ehime-u.ac.jp)まで
電話:089-927-9644(直通)、Fax No. 089-927-9640
**********************************
同時開催! 微化石展 小さな生物が語る地球のなぞ2011年10月29日〜11月7日
愛大ミュージアム 企画展示室 日本古生物学会後援
**********************************
■東海地震防災セミナー2011 [第28回]
日時:2011年11月10日(木) 13:30〜16:00
場所:静岡商工会議所静岡事務所5階ホール(JR静岡駅北口西側)
テーマ:東日本大震災に学ぶ
1.最近の研究から明らかになった東海・東南海・南海地震の連動発生の
可能性とその影響(東京大学地震研究所 古村 孝志)
2.減災社会を築く(静岡県危機管理部 岩田 孝仁)
主催:東海地震防災研究会
連絡先:〒422-8035静岡市駿河区宮竹1-9-24 土研究事務所
Tel:054-238-3240, Fax:054-238-3241(土 隆一)
■提言「新しい高校地理・歴史教育の創造 −グローバル化に対応した時空間
認識の育成−」
日本学術会議は、2011年8月3日に高校地理歴史科教育における地理基礎、
歴史基礎の新設2科目必修化の提言を公表しました。
提言の内容は、、、
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-21-t130-2.pdf
日本学術会議の提言・報告書:
http://www.scj.go.jp/ja/info/
■日本学術会議会長談話「66年目の8月15日に際して―「いのちと希望を育
む復興」を目指す」
8月15日、日本学術会議会長談話「66年目の8月15日に際して―「いのちと希
望を育む復興」を目指す」が日本学術会議より発出されました。
本文はこちらから、、、
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-21-d12.pdf
■JABEE 事務局ニュース No. 17(2011/8/9版)
JABEE事務局ニュースは社員(正会員)、賛助会員、理事、監事、顧問、
委員会委員宛に配信されています。
情報のより広い共有のため、会員の皆様にもご転送いたします。
2011/8/9版ニュース PDFはこちら、、
http://www.jabee.org/OpenHomePage/koho/jabee_e-news_17_110809.pdf
JABEEホームページ http://www.jabee.org/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■北海道大学大学院:自然史科学部門地球惑星システム科学分野(教授) (10/28)
■高知大学:教育研究部自然科学系理学部門(助教) (10/21)
■九州大学総合研究博物館:分析技術開発系(教授)(10/14)
---------------
■平成24年度学術研究船白鳳丸共同利用公募(9/20)
■平成24年度学術研究船淡青丸共同利用公募(9/20)
■平成24年度笹川科学研究助成の募集(10/1〜14)
■東京大学大気海洋研究所:国際沿岸海洋研究センター共同利用(9/5)
■高知大学:海洋コア総合研究センター全国共同利用研究公募 (後期8/31)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。。
No.144 2011/8/2 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.144 2011/8/2 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】水戸大会:間もなく参加登録締切!
【2】見学旅行へ行こう! 見学旅行申込も締切間近!
【3】解説:地質年代表における年代数値―その意味すること
【4】地質図の紹介:「アジア地質図 1:5,000,000」寺岡易司・奥村公男著
【5】会員名簿データを整理中です。住所変更はお早めに!
【6】Island Arc 2010年最多ダウンロード論文賞が決定
【7】「地質構造百選」の候補地・写真の投稿、ありがとうございました。
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞情報
【10】地質マンガ 「ルーツ」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】水戸大会:間もなく参加登録締切!
──────────────────────────────────
水戸大会の参加登録は、今週末【8月5日(金)18時】までです。
まだ申し込んでない方は、すぐに登録ページへ↓
http://www.geosociety.jp/mito/content0026.html
水戸大会関連の締切一覧:
■参加登録:申込締切:オンライン 【8/5(金)18時】※FAX/郵送は締切りました
■見学旅行:申込締切:オンライン 【8/5(金)18時】
http://www.geosociety.jp/mito/content0026.html
■託児室・学童ルーム 【8/12(金)】
http://www.geosociety.jp/mito/content0036.html
■「東日本大震災関連ポスター展示」の募集 締切延長!【8/22(月)17時】
http://www.geosociety.jp/mito/content0046.html
■「市民向けポスター展示」の募集 締切延長!【8/22(月)17時】
http://www.geosociety.jp/mito/content0044.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】見学旅行へ行こう! 見学旅行申込も締切間近!(8/5締切)
──────────────────────────────────
見学旅行のお申し込みも締切間近です。
魅力的なコースをたくさん用意しています。
まだ定員まで余裕があります。
多くの皆様の参加をお待ちしています。
既に大会参加登録された方で見学旅行のお申し込みをされていない方、
オンラインで追加で見学旅行参加申込ができます。
--------------------------
コース名
A班:日本最古の地層-日立のカンブリア系変成古生層(9/12-13)
B班:筑波山周辺の深成岩・変成岩(9/12日帰り)
C班:磐梯・吾妻・安達太良−活火山ランクBの三火山(9/12-13)
D班:常磐地域の白亜系〜新第三系と前弧盆堆積作用(9/12-13)
E班:棚倉断層のテクトニクスと火山活動・堆積作用(9/12-13)
F班:栃木の新第三系−荒川層群中部の層序と化石および大谷地域の応用地質(9/12日帰り)
G班:常陸台地の第四系下総層群の層序と堆積システムの時空変化(9/12日帰り)
H班:鬼怒川低地帯の第四紀テフラ層序−火山噴火史と平野の形成史(9/12-13)
I班:伊豆衝突帯の最前線−関東のテクトニクス(9/12-13)
J班:地層を見る・はぎ取る・作る(9/10)
--------------------------
見学旅行:各コースの魅力と見どころはこちらから↓
http://www.geosociety.jp/mito/content0030.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】解説:地質年代表における年代数値―その意味すること
──────────────────────────────────
兼岡一郎(前学術会議地質年代小委員会委員長、
元IUGS国際地質年代小委員会副委員長)
IUGS (国際地質学連合)では、ICS(国際層序委員会 )から提案されていたInternational Stratigraphic Chart(地質系統・地質年代表)におけるQuaternary(第四紀)の始まりの境界を、GelasianとPiacenzianとすることを
2009年6月に承認した。その境界の年代数値としては2.588Maとされており、以前にQuaternary境界として割り当てられていたCalabrian底部の年代数値よりは約78万年古くなっている。わが国でもこの経緯を踏まえて、地質年代関連分野の各学協会から推薦された委員によって構成された委員会で、国際規約に沿ったQuaternaryの定義などを受け入れることを決め、その件に関して周知徹底が計られた(奥村, 2010など)。しかし、その過程において、地質年代表における年代数値の意味の詳細についての理解が、わが国の研究者間で必ずしも同じではない様子が見受けられた。さらにそうしたことが要因となって生じたと考えられる事例を、私自身の周囲でも経験することになった。そのため、10年前まではICSの中の小委員会のひとつとして存在していたSOG(国際地質年代小委員会)に在籍したことのある立場から、ISCに付された年代数値を利用する人たちが、それらについて的確な取り扱いをされるようにその意味を説明しておきたい。
続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0322.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地質図の紹介:「アジア地質図 1:5,000,000」寺岡易司・奥村公男著
──────────────────────────────────
これは,同じ著者らによる1:3,000,000の東アジア地質図(2003)及び中央アジア地質図(2007)の領域を南北と西に拡張し,地質の編集をやり直して,手頃な大きさ(東西2枚を貼り合わせると165 x 114 cm)で一覧できるようにしたものである.東は日本,北はサハリンとバイカル湖,西はカスピ海とオマーン,南はスリランカとインドシナまでが含まれる.主な都市や河川,湖などが詳しく記入されており,通常の地図との比較が容易である.地名,凡例,文献などはすべて英語である.海底地形も1000 mごとの等深線で色分けされており,大陸棚や深海の分布がよくわかる.ただし,山や山脈,盆地や砂漠,島や半島などの名前は示されていない.この図を見ながらいろいろ考えたり議論したりする立場からは,少なくとも盆地の名称が記されていると便利である.
地質の凡例は年代を色,岩質を模様で表示しており,色の違いで地層の年代分布がよくわかるように工夫されている.貫入岩類(主に花崗岩)は赤,茶,紫などの濃色で示されているが,やはり年代によって色分けされている.年代区分の最小単位は紀(系)であり,堆積岩は陸成層・海成層の別,火山岩は珪長質・中性・苦鉄質の区分が模様で示されている.凡例にはメインの年代区分の横に6列の色分けされた柱があるが,これらは特に地理的区分や岩相区分とは関係なく,いくつかの紀をまとめて示す場合の色分けや記号を示す.これらの他に,付加体,オフィオライト,岩塩ストックが別の記号で示されている.遠くから見て最も目立つオフィオライトはオマーンのものであるが,各造山帯の主な岩体がよく描かれている.岩塩ストックは地質図西端のイランやカスピ海北側に点々と見られるが,付加体は地質図東端の日本とその周辺のみに示されている.この地質図の東西両端に全く異なる地史を示すこれらの特徴が示されているのは面白い.ただ,最近はロシア・モンゴル国境付近の原生代の地層が付加体であるとする論文も出ており(Kuzmichev et al., 2007),今後はアジア中央部でも原生代や古生代の付加体が広く分布することになるかもしれない.変成岩は堆積岩と同じ色で示されており,低〜中圧型(角閃岩相以上)と高圧型を模様で区別しているが,変成岩の分布はわかりにくい.中国東部やカザフスタン,キルギスタンなどで超高圧変成岩が発見され,この地域の大陸衝突テクトニクスを考える上で重要視されているので,高圧・超高圧変成岩をもう少し強調して表示する方がよいと思う.
アジア大陸主部の地質を概観してまず目に飛び込んでくるのは,地質図の中央を東西にうねって続くヒマラヤ・チベットの幅広い造山帯であり,それは東方でさらに幅を増して中国南部からインドシナまで拡がるように見え,その流れの中に四川とコラート(インドシナ中央部)のジュラ・白亜紀堆積盆地が中州のように存在している.また,この地質図の北半部には,カザフスタンからモンゴルを経てオホーツク海北部に至る中央アジア造山帯の東西に伸びる地層の連なりがよく描かれている.一方,この地質図の中央北端部にはバイカル湖に接するアンガラ地塊(シベリア剛塊の南端部)とそれを覆うカンブリア・オルドビス系がまとまった領域を占め,地質図の南西部にはインド地塊の広大な太古代の地層とそれを覆うデカン巨大火成岩区(LIP)の白亜紀玄武岩が大きくまとまった領域を占めている.この地質図は,アジア大陸の主体部分が古生代以後の変動帯からなっていることを,南北両端のアンガラ地塊・インド地塊との対比によってよく示している.中朝・揚子地塊などの太古界・原生界や四川盆地などの中生代以後の堆積盆は,この東西方向にのびる幅5000 km(バイカル湖からインドシナまで)の大造山帯に浮かぶ中州のように見える.インド地塊やアンガラ地塊に比べると,揚子(南中国)地塊や中朝地塊の地層の分布パターンは細かく断片化されていて,周囲の変動帯と大差ないように見える.細かく見ると,中朝地塊には太古代の地層が多いが,揚子地塊は古くても中期原生代であるという違いもよくわかる.
ところで,この地質図の地域には,上述のデカンLIPの他に蛾眉山(Emeishan)LIPがある.よく目をこらして見れば,四川盆地の南側にペルム紀の玄武岩が広く分布しているのがわかるが,遠くから見てここがLIPであることはよくわからない.その目で探すと,バイカル湖の南方にもかなり大きなペルム紀と三畳紀の玄武岩分布域があることがわかる.最近,シベリアLIPの活動(ペルム紀後期)が北東方に延びていることが報告され(Kuzmichev and Pease, 2007),さらにベーリング海峡近くまで延びる可能性があるが(筆者らの調査),南方にも延びているのかもしれない.
日本は主にジュラ・白亜紀の付加体と新生代の火山岩・堆積岩からなっているが,同じような地質の場所はアジア大陸にはほとんどなく,ロシアのサハリンと沿海州そして台湾だけが日本と類似している点が目を引く.ただ,インドの両側のパキスタンとミャンマーにはオフィオライトを伴うジュラ・白亜紀〜新生代の海成層が広大に分布しており,これらは日本と同時代の付加体の可能性があると思う.また,前述のアジア中央部の原生界を含め,「日本風」の付加体が大陸のあらゆる年代の地層に広く分布している可能性がある.
以上のように,これは日本と大陸の地質のつながりを考える資料としてこの上ない,手頃な大きさと価格の優れた地質図であり,地質家の研究室の壁に飾るのに好適な美しい地質図である.そして,このように気宇壮大な地質図は,研究や仕事上の世界戦略を形成するための基礎となり,学生教育上も有益である.会員諸兄諸姉に御一覧をお勧めする.10年後のアジア地質図がどうなっているか,楽しみである.
なお,本地質図は地学情報サービス株式会社(029-856-0561)または産業技術総合研究所地質標本館(029-861-3750)で購入できる.
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
文献
Kuzmichev, A.B., Pease, V.L. 2007: Siberian trap magmatism on the New Siberian Islands: constraints for Arctic Mesozoic plate tectonic reconstruction. J. Geol. Soc. London, 164, 959-968.
Kuzmichev, A., Sklyarov, E., Postnikov, A., Bibikova, E. 2007: The Oka Belt (Southern Siberia and Northern Mongolia): A Neoproterozoic analog of the Japanese Shimanto Belt? Island Arc, 16, 224–242.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】会員名簿データを整理中です。住所変更はお早めに!
──────────────────────────────────
今年は会員名簿の発行年です(News誌6月号p.23-24参照)。
住所・所属など会員情報に変更のある方はできるだけ早めに、学会事務局
<main@geosociety.jp>にご連絡いただくか、学会HP会員のページから会員
情報の更新を行って下さい。
会員ページへのログインはこちら、、、(ログイン情報が分からない場合
は事務局にご連絡ください)
https://www.geosociety.jp/user.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】Island Arc 2010年最多ダウンロード論文賞が決定
──────────────────────────────────
Island Arc 2010年最多ダウンロード論文賞が以下の論文に決定しました。
Sugawara,D., Minoura, K., Nemoto, N., Tsukawaki, S., Goto, K.
and Imamura, F. (2009) Foraminiferal evidence of submarine sediment
transport and deposition by backwash during the 2004 Indian Ocean
tsunami. Island Arc, 18, 513-525
最多ダウンロード賞は、過去5年間に最もダウンロード数の多かった論文に
対してWiley-Blackwell社から与えられる賞です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】「地質構造百選」の候補地・写真の投稿、ありがとうございました。
──────────────────────────────────
7月末日をもちまして、「日本の地質構造百選」の写真および候補地の募集
を締め切らせていただきました。おかげさまで当初の目標である100件を超え
る応募をいただきました。選定の結果は地質学会水戸大会にて発表する予定
です。
構造地質部会「日本の地質構造百選」編集委員会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第3回ジオ多様性フォーラム
地質、地形、測地、地震、水、文明などからみたジオ多様性
2011年10月7日(金)〜8日(土)
場所:JAMSTEC東京事務所(千代田区内幸町2-2-2-23F)
問い合わせ先:矢島道子 pxi02070@nifty.com
■香取−成田−潮来国際宣言「2011年東日本太平洋沖地震にかかわる国際
地質災害防止宣言」
国際地質科学連合の人工地層と地質汚染ワーキンググループが2011年6月18日
に開催した人工地層と地質汚染に関わる国際ワークショップにおいて、
香取−成田−潮来国際宣言「2011年東日本太平洋沖地震にかかわる国際
地質災害防止宣言」がなされました。
宣言の内容はこちらから、、、
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/geoFlash_img/no144_IUGS-GEM20110720.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター(助教)(10/31)
■第14回大学女性協会守田科学研究奨励賞受賞候補者募集(11/30)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】地質マンガ 「ルーツ」
──────────────────────────────────
ルーツ
(原案:坂口有人 マンガ:key)
http://www.geosociety.jp/faq/content0323.html
──────────────────────────────────
マンガの原作募集中!もうストックがありません.テキストで原案を投稿下
さいますとマンガ化いたします.「マンガ+解説」で研究紹介にもご活用下さい.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
夏季特別スケジュールのため、次号の配信は8月23日(火)とさせて頂きます。
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
地質マンガ 水戸大会に行こう
地質マンガ
戻る|次へ
会員の皆さん,水戸大会に行きましょう!
水戸大会は9月9日(金)〜11日(日)に,水戸市の茨城大学水戸キャンパスをメイン会場として開催されます(見学旅行は12,13日).今大会は日本鉱物科学会および茨城大学との共催であり,首都圏での開催ということもあり,発表申込数が何と800件を超えました! 今大会はここ10年間で最大規模の大会になる見込みです.
大会の中心は何と言っても学術発表と討論ですが,今大会ではその他に次のような魅力的な行事も多数開催されます.ぜひ足を運び,日本最大の「地質学の祭典」を楽しんでください!
市民講演会「東日本大震災と地震・津波・原発」
3名の著名研究者による講演会です.一般市民の皆様だけでなく,研究者の方も時間の許す限り参加して ほしいテーマです.会場は大学講堂(水戸キャンパス内)です.
実行委員会主催特別講演会
「日本のジオパーク:列島の大地に学ぶ」というタイトルで,日本ジオパーク委員会委員長(前京大総長,京大名誉教授)の尾池 和夫氏に講演していただきます.会場は大学講堂(水戸キャンパス内)です.
地質情報展
毎年好評の実演やジオ写真展に加え,新企画「市民向けポスター展示説明会」や「震災関連展示」もあります.会場は堀原運動公園武道館です (水戸キャンパスから徒歩10分).
見学旅行
最近注目を集める日立古生層をはじめ,魅力的なフィールドを多数用意しました.全コース催行予定です.
星 博幸(行事委員長,愛知教育大学)
No.147 2011/9/6 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.146 2011/8/23 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
----------------
水戸大会関連
【1】間もなく水戸大会!
【2】水戸大会アンケート募集!
【3】地質学会セミナー「地質図に関するJISの解説と2012年改正の要点」
【4】深海掘削に関する文科省担当者による緊急説明会(水戸大会会場)
----------------
【5】報告:東日本の太平洋沿岸各市町村の2011.3.11津波による人的被害について
【6】津波観測に係わる「観測施設復旧に関する要望書」を提出しました
【7】「隠岐」が世界ジオパークに推薦決定
【8】東日本大震災に対する学会員の声
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞情報
【11】地質マンガ 「水戸大会に行こう」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】間もなく水戸大会!
──────────────────────────────────
水戸大会まであと僅かとなりました。大会期間中には、学術講演だけでなく
市民に向けたイベントなども行われます。お楽しみに。
■地質情報展2000みと ―未来に活かそう大地の鳴動―
・震災関連ポスター展示
・市民向けポスター展示
・地質フォトコンテスト入賞作品展
・ほか、体験実験、解説コーナーなど盛り沢山
日時:10日(土)〜11日(日)10:00〜16:00
場所:堀原運動公園 武道館(茨城大から徒歩5分以内)
■特別講演会「日本のジオパーク ―列島の大地に学ぶ」(尾池和夫)
日時:10日(土)14:30〜15:30
場所:茨城大 講堂
■「小さなEarth Scientistのつどい」〜第9回小中高校生徒「地学研究」発表会〜
日時:11日(日)9:00〜15:30
場所:茨城大 ポスター会場(大学会館)
■ 就職支援プログラム
日時 10日(土)14:30〜18:30
場所:茨城大 人文24・25番教室
※会場が変更になりましたのでご注意ください!
■市民講演会「東日本大震災と地震・津波・原発」
・巨大津波の教訓(都司嘉宣)
・地層が語る過去の巨大地震と津波(澤井祐紀)
・2011年東北地方太平洋沖巨大地震と福島原発震災(石橋克彦)
日時:11日(日)14:30〜17:00
場所:茨城大 講堂
■地質学会セミナー「地質図に関するJISの解説と2012年改正の要点」
日時:11日(日)14:30〜16:00
場所:茨城大 共通32
<<今一度ご確認を>>
水戸へ出かけるときは、郵送された「確認書(2通)」と「名札」,「クーポン」
をお忘れなく!
(クーポンはお弁当と懇親会の申込をされた方のみ送付。参加登録や冊子等
の注文者に対しては確認書と名札のみ送付しています。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】水戸大会アンケート募集!
──────────────────────────────────
いよいよ水戸大会が始まります。今後の学術大会をより充実したものとする
ため、水戸大会・普及行事について皆様の忌憚なきご意見をお寄せ下さい。
Webアンケートはこちらから、、、
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGtzVWpTOF9zNXl5QnRKT3N6SHA4T3c6MQ
大会会場にも同じ内容のアンケート用紙を置く予定です。どちらで回答して
いただいてもかまいません。ご協力よろしくお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】地質学会セミナー「地質図に関するJISの解説と2012年改正の要点」
──────────────────────────────────
水戸大会の3日目(9月11日)午後に、地質学会地質用語国際標準対応委員会
の主催により、下記の通り「地質学会セミナー」を開催いたします。本セミナ
ーでは、地質図JIS原案作成委員会事務局の鹿野和彦氏に、地質図に関する
JISについて、その概要と2012年の改正のポイントを解説していただきます。
現在、地質コンサルタント業界では、地質図に関するJISは広く使われ、政府、
地方公共団体の仕事の受注には必須となっております。このため、地質コン
サルタントの方々だけでなく、学生、大学院生、また学生の教育に関わって
おられる方には、ぜひ聞いていただきたい内容です。
鉱物科学会の会員も参加できますので,同学会にお知り合いの方がいらっしゃ
いましたら,ぜひご紹介をお願いいたします.
多くの方のご参加をお待ちしております。
日本地質学会地質用語国際標準対応委員会委員長 井龍康文
日時:9月11日(日)14:30〜16:00
場所:茨城大学 共通32
内容:「地質図に関するJISの解説と2012年改正の要点」
講師:地質図JIS原案作成委員会事務局 鹿野和彦(産総研)
主催:日本地質学会地質用語国際標準対応委員会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】深海掘削に関する文科省担当者による緊急説明会(水戸大会会場)
──────────────────────────────────
2013年以降の深海掘削に関して米国NSFの重大発表がありましたが、それに
関する緊急説明会を文科省担当者が行うことになりました。日時と場所につい
ては大会受付(共通教育棟1階)に掲示します。どうぞお集まりください。
(参考)
2013年以降の深海掘削に関する米国NSFからのアナウンスメント
http://www.oceanleadership.org/2011/nsf-an-important-announcement-to-the-ocean-drilling-community/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】報告:東日本の太平洋沿岸各市町村の2011.3.11津波による人的被害について
──────────────────────────────────
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
東日本の太平洋沿岸部の各市町村における今年3月11日の大震災(主に津波)
による死者・行方不明者の統計を見て気がついたこと述べ,今後の防災や土
地利用計画の参考に供したい.資料は河北新報と朝日新聞の記事及び河北新
報社の「東日本大震災全記録」(2011.8.5発行)に基づく.
1.死者・行方不明者が最も多かったのは宮城県石巻市(4043人)であり,
岩手県陸前高田市(2122人)がこれに次ぐ.石巻市は津波の浸水面積が最大
であり(73km2),陸前高田市では18mの高さの津波が市街を襲った.死者・
行方不明者が1000人以上に達するのは岩手県大槌町から宮城県東松島市まで
の6つの市町村であり,500人以上は岩手県宮古市から福島県南相馬市までの
14の市町村である.この他に福島県最南部のいわき市でも347人,千葉県旭市
でも13人の死者・不明者が出た.複数の死者が出た青森県水沢市から千葉県
旭市までは直線距離で560kmあり,これはほぼ今回の地震の余震域の長さに
対応する.
続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/hazard/content0065.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】津波観測に係わる「観測施設復旧に関する要望書」を提出しました
──────────────────────────────────
震災によるGPS波浪計及び潮位観測施設の故障のため、津波観測に支障が出て
いるとの報道を受け、日本地質学会は「観測施設復旧に関する要望書」を気
象庁、国土交通省、海上保安庁、国土地理院宛に提出しました。
要望書本文はこちらから、
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/geoFlash_img/no147_req20110802.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】「隠岐」が世界ジオパークに推薦決定
──────────────────────────────────
9月5日に日本ジオパーク委員会が開催され、今年申請されていた世界ジオパ
ーク候補地1件「隠岐ジオパーク」の国内推薦が決まりました。
また、日本ジオパークとして「男鹿半島・大潟、磐梯山、茨城県北、下仁田、
秩父、白山手取川」の6件が認定され、これで日本ジオパークは20地域となり
ました。
なお、今年世界ジオパークの審査を受けていた「室戸ジオパーク」は、ノル
ウェーで9月18日に審査結果が発表されます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】東日本大震災に対する学会員の声
──────────────────────────────────
「東日本大震災について地質家の取り組みが求められる課題の
総ざらえを考えよう」
志岐常正
東日本大震災についての会員の声が募集されています。私にもいろいろと
述べたいことがあります。とくに地質学抜きにはできないことが少なくない
こと、それなのに社会にその認識がないことを痛感しています。本当は今こ
そ地質家の出番です。
しかし、今回、以下には、私が関心を持っている調査・研究課題を列挙し
てみたいと思います。正直なところ、今の私には、それら課題のほんの一部
にさえ取り組む力がありません。それで会員の皆様にその実行をを訴えたい
と思う次第です。どなたかに参考にして頂ければ幸です。
続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/hazard/content0063.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■東京大学大気海洋研究所共同利用研究集会
「南海トラフ海溝型巨大地震の新しい描像
―大局的構造と海底面変動の理解(その2)―」
日時:2011年9月 7日(水)〜 8日(木)
場所:東京大学大気海洋研究所 講堂(千葉県柏市)
プログラムなど詳細は、
http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/news/j/index.cgi?mode=art_view&id=388
■第137回深田研談話会
世界一稠密高精度地震観測網で見る日本列島の様々な地震
―2011年東北地方太平洋沖地震はどう考えるか―
日時:2011年9月30日(金)15:30〜17:30
会場:深田地質研究所 研修ホール(文京区本駒込2-13-12)
申込は http://www.fgi.or.jp/
■文科省から博物館の基準についてパブコメの募集
文科省から「博物館の設置及び運営上の望ましい基準」の一部改正案に
関するパブコメの募集が出されています。期限は9月20日までです。
博物館での研究活動、教育普及活動について重要な問題が含まれています。
是非ご検討下さい。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000532&Mode=0
■原子力総合シンポジウム2011「原子力安全の再構築―東日本大震災を踏まえて―」
参加事前登録が始まりました。
日時:2011年10月19日(水)
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木7-22-34)
主催:日本学術会議 総合工学委員会
参加費:無料(要事前登録)
プログラム詳細、参加事前登録はこちらから、、、
http://www.aesj.or.jp/2011symp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■千葉大学大学院:理学研究科・地球生命圏科学専攻地球科学コース
(准教授/助教) (10/31)
■岡山大学大学院:自然科学研究科(教授) (10/31)
■山口大学大学院:理工学研究科 地球科学分野(教授/准教授)(10/14)
---------------
■山田科学振興財団2012年度研究援助候補推薦(1月末学会締切)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】地質マンガ 「水戸大会に行こう」
──────────────────────────────────
「水戸大会に行こう!」 原案:星 博幸 マンガ化:Key
http://www.geosociety.jp/faq/content0328.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.153 2011/9/20 geo-flash 速報:紀伊半島における地盤災害合同調査
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.153 2011/9/20 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】速報:台風12号による紀伊半島における地盤災害合同調査
【2】おめでとう金メダル!第5回国際地学オリンピック大会(イタリア大会表彰式)
【3】室戸ジオパークが世界認定
【4】地質学雑誌の投稿・査読システムが変わります!
【5】選挙告知:2012年度代議員および役員選挙について
【6】水戸大会アンケート中間報告
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】速報:台風12号による紀伊半島における地盤災害合同調査
──────────────────────────────────
地盤工学会、日本応用地質学会、日本地質学会、関西地質業協会による合同
調査団「平成23年台風12号による紀伊半島における地盤災害合同調査団」の
奈良県班からの調査速報が届きました。
奈良県班 調査報告はこちらから、、、
http://www.geosociety.jp/hazard/content0067.html
今後、調査結果が届き次第、ホームページやgeo-Flashで公開していきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】おめでとう金メダル!第5回国際地学オリンピック大会(イタリア大会表彰式)
──────────────────────────────────
色取り取りの国旗や民族衣装に彩られた表彰会場に金メダルを表彰するアナ
ウンスが、「フロムジャポネ ミドリワタナベ!」と響きました。高校一年
生の渡辺 翠さんがゆっくりとステージに上がると会場は拍手に包まれました。
メダルと賞状を手に、はにかむ彼女の表情からは嬉しさと緊張が伝わってき
ました。この表彰式に致るまでの9月5日から14日までの10日間に渡って、世
界各国から集結した高校生たちは、筆記試験、野外での実技試験、海洋実習、
巡検、発表会、被災地の宮城一校との中継交流、地元学校訪問、討論会等の
競技をイタリア北部の小さな街モデナ周辺で取り組んできました。
その結果、日本代表選手は次の輝かしい成績を残しました。おめでとう。
続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/name/content0020.html
写真はこちら
http://www.geosociety.jp/faq/content0334.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】室戸ジオパークが世界認定
──────────────────────────────────
室戸ジオパークは、9月17日20時40分(現地時間)にノルウェーで開かれた欧
州ジオパーク会議においてユネスコの支援する世界ジオパークネットワークへの
加盟が認定されました。ジオパークは、貴重な地質や地形とともに、生物多様性
や文化遺産などの資源を保護し、研究や観光に活用して地域の持続的な発展につ
なげる活動で「人が地球に出会う場所、地球活動の遺産」です。
プレートの沈み込み帯における陸地の形成過程によって特徴づけられる室戸
ジオパークは、高知県東部の室戸半島に位置し室戸市全域を範囲としています。
プレートテクトニクスによってつくられた付加体、洪積世の氷河性海水準変動と
地震隆起によって形成された海成段丘、巨大地震によって離水した海岸地形など
の地質遺産を見ることができ、大地形成のダイナミズムを実感できます。また、
陸だけでなく周辺の海には、海底地形と海流により多様な生物が生息していま
す。さらに、空海の修行の地、四国八十八ヶ所の巡礼地、土佐漆喰の白壁・水切
り瓦などが特徴的な吉良川町の懐かしい町並みなどの歴史文化遺産にも接するこ
とができます。こうした多様な資源の宝庫である室戸ジオパークでは、人と自然
の関わりについて学ぶことができます。
2008年に室戸市・高知県・地元団体とともに高知大学・高知工科大学・海洋
研究開発機構などにより設立した室戸ジオパーク推進協議会は、精力的に活動で
を続けてきました。昨年、世界ジオパークへの加盟申請書を提出し、7月には現
地審査を受けました。審査の中で、地域のことだけでなく「地震による災害と
恵」と「変動帯である日本」について市民のとともに強く訴えてきました。
私は地質専門員として室戸ジオパークの活動をに関わってきており、地質学
会の皆様をはじめ多くの方々の思いが届いたことに感動しました。室戸ジオパー
クの地質や地形の学術的な価値は、多くの研究者がこれまでに重ねてきた成果に
基づいています。今後も研究や教育に活用できるジオパーク活動をに貢献したい
と思います。最後になりましたが、室戸ジオパークを応援してくださった方々に
お礼申し上げます。
以下、審査員をつとめたパトリック・マッキーバー教授(北アイルランド地質調
査所)のコメントです。
ご存知のようにこのエリアでは今年、日本の東海岸で、大きな悲劇がありまし
た。その地震・津波・そして福島でのトラブル以来、日本は非常な苦しみを経験
してきました。この新しいGGNメンバーのジオパークには、ジオパークマスター
のプログラムがあります。地元の人々がボランティアとして養成講座を受けてい
ます。3月の災害以来、このジオパークで旅行者から受け取るガイド料金は、す
べて被災地の復興のため義捐金として送られました。彼らは、このネットワーク
のメンバーになる前から、助け合いの精神を見せていたのです。ですから、この
新しいメンバーに、特別な祝福を贈りましょう。世界ジオパークになった、日本
の室戸ジオパークです。
室戸ジオパーク推進協議会柴田 伊廣(地質専門員)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地質学雑誌の投稿・査読システムが変わります!
──────────────────────────────────
地質学雑誌の投稿・編集システムが、現在のJ-Stageのシステム廃止に伴い、
10月1日よりScholarOne Manuscriptsに変更になります。これまでのシステム
に慣れ親しんでいた会員の皆様には、戸惑うことも多いであろうと想像します。
一方で、このシステムはIsland Arcを始め多くの国際誌が採用していますので、
かえって使いやすいと思われる会員の方々も多いのかもしれません。しかし、
我々編集委員はまだ慣れておらず試行錯誤の段階です。最初の数ヶ月は何かと
ご迷惑をおかけすることになろうかと思いますが、よろしくお願いいたします。
新規投稿窓口のURLは10月1日以降に地質学会のホームページでお知らせいた
します。なお、現在査読・編集中の論文については、2012年3月まではJ-Stage
での編集となります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】選挙告知:2012年度代議員および役員選挙について
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会定款ならびに選挙規則・選挙細則に基づいて、
代議員および役員(監事、理事)選挙を実施いたします。
1.代議員選挙日程(選挙人,被選挙人とも正会員)
立候補受付期間 10月11日(火)〜11月10日(木)*最終日18時必着
2.理事の選挙日程(選挙人,被選挙人とも代議員)
立候補受付期間 1月23日(月)〜2月10日(金)*最終日18時必着
3.監事の選挙日程(選挙人は代議員,被選挙人は会員および非会員)
立候補受付期間 10月11日(火)〜2月10日(金)*最終日18時必着
選挙規則類,実施の要点や詳細はNews誌9月号を参照してください.
2011年9月9日
日本地質学会選挙管理委員会委員長 兼子 尚知委員 氏家 恒太郎・高橋 聡 守屋 和佳・和仁 良二
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】水戸大会アンケート中間報告
──────────────────────────────────
皆様からお寄せいただいた水戸大会アンケートの中間報告です。
http://www.geosociety.jp/mito/content0050.html
Webアンケートは継続中です。まだの方はこちらから、、、
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGtzVWpTOF9zNXl5QnRKT3N6SHA4T3c6MQ
学術大会・見学旅行・関連行事をより良くするために、会員の皆様の声が必要です!
ぜひ、ご協力よろしくお願いします。
(今月末まで募集いたします)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■産総研オープンラボ2011
日時:2011年10月13日(木)・14日(金)
場所:産業技術総合研究所(茨城県つくば市)
内容:産総研のこれまでの研究成果や最新の実験装置・共用設備等の研究
リソースを企業・法人の経営者、研究・技術者、及び大学・公的機関の皆
様に広くご覧頂き、連携と共同研究の促進を目的とした催しです。本年度
は、340以上の展示と約120カ所のラボを公開致します。このうち、地質分
野からは24件の展示と12件のラボ見学が予定されており、さらに以下2つ
の講演会を企画しております。
http://www.aist-openlab.jp/program
○「グリーンエネルギー転換に必須な資源”レアアース”」(10/13)
○「地震災害からの復興と防災を考慮した土地利用に向けて
〜地質・衛星情報の活用〜」(10/14)
地質分野の展示内容:
http://www.aist-openlab.jp/lab_list.php?mode=field&key=6
参加申し込み: https://www.aist-openlab.jp/regist/login.php
ラボ見学予約締切:10月5日(水)
来場者登録〆切:10月10日(月)
地質分野出展・講演会に関する問い合せ先: geo-liaison@m.aist.go.jp
■日本原子力研究開発機構東濃地科学センター情報・意見交換会
「平成23年度 東濃地科学センター 地層科学研究 情報・意見交換会」
日時:平成23年11月1日(火)13:00〜17:00
場所:瑞浪市地域交流センター「ときわ」(岐阜県瑞浪市)
定員:約150名
「瑞浪超深地層研究所 深度300m水平坑道見学会」
日時:平成23年11月2日(水)9:15〜12:00
場所:瑞浪超深地層研究所
定員:約40名
入場無料(要事前申込、先着順)
申込先
(独)日本原子力研究開発機構 東濃地科学センター 瑞浪超深地層研究所
地層処分研究開発部門 結晶質岩工学技術開発グループ
E-メールアドレス: tono-koukankai2011@jaea.go.jp
ホームページアドレス: http://www.jaea.go.jp/04/tono/index.htm
■第3回ジオ多様性フォーラム
日時:2011年10月7日(金)15:00〜17:30
2011年10月8日(土) 9:30〜12:30
場所:JAMSTEC東京事務所
http://www.jamstec.go.jp/j/about/access/tokyo.html
TEL:03-5157-3900
詳細,申込方法はこちらから
http://www.geosociety.jp/outline/content0096.html
■平成25・26・27年度学術研究船白鳳丸研究計画の公募ならびに
研究計画企画調整シンポジウム開催
学術研究船白鳳丸は、昭和43年度以来3カ年毎に立案される航海計画に
基づいて運航しています。本年は平成25〜27年度の運航計画作成の年
にあたります。
つきましては、下記要領により共同利用研究計画を公募し、個々の研究
者の発意に基づく魅力的な研究航海計画を広く募り、研究計画企画調整
シンポジウムを開 催して各位のご意見を承りたいと存じます。シンポ
ジウムでは、各々の研究航海計画を発表していただき、それらについて
検討するとともに、今後の海洋研究の 方向性を他の研究船の航海計画
を含めて議論し、申請された研究計画相互の調整を行います。このシン
ポジウムの結果を踏まえて、研究船共同利用運営委員会に おいて各研
究計画の評価を行い、3カ年間の運航計画案を作成いたします。
開催時期:平成23年11月29日(火)〜12月1日(木)(3日間)
開催場所:東京大学大気海洋研究所 講堂
申請書の提出期限:平成23年10月20日(木)(厳守)
申込資格:国・公・私立大学及び公的研究機関の研究者並びにこれに準ずる者
その他詳細、申請書類はこちらから
http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/coop/hakuho_3_25.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■筑波大学:生命環境科学研究科(准教授)(10/31)
■神戸大学:自然科学系先端融合研究環 内海域環境教育研究センター
(講師/助教)(10/28)
------------
■平成25〜27年度学術研究船白鳳丸研究計画公募(10/20)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.148 2011/9/9 geo-flash(大会臨時号) 水戸大会開幕!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.148 2011/9/9 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】歓迎!日本地質学会水戸大会
【2】平成23年台風12号による紀伊半島における日本地質学会地質災害調査団(仮称)の募集
【3】JAMSTECによるIODP次期フェーズ説明会(水戸大会会場)
【4】水戸大会:9月9日(金)の主なイベント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】歓迎!日本地質学会水戸大会
──────────────────────────────────
水戸へやって来ました。青空で気持ちの良い天気です。
水戸駅では「歓迎!日本地質学会第118年学術大会・日本鉱物科学会2011年
年会合同学術大会(水戸大会)」の横断幕が迎えてくれるかと期待しましたが
残念ながら見当たらず、でも、キオスクの横に水戸大会のポスターがそっと貼
ってあったので安心しました。名前が長すぎて横断幕に入りきらなかったのか
もしれません。
茨大では会場設営も終わり、大会の準備万端。
いよいよ明日朝9時からプログラムスタートです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】平成23年台風12号による紀伊半島における日本地質学会地質災害調査団(仮称)の募集
──────────────────────────────────
今回の台風12号では紀伊半島を中心に大きな災害になっているのはご存じの
通りと思います。
地質学会は、地質災害調査団を結成し、関連学会とともに、地質災害の原因
解明に当たりたいと考えております。
意欲のある方を募集します。
【期限:9月9日(金)】←明日です!
連絡先: 日本地質学会事務局 (main@geosociety.jp)
大会にかかるため,地質災害委員会委員長の斎藤(saitomkt@ni.aist.go.jp)
に必ずccしてください。
http://www.geosociety.jp/hazard/content0066.html
■関連情報
産総研地質調査総合センターHPに今回の災害に関する情報が掲載されました。
→「2011年9月台風12号による紀伊半島の土砂災害(地質概要)」
http://www.gsj.jp/Gtop/topics/kiihanto/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】JAMSTECによるIODP次期フェーズ説明会(水戸大会会場)
──────────────────────────────────
前回のgeo-Flashでお知らせしたIODPに関する説明会の日時が決まりました。
日時:9月11日(日)12:00〜13:00
場所:茨城大学水戸キャンパス 人文15番教室
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】水戸大会:9月9日(金)の主なイベント
──────────────────────────────────
■シンポジウム「関東盆地の地質・地殻構造とその形成史」(9:00〜 講堂)
■地質学会表彰式・記念講演会(13:00〜 講堂)
14:50〜
・日本地質学会小澤儀明賞受賞スピーチ 黒田潤一郎会員
「白い時代の黒い石 〜白亜紀黒色頁岩の魅力と,白黒つかない問題〜」
・日本地質学会柵山雅則賞受賞スピーチ 河野義生会員
「弾性波速度を観察して」
15:20〜
・平成22年度日本鉱物科学会研究奨励賞第7回受賞者受賞講演 大藤弘明会員
・平成22年度日本鉱物科学会研究奨励賞第8回受賞者受賞講演 石丸聡子会員
15:55〜
・日本地質学会国際賞受賞記念講演 Dr. J. Casey Moore
「The Shimanto Complex and Ocean Drilling : Linking Across the Pacific」
・日本地質学会賞受賞記念講演 岩森 光会員
「地球内部の地質学」
17:00〜
・平成22年度日本鉱物科学会賞第6回受賞者受賞講演 板谷徹丸会員
「希ガス同位体の迅速分析技術の開発とK-Ar法・Ar-Ar法を駆使した造山運動の研究」
・平成22年度日本鉱物科学会賞第7回受賞者受賞講演 杉山和正会員
「複雑構造を有する物質群の構造解析法の開発研究」
■懇親会(19:00〜)水戸三の丸ホテルにて
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.150 2011/9/11 geo-flash(大会臨時号) 大会最終日:そろそろ肝臓が...
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.150 2011/9/11 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】水戸大会二日目の様子
【2】水戸大会アンケートお願いします
【3】水戸大会:9月11日(日)の主なイベント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】水戸大会二日目の様子
──────────────────────────────────
■地質情報展2011みとがオープンしました。会場の東日本大震災関連ポスターの
コーナーには、力の入った展示が並んでいます。
■午後には就職支援プログラムが開催され、参加した学生たちは各企業の説明を
熱心に聞いていました。いい情報が得られたに違いありません。
■優秀ポスター賞の初日と二日目の表彰式が行われました。
受賞ポスターは以下の通り。
初日:
「南房総千倉層群の酸素同位体層序」 所佳実ほか (R10-P-4)
「八溝山地鶏足山塊における中生代付加体」 綿引麻衣子ほか (R10-P-17)
「北海道太平洋側海域の漸深海以浅の地質構造:島弧−島弧衝突帯の東西」 辻野匠ほか (R10-P-18)
「棚倉断層帯周辺に分布する新第三系の堆積環境の復元」 滝本春南・天野一男 (R10-P-21)
「房総半島中部更新統長浜層の堆積サイクルと粗粒セディメントウェーブ堆
積物」 高岡進一ほか (R10-P-23)
二日目:
「海底音波探査による鹿児島県・鬼界カルデラの構造解析」 池上郁彦ほか (R12-P-9)
「房総半島南端白浜層に認められる3.5Maの相模トラフで形成された粗粒セディ
メントウェーブ堆積物」 伊藤慎ほか (R15-P-8)
「和泉層群に見られるランダムな方向のスランプ褶曲」 小山俊之ほか (R19-P-3)
「霞ヶ浦の環境変化と珪藻群集変化」 畑中雄太ほか (R22-P-2)
茨大の活躍が目立ちます。
夜間小集会が終わる頃、満員のバスに揺られて水戸のまちへくり出していく
参加者たちの姿。明日は最終日、あと一息がんばりましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】水戸大会アンケートお願いします
──────────────────────────────────
水戸大会に参加しての皆様からのご意見を是非お寄せください。
意見・コメント・感想・改善点など、どんなことでも今後の大会の力になります。
よろしくお願いします。
Webアンケートはこちらから、、、
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGtzVWpTOF9zNXl5QnRKT3N6SHA4T3c6MQ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】水戸大会:9月11日(日)の主なイベント
──────────────────────────────────
■地質情報展2000みと ―未来に活かそう大地の鳴動―
・震災関連ポスター展示
・市民向けポスター展示
・地質フォトコンテスト入賞作品展
・ほか、体験実験、解説コーナーなど盛り沢山
日時:10日(土)〜11日(日)10:00〜16:00
場所:堀原運動公園 武道館(茨大から徒歩5分以下)
■「小さなEarth Scientistのつどい」〜第9回小中高校生徒「地学研究」発表会〜
日時:11日(日)9:00〜15:30
場所:茨大 ポスター会場
■市民講演会「東日本大震災と地震・津波・原発」
・巨大津波の教訓(都司嘉宣)
・地層が語る過去の巨大地震と津波(澤井祐紀)
・2011年東北地方太平洋沖巨大地震と福島原発震災(石橋克彦)
日時:11日(日)14:30〜17:00
場所:茨大 講堂
■地質学会セミナー「地質図に関するJISの解説と2012年改正の要点」
日時:11日(日)14:30〜16:00
場所:茨大 共通32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.149 2011/9/10 geo-flash(大会臨時号) 今日から地質情報展2011みと
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.149 2011/9/10 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】初日の水戸大会
【2】水戸大会:9月10日(土)の主なイベント
【3】写真速報!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】初日の水戸大会
──────────────────────────────────
大会初日の受付は大混雑。
講演会場も熱気に包まれています。心なしか気温も上がってきました。
午後からは学会表彰式と受賞記念講演会が行われました。鉱物科学会の受賞
スピーチもあり、盛り沢山な講演会でした。
大学から歩いて5分ほどの武道館では、明日オープンの地質情報展の準備が
進められました。
午後にはプレオープンとなり、小学生の団体が実験コーナーなど大変な盛り
上がりを見せていました。明日(10日)の本オープンが楽しみです。
地質学会からも、震災関連ポスターや市民向けポスターなどが出展されます。
地質フォトコンの入賞作品も展示されています。連合大会で展示した小さな
プリントではなく大きなパネルでの展示なので、迫力が違います。必見です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】水戸大会:9月10日(土)の主なイベント
──────────────────────────────────
■地質情報展2011みと ―未来に活かそう大地の鳴動―
・震災関連ポスター展示
・市民向けポスター展示
・地質フォトコンテスト入賞作品展
・ほか、体験実験、解説コーナーなど盛り沢山
日時:10日(土)〜11日(日)10:00〜16:00
場所:堀原運動公園 武道館(茨大から徒歩5分以下)
■就職支援プログラム
日時:10日(土)14:30〜18:30
場所:茨大 人文学部棟2F(人文24・25)
■特別講演会「日本のジオパーク ―列島の大地に学ぶ」(尾池和夫)
日時:10日(土)14:30〜15:30
場所:茨大 講堂
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】写真速報!
──────────────────────────────────
大会初日の様子を速報写真でご覧ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.151 2011/9/12 geo-flash(大会臨時号) 大阪でまた会いましょう!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.151 2011/9/12 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】水戸大会最終日の様子
【2】大阪で会いましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】水戸大会最終日の様子
──────────────────────────────────
■市民講演会「東日本大震災と地震・津波・原発」には、市民も多く参加し
聞き入っていました。TVカメラも取材に入り、一般の人々の関心が高いことが
わかります。
■「小さなEarth Scientistのつどい」〜第9回小中高校生徒「地学研究」発表会〜
例年よりもさらに気合いの入った生徒たちの発表が並びました。
大人のポスターに混じって、学会員と議論したりアドバイスを受けたり、
生徒たちは激しく刺激を受けていたようです。
今年で高校最後といっていた彼、来年は大学生になって学会員として発表しに
来てくれるといいですね。
■優秀ポスター賞 三日目の表彰式が行われました。
受賞ポスターは以下の通りです。
「美濃帯の上部三畳系遠洋性堆積岩中に記録された天体衝突の証拠」
佐藤峰南ほか (T12-P-1)
「南インドの先カンブリア代の縫合帯の花崗岩類とチャーノッカイトのジル
コンU-Pb年代:プレートテクトニクス周期に関連した火成活動の履歴」
佐藤桂ほか (R9-P-2)
「四国南部・三波川帯の大規模褶曲」森宏・ウォリス サイモン (R9-P-12)
「Key speciesを用いたサンゴ礁生態系の復元」本郷宙軌・茅根創 (R14-P-5)
来年はみんな大阪に来てください!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】大阪で会いましょう!
──────────────────────────────────
参加者の皆さんのおかげで、講演プログラムは盛況のうちに終了しました。
明日からの見学旅行、気をつけてお出かけください。
見学旅行の集合時間と場所は↓
http://www.geosociety.jp/mito/content0029.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.154 2011/10/4 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.154 2011/10/4 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】台風12号による紀伊半島における地盤災害合同調査団調査速報
【2】地球惑星科学連合2012年大会のセッション提案にご注意下さい
【3】本の紹介:「宮澤賢治地学用語辞典」加藤碩一著
【4】水戸大会アンケート結果:ご協力ありがとうございました
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞情報
【8】地学クロスワードパズル
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】台風12号による紀伊半島における地盤災害合同調査団調査速報
──────────────────────────────────
9月23日〜25日にかけて奈良県内で実施された、台風12号に伴う大雨で発生
した主要な大規模な斜面変動を対象とした緊急調査の調査速報を掲載します。
調査結果概要:調査の結果、以下の状況が確認できた。
・大半の崩壊が、泥質メランジュ(泥質混在岩)でかつ流れ盤構造の斜面
で発生した。
・過去の崩積土と共に地山が崩壊している箇所が多かった。
・多くの崩壊前地形に地すべり地形(不規則な変状など)が認められる。
・黒滝村赤滝の2つの崩壊斜面は断層破砕帯からなる。その断層破砕帯の
一つは、四万十帯・秩父帯の境界断層に相当する。
調査速報全文はこちらから、、、
http://www.geosociety.jp/hazard/content0067.html
<参考情報>
産総研地質調査総合センターHPに関連する地質概要が掲載されています。
「2011年9月台風12号による紀伊半島の土砂災害(地質概要)」(産総研HP)
http://www.gsj.jp/Gtop/topics/kiihanto/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】地球惑星科学連合2012年大会のセッション提案にご注意下さい
──────────────────────────────────
来年(2012年)の日本地球惑星科学連合大会でセッション開催を予定している
専門部会及び会員の皆様へ
すべてのセッションが公募になっています。セッション提案を予定している
場合は、お忘れのないよう申込手続きをお願いします。
締切は【10月21日(金)】です。
地質学会主催または共催の形(地質学会を提案母体にする形)でセッション提案
を予定している専門部会及び会員は、次のような手続きをお願いします。
・最も関連する(または従来母体となってきた)専門部会の行事委員を通じて
行事委員会に報告し、承認を得たら申込手続き。
・関連する専門部会がない場合は,コンビーナーが行事委員会(学会事務局)
に直接報告し、承認を得たら申込手続き。
ご協力よろしくお願いします。
日本地質学会行事委員会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】本の紹介:「宮澤賢治地学用語辞典」加藤碵一著
──────────────────────────────────
愛智出版 2011年9月16日発行
カラー口絵3ページ,A5判460ページ
ISBN978-4-87256-416-7 定価本体6000円+税
宮澤賢治ほど,多くの人びとに愛され親しまれ続けている作家は少ない。賢治の作品には,地質や鉱物に関する多くの専門用語がきら星のように詰まっており,多くの賢治愛好家による解釈・論評がなされている。けれども,これらの用語が賢治作品に現われるとき,知識不足の故に,それに対する解釈が誤りの多いままに見過ごされてきた。著者は,このような事情を憂えて,これまでに賢治に関する多数の著書を公刊された。著者による『宮澤賢治の地的世界』(愛智出版)は,その嚆矢(こうし)として高く評価され,2007年度の宮澤賢治奨励賞を受賞された。
今回上梓された本書は,さらに賢治の文学に用いられている地学用語に関しての徹底的な解説を試みた労作である。著者の立場は,「はじめに」にあるように「地質学分野の学術用語の解説等には,残念ながら非常に多くの誤りないし疑わしい事例が見られ,このことは作品の理解を妨げるだけでなく誤りが再生産されることによってひいては地質学の普及啓蒙にも影響を及ぼしかねない。・・・わかりにくい用語や見知らない用語を一方的に「賢治の造語・修辞」として思考停止するのはいかがなものであろうか。・・・いずれにしても基本的な記述・解説は正確であるべきである」ことであり,「作品・テクストそのものとだけ向き合えば必要十分だといった感傷的な反発では,かえって賢治作品の素晴らしさを見逃しかねない」との考えで終始一貫している。
本書の構成の特徴は,まず賢治が参考にしたと思われる所蔵図書,ならびに盛岡高等農林学校在籍当時に同校に備えられていた蔵書目録などが載せられていることである。周知のように,賢治の書簡には彼がたびたび仙台や東京・日本橋の丸善,あるいは古書店などに出向いて岩石学や鉱物学の洋書を求めたことが記されている。賢治はDana, Harker, Iddingsなど,当時の第一級の専門家によるテキストブックが刊行されるたびに求め,読んでいた。実を言うと,これらの書物の何冊かは私の学生時代にもお世話になったものもある。これらの蔵書目録から,賢治が相当専門的な知識を得ていたことが理解される。続いて,賢治やその作品に関係する地質学者,地球物理学者や学協会についての紹介があり,当時の日本における地質学界の様子が概観されて興味深い。そして,用語解説と続く。 著者があえて『辞典』とした理由は,それぞれの用語に関して,単なる用語の解説にとどまらず,賢治が作品を書いた当時の地学用語の解釈や,学問的・社会的背景について詳述され,それぞれの用語がどの作品,あるいは書簡などに現われているかが詳しく紹介されているからであろう。例えば,「地球」の項では,19世紀から20世紀初頭にかけてはケルヴィン卿による地球年齢の推定から,ラザフォードによる放射性同位体を用いた年代測定への転換期に相当し,ハッブルの宇宙膨張説が提唱された頃なので,賢治もそういった科学の進歩をどのように捉えていたかを改めて問う必要があるとしている。また,「イリドスミン」の項では,明治中期に北海道夕張川で発見・同定されたイリドスミンの実物を賢治が実際に見たであろうこと,その後,北海道や陸前・常陸などでも発見され話題になっていたことを受けて,賢治が早池峰山を中心とした北上山地の蛇紋岩地帯でイリドスミン採掘を夢見ていたことが詳しく書かれている。「地形図・地図」ならびに「地質図」「地質調査」の項では,当時の地形図の発行状況,地質学者としての賢治がいかに活躍したかなどが,彼の調査した地域を具体的に挙げ,さらに賢治の作品に彼の調査結果がどのように現われているか,詳しく紹介されており,たいへん興味のあるところである。「鉱物」の項でも,古く「金石学」と呼ばれた頃の状況,賢治がたびたび参考にした盛岡高等農林学校所蔵の京都島津製作所製,あるいはクランツ社製鉱物標本,当時の農商務省地質調査所鉱物陳列館や上野の帝室博物館の様子などが詳しく紹介されている。こういった項目における詳細な記述は,賢治の生きた時代についての科学史的側面を浮き彫りにした役割も果たしていると考えられる。その他の一つ一つの項目においても,賢治作品中の地質学用語に関するこれまでの解釈に疑義のあるものについては詳しい論評が加えられている。さらに誤りの一人歩きを危惧して,誤植と思われる小さな誤りまでが洗い出され,指摘されている。
最後に参考文献が掲載されているが,本書執筆のものの他に,『盛岡高等農林学校図書館 和漢書目録』(1937)が載せられており,賢治が在籍した当時,自分の蔵書の他に,彼がどのような書物に囲まれていたかが分かる。さらに,補遺の中で,賢治の作品によく出てくる西域やトランスヒマラヤに関する知識をどうやって得たのかが述べられているのは,大変興味の深いところである。賢治が得た知識の源として,本学会の前身である東京地質學會による『地質學雑誌』の他に,東京地學協会の『地學雑誌』や『地學論叢』の果たした役割は大きかった。
賢治のすべての作品に目を通し,地学用語を洗い出してその解説のみならず,作品評論から当時の社会情勢まで話が及んでおり,著者の並々ならぬ賢治作品への畏敬の念と,情熱がひしひしと感じられる。いままでの「基本的な記述・解説は正確であるべきである」ことに欠けていた賢治研究者はもちろん,地学の知識をあまり持ち合わせない一般読者にとっても格好な辞典と言える。本書のカバーに描かれている賢治の点描画は,物見山の閃緑玢岩露頭を背にして,物思いにふけりつつもハンマーを手に持ち,明日への希望をうかがわせる明るい賢治像となっている。あたかも賢治が地学の魅力を語りかけているような印象を受けて興味深い。 こういった豊かな内容であるが,索引があればさらに便利であると感じた。賢治の作品を読んで,難しい地学関連の用語が出てきたときに,すぐに探し出すのはちょっと難しい。例えば岩手山のシンボルともいえる「焼走溶岩流(本書では熔岩流)」については独立した項目ではなく,「岩手山」の項にわずかに,しかし「熔岩流・鎔岩流」の項に詳述されている。賢治作品にしばしば出てくる「早池峰山」の説明も各所にあるが,項目としては独立していない。
たびたび東北地方を襲った飢饉,火山活動,大地震,津波などは賢治の作品にもしばしば現われている。地学の裾野を広げることは,地質学の存在感を世間に知らしめる重要な課題である。2011年3月に襲った東日本大震災を「想定外」などとせずに,貴重な教訓とし,今後の対策を立て,未来を予測するために,地質学の果たす役割は大きい。このような時にこそ,私たち学会員は賢治の作品を正確に読み,それを通して地質学の重要性を一般の人びとに認識してもらう努力をしなければならない。そのためには,本書は必読のものだと考える。そういった意味で,会員各位のみならず,一般の方々,そして賢治研究家の人びとの座右に是非そろえて欲しい一冊である。
蟹澤 聰史
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】水戸大会アンケート結果:ご協力ありがとうございました
──────────────────────────────────
皆様からお寄せいただいた水戸大会アンケート結果の報告です。
http://www.geosociety.jp/mito/content0050.html
皆様からのご意見を、次回以降の大会に活かしていきたいと思います。
ご協力ありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報
──────────────────────────────────
■関東支部
・関東支部2011年度地質見学会 城ヶ島に続く第2弾!
「霞ヶ浦のあゆみ —環境変遷、過去から未来へ—(地質と霞ヶ浦導水路見学)」
日時:11月26日(土)10:00-17:30
※見学場所が多いため集合時間が9時となる可能性もあります
集合:JR常磐線土浦駅東口バス乗り場付近
参加費:3000円
申込締切:11月18日(金)
詳しくは支部HPまたはジオスクーリングネットへ
http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第3回シンポジウム「海は学びの宝庫〜海洋教育の研究と実践〜」
東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究センター
日時: 2011年10月15日(土)13:00〜17:00
場所: 東京大学工学部2号館213号室
対象: 小・中・高等学校教諭、学生、一般
参加費: 無料(要事前登録)
プログラム詳細: http://www.oa.u-tokyo.ac.jp/RCME/Sympo20111015.pdf
参加登録はこちらから、、、
http://www.oa.u-tokyo.ac.jp/RCME/information/20110910_694.html
■第5回国際海底地すべりシンポジウム
5th International Symposium on Submarine Mass Movements and Their Consequences
(ISSMMTC-5)
日時: 2011年10月24日(月)〜26日(水)
場所: 京都大学
ISSMMTC-5は,IGCP-511とそれに引き続くIGCP-585の旗の下,海底地すべり
の研究者が約2年毎に開催する学術会議で,今回は初めて欧米以外での開催に
なります.シンポジウム前後には,神戸の地すべりや房総半島への野外巡検
も計画しています.
招待講演者7名のほか,世界各国から海底地すべりとそれに関連する幅広い
領域の研究者が京都大学に集い,最新の研究成果を発表します.また,地震と
津波,地盤流動,リスクアセスメントなどを多方面から議論するパネルディス
カッションを内外の著名な研究者を招聘して行います.野外地質観察,海洋調
査,モデリング,解析などに基づいた海底地すべりとその関連研究の第一線の
方々が日本に集まるまたとない機会です.
詳細はこちらから、、、
http://www.landslide.jp/
サードサーキュラー(詳細版):
http://www.landslide.jp/images/Third_Circular.pdf
第5回国際海底地すべりシンポジウム事務局
FAX 03-3944-5404、Email: info@landslide.jp
■いわて三陸ジオパーク震災復興シンポジウム〜震災の記憶を伝え生かすために〜
(日本地質学会学会 後援)
日時:2011年11月25日(金)シンポジウム 13:30〜17:00
(ポスター展示 10:00〜18:00)
26日(土)被災地巡検
場所:アイーナホール(いわて県民情報交流センター:盛岡市盛岡駅西通1-7-1)
内容
◇記念講演 尾池和夫氏(日本ジオパーク委員会委員長・元京大総長)
「東日本大震災においてジオパークができること」
◇事例紹介
杉本伸一氏(島原半島ジオパーク事務局・ジオパーク国際ユネスコ会議事務局長)
「雲仙普賢岳噴火災害から20年〜復興の軌跡」
草野 悟氏(三陸鉄道を勝手に応援する会会長)
「被災地の思いを伝える〜三陸鉄道の取組」
◇パネルディスカッション
○コーディネーター 中川和之氏
○パネラー 杉本伸一氏(同上)・草野 悟氏(同上)・大石雅之氏(岩手県立
博物館首席専門学芸員)・永広昌之氏(仙台市教育委員・東北大学名誉教授)
・渡辺真人氏(産業技術総合研究所主任研究員・日本ジオパーク委員会事務局)
◇閉会挨拶 実行委員長 豊島正幸氏
詳細はこちらから、、、
http://sanriku-fukkou.net/file/geopark%20fukkou%20symposium.pdf
■34th IGC Third Circular
2012年8月5日〜10日にブリスベンで開催される第34回IGCのThird Circular
が公開されました。
Third Circular:
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/geoFlash_img/no154_34igc_third_circular_v5.pdf
事前参加登録も始まっています。
詳しくは: 34th IGC Home
■ウィーン大学ホーヘンエッガー教授の著書のご案内
Hohenegger, J., 2010, Large Foraminifera - Greenhouse constructions and
gardeners in the oceanic Microcosm, Bull. 5, 81 pp.
鹿児島大学総合研究博物館では上記の本を出版致しました。81ページで6図、
270枚のカラー写真を掲載しております。
ご本人が、おもに琉球列島周辺海域で調査研究された結果をもとに大型有孔虫を
わかりやすく紹介しております。生体から化石まで網羅され教科書に最適な著書
です。活用いただける方には無料(送料は受取人着払い)でお送り致します。
お問合せ先:〒890-0065 鹿児島市郡元1丁目21-30
鹿児島大学総合研究博物館内 大木公彦
e-mail: oki@sci.kagoshima-u.ac.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■鹿児島大学総合研究博物館(教授/准教授) (10/14)
■茨城大学:教育学部理科教育教室教員公募(准教授) (10/18)
■北海道大学大学院:
工学研究院環境循環システム部門資源循環工学分野(准教授)(11/30)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】地学クロスワードパズル
──────────────────────────────────
地学クロスワードパズル タテとヨコのカギ(ヒント)を使って,マス目に文字を当てはめて下さい.
最後に完成するABCDのマス目に当てはまる文字から作られる言 葉がこのクロスワードパズルの答えです.地学系雑誌では,American Geological Instituteの雑誌「EARTH」(http://www.earthmagazine .org/)にクロスワードパズルが毎回掲載されています.
もっと,むずかしいクロスワードを楽しみたい方は,そちらをご覧下さい.
楽しく 学んで,遊ぼう地学.
(川村喜一郎 深田地質)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
アメリカ合衆国ユタ・コロラド州境界、ダイノソー・ナショナル・モニュメントと.....(前編)
アメリカ合衆国ユタ・コロラド州境界、ダイノソー・ナショナル・モニュメントとユインタ山系の地質概略(紹介):前編
小川勇二郎(ユタ州プロヴォ、ブリガム・ヤング大学)
1.はじめに
図1.赤で示したルートが、ダイノソー・ダイアモンドたる周遊コース。差し渡し約150 マイル。全部を経めぐると、500マイルになろうというものだ。恐竜マークが、露頭を見学できる産地。(なお、人が手足をあげているマークは、アメリカ先住民の壁画などの遺跡)。場所によっては、化石を掘らせてもくれるところもある。このような見学個所は、茶色のボードで沿道に示してあるので、分かりやすい。起点となるユタ州のソルトレイクシティーからは、このコースの入口たるデュシェーン(と読むそうだ)へは、自動車で約3時間。そこから公園の入り口、バーナルまで、ローズベルト(と読むそうだ)を経て2時間。バーナルから、今回主として紹介する恐竜化石の壁(ダイノソー・ウォール)のジェンセンへは、約30分。また、コロラド州側のダイノソー(と呼ばれる町;現在はゴーストタウン然としている)のビジターセンターへは、1時間。なお、このダイノソ−から公園内へのルートは、シニックではあるが、恐竜化石は出ない(ので、間違えないようにと、入口に書いてある)。
ダイノソー・ダイアモンドという名称をご存じだろうか?まだあまり人口に膾炙していないかもしれないが、ユタ州とアリゾナ州にまたがる国立公園めぐりのメッカ、グランド・サークルの向こうを張った、ユタ州とコロラド州の一部を主とする、ダイノソーめぐりの新しい観光ルートのキャンペーンなのである(図1)。以下に、その北東部の、ダイノソー・ナショナル・モニュメント(Dinosaur National Monument)とユインタ山系(Uinta Mountains)の地質を中心として、若干の観察を交えて、見学の概略を紹介したい。(なお、今回、コースの大略を紹介するが、徐々にメートル法も使用されて来つつあるものの、アメリカの道路は依然としてすべてマイル表示なので、距離はあえてマイルで記した。1マイル約1.6 kmである。また、公式には使用を禁じられている第三紀なる用語も使用してある。)
この図の最北部、バーナルは、ダイノソー・ナショナル・モニュメント(アメリカで受賞経験もあるという恰好のガイドブック「地球の歩き方」シリーズ中の「アメリカの国立公園」では、ナショナル・モニュメントを国定公園と訳している。本稿では国立記念物とした。)の前線基地であり、その先のネイプルズと合わせてモーテルが20軒ほどあり、宿泊に便利である。ここには、とてもよい自然史博物館(Utah Field House of Natural History State Park Museum;但し日曜日休館)があって、恐竜を中心として、自然や文化、歴史などを色々と学べるようになっている。白眉は、建物の周辺に置かれた、さまざまな恐竜の極彩色の実物大模型である(図2)。また、周辺には、化石発見トラッキングルートなども用意されている(www.stateparks.utah.gov)。
図2.バーナルの自然史博物館の野外展示。模型とは言え、迫力満点。愛嬌もある。
この博物館には、内部にはもちろんさまざまな骨(化石)が陳列してある。このバーナルの東約15マイルには、東西幅約50マイルにおよぶダイノソー・ナショナル・モニュメントがコロラド州にかけてあり、その西端の入り口近くには、恐竜化石の壁(ダイノソー・ウォール)があって、恐竜化石愛好家のメッカでもあった。だが、2006年まで見学可能だった建物は、基盤のジュラ紀層のベントナイトの不等沈下のために、ひびが入ったり、柱が傾いたりして閉鎖。しかし、深さ最大18 mまで基礎を固め、再建なった新しい建物で、今秋、再びおびただしい化石の骨を地層に入ったままの状態で間近に観察できるようになった。
ユタ州側の最後の街ジェンセンの国道40号線に沿うウェルカムセンターの手前から、7マイル北へ州道149号線(以下、国道、州道を省略)を入った所に、黄色のビジターセンターが新しくオープンした。その裏山には、州道からは見えにくいが、恐竜ウォールが2011年10月、再開館した(なんと無料だ)。そこへは、直接自家用車で乗りつけることも可能だし、ビジターセンターに駐車して、歩いて露頭を観察しながら赴くこともできる(入館は、毎日9時15分から16時30分まで。www.nps.gov/dino)。屋外には、周囲の地層の観察ルートも整備されていて、探すと、礫岩、砂岩の中に恐竜の骨を見つけることができる(採集は禁じられている。時々、少しくらいはいいか、と考えて持ち帰る人がいるようだが、岩石一つ、植物一つでも、動かしてはいけなく、絶対に持ち帰るようなことを考えてはいけない。レインジャーが頻繁に監視をしており、万一見つかった場合は、とがめられる程度で済む問題ではないので、互いに注意しあおう。ハンマーなども、たとえスケール代わりにしようと思ったとしても、持たない方がよい。なお、ついでだが、歩行はトレイル内にとどめ、勝手にあちこちと入ってはいけない。また、立ち入り禁止とあるところ(Do not trespass. No trespassing.などと書いてある)へは、絶対に入ってはいけない)。
図3.恐竜ウォール。最初に研究したEarl Douglass博士は、化石をいたずらに取り去るのではなく、あるがままに保存すべきだ、と主張したという。もともとの半分程度の高さになっているそうだが、Douglass博士の意向が実現されているのである。この上部には、そっくり一体あるという。
図4.内部の様子。生活の様が復元されている。
このウォールは、ジュラ紀最末期の広大な湿地・湖・河川などからなる広大なベイスン(ベーズンではない)に堆積した、Morrison Formationという泥岩・砂岩(しばしば礫質)互層からなり、上下の泥岩に挟まる河川成の(チャネル)堆積物である砂岩や礫岩(クロスベッドを含む)に、恐竜の部分化石の集合や、そっくり一体分の個体化石が含まれていたりする(図3)。最も多産するのは、Camarasaurus であり、Allosaurus, Diplodocus, Stegosaurusなどの有名化石も出る。個体数としては、2000個の骨、300個体分も採集されたといい、種数は12であるという(インタープリターの説明)。さらに、建物内には、様々な復元や生活の様子が、分かりやすく説明されている、立体的な博物館と言える。ここからの化石は、基本的にはカーネギー博物館(ペンシルバニア州ピッツバーグ)に多くが納められているそうだが、ロンドンやワシントンD.C.の博物館にも、ここから出た恐竜化石の実物や型が送られたのだという。
ここのモニュメント一帯は、グリーンリバーの上流に近く、先カンブリア時代の地層や岩石、後期古生代から中生代までの地層が、何回か背斜・向斜を作って、それらの内部や上部の地層を現出せしめている。その堆積から変形時のさまざまな構造をも見ることができる。以下に、特徴的な地形、地質構造を紹介しよう。
2.ユタ州の周辺の地形と地質
図5.2011年に90歳を迎えた、ユタ州の地質屋の大家、フィールドジオロジストの権化、リーハイ・ヒンツィー ブリガムヤング大学名誉教授。
グリーンリバーはユタ州南部のキャニオンランズ国立公園内に至って(第1図のモアブの西方)、コロラド川に合流し、そこからは、グレンキャニオンダム(パウエル湖)、グランドキャニオン、フーバーダム(ミード湖)と経て、最後に、累々たる中新世の島弧性火山岩の中を流れて、カリフォルニア湾へ注いでいる。コロラド川は、ワイオミング州に端を発し、赤い川と言われるごとく、褐色をしている。一方、グリーンリバーは、その名のごとく、緑色であり、ともに蛇行を繰り返して、穏やかな流れをなす。
ユタ州の最東北部のバーナル地方では、グリーンリバーの支流は、あるものは東へ流れ、あるものは西、さらに180度向きを変えたりなど、複雑である。後に述べるこのモニュメント内の背斜構造部分でも穿入蛇行し、平坦な高原や平地に出ても、蛇行する。こうした蛇行河川は、隆起が速くない、流れがゆるやかな場所で発達する傾向があるので、この地域は、長い間、ごくゆっくりとした沈降・上昇をしつつ、ほとんど平坦で安定していたのだろう。でも、周辺の地形・地質は、おそらく、そう遠くない過去の(文献によると、約600万年前の中新世後期以降)テクトニズムを示しているのであろう。それはこの地域の堆積盆地の沈降や、中古生層の作る背斜・向斜の上昇と関連するだろうと想像される。それらは、後で述べるユインタ山系の不思議な直交「かまし」の成長をも含むのであろう。後述するが、このユインタ山系の上昇を含む、背斜・向斜の形成は、そのまま第三紀層の堆積・変形まで影響を与えている、いわゆるララマイド(ララミー)変動によるものである。
図6.Hintze教授著、Utah’s Spectacular Geology の表紙から。ユインタ山系(遠景)にへばりつくように発達するダイノソー・ナショナル・モニュメントの主要部分を占める背斜構造。軸にほぼ直交する割れ目系も、見事である。また、スプリット・マウンテンと言われるごとく、軸近くにグリーンリバーが潜入蛇行して背斜構造を分けている。恐竜ウォールは、この画面左端すぐ外に位置する。この背斜構造の南側(画面手前側)の向斜構造を挟んで、もうひとつ背斜構造が発達する(図8、12参照のこと)。
図7.ジェンセンのウェルカムセンター内に示された、本モニュメントを南北に切る簡略断面図。この背斜の横に、もうひとつアンチクラインが並走していて、複背斜構造を作っている(図8、12、14参照)。コロラドプラトー(広義)には、翼部が急傾斜の、いわゆるモノクライン状の構造が多く、そこでは、地層が急傾斜から急激に緩傾斜に移行する場合が多い。それらが、特徴的なリーフ(障害物という意味)や、スウェル構造を作り、グランドサークルに様々な景観を作っている(キャピトルリーフ、サンラファエルスウェルなど)。そこでは、層序をまとめて提供する(いわゆるテレスコーピングな)フラットアイアンを見ることができる。
さて、ソルトレイクシティーに降り立って、レンタカーを駆ってインターステイト80号から国道40号を東へ進む。ところどころに貯水池(レザヴォア;日本ではほとんどの人や教科書までが、リザーバーとしているが、完全な発音間違いである。アクセントは、レ)を見つつ、3時間ほどでデュシェーンに着く。そこからバーナルまでの 40号線(191でもある)沿いでは、第三紀層が、ほとんど水平ないし緩傾斜をなして、ゆるやかなベイスンを作っている。(なお、すでに示したように、本稿では第三紀なる名称を使用しているが、最近のアメリカの文献では、依然としてTertiaryを使っている場合と、注意深く、Early Cenozoic, Late Cenozoic として、区別をして使用している場合とがある。問題は、両者にまたがるような事象を説明するときにどのようにするかだが、どちらかに重きを置く場合はそれを使い、全く同程度のときは、Early to Late Cenozoicまたは、たとえば、late Oligocene to early Mioceneなどと、せざるを得ないのであろう。)ここまでのルートでも、そこここに恐竜を主とする、大小さまざまな自然史博物館や岩石・化石ショップがある。
図8.スプリット・マウンテン(グリーンリバーが蛇行をしている個所)が一つの背斜構造内部で、山を分けてしまっている(左側部分;図6の場所に相当)。さらにその南の向斜構造をはさんで、もうひとつ南に背斜構造がある(中央下の部分)。約75,000分の1の地形図、Dinosaur (National Geographic)から。恐竜ウォールは矢印の場所。
バーナルを過ぎて、ジェンセンに向かうと、曲線美の山並みとごつごつした、いかつい崖が見えてくる。第三紀層が柔らかな印象を与えるのと対照的に、硬そうに見える。曲線的な構造は、背斜の曲率だということは、すぐに分かるが、いかつい崖は、裂けて割れたゴロゴロの山、ペルム紀のWeber Sandstoneだ。その間に、ちょうど背斜の軸が、二つの山稜を分けてしまったために、スプリット・マウンテン・キャニオンと呼ばれる谷が形成され、そこをグリーンリバーが流れている(図7)。地形と地質構造の因果関係が理解される瞬間である(図8)。ここの背斜の南翼部は、一部でかなり急傾斜であり、恐竜ウォールは、そこに出ている(図6,7)。この層準では、50度以上に傾いている(図9)。
図9.この礫岩層(モリソン層(図10)の一部)に、恐竜の骨が多産する。50度程度南傾斜。
図10.ジュラ紀最末期のモリソン層の堆積域(モリソン・ベイスン)の分布。モンタナ州からニューメキシコ州へと、南北長500マイル以上におよぶほど、広い。このころ、西方からは、先カンブリア時代の岩石が砕屑物を提供していた。このベイスンが、白亜紀にさらに発達して、いわゆる、Western (またはAmerican)Interior Seaway (Cretaceous Interior Seawayとも呼ばれる)となった。ともに内陸盆地を形成していた(安藤・平野、1990参照)。
図11.見かけの傾斜不整合。実は、ペルム紀のWeber Ssが、こちら向きに傾いて、背斜の外翼を構成しているのだ(図8参照)。
背斜の内部から外翼に掛けては、ペルム紀から白亜紀に至る地層が分布している。背斜の内部には、ペルム紀のMorgan Formationという赤色層が分布している。なじみのバーミリオン色のMoenkopi Formation(トリアス紀)(日本人には、なぜか覚えやすい名称だ)なども出ている。アリゾナからなんと600マイルも北へ続いているのだ。ここでは、グランド・サークル一帯に緩傾斜で展開するグランド・ステアケースに見られるほとんどの層(と同時代の層)のテレスコーピングな層序と構造が一堂に会しているのである。それは、この背斜の全貌を、空撮で見ることで理解できる(図6)。 それらを陸上で見るべく、ジェンセンからさらに40号線を東へたどると、北側に、もうひとつ南傾斜の大規模な褶曲の外翼が見えてくる。これも白色のペルム紀のWeber Sandstoneであり、あたかもその上の地層との間に、傾斜不整合があるように見えてしまうが、これは見かけである(図11)。
(後編に続く)
磁鉄鉱系・チタン鉄鉱系花崗岩の帯磁率の境界値:鬼首カルデラ周辺の例
磁鉄鉱系・チタン鉄鉱系花崗岩の帯磁率の境界値:鬼首カルデラ周辺の例
石渡 明1・佐藤勇輝2・久保田 将2・濱木健成2
(1東北大学東北アジア研究センター,2東北大学理学部地球惑星物質科学科)
花崗岩の野外調査に帯磁率計が役立つことは30年以上前からよく知られている(Ishihara, 1979).磁鉄鉱系花崗岩は帯磁率が高く,チタン鉄鉱系花崗岩は帯磁率が低い.帯磁率を表すのに,かつてはcgs単位系のemu (electro-magnetic unit)という単位が使われていたが,現在はmks単位系のSIユニット(Système International d'Unités; 国際単位系)に統一されている.我々が使用しているチェコのGeofyzika社製のKAPPAMETER KT-6も,測定値はSIユニットで表示される.地学団体研究会編「新版地学事典」(平凡社, 1996)の磁鉄鉱系花崗岩とチタン鉄鉱系花崗岩の説明文(石原舜三氏執筆)には,磁鉄鉱系とチタン鉄鉱系の花崗岩の帯磁率の境界として「100×10-6 emu (30×10-3 SI)」という値が与えられている.しかし,このSIの値は明らかに1桁大き過ぎる.小数点が抜けているだけかもしれないが,いずれにしてもこれは大きな間違いで,帯磁率が30×10-3 SIもある岩石は花崗岩ではなく,鉄に富む玄武岩,斑れい岩,蛇紋岩などである.さらに,両花崗岩系列の境界値が3×10-3 SIでよいかというと,実はこれも問題である.上野(1987)の換算式に基づいて岩石の密度を2.7g/cm3としてemuの値から換算すると,この程度のSI値になるのであるが,金谷(1987)が3種類の帯磁率計で同じ岩石を実測して比較した結果によると,BISON 3101やSCINTREX SM5などの帯磁率計によってemu単位で表示される値を10〜12倍すると,KAPPAMETER KT-3のSIの値にほぼ等しくなる.KAPPAMETERは励起周波数が他の帯磁率計に比べて1桁高いため,標本によって他の帯磁率計の測定値との比率は若干異なる.金谷(1987)の実験結果を適用すると,もし磁鉄鉱系とチタン鉄鉱系の境界が100×10-6 emuであるならば,それはほぼ1.0×10-3 SIに相当するはずである.
図1.鬼首カルデラ周辺の花崗岩類の帯磁率の分布.●の大きさは各地点における最大値を表す(各地点で10ヶ所程度測定).鬼首―湯沢マイロナイト帯の西で低く東で高い.
我々は,2011年8月23日〜28日に,東北大学理学部地球惑星物質科学科の夏期フィールドセミナー(進論)として,宮城県北西端部の鬼首(おにこうべ)カルデラ周辺に露出する花崗岩のマイロナイト化について調査し,その中で花崗岩露頭(または沢の転石)のKT-6による帯磁率測定を行った.この地域には,鬼首カルデラの西縁部に露出する花崗岩体群を北北西〜南南東に縦断する鬼首―湯沢マイロナイト帯の存在が知られており,このマイロナイト帯を境界として,西側には阿武隈帯の帯磁率の低いチタン鉄鉱系の花崗岩が分布し,東側には北上帯の帯磁率が高い磁鉄鉱系の花崗岩が分布することがわかっている(笹田,1984, 1985; 広域分布はIshihara, 1979).我々の帯磁率測定でも,このマイロナイト帯の東西での花崗岩帯磁率の違いは明瞭に追認され,西側の花崗岩は概ね0.5×10-3 SI以下,東側の花崗岩は0.5×10-3 SI以上のものが多かった(図1).野外観察では,西側の花崗岩はカリ長石に富む優白質のものが多く,東側の花崗岩はやや苦鉄質鉱物に富む石英閃緑岩質のものが多い印象であるが,我々のモード測定結果では両地域とも(帯磁率の高いものも低いものも)狭義の花崗岩から石英閃緑岩まで広くばらつき,東西でモード組成の顕著な違いは見られない.
図2.鬼首カルデラ周辺で測定した花崗岩類の帯磁率の頻度分布(総数51).横軸は区間幅が等比級数的に増加する(0.2×2n-1)ようにしてある.各地点で10ヶ所程度測定した平均値を1つのデータとしている.0.5×10-3 SI付近に谷をもつ二極分布をなす.
この地域全体の花崗岩の帯磁率の頻度分布を見ると,0.2〜0.6×10-3 SIで出現頻度が小さく,0.5×10-3 SI付近に谷をもつ二極的な分布になっていて(図2),これはこの地域に独立した2つの系列の花崗岩が存在することを示唆する.笹田(1985)によるこの地域の帯磁率分布においても,鬼首―湯沢マイロナイト帯の西側では50×10-6 emu(上述の換算で0.5×10-3 SIに相当)以下,東側ではそれ以上となっている.一方,東側でも3.0×10-3 SI以上の帯磁率を示す花崗岩は少数であり(図2),磁鉄鉱系列とチタン鉄鉱系列の境界値として,やはりこの値は高過ぎるように思う.金谷(1987)の実験結果に基づき1.0×10-3 SI程度とするか,笹田(1985)及び今回の我々の鬼首地域での実測値に基づいて0.5×10-3 SI程度とするのが妥当であろう.野外での測定は,かなり凹凸のある面や風化した面に帯磁率計を当てて測定するので,実験室において平滑で新鮮な切断面に計器を当てて測定した場合に比べて低い帯磁率になるのは理解できる.野外での実測値の目安としては,0.5×10-3 SIの方が妥当な境界値であろう.
なお,この調査ではマイロナイトについても新知見があった.マイロナイト化作用は鬼首―湯沢マイロナイト帯だけでなく,その約5km西の花立山東方や約10 km東の相達沢の花崗岩にも顕著に認められ,多くのマイロナイト帯が鬼首―湯沢マイロナイト帯と平行に走っている可能性が高い.これは阿武隈山地東縁の阿武隈帯・北上帯境界付近に数本の断層が並行していることと調和的である.また,笹田(1984)は大森付近の仙北沢において,北部の非変形で帯磁率の高い石英閃緑岩がマイロナイト化の後に貫入したと判断したが,鬼首カルデラ東方の清水山周辺の帯磁率の高い花崗岩体もその北部の相達沢では著しくマイロナイト化しており,マイロナイト化は高帯磁率の花崗岩の貫入後にも起こったと考えられる.
ところで,上述の地学事典のSI値は,2007年に印刷された版でも間違ったままである.地学事典の新版が1996年に出版されて以来(旧版にはこれらの項目はなかった),だれもこの間違いに気がつかず,修正がなされなかったのは残念である(地学団体研究会には連絡済み).我々は岩石磁気学の専門家ではないが,上で報告したことは地球科学の研究や教育の基礎的な部分に関わる問題と考え,敢えて筆を執った次第である.
本報告の準備段階で貴重なコメントをいただいた産総研東北サテライトの高橋裕平氏と同地圏資源環境研究部門の高木哲一氏,そして拙稿をチェックしていただいた石原舜三氏に感謝する.野外調査でお世話になった大学院生TAの伊集院 勇氏と佐藤 景氏に感謝する.
【文献】
Ishihara, S. (1979) Lateral variation of magnetic susceptibility of the Japanese granitoids. Journal of Geological Society of Japan, 85, 509-523.
金谷 弘 (1987) 岩石帯磁率についての2―3の問題―測定における問題点と表示方法―.地質調査所月報, 38, 203-216.
笹田政克 (1984) 神室山―栗駒山地域の先第三紀基盤岩類,その1.鬼首―湯沢マイロナイト帯.地質学雑誌, 90, 865-874.
笹田政克 (1985) 神室山―栗駒山地域の先第三紀基盤岩類,その2.阿武隈帯と北上帯の境界.地質学雑誌, 91, 1-17.
上野宏共 (1987) 岩石の磁気的諸量の国際単位系(SI)とCGS系間の換算.岩鉱, 82, 441-444.
(原稿受付 2011年10月17日)
No.156 2011/11/1 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.156 2011/11/1 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2012年度代議員および役員選挙について―立候補受付は11/10まで―
【2】2012年度学会各賞募集中
【3】2012年度会費払込/学部学生・院生割引申請受付中
【4】故長岡信治先生の遺児育英資金募集について(お願い)
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞情報
【8】地質図の在庫一掃セールを行います!― 第一弾! 10月18日〜11月18日
【9】地質マンガ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2012年度代議員および役員選挙について―立候補受付は11/10まで―
──────────────────────────────────
「代議員」と「監事」の立候補届の受付は11月10日(木)までです。
選挙告示は9月号のNews誌に掲載されておりますので、選挙規則類、実施の
要点等の詳細については、そちらを参照してください。
代議員立候補受付期間
10月11日(火)〜11月10日(木)*最終日18時必着
監事立候補受付期間
10月11日(火)〜2月10日(金)*最終日18時必着
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
○会員番号・パスワードによるログインが必要です。
○「会員のページ」の選挙に関する案内から、立候補届の書式がダウンロード
できるようになっています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2012年度学会各賞募集中
──────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして、研究の援助・奨励および研究
業績の表彰を行っています(定款第3条)。本年も各賞の自薦、他薦による
候補者を募集いたします。
期日厳守にて、たくさんのご応募をお待ちしております。
応募締切:2011年12月26日(月)必着
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
○会員番号・パスワードによるログインが必要です。
○「会員のページ」の各賞推薦候補者募集に関する案内から、推薦書式等が
ダウンロードできるようになっています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2012年度会費払込/学部学生・院生割引申請受付中
──────────────────────────────────
■2012年度会費払込について
次年度分会費の前納をお願いいたします。自動引き落としを登録されている
方の引き落としは、12月26日(月)です。お振込の方へは、12月中旬頃まで
に請求書兼郵便振替用紙をお送りいたします。
詳しくは、 https://www.geosociety.jp/user.php(会員番号によるログイン
が必要です)
■2012年度(2012.4〜2013.3)学部学生・院生割引申請受付中
一次締切(会費請求書発行前):2011年11月16日(水)
会費の自動引落を利用している学部学生・院生のかたは、一次締切日までに
申請書のご提出をお願いいたします。
申請書のダウンロードは、
https://www.geosociety.jp/user.php(会員番号によるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】故長岡信治先生の遺児育英資金募集について(お願い)
──────────────────────────────────
日本地質学会会員の皆様,
本学会会員の長岡信治先生(長崎大学教育学部・教授)が,今年7月10日
に急逝されました(享年52才).早いものでもう3ヶ月が過ぎました.突然
のことで,今も信じられない気持ちでおられる方も多いものと思います.
長岡先生の急逝によりお母様と奥様,そして,愛娘かさねちゃん(9才)が
残されました.長岡先生と直接交流のあった方は,娘さんのお話を少なから
ず聞かれたと思います.娘さんの成長を見届けられないことは,長岡先生に
とって無念としか言えません.このような心情を察し,せめて娘さんに微力
ながら力添えできたらと思っていましたが,この度,教育学部の有志の皆様
が,遺児育英資金を募集されていることを知りました.
詳しい趣意書,ならびに申し込み用紙は,以下のURLからダウンロードでき
ます.皆様のご理解・ご厚情を賜りますようお願いします.〆切が11月末と
なっております.
https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-k2wftfb6zuvs4m372472gysyey-1001&uniqid=617690a3-5d22-4755-bec6-3c3cf0319c8a&viewtype=detail
福岡大学理学部 奥野 充(okuno@fukuoka-u.ac.jp)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報
──────────────────────────────────
■秩父ジオパーク「秩父札所のジオめぐり」(関東支部後援)
○第1回目【秩父札所をめぐり秩父帯と秩父盆地南縁の断層を見る】
日時: 2011年10月30日(日) 10:00〜16:30
○第2回目【秩父札所をめぐり荒川がつくった段丘を見る】
日時: 2011年12月11日(日) 9:30〜16:00
問合せ:小幡喜一 電話:0494-23-4606、obata.k@kumagaya-h.spec.ed.jp
詳細はこちらから、、、
http://www.geocities.jp/obt_kk/geo_park/event.html
■関東支部2011年度地質見学会 第二弾!!
「霞ヶ浦のあゆみ −環境変遷,過去から未来へ−(地質と霞ヶ浦導水路見学)」
日時:2011年11月26日(土) 10:00〜17:30
集合:JR常磐線土浦駅東口バス乗り場付近
参加費:3000円
申込締切:11月18日(金)
詳細はこちら、、、(pdfファイル)
http://kanto.geosociety.jp/junken/2011/20111126/20111126_kasumigaura.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■男女共同参画委員会 研究交流会(学習会・巡検)まだ募集中です.
メルマガNo.155で募集しました集会参加者募集は11/7までですが,それ以降
でも参加できる方はご連絡ください.
「3.11福島県南相馬地域の被災地を巡る」
案内者:田崎和江,高橋正則(庄建技術)
日程:2011年11月12日(土)〜13日(日)
11/12(土)福島駅13時集合,解散 相馬市付近14時頃
連絡先:yukiko@kescriv.kj.yamagata-u.ac.jpまたは080-6055-3470(大友)
詳細はこちら、、、(下記の先週の記事に)
11/12(土)福島駅13時
・福島から南相馬(原ノ町)に移動しながら,高放射能汚染地域,除洗実験
地の見学
・原ノ町周辺に宿泊
・宿舎で学習会,交流会(いろいろな活動,研究等話題提供できる方は資料
を持ち寄る)
11/13(日)
・南相馬〜相馬にかけての津波被害地の見学
・解散 相馬市付近14時頃(福島バス相馬営業所14:20の福島行きバスに
乗れるようにします。福島着は15:50)
○参加費(宿泊費等)1万円程度(未定)
○参加希望者は,11/7までに大友幸子宛メール( yukiko@kescriv.kj.yamagata-u.ac.jp )
をください(受け付けましたら返信メールを送ります).
○参加は男女問わず,非会員の方もどうぞ.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■日本原子力研究開発機構: 平成24年度「先行基礎工学研究」の公募(12/15)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】地質図の在庫一掃セールを行います!―第一弾!10月18日〜11月18日―
──────────────────────────────────
現在、地質学会に在庫があるものについてのみ、整理のため特別に販売いた
します。在庫リストはホームページに掲載していますのでご覧いただくか、
事務局にお尋ねください。
ご注文は電話(03-5823-1150)かE-mail(main@geosociety.jp)でお願いいた
します。 種類と数に限りがありますので、ご注文は先着順といたします。
リストにないもの、追加等のご注文には応じられませんのでご了承ください。
なお、セールの期間は、とりあえず10月18日より11月18日までとさせていただ
きます。
詳細はご注文の際に地質学会事務局にお問い合わせください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】地質マンガ
─────────────────────────────────
包丁は必要 原案:川村喜一郎 マンガ:KEY
http://www.geosociety.jp/faq/content0340.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
地質マンガ 統合国際深海掘削計画IODPで活躍するプラットフォームたち
地質マンガ
戻る|次へ
No.155 2011/10/18 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.155 2011/10/18 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】コラム:磁鉄鉱系・チタン鉄鉱系花崗岩の帯磁率の境界値:鬼首カルデラ周辺の例
【2】地球惑星科学連合の代議員選挙投票のお願い ―連合に参加しよう―
【3】サイエンスライターになって頂けませんか?
【4】2012年度代議員および役員選挙について―立候補届受付開始!―
【5】2012年度学会各賞募集開始
【6】2012年度会費払込/学部学生・院生割引申請受付開始!
【7】男女共同参画委員会 研究交流会(学習会・巡検)のおしらせ
【8】2011年度日本地質学会震災復興事業プランの応募は,9月末をもって締切られました.
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞情報
【12】地質図の在庫一掃セールを行います!― 第一弾!10月18日〜11月18日 ―
【13】地質マンガ 「統合国際深海掘削計画IODPで活躍するプラットフォームたち」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】コラム:磁鉄鉱系・チタン鉄鉱系花崗岩の帯磁率の境界値:鬼首カルデラ周辺の例
──────────────────────────────────
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)・佐藤勇輝・久保田 将・濱木
健成(東北大学理学部地球惑星物質科学科)
花崗岩の野外調査に帯磁率計が役立つことは30年以上前からよく知られて
いる(Ishihara, 1979).磁鉄鉱系花崗岩は帯磁率が高く,チタン鉄鉱系花
崗岩は帯磁率が低い.帯磁率を表すのに,かつてはcgs単位系のemuという単
位が使われていたが,現在はmks単位系のSIユニットに統一されている.我々
が使用しているチェコのGeofyzika社製のKAPPAMETER KT-6も,測定値はSI
ユニットで表示される.地学団体研究会編「新版地学事典」(平凡社, 1996)
の磁鉄鉱系花崗岩とチタン鉄鉱系花崗岩の説明文(石原舜三氏執筆)には,
磁鉄鉱系とチタン鉄鉱系の花崗岩の帯磁率の境界として「100×10-6 emu
(30×10-3 SI)」という値が与えられている.しかし,このSIの値は明らかに
1桁大き過ぎる.小数点が抜けているだけかもしれないが,いずれにしてもこ
れは大きな間違いで,帯磁率が30×10-3 SIもある岩石は花崗岩ではなく,鉄
に富む玄武岩,斑れい岩,蛇紋岩などである.さらに,両花崗岩系列の境界
値が3×10-3 SIでよいかというと,実はこれも問題である.
続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0337.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】地球惑星科学連合の代議員選挙投票のお願い ―連合に参加しよう―
──────────────────────────────────
9月29日より,日本地球惑星科学連合の代議員選挙の投票が開始されています.
日本地球惑星科学連合の個人会員(正会員)より選ばれた代議員(社員)の
方々はセクションプレジデントならびに理事の被選挙者となるとともに,団
体(学協会)会員とともに,定時・臨時社員総会において,役員の選出,事
業計画の承認,その他の連合の運営に関わる諸事項についての決議を行なう
こととなります.
代議員を選出する選挙の投票は,ホームページ上で行なわれますが,代議員
選挙の投票締切日(10月28日)までに会員登録をされた個人会員(正会員)
の方は,ご自分が登録した登録区分の候補者のなかから,5名(あるいはそれ
より少ない人数)を選んで,投票することができます.
連合の会員登録されている地質学会員の皆様はもちろんですが,まだ登録さ
れていない方はぜひともこの機会に会員登録をしていただき,連合の代議員
選挙にご参加いただきますよう,よろしくお願い致します.ちなみに連合の
年会費は2,000円で,連合大会の参加登録料が会員は非会員に比べ7,000円安
くなるほか,ニュースレター(JGL)も受け取ることができます.
[選挙日程] 2011年
代議員選挙
9月29日(木)投票開始
10月28日(金)投票締切 ←←←←←【投票締切まで残り10日!】
11月 4日(金)開票,結果報告
セクションプレジデント選挙
11月 4日(金)公示
[投票]
個人会員ログインページよりログイン後,「代議員選挙投票」をクリックして
行ってください https://secure.jtbcom.co.jp/jpgu/
[新規会員登録]
投票締切日(10月28日)までに正会員登録されると代議員選挙に投票できます
http://www.jpgu.org/touroku/entry_new.html
[代議員候補者名簿]
http://www.jpgu.org/whatsnew/daigiinlist.pdf
一般社団法人日本地質学会執行理事会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】サイエンスライターになって頂けませんか?
──────────────────────────────────
昨今地球科学に対する社会的関心がたいへん高まっており,アウトリーチの重
要な課題となっています.研究者自身による情報発信も重要ですが,一般の皆様
に最新の研究成果をわかりやすく伝えていくためには,普及教育を目的としたサ
イエンスライターの育成が鍵となると考えております.そこで地質学会として
ウェブサイトや広報誌,それに地学オリンピックに関心ある高校生などを対象と
した一般向けの解説記事を書いて下さる方を募集いたします.
【内容】文献による下調べとSkype等による通信やインタビューを通じて地球科学の研究
成果をわかりやすく紹介する一般向けの解説記事(署名記事)を執筆する.解説文の
テーマや推敲等は関係する委員会と協力して取り組む.概ね1000〜2000文字の解
説文を年に1〜2本程度とする.謝金あり.
【募集人数】2〜3名程度
【応募者】普及教育事業に理解がある地質学会会員,もしくは広報委員会および
地学オリンピック支援委員会より推薦された方.
【応募締切】2011年11月7日(月)
【お問い合わせ先】学会事務局
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2012年度代議員および役員選挙について―立候補届受付開始!―
──────────────────────────────────
10月11日(火)から、「代議員」と「監事」の立候補届の受付が開始されま
した。選挙告示は9月号のNews誌に掲載されておりますので、選挙規則類、
実施の要点等の詳細については、そちらを参照してください。
代議員立候補受付期間
10月11日(火)〜11月10日(木)*最終日18時必着
監事立候補受付期間
10月11日(火)〜2月10日(金)*最終日18時必着
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
○会員番号・パスワードによるログインが必要です。
○「会員のページ」の選挙に関する案内から、立候補届の書式がダウンロード
できるようになっています。
<<2012年度代議員および役員選挙告示記事の訂正とお詫び>>
9月9日付でHPとニュース誌に掲載しました表記記事のうち、以下の記載に
ミスがありました。お詫びをして、訂正いたします。
日本地質学会選挙管理委員会
* News誌9月号、p(9)に掲載の表
I. 選挙管理委員会によって行われる選挙
2. 理事選挙 階層指定の定数
院生(研究生) 3名(誤) → 2名(正)
得票順 16名(誤) → 17名(正)
* ホームページに掲載の表は訂正済みです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2012年度学会各賞募集開始
──────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして、研究の援助・奨励および研究
業績の表彰を行っています(定款第3条)。
本年も各賞の自薦、他薦による候補者を募集いたします。期日厳守にて、
たくさんのご応募をお待ちしております。
応募締切:2011年12月26日(月)必着
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
○会員番号・パスワードによるログインが必要です。
○「会員のページ」の各賞推薦候補者募集に関する案内から、推薦書式等が
ダウンロードできるようになっています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】2012年度会費払込/学部学生・院生割引申請受付開始!
──────────────────────────────────
■2012年度会費払込について
次年度分会費の前納をお願いいたします。自動引き落としを登録されている方の
引き落としは、12月26日(月)です。お振込の方へは、12月中旬頃までに請求書
兼郵便振替用紙をお送りいたします。
詳しくは、 https://www.geosociety.jp/user.php(会員番号によるログインが必要です)
■2012年度(2012.4〜2013.3)学部学生・院生割引申請受付中
一次締切(会費請求書発行前):2011年11月16日(水)
会費の自動引落を利用している学部学生・院生のかたは、一次締切日までに申請書の
ご提出をお願いいたします。
申請書のダウンロードは、
https://www.geosociety.jp/user.php(会員番号によるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】男女共同参画委員会 研究交流会(学習会・巡検)のおしらせ
──────────────────────────────────
「3.11福島県南相馬地域の被災地を巡る」
案内者:田崎和江,高橋正則(庄建技術)
日程:2011年11月12日(土)〜13日(日)
11/12(土)福島駅13時
・福島から南相馬(原ノ町)に移動しながら,高放射能汚染地域,除洗実験
地の見学
・原ノ町周辺に宿泊
・宿舎で学習会,交流会(いろいろな活動,研究等話題提供できる方は資料
を持ち寄る)
11/13(日)
・南相馬〜相馬にかけての津波被害地の見学
・解散 相馬市付近14時頃(福島バス相馬営業所14:20の福島行きバスに
乗れるようにします。福島着は15:50)
○参加費(宿泊費等)1万円程度(未定)
○参加希望者は,11/7までに大友幸子宛メール(yukiko@kescriv.kj.yamagata-u.ac.jp)
をください(受け付けましたら返信メールを送ります).
○参加は男女問わず,非会員の方もどうぞ.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】2011年度日本地質学会震災復興事業プランの応募は,9月末をもって締切られました.
──────────────────────────────────
2011年度の東日本大震災にかかわる復旧・復興に関連する事業プランは,9月
末日をもちまして〆切とさせていただきました.
申請計画8件のなかから,下の6件が採択され,いずれも30万円の予算枠内で
すでに調査・研究が進められています.
geo-Flash No.139 (6/21) でお伝えしましたように,このプランにかかわる
研究終了後の報告義務としては,
1.収支報告書を地質学会事務局に提出するとともに,成果報告概要をニュ
ース誌に掲載すること.
2.2012年地質学会年会(大阪)で発表すること(2件目の発表を可とする).
となっています.なお,標本レスキュー事業につきましては,8月13日の朝日
新聞朝刊でも大きく取り上げられています.
-- 2011年度 東日本大震災の復旧・復興にかかわる事業計画の採択リスト --
(括弧内は申請日)
榊原 正幸・佐野 栄: 放射性セシウムに汚染された水田土壌のカヤツリグサ科
マツバイによるファイトレメディエーション(6月23日)
永広 昌之: 歌津魚竜館大型標本レスキュー事業(6月29日)
高橋 正則: 微生物による放射性物質の除染の実証試験(7月5日)
卜部 厚志: 関東平野内陸部の住宅地での盛土材質の相違による液状
化要因の解明(7月11日)
大石 雅之: 陸前高田博物館標本レスキュー事業(7月15日)
上砂 正一: 福島第一原子力発電所周辺の放射線量の測定方法と地質
学的除染方法の検討(8月29日;9月26日修正)
日本地質学会執行理事会 震災復興事業プランWG
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】支部情報
──────────────────────────────────
■関東支部2011年度地質見学会 第二弾!!
「霞ヶ浦のあゆみ −環境変遷,過去から未来へ−(地質と霞ヶ浦導水路見学)」
日時:2011年11月26日(土) 10:00〜17:30
※見学場所が多いため,集合時間が9時となる可能性もあります
集合:JR常磐線土浦駅東口バス乗り場付近
参加費:3000円
申込締切:11月18日(金)
詳細はこちら、、、(pdfファイル)
http://kanto.geosociety.jp/junken/2011/20111126/20111126_kasumigaura.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■シンポジウム「大地震・大津波に備えて〜海からの視点で考える〜」
東日本大震災によって東北地方の沿岸部を中心とする各地に甚大な被害が
もたらされました。海運・造船・漁業・水産等、海をその拠り所とする産業
においても大きな被害を受け、復旧・復興が急がれています。阪神地方にあ
っては16年前に阪神・淡路大震災に襲われ、その経験から対策も提言されて
きています。はたして対策は有効であったのか、今後の大災害に備えるため
には何が必要か、最新の現状報告とともに、海からの視点で考えるシンポジ
ウムを開催します。
日時:2011年10月31日(月) 10:00〜17:35
場所:神戸国際会議場メインホール(神戸市中央区港島中町6-9-1)
主催:日本船舶海洋工学会
参加費:無料(要参加登録)
参加登録はこちらから、https://www.webmasters.co.jp/jsn-event/20111031/
プログラムなど詳細は、
http://www.jasnaoe.or.jp/lecture/symp/shinsai_201109.html
■日本学術会議東北地区会議公開学術講演会の開催について
日時:2011年11月11日(金) 13:00〜17:00
場所:岩手大学教育学部 北桐ホール
(岩手県盛岡市上田3丁目18-8)
主催:日本学術会議東北地区会議
共催:岩手大学、日本学術会議同友会東北部会
参加費:無料
内容:
開会挨拶
栗原和枝(日本学術会議東北地区会議前代表幹事・会員、
東北大学原子分子材料科学高等研究機構教授)
藤井克己(岩手大学長、日本学術会議連携会員)
講演
「東日本大震災からの復興における日本学術会議としての取組」
石川幹子(東京大学大学院工学系研究科教授、日本学術会議会員)
「東北地方太平洋沖地震による津波発生のメカニズム」
今村文彦(東北大学大学院工学研究科教授、日本学術会議連携会員)
「津波被害とまちづくり −岩手県沿岸市町村の復興計画から−」
堺 茂樹(岩手大学工学部長)
パネルディスカッション「被災地に寄りそう支援活動と科学技術」
パネリスト:石川幹子(東京大学大学院工学系研究科教授、日本学術会議会員)
砂山 稔(岩手大学人文社会科学部教授)
山崎友子(岩手大学教育学部教授)
堺茂 樹(岩手大学工学部長)
廣田純一(岩手大学農学部教授)
司会:岩渕 明(岩手大学理事(総務・地域連携・国際連携)・副学長、
日本学術会議連携会員)
問合せ:日本学術会議東北地区会議事務局(東北大学研究協力部研究協力課内)
TEL:022-217-4840 FAX:022-217-4841
■高校生のための先進的科学技術体験合宿プログラム
「ウインター・サイエンスキャンプ '11-'12」参加者募集
サイエンスキャンプは先進的な研究テーマに取り組んでいる日本各地の
大学・公的研究機関等(10会場)で、冬休み期間中に本格的な実験・実習
が受けられる、高校生のための科学技術体験合宿プログラムです。これま
での2泊3日のプログラムに、今年度より3泊4日以上の探究・深化型プログ
ラム「サイエンスキャンプDX」が加わり、さらに充実した内容で実施し
ます。
開 催 日:2011年12月25日〜2012年1月7日の期間中の2泊3日〜3泊4日
対 象:高等学校、中等教育学校後期課程または専門学校(1〜3学年)
会 場:大学、公的研究機関 (10会場)
定 員:受け入れ会場ごとに10〜40名 (計206名)※前年度平均応募倍率2.5倍
参 加 費:無料(自宅と会場間の往復交通費は自己負担。宿舎・食事は用意します)
応募締切:2011年11月8日(火)郵送必着
主 催:独立行政法人 科学技術振興機構
共 催:受入実施機関
ホームページ:http://ppd.jsf.or.jp/camp/
応募・問い合わせ先:サイエンスキャンプ本部事務局
(公財)日本科学技術振興財団 振興事業部内
電話:03-3212-2454 FAX:03-3212-0014 E-mail:camp@jsf.or.jp
■JABEE 事務局ニュース No. 18(2011/10/5版)
JABEE事務局ニュースは社員(正会員)、賛助会員、理事、監事、顧問、
委員会委員宛に配信されています。
情報のより広い共有のため、会員の皆様にもご転送いたします。
2011/10/5版ニュース PDFはこちら、、
http://www.jabee.org/OpenHomePage/koho/jabee_e-news_18_111005.pdf
JABEEホームページ http://www.jabee.org/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■東京工業大学:理工学研究科地球惑星科学専攻
地質学(助教),個体地球科学(助教)(11/30)
■東京工業大学:理工学研究科地球惑星科学専攻 (11/30)
■海洋研究開発機構:地球内部ダイナミクス領域 海洋・極限環境生物圏領域
(研究職・技術研究職・ポスドク研究員)(11/25)
■東京大学大学院:理学系研究科地球惑星科学専攻(教授)(12.1.10)
■岡山大学地球物質科学研究センター:研究員 (11/30)
--------
■第29回「とやま賞」(11/22)(学会締切11/10)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】地質図の在庫一掃セールを行います!― 第一弾!10月18日〜11月18日 ―
──────────────────────────────────
現在、地質学会に在庫があるものについてのみ、整理のため特別に販売いた
します。在庫リストはホームページに掲載していますのでご覧いただくか、
事務局にお尋ねください。
ご注文は電話(03-5823-1150)かE-mail(main@geosociety.jp)でお願いいた
します。 種類と数に限りがありますので、ご注文は先着順といたします。
リストにないもの、追加等のご注文には応じられませんのでご了承ください。
なお、セールの期間は、とりあえず10月18日より11月18日までとさせていただ
きます。
詳細はご注文の際に地質学会事務局にお問い合わせください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】地質マンガ 「統合国際深海掘削計画IODPで活躍するプラットフォームたち」
──────────────────────────────────
統合国際深海掘削計画IODPで活躍するプラットフォームたち
(原案・マンガ:黒田潤一郎)
http://www.geosociety.jp/faq/content0338.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
地質マンガ 包丁は必要
地質マンガ
戻る|次へ
No.157 2011/11/8 (臨時)geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.157 2011/11/8 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】選挙管理委員会から緊急のお知らせ―2012年度代議員選挙、立候補受付〆切迫る
【2】その他のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】☆☆選挙管理委員会から緊急のお知らせ☆☆
―2012年度代議員選挙、立候補受付〆切迫る―
──────────────────────────────────
「代議員」の立候補届の受付は11月10日(木)が締め切りです。
届け出の状況は下記に示したように、現時点ではやや低調です。
選挙の詳細は、News誌9月号または、HPの「会員のページ」に
掲載されていますので参照ください。
立候補を予定されている方は、〆切期日に遅れないようご提出ください。
○代議員立候補受付〆切最終日 11月10日(木) 18時必着
(郵送、E-mail 受付可)
なお、代議員に立候補される方のうち、その後、会長及び副会長
への立候補の意思のある方は、会員による意向調査のための
マニュフェストを添付してください。
立候補の届出先は選挙管理委員会(main@geosociety.jp)あてに
お願いします。本メールマガジン(geo-flash)へそのままご返信されると、
選挙管理委員会には立候補届のメールが届きませんので、ご注意ください。
○11月8日、現在までの立候補者数は以下のとおりです。( )内は定員数。
・全国区 44名 (100)
・地方支部区 21名 (100)
内訳:北海道0(5) 東北2名(7) 関東13名(42)
中部4名(17) 近畿0(11) 四国1名(4)
西日本1名(14)
○立候補届の書式は、「会員のページ」の選挙に関する案内から
ダウンロードできます。
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
「会員のページ」は、IDとパスワードによるログインが必要です。
ID=会員番号(*)、パスワード=姓、名それぞれの頭文字に続けて会員番号
(*)会員番号は、学会からの郵便物のあて名に印字(数字7ケタ)されています。
不明の方は、事務局(TEL.03-5823-1150)にお問い合わせください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■ 公開シンポジウム「東京電力福島原子力発電所事故への科学者の役割と
責任について」
日時:2011年11月26日 (土) 10:00〜17:00
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木7-22-34)
参加費:無料(定員300名・事前登録制)
主催:日本学術会議、独立行政法人科学技術振興機構
研究開発戦略センター(CRDS)
後援:(予定)
日本原子力学会、日本機械学会、日本化学会、土木学会、
日本医学放射線学会、日本原子力研究開発機構
参加申し込み・プログラムはこちらから、、、
http://crds.jst.go.jp/sympo/kagakusya
問い合せ先:シンポジウム事務局
株式会社オーエムシー内
TEL:03-5362-0128 受付時間:10:00から17:00(土日祝日除く)
FAX:03-5362-0125
E-mail: crds@omc.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.158 2011/11/10 (臨時)geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.158 2011/11/10 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】☆☆選挙管理委員会から緊急のお知らせ
―2012年度代議員選挙、立候補受付 本日18時〆切!―
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】☆☆選挙管理委員会から緊急のお知らせ
―2012年度代議員選挙、立候補受付 本日18時〆切!―
──────────────────────────────────
「代議員」の立候補届の受付は本日10日(木)18時が締め切りです。
2年に一度の選挙で、現在の全代議員、全理事が改選となります。
現時点での届け出の状況は下記に示下とおりです。
選挙の詳細は、News誌9月号または、HPの「会員のページ」に
掲載されていますので参照ください。
立候補を予定されている方は、〆切期日に遅れないようご提出ください。
○代議員立候補受付〆切最終日 11月10日(木) 18時必着
(郵送、E-mail 受付可)
なお、代議員に立候補される方のうち、その後、会長及び副会長
への立候補の意思のある方は、会員による意向調査のための
マニュフェストを添付してください。
立候補の届出先は選挙管理委員会(main@geosociety.jp)あてに
お願いします。本メールマガジン(geo-flash)へそのままご返信されると、
選挙管理委員会には立候補届のメールが届きませんので、ご注意ください。
○11月10日、12時までの立候補者数は以下のとおりです。( )内は定員数。
・全国区 76名 (100)
・地方支部区 51名 (100)
内訳:北海道3名(5) 東北4名(7) 関東24名(42)
中部10名(17) 近畿7名(11) 四国2名(4)
西日本1名(14)
○立候補届の書式は、「会員のページ」の選挙に関する案内から
ダウンロードできます。
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
「会員のページ」は、IDとパスワードによるログインが必要です。
ID=会員番号(*)、パスワード=姓、名それぞれの頭文字(小文字)に続けて会員番号
(*)会員番号は、学会からの郵便物のあて名に印字(数字7ケタ)されています。
不明の方は、事務局(TEL.03-5823-1150)にお問い合わせください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.159 2011/11/15 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.159 2011/11/15 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】コラム:アメリカ合衆国ユタ・コロラド州境界、ダイノソー・ナショナル・
モニュメントとユインタ山系の地質概略(紹介)(前編)
【2】第三回 惑星地球フォトコンテスト募集開始
【3】2012年度学会各賞募集中
【4】2012年度会費払込/学部学生・院生割引申請受付中
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】コラム:アメリカ合衆国ユタ・コロラド州境界、ダイノソー・ナショナル・
モニュメントとユインタ山系の地質概略(紹介)(前編)
──────────────────────────────────
小川勇二郎(ユタ州プロヴォ、ブリガム・ヤング大学)
ダイノソー・ダイアモンドという名称をご存じだろうか?まだあまり人口に
膾炙していないかもしれないが、ユタ州とアリゾナ州にまたがる国立公園め
ぐりのメッカ、グランド・サークルの向こうを張った、ユタ州とコロラド州
の一部を主とする、ダイノソーめぐりの新しい観光ルートのキャンペーンな
のである。以下に、その北東部の、ダイノソー・ナショナル・モニュメント
とユインタ山系の地質を中心として、若干の観察を交えて、見学の概略を紹
介したい。
続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0342.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第三回 惑星地球フォトコンテスト募集開始
──────────────────────────────────
今回で三回目となる惑星地球フォトコンテストの作品募集が始まりました。
こんな作品を大募集!
•惑星地球の美しい自然
•地層や火山など活きた地球の姿を表す優れた作品
•学術的意義の高い作品(解説文を含む)
•ジオパークに関係する優れた作品
•鉄道と地球の姿を組み合わせた「ジオ鉄」の優れた作品
•学術的・教育的な価値のある優れた作品
•そのほか地球科学に関係した作品
応募締切:2012年1月31日(火)
詳細は、、、
http://photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2012年度学会各賞募集中
──────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして、研究の援助・奨励および研究
業績の表彰を行っています(定款第3条)。本年も各賞の自薦、他薦による
候補者を募集いたします。
期日厳守にて、たくさんのご応募をお待ちしております。
応募締切:2011年12月26日(月)必着
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
○会員番号・パスワードによるログインが必要です。
○「会員のページ」の各賞推薦候補者募集に関する案内から、推薦書式等が
ダウンロードできるようになっています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2012年度会費払込/学部学生・院生割引申請受付中
──────────────────────────────────
■2012年度会費払込について
次年度分会費の前納をお願いいたします。自動引き落としを登録されている
方の引き落としは、12月26日(月)です。お振込の方へは、12月中旬頃まで
に請求書兼郵便振替用紙をお送りいたします。
詳しくは、 https://www.geosociety.jp/user.php(会員番号によるログイン
が必要です)
■2012年度(2012.4〜2013.3)学部学生・院生割引申請受付中
一次締切(会費請求書発行前):2011年11月16日(水)
会費の自動引落を利用している学部学生・院生のかたは、一次締切日までに
申請書のご提出をお願いいたします。
申請書のダウンロードは、
https://www.geosociety.jp/user.php(会員番号によるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報
──────────────────────────────────
■秩父ジオパーク「秩父札所のジオめぐり」(関東支部後援)
○秩父札所をめぐり荒川がつくった段丘を見る
日時: 2011年12月11日(日) 9:30〜16:00
問合せ:小幡喜一 電話:0494-23-4606、 obata.k@kumagaya-h.spec.ed.jp
詳細はこちらから、、、
http://www.geocities.jp/obt_kk/geo_park/event.html
■関東支部2011年度地質見学会 第二弾!!
「霞ヶ浦のあゆみ −環境変遷,過去から未来へ−(地質と霞ヶ浦導水路見学)」
日時:2011年11月26日(土) 10:00〜17:30
集合:JR常磐線土浦駅東口バス乗り場付近
参加費:3000円
申込締切:11月18日(金)
詳細はこちら、、、(pdfファイル)
http://kanto.geosociety.jp/junken/2011/20111126/20111126_kasumigaura.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■平成23年台風12号による地盤災害合同調査団報告会
日時:2011年11月24日(木) 13:00〜17:30
場所:エル大阪南ホール(大阪市中央区北浜東3-14)
主催:地盤工学会関西支部、日本地質学会、日本応用地質学会、関西地質調査業協会
参加費:1000円(先着200名、要申込み)
※ジオ・スクーリングネットからCPD単位の取得が可能です。(https://www.geo-schooling.jp/)
プログラム、申込み等詳細は、、、
http://www.jgskb.jp/japanese/info/
■いわて三陸ジオパーク震災復興シンポジウム〜震災の記憶を伝え生かすために〜
(日本地質学会学会 後援)
日時:2011年11月25日(金)シンポジウム 13:30〜17:00
(ポスター展示 10:00〜18:00)
26日(土)被災地巡検
場所:アイーナホール(いわて県民情報交流センター:盛岡市盛岡駅西通1-7-1)
内容
◇記念講演 尾池和夫氏(日本ジオパーク委員会委員長・元京大総長)
「東日本大震災においてジオパークができること」
◇事例紹介
杉本伸一氏(島原半島ジオパーク事務局・ジオパーク国際ユネスコ会議事務局長)
「雲仙普賢岳噴火災害から20年〜復興の軌跡」
草野 悟氏(三陸鉄道を勝手に応援する会会長)
「被災地の思いを伝える〜三陸鉄道の取組」
◇パネルディスカッション
○コーディネーター 中川和之氏
○パネラー 杉本伸一氏(同上)・草野 悟氏(同上)・大石雅之氏(岩手県立
博物館首席専門学芸員)・永広昌之氏(仙台市教育委員・東北大学名誉教授)
・渡辺真人氏(産業技術総合研究所主任研究員・日本ジオパーク委員会事務局)
◇閉会挨拶 実行委員長 豊島正幸氏
詳細はこちらから、、、
http://sanriku-fukkou.net/file/geopark%20fukkou%20symposium.pdf
■公開シンポジウム「東京電力福島原子力発電所事故への科学者の役割と
責任について」
主旨:
東京電力福島原子力発電所事故への対応において科学者が果たすべき役割は
大きく、また、この問題に貢献することは科学者の責任でもあります。長期間
を要することになる事故への対応においては、科学者が持つ知識や経験が分野・
組織・世代・国を超えて課題の解決に向けて総合的に発揮できる仕組みを構築
すること、科学者が市民や国、自治体などのニーズや期待に的確に応えていく
こと、科学者が十分な情報を踏まえて対応できるようにすること――などの問
題に対し、今後、科学者を含む関係者が一体となって持続的に取り組んでいく
ことが必須です。
本シンポジウムでは、上記のような視点から、主要学会の会長や米国科学ア
カデミーの専門家など内外の有識者を招き、講演とパネルディスカッションを
通じて、今回の事故への対応についての科学者の役割と責任について議論を深
めたいと考えています。
日時:2011年11月26日 (土) 10:00〜17:00
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木7-22-34)
参加費:無料(定員300名・事前登録制)
主催:日本学術会議、独立行政法人科学技術振興機構
研究開発戦略センター(CRDS)
後援:(予定)
日本原子力学会、日本機械学会、日本化学会、土木学会、
日本医学放射線学会、日本原子力研究開発機構
参加申し込み・プログラムはこちらから、、、
http://crds.jst.go.jp/sympo/kagakusya
問い合せ先:シンポジウム事務局
株式会社オーエムシー内
TEL:03-5362-0128 受付時間:10:00から17:00(土日祝日除く)
FAX:03-5362-0125
E-mail: crds@omc.co.jp
■Project A meeting in Taiwan
日程 2012年3月5〜9日
場所 台湾海洋大学 国際シンポジウム
"Oceanic environmental change though earth history: From Archean to
Modern ocean"
「地球史を通した海洋環境と変遷 --太古代から現在まで--」
参加者: 若手研究者、大学院生を歓迎
コンビーナー:清川昌一(九大)、渡邉剛(北大)、Min-Te Chen(台湾海洋大学)
参加申込み:12月3日まで(名前、タイトル)、(アブストは1月末までにA4)
メールにて受付
宛先:清川昌一 kiyokawa@geo.kyushu-u.ac.jp,
渡辺剛 nabe@mail.sci.hokudai.ac.jp
詳細は http://www.archean.jp を参照してください。
■第48回 霞ヶ関環境講座
講座「レアアース(希土類)資源:その実態と将来」
浦辺徹郎(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教授)
三宅賞受賞記念講演「分析電子顕微鏡および実験的手法による始原的隕石の形成・進化の研究」
留岡和重博士(神戸大学大学院理学研究科 教授)
日時:2011年12月3日 (土) 14:30〜
場所:霞ヶ関ビル35階東海大学校友会館
参加費:賛助会員および学生は無料、一般1,000円(資料代を含む)、懇親会へも参加できます。
プログラム詳細、参加申し込みは、、、
http://wwwsoc.nii.ac.jp/gra/News.htm
地球化学研究協会ホームページ http://wwwsoc.nii.ac.jp/gra/
■第4回ジオ多様性フォーラム
(ジオ多様性の普及に向けて,ワインからみたジオ多様性 他)
日時:2012年2月10日(金)〜11日(土)
場所:京都大学博物館を予定
問い合わせ先:矢島道子 pxi02070@nifty.com
■国際シンポジウムMISASA IV「太陽系物質科学 〜太陽系科学ミッションと
総合的物質科学研究が拓く未来像〜」
日時:2012年2月24日(金)〜26日(日)
場所:倉吉未来中心(鳥取県倉吉市駄経寺町212-5)
主催:岡山大学地球物質科学研究センター
共催:宇宙航空研究開発機構/宇宙科学研究所,千葉工業大学惑星探査研究センター
参加登録開始:2012年1月初旬
詳細は、
http://sympo.misasa.okayama-u.ac.jp/misasa_iv/
■20万分の1日本シームレス地質図を改訂しました.(産総研地質調査総合センター)
http://riodb02.ibase.aist.go.jp/db084/
本年度いくつかの大きな改訂があります.
1)特定の地質を選択して表示できるようにしました.超苦鉄質岩だけの
表示等ができます.
2)カーソル位置の情報をクリックで固定する機能等を追加しました.
3)スマートフォン版・携帯版を公開しました(パケット定額コースは必須です)
4)2008年-2010年出版の20万分の1地質図幅に基づき,データを更新しま
した(静岡及び御前崎,名古屋,伊勢,中之島及び宝島,魚釣島,石垣島,
徳之島,小笠原諸島).
なお,「シームレス地質図」の商標登録を行いましたのでお知らせいたします.
http://www.gsj.jp/Gtop/news/seamless20111101/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■2012年Hervey賞 推薦候補者募集(12/31)
■第24年度東京大学大気海洋研究所 共同利用公募(11/30)
■第53回藤原賞 推薦候補者募集(学会締切1/10)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。 geo-Flashは、
月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日 までに
事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
アメリカ合衆国ユタ・コロラド州境界、ダイノソー・ナショナル・モニュメントと.....(後編)
アメリカ合衆国ユタ・コロラド州境界、ダイノソー・ナショナル・モニュメントとユインタ山系の地質概略(紹介):後編
小川勇二郎(ユタ州プロヴォ、ブリガム・ヤング大学)
3.コロラド州側の地形と地質
図12.ダイノソー・ナショナル・モニュメントの地図。ユタ州側のジェンセンから北へ入ると、恐竜ウォール、コロラド州側のダイノソーから北へ入ると、地形・地質の観察ルート。車は路肩ではなく、駐車場のみに停めるように。
さらに東進して、コロラド州側のダイノソーという集落の先のビジターセンターから北へ、このモニュメントの奥深く入って、かなり長いスカイラインを進むと(図12)、全体の地形や地質を概観することができる(ただし、すでに述べたように、恐竜化石が見えるルートではない)。ここでも、そここに、地質や環境に関する案内板がある。(なお、車は、View areaとある駐車場に停め、それ以外の、一般の路肩には停めないように、と指導されている。また、制限速度は一般に速く設定されているが、決してそれを越えないように。)先の二つの背斜に挟まれた向斜部に、モエンコピ層からなる不思議な赤い島のような地形(Vivas Cake Hill と呼ばれている)が位置する(図13)。それは先のスプリット・マウンテンの東方延長の背斜の翼部が、急激に水平層へ移化するので、その部分に上位の地層が位置するようになるのだ。面白い。この島のような地形は、キャニオン・オーバールックと呼ばれるビューエリアなどから見ることができる。その他、このコロラド州側のルートでは、河川の蛇行のありさまなどや、岩相別の侵食の違いなどを観察できる。(もし、4WDがあれば、所々からグリーンリバーやその支流へ降りるルートをとることもできるが、時間がかなりかかるので、要注意である。)
公園全体の見学を終わったら、来た道を戻ろう。さらに東へ進もうとすると、これから57マイル、ガスなしなどと書いてあり、ダイノソー・ダイアモンド一周をする目的以外では、行程がかかりすぎる。ただし、コロラド州や、ユタ州南部、アリゾナ州方面へ行くと、白亜紀層を中心とした壮大な地質的景観が楽しめる(安藤・平野, 1990参照)。また、そこここに、恐竜の産地があるので、それはまた別の機会に訪れるのでもよいだろう。なお、ダイアモンドを一周するのには、少なくとも3泊4日、できれば1週間くらいの余裕がほしい。時間が許せば、モアブ近郊のアーチーズやキャニオンランズなどの国立公園、デッドホースポイント州立公園などに立ち寄ると、教科書的な堆積構造や変形構造、河川の侵食、タフォニと呼ばれる乾燥地域独特の化学的風化などを観察できる(ここは、グランド・サークルにも入っているし、モアブの北には、恐竜化石を掘らせてくれる箇所もある)。また、ダイアモンドを時計回りに回った最後の地点プライスには、博物館があるほか、6(191)号線沿いでは、稼行が続く白亜紀石炭層とその周辺の堆積や変形構造の観察もできる(安藤・平野、1990)。
図13.コロラド州側の公園ルートのキャニオン・オーバールックからの向斜軸の眺め。背斜の南翼(画面左端)で、地層の傾斜が急に水平になるために、その軸部にトリアス紀モエンコピ層の赤い島(Vivas Cake Hill)が位置する。不思議な感覚にとらわれる。
191(40)号線を西へ戻り、ローズベルトを抜け、今度は、デュシェーンから北へ87号線、さらにすぐに西へ35号線の谷沿いルートを取って、ソルトレイクシティー方面へと入ると、あたりにはゆったりとした気持ちのいい牧場が広がる。別荘を作って一生を暮したいような所だ。そこからは、ユインタ山系のシニックロードが続く。ここには、中古生代の赤色層を始め、古生代後期の石灰岩層や先カンブリア時代の地層と岩石が、一大背斜構造を作って、分布している(図14)。デュシェーンからプロヴォまでは、3時間あまり。ソルトレイクシティーへは4時間余り。すれ違う車は少ない。冬期は不可。
なお、ソルトレイクシティーには、市街東部のユタ大学キャンパスの裏の丘陵に、2011年11月、新装なったユタ大学自然史博物館が開館した。恐竜はもちろん、さまざまな地質、古生物、先住民族などの展示は、見事である。ぜひ、観覧をお薦めする。
4.テクトニクス
さて、こうした地質はどのようにしてできたのだろうか?ユタ州のハイウェイ・ジオロジカルマップ(図14.これもヒンツィー教授(1980, 1997)になるもので、全米随一との評判が高い。)をよく見ると、東西に走るユインタ山系の周囲には、古生代から中生代におよぶ地層が褶曲構造を作ってへばりついていているのが分かる。この構造は、上方へより緩やかにはなるが、第三紀層まで続いている。ということは、第三紀が始まるまでは、ユインタ山系の上昇はあまり活発ではなく(暁新世の60 Maころに始まったとは言われている。)、その堆積中に、上昇が活発化したのであろう、と推察できる。コロラド・プラトー(広義;トーにアクセントがある)の西端に発達する、白亜紀に最盛期を迎えた付加体類似のセビア・(フォールド・アンド・)スラストベルトは、このユインタ山系によって、南北に分断され、北部は、ワイオミング・(オにアクセントあり)スラストベルトとして、半ば独立している。しかし、起源的には、南北は本来連続していたに違いない。そっくりな地質だからだ。ユインタは、その後ここに闖入してきたのではないか?とも思われる。現地の地質研究者の間でも、さまざまな議論が続けられているが、先述のHintze (2005)や、Hintze and Kowallis (2009), Harris(2011)によると、初めからその萌芽があったようである。(詳しくは、別稿で述べる予定である。)
図14.ヒンツィー教授(Hintze, 1980, 1997)の手になるユタ州ハイウェイ・ジオロジカルマップの最北東部。東西に延びるサンショウウオのような異様な「かまし」が、ユインタ山系。その紫色部分は先カンブリア紀の地層と岩石。ソルトレイクシティー(最西部の赤い部分付近)まで、さらに西方へ、ネバダ州まで続いている(図17)。ユインタ山系の周囲には、主として灰色から青の石炭紀層ペルム紀層と緑色(中生の代)地層が褶曲しているのがおわかりだろう。その最東部分が、今回述べた、ダイノソー・ナショナル・モニュメントがある部分。茶色から黄色が第三紀のユインタベイスンの地層。本図の西側部分、南北性の構造が、セビア・スラストベルトとその西方のベイスン・アンド・レインジにほぼ対応する。
この地質図(大抵の国立公園や記念物のインフォーメイションセンターで購入可能)で分かるように、ユインタ山系やその周辺のこの地帯一帯には、先カンブリア時代からの地層や岩石が分布している。つまり、この周辺は、大陸基盤(17億年前とも言われる)からなる。一昔前の論文や、教科書には(また、今でも、時々使われるが)、マイオ(ミオ)ジオシンクラインまたはマイオジオクラインとされていて、長い間いわゆる非活動的大陸縁であった。広義のコロラド・プラトーの範疇でもある。古生代後期(前期は場所により欠けている)から中生代、さらに一部では新生代の前期まで、ここは、浅海ないし陸成層が淡々とたまる場所だったのである。それだから、石灰岩も、恐竜化石も出るのである。その後、コロラド・プラトーの西部を中心として、その地層や岩石の一部は、白亜紀を中心とするセビア・スラストベルトに特徴的な東西側方短縮の付加体類似の変形を受け(セビア造山運動とも呼ばれる)、さらに、プラトー全体では、第三紀の主として始新世から漸新世にかけて、高角の断層による変形(ララマイド変動)を受けたのである(Hintze and Kowallis, 2009; Harris, 2011, Fillmore, 2011)。
図15.コロラド・プラトー(広義)最東部のロッキー山脈フロントレインジ(今回はふれてない)を東西に(上図)、ユインタ山系を南北に(下図)切る断面図。下図の左方、Split Mountainとあるところの青から緑色の褶曲部分が、今回のダイノソーの場所に相当する。断層が、高角(Thick-skinned)か(基盤の運動による)、低角(Thin-skinned)か(基盤を含むこともあるが、最下底でほぼ水平のいわゆるデタッチメント断層(デコルマンとほぼ同義))は、絶えず議論されている。地表の調査だけでは決着がつかない。モホまで見えるサイズミック・プロファイルが必要だ。結果的には、ここは、高角断層が支配する、いわゆるララマイド変動を受けて上昇したと解釈されている。
こうして、コロラド・プラトーでは、それ以前のほぼ水平な地質構造(若干北に緩く傾斜する。それゆえ、グランド・ステアケースと呼ばれる、巨大な階段状の地形を作っているのだが)に、ララマイド変動と呼ばれる、高角の断層運動が重なっている。(それが始まるのは、古くは60 Ma頃とされている。)その後、この運動は、始新世から漸新世にかけて(Fillmore, 2011; Harris, 2011)、いわゆる基盤の断層運動(全体的には北東―南西圧縮)として活発化した。でも、どうして、ユインタ山系は、それ以外の北米の構造方向がほぼ南北なのにもかかわらず、直交に東西に割って入ったのか?との疑問は残ろう。ヒンツィー教授も考えたのだろう。ここは、もともと東西に延びるオラーコジンだった?と思いついたに違いない。その解釈に至った図を最後に載せよう(図16, 17)。
オラーコジンは、国際的には有名な用語だ。フェイルド・リフトを聞いたことがある人も多かろうが、アフリカと南アメリカが白亜紀に開き始めたときに、三重点をつくって120度で開こうとしたが、アフリカ側は、あまりうまくいかず、途中で開くのをやめてしまった。それが、オラーコジンの好例である。超大陸ロディニアの拡大時(約9億年前)のオラーコジンに、先カンブリア時代末期の地層(氷河の堆積物、ティライトもある)と中古生代の地層がたまったのが、ユインタ山系に見られる層序だ(図16,17)。特に、ユインタ山系のある場所では、そのフェイルド・リフト内部の盆地に堆積物が厚くたまっていたが、その後の第三紀中の側方圧縮によって、インバージョン・テクトニクスが生じ、逆に隆起したのであるという。また、この変動によって、プラトー各地では表層部にさまざまな褶曲や岩塩ドームの構造を作るなどしたことが、この地域(広義のコロラド・プラトー)の特徴である。詳しくは別に報告する予定であるが、ユインタ山系とこのダイノソー・ナショナル・モニュメント周辺の構造形成も、こうした先カンブリア時代末期からの長い地質時代からの状況を受け継ぎつつ、最後は、第三紀を中心とするララマイド変動による結果の一部であるといえる。
図16.超大陸ロディニアの分裂時(約9億年前)、ユインタはここだった?(赤枠)(Hintze, 2005による)。
図17.ユタ州の北部を東西に走る先カンブリア時代末期の岩石の分布。(Hintze, 2005による)。フェイルド・リフトを実感させる。
5.あとがき
アメリカは広大で、かつ自然がすばらしい。さらに、それを国民全体で保護また見学しよう、との意識が強い。日本では、最近特に、世界遺産への関心が強いように見受けられるが、アメリカでは、国民から見た、国立公園運動がむしろ盛んである。国民の多くが、自然と自然に親しむようになっていて、さまざまなナチュラリストも多い(その草分けは、トルストイやガンジーなどへも絶大な影響を与えたと言われている、ヘンリー・デイビッド・ソウロウである)。各国立公園や国立記念物には、ビジターセンターがあって、内容が充実しており、レインジャーが常駐して、専門的な質問にも対応している。地質の書物や地質図なども売っている。多くのアメリカの家族が、こうした個所を頻繁に訪れて、家族ぐるみで自然に学び、親しんでいる。
図18.このような展示や構造物で、必要かつ十分ではないだろうか?説明のレベルも、高すぎず、低すぎず... ジェンセン東方の40号線に沿うView areaで。遠景は、ペルム紀のWeber砂岩層の背斜の翼部。
ホテルやレストランなどにも、地質図が掲げられていることも多い。また、さまざまな地点に、地質や地形の説明が、さりげなく置かれている。このようなことは、イギリス(ナショナル・トラスト運動が盛んである)や、ドイツ、スイスなどのヨーロッパ諸国でも、普通に見受けられる。これらは、特に、巨額の予算を必要とはしないと思われる。日本では、学会を上げての、ジオパーク運動も盛んである。さらに、高校生のための国際地学オリンピックへの関心も高く、好成績を残してもいる。環境問題や、資源・エネルギー問題、地震・火山・津波・洪水・地すべりなどの自然災害防止や軽減などについての国民の関心も高い。それらの現象の多くは、地質的なものである。しかし、地質への理解が国民のものになっているか、と考えると、まだ不十分と言わざるを得ない。まずは、アメリカやヨーロッパに見習って、簡単で、しかも効果のあがる方策を実行すべきではないだろうか?最後は、お説教になってしまったが、簡単な一例を以下の図18にあげて、終わりとする。(内容、構成に関して、ブリガム・ヤング大学のRon Harris教授にご教示いただいた。末筆ながら記して感謝したい。)
【文献】
安藤寿男・平野弘道 (1990) 第28回IGC野外巡検「ユタ・コロラド・ニューメキシコ州Western Interior Basinにおける白亜系陸棚砂岩層と陸棚堆積シークエンス」に参加して.堆積学研究会報, 33号, p. 79-86.
Fillmore, R. (2011) Geological evolution of the Colorado plateau of eastern Utah and western Colorado. University of Utah Press, 496pp.
Harris, R. (2011) Exploring the geology of Little Cottonwood Canyon, Utah. The greatest story ever told by nine miles of rock. Brigham Young University Press, Utah, USA. 80pp.
Hintze, L. F. (1997) Geologic highway map of Utah. Department of Geology, Brigham Young University, Provo, Utah.
Hintze, L. F. (2005) Utah’s spectacular geology. Brigham Young University Press. 203pp.
Hintze, L. F. and Kowallis, B.J. (2009) Geologic history of Utah. Brigham Young University Press, Utah, USA. 225pp.
(2011.11.11)
本稿投稿後、以下の様な地質断面図を入手した(USGS, 1966)。それによると、今回紹介した複背斜構造は、本文で述べた通り、より大規模なユインタ背斜(ユインタ山系を作る)の南側の従属的構造であり、高角の逆断層伴って発達する褶曲である。
付図1では、差し渡し40マイル以上に及ぶ緩やかな背斜構造(ユインタ背斜)が見えるが、その南半分には、ダイノソー国立記念物を占めるスプリット・マウンテン複背斜が顕著であることが分かる。その拡大が付図2であり、これで分かるように、断層近くでは、地層の傾斜の急変が著しく、場所によりモノクライン状になる。それゆえ、ほぼ直立する地層が、突然ほぼ水平に変わる場所もある。深部で高角、浅部で一部低角になる逆断層構造と解釈されており、それに伴う褶曲構造とともに、いわゆるララマイド変動の特徴として、コロラド・プラトーのあちこちに発達する。
付図1.USGS (1966)による、地質断面図。上の断面図は、コロラド州側、下はユタ州側(右側が南)。
付図2.1の南半分の拡大図。
【追加文献】
USGS (1966) Topographic map of Dinosaur National Monument (1: 62,500).
National Geographic (1989) Outdoor recreation map (1:75,000), Dinosaur.
(その他の諸注意)
すでに、本文でも若干注意事項を述べたが、「アメリカの国立公園」にもあるように、外国からの訪問者は現地の法律や規則、習慣を守るようにしたい。また、交通ルールや道路走行方法なども、日本とかなり異なる場合が多いので、絶対に事故のないように、十分に気をつけられたい。また、路肩や駐車禁止のところには、絶対に停めないように。なお、今回報告した場所を含めて、アメリカの多くの個所が、高所(1500〜2000 m前後)にあり、空気が希薄な上に、紫外線が強く、また乾燥している。日中と朝晩の気温差も大きい。さらに、到着後しばらくは時差の関係で、睡魔に陥りやすい。そのような条件での長距離の移動には、無理な行動は慎みたい。
No.160 2011/11/25(臨時) geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.160 2011/11/25 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2012年度代議員選挙の投票が開始されます(投票期間11/28〜2012/1/5)
【2】その他のお知らせ
【3】2012年度学会各賞募集中
【4】2012年度会費払込/学部学生・院生割引申請受付中
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2012年度代議員選挙の投票が開始されます(投票期間11/28〜2012/1/5)
──────────────────────────────────
表記選挙については11月10日に立候補が締め切られました。今回は、
全国区への立候補者は定数未満の95名(定数100名)、地方支部区にお
いては立候補者数合計88名(合計定数100名)、各支部区とも定数を超
える立候補者がありませんでしたので、全員が当選となります。
ただし、地方支部区については、支部枠理事を選出するために順位
付けが必要ですので,そのための投票を行います。
また、学会の代表理事となる会長およびその補佐役の副会長を選出す
るにあたり,会員の意向を伺うために、投票による意向調査を行います。
既に投票用紙、会長立候補者らのマニュフェスト等は会員各位に郵送
いたしましたので、早い方は既にお手元に届いているころかと思います。
選挙に関するスケジュールは以下のとおりです。
詳細は、郵送物、News誌11月号及びHPなどをご覧ください。
投票はお早めに、多くの会員が投票くださいますようご協力をお願い
いたします。
【投票期間】 11月28日(月)〜2012年1月5日(木)、消印有効
【選挙活動期間】 11月28日(月)〜12月18日(日)
【開票日】 1月13日(金)
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/members/content0059.html
○会員番号・パスワードによるログインが必要です。
一般社団法人日本地質学会選挙管理委員会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■千葉県立中央博物館秋の展示「砂のふしぎ」
砂の液状化などいろいろな性質について紹介しています。
主な展示項目:砂って何?,砂のいろいろ,砂の模様,砂の科学,砂のある風景
【会場】千葉県立中央博物館 本館 企画展示室
【会期】2011年10月1日(土)〜12月4日(日)
【開館時間】9:00〜16:30 (入館は16:00まで)
【休館日】毎週月曜日
【入場料】一般300円(240円)・高大学生150円(120円)
(カッコ内は20名以上の団体料金)
※次の方は入場料が無料です。中学生以下/65歳以上の方(年齢を示すもの
をご提示ください)/身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳
をお持ちの方とその介護者(手帳をご提示ください)
【お問合せ先】
〒260-8682 千葉市中央区青葉町955-2 (青葉の森公園内)
千葉県立中央博物館
[電話] 043 265 3111(代表)[ファクス] 043 266 2481
ホームページ:http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2012年度学会各賞募集中
──────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして、研究の援助・奨励および研究
業績の表彰を行っています(定款第3条)。本年も各賞の自薦、他薦による
候補者を募集いたします。
期日厳守にて、たくさんのご応募をお待ちしております。
応募締切:2011年12月26日(月)必着
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
○会員番号・パスワードによるログインが必要です。
○「会員のページ」の各賞推薦候補者募集に関する案内から、推薦書式等が
ダウンロードできるようになっています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2012年度会費払込/学部学生・院生割引申請受付中
──────────────────────────────────
■2012年度会費払込について
次年度分会費の前納をお願いいたします。自動引き落としを登録されている
方の引き落としは、12月26日(月)です。お振込の方へは、12月中旬頃まで
に請求書兼郵便振替用紙をお送りいたします。
詳しくは、 https://www.geosociety.jp/user.php(会員番号によるログイン
が必要です)
■2012年度(2012.4〜2013.3)学部学生・院生割引申請受付中
最終締切日:2012年3月30日(金)
申請書を毎年ご提出いただかなければ割引会費は継続されていきませんので、
くれぐれもご注意下さい。
一次締切日(11月16日)までに申請書をご提出いただけなかった学部学生・
院生のかたに対しては、一旦【正会員】の金額にて請求書を発行(引落のかた
は12月26日に自動引落)いたします。
割引会費を希望する学部学生・院生のかたは、必ず最終締切までに申請書の
提出をして下さい。あわせて12月に発行する請求書(=郵便振替用紙)の金
額を訂正し、2012年度会費をご送金ください(郵便振替用紙の再発行はいた
しません)。
申請書のダウンロードは、
https://www.geosociety.jp/user.php(会員番号によるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。 geo-Flashは、
月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日 までに
事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.161 2011/12/6 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.161 2011/12/6 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】コラム:アメリカ合衆国ユタ・コロラド州境界、ダイノソー・ナショナル・モニュメントとユインタ山系の地質概略(紹介)(後編)
【2】2012年度代議員選挙の投票受付中です 締切:2012年1月5日(木)消印有効
【3】第4回日本地学オリンピック 参加応募総数過去最高
【4】2012年度学会各賞募集中 締切:12月26日(月)
【5】2012年度会費払込/学部学生・院生割引申請受付中
【6】地質図の在庫一掃セール!― 第二弾! 12月6日〜12月25日
【7】支部・専門部会情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】コラム:アメリカ合衆国ユタ・コロラド州境界、ダイノソー・ナショナル・
モニュメントとユインタ山系の地質概略(紹介)(後編)
──────────────────────────────────
小川勇二郎(ユタ州プロヴォ、ブリガム・ヤング大学)
<後編は"コロラド州側の地形と地質"から>
さらに東進して、コロラド州側のダイノソーという集落の先のビジターセン
ターから北へ、このモニュメントの奥深く入って、かなり長いスカイライン
を進むと、全体の地形や地質を概観することができる。ここでも、そここに、
地質や環境に関する案内板がある。先の二つの背斜に挟まれた向斜部に、
モエンコピ層からなる不思議な赤い島のような地形が位置する。それは先の
スプリット・マウンテンの東方延長の背斜の翼部が、急激に水平層へ移化す
るので、その部分に上位の地層が位置するようになるのだ。面白い。この島
のような地形は、キャニオン・オーバールックと呼ばれるビューエリアなど
から見ることができる。その他、このコロラド州側のルートでは、河川の蛇
行のありさまなどや、岩相別の侵食の違いなどを観察できる。(一部略)
続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0346.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2012年度代議員選挙の投票受付中です 締切:2012年1月5日(木)消印有効
──────────────────────────────────
投票用紙、会長立候補者らのマニフェスト等は会員各位に郵送いたしました。
選挙に関するスケジュールは以下の通りです。
詳細は、郵送物、News誌11月号及びHPなどをご覧ください。
投票はお早めに、多くの会員が投票してくださいますようご協力をお願いいた
します。
【投票期間】 11月28日(月)〜2012年1月5日(木)消印有効
【選挙活動期間】11月28日(月)〜12月18日(日)
【開票日】 1月13日(金) 午前10時から 地質学会事務局
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0059.html
○会員番号・パスワードによるログインが必要です。
(ログインの方法は http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html)
―訂正:代議員選挙(地方支部区)立候補者リストの訂正とお詫び―
皆さまにお送りした書類に一部誤りがありましたので、ここに訂正し、
お詫びいたします。
■代議員選挙(地方支部区)立候補者リストの訂正
【代議員選挙の地方支部区(中部支部)】
13番 長谷部徳子会員 氏名
(誤)長谷 部徳子
(正)長谷部 徳子
2011年12月1日
日本地質学会選挙管理委員会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】第4回日本地学オリンピック 参加応募総数過去最高
──────────────────────────────────
11月15日に締め切られた第4回日本地学オリンピック参加の応募総数は過去最高
の924名となりました。昨年は869名でした。
12月18日に全国の会場で予選(筆記試験)が行われ、選抜された20数名が来年3月
25日から27日につくば市で実施される本選(グランプリ地球にわくわく)に
臨みます。本選では実技試験(筑波大学会場)が実施され、産業技術総合研究所や
防災技術研究所などから派遣された講師による「とっぷレクチャー」(一般市民
聴講可)が開催されます。なお来年の国際大会はアルゼンチン(ブエノスアイレ
ス)で10月に開催される予定です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2012年度学会各賞募集中 締切:12月26日(月)
──────────────────────────────────
各賞の自薦、他薦による候補者を募集しています。
期日厳守にて、たくさんのご応募をお待ちしております。
応募締切:2011年12月26日(月)必着
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
○会員番号・パスワードによるログインが必要です。
(ログインの方法は http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html)
○「会員のページ」の各賞推薦候補者募集に関する案内から、推薦書式等が
ダウンロードできます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2012年度会費払込/学部学生・院生割引申請受付中
──────────────────────────────────
■2012年度会費払込について
次年度分会費の前納をお願いいたします。自動引き落としを登録されている
方の引き落としは、12月26日(月)です。お振込の方へは、12月中旬頃まで
に請求書兼郵便振替用紙をお送りいたします。
詳しくは、 https://www.geosociety.jp/user.php
(会員番号によるログインが必要です。
ログインの方法は http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html)
■2012年度(2012.4〜2013.3)学部学生・院生割引申請受付中
最終締切日:2012年3月30日(金)
申請書を毎年ご提出いただかなければ割引会費は継続されていきませんので、
くれぐれもご注意下さい。
一次締切日(11月16日)までに申請書をご提出いただけなかった学部学生・
院生のかたに対しては、一旦【正会員】の金額にて請求書を発行(引落のかた
は12月26日に自動引落)いたします。
割引会費を希望する学部学生・院生のかたは、必ず最終締切までに申請書の
提出をして下さい。あわせて12月に発行する請求書(=郵便振替用紙)の金
額を訂正し、2012年度会費をご送金ください(郵便振替用紙の再発行はいた
しません)。
申請書のダウンロードは、
https://www.geosociety.jp/user.php(会員番号によるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質図の在庫一掃セール!― 第二弾! 12月6日〜12月25日
──────────────────────────────────
現在、地質学会に在庫があるものについてのみ、特別販売いたします。
最新の在庫リストはホームページに掲載していますのでご覧いただくか、
事務局(電話:03-5823-1150)にお尋ねください。
ご注文はE-mail(main@geosociety.jp)またはFax(03-5823-1156)でお願い
いたします。 種類と数に限りがありますので、ご注文は先着順といたします。
リストにないもの、追加等のご注文には応じられませんのでご了承ください。
なお、第二弾のセールの期間は、12月6日〜12月25日までといたします。
特別価格の詳細はご注文の際に地質学会事務局にお問い合わせください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部・専門部会情報
──────────────────────────────────
■東北支部:2009〜2010年度総会,個人講演会
日時:2011年12月17日(土)〜18日(日)
場所:福島大学共生システム理工学類後援募金記念棟
2011年12月17日(土)
13:00-14:00 東北支部2009〜2010年度総会
14:15-15:45 2013年仙台大会にむけて
16:00-17:00 個人講演(口頭発表プログラム)
ベトナム・ドンタップ省タイ島における地下水ヒ素汚染分布についての3次元
地下水シミュレーション解析:佐藤真一(福島大学大学院)・柴崎直明(福島
大学)・メコン川流域地下水ヒ素汚染研究グループ
「ホットスポットの位置は変わらない」のか?:星 博幸(愛知教育大学)
東日本巨大地震のプレートダイナミクス:新妻信明(静岡大学,仙台)
18:00- 懇親会
2011年12月18日(日)
9:00-11:00 個人講演(口頭発表プログラム)
11:00-12:00 ポスター発表コアタイム
山形大学に移設したICP質量分析計を用いたREE分析の際の濃度計算に
ついて:渡辺翔太*・大泉涼・渡邉沙織・伴雅雄・岩田尚能・加々島慎一・中島
和夫(山形大学,*現在筑波大)
山形盆地周辺に分布する約10〜8Maの珪長質火山噴出物の岩石学的特徴:道上
惟史・伴雅雄(山形大学)
12:00 解散
■関東支部:秩父ジオパーク「秩父札所のジオめぐり」(関東支部後援)
○秩父札所をめぐり荒川がつくった段丘を見る
日時: 2011年12月11日(日) 9:30〜16:00
問合せ:小幡喜一 電話:0494-23-4606、obata.k@kumagaya-h.spec.ed.jp
詳細はこちらから、、、
http://www.geocities.jp/obt_kk/geo_park/event.html
■西日本支部:平成23年度総会・第162回例会
日時:2012年2月11日(土)
場所:鹿児島大学郡元キャンパス
同日夕刻に懇親会を、前日(2月10日(金))夕刻に幹事会を催す予定です。
他、詳細は追ってお伝えします。
問合先 :西日本支部庶務:宮本知治 miyamoto@geo.kyushu-u.ac.jp
■構造地質部会緊急例会「社会への発信とリテラシー」
東日本大震災後,地球科学と社会との関わりを考え直すべきときが来ている
のではないか?という問いから,今回の緊急例会を企画いたしました.
地球科学の理解がかつてないほど必要とされているこの時代に,どのように
その必要性を発信して行くべきでしょうか?
地球科学リテラシーの向上のためのアウトリーチのあり方などを構造地質を
専門とする研究者が集い,考える会にしたいと思っております.
日時:2012年3月17日(土)、18日(日)
場所:東北大学理学部
詳しくは、、、
http://struct.geosociety.jp/SGMeeting2012/SGMeeting2012/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第1回アジア・アフリカ鉱物資源会議
(Asia Africa Mineral Resources Conference 2011)
日時:2011年12月8日(木) 会議および懇親会
12月9日〜11日:フィールド巡検(菱刈鉱山、春日鉱山など)
場所:九州大学伊都キャンパス 稲盛ホール
主催:九州大学地球資源システム工学部門
後援:独立行政法人日本学術振興会
レアメタルなどの鉱物資源開発における最近の成果やアジア・アフリカ地域の
鉱物資源のポテンシャルなどについて発表・議論することを目的としています。
使用言語は英語です。
詳細は http://xrd.mine.kyushu-u.ac.jp/AsiaAfrica_seminar.html
■社会地質学会シンポジウム
「利根川中・下流域の液状化・流動化・地波現象
−人工改変地と液状化地域・安全な街づくりを考える−」
日時:2011年12月18日(日)10:00〜17:00
場所:茨城県潮来市立中央公民館(潮来市日の出)
参加費:無料・(別途資料代:1,000 円)
プログラムなど詳細は、
http://www.npo-geopol.or.jp/files/sympo_21.pdf
■第10回地球システム・地球進化ニューイヤースクール(関西初開催)
「移動から始まる世界 〜地球の中から外まで〜」
日時: 2012年1月7日(土)〜8日(日)
場所:大阪大学豊中キャンパス 大阪大学会館
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/toyonaka.html
https://55099zzwd.coop.osaka-u.ac.jp/daigaku-hall/
参加費:3500円(懇親会費込み)
申込締切:2011年12月16日(金)
詳しくは、
http://discovery.ess.sci.osaka-u.ac.jp/~earth21/school/2011/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■京都大学大学院:理学研究科地球惑星科学専攻地球物理学分野(教授)(2/17)
■国立科学博物館:地学研究部(研究員)(1/23)
■様似町職員(学芸員)(12/22)
■徳島大学大学院:ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部
基礎科学研究部門 自然科学分野(准教授または講師) (12/1/12)
■九州大学大学院:理学研究院地球惑星科学部門あるいは化学部門
(准教授または助教) (12/16)
■第39回「環境賞」候補の募集(1/20)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。 geo-Flashは、
月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日 までに
事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.162 2011/12/20 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.162 2011/12/20 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】コラム:中国と日本のジオパーク
【2】本の紹介:「東北アジア 大地のつながり」石渡 明・磯崎行雄 著
【3】2012年度代議員選挙の投票受付中です 締切:2012年1月5日(木)消印有効
【4】2012年度学会各賞募集〆切迫る!:12月26日(月)
【5】2012年度会費払込/学部学生・院生割引申請受付中
【6】地質図の在庫一掃セール!― 第二弾! 12月6日〜12月25日
【7】支部・専門部会情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】コラム:中国と日本のジオパーク
──────────────────────────────────
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
国際地質科学連合(IUGS)の機関誌Episodesの最新号に中国のジオパーク
についての記事が出た(Yang et al. 2011).これは非常に内容の濃い,示
唆に富む優れたまとめであり,表と写真を交互に参照しながら読みふけって
しまった.中国と日本のジオパークを比べて,感じたこと,気がついたこと
を述べてみたい.
続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0350.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】本の紹介:「東北アジア 大地のつながり」石渡 明・磯崎行雄 著
──────────────────────────────────
東北大学出版会 2011年12月3日発行
四六判 94ページ、ISBN978-4-86163-178-8
定価本体2,000円+税
小冊子ながら、東北アジアと日本との地質について、手際よくまとめられた好著が発行された。内容は、東北大学東北アジア研究センターが2009年12月に仙台市で行われた市民向けの公開講演会「日本と東北アジア 大地のつながり」に基づいたものである。著者のお二人は、そのときの演者である。
本書の内容は2部に分けられており、「1 日本と中国・朝鮮の地質のつながり」を磯粼氏が、「2 日本とロシア東部の地質のつながり」を石渡氏が担当された。
1部は11の章に分かれており、日本列島の地質学的特徴とその形成史について自説に沿って説かれている。ここでは、日本列島が4つのプレートからなり、形成年代や構成岩石の異なった複数の地帯から構成されていること、アジア大陸の東縁にあたるプレートの沈み込みの地帯「太平洋型大陸縁」に属すること、そのため地震の多発地帯であり、断層が多く発達している活動的な場所であること、したがって日本のどこでも大きな地震災害に見舞われる可能性が指摘されている。日本列島の誕生は、古生代末のパンゲアよりも一世代前のロディニア超大陸の分裂に関係していること、そしてこのような超大陸の分裂はマントルに由来するスーパープルームに起因するという。このプルームによって現在の中国と北米大陸との間に太平洋が生まれた。その後、反対側で別の海(古大西洋)が生まれたため、太平洋側では収縮が始まり、現在のアジア東部の大陸縁は太平洋型の沈み込みとなった。その後は、海溝に溜まった堆積物が付加体として次々に大陸縁に貼り付いて成長し続けている。この大陸縁に軒先を借りていたのが日本列島なので、その母屋にあたる中国の地質を理解することがすなわち日本列島の地質の発達を理解することになる。日本列島の中で、能登半島、日立、山陰や隠岐などに中国大陸のものと類似する変成岩が産出すること、日本列島はそのほぼ8割が付加体であり、緩く傾斜する板状の付加体が下から貼り付いているために,古い付加体ほど上部を占めていること、などが示されている。
ところで、東アジア地域では、北中国と南中国のブロックが衝突し、大規模な山脈を生じ、南中国が北中国の下に緩くもぐり込んだ。北中国の地質に相当するものが、朝鮮半島南部から山陰の海岸や隠岐、飛騨へと続く。一方で、日立、飛騨山地東部、九州北部などには南中国の延長と考えられる岩石が分布し、日本列島の大部分は南中国に対応するというという著者の考えが述べられている。
最後に日本列島の将来について、現在のプレートの動きがこのまま続けば、5千年後には南半球のオーストラリアが北上し、パプア・ニューギニアやフィリピンを抱き込みながら日本と衝突するだろうこと、さらに2億5千万年後には北アメリカが日本に衝突して,太平洋はなくなり、日本は完全に大陸に取り込まれてしまうとの予測をしている。この将来の仮想的大陸はアメイジアと名付けられた。
石渡氏担当の2部は23の章から成り立っている。本論に入る前に、大陸地殻と海洋地殻に関しての説明があり、マントルの上に浮いている地殻は大陸移動が行われ、それらの証拠となったのは、海洋底に残された地磁気の逆転現象とその結果生じた縞模様であることが解説されている。
本論では、大陸と日本との間に生じた日本海の成因に関して重要な役割を果たしたマントルプルームについて、また大洋および縁海の形成年代についての詳しい説明が続く。新しい火山のタイプとしてのプチスポットも紹介されている。そして、日本海が開いて日本列島がアジアから分離したとの考えは、かつて寺田寅彦が発表し、小林貞一によって化石の証拠から支持されたことも紹介されている。日本海の拡大に関して、「裂開漂移モデル」があり、これには「引き裂き(プルアパート)モデル」と「回転(観音開き)モデル」の2つがあるが、いずれにしても日本列島と沿海州(沿海地方というのが正しいとのこと)との地質学的な類似性を見いだす必要があり、そのための苦闘が続く。調査地は高緯度であり、治安もあまり良くなく、ときどき虎が出たりするといったエピソードも盛り込まれている。これまでに、西南日本内帯に分布する中生代ジュラ紀から白亜紀にかけての付加体の分布がロシア沿海州にかけて整然と続いていることが判明していた。著者の石渡氏は、付加体が日本とロシアの間で続くならば、オフィオライトも続くであろうとの見通しのもとに、沿海州、サハリン、カムチャツカ半島北方、コリヤーク山地にわたる調査を続けた。読者のためにオフィオライトとは何かの説明を加え、近畿地方西南日本内帯の先白亜系オフィオライトと沿海州、コリヤーク山地のオフィオライトの類似性を述べている。
さらに、環太平洋型造山帯と衝突型造山帯との関係、それらに由来する砂岩の特徴、中国の大陸衝突型造山帯と日本の地質との関係について、著者の考えが述べられている。また、一般市民向けという目的故であろう、金鉱床との関連や地質調査を行っている際の一般人の反応など、著者自身の経験をもとにした感想も最後に述べられている。
中国・ロシアと日本列島の間の地質学的連続性に関しては、著者の間での見解の相違があるようで、八重山諸島の石垣島の地質が中国の衝突型造山帯の延長である可能性が指摘されているが、本書の中では詳しくは言及されていない。
一般市民向けの公開講座ということで、講演後の質疑応答も臨場感があってたいへん興味深い。原発立地などに関しても質疑があった。 最後に、本稿執筆後に東日本大震災が起こり、それは現実にプレートの動きがダイナミックに我々の前に現れたものであること、地道な地質学者の活動にももっと目を向けて欲しいといった感想が述べられている。このことは紹介者も全く同感であり、地質学者の側からのこのような講演や書物をとおしての啓蒙・普及活動も重要な責務であろう。
限られたページ数に、こういった先端的な内容まで詳しく盛り込むことはかなり困難であったと推察される。お二人の著者がそれぞれ独自に執筆されたらしく、ウェゲナーの紹介やプルームの説明など、重複しているところもあり、引用された一部図版の説明が専門家向きで、一般読者にはやや分かり難いところもあるとはいえ、本書が市民の目に触れて、地質学の重要性を理解してもらうには格好の著書である。
全体としてたいへん良くできており、一般市民のみならず、異なる専門分野の本会会員が東北アジアと日本の関連を知るため、あるいは大学初年生の入門書としても充分にその機能を果たし得るものである。これは出版社の問題であろうが、上述の目的達成のために、もう少し求めやすい価格に設定して欲しかった。
(蟹澤聰史)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2012年度代議員選挙の投票受付中です 締切:2012年1月5日(木)消印有効
──────────────────────────────────
現在、代議員選挙の投票を受付中です。
選挙に関するスケジュールは以下の通りです。
詳細は、11月下旬にお送りした郵送物、News誌11月号及びHPなどをご覧ください
(立候補者名簿・マニフェストなどは学会HPでもご覧いただけます)。
投票はお早めに、多くの会員が投票してくださいますようご協力をお願いいた
します。
【投票期間】 11月28日(月)〜2012年1月5日(木)消印有効
【選挙活動期間】11月28日(月)〜12月18日(日)
【開票日】 1月13日(金) 午前10時から 地質学会事務局
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0059.html
○会員番号・パスワードによるログインが必要です。
(ログインの方法は http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html)
2011年12月1日
日本地質学会選挙管理委員会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2012年度学会各賞募集〆切迫る!:12月26日(月)
──────────────────────────────────
日本地質学会各賞の推薦締め切りが迫っています。
是非たくさんの候補者並びに候補論文を、各賞選考委員会(学会事務局
main@geosociety.jp)宛にご推薦下さいますよう、何卒よろしくお願い
いたします。
応募締切:2011年12月26日(月)必着
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
○会員番号・パスワードによるログインが必要です。
(ログインの方法は http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html)
○「会員のページ」の各賞推薦候補者募集に関する案内から、推薦書式等が
ダウンロードできます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2012年度会費払込/学部学生・院生割引申請受付中
──────────────────────────────────
■2012年度会費払込について
次年度分会費の前納をお願いいたします。自動引き落としを登録されている
方の引き落としは、12月26日(月)です。お振込の方へは、請求書 兼 郵便
振替用紙を、12月19日に発送いたしました。お手元に届きましたら、ご送金
をお願いします。
詳しくは、 https://www.geosociety.jp/user.php
(会員番号によるログインが必要です。
ログインの方法は http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html)
■2012年度(2012.4〜2013.3)学部学生・院生割引申請受付中
最終締切日:2012年3月30日(金)
申請書を毎年ご提出いただかなければ割引会費は継続されていきませんので、
くれぐれもご注意下さい。
一次締切日(11月16日)までに申請書をご提出いただけなかった学部学生・
院生のかたに対しては、一旦【正会員】の金額にて請求書を発行(引落のかた
は12月26日に自動引落)いたします。
割引会費を希望する学部学生・院生のかたは、必ず最終締切までに申請書の
提出をして下さい。あわせて、請求書(=郵便振替用紙)の金額を訂正し、
2012年度会費をご送金ください(郵便振替用紙の再発行はいたしません)。
※郵便振替にて送金されるかたへ※
請求書に同封されている会費請求案内(黄色の用紙)の裏面に割引会費の
申請書が印刷されていますので、ご利用ください。
申請書のダウンロードは、
https://www.geosociety.jp/user.php(会員番号によるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質図の在庫一掃セール!― 第二弾! 12月6日〜12月25日
──────────────────────────────────
現在、地質学会に在庫があるものについてのみ、特別販売いたします。
最新の在庫リストはホームページに掲載していますのでご覧いただくか、
事務局(電話:03-5823-1150)にお尋ねください。
ご注文はE-mail(main@geosociety.jp)またはFax(03-5823-1156)でお願い
いたします。 種類と数に限りがありますので、ご注文は先着順といたします。
リストにないもの、追加等のご注文には応じられませんのでご了承ください。
なお、第二弾のセールの期間は、12月6日〜12月25日までといたします。
特別価格の詳細はご注文の際に地質学会事務局にお問い合わせください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部・専門部会情報
──────────────────────────────────
■西日本支部:平成23年度総会・第162回例会
日時:2012年2月11日(土)
場所:鹿児島大学郡元キャンパス
同日夕刻に懇親会を、前日(2月10日(金))夕刻に幹事会を催す予定です。
他、詳細は追ってお伝えします。
問合先 :西日本支部庶務:宮本知治 miyamoto@geo.kyushu-u.ac.jp
■構造地質部会緊急例会「社会への発信とリテラシー」
東日本大震災後,地球科学と社会との関わりを考え直すべきときが来ている
のではないか?という問いから,今回の緊急例会を企画いたしました.
地球科学の理解がかつてないほど必要とされているこの時代に,どのように
その必要性を発信して行くべきでしょうか?
地球科学リテラシーの向上のためのアウトリーチのあり方などを構造地質を
専門とする研究者が集い,考える会にしたいと思っております.
日時:2012年3月17日(土)、18日(日)
場所:東北大学理学部
詳しくは、、、
http://struct.geosociety.jp/SGMeeting2012/Top.html
参加登録も開始いたしました。締め切りは2012年2月22日です。
http://struct.geosociety.jp/SGMeeting2012/can_jia_deng_lu.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■高校生のための先進的科学技術体験合宿プログラム
「スプリング・サイエンスキャンプ 2012」参加者募集
サイエンスキャンプは、3月下旬の春休み期間中、先進的な研究テーマに取り
組んでいる日本各地の大学、公的研究機関、民間企業等(18会場)を会場と
して、第一線で活躍する研究者・技術者から本格的な講義・実験・実習が受
けることができる、高校生のための科学技術体験合宿プログラムです。
今年度より3泊4日以上の探究・深化型プログラム「サイエンスキャンプDX」
が加わり、さらに充実した内容で実施します。
開 催 日:2012年3月17日〜3月29日の期間中の2泊3日〜3泊4日
対 象:高等学校、中等教育学校後期課程または専門学校(1〜3学年)
会 場:大学、公的研究機関、民間企業等(18会場)
定 員:受け入れ会場ごとに8〜40名 (計283名)※前年度平均応募倍率2.5倍
参 加 費:無料(自宅と会場間の往復交通費は自己負担。宿舎・食事は用意します)
応募締切:2012年1月24日(火)郵送必着
主 催:独立行政法人 科学技術振興機構
共 催:受入実施機関
応募方法:Webより募集要項・参加申込書を入手し、
必要事項を記入の上事務局宛郵送
URL:http://ppd.jsf.or.jp/camp/
応募・問い合わせ先:サイエンスキャンプ本部事務局
(公財)日本科学技術振興財団 振興事業部内
TEL:03-3212-2454 FAX:03-3212-0014
E-mail:camp@jsf.or.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■産業技術総合研究所 ポスドク(イノベーションスクール生)募集(20名程度)(1/22)
■山梨大学教育人間科学部理科教育講座(教授または准教授)(2/29)
■名古屋大学年代測定総合研究センター新年代測定法開発研究分野(教授)(1/31必着)
■三菱財団 平成24年度助成金公募(第43回自然科学研究助成)(2/3必着)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。 geo-Flashは、
月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日 までに
事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
中国と日本のジオパーク
中国と日本のジオパーク
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
図1.2011年現在の中国と日本のジオパークの分布
国際地質科学連合(IUGS)の機関誌Episodesの最新号に中国のジオパークについての記事が出た(Yang et al. 2011).これは非常に内容の濃い,示唆に富む優れたまとめであり,表と写真を交互に参照しながら読みふけってしまった.中国と日本のジオパークを比べて,感じたこと,気がついたことを述べてみたい.
まずジオパークの歴史を簡単に振り返る.1996年に北京で開催された万国地質学会議IGCでジオパークについて初めて国際的に議論され,翌1997年にユネスコ・ジオパーク計画が提唱された.当時のユネスコ地球科学部長のWolfgang Eder氏はジオパークの父と呼ばれる(佃, 2007).2000年頃に欧州と中国のジオパーク・ネットワークが成立し,ジオパークの設置と運用が始まった.2004年に第1回国際ユネスコ・ジオーパーク会議が中国で開催され,欧州と中国を立ち上げメンバーとして世界ジオパーク・ネットワークが成立した(加藤ほか編, 2010).日本では,2004年に故大矢 暁氏,岩松 暉氏,波田重熙氏らによってジオパーク設立活動が始まり,2007年に日本地質学会ジオパーク委員会が設立され,産業技術総合研究所を中心に設立運動が高まった.そして2009年に日本最初の3つの世界ジオパーク(洞爺湖有珠山,糸魚川,島原半島)が認定された.その後2011年末の現時点でジオパークの数は20となり(図1),そのうち5つ(山陰海岸と室戸が追加)が世界ジオパークである.
中国には現在139ヶ所の国立ジオパーク(地質公園)があり(Yang et al. 2011),そのうち138ヶ所は2007年までに設置された(Zhao and Zhao, 2007; この報告の表1にある44ヶ所のジオパークは,名前が違う場合もあるが,全てYang et al.に載っている).うち22ヶ所が世界ジオパークである(加藤ほか編, 2010; Zhao and Zhaoによると2007年時点では18ヶ所だった).その分布を見ると,中国東部と南部に集中していて,東北,内モンゴル,西部には少ないが,全国どの省にも最低1つは存在する(図1).それらをメインテーマ別に見ると,地形に関するジオパークが105ヶ所(76%)と圧倒的に多く,その内訳は石灰岩侵食地形(カルスト)28,砕屑岩侵食地形(丹霞Danxia地形など)23, 火山地形16,花崗岩風化侵食地形11,河川・湖水地形11, 氷河地形8, 黄土・風成地形4,海食地形4となっている.地質をメインテーマとするジオパークは34ヶ所で, 動植物化石17(うち恐竜6, 人類1),地層の模式地8, 地質構造5, 地すべりなど地質災害3,鉱物1となっている.つまり,中国のジオパークの大部分は石灰岩・砂岩・花崗岩などの侵食地形を主要なテーマとしており,これはZhao and Zhao (2007)の冒頭に述べられている「ジオパークとは特有の地形をもつ自然区域のことである」という中国独特の定義と符合する.特に広東省北部の丹霞Danxia山を模式地とする丹霞地形は,よく成層した水平ないし緩傾斜の赤色砂岩・礫岩層(主に白亜系)が鉛直方向の節理に沿って侵食され,急崖あるいは高い塔が並んだような地形になっているもので,12ヶ所のジオパークが丹霞地形をメインテーマにしている(そのうち世界ジオパークは丹霞山,江西省竜虎山,福建省泰寧の3カ所).同じような砂岩・礫岩の侵食地形には,例えばギリシャのメテオラの修道院群,日本の熊本県山鹿市の不動岩などがあるが,中国のものはこれらより大規模で分布も広い.また,石灰岩の侵食地形(カルスト,ドリーネ,鍾乳洞など)をテーマにしているジオパークには,雲南省の石林Shilinなど有名な観光地が多いが,世界に名高い広西壮族自治区の桂林Guilinはなぜかジオパークに名を連ねていない.Zhao and Zhao (2007) には,太行山脈南麓,河南省焦作市の北(山西省との境界)に位置する雲台山ジオパーク(面積556 km2)の成功例が特記されている.これは日本の長瀞や大歩危に似た渓谷美と竹林の七賢が隠棲した寺院群などをテーマにしており,2004年末時点で観光業界での雇用は3万人,間接雇用は22万人,観光客は805万人に達し,1999年(ジオパーク設立前)に比べて雇用者は8〜12倍,観光客は17倍になったそうである.ジオパーク事業は,中国の観光産業を活性化するだけでなく,地質学のステータスを向上させ,地質関係者に多くの就職先を提供しているに違いない.ただし,雲台山ジオパークは土地を囲い込んで入場料を徴収する方式であり,行くだけなら無料(ジオツアーに参加料を支払う)という日本の方式とは異なる.
一方,日本ジオパーク・ネットワークのホームページ(http://www.geopark.jp/)による日本のジオパーク20ヶ所の分布は,北海道3,本州12(離島含む),四国1,九州4となっている(図1).「かんらん岩」や「黒曜石」のように目玉となる岩石を前面に打ち出しているところや,「水の旅」というテーマで山地から海岸までのジオサイトを有機的に組織化しているところもあるが,テーマや目玉があまりはっきりしないジオパークもある.日本のジオパークでは,エコとジオそして人とのつながり,さらにジオダイバーシティー(地質多様性geodiversity)が重視されており,それはすばらしいことであるが,反面でテーマや目玉をわかりにくくしている.一般人や外国人がもっととっつきやすいように,キーワードをはっきりさせ,テーマやストーリーをもっと明確に示した方がよいと思う.私の主観的な印象では,日本のジオパークが目玉としている地質学的対象は火山,岩石・鉱物,変動地形などが多く,地質構造,化石,水理地質などもあるが,上述のように内陸の侵食地形を目玉にしているものが多い中国のジオパークとは,全体として内容がずいぶん異なる.外国に学び,日本のジオパークの独自性をはっきり意識して外国にアピールすることが必要だと思う.加藤ほか編(2010)は日本,中国,欧州などの主なジオパークを写真入りで解説し,ジオパークの歴史や国際・国内組織についても述べていて,この目的に有用な本であるが,地名などに間違いがあるので注意が必要である.また,私はオフィオライトの専門家であるが,「シェットランドのオフィオライトは世界で一番緻密でよく露出しており完璧な形で残っていて観察しやすい」(同書p. 156)という話は聞いたことがなく,「緻密なオフィオライト」とはどういうものかもよくわからない.ご当地自慢,手前味噌はある程度許容するとしても,ジオパークの現場の説明やパンフレットなどに,地質学者の目がよく行き届くようにすることが必要であろう.
岩松(2007)は,日本では地質学が市民権を得ておらず,市民権を得るためにジオパークは重要だとし,旭山動物園の成功例を挙げて,本当の地質のすばらしさを市民に実感させるジオパークができれば,地質学は市民にとって「どうでもいい」ものではなくなり,必要不可欠なものとなる,と言っている.そして,日本のジオパークが目指す独自の目標として,自然を人間と対置し,自然を征服しようとする西欧文明(砂漠文明)の人間中心主義とは異なる,「自然と折り合いをつけて暮らしてきた日本の祖先の知恵に学ぶ」ための,森林文明のジオパークにすべきだと述べている.彼のこの文章は,ジオパークの意義について,地学リテラシー向上などの表層レベルから文明論のレベルまで掘り下げて格調高く論じているだけでなく,地質学が置かれている現状を簡明的確に総括し,地質学に自己変革を迫る檄文であり,ジオパークをそのための重要な手段と位置づけている.東日本大震災と原発事故発生後の今日,この文章の重要性は一層増している.「『地球上に住む以上,地学は必要だ』などと密かに自負するだけではダメで,それは学問の消滅へとつながっていく」,「地質図も天気図くらいに身近なものになって欲しい.本当はカーナビにも入っているくらいに普及したいものだ」,「先年のインド洋大津波のとき,日本人が『津波だあ!』と叫んで率先して逃げていれば,どれだけ大きな国際貢献になっていたか計り知れない」,「教育における地学の比重低下の結果として,日本人の地学リテラシーは最低に近くなった.安心安全の国づくりが叫ばれている今,地学の復権と,地学の普及が喫緊の課題となってきた」などのフレーズは我々の心に突き刺さる.彼は「エコとジオの社会的認知度の違いには,それぞれの分野の努力の度合いが反映しているのである」と言っている.努力の差だけが原因ではないと思うが,ジオはもっと努力して社会的認知度を上げる必要があるのは確かだ.
今後の日本のジオパークの課題としては,各ジオパークのテーマとストーリーの明確化及びジオサイトの有機的な組織化と英文ガイドブック出版などによる国際的アピールが必要であろう.このようにして初めて,国外からのジオツーリストを多数呼び寄せることができ,今後のジオパーク事業の発展につなげることができると思う.上のホームページを見る限り,テーマやストーリーが前面に出ていないジオパークが多い.また,学界でまだ評価が定まっていない「隕石クレーター」などを目玉の一つにしているジオパークもあり,各テーマやジオサイトの学問的な吟味を行う必要がある.テーマやストーリーを明確化し,学問的な裏付けをしっかりさせることが,ジオパークを一流の観光地に引き上げ,国民の地学リテラシーを高めるとともに,地質学が生き残るための道である.実際,ジオパークを抱えるいくつかの自治体で,地学の学芸員が採用され始めている.この分野の学問と産業の大きな流れに沿って言うと,地質学は産業革命による石炭掘りの第一次産業から生まれ,資源需要の増大とともに発展したが,その後衰退し,20世紀後半からは土木・建設業などの第二次産業と組んで生きのびてきた.今後はジオパークなどの第三次産業に積極的にシフトすることによって命脈を保って行こう,ということだと思う.
拙稿を校閲して貴重なご意見をいただいた宮下純夫氏,高木秀雄氏,佃 栄吉氏,サイモン・ウォリス氏に感謝する.
【文献】
岩松 暉 (2007). 今なぜジオパークか.地質ニュース, 635, 8-14.
加藤碵一・渡部真人・吉川敏之・矢島道子・宮野素美子(世界のジオパーク編集委員会・日本ジオパーク・ネットワークJGN)編 (2010). 世界のジオパーク.オーム社, 193 p.
佃 栄吉 (2007). 日本にもたくさんのジオパークを! 地質ニュース, 635, 6-7.
Yang, G.F., Chen, Z.H., Tian, M.Z., Wu, F.D., Wray, R.A.L. and Ping, Y.M. (2011). On the growth of national geoparks in China: Distribution, interpretation, and regional comparison. Episodes, 34, 157-176.
Zhao, T. and Zhao, X. (2007). 中国におけるジオパークの整備と意義.地質ニュース, 635, 27-34.
(2011.12.16)
No.166 2012/1/17 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.166 2012/1/17 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2012年度代議員選挙の結果報告
【2】第3回惑星地球フォトコンテスト応募締切り迫る!
【3】2012年度会費払込/学部学生・院生割引申請受付中
【4】支部・専門部会情報
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2012年度代議員選挙の結果報告
──────────────────────────────────
選挙規則ならびに選挙細則に基づき、標記選挙を実施いたしましたので
ご報告いたします。
2012年1月13日
一般社団法人日本地質学会 選挙管理委員会委員長 兼子尚知
開票立会人 巌谷敏光・山本由弦
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0063.html
○会員番号・パスワードによるログインが必要です。
(ログインの方法は http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html)
*監事立候補受付中です(〆切:2/10〔金〕)
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0056.html
○会員番号・パスワードによるログインが必要です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第3回惑星地球フォトコンテスト応募締切り迫る!(1/31〆切)
──────────────────────────────────
このコンテストはユネスコおよび国際地質科学連合による国際惑星地球年
(2007-2009年)を契機に始められたもので、ジオフォトとしては最高峰のコン
テストです。私たちの惑星「地球」をテーマにした写真を公募し、優秀な
作品を表彰するとともに、広報、普及、教育活動を通じて地球科学に対する
理解を深め、学術の振興と社会の発展に寄与・貢献することを期待するもの
です。
★今年も多数のご応募をお待ちしています★
こんな作品を大募集!
・惑星地球の美しい自然
・地層や火山など活きた地球の姿を表す優れた作品
・学術的意義の高い作品(解説文を含む)
・ジオパークに関係する優れた作品
・鉄道と地球の姿を組み合わせた「ジオ鉄」の優れた作品
・学術的・教育的な価値のある優れた作品
・そのほか地球科学に関係した作品
応募締切: 2012年1月31日(火) 締切迫る!!
賞および賞金: 最優秀賞 賞金5万円/優秀賞 賞金3万円ほか
詳しくは、 http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2012年度会費払込/学部学生・院生割引申請受付中
──────────────────────────────────
■2012年度会費払込について
次年度分会費の前納をお願いいたします。自動引き落としを登録されている
方は、12月26日(月)に引き落としを行いました。お振込の方へは、請求書
兼 郵便振替用紙を、12月19日に発送いたしましたので、折り返しご送金を
お願いします。
詳しくは、 https://www.geosociety.jp/user.php
(会員番号によるログインが必要です。
ログインの方法は http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html)
■2012年度(2012.4〜2013.3)学部学生・院生割引申請受付中
最終締切日:2012年3月30日(金)
申請書を毎年ご提出いただかなければ割引会費は継続されていきませんので、
くれぐれもご注意下さい。
一次締切日(11月16日)までに申請書をご提出いただけなかった学部学生・
院生のかたに対しては、【正会員】の金額にて請求書を発行(引落のかた
は12月26日に自動引落)いたしました。
割引会費を希望する学部学生・院生のかたは、必ず最終締切までに申請書の
提出をして下さい。あわせて、請求書(=郵便振替用紙)の金額を訂正し、
2012年度会費をご送金ください(郵便振替用紙の再発行はいたしません)。
※郵便振替にて送金されるかたへ※
請求書に同封されている会費請求案内(黄色の用紙)の裏面に割引会費の
申請書が印刷されていますので、ご利用ください。
申請書のダウンロードは、
https://www.geosociety.jp/user.php(会員番号によるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】支部・専門部会情報
──────────────────────────────────
■北海道支部:支部総会・個人講演会
日程:2012年2月11日(土)13:30より
場所:北海道大学大学院環境科学研究院D棟101室
個人講演会講演申込締切:1月20日(金)
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
■西日本支部平成23年度総会・第162回例会
日時:2012年2月11日(土) 9:30〜17:30
場所:鹿児島大学郡元キャンパス
※例会プログラムは、講演申込み〆切後、早急にご連絡差し上げます。
同日夕刻(例会終了後)に懇親会を、前日(2月10日(金))夕刻に幹事会を
催す予定です。
参加費:お一方1,000円(懇親会参加費はお一方3,000円を予定)
講演申込み〆切:2月6日(月)17時
※講演申込について
講演は口頭・ポスターを予定しております。
講演要旨(A4一枚。PDFファイル。地質学会年会の講演要旨原稿フォー
マットにそろえてください)をご準備下さい。
ご準備いただいた講演要旨は、西日本支部庶務:宮本知治(e-mail:
miyamoto@geo.kyushu-u.ac.jp)宛、e-mailにて、お送り下さい。
その際に、連絡先(発表者氏名・所属・e-mail・電話、の全て)、
発表様式希望(口頭・ポスター・どちらでも可、のいずれか)をお知ら
せ下さい。
ポスターサイズは90cm×120cmです。(ただし、発表様式につきましては、
ご希望に添えないことも有ります。その際はご了承下さい)
また,例会終了後に予定しております懇親会の参加希望についても合わせて
ご連絡下さい。他、詳細は追ってお伝えします。
問合せ先:西日本支部庶務:宮本知治(e-mail:miyamoto@geo.kyushu-u.ac.jp)
なお、ご連絡いただいた個人情報は西日本支部運営以外の目的に流用すること
はございません。
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
■構造地質部会緊急例会「社会への発信とリテラシー」
東日本大震災後,地球科学と社会との関わりを考え直すべきときが来ている
のではないか?という問いから,今回の緊急例会を企画いたしました.
地球科学の理解がかつてないほど必要とされているこの時代に,どのように
その必要性を発信して行くべきでしょうか?
地球科学リテラシーの向上のためのアウトリーチのあり方などを構造地質を
専門とする研究者が集い,考える会にしたいと思っております.
日時:2012年3月17日(土)、18日(日)
場所:東北大学理学部
プログラム等、詳細は、、、
http://struct.geosociety.jp/SGMeeting2012/
参加登録も開始いたしました。締め切りは2012年2月22日(水)です。
http://struct.geosociety.jp/SGMeeting2012/can_jia_deng_lu.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■日本学術会議主催学術フォーラム
「東日本大震災を教訓とした巨大災害軽減と持続的社会実現への道」
日時:2012年2月11日(土)13:00〜17:30
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木7-22-34)
参加:無料(要申込み、定員300名)
プログラム等詳細は、、、
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/142-s-0211.pdf
■第4回ジオ多様性フォーラム「ジオ多様性とは何か、その重要性を問う」
日時:2012年2月10,11日(金・土)
場所:京都大学総合博物館講演室
プログラム
2月10日(金)15:00〜17:30
開会挨拶 尾池和夫
・田村憲司(筑波大学)「ジオ多様性における土壌の役割 —土壌多様性の意義−」
・井上章一(国際日本文化研究センター)「建築とジオ多様性」(仮)
・近藤高弘(陶芸・美術家)「焼きモノとジオ多様性」
〜 懇談会
2月11日(土)9:30〜 (午前中で終了予定)
・山口正視(千葉大学)「真菌から見たジオ多様性」
・坂本雄一(有限会社 坂本酒店)「ワインとジオ多様性の美味しい関係」
〜 討論
連絡先:矢島道子 pxi02070@nifty.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■産業技術総合研究所:博士型任期付研究職員募集(一次4/13, 二次4/27)
公募課題名(地質分野):
1) 国土及び周辺域の地質基盤情報の整備と利用拡大
・重要地域(陸域)の地質調査及び地質図作成
・重要地域(海域)の地質調査
・都市沿岸域の地球物理情報の整備
2) 地質災害の将来予測と評価技術の開発
・火山噴煙観測に基づく火山活動推移評価手法の開発
・自然地震の解析に基づく地下深部構造・応力場の研究
・地形・地質に基づく海溝型巨大地震の履歴に関する研究
3) 地圏の環境と資源に係る評価技術の開発
・レアメタル資源の探査開発
・地熱資源の研究開発
・地中熱資源のポテンシャル評価
・天然ガス資源開発技術の研究
・二酸化炭素地中貯留評価技術の研究
・地下環境汚染評価技術の開発
・地層処分にかかわる物理探査評価技術の開発
■広島大学大学院:理学研究科地球惑星システム学専攻(教授)(2/29)
■消防庁 平成24年度研究開発課題の公募(2/13)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。 geo-Flashは、
月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日 までに
事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.164 2012/1/4 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.164 2012/1/4 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★各賞選考委員会からお知らせ★★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】日本地質学会2012年度各賞候補者募集:1/5締切
──────────────────────────────────
各賞候補者募集は1月5日(木)締切りです。是非たくさんの候補者並びに
候補論文を、各賞選考委員会(学会事務局 main@geosociety.jp)宛にご推薦
下さいますよう、何卒よろしくお願いいたします。
応募〆切:2012年1月5日(木)必着
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
○会員番号・パスワードによるログインが必要です。
(ログインの方法は http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html)
○「会員のページ」の各賞推薦候補者募集に関する案内から、推薦書式等が
ダウンロードできます。
-----------------------------------------------------
下記の賞の候補者を募集中です。たくさんのご応募をお待ちしております。
1.日本地質学会賞
授賞対象:地質学に関する優秀な業績をおさめた本会正会員もしくは名誉会員,
またはこれらの会員を代表とするグループ.
2.日本地質学会国際賞
授賞対象:地質学に関する画期的な貢献があり,加えて日本列島周辺域の研究
や日本の地質研究者との共同研究などを通じた日本の地質学の発展に関する顕
著な功績があった非会員
3.日本地質学会小澤儀明賞・柵山雅則賞
授賞対象:地質学に関して優れた業績を上げた,2011年9月末日で満37歳以下
の会員(研究テーマによって小澤儀明賞・柵山雅則賞のいずれかを授与)
4.日本地質学会研究奨励賞
授賞対象:2009年10月から2011年9月までの過去2年間に地質学雑誌およびIsland Arcに
優れた論文を発表した,2011年9月末日で満35才未満の正会員.筆頭著者であれ
ば共著でもよい.
5.日本地質学会論文賞
授賞対象:
1)2008年10月から2011年9月までの過去3年間に「地質学雑誌」発表された
優れた論文
2)2008年4号から2011年3号(9月)までの過去3年間に「Island Arc」に
発表された筆頭著者が本会会員による優れた論文
6.日本地質学会小藤賞
授賞対象:2010年10月から2011年5月までの間に地質学雑誌に発表された短報で,
重要な発見または独創的な発想を含むもの.
7.日本地質学会小藤文次郎賞(新設)
授賞対象:2009年10月から2011年9月までの間に会員が発表した重要な発見また
は独創的な発想を含む論文.
8.日本地質学会功労賞
授賞対象:長年にわたり地質学の発展に貢献のあった本会会員もしくは非会員.
またはこれらを代表するグループ.
9.日本地質学会表彰
授賞対象:地質学の教育活動,普及・出版活動,新発見および露頭保全,あるい
は新しい機器やシステム等の開発等を通して地質学界に貢献のあった個人,団体
および法人.
*2011年から規則が変わり,対象者は会員・非会員を問いません.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。 geo-Flashは、
月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日 までに
事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.163 2011/12/27 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.163 2011/12/27 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★各賞選考委員会からお知らせ★★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】日本地質学会2012年度各賞候補者募集:〆切延長(2012/1/5〔木〕まで)
──────────────────────────────────
12/26で〆切となりました各賞候補者募集ですが、さらに多くのご推薦・
ご応募をいただきたく、締め切り日を延長いたします。
是非たくさんの候補者並びに候補論文を、各賞選考委員会(学会事務局
main@geosociety.jp)宛にご推薦下さいますよう、何卒よろしくお願いいた
します。
応募〆切延長:2012年1月5日(木)まで
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
○会員番号・パスワードによるログインが必要です。
(ログインの方法は http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html)
○「会員のページ」の各賞推薦候補者募集に関する案内から、推薦書式等が
ダウンロードできます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。 geo-Flashは、
月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日 までに
事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
水星の地質について
水星の地質について
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
太陽系惑星で最も内側の軌道を回る水星の探査は、1974〜75年のマリナー10号以来30年以上途絶えていた。そのため、地球型惑星の地質学・物質科学においては,水星を軽視する傾向があった(例えば武田2009)。2004年に打ち上げられた米国のMESSENGER (Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry, and Ranging)探査機は、2008〜10年の間に3回ほど水星近傍を通過して観測を行い、2011年3月18日には水星周回軌道に入って連続観測を行っており、その高解像度写真やX線、γ線などによる化学組成分析データに基づき新知見が続々と公表されつつある。ここでは,それらを簡単にまとめて地質学会会員諸氏の参考に供する。MESSENGER以前の知識は宮本ほか編(2008)の水星の章によくまとめられており,本文中で比較する火星については同書の他に臼井(2011)による最新の優れた総説があるので参照されたい.
水星は半径が地球の約1/3、質量は約1/20という太陽系最小の惑星であるが、太陽系で最も高密度の惑星であり、これは半径2400 kmの惑星に半径1800 kmの大きな鉄の核(コア)があるためと考えられており、水星にはこの核に由来する磁場が存在する。このように核が大きく、マントルが薄いことを説明する仮説として、(1)巨大衝突説:惑星サイズの天体と衝突したために表面部分が飛散してしまった、(2)表面蒸発説:原始太陽系星雲の中心部が高温になった時期に、最も内側の軌道を回る水星の表面の岩石が蒸発してしまった(現在でも日中の表面温度は600℃になる)、(3)流体力学説(選択集積説):星雲の中心近くに鉄に富む密度の大きい粒子が集まり、それが合体して水星ができた、などが考えられている(Solomon, 2011)。水星は太陽に近くて大気も極端に薄いため、表面の宇宙風化が激しく、MESSENGER以前の赤外線分光では各鉱物特有の吸収スペクトルがよく観測できなかった。ただし、波長1μm附近の鉄の吸収線がないことから、表面は鉄分に乏しいCa-Mg珪酸塩でできていると考えられていた。
地形については、マリナー10号の写真から、クレーターだらけの「高地」と、クレーターの少ない円形の「海」からなる、月に似た惑星であるとされていた。月では、高地と海の色が、地球から肉眼で見てもよくわかるほど顕著に異なるのに対して、水星では色の差がはっきりしない(または月と逆に海の方がやや明るい色を呈する)。水星独自の地形的特徴として、惑星の冷却収縮によると考えられる衝上断層がいくつか確認されていたが、今回の探査でもそれらが惑星全体に多数存在し、断層のずれも1 km以上に達することが確認された。そして今回の探査の新知見として、北極から北緯40度にかけての広大な不規則型の地域(水星の全表面積の6%)が洪水玄武岩(ないしコマチアイト)の厚さ1 km以上の溶岩流に覆われていることがわかった。このことは、太陽系の隕石重爆撃期(40〜38億年前)の後も水星の大規模火山活動が続いていたことを示す(Head et al. 2011)。この地域の周囲では、溶岩の供給源となった凹地、個々の溶岩流、溶岩流に侵食された涙型の丘陵、溶岩流に埋め立てられた幽霊クレーターなどがよく見られる。Degasクレーター(直径52 km)の底面には溶岩湖が冷えてできたと考えられる割れ目が発達する(Showstack, 2011)。また、水星全体の57ヶ所のクレーター内の中央丘、外輪山、その内側斜面、底部などにある直径数10〜数1000 mの凹地には、その内部や周囲に反射率の高い物質が飛散しており、これは爆発的噴火によってできた可能性があって、水星の岩石は従来考えられていたよりも揮発性元素を多く含むらしい(Blewett et al. 2011)。なお、両極附近の太陽光が届かないクレーターの底にも反射率の高い物質があって、H2Oの氷または硫黄の可能性がある(Solomon, 2011)。
周回軌道上のMESSENGERによる太陽面爆発(フレア)を利用した蛍光X線分析によると、水星表面の岩石はMg/Si比が高く、Al/Si, Ca/Si比が低くて、斜長石に富む地球の大陸地殻や月の高地の岩石とは異なり、玄武岩とコマチアイトの中間的な組成を示す(Nittler et al. 2011; Head et al. 2011)。そして地球や月の岩石の10倍以上の硫黄を含み、火星や金星の岩石に似る。ただし、水星表面の岩石は鉄やチタンが非常に少ない。これらのことは、水星が非常に還元的で金属に富む頑火輝石球粒隕石(enstatite chondrite)や炭素質CB型球粒隕石または水に乏しい彗星物質などの集積によってでき、金属核とマントルの珪酸塩岩石の分離は効果的に起こったが、月の高地のような斜長石に富む地殻は形成されなかったことを示唆する(Nittler et al. 2011)。
γ線スペクトル分析によると、水星表面の岩石はThに乏しいが(0.22 ppm程度)、ややKに富み(1150 ppm程度)、K/Th比は平均5200程度である。火星、金星、地球の表面の岩石(K=2000〜5000 ppm)に比べるとKやThは少ないが、K/Th比は同様であって(地球・金星・火星ではこの比が2000〜7000の間)、特に火星隕石(シャーゴッタイト)や地球の海洋地殻の岩石(MORB)に似る(Peplowski et al. 2011)。一方、月の岩石はK/Th比が360程度と1桁以上小さく(Thに富む)、月は他の地球型惑星に比べて揮発性元素に著しく枯渇していることを示唆する。水星のK/Th比が火星、金星、地球と大差なく、比較的揮発性元素に富むことは、巨大衝突説や表面蒸発説に不利である。結局、揮発性元素に枯渇し金属鉄に富む物質と揮発性元素に富む物質が混合して集積し、水星を形成したという一種の選択集積説が、現時点で最も妥当な考え方と思われる。また、水星表面の岩石のU含有量は0.09 ppm程度で、Th/U比は約2.5であり、球粒隕石と大差ない。このことは、Uが金属核に濃集したためにその崩壊熱で核が融解し、液体核の運動で磁場が生じているとする考えには不利である(Peplowski et al. 2011)。
以上のように、最近数年間(特に最近数カ月間)のMESSENGERの探査によって、水星表面のマグマ活動や構造運動、そして岩石の化学組成などについて、既に調査研究が進んでいる他の地球型惑星と比較しながら議論できる程度にデータが揃ってきた。その結果、表面の地形が月に類似するとされていた水星は,物質科学的にはむしろ火星や金星そして地球の海洋底に似ており、月の岩石はこれらと非常に異なっていることがわかってきた.太陽系の地球型天体においては,一般に大きな天体ほどマグマ活動が長続きするので分化作用が進み、表面に多様な岩石が形成されると言われているが,月の斜長岩や小惑星ベスタのユークライトなどのように,比較的小さい天体でもマグマ活動によって分化した岩石が地表面に広く分布していることがある(武田, 2009)。むしろ、最近の探査・研究の進展によって、火星、地球、金星、水星の主要なマグマ組成(玄武岩〜コマチアイト質)の共通点が明らかになってきたことは注目すべきだと思う.2014年打ち上げ予定の日本と欧州の共同水星探査機BepiColomboは2020年から水星の観測を始める予定である。水星の地質を更に明らかにすることにより、地球を含む太陽系全体の惑星形成・分化プロセスを統一的に理解できるようになれば素晴らしいと思う。
惑星地質は筆者の専門外なので本文に誤解や勘違いがあることを恐れる.読者のご叱正をお願いする.
【文献】
Blewett, D.T., Chabot, N.L., Denevi, B.W. et al. (2011) Hollows on Mercury: MESSENGER evidence for geologically recent volatile-related activity. Science, 333, 1856-859
Head, J.W., Chapman, C.R., Storm, R.G. et al. (2011) Flood volcanism in the northern high latitudes of Mercury revealed by MESSENGER. Science, 333, 1853-1856.
宮本英昭・橘 省吾・平田 成・杉田精司 (2008) 惑星地質学. 東京大学出版会. 260 p.
Nittler, L.R., Starr, R.D., Weider, S.Z. et al. (2011) The major-element composition of Mercury’s surface from MESSENGER X-ray spectrometry. Science, 333, 1847-1850.
Peplowski, P.N., Evans, L.G., Hauck, S.A.II et al. (2011) Radioactive elements on Mercury’s surface from MESSENGER: Implications for the planet’s formation and evolution. Science, 333, 1850-1852.
Showstack, R. (2011) Mission provides new findings about Mercury. EOS, 92(26), 218-219.
Solomon, S.C. (2011) A new look at the planet Mercury. Physics Today, Jan. 2011, 50-55.
武田 弘 (2009) 固体惑星物質進化. 現代図書, 131 p.
臼井寛裕 (2011) 近年の火星隕石研究・火星探査から得られた新しい火星の描像. 地球化学, 45, 159-173.
(2012.1.5)
No.165 2012/1/6 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.165 2012/1/6 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2012年の年頭にあたって:会長挨拶
【2】コラム:水星の地質について
【3】第3回惑星地球フォトコンテスト応募締切り迫る!
【4】2012年度会費払込/学部学生・院生割引申請受付中
【5】支部・専門部会情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2012年の年頭にあたって:会長挨拶
──────────────────────────────────
会長 宮下 純夫
2012年の年頭にあたり,地質学会理事会を代表して会員の皆様に年頭のご
挨拶を申し上げます.昨年は日本の歴史に残る3.11東日本大震災と原発災害
を始め,台風12号による紀伊半島を中心とした地盤災害など,大きな自然災
害が頻発しました.日本地質学会は,犠牲者の皆様への哀悼を捧げるととも
に,地質学的視点から復興への貢献に邁進する決意です.マグニチュード9の
超巨大海溝地震の余波はまだ続いており,それまで西方へ圧縮されて短縮し
ていた東北日本は,逆に東側へと引っ張られている異常な状態が続いていま
す.大きな余震や火山噴火も懸念されており,今後の推移を注意深く見守る
とともに,巨大地震や津波,地盤災害,火山噴火などの自然災害に関する研
究の発展に努め,減災・防災への貢献を強化する中で,地質学のさらなる発
展の年にしたいものです.
続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/outline/content0097.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】コラム:水星の地質について
──────────────────────────────────
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
太陽系惑星で最も内側の軌道を回る水星の探査は、1974-75年のマリナー10号
以来30年以上途絶えていた。そのため、地球型惑星の地質学・物質科学において
は,水星を軽視する傾向があった(例えば武田2009)。2004年に打ち上げ
られた米国のMESSENGER (Mercury Surface, Space Environment,
Geochemistry, and Ranging)探査機は、2008-10年の間に3回ほど水星近傍を
通過して観測を行い、2011年3月18日には水星周回軌道に入って連続観測を
行っており、その高解像度写真やX線、γ線などによる化学組成分析データに
基づき新知見が続々と公表されつつある。ここでは,それらを簡単にまとめて
地質学会会員諸氏の参考に供する。
続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0352.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】第3回惑星地球フォトコンテスト応募締切り迫る!
──────────────────────────────────
このコンテストはユネスコおよび国際地質科学連合による国際惑星地球年
(2007-2009年)を契機に始められたもので、ジオフォトとしては最高峰のコン
テストです。私たちの惑星「地球」をテーマにした写真を公募し、優秀な
作品を表彰するとともに、広報、普及、教育活動を通じて地球科学に対する
理解を深め、学術の振興と社会の発展に寄与・貢献することを期待するもの
です。
★今年も多数のご応募をお待ちしています★
こんな作品を大募集!
・惑星地球の美しい自然
・地層や火山など活きた地球の姿を表す優れた作品
・学術的意義の高い作品(解説文を含む)
・ジオパークに関係する優れた作品
・鉄道と地球の姿を組み合わせた「ジオ鉄」の優れた作品
・学術的・教育的な価値のある優れた作品
・そのほか地球科学に関係した作品
応募締切: 2012年1月31日(火) 締切迫る!!
賞および賞金: 最優秀賞 賞金5万円/優秀賞 賞金3万円ほか
詳しくは、 http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2012年度会費払込/学部学生・院生割引申請受付中
──────────────────────────────────
■2012年度会費払込について
次年度分会費の前納をお願いいたします。自動引き落としを登録されている
方は、12月26日(月)に引き落としを行いました。お振込の方へは、請求書
兼 郵便振替用紙を、12月19日に発送いたしましたので、折り返しご送金を
お願いします。
詳しくは、 https://www.geosociety.jp/user.php
(会員番号によるログインが必要です。
ログインの方法は http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html)
■2012年度(2012.4〜2013.3)学部学生・院生割引申請受付中
最終締切日:2012年3月30日(金)
申請書を毎年ご提出いただかなければ割引会費は継続されていきませんので、
くれぐれもご注意下さい。
一次締切日(11月16日)までに申請書をご提出いただけなかった学部学生・
院生のかたに対しては、【正会員】の金額にて請求書を発行(引落のかた
は12月26日に自動引落)いたしました。
割引会費を希望する学部学生・院生のかたは、必ず最終締切までに申請書の
提出をして下さい。あわせて、請求書(=郵便振替用紙)の金額を訂正し、
2012年度会費をご送金ください(郵便振替用紙の再発行はいたしません)。
※郵便振替にて送金されるかたへ※
請求書に同封されている会費請求案内(黄色の用紙)の裏面に割引会費の
申請書が印刷されていますので、ご利用ください。
申請書のダウンロードは、
https://www.geosociety.jp/user.php(会員番号によるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部・専門部会情報
──────────────────────────────────
■北海道支部:支部総会・個人講演会
日程:2012年2月11日(土)13:30より
場所:北海道大学大学院環境科学研究院D棟101室
個人講演会講演申込締切:1月20日(金)
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
■西日本支部平成23年度総会・第162回例会
日時:2012年2月11日(土) 9:30〜17:30
場所:鹿児島大学郡元キャンパス
※例会プログラムは、講演申込み〆切後、早急にご連絡差し上げます。
同日夕刻(例会終了後)に懇親会を、前日(2月10日(金))夕刻に幹事会を
催す予定です。
参加費:お一方1,000円(懇親会参加費はお一方3,000円を予定)
講演申込み〆切:2月6日(月)17時
※講演申込について
講演は口頭・ポスターを予定しております。
講演要旨(A4一枚。PDFファイル。地質学会年会の講演要旨原稿フォー
マットにそろえてください)をご準備下さい。
ご準備いただいた講演要旨は、西日本支部庶務:宮本知治(e-mail:
miyamoto@geo.kyushu-u.ac.jp)宛、e-mailにて、お送り下さい。
その際に、連絡先(発表者氏名・所属・e-mail・電話、の全て)、
発表様式希望(口頭・ポスター・どちらでも可、のいずれか)をお知らせ
下さい。
ポスターサイズは90cm×120cmです。(ただし、発表様式につきましては、
ご希望に添えないことも有ります。その際はご了承下さい)
また,例会終了後に予定しております懇親会の参加希望についても合わせてご連絡下さい。
他、詳細は追ってお伝えします。
問合せ先:西日本支部庶務:宮本知治(e-mail:miyamoto@geo.kyushu-u.ac.jp)
なお、ご連絡いただいた個人情報は西日本支部運営以外の目的に流用することはございません。
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
■構造地質部会緊急例会「社会への発信とリテラシー」
東日本大震災後,地球科学と社会との関わりを考え直すべきときが来ている
のではないか?という問いから,今回の緊急例会を企画いたしました.
地球科学の理解がかつてないほど必要とされているこの時代に,どのように
その必要性を発信して行くべきでしょうか?
地球科学リテラシーの向上のためのアウトリーチのあり方などを構造地質を
専門とする研究者が集い,考える会にしたいと思っております.
日時:2012年3月17日(土)、18日(日)
場所:東北大学理学部
プログラム等、詳細は、、、
http://struct.geosociety.jp/SGMeeting2012/
参加登録も開始いたしました。締め切りは2012年2月22日(水)です。
http://struct.geosociety.jp/SGMeeting2012/can_jia_deng_lu.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第21回環境地質学シンポジウム
開催日:2012年1月24日(火)・25日(水)
場 所:早稲田大学 国際会議場第一会議室
主 催:地質汚染−医療地質−社会地質学会
準主催:Japan Branch of GEM-IUGS
詳細は、以下のホームページをご覧ください。
http://www.jspmug.org/envgeo_sympo/21st_sympo/21th_sympo.html
■第1回アジア太平洋大規模地震・火山噴火リスク対策ワークショップ
日時:2012年2月22日(水)〜24日(金)
場所:産業技術総合研究所つくば中央共用講堂
主催:産業技術総合研究所地質調査総合センター
後援:日本地質学会,日本地震学会,日本火山学会,米国地質調査所,
欧州地質調査所連合ほか
詳細は、http://www.gsj.jp/Event/AsiaPacific/
■三朝国際シンポジウム MISASA IV
「太陽系物質科学〜太陽系科学ミッションと総合的物質科学研究が拓く未来像」
日時:2012年2月24日(金)〜26日(日)
場所:倉吉未来中心(鳥取県倉吉市)
参加登録〆切:1月23日(月)
アブストラクト〆切:2月15日(水)
詳細:http://sympo.misasa.okayama-u.ac.jp/misasa_iv/
■第7回「海洋と地球の学校」のお知らせ
独立行政法人海洋研究開発機構では、海洋科学技術の最先端のテーマを設定し、
大学生及び大学院生を対象に、21世紀の海洋科学技術の研究・開発を担う人材
育成に資することを目的として、「海洋と地球の学校」を開催しています。
カリキュラムは宿泊型の研修形式とし、研究者による講義と研究施設の見学等
のほか、野外実習等を実施することで、大学の講義では得られない海洋科学に
関する総合的な学習の場を提供することを目指します。
このたび、第7回「海洋と地球の学校」を下記の通り開催することになりました
ので、ご興味のある学生・院生のみなさまの参加を募集しております。
開催日:2012年3月13日(火)〜17日(土)
場 所:独立行政法人海洋研究開発機構 横須賀本部(神奈川県横須賀市)
同 横浜研究所(神奈川県横浜市金沢区)
三浦半島周辺地域(野外巡検)
※宿泊は横須賀本部及び三浦市内(15日のみ)を予定しています。
テーマ:「進化を探る」―海洋や地球はどのように進化してきたのか―
対 象:大学生及び大学院生(短大、高等学校専攻科を含む)
(応募者数により一般社会人の参加も可能)
詳細は、以下のホームページをご覧ください。
http://www.jamstec.go.jp/j/pr/school/007/index.html
なお、聴講生についてもあわせて募集しております。
(ご関心のある講義のみへの参加も可能)
【お問い合わせ先】
独立行政法人海洋研究開発機構 広報課 海洋と地球の学校 事務局
〒236-0001 横浜市金沢区昭和町3173-25
TEL:045-778-5334(設楽)
E-mail:kaiyo-gakko@jamstec.go.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■岡山理科大学地球惑星環境科学研究センター 共同利用研究(1/25)
■産業技術総合研究所特別研究員募集(若干名)(1/27)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。 geo-Flashは、
月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日 までに
事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.167 2012/1/20 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.167 2012/1/20 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】連合大会(JpGU)の投稿・参加登録はじまる!
──────────────────────────────────
日本地球惑星連合 2012年大会の投稿・参加登録が1月11日から始まりました。
投稿早期締切は 2月3日(金)、投稿最終締切は 2月17日(金)です。
http://www.jpgu.org/meeting/index.htm
なお、日本地質学会は次のセッションの提案母体または共催団体になっています。
(カッコ内はセッションID、代表コンビーナ)
・人間環境と災害リスク(H-SC24,鈴木康弘)
・湿潤変動帯の地質災害(H-DS25,千木良雅弘)
・堆積物・堆積岩から読みとる地球表層環境情報(H-CG30,藤野滋弘)
・活断層と古地震(S-SS35,吾妻 崇)
・地域地質と構造発達史(S-GL44,束田和弘)
・変形岩・変成岩とテクトニクス(S-MP46,乾 睦子)
・火山・火成活動とその長期予測(S-VC53,及川輝樹)
・Creation and Destruction of Continental Crust by Plate Tectonics(S-CG04,田村芳彦)
・Convergent boundary dynamics: collision, subduction, crustal growth and deformation
(S-CG05,Ur Rehman Hafiz)
・岩石・鉱物・資源(S-CG62,角替敏昭)
・応力と地殻ダイナミクス(S-CG68,大坪 誠)
・地球科学の科学史・科学哲学・科学技術社会論(G-01,矢島道子)
・津波堆積物(M-IS25,後藤和久)
・ジオパーク(M-IS32,目代邦康)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】フォトコンも応募お待ちしております
──────────────────────────────────
第3回 地球惑星フォトコンテストの応募締め切りは1月31日(火)です。
詳しくは、 http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。 geo-Flashは、
月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日 までに
事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.168 2012/2/7 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.168 2012/2/7 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】第3回惑星地球フォトコンテストご応募ありがとうございました
【2】地質図の在庫一掃セール!― 第三弾!2月8日〜2月29日
【3】2012年度会費払込/学部学生・院生割引申請受付中
【4】支部・専門部会情報
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】第3回惑星地球フォトコンテストご応募ありがとうございました
──────────────────────────────────
1月31日をもって第3回惑星地球フォトコンテストの応募が締め切られました。
今年は総数320点(高校生以下14点を含む)もの作品を応募いただきました。
審査結果は3月末に地質学会ホームページ上にて公表する予定です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】地質図の在庫一掃セール!― 第三弾! 2月8日〜2月29日
──────────────────────────────────
現在、地質学会に在庫があるものについてのみ、特別販売いたします。
最新の在庫リストはホームページに掲載していますのでご覧いただくか、事務局(電話:03-5823-1150)にお尋ねください。
ご注文はE-mail(main@geosociety.jp)またはFax(03-5823-1156)でお願いいたします。 種類と数に限りがありますので、ご注文は先着順といたします。
リストにないもの、追加等のご注文には応じられませんのでご了承ください。
なお、第三弾のセールの期間は、2月8日〜2月29日までといたします。
特別価格の詳細はご注文の際に地質学会事務局にお問い合わせください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2012年度会費払込/学部学生・院生割引申請受付中
──────────────────────────────────
■2012年度会費払込について
次年度分会費の前納をお願いいたします。自動引き落としを登録されている方は、12月26日(月)に引き落としを行いました。お振込の方へは、請求書 兼 郵便振替用紙を、12月19日に発送いたしましたので、折り返しご送金をお願いします。
詳しくは、 https://www.geosociety.jp/user.php
(会員番号によるログインが必要です。
ログインの方法は http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html)
■2012年度(2012.4〜2013.3)学部学生・院生割引申請受付中
最終締切日:2012年3月30日(金)
申請書を毎年ご提出いただかなければ割引会費は継続されていきませんので、くれぐれもご注意下さい。
一次締切日(11月16日)までに申請書をご提出いただけなかった学部学生・院生のかたに対しては、【正会員】の金額にて請求書を発行(引落のかたは12月26日に自動引落)いたしました。
割引会費を希望する学部学生・院生のかたは、必ず最終締切までに申請書の提出をして下さい。あわせて、請求書(=郵便振替用紙)の金額を訂正し、2012年度会費をご送金ください(郵便振替用紙の再発行はいたしません)。
※郵便振替にて送金されるかたへ※
請求書に同封されている会費請求案内(黄色の用紙)の裏面に割引会費の申請書が印刷されていますので、ご利用ください。
申請書のダウンロードは、
https://www.geosociety.jp/user.php(会員番号によるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】支部・専門部会情報
──────────────────────────────────
■北海道支部:支部総会・個人講演会・地質災害討論会
日程:2012年2月11日(土)9:30〜17:00
場所:北海道大学大学院環境科学研究院D棟101室
総会(9:30〜10:20)
<休憩>
個人講演会(10:30〜12:45,質疑応答を含め15分)
<昼食>
地質災害討論会2012(14:00〜17:00)
1.東日本大震災の現場を見て
2.自然災害に関する地学教育の推進
3.総合討論
参加無料
懇親会18:00〜20:00(場所未定、参加費あり)
問い合わせ先
北海道支部幹事 山本正伸
北海道大学大学院地球環境科学研究院
TEL: 011-706-2379 FAX: 011-706-4867
E-mail: myama@ees.hokudai.ac.jp
詳細はこちらから
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
■西日本支部平成23年度総会・第162回例会
日時:2012年2月11日(土) 9:30〜17:30
場所:鹿児島大学郡元キャンパス
※同日夕刻(例会終了後)に懇親会、前日(2月10日(金))夕刻に幹事会を
催す予定です。
参加費:お一方1,000円(懇親会参加費はお一方3,000円を予定)
また,例会終了後に予定しております懇親会の参加希望についても合わせてご連絡下さい。他、詳細は追ってお伝えします。
・鹿児島大学への交通アクセス
http://www.kagoshima-u.ac.jp/access/
・郡元キャンパスの見取り図
http://www.kagoshima-u.ac.jp/campusmap/index.html#a1
例会当日は、理学部の正面玄関に理学部内の会場案内図を掲示していただけるとのことです。
なお、11日当日は休日ですので郡元キャンパスの車両ゲートが閉まっています。自家用車で来場される方はキャンパス近辺のコインパーキングを利用してください。
問合せ先:西日本支部庶務:宮本知治(e-mail:miyamoto@geo.kyushu-u.ac.jp)
なお、ご連絡いただいた個人情報は西日本支部運営以外の目的に流用することはございません。
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
■構造地質部会緊急例会「社会への発信とリテラシー」
東日本大震災後,地球科学と社会との関わりを考え直すべきときが来ているのではないか?という問いから,今回の緊急例会を企画いたしました.
地球科学の理解がかつてないほど必要とされているこの時代に,どのようにその必要性を発信して行くべきでしょうか?
地球科学リテラシーの向上のためのアウトリーチのあり方などを構造地質を専門とする研究者が集い,考える会にしたいと思っております.
日時:2012年3月17日(土)、18日(日)
場所:東北大学理学部
プログラム等、詳細は、、、
http://struct.geosociety.jp/SGMeeting2012/
参加登録も開始いたしました。締め切りは2012年2月22日(水)です。
http://struct.geosociety.jp/SGMeeting2012/can_jia_deng_lu.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■はやぶさサンプル第1回国際公募
JAXAはこのたび、はやぶさサンプル第1回国際公募を開始致しました。
はやぶさサンプルは、2010年6月、探査機はやぶさにより地球に持ち帰られた、月以外で初めての地球外物質です。初期分析の結果はすでに Science 誌
(2011年8月26日号)に掲載されております。
多くのみなさまがこの貴重な試料の研究に参加され、新しい科学を切り開いてくださることを期待しておりおります。
第1回国際公募 申請書提出締め切り:2012年3月7日(日本時間)15時
審査結果は2012年5月中旬までに決定予定です。
詳細は以下をご覧ください。
http://hayabusaao.isas.jaxa.jp/
JAXA 宇宙科学研究所所長 小野田淳次郎
JAXA 月・惑星探査プログラムグループ統括リーダー 山浦雄一
■日本学術会議主催学術フォーラム
「東日本大震災を教訓とした巨大災害軽減と持続的社会実現への道」
日時:2012年2月11日(土)13:00〜17:30
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木7-22-34)
参加:無料(要申込み、定員300名)
プログラム等詳細は、、、
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/142-s-0211.pdf
■第4回ジオ多様性フォーラム「ジオ多様性とは何か、その重要性を問う」
日時:2012年2月10日,11日(金・土)
場所:京都大学総合博物館講演室
プログラム
2月10日(金)15:00〜17:30
開会挨拶 尾池和夫
・田村憲司(筑波大学)「ジオ多様性における土壌の役割 —土壌多様性の意義−」
・井上章一(国際日本文化研究センター)「建築とジオ多様性」(仮)
・近藤高弘(陶芸・美術家)「焼きモノとジオ多様性」
〜 懇談会
2月11日(土)9:30〜 (午前中で終了予定)
・山口正視(千葉大学)「真菌から見たジオ多様性」
・坂本雄一(有限会社 坂本酒店)「ワインとジオ多様性の美味しい関係」
〜 討論
連絡先:矢島道子 pxi02070@nifty.com
■平成23年度海洋情報部研究成果発表会
日時:2012年2月14日(火)13:30〜17:30
場所:海上保安庁海洋情報部10階国際会議室(江東区青海2-5-18)
問い合わせ:海上保安庁海洋情報部技術・国際課 TEL:03-5500-7122
http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/kouhou/h24/k20120130/k120130-2.pdf
■平成24年度サイエンス・リーダーズ・キャンプ(SLC)
受入実施機関募集開始のお知らせ
サイエンス・リーダーズ・キャンプ(SLC)は、夏季休業の期間中、全国の中学校、高等学校、中等教育学校等の理数教育を担当する教員に、先進的な研究施設や実験装置がある研究現場で実体験して、第一線で活躍する研究者等から直接講義や実習指導を受けることなどを通じて、最先端の科学技術を体感させるとともに、才能ある生徒を伸ばすための効果的な指導方法を修得させる合宿形式のプログラムです。
このたび、受入実施機関と実施プログラムを、下記の通り広く募集しております。
1.募集期間:2012年2月1日(水)〜3月9日(金)
2.実施時期:2012年度夏季休業期間中(2泊3日又は3泊4日)
3.採択予定プログラム数:計5プログラムを予定
4.支援額:1プログラムあたり400万円程度まで
5.その他:参加教員の募集選考は本募集の選定後に当機構が行います。
6.応募方法等の詳細は下記ホームページをご覧下さい。
[ホームページアドレス] http://rikai.jst.go.jp/slc/
問い合わせ先:
独立行政法人科学技術振興機構
理数学習支援部 教員支援担当
〒102-8666 東京都千代田区四番町5-3 サイエンスプラザ 4階
Tel:03-5214-7634 Fax:03-5214-7635 E-mail:slc@jst.go.jp
■GSJ地質ニュース創刊のお知らせ
産業技術総合研究所地質調査総合センター(GSJ)では、このたび新しい広報誌の発行を開始しました。誌名を「GSJ地質ニュース」として、2011年3月まで発行されていました「地質ニュース」と2011年12月まで発行していました「GSJニュースレター」を継承する月刊誌です。皆様には以下のURLにて閲覧をお願いいたします。「GSJ地質ニュース」には、GSJの研究業務の紹介とともに、地球科学の普及や啓発を目的とする記事の掲載も予定しています。昨年度末で発行終了となりました「地質ニュース」同様、広く皆様にご愛読いただけますと幸いです。
記事の閲覧 http://www.gsj.jp/gcn/index.html
【お問い合わせ先】
GSJ地質ニュース編集委員会
事務局(産総研 地質標本館内)担当 宮内
E-mail:g-news@m.aist.go.jp Tel:029-861-3754 http://www.gsj.jp/
■国際地学教育会議の最新ニュースレター
国際地学教育会議の最新ニュースレターが届きました。このニュースレター配信は2010年から中断していたものですが、以下のサイトで見ることができます。本ニュースレターでは、過去の国際地学教育会議のようすや今年開催される国際地学オリンピック・アルゼンチン大会の紹介記事が掲載されています。
http://www.geoscied.org/newsletter/
なお、前回の国際地学教育会議参加報告に関しましては、日本地質学会News13(10)をご覧ください。
久田健一郎
■「JABEE NEWS」第4号(2/6発行)よりお知らせ
「技術士を目指す理系学生のための」技術士制度説明会開催についてのご案内
公益社団法人日本技術士会は多くの理系学生に、国家資格である技術士を目指していただくために、各教育機関のご要望に応じ「技術士説明会」の開催
協力を行っています。
ご承知の通り、JABEEの認定プログラム修了者は技術士の第一次試験が免除されていますが、日本技術士会はJABEEの正会員であるほか、同会の「修習技術者支援制度検討WG」にはJABEEの岸本業務執行理事が委員として参加するなど技術士制度普及のために相互に協力を行っています。
日本技術士会では、技術士及び技術士制度の紹介とともに、若手技術士からのビデオメッセージ等も活用し、企業における技術士の位置付けや若手技術士のアンケート結果など学生が技術士や将来の自分の姿を具体的にイメージできるような資料を準備しています。学生の将来目指すべき方向や向学心の向上を図るため、その趣旨をご検討いただき必要の場合は開催につきお申込みをいただきたくご案内いたします。
詳細とお申込みは、以下をご覧ください。
http://www.engineer.or.jp/c_topics/000/000021.html
=========
日本技術者教育認定機構(JABEE)は、JABEE認定プログラム関係者の情報共有を目的として「JABEE NEWS」(メールニュース)の配信を始めました。
配信希望の方はJABEE事務局(koho@jabee.org)まで。
JABEEホームページ http://www.jabee.org/
=========
「JABEE NEWS」バックナンバーはこちらでも閲覧可能です。
http://www.jabee.org/OpenHomePage/about_jabee1.htm#news
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■2012年度地球化学研究協会学術賞「三宅賞」および「奨励賞」候補者の募集
(学会推薦)(7/2[月]学会締切)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。 geo-Flashは、
月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日 までに
事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.169 2012/2/21 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.169 2012/2/21 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】東日本大震災で被災した南三陸地域の自然史標本と「歌津魚竜館化石標本レスキュー事業」
【2】2012年度一般社団法人日本地質学会理事選挙の実施について
【3】地質図の在庫一掃セール!― 第三弾! 2月8日〜2月29日
【4】2012年度会費払込/学部学生・院生割引申請受付中
【5】支部・専門部会情報
【6】第34回万国地質学会議(IGC)ブリスベン大会の要旨締切(2/26)
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】東日本大震災で被災した南三陸地域の自然史標本と「歌津魚竜館化石標本レスキュー事業」
──────────────────────────────────
2011年3月の東北地方太平洋沖地震とそれによって引き起こされた大津波は東日本の太平洋岸地域に大きな被害(東日本大震災)をもたらした.東日本大震災では多くの博物館等も被災したが,とくに三陸海岸沿いでは津波による被害が大きく,地質標本を含む多くの資料標本が破損し,流失した.地質標本は地球史を考える上で欠くことのできない重要な歴史資料であり,現在の研究・教育に活用するとともに将来に安全に引き継がれなければならないものである.東北大学総合学術博物館では,地質学会の東日本大震災対応作業部会報告書に係る研究・調査・事業プランとして「歌津魚竜館化石標本レスキュー事業」を申請し採択された.この事業では,宮城県南三陸町の「歌津魚竜館」からレスキューされた資料標本を安全に保管・継承し,展示等に活用するために,標本の洗浄・消毒および修復などの作業を行ったが,ここでは南三陸地域の博物館等の被災状況・レスキュー活動について簡単に報告した上で,本事業について紹介する.
http://www.geosociety.jp/hazard/content0069.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2012年度一般社団法人日本地質学会理事選挙の実施について
──────────────────────────────────
2月10日に役員の立候補が締め切られました.選挙規則,選挙細則に基づき,2012年度の理事選挙を2月20日(月)〜3月8日(木)まで実施いたします.
理事選挙は2012年度からの新代議員による投票となります.
監事については会員から1名,理事会推薦から1名,計2名の立候補届出がありましたが,会員からの候補者は定数内のため,監事の投票は行いません.
■理事立候補者,および監事立候補者の名簿は、、、
http://www.geosociety.jp/members/content0064.html
(会員番号・パスワードによるログインが必要です。
ログインの方法は http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html)
理事選挙の開票は3月14日(水)14時から学会事務局で行います.
開票の立ち会いをご希望のかたは,3月7日(水)までに選挙管理委員会
(main@geosociety.jp)にお申し出ください.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】地質図の在庫一掃セール!― 第三弾! 2月8日〜2月29日
──────────────────────────────────
現在、地質学会に在庫があるものについてのみ、特別販売いたします。
最新の在庫リストはホームページに掲載していますのでご覧いただくか、事務局(電話:03-5823-1150)にお尋ねください。
ご注文はE-mail(main@geosociety.jp)またはFax(03-5823-1156)でお願いいたします。 種類と数に限りがありますので、ご注文は先着順といたします。
リストにないもの、追加等のご注文には応じられませんのでご了承ください。
なお、第三弾のセールの期間は、2月8日〜2月29日までといたします。
特別価格の詳細はご注文の際に地質学会事務局にお問い合わせください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2012年度会費払込/学部学生・院生割引申請受付中!3月30日(金)〆切
──────────────────────────────────
■2012年度会費払込について
次年度分会費の前納をお願いいたします。自動引き落としを登録されている方は、12月26日(月)に引き落としを行いました。お振込の方へは、請求書兼 郵便振替用紙を、12月19日に発送いたしましたので、折り返しご送金をお願いします。
詳しくは、 https://www.geosociety.jp/user.php
(会員番号によるログインが必要です。
ログインの方法は http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html)
■2012年度(2012.4〜2013.3)学部学生・院生割引申請受付中
最終締切日:2012年3月30日(金)
申請書を毎年ご提出いただかなければ割引会費は継続されていきませんので、くれぐれもご注意下さい。
一次締切日(11月16日)までに申請書をご提出いただけなかった学部学生・院生のかたに対しては、【正会員】の金額にて請求書を発行(引落のかたは12月26日に自動引落)いたしました。
割引会費を希望する学部学生・院生のかたは、必ず最終締切までに申請書の提出をして下さい。あわせて、請求書(=郵便振替用紙)の金額を訂正し、2012年度会費をご送金ください(郵便振替用紙の再発行はいたしません)。
※郵便振替にて送金されるかたへ※
請求書に同封されている会費請求案内(黄色の用紙)の裏面に割引会費の
申請書が印刷されていますので、ご利用ください。
申請書のダウンロードは、
https://www.geosociety.jp/user.php(会員番号によるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部・専門部会情報
──────────────────────────────────
■構造地質部会緊急例会「社会への発信とリテラシー」
東日本大震災後,地球科学と社会との関わりを考え直すべきときが来ているのではないか?という問いから,今回の緊急例会を企画いたしました.
地球科学の理解がかつてないほど必要とされているこの時代に,どのようにその必要性を発信して行くべきでしょうか?
地球科学リテラシーの向上のためのアウトリーチのあり方などを構造地質を専門とする研究者が集い,考える会にしたいと思っております.
日時:2012年3月17日(土)、18日(日)
場所:東北大学理学部
プログラム等、詳細は、、、
http://struct.geosociety.jp/SGMeeting2012/
参加登録も開始いたしました。締め切りは2012年2月22日(水)です。
http://struct.geosociety.jp/SGMeeting2012/can_jia_deng_lu.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】IGCブリスベンの締切迫る
──────────────────────────────────
第34回万国地質学会議(IGC)ブリスベン大会の要旨締切が2/26まで延長されました.詳しくは下記をご覧ください。
34IGC Website: http://www.34igc.org
http://www.34igc.org/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■有人月探査を見据えた 科学・利用ミッション ワークショップ
国際有人探査のロードマップ(Global Exploration Roadmap)により、月は次期有人探査の主要な目的地として位置付けられ、有人月探査の検討は今後、具体化が進むと考えられます。そのような中、SELENE(かぐや)の成功により、月科学分野において先進性と優位性とを獲得しつつある我が国にとって、有人による月の科学探査・利用ミッションは最も貢献出来る分野の一つだと考えられます。そこで、「有人月探査を見据えた科学・利用ミッションワークショップ」を開催し、皆様と議論を深めてまいりたいと思います。是非ご参加ください。
開催日 : 2012年 3月8日(木) 午前 9時50分〜
会場 : 宇宙航空研究開発機構(JAXA) 宇宙科学研究所 A棟2階 大会議場
主催 : 宇宙航空研究開発機構 月・惑星探査プログラムグループ
(JSPEC)/SE室/ 有人月拠点システムチーム
共催 : 宇宙理学委員会
参加登録 : 当日受付(参加費:無料)
問い合わせ先:
佐藤直樹
宇宙航空研究開発機構 有人宇宙環境利用ミッション本部
システムズエンジニアリング室
TEL +81-50-3362-2882
FAX +81-29-868-3950
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■東北大学災害科学国際研究所:災害研究部門 低頻度リスク評価研究分野
(教授または准教授)(3/30)
■静岡大学理学部地球科学科:固体地球科学(地球ダイナミクス講座関連分野
(講師または助教)(4/13)
■いわて三陸ジオパーク推進協議会(事務局員)(2/23)
■第9回日本学術振興会賞授賞候補者募集(学会締切3/30)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。 geo-Flashは、
月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日 までに
事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
糸魚川-静岡構造線新倉露頭の断層上盤側の崩落
糸魚川−静岡構造線新倉露頭の断層上盤側の崩落
狩野 謙一(静岡大学理学部)
はじめに
日本を代表する逆断層露頭として有名な糸魚川−静岡構造線 (以下,糸静線)の新倉(あらくら)露頭(別称:新倉断層)の断層上盤側 が,2011年9月の台風に伴う豪雨によって崩落し,露頭状況が一変した.この露頭の2011年12月末時点での状況について報告する.図1は崩落以前,図2は崩落後の状況である.いずれも露頭の全容が把握しやすい落葉後の写真を採用した.
ジオサイトとしての新倉露頭
新倉露頭は,山梨県南巨摩郡早川町新倉北方,早川とその支流の内河内川との合流点から上流約100m,時計回りに蛇行する内河内川の左岸側,すなわち攻撃斜面側の谷壁に位置している(位置については,下記の文献等を参照).この露頭はその規模の大きさと露出の良好さなどから,日本を代表する逆断層露頭として古くから知られ,論文,中学校・高等学校の教科書,参考書, 地学案内書などに様々な形で紹介されてきた.ここは,大型バス数台が駐車可能な場所から,林道沿いに徒歩約2分というアクセスの良好な場所でもある.
この露頭を誰が何時頃に最初に紹介したのかは不明である.鮮明な写真を伴った論文としては小山(1984)がある.山下(1995)は,この露頭を「断層の露頭としては日本一と言ってよい」と評価している.最近では,日本地質学会の巡検(天野 ほか,2003),日本地方地質誌「中部地方」(狩野・河本,2006),「日本列島ジオサイト地質百選」(社団法人全国地質調査業協会 連合会/特定非営利活動法人地質情報整備・活用機構・共編, 2007),「日本の地質構造100(」狩野,2012)などで紹介されている.2010年秋には,早川町を紹介するNHKのTV全国放送でこ の露頭も取り上げられた.また,様々なレベルの地質巡検の適 地(ジオサイト)として活用され,早川流域を訪れる一般の 方々の観光スポットにもなってきた.「新倉露頭」をキーワー ドとしてインターネット検索をすれば,多数の情報がヒットす る(Yahoo,Googleともに2000件以上).
このような点から,この露頭は2001年8月に国指定の天然記念物として保護されることになった.この指定以前から,露頭についての案内看板などが設置されていた.崩落直前の2011年8月には,この露頭を含めた早川沿いに露出する糸静線についての案内看板(南アルプス東部,早川沿いの糸魚川−静岡構造線観察ガイド)が駐車場に新設され,案内パンフレット(日本列島の裂け目(糸魚川−静岡構造線):フォッサマグナを訪ねて)も作成された(いずれも早川町教育委員会,監修・狩野). 私が最初にこの露頭を見学したのは1970年代である.80年代にはほぼ毎年,90年以降の約20年間は学生巡検の案内を含めて 年数回以上は訪れている.露頭南部(図1手前側)の斜面下部 が崩落砂礫や落ち葉でおおわれたり,倒木が観察の邪魔になったりと,露頭状況は訪れるたびに異なっていた.しかしながら,少なくとも最近30年以上にわたって,この露頭の状況に大きな 変化はなかった.ちなみに狩野・河本(2006)の例(2004年撮影)では,ほとんど被覆物がなく露頭下部に新鮮な破砕帯が好露出していた.今回の断層上盤側の崩落により,30年あるいはそれ以上にわたって保持されてきた露頭状況が大改変された.
図1 上盤側が崩落する以前の糸魚川−静岡構造線新倉露頭(1999年初春撮影).人物2名が立つ斜面が断層面下盤側.左側人物の足部左側の凹みに断層破砕帯が好露出.
図2 崩落後の新倉露頭(2011年12月29日撮影)
新倉露頭での糸魚川−静岡構造線
以下では,主として小山(1984)と狩野・河本(2006)に基づいて新倉露頭における糸静線の概況を述べる.
ここでの糸静線は,N20°Wの走向で約45°西傾斜した平滑な断層面を有している.断層の上盤側は四万十帯の古第三系瀬戸川層群のスレート(粘板岩)から,下盤側は南部フォッサマグナに属する中部中新統巨摩層群櫛形山亜層群の安山岩質火山砕屑岩(凝灰岩ないしは凝灰角礫岩)からなる.崩落前には,露頭の北部の高さ20m以上の南向き斜面に,粘板岩と火山砕屑岩とが接している断層露頭が観察できた(写真1). 断層面に接するスレートは数10cmの幅で固結,一部半固結状態のカタクレーサイトからなる破砕帯を持ち,断層面近傍では細粒に破砕され,断層面から離れるにつれて破砕の程度が弱くなり,母岩のスレートに漸移する.母岩中のスレート劈開の走向はほぼ南北で,西に60〜80度傾斜する.下盤側の火山砕屑岩はほとんど破砕されていない.露出する断層面より南側(図1の手前側)では,火山砕屑岩が作る南北幅約10mは断層面とほぼ平行で平滑な斜面に連続する.すなわち,この平滑な斜面は,破砕された上盤側がとりはずされた断層面そのものである.
崩落の概要
私は糸静線を調査中の千葉大学大学院の風戸良仁氏とともに,2011年8月29日に早川町教育委員会主催の糸静線巡検の案内時に,以前と変わらぬ露頭状況を確認している.崩落を知ったのは10月20日の風戸氏からのメールであった.正確な日時は特定できないが,崩落は9月4日の12号台風または同22日の15号台風,あるいはその両者に伴う豪雨が誘因であったことに疑いはない.実際,両台風ともに早川町内に土砂災害をもたらし,その規模は30年ぶりということであった.12月末での露頭状況(図2)は,10月中旬に撮影された状況と大きな変化はない.図3は図2にもとづく露頭のスケッチで,崩落の解釈を加えた情報を含んでいる.図4は崩落主部の拡大写真である.図1を 含む崩落以前の撮影時期の異なる数枚の写真と,図2,4を含む崩落後の写真とを比較しながら,以下に崩落の概要を記す.崩落は大別すると南北2つの部分にわかれる.一つは露頭南部(手前側)での崩落砂礫による断層下盤側を構成していた平滑斜面の埋積である.斜面上部にあった上盤側の風化したスレートが分離・崩壊しながら,砂礫として落下し,斜面下部の大部分を覆ったものである.崖錘状に堆積した崩壊砂礫の厚さは斜面底部で最大1m程度,南北幅は10m前後と見積もられる.この露頭ではこのタイプの崩落による斜面下部の埋積は,過去にも度々認められたが,これほどの規模の崩落を見た覚えはない.
もう一つは,露頭北部(後方側)で生じた上盤側岩塊の斜面下部すなわち西方への滑落である.ここはもともと断層上盤側 の破砕帯を底部に持つスレートが露出していた場所で,露頭上部のスレートは風化していた.滑落岩塊の厚さは最大5〜6m程度,斜面に沿って残存する長さは約8〜10m,斜面にそう移動距離は10〜12m程度と見積もられる.滑り面は,露頭手前側では地表に露出していた断層破砕帯を利用し,奥に向かってスレートを斜めに切りながら,数m北側(後方側)で地表に到達したものと推定される.図4上部の灰色部分は滑落崖の上部と推定され,滑落崖下部および滑り面の大部分は崩落砂礫によっ て被覆されている.この滑落にともない,岩塊中のスレートは破壊されたが,完全に分離はせず,斜面にそっての長径数10cmの劈開面を破断面とする板状岩片の集合体からなる部分を作っている(図4).もともと断層面よりも高角に傾斜していたスレート劈開は,断層面と平行になるように回転し,劈開と直交する開口した破断面を軸面とする緩く開いた折れ曲がり状の褶曲を呈している.
滑落岩塊上部の露頭状況,滑落岩塊および滑落崖の規模と形態から判断して,図3中の矢印付き曲線で示すように,滑落は 岩塊が手前側斜め下にせり出すようにしてはじまった,そして,下方からの支持を失った後に,岩塊は斜面に沿って下方に滑落したものと推定される.
図3 図2にもとづく崩落の概要を示すスケッチ.四角枠内は図4の位置,矢印付き曲線は滑落岩塊の推定移動方向.
図4 滑落岩塊の拡大写真(2011年12月29日撮影).位置は図3参照
おわりに
早川流域を含む赤石山地(南アルプス)は,年間数mmの日 本有数の隆起度をもち,年間降雨量は3000mm前後に達している.急激に隆起する山地は豊富な降雨の影響を受けて急に浸食・崩壊し,生産された大量の砂礫は急流河川によって平野側 に運搬されていく(たとえば,南アルプス世界自然遺産登録推進協議会・総合学術検討委員会・編,2010).
今回の崩落は,山地全体に分布する崩壊地の規模と比較するとごく小規模なものではあるが,重要なジオサイトに大きな影響をもたらした.現在の新倉露頭の断層面の大部分を覆うのは 崩落物質であって,崩落以前のように本来の糸静線の断層面を観察するのは難しい.この状況を自然に回復させるためには,露頭を覆っている崩壊砂礫・滑落岩塊が豪雨によって洗い流される必要がある.崩落以前に露出していた断層面に規制された南側の断層下盤側平滑斜面は,このような数10年以上の間隔で起こるかもしれない今回と同様な断層上盤側の崩落によって露出したものと考えられる.今回の崩落は,平滑斜面を作ったのと同様な自然のサイクルの一環として発生したものであろうが,重要なジオサイトの保全についての困難さを感じさせる一例となった.
【文献】
天野一男・Martin, A.・依田直樹, 2003, 南部フォッサマグナにおける衝突地塊. 日本地質学会第110年学術大会, 見学旅行案内書, 95-106.
狩野謙一, 2012, 早川流域の糸魚川−静岡構造線露頭. 高木秀雄ほか・編, 日本の地質構造100. 朝倉書店, 印刷中.
狩野謙一・河本和朗, 2006, 19. 9 : 糸魚川−静岡構造線新倉露頭:西南日本と南部フォッサマグナの境界断層の代表露頭. 新妻信明・ほか(編), 2006 : 日本地方地質誌4「中部地方」, 朝倉書店, 444-445.
小山 彰, 1984, 山梨県早川沿いの糸魚川−静岡構造線―特に断層帯の形成について. 地質学雑誌, 90, 1-16.
南アルプス世界自然遺産登録推進協議会・総合学術検討委員会(編), 2010, 南アルプス学術総論. 南アルプス世界自然遺産登録推進協議会, 134p. (http://www.minamialps-wh.jp/pdf/library/015.pdf)
社団法人全国地質調査業協会連合会/特定非営利活動法人地質情報整備・活用機構・共編, 2007, 日本列島ジオサイト地質百選. オーム社, 200p.
山下 昇・編著, 1995, フォッサマグナ. 東海大学出版会, 311p.
(2012.1.20)
英語クロスワードのすすめ
英語クロスワードのすすめ
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
英語がなかなか上達しないというのが私を含めて多くの日本人研究者の悩みである.私はパズルが好きなので,外国に行くと英字新聞のパズルを解いてみるのだが,どこの国でも数独(Sudoku)は何とか解けるのに,クロスワードは歯が立たないことが多い.その国の三面記事に通じていないという事情もあるが,やはり基本的な単語力が弱いためである.クロスワードは完成した時に何とも言えない達成感があり,多少わからない単語があっても完成できるので,楽しみながら単語力をつけるのに最適のパズルであるが,邦字紙には英語のクロスワードが滅多に載っておらず,英字紙のクロスワードは難しすぎる.そこでネット書店で探してみたところ,文末のリストのような学習者向けの英語クロスワードの本があることがわかったので,自分で解いてみた感想を含めて紹介する.
まず,クロスワードの歴史と解き方について簡単に述べる.ウィキペディア英語版によると,1890年のイタリアの雑誌に4×4字で黒マスのないパズルが載っているのが最初だと言う.新聞連載は1913年の暮れにArthur Wynne氏の作をNew York World紙が始めたのが最初とされる.つまり来年で100年になる.最初はワードクロスという名だったが,黒須氏によると,ある日の題字を植字工が間違えて逆にしたため,それ以後クロスワードになった.当初は菱形だったが,1924年にSimon とSchuster両氏がクロスワード集の本を出版し,この時から現在のような正方形になった.この本は大ブームになり,医学界が「目に悪い」,「不眠症になる」などの警告を発し,パズルに熱中して子供の養育を怠った被告に「1日2題まで」とする判決が出るなど,社会現象になったそうだ.確かに中毒性はある(addictive).彼らのベンチャー出版社はこの本の成功により大発展した.現在は世界の新聞・雑誌の大部分に掲載されるが,黒須氏によると英字紙のクロスワードには次のような特徴があるという.(1) 15マス四方で黒マスは対称に並ぶ(入門用は9マス),(2) 月曜から土曜へ次第に難しくなり日曜は大型版,(3) パズル毎にテーマが設定されている.
日本語のクロスワードでは文字が並ぶ方向を「ヨコ」と「タテ」,問題文を「カギ」と呼ぶが,英語ではそれぞれacross, down, clueと呼び,答えは全て大文字で記入する.黒須氏によると英語の解き方にはそれなりのコツがある.単数・複数や時制などは問題文から判断する.例えば答えが5文字なら,”Presses with the foot”というカギの答えはstampではなくstepsであり,”I ___ a letter with a pen yesterday”の答えはwriteではなくwroteである.カギが過去形なら過去形で,進行形なら進行形で答えるので,これはヒントになる(最後が-edや-ing).Peach or pearの答えはfruitであるが,andならfruitsである,省略形(abbr.)や記号(symbol;特に元素記号)などの指示にも注意する.2語以上つなげて答えさせる場合もある.”Alphabet run”というカギもあり,これにはabc, klmnなどと答えるそうだ.英語はEやLの字を多用するので,これらが入る短い単語は作題者に重宝される.山岡氏などによると,eel(ウナギ), elm(ニレ), ere(before,古語),err(誤つ),eve(前夜),ewe(雌羊),lo(see, 古語,lo and beholdは「こはいかに」)などを覚えておくとよい.もちろんeyeも酷使されるので要注意である.
元高校教師の山岡氏の本は初心者向けで,カギの半分程度は日本語なので最も解きやすい.テーマの設定はなく黒マスの配列は不規則である.「受験生からビジネスマンまで,通勤・通学のちょっとした時間を利用して,基本の英単語を押さえよう」というキャッチフレーズがついている.忘れていた高校英語を楽しく再生・活用できる.
黒須氏の本には初級から超上級まで4段階が含まれており,多くはテーマがあって黒マスは対称的である.カギは英語であるが,難題には中級まで日本語のヒントがついている.帯には「単語は埋めて増やす!頭がやわらかくなって,英単語も覚えられるクロスワードパズル50編をレベル別に収録」とある.それぞれ欄外に枠付きマス並べがあり,これもヒントになる.本書は入門から実戦への橋渡しとして好適である.
Crowther氏の本はIntroductory, Elementary, Intermediate, Advancedの4冊があり,私はIntermediateを解いた.30編のパズルは9マスが基本だが形は様々で黒マスは全て対称に配置され,解答も同じ字が一列に並ぶなど非常に凝った造りであるが,特にテーマはない.カギには絵が多用されており,日本語は一切ない.例えば,子供が3人並んだ絵が描いてあり,カギはSee pictureだけである.Kids, pupils, friendsなどの言葉を思い浮かべて,字数などから判断する.A very big countryのように不定冠詞がつく場合はempireとかsuperpowerとかではなく1つの国の名を問うている.風見鶏の絵が描いてあって,これは英語で何と言うか思い出せずに他のカギを解いていると,ある方位が答えであることがわかる.不審に思って絵をよく見ると,鶏の下の東西南北のその字が他の字よりも大きく,鶏がそっちを向いている,というような意外性がある.建物の前で荷物を持ったボーイが客と話している絵があると,bellboyやporterやpageではなく,実はその建物が答えである.なぜかお金に関する話題が多いのが気になるが,意表を衝くことが好きで凝り性な著者の性格とイギリス英語の特徴が強く出ていて,異文化体験という意味で非常に面白い.外国語を学ぶことはその国の文化を受け容れることだということがよくわかる.
Hovanec氏の本は米国の子供向けで,タイトルは偽悪的だが内容は至って教育的である.次の本の編者Shortz氏の冗談混じりの序文がついている.上述の3冊は小型本だが,本書はA5判より少し縦長である.パズルは40編あるが,クロスワードはその半分程度で,9〜13マス四方である.「〜に似た音」,「〜と同じ韻」(語尾が同じ),「〜を並べ替え」などのヒントがあり,難しい言葉はないので,米国の子供文化を知らなくても何とか解ける.各編に1つずつ謎がかけてあり、その編を全部解くと謎も解けるようになっている。発音関連のパズルは解きにくいが、言葉捜しなどは簡単で、子供に戻った気分で楽しめる.
さて,黒須氏とウィキペディアによると,クロスワードの流行当初,The New York Times紙はこれをa primitive sort of mental exerciseだとかsinful waste in the utterly futile finding of wordsだとか馬鹿にして掲載しなかったが,1942年(第二次世界大戦中!)から掲載に踏み切った.その時どういう言い訳をしたのかは不明である.日本の新聞は今も片仮名クロスワードを週末しか載せないものが多いが,こういう偏見がまだあるのかもしれない.英字紙は毎日載せるのが普通である.この米国を代表する英字紙の「最もやさしい」(つまり月曜日の)クロスワードを集めたのがShortz氏編の本である.序文では,月曜から土曜へ難しくなるのを,読者の生活リズムに合わせるためだと力説している.レターサイズ(〜A4判)のスパイラル綴じ本で15字四方の標準パズルが50編ある.黒マスは対称で必ずテーマがあり,それぞれ出題者名が明記されている.月曜版とはいえさすがに本格的なもので,タイトルのeasiestに釣られて最初からこれに挑戦することはお勧めしない.この新聞のクロスワードは米国で最も難しいらしい.本の裏の難易度表示は「困難」より「容易」側に寄るが,スタイルの表示は「伝統的」(辞書に載る語のみ)よりも「現代的」(若者文化,流行語,言葉遊び)に寄る.副題のapproachableが妥当な形容だと思う.
まずは初心者・子供向けの本を全部埋め尽くしてから,Shortz氏の本または月曜日の英字紙で本格的なクロスワードを解いてみるのがよいだろう.なお,英語の話し方と英語の会議についても,本メルマガの23号と32号(2008年)に発表したので,興味のある方は参照されたい.拙文が若い会員の英語力向上に少しでも資すれば幸いである.
拙稿を校閲して貴重なご指摘をいただいた蟹澤聰史先生とSimon Wallis氏に感謝する.
【文献】(上に紹介した順.和書の価格は定価,洋書の価格は新品購入時の実費,変動あり)
山岡憲史 (2005) [基本単語徹底活用]英語のクロスワード101. 大修館書店.229 p. \1200+税.
黒須和土・ジャパンタイムズ「週刊ST」編 (2003) チャレンジ!英語のクロスワード.ジャパンタイムズ.125 p. \980+税.
Crowther, Jonathan (1980) Intermediate crosswords for learners of English as a foreign language. Oxford University Press, 43 p. \1000税込.
Hovanec, Helene (2002) Outrageous crossword puzzle and word game book for kids. St. Martin’s Griffin. 94 p. \572税込.
Shortz, Will (ed) (2000) The New York Times easiest crossword puzzles, Volume 1. Random House. 62 p. \718税込.
(2012.2.24)
No.170 2012/2/23 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.170 2012/2/23 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2012年大阪大会:トピックセッション募集中! 3月12日(月)〆切り!!
──────────────────────────────────
日本地質学会は,近畿支部の支援のもと,大阪府立大学(中百舌鳥キャンパス)において第119年学術大会(2012年大阪大会)を2012年9月15日(土)〜17日(月)の日程で開催いたします.
1月号のNews誌(p.4-5)において,既にご案内しておりますが,現在,トピックセッションの募集期間中です.トピックセッションは,広く地質学の領域をカバーし,これから新分野あるいは注目すべき分野になりそうな内容を扱うものとします.形式はレギュラーセッション(旧:定番セッション)と同じです(15分間の口頭発表,あるいはポスター発表).
なお,本大会も前回(水戸大会)同様,シンポジウムの募集はありません.
募集締切:2012年3月12日(月)
応募方法など詳細は、、、
http://www.geosociety.jp/science/content0050.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。 geo-Flashは、
月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日 までに
事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.173 2012/4/3 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.173 2012/4/3 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】第4回日本地学オリンピック本選の結果が発表されました
【2】本の紹介:「クラカトアの大噴火 世界の歴史を動かした火山」
【3】地球惑星フォトコンテスト―入選作品展示会のお知らせ―
【4】支部・専門部会情報
【5】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】第4回日本地学オリンピック本選の結果が発表されました
──────────────────────────────────
第4回日本地学オリンピック本選が茨城県つくば市において3月25〜27日に
行われ、最優秀賞4名、優秀賞4名のほか、茨城県知事賞、つくば市長賞、
つくば科学万博記念財団理事長賞、産総研地質調査総合センター賞が授与さ
れました。
第4回日本地学オリンピック最優秀賞
井原 央翔(イハラ ヒロカ)高2 愛媛県立松山東高等学校
中里 徳彦(ナカサト ノリヒコ)高2 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校
松尾 健司(マツオ ケンジ)高2 灘高等学校
丸山 純平(マルヤマ ジュンペイ)高2 聖光学院高等学校
第4回日本地学オリンピック優秀賞
真田 兼行(サナダ カズユキ)中3 灘中学校
島本 賢登(シマモト ケント)高2 広島学院高等学校
新宅 和憲(シンタク カズノリ)高1 広島学院高等学校
杉 昌樹(スギ マサキ)中3 灘中学校
茨城県知事賞(総合成績1位)
中里 徳彦(ナカサト ノリヒコ)高2 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校
つくば市長賞(女子1位)
渡邊 ふみ(ワタナベ フミ)高2 AICJ高等学校
つくば科学万博記念財団理事長賞(中学生1位)
真田 兼行(サナダ カズユキ)中3 灘中学校
産総研地質調査総合センター賞(標本鑑定1位)
松尾 健司(マツオ ケンジ)高2 灘高等学校
なお、今年行われる第6回国際地学オリンピック アルゼンチン大会への派遣
選手は、4月中旬頃に発表される予定です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】本の紹介:クラカトアの大噴火 世界の歴史を動かした火山
──────────────────────────────────
サイモン・ウィンチェスター著 柴田裕之訳
クラカトアの大噴火 世界の歴史を動かした火山
早川書房 2004年1月31日初版 ISBN4-15-208542-6 C0025
466 p. 157x217x37 mm, \2800+税
Simon Winchester
Krakatoa: The Day the World Exploded, August 27, 1883
Penguin, 2004 (Viking, 2003) ISBN-13: 978-0-141-00517-1
432 p. 128x197x30 mm, \2205税込(購入時の実費,変動あり)
この本は,19世紀以後の現代世界で最大の噴火の1つであるインドネシアのクラカトア火山1883年噴火(噴出量25 km3,火山爆発指数VEI=6.5;本書による)について,この噴火の推移とそれによる津波災害(死者36,000以上)を中心に,プレートテクトニクスに基づく地球科学的背景やこの火山の噴火史,生物学・生物地理学・気象学・大気物理学分野の関連現象,そしてこの噴火の社会的な背景・影響,歴史的意義を含めて,「人に焦点を当てて壮大なスケールで描いた」(早川書房の宣伝文)文理融合的な労作である.これは地質図の創始者ウィリアム・スミスを扱った同じ著者の「世界を変えた地図」(原書2001年、和訳は早川書房から本書より遅れて2004年7月に出版)の次作であり、2003年の出版(和訳は2004年1月)から8年も経過しているので,既に新聞,雑誌,ネットなどに火山の専門家や一般人が多数の書評や感想文(多くは好意的)を発表している.今さらの感もあるが,東日本大震災を経たこの時期に,もう一度この本を読み直し,我々の学問を見直す必要があるのではないかと考え,ここに紹介する.
本書の訳者は,あとがきの最後に,「日本に暮らす私たちにしてみれば,クラカトアの動きを待つまでもなく,地殻の活動の影響を体験する機会はいくらでもある.ただし,人的・物的被害はあくまで本書のような読み物の世界の中に収まっていてほしいものだ」という願いを述べている.しかし,本書の出版直後の2004年12月に,同じインドネシアを震源として,同国やインド洋周辺諸国で津波による死者計28万以上を出した海溝型のスマトラ大地震が発生し,2005年3月にもその南の隣接地域で死者1300以上の海溝型地震が,2006年5月にはジャワで死者5000以上の直下型地震が起きた.2008年5月には死者7万に近い中国の四川地震,2010年1月には,カリブ海のハイチで死者22万以上の直下型地震が発生した.そして,2011年3月に死者・行方不明者2万に達する東日本大震災が発生した.この間,イラン,パキスタン,チリ,トンガ,ニュージーランド,イタリア等の地震でも相当数の死者が出た.訳者の願いも空しく,本書が出てから現在までの8年間に,クラカトア大噴火による死者の15倍以上,60万人を超える人々が地殻の活動に起因する自然災害で死亡した.火山の噴火による死者は少なかったが,例えば2010年にアイスランドのエイヤフィヤトラ氷河火山が噴火し,その火山灰により欧州の航空網が1週間も麻痺する事態が発生した(鈴木雄治郎(2010),日本地質学会News, 13(5), 10-12).
現時点でこの本を読む1つの意味は,巨大噴火の実像を全体的に把握できる優れたドキュメントという点である.インドネシアのタンボラ火山噴火(1815年,100 km2)など,クラカトアより大規模な歴史時代の巨大噴火は他にも知られているが,噴火や被害の様子が最も詳しく記録されているのは最新のクラカトアである.もし日本で巨大噴火が発生するとどうなるかについては,石黒耀の小説「死都日本」(講談社, 2002年,2005年本学会表彰)によく描かれているが,実際には約7300年前の鬼界カルデラの噴火(噴出量>170 km3)以後,日本で巨大噴火は起きていない.歴史時代に日本が経験した最大の火山噴火は朝鮮と中国の国境に位置する白頭山の噴火(平安時代,噴出量50 km3)であり,その火山灰は東北地方から北海道にかけて5 cm程度の厚さで堆積しているが,この噴火についての確実な歴史資料は日本,朝鮮,中国いずれの国にも残っていない(宮本ほか, 2002; 月刊地球号外39, 202-).渤海国がこの巨大噴火で滅んだという議論があったが(町田洋, 1992;火山噴火と渤海の衰亡,「謎の王国・渤海」,104-, 角川選書),最近の目潟火山湖底堆積物の年縞の研究によると噴火発生は929年であり(川手ほか, 2010; 地質雑, 116, 349-),同国滅亡(926年)の直接の原因ではないらしい.しかし,亡国の混乱期に噴火が追い打ちをかけたことは間違いないだろう.
本書には時系列的に事項を並べた表がついていないので,噴火に伴うイベントがどのような順序で起こったのかを理解するには,ノートをとりながら読む必要がある.1883年の噴火は,まず5月10日の地震や空振で始まり,5月20日にクラカトア島の南峰(ラカタ)が噴火した.この噴火は翌日まで続いたが,被害はなく,22日には静かになった.6月24日に島の中部のダナンから噴火が再開し,7〜8月にかけて噴火が続いたが,特に被害はなかった.しかし,8月26日(日)の午後になって,ジャワ島西岸の町に熱い軽石が降るようになり,大きな大砲を打つような音が聞こえ,夜には空振でガラスが割れるなどの被害が出るようになった.そして27日(月)になって大きな爆発が4回発生した(クラカトア時間で5:30, 6:44, 8:20, 10:02).このうち3回は地球全体で気圧の変化が観測され,4回目の最大の爆発の衝撃波は地球を7周回ったことが各地の気圧計に記録されている.最初の爆発で大きな津波が起き,6:15にスマトラ島のケティンバンが壊滅,ジャワ島のアンイェルもこの頃津波で壊滅した.津波は9:00にジャワ島北西端のメラックに達し,11:30にはジャワ島北岸中部のバタビア(現ジャカルタ)に達した.同市では12:36に最大津波が襲来し,この日の午後まで暗い灰に覆われ,泥の雨が降ったが,28日(火)の夜明けには全て止んだ.つまり,これほどの規模の噴火でも26日の午後から27日の午後まで,激しい活動は24時間程度であったことがわかる.これは過去や将来の巨大噴火を考える上で参考になる.
本書のもう一つの興味は,様々な学説や学者についての著者独自の見解である.この本では,大規模な地質区の意味や科学史的な時代背景を読者に理解させるために,まずアジアとオーストラリアの動物区の境界であるウォーレス線の話が出てくる.しかし,ウォーレスの進化論における大きな貢献を,同時代のダーウィンが正当に扱わなかった,という方向に話が進んでしまう.地質的な境界(プレート境界)とウォーレス線はどう見ても一致せず,ほぼ直交するのに,この不一致についての説明はなく,同じ沈み込み帯上のバリ島とロンボク島の間の幅25 kmの海峡をウォーレス線が通る理由も説明がないのは残念である.一方,大陸移動説のウェーゲナーが同時代の学界からいかに憎まれていたか,その理由は何か,なぜ彼の学説が長く欧米の地質学界で無視されたかについては,よく説明されている.プレートテクトニクスの創始者の一人であるT. ウィルソンが,いつもポケットにトランスフォーム断層の模型を入れていて,誰にでも嬉々として実演したというようなエピソードが随所に散りばめられている.中でもオックスフォード大学の地質学科出身の著者自身の体験談は面白い.著者は学生時代,プレートテクトニクス創始者の一人であるH.H.ヘスの講演会の代表世話役をしたが,いろいろ不運が重なって大失敗をした話は非常に生き生きしており,ヘスの酒好きで人なつこい性格をよく伝えている.学生時代にグリーンランドで古地磁気試料採集のための探検旅行に手伝いとして参加した話にも,青年期の実体験に裏付けられた輝きがある.
本書の文系の話について私はあまり批評能力がないが,少しだけ指摘する.インドネシアにおけるイスラム教の原理主義化と独立運動がクラカトアの噴火を機に顕在化した,という本書第9章の話は,「イスラム教が根本的に帝国主義の宗教であることを忘れてはならない」,「インドネシアはアラビア人によって改宗させられ,今なお,アラビアやアラビア人に精神的な指標やよりどころを求めている」(訳書p. 367)という基本認識が基調となっていて,2001年の米国東部9.11テロ事件や2002年のバリ島爆弾テロ事件(p. 379)が続いていた本書執筆時の欧米の雰囲気を色濃く反映しているように思う.また,本書前半のオランダの東インド会社に関する記述を読むと,15世紀末の「教皇贈与」によって世界を半分ずつ与えられたスペインとポルトガルに遅れて,16世紀から植民地獲得競争に参入したオランダとイギリスの相互関係がよくわかる.1726年出版のスウィフトのガリバー旅行記にはオランダ人への悪口がずいぶん書かれているが,本書にも多少そういう気分がある.
さて,クラカトア島は1883年の噴火で一度消滅したが,1928年にアナック(子供)・クラカトア島が現れ,それ以後噴火を繰り返しながら,著者の計算では毎週5インチ(これを12.7 cmと訳すのは数学的には正しいが地学的には誤り)のスピードで現在も成長を続け,既に標高500 mを超える火山になっている.大噴火前のクラカトア島南峰の標高は約800 mだったので,それに近づいている.本書最終章には著者のクラカトア島訪問記がある.
本書の巻末には,「この本を書くために有益で面白かった本」が100冊リストアップされている.私の高校時代の恩師は,「本を1冊書くには,100冊は読まなければダメだ」と仰っていた.この著者はそれを実践しており,見習わなくてはならないと思う.推薦図書や映画の説明も,「推薦できない1本の映画」の批評を含めて大変面白い.
この本の日本語訳は非常によくできていて,専門用語の訳も正確である.しかし,原書の著者の勘違いによるいくつかの間違いがそのまま訳されている.訳書115頁の「ブリュンヌは更新世の終わり,今からおよそ1万年前に磁場の逆転があったことを示した」というのは,およそ70万年前の間違いである.これに関連して,原書では松山基範の名前がMotonariになっている.また,原書384頁(訳書425頁)の脚注に小笠原の海底火山「福徳岡の場」が出てくるが,Fukoto Kuokanabaになっている.訳書129頁の「海洋リソスフェアは薄く,厚さはおそらく6〜7 km」というのも原書の著者が海洋地殻と海洋リソスフェアを混同している.場所にもよるが,厚さ約100 kmが正しい.また,この頁の「その熱は今,引いている」という訳はわかりにくい.これは地球内部に蓄えられた集積熱と放射性同位体の崩壊熱が次第に減少していることを指す.
現時点で本書を読んで思うことは,10年後でも20年後でもよいから,日本人が世界に向けて,本書のように地球科学と人文学を縦横に編み上げた,しかし日本人独自の世界観に基づく,筋の通った一般向けの東日本大震災についてのドキュメントを書くとすれば,どのような内容になるだろうか,ということである.しかし,我々地質学研究者は文筆家ではないので,最近も世界で年平均数万人が犠牲になる地震,火山,津波などの「プレート災害」を少しでも減災するために真剣に研究を進め,世界と連携して行動していく必要がある.津波は現在の科学レベルでもその襲来の10分以上前(場合によっては数時間以上前)に予報できる災害であり,火山噴火も予報に成功して住民を避難させた例が日本にあり、地震も大きな揺れが到達する数秒前に予報するシステムが世界に先駆けて日本で機能している.希望を持って進もう.本文中の噴出量,死者数などは,特に断らない限り2012年版理科年表に基づく.
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】惑星地球フォトコンテスト―入選作品展示会のお知らせ―
──────────────────────────────────
惑星地球フォトコンテストの入選作品展示会が「地質の日」にあわせて
開催されます.皆さまお誘い合わせの上,ご来場ください.
■第2回惑星地球フォトコンテスト入選作品展示(昨年の入選作品)
主催:東海大学自然史博物館(共催:一般社団法人日本地質学会)
会場:東海大学社会教育センター東海大学自然史博物館
〒424-8620 静岡県静岡市清水区三保2389
期間:2012年4月28日(土)〜5月13日(日)
http://www.sizen.muse-tokai.jp/
■第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品展示(本年の入選作品)
主催:一般社団法人日本地質学会/千葉県立中央博物館
会場:千葉県立中央博物館
〒260-8682 千葉県千葉市中央区青葉町955-2
期間:2012年4月21日(土)〜6月3日(日)
http://www2.chiba-muse.or.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】支部・専門部会情報
──────────────────────────────────
■地質技術伝承講習会開催
日時:2012年4月8日(日)14:00〜16:00
場所:北とぴあ 第1研修室(7階)(東京都北区王子1-11-1)
講師:古谷 尊彦氏 (千葉大名誉教授・日さく顧問)
テーマ:地形情報から見た地質の理解 −斜面変動現象との関連で−
共催:(社)全国地質調査業協会連合会 関東地質調査業協会
参加費:無料,どなたでも参加できます.
申し込み方法:公開中のジオ・スクーリングネットによる登録または
学会へのFAX,下記担当幹事へのe-mailにて受け付けます.
1)ジオ・スクーリングネット; https://www.geo-schooling.jp/
2)関東支部担当幹事 緒方信一(中央開発株式会社 ogata@ckcnet.co.jp 兼,問い合わせ先)
3)日本地質学会事務局気付 関東支部 FAX:03-5823-1156
■関東支部 2012年度総会
日時:2012年4月8日(日)16:00〜17:00
報告および議題
1)支部功労賞授与式
2)支部幹事選挙結果報告
3)2011年度 活動報告・会計報告
4)2012年度 活動方針・予算報告
5)関東支部選挙関連の規定の改正
関東支部会員の方で総会に欠席される方は委任状をお願いします.
委任状送付方法:
○郵送またはFAXの場合は下記にお送りください.
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F
日本地質学会事務局気付 関東支部事務局
FAX:03-5823-1156
○E-mail送付の場合
関東支部のメールアドレス(kanto@geosociety.jp)へ委任状をご返信下さい
(このまま返信しても届きます.ただし,下記の委任状へのご記入をお忘れなく).
メールによる委任状の締切は4月7日(土)午後6時まで.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■名古屋大学博物館 特任助教(1名) (5/15)
■島根大学総合理工学部地球資源環境学科(応用地質学) 教授(1名) (5/18)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。 geo-Flashは、
月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日 までに
事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.172 2012/3/21 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.172 2012/3/21 ┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】理事選挙および監事選挙結果のお知らせ
【2】コラム:世界のM9地震と地質学の課題
【3】本の紹介:「日本の地形・地質―見てみたい大地の風景116」
【4】プレスリリース「東日本大震災にかかる地質学の役割と対応について」
【5】2012年度会費払込/学部学生・院生割引申請受付中!3月30日(金)〆切
【6】支部・専門部会情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】理事選挙および監事選挙結果のお知らせ
──────────────────────────────────
選挙規則ならびに選挙細則もとづき、一般社団法人日本地質学会理事選挙および監事選挙を実施いたしましたので、ご報告いたします。
一般社団法人日本地質学会 選挙管理委員会
委員長 兼子 尚知
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0065.html
(会員番号・パスワードによるログインが必要です。
ログインの方法は http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】コラム:世界のM9地震と地質学の課題
──────────────────────────────────
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
マグニチュード9.1(ここでは国立天文台(2011)に基づくモーメント・マグニチュード(Mw)を用いる)の2011年東北地方太平洋沖地震とそれに伴う津波および原子力発電所の事故による東日本大震災が発生してから1年になる。体に感じる余震はまだ頻発しているが、ここ数ヶ月間は被害を伴う地震の発生はない。今後の地震災害について考えるために、地球上で過去にM9クラスの超巨大地震が発生した地域における、その前後の地震活動の推移を知ることが大切だと思い、それらの地域における最近の大地震の時空分布を簡単にまとめてみた。そして、我々地質研究者の当面の課題について考えてみたい。
続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0365.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】本の紹介:「日本の地形・地質 見てみたい大地の風景116」
──────────────────────────────────
写真:北中康文、解説:斎藤 眞・下司信夫・渡辺真人
文一総合出版、東京、287 p.(18x11 cm)、定価:2,200円+税
表題にある大地の写真+解説集、見て・読んで・楽しい本が出版された。旅好きの方に必携の1冊であり、温泉巡りの旅にも携帯すると自然の美しさ・素晴らしさが道々理解でき、充実した旅となること請け合いである。また大地をこれから研究しようとする学生諸君を手引してくれる書でもある。本書は日本全国の天然記念物・世界遺産・ジオパーク・地質百選などから116ケ所の美しい自然景観を選び、その場の地質現象やそれが持つ意味が解説される。解説地点は冒頭の日本地質図上にプロットされている。写真はそれぞれの地点で最適な時期を見て撮影されたものと思われ、非常にきれいで魅力的である。
本書は、まず「自然の風景を楽しむために」と題して、筆頭著者の斎藤 眞さんが本書出版の目的について述べ、観光地や温泉地など、何処にでもある地形や露頭に現れた地質現象が本書の解説などによって正しく理解され、内容を知ることによって自然現象を深く理解し・楽しむことを提案する。写真は全国からの116ケ所550枚に及ぶが、それぞれが適切な時期に写真家、北中康文さんによって撮影されており、見事な出来栄えである。前書には「シャッターを切る前に」と題して、時間軸が重要な地質現象などの撮影を成功させる秘訣の解説がある。
本書は北海道地方から九州・沖縄まで8章に分けられている。北海道地方は、冒頭の知床五湖から見る紅葉に新雪を被る羅臼岳知床連峰の見開き写真に度肝を抜かれる。現世の知床半島火山岩類の解説があり、ついで後期白亜紀の根室の水中玄武岩、車石の解説がある。次いで白滝黒曜石、北海道ならではの夕張石炭大露頭と幌満かんらん岩体、そして新冠泥火山・有珠山と昭和新山などの現世火山岩類である。
東北地方は、まず青森県の恐山の金鉱床、仏ヶ浦の中新世凝灰岩類の海食地形、五能線沿いの十二湖・日本キャニオンの凝灰岩の崩落地形、岩手県では陸中海岸北部と南部の海食地形が6頁にわたり、そして夏油温泉の石灰華も収録されている。秋田-山形県からは、目潟火山群のマール、鳥海山は4頁にわたり紹介された。山形-宮城県からは蔵王山、福島県の磐梯山などの著名な火山がそれぞれ2頁を費やして紹介された。福島県には他に鮮新世凝灰岩の浸食地形のきのこ岩、塔のへつりなどがある。
関東地方の茨城県からは中新世火砕岩が作る袋田の滝、出島のカキ礁:カキ殻は埋れないように比重が軽くカキ礁を作りやすい。栃木県からは塩原木の葉化石、安山岩で堰き止められた華厳の滝、建材で有名な大谷石。群馬県からは中新世凝灰岩の河食地形である吹割の滝、急崖を流れる常布の滝、草津白根山の湯釜、浅間山とその周辺。その他、埼玉県の秩父・長瀞、千葉県の犬吠埼と屏風ヶ浦、南関東ガス田、鮮新世の黒滝不整合、館山の海成段丘。東京都も1件あって、山の手崖線地形・武蔵野台地。神奈川県は三浦半島。
中部地方はまず新潟県の中新世の新津油田、糸魚川・静岡構造線、小滝ヒスイ峡、富山県では現世凝灰岩を削った称名滝、立山カルデラと大崩壊、石川県では百万貫岩と桑島化石壁、福井県の東尋坊海岸、山梨県の瑞牆山岩峰群、名峰冨士山には6頁割り当てられた。長野県大鹿村の中央構造線、氷河地形の木曽駒ヶ岳千畳敷、花崗岩の河食地形の寝覚ノ床、岐阜県の飛水峡、根尾谷断層、春日のスカルン鉱床、石灰岩の赤坂金生山、木曽三川と濃尾平野、愛知県は鳳来寺山が選択された。
近畿地方に入って滋賀県は伊吹山、三重県の二見浦の夫婦岩、熊野鬼ヶ城と獅子岩赤目四十八滝、京都府の天橋立、琴引浜、大阪府-奈良県の二上山、奈良県兜岩と鎧岳、屏風岩、和歌山県の一枚岩と虫喰岩、橋杭岩、さらし首層、滝の拝、瀞八丁など5件、兵庫県の六甲山、玄武洞、兵庫-鳥取県の山陰海岸など多数。
中国地方は鳥取砂丘、島根県の立久恵峡・石見銀山、岡山県は神庭の滝、広島県の帝釈峡の雄橋・久井の岩海・三段峡の竜門、山口県の高山と須佐湾、秋吉台、網代ノ鼻の赤色層、四国地方は香川県の屋島、徳島県の阿波の土柱、四国の中央構造線、土釜、大歩危・小歩危、宍喰浦の化石漣痕、愛媛県に入って別子銅山、砥部衝上断層、面河渓、四国カルスト、高知県の室戸岬、竜串海岸など。
九州地方では福岡県の平尾台、芥屋の大門、佐賀県は七ッ釜、長崎県の雲仙平成新山、熊本県は阿蘇カルデラ、立神峡、球泉洞と槍倒、天草御所浦、大分県の耶馬渓、八丁原地熱発電所、宮崎県高千穂峡、青島・鬼の洗濯岩、猪崎鼻フルートキャスト、関之尾滝、鹿児島県は霧島火山群、曽木の滝、桜島と姶良カルデラ、開聞岳、種子島の砂鉄、屋久島、沖縄県は石灰岩の海食崖である万座毛、槍穂の様に鍾乳石が垂れ下がる玉泉洞が取り上げられている。
末尾には日本の主要な地質史が纏められ、また火成岩・堆積岩・変成岩の分類が示され、また本書で使われた用語の解説も行われているので、一般利用者に非常に便利な配慮がなされている。
解説者はかって(1992年)、天然記念物特集を地質ニュース453,454号で企画し地学の普及に努めたが、今回はより広範囲に数多くの地質現象が取り上げられており、読者の地形・地質に対する理解がより深まるものと期待される。一般有識者や学生諸君に是非一読をお勧めしたい。
<石原舜三>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】プレスリリース「東日本大震災にかかる地質学の役割と対応について」
──────────────────────────────────
東日本大震災から1年を迎えるにあたり、この間の日本地質学会の取り組みと成果についてのプレスリリースを行いました。
提言の公表、シンポジウムの開催、学術的復旧事業への取り組み、学術的復旧事業の成果などを紹介しています。
プレスリリースの内容はこちら、、、
http://www.geosociety.jp/engineer/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2012年度会費払込/学部学生・院生割引申請受付中!3月30日(金)〆切
──────────────────────────────────
■2012年度会費払込について
次年度分会費の前納をお願いいたします。自動引き落としを登録されている方は、12月26日(月)に引き落としを行いました。お振込の方へは、請求書兼 郵便振替用紙を、12月19日に発送いたしましたので、折り返しご送金をお願いします。
詳しくは、 https://www.geosociety.jp/user.php
(会員番号によるログインが必要です。
ログインの方法は http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html)
■2012年度(2012.4〜2013.3)学部学生・院生割引申請受付中
最終締切日:2012年3月30日(金)
申請書を毎年ご提出いただかなければ割引会費は継続されていきませんので、くれぐれもご注意下さい。
一次締切日(11月16日)までに申請書をご提出いただけなかった学部学生・院生のかたに対しては、【正会員】の金額にて請求書を発行(引落のかたは12月26日に自動引落)いたしました。
割引会費を希望する学部学生・院生のかたは、必ず最終締切までに申請書の提出をして下さい。あわせて、請求書(=郵便振替用紙)の金額を訂正し、2012年度会費をご送金ください(郵便振替用紙の再発行はいたしません)。
※郵便振替にて送金されるかたへ※
請求書に同封されている会費請求案内(黄色の用紙)の裏面に割引会費の申請書が印刷されていますので、ご利用ください。
申請書のダウンロードは、
https://www.geosociety.jp/user.php(会員番号によるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部・専門部会情報
──────────────────────────────────
■関東支部 2012年度総会・地質技術伝承講習会開催
日時:2012年4月8日(日)13:30〜16:00
13:30〜 受け付け開始
14:00〜16:00 地質技術伝承講習会
講師:古谷 尊彦氏 (千葉大学教授 株式会社日さく顧問)
場所:北とぴあ 第一研修室(東京都北区王子1-11-1)
参加費:無料(会員,一般共)
※地質技術講習会に引き続き,関東支部総会(16:00〜16:45)を開催いたします.
地質技術伝承会に引き続き参加をお願いいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第11回中生代陸域生態系国際シンポジウム(以下MTE)および韓国の恐竜サイト巡検
中生代の陸域生態系のダイナミクス―超大陸の分裂に連動する環境変動に対する応答―を理解することを目指し,表題の国際シンポジウムが開催されます.
提案中のIGCP507後継プロジェクトが採択された場合,合同で第一回国際シンポジウムを開催する予定です.
シンポジウム
場所:韓国・光州市・金大中コンベンションセンター
日時:2012年8月15日(水)〜18日(土)
巡検(韓国南部の恐竜化石産出地):2012年8月19日(日)〜22日(水)
申込み締切:2012年3月30日(金)
詳細な情報,申し込みはホームページをご参照ください.
http://www.2012mte.org/
(情報提供:長谷川卓)
■地質標本館特別展「砂漠を歩いてマントルへ −中東オマーンの地質探訪」
開催期間:2012年4月17日(火)〜7月1日(日)
場所:産業技術総合研究所 地質標本館(茨城県つくば市東1-1-1)
詳しくは、、、
http://www.gsj.jp/Muse/eve_care/2012/omans_geology/omans_geology_index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■第3回(平成24年度)日本学術振興会 育志賞受賞候補者募集(学会締切5/30)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.171 2012/3/6 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.171 2012/3/6 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】「ネット地学部 ちーとも」まもなくスタート!
【2】2012年大阪大会:トピックセッション募集中! 3月12日(月)〆切!!
【3】英語クロスワードのすすめ
【4】2012年度一般社団法人日本地質学会理事選挙の実施について
【5】2012年度会費払込/学部学生・院生割引申請受付中!3月30日(金)〆切
【6】支部・専門部会情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「ネット地学部 ちーとも」まもなくスタート!
──────────────────────────────────
「ネット地学部 ちーとも」は、日本地質学会が提供するSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)です。
地質学会では学生・生徒、教師、研究者などアマチュアからベテランまで、会員に限らず多くの方に地球科学をキーワードにして交流して頂ける場を提供しようと、昨年より準備を重ねて参りました。現在、仮運転中のサイトでは既にいくつかのコミュニティが立ち上がり、参加者も徐々に増えつつあります。会員の皆様には、これから4月からの「ちーとも」本格稼働に向けて、ぜひサイトを見て頂き「ちーとも」の活動にご協力頂けるようお願いします。
「ちーとも」はこちらから →→ http://www.chitomo.jp
「ちーとも」は地球科学に関心を持つ仲間の集まるバーチャルな地学部を目指しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2012年大阪大会:トピックセッション募集中! 3月12日(月)〆切!!
──────────────────────────────────
日本地質学会は、近畿支部の支援のもと、大阪府立大学(中百舌鳥キャンパス)において第119年学術大会(2012年大阪大会)を2012年9月15日(土)
〜17日(月)の日程で開催いたします。
1月号のNews誌(p.4〜5)において、既にご案内しておりますが、現在、トピックセッションの募集期間中です。トピックセッションは、広く地質学の領域をカバーし、これから新分野あるいは注目すべき分野になりそうな内容を扱うものとします。形式はレギュラーセッション(旧:定番セッション)と同じです(15分間の口頭発表,あるいはポスター発表)。
なお、本大会も前回(水戸大会)同様、シンポジウムの募集はありません。
募集締切:2012年3月12日(月)
応募方法など詳細は、、、
http://www.geosociety.jp/science/content0050.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】英語クロスワードのすすめ
──────────────────────────────────
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
英語がなかなか上達しないというのが私を含めて多くの日本人研究者の悩みである。私はパズルが好きなので、外国に行くと英字新聞のパズルを解いてみるのだが、どこの国でも数独(Sudoku)は何とか解けるのに、クロスワードは歯が立たないことが多い。その国の三面記事に通じていないという事情もあるが、やはり基本的な単語力が弱いためである。クロスワードは完成した時に何とも言えない達成感があり、多少わからない単語があっても完成できるので、楽しみながら単語力をつけるのに最適のパズルであるが、邦字紙には英語のクロスワードが滅多に載っておらず、英字紙のクロスワードは難しすぎる。そこでネット書店で探してみたところ、文末のリストのような学習者向けの英語クロスワードの本があることがわかったので、自分で解いてみた感想を含めて紹介する。
詳しくはこちら、、、http://www.geosociety.jp/faq/content0360.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2012年度一般社団法人日本地質学会理事選挙の実施について
──────────────────────────────────
2月10日に役員の立候補が締め切られました。選挙規則、選挙細則に基づき、2012年度の理事選挙を2月20日(月)〜3月8日(木)まで実施いたします。
理事選挙は2012年度からの新代議員による投票となります。
監事については会員から1名、理事会推薦から1名、計2名の立候補届出がありましたが、会員からの候補者は定数内のため、監事の投票は行いません。
■理事立候補者、および監事立候補者の名簿は、、、
http://www.geosociety.jp/members/content0064.html
(会員番号・パスワードによるログインが必要です。
ログインの方法は http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html)
理事選挙の開票は3月14日(水)14時から学会事務局で行います。
開票の立ち会いをご希望のかたは、3月7日(水)までに選挙管理委員会
(main@geosociety.jp)にお申し出ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2012年度会費払込/学部学生・院生割引申請受付中!3月30日(金)〆切
──────────────────────────────────
■2012年度会費払込について
次年度分会費の前納をお願いいたします。自動引き落としを登録されている方は、12月26日(月)に引き落としを行いました。お振込の方へは、請求書兼 郵便振替用紙を、12月19日に発送いたしましたので、折り返しご送金をお願いします。
詳しくは、 https://www.geosociety.jp/user.php
(会員番号によるログインが必要です。
ログインの方法は http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html)
■2012年度(2012.4〜2013.3)学部学生・院生割引申請受付中
最終締切日:2012年3月30日(金)
申請書を毎年ご提出いただかなければ割引会費は継続されていきませんので、くれぐれもご注意下さい。
一次締切日(11月16日)までに申請書をご提出いただけなかった学部学生・院生のかたに対しては、【正会員】の金額にて請求書を発行(引落のかたは12月26日に自動引落)いたしました。
割引会費を希望する学部学生・院生のかたは、必ず最終締切までに申請書の提出をして下さい。あわせて、請求書(=郵便振替用紙)の金額を訂正し、2012年度会費をご送金ください(郵便振替用紙の再発行はいたしません)。
※郵便振替にて送金されるかたへ※
請求書に同封されている会費請求案内(黄色の用紙)の裏面に割引会費の 申請書が印刷されていますので、ご利用ください。
申請書のダウンロードは、
https://www.geosociety.jp/user.php(会員番号によるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部・専門部会情報
──────────────────────────────────
■構造地質部会緊急例会「社会への発信とリテラシー」
東日本大震災後,地球科学と社会との関わりを考え直すべきときが来ているのではないか?という問いから,今回の緊急例会を企画いたしました.
地球科学の理解がかつてないほど必要とされているこの時代に,どのようにその必要性を発信して行くべきでしょうか?
地球科学リテラシーの向上のためのアウトリーチのあり方などを構造地質を専門とする研究者が集い,考える会にしたいと思っております.
日時:2012年3月17日(土)、18日(日)
場所:東北大学理学部
プログラム等、詳細は、、、
http://struct.geosociety.jp/SGMeeting2012/
参加登録も開始いたしました。締め切りは2012年2月22日(水)です。
http://struct.geosociety.jp/SGMeeting2012/can_jia_deng_lu.html
■関東支部 2012年度総会・地質技術伝承講習会開催
日時:2012年4月8日(日)13:30〜16:00
13:30〜 受け付け開始
14:00〜16:00 地質技術伝承講習会
講師:古谷 尊彦氏 (千葉大学教授 株式会社日さく顧問)
場所:北とぴあ 第一研修室(東京都北区王子1-11-1)
参加費:無料(会員,一般共)
※地質技術講習会に引き続き,関東支部総会(16:00〜16:45)を開催いたします.
地質技術伝承会に引き続き参加をお願いいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■有人月探査を見据えた 科学・利用ミッション ワークショップ
国際有人探査のロードマップ(Global Exploration Roadmap)により、月は次期有人探査の主要な目的地として位置付けられ、有人月探査の検討は今後、具体化が進むと考えられます。そのような中、SELENE(かぐや)の成功により、月科学分野において先進性と優位性とを獲得しつつある我が国にとって、有人による月の科学探査・利用ミッションは最も貢献出来る分野の一つだと考えられます。そこで、「有人月探査を見据えた科学・利用ミッションワークショップ」を開催し、皆様と議論を深めてまいりたいと思います。
是非ご参加ください。
日時:2012年3月8日(木)9:50〜
会場:宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙科学研究所 A棟2階 大会議場
主催:宇宙航空研究開発機構 月・惑星探査プログラムグループ
(JSPEC)/SE室/ 有人月拠点システムチーム
共催:宇宙理学委員会
参加登録:当日受付(参加費:無料)
問い合わせ先:
佐藤直樹
宇宙航空研究開発機構 有人宇宙環境利用ミッション本部
システムズエンジニアリング室
TEL +81-50-3362-2882
FAX +81-29-868-3950
■第2回仁科記念シンポジウム「アイソトープ科学の最前線」
日時:2012年3月23日(金)14:00〜17:00
場所:科学技術館サイエンスホール(東京都千代田区北の丸公園)
主催:仁科記念財団、日本アイソトープ協会、理化学研究所仁科加速器研究センター
参加費:無料
詳しくは、http://www.nishina-mf.or.jp/kouen/2012_3_23_poster.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■福岡大学国際火山噴火史情報研究所:PD研究員(3/21)
■新潟大学教育研究院:自然科学系教員(教授または准教授)(4/27)
■平成24年度東レ科学技術賞および東レ科学技術研究助成候補者募集(学会締切8/31)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。 geo-Flashは、
月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日 までに
事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
世界のM9地震と地質学の課題
世界のM9地震と地質学の課題
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
マグニチュード(M)9.1(ここでは国立天文台(2011)に基づくモーメント・マグニチュード(Mw)を用いる)の2011年東北地方太平洋沖地震とそれに伴う津波および原子力発電所の事故による東日本大震災が発生してから1年になる。体に感じる余震はまだ頻発しているが,ここ数ヶ月間は被害を伴う地震の発生はない(※)。今後の地震災害について考えるために,地球上で過去にM9クラスの超巨大地震が発生した地域における,その前後の地震活動の推移を知ることが大切だと思い,それらの地域における最近の大地震の時空分布を簡単にまとめてみた(図1,2)。そして,我々地質研究者の当面の課題について考えてみたい。 世界で観測史上最大の地震の規模はM9.5だったので,ここではM8.6〜9.5をM9クラスの超巨大地震,M7.6〜8.5をM8クラスの巨大地震,M6.6〜M7.5をM7クラスの大地震と呼ぶことにする。M値が1つ大きいと地震のエネルギーは32倍,2つ大きいと1000倍になる。これは,同じ規模の地震がもう1度起きるとM値0.2の増加に相当し,10回起きると0.7,32回起きると1.0の増加に相当するということである。M9地震のエネルギーは約1018Jになり,これは長崎型原子爆弾約1万発分,大型水素爆弾約10発分の爆発エネルギーに相当する。また,海洋プレートが沈み込む海溝とそこから内陸側のマントルへ斜めに下がっていく断層面またはその近くで起きる地震を海溝型地震,沈み込み帯上の島弧や大陸縁の地殻の浅部で起きる地震を(内陸)直下型地震と呼ぶことにする。直下型地震の場合はM6.5以下の中小規模の地震でも大きな人的被害を生じることがある。
図1.日本(a),スマトラ(b),カムチャッカ・アリューシャン・アラスカ(c),南米太平洋岸(d)の最近の大地震の震源位置,発生年月日と地震の規模。期間は(a), (b)が最近20年,(c), (d)が最近80年。M7.8以上または地震・津波の死者数が1000人以上の地震のみを示した。ただし(a)についてはM7クラスの直下型地震も位置のみ示した。(d)ではチリとその周辺の地震のみ年月日などを示した。どの図も沈み込む海洋プレートが右下または下側に,大陸側が左上または上側になるように配置し,プレートの沈み込み境界(海溝)を太線で示した。また,本文中で触れた超巨大地震と関連して噴火したと思われる火山も示した。データは国立天文台編(2011)に基づく。
まず,日本付近の地震の起こり方の特徴を最近20年間について見ると,1995年前後と2005年前後に千島〜北海道〜三陸北部沖の海溝沿いでM8クラスの巨大地震が頻発し,同じ時期に1995年の兵庫県南部地震や2004年の中越地震など内陸直下型地震も頻発したので,2回の地震活動のピークがあったように見える(図2a)。特に2005年の三陸南部沖M7.2地震が発生した前後に,宮城県と岩手県で直下型地震が頻発し,中でも2008年の岩手・宮城内陸地震は規模と被害が大きかった。そして2005年の地震とほぼ同じ場所で,2011年3月9日にM7.4の地震が発生し,ついに11日のM9.1超巨大地震に至った。また,同日中にさらに南の茨城県沖で最大余震(M7.9)が発生した。このように,最近20年間に千島海溝〜日本海溝沿いでM8クラスの巨大地震が多数発生しており,2011年3月11日の超巨大地震はこの海溝型地震の活動域の南端で発生したことがわかる(図1a)。一方,日本の内陸各地だけでなく,日本海東縁地震帯の北海道南西沖(1993年)やサハリン(1995年),そして南方の台湾(1986,1999年)や西方の中国(1997, 2001, 2008年)でもこの20年間に大地震が頻発したが,関東・東海・紀伊・四国南部・九州南部・琉球などの南海トラフ沿いの長大な地域で直下型大地震も海溝型大地震も起きていないことが注目される(図1a)。
さて,世界では過去80年の間にM9クラスの超巨大地震が日本の東北地方,インドネシアのスマトラ,ロシアのカムチャッカ,米国のアリューシャンとアラスカ,そして南米チリの6つの地域で8回起き,平均して10年に1回ずつ起きてきたことになる。
スマトラ島周辺の最近20年間の地震の起き方を見ると,2004年末のM9.0(一説によるとM9.3)の超巨大地震以後,スマトラ島のインド洋岸沿いに平均年1回のペースでM8クラスの巨大地震が起きており,それ以前の大地震は,2000年にスマトラ島南部沖で1回あっただけである(図2b)。2004年以後のM8クラスの巨大地震は,この2000年と2004年の両震源の間の地域で発生している(図1b)。2004年の地震の震源断層(余震域)はスマトラ北端沖の震源から北へ1200 kmのアンダマン諸島まで達するが,スマトラ中・南部沖は余震域に含まれず,その後の一連の巨大地震は2004年地震の余震ではない。特に2005年3月に起きた地震(M8.6)は超巨大地震に匹敵し,2007年の地震もM8.5と大きかった。東北〜北海道沖では,一連の巨大地震の頻発後に超巨大地震が起きたが,スマトラではまず超巨大地震が起き,その後に巨大地震が頻発しているという違いがある。しかし,1000 km程度の範囲で超巨大地震に伴って巨大地震が頻発するという点は共通している。また,M7クラス以下の内陸直下型地震も起きているが,発生頻度は日本より少ないようである。この20年間で最も大きな被害が出た直下型地震は2006年にジャワ島中南部のジョグジャカルタ附近で死者5700人以上を出したM6.3の地震である(図1b)。
カムチャッカ・アリューシャン・アラスカ地域は比較的地震が少ないが,M9クラスの超巨大地震は最も多く,最近80年間に4回起きている(図2c)。1952年にカムチャッカ沖でM9.0,1957年にアリューシャン列島中部でM9.1,そして1964年にアラスカでM9.2と,西から東へM9クラスの超巨大地震が5〜7年間隔で起き,更に翌1965年には再び列島中部でM8.7の超巨大地震が発生し,その震源は1957年の震源と200 km程度しか離れていない(図1c)。1964年アラスカ地震では,地殻変動により海岸沿いの広範囲の陸地が20 mほど海側へ移動し(2011年の東北地震では5 m),アンカレッジでは地滑りで市街が海側へ移動した(力武, 1996)。1958年に発生したアラスカのリツヤ湾地震では,湾奥で発生した地滑りが海になだれ込み,最大波高527 mという世界の歴史上最大の津波が発生した(同書)。そして,この時期の1958年と1963年に千島列島南部沖でも相次いでM8クラスの巨大地震が発生した。カムチャッカ・アリューシャン・アラスカ地域では,日本やインドネシアのようにM9地震の前または後に,隣接地域でM8クラスの巨大地震が毎年のように頻発するということはなかったが,アリューシャン列島中部でM9クラスの超巨大地震が1957年と1965年に8年の間をおいて繰り返し起きたことは注目に値する。
南米のチリからペルーを経てエクアドル・コロンビアに至る太平洋岸沿いも,日本やインドネシアに比べると地震の発生頻度は低いが,この沿岸全域でM8クラスの巨大地震が発生しており,内陸直下型大地震もある程度発生する(図1d)。M9.5という観測史上世界最大の超巨大地震が1960年にチリ中部沖で発生し,その津波により日本でも大きな被害が出た(日本での最大波高6 m)。そして,その50年後の2010年に約400 km北方でM8.8の超巨大地震が発生した(図1d)。この地震の津波も日本に来たが,1 m程度の波高だった。これは東北沿岸の住民の津波に対する警戒心を弱める逆効果をもたらし,結果的に東日本大震災の被害を拡大させた。これらは南米の太平洋沿岸で最近80年間に発生した地震のうち最大の2つである。1960年のM9.5の超巨大地震の前と後を比べると,前の方がM8クラスの巨大地震の発生頻度がやや高かったようであるが,2010年の超巨大地震の前に巨大地震の発生頻度が高くなったようには見えない(図2d)。
図2.日本(a),スマトラ(b),カムチャッカ・アリューシャン・アラスカ(c),南米太平洋岸(d)の最近の大地震発生の時系列。期間やデータは図1と同じ。ただし,(c)は千島地域の地震を除く。
以上のような世界各地の超巨大地震の起き方を比較すると,次のようなことが言える。
1.M9クラスの超巨大地震がもう一度来ることはあるか
超巨大地震が500 km以内の地域で続けて起きることは,上述の6つの地域(東北日本,スマトラ,カムチャッカ,アリューシャン,アラスカ,チリ)のうち3地域で発生した。スマトラでは3ヶ月後(と3年後),アリューシャンでは8年後,チリ中部では50年後に次の超巨大地震が来た。東北日本は地震発生後の年数が不足のため事例から除外すると,5地域のうち3地域で50年以内に次の超巨大地震が来たことになる。事例が少ないとはいえ,東北日本でもその可能性があると思った方がよい。
2.M8クラスの巨大地震が今後頻発することはあるか
インドネシアでは,2004年にM9.0の超巨大地震が発生して以後,その震源の南に隣接する地域でM8クラスの巨大地震が年1回程度の割合で発生し続けているが,東北〜北海道沖ではこれと逆に,巨大地震が相次いで発生していた地域の南端で超巨大地震が発生した。そして,他の4地域では超巨大地震の前後に隣接地域で巨大地震が頻発するということはなかった。今後もM8クラスの巨大地震が東北〜北海道沖で引き続き頻発するか,これで収束するかは判断できないが,もともと日本の地震活動は世界で最も活発なことを念頭に置く必要がある。巨大地震の震源が南方に広がる傾向があり(図1a),今後は伊豆諸島沖や関東〜九州〜琉球にかけての海溝沿いでも巨大地震が発生する可能性がある。
3.M7クラスの内陸直下型大地震が今後頻発することはあるか
日本では2000年以後M7クラスの直下型大地震が毎年のように発生している。特に中央〜西南日本では,海溝型の巨大地震が発生する前後には内陸直下型地震の発生頻度も高くなることが過去数100年間の歴史資料により明らかになっている(尾池, 1997)。1944年の東南海地震(M7.9)と1946年の南海地震(M8.0)以後,1948年の福井地震から1995年の阪神大震災までの約50年間は比較的地震の発生が少なく,日本はこの間に高度経済成長を遂げた。しかし2000年以後の地震頻発傾向は,今後数10年間続くと考えた方がよい。
以上のような今後の地震活動についての見通しを確認した上で,地質学者が現時点で緊急に研究すべき2つの課題について論じる。
第1は火山活動である。1703年12月31日の元禄関東地震(M8級),1707年10月28日の宝永東海・東南海地震(M8.6)に続いて1707年12月16日に富士山が噴火し,江戸にも火山灰が降ったことがよく知られている。しかし,1854年の安政東海・南海地震,1855年の江戸地震や1923年関東地震,1944年東南海地震,1946年南海地震などでは富士山の噴火はなかった。インドネシアでは2004年12月の超巨大地震の後,2005年4月にメラピ火山が噴火したことが知られているが,地震はスマトラ島北端が震源で,メラピ山はジャワ島東部にあり,両者は2000 km以上離れている。ジャワ島東部では2007年10月以後ケルート火山も噴火を続けている。スマトラ島ではマラピ火山などが噴火を続けているが,地震に伴う大噴火はなかった。カムチャッカでは1952年の超巨大地震の震源の北方にあるベズイミアニ火山が1956年に有史以来初噴火し,山頂部が大爆発して標高が185 m低下した。1975-76年には隣のトルバチク火山でも最大級の噴火があった。アリューシャンでは1957年の超巨大地震の7年前の1950年にグレートシトキン島が大噴火した。アラスカでも1964年の超巨大地震の11年前の1953年にスパー火山が有史以来初の大噴火を起こし,噴煙の高さが23kmに達した。トライデント火山も1953年と1962-63年に大噴火した。チリでは1960年の超巨大地震の後,1964年に震源近くのヴィジャリカ火山が噴火し,死者22人を出した。この火山は1971-72年にも噴火し,南方のハドソン火山も1971年と1991年に噴火した。要するに,超巨大地震の震源から数100 km以内の地域でその前後10年程度の期間に火山が大噴火を起こす例はカムチャッカ,アリューシャン,アラスカ,チリ等でも見られた。東北地方では,貞観(869),慶長(1611),明治(1896),昭和(1933)などの津波地震の前後に噴火した火山は鳥海山(871),磐梯山(1888),吾妻山(1893),安達太良山(1899)があり,秋田焼山,秋田駒ケ岳,栗駒山,蔵王山,日光白根山などでも小規模噴火があったようだ。特に磐梯山の噴火は山体崩壊を伴い,死者461人を出すなど大きな被害があった。東北地方ではカルデラ火山の火砕流を伴う噴火は十和田の915年噴火以後ないが,その可能性も視野に入れる必要がある。
第2は地滑りである。アラスカのリツヤ湾地震を筆頭として,地震が地滑りを誘発し,それによって大きな被害が出ることがある。しかも,地滑りは地震時に発生するとは限らず,しばらく経過してから発生することも多い。1964年6月16日の新潟地震の震源に近く,大きな地殻変動が起きた新潟県北部沖の粟島では,その10年後の1974年3月22日に大規模な地滑りが発生し,粟島浦村中心部の港湾施設や総合庁舎,保育園などを載せた海岸部の土地が長さ480 m幅60 mにわたって海中へ消え去った(加藤, 1981)。このような地滑りが湾内で発生すると,リツヤ湾のように局地的な大津波を引き起こす可能性がある。斜面の高さと傾斜,地層や断層の走向傾斜などから,危険な場所はある程度予測可能なはずである。あれだけの揺れと地殻変動に襲われた地域なので,近々東北地方太平洋岸のどこかで大規模な地滑りが発生すると思って準備した方がよい。地滑りは地割れ,地鳴りなどの前兆現象を伴うことが多いので,注意していれば事前に避難することも可能である。津波を生じる地滑りは火山噴火や火山体の崩壊でも発生し,日本では雲仙火山の眉山崩壊とそれによる津波(1792年,島原大変肥後迷惑)で大きな被害が出たが,これはM6.4の地震がきっかけだったという説もある。大規模工事が地滑りを誘発することもあり,1979年のフランス・ニース海上空港の建設に伴う崩壊と津波の例が知られている。海底地滑りが津波を引き起こすこともあるが,これは事前の調査や予測が不可能である。まず陸上の危険個所を洗い出し,適切な周知活動を起こすことが必要だと思う。
その他,活断層や津波堆積物の調査,震源域の海底掘削と掘削試料の解析,原発事故後の放射性物質の処理,液状化危険度の評価,復興計画への参画,被災博物館などの貴重な標本の修復,災害の記録と検証,防災教育など,地質研究者が貢献できる領域は広い。会員諸氏のご活躍を期待する。また,昨年の超巨大地震を「1000年に1度」などと言うが,それは東北日本に限った話であって,上述のように地球上では10年に1回程度発生する現象である。世界に学び,我々の経験を世界で役立てていかねばならない。それについて気になるのは,まだ世界共通の震度階がないことである。0〜7の震度階を使っているのは日本だけで,最近は強とか弱とか複雑化している。実際,地震の際に外国人との意思疎通に不便を感じた。これを機に一般人にわかりやすく使いやすい,例えば0から9まで10段階の世界共通の震度階を作ったらよいと思う。
1年後の現時点で,改めて東日本大震災の犠牲者に哀悼の意を表するとともに,地震,津波,原子力発電所事故など震災関連の被害を受けられた方々に心からお見舞い申し上げる。
拙稿を校閲して貴重な改善意見をいただいた宮下純夫氏,久田健一郎氏およびサイモン・ウォリス氏に感謝する。
※追記:この原稿は2012年3月11日に投稿したが,その後14日21:05に千葉県東方沖でM6.1の地震が発生し,茨城県や千葉県の一部で震度5強を観測,死者1名,負傷者1名,塀の倒壊,地盤の液状化などの被害があった.(2012年4月2日)
追記2:新聞・テレビなどの報道によると,日本時間2012年4月11日午後17:40(現地時間15:40)頃,インドネシアのスマトラ島北部西方沖のインド洋底を震源とするM8.6の超巨大地震があった.約2時間後にM8.2の余震があり,その後も余震が続いている.この地震は沈み込むインド洋プレート内部で横ずれ成分の大きい断層が動いたものとされ,津波は高いところでも1〜3 mだった.本文で述べたように,2004年末のM9地震以来,スマトラ島周辺では大地震が毎年のように発生しており,今回もそれらの1つと考えられる.アリューシャンやチリでもM9地震から50年以内に,約500 km以内の地域で次のM9地震が発生しており,関東・東北・北海道地域でも警戒が必要である.
【文献】
加藤碩一 (1981) 粟島地域の地質. 地域地質研究報告5万分の1図幅, 秋田6-81, 地質調査所. 32 p.
国立天文台編 (2011) 理科年表. 平成24年版, 丸善, 1108 p.
尾池和夫 (1997) 日本列島の地震とその観測体制. 日本学術会議編「明日の震災にどう備えるか」日学双書27, 17-34.
力武常次監修 (1996) 近代世界の災害. 国会資料編纂会, 415 p.
(2012.3.12)
第3回フォトコン入選作品:最優秀賞
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品:最優秀賞
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品:最優秀賞: 「27億年前の鉄鉱山」
写真:清川 昌一(福岡県) 撮影場所:ブラジル中東部(フェドロ・クアドラングル地域:サンフランシスコクラトン) Pau Branco 鉱山
【撮影者より】
ブラジルはオーストラリアとともに、世界の鉄を供給する重要な場所である。深度200m以上の著しい風化作用を被っており、地層は非常に柔らかである。逆断層にそった地質構造にそって露天掘りをしており、中央の黒い部分が新鮮なヘマタイト層がみられる。黄色い部分はゲーサイト化してい部分。日曜日なので作業はしていなかった。
【審査委員長講評】
世界の鉄鉱床の大部分は27億〜25億年前、海中に酸素が豊富になった時期にできたものです。作者はプロの地質研究者で専門は先カンブリア時代の地質ですから、このような場所で撮影できたのでしょう。とはいっても、太陽光の当たり具合や構図はよく計算されており、巨大な鉄鉱山のようすを余すところなく表現されています。行って見たくなるような作品です。
【地質的背景】
目次 進む→
第3回フォトコン入選作品:優秀賞
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品:優秀賞
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品:優秀賞: 「ある惑星にて」
写真:公文 俊朗(愛知県) 撮影場所:高知県室戸市 室戸岬 タービダイト層
【撮影者より】
世界ジオパークに認定された室戸岬のタービダイトです。 異世界感、非日常感を表現するため、フィルターを使用して撮影しました。 小さい頃よく遊んでいた室戸岬の岩場です。 ジオパークに認定されたのを機に、帰省した折に散策しました。 ふと見上げると、岩の先端を中心に天が裂けているようにも見え、そこがよく知っている場所であるにも関わらず、まるで地球ではない別の惑星であるかのような、不思議な感覚を一瞬覚えました。 この写真は、マーズローバーのような惑星探査車が伝えてくる荒涼とした風景をイメージして撮影しました。
【審査委員長講評】
曇天の日にこのような写真を撮影すると、空の部分が露出オーバーになりますが、作者はハーフNDフィルターを使って空の部分の減光しているものと思います。モノクロ的な色彩と変形した砂泥互層のフォルムがよく調和し、非日常的な力強い作品となっています。
【地質的背景】
←戻る 目次 進む→
第3回フォトコン入選作品:優秀賞
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品:優秀賞
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品:優秀賞: 「自然の威力」
写真:永友 武治(宮崎県)
撮影場所:宮崎県えびの市大字末永 えびの高原 韓国岳山頂(1,700m)から新燃岳を撮影
【撮影者より】
2011年1月27日午後3時半ごろに韓国岳登山をしていましたら噴火に出合いました。恐怖がありましたが世紀の歴史の1ページと思いまして撮影しました。撮影時刻は午後5時頃です。被写体までの距離は約3?qです 平成23年1月26日に1回目の噴火が起こり、27日深夜にマグマ噴出がありまして午前4時に撮影に入りましたが,再度27日の夜にマグマ噴出が発生するかもと思い、その日の午後3時半に韓国岳に登山開始しました。2合目付近で下山者と出会いまして、新燃岳が噴火したらしいという情報をいただきまして私は無我夢中で頂上を目指しました。 頂上に着いたら、想像を絶する光景で噴煙、噴石が地上高く吹き上げていました。頭上高く舞い上がる噴煙とごう音に恐怖で自分の心が震えるのを抑えながら世紀の記録と思いまして、心を落ち着かせて撮影しました。
【審査委員長講評】
2011年1月27日に霧島連峰の主峰、韓国岳の登山中に隣接する新燃岳の噴火に出くわし、それを的確に捉えた写真です。モクモクと上昇する灰色の噴煙、放物線を描いて飛び散る火山弾など噴火の凄まじさがよくわかります。今回の新燃岳噴火では、夜の写真には秀作が多いのですが、この作品は昼の写真としては第一級のものです。
【地質的背景】
←戻る 目次 進む→
第3回フォトコン入選作品:優秀賞
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品:優秀賞
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品:優秀賞: 「新燃岳の噴火と火山雷」
写真:中馬 辰紀(宮崎県) 撮影場所:宮崎県西諸県郡高原町大字広原
【撮影者より】
2011年1月26日午後に始まった新燃岳の激しいマグマ噴火は27日の朝まで続いた。26日の夜半から27日の朝にかけて、山頂付近は真っ赤に焼けた噴煙を弧を描いて飛散する噴石が見られ、ひっきりなしに、山頂から噴煙の中に雷光が走った。噴火に伴う鳴動と空振はずっと続き不気味であった。
【審査委員長講評】
この作品は、新燃岳の東北東7kmの広野から撮影したものです。撮影したのは27日早朝です。この頃が噴火のピークで、火山灰同士の摩擦によって発生する雷、火山雷を見事に捕らえています。翌日からはこのような火山雷はほとんど見られなくなってしまいました。
【地質的背景】
←戻る 目次 進む→
第3回フォトコン入選作品
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品:「渓谷を行くSL」
写真:竹内 久俊(東京都) 撮影場所:スイス・フルカ峠付近
【撮影者より】
2011年夏に、家族でスイス旅行をした際に撮影したものです.観光バスの車窓から谷間に漂う煙を見つけ,SLを確認しました.バスの窓越しに夢中でシャッターを切りました.鳥になった気分で,上から見下ろす渓谷の風景.谷底を力強く走るSL,スイスのSL山岳鉄道,絵になる風景です.
【審査委員長講評】
撮影場所はスイスのフルカ峠(標高2431m)で、峠から東側の水は黒海へ、西側の水は地中海に流れる分水嶺になっています。作品はU字谷を走るSLがテーマになっていますが、もう少しジオの要素を取り入れてほしかったと思います。
【地質的背景】
←戻る 目次 進む→
第3回フォトコン入選作品
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品:「しらひげの滝 (青い池の上流には滝があった)」
写真:宇津木 圭(北海道) 撮影場所:北海道上川郡美瑛町字白金 しらひげの滝
【撮影者より】
北海道の美瑛白金では青い池が有名になりましたが、この青い池の上流はどのようになってるかと思い砂利道を進んで行くと温泉街に到着する事ができます。川の上にかかる橋の上から下を覗き込むとそこは絶景が広がってました。白い滝と青い滝壺が存在してます。さらに水質のせいか川底の大きな石が白い石に変化しております。とても驚く白ヒゲの滝です。青と白の不思議な世界が広がります。 しらひげの滝から下流には青い池が数年前に出来ました。とてもブルーが美しく本当に驚く場所です。写真のしらひげの滝は滝壺が青白く不思議な場所です。 流れ落ちる滝も青白く季節によって色が変わったり太陽の光線の状態でも変わる神秘的な雰囲気が広がります。
【審査委員長講評】
この作品をよく見ると岩石の間から滲み出した伏流水がしらひげの滝を作っていることがわかります。この伏流水は十勝連峰に源を発するもので、岩石が白くなっているのも、水が青い原因も水に溶け込んだ硫黄などの成分が関係していると思われます。
【地質的背景】
←戻る 目次 進む→
第3回フォトコン入選作品
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品:「尖塔」
写真:林 孝信(東京都) 撮影場所:青森県下北郡佐井村・仏ヶ浦展望台
【撮影者より】
本当に自然が創り上げたのが信じられないほど、ダイナミックで印象的な地形でした。 仏ヶ浦は地球が生まれてから刻々と変化してきて今の形となったものだと思います。 人間の尺度で変化の分かる夕暮れと、地球の尺度での仏ヶ浦。 二つが合わさった瞬間を切り取りました。
【審査委員長講評】
青森県の名勝地、仏ヶ浦は中新世の海底火山活動によってもたらされた凝灰岩が侵食されたものです。仏ヶ浦は、観光船を利用して海から撮る、遊歩道を下りて海岸で撮るなどの撮影方法がありますが、この作品のように北側の国道から見下ろすと仏ヶ浦全体が見渡せます。手前の木の枝を避ける工夫をしたかった。
【地質的背景】
←戻る 目次 進む→
第3回フォトコン入選作品
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品:「初めてのジオパーク」
写真:高橋 伸輔(秋田県) 撮影場所:秋田県男鹿市館山崎
【撮影者より】
2011年9月に日本ジオパークに正式認定された「男鹿半島・大潟ジオパーク」。ふとした事からガイド養成講座に参加し、「こんなに素晴らしい場所が地元にあったのか!」と思わせてくれた初めての場所であり、ジオパークにのめり込むきっかけとなった鮮やかでかつ迫力のある緑色凝灰岩。 自分の地元にはいい所なんて何もないと言う方が多いがそれは知らないだけ もっともっと目をこらして見てみれば今まで気付いていない魅力が山のように見えてくる
【審査委員長講評】
館山崎は男鹿半島の南部にあり、中新世台島層がよく観察できる場所です。中新世は日本海が拡大したときの火成活動が盛んだった時代です。今回の入選作品には中新世の地層を撮影された作品が4点もあり、日本列島の歴史の中で日本海の拡大がいかに大事件であったかがわかります。
【地質的背景】
←戻る 目次 進む→
第3回フォトコン入選作品
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品:「よろい岩」
写真:中桐 晴己(大阪府) 撮影場所:島根県隠岐の島町中村海苔田ノ鼻の散策路
【撮影者より】
よろい岩の下半分は柱状節理の著しい暗灰色のアルカリ粗面岩で、上半分は暗黒色のアルカリ玄武岩の岩脈で、放射状に柱状節理が発達しているため武者の着ける鎧に見えることから鎧岩と名付けられた。(インターネットより) 柱状節理が海中から立上り,その柱状節理の上に別の柱状節理が放射状に広がっていて,特異な景観となっている. 隠岐の島へは仕事で単身赴任を1年間しました。「よろい岩」には単身赴任が終了する直前に 訪れました。海の中から柱状節理が立ち上がっているその上に、異なる柱状節理が重なり合い 特異な景観を創り出しているのに感動しました。
【審査委員長講評】
隠岐諸島は2009年に日本ジオパークに認定された地域で、日本海が開いた時の火成活動の跡がよく保存されています。よろい岩はその中の名所の1つで、すでにあった粗面岩の中に玄武岩が貫入した地層ですが、この作品はその関係がわかりやすく説明されています。コンパクトデジカメで撮影されたものです。
【地質的背景】
←戻る 目次 進む→
第3回フォトコン入選作品
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品:「凍土の星」
写真:兼子 昌根(千葉県) 撮影場所:ロシア上空の飛行機内
【撮影者より】
ヨーロッパから日本へ向かう飛行機は北極圏上空を飛行する時があり、そういう場合はすばらしい風景が飛行機の窓から見ることが出来ます。 高度一万メートルからの地球はすばらしいの一言です。 これ以上の高度から地球を見るには宇宙船に乗るしかありませんが、いつかは宇宙船から地球を見てみたいものです。
【審査委員長講評】
北極圏のシベリアには行くことは大変なことですが、ヨーロッパ〜日本間の旅客機からはこの作品のように容易に眺めることができます。右上に下弦の月が写っていることから南西方向を撮影していることがわかります。低い山並みが続いていますが、シベリアのどのあたりを撮影したものでしょうか。
【地質的背景】
←戻る 目次 進む→
第3回フォトコン入選作品
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品:「夜来たる」
写真:公文 俊朗(愛知県) 撮影場所:高知県室戸市 室戸岬 月見が浜
【撮影者より】
世界ジオパークに認定された室戸岬の岩礁帯です。 神秘的な雰囲気を出すため、土佐の荒波を間近に感じながら日没直後に撮影しました。 夕日が沈み、夜が訪れようとする室戸岬の岩礁帯は波と風の音以外は何も聞こえずとても神秘的です。 近くには19才の空海が修行したという洞窟があります。 空海がいた1000年以上も前の時代の地形と比べると、現在はいくらか違いがあるかと思いますが、荒々しい岩場、とめどなく打ち寄せる波の音は空海がいた頃と変わりがありません。
【審査委員長講評】
昨年9月に世界ジオパークに認定された室戸の岩礁です。夜のとばりが下りる時刻に撮影されたもので、印象深い作品となっています。しかしこの作品は、どちらかというと風景写真に分類されるものです。優れた写真技術をお持ちですから、もう少しジオの要素を取り入れた作品作りも試みてはいかがでしょうか。
【地質的背景】
←戻る 目次 進む→
第3回フォトコン入選作品
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品:「柱状節理」
写真:辰巳 功(東京都) 撮影場所:静岡県下田市須崎爪木崎
【撮影者より】
爪木崎灯台の柱状節理の岩場です。五角形の柱状の岩がきれいに並ぶ、と云うのは不思議です。自然はアーティストです。そこに波が白く砕けていました。それをスローシャッターで雲海のように表現しました。
【審査委員長講評】
伊豆下田の爪木崎の柱状節理とらえたものです。データを見るとf29、シャッタースピード30秒とありますから、夜間に三脚をかまえて月光下で撮影されたものでしょう。砕けた白波が柱状節理を照らし出し、格調高い作品となっています。
【地質的背景】
←戻る 目次 進む→
第3回フォトコン入選作品
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品:「27億年前の海台1(枕状溶岩)」
写真:清川 昌一(福岡県) 撮影場所:ジンバブエ 南部 Ngezi 川沿い
【撮影者より】
ベリンギー(Belingwe)グリーンストーン帯はジンバブエに残る27億年前の地質帯で、厚い玄武岩やコマチアイト溶岩が特徴である。当時の海台が付加したという説と太古代特有のリフト帯説で盛んに議論されている場所である。枕状溶岩は比較的発砲痕がのこり、急冷層が顕著にみられる。当時の海底の熱水作用の後だと思われる石英が隙間を埋めて、不気味な光景が見られる。
【審査委員長講評】
この作品も最優秀賞を受賞された清川昌一氏によるもので、コマチアイトの枕状溶岩を撮影したものです。コマチアイトは太古代のみに見られる低粘性の高温の溶岩流ですが、その枕状溶岩を見るのは初めてでびっくりしました。上端が窮屈なので、空をもう少し入れたほうがよかった。
【地質的背景】
←戻る 目次 進む→
第3回フォトコン入選作品
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品:「地球の記憶」
写真:柳瀬 真(新潟県) 撮影場所:新潟県佐渡市江積の海岸付近
【撮影者より】
佐渡市江積の海岸部に、観光客にはほとんど知られていないこの様な枕状溶岩が見られます。佐渡には好んでよく足を運びますが、地質学的にかなり魅力的な島であることを最近知りました。江積からもう少し離れた平根崎では、島の隆起による海岸の傾斜がみられ、小木地方の沿岸部ではこれ以外にも海底火山でできた岩石が陸上に姿を現しています。 岩の形状とその模様に惹かれ、写真に収めたものです。 太古の時代に想いを巡らせながら,地球が造り出した自然の造形美を堪能していただけたらと思います.
【審査委員長講評】
佐渡島南西部の小木は、中新世の海底火山活動の堆積物が豊富に見られる地域です。特に有名なのが写真のような枕状溶岩です。この作品は、海岸沿いの道路のすぐ近くにある露頭を撮影したものです。説明的な写真としては成功していますが、もう一ひねりほしいところです。
【地質的背景】
←戻る 目次 進む→
第3回フォトコン入選作品
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品:「チョコレート・ボンボン」
写真:吉田 宏(神奈川県) 撮影場所:フィリピン・ビサヤ諸島 ボホール島チョコレートヒル
【撮影者より】
フィリピンの首都マニラから南へ約530km、VISAYAS(ビザヤ)諸島を構成するボホール島で見る光景。 数千万年前には海底であったところが隆起したもので楕円形の丘が連なる。 近年のヘリからの調査では、丘の連なりは2千個以上も数えられだ。丘の上には木は生えず、短い草に覆われている。草が枯れて焦茶色になると,まるでチョコレート・ボンボンを連想させることからチョコレート・ヒルと呼ばれている。 番外:島には宿泊施設が無い為、グランドキャニオンやカッパドキアの様に観光客は訪れず、日本人で訪れる人は皆無に等しい。
【審査委員長講評】
撮影地のボホール島は、セブ島の隣に東京都の2倍の面積をもつ島で、ダイビングの名所だそうです。チョコレート・ヒルは石灰岩の侵食でできた地形ですが、同じ石灰岩でも元々の構造や侵食のされ方によって桂林(中国)のようになったり、ツィンギ(マダガスカル)のような尖塔群になる場合もあり、興味深いものです。
【地質的背景】
←戻る 目次 進む→
第3回フォトコン入選作品
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品
第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品:「褶曲」
写真:平山 弘(和歌山県) 撮影場所:和歌山県すさみ町天鳥海岸
【撮影者より】
すさみ町の海岸に、大地創造を思わせる岩壁があるが、険しい場所のため釣り人ぐらいしか訪れることはない。 非常に道が悪いので行かれる方は充分に注意してください.波の高い時は危険です.行かないで下さい.
【審査委員長講評】
和歌山県のすさみ町海岸にある、日本では最もよく知られた“褶曲”です。もっともこの“褶曲”は構造運動による褶曲ではなく、海底に堆積した砂泥互層が海底地滑りで折り重なったできたランプ構造ではないかと考えられています。作者は地元の方で、潮の満干や太陽光の当たり方などを考慮して、良い撮影条件を選んで撮影しています。
【地質的背景】
←戻る 目次
geo-Flash No.199(臨時) 事務局/執行理事会 誤った分析結果に関する受注 会社の告知を受けて
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.199 2012/10/26 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】事務局/執行理事会 誤った分析結果に関する受注会社の告知を受けて
【2】イタリア、ラクィラ地震裁判有罪判決について
【3】大飯発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】事務局/執行理事会 誤った分析結果に関する受注会社の告知を受けて
──────────────────────────────────
日本地質学会会員各位
三菱マテリアルテクノ(株)(HP http://www.mmtec.co.jp/)より,誤分析に関
する情報の開示がありました.地質学会の会員の皆様には,10月5日に,
「【geo-Flash】No.196(臨時)分析会社の誤分析に関する情報」でお知らせ
いたしましたが,その際には,当該会社からの正式発表前でしたので,会社
名は伏せました.
現在までに,地質学雑誌,Island Arcでは,本件に該当する誤った分析値を
報告した論文は見つかっておりません.しかしながら,学術大会の要旨等で
該当するものがある可能性は否定できません.また,誤った分析値をコンパ
イルしたケースや,そのような分析値を引用して考察が展開されているケー
スも想定されます.
そこで,上記に該当する論文,講演要旨等の著者の方は,井龍
(iryu@m.tohoku.ac.jp)まで御連絡下さいますようお願いいたします.
(学会事務局(main@geosociety.jp)にもCCでお送り下さい。)
井龍康文(執行理事・学術研究部会長)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】イタリア、ラクィラ地震裁判有罪判決について
──────────────────────────────────
死者300人以上を出した2009年4月6日のラクィラ地震に関して、同地の裁判所
に起こされていた裁判で、イタリアの地震学者6人と防災関係者1人の計7人
の被告に対し、過失致死罪で求刑を超える禁固6年と多額の罰金を科す判決が
2012年10月22日に出た。本震6日前の群発地震が続いていた最中に、彼らの委
員会の代表がメディアを通じて「安全宣言」とも受け取れる発言をしたことに
は問題があるが、群発地震が大地震の発生に結びつかない場合が多いことは
事実であり、地震学者たちが群発地震の推移を見て、大地震が起こる可能性は
低いと判断したからと言って、彼らに刑事罰を科すのは間違いである。このよ
うな判決は科学者に不当な負担を強いるものであり、科学者の自由な活動を
阻害するものである。上級の裁判所が正しい判決を下すことを期待する。
参考文献
Hall, Stephen, S. (2011) At fault? In 2009, an earthquake devastated
the Italian city of L'Aquila and killed more than 300 people. Now,
scientists are on trial for manslaughter. Nature, 477, 264-269.
なお、8月18日に放送されたNHK「訴えられた科学者たち〜イタリア地震予知
の波紋〜」が10月27日(土)22:00〜22:49に再放送されるそうです。
http://www.nhk.or.jp/documentary/
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】大飯発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合
──────────────────────────────────
本学会からの推薦委員を含む原子力規制委員会の標記の事前会合(10月23日)
のビデオと配布資料が次のサイトに公表されています.現地調査は11月2日
に実施予定とのことです。
http://www.youtube.com/watch?v=uo6Ye4vWOYU&feature=plcp
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/ooi_hasaitai/20121023.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
<ニュース誌表紙写真,特に募集中です!お待ちしてます. >
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
No.174 2012/4/17 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.174 2012/4/17 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】第3回惑星地球フォトコンテスト 審査結果発表
【2】大阪大会:シンポジウム,トピック/レギュラーセッション決定
【3】2012年「地質の日」イベント案内
【4】本の紹介:高校教師のための課題研究指導サポートブック
【5】支部・専門部会情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】第3回惑星地球フォトコンテスト 審査結果発表
──────────────────────────────────
第3回惑星地球フォトコンテストの審査が行われ、応募総数321点の中から
最優秀賞「27億年前の鉄鉱山」(清川昌一さん、福岡県)など16作品の入選
が決定しました。授賞式は、5月19日(土)13:30より、東京都北区王子の
「北とぴあ」にて行われます。
また、千葉県立中央博物館において、入選作品の展示会が4月21日(土)から
6月3日(日)の期間で開催されますので、ぜひ足をお運び下さい。
入選作品はこちらから、、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0009.html
早速ですが、第4回フォトコンが今から楽しみです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】大阪大会:シンポジウム,トピック/レギュラーセッション決定
──────────────────────────────────
今年の第119年学術大会(大阪大会:9月15日〜17日開催)でのシンポジウム・
セッションが決定いたしました.このほかにも市民講演会や地質情報展,国際ワー
クショップなど,多数の関連事業を企画・準備中です.募集・予告記事はニュー
ス誌5月号に掲載します.また,講演申込や参加登録は5月末頃受付開始予定です.
(日本地質学会行事委員会)
詳しくは、、、、
http://www.geosociety.jp/osaka/content0021.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2012年「地質の日」イベント案内
──────────────────────────────────
■徒歩見学会 街中ジオ散歩 in Tokyo「身近な地層や岩石を知ろう」(5/13)
■記念展示 私たちの生活を支える金属鉱床ー札幌周辺の鉱山を例に(4/24-5/27)
■2012年『地質の日』くまもと(5/26)
■記念観察会「深海から生まれた城ヶ島」(5/12)
詳しくは、こちらから
http://www.geosociety.jp/name/content0014.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】本の紹介:高校教師のための課題研究指導サポートブック
──────────────────────────────────
高校教師のための課題研究指導サポートブック
〜学校の体制つくり・テーマ探し・研究指導の実際〜
野曽原友行編(千葉大学先進科学センター)
地質学会会員である千葉県我孫子高校の小泉治彦氏が著した「理科課題研究ガイドブック」(2010年.千葉大学先進科学センター)については.2011年日本地質学会
News2月号で久田が紹介させていただいた.約6500部も発行されたそうだが.本書はその教師用版である.
今回は.千葉県教育委員会の協力を得て.高校教員と千葉大学が力を合わせて作った理科課題研究の指導に関わる手引書である.
第1部 課題研究を始めるにあって(執筆は千葉大学及び千葉県教育庁関係者3名)
第2部 授業を中心とした課題研究指導(千葉県高校教諭7名)
第3部 部活動を中心とした課題研究指導(大学.高校.中学校関係者4名)
参考資料 (大学及び市科学館関係者3名)
で.構成されており.数学などの課題研究指導も含まれており.広く理数系のための指導書となっている.
それぞれのタイトルを見ると.「誰でもチャレンジ!課題研究と発表会」「課題研究ゼロからの再出発」「地学課題研究模索の記」などがあり.課題研究を生徒に課する時にすぐに役立ちそうな内容が多くみられる.前出の小泉氏は.「誰でもチャレンジ!課題研究と発表会」の中の最後において.「(1)教わることに慣れすぎた生徒たち.(2)間違いをこわがる生徒たち.(3)もっと勉強で遊ぼうよ!」をあげ.理科課題研究に取り組む生徒の姿勢をまとめている.
高校で課題研究に取り組む教員はもちろんのこと.大学などで地質学の専門教育や地学教育に関わる者にとっても.卒業研究などの課題研究をより良いものにするための示唆を与えてくれる.
「理科課題研究ガイドブック」希望者は.千葉大学高大連携企画室(koudairenkei@office.chiba-u.jp )へ.subject欄に「サポートブック(高校名)」を記入し.①希望冊数.②名前(複数の場合.受け取る先生の名前とメールアドレス).③送り先.〒番号・住所・氏名を記入して.申し込むとよい.なお本ガイドブックは教師用なので.生徒配布はできない.また.生徒用「理科課題研究ガイドブック」は.現在千葉大学高大連携企画室HP(http://koudai.cfs.chiba-u.ac.jp/guidebook2.html )より.そのPDFがダウンロードできるそうである.
(久田健一郎)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部・専門部会情報
──────────────────────────────────
■中部支部:2012年年会開催のお知らせ
日程:2012年6月16日(土)・17日(日)
会場:岐阜大学教育学部B102教室
16日(土)シンポジウム「中部地方の活断層にかかわる最新の知見」
17日(日)地質巡検「根尾谷断層にかかわる新知見」
参加申し込み:
総会・シンポジウム・懇親会:当日まで申込可
地質巡検:定員になり次第締切.できるだけ6月1日(金)までに
詳しくは、、、
http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第5回フォーラム「ジオ多様性とは何か、その重要性を問う」
日時:2012年6月8日(金)・9日(土)
場所:JAMSTEC横浜事務所
http://www.geosociety.jp/outline/content0099.html#20120608
■地質学史懇話会
日時:2012年6月10日(日) 13:30〜17:00
場所:北とぴあ 9階901号室
http://www.geosociety.jp/outline/content0095.html#2012-5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■名古屋大学大学院環境学研究科地球環境科学専攻教員(教授または准教授) (6/29)
■九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 CO2貯留部門公募(6/6)
■平成24年度東京大学地震研究所共同利用2次公募(5/7)
■2012年度「信州フィールド科学賞」募集 (7/2)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。 geo-Flashは、
月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日 までに
事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.175 2012/5/1 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.175 2012/5/1 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】東日本大震災復興事業プラン:成果報告 第2弾
【2】大阪大会:巡検の魅力・見どころ紹介
【3】2012年「地質の日」イベント案内
【4】パブリックコメント:地震及び火山噴火予知のための観測研究計画
【5】第4回(2012年度)総会開催について
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】東日本大震災復興事業プラン:成果報告 第2弾
──────────────────────────────────
■陸前高田市立博物館地質標本救済事業報告
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の津波により被災した陸前高田市立博
物館所蔵の地質標本について,「陸前高田市立博物館地質標本救済事業」を実施し
たので報告する.
陸前高田市立博物館は,昭和34年に東北地方で最初に登録された公立博物館であ
り,地域の文化史から自然史にわたる約15万点の資料を保有していた.同館はこの
たびの津波災害により壊滅的な被害を受け,6人の職員全員が死亡または行
方不明となった.このため同市立海と貝のミュージアムや市教育委員会の職員が岩
手県内の博物館等の協力を得て資料救出を行い,再生のための作業を進めてき
た.この事業は,文化庁の被災文化財等救援委員会による事業の中に位置づけられ,
陸前高田市の要請により岩手県教育委員会主導のもとに4月当初から岩手県立博物館
が中心となって進めてきたものである.
詳しくは、http://www.geosociety.jp/hazard/content0071.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】大阪大会:巡検の魅力・見どころ紹介
──────────────────────────────────
本年9月に行われる大阪大会では,近畿支部を中心に多くの会員の協力を得て,
10コースの巡検・ワークショップを企画し現在その準備を進めております.
大阪大会では,巡検を近畿周辺地域の地質理解のための重要な行事と位置付け,
参加者に満足していただける特徴的なコース作りを目指しました.以下に会員
の皆様に各コースの魅力や見どころを詳しく紹介していきたいと思います.
(巡検準備委員会委員長 奥平敬元)
各コースの詳細は、http://www.geosociety.jp/osaka/content0022.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2012年「地質の日」イベント案内
──────────────────────────────────
■記念展示 私たちの生活を支える金属鉱床―札幌周辺の鉱山を例に
期間:2012年4月24日(火)〜5月27日(日)
会場:北大総合博物館1階「知の統合コーナー」
■惑星地球フォトコンテスト 展示会
○第2回入選作展示
期間:2012年4月28日(土)〜5月13日(日)
場所:東海大学自然史博物館(静岡市清水区三保2389)
○第3回入選作展示
期間:2012年4月21日(土)〜6月3日(日)
場所:千葉県立中央博物館(千葉市中央区青葉町955-2)
全国の2012年の「地質の日」イベントとその由来に関する情報は,
http://www.gsj.jp/geologyday/2012/index.html
(地質の日事業推進委員会サイト)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】パブリックコメント:地震及び火山噴火予知のための観測研究計画
──────────────────────────────────
文部科学省は、東北地方太平洋沖地震を踏まえた「地震及び火山噴火予知のため
の観測研究計画」の見直し審議の経過報告をまとめ,これに対して意見を募集し
ています.下記よりご意見を提出してください.(5/19まで)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000576&Mode=0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第4回(2012年度)総会開催について
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会 第4回(2012年度)総会
日時:2012年5月19日(土)14:30〜16:00
会場:北とぴあ 第2研修室(東京都北区王子1-11-1)
*定款第20条により本総会は役員ならびに代議員による総会となります.ただし定
款により正会員は総会に陪席することができます.
議事次第等詳しくは、こちら、、、
http://www.geosociety.jp/outline/content0100.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■海底地形名称の提案募集のお知らせ
海上保安庁では,海図や海底地形図などに記載する海底地形の名称を決定する「海
底地形の名称に関する検討会」を開催します.
開催にあたり,関係学会等に広く海底地形名称を募集することとしましたのでお知
らせします.
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KOKAI/ZUSHI3/topographic/topographic.htm
■34th International Geological Congress:IGC
2012年8月5日(日)〜10日(金)
会場:Brisban Australia
http://www.34igc.org
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■御所浦白亜紀資料館非常勤嘱託員(学芸員)募集(5/22)
■東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教員公募(6/29)
■山田科学振興財団国際学術集会開催援助公募のお知らせ(4/1-2013/2/28)
■第16回尾瀬賞の募集(8/31)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。 geo-Flashは、
月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日 までに
事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.176 2012/5/15 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.176 2012/5/15 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】広報誌「ジオルジュ」創刊のお知らせ
【2】日本地質学会第119年学術大会(大阪大会)まもなく受付開始
【3】支部情報
【4】第4回(2012年度)総会開催について
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】広報誌「ジオルジュ」創刊のお知らせ
──────────────────────────────────
この5月10日(地質の日)より,一般向けの広報誌「ジオルジュ」を刊行する
こととなりました.まもなく会員皆様のお手元に届くことと存じます.誌名のジ
オルジュは「ジオ」と「コンシェルジュ(案内人)」の造語であり,地質学の魅
力を広く伝えるものになって欲しいとの願いが込められています.地質学は,他
の自然科学分野と比べて,ジオパーク,博物館,天然記念物,国立公園,自然遺
産,などアウトリーチの幅がたいへん厚いのが特徴です.これらの資産を活かし
て,わかりやすく,楽しく,そして美しい雑誌にしていく所存です.
ジオルジュはサイエンスライターによる,わかりやすい記事とグラフィカルな誌
面が特徴です.創刊号は16pフルカラーで2011年の東北地方太平洋沖地震の特集
号となっております.
なおジオルジュは年二回発行の有料雑誌です.会員の皆様には地質学雑誌・ニュー
ス誌ともども郵送させて頂きます.もしお近くに興味を持って頂ける方がおられ
ましたら,なにとぞお奨め頂けますようお願い申し上げます.
ジオルジュ 年二回発行 定期購読450円(税込み)
オンラインストア(あわせて非会員向けにストアも開設いたしました)
http://store.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】日本地質学会第119年学術大会(大阪大会)まもなく受付開始
──────────────────────────────────
今年も例年同様オンラインで受付いたします。
奮ってお申し込み下さい。
詳細は、大会HP(近日掲載)・News5月号に掲載いたします。
講演申込受付:5月28日(月)10:00〜7月3日(火)17:00締切(郵送6/27締切)
参加申込受付:5月下旬(予定)〜8月17日(金)締切
大阪大会HP
http://www.geosociety.jp/osaka/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】支部情報
──────────────────────────────────
■北海道支部:地質巡検のお知らせ
日時:2012年7月14日(土)〜16日(月・祝)
内容:
7/14 花崗岩類と弱・非変成中の川層群(日勝峠周辺)
7/15 西帯オフイオライト〜主帯の変成・深成岩類(パンケヌシ川)
7/16 西帯の苦鉄質〜超苦鉄質深成岩類(ウエンザル川)
費用:20,000円(懇親会費込み)
申込締切:6月11日(月)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第4回(2012年度)総会開催について
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会 第4回(2012年度)総会
日時:2012年5月19日(土)14:30〜16:00
会場:北とぴあ 第2研修室(東京都北区王子1-11-1)
*定款第20条により本総会は役員ならびに代議員による総会となります.ただし定
款により正会員は総会に陪席することができます.
*当日13:30より同会場にて、第3回惑星地球フォトコンテスト表彰式も行われます。
一般会員の方もぜひご出席下さい。
議事次第等詳しくは、こちら、、、
http://www.geosociety.jp/outline/content0100.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地球惑星科学連合大会中における日本学術振興会科研費説明会
日時:2012年5月22日(火) 17:15〜18:15
場所:幕張メッセ国際会議場 105号室
主催:日本学術振興会学術システム研究センター
内容:科研費を巡る予算動向,科研費および特別研究員の採択動向,科研費および
特別研究員審査システム,学術システム研究センターの仕事 など につき,学術振
興会担当者が説明をし,みなさんからの質問にお答えします
説明者:日本学術振興会研究事業部研究助成第一課長松本昌三および日本学術振
興会学術システム研究センター企画官 樋口和憲
(日本学術振興会学術システム研究センター研究員 永原裕子)
■日本堆積学会2012年札幌大会
日程:2012年6月15日(金)〜 18日(月)
場所:北海道大学
http://sediment.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■北海道大学大学院理学研究院自然史科学部門地球惑星システム科学分野
テニュアトラック助教の公募(6/25)
■山形大学理学部地球環境学科教員公募(8/10)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。 geo-Flashは、
月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日 までに
事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.177 2012/5/20 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.177 2012/5/20 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】速報!国際地学オリンピック 日本大会立候補へ
──────────────────────────────────
昨年の東日本大震災で延期となっておりました、国際地学オリンピック日本
大会が、このたび2016年国際地学オリンピックを三重県内で開催する方向で
まとまりました。本年10月のアルゼンチン大会国際委員会で正式に立候補す
る見通しです。将来の地球科学を担う若者たちが世界から集います。
みんなで大会を成功させましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。 geo-Flashは、
月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日 までに
事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
新潟および関東地方の天然ガスの起源と賦存状態について
新潟および関東地方の天然ガスの起源と賦存状態について
金子信行(産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門)
新潟県は、わが国の有数の石油・天然ガス地帯である。また、南関東ガス田はわが国の天然ガス生産量の10%程度を占め、数百年分の埋蔵量を誇るガス田である。最近は原子力発電所の停止により輸入液化天然ガス(LNG)が注目されているが、国内にも貴重な石油・天然ガス鉱床は存在する。資源ナショナリズムの問題もあり、国産資源に目を向ける動きもあるが、資源の研究に従事する者としては、爆発事故等が起きる度に、一時的に国内の天然ガス資源が注目されることを残念に思う。
ひと言で“天然ガス”というが、狭義には「可燃性天然ガス」を意味し、その起源には微生物起源のものと熱分解起源のものが存在する。両者は、メタンの炭素同位体比(δ13C1)とガス組成のメタン/(エタン+プロパン)比(C1/(C2+C3))で区別される(例えば、金子ほか,2002:早稲田・岩野,2007)。微生物は12Cを選択的に利用してもっぱらメタンのみを生成するために、天然ガスはPDBスケールで-60‰よりも小さなδ13C1と、1000を超える大きなC1/(C2+C3)比を示す。一方、熱分解起源の天然ガスでは、δ13C1は-50‰よりも大きく、エタンやプロパンを相当量含むためにC1/(C2+C3)比は100以下となる。地質環境の下では、両者の混合したガスも存在し、一般にδ13C1、C1/(C2+C3)比ともに小さめの値を示す。また、地表で認められる熱分解起源のガス徴では、メタンの割合が増加してC1/(C2+C3)比が大きな値を示すものもある。
ここ数年、天然ガスに起因した事故が多く起きたが、そのほとんどは南関東ガス田分布域での上総層群中に胚胎する微生物起源ガスに起因する事故であった。この地域では、メタンは地下では間隙水に溶存する形で存在しており(水溶性天然ガス鉱床)、ガス田や温泉の開発によって地下深部から揚水しなければメタンが大規模に遊離することはない。「地震によって地下からガスが噴出し、首都圏が火の海になる」などという妄言に人々が惑わされないよう、地質学に関わる者として啓蒙しなければならない。一方、房総地域の地表ではガス徴が認められるように、遊離したガスの一部が地表まで移動して来ることがあり、密閉した構造物などでの爆発事故が危惧される。また、これとは別に、沖積層内で生成したメタンに起因するトンネル掘削事故や、地下水位の減少と回復に起因した古井戸からのメタンガス湧出が報告されており(東京都土木研究所,1993)、土木関係者等へのメタンガス存在の危険性を周知する必要がある。また、上総層群に限らず、関東平野ではその下位の三浦層群・葉山層群相当層にもメタンガスが含まれることが大深度温泉の掘削によって明らかになっており、注意を喚起したい。稀に、新第三系・第四系と接する基盤岩中の温泉に、メタンが付随するケースもある。
新潟県内にも、南関東ガス田と同様の水溶性天然ガス鉱床が、下越地域の海岸付近に分布している。貯留層は、西山層よりも若い地層である。一方で、地下数千mにおいて熱分解により生成した石油・天然ガスを胚胎する鉱床は、県内の新第三系堆積盆地内に広く分布している。根源岩とされる七谷層・寺泊層中で熱分解により生成した石油・天然ガスは、浮力により浸透率の大きな地層中を上方へ移動し、背斜や断層などのトラップを有する孔隙率が大きな貯留岩中に集積する。場合によっては、断層を介して層序的に下位の地層中に胚胎する。グリーンタフ中の天然ガス鉱床はその例である。一説によれば、新潟地域での集積率は1/40程度とされるので、多くの炭化水素は地層中を移動しているか、地表へと逸散、または微生物により消費されていると考えられる。したがって、新潟においても、関東地方同様に地下構造物の建設においては、天然ガスが湧出する危険がある。周辺に油・ガス田がなくても、それは経済的に稼行するだけの量の集積がなかっただけで、油やガスが地中に存在しないことにはならない。特に、地表でガス徴と呼ばれるガスの湧出が認められる地域では、危険度が高いことを指摘したい。ガス徴の確認には、詳細な地質調査や地元での聞き込みが必要であるが、インターネットで情報収集できることもある。(例えば、新潟県南魚沼市河原沢鉱泉 http://snow-country.jp/?a=contents&id=1149)
上記以外の地域でも、石炭層を狭在する北海道や九州の古第三系分布域など、天然ガスを含む地層は全国に分布する。国内における天然ガスの賦存可能性については、地質調査所発行の日本油田・ガス田分布図で概要が把握できる。
【文献】
地質調査所(1976)日本油田・ガス田分布図(第2版).
金子信行・猪狩俊一郎・前川竜男(2002)アーケアによるメタン生成と間隙水への濃集機構.石油技術協会誌,67,97-110.
東京都土木研究所(1993)東京下町低地における可燃性ガスの噴出について.東京都土木研究所特別報告第1号,42p.
早稲田周・岩野裕継(2007)ガス炭素同位体組成による貯留層評価.石油技術協会誌,72,585-593.
(2012.6.2)
No.178 2012/6/5 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.178 2012/6/5 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】新潟県南魚沼市のトンネル爆発に関連する地質情報
【2】解説:新潟および関東地方の天然ガスの起源と賦存状態について
【3】大阪大会の演題登録,参加登録サイトがオープン!
【4】AERA特集号の地質学者を貶める記事の訂正について
【5】第3回惑星地球フォトコンテスト表彰式開催
【6】一般社団法人日本地質学会2012年度総会開催報告
【7】2012年度会費督促請求について
【8】支部情報
【9】「北海道自然誌博物館ネットワーク」の紹介
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞情報
【12】サイエンスライター第2期募集
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】新潟県南魚沼市のトンネル爆発に関連する地質情報
──────────────────────────────────
5月24日に新潟県南魚沼市のトンネル工事現場において4名の方々が亡くなられた爆発事故がありました。亡くなられた方々とご遺族に対し謹んで哀悼の意を表します。
燃料資源の研究をされている産総研の金子信行会員に「新潟および関東地方の天然ガスの起源と賦存状態について」の解説を書いていただきましたので、以下に掲載させていただきました。
また、産業技術総合研究所地質調査総合センターのサイトには当該地域周辺の地質についての詳細な解説が掲載されています。
産総研サイトの地質解説「新潟県南魚沼市八箇峠トンネル(仮称)周辺の地質」はこちら、、、
http://www.gsj.jp/hazards/geologic-hazard/gas-explosion.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】解説:新潟および関東地方の天然ガスの起源と賦存状態について
──────────────────────────────────
金子信行(産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門)
新潟県は、わが国の有数の石油・天然ガス地帯である。また、南関東ガス田はわが国の天然ガス生産量の10%程度を占め、数百年分の埋蔵量を誇るガス田である。最近は原子力発電所の停止により輸入液化天然ガス(LNG)が注目されているが、国内にも貴重な石油・天然ガス鉱床は存在する。資源ナショナリズムの問題もあり、国産資源に目を向ける動きもあるが、資源の研究に従事する者としては、爆発事故等が起きる度に、一時的に国内の天然ガス資源が注目されることを悲しく感じる。
続きはこちらから、、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0386.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】大阪大会の演題登録,参加登録サイトがオープン!
──────────────────────────────────
演題登録締切(オンライン):7月3日(火)17時
参加登録締切(オンライン):8月17日(金)18時
本大会の新しい試みは,,,
・「日本地質学会アウトリーチセッション」を新設!
・ポスター発表の使用可能面積を大幅に拡大(横1200mm予定)!
・無線ネット利用可能エリアを大幅拡大!
・ミーティングスペースを設置!
ますますパワーアップした学術大会,どうぞご期待下さい.
詳しくはニュース誌5月号(大会予告記事),大会ホームページをご覧下さい.
http://www.geosociety.jp/osaka/content0001.html
(行事委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】AERA特集号の地質学者を貶める記事の訂正について
──────────────────────────────────
週刊誌AERAの特集号「震度7を生き残る」(2012年4月20日発行)に多数の地震学者へのインタビューを採録した「地震学者20人予想」の記事があります。
その26ページに上田誠也・東京大学名誉教授の回答があり、Q3「M7クラスの地震が南関東で発生する確率は今後4年以内に70%との試算」に対する回答として、「関係研究者(地質学者)とメディアの科学的素養の低さを示すもの」とするコメントが載っています。地質学会として看過できないと判断し,上田氏本人からこれが誤植であるとの言を得た上で,AERA編集部に確認を求めたところ、これは「関係研究者(地震学者)とメディアの……」の誤りで、「日本地質学会の会員のみなさまに、お詫びします」との回答があました。
下記Webにも訂正が公開されましたので、会員の皆様にお知らせいたします。
なお会員の皆様におかれましては、今回の震災の結果「地震活動の予測には長期的な時間軸を持った地質学的観点が必要」という認識が地震学者の中でも広まりつつあることも含めて、本件を周囲の方々にお知らせくださいますようお願いいたします。
日本地質学会会長 石渡 明
【6/12追記】当該雑誌については、3刷で問題部分が修正され、今後店頭に配送されるものは正しい誌面になるとの連絡をAERA編集部よりいただきました。
[朝日新聞出版の訂正掲載ページ]
http://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=13753
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第3回惑星地球フォトコンテスト表彰式開催
──────────────────────────────────
第3回惑星地球フォトコンテストの表彰式が5月19日に北とぴあ(東京都北区)で開催されました。最優秀賞の清川昌一さん、優秀賞の公文俊朗さん、永友武治さん、中馬辰紀さん、入選の林孝信さんの5名の受賞者が出席し白尾審査委員長より賞が授与されました。
「地質に写真はとても大切。もっと良い写真を取れるよう精進したい」と世界各地で地質写真を撮影している清川さん。「山が燃えているとの情報に、桜島撮影の経験からピンときてすぐに登って撮影した」(永友さん)「激しい鳴動の中、夜半に登った。ピントが難しくオリオン座で合わせた」(中馬さん)は新燃岳の噴火が題材。「いつも知っている場所なのに、違う場所のような不思議な景色になった」(公文さん)室戸岬の変化の激しい空模様での撮影。
白尾審査委員長は各入選作品を講評しつつ、次回さらなる力作が集まるよう会員の皆さんにも良い写真を撮って欲しいとの期待を述べました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】一般社団法人日本地質学会2012年度総会開催報告
──────────────────────────────────
5月19日には、フォトコンテスト表彰式に引き続き、一般社団法人日本地質学会2012年度総会が開催されました。
総会の議事録等詳細はNews誌7月号に掲載予定です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】 2012年度会費督促請求について
──────────────────────────────────
■2012年度およびそれ以前の会費が未入金の方へ■
1.次回の自動引き落とし日は6月25日(月)です。2012年度会費が未入金のかたで、1月から5月上旬までの間に自動引落の手続きをされたかたは6月25日に引き落としがかかります。引き落とし不備にならぬよう、残高の確認をお願いします。
2.郵便振替用紙によるお振り込みの方には、督促請求書(郵便振替用紙)を送付いたします。お手元に届きましたら、早急にご送金くださいますようお願いいたします。督促請求書の発送は6月中旬頃を予定しております。
※7月上旬頃までに入金確認が取れない場合には、7月号の雑誌から発送停止となります。定期的に雑誌をお受け取りになりたい方は、お早めにご送金くださいますよう、よろしくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
──────────────────────────────────
■中部支部:2012年年会
シンポジウム『中部地方の活断層にかかわる最新の知見』
日時:2012年6月16日(土)13:00〜17:00
場所:岐阜大学教育学部B102教室
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
■北海道支部:地質巡検のお知らせ
日時:2012年7月14日(土)〜16日(月・祝)
7/14 花崗岩類と弱・非変成中の川層群(日勝峠周辺)
7/15 西帯オフィオライト〜主帯の変成・深成岩類(パンケヌシ川)
7/16 西帯の苦鉄質〜超苦鉄質深成岩類(ウエンザル川)
費用:20,000円(懇親会費込み)
申込締切:6月11日(月)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】「北海道自然誌博物館ネットワーク」の紹介
──────────────────────────────────
北海道各地には、地質や化石を専門とする博物館・資料館等が数多く存在していますが、それらを包括する組織は存在していませんでした。
そのため今回、平成23年度北海道博物館協会学芸職員部会調査研究助成金の支援を受け、標記の「北海道自然誌博物館ネットワーク」を立ち上げることとしました。
現時点では、利用者との双方向の窓口として、「北海道地質と化石の相談室」http://www.hkmuseumnet.jp/ を公開しています。
このHPの目的は大きく2つあります。
1.各館に関する情報の一元的な発信
各担当者によって各館の情報が入力されることにより、利用者は北海道内各地の館情報を一箇所で閲覧することができる。
2.地質や化石に関する質問の受付・回答
利用者の質問に対し、それぞれの専門分野の協力者が回答する。質問の受付・回答は、相談窓口を通じて行なう。
このほか、夏休み等の自由研究の題材例や、各館を巡る見学ルートを提示するなど、内容については順次充実していく予定です。
このネットワークは、櫻井(穂別博物館)のほか、栗原憲一(三笠市立博物館)、澤村寛(足寄動物化石博物館)、篠原暁(沼田町化石館)の4名で準備を進めて来ました。加盟は施設や組織単位ではなく、協力者個人となります。負担金等については、今年度は不要です。現在のところ、上記のほか、山の手博物館や小平町文化交流センターの担当者が加わり、その他の方からも参加の意向を頂いています。
興味のある方はぜひ一度HPをご覧頂き、ご意見・ご感想をお知らせ頂けたら幸いです。
なお、組織については、順次拡大を図っていきたいと考えています。北海道内の地質や化石に関わる博物館等の情報を提供頂ける協力者はもちろんのこと、HPに送られた質問に対する回答にご協力頂ける方も大歓迎いたします。お気軽にご連絡頂けたら幸いです。
北海道自然誌博物館ネットワーク
代表 櫻井和彦(むかわ町立穂別博物館 学芸員)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■日本学術会議における公開シンポジウム
日本学術会議連続シンポジウム「巨大災害から生命と国土を護る−二十四
学会からの発信−」第五回「大震災を契機に地域・まちづくりを考える」
日時:2012年6月21日(木)14:00〜17:45
場所:日本学術会議講堂
ほか多数シンポあり.詳しくは、
http://www.scj.go.jp/ja/event/index.html
■資源地質学会第62回年会学術講演会
日程:2012年6月27日(水) 〜 29日 (金)
場所:東京大学小柴ホール
http://www.kt.rim.or.jp/~srg/documents/2012_nenkai.pdf
■東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究センター(RCME)・日本財団共催
第4回シンポジウム「海は学びの宝庫」
日時:2012年6月30日(土)13:00〜17:00
場所:東京大学本郷キャンパス・理学部1号館・小柴ホール
対象:小中高教員、学生、一般参加費:無料
下記URLより要事前登録
http://rcme.oa.u-tokyo.ac.jp/information/20120430_104.php
■「青少年のための科学の祭典」2012全国大会
日本地質学会後援
日時:2012年7月28日(土)〜29日(日) 9:30〜16:50
会場:科学技術館(東京都千代田区北の丸公園2-1)
http://www.kagakunosaiten.jp
*全国各地でも開催されています.
2012年度の開催予定はこちらから
http://www.kagakunosaiten.jp/country/schedule.php
■高校生のための先進的科学技術体験合宿プログラム
「サマー・サイエンスキャンプ2012」参加者募集
開催日:2012年7月23日〜8月26日の期間中の2泊3日〜5泊6日
対象:高等学校、中等教育学校後期課程または専門学校(1〜3学年)
応募締切:2012年6月14日(木)必着
主催:独立行政法人科学技術振興機構
詳しくは、 http://rikai.jst.go.jp/sciencecamp/camp/
スマートフォンサイト: http://rikai.jst.go.jp/sciencecamp/camp/sp/
■第11回中生代陸域生態系国際シンポジウムおよび韓国の恐竜サイト巡検
シンポジウム: 2012年8月15日(水)〜18日(土)
巡検(韓国南部の恐竜化石産出地): 8月19日(日)〜22日(水)
場所: 韓国・光州
http://www.2012mte.org/
【訂正】ニュース誌・HP掲載の記載情報(場所・問い合わせ先)に一部誤りがあり
ました。正しくは上記の通りです。
■日本第四紀学会2012年大会
日本地質学会共催
日程: 2012年8月20日(月)・21日(火)
会場: 立正大学熊谷キャンパス・アカデミックキューブ(埼玉県熊谷市)
http://quaternary.jp/meeting/index.html
発表申込〆切:6月25日(月)
*共催学会の会員は、日本第四紀学会会員と同じ資格でセッションで筆頭者として
(口頭1件+ポスター1件まで)発表ができます。
■2012年度日本地球化学会年会
日本地質学会共催
会期:2012年9月11日(火)〜13日(木)
会場:九州大学箱崎キャンパス文系地区
講演申込・要旨提出:7月17日(火)予定
http://www.geochem.jp/index.html
■第28回ゼオライト研究発表会発表募集
日本地質学会協賛
日時: 2012年11月29日(木)〜11月30日(金)
会場: タワーホール船堀(〒134-0091東京都江戸川区船堀)
講演申込締切: 8月8日(水)
詳しくは、http://www.jaz-online.org/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■平成24年度福井県職員(古生物学)募集(6/25)
■美祢市職員採用試験:一般行政事務及び地質学専門業務(6/22)
■JAMSTEC地球情報研究センター 技術職員公募(6/29)
■JAMSTECアプリケーションラボ 深海応用理工学プログラム ポストドクトラル研
究員公募(8/10)
■平成25年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞及び若手科学者賞受賞候
補者募集(推薦)(学会締切7/5)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】サイエンスライター第2期募集
──────────────────────────────────
5/10に地質学会プロデュースの広報誌「ジオルジュ」が創刊されました。
会員の皆様のお手元には、地質学雑誌と一緒に届いた頃でしょうか。
一般の読者に向けて地球科学に関する広い話題をわかりやすく紹介するため、ジオルジュはサイエンスライターの皆さんの手により作られています。昨年募集した第1期のサイエンスライターは、さらに良いものを作るべく第2号の編集に早速取り掛かっています。今後、ジオルジュを多くの人に親しまれる雑誌にするため協力していただける方、その他の学会刊行物にサイエンスを紹介する記事を書きたいという方は、事務局までお問い合わせ下さい。応募の際には,これまでに一般向けに書かれた原稿など参考になるものを付けて下さい.
応募多数の場合は審査させて頂きます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
福井県西部地域の地質について
福井県西部地域の地質について
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
最近,大飯(おおい)原子力発電所の運転再開問題が社会の注目を集め,同発電所周辺の活断層が問題になっている。私はこの発電所の完成前から現在まで約40年にわたり,これが立地する福井県おおい町大島半島とその周辺の地質学的研究を続けている。そこで今回は,大飯など複数の原子力発電所がある福井県西部の地質について,断層や地震を含め,これまでに公表されている基礎的な知識をまとめ,一般会員に向けて解説することにする。
図1. 福井県おおい町大島半島周辺の地質図。石渡 (1978),石渡・中江 (2001)に基づく。「輝緑岩」は岩脈などとして地下で固結した結晶質の玄武岩。「ダナイト」,「ハルツバージャイト」,「ウェルライト」はかんらん岩の種類で,それぞれかんらん石,かんらん石+斜方輝石,かんらん石+単斜輝石を主成分とする岩石。
大島半島の地質図としては,広川ほか (1957),広川・黒田 (1957),平野 (1969),石渡 (1978,1985英),福井県 (2010) などが出版されている。大島半島に露出する岩石は古くから「夜久野(貫入)岩類」と呼ばれていたが(広川ほか, 1957),石渡 (1978) はこれらが一連のオフィオライトをなしていると考え「夜久野(やくの)オフィオライト」と呼んだ。オフィオライトとは,地球の海洋底をつくっていた海洋地殻とその直下のマントルが,全体の構造を保ったまま地殻変動によって陸上に現われている層状火成岩体のことである(図1)。すなわち,マントルのかんらん岩類,地殻下部の斑れい岩類,そして地殻上部の玄武岩類や堆積岩類が下から上へ重なる厚さ8 km以上の岩体が,福井県大島半島から京都府,兵庫県を横切って岡山県南西部まで延長250 km以上にわたり断続的に分布している。夜久野オフィオライトは約2億8000万年前(古生代ペルム紀前期)に,その当時の島弧・縁海系で形成されたと考えられる(石渡, 1999, 市山・石渡, 2004英)。そして,夜久野オフィオライトはその直下のペルム紀付加体(超丹波(ちょうたんば)帯)や更にその下のジュラ紀付加体(丹波帯,約1億5000万年前)に衝上(しょうじょう)している。付加体は主に当時の海溝(かいこう:プレート沈み込み帯)に集積した砂岩,頁(けつ)岩,チャートなどの堆積岩よりなる。つまり,大飯原子力発電所は古生代後期の海洋地殻の上に立地しており,変質した玄武岩類(流紋岩や頁岩を伴う)の上にあって(石渡, 1978, 1985英),その北側の鋸(のこぎり)崎周辺には玄武岩質の枕状(まくらじょう)溶岩や集塊(しゅうかい)岩が見られる(平野, 1969)。また,その南東側のおおい町宮留(みやどめ)の赤礁(あかぐり)崎周辺の海岸には,超丹波帯のペルム紀赤色チャート層に衝上する夜久野オフィオライトの破砕されたマントルかんらん岩(小森・道林, 2011)がよく露出している。この地域の地質解説書としては,北陸の自然をたずねて編集委員会(2001,第2コース),石渡・中江(2001),日本地質学会(2006; 各論第3章)があり,露頭写真集としては,石渡ほか(1999),ふくい地質景観百選編集委員会(2009; p. 28-29, 48-49, 110-111など),日本地質学会構造地質部会(2012; 第8・第9地点)がある。オフィオライトについての解説は石渡 (2010)を参照されたい。
図2. 若狭湾周辺の活断層と地震の分布。活断層研究会 (1992)と中江ほか (2002) に基づく。若狭地震の震源位置は理科年表平成24年版(丸善)による。産業技術総合研究所地質調査総合センターの既刊5万分の1地質図幅の図幅名と範囲も示した。
大島半島の北半部には玄武岩,流紋岩,頁岩などからなるオフィオライトの上部の岩石が分布し,その南半部にはマントルかんらん岩,斑れい岩などオフィオライトの下部の岩石が分布していて,両者の間には東南東方向の断層が存在する(平野, 1969; 石渡, 1978, 1985英)。この断層は地形的なリニアメント(線状配列)が顕著で,露頭でも破砕帯や鏡肌(かがみはだ)が発達しているが,活断層かどうかは不明である。この断層は,広域的にみると,小浜(おばま)市街から東南東に延びる北川の谷沿いの活断層である「熊川断層」の西方延長に当たるように見える(図2)。熊川断層沿いでは,その北側の山地が南側に比べて200〜300 mほど低くなっていて,水平方向には若干の左横ずれを示すが,この断層の活動履歴は明らかでない(中江・吉岡, 1998)。また,大島半島の北方の若狭湾底には,長さ約20 kmの北西方向の活断層が推定されており(活断層研究会, 1992; 中江ほか,2002),その南東延長は小浜湾内に達する(図2)。しかし,これら2本の断層の延長が交わる小浜湾の中央部では,活断層が確認されていない(中江ほか, 2002)。一方,小浜市街の北東20 kmにある三方(みかた)五湖の日向(ひるが)湖と菅(すが)湖を貫く南北方向の日向断層(およびその東側に並行する三方断層)は,1662年6月16日の寛文(かんぶん)地震(マグニチュード7.2〜7.6)を起こし,断層の東側が約3メートル隆起したとされる(中江ほか,2002)。1325年,1683年,1748年にも若狭地方で被害が出る地震があった。そして1963(昭和38)年3月27日には若狭湾でマグニチュード6.9の地震が発生し,敦賀(つるが)と小浜の間で被害があった。この地震の震源は三方五湖の北約25 kmの海底であり,越前岬沖地震,福井県沖地震とも呼ばれる(図2)。
このように,大飯原子力発電所など若狭湾岸の原発が立地する福井県西部地域は,2.8億年前の海洋地殻と,その下盤側の1.5億年前までのプレート沈み込みによって形成された付加体から構成されており,日本の他の場所と同様に多数の活断層が存在していて,江戸時代から現代までの間にも複数回の大地震が発生している。
なお,私はこれまで原子力発電所の立地や安全性の評価に関わる仕事を依頼されたことは一切ない。この文章は,長年この地域の研究をしてきた一人の地質学者として,基礎的な知識を現時点で広く一般会員にお伝えする必要があると考え,執筆したものである。拙稿を校閲して貴重な改善意見をいただいた宮下純夫氏,斎藤 眞氏,坂口有人氏,ウォリス サイモン氏,渡部芳夫氏に感謝する。
【文献】
ふくい地質景観百選編集委員会 (2009) 「ふくい地質景観百選」.福井市自然史博物館.
福井県 (2010)「福井県地質図」(10万分の1)及び説明書.財団法人福井県建設技術公社.
平野英雄 (1969) 福井県大島半島の超塩基性岩.地質学雑誌, 75, 579-589.
広川治・磯見博・黒田和男 (1957) 5万分の1地質図幅「小浜」及び説明書.地質調査所.
広川治・黒田和男 (1957) 5万分の1地質図幅「鋸崎」及び説明書.地質調査所.
北陸の自然をたずねて編集委員会 (2001)「北陸の自然をたずねて」.築地書館.
Ichiyama, Y., Ishiwatari, A. 2004: Petrochemical evidence for off-ridge magmatism in a back-arc setting from the Yakuno ophiolite, Japan. Island Arc, 13, 157-177.
石渡明 (1978) 舞鶴帯南帯の夜久野オフィオライト概報.地球科学, 32, 301-310.
Ishiwatari, A. (1985) Granulite-facies metacumulates of the Yakuno ophiolite, Japan: Evidence for unusually thick oceanic crust. Journal of Petrology, 26, 1-30.
石渡明 (1999) 西南日本内帯の古生代海洋性島弧地殻断片:兵庫県上郡変斑れい岩体.地質学論集, No.52, 273-285.
石渡明 (2010) オフィオライト研究の新展開.地学雑誌, 119, 841-851.
石渡明・中江訓 (2001) 福井県若狭地方の夜久野オフィオライトと丹波帯緑色岩.日本地質学会第108年学術大会(金沢)見学旅行案内書, p. 67-84.
石渡明・辻森樹・早坂康隆・杉本孝・石賀裕明 (1999) 西南日本内帯古〜中生代付加型造山帯のナップ境界の衝上断層.地質学雑誌,105(2), III-IV(口絵).
活断層研究会 (1992) 「日本の活断層図 地図と解説」.東京大学出版会.
小森直昭・道林克禎 (2011) 夜久野オフィオライト待ちの山超マフィック岩体南部断層境界に発達したブロックインマトリックス構造.静岡大学地球科学研究報告, 38, 21-26.
中江訓・小松原琢・内藤一樹 (2002) 地域地質研究報告5万分の1地質図幅「西津地域の地質」.産業技術総合研究所地質調査総合センター.
中江訓・吉岡敏和 (1998) 地域地質研究報告5万分の1地質図幅「熊川地域の地質」.地質調査所.
日本地質学会(編)(2006) 「日本地方地質誌 中部地方」.朝倉書店.
日本地質学会構造地質部会(編)(2012)「日本の地質構造100選」.朝倉書店.
(2012.6.13)
No.179 2012/6/19 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.179 2012/6/19 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】福井県西部地域の地質
【2】パブリックコメント文科省「新たな地震調査研究の推進について」
【3】東日本大震災の復旧・復興に関わる調査・研究の公募
【4】大阪大会ニュース:国際ワークショップ「The Geology of Japan」を開催 ほか
【5】地質雑「早期公開」開始しました。
【6】2012年度およびそれ以前の会費が未入金の方へ
【7】支部情報
【8】本の紹介:「四国中央部三波川変成帯の地質」
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】福井県西部地域の地質
──────────────────────────────────
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
最近,大飯(おおい)原子力発電所の運転再開問題が社会の注目を集め,同発電所周辺の活断層が問題になっている。私はこの発電所の完成前から現在まで約40年にわたり,これが立地する福井県おおい町大島半島とその周辺の地質学的研究を続けている。そこで今回は,大飯など複数の原子力発電所がある福井県西部の地質について,断層や地震を含め,これまでに公表されている基礎的な知識をまとめ,一般会員に向けて解説することにする。
続きを読む、、、、 http://www.geosociety.jp/faq/content0388.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】パブリックコメント文科省「新たな地震調査研究の推進について」
──────────────────────────────────
地震に関する観測、測量、調査及び研究の推進についての総合的かつ基本的な施策の見直し(案)のパブリックコメントが文部科学省研究開発局地震・防災研究課より募集されています.積極的に参加してください.
締切:7月7日
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000578&Mode=0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】東日本大震災の復旧・復興に関わる調査・研究の公募
──────────────────────────────────
日本地質学会では,昨年度に引き続き,会員による表記の調査・研究費として,1件最大30万円を目安として3件程度の提案を公募することになりました.
応募締切:2012年7月31日(水)
申請書類のダウンロードおよび公募概要は下記から
http://www.geosociety.jp/hazard/content0075.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】大阪大会ニュース:国際ワークショップ「The Geology of Japan」を開催 ほか
──────────────────────────────────
■国際ワークショップ「The Geology of Japan」
日本列島の地質をテーマとした書籍はこれまで多数出版されていますが,それらの多くは日本語で書かれています.海外への情報発信のためには最新研究成果を含む英語版書籍の出版が必要不可欠ですが,この20年間出版されていない状況です.この空白域を埋めるために,このたびイギリス地質学会が出版する「The Geology of Japan」と題する書籍に日本地質学会が執筆やワークショップ開催等を通じて協力する運びとなりました.
【世話人】ウォリス サイモン(名大),石渡 明(東北大),平 朝彦(JAMSTEC),小島知子(熊本大)
【開催日時】9月16日(大会2日目)午後
■復旧復興にかかわる調査・研究事業の成果発表会
2011年度の「復旧復興にかかわる調査・研究事業」採択研究者による成果発表をポスター会場で開催します.
詳しくは、大会HP
http://www.geosociety.jp/osaka/content0045.html
■講演申込をお忘れなく!
申込〆切: オンライン 7月3日(火)17時(郵送 6月27日(水) 必着)
http://www.geosociety.jp/osaka/content0024.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質雑「早期公開」開始しました。
──────────────────────────────────
地質学雑誌の特集号に受理された論文を,当該特集号の印刷前に,順次このWEBサイトで公開します.ただし,このWEBサイトを閲覧できるのは,地質学会会員のみです.
ここに掲げられた論文のPDFファイルは,当該特集号の冊子体の印刷とともにこのサイトからは削除され,J-STAGEのサーバーに移動して通常号と並んで公開されます.
詳しくは、学会ホームページ「会員のページ」からアクセスして下さい.
(会員番号・パスワードによるログインが必要です)
https://www.geosociety.jp/login.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】2012年度およびそれ以前の会費が未入金の方へ
──────────────────────────────────
1.次回の自動引き落とし日は6月25日(月)です。2012年度会費が未入金のかたで、1月から5月上旬までの間に自動引落の手続きをされたかたは6月25日に引き落としがかかります。引き落とし不備にならぬよう、残高の確認をお願いします。
2.郵便振替用紙によるお振り込みの方には、督促請求書(郵便振替用紙)を送付いたしました。早急にご送金くださいますようお願いいたします。督促請求書の発送は6月中旬頃を予定しております。
※7月上旬頃までに入金確認が取れない場合には、7月号の雑誌から発送停止となります。定期的に雑誌をお受け取りになりたい方は、お早めにご送金くださいますよう、よろしくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】 支部情報
──────────────────────────────────
■北海道支部:地質巡検のお知らせ
日時:2012年7月14日(土)〜16日(月・祝)
7/14 花崗岩類と弱・非変成中の川層群(日勝峠周辺)
7/15 西帯オフィオライト〜主帯の変成・深成岩類(パンケヌシ川)
7/16 西帯の苦鉄質〜超苦鉄質深成岩類(ウエンザル川)
費用:20,000円(懇親会費込み)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】本の紹介:「四国中央部三波川変成帯の地質」
──────────────────────────────────
遅沢壮一 著
愛媛県総合科学博物館,2012年3月31日発行,「四国中央部三波川変成帯の地質」地質図+解説文(A4版)6ページ,500円
紹介するのは,遅沢さんが作成した四国中央部の三波川変成帯の地質図と解説文である.地質図の縮尺は,約7万5千分の1で,カラー印刷である. 三波川帯の地質調査と地質図作成は,第二次世界大戦後,広島大学の小島丈児先生や秀 敬先生,原 郁夫先生とその門下生(小島学派)が精力的におこなってきた.その野外調査のすさまじさは,愛媛で生まれ育った紹介者は,様々な場所で伝説的な話として聞いてきたし,室内外において露頭の観察方法を指導していただいたりした.三波川帯の調査・研究に関しては,原 郁夫先生の著書(2008)「地域地質学の方法論 小島学派,一つの回想」(丸源書店)を読んでいただくこととし,「四国中央部三波川変成帯の地質」の紹介にもどる.
遅沢さんは,様々な意味で調査が大変であることを自覚したうえで,四国中央部の急峻な山岳地域を調査し,下位から大歩危スラスト,蛇野アウトオブシークエンススラスト,これに切られるエクスツルージョナルウェッジ,汗見川デタッチメント断層等を見出し,地質図とその断面図を作成した.解説文に「本地質図には,大歩危ユニットを含む各変成鉱物帯の構造的累重関係を,それらの分布とともに,忠実に表現している.本地質図が三波川帯研究の基礎資料となることを願っている.縮小した指標図ファイルは,筆者に請求頂ければ提供するので,引用のうえで使用頂ければと思う.」と述べている.
東北大学の,敢えて旧称を用いるが,地質学古生物学教室の伝統は,とてつもなく広範囲を,行けるところは全部行って,かつ精度良く調査することであった.本地質図を作成した遅沢さんに敬意を表するとともに,本地質図を地質学会会員の皆様にご紹介し,一人でも多くの人にじっくり検討していただければと思う次第である.
目次
はじめに
地形
岩相
D1とプレD1の露頭・薄片規模の変形
エクスツルージョナルウェッジと汗見川デタッチメント断層
蛇野アウトオブシークエンススラスト(OST)
富郷デュープレックス
大歩危背斜
エクロジャイトの起源
応用地質
文献
Abstract
本書は,愛媛県総合科学博物館・ミュージアムショップで500円で購入できる.発送は郵送とし,郵送を希望される方は,ファックスまたは電子メールでお申込みください.その際,「氏名,送付先(郵便番号も記入),連絡先(電話番号),希望部数」をお知らせください.折り返し,送料や振込先の連絡がいきます.1部ですと140円の送料になります.なお,振込みは銀行で,振込手数料は購入者負担となります.
申込先は,〒792-0060 愛媛県新居浜市大生院2133-2(TEL:0897-40-4100 Fax:0897-40-4101 E-mail:top@i-kahaku.jp )
(高橋治郎)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第14回、15回尾瀬賞合同授賞式、記念講演
日時:2012年6月29日(金)
会場:都道府県会館( 東京都千代田区平河町)
http://www.oze-fnd.or.jp/
■地震発生及び火山噴火研究の将来構想シンポジウム
「地震及び火山噴火予知のための観測研究」を実施してきた研究
グループは,社会が地震や火山噴火の研究に対して何を期待して
いると考えるか, その期待に応えていくため地震や火山現象の
解明に向けてどのような研究を今後進めていくべきか,具体的に
どのような研究が必要なのかについて議論するシンポジウムを
開催します.
日程:2012年7月5日(木)10:00 〜7月6日(金)17:00
申込締切:6月22日(金)正午
要旨締切:6月29日(金)正午
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/YOTIKYO/nenji/h24_planning_workshop.htm
■第21回市民セミナー
「大震災後の水環境ー何が起こったのか、どう備えるか」
日時:2012年8月3日(金)
場所:東京会場:地球環境カレッジ(いであ(株)内)(東京都世田谷区駒沢)
大阪会場:いであ(株)大阪支社ホール大阪市住之江区南港北)
申し込み・問合せ先:
(公社)日本水環境学会セミナー係 山本
TEL:03-3632-5351 e-mail:yamamoto@jswe.or.jp
■第13回目「地震火山こどもサマースクール」(in 糸魚川ジオパーク)
日本地質学会・日本地震学会・日本火山学会共催
日程:2012年8月18日(土)〜19日(日)
テーマ「東と西に引き裂かれた大地のナゾ」.
参加対象:小学5年〜高校生(40名)
参加申込〆切:7月20日(金)
募集要項など詳しくは、
http://www.kodomoss.jp/ss/itoigawa
■ワークショップ “ULTRA-DEEP DRILLING INTO ARC CRUST:
genesis of continental crust in volcanic arcs”
日程:2012年9月17日〜21日
場所:Waikoloa Beach Marriott Resort & Spa, Kona, Hawaii, USA
大陸は、太陽系の惑星の中では、地球にしかない、と言われています。不思議ですね。大陸の成因の解明に、多くの研究者が取り組んでいます。しかし、古い地層を研究するだけでは、ダイナミックな地球の営みを解明することはできません。ツナ缶を開けても、大海を群遊するマグロを想像できないのと同じです。そこで、直接、大陸のできるところを海底掘削で調べてみよう、という国際プロジェクトができました。海を研究する研究者と大陸を研究する研究者を一堂に会するワークショップです。皆様のご応募をお待ちしています。
http://www.jamstec.go.jp/ud2012/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■滋賀大学教育学部理科教育講座(地質鉱物学)(8/31)
■京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻地質学鉱物学教室公募(9/3)
■北海道立総合研究機構(地質研究所)平成25年度採用の研究職員採用(6/29)
■第2回「海のフィロンティアを開く岡村健二賞」推薦候補者募集(学会締切8/10)
■2013年度 「猿橋賞」受賞候補者募集(11/30)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.180 2012/6/29 geo-flash(臨時)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.180 2012/6/29 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】大阪大会 講演申込〆切迫る! 7月3日(火)17時締切です!
──────────────────────────────────
大阪大会,演題登録締切が近づいてきました!
(行事委員会)
演題登録締切(オンライン):7月3日(火)17時
年に一度の「地質学の祭典」で研究成果を発表し,地質学を前進させましょう!
日本地質学会は,あなたの大会参加と研究発表を歓迎いたします.
本大会の新しい試みは,,,
・「日本地質学会アウトリーチセッション」を新設!
・ポスター発表の使用可能面積を大幅に拡大(横1200mm予定)!
・国際ワークショップを開催!
・無線ネット利用可能エリアを大幅拡大!
・ミーティングスペースを設置!
詳しくはニュース誌5月号(大会予告記事),大会ホームページをご覧下さい.
http://www.geosociety.jp/osaka/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。 geo-Flashは、
月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日 までに
事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.181 2012/7/2 geo-flash(臨時)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.181 2012/7/2 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】<大阪大会> 講演申込:締切延長 7/4(水)17時!
──────────────────────────────────
日本地質学会第119年学術大会(大阪大会)「都市から発信する地質学」
多くの方々にご講演いただくため、講演申込の締切を延長いたしました。
お申し込みをお待ちしています。(行事委員会)
オンライン講演申込締切:7月4日(水)17時厳守(郵送分は締切ました)
詳しくは,大会HPをご覧下さい。
http://www.geosociety.jp/osaka/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。 geo-Flashは、
月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日 までに
事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.182 2012/7/3 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.182 2012/7/3 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】<大阪大会>講演申込、いよいよ最終締切!
【2】<大阪大会>各種申込み締切のお知らせ
【3】広報誌ジオルジュ 一括割引購入のご案内
【4】支部情報
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】<大阪大会>講演申込、いよいよ最終締切!
──────────────────────────────────
昨日、講演申込が24時間延長されましたが、いよいよ7月4日17時の最終締切が目前に迫りました。
ラストスパートで講演申込みお忘れなく。
注目のシンポジウム、イベント満載の大阪大会でお会いしましょう!
講演申込は、こちらから
http://www.geosociety.jp/osaka/content0024.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】<大阪大会>各種申込み締切のお知らせ
──────────────────────────────────
■ 小さなEarth Scientistのつどい
〜第10回 小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜
申込締切:7月17日(火)
http://www.geosociety.jp/osaka/content0012.html#happyo1
■ 企業・研究機関等関係団体による展示会の出展募集
地質関係機関・関連企業のご活躍を広く地質学会員に紹介していただくため、会期中、企業展示会を開催致します。
企業紹介・業務紹介・研究成果・新技 術・特許などご自由に展示内容を構成いただけます。奮ってご出展のお申込 をいただきますようお願い申し上げます。
募集締切:7月27日(金)
http://www.geosociety.jp/osaka/content0039.html
■ 書籍・販売ブースご利用の募集
申込締切:7月27日(金)
http://www.geosociety.jp/osaka/content0039.html#book
■ 講演要旨集,広告協賛の募集
申込締切:7月27日(金)
http://www.geosociety.jp/osaka/content0039.html#kokoku
■ 就職支援プログラム 参加企業・団体募集
申込締切 8月10日(金)
http://www.geosociety.jp/osaka/content0013.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】広報誌ジオルジュ 一括割引購入のご案内
──────────────────────────────────
学会の新広報誌「ジオルジュ」(年2回発行、定価250円)を博物館・学校・研究機関などで、イベントでの配布物、友の会へのプレミアグッズ、ストア などでの販売物として、利用してみませんか。部数に応じて割引価格を設定しております。是非ご検討下さい。
<割引価格例>
100部: 20,000円(定価2割引)
300部: 52,500円(定価3割引)
これ以外についてもご希望に応じてご相談承ります。毎号各地のジオパークの特集記事の掲載も企画しています。
ジオパークの広報の一環としてもご活用ください。
<購入に関するお問い合わせ>
一般社団法人日本地質学会
電話03-5823-1150 FAX 03-5823-1156
E-mail: main@geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】支部情報
──────────────────────────────────
■ 北海道支部:地質巡検のお知らせ
日時:2012年7月14日(土)〜16日(月・祝)
7/14 花崗岩類と弱・非変成中の川層群(日勝峠周辺)
7/15 西帯オフィオライト〜主帯の変成・深成岩類(パンケヌシ川)
7/16 西帯の苦鉄質〜超苦鉄質深成岩類(ウエンザル川)
費用:20,000円(懇親会費込み)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■ シンポジウム「海洋教育から考える"津波・防災"−東南海地震に備えて−」
日時:2012年7月8日(日)13時〜17時30分
会場:豊橋技術科学大学 A棟101講義室 (愛知県豊橋市)
対象:小中高教員、学部学生、大学院学生、一般
参加費:無料
http://rcme.oa.u-tokyo.ac.jp/information/20120411_100.php
■ 日本学術会議における公開シンポジウム
シンポジウム「安全工学シンポジウム2012」
日時:7月5日(木)〜6日(金)
場所:日本学術会議講堂
シンポジウム「巨大自然災害・原発災害と法−基礎法学の視点から−」
日時:7月7日(土) 13時00分〜18時00分
場所:日本学術会議講堂
シンポジウム「巨大災害から生命と国土を守る−24学会からの発信−」
第6回「原発事故からエネルギー政策をどう建て直すか」
日時:7月24日(火) 13時00分〜17時00分
場所:日本学術会議講堂
詳しくは
http://www.scj.go.jp/ja/event/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■鳴門教育大学自然・生活系教育部自然系コース(理科)地学教員公募(准教授または講師)(8/6)
■海洋研究開発機構 平成25年度研究船利用課題の募集(なつしま、よこすか、かいれい、みらい等)(6/27〜7/19)
■第34回(平成24年)沖縄研究奨励賞推薦応募(学会締切:8/31)
■平成24年度東レ科学技術賞および東レ科学技術研究助成の候補者推薦(学会締切:8/31)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.183 2012/7/17 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.183 2012/7/17 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】<大阪大会>巡検参加申込受付中!
【2】<大阪大会>プレス発表を希望される方へ
【3】<大阪大会>緊急展示の申込について
【4】<大阪大会>各種申込み締切のお知らせ
【5】2012年度地質の調査研修 参加者募集
【6】津波堆積物ワークショップ&巡検を紀伊半島で開催します
【7】地学オリンピック:地球にわくわく小・中学生自由研究コンテスト作品募集
【8】紹介:『物質科学を学ぶための量子力学,解析力学,統計力学,電磁気学の「基礎事項シリーズ講義録」
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】<大阪大会>巡検参加申込受付中!
──────────────────────────────────
第119年学術大会(2012年・大阪)巡検の参加申込を受付中です.
今年は近畿の地質の理解を深めるために企画された興味深い巡検コースが目白押しです.多くの会員の皆さまのご参加をお待ちしています.GISのワークショップや地学教育関連の半日巡検もあります.是非ご参加下さい.
各巡検コースの詳細は,大阪大会のホームページ
(http://www.geosociety.jp/osaka/content0001.html)
をご覧下さい.
(巡検準備委員会 奥平敬元)
大会参加申込(巡検参加含む)締切:8月17日(金)(郵送8月10日締切)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】<大阪大会>プレス発表を希望される方へ
──────────────────────────────────
大阪大会での講演や行事について,9月上旬にプレス発表を行う予定です.
例年多数のメディアに取り上げられ,会員の研究成果が大いに注目されています.大阪大会で発表される予定の案件で,学会からのプレス発表をご希望の方は,7月31日(火)までに学会事務局にご連絡願います.
全ての案件をプレス発表することはできませんが,社会への情報発信として特筆すべき成果は積極的に公表して行きたいと考えております.
大阪大会の成功と地球科学の成果のアピールのため,ご協力よろしくお願い申しあげます.
登録締切:7月31日(火)
プレス発表(投げ込み):9月上旬
連絡先:日本地質学会事務局 journal@geosociety.jp
(日本地質学会広報委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】<大阪大会>緊急展示の申込について
──────────────────────────────────
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害調査報告や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コーナー」を設けます.
ポスター展示を希望する方は,8月31日(金)までに次の内容を下記申込先にご連絡ください.
1)発表要旨PDF(ニュース誌5月号参照) 2)緊急展示の必要性 3)発表代表者と連絡先 4)希望枚数(1枚:幅90×180cm) 5)展示に関わる要望
(2〜5の様式は自由)
実行委員会は行事委員会と協議し,可否の判断を致します.希望にはできるだけ応えるようにしますが,展示方法等については実行委員会の指示に従ってください.
申込先:main@geosociety.jp
担当:石井和彦(大阪大会実行委員会)・須藤 宏(行事委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】<大阪大会>各種申込み締切のお知らせ
──────────────────────────────────
■ 企業・研究機関等関係団体による展示会の出展募集
地質関係機関・関連企業のご活躍を広く地質学会員に紹介していただくため、会期中、企業展示会を開催致します。企業紹介・業務紹介・研究成果・新技術・特許などご自由に展示内容を構成いただけます。奮ってご出展のお申込をいただきますようお願い申し上げます。
募集締切:7月27日(金)
http://www.geosociety.jp/osaka/content0039.html
■ 書籍・販売ブースご利用の募集
申込締切:7月27日(金)
http://www.geosociety.jp/osaka/content0039.html#book
■ 講演要旨集,広告協賛の募集
申込締切:7月27日(金)
http://www.geosociety.jp/osaka/content0039.html#kokoku
■ 就職支援プログラム 参加企業・団体募集
申込締切 8月10日(金)
http://www.geosociety.jp/osaka/content0013.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2012年度地質の調査研修 参加者募集
──────────────────────────────────
日本地質学会では,社会貢献事業の一端として,支部や他学会・機関と連携した研修事業等を企画,実施することとしています.その背景には,国内の地質調査業や関連事業団体からの地質調査技術の研修要請に対する定常的な仕組みがほとんど存在していないことが挙げられます.日本地質学会では,地方支部のネットワーク等を有効に利用して,これらの社会要請に幅広く対応できる体制を構築していくべきと判断し,2012年度よりモデル事業を立ち上げることとしました.充実した地質調査研修プログラムをご用意いたしますので,是非ご参加ください.
(2012年7月 日本地質学会社会貢献部会)
日程:2012年10月29日(月)〜11月2日(金)4泊5日
場所:千葉県君津市及びその周辺地域(房総半島中部域)
募集対象:主に地質関連会社の若手技術者(会員・非会員を問いません)
募集人数:6名
募集締切:2012年9月21日(金)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/engineer/content0021.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】津波堆積物ワークショップ&巡検を紀伊半島で開催します
──────────────────────────────────
本学会は日本堆積学会と共催で,津波堆積物に関するワークショップと巡検を10月に開催することになりました.
【日程】
10/6 ワークショップ(三重県津市を予定)
10/7-8 巡検(鳥羽-尾鷲-南紀白浜を予定)
【ワークショプ講演者】
菅原大助会員(東北大・災害科学国際研),小松原純子会員(産総研・地質情報),後藤和久会員(千葉工大・惑星探査研究セ),藤野滋弘会員(筑波大・生命環境系)
参加募集要項,参加費等の詳細が決まり次第,ニュース誌,学会ホームページ,geo-Flash等でお知らせします.ご期待下さい!
(日本地質学会行事委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】地学オリンピック:地球にわくわく小・中学生自由研究コンテスト作品募集
──────────────────────────────────
地学オリンピックは、地球にわくわく小・中学生自由研究コンテスト作品を募集しています!小学生、中学生の皆さん!夏休みに自由研究で宇宙や地球、そして周りの環境を調べてみませんか。
募集期間:2012年8月1日(水)〜10月31日(水)
応募資格・部門:小学生2部門(3・4年、5・6年)、中学生1部門
研究テーマ:地球や宇宙、環境に関する自由研究(例:天気調べ、流星群の観察、河原の石くらべなど)
応募方法、郵送先など詳細は
地学オリンピックHPまで http://jeso.jp/wakuwaku/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】紹介:『物質科学を学ぶための量子力学,解析力学,統計力学,電磁気学の「基礎事項シリーズ講義録」
──────────────────────────────────
川邊岩夫著
『物質科学を学ぶための量子力学,解析力学,統計力学,電磁気学の「基礎事項シリーズ講義録」が名古屋大学中央図書館リポジトリーへ登録された.
本書は,著者が『希土類元素の化学と地球化学』を執筆する為に,その基礎となる物理化学を学び整理したその結果としての講義録(電子書籍:無料)で,以下の4部に区分されている.
・物質科学を学ぶための解析力学の基礎事項
http://i.nul.nagoya-u.ac.jp/jspui/handle/2237/16106
・物質科学を学ぶための統計力学の基礎事項
http://i.nul.nagoya-u.ac.jp/jspui/handle/2237/16107
・物質科学を学ぶための電磁気学の基礎事項
http://i.nul.nagoya-u.ac.jp/jspui/handle/2237/16108
・量子力学の基礎事項
http://i.nul.nagoya-u.ac.jp/jspui/handle/2237/16109
それぞれの部は,16から28の節から構成されており,全体で2000ページにのぼる大著である.しかし,そこは電子書籍の利点で,興味がある,あるいは必要な部分を抜き出して読み,あるいはプリントすることができるとてもハンデイな書である.とはいえ,著者には「希土類元素の化学と地球化学を解明するため」として見えていた学ぶ目標が,評者には定まっていないことによるのか,本書はなかなか難解であった.本書の理解を速めるのは,常に読者自身が究めたい地球科学に回帰しながら読むことであろう.
本書の中でも,第2分冊の§13 化学反応とその平衡,などは地球科学でもなじみのある部分である.一つには分かり易い例題が載せられており,どのような地球科学に応用出来るかが理解し易いからである.ほかの章や節にも,このような地球科学の例題が載せられるならば,読者の理解は一層容易になると考えられる.しかし例題はなくとも,地球科学をこれから始めようと考える柔軟な思考を持つ学生が,広範な基礎事項を含む本書を通読することによって,従来の地球化学には無かった新しい視点が芽生える事も大いに期待される.
本書は,電子出版であるが故に,改訂が容易であろう.読まれた方が,感想や質問を著者に返すことにより,地球科学で広く読まれる,すぐれた基礎事項書となろう.
(田中 剛)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■ 第15回日本水環境学会シンポジウム
日時:2012年9月10日(月)〜11日(火)
会場:佐賀大学本庄キャンパス
予約参加申込申込期限:8月10日(金) 24:00
(それ以降は当日申込扱いとなります)
http://www.jswe.or.jp
■ 第6回地殻応力国際シンポジウム
日本地質学会 後援
日時:2012年8月20日(火)〜22日(木)
会場:仙台国際センター(宮城県仙台市)
講演申込期限:2012年11月30日(金)
http://www2.kankyo.tohoku.ac.jp/rs2013/
■ 学術会議公開講演会
「東日本大震災復興の道筋と今後の日本社会」
日時:2012年7月29日(日)13:30〜
会場:京都大学北部総合教育研究棟益川ホール
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/154-s-1-1.pdf
■「希少元素代替材料」に関する日本−EU共同研究課題
・対象領域:希少元素代替材料
(Development of new materials for the substitution of critical metals)
・支援規模:1課題あたり総額2億円(上限、間接経費含む)
・応募締切:平成24年10月23日(火)午後5時
http://www.jst.go.jp/sicp/announce_eujoint_02.html
問い合わせ先:独立行政法人科学技術振興機構(JST)
E-mail:jointeu@jst.go.jp(担当:長谷川)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■2012年度「朝日賞」候補者推薦(学会締切8/10)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flash No.194 地質学会に「環境変動史部会」が設立決定
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.194 2012/9/18 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】速報:10月1日、地質学会に「環境変動史部会」が設立決定
【2】産総研:日本シームレス地質図を更新
【3】フィールドジオロジー:会員特別販売のご案内
【4】その他のお知らせ
【5】公募情報・各賞情報
【6】訂正
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】速報:10月1日、地質学会に「環境変動史部会」が設立決定
──────────────────────────────────
2012年10月1日より、日本地質学会に新たな部会として「環境変動史部会」が設立さ
れることが決まりました。
地球環境変動史の解明に取り組む新たな部会です。
部会の詳細および部会への登録方法は後日改めてお知らせします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】産総研:日本シームレス地質図を更新
──────────────────────────────────
産総研の公開する日本シームレス地質図が、約14ヶ月ぶりに最新20万分の1
図幅に基づき大幅更新されました。
<更新内容>
2009〜2010年出版の1/20万地質図幅「与論島及び那覇」、「西郷」、「中津」、
「八代及び野母崎の一部」に基づき基本版および詳細版のデータ更新。
通常版、スマートフォン・タブレットPC版で利用できます。
シームレス地質図はこちらから、、、
http://riodb02.ibase.aist.go.jp/db084/maps.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】フィールドジオロジー:会員特別販売のご案内
──────────────────────────────────
このたびは全9巻完結いたしました「フィールドジオロジーシリース」を特別割引
価格にて会員の皆様にご案内いたします。
・フィールドジオロジー 全9巻 全巻セット 特価16,000円(定価18,900円)
・8巻 火成作用(9月新刊)高橋正樹・石渡 明著 特価1,900円(定価2,100円)
・9巻 第四紀(9月新刊)遠藤邦彦・小林哲夫著 特価1,900円(定価2,100円)
*いずれも送料込み
専用申込用紙は、学会HP・会員のページにアクセスして下さい。
(会員番号によるログイン情報が必要です)
http://www.geosociety.jp/user.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■東京大学大気海洋研究所共同利用研究集会
南大洋インド洋区における海洋地球科学合同観測の成果〜IODP 掘削へ向けて〜
日時:9月24日(月)13:30-17:00
9月25日(火)10:00-12:00
場所:東京大学大気海洋研究所2F 講堂
http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/aori_news/meeting/2012/20120924.html
■文部科学省JST社会技術研究開発センター
「科学技術と社会の相互作用」第5回シンポジウム
日時:9月29日(土)10:00-17:35 参加費無料(事前登録制)
会場:TEPIAホール(東京都港区北青山2丁目)
http://www.ech.co.jp/jst-sth05-sympo
■日本学術会議国際シンポジウム
「原子力発電所事故の教訓・過酷事故発生時の世界の科学アカデミーの役割」
インターアカデミーカウンシル(IAC)共催
日時:10月10日(水)13:30-18:00 参加費無料
会場:日本学術会議 講堂
http://www.scj.go.jp/ja/int/kaisai/121009sinpo.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■山田科学振興財団2013年度研究援助候補推薦(2013/1/31学会締切)
■北海道大学大学院理学研究院自然史科学部門地球惑星システム科学分野准教授公
募(10/10)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】訂正
──────────────────────────────────
日本地質学名誉会員 飯山敏道氏が、平成24年9月15日(土)にご逝去されました。
昨日geo-Flashにてお知らせいたしましたが、逝去日に誤りがありましたので、訂正
させて頂きます。正しくは、平成24年9月15日(土)です。大変失礼いたしました。
申し訳ございません。告別式等については、先にお知らせの通りです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
<ニュース誌表紙写真,特に募集中です!お待ちしてます. >>
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
No.184 2012/8/7 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.184 2012/8/7 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】<大阪大会>事前参加登録まもなく締切です!(最終締切:8/17 )
【2】<大阪大会>緊急展示の申込について
【3】<大阪大会>就職支援プログラム 参加企業・団体募集
【4】<大阪大会>学術大会の改革:オープンディスカッション
【5】津波堆積物ワークショップ&巡検:参加者募集
【6】2012年度地質の調査研修 参加者募集
【7】支部情報
【8】「日本の地質構造100選」会員特別割引販売のお知らせ
【9】紹介:「おくのほそ道」を科学する
【10】第3回フォトコンの入選作品が「月刊日本カメラ」で紹介されました
【11】産総研:シームレス地質図に火山表示機能追加
【12】その他のお知らせ
【13】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】<大阪大会>事前参加登録まもなく締切です!(最終締切:8/17 )
──────────────────────────────────
大会参加申込(巡検参加含む)締切:8月17日(金)(郵送8月10日締切)
■事前参加登録まもなく締切です!
全体日程表を大会HPに掲載しました。スケジュール等をご確認の上、大会参加予定の方は、忘れずにご事前登録を行って下さい.
全体日程表はこちらから
http://www.geosociety.jp/osaka/content0009.html
■巡検参加申込受付中!
今年は近畿の地質の理解を深めるために企画された興味深い巡検コースが目白押しです.GISのワークショップや地学教育関連の半日巡検もあります.是非ご参加下さい.8/6現在の申込状況もご確認頂けます.
http://www.geosociety.jp/osaka/content0001.html
巡検各コースの見所はこちら、、、
http://www.geosociety.jp/osaka/content0022.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】<大阪大会>緊急展示の申込について
──────────────────────────────────
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害調査報告や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コーナー」を設けます.
ポスター展示を希望する方は,8月31日(金)までにご連絡ください.
担当:石井和彦(大阪大会実行委員会)・須藤 宏(行事委員会)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/osaka/content0047.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】<大阪大会>就職支援プログラム 参加企業・団体募集
──────────────────────────────────
本プログラムは,学会に参加される学生・院生および大学教官の会員,ならびに大阪府立大学等の学生・院生・関係者らを対象に,本会賛助会員をはじめとする関連業界との情報交換を行う場を提供しようというものです.多くのご参加をお待ちしています.
参加企業・団体申込締切 8月10日(金)
http://www.geosociety.jp/osaka/content0013.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】<大阪大会>学術大会の改革:オープンディスカッション
──────────────────────────────────
日時:9月17日(月)18:00〜19:30
会場:B3教育棟2階,第5会場(予定)
より多くの会員に「日本地質学会の会員として,学術大会に参加したい! 発表したい!」と思われる大会にしたいと行事委員会は考えています.セッション構成,参加費,院生・ポスドク等の若手やシニアの活躍・交流の場の創設など,さまざまな観点から検討する必要があります.
行事委員会は,今年度中に学術大会の改革案(ブループリント)を作成する予定です.それにむけて,会員の皆様からアイディアや他学協会等の情報を頂き,自由闊達な意見交換をしたいと考え,どなたでも参加できるオープンディスカッションの機会を設けます.
大会最終日の夜間ですが,本学会を愛する皆様の積極的なご参加をお待ちしております.
詳しくは、http://www.geosociety.jp/osaka/content0048.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】津波堆積物ワークショップ&巡検:参加者募集
──────────────────────────────────
本学会は日本堆積学会と共催で,津波堆積物に関するワークショップと巡検を10月に開催することになりました.
【日程】
10/6 ワークショップ(津市三重県総合文化センター大研修室)
10/7-8 巡検(鳥羽-尾鷲-南紀白浜を予定)
【申込締切】8月31日(金)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0106.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】2012年度地質の調査研修 参加者募集
──────────────────────────────────
日程:2012年10月29日(月)〜11月2日(金)4泊5日
場所:千葉県君津市及びその周辺地域(房総半島中部域)
募集対象:主に地質関連会社の若手技術者(会員・非会員を問いません)
募集人数:6名
募集締切:9月21日(金)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/engineer/content0021.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
関東支部:銚子巡検のご案内
関東支部では関東地質調査業協会(共催)と日本第四紀学会(後援)のもと,2012年度事業として10月27日と28日の2日間にわたり「銚子巡検」を開催いたします.巡検では,銚子周辺にみられる薄衣型礫岩(ペルム紀?)やジュラ紀付加体,白亜紀以降の前弧海盆堆積物や前期中新世の古銅輝石安山岩溶岩,そして鮮新統〜更新統の犬吠層群までを観察します.さらに,夜間講演会では,観察事項,昨今の知見,およびそれらに基づく日本列島形成史や関東平野の変動史の解説が案内者によりなされます.最終的に,参加者の皆様には変動帯としての日本列島の鳥瞰的理解を深めていただきたいと考えております.会員の方はもとより,広く参加者を募集します.CPDは16単位取得可能です(銀行振込後の参加者交代は可能).
詳細は,参加者の皆様へ直接メールにてご連絡いたします.
主催:日本地質学会関東支部
共催:関東地質調査業協会
後援:日本第四紀学会
開催日時:2012年10月27日(土)〜28日(日),1泊2日
主なルート:1日目 8:30JR錦糸町駅北口発→11:00〜16:30銚子周辺→17:00宿
2日目 8:00宿→8:30〜15:30屏風ヶ浦周辺→18:00錦糸町駅解散
募集対象・募集人数:会員および一般,40名程度
参加費:17,000円(学生は10,000円).宿泊代(二食+2日目昼食)および往復貸し切りバス代を含む.初日の昼食は各自弁当持参.
講師:高橋雅紀氏(産総研),鈴木毅彦氏(首都大学東京)
申込:ジオ・スクーリングネット(https://www.geo-schooling.jp/)または担当幹事へお願いします.
申込締切:10月20日(土)17時.
担当幹事:加藤 潔(駒澤大学)kiyoshi.katoh@gmail.com
細根清治(株式会社東建ジオテック)s.hosone@tokengeotec.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】「日本の地質構造100選」会員特別割引販売のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地質学会構造地質部会編集
日本の地質構造100選 (B5判 180頁 オールカラー)
定価3,990円(税込)を会員特別割引価格3,700円(税・送料込)
[2012年10月末日まで]
専用申込用紙は,下記学会HP会員のページまたは
学会ニュース誌7月号をご覧下さい.
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】紹介:「おくのほそ道」を科学する
──────────────────────────────────
蟹澤聰史著
河北新報出版センター(河北選書)
2012年6月15日,B6判 211ページ 定価800円+税,ISBN978-4-87341-276-4(表紙は松島の五大堂)
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
本書は「文学を旅する地質学」,「石と人間の歴史」に次ぐこの著者の最新刊であり,今回は芭蕉の「奥の細道」に沿う地学紀行である.前回までと大きく違うのは,仙台在住の著者が2011年の東日本大震災で被災し,「人生観を根底から変えてしまう」(あとがき)体験をした後の著作という点である.実際,本書には大震災に関する記述が随所に見られ,無常観に根差す一種の「ゆとり」が加わったように思う.
私は数年前に嵐山光三郎氏の「芭蕉紀行」(2000年初刊)や「悪党芭蕉」(2006年初刊,いずれも現在は新潮文庫所収)を読んで,芭蕉という人物や「奥の細道」という紀行文の性格について先入観を植え付けられていたので,今回の本は非常に興味深く読むことができた.ただし,嵐山氏のこれらの作品は本書の文献リストには載っていない.
「奥の細道」は西暦1689(元禄2)年5月中旬から同年10月初旬まで,(現在の県名で)東京を発って埼玉,群馬,栃木,福島,宮城,山形,秋田,新潟,富山,石川,福井,滋賀をめぐり,岐阜県大垣に至る5ヶ月間の旅の(かなり再構成された)紀行文である.芭蕉は1644年生まれなので満45歳,平均寿命が30代だった当時としては老境に入ってからの旅であり,彼はこの5年後に逝去する.
本書はまず現在我々が過ごしている時間と芭蕉の当時の時間,そして地質学的な時間の大きな相違を取り上げる.5月16日(3/27,以下旧暦はこのように表記)の旅立ちの文には「明ぼのの空朧々(ろうろう)として,月は在明(ありあけ)にて」とあり,日の出前のおぼろ雲を通して東の空に細い月が見えたように書いてあるが,曾良の旅日記によると出発は3/20になっており,食い違いがある.しかし,3/20だとしても西には有明の月があったはずで,完全な創作でもないだろういう見解を述べている.また江戸時代の時刻は日の出・日の入を基準にした不定時法で,その時刻を現在の定時法で考えると,芭蕉たちがものすごい速さで歩いたことになる(ここから芭蕉忍者説が生まれる)という面白い話もある.「上野谷中(やなか)の花の梢(こずえ),又いつかはと心ぼそし」の「花」は,出発が新暦5月なので今の感覚では桜には遅すぎるが,今の桜(ソメイヨシノ)は江戸時代末期にできた品種で芭蕉の当時はまだなく,ヤマザクラだとすれば無理がなくて,しかも当時は太陽黒点が少なく地球全体の気温が低かった「マウンダー小氷期」に当たり開花が遅かっただろうから矛盾はない,と考察している.
この後,芭蕉は日光東照宮(あらたうと…),那須の殺生石(野をよこに…),白河の関(卯の花を…)を訪れて東北地方に入り,二本松の黒塚(鬼婆の話は恐ろしい),福島のしのぶもじずり石などの歌枕を訪ねる.那須では地震があったことが曾良の旅日記に書かれていて(4/18),これは1683年の日光地震の余震だろうとしている.仙台では現在の東北大学川内キャンパス(蟹澤氏の元職場,私の現職場,当時は城内)にあった茶室や隣の亀岡八幡宮にも詣でている.仙台北東方の多賀城には末の松山,壺碑(つぼのいしぶみ),沖の石(二条院讃岐の「我が袖は…」の歌が百人一首にある)など歌枕が多い.「末の松山なみこさじとは」という清原元輔の歌も百人一首にあるが,昨年の大津波は末の松山の直下に達したものの,この山は越えなかった.この歌は平安時代の貞観の津波も末の松山を越えなかったことに基づいているのかもしれないという.
松島を訪れることは,「奥の細道」の冒頭部分に「三里に灸すゆるより,松島の月,先ず心にかかりて…」とあるように,この旅の主目的であり,芭蕉は中国の洞庭・西湖にも恥じない日本一の好風としているが,後に訪れた秋田県の象潟(きさがた)では「象潟や雨に西施がねぶの花」という名句を得ているのに,松島ではあまりいい句が浮かばなかったようだ.嵐山氏は,ここは芭蕉が文章で読ませたかった部分だと解釈し,蟹澤氏は洞庭・西湖についての蘊蓄を傾けている.その後(現在の地名で)石巻,登米,平泉(五月雨の降のこしてや光堂),岩出山,鳴子温泉,尿前(しとまえ)の関(蚤虱馬の尿する枕もと)を通って山形県に入り,歌枕ではない山寺を訪れて「閑さや岩にしみ入蝉の声」の名句を得た(嵐山氏によると実は数回の推敲後の句).斎藤茂吉と小宮豊隆の間に,これがアブラゼミかニイニイゼミかという論争があったが,芭蕉がここを訪れたのは7月13日(5/27)で,まだアブラゼミの時期ではなく,ニイニイゼミ(小宮)の勝ちになったという.
芭蕉はその後船で最上川を下り,「五月雨をあつめて早し最上川」の名句を得たが,蟹澤氏はここで日本と外国の川の河川勾配の違いを説明している.次に芭蕉は月山(がっさん),羽黒山,湯殿山の出羽三山へ登った(雲の峰幾つ崩れて月の山).出羽三山も歌枕ではなく,また出羽三山の登山は一種の臨死体験として宗教的な意味があるが,蟹澤氏も嵐山氏も,芭蕉は文学的,宗教的興味ではなく,単に高い山への強い好奇心で登ったと考えていて,蟹澤氏はゲーテがベスビオス火山やエトナ火山に登ったことと比較している.その後芭蕉は新潟県に入り,鼠ヶ関で「荒海や佐渡によこたう天河」の句を得るが(8月18日),この頃は雨が続き芭蕉は疲れていて記録も少なく,天の川を見ての句ではなくて,佐渡に流され辛酸を味わった人々の心を想って詠んだというのが蟹澤氏の解釈である.嵐山氏は,想像だという点は同じだが,月山で月,象潟で花を詠んだので,新潟では恋という順序になる,という見立てで,これが「文月や六日も常の夜には似ず」(翌日は七夕)の句に並べて「荒海や…」の句を記し,次の市振で遊女の話の聞き書きを挿入する理由だという解釈である.なるほど,佐渡が天の川によこたわっていれば,波が荒くても織姫と彦星は金鉱山の辺りで出会える.芭蕉は宮澤賢治ではなく,幽玄な世界が一転ロマンチックに華やぐ.その後芭蕉たちは親不知(おやしらず)を越え,市振(いちぶり)に宿をとり,そこで新潟の遊女と同宿になるわけだが,嵐山氏によるとこの部分は完全な創作だという.
そして8月29日に金沢に着き,9月10日に山中温泉に泊まっている.近くの那谷寺(なたでら)を訪れ「石山の石より白し秋の風」の句を得た.那谷寺は医王山層の流紋岩質凝灰岩の岩肌に沿って作られており,この石の色を秋の気配と重ねた句である.蟹澤氏によると,芭蕉は松島や那谷寺など新生代の地層の美しさには感嘆しているが,中・古生代の地層にはそれほどの美は感じなかったようだという.芭蕉は山中温泉で曾良と別れ,永平寺などを訪れて,10月4日(8/21)頃に大垣でこの旅を終えた.蟹澤氏は,大垣の近くの美濃赤坂金生山で1874年に日本初のフズリナ化石をドイツ人が記載したことを指摘し,大垣は奥の細道の終点であるが,日本の古生物学にとっては発祥の地であると結んでいる.
本書は,蟹澤氏が東日本大震災の被災経験を経て,芭蕉の「不易流行」(変わらぬ真理(天地)と転変する社会(人間)を帰一する)哲学に深く共感し,読者が自然をよく知り,その一員であることを深く感じ取れるように,そして「あそび」の心を大切にして新たな発想を生む礎としてもらうために,地質学のみならず幅広い学問を織り込んで執筆したものであり,ご一読をお勧めする.そして,蟹澤氏が本年5月の日本地質学会総会で同会名誉会員に推挙されたことを申し添える.
芭蕉は1694(元禄7)年,満50歳で大阪にて亡くなったが,その7年後の1701(元禄14)年に江戸で赤穂浪士の討ち入りがあり,翌1702(元禄15)年に「奥の細道」が出版された.そして1703(元禄16)年に元禄関東地震(死者数千人),1707(宝永4)年に我が国の歴史上最大の被害地震の一つである駿河・南海トラフ沿いの宝永地震(M8.6; 10月28日,死者2万人以上)と富士山の噴火(12月16日)があった.今後同様の経過にならないことを切に願って本書の紹介を終える.なお,本書は次のサイトから購入できる.
http://www.kahoku-ss.co.jp/okunohosomichi.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】第3回フォトコンの入選作品が「月刊日本カメラ」で紹介されました
──────────────────────────────────
第3回惑星地球フォトコンテストの入選作品が「月刊日本カメラ」8月号(7/20発売)に掲載されました。見開き2ページを使って大きく紹介されています。書店へぜひ!
次回のフォトコンがますます楽しみになってきました。
みなさま、次回応募作品の準備をお忘れ無く。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】産総研のシームレス地質図に火山表示機能が追加
──────────────────────────────────
産総研地質調査総合センターがWeb公開している「日本シームレス地質図」のスマートフォン・タブレットPC版で,国内の火山を表示する機能が追加され ました.
これにより,これまでの地図上で地質凡例と活断層情報を表示する機能に加えて,日本の第四紀火山データベースを基にした火山の形式や噴火記録など詳細な情報を表示することができるようになりました.
旅行や巡検などで山へ出かけた際に,噴火記録を確認するなどの利用方法が考えられます.
日本シームレス地質図のスマートフォン・タブレットPC版:
http://riodb02.ibase.aist.go.jp/db084/smart.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■企画展示:発見された明治三陸津波の古写真〜石黒敬七・敬章コレクションより〜
116年前の災害を伝える古写真を一堂に展示
開催期間:2012年7月7日(土)〜9月17日(月)
場所:杉並区郷土博物館分館(杉並区天沼3丁目:JR荻窪駅徒歩10分)
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/histmus/event/index.asp?event=16883
■日本学術会議における公開シンポジウム
「巨大災害から生命と国土を守る−24学会からの発信−」
日時:2012年8月8日(水)14:00〜17:45
場所:日本学術会議講堂
ほか、http://www.scj.go.jp/ja/event/index.html
■日本学術会議主催学術フォーラム
「データと発見ーDeta Intensive Scientific Discovery」
日時:2012年9月10日(月)13:00〜
http://johokanri.jp/stiupdates/event/2012/08/007557.html
■第4回 建コンフォト大賞 作品募集
テーマ『あなたのお気に入りの“土木施設”』
応募締切:9月30日(日)当日消印有効
http://www.jcca.or.jp/achievement/photo_contest/photocon/h24photo.html
■3rd Asia-Pacific Conference on Luminescence and ESR dating
日本地質学会協賛
日程: 2012年11月18日(日)〜22日(木)
会場: 岡山理科大学50周年記念館
http://www.rins.ous.ac.jp/eps/theme/symposium.html
■極域科学シンポジウム特別セッション
「海・陸・氷床から探る後期新生代の南極寒冷圏環境変動」
会期:2012年11月26日(月)〜27日(火)
会場:国立極地研究所および国立国語研究所
http://polaris.nipr.ac.jp/~daiyonkigroup/PolarScienceSympo_special/index.html
■地質学史懇話会
日時:2012年12月23日(日)13:30〜17:00
場所:北とぴあ
鈴木寿志『「要説地質年代」を訳して』他
問い合わせ:矢島道子 pxi02070@nifty.com
■ 第6回地殻応力国際シンポジウム
日本地質学会 後援
日程:2013年8月20日(火)〜22日(木)
会場:仙台国際センター(宮城県仙台市)
講演申込期限:2012年11月30日(金)
http://www2.kankyo.tohoku.ac.jp/rs2013/
【訂正】前号で開催日程が2012年8月となっていましたが,正しくは2013年8月です.
■第2回学生のヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集
実習実施時期:2013年3月上旬,出国から帰国まで14日間.
参加申込締切:2012年10月末日
参加費用:学生・大学院生:約20万円以内 ほか
詳しくは、http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
■地震調査研究推進本部:ニュース7月号発刊
http://www.jishin.go.jp/main/p_koho04.htm
「地震本部ニュース」につきましては、環境への配慮と効率化の観点から、本年6月号をもって,紙による印刷及び送付を終了となりました.
7月号以降は,地震調査研究推進本部のウェブサイトへの掲示となります.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■金沢大学理工研究域自然システム学系(地球学)テニュアトラック助教公募(9/24)
■広島大学大学院理学研究科地球惑星システム学専攻教員公募(准教授)(10/12)
■京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻地質学鉱物学教室教員公募(准教授)(10/1)
■平成25年度地震研究所研究課題登録及び外国人客員教員公募(8/31)
■平成25年度地震研究所共同利用・特定研究課題登録(8/17締切)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flash No.195(10/2号)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.195 2012/10/2 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】日本ジオパークに5地域が認定
【2】地球惑星科学連合2013年大会のセッション提案にご注意下さい
【3】支部情報
【4】フィールドジオロジー:会員特別販売のご案内
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】日本ジオパークに5地域が認定
──────────────────────────────────
9月24日に開催された日本ジオパーク委員会で、新たに5つの地域が
日本ジオパークに認定されました。
八峰白神(秋田県)、ゆざわ(秋田県)、銚子(千葉県)、箱根(神奈川県)、
伊豆半島(静岡県)
これにより、日本ジオパークは25地域となりました。
詳しくは、、、
http://www.geopark.jp/about/datacenter/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】地球惑星科学連合2013年大会のセッション提案にご注意下さい
──────────────────────────────────
来年(2013年)の日本地球惑星科学連合大会でセッション開催を予定している
専門部会及び会員の皆様へ
すべてのセッションが公募になっています。セッション提案を予定している
場合は,お忘れのないよう申込手続きをお願いします。
締切は10/26(金)17:00です。
日本地質学会主催または共催の形(地質学会を提案母体にする形)でセッション
提案を予定している専門部会及び会員は,次のような手続きをお願いします。
・最も関連する(または従来母体となってきた)専門部会の行事委員を通じて
行事委員会に報告し,承認を得たら申込手続き。
・関連する専門部会がない場合は,コンビーナーが行事委員会(学会事務局)
に直接報告し,承認を得たら申込手続き。
ご協力よろしくお願いします。
(日本地質学会行事委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】支部情報
──────────────────────────────────
■関東支部:「銚子巡検」☆祝 日本ジオパーク認定☆
10月27日(土)〜28日(日),1泊2日
主なルート:
1日目8:30JR錦糸町駅南口付近発→11:00〜16:30銚子周辺→17:00宿
2日目8:00宿→8:30〜15:30屏風ヶ浦周辺→18:00錦糸町駅解散
募集対象・募集人数:会員および一般,40名程度
参加費: 17,000円(学生は10,000円)
講師:高橋雅紀氏(産総研),鈴木毅彦氏(首都大学東京)
申し込み:ジオ・スクーリングネット( https://www.geo-schooling.jp/)または
申込書( http://kanto.geosociety.jp/よりダウンロードできます。)
にご記入の上担当幹事へご連絡をお願いします.
申込締切:10月20日(土)17時.
http://www.geosociety.jp/faq/content0397.html#2
■関東支部:関東支部功労賞募集
日本地質学会関東支部では,支部の顕彰制度に基づき2012年度も支部活動や地質学
を通して社会貢献された個人・団体を関東支部として顕彰いたします.つきまして
は,下記の要領で支部会員からの推薦を募集します.
対象者 :支部活動や地質学を通して広く社会貢献をされた関東支部内に在住の個
人・団体
*社会貢献や活動の評価においては,必ずしも学問的な成果を問うものではありま
せん.
公募期間:2012年12月10日〜2013年1月10日
詳しくは、http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】フィールドジオロジー:会員特別販売のご案内
──────────────────────────────────
このたびは全9巻完結いたしました「フィールドジオロジーシリース」を特別割引
価格にて会員の皆様にご案内いたします。
・フィールドジオロジー 全9巻 全巻セット 特価16,000円(定価18,900円)
・8巻 火成作用(9月新刊)高橋正樹・石渡 明著 特価1,900円(定価2,100円)
・9巻 第四紀(9月新刊)遠藤邦彦・小林哲夫著 特価1,900円(定価2,100円)
*いずれも送料込み
専用申込用紙は、学会HP・会員のページにアクセスして下さい。
(会員番号によるログイン情報が必要です)
http://www.geosociety.jp/user.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■深田研一般公開2012
10月21日(日)10:00〜16:00
場所:深田地質研究所(東京都文京区本駒込2丁目)
申込不要・入場無料
講演:「イーハトーブのジオー宮沢賢治の地学童話を読み解こう!」(講師:加
藤碵一)mini講演:地質図ってなんだろう/作って楽しむアンモナイトアクセサリー
など
詳しくは、http://www.fgi.or.jp/
■三浦半島活断層調査会・地質情報普及講座
『深海から生まれた城ヶ島』(日本地質学会 後援)
11 月 4日(日)10時〜15 時(小雨決行)
集合場所・時間:城ヶ島バス停(終点)10時
場所:三浦市城ヶ島
申込締切:10月19日(金)
申込先:三浦半島活断層調査会事務局(松崎健一方)
〒238-0042 横須賀市汐入町3丁目23番地
Tel 046-825-6665 <k345matsu@yahoo.co.jp>
■「平成24年度 東濃地科学センター地層科学研究 情報・意見交換会」
11月14日(水)13:00〜17:00
場所:瑞浪市地域交流センター「ときわ」(※定員:約150名)
「瑞浪超深地層研究所 深度300m水平坑道見学会」
日時:平成24年11月15日(木)9:15〜12:00
場所:瑞浪超深地層研究所(定員:40名)
※いずれも、申込者が多数の場合は、先着順とさせていただきます。ご了承下さい。
※入場無料(事前の申し込みが必要です。)
※申込締切 10月31日(水)
http://www.jaea.go.jp/04/tono/index.htm
■日本学術会議公開シンポジウム
「日本の復興・再生に向けた産学官連携の新しいありかた」
11月26日(月)13:00〜17:00
会場:日本学術会議 講堂
参加費:無料
http://unit.aist.go.jp/raipl/sympo20121126.html
■日本学術会議主催学術フォーラム
「巨大災害から生命と国土を護る−三十学会からの発信−」
11月29日(木)13:00〜18:00
会場:日本学術会議講堂
趣旨:東日本大震災を受けて、巨大災害からわが国を護るため、学会が集まり連続
シンポジウムを開催してきました。すべての学会の代表が結集総括フォーラムを開
催します。
参加費:無料
http://jeqnet.org/sympo/no8.html
■日EU科学政策フォーラム〜
「日本の新しいエネルギーミックス―信頼できる政策構築に向けて」
10月6日(土)13時〜17時15分
会場:グランドプリンスホテル京都 プリンスホール
主催:駐日欧州連合(EU)代表部、欧州連合加盟国、政策研究大学院大学
参加費無料・日英同時通訳付き
詳しくは、
http://www.euinjapan.jp/media/news/news2012/20120913/132744/
■平成27(2015)年度共同主催国際会議の募集
この度、日本学術会議の行う国際学術交流事業の実施に関する内規の一部を改正
しました。この改正により、申請要件の緩和や、申請書類の簡略化を行いました。
さらに、一部の会議については、決定を翌年度末まで保留し、準備に充てていた
だく時間を設けることにしました。この改正によって、これまで限られた国際会議
しか共同主催として申請し難かっ
た状況を見直し、より広い範囲の国際会議に申請していただけるような仕組みとし
ました。これを機に、ぜひ共同主催国際会議について御検討いただきますようお願
い致します。
平成27(2015)年度に開催される国際会議を対象に、
平成24年10月1日(月)〜11月30日(金)まで共同主催の募集を行います。
詳しくは、
http://www.scj.go.jp/ja/int/kaisai/entry.html
■国際会議のお知らせ:
International Petroleum Technology Conference (IPTC)
2013年3月26日〜28日
場所:Beijing, China
http://www.iptcnet.org/
■地震本部ニュース8月号
地震本部ニュース8月号が発行されました(9/26付け)。
http://www.jishin.go.jp/main/p_koho04.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■静岡大学理学部地球科学科学科教員公募(11/16)
■愛媛大学大学院理工学研究科数理物質科学専攻地球進化学講座助教公募(11/30)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
<ニュース誌表紙写真,特に募集中です!お待ちしてます. >>
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
No.185 2012/8/17 geo-flash(臨時) 橋本光男 名誉会員 ご逝去
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.185 2012/8/17 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 橋本光男 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
日本地質学名誉会員 橋本光男氏(元茨城大学教授)が、平成24年8月16日(木)
午前2時20分、肺炎のため亡くなりました(享年87歳)。
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
なお、前夜式ならびにご葬儀式は、下記のとおり執り行われますので併せてお知らせ申し上げます。
前夜式:8月17日(金)18時より
葬儀式:8月18日(土)12時30分より
式場:日本キリスト教団井草教会(東京都杉並区井草1-42-6)
喪主:橋本 純(長男)
ご香典はご辞退されるとのことですが、
ご葬儀に関する問い合わせ,献花等は下記宛にご連絡下さい。
株式会社公益社(電話 03-5491-3070 FAX 03-5491-5195)
会長 石渡 明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です.
<ニュース誌表紙写真、特に募集中です!お待ちしてます.>
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
★大阪大会参加申込締切★ 8月17日(金)間もなく締切りです!!
http://www.geosociety.jp/osaka/content0001.html
No.186 2012/8/21 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.186 2012/8/21 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】<大阪大会>事前参加登録の内容をご確認ください
【2】<大阪大会>緊急展示の申込について
【3】津波堆積物ワークショップ&巡検:参加者募集
【4】支部情報
【5】「日本の地質構造100選」会員特別割引販売のお知らせ
【6】紹介:「31文字のなかの科学」
【7】科学研究費補助金「奨励研究」申請書作成上の留意点
【8】第3回日本ジオパーク全国大会(室戸大会)参加者募集
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】<大阪大会>事前参加登録の内容をご確認ください
──────────────────────────────────
事前参加登録は8月17日に締切りました.多数のご登録ありがとうございました.
事前登録された方,とくに参加登録以外のオプション(懇親会や巡検など)をお申し込みの方は,登録内容をご確認の上,速やかなご送金をお願いいたします(お振込の場合).
ご入金済みの事前登録者には締切後,確認書・名札,また申込内容に応じてクーポン等を発送します.大会開催10日前にはお手元に届くようお送り致します.締切時点で入金確認が取れない場合は,未入金の旨記載された確認書のみ送付いたします.
大阪大会HP>>http://www.geosociety.jp/osaka/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】<大阪大会>緊急展示の申込について
──────────────────────────────────
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害調査報告や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コーナー」を設けます.
ポスター展示を希望する方は,8月31日(金)までにご連絡ください.
担当:石井和彦(大阪大会実行委員会)・須藤 宏(行事委員会)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/osaka/content0047.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】津波堆積物ワークショップ&巡検:参加者募集
──────────────────────────────────
本学会は日本堆積学会と共催で,津波堆積物に関するワークショップと巡検を10月に開催することになりました.
【日程】
10/6 ワークショップ(津市三重県総合文化センター大研修室 )
10/7-8 巡検(鳥羽-尾鷲-南紀白浜を予定)
【申込締切】8月31日(金)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0106.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】支部情報
──────────────────────────────────
■関東支部では大学での野外実習授業の減少問題に取り組んでいます.今年は京都大学,千葉大学の協力を得て,以下の要項で千葉での実習授業の見学を企画しましたので,今後野外実習授業を検討されている方等の参加をお待ちしております.
対象:大学教員(関東支部以外の地域の方も可)
見学予定日:
千葉大学実習授業の見学:2012年8月31日(金)
京都大学実習授業の見学:2012年8月22日(水)〜25日(土)のいずれか
当日集合場所:東京大学清澄宿舎〒299-5505 千葉県鴨川市清澄135 午前8時30分
注意:宿舎より実習場所まで車に分乗しますが,現地ではヒル対策が必要です.
当日の行動についての保険はかけません.
問合せ・見学申込み:関東支部幹事長 笠間友博宛メール kasama@nh.kanagawa-museum.jp
タイトルは「千葉実習見学参加」として下さい.
見学申込締切:
千葉大学実習授業の見学:2012年8月27日(月)17:00
京都大学実習授業の見学:2012年8月23日(木)17:00
※申込状況や現地の都合によって日程を調整させていただく場合もありますので,予めご了解下さい.
■関東支部:銚子巡検のご案内
関東地質調査業協会(共催)と日本第四紀学会(後援)のもと,「銚子巡検」を開催します.巡検では,銚子周辺にみられる薄衣型礫岩(ペルム紀?)やジュラ紀付加体,白亜紀以降の前弧海盆堆積物や前期中新世の古銅輝石安山岩溶岩,そして鮮新統〜更新統の犬吠層群までを観察します.
日程:2012年10月27日(土)〜28日(日),1泊2日
講師:高橋雅紀氏(産総研),鈴木毅彦氏(首都大学東京)
申込締切:10月20日(土)17時.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/faq/content0394.html#7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】「日本の地質構造100選」会員特別割引販売のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地質学会構造地質部会編集
日本の地質構造100選 (B5判 180頁 オールカラー)
定価3,990円(税込)を会員特別割引価格3,700円(税・送料込)
専用申込用紙利用期日:2012年10月末日まで
専用申込用紙は,下記学会HP会員のページまたは
学会ニュース誌7月号をご覧下さい.
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】紹介:「31文字のなかの科学」
──────────────────────────────────
松村由利子著
2009年7月2日発行,NTT出版,B6判208ページ,1,800円+税,ISBN978-4-7571-5069-0 C0095
この本は、毎日新聞科学部の女性記者だった著者が、医学や地学,原子力など科学全般の題材を詠み込んだ短歌223首を分野別にまとめて解説したものであり、地球史や化石などに関する歌も取り上げられている。帯のキャッチフレーズは「身体から宇宙まで歌を通して見はるかす。小さな詩型に科学のテーマが盛り込まれている不思議。新聞記者だった歌人が魅力的な歌の数々を紹介する」であり、「はじめに」では「科学を題材にした現代短歌を読むのは、ニュースの意味を改めて考えることであり、同時代に生きる感覚を共有することではないだろうか・・・それは多分、科学者自身も気づかない科学の本質であり側面である」と述べている。歌人の年代幅は明治生まれの与謝野鉄幹や斎藤茂吉から1960年代生まれの著者や俵 万智を経て70年代生まれの永田 紅や80年代生まれの小島なおに及ぶ。そしてこの本の選歌や解説の背景には、著者が女性職業人として、母として、さらに離婚を経験して味わった濃密な人生の喜びと悲しみがある。本書の中から、強く印象に残った歌をいくつか掲げる。解説は本書をご覧いただきたい。
【医学分野】
まだ魚の時間にゆれてゐた吾子と海抱くわれに雪やはらかく 紺野万理「過飽和・あを」
あっさりと離婚を決めた友は言う「卵子は毎日古くなるのよ」 畑 彩子「卵 egg」
ああなにか魚のようだ冷凍し精子を残すアメリカの兵 吉川宏志「海雨」
妻とわが二重らせんのからみあふ微小世界の吾子を抱けり 岩井謙一「光弾」
人は部品(パーツ:るび)より成るか成らぬかわが子にはきっと欲しがるだらう臓器を 水谷文子「齶田」
やまいだれの中をしみじみ見つめれば癌(がん:るび)という字は象形文字なり 久山倫代「弱弯の月」
あんたは誰 口拭かれつつ吾に問う祖母の笑顔の百歳ぞよし 佐々木千代「菜の花いろ」
ふるさとの野山に遊ぶたましひをアルツハイマーと人は呼ぶなり 森島峰子「生命の水」
小児科医アスペルガーの業績が病名となり人悲します 松村由利子「鳥女」
動物の中で笑いを知っている人間が哀しい顔ばかりする 浅井和代「春の隣」
【地学分野】
二時間後また満月にもどることを疑わずに見る部分月蝕 森尻理恵「グリーンフラッシュ」
月面に青痣(あざ)のごとき翳(かげ)りあり受胎告知の夢よりさめて 松平盟子「青夜」
飛行士の足形つけてかがやける月へはろばろ尾花をささぐ 香川ヒサ「TEXNH<テクネー>」
黒人の宇宙飛行士混らざる米国アポロ計画を思ふ 宮 柊二「獨石馬」
彗星は精子のようにぬばたまの闇の大宇宙(おおぞら:るび)流れてゆけり 新井貞子「生命祭」
髪のにほひ夜のすきまをわけくればカンブリア紀の海とおもひぬ 坂井修一「ジャックの種」
私が羊歯(しだ:るび)だったころ降っていた雨だったかも知れぬ今日降る雨は 柳澤桂子「いのちの声」
あまがえる進化史上でお前らと別れた朝の雨が降ってる 笹井宏之「ひとさらい」
ふるき世のパンゲア大陸よりわれに輪廻の果ての陽がそそぐなり 辻井朱美「吟遊詩人」
銀杏の実はころころと転がりて遥かジュラ紀の歌くちずさむ 樋口智子「つきさっぷ」
恐竜はつぶやいていた「星の降るような夜だな」滅亡前夜 松木 秀「5メートルほどの果てしなさ」
恐竜の滅亡を子よとくと見よ楽しい日には終わりがあるの 松村由利子「薄荷色の朝に」
われらみな宇宙の闇に飛び散りし星のかけらの夢のつづきか 沢田英史「異客」
垂直に四十億年 水平に八千万種 交点に佇(た:るび)つ 紺野万理「過飽和・あを」
人間をしばらく棲まわせたばっかりにこの水の星崩(く:るび)えはじめたり 志垣澄幸「梁」76号(2008年)
「地球とは」こう主語にして語るときあなたはすでに傲慢である 松木 秀「5メートルほどの果てしなさ」
【原子力分野】
科学は最初男のものであったが、19世紀後半から女性も重要な貢献をするようになり、特に原子力に関しては次の2人の女性研究者に負うところが大きい。
素手でつかむ鉱石 四十六歳のマリー・キュリーの明眸(めいぼう:るび)と老い 今野寿美「龍笛」
核分裂(フィッション:るび)とふことばはついに放たれきリーゼ・マイトナーとふおみなによりて 小関祐子「北方果樹」(「とふ」は「という」、「おみな」は「女」)
しかし、
原発から二十キロ弱のわが家かな帰りきて灯を消して眠りにつけり 大口玲子「ひたかみ」
記憶せよ 八十三日目の被爆死、ずたずたになった染色体を 飯沼鮎子「シューベルトの眼鏡」(1999年の東海村臨界事故)
核弾頭五万個秘めて藍色の天空に浮くわれらが地球 加藤克己「ルドンのまなこ」
君の言う核戦争のそのあとを流れる水にならんか我と 俵 万智「サラダ記念日」
私が育った東京郊外の町には、「多摩川にさらす手作さらさらに何ぞこの児のここだ愛(かな:るび)しき」という万葉集第14巻の有名な東歌の歌碑(松平定信筆)があり、小学校時代はその辺でよく遊んだものである。それ以来、和歌や短歌には長年接してきたのに、まだ山吹の実の有無が判然としない状態なのは残念である。しかし、敷島の道をはるか先に進んでいる地質学者もおり、本学会名誉会員の諏訪兼位先生は朝日歌壇に作品がよく載る。例えば、2010年8月30日に載った歌は、「浮子(うき:るび)すべて底に沈みて眠りたり夏眠は深しガリレオ温度計」であり、今年7月16日の歌は「草も木もみんな泣きよるあの笑顔春風のごと原田さん逝く」(水俣病の被害者を支援した医師、原田正純氏を悼む)である。短歌は31音節の短い詩形であるが、上のような深い内容をもつ具体的で力強いメッセージを心に直接届けることができる。短歌も科学も人間の心が紡ぎ出したもので、それを他者の心に伝えるコミュニケーションとしての人間の営みであるという点で変わりはない。科学者としての感性を研ぐために、科学を詠み込んだ短歌の世界を覗いてみるのも悪くないと思う。会員諸兄諸姉に是非本書のご一読をお勧めする。
石渡 明 (東北大学東北アジア研究センター)
追記:(2012年9月2日)
上の拙文をお読みいただいた諏訪兼位先生から、先生が執筆された短歌に関する本と論説をお送りいただいたので、それらについて追記する。「科学を短歌によむ」(岩波科学ライブラリー136, 2007年)は「和歌」と「短歌」の違いや短歌づくりのアドバイスから説き起こし、「素人(アマチュア)短歌の時代に生きて」、「時代を切り取った歌」、「研究・技術開発の現場で詠む」、「研究者を詠む」、「生と死をみつめて」、「戦争と平和を詠む」の6章に分けて計127首の短歌(清水大吉郎氏や高橋正樹氏など最近の地質学者の歌も含む)を選評とともに紹介している。そのうち40首は朝日歌壇に採歌された先生ご自身の作品で、現在までの採歌数は270以上に達するという。この本については地質学会Newsの11巻1号9ページ(2008年1月)に沢田順弘氏の紹介文があるので参照されたい。同題の講演要旨が学士会会報885号62-72ページ(2010年11月)に掲載されており、またこの本では触れていない科学者歌人の評伝が「渡邊萬次郎:短歌と人生」(1891-1980, 金属鉱床学者、地球科学, 65巻3号125-132ページ(2011年5月))及び「柴田雄次―短歌と人生―」(1882-1980, 無機化学・地球化学者、同誌890号65-71ページ(2011年9月))として最近公表された。いずれも、凝縮された短歌の調べをアクセントにして、科学者の生きざまをよく描き出している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】科学研究費補助金「奨励研究」申請書作成上の留意点
──────────────────────────────────
今年も科研費申請の時期が近づいてきましたが、「奨励研究」は小・中・高等の学校教員、博物館研究員、大学・研究所技術系職員などの方々を対象にした種目です。詳細はhttp://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/11_shourei/koubo.htmlを参照して下さい。採択への道は決して難しいものではありません。積極的に申請されることをお勧めします。
奨励研究の目的は「大学等の研究機関で行われないような教育的・社会的意義を有する研究」を助成・奨励することです。したがって、例えば学校教員の方なら授業・教材・クラブ活動などとの関連を、博物館研究員等の方なら普及・展示などとの関わりを、技術系職員の方なら教育研究支援との関わりなどが明確になっていることが大切です。ところがこの趣旨に沿っていないために不採択となるケースは、天文学や地球物理学分野からの申請に比べて地学分野からの申請に目立って多いことが問題です。技術系職員の場合、関係する研究者が別途研究資金で行う研究の一部とみなされないよう、はっきりと切り分けることも大切でしょう。
審査は申請書のみに基づいて行われますから、申請書の出来栄えが大変重要です。科研費申請がいつも採択されているような最寄りの大学の先生にチェックしてもらうことをお勧めします。
文責 大槻憲四郎(東北大学理学研究科)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】第3回日本ジオパーク全国大会(室戸大会)参加者募集
──────────────────────────────────
日本地質学会 後援
日程:2012年11月2日(金)〜5日(月)
会場:室戸市保健福祉センターやすらぎ(メイン会場)ほか
ジオツアー:11月2日(金)・5日(月)
参加申込締切:9月14日(金)
詳しくは大会HP
http://conference.muroto-geo.jp/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第62回東レ科学講演会:自然の嘆きを聴く
日時:2012年9月24日(金)17:00〜20:00
場所:有楽町朝日ホール(有楽町マリオン11階)
http://www.toray.co.jp/tsf/info/inf_006.html
■日本学術会議主催学術フォーラム
「原発事故調査で明らかになったこと−学術の役割と課題−」
日時:2012年8月31日(金)12:30〜18:15
会場:日本学術会議 講堂
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/156-s-0831.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■海洋研究開発機構:海洋・極限環境生物圏領域(研究職/技術研究職/ポストドクトラル研究員)(10/9)
■海洋研究開発機構:海洋・極限環境生物圏領域(技術総合職)(10/9)
■高知大学:教育研究部総合科学系複合領域科学部門教員公募(講師)(10/25)
■熊本大学大学院:自然科学研究科理学専攻地球環境科学講座教員公募(10/26)
■山口大学大学院:理工学研究科地球科学(とくに岩石学分野)教員公募(10/5)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
<ニュース誌表紙写真,特に募集中です!お待ちしてます.>
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.187 2012/9/4 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.187 2012/9/4 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】<大阪大会>講演プログラムが公開になっています・・・ほか
【2】コラム:原発再調査と地学専門家の責任
【3】「日本の地質構造100選」会員特別割引販売のお知らせ
【4】支部・専門部会情報
【5】第3回日本ジオパーク全国大会(室戸大会)参加者募集
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】<大阪大会>講演プログラムが公開になっています・・・ほか
──────────────────────────────────
■講演プログラムが公開になっています。
詳しくは,大会ホームページ・News8月号をご覧下さい。
http://www.geosociety.jp/osaka/content0001.html
■確認書・クーポンを発送しました。
8月30日に事前参加登録された方へ確認書およびクーポン(お弁当・懇親会申込者のみ)を発送しました。
【入金確認済みの方】
記名名札と懇親会、お弁当申込の方には、参加・引換用のクーポンを同封しています。確認書(本人控と受付提出用)および名札・クーポンは当日忘れずにご持参下さい。
【未入金の方】
確認書送付時点で事前参加登録費が未入金の方には黄色い用紙の確認書(本人控と受付提出用)のみお送りしています。
9月10日(月)までにご送金をお願い致します。本状と行き違いで入金済みの場合は当日受付にて照会いたします。念のため、振込み時の控え等をご持参下さい。9/10日(月)までにお振込いただけなかった場合は、当日会場受付にてご清算をお願いいたします。
<振込先>
振込時には、振込者氏名の前に必ず申込No.を入力して下さい。
(1)三井住友銀行 神田駅前支店(普通)1711424
(社)日本地質学会 / シヤ)ニホンチシツガツカイ
(2)郵便振替 00140-8-28067 (社)日本地質学会
※郵便局に備え付けの郵便振替用紙をご利用ください。
■大会期間中のお食事について
学会期間中の大学生協食堂の営業時間が以下のように変更になりました。
9/15(土)11:30〜14:00
9/16(日)11:30〜14:00
9/17(月・祝)11:30〜13:30
臨時営業のため、利用者が300〜350人/日に達しない場合は、さらに営業時間が短縮される可能性があります。期間中の昼食は、ぜひ大学生協食堂のご利用をお願いします。
大阪大会大会ホームページ
http://www.geosociety.jp/osaka/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】コラム:原発再調査と地学専門家の責任
──────────────────────────────────
大槻憲四郎(東北大学理学研究科)
経済産業省原子力安全・保安院は7月17日、地震・津波に関する専門家の意見聴取会を開催した。報道によれば、席上専門家から、北陸電力志賀原発(石川県)の敷地内を通るS-1断層、および関西電力大飯原発(福井県)の敷地内を通るF-6断層が、「耐震安全上考慮すべき活断層」である可能性が高い旨の強い指摘があったという。これを受け、7月18日保安院は当該電力会社に追加調査を指示した。
志賀原発1号機と2号機の設置許可は、それぞれ1987年と1997年に申請され、大飯原発1・2号機と同3・4号機の設置許可は、それぞれ1971年と1985年に申請された。2006年には発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針が改定され、既存原発が指針に適合しているか否かを確認する耐震安全評価(バックチェック)が行われた。しかし、冒頭に紹介した専門家の意見聴取会での事態は、当初の原発設置申請の審査もその後のバックチェックも不十分であったことを白日の下に晒した。意見聴取会で配布された資料(http://www.nisa.meti.go.jp/shingikai/800/26/019/240717.html)を見れば、S-1断層とF-6断層は活断層である可能性が高いと言わざるを得ないが、それにも拘わらずなぜ問題とならなかったのか。「原子力ムラ」の住民には地学の専門家も含まれていたのかと疑われても仕方がない。
今後、原発再稼働が次々に申請されるであろうし、並行して各原発の追加調査も行われであろう。このような事態に地質学者と地質学会はいかに対処すべきか、地学に対する信頼を回復させるためにも、以下の3点を指摘しておきたい。
① 科学的解明第一主義に徹しなければならない。これは、原発に対する賛否とは別問題である。
② 全ての調査資料が公開されなければならない。地質学会はそのことを関係機関に申し入れるべきである。公開の原則は、広く専門家の検討に委ねることによってより正しい結論に到達するための条件であるとともに、「原子力ムラ」の弊害を防止する仕組みとなる。公開の原則は、電力会社、地質コンサルタント会社、大学・研究所等の地学専門家の力量がより発揮される条件にもなり得る。
③ 追加調査で問題となるのは、活動性の低い活断層や津波などの評価であろう。「稀だから無視できる」ということと「稀だが確実に起きる」ことに関して、3.11の経験を取り込んだ評価法を吟味する必要がある。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】「日本の地質構造100選」会員特別割引販売のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地質学会構造地質部会編集
日本の地質構造100選 (B5判 180頁 オールカラー)
定価3,990円(税込)を会員特別割引価格3,700円(税・送料込)
専用申込用紙利用期日:2012年10月末日まで
専用申込用紙は,下記学会HP会員のページ または 学会ニュース誌7月号をご覧下さい.
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】支部・専門部会情報
──────────────────────────────────
■関東支部: 「銚子巡検」
日時: 2012年10月27日(土)〜28日(日),1泊2日
主なルート:1日目 8:30JR錦糸町駅南口付近発→11:00〜16:30銚子周辺→17:00宿
2日目 8:00宿→8:30〜15:30屏風ヶ浦周辺→18:00錦糸町駅解散
募集対象・募集人数: 会員および一般,40名程度
参加費: 17,000円(学生は10,000円).宿泊代(二食+2日目昼食)および
往復貸し切りバス代を含む.初日の昼食は各自弁当持参.
講師:高橋雅紀氏(産総研),鈴木毅彦氏(首都大学東京)
申し込み: ジオ・スクーリングネット(https://www.geo-schooling.jp/)または申込書( http://kanto.geosociety.jp/よりダウンロード:近日掲載予定)にご記入の上担当幹事へご連絡をお願いします.
申込締切: 10月20日(土)17時.
担当幹事:
加藤 潔(駒澤大学) kiyoshi.katoh@gmail.com
細根清治(株式会社東建ジオテック) s.hosone@tokengeotec.co.jp
■関東支部:ミニ巡検シリーズ「御坂・櫛形山地黒鉱巡検」
日程: 2012年10月6〜7日
案内者: 浦辺徹郎さん(東大地惑)
参加者上限: 10名程度(使用車両の状況によっては多少の増員可能).
申込先: 9月13日までに伊藤谷生( tito@thu.ac.jp)まで.先着順で参加者決定.
ミニ巡検の詳細は参加者と相談しながら決定.
【関東支部ミニ巡検シリーズ】
関東支部は年に1〜2回地質巡検(今年度は10月27〜28日銚子巡検)を企画していますがそれ以外にも会員有志による様々なミニ地質巡検が自主的に行われてきました.こうしたミニ巡検は支部が主催したり後援するものではありませんでしたが,フィールドジオロジーの継承と発展に寄与してきたことは疑いありません.そこで関東支部としては,今後,企画者からの要請があればミニ巡検の案内を広く会員諸氏に紹介したいと思います.その第1弾は以下のとおりです.今後,色々なミニ巡検が企画されることを期待していますので,遠慮なく関東支部幹事会(kanto@geosociety.jp)にご相談ください.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第3回日本ジオパーク全国大会(室戸大会)参加者募集
──────────────────────────────────
日本地質学会 後援
日程:2012年11月2日(金)〜5日(月)
会場:室戸市保健福祉センターやすらぎ(メイン会場)ほか
ジオツアー:11月2日(金)・5日(月)
参加申込締切:9月14日(金)
詳しくは大会HP
http://conference.muroto-geo.jp/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■岩盤工学特別講演会2012
最新の岩盤応力測定技術と応用事例について
9月24日(月)14:00〜
会場:深田地質研究所研修ホール
参加無料(申込締切:9/18)
http://www.fgi.or.jp
■第144回深田研談話会
次世代の火山防災のあり方を考える
9月28日(金)15:00〜17:00
会場:深田地質研究所研修ホール
講師:中村洋一氏(宇都宮大学教育学部)
参加無料(申込締切:9/26)
http://www.fgi.or.jp
■IUGS E-BULLETIN 情報
1) 概要
2) 新理事選出 日本からは小川勇二郎会員が就任
3) これから開催されるイベント情報(重要)
4) そのほか
IUGS E-BULLETIN (NO. 77, AUGUST 2012)より抜粋
1)概要
第34回IGC(万国地質学会議;オーストラリア、ブリスベーン)成功裏に終了。
(なお、日本代表からの報告は、別途なされるだろう。)
8年間にわたって準備されてきた表記の学会が終了した。137カ国から6000人が参加し、3232の発表が5日間にわたって行われた。24のワークショップ、283のエキシビションが開かれ、29のフィールドトリップが行われた。第二回の若手地球科学者会議(http://www.networkyes.org/)、一般の市民対象のイベントなども行われた。発展途上国からの参加者を援助するための、ジオホスト、多くの出版物(Episode;http://www.episodes.co.in/、オーストラリアの地質などを含む;http://www.ga.gov.au/products-services/publications/shaping-a-nation.html) なども出版された。
2)新理事選出 日本からは小川勇二郎会員が就任
2012-2016にわたる任期の理事による理事会:IUGS-IGC Council meeting (前回のノルウェー大会で決議されたように、IUGSがIGCを行うことになった)が8月9日に開かれ、新しいメンバーを含む以下のような理事が選出された。
PRESIDENT - Prof. Roland OBERHANSLI (Germany)
SECRETARY GENERAL - Dr. Ian LAMBERT (Australia)
TREASURER - Dr. Shuwen DONG (China)
VICE PRESIDENTS: Prof. Yildirim DILEK (USA); Prof. Marko KOMAC (Slovenia)
COUNCILLORS 2010-2014: Wesley HILL (USA); Prof. Sampat Kumar TANDON (India)
COUNCILLORS 2012-2016: Prof. Hassina MOURI (South Africa); Prof. Yujiro OGAWA (Japan)
COUNCILLORS 2014-2018: Dr. Amel BARICH (Morocco); Prof. Stephen JOHNSTON (Canada)
PAST PRESIDENT Prof. Alberto RICCARDI (Argentina)
3)2020年IGCはインド開催
2020年の第36回のIGCは、インドのデリーで開かれることが投票で決まった。
インドにバングラデシュ、ネパール、パキスタンおよびスリランカが協力する。
(http://igc2020delhi.com/)。(なお、2016年の第35回は、8月27日ー9月5日、南アフリカ連邦のケープタウンで開かれる。http://www.35igc.org )
4)これからの集会案内(重要事項)
以下は、近未来の集会、学会などの情報である。
多くは、IUGS website (www.iugs.org) に載せられているので、参照されたい。
特に、以下のサイトは情報を確認するのに便利である。
http://iugs.org/index.php?page=calendar&phpMyAdmin=2c9f06db78f0953a55b10dcfdc5907f6
もし、各グループなどの集会の情報をこれに載せたい場合は、直接以下にメールすること。
IUGS Secretary General at pbobrows@nrcan.gc.ca
以下は、近未来の情報である。
AAPG2012, Singapore
http://www.aapg.org/singapore2012/AboutICE2012.cfm
16-19, Sept. 2012
GeoPower Turkey: 16-17 October, Istanbul 2012, www.greenpowerconferences.com
Past Changes in Fluvial Systems, Floodplains and Estuaries, Abstract deadline: 8 Sept 2012
http://www.pages-osm.org/osm/program/sessions/570-osm06
IGCP585; 6th International Symposium on Submarine Mass Movements and Their Consequences; 23rd‐25th September, 2013, GEOMAR, Kiel, Germany
14 Sep. 2012: Deadline for abstract
http://www.geomar.de/en/research/fb4/fb4‐gdy/research‐topics/6th‐international‐symposium (日本から、山田泰広氏(京大)がアドバイザリーボードに参加している)
September 30 to October 5, 2012. 46th Brazilian Geological Congress (46o Congresso Brasileiro de Geologia ? 46 CBG). Mendes Group Convention Center, Santos, Sao Paulo, Brazil. Theme: "Managing Natural Resources to Generate
Social Resources". Details at: http://www.46cbg.com.br
September 8-12, 2012. Workshop on Dryland Geomorphology. Gobabeb Desert
Research Station, Namibia. Hosted by the South African Association of Geomorphologists and supported by the Royal Geographical Society. See the IAG/AIG website at: http://www.geomorph.org/main.html.
December 4-7, 2012. National Ground Water Association (NGWA) Groundwater
Expo and Annual Meeting. Las Vegas, California, USA. Theme: “Discover - Connect - Grow!” See: http://groundwaterexpo.com/
------2013-----
January 8-14, 2013. The 24th Colloquium of African Geology (CAG24). The United Nations Conference Centre, Addis Ababa, Ethiopia. Theme: "40 years of GSAf (1973-2013), Earth Science Solutions to African Development
Challenges". Online Registration open until 30 September 2012. See: http://www.cag24.org.et.
February 6-8, 2013. EAPCE'13. The 6th East African Petroleum Conference & Exhibition. Arusha, Tanzania.
Theme "East Africa Region. "The emerging Destination for investment and Future Supply of Oil and Gas for Sustainable Development. See: http://www.tpdc-tz.com
June 24-28, 2013. AOGS 3013. 10th Annual Meeting of the Asia Oceania Geosciences Society. Brisbane, Australia. Session proposals close 12 November 2012. Abstract submission 29 January 2013. Details at: http://www.asiaoceania.org
August 25-29, 2013. MEDGEO 2013 - The 5th International Conference on Medical Geology. Hilton Crystal City Hotel, Arlington, Virginia, USA.
Theme: "The Natural Environment & Health - Hidden Dangers, Unlimited Opportunities". The deadline for abstracts is January 31, 2013; the deadline for early registration is March 31, 2013. See the GSA website at: http://rock.geosociety.org/GeoHealth/MEDGEO_2013/INFO.html and the IMGA website at: http://www.medicalgeology.org/pages/members/activities/Conferences/flyer2.pdf.
August 27-31, 2013. 8th IAG/AIG International Conference on Geomorphology.
Paris. Theme: “Geomorphology and Sustainability”. Abstract submission closes on 15 October 2012. The session outlines and field trips notices are available online. See details at: http://www.geomorphology-iag-paris2013.com/
September 1-5, 2013. International Symposium on the Cretaceous System. Metu Congress Centre, Ankara, Turkey. See: http://www.cretaceous2013.org
------2014-----
September 15-18, 2014. IAEG X11 Congress. Torino, Italy. Theme: "Engineering Geology for Society and Territory". See: See the website at: http://www.iaeg2014.com/
5)そのほか
また、今IGCで行われた多くのイベントや、学会などについて、学会誌特別号などの情報が来ているものは、以下のものである。
期限間近かのものもあるが、関心のある方は、各ホームページに当たられたい。
GEOETHICS AND GEOLOGICAL CULTURE:
http://www.annalsofgeophysics.eu/index.php/annals/issue/view/482
NATIONAL GROUND WATER ASSOCIATION (NGWA) UPDATES:
http://www.ngwa.org/Pages/default.aspx
http://www.ngwa.org/Media-Center/briefs/Documents/GW_Importance_Declaration.pdf
http://wellowner.org/water-quality/hydraulic-fracturing-brochure-for-water-well-owners/
http://www.ngwa.org/Foundation/Pages/default.aspx
\\\
ICSU Grants Programme 2013
http://www.icsu.org/member-zone/documents-for-members/grants-programme-2011/2013-grants-programme
\\\
新しいIUGSのE-Bulletinsに関しておよび各国や地域ごとの各分野の様々な活動の情報は、以下に情報がある。(日本の産業技術総合研究センターの地質情報センターも、その一翼を担っている。)
http://www.uni-mainz.de/FB/Geo/Geologie/GeoSurv.html
http://www.gsj.jp/information/gsj-link/dir/index.html
http://geology.com/groups.htm.
\\\
American Geosciences Institute (AGI)
http://www.agiweb.org/outreach/index.html
CCOP E-News The Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia (CCOP)
http://www.ccop.or.th/download/e-news/CCOP_e-news
CPCEMR - The Circum-Pacific Council for Energy and Mineral Resources
(CPCEMR) website is at: http://www.circumpacificcouncil.org
EFG - The European Federation of Geologists (EFG) magazine "European Geologist", and the EFG monthly newsletter "GeoNews"
http://www.eurogeologists.eu/.
EGS - EuroGeoSurveys (EGS) a consortium of 32 European Geological Surveys
http://eurogeosurveys.org/newsletters.html.
http://www.eurogeosurveys.org/newsletterssubscription.html
Future Earth Initiative
http://www.icsu.org/future-earth/
GEO - The Group on Earth Observations (GEO) is coordinating efforts to build a Global Earth Observation System of Systems (GEOSS).
http://www.earthobservations.org/index.shtml
GEOETHICS - The latest copies of the "Geoethics News" newsletter
http://tierra.rediris.es/Geoethics_Planetary_Protection/
GIS - Maps of the World see:
http://gis.mapsofworld.com/government/government-agencies/
GSAf - The Geological Society of Africa (GSAf) Newsletters
http://www.geologicalsocietyofafrica.org
GS - The Geochemical Society (GS) (http://www.geochemsoc.org/)
http://multibriefs.com/briefs/gs/sample.htm.
GSL - The Geological Society of London (GSL)
http://www.geolsoc.org.uk; and http://www.geolsoc.org.uk/bookshop.
GWP - For the Global Water Partnership (GWP) Monthly Newsletter "NewsFlow"
http://www.gwp.org/en/Get-involved/Subscribe-to-NewsFlow/
IAG - The International Association of Geomorphologists (IAG/AIG) publishes
http://www.geomorph.org/pb/pbnew.html
IAH - The International Association of Hydrogeologists (IAH) publishes "Groundwater eNews"
http://www.iah.org/news_enews.asp.
ICSU - The International Council for Science (ICSU) newsletter "ICSU Insight"
http://www.icsu.org/news-centre/insight.
http://www.icsu.org/
IFA - The International Fertilizer Industry Association (IFA) has produced a Fertilizer Glossary
http://www.fertilizer.org/ifa/HomePage/LIBRARY/Glossary-of-fertilizer-terms
IGBP - The International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP)
http://www.igbp.net
http://www.igbp.net/4.d8b4c3c12bf3be638a8000369.html
IMGA - The International Medical Geology Association (IMGA) newsletter
http://www.medicalgeology.org/pages/public/publications/page_Publications.htm
IUCr - The International Union of Crystallography. See the newsletter at:
http://www.iucr.org/news/newsletter
IUGG - The International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)
http://www.iugg.org/publications/ejournals/
(NOTE the 18 July edition lists the IUGG Bureau members and Association Presidents and Secretaries General for 2011-2015)
IUGS - International Union of Geological Sciences (IUGS). back issues of the IUGS "Episodes" magazine
http://www.episodes.co.in/www/backissues.htm.
IUGS E-Bulletins issued since October 2002
http://iugs.org/index.php?page=e-bulletins.
IUSS - The International Union of Soil Sciences (IUSS) Bulletin
http://www.iuss.org .
OneGeology - an international initiative of the geological surveys of the world with a target of creating dynamic geological map data of the world, available to everyone
http://www.onegeology.org/
ProGEO News - the newsletter of the European Association for the Conservation of the Geological Heritage
http://www.progeo.se/
RCMNS - Bulletin of the Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy (RCMNS)
http://www.geomare.na.cnr.it/
SCAR - The Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR)
http://www.scar.org/news/newsletters/issues2011/.
For their "Antarctic Science and Policy Advice in a Changing World: SCAR Strategic Plan 2011-2016"
http://www.scar.org/strategicplan2011/
SCOPE - The Scientific Committee on Problems of the Environment (SCOPE)
quarterly transdisciplinary journal "Environmental development"
http://www.sciencedirect.com/science/journal/22114645
SEPM - The Society for Sedimentary Geology (SEPM) quarterly publication The Sedimentary Record.
http://www.sepm.org/pages.aspx?pageid=37
SGA - The Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA) newsletters.
http://www.e-sga.org
UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization open access journal "A World of Science"
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/resources/periodical/a-world-of-science/
YES -The Young Earth-Scientists YES Network Newsletters
http://www.networkyes.org/index.php/news/
To find information on websites and newsletters of IUGS Commissions, Task Groups, Initiatives, and Joint Programs
http://iugs.org/ or http://iugs.org/index.php?page=directory
■東海地震防災セミナー2012
11月8日(木)13:30〜16:00
会場:静岡商工会議所静岡事務所5階ホール(JR静岡駅北口西側)
テーマ:東日本大震災に学ぶ
1. 東海地震はなぜ予知出来ないのか(東京大学:井出 哲)
2. 東海地震の災害医療(静岡県立総合病院副院長:安田 清)
問い合わせ:土研究事務所:土 隆一
Tel.:054-238-3240
Fax:054-238-3241
■International Symposium on Emerging Issues after the 2011 Tohoku Earthquake
11月27日(火)
会場:筑波大学 総合研究棟D(筑波キャンパス)
講演申込締切:2012年10月12日(金)
http://www.nourin.tsukuba.ac.jp/~engei/mizuta/?page_id=171
■日本学術振興会平成25年度科学研究費助成事業(研究成果公開促進費)「国際情報発信強化」及び「データベース」の公募に関する説明会
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/02_koubo/h25_koubo/index.html
【問合せ先】独立行政法人日本学術振興会
研究事業部研究助成第二課成果公開・普及係
(Tel:03-3263-4926,1699,4920)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■熊本大学大学院:自然科学研究科理学専攻(教授あるいは准教授)(10/26)
■文部科学省平成25年度科学研究費助成事業【研究成果公開促進費】の公募
■平成24年度群馬県立自然史博物館学芸員募集(10/3)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
<ニュース誌表紙写真,特に募集中です!お待ちしてます.>
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.189 2012/9/14 geo-flash (大会臨時号)大阪大会開幕!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.189 2012/9/14 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】日本地質学会大阪大会開幕!
【2】大阪大会:9月15日(土)の主なイベント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】日本地質学会大阪大会開幕!
──────────────────────────────────
14日、大阪大会目前の大阪はとても暑かったです。
すでにプレ巡検に出かけた班もあり、大会気分も盛り上がり始めました。
明日からは府立大が参加者でいっぱいになるかと思うと、なんだかロンドン
オリンピックの開幕前のわくわくする気分を思い出します。
せっかくなので、聖火が欲しくなりますね。
この大会にみんなが持ち寄るのは「せいか」ですが...
毎年、初日の朝の受付は大変混み合います。余裕を持ってお早めに!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】大阪大会:9月15日(土)の主なイベント
──────────────────────────────────
■地質情報展2012おおさか 開会式(13:00〜 大阪市立自然史博物館)
■地質学会表彰式・受賞記念講演(15:30〜17:30 Uホール白鷺)
16:40〜16:55
・日本地質学会小澤儀明賞受賞スピーチ 山本伸次会員
「とことんやってみる ―変態科学と私―」
17:00〜17:30
・日本地質学会賞受賞講演 木村学会員
「地質学の自然観」
■懇親会(18:00〜20:00 大阪府立大学生協食堂)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.190 2012/9/15 geo-flash (大会臨時号)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.190 2012/9/15 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】大阪大会初日
【2】大阪大会:9月16日(日)の主なイベント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】大阪大会初日
──────────────────────────────────
■学術交流協定調印
日本地質学会と韓国地質学会との間で学術交流協定が結ばれました。
■今年の地質情報展は講演会場からちょっと離れていますが、大阪市立自然史
博物館が会場です。
なんと、初の試みのバナナ園の温室ハウスのような緑に囲まれた「花と緑の
地質情報展」です。昼過ぎに開会式が行われると、石割りコーナーや化石
レプリカ作りにはあっという間に長蛇の列ができました。
地質学会のブースには、フォトコンテストの作品のパネル展示と、地学オリ
ンピックなどです。
ぜひのぞいてみてください。
■初日の優秀ポスター賞(2件)の表彰が行われました。
初日の優秀ポスター賞の表彰は、他の表彰と同じく大きなUホール白鷺での
表彰です。ポスター賞を狙うなら、初日のセッションですね。
初日の優秀ポスター賞は:
「岩手県和賀町周辺奥羽脊梁山脈の前期〜中期中新世テクトニクス」
細井淳ほか (T2-P-1)
「霞ヶ浦を構成する2湖沼(西浦・北浦)における過去500年間の環境変化比較」
畑中雄太ほか (R20-P-10)
■大盛況の懇親会
懇親会チケットが売りきれるほどの大盛況でした。
韓国地質学会会長の挨拶など聞きながら会が進むうちに、受賞者挨拶の頃
には大騒ぎでほとんど聞こえてない状況でした。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】大阪大会:9月16日(日)の主なイベント
──────────────────────────────────
■公開シンポジウム
「上町断層の地下構造と運動像―都市域伏在活断層の地質学―」
(9:00〜12:00 Uホール白鷺)
■東日本大震災復旧復興にかかわる調査・研究事業報告
標本レスキュー関係2件
■市民講演会
「地震・津波・地盤災害 〜知ること、伝えること〜」
(14:30〜17:00 Uホール白鷺)
■国際ワークショップ「The Geology of Japan」
(14:30〜18:05 第3会場)
■就職支援プログラム(14:30〜18:00 B3棟3F)
■小さなEarth Scientistのつどい(9:00〜15:30 学術交流会館ポスター会場)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.188 2012/9/12 geo-flash
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.188 2012/9/12 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】大阪大会についてのプレスリリースをおこないました
【2】今年もgeo-Flash大会臨時号出します
【3】会場へのアクセス・会場内の移動など時間がかかります。ご注意下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】大阪大会についてのプレスリリースをおこないました
──────────────────────────────────
プレスリリースの概要は、
1)日本地質学会第119年学術大会(大阪大会)を開催
公開シンポジウム
「上町断層の地下構造と運動像 ―都市域伏在活断層の地質学―」
「西日本の海溝型地震と津波を考える」
2)特筆すべき個人、団体の学術発表
(1)衛星情報から僅かな地盤のズレを検知することによる広域災害警戒技術
(2)巨大津波によってえぐられた気仙沼湾の海底 −気仙沼湾復興を目指した最
新観測調査−
【既報の成果に関する研究発表】
(3)Japan Trench Fast Drilling Project (JFAST): 2011年東北地震の巨大滑り
を理解するための掘削調査
3)表彰
4)関連行事
(1)市民講演会「地震・津波・地盤災害 〜知ること、伝えること〜」
(2)地質情報展2012おおさか 「過去から学ぼう 大地のしくみ」
(3)小さなEarth Scientistのつどい 第10回小、中、高校生徒「地学研究」発
表会
詳しい内容は、、、http://www.geosociety.jp/engineer/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】今年もgeo-Flash大会臨時号出します
──────────────────────────────────
大阪大会についての情報をいち早くお知らせできるよう
大会臨時号を出します。お楽しみに。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】会場へのアクセス・会場内の移動など時間がかかります。ご注意下さい。
──────────────────────────────────
会場である大阪府立大学中百舌鳥キャンパスは広く、構内の移動にもかなり時間を
要する模様です。参加者の皆様には,講演時間などをご確認の上、時間に余裕をもっ
て会場にお越し頂きますようお願いいたします。
【最寄り駅〜大学】
南海高野線「中百舌鳥駅」〜大学(中百舌鳥門)まで:約1000m.(徒歩約13分)
地下鉄「なかもず駅」〜大学(中百舌鳥門)まで:約1000m.(徒歩約13分)
南海高野線「白鷺駅」〜大学(白鷺門)まで:約500m.(徒歩約6分)
【大学構内】
白鷺門〜〜講演会場B3棟まで(約400m)
中百舌鳥門〜講演会場B3棟まで(約600m)
会場アクセスなど詳細は、
http://www.geosociety.jp/osaka/content0015.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
<ニュース誌表紙写真,特に募集中です!お待ちしてます. >>
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
No.191 2012/9/16 geo-flash (大会臨時号)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.191 2012/9/16 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】大阪大会二日目
【2】大阪大会:9月17日(月)の主なイベント
【3】写真満載、初日と2日目!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】大阪大会二日目
──────────────────────────────────
■市民講演会
小学生からお年寄りまで多くの市民が集まりました。
地震・津波に対する市民の関心の高さがわかります。
真剣な顔して聴いていた小学生もわかったかな?
市民向けポスター展示もみなさん興味津々
■小さなアースサイエンティストのつどい
会員のポスター発表に並んで中高生の研究発表が行われました。
生徒たちの元気さとすばらしい発表に会員も刺激を受けました。
優秀賞(3件):
「高級石材凝灰岩「竜山石」の特性をリサイクル商品に活かす」
兵庫県立加古川東高等学校地学部(竜山石班)
「介形虫化石からみる番の州の古環境の変化 〜更新世から完新世〜」
高松第一高等学校
「棚倉堆積盆玉川層における堆積環境の変遷」
私立水戸葵陵高等学校
■二日目の優秀ポスター賞(3件)の表彰
今日の優秀ポスター賞は:
「東北沖日本海溝に沈み込む海洋性粘土質堆積物の地震性高速すべり挙動」
澤井みち代・廣瀬丈洋 (T5-P-3)
「北海道天塩中川地域、蝦夷層群における上部白亜系砕屑性重鉱物の化学組成」
西尾真由子・吉田孝紀 (R8-P-1)
「地学教科書における続成作用の記述と砂岩の続成作用を教えるための氷塊を使った実験」
廣木義久 (R19-P-4)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】大阪大会:9月17日(月)の主なイベント
──────────────────────────────────
■公開シンポジウム
「西日本の海溝型地震と津波を考える」
(9:00〜12:00 Uホール白鷺)
■東日本大震災復旧復興にかかわる調査・研究事業報告
応用地質学・環境地質学的視点からの液状化、除染関係2件
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】会場の様子(初日表彰式から2日目まで)
──────────────────────────────────
大会初日の表彰式の様子です。
懇親会は若手も大勢参加して、チケットが売りきれるほど大盛況でした。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.192 2012/9/17 geo-flash (臨時)飯山敏道名誉会員 訃報
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.192 2012/9/17 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 飯山敏道 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
日本地質学名誉会員 飯山敏道氏が、平成24年9月15日(土)にご逝去され
ました。
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
なお、通夜ならびに告別式は、下記のとおり執り行われますので併せてお知ら
せ申し上げます。
通夜:9月17日(月)17:00より
告別式:9月18日(火)8:30より
式場:カトリック西千葉教会(〒260-0034 千葉市中央区汐見丘町11-14)
西千葉駅下車徒歩8分
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
geo-Flash No.202 第4回惑星地球フォトコンテスト作品募集
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.202 2012/11/20 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2013年度日本地質学会各賞候補者募集中
【2】第4回惑星地球フォトコンテスト作品募集
【3】Island Arc 新名称公募のお知らせ
【4】2013年度会費払込のお知らせ
【5】コラム:オーストラリア国立大学に設置されたS/Iタイプ花崗岩ベンチ
【6】男女共同参画学協会連絡会・第3回大規模アンケートへのご協力のお願い
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞情報
【10】地質マンガ:『青春の伝説』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2013年度日本地質学会各賞候補者募集中
──────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして,研究の援助・奨励および研究業績の表彰を行っています(定款第3条).
具体的には,運営規則第16条および各賞選考規則に,表彰の種別や選考の手続きを定めています.これらにしたがい,各賞の自薦,他薦による候補者を募集 いたします.
ご応募いただいた候補者を,各賞選考委員会(委員は理事会の互選と職責により選出)が選考し,理事会で候補者を決定し,総会の承認を経て表彰 を行います.日本地質学会功労賞・日本地質学会表彰以外は,会員(正会員・名誉会員)であればどなたでも推薦できます.
各賞選考委員会(学会事務局)あてご応募下さい.期日厳守にて,たくさんのご応募をお待ちしております.なお,ご応募いただいた場合には,必ず受け取りのお返事をお出ししますのでご確認ください.
応募締切:2012年12月25日(火)必着
選考規則など詳しくは,
http://www.geosociety.jp/members/content0069.html
(会員によるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第4回惑星地球フォトコンテスト作品募集
──────────────────────────────────
今年もフォトコンテストの募集が始まっています。たくさんのご応募お待ちしています。
【こんな作品を大募集!】
・惑星地球の美しい自然
・地層や火山など活きた地球の姿を表す優れた作品
・学術的意義の高い作品(解説文を含む)
・ジオパークに関係する優れた作品
・「ジオ鉄」の優れた作品学術的・教育的な価値のある優れた作品
・そのほか地球科学に関係した作品
締切:2013年1月31日(木)17:00
応募方法など詳しくは,
http://photo.www.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】Island Arc 新名称公募のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地質学会の公式英文雑誌としてIsland Arc(当初はThe Island Arc)が誕生して20年が経過しました。
初版の出版から20年の節目を迎え,Island Arcの本来の出版目的がより効果的に達成され,さらには,私たちの研究成果を世界に向けて発信する国際学術雑誌としての飛躍を図るために,Island Arcという雑誌名を刷新し,
新たな一歩を踏む出すこととなりました。
日本地質学会ならびに協賛学会の会員の皆様方には,この機会に是非とも魅力ある新しい雑誌名のご提案をお願い申し上げる次第です。
新しい雑誌名の条件
1)既に出版されている国内外の学術雑誌名と異なること。
2)地球科学全般をカバーした国際学術雑誌であることがわかること。
応募の締切:2013年1月31日(木)必着
応募方法など詳しくは,
http://www.geosociety.jp/publication/content0005.html#new
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2013年度会費払込のお知らせ
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下さいますようお願いいたします.
■2013年度分会費の引き落とし日:12月25日(火)です.
請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下さい.
■自動引き落とし以外の方(お振り込み)
12月中旬頃までに請求書兼郵便振替用紙をお送りいたします.折り返しご送金くださいますようお願いいたします.
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/outline/content0108.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】コラム:オーストラリア国立大学に設置されたS/Iタイプ花崗岩ベンチ
──────────────────────────────────
石原舜三(産業技術総合研究所 顧問)
Bruce ChappellおよびAllan Whiteの業績をしのんで、S/Iタイプ花崗岩を用いたベンチが国立大学校内の一隅に設けられ、そのお披露目がBruceの死後6か月に当たる2012年10月19日に行われた。
続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0414.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】男女共同参画学協会連絡会・第3回大規模アンケートへのご協力のお願い
──────────────────────────────────
男女共同参画学協会連絡会では、研究者・技術者を取り巻く現状を把握するために、第3回大規模アンケートを実施致します。連絡会では、これまで2003年、2007年の2回にわたり大規模アンケート調査を行い、それぞれ約2万人の回答を得ました。それらの調査結果は若手・女性研究者や技術者が直面する様々な問題点を議論する上での統計的根拠として、現在も様々な場面で引用されております。また、それに基づいて作成した提言は、国の政策決定に反映されており、実際に様々な支援策が講じられてまいりました。このようなアンケート調査を継続して実施することは、男女共同参画の実情やその認識の変化を明らかにし、実施されている政府事業の効果を検証し、さらに新たな課題を見出す上で大変重要と考えております。
アンケート回答期間(2012年11月1日(木)〜11月30日(金))中に、
アンケート回答URL https://wss2.5star.jp/survey/index/n3dd5zyv/4134/
にアクセスしていただき、ご回答下さい。
併せて、男女共同参画学協会連絡会HP
http://annex.jsap.or.jp/renrakukai/enquete.html
に記載の情報もご確認いただけますと幸いです。多くの皆様からのご協力をお願い申し上げます。
※参考URL
第1回アンケート調査報告書
http://annex.jsap.or.jp/renrakukai/2003enquete/PDF/2004ReportWeb.pdf
第2回アンケート調査報告書
http://annex.jsap.or.jp/renrakukai/2007enquete/h19enquete_report_v2.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
■関東支部:地質学会関東支部『地質研究サミット』シリーズ開催について関 東支部が担う予定の第123年学術大会(2016年開催)の成功に向けて多面的な準備を開始しました。その一つが、関東地方の地質に対して鋭い
斬りこみを かけている研究グループ群を鼓舞激励しつつ関東地方地質研究の新展開を図り、それを第123年学術大会において披瀝しようとするものです。そのためこれまで1年に一度開催していた支部シンポジウムの形式を改め、各研究グループの中心メンバーが一同に会してホットな研究成果を発表するとともに建設的な議論を 行う場を設定することにしました。
名づけて、『地質研究サミット』です。もちろん、この『地質研究サミット』は、“一匹狼”や膨大なデータを蓄積してこら れた諸先輩の参加も大歓迎です。
なお、『地質研究サミット』は、対象が関東地方の地質ではありますが、全国に開かれたものとして運営されます。
★第1回「房総・三浦地質研究サミット」開催のお知らせ及び講演募集
期日:平成25年3月9日(土)・10日(日)
場所:千葉県立中央博物館(千葉市中央区青葉町955−2)
講演申込締切:平成25年1月20日(日)
詳しくは関東支部HP(http://kanto.geosociety.jp/)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第145回深田研談話会
「日本列島・地球史・「ちきゅう」そして新しい地球生命感」
講師:平 朝彦
11月30日(金)15時〜
会場:深田地質研究所研修ホール
参加費無料
http://www.fgi.or.jp
■第146回深田研談話会
「巨大地震・津波の想定と課題」
講師:岡村行信
12月14日(金)15〜17時
会場:深田地質研究所研修ホール
参加費無料
http://www.fgi.or.jp
■平成24年度自然史学会連合講演会自然災害とナチュラルヒストリー
12月1日(土)10:00-16:30
会場:栃木県立博物館 講堂
主催:自然史学会連合
共催:栃木県立博物館
http://ujsnh.org/sympo/2012/index.html
■地球化学研究協会
第49回の霞ヶ関環境講座・第40回の三宅賞受賞者の受賞記念講演
・「炭素14から探る過去の気候変動」今村峯雄先生(国立歴史民俗博物館名誉教授)
・受賞記念講演「先端計測技術に基づくオゾンおよびブラックカーボンの大気環境への影響」近藤豊博士(東京大学大学院理学系研究科教授 )
12月1日 (土)14:30〜
場所:霞ヶ関ビル35階東海大学校友会館
参加費:賛助会員および学生は無料、一般1,000円(資料代を含む)
http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~e881147/Geochem/index.html
■第22回環境地質学シンポジウム
12月7日(金)・8日(金)
場所:産業技術総合研究所共用講堂
主催:地質汚染−医療地質−社会地質学会
共催:日本地質学会環境地質部会ほか
http://www.jspmug.org/envgeo_sympo/22nd_sympo/22nd_sympo.html
■第12回東北大学多元物質科学研究所研究発表会
12月10日(月)
場所:東北大学片平さくらホール
参加申込締切:11月30日(金)
http://www.tagen.tohoku.ac.jp/general/info/event/meeting/2012/
■日本学術会議中部地区会議学術講演会
「生命科学・地球科学からのメッセージ」
12月14日(金)13:00-16:00
場所:岐阜大学全学共通教育講義棟1階105番講義室
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/161-s-1214.pdf
■○Post Symposium of 4.5-session 1, the 34th IGC, Geopollution,
dust, and man made strata “A flight of stone steps in Brisbane”
“ブリスベーンで見た坂の上の雲”
12月16日(日)13:00〜17:30
主催:国際地質学連合環境地質研究委員会日本支部
共催:日本地質学会環境地質部会ほか
場所:江戸川グリーンパレス(東京都江戸川区)
詳細は,IUGS環境管理研究委員会日本支部
Tel:0478-59-1491 Fax:0478-59-1491
■第13回岩の力学国内シンポジウム
日本地質学会 協賛
(併催:第6回日韓ジョイントシンポジウム)
2013年1月9日(水)〜11日(金)
会場:沖縄コンベンションセンター
事前参加申込締切:12月7日(金)
http://www.rocknet-japan.org/jsrm2013/
■第14回情報学シンポジウム:数値シミューションと情報学
2013年2月19日(火)13:00-17:20
会場:京都大学百周年時計台記念館百周年記念ホール
http://ict-nw.i.kyoto-u.ac.jp/ict-innovation/2013/
■ICDP関連ワークショップ開催
“Japan Beyond-Brittle Project (JBBP) - Scientific drilling
to demonstrate a feasibility of the engineered geothermal system
in ductile zones –”
主催: 国際陸上科学掘削計画(ICDP)Japan Beyond-Brittle Project
日程: 2013年3月12日(火)〜16日(土)
(14日は見学会。松川,八幡平地域を予定。16日は有志による報告書執筆。)
会場: 東北大学工学部(仙台市青葉区)
参加費無料
参加申込締切:2013年3月1日(金)
申込方法:事務局へメールまたはFAXにて連絡
問合せ先:東北大学・大学院環境科学研究科内ワークショップ事務局 浅沼 宏
TEL&FAX 022-795-7399 jbbp@geoth.kankyo.tohoku.ac.jp
http://www.icdp-online.org/front_content.php?client=29&lang=28&idcat=309&idart=3557&m=&s=
■日本学術会議の「Twitter」の活用について(お知らせ)
日本学術会議の活動を一般国民に対して広く周知するために、「Twitter」を
活用した広報を始めます。具体的には、日本学術会議が主催する学術フォーラム、
講演会、シンポジウム等の開催に関する情報等を発信いたします。
ツイッターアカウント: @scj_info
日本学術会議広報のTwitterのページはこちら
http://twitter.com/scj_info
Twitterの運用方針についてはこちら
http://www.scj.go.jp/ja/twitter/unyou.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■北海道大学低温科学研究所有機地球化学分野教授公募(1/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】地質マンガ:『青春の伝説』
──────────────────────────────────
『青春の伝説』 作:本郷宙軌 画:Key
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
<ニュース誌表紙写真,特に募集中です!お待ちしてます.>
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
No.193(大会臨時号)ありがとう大阪!仙台で会いましょう!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.193 2012/9/17 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】大阪大会最終日
【2】来年また仙台で会いましょう!
【3】写真で満載 2日目と最終日の会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】大阪大会最終日
──────────────────────────────────
■公開シンポジウム「西日本の海溝型地震と津波を考える」
やはり地震・津波の話題は市民の関心も高く、参加者は真剣に聞き入って
いました。テレビカメラも入ってました。
■三日目の優秀ポスター賞(3件)の表彰
最終日の優秀ポスター賞は:
「非造礁性六射サンゴにおける出芽による無性増殖様式と群体形成」
千徳明日香ほか (R15-P-6)
「走査型電子顕微鏡(SEM)を用いた断層破砕帯の定方位試料の微細組織観察」
亀高正男ほか (R14-P-7)
「ニュージーランドカンタベリー堆積盆地における鮮新−更新統の貝形虫
化石群集を用いた古水深変動の復元」
中村めぐみほか (R15-P-12)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】来年また仙台で会いましょう!
──────────────────────────────────
最終日公演プログラムが終わって外へ出てみると、きれいな虹が架かって
いました。名残惜しいですが、来年また仙台で合いましょう!
でもまだ巡検は続きます。お気をつけて!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】写真で満載 2日目と最終日の会場
──────────────────────────────────
受賞者展示
今日は高校生セッション
たいへんな熱気です
ポスターコアタイム!
熱心な説明にたじたじ
日韓交流事業の昼食会
大阪名物おいしい
セッション会場もいっぱい
高校生セッション表彰
受賞おめでとうございます
市民講演会も大好評
優秀ポスター賞表彰式
おめでとうございます。
──────────────────────────────────
最終日の様子です
今日も暑いぜ
会場も暑いぜ(涼しいけど)
ポスター賞授賞式
おめでとうございます!
まだまだ議論は終わらないっっっ
仙台につながる虹だあ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flash No.197(臨時)国際地学オリンピック金メダル獲得!&2016年大会日本開催決定
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.196 2012/10/13 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】国際地学オリンピック 金メダルおめでとう!
【2】2016年大会の日本開催が決定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】国際地学オリンピック 金メダルおめでとう!
──────────────────────────────────
アルゼンチンで10月8日〜12日の日程で開催されていた第6回国際地学オリンピック
で日本選手が金メダル1個、銀メダル3個を獲得しました。
受賞者は以下のとおりです。
金メダル:
中里徳彦さん 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校(神奈川県)3年
銀メダル:
島本賢登さん 広島学院高等学校(広島県)3年
松尾健司さん 灘高等学校(兵庫県)3年
丸山純平さん 聖光学院高等学校(神奈川県)3年
おめでとうございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2016年大会の日本開催が決定
──────────────────────────────────
アルゼンチン大会中に開催された国際地学オリンピック運営委員会で、2016年
第10回国際地学オリンピック日本大会の開催が正式決定されました。
開催地は三重県となります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
<ニュース誌表紙写真,特に募集中です!お待ちしてます. >>
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
geo-Flash No.196(臨時)分析会社の誤分析に関する情報
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.196 2012/10/5 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】分析会社の誤分析に関する情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】分析会社の誤分析に関する情報
──────────────────────────────────
日本地質学会会員各位
執行理事会に,ある分析会社の誤分析に関する以下のような情報が寄せられました.
極めて重大な問題であり,執行理事会としては,会員の皆様にも大きな影響が及ぶ
と判断し,独自の調査を始めたところです.分析会社から既に説明を受けた方や,
お心当たりがある方がいらっしゃいましたら,井龍(iryu@m.tohoku.ac.jp)まで
御一報下さるようお願いいたします.
[誤分析の概要]
・対象分析データ:水試料(表層水,地下水,氷)の水素・酸素同位体比測定値.
・誤分析が生じた原因:分析の際,適切に管理されていない標準試料を使用した
ため,誤った測定値を報告した.
・誤分析の及ぶ範囲:該当業者が最近4〜5年間に報告した上記の分析データの全て
(最近10年間のデータについても,その値の信頼性には疑問がある).
井龍康文(執行理事・学術研究部会長)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
<ニュース誌表紙写真,特に募集中です!お待ちしてます. >>
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
geo-Flash No.198 Island Arcが完全電子ジャーナル化
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.198 2012/10/16 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】Island Arc:冊子体を廃止し,オンライン閲覧のみになります
【2】2013年度会費払込/学部学生・院生割引申請のお知らせ
【3】男女共同参画実態調査へのご協力のお願い
【4】その他のお知らせ
【5】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】Island Arc:冊子体を廃止し,オンライン閲覧のみになります
──────────────────────────────────
Island Arcは,2013年 (Vol. 22) より,冊子体を廃止し,オンライン閲覧のみになります.
現在,IARは冊子体と電子ジャーナルの双方を出版しております.しかしながら,冊子体の発行部数は極めて少なく,W-B社としては2013年より完全電子ジャーナル化に踏み切りたいとの連絡がありました.編集委員会および執行理事会で,本提案に関して慎重に審議した結果,出版の電子化という趨勢と完全電子ジャーナル化のメリットに鑑み,W-B社の提案を受諾することになりました.
オンライン化するにあたり,投稿規定等が一部変更になります(準備中).
現在投稿中の方など,ご不明な点があれば,IAR編集事務局(iar-office@geosociety.jp)へお問い合わせください.
・カラーチャージがなくなります
冊子体のモノクロ用にと,ひと手間かかっていた図の網かけ等は不要です.
・Supporting Infomationの活用
ファイル容量の上限はありますが,Supplementary material(video footage, tables, figures, and appendices)を活用しやすくなります.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2013年度会費払込/学部学生・院生割引申請のお知らせ
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下さいますようお願いいたします.
■2013年度分会費の引き落とし日:12月25日(火)です.
請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下さい.
■自動引き落としをご利用下さい.
新たに会費の引き落としをご希望の方は,振替依頼書を11月9日(金)までに事務局までお送り下さい.
■自動引き落とし以外の方(お振り込み)
12月中旬頃までに請求書兼郵便振替用紙をお送りいたします.折り返しご送金くださいますようお願いいたします.
■学部学生割引・院生割引会費の適用を希望される方へ
11月14日(水)までに学部学生割引会費・院生割引会費申請書をご提出下さい.
期日までにご提出のない場合は,正会員の会費でご請求ががかかります.
ご了解下さい.
詳しくは(割引会費申請書,振替依頼書(PDF)のダウンロードも)、
こちらから↓
http://www.geosociety.jp/outline/content0108.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】男女共同参画実態調査へのご協力のお願い
──────────────────────────────────
男女共同参画学協会連絡会による「第3回科学技術系専門職の男女共同参画実態調査」への協力依頼が日本地球惑星科学連合よりありました。
この調査は、多くの科学技術専門職の方々のワーク(研究)ライフバランスやキャリアパス、任期つき雇用の問題などの意見を汲み出すことで、男女共同参画状況の推移を見極め、今後の研究者雇用施策に反映させる基礎情報とすることを目的としています。
科学者・技術者・教員だけでなく学生も、性別を問わず回答できるとのことですので、積極的なご協力をお願いします。
アンケートは11月1日から開始されます。
アンケート実施方法:オンラインによる実施 (web回答方式)
https://wss2.5star.jp/survey/index/n3dd5zyv/4134/ (11月1日より)
アンケート実施期間:平成24年11月1日(木)〜11月30日(金)(予定)
※参考URL
第1回アンケート調査報告書
http://annex.jsap.or.jp/renrakukai/2003enquete/PDF/2004ReportWeb.pdf
第2回アンケート調査報告書
http://annex.jsap.or.jp/renrakukai/2007enquete/h19enquete_report_v2.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■東アジア共同研究プログラム(e-ASIA JRP)事業説明会
JSTは、東アジア首脳会議18カ国との多国間(3カ国以上)の共同研究プログラム(略称:e-ASIA JRP)を平成24年6月に発足させました。
本プログラムは、東アジア地域において、科学技術分野における研究交流を加速することにより、研究開発力を強化するとともに、環境、防災、感染症など、東アジア諸国が共通して抱える課題の解決を目指すものです。
本プログラムにおいては、第一回のパイロット公募が終了し、今後さらに各分野での公募を実施する予定です。つきましては、今後の公募に先立ち、事業説明会を開催することとなりました。
イベントでは、事業に関する説明と今後の予定について説明を行うとともに、ご参加いただく研究者の皆様とともに、東アジア地域での研究課題形成に向け、情報交換、意見交換させていただき、JSTとして本事業の今後の運営や発展に反映していく予定です。本事業での公募にご興味、ご関心をお持ちの方はぜひともご参加いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
場所:JST本部別館4階会議室
参加費:無料
募集対象分野:「防災」「感染症」「イノベーションのための先端融合分野」「ナノテク・材料」「バイオマス・植物科学」
公募開始:各国機関の参加状況による。11月以降を予定。
参加申込(申込締切:10月31日)
emailにてeasiajrp@jst.go.jpまでお申し込みください。
以下の必要情報をお知らせください。
-----------------------------------------------
・ご所属・役職
・氏名
・参加セッション(「感染症」、「防災」)
・ご質問・ご要望(もしあれば)
-----------------------------------------------
e-ASIA JRPの詳細,http://www.the-easia.org/jrp/
■ウインター・サイエンスキャンプ '12-'13参加者募集
先進的な研究テーマに取り組む大学・研究機関等を会場として、第一線で活躍する研究者・技術者から本格的な講義・実験・実習が受けることができる、高校生のための科学技術体験合宿プログラム。会期は12月下旬から1月上旬の冬休み期間中の3〜4日。詳しくはWEBを参照。
http://rikai.jst.go.jp/sciencecamp/camp/
締切:2012年11月6日(火)必着
■東京大学大気海洋研究所共同利用研究集会
「バイオミネラリゼーションと石灰化―遺伝子から地球環境まで―」
11月8日(木)13:00〜17:00
11月9日(金)9:30〜12:00
場所:東京大学大気海洋研究所2F講堂
http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/aori_news/meeting/index.html
■学術会議サイエンスアゴラ2012
『地球に生きる素養を身につけよう』
11月11日(日) 10時30分〜12時
会場:産業技術総合研究所臨海副都心センター別館 11階 第2・3会議室
(東京都江東区青海2−3−26)
◆概要
大地震、津波、集中豪雨、突風・竜巻など、地球上に生きる、我々、地球人は、活動的な地球によってさまざまな影響を被っている。激しく変化する自然現象に対して、安全に立ち向かうためには、「地球に生きる素養を身につける」ことが大切である。地球、そして身の回りにある自然を科学的に理解し、自然が引き起こす影響を適切に予測しまた、予測の限界を知ったうえで行動できることが、「地球に生きる素養」あるいは「教養」である。本講演会では、さまざまな自然現象に対して、われわれがどう対処し、暮らすのか? について紹介し、参加者と議論する。
◆プログラム(敬称略)
1.シンポジウムの趣旨説明
北里 洋(日本学術会議第三部会員、独立行政法人海洋研究開発機構海洋・極限環境生物圏領域領域長)
2.2011.3.11 地震・津波に学ぶ
入倉 孝次郎(日本学術会議連携会員、京都大学名誉教授)
3.日本列島の成り立ちと地質災害
千木良 雅弘(日本学術会議連携会員、京都大学防災研究所教授)
4.「命の水」の危機−水資源の未来
益田 晴恵(日本学術会議連携会員、大阪市立大学大学院理学研究科教授)
5.ガスハイドレートをエネルギー資源に
松本 良(日本学術会議連携会員、東京大学名誉教授)
6.住んでいる土地を知る
熊木 洋太(日本学術会議連携会員、専修大学文学部教授)
7.宇宙から地球を考える
佐々木 晶(日本学術会議連携会員、大学共同利用機関法人自然科学研究機構国立天文台水沢観測所教授)
■学術会議サイエンスアゴラ2012
『討議:高レベル放射性廃棄物の処分はどうあるべきか!?』
11月11日(日) 10時30分〜12時
会場:日本科学未来館7階みらいCANホール(東京都江東区青海2−3−6)
◆概要
日本学術会議が平成24年9月11日に原子力委員会に回答した「高レベル放射性廃棄物の処分に関する回答」を紹介し、パネルディスカッションを通じて高レベル放射性廃棄物の処分に関する様々な見解を会場に提示し、その上で、会場と意見交換を行う。
会場にこられた方々の日本学術会議の回答に関する理解を深めるとともに、各自が高レベル放射性廃棄物の処分問題を自らの課題として捉え、解決への道を各々検討してもらう礎とする。
◆プログラム(敬称略)
1.開会挨拶および基調講演(25分)
「高レベル放射性廃棄物の処分に関する回答」
今田 高俊(日本学術会議第一部会員、東京工業大学大学院社会理工学研究科教授)
2.パネル討論(40分)
パネリスト:
今田 高俊(日本学術会議第一部会員、東京工業大学大学院社会理工学研究科教授)
武田 精悦(原子力発電環境整備機構理事)
西尾 獏(特定非営利活動法人原子力資料情報室共同代表)
小出 五郎(元NHK解説委員、科学ジャーナリスト)
コーディネーター:
柴田 徳思(日本学術会議連携会員、(株)会社千代田テクノル大洗研究所研究主幹)
3. 会場との意見交換(20分)
4. 閉会挨拶(5分)
山地 憲治(日本学術会議第三部会員:地球環境産業技術研究機構(RITE) 理事・所長)
※上記5件とも、入場無料
シンポジウム詳細URL http://scienceagora.org/
■農業・農村の地域再生に関する技術シンポジウム
11月15日(木曜日) 11:00〜16:30
場所:東北大学百周年記念会館川内萩ホール
入場無料・要申込
http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2012/09/043933.html
■東北大学多元物質科学研究所第21回素材工学研究懇談会
11月16日(金)
場所 片平さくらホール(仙台市青葉区片平)
要参加申込(10/31締切)
http://www.tagen.tohoku.ac.jp/
■Tecno-Ocean 2012
11月18日(日)〜20日(火)
会場:神戸国際会議場(神戸ポートアイランド内)
http://www.techno-ocean2012.com/
■第6回ジオ多様性フォーラム
12月21日(金)〜22日(土)
場所:JAMSTEC東京事務所(千代田区内幸町)
http://www.geosociety.jp/outline/content0099.html#2012_1221
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■海洋研究開発機構地球内部ダイナミクス領域(研究職/技術研究職)公募(11/30)
■海洋研究開発機構地球内部ダイナミクス領域(技術総合職)公募(11/30)
■海洋研究開発機構地球内部ダイナミクス領域(研究技術専専任スタッフ)公募(11/30)
■第30回「とやま賞」候補者推薦(学会締切11/8)
■第40回「環境賞」募集(12/21)
■平成25年度学術研究船白鳳丸共同利用公募(10/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
<ニュース誌表紙写真,特に募集中です!お待ちしてます.>
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
geo-Flash No.201 ラクイラ地震裁判における科学者への実刑判決を憂慮する
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.201 2012/11/6 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】ラクイラ地震裁判における科学者への実刑判決を憂慮する(声明)
【2】Island Arc 新名称公募のお知らせ
【3】GSJの地質図幅がWeb公開!「地質図Navi」の試験公開始まりました
【4】2013年度会費払込/学部学生・院生割引申請のお知らせ
【5】男女共同参画学協会連絡会・第3回大規模アンケートへのご協力のお願い
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】ラクイラ地震裁判における科学者への実刑判決を憂慮する
──────────────────────────────────
日本地質学会は、イタリアの2009年ラクイラ地震に関する裁判において、6人の地球科学者が過失致死罪で禁錮6年の実刑判決を受けたことについて、重大な懸念を表明する。
、、、、、全文を読む(和/英)
http://www.geosociety.jp/engineer/content0018.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】Island Arc 新名称公募のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地質学会の公式英文雑誌としてIsland Arc(当初はThe Island Arc)が誕生して20年が経過しました。
初版の出版から20年の節目を迎え,Island Arcの本来の出版目的がより効果的に達成され,さらには,私たちの研究成果を世界に向けて発信する国際学術雑誌としての飛躍を図るために,Island Arcという雑誌名を刷新し,新たな一歩を踏む出すこととなりました。
日本地質学会ならびに協賛学会の会員の皆様方には,この機会に是非とも魅力ある新しい雑誌名のご提案をお願い申し上げる次第です。
新しい雑誌名の条件
1)既に出版されている国内外の学術雑誌名と異なること。
2)地球科学全般をカバーした国際学術雑誌であることがわかること。
応募の締切:2013年1月31日(木)必着
応募方法など詳しくは,
http://www.geosociety.jp/publication/content0005.html#new
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】GSJの地質図幅がWeb公開!「地質図Navi」の試験公開始まりました
──────────────────────────────────
GSJの地質図幅が見られるWebサイト「地質図Navi」が、産業技術総合研究所から公開(試験公開)されました。これまでは、図書室の書庫の奥で目当ての図幅を探す苦労がありましたが、今後はWebブラウザで素早く地質図を確認することができるようになります。
地質図Naviは、1/5万地質図幅を始めとする千枚以上の地質図幅類を表示でき、シームレス地質図、活断層、第四紀火山、地球物理・地球化学データなど各種の情報も合わせて表示することが可能です。
今後、産総研の整備する各種データベースと連携することで、表示可能な情報が追加されていく予定です。
「地質図Navi」試験公開サイト: http://gsj-seamless.jp/geonavi/
簡単使い方ガイド: http://gsj-seamless.jp/geonavi/gm/help/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2013年度会費払込/学部学生・院生割引申請のお知らせ
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下さいますようお願いいたします.
■2013年度分会費の引き落とし日:12月25日(火)です.
請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下さい.
■自動引き落としをご利用下さい.
新たに会費の引き落としをご希望の方は,振替依頼書を11月9日(金)までに事務局までお送り下さい.
■自動引き落とし以外の方(お振り込み)
12月中旬頃までに請求書兼郵便振替用紙をお送りいたします.折り返しご送金くださいますようお願いいたします.
■学部学生割引・院生割引会費の適用を希望される方へ
11月14日(水)までに学部学生割引会費・院生割引会費申請書をご提出下さい.
期日までにご提出のない場合は,正会員の会費でご請求ががかかります.
ご了解下さい.
詳しくは(割引会費申請書,振替依頼書(PDF)のダウンロードも)、
こちらから↓
http://www.geosociety.jp/outline/content0108.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】男女共同参画学協会連絡会・第3回大規模アンケートへのご協力のお願い
──────────────────────────────────
男女共同参画学協会連絡会では、研究者・技術者を取り巻く現状を把握するために、第3回大規模アンケートを実施致します。連絡会では、これまで2003年、2007年の2回にわたり大規模アンケート調査を行い、それぞれ約2万人の回答を得ました。それらの調査結果は若手・女性研究者や技術者が直面する様々な問題点を議論する上での統計的根拠として、現在も様々な場面で引用されております。また、それに基づいて作成した提言は、国の政策決定に反映されており、実際に様々な支援策が講じられてまいりました。このようなアンケート調査を継続して実施することは、男女共同参画の実情やその認識の変化を明らかにし、実施されている政府事業の効果を検証し、さらに新たな課題を見出す上で大変重要と考えております。
アンケート回答期間(2012年11月1日(木)〜11月30日(金)中に、
アンケート回答URL https://wss2.5star.jp/survey/index/n3dd5zyv/4134/
にアクセスしていただき、ご回答下さい。
併せて、男女共同参画学協会連絡会HP
http://annex.jsap.or.jp/renrakukai/enquete.html
に記載の情報もご確認いただけますと幸いです。
多くの皆様からのご協力をお願い申し上げます。
※参考URL
第1回アンケート調査報告書
http://annex.jsap.or.jp/renrakukai/2003enquete/PDF/2004ReportWeb.pdf
第2回アンケート調査報告書
http://annex.jsap.or.jp/renrakukai/2007enquete/h19enquete_report_v2.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
■関東支部:ミニ巡検「八ッ場ダム地域の層序を知る」
八ッ場(やんば)ダム建設予定地のある吾妻川水系の流域には,新第三系の火山岩-深成岩類・火山砕屑岩層が広く分布し,第四紀前半の火山が点在しています.今回の巡検は、ダム予定地がどのような地質の所に建設されるのか知ることを目的としています。
日程:12月1日(土)、2日(日) 1泊2日
案内者:中村 庄八
参加可能人数:10名程度(地質学会員に限る。所属支部は問わない)
参加申込締切:11月17日(土)
申込方法:(今後の連絡、および保険加入のため:氏名、住所、年齢(生年月日)、メールアドレス)を明記の上,
世話人:中山俊雄<otto.nakaya@gmail.com>
までお申し込み下さい.
見どころや詳細スケジュールなどは関東支部HPをご参照下さい。
http://kanto.geosociety.jp/junken/mini-2.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地震本部ニュース9月号(2012.10.23)
http://www.jishin.go.jp/main/herpnews/2012/sep/index.htm
■海洋調査技術学会第24回研究成果発表会
11月8日(木)〜9日(金)
会場:海上保安庁海洋情報部10階国際会議室
(東京都江東区青梅2-5-18)
参加費無料
http://jsmst.org/news.html
■海洋プレート研究:掘削技術・成果と次の科学に関する勉強会
11月9日(金)〜10日(土)
場所 JAMSTEC東京事務所
参加費・参加資格などありません.自由に参加してください.
http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~s-moho/sympo2012/2012seminar.html
■東京大学地震研究所・研究集会
「地学教育の現状とその改革」
11月17日(土)・18日(日)
場所: 東京大学地震研究所1号館3階セミナー室
参加費: 無料
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/symposium/2012/201211_ChigakuSympo.pdf
■「海・陸・氷床から探る後期新生代の南極寒冷圏環境変動」
―第三回極域科学シンポジウム横断セッション−
11月26日(月)〜27日(火)の2日間
会場:国立国語研究所(国立極地研究所から徒歩数分)
共催:JAMSTEC 入場無料・事前申込不要
http://polaris.nipr.ac.jp/~daiyonkigroup/PolarScienceSympo_special/index.html
■JpGU教育問題検討委員会主催学習会
「学習指導要領改訂と地学教育への影響 −次期改訂に備えて−」
12月2日(日)
場所:都立両国高校(墨田区江東橋1丁目)
http://www.jpgu.org/whatsnew/121202learning.pdf
■平成24年度国土技術政策総合研究所(国総研)講演会
12月4日(火)
場所:日本教育会館 一ツ橋ホール(千代田区一ツ橋2-6-2)
参加費無料・要申込
http://www.nilim.go.jp/
■日本学術会議主催学術フォーラム
「高レベル放射性廃棄物の処分を巡って」
12月2日(日)13:00〜18:00
会場:日本学術会議 講堂
http://www.scj.go.jp/ja/event/index.html
■産技連・地質関係合同研究会
地質地盤および地圏環境に関する最近の成果
12月6日(木)10:00-17:00
参加費無料・要申込
会場:ホテル福島グリーンパレス(JR福島駅前)
http://www.gsj.jp/HomePageJP.html
■水環境学会第58回セミナー
「東日本大震災後の水環境における放射性物質の挙動」
2013年1月24日(木)
場所:自動車会館大会議室(千代田区九段南)
https://www.jswe.or.jp/
■The International Biogeoscience Conference 2013 Nagoya, Japan
2013年11月1日〜4日
場所:名古屋大学
口頭及びポスター発表を行います.枠が限られていますので,ご希望の方は
なるべく早くお申し込み下さい.
詳細と最新情報は下記で公開しています:
http://www.info.human.nagoya-u.ac.jp/~sugi/Site/Biogeoscience_Conference_2013.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所CO2貯留部門学術研究員(ポスドク)公募(11/29)
■山口大学地球圏システム科学科構造地質学分野公募(准教授または講師)(12/25)
■国立科学博物館研究員(海洋微古生物学)公募(2013/1/15)
■平成25年度東京大学海洋研究所共同利用研究・学際連携研究公募(11/30)
■第54回藤原賞(学会締切2013/1/10)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
<ニュース誌表紙写真,特に募集中です!お待ちしてます.>
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
geo-Flash No.200(臨時) 大型研究計画に関する予備調査に関して
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.199 2012/10/26 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】学術の大型研究計画に関する予備調査について
──────────────────────────────────
日本地質学会会員各位
すでに多くの会員の方々が御存知と思いますが,日本地球惑星科学 連合から,
以下のような連絡がありました.
本予備調査に対して,日本地質学会を「母体となる学協会」とし て,応募なさり
たい方は,メールにて,研究の目的・計画・期待さ れる成果等を簡潔にまとめた
「研究の概要説明」を井龍( iryu@m.tohoku.ac.jp )までお送り下さい.
その際,地質学会事務局( main@geosociety.jp )にもメールをcc で送って
いただけますよう,お願いします.
遅くとも,締め切りの5日前(11月10日)までに は御連絡下さい.
よろしくお願いいたします.
井龍康文(執行理事・学術研究部会長)
*****************************************************
┌┐
└■ 1.学術の大型研究計画に関する予備調査開始について 【締切11/15)】
—大型研究計画マスタープランの改訂—
日本地球惑星科学連合会員の皆様
日本学術会議は,”学術の大型研究計画マスタープラン”,2014年 4月の策定
を目指して改訂することになりました,
日本学術会議地球惑星科学委員会は,日本地球惑星科学連合と協議 の結果,
地球惑星科学コミュニティにおいては,コミュニティの事前の議 論・よりよ
い計画の立案のために,予備調査をおこない,その結果を公表する こととし
ました.
予備調査の回答にあたっては,以下をよくお読みいただき、趣旨お よび策定
方針を御確認ください.回答は,11月15日までに下記専用 フォームにて
ご提案を提出ください.
22期学術の大型施設計画・大規模研究計画に関するマスタープラ ン策定の方針:
http://www.jpgu.org/whatsnew/121019sakuteihoshin.pdf
大型研究計画マスタープラン改定について:
http://www.jpgu.org/news/121019chosa.html
本予備調査について:
http://www.jpgu.org/news/121019yobichosa.html
★回答専用フォーム【 締切11/15(木)】:
https://ssl.formman.com/form/pc/H5dDnq20rlygdc8d/
どうぞよろしくご協力をお願いいたします.
日本学術会議地球惑星科学委員会委員長 永原 裕子
公益社団法人日本地球惑星科学連合会長 津田 敏隆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
<ニュース誌表紙写真,特に募集中です!お待ちしてます. >
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
geo-Flash 地質学会メールマガジン No.101〜200
geo-Flash! 日本地質学会公式メールマガジン
geo-Flash(ジオフラッシュ)は、学会活動の改善の一環として、地質
学に関わるあるいは学界活動に関する情報をいち早く会員の皆様にお届
けすることを目的として発足いたしました。会員の皆様からの情報も積極的に
載せていく予定ですので、大いにご活用いただきますようお願い申し上げます。
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬【geo-Flash】日本地質学会メールマガジン ┴┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.001 Since 2007/07/3 ┴┬┴┬
geo-Flash No.206(臨時)2013年度各賞候補者募集:〆切延長!(1/10〔木〕17時まで)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.206 2012/12/26┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★各賞選考委員会からお知らせ★★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】日本地質学会2013年度各賞候補者募集:〆切延長!(1/10〔木〕17時まで)
──────────────────────────────────
12/25日で〆切となりました各賞候補者募集ですが、さらに多くのご推薦・
ご応募をいただきたく、締め切り日を延長いたします。
とくに、論文賞や研究奨励賞の推薦をお待ちしております。
是非たくさんの候補者並びに候補論文を、各賞選考委員会(学会事務局
main@geosociety.jp)宛にご推薦下さいますよう、何卒よろしくお願いいた
します。
応募〆切延長:2013年1月10日(木)17時まで
選考規則など詳しくは,
http://www.geosociety.jp/members/content0069.html
○会員番号・パスワードによるログインが必要です。
(ログインの方法は http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html)
○「会員のページ」の各賞推薦候補者募集に関する案内から、推薦書式等が
ダウンロードできます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
※2013年新年号は1月4日(金)配信予定です。
geo-Flash No.208 (臨時)増田孝一郎 名誉会員 ご逝去
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.208 2013/1/9 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 増田孝一郎 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
日本地質学名誉会員 増田孝一郎氏(宮城教育大学名誉教授)が、平成25年1月8日(月)にご逝去されました(享年85歳)。
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
なお、通夜ならびに告別式は、下記のとおり執り行われますので併せてお知らせ申し上げます。
通夜:1月10日(木)18:00より
告別式:1月11日(金)13:00より
式場:菊葬会館(〒980-0014 仙台市青葉区本町2-19-15)
電話022-223-3282 FAX022-263-3457
喪主:ご長男 増田俊雄様
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
※1/10に配信の訂正内容を反映して掲載しております※
geo-Flash No.209 はやくフォトコン応募しなきゃ!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.209 2013/1/15 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】第4回惑星地球フォトコンテスト:締切間近!!
【2】第120年学術大会:9月14日(土)〜16日(月)東北大学にて開催
【3】環境変動史部会が発足しました
【4】コラム:地震雲についての雑感
【5】Island Arc 新名称募集中
【6】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
【7】JSEC2012:地球科学関係の発表が入賞しました
【8】地質図の在庫一掃セール!— 2013年3月末日まで
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】第4回惑星地球フォトコンテスト:締切間近!!
──────────────────────────────────
まもなく応募締切です。たくさんのご応募お持ちしています。
締切:2013年1月31日(木)17:00
大学生、高校生の作品も大歓迎。
iPhoneなどで撮ったスナップなども受け付けています。
投稿はWebフォームから簡単です。
【こんな作品を大募集!】
・惑星地球の美しい自然
・地層や火山など活きた地球の姿を表す優れた作品
・学術的意義の高い作品(解説文を含む)
・ジオパークに関係する優れた作品
・「ジオ鉄」の優れた作品学術的・教育的な価値のある優れた作品
・そのほか地球科学に関係した作品
応募方法など詳しくは,http://photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第120年学術大会:9月14日(土)〜16日(月)東北大学にて開催
──────────────────────────────────
日本地質学会は,東北支部の支援のもと,東北大学川内キャンパスにおいて第120年学術大会(2013年仙台大会)を2013年9月14日(土)〜16日(月)の日程で開催致します.
プレ巡検は9月13日(金),ポスト巡検は9月17日(火)〜18日(水)に開催予定です.
2013年仙台大会準備委員会
委員長 箕浦幸治,事務局長 西 弘嗣
続きを読む、、、
http://www.geosociety.jp/science/content0051.html
★トピックセッション募集:3月11日(月)締切
詳しくは,こちらから
http://www.geosociety.jp/science/content0052.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】環境変動史部会が発足しました.
──────────────────────────────────
日本地質学会環境変動史部会が2012年10月に発足しました.
環境変動史部会は,地層や岩石から過去の地球の姿を読み解き,地球環境の変動史を理解する研究分野の専門部会です.
多様な研究手法,様々な時間スケールで地球環境変動を捉える研究分野の発展に貢献することを目的としています.
この専門部会を,環境変動研究者の情報交換・情報発信の場として機能させたいと考えています.
部会長:黒田潤一郎(JAMSTEC)
幹事: 佐藤時幸(秋田大学)
幹事: 川幡穂高(東京大学)
http://www.geosociety.jp/outline/content0049.html
(環境変動史部会のホームページは近日公開予定です)
*専門部会への登録は、会員ログインページ (https://www.geosociety.jp/user.php)から行えます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】コラム:地震雲についての雑感
──────────────────────────────────
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
半年前,あるニュース社からの取材を受け,世間でよく言われる地震の前兆現象の中で科学者として信じられるものはどれか,というアンケートに○△×で答えたことがある(石渡,2012).動物の異常行動,前震,鳴動,地盤の隆起と沈降,井戸水や温泉の異常(水量やラドン含有量の変化を含む),電磁気異常,発光現象などには△をつけたが,地震雲だけは×をつけた.地震学者が書いた前兆現象に関する従来の論文や書籍を見ても,地震雲についてはほとんど取り上げられていない。そこで,地震雲についての書籍を読んで勉強してみたので,その感想を述べて会員の皆様の参考に供する.
続きを読む、、、http://www.geosociety.jp/faq/content0421.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】Island Arc 新名称募集中
──────────────────────────────────
新しい雑誌名を募集するに至った経緯は,News (Vol.15, No.11, 2012, p.28)を参照下さい。
(1)新しい雑誌名の条件
1)既に出版されている国内外の学術雑誌名と異なること。
2)地球科学全般をカバーした国際学術雑誌であることがわかること。
*現雑誌名 (Island Arc)の継続が望ましいとお考えの場合には,「Island Arc」を雑誌名として応募いただいて構いません。
(2)応募方法
1)新しい雑誌名の名称と応募者の氏名と連絡先を明記の上,Island Arc 編集事務局(iar-office@geosociety.jp)へメールにて応募下さい。
(3)応募に関するお問い合わせ先:Island Arc 編集事務局(iar-office@geosociety.jp)までお願いします。
応募の締切:2013年1月31日(木)必着
応募方法など詳しくは,
http://www.geosociety.jp/publication/content0005.html#new
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地質学会では,災害救助法適用地域で被災された会員の方々のご窮状をふまえ,以下の措置を取らせていただきます.
「日本地質学会に届出の住居または勤務地が災害救助法適用地域に該当する会員のうち,希望する方」は2013年度(平成25年度)会費を免除することといたします.
2012年度中に,災害により被害にあわれた方のうち,この措置の適用を希望される会員は,(1)会員氏名(2)被害地域(3)被災状況(簡単に)を明記し,学会事務局までお申し出下さい.お申し出の方法は,郵送,FAX,e-mailのいずれでも結構です.
締切は,2013年2月25日(月)までとさせていただきます.
※ 通常の会費払込については,「2013年会費払い込みについて」をご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0108.html
2013年1月4日 日本地質学会会計委員会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】JSEC2012:地球科学関係の発表が入賞しました
──────────────────────────────────
第10回高校生科学技術チャレンジ(JSEC2012)(日本地質学会後援)で,応募総数の208件の中から予備審査・一次審査を通過した30件が最終審査会(12/15-16)に出場し,地球科学関係の発表として,下記の受賞がありました.
・科学技術振興機構賞:大阪府立春日丘高定時制課程
「微小重力をつくる—室内でできる小型微小重力発生装置の製作と改良—」
・審査委員奨励賞:東京都立日比谷高等学校
「地球磁場の生成と磁極の逆転に関する実験的考察—三重水槽を用いたモデル実験
を基にして」
JSECはアメリカで行われるISEFに代表を送っています.上記2件のうち大阪府立春日丘高定時制課程はレポーターとして派遣されます.高校現場で生徒を指導されている先生方,どうぞ,これまでの発表をご参考にさらにご指導いただくことを希望します.
なお,受賞発表の一覧など情報は以下のURLでも見ることができます.
JSEC2012のサイト http://www.asahi.com/shimbun/jsec/
http://www.asahi.com/science/update/1217/TKY201212170458.html
http://www.asahi.com/news/intro/TKY201212240385.html?id1=2&id2=cabcbccf
(矢島道子)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】地質図の在庫一掃セール!— 2013年3月末日まで
──────────────────────────────────
※現在、地質学会に在庫があるものについてのみ、特別販売いたします。
最新の在庫リストはホームページに掲載していますのでご覧いただくか、事務局(電話:03-5823-1150)にお尋ねください。
ご注文はE-mail( main@geosociety.jp)またはFax(03-5823-1156)でお願いいたします。 種類と数に限りがありますので、ご注文は先着順といたします。
リストにないもの、追加等のご注文には応じられませんのでご了承ください。
なお、今回のセール期間は、2013年3月末日までといたします。
特別価格の詳細はご注文の際に地質学会事務局にお問い合わせください。
在庫リストはこちらから。
http://www.geosociety.jp/news/n96.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】支部情報
──────────────────────────────────
■西日本支部
西日本支部平成24年度総会・第163回例会
2月23日(土)
場所:島根大学総合理工学研究科
講演申込締切:2月15日(金)17時
申込について詳しくは,
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
■関東支部
関東支部『地質研究サミット』シリーズ
第1回「房総・三浦地質研究サミット」開催(第2報)
関東地方の地質に対して鋭い斬りこみをかけている各研究グループの中心
メンバーが一堂に会してホットな研究成果を発表するとともに建設的な議論を
行い,関東地方地質研究の新展開を図ります.
主催:日本地質学会関東支部
共催:千葉県立中央博物館,協力:横須賀市自然・人文博物館
期日:平成25 年3 月9 日(土)・10 日(日)
場所:千葉県立中央博物館(千葉市中央区青葉町955−2)
対象:日本地質学会員および一般の方
(参加申込不要;参加費無料;要旨集1,000円予定)
講演申込方法:講演者・講演タイトル・口頭/ ポスターの希望を明記のうえ
事務局(高橋直樹)あてメール(takahashin@chiba-muse.or.jp)で申し込みくださ
い.
講演申込締切:平成25 年1 月20 日(日)
主な日程(講演数によっては若干の時間変更とセッションの日時移動があります)
3月9日(土) 9:30 受付
10:00〜18:00 シンポジウム
セッション1:房総・三浦半島の地質:全体像
セッション2:房総・三浦の地殻大構造
セッション3:葉山—嶺岡帯解明の今日的意義
※シンポジウム終了後に懇親会を予定(博物館内予定)
3月10日(日) 9:30 受付
10:00〜17:00 シンポジウム
セッション4:沿岸—浅海地質調査のすすめ
セッション5:防災・減災最前線としての房総・三浦
ポスター発表コアタイム
総合討論
世話人:山本由弦(JAMSTEC),石川正弘(横国大),亀尾浩司(千葉大),高橋直樹(千葉中央博),柴田健一郎(横須賀博),米澤正弘(県船橋高),伊藤谷生(帝京平成大)
問合せ先 千葉県立中央博物館 高橋直樹(takahashin@chiba-muse.or.jp)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■国際シンポジウム「世界水準の大学間の協力を通したグローバル理工系人材の育成」
1月17日(木)
場所:東京工業大学大岡山キャンパス
http://www.ipo.titech.ac.jp/tierforum/index.html
■JABEEシンポジウム「海外の技術者教育認定の実例」
1月18日(金)14時〜
場所:芝浦工業大学豊洲キャンパス
http://www.jabee.org/OpenHomePage/news.htm
■GSJ第20回シンポジウム
「地質学は火山噴火の推移予測にどう貢献するか」
1月22日(火)13:15〜18:00
会場 秋葉原ダイビルコンベンションホール
http://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo20/index.html
■スプリング・サイエンスキャンプ2013参加者募集
締切:1月22日(火)必着
http://rikai.jst.go.jp/sciencecamp/camp/
■学術フォーラム「自然災害国際ネットワークの構築にむけて:固体地球科学と市民との対話」
日本地質学会 後援
2月1日(金)13:00〜18:00
場所:日本学術会議講堂(東京都港区乃木坂)
コーディネーター:北里 洋(第三部会員)ほか
http://www.scj.go.jp/ja/event/index.html
■J-DESC陸上掘削部会「地学雑誌特集号:陸上掘削科学の新展開」出版記念シンポジウム
2月23日(土) 13〜18時
場所:JAMSTEC東京事務所
http://www.j-desc.org/m3/events/130223_rikujo_sympo.html
■変成岩などシンポジウム
日本地質学会岩石部会 後援
3月15日(金)〜17日(日)
会場:北海道定山渓温泉 ホテル鹿の湯(札幌市南区)
参加費:21,000円
問い合わせ:竹下 徹 torutake@mail.sci.hokudai.ac.jp
■ひょうご恐竜化石国際シンポジウム
日本地質学会ほか 後援
日程:2013年3月16日(土)・17日(日)
会場:兵庫県立人と自然の博物館ほか
http://hitohaku.jp/top/dinosaur_symp.html
■第8回「海洋と地球の学校」
3月19日(火)〜23日(土)
場所:高知県立青少年センター・のいちふれあいセンター・室戸周辺地域(野外巡検)
応募締切:平成25年3月12日(火)必着
http://www.jamstec.go.jp/j/pr/school/008/index.html
■CHIKYU+10 国際ワークショップ
4月21日(日)〜23日(火)
場所:一橋講堂(東京都千代田区一ツ橋)(予定)
http://www.jamstec.go.jp/chikyu+10/
■2013 Western Pacific Sedimentology Meeting
5月13日(月)〜18日(土)
13・14日:研究発表 15〜18日:巡検
台湾地質学会,日本堆積学会 主催
日本地質学会,IAS,SEPMほか 共催
場所:The Longtan Aspire Resort, Taoyuan, northern Taiwan
講演要旨締切:2013年2月28日
http://wpsm.ncu.edu.tw/
■第50回 アイソトープ・放射線研究発表会発表論文の募集
日本地質学会ほか 共催
会期:7月3日(水)〜7月5日(金)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1)
申込締切:2月28日(木)
http://www.jrias.or.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■名古屋大学大学院環境学研究科地球環境科学専攻(地球惑星科学系)公募(3/18締切)
■産総研活断層・地震研究センター特別研究員募集(2/4締切)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
日本で唯一のモホ面露頭の保全について
日本で唯一のモホ面露頭の保全について
日本地質学会会長 石渡 明
福井県大飯郡おおい町の大島半島には夜久野(やくの)オフィオライトが分布しており,県道241号線(赤礁(あかぐり)崎公園線)の大島トンネル北口から約200m北西の浦底(うらぞこ)地内の露頭(図1)には,そのモホ面(モホロビチッチ不連続面,地殻とマントルの境界)が露出しています.これは,道路沿いで容易に観察できるモホ面の露頭としては日本国内で唯一のものであり,かんらん岩・輝石岩・斑れい岩からなる層状構造が露出しています(図2).ここではモホ面の岩石や構造をよく観察することができます. この露頭は,大飯原子力発電所の建設工事に伴う県道設置により1973年に開削され,それ以後約40年間,ほぼそのままの状態を保っていて,その間に多くの地質研究者や学生の研究・教育に利用されてきました.しかし,2012年11月に落石防止用の擁壁設置工事が行われ,当初の計画では吹き付け工法で露頭を覆ってしまうことになっていました.日本地質学会は,この露頭が地質学の研究・教育上重要であると判断し,施工者の福井県小浜土木事務所に対して別紙のような露頭保全に関する要望書を送り,露頭の保全を働きかけました.その結果,この露頭の学術的・教育的重要性を理解していただき,擁壁は設置するものの,露頭は被覆せずに露岩のままとするよう,計画を変更していただくことになりました.既に工事が進行中であったにもかかわらず,迅速に計画の変更をご決定いただき,今後の研究・教育に利用できるよう露頭を保全していただいた福井県小浜土木事務所の皆様に,日本地質学会として心から感謝申し上げます.
現場の露頭は県道の急カーブの外側に当たり(図3),従来は露頭の観察に交通事故の危険がありましたが,このたびのコンクリート擁壁の設置により,高速で通行する車両から観察者が守られることになり,観察者が交通の邪魔になることもなくなりました.擁壁設置により露頭の下部2mほどが隠れてしまいましたが,一方で露頭の上部を安全に観察できるようになり,工事中に露頭を1 m程度削ったことにより新鮮な岩石が露出するようになりました(図2).露頭には擁壁北西端(向かって右側)の土盛りから登ることができます.ただし,この露頭は大島半島中央部を東西に横切る断層に近く,破砕帯が発達していて岩石が崩れやすいため,観察に当たってはヘルメットの着用と落石への注意が必要です.
なお,このオフィオライトのモホ面は,ハッキリした1つの面ではなく,かんらん岩,輝石岩,斑れい岩の層が繰り返しながら,次第にかんらん岩を主体とするマントルから斑れい岩を主体とする地殻下部へ100 m程度の範囲で移り変わるもので(図3),浦底のモホ面露頭はその「モホ漸移(ぜんい)帯」の中で特に黒っぽいかんらん岩と白っぽい斑れい岩の互層がよく発達する部分です(図2).今から約2億8千万年前の古生代の厚い海洋地殻の下の,海底から約20 kmの深さにあったモホ面が,その後の造山運動による隆起と侵食により現在の地表に露出していると考えられており,この露頭ではその証拠となるスピネル・斜長石レールゾライト(かんらん岩)やスピネル変斑れい岩などを観察することができます.詳しくは次の論文をご参照下さい:Ishiwatari, A. (1985) Granulite-facies metacumulates of the Yakuno ophiolite, Japan: evidence for unusually thick oceanic crust. Journal of Petrology, 26, 1-30.
図1.露頭の全景.画面右半部の白くて新しいコンクリート擁壁の裏がモホ面露頭.左端の道路標識に道路名と地名が表示されている.露頭の東側から西向きに撮影.写真の撮影日はすべて2012年12月16日.
図2.露頭に発達するかんらん岩(黒色)と斑れい岩(白色)の互層.コンクリート擁壁の裏側で北西方向を向いて撮影.
図3.露頭の遠景.画面中央の白くて新しいコンクリート擁壁の裏がモホ面露頭.露頭の北側から南向きに撮影.露頭の背後の山は大島超苦鉄質岩体のマントルかんらん岩,露頭より手前側は地殻下部の斑れい岩から構成される.
(2012.12.17)
第4回フォトコン入選作品:最優秀賞
第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品
第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品:最優秀賞「深い海底の流れ」
写真:坂口 有人(神奈川県) 撮影場所:宮崎県日南市大堂津猪崎鼻(四万十帯日南層群)
【撮影者より】
水流の渦によって海底がえぐれます。上流側が大きくへこみ、下流側に浅くなる細長い溝状のパターンができます。縦笛(フルート)のような細長い痕跡(マーク)なのでフルートマークといいます。これはフルートマークのへこみを鋳型(キャスト)として砂層が堆積したものです。砂層は丈夫で保存されやすいので、露頭で観察するにはこのようなフルードキャストが最適です。それにしても、これほど見事なフルートキャストはめったにありません。
【審査委員長講評】
この作品は海岸でローアングルから撮影したものです。普通の人ならば見落としてしまいそうなフルートマークを下から見上げるように撮影したために、陰影がついて構造がはっきりとわかるようになりました。または背景の青空と雲のバランスもよく、爽快感のある写真となっています。(白尾)
【地質的背景】
(準備中)
目次 進む→
geo-Flash No.205 学会各賞推薦ぜひ!【12/25〆切】
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.205 2012/12/18 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2013年度日本地質学会各賞候補者募集中:12/25締切間近!
【2】コラム:日本で唯一のモホ面露頭の保全について
【3】第4回惑星地球フォトコンテスト作品募集中
【4】Island Arc 新名称募集中です
【5】2013年度会費払込のお知らせ
【6】学会オリジナルフィールドノート:名入れ承ります
【7】地質図の在庫一掃セール! 2012年12月18日〜2013年3月末日
【8】2013年連合大会:2013年1月10日受付開始!
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞情報
【12】訃報 森本良平名誉会員 ご逝去
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2013年度日本地質学会各賞候補者募集中:12/25締切
──────────────────────────────────
日本地質学会各賞の自薦,他薦による候補者を募集しています.日本地質学会功労賞・日本地質学会表彰以外は,会員(正会員・名誉会員)であればどなたでも推薦できます.
ご応募いただいた場合には,必ず受取のお返事をお出ししますのでご確認ください.たくさんのご応募をお待ちしております.
下記の賞の候補者を募集中です。たくさんのご応募をお待ちしております。
1.日本地質学会賞
授賞対象:地質学に関する優秀な業績をおさめた本会正会員もしくは名誉会員, またはこれらの会員を代表とするグループ.
2.日本地質学会国際賞
授賞対象:地質学に関する画期的な貢献があり,加えて日本列島周辺域の研究や日本の地質研究者との共同研究などを通じた日本の地質学の発展に関する顕著な功績があった会員及び非会員
3.日本地質学会小澤儀明賞・柵山雅則賞
授賞対象:地質学に関して優れた業績を上げた,2012年9月末日で満37歳以下の会員(研究テーマによって小澤儀明賞・柵山雅則賞のいずれかを授与)
4.日本地質学会研究奨励賞
授賞対象:2010年10月から2012年9月までの過去2年間に地質学雑誌およびIsland Arcに優れた論文を発表した,2012年9月末日で満35才未満の正会員.筆頭著者であれば共著でもよい.
5.日本地質学会論文賞
授賞対象:
1)2009年10月から2012年9月までの過去3年間に「地質学雑誌」発表された優れた論文
2)2009年4号から2012年3号(9月)までの過去3年間に「Island Arc」に発表された筆頭著者が本会会員による優れた論文
6.日本地質学会小藤文次郎賞
授賞対象:2010年10月から2012年9月までの間に重要な発見または独創的な発想を含む論文を発表した会員.
7.日本地質学会功労賞
授賞対象:長年にわたり地質学の発展に貢献のあった本会会員もしくは非会員.またはこれらを代表するグループ.
8.日本地質学会表彰
授賞対象:地質学の教育活動,普及・出版活動,新発見および露頭保全,あるいは新しい機器やシステム等の開発等を通して地質学界に貢献のあった個人,団体および法人.
*2011年から規則が変わり,対象者は会員・非会員を問いません.
応募締切:2012年12月25日(火)必着
選考規則など詳しくは,こちらから(会員によるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】コラム:日本で唯一のモホ面露頭の保全について
──────────────────────────────────
日本地質学会会長 石渡 明
福井県大飯郡おおい町の大島半島には夜久野(やくの)オフィオライトが分布しており,県道241号線(赤礁(あかぐり)崎公園線)の大島トンネル北口から約200m北西の浦底(うらぞこ)地内の露頭(図1)には,そのモホ面(モホロビチッチ不連続面,地殻とマントルの境界)が露出しています.これは,道路沿いで容易に観察できるモホ面の露頭としては日本国内で唯一のものであり,かんらん岩・輝石岩・斑れい岩からなる層状構造が露出しています(図2).ここではモホ面の岩石や構造をよく観察することができます.
、、、、、続きを読む
http://www.geosociety.jp/faq/content0418.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】第4回惑星地球フォトコンテスト作品募集中
──────────────────────────────────
締切:2013年1月31日(木)17:00
応募方法など詳しくは,
http://photo.www.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】Island Arc 新名称募集中です
──────────────────────────────────
応募の締切:2013年1月31日(木)必着
応募方法など詳しくは,
http://www.geosociety.jp/publication/content0005.html#new
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2013年度会費払込のお知らせ
──────────────────────────────────
■2013年度分会費の引き落とし日:12月25日(火)です.
請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下さい.
■自動引き落とし以外の方(お振り込み)
12月中旬頃までに請求書兼郵便振替用紙をお送りいたします.折り返しご送金くださいますようお願いいたします.
■割引会費申請(院生・学部学生):最終締切 2013年3月29日(金)
忘れずにご提出下さい。
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/outline/content0108.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】学会オリジナルフィールドノート:名入れ承ります
──────────────────────────────────
ご好評いただいております,学会オリジナルフィールドノートは,名入れサービスも承ります(有料;プラス500円/冊程度)。卒業記念やイベントでのグッズなど幅広くご利用下さい。ビニールコーティングの表紙は,水や摩擦・衝撃にも強く野外調査に最適です。ぜひご活用ください。
サイズ:12×19cm.中:レインガード紙使用.2mm方眼.
カバー:ハードカバー,ビニールコティング,金箔押し.
色:ラセットブラウン(小豆色)
会員頒価:500円
ご注文は,学会事務局まで<main@geosociety.jp>
見本写真はコチラ
http://www.geosociety.jp/publication/content0040.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】地質図の在庫一掃セール!— 2012年12月18日〜2013年3月末日
──────────────────────────────────
※現在、地質学会に在庫があるものについてのみ、特別販売いたします。
最新の在庫リストはホームページに掲載していますのでご覧いただくか、事務局(電話:03-5823-1150)にお尋ねください。
ご注文はE-mail(main@geosociety.jp)またはFax(03-5823-1156)でお願い
いたします。 種類と数に限りがありますので、ご注文は先着順といたします。
リストにないもの、追加等のご注文には応じられませんのでご了承ください。
なお、今回のセール期間は、2012年12月18日〜2013年3月末日までといたします。
特別価格の詳細はご注文の際に地質学会事務局にお問い合わせください。
在庫リストはこちらから。
http://www.geosociety.jp/news/n96.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】2013年連合大会:2013年1月10日受付開始!
──────────────────────────────────
予稿原稿投稿締切:2月3日(日) 23:59 早期締切*
事前参加登録締切:5月7日(火) 17:00
2013年連合大会:5月19日(日)〜24日(金)
* 早期投稿料金は,締め切りまでにお支払いが完了された場合にのみ適用されます.2月3日(日)締切時刻にお支払い確認ができなかった場合は,自動的に通常投稿料金に変更されますのでご注意下さい.
大会HP: http://www.jpgu.org/meeting/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】支部情報
──────────────────────────────────
■西日本支部
西日本支部平成24年度総会・第163回例会
2月23日(土)
場所:島根大学総合理工学研究科
同日夕刻に懇親会を、前日(2月22日(金))夕刻に幹事会を予定。
問い合わせ先:西日本支部庶務:宮本知治
e-mail:miyamoto@geo.kyushu-u.ac.jp
■関東支部
第1回「房総・三浦地質研究サミット」
3月9日(土)・10日(日)
場所:千葉県立中央博物館(千葉市中央区青葉町955-2)
講演申込締切:平成25年1月20日(日)
http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第13回岩の力学国内シンポジウム(併催:第6回日韓ジョイントシンポジウム)
日本地質学会 協賛
1月9日(水)〜11日(金)
会場:沖縄コンベンションセンター
http://www.rocknet-japan.org/jsrm2013/
■国際シンポジウム「世界水準の大学間の協力を通したグローバル理工系人材の育成」
1月17日(木)
場所:東京工業大学大岡山キャンパス
参加費無料・要申込(日英同時通訳付き)
東京工業大学が実施する文部科学省「大学の世界展開力強化事業」採択プログラムに関係する対象大学の代表者により、それぞれの大学の優れた国際協力の取り組みが紹介される他、国内外の大学関係者による大学間の質の保証を伴う教育の交流、理工系リーダー教育について講演と意見交換が行われます。
http://www.ipo.titech.ac.jp/tierforum/index.html
■JABEEシンポジウム「海外の技術者教育認定の実例」
1月18日(金)14時〜
場所:芝浦工業大学豊洲キャンパス
申込先着順受付、参加費無料
米国ABETの認定を受けているマサチュセッツ工科大学機械工学科教授(予定)、ニューヨーク州立大学機械工学科教授、カルフォル二ア大学機械工学科教授、中国CASTの認定を受けている清華大学教授に加え、最近の海外の審査現場の体験やスタンフォード大学Institute of Designを視察したJABEE関係者をパネリストとしてお呼びし、パネルディスカッションによる海外の実例の紹介をします。
http://www.jabee.org/OpenHomePage/news.htm
■GSJ第20回シンポジウム
「地質学は火山噴火の推移予測にどう貢献するか」
1月22日(火)13:15〜18:00
会場 秋葉原ダイビルコンベンションホール
参加費 無料・要申込(オンライン登録)
http://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo20/index.html
■スプリング・サイエンスキャンプ2013参加者募集
先進的な研究テーマに取り組む大学・民間企業等を会場として、第一線で活躍する研究者・技術者から本格的な講義・実験・実習が受けることができる、高校生のための科学技術体験合宿プログラム。会期は3月下旬の春休み期間中の3〜4日。
応募方法:Webより必要書式を入手し、必要事項を記入の上事務局宛送付。
締切:1月22日(火)必着
http://rikai.jst.go.jp/sciencecamp/camp/
■学術フォーラム「自然災害国際ネットワークの構築にむけて:固体地球科学と市民との対話」
日本地質学会 後援
2月1日(金)13:00〜18:00
場所:日本学術会議講堂(東京都港区乃木坂)
コーディネーター:北里 洋(第三部会員)ほか
http://www.scj.go.jp/ja/event/index.html
■J-DESC陸上掘削部会「地学雑誌特集号:陸上掘削科学の新展開」出版記念シンポジウム
2月23日(土) 13〜18時
場所:JAMSTEC東京事務所
http://www.j-desc.org/m3/events/130223_rikujo_sympo.html
■Project A 2012年 in 伊豆下田
3月5日(火)〜8日(金)
場所:伊豆半島下田(静岡県)
・シンポジウム
「地球史と海底カルデラ:海底火山活動を記録する伊豆半島とジオパーク」
・一般発表(若手研究者・ポスドク・大学院生・学部生の成果報告)
・地質巡検(2日間:伊豆半島全域)
申込締切 :1月10日(木)メールにて受付
申込先(コンビーナ)
清川昌一< kiyokawa@geo.kyushu-u.ac.jp>,伊藤孝 <tito@mx.ibaraki.ac.jp>
http://www.archean.jp
■変成岩などシンポジウム
日本地質学会岩石部会 後援
3月15日(金)〜17日(日)
会場:北海道定山渓温泉 ホテル鹿の湯(札幌市南区)
参加費:21,000円
問い合わせ:竹下 徹<torutake@mail.sci.hokudai.ac.jp>
■CHIKYU+10 国際ワークショップ
4月21日(日)〜23日(火)
場所:一橋講堂(東京都千代田区一ツ橋)(予定)
概要:2013年10月から10年間の計画で始まる新しいIODP (International Ocean Discovery Program)において「ちきゅう」 が実施するべき科学プロジェクトに関する国際的な議論を行います。
http://www.jamstec.go.jp/chikyu+10/
■2013 Western Pacific Sedimentology Meeting
5月13日(月)〜18日(土)
13・14日:研究発表 15〜18日:巡検
主催:台湾地質学会,日本堆積学会
共催:日本地質学会,IAS,SEPMほか
場所:The Longtan Aspire Resort, Taoyuan, northern Taiwan
講演要旨締切:2013年2月28日
参加登録締切:2013年3月15日
http://wpsm.ncu.edu.tw/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■平成24年度北海道職員(学芸職員:北海道開拓記念館)採用選考募集(1/7)
■金沢大学理工研究域自然システム学系地球学コース教員公募(助教)(2/4)
■大阪市立自然史博物館:学芸員(脊椎動物化石担当)募集(1/18)
■国立極地研究所:地圏研究グループ地質学、地球化学分野教員公募(助教)(2/22)
■静岡大学理学部地球科学科教員公募(助教)(2/15)
■新潟大学教育研究院自然科学系環境科学系列教員公募(教授もしくは准教授)(1/28)
■平成25年度産業技術総合研究所ポスドク(イノベーションスクール)の公募(1/20)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】訃報:森本良平名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
日本地質学名誉会員 森本良平氏(元東京大学地震研究所所長)が、平成24年11月19日(月)に老衰のため亡くなりました(享年95歳)。
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
なお、ご葬儀は既に近親者のみで執り行われたとのことです。
会長 石渡 明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【事務局年末年始休業】12/29〜1/3
geo-Flash次号は、1月4日(金)配信予定です。
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
<ニュース誌表紙写真,特に募集中です!お待ちしてます >
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
geo-Flash No.207 謹賀新年 2013
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.207 2013/1/4 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】年頭あいさつ
【2】日本地質学会2013年度各賞候補者募集:〆切延長!(1/10〔木〕17時まで)
【3】巽 好幸会員 米国地球物理連合(AGU)の2012年度ボーエン賞を受賞
【4】その他のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】年頭あいさつ
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会 会長 石渡 明
2013年の年頭に当たり,日本地質学会理事会を代表して会員の皆様にごあいさつを申しあげます.昨年5月に日本地質学会の会長に就任してから半年が経ちました.昨年は一昨年と異なり,5月の新潟県でのトンネル工事現場での天然ガス爆発事故や梅雨前線や台風に伴う豪雨災害は多少あったものの,大きな地震や火山噴火はなく,地学現象による災害は比較的少ない年でした.まず本学会に関連する昨年の動きを振り返りますが,特に最近の3ヶ月間は地質学会にとって様々な事がございました.
続きを読む、、、、
http://www.geosociety.jp/outline/content0109.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】日本地質学会2013年度各賞候補者募集:〆切延長!(1/10〔木〕17時まで)
──────────────────────────────────
昨年12/25で〆切となりました各賞候補者募集ですが、さらに多くのご推薦・ご応募をいただきたく、締め切り日を延長いたしました。
とくに、論文賞や研究奨励賞の推薦をお待ちしております。
是非たくさんの候補者並びに候補論文を、各賞選考委員会(学会事務局 main@geosociety.jp)宛にご推薦下さいますよう、何卒よろしくお願いいたします。
応募〆切延長:2013年1月10日(木)17時まで
選考規則など詳しくは,
http://www.geosociety.jp/members/content0069.html
○会員番号・パスワードによるログインが必要です。
(ログインの方法は http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html)
○「会員のページ」の各賞推薦候補者募集に関する案内から、推薦書式等がダウンロードできます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】巽 好幸会員 米国地球物理連合(AGU)の2012年度ボーエン賞を受賞
──────────────────────────────────
巽 好幸会員(神戸大学教授)がAGU秋季大会(サンフランシスコ)において2012年12月4日に同連合の火山・地球化学・岩石学(VGP)部会からボーエン賞(Bowen Award)を受賞し,「安山岩問題:なぜこの惑星は地球であるのか」と題する記念講演を行った.
(VGP部会ニューズレターによる受賞理由)巽氏はマグマプロセス及び地殻の進化を明らかにするための実験的研究,野外岩石学的研究,それらに関連する理論的モデル研究において,多数の本質的に重要な貢献を行った.彼はホットスポット及び海洋沈み込み帯(特に伊豆・小笠原・マリアナ島弧系)におけるマグマ活動及びくさび型マントルにおけるマグマ移動システムの理解において中心的役割を演じた.
原文(資料)
The Bowen Award lecture. Yoshiyuki Tatsumi: "The andesite problem: Why is this planet to be the Earth?" Convener(s): RSJ Sparks (University of Bristol) and Matthew Kohn (Boise State University), Tuesday December 4, 10:20 AM - 11:20 AM; 103 (Moscone South)
【2012年8月31日のAGU Volcanology, Geochemistry and Petrology Section Newsletter】
- VGP Awards
The Bowen Award for 2012 is given to Dr. Yoshiyuki Tatsumi of Kobe University.
Dr Tatsumi has made numerous fundamental contributions to our knowledge of magmatic processes and their role in understanding the evolution of the Earth's crust through laboratory experiments, field-related petrological studies and associated modeling. He has been central in advancing our knowledge of magmatism in hot-spots and subduction zones (especially the Izu-Bonin-Marianas intraoceanic subduction system), and transport processes in the mantle wedge.
Congratulations to Yoshiyuki. VGP members will be looking forward to his lecture as one of highlights of Fall AGU.
The 2012 Kuno Awardee is Rajdeep Dasgupta. Raj was educated at Jadavpur University and University of Minnesota, completed a postdoctoral fellowship at the Lamont-Doherty Earth Observatory, and is currently a faculty member in the Department of Earth Sciences at Rice University. Raj's greatest contributions lie in the area of the deep carbon cycle, specifically investigations of the partial melting behavior of carbonated eclogite and peridotite. Most recently, he has turned his attention to the problem of how to distinguish basalts generated by melting of different mantle lithologies using major element chemistry.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
【日本学術会議関連情報】
■公開シンポジウム:科学者はフクシマから何を学ぶのか?
-科学と社会の関係の見直し-
1月12日(土)13時00分〜18時00分(12時30分開場)
会場:日本学術会議会議室6階
一般公開。予約不要・参加費は無料。
http://www.scj.go.jp/ja/event/index.html
■公開講演会(第3回国際北極研究シンポジウム)「今、北極がアツい!」
1月14日(月・祝)14:00〜16:15
会場:日本科学未来館7階みらいCANホール
http://www.jcar.org/isar-3/lecture.html
■日本学術会議主催国際会議:持続可能な社会のための科学と技術に関する国際会議「災害復興とリスク対応のための知"Wisdom for Recovery from Disasters and Risk Control"」
1月17日(木)、18日(金)
場所 日本学術会議 講堂
先着200名/各日(Webによる事前登録制)
入場無料・日英同時通訳あり
http://www.scj.go.jp/ja/int/kaisai/jizoku2012/ja/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
地震雲についての雑感
地震雲についての雑感
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
1.はじめに
半年前,あるニュース社からの取材を受け,世間でよく言われる地震の前兆現象の中で科学者として信じられるものはどれか,というアンケートに○△×で答えたことがある(石渡,2012).動物の異常行動,前震,鳴動,地盤の隆起と沈降,井戸水や温泉の異常(水量やラドン含有量の変化を含む),電磁気異常,発光現象などには△をつけたが,地震雲だけは×をつけた.地震学者が書いた前兆現象に関する従来の論文や書籍を見ても,地震雲についてはほとんど取り上げられていない。そこで,地震雲についての書籍を読んで勉強してみたので,その感想を述べて会員の皆様の参考に供する.
2.雲とは
まず雲についての教科書的知識を復習する.雲は大気中で水蒸気が凝結して水滴や氷晶になり,それらの集団がある大きさと形をもつ物体として大気中に浮いているもので,地表からの高さと形状によって分類されている.世界気象機関が制定した「国際雲級図帳」によると,層状に広がる雲は,まず高さによって上層雲(温帯地方での高さ:5〜13 km),中層雲(2〜7 km),下層雲(0〜2 km)に区分され,次に形状によって上層雲は巻雲(すじ雲Ci),巻積雲(うろこ雲Cc),巻層雲(うす雲Cs)(「巻」は「絹」とも記す),中層雲は高積雲(ひつじ雲Ac),高層雲(おぼろ雲As),乱層雲(雨雲Ns),下層雲は層積雲(むら雲Sc)と層雲(きり雲St)に区分される.そして中・下層から上層へ鉛直方向に発達する積雲(わた雲Cu)と積乱雲(入道雲Cb)を加え,雲は10種類に分類されている.
3.地震雲のはじまり
東洋では昔から雲の形や動き,風の向きや強さ,太陽や月の見え方などを観察して天気を予知する「観天望気」が行われていた.これは長年の経験の蓄積に基づくもので,「夕焼けなら翌日は晴」,「月に笠がかかると翌日は雨」といった類である.これらは気象学的な説明が可能であり,かなりの確率で当たる.一方,「はじめに」で述べた前兆的「宏観異常」の観察による大地震の予知も中国では昔から行われており,1975年の海城地震はこの観察によって予知され,住民を避難させて人的被害をかなり軽減したとされる(ただし翌年の唐山地震は直前予知に失敗して大災害になった).そして日本では,戦時中に鍵田忠三郎(かぎたちゅうざぶろう)が雲と地震の関係に気づき,福井地震(1948年)を2日前に予知して確信した.彼は1967〜81年に奈良市長を務め,その間に公衆の面前で何回も地震を予知して的中させ,観天望気による地震予知の経験を著述して1980年に出版した(九州大学の真鍋大覚が監修).つまり「地震雲」という言葉は鍵田が創始し,彼の出世とともに日本社会に広まった.これに対し,気象庁は「地震雲という雲は存在しない」,「大気の現象である雲と大地の現象である地震は全く関係がない」,「有感地震は毎日必ず日本のどこかで起きており,地震雲が出たと言えば必ず当たる」のような見解を1983年に新聞紙上で発表してその科学的根拠を否定した(鍵田, 1983).しかし,鍵田の追随者は今も多い(上出,2005;白木,2007など).
地震雲は震源地の上だけに出るのではなく,例えば奈良の上に出る雲が,中国唐山や北海道沖の地震をも知らせる.鍵田(1983)は,彼が「恐ろしい」と感じる雲が出た数日後に,必ずどこかで大地震があったというニュースを新聞,ラジオ,テレビが報じるようになったために,雲と地震の関係がわかったのであり,通信が未発達の時代には地震雲を認識できなかったのだという.彼は数百回の地震を予知したと言い,予知を公表して的中させた8例について経緯を記述している.また彼以外の地震予知成功例として1973年のグアテマラと1975年の海城地震を挙げ,どちらも前日に真っ赤な夕焼けが出たと指摘している.なお,鍵田はその後自民党の衆議院議員を1期務め、阪神大震災の前年に逝去した.
4.地震雲のタイプ
「晴れた空に一筋の太い帯状の雲」(図1)というのが最も出現数の多い地震雲のタイプであり(上出,2005によると地震雲全体の7〜8割),放射型の帯状雲の場合はその延長方向で,波紋型(同心円状)の帯状雲の場合は直角方向で,2日後(鍵田,1983)または数日後〜10日後(上出)に地震が起きるという.その他に上出は断層型(層状の雲と青空の境界が直線),肋骨状,放射状,弓状,さや豆状,波紋型,稲穂型など,鍵田は石垣状,レンズ状,点状,綿状の白旗雲,縄状の低い雲,白蛇状,断層状(層状の雲が直線的に割れる)があるとし,「足のない入道雲」が関東大震災の数時間前に出たと言う.また,異常に赤い朝焼けや夕焼け,赤い月や太陽・月の周囲の光柱なども地震の前兆とされる.しかし上出は,「間違えやすい雲も多く,実際に雲を眺めて『これは,普通の雲』『これは,地震雲』と区別することも容易ではありません」,「この判断ができるようになるには時間がかかります.私の場合は約十余年かかりました」と述べており,「これであなたも大地震を予知できる」という彼の本のタイトルとは違う.「地震を止める雲」というのもあり,これが地震雲と一緒に出ると地震は起きないという.最も有名な地震雲は,1995年1月17日の阪神大震災の8日前〜前日にかけて何回か神戸付近の上空に出現した竜巻型(らせん状)の雲であるが(弘原海, 1998),上出は竜巻型を地震雲の仲間に入れず,飛行機雲としている.また,衛星画像から「さざなみ雲」を探して,その分布範囲の中心が震源位置で,面積がマグニチュードを示すとして地震予報を行っている人もいるが(森谷,2009),これは地震雲から震源地を推定する「鍵真(がんじん)の法則」(鍵田, 1983)に似ている.
太い帯状の雲にしても,なぜ,どのように地震と関連して形成されるのかは説明されておらず,結局のところ地震雲かどうかを決めるのは観察者の直感であり,雲の形,大きさ,高さなどの客観的かつ厳密な基準は示されていない.地震雲から地震が起こる時期、場所、規模を推定するやり方についても同様である.素人は本の写真と見比べて判断するしかないが,本に載っている地震雲と同じような雲(図1)が空に出ていても,騒がない方がよい.心配なら訓練のつもりで数日間,自分一身の安全に配慮した行動をとればよい.1993年1月15日の釧路沖地震の一週間後に「地震雲が出た.また大地震が来る」というデマが広がり,多くの釧路市民が不安におびえた事例がある(毎日新聞1993年5月3日東京版).実際には,釧路での次の大地震は翌年10月4日の北海道東方沖地震だった.また,空振りの地震予告が広まって大きな混乱と経済的損失をもたらした事例としては1978年のメキシコや1981年のペルーの騒動がある(森谷,2009).一方で2009年のイタリア・ラクイラ群発地震では,安全宣言が出た数日後に大地震が起こって300人以上が死亡し,安全宣言に関与した地震学者らが刑事裁判で有罪判決を受けた(本学会は2012年11月2日にこれを憂慮する声明を発表).地震が「起きる」と言っても「起きない」と言っても非常に危うい.
5.雲と放射線・電磁気など
雲は放射線の通過や人工的な微粒子の付加によっても生じる.放射線の飛跡を示す「ウィルソンの霧箱」の実験は,放射線の通路に沿って水滴の列(雲)ができることを示している.飛行機雲は,飛行機のエンジンから排出された微粒子の周囲に氷の結晶ができ,それがしばらくの時間,飛行機の飛跡に残ることを示している.人工降雨の実験も,上空に雨滴の核となる微細な結晶を撒いたり,地表で古タイヤを燃やしたりする.渋滞が激しい東京の環状8号線沿いにできる「環八雲」はある種の地震雲と似ている.ただし,これらは空気中の水蒸気量が飽和していることが条件で,飛行機雲が出る時に地震雲が出やすい(上出,2005; p. 108)という経験則はうなずける.地震の震源付近から何らかの放射性物質や微粒子が放出されるのであれば,その上の水蒸気に飽和した大気に特徴的な雲ができるのは,あり得ることである.実際いくつかの地震の前に,それらの震源の近くで,地下からのラドン(気体の放射性元素)の放出が観測されている(例えば阪神大震災の前;安岡ほか, 1996; 脇田, 1996; 佐伯ほか, 1995).ラドンは岩石中のトリウムやウランの放射壊変により発生するもので,平常時でも地下室の空気中には比較的多く含まれ,断層,地すべり,地割れなどが発生すると地表へ放出される(人為的な掘削工事でも同様).因みに人間の自然被曝の半分程度は,ラドンを呼吸することによる内部被曝である.ラドン222の半減期は3.8日であり,これが震源付近から放出され,上昇気流に乗って上空に達すると,水蒸気に飽和した大気中に帯状の雲ができる可能性はあるが,実証されていない.ラドンに起因する大気イオン(帯電エアロゾル)濃度を各地で測定して地震予測をめざす全国組織もある(弘原海, 1998).この他,震源域から発生する電磁波や流体力学的な重力波(表面波)で地震雲が形成されるとする考えもある(週刊現代特別取材班, 2005; 森谷, 2009).一方,オーストラリア北東部に特徴的なMorning Gloryという雲は白蛇状〜波紋型地震雲に似るが,この地域には地震は起きない.奇妙な雲を地震と直結せず、まずは気象学的によく考える必要がある.
最近,M9クラスの巨大地震発生の40〜50分前より,GPS衛星(高度約2万km)から震源地域周辺のGPSステーションに届く電波が遅れることがわかり,高層大気の電離層に電子数の増加などの地震前兆現象が現れる可能性が指摘されている(日置, 2011; 2012).ただし,M8クラス以下の地震では,この前兆現象は現れないという.1990年代以来,電離層またはより下層の大気圏で反射されて遠方から届く放送電波を検知して地震を予測する研究が行われてきた(串田,2012; 早川,2011; 森谷,2009など).電離層(高度70 km以上,最も電子密度が高いのは200〜300 km上空)は雲ができる高さ(10 km程度以下)よりはるか上にあるが,大気が電離しているので地表や地下の電磁気的な変化に敏感に反応するのかもしれない.この方法の研究者は,既に地震が「予報」できる段階になっていると言うが(震源が浅いM6以上の直下型地震は的中率9割以上:早川, 2011)、東日本大震災などの海溝型地震や深発地震の場合は予報が難しく,大震災以後は福島の電波施設の被害と「日本の地下がぐちゃぐちゃに荒れて」いるため的中率6〜7割が限度という(早川,2011).これは地電流によるギリシャ式地震予知法と同程度の的中率である(石渡, 2010).電波を使う方法も,地震の前に震源上空の高層大気に出る「電子の地震雲」を受信機で捉えようとする観天望気の一種であり,太陽活動など他の要因をよく考慮する必要がある.
6.まとめ
地震雲という語は,戦後の高度成長期に奈良市長を14年務めた鍵田忠三郎によって創始されたが,その思想は古代から東洋に続く観天望気の経験論の延長上にある.鍵田の思想は,「地震は地球の病気,大気と大地は一体,自然に帰る,衆生済度」などのキーワードで捉えることができる.鍵田(1983)は,雲で地震を予知することと,大都会の生活を捨てて「自らの生活を正し自然生活に戻ること」が地震災害を防ぐ唯一の方法だと述べている(p. 150).しかしこれは,「地震雲」が認識可能になったのは通信の発達(都市文明の恩恵)によるという,彼が同じ本の中で述べていることと矛盾するように思う.また、彼は市長在職中に多額の税金を滞納し、この負の遺産は後に市長になった彼の二男を辞職に追い込んだというから(毎日新聞2004年12月25日奈良版),彼が「自らの生活を正し」たかどうかも疑問である。私は,漢方的な観天望気の重要性・有用性を認めており,個人の科学研究の出発点は,思い付き,思い込み,思い違いであっても構わないと考えている.地震雲の研究は日本で生まれた「草の根」的な学問であり,誰かが突破口をみつければ客観的な科学になって世界に貢献する可能性があるが,まだその域に達していないように思う.地震雲は,全天曇り,雨や雪,雲のない快晴,夜間の場合は観測が困難だが,高層大気の「電子の雲」の電波観測は天候や昼夜によらず可能でデータの客観性が高く,公的な地震予報につながる可能性がある.しかし,地震の前にそのような電子の雲ができるメカニズムは地震雲と同様に不明である.地質学では,大気の変化と地質現象(特に火山活動や風化過程)との関連を昔から研究してきたが,地下深部での岩石の破壊・変形現象も地質学の守備範囲であり,今後はその電磁気学的,放射化学的な側面も研究すべきだと思う.
7.おわりに
私は最近,米国出張中にサンフランシスコ市内からサンアンドレアス断層沿いに出現した「地震雲」を目撃したが(図1;周囲の飛行機雲よりずっと太かった),サンフランシスコ周辺でその後10日以内に大地震が起きたという話は幸いにして聞かない.半年前のアンケートで地震雲に×をつけたのは,今のところ間違っていなかったと思っている.珍しい雲についてご教示いただいた池田保夫・平田大二両会員に感謝する.
図1.2012年12月7日午前8時45分(日本時間8日午前1時45分)にサンフランシスコ上空に出た,いわゆる「地震雲」によく似た雲.南を向いて石渡が撮影.
【引用文献】
早川正士 (2011) 地震は予知できる! 3.11東日本大震災の前兆もキャッチしていた! KKベストセラーズ.
日置幸介 (2011) 超高層大気は巨大地震の発生を知っていたか? 科学, 81, 1063-1064.
日置幸介 (2012) 巨大地震の直前に変化する電離圏電子数.なゐふる, no. 92.
石渡 明 (2010) ギリシャ式地震予知に関するEOS誌上での最近の討論について.地質学会News, 13(9), 12-13(geo-Flash, no. 107, 記事2).
石渡 明 (2012) クジラ,雲,体感…地震の前触れとして信じていい現象とは? マイナビニュース, http://news.mynavi.jp/c_career/level1/yoko/2012/07/post_1944.html
鍵田忠三郎 (1983) 決定版 これが地震雲だ 雲はあなたを大地震から救ってくれる.株式会社NGS(初出は1980年).
上出孝之 (2005) わかりやすい地震雲の本 これであなたも大地震を予知できる. 北國新聞社(初出は2003年).
串田嘉男 (2012) 地震予報.PHP新書.
森谷武男 (2009) 地震予報のできる時代へ.青灯社. http://nanako.sci.hokudai.ac.jp/~moriya/fm.htmも参照.
佐伯雄司・五十嵐丈二・佐野有司・高畑直人・済川 要・田阪茂樹・佐々木嘉三・高橋 誠 (1995) 1995年兵庫県南部地震前の西宮における地下水中ラドン濃度の変動.月刊地球,号外13, 194-198.
白木妙子 (2007) 地震と雲 地震の前にあらわれる変わった形の雲の写真集.ソラと星出版.
週刊現代特別取材班編 (2005) 緊急出版 巨大地震と地震雲.講談社.
弘原海 清 (1998) 大地震の前兆現象 空が、大地が、動物が異常を発信する.KAWADE夢新書.
脇田 宏 (1996) ラドン観測と地震予知.保健物理,31, 215-222.
安岡由美・志野木正樹 (1996) ガスモニタが捕らえた兵庫県南部地震の前兆.アイソトープニュース, 1996(4), 74-76.
(2012.12.27)
地質学者に答えてもらおう
地質学者に答えてもらおう
地球科学に関する疑問質問はありませんか? もしも自分で調べてみてもどうしてもわからない,そんな時は専門家に聞いてみましょう.問い合わせフォームの注意事項をお読みのうえお問い合わせ下さい.注意:メールアドレスの入力・記載に誤りがあり,回答を返信できないケースがあります.ご注意ください.
▶▶▶ 「地質学者に答えてもらおう」の問い合わせフォームへ
〜 これまでの質問 〜 それぞれの質問をクリックすると回答へジャンプします。
Q:同じ化学組成の岩石でも、見た目が違うという現象が起こるのはなぜですか?
Q:全球凍結と、氷河時代という言葉の違いがわかりません。
Q:磁場逆転について教えてください。
Q:三宅島に行きました。そこで初めてローム層が火山由来の層ではなく、火山活動休止期の地層であると知りました。しかし、関東ローム層は富士山や箱根の火山灰が積もってできた火山由来の層です。ローム層というのはやはり火山由来の層ということになりませんか?
Q:マントル対流について、マントル物質は海嶺まで上昇していくとき、当然それぞれの自転半径が増加することになるので、運動量保存というのか、アイススケートの選手が回転する際に腕を縮めると回転速度が上がりますが、同様にマントル物質は上昇により回転速度が落ちることはないのでしょうか。
Q:国内でろ過砂に適した原材料となる砂を探しています。どのあたりになるでしょうか。
Q:富士山の山梨側に青木ヶ原樹海があります。何故あのような、樹海が出来たのか、他とは違う土に含まれている成分や、地中の構造などはあるのでしょうか。
Q:ギアナ高地は昔地軸の位置にあったため、垂直に切り立ったテーブルマウンテンができたという事ですが、そこから考えるに大昔の地表の位置は今よりも高かったということになるのでしょうか。 もし地表の位置が高かったのであれば、なぜ低くなったのでしょうか?
Q:沢歩きをして露頭写真等を撮っていたいるのですが,写真の緯度経度が数十mズレることがよくあります.(中略)GPS搭載カメラでフィールド写真を撮っている方はどんな高精度GPS搭載カメラを使用しているか教えて下さい.
Q:2021/5/9のオンライン講座を拝聴していまして,以前地質標本館で実施されていた「祝チバニアン誕生!拡大版―もっと知りたい千葉時代―」を見に行った際に思ったことで,byk火山灰は柳川から小草畑の間では田淵でしか見られないのでしょうか.また,柳川より西側では見られないのでしょうか.
Q:化石や鉱物の層準分布、採取地点、露頭の写真が記載されていますが、これらは所有者にどのような許可を得ているのでしょうか。
Q:崖錐、岩屑、崩積土の違い、見分け方を教えてください
Q:神社仏閣の石碑など文化財に使用された日本花崗岩産地の科学的同定は可能ですか?
Q: 愛知県北設楽郡東栄町は、木曽山脈の南端に位置している、町ということもあり、以前より「木曽山系」と思っていましたが、「赤石山系ではないか?」という意見がありました。どちらなのかわかりますか?
Q:地球の地下を掘り進めてもたいした距離まで進めないという話を聞きました。マントルまで行く方法について...
Q:地殻は上部地殻と下部地殻に分類されていますが、 西南日本弧における古生代〜ジュラ紀の付加体は上部地殻に分類されるのですか?
Q:地質・地球活動分野の基本的・教科書的な参考図書、事典的な本などを教えてください。
Q:《電磁波が雲を発生させる》という事は実証されているという記述をいくつか見ました。 このことについての真偽が知りたいです
Q:山梨県の三ツ峠山、母の白滝の岩について
Q:千葉県市原市田淵の地球磁場逆転地層について:正式に認定された場合、認定決定からゴールデンスパイクが打たれるまでにはどれくらいの期間かかるのでしょうか?
Q:最近泉質が大きく変わり、湯の色も透明から濁ったものに変わってきた温泉があるので、その理由を知りたい
Q:千葉県市原市田淵の地球磁場逆転地層について
Q:栃木の大谷石、千葉の房州石、静岡の伊豆石等、本来の日本海側産以外の中新世海底噴出起源の緑色変質した火山岩類に対して、「グリーンタフ」の呼称を用いても学術上の問題はないのでしょうか?
Q:海底が隆起してできたのは千葉セクションだけなのでしょうか?
Q:山形県に広河原温泉という間欠泉があり、湯船の真ん中から、間欠泉が絶え間なく吹き上げています。この間欠泉の地下構造と、どのような作用により、間欠泉が噴き出すのでしょうか。
Q:黒曜石は流紋岩と同様の成分なのになぜ黒いのでしょうか
Q:何故台湾島ではフィリピン海プレートがユーラシアプレートの上に乗り上げるのですか?
Q:鉄丸石を拾いました.どのようにしてこの丸いものが出来たのでしょうか。
Q:千葉県田淵付近にある地層のうち、白尾火山灰層(Byk-E)に含まれているSiO2成分は、42.84%だそうです。...色が黒いものだと予想していたのですが、先日修学旅行で行ったところ、彩度が高く、驚きました。なぜですか?
Q:堆積岩(れき・砂・泥など)からできた地層からはどんな化石でも見つかることがあるのでしょうか。
Q:新(または修正)モース硬度は何時誰が決めたものですか?
Q:黒っぽい溶岩石の比重はどの程度でしょうか。
Q:日本のごく一般的な地質で、上部に積載加重が無い場合において、短期的に見て、垂直に掘削した場合、何mの高さまで自立してくれるのでしょうか。 (富山県 シロハカセ さん)
Q:花崗岩を体内に摂取してしまった場合の内部被ばくの危険性はどの程度ありますか。
Q:含礫泥岩の扱い方について質問します。
Q:大陸棚では石灰岩ができるほどの大量の生物起源の堆積物があるのでしょうか。 (茨城県 inakamon さん)
Q:東京都あきる野市にある、弁天山の地質と弁天洞窟の岩質を教えてください (東京都 ジオダイスケ さん)
Q:六甲山系の谷を歩いていると岩肌が赤く染まっている箇所をよく見かけます。...熱水貫入で赤いのでしょうか? (鳥取県 太朗 さん)
Q:花こう岩は、水がある地球だけに存在するもので、ほかの惑星には花こう岩はない」という話を聞きます。 それなら、玄武岩質マグマから分化作用で生成する火山岩の安山岩や流紋岩、また、深成岩の斑れい岩や閃緑岩なども地球上には存在しないということになるのでしょうか。 (茨城県 inakamon さん)
Q:那須塩原の遊歩道、回顧コースで変わった岩を見つけました。岩に生えている苔が木の年輪の様になっています。この様な岩は自然にできるものなのでしょうか。
Q:高速の北関東道で佐野方面から太田方面へ向かう足利の五十部トンネルを抜けて渡良瀬川までの間の左側に山を削った場所があるのですが、その場所に出べそのように地層の岩体があります
Q:昔の地球の磁場が岩石に記録されているといいますが、カセットテープのように消えてしまわないのはなぜですか? (ja7tdo さん)
Q:地球の外核は液体だそうですが、生卵のように不安定な回転にならないのはなぜでしょうか?
Q:葉山町の「森戸川の上流部」の沢床が赤褐色の岩盤なのですが、この岩(石)は何の石でしょうか?(神奈川県 吉田さん)
Q:京都周辺の砥石について(大阪府 KON-Chanさん)
Q: 海洋プレートは、海嶺で上部マントルのかんらん岩を融かした玄武岩からなりますが、沈み込み帯でできる大陸プレートも花崗岩の下には玄武岩が存在するのでしょうか。(茨城県 inakamon さん)
Q:リップルマークとクロスラミナの違いを教えてください。(埼玉県 かべちゃさん)
Q: 伊豆半島ではプレートの移動や衝突の証拠を見ることができるが、これとは逆にプレートが開く場所を見られるジオパークがある国は何処でしょうか。(静岡県 ランチチさん)
Q:日本シームレス地質図を見ての疑問ですが、足利市を中心とし、渡良瀬川左岸、北東側に同心円上に地層が分布している様に見られるのですが、他を探しても同じ様な所は見当たりませんでした。長い時間をかけて約180度曲げられたということでしょうか?(栃木県 gagiさん)
Q:日本列島が沈没する可能性ってどのくらいですか? (匿名希望)
Q:どうして火山灰を調べると,どこの火山のものかわかるのですか? (富山県 匿名希望)
Q:(東京都多摩市)大栗川の二枚貝の化石について、この地質は何時頃のもので、何故そこに貝の化石があるのでしょうか?(東京都 りんごさん)
Q:ジュール・ベルヌの『海底二万マイル』にでてくる火山について教えて下さい(東京都 さゆみんさん)
Q:花崗岩(御影石)について 、私は彫刻家で彫刻の素材として、御影石を使用しているのですが、どれぐらいの期間で風化がはじまるのでしょうか。素材の限界を知りたいのです。(東京都 彫刻家)
Q:造陸運動とはどのようなもですか?(兵庫県 Kさん)
Q:千葉県市原市田淵の白尾火山灰層は更新世前期、中期境界の国際模式地として認定されたのでしょうか?ゴールデンスパイクが打たれるのか話題になっていたようですが、その後のことがわかりません。教えて頂けますでしょうか。(千葉県 どんぐりさん)*現状について追記しました(2016年10月11日)
Q:原発の活断層問題に関心があります。テフラによる地層の年代同定について、地質学の専門家が、以下のようなコメントをされていますが、
「例えば1mのローム層を10cm毎に連続サンプリングし、ある層準で3,000 個数えて斑晶鉱物が100 個有り、その上下で30 個、さらにその上下で10 個ということであれば説得力があると思います。しかし、1mのローム層のうち、ある層準だけに3,000 個数えて斑晶鉱物が1 個未満でその前後で検出できなければ、信頼性はかなり低いと言わざるを得ないと思います。」
ここで、「3000個数えて」と言っていますが、3000個とは何をどのようにとると考えれば良いのでしょうか?すなわち、地層には火山灰のみでなく、いろいろなものが堆積して形成されると思うのですが、それらを含めて定義しているのか、あるいは例えばある大きさのテフラ鉱物のみをスクリーニングしたものを取るのか等について教えてください。
また、なぜ3000個に対して数十個以上の斑晶鉱物がなければ(特定?)テフラとして同定する上で信頼性が低いと考えておられるのでしょうか?
また、専門家のコメントでは、
・テフラの降灰時期にピークがあるはず
・何十cmも積るはずである
とも読めるのですが、どう考えればよいのでしょうか?
(千葉県 片山 昇さん)
Q:尼崎市は武庫川と猪名川に囲まれた沖積層平野ですが、通常、地形をご説明するとき「大阪湾に下る三角州上に立地」と述べています。先日『「三角州」とはあくまで広辞苑にもあるように「ほぼ三角形」の形状の土地を指すのであって、尼崎市の地形は「三角州」ではないのではないか』、というご指摘をいただきました。そこでご質問なのですが、地質学的に言って、尼崎市の地形は「三角州」に分類されるのでしょうか。(兵庫県 あまっこさん)
Q:花崗岩についてお尋ねします。庭に花崗岩の砂利が敷いてあります。原発事故の影響が気になって最近エアカウンターという線量計を買ったのですが、それで計測すると砂利の上の線量が0.08〜0.1くらい上がってしまいます。花崗岩にウランが含まれているというのは理解できたのですが、それがラドン・ポロニウムを放出し、呼吸によって内部被ばくするというのをきき、とても不安です。岩盤でなく砂利でもポロニウム等を放出しているのでしょうか。それはどれくらいの量なのでしょうか。
(愛知県 あかつきさん)
Q:滋賀県蒲生郡日野町鍵掛のシャクナゲを見に行きましたが、遊歩道沿いの岩肌が層状になっていてとても不思議でした。あたりには石灰岩地域に生育するイワカガミがたくさんありました。この岩はどういうものなのか教えていただけたら幸いです。(奈良県 ちょびさん)
Q:原子力発電所の活断層問題に関心があります。活断層が動いた場合、その近傍の地層が引きずられて動く(副断層)ことは素人でも想像がつくのですが、過去の活断層による地震の際、活断層からどの程度の距離では、どの程度副断層(岩盤まで届く)が出来、どの程度動いたことがあるのか、データはとられているのでしょうか?もし、整理されたデータがあれば、リンク先を教えてください。整理されたデータがなければ、例をいくつか教えてもらえないでしょうか?(ちなみに、原子力規制委員会では、活断層から1Km以内は何が起こるかわからないと言った議論が行われていました。)
(千葉県 片山 昇さん)
Q:地質学の以下の4つの法則は、地質分野の中では一般的にオーソライズされているのでしょうか?
[1]地層累重の法則 [2]堆積初期の地層水平の法則 [3]堆積初期の地層連続の法則 [4]地層切断の法則
[1]は、私の周囲の大部分の方は認知しているのですが、[2]〜[4]はあまり聞いたことがないということでして、地質学の4つの法則としてオーソライズされているのか教えて頂けないでしょうか?
(埼玉県 匿名希望さん)
Q:北海道の支笏火山のことですが、支笏火山の大噴火の時期について3万2千年前とする表記と4万年前とする表記の二つあり、身近では、2004〜2008年頃のものには3〜4万年前、2009年以降には4万年前が多いようです。統一されていますか?また、2009年の「第四紀下限の変更」と何か関係がありますか?
(北海道 EDOさん)
Q:氷河期に関して。氷河期と氷河期の間を間氷期と表現する記事と、温暖期と表現する記事を見ます。1)どちらが正しいのでしょうか?またその根拠は? 2)氷河期と間氷期の区別は? 氷河期が終わった、あるいは氷河期に入ったという判断は何を持ってそのようにしているのでしょうか?酸素同位体比は我々が日常使う温度表記ではなく相対温度になってしまいよく判らないのです。
(匿名希望さん)
Q:過去の地球を知ることで私達社会にどのような利益をもたらすのですか?
(匿名希望さん)
Q: 地層は、様々なものが堆積して出来るということですが、どうしても分からない点があります。上の図の、①が初めの状態だとしますと、それぞれ長い年月の間に各地点の土などが風雨によって運ばれ②のように別の場所へ移動します。1ヶ所だけみていますと、確かに積っていきそうですが、地球上満遍なくこれが起きると考えると一旦積った土などもまたどこかへ移動していかざるを得ず、堆積していかないように思えるのです。別の例えをしますと、山の土が削れてその周辺地帯に堆積するのは分かるのですが、地球全体満遍なく起るのは、山のない平野もありますし、おかしい。その土はどこから来たのか?部分的なら分かりますが、地球上満遍なく起る点が分からないのです。
(千葉県 H.M.さん)※質問内の"図"は回答ページにて表示してあります。
地質学者に答えてもらおう:回答
地質学者に答えてもらおう 回答一覧
〜 これまでの質問と回答 〜
Q: 同じ化学組成の岩石でも、見た目が違うという現象が起こるのはなぜですか?(愛知県:匿名希望)
岩石は鉱物などの集合からなり、固結したものです。 なので、全体の化学組成が同じでも、含まれる鉱物の種類や量比が異なると違うもの(異なる岩石名がつけられる)となります。 例えば、炭素(C)からなる岩石でも、Cがダイヤモンドなら、ダイヤモンド岩となりますし、グラファイト(石墨)からなるならばグラファイト岩となり、当然見かけも大きく異なります。 さらに、それらの鉱物がどのように含まれるのかによっても、違う岩石となります。 鉱物が小さい場合と大きな場合でも見かけが大きく異なります(岩石名が異なります)。 例えば、花崗岩と流紋岩やハンレイ岩と玄武岩 の関係のように全体の岩石の化学組成や含まれる鉱物はおおよそ同じでも粒度が異なると見かけも大きく異なります(岩石名も異なります)。 さらに、鉱物の配置の仕方も影響します。細長い鉱物や板状の鉱物が配向して分布すると、片岩や片麻岩と呼ばれ、層状や縞状の見かけになります。 例えば、花崗岩と花崗岩質片麻岩(正片麻岩と呼ばれる)の関係。両者は同じ鉱物の種類や量比からなりますが、後者は鉱物の分布が偏っていて、無色の鉱物と有色の鉱物がそれぞれ多いところが縞状に分布するため、縞状に見かけになります。
Q:全球凍結と、氷河時代という言葉の違いがわかりません。ある参考書には「極に氷床が形成されている時期が氷河時代」とあり、それに倣うと全球凍結は数ある氷河時代の一つだったと考えられます。その認識でいいのでしょうか?全球凍結という特別な呼び名があるのならば、数ある氷河時代の中でも、全球凍結が起きた氷河時代が最も地球が寒かったのでしょうか。(福岡県:匿名希望)
氷河時代は、年間を通じて氷床が存在する時代(一般には極地・陸地に)を指します。そのため、現在も氷河時代となります。 一方全球凍結は、その言葉の通り、海洋も含めて地球全体が氷に覆われたイベントを指します。 そのため、全球凍結は氷河時代のさらに極端なものという認識でよろしいかと思います。 ただし、全球凍結は氷河時代の延長というわけではなく、その間には大きなギャップがあります(その中間は不安定で起こらないとされています)。
Q:磁場逆転について教えてください。 地磁気が逆転するまでの時間のオーダーはわかりますか?反転する際の挙動(地軸成分のみが、だんだん小さくなって、ゼロになり逆方向になるのか、磁場の大きさが一定で、回転して逆転するのか)はどのようなものですか?また,磁場反転の挙動は、ダイナモ理論で予測できるのしょうか?(神奈川県:匿名希望)
地磁気は、地球の中心に、地軸と平行な方向に置いた双極子(N極とS極が対になった棒磁石と同じ)によって出来る磁場とほぼ同じ形になっています。地磁気逆転は、その棒磁石の大きさが徐々に小さくなり(磁場が弱くなっていく)、もとの1割程度の大きさになった所で、N極とS極が急速に入れ替わる(棒磁石が反転する)ことで起こるように見えます。その後、棒磁石は徐々に大きくなり、地磁気の強さも元にもどります。地磁気強度が弱くなって逆転し、強度が元にもどるまで1万年程度かかっているようです。 もちろん、実際に地球の中心に棒磁石が埋まっているわけではなく、地球外核の流体鉄が流れることで電流が流れ、磁場が発生しています。これを地磁気ダイナモと呼び、スパコンによるシミュレーションでは、地磁気逆転が再現されています。
Q:学校の巡検で三宅島に行きました。そこで初めてローム層が火山由来の層ではなく、火山活動休止期の地層であると知りました。関東ローム層は富士山や箱根の火山灰が積もってできた火山由来の層です。ローム層というのはやはり火山由来の層ということになりませんか?それとも、関東ローム層という名前が特殊で、これはローム層とはイコールではないのですか?(千葉県:匿名希望)
日本の火山周辺に分布する「ローム層」(関東ローム層を含む)は風化火山灰土からなります.風化火山灰土とは陸上に2次堆積した火山灰や風成塵(例えば黄砂)などが水や植物などの影響を受けて風化し土壌化したものです.つまりすべてが火山由来の物質からなるわけではありません.また含まれる火山由来物質も火山噴火のときに降り積もった火山灰の層そのものというよりは,それが風で舞い上がるなどして移動し再堆積したものが多いとされています.一方で大きな噴火があったときは厚い火山灰層が堆積しますが,一度に厚く堆積すると土壌化が起こりにくく,層のまま保存されます.つまりたくさんの火山灰層のあいだに挟まれる風化火山灰土(ローム層)は大きな噴火とその次の大きな噴火の間に形成されたと考えることができます.
Q:マントル対流について、マントル物質は海嶺まで上昇していくとき、当然それぞれの自転半径が増加することになるので、運動量保存というのか、アイススケートの選手が回転する際に腕を縮めると回転速度が上がりますが、同様にマントル物質は上昇により回転速度が落ちることはないのでしょうか。(長野県:匿名希望)
マントルは非常に高粘性であるため、マントル対流は浮力と粘性抵抗のみのバランスとして起こっています。地球の自転は対流に影響を与えません。マントル深部から湧き出してくる流れは、上昇する過程で常に周りの岩石と角運動量を交換しながら浮上してくるので、浮上する過程で角運動量を保存することはありませんし、質問のように周りの岩石と異なる自転速度で運動することもありません。
Q: 国内でろ過砂に適した原材料となる砂を探しています。 河川の砂で、黄土色〜白っぽい砂(河川の中流、下流などに堆積していて,川を流れる間に、角が取れ、丸みを帯びた砂で、破砕しにくい砂)が出土するような地域は日本でいうとどのあたりになるでしょうか。(神奈川県:匿名希望)
産業技術総合研究所地質調査総合センターから、河床の堆積物のデータベースが提供されています。 まずは、こちらを参考にしていただくのがよろしいかと思います。 https://gbank.gsj.jp/geochemmap/
Q: 富士山の山梨側に青木ヶ原樹海があります。富士山と言う厳しい環境で何故あのような、樹海が出来たのか、地質学者の方から見て、他とは違う土に含まれている成分や、地中の構造などはあるのでしょうか。(静岡県:スッポンさん)
富士山の北西山麓にある青木ヶ原樹海についての質問ありがとうございます。
厳しい環境で何故とありますが、樹海よりも高い標高の場所にも樹林帯が形成しておりますし、北海道にも樹林帯はありますので、樹木の種類によっては、青木ヶ原樹海のある地域は特に成長環境として厳しいというわけでは無いと思います。一方で、青木ヶ原樹海は特殊な環境で形成した樹林帯ですのでそれについて説明します。
青木ヶ原樹海は、西暦864年~866年にかけて噴火した貞観噴火で噴出した青木ヶ原溶岩の上に形成された樹林帯のことをです。溶岩の上には少しの土壌しか形成されておらず、その上に樹木が生長している構造になっています。これは富士山の他の溶岩も同じような形態をしています。富士山の周辺では、溶岩が流れた後まず始めに、陽樹であるアカマツが成長します。その後、陽樹から陰樹へと遷移し、ヒノキやツガの林となり、最後にナラ林になります。 1200年前に噴出した青木ヶ原溶岩の上にはヒノキやツガの樹海が形成されていますが、1000年前に噴出した北東山麓の剣丸尾溶岩尾上にはアカマツ林が形成されています。一方で、約3000年前に噴火した大室山(北西山麓)はブナ林となっており、噴火の年代とともに樹林帯の構成が異なっていることが特徴です。
Q: ギアナ高地は昔地軸の位置にあったため、垂直に切り立ったテーブルマウンテンができたという事ですが、そこから考えるに大昔の地表の位置は今よりも高かったということになるのでしょうか。 もし地表の位置が高かったのであれば、なぜ低くなったのでしょうか?(東京都:匿名希望)
ギアナ高地を構成しているのは堆積岩や火山岩で、その堆積物は20-14億年前に太古代の基盤の上に堆積しました。その頃は、南米と西アフリカは合体・近接していて、コロンビア、ロディニア、ゴンドワナ、パンゲア超大陸の一部または近接する大陸として存在していました。 そして、ジュラ紀になり、パンゲア超大陸が分裂します。白亜紀に南米大陸とアフリカ大陸とに分裂をします。 大陸分裂の際のプルームの上昇によって、この地域全体が隆起し、その隆起によってギアナ高地が形成され、その後侵食を受け現在のような地形となりました。 以上のように、堆積物の堆積時は海底(大陸棚)でした。また、陸地化してからは侵食を受けるようになりますが、隆起する一方で、削剥もされますので、削剥された分だけそのまま現在よりも高かったわけではないです。
Q: 沢歩きをして露頭写真等を撮っていたいるのですが,写真の緯度経度が数十mズレることがよくあります.調べてみたら東京付近では緯度1秒で約30m,経度1秒で約25mと言うことが分かりましたが,もっと高精度の位置情報を収めたいです.GPS搭載カメラでフィールド写真を撮っている方はどんな高精度GPS搭載カメラを使用しているか教えて下さい.(匿名希望)
最近の「みちびき(=QZSS)」対応のGPSセンサが搭載されていれば、山間部でも多少は精度があがると思います。QZSS対応のGPS(およそ2019年以降発売のスマホ等には普通に搭載されてる)でも数メートルくらいの精度は出ると思います。 次のサイトで、QZSS対応の製品の一部が検索が可能ですが、網羅されてないので「みちびき対応 デジカメ」で検索が早いかも知れません。 https://qzss.go.jp/usage/products/list.html その他、こちらのサイトの情報もお薦めです: https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/chizu3/1142801.html
Q: 2021/5/9のオンライン講座※を拝聴していまして,以前地質標本館で実施されていた「祝チバニアン誕生!拡大版―もっと知りたい千葉時代―」を見に行った際に思ったことで,byk火山灰は柳川から小草畑の間では田淵でしか見られないのでしょうか.また,柳川より西側では見られないのでしょうか.(匿名希望)
柳川から小草畑の間では田淵以外でも、また柳川より西側でも 見られるとされているので、探してみると良いかと思います.
※地質の日 オンライン一般講演会(YouTube配信中)(2021.5.12現在)
Q: 地学ガイド」や「論文」において、化石や鉱物の層準分布、採取地点、露頭の写真が記載されていますが、これらは所有者にどのような許可を得ているのでしょうか。巡検の許可以外に必要な手続や所有者に説明しておかなければならない事項を教えてください。また、過去に許可を得たが、新しい所有者になった場合、新たに許可を取らないと、その論文は無効になるのでしょうか?(兵庫県:匿名希望)
産業レベルだと別の法律があるのかと思いますが、ここでは個人レベルということで話を進めます。 その場所が私有地なのか、国有地なのか、さらには保護されているものなのか(国立・国定公園、天然記念物 等)によるのかと思います。 私有地内でしたら、その所有者からその場所に入る許可を取る必要があります。また、試料を採取する許可も必要です。
所有者も、他人がその土地に入り、物を取る理由が知りたいでしょうから、所有者に納得してもらえるように、その理由を説明する必要があります。 それは、立ち入る場所や採取するもの(例えば、作物、樹木や花とかではないだけでも良いのかもしれません) だけでも良いのかもしれませんし、科学的理由も問われるかもしれません。また、樹木を育てていたり、神聖な 場所であったり、水源であったりなどといったこともありますので、立ち入る際の注意点なども聞く必要があります。日本だと、勝手に立ち入ってトラブルになる、不法侵入という罪になるといったところですが、海外だと撃たれるといったこともしばしばあります。 ところで、その土地が私有地なのかどうか、さらには誰の土地なのかわからない場合も多いかと思います。まずは地元の自治会長さんなど地元の方に相談するのが良いでしょう。 さらに、私有の山林の場合、市街地と違って地籍調査が未了の場所が多く、地番と登記が非公開になっています。
このような場合、道路工事のような公共性が高いケースでないと所有者を教えてもらえません。そういった点でも、地元の方(たとえば自治会長さん)に挨拶しておくのが現実的です。
国立・国定公園、天然記念物等でしたら、それを管轄する自治体や環境省などから許可を取る必要があります。 市有林や県有林の場合は、森林管理事務所(役所の森林政策課)で許可を取ります。もちろん、国立公園などでは制限区域以外の場所に立ち入る(観察したり、写真を撮る)だけならば許可は要りません。 詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0064.html を確認してください。
また、「過去に許可を得たが、新しい所有者になった場合、新たに許可を取らないと、その論文は無効になるのでしょうか?」とうことですが、立ち入ったり、試料採取の時に許可が要るかどうかなので、この点に関しては特に問題はありません。もちろん、新たに立ち入るならば、許可が必要です。さらに、すでに過去に許可を取っていたとしても、その許可が永続的なものとは限らないので、その都度必要かと思います。
Q: 崖錐、岩屑、崩積土の違い、見分け方がありましたら、ご教授ください。添付します写真は集水地形の状況です。このように石が集合するような場合の呼び名などありますでしょうか。(ペンネーム:りょ)
ご質問の「崖錐」「岩屑」「崩積土」は以下のような意味で使用されることが多いようです.
崖錐 急崖等において風化生産された岩屑が,崖の基部に堆積してつくられた円錐状の堆積地形で,同時に岩屑斜面の一種である崖錐斜面を構成する. 国土地理院HP「日本の典型地形について」参照(https://www.gsi.go.jp/kikaku/tenkei_sonota.html#崖錐)
岩屑 岩石が分解してできた締っていない物質で,機械的な風化作用を受けてできた岩石片や鉱物片,またはそれらの集合体.風化生成物として生成原地にあるものも,川や氷河によって運搬されたものも岩屑と呼ばれる.しかし円摩された岩石片や,堆積層をなした岩石片の集合体は一般には岩屑とは呼ばない. 朝倉書店 岩石学辞典参照(https://kotobank.jp/word/岩屑-49074)
崩積土 斜面上の風化物がクリープなど重力の作用によって斜面下方に移動・堆積(たいせき)した,角礫(かくれき)混じりの非常に淘汰(とうた)の悪い堆積物.およびそれを母材とする土壌. 日本大百科全書(ニッポニカ)参照(https://kotobank.jp/word/崩積土-132228)
崖錐は地形を表す用語,岩屑および崩積土は堆積物を表す用語です. 頂いた写真からは残念ながら地形は判別できません.また写真では表層に岩屑がみられるようですが,この緩斜面をつくる堆積物全体が岩屑で構成されるかは分かりません.
Q: 神社仏閣の石碑など文化財に使用された日本花崗岩産地の科学的同定は可能ですか?具体的には瀬戸内海沿岸から北前船で運搬された御影石などについて。鉱物組成、元素分析、色調などにより広島県、岡山県、兵庫県の区別です。(匿名)
お調べになりたい花崗岩が,具体的に、どこの「花崗岩体」由来なのかという候補がわかっていれば、それに似ていると言うような議論は可能と思います。しかし、瀬戸内海沿岸に分布する花崗岩は,基本的にいずれも領家花崗岩体に属し、同じなので、各県での特徴というよりは、各岩体の個性や各岩体内の違いも重要になってくるので、不確定要素が大きいかと思います。
Q: 愛知県北設楽郡東栄町は、木曽山脈の南端に位置している、町ということもあり、以前より「木曽山系」と思っていましたが、「赤石山系ではないか?」という意見がありました。どちらなのかわかりますか?また、調べ方はありますか?(匿名)
天竜川を境にして、西側が木曽山脈、東側が赤石山脈という位置づけに基づけば、東栄町は、天竜川の西側に位置していますので、「木曽山系」と呼称することで良いかと思います。
一方、地理院地図では東栄町付近を「美濃三河高原」としています.木曽山脈の南端を恵那山とすることもあるので,東栄町付近は、「木曽山系」というよりは「美濃三河高原」あるいは「三河高原」とするのが より的確かと思います.
また、地質情報をお調べになる際は、ネット(Wikipedia等)で情報 検索することも有用かと思います。ただし、Wikipediaは勝手に誰かが書いただけで、検証されていませんので、引用文献を辿るなどして自身で検証する必要はあります。ご参考まで。
Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/赤石山脈
https://ja.wikipedia.org/wiki/木曽山脈
コトバンク:大日本大百科全書(ニッポニカ)
木曽山脈
https://kotobank.jp/word/木曽山脈-474216
美濃三河高原
https://kotobank.jp/word/美濃三河高原-139348
三河高原
https://kotobank.jp/word/三河高原-138331
Q: 私は地球の地下、マントルなどに興味があるのですが、地球の地下を掘り進めてもたいした距離まで進めないという話を聞きました。ただその後マグマはマントルが溶けだして浮いてきたものだということを知り、別に掘らなくてもマグマの中に入っていけば硬さなど関係なしにマントルまで行けるのではないかと思いました。そのようなことは可能でしょうか。また地表をただ掘削するだけでなく、岩石を熱して柔らかくしたところで進むなどの方法も可能でしょうか?(匿名)
現在、地底掘削の記録はロシアのコラ半島で掘削されたSG-3が1992年に巣直進度12261mまで掘られました。アジアでは中国が最近記録をした8500mくらいの深度が記録となっているようです。現在、深海掘削船「ちきゅう」でもマントルまで掘削しようとしていますが、技術的な問題が多いようです。特に、熱による影響で先端(ビット)の摩耗が大きく、掘り進んでいくための素材の開発等が進んでいます。 しかし、マントルの上部はリソスフェアと呼ばれる固い岩盤です。一方、その下にはアセノスフェアと呼ばれる柔らかい部分があります。柔らかいといっても、年間数cm程度流動するかどうかのすごくネバネバなものです。いずれせよ固体ですから、私たちの時間レベルで深部に進もうとするなら、掘る必要があります。 また、マントルが部分融解していてマグマがあるので、それを辿ればという意見ですが、鉱物間のマグマは10%も融解すれば鉱物間を伝わって上に移動してしまいます。つまり、超ミクロでもない限り、マントル内のマグマを伝って深部に行くことはできません。また、温度も1300℃を越えます。
Q:地殻は上部地殻と下部地殻に分類されていますが、 西南日本弧における古生代〜ジュラ紀の付加体は上部地殻に分類されるのですか?それとも上部地殻も下部地殻も付加体なのですか?(匿名)
上部地殻、下部地殻の区分は岩石の種類で分けています。これに対して、付加体は表層の堆積物、海洋地殻や海山、これらが深部で変成された変成岩からなります。表層に露出している部分もありますが、地面より深いところにある部分もあるようです。たがって、付加体の岩石は正確にいうと海洋地殻や上部地殻の両者を含んでいることになります。このように区分の基準が異なるので単純に分けるのは難しいです。地表の付加体のみを考えると表層にあるので、上部地殻といえると思います。
Q:地質・地球活動分野の基本的・教科書的な参考図書、事典的な本などを教えてください。現在、公立中学で理科部指導員をしています(教育委員会からの派遣)。 地質分野への興味が薄く気になっています。私自身、古い中学までの知識しかなく、指導できずにいます。現在、大人の読む高校地学系の本(数研の高校地学、新しい高校地学の教科書)を読み進めていますがもう少し深く知りたいです。どんな本で勉強したらいいでしょうか? また、事典的なものを探しています。2万円以上と高価ですが、アマゾンで『地学事典(地学団体研究会)』を見つけました。が、1996年発行と、少し古いのが気になります。何かいい事典はないでしょうか?どこにお尋ねしたらいいかわからず、失礼します。 教えていただけると幸いです。(匿名)
大学生向きの地球科学の本は多く出ていますが、やはり、地球科学全般が書かれているため、地質の部分は簡潔になっています。また、各本で特徴があり、これだけでいいというのはなかなかありません。比較的まとまっているのは「もう一度読む数研の高校地学」は全体をバランスよく網羅してあります。最近の成果を知りたいときには、中公新書やブルーバックス(地学のススメ、地球の歴史上〜下、図説プレートテクトニクスなど多数)が安価でお薦めですが、どうしてもテーマが個別的になります。地質学会ではField Geologyというシリーズ(共立出版)を出版しています。この本は、野外での調査を中心に総括しており、かなり内容の濃いものにないます。また、日本列島に関しては「絵でわかる日本列島の誕生」、「絵でわかる日本列島の地形・地質・岩石」もわかりやすく解説しています。また、地学事典はアップグレードされていません。地球科学の事典は幾つかがあります。図説地球科学の事典(8856円、朝倉書店)もあります。参考にしてください。
Q:私は神奈川県に住んでおりますが、先日、関越自動車道を通って、群馬県を通過した ところ、山々が切り立って、神奈川で見る富士、箱根、丹沢の山々とは山容が違うと思われました。これは、群馬の山々が火山性溶岩の中でも粘り気の強いものでできているからではないかと思いましたが、この理解でよろしいのでしょうか。 また、こうした、日本のおおまかな地域ごとの地質の違いと、その由来を知るのによ い情報源(書籍・Webアドレス等)がございましたらご教示をいただきけません でしょうか。なにとぞの助力を賜りたくご存じ上げます。(匿名)
産業総合研究所から発行されている日本シームレス地質図 (webで簡単に検索できます)を参考にしてください。それを使って調べると、各地域の地層や火山がどのような岩石からできているかわかると思います。
Q:高校の部活で地震と雲の関係について研究している者です。 地震で発生した電磁波が雲を発生させるという説が一般にしられており、その科学的 根拠はないとされていますが、《電磁波が雲を発生させる》という事は実証されて いるという記述をいくつか見ました。 このことについての真偽が知りたいです。また、その原理もしくは、原理について触 れられている論文や、研究結果などを教えてください。 (匿名)
この問題は諸説があり確定していないように思います。関係があるという研究者と関係がないという見解があり、議論されているところだと思います。
Q:山梨県の三ツ峠山、母の白滝を訪れました。滝周辺の岩で、特に興味を持った3つの岩塊について
●質問●
1. これらの岩の質はどういったものでしょうか?
2. 1-1の岩はどうしてキューブ状になっているのでしょうか。金峰山のような花崗岩の方状節理というものに似ているのでしょうか?
3. 2-1の岩も時間が経つと1-1のようなキューブ状になるのでしょうか?
4. 滝が流れる3-1の岩は1-1や2-1の岩と比べると色が若干黒っぽく、硬そうで鋭い割れ目があるのですが、1-1および2-1の岩とは成り立ちに大きな違いがあるのでしょうか。 (匿名)
産業総合研究所から発行されている日本シームレス地質図 (webで簡単に検索できます)を参考にしてください。それを使って調べると、その場所がどのような岩石からできているかわかると思います。それが火山の石か堆積岩かによって成因は変わりますので、写真だけでは判断がつきかねます。
Q: 翡翠の原石を購入し、勾玉を製作していたところ、苦土リーベック閃石にナヌカワ石がついたものと、翡翠が混合した原石であることが分かりました。鉱物に知識のない私は、翡翠であると信じて、ダイヤモンドヤスリで磨いてしまいました。 5gは研磨しました。マスクはしていましたが、サージカルマスクで、風呂に浸かりながら、磨いていました。磨く際には、プラスチックケースに水をはり、水につけながら主に磨いていたので、目視では飛散はしていないようにおもいますが、顔の近くで削っていたときもあり、また、削った後、手は白くなっていました。念入りに何度も何度も手荒い、体を洗いました。これを2度行い、計四時間ほど研磨に費やしました。これがこれまでの経緯ですが、アスベストによる健康被害はありますか? 地元の鉱物に詳しい先生に聞いたのですが、まったく心配ない、と断言してくださいましたが、その判断は正しいですか?角閃石の粉を吸った場合についても教えてください。ルーペで見ると、繊維が含まれているように見えますし、繊維か磨き傷かはわかりませんが、繊維のようなものがみえます。が、繊維が目視で繊維状と分かるほどではありません。気にしなくて良いレベルでしょうか?心配で眠れません。 (滋賀県 タイ さん)
健康被害に関しては、個人差があり一概には言及できません。気になる点は医師に御相談いただいた方がいいと思います。
Q:千葉県市原市田淵の白尾火山灰層(地球磁場逆転期の地層)に関連した、以下の内容について教えていただけましたら嬉しいです。 この地層がGSSPとして認定されるとゴールデンスパイクが打たれる、とのことですが、もし正式に認定された場合、認定決定からゴールデンスパイクが打たれるまでにはどれくらいの期間かかるのでしょうか? 地層に打ち込まれていた赤や緑の杭のことを教えていただきたいです(名称や色の意味など)。地層をマーキングするのに一般的な道具なのでしょうか?(現地を見て疑問に思ったのですが、地質学に関しては初心者なため詳細がわかりませんでした) (東京都 はるみ さん)
「ゴールデンスパイクが打たれる」という言い方がされていますが、実際に国際機関が打ちに来てくれるわけではありません。ただし現場でGSSPがどのポイントであるかを示す必要があるので、申請チームや露頭を管理する役場などが国際機関関係者とともに円形のプレートを設置したりスパイクを打つことがあります。
(以下,2021/10/12追記)
現場の管理者である市原市によるゴールデンスパイク設置および記念式典が予定されています。
国際関係者を招待して安全に式典を行うため、2021年の実施が見送られました。2022年実施予定とのことです。
Q:温泉仲間から聞かれたのですが、最近泉質が大きく変わり、湯の色も透明から濁ったものに変わってきた温泉があるので、その理由を知りたいとのことです。具体的な温泉名は、大川温泉 磯の湯 http://www.e-izu.org/spot/202/ 静岡県賀茂郡東伊豆町大川 TEL.0557-22-0248 平成17年4月14日の分析結果では 源泉利用施設名称:いさり火 源泉名:銀泉 大川21号 泉温:71.1℃ pH:8.2 メタケイ酸:0.6mg 成分総計:2.869g/kg 泉質:ナトリウム・カルシウム−塩化物・炭酸水素塩温泉 平成21年11月27日の分析結果 源泉利用施設名称:いさり火 源泉名:銀水 大川21号 泉温:73.3℃ pH:7.13 メタケイ酸:32.1mg 成分総計:2.872g/kg 泉質:ナトリウム・カルシウム−塩化物・硫酸塩泉 (質問) 4年足らずの間にこんなに成分が変わり、湯の透明度も変わってくる原因は、どんなことが考えられますか。(小堀雄三 さん)
一般論として、天水の量が変わったとか、海水の混合比が変わったとか、火山性の水の量が変わったなどがありますが、個別の温泉の原因については、温泉水を研究している研究所が国内にいくつかありますので、そちらで聞いた方が良いかと思います。
Q:千葉県市原市田淵の地球磁場逆転地層についてご質問させていただきます。養老川沿いに歩き実際に赤黄緑のスパイクが打たれている場所の他に、鶴舞方向から田淵会館に向けた細い側道に入る道の手前の橋から、養老川沿いの地層が同じように見えます。この地層の上の方にやはりラインが一本入っているように見える場所があるのですが、これがスパイクの打たれている場所から続く同じ地層と考えてもよろしいでしょうか?現場は川床に降りるにはあまりにも足場が悪く、年輩の方をお連れすることができませんが、この橋の上からでしたら比較的容易に見ることが出来ます。 (匿名)
ご指摘の橋から見えるラインは、おそらく薄い砂の層です。そのあたりの地層は、地磁気逆転層よりも恐らく100mほど上位の地層にあたると思われます。
Q:栃木の大谷石、千葉の房州石、静岡の伊豆石等、本来の日本海側産以外の中新世海底噴出起源の緑色変質した火山岩類に対して、「グリーンタフ」の呼称を用いても学術上の問題はないのでしょうか?(東京都 たぬたぬ さん)
グリーンタフ層の日本語訳は緑色凝灰岩層で、本来は日本海側油田地帯の漸新〜中新の地層に対して使用されていました。主として、後期中新世より古い火山活動による堆積物が主体です。この堆積物は、日本海の拡大に関連して形成されたと考えられています。この名称は広く使われていますが、学術的には厳密に使う必要があります。千葉の房州石は、後期中新世、伊豆石も中期〜後期更新世で形成された時代が違うので使うのは適当ではありません。
Q:海底が隆起してできたのは千葉セクションだけなのでしょうか? イタリアのモンテルバーノ・イオニコと、ビィラ・デ・マルシェは隆起とは違うのでしょうか? ポールシフトが起こったとき、地上ではどんな変化が起こっていたのでしょうか? オーロラが千葉で見れたり、渡り鳥が渡らなかったのではないかといわれているそうですが、生きものは大丈夫だったのでしょうか? 隕石などがたくさんおちたり、放射線が強くあったったりしたのでしょうか? (千葉県 しゅう さん)
海底が隆起してできた地層はたくさんあります。ヒマラヤ山脈もその一つです。イタリアのそれらの場所がどのような岩石からできているか、情報がないとお答えできませんが、海成層なら隆起したものと考えられます。また、ポールシフトが起こったときに絶滅が起こったと書かれた論文もありますが、頻繁に大きな事件があったという証拠はないようです。しかし、どのような環境変化が起こったのかはわかっていません。あるいは、何も起こらないので、地質記録に残っていないのかもしれません。
Q:「山形県西置賜郡飯豊町大字広河原字湯ノ沢448-2」に広河原温泉という間欠泉があり、湯船の真ん中から、間欠泉が絶え間なく吹き上げています(0m〜3mぐらい)。旅館の案内板によると「炭酸ガスにより噴き出す」と書いてありました。四六時中噴き出しているので間欠泉と言わない方が良いのかも知れませんが、この間欠泉の地下構造と、どのような作用により、間欠泉が噴き出すのでしょうか。 (小堀雄三 さん)
間欠泉は地下水(温泉水)が噴出したり休んだりを繰り返す現象をいいます。間欠泉は、水蒸気を噴出する間欠沸騰泉と炭酸ガスを噴出する間欠泡沸泉とに大別されます(大沢編、「温泉科学の新展開」ナカニシヤ出版、2006)。 ともに、地下でガスの圧力が上昇し、割れ目やボーリング孔などを通じて一気に地表へ噴出し、噴出後に地下の圧力が大気と同じになると、活動は停止し,またガス圧の上昇が始まるというメカニズムです。前者は水蒸気の圧力で有り、後者は炭酸ガスによるものです。 我が国における間欠沸騰泉の例としては、宮城県鳴子町の吹上間欠泉、長野県諏訪市の諏訪間欠泉などがあります。45分間隔で噴出する世界的に有名な米国イエローストン国立公園の間欠泉も,これに含まれます。 間欠泡沸泉の例としては、島根県吉賀町の木部谷間欠泉や質問の中で述べられている山形県飯豊町の広川原間欠泉などがあります。 いずれの場合にも、ガスの圧力が上昇するためには一旦ガスが地下で貯留される必要があり,上部を栓シールするような地質構造が必要となります。 ご質問の間欠泉は炭酸ガスが噴出していることから、間欠泡沸騰泉と考えられます。このタイプの間欠泉は一般に炭酸泉であり、もともと地下深部では炭酸ガスが水中に溶け込んでおり、地表付近では圧力が低減するためにガスが出現します。これを脱ガスと呼んでいます。これはラムネのガラス玉を抜くと炭酸ガスの泡が吹き出る現象と同じです。島根県の木部谷(きべだに)間欠泉では正確に約25分間隔で噴出が起こり、噴出は約5分間継続し、最も活動的なときの水柱は約2m程度の高さまで到達します。 噴出する地下水の酸素水素同位体比や水質などの特性より、間歇泉にはわずかですが、地下深部からもたらされた涼み混んだスラブから放出された深部流体が混入している可能性が指摘されています。 間欠泉における地化学特性の時間変化から,噴出初期は地下浅部に浅層地下水が流入し,噴出し、噴出中期になると深部流体の寄与が最も大きい地下水が噴出する.そして,徐々に浅層地下水の流入が起こり始め,希釈された地下水が噴出すると考えられています. 噴出箇所には断層の分布が想定されており、粘土などがらなる断層破砕帯が、岩盤に蓋をして栓ようなの役割をしたために、炭酸ガスを含む地下水が一時地下に滞留し、脱ガスによりガスの圧力が高まり噴出したものと考えられます。
Q:黒曜石は流紋岩と同様の成分なのになぜ黒いのでしょうか(神奈川県 渡邊裕 さん)
黒曜石は不純物を多く含むガラスなので、細かく砕けば無色透明のガラスですが、大きな塊では、中に入った光が不純物に吸収されて外に出てこないために、黒く見えるのだと思います。例えば、海の水はコップに入れれば無色透明ですが、深い海を真上から見れば青黒く見えるのと同じ原理だと思います。あえて黒曜石の表面をすりガラス状にすれば、白く見えるはずです。一方、流紋岩が白く見えるのは、石英、長石などの無色鉱物の微細な結晶を多量に含むため、それ らの表面で光が反射されて白く見えるのだと思います。(2023.3.30訂正)
Q:私は年金生活になってから石に興味を持った初心者です。先日(10月9日)NHK BS 15:30〜『グレートネイチャー選 大隆起の絶景台湾』と言う番組見ました。その番組では『フィリピン海プレートがユーラシアプレートに乗り上げているので台湾は隆起している』と言っていると理解しました。しかし(1)日本列島(西日本)はユーラシアプレート上にありその下にフィリピン海プレートが沈み込んでいる(ので東海地震などが心配されている)。(2)海洋プレートは重いので軽い大陸プレートの下に沈み込む。と思っていましたので違和感を感じました。そこで、何故台湾島ではフィリピン海プレートがユーラシアプレートの上に乗り上げるのか?をご教授お願いします。宜しくお願いします。 (愛知県 藤戸石 さん)
海洋プレートが他のプレートに乗り上げる例は、他の地域でも観察されています。たとえばオマーン地域にある地層はその代表的な例と考えられています。しかし、台湾の場合はこれとは異なり、ユーラシアプレートが逆にフィリピン海プレートの下に沈み込んでいるため、その前面につくられた付加体とよばれる堆積物が積み重なって隆起帯を構成していると考えられています。
Q:地学をかじり始めたばかりです。 石を拾いました。調べたところ鉄丸石だと思っていますが、どのようにしてこの丸いものが出来たのでしょうか。しかも1500年程度で出来たようですが。不思議です。出来方はどの様な過程でしょうか。お教えください。 (塩沢邦夫 さん)
神奈川県立博物館の調査研報(自然)2012, 14, 93-102に詳しいことが書いてあります。そちらをご参考ください。
蟹江ほか 2012. 四万十累層群の生痕化石起源の炭酸塩類コンクリーション – 三浦半島と房総半島の葉山・保田層群産へそ石・ 静岡県と高知県の瀬戸川層群と室戸半島層群産鉄丸石 –
Q:千葉県田淵付近にある地層のうち、白尾火山灰層(Byk-E)に含まれているSiO2成分は、42.84%だそうです。(古期御岳火山起源の中期更新世テフラと房総半島上総層群中テフラの対比 より)42.84%だと、玄武岩よりもその割合が低く、(ニューステージ 新地学図表 より)色が黒いものだと予想していたのですが、先日修学旅行で行ったところ、彩度が高く、驚きました。なぜですか? (千葉県 菊花石 さん)
この値は、Takeshita et al.(2016)という論文の値ですが、火山灰に含まれている角閃石という鉱物の化学組成を示したものです。火山灰全体のSiO2成分はもっと高いです。
Q:堆積岩(れき・砂・泥など)からできた地層からはどんな化石でも見つかることがあるのでしょうか。例えば,アンモナイトは泥岩層からでしか産出されない。ブナの葉の化石は砂岩層からでしか見つからない。あるいはどの化石も,どのような層からも産出されるなど特徴があるのでしょうか。ブナの葉,アンモナイト,三葉虫,貨幣石,ビカリアなど代表的な化石についてお聞かせ願えないでしょうか。よろしくお願いいたします。 (回答者匿名)
堆積した環境によりみつかる化石は異なります。場合によっては、礫岩、砂岩、泥岩からも同じ化石が見つかることもあります。ブナの葉は通常、陸上で堆積することが多いので、砂岩、泥岩、凝灰岩から産出すると考えられます。それ以外の3つの化石は海の生物の化石で、砂岩、泥岩、石灰岩などから産出します。これらの化石は、古生物図鑑などをみると写真や図が掲載されていますのでそちらを参考にしてください。
Q:新(または修正)モース硬度は何時誰が決めたものですか?
ドイツの鉱物学者Friedrich Mohsが作ったそうです。1822年頃から使われるようになりました。
Q:黒い溶岩石を造園として利用しようとしています。そこで一点教えていただきたいのですが、黒っぽい溶岩石の比重はどの程度でしょうか。多孔質のものとそうではないものとある様なのですが、其々どの程度の比重か教えてください。 (伊波一哉 さん)
岩石も黒っぽいだけでは比重はわかりません。岩石名は何なのでしょうか。まずはそれを調べてみてください。
Q:日本のごく一般的な地質で、上部に積載加重が無い場合において、短期的に見て、垂直に掘削した場合、何mの高さまで自立してくれるのでしょうか。 (富山県 シロハカセ さん)
「築城に関してのご質問のようですが、日本の地質は多様であり、「ごく一般的」という観点でお答えすることは難しいです。山地をなす深成岩や変成岩、新第三紀以前の堆積岩ですと硬いですが、硬すぎるとそもそも掘削に困難を伴います。一方、平野に分布する沖積層は軟らかく、加工しやすい反面崩れやすくもあります。また沖積層の中でも崩れやすい層と崩れにくい層があります。垂直に掘削した場合に最も崩れやすいのは砂丘のような未固結な砂層で、掘ったそばから崩れてしまいます。泥の層は砂よりも崩れにくく、数mから10mは自立するのではないでしょうか。大まかには丘陵地は山地よりも柔らかく、平地よりも硬い地層が分布しますが、場所によりけりです。」
Q: 花崗岩を体内に摂取してしまった場合の内部被ばくの危険性はどの程度ありますか。先日,焼き栗を食べた時に,細かな黒い粉がたくさんついており,拭き取りきれず,食べた時にじゃりじゃりしたのですが,後からその粉は焼き栗を作る時に使用される花崗岩(御影石)だと知りました。花崗岩は放射性物質だと聞いたことがあるため,内部被ばくの危険性があるかどうか,また,あるとしたらどの程度なのか心配になりました。すでにQ&Aに花崗岩を砂利として使用した場合の危険性についての投稿・お答えはありましたが,実際に石そのものを体内に摂取してしまった場合についての危険性につきまして,ご意見を伺わせていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 (回答者匿名)
「花崗岩1kgあたりの放射能は約1,200Bq(ベクレル)で、これはウランの鉱石として採掘される燐銅ウラン石や燐灰ウラン石の約7万分の1です。また、そもそも人体もカリウム40や炭素14による放射能を持っていますが、人体の放射能は、体重1kgあたり約96Bqで、体重70kgの成人男性の場合約6,700Bqとなります。仮に花崗岩を10g体内に摂取したとしても、それは人体自身が発する放射能の数百分の1にしかならず充分に低い値で、また1日もすれば排泄されますので、被ばくの危険性は限りなく低いと考えられます。」
Q:含礫泥岩の扱い方について質問します。私の学生時代(1980年代のはじめ)のころは,含礫泥岩というと氷床や氷山などによって運ばれた礫が海洋底の泥層中に含まれる場合や,海底地すべりによって周囲の未固結堆積物と混ざり合ってできた異常堆積物というように,成因がはっきりしている用語と認識していました。でも,最近の論文などでは,付加体地質における混在岩の別名のような表現をされているものを見かけます。混在岩はメランジュの中で2.5万分の1地質図では表現できないような小規模の岩体について記載する用語で,しかもその成因については限定していないと思います。なので,「含礫泥岩を起源とする構造性メランジュ」というなら理解はできますが,「含礫泥岩は混在岩と同義語」と書かれているものについてはどうも合点がいきません。とはいえ,言葉は時代とともに変化するもの。わたしの学生時代からは随分と時が流れたので,今や含礫泥岩の扱い方も変化したのでしょうか。ご回答のほどよろしくお願いいたします。 (回答者匿名)
「含礫泥岩」は,「泥岩中に礫を含む堆積岩のことを言う記載用語」です.その成因として,海底地すべりによる周囲の未固結堆積物との混合などが挙げられています.一方「混在岩」は,おもに泥質基質中にいろいろな種類の岩石がまじりあった岩石で,構造性メランジュや泥ダイアピルなども含みます.堆積性のものと判断した場合に含礫泥岩と呼ぶこともあります.
Q:石灰岩の生成は、生物起源と科学的沈殿の2種類があります。生物起源は、遠い外洋でサンゴなどが堆積し、これがプレートに乗って移動し付加体となったものと理解しています。しかし、外洋から運ばれたもの以外で、陸の大陸棚に堆積してできた石灰岩もあると聞いています。この場合、大陸棚では石灰岩ができるほどの大量の生物起源の堆積物があるのでしょうか。 (茨城県 inakamon さん)
通常、世界の石灰岩をみると大陸の縁辺で形成された石灰岩は大量にあります。大陸縁辺は海洋底よりも生物の生産量が高いので容易に石灰岩が形成されます。
Q:東京都あきる野市にある、弁天山の地質と弁天洞窟の岩質を教えてください (東京都 ジオダイスケ さん)
産業総合研究所から発行されている日本シームレス地質図 (webで簡単に検索できます)を参考にしてください。それを使って調べると、その場所がどのような岩石からできているかわかると思います。
Q:六甲山系の谷を歩いていると岩肌が赤く染まっている箇所をよく見かけます。画像検索をしたところ和歌山県のハリオの滝でも同じような赤い色の写真を見つけました。知り合いの岩石に詳しい人に聞いたら熱水貫入じゃないかと言われたのですが、熱水貫入の画像を調べても同じような色は見当たりません。これらは本当に熱水貫入で赤いのでしょうか? (鳥取県 太朗 さん)
画像では解像度が悪くよくわかりません。産業総合研究所から発行されている日本シームレス地質図 (webで簡単に検索できます)を参考に地層を調べてみてください。その場所がどのような岩石からできているかわかると思います。
Q:花こう岩は、水がある地球だけに存在するもので、ほかの惑星には花こう岩はない」という話を聞きます。 それなら、玄武岩質マグマから分化作用で生成する火山岩の安山岩や流紋岩、また、深成岩の斑れい岩や閃緑岩なども地球上には存在しないということになるのでしょうか。 (茨城県 inakamon さん)
玄武岩マグマの分化で生じる花崗岩質マグマの量はとても少量です。また、水のない条件で玄武岩を溶かして作る花崗岩マグマも少量です。このような少量の花崗岩質マグマの存在は現在の観測体制では見つけることはできません。なので、このような少量の花崗岩の存在を否定しているわけではありません。一方、地球のように岩体レベルで見られる花崗岩は存在していません。安山岩質と思われるものは他の惑星でも見つかっています。 ちなみに、安山岩マグマは玄武岩マグマの分化というよりは、玄武岩マグマと地殻の混合・融解(混染という)、が重要なプロセスです。
Q:那須塩原の遊歩道、回顧コースで変わった岩を見つけました。岩に生えている苔が木の年輪の様になっています。この様な岩は自然にできるものなのでしょうか。 (群馬県 森部正樹 さん)
コケが生えているのでどのような岩石か写真だけでは判断は難しいですが、人為的なものではなさそうです。
Q:高速の北関東道で佐野方面から太田方面へ向かう足利の五十部トンネルを抜けて渡良瀬川までの間の左側に山を削った場所があるのですが、その場所に出べそのように地層の岩体があります、色は黄土色と赤茶の中間くらいです、毎日のように高速道路から見ていて気になってしょうがないです、いつの時代のものなのか知りたいのですがどうしたらよいのでしょうか (群馬県 たつ さん)
詳しい場所の情報がないとわかりません。産業総合研究所から発行されている日本シームレス地質図(webで簡単に検索できます)を参考に地層を調べてみてください。その場所がどのような岩石からできているかわかると思います。
Q:昔の地球の磁場が岩石に記録されているといいますが、カセットテープのように消えてしまわないのはなぜですか? (ja7tdo さん)
高温になったり(600℃ほど)、融解したりすると消えますし、雷が当たったら変化してしまったりします。また、鉱物が変質したりしても消えます。
Q:ISS、宇宙ステーションの実験で、生卵とゆで卵を回転させる様子がyoutubeにありました。ゆで卵は、くるくる回転しますが、生卵はすぐに不安定な回転になります。地球の外核は液体だそうですが、生卵のように不安定な回転にならないのはなぜでしょうか?https://www.youtube.com/watch?v=BPMjcN-sBJ4 実験では、液体をつめたボトルも回転させていますが、やはり不安定になります。地球の回転が安定しているのは、中に液体がないからではないでしょうか?
外核が液体でできていることは地震波の研究から明らかになっています。時間スケールと粘性が全く異なります。
Q: 神奈川県逗子市の二子山を源とする葉山町の「森戸川の上流部」の沢床が赤褐色の岩盤なのですが、この岩(石)は何の石でしょうか?(神奈川県 吉田 さん)
5万分の1地質図幅「横須賀」をご覧下さい.森戸川の上流部は葉山層群の大山層の凝灰質砂岩です.過去の火山の噴火に由来する砕屑粒子を比較的多く含む砂岩で,粗いところは礫岩のところがあり,泥岩も挟みます.
河床の石が赤褐色なのは,水の影響により酸化鉄が生じ,そのおかげで赤く見えているからではないかと思われます.森戸川沿いには林道があります.その路肩の新鮮な崖はあまり赤くなく,川底や風化した部分が赤いのではないでしょうか.ぜひ再度観察されてはいかがでしょうか.(回答者匿名)
Q: 先般テレビで亀岡の砥石を作っておられる方がテレビに出ておられました.この中で砥石となる泥岩は、はるか昔、ハワイ付近の海底で堆積した泥がプレートの移動と、海底の隆起で亀岡に出て来たとの事を説明されていました。日本ではこの京都の亀岡や高雄以外に、九州地方は出ている所があると聞いていますが、東北、北海道でも出ている地域はあるのでしょうか。又、亀岡には砂岩以外に桜石というものがありますが、根室の車石などが出来たのとも同じような海底隆起、浸食という歴史と関連するのでしょうか。(大阪府 KON-cyan さん)
京都周辺で砥石として採掘されている岩石は,砂などの砕屑粒子が運ばれてこない,陸から離れた地域でたまった粘土が岩石になった後に,マグマによる熱の影響を受け,さらに少し風化したものが採掘対象で,「鳴滝砥石」などとして採掘されています.この岩石は泥岩の仲間でも特に粒度の細かい粘土岩で,古生代ペルム紀と中生代三畳紀の境で起きた海水の酸素の欠乏の直後にたまった,前期三畳紀の粘土岩です.これらは,チャートに覆われつつ海洋プレートの移動によって大陸の縁までやってきて,海溝でたまった砂などとともに,中生代ジュラ紀に大陸の縁にくっついて付加体という地層になったものです.このような成因のため,同様の岩石は,「ジュラ紀付加体」と呼ばれる地層の中にチャートとともにあるのが普通です.ジュラ紀付加体の分布は,20万分の1日本シームレス地質図(旧版)の機能を使うとわかります.ただ,砥石として利用可能なものは,この前期三畳紀の粘土岩が弱い熱の影響を受け,さらに少し風化したものである必要があるので,条件は限られます.なお,亀岡の桜石は,泥岩が,砥石よりマグマだまりにずっと近いところに位置したことによって,より高温の接触変成作用を受けて菫青石という鉱物が新たにでき,変質作用によってその鉱物の結晶の形が浮かび上がったもののことです.根室の車石はもとはマグマそのものであり,マグマの冷却でできた節理が放射状に広がって車輪のように見えるもので,両者の成因は異なります.(回答者匿名)
Q:山形県西置賜郡飯豊町大字広河原字湯ノ沢に広河原温泉という間欠泉があり、湯船の真ん中から、間欠泉が絶え間なく吹き上げています(0〜3mぐらい)。この間欠泉の地下構造と、どのような作用により、間欠泉が噴き出すのでしょうか。
(神奈川県 小堀雄三さん)
間欠泉は地下水(温泉水)が噴出したり休んだりを繰り返す現象をいいます。間欠泉は、水蒸気を噴出する間欠沸騰泉と炭酸ガスを噴出する間欠泡沸泉とに大別されます(大沢編、「温泉科学の新展開」ナカニシヤ出版、2006)。 ともに、地下でガスの圧力が上昇し、割れ目やボーリング孔などを通じて一気に地表へ噴出し、噴出後に地下の圧力が大気と同じになると、活動は停止し,またガス圧の上昇が始まるというメカニズムです。前者は水蒸気の圧力で有り、後者は炭酸ガスによるものです。 我が国における間欠沸騰泉の例としては、宮城県鳴子町の吹上間欠泉、長野県諏訪市の諏訪間欠泉などがあります。45分間隔で噴出する世界的に有名な米国イエローストン国立公園の間欠泉も,これに含まれます。 間欠泡沸泉の例としては、島根県吉賀町の木部谷間欠泉や質問の中で述べられている山形県飯豊町の広川原間欠泉などがあります。 いずれの場合にも、ガスの圧力が上昇するためには一旦ガスが地下で貯留される必要があり,上部を栓シールするような地質構造が必要となります。 ご質問の間欠泉は炭酸ガスが噴出していることから、間欠泡沸騰泉と考えられます。このタイプの間欠泉は一般に炭酸泉であり、もともと地下深部では炭酸ガスが水中に溶け込んでおり、地表付近では圧力が低減するためにガスが出現します。これを脱ガスと呼んでいます。これはラムネのガラス玉を抜くと炭酸ガスの泡が吹き出る現象と同じです。島根県の木部谷(きべだに)間欠泉では正確に約25分間隔で噴出が起こり、噴出は約5分間継続し、最も活動的なときの水柱は約2m程度の高さまで到達します。 噴出する地下水の酸素水素同位体比や水質などの特性より、間歇泉にはわずかですが、地下深部からもたらされた涼み混んだスラブから放出された深部流体が混入している可能性が指摘されています。 間欠泉における地化学特性の時間変化から,噴出初期は地下浅部に浅層地下水が流入し,噴出し、噴出中期になると深部流体の寄与が最も大きい地下水が噴出する.そして,徐々に浅層地下水の流入が起こり始め,希釈された地下水が噴出すると考えられています. 噴出箇所には断層の分布が想定されており、粘土などがらなる断層破砕帯が、岩盤に蓋をして栓ようなの役割をしたために、炭酸ガスを含む地下水が一時地下に滞留し、脱ガスによりガスの圧力が高まり噴出したものと考えられます。(回答者匿名)
Q: 海洋プレートは、海嶺で上部マントルのかんらん岩を融かした玄武岩からなりますが、沈み込み帯でできる大陸プレートも花崗岩の下には玄武岩が存在するのでしょうか。
(茨城県 inakamon さん)
ユーラシア大陸や北米大陸などの大陸プレートは大まかに言うとケイ素やアルミニウムに富んだ花崗岩質の上部地殻と鉄やマグネシウムに富んだ玄武岩質の下部地殻から構成されていると考えられています。
このような玄武岩質の下部地殻はマントルで出来た玄武岩質マグマが大陸の底に繰り返し貫入して固まることで成長してきたとされています。でも玄武岩といっても大陸の厚さは平均して40 km程度ありますので、そういった深いところで玄武岩質マグマが固まるとハンレイ岩と呼ばれるような完晶質の深成岩や、それが高温・高圧下で鉱物種が変化した変成岩になります。またこのような玄武岩質下部地殻が部分的に融けることで大陸地殻の元となる花崗岩質マグマが出来るのですが、融け残った物質は玄武岩質、あるいはもっと鉄やマグネシウムに富んだ超苦鉄質岩と呼ばれるような岩石になります。
このように大陸プレートの下部は玄武岩質の深成岩・変成岩や花崗岩質マグマを作ったあとの融け残り岩などの多様な岩石から構成されている可能性が高いと考えられていますが、大陸の深いところを直接研究することは難しく不明な点も沢山あります。このため昔の大陸プレートの深い部分が上昇して現在の地表に露出している場所(南極など)で現在も精力的に研究が進められています。(回答者匿名)
Q: リップルマークとクロスラミナの違いを教えてください。
(埼玉県 かべちゃさん)
リップルマーク、クロスラミナ(斜交葉理)はどちらも水流や風などの流れによって形成される構造ですが、リップルマークは堆積物の表面(たとえば海底など)に見られる形態をあらわすのに対し、クロスラミナは堆積物の内部または断面に見られ、層理面に斜交する葉理のことを言います。リップルマークのうち、水流により形成されるものを日本語で漣痕と呼びます。(回答者匿名)
Q: 伊豆半島ではプレートの移動や衝突の証拠を見ることができるが、これとは逆にプレートが開く場所を見られるジオパークがある国は何処でしょうか。
(静岡県 ランチチさん)
プレートが開く場所を見られる国はアイスランドです。アイスランド島は大西洋中央海嶺にホットスポットが重複することで形成された島で、海嶺の延長の火成活動を陸上で見ることができる数少ない場所です。カトラ (Katla Geopark)とレイキャネス (Reykjanes Geopark) の2つのジオパークが世界ジオパークに登録されています。(山口飛鳥)
Q: 日本シームレス地質図を見ての疑問ですが、足利市を中心とし、渡良瀬川左岸、北東側に同心円上に地層が分布している様に見られるのですが、他を探しても同じ様な所は見当たりませんでした。長い時間をかけて約180度曲げられたということでしょうか?
(栃木県 gagiさん)
この付近の地層は1.7億年前くらい前に,海洋プレートの沈み込みによってできた「付加体」と呼ばれる複雑な地層です.同心円状ではなくて,足利市の方向に開いたU字状に見えますね.折れ曲がるのにかかった時間は1.7億年よりはるかに短く,地質学的には一瞬の時間で形成されたものでしょう.ただ人間から見るととても長い時間ですが.
地表でこのように折れ曲がってみえる構造を褶曲と言いますが,地層は表面だけではなく三次元で考える必要があります.立体的に考えてみてください.三次元的には同じ形態でも,どの部分が地表面になるかで,地質図に表される形は変わります.似たような地層の分布は岐阜県南部などにもあります.探してみてください.(斎藤 眞)
Q: 日本列島が沈没する可能性ってどのくらいですか?
(匿名希望)
地すべり、火山噴火、地震による沈降、隕石衝突などに伴って陸地の一部が海底に沈むことはあります。また、温暖化による海水準の汎世界的な上昇により、標高の低い土地が水没することもあります。しかし、それらを除けば、日本列島全体のような広範囲の陸地が数日〜数十年で短期間に海底に沈む地学現象は知られていませんし、力学的にも困難です。なので、小説や映画の「日本沈没」のように、「日本列島全体が、数日〜数十年で沈没する」という確率はほぼ「0」と言っていいと思います。数千万年〜数億年の時間スケールでは大陸は徐々に大きくなったり、逆に小さくなったりすると考えられており、さまざまな地質学的証拠から大陸の成長・消滅過程を読み解く研究もなされています。(山口飛鳥)
Q: 火山の本を読んでいたら、「火山灰を調べたら、どこの火山か分かる」というようなことが書いてありました。それは、どうして分かるのでしょうか。どんなちがいがあるのでしょうか。含まれる物がちがうのでしょうか。結晶の形や色などがちがうのでしょうか。見たことはありませんが、灰を顕微鏡などで見ると分かるのでしょうか。
(富山県 匿名希望)
火山灰には、地下のマグマ(どろどろに融解した岩石)から晶出した結晶(鉱物)や、マグマのしぶきが空気中で冷えて固まった破片(火山ガラス)が含まれています。マグマの性質は火山ごとに異なり、また同じ火山でも噴火ごとに異なります。そこで、マグマの性質を反映する火山灰の色や組織、火山灰中に含まれる鉱物の種類や割合、火山ガラスの屈折率や化学組成などといった情報を抽出し、さまざまな地点の火山灰の情報をもとに作成されたカタログと比較することで、どこの火山でいつ噴火した火山灰なのかを知ることができます。
Q: (東京都多摩市)大栗川の宝蔵橋から上流の新堂橋付近にかけて、川底が青みがかった灰色の粘土のような地質となっており、そこには15×9mm程度の二枚貝の化石があります。この地質は何時頃のもので、何故そこに貝の化石があるのでしょうか。
(りんごさん)
地域の地質に興味を持つ地元の方のご質問ということで,大変嬉しく思います.ご質問の地層は上総層群連光寺層といい,約150万年前に浅い海で堆積した砂や泥からなります.浅い海底に生きていた貝の化石やゴカイの仲間の住み跡が良く見られることで有名です.連光寺層は,多摩川の河原にもよく露出していますので,ご覧になられることをオススメします.専門的な内容については,産総研発行の5万分の1地質図幅「八王子」および「青梅」,また電子版の「地質図Navi(https://gbank.gsj.jp/geonavi/)」もご参照ください.今後とも,日本地質学 会を宜しくお願いいたします.(植木岳雪)
Q: ジュール・ベルヌの『海底二万マイル』を読んでいて、ギリシャの火山の描写で疑問を感じました。西暦69年に沈み、1866/2/13に現れたアフロッサ島(実在するか存じません)は、「島の形は丸く、直径300フィート、高さは30フィート。長石の破片のまざったガラス質の黒い溶岩」とありました。この火山は溶岩ドームで酸性岩だと思うのですが、SiO2が多いという記述からすると色は白っぽいのでは?この火山は火山岩でしょうか?それとも深成岩ですか?ギリシャの火山の特徴と、黒い理由についても教えて下さい。
(東京都 さゆみん)
ジュール・ベルヌの『海底二万マイル』に出てくるギリシャの火山はサントリーニ火山だと考えられます。サントリーニ火山は約3600年前のミノア噴火で大量の軽石を放出、径7.5×11kmのカルデラを生じ、現在、サントリーニ島、ティラシア島、アスプロニシ島、ネア・カメニ島、パレア・カメニ島の5つの島からなります。三つの島(サントリーニ島、ティラシア島、アスプロニシ島、)は外輪山の残骸で、特に、サントリーニ島の高さ200-300 mのカルデラ壁とその上の白壁の家々はエーゲ海の著名な観光地の一つになっています。ネア・カメニとパレア・カメニの二島はカルデラの中にできた中央火口丘 (溶岩ドーム)です。ノーチラス号は「ネア・カメニとパレア・カメニとのあいだの水路にいる」と書かれています。これら二つの島はカルデラが形成されたあと、紀元前197年に海面上に出現し、最後の噴火は1950年です。1866-70年にネア・カメニの周辺で海底噴火が起こり、三箇所から溶岩を噴出しました。ジョージ、アフレッサというのはその内の二箇所の溶岩噴出口の名前のようです。新しい火口は溶岩流出により、ネア・カメニ島と合体したので、現在はこのような名前の島はありません。ネア・カメニとパレア・カメニはカメニ火山と呼ばれており、SiO2(シリカ)量が65%前後のデイサイト溶岩からできています。シリカ量の多い溶岩でも、ガラス質のものは黒色です。特に海底に噴出するデイサイトは黒いことが多いので、色からシリカ量を推定することはできません。(田村芳彦)
Q: 花崗岩(御影石)について 、私は彫刻家で彫刻の素材として、御影石を使用しているのですが、どれぐらいの期間で風化がはじまるのでしょうか。素材の限界を知りたいのです。web上では、半永久的と出てくるのですが、真砂土があるのでそんなことはないはずで、仕上げ方法にもよると思いますが、切り出した状態で、おおよそで、100年単位でもかまいませんので、風化のはじまり時期及び真砂土になるまでの期間をお教え下さい。
(東京都 彫刻家)
花崗岩が、石材や外壁材として加工後、大気や雨水に触れる状態になれば、顕微鏡で見るスケールとはいえ、必ず風化が始まります。花崗岩は、鉱物の結晶(石英や長石、黒雲母など)が集合した緻密な岩石で、一見隙間がないように見えますが、顕微鏡で見ると、数ミクロン程度の隙間が必ずあります。そこから雨水がしみ込み、わずかずつですが、鉱物を溶かし始めます。これが風化の始まりです。時間が経つと、溶解によって隙間が広がり、そこに自然界では苔などの植物が付着・繁殖し、根から出される根酸などによってさらに溶解が促進されることになります。ご質問にある風化の速度についてですが、地質学的な調査事例として、年代の分かる墓石の風化や、埋没年代の分かる段丘礫の調査などがあります。墓石の研究から言えるのは、100年程度であれば墓石でも十分に形状は保つものの、ピカピカに磨いてあった表面の鉱物も、わずかに溶解され、肌触りがざらざらになってくるということです。
約30万年前の河岸段丘に含まれていた円礫の花崗岩は、その形状は保たれていますが、指で崩すことのできるいわゆる「くされ礫」となっていることが報告されています。つまりこれは「真砂」の状態です。約30万年かかって、ちょうど真砂になりきったのかどうかは分かりませんが、真砂になるには少なくとも100年単位ではなく、おそらく万年単位の時間が必要だと考えられます。
もちろん、風化する速さは水の量に大きく左右されますので、乾燥地域(状態)ほど遅くなります。また、同じ約30万年前の河岸段丘に含まれている砂岩礫では、表面が褐色になっているものの、くされ礫という状態にはなっていません。つまり、岩石の種類によっても風化の速度が異なることがわかります。
Q:「造陸運動」とはどのようなものですか?
(兵庫県 Kさん)
「造陸運動」
英語では,“epeirogeny”または“epirogenetic movement”といいます.19世紀末から20世紀初めに、世界中の山脈がどうやってできたかを議論しているときに出てきた理論です。
1890年にアメリカの地質学者G.K.ギルバートが初めて提唱し、1919年にはドイツの地質学者のH.シュティレが定義しなおしました。大陸のような広い地域が、地質構造の著しい変化なしに隆起したり沈降したりする地殻の運動のことです。ふつう、非常に長い時間をかけて徐々に起こる変動と考えられ、急激な造山運動とは区別され対立するものとされました。
つまり、造山運動を考えるときに、ゆっくりした運動を区別したものです。現在はこの考え方はほとんど使われていません。(日本地質学会会員 矢島道子)
Q:千葉県市原市田淵の白尾火山灰層は更新世前期、中期境界の国際模式地として認定されたのでしょうか?ゴールデンスパイクが打たれるのか話題になっていたようですが、その後のことがわかりません。教えて頂けますでしょうか。
(千葉県 どんぐりさん)
下部ー中部更新統境界の国際模式地については、イタリアの2セクションと千葉セクション(市原市田淵)の計3セクションが模式地候補となっていますが、これまではどの候補地も決め手に欠き、結論が先送りされてきました。しかし先の国際層序委員会(ICS)において、その下部組織である第四紀層序委員会(SQS)が2015年(来年)中に結論の原案を作成することが決定されました。正式な模式地としての承認は、国際層序委員会における委員の投票(おそらく2016年開催の万国地質学会で行われる)で決まるので、委員に対して候補地の地層が模式地としてふさわしいという印象を持ってもらう必要があります。そのため各候補地に関係する研究者グループでは、国際層序委員会の委員を交えた形のシンポジウムや巡検(地層の見学旅行)を企画しています。日本でも来年秋に名古屋で開催される国際第四紀学会の時に、関連シンポジウムや千葉セクションの巡検を企画しており、関係する研究者グループが鋭意準備中です。もしこれらの活動が実を結び、晴れて模式地としての承認を受ければ、再来年には市原市田淵に日本で最初のゴールデンスパイクが打たれることでしょう。
******************************************************************************
GSSP(Global Boundary Stratotype Section and Point)は,国際層序委員会のワーキンググループやその上位委員会での何段階かの議論,投票を経て,最終決定する見込みです(2017年頃予定).(2015年11月追記)
*******************************************************************************
2015年夏に行われた国際第四紀学連合(INQUA)名古屋大会で、当初2015年秋であった申請書提出の締切が2016年末に延期され、さらに2016年8月に行われた万国地質学会で、2017年5月を申請書提出の締切とすることが決まりました。正式な模式地としての承認は、下部ー中部更新統境界作業部会(L-M boundary WG)、SQS、ICS、そして国際地質科学連合 (IUGS) における委員の投票(それぞれの段階で数ヶ月程度かかる)で決まるので、最終決定は早くても2018年中旬と目されます。現在各候補地に関係する研究者グループでは、申請書作成のための最終的な作業を行っています。(2016年10月11日追記)
Q:原発の活断層問題に関心があります。テフラによる地層の年代同定について、地質学の専門家が、以下のようなコメントをされていますが、
「例えば1mのローム層を10cm毎に連続サンプリングし、ある層準で3,000 個数えて斑晶鉱物が100 個有り、その上下で30 個、さらにその上下で10 個ということであれば説得力があると思います。しかし、1mのローム層のうち、ある層準だけに3,000 個数えて斑晶鉱物が1 個未満でその前後で検出できなければ、信頼性はかなり低いと言わざるを得ないと思います。」
ここで、「3000個数えて」と言っていますが、
(1)3000個とは何をどのようにとると考えれば良いのでしょうか?すなわち、地層には火山灰のみでなく、いろいろなものが堆積して形成されると思うのですが、それらを含めて定義しているのか、あるいは例えばある大きさのテフラ鉱物のみをスクリーニングしたものを取るのか等について教えてください。
(2)また、なぜ3000個に対して数十個以上の斑晶鉱物がなければ(特定?)テフラとして同定する上で信頼性が低いと考えておられるのでしょうか?
(3)また、専門家のコメントでは、
・テフラの降灰時期にピークがあるはず
・何十cmも積るはずである
とも読めるのですが、どう考えればよいのでしょうか?
(千葉県 片山 昇さん)
※質問文頭の数字がそれぞれ回答文頭の数字に対応しています。
(1)まず,ご質問では専門家はローム層のことについて述べておりますが,ローム層は風成の堆積物で,日本の場合,火山灰や,その再堆積物,土壌等のちりなどからなっています.この場合は,ローム層のある特定の層準を検討した時に含まれる鉱物粒子全体のなかで,火山灰起源である斑晶鉱物のことを言っていると考えられます.
これが砂礫層の場合では,その場所が火山から遠く離れているなら,火山起源の鉱物はそれほど大きな粒径にはならないので,砂サイズの粒子だけふるいで集めて,その中で摩耗していないきれいな鉱物が火山灰起源と考えて数を数えていると思われます.特に,角閃石,輝石,β-石英は火山灰によく含まれ,周囲の岩盤中に含まれていないとすると,それらの内できれいな形をしているものを火山灰起源としてカウントしているのではないでしょうか.
(2)テフラを同定する上では通常,他の層準と比べて,区別できる程度の量の斑晶鉱物が含まれていないと,それがその時点で降ってきたテフラかどうか認定できません.肉眼で見て火山灰層であると確認できない場合,地層中に火山灰起源の鉱物がどのくらい混じっているかで,火山灰が降った層準かどうかを判断しますが,特に水中でたまった堆積物の場合には,火山灰起源の鉱物が再堆積して,幅広い層準に散らばってしまうことがあります.従って火山灰起源の鉱物が見つかったからといってその層準が降灰した時期とは限りません.個数は別にして,他の層準と区別できるだけの量が認められた時(ピークが有る時),テフラが存在する,あるいは降灰があったと認定できる可能性がでてきます.
ただし,注意しなければならない点として,複数の火山灰起源の鉱物が混じっていることがよくあります.その場合には,個々の鉱物の屈折率や化学組成を求めて,複数のグループに分けられるかどうか,そしてその各々のピークが別の層準にあるかどうかといったことで識別しますが,類似した特徴を持つ火山灰は多く,また組成にも幅があることから,識別は難しいのが普通です.有意な違いを見つけるためにはそれだけ多くの粒が必要になるのです.
(3)降灰時期のピークに関しては上述のとおりです.
何十cmがどのような場面で言われたのかよくわかりませんが,一般論として,周囲に例えば20cm厚のテフラがあれば,その地域もほぼ同様に降灰があったと考えられますが,それがその後の降水等によってどう流出し,どう残るかは別の問題だと考えられます.
Q:尼崎市は武庫川と猪名川に囲まれた沖積層平野ですが、通常、地形をご説明するとき「大阪湾に下る三角州上に立地」と述べています。先日『「三角州」とはあくまで広辞苑にもあるように「ほぼ三角形」の形状の土地を指すのであって、尼崎市の地形は「三角州」ではないのではないか』、というご指摘をいただきました。そこでご質問なのですが、地質学的に言って、尼崎市の地形は「三角州」に分類されるのでしょうか。
(兵庫県 あまっこさん)
ご質問にお答えします。尼崎市の地形は「三角州」に分類されます。
三角州という用語は,ナイル川の河口域が地中海に向かってギリシャ文字のデルタ(Δ)に似た形で突き出ていることから,紀元前5世紀にヘロドトスによって作られたと言われています。一般に三角州とは,河川からの活発な土砂の供給にともなって,沖合方向へ前進した堆積物の集合体(専門用語で「堆積体」と言います)で,周辺の海岸線に比べて沖合に突き出していることが最も大きな特徴です。一方,三角州の形は,河川から供給される土砂の供給量や粒度,さらに河口周辺で作用する波浪や潮流の強さなど,様々な要因によって変化することが知られています。したがって,三角州の中には,「ほぼ三角形」の形状を示さないものも多数認められています。例えば,メキシコ湾に注ぐミシシッピー川の河口域に形成された三角州は,鳥の趾のような形状を示すため,鳥足趾状三角州とよばれています。また,東京湾アクアラインの千葉県側の基点が設置されている小櫃川の河口域では,円弧状の形状を示す三角州が形成されています。
尼崎市が立地する沖積平野の海岸線を詳しく見てみますと,埋め立てなどの影響で多くの場所で海岸線の形状が人工的に改変されてはいますが,武庫川の河口域が周辺の海岸線に比べて大阪湾に向かって突き出していることが読み取れます。このような特徴から,尼崎市が立地する沖積平野が三角州として発達してきたことが理解されます。これまでの研究(Web版尼崎地域史事典「apedia」)で,武庫川は六甲山地を起源とする花こう岩質の砂礫を多量に運搬したために,河口域で三角州を発達させたと考えられています。これに対し,近隣の猪名川では,上流域に花こう岩が発達していないため土砂の供給量が少なく,河口域で三角州が発達しなかったと考えられています。このように,波浪や潮流の強さがほぼ一様な大阪湾に注ぐ河川の河口域を比べた場合,河川による土砂の供給量の違いによって,三角州が発達する場合としない場合のあることが理解されます。
花崗岩についてお尋ねします。庭に花崗岩の砂利が敷いてあります。原発事故の影響が気になって最近エアカウンターという線量計を買ったのですが、それで計測すると砂利の上の線量が0.08〜0.1くらい上がってしまいます。花崗岩にウランが含まれているというのは理解できたのですが、それがラドン・ポロニウムを放出し、呼吸によって内部被ばくするというのをきき、とても不安です。岩盤でなく砂利でもポロニウム等を放出しているのでしょうか。それはどれくらいの量なのでしょうか。
(愛知県 あかつきさん)
花崗岩にかぎらず、自然の岩石には極微量の放射性元素がもともと含まれているため、微量の放射線が出ています。この放射線のほとんどは岩石に含まれるカリウム、ウラン、トリウムから出されるもので、測定される放射線の強さはこれらの含有量によってほぼ見積もることができます。
例えば、愛知県で多く使われる三河地域の花崗岩には、カリウムが約5%、ウランが約1〜5ppm、トリウムが約10〜20ppm程度含まれています。この岩石の分布する場所での地表から1mの高さでの放射線量は約0.15マイクロシーベルト/hと見積もられ、線量計で測定される放射線の内訳はおよそ6割がカリウムによるもので、残りの1割がウランによるもの、3割がトリウムによるものと考えられます。
放射線量の6割以上を占めるカリウムの崩壊でできる元素は、カルシウム-40またはアルゴン-40でどちらも安定同位体で放射線は出しません。
ウランやトリウムがいくつもの段階を経て崩壊していく過程の一部に、ご質問にあったラドンやポロニウムが現れます。
ご質問のラドン・ポロニウムの生成量を大雑把に見積ってみます。
ウラン濃度5ppmの花崗岩1kgがあった場合、ここに含まれるウランの放射能の量は約60ベクレルなので、1年間に約20億個のウラン原子が崩壊すると見積もられます。ウランが放射平衡状態にあるとすれば、大雑把には、崩壊したウラン原子とほぼ同じ数のラドンが現れると見ることができます。仮に1年間にできるラドンを気体として全て集めたとすると、その体積は約7×10-14リットル(1リットルの700万分の1のさらに1億分の1)となり、非常にわずかな量であることが分かります。
ポロニウムは、ラドンが崩壊して生成される娘核種なので、現れる原子数は同じ程度です。実際には、ラドン222は半減期3.8日、ポロニウム218は半減期3.1分、ポロニウム210でも半減期138日で崩壊するため、このように1年分を集めることはできず、存在量はさらに小さなものになります。
また、花崗岩に含まれるウランの多くの部分は鉱物結晶の中に固定されており、崩壊で生じたラドンは、ほとんど結晶の中から動くことなく短期間に崩壊し生成される娘核種もその場に留まったままになると考えられますので、岩石の外へは殆んど放出されないと考えて良いでしょう。
花崗岩は自然の岩石の中では比較的放射線量の高い岩石ですが、庭に砂利として撒いても周辺への影響は無いと思われます。心配な点があるようでしたら、三河地域や岐阜には岩盤全てが花崗岩でできている地域が広がっていますので、そのような地域での昔からの生活状況などを確認されてはいかがでしょうか。
以下のページに自然の岩盤から見積もられる自然放射線量を地図に示していますので、地域ごとの岩盤から受ける放射線量の参考にしてみてください。
http://www.geosociety.jp/hazard/content0058.html
なお、インターネットなどで自治体等が報告している放射線量は、地上1m(胸の高さ)で測定した値である場合が多く、地面に測定器を置いて測定した値とは異なります。また、線量計の種類・特性によっても表示される値は大きく異なりますので、他の報告値と自分の測定値を比較する際には注意が必要です。
Q:滋賀県蒲生郡日野町鍵掛のシャクナゲを見に行きましたが、遊歩道沿いの岩肌が層状になっていてとても不思議でした。あたりには石灰岩地域に生育するイワカガミがたくさんありました。この岩はどういうものなのか教えていただけたら幸いです。
(奈良県 ちょびさん)
ご質問の岩石は,チャートではないでしょうか。
正確な位置がわかりませんが,滋賀県蒲生郡日野町鍵掛のシャクナゲ群落の付近には,チャートという岩石が分布しています。
チャートは堆積岩の一種で,二酸化珪素(SiO₂)を95%以上含んでおり,緻密で非常に硬く,割れ目は鋭いです。
層状,塊状,ノジュール状のものがありますが,この地域では層状のものがよく見られます。層状チャートは,放散虫など微生物の遺骸が大陸から遠く離れた深海底で堆積した遠洋性堆積物と考えられています。
((独)産業技術総合研究所,20万分の1日本シームレス地質図より)
岩肌が層状になっているとのことなので,ご質問の岩石はチャートではないかと思われます。
該当地域の地質については,20万分の1日本シームレス地質図のサイトもご参照ください。
Q:原子力発電所の活断層問題に関心があります。活断層が動いた場合、その近傍の地層が引きずられて動く(副断層)ことは素人でも想像がつくのですが、過去の活断層による地震の際、活断層からどの程度の距離では、どの程度副断層(岩盤まで届く)が出来、どの程度動いたことがあるのか、データはとられているのでしょうか?もし、整理されたデータがあれば、リンク先を教えてください。整理されたデータがなければ、例をいくつか教えてもらえないでしょうか?(ちなみに、原子力規制委員会では、活断層から1Km以内は何が起こるかわからないと言った議論が行われていました。)
(千葉県 片山 昇さん)
地震断層で生じた断層帯の幅については,1)主断層の周辺に副断層が生じることによる幅の広がりと,2)主断層自体がステップしながら延びることによるステップ区間での幅の拡がり,の2つに分けて考える必要があります.そこで,断層帯の幅について,1)と2)について以下の資料を紹介させていただきます.
副断層でのずれの量については,主断層よりも小さいことは当然ですが,さまざまなケースがあり,幾つかの地震断層について詳しい調査もなされていますが一般化した論文は見かけません.
[資料1]
粟田泰夫(2007)2.1 地震断層の実測データ収集.H19年度原子力安全基盤研究「断層帯近傍における変形帯の幅に関する研究, p.4-18 http://www.atom-library.jnes.go.jp/H19_6_11.pdf
[解説]
1)主断層の周辺に副断層が生じることによる幅の広がりについて,カリフォルニア州の1992年Landers地震,1995年兵庫県南部地震,トルコの1999年Izmit地震の事例から,概ね数10m以下としています.(図2.1.1-1;図2.1.1-4,図2.1.1-5を参照して下さい.なお,地震断層のイメージを示した図2.1.1-8では,主断層が太い実線で示されています)
2)主断層自体がステップしながら延びることによるステップ区間(「ジョグ」と呼びます)での幅の拡がりについては,そのイメージが図2.1.1-8では網掛けの長方形で示されています.このジョグの中では,多くの副断層が生じています.図においてランク1とされる小さいものではジョグの幅が数10m程度ですが,ランク3の大きなジョグでは幅が数km以上に及ぶ例もあります.
なお,厳密に言いますと,1)の主断層の周辺に生じる副断層と,2)の小規模なジョグとされる断層とは,同じものを指す場合が少なくありません.
[資料2]
Lettis et al.(2002)Influence of Releasing Step-Overs on Surface Fault Rupture and FaultSegmentation: Examples from the 17 August 1999 I˙zmit Earthquake on the North Anatolian Fault, Turkey.Bulletin of the Seismological Society of America, vol.92, n0.1. p.19-42.
[解説]
主断層がステップすることによって生じるジョグの規模を,世界中の地震断層から抽出してまとめたデータが,表3と図10に掲載されています.ジョグは,a)地震断層の中間部に生じたもの,すなわち1回の地震による破壊が次々と飛び越えていったものと,b)地震断層の末端部に生じたもの,すなわち断層の破壊が伝わるのを止めた大規模なものとに,大きく2区分されています.(このイメージも,上記の資料1の図2.1.1-8を参考にして下さい)
a)地震断層の中間部に生じたジョグでは,最大で2-4kmまで断層帯の幅が拡がるとされています(図10の白丸).
b)地震断層の末端に生じたジョグでは,隣り合う別の地震断層の末端との間に2-10kmにも及ぶ大きな幅の断層帯が形成されます(図10の黒丸).ただし,このように大規模な末端部のジョグでは,多くの副断層が生じても,その分布密度は a)と比べて相対的に小さいとも考えられます.
Q:地質学の以下の4つの法則は、地質分野の中では一般的にオーソライズされているのでしょうか?
[1]地層累重の法則 [2]堆積初期の地層水平の法則 [3]堆積初期の地層連続の法則 [4]地層切断の法則
[1]は、私の周囲の大部分の方は認知しているのですが、[2]〜[4]はあまり聞いたことがないということでして、地質学の4つの法則としてオーソライズされているのか教えて頂けないでしょうか?
(埼玉県 匿名希望さん)
お問い合わせの件は,斉一過程原理とあわせて地質学の古典的な基本原理と呼ばれるものです.これらは層位学の基礎となるものではありますが,必ずしも現在の堆積学の知識とは整合しないことは予めお含みください.陶山国男・羽田忍共著, ”現場技術者のためのやさしい地質学”築地書館刊に記載がありますのでご参照ください.
(a) 地層累重の法則
1791年にウイリアム・スミスによって提唱された層位学の基本法則であり,”地層は基本的に万有引力の法則に従って,下から上に向かって堆積する.下にあるものほど、古い.”という層位学の基本的な考え方であり,地層の新旧や年代判定を行う上での基本原理といえる.
広義の地層累重の法則は次の3つの法則からなる.
<第1法則>地層は水平に堆積する(初原地層水平堆積の法則.Law of original horizontality).
<第2法則>その堆積は側方に連続する(地層の側方連続の法則.Law of lateral continuity).
<第3法則>古い地層の上に新しい地層が累重する.
(b) 堆積初期の地層水平性の法則(=地層累重の法則の第1法則)
”水成の堆積物は、ほぼ水平に堆積し,しかも堆積する下の面に平行か、あるいは平行に近い層になって堆積する.”という趣旨.
(c) 堆積初期の地層連続の法則(=地層累重の法則の第2法則)
”水中で堆積した層は,それが作られたときには横のあらゆる方向に連続していて,その縁の方では,堆積作用が行われないために薄くなって消え去っているか,あるいは堆積盆地の周辺では古い地層や岩石に接して終焉している.”という趣旨.
(d) 地層切断の法則
”地層がその堆積した盆地の縁以外の地点で急に途切れている場合は,浸食によって削除されたか,断層等の構造運動によって移動された.”という趣旨.
(e) 斉一過程原理
ジェームズ・ハットンとチャールズ・ライエルによって導入された地質学古生物学の基本原理であり,"現在は過去の鍵である".すなわち、”現在私たちの身近に起こっている自然現象によって,大昔に作られた地層の生成を説明することができる”という趣旨.
Q:北海道の支笏火山のことですが、支笏火山の大噴火の時期について3万2千年前とする表記と4万年前とする表記の二つあり、身近では、2004〜2008年頃のものには3〜4万年前、2009年以降には4万年前が多いようです。統一されていますか?また、2009年の「第四紀下限の変更」と何か関係がありますか?
(北海道 EDOさん)
現在の支笏湖を形成した噴火では大きく分けて支笏降下軽石堆積物(Spfa1)と支笏火砕流堆積物(Spfl)が噴出しました(勝井,1959;曾屋・佐藤,1980など).下位のSpfa1中にはしばしば炭化木が含まれることから,古くは1950年代から放射性炭素年代の測定対象となってきました.Spfa1に埋没した木はSpflの熱で炭化したと推定されるため,炭化木が形成されたのはカルデラ形成とほぼ同時と見ることができます.
1980年代頃までにおこなわれた測定は測定限界が若く,3〜4万年前という測定値は検出限界に近い年代です。また,試料の化学洗浄法なども確立されておらず,現世の若い有機炭素が混入して若い年代が出ていた可能性もあります.
1980年代後半以降は,加速器を利用した放射性炭素年代測定の手法が実用化され,精度が向上しました.その結果,ほぼ同じ場所の炭化木から4万年前前後の測定値が報告されるようになりました。しかし,それらの年代値も,現世の炭素の影響が完全に取り除かれていないためか,4万年前を中心として,その前後3千年ほどばらついているのが現状です.そのため,最近になって多くの人が4万年前頃という放射性炭素年代を支持するようになったという状況であり,2009年の「第四紀下限の変更」とは関係ありません.
(古川竜太 産業技術総合研究所)
Q:氷河期に関して。
氷河期と氷河期の間を間氷期と表現する記事と、温暖期と表現する記事を見ます。1)どちらが正しいのでしょうか?またその根拠は? 2)氷河期と間氷期の区別は? 氷河期が終わった、あるいは氷河期に入ったという判断は何を持ってそのようにしているのでしょうか?酸素同位体比は我々が日常使う温度表記ではなく相対温度になってしまいよく判らないのです。
(匿名希望さん)
地球の歴史の中で,大陸に氷床が発達した時期を氷河期と呼びます.氷河期の中でも,相対的に寒冷で氷床が発達した時期を氷期,氷期と氷期の間の相対的に温暖で氷床があまり発達しなかった時期を間氷期と呼びます.一方,氷河期であるなしに関わらず,地球の歴史の中で相対的に気温や海水温が高かった時期は温暖期と呼ばれます.したがって,間氷期と温暖期は定義が異なります.まず,氷河期と氷期・間氷期に関して正しい定義を理解して下さい.
氷床が発達した時期や場所は,陸上でみられる氷河成の地形や堆積物から分かります.現在では,地球の歴史では,4回の大きな氷河期があったとされています.それらは,先カンブリア時代古原生代および新原生代,オルドビス紀〜シルル紀,石炭紀〜ペルム紀,第四紀です.なかでも新原生代(クライオジェニアン紀)は地球の歴史で最も氷床が発達した時期で,地球は氷床に覆い尽くされたことが分かっています(全球凍結事変).
かつて第四紀の氷期は,氷河成の地形や堆積物から識別されていました.有名なギュンツ氷期やミンデル氷期等の名称が,それに該当します.しかし,近年,有孔虫の殻の酸素同位体比が,氷床の発達と衰退に伴う海水の酸素同対比の変化を反映していることが分かり,
・北半球の高緯度域に氷床が形成・発達したのは,約260万年前からであること
・氷期・間氷期は約90万年前までは4万年周期で繰り返し,30万年間の移行期間を経たうえで,60万年以降は10万年周期で繰り返して来たこと
が明らかとなり,氷床の発達と衰退には,地球が太陽の周りを公転する際の軌道要素の周期的な変化が大きく関わっていると理解されています.
(井龍康文 東北大)
Q:過去の地球を知ることで私達社会にどのような利益をもたらすのですか?
(匿名希望さん)
盛岡高等農林学校の大正5年の夏季地質調査実習に参加した宮澤賢治を含む学生たちの報告書には次のように書かれています(現代語に直してあります)。
「地質学は、私たちが生活している地球の成り立ちを追求し、現在の地殻の構造を解明し、また地殻に起こるいろいろな変動について、その原因と結果を説明する。たとえば(子供に)我が家の歴史を教え、その成立と発展を理解させるようなもので、いやしくも知能をそなえたものに多大な興味を与えることは、論じるまでもなく明らかである」。
あなたの先輩たちが見事に述べているように、過去の地球を知ることの利益は、まずこのように知能をそなえた人間として当然持っているはずの、自分たちが生活しているこの大地の構造や歴史への興味に解答を与えることです。つまり、まず「自分自身を知る」こと、「人間をつくる」ことに役立つと言えるでしょう。
過去の地球を知ることだけで、私たち社会に直接利益をもたらすことは一般にはあまり知られていません。自然の風景(地形や地質)ができるストーリーは、過去の地球を知ることによってイメージが湧くものが多く、ジオパークなどで活用されています。
しかし、もっと重要なことは、過去の地球から現在までの変化を知ることが、これからの地球の変化を予測するための基礎資料になることだと思います。また、過去に起こったことが理解できれば、現在起こっていることを理解する助けにもなります。例えば、地質に起因する自然災害(地震、火山、地すべりなどの斜面崩壊、液状化など)は、過去の歴史を知ることによって、今後どのようなことが起こるかを推測できます。温暖化・寒冷化などの気候変動も、過去からの変化を理解することによって、今後起こりうることの推測につながります。また、鉱産資源などは過去にできた地層・岩石の中にあるので、過去にどのような状況でできたかを知ることによって、鉱産資源の探査ができ、社会の役に立ちます。また、過去にどのような場所でできた地層か調べることは、その場所に建物を建てたり、人が住んだりして良いか?、どういう工法をとったらいいか?という判断の助けにもなります。
まさに過去の地球をよく知ることによって、私たちが地球と共に生きていく重要な情報になるのです。
過去の地球のことを研究した成果(例えば地質図など)が社会にどう役立っているか、について、以下のサイトに資料がありますので参考にしてはいかがでしょうか。
(独)産業技術総合研究所地質調査総合センターWeb
「地質図の利用」
http://www.gsj.jp/geology/geomap/geomap-use/
経済産業省Web
http://www.meti.go.jp/committee/summary/0003843/004_haifu.html
の参考資料2 知的基盤の活用事例集p.100-119,p.120-145
(地質学会 斎藤 眞・石渡 明)
Q:地層は、様々なものが堆積して出来るということですが、どうしても分からない点があります。
上の図の、[1]が初めの状態だとしますと、それぞれ長い年月の間に各地点の土などが風雨によって運ばれ[2]のように別の場所へ移動します。1ヶ所だけみていますと、確かに積っていきそうですが、地球上満遍なくこれが起きると考えると一旦積った土などもまたどこかへ移動していかざるを得ず、堆積していかないように思えるのです。別の例えをしますと、山の土が削れてその周辺地帯に堆積するのは分かるのですが、地球全体満遍なく起るのは、山のない平野もありますし、おかしい。その土はどこから来たのか?部分的なら分かりますが、地球上満遍なく起る点が分からないのです。
(千葉県 H.M.さん)
山などが削られ、削られて運ばれた土砂が堆積して地層ができるというのが主な地層のでき方です。地球上には、削られやすい場所と堆積しやすい場所があり、今の瞬間を見れば地層のできる場所は堆積しやすい場所(湖や海などの凹地)に偏っています。このため、地球上満遍なく堆積が起きているという考えは正しくはありません。
しかし、地球の時間のスケールで見た場合は異なります。
数万年単位で見ると、気候変動により海水面が上下して、平野が海になり堆積しやすい場所になったり、浅い海が陸になり削られやすい場所になったりします。
さらに、数億年単位でみると、地球を覆うプレートの動きにより海底の堆積物が陸に持ち上げられたり、ヒマラヤなどの山脈が作られるような現象が起きたりするなど、削られやすい場所と堆積しやすい場所が大きく変化していきます。
現在地球上で見られる地層の様子は、このような長い地球の歴史を通じて起きた作用が足しあわされた結果なのです。
上町断層によって撓曲した大阪層群の貴重な露頭が消失の危機に
上町断層によって撓曲した大阪層群の貴重な露頭が消失の危機に
中条武司(大阪市立自然史博物館)・廣野哲朗(大阪大学)
閑静な住宅地に囲まれた大阪府豊中市西緑丘に,佛念寺山断層(上町断層)の活動によりほぼ直立に撓曲した大阪層群の露頭があります(図1).この学術的にも教育的にも貴重な露頭が開発により失われようとしています.この問題について広く地質学会学会員の方に報告し,露頭保存のあり方について一考いただければと思います.
大阪層群は,大阪北部の千里丘陵を模式地として,層序,火山灰,古地磁気,化石,地球化学,地盤工学などの面から様々な研究が行われ,日本の第四系の標準層序として確立しています.しかし,高度成長期以来の都市開発により,地表部で大阪層群を確認できる箇所は非常に限られています.また,上町断層は大阪平野を南北に貫く第一級の活断層です(北部では佛念寺山断層と呼ばれます).政府の地震調査研究推進本部では,30年以内に2-3%の確率でのM7.5規模の地震発生の可能性が報告されています.様々な機関が今までに実施した調査の結果(主に地下構造探査),上町断層(佛念寺山断層)は地表から地下1-2 kmでは明瞭な断層として発達しておらず,撓曲構造をなしていることがわかっています.
この豊中市西緑丘の露頭は,模式地である千里丘陵に残された数少ない大阪層群の露頭であり,かつ地表で上町断層による撓曲構造を観察できる唯一の露頭でもあります.また,「新修豊中市史」や豊中市が発行する「とよなか文化財ブックレット」,豊中市が選ぶ「とよなか百景」で「直立した地層」として紹介されており,地元でもよく知られている露頭です.他にも,菅野・柴山(1987)により学校教材としての重要性が紹介されたり,地学団体研究会大阪支部が1998年発行した「関西自然史ハイキング」において,千里丘陵の大阪層群の見学コースの一地点として紹介しています.これはこの露頭が都市域に残された地質現象を観察できる貴重な場所として,普及教育面においても重要な露頭であることをあらわしています.
しかし,この露頭を含む土地が平成22年に豊中市から民間に売却され,近々,民間の事業による開発工事によって消失する可能性があり,開発を知った地元の方々から開発反対の声が上がっています.報告者らは地質学の専門家として,保存を求める地元の方々に,この露頭の学術的意義や活用方法などへの助言を行っています.
本来ならば,大阪府や豊中市もしくは国が,天然記念物や文化財として認定し恒久的な保存,教育活動や防災面での啓発活動での活用が望ましいのですが,残念ながら露頭を含む土地の売却に至ってしまいました.一方で,1995年の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災),2011年の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)以降,日本国民の地震や活断層への意識は非常に高まっており,都市に伏在する活断層の活動を直接目にすることのできる露頭として,その重要性はますます高まっています.これはこの露頭が学術的価値のみならず,防災教育や理科教育の観点からも重要な保存すべき露頭であることを示しています.一方,大阪層群という未固結層のため,露頭が崩落する危険や,その保存維持には費用や手間がかかるという問題もあります.
開発によりこの露頭が失われるか,地元の反対運動により保存へと向かうのか現状ではわかりません.しかし,この問題は開発の危機にさらされる可能性の高い都市部の重要露頭の現状を端的に表しているといえます.
図1.開発により消失の危機にある上町断層の活動によって撓曲した大阪層群の露頭.
【文献】
地学団体研究会大阪支部編,1998,関西自然史ハイキング.創元社,大阪,306pp.
菅野耕三・柴山元彦,1987,大阪府豊中市緑丘にある垂直層の見える崖の教材化.大阪教育大学理科教育研究年報,11,27-36.
豊中市教育委員会,1985),とよなか300万年−大地のなりたちから旧石器時代まで−.とよなか文化財ブックレットNo.1,18pp.
豊中市市史編さん委員会編,1999,新修豊中市史 第3巻 自然.豊中市,720pp.
地震調査研究推進本部地震調査委員会「上町断層帯の長期評価について」http://www.jishin.go.jp/main/chousa/04mar_uemachi/index.htm 2013年1月23日閲覧
とよなか百景「直立した地層(西緑丘)」http://www.city.toyonaka.osaka.jp/top/bousai/toshikeikan/hyakei/shouji/nisimidorigaokachisou.html 2013年1月23日閲覧
(2013.1.25)
geo-Flash No.210(臨時)フォトコン締切迫る!連合大会は受付開始!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.210 2013/1/29 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】第4回惑星地球フォトコンテスト:締切間近!!
【2】連合大会(JpGU)の投稿・参加登録はじまる!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】第4回惑星地球フォトコンテスト:締切間近!!
──────────────────────────────────
まもなく応募締切です。たくさんのご応募お持ちしています。
締切:2013年1月31日(木)17:00
大学生、高校生の作品も大歓迎。
iPhoneなどで撮ったスナップなども受け付けています。
投稿はWebフォームから簡単です。
【こんな作品を大募集!】
・惑星地球の美しい自然
・地層や火山など活きた地球の姿を表す優れた作品
・学術的意義の高い作品(解説文を含む)
・ジオパークに関係する優れた作品
・「ジオ鉄」の優れた作品学術的・教育的な価値のある優れた作品
・そのほか地球科学に関係した作品
応募方法など詳しくは,http://photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】連合大会(JpGU)の投稿・参加登録はじまる!
──────────────────────────────────
2013年連合大会(5/19-24)の投稿・参加登録の受付が始まっています。
投稿早期締切:2月3日(日)24:00
投稿最終締切:2月15日(金)12:00
http://www.jpgu.org/meeting/submission.html
なお,日本地質学会は次のセッションの提案母体になっています.
(カッコ内はセッションID,代表コンビーナ)
・津波堆積物(M-IS25, 後藤和久)
・地球科学の科学史・科学哲学・科学技術社会論(M-ZZ41, 矢島道子)
・変形岩・変成岩とテクトニクス(S-MP43, 石井和彦)
・人間環境と災害リスク(H-SC25, 青木賢人)
・火山・火成活動とその長期予測(S-VC53, 及川輝樹)
・Collision, Subduction, and Metamorphic processes(S-CG07, Ur Rehman Hafiz)
・地域地質と構造発達史(S-GL41, 束田和弘)
・活断層と古地震(S-SS32, 吾妻 崇)
・ジオパーク(M-IS32, 目代邦康)
・堆積・侵食・地形発達プロセスから読み取る地球表層環境変動(H-CG33, 藤野滋弘)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
第4回フォトコン入選作品:優秀賞01
第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品
第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品:優秀賞「ホイールストーン」
写真:堀内 勇(和歌山県) 撮影場所:根室市花咲港 根室車石
【撮影者より】
昭和14年9月に指定された国の天然記念物「根室車石」。
その奇観と大きさは世界でも類を見ないことで知られています。
前に立つと、そのどっしりとした風格に引き込まれそうな気がしました。
【審査委員長講評】
夕焼け空を背景に根室の車石を撮影した作品です。背景の夕焼け空が明るいので、空に露出を合わせると車石は真っ黒になってしまいます。この作品で階調が出ているのは、撮影後にHDR(ハイダイナミックレンジ)処理をしたか、撮影時に段階露出によってHDR合成をしているためでしょう。車石は人気のある撮影対象ですが、この作品はデジタル処理によって見慣れた車石とは違った、格調高いものとなっています。(白尾)
【地質的背景】
(準備中)
←戻る 目次 進む→
geo-Flash No.211 地質系統・年代の日本語記述ガイドライン改訂
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.211 2013/2/5 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】地質系統・年代の日本語記述ガイドライン 2013年1月改訂
【2】日本学術会議大型研究計画マスタープランへの応募
【3】日本地質学会は日本学術会議の提言「地質地盤情報の共有化に向けて」に賛同します
【4】学会サイトにコミュニティ機能を追加しました
【5】TOPIC:上町断層によって撓曲した大阪層群の貴重な露頭が消失の危機
【6】2013年仙台大会:トピックセッション募集中
【7】連合2013年大会:予稿投稿・事前参加登録受付中
【8】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
【9】地質図の在庫一掃セール!— 2013年3月末日まで
【10】支部情報
【11】その他のお知らせ
【12】公募情報・各賞情報
【13】地質マンガ:デジタル派 VS アナログ派
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】地質系統・年代の日本語記述ガイドライン 2013年1月改訂
──────────────────────────────────
地質学会のホームページに掲載されている地質系統・年代の日本語記述ガイドラインを改訂しました(http://www.geosociety.jp/name/content0062.html).
これは,JIS(ベクトル数値地質図—品質要求事項および主題属性コード;JIS A 0205: 2012)における地質系統・年代の表記を,International Commission on Stratigraphy(国際層序委員会)の発行したInternational Stratigraphic Chart(ISC,国際年代層序表;2012年8月発行)に当てはめた原案を,地質用語国際標準対応委員会で検討したものです.なお,従来のものは,2008年発行のISCの日本語版でした.今後,一般社団法人日本地質学会刊行の公式出版物(地質学雑誌等)においては,原則として,この年代表記に従っ て下さいますようお願いいたします.
年代表はこちらから,http://www.geosociety.jp/name/content0062.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】日本学術会議大型研究計画マスタープランへの応募
──────────────────────────────────
日本地質学会会員各位
本募集において,コミュニティ合意に関して言及することが求められているようです.コミュニティの中に日本地質学会を含めることを希望される方は,メールして応募内容をまとめた「応募の概要」を井龍(iryu@m.tojhoku.ac.jp)までお送り下さい.その際,地質学会事務局(main@geosocirty.jo)にもメールをccで送っていただけますよう,お願いします.
遅くとも,締め切りの7日前(3月25日)までには御連絡下さい.
よろしくお願いいたします.
(日本地質学会担当執行理事 井龍康文)
-----------------------------詳細は下記のとおり-----------------------------
日本学術会議大型研究計画マスタープランへの応募を検討されている皆様
日本学術会議による大型研究計画マスタープラン策定に関する方針と,地球惑星科学分野における今後の進め方に関する方針がほぼ確定しました.応募予定の機関,学協会等におかれましては,方針をよくお読みのうえ,準備をお願いいたします.
なお,マスタープラン掲載計画は大規模予算をともなうため,概算要求を提案できる中心的組織の存在が必須となりますので,十分にご注意お願いいたします.
1.学術会議方針
(1) 策定方針
学術会議方針は,学術会議web サイト(http://www.scj.go.jp/)にて公開中(注:必ずお読みください)
(2) 公募期間
公募期間は 2013年2月15日 - 2013年3月31日
(3) 応募方法
学術会議内に設置されるウェブサイトより入力
(4) 応募内容
・現在まだ確定していませんが,マスタープラン2010,2011を参考に準備をおすすめください.
・具体的には,計画タイトル,概要,予算規模,年次計画,主な実施機関,研究組織,準備状況,コミュニティ合意,社会的価値,他の研究費を充てることのできない理由,等につき,説明についてはそれぞれ数百字程度が求められる見込みです.また,説明の図1ページが求められると思われます.
(5) 審査・評価方法(一部策定方針と重複)
・学術大型研究については,学術会議の分野ごとに”評価分科会”を設置し,そこにおいて課題の絞り込み等の審議をおこなう・評価分科会は10名程度で構成し,原則として分野別委員長が評価分科会委員長をつとめる
・評価分科会委員会は,利益相反に十分に配慮して構成する
・評価項目は,学術的価値,科学者コミュニティの合意,計画の実施主体・共同利用体制の充実度,社会的価値,大型研究計画としての適否等とする
・評価分科会は,分野に出された全提案につき,5段階の総合評価をおこなう
・すでに予算化されている計画については,進捗状況が適切であれば,別表に掲載の方向で議論中
・日本学術会議大型研究計画検討分科会は,各分野の判断をもとに,諸バランスを考慮して学術の大型研究計画を策定する
・重点大型計画については,学術大型計画策定後に検討する
・審査は別途作られる審査小委員会においてこなわれる
2.地球惑星科学委員会方針
(1) 地球惑星科学評価分科会
・原則的に,日本学術会議地球惑星科学委員会企画分科会がこれを構成する
・利益相反に十分配慮し,必要であれば委員の交代をおこなう
(2) 審査・評価会
・日時:2013年4月5日(金)・6日(土)(時間未定)
・場所:東京大学地震研究所
・全提案に発表をいただくか,書類による絞り込みをおこない,一部の提案のみとするかは,全提案数が確定した後に決定します.
注:この件についてのご質問・ご意見等は,永原(hiroko@eps.s.u-tokyo.ac.jp)までお願いいたします
2013年2月1日
日本学術会議地球惑星科学委員会 委員長 永原裕子
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本地質学会は日本学術会議の提言「地質地盤情報の共有化に向けて」に賛同します
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会 会長 石渡 明
1月31日付けで日本学術会議地球惑星科学委員会より「地質地盤情報の共有化に向けて —安全・安心な社会構築のための地質地盤情報に関する法整備—」との提言がなされました.ボーリングデータをはじめとする地質地盤情報は防災・資源・環境に関わる社会的な諸問題を解決するために必要不可欠であることは,我々地質に関わる者にとって言うまでもありません.しかし地質地盤情報の整備・公開,そして情報の共有化は必ずしも進んでいないのが現状です.
日本学術会議の提言では,地質地盤情報が社会にとって極めて重要な情報であること,そして地質地盤情報の整備・公開・共有化を進めるためには,法律の制定,共有化等の仕組みの構築,利用促進と国民の理解向上が必要であることが述べられています.このような具体的な提言が日本学術会議からなされたことは極めて高く評価されるものであり,当学会もこの提言に共感し,賛同するとともに、この提言に沿った地質地盤情報の共有化が実現することを切に願うものです.
全文を読む、、、、、http://www.geosociety.jp/engineer/content0024.html
日本学術会議による提言:「地質地盤情報の共有化に向けて−安全・安心な社会構築のための地質地盤情報に関する法整備−」
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-t168-1.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】学会サイトにコミュニティ機能を追加しました
──────────────────────────────────
日本地質学会のホームページ(http:// geosociety.jp)の左メニューの「ログイン」からアクセスして頂きますと,Island Arcの無料閲覧,会員特別割引販売,住所等の会員情報変更などのサービスをご利用頂けます.このたび新しい機能が追加されましたので,お知らせいたします.
◆コミュニティ機能
ログインいたしますと,左の会員メニューに支部情報,専門部会情報,ブログなどの新しいボタンが増えています(図1).
専門部会,支部における情報交換:
専門部会および支部内の情報交換を目的とするものです(図2,3).メンバーに登録すると,ここにトピックスを作成して投稿・閲覧することができます(支部登録は各登録住所の所在地により自動的に登録済み).投稿すると,所属メンバーにメールとして通知されます.部会や支部の連絡網です.従来のメーリングリストとほぼ同じですが,発言内容がサーバー上に保存され,新規加入者を含めて過去ログを遡って閲覧できることがポイントです.また,オンラインで所属部会や住所を変更しますと,専門部会情報および支部情報の連絡網にも即座に反映されます.専門部会への登録は,「会員情報登録」からご自身で行っていただけます(最大3つまで登録可).
会員個人の情報発信:
個人のページとしてブログ(日記)を記録することができます.会員相互の情報交換と長期的な情報の蓄積を目的としています.非会員の方は閲覧できませんので,学会内の交流にご活用ください.左メニューの「ブログを読む」は,他の会員の方が書かれたブログの一覧がご覧頂けます.「ブログを書く」からはご自身のページにブログを記録するとこが出来ます.写真やファイルを添付することもできます.
積極的にご活用下さい!
日本地質学会広報委員会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】TOPIC:上町断層によって撓曲した大阪層群の貴重な露頭が消失の危機
──────────────────────────────────
中条武司(大阪市立自然史博物館)・廣野哲朗(大阪大学)
閑静な住宅地に囲まれた大阪府豊中市西緑丘に,佛念寺山断層(上町断層)の活動によりほぼ直立に撓曲した大阪層群の露頭があります(写真).この学術的にも教育的にも貴重な露頭が開発により失われようとしています.この問題について広く地質学会学会員の方に報告し,露頭保存のあり方について一考いただければと思います.
続きを読む、、、http://www.geosociety.jp/faq/content0428.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】2013年仙台大会:トピックセッション募集中
──────────────────────────────────
仙台大会は,東北支部のご協力のもと,仙台市の東北大学川内キャンパスをメイン会場として2013年9月14日(土)〜16日(月)に開催されます.
現在,トピックセッションを募集中です.トピックセッションは,広く地質学の領域をカバーし,これから新分野あるいは注目すべき分野になりそうな内容を扱うものとします.形式はレギュラーセッションと同じです(15分間の口頭発表,あるいはポスター発表).
なお,本大会も前回同様,シンポジウムの一般募集はありません.
募集締切:3月11日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0052.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】連合2013年大会:予稿投稿・事前参加登録受付中
──────────────────────────────────
連合2013年大会:予稿投稿・事前参加登録受付中
最終投稿締切 :2013年 2月15日(金) 12:00
事前(割引)参加登録締切 :2013年 5月 7日(火) 17:00
詳しくは,大会トップページ:http://www.jpgu.org/meeting/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地質学会では,災害救助法適用地域で被災された会員の方々のご窮状をふまえ,以下の措置を取らせていただきます.
「日本地質学会に届出の住居または勤務地が災害救助法適用地域に該当する会員のうち,希望する方」は2013年度(平成25年度)会費を免除することといたします.
2012年度中に,災害により被害にあわれた方のうち,この措置の適用を希望される会員は,(1)会員氏名(2)被害地域(3)被災状況(簡単に)を明記し,学会事務局までお申し出下さい.お申し出の方法は,郵送,FAX,e-mailのいずれでも結構です.
締切は,2013年2月25日(月)までとさせていただきます.
※ 通常の会費払込については,「2013年会費払い込みについて」をご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0108.html
2013年1月4日 日本地質学会会計委員会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】地質図の在庫一掃セール!— 2013年3月末日まで
──────────────────────────────────
※現在、地質学会に在庫があるものについてのみ、特別販売中です。
最新の在庫リストはホームページに掲載していますのでご覧いただくか、事務局(電話:03-5823-1150)にお尋ねください。
詳しくは,こちらから
http://www.geosociety.jp/news/n96.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】支部情報
──────────────────────────────────
■北海道支部
平成24年度総会・講演会
2月16日(土)14:30〜18:00
場所:北海道大学理学部6号館2階 6-204室
総会:14:30〜15:30
講演会:「北海道白亜系研究の最前線」
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
■西日本支部
西日本支部平成24年度総会・第163回例会
2月23日(土)
場所:島根大学総合理工学研究科
講演申込締切:2月15日(金)17時
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
■関東支部
第1回「房総・三浦地質研究サミット」開催のお知らせ(第3報)
日本地質学会関東支部は,『地質研究サミット』を開催します.関東地方の地質に対して鋭い斬りこみをかけている各研究グループの中心メンバーが一堂に会してホットな研究成果を発表するとともに建設的な議論を行い,関東地方地質研究の新展開を図ります.シリーズ1 回目は,房総・三浦半島です.
(*『地質研究サミット』は,全国に開かれたものとして運営されています.またCPD単位の取得が可能です.)
主催:日本地質学会関東支部
共催:千葉県立中央博物館,協力:横須賀市自然・人文博物館
期日:平成25 年3 月9 日(土)・10 日(日)
場所:千葉県立中央博物館(千葉市中央区青葉町955−2)
[交通案内 http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=204]
対象:日本地質学会員および一般の方(参加申込不要;参加費無料;要旨集1,000円予定)、参加者は無料で千葉中央博物館展示室の見学ができます。
懇親会:3月9日(土)18:00〜20:00 博物館内喫茶室「あおば」にて開催。会費:一般3,000円、学生1,500円。当日申込可能ですが、できれば事前に事務局(高橋直樹)あてメール(takahashin@chiba-muse.or.jp)で申し込みください.
【プログラム】演者および演題につきましては、次回ジオフラッシュにてご連絡いたします。
各セッションも最後に討論を行います。
3月9日(土)
9:30- 受付
10:00-10:05 開催あいさつ
10:05-12:00 セッション1 房総・三浦半島の地質:全体像 前半
12:00-13:00 昼休み
13:00-14:00 セッション1 房総・三浦半島の地質:全体像 後半
14:00-14:40 セッション2 沿岸—浅海地質調査のすすめ
14:40-15:00 休憩
15:00-17:00 セッション3 房総・三浦の地殻大構造
17:00-17:30 ポスター紹介およびポスターコア
17:30-18:00 第1日目総合討論
18:00-20:00 懇親会(博物館内喫茶「あおば」)
3月10日(日)
9:30- 受付
10:00-12:20 セッション4 葉山—嶺岡帯解明の今日的意義
12:20-13:20 昼休み
13:20-14:20 博物館展示見学
14:20-16:20 セッション5 防災・減災最前線としての房総・三浦
16:20-17:00 総合討論
問合せ先: 上記事務局 千葉県立中央博物館高橋直樹までお願いいたします。
その他関東支部HPもご参照ください.http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■海洋研究開発機構研究報告会「JAMSTEC2013」
2月13日(水)13:00〜17:30
場所:東京国際フォーラムホールB7(千代田区丸の内)
http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20130118/
■第1回TONセミナー:宇宙から海洋への貢献
2月14日(木)16:00〜19:00
場所:海洋研究開発機構東京事務所会議室(千代田区内幸町2-2-2富国生命ビル23F)
E-mail:techno-ocean@kcva.or.jp
Tel:078-302-0029 Fax:078-302-1870
■J-DESC陸上掘削部会「地学雑誌特集号:陸上掘削科学の新展開」出版記念シンポ
2月23日(土) 13〜18時
場所:JAMSTEC東京事務所
http://www.j-desc.org/m3/events/130223_rikujo_sympo.html
■企画展「飛騨地方の火山」
日本地質学会ほか 後援
2月27日(水)〜12月10日(火)
会場:光記念館(岐阜県高山市)
http://h-am.jp/
■国立公園フォーラム ジオパークを活かした地域づくり
2月26日(火)14:00-16:00
会場:神奈川県立生命の星・地球博物館SEISAミュージアムシアター
入場無料
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//geoFlash_img/no211/hakone201302.pdf
■平成24年度海上保安庁海洋情報部研究成果発表会
2月27日(水)13:15-17:45
会場:海上保安庁海洋情報部10階(東京都江東区青梅)
入場無料
プログラムなど詳細は,http://www1.kaiho.mlit.go.jp/
■津波堆積物国際ワークショップ
(International Workshop on the 2011 Tohoku-oki tsunami deposits)
東北大学災害科学国際研究所 主催
日本地質学会,日本堆積学会 共催
3月8日(金)
会場:東北大学工学部総合研究棟101講義室
問い合わせ:菅原大助 sugawara@irides.tohoku.ac.jp
以下のウェブサイトで申し込み方法をご確認ください.
事前参加申込締切:2月28日(木)
http://www.irides.tohoku.ac.jp/event/tdeposit/index.html
■第47回日本水環境学会(大阪)年会
3月11日(月)〜13日(水)
場所:大阪工業大学大宮キャンパス(大阪市旭区大宮)
https://www.jswe.or.jp/index.html
■変成岩などシンポジウム
日本地質学会岩石部会 後援
3月15日(金)〜17日(日)
会場:北海道定山渓温泉 ホテル鹿の湯(札幌市南区)
参加費:21,000円
問い合わせ:竹下 徹 torutake@mail.sci.hokudai.ac.jp >
■ひょうご恐竜化石国際シンポジウム
「白亜紀前期の恐竜研究最前線」
日本地質学会ほか 後援
3月16日(土)10:00-16:00
会場:兵庫県立人と自然の博物館
http://hitohaku.jp/top/dinosaur_symp.html
(3月17日:関連事業あり)
■第8回「海洋と地球の学校」
3月19日(火)〜23日(土)
場所:高知県立青少年センター・のいちふれあいセンター・室戸周辺地域(野外巡検)
応募締切:平成25年3月12日(火)必着
http://www.jamstec.go.jp/j/pr/school/008/index.html
■CHIKYU+10 国際ワークショップ
4月21日(日)〜23日(火)
場所:一橋講堂(東京都千代田区一ツ橋)(予定)
http://www.jamstec.go.jp/chikyu+10/
■2013 Western Pacific Sedimentology Meeting
5月13日(月)〜18日(土)
13・14日:研究発表 15〜18日:巡検
台湾地質学会,日本堆積学会 主催
日本地質学会,IAS,SEPMほか 共催
場所:The Longtan Aspire Resort, Taoyuan, northern Taiwan
講演要旨締切:2013年2月28日
http://wpsm.ncu.edu.tw/
■地質学史懇話会
6月23日(日)13:30〜17:00
場所:北とぴあ8階808号室(JR京浜東北線王子駅下車3分)
中川智視 『小泉八雲と服部一三(仮題)』
平林憲次 『戦前の樺太油田開発(仮題)』
問い合わせ:矢島道子
■第50回 アイソトープ・放射線研究発表会発表論文の募集
日本地質学会ほか 共催
会期:7月3日(水)〜7月5日(金)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1)
申込締切:2月28日(木)
http://www.jrias.or.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■産業技術総合研究所「地質分野」研究職員公募(4/12 or 4/26)
■早稲田大学教育学部理学科地球科学専修教員公募(5/10)
■京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻地質学鉱物学分野准教授公募(4/8)
■総合科学研究機構東海事業センター研究系職員・技術系職員募集(3/7)
■2013年度地球化学研究協会学術賞「三宅賞」および「進歩賞」候補者募集(8/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】地質マンガ:デジタル派 VS アナログ派
──────────────────────────────────
デジタル派 VS アナログ派
原案:chiyodaite マンガ:KEY
http://www.geosociety.jp/faq/content0057.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flash No.224 仙台大会:事前参加登録受付中!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.224 2013/7/16 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[仙台大会]事前参加登録受付中!
【2】[仙台大会]学術大会に係るプレス発表会へのご協力のお願い
【3】[仙台大会]緊急展示の申込について
【4】津波堆積物ワークショップ 申込受付開始!
【5】コラム:鳥が首岬の謎
【6】本の紹介:東日本大震災を分析する
【7】名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[仙台大会]事前参加登録受付中!
──────────────────────────────────
講演申込をされた方も,別途事前参加登録を行って下さい。
(当日参加登録の場合は申込費用が異なります。)
締切:8月20日(火)17時(郵送 8月20日(金) 必着)
※※※巡検のみ締切が異なります※※※
締切:8月9日(金)17時(郵送 8月7日(水) 必着)
巡検の見どころ紹介→http://www.geosociety.jp/sendai/content0016.html
そのほか、小さなEarth Scientistのつどい,企業展示出展募集、ブース利用募集、広告協賛など、お申込受付中です。申込の締切がそれぞれ異なりますので、確認のうえ、お早めにお申し込み下さい。
仙台大会HPはこちら
http://www.geosociety.jp/sendai/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[仙台大会]学術大会に係るプレス発表会へのご協力のお願い
──────────────────────────────────
本年も仙台大会においてプレス発表会を開催する予定です.この機会に会員皆様の研究成果を「特筆すべき研究成果」として広報委員会へ是非ご推薦下さい.
「特筆すべき研究成果」の応募締切:2013年7月19日(金)17時
応募方法など詳しくはこちら.
http://www.geosociety.jp/sendai/content0006.html
日本地質学会広報委員長
内藤一樹
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[仙台大会]緊急展示の申込について
──────────────────────────────────
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害調査報告や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コーナー」を設けます.ポスター展示を希望する方は,8月30日(金)までに次の内容を下記申込先にご連絡ください.
1)発表要旨PDF(ニュース誌5月号参照) 2)緊急展示の必要性 3)発表代表者と連絡先 4)希望枚数(1枚:幅90×180cm) 5)展示に関わる要望(2〜5の様式は自由)
実行委員会は行事委員会と協議し,可否の判断を致します.希望にはできるだけ応えるようにしますが,展示方法等については実行委員会の指示に従ってください.
申込先:main@geosociety.jp
担当:鈴木紀毅(仙台大会実行委員会)・須藤 宏(行事委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】津波堆積物ワークショップ 申込受付開始!
──────────────────────────────────
9月開催の津波堆積物ワークショップの詳細が決定いたしました。
http://www.geosociety.jp/science/content0057.html
◆第4回津波堆積物ワークショップ
テーマ:「震災前・震災直後—何がわかっていたのか−」
2013年9月14日(土)9:00〜12:00
◆第5回津波堆積物ワークショップ
テーマ「震災から2年半,津波堆積物研究と社会」
2013年9月18日(水)10:00〜16:15
申込受付も開始いたしましたので、早めにお申込ください。
申込締切:8月30日(金)17:00
専用申込フォームはこちら.http://photo.geosociety.jp/tsunami_ws.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】コラム:鳥が首岬の謎
──────────────────────────────────
高山 信紀 ((株)JPビジネスサービス)
以前、米国ユタ州サンファン川(San Juan River)の「Gooseneck」や、愛媛県を流れる肱川中流の「鳥首」を訪れたことがあるが、いずれも地名は河川の蛇行を鳥の首に例えたことに由来する。
鳥が首岬は、新潟県上越市西方(糸魚川市寄り)に位置し、全国的にはそれほど有名では無いが国土地理院発行の20万分の1地形図や2万5千分の1地形図にはその名が記載されている。鳥が首岬の地名は何に由来するのだろう?
続きはこちらから.
http://www.geosociety.jp/faq/content0461.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】本の紹介:東日本大震災を分析する
──────────────────────────────────
平川 新・今村文彦・東北大学災害科学国際研究所 編著
東日本大震災を分析する
第1巻 地震・津波のメカニズムと被害の実態
第2巻 震災と人間・まち・記録
明石書店 2013年6月発行 A5版
第1巻 280ページ ISBN978-4-7503-3823-1
第2巻 258ページ ISBN978-4-7503-3824-8
定価 両巻それぞれ3,800円+税
「東日本大震災を分析する」という本書のタイトルから,この本はこの震災を引き起こした地震や津波の地球物理学的な解析結果や,災害の特徴・救援および復興活動などの諸相を分析した結果を述べた専門書であると考えられた方も多いのではないだろうか.内容は確かにその通りであるが,本書は,そういった難しい内容を一般向けに解説したものである.本書は,その目的を見事に達成している.その証拠に,医療やまちづくりを専門としない評者でも,苦労することなく本書を読み通すことができた.
東日本大震災で被害を被った地域の中心に位置する東北大学が,この未曾有の災害に無関心でいられるはずがないことは想像に難くない.本書は,東北大学の,主として教員の,東日本大震災に対する諸活動の集大成であり,今後も続くであろう活動の中間報告でもある.東北大学は東日本大震災の発生から1ヶ月後,3ヶ月後,6ヶ月後,1年後の4回にわたり,大震災に関する報告会を開催している.その報告会の内容を,一般向けにまとめたのが本書なのである.この報告会は,大震災前から発生が予測されていた宮城県沖地震に備えて組織された,東北大学防災科学研究拠点が主催したものであるが,同拠点は,大震災後,災害科学国際研究所としてグレードアップしている.今後も,多くの成果を挙げられることであろう.
本書は2冊組の書籍であり(本書評では第1巻,第2巻と記述することにする),その構成は次のようになっている.
第1巻 地震・津波のメカニズムと被害の実態
第1部 巨大地震に備えて
第2部 地震・津波のメカニズム
第3部 東日本大震災—被害の実態と要因
1.津波と洪水の被害
2.建物の被害
3.被害の諸相
第2巻 震災と人間・まち・記録
第1部 ひと・命・心
第2部 防災と復興のまちづくり
第3部 震災の歴史と記録
各部は,東北大学の研究者を主体とする執筆者による,いくつかの章からなる.各章の最初は,その章で何が語られるかを簡潔にまとめた「要旨」から始まり,読者の理解と利便性を高めている.各章は10ページ程度にコンパクトにまとめられているのでたいへん読みやすい.そして,どこから読んでもよいように,各章は独立している.「東日本大震災の○○○について知りたい」と思った時に,さっと使えるようになっている.
本書の内容は,上記の構成に示した通りであるが,それだけではその魅力を伝えきれないと思う.各部に含まれる全ての章の紹介は紙面の都合で割愛するが(興味のある方は出版社のホームページなどを参照して下さい),個人的に印象に残った内容を,やや網羅的に紹介したい.
第1巻,第1部では,東日本大震災以前に行われていた地震・津波対策の概要が記述され,それが今回の超巨大地震・津波に対しては不十分であったことが,反省とともに述べられている.第2部では,東北地方太平洋沖地震がどのような地震だったのかが,他機関の観測結果もふまえながら分析されている.特に,海底に設置された観測機器から探る超巨大地震・津波の発生メカニズムに関する記述に多くの紙面が割かれている.また,早期地震警報システムや地盤工学に関連した課題についても分析がなされている.第3部では,まず,衛星画像を用いた津波被害の実態や,映像解析による津波の流況の解析結果が紹介される.さらに,堤防,海岸林,アースフィルダム,ため池,建築物,造成宅地の被害の実態およびその分析結果が述べられている.最後に,被害の諸相として,福島第一原発の放射能汚染,交通ネットワーク被害,ロボットによる震災対応,墓石転倒率調査結果などが記述されている.
第2巻,第1部では,被災者のいのちと健康を護るためにどう備えるべきかが述べられている.具体的には,災害保健医療支援室の活動から見た救援期の支援ニーズの推移,医療現場の脆弱性と想定外対応能力,被災者のマナー,産婦人科医療・精神医療などに関する分析結果が詳述されている.第2部は復興とまちづくりに関する章からなり,仙台市および石巻市中心市街地でのまちづくり事例と東北大学のかかわりが紹介されている.また,建築家による復興支援(「アーキエイド」)や「せんだいスクール・オブ・デザイン」など興味深い活動の紹介がされ,さらに,日本の災害対策法制に関する問題提起もなされている.第3部では,最初に,地質学との関連も深い,弥生時代の津波および貞観津波の堆積物研究,慶長奥州地震津波に関する古文書分析などの結果が紹介されている.次に,被災した古文書の復旧活動や東日本大震災の経験を後世に伝えるためのアーカイブプロジェクト(「みちのく震録伝」と呼ばれている)など,意義深い活動が紹介されている.また,ウェブ情報とその解析という社会現象的な解析結果も述べられている.
東日本大震災を分析しているのは東北大学だけではない.他大学,政府機関,民間団体など様々な組織がこの震災について検討を加えている.しかし,震災域の中央に位置するという地の利を生かし,現場へ足繁く通って集めたデータによる分析や,様々な分野の研究者を抱える東北大学が総力を結集し学際的に行った分析は,たいへん多彩で奥深く,他者の追従を許さないと感じた.また,自分たち自身が被害者であるにも関わらず,これだけの研究を遂行していることに,私は感銘を受けた.見上げた研究者魂である.
唯一残念なのは,A5版という本書のサイズや各章をコンパクトにまとめるという制限のためか,写真や図表類が小さく見づらいことである(評者の老眼が進んでいることも原因かもしれないが).一部の写真・図については,別途,Web上に高解像度のカラー版が掲載されており,読者の便を図っているが,同様なサービスが他の写真・図についても期待される.
最後に,ある章に記述されているこの言葉を紹介して筆を置きたい.「今回の災害の第一の教訓は“備えがないことはできない”ということだった」
(小嶋 智)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】 名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
──────────────────────────────────
日本地質学会では,学会員相互の交流と親睦を図る目的で,2年ごとに会員名簿を発行することを運営規則にうたっております.2013年はその発行年にあたり,本年11月末日発行の予定で準備を行っております.
名簿の発行様式は前回と同様で,全会員を収録します.本会としては,個人情報保護法の制約はあるとしても,会員の皆様が上記の目的に沿って利用できるような,従来規模の名簿を作成したいと考えておりますので,調査の実施にご理解とご協力をお願いいたします.
アンケート提出およびWeb画面更新締切日:2013年10月4日(金)
詳しくは,コチラ↓
http://www.geosociety.jp/outline/content0132.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
──────────────────────────────────
■関東支部
緊急研修会『地表付近の地質学的調査における応用地質学的・土木地質学的留意点』
日程:7月27日(土)午前10時〜午後5時
会場:日本大学文理学部3号館5階3507号室
参加申込締切:7月19日(金)
詳しくは関東支部HPをご参照ください
http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地球にわくわく小・中学生自由研究コンテスト
募集期間:8月1日〜10月31日
応募資格・部門:小学生2部門(3・4年生、5・6)年生、中学生1部門
問い合わせ先:wakuwaku@jeso.jp
地学オリンピック日本委員会HP http://jeso.jp/
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//olympic/2013waku.jpg
■第11回高校生科学技術チャレンジ研究作品募集
募集期間:9月2日(月)〜10月7日(月)
応募資格:国内の高校生・高等専門学校生(3年生まで)、個人またはチーム
http://www.asahi.com/jsec/
■室戸ジオパークサマースクール2013
来るならきいや南海地震、土佐はうちが守るきね!
日本地質学会 後援
8月8日(木)9:00〜9日(金)16:00
場所:室戸市内の海岸、室戸市保健福祉センター、国立室戸青少年自然の家
対象:小学校5年生〜高校3年生まで
募集締切:7月16日(定員:35名)
http://ss.muroto-geo.jp/
■第57回粘土科学討論会
日本地質学会 共催
9月4日(水)〜6日(金)
会場:高知市文化プラザかるぽーと
http://www.cssj2.org/
■第4回・第5回津波堆積物ワークショップ
(120年学術大会:同時開催行事)
日本地質学会・日本堆積学会 共催
第4回:9月14日(土)9:00-12:00
第5回:9月18日(水)10:00-16:15
場所:東北大学川内北キャンパス マルチメディア棟M206号室
申込締切:8月30日(金)17:00
http://www.geosociety.jp/science/content0057.html
■2013年度日本地球化学会年会
日本地質学会 共催
9月11日(水)〜13日(金)
会場:筑波大学第一エリア1D棟、1E棟
固有セッション申込締切: 7月17日(水)
共通セッション申込:[終了]
事前参加登録締切:8月23日(金)
http://www.wdc-jp.biz/geochem/2013/
■第39回リモートセンシングシンポジウム
日本地質学会 協賛
11月25日(金)
場所:東京農業大学世田谷キャンパス
申込締切:11/1 講演申込締切:10/15
http://www.sice.jp/
■第29回ゼオライト研究発表会
日本地質学会 協賛
11月27日(水)〜28日(木)
会場:東北大学
http://www.jaz-online.org/index.html
■地質学史懇話会
12月23日(月)13:30〜
場所:北とぴあ803号室(北区王子1-11-1)
・長田敏明「戦前の満州の科学博物館の活動について(仮)」
・小野田滋「地質工学の開拓者・渡辺貫とその周辺(仮)」
問い合わせ先:矢島道子 pxi02070@nifty.com
■第3回学生のヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集
日本地質学会ほか 推薦
実習実施時期:2014年3月5日出発,19日帰国(15日間)
申込締切:11月30日
実習コース:カトマンズ−ポカラ−ムクチナート−タンセン−ルンビニ
参加費用:学生・大学院生20万円以内、その他の個人参加者25万円以内、大学・企業などの組織派遣教員/社員30万円以内
http://www.geocities.jp/gondwanainst/
■日本地球惑星科学連合2014年大会
2014年4月28日(月)〜5月2日(金)
会場:パシフィコ横浜会議センター(横浜市西区みなとみらい1-1-1)
予稿集原稿投稿募集:2014年1月08日(水)〜2月12日(水)
http://www.jpgu.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/outline/content0098.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■愛媛大学大学院:理工学研究科数理物質科学専攻地球進化学講座(教授または准教授)(9/13)
■平成26年度研究船利用課題の募集(なつしま、よこすか、かいれい、みらい等)(7/24)
■2013年朝日賞推薦候補者募集(8/31 学会締切8/9)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flash No.212 仙台大会トピックセッション募集中! 3/11締切
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.212 2013/2/19 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】日本学術会議大型研究計画マスタープランへの応募
【2】日本学術会議大型研究計画−地球惑星科学分野大型研究ヒアリングについて
【3】2013年仙台大会:トピックセッション募集中
【4】「割引会費申請」最終締切/災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
【5】地質図の在庫一掃セール!— 2013年3月末日まで
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】日本学術会議大型研究計画マスタープランへの応募
──────────────────────────────────
日本地質学会会員各位
本募集において,コミュニティ合意に関して言及することが求められているようです.コミュニティの中に日本地質学会を含めることを希望される方は,メールして応募内容をまとめた「応募の概要」を井龍(iryu@m.tojhoku.ac.jp)までお送り下さい.その際,地質学会事務局(main@geosocirty.jo)にもメールをccで送っていただけますよう,お願いします.
遅くとも,締め切りの7日前(3月25日)までには御連絡下さい.
よろしくお願いいたします.
(日本地質学会担当執行理事 井龍康文)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】日本学術会議大型研究計画−地球惑星科学分野大型研究ヒアリングについて
──────────────────────────────────
2013年2月15日
日本学術会議地球惑星科学委員会 委員長 永原 裕子
日本学術会議による大型研究計画の公募が開始いたしました.地球惑星科学分野のヒアリングについてお知らせいたします.
(1) 詳細および応募
学術会議ホームページ
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/ogata/22-koubo.html
をごらんください
(2) 地球惑星科学分野の評価
地球惑星科学分野の提案は,日本学術会議地球惑星科学委員会が評価いたします. 評価委員は以下のとおりです.
永原裕子(委員長),碓井照子,大久保修平,奥村晃司,川口淳一郎,北里 洋,木村 学,熊木洋太,佐々木 晶,高橋栄一,中島映至,花輪公雄,春山成子
(3) 利益相反について
評価委員がある提案の推薦者となっている場合は,評価に際してはその提案の採点には参加しません.
(4) ヒアリング
地球惑星科学分野においては,全提案につき,ヒアリングをおこないます.
月 日 :原則として4月5日(金)- 6 日(土)
総提案数が多い場合は,4月4日(木)にもおこないます.
場 所 :東京大学地震研究所講堂
プログラム:応募が締め切られた後,4月初めに決定いたします.
説明時間 :各提案,説明15分+質疑15分程度を想定しています.
ただし,提案総数によって増減がありえます.
説 明 者:提案者以外の方でも結構ですが,責任をもって計画の全体を説明・質問への応答をすることのできる方に限ります.
公 開 :ヒアリングは公開です.提案者に限らずどなたでも傍聴いただけます.
ただし座席数には限りがあります.予約はできません.
*質問等は下記までお願いいたします.
日本学術会議地球惑星科学委員会委員長
永原裕子(hiroko@eps.s.u-tokyo.ac.jp)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2013年仙台大会:トピックセッション募集中
──────────────────────────────────
仙台大会は,東北支部のご協力のもと,仙台市の東北大学川内キャンパスをメイン会場として2013年9月14日(土)〜16日(月)に開催されます.
現在,トピックセッションを募集中です.トピックセッションは,広く地質学の領域をカバーし,これから新分野あるいは注目すべき分野になりそうな内容を扱うものとします.形式はレギュラーセッションと同じです(15分間の口頭発表,あるいはポスター発表).
積極的にご活用下さい!
トピックセッション募集締切:3月11日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0052.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】「割引会費申請」最終締切/災害に関連した会費特別措置のお知らせ
──────────────────────────────────
■学部学生・院生(研究生)の方へ「割引会費申請」
最終締切:3月29日(金)
■災害に関連した会費の特別措置
締切:2月25日(月)
※ 通常の会費払込については,「2013年会費払い込みについて」をご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0108.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質図の在庫一掃セール!— 2013年3月末日まで
──────────────────────────────────
※現在、地質学会に在庫があるものについてのみ、特別販売中です。 最新の在庫リストはホームページに掲載していますのでご覧いただくか、事務局(電話:03-5823-1150)にお尋ねください。
詳しくは,こちらから
http://www.geosociety.jp/news/n96.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
■北海道支部
支部例会(個人講演会)
2013年4月27日(土)10:00〜18:00(予定)
場所:北海道大学理学部5号館2階 5-201室
発表申込締切:2013年3月11日(月)
(講演タイトル・発表者を電子メールまたは郵送で申込みください)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
■西日本支部
西日本支部平成24年度総会・第163回例会
2月23日(土)
場所:島根大学総合理工学研究科
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
■関東支部
日本地質学会関東支部『地質研究サミット』シリーズ
第1回「房総・三浦地質研究サミット」開催のお知らせ(第4報)
日本地質学会関東支部は,『地質研究サミット』を開催します.関東地方の地質に対して鋭い斬りこみをかけている各研究グループの中心メンバーが一堂に会してホットな研究成果を発表するとともに建設的な議論を行い,関東地方地質研究の新展開を図ります.シリーズ1 回目は,房総・三浦半島です.
(*『地質研究サミット』は,全国に開かれたものとして運営されています.)
主催:日本地質学会関東支部
共催:千葉県立中央博物館,協力:横須賀市自然・人文博物館
協賛:(株)地圏総合コンサルタント,(株)ダイヤコンサルタント,石油資源開発(株),国際航業(株),川崎地質(株),アジア航測(株),(株)東建ジオテック
期日:平成25 年3 月9 日(土)・10 日(日)
場所:千葉県立中央博物館(千葉市中央区青葉町955-2)
[交通案内 http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=204]
対象:日本地質学会員および一般の方(参加申込不要;参加費無料;要旨集1,000円予定)
懇親会:3月9日(土)18:00〜20:00 博物館内喫茶室「あおば」にて開催。会費:一般3,000円、学生1,500円。当日申込可能ですが、できれば事前に事務局(高橋直樹)あてメール(takahashin@chiba-muse.or.jp)で申し込みください.
[プログラムはこちらから]
■関東支部
2013年度関東支部総会と地質技術伝承講演会のお知らせ(第1報)
関東支部では下記のとおり2013年度総会と地質技術伝承講習会を開催いたします.
同日,地質技術伝承講習会は(社)全国地質調査業協会連合会 関東地質調査業協会との共催で行います.多数の支部会員のご参加をお願いいたします.
2013年4月13日(土)午後
場所 北とぴあ(東京都北区王子1-11-1)
【地質技術伝承講習会】参加費無料
時間:14:00〜16:00(予定)
講師:アジア航測株式会社 今村遼平氏
【関東支部総会】
時間:16:00〜16:45(予定)
問合せ先
神奈川県小田原市入生田499
神奈川県立生命の星・地球博物館 笠間友博(幹事長)
電話0465-21-1515
メールkasama@nh.kanagawa-museum.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地震本部ニュース平成24年11月号発行
http://www.jishin.go.jp/main/p_koho04.htm
■第13回アジア学術会議タイ会合国際シンポジウムCall for Papers論文要旨提出期限
延長のご案内
スケジュール
2月28日:論文要旨提出期限(当初期限1月31日より4週間延長)
3月15日:審査結果通知(Notification of acceptance of abstract)
4月5日:論文(Full Paper)提出期限
http://www.scj.go.jp/en/sca/index.html
■津波堆積物国際ワークショップ
(International Workshop on the 2011 Tohoku-oki tsunami deposits)
東北大学災害科学国際研究所 主催
日本地質学会,日本堆積学会 共催
3月8日(金)
会場:東北大学工学部総合研究棟101講義室
問い合わせ:菅原大助 sugawara@irides.tohoku.ac.jp
事前参加申込締切:2月28日(木)
http://www.irides.tohoku.ac.jp/event/tdeposit/index.html
■第1回アジア太平洋地域大規模地震・火山噴火リスク対策(G-EVER)国際シンポジウム
-アジア太平洋地域の地震火山災害の現状と将来展望-
3月11日(月) 9:00-18:00
場所:産業技術総合研究所 共用講堂
http://g-ever.org/ja/symposium/
■平成24年度海洋研究開発機構成果発表会「ブルーアース2013」
3月14日(木)10:00-17:40、15日(金)10:00-17:20
場所:東京海洋大学品川キャンパス白鷹館講義棟(港区港南4-5-7)
問い合わせ:運航管理部計画グループ
Tel: 046-867-9865 E-mail: riyo-kobo@jamstec.go.jp
http://www.jamstec.go.jp
■変成岩などシンポジウム
日本地質学会岩石部会 後援
3月15日(金)〜17日(日)
会場:北海道定山渓温泉 ホテル鹿の湯(札幌市南区)
参加費:21,000円
問い合わせ:竹下 徹 torutake@mail.sci.hokudai.ac.jp
■ひょうご恐竜化石国際シンポジウム
「白亜紀前期の恐竜研究最前線」
日本地質学会ほか 後援
3月16日(土)10:00-16:00
会場:兵庫県立人と自然の博物館
http://hitohaku.jp/top/dinosaur_symp.html
■2013 Western Pacific Sedimentology Meeting
台湾地質学会,日本堆積学会 主催
日本地質学会,IAS,SEPMほか 共催
5月13日(月)〜18日(土)
13-14日:研究発表 15-18日:巡検
場所:The Longtan Aspire Resort, Taoyuan, northern Taiwan
講演要旨締切:2013年2月28日
http://wpsm.ncu.edu.tw/
■第50回 アイソトープ・放射線研究発表会発表論文の募集
日本地質学会ほか 共催
7月3日(水)〜7月5日(金)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1)
申込締切:2月28日(木)
http://www.jrias.or.jp
■第57回粘土科学討論会
日本地質学会 共催
9月4日(水)〜6日(金)
会場:高知市文化プラザかるぽーと
参加・講演の申込期間 :6月3日(月)〜 14日(金)
講演要旨送付締切 :7月12日(金)
http://www.cssj2.org/
■International Biogeoscience Conference 2013
登録受付開始しています。
11月1日(金)〜4日(月)
場所:名古屋大学
http://www.info.human.nagoya-u.ac.jp/~sugi/Site/Biogeoscience_Conference_2013.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/outline/content0098.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■大阪市立大学大学院理学研究科・理学部地球学教室 特任講師募集(3/1)
■東京工業大学大学院理工学研究科地球惑星科学専攻准教授公募(4/15)
■北海道大学大学院理学研究院自然史科学部門講師公募(3/28)
■消防防災科学技術研究推進制度平成25年度研究開発課題募集(3/7)
■第10回日本学術振興会賞受賞候補者の推薦募集(学会締切3/31)
■東レ科学技術賞・科学技術研究助成推薦募集(学会締切8/30)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flash No.213 フォトコン結果速報
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.213 2013/3/5 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】速報!!第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品決定
【2】2013年仙台大会:トピックセッション間もなく締切り!(3/11締切)
【3】2013年度春季地質の調査研修:参加者募集
【4】国際交流:日本−タイ地質学会学術交流協定
【5】コラム 丹那断層と丹那トンネル難工事と二つの大地震(その1)
【6】日本学術会議大型研究計画マスタープランへの応募
【7】日本学術会議科研費改革に関するアンケ−トの結果
【8】「割引会費申請」3/29:最終締切
【9】地質図の在庫一掃セール!2013年3月末日まで
【10】2013年「地質の日」行事予定
【11】支部情報
【12】その他のお知らせ
【13】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】速報!!第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品決定
──────────────────────────────────
多数のご応募ありがとうございました.厳正なる審査の結果,第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品が決定しました。
講評と作品はWEB(http://www.photo.geosociety.jp/)上にて近日公開予定です.
最優秀賞:「深い海底の流れ」坂口有人(神奈川県)
優秀賞:「根室車石」堀内 勇(和歌山県)
優秀賞:「地層模様」細井 淳(茨城県)
優秀賞:「空気砲」大江雅史(愛知県)
ジオパーク賞:「活躍するボランティアガイド」本多優二(群馬県)
入選:「静けさ」檜山貴史(北海道)
入選:「1934-35昭和硫黄島」」池上郁彦(福岡県)
入選:「マグマの上で」高橋伸輔(秋田県)
入選:「火山の造形」坪田敏夫(神奈川県)
入選:「地層のデザイン」坂口有人(神奈川県)
入選:「東南極セール・ロンダーネ山地の巨大岩峰」菅沼悠介(東京都)
入選:「輝く岩山」佐藤 忠(東京都)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2013年仙台大会:トピックセッション間もなく締切り!(3/11締切)
──────────────────────────────────
トピックセッション募集締切:3月11日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0052.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2013年度春季地質の調査研修:参加者募集
──────────────────────────────────
地質調査法の基本技術の修得をめざすとともに,それをベースに得られた過去の調査や研究の成果についても学びます.地質調査の経験のない方でも,地質調査法の基本を体で習得することを目指します.
日程:2013年5月27日(月)〜31日(金)4泊5日
場所:千葉県君津市及びその周辺地域(房総半島中部域)
募集人数:6名
参加費:12万円
申込締切:2013年4月19日(金)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/engineer/content0027.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】国際交流:日本−タイ地質学会学術交流協定
──────────────────────────────────
日本地質学会とタイ国地質学会の学術交流協定を締結しておりましたが,昨年,その期限が満期となりました.そこで,昨年末より,両国地質学会の国際交流担当者が連絡を取り,協定の更新手続きをいたしました.HPに,その全文を掲載いたしました.
井龍康文(執行理事:国際交流担当)
協定書全文は,こちらから
http://www.geosociety.jp/science/content0054.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】コラム 丹那断層と丹那トンネル難工事と二つの大地震(その1)
──────────────────────────────────
その1: 提案「丹那盆地を地殻変動観測の拠点に」
正会員 服部 仁
提案の目的
丹那盆地は,地殻変動の活発な伊豆半島北端に位置し,徑約1㎞の環状地形をなしている.東縁には南北性丹那断層が通り,北縁の地下約150 mには東西方向に日本の幹線鉄道の丹那トンネルおよび新丹那トンネルが貫いている.両トンネルは盆地中頃において丹那断層とほぼ直交する.
続きを読む、、、、、、http://www.geosociety.jp/faq/content0432.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】日本学術会議大型研究計画マスタープランへの応募
──────────────────────────────────
日本地質学会会員各位
本募集において,コミュニティ合意に関して言及することが求められているようです.コミュニティの中に日本地質学会を含めることを希望される方は,メールにて応募内容をまとめた「応募の概要」を井龍(iryu@m.tohoku.ac.jp)までお送り下さい.その際,地質学会事務局(main@geosociety.jp)にもメールをccで送っていただけますよう,お願いします.
遅くとも,締め切りの7日前(3月25日)までには御連絡下さい.
日本学術会議大型研究計画マスタープランへの応募の詳細はこちらから
http://www.geosociety.jp/faq/content0429.html#02
地球惑星科学分野大型研究ヒアリングについて
http://www.geosociety.jp/faq/content0430.html#02
(日本地質学会担当執行理事 井龍康文)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】日本学術会議:科研費改革に関するアンケ−トの結果
──────────────────────────────────
昨年12月に各学術研究団体に依頼されていました,科研費改革に関するアンケ−トの結果につきまして、日本学術会議科学者委員会学術誌問題検討分科会において取りまとめ、日本学術会議のHPにおいて公表されましたので,お知らせ致します。
○科研費成果公開促進費の改訂に関する学協会の意識調査(PDF)
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/kiroku/1-250214.pdf
※日本学術会議HP「記録」内に掲載しております。
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/kiroku/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】「割引会費申請」最終締切
──────────────────────────────────
■学部学生・院生(研究生)「割引会費申請」最終締切:3月29日(金)
※ 通常の会費払込については,「2013年会費払い込みについて」をご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0108.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】地質図の在庫一掃セール!― 2013年3月末日まで
──────────────────────────────────
※現在、地質学会に在庫があるものについてのみ、特別販売中です。
最新の在庫リストはホームページに掲載していますのでご覧いただくか、事務局(電話:03-5823-1150)にお尋ねください。
詳しくは,こちらから http://www.geosociety.jp/news/n96.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】支部情報
──────────────────────────────────
■北海道支部
支部例会(個人講演会)
日時:2013年4月27日(土)10:00〜18:00(予定)
場所:北海道大学理学部5号館2階 5-201室
発表申込締切:2013年3月11日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
■関東支部
第1回「房総・三浦地質研究サミット」
3月9日(土)・10日(日)
場所:千葉県立中央博物館(千葉市中央区青葉町955-2)
対象:日本地質学会員および一般の方
(参加申込不要;参加費無料;要旨集1,000円予定)
参加者は無料で千葉中央博物館展示室の見学ができます。
http://www.geosociety.jp/faq/content0430.html#06-3
2013年度関東支部総会・地質技術伝承講演会
4月13日(土)午後
場所 北とぴあ(東京都北区王子1-11-1)
【地質技術伝承講習会】参加費無料
時間:14:00〜16:00(予定)
講師:アジア航測株式会社 今村遼平氏
【関東支部総会】
時間:16:00〜16:45(予定)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/faq/content0430.html#06-4
関東支部HPもご参照下さい。http://kanto.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】2013年「地質の日」行事予定
──────────────────────────────────
2008年より5月10日が『地質の日』に制定され,これを記念した多くのイベントが,全国各地の博物館・大学で開催されています。
今年も学会関連の行事が多数予定されています.
◆地質学会・応用地質学会主催:街中ジオ散歩in Tokyo「石神井川がつくる地形の移り変わりと地質(仮)」
◆近畿支部:地球科学講演会「大阪平野の地盤環境と地盤災害」
◆北海道支部:「地質の日」記念展示「豊平川と共に―その恵みと災い―」
◆西日本支部:身近に知る『くまもとの大地』
それぞれのイベントの詳細は,学会HPの「地質の日」よりご覧頂けます.
http://www.geosociety.jp/name/content0014.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第1回アジア太平洋地域大規模地震・火山噴火リスク対策(G-EVER)国際シンポジウム
−アジア太平洋地域の地震火山災害の現状と将来展望−
3月11日(月) 9:00-18:00
場所:産業技術総合研究所 共用講堂
http://g-ever.org/ja/symposium/
■津波堆積物国際ワークショップ
(International Workshop on the 2011 Tohoku-oki tsunami deposits)
東北大学災害科学国際研究所 主催
日本地質学会,日本堆積学会 共催
3月8日(金)
会場:東北大学工学部総合研究棟101講義室
問い合わせ:菅原大助 sugawara@irides.tohoku.ac.jp
http://www.irides.tohoku.ac.jp/event/tdeposit/index.html
■平成24年度海洋研究開発機構成果発表会「ブルーアース2013」
3月14日(木)10:00-17:40、15日(金)10:00-17:20
場所:東京海洋大学品川キャンパス白鷹館講義棟(港区港南4-5-7)
問い合わせ:運航管理部計画グループ
Tel: 046-867-9865 E-mail: riyo-kobo@jamstec.go.jp
http://www.jamstec.go.jp
■変成岩などシンポジウム
日本地質学会岩石部会 後援
3月15日(金)〜17日(日)
会場:北海道定山渓温泉 ホテル鹿の湯(札幌市南区)
参加費:21,000円
問い合わせ:竹下 徹 torutake@mail.sci.hokudai.ac.jp
■ひょうご恐竜化石国際シンポジウム
「白亜紀前期の恐竜研究最前線」
日本地質学会ほか 後援
3月16日(土)10:00-16:00
会場:兵庫県立人と自然の博物館
http://hitohaku.jp/top/dinosaur_symp.html
■日本堆積学会2013年千葉大会
4月10日(水)〜15日(月)
会場:千葉大学西千葉キャンパスけやき会館ほか
講演申込・巡検申込締切:3月15日(金)
http://sediment.jp/04nennkai/2013/annnai.html
■第149回深田研談話会
レアアース泥鉱床は日本を救えるか?
講師:加藤泰浩(東京大学)
4月12日(金)15:00-17:00
会場:深田地質研究所研修ホール
http://www.fgi.or.jp
■2013 Western Pacific Sedimentology Meeting
台湾地質学会,日本堆積学会 主催
日本地質学会,IAS,SEPMほか 共催
5月13日(月)〜18日(土)
13-14日:研究発表 15-18日:巡検
場所:The Longtan Aspire Resort, Taoyuan, northern Taiwan
http://wpsm.ncu.edu.tw/
■第50回 アイソトープ・放射線研究発表会発表論文の募集
日本地質学会ほか 共催
7月3日(水)〜5日(金)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1)
http://www.jrias.or.jp
■第57回粘土科学討論会
日本地質学会 共催
9月4日(水)〜6日(金)
会場:高知市文化プラザかるぽーと
参加・講演の申込期間 :6月3日(月)〜 14日(金)
講演要旨送付締切 :7月12日(金)
http://www.cssj2.org/
■International Biogeoscience Conference 2013
登録受付開始しています。
11月1日(金)〜4日(月)
場所:名古屋大学
http://www.info.human.nagoya-u.ac.jp/~sugi/Site/Biogeoscience_Conference_2013.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/outline/content0098.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■The University of Bremen, Junior Research Group Leader公募(3/28)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
丹那断層と丹那トンネル難工事と二つの大地震(その1)
丹那断層と丹那トンネル難工事と二つの大地震
—その1: 提案「丹那盆地を地殻変動観測の拠点に」—
服部 仁
第1図 丹那盆地の約150 m下を通るトンネルと6本のボーリング位置を示す鳥瞰図. 地表から厚さ40 mの湖成堆積層があり,遮水性粘土層を挟む.図の右側が西で三島口,左が熱海口になる.鐡道省熱海建設事務所(1933), p.118の原図を複製.
提案の目的
丹那盆地は,地殻変動の活発な伊豆半島北端に位置し,徑約1㎞の環状地形をなしている.東縁には南北性丹那断層が通り,北縁の地下約150 mには東西方向に日本の幹線鉄道の丹那トンネルおよび新丹那トンネルが貫いている.両トンネルは盆地中頃において丹那断層とほぼ直交する (第1図).
丹那トンネル掘削は難工事の連続で,完成まで16年を要した.その期間中,詳細な地質調査と断層・出水事故・原因究明などが克明に記録された.とくに,北伊豆地震に襲われた時,トンネル内では幅40 m以上の丹那断層と格闘中,切羽が約2.4 m左横ずれした.ところが,地表に現れたのは雁行状地割れのなす地震断層であり,方向・性質・規模が違いすぎる.はたして地下何メートルまでその形態が続くのか,トンネルレベルの古い火山岩・地層内の丹那断層にどう直結するか,あるいは別の形態の断層に変わるのか,未解明のままである.本提案の第一の目的は,地表とトンネルまでの間の丹那断層の三次元立体実像を解明することです.
次に,丹那盆地の北西方40㎞には活火山の富士山があり,種々観測が進められている. 丹那盆地でも,地殻変動を的確に観測する拠点として,両トンネル付近の地下200mまでを含む,立体的な総合観測網を計画してはどうか,という提案が第二の目的です.
難工事の克明な記録
東海道新幹線は,熱海を過ぎると間もなく新丹那トンネルに入り2分あまりで通り抜け,三島に向かう.このトンネル50 m南側を全長7,804 mの東海道本線丹那トンネルが並行するが,1918年(大正7年)から16年の年月を要した難工事であったことはもう忘れられてしまったらしい.
最大の難所は,丹那トンネルの中頃を貫く丹那断層の断層破砕帯40 mの掘進であり(第1図: C号ボーリング近く;鐡道省熱海建設事務所,1933),1930年6月から1933年3月まで34か月の間,21本の長さ2,370 m水抜坑,無数ともいえる水平水抜きボーリングを要した.わけても,1930年11月26日北伊豆地震に襲われ,丹那断層が水抜坑の切羽で約2.4 m左横ずれした.その観察スケッチ,写真,記述の工事誌は貴重である(鐡道省熱海建設事務所, 1936).他の断層とともに,滝のように湧き出す地下水対策,さらに膨潤性火山岩で膨れ上がる岩圧などにより44か月も掘進できなかった難工事は克明に記録された.水抜坑の総延長は14,630m,本坑トンネルの約2倍近くに達した.
北伊豆地震の直後には,丹那断層のみならず広範囲にわたり震災調査が実施され,報文とともに詳細な地質図が出版された(伊原・石井,1932).こうした公式記録のほか,解説書,随筆,子供向け読本,小説も発表され,新橋演舞場の劇「丹那隧道」も人気を博し,丹那トンネルはマスメディアによる報道によって一大社会問題になった.
第2図 丹那盆地下を通る東海道線トンネルと水抜坑(青色), 掘削坑レベルの丹那断層の形状(刃先型:赤色),地表における丹那断層 (緑色線:伊原・石井,1932)および丹那断層公園の位置(赤の小四角).服部(2006)のカラー図4にスケールなどを追記.原図は鐡道省熱海建設事務所(1936)の第351図. 水抜坑および掘削坑レベルの丹那断層の詳しい形状は,本稿続編:その3の第5図に示す.(※拡大は図をクリック)
将来予測に向けて科学技術の粋を
地球科学からみると,丹那断層と丹那トンネルが交差する丹那盆地は,地殻変動の活発な位置にあり,今日的手法により多角的に実態解明できる適切な場所である,と私は思います.未来予測に必須の基礎データを蓄積し,また諸説を検証する最適な観測拠点を構築できたらと考えている.すでに,盆地南東隅の丹那断層(第2図)は国の天然記念物指定を受け,公園化されトイレなど諸設備が整備されている.中に深さ2 mほどの長方形溝が掘られ,断層の地下断面が観察できる地下観察館がある(小山, 2011).
濃尾地震による水鳥断層とともに世界に知れ渡ったこの丹那断層は,淡路島の野島断層とともに,最も激しく地殻変動を受けている場所である.ただ,観察スポットにとどまらず,地殻変動を的確に観測する拠点にしてほしい,と願う地学研究者は少なくありません.できることなら,両トンネル付近の地下200 mまでを含む,立体的な総合観測網を計画する,というのが私の提案です.
丹那断層の未来の活動については,過去の活動史解析に基づく仮説があります.地殻変動が,規則的に繰り返す自然現象であるのか,予測不能で気まぐれな突発現象はないのか,を検証することが肝要です.そのため,地表と地中における基礎的で基本的な観測データが不可欠です.検証とともに,もし大地変が発生した時,どこが,どこよりもどの程度危ないか,あるいは安全か,とくに断層・活断層・地盤について具体的に人々に説明できる防災・減災のための科学技術の知識・知恵が求められている,と思います.
短年月で成果を期待するのは難しいでしょうが,100年以上先を見据えた安全・安心を保証するため,地震・火山大国で研究先進国の日本で,総合観測網設置の種まきを始める試みです.
第3図 丹那断層(左図)および丹那トンネル直上北側の地表に現れた雁行状地割れ(右図).陥没地はトンネルルートの北側. 伊原・石井(1932)の第1,2図を複製.(※拡大は図をクリック)
観測拠点の概要
地質学・地形学にとどまらず土木学・地震学・地震工学・応用地質学・地盤工学など縦割り研究分野を越え,総合的・統合的観測拠点を創出することです.
この観測拠点では,子供から大人まで多様で素朴な疑問や批判に対して開かれた討論の場を確保するとともに,社会学・経済学・政治学・心理学・医療面など異分野の研究者や市民とも交流できる共用施設と資料館を付加し,一部を一般見学可能にする透明ガラス窓などの施設・設備を作り公開すれば,一層認識が高まるでしょう.
その素案は次の通りです.まず,地震波動を把握するための水平方向・鉛直方向のアレイ観測網を整備すること.アレイ観測はすでに,防災科学技術研究所によるものや旧鉱山跡地に設置されています.丹那盆地では盆地内外約2㎞四方に,硬軟地盤別に地表500mごとに高密度GPS観測網を置くとともに,地中には地下250m位まで立坑を一本堀抜き,各地層別に水平の調査坑を設け,地震波のアレイ観測とともに,変位計,ひずみ計,傾斜計,地磁気計,重力計などに地下水位計・地殻熱流量計を組み入れ,常時高精度の観測データを取得する.観測データはリアルタイム情報公開し,防災・減災に役立てる重要拠点にする.
次に解明してほしい課題は,丹那断層の三次元立体的実像です.地表に現れた雁行状地割れのなす地震断層(第3図)は,南北方向に帯状に延びるが,厚さ40 mほどの湖成堆積物の表層部の現象に過ぎない.はたして地下何メートルまでその形態が続くのか,湖成 堆積物下110 mのトンネルレベルの古い火山岩・地層内の断層にどう直結するか,あるいは別の形態の断層に変わるのか,明確に実証してほしいのです.
「丹那隧道工事誌」(鐡道省熱海建設事務所, 1936)を読むと,トンネルレベルにおける丹那断層は地表の地震断層と方向・性質・規模が大きく違います(第2図).
丹那盆地では,地表の活断層・地震断層はもとより,直下150mほどのトンネルレベルの地質・岩石・断層が詳細に記載されており,また6本のボーリング調査資料もあり,他に例をみない立体実像取得の好条件に恵まれています.
非売冊子などからの話題
2006年,ゼネコン研究所で鉄道に関する社内誌をまとめる際,多数の工事記録および回想録を参考に私は「丹那トンネルと新丹那トンネル」(服部,2006)を執筆した.旧工事記録の徹底的分析と地質の理解を基礎に,新丹那トンネルを4年で完成させた新技術開発の足跡をたどった.この冊子は残念ながら非売品で,一般には広めていません.この内容をベースにし,大正−昭和にかけて20年ほど日本中をとりこにした社会問題,丹那トンネルにまつわる話題を核に随想風に問題点を書きました.
「丹那盆地を地殻変動観測の拠点に」の本提案に添えて,種々記録を参照・引用して以下10項目の話題にまとめ次号以降に紹介します.約90年前,活断層・地震被害・盆地の渇水対策など関係者がいかに奮闘してきたかに想いをはせていただければありがたく思います.
【文献】
伊原敬之助・石井清彦, 1932, 北伊豆震災地調査報文.地調報告, 112, 111p.
服部 仁,1996,復刊紹介「丹那トンネルの話」.地質雑,102,143-144.
服部 仁,2006,丹那トンネルと新丹那トンネル.鹿島技術研究所編,鉄道の鹿島−『技術の鹿島』そのDNAを訪ねて 第2集,170-182.
小山真人, 2011, 丹那断層見学ガイド.静岡大学小山研究室ホームページ. http://sk01.ed.shizuoka.ac.jp/koyama/public_html/tanna/tanna.html
久野 久,1962,旧丹那トンネルと新丹那トンネル.科学,32, 397-401.
日本国有鉄道新橋工事々務所編,1954,開通二十周年記念 随筆 丹那とんねる.作品社,333p.
内,
新井堯爾,驛長の頃から.235-241.
青木槐三,記者の眼で見た丹那隧道.254-272.
門屋盛一,生埋日記.108-128.
石川九五,隧道のスピード.11-35.
太田善雄編, 1965, 新丹那トンネル工事の記録.鹿島, 131 p.
鐡道省熱海建設事務所,1933, 丹那トンネルの話.224p+序文3p+目次4p. (復刻版,1995)
鐡道省熱海建設事務所,1936, 丹那隧道工事誌.602p.
(その2に続く)
(2013.3.5)
丹那断層と丹那トンネル難工事と二つの大地震(その2)
丹那断層と丹那トンネル難工事と二つの大地震
—その2: トンネルルート選定・地質調査・断層からの大湧水—
服部 仁
1.東海道線(現JR御殿場線)からトンネルルートの東海道本線へ
熱海から丹那トンネル経由で三島へ抜けるまで,東海道線は現在のJR御殿場線を通っていた.当時,降雨量が多いと毎年のように線路と並行する鮎澤川が氾濫し,堤防の決壊,山崩れが起こり,しばしば不通になった.1か月以上も不通状態が続くこともあった.その上,富士山麓の御殿場を中心に上り下りともに40分の1の急勾配が長いため,貨物列車が蒸気機関車三台つけて牽引されても,あえぎ,あえぎ走っていた.丹那トンネル完成前,1934年末までの日本の幹線鉄道は,東海道メガロポリスを支える大動脈の役割を果たしてはいなかった.
御殿場線の改良策,小田原と沼津を直結する芦ノ湖の下を通す第一案,熱海と函南を通す熱海線など計8線路が,地形測量とともに検討された.最終案は,熱海線建設(丹那山トンネル:当時の名称で,1922年に山を削除)であった.丹那トンネルは,鐡道院にとって中央線笹子トンネルなどの規模を超える未経験の大断面・複線型の長い山岳トンネルであり,大国家事業であった.
2.不十分な事前調査
建設当初の所管局長古川阪次郎博士は,若い時分中央線笹子トンネルを手懸けた技師で,トンネルの事は自分が日本の第一人者だという確信を持っていた.丹那トンネルもこの局長確信の下に出発したが,起工後工事は多くの困難に出逢い,事故は続出,死傷者がでた.工事中止をめぐり,議会問題化し貴衆両院議員までが視察にでかけた.工事担当者から,古川博士が自信の余り地質の調査研究もせず着工したためだった,との意見もでた.
西園寺公望公が古川阪次郎局長を呼び,その頃,来日していた独逸人のトンネル技師に相談し,よく調査してもらうよう勧めた.それにもかかわらず,古川博士はトンネルには自信があったので,自分の調査結果からその必要を認めず実行しなかった(新井,1954).伊豆半島にはすでにたくさんの金銀鉱山が開発されていて,類似の地質について調査研究がなかったわけではない.しかし,丹那トンネルのルートに関しては,事前調査が十分でなく,その上,地質学界権威の間で見解がまとまらなかった.
10数年を経て貫通を迎えたとき,古川博士は丹那の始めから貫通まで終始,鉄道技術家として活躍されており,77才で元鐡道院副総裁として,貫通にも立ち会った.1933年6月19日午前11時30分,三土(みつち)忠造(ちうぞう)鉄道大臣(三土大臣の次男が三土知芳氏,1947.9〜1953.10地質調査所所長)の卓上のボタン指示で貫通発破が行われた.貫通確認の直後に,古川阪次郎翁はしゃがれ声で,トンネル内から三土大臣に「計画者の一人として,このトンネルの完成には責任を感じている.貫通に立会い,衷心からお喜びを申し上げます」と電話で感慨深い祝辞を述べた(青木,1954).
第4図:新丹那トンネル地質断面図.下図の平面図には水抜坑と主な断層の位置を示した.
服部(2006)の図3を複製. 地質断面図は久野(1962)の第1図を浄書・加筆し,丹那トンネル難工事箇所に★印を追記.平面図は鐡道省熱海建設事務所(1936)の第246図を使用.
(※拡大は図をクリック)
3.久野 久の貢献
事前の地質調査が十分でなかったこと,さらに大事故が続発したため,1923年,東京帝國大學理學部地質學科卒業の渡邊貫,廣田孝一,佐伯謙吉の三理学士が初めて地質技術者として鐡道省(鐡道院から1920年鐡道省へ)に採用された.地質の立場から,工事の進歩を助けた一面 (鐡道省熱海建設事務所,1933)はあるものの,全体の地質状況と火山岩の諸性質を理解するまでには至らず,事故発生の事後処置に追われた.約10年後以降の久野 久による研究成果を待たねばならなかった.
久野は,1931年から箱根・伊豆半島の地質・岩石・鉱物の卒業研究(東京帝國大學 地質學教室)を始めた.貫通前後の旧丹那トンネル中央部の1.5kmにしばしば入坑して,側壁の岩石露出面を観察し,さらに,旧丹那トンネルの地質断面図を作製するため,地表の踏査は少なくとも実動100日を費やしている.1939年助教授に昇任後,1941年7月徴用されて満州の軍務につき,1946年抑留地から帰国して間もなく,戦時中に掘られた新丹那トンネル部分を調査し始めた.東海道新幹線の新トンネルとして,1959年9月工事再開後はほとんど毎月1回トンネル坑内に入って調査を行い(一時:国鉄嘱託),トンネル全域にわたる地質断面図を改定するとともに,火山岩の種類と分布,火山岩のできかた,空洞・空隙の存在形態,断層の精査,採集岩石試料の岩石学的研究を続けた.また,坑内で工事関係者に種々解説されている(太田編, 1965 ).
詳細な地表および坑内地質調査,持ち帰った採取試料の顕微鏡観察,火山岩の成因(水中自破砕溶岩など),変質状況などを把握し,箱根・伊豆を中心とした立派な研究業績を内外に公表した.日本以外の火山および火山岩を含め,岩石学的・鉱物学的研究の世界第一人者と認められようになった.1962年9月20日の新丹那トンネル貫通直前に,「旧丹那トンネルと新丹那トンネル」と題する地質学的論文を公表した(久野, 1962).1969年7月21日,アポロ11号の月面着陸と岩石試料採取についてのNHKテレビ中継の解説を務めたが,画面では病魔に侵されて痩せ細った顔が映されていた.その直後,8月6日胃がんのために逝去された.東京大学教授定年退職半年あまり前のことであった.国内誌よりも海外の著名な学会誌の方が多く,久野 久のあまりにも早い逝去を惜しみ追悼文を載せた.久野教授の学問的貢献はいうに及ばず,新丹那トンネル工事の円滑な進行に計り知れない影響を与えた.他の多くのトンネル工事において,久野教授を超えるような助言・指導を行った地質学者はおそらく他にはいないであろう(第4図).
4.最初の事故
26才の青年号令(現在の現場主任に相当)として幸い生き残り,後に参議院議員として2年半務めた門屋盛一氏の回顧録(門屋, 1954)から述べる.熱海口の坑口から約300m位入ったところで大事故が起こった.事故箇所は,その当時でも微温湯位の温泉が出ていた.地熱による地質の変化,それから小さな断層鏡面があった.その断層は大体トンネルに向って左手から右手の方に45度で走り,断層の幅は約6mである.その断層を取った折にできた,1921年4月1日,午後4時20分頃の事故である.
助かった原因:33名が遭難し,16名は崩落事故の真下にあって圧死したが,そこより奥の先進導坑で働いていた17名は閉じ込められて,7日後の4月8日の午後11時に救助された.その当時は単線型のトンネル以外の経験がなく,延長約8kmの大隧道で,しかも箱根火山地帯の難しい地質の中を掘削して行くというので当時の鉄道省としても最も精鋭の技術陣を配した.しかし,私は19才の時から2年半程長崎沖の三菱の端島炭坑,崎戸炭坑等で働いていたので,炭坑の坑内設備(坑内の電燈,動力線,下水,電話も装備済)が非常によかったことを知っていた.当初の丹那トンネル工事では,まだカンテラをつけて坑内に入り電燈の設備がなく,1.6km程先の導坑には電話もなく,一寸の連絡でも徒歩で奥から出なければならず,従来の工法を一歩も出ていなかった.
下水の事を,飯田清太さんと私,門屋盛一が必死になって頼んだ.その結果,事故の起る数日前,確か2寸厚みの板で深さ1尺,幅2尺の下水が出来ていた.そのお陰で我々が溺死を免れたのです.当時毎秒1.5立方尺(=42 ℓ/sec)位の水が出ていたので,我々は三昼夜位でガスで窒息するか,あるいは溺死していた筈であった.我々の願いを,幸いにも竹股技師が聴き入れ,いいと思うことを直ぐやってくれたので助かった訳である.たまたま4月1日は朔日で公休日のため,導坑と山の悪いところでコンクリート工を進め,他は全部休んでいた.従事員が余計入っていなかったのは不幸中の幸いであった.また,当時建設事務所の富田保一郎所長は勅任官(天皇の御璽を捺した勅書によって任命される.各省次官や参事官,府県知事,帝国大学教授,陸海軍中将少将など高等官1〜2等に相当)であり,とても偉い所長であったが,1921年当時,26才の一介の青年号令の要望を所長が認め,激励されたのである.
丹那トンネルの熱海口において,鉄道工業の丁場にストライキがあったことはあまり知られていない.原因は,崩壊事故の直後,救助坑の位置について鉄道当局の対策への不満からであった.この崩壊事故と同時に,その時の当番の宗像という男が,トンネルの一番真中の上部から救助坑を開けたいと願い出た.しかし,鉄道当局の意向は,上は危いとの事で,両方の側壁コンクリートの生きているところ,および底設から入れとの指示であった.ところが,2日遅れて応援に来た三島口施工の鹿島組親方,伊沢京七氏がかけつけて上から行かなければいかんといって,宗像達が先に申し出た処から取りかかり,その上の救助坑から我々の救出に成功した.それでストライキの言い分は,なぜ俺達の言い分を聴いてくれなかったか,という点にあった.
5.断層や大湧水の観察記録と理解・原因究明
断層そのものについての智識は,その当時不十分であった.三島口工区 1,509m(四千九百五十呎)における1年あまりの経験が,その後のトンネル技術者の断層および地質に対する智識を非常に進歩させた.大きな玉石が,方々の川で見受ける様な丸い玉石であって,断層の中にあるものとは考えられなかったからである.また,砂も多量流出していたので,砂や玉石の河床の層にぶつかり,多量の地下水のために流れ出したものだ,と考えられそうな地質であった.しかし,実際は断層であり,玉石は断層角礫であった.断層角礫とは堅岩が断層作用によってグザグザに砕けた岩片をいうのであるが,場合によってはグザグザにならず種々の大きさに割れ,これが断層作用によって回転し,川の底をころがったと同じ様に丸くなるのである.だから,玉石は何も水に流されて出きたものとは限らず,断層作用によってできる玉石もあるのである.断層の性質は一様で無く,種々の変化があるから断層なるものを熟知する事はなかなか難しい(石川, 1954).
東京帝國大學工學部鉱山學科卒業後,石川九五技師が西口大竹詰所に着任したのは,三島口1,509m付近の大崩壊事故が収拾され,断層の裏側に廻り坑奥を掘削していた1924年8月である.以降,1934年12月1日の熱海線開通まで満10年以上在勤した珍しい技術者である.石川は,10年間におもな大難工事に立ち会っていて,新工法を試行するとともに,多くの事故について的確な観察記録を残している.
【文献】
服部 仁,1996,復刊紹介「丹那トンネルの話」.地質雑,102,143-144.
服部 仁,2006,丹那トンネルと新丹那トンネル.鹿島技術研究所編,鉄道の鹿島−『技術の鹿島』そのDNAを訪ねて 第2集,170-182.
鹿島技術研究所,2006, 鉄道の鹿島−『技術の鹿島』そのDNAを訪ねて第2集, 270p.
内,
服部 仁,2006, 丹那トンネルと新丹那トンネル, 170—182.
久野 久, 1962, 旧丹那トンネルと新丹那トンネル,科学, 32, 397—401.
日本国有鉄道新橋工事々務所編, 1954, 開通二十周年記念 随筆 丹那とんねる, 作品社, 333p.
内,
新井堯爾, 驛長の頃から, 235—241.
青木槐三, 記者の眼で見た丹那隧道, 254—272.
門屋盛一, 生埋日記, 108—128.
石川九五, 隧道のスピード, 11—35.
太田善雄編, 1965 , 新丹那トンネル工事の記録, 鹿島, 131 p.
鐡道省熱海建設事務所,1933, 丹那トンネルの話,224p.+序文3p.+目次4p.;復刻版,1995.
鐡道省熱海建設事務所, 1936, 丹那隧道工事誌, 602p.
(その3に続く)
(2013.3.5)
丹那断層と丹那トンネル難工事と二つの大地震(その3)
丹那断層と丹那トンネル難工事と二つの大地震
—その3: トンネル内丹那断層の立体像・二大地震のとき・将来は?—
服部 仁
第5図 丹那断層付近の先進導坑・本線・水抜坑・立坑・水抜きボーリング掘進状況.
坑奥切羽から松葉のように放射状に延びた線は水抜きボーリングであり,クラリヤス式試錐機およびデンバー式削岩機が使用された。服部(2006)の図7を複製. 原図:鐡道省熱海建設事務所(1933), 187ページを反転加筆浄書.
(※拡大は図をクリック)
6.トンネル坑内における丹那断層の立体像
丹那断層は,丹那盆地の地表において,地割れが雁行状にできていて,道路や畦道を左横ずれさせながら,その分布幅は数mから10mほどで,ほぼ直線状に南北性に延びている状況が北伊豆地震の現地調査結果から明らかになっている(その1:第3図).この分布状況は,坑内で確認された丹那断層の実態と著しく異なっている.坑内の断層は,幅が20m以上で,周辺に破砕帯を伴うなど40mに及ぶ広い範囲に断層角礫帯をなし,南側第三水抜坑から北側大迂回水抜坑まで北西−南東方向に約300m延びていた.丹那断層の北西端部分は,紙のように薄くなって尖滅状況にあった(第5図).トンネル内で確認されている丹那断層の立体像は,地表における南北性の地割れ状の丹那断層と規模と方向を見ても,とても同一の断層(その1:第2図)とは想像できないであろう.北側大迂回水抜坑は,北伊豆地震発生後に掘削されており,断層周辺の岩石は堅固であり,1932年6月22日断層鏡面を撮影した写真が残っており,湧水量約28 ℓ/secが記録されている(鐡道省熱海建設事務所, 1936, p.174対面).
7.水抜き工法の三位一体計画
西口1,494m(4,900呎)付近で,水平ダイヤモンドボーリングの試錐は,スウェーデン人のエリックソンさんやノードヤークさんの指導を受けていた.柳川君がダイヤモンド埋込作業など補修技術を会得し,以降日本人だけでもやれるようになった.丹那盆地のA,B,C,Dボーリング(その1:第1図)を始めた動機は,
(1)トンネル内の地下水を立坑からポンプアップする,という奇抜とも思える様な着想が,当時,建設局の太田工事課長から発案され,具体的な検討を大学新卒の河西,佐藤,渡辺君などに研究課題として与えたのが動機となり,次いで
(2)同時にトンネルレベルまでの地質を調査するためであった.
4本のボーリングの内,C号ボーリングは丹那盆地東側を走る丹那断層に至近のところに位置していた.このボーリングの地質柱状図を見ると,トンネルから40m位高い地点に厚さ約18mの堅固な安山岩溶岩層がある.短時間にこの高さまで水位を下げる事ができるので,北側水抜坑においてこの案を実行して水を絞りつつ,セメント注入により断層と悪地質を切抜けことに成功した.
地下水位低下のため,①南側と北側水抜坑および切羽から砲列を敷いたような多数の水平排水ボーリング,②立坑からの上部水抜坑,および③最後に突破する坑道のセメント注入を行ったが,これらを地下水位低下法の三位一体計画の仕事と呼んでいる(鐡道省熱海建設事務所, 1933, 1936).
8. 丹那盆地の渇水問題とトンネル内の地下水
丹那地方は豊富な水に恵まれた所で,溪間には泉が湧いて山葵が栽培せられ,農家はその水を引いて飲料水としていた.牧畜も行われ水車は回り,水田は水の多いのに苦しんだ程であった.この豊富であった水がだんだん減ることに,人々が氣づきだしたのは関東大地震後の1924年頃で,盆地の東部畑区の細井澤から次第に大久保澤,檜澤と広がっていった.一方,トンネル坑内の湧水は工事進行とともに増加して,三島口ではおびただしい量の水が出てきて,トンネル工事のため盆地の水が下に吸い取られるのではないか,と疑い始められた.
工事関係者は,これまで経験したこともない程の膨大な量の湧水に驚きながらも,地下水に考えが及ばなかった.農民はトンネルで水を抜くから丹那の水が減って行くのは当たり前,と主張し,善後策を求めて建設事務所へたびたび請願にきた.役所の方でも,関東地震直後のことであり地下に変動があって水の通路が変ったのかも知れないし,また1924年から続いて3年ほど降雨量の少なかったこともあり,湧水が減ったのではないか,などと因果関係についてはまだ半信半疑であった.
渇水はますますひどくなり,坑内からの湧水は激増して,1926年になると,盆地の渇水はトンネルのせいではないなど,ともう否定できなくなった.翌年から渇水による不作の見舞金を出すこと,飲料水の缺乏した所には水道を引いて,一時的沈静化を計るとともに,水収支関係をつきとめるため徹底的に調査することとなった.丹那盆地内外の10か所に雨量計を据えつけ,また柿澤川,谷下川,冷川,和田川,加茂川,千歳川の各河川に堰を設けて毎日流量を観測した.各河川は互いに接近し,地形・林野の状態,氣象の関係など大体似ているのに,流域面積一平方里あたりの川の流量は非常に違っていた.千歳川や加茂川は,それまで日本各所で計った数字と大差がないのに,著しく渇水した柿澤川や谷下川,和田川などでは特別に少なかった.降雨量と川水の流量の割合でも同じように渇水地域では少なくて,雨の大部分は地下に滲みこんでいること,およびこの滲透量は年とともに多くなったことが確認された.
工事が進行するにつれて渇水区域も広がっていった.各河川の水量が減るにしたがって,灌漑用水が得られず,下流の広大な区域では作付けのできないところが多くなり,農民達が役所に押しかける大騒ぎに発展した.1933年度になって,静岡県庁の協力により酪農業の振興策を含めて水対策は解決され,被害民もようやく安堵した(鐡道省熱海建設事務所, 1933).
この渇水事件から、多くの知識を得ることができ、新たな知恵が生まれて水文学に発展した,といわれている.
今日では,トンネル掘進の場合のみならず,地下構造物を造る時,地下水と地表水に大影響を与えないよう愼重に工事が管理されている.丹那盆地における80年前の渇水問題は,多くの貴重な試練を与えており,それらの経験から環境保全対策の基本を習得したことは史実であり,長く記憶にとどめることであろう.
9. 丹那トンネル内における関東大地震と北伊豆地震の影響
1923年関東大地震の時,三島口は1,509m(4,950呎)の断層を掘っていて,電気は止まったが,坑外では宿舎の破損はあったものの倒壊などの被害も死傷者もでなかった.三島口近くの大場,韮山集落等は家が大半潰され,圧死者も多数でて大騒ぎであった.トンネル内ではゴーという山鳴りが聞えたので,それ崩壊だと皆あわてて逃げ出した.しかし,現場では別に異状もなく,電線が揺れるのを見て始めて地震だと氣がついた位であった.
1930年北伊豆地震の時は,震源に近かったためか山鳴りや上下動を感じた.三島口坑内では,3,353m(11,000呎)辺りが崩壊して,ずり出しの4人と蓄電車の運転手1人が埋没された.直に救助作業にかかり,運転手とずり出しの1人は救い出されたが,他の3人は4日後に死亡が確認された.他の部分では,853m(2,800呎)辺りではトンネルを横断して亀裂を生じ,2,195m(7,200呎)から2,316m(7,600呎)辺りにかけては側壁に縦に長い亀裂が入った.また,3,048m(10,000呎) の断層を境に,奥の方は18cm(7吋)も基盤が下り,側壁コンクリートに割目ができた.3,261m(10,700呎) 辺りから奥61m(200呎)までは,切り広げが済みコンクリート巻き直前で,トンネル工事中で一番不安定な場所であった.ここが地震で激しく揺れて,先づ支保工が倒れ,次いで支えていた土砂がその上に崩れ落ちてトンネルの大部分を覆い,上部は高くまでえぐられて洞穴となり,奥の崩れない部分に達していた.
崩壊個所を避けて水抜坑を廻って,更に奥の方では底設導坑は切羽から土砂が噴いたらしく,約30m(100呎)位の間土砂が堆積していたが,支保工には別状はなかった.南側第二水抜坑に入って見ると,そこの切羽は地質が悪かったので作業を中止し,切羽に地上で見るように松丸太を充填して土留としていた.先方の地質を調べるため水平に61m(200呎)ボーリングを行い,そのためのケーシングチュウブを松丸太の間に入れてあった.驚いたことに,松丸太もケーシングチュウブも正面を向いていたはずなのに,一様に45度位南に向きを変えていた.
南側第三水抜坑に入って見ると,ここも鉄製支保工が途中で切断されて,正面にはきれいな断層鏡面が現われ,ほぼ水平に條痕がついていた.この断層を境にして東西の地塊が運動し,西の方が南に2.4m(8呎) 位ずったことがわかった.
熱海口では2,743m(9,000呎)の断層が動いて,断層の方向に亀裂が入った位である.
丹那トンネルは,1918年から16年間の工事中に2回も激震の洗礼を受けたことになる.激震によって少なくとも,その時までにできていたコンクリート巻部分に少々の亀裂が生じた程度で,トンネルがつぶれる様なことはないとわかった.大地震後,東京帝國大學地震研究所が丹那盆地の地表とその真下の水抜坑に地震計を据えつけて計ったところ,同じ地震でも,地下では地表の3分の1位しか震動しないことがわかった(鐡道省熱海建設事務所, 1933, 1936).
10.もし、再び大地震に襲われたら
以下の随想文は,ウイットあふれる解説文になっているので,参考までに再録する(鐡道省熱海建設事務所, 1933).
“それでは,三島口3,658m(12,000呎)の丹那大断層がもう一度2.4m(8呎)動いたらどうなるか,とよく聞かれます.その時には綺麗に8呎の食違いができるかも知れませんし,または崩壊して通れなくなるかも知れません.その時,ちょうど汽車がそこを通っておれば,もちろん脱線転覆してたくさんの死傷者をだすことでしょう.しかし,そんな大地震は滅多にあるものではありません.恐らく,このトンネルの経済的利用価値のある間にはもう起らないでしょう.たとえ起ったとしても,その悪い箇所を汽車が通り抜ける時間は数秒に過ぎないのです.一生に一度の数秒間の時間を,ちょうどそこに居合はせて災難に出遇ってもよくよくの不運とあきらめて下さい.汽車の走る道ではそんな所より,切取りや築堤や橋梁等,大地震の時,危い箇所がまだたくさんあります.いやそれよりも危険率からいったら,東京の市街で圓タクに乗る方がさらに恐しいことです.そんなことは氣にかけず,この「丹那トンネルの話」でも読みながら,安心してトンネルを通ってください.”
【引用文献】
服部 仁,2006,丹那トンネルと新丹那トンネル.鹿島技術研究所編,鉄道の鹿島−『技術の鹿島』そのDNAを訪ねて 第2集,170-182.
鐡道省熱海建設事務所,1933, 丹那トンネルの話.224p+序文3p+目次4p. (復刻版,1995)
鐡道省熱海建設事務所,1936, 丹那隧道工事誌.602p.
【参考資料】
鹿島社内報, 1961, 建設進む新丹那トンネル, 35 p.
菅野忠五郎編, 1963, 鹿島組史料の内,第三十六章 丹那隧道工事, 107-121.
Kuno, H.,1951, Geology of Hakone Volcano and adjacent areas. Part 穸. Jour.Fac.Sci. Univ.Tokyo, Sec.穸, 7, 351-402. (カラー地質図:BY HISASHI KUNO,1938)
久野 久, 1952, 七万五千分の一地質図幅『熱海』および同説明書、地質調査所, 153p.
松田時彦, 1972, 1930年北伊豆地震の地震断層, 伊豆半島,東海大学出版会,73-93.
静岡幹線工事局, 1965, 東海道新幹線工事誌, 587p.
田方郡町村会・教育長会・校長会・教育研究会, 1981, 昭和5年の北伊豆地震に学ぶ, 16p.
吉村 昭, 1990, 闇を裂く道, 文春文庫, 430p.
(2013.3.5)
第4回フォトコン入選作品:優秀賞02
第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品
第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品:優秀賞「地層模様」
写真:細井 淳(茨城県) 撮影場所:茨城県北茨城市長浜海岸
【撮影者より】
砂岩・泥岩・珪質泥岩が薄く重なった地層は、上(層理面上)から見ると侵食の具合によって不思議な模様を形成する。撮影場所周辺には海食崖と海食棚が発達している。これらを形成する地層の模様は、海食崖では綺麗な縞模様であり海食棚では写真のような不思議な模様である。
撮影地点周辺にはこの地層が形成した美しい景観が広がっており、茨城県北ジオパークの見所の一つになっている。
【審査委員長講評】
薄く重なった地層を上から眺めると地図の等高線のようなパターンがあらわれ、面白いものです。左上にある海草?からおよその大きさがわかりますが、海草を取り除いて大きさをわからなくしてしまい、より抽象的にする手もあります。評者は、この写真を見て、アイスランドの火山灰の縞々模様のあるバトナ氷河を思い出しました。(白尾)
【地質的背景】
(準備中)
←戻る 目次 進む→
第4回フォトコン入選作品:優秀賞03
第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品
第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品:優秀賞「空気砲」
写真:大江 雅史(愛知県) 撮影場所:桜島
【撮影者より】
垂水から走って桜島が近づいてきた。噴火が激しく、日に何度も噴煙を上げているらしい。快晴の穏やかなようすを撮ろうとカメラを構えた瞬間、大きな噴火があり、まわりの空気がビリビリと震動した。
【審査委員長講評】
桜島南岳の昭和火口は2009年頃から噴火が活発となり、最近は毎日のように爆発的噴火を繰り返しています。対岸から撮影したこの作品は、天気にも恵まれ、昭和火口とその手前にある鍋山、モクモクと上がる噴煙、噴煙から落ちる火山灰のようすなどがよくわかります。(白尾)
【地質的背景】
(準備中)
←戻る 目次 進む→
第4回フォトコン入選作品:ジオパーク賞
第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品
第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品:ジオパーク賞「活躍するボランティアガイド」
写真:本多 優二(群馬県) 撮影場所:群馬県甘楽郡下仁田町(青岩公園)
【撮影者より】
下仁田ジオパークでは、こどもを対象にした体験教室の指導をはじめ、ジオツアーのご案内をボランティアガイドが行っています。
下仁田の子どもたちの未来のために、また、下仁田を訪れていただいた方々に、下仁田ジオパークの魅力を知っていただくため、ボランティアガイドが、きょうも活躍しています。
【講評】
ジオパークに関係した写真は今年大幅に増えましたが、大部分が景観や露頭の写真でした。その中で、本多さんの写真は子供と同じ視線でジオツアーを楽しんでいる地元ボランティアガイドさんと、石積みに熱中している小学生の姿が生き生きと映し出されており、ほのぼのとした雰囲気を醸し出しています。ジオパークは「人の活動」が重要視されることからも、この写真が選ばれました。(ジオパーク担当理事:高木秀雄)
【地質的背景】
(準備中)
←戻る 目次 進む→
第4回フォトコン入選作品:入選01
第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品
第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品:「静けさ」
写真:檜山 貴史(北海道) 撮影場所:北海道苫小牧市 樽前ガロー
【撮影者より】
昭和54年に苫小牧市の自然環境保全地区に指定されました。
樽前山の噴火で出来た溶結凝灰石を少しずつ川が浸食し、山麓の林間に形成された渓谷地帯で、壁一面を60数種もの深緑色のコケが覆っている幻想的な場所です。
スローシャッターで水の流れる音や鳥のさえずりだけが聞こえてくるような静かで幻想的な空間を表現しました。
【審査委員長講評】
樽前ガローは、樽前火山の南側にある溶結火砕流堆積物が水の浸食で削られたものです。ガローとは両側が絶壁になっている場所だそうです。北側の支笏湖側にはよく似た苔の洞門があります。この作品では崖のようすがようやくわかる程度までアンダー気味にしていますが、そのことが題名のような幽玄な雰囲気を出すのに役立っています。(白尾)
【地質的背景】
(準備中)
←戻る 目次 進む→
第4回フォトコン入選作品:入選02
第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品
第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品:「1934-35昭和硫黄島」
写真:池上 郁彦(福岡県) 撮影場所:鹿児島県三島村 薩摩硫黄島
【撮影者より】
鹿児島県三島村にある昭和硫黄島は1934年末から35年にかけて起こった海底噴火により形成された新島である。比高300mの山体は鬼界カルデラの内輪に位置し、その活動は過去100年の日本における最大の火山活動であった。当時海は白煙を上げる軽石で埋め尽くされたと言われるが、現在その痕跡が認められるのは薩摩硫黄島の対岸部に限られる。写真で薩摩硫黄島特有の変色した海の向こうに見えているのが昭和硫黄島である。
【審査委員長講評】
昭和硫黄島は、活発に噴火活動を続ける薩摩硫黄島の東2kmにある新島です。遠景が1934〜35年でできた新島、手前はその時の噴火で流れ着いた軽石です。非常にわかりやすい写真で、撮影地の昭和硫黄島は鹿児島港から4時間ですから行きたくなってきます。(白尾)
【地質的背景】
(準備中)
←戻る 目次 進む→
第4回フォトコン入選作品:入選03
第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品
第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品:「マグマの上で」
写真:高橋 伸輔(秋田県) 撮影場所:秋田県山本郡八峰町
【撮影者より】
昨年日本ジオパークに正式認定された『八峰・白神ジオパーク』にある柱状摂理。当地へは普段着で気軽に足を運ぶ事が容易で、また登る事もできる。
この巨大な岩山に登ってみると、当時の海底で燃え上がるようなマグマの活動が頭に浮かび、まさに地球は生きているのだという事を実感させられる。
【審査委員長講評】
八峰町(はっぽうちょう)は、青森県と秋田県にまたがる白神山地の南西部に位置し、海岸沿いに地質の見どころがあります。作者は溶岩流の柱状節理の中から形の良いものを選んで撮影しました。柱状節理という六角の柱状と思いがちですが実際にはいろいろな形のものがあります。(白尾)
【地質的背景】
(準備中)
←戻る 目次 進む→
第4回フォトコン入選作品:入選04
第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品
第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品:「火山の造形」
写真:坪田 敏夫(神奈川県) 撮影場所:静岡県伊東市 大室山
【撮影者より】
伊豆半島の観光名所、伊東市の大室山です。後ろには天城連山が連なります。平たんな場所にポッコリと隆起した地形は火山の威力を感じさせてくれます。なだらかな斜面と直径300メートルのすり鉢状の火口は火山がつくりだす造形美だと思います。
【審査委員長講評】
伊豆大室山は標高580mの単成火山で、作者は東側700mほどの高度から撮影したと思われます。軽飛行機をチャーターしたのでしょうか。良い時間帯を選んで撮影したので、陰影に富んだ大室山とバックの天城山が美しく、登山リフトやシャボテン公園などもわかって楽しい写真となっています。(白尾)
【地質的背景】
(準備中)
←戻る 目次 進む→
第4回フォトコン入選作品:入選05
第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品
第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品:「地層のデザイン」
写真:坂口 有人(神奈川県) 撮影場所:神奈川県横須賀市野比海岸
【撮影者より】
砂岩泥岩の互層がきれいな幾何学パターンを成しています。これはおそらく水平にたまった地層が、断層や地すべり等によってずれたものです。画面の上側が右方向に、下側が左方向にずれたために、間に挟まれた地層が短冊状に切れて、時計回りに回転したと考えられます。それにしても海底でこんなきれいなパターンができていると思うと不思議な感じがします。
【審査委員長講評】
この作品も最優秀賞を獲得された坂口有人氏のものです。この作品には露頭の大きさがわかるスケール的なものが入っていませんが、モノトーンの調子と相まって形の面白さが強調されています。日本は海岸線も長く、地質も変化に富んでいるので、海岸を歩いていると思わぬ発見があります。(白尾)
【地質的背景】
(準備中)
←戻る 目次 進む→
第4回フォトコン入選作品:入選06
第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品
第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品:「東南極セール・ロンダーネ山地の巨大岩峰」
写真:菅沼 悠介(東京都) 撮影場所:東南極セール・ロンダーネ山地
【撮影者より】
第53次南極地域観測隊での調査時に撮影したものです。ゴンドワナ大陸の誕生時に変成作用を受けた片麻岩類の基盤に、花崗岩質マグマが貫入している様子が見て取れます。岩峰の高さは約400 mもあり、横を走るスノーモービルの大きさからも、その巨大さが実感できます。
【審査委員長講評】
作者は国立極地研究所の研究者で、昭和基地から西へ700kmの位置にあるセール・ロンダーネ山地での調査中に撮影した作品です。普通の人が行けない場所だけに魅力的で、「行きたい」と思わせます。スノーモービルを手前に置くことによって岩峰の巨大さがわかります。雲があったのが残念。(白尾)
【地質的背景】
(準備中)
←戻る 目次 進む→
第4回フォトコン入選作品:入選07
第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品
第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品:「輝く岩山」
写真:佐藤 忠(東京都) 撮影場所:アメリカ・アリゾナ州ナバ木族居留地内
【撮影者より】
夕日に照らされた岩山は地層豊かな所でした。とても歩きにくく岩の上に足をかけると割れる程やわらかく、走行に注意が必要です。かけ落ちた岩は風に舞い、砂となって岩をけずり、この様な形が出来たと思う、とても美しい所でした。
【審査委員長講評】
アリゾナとユタの州境にあるThe Waveでの撮影でしょうか。ここはジュラ紀の「サハラ砂漠」、ナバホ砂岩からなり、侵食された砂岩が方向によって波打って見えます。人気撮影スポットなので類型的な写真になりがちですが、作者は日没寸前まで粘って力強い作品をものにしました。(白尾)
【地質的背景】
(準備中)
←戻る 目次
geo-Flash No.214 復旧・復興に関わる調査研究報告(5)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.214 2013/3/19 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】復旧・復興に関わる調査研究報告(5)
【2】コラム:丹那断層と丹那トンネル難工事と二つの大地震(その2)
【3】行事委員会より:レギュラーセッションの再編や招待講演について
【4】2013年「地質の日」行事予定
【5】2013年度春季地質の調査研修:参加者募集
【6】地質科学国際研究計画(IGCP)608の採択
【7】「割引会費申請」3/29:最終締切
【8】地質図の在庫一掃セール!2013年3月末日まで
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】復旧・復興に関わる調査研究事業報告(5)
──────────────────────────────────
関東平野内陸部の住宅地での盛土材質の相違による液状化要因の解明
新潟大学災害・復興科学研究所 卜部厚志
2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震によって,関東地方南部では埋立地などの人工地盤を中心に多くの地域で液状化が発生した.このうち,千葉県の浦安地域などの東京湾沿岸の埋立地では,顕著な液状化により多くの建物に被害が及んだ.埋立地における液状化被害は,国内外のこれまでの地震によっても繰り返されてきた現象である.一方で,関東地方内陸部の埼玉県,千葉県や茨城県内においても,一部の地域で液状化による建物被害が発生しており,千葉県や茨城県では現在の利根川流域に被害が集中している.このため,本研究では,関東地方内陸部の液状化被害に着目して,液状化被害の記載と分布,立地地盤と液状化の発生要因について検討を行った.
続きを読む、、http://www.geosociety.jp/hazard/content0079.html
本事業は,日本地質学会が公募した,会員による東日本大震災の復旧・復興に関わる調査・研究事業のひとつです.
その他採択された事業については,こちらから
http://www.geosociety.jp/hazard/content0068.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】コラム 丹那断層と丹那トンネル難工事と二つの大地震(その2)
──────────────────────────────────
正会員 服部 仁
熱海から丹那トンネル経由で三島へ抜けるまで,東海道線は現在のJR御殿場線を通っていた.当時,降雨量が多いと毎年のように線路と並行する鮎澤川が氾濫し,堤防の決壊,山崩れが起こり,しばしば不通になった.1か月以上も不通状態が続くこともあった.その上,富士山麓の御殿場を中心に上り下りともに40分の1の急勾配が長いため,貨物列車が蒸気機関車三台つけて牽引されても,あえぎ,あえぎ走っていた.丹那トンネル完成前,1934年末までの日本の幹線鉄道は,東海道メガロポリスを支える大動脈の役割を果たしてはいなかった.
続きを読む、、、、、http://www.geosociety.jp/faq/content0433.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】行事委員会より:レギュラーセッションの再編や招待講演について
──────────────────────────────────
昨年の学術大会(大阪大会)において「学術大会の改革:オープンディスカッション」という公開会議が開催され,学術大会の活性化と本学会の発展,さらには地質学の発展につながるような方策について意見が交わされました(ニュース誌,15(11),29-30).その議論を受けて,行事委員会は現在,レギュラーセッション(以下,RS)の再編やRSでの招待講演について検討を進めています.
・新レギュラーセッション
・レギュラーセッションで招待講演が可能になります
・レギュラーセッションを他学協会との共催にできます
行事委員長(行事担当理事) 星 博幸
詳しく読む、、、http://www.geosociety.jp/science/content0055.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2013年「地質の日」行事予定
──────────────────────────────────
2008年より5月10日が『地質の日』に制定され,これを記念した多くのイベントが,全国各地の博物館・大学で開催されています。
今年も学会関連の行事が多数予定されています.
◆地質学会・応用地質学会主催:街中ジオ散歩 in Tokyo「石神井川がつくる地形の移り変わりと地質(仮)」(5/12)
◆近畿支部:地球科学講演会「大阪平野の地盤環境と地盤災害」(5/12)
◆北海道支部:「地質の日」記念展示「豊平川と共に―その恵みと災い―」(4/23〜6/2)
◆西日本支部:身近に知る『くまもとの大地』 (5/11)
それぞれのイベントの詳細は,学会HPの「地質の日」よりご覧頂けます.
http://www.geosociety.jp/name/content0014.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2013年度春季地質の調査研修:参加者募集
──────────────────────────────────
地質調査法の基本技術の修得をめざすとともに,それをベースに得られた過去の調査や研究の成果についても学びます.地質調査の経験のない方でも,地質調査法の基本を体で習得することを目指します.
日程:2013年5月27日(月)〜31日(金)4泊5日
場所:千葉県君津市及びその周辺地域(房総半島中部域)
募集人数:6名. 参加費:12万円
申込締切:2013年4月19日(金)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/engineer/content0027.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質科学国際研究計画(IGCP)608の採択
──────────────────────────────────
2013〜2017年の5年間にわたる国際プロジェクト,地質科学国際研究計画(International Geoscience Program:IGCP) の新規提案が,このたびUNESCOのIGCP本部より採択されました.
IGCP608 "Cretaceous ecosystems and their responses to paleoenvironmentalchanges in Asia and the Western Pacific" 「白亜紀のアジア−西太平洋地域の生態系システムと環境変動」
略称:白亜紀アジア−西太平洋生態系 (Asia-Pacific Cretaceous Ecosystems)
詳細につきましては,4月号の地質学会ニュースや,現在開設準備中のWebsiteで改めてお知らせいたします.
日本の研究者が筆頭リーダーとして活動する久しぶりのプロジェクトに,是非ご参加・ご協力・ご支援をよろしくお願いします.
(IGCP608 プロジェクトリーダー 安藤寿男)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】「割引会費申請」最終締切
──────────────────────────────────
■学部学生・院生(研究生)「割引会費申請」最終締切:3月29日(金)
※ 通常の会費払込については,「2013年会費払い込みについて」をご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0108.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】地質図の在庫一掃セール!― 2013年3月末日まで
──────────────────────────────────
※現在、地質学会に在庫があるものについてのみ、特別販売中です。
最新の在庫リストはホームページに掲載していますのでご覧いただくか、事務局(電話:03-5823-1150)にお尋ねください。
詳しくは,こちらから http://www.geosociety.jp/news/n96.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】支部情報
──────────────────────────────────
■北海道支部
支部例会(個人講演会)
日時:2013年4月27日(土)10:00〜18:00(予定)
場所:北海道大学理学部5号館2階 5-201室
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
■関東支部
2013年度関東支部総会・地質技術伝承講演会
4月13日(土)午後
場所 北とぴあ(東京都北区王子1-11-1)
【地質技術伝承講習会】参加費無料
時間:14:00〜16:00(予定)
講師:アジア航測株式会社 今村遼平氏
【関東支部総会】
時間:16:00〜16:45(予定)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/faq/content0430.html#06-4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地震本部ニュース12月号(2013.3.4配信)
http://www.jishin.go.jp/main/p_koho04.htm
■学術会議公開シンポジウム
「農林水産業への地球観測・地理空間情報技術の応用」
3月21日(木)13:00-17:00
場所:日本学術会議講堂
http://krs.bz/scj/c?c=46&m=21728&v=ef9d2d96
■2013 Western Pacific Sedimentology Meeting
台湾地質学会,日本堆積学会 主催
日本地質学会,IAS,SEPMほか 共催
5月13日(月)〜18日(土)
13-14日:研究発表 15-18日:巡検
場所:The Longtan Aspire Resort, Taoyuan, northern Taiwan
http://wpsm.ncu.edu.tw/
■日本古生物学会2013年年会
6月28日(金)〜6月30日(日)
会場:熊本大学
http://www.palaeo-soc-japan.jp/
■第50回 アイソトープ・放射線研究発表会発表論文の募集
日本地質学会ほか 共催
7月3日(水)〜5日(金)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1)
http://www.jrias.or.jp
■第57回粘土科学討論会
日本地質学会 共催
9月4日(水)〜6日(金)
会場:高知市文化プラザかるぽーと
参加・講演の申込期間 :6月3日(月)〜 14日(金)
講演要旨送付締切 :7月12日(金)
http://www.cssj2.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/outline/content0098.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■東京大学大気海洋研究所平成25年度海洋調査船共同利用公募(3/25)
■平成25年度日本学術振興会育志賞候補者の推薦(学会締切5/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flash No.215 いよいよ新年度スタート!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.215 2013/4/2 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】日本地質学第5回総会開催について
【2】コラム:丹那断層と丹那トンネル難工事と二つの大地震(その3)
【3】2013年「地質の日」行事予定
【4】「石垣島東海岸の津波石群」が天然記念物指定: 調査では法令の遵守を!
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】日本地質学第5回総会開催について
──────────────────────────────────
日時 2013年5月18日(土)12:30〜14:00
会場 北とぴあ 第2研修室(東京都北区王子1-11-1)
1. 定款第20条により本総会は役員ならびに代議員による総会となります.ただし
定款により正会員は総会に陪席することができます.
2. 定款第28条第1項により,代議員には別途,総会開催通知ならびに総会規則にも
とづく議決権行使書,委任状などをお送りいたします.ご都合で欠席される方は,
議決権行使書または委任状を提出してください.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0111.html
*総会終了後,同会場にて第4回惑星地球フォトコンテストの表彰式を行います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】コラム 丹那断層と丹那トンネル難工事と二つの大地震(その3)
──────────────────────────────────
―その3: トンネル内丹那断層の立体像・二大地震のとき・将来は?―
正会員 服部 仁
丹那断層は,丹那盆地の地表において,地割れが雁行状にできていて,道路や畦
道を左横ずれさせながら,その分布幅は数mから10 mほどで,ほぼ直線状に南北性
に延びている状況が北伊豆地震の現地調査結果から明らかになっている(その1:第
3図).この分布状況は,坑内で確認された丹那断層の実態と著しく異なっている.
続きを読む、、、、、http://www.geosociety.jp/faq/content0434.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2013年「地質の日」行事予定
──────────────────────────────────
2008年より5月10日が『地質の日』に制定され,これを記念した多くのイベントが,
全国各地の博物館・大学で開催されています。
今年も学会関連の行事が多数予定されています.
◆地質学会・応用地質学会主催:街中ジオ散歩 in Tokyo「石神井川がつくる地形の
移り変わりと地質(仮)」(5/12開催)
◆近畿支部:地球科学講演会「大阪平野の地盤環境と地盤災害」(5/12開催)(申
込締切4/30)←HP情報更新しました。
◆北海道支部:「地質の日」記念展示「豊平川と共に―その恵みと災い―」(4/23
〜6/2)
◆西日本支部:身近に知る『くまもとの大地』(5/11開催)
それぞれのイベントの詳細は,学会HPの「地質の日」よりご覧頂けます.
http://www.geosociety.jp/name/content0014.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】「石垣島東海岸の津波石群」が天然記念物指定: 調査では法令の遵守を!
──────────────────────────────────
「石垣島東海岸の津波石群【沖縄県石垣市】」が天然記念物(地質・鉱物)に
指定されました。
http://www.bunka.go.jp/ima/press_release/pdf/shiseki_shitei_121116_ver2.pdf
津波被害を具体的に伝える証拠としての重要性が認められたとのことです。
今回指定された津波石群にかぎらず、野外の調査・研究に際しては、事前
に十分な下調べを行い、研究対象が国立公園や国定公園の範囲内にないか、
サンプリング対象物が法令によって採取を禁止・制限されていないかチェック
し、必要に応じて関係諸機関の許諾を得ることを要請しておくことが重要です。
野外調査にあたっては法令遵守を十分に心がけてください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報
──────────────────────────────────
■北海道支部
支部例会(個人講演会)
日時:4月27日(土)10:00〜18:00(予定)
場所:北海道大学理学部5号館2階 5-201室
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
■関東支部
2013年度関東支部総会・地質技術伝承講演会
4月13日(土)午後
場所 北とぴあ 第1研修室(東京都北区王子1-11-1)
【地質技術伝承講習会】参加費無料
時間:14:00〜15:40
講師:アジア航測株式会社 今村遼平氏「土石流の実態と防災対策」
【関東支部総会】
*支部会員の方で総会に欠席される方は委任状をお願いします(4/12:18時まで).
時間:15:50〜16:45
詳しくは, http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地震本部ニュース1月号(2013.3.22配信)
http://www.jishin.go.jp/main/p_koho04.htm
■(独)科学技術振興機構社会技術研究開発センター(RISTEX)
平成25年度の戦略的創造研究推進事業提案募集・募集説明会
提案プログラム
・科学技術イノベーション政策のための科学
・研究開発成果実装支援プログラム など
募集説明会(東京・京都)
・JST東京本部別館:4/16(火)14時〜
・メルパルク京都:5/16(木)13時〜ほか
http://www.ristex.jp/examin/suggestion.html
http://www.ristex.jp/stipolicy/program/proposal.html
■第54回科学技術映像祭:入選作品上映会
東京会場:4月18・19日(会場:科学技術館サイエンスホール)
大阪会場:4月15〜21日(会場:大阪科学技術センター)など
上記以外にも,全国13箇所での上映会が予定されています。
詳しくは,http://ppd.jsf.or.jp/filmfest/
■2013 Western Pacific Sedimentology Meeting
台湾地質学会,日本堆積学会 主催
日本地質学会,IAS,SEPMほか 共催
5月13日(月)〜18日(土)
13-14日:研究発表 15-18日:巡検
場所:The Longtan Aspire Resort, Taoyuan, northern Taiwan
http://wpsm.ncu.edu.tw/
■第50回 アイソトープ・放射線研究発表会発表論文の募集
日本地質学会ほか 共催
7月3日(水)〜5日(金)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1)
http://www.jrias.or.jp
■第57回粘土科学討論会
日本地質学会 共催
9月4日(水)〜6日(金)
会場:高知市文化プラザかるぽーと
参加・講演の申込期間 :6月3日(月)〜 14日(金)
講演要旨送付締切 :7月12日(金)
http://www.cssj2.org/
■2013 International Association for Gondwana Research (IAGR) and 10th
Gondwana to Asia, in collaboration with IGCP 592.
会議・シンポジウム:9月30日(月)~10月2日(水)、
巡検:10月3日(木)~4日(金).
発表要旨締切:7/31(sungwon@kigam.re.kr)
参加登録締切:8/31
場所:韓国Daejeon(大田広域市),KIGAM(Korean Inst. Geosci. and Mineral
Resources)
http://iagr2013.kigam.re.kr or http://www.elsevier.com/locate/gr
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/outline/content0098.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■鹿児島大学大学院理工学研究科地球環境科学専攻地質科学講座教員公募(5/31)
■北海道大学大学院理学研究院自然史科学部門地球惑星システム科学分野教員公募
(6/28)
■三朝国際インターンプログラム2013参加学生募集:分析地球化学部門(4/30締切),
実験地球物理学部門(5/7締切)
■広島県イノベーション人材等育成事業補助金の公募(毎月末日毎に締切,翌月審
査)(*広島県内に本社または本店を置く中小企業及び中堅企業対象)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
第66回国際地質科学連合(IUGS)理事会出席報告(2013.3.27)
第66回国際地質科学連合(IUGS)理事会出席報告
小川勇二郎(IUGS理事)
図1 2012年8月から4年間の役員;左から,会計幹事(トレジャラー)Dong Shuwen氏,従来の事務局の書記,会長(プレジデント)Roland Oberhaensli氏,幹事長(セクレタリージェネラル)Ian Lambert氏.
1.はじめに
2013年2月19〜22日(火〜金),パリのユネスコ・アネックスで開かれた標記の国際地球科学連合 (International Union of Geological Sciences,以下,IUGSと略記; http://www.iugs.org/) の理事会 (Executive Committee) に,初めて出席した.以下はその感想を交えた報告である.
私は,2012年8月オーストラリアのブリスベーンで開かれた第34回万国地質学会議(IGC)でのIUGSの総会で,新規の理事(任期4年)に選出された.会長ほかを含めて理事等計9名で理事会(Executive Committee)を構成する.ほぼ各大陸区分ごとにある程度バランスを取って選出される模様であるが,出資金にもある程度比例しているようである.以下は理事会のメンバーである(カッコ内は出身国と地域区分,およその専門分野).
会長:Roland Oberhaensli(スイス;ヨーロッパ;変成岩);副会長:Yildirim Dilek(アメリカ合衆国;北米;オフィオライト)(今回は欠席);副会長:Marko Komac(スロベニア;ヨーロッパ;情報地質学);会計幹事(トレジャラー):Dong Shuwen(中国;東アジア;岩石学);幹事長(セクレタリージェネラル):Ian Lambert(オーストラリア;オセアニア;資源地質学)(以上5名が,ビュローを構成する.図1)
理事:Wesley Hill(アメリカ合衆国;北米;地学教育)(女性);理事:Hassina Mouri(南アフリカ;アフリカ;地学教育)(女性);理事:Sampat K. Tandon(インド;南アジア;堆積岩岩石学)(任期あと2年);理事:Yujiro Ogawa(日本;東アジア;野外地質学,海洋地質学)
このほか引き継ぎ役員として,前回までの会長と幹事長(絶大な情報量と権限を持っているようだ)(それぞれAlberto Riccardi氏(アルゼンチン;古生物学)とPeter Bobrowski氏 (カナダ;災害科学))も1年間同席するとのことであった(が,Riccardi氏は体調不良のため引退するとのことである.代理(職務権限を伴う)はBobrowski氏).なお,今後のIGC開催国である南アフリカ(ケープタウン;2016年)とインド(デリー;2020年)から,あえて代表団として理事を選んだ模様である.なお,この役員の選出は国家を代表するものではない.
2.IUGSとその周辺の構造および関係
IUGSは基本的にNGOであり,同じくNGOであるICSU (International Council for Science;国際科学会議; http://www.icsu.org/about-icsu/about-us)のメンバーである.後者はユニオンの連合である.ユニオンとは各学問の大くくりの国際的な団体を指し,たとえば,IUGGは測地・地球物理連合,IGUは地理学連合である.それらが国際学会を数年ごと(多くは,3または4年毎)に,たとえば,IUGSの場合は,万国地質学会(International Geological Congress; IGC)を開いている.(ただし,このIUGSとIGCとの関係の沿革は簡単ではない.2004年までは,IGCを開催する国がその予算を独自に編成していたが,それ以降はIUGSが全体を統括しつつIGCも開催することになった.).(なお,IUGSなどのユニオンは国連の組織であるユネスコ(UNESCO)の傘下にはない.一方,後に出てくる国際地質科学計画(International Geoscience Programme; IGCP, http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/international-geoscience-programme/) は,ユネスコ傘下である.)
IUGSの内部には上記の理事会のほかに,さまざまな事象特に資金の管理を取り扱う秘書部(セクレタリアートと呼ばれる)があり,今回を期して,合衆国の地質調査所(USGS;Reston)から中国の地質アカデミー(北京)に移動し,今後5年間はそこで多くの事務を取り扱う.秘書部の代表はLi Zhijian (李志堅)氏である.この秘書部では7名の職員が常勤か非常勤化で働いているとのことである.
IUGSとほかの関連する組織との関連はやや複雑である.私が理解する限り以下のようである.IUGSに代表を送るのは各国のIUGS委員会であり,日本では学術会議第三部会地球惑星科学委員会の中にある,IUGS分科会である(委員長は海洋研究開発機構の北里洋氏).各国はIUGSの総会において拠出金に応じての投票権の数が割り振られており,日本は7票である(これは,米国,中国などに次ぐものであり,イギリスなどよりも多い.なお,本年から中国は8票分の拠出金となった).IUGSは,UNESCO傘下の地質関連事業のIGCP (International Geoscience Project; 以前は,International Geological Correlation Projectと呼ばれていた)と内容的にかなり重複することがあり,競合関係にあるようにも見える場合がある.(なお,IGCPの日本からの代表は早稲田大学の平野弘道氏である.)
また,ユニオン連合という任意の連合もあり,たとえば地球科学連合(計9つの団体の連合)がボランティアで組織され,数年前から活動しているという(日本の連合大会に似ている).これをICSU内部の公式の連合とするかどうかは今回の理事会でも議論はされたが,まだ意見の統一は見られていないようである.
図2 2012年度のIUGS年次報告書の表紙
3.報告と審議
4日間の理事会の議事の大半は,理事のほか各プロジェクトの委員などの出席(計約60名)による報告事項であった.以下にそれと審議事項を列挙する.また,最後に筆者の感想を述べる.
1)主たる報告事項.第63, 64, 65回理事会の議事録の承認.また,2012年度(各年度はカレンダーイヤーに一致)の年報(報告書,833ページ;表紙は図の通り)が配布された.それ以外の昨今のとりまく重要事項としては,以下に箇条書きする通りの報告と意義づけが行われた.IUGSの公式雑誌Episodesの編集が中国からインドへ移行した.GeoParks運動(以下,運動というのは本報告での名称での筆者が使う,活動,プロジェクトなどの意味である)が重要事項として認められた.OneGeology運動(イギリスとフランス主導)の意義づけも行われた.国連はFuture Earthと呼ばれる運動を,以前のSystem Earth運動に代って開始し,本IUGSへも積極的参加を要請している.IUGSは2013年10月のデンバーにおけるGSA125周年においてブースを出し,世界全体への地質科学(地球科学)の主導権の発揮(Geoscience Initiativeという)を訴える.(これは「我々のdirection」と呼ばれており,従来とかく遅れがちであった地質科学分野の国際貢献を活発化したい,ということである.)IUGSのレファランス・マニュアル(欽定;v. 24; 計136ページ)を承認し,今後運用する.Resource for Future Generations(今後の時代の各種資源;金属非金属,エネルギー,水などの調査研究重要性)をデンバーで提出する.地球観測衛星のペイロード(取り付け装置)への発案,仙台における沈み込み帯地学災害ワークショップの日本からの提案の支援などを通じて,地質的考察の重要性を政治家や役人(political decision makers)に周知させるべく努力する.(これらは,地質学のコミュニティーをピュアなサイエンスにとどまることはなく,社会,政治などへ広く影響を与えることを目指すものである.そのためには広義の教育問題でもある.)そのほか,IUGSの会費の滞納金問題(支払いが遅れている,または滞っている国への対応),IGCPとの競合問題(この問題はかなり深刻であるようだ,それは互いに類似の行動やプロジェクトがあるからと思われる.)など.世界的に見て,全体に,こうした学術への予算が削減方向にあるが,今後UNESCOやICSUにさらなる援助の働きかけを行いたいなど.
2) IUGSの会計報告.会計幹事のDong氏から,会計報告がなされた.昨年度(2012カレンダー年)は,IGCなどがあったため赤字であった(主要な要因は,会費の未納のほか,オーストラリアドルの高騰(ユーロに対して1.4倍になった)ことにあるようである)).メンバー国は会費支払区分によって,active, pending, inactiveそれぞれ,80,6,34ケ国となっている.2013年は,経費の削減を行わなければならないだろう.
3)IUGS内部および支援している各活動団体の報告は以下の通り.
・Publication Committee (Brian Marker氏):Episodesの編集と内容のレベルアップをはかること.インパクトファクターが落ちている(最近は,1〜2程度).投稿はあるが,もう少し編集に力を入れるべきだ.(なお,日本からのアソシエイト・エディターは,明治大学の松本良氏である).
・International Commission on Stratigraphy (ICS) (Stan Finney氏):サントニアンの問題.Geobiodiversity databaseの作成.なお,International Chornostratigraphic chartが作成された.ベントナイトが多くの定量的データを含む(ジルコンなど)ので,今後重要である.www.stratigraphy.org.なお,今後とも野外地質学は重要なので,フィールドミーティングや後進国の若手援助を充実したいとのこと.
・Education, Training and Technology Transfer (CODE) (Jesus Martines Frias氏):後進国への教育的支援に関して.(ヨーロッパの人々から見た後進国とは,主としてアフリカを指すらしい)それらの人々を,実質的な教育を通して支援したい.www.iugscoge.org
・Management and Application of Geoscience Information (CGI) Francois Robidia氏.History of Geological Sciences (INHIGEO) (Wesley Hill氏):これらも,教育の一環でもある.
・Tectonics and Structural Geology (TecTask, www.tectask.org)(Manuel Sintabin氏):さまざまな取り組み,特に,残すべき露頭の保全,写真集,GoogleEarthへの対応など.www.outcropedia.org このグループには,日本から北海道大学の竹下徹氏が入っている.日本地質学会構造地質学部会編の「日本の構造地質露頭100選」と同じ趣旨のようであり,今後,協力するべきだろう(なお,Sintabin氏の示したGoogleEarth mapには,日本でのプロットはなかった).また,John Ramsay medal, Henk Zwart medalというものを用意する.さらにglacier watch, geo-vandalism, geoheritageなど破壊されつつある自然をどのように守るか,に関する積極的発言をしていくとのこと.我が国でも,身につまされることが多かった.
・Geoscience for Environmental Management (GEM) (Brian Marker氏):これには地質学的な公害(沈下,地下水,ダスト気候変動,金水銀などの鉱山跡の処置,自然災害,人工的な地層の問題など,人間活動による地学災害)の防止の情宣活動を行っている.日本からも国際的な貢献が望まれる.
・新しいプロポーザルの方向性(Ian Lambert氏):今後Future Earthの一環としてのさまざまな問題提起を行っていきたい.持続的社会を造るためには,decision makerが誰なのか,それが分かれば働きかけがしやすい.しかし社会は複雑なので,簡単ではない.日本の津波災害では,古地震学・古津波学の成果を社会が生かしきれなかった苦い経験がある.GeoscienceのFuture predictionの方法論を確立して,それを社会に生かす工夫をすべきである.今後,Strategy Implementation Groupを作って,ロードマップを作成し,イニシアチブを構築したい.これは,short-lived task groupとなろう.重要なのは,nature-human-environment-tectonicsを一つながりのものとして,統合的に取り組むことである.ドイツのある大学では,Geogovernment, geopoliticsというコースを作った.このような運動には,広く交流や教育活動が重要である.すでにこうした社会での活動は,ほかにオーストラリアやスウェーデンでも始まっている.人口密集の問題,景観の喪失,外交・政治問題との抵触などがある.後進国では,水問題,水汚染が深刻である.基本となるのは,市民は,そのような身の回りの状況を知る権利を持っているということ,市民は,教育を受けるべきであることである.将来に禍根を残さないために,急ぐ必要がある.特に,社会科学方面の人々に,自然科学からのインプットをするべきである.ここにきて,大気汚染,鉱物・エネルギー資源の問題が重要になってきた.つまり,経済界・工業鉱業関係者,政府,およびアカデミア(学術関係者)の3つが,互いに密接に協議すべきである.われわれアカデミアは,上意下達でなく,ダウンツートップでやるべきだ.その時,自由なものは,責任を取ることである.(筆者の感想:全くその通り.各分野の人々が,国際感覚をもって,これらの問題を,広く深く議論すべきである.)
4)各タスクグループの報告.以下のようなものがあった.
・Global Geochemical Baseline (TGGGB) (Sampat Tandon氏):国際標準化が進み,ゴールドシュミット会議でも地球化学的マップを作成しつつある.
・Geoheritage (Patrick de Weber氏):IUGS-ProGeoが終了し,一覧表を作った.地質露頭の保護,ジオツーリズムなどの活動.geoheritage-iugs.mnhn.fr
・Heritage Stone (TGHS) (Dokores Pereira氏):建造物に残された岩石の意義.日本からの代表は,産総研の加藤碩一氏.www.globalheritagestone.org
・Global Geoscience Professionalism (Ruth Allington氏):これは,地質学上の専門知識を社会にどのように役立てたらよいか,に関する実質的運動.広く興味を持たれた.社会を安全,安心で暮らせるようにするためには,社会全体と個人が知識を共有する必要がある.そのためには,専門家がその知識を広く社会に役立てるべく努力するべきである.Expertiseという用語がよく使われる.
5)新しいイニシアチブの提案.
・Initiative on Forensic Geology (Laurence Donnelly氏):地質学を犯罪捜査に役立てる.犯罪地質学,捜査地質学とも呼ぶべきもの.今後,重要になるであろうと思われる.また,地質学的公害や汚染を削減することに努力すべきである.すなわち,研究者は,儲けるためにやっているのではない.儲からないことにお金を掛ける意味を,社会全体で考えるべきだ.
図3 世界地質図(拡大は画像をクリック)
6)関連する組織との対応
・Outreach問題(Wolfgang Eder氏):さまざまな活動が行われている.Geoheritage, Geoparks, Geotourismという運動がSpringerの支援で行われている.そのほか,Geoschools, Disaster Riskなどの運動が活動的だ.Ground Water, Soil Resource などグローバルな理解が必要なことが多い.
・Geoethics問題:世界的に地質関連の倫理問題が多く起きている.公害問題にとどまらず,人類が危機に立たされている.IUGSがやらなければどこがやるのか?多くの人々の力と協力をお願いしたい.
・IAGETH (Jesus Martinez-Frias氏):社会地質学的な倫理問題が多く起きている.国際学会が組織されている.
・GS Europe:ヨーロッパ各国の地質調査所連合を作っている.データの共有のための標準化が求められている.
・European Federation of Geologists:ヨーロッパの地質学連合.
・Commission for the Geological Map of the World (CCGM)(Philippe Rossi氏):OneGeologyの一環.アジアの地質図も出版された.日本からは,産総研の佃榮吉氏が参加.www.cgmw.net, ccgm.orgから注文可能.(図3)
・Young Earth Scientist Group (Wen Mang氏):世界の若手研究者の連合.活発に活動している.日本からは静岡大学のサツカワ・タカオ氏が参加.www.networkyes.org.
(以下は,UNESCOのプログラムのIUGS関連のものによる報告)
・Geological World Heritage (Wesley Hill氏):UNESCOでしかできない最重要地質的世界遺産.GeoParksよりも大規模,重要なものに対して論じている.なお,最も力を入れているのは,現生で行われつつある重要な地質作用の保存や,失われたら取り戻せない重要な景観の保存である.その一例が,アンコールワットであるという.日本では,歴史,文化,危機,自然遺産などがよく知られているようだが,この地質遺産としても,今後検討を加えるような方向になるかもしれない.ただし,非常に重要な遺産だけを取り上げるべきだろうとのことであった.
・Task Group on Isotopic Geology (Igor Villa氏):これはStratigraphic Commissionの一部として活動している.重大な問題は,地域(ロシアとそれ以外)によって,壊変定数が異なることである.また物理と化学分野で言語が異なることもある.しかし,時代決定は,コンコーディア年代の決定と第四紀の気候変動にきわめて重要である.
・OneGeology (Marco Komac氏):各国ごとに基準が異なる場合が多く,データの共有化は簡単ではないなどの問題を抱えている.
・International Lithosphere Programme (ILP) (Magdalena Scheck-Wenderoth氏):さまざまな取り組みが行われ,広範囲な活動をしている.その多くが,地質学にもかかわるので,今後とも,IUGSとの協力関係を続けたい.日本からの代表は,神戸大学の巽好幸氏.なお,示された表には,日本は分担金を未払いのように示されていた.確認が必要.
・Global Geoscience Initiative (GGI) (Edmund Nickless氏):英仏で盛んになってきた運動で,OneGeologyや,IRDR(災害リスク統合研究計画;http://www.irdrinternational.org/ 日本からは,土木研究所の水災害・リスクマネジメント国際センター竹内邦良氏が理事として参加している.),その他の地質災害・公害研究組織などと関連している.そのお題目は,社会に根差した全地球的地球科学を目指すというもので,地質学の知識を社会に役立てることを考えている.さまざまに分断されているコミュニティーを統合し,情報や知識,理解を共有することを行っている.有名人との対話や問答を通じて,学問と市民を結びつける展開.日本でも,学術フォーラムや地質学会開催時における市民フォーラムなどが開かれているが,市民との対話をより重視し,「今何をすべきか」を考え行動する努力をすべきと思われる.(なお,Edmund Nickless氏からは,日本が主導しようとしている災害リスク行動(たとえばG-EVERなどと協調して行きたい,とのことであった.).
・34th IGC報告(Ian Lambert氏)
・35thIGC計画(Daniel Barnardo氏):2016年8月,ケープタウンにおける準備は進んでいる.アフリカ全体が協力する学会と位置付けており,非常に多くの(80もの)巡検を計画している.
・36thIGC計画(Sampat Tandon氏):2020年2月,デリーにおける準備を開始した.
7)ユネスコの報告:
・ユネスコにおける地球科学の取り組み(Patrick McKeever氏):そもそもIUGSもその中の諸組織も,大きい目で見ると,UNESCOと協調して行かなければならない.同氏からは,昨今の状況と詳しい取組が報告され,それぞれに問題点が指摘された.日本に関連するものとしては,IGCP の活動と,それとIUGSの関連(IUGSは,IGCPを同列として考えているが,IGCPのロゴマークが,誤解を招きやすいとの指摘が,複数の理事から出された.今後の検討課題.),国連傘下のFutureEarth運動とICSU傘下のIRDR(自然災害リスク計画)などがある.最大の問題は,資金の低減化である.
・IGCP-ARC (Marco Komac氏):ARCというのは,Ad hoc evaluationのことで,公正に見たIGCPの各プロジェクトの評価であった.非常に厳しいものもあり,特に,同一のグループないし人物が,名称を変えながら,類似のプロジェクトを延々と続けていることが指摘されている.なお,IGCP側からも,予算が少ないうえに,膨大なレポートを要求されているなどのことが言われているようであり,今後,競合するプロジェクトも出てくると思われる.そのほか,以下のような活動の報告があった.
・Geological Application on Remote sensing (GARS) (Patrick McKeever氏),
・Group on Earth Observation (GEO) (Stuart Marsh氏,S. Chevrel氏):これはGEOSS (systems of system)というお題目でやっており,一段と進んだ地球観測を行いたいようである.従来のシステムの理解を超えて,サブシステムのシステムへの効果を立体的に理解しようとのことである.
・Earth Science Education on Africa (Patrick McKeever氏):UNESCOもIUGSも,アフリカへの教育の重要性をことあるごとに強調していた.
8)International Council for Science (ICSU)関連(いくつかは,上記のものと重複する)
・ICSUとIUGSとの関連.IUGSの各運動も,できればICSUからの資金援助を取付けたいが,簡単ではない.
・ICSU内部の各地球科学関連のユニオンの連合体の構想(Peter Bobrowski氏):前出.Planetary Earthの大題目のもとに,9つのユニオンが結集する.IUGS, IUGGなどのほかには,Soil Science, INQUA, IGU, IAOなどが含まれる.
・ユニオン集会:2013年4月にパリで行われる.
9)その他の議論.
・IUGS e-bulletinを,毎月発行するように努力する.
10)2013年度のIUGS予算案の審議と決定 IUGSの2013年度の事業への予算額の総額は,約524,000ドルであり,昨年度から2割減である.その中で,日本に重要なのは,10月に仙台で開かれる産総研・学術会議,IUGS共同主催(日本地質学会後援)のG-EVERシンポジウム(地震・津波・火山災害関連のリスク削減)に,IUGSとしても津波関連のワークショップを推奨する方向で,15,000ドルを上限として研究者の招へいに使用することが決定されたことである.
4.筆者の感想とまとめ
以上,筆者の興味を持つ事項をやや詳しく,それ以外は羅列的に記した.昨今の状況としては,人間活動の活発化にともなって地球規模のさまざまな問題が発生しており,学問は進歩しているにもかかわらず,それ以上に重要な課題が山積してきた.環境,資源,災害など,人口の増加,密集,産業の高度化などにも関連する問題が多い.国連のFuture Earth 運動を積極的に支援するために,地質科学分野の果たす役割は大きい.そのために,最重要なのは,IUGSによるGeoscience Initiativeの明確化と実行であろう.そのためのstrategic planを具体化しようとの概念や試みは上記のように始まっているが,相手とする分野や現象が多岐にわたるために,見通しの良い活動を行うのは全体に簡単ではない.特に各国の足並み,分野やグループごとの作業を標準化,共有化することに,多くの労力が必要である.アフリカを中心とする後進国への教育的支援は重要ではあり,多くの努力がなされているものの,遅々としている.また先進国では後進国を巻き込む倫理問題が発生している.特にGeo-vandalismと称される,地球科学的野蛮行為(環境破壊,資源の枯渇,公害の発生など.明確化はされなかったが,原発事故も含まれる)が顕著になってきた.
こうした人類の抱える諸問題の解決のためには,地質科学が重要であることは論を待たないが,政策決定者や政治家,立法府の人々に,その重要性や学問の役割などが浸透していないというゆゆしい問題がある.また新しい世代の新しい人的資源の開発,確保も,重要である.多くの人が活発な活動を展開してはいるが,資金が低減化する傾向にあり,予断を許さない.
IUGS-IGCは4年で一回の開催でよいか,という問題もある.ほかのユニオンは,3〜4年に一度と類似である場合が多いが,その間により小規模な国際集会を行うユニオンも多い.地域や焦点を変えて,またほかのユニオンとの共同でやったらよいとの意見には,賛同したい.今回,カナダのバンクーバーで中間期のIUGS集会をほかのユニオンとも共同で2018年に開きたい,とのプロポーザルがあった.なお,2014年に中国において,Future resources summitが開かれるほか,いくつかの地域で,火山災害,地震・津波災害などの集会が開かるが,このようなテーマを絞ったショートコースやワークショップを積極的に開く必要があろう.上に述べたように,日本でも2013年10月の仙台における自然災害ハザードとリスクシンポジウムが,産総研内部のG-EVERという運動として行われるが,それはIUGS,日本学術会議,地質学会なども共同主催,後援などとして加わる予定である.
今後はそのような活動を通じて,地域,企業などの各人の社会などの中で,サイエンティスト集団(アカデミア)と一般社会やディシジョンメーカーなどとの交流を深め,人類と地球の将来のために,学問を役立てるべきであることの重要性を再認識した.
すでに述べたように,個別の話題に関して,筆者が強く興味を持ったのは以下のような事項である.最近,Geo-vandalism(地球科学的野蛮行為)と一括される地質関連の倫理問題が世界的に多く起きている.公害問題にとどまらず,人間活動がもとでの非倫理的蛮行によって,環境,資源,知的財産つまり人類を取り巻く多くの事項が危機に立たされている.IUGSがやらなければどこがやるのか?多くの人々の力と協力をお願いしたい,という意見には全く同感であった.人々はそれぞれの属する組織に縛られた立場もあるであろうが,日本の原発事故などを受けて,多くの参加者が地球全体のエネルギー資源と環境問題との調和に,ひそかに強い関心を持っているということがうかがえた.
また,IUGSには広い意味での教育問題に関心があるということである.これは,特に後進国(アフリカ諸国を特に意識)や若い世代の育成に焦点を当てたものと受け取れた.昨今,過去の時代に活躍した世代の多くの人がリタイアしつつあるが,その世代にも果たすべき役割があるに違いない.若手のいいところを伸ばすべく援助をして,老人の知識と経験とエネルギーを若い人すなわち将来のために役立てるべきだろう,ということである.
経済活動の行き詰まりなどから,どこも資金難である.具体的な妙案はないようである.世の中には地球科学的なさまざまな委員会,行動,プロジェクトなどがあるが,その間での重複がきわめて多い.ほとんど類似のプロジェクトが複数あるといってもよい.それらをどのように整理するかについても議論はされたが,これも妙案はない.
最後に,4日間の会議中に,同じ建物でIGCPの会議があり,日本から,産総研の斎藤文紀氏が出席していた.また,同時に,津波工学の集会が開かれており,気象庁の角田健二氏が国際委員として参加していた(面会やメールなどで状況を知ることができた).以上のように,類似の分野での相互の情報交換は重要である.また,ジェンダーバランスについても考えさせられた.時に応じて,内外からしばしば指摘されることであるが,国際的には女性の等価,等量の参加が求められていて,ジェンダーバランスを取る,と言われている.今回,9名の理事役員のうち,女性は2名であり,報告を行った各グループの代表のかなりの人々が女性であった.日本でも女性の進出は徐々にではあるが認められるようではあるが,十分とは言えないようである.
以上,部分的にやや詳しく述べたが,それぞれにさまざまな問題を含んでいる.今後ともその解決に向けて十分に注視していきたい.皆様からのご意見をお願いしたい.
(2013.3.27)
※本原稿の縮小Verは,日本地質学会News, Vol.16 No.4(2013年4月号)に掲載
geo-Flash No.216 惑星地球フォトコンテスト作品展開催が決定
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.215 2013/4/16 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】第4回惑星地球フォトコンテスト 審査結果
【2】日本地質学第5回総会開催について
【3】第66回国際地質科学連合(IUGS)理事会出席報告
【4】行事委員会より:シンポジウムとセッションが決定しました
【5】本の紹介:「観光地の自然学—ジオパークでまなぶ」
【6】IGCP608 Asia-Pacific Cretaceous EcosystemsのWebsite開設
【7】2013年「地質の日」行事予定
【8】「ジオルジュ」ライター募集
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】第4回惑星地球フォトコンテスト 審査結果
──────────────────────────────────
第4回惑星地球フォトコンテストの審査が行われ、応募総数205点の中から最優秀賞「深い海底の流れ」(坂口有人さん、神奈川県)など12作品の入選が決定しました。授賞式は、5月18日(土)14:15より、東京王子の「北とぴあ」にて行われます。
入選作品はこちらから、、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0009.html
——入選作品展示会のお知らせ——
入選作品の展示会が以下のように開催されます。迫力のある作品を
ぜひ会場でご覧ください。
埼玉県立 自然の博物館: 5月25日(土)〜6月9日(日)
兵庫県立 人と自然の博物館: 7月6日(土)〜8月4日(日)
地質情報展(仙台大会): 9月14日(土)〜9月16日(月)
あいちサイエンスフェスティバル: 10月初旬〜11月
奥出雲多根自然博物館: 12月21日(土)〜2月3日(月)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】日本地質学第5回総会開催について
──────────────────────────────────
日時 2013年5月18日(土)12:30〜14:00
会場 北とぴあ 第2研修室(東京都北区王子1-11-1)
1. 定款第20条により本総会は役員ならびに代議員による総会となります.ただし定款により正会員は総会に陪席することができます.
2. 定款第28条第1項により,代議員には別途,総会開催通知ならびに総会規則にもとづく議決権行使書,委任状などをお送りいたします.ご都合で欠席される方は,議決権行使書または委任状を提出してください.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0111.html
*総会終了後,同会場にて第4回惑星地球フォトコンテストの表彰式を行います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】第66回国際地質科学連合(IUGS)理事会出席報告
──────────────────────────────────
小川勇二郎(IUGS理事)
2013年2月19〜22日(火〜金),パリのユネスコ・アネックスで開かれた標記の国際地球科学連合 (International Union of Geological Sciences,以下,IUGSと略記; http://www.iugs.org/) の理事会 (Executive Committee) に,初めて出席した.以下はその感想を交えた報告である.
私は,2012年8月オーストラリアのブリスベーンで開かれた第34回万国地質学会議(IGC)でのIUGSの総会で,新規の理事(任期4年)に選出された.会長ほかを含めて理事等計9名で理事会(Executive Committee)を構成する.ほぼ各大陸区分ごとにある程度バランスを取って選出される模様であるが,出資金にもある程度比例しているようである.
続きはこちらから.http://www.geosociety.jp/faq/content0449.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】行事委員会より:シンポジウムとセッションが決定しました
──────────────────────────────────
本年9月に開催される第120年学術大会(仙台大会)のシンポジウムとセッションが決定しましたので,速報としてお知らせします.詳細はニュース誌大会予告号(5月号)と大会ページに掲載します.
行事委員長(行事担当理事) 星 博幸
セッション名等はこちらから.http://www.geosociety.jp/science/content0055.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】本の紹介:「観光地の自然学—ジオパークでまなぶ」
──────────────────────────────────
小泉武栄 著 古今書院
A5判 198頁(カラー88頁)2,600円(税別)
著者の小泉武栄(たけえい)氏は東京学芸大教授で,自然地理学,地生態学がご専門である.登山愛好家の知人から山の自然学に関する本の著者である小泉氏のことを聞いたことがあり,筆者もお名前だけは知っていた.5年近く前から,日本ジオパーク委員会委員として,会議や現地視察でご一緒する機会も増えたこともあり,ジオパークに関連した著書として紹介・推薦する次第である.
本書の主旨は,「はじめに」を読んでいただければよくわかる.その中で「知的観光旅行をしよう!地形,地質,森や植物,滝,棚田,神社,土地利用・・・.面白そうなものをみつけ,なぜそれができたのかを考えよう.」という呼びかけに,本書の中身が集約されている.小泉氏は知的好奇心が旺盛な社会人の巡検サークル「山遊会」のメンバーと巡検を行い,地形・地質から水,植物,ときには昆虫などまで取り上げ,それぞれの繋がりを重視しながら,なぜそこにそれがある(いる)のかを説明されているという.その巡検案内をとりまとめたのが本書である.実は筆者が「日本の地質構造百選」(日本地質学会構造地質部会編)を2年前に企画していたとき,南紀州の天鳥の褶曲を取材するためにネットで検索していた所,「山遊会」の巡検紀行のホームページが露頭の場所を探すのに大変参考になった.
ジオパークはジオ(地形や地質)だけではなく,ジオとエコ(生態)さらには人がつくった文化や歴史などとのつながりをまるごと学び・楽しむ大地の公園である.ただ,私のような地質屋にとっては,植物や動物の知識に乏しいので,なかなかジオとエコの繋がりを説明する事はできない.小泉氏は,この部分がご専門で大変精通しており,その意味でも貴重なガイドブックとなっている.
本書で取り上げられた観光地は下の15地域(テーマ)に及び,多くの美しい写真や見やすい地形図も盛り込まれている.その地域は,1.伊豆半島,2.昇仙峡,3.南紀州,4.室戸岬,5.足摺岬,6.英彦山・耶馬渓・由布岳,7.秋吉台・平尾台・四国カルスト,8.北長門海岸,9.隠岐諸島,10.丹後半島,11.立山,12.佐渡島,13.きのこ岩・塔のへつり,14.磐梯山,15.岩手山・焼走り溶岩流 となっている.そのほか,8つのコラムにはその他のお薦めの地域が記されている.ジオパークという観点で見ると,上記の1, 4, 9, 10, 14の地域(の一部)がすでに日本ジオパークに認定されており,筆者が知る限り3, 7, 8, 12 の地域(の一部)が現在ジオパークを目指している.そのほかの地域も,小泉氏自身が優れたジオサイトをもつという点において将来ジオパークになる資格が充分あるとされている地域である.筆者も様々な地域を旅した経験があるが,たとえば英彦山東方のビュートとか,郡山市のきのこ岩,萩市北方の溶岩平頂丘の萩六島など,日本にもこんな珍しい地形があるのか,と驚かされるものもあり,そのでき方も説明されているので大いに楽しめると同時に,日本列島のジオの多様性を改めて認識させられる.
本書で挙げられた15の地域について,読者はどういう順番で読んでもよく,もしこれらの地域に出かける時は,その章をコピーして持参すると良いだろう.15の地域についてひとつひとつ紹介しても良いが,それは読者の楽しみに残しておくとして,本書のひとつの特徴である「ジオとエコのつながり」についての記述例を11.立山 にみてみよう.筆者も2009年秋に登山に行った場所であるが,その時はジュラ紀の花崗岩の分布や大崩落で有名な立山カルデラに興味を持った程度であった.小泉氏の記述によると,弥陀が原の下部はタテヤマスギの原生林となっているが,この程度の標高であれば白山にみられるように全域がブナ林になっているのが普通なので,ブナが少なく,タテヤマスギが優先しているのは異常だと言う.その種明かしは次のように書かれている.すなわち,タテヤマスギ林の内部には,地形的,地質的条件の悪い所に生える樹木が見られ,スギも同様の悪条件の立地に生育する.弥陀が原の溶結凝灰岩の大地は,形成後10万年近く経過しているにもかかわらず樹木の生育にとって好条件ではなく,厚い土壌を好むブナが少ない.さらにその上部では,通常であればシラビソやオオシラビソなどの亞高山帯の針葉樹林が表れるが,それがみられず,さらに上部の花崗岩分布域でオオシラビソの森となっているという.筆者は八方尾根から唐松岳に登った時に蛇紋岩帯とその上位の砂岩・泥岩分布域で明瞭な植生の違い(森林の逆転現象)を認識することができたが,溶結凝灰岩と花崗岩の違いも表層地質の違いをもたらし,植生の違いをもたらすことがわかり,次回立山に行けば,もっと楽しめるに違いないと思う.立山以外でも,いくつか取り上げられている火山地域では,噴火の時期とその後の植生の変化についても解説されており,興味はつきない.
本書では文中の草花や樹木のいくつかは写真が付けられているが,できれば巻末にでも植物の名称について写真付きで紹介いただけるとありがたい.また様々な岩石名や地形などの専門用語も出てくるので,その説明もどこかに触れられると専門でない読者には助かるであろう.ただ,紙面の都合もあるので,将来たとえば地域別に分冊で小泉流知的ジオ(+エコ)ツーリズムを特集いただき,山にも携帯できる薄めのガイドブックが出版されるとありがたいと思うが,いかがだろうか.
冒頭にも述べたが,本書にちりばめられた謎解きの旅は,多くの自然愛好家の知的好奇心を満足することであろう.ジオパーク関係者はもとより,自然が好きなすべての読者に一読を薦める.
(高木秀雄)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】IGCP608 Asia-Pacific Cretaceous EcosystemsのWebsite開設
──────────────────────────────────
2013年3月に採択され活動を開始した,地質科学国際研究計画(International Geoscience Programme:IGCP)608 Cretaceous ecosystems and their responses to paleoenvironmental changes in Asia and the Western Pacific (白亜紀のアジア−西太平洋地域の生態系システムと環境変動)(略称:Asia-PacificCretaceous Ecosystems 白亜紀アジア−西太平洋生態系) のWebsiteが開設されましたので,ぜひご覧ください.今後,活動の各種情報を随時提供していきます.ご参加・ご協力・ご支援をよろしくお願いします.
URL: http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/
(IGCP608 プロジェクトリーダー 安藤寿男)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】2013年「地質の日」行事予定
──────────────────────────────────
2008年より5月10日が『地質の日』に制定され,これを記念した多くのイベントが,全国各地の博物館・大学で開催されています。
今年も学会関連の行事が多数予定されています.
◆地質学会・応用地質学会主催:街中ジオ散歩 in Tokyo「石神井川がつくる地形の移り変わりと地質(仮)」(5/12開催)
◆近畿支部:地球科学講演会「大阪平野の地盤環境と地盤災害」(5/12開催)(申込締切4/30)←HP情報更新しました。
◆北海道支部:「地質の日」記念展示「豊平川と共に—その恵みと災い—」(4/23〜6/2)
◆西日本支部:身近に知る『くまもとの大地』(5/11開催)
◆三浦半島活断層調査会:地質の日記念観察会:「深海から生まれた城ヶ島」(日本地質学会後援)(5/11開催)
それぞれのイベントの詳細は,学会HPの「地質の日」よりご覧頂けます.
http://www.geosociety.jp/name/content0014.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】「ジオルジュ」ライター募集
──────────────────────────────────
地質学会広報誌「ジオルジュ」は創刊1周年です.来月には2013前期号が皆様のお手元に届きます.
一般の読者に向けて地球科学に関する広い話題をわかりやすく紹介するため、ジオルジュはサイエンスライターの皆さんの手により作られています。ジオルジュを多くの人に親しまれる雑誌にするため協力していただける方、その他の学会刊行物にサイエンスを紹介する記事を書きたいという方は、下記事務局までお問い合わせ下さい。応募多数の場合は審査させて頂きます.
eメール main@geosociety.jp 電話03-5823-1150
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】支部情報
──────────────────────────────────
■北海道支部
支部例会(個人講演会)
日時:4月27日(土)10:00〜18:00(予定)
場所:北海道大学理学部5号館2階 5-201室
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
■関東支部
第3回関東支部ミニ巡検=房総・三浦研究サミット関連巡検第1弾
『房総半島南東部夷隅地方における正断層群』
5月25日(土)〜26日(日)
集合場所:JR蘇我駅(自家用車参加不可)
募集人数:10名(先着順)地質学会会員優先
参加申込締切:4/25
詳しくは,http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■電中研ニュースNo.474 発行
「雷から電力流通設備を守るためのガイドを作成」
http://criepi.denken.or.jp/research/news/
■地震本部ニュース2月号(2013.4.5配信)
九州地域の活断層の長期評価(第一版)ほか
http://www.jishin.go.jp/main/p_koho04.htm
■地震本部ニュース3月号(2013.4.15配信)
地震調査委員会[第247回]ほか
http://www.jishin.go.jp/main/p_koho04.htm
■海底地形名称の提案募集のお知らせ
海上保安庁では、海底調査で明らかになった海底地形に名称を付与し海図や海底地形図などに記載するとともに、学術分野等での利用の便宜を図っており、下記のとおり、新たな海底地形名称の提案を受け付けています。
詳しくはこちらから.
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//others-pdf/20130416-gf.pdf
■平成24年度笹川科学研究奨励賞受賞研究発表会
4月26日(金)
研究発表会 9:30〜 ※出入り自由
研究奨励の会 11:45〜12:20 研究者交流会 12:30〜14:30
http://www.jss.or.jp/ikusei/sasakawa/kenkyuu/kenkyuu.html
■第150回深田研談話会
5月10日(金)15:30〜17:30
会場:深田地質研究所研修ホール(文京区本駒込2-13-12)
定員:80名(先着順) 参加費:無料
申込締切:5/8
http://www.fgi.or.jp/
■三浦半島活断層調査会・地質情報普及講座 地質の日・記念観察会
『深海から生まれた城ヶ島 』
日本地質学会 後援
5月11日(土)10:00〜15:00(小雨決行)
集合場所:城ヶ島バス停
申込締切:5/3 募集人数:50名
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//others-pic/2013jogashima-miura.gif
■2013 Western Pacific Sedimentology Meeting
台湾地質学会,日本堆積学会 主催
日本地質学会,IAS,SEPMほか 共催
5月13日(月)〜18日(土)
13〜14日:研究発表 15〜18日:巡検
場所:The Longtan Aspire Resort, Taoyuan, northern Taiwan
http://wpsm.ncu.edu.tw/
■日本地球惑星科学連合2013年大会
5月19日(日)〜24日(金)
場所:幕張メッセ国際会議場(千葉市美浜区)
事前(割引)参加登録申込締切:5月7日(火) 17:00 JST
5/19:パブリックセッション(一般対象:参加費無料)
5/20-24 13:00-13:40(昼休み):スペシャルレクチャー(大学生・若手研究者対象)
http://www.jpgu.org/meeting/index.htm
■地球惑星科学NYS若手合宿2013
5月24日(金)〜26日(日)
場所:東京大学検見川セミナーハウス
定員:50名(学部生以上)
参加申込締切:4/26(定員を超えた場合、締切前に申し込み終了する場合あり)
https://sites.google.com/site/nyswakate2013/home
■第50回 アイソトープ・放射線研究発表会発表論文の募集
日本地質学会ほか 共催
7月3日(水)〜5日(金)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1)
http://www.jrias.or.jp
■第57回粘土科学討論会
日本地質学会 共催
9月4日(水)〜6日(金)
会場:高知市文化プラザかるぽーと
参加・講演の申込期間 :6月3日(月)〜 14日(金)
講演要旨送付締切 :7月12日(金)
http://www.cssj2.org/
■第30 回歴史地震研究会
9月14日(水)〜16日(月・祝)
会場:秋田大学
講演発表申込締切 :5月31日(金)
講演要旨送付締切 :7月31日(水)
懇親会・巡検・昼食申込締切 :7月31日(水)
http://sakuya.ed.shizuoka.ac.jp/rzisin/menu7.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/outline/content0098.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■北海道教育大学:釧路校地学分野教員(教授または准教授)(5/31)
■2014年〜2015年開催藤原セミナーの募集(学会締切:6/28)
■2013年度「信州フィールド科学賞」(6/28)
■East Asia Geoscience and Environmental Research (EAGER)賞の募集(6/1)
■山田科学振興財団 国際学術集会開催助成の公募(2014/2/28)
■公益財団法人住友財団 2013年度基礎科学研究助成、環境研究助成の公募(6/28 メール締切:6/20)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
会議参加報告など-目次
会議参加報告など
第35回万国地質学会議(IGC)ほかのご案内
小川 勇二郎 (国際地質科学連合理事)
かねてからご案内の通り、第35回万国地質学会議(IGC; http://www.iugs.org)は、2016年8月27日〜9月4日に南アフリカ共和国のケープタウンの国際コンベンションセンターで開催されるが(http://www.35igc.org/)、その準備状況が、本年1月の国際地質科学連合(IUGS)理事会で説明された。
>>>>> 続きを読む
国際地質科学連合(IUGS) 第67回理事会報告および第35回、36回万国地質学会議(IGC)案内
小川 勇二郎 (国際地質科学連合理事)
昨年のニュース誌で国際地質科学連合(International Union of Geological Sciences;以下IUGS)第66回理事会の報告をしたが、それと重複することもあるが、以下に第67回理事会(2014年2月7日から2月10日まで、インド、ゴア州のボグマロ・リゾートホテル)が開かれたので、以下に簡単に報告する。
>>>>> 続きを読む
第2回G-EVER国際シンポジウム・第1回IUGS・日本学術会議国際ワークショップ 参加報告
日本地質学会会長 石渡 明
この国際シンポジウムは2012年2月22-24日につくば市で開催された第1回G-EVERワークショップ及び2013年3月11日に同市で開催されたG-EVER国際シンポジウムに次ぐもので、今回は2011年の東日本大震災の被災地の中心にある仙台市で2013年10月19-20日に開催された。
>>>>> 続きを読む
韓国2013秋季地質科学連合学術大会(大韓地質学会第68次定期総会)公式訪問の報告
日本地質学会会長 石渡 明
標記の大会は2013年10月23日〜27日、韓国済州島のフェニックス・アイランドで開催された。昨年の日本地質学会大阪大会で延長締結された大韓地質学会との学術交流協定に基づき、日本地質学会会長 石渡 明(筆者)と副会長Simon Wallisが公式に招待された。ここでは、標記学会に参加しての見聞を簡単に報告する。
>>>>> 続きを読む
欧州地球科学連合(EGU)2013年総会(ウィーン,2013年4月7-12日)参加見聞記
石渡 明・荒井章司・川幡穂高・宮下純夫・安間 了・山路 敦・石塚 治
会場は例年通りウィーン東部を流れるドナウ川の中洲にあるオーストリア国際会議場である(図1).ウィーン中心街から地下鉄(会議場付近では高架)で約10分の駅より歩いて数分という非常に便利な場所にある.上から見ると三角形の角を取った形のメインの4階建ての会場は主に口頭発表と企業展示などに使われ,隣接する広大な地下(実は地上1階)の展示スペースは主にポスター発表やPICO(後述)の会場として使われている.隣には国際原子力エネルギー機構(IAEA)本部などが入る国連の建物がある.
>>>>> 続きを読む
第66回国際地質科学連合(IUGS)理事会出席報告
小川勇二郎(IUGS理事)
2013年2月19〜22日(火〜金),パリのユネスコ・アネックスで開かれた標記の国際地球科学連合 (International Union of Geological Sciences,以下,IUGSと略記; http://www.iugs.org/) の理事会 (Executive Committee) に,初めて出席した.以下はその感想を交えた報告である.
>>>>> 続きを読む
欧州地球科学連合(EGU)2013年総会 参加見聞記
欧州地球科学連合(EGU)2013年総会(ウィーン,2013年4月7-12日)参加見聞記
石渡 明・荒井章司・川幡穂高・宮下純夫・安間 了・山路 敦・石塚 治
Conference Report: European Geosciences Union General Assembly 2013, Vienna, 07-12 April 2013
A. Ishiwatari, S. Arai, H. Kawahata, S. Miyashita, R. Anma, A. Yamaji and O. Ishizuka
図1.ウィーン郊外のEGU会場(Austria Center,右側の4階建て)
会場は例年通りウィーン東部を流れるドナウ川の中洲にあるオーストリア国際会議場である(図1).ウィーン中心街から地下鉄(会議場付近では高架)で約10分の駅より歩いて数分という非常に便利な場所にある.上から見ると三角形の角を取った形のメインの4階建ての会場は主に口頭発表と企業展示などに使われ,隣接する広大な地下(実は地上1階)の展示スペースは主にポスター発表やPICO(後述)の会場として使われている.隣には国際原子力エネルギー機構(IAEA)本部などが入る国連の建物がある.
今回の大会は,毎朝会場で配布されるニューズレター“EGU Today”によると,500以上のセッションが開催され,提出された要旨の数は13,000件以上に達する.これは米国地球物理連合(AGU)秋季大会(毎年12月にサンフランシスコで開催)の参加者24,000以上,口頭発表15,000以上,ポスター発表7,000以上(いずれも2012年大会,同連合HPによる)に比べると半分程度だが,日本地球惑星科学連合の参加者約7,300人,発表約3,900件(2012年大会,HPによる)に比べると発表数で3倍以上になる.
受付で配布される小冊子にはセッションのリストと会場などの案内が載っているだけだが,名札と一緒に2GBのUSBメモリーを渡され,これに詳しいプログラムと要旨が入っている.それを開くと,個人用のプログラムを作成できたり,キーワードや著者名などで検索できたり,大変便利なシステムになっていて,これをパソコンやタブレットに入れて閲覧している人も多かった.会場に何十台と並んだパソコンでも,同じものが閲覧できた.また,各々の口頭発表会場の入り口にはその日の講演者・講演題目・講演時間を書いた紙が掲示される.この大会の運営はEGUと一体のコペルニクスという会社がやっていて,その会社の名前やロゴはあまり表面に出ないが,ほとんどトラブルなく上手に運営されている印象だった.EGUのジャーナルもコペルニクスが運営していて,近年評判が高いものが多い.なお,名札には個人を識別するバーコードが印刷されていて,会場のパソコンでそれを読むと,自分の講演番号・日時・部屋番号が表示される仕組みになっていた.またその裏の券を示せば,会期中,市内のバス・地下鉄などが無料で利用できるサービスがあり,ありがたかった.会場ではかなり高速の無線LANでインターネットに接続できた.
口頭発表は通常15分で,招待講演や受賞記念講演の場合は30分や1時間の場合もある.最近の流行なのか,招待講演はinvitedではなくsolicitedと表記されている.もしかしたら,invited(招待)だと「旅費を出せ」と要求する人がいるので,solicited(要請)にしたのかもしれない.例えばY. Dilekと安間が座長を務めるオフィオライトのセッションでは12件の口頭発表のうち筆者らの数人を含む5件がsolicitedだった.時間になってもベルを鳴らさず,座長が手ぶりや起立などで講演者に知らせる.講演のあとは必ず拍手する.母国語が英語でない人が多いので,比較的ゆっくり話し,わかってもらおうとする努力が感じられる場合が多かった.
ポスター発表は横長のパネルで,日本の縦長パネルをギッシリ並べる展示に比べるとはるかに余裕がある.しかも,パネルを直線的に並べず,雁行状に配置して,隣のパネルとの間にパソコンを置ける程度の小さな台と電源コンセントを用意しているのは親切だと感じた.ただし,照明は十分でなく,かなり暗い部分があった.ポスターにもsolicitedと表記したものがあったが,口頭発表と同じ内容をポスター発表している人もいた.ポスター発表の時間は毎日午後7時までだが,6時になるとビールや赤・白のワインが無料で大量に供給され,この時間を境に会場の音量と匂いが大きく変化する.この飲料供給は参加者をポスター会場に呼び込むのに大きな効果を発揮していた.企業等の展示ブースは72件が出展された.日本地球惑星科学連合のブースは,昨年は職員が出張し,ティッシュなどを配って盛況だったが,今年は連合大会の準備で多忙な期間と重なり職員が出向けなかったので,あまり目立たなかった.アジア・オセアニア地球科学会議(AOGS)のブースでは派手な折りたたみ傘を配っていた.また,中国地質大学の大きなブースが目立った.
図2.今回から新たに設けられたPICOセッションの会場.後方に液晶モニターが並ぶ.
PICO(Presenting Interactive Contents)というセッションが今年から新たに設けられた(図2).これはポスターと口頭発表の中間的なもので,椅子を100個並べ,液晶プロジェクター1台とスクリーン1幅の他に14台の30インチ程度のタッチパネル式液晶モニターを並べた独立の区画がポスター会場の隅などに5つ設けられた.それぞれの発表者は聴衆への3分間の口頭発表の他に,個々のお客さんにモニターを使ってポスター発表のような説明をすることができる.お客さんは,発表者がいなくても,いずれかのモニターで自分が見たい発表を見ることができる(ただし声は出ない).荒井はこのセッションで発表したが,発表者が立つべきモニターの番号が指定されておらず,発表者と直接議論したい場合にその場所がわからないので,この点は改善の余地があると感じた.また,液晶モニターを揃えるのにかなりの初期投資が必要だと思う.一方,昔の学会では参加者がメッセージを貼り出すことができる掲示板が会場入口に用意されていたが,今回はなかった.人が集まる利点を生かす上で,こういう旧式の情報伝達手段も案外有用だと思う.
シェールガスに関する討論が,シェークスピアをモジった“To frack or not to frack”という題で3日目に行われ,多数の立ち見を含めて1000人ほどの聴衆を集めた.Frackingというのはhydraulic fracturingを略した業界用語で,辞書には出ていない(fraccingとも).シェールガスを取り出すためにその地層に薬剤を混ぜた水を高圧で送り込むことで,これによる環境汚染や岩盤の破壊による地震発生などが懸念されている.4人のパネラーが推進,反対の立場からプレゼンテーションを行い,パネラー相互の議論,そして聴衆からの質問という順序で進んだ.欧州にはシェールガスの資源は豊富に存在するが,開発は進んでいない.あるパネラーが「シェールガスを必要だと思う人は手を挙げて」と会場に呼びかけたら,手を挙げたのは2割くらいだった.全体として,frackingに伴う環境負荷やリスクが強調され,あるフランス人参加者は「原子力も重要な選択肢ではないか」と質問して失笑を買った.米国人参加者は自国の開発方針を擁護する発言をしたが,シェールガス開発を推進すべきだとする意見は少数にとどまった.一方,「チェルノブイリから福島へ:地球科学者の知識の発達」というセッションもあり、これも立ち見が出るほど盛況だった。IAEAが会場の隣にあるためか、核爆発モニタリングに関するセッションもあって、原子力に関する欧州のコミュニティーの関心の高さが伺われた。ただし,米国の火星探査機キュリオシティーの成果についてのセッションも大々的に行われたものの,空席が目立った.一般に,参加者は「欧州」を強く意識していて,米国とは一線を画している印象だった.
IODP・ICDP(海洋・大陸掘削)関連のセッションも多く,欧州の推進機関であるECORDのタウンホール集会では「ちきゅう」の下北半島沖掘削の記録映画が上映され,いくつかの一般向け講演が行われて酒食が供された.日本ではICDPについてあまり知られていないが,最終日のIODP・ICDP合同セッションでは,ナポリ西郊のCampi Fregreiのカルデラ縁掘削,トルコのアナトリア断層掘削,ボヘミアのリフト帯掘削など,興味深い話を聞くことができた.日本の「ちきゅう」による南海トラフの震源断層掘削についても紹介があった.岩石分野に関しては,層状貫入岩体のセッションなどは日本では聞けないものであり,大陸ならではと感じた.火山関係のセッションも充実していた.さすがに最終日(金曜)の午後のポスター会場は閑散としていたが,その中で氷河・陸水のセッションだけは終了時間の午後7時まで賑やかだったのが印象的だった.
荒井は2006年からほぼ毎年EGUに参加しており,年々規模が大きくなることを実感してきが,コミュニティー意識が強過ぎて,マンネリ感が充満するセッションもあるように感じる.石渡はフランス留学中の1982年頃にストラスブールで開催された欧州地球科学連合の前身の大会に参加したことがあるが,今回は約30年ぶりの参加となり,隔世の感を強くした.当時はまだフランス語などで発表する参加者もかなりいたが,今回は英語以外の講演は1つもなかった.当時は全てスライドやOHPでの発表だったが,今回は電子ファイル以外の発表は1つもなかった.今回の大会は,春の嵐で成田空港からの出発が大幅に遅れるなどのアクシデントはあったが,現地では比較的暖かい晴天に恵まれ,筆者一同,毎日おいしいパンとハム,ソーセージ,シュニッツェルなどを満喫して,1週間楽しく有意義に過ごすことができた.
(2013.4.16)
geo-Flash No.217 5月10日は「地質の日」:全国でイベント開催
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.217 2013/5/7 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】日本地質学第5回総会開催について
【2】学士課程教育における地球惑星科学分野の参照基準
【3】欧州地球科学連合(EGU)2013年総会 参加見聞記
【4】2013年「地質の日」行事予定
【5】「ジオルジュ」ライター募集
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】日本地質学第5回総会開催について
──────────────────────────────────
日時 2013年5月18日(土)12:30〜14:00
会場 北とぴあ 第2研修室(東京都北区王子1-11-1)
1. 定款第20条により本総会は役員ならびに代議員による総会となります.
ただし定款により正会員は総会に陪席することができます.
2. 定款第28条第1項により,代議員には別途,総会開催通知ならびに総会規則にもとづく議決権行使書,委任状などをお送りいたします.ご都合で欠席される方は,議決権行使書または委任状を提出してください.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0111.html
*総会終了後,同会場にて第4回惑星地球フォトコンテストの表彰式を行います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】学士課程教育における地球惑星科学分野の参照基準
──────────────────────────────────
学術会議において大学教育の参照基準作りが進められています。この度、地球惑星科学分野における原案が,大学教育分科会を中心とした活動によりほぼ完成いたしました.参照基準は,大学教育のガイドラインともいえるもので,各大学における教育の重要な基準ともなるべきものです.
原案は遠からず公開され,パブコメが求めれらますが,そのとりまとめにあたり広い議論を経るため、以下の要領でシンポジウムが計画されました.
日時:6月16日(日)13:00-16:00
場所:東京大学地震研究所2号館第1会議室
シンポジウムでは,21期より学術会議における全体とりまとめをおこなってきておられる北原和夫先生の講演,西山大学教育問題分科会委員長の報告,パネルディスカッションが予定されています.
大学教育の重要な問題ですので,多くの方にご参加いただけるようお願い致します.
地球惑星大学教育問題分科会委員・地質学会理事 小嶋 智
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】欧州地球科学連合(EGU)2013年総会 参加見聞記
──────────────────────────────────
(石渡 明・荒井章司・川幡穂高・宮下純夫・安間 了・山路 敦・石塚 治)
会場は例年通りウィーン東部を流れるドナウ川の中洲にあるオーストリア国際会議場である.ウィーン中心街から地下鉄(会議場付近では高架)で約10分の駅より歩いて数分という非常に便利な場所にある.上から見ると三角形の角を取った形のメインの4階建ての会場は主に口頭発表と企業展示などに使われ,隣接する広大な地下(実は地上1階)の展示スペースは主にポスター発表やPICO(後述)の会場として使われている.隣には国際原子力エネルギー機構(IAEA)本部などが入る国連の建物がある.
続きはこちらから.
http://www.geosociety.jp/faq/content0452.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2013年「地質の日」行事予定
──────────────────────────────────
2008年より5月10日が『地質の日』に制定され,これを記念した多くのイベントが,全国各地の博物館・大学で開催されています。
今年も学会関連の行事が多数予定されています.
◆地質学会・応用地質学会主催:街中ジオ散歩 in Tokyo「石神井川がつくる地形の移り変わりと地質(仮)」(5/12開催)
◆近畿支部:地球科学講演会「大阪平野の地盤環境と地盤災害」(5/12開催:申込終了)
◆北海道支部:「地質の日」記念展示「豊平川と共に—その恵みと災い—」(4/23〜6/2)
◆西日本支部:身近に知る『くまもとの大地』(5/11開催)
◆三浦半島活断層調査会:地質の日記念観察会:「深海から生まれた城ヶ島」
(日本地質学会後援)(5/11開催)
◆埼玉県立自然の博物館:第4回惑星地球フォトコンテスト入選作品展示
(日本地質学会共催)(5/25〜6/9展示)
それぞれのイベントの詳細は,学会HPの「地質の日」よりご覧頂けます.
http://www.geosociety.jp/name/content0014.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】「ジオルジュ」ライター募集
──────────────────────────────────
地質学会広報誌「ジオルジュ」は創刊1周年です.今月末には2013前期号が皆様のお手元に届きます.
一般の読者に向けて地球科学に関する広い話題をわかりやすく紹介するため、ジオルジュはサイエンスライターの皆さんの手により作られています。ジオルジュを多くの人に親しまれる雑誌にするため協力していただける方、その他の学会刊行物にサイエンスを紹介する記事を書いて頂ける方は、下記事務局までお問い合わせ下さい。応募多数の場合は審査させて頂きます.
eメール: main@geosociety.jp 電話03-5823-1150
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
■中部支部
中部支部総会(石川県大会)のご案内
日時:2013年6月29日(土)〜30日(日)
会場:白山市交流センター
29日(土曜日)インドアミーティング
石川県関係として、白山火山に関する研究と防災に関する話題を金沢大学の平松良浩先生と酒寄淳史先生に提供していただく予定.
30日(日曜日)白山手取川ジオパークに関連した野外巡検を企画.
その他の講演内容、参加者,参加費に関する情報は、随時下記で公開.
http://earth.s.kanazawa-u.ac.jp/tomo/GSJ-Ishikawa13/GSJ-Ishikawa13.html
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
■西日本支部
日本地質学会西日本支部 第164回例会およびシンポジウム「長岡信治:海から山,火山でのフィールドワーク」
日時:2013年6月8日(土)〜9日(日)
会場:雲仙岳災害記念館(がまだすドーム)セミナー室
〒855-0879 長崎県島原市平成町1-1
主催:日本地質学会西日本支部,福岡大学国際火山噴火史情報研究所
共催:長崎県地学会
・宿泊および懇親会申し込みの〆切:5月17日(金)17時
・講演申し込みの〆切:5月30日(木)12時
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地震本部ニュース4月号(2013.4.30配信)
地震調査委員会[第248回]ほか
http://www.jishin.go.jp/main/p_koho04.htm
■2013 Western Pacific Sedimentology Meeting
台湾地質学会,日本堆積学会 主催
日本地質学会,IAS,SEPMほか 共催
5月13日(月)〜18日(土)
13〜14日:研究発表 15〜18日:巡検
場所:The Longtan Aspire Resort, Taoyuan, northern Taiwan
http://wpsm.ncu.edu.tw/
■日本地球惑星科学連合2013年大会
5月19日(日)〜24日(金)
場所:幕張メッセ国際会議場(千葉市美浜区)
5/19:パブリックセッション(一般対象:参加費無料)
5/20〜24 13:00〜13:40(昼休み):スペシャルレクチャー(大学生・若手研究者対象)
http://www.jpgu.org/meeting/index.htm
■第2回TONセミナー「水産と工学の連携」
5月23日(木)
場所:海洋研究開発機構東京事務所会議室(千代田区内幸町2-2-2富国生命ビル23F)
E-mailまたはFAXにて申込,先着60名
テクノオーシャン・ネットワーク(TON)事務局
techno-ocean@kcva.or.jp FAX: 078-302-1870
■東京大学大気海洋研究所共同利用研究集会
5月27日(月)〜28日(火)
場所:東京大学大気海洋研究所2F 講堂(千葉県柏市柏の葉5-1-5)
プログラム(日本語)
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//others-pdf/20130430jpn.pdf
Program (English)
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//others-pdf/20130430eng.pdf
■第50回 アイソトープ・放射線研究発表会発表論文の募集
日本地質学会ほか 共催
7月3日(水)〜5日(金)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1)
http://www.jrias.or.jp
■第57回粘土科学討論会
日本地質学会 共催
9月4日(水)〜6日(金)
会場:高知市文化プラザかるぽーと
参加・講演の申込期間 :6月3日(月)〜 14日(金)
講演要旨送付締切 :7月12日(金)
http://www.cssj2.org/
■2013年度日本地球化学会年会
日本地質学会 共催
9月11日(水)〜13日(金)
会場:筑波大学第一エリア1D1E棟
固有セッション申込:6月13日(木)〜 7月17日(水)
共通セッション申込:6月7日(金)〜 23日(日)
事前参加登録締切:8月23日(金)(予定)
http://www.geochem.jp/
■第67回日本人類学会大会・総会
11月1日(金)〜4日(月)
場所:国立科学博物館筑波研究施設ほか
企画募集締切:5/31 演題募集・参加登録締切:8/9
http://www.gakkai.ne.jp/anthropology/67_annual_meeting
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/outline/content0098.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■第17回尾瀬賞の募集(8/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flash No.218 私も欲しい!「ちきゅう」プラモ
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.218 2013/5/21 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】「原子炉施設の敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド(案)」に対する日本地質学会のコメント
【2】紹介:地球深部探査船「ちきゅう」プラモデル
【3】第4回惑星地球フォトコンテスト:入選作品展示会のお知らせ
【4】仙台大会関連情報
【5】地質図幅をネットで読める「地質図Navi」が正式公開
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「原子炉施設の敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド(案)」に対する日本地質学会のコメント
──────────────────────────────────
現在,原子力規制委員会の中では「発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる規制基準」の策定が行われております.その中で,添付の「敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド(案)」が策定され,これに対する意見募集が行われました.これに対して,日本地質学会から以下のとおり意見を提出しましたので紹介します.
日本地質学会より提出した意見書,意見募集の本文など,詳しくは
http://www.geosociety.jp/engineer/content0024.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】紹介:地球深部探査船「ちきゅう」プラモデル
──────────────────────────────────
図1. 「ちきゅう」プラモデルの完成品(今回組み立てたもの).
株式会社バンダイ 外箱387x309x81 mm, 完成品 300x186x55 mm(台座を含めると高さ250 mm)参考価格5,985円
「ちきゅう」のプラモデルが発売された。日本が建造・所有し、統合国際深海掘削計画(IODP)の枠組みの中で運用している世界最大の科学目的の海底掘削船(ただし運用時間の半分程度は経済活動に従事)の精巧な模型である。2007年の運用開始以来、主に南海トラフの付加体・震源断層掘削を行ってきたが、2012年のJFAST(IODP Exp. 343)航海においては、従来の米国の掘削船ジョイデス・レゾリューション(水深5000 m程度での掘削が限界)では不可能だった東北沖の海溝軸近くの水深7000 mの海底を800 m以上掘削することに成功し、2011年東北地方太平洋沖地震の震源断層と思われる破砕帯を貫くコア試料回収に成功したことは記憶に新しい。その他、沖縄トラフの熱水噴出帯や八戸沖の海底深部の炭層など地下深部生命圏の解明を主目的とする掘削も行い、今年に入ってからも伊勢湾沖で海底下のメタンハイドレート濃集層から天然ガス回収に成功したことが大きく報道された。この掘削船の特徴は通常の掘削の他にライザー(riser)掘削機能を持つことで、船から海底まで通常のドリルパイプよりも太いパイプを降ろしてその中に「泥水」(潤滑剤などを含む特殊な液体)を循環させ、岩石の切り屑を絶えず洗い流し、掘削孔内部の圧力を保持しながら効率的に掘削を進めることができる。この機能は、人類の夢であるマントルへの掘削には必須である。また、泥水とともに船まで上がってきた切り屑を回収することによって、時間のかかるコア試料の回収を行わなくても掘削している地層や岩石の砕片試料を得ることができるなど、他のメリットもある。ただし掘る穴の直径が大きくなり、泥水を循環させる必要があるので、通常のライザーレス掘削より大きな動力と長い時間を要し費用も嵩む。
さて、実際に作ってみると、このプラモデル作りはかなり難物で、完成させるには相当の忍耐力と注意力、手の器用さが必要である。私はちょうど連休の前半に風邪を引いてしまい、家に蟄居していなくてはならなかったので、その間にこれを作ったが、完成には丸2日を要した。外箱には「対象年齢15才以上」と明記されているが、大人でも「細かな手作業は嫌いだ」という人には向かない。作業を始める前にニッパー、ピンセット、カッター、はさみ、綿棒、つま楊枝、そしてセメダインなどの接着剤を別途用意する必要がある。組み立てる部品数は貼り付けシールを含めると300個を超える。「ちきゅう」の特徴や建造の経緯、主な研究成果などまで含めた、モリナガ・ヨウ氏のイラスト入りの28ページの説明書が附属している。完成品は全長30 cm、実物の1/700のモデルになる(図1)。
作業中に気がついたこととしては、部品を枠からニッパーで切り取った後にカッターなどでなるべく丁寧に「バリ」を取ることが美しく仕上げるコツであること、シールの貼り付けが特に難しく技術と経験を要すること、とにかく余計なことを考えず説明書をよく読みながら愚直に順番と細かな指示を守って組み立てるのが最小の時間とストレスで完成させる道であること、などである。この説明書は非常によくできており、図解が豊富かつ正確で、説明文も親切である。このモデルでは、ライザーパイプ(白色)と通常のドリルパイプ(黒色)の太さ・長さの違いがよくわかる。本体右側面の前部と中部を完成後も簡単に取り外すことができ、ムーンプール(ドリルパイプを降ろす船底の孔)周辺や研究ラボの内部が見られるようになっている。意外だったのは、この船には船尾の大きなスクリューがなく、アジマス・スラスタ(azimuth thruster)と呼ばれる本体底面の6つの方向可変のスクリューだけで推進力を得ていることである。水面下の部分は見学に行っても見えない。なお、このモデルは、完成後でも船底の赤い部分を外して「洋上ディスプレイ」にすることが可能である。また、ドリルパイプ(黒色)やヘリコプターは、完成後の教材としての持ち運びを考えると、本体に接着してしまった方がよい。操舵室の上の高いアンテナは折れやすいので、持ち運びの際は特に注意が必要である。
会員各位がこの船のプラモデルを身近に置き、最近得られたこの船による上述の研究成果や将来のマントル掘削などの計画を話してあげることによって、日本が参画している国際的、先端的な巨大科学の1つである地球深部掘削に学生・生徒・子供の興味を向けることができ、地球科学の普及と次世代の地球科学者・技術者育成につなげることができると思う。もちろん、少年時代を思い出して、久しぶりにプラモデル作りに熱中してみるだけでも悪くない。このプラモデルはインターネットからも購入でき、価格は販売者によって異なる。私は4月に東京で開催されたChikyu+10ワークショップの会場において割引価格で購入したが、そこでは英語の説明書も添付され、多数の外国人参加者も購入していた.なお、「しんかい6500」のプラモデルも同じ会社で製造している。
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター、IODP委員)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】第4回惑星地球フォトコンテスト:入選作品展示会のお知らせ
──────────────────────────────────
全205点の応募作品の中から,12点が入選しました.各地で入選作品の展示会を予定しています。皆様お誘い合わせの上,迫力ある作品を是非会場でご覧下さい.
・5/25〜6/9:埼玉県立自然の博物館(秩父郡長瀞町)
・7/6〜8/4:兵庫県立人と自然の博物館(兵庫県三田市)
・9/14〜16:地質情報展(仙台大会)(仙台市)
・10月初旬〜11月:あいちサイエンスフェスティバル(愛知蒲郡市)
・12月〜2014年2月:奥出雲多根自然博物館 など
詳しくは,http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】仙台大会関連情報
──────────────────────────────────
日本地質学会120年学術大会 (仙台大会)
2013年9月14日(土)〜16日(月・祝)
会場:東北大学川内北キャンパスほか
講演申込,事前参加登録は,まもなく受付開始です(5月末頃予定)。
大会HP近日公開予定です。また,学会ニュース誌5月号(5月末配布)掲載の大会予告記事もあわせてご参照ください。
http://www.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質図幅をネットで読める「地質図Navi」が正式公開
──────────────────────────────────
産総研が昨年11月から試験公開してきた,地質図幅をネットで読める「地質図Navi」が,5月10日「地質の日」に正式公開されました.
地質図Naviは,PCやタブレットPC等から利用できる地質図表示サイトで,産総研の発行する1000枚以上の地質図幅を表示できるほか,活断層や第四紀火山,地球化学・物理データなど様々な種類の地質情報の表示が可能です.
正式公開での試験公開からの変更点は,
・2007〜2012年発行の地質図幅データの追加
・Retinaディスプレイなどの高解像度デバイスでの高精細表示
・GSJ公式サーバからの配信によるサービスの安定化
・GSJの地質情報配信サービスgbankの運用開始
・表示等の不具合の修正
などです.
野外調査や巡検の下調べなど,地質図幅の電子図書館として利用できます.
地質図Naviはこちらから,
https://gbank.gsj.jp/geonavi/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
■中部支部
中部支部総会(石川県大会)のご案内
日時:2013年6月29日(土)〜30日(日)
会場:白山市交流センター
29日(土曜日)インドアミーティング
石川県関係として、白山火山に関する研究と防災に関する話題を金沢大学の平松良浩先生と酒寄淳史先生に提供していただく予定.
30日(日曜日)白山手取川ジオパークに関連した野外巡検を企画.
その他の講演内容、参加者,参加費に関する情報は、随時下記で公開.
http://earth.s.kanazawa-u.ac.jp/tomo/GSJ-Ishikawa13/GSJ-Ishikawa13.html
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
■西日本支部
日本地質学会西日本支部 第164回例会および
シンポジウム「長岡信治:海から山,火山でのフィールドワーク」
日時:2013年6月8日(土)〜9日(日)
会場:雲仙岳災害記念館(がまだすドーム)セミナー室
〒855-0879 長崎県島原市平成町1-1
主催:日本地質学会西日本支部,福岡大学国際火山噴火史情報研究所
共催:長崎県地学会
・宿泊および懇親会申し込み:5月17日(金)17時
・講演申し込みの〆切:5月30日(木)12時
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地質研究所ニュース 第31号
http://www.gsh.hro.or.jp/publication/gshnews/news_pdf/vol29_no1.pdf
■日本地球惑星科学連合2013年大会
5月19日(日)〜24日(金)
場所:幕張メッセ国際会議場(千葉市美浜区)
5/20〜24 13:00〜13:40(昼休み):スペシャルレクチャー(大学生・若手研究者対象)
http://www.jpgu.org/meeting/index.htm
■第26回東京国際ミネラルフェア
6月7日(金)〜11日(火)10:00-18:00(最終日は17:00まで)
場所:小田急第一生命ビル2F 特別展示場(新宿区西新宿2-7-1)
http://www.tima.co.jp/
■深田研ジオフォーラム2013
6月22日(土)9:30-16:30(受付開始9:00)
場所:深田地質研究所研修ホール(文京区本駒込2-13-12)
申込締切:6月19日(水)[定員50名:定員に達し次第締切]
http://www.fgi.or.jp/
■森里海シンポジウム「人と自然のきずな〜森里海連環学へのいざない〜」
6月29日(土)
場所:東京都港区赤坂1丁目2番2号 日本財団ビル
参加費無料
http://fserc.kyoto-u.ac.jp/cohho/index/130629sympo/
■第50回 アイソトープ・放射線研究発表会発表論文の募集
日本地質学会ほか 共催
7月3日(水)〜5日(金)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1)
http://www.jrias.or.jp/
■高校生のための先進的科学技術体験合宿プログラム
「サマー・サイエンスキャンプ2013」参加者募集
7月23日〜8月28日の期間中の2泊3日〜4泊5日
会場:大学、公的研究機関、民間企業等(58会場)
締切:6月14日(金)必着
http://rikai.jst.go.jp/sciencecamp/camp/
■第57回粘土科学討論会
日本地質学会 共催
9月4日(水)〜6日(金)
会場:高知市文化プラザかるぽーと
参加・講演の申込期間 :6月3日(月)〜 14日(金)
講演要旨送付締切 :7月12日(金)
http://www.cssj2.org/
■第4回・第5回津波堆積物ワークショップ
(120年学術大会:同時開催行事)
日本地質学会・日本堆積学会 共催
9月14日 午前 第4回ワークショップ
9月18日 午前 第5回ワークショップ
場所:仙台(東北大学)
http://www.geosociety.jp/science/content0057.html
■2013年度日本地球化学会年会
日本地質学会 共催
9月11日(水)〜13日(金)
会場:筑波大学第一エリア1D1E棟
固有セッション申込:6月13日(木)〜 7月17日(水)
共通セッション申込:6月7日(金)〜 23日(日)
事前参加登録締切:8月23日(金)(予定)
http://www.geochem.jp/
■第67回日本人類学会大会・総会
11月1日(金)〜4日(月)
場所:国立科学博物館筑波研究施設ほか
企画募集締切:5/31 演題募集・参加登録締切:8/9
http://www.gakkai.ne.jp/anthropology/67_annual_meeting
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/outline/content0098.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■新潟大学:教育研究院自然科学系教員(准教授・助教)(7/12)
■海洋研究開発機構:地球内部ダイナミクス領域地球内部物質循環研究プログラム(上席研究員)(6/28)
■海洋研究開発機構:海洋・極限環境生物圏領域(ポストドクトラル研究員)(6/28)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flash No.219 仙台大会講演申込が始まりました
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.219 2013/6/4 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】仙台大会講演申込・要旨投稿受付開始
【2】2013年度会費督促請求について
【3】Island Arcからのお知らせ
【4】やったぜ千葉高生 Intel ISEF 2013 で快挙
【5】深海底岩石サンプルデータベース がリニューアル
【6】IGCP608白亜紀アジア−西太平洋生態系の第1回国際研究集会はインドで
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】仙台大会講演申込・要旨投稿受付開始
──────────────────────────────────
仙台大会講演申込の投稿受付を5/27より開始しました。
締切は,7月2日(火)17時(郵送 6月26日(水) 必着)です。
講演申込要領・発表要領の内容を確認の上,お申し込みください。
申込・登録はこちらから
http://www.geosociety.jp/sendai/content0017.html
仙台大会HPはこちら
http://www.geosociety.jp/sendai/content0001.html
大会参加登録もまもなく受付開始予定です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2013年度会費督促請求について
──────────────────────────────────
■2013年度およびそれ以前の会費が未入金の方へ■
1.次回の自動引き落とし日は6月24日(月)です。2013年度会費が未入金のかたで、1月から5月上旬までの間に自動引落の手続きをされたかたは6月24日に引き落としがかかります。引き落とし不備にならぬよう、残高の確認をお願いします。
2.郵便振替用紙によるお振り込みの方には、督促請求書(郵便振替用紙)を送付いたします。お手元に届きましたら、早急にご送金くださいますようお願いいたします。督促請求書の発送は6月中旬頃を予定しております。
※7月上旬頃までに入金確認が取れない場合には、7月号の雑誌から発送停止となります。定期的に雑誌をお受け取りになりたい方は、お早めにご送金くださいますよう、よろしくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】Island Arcからのお知らせ
──────────────────────────────────
【名称変更について結果報告】
新名称の募集に際し,Island Arcを含め41の提案をいただきました.
これらの名称について,Editorial Advisory Board, Associate Editors, Editor-in-Chief, Executive Editorにて、協議を踏まえ計2回の投票を行いました.
その結果,現雑誌名「Island Arc」の継続を支持する意見が多数を占め,「Island Arc」を継続することとなりました.
今後のIsland Arc誌発展と改善に向けて,編集委員・編集事務局一同,努力いたします.
原稿のご投稿や査読のご協力を今後ともよろしくお願いいたします.
Island Arc編集委員長
伊藤 慎
海野 進
【最新号22-2号がオンライン出版されました】
詳しくはこちらを御覧下さい.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iar.2013.22.issue-2/issuetoc
<日本語要旨掲載ページ>
http://www.geosociety.jp/publication/content0068.html
IAR最新号は,学会webサイトから無料で閲覧出来ます。
ログイン方法はこちらから,
https://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
【2013 Island Arc賞】
今年のIsland Arc賞は,Hattori et al. (2010) ”Subduction of mantle wedge peridotites: Evidence from the Higashi-akaishi ultramafic body in the Sanbagawa metamorphic belt.” (Island Arc, Vol. 19, p. 192-207)に贈られます.日本地質学会第120年学術大会(仙台大会)において授賞式が行なわれ(9月14日),第一著者の服部恵子博士(オタワ大学)も出席される予定です.
論文紹介と受賞理由はこちらから,
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iar.12029/abstract
【最多ダウンロード賞】
2013年最多ダウンロード賞は,Ayalew and Ishiwatari (2011) ”Comparison of rhyolites from continental rift, continental arc and oceanic island arc: Implication for the mechanism of silicic magma generation”. (Island Arc, Vol. 20, p. 78-93) に贈られます.本賞は,2007年〜2011年に出版された論文のうち,2012年に最もダウンロードされた論文に対しWiley社より与えられます.受賞論文はこちらから,
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1440-1738.2010.00746.x/abstract
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】千葉高生がIntel ISEF 2013 で日本人初の部門最優秀賞受賞
──────────────────────────────────
アメリカ合衆国(アリゾナ州フェニックス)で開催された「インテル国際学生科学技術フェア(Intel ISEF)2013」にて,千葉高等学校2年の田中 堯さんが、部門最優秀賞等を獲得しました! 日本人初の部門最優秀賞受賞とのことです.
盛大な拍手を送りましょう.これからの活躍に期待されます.
テーマ「微小貝は古環境指標として有用か」
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/05/1335145.htm
http://isef.jp/news/2013/05/intel-isef-2013-4.html
http://news.mynavi.jp/articles/2013/05/20/isef3/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】深海底岩石サンプルデータベース "GANSEKI" がリニューアルされました。
──────────────────────────────────
海洋研究開発機構(JAMSTEC)では、JAMSTEC船舶によって採取された岩石サンプルやその関連情報を研究・教育用途の利用に無償公開しています。
2006年から運用が始まったGANSEKIデータベースには、2万数千件のメタデータ、1万数千件の分析データおよび、8千数百点の岩石サンプルコレクションの保管情報が登録されています。このGANSEKIデータベースが大改修を終え、2013年5月に公開されました。
新しいGANSEKIでは検索・閲覧機能が強化され、分析データの数値や画像情報によるサンプルの選択、「マイリスト」機能による効率的なデータの整理・比較が可能になりました。
「航海・潜航データ探索システム(DARWIN)」などGANSEKI以外の各種データサイトとの連携機能も強化され、研究に役立つコンテンツの充実を目指しています。
「深海底岩石サンプルデータベース "GANSEKI"」
URL: http://www.godac.jamstec.go.jp/ganseki/j
JAMSTEC 岩石サンプルキュレーター
富山隆將 (tomi@jamstec.go.jp)
※GANSEKIや岩石サンプルキュレーションに関するご意見やご要望をお知らせ下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】IGCP608白亜紀アジア−西太平洋生態系の第1回国際研究集会はインドで
──────────────────────────────────
2013年3月より活動を開始した, IGCP608 Asia-Pacific Cretaceous Ecosystems (地質科学国際研究計画608:白亜紀アジア−西太平洋生態系)の第1回国際研究集会は,2013年12月20-27日の予定で,インド・ラクナウのバーバル・サーニー古植物 研究所(Birbal Sahni Institute of Palaeobotany: http://www.bsip.res.in/)で行われます.詳しくはIGCPのWebsiteでご確認下さい.案内ビラ(First Circular)もダウンロード可。
http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/
http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/index.php?id=5
(IGCP608 プロジェクトリーダー 安藤寿男)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
■関東支部
立川断層榎トレンチ調査は、文部科学省が実施している「立川断層帯の重点的な調査観測」(受託先:東京大学地震研究所)の一環として実施されたものです。その掘削現場を東京大学地震研究所が2月8〜9日に一般公開を行うことになったのですが、この説明会には相当数の市民の方々が参加されることが予想されました。また、日本地質学会関東支部所属の多くの会員も立川断層に強い興味を持っていました。そこで、関東支部幹事会は支部独自の見学会を1月26日に行って詳細に観察した上で、その一般公開が有意義なものとなるよう後援することにした次第です。
一般公開の後に、東大地震研究所の研究グループは、同グループ自身が行った追加調査によって「主断層帯とした部分に列状に配列する特徴的な白色粘土塊が人工物であることが判明」したとして、一般公開時の説明会内容を訂正した報告を、3月29日付でホームページに公開しました。
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/project/tachikawa/
この追加調査に至るうえでは、1月26日の支部観察会に参加した地質技術者(支部所属会員)から「トレンチ壁で観察された白色粘土塊は人工物ではないか」という疑義が出されたことを受け、支部幹事会が所属会員である地質研究者に鉱物分析等を委託したことが一つの重要な契機となっています。しかし、このような疑義が出されるまで、他の支部観察会参加者から誤認を明確に指摘する声はあがりませんでした。このことから、白色粘土塊についての誤認問題は地表近傍・地下浅所の人工改変に関する知見と経験が、地質学界全般においてなお不足していることにも起因しているのではないか、と反省せざるを得ません。さらに、もう一つ重要なことは、従来、立川断層による変動地形と想定されていたものが、今回のトレンチ調査によって「むしろ浸食崖である可能性が高いと判断」(東大地震研究所)されたことです。
これらの事態を受け、関東支部としても次の2つのことがらについて取り組む必要性を感じています。
第1には、地表近傍・地下浅所の人工改変に関する土木地質学上の基礎的理解・知識、さらには地すべり等による自然改変に関する応用地質学上の基礎的理論・知識を、豊富な現場の実例を踏まえつつ学ぶことです。
第2には、変動地形の認定方法やその根拠となる変動地形論をいっそう深化させることです。
第2のテーマは今後多くの研究者によって取り組まれることが期待されていますので、第1の点に関する緊急研修会を日本地質学会応用地質部会の後援をいただいて以下のように開催します。奮ってご参加ください。
◎主催:日本地質学会関東支部 後援:日本地質学会応用地質部会
◎講師と講義題目:
山崎孝成先生(国土防災技術株式会社技術本部長:静岡大学農学部非常勤講師、日本地すべり学会前理事)「すべり面の実態と斜面の安定:すべり面は断層面に似ているか?」
北誥昌樹先生(東京工業大学理工学研究科土木工学専攻教授:地盤工学会基準部会前部長)「我が国の地盤改良技術」
見掛信一郎先生(日本原子力研究開発機構東濃地科学センター:土木学会)「グラウチングによって亀裂性岩盤内に形成される組織と構造」
田中耕一先生(鹿島建設䆿 土木設計本部 地盤基礎設計部:地盤工学会理事)「土木建築工事に伴う人工的な地盤改変(地盤改良工事)の事例と見分け方」
日程:7月27日(土)午前10時〜午後5時
会場:日本大学文理学部3号館5階3507号室
受講を希望する方は、資料準備の都合もありますので7月19日(金)までに、関東支部 kanto@geosociety.jp 宛にご連絡ください。なお資料代は1,000〜1,500円程度です。プログラムを含めて詳細は追って関東支部HP http://kanto.geosociety.jp/ に掲載いたします。
問合せ先
関東支部幹事長 笠間友博
神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県小田原市入生田499
Eメール:kasama@nh.kanagawa-museum.jp
電話:0465-21-1515
■中部支部
中部支部総会(石川県大会)のご案内
日時:2013年6月29日(土)〜30日(日)
会場:白山市交流センター
29日(土曜日)インドアミーティング
石川県関係として、白山火山に関する研究と防災に関する話題を金沢大学の平松良浩先生と酒寄淳史先生に提供していただく予定.
30日(日曜日)白山手取川ジオパークに関連した野外巡検を企画.
その他の講演内容、参加者,参加費に関する情報は、随時下記で公開.
http://earth.s.kanazawa-u.ac.jp/tomo/GSJ-Ishikawa13/GSJ-Ishikawa13.html
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
■西日本支部
日本地質学会西日本支部 第164回例会および
シンポジウム「長岡信治:海から山,火山でのフィールドワーク」
日時:2013年6月8日(土)〜9日(日)
会場:雲仙岳災害記念館(がまだすドーム)セミナー室
〒855-0879 長崎県島原市平成町1-1
主催:日本地質学会西日本支部,福岡大学国際火山噴火史情報研究所
共催:長崎県地学会
・宿泊および懇親会申し込み:5月17日(金)17時
・講演申し込みの〆切:5月30日(木)12時
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■電中研TOPICS VOL.15発行のお知らせ(2013.5.27配信)
「電力の安定供給を担う火力発電設備の保守管理技術」
http://criepi.denken.or.jp/research/topics/
■日本学術会議公開シンポジウム
「学士課程教育における地球惑星科学分野の参照基準」
6月16日(日)13:00-16:00
場所:東京大学地震研究所2号館第1会議室
参加費:無料(事前申込み不要)
プログラム詳細:下記URLをご覧ください
http://www.sci.kumamoto-u.ac.jp/earthsci/nishiyama/SCJSymposium.pdf
■石油技術協会平成25年度春季講演会
6月27日(木)〜28日(金)
場所:国立オリンピック記念青少年総合センター(代々木)
http://www.japt.org/
■資源地質学会第63 回年会学術講演会
6月26日(水)〜28日(金)
会場:東京大学小柴ホール
http://www.resource-geology.jp/events/#p86
■第50回 アイソトープ・放射線研究発表会発表論文の募集
日本地質学会ほか 共催
7月3日(水)〜5日(金)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1)
http://www.jrias.or.jp/
■GSJ第21回シンポジウム
「古地震・古津波から想定する南海トラフの巨大地震」
7月10日(水)
場所:秋葉原ダイビル コンベンションホール
http://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo21/index.html
■Joint Conference of 28th Himalaya-Karakoram-Tibet (HKT) workshop and 6th International Symposium on Tibetan Plateau
(第28回HKTワークショップと第6回チベット高原に関する国際シンポジウムの合同大会)
8月22日(木)〜24日(土)
場所:Tübingen University, Germany
講演要旨締め切り:6月30日
ポストコンファレンス巡検
1. 8/25〜31:Geological Highlights of the Western Alps
2. 8/25〜30:Environment
問い合わせ:酒井治孝(hsakai@kueps.kyoto-u.ac.jp)
http://www.tip.uni-tubingen.de/index.php/en/hkt-istp-2013-tuebingen
■第57回粘土科学討論会
日本地質学会 共催
9月4日(水)〜6日(金)
会場:高知市文化プラザかるぽーと
参加・講演の申込期間 :6月3日(月)〜 14日(金)
講演要旨送付締切 :7月12日(金)
http://www.cssj2.org/
■第4回・第5回津波堆積物ワークショップ
(120年学術大会:同時開催行事)
日本地質学会・日本堆積学会 共催
9月14日 午前 第4回ワークショップ
9月18日 午前 第5回ワークショップ
場所:仙台(東北大学)
http://www.geosociety.jp/science/content0057.html
■2013年度日本地球化学会年会
日本地質学会 共催
9月11日(水)〜13日(金)
会場:筑波大学第一エリア1D1E棟
固有セッション申込:6月13日(木)〜 7月17日(水)
共通セッション申込:6月7日(金)〜 23日(日)
事前参加登録締切:8月23日(金)(予定)
http://www.geochem.jp/
■第29回ゼオライト研究発表会
日本地質学会 協賛
11月27日(水)〜11月28日(木)
会場:東北大学
http://www.jaz-online.org/index.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/outline/content0098.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■平成25年度福井県職員(古生物学)募集(6/26)
■関西学院大学:理工学部教育技術職員募集(7/31)
■電力中央研究所:地球工学研究所職員募集(特別契約研究員)(8/23)
■第8回「科学の芽」賞募集(8/20-9/30)
■平成26年度科学技術分野の文部科学大臣表彰受賞候補者の推薦(7/17 学会締切7/5)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flash No.220 (臨時)仙台大会巡検:M班中止のお知らせ
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.220 2013/6/10 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】仙台大会巡検:M班中止のお知らせ
──────────────────────────────────
第120年学術大会(仙台大会)の巡検について,巡検案内者の都合により,下記巡検コースは中止となりました。
申込受付開始後の中止のため,皆様にはご迷惑をおかけ致しますが,何卒ご了承下さい。すでにお申込を頂いた方は,学会事務局よりキャンセルのお手続きをさせて頂きます。
【中止】M班 2008年岩手・宮城内陸地震による斜面災害
(案内者 川辺孝幸・籾倉克幹)
仙台大会HP http://www.geosociety.jp/sendai/content0001.html
(日本地質学会行事委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flash No.221 仙台大会:巡検に行こう!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.221 2013/6/18 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[仙台大会]講演申込はお済みですか?ー各種申込受付中ー
【2】[仙台大会]学術大会に係るプレス発表会へのご協力のお願い
【3】[仙台大会]巡検の魅力・見どころ紹介
【4】2013年度会費督促請求について
【5】名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
【6】惑星地球フォトコンテスト:入選作品展示会(in 兵庫)
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[仙台大会]講演申込はお済みですか?ー各種申込受付中ー
──────────────────────────────────
<講演申込・投稿>
締切:7月2日(火)17時(郵送 6月26日(水) 必着)
<事前参加登録>
締切:8月20日(火)17時(郵送 8月20日(金) 必着)
※※※巡検のみ締切が異なります※※※
締切:8月9日(金)17時(郵送 8月7日(水) 必着)
▶▶巡検M班は中止になりました。詳しくはこちら
http://www.geosociety.jp/sendai/content0002.html#130610
<ランチョン・夜間集会>
締切:6月26日(水)
<小さなEarth Scientistのつどい:参加校募集>
〜第11回小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜
締切:7月17日(水)
そのほか、企業展示出展募集、ブース利用募集、広告協賛など、お申込受付中です。申込の締切がそれぞれ異なりますので、確認のうえ、お早めにお申し込み下さい。
仙台大会HPはこちら
http://www.geosociety.jp/sendai/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[仙台大会]学術大会に係るプレス発表会へのご協力のお願い
──────────────────────────────────
日本地質学会では,学術大会の際に,学術大会や地質情報展の開催案内,そして「特筆すべき研究成果」等を開催地および文科省の記者クラブに情報提供してまいりました.特に開催地での記者会見には,例年多くの報道機関の方が来場され,TV,新聞等で取り上げられています.
本年も仙台大会においてプレス発表会を開催する予定です.この機会に会員皆様の研究成果を「特筆すべき研究成果」として広報委員会へ是非ご推薦下さい.
「特筆すべき研究成果」の応募締切: 2013年7月19日(金)17時
応募方法など詳しくはこちら.
http://www.geosociety.jp/sendai/content0006.html
日本地質学会広報委員長
内藤一樹
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[仙台大会]巡検の魅力・見どころ紹介
──────────────────────────────────
本年9月に行われる仙台大会では,12コースの巡検が企画されています.
各コースの魅力と見どころは「各コースの詳細と魅力・見どころの紹介」
http://www.geosociety.jp/sendai/content0016.html
でご確認いただけます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2013年度会費督促請求について
──────────────────────────────────
■2013年度およびそれ以前の会費が未入金の方へ■
1.次回の自動引き落とし日は6月24日(月)です。2013年度会費が未入金のかたで、1月から5月上旬までの間に自動引落の手続きをされたかたは6月24日に引き落としがかかります。引き落とし不備にならぬよう、残高の確認をお願いします。
2.郵便振替用紙によるお振り込みの方には、督促請求書(郵便振替用紙)を送付いたします。お手元に届きましたら、早急にご送金くださいますようお願いいたします。督促請求書の発送は6月中旬頃を予定しております。
※7月上旬頃までに入金確認が取れない場合には、7月号の雑誌から発送停止となります。定期的に雑誌をお受け取りになりたい方は、お早めにご送金くださいますよう、よろしくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
──────────────────────────────────
日本地質学会では,学会員相互の交流と親睦を図る目的で,2年ごとに会員名簿を発行することを運営規則にうたっております.2013年はその発行年にあたり,本年11月末日発行の予定で準備を行っております.
名簿の発行様式は前回と同様で,全会員を収録します.本会としては,個人情報保護法の制約はあるとしても,会員の皆様が上記の目的に沿って利用できるような,従来規模の名簿を作成したいと考えておりますので,調査の実施にご理解とご協力をお願いいたします.
アンケート提出およびWeb画面更新締切日:2013年10月4日(金)
詳しくは,コチラ↓
http://www.geosociety.jp/outline/content0132.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】惑星地球フォトコンテスト:入選作品展示会(in 兵庫)
──────────────────────────────────
埼玉県立自然の博物館に続き,7月からは,兵庫県立人と自然の博物館との共催で作品展示会を開催させて頂きます。
第4回惑星地球フォトコンテストの入選作品と過去の優秀作品が展示されます.皆様お誘い合わせの上,是非お越し下さい.
7月6日(土)〜8月4日(日)
場所 :兵庫県立人と自然の博物館 3階ギャラリー( 三田市弥生が丘6丁目)
詳しくは,
http://www.hitohaku.jp/exhibits/temporary_old/2013/mini13.html#earthphoto
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
■関東支部
◆緊急研修会『地表付近の地質学的調査における応用地質学的・土木地質学的留意点』
日程:7月27日(土)午前10時〜午後5時
会場:日本大学文理学部3号館5階3507号室
参加申込締切:7月19日(金)
◆清澄フィールドキャンプ:参加者募集
期間:8月19日(月)〜8月24日(土)
場所:東京大学千葉演習林(〒299-5505 千葉県鴨川市清澄)
応募締切日:7月5日(金)(*応募書類はHPの所定のフォーマットを使用のこと)
いずれも詳しくは関東支部HPをご参照ください
http://kanto.geosociety.jp/
■中部支部
中部支部総会(石川県大会)のご案内
日時:6月29日(土)〜30日(日)
会場:白山市交流センター
29日(土)インドアミーティング
30日(日)白山手取川ジオパークに関連した野外巡検を企画.
その他の講演内容、参加者,参加費に関する情報は、随時下記で公開.
http://earth.s.kanazawa-u.ac.jp/tomo/GSJ-Ishikawa13/GSJ-Ishikawa13.html
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第50回 アイソトープ・放射線研究発表会発表論文の募集
日本地質学会 共催
7月3日(水)〜5日(金)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1)
http://www.jrias.or.jp/
■第48回地盤工学研究発表会
7月23日(火)〜26日(金)
会場:富山国際会議場、富山市民プラザ、富山県民会館
入場無料、事前申込不要
問い合わせ:地盤工学会北陸支部
025-281-2125 jibanhokuriku@piano.ocn.ne.jp
■変形・透水試験機設計セミナー2013
“変形と物質移動”は,テクトニクス・地震・地球内部流体循環・環境問題・応用地質など多くの分野に関わる基本的なプロセスです.自然界でおこっている変形と物質移動のプロセスを動的に捉えるためには,岩石の組織や構造 の解析に加えて,それらのプロセスを実験的に再現する必要があります.
本セミナーでは,岩石の変形と物質移動を調べるための試験機の実用的な設計法を取り上げます.セミナーの最後には,参加者全員が標準的な変形・透水試験機の図面を作成して,発表会を行う予定です.試験機の設計は,ポイントを押さえることができれば決して難しいものではありません.皆様 (特に学生の皆様)の参加をお待ちしております.
7月31日(水) 13:00 〜 8月2日(金)12:00
場所:広島大学大学院理学研究科
講師:堤 昭人(京都大学)・高橋美紀(AIST)・廣瀬丈洋(JAMSTEC)・片山郁夫(広島大学)
締め切り:6月28日(金)
参加・宿泊の申し込み:氏名,所属,学年,E-mailを明記し,片山(katayama@hiroshima-u.ac.jp)まで.
問い合わせ:
廣瀬丈洋(独立行政法人海洋研究開発機構:hiroset@jamstec.go.jp)
片山郁夫(広島大学大学院理学研究科:katayama@hiroshima-u.ac.jp)
■日本水環境学会第22回市民セミナー
「身近な水環境、池・沼・湖の保全を考える−ため池から琵琶湖まで」
8月2日(金)10:00-16:30
場所:
東京会場:地球環境カレッジ(いであ(株)内)(東京都世田谷区駒沢)
大阪会場:いであ(株)大阪支社ホール(大阪市住之江区南港北)
http://www.jswe.or.jp/event/seminars/
■室戸ジオパークサマースクール2013
来るならきいや南海地震、土佐はうちが守るきね!
日本地質学会 後援
8月8日(木)9:00〜9日(金)16:00
場所:室戸市内の海岸、室戸市保健福祉センター、国立室戸青少年自然の家
対象:小学校5年生〜高校3年生まで
募集期間:平成25年6月15日〜7月16日(定員:35名)
http://ss.muroto-geo.jp/
■第57回粘土科学討論会
日本地質学会 共催
9月4日(水)〜6日(金)
会場:高知市文化プラザかるぽーと
参加・講演の申込期間 :締切
講演要旨送付締切 :7月12日(金)
http://www.cssj2.org/
■第4回・第5回津波堆積物ワークショップ
(120年学術大会:同時開催行事)
日本地質学会・日本堆積学会 共催
9月14日 午前 第4回ワークショップ
9月18日 午前 第5回ワークショップ
場所:仙台(東北大学)
http://www.geosociety.jp/science/content0057.html
■2013年度日本地球化学会年会
日本地質学会 共催
9月11日(水)〜13日(金)
会場:筑波大学第一エリア1D1E棟
固有セッション申込:6月13日(木)〜 7月17日(水)
共通セッション申込:6月7日(金)〜 23日(日)
事前参加登録締切:8月23日(金)(予定)
http://www.geochem.jp/
■第29回ゼオライト研究発表会
日本地質学会 協賛
11月27日(水)〜11月28日(木)
会場:東北大学
http://www.jaz-online.org/index.html
■第3回学生のヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集
日本地質学会ほか 推薦
参加申込締切:11月30日
実習実施時期:2014年3月5日出発,19日帰国(15日間)
実習コース:カトマンズ−ポカラ−ムクチナート−タンセン−ルンビニ
参加費用:学生・大学院生20万円以内、その他の個人参加者:25万円以内、大学・企業などの組織派遣教員/社員:30万円以内
http://www.geocities.jp/gondwanainst/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/outline/content0098.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞情報
──────────────────────────────────
■海洋研究開発機構:海洋・極限環境生物圏領域(ポストドクトラル研究員)(7/12)
■海洋研究開発機構:海洋・極限環境生物圏領域(研究技術専任スタッフ)(7/5)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
東海道五十三次と地震・津波・噴火
東海道五十三次と地震・津波・噴火
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
江戸時代のはじめ、参勤交代制の開始(1635年)とともに整備された東海道五十三次は、橋のない川や厳しい関所などの問題はあったが、当時としては世界で最も安全・快適に旅行できるハイウェー・システムであった。しかし、この道はいくつかの場所で海岸沿いを通り(図1)、そこではしばしば自然災害に襲われてきた。この地域は相模トラフや南海トラフのプレート境界に沿っていて地震・津波の被害があり、また多くの台風が直撃して高潮、洪水、山崩れなどの被害があった。そして巨大な活火山である富士山がこの街道の間近にそびえている。ここでは、東海道の宿駅の歴史を概観して、この地域の自然災害について一考する。
図1.東海道五十三次の地図。本文中に出てくる宿駅(●印)や地名、プレート境界の位置も示した。
※拡大は画像をクリック
吉原宿は現在の静岡県富士市中心部にあったが、この場所に落ち着くまでに、災害によって何回も場所を変えた(馬頭町広重美術館, 2002)。ここは駿河湾の最奥に位置し、高潮の被害を受けやすい。宿駅はもともと海岸沿いにあったが、1639(寛永16)年の高潮で壊滅的被害を受けて山側へ移転したものの、1680(延宝8)年に再び高潮に見舞われ、さらに内陸側ヘ1 kmほど移動した。これらは地震津波ではなく、台風による高潮と考えられている。この移転によって、街道は大きく内陸側へ迂回することになった。江戸から京都に向かう東海道沿いでは、富士山は常に右手に見えるが、この迂回路だけは富士山が左側に見えるので、「左富士」と呼ばれて珍しがられた。
由比(由井)宿は吉原宿の2つ先にあり、そのすぐ南に東海道一の難所「薩埵(さった)峠」がある。もともと街道はこの山の下の海岸を通っていたが、時々波をかぶる危険な道だったため、明暦年間(1655-57)に徳川幕府が朝鮮通信使来朝に合わせて薩埵山を切り開き、峠道を作った。それ以後、海沿いの道は使われなくなったが、幕末の安政元年(1854)の地震で海岸が隆起し、以後は再び街道が海岸沿いを通るようになった。現在もJR東海道線、国道1号線、東名高速(これは海上の高架)が海岸沿いを通っているが、危険な場所であることに変わりはない。なお、この安政東海地震では、富士川の東側(吉原や伊豆方面)は地震の揺れによる被害が少なかったが、西側(断層の上盤側)の蒲原、由比、奥津などでは多数の死者が出た。また、駿河湾周辺では6 m程度の津波があり、これによる死者も多かった(つじ, 1992)。
浜名湖は明応7年(1498)の南海トラフ地震で海寄りの砂州が切れて遠州灘とつながってしまった。切れた砂州を今切(いまぎれ)と呼び、舞阪と新居(荒井)を結ぶ海上1 kmの舟渡しを今切の渡しと言った。砂州が切れたのは永正7年(1510)という説もある。大地震の約10年後に海底地すべりが発生して海岸の土地が失われた例としては、1964年新潟地震の震源地に近い粟島で、1974年に起きた地すべりがある。
白須賀宿は新居宿の次にあり、元々は海岸沿いにあったが、宝永7年(1707)の南海トラフ地震と津波により壊滅したため、汐見坂の上に移った。この地域の堆積物調査によると、1498年、1605年、1707年、1854年の津波堆積物が同定され、1680年または1699年の高潮によると思われる堆積物も確認されている(小松原ほか,2006)。伊勢街道に沿う三重県の津も、もとは安濃津と呼ばれる栄えた港だったが、1494年と1498年の2回の地震で市街や松原が海中に没してしまい、内陸側の現在の場所に移った。一方、1688年に刊行された浅井了意の東海道名所記(東洋文庫)によると、鈴鹿峠南側の坂下宿は、慶安3年(1650)の大雨による山崩れで宿場が埋まり多数の死者が出たため、その後1 kmほど下流側に移った。
さて、富士山は葛飾北斎の富岳三十六景(1831年頃出版)や安藤広重の東海道五十三次(1833年出版)によく描かれているが、この画家たちは富士山の地形的特徴をよく捉えている。広重の「原」の富士には右側の斜面に宝永火口の高まりが描かれ、手前の浸食が進んだ愛鷹山との地形の対比が強調されている。北斎の甲州三島越の富士は西側斜面を東側よりも急傾斜に描き、この成層火山の東西方向の非対称性をよく表現している。これらはいずれも1707年の宝永噴火から100年以上後に描かれたもので、現在の富士山の姿とほとんど変わりない。この噴火は太陽暦の12月16日に始まり、翌年1月初めまで続いた。火山灰が火口から東方へ運ばれ、小田原付近で20〜30 cm程度、横浜付近で15〜20 cm程度、江戸でも2〜3 cm程度堆積した(宮地・小山, 2007)。江戸では粒径数mm以下の火山灰で、これにより呼吸器疾患が増加したという記録があるが、小田原付近では10〜20 mmの火山礫が降った。最初は白〜灰色のデイサイト質の灰が降り、次第に黒い玄武岩質の灰に変わった。富士山東麓では火山灰や火山礫が数メートルも堆積し、家が潰れたり埋まったりしたほか、広大な農地が灰をかぶった。この火山灰は雨が降るたびに下流に流れ出し、洪水を引き起こし、数年にわたって飢饉を生じた。人口が半分以下になった村も多く、酒匂川沿いの足柄平野のある村では、その後11年間も年貢が免除された。二宮金次郎はこの噴火の約80年後に足柄上郡栢山村に生まれたが、その頃もまだ洪水が頻発し、彼の家の田畑も流されるような状況だった。富士山噴火がこの地域に課した試練が、その後二宮尊徳と呼ばれる人格者を育て上げたとも言える。東海道の酒匂川は、この噴火以前は船で渡していたが、以後は歩いて渡る渡渉制になった(宇佐美, 1998)。十返舎一九の東海道中膝栗毛(岩波文庫)は1801年に刊行されたので、弥次喜多も歩いて渡ったはずである(その夜に小田原宿で五右衛門風呂に下駄履きで入って釜を壊した)。なお、朝鮮、琉球、オランダなどの外国使節が通行するときは、周辺の村から多数の船を調達して船橋を作った。
以上のように、東海道は17世紀に街道として整備されてからも様々な自然災害をこうむり、その影響を受けて変化しながら日本の交通の動脈としての役割を果たし続けてきた。明治以後も、1891年の濃尾地震で岐阜の東海道本線長良川鉄橋が落下したり、1923年の関東大地震の時に根府川駅で列車が山崩れに巻き込まれて駅ごと海中に滑落したり、1930年の北伊豆地震により掘削工事中の丹那トンネルが断層で大きく変位したりした。このトンネルは1916年から掘り始めたが、1934年の完成までの間に2回の大地震を経験したことになる(服部, 2013)。戦時中の東南海地震(1944年12月7日)では東海地域から紀伊半島にかけて最大9 mの津波があり、1200人以上の死者が出て、東海地域の軍需工場も大きな被害を受けた。日本政府は被害を隠したが、米国は地震の場所や規模を把握しており、その6日後に米軍が名古屋を空爆した。また、戦後の1959年の伊勢湾台風では、高潮により名古屋を中心に愛知・三重などで5,000人以上の死者が出た。そして、JR東海道本線の終点である神戸でも、1995年の阪神大震災ではこれを上回る死者が出て、列車の脱線や新幹線・高速道路の高架の崩落などがあった。
2011年の東日本大震災の経験から言えることは、広域的に交通の代替経路を複数確保することの重要性である。被災地からの避難、被災地への物資や人員の供給のために、日頃から代替路線を整備し、日常的に活用することが急務である。「備えがないことはできない」ということを肝に銘じるべきである。そして、これを実行するためには、地域の災害の歴史を文献から学び、自分のこととして地域の防災・減災を考えることが第一歩である。
【引用文献】
馬頭町広重美術館 (2002) 江戸の旅東海道五拾三次展図録。同館。151 p.
服部 仁 (2013) 丹那断層と丹那トンネル難工事と二つの地震。地質学会News, 16(3), 12-13; 16(4), 17-18; 16(5), 17-18.
小松原純子・藤原 治・高田圭太・澤井祐紀・タン・ティン・アオン・鎌滝孝信 (2006) 沿岸低地堆積物に記録された歴史時代の津波と高潮:南海トラフ沿岸の例。活断層・古地震研究報告, 6, 107-122.
宮地直道・小山真人 (2007) 富士火山1707年噴火(宝永噴火)についての最近の研究成果。荒牧重雄・藤井敏嗣・中田節也・宮地直道編「富士火山」。山梨県環境科学研究所。p. 339-348.
つじよしのぶ (1992) 富士山の噴火:万葉集から現代まで。築地書館。261 p.
宇佐美ミサ子 (1998) 近世助郷制の研究—西相模地域を中心に—。法政大学出版局。373 p.
(2013.6.26)
_______________________
追記:笠間友博会員から左富士は南湖(茅ヶ崎)
にもあったというご指摘をいただいた。
_______________________
geo-Flash No.222(臨時)締切延長!!講演申込まだ間に合います
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.222 2013/7/1 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[仙台大会]締切延長!!講演申込まだ間に合います
──────────────────────────────────
多くの方々にご講演いただくため、講演申込の締切を延長いたしました。
お申し込みをお待ちしています。ただし,郵送分は締切ましたので,オンラインでの申込のみ受付可能です。
オンライン講演申込締切:7月3日(水)17時厳守
講演申込はこちらから
http://www.geosociety.jp/sendai/content0017.html
★★事前参加登録も別途忘れずにお申し込み下さい★★
(受付番号・パスワードは講演申込とは異なります.ご注意下さい)
締切:8月20日(火)18時(郵送 8月16日(金) 必着)
注意)巡検のみ:8月9日(金)18時(郵送 8月7日(水) 必着)締切
仙台大会HPはこちら
http://www.geosociety.jp/sendai/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
鳥が首岬の謎
鳥が首岬の謎
高山 信紀 ((株)JPビジネスサービス)
1.鳥が首岬の謎
以前、米国ユタ州サンファン川(San Juan River)の「Gooseneck」や、愛媛県を流れる肱川中流の「鳥首」を訪れたことがあるが、いずれも地名は河川の蛇行を鳥の首に例えたことに由来する。
「Gooseneck」( © Google earthより)
「鳥首」( © Google earthより)
「鳥が首岬」( © Google earthより)
鳥が首岬は、新潟県上越市西方(糸魚川市寄り)に位置し、全国的にはそれほど有名では無いが国土地理院発行の20万分の1地形図や2万5千分の1地形図にはその名が記載されている。鳥が首岬の地名は何に由来するのだろう?国土地理院発行の2万5千分の1地形図では、鳥が首岬周辺に「Gooseneck」や「鳥首」のような河川の蛇行は見当たらなかった。また、岬を上空から見た地形も鳥の首とは関係なさそうだった。鳥が落ちたというような伝説でもあるのだろうかとインターネットで調べたが地名の由来は分からず、前から気になっていた。そこで、糸魚川・焼山温泉を巡る地質とサイクリングの旅に出かけたおり、Hさんの車で鳥が首岬を往復してもらった。しかし、それらしい地形は分からなかった。謎は深まった。
2.謎が解けた!
仕方がないので、旅から帰った後、上越市観光振興課に鳥が首岬の地名の由来を電話で聞いてみた。「分からないので調べてみます」ということだった。数日後、同課から携帯に電話が入っていた。翌朝こちらから観光振興課に電話したところ、「『鳥が首岬は名立川、桑取川の水源をなす粟立、三峰等の山々の尾根が北に延びて来て名立村大菅の東部で一旦標高200mに下り、更に頭を上げた様に高さを増し313m5となり下って段を作って海に入るその形が遠方より見ると鴨等の鳥の首を平らに置いたのに似ているからつけられた名称である』という文献がありました。」と教えて頂いた。また、上越市立高田図書館から、その文献は月橋正樹著『名立崩・親不知・上路の山姥』(1942年)であるとメールを頂いた。担当された方々の親切な対応に深く感謝した。
その週末に © Google earthを操作してみた。本当だ、鴨が首を伸ばしているように見える! 「Gooseneck」や「鳥首」は河川の蛇行を高所から俯瞰して鳥の首に例えたのに対し、「鳥が首岬」は地形を横から見て鳥が首を伸ばしているように見たてたのだ(岬は嘴の先端)。昔の人たちにとって、鴨は季節を知らせる身近で大切な鳥で、鳥と言えば鴨を意味したのかもしれない。 「首」が頭部を指す場合もあることから、岬南方の鴨の頭部にあたる標高約300mの台を「鳥が首」と呼んでいるか図書館に問い合わせたところ、上越市名立区総合事務所に連絡して頂き、同事務所より「地元ではその台を鳥が首とは呼んでいないようです。鳥が首という地名は岬しかありません。なお、地名ではありませんが、その岬にある灯台にも鳥が首という名称がついています。」と、またも親切な回答を頂き、再度深く感謝した。なお、国土地理院発行の2万5千分の1地形図では、その台は三角点が設置され無機的に「三角台」と記載されている。 どこから見れば鳥の首のように見えるのだろう? © Google earthで見ると、陸上からでは難しいように思う。漁師などが岬西方の海上から陸地を見て鴨の姿を想い、鳥が首岬と呼ぶようになったのではないだろうか。
鳥が首岬(左端)の西方海上より岬方向を見た画像( © Google earthより)
右の画像のように首を伸ばした状態の鴨の写真をインターネットで探したが、大半は鴨が頭を上げて泳いでいる姿であった。昔の人たちは、鴨が首を伸ばしている姿(飛んでいる姿か、水に潜る直前の姿?)をよく見ていたのだろう。その観察力と想像力の豊かさを想う。
【文献】
月橋正樹(1942), 名立崩・親不知・上路の山姥, p4
竹内圭史・加藤碵一・柳沢幸夫・広島俊男(1994), 20万分の1地質図幅「高田」, 地質調査所
(2013.6.16)
geo-Flash No.223 仙台大会の講演申込は済みましたか?【7/3, 17時締切】
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.223 2013/7/2 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[仙台大会]7月3日17時:講演申込最終〆切です!!
【2】[仙台大会]事前参加登録も別途忘れずにお申し込み下さい
【3】[仙台大会]学術大会に係るプレス発表会へのご協力のお願い
【4】東海道五十三次と地震・津波・噴火
【5】名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
【6】Island Arcからのお知らせ:2012年IFは1.071
【7】第四紀小委員会,第四紀研究連絡委員会の資料を探しています.
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[仙台大会]7月3日17時:講演申込最終〆切です!!
──────────────────────────────────
多くの方々にご講演いただくため、講演申込の締切を延長いたしました。
お申し込みをお待ちしています。
オンライン講演申込締切:7月3日(水)17時厳守(郵送分は締切ました)
講演申込はこちらから
http://www.geosociety.jp/sendai/content0017.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[仙台大会]事前参加登録も別途忘れずにお申し込み下さい
──────────────────────────────────
講演申込をされた方も,別途事前参加登録を行って下さい。受付番号・パスワードは講演申込とは異なります.ご注意下さい。
締切:8月20日(火)17時(郵送 8月20日(金) 必着)
※※※巡検のみ締切が異なります※※※
締切:8月9日(金)17時(郵送 8月7日(水) 必着)
巡検の見どころ紹介→http://www.geosociety.jp/sendai/content0016.html
そのほか、小さなEarth Scientistのつどい,企業展示出展募集、ブース利用募集、広告協賛など、お申込受付中です。申込の締切がそれぞれ異なりますので、確認のうえ、お早めにお申し込み下さい。
仙台大会HPはこちら
http://www.geosociety.jp/sendai/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[仙台大会]学術大会に係るプレス発表会へのご協力のお願い
──────────────────────────────────
本年も仙台大会においてプレス発表会を開催する予定です.この機会に会員皆様の研究成果を「特筆すべき研究成果」として広報委員会へ是非ご推薦下さい.
「特筆すべき研究成果」の応募締切:2013年7月19日(金)17時
応募方法など詳しくはこちら.
http://www.geosociety.jp/sendai/content0006.html
日本地質学会広報委員長
内藤一樹
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】東海道五十三次と地震・津波・噴火
──────────────────────────────────
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
江戸時代のはじめ、参勤交代制の開始(1635年)とともに整備された東海道五十三次は、橋のない川や厳しい関所などの問題はあったが、当時としては世界で最も安全・快適に旅行できるハイウェー・システムであった。しかし、この道はいくつかの場所で海岸沿いを通り、そこではしばしば自然災害に襲われてきた。この地域は相模トラフや南海トラフのプレート境界に沿っていて地震・津波の被害があり、また多くの台風が直撃して高潮、洪水、山崩れなどの被害があった。そして巨大な活火山である富士山がこの街道の間近にそびえている。ここでは、東海道の宿駅の歴史を概観して、この地域の自然災害について一考する。
続きはこちらから.
http://www.geosociety.jp/faq/content0458.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】 名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
──────────────────────────────────
日本地質学会では,学会員相互の交流と親睦を図る目的で,2年ごとに会員名簿を発行することを運営規則にうたっております.2013年はその発行年にあたり,本年11月末日発行の予定で準備を行っております.
名簿の発行様式は前回と同様で,全会員を収録します.本会としては,個人情報保護法の制約はあるとしても,会員の皆様が上記の目的に沿って利用できるような,従来規模の名簿を作成したいと考えておりますので,調査の実施にご理解とご協力をお願いいたします.
アンケート提出およびWeb画面更新締切日:2013年10月4日(金)
詳しくは,コチラ↓
http://www.geosociety.jp/outline/content0132.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】Island Arcからのお知らせ:2012年IFは1.071
──────────────────────────────────
トムソン・ロイター社より2012年Impact Factorが発表され,Island ArcのIFは「1.071」でした.
またGeosciences, Multidisciplinaryのカテゴリーでは,170誌中113位でした.
昨年は,IFが「1.012」で順位が113位でしたので,IFは上昇しましたが,順位は同じということになります.
IARへの積極的な投稿,またIAR掲載論文の引用をお願いいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】第四紀小委員会,第四紀研究連絡委員会の資料を探しています.
──────────────────────────────────
名古屋国際会議場で2015年の夏に国際第四紀学連合(INQUA)の大会が初めて日本で開催するのに際し,日本におけるINQUA対応の歴史に関する資料を探しています.日本学術会議の地質学研究連絡委員会に1950年11月17日に第4紀小委員会が設けられました.更に日本学術会議第5期において,1960年1月に第四紀研究連絡委員会が新設されます.それ以降,INQUA対応の委員会が継続して存続しており,現在は,日本学術会議の国際対応分科会のINQUA分科会がその任を担っています.
1956年の日本第四紀学会の設立に際し,第四紀小委員会は矢部長克委員長の下,15名の委員からなる新生の小委員会となります.この時のメンバー構成に関する資料を探しています.また第四紀研究連絡委員会が設置されて以降,第6期(1963-1966)の研連委員構成に関する資料も探しています.多田文男委員長、宮地伝三郎(会員),渡辺 光(会員),以上の3名が委員であったことは分かっていますが他の委員構成がわかりません.以上の情報をお持ちの方は,第19回第四紀国際第四紀学連合大会組織委員会までご一報頂けると幸いです.
連絡先:〒305-8567 つくば市東1−1−1中央第7
産業技術総合研究所地質情報研究部門
斎藤文紀
E-mail:yoshiki.saito@aist.go.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
──────────────────────────────────
■関東支部
◆緊急研修会『地表付近の地質学的調査における応用地質学的・土木地質学的留意点』
日程:7月27日(土)午前10時〜午後5時
会場:日本大学文理学部3号館5階3507号室
参加申込締切:7月19日(金)
◆清澄フィールドキャンプ:参加者募集
期間:8月19日(月)〜8月24日(土)
場所:東京大学千葉演習林(〒299-5505 千葉県鴨川市清澄)
応募締切日:7月5日(金)(*応募書類はHPの所定のフォーマットを使用のこと)
いずれも詳しくは関東支部HPをご参照ください
http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地震本部ニュース5月号(2013.6.24)
http://www.jishin.go.jp/main/p_koho04.htm
■第50回 アイソトープ・放射線研究発表会発表論文の募集
日本地質学会 共催
7月3日(水)〜5日(金)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1)
http://www.jrias.or.jp/
■第151回深田研談話会
「放射性物質を追跡して環境変化を捉える」
7月12日(金)
申し込み締切:7/10 先着:80名 参加無料
会場:深田地質研究所 研修ホール(文京区本駒込2-13-12)
http://www.fgi.or.jp/
■室戸ジオパークサマースクール2013
来るならきいや南海地震、土佐はうちが守るきね!
日本地質学会 後援
8月8日(木)9:00〜9日(金)16:00
場所:室戸市内の海岸、室戸市保健福祉センター、国立室戸青少年自然の家
対象:小学校5年生〜高校3年生まで
募集締切:7月16日(定員:35名)
http://ss.muroto-geo.jp/
■第57回粘土科学討論会
日本地質学会 共催
9月4日(水)〜6日(金)
会場:高知市文化プラザかるぽーと
参加・講演の申込 :[終了]
講演要旨送付締切 :7月12日(金)
http://www.cssj2.org/
■第4回・第5回津波堆積物ワークショップ
(120年学術大会:同時開催行事)
日本地質学会・日本堆積学会 共催
9月14日 午前 第4回ワークショップ
9月18日 午前 第5回ワークショップ
場所:仙台(東北大学)
http://www.geosociety.jp/science/content0057.html
■2013年度日本地球化学会年会
日本地質学会 共催
9月11日(水)〜13日(金)
会場:筑波大学第一エリア1D1E棟
固有セッション申込締切: 7月17日(水)
共通セッション申込:[終了]
事前参加登録締切:8月23日(金)(予定)
http://www.geochem.jp/
■第29回ゼオライト研究発表会
日本地質学会 協賛
11月27日(水)〜28日(木)
会場:東北大学
http://www.jaz-online.org/index.html
■第3回学生のヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集
日本地質学会ほか 推薦
実習実施時期:2014年3月5日出発,19日帰国(15日間)
申込締切:11月30日
実習コース:カトマンズ−ポカラ−ムクチナート−タンセン−ルンビニ
参加費用:学生・大学院生20万円以内、その他の個人参加者25万円以内、大学・企業などの組織派遣教員/社員30万円以内
http://www.geocities.jp/gondwanainst/
■第6回国際レルゾライト会議 6th International Orogenic Lherzolite Conference
2014年5月4日〜14日
場所:Marrakech, Morocco
オプション巡検:
・Pre-conference
2014年5月4日〜5月7日
場所:Beni Bousera Orogenic Peridotite
・Post-conference 1
2014年5月11日〜5月13日
場所:Middle-Atlas (Volcanics and Mantle Xenoliths)
・Post-conference 2
場所:Anti-Atlas (Pan-African Ophiolites)
2014年5月11日〜5月14日
http://www.gm.univ-montp2.fr/Lherzolite/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/outline/content0098.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■電力中央研究所:地球工学研究所 変動地形学 研究職員公募(8/30)
■新潟大学:教育研究院自然科学系 環境科学系列教員(准教授)(8/16)
■東京大学大学院:理学系研究科地球惑星科学専攻(准教授)(8/30)
■平成25年度 東北海洋生態系調査研究船(学術研究船)「新青丸」(淡青丸の後継船)の共同利用公募(7/31)
■第54回東レ科学技術賞および東レ科学技術研究助成候補者募集(10/10 学会締切8/30)
■第35回沖縄研究奨励賞推薦候補者募集(9/30 学会締切8/30)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
福島原発事故に伴う福島県の放射性物質汚染
福島原発大事故に伴う福島県の放射性物質汚染
—汚染地域の住民から見た汚染の実態—
千葉茂樹(福島県立小野高校平田校)
1.はじめに
著者は,事故当時「福島市渡利」に居住していた.本稿では,汚染地域「福島市渡利」に居住していた人間の視点から汚染の実態を報告する.著者は今までに汚染の状況を報告してきた(千葉ほか2013など)が,本稿ではそれも含め,新たに「8.森林における放射性物質の濃集—楯状高放射線量土—」も記載する.この内容は,著者が知る限りにおいては報告例がなく初めての報告と思われる.発見の経緯なども含め詳しく記載する.さらに,今回,2011年6〜7月の福島市渡利における地上1cmの実測値(cps)を Bq/cm2(Bq/m2)に換算した.驚嘆する値である.
なお,原発事故直後は放射線計が入手しにくい状態が続き,著者もその入手に苦労した.その後,放射線計を買い足している.本論には多数の放射線計が登場し理解しにくい点がある.原発事故直後の混乱を考慮しご容赦いただきたい.なお,測定器毎の換算はそれぞれの項目で説明しているが,本項目「はじめに」の最後に,これらをまとめ「単位」「測定機器」「換算式」として掲示した.
また,隣接県の仙台周辺の汚染状況については石渡明氏のHP(http://www.cneas.tohoku.ac.jp/labs/geo/ishiwata/RadiationSendai.htm)が詳しいので,本稿とあわせてご覧いただきたい.
福島第一原子力発電所は,2011年3月11日の東北太平洋沖地震の直接間接の影響により,制御不能になった.1〜3号炉は炉心溶融を,4号炉は火災を,起こした.更に1・3・4号炉では,建屋が水素爆発で吹き飛んだ.これら一連の事故により,放射性物質が大量にかつ広範囲に飛散した.福島県の汚染は, 3月15日が特に著しい.この日,放射性物質を含んだプルームは,南東風に載り浪江町津島や飯舘村などを,更に北風に載り中通りの福島市・二本松市・本宮市・郡山市などを,濃厚に汚染した(第1図).
第1図 福島原発事故の放射物質の汚染状態 早川(2013)を使用した.※拡大は図をクリック
▶▶白黒版の図を表示
放射線が人体に及ぼす影響(福島原発事故も含めて)に関しては,いろいろな見解がある.また,福島原発事故による放射性物質の汚染に関しても,多種多様な報告がある.原発事故による放射性物質の汚染および発生した疾患で最も重要なのはチェルノブイリ原発事故の報告である.しかしこれもロシア政府報告・ウクライナ政府報告のように見解が大きく分かれている.更に,福島県などの汚染地域では,原発事故の放射性物質の汚染に対して拒絶姿勢をとる方も存在する.しかし,著者は「汚染の実態を詳細に記録することが極めて重要である」と考えている.これは,将来(利害関係者がいなくなった段階で),放射性物質による汚染及びこれに伴う疾患の再検証が必ず行われる.その際に,「汚染の実態を示す基礎データが極めて重要になる」と考えるからである.野外調査を行ってきたフィールドワーカーは,その特性を生かし詳細な汚染地図を作っていく必要があるとも考えている.
なお、本稿の中で「ホットポイント」という言葉を使用している。一般に比較的広範囲の高放射線地域を「ホットスポット」と呼ぶが、著者はこれより狭い範囲(数平方メートル以下)の高放射線点を「ホットポイント」と呼んで区別している.
・単位
cps:
測定器が計測した1秒間当りの放射線量
cpm:
測定器が計測した1分間当りの放射線量
Sv:
等価線量.人体組織に対してどれだけのダメージを与えるか.組織や臓器によって異なる.皮膚組織に対しては,Sv≒Gy(物体が吸収した放射線量).
Bq:
放射性物質が1秒間に放出する放射線の数.
・測定機器
地上1cm(物体表面)の測定--- GM1,LUDLUM3,CoMo170
空間放射線量(1m)の測定---TCS-172B,ИР-001,PM1703M,GammaRAEIIR
・地上1cmの実測値の換算(137Csのγ線に関して)
LUDLUM3+44-9の実測値(cpm)×0.0076⇒GM1の値(cps)
GM1の実測値(cps)×0.456 ⇒Bq/cm2
GM1の実測値(cps)×4560 ⇒Bq/m2
・製造企業公表の換算式(測定値⇒137Csのγ線量μSv/h)
GM1の実測値(cps)÷3 ⇒μSv/h
LUDLUM3+44-9の実測値(cpm)÷2÷330 ⇒μSv/h
(プローブをビニルで覆うとβ線も計測するので,2で割りβ線分を除く.実測でβ線量とγ線量はほぼ同じ)
2.福島市渡利の汚染を体験して
著者は東北太平洋沖地震の発生した2011年3月11日には,福島市渡利字岩崎町に居住していた.翌12日から福島第一原子力発電所の原子炉が不安定になった.著者は,12日奥羽山脈を越して猪苗代町に避難し住宅を確保した.猪苗代町への避難理由は,「放射性物質の多くは空気より数倍重いため高い山を越す量は少ないであろう」という判断であった.避難後は,仕事のため福島市と猪苗代町を行き来していた.7月30日,猪苗代町に完全に転居した.
この間の著者の体験を記載する.福島市の主たる汚染は3月15日の夕方であった.著者は,この時には猪苗代町に避難していた.3月20日,避難先の猪苗代町から福島市に戻った.このとき,目と手に違和感を覚えた.翌21日,左目が腫れ上がり30日まで続いた.この間,目の洗浄を繰り返した.同じ時期,手の指先が針で突くような痛みと痒みを感じた.こちらは,なかなか治らず,5月下旬まで続いた.これらの症状は,20日に福島市に戻り放置していた乗用車を触った後からであった.なお,放射線計入手後の2011年6月にこの乗用車を測定したところサイドウインドー下の植毛部で40cps(GM1,後述)の放射線量を感知した.
更に,事故直後から7月下旬までの状況で,特に気がついたことを書く.①鳥類がいなくなった.②地面を這うように生育する「コモチマンネングサ」の葉の色の変化であった.5月中旬,福島市から南下し小野町まで行った際,葉の色が黄色から緑色に徐々に変化していった.福島市では黄色であったが,田村市船引町や小野町では緑色であった.放射線量は,福島市で高く,南下するに従い低下し田村市船引町に入ると急激に低下している.放射線計の入手前で,放射線量は公的機関発表のデータである.
乗用車の汚染について付け加える.2011年8月,猪苗代町で,浪江町から避難してきた乗用車を測定したところ40cps(GM1)の放射線量であった.このほか,郡山市の自家用車からも放射線が検出された.なお,検出位置は,フロントガラスの下,サイドガラスの下,フロントグリル,タイヤハウスなど車によって様々である.2011年8月,著者は磐越自動車道(猪苗代−小野)をほぼ毎日走行したが,車の後部に溜まったアスファルト粒から微量ながら放射線が検出できた.更に,2013年4月現在,福島県中通りを走行している車では,未だに微量の放射線が検出されることが多い.
3.放射線計
放射線計は,原発事故直後には非常に入手しにくい状況で,しかも高価であった.著者が放射線計を入手できたのは2011年6月で,しかも空間放射線量を測定する器械ではなく,放射線源を測定する「RPI Instruments製Rad-Monitor GM1(137Csのγ線で校正)」であった(以下,GM1).これを使い,福島市を中心に地上1cmの放射線量を測定した.
その後は,多種多様の放射線計を試用し、測定に適するものを選別した.主に使用した機種は,以下の通りである.空間線量計として「НЕЙВА製ИР-001」「日立アロカ製TCS-172B」「POLIMASTER製PM1703M」「RAE Systems製GammaRAEIIR」,地上1cmの測定用として「RPI Instruments製Rad-Monitor GM1」「LUDLUM製3型+44-9プローブ」である.
さらに,2013年6月下旬,SEA製CoMo170を入手し,地表1cmの放射線量(Bq・Bq/cm2)の測定を始めた.
4.放射線量計の比較・換算
空間放射線量の測定は,2011年8月からウクライナ製「НЕЙВА製ИР-001」を使用した.さらに,2012年4月からは「日立アロカ製TCS-172B」を使用した.更に常時携帯用として「POLIMASTER製PM1703M」「RAE Systems製GammaRAEIIR」も使用している.
このうち,主力として使用した「TCS-172B」と「ИР-001」を実測・比較した.「ИР-001」は,1μSv/hでは「TCS-172B」とほぼ同じ値,0.1μSv/h付近では「TCS-172B」の1.25倍,4μSv/hでは「TCS-172B」の0.75倍程度の値を表示した.
「TCS-172B」と「GammaRAEIIR」「PM1703M」の比較では,「GammaRAEIIR」は「TCS-172B」とほぼ同じ値を表示したが,「PM1703M」は「TCS-172B」の約20%低い値を表示した.
なお,「TCS-172B」「GammaRAEIIR」「PM1703M」の各機種について,2〜3台で比較したが,それぞれ10%程度の個体差があった.
地上1cmの放射線量の測定には,2機種を用いた.2011年6月から測定に使用したのは,「Rad-Monitor GM1」(以下GM1)で,2011年10月からは「LUDLUM製3型+44-9プローブ」(以下LUDLUM 3+44-9)も使用した.2012年6月30日,飯舘村「ニュートラックいいたて」において,上記2機種を使い「黒い高放射線土」(後述)を実測し比較した。実測値の代表的な値は、「LUDLUM3+44-9」50000cpm,「Rad-Monitor GM1」380cpsであった。実測値から換算値を求めると、「LUDLUM3+44-9の実測値(cpm)×0.0076⇒GM1の換算値(cps)」になる.
5.福島市渡利の放射線量(2011.6〜7)
2011年6月中旬,「RPI Instruments製Rad-Monitor GM1(137Csのγ線で校正)」を入手した.器械の特性を知るべく試の測定を2日間実施した後,地上約1cmの放射線量の測定を開始した.調査目的を「短期間に,測定地点を多く」とし,プローブにビニルのみをかけて測定した.第1図は福島市渡利の2011年6月29日から7月24日の測定結果である(第2図).放射線量が125〜500cpsの地点が多く,500cps以上の地点が点在した.最高は渡利字八幡町の1300cpsであった.この近くには渡利小学校がある.また,これらの調査で,空間放射線量(地上1m,この時はGM1で測定)が高いところでは,地表に高放射線土が存在する場合が多かった(後述).さらに,著者の自宅の庭(土やコンクリート塀の表面)は約40cpsで,最大で130cpsのところもあった.
第2図 福島市渡利の地表の放射線量分布図 測定はRad-Monitor GM1.国土地理院の1/2.5万 地形図を使用した. ※拡大は図をクリック
▶▶白黒版の図を表示
著者はこれらの実測した放射線量分布地図を講演等で話してきた.その中で,測定値の単位(cps)では「どのくらいの放射線量なのかわからない」との意見が多かった.このため測定値(cps)をBq/cm2への換算することを試みた.2013年5月,飯舘村「ニュートラックいいたて」において「黒い高放射線土」を実測し比較した。すなわちプローブの覆いを(なし,ビニル,アルミ箔)の3種の状態でそれぞれ測定し,その値を比較した.その結果は3種ともほとんど同じ値であった.従って,測定に用いたGM1は「γ線のみを感知している」と見てよい.次に,トロント大学の換算式(ネット公開)で,測定値(cps)からBq/cm2への換算を行った.それによれば,「測定値(cps)×0.456⇒Bq/cm2〔測定値(cps)×4560⇒Bq/m2〕」となる.なお,この値はバックグラウンドがゼロに近い場合であり,渡利の場合はバックグラウンドがかなり高いので誤差が相当量含まれる.
2013年6月末,SEA製CoMo170を購入した.高放射線土の表面をRad-Monitor GM1とCoMo170で実測し,測定値(GM1=cps,CoMo170=Bq/cm2)の比較を行った.7月7日,飯舘村の「ニュートラックいいたて」の駐車場における計測では,GM1(280cps),CoMo170(140Bq/cm2)であった.7月10日,平田村西山の旧西山小学校のテラスにおける計測では,GM1(15cps),CoMo170(7.34Bq/cm2)であった.計測数は少ないが,「GM1の測定値(cps)×0.5≒CoMo170の測定値(Bq/cm2)」となる.この値はトロント大学の換算式「GM1の測定値(cps)×0.456⇒Bq/cm2」とほぼ同じである.
トロント大学の式を用い換算し考察する.福島市渡利における2011年6〜7月の地表1cmの放射線量はすさまじい値となる.まず,著者宅の庭は18 Bq/cm2(18万Bq/m2),最大で59 Bq/cm2(59万Bq/m2)となる.さらに,福島市渡利には57〜228 Bq/cm2(57万〜228万Bq/m2)の高い放射線を出す地面が至る処にあった.最高値の渡利字八幡町では593 Bq/cm2(593万Bq/m2)であった.放射線管理区域が4万Bq/m2以上であることを考えると,汚染が如何に深刻であるかがよくわかる.
第3図 平田村の地上1mの放射線量分布図 測定はHEЙBA ИP-001。国土地理院の1/2.5万 地形図を使用した。 ※拡大は図をクリック
▶▶白黒版の図を表示
6.平田村の空間放射線量(2011.8)
平田村は阿武隈山地中央部にあり,福島第一原子力発電所から、南西約40kmに位置する.2011年8月中旬、平田村の中心部の調査を行った(第3図).放射線計は「HEЙBA ИP-001」で地上1mの空間線量を測定した。測定結果は,平坦部(標高約500m)では0.15〜0.30μSv/hであった.また、蓬田岳(標高952m)では、標高が高くなるにつれて放射線量も増加し、山頂部では2.5μSv/hであった.全体の傾向として,平坦部では放射線量は低いが,山岳部では放射線量が高かった.
1年後の2012年8月にも日立アロカ製TCS-172Bで地上1mの放射線量を測定した.その結果,平坦部の平田村上蓬田では約0.15μSv/hで,1年前より低下していた.ただし,局部的な上昇も見られ,最高値は0.55μSv/hであった.蓬田岳頂部(山頂より標高で約5m低い)では,3.16μSv/h(PM1703M)とやや上昇していた.
7.本宮市の空間放射線量(2012.8)
著者はそれまでの実地調査から,空間線量が「狭い地域においても局地的に高低がある」ことに気がついた.このことから,高汚染地域において,高密度に測定し,局地的な放射線量の変化を明らかにする必要性を感じた.このため,2012年8月,高い汚染地域の本宮市の中心部において,高密度な調査を行った.調査密度は10m×10mに1地点程度である.測定は,放射線計「日立アロカ製TCS-172B」・高さ「地表1 m」・時定数「30秒」で行った.第4図はその結果である.空間放射線量は,傾向として南西方面で低く(0.3μSv/h〜0.7μSv/h)北東方向で高い(0.3μSv/h〜1.9μSv/h).地形的には,北西部が丘陵地で高く,北東部は阿武隈川沿いで低い.また,所々に1.7〜3.5μSv/hの高放射線量地点(ホットポイント)が点在した.
第4図 本宮市中心部の地上1mの放射線量分布図 ゼンリンのインターネット地図を使用した.国土地理院の承認 平13東使 第8号. ※拡大は図をクリック
▶▶白黒版の図を表示
この結果から,放射性物質は,全体として地形的に高い所から低い所に移動しているように読み取れる.また、局地的な移動・集積も読み取れる.これらの主要因は,放射性物質が雨水で移動したためと推定される.
8.高い放射線を発する土
著者は2011年6月から福島県内の放射線量の測定を行ってきた。その中で、高い放射線を発する地表に共通の特徴があることに気が付いた。その特徴とは、高放射線土は「色が黒い」「表面に亀甲状の亀裂がある」ことであった.
第5図は,2012年4月30日,飯舘村の「ニュートラックいいたて」にあった高放射線土である.アスファルト面上の真っ黒いものが高放射線土である.空間線量(1m)は3.24μSv/h(ИР-001),地上1cmの放射線量は80000cpm(LUDLUM3+44-9,β線+γ線,137Csのγ線に換算すると121μSv/h)であった.この高放射線土を京都大学原子炉実験所の小出裕章氏に測定していただいた.小出氏のご厚意により掲載させていただく.134Cs;430万Bq/kg,137Cs;1000万Bq/kgとすさまじい値である(2012.04.30千葉茂樹採集,2013.07.10小出裕章氏測定).2013年7月10日時点で,小出氏が計測した福島原発事故の高放射線土の中では最高値とのことである.また,同じ場所の高放射線土を,1年後の2013年4月29日に採集し,測定した.134Cs;200万Bq/kg,137Cs;500万Bq/kgである(2013.04.29千葉茂樹採集,2013.07.10小出裕章氏測定).測定日は同じであるが,約1年野外に存在した高放射線土は,室内保管の高放射線土の約半分の放射性物質濃度である.
2013年7月7日, SEA製CoMo170で高放射線土表面の放射線量を測定すると216Bq/cm2(216万Bq/m2)であった.なお,空間放射線量(1m)は4.46μSv/h,地上1cmの放射線量は30μSv/hオーバーであった(TCS-172B).
このほか,高放射線土は,福島市・郡山市など空間放射線量(1m)の高いところでは至る所に存在した.更に,空間放射線量(1m)の比較的低い猪苗代町・平田村にも見られた.更に遠方の山形市や一関市にも存在した.
第5図 高放射線の土—飯舘村「ニュートラックいいたて」— ※拡大は図をクリック
▶▶白黒版の図を表示
9.高放射線土の移動
第6図は,福島市渡利字岩崎町における高放射線土の移動を示したものである.左端は2011年7月4日の状態である.高放射線土は黒色で表面に亀甲状の模様が確認できる.地上1cm の放射線量は500cps(GM1)であった.約1ヵ月半後の2011年8月18日には,放射線土はなくなり,代わりに粗粒の真砂があった.地上1cm の放射線量は40cps(GM1)であった.その後,2012年4月21日には,再度,黒色・亀甲模様の高放射線土が出現した.地上1cmの放射線量線量は1520cpm(LUDLUM3+44-9)であった.GM1の値に換算すると92cpsになる.
最初の測定の2011年7月4日と次の測定の8月18日の間に,大雨洪水警報が発令された豪雨が数度あった.このことから,高放射線土は雨水および地表水により移動していると考えるのが妥当であろう.
第6図 高放射線土の移動—福島市渡利字岩崎町— ※拡大は図をクリック
▶▶白黒版の図を表示
10.森林における放射性物質の濃集—楯状高放射線量土—
著者は,原発事故汚染地域において,アスファルト上やコンクリート上などに集積した黒い土が,高い放射線を発することを報告した(千葉ほか2013).この黒い土に関しては,京都大学の小出裕章氏が放射線量をいち早く測定し,さらに神戸大学の山内知也氏が黒い土には放射性セシウムを体内に取り込んだ藍藻類の遺骸が大量に存在することを,ネット上に公開した.更に,斎藤(2012)では,各執筆者が放射性物質の挙動について多方面から解説している.たとえば,田崎和江氏はバクテリアが放射性物質を体内に吸着し鉱物化することを記載している.浅見(2013)も土壌中の放射性物質の挙動について,詳しく解説している.
第7図 森林に存在する高い放射線の土—福島県高柴山— ※拡大は図をクリック
▶▶白黒版の図を表示
「森林における放射線物質の挙動」に関しては,古くは川瀬ほか(1971),最近では斎藤(2012),浅見(2013)に記載されている.しかし,「著者が今回発見した森林内の高い放射線を発する土」に関しての記載はない.
著者は,2013年5月16日,福島県の高柴山の森林において高い放射線を発する土を発見した(第7図).高柴山は阿武隈山地にあり,標高884mで花崗閃緑岩からなる.この一帯の空間放射線量(地上1m)は0.16〜0.36μSv/hである(2013.05.18 著者測定,日立アロカ製TCS-172B).以下,発見の経緯について記す.牧野口(北東側登山口)からの登山中,空間放射線量(地上1m)が所々で急に高くなった.このため,下山の際,登山時に気が付いた高い空間放射線量の地点付近を注意深く探索した.その結果,高い空間放射線量の地点付近では,広葉樹の根元に高い放射線を出す土があることを発見した.
5月18日に再調査を行い,高い放射線を出す土(領域)を4箇所確認した.23日には更に1箇所を確認した.これらはすべて登山道の切割りの急斜面(60〜80度)にあり,更に広葉樹の根元から下方向へ,楕円状の広がりをもって分布していた(以下,楯状高放射線量土とする).代表的なひとつ(整理番号3)について記載する(第7図).楯状高放射線量土の位置的に最も高い部分は,登山道底面から高さ約100cmにある.分布は,位置的に最も高い部分を起点として,下方へ斜面なりに楕円状に広がる.面積は,水平方向約35cm×天地方向約60cmである.表面全体の形状は楯状(鏡餅状)で,周辺より最大で約10cm盛り上がっている.更に,表面の状態は,黒色で鈍い光沢があり,大きさが3〜10cm程度の亀甲状の模様がある.この鈍い光沢は数m離れても識別できる.表面は,光沢の存在から平滑のように思えるが,接近するとスレッドレーススコリアのような凹凸および空隙が見られる.更に園芸用の小スコップで表面に穴を開けると,表面約1〜2mmは硬く,内部は空隙の多いやわらかい土である.イメージは,固焼きシュークリームの皮のようである.周辺の土は畑の土程度の固さであり,楯状高放射線量土は周辺の土よりはるかに固い.ここでの空間放射線量(地上1m)は0.50μSv/h,楯状高放射線量の表面(約1cm上)の放射線量は最大で8.07μSv/hである(TCS-172B).小出裕章氏の測定では,134Cs;13万Bq/kg,137Cs;32万Bq/kgである(2013.05.18千葉茂樹採集,2013.07.10小出裕章氏測定).
なお,高柴山に存在する楯状高放射線量土5箇所における表面(約1cm上)の放射線量の最大値は11.63μSv/h (TCS-172B)である(整理番号5〕.小出裕章氏の測定では,134Cs;40万Bq/kg,137Cs;100万Bq/kgである(2013.05.18千葉茂樹採集,2013.07.10小出裕章氏測定).
上記の楯状高放射線量土が如何なる理由で高放射線を出すのか,著者は調べるすべを持たない.しかし,①放射線物質が雨滴により樹幹を通って流れ下りこの部分に集積した,②微生物によって放射性物質が濃集した,①と②の複合,のどれかと考えている.
11.まとめ
福島県の中通り・浜通り地域は,2011年3月11日の震災に伴い発生した福島第一原発事故のため放射性物質で著しく汚染された.
著者は,事故当時,福島市渡利に居住していた.2011年6月,放射線計を入手し,汚染地域の放射線量(地上1cm)を調査した.その結果,福島市渡利では125〜500cps(57万〜228万Bq/m2)の高放射線土が至る所にあり,最大は,八幡町の1300cps(593万Bq/m2)であった.また,阿武隈山系の平田村の汚染は,低地では少なく里山では著しかった.更に,2012年8月の本宮市では,放射線量の分布に濃淡が見られた.この原因は,放射性物質の雨水での移動が考えられる.
また,空間放射線量の高い地域(飯舘村・福島市・郡山市など)では,地表には高い放射線を出す亀甲模様の黒い土(高放射線土)が多数存在していた.高放射線土は,比較的放射線量の低い地域の猪苗代町や平田村,山形市や一関市などにも存在した.また,福島市渡利では,高放射線土が雨水で移動していることを確認した.
更に,福島県高柴山の森林において,高い放射線を発する土(楯状高放射線量土,表面の放射線量11.63μSv/h)を発見した.
【文献】
浅見輝男(2013):環境土壌学者が見る福島原発事故−データで読み解く土壌.食品の放射性核種汚染.アグネ技術センター.299p.
千葉茂樹(2011、2012、2013):福島原発事故の汚染.そくほう.670.677.678.679.681.683.685.地学団体研究会.
千葉茂樹・諏訪兼位・鈴木和博(2013):福島県の放射性汚染土壌−とくに黒い物質−の野外の産状について.名古屋大学加速度器質量分析計業績報告書.鶸.78−96.
早川由紀夫(2013)福島原発事故の放射能汚染地図.早川由紀夫の火山ブログ.http://kipuka.blog70.fc2.com/
川瀬金次郎・小林宇五郎・小山誠太郎・滝澤行雄(1971):環境と放射能 汚染の実態と問題点.東海大学出版.420p.
齋藤勝裕(2012):東日本大震災後の放射性物質汚染対策−放射線の基礎から環境影響評価,除染技術とその取り組み−.エヌ・ティ・エヌ.324p.
(2013.7.15)
▶▶ English Abstract(英文要旨)
geo-Flash No.225(臨時)巡検締め切りまであと2週間!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.225 2013/7/26 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[仙台大会]巡検締め切りまであと2週間
【2】[仙台大会]同窓会を開催しませんか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[仙台大会]巡検締め切りまであと2週間
──────────────────────────────────
巡検の締め切り(オンライン:8月9日,FAX・郵送:8月7日)まであと2週間となりました.津波巡検は好評につき,当初の定員より大幅増員を行いました.他の巡検につきましても,まだ定員まで十分に余裕がありますので,皆様,ふるってご参加いただきますようお願い申し上げます.現在の巡検の申し込み状況(7月23日10時45分現在)は以下の通りです.
左から,
申込件数/(定員〔最少催行人数〕),班名:備考
43/(30〔20〕),A班:津波(9/13コース)→ 定員45名 に変更
10/(20〔15〕),B班:岩手・宮城内陸地震-断層
38/(40〔15〕),C班:地学教育・アウトリーチ
12/(25〔20〕),D班:南部北上の古−中生界
05/(20〔15〕),E班:南部北上帯の中生界
10/(20〔20〕),F班:岩手県白亜系
14/(20〔15〕),G班:仙台新第三系
12/(15〔13〕),H班:蔵王
20/(22〔20〕),I班:北上山地古生代初期オフィオライト
11/(20〔15〕),J班:阿武隈東縁の花崗岩
03/(20〔15〕),K班:北鹿黒鉱
32/(20〔15〕),L班:津波(9/17コース)→ 定員45名 に変更
巡検申込締切:8月9日(金)17時(郵送 8月7日(水) 必着)
巡検の見どころ紹介→ http://www.geosociety.jp/sendai/content0016.html
仙台大会HPはこちら
http://www.geosociety.jp/sendai/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[仙台大会]同窓会を開催しませんか?
──────────────────────────────────
懇親会に引き続き(20:00〜21:00),旧友・卒業生・恩師との親睦を図るため,各大学の同窓会ごとのブースを設ける予定です.
持ち込み可能です.ふるってご参加下さい.
申込締切:8月20日(金)
詳しくは,こちらから
http://www.geosociety.jp/sendai/content0034.html#dosokai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flash No.226(臨時)垣見俊弘名誉会員 訃報
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.226 2013/7/29 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 垣見俊弘 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
日本地質学元副会長 垣見俊弘 名誉会員(元地質調査所所長)が,平成25年7月1日(月)にご逝去されました(享年84歳)。
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げ ます。
通夜・ご葬儀は,近親者によりしめやかに執り行なわれ,ご遺族のご意向により弔問等はご遠慮願いたいとのことです。
会長 石渡 明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
geo-Flash No.227 巡検申込みお忘れなく【8/9締切】
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.227 2013/8/6 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[仙台大会]事前参加登録受付中!
【2】[仙台大会]同窓会ブース募集中
【3】[仙台大会]緊急展示の申込について
【4】津波堆積物ワークショップ 申込受付中!
【5】コラム:福島原発大事故に伴う福島県の放射性物質汚染
—汚染地域の住民から見た汚染の実態—
【6】 本の紹介:明治時代の地学普及書を読む:「日本風景論」と「地人論」
【7】名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞情報
【10】地質マンガ:ハンマーの行方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[仙台大会]事前参加登録受付中!
──────────────────────────────────
全体日程表はこちらから↓
http://www.geosociety.jp/sendai/content0007.html
○巡検:申込締切まであとわずか!
※締切前でも定員に達した場合は、早めに受付を終了する場合があります。
(A・C・F・H・I・L班は受付終了)
締切:8月9日(金)17時(郵送 8月7日(水) 必着)
申込状況→http://www.geosociety.jp/sendai/content0047.html
見どころ紹介→http://www.geosociety.jp/sendai/content0016.html
○参加登録
講演申込をされた方も,別途事前参加登録を行って下さい。
(当日参加登録の場合は申込費用が異なります。)
締切:8月20日(火)17時(郵送 8月20日(金) 必着)
○若手会員のための業界研究サポート:出展募集
締切:8月9日(金)
http://www.geosociety.jp/sendai/content0041.html
○企業展示出展募集、ブース利用募集、広告協賛
締切:8月9日(金)18時
○託児室利用申込
締切:8月23日(金)
仙台大会HPはこちら
http://www.geosociety.jp/sendai/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[仙台大会]同窓会ブース募集中
──────────────────────────────────
申込締切 8月20日(火)
懇親会に引き続き(20:00〜21:00),旧友・卒業生・恩師との親睦を図るため,各大学の同窓会ごとのブースを設ける予定です.ブースを希望される各大学同窓会関係者の方は,8月20日(火)までにご連絡下さい.持ち込み可能です.ふるってご参加下さい.
詳しくは,こちらから
http://www.geosociety.jp/sendai/content0034.html#dosokai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[仙台大会]緊急展示の申込について
──────────────────────────────────
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害調査報告や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コーナー」を設けます.ポスター展示を希望する方は,8月30日(金)までに次の内容を下記申込先にご連絡ください.
1)発表要旨PDF(ニュース誌5月号参照) 2)緊急展示の必要性 3)発表代表者と連絡先 4)希望枚数(1枚:幅90×180cm) 5)展示に関わる要望(2〜5の様式は自由)
実行委員会は行事委員会と協議し,可否の判断を致します.希望にはできるだけ応えるようにしますが,展示方法等については実行委員会の指示に従ってください.
申込先:main@geosociety.jp
担当:鈴木紀毅(仙台大会実行委員会)・須藤 宏(行事委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】津波堆積物ワークショップ 申込受付中!
──────────────────────────────────
9月開催の津波堆積物ワークショップの詳細が決定いたしました。
お申込はお早めに!
◆第4回津波堆積物ワークショップ
テーマ:「震災前・震災直後—何がわかっていたのか−」
2013年9月14日(土)9:00〜12:00
◆第5回津波堆積物ワークショップ
テーマ「震災から2年半,津波堆積物研究と社会」
2013年9月18日(水)10:00〜16:15
申込締切:8月30日(金)17:00
http://www.geosociety.jp/science/content0057.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】コラム:福島原発大事故に伴う福島県の放射性物質汚染—汚染地域の住民から見た汚染の実態—
──────────────────────────────────
千葉茂樹(福島県立小野高校平田校)
著者は,事故当時「福島市渡利」に居住していた.本稿では,汚染地域「福島市渡利」に居住していた人間の視点から汚染の実態を報告する.著者は今までに汚染の状況を報告してきた(千葉ほか2013など)が,本稿ではそれも含め,新たに「8.森林における放射性物質の濃集—楯状高放射線量土—」も記載する.この内容は,著者が知る限りにおいては報告例がなく初めての報告と思われる.発見の経緯なども含め詳しく記載する.
続きはこちらから.
http://www.geosociety.jp/faq/content0463.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】本の紹介:明治時代の地学普及書を読む:「日本風景論」と「地人論」
──────────────────────────────────
志賀重昴著、近藤信行校訂「日本風景論」
岩波文庫青112-1、1995年, 395ページ、770円
ISBN4-00-331121-3 C0125.
内村鑑三著「地人論」
岩波文庫33-119-0, 2011年第3刷、216ページ、660円
ISBN4-00-331190-6 C0125
日本地質学会の創立は1893年であるが、地質学雑誌の第1巻は翌1894年に出版された。この年に志賀重昂(しげたか)の「日本風景論」が出版され、1902年までに14版を重ねるベストセラーになった。また同じ年に内村鑑三の「地理学考」が出版され、1897年に「地人論」と改題された。ここでは、明治の颯爽(さっそう)たる骨太の気風に満ちたこれらの地理・地学普及書を紹介し、昨今の豪雨と炎暑に苦しむ会員諸氏への清涼剤としたい。
「日本風景論」の主題はその冒頭に提示されている「江山洵美是吾郷」(大槻磐渓の原詩は「江山信美是吾州」)であり、日本の風景が諸外国に比べ優れていることを地理学、地質学、気象学、生物学的な根拠を援用しながら力説したものである。日本の風景の優れた点を「瀟洒(しょうしゃ、清楚の意)」、「美(華美)」、「跌宕(てっとう、跌蕩とも、雄大の意)」に大別し、それぞれの例として「鈴虫声は咽(むせ)ぶ萩花の路、風は清し宮城野(みやぎの)外の秋」(瀟洒)、「桃山の落花、乱点して紅雨の如く、地に布(し)きて錦繍(きんしゅう)に似る」(美)、「天長(とこしえ)に繊雲なく、富士の高峰、武蔵野の地平線上に突兀(とっこつ)す」(跌宕)などを挙げている。「日本には気候、海流の多変多様なる事」、「日本には水蒸気の多量なる事」、「日本には火山岩の多々なる事」、「日本には流水の侵食激烈なる事」の各章に分けて日本の地形の特徴を論じ、付録として「登山の気風を興作すべし」の章を設け登山について具体的に解説している。文庫初版の解説で小島烏水は「志賀氏は日本山岳のためには恩人である、山岳会のために、間接の創設者である」と述べている。1893年6月の福島県吾妻山噴火の調査中に殉職した理学士(地学専攻)三浦宋次郎・西山惣吉の追悼文を、科学調査目的の登山の本邦初の犠牲者として、三浦が撮影した噴煙の写真とともに載せていることは特筆される。面白いのは、登山に持参する米は1日1人6合という記述で、これはちょっと多すぎるのではないかと思う。私が若い頃の地質調査では4合で足りた。宮澤賢治の「雨ニモマケズ」にも「一日ニ玄米四合」とある。
文庫本には、六合雑誌(168号、1894年)に載った内村鑑三による本書の批評が掲載されている。内村はこの3年前の1891年、高等中学の教員だった時、教育勅語奉読式で明治天皇の親筆署名に対して最敬礼しなかった(ただし敬礼は行った)ことが社会問題になり、翌年辞職した。彼は「再び不敬人の賊名を蒙(こうむ)らんことを懼(おそ)る」と言いながら、「日本は美なり、園芸的に美なり、公園的に美なり、然れど吾人をして他州に譲る所あらしめよ」、「人を高むるの美、即ち自己以上に昇らしむるの美は、吾人はこれを万国に求めざるべからず」、「愛国心上騰の今日に方(あたっ)て、この非国家的の言を発す、批評家の任また難(かた)きかな」と、国外には日本以上の風景の美があることを強調している。なお、内村と志賀は札幌農学校の先輩と後輩の関係にある(卒業は3年違い)。
一方、地学雑誌第6巻(71号649-651頁, 1894)には崝南(巨智部忠承)の批評が掲載され、「其の所見の浩瀚にして編中述ぶるところ、胸宇に儲蔵する万象を羅列し、其の塩梅の巧妙、読んで倦むことを知らざらしむるに至りては、詞壇雄将の令名虚しからずと信ず」と最大限の賛辞を述べているが、そのあとで裾野、深谷、流岩(溶岩)、地層の断面などの地学的景観の記述が不足していることを指摘している。
地質学雑誌第2巻(17号190-193頁, 1895)には小川琢治の「日本風景論を評す」が掲載されている。その冒頭は「渤海の風浪腥(なまぐさ)を帯び、満州の氷雪紅(くれない)を印したる秋なれば、文章に、画図に、渾(すべ)て殺伐の気を夾めるに」という不吉な文言で始まるが、これはこの年日清戦争で多くの犠牲者が出たことを指し、その中にあって日本風景論は「独り超然として」、「別天地の観を具え」、「万緑草中紅一点なるもの」と述べ、「此書の着想の奇、行文の快、実に日本の山水其物と相並て奇絶快絶なり」と絶賛している。しかしそのすぐ後で、「先生はその過半の力を日本の火山に尽くされ」たが「火山の外形とその内部の構造及び変遷の歴史」についての記述がないこと、水成岩(堆積岩)やその地質構造がつくり出す地形があまり扱われていないことを述べ、上記の崝南の批評に同意して「一種の進化せる名所図会として更に進歩を促すことなくして畢(おわ)らんも」などとかなり手厳しいことを言っている。小川は、「我が日本少年が異日地球上至る所に実業上学問上の遠征を試むるの第一の着歩として、先ず国内の山川、江海を跋渉して、事物を精細に観察するの良習慣を養成する」ことが大切だと述べ、科学的視点が薄弱な本書を批判している(確かに、地理書なのに地図が1つもない)。しかし、この小川の批評文はその後の「日本風景論」の巻頭に序文がわりに印刷されたそうで(文庫本にはない)、これは「志賀重昴の虚心な人柄」(近藤信行, 1995; 文庫本解説)を示すとされる。
本書については、剽窃(無断引用)が多いという指摘が最近まで続くが(例えば米地文夫、1999; 総合政策, 1(4), 477-488、2004; 同誌, 5(2), 349-367など)、近藤は「借用文献をいちいち明記しなかったのは、重昴のおおざっぱな性格によるのかもしれない」、「(本書は)当時の地理学を基礎とした一般読者むけの百科事典のような書物である。地理学者(小川)や思想家(内村)から不満と批判があったとしても、日本の風景にたいし集約をしめした点では画期的であった。それを外国文献の剽窃とよんで、あたかも鬼の首をとったかのような言説を吐くのは、明治の啓蒙時代にたいする認識がないからである」と述べている。
一方、「地人論」は、日本人を「世界の民」にすることを目的に、政治、経済、歴史、文学の基礎としての地理学の重要性を解き、「地名の暗誦、山川方向の暗記は記憶力発達のためにあらずしてその内に至大なる功用と深遠なる真理の存すればなり、真理を恋い慕う誠意を以てすれば地理学は一種の愛歌なり、山水を以て画かれたる哲学なり、造物主の手に成れる預言書なり」というキリスト教的な目的論の観点から書かれている。まず世界の国を山国(スイスなど)、平原国(ロシアなど)、海国(イギリスなど)に分け、その長短得失を述べた後、大陸配列の「摂理」(神の意思)を説く。それは北極を中心に、3つの方向に大陸が並ぶというもので、(1)南北アメリカ、(2)欧州・アフリカ、(3)アジア・オーストラリアであり、それぞれ北の国が南の大陸を開拓するようにデザイン(意匠)されているという。次いでアジア論(中央アジアの高地で最初の文明が生まれた)、欧州論、アメリカ論(この順に文明が伝わった)があり、東洋論(インド・中国)、日本の地理とその天職に話が及ぶ。日本の天職とは、「パミール高原の東西に於て正反対の方向に向ひ分離流出せし両文明は、太平洋中に於て相会し、二者の配合に因りて胚胎せし新文明は、我(日本)より出でて再び東西両洋に普(あまね)からんとす」ということで、「さし出る此(この)日の本のひかりよりこま(高麗)もろこし(唐)も春をしるらむ」という本居宣長の歌を引用している(原著では平賀源内になっているらしい)。東西方向の山脈は文明の障壁になるが、南北方向の山脈は障壁にならないなど、掲載された多数の地図を示しながら面白い考察を行っている。そして最後に南半球の三大陸について触れ、「豪(オーストラリア)は亜(アジア)、特に東亜の付属国たるの位置に居るが如し、然れども歴史は全く地理学上の指示に反し、今や南洋の全体は欧人の版図として存す」と嘆き、本書の最後を「沈思、万国図に対する時、吾人をして神命の重きを感ぜしめよ」という言葉で結んでいる。
本書については、ギョー(A.H. Guyot、平頂海山にその名が残る)の1849年の「地人論」(講演録)を祖述しただけという評価もあったが、辻田右左男(1977, 奈良大紀要6)は両書を読み比べ、「名前は同じでも内容的にはかなり異質的である」、「日本人の心を世界につなぎ、日本に生まれた世界の市民を作ることが彼(内村)の目標であった」と述べている。
両書はいずれも和漢洋の詩歌や先哲の高説を多数引用しながら論を進めており、現今の無味乾燥な、文学的教養と縁のない地学関係の普及書を読み慣れた者からすると、このような本をベストセラーとした当時の読者の教養の高さに驚かされる。また「地人論」は、非常に強引な論調ではあるが、全体の論理構成の美しさと一貫性が際立っている。論文というのはこうやって書くのだ、という1つの見本だと思う。それに対して「日本風景論」は行き当たりばったりの書き方で話があちこちへ飛び、やたら羅列が多い。しかし、一般の日本人にはこのような書物の方が親しみやすく、広く受け入れられたのであろう。もうすぐ読書の秋である。地質学会発足当時に出版されたこれらの対照的な地理・地学普及書を読み比べて、その後120年間の我が学界の来し方・行く末に思いを巡らすのは如何だろうか。少なくとも日本地質学会の創立が当時の社会状況と無縁でなかったことは、両書を読めば実感できるだろう。地質学会では5年後に125周年記念事業を予定しており、この清涼剤がその着火剤になれば幸いである。
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
──────────────────────────────────
日本地質学会では,学会員相互の交流と親睦を図る目的で,2年ごとに会員名簿を発行することを運営規則にうたっております.2013年はその発行年にあたり,本年11月末日発行の予定で準備を行っております.
名簿の発行様式は前回と同様で,全会員を収録します.本会としては,個人情報保護法の制約はあるとしても,会員の皆様が上記の目的に沿って利用できるような,従来規模の名簿を作成したいと考えておりますので,調査の実施にご理解とご協力をお願いいたします.
アンケート提出およびWeb画面更新締切日:2013年10月4日(金)
詳しくは,コチラ↓
http://www.geosociety.jp/outline/content0132.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地質研究所ニュース 第32号
http://www.gsh.hro.or.jp/publication/gshnews/news_pdf/vol29_no2.pdf
■日本学術会議の提言「東日本大震災に係る学術調査—課題と今後について—」
http://www.geosociety.jp/engineer/content0032.html
■地球にわくわく小・中学生自由研究コンテスト
募集締切:10月31日
応募資格・部門:小学生2部門(3・4年生、5・6)年生、中学生1部門
問い合わせ先:wakuwaku@jeso.jp
地学オリンピック日本委員会HP http://jeso.jp/
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//olympic/2013waku.jpg
■第11回高校生科学技術チャレンジ研究作品募集
募集期間:9月2日(月)〜10月7日(月)
応募資格:国内の高校生・高等専門学校生(3年生まで)、個人またはチーム
http://www.asahi.com/jsec/
■電気新聞論説フォーラム「原子力規制の合理的プロセスと行政責任を考える」
8月19日(月)13:00〜17:00
会場:イイノカンファレンスセンター(千代田区内幸町2-1-1飯野ビル4F)
申込締切:8/14(定員250人)
http://www.shimbun.denki.or.jp
■第57回粘土科学討論会
日本地質学会 共催
9月4日(水)〜6日(金)
会場:高知市文化プラザかるぽーと
http://www.cssj2.org/
■第4回・第5回津波堆積物ワークショップ
(120年学術大会:同時開催行事)
日本地質学会・日本堆積学会 共催
第4回:9月14日(土)9:00-12:00
第5回:9月18日(水)10:00-16:15
場所:東北大学川内北キャンパス マルチメディア棟M206号室
http://www.geosociety.jp/science/content0057.html
■2013年度日本地球化学会年会
日本地質学会 共催
9月11日(水)〜13日(金)
会場:筑波大学第一エリア1D棟、1E棟
事前参加登録締切:8/23(金)
http://www.wdc-jp.biz/geochem/2013/
■第2回G-EVER国際シンポジウム,第1回IUGS・日本学術会議国際ワークショップ〜アジア太平洋地域の災害とリスクマネジメント: 沈み込み帯の地震・津波・火山噴火・地すべり
日本地質学会 共催
10月19日(土)〜20日(日)[21日巡検あり]
場所:仙台市情報・産業プラザ
講演要旨投稿締切:8/20 参加登録:9/15(登録料無料,先着70名)
http://g-ever.org/en/symposium/symposium2.html
■東海地震防災セミナー2013
11月7日(木)13:30−16:00
会場:静岡商工会議所静岡事務所5階ホール(JR静岡駅北口西側)
連絡先:土 隆一(土研究事務所)
Fax:054-238-3241/Tel.:054-238-3240
■第39回リモートセンシングシンポジウム
日本地質学会 協賛
11月25日(金)
場所:東京農業大学世田谷キャンパス
申込締切:11/1 講演申込締切:10/15
http://www.sice.jp/
■第29回ゼオライト研究発表会
日本地質学会 協賛
11月27日(水)〜28日(木)
会場:東北大学
http://www.jaz-online.org/index.html
■第3回学生のヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集
日本地質学会ほか 推薦
実習実施時期:2014年3月5日出発,19日帰国(15日間)
申込締切:11/30
実習コース:カトマンズ−ポカラ−ムクチナート−タンセン−ルンビニ
参加費用:学生・大学院生20万円以内、その他の個人参加者25万円以内、大学・企業などの組織派遣教員/社員30万円以内
http://www.geocities.jp/gondwanainst/
■日本地球惑星科学連合2014年大会
2014年4月28日(月)〜5月2日(金)
会場:パシフィコ横浜会議センター
(横浜市西区みなとみらい1-1-1)
予稿集原稿投稿募集:2014年1月08日(水)〜2月12日(水)
http://www.jpgu.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/outline/content0098.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■九州大学:カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 CO2貯留部門(ポスドク公募)(9/30)
■海洋研究開発機構:生命の進化と海洋地球生命史分野 任期制職員(研究職、技術研究職、技術総合職、ポスドク研究員公募)(9/24)
■平成26年度学術研究船白鳳丸の共同利用公募(8/30)
■平成26年度東北海洋生態系調査研究船(学術研究船)「新青丸」(淡青丸の後継船)の共同利用公募(9/6)
■高知大学海洋コア総合研究センター:平成25年度(後期)全国共同利用研究課題の公募(8/30)
■平成26年度笹川科学研究助成(学術研究部門:10/1〜10/15、実践研究部門:11/1〜11/15)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】地質マンガ:ハンマーの行方
──────────────────────────────────
ハンマーの行方
原案:chiyodaite マンガ:Key
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//manga/63.gif
その他の地質マンガはこちらから!
http://www.geosociety.jp/faq/content0057.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flash No.228 仙台大会事前参加登録:本日締切!!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.228 2013/8/20 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[仙台大会]事前参加登録 本日締切!!
【2】[仙台大会]同窓会ブース募集中
【3】[仙台大会]緊急展示の申込について
【4】津波堆積物ワークショップ(in 仙台)も 申込受付中!
【5】2013年度秋季地質の調査研修:参加者募集
【6】 日本-ロンドン地質学会学術交流協定を締結
【7】名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[仙台大会]事前参加登録 本日締切!!
──────────────────────────────────
全体日程表はこちらから↓
http://www.geosociety.jp/sendai/content0007.html
○参加登録(巡検申込は終了)
締切:8月20日(火)18時(郵送分は締切りました)
※講演申込をされた方も,別途事前参加登録を行って下さい。
(当日参加登録の場合は申込費用が異なります。)
※登録申込済みで未送金の方は、早めにご送金ください。
○託児室利用申込
締切:8月23日(金)
仙台大会HPはこちら
http://www.geosociety.jp/sendai/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[仙台大会]同窓会ブース募集中
──────────────────────────────────
申込締切 8月20日(火)
懇親会に引き続き(20:00〜21:00),旧友・卒業生・恩師との親睦を図るため,各大学の同窓会ごとのブースを設ける予定です.ブースを希望される各大学同窓会関係者の方は,8月20日(火)までにご連絡下さい.持ち込み可能です.ふるってご参加下さい.
詳しくは,こちらから
http://www.geosociety.jp/sendai/content0034.html#dosokai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[仙台大会]緊急展示の申込について
──────────────────────────────────
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害調査報告や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コーナー」を設けます.ポスター展示を希望する方は,8月30日(金)までに次の内容を下記申込先にご連絡ください.
1)発表要旨PDF(ニュース誌5月号参照) 2)緊急展示の必要性 3)発表代表者と連絡先 4)希望枚数(1枚:幅90×180cm) 5)展示に関わる要望(2〜5の様式は自由)
実行委員会は行事委員会と協議し,可否の判断を致します.希望にはできるだけ応えるようにしますが,展示方法等については実行委員会の指示に従ってください.
申込先:main@geosociety.jp
担当:鈴木紀毅(仙台大会実行委員会)・須藤 宏(行事委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】津波堆積物ワークショップ(in 仙台)も 申込受付中!
──────────────────────────────────
参加申込締切:8月30日(金)17:00
(注意:専用申込フォームからの事前参加申込が必要です)
◆第4回津波堆積物ワークショップ
テーマ:「震災前・震災直後—何がわかっていたのか−」
2013年9月14日(土)9:00〜12:00
◆第5回津波堆積物ワークショップ
テーマ「震災から2年半,津波堆積物研究と社会」
2013年9月18日(水)10:00〜16:15
会場はいずれも仙台大会と同じ、東北大学川内北キャンパスです。
仙台大会の前と後に是非ご参加下さい!
プログラム,参加申込などは下記より,
http://www.geosociety.jp/science/content0057.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2013年度秋季地質の調査研修:参加者募集
──────────────────────────────────
地質調査法の基本技術の修得をめざすとともに,それをベースに得られた過去の調査や研究の成果についても学びます.地質調査の経験のない方でも,地質調査法の基本を体で習得することを目指します.
日程:2013年11月18日(月)〜22日(金)4泊5日
場所:千葉県君津市及びその周辺地域(房総半島中部域)
募集人数:6名. 参加費:12万円
申込締切:2013年10月18日(金)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/engineer/content0033.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】日本-ロンドン地質学会学術交流協定を締結
──────────────────────────────────
日本地質学会とロンドン地質学会は、日英交流400 年に当たり、学術交流協定に調印しました。石渡会長とロンドン地質学会デービッド・シルストン会長によって署名された協定書には、相互の情報交換、研究・出版活動への共同参加、そしてセミナーや学術大会の共同開催などが記されています。
詳しくはこちらから
http://www.geosociety.jp/engineer/content0028.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
──────────────────────────────────
日本地質学会では,学会員相互の交流と親睦を図る目的で,2年ごとに会員名簿を発行することを運営規則にうたっております.2013年はその発行年にあたり,本年11月末日発行の予定で準備を行っております.
名簿の発行様式は前回と同様で,全会員を収録します.本会としては,個人情報保護法の制約はあるとしても,会員の皆様が上記の目的に沿って利用できるような,従来規模の名簿を作成したいと考えておりますので,調査の実施にご理解とご協力をお願いいたします.
アンケート提出およびWeb画面更新締切日:2013年10月4日(金)
詳しくは,コチラ↓
http://www.geosociety.jp/outline/content0132.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】 支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■富士山巡検
11月2日(土)〜3日(日):1泊2日(雨天決行)
申込期間:9月9日(月)〜10月18日(金)
■関東支部『地質研究サミット』シリーズ「伊豆衝突帯地質研究サミット」
11月23日(土)〜24日(日)
場所:横浜国立大学(横浜市保土ヶ谷区常盤台79−7)
■関東支部ミニ巡検シリーズ「丹沢ミニ巡検」
11月30日(土)〜12月1日(日):1泊2日
詳しくは関東支部Webサイトへ → http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地質研究所ニュース 第32号
http://www.gsh.hro.or.jp/publication/gshnews/news_pdf/vol29_no2.pdf
■日本学術会議の提言「東日本大震災に係る学術調査—課題と今後について—」
http://www.geosociety.jp/engineer/content0032.html
■JABEE NEWS 第18号(2013年8月16日)より
<修士プログラム修了生も技術士第一次試験免除
−2011年認定プログラムの官報告示>
技術士法の規定に基づき、JABEE認定プログラムの修了者には、技術士第一次試験の合格と同等の資格が認められています(平成12年 技術士法第31条の2第2項)。
従来は、学士課程の認定プログラムのみがその対象となっておりましたが、修士課程の認定プログラムも本年7月25日付官報号外第161号に告示されました。これにより、それぞれの修士課程プログラムが認定されて以降の修了者については、全員が技術士第一次試験が免除されます。
■地球にわくわく小・中学生自由研究コンテスト
募集締切:10月31日(木)
応募資格・部門:小学生2部門(3・4年生、5・6)年生、中学生1部門
問い合わせ先:wakuwaku@jeso.jp
地学オリンピック日本委員会HP http://jeso.jp/
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//olympic/2013waku.jpg
■第11回高校生科学技術チャレンジ研究作品募集
募集期間:9月2日(月)〜10月7日(月)
応募資格:国内の高校生・高等専門学校生(3年生まで)、個人またはチーム
http://www.asahi.com/jsec/
■第57回粘土科学討論会
日本地質学会 共催
9月4日(水)〜6日(金)
会場:高知市文化プラザかるぽーと
http://www.cssj2.org/
■第4回・第5回津波堆積物ワークショップ
(120年学術大会:同時開催行事)
日本地質学会・日本堆積学会 共催
第4回:9月14日(土)9:00〜12:00
第5回:9月18日(水)10:00〜16:15
場所:東北大学川内北キャンパス マルチメディア棟M206号室
http://www.geosociety.jp/science/content0057.html
■2013年度日本地球化学会年会
日本地質学会 共催
9月11日(水)〜13日(金)
会場:筑波大学第一エリア1D棟、1E棟
事前参加登録締切:8月23日(金)
http://www.wdc-jp.biz/geochem/2013/
■第63回東レ科学講演会
9月20日(金)17:00-21:00
場所:有楽町朝日ホール(有楽町マリオン11F)
http://www.toray.co.jp/tsf/index.html
■第152回深田研談話会(現地)
9月28日(土)8:45〜16:30
見学場所(予定):神田明神・湯島聖堂、神田佐久間町、回向院ほか
参加費:3000円 定員:30名
申込締切 :9月3日(火)
http://www.fgi.or.jp/
■第2回G-EVER国際シンポジウム,第1回IUGS・日本学術会議国際ワークショップ〜アジア太平洋地域の災害とリスクマネジメント: 沈み込み帯の地震・津波・火山噴火・地すべり
日本地質学会 共催
10月19日(土)〜20日(日)[21日巡検あり]
場所:仙台市情報・産業プラザ
参加登録:9/15(登録料無料,先着70名)
http://g-ever.org/en/symposium/symposium2.html
■東海地震防災セミナー2013
11月7日(木)13:30〜16:00
会場:静岡商工会議所静岡事務所5階ホール(JR静岡駅北口西側)
連絡先:土 隆一(土研究事務所)
Fax:054-238-3241/Tel.:054-238-3240
■第16回日本水環境学会シンポジウム
11月9日(土)〜10日(日)
会場:琉球大学千原キャンパス(農学部)(沖縄県西原町字千原1)
http://www.jswe.or.jp/
■第39回リモートセンシングシンポジウム
日本地質学会 協賛
11月25日(金)
場所:東京農業大学世田谷キャンパス
申込締切:11/1 講演申込締切:10/15
http://www.sice.jp/
■第29回ゼオライト研究発表会
日本地質学会 協賛
11月27日(水)〜28日(木)
会場:東北大学
http://www.jaz-online.org/index.html
■第3回学生のヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集
日本地質学会ほか 推薦
実習実施時期:2014年3月5日(水)出発,19日(水)帰国(15日間)
申込締切:11月30日(土)
実習コース:カトマンズ−ポカラ−ムクチナート−タンセン−ルンビニ
参加費用:学生・大学院生20万円以内、その他の個人参加者25万円以内、大学・企業などの組織派遣教員/社員30万円以内
http://www.geocities.jp/gondwanainst/
■日本地球惑星科学連合2014年大会
2014年4月28日(月)〜5月2日(金)
会場:パシフィコ横浜会議センター
(横浜市西区みなとみらい1-1-1)
予稿集原稿投稿募集:2014年1月08日(水)〜2月12日(水)
http://www.jpgu.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/outline/content0098.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flash No.238 (臨時)奈須紀幸 名誉会員 訃報
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.238 2013/10/8 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 奈須紀幸 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
奈須紀幸 名誉会員(東京大学旧海洋研究所 元所長)が,平成25年10月3日(木)にご逝去されました(享年89歳)。 これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 通夜・ご葬儀は,10月6日にすでに近親者によりしめやかに執り行なわれ,ご遺族のご意向により弔問等はご遠慮願いたいとのことです。
会長 石渡 明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
geo-flash No.239 報告:原子力規制委員会の評価会合についての意 見交換会
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.239 2013/10/15 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2014年度代議員選挙,各賞募集について
【2】2014年度会費払込のお知らせ:割引申請は忘れずに!
【3】2013年度秋季地質調査研修:参加者募集
【4】報告:原子力規制委員会の評価会合についての意見交換会
【5】日本地球惑星科学連合代議員選挙についてのお願い
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2014年度代議員選挙,各賞募集について
─────────────────────────────────
■2014年度代議員選挙立候補届 受付中
受付締切:11月6日(水)18時必着
■2014年度学会各賞募集 受付中
応募締切:11月30日(土)必着
それぞれ詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
※「会員のページ」の各ページ内に、立候補届書式、推薦書式等が
ダウンロードできるようになっています。
○会員番号・パスワードによるログインが必要です。
ログインの方法はこちら。
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2014年度会費払込のお知らせ:割引申請は忘れずに!
─────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下さいますよ
うお願いいたします.
■2014年度分会費の引き落とし日:12月24日(火)です.
請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下
さい.
■自動引き落とし以外の方(お振り込み)
12月中旬頃までに請求書兼郵便振替用紙をお送りいたします.折り返しご送金
くださいますようお願いいたします.
■新規登録、引落口座変更の振替依頼書提出締切:11月8日(金)
■割引会費申請(院生・学部学生):請求書発行前締切 11月13日(水)
忘れずにご提出下さい。
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/outline/content0135.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2013年度秋季地質調査研修:参加者募集
──────────────────────────────────
地質調査法の基本技術の修得をめざすとともに,それをベースに得られた
過去の調査や研究の成果についても学びます.地質調査の経験のない方でも,
地質調査法の基本を体で習得することを目指します.
日程:2013年11月18日(月)〜22日(金)4泊5日
場所:千葉県君津市及びその周辺地域(房総半島中部域)
募集人数:6名 参加費:12万円
申込締切:2013年10月18日(金)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/engineer/content0033.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】報告:原子力規制委員会の評価会合についての意見交換会
──────────────────────────────────
仙台大会期間中の2013年9月16日(月)に,原子力規制委員会の評価
会合の委員に推薦させて頂いた皆様を中心に,一般会員も含めた意
見交換会を行いました.この意見交換会では,評価会合の内容につ
いて,学会内の専門家の間での率直な意見交換を目的としたため,
参加者は会員に限定させて頂きました。
既に委員会にお出になっている方々には,現状の報告をしていただ
くと共に,これまで原発審査等の委員を務め,評価会合の委員推薦
時の推薦対象とならなかった会員の方も含めて活発な意見交換を行
いました。
議事録,当日の発表資料などは下記から閲覧いただけます。
(会員番号・パスワードによるログインが必要です)
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
世話人 斎藤 眞(常務理事)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】日本地球惑星科学連合代議員選挙についてのお願い
─────────────────────────────────
地球惑星連合の代議員選挙投票の締め切りは,10月25日(金)です。
連合から加盟学協会長宛に連合に会員登録している当会会員宛へ投票
を呼びかけてほしい旨の依頼がありましたので,お知らせします。
地質学会では特に学会推薦の候補者を決めていませんが,地質学会
の会員の方々も多数立候補しています。連合へ個人会員登録されてい
る会員の皆さんは,忘れずに投票して下さい.
連合2013年選挙については,下記よりご参照ください。
http://www.jpgu.org/2013election/schedule_2013.html
立候補者リストはコチラから
http://www.jpgu.org/whatsnew/daigiinlist.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】 支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■富士山巡検 >>参加募集締切ました
11月2日(土)〜3日(日):1泊2日(雨天決行)
※定員に達しましたので、参加者募集を締め切らせて頂きます。
キャンセル待ちは受付可能です。ご希望の方は担当者まで。
巡検の詳細はこちら
http://kanto.geosociety.jp/junken/130903_fujijyunken.pdf
■関東支部『地質研究サミット』シリーズ
「伊豆衝突帯地質研究サミット」(第2報)
11月23日(土)〜24日(日)
地質学,地下構造探査,地学防災減災リテラシーなどの様々な
角度から議論します.
会場:横浜国立大学・教育文化ホール
■関東支部ミニ巡検シリーズ「丹沢ミニ巡検」
11月30日(土)〜12月1日(日):1泊2日
それぞれ詳細は関東支部Webサイトへ
→ http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地球にわくわく小・中学生自由研究コンテスト
募集締切:10月31日(木)
応募資格・部門:小学生2部門(3・4年生、5・6年生)、中学生1部門
問い合わせ先:wakuwaku@jeso.jp
地学オリンピック日本委員会HP http://jeso.jp/
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//olympic/2013waku.jpg
■あいちサイエンスフェスティバル2013
開催中〜11月4日(月・祝)まで
会場:蒲郡市生命の海科学館など
○惑星地球フォトコンテスト入賞作品展
日本地質学会 共催
https://aichi-science.jp/
■第2回G-EVER国際シンポジウム,第1回IUGS・日本学術
会議国際ワークショップ〜アジア太平洋地域の災害とリスク
マネジメント: 沈み込み帯の地震・津波・火山噴火・地すべり
日本地質学会 共催
10月19日(土)〜20日(日)[21日巡検あり]
場所:仙台市情報・産業プラザ
[参加登録は受付終了]
http://g-ever.org/en/symposium/symposium2.html
■深田研 一般公開2013
10月20日(日)
場所:深田地質研究所(文京区本駒込2-13-12)
http://www.fgi.or.jp
■山陰海岸ジオパーク国際学術会議「城崎会議」
日本地質学会ほか 後援
テーマ:自然の恵と災害
10月26日(土)・27日(日)
参加申込締切:10月18日(金)
場所:城崎温泉西村屋ホテル招月庭(兵庫県豊岡市城崎町)
http://sanin-geo.jp/modules/geopark/index.php/kinosaki_kaigi2013.html
■錦秋 筑波山地域ジオツアー
11月2日(土)9:00〜17:00
場所:TXつくば駅集合・解散
参加申込締切:10月28日(月)
http://www.geog.or.jp/tour/tourscheduled/190-25.html
■公開シンポジウム 『新第三紀の終焉と第四紀の始まり
−東海層群から読み解く気候変動− 』
11月10日(日)13:00-16:30
場所:三重県総合博物館 レクチャールーム
http://www.geosociety.jp/outline/content0096.html
■第24回地質汚染調査浄化技術研修会
日本地質学会環境地質部会 ほか 共催
11月22日(金)〜24日(日)
会場:NPO法人日本地質汚染審査機構本部ミーテング・ルーム
http://www.npo-geopol.or.jp
■第39回リモートセンシングシンポジウム
日本地質学会 協賛
11月25日(金)
場所:東京農業大学世田谷キャンパス
申込締切:11/1 講演申込締切:10/15
http://www.sice.jp/
■第29回ゼオライト研究発表会
日本地質学会 協賛
11月27日(水)〜28日(木)
会場:東北大学
http://www.jaz-online.org/index.html
■第22回地質調査総合センターシンポジウム
「アカデミックから身近な地質情報へ」
11月30日(土)13:00〜18:00
場所:AP東京八重洲通り11F(東京都中央区京橋)
参加費無料・要事前登録
https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo22/
■信州大学山岳科学総合研究所シンポジウム
「日本アルプスの大規模地すべり:第四紀地形学・地質学の視点から」
12月7日(土)10:00−16:50
場所:信州大学理学部C棟2階大会議室(松本市旭3-1-1)
参加費および事前申し込み不要
http://ims.shinshu-u.ac.jp/documents/2013/event2013.html#131207
■高校生のための先進的科学技術体験合宿プログラム
ウインター・サイエンスキャンプ'13-'14参加者募集
会期:12月下旬〜1月上旬(冬休み期間中の3〜4日)
締切:2013年11月8日(金)必着
http://www.jst.go.jp/cpse/sciencecamp/camp/
■第3回学生のヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集
日本地質学会ほか 推薦
実習実施時期:2014年3月5日(水)出発,19日(水)帰国(15日間)
申込締切:11月30日(土)
http://www.geocities.jp/gondwanainst/
■International Symposium on Asian Dinosaurs
2014年3月21日(金)〜23日(日)
場所:[20〜21日]福井県立大学(個人講演、ポスターセッション)
[23日]福井県立恐竜博物館(普及講演)
http://www.dinosaur.pref.fukui.jp/ADA/
■日本地球惑星科学連合2014年大会
2014年4月28日(月)〜5月2日(金)
会場:パシフィコ横浜会議センター(横浜市西区みなとみらい1-1-1)
予稿集原稿投稿募集:2014年1月08日(水)〜2月12日(水)
http://www.jpgu.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/outline/content0098.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■九州大学大学院:工学研究院地球資源システム工学部門(准教授)(12/25)
■静岡大学大学院:理学研究科地球科学専攻(講師または助教)(11/22)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flash No.229 仙台で会いましょう!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.229 2013/9/3 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[仙台大会]講演プログラムを掲載しました
【2】[仙台大会]事前参加登録の確認書等を発送しました
【3】[仙台大会]原子力規制委員会の評価会合についての意見交換会のご案内
【4】[仙台大会]各種イベント
【5】津波堆積物ワークショップ:申込締切延長 9月6日(金)17時
【6】2013年度秋季地質の調査研修:参加者募集
【7】Island Arcからのお知らせ
【8】名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[仙台大会]講演プログラムを掲載しました
──────────────────────────────────
全体日程表、各講演のプログラムを掲載しました。
詳しくは,大会ホームページ・News誌8月号をご覧下さい。
http://www.geosociety.jp/sendai/content0007.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[仙台大会]事前参加登録の確認書等を発送しました
──────────────────────────────────
事前参加登録された方へ、8月29日に確認書およびクーポン(お弁当・懇親会申込者のみ)を発送しました。
【入金確認済みの方】
記名名札と懇親会、お弁当申込の方には、参加・引換用のクーポンを同封しています。確認書(本人控と受付提出用)および名札・クーポンは当日忘れずにご持参下さい。
【未入金の方】
確認書送付時点で事前参加登録費が未入金の方には黄色い用紙の確認書(本人控と受付提出用)のみお送りしています。
9月9日(月)までにご送金をお願い致します。行き違いで入金済みの場合は当日受付にて照会いたしますので念のため、振込み時の控え等をご持参下さい。9月9日(月)までにお振込いただけなかった場合は、当日会場受付にてご清算をお願いいたします。
<振込先>
振込時には、振込者氏名の前に必ず申込No.を入力して下さい。
(1)三井住友銀行 神田駅前支店(普通)1711424
(社)日本地質学会 / シヤ)ニホンチシツガツカイ
(2)郵便振替 00140-8-28067 (社)日本地質学会
※郵便局に備え付けの郵便振替用紙をご利用ください。
詳しくはこちら。
http://www.geosociety.jp/sendai/content0004.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[仙台大会]原子力規制委員会の評価会合についての意見交換会のご案内
──────────────────────────────────
日時:9月16日(月)(大会3日目)17:00〜19:00
(東京に帰ることができる時間内に終了予定)
会場:会場4(B棟2階B203)
注意:この意見交換会の参加は日本地質学会会員に限ります
日本地質学会では,仙台大会において,原子力規制委員会の評価会合の委員に推薦させて頂いた皆様を中心に,一般会員も含めた意見交換会を行います.この意見交換会では,評価会合の内容について,学会内の専門家の間での率直な意見交換を目的とし,参加者は会員限りとします.非会員、マスコミ関係者は除外します.
話題提供者の方々には,現状の報告をしていただくと共に,これまで原発審査等の委員を務め,評価会合の委員推薦時の推薦対象とならなかった方の出席も期待し,専門的な意見交換をしたいと考えております.会員の皆様の参加を期待します.
世話人:斎藤 眞(常務理事)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[仙台大会]各種イベント
──────────────────────────────────
大会期間中には、学術講演だけでなく、市民に向けたイベントなども行われます。お楽しみに!
■地質情報展2013みやぎ —大地を知って明日を生かす—
体験実験、解説コーナーなど盛り沢山
日時:14日(土)〜16日(月)
14日13:00〜16:45、15日9:00〜16:45、16日9:00〜12:30
場所:仙台市科学館(仙台市地下鉄南北線「旭ヶ丘駅」下車徒歩約5分、「仙台駅」より乗車時間約10分)
■市民講演会「災害に備える安全な社会とは〜求められる発想の転換と主体性〜」
日時:16日(月)14:30〜16:00
講師:柳田邦男(作家・評論家)
会場:東北大学百周年記念会館川内萩ホール
■一般公開シンポジウム「東日本大震災:あの時,今,これから」
日時:15日(日)14:30〜18:00
場所:東北大学百周年記念会館川内萩ホール
■ 小さなEarth Scientistのつどい〜第11回 小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜
日時 15日(日)9:00〜15:30
場所:仙台大会ポスター会場(川内北キャンパス講義棟C棟)
■若手会員のための業界研究サポート」(旧:就職支援プログラム)
日時 15日(日)14:00〜18:00
場所:東北大学川内北キャンパス講義棟C棟
詳しくはこちら。
http://www.geosociety.jp/sendai/content0012.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】津波堆積物ワークショップ:申込締切延長 9月6日(金)17時
──────────────────────────────────
9月14日,9月18日に行われる第4回,第5回津波堆積物ワークショップですが,多数の申し込みを頂きました.まだ座席に若干の余裕がありますので,学会員向けに締め切りを9月6日(金)17:00まで延長したいと思います.特に,9月14日の第4回は,地質学会の会期中ですが,ワークショップの会場にお越し頂くには地質学会の参加申し込みとは別に,ワークショップの事前申し込みが必要となりますので,ご留意願います.お申し込みは,以下のウェブサイトからよろしくお願いします.
申込締切:2013年9月6日(金)17:00
プログラム,申込フォームなどはこちらから↓
http://www.geosociety.jp/science/content0057.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】2013年度秋季地質の調査研修:参加者募集
──────────────────────────────────
地質調査法の基本技術の修得をめざすとともに,それをベースに得られた過去の調査や研究の成果についても学びます.地質調査の経験のない方でも,地質調査法の基本を体で習得することを目指します.
日程:2013年11月18日(月)〜22日(金)4泊5日
場所:千葉県君津市及びその周辺地域(房総半島中部域)
募集人数:6名. 参加費:12万円
申込締切:2013年10月18日(金)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/engineer/content0033.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】 Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
◆22-3号がオンライン出版されました
本号は,「ジルコンとマルチクロノロジー:フィッション・トラック法とU-Pb法,およびそれらを組み合わせた年代研究」の特集号8編と一般原稿2編から構成されています.
詳しくはこちら から
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iar.2013.22.issue-3/issuetoc
<日本語要旨掲載ページ>
http://www.geosociety.jp/publication/content0072.html
IAR最新号は,学会webサイトから無料で閲覧出来ます。
ログイン方法はこちらから,
https://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
◆2012年度Island Arc編集委員会報告(日本地質学会Island Arc編集委員会)
日本地質学会の公式英文誌としてIsland Arc(IAR)が発行されてから,今年で21周年となります. 2013年からは,IARの出版が全面的にオンライン化され,カラーによる図表類の出版に制限がなくなりました.ここでは出版社であるWiley社から送られてきた出版報告をもとに,IARの現状を日本地質学会の会員の皆様に御紹介したいと思います.
続きはこちらから.
http://www.geosociety.jp/publication/content0071.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
──────────────────────────────────
日本地質学会では,学会員相互の交流と親睦を図る目的で,2年ごとに会員名簿を発行することを運営規則にうたっております.2013年はその発行年にあたり,本年11月末日発行の予定で準備を行っております.
名簿の発行様式は前回と同様で,全会員を収録します.本会としては,個人情報保護法の制約はあるとしても,会員の皆様が上記の目的に沿って利用できるような,従来規模の名簿を作成したいと考えておりますので,調査の実施にご理解とご協力をお願いいたします.
アンケート提出およびWeb画面更新締切日:2013年10月4日(金)
詳しくは,コチラ↓
http://www.geosociety.jp/outline/content0132.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】 支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■富士山巡検
11月2日(土)〜3日(日):1泊2日(雨天決行)
申込期間:9月9日(月)〜10月18日(金)
■関東支部『地質研究サミット』シリーズ「伊豆衝突帯地質研究サミット」
11月23日(土)〜24日(日)
場所:横浜国立大学(横浜市保土ヶ谷区常盤台79−7)
■関東支部ミニ巡検シリーズ「丹沢ミニ巡検」
11月30日(土)〜12月1日(日):1泊2日
詳しくは関東支部Webサイトへ → http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地球にわくわく小・中学生自由研究コンテスト
募集締切:10月31日(木)
応募資格・部門:小学生2部門(3・4年生、5・6)年生、中学生1部門
問い合わせ先:wakuwaku@jeso.jp
地学オリンピック日本委員会HP http://jeso.jp/
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//olympic/2013waku.jpg
■第11回高校生科学技術チャレンジ研究作品募集
募集締切:10月7日(月)
応募資格:国内の高校生・高等専門学校生(3年生まで)、個人またはチーム
http://www.asahi.com/jsec/
■第57回粘土科学討論会
日本地質学会 共催
9月4日(水)〜6日(金)
会場:高知市文化プラザかるぽーと
http://www.cssj2.org/
■第4回・第5回津波堆積物ワークショップ
(120年学術大会:同時開催行事)
日本地質学会・日本堆積学会 共催
第4回:9月14日(土)9:00〜12:00
第5回:9月18日(水)10:00〜16:15
場所:東北大学川内北キャンパス マルチメディア棟M206号室
http://www.geosociety.jp/science/content0057.html
■2013年度日本地球化学会年会
日本地質学会 共催
9月11日(水)〜13日(金)
会場:筑波大学第一エリア1D棟、1E棟
http://www.wdc-jp.biz/geochem/2013/
■第2回G-EVER国際シンポジウム,第1回IUGS・日本学術会議国際ワークショップ〜アジア太平洋地域の災害とリスクマネジメント: 沈み込み帯の地震・津波・火山噴火・地すべり
日本地質学会 共催
10月19日(土)〜20日(日)[21日巡検あり]
場所:仙台市情報・産業プラザ
参加登録:9/15(登録料無料,先着70名)
http://g-ever.org/en/symposium/symposium2.html
■日本学術会議:公開シンポジウム
− 学協会の新公益法人法への対応の現状と展望 −
10月22日(火)13:00〜16:40
場所:日本学術会議 講堂(東京都港区六本木 7-22-34)
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/177-s-1022.pdf
■The 11th International Symposium on Mitigation of Geo-Disasters in Asia
10月22日(火、カトマンズ)、24日(ポカラ)会議
10月23日、25日〜28日(日)巡検
場所:カトマンズ・ラディソンホテル及びポカラ・バラヒホテル
参加登録料(巡検経費込み):450ドル(学生は半額)
http://hils.org.np/hils/mgda/2ndCircular.pdf
■山陰海岸ジオパーク国際学術会議「城崎会議」
日本地質学会 後援
テーマ:自然の恵と災害
10月26日(土)〜27日(日)
場所:城崎温泉西村屋ホテル招月庭(兵庫県豊岡市城崎町)
要旨提出締切:9月6日(金)
http://www.sanin-geo.jp/
■平成25年度 東濃地科学センター 地層科学研究 情報・意見交換会
10月29日(火)13:10〜17:00
場所:瑞浪市地域交流センター「ときわ」(岐阜県瑞浪市)
定員:約150名 申込締切:10/10
http://www.jaea.go.jp/04/tono/topics/topics1308_1/1308_1.html
■瑞浪超深地層研究所 深度300m水平坑道見学会」
10月30日(水)9:15〜12:00
場所:瑞浪超深地層研究所
定員:40名 申込締切:10/10
http://www.jaea.go.jp/04/tono/topics/topics1308_1/1308_1.html
■第39回リモートセンシングシンポジウム
日本地質学会 協賛
11月25日(金)
場所:東京農業大学世田谷キャンパス
申込締切:11/1 講演申込締切:10/15
http://www.sice.jp/
■第29回ゼオライト研究発表会
日本地質学会 協賛
11月27日(水)〜28日(木)
会場:東北大学
http://www.jaz-online.org/index.html
■第3回学生のヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集
日本地質学会ほか 推薦
実習実施時期:2014年3月5日(水)出発,19日(水)帰国(15日間)
申込締切:11月30日(土)
実習コース:カトマンズ−ポカラ−ムクチナート−タンセン−ルンビニ
参加費用:学生・大学院生20万円以内、その他の個人参加者25万円以内、大学・企業などの組織派遣教員/社員30万円以内
http://www.geocities.jp/gondwanainst/
■日本地球惑星科学連合2014年大会
2014年4月28日(月)〜5月2日(金)
会場:パシフィコ横浜会議センター
(横浜市西区みなとみらい1-1-1)
予稿集原稿投稿募集:2014年1月08日(水)〜2月12日(水)
http://www.jpgu.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/outline/content0098.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■北海道大学大学院:理学研究院自然史科学部門地球惑星システム科学(助教)(10/31)
■原子力規制委員会(職員)(9/8)
■産業技術総合研究所:活断層・地震研究センター 博士型任期付研究員
(複数応募締切:10/11,1件応募締切:10/25)
■海洋研究開発機構:高知コア研究所 研究員もしくはポストドクトラル研究員(9/30)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flash No.230 (臨時)隠岐、世界ジオパーク認定!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.229 2013/9/3 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】隠岐ジオパークが世界ジオパークに認定!
──────────────────────────────────
韓国のチェジュ島で開催中の第3回アジア太平洋ジオパーク大会において,昨年保留となっていた隠岐ジオパークの世界ジオパークネットワーク(GGN)への加盟が認定されました.
日本海生成に関わる貴重な地質と多様な自然景観,生態系などの保護保全とそれらの活用が評価されたものと思われます.これで,今年10月に隠岐で開催される日本ジオパーク全国大会にも,弾みがつくことでしょう.
また,2009年に国内で初めて認定された洞爺湖有珠山,糸魚川,島原半島も,4年目の再審査を経て再認定されました.
これで日本は世界ジオパークが6地域となり,わずか5年間で世界で4番目のGGN加盟地域数をもつ国となりました.この数は今後も増え続けるものと思われます.
今後はJGNはもとより,アジア太平洋ジオパークネットワークおよびGGNメンバーとしての国際的な貢献が期待されます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flash No.232 (大会臨時号)仙台大会初日
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.232 2013/9/14 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】仙台大会初日の様子
【2】仙台大会:9月15日(日)の主なイベント
【3】国際地学オリンピック(インド大会) 【現地速報!】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】仙台大会初日の様子
──────────────────────────────────
■今年の地質情報展は、スリーエム仙台市科学館が会場です。
地質学会のブースには、フォトコンテストの作品のパネル展示と、地学オリ
ンピックなどです。
ぜひのぞいてみてください。
■ 表彰式が開かれました。
■懇親会!
■初日の優秀ポスター賞(4件)の表彰がマルチメディアホール表彰式会場で行われました。
初日の優秀ポスター賞は:
「堆積岩中の炭質物の石墨化におけるタイムスケール−接触変成作用と
熱モデリングによる証拠−」森なつみほか(R4-P-1)
「サンアンドレアス断層直上Redwood蛇紋岩岩体の反応過程」
宇野正起・カービー ステファン(R4-P-6)
「棚倉断層沿いに発達するストライクスリップ堆積盆(矢祭堆積盆)における
新第三紀堆積環境変遷」澤畑優理恵・天野一男(R5-P-6)
「紀伊半島北西部における微小地震クラスターの分布に対する地質構造との関係」
前田純伶ほか(R5-P-19)
写真付きの記事はこちらから、、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0***.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】仙台大会:9月15日(日)の主なイベント
──────────────────────────────────
■公開シンポジウム「東日本大震災:あの時,今,これから」
14:30〜18:00 川内萩ホール
■若手会員のための業界研究サポート
14:30〜18:00 C棟
■小さなEarth Scientistのつどい
9:00〜15:30 C棟ポスター会場
■地質情報展2013みやぎ
9:00〜16:45 スリーエム仙台市科学館
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】国際地学オリンピック(インド大会)【現地速報!】
──────────────────────────────────
仙台から時差3.5時間、インドのマイソールにて国際地学オリンピック2013が開
催中です。世界22ヶ国から86名の高校生が集結し、地学で白熱しています。本日
はいよいよ筆記試験。日本代表の安藤さん、桑原さん、安河内さん、八幡さん、
がんばってください。仙台からエールを送りましょう。
参加国一覧
ベルラーシ、ブラジル、コロンビア、フランス、ドイツ、インド、インドネ
シア、イタリア、日本、ルーマニア、ロシア、韓国、スペイン、スリランカ、台湾
、タイ、ウクライナ、アメリカ、バングラディッシュ(初)、イスラエル
(初)、オーストラリア、クウェート
(オブザーバー参加:アルゼンチン、マラウィー)
引率者のブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/akitachigaku
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flash No.231 (大会臨時号)いよいよ仙台大会開幕!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.231 2013/9/13 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】仙台大会開幕!
【2】仙台大会:9月14日(土)の主なイベント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】仙台大会開幕!
──────────────────────────────────
「東北,いま,たちあがる地質学」をキャッチフレーズにした仙台大会が
いよいよ開幕します。
今大会では、自然災害や防災に地質学が果たす役割を考えようと、公開シンポ
ジウム「東日本大震災:あの時,今,これから」や、柳田邦男氏による市民
講演会「災害に備える安全な社会とは〜求められる発想の転換と主体性〜」
などが企画されています。
また、セッション世話人が選んだ「おもしろそう、注目すべき、ぜひ聞いて
ほしい」講演を紹介したハイライトが作られましたので、参考にしてください。
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//science/2013sendai/files/highlight.pdf
毎年、初日の朝の受付は大変混み合います。余裕を持ってお早めに!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】仙台大会:9月14日(土)の主なイベント
──────────────────────────────────
■地質情報展2013みやぎ 開会式(12:30〜 スリーエム仙台市科学館)
■地質学会表彰式・受賞記念講演(15:30〜17:50 マルチメディアホール)
16:20〜16:35
・日本地質学会小澤儀明賞受賞スピーチ 尾上哲治会員
「放散虫革命ジュニア世代のジュラ紀付加体地質学」
16:35〜16:50
・日本地質学会柵山雅則賞受賞スピーチ 岡本 敦会員
「岩石組織とモデルと」
16:50〜17:20
・日本地質学会賞受賞講演 井龍康文会員
「細かい観察・分析は地球環境科学を発展させるか−私の地球科学感−」
17:20〜17:50
・日本地質学会賞受賞講演 乙藤洋一郎会員
「古地磁気学と地質学」
■懇親会(18:15〜20:00 東北大学川内北キャンパス・川内の杜ダイニング)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flash No.233 (大会臨時号)雨ニモマケズ 大入御礼!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.233 2013/9/15 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】大会会場の様子
【2】仙台大会:9月16日(月)の主なイベント
【3】地学オリンピック(インド大会)情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】大会会場の様子
──────────────────────────────────
■ 大会会場の様子
■ 小さなEarth Scientistsのつどい 第11回小、中、高生徒地学研究発表会
今年も生徒さんたちの元気とレベルの高さに驚かされました。
■ 本日の優秀ポスター賞(4件)は、
「大型砂岩試料の粒子方位解析手法の開発」 宮田雄一郎・下梶秀則 (R9‑P‑1)
「火星における隕石衝突津波と巨礫移動に関する数値計算」 飯嶋耕崇ほか (T2‑P‑1)
「三陸ジオパーク構想における地域形成史の整理とその理解」 伊藤太久ほか (R6‑P‑3)
「東道後温泉組成の時系列変化―地殻変動との対応関係の検討」 日野愛奈ほか (R20‑P‑1)
おめでとうございます!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】仙台大会:9月16日(月)の主なイベント
──────────────────────────────────
■国際シンポジウム「環太平洋オフィオライト:沈み込み,付加作用,マントル・プロセス」
8:45〜11:45 会場2 (C200)
■市民講演会「災害に備える安全な社会とは〜求められる発想の転換と主体性〜」
講師:柳田邦男(作家・評論家)
14:30〜16:00 川内萩ホール
■原子力規制委員会の評価会合についての意見交換会【会員限り】
17:00〜19:00 会場4 (B203)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】地学オリンピック(インド大会)情報
──────────────────────────────────
インド大会5日目の本日は、実技試験です。固体地球・地質科学分野、気象・海洋科学分野、天文・地球惑星科学分野の三部門です。なお地学オリンピックに関するポスターは、小さなEarth Scientists の集い会場、および地質情報展(仙台科学館)にもポスターが展示してあります。 なお仙台大会は、地学オリンピックの元選手も参加しております! オリンピックを経た若者たちの活躍が楽しみです。写真は、学生スタッフとして支えてくている浅見さん(イタリア大会(2011年)日本代表)です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.245(臨時)北川芳男 名誉会員 ご逝去
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.245 2013/12/9 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 北川芳男 名誉会員 ご逝去
─────────────────────────────────
日本地質学会名誉会員 北川芳男氏(元北海道開拓記念館)が、
平成25年12月9日にご逝去されました(享年85歳)。
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福を
お祈り申し上げます。
なお、通夜ならびに告別式は、下記のとおり執り行われますので
併せてお知らせ申し上げます。
・お通夜:12月10日(火)PM 7:00から
・告別式:12月11日(水)AM 9:00から
・場所:やわらぎ斎場センティア28(札幌市中央区南2条西8丁目12-1)
TEL:011-233-4411
http://www.yawaragisaijyo.com/tyuoh.html
・喪主:北川 恵子
会長 石渡 明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flash No.234 (大会臨時号)来年も、鹿児島で会いましょう!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.234 2013/9/16 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】大会会場の様子
【2】原子力規制委員会の評価会合についての意見交換会開催される
【3】地学オリンピック(インド大会)情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】大会会場の様子
──────────────────────────────────
■ポスター発表会場および企業ブースの様子
連日の賑わいです。
■市民講演会「災害に備える安全な社会とは〜求められる発想の転換と主体性〜」
台風にもかかわらず会場には大勢の人が集まりました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】原子力規制委員会の評価会合についての意見交換会開催される
──────────────────────────────────
最終日の17:00〜19:00に大会会場で開催されました。学会から原子力規制委員会
の評価会合に推薦させて頂いた皆様との意見交換会とあって、台風の最終日にも
関わらず70名の会員が来場されました。時間を押しながらも静かな熱気に包まれ
ていました。なお意見交換会の資料は、可能なものは学会HPから公開される予定
です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】地学オリンピック(インド大会)情報
──────────────────────────────────
メダルをかけたcompetitionが終了し、本日からは世界の高校生たちと協力して
国際協力野外調査(ITFI)が行われています。写真はwelcome partyで自己紹介
の様子です。 このあと現地での表彰式を経て18日に発表されます。帰国には文
科省表敬訪問が予定されています。関係者皆様の元気な帰国と嬉しい成果が待ち
ましょう。
昨日の仙台大会ポスター賞受賞者の日野愛奈さんは国際地学オリンピック(フィ
リピン大会)の代表選手であるとご指摘いただきました。地学オリンピックが優
秀な人材を育て、若者たちが活躍していることはたいへん喜ばしいことです。
日本選手の自己紹介
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flash No.235 秋季地質調査研修:参加者募集
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.235 2013/9/17 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】仙台大会終了しました
【2】2013年度秋季地質調査研修:参加者募集
【3】名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
【4】支部情報
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】仙台大会終了しました
─────────────────────────────────
今年もたくさんの方々にご参加いただき,盛会のうち仙台大会は終了いた
しました。大会の報告は,ニュース誌11月号に掲載予定です。また,geo
-flash大会臨時号などでも,会場の様子をお伝えしています。
http://www.geosociety.jp/faq/content0005.html
来年は,鹿児島でお会いしましょう。
★第121年学術大会(鹿児島大会)
日程:2014年9月13日(土)〜15日(月・祝)
会場:鹿児島大学 ほか
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2013年度秋季地質調査研修:参加者募集
──────────────────────────────────
地質調査法の基本技術の修得をめざすとともに,それをベースに得られた
過去の調査や研究の成果についても学びます.地質調査の経験のない方でも,
地質調査法の基本を体で習得することを目指します.
日程:2013年11月18日(月)〜22日(金)4泊5日
場所:千葉県君津市及びその周辺地域(房総半島中部域)
募集人数:6名. 参加費:12万円
申込締切:2013年10月18日(金)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/engineer/content0033.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】 名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
──────────────────────────────────
日本地質学会では,学会員相互の交流と親睦を図る目的で,2年ごとに会員
名簿を発行することを運営規則にうたっております.2013年はその発行年に
あたり,本年11月末日発行の予定で準備を行っております.
名簿の発行様式は前回と同様で,全会員を収録します.本会としては,個人
情報保護法の制約はあるとしても,会員の皆様が上記の目的に沿って利用で
きるような,従来規模の名簿を作成したいと考えておりますので,調査の実
施にご理解とご協力をお願いいたします.
アンケート提出およびWeb画面更新締切日:2013年10月4日(金)
詳しくは,コチラ↓
http://www.geosociety.jp/outline/content0132.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】 支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■富士山巡検
11月2日(土)〜3日(日):1泊2日(雨天決行)
申込期間:9月9日(月)〜10月18日(金)
■関東支部『地質研究サミット』シリーズ「伊豆衝突帯地質研究サミット」
11月23日(土)〜24日(日)
場所:横浜国立大学(横浜市保土ヶ谷区常盤台79−7)
■関東支部ミニ巡検シリーズ「丹沢ミニ巡検」
11月30日(土)〜12月1日(日):1泊2日
詳しくは関東支部Webサイトへ → http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地球にわくわく小・中学生自由研究コンテスト
募集締切:10月31日(木)
応募資格・部門:小学生2部門(3・4年生、5・6)年生、中学生1部門
問い合わせ先:wakuwaku@jeso.jp
地学オリンピック日本委員会HP http://jeso.jp/
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//olympic/2013waku.jpg
■第11回高校生科学技術チャレンジ研究作品募集
募集締切:10月7日(月)
応募資格:国内の高校生・高等専門学校生(3年生まで)、個人またはチーム
http://www.asahi.com/jsec/
■あいちサイエンスフェスティバル2013
9月28日(土)〜11月4日(月・祝)
会場:蒲郡市生命の海科学館など
▷惑星地球フォトコンテスト入賞作品展
日本地質学会 共催
https://aichi-science.jp/
■国際ミネラルアート&ジェム展 IMAGE 2013
10月4日(金)〜7日(月)
場所:ハイアット・リージェンシー東京/小田急第一生命ビル1F
スペースセブンイベント会場ほか
http://www.tima.co.jp
■第2回G-EVER国際シンポジウム,第1回IUGS・日本学術
会議国際ワークショップ〜アジア太平洋地域の災害とリスク
マネジメント: 沈み込み帯の地震・津波・火山噴火・地すべり
日本地質学会 共催
10月19日(土)〜20日(日)[21日巡検あり]
場所:仙台市情報・産業プラザ
参加登録:9/15(登録料無料,先着70名)
http://g-ever.org/en/symposium/symposium2.html
■山陰海岸ジオパーク国際学術会議「城崎会議」
日本地質学会ほか 後援
テーマ:自然の恵と災害
10月26日(土)・27日(日)
場所:城崎温泉西村屋ホテル招月庭(兵庫県豊岡市城崎町)
要旨提出締切:9月6日(金)
http://www.sanin-geo.jp/
■第39回リモートセンシングシンポジウム
日本地質学会 協賛
11月25日(金)
場所:東京農業大学世田谷キャンパス
申込締切:11/1 講演申込締切:10/15
http://www.sice.jp/
■第29回ゼオライト研究発表会
日本地質学会 協賛
11月27日(水)〜28日(木)
会場:東北大学
http://www.jaz-online.org/index.html
■第3回学生のヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集
日本地質学会ほか 推薦
実習実施時期:2014年3月5日(水)出発,19日(水)帰国(15日間)
申込締切:11月30日(土)
実習コース:カトマンズ−ポカラ−ムクチナート−タンセン−ルンビニ
参加費用:学生・大学院生20万円以内、その他の個人参加者25万円以内、
大学・企業などの組織派遣教員/社員30万円以内
http://www.geocities.jp/gondwanainst/
■日本地球惑星科学連合2014年大会
2014年4月28日(月)〜5月2日(金)
会場:パシフィコ横浜会議センター
(横浜市西区みなとみらい1-1-1)
予稿集原稿投稿募集:2014年1月08日(水)〜2月12日(水)
http://www.jpgu.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/outline/content0098.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■信州大学:理学部地質科学科(助教:テニュア・トラック)(11/29)
■信州大学:理学部物質循環学科(助教:テニュア・トラック)(11/15)
■海洋研究開発機構:研究部門 上席研究員(9/30)
■海洋研究開発機構:研究部門 ポストドクトラル研究員(10/25)
■海洋研究開発機構:研究部門 任期制職員
【研究職、技術研究職、技術総合職、ポストドクトラル研究員】(11/8)
■第17回尾瀬賞の募集(9/30)[募集期間延長]
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flash No.236 (臨時)国際地学オリンピック 金メダル受賞!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.236 2013/9/20 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】国際地学オリンピック 金メダルおめでとう!
【2】「災害の軽減に貢献するため・・」に関するパブリックコメントの募集
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】国際地学オリンピック 金メダルおめでとう!
──────────────────────────────────
インドのマイソールで9月11日〜19日の日程で開催されていた第7回国際地学オリンピックで日本選手が金メダル1個、銀メダル3個を獲得しました。
受賞者は以下のとおりです。
金メダル
安藤 大悟さん 灘高等学校(兵庫県)(3年)
銀メダル
桑原 佑典さん 開成高等学校(東京都)(3年)
安河内健志朗さん 栄光学園高等学校(神奈川県)(3年)
八幡 幸太郎さん 筑波大学附属駒場高等学校(東京都)(3年)
安藤大悟さんは、気象・海洋科学部門の部門トップ賞も受賞されました。
おめでとうございます。
以下の引率者のブログで、地学オリンピック参加者の現地での活発な活動の様子などが紹介されています。
http://blogs.yahoo.co.jp/akitachigaku/
来年は国際地学オリンピック アメリカ大会です。
それに向けた日本地学オリンピック予選は12月15日に行われます。
中学・高校生のみなさん、チャレンジしてみませんか?
詳しくは、地学オリンピック日本委員会のホームページから。
http://jeso.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】「災害の軽減に貢献するため・・」に関するパブリックコメントの募集
─────────────────────────────────
会員各位
文部科学省科学技術・学術審議会測地学分科会(藤井敏嗣委員長)は,「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画の推進について」(中間まとめ)に関するパブリックコメントを求めています。
【意見募集期日:10月3日(木)】
会員の皆様におかれましても中間まとめをご一読下さい.ご意見を提出される場合は,参考までに別途地質学会[main@geosociety.jp]にもお知らせ頂ければ幸いです。
学会に対しても意見が求められていますので,各専門部会等からの意見を集約し,コメントを提出する予定です。
「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画の推進について」(中間まとめ)に関する意見募集の実施の詳細については,下記URLをご参照ください。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000653&Mode=0
(日本地質学会執行理事会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
「日本からみつかった巨大隕石衝突の証拠」発表までの道のり
「日本からみつかった巨大隕石衝突の証拠」発表までの道のり
佐藤峰南(九州大学大学院理学府 博士課程2年)
三畳紀層状チャートの露頭で有名な岐阜県坂祝(さかほぎ)町の木曽川河床では,隕石衝突により堆積した粘土岩が観察されます(図1).2013年9月16日,この粘土岩についてオスミウム同位体分析を行った著者らの研究成果がNature Communications誌に掲載されました(Sato et al., 2013).本稿では,多くのメディアに取り上げていただきましたこの研究のきっかけや経緯につきまして,自身の経験談を中心にご紹介させていただきます.なお詳しい研究の内容は,プレスリリース資料(http://www.sci.kumamoto-u.ac.jp/~onoue/press.pdf)に掲載してあります.
図1 オスミウムの同位体分析により隕石衝突の証拠が発見された粘土岩の写真.図中の番号はオスミウム同位体分析に用いたサンプル番号.岐阜県坂祝町.
研究が始動したのは2009年春,私が研究室に配属されてからはじめての調査でした.「三畳紀後期は複数の隕石衝突が起きた時代」というキーワードのもと,研究対象は三畳紀後期の遠洋性堆積物である美濃帯犬山の層状チャートに決まりました.最初は先行研究による放散虫化石年代に基づき,あてもなくひたすら三畳紀後期のチャートに挟まれる頁岩を単層ごとに採取していきました.4年生になったばかりの私は,これが卒論のテーマということで,大きな賭けをする気持ちでした.
持ち帰ったサンプルを粉末にし,大きさ数10ミクロンの磁性鉱物を1つずつ拾い出す作業がしばらく続いたあと,SEMを用いて反射電子像を撮影していきました.このとき,真球状の宇宙塵とは明らかに異なる多角形の粒子が大量に含まれているサンプルがあることに気づきました.EDXで元素の定性分析を行うと,Niのピークがあらわれました.これは,白亜紀/古第三紀境界から報告されている隕石衝突起源粒子と同じ粒子を発見した瞬間です(佐藤・尾上,2010).その後は,薄片作成,スフェルールの回収にはじまり,白金族元素の定量分析,オスミウム同位体分析など,私にとっては全く未知の「分析」という研究がはじまっていきました.なんとしても隕石衝突を証明したいと,その一心でした.
図2 オスミウム同位体分析に用いた粉末試料.NH52-R2のサンプルは,隕石衝突により形成された球状粒子(スフェルール)を含む.
修士2年の地球惑星科学連合大会期間中,オスミウム同位体分析による隕石衝突の証拠解明を行うため,海洋研究開発機構地球内部ダイナミクス領域(IFREE)の鈴木勝彦主任研究員および野崎達生研究員と共同研究のお話をさせていただきました.当時指導教員であった尾上哲治准教授(当時鹿児島大学助教)と4人でテーブルに座り,面接のようなやりとりが繰り広げられました.「大丈夫か,頑張れるか」という問いに,私は「はい」と答えるほかありませんでした.しかし,学部時代に化学実験すら受講していなかった私は,本当に大丈夫なのだろうかと不安でしょうがなかったです.その後,共同研究がスタートし,とりあえず私はひたすら粉末サンプルを作成しはじめました.チャートの風化していないきれいな面を岩石カッターで切り出し,メノウ乳鉢でゴマ粒ほどの大きさに粉砕します.そのあと,脈などをピンセットでひとつひとつ丁寧に取り除き,粉砕用ボールミルにサンプルを投入するまでにはかなりの時間を要します.チャートは硬く,何度もメノウ乳鉢を投げ捨てたい衝動にかられました.全27サンプルを作り終えたのは作り始めてからどれくらいの期間が過ぎた頃でしょうか,その日は朝2時を過ぎたあたりで,一人実験室でテンションがあがり,小さな瓶に詰められたふわふわのサンプルを並べて,写真を撮ったのを覚えています(図2).露頭でのサンプル採取からはじめたこの粉末サンプルたちは,この時から愛着が湧き,手放せないものになりました.
大事なサンプルたちを抱えて,夏休みに3週間ほどの間,海洋研究開発機構IFREEに設置されているマルチコレクター誘導結合プラズマ質量分析装置(MC-ICP-MS)での分析が始まりました.オスミウムの含有量は極微量なうえ,酸化されると揮発するというやっかいな性質をもつため,分析までの試料作成はこれでもかというくらい注意をはらって行わなければなりませんでした.初日は手の指と肩が筋肉痛になりましたが,野崎さんは前処理を丁寧かつ的確に指導してくださいました.あとから考えると,もう絶対にやりたくない(その後も2回分析させていただくことになったのですが…もちろんデータが必要なためですが,意外とやみつきになるものです)と思うのですが,その時は必死で,今自分がしている作業はどういう意味があるのかを逐一確認して頭に詰め込むことで精一杯で,どきどきしながらの毎日でした.
肝心の隕石衝突層準と思われるサンプルは,最後に測定が行われました.結果が出てくるまでは,不安で分析装置の前から片時も離れることはできません.オスミウム同位体分析の最後のデータが出たとき,これまで分析に関することを1から教えて下さった野崎さんとガッツポーズして喜んだことを今でもよく覚えています.ハイタッチまでしたかもしれません.隕石衝突を証明した瞬間でした.今回発表された論文で強調した「隕石衝突の絶対的な証明」として行ったオスミウム同位体分析の成功です.
首都大学東京では,海老原充教授の研究室でICP-MS分析装置をお借りし,白井直樹助教のご指導のもと白金族元素の定量分析が行われました.博士1年になった夏のことです.当たり前ですが,実験室は非常にクリーンな状態が保たれており,窓を開けることはできません.真夏の実験室で毎日立ちくらみを起こしながら,ご飯も食べずに実験に打ち込む日々でした.前処理が終わっていよいよ測定日となったとき,夜通し機器を止めずに測定することに決めた白井先生と私は,今度はクーラーで管理された寒い空間で24時間戦うことになりました.
その日,夜遅くなって,海老原先生がコーヒーをいれてくださり,「少しあたたまったらどうですか」と声をかけて下さいました.交代で研究室に戻ると,そこには何も言わずにお寿司のお弁当が置いてありました.慣れない環境とはじめての分析で気づかないうちに疲れがたまっていた私は,その優しさに一人号泣してしまいました.本当に私は人に恵まれてここまでこられたのだとつくづく思います.
分析をしている間はとにかく必死でしたが,そのあとに待っているのはもちろん論文執筆です.はじめての国際誌ということで,分からないことばかりでした.投稿規定を把握するだけでも,ものすごい時間を要しました.海洋研究開発機構の方々の後押しにより,Nature Geoscienceに投稿するという恐ろしい事態に直面しましたが,投稿からわずか4日でリジェクトの通知が届きました.その後は,次の投稿に向けて原稿を修正し,Nature Communicationsへリベンジです.編集者から「査読にまわした」と連絡がくるまで,私の睡眠時間は4時間をきっていました.夜中になると,イギリスの時間が気になり,メールの更新ボタンを何度も押してしまっていました.約1ヶ月後に3人の査読者からコメントが届いてからは,また怒濤の日々の始まりです.再分析のため粉末サンプルを作り直し,もう一度野外調査に行き,海洋研究開発機構でオスミウム同位体分析を行いました.そして,それを論文に加筆し,査読者のコメントに答える…私の脳みそは毎日沸騰しっぱなしで,お風呂に入ると明らかに抜け毛が多くぎょっとしました.このようにつらいことばかりだったように思われますが,共著者の方々は,私の目茶苦茶な英語に丁寧にコメントを下さり,なぜその書き方がだめなのか,レクチャーしていただくことさえありました.私はこの論文が少しずつ前に進むたび,本当にこのメンバーで研究できて幸せだなと感じていました.なんだか,ファミリーのような気持ちになっていたのです.
2度目のレスポンスを提出してから約3週間後,編集者から論文受理のメールが届きました.なかなかメールを開けず,挙動不審になっていた私を,研究室にいた後輩は何も言わず見守っていてくれました.声が震えながら尾上先生に電話をすると,だめだったのか…という反応でしたが,私が内容を伝えると,おそらく電話の向こうで拳を突き上げていたのではないかというくらい絶叫していました.査読者の1人は,最初はかたくなに出版を拒んでいましたが,受理が決まったとき,「私の挑発的な問いに負けず,よく頑張った.これはこの雑誌に掲載されるに値する」というコメントをつけてくださいました.またしても号泣です.喜んだのもつかの間,出版にあたり細かな修正やプレスリリースの準備に追われながらも,だんだんと実感が湧いてきました.文部科学省で行った記者会見は緊張で震えましたが,たくさんのメディアに取り上げていただき本当に嬉しかったです.そして何より,雑誌のホームページに論文が掲載された画面をみたときは,なんとも言い表せないほど嬉しい気持ちになりました.
地質学を通して,2億1500万年前に起きた隕石衝突による残骸が,今自分の手の中にあるという実感を得られたことは,とても幸せなことだと思います.そして,分析の結果をみて,なぜそうなったのかと,もう一度露頭に行き観察する,その繰り返しが,とても難しく,そしてとても楽しいです.
運の強さと素敵な指導教員,今まで出会ったすべての共同研究者の方々に恵まれ,今回このような結果を残すことができました.そして,論文を執筆するにあたり,頼りない筆頭著者にご助言・ご指導いただき支え続けてくださった共著者の皆様に心から感謝いたします.
【文献】
佐藤峰南・尾上哲治,2010,中部日本,美濃帯の上部トリアス系チャートから発見したNiに富むスピネル粒子.地質雑,116,575-578.
Sato, H., Onoue, T., Nozaki, T. and Suzuki, K., 2013, Osmium isotope evidence for a large Late Triassic impact event. Nature Communications, 4, 2455, doi:10.1038/ncomms3455.
(2013.9.26)
geo-Flash No.237 コラム:「日本からみつかった巨大隕石衝突の証拠」発表までの道のり
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.237 2013/10/1 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2014年度代議員および役員選挙について
【2】2014年度学会各賞募集開始
【3】地質学雑誌では図版を廃止しました
【4】コラム:「日本からみつかった巨大隕石衝突の証拠」発表までの道のり
【5】2013年度秋季地質調査研修:参加者募集
【6】名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2014年度代議員および役員選挙について
─────────────────────────────────
10月7日(月)から、「代議員」の立候補届の受付が開始されます。選挙告示は9月号のNews誌に掲載されておりますので、選挙規則類、実施の要点等の詳細については、そちらを参照してください。
代議員立候補受付期間
10月7日(月)〜11月6日(水)*最終日18時必着
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
※「会員のページ」の選挙に関する案内から、立候補届の書式がダウンロードできるようになっています。
○会員番号・パスワードによるログインが必要です。
ログインの方法はこちら。
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2014年度学会各賞募集開始
─────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして、研究の援助・奨励および研究業績の表彰を行っています(定款第3条)。
本年も各賞の自薦、他薦による候補者を募集いたします。期日厳守にて、たくさんのご応募をお待ちしております。
応募締切:2013年11月30日(土)必着
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
※「会員のページ」の各賞推薦候補者募集に関する案内から、推薦書式等がダウンロードできるようになっています。
○会員番号・パスワードによるログインが必要です。
ログインの方法はこちら。
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】地質学雑誌では図版を廃止しました
─────────────────────────────────
地質学雑誌を含め,かつては学術誌の印刷の品質が低かったため,重要な証拠写真は図版として本文とは違う光沢紙に印刷し,論文の末尾に添付するのが普通でした.このほど地質学雑誌では,図版を廃止することになったことをお知らせします.
廃止の理由は,まず,地質学雑誌でも全ページにコート紙を用いるようになり,紙質と印刷の品質において,図版と本文とのあいだで差がなくなったことが挙げられます.また,図版にはページ番号が振っていないので,図版があるとページ数の見積もりや出版費の計算などの事務が繁雑になります.
さらにまた,図書館を通じて論文の複写依頼をする際,ページ番号がないことが落とし穴になって,図版部分が欠如したコピーが送られて来るというような事もおこっています.地質学雑誌で図版を含む論文は,最近は年に1編程度であり,図版がなくても 1ページ大の写真は掲載できるので,廃止による不都合はないと判断したわけです.
図版の廃止を趣旨とした「地質学雑誌投稿編集出版規則」改正案は,本年9月の理事会で承認されました.今後も地質学雑誌への投稿をお願いします.
地質学雑誌投稿編集出版規則
http://www.geosociety.jp/publication/content0002.html#touko
地質学雑誌編集委員会委員長 山路 敦
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】コラム:「日本からみつかった巨大隕石衝突の証拠」発表までの道のり
─────────────────────────────────
三畳紀の巨大隕石落下の証拠が日本で見つかったという報告が、Nature Communications (2013/9/16版) に掲載され、報道でも大きな話題となりました。
この研究を進めてきた佐藤峰南会員と尾上哲治会員には、昨年の小藤賞、尾上会員には2005年の研究奨励賞と今年の小澤儀明賞が地質学会より授与されており、これまで学会として応援してきた研究が大きな成果を挙げたことを喜ばしく思います。
今回、この研究を中心となって進めてこられた佐藤会員に、研究のきっかけやこれまでの経緯を紹介していただきました。
----------------------------
佐藤峰南(九州大学大学院理学府 博士課程2年)
三畳紀層状チャートの露頭で有名な岐阜県坂祝(さかほぎ)町の木曽川河床では,隕石衝突により堆積した粘土岩が観察されます(図1).2013年9月16日,この粘土岩についてオスミウム同位体分析を行った著者らの研究成果がNature Communications誌に掲載されました(Sato et al., 2013).本稿では,多くのメディアに取り上げていただきましたこの研究のきっかけや経緯につきまして,自身の経験談を中心にご紹介させていただきます.
続きはこちらから.
http://www.geosociety.jp/faq/content0477.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2013年度秋季地質調査研修:参加者募集
──────────────────────────────────
地質調査法の基本技術の修得をめざすとともに,それをベースに得られた過去の調査や研究の成果についても学びます.地質調査の経験のない方でも,地質調査法の基本を体で習得することを目指します.
日程:2013年11月18日(月)〜22日(金)4泊5日
場所:千葉県君津市及びその周辺地域(房総半島中部域)
募集人数:6名. 参加費:12万円
申込締切:2013年10月18日(金)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/engineer/content0033.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】 名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
──────────────────────────────────
日本地質学会では,学会員相互の交流と親睦を図る目的で,2年ごとに会員名簿を発行することを運営規則にうたっております.2013年はその発行年にあたり,本年11月末日発行の予定で準備を行っております.
名簿の発行様式は前回と同様で,全会員を収録します.本会としては,個人情報保護法の制約はあるとしても,会員の皆様が上記の目的に沿って利用できるような,従来規模の名簿を作成したいと考えておりますので,調査の実施にご理解とご協力をお願いいたします.
アンケート提出およびWeb画面更新締切日:2013年10月4日(金)
詳しくは,コチラ↓
http://www.geosociety.jp/outline/content0132.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】 支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■富士山巡検
11月2日(土)〜3日(日):1泊2日(雨天決行)
参加費用:一般15,000 円、学生・院生10,000 円
案内者:千葉達朗氏(アジア航測株式会社)
申込締切:10月18日(金)
申込方法・振込方法等詳細はこちら
http://kanto.geosociety.jp/junken/130903_fujijyunken.pdf
申込・問合先:細根 清治[(株)東建ジオテック]
E-mail: s.hosone@tokengeotec.co.jp
Tel: 080-1201-7453 FAX: 048-826-0151
■関東支部『地質研究サミット』シリーズ「伊豆衝突帯地質研究サミット」(第2報)
11月23日(土)〜24日(日)
地質学,地下構造探査,地学防災減災リテラシーなどの様々な角度から議論します.
会場:横浜国立大学・教育文化ホール → http://www.ynu.ac.jp/access/
(横浜駅西口バス乗り場10番より相鉄バス「浜10系統」乗車、「岡沢町」下車、徒歩5分)
■関東支部ミニ巡検シリーズ「丹沢ミニ巡検」
11月30日(土)〜12月1日(日):1泊2日
それぞれ詳細は関東支部Webサイトへ → http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地球にわくわく小・中学生自由研究コンテスト
募集締切:10月31日(木)
応募資格・部門:小学生2部門(3・4年生、5・6)年生、中学生1部門
問い合わせ先:wakuwaku@jeso.jp
地学オリンピック日本委員会HP http://jeso.jp/
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//olympic/2013waku.jpg
■第11回高校生科学技術チャレンジ研究作品募集
募集締切:10月7日(月)
応募資格:国内の高校生・高等専門学校生(3年生まで)、個人またはチーム
http://www.asahi.com/jsec/
■あいちサイエンスフェスティバル2013
9月28日(土)〜11月4日(月・祝)
会場:蒲郡市生命の海科学館など
▷惑星地球フォトコンテスト入賞作品展
日本地質学会 共催
https://aichi-science.jp/
■講演会『地球深部探査船「ちきゅう」が解き明かす東北沖地震の謎』
10月12日(土)14:00〜
場所: 東北大学片平キャンパス さくらホール(2階)
講師: 斎藤 実篤(海洋研究開発機構地球内部ダイナミクス領域)
参加登録不要 入場無料
http://www.cneas.tohoku.ac.jp/news/2013/news130910_1.html
■第2回G-EVER国際シンポジウム,第1回IUGS・日本学術会議国際ワークショップ
〜アジア太平洋地域の災害とリスクマネジメント: 沈み込み帯の地震・津波・火山噴火・地すべり
日本地質学会 共催
10月19日(土)〜20日(日)[21日巡検あり]
場所:仙台市情報・産業プラザ
参加登録[受付終了]
http://g-ever.org/en/symposium/symposium2.html
■山陰海岸ジオパーク国際学術会議「城崎会議」
日本地質学会ほか 後援
テーマ:自然の恵と災害
10月26日(土)・27日(日)
場所:城崎温泉西村屋ホテル招月庭(兵庫県豊岡市城崎町)
http://www.sanin-geo.jp/
■第24回地質汚染調査浄化技術研修会
日本地質学会環境地質部会 ほか 共催
11月22日(金)〜24日(日)
会場:NPO法人日本地質汚染審査機構本部ミーテング・ルーム
http://www.npo-geopol.or.jp
■第39回リモートセンシングシンポジウム
日本地質学会 協賛
11月25日(金)
場所:東京農業大学世田谷キャンパス
申込締切:11/1 講演申込締切:10/15
http://www.sice.jp/
■森里海連環学国際シンポジウム
11月26日(火)〜28日(木)
場所:京都大学芝蘭会館
http://fserc.kyoto-u.ac.jp/isymposium/
■第29回ゼオライト研究発表会
日本地質学会 協賛
11月27日(水)〜28日(木)
会場:東北大学
http://www.jaz-online.org/index.html
■第6回 惑星科学実験実習
大学院生を対象とした『惑星科学実験実習』を開催します.
惑星科学という名前を冠しておりますが,固体地球科学も広く対象としています.
奮ってご参加下さい.
対象者 :地球惑星科学を志す大学院生
申込締切:10 月 18 日 (金)
テーマ A:レーザーアブレーションによる衝突蒸気の高速分光実験
場所:東京大学柏キャンパス
日程:12 月2日 - 4日
テーマ B:高速度での堆積岩へのクレーター形成実験
場所:宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所
日程:11月5日 -7日
テーマ C:砂へのクレーター形成実験と放出物のその場観測
場所:神戸大学六甲台キャンパス
日程:11月 11日 - 13日
テーマ D:レーザ誘起絶縁破壊分光装置(LIBS)を用いた野外における岩石のその場測定
場所:千葉工業大学津田沼キャンパス
日程:11月27日 - 29日 or 12月11日 - 13日
http://impact-res.sakura.ne.jp/lab-training/index.html
http://impact-res.sakura.ne.jp/lab-training/2013/adv2013-1stcircular.html
■第3回学生のヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集
日本地質学会ほか 推薦
実習実施時期:2014年3月5日(水)出発,19日(水)帰国(15日間)
申込締切:11月30日(土)
実習コース:カトマンズ−ポカラ−ムクチナート−タンセン−ルンビニ
参加費用:学生・大学院生20万円以内、その他の個人参加者25万円以内、大学・企業などの組織派遣教員/社員30万円以内
http://www.geocities.jp/gondwanainst/
■日本地球惑星科学連合2014年大会
2014年4月28日(月)〜5月2日(金)
会場:パシフィコ横浜会議センター
(横浜市西区みなとみらい1-1-1)
予稿集原稿投稿募集:2014年1月08日(水)〜2月12日(水)
http://www.jpgu.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/outline/content0098.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■山田科学振興財団2014年度研究援助候補推薦(2/28 学会締切1/31)
■第17回尾瀬賞の募集(10/31)[募集期間延長]
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.244 フォトコン作品募集中!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.244 2013/12/3 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】第5回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中!
【2】2014年度会費払込のお知らせ:割引申請は忘れずに!
【3】支部情報
【4】その他のお知らせ
【5】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】第5回惑星地球フォトコンテスト 作品募集開始!
─────────────────────────────────
今年もフォトコンテストの募集が始まりました。たくさんのご応募お待ちしています。
【こんな作品を大募集!】
・惑星地球の美しい自然
・地層や火山など活きた地球の姿を表す優れた作品
・学術的意義の高い作品(解説文を含む)
・ジオパークに関係する優れた作品
・「ジオ鉄」の優れた作品学術的・教育的な価値のある優れた作品
・そのほか地球科学に関係した作品
締切:2014年1月31日(金)17:00
応募方法など詳しくは, http://photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2014年度会費払込のお知らせ:割引申請は忘れずに!
─────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下さいますようお願いいたします.
■2014年度分会費の引き落とし日:12月24日(火)です.
請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下さい.
■自動引き落とし以外の方(お振り込み)
12月中旬頃までに請求書兼郵便振替用紙をお送りいたします.折り返しご送金くださいますようお願いいたします.
■割引会費申請(院生・学部学生):最終締切 2014年3月31日(月)
忘れずにご提出下さい。
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0135.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】 支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■功労賞募集
関東支部では,支部の顕彰制度に基づき,支部活動や地質学を通して社会貢献された個人・団体等を関東支部として顕彰いたします.つきましては,今年度も下記の要領で支部会員の推薦を募集します.積極的なご推薦をお待ちしております.
対象者:支部活動や地質学を通して広く社会貢献をされた関東支部内に在住の個人・団体等
*社会貢献や活動の評価においては,必ずしも学問的な成果を問うものではありません.
公募期間:2013年12月16日〜2014年1月19日
選考期間:2014年1月20日〜2014年2月10日
<関東支部功労賞審査委員会(委員長:中山俊雄 前支部長)を設置>
審査結果報告:NEWS誌、支部会員ML、関東支部総会
推薦方法:対象者氏名,推薦者氏名,推薦理由(400字程度)を記入の上,関東支部功労賞推薦としてメールもしくはFAXにて下記へお送りください.
推薦受付:神奈川県立生命の星・地球博物館 笠間友博(幹事長)
〒250-0031 小田原市入生田499
E-mail:kasama@nh.kanagawa-museum.jp ,FAX:0465-23-8846
[西日本支部]
■平成25年度総会・第165回例会
2014年2月22日(金)[21日:幹事会]
場所:佐賀大学,本庄キャンパス,大学会館
講演申込み〆切:2月5日(水)12時
*総会へ欠席の方は,委任状をお送り下さい。
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■2013年度東京大学地震研究所共同利用研究集会
「地震の研究者と小・中・高等学校教員との連携
−地震教育の現状に即した知識普及活動を目指して−」
12月26日(木)〜27日(金)
会場:東京大学地震研究所1号館2階セミナー室
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/index-j.html
■第59回セミナー「水道資源の新たな水質危機と対応の最新動向」
2014年2月3日(月)
場所:自動車会館大会議室(千代田区九段南4-8-13)
定員:先着160名 要申込
https://www.jswe.or.jp/event/seminars/index.html
■第3回学生のヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集
日本地質学会ほか 推薦
実習実施時期:2014年3月5日(水)出発,19日(水)帰国(15日間)
申込締切:11月30日(土)
http://www.geocities.jp/gondwanainst/
■日本地球惑星科学連合2014年大会
2014年4月28日(月)〜5月2日(金)
会場:パシフィコ横浜会議センター(横浜市西区みなとみらい1-1-1)
予稿集原稿投稿募集:2014年1月8日(水)〜2月12日(水)
http://www.jpgu.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/outline/content0098.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■高知大学:海洋コア総合研究センター公募(特任助教)(2014/1/17)
■海洋研究開発機構:地球内部物質循環研究分野 研究職/技術研究職公募(12/27)
■三菱財団 平成26年度助成金公募(自然科学:2014/1/7-2/4)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.240
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.240 2013/10/30 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2014年代議員選挙立候補届 受付締切迫る!
【2】2014年度学会各賞募集 受付中
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2014年度代議員選挙立候補届 受付締切迫る!
─────────────────────────────────
■2014年度代議員選挙立候補届 受付中
受付締切:11月6日(水)18時必着(郵送またはe-mailで)
立候補届けを受け取りましたら,必ず立候補者へ受領書を発行いたしますので,
ご確認下さい。
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
(上記より立候補届書式等がダウンロードできるようになっています。)
○会員番号・パスワードによるログインが必要です。
ログインの方法はこちら。
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2014年度学会各賞募集 受付中
─────────────────────────────────
■2014年度学会各賞募集 受付中
応募締切:11月30日(土)必着
今年は,応募締切が例年より1ヶ月早くなっています。お間違えのないよう
お早めにご応募下さい。
ご応募頂いた場合は,必ず受取のお返事をお出しますので,ご確認下さい。
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
(上記より,推薦書式や対象論文リスト等がダウンロードできるようになっています。)
○会員番号・パスワードによるログインが必要です。
ログインの方法はこちら。
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
韓国2013秋季地質科学連合学術大会(大韓地質学会第68次定期総会)公式訪問の報告
韓国2013秋季地質科学連合学術大会(大韓地質学会第68次定期総会)公式訪問の報告
日本地質学会会長 石渡 明
図1.2013年10月23日に済州島で行われた大韓地質学会・日本地質学会の公式会談の 出席者。前列左からYu, Kang-Min(兪剛民)会長、石渡明、後列左からChoi, Weon Hack,(崔元学)総務理事、Simon Wallis副会長、Cho, Moonsup(趙文燮)副会長、Lee, Jin-Yong(李珍容)理事。
標記の大会は2013年10月23日〜27日、韓国済州島のフェニックス・アイランドで開催された。昨年の日本地質学会大阪大会で延長締結された大韓地質学会との学術交流協定に基づき、日本地質学会会長 石渡 明(筆者)と副会長Simon Wallisが公式に招待された。ここでは、標記学会に参加しての見聞を簡単に報告する。
この学会の主幹は大韓地質学会であり、共同主催は大韓資源環境地質学会、韓国古生物学会、韓国鉱物学会、韓国岩石学会である。また、後援は韓国科学技術団体総連合会、韓国地質資源研究院(KIGAM)、韓国ガス公社、現代(ヒュンデー)資源開発であり、プログラムに広告を出している企業・公団などとしては、三星(サムスン)、大宇(デーウー)、コーチャン石材事業団、Geo-Marine-Technology(釜山)、韓国石油公社(NOC)、韓国鉱物資源公社(KORES)、韓国海洋科学技術院(KIOST)、韓国原子力環境公団(KORAD)、大韓資源開発などがある。
簡略化して日本語に訳したこの学会のプログラムを次に掲げる。
図2.懇親会会場にて大韓地質学会のYu, Kang-Min(兪剛民)会長と日本地質学会のWallis副会長。
23日午前10時から両学会の公式協議が行われた。出席者を図1に示す。大韓地質学会からは、会員数が約1500人で、毎年100人程度ずつ増加していること、予算規模が拡大していること、会長選挙の結果が今回の総会で発表され、理事のほとんどが交代して2014年1月に新執行部が発足すること、2年後に70周年記念事業を計画していること、英語ホームページを作成中であることなどが説明された。日本地質学会からは来年の鹿児島大会でロンドン地質学会と共催の津波堆積物に関するシンポジウムが行われる予定であること、Geology of Japanの編集が進行中であること、5年後に125周年記念事業を計画していることなどを説明し、日本地球惑星科学連合大会やAOGS札幌大会などについての情報も伝えて、多くの大韓地質学会会員が2014年に日本へ来られるようにとの期待を表明し、贈り物を交換した。日本側からはフィールドジオロジー全巻セットと化石チョコレートなどを贈った。韓国側からはトルハンバン(済州島独特の石像)とタオル、済州島観光案内書などが贈られた。
図3.懇親会会場で行われたポスター賞の授賞式。中央は兪会長。
セッションは10月23日の午後から10月25日の午前まで、5つの会場で行われた。ポスター発表は23・24日の2日間掲示でき、コアタイムは24日の17:50-19:00であった。大韓地質学会総会は24日の13:00-15:00に行われた(その間はセッションなし)。25日の午後は「一般踏査」(巡検)が行われ(後述)、26日と27日にも教師向けの地質踏査と火山踏査が行われた。本大会には大韓地質学会会員約1500人のうち約600人が参加したとのことである。プログラムを数えたところ、口頭184件、ポスター238件、計422件の発表があった。欠席率は非常に低いようだった(全部で数件?)。Wallis副会長は「南チベットの東西伸長の年代と構造的重要性」について23日午後の大陸衝突セッションで講演した。このセッションは大人気で100人程度の聴衆がいた。石渡は「東北アジアのオフィオライト帯とP型オフィオライトの重要性」について24日午前のGlobal Tectonicsのセッションで講演したが、このセッションの聴衆は30人程度だった。3日目の地球化学のセッションの聴衆は15人程度だった。ポスター発表は半分程度が韓国語のみで書かれており、英語のタイトルや説明がついているものが3割程度、全部英語で書かれているものが2割程度であった。いくつか質問したところ、学生の英語力はかなり高いようだった。
総会では、大韓地質学会Yu, Kang-Min(兪剛民)会長、私、KIGAM(韓国地質資源研究院)Kim, Kyu Han(金奎漢)院長の挨拶に続いて、表彰式、会計報告、選挙結果の報告などがあったが、その間に私とWallis副会長は別室で金院長と会談した。金院長は名古屋大学出身だそうで、京都大学出身の兪会長と同様に日本語が達者である。彼らにはとても及ばないが、私の挨拶にも若干韓国語を交えた。この総会では、2009年にIsland Arc賞を受賞したOh, Chang Whan(呉昌桓)教授が今年度の最優秀科学者賞を受賞した。彼は韓国岩石学会の現会長である。選挙により、大韓地質学会の新会長にはCheong, Daekyo(鄭大教)教授(江原道春川市 江原国立大学地質学科)が選出された(2014年1月着任予定)。鄭教授は日本の研究者に知り合いが多く、韓国で博士号を取得した江川浩輔氏(産総研)の指導教官だったそうで、米国イリノイ大学などに留学経験がある。現副会長の趙文燮(Cho, Moonsup)教授は残念ながら当選を逃した。
24日夕刻の懇親会は、立食ではなく、多数の円卓を囲んで530席が用意され(図2)、料理も非常に豪華だった。懇親会のはじめにポスター賞や写真コンテストの表彰式があり(図3)、兪会長、私、Wallis副会長らが挨拶した。そして88歳のソウル大学名誉教授Lee, Sang Man(李商萬)先生(岩石学、趙文燮副会長の元指導教官)の発声で乾杯した。その後もChang, Ki-Hong(章基弘)先生をはじめ老先生や来賓の挨拶などが沢山あったが、歌や踊りなどのイベントはなかった。
図4.済州島東部の火山巡検で訪れた竜臥岳山頂にて。後方に風車とスコリア丘が見える。左からWallis副会長、井上大榮博士、Choi, Weon Hack(崔元学)総務理事、石渡。
25日の午後、私とWallis副会長は大韓地質学会総務理事のChoi, Weon Hack(崔元学)氏とともに済州島東部の火山巡検に参加することができた(図4)。この巡検の案内者は米国陸軍極東工兵団に所属するPak, Chun-Pom(朴埈範)博士で(図5)、参加者は大型バス1台分(40人程度)であった。博士は軍人らしい精悍な感じの人だが、いろいろ親切に教えてくれた。海岸沿いのマントル捕獲岩の産地とスコリア丘(竜臥岳、ヨンヌニオルム)を見たところで時間切れとなり、我々は帰国のため空港に向かったが、巡検隊はその後水中火山活動の産物を見たはずである。なお、巡検の途中で聞いた崔氏の話では、済州島は三多と三無の島だそうで、三多というのは風と石(玄武岩)と女(海女として男よりもよく働く)で、三無というのは水と門と盗(泥棒)だそうである。確かに竜臥岳山頂は強風で、眼下には多数の風力発電施設が見えた(図4)。点在するスコリア丘の間に牛や馬の放牧場が広がり、海岸にはハイアロクラスタイトの火山が城壁のようにそびえていて、非常に風光明媚な場所である。この島はユネスコの生物圏保全地域、世界自然遺産、そして世界ジオパーク(地質公園)に指定されている。
図5.済州島東部火山巡検の案内者、Pak, Chun-Pom(朴埈範)博士と石渡。
この公式訪問では日本地質学会と大韓地質学会の友好関係を深めることができたと思う。個人的にも、ご無沙汰していた多くの旧友と再会することができ、また新しい友人ができ、 そしてこの会に参加していた日本人研究者(多田隆二氏、竹村惠二氏、田中 剛氏、井上大榮氏ら)とも交流することができた。兪剛民会長、趙文燮副会長をはじめとする大韓地質学会幹部の皆様には、非常にデラックスなホテルとおいしい食事、レンタカーによる送迎などをお世話いただき、厚く感謝する。22日の非公式の夕食も非常に楽しかった。特に、大会全般を取り仕切って超多忙の中、我々の世話をして下さった大韓地質学会総務理事の崔元学博士と全日程にわたって運転手を務めて下さった江原国立大学大学院生のJeon, Woo-Hyun(全佑賢)氏に厚くお礼申し上げる。これを機会に、両学会の学術・教育交流が一層発展することを期待する。
(2013.10.31)
第2回G-EVER国際シンポジウム・第1回IUGS・日本学術会議国際ワークショップ 参加報告
The 2nd G-EVER International Symposium and the 1st IUGS & SCJ International Workshop on Natural Hazards and Risk Management in Asia-Pacific Region: Earthquake, Tsunami, Volcanic Eruption and Landslide in Subduction Zones
第2回G-EVER国際シンポジウム・第1回IUGS・日本学術会議国際ワークショップ
2013年10月19-20日、仙台市情報・産業プラザ(仙台駅西口前アエル6階)
主催:G-EVERコンソーシアム、 産総研地質調査総合センター、国際地質科学連合(IUGS)、日本学術会議(SCJ)
共催:日本地質学会、Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia (CCOP, 東・東南アジア地球科学計画調整会議)
後援:東北大学、京都大学防災研究所、防災科学技術研究所、フィリピン火山・地震研究所、日本地震学会、日本火山学会、日本第四紀学会、日本活断層学会、応用地質学会、東京地学協会
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
この国際シンポジウムは2012年2月22-24日につくば市で開催された第1回G-EVERワークショップ及び2013年3月11日に同市で開催されたG-EVER国際シンポジウムに次ぐもので、今回は2011年の東日本大震災の被災地の中心にある仙台市で2013年10月19-20日に開催された。2日間で口頭34件(あいさつを含む)とポスター26件の発表があり、翌21日には津波被災地域への巡検が行われた。G-EVERというのはGlobal Earthquake and Volcanic Eruption Risk Management(国際地震・火山噴火危機管理)の略である。また、21日からは仙台市国際センターでCCOP(東・東南アジア地球科学計画調整会議)が開催された。G-EVERは学術的、CCOPは実務的・政策的という印象だった。
冒頭、産総研地質調査総合センター所長でG-EVERコソーシアム会長の佃栄吉氏、IUGSのRoland Oberhänsli会長(ドイツ)、日本学術会議のIUGS日本支部代表松本良氏、CCOP事務局長のAdichat Surinkum氏の開会あいさつがあった。第1セッションは「自然災害への科学的挑戦と減災」と題して、IUGS事務局長のIan Labmert氏(オーストラリア)(地震・津波災害の減災に向けて)、日本地質学会会長の石渡明(東北大学)(東日本大震災の体験:地震・津波・原発事故)、水災害・リスクマネジメント国際センター(ICHARM) ・土木研究所(PWRI)の竹内邦良氏(2000年のMillenium Development Goalから2015年以後のSustainable Development Goalへ)、アラスカ大学・G-EVER副会長のJohn Eichelberger氏(遠隔地の火山噴火と航空機の安全)、シンガポールのChris Newhall氏(VEI≧7噴火予測への科学的・社会的挑戦)、産総研の宝田晋治氏(次世代火山災害評価システムとアジア太平洋地域災害予測地図)が講演した。
午後の第2セッションは「火山噴火、地すべり、地震災害」と題して、地震研の中田節也氏(霧島新燃岳2011年噴火)、カナダSimon Fraser大学のPeter Bobrowsky氏(オレゴンやアラスカの沈み込み帯地震に伴う地すべり)、山口大学の川村喜一郎氏(海底地すべりとその災害)、京都大学防災研の千木良雅弘氏(地震・降雨によって引き起こされる地すべり)、台湾の中国科学院のLin, Chen-Hong氏(地震観測網による地すべりの検知)、中国国家地震局の温瑞智氏(2013年4月20日の四川省廬山地震)、産総研の石川有三氏(ISC-GEM地震カタログ)、ベトナム科学技術アカデミーのNguyen Hong Phuong氏(フィリピン西方で発生する南シナ海の地震津波)が講演した。中国地質科学院(北京)のDong, Shuwen氏(四川省西部の2013年地震の地震テクトニクス)は欠席だった。この日の夕刻に仙台駅前の居酒屋で懇親会があった。
2日目の第3セッションは「災害評価、2011東北沖地震と沈み込みテクトニクス」と題してPilar Villamor氏(GEM全地球活断層データベース)、防災科学技術研究所のKen Xiansheng Hao氏(東アジア地域の地震災害評価図)(以上2件は前日に講演)、東北大学の松沢暢氏(東北沖地震前後の地震活動)、北海道大学地震火山研究観測センター所長の谷岡勇市郎氏(津波発生機構と迅速な津波予測、東北沖地震津波高の85%は断層運動、15%は地すべりによる)、テキサス大学のMark Cloos氏(沈み込み帯のタイプと東北沖地震)、京都大学防災研の西村卓也氏(東北沖地震を含む過去100年間の東北地方の地殻変動)、東京大学の池田安隆氏(中新世以後の東北日本のテクトニクスと東北沖地震)が講演した。
そして最後の第4セッションは「東北沖地震と津波」と題し、東北大学の後藤和久氏(津波堆積物の確認限界)、菅原大助氏(仙台平野の津波シミュレーション、津波堆積物の厚さは津波高の2%)、ニューサウスウェールズ大学のJames Goff氏(津波堆積物)、静岡大学の安藤雅孝氏(東北沖地震津波とその人的被害、浸水地域の平均死亡率5%、夜間だったら10万人死亡?)、オーストラリア国立大学のPhil Cummins氏(東北沖地震をジャワ、トンガに適用する)、米国Brigham Young大学のRonald Harris氏(インドネシア東部での大津波の可能性)、そして米国マイアミ大学のYildirim Dilek氏(Geopolitics: 自然災害が世界史を変えた…地中海での火山噴火による青銅器時代の終焉、アラビアの乾燥化によるイスラムの勃興と拡張、アイスランドの火山噴火によるフランス革命など)が講演した。最後に産総研地質調査総合センター元所長の加藤碵一氏が閉会のあいさつを行った。その後、1時間半をかけて、総合討論が持たれた。発表された研究のまとめと、強調すべき事柄の整理が各自から簡単に発表され、今後の研究の焦点や方向性などが議論された。会議後、Sendai Agreement が宣言されるとのことである。ポスター発表にも興味深いものが多数あったが、紙数の関係で割愛する。
図1.G-EVER会議のBobrowsky氏の講演で示された20世紀の「災害」による米国の死者数(John Pike氏作成。http://www.astrobio.net/debate/378/much-ado-about-nothing)。世界全体の災害や戦争による死者数の統計は、例えば次のウェブサイトを参照。
http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/4367.html
http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/5228.html
今回の講演で私が特に印象に残ったのは、カナダのBobrowsky氏が紹介した20世紀の米国の「災害」による死者数を示した円グラフである(図1)。データの根拠ははっきりしないが、伝染病、飢餓、戦争、気象災害、地震、火山噴火による死者数を比べると、戦争による死者が2/3を占め、残りの大部分は伝染病と飢餓による死者で、自然災害による死者は全部合わせても5%に満たないが、その中では気象災害による死者が多いとされている。しかし、20世紀の世界全体の統計を見ると、地震・地すべり・津波・火山噴火による死者は130万人以上に達し、気象災害による死者(約95万人)はこれより少ない。従って上の米国の統計は、地震が少なくハリケーン・竜巻などの気象災害が多いこの国の事情を反映していると考えられる。また、二度の世界大戦があった20世紀の戦争による世界の死者は約1億人に達するという統計があり、そうだとすると自然災害による死者は災害全体の2%弱になるはずである。これが図1で約5%になっているのは、米国が戦勝国で自国が戦場にならなかったため、戦争の死者が相対的に少なかったことが理由と思われる。また、この図には「犯罪(殺人、正当防衛も含む)」が入っていないが、これを加えるとグラフの様相が一変するようにも思う。戦争が災害なら犯罪も災害だろう。21世紀に入ってからの地震と津波による世界の死者は既に60万人を超えており、特に2004年スマトラ沖地震によるインド洋大津波と2010年ハイチ地震による死者がその2/3を占める。つまり、地震などの「プレート災害」による死者数は、21世紀が始まってからまだ13年しか経過していないのに、20世紀全体の死者数の半分近くに達している。20世紀と同様に21世紀も世界規模の大戦争が勃発し、一方で地球温暖化の影響により気象災害が著しく増加すると考えると、21世紀の世界の「災害」による死者数の割合は図1の円グラフに類似した比率になる可能性がある。人類全体の福祉のためには、戦争・飢餓・伝染病を防ぐことの方が重要であり、それには文系・理系の学問の総力を結集して当たらなくてはならないが、我々の分野の守備範囲としては、少しでも「プレート災害」による死者数を減らすことにつながる研究を展開していく必要がある。その意味で、今回の第2回G-EVER国際シンポジウム・第1回IUGS・日本学術会議国際ワークショップ(図2)は、東日本大震災の教訓を組み込んだ最新の研究成果が多数発表され、非常に有意義なものだったと思う。今回の会議で発表された研究は、IUGS発行の国際誌Episodesと、もう一つの国際誌に特集号として発表されるという。
拙稿を校閲して貴重な改善意見を寄せられた小川勇二郎先生と宝田晋治氏に感謝する。
図2.第2回G-EVER国際シンポジウム・第1回IUGS・日本学術会議国際ワークショップの参加者
(2013.11.5)
geo-flash No.241 代議員選挙 立候補締切【明日(11/6) 18時】
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.241 2013/11/5 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】☆☆選挙管理委員会から緊急のお知らせ☆☆
—2014年度代議員選挙、立候補受付〆切迫る—
【2】2014年度各賞募集について
【3】韓国2013秋季地質科学連合学術大会(大韓地質学会第68次定期総会)公式訪問の報告
【4】第5回惑星地球フォトコンテスト 作品募集開始!
【5】2014年度会費払込のお知らせ:割引申請は忘れずに!
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】☆☆選挙管理委員会から緊急のお知らせ☆☆—2014年度代議員選挙、立候補受付〆切迫る—
─────────────────────────────────
「代議員」の立候補届の受付は11月6日(水)が締め切りです。
届け出の状況は下記に示したように、現時点ではやや低調です。
立候補を予定されている方は、〆切期日に遅れないようご提出ください。
○代議員立候補受付〆切最終日 11月6日(水) 18時必着
(郵送、E-mail 受付可)
なお、代議員に立候補される方のうち、その後、会長及び副会長への立候補の意思のある方は、会員による意向調査のためのマニュフェストを添付してください。
立候補の届出先は選挙管理委員会(main@geosociety.jp)あてにお願いします。本メールマガジン(geo-flash)へそのままご返信されると、選挙管理委員会には立候補届のメールが届きませんので、ご注意ください。
○11月5日、現在までの立候補者数は以下のとおりです。( )内は定員数。
(11月5日17:30時現在)
・全国区 62名 (100)
・地方支部区 36名 (100)
内訳:北海道 5名(5) 東北 1名(8) 関東 21名(41)
中部 3名(17) 近畿 0名(11) 四国 2名(4)
西日本 4名(14)
◆◆◆ 最新の届出状況はこちらで確認できます ◆◆◆
○立候補届の書式は、「会員のページ」の選挙に関する案内からダウンロードできます。
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
「会員のページ」は、IDとパスワードによるログインが必要です。
ID=会員番号(*)、パスワード=姓、名それぞれの頭文字に続けて会員番号
(*)会員番号は、学会からの郵便物のあて名に印字(数字7ケタ)されています。
不明な方は、事務局(TEL.03-5823-1150)にお問い合わせください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2014年度各賞募集について
─────────────────────────────────
■2014年度学会各賞募集 受付中
応募締切:11月30日(土)必着
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
※「会員のページ」の各ページ内に、推薦書式等がダウンロードできるようになっています。
○会員番号・パスワードによるログインが必要です。
ログインの方法はこちら。
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】韓国2013秋季地質科学連合学術大会(大韓地質学会第68次定期総会)公式訪問の報告
─────────────────────────────────
日本地質学会会長 石渡 明
標記の大会は2013年10月23日〜27日、韓国済州島のフェニックス・アイランドで開催された。昨年の日本地質学会大阪大会で延長締結された大韓地質学会との学術交流協定に基づき、日本地質学会会長 石渡 明(筆者)と副会長Simon Wallisが公式に招待された。ここでは、標記学会に参加しての見聞を簡単に報告する。
続きはこちらから
http://www.geosociety.jp/faq/content0481.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第5回惑星地球フォトコンテスト 作品募集開始!
─────────────────────────────────
今年もフォトコンテストの募集が始まりました。たくさんのご応募お待ちしています。
【こんな作品を大募集!】
・惑星地球の美しい自然
・地層や火山など活きた地球の姿を表す優れた作品
・学術的意義の高い作品(解説文を含む)
・ジオパークに関係する優れた作品
・「ジオ鉄」の優れた作品学術的・教育的な価値のある優れた作品
・そのほか地球科学に関係した作品
締切:2014年1月31日(金)17:00
応募方法など詳しくは, http://photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2014年度会費払込のお知らせ:割引申請は忘れずに!
─────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下さいますようお願いいたします.
■2014年度分会費の引き落とし日:12月24日(火)です.
請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下さい.
■自動引き落とし以外の方(お振り込み)
12月中旬頃までに請求書兼郵便振替用紙をお送りいたします.折り返しご送金くださいますようお願いいたします.
■新規登録、引落口座変更の振替依頼書提出締切:11月8日(金)
■割引会費申請(院生・学部学生):請求書発行前締切 11月13日(水)
忘れずにご提出下さい。
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0135.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】 支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■関東支部『地質研究サミット』シリーズ「伊豆衝突帯地質研究サミット」(第2報)
11月23日(土)〜24日(日)
地質学,地下構造探査,地学防災減災リテラシーなどの様々な角度から議論します.
会場:横浜国立大学・教育文化ホール
■関東支部ミニ巡検シリーズ「丹沢ミニ巡検」
11月30日(土)〜12月1日(日):1泊2日
申込締切:11月17日(日)正午(定員になり次第締め切り)
それぞれ詳細は関東支部Webサイトへ → http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地質研究所ニュース Vol. 29,no. 3
http://www.gsh.hro.or.jp/publication/gshnews/news_pdf/vol29_no3.pdf
■公開シンポジウム 『新第三紀の終焉と第四紀の始まり
−東海層群から読み解く気候変動− 』
11月10日(日)13:00-16:30
場所:三重県総合博物館 レクチャールーム
http://www.geosociety.jp/outline/content0096.html
■学術フォーラム「地殻災害の軽減と学術・教育」
11月16日(土)10:00-17:00
場所:日本学術会議講堂
参加費:無料 申し込み:不要、当日先着順
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/178-s-1116.pdf
■JAXAシンポジウム
「宇宙開発のためのテクノロジー最前線
〜マテリアルやロケットエンジンの分野について〜」
11月18日(月)14:30-17:00
場所:東北大学片平さくらホール
申込締切:11/8
http://res.tagen.tohoku.ac.jp/~jaxasymp/form1.html
■日本学術会議 九州・沖縄地区会議学術講演会
「かごしまの水を考える ‐鹿児島大学『水』研究最前線‐」
11月18日(月)14:30-17:00
場所:鹿児島大学稲盛会館【キミ&ケサ メモリアルホール】
(鹿児島市郡元1丁目21-40)
入場無料
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/177-s-1118.pdf
■日本学術会議 中部地区会議学術講演会
「大学からの知の発信 〜文理融合の視点から〜 」
11月20日(水)13:00-16:00
場所:名古屋大学物質科学国際研究センター2階野依記念講演室
(名古屋市千種区不老町)【東山キャンパス】
入場無料
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/179-s-1120.pdf
■第24回地質汚染調査浄化技術研修会
日本地質学会環境地質部会 ほか 共催
11月22日(金)〜24日(日)
会場:NPO法人日本地質汚染審査機構本部ミーテング・ルーム
http://www.npo-geopol.or.jp
■第39回リモートセンシングシンポジウム
日本地質学会 協賛
11月25日(金)
場所:東京農業大学世田谷キャンパス
http://www.sice.jp/
■第29回ゼオライト研究発表会
日本地質学会 協賛
11月27日(水)〜28日(木)
会場:東北大学
http://www.jaz-online.org/index.html
■平成25年度国土技術政策総合研究所 講演会
12月3日(火)10:00-17:15
場所:日本教育会館一ツ橋ホール
http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/kouenkai/kouenkai2013/kouenkai2013.htm
■第13回東北大学多元物質科学研究所研究発表会
12月6日(金)9:50-20:00
場所:東北大学片平さくらホール
http://www.tagen.tohoku.ac.jp/general/info/event/meeting/2013/
■第3回学生のヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集
日本地質学会ほか 推薦
実習実施時期:2014年3月5日(水)出発,19日(水)帰国(15日間)
申込締切:11月30日(土)
http://www.geocities.jp/gondwanainst/
■日本地球惑星科学連合2014年大会
2014年4月28日(月)〜5月2日(金)
会場:パシフィコ横浜会議センター(横浜市西区みなとみらい1-1-1)
予稿集原稿投稿募集:2014年1月8日(水)〜2月12日(水)
http://www.jpgu.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/outline/content0098.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■国立科学博物館:地学研究部岩石学分野研究員(2014/1/15)
■東北大学大学院:理学研究科地学専攻(助教)(11/29)
■日本原子力研究開発機構:博士研究員(特定課題推進員)(11/15)
■海洋研究開発機構:地震津波・防災研究プロジェクトポストドクトラル職、特任研究職、特任技術研究職、特任技術総合職)(11/22)
■熊本大学:沿岸域環境科学教育研究センター特定事業教員(特任助教)(12/13)
■大気海洋研究所(柏地区)共同利用、国際沿岸海洋研究センター共同利用(11/29)
■第55回藤原賞(学会締切12/25)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.243 各賞推薦、まだ間に合います【11/30締切】
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.243 2013/11/19 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2014年度各賞募集について
【2】第2回G-EVER国際シンポジウム・第1回IUGS・日本学術会議国際ワークショップ 参加報告
【3】第5回惑星地球フォトコンテスト 作品募集開始!
【4】2014年度会費払込のお知らせ:割引申請は忘れずに!
【5】Island Arc からのお知らせ
【6】地層処分の技術的信頼性に関する意見募集
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2014年度各賞募集について
─────────────────────────────────
■2014年度学会各賞募集 受付中
応募締切:11月30日(土)必着
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
※「会員のページ」の各ページ内に、推薦書式等がダウンロードできるようになっています。
○会員番号・パスワードによるログインが必要です。
ログインの方法はこちら。
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第2回G-EVER国際シンポジウム・第1回IUGS・日本学術会議国際ワークショップ 参加報告
─────────────────────────────────
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
この国際シンポジウムは2012年2月22-24日につくば市で開催された第1回G-EVERワークショップ及び2013年3月11日に同市で開催されたG-EVER国際シンポジウムに次ぐもので、今回は2011年の東日本大震災の被災地の中心にある仙台市で2013年10月19-20日に開催された。2日間で口頭34件(あいさつを含む)とポスター26件の発表があり、翌21日には津波被災地域への巡検が行われた。G-EVERというのはGlobal Earthquake and Volcanic Eruption Risk Management(国際地震・火山噴火危機管理)の略である。
続きはこちらから
http://www.geosociety.jp/faq/content0482.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】第5回惑星地球フォトコンテスト 作品募集開始!
─────────────────────────────────
今年もフォトコンテストの募集が始まりました。たくさんのご応募お待ちしています。
【こんな作品を大募集!】
・惑星地球の美しい自然
・地層や火山など活きた地球の姿を表す優れた作品
・学術的意義の高い作品(解説文を含む)
・ジオパークに関係する優れた作品
・「ジオ鉄」の優れた作品学術的・教育的な価値のある優れた作品
・そのほか地球科学に関係した作品
締切:2014年1月31日(金)17:00
応募方法など詳しくは, http://photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2014年度会費払込のお知らせ:割引申請は忘れずに!
─────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下さいますようお願いいたします.
■2014年度分会費の引き落とし日:12月24日(火)です.
請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下さい.
■自動引き落とし以外の方(お振り込み)
12月中旬頃までに請求書兼郵便振替用紙をお送りいたします.折り返しご送金くださいますようお願いいたします.
■割引会費申請(院生・学部学生):最終締切 2014年3月31日(月)
忘れずにご提出下さい。
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0135.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
Island Arc 22-4号がオンライン出版されました.
本号は,Research Article 7編とReview Article 1 編から構成されています.
詳しくはこちら
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iar.2013.22.issue-4/issuetoc
<日本語要旨のページ>
http://www.geosociety.jp/publication/content0074.html
IAR最新号は,学会webサイトから無料で閲覧出来ます。
ログイン方法はこちらから,
https://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地層処分の技術的信頼性に関する意見募集
──────────────────────────────────
総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 原子力小委員会 地層処分技術WGでは、現段階の科学的知見に基づく地層処分の技術的信頼性について、専門家からの意見を募集しております。募集期間は平成25年11月5日から平成25年12月4日です。
詳細は下記HPを御覧ください。
http://www.enecho.meti.go.jp/rw/shobungijyutsu-iken.html
問い合わせ先
資源エネルギー庁放射性廃棄物等対策室
地層処分の技術的信頼性に関する意見募集担当
電話:03-3501-1511(内線4781)
E-mail:rwt-opinion@meti.go.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】 支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■関東支部『地質研究サミット』シリーズ「伊豆衝突帯地質研究サミット」(第2報)
11月23日(土)〜24日(日)
地質学,地下構造探査,地学防災減災リテラシーなどの様々な角度から議論します.
会場:横浜国立大学・教育文化ホール
■関東支部ミニ巡検シリーズ「丹沢ミニ巡検」
11月30日(土)〜12月1日(日):1泊2日
それぞれ詳細は関東支部Webサイトへ → http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■日本地球惑星科学連合メールニュース 11月号 No.187(11.11配信)
連合大会セッション提案受付状況のご報告 など
http://www.jpgu.org/664/mailnews/2013/131111.html
■地震本部ニュース8月号(11.13配信)
東海・東南海・南海地震の連動性評価研究プロジェクト など
http://www.jishin.go.jp/main/p_koho04.htm
■第24回地質汚染調査浄化技術研修会
日本地質学会環境地質部会 ほか 共催
11月22日(金)〜24日(日)
会場:NPO法人日本地質汚染審査機構本部ミーテング・ルーム
http://www.npo-geopol.or.jp
■第39回リモートセンシングシンポジウム
日本地質学会 協賛
11月25日(金)
場所:東京農業大学世田谷キャンパス
http://www.sice.jp/
■第29回ゼオライト研究発表会
日本地質学会 協賛
11月27日(水)〜28日(木)
会場:東北大学
http://www.jaz-online.org/index.html
■第23回環境地質学シンポジウム
日本地質学会環境地質部会ほか 共催
11月29日(金)〜30日(土)
場所:産業技術総合研究所(つくば)共用講堂
http://www.jspmug.org/
■日本学術会議公開シンポジウム
「増大する災害と地球環境問題に地球人間圏科学はどう取り組むか?」
12月5日(木) 13:00〜17:00
会場:日本学術会議講堂(東京都港区六本木7-22-34)
事前申込不要
http://www.jpgu.org/images/scj_sympo/scj_sympo_20131205.pdf
■産業技術連携推進会議 地質地盤情報分科会
講演会「東日本大震災による液状化被害と地質地盤情報の活用」
12月6日(金)
会場:明海大学浦安キャンパス(浦安市明海)
https://www.gsj.jp/information/domestic/sgr/index.html
■地球化学研究協会「公開講座」
(第50回霞ヶ関環境講座、第41回三宅賞受賞者受賞記念講演第1回進歩賞受賞者研究概要紹介)
12月7日(土)14:10〜
場所:霞が関ビル35階 東海大学校友会館
参加費:賛助会員および学生は無料、一般1,000円(資料代を含む)
http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~e881147/Geochem/
■日本学術会議 中国・四国地区会議学術講演会
「大災害への備え—いのちと暮らしを守るために—」
12月7日(土)13:30-17:00
場所:かがわ国際会議場(サンポート高松:JR高松駅前シンボルタワー、タワー棟6階)
参加無料、要事前申込
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/177-s-1207.pdf
■第155回深田研談話会
森林に学ぶ〜「持続性」を導く分子規格と社会規格〜
12月13日(金)
申し込み締切:12/11 先着:80名 参加無料
会場:深田地質研究所 研修ホール(文京区本駒込2-13-12)
http://www.fgi.or.jp/
■海底下の炭化水素資源・炭素循環と地球生命工学
2014年1月24日(金)
場所:東京大学本郷キャンパス小柴ホール(理学部1号館2階)
http://www.jamstec.go.jp/j/pr/event/
■第13回Project A春期ミーティング in 薩摩硫黄島 2014
2014年3月4日〜3月7日
4日:シンポジウム・一般講演会(3時頃到着)
5日:シンポジウム・ミーティング
6日:巡検
7日:朝巡検(10時出発)
http://archean.jp
■第3回学生のヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集
日本地質学会ほか 推薦
実習実施時期:2014年3月5日(水)出発,19日(水)帰国(15日間)
申込締切:11月30日(土)
http://www.geocities.jp/gondwanainst/
■日本地球惑星科学連合2014年大会
2014年4月28日(月)〜5月2日(金)
会場:パシフィコ横浜会議センター(横浜市西区みなとみらい1-1-1)
予稿集原稿投稿募集:2014年1月8日(水)〜2月12日(水)
http://www.jpgu.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/outline/content0098.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■岡山理科大学:教育開発支援機構 理科教育センター(教授,准教授または講師)(12/16)
■東京大学地震研究所:技術職員(実験系)公募(12/25)
■産業技術総合研究所:活断層・地震研究センター公募(ポスドク)(1/6)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
No.242(臨時)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.242 2013/11/8 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2014年度代議員選挙について
【2】継続教育CPDの利用環境の改善について(アンケートご協力のお願い)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2014年度代議員選挙について
─────────────────────────────────
選挙規則ならびに選挙細則に基づき,標記選挙を実施するにあたっての立候補届は、11月6日に締め切られました。その結果、全国区・地方支部区とも立候補者数が定数を超えませんでしたので、選挙規則第6条に基づき投票は行わず、全員を無投票当選といたします。
なお、立候補の抱負など、当選された方の詳細につきましては別途名簿をお送りいたしますので、ご覧ください。
また、代議員選挙は無投票となりましたが、会長・副会長の意向調査につきましては、予定通り実施いたします。意思表明者のマニフェストならびに調査票は代議員当選者の名簿とともに、11月23日ころまでにお送りいたしますので、ご返信を宜しくお願いいたします。
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/members/content0080.html
2013年11月8日
選挙管理委員会委員長
阿部なつ江
※会員番号・パスワードによるログインが必要です。
ログインの方法はこちら。
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】継続教育CPDの利用環境の改善について(アンケートご協力のお願い)
──────────────────────────────────
地質学会は、学会員の継続教育(CPD)の一環として、ジオ・スクリーニングネットに加盟し、支部活動等のイベント申し込みに利用しています。このたび、学会員の利用者(登録者)にアンケートが配信されたと思います。これは利用者へのサービス向上を図ったもので、学会に対しても協力依頼がありましたので、積極的に回答願います。回答に関しては、各人へ届いた回答法によって返信してください。よろしくお願いします。
(地質技術者教育委員会 委員長 山本高司)
◆アンケート協力依頼文章はこちら
このアクセスは情報保護のためセキュリティモードを使用しています(推奨)
https://eus.hnlk.net/index.cgi?hnav=5cf79be787b0fde7ad41124c1569d452a8
上記URLでうまく接続できない場合はこちら
http://eus.hnlk.net/index.cgi?hnav=5cf79be787b0fde7ad41124c1569d452a8
Web掲示期限 2013年11月15日(金)まで
◆アンケートはこちら
このアクセスは情報保護のためセキュリティモードを使用しています(推奨)
https://eus.hnlk.net/index.cgi?hnav=4cf79be787b0fde7a9af511e0dc8e24d36
上記URLでうまく接続できない場合はこちら
http://eus.hnlk.net/index.cgi?hnav=4cf79be787b0fde7a9af511e0dc8e24d36
Web掲示期限:2013年11月15日(金)まで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.246 「とかち鹿追」日本ジオパーク認定!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.246 2013/12/17 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】日本ジオパーク審査結果:“とかち鹿追” が新たに認定!
【2】早く載ります 地質学雑誌
【3】鉱業法第100条の2に基づく鉱物の探査に係る許可申請について
【4】JSEC2013:地学関係の発表が入賞しました
【5】福島第一原子力発電所における汚染水対策に関する技術提案が公表されています
【6】第5回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中!
【7】2014年度会費払込のお知らせ:割引申請は忘れずに!
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞情報
【11】地質マンガ:楽しみのリサイクル
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】日本ジオパーク審査結果:“とかち鹿追”が新たに認定!
──────────────────────────────────
昨日開催の第19回日本ジオパーク委員会において、次のとおり決定されましたのでご報告します。
◎日本ジオパーク再認定審査結果
・山陰海岸ジオパーク(再認定)
・天草御所浦ジオパーク(再認定)
・恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク(条件付き再認定)
◎日本ジオパーク認定申請地域審査結果
・とかち鹿追(認定)
◎エリア拡大申請地域審査結果
・山陰海岸ジオパーク(鳥取市の一部を追加)
・伊豆半島ジオパーク(長泉町、清水町の追加)
以上の結果、日本ジオパークは33地域(世界認定6地域を含む)となりました。なお,GGN(世界ジオパークネットワーク)加盟申請に推薦された阿蘇ジオパークは,11月末日に,申請書をユネスコ本部に提出しました.来年度GGNの視察が入り,世界ジオパークの可否が決定されます.
(日本ジオパーク委員会 高木秀雄)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】早く載ります 地質学雑誌
──────────────────────────────────
地質学雑誌では,特集号が最近2年間に次々と出ましたが,次の特集号までにはしばらく時間があります.特集号の間隔があく分,通常号用の原稿にとっては,受理から印刷までの待ち時間が短い状況です.完成度の高い原稿は早く出版できますので,原稿をお寄せください.また,特集号の新規提案も歓迎します.
地質学雑誌編集委員会委員長
山路 敦
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】鉱業法第100条の2に基づく鉱物の探査に係る許可申請について
──────────────────────────────────
2012年1月21日より施行された改正鉱業法では、「鉱物の探査」行為に関する許可制度が新設されました。資源開発や科学的調査などの目的に関わらず地震探査法や海での電磁法などが許可申請の対象となるとのことですので、ご確認ください。
「鉱物の探査に係る許可申請について」資源エネルギー庁からの連絡文書
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//others-pdf/20131213-1.pdf
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//others-pdf/20131213-2.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】JSEC2013:地学関係の発表が入賞しました
──────────────────────────────────
12月7日-8日に,第11回高校生科学技術チャレンジ(朝日新聞主催,日本地質学会後援)の最終審査会がありました。審査の結果、ファイナリスト30研究から各賞の受賞者が決定し、表彰式が行われました。受賞者は,来年5月にカリフォルニアで開かれる国際大会に派遣されます。
地学関係の受賞:JSEスチール賞
「縞状鉄鉱層の形成過程」本松千波さん(千葉県立薬円台高等学校3年)
詳しくは,http://www.asahi.com/shimbun/jsec/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】福島第一原子力発電所における汚染水対策に関する技術提案が公表されています
──────────────────────────────────
福島第一原子力発電所における汚染水問題への対応について、国際廃炉研究開発機構(IRID)が募集した技術提案の内容が公表されています。地下水流入抑制の敷地管理について日本陸水学会から「地下水流入抑制にかかわる導水路の設置」が提案されるなど、様々な技術提案がされています。
これらの提案内容は、 経済産業省の汚染水処理対策委員会で精査されていく予定です。
経済産業省:福島第一原子力発電所における汚染水対策
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku.html
汚染水対策に関する技術提案の公表
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/20131108_01.html
提案一覧
http://irid.or.jp/cw/public/group/info_list.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】第5回惑星地球フォトコンテスト 作品募集開始!
─────────────────────────────────
今年もフォトコンテストの募集が始まりました。たくさんのご応募お待ちしています。
【こんな作品を大募集!】
・惑星地球の美しい自然
・地層や火山など活きた地球の姿を表す優れた作品
・学術的意義の高い作品(解説文を含む)
・ジオパークに関係する優れた作品
・「ジオ鉄」の優れた作品学術的・教育的な価値のある優れた作品
・そのほか地球科学に関係した作品
締切:2014年1月31日(金)17:00
応募方法など詳しくは, http://photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】2014年度会費払込のお知らせ:割引申請は忘れずに!
─────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下さいますようお願いいたします.
■2014年度分会費の引き落とし日:12月24日(火)です.
請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下さい.
■自動引き落とし以外の方(お振り込み)
12月中旬頃までに請求書兼郵便振替用紙をお送りいたします.折り返しご送金くださいますようお願いいたします.
■割引会費申請(院生・学部学生):最終締切 2014年3月31日(月)
忘れずにご提出下さい。
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0135.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■功労賞募集
関東支部では,支部の顕彰制度に基づき,支部活動や地質学を通して社会貢献された個人・団体等を関東支部として顕彰いたします.つきましては,今年度も下記の要領で支部会員の推薦を募集します.積極的なご推薦をお待ちしております.
公募締切:2014年1月19日
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/faq/content0486.html#03
[西日本支部]
■平成25年度総会・第165回例会
2月22日(金)[21日:幹事会]
場所:佐賀大学,本庄キャンパス,大学会館
講演申込み〆切:2月5日(水)12時
*総会へ欠席の方は,委任状をお送り下さい。
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■電中研ニュースNo. 475
「地熱発電開発と温泉事業との共生のための方策を提案」
http://criepi.denken.or.jp/research/news/index.html?m=131212
■「海の魅力を伝えます!海を学び、海で働く女性から女子中高生へ」
2014年1月26日(日)13:00〜16:00
会場:東京大学理学部4号館2階
対象:中学・高校の女子生徒。ただし、引率の保護者,教員の参加可
定員:80名、参加費:無料
参加申込締切:2014年1月25日(土)10:00まで
http://www.oa.u-tokyo.ac.jp/news/2013/11/25/umipro2_gaiyo.pdf
■「第55回科学技術映像祭」参加作品の募集
募集締切:2014年1月21日(火)
参加方法:科学技術映像祭公式HPより申込
http://ppd.jsf.or.jp/filmfest/
■第3回学生のヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集
日本地質学会ほか 推薦
実習実施時期:2014年3月5日(水)出発,19日(水)帰国(15日間)
http://www.geocities.jp/gondwanainst/
■第48回日本水環境学会年会(2013年度)
2014年3月17日(月)〜19日(水)
会場:東北大学川内北キャンパス
https://www.jswe.or.jp/index.html
■スプリング・サイエンスキャンプ2014
2014年3月21日(金)〜29日(土)のうち2泊3日
場所:大学、公的研究機関、民間企業等(12会場)
応募締切:1月24日(金)必着
http://www.jst.go.jp/cpse/sciencecamp/camp/
スマートフォンサイトhttp://www.jst.go.jp/cpse/sciencecamp/camp/sp/
■日本地球惑星科学連合2014年大会
2014年4月28日(月)〜5月2日(金)
会場:パシフィコ横浜会議センター(横浜市西区みなとみらい1-1-1)
予稿集原稿投稿募集:2014年1月8日(水)〜2月12日(水)
事前参加登録締切:2014年4月16日(水)予定
http://www.jpgu.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/outline/content0098.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■広島大学大学院:総合科学研究科環境自然科学講座 女性教員公募(教授または准教授)(2014/1/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】地質マンガ:楽しみのリサイクル
──────────────────────────────────
『楽しみのリサイクル』
原案:chiyodaite マンガ:Key
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//manga/64.gif
その他の地質マンガはこちらから!
http://www.geosociety.jp/faq/content0057.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
福井県大島半島北部、台場浜の蛇紋岩について
福井県大島半島北部、台場浜の蛇紋岩について
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
私は関西電力大飯原子力発電所が完成する前の1973-74年に、横浜国立大学の卒業論文研究のために、同発電所敷地内を含む大島半島とその周辺地域の地質調査を行った(図1)。2012年秋から始まった原子力規制委員会の有識者会合による大飯原子力発電所敷地内の破砕帯調査の過程で、原子炉の裏山の北に位置する台場浜西部のトレンチ調査で出現した断層について、有識者会合の委員の間でこの地層のずれを活断層の運動によるとする見解と地すべりによるとする見解が出て、衆人環視の中で激しい議論が行われたことは記憶に新しい(「原子力規制委員会 有識者会合 大飯」でウェブ検索すれば、そのビデオと議事録が見られる。2012年11月4日の会合)。そこでは、トレンチ法面の段丘堆積物の下に露出した基盤岩が蛇紋岩だったので、「蛇紋岩は軟弱で滑動しやすい」という一般論が地すべり説の一つの補強材料になっていた。私自身はそのトレンチを観察したことがなく、隔靴掻痒の感があるが、40年前の学生時代の地表観察結果に基づき、この蛇紋岩の地質学的性格と意義についての知見を述べて有識者と地質学会会員諸氏の参考に供したい。なお、大島半島とその周辺の地質の概略については、既公表の拙著解説文を参照されたい(石渡2001, 2006, 2012, 石渡・中江2001)。
図1.大島半島北部の概略的な地質ルートマップ。1973-74年の石渡の調査に基づく。図2の位置を□で示す。①〜④は大飯原子力発電所の1号炉〜4号炉の大体の位置を示す。3・4号炉西側の破砕帯については原子力規制委員会(2012a)を参照。なお、「輝緑岩」はJISにない古い用語であり、現在は「粗粒玄武岩」、「結晶質玄武岩」などと言い換えられているが、ここではもとの調査資料に従い輝緑岩とする。
台場浜の超苦鉄質岩は広川・黒田(1957)が「コートランダイト」と呼び、Ishiwatari (1985) が「貫入かんらん岩(intrusive peridotite)」と呼んだもので、自形かんらん石が単斜輝石、斜方輝石、角閃石に包有されるポイキリティック組織を示し、スピネルや金雲母を含む。各鉱物の分析値を表1に示す。同じ岩石は大飯原発南方の宮留の北にも分布し(図1)、Ishiwatari (1985)には標本番号210としてその鉱物分析値が掲載されている。この岩石は、宮留においても台場浜においても斑れい岩を伴い、斜長石の増加によって斑れい岩に移り変わる。台場浜では、この超苦鉄質岩・斑れい岩複合岩体は幅約100 mの北東—南西方向の岩脈状に黒色頁岩・玄武岩・輝緑岩などを貫いて分布しており、その内部では大きく見て南東部に超苦鉄質岩、北西部に斑れい岩が分布し、両者はN70゚E, 45゚Nの断層で接する(図1)。南東部の超苦鉄質岩は浜沿いに33 mにわたって露出し、その中央部は比較的新鮮で火成鉱物がよく残存するが、斑れい岩から1 mと黒色頁岩から8 mの両縁部は著しく破砕され蛇紋岩化している。斑れい岩にはN50゚E, 40゚N方向の層状構造が発達し、閃緑岩〜巨晶閃緑岩質の層も見られる。そして、北西側の頁岩との境界付近には再び厚さ3 m以下の超苦鉄質岩が見られ、超苦鉄質岩中にも斑れい岩中のものと平行な層状構造が存在する(図2)。両者の境界は、ここでは漸移的である。この北西側の超苦鉄質岩と頁岩との境界は非常に入り組んでおり、超苦鉄質岩が頁岩中に枝状に入り込んでいて、境界から数m以内の黒色頁岩は白色のホルンフェルス(接触変成岩)に変化している(図2)。これらの証拠は、超苦鉄質岩・斑れい岩複合岩体がマグマとして頁岩中に貫入したことを示している。
表1.台場浜の貫入かんらん岩の鉱物分析値(標本番号551a, 地点番号734)。石渡の博士論文(1981, 英文,東京大学大学院理学系研究科)より。スピネルは変質していて分析できなかった。宮留北方の同種の岩石の分析値はIshiwatari (1985)に標本番号210として掲載されているが、どの珪酸塩鉱物も551aとよく類似した化学組成である。※拡大は表をクリック
この複合岩体の南東側の境界は台場浜トレンチやその周辺のボーリング調査によって追跡され、南東側に凸な湾曲した曲線をなして西側の海岸へ抜けるらしく、上述の海岸沿いの観察結果と同様に、境界沿いには破砕帯が発達していて蛇紋岩化が著しいようである(原子力規制委員会2012b; 前半p. 37までが台場浜関連, p. 23-24に蛇紋岩の分布推定図がある)。台場浜トレンチで下末吉相当の段丘堆積物を切る断層(N2゚W, 46゚N)は輝緑岩との境界から5 mほどの蛇紋岩中に続いている。南東側の頁岩(及び玄武岩・輝緑岩)側には接触変成帯が欠如しており、もともとの貫入境界や接触変成帯を含む幅数m以上の境界部が、現在の地表露頭やトレンチ断面では断層運動によって失われていることを示唆する。これが地すべりや活断層の運動によって失われたとすると、かなりの距離(10 m以上)のずれを考える必要があるが、古い時代の断層運動によって既に失われていた可能性が大きい。いずれにしても、台場浜の超苦鉄質岩・斑れい岩複合岩体の北西側と南東側の境界の状況が、どちらも境界に超苦鉄質岩があるにもかかわらず、北西側では火成貫入境界、火成層状構造、接触変成帯がよく保存されているのに対して、南東側は超苦鉄質岩が著しく蛇紋岩化し、蛇紋岩自体や周囲の岩石との境界が著しく破砕され、周囲の岩石には接触変成帯が欠如するというように、超苦鉄質岩・斑れい岩複合岩体の両側で状況が対照的に異なることがおわかりいただけたと思う。
図2.台場浜西部の露頭スケッチ。超苦鉄質岩・斑れい岩複合貫入岩体の北西側の黒色頁岩との接触部の状態を示す。超苦鉄質岩が枝状に頁岩中に入り込んでおり、境界に沿って接触変成岩(白色ホルンフェルス)が形成されていて、岩体内部にはマグマ固結時に形成された層状構造がよく保存されており、それらの特徴が欠如する南東側の境界とは著しく異なる。
超苦鉄質岩だからどれも蛇紋岩化している、超苦鉄質岩は常に軟弱な岩石だ、というわけではなく、蛇紋岩化され破砕されるにはそれなりの理由がある。地球上には、北海道の幌満かんらん岩体のように蛇紋岩化が非常に軽微で、マントル岩石がそのまま地表に露出している超苦鉄質岩体もある(解説と文献は高橋・石渡(2012)を参照)。一方、大島半島南部の大島超苦鉄質岩体では、岩体の南縁を限る衝上断層に沿って幅100 m程度にわたってかんらん岩が著しく蛇紋岩化し、岩体中央部を東西に貫く断層及び岩体北縁の断層に沿ってもかなり蛇紋岩化しているが、それ以外の部分ではかんらん岩の鉱物がよく残存している(石渡, 2006、石渡・中江2001、Ishiwatari 1985)。大飯原子力発電所から1 kmほど南東の待ちの山超苦鉄質岩体では、岩体全体が礫岩状に破砕され、特に南東縁の衝上断層沿いにこれと平行な破砕帯が発達していて蛇紋岩化が著しいが(小森・道林2011)、礫状部の中心ではもとのかんらん岩がよく残存している。台場浜の超苦鉄質岩も、一部にかんらん石などの火成鉱物が残存している。このような状況から考えると、台場浜西部の超苦鉄質岩・斑れい岩複合岩体の南東側の境界は、活断層や地すべりなどの新しい動きが生じる以前から(おそらく夜久野オフィオライトが付加体に衝上した時期の)断層境界であり、そのために蛇紋岩化が著しく、破砕帯が発達していたものと考えられる。このことは、問題の地層のずれが地すべりか活断層かということと直接の関係はないが、ずれている「蛇紋岩」がどういう起源の岩石であるかは関係者に知らせておくべきだと思い、ここに一文を草した次第である。
ところで、この文章はもっと早く執筆すべきであったが、私の研究室が入っている建物の震災復旧工事のために、研究資料を1年間以上遠隔地の倉庫に入れたままにして避難生活をしていたため、過去の資料を参照しての準備ができなかった。最近ようやく工事が完了し、研究室が元の状態に復旧したので、ようやく自分の調査資料を参照できるようになった。その点、ご寛恕いただきたい。
【文献】
原子力規制委員会 (2012a) 大飯発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合 事前会合における配付資料「参考資料東北大学教授 石渡明様からの提供資料」について.2012年11月4日第1回評価会合, 参考資料1.https://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/ooi_hasaitai/data/0002_02.pdf
原子力規制委員会 (2012b) 大飯発電所敷地内F−6破砕帯の追加調査−有識者会合(11/2,11/4)を踏まえた報告(関西電力(株)).2012年11月7日配布資料 大飯・現調3-1. https://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/ooi_hasaitai/data/0003_01.pdf
広川 治・黒田和男 (1957) 5万分の1地質図幅「鋸崎」及び説明書.地質調査所.
Ishiwatari, A. (1985) Granulite-facies metacumulates of the Yakuno ophiolite, Japan: Evidence for unusually thick oceanic crust. Journal of Petrology, 26, 1-30.
石渡 明 (2001) 大飯−大島半島の夜久野オフィオライト.北陸の自然をたずねて.同書編集委員会編.p. 10-15. 築地書館.
石渡 明 (2006) 舞鶴帯・超丹波帯:古生代後期の海洋底基盤岩とそれをおおう堆積物.日本地方地質誌中部地方.日本地質学会編.p. 184-193. 朝倉書店.
石渡 明(2012) 福井県西部地域の地質について.日本地質学会ホームページ http://www.geosociety.jp/faq/content0388.html
石渡 明・中江 訓 (2001) 福井県若狭地方の夜久野オフィオライトと丹波帯緑色岩.日本地質学会第108年学術大会(金沢)見学旅行案内書, p. 67-84.
小森直昭・道林克禎 (2011) 夜久野オフィオライト待ちの山超マフィック岩体南部断層境界に発達したブロックインマトリックス構造.静岡大学地球科学研究報告, 38, 21-26. http://ir.lib.shizuoka.ac.jp/bitstream/10297/6209/1/38-0021.pdf
高橋正樹・石渡 明 (2012) 火成作用.日本地質学会フィールドジオロジー8.共立出版.
(2013.12.27)
geo-flash No.247 謹賀新年:今年もフォトコン応募よろしくお願いします
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.247 2014/1/7 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】年頭あいさつ
【2】鉱物資源部会が発足しました
【3】福井県大島半島北部、台場浜の蛇紋岩について
【4】日本地球惑星科学連合2014年大会:明日から受付開始!
【5】第5回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中!
【6】「割引会費申請」忘れずに
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】年頭あいさつ
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会 会長 石渡 明
2014(平成26)年の年頭に当たり、日本地質学会理事会を代表して、会員の皆様にごあいさつを申し上げます。2012年5月に会長に就任してから既に1年半以上が経過し、任期も残り少なくなってきました。この1年間の本学会の活動を振り返り、今後の活動方針をお示しして、年頭のごあいさつとしたいと思います。
2013年9月14日〜16日に仙台市の東北大学川内キャンパスで日本地質学会第120年学術大会が開催されました。この大会では,「東北,いま,たちあがる地質学」のテーマのもとに,公開シンポジウム「東日本大震災 あの時,今,これから」,柳田邦男氏の市民講演会「災害に備える安全な社会とは」,原子力規制委員会の評価会合についての意見交換会、環太平洋オフィオライトに関する国際シンポジウムなどが開催され,16日の台風18号(Man Yi)の直撃にもかかわらず、近年では最多の987名の参加者と635件の講演数を得て、大成功の大会になりました。
続きはこちらから.
http://www.geosociety.jp/outline/content0137.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】鉱物資源部会が発足しました
──────────────────────────────────
日本地質学会鉱物資源部会が2013年12月に発足しました.
鉱物資源部会は,地球に産する様々な鉱物資源を,地質学的な視点から解明する研究分野の専門部会です.海底鉱物資源をはじめとする新しい資源の開発に向けた動きが活発化している中,地質学的観点に立って鉱物資源の成因解明に取り組み,この分野の発展に貢献することを目的としています.この専門部会を,鉱物資源研究者の情報交換・情報発信の場として機能させたいと考えています.
部会長:加藤泰浩(東京大学)
幹 事:岩森光(JAMSTEC)
幹 事:中村謙太郎(東京大学)
http://www.geosociety.jp/outline/content0049.html
(鉱物資源部会のホームページは近日公開予定です)
鉱物資源部会はできたばかりの若い専門部会です.メンバーの方々と一緒に築いていきます.
部会長 加藤泰浩
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】福井県大島半島北部、台場浜の蛇紋岩について
──────────────────────────────────
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
私は関西電力大飯原子力発電所が完成する前の1973-74年に、横浜国立大学の卒業論文研究のために、同発電所敷地内を含む大島半島とその周辺地域の地質調査を行った。2012年秋から始まった原子力規制委員会の有識者会合による大飯原子力発電所敷地内の破砕帯調査の過程で、原子炉の裏山の北に位置する台場浜西部のトレンチ調査で出現した断層について、有識者会合の委員の間でこの地層のずれを活断層の運動によるとする見解と地すべりによるとする見解が出て、衆人環視の中で激しい議論が行われたことは記憶に新しい(「原子力規制委員会 有識者会合 大飯」でウェブ検索すれば、そのビデオと議事録が見られる。2012年11月4日の会合)。
続きはこちらから.
http://www.geosociety.jp/faq/content0489.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】日本地球惑星科学連合2014年大会:明日から受付開始!
──────────────────────────────────
予稿集原稿投稿募集:1月8日(水)〜2月12日(水)
※早期投稿締切:2月3日(月)
事前参加登録締切:4月16日(水)予定
2014年連合大会:4月28日(月)〜5月2日(金)
会場:パシフィコ横浜会議センター(横浜市西区みなとみらい1-1-1)
大会Webサイト http://www.jpgu.org/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第5回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中!
──────────────────────────────────
今月末がいよいよ締切です!たくさんのご応募お待ちしています。
【こんな作品を大募集!】
・惑星地球の美しい自然
・地層や火山など活きた地球の姿を表す優れた作品
・学術的意義の高い作品(解説文を含む)
・ジオパークに関係する優れた作品
・「ジオ鉄」の優れた作品学術的・教育的な価値のある優れた作品
・そのほか地球科学に関係した作品
締切:1月31日(金)17:00
応募方法など詳しくは, http://photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】「割引会費申請」忘れずに
──────────────────────────────────
■学部学生・院生(研究生)「割引会費申請」最終締切:3月31日(月)
※ 通常の会費払込については,「2014年会費払い込みについて」をご参照下さい.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0135.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■功労賞募集
関東支部では,支部の顕彰制度に基づき,支部活動や地質学を通して社会貢献された
個人・団体等を関東支部として顕彰いたします.つきましては,今年度も下記の要領で
支部会員の推薦を募集します.積極的なご推薦をお待ちしております.
公募締切:1月19日
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/faq/content0486.html#03
[西日本支部]
■平成25年度総会・第165回例会
2月22日(金)[21日:幹事会]
場所:佐賀大学,本庄キャンパス,大学会館
講演申込み〆切:2月5日(水)12時
*総会へ欠席の方は,委任状をお送り下さい。
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■学術会議公開シンポジウム
「地域の再生と国のかたち─東日本大震災の教訓を活かす─」
1月12日(日) 13:00-17:00
会場:日本学術会議6階会議室(東京都港区六本木7−22−34)
http://www.scj.go.jp/ja/event/index.html
■大学教育の分野別質保証に関する教育課程編成上の参照基準:地理学
1月12日(日) 10:00-12:00
会場:日本学術会議6階会議室(東京都港区六本木7−22−34)
http://www.scj.go.jp/ja/event/index.html
■平成25年度地球温暖化対策技術開発成果発表会
1月16日(木)14:00-16:50
場所:イイノホール&カンファランスセンターRoom B1〜3(千代田区内幸町2-1-1)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17501
■第3回学生のヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集
日本地質学会ほか 推薦
実習実施時期:3月5日(水)出発,19日(水)帰国(15日間)
http://www.geocities.jp/gondwanainst/
■スプリング・サイエンスキャンプ2014
3月21日(金)〜29日(土)のうち2泊3日
場所:大学、公的研究機関、民間企業等(12会場)
応募締切:1月24日(金)必着
http://www.jst.go.jp/cpse/sciencecamp/camp/
スマートフォンサイトhttp://www.jst.go.jp/cpse/sciencecamp/camp/sp/
■日本地球惑星科学連合2014年大会
4月28日(月)〜5月2日(金)
会場:パシフィコ横浜会議センター(横浜市西区みなとみらい1-1-1)
予稿集原稿投稿募集:1月8日(水)〜2月12日(水)
事前参加登録締切:4月16日(水)予定
http://www.jpgu.org/
■地質学史懇話会
6月28日(土)13:30-17:00
場所:北とぴあ8階803号室
相原延光『お天気博士藤原咲平の生涯と地学史における再評価(仮題)』
加藤碵一『「地文学」と「地人論」考』
■第11回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム、
国際ゴンドワナ研究連合2014年会及び付属野外巡検
9月19日(金)〜21日(日)(会議)
9月22日(月)〜24日(水)(巡検)
場所:北京、China University of Geosciences Beijing
http://www.iagrhomepage.com
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/outline/content0133.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■産業技術総合研究所:ポスドク(イノベーションスクール生)募集(1/16)
■産業技術総合研究所:活断層・地震研究センター公募(ポスドク)(1/20)
■京都大学大学院:理学研究科地球惑星科学専攻地質学鉱物学分野(技術職員)(1/23)
■大阪市立大学大学院:理学研究科理学部地球学教室職員公募(特任講師)(1/31)
■島根大学大学院:総合理工学研究科地球資源環境学領域教員公募(2/7)
■糸魚川ジオパーク研究調査助成(2014年4月下旬応募受付予定)
■「消防防災科学技術研究推進制度」平成26年度研究開発課題の募集 (2/7)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.249 鹿児島大会トピックセッション募集中!3/17締切
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.249 2014/2/4 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[鹿児島大会]大会開催通知
【2】[鹿児島大会]トピックセッション募集
【3】新刊:電子書籍「地学を楽しく!:ジオパーク・ジオツアー・地学オリンピック」が出版されました!
【4】地層処分の技術的信頼性に関する意見募集
【5】第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会セッション提案募集
【6】The 2nd IGCP608 Waseda 2014のFirst Circular 配布開始
【7】2014年度の会費払込等について
【8】支部情報
【9】日本地球惑星科学連合からのお知らせ:2014年大会
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[鹿児島大会]大会開催通知
──────────────────────────────────
日本地質学会は,西日本支部の支援のもと,鹿児島大学郡元キャンパスにおいて第121年学術大会(2014年鹿児島大会)を2014年9月13日(土)〜15日(月)に開催致します.
巡検は期間中の9月13日(土)と,大会後の9月16日(火)〜18日(木)に開催する予定です.
2014年は大正3(1914)年に発生した桜島火山の大正噴火から,ちょうど100周年にあたります.
それまで名実共に島であった桜島が,流出した溶岩により大隅半島と陸続きになってしまいました.
続きはこちらから.
http://www.geosociety.jp/science/content0059.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[鹿児島大会]トピックセッション募集
──────────────────────────────────
日本地質学会行事委員会
第121年学術大会は,西日本支部のご協力のもと,鹿児島大学をメイン会場として2014年9月13日(土)〜15日(月)に開催されます.
現在,トピックセッションを募集中です.
なお,本大会も前回同様,シンポジウムの一般募集はありません.
※シンポジウムは鹿児島大会実行委員会および学会執行部が企画します.
募集締切:3月17日(月)
詳しくはこちら.
http://www.geosociety.jp/science/content0060.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】新刊:電子書籍「地学を楽しく!:ジオパーク・ジオツアー・地学オリンピック」が出版されました!
──────────────────────────────────
地学を楽しく!:ジオパーク・ジオツアー・地学オリンピック[Kindle版]
吉田 勝,天野一男,中井 均 編集
一般社団法人日本地質学会 発行
価格:¥1,380
ISBN 978-4-907604-00-4
ご購入は,Amazon Kindleストア(http://www.amazon.co.jp)から電子書籍は,Amazonが販売する電子ブックリーダー端末(Kindle)か,スマートフォン,タブレットなどで読むことができます.
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/publication/content0076.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地層処分の技術的信頼性に関する意見募集
──────────────────────────────────
会員各位
総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 原子力小委員会地層処分技術WGより、科学的知見に基づく地層処分における好ましい地質環境特性について、意見募集の案内がありましたので,お知らせします。広く専門家からの意見を募集しています。下記HPをご参照のうえ,是非ご意見をお寄せ下さい。
募集期間:平成26年1月24日〜2月24日
詳細は下記HPを御覧ください。
http://www.enecho.meti.go.jp/rw/shobungijyutsu-iken.html
問い合わせ先
資源エネルギー庁放射性廃棄物等対策室
地層処分の技術的信頼性に関する意見募集担当
電話:03-3501-1511(内線4781)
E-mail:rwt-opinion@meti.go.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会セッション提案募集
──────────────────────────────────
共催 日本地質学会 ほか
国際第四紀学連合 (INQUA)の第19回大会が,2015年に名古屋で開催されます.
アジアで2回目,日本で初めてのINQUA大会の開催になります.同大会のセッション提案の募集が始まりました.大会では80〜100のセッションを予定しており,セッション提案の締め切りは3月末になります.5-6月にセッション確定後,7月から発表や巡検の申し込みを開始予定です.多くの学協会と緊密に関連するセッションが持てる機会ですので是非ともセッションの提案をお願い申し上げます.
日本第四紀学会会長 小野 昭
INQUA名古屋大会組織委員長 斎藤文紀
セッション提案募集締切:2014年3月31日(月)
大会日程:2015年7月27日〜8月2日
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1-1)
詳しくは,http://inqua2015.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】The 2nd IGCP608 Waseda 2014のFirst Circular 配布開始
──────────────────────────────────
IGCP608 Asia-Pacific Cretaceous Ecosystems (白亜紀アジア−西太平洋生態系)第2回 国際シンポジウム(The 2nd IGCP608 Waseda 2014)
「白亜紀の陸−海リンケージと生物相進化:アジア−西太平洋地域からの貢献」
期日:2014年9月4日(木)〜6日(土)
場所:早稲田大学大隈講堂
巡検:9月7日(日)〜10日(水)
「本州中部太平洋岸の白亜紀前弧堆積盆の珪質砕屑物サクセッションの堆積相と動植物化石相」
(銚子層群,那珂湊層群,双葉層群)
First Circularダウンロードサイト: http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/
連絡先: igcp608.waseda@gmail.com 太田 亨(実行委員会事務局長)
(IGCP608 プロジェクトリーダー 安藤寿男)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】2014年度の会費払込等について
──────────────────────────────────
■2014年度の会費払込について
1.自動引落を登録されている方:2013年12月24日(火)に引き落としを行いました.
請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下さい.
これより以前に不足額がある場合には加算され,余剰金がある場合はその分を減額して引き落としされています.通帳には金額とともに「チシツカイヒ」あるいは「フリカエ」,「SMBC」などと表示されておりますので,必ずご確認下さい.
2.上記以外の方(お振り込み)
12月中旬頃に請求書兼郵便振替用紙をお送りいたしました.折り返しご送金くださいますようお願いいたします.
■災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
日本地質学会では,災害救助法適用地域で被災された会員の方々のご窮状をふまえ,以下の措置を取らせていただきます.
「日本地質学会に届出の住居または勤務地が災害救助法適用地域に該当する会員のうち,希望する方」は2014年度(平成26年度)会費を免除することといたします.
2013年度において,災害により被害にあわれた方のうち,この措置の適用を希望される会員は,(1)会員氏名(2)被害地域(3)被災状況(簡単に)を明記し,学会事務局までお申し出下さい.
お申し出の方法は,郵送,FAX,e-mailのいずれでも結構です.
締切は,2014年2月24日(月)までとさせていただきます.
■学部学生・院生(研究生)「割引会費申請」
最終締切:3月31日(月)
毎年更新となりますので,次年度会費について該当する方は,必ず申請してください.
それぞれ詳しくは,
http://www.geosociety.jp/outline/content0135.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】 支部情報
──────────────────────────────────
[東北支部]
■2012-2013年度総会・講演会
3月1日(土)午後〜2日(日)午前[なお1日午前:幹事会]
場所:山形大学小白川キャンパス
講演申込み締切:2月10日(月)12時
申込先:大友幸子(yukiko@e.yamagata-u.ac.jp)下記1-4をご連絡ください.
1.発表題目,2.発表者氏名・所属,3.発表様式希望(口頭・ポスター・どちらでも可,のいずれか),4.発表申込者のe-mailと電話
講演要旨締切:2月20日(木)18時
講演要旨:A4一枚.PDFファイル.地質学会年会の講演要旨原稿フォーマットで作成し,e-mailにて加々島 慎一(kagashima@sci.kj.yamagata-u.ac.jp)宛にお送り下さい.
*総会欠席の方は,川辺孝幸(kawabe@kescriv.kj.yamagata-u.ac.jp)宛に委任状をお送り下さい.
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
[西日本支部]
■平成25年度総会・第165回例会
2月22日(金)[21日:幹事会]
場所:佐賀大学,本庄キャンパス,大学会館
講演申込み締切:2月5日(水)12時
*総会へ欠席の方は,委任状をお送り下さい.
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】日本地球惑星科学連合からのお知らせ:2014年大会
──────────────────────────────────
○最終投稿締切:2/12(水)12:00(通常投稿料 4000円/1件)
http://www.jpgu.org/meeting/submission.html
○大会期間中の宿泊手配のお願い
2014年大会は5月の連休と一部日程が重なるため,周辺ホテルの確保が難しくなる恐れがあります.お早目の手配をお願いいたします.
○プレミアムブックマーケットのお知らせ
お手元にある蔵書で有効活用してほしいものがありましたら,連合大会にて,フリーマーケット風にご提供いただけませんか?
http://www.jpgu.org/meeting/bookmarket.html
JpGU2014 大会ページ
http://www.jpgu.org/meeting/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地震本部ニュース11月号
http://www.jishin.go.jp/main/p_koho04.htm
■地質研究所ニュース ダイジェスト版 第34号
http://www.gsh.hro.or.jp/publication/gshnews/news_pdf/vol29_no4.pdf
■第3回学生のヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集
日本地質学会ほか 推薦
実習実施時期:3月5日(水)出発,19日(水)帰国(15日間)
http://www.geocities.jp/gondwanainst/
■第284回地学クラブ講演会
微生物がつくり、人が護る:「天然記念物“オンネトー湯の滝マンガン酸化物生成地”」と「錦沼」講演会
3月15日(土)14:00-15:30
http://www.geog.or.jp/lecture/lecturescheduled/203-284-.html
■日本地球惑星科学連合2014年大会
4月28日(月)〜5月2日(金)
会場:パシフィコ横浜会議センター(横浜市西区みなとみらい1-1-1)
予稿集原稿投稿締切:2月12日(水)
事前参加登録締切:4月16日(水)予定
http://www.jpgu.org/
■第14回アジア学術会議マレーシア会合国際シンポジウム
6月18日〜19日
会場:Istana Hotel(クアラルンプール、マレーシア)
http://www.scj.go.jp/ja/int/sca/index.html
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
2015年7月27日〜8月2日
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1-1)
http://inqua2015.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0133.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■東邦大学:理学部化学科地球化学 ポスドク公募(3/31)
■海洋研究開発機構:生命の進化と海洋地球生命史ポストドクトラル研究員もしくは技術支援職公募(2/28)
■静岡大学大学院:理学研究科地球科学専攻教員(2/28)
■日本原子力研究開発機構:地層処分研究開発部門任期付研究員(2/28)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.248 フォトコン応募忘れずに【1/31締切】
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.248 2014/1/21 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】会長・副会長立候補意思表明者にたいする意向調査結果報告
【2】自然史学会連合:出版物(小学生向け)のテーマ提案募集
【3】第5回惑星地球フォトコンテスト もうすぐ締め切り!
【4】「割引会費申請」忘れずに
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】会長・副会長立候補意思表明者にたいする意向調査結果報告
──────────────────────────────────
2014年1月10日
一般社団法人日本地質学会
選挙管理委員会委員長 阿部 なつ江
開票立会人 巌谷 敏光
開票立会人 高橋 聡
選挙規則ならびに選挙細則に基づき,標記意向調査を実施いたしました.
法人の代表理事は法律により,理事会において選任することが定められています.
学会の代表理事となる会長およびその補佐役の副会長を選出するにあたり,会員の皆様の意向を伺うためにこの調査を行いました.
詳しくはこちら.
http://www.geosociety.jp/members/content0081.html
○会員番号・パスワードによるログインが必要です.
(ログインの方法は http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】自然史学会連合:出版物(小学生向け)のテーマ提案募集
──────────────────────────────────
自然史学会連合では,「12歳までに知っておきたい 自然にまつわる ふしぎなお話365(仮)」の書籍出版計画にあたり,各学協会に対してテーマ提案の募集を行っています.
1学協会につき10〜20項目の話題候補を集め,それをもとに,365のテーマを出版社サイドで絞ります.それぞれの学協会の多様な研究をカバーする,幅広い話題提案をお待ちしています.
提案用書式をご利用の上,下記送付先までメール添付でお寄せ下さい.
分野を超えての力を結集し,自然史科学の普及・振興に役立てればとの思いで動いておりますので,何卒ご協力のほど,よろしくお願いいたします.
【送付締切:1月28日(火)】
<提案用書式>
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//name/20140109/sheet-JGS.doc
※取材候補者については,可能であればご記入ください.365の話題が決まってからの推薦でも構いません.
<問い合わせ先・アンケート送付先>
矢島道子(自然史学会連合書籍編集員:日本地質学会)
pxi02070@nifty.com
<参考>
[自然史書籍企画概要]
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//name/20140109/kikakusho.pdf
[テーマ候補の話題案]
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//name/20140109/wadaian.pdf
※話題案と重複して構いませんが,これは今回対象としている小学校低学年よりも上の読者層を意識したものです.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】第5回惑星地球フォトコンテスト もうすぐ締め切り!
──────────────────────────────────
今月末がいよいよ締切です!たくさんのご応募お待ちしています。
【こんな作品を大募集!】
・惑星地球の美しい自然
・地層や火山など活きた地球の姿を表す優れた作品
・学術的意義の高い作品(解説文を含む)
・ジオパークに関係する優れた作品
・「ジオ鉄」の優れた作品学術的・教育的な価値のある優れた作品
・そのほか地球科学に関係した作品
締切:1月31日(金)17:00
応募方法など詳しくは, http://photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】「割引会費申請」忘れずに
──────────────────────────────────
■学部学生・院生(研究生)「割引会費申請」最終締切:3月31日(月)
※ 通常の会費払込については,「2014年会費払い込みについて」をご参照下さい.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0135.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】 支部情報
──────────────────────────────────
[東北支部]
■2012-2013年度総会・講演会
3月1日(土)〜2日(日)[1日:幹事会]
場所:山形大学小白川キャンパス
講演申込み締切:2月10日(月)12時
講演要旨締切:2月20日(木)18時
*総会欠席の方は,委任状をお送り下さい.
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
[西日本支部]
■平成25年度総会・第165回例会
2月22日(金)[21日:幹事会]
場所:佐賀大学,本庄キャンパス,大学会館
講演申込み締切:2月5日(水)12時
*総会へ欠席の方は,委任状をお送り下さい.
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地震本部ニュース10月号
http://www.jishin.go.jp/main/p_koho04.htm
■電中研ニュースNo. 476
「CO2排出削減の長期目標について現実的な考え方を提案」
http://criepi.denken.or.jp/research/news/
■第2回セミナー
『海の魅力を伝えます!海を学び,海で働く女性から中高生へ』
1月26日(日)13:00-16:00
場所:東京大学理学部4号館2階
申込締切:1月25日(土)10:00 定員:80名 参加無料
http://www.oa.u-tokyo.ac.jp/news/2013/12/22014126.html
■IFREE公開シンポジウム
「地球大変動IIー地殻大変動を引き起こす地球深部の巨大運動が見えてきた!」
2月8日(土)13:00-17:30
場所:建築会館ホール(東京都港区芝5-26-20)
入場無料
http://www.jamstec.go.jp/ifree/j/sympo/2013/
■ブルーアース2014
2月19日〜20日
場所:東京海洋大学 品川キャンパス
入場料無料 事前申込不要(要旨集は会場にて配布)
http://www.jamstec.go.jp/maritec/j/blueearth/2014/
■第3回学生のヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集
日本地質学会ほか 推薦
実習実施時期:3月5日(水)出発,19日(水)帰国(15日間)
http://www.geocities.jp/gondwanainst/
■日本地球惑星科学連合2014年大会
4月28日(月)〜5月2日(金)
会場:パシフィコ横浜会議センター(横浜市西区みなとみらい1-1-1)
予稿集原稿投稿締切:2月12日(水)
事前参加登録締切:4月16日(水)予定
http://www.jpgu.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0133.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■鳥取県立博物館:非常勤職員(地学標本専門員)募集(2/7)
■福井県里山里海湖研究所:任期付職員募集(1/24)
■産業技術総合研究所:活断層・地震研究センター 博士型任期付研究員または中堅型研究員(4/16)
■静岡県:ふじのくに地球環境史ミュージアム(仮称)職員(2/20)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.250 地質系統・年代の日本語記述ガイドライン(改訂版)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.250 2014/2/18 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2014年度一般社団法人日本地質学会理事選挙の実施について
【2】地質系統・年代の日本語記述ガイドライン 改訂版
【3】2014年度春季地質調査研修参加者募集
【4】日本地質学会の60, 75, 100周年記念誌を読む:125周年に向けて
【5】Island Arc よりお知らせ
【6】地球全史スーパー年表:会員特別販売のお知らせ
【7】熊本大学総合科学技術共同教育センター特別講義のご案内
【8】2014年度の会費払込等について
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2014年度一般社団法人日本地質学会理事選挙の実施について
──────────────────────────────────
2月7日に役員の立候補が締め切られました.選挙規則,選挙細則に基づき,2014年度の理事選挙を2月20日(木)〜3月7日(金)まで実施いたします.
理事選挙は2014年度からの新代議員による投票となります.
地方支部区枠の理事の選出については,各支部区から1名ずつ立候補届出があり,候補者は定数内のため,投票は行いません.
理事選挙の開票は3月13日(木)10時から学会事務局で行います〔*〕.
開票の立ち会いをご希望のかたは,3月6日(木)までに選挙管理委員会(main@geosociety.jp)にお申し出ください.
*理事選挙の開票日は当初3月10日(月)を予定しておりましたが,3月13日(木)10時からに変更となりました.
候補者名簿はこちらから.
http://www.geosociety.jp/members/content0082.html
※会員番号・パスワードによるログインが必要です。
ログイン方法はこちら.
https://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】地質系統・年代の日本語記述ガイドライン 改訂版
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会 執行理事会
ニュース誌(2013年2月号)に,国際地質科学連合(International Union of Geological Sciences; IUGS)の国際層序委員会(International Commission on Stratigraphy; ISC)が公開した,2012年8月版国際年代層序表(International Chronostratigraphic Chart)の日本語版を掲載しました.その後,2013年1月版国際年代層序表が発表され,以下の修正が加えられております.
1. サントニアン階の基底を定義するGSSPが設定された.
2. ジュラ紀と白亜紀の境界の年代値が修正された.
3. ラディニアン期とカーニアン期,カーニアン期とノーリアン期の境界の年代値が 修正された.
4. ペルム紀の年代値の多くに修正がなされた.
日本語版PDFは下記ページよりダウンロードできます。
http://www.geosociety.jp/name/content0062.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2014年度春季地質調査研修参加者募集
──────────────────────────────────
地質調査法の基本技術の修得をめざすとともに,それをベースに得られた過去の調査や研究の成果についても学びます.地質調査の経験のない方でも,地質調査法の基本を体で習得することを目指します.
日程:5月12日(月)〜5月16日(金)4泊5日
場所:千葉県君津市及びその周辺地域(房総半島中部域)
募集人数:6名. 参加費:12万円
申込締切:4月11日(金)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/engineer/content0035.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】日本地質学会の60, 75, 100周年記念誌を読む:125周年に向けて
──────────────────────────────────
1893年の創立から今年で121年になるが(ただし1934年までは「東京地質学会」)、本学会は60、75、100周年に記念誌を刊行してきた。この他、1985年に地質学論集25号「日本の地質学—1970年代から1980年代へ」、1998年に同49号「21世紀を担う地質学」と50号「21世紀の構造地質学にむけて」の総説集を刊行した。ここでは、これらを読んで簡単な感想を述べ、125周年に向けての一歩としたい。敬称を略すことをお許し願いたい。
1918年の25周年は記念大会を行ったが(山崎直方会長)、記念誌は展覧会の目録以外見当たらない。しかし、1905年の地質学雑誌12巻393-405頁に初代会長神保(じんぼ)小虎の「本邦に於ける地質学の歴史」がある。「西国の開化我国に移らんとして以来経年の短きに比して進歩の甚(はなはだ)著し」という書き出しで約30年間の日本地質学をまとめ、「要するに我国の(地質)探検は、初めは幕府及び開拓使のアメリカ人に因(よ)りて基(もとい)を開かれ、後ドイツ流にて中央政府の地質調査所起こり、之に倣(なら)って北海道庁の地質略察始まり、一方にはドイツ風を輸入せる東京大学の地質学科ありて(中略)今日の状態に達した」と結び、初期の白野夏雲の功に言及している。神保はライマンの地質調査を強烈に批判したが、ここでは彼の業績も淡々と記している。詳細は佐藤伝蔵の追悼文(1923, 地質雑 30, 図版15)、佐藤博之(1983, 地質ニュース346号)、松田義章(2010, 地質学史懇話会会報34, 35号)、浜崎健児(2011, 同36号)を参照されたい。神保は徳川旗本の家の出で、本学会は幕府側出身の会長で出発したことになる。1905年の会員数は161人だったが、会誌は創刊以来毎月発行されていた。
1943年の50周年は太平洋戦争の最中で、東大での総会に加え北大で臨時総会と記念学術大会が開催されたが、記念誌の発行はなかった。そこで、戦争が終結して8年後の1953年に60周年記念の「日本地質学会史」(185頁)を発行した。ソフトカバーで紙質も印刷も悪いが、内容は非常に読み応えがある。編集委員長は鹿間時夫、編集委員は生越(おごせ)忠、小林英夫、牛来(ごらい)正夫、坂田嘉雄、須藤俊男、高井冬二、西山芳枝、宮沢俊弥、向山 広、森本良平、渡部景隆である。内容は、日本地質学会60年略史(早坂一郎)、日本地質学史年表(編集委員会)、部会史(古生物、鉱山、鉱物)、歴代会長名及び評議員名、研究奨励金受賞者、明治時代の日本における地質学(矢部長克)、おもいで(主に明治時代7編)、追悼の辞(鹿間)、物故者一覧(写真つき、82名)、追悼文(五十音順、86名)、各大学研究室の歴史(19教室)、新制大学地学関係教室一覧、地質調査所・博物館・研究所等の歴史、関係学会及び関係団体の歴史、外地の調査研究機関の歴史、関係会社の地質調査研究史、地質学者以外の功労者(須藤)、地質学、鉱物学会における開拓者、特(篤)志家、標本家、標本商列伝(櫻井欽一)、日本産新鉱物表(附台湾・朝鮮産)(櫻井)となっている。特に矢部と櫻井の文章は一読の価値があり、鹿間の追悼の辞も切々と胸に迫るものがある。各人の追悼文を読むと、大部分の人は病死または戦病死であるが、阿波丸に乗船していて台湾沖で「米国潜水艦の魚雷攻撃を受け同船沈没と共に戦死」、「30歳を一期に船と共に爆沈」といった記述が数件あり、「(西南太平洋にて)米軍艦船40隻の来襲を受け戦死」、「仏印寧平南方15粁チョガンにて戦死」という人もいる。一方で「地質調査所に入所間もなく任官辞令を入質して酒を呑んだということは地質開闢(かいびゃく)以来始めてだと先輩をして唖然とさせた」といった楽しいエピソードもある(この人は福井県中竜鉱山附近のクロリトイド片岩の発見者)。朝鮮、台湾、満州、中国、南洋の調査機関の歴史は各機関で指導的立場だった人が執筆しているが、樺太だけは委員長の鹿間が「執筆者不在につき代筆」している。事情は不明だが、鹿間は満州国の新京(長春)工業大学教授として1942年に赴任する前、東北大学副手だった1937年に樺太庁嘱託で南樺太を調査しており(地質雑, 45, 423-424)、そのつながりだろう。私は学部時代に彼の所属教室で過ごし、大陸からの引揚げの苦労話はよく聞いたが、この記念誌を編集・執筆した話は全く聞いておらず、「教室史」にも記事がない。1953年の会員数は1662人であり、半世紀前に比べ1桁増えた。偶然にも私はこの年に生まれた。
1968年に発行された75周年記念の「日本の地質学—現状と将来への展望—」は610頁の黄色のハードカバー本で、編集委員長は大森昌衛、委員は青木滋、大町北一郎、杉村新、高野幸雄、松尾禎士、山下昇であり、年表委員として今井功、小林宇一、服部一敏が加わり、執筆者は共著者を含め48人に達する。75周年記念大会も委員長渡辺武男(会長)、実行委員長森本良平らにより組織された。時は佐藤栄作首相下の高度成長の最盛期、ベトナム戦争に米軍が本格介入していて、日本の大学では反戦運動や70年安保に向けての反対闘争が盛り上がりつつあった頃である。「はしがき」では「専門分野の著しい分化と大量の図書・論文の出現により(中略)他の分野あるいは学界全般の現状を知ることに著しい困難を生じている。本書は、このような問題に対処することを目ざした」と言う。この本には戦争の影は既になく、全巻学問的なレビュー集である。第I部は特別寄稿で、渡辺武男の万国地質学会議の話、矢部長克の四国構造論(英文)、坪井誠太郎の岩石学雑想が載っている。第II部は日本の地質学の展望で、各分野の23編のレビューが掲載されている。第III部は日本の地質学界の展望として、学会史年表、会員数と役員の推移、学会賞・研究奨励金受賞者、大学地学教室一覧、アンケートのまとめ、地学関係研究所、学協会、団体、賛助会員、会社、博物館、そして長期研究計画の現状が掲載されている。この年の会員数は2481人だった。
1985年の論集(518 頁)は日本地質学の地向斜論からプレート論へのパラダイム転換の最中に出版され、今読み直すと非常に面白い。刊行委員長は端山好和、委員は兼平(かねひら)慶一郎、鈴木尉元、床次(とこなみ)正安、楡井(にれい)久、野沢保、浜田隆士、吉田尚で、編集実務は橋辺菊恵(現事務局長)が担当した。極端な地向斜派から急進的なプレート派までを網羅し、端山のまえがきはプレート論に懐疑的だが、プレート論の成立過程やそれに関わった日本の研究を見事にまとめた堀越叡の島弧論が光っている。またこの論集には、本学会のこの種の出版物では初の女性執筆者が登場する(永原裕子「日本の隕石学」)。会員数は4928人と倍増した。
1993年発行の100周年記念誌は706頁の紺地に金文字の堂々たるハードカバー本で、編集委員長は鈴木尉元、委員は天野一男、市川浩一郎、今井 功、遠藤邦彦、酒井豊三郎、島崎英彦、鳥海光弘、端山好和、山下 昇の9名であり、執筆者は78人にのぼる(私を含む)。会長の端山は序文で「現在、日本地質学は、学問体系そのものの転換を求められている」と言っているが、この頃はもう「転換済み」だったと思う。この年はバブル崩壊後の経済停滞期で、オウム真理教の活動が不気味さを増し、2年後に阪神大震災と地下鉄サリン事件が起きた。ソ連崩壊の2年後、湾岸戦争の3年後、天安門事件の4年後に当たる。しかし、地質学会としては、会員数が5000人の大台を超え、前年には皇太子殿下を総裁にお迎えして第28回万国地質学会議(IGC)京都大会を成功させ、英文学術誌The Island Arc(表紙は沈み込み帯の断面図。今はTheがない)が創刊されて、100周年誌はいわば地質学会の絶頂期の記念碑である。この本の冒頭には山下の「ナウマンから江原真伍まで」、端山の「小藤文次郎」、清水大吉郎の「小川琢治」、佐藤正の「小林貞一」などの評伝があり、列島形成論の歴史、島弧論、環境、災害、地下資源、国際交流、地学教育などの各論も充実している。今井功の学会史年表は資料価値が高いが、国際誌に発表した日本の重要論文の採録が少ない。岡野武雄の「第二次大戦前・中の海外地質調査」は多くの資料に基づく労作であるが、樺太の項は短く、日本が関与して成功した北樺太の石油開発の記述がないのは残念である。
1998年の地質学論集49号の編集委員は秋山雅彦、小松正幸、坂幸恭、新妻信明、50号は狩野謙一、高木秀雄、金川久一、木村克己、伊藤谷生、山路敦、小坂和夫で、執筆者は計78人(私を含む)、うち女性は3人である(田崎和江、清水以知子、佐々木みぎわ)。49号は平朝彦の「付加体地質学の誕生と発展」や丸山茂徳の「21世紀の日本の地質学」、陸上・海底掘削のレビュー、弘原海(わたつみ)清の「宏観異常による地震危険予知」などがある。1995年の阪神大震災を受けた杉山雄一の「活断層調査の現状と課題」もあるが原発の語は一つもない。50号はフラクタルなど2編が英語で、基礎的な構造地質学や日本列島地質構造論(磯崎行雄など)の他に月と火星のテクトニクス、応用地質のレビューがあり、「地震予知研究における構造地質学の役割」(嶋本利彦)もある。この時期は地震予知を楽観視していたようだ。会員数は翌1999年に5200人を越えたが、これ以後減少し、現在は4000人を少し下回る。
2014年の現在まで15年間以上、この種の大きな総説集は本学会では刊行されていない。この間、日本国内では直下型の被害地震が多発して柏崎刈羽原発が被災し、ついには「想定外」の海溝型超巨大地震が発生して福島第一原発のメルトダウン事故が起きてしまった。これを受けて、原子力規制委員会による原発敷地内の破砕帯調査が開始され、本学会が推薦した委員が国民注視の中で調査を行う事態になっている。また、イタリアのラクイラ地震裁判では、地震学者や地質学者が不適切な情報を住民に伝え被害を拡大させたとして有罪判決を受け、本学会はこれに憂慮を表明した。さらに、地球温暖化の進行とともに土砂災害も増加し、地質研究者と社会の関わりが増している。最近のジオパークの発展や津波堆積物への世界的関心はその肯定的な面であろう。一方で他の惑星や衛星の地質学が発展し、その成果に基づいて地球の地質を見直す必要が出てきている。現在、70〜80年代の学問的なパラダイム転換とは異質の、科学者としての意識や価値観の転換が求められているように感じる。今、地質学の歩みを振り返り、新しい展望を示すことが、是非とも必要である。4年後の125周年に向けて、日本地質学の新たな展望を示す総括的なレビューを行うべきだと思う。
石渡 明(日本地質学会会長、東北大学東北アジア研究センター)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】Island Arc よりらのお知らせ
──────────────────────────────────
■Island Arc 23-1号がオンライン出版されました.
本号は,Research Article 5編から構成されています.
詳しくはこちら
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iar.2014.23.issue-1/issuetoc
<日本語要旨のページ>
http://www.geosociety.jp/publication/content0077.html
■『Virtual Special Issue』として『Precambrian World 2009』が公開されました.
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1440-1738/homepage/virtual_special_issues.htm
Island Arcは、学会webサイトから無料で閲覧出来ます。(要ログイン)
ログイン方法はこちらから.
https://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地球全史スーパー年表:会員特別販売のお知らせ
──────────────────────────────────
<<本日発売!>>
地球全史スーパー年表
日本地質学会[監修]
清川昌一・伊藤 孝・池原 実・尾上哲治[著]
B5判オールカラー/ケース入り(年表1枚:364mm×1030mm、解説24頁)
本体価格:1300円(税込 1365円)
地球46億年の全歴史が、1枚の特大ポスターになりました!
地球科学の最新研究を取り込み、地質年代の区分を主要な出来事、環境データなどを収録した年表に、要点をまとめた解説書付きです。
会員の方は3月末日の受付分まで、送料無料となります。
お申込はお早めに!
会員特別販売の申込書は、会員ページよりダウンロードできます。
http://www.geosociety.jp/members/content0082.html
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//member/super20140218.pdf
(要ログイン)
ログイン方法はこちら.
https://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
(申込書はNews誌Vol. 17-2にも掲載予定)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】熊本大学総合科学技術共同教育センター特別講義のご案内
──────────────────────────────────
Announcement of Lectures in English by Invited Researcher
Global Joint Education Center for Science and Technology (GJEC) will offer the following intensive course in English.
Dr. James F. Allan of National Science Foundation (USA) will give
lectures from February 26 to 27.
==========================================================
Title: Ocean Drilling Science
Lecturer: Dr. James F. Allan (National Science Foundation, USA)
Date and place:
2/26 (Wed) 10:20-16:00 MOT lecture room, 4F Bldg. of Grad School Sci Tech.
16:10-17:40 Room C-420 Seminar room, Bldg. of Faculty of Science
2/27 (Thu) 10:20-17:40 MOT lecture room, 4F Bldg. of Grad School Sci Tech.
----------------------------------
Lecture content:
1) Scientific Ocean Drilling: IODP, and the JOIDES Resolution drills offshore Antarctica (general talk with film)
2) NSF and IODP: Lessons learned from a decadal drilling program- how to do and how not to do big international science programs
3) The National Science Foundation and recommendations for writing a good proposal
4) Scientific Ocean Drilling: How it works
5) The Colima Rift, Mexico: a tectonic terrane in the making?
6) Fernandina Volcano: How robust is the Galapagos hotspot?
7) Cr-spinel in basalt, an overlooked gem
----------------------------------
Seminar:
2/26 (Wed) 16:10-17:40 Topic (2)
at Room C-420 Seminar room, Bldg. of Faculty of Science
2/27 (Thu) 16:10-17:40 Topic (3)
at MOT lecture room, 4F Bldg. of Grad School Sci Tech.
----------------------------------
2/28, 3/1(Sat, Sun) Field trip to Sakurajima and Unzen.
----------------------------------
問い合わせ(詳細・聴講希望等)
熊本大学・長谷中 利昭 E-mail: hasenaka@sci.kumamoto-u.ac.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】 2014年度の会費払込等について
──────────────────────────────────
■2014年度の会費払込について
1.自動引落を登録されている方:2013年12月24日(火)に引き落としを行いました.
請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下さい.
これより以前に不足額がある場合には加算され,余剰金がある場合はその分を減額して引き落としされています.通帳には金額とともに「チシツカイヒ」あるいは「フリカエ」,「SMBC」などと表示されておりますので,必ずご確認下さい.
2.上記以外の方(お振り込み)
12月中旬頃に請求書兼郵便振替用紙をお送りいたしました.折り返しご送金くださいますようお願いいたします.
■災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
日本地質学会では,災害救助法適用地域で被災された会員の方々のご窮状をふまえ,以下の措置を取らせていただきます.
「日本地質学会に届出の住居または勤務地が災害救助法適用地域に該当する会員のうち,希望する方」は2014年度(平成26年度)会費を免除することといたします.
2013年度において,災害により被害にあわれた方のうち,この措置の適用を希望される会員は,(1)会員氏名(2)被害地域(3)被災状況(簡単に)を明記し,学会事務局までお申し出下さい.
お申し出の方法は,郵送,FAX,e-mailのいずれでも結構です.
締切は,2014年2月24日(月)までとさせていただきます.
■学部学生・院生(研究生)「割引会費申請」
最終締切:3月31日(月)
毎年更新となりますので,次年度会費について該当する方は,必ず申請してください.
それぞれ詳しくは,
http://www.geosociety.jp/outline/content0135.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】支部情報
──────────────────────────────────
[北海道支部]
■日本地質学会北海道支部平成25年度総会
3月8日(土)14:00-16:00
場所:北海道大学理学部5号館3階 5-301室
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[東北支部]
■東北支部2012-2013年度総会・講演会
3月1日(土)[3月1日(土)のみの開催になりました]
場所:山形大学小白川キャンパス 地域教育文化学部2号館
(午前中 幹事会(山形大及び次期担当の岩手大)
*総会欠席の方は,川辺孝幸(kawabe@kescriv.kj.yamagata-u.ac.jp)宛に委任状をお送り下さい.
プログラム等,詳しくは,
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
[西日本支部]
■平成25年度総会・第165回例会
2月22日(金)[21日:幹事会]
場所:佐賀大学,本庄キャンパス,大学会館
*総会へ欠席の方は,委任状をお送り下さい.
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地質・地盤情報活用促進に関する法整備推進協議会からの緊急提言
わが国の地下に眠るビッグデータ・・・
国民の安全・安心と国土強靭化のために地盤情報の再活用を!!
そのための法整備を!!
http://www.zenchiren.or.jp/suishin/suishin_index.html
■JAMSTEC2014
3月5日13:00-17:30
場所:東京国際フォーラム ホールB7(千代田区丸の内3−5−1)
入場料無料 事前申込不要(要旨集は会場にて配布)
http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20140205/
■第3回学生のヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集
日本地質学会ほか 推薦
実習実施時期:3月5日(水)出発,19日(水)帰国(15日間)
http://www.geocities.jp/gondwanainst/
■NUMO技術開発報告会 −自然現象の確率論的評価手法の適用性−
3月6日(木)10:00-17:00
場所:三田NNホール&スペース 多目的ホール
参加費:無料 申込期限:2月24日(月)
http://www.numo.or.jp/topics/2013/14021811.html
■日本堆積学会2014年山口大会
3月14日(金)〜17日(月)
会場: 山口大学吉田キャンパス大学会館ほか
http://sediment.jp/04nennkai/2014/annai.html
■「ヒト−資源環境系の歴史的変遷に基づく先史時代人類誌の構築」
2013年度公開研究集会
3月15日(土)12:55-17:30,16日(日)9:00-15:00
会場:明治大学駿河台キャンパスグローバルフロント1階 グローバルホール
(東京都千代田区神田駿河台1-1)
参加費:無料 申込締切:3月7日(金)
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//others-pdf/geo201402181709.pdf
■日本地球惑星科学連合2014年大会
4月28日(月)〜5月2日(金)
会場:パシフィコ横浜会議センター(横浜市西区みなとみらい1-1-1)
予稿集原稿投稿締切:2月12日(水)
事前参加登録締切:4月16日(水)予定
http://www.jpgu.org/
■第51回 アイソトープ・放射線 研究発表会
7月7日(月)〜9日(水)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1)
発表申込締切:2月28日(金)
講演要旨原稿締切:4月11日(金)
http://www.jrias.or.jp/seminar/cat4/505.html
■第31回歴史地震研究会(名古屋大会)
9月20日(土)〜22日(月)
会場:名古屋大学減災連携研究センター 減災ホール
講演申込締切:5月30日(金)
http://sakuya.ed.shizuoka.ac.jp/rzisin/menu7.html
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会 日本地質学会ほか 共催
2015年7月27日〜8月2日
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1-1)
http://inqua2015.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0133.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■産業技術総合研究所:博士型任期付研究員または中堅型研究員募集(4/16)
■2014年度地球化学研究協会学術賞「三宅賞」および「進歩賞」候補者募集(8/31)
■第11回 日本学術振興会推薦募集(4/14-16 学会締切:3/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.254 新発売!「青木ヶ原溶岩のたんけん」
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.254 2014/4/1 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】★新発売★ リーフレットたんけんシリーズ4 青木ヶ原溶岩のたんけん
【2】日本地質学第6回総会開催について
【3】[地質の日]公開講演会やジオ散歩など開催予定
【4】日本地質学会初代会長神保小虎小伝
【5】地層処分技術WG中間とりまとめに関するパブリックコメント
【6】2014年度春季地質調査研修参加者募集
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】★新発売★ リーフレットたんけんシリーズ4 青木ヶ原溶岩のたんけん
──────────────────────────────────
地質リーフレットたんけんシリーズ4
富士山青木ヶ原溶岩のたんけんー樹海にかくされた溶岩の不思議ー
青木ヶ原の「溶岩」をテーマにした新しいリーフレットができました.道の駅や西湖コウモリ穴など,アクセスしやすい観察ポイントです.写真やイラストをふんだんに使用し,わかりやすく火山現象を解説しています.
編集:日本地質学会地学教育委員会
(編集委員:小尾 靖・鈴木邦夫・高橋正樹・矢島道子)
2014年3月31日 発行 A2版 8折 両面フルカラー印刷
定価400円(会員頒価 300円)*20部以上ご注文の場合は割引有
http://www.geosociety.jp/publication/content0004.html
ご注文は学会事務局まで
e-mai: main@geosociety.jp FAX: 03-5823-1156
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】日本地質学第6回総会開催について
─────────────────────────────────
5月24日(土)15:30-17:00
会場 北とぴあ 第2研修室(東京都北区王子1-11-1)
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/outline/content0138.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[地質の日]公開講演会やジオ散歩など開催予定
─────────────────────────────────
■公開講演会「日本の地質学:最近の発見と応用」
Recent progress in geological science in Japan
主催:一般社団法人日本地質学会
5月24日(土)13:00-15:00
会場:北とぴあ第2研修室(東京都北区王子)
参加費:会員無料,非会員500円.[CPD単位取得可(2)]
問い合わせ先(世話人):斎藤 眞(常務理事)・星 博幸(行事委員長)
e-mail;main@geosociety.jp
詳しくはこちら。
http://www.geosociety.jp/name/content0107.html
<同会場にて以下の行事も予定>
・第5回惑星地球フォトコンテスト表彰式(11:00-12:00)
※作品展示有り
・一般社団法人日本地質学会第6回総会(15:30-17:00)
※正会員は,総会に陪席することができます
■街中ジオ散歩in Tokyo「下町低地の地盤沈下と水とくらし」
主催:一般社団法人日本地質学会,一般社団法人日本応用地質学会
5月10日(土)9:50-17:00 少雨決行(予定)
場所:東京都江東区清澄白河、住吉、東大島、南砂町界隈(仙台堀川、小名木川)
会費:一般2,000円, 小中学生500円(予定)保険代、入場料含。ます(当日支払)
詳しくはこちら。
http://www.geosociety.jp/name/content0110.html
■地球科学講演会「プレートの沈み込みと国土形成 −紀伊半島南部のおいたちとジオパーク構想−」
主催:大阪市立自然史博物館・地学団体研究会・日本地質学会近畿支部
5月25日(日)13:30-15:30
場所:大阪市立自然史博物館 講堂
参加費:無料(申し込み不要)
詳しくはこちら。
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】日本地質学会初代会長神保小虎小伝
─────────────────────────────────
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
筆者は日本地質学会会長の任期を終えるに当たり、初代会長神保小虎(1867-1924)の小伝を記してその心意気を会員諸兄諸姉に伝え、本学会の今後の発展の一助としたい。
続きはこちらから、、、
http://www.geosociety.jp/faq/content0921.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地層処分技術WG中間とりまとめに関するパブリックコメント
─────────────────────────────────
昨年夏に経済産業省資源エネルギー庁より学会が依頼を受け,渡部副会長を推薦して進められていた「総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原子力小委員会地層処分技術WG」では,その検討結果をまとめた中間報告書を公開し,平成26年 3月25日〜平成26年4月24日の期間にパブリックコメントを募集しています.
本学会では,会員の皆様のご意見を積極的にパブリックコメントとして登録し開かれた議論を進めて頂きたいと考えています.以下のページをご覧下さい.
http://www.enecho.meti.go.jp/rw/shobungijyutsu-iken.htm
問い合わせ先
資源エネルギー庁放射性廃棄物等対策室 地層処分の技術的信頼性に関する意見募集担当
電話:03-3501-1511(内線4781)
E-mail:rwt-opinion@meti.go.jp
(日本地質学会執行理事会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】2014年度春季地質調査研修参加者募集
─────────────────────────────────
地質調査法の基本技術の修得をめざすとともに,それをベースに得られた過去の調査や研究の成果についても学びます.地質調査の経験のない方でも,地質調査法の基本を体で習得することを目指します.
日程:5月12日(月)〜5月16日(金)4泊5日
場所:千葉県君津市及びその周辺地域(房総半島中部域)
募集人数:6名. 参加費:12万円
申込締切:4月11日(金)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/engineer/content0035.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】 支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■2014年度支部総会・地質技術伝承講演会
4月19日(土)
14:00-15:40 地質技術伝承講習会
15:50-16:45 関東支部総会
場所:北とぴあ7階第2研修室(東京都北区王子1-11-1)
講師:佐藤 尚弘氏(明治コンサルタント株式会社)
タイトル:切土のり面にまつわる話(長期追跡調査、樹林化など)
参加費:無料 どなたでも参加できます.CPD単位取得可能(2.0)
申し込み方法
1)ジオ・スクーリングネット https://www.geo-schooling.jp/
2)担当幹事 加藤 潔(駒澤大学)kiyoshi.katoh@gmail.com
3)日本地質学会関東支部気付 関東支部 FAX:03-5823-1156
※委任状をお願いします( kanto@geosociety.jp へ;締切:4月18日18時)
詳しくは,支部HP http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地震本部ニュース2月号,3月号
http://www.jishin.go.jp/main/p_koho04.htm
■三朝国際インターンプログラム2014(分析化学部門)
7月1日(火)〜8月8日(金)
募集人数:5名程度
応募締切:5月6日(火)
宿泊:三朝宿泊施設を利用します。
費用:旅費・プログラム期間の生活費を全額支給します。
応募資格他:学問に意欲を持つ、学部3・4年生、修士課程学生。
地球科学分野以外、例えば物理学、化学、生物学、工学などを専攻している学生の皆さんの応募も歓迎します。国籍・キャリアは問いません。
なお、プログラムに関わるコミュニケーションは基本的に英語で行います。
http://intern.misasa.okayama-u.ac.jp/pml2014/?lang=ja
■第55回科学技術映像祭表彰式・上映会
表彰式 :4月18日(金)
東京上映会:4月17日(木)〜18日(金)
(その他、全国各都市の科学館にて上映)
http://ppd.jsf.or.jp/filmfest/
■日本地球惑星科学連合2014年大会
4月28日(月)〜5月2日(金)
会場:パシフィコ横浜会議センター(横浜市西区みなとみらい1-1-1)
事前参加登録締切:4月16日(水)
http://www.jpgu.org/
■第159回深田研談話会[現地]「東西日本の地質境界を歩く」
5月17日(金)9:30-16:30(銚子駅集合/解散)
申し込み締切:4月22日(火)
定員:20名(申込多数の場合は抽選)
参加費:3000円
http://www.fgi.or.jp/
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
2015年7月27日(月)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1-1)
http://inqua2015.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0133.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■ソウル国際大学:海洋地質学テニュアトラックポジション募集(4/14)
■明治大学研究・知財戦略機構:黒耀石研究センター特任教員公募(5/19)
■日本学術振興会 育志賞受賞候補者推薦募集(6/11-13 学会締切:5/16)
■2017年度 国際学術集会開催助成(4/1-2015/2/27)
■藤原セミナー開催希望者募集(7/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
【geo-Flash】No.497 名古屋大会代替企画!様々な企画が進んでいます!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.497 2020/8/18┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】名古屋大会代替企画
【2】令和2年7月豪雨災害等地質災害関連情報
【3】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【4】トピック:昇仙峡は黒富士が造った?(後編)
【5】大学院生を対象にしたアンケート調査:全国大学院生協議会(全院協)
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】名古屋大会代替企画
──────────────────────────────────
WEBによる代替企画!様々な企画が進んでいます!
・2020年度学会各賞受賞記念講演 9/13配信予定(どなたでも視聴可能!)
・第1回ショートコース 9/19開催[参加申込受付中:9/7締切]
・コロナ禍での地質学教育に関するサイバーシンポジウム 9/27開催
(プレゼンターが決定しました。参加無料、どなたでも視聴可能!)
・ジュニアセッション(旧小さなESの集い)[参加校募集中:9/30締切]
ほか
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0041.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】令和2年7月豪雨災害等地質災害関連情報
──────────────────────────────────
令和2年7月豪雨災害関する情報
http://www.geosociety.jp/hazard/content0098.html
地質災害緊急調査について
http://www.geosociety.jp/hazard/content0024.html
会費の特別措置のお知らせ
http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html#saigai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■地質学雑誌
・126巻8月号(予告)特集号「法地質学の進歩」
「法地質学入門」(ノート)杉田律子ほか/「石英粒子の形状および表面形態
を用いた法科学的検査法の開発」(論説)板宮裕実ほか/「日本の法地質学
の歩み」(総説)組坂健人ほか/「法地質学の国際動向」(総説)杉田律子/
「The Geoforensic Search Strategy: A High Assurance Search Method to Assist
Law Enforcement Locate Graves and Contraband Associated with
Homicide, Counter Terrorism and Serious and Organized Crime」(総説)
Donnelly and Harrison/「法地質学のツールとしての磁気測定:レビュー」
(総説)川村紀子
■Island Arc
新しい論文等が公開されています.
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14401738/2020/29/1
Island Arcでは著者制作のVideo Abstractの掲載が可能です.
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14401738/homepage/video_abstracts
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】トピック:昇仙峡は黒富士が造った?(後編)
──────────────────────────────────
昇仙峡は黒富士が造った?:
「地質図Navi」と「地理院地図」で楽しむ四次元の旅(後編)
正会員 高山信紀
「前編」に引き続き,後編では,「旧荒川」,「旧板敷川」のルートと縦断面,
大滝,仙娥滝の成り立ちについて検討した内容を述べる.
つづきはこちら、、、 http://www.geosociety.jp/faq/content0919.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】大学院生を対象にしたアンケート調査:全国大学院生協議会(全院協)
──────────────────────────────────
本調査は,全院協が,全国各大学の加盟院生協議会・自治会の協
力の下に実施する,全国規模のアンケート調査です.本調査は,大
学院生の研究及び生活実態を客観的に把握し,もってその向上に
資する目的で行うものです.
【アンケート回答期限】2020年8月31日
【アンケート回答フォームURL】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVDp5Nqhz4iIWY_sS5s4W5Zg1zNZX0qR8lae91PXYXKAotbA/viewform
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)旭町学術資料展示館企画展示
「ジオパークの微化石展」
8月1日(土)-9月6日(日)
会場: 新潟大学旭町学術資料展示館(新潟市中央区旭町通)
http://www.lib.niigata-u.ac.jp/tenjikan/
日本学術会議主催学術フォーラム
「学術振興に寄与する研究評価を目指して」
8月29日(土)13:00-18:00
場所:オンライン
参加費無料
http://www.scj.go.jp/ja/event/2020/287-s-0829.html
ぼうさいこくたい2020
頻発化する大規模災害に備える
−「みんなで減災」助け合いをひろげんさい−
10月3日(土)[オンライン大会]
http://bosai-kokutai.jp/
2020年度第1回(初心者向け)地質調査研修(追加)【参加者募集中】
10月12日(月)-16日(金)(注)
室内座学:茨城県つくば市(産総研)
野外研修:茨城県ひたちなか市,福島県いわき市
定員 6名(最小催行人数:4名)(定員になり次第締切)
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2020-1.html
(協)第36回ゼオライト研究発表会
11月19日(木)-20 日(金)
場所:富山国際会議場
https://jza-online.org/events
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
─────────────────────────────────
・神戸大学大学院海事科学研究科海洋政策科学部(新設)地球化学分野(教授
又は准教授)及び固体地球科学分野(准教授又は講師)公募 (9/30)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
国際地質科学連合(IUGS) 第67回理事会報告および第35回、36回万国地質学会議(IGC)案内
国際地質科学連合(IUGS) 第67回理事会報告 および第35回、36回万国地質学会議(IGC)案内
小川 勇二郎(会員、国際地質科学連合理事)
昨年のニュース誌(Vol. 16-4: 2013年4月号)で国際地質科学連合(International Union of Geological Sciences;以下IUGS)第66回理事会の報告をしたが、それと重複することもあるが、以下に第67回理事会(2014年2月7日から2月10日まで、インド、ゴア州のボグマロ・リゾートホテル)が開かれたので、以下に簡単に報告する。日本からは、北里洋学術会議IUGS分科会委員長と、小川が出席した。会長以下理事(欠席の幹事Ian Lambert (オーストラリア)を除く)計8名、および各関連プロジェクト委員、インド科学アカデミー会員、当地の南極・海洋研究所代表、北京の秘書部の係員など、総計45名が出席した。
理事会は、2月7日の準備会、8,9日の全体会議、10日の理事のみの会議の、計4日間であった。インド科学アカデミーと南極・海洋研究所の周到な準備と歓迎により、会議はスムーズに行われた。最後の日の夕刻、南極・海洋研究所への見学旅行が行われた。関係所轄の方々に感謝する。
以下、主要な議論と感想を述べる。
1.IUGSとその理事会の概要
IUGSは、世界各国の地質学研究者・教育者らの集まるUNION(連合)と呼ばれる組織が集まるICSU(国際学術会議)のもとでのNGOで、その理事会はソフトな執行機関で事務局は北京の地質科学院に置いている。毎年の諸報告や提案に基づき、地質学にかかわる研究・教育等の行動・運動計画を審議・実行し、予算・決算の審議をはじめ、国際的に必要と思われる事項を探し出し、勧告や行動を起こしている。各国からの分担金で運営され、日本は、学術会議が管轄している。最近では、万国地質学会議(IGC)を主導し、国連やその中のユネスコ関連の事業に積極的に関与する方向である。理事会は会長、副会長、会計、幹事、理事(総計9名)が中心となって、各関連機関(グループ)の活動報告をもとにして将来計画を練り、国連の提唱する総合計画のために、研究者、研究機関および各関連機関(グループ)がどのような役割を果たすべきかを議論している。さらに、ユネスコの諸活動を援助するために、経済的援助をも行っている。役員(理事会メンバー)は、それぞれの担当分野を持ち、世界の活動状況を監視し、助言するよう求められている。
2.理事会での審議内容、感想を含む
1)冒頭、開催国のインド科学アカデミーの代表者から歓迎の挨拶、それに対して、当IUGSの会長から、感謝の言葉があった。
2)議事進行、昨年の議事録の承認、最近の役員会の報告があった。特に、関係が深いGSA(アメリカ地質学会)の125周年記念事業やEGU(ヨーロッパ地球科学連合)でのエキシビションの報告があった。どちらも盛況であったとのことである。
3)難しい関係になっているユネスコとの問題が指摘され、今理事会でのメインテーマとして取り上げる。特に、IGCP(国際地質科学プロジェクト)とGlobal Geoparks Network (ジオパーク運動)について。
4)会計報告(2013年度の決算と年会費の支払い状況)活動的、非活動的、ペンディングおよび脱退の国名の列挙。各地域で、対応するようにとの指摘があった。( 脱 退 :アルジェリア。なお、脱退を考慮中(ペンディングという)および活動中止(分担金未払い)の国が、それぞれ複数ある。)日本は、アジア諸国の状況を調べる。様々な問題はあるが、全体に収支は好調である。
5)隣接する分野のIUGG(国際測地学地球物理学連合)の会長Harsh Gupta 氏 (インド)から、協力すべきは協力するとのコメント。関連のテーマを確認。それは、資源、気候変動、災害、水問題、ダイナミクスなどである。
6)IGCPとGeoparksへの財政的および審査協力などについて、かなりの時間をかけて議論した。委員会を作ってさらに議論することを提案する(なお、財政的な支援を強化することで合意。)。問題は、ユネスコ(国連傘下)と、当IUGS(NGO)とがどのような関係で進むかに関しては、いまだに決定的な合意に至っていないことである。
7)諸活動の報告。IUGSとしての活動は、上記のユネスコ関連の事業へのかかわりのほかに、次の3段階がある。はじめ、イニシアチブと呼ばれる研究・教育活動の準備段階、次いで実質的な活動であるタスクグループ、さらに本格的な行動であるジョイントプログラムへと進む。今回は、それらのいくつかの活動の報告が以下のようにあった。列挙する。
地質的な倫理に関しての関心が強まっている。災害科学への貢献に力を入れる(2013年10月の、日本の主導でのG-EVER研究集会(仙台)へのIUGSと日本学術会議からの貢献の報告を含む)。ILP(国際リソスフィア計画)、地球化学マッピング(統一基準で世界の岩石の分布図を作る)、犯罪地質学、気候変動問題、世界遺産、ジオパーク、露頭保全(特に構造地質、http://outcropedia.org/)、石材地質、専門家育成、南北問題(アフリカを意識、フィールドスクールなどの推進)、GEM (http://www.globalquakemodel.org/)、大学でのカリキュラムの向上、若手地質グループの活動支援、次世代の資源問題(RFGという)などについて、報告と積極的な支援の発言が続いた。(その報告や評価に基づいて、次年度の予算が審議される。)
8)6年前の2010年のIGC(万国地質学会議、オスロ、毎回オリンピックの年に行われている)において、それまで開催国が主導していた同会議を、以後当IUGSが主導することに決まった。次回の2016年の35回IGCは、南アフリカ・ケープタウンで8月27日から9月4日まで(http://www.35igc.org/html/index.html;すでにセッションのプロポーザルの受付が始まっている。多くの方々のプロポーズをお願いしたい。また、講演、ポスターなどの要旨の受け付けは、2015年初頭には開始されるという。アフリカ諸国が一丸となって、多くの巡検が用意されるとのことである。この機会に、ぜひ、アフリカ訪問を計画されたい。)、またその次の2020年の36回IGCは、インド・デリーで3月2日から8日まで行われる。ただし、前回34回のオーストラリア・ブリスベーンが、非常に高額な登録料であったこともあり、将来の開催においては、多くの人にとって参加可能範囲を超えていないかが議論された。今後、検討する。なお、ケープタウンでのIGCの標語は、Geology in Society: Economy and Scienceとのことで、地質科学の社会貢献が求められてはいるものの、この資源国家での地質学の経済への依存度と貢献度の強さをうかがわせるものと感じた。
9)ICSU(国際学術会議)の会長のSteve Wilson氏(パリ;地球物理学出身とのこと)と、Skypeを用いての討論を行った。国連主導の10年計画である、Future Earthへの取り組みについて説明があったのち、質疑応答を行った。ICSUでは、地質学の負の面(鉱毒、公害など)が強調されるきらいがあり、資源や環境、災害対策などの正の面があまり評価されていないことが浮き彫りになり、理事会メンバーからは危機感が発せられた。これは、ユネスコでの地質学の立場の低下にもいえるとのことで、世界の科学研究・教育のベースであるとの自負を持っている地質学の将来について、今後より一層議論すべきであることを強く感じた。
10)今後の取り組み。予算をとってIUGSで活動するためには、上に述べたように、まずイニシアチブという準備段階の組織を立ち上げ、2,3年後、タスクグループというより具体的な活動を起こし、その上で、プログラムへと進むことが求められる。IGCPやGeoparksなどは、別組織のもとであるが、その審査などは、当IUGSが積極的に関与する方向である。なお、IGCPは純粋科学の推進をする研究組織であり、汎世界的(特に途上国を含む)なものである必要がある。従来、日本は多くのIGCPのプログラムを積極的に推進してきたが、今後はより厳しい状況(全体のプログラム数の縮小)がある見込みである。心すべきであると感じた。
11)来年の理事会は、カナダ・バンクーバーのコンベンション・ホールで、2015年1月26-29日に行われる。
12)Annual Report of IUGS-EC (USB memory), Episodes (当科学連合の機関論文誌)が配布された。
南極・海洋研究所からのデカントラップ洪水玄武岩(白亜紀)と表層のラテライト。 段丘の成因たる隆起運動は、沖合の堆積盆の荷重をコンペンセイトするためのゆっくりとしたシーソー的なリバウンドによるもの、との説明があった。
3. 一般的な感想、今後の重要課題等
地質科学は、自然科学の分野のうちの基礎をなす地球(および惑星、宇宙をも部分的に含む)の46億年の諸現象を四次元的に研究するが、それらは、惑星科学、地球物理学、地球化学、地球生物学とも密接な関連がある。ICSU(国際学術会議)の中でも、地球惑星連合を作る動きがあり、統合的な活動も模索されている。さらに、国連は、2012年までの、Earth Systemという大きな題目ののちに、2013年からは、Future Earth という、人類生き残りをかけた大きなタイトルのもとで、国際的な研究・教育活動を開始した。それらの中で、地質科学の果たすべき役割を見極めて、積極的な活動・提案をして行くことになっている。国家間の競争よりも、協力関係を築き、南北問題(主としてアフリカを想定する)、教育活動にも、力を入れている。また、各国および地域の地質科学の重要な教育手法である、ジオパークや世界自然遺産、世界地質遺産と言った運動へも積極的に参加する方向である。
国際的な科学の研究・教育は、従来ユネスコを中心として行われてきたが、最近、財政的な窮地に陥っている。それを打開し、従来にも増して研究・教育を世界的に浸透させるためには、NGOである当IUGSを含む研究連合が、積極的な援助をすべきであるとの議論が高まっている。それを、財政的、参画の方法論などの基本的な事項から、具体的な方法までの多様な活動を模索する必要があり、重要な局面を迎えている。アジアおよびアフリカの指導的な働きをすべき日本へも、大いなる期待が寄せられている。一方で、分担金の支払いが滞るケースが増えており、そのような財政的な問題も生じている。
2012年からの新理事会メンバーの活躍は目を見張るばかりであり、今後の進展が注目される。特に、国連、国際学術連合との協調関係は、大いに期待される。ただし、国際的な経営難は、ユネスコの関連事業に広く及んでおり、比較的潤沢な当IUGSの役割の増大が期待される。ただし、ユネスコ傘下で行われてきた諸プログラムは、ユネスコのロゴ(テンプルと呼ばれる建物の図案)の下での活動を希望しているようであり、それらとの調整が微妙である。なお、2年前に就任した当IUGSの会長である、オーベルヘンスリ氏は、会議のほとんどを主導し、不偏不党の立場から、会議を公平・積極的にリードした。その努力に深く敬服したい。
なお、地質学の関連する国際研究・教育機関としての統括を目指すIUGSの最大の催しは、毎回オリンピックの年に開かれるIGCである。今まで多くのIGCに参加し、4年毎の学問の進展、その地域の地質や人間活動に親しみ、多くの刺激や感化を受け、さまざまな交流をする契機になった方も多いと思われる。老若男女を問わず、次回の2016年、2020年の南アフリカ、インドとも、地質には非常に重要な地域であり、日本からの地質研究者も多い。この際、ぜひ、これに参加することを目指していただきたいと思う。なお、理事会において、小川は、変動帯でのIGCがこのところ少ないことを指摘し、今後、それへの考慮もお願いしたい、と発言しておいた。これから研究者・教育者・行政や企業活動に携わる方々も、上記のいくつかのテーマ(環境、資源、災害、教育など)に、地質学が果たす役割が期待されていることを心して、ぜひ、今後もIUGS-IGCに関心を持っていただきたい(www.iugs.org/)。ご質問、ご要望は、fyogawa45@yahoo.co.jpまで。(※@を半角にしてください)
(2014.2.27)
地質マンガ 地学系よくある勘違い
地質マンガ
地学系よくある勘違い
原案:本郷宙軌 マンガ:KEY
ボーリング(boring):地中に孔を掘ること.
ボーリングは地質試料の採取や掘削孔を利用した物理探査などのために実施される.
目的や掘削深度,岩質に応じて様々な掘削方法がある.
陸上だけではなく船上や水中からでも掘削されている.
ボーリングによって円筒状に採取された堆積物をボーリングコアと呼ぶ.
ボウリング(bowling):ボールを転がし10本のピンを倒して点を競い合うスポーツ.
ボーリングは大地の歴史を知るためのわくわくするものであり,
決してつまらない(boring)ものではありません.
geo-flash No.251 フォトコン結果速報
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.251 2014/3/4 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】第5回惑星地球フォトコンテスト審査結果
【2】地質調査総合センターの出版物に係る誤分析データの記載について
【3】国際地質科学連合(IUGS) 第67回理事会報告および第35回、36回万国地質学会議(IGC)案内
【4】2014年度春季地質調査研修参加者募集
【5】地球全史スーパー年表:会員特別販売のお知らせ
【6】「割引会費申請」忘れずに!
【7】支部情報
【8】科研費助成事業の審査に係る「系・分野・分科・細目表」等への意見募集
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞情報
【11】地質マンガ:地学系よくある勘違い
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】第5回惑星地球フォトコンテスト審査結果
──────────────────────────────────
応募作品全294作品のうち,上位入選作品は以下の14作品に決定いたしました.
今回も多数のご応募を頂き,ありがとうございました.
入選作品の詳細,今後展示会の予定などは,WEBおよび学会ニュース誌でお知らせする予定です。
第5回惑星地球フォトコンテスト審査委員会
委員長:白尾元理
委 員: 高木秀雄・内藤一樹・松田達生・清川昌一
最優秀賞「Earth scape of Japan」 山本直洋(埼玉県)
優秀賞「地層風景」 増見芳隆(東京都)
優秀賞「枕状溶岩とアオウミガメの産卵」 後藤文義(神奈川県)
ジオパーク賞「活火山桜島」 山田宏作(鹿児島県)
入選「恵比寿島のジオサイト:海底土石流の名残」 竹之内範明(静岡県)
入選「Floating Alps」 山本直洋(埼玉県)
入選「火山(堰止)湖のある風景」 森井悠太(千葉県)
入選「原生代の谷」 池上郁彦(福岡市)
入選「タイムアーチ」 糸満尚貴(大分県)
入選「台湾燕巣泥火山」 田中郁子(兵庫県)
入選「東京砂漠」 鈴木正人(静岡県)
入選「王冠形態をつくる岩片インパクト」 椎野勇太(東京都)
入選「桜島火山雷」 永友武治(宮崎県)
入選「FACE」 平山 宏(和歌山県)
*今回,中・高校生以下での入選は該当がありませんでした.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】地質調査総合センターの出版物に係る誤分析データの記載について
──────────────────────────────────
分析業者による水試料(水素・酸素安定同位体組成)の誤分析データを用いた出版物の公表(2012年10月29日)に係る地質調査総合センター出版物への影響につきまして精査した結果をご報告申し上げます。
なお、該当出版物を所有されている方々に対する今後の対応方針につきましては、現在検討を進めているところです。ご心配をおかけし大変恐縮ですが、後日改めて本ホームページ上にてお知らせいたします。
誤分析データが使用されている出版物および編集物は下記をご覧下さい。
https://www.gsj.jp/publications/oshirase/info02.html
問い合わせ先: 産業技術総合研究所地質分野研究企画室
TEL 029-862-6034 E-mail: rp-geo-ml@aist.go.jp
[追記:2014.3.6]
(このお知らせは,産総研地質調査総合センターからの依頼により,2012年12月19日にセンターのホームページ上に掲載された報告について,再度注意喚起するものです)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】国際地質科学連合(IUGS) 第67回理事会報告および第35回、36回万国地質学会議(IGC)案内
──────────────────────────────────
小川 勇二郎 (会員、国際地質科学連合理事)
昨年のニュース誌で国際地質科学連合(International Union of Geological Sciences;以下IUGS)第66回理事会の報告をしたが、それと重複することもあるが、以下に第67回理事会(2014年2月7日から2月10日まで、インド、ゴア州のボグマロ・リゾートホテル)が開かれたので、以下に簡単に報告する。日本からは、北里洋学術会議IUGS分科会委員長と、小川が出席した。会長以下理事(欠席の幹事Ian Lambert (オーストラリア)を除く)計8名、および各関連プロジェクト委員、インド科学アカデミー会員、当地の南極・海洋研究所代表、北京の秘書部の係り員など、総計45名が出席した。
続きはこちらから.
http://www.geosociety.jp/faq/content0494.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2014年度春季地質調査研修参加者募集
──────────────────────────────────
地質調査法の基本技術の修得をめざすとともに,それをベースに得られた過去の調査や研究の成果についても学びます.地質調査の経験のない方でも,地質調査法の基本を体で習得することを目指します.
日程:5月12日(月)〜5月16日(金)4泊5日
場所:千葉県君津市及びその周辺地域(房総半島中部域)
募集人数:6名. 参加費:12万円
申込締切:4月11日(金)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/engineer/content0035.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地球全史スーパー年表:会員特別販売のお知らせ
──────────────────────────────────
<<好評発売中!>>
地球全史スーパー年表
日本地質学会[監修]
清川昌一・伊藤 孝・池原 実・尾上哲治[著]
B5判オールカラー/ケース入り(年表1枚:364mm×1030mm、解説24頁)
本体価格:1300円(税込 1365円)
地球46億年の全歴史が、1枚の特大ポスターになりました!
地球科学の最新研究を取り込み、地質年代の区分を主要な出来事、環境データなどを収録した年表に、要点をまとめた解説書付きです。
会員の方は3月末日の受付分まで、送料無料となります。
お申込はお早めに!
会員特別販売の申込書は、会員ページよりダウンロードできます。
http://www.geosociety.jp/members/content0082.html
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//member/super20140218.pdf
(要ログイン)
ログイン方法はこちら.
https://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
(申込書はNews誌Vol. 17-2にも掲載予定)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】「割引会費申請」忘れずに!
──────────────────────────────────
■学部学生・院生(研究生)「割引会費申請」最終締切は3月31日(月)です.
毎年更新となりますので,次年度会費について該当する方は,必ず申請してください.
申請書のダウンロードなど、詳しくはこちら.
http://www.geosociety.jp/outline/content0135.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[北海道支部]
■日本地質学会北海道支部平成25年度総会
3月8日(土)14:00-16:00
場所:北海道大学理学部5号館3階 5-301室
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[東北支部]
■東北支部2012-2013年度総会・講演会 報告
2014年(平成26年)3月1日山形大学地域教育文化学部において,10:30〜12:00に支部引継幹事会,13:00〜13:50に総会,14:00〜18:15に講演会が行われた.
口頭発表10件,ポスター発表10件があり,26名の参加者があった.
詳細はこちらから.
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
[関東支部]
■2014年度総会・地質技術伝承講演会
4月19日(土)14:00:16:45
場所:北とぴあ7階第2研修室(東京都北区王子1-11-1)
講師:佐藤 尚弘氏(明治コンサルタント株式会社)
*総会に欠席される方は委任状(kanto@geosociety.jpへ)をお願いします.
詳しくは,http://kanto.geosociety.jp/
■支部幹事の選出
立候補期間:3月3日(月)〜3月13日(木)
候補者(支部会員)は,氏名・所属・連絡先を下記に届け出てください.
受付先:日本地質学会関東支部あて,メール,郵送,FAXにより受け付けます.
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル内
FAX:03-5823-1156
メール:main@geosociety.jp 見出しは「関東支部選挙」で
詳しくは,News誌Vol. 17-2に掲載
[西日本支部]
■165回日本地質学会西日本支部 例会・総会 報告
2014年(平成26年)2月22日10:00〜17:00に支部例会,12:15〜13:15に総会が佐賀大学本庄キャンパスの大学会館において行われた.例会では口頭発表,ポスター発表併せて20件が行われ,40名を超える参加者があった.
詳細はこちらから.
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】 科研費助成事業の審査に係る「系・分野・分科・細目表」等への意見募集
──────────────────────────────────
独立行政法人日本学術振興会では、科学研究費助成事業の審査に係る「系・分野・分科・細目表」(以下「細目表」という。)の別表「時限付き分科細目表」の改正案の作成にあたり、毎年期間を限ってホームページにより意見を受け付けておりましたが、今後は、「細目表」及び「時限付き分科細目表」への意見を常時受け付けることといたしました。
詳しくは,http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■平成25年度海洋情報部研究成果発表会
3月10日(月)13:15-17:45
会場:海上保安庁海洋情報部(東京都江東区青海2-5-18)
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KIKAKU/press/2014/H260218_kenkyu.pdf
■学術フォーラム「世界のオープンアクセス政策と日本:研究と学術コミュニケーションへの影響」
3月13日(木)13:00-17:30
場所:日本学術会議講堂
参加:無料、要事前登録(https://form.cao.go.jp/scj/opinion-0003.html)
問い合わせ先:日本学術会議事務局企画課学術フォーラム担当
TEL:03-3403-6295 FAX:03-3403-1260
■日本地球惑星科学連合2014年大会
4月28日(月)〜5月2日(金)
会場:パシフィコ横浜会議センター(横浜市西区みなとみらい1-1-1)
事前参加登録締切:4月16日(水)
http://www.jpgu.org/
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
2015年7月27日〜8月2日
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1-1)
http://inqua2015.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0133.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■東京大学大学院:理学系研究科地球惑星科学専攻 助教募集(4/21)
■東京工業大学:火山流体研究センター 研究員募集(3/17)
■室戸ジオパーク推進協議会:地質専門員募集(3/26)
■平成26年度東レ科学技術賞/科学技術研究助成(6月〜10/10 学会締切:8/31)
■国土地理協会 平成26年度学術研究助成(4/1-18)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】地質マンガ:地学系よくある勘違い
──────────────────────────────────
『地学系よくある勘違い』
原案:本郷宙軌 マンガ:KEY)
http://www.geosociety.jp/faq/content0495.html
その他の地質マンガはこちらから!
http://www.geosociety.jp/faq/content0057.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.252(臨時) トピックセッション募集 締切間近!!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.252 2014/3/11 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2014鹿児島大会:トピックセッション募集。締切間近!!〔3月17日(月)〕
【2】産総研地質調査総合センターの出版物に係る閲覧時の注意
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2014鹿児島大会:トピックセッション募集。締切間近!!〔3月17日(月)〕
──────────────────────────────────
日本地質学会は、西日本支部の支援のもと、鹿児島大学(郡元キャンパス)において第121年学術大会(2014年鹿児島大会)を2014年9月13日(土)〜15日(月)の日程で開催いたします。 1月号のNews誌(p.4〜5)において、既にご案内しておりますが、現在、トピックセッションの募集期間中です。トピックセッションは、広く地質学の領域をカバーし、これから新分野あるいは注目すべき分野になりそうな内容を扱うものとします。形式はレギュラーセッションと同じです(15分間の口頭発表,あるいはポスター発表)。 なお、本大会も前回同様,シンポジウムの一般募集はありません。 ※シンポジウムは鹿児島大会実行委員会および学会執行部が企画します。
募集締切:3月17日(月)
詳しくはこちら。
http://www.geosociety.jp/science/content0060.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】産総研地質調査総合センターの出版物に係る閲覧時の注意
──────────────────────────────────
産総研地質調査総合センターの出版物に記載している水試料に対する水素・酸素安定同位体比の分析結果に関して,分析を依頼した業者から誤りがあったことが公表され(2012年10月29日),センターから,出版物への誤分析の影響について精査を行なった結果として,下記の出版物について誤分析データが使用されていることが報告されました(下記URL参照).
この報告は2012年12月19日にセンターのホームページ上に掲載済みのものですが,この度,当該出版物のうち当会が所蔵するものについて,閲覧時に誤分析データが含まれている出版物である旨,注意喚起を行うようセンターより文書による依頼がありました.会員の皆様におかれましても下記出版物をご覧の際はご注意ください.
誤分析データが使用されている出版物および編集物
https://www.gsj.jp/publications/oshirase/info02.html
本件お問い合わせ先:
産業技術総合研究所地質分野研究企画室:
電話 029-862-6034
E-mail : rp-geo-ml@aist.go.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.253 学部学生・院生の割引会費申請は間もなく締切です
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.253 2014/3/18 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】理事選挙結果のお知らせ
【2】連合2014年大会(4月28日〜5月2日)のお知らせ
【3】2014年度春季地質調査研修参加者募集
【4】地球全史スーパー年表:会員特別販売のお知らせ
【5】「割引会費申請」間もなく締め切り!
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】理事選挙結果のお知らせ
──────────────────────────────────
選挙規則ならびに選挙細則もとづき、一般社団法人日本地質学会理事選挙を実施いたしましたので、ご報告いたします。
一般社団法人日本地質学会 選挙管理委員会
委員長 阿部 なつ江
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0083.html
※会員番号・パスワードによるログインが必要です。
ログインの方法は http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】連合2014年大会(4月28日〜5月2日)のお知らせ
─────────────────────────────────
★コマ割り公開
2014年大会日程のコマ割りが3月5日に公開されました.
http://www.jpgu.org/meeting/downloads/sessionlist.pdf
★大会参加登録 事前申込受付中!
事前(割引)参加登録申込締切
2014年4月16日(水) 17:00 JST
http://www.jpgu.org/meeting/registration.html
★スペシャルレクチャー 今年も開催決定!
ワールドクラスの研究者が研究分野を越えて学生・若手研究者に贈る地球惑星科学の特別講義シリーズ!『スペシャルレクチャー』を連合大会期間中の5日間,毎日お昼休み(13:00〜13:40)に開催します
★高校生セッション申込み受付中
申込み締切は4月9日(水)です.
http://www.jpgu.org/highschool_session/2014/
大会サイトhttp://www.jpgu.org/meeting/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2014年度春季地質調査研修参加者募集
─────────────────────────────────
地質調査法の基本技術の修得をめざすとともに,それをベースに得られた過去の調査や研究の成果についても学びます.地質調査の経験のない方でも,地質調査法の基本を体で習得することを目指します.
日程:5月12日(月)〜5月16日(金)4泊5日
場所:千葉県君津市及びその周辺地域(房総半島中部域)
募集人数:6名. 参加費:12万円
申込締切:4月11日(金)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/engineer/content0035.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地球全史スーパー年表:会員特別販売のお知らせ
─────────────────────────────────
<<好評発売中!>>
地球全史スーパー年表
日本地質学会[監修]
清川昌一・伊藤 孝・池原 実・尾上哲治[著]
B5判オールカラー/ケース入り(年表1枚:364mm×1030mm、解説24頁)
本体価格:1300円(税込 1365円)
地球46億年の全歴史が、1枚の特大ポスターになりました!
地球科学の最新研究を取り込み、地質年代の区分を主要な出来事、環境データなどを収録した年表に、要点をまとめた解説書付きです。
会員の方々のみ、3月末日の受付分まで、送料無料となります。
お申込はお早めに!
会員特別販売の申込書は、会員ページよりダウンロードできます。
http://www.geosociety.jp/members/content0026.html
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//member/super20140218.pdf
(要ログイン)
ログイン方法はこちら.
https://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
(申込書はNews誌Vol. 17-2にも掲載)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】「割引会費申請」間もなく締め切り!
─────────────────────────────────
■学部学生・院生(研究生)「割引会費申請」最終締切は3月31日(月)です.
毎年更新となりますので,次年度会費について該当する方は,必ず申請してください.
申請書のダウンロードなど、詳しくはこちら.
http://www.geosociety.jp/outline/content0135.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】 支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■2014年度総会・地質技術伝承講演会
4月19日(土)14:00〜16:45
場所:北とぴあ7階第2研修室(東京都北区王子1-11-1)
講師:佐藤 尚弘氏(明治コンサルタント株式会社)
*総会に欠席される方は委任状(kanto@geosociety.jpへ)をお願いします.
詳しくは,http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■電中研TOPICS Vol.16
http://criepi.denken.or.jp/research/topics/index.html?m=140318
■地震本部ニュース12月号、1月号
http://www.jishin.go.jp/main/p_koho04.htm
■日本学術会議会長談話「緊急事態における日本学術会議の活動に関する指針の策定について」の公表について
2/28の日本学術会議の幹事会において「緊急事態における日本学術会議の活動に関する指針」が策定されました。また、この指針の趣旨、内容に関する日本学術会議会長談話「緊急事態における日本学術会議の活動に関する指針の策定について」が公表されました。
[日本学術会議会長談話本文]
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-d5.pdf
[緊急事態における日本学術会議の活動に関する指針]
http://www.scj.go.jp/ja/scj/kisoku/117.pdf
■ 第158回深田研談話会「地形・地質、自然史から植物の分布を読む」
4月11日(金)15:00〜17:00
申し込み締切:4月9日(水) 先着:80名 参加無料
会場:深田地質研究所 研修ホール(文京区本駒込2-13-12)
http://www.fgi.or.jp/
■日本地球惑星科学連合2014年大会
4月28日(月)〜5月2日(金)
会場:パシフィコ横浜会議センター(横浜市西区みなとみらい1-1-1)
事前参加登録締切:4月16日(水)
http://www.jpgu.org/
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
2015年7月27日(月)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1-1)
http://inqua2015.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0133.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.260 井龍会長就任挨拶
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.260 2014/6/17 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】会長挨拶:日本地質学会長就任にあたって
【2】[鹿児島大会]事前参加登録受付開始!・演題登録も受付中
【3】[鹿児島大会]講演申込画面(PASREG):入力時の注意
【4】[鹿児島大会]ランチョン・夜間集会申込受付中
【5】[鹿児島大会]講演予定者で,現在未入会のかたへ周知のお願い
【6】2014年度会費督促請求について
【7】惑星地球フォトコンテスト入選作品展示会のお知らせ
【8】地学オリンピックキャラクターデザインコンテスト開催中!
【9】街中ジオ散歩 in Tokyo 開催報告
【10】第4回学生のヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集
【11】支部情報
【12】その他のお知らせ
【13】公募情報・各賞情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[会長挨拶:日本地質学会長就任にあたって
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会長 井龍康文
(東北大学大学院理学研究科地学専攻)
この度,日本地質学会(以後,地質学会と略します)会長に就任いたしました.2年間の任期中,率先して地質学会のために尽力する所存です.「汗をかく執行体制」を確立し,日本の地球惑星科学分野における地質学会のプレゼンスの向上に努めます.私は,会長に立候補する際に5つの公約をあげました.ここでは,抱負として,それらの公約をさらに詳しく説明したいと思います.なお,紙面が制約されている関係上,公約の中で,ここで言及することができない事項があることを御了承下さい. ・・・・・・
続きはこちらから.
http://www.geosociety.jp/outline/content0137.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[鹿児島大会]事前参加登録受付開始!・演題登録も受付中
─────────────────────────────────
日本地質学会第121年学術大会(鹿児島大会)の事前参加登録の受付を開始しました。
演題登録受付中です!
今年もたくさんの参加・発表申込をお待ちしています。
9月13日(土)〜15日(月)
会場:鹿児島大学 ほか
◆事前参加登録:8/19(火)締切[※巡検のみ 8/8(金)締切]
◆演題登録:7/1(火)締切
〔注〕演題登録と事前参加登録は,それぞれ別のお申し込みになります。ご注意ください。
鹿児島大会HPはコチラ↓
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[鹿児島大会]講演申込画面(PASREG):入力時の注意
─────────────────────────────────
(1)新規登録:〔受付番号〕と〔パスワード〕を取得しましょう
参加登録トップ画面一番下【新規登録はこちらから】から新規登録を行い,〔受付番号〕と〔パスワード〕を取得してください。
登録画面には“演題情報”のほかに“連絡者情報(一度登録しておけば書き換える必要の無い項目)”もあります。まずは新規登録を行い,〔受付番号〕と〔パスワード〕を取得することをお勧めします。
(2)修正する場合:画面右上【マイページ】からログイン
〔受付番号〕と〔パスワード〕で,【マイページ】からログインいただき,締切まで何度でも入力情報の修正ができます。
画面操作に慣れていないと,タイムアウトする可能性が高く,締切直前の登録は入力ミス等も多くなります。余裕をもってご登録下さい。
講演申込画面(PASREG)はこちらから
https://www.pasreg.jp/reg/top/geosocjp/author
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[鹿児島大会]ランチョン・夜間集会申込受付中
─────────────────────────────────
鹿児島大会,ランチョン・夜間集会の申込受付中です。会合を予定されている皆様は,忘れずにお申込下さい。
ランチョン・夜間集会申込締切:6月25日(水)必着
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0038.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[鹿児島大会]講演予定者で,現在未入会のかたへ周知のお願い
─────────────────────────────────
会員の皆さまの周囲に,鹿児島大会で講演する予定で,入会申込の手続きを済ませていない学部生・院生・職場の同僚のかたがおりましたら,7/1日(火)までに入会申込書の郵送手続きを完了するよう,ご周知願います。
申込締切時点(7/1)で入会申込書の提出がない場合,発表申込が受理できませんので,ご注意ください。入会申込書は7/1日までに必着でお願いします。
入会申込書は以下よりダウンロードできます。
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//outline/nyukai.pdf
〔注1〕入会申込中でも演題登録(講演申込)は可能です。入力の際,会員番号欄は空欄のまま,会員種別欄は『入会申込中』を選択して操作を進めてください。
〔注2〕鹿児島大会において発表される方は演題登録のほかに事前参加登録も忘れずに,必ず手続きしてください。
演題登録と事前参加登録は,それぞれ別のお申し込みになります。ご注意ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】2014年度会費督促請求について
─────────────────────────────────
1.督促請求のための自動引き落とし日は6月23日(月)です。
2014年度会費が未入金のかたで,1月から5月上旬までの間に自動引落の手続きをされたかたは6月23日に引き落としがかかります。
引き落とし不備にならぬよう,残高の確認をお願いします。
2.郵便振替用紙によるお振り込みの方には,6月13日(金)に督促請求書(郵便振替用紙)を郵送しました。お手元に届きましたら,早急にご送金くださいますようお願いいたします。
※7月上旬頃までに入金確認が取れない場合には,7月号の雑誌から発送停止となります。定期的に雑誌をお受け取りになりたい方は,お早めにご送金ください.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】惑星地球フォトコンテスト入選作品展示会のお知らせ
──────────────────────────────────
今回は,最新の第5 回の入選作品をはじめとして過去の作品も多数展示いたします.
お誘い合わせの上,迫力ある作品を是非ご覧下さい.
7月1日(火)〜31日(木)
場所:みどりのiプラザ(東京都千代田区日比谷公園内緑の水の市民カレッジ3階)
https://www.tokyo-park.or.jp/college/green/
開館時間 9:00〜17:00 休館日 日曜・祝日 入場無料
詳しくは、http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】地学オリンピックキャラクターデザインコンテスト開催中!
──────────────────────────────────
<中・高教員ならびに,中高生のお子さんがいる父兄の会員の方へ>
地学オリンピック日本委員会では、日本地質学会との共催で中学生・高校生を対象としたキャラクターデザインコンテストを実施しています。
素敵なキャラクターで地学オリンピックをPRしてみませんか?
周囲の中・高生にぜひお声掛け下さい。
募集締切:10月31日
応募資格:中学生・高校生
多くの皆様からのご応募をお待ちしております。
募集要項のダウンロードはこちらから
http://jeso.jp/wp-content/uploads/2014/06/ieso_character_design_contest.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】街中ジオ散歩 in Tokyo 開催報告
──────────────────────────────────
地質の日の街中ジオ散歩も今年で3回目になります.1回目の千代田区,2回目の石神井川に続いて,今回は江東区の地盤沈下と内水管理をテーマに実施しました.
(中略)
当日は晴天に恵まれ,参加者一同,楽しく出発しました.午前中は排水ポンプ場を見学しながら,水門管理センターの方々から,江東区三角地帯は地盤沈下のため,きめ細かな内水管理が必要とされるとの説明を受けました.そして近隣の清澄庭園を見学しました. ........(緒方信一)
続きはこちらから.
http://www.geosociety.jp/name/content0120.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】第4回学生のヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集
──────────────────────────────────
<日本地質学会等推薦>
ヒマラヤ地学や野外地質学に造詣の深い日本全国の大学教員,元教員や技術者ら(30人が指導・引率者として登録)がボランティアで,日本の学生に素晴らしいヒマラヤの地学と自然環境を実地で実習指導します.航空運賃,宿泊費,食費,車のチャーター,現地ガイドやポーターの雇用等の必要経費一切込みで参加費学生1人20 万円以内,実施主体の利益なし完全ボランティアのプログラムです.
実施時期: 2015 年3 月上旬(4日頃)出発,出国から帰国まで15 日間
参加募集対象:全国の地学,災害地質,自然環境等に関係する学科・専攻科の学生・大学院生を優先※学生の指導教員,関係企業の新人技術者や指導上司,及び高校生や中学・高校の理科教員,一般市民も受け入れます.
定員:20名
参加費:学生,大学院生は20 万円以内(暫定)
参加申込締切:2014年11月末日
詳細はこちら
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
学生のヒマラヤ野外実習プロジェクト世話人
世話人会 代表 吉田 勝
E-mail: gondwana@oregano.ocn.ne.jp
Tel/Fax: 0736-36-7789
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■夏休み教師巡検:5億年前と10万年前の茨城を見る
関東在住の小・中・高校で教育に携わっておられる教員の皆様が対象ですが、会員外や教員以外の方の参加も大歓迎です。
8月20日(水)〜21日(木)
場所:20日:北浦東岸の下総層群(堆積構造、貝化石、生痕等)
21日:日立周辺(カンブリア紀の赤沢層、日立鉱山、石炭層等)
案内者:荒川真司清真学園教諭、田切美智雄茨城大名誉教授
費用:15,000円(予定)(宿泊費・交通費・諸雑費込)
参加申込締切:7月11日(金)下記宛にメールでお申込下さい。
連絡先:米澤正弘 my-yonezawa@y6.dion.ne.jp
■清澄フィールドキャンプ 参加者募集
8月25日(月)〜31日(日)
場所:東京大学千葉演習林(〒299-5505 千葉県鴨川市清澄)
費用:宿泊・食事・保険(約15000円/6泊)+レンタカー代(約12000円)
応募締切:7月4日(金)(*応募書類は所定のフォーマットを使用のこと)
詳しくは,支部HPへ http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■公開シンポジウム「航空宇宙、船舶海洋分野等における研究開発と利用応用の橋渡しとバランス〜双方向の流れをめざして〜」
6月27日(金)9:30〜17:30
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木7-22-34)
http://www.jaxa-sf.jp/
■海洋教育セミナー&フォーラム「海の学びの万華鏡」
7月20日(日)
「海洋教育セミナー」10:00〜12:00(9:30受付開始)
「海洋教育フォーラム」13:30〜17:00(13:00受付開始)
会場:東京大学・本郷キャンパス 福武ホール(http://fukutake.iii.u-tokyo.ac.jp/)
対象:小・中・高等学校教員、教育関係者、学生、一般
定員:180名 参加費:無料
http://rcme.oa.u-tokyo.ac.jp/information/20140524_502.php
■「青少年のための科学の祭典」2014全国大会
7月26日(土)〜27日(日)
日本地質学会 後援
場所:科学技術館(千代田区北の丸公園)
http://www.kagakunosaiten.jp/
■IGCP608 Asia-Pacific Cretaceous Ecosystems(白亜紀アジア−西太平洋生態系)
第2回国際シンポジウム
日本地質学会ほか 共催
9月4日(木)〜6日(土)(シンポジウム)
9月7日(日)〜10日(水)(巡検:銚子・那珂湊・双葉層群)
会場:早稲田大学 大隈講堂 小講堂
http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/
■第17回日本水環境学会シンポジウム
9月8日(月)〜10日(水)※10日は見学会のみ
場所:滋賀県立大学
参加申込:7月1日(火)〜8月18日(月)
http://www.jswe.or.jp/event/symposium/2014/joinGuide.html
■2014年度日本地球化学会第61回年会
日本地質学会ほか 共催
9月16日(火)〜18日(木)
会場:富山大学五福キャンパス
講演申込締切:7月16日(水)14:00
事前参加登録締切:8月29日(金)14:00
http://www.geochem.jp/conf/2014/
■第58回粘土科学討論会
日本地質学会ほか 共催
9月24日(水)〜27日(土)
会場:福島市A・O・Z(アオウゼ)
参加・講演申込締切:7月11日(金)
講演要旨送付締切:7月25日(金)
http://www.cssj2.org/
■GSA2014
10月19日(日)〜22日(水)
場所:カナダ,バンクーバー
講演要旨締切:7月29日(火)
http://community.geosociety.org/gsa2014/home/
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
2015年7月27日(月)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1-1)
http://inqua2015.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0133.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■千葉県:職員採用選考考査(地質職)(7/3)
■原子力規制庁:職員(各分野経験者)公募(7/11)
■名古屋大学大学院:環境学研究科地球環境科学専攻地質・地球生物学講座教員公募(准教授または助教)(8/18)
■北海道大学大学院:理学研究院 自然史科学部門 地球惑星システム科学分野教員公募(8/29)
■東京大学地震研究所平成27年度国際室客員教員公募(8/27)
■東京大学地震研究所平成27年度特定共同研究課題登録(7/31)
■東京大学地震研究所平成27年度特定機器利用の公募(7/31)
■平成26年度東レ科学技術賞/科学技術研究助成(10/10 学会締切:8/29)
■アースウォッチ・ジャパン2015年度野外調査プログラム募集(8/31)
■Mine秋吉台ジオパーク構想研究チャレンジ助成事業(6/30)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.255 地質の日イベントが目白押し!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.255 2014/4/15 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[鹿児島大会]シンポジウム・セッション決定
【2】日本地質学第6回総会開催について
【3】日本地質学会125周年を迎えるにあたって
【4】5月10日は地質の日!
【5】地質学雑誌規則の大改正
【6】地質学論集58号について
【7】Marjorie Chan教授講演会の案内
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[鹿児島大会]シンポジウム・セッション決定
──────────────────────────────────
本年9月に開催される第121年学術大会(鹿児島大会)のシンポジウムとセッションが決定しましたので,速報としてお知らせします.詳細は後日大会HPまたはNews誌5月号(大会予告号)に掲載します.
■シンポジウム(2件)
■トピックセッション(9件)
■レギュラーセッション (25件)
一覧はこちらから.
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0045.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】日本地質学第6回総会開催について
─────────────────────────────────
5月24日(土)15:30-17:00
会場 北とぴあ 第2研修室(東京都北区王子1-11-1)
総会議案はこちらから
http://www.geosociety.jp/outline/content0138.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本地質学会125周年を迎えるにあたって
─────────────────────────────────
125周年記念事業準備委員会
委員長 矢島道子
委員 天野一男・永広昌之
佐々木和彦・宮下純夫
日本地質学会は地質学の発展や普及を目指して、1893(明治26)年に創立されました。2018年に125周年を迎えます。地質学徒としては大変嬉しいことです。75周年、100周年には記念出版物が刊行され、学会の歴史や研究の動向などが総括されています。
125周年に関しては、理事会のもとに125周年記念事業準備委員会(矢島、天野、佐々木、永広、宮下)が設置され、検討を重ねてきました。 .....
続きはこちらから。
http://www.geosociety.jp/science/content0063.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】5月10日は地質の日!
─────────────────────────────────
各地で地質に関するイベントが開催されますので、是非足をお運びください。
■第5回惑星地球フォトコンテストほか入選作品展示会
5月3日(土)17:00〜5月17日(土)13:00
場所:銀座プロムナードギャラリー(中央区銀座4丁目地内 東銀座地下歩道壁面)
■地質の日記念 街中ジオ散歩in Tokyo「下町低地の地盤沈下と水とくらし」
5月10日(土)9:50-17:00 少雨決行(予定)
場所:東京都江東区清澄白河ほか
■公開講演会「日本の地質学:最近の発見と応用」
・「犯罪捜査と地質学」杉田律子(科学警察研究所)
・「巨大地震の巣を掘る そこから見えてきたもの」坂口有人(山口大学)
・「宇宙からの贈りもの:日本の地層から隕石衝突の証拠を発見」佐藤峰南(九州大学)
・「日本全国の地質情報をあなたへ〜進化する日本シームレス地質図〜」
西岡芳晴(産業技術総合研究所)
5月24日(土)13:00-15:00
会場:北とぴあ第2研修室(東京都北区王子)
その他イベント、各イベントの詳細はこちらから。
(ポスターのダウンロードもできます。)
http://www.geosociety.jp/name/content0014.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質学雑誌規則の大改正
─────────────────────────────────
今月5日の地質学会理事会で『地質学雑誌投稿編集出版規則』の大改正が承認されました.新しい規則は,すでに地質学雑誌のホームページで公開しています.
また,大改正に関する解説記事を地質学雑誌4月号に載せますので,ご覧ください.
今回の改正の目玉は,連載講座を載せられるようにしたことです.
会員個人だけでなく,部会などグループとして連載を企画していただくこともできます.編集委員会としては,学部後期〜修士の教科書になるような連載を期待しています.
投稿をお待ちします.
「地質学雑誌」のページはこちら
http://www.geosociety.jp/publication/content0002.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質学論集58号について
─────────────────────────────────
地質学論集 第58号
「地震イベント堆積物ー深海底から陸上までのコネクションー」
藤原 治ほか編 169頁 2004年12月刊行 会員頒価2,900円,送料350円
論集58号は,これまで売り切れとなっていましたが,在庫が確認されましたので,再度販売を開始いたします。購入希望の方は,学会事務局までお申込下さい。
FAX 03-5823-1156 E-mail: main@geosociety.jp
この他,学会出版物在庫案内はコチラ
http://www.geosociety.jp/publication/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】Marjorie Chan教授講演会の案内
──────────────────────────────────
ユタ大学地質学地球物理学教室のMarjorie Chan教授が米国地質学会(GSA)の講演ツアーの一環で来日されるにあたって,東京及び京都での講演会を下記の通り開催いたします.講演では,Chan教授が精力的に研究を行っている火星の堆積作用・堆積史についてお話しいただきます.これに加えて東京では,世界的に見て重要なレザバーの一つである風成砂丘システムの講演もいただきます.講演ツアー並びに講演概要は,GSAのウェブサイト(http://www.geosociety.org/Sections/International/LectureTour/)をご参照ください.
いずれも日本では聞ける機会の少ない興味深い話題と思いますので,皆さまの積極的なご参加をお願いいたします.
講演会
1.東京講演会
5月9日(金)15:00-17:00
場所:東京工業大学地球生命研究所セミナー室(4階)
http://www.elsi.jp/access.html
講演題名:
1) Eolian Explorations: Dunes, Deformation, and Diagenesis
2) Mars for Earthlings: Using Earth Analogs to Decode the Sedimentary History of Mars
2.京都講演会
5月11日(日)15:00-16:00
場所:京都大学百周年時計台記念館国際交流ホールI
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/clocktower/
講演題名:Mars for Earthlings: Using Earth Analogs to Decode the Sedimentary History of Mars
主催:日本堆積学会,日本地質学会,石油技術協会探鉱技術委員会
問い合わせ先:
日本堆積学会国際交流委員会
池原 研(産業技術総合研究所地質情報研究部門)
mail: k-ikehara@aist.go.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
──────────────────────────────────
[北海道支部]
■日本地質学会北海道支部平成26年度例会(個人講演会)
5月31日(土)10:00-18:00(予定)
場所:北海道大学理学部5号館大講堂(5-203)
発表申込締切:5月2日(金)
要旨提出締切:5月15日(木)
■野外巡検「裏山の地質災害—豊平川の洪水」
6月1日(日)8:00-15:30
定員20名、参加費2500円(予定)[学生・院生割引有(検討中)]
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[関東支部]
■2014年度支部総会・地質技術伝承講演会
4月19日(土)
14:00-15:40 地質技術伝承講習会
15:50-16:45 関東支部総会
場所:北とぴあ7階第2研修室(東京都北区王子1-11-1)
講師:佐藤 尚弘氏(明治コンサルタント株式会社)
タイトル:切土のり面にまつわる話(長期追跡調査、樹林化など)
参加費:無料 どなたでも参加できます.CPD単位:2.0
※欠席の方は委任状をお願いします(kanto@geosociety.jp へ;締切:4月18日18時)
■緊急学習会:『福島第一原子力発電所汚染水処理問題収束のために
地質学は何をなさねばならないか』
5月17日(土)13:00-17:00
会場:日本大学文理学部3号館3505教室
京王線桜上水駅または下高井戸駅から徒歩8分
申込締切:5月7日(水)
参加費:資料代として1,500円(学生・大学院生は500円) CPD単位:4.0
申込方法など,それぞれ詳しくは,支部HP http://kanto.geosociety.jp/
[中部支部]
■2014年支部年会
6月14日(土)〜15日(日)
14日:支部総会、シンポジウム、研究発表会、懇親会
15日:地質巡検
場所:信州大学理学部大会議室
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第13回重金属類・廃棄物に関わる地質汚染調査浄化技術研修会
日本地質学会ほか 共催
4月25日(金)10:30 〜27日(日)17:00
定員:30名
会場:潮来ホテル(JR潮来駅前)ほか
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
■平成25年度笹川科学研究奨励賞受賞研究発表会
4月25日(金)9:30〜
場所:ANAインターコンチネンタルホテル(東京都港区)
(出席を希望される場合には、学会事務局へご連絡ください)
http://www.jss.or.jp/ikusei/sasakawa/kenkyuu/kenkyuu.html
■日本地球惑星科学連合2014年大会
4月28日(月)〜5月2日(金)
会場:パシフィコ横浜会議センター(横浜市西区みなとみらい1-1-1)
事前参加登録締切:4月16日(水)
http://www.jpgu.org/
■地球惑星科学NYS若手合宿2014
5月2日(金) 〜 4日(日)
場所:八王子セミナーハウス(東京)
プログラム:若手研究者講演、参加者同士の研究交流、グループディスカッション、懇親会 ※詳細はWebサイト参照
参加費:10,000円(2泊3日:食費宿泊費込,遠方参加者補助有り)
定員:50名 対象:学部生以上
申込締切:4月中旬(定員を超えた場合、締切前に申込みを終了場合有り)
Webサイトで確認していただくか、NYS事務局へメールでお問い合わせ下さい。)
連絡先:nys.earth21@gmail.com
https://sites.google.com/site/nyswakate/2014
■東京地学協会春季特別公開講演会「日本と世界の奇岩に見るジオ多様性」
5月17日(土)14:00-16:30
場所:東京地学協会地学会館講堂
加藤碵一(産総研・地質情報整備活用機構)「日本奇岩百景とジオ多様性」
須田郡司(石の写真家・巨石ハンター)「世界奇岩巡礼」
参加費・予約不要
http://www.geog.or.jp/
■IGCP608 Asia-Pacific Cretaceous Ecosystems(白亜紀アジア−西太平洋生態系)
第2回国際シンポジウム
日本地質学会ほか 共催
9月4日(木)〜6日(土)(シンポジウム)
9月7日(日)〜10日(水)(巡検:銚子・那珂湊・双葉層群)
会場:早稲田大学 大隈講堂 小講堂
http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/
■第31回歴史地震研究会(名古屋大会)
9月20日(土)〜9月22日(月)
会場:名古屋大学減災連携研究センター 減災ホール
講演申込締切:5月30日(金)
http://sakuya.ed.shizuoka.ac.jp/rzisin/menu7.html(第2報)
■第58回粘土科学討論会
日本地質学会ほか 共催
9月24日(水)〜27日(土)
会場:福島市A・O・Z(アオウゼ)
参加・講演申込期間:6月16日(月)〜7月11日(金)
講演要旨送付締切:7月25日(金)
http://www.cssj2.org/
■IGCP589「アジアにおけるテチス区の発達」第3回国際シンポジウム
プレ巡検:10月19日(日)〜20日(月)
シンポジウム:10月21日(火)〜22日(水)
ポスト巡検:10月23日(木)〜26日(日)
開催場所:テヘラン,Hoveizehホテル
http://igcp589.cags.ac.cn/Symposia.htm
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
2015年7月27日(月)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1-1)
http://inqua2015.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0133.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■早稲田大学 教育・総合科学学術院:常勤嘱託職員募集(4/22)
■住友財団 2014年度基礎科学研究助成/環境研究助成公募(4/15-6/30)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
第5回惑星地球フォトコンテスト入選作品:最優秀賞
第5回惑星地球フォトコンテスト入選作品
最優秀賞:Earthscape of Japan(組写真)
写真:山本直洋(埼玉県) 撮影場所:静岡県伊東市大室山・山口県美祢市秋吉台・熊本県阿蘇地方米塚
【撮影者より】
「Earthscape」と題して,地球を感じる写真をテーマに作品を撮り続けています.今回組み写真として自然が作り出した不思議な地形を撮影した3作品を並べました.地殻の変動等スケールの大きい自然の力によってできたこれらの地形を空から見ることで,地球の息吹を感じることができました.
【審査委員長講評】
この作品はいずれもモーターパラグライダーを使って低空からの撮影で,新しい視点からの写真が新鮮です.冬枯れの伊豆大室山は斜光で,新緑の阿蘇米塚は順光で,秋吉台は早朝に飛行して日中では分かりにくい浅いすり鉢状のくぼ地,ドリーネを印象的に捉えています.それぞれの写真もしっかりしていますが,3点の組み写真としても成功しています.この調子で日本全国の地形を撮影されることを期待します.
【地質的背景】
大室山は4000年前,米塚は千数百年前の噴火でできた小型火山で,スコリア(黒っぽい軽石)からなる砕屑丘.どちらも春先には山焼きをするので樹木はなく,草地になっている.ドリーネは,雨水が石灰岩の割れ目にそって地下に浸透するときに周囲の石灰岩を溶かしてできるすり鉢状の地形.(審査委員長 白尾元理)
目次 進む→
第5回惑星地球フォトコンテスト入選作品:優秀賞
第5回惑星地球フォトコンテスト入選作品
優秀賞:地層風景
写真:増見芳隆(東京都) 撮影場所:アメリカ ユタ州国道163号線メキシカンハット近郊サン・ホアン川
【撮影者より】
国道163のモニュメントバレーからアーチーズ国立公園を結ぶあたりにこの地層が見えます.サン・ホアン川に削られた侵食と風化を繰り返してきた,この地層の歴史と変化は,私にはすばらしい自然のアートを発見した想いで撮影しました.
【審査委員長講評】
アメリカ西部は乾燥気候のために植生に乏しく,地層や地形の撮影には適した場所です.コロラド高原を何百㎞もドライブしていると,このような風景に出会ってドキッとすることがあります.作者は,平行な地層が変形していく場所を選んで撮影しました.地層の灰色と赤褐色,河辺の緑,空の青と雲の白,色彩豊富な地質写真となっています.
【地質的背景】
米国ユタ州南東端Mexican Hat付近で見られるRaplee monocline.コロラド高原のほぼ中央部に位置します.写真は,南北に約15 km程連なる山地の最も標高の高い部分の西側斜面を捉えています.斜面を構成する地層は後期石炭紀のHermosa層群で,石灰岩・砂岩・頁岩からなります.San Juan川の両岸に広がる赤褐色の水平層はペルム紀のHalgaito頁岩層.この構造は,中生代末から新生代初期にかけて起こったララミー変動に伴う圧縮応力による変形であり,単斜構造の下には逆断層が存在すると考えられています.(早稲田大学 小笠原義秀)
←戻る 目次 進む→
第5回惑星地球フォトコンテスト入選作品:優秀賞
第5回惑星地球フォトコンテスト入選作品
優秀賞:枕状溶岩とアオウミガメの産卵
写真:後藤文義(神奈川県) 撮影場所:父島小港海岸
【撮影者より】
2013/5/10日の早朝,宿近くの小港海岸出かけたところ,砂上にウミガメの上陸跡が確認できました.その跡をたどると,なんと,枕状溶岩壁の前でアオウミガメが,目に涙をいっぱいためて産卵中でした.その後,彼女は2時間位で仕事を終え,ゆっくりと,何回も休息を交えながら無事海に入って行きました.
【審査委員長講評】
小笠原諸島父島,小港海岸の枕状溶岩は日本を代表する枕状溶岩の産地です.多数の写真が撮影されているので類型的になりがちですが,作者はウミガメが枕状溶岩の前で産卵するのに偶然出くわしました.このような写真では露頭はないがしろにされがちですが,この作品ではウミガメも露頭もきちんと撮影されていることから優秀賞としました.
【地質的背景】
父島の枕状溶岩は古第三紀始新世(約5000万年前)の海底噴火によって堆積したものです.海底に噴出した溶岩は海水に触れると急冷して固結しますが,内部はまだ融けているので前進します.この繰り返しで枕状溶岩ができます.父島の枕状溶岩は,ボニナイトと呼ばれるマグネシウムに富んだ安山岩です.(審査委員長 白尾元理)
←戻る 目次 進む→
第5回惑星地球フォトコンテスト入選作品:ジオパーク賞
第5回惑星地球フォトコンテスト入選作品
ジオパーク賞:活火山桜島
写真:山田宏作(鹿児島県) 撮影場所:鹿児島県垂水氏牛根
【撮影者より】
火山活動が活発な桜島は,夜になると火山雷を伴った噴火を繰り返して,そのシーンは圧巻で地球の生きる姿そのもので,それを近くで見ることのできる希少なジオパークです.
【講評】
桜島昭和火口の噴火を桜島と大隅半島が接している牛根付近から撮影したものです.最近は活発になったとはいえ,夜の噴火は毎日1〜2回.このような写真を撮るためには幾晩も通わなければ撮影できません.この作品は望遠レンズで撮影して迫力のあるものとなりました.
日本のジオパークは,全34地域のおよそ6割が火山と関わりのある点で,海外のジオパークとは大きく異なります.その中でも国内で最も活発に噴火を繰り返している桜島の写真を,ジオパーク賞として選定しました.(ジオパーク担当理事:高木秀雄)
【地質的背景】
桜島は鹿児島市の対岸にある安山岩質の成層火山.北岳(標高1117m)と南岳(標高1040m)があり,最近4000年間は南岳の噴火が活発.1955年から2000年までは南岳の噴火が盛んで,その後しばらくは静穏でした.2006年から南岳に隣接する昭和火口からの噴火ははじまり,2010年からは活発化になり,現在まで毎年約1000回以上のブルカノ式噴火が続いています.(審査委員長 白尾元理)
←戻る 目次 進む→
第5回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第5回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:東京砂漠
写真:鈴木正人(静岡県) 撮影場所:東京都神津島村天上山.「裏砂漠」とよばれるポイント
【撮影者より】
初夏に初めて家族で出かけた神津島は島の海岸沿いの景色にも圧倒されましたが,島全体を作っている「天上山」の頂上の景色には驚かされました.神津島はビーチへは行ったことはあったのものの,島野象徴であるこの山に登るのは初めてでした.いっしょに登った子どもたちもこの「裏砂漠」についた時,TVで見る月面のような風景に「日本にもこんなそれも東京にこんな風景があるんだ.なんだここは」とびっくりして言葉がでませんでした.これまでに見たことがない景色に感動するとともに,大地の鼓動を感じるようでした.
【審査委員長講評】
神津島は,伊豆諸島の中ほどにある火山島で,島のほぼ中央にあるのが天上山(標高572m)です.山頂部の植生のない平坦地は裏砂漠と呼ばれています.お母さんと一緒に歩いていたお子さんが,見たこともない風景に出会って嬉しくて走り出したのでしょう.楽しそうな様子が伝わってきます.
【地質的背景】
神津島はいくつもの流紋岩質の溶岩ドームからなる火山島です.流紋岩質の溶岩は白っぽく粘性が高いために,玄武岩質の伊豆大島や三宅島とは全く雰囲気が異なります.神津島最新の噴火は838年からはじまった噴火で,この時できたのが天上山の溶岩ドーム.この噴火からまだ千数百年しかたっていないので溶岩ドームの地形がよく保存され,天上山やその南東海岸ではそのときの溶岩や火砕流堆積物を観察できます.(審査委員長 白尾元理)
←戻る 目次 進む→
第5回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第5回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:海底土石流の名残
写真:竹之内範明(静岡県) 撮影場所:静岡県下田市須崎海岸恵比寿島東側の海岸
【撮影者より】
伊豆下田市須崎海岸の小さな島「恵比須島」には,東西の海岸に二つの異なったジオサイトがあり,これは東側のものです.海底の土石流の跡がその後隆起して,さらに波や雨風の侵食を受けて今の海岸を形作っていると言われています.西側の海底火山灰の堆積した美しい縞模様と違って,ただ大小の石ころが固まっているだけの余り写真向きの被写体とは言えませんが,侵食により今にも崩れてきそうな荒々しい太古の名残を写し取りたいと撮影しました.
【審査委員長講評】
伊豆半島は2012年9月に新たに日本ジオパークに認定された場所です.作者は,普通の人にとってはただの礫岩にしか見えないような海底土石流堆積物を,丹念にアングルを選んで魅力的な作品にしています.左手前のアップで構成物質が,右奥の遠景で地層の堆積のようすがよくわかります.上部の岩陰の黒と空の青のコントラストも印象的です.
【地質的背景】
白浜層群は伊豆半島南部に広く分布する地層で,中新世後期から鮮新世(1000万年〜200万年前)の海底火山の噴出物とそこから削られた土砂が近くの浅い海底に堆積したもの.写真に写っている礫は角ばっていて,海底土石流の移動距離がわずかだったことが分かります.(審査委員長 白尾元理)
←戻る 目次 進む→
第5回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第5回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:Floating Alps
写真:山本直洋(埼玉県) 撮影場所:ノルウェーロフォーテン諸島
【撮影者より】
ロフォーテン諸島は,アルプス山脈が海に浮かんでいるような景観と言われています.海抜0mのフィヨルドから一気にそそり立つ山々ははるか昔氷河に削られ荒々しく,さほど高くない山でもアルプスの3,000m級の山を思わせる迫力でした.
【審査委員長講評】
この作品は,最優秀賞と同じ山本直洋さんがモーターパラグライダーを使って撮影したものです.道路や家々をうまく取り込むことによって地形の大きさを表現しているとともに,そこで生活している人々の暮らしも感じさせます.
【地質的背景】
ロフォーテン諸島は,ノルウェー北部の北緯68̊の北極圏にある島で,第四紀にはスカンジナビア氷床に厚く覆われた場所です.ここに写っている山々は標高1000m足らずですが,氷河によって削られたU字谷に海水が浸入してフィヨルド海岸となっています.(審査委員長 白尾元理)
←戻る 目次 進む→
第5回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第5回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:火山湖のある風景
写真:森井悠太(千葉県) 撮影場所:潟沼(宮城県大崎市)・中禅寺湖と男体山(栃木県日光市)・Terkhiin-tsagaan湖(モンゴル)・姿見の池と旭岳(北海道上川郡東川町)
※この作品は横長のため画像をクリックすると別画面で大きな画像を表示します.
【撮影者より】
火山活動によって生じた湖を題材にしました.火山活動の影響を強く受けた湖には特有の静けさがあるように思います.火山活動によって生物多様性が低下することに由来するのかもしれません.組写真というものにはじめて挑戦しました.水面に写る稜線をそろえた時,不意に浮かび上がったひとまとまりの景色に妙に感動したことを覚えています.表現方法に大きな可能性を感じることができた意義深い作品です.
【審査委員長講評】
見た瞬間には何の写真かわかりませんが,パターンの面白さに引きつけられてしまいます.火山の近くにできた湖や沼の写真4枚を凹凸になるようにトリミングしてつなぎ合わせた写真です.水面に映り込んだ凹凸によって上下のシンメトリーもあるので魅力的な組み写真となりました.
【地質的背景】
地質的背景:左から,潟沼(宮城県)・中禅寺湖と男体山(栃木県)・Terkhiin-tsagaan湖(モンゴル)・姿見の池と旭岳(北海道).潟沼と姿見の池は古い火口に水が溜まった火口湖,他2つは火山噴出物よって生じた堰止湖です.(撮影者)
←戻る 目次 進む→
第5回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第5回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:原生代の谷
写真:池上郁彦(福岡県) 撮影場所:Salt River Canyon, アリゾナ
【審査委員長講評】
アリゾナ州東部の原生代の地層を写した作品です.この写真は選者4人の意見が分かれました.地層に比べて道路や橋脚,道路標識が大きすぎて,主題である地層がその中に埋もれてしまったのが残念です.もう少し不要なものを整理して撮影されたらと思います.
【地質的背景】
Salt River Canyonはアリゾナ州東部に位置する渓谷で,有名なGrand Canyonの最下部に対比される原生代の堆積岩が観察されます.この写真はその中でもApache groupと呼ばれる原生代中期の層序に位置するDripping Spring Quartziteを写しています.この浅海で堆積した砂岩は後の変成により極めて高い侵食耐性を持つため,同地域では写真のように崖を成しています.またここでは本層準の堆積後,ストロマトライト構造を持つ上位のMescal Limestoneと共に多くの生命の痕跡が現れるようになります(撮影者).
←戻る 目次 進む→
第5回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第5回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:タイムアーチ
写真:糸満尚貴(大分県) 撮影場所:高知県土佐清水市竜串海岸
【撮影者より】
竜串一帯では砂岩と泥岩の層が波や風に侵食され,数多くの奇岩を見ることができます.写真は生痕化石と呼ばれているもので,およそ3000万年前にこの場所に住んでいたアナジャコの巣穴の跡だといわれています. 無数に生痕化石が並ぶ中,時の経過をを感じさせる小さなアーチを撮影しました.
【審査委員長講評】
アナジャコの巣穴が生痕化石として残っているのをうまく撮影しました.巣穴に入った細粒物質が周囲の砂岩よりも風化しにくいために,このように取り残されたのでしょうか.ローアングルから前後をぼかして巣穴を浮き出したのもよかった.
【地質的背景】
竜串層は台風の影響を受けた浅海域の地層が広く分布し,様々な堆積構造がみられ,巡検や実習コースとしても最適な場所である.本作品はその広く分布する砂岩の中に残っている奇妙な形の異物.オフィオモルファー(Ophiomorpha)という生痕化石の一種をフォーカスしたものである.作品は数ある生痕の中からアーチ状のものを見つけたのでしょうか,それに焦点を当てたものである.地質写真としては,オフィオモルファーのパイプ状の全体像がきちんと見えたほうが評価が高かったかもしれません.
←戻る 目次 進む→
第5回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第5回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:台湾燕巣泥火山
写真:田中郁子(兵庫県) 撮影場所:台湾高雄県高雄市燕巣区金山村,烏山頂泥火山自然保護区
【撮影者より】
学部時代に留学していた台湾に思いを馳せ,金沢大の後輩の台湾一周大巡検に通訳として同行させて頂いた際の一枚です.これは台湾の最南端高雄市に位置する台湾最大の泥火山です.泥火山とは,地下深くの粘土鉱物に地下水が加わり噴出したもので,この写真は火口より噴出するバブルの決定的瞬間をとらえたものです.バブルはメタンを主成分としているため,火を近づけるとボッと激しく燃えます.
【審査委員長講評】
作者は泥の泡が破裂する直前を良いタイミングで撮影しています.日本でも別府や雲仙などの温泉の地獄巡りではこのような光景に出会いますが,破裂直前をとらえるのは難しいものです.デジタルカメラが普及した現在,フイルム代を気にすることもなく,連写機能を使ってこのような写真が撮りやすくなりました.
【地質的背景】
泥火山は堆積岩分布地域において,噴出する泥,地下水,ガス,石油などが形成した小高い地形的高まりと定義されています.写真の台湾燕巣泥火山は,地下深部において粘土鉱物の脱水により形成された異常間隙水圧層によりChishan(籏山)断層沿いに上昇した流体が形成したもので,標高180mの 尾根部に開けた平地に7個の噴出口を持ち,現在でも間欠的に活動しています.比高は3.3mあり,最も高いものは4.5mに及びます.湧出する地下水のδ18Oは6.13‰,δDは-17.7‰,Cl-濃度は5242.9mg/lであり,化石海水(大昔の海水が地層の隙間などに閉じ込められたもの)が起源と考えられています.(山口大学 田中和広)
←戻る 目次 進む→
第5回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第5回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:王冠形態をつくる岩片インパクト
写真:椎野勇太(東京都) 撮影場所:ユーシャン採石場(スウェーデンダーナラ県シリヤン地域)
【撮影者より】
雨天続きで調査が難航しつつ,ようやく晴天に恵まれたある日,ユーシャン採石場の片岡に捲れ上がった王冠を見つけました.それは,蹟石衝突直後の一瞬を連想させるような静かな躍動感でした.
【審査委員長講評】
これも内部からのガスによって泥の泡が飛び散った瞬間を撮影した写真かと思いましたが,そうではなく王冠状に固結した衝突孔だということです.それぞれの王冠の中には大きな岩片が入っているので,雨上がりの採石場の泥だまりに岩片を投げ込んで作った人為的な衝突孔のようです.
【地質的背景】
スウェーデン中南部シリヤン地域には,オルドビス紀(およそ4億5000万年前)の生物礁に由来する石灰岩の採石場が散点的に分布します.重機や発破などの石灰採掘作業で舞い上がった粉塵は場内に再堆積し,ひとたび雨が降れば,至るところが細粒泥質の泥溜りと変貌します.まだ乾燥しきらない泥溜りに岩片が飛び込むと,まるで隕石が衝突したかのようにめり込み,飛び散った泥が空中で固化することもあります.絶妙な保湿量と泥溜りの粘性が,その底面に王冠のような衝突痕を形成しました.(撮影者)
←戻る 目次 進む→
第5回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第5回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:Face
写真:平山 弘(和歌山県) 撮影場所:和歌山県白浜町にある「いそぎ公園」(通称:チャボ公園)を抜け,太平洋に面した断崖
【撮影者より】
海岸の岩の質が他とは違うのか,風化されおもしろい風景を作り出しています.釣り人しか訪れることのない断崖です.長い年月で侵食された岩肌が広がっており,人の顔に見える物など楽しみながら撮影しました.
【審査委員長講評】
最初は題名の意味がわかりませんでしたが,よく見ると手前には2つの目が,その下には鼻があってなるほどと思いました.複雑に曲がりくねった地層をやや逆光気味に撮影したために,鮮やかに凹凸のある地層を捉えています.天気の良い日にこんな海岸を散歩したいものですね.
【地質的背景】
撮影場所周辺には中新世の前弧海盆堆積物である田辺層群上部の白浜累層が分布しており,写真の露頭は白浜累層上部の厚層理砂岩層で海側にゆるく傾斜しています.波浪の卓越する浅海で堆積した砂岩層ですが,堆積構造よりむしろ砂岩表面の風化による凹凸や褐色の模様が目に付きます.砂岩は珪長質で,風化すると白っぽくなります.褐色ないし黄褐色に見える部分は粒子の間に褐鉄鉱など酸化鉄や水酸化鉄からなる鉱物が沈殿した部分です.そのため層状に見える構造は砂岩層の堆積構造とは限らず,地層観察の際は注意してみる必要があります.(山口大学 宮田雄一郎)
←戻る 目次 進む→
第5回惑星地球フォトコンテスト入選作品:入選
第5回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:桜島火山雷
写真:永友武治(宮崎県)
撮影場所:鹿児島県桜島黒神地区国道より撮影.牛根大橋より右へ回って50m位の地点
【撮影者より】
桜島噴火の火山雷の撮影です.毎日数回の噴火を繰り返しています.最近は火口が大きくなっているように感じられます.また,3,000m〜5,000m上昇の噴煙も時々出ますので,地鳴りがするときもあります.2011より撮影を続けてきました.活動期は年間900回以上の噴火がありましたが,最近は急に減少しました.今後も噴火の変化を記録するために,撮影を続けたいと思っています.
【審査委員長講評】
この作品も,ジオパーク賞の山田さんの作品とほぼ同じ場所から撮影したものです.この作品は,より広角のレンズで撮影しているので周囲の状況が分かり,上昇する噴煙やそこからの力強い火山雷が魅力的です.山田さんの作品と甲乙つけがたい秀作です.
【地質的背景】
「ジオパーク賞:活火山桜島」参照
←戻る 目次
geo-flash No.256 5月10日は「地質の日」!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.256 2014/5/2 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
※通常配信日の5月6日は振替休日のため、本日配信いたします。
★★目次 ★★
【1】電子書籍「地学を楽しく!」PDF版発売開始
【2】5月10日は地質の日!
【3】日本地質学第6回総会開催について
【4】ジオルジュ 最新号まもなく刊行
【5】The 2nd IGCP608 Waseda 2014のSecond Circular 配布開始
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・教員採用試験情報・各賞情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】電子書籍「地学を楽しく!」PDF版発売開始
──────────────────────────────────
地学を楽しく!:ジオパーク・ジオツアー・地学オリンピック [Kindle版/PDF版]
吉田 勝,天野一男,中井 均 編集 一般社団法人日本地質学会 発行
価格:¥1,380 ISBN 978-4-907604-00-4
広くたくさんの方々にお読みいただくために,電子書籍のPDF版も発売を開始いたしました。PDF版なら専用端末が無くても,パソコンさえあればOK!
*PDF版は各章ごとの分割販売も行っています。
◆PDF版のご購入は,学会オンラインストア『ジオストア』から
>> http://geosociety2.sakura.ne.jp/store3/ec/
◆Kindle版のご購入は,Amazon Kindleストアから
>> http://www.amazon.co.jp/dp/B00HFIK1WW
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】5月10日は地質の日!
─────────────────────────────────
各地で地質に関するイベントが開催されます!
是非足をお運びください。
[日本地質学会主催等のイベント]
<明日夕方より!>
■第5回惑星地球フォトコンテストほか入選作品展示会
5月3日(土)17:00〜17日(土)13:00
場所:銀座プロムナードギャラリー(中央区銀座4丁目地内 東銀座地下歩道壁面)
■地質の日記念 街中ジオ散歩 in Tokyo「下町低地の地盤沈下と水とくらし」
5月10日(土)9:50〜17:00 少雨決行(予定)
場所:東京都江東区清澄白河ほか
■公開講演会「日本の地質学:最近の発見と応用」
5月24日(土)13:00〜15:00[申込不要]
会場:北とぴあ第2研修室(東京都北区王子)
・「犯罪捜査と地質学」杉田律子(科学警察研究所)
・「巨大地震の巣を掘る そこから見えてきたもの」坂口有人(山口大学)
・「宇宙からの贈りもの:日本の地層から隕石衝突の証拠を発見」佐藤峰南(九州大学)
・「日本全国の地質情報をあなたへ〜進化する日本シームレス地質図〜」
西岡芳晴(産業技術総合研究所)
>>講演要旨のダウンロードはこちら
http://www.geosociety.jp/name/content0107.html
○学会関連各イベントの詳細はこちら
http://www.geosociety.jp/name/content0014.html
○地質の日事業推進委員会のページ
https://www.gsj.jp/geologyday/
○その他、各地で行われる2014年地質の日関連のイベント
https://www.gsj.jp/geologyday/2014/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本地質学第6回総会開催について
─────────────────────────────────
5月24日(土)15:30〜17:00
会場 北とぴあ 第2研修室(東京都北区王子1-11-1)
総会議案はこちらから
http://www.geosociety.jp/outline/content0138.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】ジオルジュ 最新号まもなく刊行
─────────────────────────────────
まもなく,学会の広報誌「ジオルジュ」最新号が刊行されます(会員の皆様へは5月号の雑誌とともに送付予定です)。
【ジオルジュ前期号(Early 2014)】
特集1 芸術は鉱物から 色をうみだす鉱物たち
特集2 ミュージアムをつくろう! 「箱根ジオミュージアム」オープン
特集3 火山島を観測する 西ノ島誕生の現場から など
ジオルジュ(年2回発行、定価250円)を博物館・学校・研究機関などで、イベントでの配布物、友の会へのプレミアグッズ、ストアなどでの販売物として、利用してみませんか。部数に応じて割引価格を設定しております。是非ご検討下さい。
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/science/content0062.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】The 2nd IGCP608 Waseda 2014のSecond Circular 配布開始
─────────────────────────────────
IGCP608 Asia-Pacific Cretaceous Ecosystems (白亜紀アジア−西太平洋生態系)
第2回 国際シンポジウム(The 2nd IGCP608 Waseda 2014)
「白亜紀の陸−海リンケージと生物相進化:アジア−西太平洋地域からの貢献」
9月4日(木)〜6日(土)
場所:早稲田大学大隈講堂
巡検:9月7日(日)〜10日(水)
「本州中部太平洋岸の白亜紀前弧堆積盆の珪質砕屑物サクセッションの堆積相と動植物化石相」(銚子層群,那珂湊層群,双葉層群)
Second Circularダウンロードサイト: http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/
連絡先: igcp608.waseda@gmail.com 太田 亨(実行委員会事務局長)
(IGCP608 プロジェクトリーダー 安藤寿男)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
─────────────────────────────────
[北海道支部]
■日本地質学会北海道支部平成26年度例会(個人講演会)
5月31日(土)10:00〜18:00(予定)
場所:北海道大学理学部5号館大講堂(5-203)
発表申込締切:5月2日(金)
要旨提出締切:5月15日(木)
■野外巡検「裏山の地質災害―豊平川の洪水」
6月1日(日)8:00〜15:30
定員20名、参加費2500円(予定)[学生・院生割引有(検討中)]
それぞれ詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[関東支部]
■緊急学習会:『福島第一原子力発電所汚染水処理問題収束のために地質学は何をなさねばならないか』
5月17日(土)13:00〜17:00
会場:日本大学文理学部3号館3505教室
(京王線桜上水駅または下高井戸駅から徒歩8分)
申込締切:5月9日(金) 【最終締切:5月14日(水)】
参加費:資料代として1,500円(学生・大学院生は500円) CPD単位:4.0
■清澄フィールドキャンプ 参加者募集
8月25日(月)〜8月31日(日)
場所:東京大学千葉演習林(〒299-5505 千葉県鴨川市清澄)
費用:宿泊・食事・保険(約15000円/6泊)+レンタカー代(約12000円)
応募締切:7月4日(金)(*応募書類は所定のフォーマットを使用のこと)
それぞれ詳しくは,支部HPへ http://kanto.geosociety.jp/
[中部支部]
■2014年支部年会
6月14日(土)〜15日(日)
14日:支部総会、シンポジウム、研究発表会、懇親会
15日:地質巡検
場所:信州大学理学部大会議室
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地震本部ニュース春号(今年度より季刊発行)
http://www.jishin.go.jp/main/p_koho04.htm
■Marjorie Chan教授講演会
日本地質学会ほか 共催
1.東京講演会 5月9日(金)15:00〜17:00
場所:東京工業大学地球生命研究所セミナー室(4階)
2.京都講演会 5月11日(日)15:00〜16:00
場所:京都大学百周年時計台記念館国際交流ホールI
問い合わせ先:日本堆積学会国際交流委員会
池原 研(産業技術総合研究所地質情報研究部門)
mail: k-ikehara@aist.go.jp
■IGCP608 Asia-Pacific Cretaceous Ecosystems(白亜紀アジア−西太平洋生態系)
第2回国際シンポジウム
日本地質学会ほか 共催
9月4日(木)〜6日(土)(シンポジウム)
9月7日(日)〜10日(水)(巡検:銚子・那珂湊・双葉層群)
会場:早稲田大学 大隈講堂 小講堂
http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/
■第58回粘土科学討論会
日本地質学会ほか 共催
9月24日(水)〜27日(土)
会場:福島市A・O・Z(アオウゼ)
参加・講演申込期間:6月16日(月)〜7月11日(金)
講演要旨送付締切:7月25日(金)
http://www.cssj2.org/
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
2015年7月27日(月)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1-1)
http://inqua2015.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0133.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・教員採用試験情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■千葉大学大学院:理学研究科地球生命圏科学専攻地球科学コース 助教募集(6/30)
■早稲田大学 教育・総合科学学術院:常勤嘱託職員公募(5/23)
■平成27年度高等学校理科(地学)
群馬県(5/20) 岩手県(5/21) 宮城県(5/21) 静岡県(5/8)
京都府(6/6) 広島県(5/30) 沖縄県(5/16:Webは5/14)
■糸魚川ジオパーク学術研究奨励事業(2014年度)(5/30)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.257 公開講演会「日本の地質学:最近の発見と応用」(5/24)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.257 2014/5/20 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[鹿児島大会]演題登録は間もなく受付開始です
【2】日本地球惑星科学連合のフェローが発表:地質学会からは8名が選出される!
【3】公開講演会「日本の地質学:最近の発見と応用」
【4】日本地質学第6回総会開催について
【5】平成26年度日本カナダ女性研究者交流 【派遣者募集】
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・教員採用試験情報・各賞情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[鹿児島大会]演題登録は間もなく受付開始です
──────────────────────────────────
日本地質学会第121年学術大会(鹿児島大会)の演題登録の受付を間もなく開始いたします。今年もたくさんの発表申込をお待ちしています。
9月13日(土)〜15日(月)
会場:鹿児島大学 ほか
演題登録:7/1(火)締切
事前参加登録:8/19(火)締切[巡検のみ 8/8(金)締切]
※詳細が決まり次第お知らせいたします。
鹿児島大会HPはこちら。
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】日本地球惑星科学連合のフェローが発表:地質学会からは8名が選出される!
─────────────────────────────────
学術研究部会長 井龍康文
日本地球惑星科学連合では,フェロー制度が設けられました.この制度は,地球惑星科学において顕著な功績を挙げ,あるいは連合の活動に卓越した貢献をした正会員を顕彰するために設置され,その要件として,
・地球惑星科学研究領域におけるパラダイムシフトやブレークスルーもしくは大きな発見などを通じて,地球惑星科学の発展に著しい貢献をした会員
・JpGUの活動に顕著な貢献をなし,日本の地球惑星科学の発展,あるいは地球惑星科学の知識普及に貢献した会員
が掲げられています.
この度,フェローに選ばれた43名の方々の中に,8名の地質学会員が含まれていました.ここに,連合のHP(http://www.jpgu.org/news/fellowlist.html)の記事を引用して紹介いたします.
フェローの約20%が地質学会から輩出されていることに,地質学会の伝統と実績が象徴されていると思います.われわれ後進も日本の地球惑星科学の発展に尽力して行きたいものです.
荒牧重雄○:
火山学,特に火山地質学,火山岩岩石学分野における顕著な功績,および火山学の普及や火山防災意識向上への顕著な貢献により
岡田尚武 :
古生物学,古海洋学分野における顕著な功績,および国際深海掘削計画における顕著な貢献をした功績により
久城育夫○:
岩石学,特に実験岩石学,マグマ成因論分野における顕著な功績により
杉村 新○:
地質学,特に日本列島のネオテクトニクス,島弧論などの分野における顕著な功績により
鎮西清高○:
地質学,特に古生物学および古生態学分野における永年にわたる顕著な功績により
藤井敏嗣 :
地質学,特に火山学・マグマ学分野における顕著な功績,および火山防災学の発展に多大な貢献をした功績により
松田時彦○:
地質学,特に構造地質学,地震地質学,活断層研究分野における顕著な功績により
丸山茂徳 :
地質学,特に全地球史解読,生命・地球の共進化分野における顕著な功績により
(○が付された方は,地質学会の名誉会員)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】公開講演会「日本の地質学:最近の発見と応用」
─────────────────────────────────
5月24日(土)13:00〜15:00
会場:北とぴあ第2研修室(東京都北区王子)
事前申込不要[会員の方は参加無料]
・「犯罪捜査と地質学」杉田律子(科学警察研究所)
・「巨大地震の巣を掘る そこから見えてきたもの」坂口有人(山口大学)
・「宇宙からの贈りもの:日本の地層から隕石衝突の証拠を発見」佐藤峰南(九州大学)
・「日本全国の地質情報をあなたへ〜進化する日本シームレス地質図〜」
西岡芳晴(産業技術総合研究所)
>>講演要旨のダウンロードはこちら
http://www.geosociety.jp/name/content0107.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】日本地質学第6回総会開催について
─────────────────────────────────
5月24日(土)15:30〜17:00
会場 北とぴあ 第2研修室(東京都北区王子1-11-1)
総会議案はこちらから
http://www.geosociety.jp/outline/content0138.html
※総会前に同会場にて【3】の公開講演会やフォトコンテストの表彰式(11:00〜)も行われます。是非あわせてご参加ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】平成26年度日本カナダ女性研究者交流 【派遣者募集】
─────────────────────────────────
<日本学術会議より>
日本カナダ女性研究者交流とは
両国の優れた若手女性研究者が相手国の大学や研究機関に滞在(1週間から10日間程度)し、専門分野における最近の研究動向等について情報交換するとともに、初等・中等教育段階の学校(小学校、中学校、高校)を訪問します。そこで、両国の研究環境や教育環境の違いや、双方の優れた点、検討すべき点等を直に体験することにより、そこで得た経験や知見を両国の女性研究者の育成や活躍のために活かしてもらうことを目的とするものです。
詳しくは
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//geoFlash_img/no257/20140509.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
─────────────────────────────────
[北海道支部]
■日本地質学会北海道支部平成26年度例会(個人講演会)
5月31日(土)10:30〜17:40
場所:北海道大学理学部大講堂
(下記支部Webサイトにて要旨公開中)
■野外巡検「裏山の地質災害—豊平川の洪水」
6月1日(日)8:30〜16:30
定員35名、参加費2000円(予定)
それぞれ詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[関東支部]
■夏休み教師巡検:5億年前と10万年前の茨城を見る(第1報)
昨年に続き支部主催第2回です。今年は茨城方面で企画しました.
ぜひご予定ください.教師以外の方の参加もお待ちしています.
8月20日(水)〜21日(木)
場所:
20日:県南部(第四紀層の堆積構造と化石)
21日:県北部日立周辺(5億年前の岩石等)
費用・講師等詳細は後日
連絡先:米澤正弘 my-yonezawa@y6.dion.ne.jp
■清澄フィールドキャンプ 参加者募集
8月25日(月)〜31日(日)
場所:東京大学千葉演習林(〒299-5505 千葉県鴨川市清澄)
費用:宿泊・食事・保険(約15000円/6泊)+レンタカー代(約12000円)
応募締切:7月4日(金)(*応募書類は所定のフォーマットを使用のこと)
詳しくは,支部HPへ http://kanto.geosociety.jp/
[中部支部]
■2014年支部年会
6月14日(土)〜15日(日)
14日:支部総会、シンポジウム、研究発表会、懇親会
15日:地質巡検
場所:信州大学理学部大会議室
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地質研究所ニュース 第35号
http://www.gsh.hro.or.jp/publication/gshnews/news_pdf/vol30_no1.pdf
■電中研ニュース No.477
http://criepi.denken.or.jp/research/news/index.html?m=140520
■水月湖はこうして世界の標準時計になった
6月1日(日)13:30〜15:00
会場:立命館大学びわこ・くさつキャンパスエポックホール
事前申込制・参加費無料
申込締切:5月22日(木)
http://www.ritsumei.ac.jp/rs/category/tokushu/140502/file/140502-nenko.pdf
※パネル展示同時開催
奇跡の湖!ー水月湖年縞堆積物の秘密に迫るー
■高校地理歴史教育に関するシンポジュウム
6月14日(土)13:00〜17:00
場所:東京大学駒場キャンパス21KOMCEEレクチャーホール
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//geoFlash_img/no257/chiri_sympo140614.pdf
■第14回ルミネッセンス・ESR年代測定国際会議
14th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating
7月7日(月)〜11日(金)(巡検12日〜13日)
場所:カナダ・モントリオール
http://www.led2014.uqam.ca
■「青少年のための科学の祭典」2014全国大会
7月26日(土)〜27日(日)
日本地質学会 後援
場所:科学技術館(千代田区北の丸公園)
http://www.kagakunosaiten.jp/
■第23回市民セミナー「黄砂と共に飛来する越境化学物質−水環境と健康に対する影響を考える−」
8月8日(金)9:45〜16:35
場所:
東京会場:地球環境カレッジ(いであ(株)内)(東京都世田谷区駒沢)
大阪会場:いであ(株)大阪支社ホール(大阪市住之江区南港北)
申し込み・問合せ先:(公社)日本水環境学会セミナー係 戸川
TEL:03-3632-5351 FAX:03-3632-5352
e-mail:togawa@jswe.or.jp
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//others-pdf/jswe20140513.pdf
■IGCP608 Asia-Pacific Cretaceous Ecosystems(白亜紀アジア−西太平洋生態系)
第2回国際シンポジウム
日本地質学会ほか 共催
9月4日(木)〜6日(土)(シンポジウム)
9月7日(日)〜10日(水)(巡検:銚子・那珂湊・双葉層群)
会場:早稲田大学 大隈講堂 小講堂
http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/
■Thermo2014:第14回国際熱年代学会議
14th International Conference on Thermochronology
9月8日(月)〜12日(金)(巡検5日〜7日)
場所:フランス・シャモニー
http://www.thermo2014.fr
■第58回粘土科学討論会
日本地質学会ほか 共催
9月24日(水)〜27日(土)
会場:福島市A・O・Z(アオウゼ)
参加・講演申込期間:6月16日(月)〜7月11日(金)
講演要旨送付締切:7月25日(金)
http://www.cssj2.org/
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
2015年7月27日(月)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1-1)
http://inqua2015.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0133.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・教員採用試験情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■■電力中央研究所:研究員公募(8/31)
■島根県立三瓶自然館:学芸員募集(7/1〜8/31)
■福井県:職員(古生物学)募集(6/18)
■第9回「科学の芽」賞募集(8/20〜9/30)
■平成27年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞および若手科学者賞 受賞候補者募集(7/17 学会締切:6/30)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.258 (臨時)[鹿児島大会]演題登録受付開始!!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.258 2014/5/27 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
[鹿児島大会関連情報]
【1】演題登録受付開始しました!!
【2】講演申込を予定しているが、まだ入会手続きをしていない方へ
------------------------------------------------------------
【3】[訃報]亀井節夫 名誉会員 ご逝去
【4】公募情報・教員採用試験情報・各賞情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[鹿児島大会] 演題登録受付開始しました!!
──────────────────────────────────
日本地質学会第121年学術大会(鹿児島大会;9/13(土)〜9/15(月)の演題登録の受付を開始いたしました。今年もたくさんのお申込をお待ちしています。
事前参加登録(8/19締切)も間もなく受付開始予定です。
***演題登録(講演要旨提出):7/1(火)18時締切***
(郵送の場合は,6/25(水)必着)
鹿児島大会HPはコチラ↓↓
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[鹿児島大会]講演申込を予定しているが、まだ入会手続きをしていない方へ
─────────────────────────────────
講演申込を予定しているが、まだ入会手続きをされていない方は,至急、入会申込書を学会事務局宛に郵送して下さい(7/1必着です)。
WEB画面から講演申込操作は現時点でも可能です。入力の際、会員番号欄は空欄のまま操作を進めて下さい。また会員種別欄では『入会申込中』を選択して下さい。
申込締切時点(7/1)で入会申込書が到着していないと、申込が受理されませんので、必ず入会申込書を郵送して下さい。
入会申込書は以下よりダウンロードできます。
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//outline/nyukai.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[訃報]亀井節夫 名誉会員 ご逝去
─────────────────────────────────
亀井節夫 名誉会員(京都大学名誉教授)が,平成26年5月23日(金)にご逝去されました(享年88歳)。
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
ご葬儀は,5月25日にすでに近親者によりしめやかに執り行なわれ,ご遺族のご意向により弔問等はご遠慮願いたいとのことです。
会長 井龍康文
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】公募情報・教員採用試験情報・各賞情報等
─────────────────────────────────
教員採用試験情報:
富山県:平成27年度中学校高等学校理科(地学)(5/30)
香川県:平成27年度高等学校理科(地学)(6/4、WEBは6/2)
徳島県:平成27年度高等学校理科(地学)(6/2、WEBは5/30)
愛媛県:平成27年度高等学校理科(地学)(6/11)
熊本県:平成27年度高等学校理科(地学)(6/6)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.259 [鹿児島大会]演題登録受付中!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.259 2014/6/3 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[鹿児島大会]演題登録受付中!
【2】[鹿児島大会]宿泊予約に関するご注意
【3】JST からのお知らせ『サイエンスアゴラ 2014』出展者募集
【4】Island Arcからのお知らせ
【5】[事務局より]会員名簿取り扱いに関する注意喚起
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・教員採用試験情報・各賞情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[鹿児島大会]演題登録受付中!
──────────────────────────────────
日本地質学会第121年学術大会(鹿児島大会)の演題登録受付中です!
今年もたくさんの発表申込をお待ちしています。
9月13日(土)〜15日(月)
会場:鹿児島大学 ほか
演題登録:7/1(火)締切
事前参加登録>>間もなく受付開始
8/19(火)締切[巡検のみ 8/8(金)締切]
※詳細が決まり次第お知らせいたします。
鹿児島大会HPはコチラ↓
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[鹿児島大会]宿泊予約に関するご注意
─────────────────────────────────
鹿児島大会期間中,鹿児島市内では他学協会のイベント等も予定されています。
宿泊予約が混み合う可能性がありますので,お早めの手配をお勧め致します。
地質学会では,近年学会を通じての宿泊・交通手配の斡旋を行っていません。
宿泊や交通については,各自で手配をお願い致します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】JST からのお知らせ『サイエンスアゴラ 2014』出展者募集
─────────────────────────────────
独立行政法人科学技術振興機構では、11月7日(金)から9日(日)に、広く社会と科学技術の関係深化を図るイベント、「サイエンスアゴラ」を開催いたします。
本イベントでは、多様な立場の方の出展・参加により、科学技術の現在の進展から、さまざまな課題、科学技術とともにある社会の将来像などについて、情報共有、対話を行います。
今年度は「サイエンスアゴラ2014〜あなたと創るこれからの科学と社会〜」と題し、以下の概要で開催する予定です。
現在、本イベントの出展者を募集しております。科学技術に関する多様な視点からのコミュニケーションを促進するため、広くみなさまのご出展および当日のご参加をお待ちしております。
詳細と出展応募
http://www.jst.go.jp/csc/scienceagora/
<サイエンスアゴラ2014概要(予定)>
11月7日(金)〜11月9日(日)
場所:東京・お台場地域
主催:独立行政法人科学技術振興機構
<出展者募集について>
募集締切:6月18日(水)12:00
出展料:無料
採択予定件数:120企画程度(終日出展、時間枠出展など)
<お問い合わせ先>
科学技術振興機構 サイエンスアゴラ事務局
MAIL:agora@jst.go.jp TEL:03-5214-7493
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】Island Arcからのお知らせ
─────────────────────────────────
【最新号23-2号がオンライン出版されました】
詳しくはこちらを御覧下さい.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iar.2014.23.issue-2/issuetoc
<日本語要旨掲載ページ>
http://www.geosociety.jp/publication/content0079.html
IAR最新号は,学会webサイトから無料で閲覧出来ます。
ログイン方法はこちらから,
https://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
【2014 Island Arc賞】
今年のIsland Arc賞は,
Zhao et al. (2010) "Dissecting large earthquakes in Japan: Role of arc magma and fluids" (Island Arc, 19, 4–16)
に贈られます.日本地質学会第121年学術大会(鹿児島大会)において授賞式が行われる予定です.
受賞理由はこちらから.
http://www.geosociety.jp/outline/content0141.html#islandarc
受賞論文はこちらから.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iar.2010.19.issue-1/issuetoc
【2014 最多ダウンロード賞】
2014年最多ダウンロード賞は,
Hickman, A. H.(2012) "Review of the Pilbara Craton and Fortescue Basin, Western Australia: Crustal evolution providing environments for early life" (Island Arc, 21, 1-31.)
に贈られます.本賞は,2008年〜2012年に出版された論文のうち,2013年に最もダウンロードされた論文に対しWiley社より与えられます.
受賞論文はこちらから.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iar.2012.21.issue-1/issuetoc
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[事務局より]会員名簿取り扱いに関する注意喚起
─────────────────────────────────
ある会員のかたから,『不動産会社から地質学会の会員を対象とした不動産(マンションやアパート)管理の営業電話がありました』との報告を受けました.
地質学会の会員名簿が,本会,あるいは会員の承諾を得ないまま地質学とは無縁の商業活動に利用されることが多くなっております.会員のみなさまにおかれましては,名簿(旧名簿も含め)の扱いには十分ご配慮くださるようお願いいたします.
もし,今回のような営業電話があった場合には,相手方にたいして,どういった経緯・経路等で個人情報を入手したのかをお尋ねいただき,分かりましたら地質学会までご一報ください.
学会事務局
TEL: 03-5823-1150
E-mail: main@geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
─────────────────────────────────
[関東支部]
■夏休み教師巡検:5億年前と10万年前の茨城を見る(第1報)
昨年に続き支部主催第2回です。今年は茨城方面で企画しました.
ぜひご予定ください.教師以外の方の参加もお待ちしています.
8月20日(水)〜21日(木)
場所:20日:県南部(第四紀層の堆積構造と化石)
21日:県北部日立周辺(5億年前の岩石等)
費用・講師等詳細は後日
連絡先:米澤正弘 my-yonezawa@y6.dion.ne.jp
■清澄フィールドキャンプ 参加者募集
8月25日(月)〜31日(日)
場所:東京大学千葉演習林(〒299-5505 千葉県鴨川市清澄)
費用:宿泊・食事・保険(約15000円/6泊)+レンタカー代(約12000円)
応募締切:7月4日(金)(*応募書類は所定のフォーマットを使用のこと)
詳しくは,支部HPへ http://kanto.geosociety.jp/
[中部支部]
■2014年支部年会
6月14日(土)〜15日(日)
14日:支部総会、シンポジウム、研究発表会、懇親会
15日:地質巡検
場所:信州大学理学部大会議室
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■学術フォーラム「国際リニアコライダー(ILC)計画」
6月23日(月)13:00〜18:00
場所:日本学術会議講堂
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/192-s-0623.pdf
■資源地質学会第64回年会学術講演会
6月25日(水)〜27日(金)
会場:東京大学小柴ホール
http://www.resource-geology.jp/
■深田研ジオフォーラム2014
6月28日(土)10:00〜16:00(受付開始9:30)
場所:深田地質研究所研修ホール(文京区本駒込2-13-12)
藤井敏嗣『日本の火山活動と火山防災』
申込締切:6月20日(金)[定員50名:定員に達し次第締切]
http://www.fgi.or.jp
■国際シンポジウム「西アジア文明学の創出1:今なせ古代西アジア文明なのか?」
6月28日(土)〜29日(日)
場所:池袋サンシャインシティ文化会館7階会議室704-705
申込不要・入場無料 先着130名
http://rcwasia.hass.tsukuba.ac.jp/kaken/
■「青少年のための科学の祭典」2014全国大会
7月26日(土)〜27日(日)
日本地質学会 後援
場所:科学技術館(千代田区北の丸公園)
http://www.kagakunosaiten.jp/
■IGCP608 Asia-Pacific Cretaceous Ecosystems(白亜紀アジア−西太平洋生態系)
第2回国際シンポジウム
日本地質学会ほか 共催
9月4日(木)〜6日(土)(シンポジウム)
9月7日(日)〜10日(水)(巡検:銚子・那珂湊・双葉層群)
会場:早稲田大学 大隈講堂 小講堂
http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/
■第58回粘土科学討論会
日本地質学会ほか 共催
9月24日(水)〜27日(土)
会場:福島市A・O・Z(アオウゼ)
参加・講演申込期間:6月16日(月)〜7月11日(金)
講演要旨送付締切:7月25日(金)
http://www.cssj2.org/
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
2015年7月27日(月)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1-1)
http://inqua2015.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0133.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・教員採用試験情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■山口大学大学院:理工学研究科 教員公募(准教授または講師)(7/31)
■法政大学社会学部:教員公募(地球と自然)(7/25)
■第18回尾瀬賞募集(8/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.266 (臨時)[鹿児島大会]全体日程が決まりました.
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.266 2014/7/16 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[鹿児島大会]全体日程が決まりました
【2】[鹿児島大会]事前参加登録受付中!
【3】[鹿児島大会]各種申込み締切のお知らせ
【4】「地震に関する総合的な調査観測計画について〜東日本大震災を踏まえて〜 案」に対する日本地質学会の意見提出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[鹿児島大会]全体日程が決まりました
─────────────────────────────────
日本地質学会第121年学術大会(鹿児島大会:9/13-15)の全体日程が確定しました.各シンポ,セッションの予定をはじめ,普及行事や関連行事の日程も決まりました.各講演(口頭・ポスター)の詳細プログラムは,後日講演者にご連絡するとともに,大会HPに掲載予定です.大会プログラムは,例年同様ニュース誌8月号掲載予定です.
全体日程表(PDF)は,大会HPよりご覧いただけます.
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0007.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[鹿児島大会]事前参加登録受付中!
──────────────────────────────────
事前参加登録のお申込を受付中です.今年もたくさんの参加をお待ちしています.
◆事前参加登録:8/19(火)締切[*巡検のみ:8/8(金)締切]
〔注〕演題登録と事前参加登録は,それぞれ別のお申し込みです.演題登録済でも,締切までに【事前参加登録】を別途行わない場合は,当日参加の扱いとなります.事前と当日とでは,参加登録費が異なりますので,ご注意ください.
◆講演要旨集について
参加登録費が発生するかた(正会員や院生割引会費適用正会員等)には,必ず講演要旨集が付きますが,参加登録費が0円のかた(名誉会員や50年会員, 学部学生割引会費適用正会員等)には要旨集は付きません.
要旨集の当日販売もありますが,ここ数年,当日販売分が売り切れてしまうことが多く,購入いただけないケースもあります.
参加を予定されているかたや要旨集を購入希望のかたは,事前参加登録または要旨集の予約購入申込をお願いいたします.
鹿児島大会HPはコチラ↓
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0001.html
参加登録費について
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0020.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[鹿児島大会]各種申込み締切のお知らせ
──────────────────────────────────
■ 企業・研究機関等関係団体による展示会の出展募集
申込締切:8月8日(金)
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0041.html
■ 書籍・販売ブースご利用の募集
申込締切:8月8日(金)
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0041.html#book
■ 講演要旨集,広告協賛の募集
申込締切:8月8日(金)
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0041.html#kokoku
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】「地震に関する総合的な調査観測計画について〜東日本大震災を踏まえて〜 案」に対する日本地質学会の意見提出
─────────────────────────────────
政府地震調査研究推進本部(地震本部)では、東日本大震災を踏まえ、今後の地震の調査観測の在り方を示す計画を策定しており,地震本部の調査観測計画部会においてその計画案が取りまとめられました。
この計画案について,7/3〜7/17に意見募集が行われ,日本地質学会から以下のとおり意見を提出しました。
詳しくはコチラ,,,
http://www.geosociety.jp/engineer/content0036.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.267 鹿児島大会:間もなく巡検申込締切!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.267 2014/8/5 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[鹿児島大会]事前参加登録:間もなく巡検申込締切!
【2】[鹿児島大会]緊急展示の申込について
【3】地質学会会員、GSA Fellow に選出
【4】研究不正ガイドライン案への意見
【5】原子力規制委員会:川内原子力発電所に関する意見募集
【6】The 2nd IGCP608 Waseda 2014のThird Circular(Program) 配布開始
【7】2014年度会費およびそれ以前の未納会費がある方へ
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[鹿児島大会]事前参加登録:間もなく巡検申込締切!
─────────────────────────────────
日本地質学会第121年学術大会(鹿児島大会)の事前参加登録のお申込を受付中です.
9月13日(土)〜15日(月)
会場:鹿児島大学 ほか
◆事前参加登録:8/19(火)18:00締切[※巡検のみ:8/8(金)18:00締切]
〔注〕演題登録と事前参加登録は,それぞれ別のお申し込みです.演題登録済でも,締切までに【事前参加登録】を別途行わない場合は,当日参加の扱いとなります.
事前と当日とでは,参加登録費が異なりますので,ご注意ください.
◆巡検について
締切前でも、コースが定員に達した場合は受付は終了しますので、お申込はお早めに!
受付終了:コース1・2・3・4・5・7
申込状況はこちら
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0011.html
◆講演要旨集について
参加登録費が発生するかた(正会員や院生割引会費適用正会員等)には,必ず講演要旨集が付きますが,参加登録費が0円のかた(名誉会員や50年会員,学部学生割引会費適用正会員等)には要旨集は付きません.
要旨集の当日販売もありますが,ここ数年,当日販売分が売り切れてしまうことが多く,購入いただけないケースもあります.
参加を予定されているかたや要旨集を購入希望のかたは,事前参加登録または要旨集の予約購入申込をお願いいたします.
鹿児島大会HPはこちら
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0001.html
参加登録費について
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0020.html
◆その他 各種申込み
○企業・研究機関等関係団体による展示会の出展募集
○書籍・販売ブースご利用の募集
○講演要旨集,広告協賛の募集
申込締切:8月8日(金)
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0041.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[鹿児島大会]緊急展示の申込について
─────────────────────────────────
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害調査報告や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コーナー」を設けます.ポスター展示を希望する方は,8月29日(金)までに次の内容を下記申込先にご連絡ください.
1)発表要旨PDF(ニュース誌5月号参照)
2)緊急展示の必要性
3)発表代表者と連絡先
4)希望枚数(1枚:幅120×210cm)
5)展示に関わる要望(2〜5の様式は自由)
実行委員会は行事委員会と協議し,可否の判断を致します.希望にはできるだけ応えるようにしますが,展示方法等については実行委員会の指示に従ってください.
申込先:main@geosociety.jp
担当:山本啓司(鹿児島大会実行委員会)・須藤 宏(行事委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】地質学会会員、GSA Fellow に選出
─────────────────────────────────
今年、GSA(The Geological Society of America、米国地質学会)のフェローには全部で59人が選出され、日本からは2名(石渡 明前会長、辻森 樹会員)が選出されました。
米国地質学会は会員数26,000人以上、フェローの数は2,000人以上いますが、大部分は米国人で、外国人は少数です。
なお、10月に開催される米国地質学会のバンクーバー大会で、石渡会員は日本列島の地質発達史とオフィオライトについての講演を行うことになっています。
推薦理由はこちらから.
http://www.geosociety.org/members/newFellows.htm
全フェローのリストはこちら.
http://rock.geosociety.org/membership/fellows.asp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】研究不正ガイドライン案への意見
─────────────────────────────────
文部科学省では「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」案を新たに定めることとなり、そのガイドライン(案)へのパブリックコメント(意見公募手続)が実施されました(7月3日〜8月1日募集)。
日本地質学会からは7月30日に下記の意見を送りましたので、会員の皆様にお知らせ致します。
意見募集案件の詳細や「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(案)は以下
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000698&Mode=0
日本地質学会より提出した意見
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//pubcome/2014/p-20140730.pdf
(2014年7月30日提出)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】原子力規制委員会:川内原子力発電所に関する意見募集
─────────────────────────────────
九州電力株式会社川内原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書(1号及び2号発電用原子炉施設の変更)に関する審査書(原子炉等規制法第43条の3の6第1項第2号(技術的能力に係るもの)、第3号及び第4号関連)
に対するパブリックコメントが実施されています.
詳細はこちら.http://www.nsr.go.jp/public_comment/bosyu140716.html
意見提出締切:8月15日(金)
※意見は個人として表明されても構いません.
また,地質学会では,部会を通じて意見を募集しておりますので,所属される部会の部会長に送っていただけましたら,学会としての取りまとめの際に参考とさせていただきます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】 The 2nd IGCP608 Waseda 2014のThird Circular(Program) 配布開始
──────────────────────────────────
IGCP608 Asia-Pacific Cretaceous Ecosystems (白亜紀アジア−西太平洋生態系)第2回 国際シンポジウム(The 2nd IGCP608 Waseda 2014)
「白亜紀の陸−海リンケージと生物相進化:アジア−西太平洋地域からの貢献」
口頭発表 44件,ポスター 37件を予定
期日:2014年9月4 日 (木) 〜9月6日 (土)
場所:早稲田大学大隈講堂
巡検:9月7日(日) 〜9月10日(水)
「本州中部太平洋岸の白亜紀前弧堆積盆の珪質砕屑物サクセッションの堆積相と動植物化石相:銚子・那珂湊・双葉層群」
Third (Last) Circular with Program ダウンロード: http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/
連絡先: igcp608.waseda@gmail.com 太田 亨(実行委員会事務局長)
(IGCP608 プロジェクトリーダー 安藤寿男)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】2014年度会費およびそれ以前の未納会費がある方へ
─────────────────────────────────
6月中旬に2014年度会費の督促請求書(郵便振替用紙)を郵送しました.
会費未納のかたは,早急にご送金くださいますようお願いいたします.
なお,7月中旬頃までに入金確認が取れていないかたにたいしては,7月号の雑誌から送本を停止しています.定期的に雑誌をお受け取りになりたいかたは,お早めにご送金ください.
また,9月鹿児島大会での講演を申し込まれた方は,忘れずにご送金をお願いいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
─────────────────────────────────
[北海道支部]
■2014年日高巡検開催
テーマ 『日高変成帯北部〜神居古潭帯の横断』
討論会 『古第三紀以降のテクトニクスの未解決問題』<<話題提供者募集中>>
10月4日(土)〜5日(日)雨天決行(雨具を用意)
19:00〜21:00 討論会『古第三紀以降のテクトニクスの未解決問題』
宿舎: 日高高原荘:宿泊は2名/1室
催行人数: 18名
参加費: 一般18,000円・学生13,000円(バス代+宿泊代+保険料+資料代・懇親会費など)
参加申込締切: 8月31日(日)
詳しくは http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[関東支部]
■「富士山巡検」のお知らせ
富士山の宝永火口や過去の噴火に伴う溶岩流、岩屑なだれ堆積物、火口列、火山灰などを観察していただき、宿泊先では案内者から富士山の地形地質に関する勉強会も予定しています.
会員の方はもとより,広く参加者を募集致します.
10月4日(土)〜5日(日),1泊2日、雨天決行
CPD単位:16単位
募集人数:会員および一般・25名程度
参加費用:一般19,000円、学生・院生12,000円
問合せ先:細根 清治[(株)東建ジオテック]
メールアドレス:s.hosone@tokengeotec.co.jp
FAX:048-826-0151 携帯:080-1201-7453
申し込み期間:8月18日(月)〜9月19日(金)
(定員に達した時点で締め切り)
詳しくは http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地震本部ニュース平成26年夏号発行
http://www.jishin.go.jp/main/p_koho04.htm
■地質研究所ニュース
http://www.gsh.hro.or.jp/publication/gshnews/news_pdf/vol30_no2.pdf
■地学オリンピックキャラクターデザインコンテスト
日本地質学会共催
募集締切:10月31日(金)
応募資格:中学生・高校生
http://jeso.jp/wp-content/uploads/2014/06/ieso_character_design_contest.pdf
■新潟のジオパーク展 −糸魚川と佐渡の魅力−
日本地質学会ほか後援
7月12日(土)〜8月29日(金)
会場:新潟大学駅南キャンパス ときめいと
http://www1.niigata-u.ac.jp/tokimate/
■日本学術会議公開シンポジウム:学校教育にもとめられるオープンデータを活用できる人材育成
8月20日(水)
場所:日本学術会議講堂
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//others-pdf/20140725.pdf
■J-DESCコアスクール・微化石コース(第8回)/第11回微化石サマースクール
日本地質学会ほか 共催
8月29日(金)〜31日(日)
場所:名古屋大学理学部 環境学研究科E棟
申込締切:8月8日(金)
http://www.j-desc.org/modules/tinyd0/rewrite/coreschool/micropal.html
■IGCP608 Asia-Pacific Cretaceous Ecosystems(白亜紀アジア−西太平洋生態系)
第2回国際シンポジウム
日本地質学会ほか 共催
9月4日(木)〜6日(土)(シンポジウム)
9月7日(日)〜10日(水)(巡検:銚子・那珂湊・双葉層群)
会場:早稲田大学 大隈講堂 小講堂
http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/
■2014年度日本地球化学会第61回年会
日本地質学会ほか 共催
9月16日(火)〜18日(木)
会場:富山大学五福キャンパス
事前参加登録締切:8月29日(金)14:00
http://www.geochem.jp/conf/2014/
■第58回粘土科学討論会
日本地質学会ほか 共催
9月24日(水)〜27日(土)
会場:福島市A・O・Z(アオウゼ)
http://www.cssj2.org/
■日本ジオパーク南アルプス大会(第5回日本ジオパーク全国大会)
日本地質学会ほか 後援
9月27日(土)〜9月30日(火)
場所:長野県伊那文化会館、伊那市生涯学習センター(いなっせ)
http://minamialps-mtl-geo.jp/
■第30回ゼオライト研究発表会
日本地質学会ほか 協賛
11月26日(水)〜27日(木)
場所:タワーホール船堀(東京都江戸川区船堀4-1-1)
講演申込締切:8月8日(金)
予稿原稿締切:10月24日(金)
http://www.jaz-online.org/
■第24回環境地質学シンポジウム
日本地質学会ほか 共催
11月28日(金)〜29日(土)
場所:日本大学文理学部8号館1階レクチャーホール
発表登録申込締切:10月18日(土)まで
原稿登録締切:11月5日(水)必着
http://www.jspmug.org/
■第4回学生のヒマラヤ野外実習ツアー
日本地質学会等推薦
2015 年3月上旬(4日頃)出発,出国から帰国まで15日間
参加募集対象:全国の地学,災害地質,自然環境等に関係する学科・専攻科の学生・大学院生を優先※学生の指導教員,関係企業の新人技術者や指導上司,及び高校生や中学・高校の理科教員,一般市民も受け入れます. 定員:20名
参加費:学生,大学院生は20 万円以内(暫定)
参加申込締切:2014年11月末日
詳細はこちら
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
2015年7月27日(月)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1-1)
http://inqua2015.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0133.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・地学教員募集情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■農林水産省地球科学系職員(経験者)募集(8/15〜8/21)
■東北大学:学術資源研究公開センター(総合学術博物館)(助教)(9/23)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.265 地震火山こどもサマースクール:参加者募集中!!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.265 2014/7/15 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[鹿児島大会]事前参加登録受付中!
【2】[鹿児島大会]各種申込み締切のお知らせ
【3】地震火山こどもサマースクール:参加者募集中!!
【4】2014年度会費およびそれ以前の未納会費がある方へ
【5】惑星地球フォトコンテスト入選作品展示会開催中
【6】GSJ地質図幅の電子無償配信スタート
【7】地質災害情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[鹿児島大会]事前参加登録受付中!
─────────────────────────────────
日本地質学会第121年学術大会(鹿児島大会)の事前参加登録のお申込を受付中です.
今年もたくさんの参加をお待ちしています.
9月13日(土)〜15日(月)
会場:鹿児島大学 ほか
◆事前参加登録:8/19(火)締切[※巡検のみ:8/8(金)締切]
〔注〕演題登録と事前参加登録は,それぞれ別のお申し込みです.演題登録済でも,締切までに【事前参加登録】を別途行わない場合は,当日参加の扱いとなります.
事前と当日とでは,参加登録費が異なりますので,ご注意ください.
◆講演要旨集について
参加登録費が発生するかた(正会員や院生割引会費適用正会員等)には,必ず講演要旨集が付きますが,参加登録費が0円のかた(名誉会員や50年会員,学部学生割引会費適用正会員等)には要旨集は付きません.
要旨集の当日販売もありますが,ここ数年,当日販売分が売り切れてしまうことが多く,購入いただけないケースもあります.
参加を予定されているかたや要旨集を購入希望のかたは,事前参加登録または要旨集の予約購入申込をお願いいたします.
鹿児島大会HPはコチラ↓
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0001.html
参加登録費について
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0020.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[鹿児島大会]各種申込み締切のお知らせ
──────────────────────────────────
■ 小さなEarth Scientistのつどい
〜第12回 小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜参加校募集
申込締切:7月16 日(水)
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0039.html
■ 企業・研究機関等関係団体による展示会の出展募集
申込締切:8月8日(金)
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0041.html
■ 書籍・販売ブースご利用の募集
申込締切:8月8日(金)
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0041.html#book
■ 講演要旨集,広告協賛の募集
申込締切:8月8日(金)
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0041.html#kokoku
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】地震火山こどもサマースクール:参加者募集中!!
──────────────────────────────────
<小・中・高教員ならびに,小中高生のお子さんがいる父兄の会員の方へ>
小学生〜高校生を対象とした,第15回地震火山こどもサマースクールが長崎県の島原半島世界ジオパークで開催されます.
「島原半島に隠された九州のヒミツ」をテーマに,世界の第一線で活躍する研究者と一緒に,見学会や室内実験を行いながら,九州という島の成り立ちを考えていきます.
九州内のジオパークに住む友達と一緒に,九州がどうやってできてきたのかを考えてみませんか?周囲の小・中・高生にぜひお声掛け下さい.
また,参加申込の期限が迫っております.お早めにお申し込み下さい.
--------------------------------------
第15回 地震火山こどもサマースクール「島原半島に隠された九州のヒミツ」
○開催日:8月2日(土)〜3日(日)
○場所:島原半島世界ジオパーク
○対象:小学校5年生〜高校生
【主催】第15回地震火山こどもサマースクール実行委員会(*)
*(公社)日本地震学会 / NPO法人日本火山学会/(一社)日本地質学会/島原半島ジオパーク協議会
●参加締切:7月18日(金) ※間もなく締切です!!
日程など詳細はこちらから
http://www.kodomoss.jp/ss/shimabara/
募集要項・応募用紙はこちらから
http://www.kodomoss.jp/ss/shimabara/images/samasuku2014.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2014年度会費およびそれ以前の未納会費がある方へ
─────────────────────────────────
6月中旬に督促請求書(郵便振替用紙)を郵送しました.
早急にご送金くださいますようお願いいたします.
7月上旬頃までに入金確認が取れない場合には,7月号の雑誌から発送停止となります.定期的に雑誌をお受け取りになりたい方は,お早めにご送金ください.
また,9月鹿児島大会での講演を申し込まれた方は,忘れずにご送金をお願いいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】惑星地球フォトコンテスト入選作品展示会開催中
─────────────────────────────────
今回は,最新の第5 回の入選作品をはじめとして過去の作品も多数展示しています.
お誘い合わせの上,迫力ある作品を是非ご覧下さい.
日程:7月1日(火)〜31日(木)
場所:みどりのiプラザ(東京都千代田区日比谷公園内緑と水の市民カレッジ3階)
https://www.tokyo-park.or.jp/college/green/
開館時間 9:00〜17:00 休館日 日曜・祝日
入場無料
詳しくは、http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】GSJ地質図幅の電子無償配信スタート
─────────────────────────────────
産総研地質調査総合センターでは,地球科学図等を含む地質情報のオープンデータ化を進めていますが,この7月よりその一環として、5万分の1地質図幅の電子配信を開始ししました。詳しくはチラシPDFをご覧下さい。なお,これらのオープンデータの2次利用にあたっては,クリエイティブコモンズライセンスを採用していますので,ほとんどの制限が撤廃されています.詳しくはGSJ公式ホームページをご覧下さい。
チラシ
https://www.gsj.jp/files/gsj/opendata_201407.pdf
GSJ公式ホームページ:2次利用ライセンス
https://www.gsj.jp/license/index.html
地質図カタログ
https://www.gsj.jp/Map/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】 地質災害情報
──────────────────────────────────
平成26年7月9日に長野県南木曽町で発生した土石流の発生地に関する地質情報が産総研のHPに掲載されました.
詳しくはこちらから.
https://www.gsj.jp/hazards/landslide/140709nagiso.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地学オリンピックキャラクターデザインコンテスト
日本地質学会共催
募集締切:10月31日(金)
応募資格:中学生・高校生
http://jeso.jp/wp-content/uploads/2014/06/ieso_character_design_contest.pdf
■島原半島の地下を見てみよう ボーリングコア公開と火山実験講座
7月20日(日)
場所:長崎県島原市国土交通省雲仙復興事務所資料館および駐車場
○ボーリングコア公開:10:00〜16:30
○火山講座「火山の観測とデータのよみ方 明日からあなたも火山学者?」:13:30〜14:00
○火山実験「体験してみよう火山噴火のしくみと火山観測」:14:00〜16:30
http://www.unzen-geopark.jp/c-event/5051
■「青少年のための科学の祭典」2014全国大会
7月26日(土)〜27日(日)
日本地質学会 後援
場所:科学技術館(千代田区北の丸公園)
http://www.kagakunosaiten.jp/
■学術フォーラム「初等中等教育における海洋教育の意義と課題
−海洋立国を担う若手の育成に向けて−」
8月1日(金) 13:00〜17:30
場所:日本学術会議講堂(地下鉄乃木坂駅 すぐ)
参加無料 要事前申込
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/193-s-0801.pdf
■新潟のジオパーク展 −糸魚川と佐渡の魅力−
日本地質学会ほか後援
7月12日(土)〜8月29日(金)
会場:新潟大学駅南キャンパス ときめいと
http://www1.niigata-u.ac.jp/tokimate/
■J-DESCコアスクール・微化石コース(第8回)/第11回微化石サマースクール
日本地質学会ほか 共催
8月29日(金)〜31日(日)
場所:名古屋大学理学部 環境学研究科E棟
申込締切:8月8日(金)
http://www.j-desc.org/modules/tinyd0/rewrite/coreschool/micropal.html
■IGCP608 Asia-Pacific Cretaceous Ecosystems(白亜紀アジア−西太平洋生態系)
第2回国際シンポジウム
日本地質学会ほか 共催
9月4日(木)〜6日(土)(シンポジウム)
9月7日(日)〜10日(水)(巡検:銚子・那珂湊・双葉層群)
会場:早稲田大学 大隈講堂 小講堂
http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/
■2014年度日本地球化学会第61回年会
日本地質学会ほか 共催
9月16日(火)〜18日(木)
会場:富山大学五福キャンパス
講演申込締切:7月16日(水)14:00
事前参加登録締切:8月29日(金)14:00
http://www.geochem.jp/conf/2014/
■第58回粘土科学討論会
日本地質学会ほか 共催
9月24日(水)〜27日(土)
会場:福島市A・O・Z(アオウゼ)
講演要旨送付締切:7月25日(金)
http://www.cssj2.org/
■第30回ゼオライト研究発表会
日本地質学会ほか 協賛
11月26日(水)〜27日(木)
場所:タワーホール船堀(東京都江戸川区船堀4-1-1)
講演申込締切:8月8日(金)
予稿原稿締切:10月24日(金)
http://www.jaz-online.org/
■第24回環境地質学シンポジウム
日本地質学会ほか 共催
11月28日(金)〜29日(土)
場所:日本大学文理学部8号館1階レクチャーホール
発表登録申込締切:10月18日(土)
原稿登録締切:11月5日(水)必着
http://www.jspmug.org/
■地質学史懇話会
12月23日(火・祝)13:30〜17:00
場所:北とぴあ8階806号室:JR京浜東北線王子駅下車3分
財部香枝「明治初年に導入されたスミソニアン気象観測法について(仮題)」
小野田 滋「広田(廣田)孝一(1896〜1972)の業績について(仮題)」
■第4回学生のヒマラヤ野外実習ツアー
日本地質学会等推薦
2015 年3月上旬(4日頃)出発,出国から帰国まで15日間
参加募集対象:全国の地学,災害地質,自然環境等に関係する学科・専攻科の学生・大学院生を優先※学生の指導教員,関係企業の新人技術者や指導上司,及び高校生や中学・高校の理科教員,一般市民も受け入れます.
定員:20名
参加費:学生,大学院生は20 万円以内(暫定)
参加申込締切:2014年11月末日
詳細はこちら
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
2015年7月27日(月)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1-1)
http://inqua2015.jp/
■International Conference on Asian Marine Geology (ICAMG-8)
2015年10月12日(月)〜16日(金)
場所:Busan, Korea
Call for Session: 21 April, 2014
Deadline of Session Call 31 August, 2014
Deadline of Abstract Submission: 31 January 2015
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//others-pdf/ICAMG8_2015.pdf
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0133.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・地学教員募集情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■広島大学大学院:理学研究科地球惑星システム学専攻教員公募(教授)(8/29)
■海洋研究開発機構:平成27年度研究船利用課題の募集(7/18)
■第36回(平成26年度)沖縄研究奨励賞推薦応募(9/30 学会締切8/29)
■平成27年度笹川科学研究助成の募集
(学術研究部門:10/1-10/15、実践研究部門:11/1-11/14)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.261 (臨時)[鹿児島大会]講演申込:締切まであと1週間!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.261 2014/6/24 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[鹿児島大会]講演申込:締切まであと1週間!
【2】[鹿児島大会]講演申込画面(PASREG):入力時の注意
【3】[鹿児島大会]各種申込み締切のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[鹿児島大会]講演申込:締切まであと1週間!
──────────────────────────────────
鹿児島大会講演申込・要旨投稿は, 来週7月1日(火)18時締切です。
締切に近づくと申込が集中しますので,できるだけ余裕をもってお手続き下さい。システムトラブル以外は,申込締切の延長はありませんので,締切を厳守して頂くよう,お願いします。
今年もたくさんのお申込をお待ちしています。
講演申込は,こちらから
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[鹿児島大会]講演申込画面(PASREG):入力時の注意
─────────────────────────────────
(1)新規登録:〔受付番号〕と〔パスワード〕を取得しましょう
参加登録トップ画面一番下【新規登録はこちらから】から新規登録を行い,〔受付番号〕と〔パスワード〕を取得してください。
登録画面には“演題情報”のほかに“連絡者情報(一度登録しておけば書き換える必要の無い項目)”もあります。まずは新規登録を行い,〔受付番号〕と〔パスワード〕を取得することをお勧めします。
(2)修正する場合:画面右上【マイページ】からログイン
〔受付番号〕と〔パスワード〕で,【マイページ】からログインいただき,締切まで何度でも入力情報の修正ができます。
画面操作に慣れていないと,タイムアウトする可能性が高く,締切直前の登録は入力ミス等も多くなります。余裕をもってご登録下さい。
講演申込は、こちらから
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[鹿児島大会]各種申込み締切のお知らせ
─────────────────────────────────
■ ランチョン・夜間集会:会合申込
申込締切:6月25日(水)必着
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0038.html
■ 事前参加登録
申込締切(Web):8月19日(火)締切[*巡検のみ 8月8日(金)締切]
申込締切(郵送):8月15日(金)必着[*巡検のみ 8月6日(水)必着]
〔注〕演題登録と事前参加登録は,それぞれ別のお申し込みになります。ご注意ください。
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0001.html
■ 小さなEarth Scientistのつどい
〜第12回 小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜参加校募集
申込締切:7月16 日(水)
■ 企業・研究機関等関係団体による展示会の出展募集
1次申込締切:7月4日(金)
http://www.geosociety.jp/osaka/content0039.html
■ 書籍・販売ブースご利用の募集
1次申込締切:7月4日(金)
http://www.geosociety.jp/osaka/content0039.html#book
■ 講演要旨集,広告協賛の募集
申込締切:8月8日(金)
http://www.geosociety.jp/osaka/content0039.html#kokoku
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.262 (臨時)[鹿児島大会]講演申込:明日(7/1)締切!(延長なし)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.262 2014/6/30 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[鹿児島大会]講演申込:明日(7/1)締切です!
【2】[鹿児島大会]講演申込画面(PASREG):入力時の注意
【3】[鹿児島大会]各種申込み締切のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[鹿児島大会]講演申込:明日(7/1)締切です!
──────────────────────────────────
鹿児島大会講演申込・要旨投稿は, 明日 7月1日(火)18時締切です。
締切間際は申込が集中しますので,できるだけ余裕をもってお手続き下さい。
システムトラブル以外は,申込締切の延長はありませんので,締切を厳守して頂くよう,お願いします.
今年もたくさんのお申込をお待ちしています。
講演申込は、こちらから
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[鹿児島大会]講演申込画面(PASREG):入力時の注意
─────────────────────────────────
(1)新規登録:〔受付番号〕と〔パスワード〕を取得しましょう
参加登録トップ画面一番下【新規登録はこちらから】から新規登録を行い,〔受付番号〕と〔パスワード〕を取得してください。
登録画面には“演題情報”のほかに“連絡者情報(一度登録しておけば書き換える必要の無い項目)”もあります。まずは新規登録を行い,〔受付番号〕と〔パスワード〕を取得することをお勧めします。
(2)修正する場合:画面右上【マイページ】からログイン
〔受付番号〕と〔パスワード〕で,【マイページ】からログインいただき,締切まで何度でも入力情報の修正ができます。
画面操作に慣れていないと,タイムアウトする可能性が高く,締切直前の登録は入力ミス等も多くなります。余裕をもってご登録下さい。
講演申込は、こちらから
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[鹿児島大会]各種申込み締切のお知らせ
─────────────────────────────────
■ 事前参加登録
申込締切(WEB)8月19日(火)締切[*巡検のみ 8月8日(金)締切]
〔注〕演題登録と事前参加登録は,それぞれ別のお申し込みになります。
ご注意ください。
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0001.html
■ 小さなEarth Scientistのつどい
〜第12回 小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜
申込締切:7月16 日(水)
■ 企業・研究機関等関係団体による展示会の出展募集
1次募集締切:7月4日(金)
http://www.geosociety.jp/osaka/content0039.html
■ 書籍・販売ブースご利用の募集
1次募集締切:7月4日(金)
http://www.geosociety.jp/osaka/content0039.html#book
■ 講演要旨集,広告協賛の募集
申込締切:8月8日(金)
http://www.geosociety.jp/osaka/content0039.html#kokoku
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.263 惑星地球フォトコンテスト入選作品展示会開催中!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.263 2014/7/1 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[鹿児島大会]事前参加登録受付中!
【2】[鹿児島大会]各種申込み締切のお知らせ
【3】2014年度会費およびそれ以前の未納会費がある方へ
【4】惑星地球フォトコンテスト入選作品展示会開催中
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[鹿児島大会]事前参加登録受付中!
─────────────────────────────────
日本地質学会第121年学術大会(鹿児島大会)の事前参加登録のお申込を受付中です.
今年もたくさんの参加をお待ちしています.
9月13日(土)〜15日(月)
会場:鹿児島大学 ほか
◆事前参加登録:8/19(火)締切[※巡検のみ 8/8(金)締切]
〔注〕演題登録と事前参加登録は,それぞれ別のお申し込みです.演題登録済でも,締切までに事前参加登録を別途行わない場合は,当日参加となります.
鹿児島大会HPはコチラ↓
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[鹿児島大会]各種申込み締切のお知らせ
──────────────────────────────────
■ 小さなEarth Scientistのつどい
〜第12回 小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜参加校募集
申込締切:7月16 日(水)
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0039.html
■ 企業・研究機関等関係団体による展示会の出展募集
1次申込締切:7月4日(金)
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0041.html
■ 書籍・販売ブースご利用の募集
1次申込締切:7月4日(金)
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0041.html#book
■ 講演要旨集,広告協賛の募集
申込締切:8月8日(金)
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0041.html#kokoku
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2014年度会費およびそれ以前の未納会費がある方へ
─────────────────────────────────
6月中旬に督促請求書(郵便振替用紙)を郵送しました.
早急にご送金くださいますようお願いいたします.
7月上旬頃までに入金確認が取れない場合には,7月号の雑誌から発送停止となります.定期的に雑誌をお受け取りになりたい方は,お早めにご送金ください.
また,9月鹿児島大会での講演を申し込まれたかたは,忘れずにご送金をお願いいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】惑星地球フォトコンテスト入選作品展示会開催中
─────────────────────────────────
今回は,最新の第5 回の入選作品をはじめとして過去の作品も多数展示いたします. お誘い合わせの上,迫力ある作品を是非ご覧下さい.
日程:7月1日(火)〜31日(木)
場所:みどりのiプラザ(東京都千代田区日比谷公園内緑と水の市民カレッジ3階)
https://www.tokyo-park.or.jp/college/green/
開館時間 9:00〜17:00 休館日 日曜・祝日 入場無料
詳しくは、
http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】 支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■夏休み教師巡検:5億年前と10万年前の茨城を見る
関東在住の小・中・高校で教育に携わっておられる教員の皆様が対象ですが、会員外や教員以外の方の参加も大歓迎です。
8月20日(水)〜21日(木)
場所:20日:北浦東岸の下総層群(堆積構造、貝化石、生痕等)
21日:日立周辺(カンブリア紀の赤沢層、日立鉱山、石炭層等)
案内者:荒川真司清真学園教諭、田切美智雄茨城大名誉教授
費用:15,000円(予定)(宿泊費・交通費・諸雑費込)
参加申込締切:7月11日(金) 下記宛にメールでお申込下さい。
連絡先:米澤正弘 my-yonezawa@y6.dion.ne.jp
■清澄フィールドキャンプ 参加者募集
8月25日(月)〜31日(日)
場所:東京大学千葉演習林(〒299-5505 千葉県鴨川市清澄)
費用:宿泊・食事・保険(約15000円/6泊)+レンタカー代(約12000円)
応募締切:7月4日(金)(*応募書類は所定のフォーマットを使用のこと)
詳しくは,支部HPへ http://kanto.geosociety.jp/
[中部支部]
2014年中部支部年会・シンポジウム・地質巡検 報告
中部支部事務局幹事 須藤 斎
中部支部では各県持ち回りで支部年会を開催し,県幹事を中心となってその県に関係した地質についてシンポジウムや地質巡検を企画し,開催運営を行っている.今年は長野県が開催県であり,2014年中部支部年会・シンポジウム・地質巡検を,6月14日(土)と15日(日)に信州大学理学部および上高地にて開催した.・・・・・
続きはこちらから. http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地学オリンピックキャラクターデザインコンテスト
日本地質学会共催
募集締切:10月31日(金)
応募資格:中学生・高校生
http://jeso.jp/wp-content/uploads/2014/06/ieso_character_design_contest.pdf
■新潟のジオパーク展 −糸魚川と佐渡の魅力−
日本地質学会ほか後援
7月12日(土)〜8月29日(金)
会場:新潟大学駅南キャンパス ときめいと
http://www1.niigata-u.ac.jp/tokimate/
■「青少年のための科学の祭典」2014全国大会
7月26日(土)〜27日(日)
日本地質学会 後援
場所:科学技術館(千代田区北の丸公園)
http://www.kagakunosaiten.jp/
■J-DESCコアスクール・微化石コース(第8回)/第11回微化石サマースクール
日本地質学会ほか 共催
8月29日(金)〜31日(日)
場所:名古屋大学理学部・環境学研究科E棟
申込締切:8月8日(金)
http://www.j-desc.org/modules/tinyd0/rewrite/coreschool/micropal.html
■IGCP608 Asia-Pacific Cretaceous Ecosystems(白亜紀アジア−西太平洋生態系)
第2回国際シンポジウム
日本地質学会ほか 共催
9月4日(木)〜6日(土)(シンポジウム)
9月7日(日)〜10日(水)(巡検:銚子・那珂湊・双葉層群)
会場:早稲田大学 大隈講堂 小講堂
http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/
■2014年度日本地球化学会第61回年会
日本地質学会ほか 共催
9月16日(火)〜18日(木)
会場:富山大学五福キャンパス
講演申込締切:7月16日(水)14:00
事前参加登録締切:8月29日(金)14:00
http://www.geochem.jp/conf/2014/
■第31回歴史地震研究会(名古屋大会)[第3報]
9月20日(土)〜22日(月)
会場:名古屋大学減災連携研究センター 減災ホール
参加申込・予稿集原稿締切等:7月31日(金)
http://sakuya.ed.shizuoka.ac.jp/rzisin/meeting/31st_taikai_v3.pdf
■第58回粘土科学討論会
日本地質学会ほか 共催
9月24日(水)〜27日(土)
会場:福島市A・O・Z(アオウゼ)
参加・講演申込期間:6月16日(月)〜7月11日(金)
講演要旨送付締切:7月25日(金)
http://www.cssj2.org/
■学術研究船白鳳丸研究計画企画調整シンポジウム
11月25日(火)〜27日(木)
場所:東京大学大気海洋研究所 講堂
申込期限:10月10日(金)
http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/coop/hakuho_28-30.html
■(協)第30回ゼオライト研究発表会
日本地質学会ほか 協賛
11月26日(水)〜11月27日(木)
場所:タワーホール船堀(東京都江戸川区船堀4-1-1)
講演申込締切:8月8日(金)
予稿原稿締切:10月24日(金)
http://www.jaz-online.org/
■第24回環境地質学シンポジウム
日本地質学会ほか 共催
11月28日(金)〜29日(土)
場所:日本大学文理学部8号館1階レクチャーホール
発表登録申込締切:10月18日まで
原稿登録締切:11月5日必着
http://www.jspmug.org/
■第4回学生のヒマラヤ野外実習ツアー
日本地質学会等推薦
2015 年3月上旬(4日頃)出発,出国から帰国まで15日間
参加募集対象:全国の地学,災害地質,自然環境等に関係する学科・専攻科の学生・大学院生を優先※学生の指導教員,関係企業の新人技術者や指導上司,及び高校生や中学・高校の理科教員,一般市民も受け入れます.
定員:20名
参加費:学生,大学院生は20 万円以内(暫定)
参加申込締切:2014年11月末日
詳細はこちら
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
2015年7月27日(月)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1-1)
http://inqua2015.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0133.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・地学教員募集情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■日本原子力研究開発機構:東濃地科学センター特定課題推進員募集(7/18)
■駒場東邦中学校・高等学校:理科教員募集(中学理科第2分野・高校地学担当)(7/24)
■2014年朝日賞推薦候補者募集(8/29 学会締切8/8)
■東京大学大気海洋研究所:平成27年度新青丸共同利用公募(8/29)
■東京大学大気海洋研究所:平成27年度白鳳丸共同利用公募(8/29)
■東京大学大気海洋研究所:平成28〜30年度白鳳丸共同利用公募(10/10)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.264 (臨時)県の岩石・鉱物・化石の出版に向けて
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.264 2014/7/4 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】“日本各県の岩石・鉱物・化石”の出版に向けて
【2】意見募集:地震に関する総合的な調査観測計画について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】“日本各県の岩石・鉱物・化石”の出版に向けて
─────────────────────────────────
日本地質学会会員の皆様へ
日本各地で記録的な豪雨とのニュースが報じられておりますが,いかがお過ごしでしょうか.
さて,日本地質学会では,2013年9月13日の理事会で、“県の石”選定に向けた石渡前会長の提案を、地質学会として進めることが承認されました.
石渡前会長の提案は,
「日本の各県では、県花、県木、県鳥などが制定されていますが,“県の石”というのは聞いたことがなく,日本地質学会として“各県の岩石・鉱物・化石”の候補を推薦し、その制定に向けて各県や文部科学省に働きかけたらよいと思います.」
との内容です.併せて,それらに関する書籍の出版も提案されております.アメリカでは,「州の鉱物,岩石,宝石」や「州の昆虫」が制定されており,一般市民に科学に対する関心をもたせるうえで一定の効果を挙げているようです.
私は,会長に立候補する際のマニフェストとして「地学を身近に」活動を展開することを挙げ,その中で,“日本各県の岩石・鉱物・化石”を完成させ,出版すると述べております.そこで,地質学会として県の石を選定する趣旨文を、各県として県の石(岩石・鉱物・化石)を制定しているか否かなど、簡単なアンケートとともに都道府県に送りました.アンケートに対する返答がまとまり次第,執行理事を中心として,支部・部会・理事各位の協力のもと,日本各県の岩石・鉱物・化石を選定し,その結果を125周年の記念出版物にしたいと考えております.
これが,各県により認定され,公式の県の岩石・鉱物・化石制定につながればさらに結構なことと思います.また,この活動を通じて,市民の方々の地質学を始めとする地球科学全般に関する関心が高まることを大いに期待しています.
県の石の選定に関し、会員の皆様にも関心をもっていただき、ご協力をお願いいたします.
日本地質学会長 井龍康文
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】意見募集:地震に関する総合的な調査観測計画について
──────────────────────────────────
政府地震調査研究推進本部(地震本部)では、東日本大震災を踏まえ、今後の地震の調査観測の在り方を示す計画を策定しております。
地震本部の調査観測計画部会(部会長:平原和朗 京都大学大学院教授)においてその計画案を取りまとめましたので、このたび、皆様から広く御意見を頂戴するため、意見募集を行っております。 募集期間:7月3日(木)〜7月17日(木)
提出方法:郵送、FAX、電子メール 意見募集対象および御提出方法の詳細は
「電子政府の総合窓口 イーガブ パブリックコメント」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000699
をご覧ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.268 [鹿児島大会]事前参加登録:本日申込締切!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.268 2014/8/19 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[鹿児島大会]事前参加登録:本日申込締切!
【2】[鹿児島大会]緊急展示の申込について
【3】[鹿児島大会]地学教育・アウトリーチ巡検;締切延長!!
【4】「県の石」募集のお知らせ
【5】「九州電力株式会社川内原子力発電所…」に対する意見を提出しました
【6】「平朝彦国際深海科学掘削研究賞」が新設!
【7】2014年度会費およびそれ以前の未納会費がある方へ
【8】2014年度秋季地質調査研修:参加者募集
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[鹿児島大会]事前参加登録:本日申込締切!
─────────────────────────────────
日本地質学会第121年学術大会(鹿児島大会)の事前参加登録のお申込は本日18時が締切となっております.
〔注1〕演題登録(発表申込)と事前参加登録は,それぞれ別のお申し込みです.
演題登録済でも,締切までに【事前参加登録】を別途行わない場合は,当日参加の扱いとなります.事前と当日とでは,参加登録費が異なりますので,ご注意ください.
〔注2〕事前参加登録をされたかたは,8月25日(月)までに参加登録費をご送金ください.
この期日までに入金確認が取れなかったかたは,【当日払いの参加費】に金額訂正した確認書を郵送します.事前登録されたかたはお早目に参加費のご送金をお願いします.
◆講演要旨集について
参加登録費が発生するかた(正会員や院生割引会費適用正会員等)には,必ず講演要旨集が付きますが,参加登録費が0円のかた(名誉会員や50年会員,学部学生割引会費適用正会員等)には要旨集は付きません.
要旨集の当日販売もありますが,ここ数年,当日販売分が売り切れてしまうことが多く,購入いただけないケースもあります.
参加を予定されているかたや要旨集を購入希望のかたは,事前参加登録または要旨集の予約購入申込をお願いいたします.
鹿児島大会HPはこちら
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0001.html
参加登録費について
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0020.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[鹿児島大会]緊急展示の申込について
─────────────────────────────────
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害調査報告や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コーナー」を設けます.ポスター展示を希望する方は,8月29日(金)までに次の内容を下記申込先にご連絡ください.
1)発表要旨PDF(ニュース誌5月号参照)
2)緊急展示の必要性
3)発表代表者と連絡先
4)希望枚数(1枚:縦210×横120cm)
5)展示に関わる要望(2〜5の様式は自由)
実行委員会は行事委員会と協議し,可否の判断を致します.希望にはできるだけ応えるようにしますが,展示方法等については実行委員会の指示に従ってください.
申込先:main@geosociety.jp
担当:山本啓司(鹿児島大会実行委員会)・須藤 宏(行事委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[鹿児島大会]地学教育・アウトリーチ巡検;締切延長!!
─────────────────────────────────
地学教育・アウトリーチ巡検「2011年新燃岳噴火と霧島ジオパーク」
9月13日(土)8:30集合出発,17:00解散(予定)
参加対象:小中高の教員ならびに一般市民を優先
申込締切:8月22日(金)[締切延長しました]
アウトリーチ巡検参加希望の方は,住所・氏名・連絡先住所・電話番号(e-mail アドレスでも可)・年齢・人数を記載して下記までお申し込み下さい.応募者多数の場合は,先着順となりますので,ご注意ください.
(注意;事前参加申込フォームからの申込は終了致しました。学術大会への参加・不参加に関わらず,本巡検へ参加希望の方は,直接下記宛にお申し込み下さい)
↓↓↓申込先・詳細はコチラ↓↓↓
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0013.html#ex_j
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】「県の石」募集のお知らせ
─────────────────────────────────
日本では古来より郷土に産する岩石,鉱物,化石を愛し,またそれらを利用しながら発展してきました.また,日本列島はプレートの沈み込み帯に位置し,深海の堆積物から火山や大陸地殻まで多様で幅広い時代の岩石から成り立っています.これほど多くの岩石に彩られている国は世界でも多くはありません.私たちが生活する大地の歴史と成り立ちを知り,郷土の地質を愛する心を再認識するために,日本地質学会では「県の石」の認定を企画しました.日本地質学会に所属する専門家のみならず,全国都道府県へのアンケート調査,そして市民の皆様の推薦を参考に各都道府県の「県の石」を認定して参ります.
応募締切:10月31日まで(鹿児島県のみ8月31日)
詳しくはこちらから.
http://www.geosociety.jp/name/content0121.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】「九州電力株式会社川内原子力発電所1号炉及び2号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案に対する科学的・技術的意見」を提出しました
─────────────────────────────────
原子力規制委員会より,九州電力株式会社川内原子力発電所1号炉及び2号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案に対する科学的・技術的意見の募集が実施されました。
地質学会として意見を提出いたしましたので,お知らせ致します。
(2014年8月14日 提出)
意見募集の詳細はコチラ
https://www.nsr.go.jp/public_comment/bosyu140716.html
日本地質学会より提出した意見(全文)はコチラ(PDF)
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//pubcome/2014/p-20140814.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】 「平朝彦国際深海科学掘削研究賞」が新設!
──────────────────────────────────
この度,アメリカ地球物理学連合(American Geophysical Union;AGU)により,世界の海洋掘削科学の発展に大きく貢献した平朝彦氏(日本地質学会元会長)を顕彰して,「平朝彦国際深海科学掘削研究賞」(The Asahiko Taira International Scientific Ocean Drilling Research Prize)が創設されました.地球科学関連学会としては世界最大の学会であるAGUにより,日本人研究者の名前を冠した国際的な学会賞が新設されたことは,深海掘削研究分野における日本の運営(地球深部探査船「ちきゅう」の建造とその運用)や科学に対する貢献が高く評価されたことを示します.この賞は,原則として,博士号を取得後15年以内の研究者を対象とし,賞金として18,000ドルが授与され,授賞式は毎年1回,AGUまたは日本地球惑星科学連合の学術大会で交互に行われるとのことです.候補者の募集が開始されましたら,優れた業績を挙げた若手研究者を御推薦下さい.
なお,AGU発行のEOSに本件に関する記事が掲載されています.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2014EO310011/abstract
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】2014年度会費およびそれ以前の未納会費がある方へ
─────────────────────────────────
6月中旬に2014年度会費の督促請求書(郵便振替用紙)を郵送しました.
会費未納のかたは,早急にご送金くださいますようお願いいたします.
なお,7月中旬頃までに入金確認が取れていないかたにたいしては,7月号の雑誌から送本を停止しています.定期的に雑誌をお受け取りになりたいかたは,お早めにご送金ください.
また,9月の鹿児島大会で発表されるかたは,学会費のご送金をお願いいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】2014年度秋季地質調査研修:参加者募集
─────────────────────────────────
地質調査法の基本技術の修得をめざすとともに,それをベースに得られた過去の調査や研究の成果についても学びます.地質調査の経験のない方でも,地質調査法の基本を体で習得することを目指します.
11月25日(日)〜29日(土)4泊5日
場所:千葉県君津市及びその周辺地域(房総半島中部の清澄山系とその周辺 )
募集人数:6名. 参加費:12万円 (CPD:40単位)
申込期間:9月1日(月)〜10月17日(金)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/engineer/content0035.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】支部情報
──────────────────────────────────
[北海道支部]
■2014年日高巡検開催
テーマ 『日高変成帯北部〜神居古潭帯の横断』
討論会 『古第三紀以降のテクトニクスの未解決問題』<<話題提供者募集中>>
10月4日(土)〜5日(日)雨天決行(雨具を用意)
19:00〜21:00 討論会『古第三紀以降のテクトニクスの未解決問題』
宿舎: 日高高原荘:宿泊は2名/1室
催行人数: 18名
参加費: 一般18,000円・学生13,000円(バス代+宿泊代+保険料+資料代・懇親会費など)
参加申込締切: 8月31日(日)
詳しくは http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[関東支部]
■「富士山巡検」のお知らせ
富士山の宝永火口や過去の噴火に伴う溶岩流,岩屑なだれ堆積物,火口列,火山灰などを観察していただき,宿泊先では案内者から富士山の地形地質に関する勉強会も予定しています.会員の方はもとより,広く参加者を募集致します.
10月4日(土)〜5日(日),1泊2日,雨天決行
CPD単位:16単位
募集人数:会員および一般・25名程度
参加費用:一般19,000円,学生・院生12,000円
問合せ先:細根 清治[(株)東建ジオテック]
メールアドレス:s.hosone@tokengeotec.co.jp
FAX:048-826-0151 携帯:080-1201-7453
申し込み締切:9月19日(金)(定員に達した時点で締め切り)
※8/25追記
参加申し込み者が定員(25名)に達しましたので、参加者募集を締め切らせて頂きました。
■ショートコース『地すべり破砕帯の構造地質学』(第一報)
10月18日(土) 10:00〜16:40
場所:帝京平成大学 中野キャンパス
主催:日本地質学会関東支部,日本地すべり学会関東支部
後援:日本地質学会構造地質部会,日本地質学会応用地質部会
費用:2,000円(資料代) CPD単位:5.5ポイント
受講申込み先:日本地質学会関東支部(kanto@geosociety.jp)宛にメールにてお申込みください.
応募締め切り:10月7日(火)
それぞれ、詳しくは http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地学オリンピックキャラクターデザインコンテスト
日本地質学会共催
募集締切:10月31日(金)
応募資格:中学生・高校生
http://jeso.jp/wp-content/uploads/2014/06/ieso_character_design_contest.pdf
■新潟のジオパーク展 −糸魚川と佐渡の魅力−
日本地質学会ほか後援
〜8月29日(金)
会場:新潟大学駅南キャンパス ときめいと
http://www1.niigata-u.ac.jp/tokimate/
■J-DESCコアスクール・微化石コース(第8回)/第11回微化石サマースクール
日本地質学会ほか 共催
8月29日(金)〜31日(日)
場所:名古屋大学理学部 環境学研究科E棟
http://www.j-desc.org/modules/tinyd0/rewrite/coreschool/micropal.html
■IGCP608 Asia-Pacific Cretaceous Ecosystems(白亜紀アジア−西太平洋生態系)
第2回国際シンポジウム
日本地質学会ほか 共催
9月4日(木)〜6日(土)(シンポジウム)
9月7日(日)〜10日(水)(巡検:銚子・那珂湊・双葉層群)
会場:早稲田大学 大隈講堂 小講堂
http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/
■地磁気・古地磁気・岩石磁気学の最前線と応用
9月3日(水)〜4日(木)
場所:東京大学大気海洋研究所2F 講堂
http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/aori_news/meeting/2014/20140903.html
■2014年度日本地球化学会第61回年会
日本地質学会ほか 共催
9月16日(火)〜18日(木)
会場:富山大学五福キャンパス
事前参加登録締切:8月29日(金)14:00
http://www.geochem.jp/conf/2014/
■第58回粘土科学討論会
日本地質学会ほか 共催
9月24日(水)〜27日(土)
会場:福島市A・O・Z(アオウゼ)
http://www.cssj2.org/
■日本ジオパーク南アルプス大会(第5回日本ジオパーク全国大会)
日本地質学会ほか 後援
9月27日(土)〜9月30日(火)
場所:長野県伊那文化会館、伊那市生涯学習センター(いなっせ)
http://minamialps-mtl-geo.jp/
■2014地球環境保護 土壌・地下水浄化技術展
日本地質学会ほか 協賛
10月15日(水)〜17日(金)10:00〜17:00
会場:東京ビッグサイト 西ホール
http://www.sgrte.jp/sgr/
■山陰海岸ジオパーク国際学術会議「湯村会議」
日本地質学会 後援
10月25日(土)〜26日(日)
場所:新温泉町夢ホール(兵庫県美方郡新温泉町湯990-8)
要旨応募締切:8月29日
http://sanin-geo.jp/modules/geopark/index.php/yumura14.html
■第25回地質汚染調査浄化技術研修会 技術研修会
日本地質学会環境地質部会ほか 共催
11月21日(金)〜23日(日)
会場:NPO法人日本地質汚染審査機構本部ミーテング・ルーム・八千代市民会館
参加費:会員(地質学会員・社会地質学会員を含む)39,000円(学生:35,000円)
(CPD:22単位)
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
■第30回ゼオライト研究発表会
日本地質学会ほか 協賛
11月26日(水)〜27日(木)
場所:タワーホール船堀(東京都江戸川区船堀4-1-1)
予稿原稿締切:10月24日(金)
http://www.jaz-online.org/
■第24回環境地質学シンポジウム
日本地質学会ほか 共催
11月28日(金)〜29日(土)
場所:日本大学文理学部8号館1階レクチャーホール
発表登録申込締切:10月18日(土)まで
原稿登録締切:11月5日(水)必着
http://www.jspmug.org/
■第4回学生のヒマラヤ野外実習ツアー
日本地質学会等推薦
2015 年3月上旬(4日頃)出発,出国から帰国まで15日間
参加募集対象:全国の地学,災害地質,自然環境等に関係する学科・専攻科の学生・大学院生を優先※学生の指導教員,関係企業の新人技術者や指導上司,及び高校生や中学・高校の理科教員,一般市民も受け入れます.
定員:20名
参加費:学生,大学院生は20 万円以内(暫定)
参加申込締切:2014年11月末日
詳細はこちら
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
2015年7月27日(月)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1-1)
http://inqua2015.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0133.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・地学教員募集情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■茨城大学:理学部地球環境科学領域(地球物理学分野)(准教授または助教)(10/31)
■茨城大学:理学部地球環境科学領域(惑星科学分野)(准教授または助教)(10/31)
■高知大学海洋コア総合研究センター:平成26年度後期分全国共同利用研究課題 公募(8/29)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.269 [鹿児島大会]講演プログラム掲載!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.269 2014/9/2 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[鹿児島大会]講演プログラムを掲載しました
【2】[鹿児島大会]事前参加登録の確認書等を発送しました
【3】[鹿児島大会]地質技術者の皆さん 鹿児島大会でCPD単位が取得出来ます
【4】[鹿児島大会]鹿児島市内の宿泊施設に宿泊される方へ
【5】[鹿児島大会]各種イベント
【6】一般社団法人日本地質学会臨時総会開催について
【7】2014年8月20日広島における土砂災害,特に地質要因
【8】「県の石」募集のお知らせ
【9】2014年度会費およびそれ以前の未納会費がある方へ
【10】今年度の世界ジオパークネットワークへの加盟推薦地域等が決定
【11】2014年度秋季地質調査研修:参加者募集
【12】日本地球惑星科学連合の2015年大会ホームページオープン
【13】防災・減災に関する国際研究のための東京会議:ポスター発表のアブストラクト募集
【14】第10回科学技術予測調査:大規模案アンケート ご協力のお願い
【15】支部情報
【16】その他のお知らせ
【17】公募情報・各賞情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[鹿児島大会]講演プログラムを掲載しました
─────────────────────────────────
全体日程表、各講演のプログラムを掲載しました。
詳しくは,大会ホームページ・News誌8月号をご覧下さい。
鹿児島大会の日程・プログラムはこちら
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0007.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[鹿児島大会]事前参加登録の確認書等を発送しました
─────────────────────────────────
事前参加登録された方へ、8月29日(金)に確認書およびクーポン(お弁当・懇親会申込者のみ)を発送しました。
<<入金確認済みの方>>
記名名札と懇親会、お弁当申込の方には、参加・引換用のクーポンを同封しています。確認書(本人控と受付提出用)および名札・クーポンは当日忘れずにご持参下さい。
<<未入金の方>>
[当日払いの参加費]に金額訂正した確認書(本人控と受付提出用)のみお送りしています。9月8日(月)までにご送金をお願い致します。行き違いで入金済みの場合は当日受付にて照会いたしますので念のため、振込み時の控え等をご持参下さい。9月8日(月)までにお振込いただけなかった場合は、当日会場受付にてご清算をお願いいたします。
<振込先>
振込時には、振込者氏名の前に必ず申込No.を入力して下さい。
(1)三井住友銀行 神田駅前支店(普通)1711424
(社)日本地質学会 / シヤ)ニホンチシツガツカイ
(2)郵便振替 00140-8-28067 (社)日本地質学会
※郵便局に備え付けの郵便振替用紙をご利用ください。
詳しくはこちら
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0004.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[鹿児島大会]地質技術者の皆さん 鹿児島大会でCPD単位が取得出来ます
─────────────────────────────────
日本地質学会は,地質技術者への継続教育の一環として,大会参加者・発表者・巡検参加者へCPD単位を発行します.大会参加と口頭/ポスター発表の参加証明書は,参加日の15時以降に「CPD受付」(会場内総合受付付近を予定)においてお渡しします.また,巡検参加者については各コースにおいて案内者よりお渡しすることになります.
[ 学術大会参加 ・口頭発表 ・ポスター発表 ・巡検参加 ]
(地質技術者教育委員会 山本高司)
取得単位数など詳しくはこちら
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0051.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[鹿児島大会]鹿児島市内の宿泊施設に宿泊される方へ
─────────────────────────────────
<宿泊施設への書類提出にご協力をお願いします>
鹿児島市内の宿泊施設への宿泊者数に応じて,鹿児島観光コンベンション協会より助成金が支給されることになっています.鹿児島市内に宿泊される方は,年会の総合受付にて宿泊施設への提出書類をお渡しいたしますので(事前参加登録者へは,確認書とあわせて提出書類を事前にお送りしました),必要事項を記入の上,宿泊施設へ必ずご提出下さい.ご協力をお願い致します.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[鹿児島大会]各種イベント
─────────────────────────────────
大会期間中には、学術講演だけでなく、市民に向けたイベントなども行われます。お楽しみに!
■地質情報展2014かごしま —火山がおりなす自然の恵み—
体験実験、解説コーナーなど盛り沢山
9月13日(土)13:00〜17:00、 14日(日)9:30〜17:00、9月15日(月)9:30〜16:00
場所:鹿児島市中央公民館
(市電:「朝日通り」電停から徒歩約5分、バス:「天文館」バス停から徒歩約10分・「金生町」バス停から徒歩約5分)
■市民講演会「桜島と諏訪之瀬島の大噴火と火山災害」
9月13日(土)14:30〜16:00【入場無料/事前申込不要】[14:00開場]
講師:小林哲夫(鹿児島大学大学院理工学研究科)
会場:鹿児島大学郡元キャンパス共通教育棟1号館111教室
■一般公開シンポジウム「九州が大陸だった頃の生物と環境」
9月15日(月)9:00〜12:30【入場無料/事前申込不要】[8:30開場]
会場:鹿児島大学郡元キャンパス共通教育棟1号館111教室
■ 小さなEarth Scientistのつどい〜第12回 小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜
9月14日(日)9:00〜15:30
場所:鹿児島大会ポスター会場(郡元キャンパス)
■若手会員のための業界研究サポート(旧:就職支援プログラム)
9月14日(日)9:00〜17:00
場所:鹿児島大学郡元キャンパス共通教育棟1号館(3階)
詳しくはこちら
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0013.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】 一般社団法人日本地質学会臨時総会開催について
──────────────────────────────────
2014年8月10日
一般社団法人日本地質学会
会長 井龍康文
臨時総会を開催いたします.
2014年9月13日(土) 14:30〜14:45
会場 鹿児島大学郡元キャンパス 共通教育棟2号館 215室
(鹿児島市郡元1丁目21番24号)
議事次第など詳細はこちら
http://www.geosociety.jp/outline/content0145.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】2014年8月20日広島における土砂災害,特に地質要因
─────────────────────────────────
日本地質学会各位
2014年8月20日の未明に,広島市で局所的大雨による土砂災害が発生し,70名を超える方々の尊い人命が奪われました.ここに謹んで哀悼の意を表します.
日本地質学会では,学術団体として,地質学的な見地から,この度の土砂災害の背景・要因を学会員ならびに社会に周知する使命があると考え,災害発生地の地質に詳しい高橋裕平氏(名古屋大学PhD登龍門推進室)に記事の執筆を依頼し,快諾を得ました.ここに,高橋会員から寄稿された記事の全文を公開いたしますので,御覧下さい.
日本地質学会長
井龍康文
記事はこちらから
http://www.geosociety.jp/hazard/content0082.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】「県の石」募集のお知らせ
─────────────────────────────────
日本では古来より郷土に産する岩石,鉱物,化石を愛し,またそれらを利用しながら発展してきました.また,日本列島はプレートの沈み込み帯に位置し,深海の堆積物から火山や大陸地殻まで多様で幅広い時代の岩石から成り立っています.これほど多くの岩石に彩られている国は世界でも多くはありません.私たちが生活する大地の歴史と成り立ちを知り,郷土の地質を愛する心を再認識するために,日本地質学会では「県の石」の認定を企画しました.日本地質学会に所属する専門家のみならず,全国都道府県へのアンケート調査,そして市民の皆様の推薦を参考に各都道府県の「県の石」を認定して参ります.
応募締切:10月31日まで(鹿児島県のみ受付終了)
詳しくはこちらから.
http://www.geosociety.jp/name/content0121.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】2014年度会費およびそれ以前の未納会費がある方へ
──────────────────────────────────
6月中旬に2014年度会費の督促請求書(郵便振替用紙)を郵送しました.
会費未納のかたは,早急にご送金くださいますようお願いいたします.
なお,7月中旬頃までに入金確認が取れていないかたにたいしては,7月号の雑誌から送本を停止しています.定期的に雑誌をお受け取りになりたいかたは,お早めにご送金ください.
また,9月の鹿児島大会で発表されるかたは,学会費のご送金をお願いいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】今年度の世界ジオパークネットワークへの加盟推薦地域等が決定
──────────────────────────────────
8月28日に日本ジオパーク委員会が,今年度の「世界ジオパークネットワークへの加盟推薦地域」と「日本ジオパークネットワーク新規加盟地域」の決定結果を公表しました。
・ 世界ジオパークネットワークには「アポイ岳ジオパーク」と「伊豆半島ジオパーク」の2地域が推薦されました。
・ 日本ジオパークネットワーク認定希望が6地域から提出されていました。その内,「館山黒部」,「南紀熊野」,「天草」の3地域が認定されました。
日本ジオパーク認定地域は36地域となりました。日本地質学会としては,今後とも積極的に支援を続けていきたいと存じます。会員各位の一層のご協力をお願いいたします。
詳細は,日本ジオパーク委員会のウェブサイト(https://www.gsj.jp/jgc/)をご覧ください。
(日本地質学会ジオパーク支援委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】2014年度秋季地質調査研修:参加者募集
──────────────────────────────────
地質調査法の基本技術の修得をめざすとともに,それをベースに得られた過去の調査や研究の成果についても学びます.地質調査の経験のない方でも,地質調査法の基本を体で習得することを目指します.
11月25日(日)〜29日(土)4泊5日
場所:千葉県君津市及びその周辺地域(房総半島中部の清澄山系とその周辺 )
募集人数:6名. 参加費:12万円 (CPD:40単位)
申込締切:10月17日(金)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/engineer/content0035.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】日本地球惑星科学連合の2015年大会ホームページオープン
──────────────────────────────────
9月1日、日本地球惑星科学連合の大会ホームページ及びセッション提案システムがオープンしました。
http://www.jpgu.org/meeting/index.htm
http://www.jpgu.org/meeting/session_t.html
セッション提案の締切は 【 10月23日(木)17:00 】 です。
セッション提案に際し、日本地質学会との共催を希望される方は、行事委員会の承認が必要ですので、提案内容を各部会行事委員を通じて各部会で承認を取っていただいた後に、行事委員会の承認を得てください。よろしくお願いいたします。
(行事委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】防災・減災に関する国際研究のための東京会議:ポスター発表のアブストラクト募集
──────────────────────────────────
第3回国連防災世界会議(平成27年3月仙台)の開催前に、同会議に参加する世界の指導者とトップクラスの研究者を招聘して、防災・減災と持続可能な開発の双方を達成する防災・減災科学技術のあり方を、第一(防災、環境、地球観測の連携)、第二(科学と社会の連携)、第三(分野間連携)の3つの観点から議論する。
持続可能な開発を担保するために、政策・計画・プログラムのすべての面で持続的開発と災害軽減との密接な連携を実現させ、災害リスク軽減を実現する体制・仕組み・人材を社会の各層において確立し、災害マネジメントサイクルのすべての局面において災害リスク軽減につながる新たな防災・減災科学技術の構築へ向けた提言を行う。
趣旨等、詳細はこちら
http://monsoon.t.u-tokyo.ac.jp/AWCI/TokyoConf/jp/introduction.htm
2015年1月14日(水)〜16日(金)
会場:東京大学 伊藤国際学術研究センター伊藤謝恩ホール(東京都文京区本郷7-1-3)
定員:500名 参加費:無料(ただし懇親会は参加費有料)
2日目(1月15日)に、ポスター発表をしていただける方々を広く募集します。
発表者は、以下の二つのセッションの両方に参加する必要があります。
何れのセッションも使用言語は英語です。
・二日目午前、ポスター口頭紹介セッション
(メインホールで全聴衆に対して一人1分程度で概要を発表)
・二日目夕方、ポスター発表セッション
(ポスター展示ホールで各自ポスターの前に立ち、個別にポスターの内容を説明)
ポスター発表をご希望の方は、9月30日(火)までに、下記のWebページからご応募をお願い致します。(入力フォームは英語のみ)
http://krs.bz/scj/c?c=69&m=21728&v=188c09e6
問い合わせ先:日本学術会議事務局 国際業務担当室 03-3403-1949
佐藤・坂本・木之井・山田
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【14】第10回科学技術予測調査:大規模案アンケート ご協力のお願い
──────────────────────────────────
この調査は、科学技術イノベーション政策や研究開発戦略の立案・策定の議論に資することを目的として、文部科学省科学技術・学術政策研究所が実施している調査です。
本アンケートの回答者は、科学技術課題について専門的知識もしくは関心をお持ちの方を対象としております。周囲の方へのお声かけも是非お願いいたします。
アンケートにご協力いただけます場合は、以下のURLにアクセスして参加登録をお願いいたします。追って、調査事務局よりアンケートサイトのご案内を申し上げます。
参加登録サイト https://stfc.nistep.go.jp/dp/
※アンケートは、回答の収斂を図るため、デルファイ法(同一の質問を2回繰り返し実施)により行われます。
・1回目アンケートは、8月下旬(回答期限:9月上中旬頃まで)
・2回目アンケートは、9月上中旬(回答期限:9月下旬頃まで)
調査の詳細等はこちらから
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//geoFlash_img/gF20140902.pdf
【問合せ先(調査事務局)】 公益財団法人未来工学研究所 政策調査分析センター
担当:大竹、野呂、依田
E-mail:yosoku2014@ifeng.or.jp
Tel: 03-5245-1015(代)、Fax:03-5245-1062
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【15】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■富士山巡検受け付け終了
参加申し込み者が定員(25名)に達しましたので、参加者募集を締め切らせて頂きました。
■ショートコース『地すべり破砕帯の構造地質学』(第一報)
10月18日(土) 10:00〜16:40
場所:帝京平成大学 中野キャンパス
主催:日本地質学会関東支部,日本地すべり学会関東支部
後援:日本地質学会構造地質部会,日本地質学会応用地質部会
費用:2,000円(資料代) CPD単位:5.5ポイント
受講申込み先:日本地質学会関東支部(kanto@geosociety.jp)宛にメールにてお申込みください.
応募締め切り:10月7日(火)
詳しくは http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【16】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■「地球にわくわく小中学生自由研究コンテスト」 の作品募集
NPO法人地学オリンピック日本委員会では、「地球にわくわく小中学生自由研究コンテスト」 の作品(夏休み自由研究など)を募集しています。
題材が地学や環境に関することなら何でも結構です。
応募締切:10月31日(金)
詳細はこちらhttp://jeso.jp/
■地学オリンピックキャラクターデザインコンテスト
日本地質学会共催
募集締切:10月31日(金)
応募資格:中学生・高校生
http://jeso.jp/wp-content/uploads/2014/06/ieso_character_design_contest.pdf
■IGCP608 Asia-Pacific Cretaceous Ecosystems(白亜紀アジア−西太平洋生態系)
第2回国際シンポジウム
日本地質学会ほか 共催
9月4日(木)〜6日(土)(シンポジウム)
9月7日(日)〜10日(水)(巡検:銚子・那珂湊・双葉層群)
会場:早稲田大学 大隈講堂 小講堂
http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/
■2014年度日本地球化学会第61回年会
日本地質学会ほか 共催
9月16日(火)〜18日(木)
会場:富山大学五福キャンパス
http://www.geochem.jp/conf/2014/
■第58回粘土科学討論会
日本地質学会ほか 共催
9月24日(水)〜27日(土)
会場:福島市A・O・Z(アオウゼ)
http://www.cssj2.org/
■あいちサイエンスフェスティバル2014
9月27日(土)〜11月3日(月・祝)
会場:蒲郡市生命の海科学館など
※(共)惑星地球フォトコンテスト入賞作品展
https://aichi-science.jp/
■日本ジオパーク南アルプス大会(第5回日本ジオパーク全国大会)
日本地質学会ほか 後援
9月27日(土)〜9月30日(火)
場所:長野県伊那文化会館、伊那市生涯学習センター(いなっせ)
http://minamialps-mtl-geo.jp/
■東京地学協会 第287回地学クラブ講演会
10月3日(金) 16:00〜17:30
場所:地学会館講堂(麹町)
小原泰彦(海上保安庁)「海洋底科学と海底地形名」
http://www.geog.or.jp/
■2014地球環境保護 土壌・地下水浄化技術展
日本地質学会ほか 協賛
10月15日(水)〜17日(金)10:00〜17:00
会場:東京ビッグサイト 西ホール
http://www.sgrte.jp/sgr/
■山陰海岸ジオパーク国際学術会議「湯村会議」
日本地質学会 後援
10月25日(土)〜26日(日)
場所:新温泉町夢ホール(兵庫県美方郡新温泉町湯990-8)
http://sanin-geo.jp/modules/geopark/index.php/yumura14.html
■東京地学協会 秋季特別公開講演会「今時の恐竜事情」
10月25日(土)14:00〜17:00
場所:弘済会館(東京)
冨田幸光(国立科学博物館)「恐竜学の最近の進歩」(仮題)
東 洋一(福井県恐竜博物館特別館長)「日本の恐竜化石について」(仮題)
http://www.geog.or.jp/
■大型研究航海 計画作成ワークショップ
11月6日(木)〜7日(金)
場所:海洋研究開発機構 横浜研究所 三好記念講堂他
(9月19日まで 研究課題も募集)
http://www.jamstec.go.jp/maritec/e/large-scale_cruise/index.html
■国際シンポジウム“The International Symposium on Multidisciplinary Sciences on the Earth"「地球の学際科学」
11月18日(火)〜19日(水)
場所:東京大学本郷キャンパス 武田ホール(参加費無料.要申込)
http://thmat8.ess.sci.osaka-u.ac.jp/Meeting2014/
■第25回地質汚染調査浄化技術研修会 技術研修会
日本地質学会環境地質部会ほか 共催
11月21日(金)〜23日(日)
会場:NPO法人日本地質汚染審査機構本部ミーテング・ルーム・八千代市民会館
参加費:会員(地質学会員・社会地質学会員を含む)39,000円(学生:35,000円)
(CPD:22単位)
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
■第30回ゼオライト研究発表会
日本地質学会ほか 協賛
11月26日(水)〜27日(木)
場所:タワーホール船堀(東京都江戸川区船堀4-1-1)
予稿原稿締切:10月24日(金)
http://www.jaz-online.org/
■第24回環境地質学シンポジウム
日本地質学会ほか 共催
11月28日(金)〜29日(土)
場所:日本大学文理学部8号館1階レクチャーホール
発表登録申込締切:10月18日(土)まで
原稿登録締切:11月5日(水)必着
http://www.jspmug.org/
■東京地学協会国内見学会「榛名山ジオツアー・日本のポンペイを訪ねて」(1泊2日)
11月29日(土)〜30(日)
案内者:下司信夫・竹内圭史
http://www.geog.or.jp/
■東京地学協会 第288回地学クラブ講演会
12月19日(金) 16:00~17:30)
場所:アルカディア市ヶ谷
藤田勝代(深田地質研究所)「ジオ鉄マップとは? その事例研究」(仮題)
http://www.geog.or.jp/
■第4回学生のヒマラヤ野外実習ツアー
日本地質学会等推薦
2015 年3月上旬(4日頃)出発,出国から帰国まで15日間
参加募集対象:全国の地学,災害地質,自然環境等に関係する学科・専攻科の学生・大学院生を優先※学生の指導教員,関係企業の新人技術者や指導上司,及び高校生や中学・高校の理科教員,一般市民も受け入れます.
定員:20名
参加費:学生,大学院生は20 万円以内(暫定)
参加申込締切:2014年11月末日
詳細はこちら
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
2015年7月27日(月)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1-1)
http://inqua2015.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0133.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【17】公募情報・地学教員募集情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■ふじのくに地球環境史ミュージアム:職員の公募(研究員)(9/26)
■海洋研究開発機構:(研究員もしくは技術研究員)(10/20)
○海洋掘削科学研究開発センター
・掘削データ統合研究グループ ・沈み込み帯掘削研究グループ
○地震津波海域観測研究開発センター
・地震津波予測研究グループ
○海洋生命理工学研究開発センター
・生命機能研究グループ
○海底資源研究開発センター
・環境影響評価研究グループ ・地球生命工学研究グループ
■東京大学地震研究所:平成27年度客員教員の公募(10/31)
■九州大学大学院:理学研究院教員公募(10/31)
■大型研究航海 計画作成ワークショップ 研究課題の募集(9/19)
■東京大学地震研究所:平成27年度共同利用の公募(10/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
地質学の復権を念う
「地質学の復権を念う:GAC/MAC年会 in Fredericton, Canadaにて
楡井 久(地質汚染診断士・地層液流動化診断士)
図1
図2
大西洋に面するカナダのファンデイ湾にセントジョンズ川が注ぐ.遡るとカナダのニュー・ブルンスウイク州(総面積73,500km²,州人口は75万1,171人)の州都フィデリクトン(Fredericton)市がある.日本の一般的地図帳には地名も無い市であるが,「赤毛のアン」物語の発祥地に近い.河川・大地は,大陸氷河が削った氷河地形そのものである(図‐1).豊かな環境と,ゆったりした生活環境が羨ましくも感じる.また、寿司バーもあり Cool Japan はこんなところにまでここまでにも普及している.ただし,経営・店員は全て韓国人である.また,歴史的遺産も環境資源として生かす努力がなされている(図‐2).
ここで,カナダ地質学協会(Geological Association of Canada:GAC),カナダ鉱物学協会(Mineralogical Association of Canada:MAC),大西洋地球科学会(Atlantic Geoscience Society),UNB大学(University of New Brunswick)主催によるGAC/MAC年会が, 今年(20152014)の5月3日〜7日にかけて開催された.GAC/MAC年会は175回目のようである.この年会に国際地質科学連合(IUGS)環境科学研究委員会(GEM)の地質環境sessionも設けられた.IUGS-GEMの委員会も,UNB大学の地球科学部の会議室でおこなわれた(図‐3).日本からは,古野邦雄氏(Secretary, Japan of Branch, IUGS-GEM)と私が出席した.
帰り際に,Faculty & Staff 掲示版が目に留まる.この学部の前身は,地質学部(創立1922年)であるが,教授団は以下のようである.
図3
図4
水文地質学(Hydrogeology)/環境地球化学(Environmental Geochemistry)・応用氷河地質学/地質工学(Engineering Geology)・応用地球物理学(Applied Geophysic)/岩石力学(Rock Physics)・堆積学(Sedimentology)/石油地質学(Petroleum Geology)・経済地質学(Economic Geology)・変成岩岩石学(Metamorphic petrology)/地質編年学(Geochronology)・古生物学(Palaeontology)/堆積学(Sedimentology)・火成山岩岩石学(Igneous Petrology)/ 火山学(Volcanology)・隕石衝突地質学(Impact Geology)/衝突変成学(Shock Metamorphism)・水成地球化学(Aqueous Geochemistry)・構造地質学(Structural Geology)/電子顕微鏡技術(Electron Microscopy)・構造地質学(Structural Geology)/テクトニクス(Tectonics).
教授団による教授・研究は地域的であり国際的な内容である.さらに調査研究Staffによる協力体制からも,それが良く理解できる(図‐4).地質学から地球科学へのパラダイムシフトも地域性を熟慮したシフトである.
各国の地質学に対する社会的背景が変化し,国際的にも地質学,地球科学,地球環境学,地球・惑星学といったそれぞれの学科・学部名を見るが,わが国でも地質学科や地質鉱物学科も他の体系も含め地質学,地球科学,地球環境学,地球・惑星学といったそれぞれの学科・学部名に変わったが,はたして日本列島や日本の人間活動をも考慮した教授・研究内容のシフトであったろうか.我が国の国状を理解したなら,地質環境学・人工地質学・地質汚染科学・水文地質学・医療地質学・法地質学などの教授・研究内容も正座してなければならない.むしろ,このような内容は,工学系が占拠し,負の技術体系を形成してきているとも思われる.抑圧移譲にもみられる.その負の技術体系が,福島第1原発での放射性物質汚染地下水漏洩の阻止を難儀させているとも思われる.国外から見たらみっともない.我が国には,もっとまともな技術体系がある.今こそ地質学の復権の時期であり,そうなければならない.
(2014.9.8)
geo-flash No.272 [鹿児島大会]2日目! 写真満載
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.272 2014/9/14 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2日目の様子
【2】鹿児島大会初日の様子(写真満載)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】県の石 「鹿児島の石」発表!
──────────────────────────────────
日本地質学会は全国各都道府県の「県の石」の認定を進めています.
鹿児島大会を記念して「鹿児島の石」が先行して決定しました!
■ 鹿児島県の石:「シラス(主に入戸火砕流堆積物)」
■ 鹿児島県の鉱物:「菱刈金山の金鉱石(自然金)」
■ 鹿児島県の化石:「甑島・獅子島の白亜紀動物化石群」
同時にプレスリリースも行いました.資料はこちらにあります.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】鹿児島大会2日目の様子
──────────────────────────────────
日本地質学会第121年学術大会(鹿児島大会)の大会二日目が, 本日(9/14)開催されました.少し火山灰が降っており,鹿児島で の大会であることが実感される日となりました. 午前中は,8つの会場で各学術セッションが行われました.お昼に は,昼食を食べながら打合せや講演等を行うランチョンが6件行わ れました(岩石部会,地学教育委員会,海洋地質部会,構造地質部 会若手の研究発表会,地質学雑誌編集委員会,現行地質過程部会). また,海外からの来賓を交えた昼食会も催されました. ポスター発表会場では「小さなEarth Scientistのつどい」が開催さ れ,高校生による地学研究の発表が行われました.研究者からの質 問にも元気よく答える姿がみられ,この中から未来の地球科学者が きっとでてくることでしょう. 午後も引き続き,8つの会場で各学術セッションが行われました. 14:30からは「若手会員のための業界研究サポート」が開催さ れ,地質系企業に興味のある学生・大学院生および指導されている 教員の方々を対象として企業からの説明ほか交流の場が設けられま した.18時からは,7件の夜間小集会が予定されております.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】鹿児島大会初日の写真(表彰式,地質情報展,懇親会)
──────────────────────────────────
■ 地質情報展開幕!
鹿児島市中央公民館
開会式
テープカット
フォトコンの展示
超巨大地質図
■ 表彰式が開かれました。
鹿児島大学会場
ポスター会場も盛況
臨時総会
市民講演会
市民講演会
表彰式の開式
国際協定の来賓挨拶
50年会員顕彰
日本地質学会賞
国際賞
小澤儀明賞
Island Arc賞
論文賞
小藤文次郎賞
研究奨励賞
学会表彰
■懇親会!
geo-flash No.273 [鹿児島大会]3日目! 写真満載
★★目次 ★★
【1】鹿児島大会3日目の様子
【2】2日目&3日目の写真
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】鹿児島大会3日目の様子
──────────────────────────────────
怒涛の3日間もあっという間に過ぎ去り,大会最終日となりました.
地元新聞やテレビをはじめ全国紙でも,地質学会・情報展の開催が報道されました.
そして今日は一般公開シンポジウム「九州が大陸だった頃の生物と環境」が開催されました.
なんとなく雨がちな3日間でしたが,昼も夜もノンストップの白熱の議論で,その勢いがつうじたのか,明日からの巡検は秋晴れのスタートです.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】鹿児島大会2日目と3日目の写真
──────────────────────────────────
鹿児島大会2日目と3日目の国際シンポジウム,ポスター会場,国際学術交流,小さなEarth Scientistの集い,若手会員のための業界研究サポート,などの写真はこちらにあります.
大会2日目
海外からの来賓相次ぐ
台湾経済部中央地質調査の訪問
国際来賓の方と会食
国際来賓の方と会食
大盛況なポスター会場
小さなEarth Scientistsの集い
小さなEarth Scientistsの集い
国際津波シンポジウム
若手会員のための業界研究サポート
高校生らの表彰式
今日のポスター賞
大会3日目の写真
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.271 [鹿児島大会臨時号]大会初日
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.271 2014/9/13 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
日本地質学会第121年学術大会(鹿児島大会)の初日が本日9/13開催されました.あいにくの雨模様となりましたが,全ての初日の行事が成功裡に実施されました.
午前中は,7つの会場で各学術セッションが行われました.お昼休みを挟み,13:30〜14:50はポスター発表のコアタイムで,あちらこちらで活 発な議論が交わされていました.14:30〜16:00は第1会場にて市民講演会「桜島と諏訪之瀬島の大噴火と火山災害」が行われ,大変盛況でした.
鹿児島市中央公民館では,地質情報展2014かごしま「火山がおりなす自然の恵み」が開催され,12:30からの開会式で,井龍会長が挨拶をされま した.また,昨日「鹿児島県の石」に決まったシラス(主に入戸火砕流堆積物)も展示されておりました.明後日(9/15)まで開催しておりますので,ぜひ 会場まで足をお運びください.
15時からは,第2会場にて会員顕彰式・各賞授与式・受賞記念講演が行われました.個別にご紹介することはできませんが,受賞された方は皆様晴れがましい表情で,記念講演も大変興味深いお話が続きました.改めて,受賞された方々に敬意を表します.
18:30からは,鹿児島大学郡元キャンパス内の学習交流プラザにて懇親会が開催されました.鹿児島LOCの方々のご尽力により,大変豪勢な懇親会 となりました.鹿児島の数々の郷土料理が並び,特設コーナーでは,黒豚のしゃぶしゃぶや,奄美の鶏飯も振る舞われました.大変美味でした!また何といって も圧巻だったのが十数種類ほども揃えられた焼酎の数々です.こちらの飲み方はお湯割りが基本で,お湯を先に入れるのがルールとのことです(お湯の方が密度 が低く,後から入れる焼酎と混ざり易いという科学的な解説付き!).参加者の皆様は,美味しい料理とお酒に舌鼓を打ちながら,また明日からの学術大会への 英気を養いました.
geo-flash No.270 [鹿児島大会臨時号]9月13日開催!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.270 2014/9/12 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
日本地質学会第121年学術大会(鹿児島大会)がいよいよ明日(9月13日)開催されます.
事務局や役員は,前日から現地入りし,万全の準備に余念がございません.
初日には,会員顕彰式・各賞表彰式・受賞記念講演が予定されておりますので,ぜひ多くの皆様のご参加をお待ちしております.
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0001.html
鹿児島大会を,盛り上げて行きましょう!!
geo-flash No.274 鹿児島大会 終了しました!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.274 2014/9/16 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】鹿児島大会 終了しました!
【2】「地震に関する総合的な調査観測計画...」の意見書に対する回答が公開されました
【3】コラム:地質学の復権を念う:GAC/MAC年会 in Fredericton, Canadaにて
【4】「県の石」募集のお知らせ
【5】2014年度秋季地質調査研修:参加者募集
【6】第7回日本地学オリンピック(第9回国際地学オリンピック2015ロシア大会日本代表選抜)参加者募集
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】鹿児島大会 終了しました!
─────────────────────────────────
今年もたくさんの方々にご参加いただき,盛会のうち鹿児島大会は終了いたしました。大会の報告は,ニュース誌11月号に掲載予定です。
来年は,長野でお会いしましう。
★第122年学術大会(長野大会)
日程:2015年9月11日(金)〜13日(日)
会場:信州大学 ほか
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】「地震に関する総合的な調査観測計画について〜東日本大震災を踏まえて〜案」の意見書に対する回答が公開されました
─────────────────────────────────
先般,「地震に関する総合的な調査観測計画〜東日本大震災を踏まえて〜」に関する意見募集に対して,地質学会としての意見を表明しました.
この度,回答が公開されましたので,御覧ください.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/engineer/content0036.html#20140908
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】コラム:地質学の復権を念う:GAC/MAC年会 in Fredericton, Canadaにて
─────────────────────────────────
楡井 久(地質汚染診断士・地層液流動化診断士)
大西洋に面するカナダのファンデイ湾にセントジョンズ川が注ぐ.遡るとカナダのニュー・ブルンスウイク州(総面積73,500km²,州人口は75万1,171人)の州都フィデリクトン(Fredericton)市がある.日本の一般的地図帳には地名も無い市であるが,「赤毛のアン」物語の発祥地に近い.河川・大地は,大陸氷河が削った氷河地形そのものである.豊かな環境と,ゆったりした生活環境が羨ましくも感じる.また、寿司バーもあり Cool Japan はこんなところにまでここまでにも普及している. 、、、、、
続きはこちらから
http://www.geosociety.jp/faq/content0529.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】「県の石」募集のお知らせ
─────────────────────────────────
日本では古来より郷土に産する岩石,鉱物,化石を愛し,またそれらを利用しながら発展してきました.また,日本列島はプレートの沈み込み帯に位置し,深海の堆積物から火山や大陸地殻まで多様で幅広い時代の岩石から成り立っています.これほど多くの岩石に彩られている国は世界でも多くはありません.私たちが生活する大地の歴史と成り立ちを知り,郷土の地質を愛する心を再認識するために,日本地質学会では「県の石」の認定を企画しました.日本地質学会に所属する専門家のみならず,全国都道府県へのアンケート調査,そして市民の皆様の推薦を参考に各都道府県の「県の石」を認定して参ります.
応募締切:10月31日まで(鹿児島県のみ受付終了)
詳しくはこちらから.
http://www.geosociety.jp/name/content0121.html
★鹿児島県先行決定!!
結果はこちら
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//press/2014/140912_kennoisihi_kagoshima.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2014年度秋季地質調査研修:参加者募集
─────────────────────────────────
地質調査法の基本技術の修得をめざすとともに,それをベースに得られた過去の調査や研究の成果についても学びます.地質調査の経験のない方でも,地質調査法の基本を体で習得することを目指します.
11月25日(火)〜29日(土)4泊5日
場所:千葉県君津市及びその周辺地域(房総半島中部の清澄山系とその周辺 )
募集人数:6名. 参加費:12万円 (CPD:40単位)
申込締切:10月17日(金)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/engineer/content0035.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】第7回日本地学オリンピック(第9回国際地学オリンピック2015ロシア大会日本代表選抜)参加者募集
──────────────────────────────────
主催:NPO法人地学オリンピック日本委員会
参加資格:中学生・高校生 参加費:無料
※ただし,第9回国際地学オリンピック・ロシア大会の代表選抜を兼ねているため,本選(国内二次選抜)に進めるのは中学3年生〜高校2年生の生徒のみです.他学年で本選選抜者と同等の成績を得た生徒には成績証明書を発行します.成績優秀者はAO入試の出願資格が得られます.
募集期間:2014年9月1日(月)〜11月15日(土)
(ウェブエントリーは24:00まで,郵送は11月15日消印有効)
応募方法:ウェブエントリーまたは郵送(団体参加は,申し込み後も締切期日まで参加者の加除訂正が可能です.また,申込教員へは生徒の成績開示となります.)
ウェブエントリー,郵送用応募フォーム
https://contest-kyotsu.com/entry/
その他募集要項等、詳しくはこちら
http://jeso.jp/wp-content/uploads/2014/08/7thjeso_information.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
─────────────────────────────────
[関東支部]
■ショートコース『地すべり破砕帯の構造地質学』(第一報)
10月18日(土) 10:00〜16:40
場所:帝京平成大学 中野キャンパス
主催:日本地質学会関東支部,日本地すべり学会関東支部
後援:日本地質学会構造地質部会,日本地質学会応用地質部会
費用:2,000円(資料代) CPD単位:5.5ポイント
受講申込み先:日本地質学会関東支部(kanto@geosociety.jp)宛にメールにてお申込みください.
応募締め切り:10月7日(火)
それぞれ、詳しくは http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
─────────────────────────────────
■地学オリンピックキャラクターデザインコンテスト
日本地質学会共催
募集締切:10月31日(金)
応募資格:中学生・高校生
http://jeso.jp/wp-content/uploads/2014/06/ieso_character_design_contest.pdf
■2014年度日本地球化学会第61回年会
日本地質学会ほか 共催
9月16日(火)〜18日(木)
会場:富山大学五福キャンパス
http://www.geochem.jp/conf/2014/
■第58回粘土科学討論会
日本地質学会ほか 共催
9月24日(水)〜27日(土)
会場:福島市A・O・Z(アオウゼ)
http://www.cssj2.org/
■第262回生存圏シンポジウム
9月27日(土)〜28日(日)
場所:京都大学宇治キャンパス内「木質ホール」
http://www.jpgu.org/event/public.php
http://www.jpgu.org/info/sympo_temp/20140928_seizonken.pdf
■あいちサイエンスフェスティバル2014
9月27日(土)〜11月3日(月・祝)
会場:蒲郡市生命の海科学館など
※(共)惑星地球フォトコンテスト入賞作品展
https://aichi-science.jp/
■日本ジオパーク南アルプス大会(第5回日本ジオパーク全国大会)
日本地質学会ほか 後援
9月27日(土)〜9月30日(火)
場所:長野県伊那文化会館、伊那市生涯学習センター(いなっせ)
http://minamialps-mtl-geo.jp/
■筑波大学大学院生命環境科学研究科説明会
10月6日(月)18:00〜20:00(受付17:20)
場所:筑波大学東京キャンパス文京校舎 134講義室
http://www.life.tsukuba.ac.jp/entrance/setsumeikai_20141006.pdf
■2014地球環境保護 土壌・地下水浄化技術展
日本地質学会ほか 協賛
10月15日(水)〜17日(金)10:00〜17:00
会場:東京ビッグサイト 西ホール
http://www.sgrte.jp/sgr/
■山陰海岸ジオパーク国際学術会議「湯村会議」
日本地質学会 後援
10月25日(土)〜26日(日)
場所:新温泉町夢ホール(兵庫県美方郡新温泉町湯990-8)
http://sanin-geo.jp/modules/geopark/index.php/yumura14.html
■第25回地質汚染調査浄化技術研修会 技術研修会
日本地質学会環境地質部会ほか 共催
11月21日(金)〜23日(日)
会場:NPO法人日本地質汚染審査機構本部ミーテング・ルーム・八千代市民会館
参加費:会員(地質学会員・社会地質学会員を含む)39,000円(学生:35,000円)
(CPD:22単位)
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
■第30回ゼオライト研究発表会
日本地質学会ほか 協賛
11月26日(水)〜27日(木)
場所:タワーホール船堀(東京都江戸川区船堀4-1-1)
予稿原稿締切:10月24日(金)
http://www.jaz-online.org/
■第24回環境地質学シンポジウム
日本地質学会ほか 共催
11月28日(金)〜29日(土)
場所:日本大学文理学部8号館1階レクチャーホール
発表登録申込締切:10月18日(土)まで
原稿登録締切:11月5日(水)必着
http://www.jspmug.org/
■第4回学生のヒマラヤ野外実習ツアー
日本地質学会等推薦
2015 年3月上旬(4日頃)出発,出国から帰国まで15日間
参加募集対象:全国の地学,災害地質,自然環境等に関係する学科・専攻科の学生・大学院生を優先※学生の指導教員,関係企業の新人技術者や指導上司,及び高校生や中学・高校の理科教員,一般市民も受け入れます.
定員:20名
参加費:学生,大学院生は20 万円以内(暫定)
参加申込締切:2014年11月末日
詳細はこちら
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
2015年7月27日(月)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1-1)
http://inqua2015.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0133.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・地学教員募集情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■東北大学大学院:理学研究科地学専攻教授の公募(11/14)
■海洋研究開発機構:国際ポストドクトラル研究員公募(11/5)
■千葉県:職員採用選考考査(地質職)(9/25)
■茨城大学:理学部地球環境科学領域教員公募[防災科学JABEE プログラム](11/10)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.280 日本地質学会各賞候補者募集中!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.280 2014/11/18 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2015年度一般社団法人日本地質学会各賞候補者募集について
【2】2015年度会費払込のお知らせ—割引会費の申請は忘れずに!
【3】学会ホームページ会員情報システム一時利用停止のお知らせ
【4】第6回惑星地球フォトコンテスト:応募受付開始しました
【5】JISに定められた地質年代の日本語表記
【6】鹿児島学術大会での国際交流
【7】2014年7月9日南木曽,8月6日岩国,8月17日福知山・丹波における土砂災害
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2015年度一般社団法人日本地質学会各賞候補者募集について
─────────────────────────────────
日本地質学会では今年も運営規則第16条および各賞選考規則にしたがい,
各賞の候補者を募集いたします.
期日厳守にて,たくさんのご応募をお待ちしております.
応募締切:2014年12月1日(月)必着
詳しくは、http://www.geosociety.jp/members/content0084.html
○会員番号・パスワードによるログインが必要です。
ログインの方法はこちら。
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2015年度会費払込のお知らせ—割引会費の申請は忘れずに!
─────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年度の会費を前納ください
ますよう,お願いいたします.
■ 2015年度分会費の引き落とし日:12月24日(水)
請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますので
ご了承ください.
■ 自動引き落とし以外のかた(お振り込み)
12月中旬頃までに請求書兼郵便振替用紙をお送りします.地質学会の
会費は前納制ですので,お手元に届きましたら折り返しご送金ください.
■ 割引会費申請(院生・学部学生):最終締切 2015年3月31日(火)
次年度も割引会費を希望のかたは,忘れずにご提出ください(締切厳守).
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/outline/content0135.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】学会ホームページ会員情報システム一時利用停止のお知らせ
─────────────────────────────────
現在進行中の,地質学会ホームページのシステムリニューアル作業に伴い,
会員情報システムが一時ご利用頂けません.利用停止期間は,下記の通り
です.
システム利用停止期間:2014年11月17日(月)〜19日(水)
(終了予定は,作業状況によって前後する場合があります)
停止期間中は,住所変更,専門部会登録等の会員情報の更新はできません
(会員ページへのログインは可能です).会員情報の更新は,システム停
止期間後に行って頂くか,学会事務局まで直接メール等でご連絡をお願い
致します.
会員の皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが,ご理解とご協力の程よろ
しくお願い申し上げます.
(日本地質学会広報委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第6回惑星地球フォトコンテスト:応募受付開始しました
─────────────────────────────────
今年も惑星地球フォトコンテストの応募作品の受付を開始いたしました.
今回より「スマホ賞」を設けました.画像を添付していただくだけで,携
帯やスマホからも手軽にご応募いただけます.皆様の力作を是非ご応募く
ださい.お待ちしています.
応募締切:2015年2月16日(月)17時(郵送の場合は同日必着)
賞:最優秀賞1点(賞金5万円),優秀賞1点(賞金2万円),
スマホ賞(賞金5千円)...など
詳しくは,http://photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】JISに定められた地質年代の日本語表記
─────────────────────────────────
(JIS・標準担当理事:中澤 努)
皆さんは日本語の論文や報告書等で地質年代を記述する場合,どのように
表記していますか.国際的な地質年代単元名は,国際地質科学連合(IUGS)
の国際層序委員会(ICS)よりInternationalChronostratigraphic Chartとして
提示され,“The Geologic Time Scale 2012”(Gradstein et al., eds., 2012a, b)
で解説されていることはご存じの方も多いかと思います.
International Chronostratigraphic Chartの地質年代は言うまでもないですが
もともと英語で表記されています.このような地質年代を和文の報告書等に
日本語で記述する場合,これまでは,どのように表記すればよいか困る場合
もありました.、、、
続きを読む
http://www.geosociety.jp/name/content0126.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】鹿児島学術大会での国際交流
─────────────────────────────────
(国際交流担当理事:Wallis, Simon)
今回の大会の特徴の一つは国際交流にあったと言っても過言ではありませ
ん.学術交流協定を結んだ海外の地質学会の代表者らを招待し,また,国
際シンポジウムが開催されました.
海外学協会からの代表者の招待
学会活動の更なる発展を考える上で各国の地質学会の代表者の訪問は重
要と執行部は考えています.訪問の機会を最大限に活かすために,執行部
同士の話あいのみならず研究の面でも発表する機会を設け,折角集まった
訪問者と一般会員との交流を促すために訪問者の研究分野に合致したセッ
ションでの講演を実施しました.、、、
続きを読む
http://www.geosociety.jp/science/content0064.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】2014年7月9日南木曽,8月6日岩国,8月17日福知山・丹波における土砂災害
─────────────────────────────────
地質災害委員会では,最近の広島土砂災害,御嶽山噴火などをはじめ,地
質災害の関連情報をより多くより広く発信するため,学術大会緊急展示で
のポスター内容を発表者の方々にお願いして,学会ニュース誌・HPへ掲載
させて頂くことにしました.
地質学の防災への貢献という観点から今後もニュース誌や地質学雑誌の報
告に原稿をお寄せ頂ければと思います.
(地質災害委員会委員長 斎藤 眞)
記事はこちらから
http://www.geosociety.jp/hazard/content0085.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
─────────────────────────────────
[関東支部 ]
■功労賞募集
関東支部では,支部の顕彰制度に基づき2014年度も支部活動や地質学を通
して社会貢献された個人・団体を関東支部として顕彰いたします.つきま
しては,下記の要領で支部会員からの推薦を募集します.
対象者:支部活動や地質学を通して広く社会貢献をされた関東支部内に在
住の個人・団体
*社会貢献や活動の評価においては,必ずしも学問的な成果を問うもので
はありません.
公募期間:2014年12月10日〜2015年1月10日
選考期間:2015年 1月11日〜2015年1月31日
関東支部功労賞審査委員会(委員長:伊藤谷生 前支部長)を設置
審査結果報告:NEWS誌、関東支部総会
推薦方法:対象者氏名,推薦者氏名,推薦理由(400字程度)を記入の上,
関東支部功労賞推薦としてメールもしくはFAXにて下記へお送り下さい.
推薦受付:神奈川県立生命の星・地球博物館 笠間友博
〒250-0031 小田原市入生田499
E-mail:kasama@nh.kanagawa-museum.jp ,FAX:0465-23-8846
[西日本支部]
■平成26年度総会・第166回例会
2015年2月21日(土)[20日:幹事会]
場所:山口大学,吉田キャンパス,大学会館
講演申込締切:2015年2月4日(水)17時
*総会へ欠席の方は,委任状をお送り下さい。
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
(訂正)前号で西日本支部総会開催日の曜日が間違っておりました。
正しくは上記の通りです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第25回地質汚染調査浄化技術研修会 技術研修会
日本地質学会環境地質部会ほか 共催
11月21日(金)〜23日(日)
会場:NPO法人日本地質汚染審査機構本部ミーテング・ルーム・八千代市
民会館
参加費:会員(地質学会員・社会地質学会員を含む)39,000円(学生:35,000円)
(CPD:22単位)
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
■東京都葛西臨海水族園開園25周年記念講演会
子どもと生きもの-子どもと生きものをつなぐために動物園水族館ができ
ること-
11月24日(月・祝)13:00〜16:15
場所:東京都葛西臨海水族園 本館2階レクチャールーム
対象:高校生以上
定員:80名(定員になり次第締切)
応募締切:11月20日(木)郵送必着・メール送信分有効
http://www.tokyo-zoo.net/topic/topics_detail?kind=event&inst=kasai&link_num=22549
■第30回ゼオライト研究発表会
日本地質学会ほか 協賛
11月26日(水)〜27日(木)
場所:タワーホール船堀(江戸川区船堀4-1-1)
http://www.jaz-online.org/
■第24回環境地質学シンポジウム
日本地質学会ほか 共催
11月28日(金)〜29日(土)
場所:日本大学文理学部8号館1階レクチャーホール
http://www.jspmug.org/
■平成26年度(第13回) 産総研・地圏資源環境研究部門研究成果報告会
「進化する地圏研究 −第三期の成果と第四期への展開−」
12月9日(火)13:30〜17:00
場所:秋葉原ダイビルコンベンションホール(千代田区外神田1-18-13)
申込締切:11月25日(火)
http://green.aist.go.jp/ja/blog/news_jp/20841.html
■第162回深田研談話会「日本の地学教育と地学オリンピックの意義」
12月12日(金)15:00〜17:00[14:30開場]
会場:深田地質研究所 研修ホール(文京区本駒込2-13-12)
定員:80名 参加費無料
申込締切:12月10日(水)
http://www.fgi.or.jp
■バイオミネラリゼーションと石灰化 -遺伝子から地球環境まで-
12月12日(金)〜13日(土)
場所:東京大学大気海洋研究所講堂
http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/aori_news/meeting/2014/20141212.html
■Project A 2015 in Korea
日本地質学会ほか 後援
2015年3月4日(水)〜8日(日)
4日オープニング、5日セッション、6〜8日巡検
会場:韓国(大田広域市)
アブストラクト締切:2015年1月23日(金)
http://archean.jp/
■第4回学生のヒマラヤ野外実習ツアー
日本地質学会等推薦
2015 年3月上旬(4日頃)出発,出国から帰国まで15日間
参加募集対象:全国の地学,災害地質,自然環境等に関係する学科・専攻
科の学生
・大学院生を優先※学生の指導教員,関係企業の新人技術者や指導上司,
及び高校生や中学・高校の理科教員,一般市民も受け入れます.
定員:20名
参加費:学生,大学院生は20 万円以内(暫定)
参加申込締切:2014年11月末日
詳細はこちら
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
■第13回微量元素の生物地球化学に関する国際会議
13th International Conference on the Biogeochemistry of Trace
Elements, ICOBTE 2015 FUKUOKA
日本地質学会 後援
2015年7月12日(日)〜16日(木)
場所:福岡国際会議場
要旨締切:2014年12月18日(木)
http://www.icobte2015.org/index.html
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
2015年7月27日(月)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1-1)
発表申込締切:2014年12月20日(土)
早期参加登録締切:2015年2月28日(土)
http://inqua2015.jp/
■第10回アジア地域応用地質学シンポジウム
日本地質学会 後援
研究発表会:2015年9月24日(木)〜25日(金)
シンポジウム:2015年9月26日(土)〜27日(日)[その後巡検予定あり]
場所:京都大学宇治黄檗プラザ
講演要旨締切:2014年11月末日
※ただし日本語の要旨を投稿すれば、正式な英文要旨は12月以降も受付
氏名・所属・Tel・E-mail・発表タイトル・選択するトピックス・要旨
(800字以内)を記載の上、2015アジア地域応用地質学シンポ事務局
(office@2015ars.com)へメールにて投稿。
http://2015ars.com/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0133.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■海洋研究海洋機構:職員公募
・地球内部物質循環研究分野(研究員もしくは技術研究員)(11/28)
・地震津波海域観測研究開発センター海底地質・地球物理観測研究グルー
プ(ポストドクトラル研究員)(11/28)
・海洋研究海洋機構:地震津波海域観測研究開発センター地震津波予測研
究グループ(ポストドクトラル研究員)(12/5)
■北海道大学大学院理学研究院自然史科学部門地球惑星システム科学分野講
師公募(専攻:宇宙化学)(12/17)
■第56回藤原賞受賞候補者推薦(2015/1/31 学会締切:1/9)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
geo-flash No.275 (臨時)御嶽山の噴火 ほか
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.275 2014/9/30 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】御嶽山の噴火
【2】国際地学オリンピック:世界トップに
【3】世界ジオパークに阿蘇が
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】御嶽山の噴火
─────────────────────────────────
報道にありますように長野県と岐阜県にまたがる御嶽山が噴火しました.
これに関する地質情報のリンクです.
・アジア航測(株)による9月29日の航空写真.
http://www.ajiko.co.jp/article/detail/ID5063VS69D/riyou
・産総研地質調査総合センター
https://www.gsj.jp/hazards/volcano/ontake2014/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】国際地学オリンピック:世界トップに
─────────────────────────────────
第8回国際地学オリンピックがスペインのサンタンデールで開催され,日本選手団は,金メダル3個、銅メダル1個の世界トップの好成績を収めました。これは過去最高の好成績です。日本代表の宇野慎介さん(兵庫県),西山 学さん(東京都),野村 建斗さん(東京都),杉 昌樹(兵庫県),おめでとうございました.
地学オリンピック委員会
http://jeso.jp/wp-content/uploads/2014/09/8thieso_result.pdf
文科省
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/09/1352272.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】世界ジオパークに阿蘇が
─────────────────────────────────
世界ジオパークネットワーク(GNN)は,9月23日に阿蘇ジオパークを世界ジオパークとして認定しました.これで国内7つ目の世界ジオパークになりました.
GNN
http://www.globalgeopark.org/News/News/8882.htm
阿蘇ジオパーク
http://aso-geopark.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.276 日本地質学会各賞候補者募集!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.276 2014/10/7 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2015年度一般社団法人日本地質学会各賞候補者募集について
【2】割引会費申請の受付開始!—2015年度会費払込のお知らせ—
【3】「研究活動における不正行為...」案の回答公開
【4】「県の石」募集のお知らせ
【5】2014年度秋季地質調査研修:参加者募集締切
【6】防災・減災に関する国際研究のための東京会議ポスター発表のアブストラクト締切延期及びプログラムのお知らせ
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2015年度一般社団法人日本地質学会各賞候補者募集について
──────────────────────────────────
日本地質学会では今年も運営規則第16条および各賞選考規則にしたがい,各賞の候補者を募集いたします.
期日厳守にて,たくさんのご応募をお待ちしております.
応募締切:12月1日(月)必着
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0084.html
○会員番号・パスワードによるログインが必要です。
ログインの方法はこちら。
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】割引会費申請の受付開始!—2015年度会費払込のお知らせ—
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,学部学生・院生(研究生)については,本人の申請によりそれぞれ割引会費が適用されます.
つきましては,次年度(2015年度)の会費についての申請受付を開始いたしますので,該当される会員は規定の書式にて申請書を提出してください(郵送に限る).
また,12月中旬頃までに次年分の会費請求書(郵便振替用紙)をお送りします.地質学会の会費は前納制ですので,2015年3月までに折り返しご送金下さいますようお願いいたします.指定の金融機関口座からの自動引き落としをご利用の場合は12月24日(水)が引落日です.
■割引会費申請(院生・学部学生)請求書発行前締切:11月17日(月)
とくに自動引落を利用の学生・院生のかたはこの期日までにご提出下さい.
■新規登録,引落口座変更の振替依頼書提出締切日:11月10日(月)必着
次年度会費の自動引落からご利用希望の場合は,11月10日(月)までに必ず預金口座振替依頼書をご提出下さい.
■2015年度分会費の引き落とし日:12月24日(水)
請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下さい.
■自動引き落とし以外のかた(お振り込み)
12月中旬頃までに請求書兼郵便振替用紙をお送りいたします.
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/outline/content0135.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」案の回答公開
──────────────────────────────────
「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」案の意見募集に対する回答が公開されました。ご覧下さい。
詳しくは,http://www.geosociety.jp/engineer/content0036.html#20140922
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】「県の石」募集のお知らせ
──────────────────────────────────
日本では古来より郷土に産する岩石,鉱物,化石を愛し,またそれらを利用しながら発展してきました.また,日本列島はプレートの沈み込み帯に位置し,深海の堆積物から火山や大陸地殻まで多様で幅広い時代の岩石から成り立っています.これほど多くの岩石に彩られている国は世界でも多くはありません.私たちが生活する大地の歴史と成り立ちを知り,郷土の地質を愛する心を再認識するために,日本地質学会では「県の石」の認定を企画しました.日本地質学会に所属する専門家のみならず,全国都道府県へのアンケート調査,そして市民の皆様の推薦を参考に各都道府県の「県の石」を認定して参ります.
応募締切:10月31日まで(鹿児島県のみ受付終了)
詳しくはこちらから.
http://www.geosociety.jp/name/content0121.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2014年度秋季地質調査研修:参加者募集締切
──────────────────────────────────
秋季地質調査研修は,定員に達しましたので受付を締め切りました.
キャンセル待ちをご希望の方は,学会事務局[main@geosociety.jp]へご連絡ください.
11月25日(火)〜29日(土)4泊5日
場所:千葉県君津市及びその周辺地域(房総半島中部の清澄山系とその周辺 )
募集人数:6名. 参加費:12万円 (CPD:40単位)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/engineer/content0035.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】防災・減災に関する国際研究のための東京会議ポスター発表のアブストラクト締切延期及びプログラムのお知らせ
──────────────────────────────────
geo-Flash No.269でお知らせいたしました、『防災・減災に関する国際研究のための東京会議』のアブストラクト締切が延長されました。
http://www.geosociety.jp/faq/content0528.html#13
ポスター発表アブストラクト締切:10月15日(水)
2015年1月14日(水)〜16日(金)
会場:東京大学 伊藤国際学術研究センター伊藤謝恩ホール
(東京都文京区本郷7-1-3)
定員:500名 参加費:無料(ただし懇親会は参加費有料)
会議の趣旨等、詳細はこちら
http://monsoon.t.u-tokyo.ac.jp/AWCI/TokyoConf/jp/introduction.htm
プログラムはこちらから。
http://monsoon.t.u-tokyo.ac.jp/AWCI/TokyoConf/jp/agenda.htm
[お問い合わせ先]
防災・減災に関する国際研究のための東京会議事務局東京会議事務局
電話:03-5841-6132(東京大学事務局)
03-3403-1949(日本学術会議事務局)
E-mail: tokyo.conf@hydra.t.u-tokyo.ac.jp(共通)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■ミニ巡検シリーズ「西伊豆巡検」
11月8日(土)〜9日(日)
参加費:25,000円(宿泊費,レンタカー代,保険料など).昼食代は別.
案内者:狩野謙一・鈴木雄介・伊藤谷生
見どころ:弁天島(白浜層群浅海性堆積物の堆積構造),入間千畳敷(未固結堆積物への貫入構造),堂ヶ島(堆積構造,火山性高温土石流堆積物,貫入と地質構造形成との関係),室岩洞(伊豆石採石場跡地),一色(仁科層群の枕状溶岩)など.
定員:10名,先着順.
申込締切:10月23日(木)
詳しくは http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】
──────────────────────────────────
■地学オリンピックキャラクターデザインコンテスト
日本地質学会共催
募集締切:10月31日(金)
応募資格:中学生・高校生
http://jeso.jp/wp-content/uploads/2014/06/ieso_character_design_contest.pdf
■あいちサイエンスフェスティバル2014
9月27日(土)〜11月3日(月・祝)
会場:蒲郡市生命の海科学館など
※(共)惑星地球フォトコンテスト入賞作品展
https://aichi-science.jp/
■2014地球環境保護 土壌・地下水浄化技術展
日本地質学会ほか 協賛
10月15日(水)〜17日(金)10:00〜17:00
会場:東京ビッグサイト 西ホール
http://www.sgrte.jp/sgr/
■山陰海岸ジオパーク国際学術会議「湯村会議」
日本地質学会 後援
10月25日(土)〜26日(日)
場所:新温泉町夢ホール(兵庫県美方郡新温泉町湯990-8)
http://sanin-geo.jp/modules/geopark/index.php/yumura14.html
■日本応用地質学会:現場研修会・講習会
【伊豆大島土砂災害より学ぶ:土砂災害の要因と対策】
11月8日(土)〜10日(月)
講 師:井口 隆氏(防災科学技術研究所),千葉達朗氏(日本大学)
募集数:40名程度
締 切:10月17日(金)
参加費:¥35,000(11/8集合場所にて徴収)
申込先:〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-3-14
日本応用地質学会事務局 TEL:03-3259-8232,
E-mail: office@jseg.or.jp
http://www.jseg.or.jp/00-main/pdf/140930_kensyu_oshima.pdf
■平成26年度 東濃地科学センター
○ 地層科学研究 情報・意見交換会
11月11日(火)13:20〜17:00
場所:瑞浪市地域交流センター「ときわ」(岐阜県瑞浪市)
定員:約150名
○瑞浪超深地層研究所 深度300m水平坑道見学会
11月12日(水)9:15〜12:00
場所:瑞浪超深地層研究所
定員:40名
※いずれも申込締切: 10月24日(金)
申込者が多数の場合は、先着順。入場無料(要事前申込)
[申込先]
独立行政法人 日本原子力研究開発機構
バックエンド研究開発部門 東濃地科学センター 地層科学研究部
結晶質岩工学技術開発グループ
E-mail:tono-koukankai2014@jaea.go.jp
http://www.jaea.go.jp/04/tono/topics/topics1410_1/1410_1.html
■7th South China Sea Tsunami Workshop
(第7回南シナ海における津波ワークショップ)
11月18〜19日: ポピュラーサイエンス関係のワークショップ
11月20〜21日: テクニカルプログラム関連のワークショップ
11月22日 : 視察
会場:台中(台湾)
国立自然科学博物館(ワークショップ)
台湾地震博物館、原子力発電所(視察)
参加登録締切:10月30日
http://www.bictam.org.cn/?p=594
■第25回地質汚染調査浄化技術研修会 技術研修会
日本地質学会環境地質部会ほか 共催
11月21日(金)〜23日(日)
会場:NPO法人日本地質汚染審査機構本部ミーテング・ルーム・八千代市民会館
参加費:会員(地質学会員・社会地質学会員を含む)39,000円(学生:35,000円)
(CPD:22単位)
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
■第30回ゼオライト研究発表会
日本地質学会ほか 協賛
11月26日(水)〜27日(木)
場所:タワーホール船堀(東京都江戸川区船堀4-1-1)
予稿原稿締切:10月24日(金)
http://www.jaz-online.org/
■第24回環境地質学シンポジウム
日本地質学会ほか 共催
11月28日(金)〜29日(土)
場所:日本大学文理学部8号館1階レクチャーホール
発表登録申込締切:10月18日(土)まで
原稿登録締切:11月5日(水)必着
http://www.jspmug.org/
■ウインター・サイエンスキャンプ'14-'15
先進的な研究テーマに取り組む大学・公的研究機関・民間企業等を会場として、第一線で活躍する研究者・技術者から本格的な講義・実験・実習を受けることができる、高校生のための科学技術体験合宿プログラム。
12月21日 〜 2015 年1月7日の期間中、 2泊3日〜6泊7日
場所:大学、公的研究機関等 (9会場)
定員:会場ごとに12〜24 名 (合計168 名)
応募締切:10月24日(金)
http://www.jst.go.jp/cpse/sciencecamp/camp/
■第4回学生のヒマラヤ野外実習ツアー
日本地質学会等推薦
2015 年3月上旬(4日頃)出発,出国から帰国まで15日間
参加募集対象:全国の地学,災害地質,自然環境等に関係する学科・専攻科の学生・大学院生を優先※学生の指導教員,関係企業の新人技術者や指導上司,及び高校生や中学・高校の理科教員,一般市民も受け入れます.
定員:20名
参加費:学生,大学院生は20 万円以内(暫定)
参加申込締切:2014年11月末日
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
■第13回微量元素の生物地球化学に関する国際会議
13th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements, ICOBTE 2015 FUKUOKA
日本地質学会 後援
2015年7月12日(日)〜16日(木)
場所:福岡国際会議場
要旨締切:2014年12月18日(木)
http://www.icobte2015.org/index.html
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
2015年7月27日(月)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1-1)
http://inqua2015.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0133.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■福島大学:共生システム理工学類(准教授又は講師)(11/14)
■原子力規制庁:職員(経験者)の公募(10/24)
■大阪教育大学:教養学科自然研究講座固体地球科学(准教授または講師)(11/10)
■産業技術総合研究所:活断層・火山研究部門活断層評価研究グループ研究員公募(10/17)
■鳥取県職員:学芸員(地学担当1名、生物担当1名) 公募(11/6)
■地球惑星科学振興西田賞 候補者募集(12/15)
■山田科学振興財団:2015年度研究援助候補推薦(2014/2/27 学会締切2014/1/31)
■平成27年度文部科学省研究公募:新学術領域「地殻ダイナミクス」(各機関毎に異なる)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.277 (臨時)首藤次男名誉会員 訃報
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.277 2014/10/8 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 首藤次男 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
日本地質学名誉会員 首藤次男氏(九州大学名誉教授)が、平成26年10月6日(月)にご逝去されました(享年93歳)。
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
なお、通夜ならびに告別式は、下記のとおり執り行われますので併せてお知らせ申し上げます。
通夜:10月8日(水)18:00より
葬儀・告別式:10月9日(木)13:00より
式場:福岡草苑(福岡市中央区平和3丁目1-5)
http://www.kinositasouen.jp/f_fukuoka.html
喪主:ご長男 首藤耕一郎様
会長 井龍康文
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.278 「県の石」募集:締切迫る!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.278 2014/10/21 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2015年度一般社団法人日本地質学会各賞候補者募集について
【2】割引会費申請の受付開始!—2015年度会費払込のお知らせ—
【3】学会ホームページ会員情報システム一時利用停止のお知らせ
【4】「県の石」募集:締切迫る!
【5】国際第四紀学連合第19回大会における発表募集開始のお知らせ
【6】地学オリンピックキャラクターデザインコンテスト 締切間近!
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2015年度一般社団法人日本地質学会各賞候補者募集について
──────────────────────────────────
日本地質学会では今年も運営規則第16条および各賞選考規則にしたがい,各賞の候補者を募集いたします.
期日厳守にて,たくさんのご応募をお待ちしております.
応募締切:12月1日(月)必着
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0084.html
○会員番号・パスワードによるログインが必要です。
ログインの方法はこちら。
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】割引会費申請の受付開始!—2015年度会費払込のお知らせ—
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,学部学生・院生(研究生)については,本人の申請によりそれぞれ割引会費が適用されます.
つきましては,次年度(2015年度)の会費についての申請受付を開始いたしますので,該当される会員は規定の書式にて申請書を提出してください(郵送に限る).
また,12月中旬頃までに次年分の会費請求書(郵便振替用紙)をお送りします.地質学会の会費は前納制ですので,2015年3月までに折り返しご送金下さいますようお願いいたします.指定の金融機関口座からの自動引き落としをご利用の場合は12月24日(水)が引落日です.
■割引会費申請(院生・学部学生)請求書発行前締切:11月17日(月)
とくに自動引落を利用の学生・院生のかたはこの期日までにご提出下さい.
■新規登録,引落口座変更の振替依頼書提出締切日:11月10日(月)必着
次年度会費の自動引落からご利用希望の場合は,11月10日(月)までに必ず預金口座振替依頼書をご提出下さい.
■2015年度分会費の引き落とし日:12月24日(水)
請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下さい.
■自動引き落とし以外のかた(お振り込み)
12月中旬頃までに請求書兼郵便振替用紙をお送りいたします.
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/outline/content0135.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】学会ホームページ会員情報システム一時利用停止のお知らせ
──────────────────────────────────
現在進行中の,地質学会ホームページのシステムリニューアル作業に伴い,会員情報システムが一時ご利用頂けません.利用停止期間は,下記の通りです.
システム利用停止期間:2014年11月17日(月)〜19日(水)
(終了予定は,作業状況によって前後する場合があります)
停止期間中は,住所変更,専門部会登録等の会員情報の更新はできません(会員ページへのログインは可能です).会員情報の更新は,システム停止期間後に行って頂くか,学会事務局まで直接メール等でご連絡をお願い致します.
会員の皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが,ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます.
(日本地質学会広報委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】「県の石」募集:締切迫る!
──────────────────────────────────
日本では古来より郷土に産する岩石,鉱物,化石を愛し,またそれらを利用しながら発展してきました.また,日本列島はプレートの沈み込み帯に位置し,深海の堆積物から火山や大陸地殻まで多様で幅広い時代の岩石から成り立っています.これほど多くの岩石に彩られている国は世界でも多くはありません.私たちが生活する大地の歴史と成り立ちを知り,郷土の地質を愛する心を再認識するために,日本地質学会では「県の石」の認定を企画しました.日本地質学会に所属する専門家のみならず,全国都道府県へのアンケート調査,そして市民の皆様の推薦を参考に各都道府県の「県の石」を認定して参ります.
応募締切:10月31日まで(鹿児島県のみ受付終了)
詳しくはこちらから.
http://www.geosociety.jp/name/content0121.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】国際第四紀学連合第19回大会における発表募集開始のお知らせ
──────────────────────────────────
国際第四紀学連合(INQUA)第19回大会の発表募集が始まりました.
今大会では116のテーマセッションが設けられております.みなさまがこれまでに行った研究成果を世界に発信できる良い機会であるとともに,海外の研究者との交流や情報交換を行うまたとない機会ですので,ぜひとも発表の申込みをご検討頂けますようお願い申し上げます.
なお,原則として各テーマセッションはINQUAが行っている5つの委員会に対応付けされています.各委員会の概要についてはhttp://www.geosociety.jp/faq/content0538.html#inquaをご参照下さい.研究内容が個々のセッションのテーマと合わない場合には,各委員会に関連した発表を広く受け付けるポスター発表セッションも用意しております.
会期:2015年7月27日(月)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1-1)
大会ホームページ(各種お申込みはこちらから):http://inqua2015.jp
セッション一覧:http://convention.jtbcom.co.jp/inqua2015/session/index.html
LOC Facebook:https://www.facebook.com/INQUA2015
【今後のスケジュール】
2014年12月20日:口頭・ポスター発表の申し込み締め切り
2014年10月下旬:大会巡検申込開始予定
2015年 2月28日:早期参加登録締め切り
【本件問合せ先】
大会組織委員会事務局: 2015inqua-sec@inqua2015.jp
【INQUAの5つの委員会の概要】
1. CMP(Coastal and Marine Processes:海洋および沿岸プロセス委員会)
海洋および沿岸に関する研究全般について取り扱っています.現在5つの作業部会があり,海岸線近傍の第四紀環境変遷や大陸棚,そして外洋の環境変遷についての研究を行っています.日々進展する年代測定についての知見も重要なテーマのひとつであり,作業部会のひとつではそれについて取り組んでいます.
2. PALCOMM(Palaeoclimate:古気候研究委員会)
プロキシと呼ばれる過去の表層環境シグナル(花粉やプランクトン,それらの化学データ等からもたらされる気温や降水量情報等)を使って気候モデルとの比較検討を行い,気候システムの理解を深めるための研究を進める委員会です.
3. HaBCom(Commission for Humans and the Biosphere:人類および生物圏研究委員会)
人類と環境の相互関係の探究とともに,気候や環境の変動が生物や人類に対してどのような影響を与えるかの解明を目指しています.地域的にも多様なプロジェクトが立ち上がっています.広く古生態学,考古学,人類進化のテーマもカバーし,時代も旧石器時代から歴史時代までフォローしています.
4. SACCOM(Stratigraphy and Geochronology Commission:第四紀層序・地質年代委員会)
層序学・編年学を通じて第四紀研究に寄与するため,各大陸の層序調査と区分,テフラ年代学,レス古土壌,乾燥地年代評価などの6つの作業部会を中心に定期的会合・出版・広報活動を行っています.
5. TERPRO(Commission on Terrestrial Processes, Deposits and History:陸域のプロセス・堆積物・地史研究委員会)
第四紀の陸域における環境とその変化に関するあらゆる分野を研究対象としています.現在,陸水,古土壌,活構造,災害,地下水に関する研究グループが活動していますが,雪氷・周氷河,沙漠,都市地質などに関する研究も,この委員会の活動に含まれます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地学オリンピックキャラクターデザインコンテスト 締切間近!
──────────────────────────────────
<中・高教員ならびに,中高生のお子さんがいる父兄の会員の方へ>
地学オリンピック日本委員会では、日本地質学会との共催で中学生・高校生を対象としたキャラクターデザインコンテストを実施しています。
素敵なキャラクターで地学オリンピックをPRしてみませんか?
周囲の中・高生にぜひお声掛け下さい。
募集締切:10月31日(金)
応募資格:中学生・高校生
多くの皆様からのご応募をお待ちしております。
募集要項のダウンロードはこちらから
http://jeso.jp/wp-content/uploads/2014/06/ieso_character_design_contest.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■ミニ巡検シリーズ「西伊豆巡検」
11月8日(土)〜9日(日)
参加費:25,000円(宿泊費,レンタカー代,保険料など).昼食代は別.
案内者:狩野謙一・鈴木雄介・伊藤谷生
見どころ:弁天島(白浜層群浅海性堆積物の堆積構造),入間千畳敷(未固結堆積物への貫入構造),堂ヶ島(堆積構造,火山性高温土石流堆積物,貫入と地質構造形成との関係),室岩洞(伊豆石採石場跡地),一色(仁科層群の枕状溶岩)など.
定員:10名,先着順.
申込締切:10月23日(木)
詳しくは http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地震本部ニュース2014年秋号
http://www.jishin.go.jp/main/p_koho04.htm
■地学オリンピックキャラクターデザインコンテスト
日本地質学会共催
募集締切:10月31日(金)
応募資格:中学生・高校生
http://jeso.jp/wp-content/uploads/2014/06/ieso_character_design_contest.pdf
■あいちサイエンスフェスティバル2014
9月27日(土)〜11月3日(月・祝)
会場:蒲郡市生命の海科学館など
※(共)惑星地球フォトコンテスト入賞作品展
https://aichi-science.jp/
■第115回「海洋フォーラム」
SIDSサモア会議と『島と海のネット』の立上げ
〜第3回国連小島嶼途上国会議からの報告〜
10月22日(水)17:00〜18:30(受付開始16:30)
場所:日本財団ビル 2階大会議室(東京都港区赤坂1−2−2)
参加無料
http://www.sof.or.jp/jp/forum/index.php
■山陰海岸ジオパーク国際学術会議「湯村会議」
日本地質学会 後援
10月25日(土)〜26日(日)
場所:新温泉町夢ホール(兵庫県美方郡新温泉町湯990-8)
http://sanin-geo.jp/modules/geopark/index.php/yumura14.html
■シンポジウム「これからの理数系教育を考える」
10月26日(日)13:20〜16:40
場所:一橋記念講堂(東京都千代田区)
https://sites.google.com/site/risukeigakkai/sympo2014
■第23回素材工学研究懇談会
「励起反応場を用いた多次元金属ナノ・マイクロ構造創成」
11月6日(木)〜7日(金)
場所:東北大学片平さくらホール2F
申込締切:10/31
http://www.tagen.tohoku.ac.jp/
■第161回深田研談話会
「土木工学の新しい風〜住民たちの力を引き出す道直し活動〜」
11月14日(金)15:00〜17:00[14:30開場]
会場:深田地質研究所 研修ホール(文京区本駒込2-13-12)
定員:80名 参加費無料
http://www.fgi.or.jp/
■第25回地質汚染調査浄化技術研修会 技術研修会
日本地質学会環境地質部会ほか 共催
11月21日(金)〜23日(日)
会場:NPO法人日本地質汚染審査機構本部ミーテング・ルーム・八千代市民会館
参加費:会員(地質学会員・社会地質学会員を含む)39,000円(学生:35,000円)
(CPD:22単位)
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
■第30回ゼオライト研究発表会
日本地質学会ほか 協賛
11月26日(水)〜27日(木)
場所:タワーホール船堀(東京都江戸川区船堀4-1-1)
予稿原稿締切:10月24日(金)
http://www.jaz-online.org/
■第24回環境地質学シンポジウム
日本地質学会ほか 共催
11月28日(金)〜29日(土)
場所:日本大学文理学部8号館1階レクチャーホール
原稿登録締切:11月5日(水)必着
http://www.jspmug.org/
■Project A 2015 in Korea
日本地質学会ほか 後援
2015年3月4日(水)〜8日(日)
4日オープニング、5日セッション、6〜8日巡検
会場:韓国(大田広域市)
アブストラクト締切:2015年1月23日(金)
http://archean.jp/
■第4回学生のヒマラヤ野外実習ツアー
日本地質学会等推薦
2015 年3月上旬(4日頃)出発,出国から帰国まで15日間
参加募集対象:全国の地学,災害地質,自然環境等に関係する学科・専攻科の学生・大学院生を優先※学生の指導教員,関係企業の新人技術者や指導上司,及び高校生や中学・高校の理科教員,一般市民も受け入れます.
定員:20名
参加費:学生,大学院生は20 万円以内(暫定)
参加申込締切:2014年11月末日
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
■北極科学サミット週間2015
4月23日(木)〜30日(木)
会場:富山国際会議場
アブストラクト締切:2014年11月10日
参加登録締切:2015年3月31日
http://www.assw2015.org/japanese/index.html
■第13回微量元素の生物地球化学に関する国際会議
13th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements, ICOBTE 2015 FUKUOKA
日本地質学会 後援
2015年7月12日(日)〜16日(木)
場所:福岡国際会議場
要旨締切:2014年12月18日(木)
http://www.icobte2015.org/index.html
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
2015年7月27日(月)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1-1)
http://inqua2015.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0133.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■東京工業大学大学院:理工学研究科地球惑星科学専攻(教授)公募(12/10)
■神戸大学:自然科学系先端融合研究環 教員公募(特命助教)(11/28)
■第42回「環境賞」候補募集(12/19 学会締切11/30)
■2015年度日本地球惑星科学連合フェロー候補者推薦募集(12/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.279 ホームページの会員情報システムを一時停止します
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.279 2014/10/21 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2015年度一般社団法人日本地質学会各賞候補者募集について
【2】割引会費申請の受付開始!—2015年度会費払込のお知らせ—
【3】学会ホームページ会員情報システム一時利用停止のお知らせ
【4】大学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準「地球惑星科学分野」の公表
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2015年度一般社団法人日本地質学会各賞候補者募集について
──────────────────────────────────
日本地質学会では今年も運営規則第16条および各賞選考規則にしたがい,各賞の候補者を募集いたします.
期日厳守にて,たくさんのご応募をお待ちしております.
応募締切:12月1日(月)必着
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/members/content0084.html
○会員番号・パスワードによるログインが必要です。
ログインの方法はこちら。
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】割引会費申請の受付開始!—2015年度会費払込のお知らせ—
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,学部学生・院生(研究生)については,本人の申請によりそれぞれ割引会費が適用されます.
つきましては,次年度(2015年度)の会費についての申請受付を開始いたしますので,該当される会員は規定の書式にて申請書を提出してください(郵送に限る).
また,12月中旬頃までに次年分の会費請求書(郵便振替用紙)をお送りします.地質学会の会費は前納制ですので,2015年3月までに折り返しご送金下さいますようお願いいたします.指定の金融機関口座からの自動引き落としをご利用の場合は12月24日(水)が引落日です.
■割引会費申請(院生・学部学生)請求書発行前締切:11月17日(月)
とくに自動引落を利用の学生・院生のかたはこの期日までにご提出下さい.
■新規登録,引落口座変更の振替依頼書提出締切日:11月10日(月)必着
次年度会費の自動引落からご利用希望の場合は,11月10日(月)までに必ず預金口座振替依頼書をご提出下さい.
■2015年度分会費の引き落とし日:12月24日(水)
請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下さい.
■自動引き落とし以外のかた(お振り込み)
12月中旬頃までに請求書兼郵便振替用紙をお送りいたします.
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/outline/content0135.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】学会ホームページ会員情報システム一時利用停止のお知らせ
──────────────────────────────────
現在進行中の,地質学会ホームページのシステムリニューアル作業に伴い,会員情報システムが一時ご利用頂けません.利用停止期間は,下記の通りです.
システム利用停止期間:2014年11月17日(月)〜19日(水)
(終了予定は,作業状況によって前後する場合があります)
停止期間中は,住所変更,専門部会登録等の会員情報の更新はできません(会員ページへのログインは可能です).会員情報の更新は,システム停止期間後に行って頂くか,学会事務局まで直接メール等でご連絡をお願い致します.
会員の皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが,ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます.
(日本地質学会広報委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】大学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準「地球惑星科学分野」の公表
──────────────────────────────────
2014年9月30日に日本学術会議より、標記の参照基準地球惑星科学分野が公開された。(全文:http://www.scj.go.jp/ja/info/index.html)
ここでは、参照基準地球惑星科学分野の内容を簡単に紹介し,参照基準策定の意義と各大学における今後の活用について説明し,大学教育に携わる皆様の注意を喚起したい。
[日本学術会議 第22期地球惑星科学委員会大学教育問題分科会委員長 西山忠男]
詳細は下記を参照
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//others-pdf/20141104.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報
──────────────────────────────────
[西日本支部]
■平成26年度総会・第166回例会
2015年2月21日(土)[20日:幹事会]
場所:山口大学,吉田キャンパス,大学会館
講演申込み〆切:2月4日(水)17時
*総会へ欠席の方は,委任状をお送り下さい。
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地質研究所ニュース(2014.10.27発行)
http://www.gsh.hro.or.jp/publication/gshnews/news_pdf/vol30_no3.pdf
■第25回地質汚染調査浄化技術研修会 技術研修会
日本地質学会環境地質部会ほか 共催
11月21日(金)〜23日(日)
会場:NPO法人日本地質汚染審査機構本部ミーテング・ルーム・八千代市民会館
参加費:会員(地質学会員・社会地質学会員を含む)39,000円(学生:35,000円)
(CPD:22単位)
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
■第30回ゼオライト研究発表会
日本地質学会ほか 協賛
11月26日(水)〜27日(木)
場所:タワーホール船堀(東京都江戸川区船堀4-1-1)
http://www.jaz-online.org/
■第24回環境地質学シンポジウム
日本地質学会ほか 共催
11月28日(金)〜29日(土)
場所:日本大学文理学部8号館1階レクチャーホール
原稿登録締切:11月5日(水)必着
http://www.jspmug.org/
■地球化学研究協会「公開講座」および「三宅賞」受賞者の受賞記念講演
・公開講座「低頻度大規模噴火はどこまで分っているか」
講師・中田節也(東京大学地震研究所教授)座長・兼岡一郎(地球化学研究協会理事長)
・三宅賞受賞者記念講演「セシウム137の高精度分析とデータベース化に基づいた海洋循環の研究」
受賞者:青山道夫 博士(福島大学環境放射能研究所教授)
12月6日(土) 午後2時40分より
場所:霞が関ビル35階 東海大学校友会館
(地下鉄銀座線虎ノ門・千代田線霞ヶ関下車)
参加費:賛助会員および学生は無料、一般1,000円(資料代を含む)、懇親会へも参加できます。
http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~e881147/Geochem/
■第23回地質調査総合センターシンポジウム
日本列島の長期的地質変動の予測に向けた取り組みと今後の課題-数十万年過去を解明し、将来を予測する技術・知見・モデル-
2015年1月16日(金)13:00〜18:10(開場:12:00)[参加無料]
会 場:東京秋葉原ダイビル 2F秋葉原コンベンションホール
(東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル2階)
参加登録 :https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo23/index.html
*CPD単位認定(CPD希望の方も事前参加登録をお願いします。)
お問合わせ先:第23回地質調査総合センターシンポジウム事務局
E-mail: gsjsympo23-ml@aist.go.jp
■Project A 2015 in Korea
日本地質学会ほか 後援
2015年3月4日(水)〜8日(日)
4日オープニング、5日セッション、6〜8日巡検
会場:韓国(大田広域市)
アブストラクト締切:2015年1月23日(金)
http://archean.jp/
■第4回学生のヒマラヤ野外実習ツアー
日本地質学会等推薦
2015 年3月上旬(4日頃)出発,出国から帰国まで15日間
参加募集対象:全国の地学,災害地質,自然環境等に関係する学科・専攻科の学生・大学院生を優先※学生の指導教員,関係企業の新人技術者や指導上司,及び高校生や中学・高校の理科教員,一般市民も受け入れます.
定員:20名
参加費:学生,大学院生は20万円以内(暫定)
参加申込締切:2014年11月末日
詳細はこちら
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
■第13回微量元素の生物地球化学に関する国際会議
13th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements, ICOBTE 2015 FUKUOKA
日本地質学会 後援
2015年7月12日(日)〜16日(木)
場所:福岡国際会議場
要旨締切:2014年12月18日(木)
http://www.icobte2015.org/index.html
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
2015年7月27日(月)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1-1)
http://inqua2015.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0133.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■日本原子力研究開発機構:平成27年度特別研究生の募集(2015/1/9)
■平成27年度東京大学大気海洋研究所:共同利用公募(11/28)
■平成27年度東京大学大気海洋研究所:学際連携研究公募(12/3)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.282 平成25年山口・島根豪雨災害の概要と調査報告
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.282 2014/12/16 ┬┴┬┴
geo-Flash 地質学会メールマガジン No.201〜250
geo-Flash! 日本地質学会公式メールマガジン
geo-Flash(ジオフラッシュ)は、学会活動の改善の一環として、地質学に関わるあるいは学界活動に関する情報をいち早く会員の皆様にお届けすることを目的として発足いたしました。会員の皆様からの情報も積極的に載せていく予定ですので、大いにご活用いただきますようお願い申し上げます。
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬【geo-Flash】日本地質学会メールマガジン ┴┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.001 Since 2007/07/3 ┴┬┴┬
geo-flash No.283 平成27年新年号
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.283 2015/1/6 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】年頭にあたって
【2】第122年学術大会開催(2015年9月11日〜13日)/トピックセッションの募集
【3】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(火)
【4】中期ビジョン中間報告と意見募集
【5】広報委員の募集
【6】第6回惑星地球フォトコンテスト:応募受付中!
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】年頭にあたって
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会 会長 井龍 康文
2015(平成27)年の年頭に当たり,日本地質学会理事会を代表して,会員の皆様にごあいさつを申し上げます.ここでは,昨年の本学会の活動を総括し,今後の活動方針を示したいと思います.
昨年の選挙により新執行体制となりました.新執行体制は,“学”在籍の会長に“産”と“官”在籍の副会長を配し,産学官の連携強化を図りました.月に1度開催される執行理事会では,報告と審議の時間を短縮し,特定の問題に関して集中して議論する時間を設け,それらの問題に対する地質学会の対応を決定するようにしています.今後も,“フットワークが軽く”,“汗をかく”執行体制を目指し,尽力してまいりたいと思います. ......
続きはこちらから.
http://www.geosociety.jp/outline/content0147.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第122年学術大会開催(2015年9月11日〜13日)/トピックセッションの募集
──────────────────────────────────
■開催通知
2015年日本地質学会長野大会実行委員会
委員長 公文富士夫
事務局長 保柳康一
日本地質学会は,中部支部の支援のもと長野市若里の信州大学長野(工学)キャンパスにて,第122年学術大会(2015年長野大会)を9月11日(金)から13日(日)に開催いたします.巡検は,開催日前日の10日(木),期間中の12日(土),大会後の14日(月),15日(火)に全8コースの実施を計画しております......
続きはこちらから.http://www.geosociety.jp/science/content0065.html
■トピックセッションの募集
日本地質学会行事委員会
第122年学術大会(長野大会)は,中部支部のご協力のもと,信州大学工学部(長野市)をメイン会場として2015年9月11日(金)〜13日(日)に開催されます.
現在,トピックセッションを募集中です.
なお,本大会も前回同様,シンポジウムの一般募集はありません.
※シンポジウムは長野大会実行委員会および学会執行部が企画します.
募集締切:3月16日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0066.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(火)
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は3月31日(火)です.
次年度も割引会費を希望のかたは,忘れずにご提出ください(締切厳守).
※通常の会費払込については,「2015年会費払い込みについて」を参照下さい.
■ 自動引落による納入
昨年12月24日(水)にお届けの金融機関口座より引き落としさせていただきました.通帳記帳等でご確認ください.請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承ください.
■ 郵便振替用紙(またはゆうちょ銀行口座)からのお振り込み
2014年12月15日(月)に請求書兼郵便振替用紙を発送しました.地質学会の会費は前納制ですので,お早めにご送金ください.
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/outline/content0135.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】中期ビジョン中間報告と意見募集
──────────────────────────────────
中期ビジョン中間報告と意見募集
中期ビジョンワーキンググループがこれまでに検討した素案を今月と来月の2回にわたって掲載します.ご意見,ご助言などございましたらぜひお寄せ下さいますようお願いいたします.
(平成26年度中期ビジョンワーキンググループ 坂口有人)
中間報告(前編)はこちらから▼▼
http://www.geosociety.jp/outline/content0148.html
意見募集締切:3月15日(日)
送付先:地質学会事務局(main@geosociety.jp)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】広報委員の募集
──────────────────────────────────
日本地質学会の広報委員会を任期満了に伴いまして委員の交代を行います.
ニュース誌,geo-Flash,ホームページ,ジオルジュ(ライター),ちーとも,プレスリリースなどの学会広報活動に関心があり,ご協力頂けます方はご連絡頂けますようお願いいたします.地質学会広報の更なる飛躍のために,積極的にご参加下さい.
連絡先:地質学会事務局(main@geosociety.jp)
締切:2月18日(水)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】第6回惑星地球フォトコンテスト:応募受付中!
──────────────────────────────────
今年も惑星地球フォトコンテストの作品を募集中です.今回より新たに「ジオ鉄賞」「スマホ賞」を設けました.また,携帯やスマホから画像を添付していただくだけで,手軽にご応募いただけるようになりました.皆様の力作を是非ご応募ください.
たくさんのご応募をお待ちしています.
応募締切:2月16日(月)17時(郵送の場合は同日必着)
賞:最優秀賞1点(賞金5万円),優秀賞1点(賞金2万円),ジオ鉄賞(賞金1万円),スマホ賞(賞金5千円)...など
詳しくは,http://photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部 ]
■功労賞募集
関東支部では,支部の顕彰制度に基づき2014年度も支部活動や地質学を通して社会貢献された個人・団体を関東支部として顕彰いたします.つきましては,下記の要領で支部会員からの推薦を募集します.
対象者:支部活動や地質学を通して広く社会貢献をされた関東支部内に在住の個人・団体
*社会貢献や活動の評価においては,必ずしも学問的な成果を問うものではありません.
公募締切:1月10日[選考期間:1月11日〜31日]
関東支部功労賞審査委員会(委員長:伊藤谷生 前支部長)を設置
審査結果報告:NEWS誌、関東支部総会
推薦方法:対象者氏名,推薦者氏名,推薦理由(400字程度)を記入の上,関東支部功労賞推薦としてメールもしくはFAXにて下記へお送り下さい.
推薦受付:神奈川県立生命の星・地球博物館 笠間友博
〒250-0031 小田原市入生田499
E-mail:kasama@nh.kanagawa-museum.jp ,FAX:0465-23-8846
■「地学教育サミット・ジオパークと教育〜楽しく元気に大地の公園〜」のお知らせ (第一報)
関東支部では関東地方の各ジオパークを、教員の方をはじめ広く一般の方々にも広く知っていただくため、次のように地学教育サミット「ジオパークと教育〜楽しく元気に大地の公園〜」を計画いたしました。皆様、是非ご参加ください。
共催 小田原市、箱根ジオパーク推進協議会
日時 3月15日(日)10:00〜16:00
場所 神奈川県小田原市生涯学習センター けやき 大会議室
参加費 無料、資料代別途(お申し込みは不要ですが資料作成上、事前連絡をお願いする予定です。詳細は第二報にてご連絡いたします)
プログラム概要
午前 基調講演
午後 関東地区各ジオパークからの実践報告・総合討論
問合せ先:神奈川県立生命の星・地球博物館 笠間友博
E-mail:kasama@nh.kanagawa-museum.jp ,FAX:0465-23-8846
[西日本支部]
■平成26年度総会・第166回例会
2月21日(土)[20日:幹事会]
場所:山口大学,吉田キャンパス,大学会館
講演申込締切:2月4日(水)17時
*総会へ欠席の方は,委任状をお送り下さい。
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第56回科学技術映像祭 参加作品募集
募集締切:1月26日(月)
参加方法:科学技術映像祭公式ホームページより申込参加申込方法など、詳細は下記をご覧ください。
http://ppd.jsf.or.jp/filmfest/
■北淡国際活断層シンポジウム2015
日本地質学会ほか 後援
1月12日(月)〜 17日(土)
場所:兵庫県淡路市 兵庫県立淡路夢舞台国際会議場
http://home.hiroshima-u.ac.jp/kojiok/outline01j.html
■Project A 2015 in Korea
日本地質学会ほか 後援
3月4日(水)〜8日(日)
4日オープニング、5日セッション、6〜8日巡検
会場:韓国(大田広域市)
アブストラクト締切:1月23日(金)
http://archean.jp/
■第4回学生のヒマラヤ野外実習ツアー
日本地質学会等推薦
3月上旬(4日頃)出発,出国から帰国まで15日間
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
■第15回アジア学術会議カンボジア会合国際シンポジウム
5月15日(金)〜16日(土)
会場:Angkor Paradise hotel(シェムリアップ、カンボジア)
問い合わせ先:Institute of Technology of Cambodia(ITC)
E-mail:sca2015@itc.edu.kh/info@itc.edu.kh
http://krs.bz/scj/c?c=143&m=21728&v=9765b8fb
■地質学史懇話会
6月20日(土)
場所:北とぴあ8階803号室(東京都北区王子)
澁谷鎮明:仮題「東アジアの地理学史」
中陣隆夫:仮題「田山利三郎の海洋地質学—業績と評価」
■第52回アイソトープ・放射線研究発表会
日本地質学会ほか 共催
7月8日(水)〜10日(金)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1)
発表申込締切:2月27日(金)
講演要旨原稿締切 :4月10日(金)
http://www.jrias.or.jp/
■第13回微量元素の生物地球化学に関する国際会議
13th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements, ICOBTE 2015 FUKUOKA
日本地質学会 後援
7月12日(日)〜16日(木)
場所:福岡国際会議場
http://www.icobte2015.org/index.html
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
7月27日(月)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1-1)
予稿投稿締切:1月8日(木)[締切延長]
早期参加登録締切:2月28日(土)
http://inqua2015.jp/
>>学生・院生の登録料免除制度
1月12日(月)
http://inqua2015.jp/j/support/Jstudents.htm
■IGCP608第3回国際シンポジウム
および第12回中生代陸成生態系シンポジウム
8月15日(土)〜18日(火)シンポジウム
8月19日(水)〜22日(土)巡検:遼寧省内の熱河層群
場所:中国瀋陽,瀋陽師範大学
■第10回アジア地域応用地質学シンポジウム
日本地質学会 後援
研究発表会:9月24日(木)〜25日(金)
シンポジウム:9月26日(土)〜27日(日)[その後巡検予定あり]
場所:京都大学宇治黄檗プラザ
http://2015ars.com/
■Arthur Holmes Meeting Tsunami Hazards and Risks: Using the Geological Record
日本地質学会 共催
9月25日(金)
場所:The Geological Society(英・ロンドン)
http://www.geolsoc.org.uk/ahm15
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0144.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■海洋研究海洋機構:地震津波海域観測研究開発センター地震発生帯モニタリング研究グループ(研究員または技術研究員)(1/13)
■大阪市立大学大学院:理学研究科・理学部地球学教室(特任講師)(1/31)
■東京大学地震研究所・京都大学防災研究所 平成27年度拠点間連携共同研究の公募(2/6)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.284 (臨時)日本原子力学会による不適切な情報発信に関して
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.284 2015/1/12 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
日本地質学会会員各位
平成27年1月8日付けの毎日新聞に,「日本原子力学会が原発の敷地内にある破砕帯などの断層について,原子炉建屋への影響などを評価する方法を策定する調査専門委員会を発足させた」との記事が掲載されました(http://mainichi.jp/select/news/20150108k0000m040131000c.html).その中に,「委員会には土木学会や地質学会,電力会社なども加わっている.」と書かれておりますが,地質学会は,原子力学会からは本件に係わるいかなる申し入れや要請を受けておらず,また同委員会に係わる本学会員からの報告等も皆無のところでした.
本学会からの問い合わせに対して,日本原子力学会は,上記の専門委員会の設置を発表した際多くの学会や団体が参加すると,誤解を招く資料を配布した不手際を認めました.9日夜の報道によれば(http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015010901002182.html),同専門委員会主査の奈良林直北海道大教授は「個人の意思に基づく活動で学会間の手続きは経ていなかった.誤解を招く表現を訂正し,速やかに学会としてウェブサイトに公表したい.」と釈明しているとのことです.
このような事態を受け,日本地質学会では常務理事(斎藤眞)名で日本原子力学会に対して,事実関係の公表とお詫びを至急公表するとともに,報道機関に対して訂正を依頼するよう申し入れを行いました.
以上,会員の皆様に周知いたします.
日本地質学会執行理事会
2015年1月15日追記
○ 15日付けの毎日新聞に,以下の記事が掲載されました。
http://mainichi.jp/select/news/20150115k0000m040062000c.html
○ 日本原子力学会のHPに詫び文が掲載されました。
http://www.aesj.or.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.285 日本原子力学会による不適切な情報発信に関して_追記
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.285 2015/1/20 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】geo-Flash No.284臨時号の追記について
【2】[長野大会]トピックセッションの募集
【3】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(火)
【4】3rd IGCP608 China 2015 & MTE-12のFirst Circular 配布開始
【5】中期ビジョン中間報告と意見募集
【6】広報委員の募集
【7】第6回惑星地球フォトコンテスト:応募受付中!
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】geo-Flash No.284臨時号の追記について
──────────────────────────────────
1月12日付のgeo-Flash(臨時号) No.284 日本原子力学会による不適切な情報発信に関しての配信後、1月15日に以下、追記いたしました。
○ 【geo-Flash】 No.284 臨時号
http://www.geosociety.jp/faq/content0545.html
● [追記]1/15日付けの毎日新聞
http://mainichi.jp/select/news/20150115k0000m040062000c.html
● [追記]日本原子力学会のHP(お詫び文)
http://www.aesj.or.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[長野大会]トピックセッションの募集
──────────────────────────────────
日本地質学会行事委員会
第122年学術大会(長野大会)は,中部支部のご協力のもと,信州大学工学部(長野市)をメイン会場として2015年9月11日(金)〜13日(日)に開催されます. 現在,トピックセッションを募集中です.
なお,本大会も前回同様,シンポジウムの一般募集はありません.
※シンポジウムは長野大会実行委員会および学会執行部が企画します.
募集締切:3月16日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0066.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(火)
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は3月31日(火)です.
次年度も割引会費を希望のかたは,忘れずにご提出ください(締切厳守).
※通常の会費払込については,「2015年会費払い込みについて」を参照下さい.
■ 自動引落による納入
昨年12月24日(水)にお届けの金融機関口座より引き落としさせていただきました.通帳記帳等でご確認ください.請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承ください.
■ 郵便振替用紙(またはゆうちょ銀行口座)からのお振り込み
2014年12月15日(月)に請求書兼郵便振替用紙を発送しました.地質学会の会費は前納制ですので,お早めにご送金ください.
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/outline/content0135.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】3rd IGCP608 China 2015 & MTE-12のFirst Circular 配布開始
──────────────────────────────────
IGCP608 Asia-Pacific Cretaceous Ecosystems (白亜紀アジア−西太平洋生態系)
第3回 国際研究集会と第12回中生代陸成生態系シンポジウム(同時開催)
日程:8月16日(日)〜8月20日(木)
場所:中国瀋陽,瀋陽師範大学
シンポジウムほか:8月16日(日)〜8月18日(火)
巡検:8月19日(水)〜8月20日(木) 遼寧省内の熱河層群
First Circularダウンロードサイト: http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/
連絡先: MTE-12@pmol.org.cn
(IGCP608 プロジェクトリーダー 安藤寿男)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】中期ビジョン中間報告と意見募集
──────────────────────────────────
中期ビジョンワーキンググループがこれまでに検討した素案を掲載しています.
ご意見,ご助言などございましたらぜひお寄せ下さいますようお願いいたします.
中間報告(前編)はこちらから▼▼
http://www.geosociety.jp/outline/content0148.html
意見募集締切:3月15日(日)
送付先:地質学会事務局(main@geosociety.jp)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】広報委員の募集
──────────────────────────────────
日本地質学会の広報委員会を任期満了に伴いまして委員の交代を行います.
ニュース誌,geo-Flash,ホームページ,ジオルジュ(ライター),ちーとも,プレスリリースなどの学会広報活動に関心があり,ご協力頂けます方はご連絡頂けますようお願いいたします.地質学会広報の更なる飛躍のために,積極的にご参加下さい.
連絡先:地質学会事務局(main@geosociety.jp)
締切:2月18日(水)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】第6回惑星地球フォトコンテスト:応募受付中!
──────────────────────────────────
今年も惑星地球フォトコンテストの作品を募集中です.今回より新たに「ジオ鉄賞」「スマホ賞」を設けました.また,携帯やスマホから画像を添付していただくだけで,手軽にご応募いただけるようになりました.皆様の力作を是非ご応募ください.
たくさんのご応募をお待ちしています.
応募締切:2月16日(月)17時(郵送の場合は同日必着)
賞:最優秀賞1点(賞金5万円),優秀賞1点(賞金2万円),ジオ鉄賞(賞金1万円),スマホ賞(賞金5千円)...など
詳しくは,http://photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
──────────────────────────────────
[東北支部 ]
■2014年度東北支部総会・講演会・シンポジウム
3月7日(土)〜8日(日)
7日:シンポジウム
8日:総会・個人講演
場所:岩手大学工学部(盛岡市上田)
問い合わせ先:
支部長:土谷信高 tsuchiya@iwate-u.ac.jp
幹事:越谷 信 koshiya@iwate-u.ac.jp
[関東支部 ]
■「地学教育サミット・ジオパークと教育〜楽しく元気に大地の公園〜」のお知らせ (第一報) 関東支部では関東地方の各ジオパークを、教員の方をはじめ広く一般の方々にも広く知っていただくため、次のように地学教育サミット「ジオパークと教育〜楽しく元気に大地の公園〜」を計画いたしました。皆様、是非ご参加ください。
共催 小田原市、箱根ジオパーク推進協議会
3月15日(日)10:00〜16:00
場所:神奈川県小田原市生涯学習センター けやき 大会議室
参加費:無料、資料代別途(お申し込みは不要ですが資料作成上、事前連絡をお願いする予定です。詳細は第二報にてご連絡いたします)
プログラム概要
午前 基調講演
午後 関東地区各ジオパークからの実践報告・総合討論
問合せ先:神奈川県立生命の星・地球博物館 笠間友博
E-mail:kasama@nh.kanagawa-museum.jp ,FAX:0465-23-8846
[西日本支部]
■平成26年度総会・第166回例会
2月21日(土)[20日:幹事会]
場所:山口大学,吉田キャンパス,大学会館
講演申込締切:2月4日(水)17時
*総会へ欠席の方は,委任状をお送り下さい。
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地震本部ニュース平成26年度冬号
http://www.jishin.go.jp/main/p_koho04.htm
■第2回全国海洋教育サミット
1月31日(土)〜2月1日(日)
会場:東京大学・本郷キャンパス・弥生講堂
http://www.a.u-tokyo.ac.jp/yayoi/map.html
参加費無料
http://rcme.oa.u-tokyo.ac.jp/events/post847.html
■平成26年度海洋情報部研究成果発表会
2月13日(金)
場所:海上保安庁海洋情報部
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KIKAKU/press/2015/H270114_kenkyu.pdf
■第163回深田研談話会
「メタンハイドレート 資源開発の現状と今後の展開」
2月13日(金)14:00〜16:00 ※いつもより1時間早くなります。
申し込み締切:2月10日(火) 先着:80名 参加無料
会場:深田地質研究所 研修ホール(文京区本駒込2-13-12)
http://www.fgi.or.jp/
■Project A 2015 in Korea
日本地質学会ほか 後援
3月4日(水)〜8日(日)
4日オープニング、5日セッション、6〜8日巡検
会場:韓国(大田広域市)
アブストラクト締切:1月23日(金)
http://archean.jp/
■第4回学生のヒマラヤ野外実習ツアー
日本地質学会等推薦
3月上旬(4日頃)出発,出国から帰国まで15日間
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
■第52回アイソトープ・放射線研究発表会
日本地質学会ほか 共催
7月8日(水)〜10日(金)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1)
発表申込締切:2月27日(金)
講演要旨原稿締切 :4月10日(金)
http://www.jrias.or.jp/
■第13回微量元素の生物地球化学に関する国際会議
13th International Conference on the Biogeochemistry of Trace
Elements, ICOBTE 2015 FUKUOKA
日本地質学会 後援
7月12日(日)〜16日(木)
場所:福岡国際会議場
http://www.icobte2015.org/index.html
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
7月27日(月)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1-1)
早期参加登録締切:2月28日(土)
http://inqua2015.jp/
■第10回アジア地域応用地質学シンポジウム
日本地質学会 後援
研究発表会:9月24日(木)〜25日(金)
シンポジウム:9月26日(土)〜27日(日)[その後巡検予定あり]
場所:京都大学宇治黄檗プラザ
http://2015ars.com/
■Arthur Holmes Meeting Tsunami Hazards and Risks: Using the Geological Record
日本地質学会 共催
9月25日(金)
場所:The Geological Society(英・ロンドン)
http://www.geolsoc.org.uk/ahm15
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0144.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■東京大学大学院:理学系研究科地球惑星科学専攻地球惑星システム科学講座(教授)(3/6)
■産業技術総合研究所:活断層・火山研究部門地震テクトニクス研究グループ(ポスドク)(2/5)
■原子力規制庁:行政職員(経験者)公募(2/13)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.286 (臨時)千地万造名誉会員 訃報
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.286 2015/2/2 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 千地万造 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
日本地質学名誉会員 千地万造氏(大阪市立自然史博物館元館長)が、平成27年1月31日(土)にご逝去されました(享年87歳)。
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
なお、通夜ならびに告別式は、下記のとおり執り行われますので併せてお知らせ申し上げます。
通 夜:平成27年2月2日(月)19時より
告別式:平成27年2月3日(火)11時より(12時出棺)
喪 主:千地広幸様
場 所:ティア岸和田
(596-0045 大阪府岸和田市別所町1-1-33 072-430-6400 南海本線岸和田駅下車すぐ)
*ご香典の儀はご辞退されます。
会長 井龍康文
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.287[長野大会]トピックセッションの募集!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.287 2015/2/3 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[長野大会]トピックセッションの募集
【2】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(火)
【3】日本地質学会名誉会員候補者募集中(2/10締切)
【4】中期ビジョン中間報告と意見募集
【5】広報委員の募集
【6】第6回惑星地球フォトコンテスト:間もなく締め切り!
【7】2015年度春季地質調査研修参加者募集[予告]
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[長野大会]トピックセッションの募集
──────────────────────────────────
日本地質学会行事委員会
第122年学術大会(長野大会)は,中部支部のご協力のもと,信州大学工学部(長野市)をメイン会場として2015年9月11日(金)〜13日(日)に開催されます. 現在,トピックセッションを募集中です.
なお,本大会も前回同様,シンポジウムの一般募集はありません.
※シンポジウムは長野大会実行委員会および学会執行部が企画します.
募集締切:3月16日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0066.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(火)
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は3月31日(火)です.
次年度も割引会費を希望のかたは,忘れずにご提出ください(締切厳守).
※通常の会費払込については,「2015年会費払い込みについて」を参照下さい.
■ 自動引落による納入
昨年12月24日(水)にお届けの金融機関口座より引き落としさせていただきました.通帳記帳等でご確認ください.請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承ください.
■ 郵便振替用紙(またはゆうちょ銀行口座)からのお振り込み
2014年12月15日(月)に請求書兼郵便振替用紙を発送しました.地質学会の会費は前納制ですので,お早めにご送金ください.
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/outline/content0135.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本地質学会名誉会員候補者募集中(2/10締切)
──────────────────────────────────
現在,日本地質学会名誉会員候補者の推薦を募集しています.
下記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することはできませんが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.ぜひ情報をお寄せ下さい。
募集期間:2014年12月17日(水)〜2015年2月10日(火)
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:
例えば,,,
・地質学への顕著な貢献
・地質学会の運営と発展への貢献
・教育現場や企業などでの活動を通じた地質学の普及と振興への貢献
など
名誉会員推薦委員会委員長 山本高司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】中期ビジョン中間報告と意見募集
──────────────────────────────────
中期ビジョンワーキンググループがこれまでに検討した素案を掲載しています.
ご意見,ご助言などございましたらぜひお寄せ下さいますようお願いいたします.
中間報告(前編)はこちらから▼▼
http://www.geosociety.jp/outline/content0148.html
意見募集締切:3月15日(日)
送付先:地質学会事務局(main@geosociety.jp)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】広報委員の募集
──────────────────────────────────
日本地質学会の広報委員会を任期満了に伴いまして委員の交代を行います.
ニュース誌,geo-Flash,ホームページ,ジオルジュ(ライター),ちーとも,プレスリリースなどの学会広報活動に関心があり,ご協力頂けます方はご連絡頂けますようお願いいたします.地質学会広報の更なる飛躍のために,積極的にご参加下さい.
連絡先:地質学会事務局(main@geosociety.jp)
締切:2月18日(水)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】第6回惑星地球フォトコンテスト:応募受付中!
──────────────────────────────────
今年も惑星地球フォトコンテストの作品を募集中です.今回より新たに「ジオ鉄賞」「スマホ賞」を設けました.また,携帯やスマホから画像を添付していただくだけで,手軽にご応募いただけるようになりました.皆様の力作を是非ご応募ください.
たくさんのご応募をお待ちしています.
応募締切:2月16日(月)17時(郵送の場合は同日必着)
賞:最優秀賞1点(賞金5万円),優秀賞1点(賞金2万円),ジオ鉄賞(賞金1万円),スマホ賞(賞金5千円)...など
詳しくは,http://photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】2015年度春季地質調査研修 参加者募集[予告]
──────────────────────────────────
地質調査法の基本技術の修得をめざすとともに,それをベースに得られた過去の調査や研究の成果についても学びます.地質調査の経験のない方でも,地質調査法の基本を体で習得することを目指します.
5月18日(月)〜5月22日(金)4泊5日
研修場所:千葉県君津市及びその周辺地域(房総半島中部域)
募集人数:6名. 参加費:12万円 (CPD:40単位)
募集期間:3月2日(月)〜4月13日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/engineer/content0039.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
──────────────────────────────────
[北海道支部]
■日本地質学会北海道支部平成26年度(2014年度)総会
2月28日(土)14:00〜16:00
場所:北海道大学理学部5号館3階 5-301室
総会:14:00〜16:00
懇親会:17:00〜
問い合わせ先:
北海道支部幹事庶務:沢田 健 sawadak@mail.sci.hokudai.ac.jp
議事次第等、詳細はこちら
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[東北支部 ]
■2014年度東北支部総会・講演会・シンポジウム
3月7日(土)〜8日(日)
7日:シンポジウム
8日:総会・個人講演
場所:岩手大学工学部(盛岡市上田)
問い合わせ先:
支部長:土谷信高 tsuchiya@iwate-u.ac.jp
幹事:越谷 信 koshiya@iwate-u.ac.jp
[関東支部 ]
■「地学教育サミット・ジオパークと教育〜楽しく元気に大地の公園〜」のお知らせ (第一報) 関東支部では関東地方の各ジオパークを、教員の方をはじめ広く一般の方々にも広く知っていただくため、次のように地学教育サミット「ジオパークと教育〜楽しく元気に大地の公園〜」を計画いたしました。皆様、是非ご参加ください。
共催 小田原市、箱根ジオパーク推進協議会
3月15日(日)10:00〜16:00
場所:神奈川県小田原市生涯学習センター けやき 大会議室
参加費:無料、資料代別途(お申し込みは不要ですが資料作成上、事前連絡をお願いする予定です。詳細は第二報にてご連絡いたします)
プログラム概要
午前 基調講演
午後 関東地区各ジオパークからの実践報告・総合討論
問合せ先:神奈川県立生命の星・地球博物館 笠間友博
E-mail:kasama@nh.kanagawa-museum.jp ,FAX:0465-23-8846
[西日本支部]
■平成26年度総会・第166回例会
2月21日(土)[20日:幹事会]
場所:山口大学,吉田キャンパス,大学会館
講演申込締切:2月4日(水)17時
*総会へ欠席の方は,委任状をお送り下さい。
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地質研究所ニュース 2015 Vol. 30 No. 4
http://www.gsh.hro.or.jp/publication/gshnews/news_pdf/vol30_no4.pdf
■第171回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
2月27日(金)18:30〜20:30 [事前予約不要]
場所:北とぴあ901会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分)
講師 :安井真也氏(日本大学文理学部地球システム科学科 准教授)
テーマ :浅間火山の噴火と北関東・利根川下流域・首都圏の災害
CPD:2単位
会費:会員、地質学会会員は500円、非会員は1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■Project A 2015 in Korea
日本地質学会ほか 後援
3月4日(水)〜8日(日)
4日オープニング、5日セッション、6〜8日巡検
会場:韓国(大田広域市)
アブストラクト締切:1月23日(金)
http://archean.jp/
■第4回学生のヒマラヤ野外実習ツアー
日本地質学会等推薦
3月上旬(4日頃)出発,出国から帰国まで15日間
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
■第172回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
3月27日(金)18:30〜20:30 [事前予約不要]
場所:北とぴあ901会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分)
講師 :高橋正樹氏(日本大学文理学部地球システム科学科 教授)
テーマ :箱根火山の噴火と首都圏都市災害—もし東京軽石規模の大規模噴火が起こってしまったら—
CPD:2単位
会費:会員、地質学会会員は500円、非会員は1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■第52回アイソトープ・放射線研究発表会
日本地質学会ほか 共催
7月8日(水)〜10日(金)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1)
発表申込締切:2月27日(金)
講演要旨原稿締切 :4月10日(金)
http://www.jrias.or.jp/
■第13回微量元素の生物地球化学に関する国際会議
13th International Conference on the Biogeochemistry of Trace
Elements, ICOBTE 2015 FUKUOKA
日本地質学会 後援
7月12日(日)〜16日(木)
場所:福岡国際会議場
http://www.icobte2015.org/index.html
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
7月27日(月)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1-1)
早期参加登録締切:2月28日(土)
http://inqua2015.jp/
■第10回アジア地域応用地質学シンポジウム
日本地質学会 後援
研究発表会:9月24日(木)〜25日(金)
シンポジウム:9月26日(土)〜27日(日)[その後巡検予定あり]
場所:京都大学宇治黄檗プラザ
http://2015ars.com/
■Arthur Holmes Meeting Tsunami Hazards and Risks: Using the Geological Record
日本地質学会 共催
9月25日(金)
場所:The Geological Society(英・ロンドン)
http://www.geolsoc.org.uk/ahm15
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0144.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■千葉大学大学院:理学研究科地球生命圏科学専攻地球科学コース(テニュアトラック特任助教)(3/19)
■電力中央研究所:研究系常勤職員募集(3/13)
■海洋研究開発機構:海洋掘削科学研究開発センター沈み込み帯掘削研究グループ(研究員/技術研究員)(3/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-flash No.288[長野大会]トピックセッション募集中!!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.288 2015/2/17 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[長野大会]トピックセッションの募集
【2】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(火)
【3】中期ビジョン中間報告と意見募集
【4】広報委員の募集
【5】平成28年度地震火山こどもサマースクール開催地の公募
【6】第7回日本地学オリンピック予選が全国77会場にて実施!
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞情報等
【10】訃報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[長野大会]トピックセッションの募集
──────────────────────────────────
日本地質学会行事委員会
第122年学術大会(長野大会)は,中部支部のご協力のもと,信州大学工学部(長野市)をメイン会場として2015年9月11日(金)〜13日(日)に開催されます.
現在,トピックセッションを募集中です.
なお,本大会も前回同様,シンポジウムの一般募集はありません.
※シンポジウムは長野大会実行委員会および学会執行部が企画します.
募集締切:3月16日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0066.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(火)
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は3月31日(火)です.
次年度も割引会費を希望のかたは,忘れずにご提出ください(締切厳守).
※通常の会費払込については,「2015年会費払い込みについて」を参照下さい.
■ 自動引落による納入
昨年12月24日(水)にお届けの金融機関口座より引き落としさせていただきました.通帳記帳等でご確認ください.請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承ください.
■ 郵便振替用紙(またはゆうちょ銀行口座)からのお振り込み2014年12月15日(月)に請求書兼郵便振替用紙を発送しました.地質学会の会費は前納制ですので,お早めにご送金ください.
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/outline/content0135.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】中期ビジョン中間報告と意見募集
──────────────────────────────────
中期ビジョンワーキンググループがこれまでに検討した素案を掲載しています.
ご意見,ご助言などをぜひお寄せ下さいますようお願いいたします.
中間報告はこちらから▼▼
http://www.geosociety.jp/outline/content0148.html
[後編追加]
意見募集締切:3月15日(日)
送付先:地質学会事務局(main@geosociety.jp)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】広報委員の募集
──────────────────────────────────
日本地質学会の広報委員会を任期満了に伴いまして委員の交代を行います.
ニュース誌,geo-Flash,ホームページ,ジオルジュ(ライター),ちーとも,プレスリリースなどの学会広報活動に関心があり,ご協力頂けます方はご連絡頂けますようお願いいたします.地質学会広報の更なる飛躍のために,積極的にご参加下さい.
連絡先:地質学会事務局(main@geosociety.jp)
締切:2月18日(水)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】平成28年度地震火山こどもサマースクール開催地の公募
──────────────────────────────────
<各地のジオパークまたはジオパーク候補地関係者,地方自治体等所属の会員のかたへ>
地震火山こどもサマースクールは,1999年夏から小・中・高校生を対象にはじまった行事で,現在,日本地震学会,日本火山学会,日本地質学会が共同で実施する,地球科学関連では最大規模の体験学習講座です.
今回,平成28年度(2016年度)に実施する第17回の開催地を公募いたします.
各地のジオパークやジオパーク候補地をはじめとして,開催をご希望されるところがありましたら,ぜひご応募ください.
応募資格:地震火山こどもサマースクールの主旨に賛同し,現地事務局を設置できる団体.
募集締切:3月4日(水)
応募資格の詳細,申込方法など詳しくは,
http://www.zisin.jp/modules/pico/index.php?content_id=3086
過去の開催内容などについては,
http://www.kodomoss.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】第7回日本地学オリンピック予選が全国77会場にて実施!
──────────────────────────────────
過去最高の受験者1868名が、2014年12月21日に2時間にわたるマークシート方式の試験に挑戦しました。
3月15日(日)〜17日(火)には、予選合格者約60名が参加する第7回日本地学オリンピック本選(グランプリちきゅうにわくわく2015)が茨城県つくば市にて開催されます。
大会期間中の「とっぷ・レクチャー」(3月15日13時〜)は、一般のみなさま(先着250名様まで)にも参加していただける講演会です。
とっぷ・レクチャーの概要や申し込み方法は、下記URLの「最新のお知らせ」をご覧ください。
詳しくはこちらから >>> http://jeso.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[北海道支部]
■日本地質学会北海道支部平成26年度(2014年度)総会
2月28日(土)14:00〜16:00
場所:北海道大学理学部5号館3階 5-301室
総会:14:00〜16:00
懇親会:17:00〜
問い合わせ先:
北海道支部幹事庶務:沢田 健 sawadak@mail.sci.hokudai.ac.jp
議事次第等、詳細はこちら
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[東北支部 ]
■2014年度東北支部総会・講演会・シンポジウム
3月7日(土)〜8日(日)
7日:シンポジウム, 8日:総会・個人講演
場所:岩手大学工学部(盛岡市上田)
問い合わせ先:
支部長:土谷信高 tsuchiya@iwate-u.ac.jp
幹事:越谷 信 koshiya@iwate-u.ac.jp
[関東支部 ]
■地学教育サミット・ジオパークと教育〜楽しく元気に大地の公園〜
3月15日(日)10:00〜16:00
場所:神奈川県小田原市生涯学習センター けやき 大会議室
参加費無料、資料代別途1,500円
申込不要。ただし資料準備のため、できるだけ事前連絡を。[3月5日(木)締切]
問合せ先:
関東支部幹事長:笠間友博 kasama@nh.kanagawa-museum.jp
■2015年度総会・地質技術伝承講演会
4月18日(土)14:00〜16:45(13:30受付)
場所:北とぴあ 7階 第1研修室(東京都北区王子1-11-1)
14:00〜15:40地質技術伝承講演会[参加費無料、CPD単位(2.0)]
申込・問い合わせ:加藤 潔 kiyoshi.katoh@gmail.com
15:50〜16:45関東支部総会
*支部会員の方で総会へ欠席の方は,委任状をお送り下さい。
関東支部 kanto@geosociety.jp[4月18日(金)午後6時締切]
各行事の詳細、委任状等はこちらから
http://kanto.geosociety.jp/
[西日本支部]
■平成26年度総会・第166回例会
2月21日(土)[20日:幹事会]
場所:山口大学,吉田キャンパス,大学会館
*総会へ欠席の方は,委任状をお送り下さい。
詳しくはこちら
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第171回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
2月27日(金)18:30〜20:30 [事前予約不要]
場所:北とぴあ901会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分)
講師 :安井真也氏(日本大学文理学部地球システム科学科 准教授)
テーマ :浅間火山の噴火と北関東・利根川下流域・首都圏の災害
CPD:2単位
会費:会員、地質学会会員は500円、非会員は1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■第10回海と地球の研究所セミナー
有人潜水調査船「しんかい6500」完成25周年
2月28日(土)13:30〜16:30
場所:神戸海洋博物館
参加無料、事前登録制、限定250名
http://www.jamstec.go.jp/j/pr/pr_seminar/010/
■Project A 2015 in Korea
日本地質学会ほか 後援
3月4日(水)〜8日(日)
4日オープニング、5日セッション、6〜8日巡検
会場:韓国(大田広域市)
http://archean.jp/
■平成26年度研究報告会「JAMSTEC2015」
3月4日(水)13:00〜17:30
会場:東京国際フォーラム ホールB7(東京都千代田区丸の内3-5-1)
http://www.jamstec.go.jp/j/pr/event/jamstec2015/
■第4回学生のヒマラヤ野外実習ツアー
日本地質学会等推薦
3月上旬(4日頃)出発,出国から帰国まで15日間
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
■第164回深田研談話会「進化学のモデル生物としても放散虫」
3月6日(金)15:00〜17:00(14:30会場)
申込締切:3月4日(水) 先着:80名 参加無料
会場:深田地質研究所 研修ホール(文京区本駒込2-13-12)
http://www.fgi.or.jp/
■三朝国際シンポジウム Comprehensive Exploration of the Solar System: Sample Return and Analysis
3月6日(金)〜8日(日)
場所:鳥取県三朝町、ブランナール三朝 *旅費サポート可
http://sympo.misasa.okayama-u.ac.jp/misasa_v/?page_id=30&lang=ja
■海洋資源開発フォーラム
3月11日(水)
会場:ANAクラウンプラザホテル神戸(神戸市中央区北野町1-1)
申込締切:2月25日(水) 参加無料
http://www.nipponkaiko.co.jp/shiryou/forum_info.pdf
■研究船による研究成果発表会「ブルーアース2015」
3月19日(木)〜20日(金)
場所:東京海洋大学 品川キャンパス 白鷹館 講義棟(東京都港区港南4-5-7)
http://www.jamstec.go.jp/maritec/j/blueearth/2015/
■第172回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
3月27日(金)18:30〜20:30 [事前予約不要]
場所:北とぴあ901会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分)
講師 :高橋正樹氏(日本大学文理学部地球システム科学科 教授)
テーマ :箱根火山の噴火と首都圏都市災害
—もし東京軽石規模の大規模噴火が起こってしまったら—
CPD:2単位
会費:会員、地質学会会員は500円、非会員は1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■第15回アジア学術会議カンボジア会合国際シンポジウム
5月15日(金)〜16日(土)
会場:Angkor Paradise hotel(シェムリアップ、カンボジア)
2月21日:論文要旨提出期限【提出期限の再延長】
2月28日:審査結果通知
4月1日:論文(Full Paper)提出期限
http://www.itc.edu.kh/meeting/
■第52回アイソトープ・放射線研究発表会
日本地質学会ほか 共催
7月8日(水)〜10日(金)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1)
発表申込締切:2月27日(金)
講演要旨原稿締切 :4月10日(金)
http://www.jrias.or.jp/
■第13回微量元素の生物地球化学に関する国際会議
13th International Conference on the Biogeochemistry of Trace
Elements, ICOBTE 2015 FUKUOKA
日本地質学会 後援
7月12日(日)〜16日(木)
場所:福岡国際会議場
http://www.icobte2015.org/index.html
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
7月27日(月)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1-1)
早期参加登録締切:2月28日(土)
http://inqua2015.jp/
■第32回歴史地震研究会
9月21日(月・祝)〜23日(水・祝)
会場:京丹後市峰山総合福祉センター(京都府京丹後市)
講演申込締切:5月29日(金)
巡検等申込・講演要旨投稿締切:7月31日(金)
http://sakuya.ed.shizuoka.ac.jp/rzisin/menu7.html
■第10回アジア地域応用地質学シンポジウム
日本地質学会 後援
研究発表会:9月24日(木)〜25日(金)
シンポジウム:9月26日(土)〜27日(日)[その後巡検予定あり]
場所:京都大学宇治黄檗プラザ
http://2015ars.com/
■Arthur Holmes Meeting Tsunami Hazards and Risks: Using the Geological Record
日本地質学会 共催
9月25日(金)
場所:The Geological Society(英・ロンドン)
プレ巡検:9月22日(火)〜23日(水)
http://www.geolsoc.org.uk/ahm15
■第30回ヒマラヤ・カラコルム・チベットワークショップ(30th HKT 2015)
10月6日(火)〜8日(木)
場所:Wadia Institute, Dehra Dun, India
プレ野外巡検:10月5日(月)
ポスト野外巡検:10月9日(金)〜12日(月)
参加申込締切:7月30日(木)
講演要旨締切:8月20日(火)
http://www.hktwadia2015.org/
■国際ゴンドワナ研究連合(IAGR)2015年総会及び第12回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム
10月21日(水)〜23日(金)
場所:筑波大学
野外巡検:10月24日(土)〜25日(日)
巡検コース:峰岡オフィオライト等
講演要旨締切:6月30日(火)
http://www.geol.tsukuba.ac.jp/~gansekihp/IAGR2015/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0144.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■神戸大学自然科学系先端融合研究環重点研究チーム「水の起源と惑星進化における役割の解析」(助教)(4/30)
■国土地理協会平成27年度学術研究助成(4/1〜4/17)
■第12回 (平成27年度)「日本学術振興会賞」受賞候補者推薦募集(学会締切3/31)
■2015年度地球化学研究協会学術賞「三宅賞」および「進歩賞」候補者の募集(8/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】訃報:斎藤昌之 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
日本地質学会名誉会員 斎藤昌之氏(元北海道立地下資源調査所所長,(株)ユニオンコンサルタント)が、平成26年11月26日にご逝去されました(享年96歳)。
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます。なお、ご葬儀などはすでに執り行われたとのことです。
会員の皆様に、謹んで御連絡申し上げます。
会長 井龍康文
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
第35回万国地質学会議(IGC)ほかのご案内
第35回万国地質学会議(IGC)ほかのご案内
小川 勇二郎(会員、国際地質科学連合理事)
かねてからご案内の通り、第35回万国地質学会議(IGC; http://www.iugs.org)は、2016年8月27日〜9月4日に南アフリカ共和国のケープタウンの国際コンベンションセンターで開催されるが(http://www.35igc.org/)、その準備状況が、本年1月の国際地質科学連合(IUGS)理事会で説明された。主たるテーマは、以下の3つである。
Geoscience for society, Fundamental geoscience, Geoscience in the economy。
その後の連絡によると、本年5月末締め切りで、セッションやワークショップ、ショートコースなどの提案の申し込みを受け付けるとのことで、各国の多くの方々に周知してほしいとのことであった。それらの詳細は、以下のHPから知ることができる(https://www.allevents.co.za/ei/getdemo.ei?id=222&s=_3F00S0JZ9)。また、周辺諸国を含む地域での多くの巡検も計画されているので、会員の方々をはじめ多くの方々にご参加をお願いしたい。今回を含め、このところ安定大陸での開催が続いているIGCではあるが、我々になじみの深い衝突・沈み込み帯をはじめとする活動的縁辺地域、海洋、環境問題などに関しても、多くのセッションを開きたい、とのことである。また、第36回IGCは、2020年3月2日〜8日に、インドのニュー・デリー近郊のエクスポセンターで、インドの主導、周辺の4か国(ネパール、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ)との協力で行うとのことである(http://www.36igc.org/)。
最近、国際学術会議(ICSU, http://www.icsu.org/)では、多くの地球惑星科学関連のユニオンの統合や学会の共同開催が議論されている。IUGSの行う4年毎のIGCに関しても、中間の2年目ごとに国際測地地球物理学連合(IUGG)との共同学会も模索されていたが、2018年6月には、資源(金属、エネルギーおよび水)に絞った形で、IUGS内部にあるResources for Future Generation(RFG)なるイニシアチブの主導により、カナダのバンクーバーでIUGS主催の国際学会を行うこととなった。つまり今後5年間で、都合2016, 2018, 2020年の3回のIUGSによる大規模な国際学会が開かれることになる。皆様の一層のご関心をお願いしたい。また、第37回IGCは2024年(または2023年、詳細は未定)に開催される予定であるが、すでに立候補の問い合わせがあるとのことである。
なお、1月に開かれたIUGS理事会の主要議事に関しては、IUGSのE-Bulletinで、そのハイライトを見ることができる (http://iugs.org/uploads/IUGS%20E-Bulletin%20104.pdf#search='Cadada+Geology+Vancouver+2018')。詳細は、小川(fyogawa45@yahoo.co.jp)までお問い合わせ下さい。
(2015.2.23)
geo-flash No.291 割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.291 2015/3/17 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(火)
【2】2015年度春季地質調査研修 参加者募集中
【3】Arthur Holmes Meeting Tsunami Hazards and Risks: Using the Geological Record
【4】地質の日イベント情報
【5】紹介:Episodes特集号 "Geohazards in Subduction Zone Environments and their Implications for Science and Society"
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(火)
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は3月31日(火)です.
次年度も割引会費を希望のかたは,忘れずにご提出ください(締切厳守).
※通常の会費払込については,「2015年会費払い込みについて」を参照下さい.
■ 自動引落による納入
昨年12月24日(水)にお届けの金融機関口座より引き落としさせていただきました.通帳記帳等でご確認ください.請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承ください.
■ 郵便振替用紙(またはゆうちょ銀行口座)からのお振り込み
2014年12月15日(月)に請求書兼郵便振替用紙を発送しました.地質学会の会費は前納制ですので,お早めにご送金ください.
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/outline/content0135.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2015年度春季地質調査研修 参加者募集中
──────────────────────────────────
地質調査法の基本技術の修得をめざすとともに,それをベースに得られた過去の調査や研究の成果についても学びます.地質調査の経験のない方でも,地質調査法の基本を体で習得することを目指します.
5月18日(月)〜5月22日(金)4泊5日
研修場所:千葉県君津市及びその周辺地域(房総半島中部域)
募集人数:6名. 参加費:12万円 (CPD:40単位)
募集締切:4月13日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/engineer/content0039.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】Arthur Holmes Meeting Tsunami Hazards and Risks: Using the Geological Record
──────────────────────────────────
The Geological Society of London(GSL)・日本地質学会 共催
9月25日(金)
場所:The Geological Society (Burlington House)(英・ロンドン)
プレ巡検:ストレッガスライド津波堆積物など
9月22日(火)〜24日(木)
◆ポスター発表募集中:8月7日(金)締切(要旨提出を含む)
◆若手研究者への渡航費用の助成:専用の申請用紙に必要事項を記入のうえ担当者までメールで送信して下さい.
4月17日(金)17時(現地時間)締切
シンポジウムのプログラム,巡検概要,費用助成の申請用紙など,詳細はシンポHPをご覧下さい.
http://www.geolsoc.org.uk/ahm15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地質の日イベント情報
──────────────────────────────────
■近畿支部
第32回地球科学講演会「阪神淡路大震災以降の近畿の活断層研究」
5月10日(日)13:30〜15:30 (受付:12:30〜)
場所:大阪市立自然史博物館 講堂
講師:岡田篤正氏(京都大学名誉教授・立命館大学客員研究員)
定員:250名(先着順)申込不要/参加費無料(博物館入館料必要)
問い合わせ先:大阪市立自然史博物館
TEL: 06-6697-6221 FAX: 06-6697-6225
E-mail: monitor@mus-nh.city.osaka.jp
地質の日イベントの各詳細はこちらから.
http://www.geosociety.jp/name/content0128.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】紹介:Episodes特集号 "Geohazards in Subduction Zone Environments and their Implications for Science and Society"
──────────────────────────────────
国際地質学連合IUGSのEpisodes2014年12月号(vol. 37, No.4)に,2013年10月に仙台市で開催された第2回G-EVER国際シンポジウム,第1回IUGS・日本学術会議国際ワークショップの特集号が掲載されました.この際に採択された"Sendai Agreement"も掲載されています(オープンアクセス).是非ご覧ください.
http://www.episodes.co.in/index.php/epi/issue/current
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部 ]
■2015年度総会・地質技術伝承講演会
4月18日(土)14:00〜16:45(13:30受付)
場所:北とぴあ 7階 第1研修室(東京都北区王子1-11-1)
14:00〜15:40地質技術伝承講演会[参加費無料、CPD単位(2.0)]
申込・問い合わせ:加藤 潔 kiyoshi.katoh@gmail.com
15:50〜16:45関東支部総会
*支部会員の方で総会へ欠席の方は,委任状をお送り下さい。
関東支部 kanto@geosociety.jp[4月17日(金)18時締切]
各行事の詳細、委任状等はこちらから
http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第172回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
3月27日(金)18:30〜20:30 [事前予約不要]
場所:北とぴあ901会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分)
講師 :高橋正樹氏(日本大学文理学部地球システム科学科 教授)
テーマ :箱根火山の噴火と首都圏都市災害
—もし東京軽石規模の大規模噴火が起こってしまったら—
CPD:2単位
会費:会員、地質学会会員は500円、非会員は1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■シンポジウム:環境資源システムを支えるジオサイエンス
5月8日(金)9:30〜17:00
場所:早稲田大学理工キャンパス63号館2F(03会議室)
会費:無料(要登録)
https://sites.google.com/site/geosciencetokyo/home
■第52回アイソトープ・放射線研究発表会
日本地質学会ほか 共催
7月8日(水)〜10日(金)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1)
講演要旨原稿締切 :4月10日(金)
http://www.jrias.or.jp/
■第13回微量元素の生物地球化学に関する国際会議
13th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements, ICOBTE 2015 FUKUOKA
日本地質学会 後援
7月12日(日)〜16日(木)
場所:福岡国際会議場
http://www.icobte2015.org/index.html
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
7月26日(日)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1-1)
通常参加登録締切:6月30日(火)
http://inqua2015.jp/
■日本ジオパークネットワークガイドフォーラム
9月15日(火)〜16日(水)
会場:アミティ丹後(京都府京丹後市網野町網野367)
バーチャルジオツアー発表者応募締切:5月29日(金)
参加登録締切:7月31日(金)
http://jgn2015.com/
■第4回アジア太平洋ジオパークネットワーク山陰海岸シンポジウム
日本地質学会ほか 後援
9月15日(火)〜20日(日)
会場:豊岡市民会館(豊岡市立野町20-34)ほか
発表要旨締切:4月30日(木)
早期参加登録締切:4月30日(木)
通常参加登録締切:7月31日(金)
http://apgn2015-jpn.com/
■第10回アジア地域応用地質学シンポジウム
日本地質学会 後援
研究発表会:9月24日(木)〜25日(金)
シンポジウム:9月26日(土)〜27日(日)[その後巡検予定あり]
場所:京都大学宇治黄檗プラザ
http://2015ars.com/
■Arthur Holmes Meeting Tsunami Hazards and Risks: Using the Geological Record
日本地質学会 共催
9月25日(金)
場所:The Geological Society (Burlington House)(英・ロンドン)
プレ巡検:9月22日(火)〜24日(木)
ポスター発表申込/要旨提出締切:8月7日(金)
若手研究者渡航費用助成:4月17日(金)17時(現地時間)締切
http://www.geolsoc.org.uk/ahm15
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0144.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■島根大学大学院:総合理工学研究科 留学生受入れに伴う専門教育教員(講師)公募(4/30)
■室戸ジオパーク推進協議会:ジオパーク専門員募集(3/26)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flash No.293(臨時)野沢 保名誉会員 訃報
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.293 2015/03/30 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 野沢 保 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
野沢 保 名誉会員(元日本地質学会会長)が,平成27年3月28日(土)
にご逝去されました(享年91歳)。
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げ
ます。なお,ご葬儀は,近親者のみで執り行われるとのことです.
会長 井龍 康文
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
全国天然記念物めぐり(TOP)
全国天然記念物めぐり:都道府県指定の地質・鉱物天然記念物一覧
【北海道】・【東北】・【関東】・【中部】・【近畿】・【四国】・【中国】・【九州 沖縄】
*エリア名をクリックすると各地の天然記念物一覧がご覧いただけます。
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
昨年末より「県の石」の選定作業が進められている。多様性に富んだ日本列島の表層地質からシンボリックな「石」(岩石・鉱物・化石)を行政区分の単位で選ぼうという大胆な試みである。この事業は一見、アメリカ合衆国の「州の岩石・鉱物・宝石」の模倣の印象も与える。しかし、日本地質学会という学術コミュニティーが事業を企画し、一般応募を含む沢山の候補の中から専門家集団が全都道府県の「石」を一度に選定する点で大きく異なる。各都道府県から1つずつという縛りのなかで専門家集団が知恵とアイデアを駆使して学術性兼ストーリー性のある「県の石」を選定すれば、社会における地質学リテラシー向上と地質学の社会的地位向上の他、「県の石」は日本列島の構成岩石と地史を国内外に分かりやすく概説する一つの手段になりえよう。
これまでに都道府県のシンボルとして「花」・「木」・「鳥」(一部で「獣」・「魚」)はあったが、「石」は定められてこなかった。一方、国指定及び広域・地方自治体指定の文化財には地質・鉱物の天然記念物及びそれに関係した名勝が沢山存在する。日本地質学会が「県の石」を提唱した後に各都道府県がそれを定めるかは別問題ではあるが、「県の石」事業は郷土の天然記念物(地質・鉱物)を再訪するきっかけとなろう。ところが我々地質コミュニティーが郷土の天然記念物に詳しいかというと必ずしもそうではなさそうである。特に、都道府県指定の天然記念物となるとかなり難しい。
国指定(文部科学大臣が指定)の天然記念物は郷土の観光案内、書籍やインターネットを通じて比較的広く知られる。例えば、ウィキペディアには「地質・鉱物天然記念物一覧」という記事が存在する(2015年3月現在)。その共同編集による情報は完全なものではないが1つのページに集約されている。日本地質学会ホームページのe-フェンスターには「天然記念物(地質鉱物編)めぐり」(2007年11月7日更新)が奥平会員(大阪市大)によって投稿されており、国が定めた天然記念物とその指定基準などがまとめられている。これまでに秋田県(2008年7月1日更新)・福岡県(2009年10月6日更新)・滋賀県(2008年6月25日更新)・京都府(2007年12月14日更新)・和歌山県(2008年1月22日更新)の5つが有志によって投稿されているので、そちらも参照されたい。ところが各都道府県指定の天然記念物をまとめて知ろうとすると簡単ではない。全都道府県指定の天然記念物を1つのリストにまとめた情報源は日本地質学会にも存在せず、各広域自治体のホームページを1つ1つ探していくしかない。ウィキペディアには「都道府県指定文化財一覧」という記事(2015年3月現在)があって、それぞれの自治体毎の記事が個別に共同編集されつつあるが、不完全である。
さて、「県の石」には一般公募を中心に沢山の候補が寄せられた。その中には国や都道府県指定の天然記念物も多々存在した。選定委員会は全ての候補が地質学的にどういった素性の「石」なのかを通覧する形で情報収集した。その一連の作業において各都道府県が定めた地質・鉱物関係の天然記念物を一覧にまとめたので、ここに紹介したい。
本一覧は2015年1月時点での情報をまとめたものである。一覧には国指定の天然記念物についても都道府県毎に列挙した。文化財指定の日付の情報については未完成であり、今後の更新が必要である。一覧については各都道府県の文化財担当課に問い合わせをして間違いや欠落を訂正して頂いた。ここに感謝する。
2015年3月26日
辻森 樹
ページtopに戻る
北海道
北海道
<特別天然記念物> 昭和新山 〔北海道有珠郡壮瞥町〕 1951年6月9日指定、1957年6月19日特別指定
<天然記念物> エゾミカサリュウ化石 〔三笠市〕 1977年7月16日指定
<天然記念物> オンネトー湯の滝マンガン酸化物生成地 〔足寄郡足寄町〕 2000年9月6日指定
<天然記念物> 名寄鈴石 〔名寄市〕 1939年9月7日指定
<天然記念物> 名寄高師小僧 〔名寄市〕 1939年9月7日指定
<天然記念物> 根室車石 〔根室市〕 1939年9月7日指定
<天然記念物> 夕張岳の高山植物群落および蛇紋岩メランジュ帯 〔夕張市・空知郡南富良野町〕 1996年6月19日指定
<北海道指定天然記念物> 二股温泉の石灰華 〔長万部町〕 1965年6月14日指定
<北海道指定天然記念物> 乙部鮪ノ岬の安山岩柱状節理 〔乙部町〕 1972年4月1日指定
<北海道指定天然記念物> 空知大滝甌穴群 〔芦別市〕 2013月8月15日指定
<北海道指定天然記念物> 夕張の石炭大露頭 〔夕張市〕 1979年12月6日指定
<北海道指定天然記念物> 当麻鍾乳洞 〔当麻町〕 1961年3月17日指定
<北海道指定天然記念物> 中頓別鍾乳洞 〔中頓別町〕 1957年1月29日指定
<北海道指定天然記念物> 白滝の流紋岩球顆 〔遠軽町〕 1991年3月30日指定
<北海道指定天然記念物> オシュンコシュン粗粒玄武岩柱状節理 〔斜里町〕 1973年3月14日指定
<北海道指定天然記念物> 樽前山熔岩円頂丘 〔苫小牧市〕 1967年3月17日指定
<北海道指定天然記念物> 新冠泥火山 〔新冠町〕 1968年1月18日指定
<北海道指定天然記念物> タキカワカイギュウ化石標本 〔滝川市〕 1984年3月12日指定
東北
青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県(県名をクリックすると各都道府県の情報に移動します)
青森県
<名勝及び天然記念物> 仏宇多(仏ヶ浦) 〔下北郡佐井村〕 1941年4月23日指定
<青森県指定天然記念物> 赤根沢の赤岩 〔今別町〕 1955年1月7日指定
<青森県指定天然記念物> 金木町玉鹿石 〔五所川原市金木町〕 1980年1月24日指定
岩手県
<特別天然記念物> 夏油温泉の石灰華 〔北上市〕 1941年2月28日指定、1957年6月19日特別指定
<特別天然記念物> 根反の大珪化木 〔二戸郡一戸町〕 1936年12月16日指定、1952年3月29日特別指定
<特別天然記念物> 焼走り熔岩流 〔八幡平市〕 1944年11月7日指定、1952年3月29日特別指定
<特別天然記念物> 蛇ヶ崎 〔陸前高田市〕 1936年12月16日指定
<天然記念物> 安家洞 〔下閉伊郡岩泉町〕 1975年2月7日指定
<天然記念物> 岩泉湧窟およびコウモリ 〔下閉伊郡岩泉町〕 1938年12月14日指定
<名勝及び天然記念物> 厳美渓 〔一関市〕 1927年9月5日指定
<天然記念物> 浪打峠の交叉層 〔二戸郡一戸町〕 1941年8月1日指定
<天然記念物> 姉帯・小鳥谷・根反の珪化木地帯 〔二戸郡一戸町〕 1941年2月21日指定
<天然記念物> 葛根田の大岩屋 〔岩手郡雫石町〕 1943年2月19日指定
<天然記念物> 館ヶ崎角岩岩脈 〔大船渡市〕 1939年9月7日指定
<天然記念物> 樋口沢ゴトランド紀化石産地 〔大船渡市〕 1957年5月8日指定
<名勝及び天然記念物> 碁石海岸 〔大船渡市〕 1937年6月15日指定
<天然記念物> 崎山の潮吹穴 〔宮古市〕 1939年9月7日指定
<天然記念物> 崎山の蝋燭岩 〔宮古市〕 1939年9月7日指定
<岩手県指定天然記念物> 藤里の珪化木 〔奥州市江刺区藤里字石名田〕 1963年12月24日指定
<岩手県指定天然記念物> コランダム産地 〔一関市大東町鳥海字向前畑〕 1965年3月19日指定
<岩手県指定天然記念物> 内間木洞及び洞内動物群 〔久慈市山形町大字小国〕 1966年3月8日指定
<岩手県指定天然記念物> 田野畑の白亜紀化石産地 〔田野畑村大字田野畑〕 1966年3月8日指定
<岩手県指定天然記念物> 三王岩 〔宮古市田老字青砂里〕 1992年9月4日指定
<岩手県指定天然記念物及び植物> 天狗森の夏氷山風穴 〔八幡平市天狗森国有林〕 1974年2月15日指定
ページtopに戻る
宮城県
<特別天然記念物> 鬼首の雌釜および雄釜間歇温泉 〔大崎市〕 1933年4月13日指定、1952年特別指定
<天然記念物> 十八鳴浜及び九九鳴き浜 〔気仙沼市〕 2011年9月21日指定
<天然記念物> 歌津館崎の魚竜化石産地および魚竜化石 〔本吉郡南三陸町〕 1975年8月2日指定
<天然記念物> 球状閃緑岩 〔白石市〕 1923年3月7日指定
<天然記念物> 小原の材木岩 〔白石市〕 1934年5月1日指定
<天然記念物> 姉滝 〔仙台市太白区〕 1934年8月9日指定
<宮城県指定天然記念物> 球状斑糲岩 〔牡鹿郡女川町〕
<宮城県指定天然記念物> 岩井崎石灰岩化石 〔気仙沼市〕
秋田県
<特別天然記念物> 玉川温泉の北投石 〔仙北市〕 1922年10月12日指定、1952年3月29日特別指定
<特別名勝及び天然記念物> 十和田湖および奥入瀬渓流 〔十和田市〕 1928年4月指定、1952年3月29日特別指定
<天然記念物> 象潟 〔にかほ市〕 1934年1月22日指定
<天然記念物> 鳥海山獅子ヶ鼻湿原植物群落及び新山溶岩流末端崖と湧水群 〔にかほ市〕 2001年1月29日指定
<天然記念物> 千屋断層 〔仙北郡美郷町〕 1995年2月14日指定
<天然記念物> 男鹿目潟火山群一ノ目潟 〔男鹿市〕 2007年7月26日指定
<天然記念物> 筑紫森岩脈 〔秋田市〕 1938年8月8日指定
<天然記念物> 鮞状珪石および噴泉塔 〔湯沢市〕 1925年12月9日指定
<秋田県指定天然記念物> 男鹿目潟火山群三ノ目潟 〔男鹿市〕
山形県
<山形県指定天然記念物> 小国のそろばん玉石 〔東北森林管理局小国事業区〕 1962年1月12日指定
<山形県指定天然記念物> ひとでの化石 〔山形市霞城町〕 1962年1月12日指定
<山形県指定天然記念物> ヤマガタダイカイギュウ化石 〔山形市霞城町〕 1992年8月28日指定
福島県
<天然記念物> 鹿島神社のペグマタイト岩脈 〔郡山市〕 1936年4月17日指定
<天然記念物> 入水鍾乳洞 〔田村市〕 1937年2月5日指定
<天然記念物> 塔のヘツリ 〔南会津郡下郷町〕 1957年6月26日指定
<天然記念物> 見彌の大石 〔耶麻郡猪苗代町〕 1941年10月3日指定
<福島県指定天然記念物> 束松塩坪層の漣痕 〔西会津町〕
<福島県指定天然記念物> 穴原の第三期漣痕 〔福島市〕
<福島県指定天然記念物> 球状花崗岩 〔石川郡石川町〕
<福島県指定天然記念物> 石川のペグマタイト鉱物 〔石川郡石川町〕
ページtopに戻る
関東
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県(県名をクリックすると各都道府県の情報に移動します)
茨城県
<茨城県指定天然記念物> 鏡岩 〔常陸大宮市照山〕
<茨城県指定天然記念物> 球状花崗岩 〔石岡市吉生〕
<茨城県指定天然記念物> 平磯白亜紀層 〔ひたちなか市平磯海岸〕
栃木県
<天然記念物> 湯沢噴泉塔 〔日光市〕 1922年3月8日指定
<天然記念物> 名草の巨石群 〔足利市〕 1939年9月7日指定
群馬県
<特別天然記念物> 浅間山熔岩樹型 〔吾妻郡嬬恋村〕 1940年8月30日指定、1952年特別指定
<名勝及び天然記念物> 三波石峡 〔藤岡市〕 1957年7月3日指定
<天然記念物> 岩神の飛石 〔前橋市〕 1938年12月14日指定
<天然記念物> 生犬穴 〔多野郡上野村〕 1938年12月14日指定
<天然記念物> 上野村亀甲石産地 〔多野郡上野村〕 1938年8月8日指定
<天然記念物> 川原湯岩脈(臥龍岩および昇龍岩) 〔吾妻郡長野原町〕 1934年12月28日指定
<天然記念物及び名勝> 吹割渓ならびに吹割瀑 〔沼田市〕 1936年12月16日指定
<群馬県指定名勝及び天然記念物> 川手山洞窟群及びズニ石 〔利根郡みなかみ町〕
<群馬県指定天然記念物及び名勝> 蝉の渓谷 〔南牧川流域(南牧村大字砥沢字東畝から同字甲斐無付近までの河川)〕
<群馬県指定天然記念物及び名勝> 線ヶ滝 〔星尾川支流域(南牧村大字星尾字線ヶ上付近の河川敷)〕
<群馬県指定天然記念物> 金島の浅間石 〔渋川市〕
<群馬県指定天然記念物> 不二洞 〔多野郡上野村〕
<群馬県指定天然記念物> 瀬林の漣痕 〔多野郡神流町〕
<群馬県指定天然記念物> 四万の甌穴群 〔吾妻郡中之条町〕
<群馬県指定天然記念物> 野栗の材化石 〔多野郡上野村〕
<群馬県指定天然記念物> 兜岩層産出のカエル化石 〔富岡市〕
<群馬県指定天然記念物> オオツノシカの化石骨 〔富岡市〕
<群馬県指定天然記念物> 高崎市吉井町産出のジョウモウクジラ化石 〔富岡市〕
埼玉県
<特別天然記念物> 御岳の鏡岩 〔児玉郡神川町〕 1940年8月30日指定、1956年特別指定
<天然記念物> 長瀞 〔秩父郡長瀞町・皆野町〕 1924年12月9日指定
<名勝及び天然記念物> 三波石峡 〔児玉郡神川町〕 1957年7月3日指定
<埼玉県指定天然記念物> 古寺鍾乳洞 〔比企郡小川町〕 1936年
<埼玉県指定天然記念物> 橋立鍾乳洞 〔秩父市〕 1936年
<埼玉県指定天然記念物> 若御子断層洞及び断層群 〔秩父市〕 1960年
<埼玉県指定天然記念物> 前原の不整合 〔秩父郡皆野町〕 1995年
<埼玉県指定天然記念物> 犬木の不整合 〔秩父郡小鹿野町〕 1995年
<埼玉県指定天然記念物> 秩父市大野原産出パレオパラドキシア骨格化石 〔秩父郡長瀞町〕 1999年
<埼玉県指定天然記念物> 小鹿野町般若産出パレオパラドキシア骨格化石 〔秩父郡長瀞町〕 1999年
<埼玉県指定天然記念物> 川本町産出カルカロドン メガロドンの歯群化石 〔秩父郡長瀞町〕 2003年
<埼玉県指定天然記念物> 川本町産出カルカロドン メガロドンの歯群化石 〔比企郡嵐山町〕 2003年
<埼玉県指定天然記念物> 川本町産出カルカロドン メガロドンの歯群化石 〔東松山市〕 2003年
<埼玉県指定天然記念物> 狭山市笹井産出アケボノゾウ骨格化石 〔秩父郡長瀞町〕 2003年
<埼玉県指定天然記念物> 狭山市笹井産出アケボノゾウ骨格化石 〔狭山市〕 2003年
<埼玉県指定天然記念物> 大野原産チチブクジラ骨格化石 〔秩父郡長瀞町〕 2005年
<埼玉県指定天然記念物> 荒川の青岩礫岩 〔大里郡寄居町〕 2012年
<埼玉県指定天然記念物> 中川低地の河畔砂丘群 志多見砂丘 〔加須市〕 2014年
ページtopに戻る
千葉県
<天然記念物> 犬吠埼の白亜紀浅海堆積物 〔銚子市〕 2002年3月19日指定
<天然記念物> 木下貝層 〔印西市〕 2002年3月19日指定
<千葉県指定天然記念物> 袖ケ浦市吉野田の清川層産出の脊椎動物化石 〔千葉市〕
<千葉県指定天然記念物> 上岩橋貝層 〔印旛郡酒々井町〕
<千葉県指定天然記念物> 千騎ケ岩 〔銚子市〕
<千葉県指定天然記念物> 犬吠埼産出のアンモナイト 〔銚子市〕
<千葉県指定天然記念物> 沼サンゴ層 〔館山市〕
<千葉県指定天然記念物> 布良の海食洞と鐘乳石 〔館山市〕
<千葉県指定天然記念物> 鴨川の枕状溶岩 〔鴨川市〕
<千葉県指定天然記念物> 白浜の鍾乳洞 〔南房総市〕
<千葉県指定天然記念物> 白浜の屏風岩 〔南房総市〕
<千葉県指定天然記念物> 白浜のシロウリガイ化石露頭 〔南房総市〕
<千葉県指定天然記念物> 南房総の地震隆起段丘 〔南房総市〕
東京都
<天然記念物> 小笠原南島の沈水カルスト地形 〔小笠原村〕
<東京都指定天然記念物> 大岳鍾乳洞 〔あきる野市〕
<東京都指定天然記念物> 南沢の鳥ノ巣石灰岩産地 〔あきる野市〕
<東京都指定天然記念物> 秋川の六枚屏風岩 〔あきる野市〕
<東京都指定天然記念物> 岩井のエントモノチス化石産地 〔日の出町〕
<東京都指定天然記念物> 神戸岩 〔檜原村〕
<東京都指定天然記念物> 白髭大岩 〔奥多摩町〕
<東京都指定天然記念物> 日原鍾乳洞 〔奥多摩町〕
<東京都指定天然記念物> 潮吹の鼻 〔大島町〕
<東京都指定天然記念物> おたいね浦の岩脈と筆島 〔大島町〕
<東京都指定天然記念物> 三宅島椎取神社の樹叢と溶岩流 〔三宅島村〕
神奈川県
<天然記念物> 諸磯の隆起海岸 〔三浦市〕 1928年3月24日指定
<天然記念物> 旧相模川橋脚 〔茅ヶ崎市〕 2013年3月27日指定
<神奈川県指定天然記念物> 漣痕(波調層) 〔三浦市海外町〕 1957年2月19日指定
<神奈川県指定天然記念物> 西丹沢の董青石、ベスブ石及び大理石 〔山北町中川〕 1975年2月7日指定
<神奈川県指定天然記念物> 鎧摺の不整合を示す露頭 〔逗子市桜山〕 1977年5月20日指定
<神奈川県指定天然記念物> 三浦市海外町のスランプ構造 〔三浦市海外町〕 1978年9月1日指定
<神奈川県指定天然記念物> 中津層群神沢層産出の脊椎動物化石 〔小田原市入生田〕 1994年2月15日指定
<神奈川県指定天然記念物> 山北町人遠のネフロレピディナを含む石灰岩 〔山北町〕 1980年2月15日指定
中部
新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県(県名をクリックすると各都道府県の情報に移動します)
新潟県
<天然記念物> 青海川の硬玉産地及び硬玉岩塊 〔糸魚川市〕 1957年2月22日指定
<天然記念物> 小滝川硬玉産地 〔糸魚川市〕 1956年6月29日指定
<名勝及び天然記念物> 清津峡 〔南魚沼郡湯沢町・十日町市〕 1941年4月23日指定
<名勝及び天然記念物> 田代の七ツ釜 〔中魚沼郡津南町・十日町市〕 1937年6月15日指定
<名勝及び天然記念物> 笹川流 〔村上市〕 1927年9月5日指定
<天然記念物及び名勝> 佐渡小木海岸 〔佐渡市〕 1934年5月1日指定
<天然記念物> 平根崎の波蝕甌穴群 〔佐渡市〕 1940年7月12日指定
<新潟県指定天然記念物> 間瀬枕状溶岩 〔新潟市西蒲区間瀬〕 1961年3月20日指定
<新潟県指定天然記念物> 櫛池の隕石 〔上越市清里区青柳〕 1974年3月30日指定
<新潟県指定天然記念物> 佐渡鉱床の金鉱石 〔佐渡市下相川〕 2009年3月24日指定
<新潟県指定天然記念物> 夏井の大波石 〔胎内市夏井〕 2010年3月23日指定
ページtopに戻る
富山県
<特別天然記念物> 魚津埋没林 〔富山県魚津市〕 1936年12月6日指定、1955年特別指定
<特別天然記念物> 薬師岳の圏谷群 〔富山県富山市〕 1945年2月22日指定、1952年特別指定
<特別名勝及び天然記念物> 黒部峡谷附猿飛ならびに奥鐘山 〔黒部市・中新川郡立山町〕 1956年9月7日指定
<天然記念物> 飯久保の瓢箪石 〔氷見市〕 1941年1月27日指定
<天然記念物> 猪谷の背斜・向斜 〔富山市〕 1941年10月3日指定
<天然記念物> 真川の跡津川断層 〔富山市〕 2003年7月25日指定
<天然記念物> 横山楡原衝上断層 〔富山県富山市・岐阜県飛騨市〕 1941年10月3日指定
<名勝及び天然記念物> 称名滝 〔中新川郡立山町〕 1973年5月29日指定
<天然記念物> 立山の山崎圏谷 〔中新川郡立山町〕 1945年2月22日指定
<天然記念物> 新湯の玉滴石産地 〔富山市〕 2013年6月21日指定
<富山県指定天然記念物> 岩室滝 〔中新川郡立山町虫谷字大滝谷〕 1965年1月1日指定
<富山県指定天然記念物> 宇奈月の十字石 〔黒部市宇奈月町小谷〕 1965年1月1日指定
<富山県指定天然記念物> 宮島峡一の滝とおうけつ群 〔小矢部市名が原小撫川河川中〕 1965年1月1日指定
<富山県指定天然記念物> 寺谷アンモナイト包蔵地 〔下新川郡朝日町境字小内山〕 1978年1月28日指定
<富山県指定天然記念物> 友坂の二重不整合 〔富山市婦中町友坂字惣野・同字熊野の一部〕 1980年4月11日指定
<富山県指定天然記念物> 唐島 〔氷見市〕 1967年3月25日指定
<富山県指定天然記念物> 赤祖父石灰華生成地 〔南砺市〕 1965年1月11日指定
<富山県指定史跡・名勝・天然記念物> 称名滝とその流域(悪城の壁、称名滝、称名廊下、地獄谷、みくりが池) 〔中新川郡立山町〕
石川県
<特別天然記念物> 岩間の噴泉塔群 〔石川県白山市〕 1954年12月25日指定、1957年特別指定
<天然記念物> 曽々木海岸 〔輪島市〕 1942年3月7日指定
<天然記念物> 山科の大桑層化石産地と甌穴 〔金沢市〕 1941年1月27日指定
<天然記念物> 手取川流域の珪化木産地 〔白山市〕 1957年07月10日指定
<石川県指定天然記念物> 藤の瀬甌穴群 〔能登町〕
<石川県指定天然記念物> 関野鼻ドリーネ群 〔志賀町〕
<石川県指定天然記念物> 内浦町不動寺の埋積珪化木群 〔能登町〕
<石川県指定天然記念物> 白峰村百合谷の珪化直立樹幹 〔白山市〕
<石川県指定天然記念物> 宇出津の漣痕 〔能登町〕
<石川県指定天然記念物> 岩屋化石層 〔七尾市〕
<石川県指定天然記念物> 平床貝層 〔珠洲市〕
<石川県指定天然記念物> 桑島化石壁産出化石 〔白山市〕
<石川県指定天然記念物> 白峰百万貫の岩 〔白山市〕
<石川県指定天然記念物> 平床貝層産出貝類化石 〔珠洲市〕
<石川県指定天然記念物> 桶滝 〔輪島市〕
福井県
<名勝及び天然記念物> 東尋坊 〔坂井市〕 1935年6月7日指定
ページtopに戻る
山梨県
<特別天然記念物> 鳴沢熔岩樹型 〔南都留郡鳴沢村〕 1929年12月17日指定、1952年特別指定
<天然記念物> 燕岩岩脈 〔甲府市〕 1934年12月28日指定
<天然記念物> 新倉の糸魚川-静岡構造線 〔南巨摩郡早川町〕 2001年8月13日指定
<天然記念物> 雁ノ穴 〔富士吉田市〕 1932年10月19日指定
<天然記念物> 吉田胎内樹型 〔富士吉田市〕 1929年12月17日指定
<天然記念物> 神座風穴 附 蒲鉾穴および眼鏡穴 〔南都留郡鳴沢村〕 1929年12月17日指定
<天然記念物> 大室洞穴 〔南都留郡鳴沢村〕 1929年12月17日指定
<天然記念物> 鳴沢氷穴 〔南都留郡鳴沢村〕 1929年12月17日指定
<天然記念物> 忍野八海 〔南都留郡忍野村〕 1929年12月17日指定
<天然記念物> 西湖蝙蝠穴およびコウモリ 〔南都留郡富士河口湖町〕 1929年12月17日指定
<天然記念物> 船津胎内樹型 〔南都留郡富士河口湖町〕 1929年12月17日指定
<天然記念物> 富岳風穴 〔南都留郡富士河口湖町〕 1929年12月17日指定
<天然記念物> 富士風穴 〔南都留郡富士河口湖町〕 1929年12月17日指定
<天然記念物> 本栖風穴 〔南都留郡富士河口湖町〕 1929年12月17日指定
<天然記念物> 龍宮洞穴 〔南都留郡富士河口湖町〕 1929年12月17日指定
<山梨県指定天然記念物> リニア高川トンネル産出新第三紀化石 〔甲府市丸の内(保管場所)〕
<山梨県指定天然記念物> 兄川から出土したナウマン象等の化石 〔甲府市下曽根町、山梨市小原西〕
<山梨県指定天然記念物> 手打沢の不整合露頭 〔身延町手打沢ゴクナシ〕
<山梨県指定天然記念物> 丹青岩鍾乳洞 〔波山村奥後山青岩谷〕
<山梨県指定天然記念物> 水晶峠のヒカリゴケ洞窟 〔甲府市御岳町〕
<山梨県指定天然記念物> 軽水風穴 〔鳴沢村軽水〕
<山梨県指定天然記念物> 溶岩球(Lavaball群) 〔鳴沢村軽水〕
長野県
<特別天然記念物> 白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石 〔松本市〕 1922年3月8日指定、1952年特別指定
<天然記念物> 横川の蛇石 〔上伊那郡辰野町〕 1940年7月12日指定
<天然記念物> 四阿山の的岩 〔上田市〕 1940年2月10日指定
<天然記念物> 高瀬渓谷の噴湯丘と球状石灰石 〔大町市〕 1922年10月12日指定
<天然記念物> 渋の地獄谷噴泉 〔下高井郡山ノ内町〕 1927年4月8日指定
<天然記念物> 中房温泉の膠状珪酸および珪華 〔安曇野市〕 1928年10月4日指定
<天然記念物> 大鹿村の中央構造線(北川露頭・安康露頭) 〔下伊那郡大鹿村〕 2013年10月17日指定
<長野県指定天然記念物> 戸隠川下のシンシュウゾウ化石 〔長野市)〕
<長野県指定天然記念物> 深谷沢の蜂の巣状風化岩 〔長野市)〕
<長野県指定天然記念物> 穴沢のクジラ化石 〔松本市)〕
<長野県指定天然記念物> 反町のマッコウクジラ全身骨格化石 〔松本市〕
<長野県指定天然記念物> シナノトド化石 〔松本市)〕
<長野県指定天然記念物> 三石の甌穴群 〔飯田市)〕
<長野県指定天然記念物> 広川原の洞穴群 〔佐久市)〕
<長野県指定天然記念物> 原牛の臼歯化石 〔上伊那郡辰野町〕
<長野県指定天然記念物> 毛無山の球状花こう岩 〔下伊那郡喬木村)〕
<長野県指定天然記念物> 恐竜の足跡化石 〔北安曇郡小谷村)〕
<長野県指定天然記念物> 裏沢の絶滅セイウチ化石 〔長野市)〕
<長野県指定天然記念物> 大口沢のアシカ科化石 〔長野市)〕
<長野県指定天然記念物> 菅沼の絶滅セイウチ化石 〔長野市)〕
<長野県指定天然記念物> 山穂刈のクジラ化石 〔長野市)〕
<長野県指定天然記念物> 大柳及び井上の枕状溶岩 〔複数地域 長野市、須坂市)〕
<長野県指定天然記念物> 小泉・下塩尻及び南条の岩鼻 〔複数地域 上田市、埴科郡坂城町)〕
<長野県指定天然記念物> 小泉のシナノイルカ 〔上田市〕
<長野県指定天然記念物> 中央アルプス駒ヶ岳 〔駒ヶ根市・宮田村〕
岐阜県
<特別天然記念物> 根尾谷断層 〔本巣市〕 1927年6月14日指定、1952年特別指定
<特別天然記念物> 根尾谷の菊花石 〔本巣市〕 1941年12月13日指定、1952年特別指定
<名勝及び天然記念物> 鬼岩 〔可児郡御嵩町・瑞浪市〕 1934年1月22日指定
<天然記念物> 美濃の壺石 〔土岐市〕 1934年1月22日指定
<天然記念物> 傘岩 〔恵那市〕 1934年1月22日指定
<天然記念物> 飛水峡の甌穴群 〔加茂郡七宗町〕 1961年7月6日指定
<天然記念物> 福地の化石産地 〔高山市〕 1962年1月12日指定
<天然記念物> 横山楡原衝上断層 〔富山県富山市・岐阜県飛騨市〕 1941年10月3日指定
<岐阜県指定天然記念物> 瑞浪の鳴石産地 〔瑞浪市〕
<岐阜県指定天然記念物> 笹又の石灰石角礫巨岩 〔揖斐川町〕
<岐阜県指定天然記念物> 明世化石 〔瑞浪市〕
<岐阜県指定天然記念物> 牛丸ジュラ紀化石 〔高山市〕
<岐阜県指定天然記念物> 尾上郷ジュラ紀化石 〔高山市〕
<岐阜県指定天然記念物> 清見層デボン紀化石産地 〔高山市〕
<岐阜県指定天然記念物> メタセコイア珪化木 〔美濃加茂市〕
<岐阜県指定天然記念物> 浅見化石コレクション 〔岐阜市〕
<岐阜県指定天然記念物> 福地化石標本 〔高山市〕
<岐阜県指定天然記念物> 鏡岩 〔岐阜市〕
<岐阜県指定天然記念物> 巌立 〔下呂市〕
ページtopに戻る
静岡県
<特別天然記念物> 湧玉池 〔富士宮市〕 1944年11月7日指定、1952年特別指定
<天然記念物> 印野の熔岩隧道 〔御殿場市〕 1927年4月8日指定
<天然記念物> 駒門風穴 〔御殿場市〕 1922年3月8日指定
<天然記念物及び名勝> 楽寿園 〔三島市〕 1954年3月20日指定
<天然記念物> 柿田川 〔駿東郡清水町〕 1985年5月20日指定
<天然記念物> 丹那断層 〔田方郡函南町〕 1935年6月7日指定
<天然記念物> 地震動の擦痕 〔伊豆の国市〕 1934年1月22日指定
<天然記念物> 手石の弥陀ノ岩屋 〔賀茂郡南伊豆町〕 1934年12月28日指定
<天然記念物> 堂ヶ島天窓洞 〔賀茂郡西伊豆町〕 1935年8月27日指定
<名勝及び天然記念物> 白糸ノ滝 〔富士宮市〕 1936年9月3日指定
<天然記念物> 万野風穴 〔富士宮市〕 1922年3月8日指定
<天然記念物> 白羽の風蝕礫産地 〔御前崎市〕 1943年8月24日指定
<天然記念物> 大室山 〔伊東市〕 2010年8月5日指定
<静岡県指定天然記念物> 笹ヶ瀬隕石重六百九十五グラム 〔浜松市〕
<静岡県指定天然記念物> ホウジ峠の中央構造線 〔浜松市〕
<静岡県指定天然記念物> 下白岩のレピドサイクリナ化石産地 〔伊豆市〕
<静岡県指定天然記念物> 偽層理 〔下田市〕
<静岡県指定天然記念物> 爪木崎の柱状節理 〔下田市〕
<静岡県指定天然記念物> 景ケ島渓谷屏風岩の柱状節理 〔裾野市〕
<静岡県指定天然記念物> 五竜の滝 〔裾野市〕
<静岡県指定天然記念物> 瀬浜海岸のトンボロ 〔西伊豆市〕
<静岡県指定天然記念物> 黄金崎のプロピライト 〔西伊豆市〕
<静岡県指定天然記念物> 鮎壷の滝 〔長泉町・沼津市〕
<静岡県指定天然記念物> 横臥褶曲 〔島田市〕
<静岡県指定天然記念物> 大井川「鵜山の七曲り」と朝日段 〔島田市〕
<静岡県指定天然記念物> 富士山芝川溶岩の柱状節理 〔富士宮市〕
<静岡県指定天然記念物> 芝川のポットホール 〔富士宮市〕
<静岡県指定天然記念物> 相良油田油井 〔牧之原市〕
<静岡県指定天然記念物> 天神山男神石灰岩 〔牧之原市〕
愛知県
<天然記念物> 阿寺の七滝 〔新城市〕 1934年1月22日指定
<天然記念物> 乳岩および乳岩峡 〔新城市〕 1934年1月22日指定
<天然記念物> 馬背岩 〔新城市〕 1934年5月1日指定
<天然記念物> 鳳来寺山 〔新城市〕 1931年7月31日指定
<天然記念物> 猿投山の球状花崗岩 〔豊田市〕 1931年2月20日指定
<愛知県指定天然記念物> 玄武岩 〔豊田市〕
<愛知県指定天然記念物> 熊野社の五枚岩 〔小牧市〕
<愛知県指定天然記念物> 高師小僧 〔豊橋市〕
<愛知県指定天然記念物> 三河地震による地震断層 〔額田郡幸田町〕
<愛知県指定天然記念物> 預り渕、煮え渕ポットホール 〔北設楽郡東栄町〕
<愛知県指定天然記念物> 光岩 〔田原市〕
近畿
三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県(県名をクリックすると各都道府県の情報に移動します)
三重県
<特別名勝及び天然記念物> 瀞八丁 〔和歌山県新宮市・三重県熊野市・奈良県吉野郡十津川村〕 1952年3月29日指定
<天然記念物及び名勝> 熊野の鬼ケ城 附 獅子巖 〔熊野市木本町字城山、熊野市井戸町字馬留〕 1935年12月24日指定
<天然記念物> 月出の中央構造線 〔松阪市飯高町月出〕 2002年12月19日指定
<天然記念物> 須賀利大池及び小池 〔尾鷲市須賀利町〕 2012年1月24日指定
<三重県指定天然記念物> 鈴鹿山の鏡岩(鏡肌) 〔亀山市関町坂下字鈴鹿山〕 1936年1月22日指定
<三重県指定天然記念物> 小川郷の火打石 〔度会郡度会町火打石字彦山〕 1938年3月17日指定
<三重県指定天然記念物> 野見坂の地層褶曲 〔度会郡南伊勢町道方〕 1941年10月14日指定
<三重県指定天然記念物> 小岐須の屏風岩 〔鈴鹿市小岐須町池の谷〕 1965年12月9日指定
<三重県指定天然記念物> 鷲嶺の水穴 〔伊勢市矢持町下村字古屋〕 1965年12月9日指定
<三重県指定天然記念物> 覆盆子洞 〔伊勢市矢持町菖蒲字冷水〕 1968年3月18日指定
<三重県指定天然記念物> 篠立の風穴 〔いなべ市藤原町篠立〕 1977年3月28日指定
<三重県指定天然記念物> 石大神 〔鈴鹿市小社町字脇の山〕 1996年3月7日指定
<三重県指定天然記念物> 逆柳の甌穴 〔伊賀市高尾字逆柳〕 2013年3月25日指定
<三重県指定天然記念物> 島勝の海食洞門 〔北牟婁郡紀北町海山区島勝字天満〕 1978年2月7日指定
<三重県指定天然記念物> 佐波留島 〔尾鷲市南浦〕 1969年3月28日指定
<三重県指定天然記念物及び名勝> 大丹倉 〔熊野市育生町赤倉字大仁倉〕 2003年3月17日指定
<三重県指定名勝及び天然記念物> 楯ヶ崎 〔熊野市甫母町字阿古崎〕 1937年8月20日指定
<三重県指定天然記念物> 榊原の貝石山 〔津市榊原町字岡 1937年12月27日指定 〕 1937年12月27日指定
<三重県指定天然記念物> 柳谷の貝石山 〔津市美里町三郷 1941年2月13日指定〕 1941年2月13日指定
ページtopに戻る
滋賀県
<天然記念物> 鎌掛の屏風岩 〔蒲生郡日野町〕 1943年8月24日指定
<天然記念物> 別所高師小僧 〔蒲生郡日野町〕 1944年11月13日指定
<天然記念物> 綿向山麓の接触変質地帯 〔蒲生郡日野町〕 1942年9月19日指定
<天然記念物> 石山寺硅灰石 〔大津市〕 1922年3月8日指定
<滋賀県指定天然記念物> 河内の風穴 〔犬上郡多賀町河内〕
京都府
<天然記念物> 郷村断層 〔京丹後市〕 1929年12月17日指定
<天然記念物及び名勝> 琴引浜 〔京丹後市〕 2007年05月18日指定
<天然記念物> 東山洪積世植物遺体包含層 〔京都市東山区〕 1943年2月19日指定
<天然記念物> 稗田野の菫青石仮晶 〔亀岡市〕
<京都府指定天然記念物> 質志鍾乳洞 〔船井郡京丹波町〕
<京都府指定天然記念物> 夜久野玄武岩柱状節理 〔福知山市〕
大阪府
兵庫県
<天然記念物> 鎧袖 〔美方郡香美町〕 1938年5月30日指定
<天然記念物> 但馬御火浦 〔美方郡新温泉町・香美町〕 1934年1月22日指定
<天然記念物> 玄武洞 〔豊岡市〕 1931年2月20日指定
<天然記念物> 神戸丸山衝上断層 〔神戸市長田区〕 1937年12月21日指定
<天然記念物> 觜崎ノ屏風岩 〔たつの市〕 1931年10月21日指定
<天然記念物> 野島断層 〔淡路市〕 1998年7月31日指定
<兵庫県指定天然記念物> 栃本の溶岩瘤 〔豊岡市〕
<兵庫県指定天然記念物> 宇日流紋岩の流理 〔豊岡市〕
<兵庫県指定天然記念物> 波食甌穴群 〔豊岡市〕
<兵庫県指定天然記念物> 諸寄東ノ洞門 〔新温泉町〕
<兵庫県指定天然記念物> 渦ケ森スラスト(衝上断層) 〔神戸市〕
<兵庫県指定天然記念物> 満池谷層の植物遺体包含層 〔西宮市〕
<兵庫県指定天然記念物> 流痕化石 〔香美町〕
<兵庫県指定天然記念物> 海底面の流痕 〔香美町〕
<兵庫県指定天然記念物> 鍾乳日本洞門、鍾乳亀山洞門 〔新温泉町〕
<兵庫県指定天然記念物> 池の島の大甌穴 〔新温泉町〕
<兵庫県指定天然記念物> 加保坂の硬玉(ヒスイ)原石露頭 〔養父市〕
<兵庫県指定天然記念物> 野島鍾乳洞 〔淡路市〕
奈良県
<天然記念物> 屏風岩、兜岩および鎧岩 〔宇陀郡曽爾村〕 1934年12月28日指定
<特別名勝及び天然記念物> 瀞八丁 〔和歌山県新宮市・三重県熊野市・奈良県吉野郡十津川村〕 1928年3月24日指定、1952年3月29日特別指定
<奈良県指定天然記念物> どんずる峯 〔香芝市〕
<奈良県指定天然記念物> 神野山 〔山添村〕
<奈良県指定天然記念物> 面不動鍾乳洞 〔天川村〕
<奈良県指定天然記念物> 五代松鍾乳洞 〔天川村〕
<奈良県指定天然記念物> 不動窟鍾乳洞 〔川上村〕
<奈良県指定天然記念物> 馬見丘陵出土シカマシフゾウ化石 〔北葛城郡河合町〕
<奈良県指定天然記念物> 馬見丘陵出土シガゾウ化石 〔北葛城郡河合町〕
<奈良県指定天然記念物> 玉置山の枕状溶岩堆積地 〔吉野郡十津川村〕
ページtopに戻る
和歌山県
<特別名勝及び天然記念物> 瀞八丁 〔和歌山県新宮市・三重県熊野市・奈良県吉野郡十津川村〕 1928年3月24日指定、1952年3月29日特別指定
<天然記念物> 橋杭岩 〔東牟婁郡串本町〕 1924年12月9日指定
<天然記念物> 古座川の一枚岩 〔東牟婁郡古座川町〕 1941年12月13日指定
<天然記念物> 高池の虫喰岩 〔東牟婁郡古座川町〕 1935年12月24日指定
<天然記念物> 栗栖川亀甲石包含層 〔田辺市〕 1937年6月15日指定
<天然記念物> 鳥巣半島の泥岩岩脈 〔田辺市〕 1936年9月3日指定
<天然記念物> 白浜の化石漣痕 〔西牟婁郡白浜町〕 1931年2月20日指定
<天然記念物> 白浜の泥岩岩脈 〔西牟婁郡白浜町〕 1931年2月20日指定
<天然記念物> 門前の大岩 〔日高郡由良町〕 1935年12月24日指定
<和歌山県指定天然記念物> 新庄町奥山の甌穴 〔田辺市新庄町奥山〕 1958年4月1日指定
<和歌山県指定天然記念物> 龍門山の磁石岩 〔紀の川市杉原〕 1959年4月23日指定
<和歌山県指定天然記念物> 釜滝の甌穴 〔紀美野町釜滝〕 1971年3月22日指定
<和歌山県指定天然記念物> 赤滑の漣痕 〔田辺市鮎川〕 1974年12月9日指定
<和歌山県指定天然記念物> 御所本の化石漣痕 〔新宮市熊野川町西〕 1983年5月24日指定
<和歌山県指定天然記念物> 百山稀少鉱物産出鉱脈 〔岩出市山崎〕 2005年5月31日指定
<和歌山県指定天然記念物> 保呂の虫喰岩 〔白浜町保呂字清水谷〕 2011年3月15日指定
<和歌山県指定天然記念物> 蟾蜍岩 〔田辺市稲成町〕
<和歌山県指定天然記念物> 鷹の巣 〔和歌山市雑賀崎〕
中国
鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県(県名をクリックすると各都道府県の情報に移動します)
鳥取県
<天然記念物> 浦富海岸 〔岩美郡岩美町〕 1928年3月27日指定
<天然記念物> 鳥取砂丘 〔鳥取市〕 1955年2月3日指定
<鳥取県指定天然記念物> 扇ノ山の火山弾 〔鳥取市東町二丁目〕 1980年3月4日指定
<鳥取県指定天然記念物> ナウマンゾウ牙温泉津沖日本海底産 〔鳥取市東町二丁目〕 1980年3月4日指定
<鳥取県指定天然記念物> ナウマンゾウ牙萩沖日本海底産 〔鳥取市東町二丁目〕 1987年4月14日指定
<鳥取県指定天然記念物> 辰巳峠の植物化石産出層 〔鳥取市佐治町栃原不動産国有林〕 2002年12月20日指定
<鳥取県指定天然記念物> 鹿野地震断層の痕跡 〔鳥取市鹿野町末用〕 2004年11月9日指定
<鳥取県指定天然記念物> 和奈見と塩上の枕状溶岩 〔鳥取市河原町和奈見・八頭郡八頭町塩上〕 2010年5月14日指定
<鳥取県指定天然記念物> かまこしき渓谷の侵食地形 〔日野郡江府町助沢、俣野〕 1999年6月29日指定
<鳥取県指定天然記念物> 赤波川渓谷のおう穴群 〔鳥取市用瀬町赤波〕 2013年9月20日指定
島根県
<特別天然記念物及び名勝> 大根島の熔岩隧道 〔松江市〕 1931年7月31日指定、1952年特別指定
<名勝及び天然記念物> 隠岐海苔田ノ鼻 〔隠岐郡隠岐の島町〕 1938年5月30日指定
<名勝及び天然記念物> 隠岐国賀海岸 〔隠岐郡西ノ島町〕 1938年5月30日指定
<名勝及び天然記念物> 隠岐知夫赤壁 〔隠岐郡知夫村〕 1935年12月24日指定
<名勝及び天然記念物> 隠岐白島海岸 〔隠岐郡隠岐の島町〕 1938年5月30日指定
<天然記念物> 岩屋寺の切開 〔仁多郡奥出雲町〕 1932年7月25日指定
<名勝及び天然記念物> 鬼舌振 〔仁多郡奥出雲町〕 1927年4月8日指定
<天然記念物> 唐音の蛇岩 〔益田市〕 1936年12月16日指定
<天然記念物> 石見畳ヶ浦 〔浜田市〕 1932年3月25日指定
<天然記念物> 三瓶小豆原埋没林 〔大田市〕 2004年2月27日指定
<天然記念物> 松代鉱山の霰石産地 〔大田市〕 1959年7月24日指定
<天然記念物> 波根西の珪化木 〔大田市〕 1936年9月3日指定
<天然記念物及び名勝> 立久恵 〔出雲市〕 1927年4月8日指定
<天然記念物及び名勝> 潜戸 〔松江市〕 1927年6月14日指定
<天然記念物> 多古の七ツ穴 〔松江市〕 1932年7月23日指定
<天然記念物> 大根島第二熔岩隧道 〔松江市〕 1935年6月7日指定
<天然記念物> 築島の岩脈 〔松江市〕 1932年7月23日指定
<島根県指定天然記念物> 黄長石霞石玄武岩 〔浜田市〕
<島根県指定天然記念物> 仁万の珪化木 〔大田市〕
<島根県指定天然記念物> 鬼村の鬼岩 〔大田市〕
<島根県指定名勝及び天然記念物> 鷲ヶ峰およびトカゲ岩 〔隠岐の島町〕
<島根県指定名勝及び天然記念物> 鑪崎及び松島の磁石石 〔益田市〕
<島根県指定名勝及び天然記念物> 志都の岩屋 〔邑南町〕
岡山県
<天然記念物> 白石島の鎧岩 〔笠岡市〕 1942年10月14日指定
<天然記念物> 象岩 〔倉敷市〕 1932年7月23日指定
<天然記念物> 大賀の押被 〔高梁市〕 1937年6月15日指定
<天然記念物> 草間の間歇冷泉 〔新見市〕 1930年8月25日指定
<天然記念物> 羅生門 〔新見市〕 1930年8月25日指定
<岡山県指定天然記念物> 成羽の化石層 〔高梁市成羽町成羽・井原市美星町明治〕 1955年7月19日指定
<岡山県指定天然記念物> 枝の不整合 〔高梁市成羽町成羽〕 1955年7月19日指定
<岡山県指定天然記念物> 浪形岩 〔井原市野上町〕 1956年4月1日指定
<岡山県指定天然記念物> 大野の整合 〔鏡野町竹田〕 1956年4月1日指定
<岡山県指定天然記念物> 阿哲台-満奇洞、秘坂鐘乳穴、宇山洞、縞嶽、諏訪の穴、井倉洞 〔新見市豊永・金谷・真庭市下呰部・新見市草間〕 1957年11月5日指定(井倉洞は、1963年4月12日の追加指定)
<岡山県指定天然記念物> 上房台 備中鐘乳穴岩屋の穴 上野呂カルスト 〔真庭市上水田・阿口・下呰部〕 1957年11月5日指定
<岡山県指定天然記念物> 塩滝の礫岩 〔真庭市関・佐引〕 1959年9月15日指定
<岡山県指定天然記念物> 藍坪 〔高梁市川上町上大竹〕 1955年7月19日指定
<岡山県指定天然記念物> 八丁畷の準平原面 〔吉備中央町吉川〕 1956年4月1日指定<
ページtopに戻る
広島県
<天然記念物> 押ヶ垰断層帯 〔山県郡安芸太田町・廿日市市〕 1965年7月1日指定
<天然記念物> 久井・矢野の岩海 〔三原市・府中市〕 1964年6月27日指定
<天然記念物> 船佐・山内逆断層帯 〔安芸高田市・三次市・庄原市〕 1961年5月6日指定
<天然記念物> 雄橋 〔庄原市〕 1987年5月12日指定
<広島県指定天然記念物> 栗谷の蛇喰磐 〔大竹市栗谷町〕 1948年9月17日指定
<広島県指定天然記念物> 矢川のクリッペ 〔福山市山野町〕 1949年10月28日指定
<広島県指定天然記念物> 上原谷石灰岩巨大礫 〔福山市山野町〕 1949年10月28日指定
<広島県指定天然記念物> 東酒屋の褶曲 〔三次市東酒屋町〕 1954年4月23日指定
<広島県指定天然記念物> 東城川の甌穴 〔庄原市東城町〕 1954年4月23日指定
<広島県指定天然記念物> 仙酔島の海食洞窟 〔福山市鞆町〕 1966年9月27日指定
<広島県指定天然記念物> 仙酔層と岩脈 〔福山市鞆町〕 1966年9月27日指定
<広島県指定天然記念物> 福山衝上断層 〔福山市奈良津町・蔵王町〕 1969年4月28日指定
<広島県指定天然記念物> 奈良津露頭 〔福山市奈良津町〕 1969年4月28日指定
<広島県指定天然記念物> 蔵王城山露頭 〔福山市蔵王町〕 1969年4月28日指定
<広島県指定天然記念物> 上布野・二反田逆断層 〔三次市布野町、君田町〕 1970年1月30日指定
<広島県指定天然記念物> 摺滝化石植物群(暁新世)産地 〔三次市作木町〕 1976年6月29日指定
<広島県指定天然記念物> 西酒屋の備北層群大露頭 〔三次市西酒屋町〕 1981年11月6日指定
<広島県指定天然記念物> 東酒屋の海底地すべり構造 〔三次市東酒屋町〕 1985年12月2日指定
<広島県指定天然記念物> 津田明神の備北層群と粗面岩 〔世羅町下津田〕 1998年9月21日指定
<広島県指定天然記念物> 鏡浦の花崗岩質岩脈 〔尾道市因島鏡浦町〕 2005年4月18日指定
<広島県天然記念物> 三次の地蝋産地 〔三次市高杉町〕 1983年11月7日指定
<広島県名勝及び天然記念物> 二級峡 〔呉市広町・郷原町〕 1949年10月28日指定
山口県
<特別天然記念物> 秋吉台 〔美祢市〕 1961年10月19日指定、1964年特別指定
<特別天然記念物> 秋芳洞 〔美祢市〕 1922年3月8日指定、1952年特別指定
<天然記念物> 岩屋観音窟 〔岩国市〕 1934年1月22日指定
<天然記念物> 吉部の大岩郷 〔宇部市〕 1935年12月24日指定
<天然記念物> 景清穴 〔美祢市〕 1922年3月8日指定
<天然記念物> 大正洞 〔美祢市〕 1923年3月7日指定
<天然記念物> 万倉の大岩郷 〔美祢市〕 1935年12月24日指定
<天然記念物> 中尾洞 〔美祢市〕 1923年3月7日指定
<天然記念物> 須佐高山の磁石石 〔萩市〕 1936年12月16日指定
<天然記念物> 須佐湾 〔萩市〕 1928年3月5日指定
<天然記念物> 青海島 〔長門市〕 1926年10月20日指定
<天然記念物> 俵島 〔長門市〕 1927年6月14日指定
<天然記念物> 龍宮の潮吹 〔長門市〕 1934年8月9日指定
<天然記念物> 石柱渓 〔下関市〕 1926年10月20日指定
<天然記念物> 大吼谷蝙蝠洞 〔下関市〕 1928年3月24日指定
<天然記念物> 六連島の雲母玄武岩 〔下関市〕 1934年1月22日指定
<山口県指定天然記念物> 田万川の柱状節理と水中自破砕溶岩 〔萩市〕
<山口県指定天然記念物> 防府市中浦の緑色片岩 〔防府市〕
四国
徳島県・香川県・愛媛県・高知県(県名をクリックすると各都道府県の情報に移動します)
徳島県
<天然記念物> 阿波の土柱 〔阿波市〕 1934年5月1日指定
<天然記念物> 宍喰浦の化石漣痕 〔海部郡海陽町〕 1979年11月26日指定
<天然記念物> 坂州不整合 〔那賀郡那賀町〕 2011年2月7日指定
<天然記念物> 大歩危 〔三好市〕 2014年年3月18日指定
<徳島県指定天然記念物> 祖谷、三名の含礫片岩 〔三好市〕
<徳島県指定天然記念物> 立川のシルル紀石灰岩 〔勝浦郡勝浦町〕
<徳島県指定天然記念物> 江川の水温異常現象 〔吉野川鴨島町〕
<徳島県指定天然記念物> 土釜 〔美馬郡つるぎ町〕
<徳島県指定天然記念物> 太刀野の中央構造線 〔三好市〕
<徳島県指定天然記念物> 大野の城山の花崗岩類 〔阿南市〕
<徳島県指定天然記念物> 加島の堆積構造群露頭 〔海部郡海陽町〕
<徳島県指定名勝及び天然記念物> 美濃田の淵 〔三好郡東みよし町〕
ページtopに戻る
香川県
<天然記念物> 円上島の球状ノーライト 〔観音寺市〕 1934年12月28日指定
<天然記念物> 屋島 〔高松市〕 1934年11月10日指定
<天然記念物> 絹島および丸亀島 〔東かがわ市〕 1940年2月10日指定
<天然記念物> 鹿浦越のランプロファイヤ岩脈 〔東かがわ市〕 1942年7月21日指定
<香川県指定天然記念物> 長尾衝上断層 〔さぬき市長尾名〕 1963年4月9日指定
<香川県指定天然記念物> ゆるぎ岩 〔綾歌郡宇多津町〕 1973年5月12日指定
愛媛県
<特別天然記念物> 八釜の甌穴群 〔浮穴郡久万高原町〕 1934年5月1日指定、1952年特別指定
<天然記念物> 砥部衝上断層 〔伊予郡砥部町〕 1938年5月30日指定
<天然記念物> 八幡浜市大島のシュードタキライト及び変成岩類 〔八幡浜市〕 2004年9月30日指定
<愛媛県指定天然記念物> 衝上断層 〔西条市丹原町湯谷口〕 1949年9月17日指定
<愛媛県指定天然記念物> 田穂の石灰岩 〔西予市城川町田穂〕 1953年10月21日指定
<愛媛県指定天然記念物> 扶桑木(珪化木) 〔伊予市森大谷〕 1956年11月3日指定
<愛媛県指定天然記念物> 小屋の羅漢穴 〔西予市野村町小松〕 1961年3月30日指定
<愛媛県指定天然記念物> エジル石閃長岩 〔上島町岩城暮坂〕 1968年3月8日指定
<愛媛県指定天然記念物> ゴトランド紀石灰岩 〔西予市城川町窪野・嘉喜尾〕 1953年2月13日指定
高知県
<天然記念物> 千尋岬の化石漣痕 〔土佐清水市〕 1953年11月14日指定
<天然記念物> 唐船島の隆起海岸 〔土佐清水市〕 1953年11月14日指定
<天然記念物> 五色ノ浜の横浪メランジュ 〔土佐市〕 2011年2月7日指定
<天然記念物> 大引割・小引割 〔高岡郡仁淀川町・津野町〕 1986年2月25日指定
<天然記念物> 小鶴津の興津メランジュ及びシュードタキライト 〔高岡郡四万十町〕 2010年3月30日指定
<天然記念物> 龍河洞 〔香美市〕 1934年12月28日指定
<高知県指定天然記念物> 菖蒲洞 〔高知市土佐山菖蒲〕 1949年8月16日指定
<高知県指定天然記念物> 天狗岳不整合 〔香美市土佐山田町新改〕 1950年6月2日指定
<高知県指定天然記念物> 高知隕石 〔高知市桟橋通〕 1953年7月21日指定
<高知県指定天然記念物> 宿毛市押ノ川の化石漣痕 〔宿毛市押ノ川〕 1957年10月22日指定
<高知県指定天然記念物> 出井渓谷の甌穴群 〔宿毛市橋上町出井〕 1965年6月18日指定
<高知県指定天然記念物> 芸西村西分漁港周辺(住吉海岸)のメランジュ 〔芸西村西分字西猫谷〕 2001年3月27日指定
<高知県指定天然記念物> 本山町汗見川の枕状溶岩 〔本山町瓜生野〕 2007年4月1日指定
<高知県指定天然記念物> 白山洞門 〔土佐清水市〕 1953年1月16日指定
九州・沖縄
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県(県名をクリックすると各都道府県の情報に移動します)
福岡県
<天然記念物> 鷹巣山 〔福岡県田川郡添田町・大分県中津市〕 1941年8月1日指定
<天然記念物> 青龍窟 〔京都郡苅田町〕 1962年1月26日指定
<天然記念物> 千仏鍾乳洞 〔北九州市小倉南区〕 1935年12月24日指定
<天然記念物> 平尾台 〔北九州市小倉南区〕 1952年11月22日指定
<天然記念物> 夜宮の大珪化木 〔北九州市戸畑区〕 1957年2月22日指定
<天然記念物> 長垂の含紅雲母ペグマタイト岩脈 〔福岡市西区〕 1934年1月22日指定
<天然記念物> 名島の檣石 〔福岡市東区〕 1934年5月1日指定
<天然記念物> 芥屋の大門 〔糸島市〕 1966年3月3日指定
<天然記念物> 水縄断層 〔久留米市〕 1997年7月28日指定
<福岡県指定天然記念物> 恋の浦海岸 〔福津市〕
<福岡県指定天然記念物> 岩屋鍾乳洞 〔田川市〕
<福岡県指定天然記念物> 霊厳寺の奇岩 〔八女市〕
<福岡県指定天然記念物> 宝珠岩屋 〔朝倉郡東峰村〕
<福岡県指定天然記念物> 梅花石岩層 附 梅花石大型置物 〔北九州市門司区〕
<福岡県指定天然記念物> 米ノ山断層と石炭層の露頭 〔大牟田市〕
<福岡県指定天然記念物> 千手川の甌穴群 〔嘉麻市〕
<福岡県指定天然記念物> 岩屋・遠見ヶ鼻の芦屋層群 〔北九州市若松区〕
<福岡県指定天然記念物> 篠栗の埋没化石林 〔糟屋郡篠栗町〕
佐賀県
<天然記念物> 屋形石の七ツ釜 〔唐津市〕 1925年10月8日指定
<天然記念物> 八藤丘陵の阿蘇4火砕流堆積物及び埋没林 〔三養基郡上峰町〕 2004年9月30日指定
<佐賀県指定天然記念物> 相浦の球状閃緑岩 〔多久市〕
<佐賀県天然記念物> 弁天島の呼子岩脈群 〔唐津市〕
ページtopに戻る
長崎県
<天然記念物> 七釜鍾乳洞 〔西海市〕 1936年12月16日指定
<天然記念物> 斑島玉石甌穴 〔北松浦郡小値賀町〕 1958年3月13日指定
<天然記念物> 平成新山 〔島原市・雲仙市〕 2004年4月5日指定
<長崎県指定天然記念物> 長崎市小ケ倉の褶曲地層 〔長崎市小ヶ倉団地〕
<長崎県指定天然記念物> 三重海岸変成鉱物の産地 〔長崎市三重町〕
<長崎県指定天然記念物> 野母崎の変はんれい岩露出地 〔長崎市野母崎町黒浜・以下宿〕
<長崎県指定天然記念物> 茂木植物化石層 〔長崎市茂木町〕
<長崎県指定天然記念物> 壱岐のステゴドン象化石産出地 〔壱岐市勝本町立石西触〕
<長崎県指定天然記念物> 壱岐長者原化石層 〔壱岐市芦辺町諸吉本村触〕
<長崎県指定天然記念物> 小佐々野島の淡水貝化石含有層 〔佐世保市小佐々町楠泊〕
<長崎県指定天然記念物> 漣痕 〔五島市三井楽町浜の畔郷〕
<長崎県指定天然記念物> 福江椎木山の漣痕 〔五島市平蔵町〕
<長崎県指定天然記念物> 千尋藻の漣痕 〔対馬市豊玉町千尋藻〕
<長崎県指定天然記念物> 脇岬のビーチロック 〔長崎市野母崎町脇岬〕
<長崎県指定天然記念物> 寺島玉石甌穴 〔佐世保市宇久町寺島郷〕
<長崎県指定天然記念物> 喜内瀬川甌穴群 〔松浦市福島町喜内瀬免〕
<長崎県指定天然記念物> 串ノ浜岩脈 〔佐世保市黒島町〕
<長崎県指定天然記念物> 櫃崎岩脈 〔松浦市福島町浅谷免〕
<長崎県指定天然記念物> 弁天島岩脈 〔松浦市福島町里免〕
<長崎県指定天然記念物> 初瀬の岩脈 〔壱岐市郷ノ浦町初山東触〕
<長崎県指定天然記念物> 古路島の岩頸 〔北松浦郡小値賀町古路島〕
<長崎県指定天然記念物> 富江溶岩トンネル「井坑」 〔五島市富江町岳郷〕
<長崎県指定天然記念物> 黄島溶岩トンネル 〔五島市富江町岳郷〕
<長崎県指定天然記念物> 生月町塩俵断崖の柱状節理 〔平戸市生月町壱部免〕
<長崎県指定天然記念物> 大島巨大火山弾産地 〔小値賀町大島郷〕
<長崎県指定天然記念物> 鬼岳火山涙産地 〔五島市上大津町〕
<長崎県指定天然記念物> 嵯峨島火山海食崖 〔五島市三井楽町嵯峨島〕
<長崎県指定天然記念物> 新魚目曽根火山赤ダキ断崖 〔南松浦郡新上五島町曽根郷〕
熊本県
<名勝及び天然記念物> 妙見浦 〔天草市〕 1935年8月27日指定
<名勝及び天然記念物> 米塚及び草千里ヶ浜 〔阿蘇市阿蘇郡南阿蘇村〕 2013年3月27日指定
<熊本県指定天然記念物> 貨幣石産地 〔天草郡河浦町〕
<熊本県指定天然記念物> メガロドン化石群産地 〔芦北町〕
<熊本県指定天然記念物> 神瀬の石灰洞窟 〔球磨村〕 *近日中に国名勝に指定されるため県指定は解除
<熊本県指定天然記念物> カマノクド 〔人吉市〕
大分県
<天然記念物> 狩生鍾乳洞 〔佐伯市〕 1934年12月28日指定
<天然記念物> 小半鍾乳洞 〔佐伯市〕 1922年3月8日指定
<天然記念物> 風連洞窟 〔臼杵市〕 1927年4月8日指定
<天然記念物> 大岩扇山 〔玖珠郡玖珠町〕 1935年6月7日指定
<天然記念物> 小野川の阿蘇4火砕流堆積物及び埋没樹木群 〔日田市〕 2011年9月21日指定
<天然記念物> 竹田の阿蘇火砕流堆積物 〔竹田市〕 2012年9月19日指定
<天然記念物> 姫島の黒曜石産地 〔東国東郡姫島村〕 2007年7月26日指定
<天然記念物> 耶馬渓猿飛の甌穴群 〔中津市〕 1935年6月7日指定
<天然記念物> 鷹巣山 〔福岡県田川郡添田町・大分県中津市〕 1941年8月1日指定
<大分県指定天然記念物> 姫島の藍鉄鉱 〔姫島村〕
<大分県指定天然記念物> 姫島の地層褶曲 〔姫島村〕
<大分県指定天然記念物> 長崎鼻の海蝕洞穴 〔豊後高田市〕
<大分県指定天然記念物> 狩生新鍾乳洞 〔佐伯市〕
宮崎県
<天然記念物> 関之尾の甌穴 〔都城市〕
<天然記念物> 青島の隆起海床と奇形波蝕痕 〔宮崎市〕 1934年5月1日指定
<天然記念物> 七折鍾乳洞 〔西臼杵郡日之影町〕 1933年2月28日指定
<名勝及び天然記念物> 柘の滝鍾乳洞 〔西臼杵郡高千穂町〕 1933年2月28日指定
<天然記念物> 五箇瀬川峡谷(高千穂峡谷) 〔西臼杵郡高千穂町〕 1934年11月10日指定
<天然記念物> 猪崎鼻の堆積構造 〔日南市〕 2014年3月18日指定
<宮崎県指定天然記念物> 鵜戸千畳敷奇岩 〔日南市鵜戸〕
<宮崎県指定天然記念物> 森永の化石群 〔国富町森永〕
ページtopに戻る
鹿児島県
<天然記念物> 志布志市夏井海岸の火砕流堆積物 〔志布志市〕 2012年9月19日指定
<天然記念物> 天降川流域の火砕流堆積物 〔霧島市〕 2013年3月27日指定
<鹿児島県指定天然記念物> 縄状玄武岩 〔指宿市開聞町脇浦花瀬崎〕 1954年5月24日指定
<鹿児島県指定天然記念物> 権現洞穴 〔南九州市川辺町上山田君野〕 1954年5月24日指定
<鹿児島県指定天然記念物> 溝ノロ洞穴 〔曽於市財部町大塚原〕 1955年1月14日指定
<鹿児島県指定天然記念物> 昇竜洞 〔大島郡知名町吉野平川〕 1967年3月31日指定
<鹿児島県指定天然記念物> 沖永良部島下平川の大型有孔虫化石密集産地 〔大島郡知名町下平川字瀬田原〕 1987年3月16日指定
<鹿児島県指定天然記念物> 鹿児島市西佐多町の吉田貝化石層 〔鹿児島市西佐多町〕 2008年4月22日指定
<鹿児島県指定天然記念物> 犬田布海岸のメランジ堆積物 〔大島郡伊仙町犬田布海岸〕 2009年4月21日指定
<鹿児島県指定天然記念物> 南種子町河内の貝化石層 〔南種子町中之上〕 2011年4月19日指定
<鹿児島県指定天然記念物> 天然橋 〔南九州市川辺町〕 1954年5月24日指定
<鹿児島県指定天然記念物> 噴火により埋没した鳥居、門柱 〔鹿児島市黒神町〕 1963年4月28日指定
<鹿児島県指定天然記念物> 住吉暗川(くらごう) 〔大島郡知名町〕 2001年4月27日指定
<鹿児島県指定天然記念物> 鹿児島市西佐多町の吉田貝化石層 〔鹿児島市西佐多町〕 2008年4月22日指定
<鹿児島県指定天然記念物> 大津勘のビーチロック 〔大島郡知名町〕 2012年4月20日指定
<鹿児島県指定天然記念物> 下甑島夜萩円山断崖の白亜系姫浦層群 〔薩摩川内市鹿島町〕 2013年4月23日指定
<鹿児島県指定天然記念物> 伏目海岸の池田火砕流堆積物と噴気帯 〔指宿市山川福元〕 2014年4月22日指定
沖縄県
<天然記念物> 塩川 〔国頭郡本部町〕 1972年5月15日指定
<天然記念物> 喜屋武海岸及び荒崎海岸 〔糸満市〕 :2012年9月19日指定
<天然記念物> 名護市嘉陽層の褶曲 〔名護市〕 2013年9月19日指定
<天然記念物> 下地島の通り池 〔宮古島市〕 2006年7月28日指定
<天然記念物> 八重干瀬 〔宮古島市〕 2013年3月27日指定
<天然記念物> 石垣島東海岸の津波石群 〔石垣市〕 2013年3月27日指定
<天然記念物> 久米島町奥武島の畳石 〔島尻郡久米島町〕 2014年7月29日指定
<沖縄県指定天然記念物> くまや洞窟 〔伊平屋村字田名〕
<沖縄県指定天然記念物> 仲島の大石 〔那覇市泉崎〕
<沖縄県指定天然記念物> 喜如嘉板敷海岸の板干瀬 〔大宜味村字喜如嘉〕
<沖縄県指定天然記念物> 本部町大石原のアンモナイト化石 〔本部町字山川〕
<沖縄県指定天然記念物 北大東村字中野の北泉洞 〔北大東村字中野〕
---------------------------------
2015年4月7日更新
第6回フォトコンテスト_ジオ鉄賞
第6回惑星地球フォトコンテスト入選作品
ジオ鉄賞:ロートホルン登山鉄道
写真:吉田 宏(神奈川県)
撮影場所:スイス・ブリエンツ
【撮影者より】
写真はスイス・ブリエンツから出発するロートホルン登山鉄道です.カラフルな客車を後ろから押して登る,前のめりに傾いたSLは,スイス唯一定期運行している蒸気機関車ですが,10月から6月まで半年以上休む夏場だけの登山鉄道でもあります.
【審査委員長講評】
カールなどの氷河地形や小氷河のかかる素晴らしい景観の山々を背景に,登山列車がゆっくりと登る状況がバランスよく写しこまれています.列車の登る斜面には地盤の凍結融解作用の繰り返しによって形成された筋状の模様が見 えます.この鉄道は急勾配を登るための対策として,アプト式のラックレールを採用し,機関車は客車の後ろに連結されています.また,機関車はボイラーを水平に保つために前のめりになった珍しい形式です.(上野将司:深田研ジオ鉄普及委員会)
【地質的背景】
列車主体の作品がいくつかありましたが,ジオ鉄写真では列車や鉄路を対象にした「鉄」に加えて,地形や地質を対象にした「ジオ」を写しこむ必要があります.応募数は少ないながら「ジオ」と「鉄」のバランスのとれた力作が多くありました.ジオ鉄賞は4枚の組み写真で応募された作品ですが,組み写真としてではなく氷河地形を背景にした登山鉄道を表現した1枚の写真が評価されたものです.(ジオ鉄普及委員会@上野将司)
※「ジオ鉄賞」:第6回より深田研ジオ鉄普及委員会より本コンテストに協賛を頂き,あらたに「ジオ鉄」賞を創設しました.鉄道と地球の姿を組み合わせた優れた「ジオ鉄」作品を表彰します.
目次に戻る
第6回フォトコンテスト_ジオパーク賞
第6回惑星地球フォトコンテスト入選作品
ジオパーク賞:太古の跡の砂滑り
写真:竹之内範明(静岡県)
撮影場所:静岡県下田市田牛サンドスキー場
【撮影者より】
南伊豆の海水浴場で穴場的存在である田牛には,サンドスキー場があり,砂滑りが楽しめます.これは海岸の砂が強風によって吹き上げられいつも一定の角度で安定しているためです.しかし,ジオサイトとしての見どころはむしろ背後の崖で,海底火山時代の噴出物が岩脈となって地上に荒々しい姿を見せています.太古の跡の残る崖の下で砂滑りに興じる子ども達の姿に魅かれて撮影しました.
【審査委員長講評】
爆発的な噴火を物語る太古の海底堆積物の前にあるのは,海岸から強風に運ばれてきた砂でできた斜面.お父さんと子供(?)が,背景の地層には見向きもせずにそり遊びに興じているようすが微笑ましく感じられます.傾斜した地層とそりの滑り跡が対照的で,作品を印象深くしています.
【地質的背景】
背景に見える礫と砂からなる互層は海底火山の噴出物で、白浜層群という鮮新世の地層です。画面中央付近をよく見ると葉脈のように枝分かれした黒い筋が3本ほど見えます。これは岩脈と言って、地下でマグマが上昇してくるときに地層を割って入ってきた跡です。ただ、普通、岩脈というものは地層を縦にスパッと割って入り、厚さもメートルオーダーはあるものです。ここの岩脈はとても薄く、枝分かれも多いため、なんとなくヨロヨロとした印象を受けます。あまり典型的でない、珍しい岩脈ですが、どうしてここではこのような岩脈が出来たのか、詳しい研究はまだされていないようです。(神奈川県温泉地学研究所 萬年一剛)
目次に戻る
第6回フォトコンテスト_スマホ賞
第6回惑星地球フォトコンテスト入選作品
スマホ賞:灼熱の谷(スマホ・携帯)
写真:三浦雅哉(神奈川県)(中学・高校生部門より)
撮影場所:箱根町大涌谷 箱根ロープウェイ
【撮影者より】
2014年秋に箱根ロープウェイから撮影しました.大涌谷は箱根火山の中央火口丘冠ヶ岳の地滑りによる崩落地で,箱根火山最大の噴煙地帯です.常に火山ガスを含む蒸気が吹き出しています.
【審査委員長講評】
スマートフォンについているカメラの進歩も著しく,1000万画素以上で露出補正,パノラマ,接写もできるものも多く,10年前の高級デジカメ以上の性能を備えています.ロープウェイから撮影されており.地上から撮影した大涌谷とは違った全体像がとらえられています.見上げるような冠ヶ岳の配置もよかった.
【地質的背景】
箱根ロープウェイの早雲山─大涌谷駅間は大涌谷という沢を通過します.ゴンドラから谷底まで100m以上あり,迫力は満点です.ゴンドラの南側の窓から3000年前の最後のマグマ噴火で形成された冠ヶ岳と,谷底を1枚に収めています.大涌谷では1910年に,大規模な土砂崩れがあり,下流に大きい被害が出たため,長年にわたり砂防工事が行われ現在も進行中です.また,カルデラからくみ上げられた水と,大涌谷の噴気を混ぜることにより箱根温泉全体の約1割にあたる量の温泉がここで作られています.利用されている噴気には自然噴気だけでなく深さ数百メートルの井戸から得られる噴気もあります.この写真では,井戸から採取した噴気と水を混ぜる造成塔と呼ばれる施設が谷底にいくつか見えます.
※追記:箱根山では,2015年4月26日から大涌谷付近を震源とする火山性地震が増加し,火山活動が活発化しています.気象庁は,5月6日に火口周辺警報を発表し,噴火警戒レベルを1(平常)から2(火口周辺規制)に引上げました.本稿執筆時,火山活動の高まりにより,一部の井戸で噴気が制御でいないほど増大しています同様の現象は2001年にもありました.また,今回の活動に関しては,各機関等HPに詳細情報が更新されています. (2015年5月19日現在)
[参考URL]
・気象庁 http://www.jma.go.jp/jma/index.html
・神奈川県 http://www.pref.kanagawa.jp/
・神奈川県温泉地学研究所 http://www.onken.odawara.kanagawa.jp/
※「スマホ賞」:ジオフォトがより身近でより親しみやすいものとなるよう,またチャンスを逃さない新たな視点の作品投稿につながるよう,携帯,スマートフォンでの撮影作品を対象に表彰します.
目次に戻る
第6回フォトコンテスト_入選1
第6回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:海上の多面体
写真:八木英雄(宮城県)
撮影場所:宮城県石巻市白浜岬
【撮影者より】
造化の妙としか言いようのない形,芸術作品を鑑賞するようにあちこちから眺め、撮影し、不思議さに感嘆しました.いつも不思議な形だなあと独り言を言いながら撮影していました.
【審査委員長講評】
被写体は,数10mの大きさはありそうですが,どのようにしてこのような多面体に割れるのか,この場所にやってきたのか,波の浸食に耐えられるのか,という謎解きに挑んでみたくなります.
【地質的背景】
石巻市白浜崎周辺には中部三畳系伊里前層の縞状砂質泥岩が分布します.ここではNE-SW走向で,ゆるくNW方向に傾斜しています.南三陸地域では NE-SW走向およびNW-SE走向で垂直に近い傾斜のものと比較的低角傾斜のものの3方向の系統的な節理が発達しています.白浜崎では,層理面(写真の手前にゆるく傾く面)と互いに直交するほぼ垂直な面をもつ節理面に沿った風化により,立方体・直方体を積み重ねたような岩塊群が形成されています.(永広昌之:東北大学総合学術博物館)
目次に戻る
第6回フォトコンテスト_佳作7-8
第6回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:バッド・ウォーター
写真:渡瀬正章(和歌山県)
撮影場所:アメリカ合衆国、カリフォルニア州、デス・バレー国立公園,
【撮影者より】
年間降水量50mm 足らず,夏の最高気温 50℃以上,谷の中心部は海抜マイナス 86m,究極の地,死の谷と呼ばれるここデス・バレーでは究極の光景が見られます.
佳作の一覧に戻る
佳作:伊豆石と街並(スマホ・携帯)
写真:蓑和雄人(静岡県)
撮影場所:静岡県下田市内
【撮影者より】
伊豆の家や街が伊豆の地質と深く関わっていることがよくわかります.石切は重要な産業の一つであり,伊豆の山や海辺でよく見かけます.
佳作の一覧に戻る
第6回フォトコンテスト_佳作9-10
第6回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:中綱湖畔の春
写真:横山俊治(高知県)
撮影場所:JR大糸線(簗場駅−ヤナバスキー場前駅)長野県大町市
【撮影者より】
列車は中綱湖と青木湖の間の峠を上っている.この峠を越えたところが姫川の源頭部であったが,地すべりによって最上流部がせき止められ,それででできた青木湖の水は現在峠を越えて中綱湖に流れている.
佳作の一覧に戻る
佳作:半化石の浜
写真:天沼 彩(神奈川県)
撮影場所:小笠原諸島 南島
【撮影者より】
沈水カルスト地形の独特な景観を持つ南島の,すり鉢状の砂浜一面をヒロベソカタマイマイの半化石が覆っている様は,美しくも一種異様な光景で衝撃的でした.1000年前に絶滅した貝が,そのまま化石になりつつあるというその過程を目の当たりにして,雄大な時の流れを感じずにはいられませんでした.南島は自然保護のため入島制限がされているので,半化石はずっとそのまま残り,いつかは本当に化石になるのでしょうか.
佳作の一覧に戻る
第6回フォトコンテスト_入選2
第6回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:雲
写真:野口絵未(東京都)(中学・高校生部門より)
撮影場所:東京都あきる野市秋川駅
【撮影者より】
夏休みに秋川でバーベキューをした帰りにふと上を見たら雲がこのようになっていました.
【審査委員長講評】
形の面白さがこの作品の魅力です.スケールがないためにかえって神秘的で,題名を見るまでは雲とは思いません.それにしても奇妙な雲です.魅力的な作品ですが,このコンテストの入選に値するかどうかは選考の際にも意見がありました.結果,このような大気現象も惑星地球を特徴づける要素という判断で入選としました.
【地質的背景】
雲底からこぶ状の房がいくつも垂れ下がっている雲は乳房雲と呼ばれ,積乱雲,層積雲,高積雲,高層雲などの比較的厚い雲の底に現れます.乳房雲は強い下降気流の発生によって発生することが多いので,大雨,あられ,雷,雷などの前兆となります.(白尾)
目次に戻る
第6回フォトコンテスト_入選3
第6回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:千畳敷
写真:山代大木(岩手県)(中学・高校生部門より)
撮影場所:岩手県釜石市箱崎半島
【撮影者より】
釜石湾と大槌湾を仕切るのように太平洋に突き出た御箱崎半島にある千畳敷にて撮影しました.波の侵食作用によって削られた花崗岩が,敷き詰められた畳のように見えることからこの名前がついたそうです.いかにも陸中海岸らしい風景だと思い,撮影しました.
【審査委員長講評】
この作品は中・高校生部門での応募ですが,中高校生にしてはまとまり過ぎているので,もう少し冒険があってもよいかもしれません.今回のコンテストでは,この作品に限らず,撮影者のコメントがしっかり書かれている作品が多いのは心強いことです.地質や地形の撮影を通して地質学への理解を深めてもらうことも,日本地質学会がこのフォトコンテストを主催する大きな意義です.
【地質的背景】
北上山地には前期白亜紀の花崗岩類が広く分布します.御箱崎半島の北半〜先端部は宮古岩体南端部の花崗岩質岩類が占めており,海岸では白色の岩肌を見せています.釜石周辺では,NE-SW〜ENE-WSW方向の節理がよく発達し,この方向がリアスの湾入方向(岬の方向)を支配しています.御箱崎も北東に細く突き出した岬で,NE-SW方向の大小の湾入を基本構造とし,それに他の方向の節理や断層に沿う侵蝕で様々な形態の微地形を造っています.(永広昌之:東北大学総合学術博物館)
目次に戻る
第6回フォトコンテスト_入選4
第6回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:柱状節理(組写真)
写真:永友武治(宮崎県)
撮影場所:宮崎県えびの市
【撮影者より】
霧島連山の西に位置するところに飯盛山(標高846m)があります.約3万年くらい前にできた火山です.撮影場所は,飯盛山の溶岩流の末端であると思われます.霧島ジオパークガイドを行っており,折々に地質露頭を観察する機会がありますが,この柱状節理の美しい姿に驚きました.全面,側面ときれいに見えていました.とても貴重なジオ材料になると思います.やがては壊されるでしょうが今回の写真を使って勉強材料にしたいと思います.
【審査委員長講評】
柱状節理の自然露頭は全国各地にありますが,自然露頭では長年の間に風化が進み,シャープさがなくなっているものですが,この柱状節理は切り出したばかりの印象的な露頭です.3枚の内1枚に人物をスケールとして入れたのは良かったのですが,人物を右端に寄せるとなお良かったと思います.
【地質的背景】
飯盛山は,南九州霧島火山の北西端にある火山体です.比高250m程度の小さな砕屑丘ですが,その北から西麓には広く溶岩が分布しています.工事現場や採石場では,写真のような柱状節理の発達した断面がよく現れます.この溶岩が流出した約3万年前の加久藤盆地は湖でした.そのため周辺には,この溶岩と湖水が接触して作られた二次噴火口がいくつも見られます.湖水の絡んだ複雑な溶岩の冷却プロセスが,縦横に走る柱状節理を作り出したと考えられます.(井村隆介:鹿児島大学)
(注意) ジオパークに限らず,このような場所を見学する際には,ヘルメットをかぶる等十分安全に配慮した上で見学を行って下さい.
目次に戻る
第6回フォトコンテスト_入選5
第6回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:自然の造形
写真:山本和恵(福岡県)
撮影場所:阿蘇山麓
【撮影者より】
地質学とは無縁の者ですが阿蘇火口付近の撮影後,下って行くと自然の造形美と思われる場所を発見.感動し部分的に撮っていました.見渡すとグランドキャニオンを思い出すような断層面もあり,全体を撮った中の一枚です.(2014年4月8日撮影)
【審査委員長講評】
阿蘇中岳第1火口は昨年夏から噴火活動が活発で,それまであった池が干上がり,火山灰を周囲にまき散らしています.この作品は阿蘇山ロープウェイ山頂駅から少し下った場所から東側の第4火口を撮影したものです.昨年8月からこの地域は立入禁止となっています.ここに写っている白い堆積物もGoogle Earthで見ると黒い火山灰に覆われてしまい,まさに地球が生きていることを感じさせます.
【地質的背景】
阿蘇中岳は,第1火口が現在も活動を続けていますが,この第4火口は1932-33年ごろに活動していた場所です.火口底にはイタドリの小丘状群落が発達し,その間を縫うように,降雨による水の流れが網目模様を形成しているとともに,流れ込んだ火山灰が扇状地状の地形をつくっています.火口壁には柱状節理が発達したアグルチネートが垂直な崖をつくり,その上に幾層もの火山灰層がみられます.このように,様々な火山の営みがつくる景観を,微妙なコントラストとともに捉えたすばらしい写真です.(池辺伸一郎:(公財)阿蘇火山博物館)
目次に戻る
第6回フォトコンテスト_入選6
第6回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:宝永山火口
写真:平井健司(静岡県)
撮影場所:富士山表口5合目より宝永山遊歩道
【撮影者より】
江戸期宝永の年に富士山大爆発によってできた大火口で,異空間の世界を作っています.溶岩に含まれる赤鉄鉱による赤岩の地層が見えます.世界文化遺産に登録された富士山はその秀麗な姿を賞賛され,四季折々に人々の目を楽しませています.しかしまぎれもなく「火山」であり,地下には膨大なエネルギーを有しています.人は保全に務めると共に自然への畏怖の念を忘れてはならないと思います.
【審査委員長講評】
宝永火口は,山頂火口よりも大きな冨士山最大の火口で,この作品は冨士宮口六合目を経て宝永火口の西縁の入口から宝永火口の全体を撮影したと思われます.左の火口壁には古い時代の溶岩流とそれを垂直に貫く岩脈群が,さらにその奧には富士山頂が,右手前には古い地層が持ち上げられた宝永山の赤岩があります.全体的に落ち着いた色調の格調高い作品に仕上がっています.
【地質的背景】
1707年12月16日(グレゴリウス暦)に始まった宝永噴火で形成されたのが,宝永火口です.宝永火口は3つあり,標高の高い北東側から,標高が低い南西側へと言う順番で宝永第一〜第三火口と呼ばれています.しかし,噴火は第二と第三火口ではじまりました.その後,これらの火口の東縁で宝永山の隆起があり,最後は第一火口が噴火して終わりました.この写真では手前に第二火口,奥に第一火口,右手に宝永山が見えています.(神奈川県温泉地学研究所:萬年一剛)
目次に戻る
第6回フォトコンテスト_入選7
第6回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:立ち上る白煙
写真:岡本芳隆(神奈川県)
撮影場所:神奈川県足柄下郡箱根町 大涌谷
【撮影者より】
大涌谷は箱根の代表的な観光スポットです.約3000年前に箱根火山の水蒸気爆発でできた神山爆裂火口の跡が 大涌谷です.今も大地から熱い水蒸気と硫気を噴出している.この日も観光客の中,多くの外国人の姿も見られ 国際的な観光地であることがわかります.
【審査委員長講評】
箱根の大涌谷を訪れると中国をはじめ外国からの観光客が多いのにびっくりしますが,彼らが黒玉子を食べ,噴気活動を眺め,はしゃいでいるようすを見ると火山国日本を漫喫してくれているようで嬉しいものです.そのすぐ近くから撮影したのがこの作品です.太陽が冠ヶ岳にかかる位置をねらって逆光を軽減し,白い噴気や秋の大涌谷の雰囲気をうまく出しました.
【地質的背景】
大涌谷とは,本来的にはスマホ賞「灼熱の谷」で写された,大涌沢の流れる谷のことを言います.この写真は冠ヶ岳のふもと,大涌谷自然研究路の終点付近で撮影されています.黒たまごを蒸している有名なスポットですが,ここだけを訪れると大涌谷の“谷”はどこのことなのか,疑問に思ってしまいますよね.なお,大涌谷の「白煙」は湯気で,火山灰は入っていません.火山学者は噴気と呼んでいますが,大涌沢の噴気はこの付近の沸点(97℃)です.噴気温度の記録は大正時代にまで遡ることができますが,沸点を超える噴気はほとんど出ていません.(神奈川県温泉地学研究所:萬年一剛)
※追記:箱根山では,2015 年4月26日から大涌谷付近を震源とする火山性地震が増加し,火山活動が活発化しています.気象庁は,5月6日に火口周辺警報を発表し,噴火警戒レベルを 1(平常)から2(火口周辺規制)に引上げました.今回の活動に関しては,各機関等HPに詳細情報が更新されています. (2015年5月19日現在)
[参考URL]
・気象庁 http://www.jma.go.jp/jma/index.html
・神奈川県 http://www.pref.kanagawa.jp/
・神奈川県温泉地学研究所 http://www.onken.odawara.kanagawa.jp/
目次に戻る
第6回フォトコンテスト_佳作11-12
第6回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:異なる食材を使った地層の変形実験(組写真)
写真:藤内智士(高知県)
撮影場所:高知大学朝倉キャンパス理学部1号館215室
【撮影者より】
地層の変形には粒子のサイズや形が大きく影響します.そのことを示す目的で,身近にある複数の食材(小麦粉−ココアパウダー互層,ザラメ砂糖,マーブルチョコレート)を使って地層の変形実験をしました.写真では,粒径が最も小さい小麦粉−ココアパウダー互層では細かな断層ができ,ザラメ砂糖層やマーブルチョコレート層では異なる形の褶曲ができているのがわかります.また,粒子自身が回転している様子も観察できます.
佳作の一覧に戻る
佳作:悠久の時を語る岩達(スマホ・携帯)
写真: 伊良部描理(沖縄県)
撮影場所:宮古島 東平安名崎 保良漁港より
【撮影者より】
1771年に起きた明和の大津波のつめ跡,M7.4の大地震がこな岩達を運び,現在ではこの様な姿となって,語りかけて来ます. 大自然の力の源を暗示し,幻想的な世界へ誘ってくれます.
佳作の一覧に戻る
第6回フォトコンテスト_佳作13-14
第6回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:大空を映して
写真:藤松政晴(佐賀県)
撮影場所:長崎県東彼杵郡龍頭泉
【撮影者より】
写真最上部に少し写っている龍頭泉橋から下ると大小さまざまな滝や淵が約500mに渡り合計48もあるといわれる千綿渓谷の最上部にある滝です.この一体は紅葉の頃の風景が有名ですが,紅葉シーズンが終わった真冬の日に行きました.冬枯れた岩石と木々の寂しい風景の中,小さい水たまりに映った青空がとても清々しくまぶしかったのを覚えています.
佳作の一覧に戻る
佳作:自然の造形
写真:佐藤 忠(東京都)
撮影場所:アメリカ アリゾナ州 パリアバーミリオンクリフ ホワイトポケット
【撮影者より】
風と雨が造り上げたアメリカの原風景撮影ツアーに参加して,大自然のこの色鮮やかな地層がいかにして出来たのかまた,これが形成されるまでの歳月が費やされたのか,どのような過程で出来たのかを写真を撮りながら大自然の力と美を考えさせられました.
佳作の一覧に戻る
第6回フォトコンテスト_佳作15-16
第6回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:漂礫岩堆積物の山
写真:加藤智津子(東京都)
撮影場所:モーリタニア アドラール州 シャール
【撮影者より】
砂丘を超えると真っ平らな世界が広がる.砕けたダイアミクタイトでローズ色に染まる大地のなかで,この山だけは青色に輝く.登っていくと,石を割ってアカシアが生え,砂の中に小さな花が咲き,漂礫岩が運んだ石英の小石が転がる.周辺にテントを張るノマドたちは,旧石器時代の人々が色石を集めて死者を弔ったように,幼子の亡がらにクライオジェニアンの青やローズ,黄色の石を積む.
佳作の一覧に戻る
佳作:大自然の造形
写真:荒井俊明(京都府)
撮影場所:京都府京丹後市経ヶ岬
【撮影者より】
経ヶ岬は丹後半島の先端.冬場はうらにし(主に山陰地方で,晩秋から冬にかけて吹く西風 ,または北西の風)が吹き荒れ大波が押し寄せるところです.海岸を歩くと異様な光景に別世界に来たような錯覚に陥ります.波を被るところは削られて丸くなり,上になるに従い元の岩肌に戻って行きます.自然の力に感服すると同時に自然の創り出す造形美に驚嘆します.
佳作の一覧に戻る
geo-Flash No.301[長野大会]事前参加登録受付開始!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.301 2015/6/16┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[長野大会]事前参加登録受付開始!・演題登録も受付中
【2】[長野大会]ランチョン・夜間小集会のお申込はお済みですか?
【3】[長野大会]キャンセルした講演の講演要旨の扱いについて
【4】[長野大会]講演予定者で,現在未入会の方へ周知のお願い
【5】2015年度会費督促請求について
【6】名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
【7】フォトコンテスト入選作品展示会(in 銀座)開催中です
【8】環境地質部会:関東地下水盆と人工地層の地質環境巡検
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[長野大会]事前参加登録受付開始!・演題登録も受付中
─────────────────────────────────
日本地質学会第122年学術大会(長野大会)の事前参加登録の受付を開始しました。
演題登録受付中です!今年もたくさんの参加・発表申込をお待ちしています。
9月11日(金)〜13日(日)
会場:信州大学長野(工学)キャンパス ほか
◆事前参加登録:8/18(火)締切[※巡検は8/7(金)締切]
◆演題登録:6/30(火)締切
〔注〕演題登録と事前参加登録は,それぞれ別のお申し込みです。ご注意下さい。
その他のお申込
◆小さなESのつどい小中高「地学研究」発表会参加申込:7月16日(木)
◆宿泊予約サイト(日本旅行のサイト)もオープンしました。
長野大会HPはコチラ↓
http://www.geosociety.jp/nagano/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[長野大会]ランチョン・夜間小集会のお申込はお済みですか?
──────────────────────────────────
ランチョン・夜間小集会のお申込はお済みですか?
今大会では,大会初日9月11日(金)にもランチョンの時間を設けました.
会合を予定されているグループは,忘れずにお申込下さい。
◆ランチョン・夜間小集会申込締切:6月24日(水)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/nagano/content0033.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[長野大会]キャンセルした講演の講演要旨の扱いについて
──────────────────────────────────
学術大会にて発表を申し込まれた講演を講演要旨印刷後にキャンセルした
場合,該当講演の要旨は印刷物として存在することになります.この講演
要旨の扱いについてお知らせします。
詳しくは,http://www.geosociety.jp/nagano/content0053.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[長野大会]講演予定者で,現在未入会の方へ周知のお願い
──────────────────────────────────
会員の皆さまの周囲に,長野大会で講演する予定で,入会申込の手続きを済ませてい
ない学部生・院生・職場の同僚の方がおられましたら,6/30(火)までに入会申込書
の郵送手続きを完了するよう,ご周知願います。
講演申込締切時点(6/30)で入会申込書の提出がない場合,発表申込が受理できませ
ん。入会申込書は6/30までに必着でお願いします。
入会申込書は以下よりダウンロードできます。
http://www.geosociety.jp/outline/content0006.html
〔注〕入会申込中でも演題登録(講演申込)は可能です。入力の際,会員番号欄は空
欄のまま,会員種別欄は『入会申込中』を選択して操作を進めてください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2015年度会費督促請求について
──────────────────────────────────
1.督促請求のための自動引き落とし日は6月23日(火)です。
2015年度会費が未入金のかたで,1月から5月上旬までの間に自動引落の
手続きをされたかたは6月23日に引き落としがかかります。
引き落とし不備にならぬよう,残高の確認をお願いします。
2.郵便振替用紙によるお振り込みの方には,6月12日(金)に督促請求書
(郵便振替用紙)を郵送しました。お手元に届きましたら,早急にご送金くだ
さいますようお願いいたします。
※7月上旬頃までに入金確認が取れない場合には、7月号の雑誌から送本
停止となります。定期的に雑誌をお受け取りになりたい方は、お早めに
ご送金くださいますよう、よろしくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】 名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
──────────────────────────────────
日本地質学会では,学会員相互の交流と親睦を図る目的で,2年ごとに会員名簿を
発行することを運営規則にうたっております.2015年はその発行年にあたり,本年
11月末日発行の予定で準備を行っております.
名簿の発行様式は前回と同様で,全会員を収録します.本会としては,個人情報保
護法の制約はあるとしても,会員の皆様が上記の目的に沿って利用できるような,
従来規模の名簿を作成したいと考えておりますので,調査の実施にご理解とご協力
をお願いいたします.
アンケート提出およびWeb画面更新締切日:2015年10月5日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0132.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】フォトコンテスト入選作品展示会(in 銀座)開催中です
─────────────────────────────────
本年(第6回惑星地球フォトコンテスト)の作品メインに過去の入選作品も展示して
います.皆様お誘い合わせの上是非お越し下さい.
日程:6月13日(土)〜27日(土)午前中
場所:銀座プロムナードギャラリー
(東京都中央区銀座四丁目:東銀座地下歩道壁面)
展示風景など詳しくは,http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】環境地質部会:関東地下水盆と人工地層の地質環境巡検
─────────────────────────────────
関東地下水盆と人工地層の地質環境巡検
―国際第四紀学連合(INQUA)第19回大会記念―
主催:日本地質学会環境地質部会
日程:2015年8月4日(火)〜5日(水)2日間
参加費:10000円(保険込)※宿泊費は各自負担
募集人員:11名 募集締切:6月30日(火)
CPD単位:16単位(2日間)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0096.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】支部情報
─────────────────────────────────
[北海道支部]
■支部巡検「裏山の自然災害―支笏湖・苔の洞門」
6月20日(土)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[関東支部]
■箱根火山ミニ巡検「大涌谷とは何か」
共催:箱根ジオパーク推進協議会
7月12日(日)(雨天決行)
定員:18人(先着順.お申込はお早めに!!)
費用:貸切バス代、昼食・保険代込で6,000円(予定)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0155.html
■巡検『秩父ジオパークをまるごと堪能する』
8月11日(火)〜12日(水) 1泊2日
場所:埼玉県秩父地域(長瀞・和銅遺跡・ようばけ・鍾乳洞・浦山ダム等)
対象:小中高教員(教員以外,非会員の参加も歓迎します)
申込締切:7月10日(金)
■清澄フィールドキャンプ参加者募集
9月1日(火)〜7日(月)
場所:東京大学千葉演習林(千葉県鴨川市清澄)
費用:35,000円(宿泊・食事・保険・レンタカー代込)
応募締切:7月3日(金)
それぞれ詳しくは,関東支部HPへ http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■電中研TOPICS Vol.20
「再生可能エネルギー大量導入時の電力系統安定運用技術」
http://criepi.denken.or.jp/research/topics/index.html?m=150522
■第1回宅地の地すべり・土砂災害・水害減災診断士認定研修会
日本地質学会環境地質部会 共催
6月25(木)〜27日(土)(時間は各日毎に異なります)
場所:大阪市立大学文化交流センター(JR大阪駅前第2ビル6F)
会費:会員10,000円/日、非会員14,000円/日
[地すべり巡検]6月28日(日):阪神・淡路大震災に発生した西宮市仁川百合野
地区の地すべり地、地すべり資料館を見学予定(定員30名)
詳しくは、http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
■第175回地質汚染イブニングセミナー
場所:北とぴあ901会議室
6月26日(金)18:30〜20:30
講師:張 銘氏(産業技術総合研究所)
テーマ:台湾の地質法について
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■「科学の芽」賞 10周年シンポジウム「科学の芽を育てるために」
6月29日(月)14:30-16:00
場所:筑波大学東京キャンパス文京校舎1階
参加申込:6月26日(金)
www.tsukuba.ac.jp/event/e201506101400.html
■第52回アイソトープ・放射線研究発表会
日本地質学会ほか 共催
7月8日(水)〜10日(金)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1)
http://www.jrias.or.jp/
■原子力総合シンポジウム2015
テーマ「原子力の安全と科学と人材育成(仮)」
日本地質学会 後援
7月16日(木)
会場:日本学術会議講堂(東京都港区六本木)
問い合わせ先:シンポジウム運営委員会事務局
kikaku@aesj.or.jp
■青少年のための科学の祭典2015全国大会
日本地質学会 後援
7月25日(土)〜26日(日)
会場:科学技術館(千代田区北の丸公園)
http://www.kagakunosaiten.jp/
■第13回微量元素の生物地球化学に関する国際会議
13th International Conference on the Biogeochemistry of Trace
Elements, ICOBTE 2015 FUKUOKA
日本地質学会 後援
7月12日(日)〜16日(木)
場所:福岡国際会議場
http://www.icobte2015.org/index.html
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
7月26日(日)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区)
通常参加登録締切:6月30日(火)
http://inqua2015.jp/
■日本ジオパークネットワークガイドフォーラム
9月15日(火)〜16日(水)
会場:アミティ丹後(京丹後市網野町)
参加登録締切:7月31日(金)
http://jgn2015.com/
■第59回粘土科学討論会
日本地質学会 共催
9月2日(水)〜 5日(土)
会場:山口大学理学部・人文学部
講演申込期間:6月15日(月)〜 7月10日(金)
http://www.cssj2.org/
■第4回アジア太平洋ジオパークネットワーク山陰海岸シンポジウム
日本地質学会ほか 後援
9月15日(火)〜20日(日)
会場:豊岡市民会館(豊岡市立野町20-34)ほか
通常参加登録締切:7月31日(金)
http://apgn2015-jpn.com/
■第11回国際化石藻類シンポジウム
9月14日(月)〜19日(土)
会場:琉球大学
■第10回アジア地域応用地質学シンポジウム
日本地質学会 後援
研究発表会:9月24日(木)〜25日(金)
シンポジウム:9月26日(土)〜27日(日)[その後巡検予定あり]
場所:京都大学宇治黄檗プラザ
http://2015ars.com/
■Arthur Holmes Meeting Tsunami Hazards and Risks: Using the Geological
Record
日本地質学会 共催
9月25日(金)
場所:The Geological Society (Burlington House)(英・ロンドン)
プレ巡検:9月22日(火)〜24日(木)
http://www.geolsoc.org.uk/ahm15
■国際シンポジウム「沈み込み帯堆積盆地のリソスフェア・ダイナミクス」
日本地質学会 後援
10月5日(月)〜7日(水)(10月8日〜9日:地質巡検)
会場:東京第一ホテルシーフォート(品川区東品川)
講演要旨締切:7月15日
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/ILP2015/
■第31回ゼオライト研究発表会
日本地質学会 後援
11月26日(木)〜27日(金)
会場:とりぎん文化会館(鳥取市尚徳町101-5)
講演申込締切: 7月24日(金)
要旨原稿締切:10月30日(金)
http://katalab.org/31zeolite/
■第5回学生のヒマラヤ野外実習ツアー(参加者受付中)
日本地質学会 推薦
暫定日程:2016年3月5日〜20日の16日間
参加申込受付期間:2015年5月1日〜11月30日
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0144.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■山口大学理学部地球圏システム科学科教員公募(10/16)
■東京大学地震研究所平成28年度国際室外国人客員教員の推薦公募(8/31)
■農林水産省経験者採用試験:係長級(技術)募集期間未定(昨年度実績8/15-21)
■岡山大学地球物質科学研究センター教員公募(8/31)
■「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画」の実施機関の募集(6/24)
■東京大学地震研究所平成28年度特定機器利用の公募(7/31)
■東京大学地震研究所平成28年度共同利用・特定研究課題登録(7/31)
■平成28年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞および若手科学者賞受賞候
補者の推薦(学会締切7/17)
■アースウォッチ・ジャパン野外調査プログラムの募集(8/31)
■第36回猿橋賞受賞候補者の推薦(11/30)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
geo-Flash No.298[長野大会]シンポジウム・セッション決定!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.298 2015/5/7 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[長野大会]シンポジウム・セッション決定
【2】第35回IGC(万国地質学会議)ケープタウン2016年8-9月のご案内
【3】JAMSTEC船舶で取得された海底地形データの不具合について
【4】「地質の日」イベント情報
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[長野大会]シンポジウム・セッション決定
──────────────────────────────────
第122年学術大会(長野大会)
日程:2015年9月11日(金)〜13日(日)
会場:信州大学長野(工学部)キャンパスほか
シンポジウム,セッションが採択されました.まもなく講演申込,事前参
加登録が開始予定です.皆様ぜひ長野大会へご参加下さい.
◆講演申込受付期間:5月末〜6月30日(火)
◆事前参加登録受付期間:5月末〜8月18日(火)
シンポジウム,セッションの詳細は大会HPをご覧下さい.
http://www.geosociety.jp/nagano/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第35回IGC(万国地質学会議)ケープタウン2016年8-9月のご案内
──────────────────────────────────
日程:2016年8月27日〜9月4日 場所:南アフリカ・ケープタウン
IGCは,4年に一度,オリンピック・パラリンピックの年に開かれる,地質
科学の国際学会です.前々々回以降,フィレンツェ,オスロ,ブリスベー
ンと開催されてき,来年(2016年)は,南アフリカ共和国の,ケープタウ
ンで開かれます.
この学会は,4年間の世界の地質科学の進歩を国際規模で確認し,将来へ
の取り組みを議論する場として,世界 各国の地質科学研究者,教育者,
政府企業関係者などが,一堂に会する,大規模な学会です.期間前後,期
間中には,多くのフィールドトリップ(巡検),ショートコース,ワーク
ショップ,研究発表セッションなどが計画されています.特に,今回は,
中部および南部アフリカ諸国の協力のもとに,日ごろ行きにくいアフリカ
地域での,多数の巡検が催されます.
最近の,世界情勢は,地質科学の分野の知識,研究を除いては理解できな
いのは,論を待ちません.皆様方には,この機会に,このIGCにご理解を
いただき,ぜひ,参加をご計画ください.
◆ショートコース・ワークショップ・発表セッションの提案締切:
5月末(締切延長されました)
◆講演申込期間:2015年7月1日〜2016年1月31日
35回IGCのサイト http://www.35igc.org/
>>>2nd サーキュラー(PDF)がダウンロードできます.
ご質問は,小川勇二郎(IUGS国際地質科学連合理事:
e-mail:fyogawa45@yahoo.co.jp)までお願いします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】JAMSTEC船舶で取得された海底地形データの不具合について
──────────────────────────────────
海洋研究開発機構(JAMSTEC)ではJAMSTEC船舶の観測航海で取得した各種
のデータを管理・公開しています.このほど,既に公開済みの海底地形デー
タについて測深値にエラーが含まれていることが判明しましたので,お知
らせいたします.ユーザーの皆様にはご不便をおかけし,申し訳ありません.
<不具合の内容>
「かいよう」「よこすか」「かいれい」「みらい」で取得された海底地形
データについて,各船舶の喫水値が正常に処理されていないことを確認し
ました.
<不具合の原因>
CARIS社製のデータ処理ソフトウェア(HIPS/SIPS)の不具合によって,特
定の音響測深機(Seabeamシリーズ)のデータフォーマットとデータ処理
ソフトウェアのバージョンの組み合わせで喫水値が正常に処理されないこ
とが原因です.不具合は複数あり,それぞれ不具合の生じ方が異なります.
詳細な報告はメーカー・代理店のホームページをご覧ください.
代理店(株)東陽テクニカホームページ:
URL:http://www.toyo.co.jp/kaiyo
トップページから「最先端電子計測機器」の「海洋調査機器」をクリック
<不具合の対象範囲>
上記の原因を踏まえて調査中です.影響の範囲と内容についてはJAMSTEC
データ公開サイトで随時情報をお知らせします.
JAMSTEC データ公開サイト「DARWIN」:
http://www.godac.jamstec.go.jp/darwin/j/
<連絡先>
海洋研究開発機構 横浜研究所 データ管理技術グループ
dmo@jamstec.go.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】「地質の日」イベント情報
──────────────────────────────────
[本部]
■街中ジオ散歩in Tokyo「等々力渓谷の地質と人の関わり」徒歩見学会
5月10日(日)【申込受付終了】
■講演会「日本の地質学:最近の発見と応用2015」
5月23日(土)12:40〜14:40
会場:北とぴあ第1研修室 (東京都北区王子)
■第6回惑星地球フォトコンテストほか入選作品展示会
6月13日(土)〜27日(土)午前中
場所:銀座プロムナードギャラリー(中央区銀座4丁目地内 東銀座地下歩道壁面)
[北海道支部]
■記念企画展示「札幌の過去に見る洪水・土砂災害」
開催期間:4月28日(火)〜5月31日(日)
会場:札幌市資料館1階 大通西13丁目
[近畿支部]
■第32回地球科学講演会「阪神淡路大震災以降の近畿の活断層研究」
5月10日(日)13:30〜15:30 (受付:12:30〜)
場所:大阪市立自然史博物館 講堂
[四国支部]
■岩石・鉱物鑑定会
5月10日(日)11:00〜16:00
主催:愛媛大学理学部地球科学科・日本地質学会四国支部
会場:ミュージアム中庭(雨天の場合は,多目的室)
[三浦半島活断層調査会](日本地質学会 後援)
■地質の日記念観察会:深海から生まれた城ヶ島
5月23日(土)【申込受付終了】
[鹿児島地学会]
■地質見学会「石の文化史,史跡と岩石の旅」(仮)
5月10日(日)9:00 〜14:00(要昼食)
集合場所:鹿児島県立博物館
案内者:成尾英仁氏 ※徒歩で史跡を巡ります
地質の日イベントの各詳細はこちらから.
http://www.geosociety.jp/name/content0014.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報
─────────────────────────────────
[中部支部]
■2015年支部年会
6月13日(土)
年会会場:黒部市吉田科学館(富山県黒部市吉田574-1)
地質巡検(6月14日):富山県北東部の中生界(定員15名程度予定)
参加申込:6月6日(土)までに
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
[西日本支部]
■西日本地質講習会
講演会:6月11日(木)会場 山口大学
巡 検:6月12日(金)「山口の活断層巡検」(30名まで.最小遂行10名)
*講演会・巡検それぞれにCPD単位が発行されます.
*11日は,18:30より懇親会を予定しています(要申込).
参加申込締切:6月1日(月)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■電中研ニュース№480「原子力発電所を竜巻災害から守るために」
http://criepi.denken.or.jp/research/news/index.html?m=150430
■日本地球惑星科学連合2015年大会
5月24日(日)〜28日(木)
会場:幕張メッセ
事前参加登録:5月12日(火)
http://www.jpgu.org/meeting/
■第52回アイソトープ・放射線研究発表会
日本地質学会ほか 共催
7月8日(水)〜10日(金)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1)
http://www.jrias.or.jp/
■第13回微量元素の生物地球化学に関する国際会議
13th International Conference on the Biogeochemistry of Trace
Elements, ICOBTE 2015 FUKUOKA
日本地質学会 後援
7月12日(日)〜16日(木)
場所:福岡国際会議場
http://www.icobte2015.org/index.html
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
7月26日(日)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区)
通常参加登録締切:6月30日(火)
http://inqua2015.jp/
■ 平成27年度全国地学教育研究大会・日本地学教育学会第69回全国大会
8月21日(金)〜24日(月)
場所:福岡教育大学
http://www.jsese-69th-meeting.jp/
■日本ジオパークネットワークガイドフォーラム
9月15日(火)〜16日(水)
会場:アミティ丹後(京丹後市網野町)
バーチャルジオツアー発表者応募締切:5月29日(金)
参加登録締切:7月31日(金)
http://jgn2015.com/
■第59回粘土科学討論会
日本地質学会 共催
9月2日(水)〜 5日(土)
会場:山口大学理学部・人文学部
講演申込期間:6月15日(月)〜 7月10日(金)
http://www.cssj2.org/
■第4回アジア太平洋ジオパークネットワーク山陰海岸シンポジウム
日本地質学会ほか 後援
9月15日(火)〜20日(日)
会場:豊岡市民会館(豊岡市立野町20-34)ほか
通常参加登録締切:7月31日(金)
http://apgn2015-jpn.com/
■第10回アジア地域応用地質学シンポジウム
日本地質学会 後援
研究発表会:9月24日(木)〜25日(金)
シンポジウム:9月26日(土)〜27日(日)[その後巡検予定あり]
場所:京都大学宇治黄檗プラザ
http://2015ars.com/
■Arthur Holmes Meeting Tsunami Hazards and Risks: Using the Geological
Record
日本地質学会 共催
9月25日(金)
場所:The Geological Society (Burlington House)(英・ロンドン)
プレ巡検:9月22日(火)〜24日(木)
http://www.geolsoc.org.uk/ahm15
■国際シンポジウム「沈み込み帯堆積盆地のリソスフェア・ダイナミクス」
日本地質学会 後援
10月5日(月)〜7日(水)(10月8日〜9日:地質巡検)
会場:東京第一ホテルシーフォート(品川区東品川)
講演要旨締切:7月15日
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/ILP2015/
■ 第31回ゼオライト研究発表会
日本地質学会 後援
11月26日(木)〜27日(金)
会場:とりぎん文化会館(鳥取市尚徳町101-5)
講演申込締切: 7月24日(金)
要旨原稿締切:10月30日(金)
http://katalab.org/31zeolite/
■第5回学生のヒマラヤ野外実習ツアー
日本地質学会 推薦
暫定日程:2016年3月5日〜20日の16日間
参加申込受付期間:2015年5月1日〜11月30日
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0144.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞情報等
──────────────────────────────────
■Mine秋吉台ジオパーク構想研究チャレンジ助成事業(5/31)
■秋田県ジオパーク研究助成事業(男鹿半島・大潟/ゆざわ/八峰白神/鳥海山・飛島)(5/31)
■静岡県ふじのくに地球環境史ミュージアム研究職(任期なし)の公募(6/8)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
geo-Flash No.297(臨時)ネパール地震のテクトニクス
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.297 2015/5/5 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
ネパールでの地震発生より1週間以上が経過し、死者数が
7400名を超えるなど大変大きな被害がでています。被災
された方々に、心より哀悼の意を表します。
このように大きな被害となった原因について、本地域に詳しい
京都大学の酒井治孝先生にテクトニクスと地盤の観点からの
解説文を頂きました。下記URLをご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/hazard/content0087.html
人自不整合
国際学術用語となった“人自不整合”
上砂正一(環境地質コンサルタント、NPO法人日本地質汚染審査機構副理事長)
25年前の日本地質学会富山大会の夜間小集会「都市地質学全国協議会」で、地質汚染などで問題となっていた自然地層と人工地層との境界“人自不整合”について、地質学用語の提唱とその重要性が指摘された。提唱者の楡井久氏達をはじめとした参加者間で大議論となり、“人自不整合”が環境地質研究員会で採択されたものの、この新概念は国内で意味が深まらずに休眠状態であった。同氏は、京都で開催された29th IGC以来、 IUGS-COGEO, IUGS-GEMで長く活躍し、国際的に高い科学レベルにある日本の環境地質学の国外紹介に尽力してきている。国際GEO-PARK創立に関わるIUGS-COGEO側からのコメントにも関わっていたようである。
このような背景があったのか、”人自不整合“の用語が国際誌「The Anthropocene Review、2015」に、
The most important aspect of the declaration from the standpoint of this paper is the significance accorded to the lower bounding surface – marking the division between anthropogenically modified layers and natural geological deposits – that is known by Japanese geologists as the Jinji(人自) unconformity or discontinuity. The Chinese character for ‘Jin’ (人) means human being and that for ‘Ji’ (自) means ‘natural’. Although of particular relevance to the understanding of artificial ground in geologically unstable regions on the Japanese east coast, the boundary is also held to demarcate the lower bounding surface of humanly modified ground elsewhere in Japan and in other parts of the world. It marks the base of cultural layers of historic and ancient origin as well as heavily contaminated layers of the industrial age (Nirei et al., 2012). It is coincident with Boundary A, the lower boundary of the archaeosphere, as referred to in this paper and in Edgeworth (2014).
http://anr.sagepub.com/content/early/2015/01/07/2053019614565394.full.pdf+html
として掲載されている。”人自不整合“は、東日本大震災を契機にその概念の重要性が国外で認識され、国際学術用語として使われているのではないかと思われる。
はたして日本発の地質学的概念が、英語論文中にその用語の「漢字」がちりばめられて紹介された例は、これまでの日本地質学史の中にあったであろうか?このような事例は今後の日本地質学史の編纂に寄与すると思われる。特に、古参の地質学会会員の方々が記憶を呼び起こし、地質学会会員の共有情報にしておくことは、若手から独創的発想の研究成果が生まれる機会にもなろう。
記事を書くに当たって、八木アンテナのことを思い出した。世界的な発見・発明である指向性の八木アンテナは発明当初日本の科学界には西洋崇拝が強く、日本の発明は重要でないと受け入れられず八木の論文は、日本では埋もれてしまった。日本の特許がアメリカ軍によって利用され、戦後まもなくテレビが世界中に普及し、同時に八木アンテナも世界中に普及した。なぜか、このような構図が地質学の世界と重なっているように感じ筆を執った次第である。
引用文献
Matt Edgeworth, Dan deB Richter, Colin Waters, Peter Haff, Cath Neal and Simon James Price,2015,Diachronous beginnings of the Anthropocene: The lower bounding surface of anthropogenic deposits,The Anthropocene Review,1–26.
(2015.5.19掲載)
地質マンガ 恋する地質学2 彼女より壁ドン
地質マンガ
恋する地質学②
彼女よりも壁ドン?
原案:本郷宙軌 マンガ:KEY
メ モ
新鮮な露頭の観察は地質学では重要です.しかし,これからも多くの人が観察できるように,岩石や化石などの採取は必要最低限にとどめておきましょう.また,露頭での採取が許可されているか,事前に関係機関に問い合わせておきましょう.
「野外調査においてこころがけたいこと,2008.10.7 日本地質学会 理事会」
http://www.geosociety.jp/outline/content0064.html
「安全のしおり Safety Note,第121年学術大会(2014年鹿児島大会)巡検案内書より」
http://www.geosociety.jp/outline/content0136.html
geo-Flash No.299 5月25日より講演申込受付を開始
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.299 2015/5/19 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[長野大会]5月25日より講演申込受付を開始します
【2】日本地質学第7回総会開催について
【3】Island Arc:論文ワークショップ開催のお知らせ
【4】コラム:国際学術用語となった“人自不整合”
【5】「地質の日」イベント情報
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】地質マンガ 恋する地質学②「彼女より壁ドン?」
【10】籾倉克幹 名誉会員 ご逝去
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[長野大会]5月25日より講演申込受付を開始します
──────────────────────────────────
第122年学術大会(長野大会)
日程:2015年9月11日(金)〜13日(日)
会場:信州大学長野(工学部)キャンパスほか
まもなく講演申込,事前参加登録が開始予定です.皆様ぜひ長野大会へ
ご参加下さい.
◆講演申込受付期間:5月25日(火)〜6月30日(火)
◆事前参加登録受付期間:5月末〜8月18日(火)
※講演申込を予定しているが、まだ入会手続きをされていない方は,忘れ
ずに,入会申込書を学会事務局宛に郵送して下さい(6月24日必着).
申込締切時点で入会申込書が到着していないと,申込が受理されませんの
で、必ず入会申込書を郵送して下さい.
詳細は大会HPをご覧下さい.
http://www.geosociety.jp/nagano/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】日本地質学第7回総会開催について
─────────────────────────────────
5月23日(土)14:50〜15:50
会場 北とぴあ 第1研修室(東京都北区王子1-11-1)
総会議案はこちらから
http://www.geosociety.jp/outline/content0152.html
※正会員は,総会に陪席することができます.
※総会前に同会場にて【5】の講演会「日本の地質学:最近の発見と応用
2015」やフォトコンテストの表彰式(11:00〜)も行われます。是非あわ
せてご参加ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】Island Arc:論文ワークショップ開催のお知らせ
─────────────────────────────────
Island Arcの出版社であるWileyでは,下記論文投稿ワークショップを企
画しています.連合大会に参加される会員の方は,是非本ワークショップ
にもご参加下さい.
「論文投稿ワークショップ −論文構成法と査読プロセスを理解しよう」
(Tips on Structuring Your Article & the Peer Review Process)
Island Arc編集委員長およびGeochemistry, Geophysics, and
Geosystems編集委員による講演
日時:2015年5月25日(月)17:20〜18:10
会場:幕張メッセ国際会議場(日本地球惑星連合2015年大会内)3階301B
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/publication/content0085.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】コラム:国際学術用語となった“人自不整合”
──────────────────────────────────
上砂正一(環境地質コンサルタント,NPO法人日本地質汚染審査機構副理事長)
5年前の日本地質学会富山大会の夜間小集会「都市地質学全国協議会」で,
地質汚染などで問題となっていた自然地層と人工地層との境界“人自不整
合”について,地質学用語の提唱とその重要性が指摘された....
つづきは,http://www.geosociety.jp/faq/content0056.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】「地質の日」イベント情報
──────────────────────────────────
[本部]
■講演会「日本の地質学:最近の発見と応用2015」
5月23日(土)12:40〜14:40
会場:北とぴあ第1研修室 (東京都北区王子)
■第6回惑星地球フォトコンテストほか入選作品展示会
6月13日(土)〜27日(土)午前中
場所:銀座プロムナードギャラリー(中央区銀座 東銀座地下歩道壁面)
[北海道支部]
■記念企画展示「札幌の過去に見る洪水・土砂災害」
開催期間:4月28日(火)〜5月31日(日)
会場:札幌市資料館1階 大通西13丁目
[三浦半島活断層調査会](日本地質学会 後援)
■地質の日記念観察会:深海から生まれた城ヶ島
5月23日(土)【申込受付終了】
地質の日イベントの各詳細はこちらから.
http://www.geosociety.jp/name/content0014.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
─────────────────────────────────
[北海道支部支部]
■平成27年度例会(個人講演会)
6月13日(土)10:00〜18:00(予定)
場所:北海道大学理学部5号館大講堂
■支部巡検「裏山の自然災害―支笏湖・苔の洞門」
6月20日(土)7:30〜16:30(予定)
申込締切:6月10日(水) (定員30名)
それぞれ詳しくは,支部HPへ
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[関東支部支部]
■清澄フィールドキャンプ参加者募集
9月1日(火)〜9月7日(月)
場所:東京大学千葉演習林(千葉県鴨川市清澄)
費用:35,000円(宿泊・食事・保険・レンタカー代込)
応募締切:7月3日(金)
■巡検『秩父ジオパークをまるごと堪能する』
8月11日(火)〜12日(水) 1泊2日
場所:埼玉県秩父地域(長瀞・和銅遺跡・ようばけ・鍾乳洞・浦山ダム等)
対象:小中高教員(教員以外,非会員の参加も歓迎します)
申込締切:7月10日(金)
それぞれ詳しくは,支部HPへ http://kanto.geosociety.jp/
[中部支部]
■2015年支部年会
6月13日(土)
年会会場:黒部市吉田科学館(富山県黒部市吉田574-1)
地質巡検(6月14日):富山県北東部の中生界(定員15名程度)
参加申込:6月6日(土)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
[西日本支部]
■西日本地質講習会
講演会・懇親会:6月11日(木) 会場 山口大学
巡 検:6月12日(金)「山口の活断層巡検」(定員30名)
*講演会・巡検それぞれにCPD単位が発行されます.
参加申込締切:6月1日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■北海道立総合研究機構地質研究所ニュース
http://www.hro.or.jp/list/environmental/research/gsh/publication/gshnews/gshnews02/index.html#vol31
■日本地球惑星科学連合2015年大会
5月24日(日)〜28日(木)
会場:幕張メッセ
http://www.jpgu.org/meeting/
■第174回地質汚染イブニングセミナー
場所:北とぴあ901会議室
5月29日(金)18:30〜20:30
講師:高松武次郎氏(元茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター長)
テーマ:都市と周辺山地の土壌に広がる慢性的重金属汚染
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■学術フォーラム「われわれはどこに住めばよいのか?
〜地図を作り,読み,災害から身を守る〜」
6月20日(土)13:00〜17:00
会場:日本学術会議講堂
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/206-s-0620.pdf
■第52回アイソトープ・放射線研究発表会
日本地質学会ほか 共催
7月8日(水)〜10日(金)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1)
http://www.jrias.or.jp/
■第13回微量元素の生物地球化学に関する国際会議
13th International Conference on the Biogeochemistry of Trace
Elements, ICOBTE 2015 FUKUOKA
日本地質学会 後援
7月12日(日)〜16日(木)
場所:福岡国際会議場
http://www.icobte2015.org/index.html
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
7月26日(日)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区)
通常参加登録締切:6月30日(火)
http://inqua2015.jp/
■日本ジオパークネットワークガイドフォーラム
9月15日(火)〜16日(水)
会場:アミティ丹後(京丹後市網野町)
バーチャルジオツアー発表者応募締切:5月29日(金)
参加登録締切:7月31日(金)
http://jgn2015.com/
■第59回粘土科学討論会
日本地質学会 共催
9月2日(水)〜 5日(土)
会場:山口大学理学部・人文学部
講演申込期間:6月15日(月)〜 7月10日(金)
http://www.cssj2.org/
■第4回アジア太平洋ジオパークネットワーク山陰海岸シンポジウム
日本地質学会ほか 後援
9月15日(火)〜20日(日)
会場:豊岡市民会館(豊岡市立野町20-34)ほか
通常参加登録締切:7月31日(金)
http://apgn2015-jpn.com/
■第10回アジア地域応用地質学シンポジウム
日本地質学会 後援
研究発表会:9月24日(木)〜25日(金)
シンポジウム:9月26日(土)〜27日(日)[その後巡検予定あり]
場所:京都大学宇治黄檗プラザ
http://2015ars.com/
■Arthur Holmes Meeting Tsunami Hazards and Risks: Using the Geological
Record
日本地質学会 共催
9月25日(金)
場所:The Geological Society (Burlington House)(英・ロンドン)
プレ巡検:9月22日(火)〜24日(木)
http://www.geolsoc.org.uk/ahm15
■国際シンポジウム「沈み込み帯堆積盆地のリソスフェア・ダイナミクス」
日本地質学会 後援
10月5日(月)〜7日(水)(10月8日〜9日:地質巡検)
会場:東京第一ホテルシーフォート(品川区東品川)
講演要旨締切:7月15日
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/ILP2015/
■ 第31回ゼオライト研究発表会
日本地質学会 後援
11月26日(木)〜27日(金)
会場:とりぎん文化会館(鳥取市尚徳町101-5)
講演申込締切: 7月24日(金)
要旨原稿締切:10月30日(金)
http://katalab.org/31zeolite/
■第5回学生のヒマラヤ野外実習ツアー
日本地質学会 推薦
暫定日程:2016年3月5日〜20日の16日間
参加申込受付期間:2015年5月1日〜11月30日
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0144.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■JAMSTEC海底資源研究開発センター(技術職・任期制)職員公募(6/12)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】地質マンガ 恋する地質学②「彼女より壁ドン?」
──────────────────────────────────
恋する地質学②「彼女より壁ドン?」
原案:本郷宙軌 マンガ:Key
http://www.geosociety.jp/faq/content0057.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】籾倉克幹 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
日本地質学名誉会員 籾倉克幹氏(元 農林水産省,基礎地盤コンサルタン
ツ)がご逝去されました(享年80歳).
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げ
ます.
通夜ならびに告別式は、下記のとおり執り行われますので併せてお知らせ
申し上げます.
通 夜:5月20日(水)18:00より
告別式:5月21日(木)10:00〜11:00より
式場:ライフケア幕張会堂
(〒262-0033 千葉市花見川区幕張本郷6-24-24 電話:043-275-4444)
JR総武線,京成線 幕張本郷駅より徒歩4分
会長 井龍 康文
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
geo-Flash No.300[長野大会]講演申込受付中です!!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.300 2015/6/2┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[長野大会]講演申込受付中です(締切:6/30)
【2】口永良部島火山の噴火に関する情報
【3】知床半島羅臼町で海岸線沿い隆起と地すべり調査報告
【4】2015地震火山こどもサマースクール in 南アルプス参加募集
【5】フォトコンテスト入選作品展示会(in 銀座)
【6】関東地下水盆と人工地層の地質環境巡検:参加募集
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[長野大会]講演申込受付中です(締切:6/30)
──────────────────────────────────
日本地質学会第122年学術大会(長野大会)
日程:2015年9月11日(金)〜13日(日)
会場:信州大学長野(工学)キャンパスほか
◆◆各種申込締切◆◆
・講演申込:6月30日(火)
・ランチョン・夜間小集会申込:6月24日(水)
・小さなEarth Scientistの集い参加申込:7月16日(木)
------------大会参加申込はまもなく受付開始です-----------
・事前参加登録受付:6月中旬〜8月18日(火)
・巡検参加申込:6月中旬〜8月7日(金) など
※講演申込を予定しているが、まだ入会手続きをされていない方は,忘れ
ずに,入会申込書を学会事務局宛に郵送して下さい(6月24日必着).
申込締切時点で入会申込書が到着していないと,申込が受理されませんの
で、必ず入会申込書を郵送して下さい.
詳細は大会HPをご覧下さい.
http://www.geosociety.jp/nagano/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】口永良部島火山の噴火に関する情報
─────────────────────────────────
産業技術総合研究所地質調査総合センターより関連情報が発表されました.
詳しくはこちらから
https://www.gsj.jp/hazards/volcano/kuchinoerabujima2015/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】知床半島羅臼町で海岸線沿い隆起と地すべり調査報告
─────────────────────────────────
2015年4月24日に北海道の知床半島羅臼町で海岸線沿いの海底部分が隆
起しているのが地元住民に目撃され,大変な話題となりました.海底隆起
の原因は,地すべりに伴う現象であることが現地を調査しました大学や行
政機関によって示されましたが,地すべりと海底隆起のメカニズムについ
ては未だに研究者間で議論が続いています.このたび,北海道立総合研究
機構地質研究所からこの現象についての速報が出されましたのお知らせし
ます.
(北見工業大学 山崎新太郎)
詳しくは,こちらから
http://www.geosociety.jp/hazard/category0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2015地震火山こどもサマースクール in 南アルプスの参加者募集
─────────────────────────────────
第16回地震火山こどもサマースクールin南アルプス(中央構造線エリア)
「まくれあがった台地と中央構造線のナゾ」
日時:2015年8月8日(土)9時〜8月9日(日)17時
活動場所:南アルプス林道、杖突峠、板山・非持・溝口露頭、長谷公民館
(戸台の化石資料室)、伊那市創造館など
集合場所:伊那市創造館(長野県伊那市荒井3520番地)
宿泊先:国立信州高遠青少年自然の家(長野県伊那市高遠町藤沢6877-11)
定員:小学5年〜高校生 40名(定員をこえた場合、学年などを考慮し先
着順で締め切ります)
参加費:2,000円(予定)
詳しくは,http://www.kodomoss.jp/ss/minamialps/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】フォトコンテスト入選作品展示会(in 銀座)
─────────────────────────────────
本年(第6回惑星地球フォトコンテスト)の作品メインに過去の入選作品も展示します.
皆様お誘い合わせの上是非お越し下さい
日程:6月13日(土)15時〜27日(土)午前中
場所:銀座プロムナードギャラリー
(東京都中央区銀座四丁目:東銀座地下歩道壁面)
詳しくは,http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】関東地下水盆と人工地層の地質環境巡検:参加者募集
─────────────────────────────────
関東地下水盆と人工地層の地質環境巡検
―国際第四紀学連合(INQUA)第19回大会記念―
国際第四紀学連合(INQUA)第19 回大会が2015年7月26日(日)〜8月2日
(日)に名古屋において開催され巡検も同時に実施されます.同大会巡検
(Po-6:The environmental management of the Big Kanto Groundwater
Basin and the distribution of man-made strata and geopollution )
は催行人員の関係で中止となりました.しかしながら,海外からの参加希
望者を含め,多数の参加希望者がいますので,同じ内容で巡検を実施しま
す.参加希 望者を募集いたします.
主催:日本地質学会環境地質部会
日程:2015年8月4日(火)〜5日(水)2日間
参加費:10000円 募集人員:11名
募集締切日:6月30日(火)
CPD単位:1日目:6単位 2日目:8単位(予定)
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/outline/content0096.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
─────────────────────────────────
[北海道支部支部]
■平成27年度例会(個人講演会)
6月13日(土)10:00〜18:00(予定)
場所:北海道大学理学部5号館大講堂
*講演プログラムを公開しました
■支部巡検「裏山の自然災害―支笏湖・苔の洞門」
6月20日(土)7:30〜16:30(予定)
申込締切:6月10日(水) (定員30名)
それぞれ詳しくは,北海道支部HPへ
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[関東支部支部]
■清澄フィールドキャンプ参加者募集
9月1日(火)〜9月7日(月)
場所:東京大学千葉演習林(千葉県鴨川市清澄)
費用:35,000円(宿泊・食事・保険・レンタカー代込)
応募締切:7月3日(金)
■巡検『秩父ジオパークをまるごと堪能する』
8月11日(火)〜12日(水) 1泊2日
場所:埼玉県秩父地域(長瀞・和銅遺跡・ようばけ・鍾乳洞・浦山ダム等)
対象:小中高教員(教員以外,非会員の参加も歓迎します)
申込締切:7月10日(金)
それぞれ詳しくは,関東支部HPへ http://kanto.geosociety.jp/
[中部支部]
■2015年支部年会
6月13日(土)
年会会場:黒部市吉田科学館(富山県黒部市吉田574-1)
地質巡検(6月14日):富山県北東部の中生界(定員15名程度)
参加申込締切:6月6日(土)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地震調査研究推進本部20周年特別シンポジウム
「巨大地震にどう向き合うか」
6月23日(火)13時30分〜18時00分
場所:東京大学本郷キャンパス伊藤謝恩ホール
http://www.jishin.go.jp/main/20years.html
■第175回地質汚染イブニングセミナー
場所:北とぴあ901会議室
6月26日(金)18:30〜20:30
講師:張銘氏(産業技術総合研究所)
テーマ:台湾の地質法について
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■第52回アイソトープ・放射線研究発表会
日本地質学会ほか 共催
7月8日(水)〜10日(金)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1)
http://www.jrias.or.jp/
■特別集中講義「地球の内部〜地震学における観測と理論」
7月8日(水)〜10日(金)
講師:Walter D. Mooney博士(アメリカ地質調査所)
Miaki Ishii教授(ハーバード大学)
場所:岡山大学地球物質科学研究センター
公開講義の聴講生を,岡山大学内外から募集します(募集締切:6/20)
http://www.misasa.okayama-u.ac.jp/jp/news/?eid=01192
■原子力総合シンポジウム2015
テーマ「原子力の安全と科学と人材育成(仮)」
日本地質学会 後援
7月16日(木)
会場:日本学術会議講堂(東京都港区六本木)
問い合わせ先:シンポジウム運営委員会事務局
kikaku@aesj.or.jp
■青少年のための科学の祭典2015全国大会
日本地質学会 後援
7月25日(土)〜26日(日)
会場:科学技術館(千代田区北の丸公園)
http://www.kagakunosaiten.jp/
■第13回微量元素の生物地球化学に関する国際会議
13th International Conference on the Biogeochemistry of Trace
Elements, ICOBTE 2015 FUKUOKA
日本地質学会 後援
7月12日(日)〜16日(木)
場所:福岡国際会議場
http://www.icobte2015.org/index.html
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
7月26日(日)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区)
通常参加登録締切:6月30日(火)
http://inqua2015.jp/
■日本ジオパークネットワークガイドフォーラム
9月15日(火)〜16日(水)
会場:アミティ丹後(京丹後市網野町)
参加登録締切:7月31日(金)
http://jgn2015.com/
■第59回粘土科学討論会
日本地質学会 共催
9月2日(水)〜 5日(土)
会場:山口大学理学部・人文学部
講演申込期間:6月15日(月)〜 7月10日(金)
http://www.cssj2.org/
■第4回アジア太平洋ジオパークネットワーク山陰海岸シンポジウム
日本地質学会ほか 後援
9月15日(火)〜20日(日)
会場:豊岡市民会館(豊岡市立野町20-34)ほか
通常参加登録締切:7月31日(金)
http://apgn2015-jpn.com/
■第11回国際化石藻類シンポジウム
9月14日(月)〜19日(土)
会場:琉球大学
■第10回アジア地域応用地質学シンポジウム
日本地質学会 後援
研究発表会:9月24日(木)〜25日(金)
シンポジウム:9月26日(土)〜27日(日)[その後巡検予定あり]
場所:京都大学宇治黄檗プラザ
http://2015ars.com/
■Arthur Holmes Meeting Tsunami Hazards and Risks: Using the Geological
Record
日本地質学会 共催
9月25日(金)
場所:The Geological Society (Burlington House)(英・ロンドン)
プレ巡検:9月22日(火)〜24日(木)
http://www.geolsoc.org.uk/ahm15
■国際シンポジウム「沈み込み帯堆積盆地のリソスフェア・ダイナミクス」
日本地質学会 後援
10月5日(月)〜7日(水)(10月8日〜9日:地質巡検)
会場:東京第一ホテルシーフォート(品川区東品川)
講演要旨締切:7月15日
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/ILP2015/
■第31回ゼオライト研究発表会
日本地質学会 後援
11月26日(木)〜27日(金)
会場:とりぎん文化会館(鳥取市尚徳町101-5)
講演申込締切: 7月24日(金)
要旨原稿締切:10月30日(金)
http://katalab.org/31zeolite/
■第5回学生のヒマラヤ野外実習ツアー(参加者受付中)
日本地質学会 推薦
暫定日程:2016年3月5日〜20日の16日間
参加申込受付期間:2015年5月1日〜11月30日
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0144.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■広島大学大学院理学研究科地球惑星システム学専攻特任助教の募集(9/30)
■鳥取環境大学環境学部教授、准教授又は講師1名(8/31)
■電力中央研究所研究員(地質分野)公募(決定次第締切)
■海洋研究開発機構国際ポストドクトラル研究員(5名)(7/21)
■北海道立総合研究機構平成28年度研究職員採用(地すべり・斜面崩壊等)(6/30)
■第19回尾瀬賞の募集(8/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
geo-Flash No.302(臨時)[長野大会]講演申込:もうすぐ締切です!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.302 2015/6/24┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[長野大会]講演申込:もうすぐ締切です!
【2】[長野大会]講演申込画面(PASREG):入力時の注意
【3】[長野大会]申込に関わるQ & Aもご利用下さい
【4】[長野大会]各種申込み締切のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[長野大会]講演申込:もうすぐ締切です!
──────────────────────────────────
長野大会講演申込・要旨投稿は, 来週6月30日(火)18時締切(WEB)です。
締切に近づくと申込が集中しますので,できるだけ余裕をもってお手続き下さい。
申込締切の延長はありませんので,締切を厳守して頂くようお願いします。
今年もたくさんのお申込をお待ちしています。
講演申込は,こちらから
http://www.geosociety.jp/nagano/content0023.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[長野大会]講演申込画面(PASREG):入力時の注意
─────────────────────────────────
(1)新規登録:まずは〔受付番号〕と〔パスワード〕を取得しましょう!
参加登録トップ画面一番下【新規登録はこちらから】から新規登録を行い,
〔受付番号〕と〔パスワード〕を取得してください。
登録画面には“演題情報”のほかに“連絡者情報(一度登録しておけば書き換え
る必要の無い項目)”もあります。要旨原稿が完成していなくてもまずは新規登
録を行い,〔受付番号〕と〔パスワード〕を取得することをお勧めします!
(2)修正する場合:画面右上【マイページ】からログイン
〔受付番号〕と〔パスワード〕で,【マイページ】からログインいただき,締切
まで何度でも入力情報の修正ができます。
画面操作に慣れていないと,タイムアウトする可能性が高く,締切直前の登録は
入力ミス等も多くなります。要旨原稿が完成していなくても、まずは〔受付番号〕
と〔パスワード〕を取得しましょう!締切までは要旨のみ後で投稿する事も
入力した情報を修正する事も可能です。余裕をもってお手続き下さい。
講演申込は、こちらから
http://www.geosociety.jp/nagano/content0023.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[長野大会]申込に関わるQ & Aもご利用下さい
─────────────────────────────────
申込手続きの際に会員から比較的多く寄せられるお問い合わせをQ & Aとしてまと
めました。【演題登録編】【参加登録編】とご用意しましたので,申込手続きで
お困りの際は、ぜひご覧下さい。
大会申込Q&Aはこちら
http://www.geosociety.jp/nagano/content0054.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[長野大会]各種申込み締切のお知らせ
─────────────────────────────────
■ 事前参加登録
申込締切(Web):8月18日(火)締切[*巡検のみ 8月7日(金)締切]
申込締切(郵送):8月14日(金)必着[*巡検のみ 8月5日(水)必着]
〔注〕演題登録と事前参加登録は,それぞれ別のお申し込みになります。
ご注意ください。
http://www.geosociety.jp/nagano/content0001.html
■ 小さなEarth Scientistのつどい
〜第13回 小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜参加校募集
申込締切:7月16 日(水)
■ 企業・研究機関等関係団体による展示会の出展募集
1次申込締切:7月3日(金)
http://www.geosociety.jp/nagano/content0036.html
■ 書籍・販売ブースご利用の募集
1次申込締切:7月3日(金)
http://www.geosociety.jp/nagano/content0036.html#book
■ 講演要旨集,広告協賛の募集
申込締切:8月7日(金)
http://www.geosociety.jp/nagano/content0036.html#kokoku
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flash No.303[長野大会]
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.303 2015/6/29┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[長野大会]講演申込明日(6/30)締切です!(延長なし)
【2】[長野大会]講演申込画面(PASREG):入力時の注意
【3】[長野大会]申込に関わるQ & Aもご利用下さい
【4】[長野大会]各種申込み締切のお知らせ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【5】高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する「地層処分技術WGのこれまでの
議論の整理」について、専門家からの御意見を募集します
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[長野大会]講演申込明日(6/30)締切です!(延長なし)
──────────────────────────────────
長野大会講演申込・要旨投稿は, 明日6月30日(火)18時締切(WEB)です。
申込締切の延長はありませんので,締切を厳守して頂くようお願いします。
締切に近づくと申込が集中しますので,できるだけ余裕をもってお手続き下さい。
今年もたくさんのお申込をお待ちしています。
講演申込は,こちらから
http://www.geosociety.jp/nagano/content0023.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[長野大会]講演申込画面(PASREG):入力時の注意
─────────────────────────────────
(1)新規登録:まずは〔受付番号〕と〔パスワード〕を取得しましょう!
参加登録トップ画面一番下【新規登録はこちらから】から新規登録を行い,
〔受付番号〕と〔パスワード〕を取得してください。
登録画面には“演題情報”のほかに“連絡者情報(一度登録しておけば書き換え
る必要の無い項目)”もあります。要旨原稿が完成していなくてもまずは新規登
録を行い,〔受付番号〕と〔パスワード〕を取得することをお勧めします!
(2)修正する場合:画面右上【マイページ】からログイン
〔受付番号〕と〔パスワード〕で,【マイページ】からログインいただき,締切
まで何度でも入力情報の修正ができます。
画面操作に慣れていないと,タイムアウトする可能性が高く,締切直前の登録は
入力ミス等も多くなります。要旨原稿が完成していなくても、まずは〔受付番号〕
と〔パスワード〕を取得しましょう!締切までは要旨のみ後で投稿する事も
入力した情報を修正する事も可能です。余裕をもってお手続き下さい。
講演申込は、こちらから
http://www.geosociety.jp/nagano/content0023.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[長野大会]申込に関わるQ & Aもご利用下さい
─────────────────────────────────
申込手続きの際に会員から比較的多く寄せられるお問い合わせをQ & Aとしてまと
めました。【演題登録編】【参加登録編】とご用意しましたので,申込手続きで
お困りの際は、ぜひご覧下さい。
大会申込Q&Aはこちら
http://www.geosociety.jp/nagano/content0054.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[長野大会]各種申込み締切のお知らせ
─────────────────────────────────
■ 事前参加登録
申込締切(Web):8月18日(火)締切[*巡検のみ 8月7日(金)締切]
申込締切(郵送):8月14日(金)必着[*巡検のみ 8月5日(水)必着]
〔注〕演題登録と事前参加登録は,それぞれ別のお申し込みになります。
ご注意ください。
http://www.geosociety.jp/nagano/content0001.html
■ 小さなEarth Scientistのつどい
〜第13回 小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜参加校募集
申込締切:7月16 日(水)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する「地層処分技術WGのこれまでの
議論の整理」について、専門家からの御意見を募集します
─────────────────────────────────
資源エネルギー庁より標記意見募集を行っておりますので,会員の皆様にお知ら
せ致します.
意見募集期間:平成27年6月26日(金)〜7月25日(土)
詳しくは,
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/rw/
gijutsu-iken.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
geo-Flash No.304[長野大会]事前参加登録受付中
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.304 2015/7/7┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[長野大会]事前参加登録受付中
【2】「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく
間接経費措置額の削減割合の基準等について
【3】名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
【4】環境地質部会からのお知らせ
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[長野大会]事前参加登録受付中
─────────────────────────────────
日本地質学会第122年学術大会(長野大会)の事前参加登録を受付中です.
今年もたくさんの皆様のほ参加をお待ちしています.
9月11日(金)〜13日(日)
会場:信州大学長野(工学)キャンパス ほか
◆事前参加登録:8/18(火)締切[※巡検は8/7(金)締切]
〔注〕演題登録と事前参加登録は,それぞれ別のお申し込みです.ご注意下さい.
その他のお申込
◆小さなESのつどい小中高「地学研究」発表会参加申込:7月16日(木)
長野大会HPはコチラ↓
http://www.geosociety.jp/nagano/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく
間接経費措置額の削減割合の基準等について
──────────────────────────────────
文部科学省より、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライ
ン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)」に基づく間接経費措置額の削減割合の
基準等について、周知するよう依頼がありましたので,会員の皆様にお知らせ
致します.
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/news/n115.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】 名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
──────────────────────────────────
日本地質学会では,学会員相互の交流と親睦を図る目的で,2年ごとに会員名簿を
発行することを運営規則にうたっております.2015年はその発行年にあたり,本年
11月末日発行の予定で準備を行っております.
名簿の発行様式は前回と同様で,全会員を収録します.本会としては,個人情報保
護法の制約はあるとしても,会員の皆様が上記の目的に沿って利用できるような,
従来規模の名簿を作成したいと考えておりますので,調査の実施にご理解とご協力
をお願いいたします.
アンケート提出およびWeb画面更新締切日:2015年10月5日(月)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0132.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】環境地質部会からのお知らせ
─────────────────────────────────
「2011年東北地方太平洋沖地震から学んだ地質災害防止と人工地層と
地質汚染に関わる国際宣言」
2015年3月14日から27日にかけて,第3回国連防災世界会議(仙台)が開催され
ました.参加者は全世界から約15万人以上にものぼりました.この世界会議を
契機に,国際地質科学連合(IUGS)環境管理研究委員会(GEM)の「国際人工地
層と地質汚染ワーキング・グループ」において 2011年6月に出した「国際地質
災害防止宣言」を総括する責務から,「2011年東北地方太平洋沖地震から学ん
だ地質災害防止と人工地層と地質汚染に関わる国際宣言」が出されました.
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/outline/content0156.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報
─────────────────────────────────
[関東支部]
■巡検『秩父ジオパークをまるごと堪能する』
8月11日(火)〜12日(水) 1泊2日
場所:埼玉県秩父地域(長瀞・和銅遺跡・ようばけ・鍾乳洞・浦山ダム等)
対象:小中高教員(教員以外,非会員の参加も歓迎します)
申込締切:7月10日(金)
詳しくは、 http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第52回アイソトープ・放射線研究発表会
日本地質学会ほか 共催
7月8日(水)〜10日(金)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1)
http://www.jrias.or.jp/
■シンポジウム「国際地質時代区分に千葉時代を設定しよう
―第四紀前期/中期(M/L)境界と環境・観光問題−」
日本地質学会環境地質部会 共催
7月11日(土)14:00〜17:00
会場:南総公民館(千葉県市原市)
http://www.geosociety.jp/outline/content0096.html#150711_chiba
■第13回微量元素の生物地球化学に関する国際会議
13th International Conference on the Biogeochemistry of Trace
Elements, ICOBTE 2015 FUKUOKA
日本地質学会 後援
7月12日(日)〜16日(木)
会場:福岡国際会議場
http://www.icobte2015.org/index.html
■原子力機構_地層処分技術に関する研究開発報告会
7月14日(火) 13:00〜16:30
会場:コクヨホール(東京都港区港南1-8-35)
定員:250名程度(事前登録制:7/9締切)参加費無料
http://www.jaea.go.jp/04/tisou/houkokukai/pdf/nendo_h27_guide.pdf
■原子力総合シンポジウム2015
テーマ「原子力の将来のあり方」
日本地質学会 後援
7月16日(木)
会場:日本学術会議講堂(東京都港区六本木)
要事前申込(7/13締切)
http://www.aesj.net/events/symposium2015
■日本学術会議 中部地区会議学術講演会
「日本海地域の未来」
7月17日(金)13:00〜16:00
会場:富山大学五福キャンパス黒田講堂会議室
http://krs.bz/scj/c?c=239&m=21728&v=405f5bf4
■青少年のための科学の祭典2015全国大会
日本地質学会 後援
7月25日(土)〜26日(日)
会場:科学技術館(千代田区北の丸公園)
http://www.kagakunosaiten.jp/
■東京大学大気海洋研究所共同利用研究集会
「海水準変動と氷床の安定性に関する国際研究集会」
7月22日(水)〜24日(金)
会場:東京大学大気海洋研究所 2F講堂
http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/aori_news/meeting/2015/20150722.html
■東京大学海洋アライアンス第10回東京大学の海研究
「新たな手法と視点が海洋の常識を覆す」
7月23日(木)13:00〜17:00
会場:東京大学農学部弥生講堂
http://www.oa.u-tokyo.ac.jp/news/2015/05/000608.html
■第291回地学クラブ講演会
7月24日(金)16:00〜
会場:東京地学協会地学会館2F講堂
上野将司「最近のシルクロードをたずねて
−海面下の灼熱の砂漠から氷河のかかる高山へ」
http://geog.or.jp/lecture/lecturescheduled/242-club291.html
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
7月26日(日)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区)
http://inqua2015.jp/
■第176回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
7月31日(金)18:30〜20:30(事前予約不要)
会場:北とぴあ901会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分)
テーマ:三陸海岸ならびに仙台平野における東北地方太平洋沖地震に起因した
津波堆積物中のヒ素ならびに重金属類の起源
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■第59回粘土科学討論会
日本地質学会 共催
9月2日(水)〜 5日(土)
会場:山口大学理学部・人文学部
講演申込期間:6月15日(月)〜 7月10日(金)
http://www.cssj2.org/
■日本ジオパークネットワークガイドフォーラム
9月15日(火)〜16日(水)
会場:アミティ丹後(京丹後市網野町)
参加登録締切:7月31日(金)
http://jgn2015.com/
■第4回アジア太平洋ジオパークネットワーク山陰海岸シンポジウム
日本地質学会ほか 後援
9月15日(火)〜20日(日)
会場:豊岡市民会館(豊岡市立野町20-34)ほか
通常参加登録締切:7月31日(金)
http://apgn2015-jpn.com/
■第11回国際化石藻類シンポジウム
9月14日(月)〜19日(土)
会場:琉球大学
■第32回歴史地震研究会
9月21日(月・祝)〜23日(水・祝)
会場:京丹後市峰山総合福祉センター(京都府京丹後市)
巡検等申込・講演要旨投稿締切:7月31日(金)
http://sakuya.ed.shizuoka.ac.jp/rzisin/menu7.html
■第10回アジア地域応用地質学シンポジウム
日本地質学会 後援
研究発表会:9月24日(木)〜25日(金)
シンポジウム:9月26日(土)〜27日(日)[その後巡検予定あり]
会場:京都大学宇治黄檗プラザ
http://2015ars.com/
■Arthur Holmes Meeting Tsunami Hazards and Risks: Using the Geological
Record
日本地質学会 共催
9月25日(金)
会場:The Geological Society (Burlington House)(英・ロンドン)
プレ巡検:9月22日(火)〜24日(木)
http://www.geolsoc.org.uk/ahm15
■国際シンポジウム「沈み込み帯堆積盆地のリソスフェア・ダイナミクス」
日本地質学会 後援
10月5日(月)〜7日(水)(10月8日〜9日:地質巡検)
会場:東京第一ホテルシーフォート(品川区東品川)
講演要旨締切:7月15日
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/ILP2015/
■第31回ゼオライト研究発表会
日本地質学会 後援
11月26日(木)〜27日(金)
会場:とりぎん文化会館(鳥取市尚徳町101-5)
講演申込締切: 7月24日(金)
要旨原稿締切:10月30日(金)
http://katalab.org/31zeolite/
■地質学史懇話会
12月23日(水・休)13:30-17:00
会場:北とぴあ8階803号室(JR京浜東北線王子駅下車3分)
・吉岡有文『日本の科学教育映画の世界』(仮題)
・秋葉文雄『日本の珪藻化石研究』(仮題)
■第5回学生のヒマラヤ野外実習ツアー(参加者受付中)
日本地質学会 推薦
暫定日程:2016年3月5日〜20日の16日間
参加申込受付期間:2015年5月1日〜11月30日
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0144.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■岡山理科大学自然科学研究所教員(教授又は准教授)募集(9/18)
■JAMSTEC地震津波海域観測研究開発センター任期制職員募集(7/24)
■第37回(平成27年)沖縄研究奨励賞推薦応募(学会締切 8/31)
■JAMSTEC平成28・29年度研究船(「よこすか」「かいれい」「みらい」)
利用公募課題の募集(7/21)
■伊豆半島ジオパーク:学術研究支援(7/31)
■隠岐世界ジオパーク:学術研究論文募集(10/30)
■隠岐世界ジオパーク:学術研究奨励事業助成金の募集(7/20)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
geo-flash no.305(臨時)イリノイ州立博物館の閉鎖危機について
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.305 2015/7/10┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
日本地質学会会員の皆様
アメリカ第四紀学会からの情報として、イリノイ州立博物館が閉館の危機に
あり、内外からの意見表明を求めているというニュースが日本の研究者のもと
にありました。このことについて、日本第四紀学会では同学会会員に対し、
広報いたしました。日本地質学会でもこの情報を入手し、事態の重要性
に鑑み、第四紀学会と同様に会員に周知することといたしました。
ついては、時間的にも逼迫していることですので、第四紀学会にお許しを
いただき、あて名以外は、同学会の文書全文をそのまま転載させていただく
ことにいたしました。
より多くの方にこの情報をお伝えするため,ぜひ周辺の方々に本文章を転送し
て下さい.
(日本地質学会執行理事会)
=======================
イリノイ州立博物館の閉鎖危機について、意見表明にご協力ください
アメリカ第四紀学会(American Quaternary Association)から、イリノイ州立
博物館機構が、州政府のコスト削減のため閉鎖されそうだとの情報が入りまし
た。皆さまもご存じの通り、イリノイ州立博物館は、第四紀の脊椎動物の充実
したコレクションで知られており、また、動物考古学の分野で活躍してこられ
たBonnie Styles博士や、北米花粉データベースを牽引してきたEric Grimm博士
を擁する研究機関です。
7月13日に閉鎖方針に関する公聴会が実施される予定で、7月21日までパブリッ
クコメントが受け付けられているそうです。アメリカ国外からの意見表明も有
効とのことですので、イリノイ州立博物館閉鎖への反対意見を、イリノイ州政
府宛にぜひお送りいただきたく、お願い申し上げます。
時期が迫っているため、組織として意見表明を検討していただくのは大変難し
いかと存じます。つきましては、皆さま個人としての意見表明をいただけ れば
幸いです。詳細については、下記をご覧ください。
1.意見表明の締切:パブリックコメント自体は7月21日(火)が締め切り。
ただし、7月13日(月)の公聴会開催日までにご意見をお送りいただけると、
公聴会で、閉鎖反対をより強く後押しできます。
2.意見の送付方法:
パプリックコメント受付アドレス facilityclosure@ilga.gov宛に、電子メー
ルにて送付してください。
*意見の送付方法について、詳細は、下記ウェブサイトをご参照ください。
Public Comments to the Commission on Government Forecasting and
Accountability : http://cgfa.ilga.gov/Resource.aspx?id=1357
ご意見は、1) pdfファイルを添付する、2) Wordファイルを添付する、3) メー
ル本文に記入する、のどれかの方法でお送りください。メールには、以下の4項
目を必ずご記入ください。
(1)あなたのお名前
(2)閉鎖対象機関:the Illinois State Museum *イリノイ州の複数の機関
が閉鎖対象になっています
(3)あなたの立場:閉鎖に賛成(Proponent)、閉鎖に反対(Opponent)、ど
ちらでもない(No position)
(4)あなたの希望する意見表明方法:公聴会での証言(Oral Testimony at
the hearing)、意見書の送付(Written Statement Filed)、賛否表明のみ(
Record of Appearance Only)
3. 閉鎖反対意見の文例:適宜修正の上、ご利用ください。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
The Honorable Bruce Rauner, Governor
State of Illinois
207 State House
Springfield, Illinois 62706
Dear Governor Rauner:
As a scientist and educator, I am deeply concerned about the proposed
closure of the Illinois State Museum System. The ISM System is an
internationally recognized museum with a strong reputation for
scientific excellence and globally recognized staff, and reliable
curation of scientific, cultural and historical objects and databases
of state, national and global importance. Some of our important
databases of Japanese plants, animals and fossils are also maintained
and updated in the System. The ISM System is essential for public
outreach and education not only for the citizens of Illinois but also
for the citizens of the international communities. Surely the people
of Illinois should not be cut off from so valuable an institution
formed for the common good, the preservation of their heritage, and
the education of their children for future success in a modern society.
Please consider the societal services provided by this modern,
significant, and high visibility museum system, and save the ISM for
the people of Illinois and elsewhere.
Sincerely,
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
*2015年閉鎖対象機関 http://cgfa.ilga.gov/Resource.aspx?id=1815
のページから、Illinois state museum を選択し、Public Commentsのリンクを
クリックすると、これまでに送付された意見(主に閉鎖に反対する意見)を
PDFで閲覧することができます。
4.イリノイ州立博物館機構(Illinois State Museum System)について
イリノイ州立博物館機構は、州内に以下の6つの部門を持っています:スプリン
グフィールドのイリノイ州立博物館および研究・収蔵センター、ルイス タウン
のディクソン墳丘博物館、ISMシカゴ美術館、ISMロックポート美術館、南イリ
ノイ美術・工芸センター。自然科学分野の研究および展示は 前半の3部門が担っ
ており、後半の3部門が美術・歴史分野を担当しています。この博物館機構は、
アメリカ博物館連盟に国家認証されています。この 認証を受けているのは、ア
メリカ合衆国の博物館・美術館のうち、わずか5%の館のみです。この認証は、
博物館の使命を十分に果たしていること、研 究活動、収蔵品、展示、教育プロ
グラム、組織のマネジメントすべてにおいて全国標準を満たすだけでなく、最
良の実践を追求していることの証です。 イリノイ州立博物館機構の使命とは、
イリノイ州の自然・文化資源および遺産に目を向け、理解し、大切にするよう、
全ての年齢の人々にはたらきかけ ることです。
イリノイ州立博物館機構は、1350万点の収蔵品を擁しています。もっとも著名
な地質学分野の収蔵品は、第四紀の脊椎動物、とくに長鼻類(マスト ドンのコ
レクションとしては世界最大級)のコレクションおよびペンシルベニア期のメ
イゾンクリーク化石群でしょう。もっとも点数が多いのは人類学 分野の収蔵品
です。とくに重要なミシシッピ文化期の遺物のみならず、原史時代のクローヴィ
ス期の遺物にまでその収蔵品の範囲は広がっており、ま た、多くの民族資料も
収集されています。イリノイ州立博物館機構はカホキア墳丘群の出土資料も管
理しています。イリノイ州立博物館機構は、オクラ ホマ州(以前はイリノイ州)
のピオリア族と、彼らの副葬品について管理するよう、セントルイス地区の工
兵隊とともに協定を結んでいます。
5.イリノイ州立博物館の閉鎖危機に関するリンク集
The public hearing on the closure is scheduled for July 13. The public
comment period runs through July 22.
Newspaper articles here:
http://www.sj-r.com/article/20150610/NEWS/150619927
http://www.sj-r.com/article/20150630/NEWS/150639947
http://www.sj-r.com/article/20150629/NEWS/150629506
Some opinion pieces:
http://www.sj-r.com/article/20150625/OPINION/150629652
http://www.sj-r.com/article/20150627/OPINION/150629564/
Statement from the American Alliance of Museums:
http://t.congressweb.com/w/?GILOPWGAPZ
Nice public radio piece here:
http://wuis.org/post/grass-roots-efforts-keep-state-museum-open
Website for public commentary:
http://cgfa.ilga.gov/Resource.aspx?id=1357
Official schedule:
http://cgfa.ilga.gov/resource.aspx?id=1822
Official closure statement from DNR:
http://cgfa.ilga.gov/upload/DNRrecommendILStateMuseum.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
geo-Flash No.306 [長野大会]事前参加登録受付中!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.306 2015/7/21┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[長野大会]全体日程表を公開しました
【2】[長野大会]事前参加登録受付中
【3】[長野大会]宿泊の手配はお早めに
【4】[長野大会]緊急展示の申込について
【5】[長野大会]各種申込み締切のお知らせ
【6】名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[長野大会]全体日程表を公開しました
─────────────────────────────────
長野大会(9/11〜13:於 信州大学長野(工学)キャンパス ほか)の
全体日程表を公開しました.各シンポ,セッションの予定をはじめ,普及行事
や関連行事の日程も決まりました.各講演(口頭・ポスター)の詳細プログラ
ムは,後日講演者にご連絡するとともに,大会HPに掲載予定です.大会プログ
ラムは,例年同様ニュース誌8月号掲載予定です.
全体日程表(PDF)は,大会HPよりご覧いただけます.
http://www.geosociety.jp/nagano/content0052.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[長野大会]事前参加登録受付中
─────────────────────────────────
ただいま,長野大会の事前参加登録を受付中です.
今年もたくさんの皆様のご参加をお待ちしています.
◆事前参加登録:8/18(火)締切
〔注〕演題登録と事前参加登録は,それぞれ別のお申し込みです.ご注意下さ
い.
◆巡検申込:8/7(金)締切
巡検申込状況(7/21, 11時現在)はこちら↓↓↓
http://www.geosociety.jp/nagano/content0055.html
長野大会HPはコチラ↓
http://www.geosociety.jp/nagano/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[長野大会]宿泊の手配はお早めに
──────────────────────────────────
長野大会期間中,長野市内では他学協会のイベント等が多数予定されていま
す.すでに宿泊予約は混み合っているようです,早めの手配をお勧め致します.
地質学会では,近年学会を通じての宿泊・交通手配の斡旋を行っていません.
宿泊や交通については,各自で手配をお願い致します.大会HPに「宿泊予約(
日本旅行のサイト)」をご紹介しています.ご参考にして下さい.
https://v3.apollon.nta.co.jp/gsj2015/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[長野大会]緊急展示の申込について
──────────────────────────────────
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害調査報告
や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コーナー」を設けます.緊
急展示は,正式な学会発表と同じく,コアタイムの時間帯が設けられ,優秀ポ
スター賞の審査対象となります.
申込締切:8月31日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/nagano/content0056.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[長野大会]各種申込み締切のお知らせ
──────────────────────────────────
■ 企業・研究機関等関係団体による展示会の出展募集
申込締切:8月7日(金)
http://www.geosociety.jp/nagano/content0036.html
■ 書籍・販売ブースご利用の募集
申込締切:8月7日(金)
http://www.geosociety.jp/nagano/content0036.html#book
■ 講演要旨集,広告協賛の募集
申込締切:8月7日(金)
http://www.geosociety.jp/nagano/content0036.html#kokoku
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】 名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
──────────────────────────────────
日本地質学会では,学会員相互の交流と親睦を図る目的で,2年ごとに会員名
簿を
発行することを運営規則にうたっております.2015年はその発行年にあたり,
本年
11月末日発行の予定で準備を行っております.
名簿の発行様式は前回と同様で,全会員を収録します.本会としては,個人情
報保
護法の制約はあるとしても,会員の皆様が上記の目的に沿って利用できるよう
な,
従来規模の名簿を作成したいと考えておりますので,調査の実施にご理解とご
協力
をお願いいたします.
アンケート提出およびWeb画面更新締切日:2015年10月5日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0132.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■青少年のための科学の祭典2015全国大会
日本地質学会 後援
7月25日(土)〜26日(日)
会場:科学技術館(千代田区北の丸公園)
http://www.kagakunosaiten.jp/
■第19回国際第四紀学連合大会,INQUA 2015 名古屋大会
日本地質学会ほか 共催
7月26日(日)〜8月2日(日)
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区)
http://inqua2015.jp/
■第176回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
7月31日(金)18:30〜20:30(事前予約不要)
会場:北とぴあ901会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分)
テーマ:三陸海岸ならびに仙台平野における東北地方太平洋沖地震に起因した
津波堆積物中のヒ素ならびに重金属類の起源
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■学術会議公開シンポジウム「人文・社会科学と大学のゆくえ」
7月31日(金)14:00〜17:00
会場:日本学術会議講堂(入場無料・事前予約不要)
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/215-s-1a.pdf
■第59回粘土科学討論会
日本地質学会 共催
9月2日(水)〜 5日(土)
会場:山口大学理学部・人文学部
http://www.cssj2.org/
■日本ジオパークネットワークガイドフォーラム
9月15日(火)〜16日(水)
会場:アミティ丹後(京丹後市網野町)
参加登録締切:7月31日(金)
http://jgn2015.com/
■第4回アジア太平洋ジオパークネットワーク山陰海岸シンポジウム
日本地質学会ほか 後援
9月15日(火)〜20日(日)
会場:豊岡市民会館(豊岡市立野町20-34)ほか
通常参加登録締切:7月31日(金)
http://apgn2015-jpn.com/
■第11回国際化石藻類シンポジウム
日本地質学会 後援
9月14日(月)〜19日(土)
会場:琉球大学
■2015年度日本地球化学会第62回年会
日本地質学会ほか 共催
9月16日(水)〜18日(金)
会場:横浜国立大学常盤台キャンパス
事前参加申込:8月28日(金)締切
http://www.geochem.jp/conf/2015/
■第10回アジア地域応用地質学シンポジウム
日本地質学会 後援
研究発表会:9月24日(木)〜25日(金)
シンポジウム:9月26日(土)〜27日(日)[その後巡検予定あり]
会場:京都大学宇治黄檗プラザ
http://2015ars.com/
■Arthur Holmes Meeting Tsunami Hazards and Risks: Using the
Geological Record
日本地質学会 共催
9月25日(金)
会場:The Geological Society (Burlington House)(英・ロンドン)
プレ巡検:9月22日(火)〜24日(木)
http://www.geolsoc.org.uk/ahm15
■国際シンポジウム「沈み込み帯堆積盆地のリソスフェア・ダイナミクス」
日本地質学会 後援
10月5日(月)〜7日(水)(10月8日〜9日:地質巡検)
会場:東京第一ホテルシーフォート(品川区東品川)
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/ILP2015/
■第31回ゼオライト研究発表会
日本地質学会 後援
11月26日(木)〜27日(金)
会場:とりぎん文化会館(鳥取市尚徳町101-5)
講演申込締切: 7月24日(金)
要旨原稿締切:10月30日(金)
http://katalab.org/31zeolite/
■地質学史懇話会
12月23日(水・休)13:30〜17:00
会場:北とぴあ8階803号室(JR京浜東北線王子駅下車3分)
・吉岡有文『日本の科学教育映画の世界』(仮題)
・秋葉文雄『日本の珪藻化石研究』(仮題)
■第5回学生のヒマラヤ野外実習ツアー(参加者受付中)
日本地質学会 推薦
暫定日程:2016年3月5日〜20日の16日間
参加申込受付期間:2015年5月1日〜11月30日
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0144.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■農林水産省経験者採用試験(係長級:技術)(募集期間:8/7-20)
■東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻専任教員公募(9/15)
■平成27年東レ科学技術賞・科学技術研究助成候補者推薦(学会締切8/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
geo-Flash No.307 [長野大会]巡検申込まもなく締切(8/7締切!!)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.307 2015/8/4┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[長野大会]巡検申込まもなく締切です!
【2】[長野大会]緊急展示の申込について
【3】[長野大会]宿泊の手配はお早めに
【4】[長野大会]各種申込み締切のお知らせ
【5】名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
【6】 フォトコンテスト入選作品展示会(in 湯島)
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】訃報
【11】訂正
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[長野大会]巡検申込まもなく締切です!(8/7締切)
─────────────────────────────────
ただいま,長野大会の事前参加登録を受付中です.
巡検の締切が迫っています.参加ご希望の方は忘れずにお申し込み下さい.
既に定員に達したコースもあります.お申込はお早めに!
【巡検申込締切:8月7日(金)18時】
巡検申込状況(7/29, 11時現在)はこちら↓↓↓
http://www.geosociety.jp/nagano/content0055.html
事前参加登録は,8/18(火)18時までお申込頂けます.大会プログラムは,ニュース誌8月号掲載予定です.
全体日程表(PDF)はコチラ→http://www.geosociety.jp/nagano/content0052.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[長野大会]緊急展示の申込について
──────────────────────────────────
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害調査報告
や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コーナー」を設けます.緊
急展示は,正式な学会発表と同じく,コアタイムの時間帯が設けられ,優秀ポ
スター賞の審査対象となります.
申込締切:8月31日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/nagano/content0056.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[長野大会]宿泊の手配はお早めに
──────────────────────────────────
長野大会期間中,長野市内では他学協会のイベント等が多数予定されていま
す.すでに宿泊予約は混み合っているようです,早めの手配をお勧め致します.
地質学会では,近年学会を通じての宿泊・交通手配の斡旋を行っていません.
宿泊や交通については,各自で手配をお願い致します.大会HPに「宿泊予約(
日本旅行のサイト)」をご紹介しています.ご参考にして下さい.
https://v3.apollon.nta.co.jp/gsj2015/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[長野大会]各種申込み締切のお知らせ
──────────────────────────────────
■ 企業・研究機関等関係団体による展示会の出展募集
申込締切:8月7日(金)
http://www.geosociety.jp/nagano/content0036.html
■ 書籍・販売ブースご利用の募集
申込締切:8月7日(金)
http://www.geosociety.jp/nagano/content0036.html#book
■ 講演要旨集,広告協賛の募集
申込締切:8月7日(金)
http://www.geosociety.jp/nagano/content0036.html#kokoku
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】 名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
──────────────────────────────────
日本地質学会では,学会員相互の交流と親睦を図る目的で,2年ごとに会員名簿を
発行することを運営規則にうたっております.2015年はその発行年にあたり,本年
11月末日発行の予定で準備を行っております.
名簿の発行様式は前回と同様で,全会員を収録します.本会としては,個人情報保
護法の制約はあるとしても,会員の皆様が上記の目的に沿って利用できるような,
従来規模の名簿を作成したいと考えておりますので,調査の実施にご理解とご協力
をお願いいたします.
アンケート提出およびWeb画面更新締切日:2015年10月5日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0132.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】 フォトコンテスト入選作品展示会(in 湯島)
──────────────────────────────────
本年(第6回惑星地球フォトコンテスト)の作品メインに過去の入選作品も展示中です.会場は湯島天神の近くです.皆様お誘い合わせの上是非お越し下さい.
日程:8月3日(月)〜14日(金)
場所:NPC日本印刷株式会社 1階ギャラリースペース
(東京都文京区湯島 3-20-12)
<その他の展示予定>
・9月11日〜13日:地質情報展(日本地質学会第122年学術大会)(長野市生涯学習センター)
・9月19日〜11月8日:あいちサイエンスフェスティバル(愛知県蒲郡市)
詳しくは,http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■富士山巡検のお知らせ
日程:10月17日(土)〜18日(日),1泊2日 雨天決行
参加費用:一般22,000円,学生・院生13,000円
CPD単位:16単位
募集人数:会員および一般・30名程度(先着順)
申込期間:8月24日(月)〜10月2日(金)(定員に達した時点で締切)
詳しくは,http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■電中研ニュース No.481
「震源を特定せず策定する地震動」対象地震の解明に挑む−2004年北海道留萌支庁南部の地震による強震動の要因解明−http://criepi.denken.or.jp/research/news/index.html?m=150730
■北海道立総合研究機構 地質研究所ニュース
・屈斜路湖の特徴的な湖底地形と堆積構造をさぐる
・羅臼町幌萌海岸で発生した地すべりと海岸隆起 など
http://www.hro.or.jp/list/environmental/research/gsh/publication/gshnews/gshnews02/index.html
■第177回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
8月28日(金)18:30〜20:30[事前予約不要]
場所:北とぴあ901会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分)
講師:宮崎 毅(東京大学名誉教授・NPO日本地質汚染審査機構理事)
テーマ:地下水挙動と農地・宅地の斜面崩壊のメカニズム
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■第59回粘土科学討論会
日本地質学会 共催
9月2日(水)〜 5日(土)
会場:山口大学理学部・人文学部
http://www.cssj2.org/
■日本ジオパークネットワークガイドフォーラム
9月15日(火)〜16日(水)
会場:アミティ丹後(京丹後市網野町)
http://jgn2015.com/
■第4回アジア太平洋ジオパークネットワーク山陰海岸シンポジウム
日本地質学会ほか 後援
9月15日(火)〜20日(日)
会場:豊岡市民会館(豊岡市立野町20-34)ほか
http://apgn2015-jpn.com/
■第11回国際化石藻類シンポジウム
日本地質学会 後援
9月14日(月)〜19日(土)
会場:琉球大学
■2015年度日本地球化学会第62回年会
日本地質学会ほか 共催
9月16日(水)〜18日(金)
会場:横浜国立大学常盤台キャンパス
事前参加申込:8月28日(金)締切
http://www.geochem.jp/conf/2015/
■第10回アジア地域応用地質学シンポジウム
日本地質学会 後援
研究発表会:9月24日(木)〜25日(金)
シンポジウム:9月26日(土)〜27日(日)[その後巡検予定あり]
会場:京都大学宇治黄檗プラザ
http://2015ars.com/
■Arthur Holmes Meeting Tsunami Hazards and Risks: Using the Geological
Record
日本地質学会 共催
9月25日(金)
会場:The Geological Society (Burlington House)(英・ロンドン)
プレ巡検:9月22日(火)〜24日(木)
http://www.geolsoc.org.uk/ahm15
■国際シンポジウム「沈み込み帯堆積盆地のリソスフェア・ダイナミクス」
日本地質学会 後援
10月5日(月)〜7日(水)(10月8日〜9日:地質巡検)
会場:東京第一ホテルシーフォート(品川区東品川)
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/ILP2015/
■第2回アジア恐竜国際シンポジウム(ISAD2015)
11月19日(木)〜24日(火)
場所:タイ バンコク
http://www.isad2015.com/isad2015/
■第31回ゼオライト研究発表会
日本地質学会 後援
11月26日(木)〜27日(金)
会場:とりぎん文化会館(鳥取市尚徳町101-5)
要旨原稿締切:10月30日(金)
http://katalab.org/31zeolite/
■地質学史懇話会
12月23日(水・休)13:30〜17:00
会場:北とぴあ8階803号室(JR京浜東北線王子駅下車3分)
・吉岡有文『日本の科学教育映画の世界』(仮題)
・秋葉文雄『日本の珪藻化石研究』(仮題)
■第5回学生のヒマラヤ野外実習ツアー(参加者受付中)
日本地質学会 推薦
暫定日程:2016年3月5日〜20日の16日間
参加申込受付期間:2015年5月1日〜11月30日
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0144.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■新潟大学教育研究院自然科学系教員(准教授)公募(9/30)
■弘前大学大学院理工学研究科(教授)公募(10/2)
■平成28年度笹川科学研究助成公募(10/1-15, 11/1-16)
■アジア恐竜協会 若手研究者支援プロジェクト(渡航費・滞在費の補助)(9/30)
■平成28年度学術研究船白鳳丸共同利用公募(9/25)
■平成28年度東北海洋生態系調査研究船新青丸の共同利用公募(9/25)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】訃報:猪木幸男 名誉会員 ご逝去
─────────────────────────────────
猪木幸男 名誉会員(元地質調査所地質部長・元山口大学教授)が,
平成27年5月9日(土)にご逝去されました(享年93歳)。
先日ご遺族よりご連絡をいただきましたので,会員の皆様にお知らせ致し
ます。これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申
し上げます。
会長 井龍 康文
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】訂正
──────────────────────────────────
2015/7/21配信記事の号数に誤りがありました。訂正しお詫び申し上げます。
(誤)No.305
(正)No.306
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.308(臨時)[長野大会]巡検参加申込:明日締切です!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.308 2015/8/6┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[長野大会]巡検参加申込:明日締切です!(8/7締切)
─────────────────────────────────
長野大会の巡検の参加申込締切が迫っています.
参加予定の方は,忘れずにお申込をお願い致します.
既に定員に達したコースもあります.お申込はお早めに!!
★★ 巡検申込締切:8月7日(金)18時 ★★
↓↓巡検申込状況(6日,12時現在)はこちら↓↓
http://www.geosociety.jp/nagano/content0055.html
事前参加登録は,8/18(火)18時までお申込頂けます.
大会プログラムは,ニュース誌8月号掲載予定です.
長野大会HP http://www.geosociety.jp/nagano/content0001.html >
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.309[長野大会]事前参加登録:本日8/18(火)18時締切!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.309 2015/8/18┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[長野大会]事前参加登録:本日8/18(火)18時締切!
【2】[長野大会]緊急展示の申込について
【3】[長野大会]宿泊の手配はお早めに
【4】2015年度会費およびそれ以前の未納会費がある方へ
【5】名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[長野大会]事前参加登録:本日8/18(火)18時に締切!
─────────────────────────────────
事前参加登録は,本日8/18(火)18時に締切です.
発表のほか,大会へ参加予定の方は忘れずにお申込下さい.
大会プログラムは,ニュース誌8月号掲載予定です.
全体日程表(PDF)はコチラ
→ http://www.geosociety.jp/nagano/content0052.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[長野大会]緊急展示の申込について
──────────────────────────────────
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害調査報告
や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コーナー」を設けます.緊
急展示は,正式な学会発表と同じく,コアタイムの時間帯が設けられ,優秀ポ
スター賞の審査対象となります.
申込締切:8月31日(月)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/nagano/content0056.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[長野大会]宿泊の手配はお早めに
──────────────────────────────────
長野大会期間中,長野市内では他学協会のイベント等が多数予定されており,
すでに宿泊予約は混み合っているようです.早めの手配をお勧め致します.
地質学会では,近年学会を通じての宿泊・交通手配の斡旋を行っていません.
宿泊や交通については,各自で手配をお願い致します.大会HPに「宿泊予約(
日本旅行のサイト)」をご紹介しています.ご参考にして下さい.
https://v3.apollon.nta.co.jp/gsj2015/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2015年度会費およびそれ以前の未納会費がある方へ
─────────────────────────────────
6月中旬に2015年度会費の督促請求書(郵便振替用紙)を郵送しました.
会費未納のかたは,早急にご送金くださいますようお願いいたします.
なお,7月中旬頃までに入金確認が取れていないかたに対しては,7月号の雑誌
から送本を停止しています.定期的に雑誌をお受け取りになりたいかたは,お
早めにご送金ください.
また,9月の長野大会で発表されるかたは,学会費のご送金をお願いいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】 名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
──────────────────────────────────
日本地質学会では,学会員相互の交流と親睦を図る目的で,2年ごとに会員名簿を
発行することを運営規則にうたっております.2015年はその発行年にあたり,本年
11月末日発行の予定で準備を行っております.
名簿の発行様式は前回と同様で,全会員を収録します.本会としては,個人情報保
護法の制約はあるとしても,会員の皆様が上記の目的に沿って利用できるような,
従来規模の名簿を作成したいと考えておりますので,調査の実施にご理解とご協力
をお願いいたします.
アンケート提出およびWeb画面更新締切日:2015年10月5日(月)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0132.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■富士山巡検のお知らせ
日程:10月17日(土)〜18日(日),1泊2日 雨天決行
参加費用:一般22,000円,学生・院生13,000円
CPD単位:16単位
募集人数:会員および一般 30名程度(先着順)
申込期間:8月24日(月)〜10月2日(金)(定員に達した時点で締切)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0157.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第177回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
8月28日(金)18:30〜20:30[事前予約不要]
場所:北とぴあ901会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分)
講師:宮崎 毅(東京大学名誉教授・NPO日本地質汚染審査機構理事)
テーマ:地下水挙動と農地・宅地の斜面崩壊のメカニズム
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■第59回粘土科学討論会
日本地質学会 共催
9月2日(水)〜 5日(土)
会場:山口大学理学部・人文学部
http://www.cssj2.org/
■日本ジオパークネットワークガイドフォーラム
9月15日(火)〜16日(水)
会場:アミティ丹後(京丹後市網野町)
http://jgn2015.com/
■第4回アジア太平洋ジオパークネットワーク山陰海岸シンポジウム
日本地質学会ほか 後援
9月15日(火)〜20日(日)
会場:豊岡市民会館(豊岡市立野町20-34)ほか
http://apgn2015-jpn.com/
■第11回国際化石藻類シンポジウム
日本地質学会 後援
9月14日(月)〜19日(土)
会場:琉球大学
■2015年度日本地球化学会第62回年会
日本地質学会ほか 共催
9月16日(水)〜18日(金)
会場:横浜国立大学常盤台キャンパス
事前参加申込:8月28日(金)締切
http://www.geochem.jp/conf/2015/
■第10回アジア地域応用地質学シンポジウム
日本地質学会 後援
研究発表会:9月24日(木)〜25日(金)
シンポジウム:9月26日(土)〜27日(日)[その後巡検予定あり]
会場:京都大学宇治黄檗プラザ
http://2015ars.com/
■Arthur Holmes Meeting Tsunami Hazards and Risks: Using the Geological
Record
日本地質学会 共催
9月25日(金)
会場:The Geological Society (Burlington House)(英・ロンドン)
プレ巡検:9月22日(火)〜24日(木)
http://www.geolsoc.org.uk/ahm15
■国際シンポジウム「沈み込み帯堆積盆地のリソスフェア・ダイナミクス」
日本地質学会 後援
10月5日(月)〜7日(水)(10月8日〜9日:地質巡検)
会場:東京第一ホテルシーフォート(品川区東品川)
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/ILP2015/
■第31回ゼオライト研究発表会
日本地質学会 後援
11月26日(木)〜27日(金)
会場:とりぎん文化会館(鳥取市尚徳町101-5)
要旨原稿締切:10月30日(金)
http://katalab.org/31zeolite/
■第5回学生のヒマラヤ野外実習ツアー(参加者受付中)
日本地質学会 推薦
暫定日程:2016年3月5日〜20日の16日間
参加申込受付期間:2015年5月1日〜11月30日
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0144.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■北海道立総合研究機構地質研究所公募(地すべり・斜面崩壊等の地質
災害の防止及び被害軽減に関する調査研究)(9/11)
■神奈川県温泉地学研究所職員(地質職)採用選考(8/31)
■科学研究費助成事業「国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)」
平成27年度公募(9/28)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.310 いよいよ長野大会が始まります!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.310 2015/9/1┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[長野大会]いよいよ長野大会が始まります!
【2】[長野大会]講演プログラムを公開しました
【3】[長野大会]予約確認書を発送しました
【4】[長野大会]学術大会でCPD単位が取得出来ます
【5】[長野大会]宿泊の手配はお早めに
【6】創立125周年記念事業:地質学雑誌特集号の募集
【7】秋季地質調査研修参加者募集ご案内(予告編)
【8】2015年度会費およびそれ以前の未納会費がある方へ
【9】名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
【10】支部情報
【11】その他のお知らせ
【12】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[長野大会]いよいよ長野大会が始まります!
─────────────────────────────────
いよいよ長野大会が始まります(9月11日〜13日)。
初日には,会員顕彰式・各賞表彰式・受賞記念講演が予定されておりますので,
ぜひ多くの皆様のご参加をお待ちしています.長野大会を,盛り上げて行きま
しょう!!
↓ ↓ 長野大会HP ↓ ↓
http://www.geosociety.jp/nagano/content0001.html
★★★注意 ★★★
今年の会場は,信州大学長野(工学)キャンパス(住所:長野市若里4-17-1)
です。松本市のキャンパスではありません。お間違いのないようご注意下さい!
http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/maps/map03.html#address
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[長野大会]講演プログラムを公開しました────────────
─────────────────────
口頭・ポスターの各講演プログラムを,大会HPで公開しました.今年も口頭・
ポスターあわせて600件以上の講演が予定されています.
講演プログラムは,ニュース誌8月号にも掲載されています(8月号は8/31発送).
講演プログラム・全体日程表(PDF)はコチラ
→http://www.geosociety.jp/nagano/content0052.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[長野大会]予約確認書を発送しました
─────────────────────────────────
事前参加申込を頂いた方に対して,申込内容に応じて確認書2枚(本人控・受付
提出用)等をお送り致しました(8/28発送).
受付提出用の確認書,名札,クーポンを当日忘れずにご持参下さい.
<一部入金もしくは未入金の方へ>
確認書発送時点で一部入金もしくは、入金確認が取れていない方へは当日払い
の参加費に金額訂正した確認書のみをお送りしました。
お支払いがまだの方は、9月7日(月)までにお振り込みをお願い致します.
詳しくは、http://www.geosociety.jp/nagano/content0007.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[長野大会]学術大会でCPD単位が取得出来ます
─────────────────────────────────
日本地質学会は,地質技術者への継続教育の一環として,大会参加者・発表者・
巡検参加者へCPD単位を発行します.大会参加と口頭/ポスター発表の参加証明
書当日会場で発行します
【発行単位】
・ 学術大会参加に対するCPD(時間に応じて):例)7時間出席 = 7単位
・ 口頭発表に対するCPD:0.4 ×15分発表 = 6単位
・ ポスター発表に対するCPD:2単位
・ 巡検参加に対するCPD:日帰り-8単位,1泊2日-16単位
詳しくは、http://www.geosociety.jp/nagano/content0050.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[長野大会]宿泊の手配はお早めに
──────────────────────────────────
長野大会期間中,長野市内では他学協会のイベント等が多数予定されており,
すでに宿泊予約は混み合っているようです.早めの手配をお勧め致します.
地質学会では,近年学会を通じての宿泊・交通手配の斡旋を行っていません.
宿泊や交通については,各自で手配をお願い致します.大会HPに「宿泊予約(
日本旅行のサイト)」をご紹介しています.ご参考にして下さい.
https://v3.apollon.nta.co.jp/gsj2015/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】創立125周年記念事業:地質学雑誌特集号の募集
─────────────────────────────────
2018年に日本地質学会創立125周年を迎えるにあたっての記念事業の一つとして,
地質学雑誌特集号を連続して企画する事が決定しました.本特集号では,創立
100周年時に刊行された「日本の地質学100年」以降の25年間を中心とした各分
野の研究動向をまとめて順次発行します.本特集号への多数の申し込みを期待
しています.
第1次募集締切:2015年11月30日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0160.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】秋季地質調査研修参加者募集ご案内(予告編)
─────────────────────────────────
実施期間:2015年11月9日(月)〜11月13日(金)(4泊5日)
実施場所:千葉県君津市とその周辺(房総半島中部域)
募集対象者:主に、地質関連会社の若手技術者
募集人員:6名(定員に到達次第、募集終了)
参加費:12万円(往復交通費や宿泊費は含まず)
参加者募集期間:9月14日(月)〜10月13日(火)
実施内容や申込方法などの詳細は,
http://www.geosociety.jp/engineer/content0043.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】2015年度会費およびそれ以前の未納会費がある方へ
─────────────────────────────────
6月中旬に2015年度会費の督促請求書(郵便振替用紙)を郵送しました.
会費未納のかたは,早急にご送金くださいますようお願いいたします.
なお,7月中旬頃までに入金確認が取れていないかたに対しては,7月号の雑誌
から送本を停止しています.定期的に雑誌をお受け取りになりたいかたは,お
早めにご送金ください.
また,9月の長野大会で発表されるかたは,学会費のご送金をお願いいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】 名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
──────────────────────────────────
日本地質学会では,学会員相互の交流と親睦を図る目的で,2年ごとに会員名
簿を
発行することを運営規則にうたっております.2015年はその発行年にあたり,
本年
11月末日発行の予定で準備を行っております.
名簿の発行様式は前回と同様で,全会員を収録します.本会としては,個人情
報保
護法の制約はあるとしても,会員の皆様が上記の目的に沿って利用できるよう
な,
従来規模の名簿を作成したいと考えておりますので,調査の実施にご理解とご
協力
をお願いいたします.
アンケート提出およびWeb画面更新締切日:2015年10月5日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0132.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■富士山巡検
日程:10月17日(土)〜18日(日),1泊2日 雨天決行
参加費用:一般22,000円,学生・院生13,000円
CPD単位:16単位
募集人数:会員および一般 30名程度(先着順)
申込期間:8月24日(月)〜10月2日(金)(定員に達した時点で締切)
http://www.geosociety.jp/outline/content0157.html
■ミニ・ショートコース:地すべり試験ラボ見学
日程:10月31日(土) 11:00〜16:00
場所:国土防災技術(株) 技術本部試験研究所(福島市南矢野目)
費用:3,000円
CPD単位:4単位
募集人数:10名(先着順,地質学会会員を優先します)
応募締切:10月9日(金)
http://www.geosociety.jp/outline/content0162.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第59回粘土科学討論会
日本地質学会 共催
9月2日(水)〜 5日(土)
会場:山口大学理学部・人文学部
http://www.cssj2.org/
■日独シンポジウム
「ダイバーシティが創る卓越性〜学術界における女性・若手研究者の進出〜」
日本学術会議・国際交流基金・ベルリン日独センター 主催
9月4日(金)13:00〜18:00
会場:日本学術会議講堂
http://www.jpf.go.jp/j/project/intel/exchange/organize/2015/08-01.html
■5th International Man-Made Strata and Geo-pollution Symposium
9月5日(土)〜6日(日)
場所:Urayasu Culture Hall
http://www.geosociety.jp/outline/content0144.html#now
■日本ジオパークネットワークガイドフォーラム
9月15日(火)〜16日(水)
会場:アミティ丹後(京丹後市網野町)
http://jgn2015.com/
■第4回アジア太平洋ジオパークネットワーク山陰海岸シンポジウム
日本地質学会ほか 後援
9月15日(火)〜20日(日)
会場:豊岡市民会館(豊岡市立野町20-34)ほか
http://apgn2015-jpn.com/
■第11回国際化石藻類シンポジウム
日本地質学会 後援
9月14日(月)〜19日(土)
会場:琉球大学
■2015年度日本地球化学会第62回年会
日本地質学会ほか 共催
9月16日(水)〜18日(金)
会場:横浜国立大学常盤台キャンパス
http://www.geochem.jp/conf/2015/
■第10回アジア地域応用地質学シンポジウム
日本地質学会 後援
研究発表会:9月24日(木)〜25日(金)
シンポジウム:9月26日(土)〜27日(日)[その後巡検予定あり]
会場:京都大学宇治黄檗プラザ
http://2015ars.com/
■Arthur Holmes Meeting Tsunami Hazards and Risks: Using the
Geological
Record
日本地質学会 共催
9月25日(金)
会場:The Geological Society (Burlington House)(英・ロンドン)
プレ巡検:9月22日(火)〜24日(木)
http://www.geolsoc.org.uk/ahm15
■ 第178回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
9月25日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ902会議室
講師:難波謙二(福島大学環境放射能研究所所長)
テーマ:東京電力福島第一原子力発電所事故と放射性物質汚染
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■国際シンポジウム「沈み込み帯堆積盆地のリソスフェア・ダイナミクス」
日本地質学会 後援
10月5日(月)〜7日(水)(10月8日〜9日:地質巡検)
会場:東京第一ホテルシーフォート(品川区東品川)
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/ILP2015/
■第31回ゼオライト研究発表会
日本地質学会 後援
11月26日(木)〜27日(金)
会場:とりぎん文化会館(鳥取市尚徳町101-5)
要旨原稿締切:10月30日(金)
http://katalab.org/31zeolite/
■第5回学生のヒマラヤ野外実習ツアー(参加者受付中)
日本地質学会 推薦
暫定日程:2016年3月5日〜20日の16日間
参加申込受付期間:2015年5月1日〜11月30日
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0144.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■名古屋大学宇宙地球環境研究所教授公募(10/30)
■2016年度瀬戸内海文化研究・活動支援助成募集(10/16)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.312 長野大会スタート!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.312 2015/9/11 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】長野大会初日の様子
【2】長野大会:9月12日(土)の主なイベント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】長野大会初日の様子
──────────────────────────────────
日本地質学会第122年学術大会(2015長野大会)の初日が本日9/11日 開催されました.午後には少し暑いほどの日差しにも恵まれ,全ての行事 が成功裡に実施されました.
午前中は,7つの会場(信州大学工学部)で各学術セッションが行われました. また,長野市生涯学習センター(TOiGO)では「地質情報展2015ながの」が始まり,井龍会長による開会の挨拶では,現在大きな被害が出ている北関東・東北での水害に言及され,最近では忘れられてきているものの過去においては水害との戦いは大変厳しいものであり,改めて洪水被害への意識を高める必要性が説かれました.また,会場には信州地域を中心とした特色ある岩石標本の展示もされておりますので,皆様ぜひ足をお運びください(9/13日の16時まで開催).
午後は,13:45から15:05までポスター発表のコアタイムで,体育館を使った 広い会場の中,あちらこちらで活発な議論がなされておりました.普段あまり地質学会に参加されていない方も結構参加されていたようで,ぜひアウェー感を感じる事無く?議論を楽しんで頂ければと思います.
16時からは,メルパルク長野にて会員顕彰式・各賞授与式・受賞記念講演会が 行われました.個別にご紹介することはできませんが,地質学会に貢献された方々に改めて敬意を表します.記念講演会も大変盛り上がりました.
18:30からは,同じくメルパルク長野(白鳳の間)にて懇親会が開催されました.長野LOCの方々のご尽力により,大変豪勢な懇親会となりました.来賓の挨拶では,本大会で学術交流協定調印式を行った台湾地質学会からご挨拶を頂きました.皆さん大変盛り上がり,明日からの学術大会も盛り上がることは間違いありません!!
大会の様子を写真でご覧ください.
■地質情報展開会
■ 大会初日と表彰式が開かれました。
井龍会長挨拶
赤羽信州大副学長挨拶
台湾地質学会との学術交流協定調印式
名誉会員表彰
斎藤靖二名誉会員
鈴木堯士名誉会員
50年会員顕彰
50年会員顕彰
50年会員顕彰
50年会員顕彰
50年会員顕彰
50年会員顕彰
50年会員顕彰
阿部正宏会員
神保幸則会員
調枝勝幸会員
新妻信明会員
楡井久会員
日本地質学会賞
脇田浩二会員
小澤儀明賞
辻 健会員
Island Arc賞
荒井章司会員
論文賞
論文賞
纐纈佑衣会員
岩野英樹会員
小藤文次郎賞
小藤文次郎賞
氏家恒太郎会員
堤 浩之会員
研究奨励賞
越智真人会員
功労賞
大山次男会員
学会表彰
白尾元理会員
■懇親会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】長野大会:9月12日(土)の主なイベント
──────────────────────────────────
■国際シンポジウム「東アジアのテクトニクスと古地理」
9:00〜17:00 信大第三会場
■若手会員のための業界研究サポート
14:00〜17:00 信大工学部講義棟2階203
■市民講演会
14:00〜16:30 ホクト文化ホール
■地質情報展2015
9:30〜17:00 長野市生涯学習センター(TOiGO)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
【geo-Flash】No.311[長野大会臨時号]9月11日開催!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.311 2015/9/10┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】いよいよ長野大会が始まります!
【2】特別講演会「地質地盤情報の利活用と法整備」
【3】講演キャンセル・一部プログラム変更のお知らせ(10日17時現在)
【4】地質図を利用した商品「Geological Textile」ICA Map Awardsを受賞
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】いよいよ長野大会が始まります!
─────────────────────────────────
日本地質学会第122年学術大会(長野大会)がいよいよ明日(9月11日)開催さ
れます.
事務局や役員は,前日から現地入りし,万全の準備に余念がございません.
初日には,会員顕彰式・各賞表彰式・受賞記念講演が予定されておりますので,
ぜひ多くの皆様のご参加をお待ちしております.
http://www.geosociety.jp/nagano/content0001.html
長野大会を,盛り上げて行きましょう!!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】特別講演会「地質地盤情報の利活用と法整備」
─────────────────────────────────
主催:一般社団法人日本地質学会
日時:9月13日(日)14:30-17:00
会場:第7会場(信州大学工学部 学部共通棟 3)
平成25年4月,地質・地盤に関する学協会・業界・研究機関等が中心になって,
「地質・地盤情報活用促進に関する法整備推進協議会」が設立されました.日
本地質学会も本協議会に加入しています.講演会では,本協議会の活動を紹介
し,地質地盤情報の整備・利用の現状,学術研究の進展,法整備の必要性,お
よび日本地質学会の現状について報告します.
プログラム詳細は,こちら
http://www.geosociety.jp/nagano/content0051.html#koen
[お詫び]ニュース8月号プログラム記事(p.(41))の会場名の掲載に誤りが
ありました.正しい会場は「第7会場」です.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】講演キャンセル・一部プログラム変更のお知らせ(10日17時現在)
─────────────────────────────────
<講演キャンセル>
9/12(土)
●R20-O-3 松田義章(R20.地学教育・地学史)
●R24-O-13 加藤泰浩(R24.鉱物資源)
9/13(日)
●S3-O-4 SCHINECK William M.(S3.法地質学の進歩)
●T5-O-9 MOORE Gregory et al (T5. 「泥火山」の新しい研究展開に向けて)
●R7-O-14 中嶋 新ほか (R7. 海洋地質)
<時間・内容変更>
9/13(日)
■■■内容変更■■■
●S3.法地質学の進歩
10:25-10:40 S3-O-4(キャンセル)
下記に変更
10:15-10:25→10:15-10:20 休憩
10:20-10:30 What was found as geological trace evidence? SUGITA
Ritsuko
10:30-10:40 Forensic Geology― Methods and Cases. MURRAY Ray
■■■時間変更■■■
●T5. 「泥火山」の新しい研究展開に向けて
11:15-11:30 T5-O-9(キャンセル)
Active mud volcanism on Ramree and Cheduba Islands, offshore west
Myanmar.Moore Gregory F.・Aung Lin Thu・Kopf Achim
以下,講演時間を繰り上げ
11:30-11:45→11:15-11:30 T5-O-10
LUSI泥火山の特徴と発生過程の再検討(レビュー).谷川 亘・西尾嘉朗
11:45-12:00→11:30-11:45 T5-O-11
フランシスカン・メランジュの最終的配置:泥岩の注入説.小川勇二郎
講演キャンセル,プログラム変更の最新情報はこちら
http://www.geosociety.jp/nagano/content0060.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地質図を利用した商品「Geological Textile」ICA Map Awardsを受賞
─────────────────────────────────
斎藤 眞会員(産業技術総合研究所)が地質学・地質図の普及活動のひとつと
して監修された地質図を利用した商品「Geological Textile」が国際地図学会
議(The 27th International Cartographic Conference)にて
ICA Map Awards,Other cartographic products部門3位を受賞しました。
・地質図を利用した商品「Geological Textile」
http://www.tcg.co.jp/product/goods/GeologicalTextle.html
・The 27th International Cartographic Conference and the16th General
Assembly of ICA
http://www.icc2015.org/
・ICA Map Awards
http://icaci.org/map-awards/
長野大会では,受賞記念の「Geological Textile」特別販売を予定しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.313[長野大会臨時号]大会2日目 快適な天気
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.313 2015/9/12 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】長野大会2日目!
【2】長野大会:9月13日(日)の主なイベント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】長野大会2日目の様子
──────────────────────────────────
日本地質学会第122年学術大会(2015長野大会)の大会二日目が, 本日(9/12)開催されました.天気も良く,朝から心地よいスタート を切る事ができました.
午前中は,8つの会場で各学術セッションが行われました.お昼には, 昼食を食べながら打合せや講演等を行うランチョンが6件行われました. (堆積地質部会,三次元地質モデル研究の展望,火山部会,構造地質部会 若手の研究発表会,地質学雑誌編集委員会,文化地質学)また,大会本部 では,広報委員会の今後の展望について打合せを行いました.
ポスターコアタイムの後,午後も引き続き8つの会場でセッションがあり, 14時からは「若手会員のための業界研究サポート」が行われました.会場 は本格的な企業面接会のようで,大変多くの若手が参加しておりました.
また,14:30から16:00まで,ホクト文化ホール(長野県民文化会館)にて 市民講演会が実施され,信州大学理学部教授,三宅康幸先生による「信州の 火山を知ろう」と同大学名誉教授の塚原弘昭先生による「糸静構造線活断層 地震が起きたとき,長野盆地・松本盆地の震災は」という講演がありました. 一般市民の方も沢山参加され,大変盛況でした.会場入り口付近では,ジオ パークのポスター展示を含むアウトリーチセッションも行われました.
17:45からは,ポスター会場にて優秀ポスター賞の表彰式が行われました. 賞状を授与された発表者は,皆さん晴れがましい表情をされていました.
18時からは,10件もの夜間小集会が予定されています. (geo-Flashは,全て配信完了するまで4時間程度掛かりますので,受信 された頃には終了しております.ご了承下さい.)
大会2日目の様子を写真でご覧ください.
国際シンポ 東アジアのテクトニクス
若手会員のための業界サポート
市民講演会会場
アウトリーチセッション
市民講演会
ポスター賞
ポスター賞
ポスター賞
ポスター賞
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】長野大会:9月13日(日)の主なイベント
──────────────────────────────────
■北部フォッサマグナ‐東西日本の地質境界:過去,現在,そして未来
(工学部講義棟200)
■法地質学の進歩 (第6会場 学部共通棟1)
■特別講演会「地質地盤情報の利活用と法整備」(第7会場)
■小さなEarth Scientistのつどい(9:00-15:30 体育館ポスター会場)
■地学教育・アウトリーチ巡検(8:30-16:00)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
【geo-Flash】No.314[長野大会臨時号]大会最終日 明日から巡検!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.314 2015/9/13 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】長野大会最終日!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】長野大会最終日の様子
──────────────────────────────────
日本地質学会第122年学術大会(2015長野大会)の大会三日目が, 本日(9/13)開催されました.今日で最終日です.
午前中は,8つの会場で各学術セッションが行われました.この内, 第8会場(太田国際記念館)のR6.ジオパークセッションは一般公開 されました.
本日のランチョンは4件(海洋地質部会,構造地質部会,岩石部会, 現行地質過程部会)開催されました.どの部会も活発に活動されて いるようです.
ポスター会場では,「小さなEarth Scientistのつどい(〜第13回 小,中,高校生徒「地学研究」発表会)〜」が開かれ,皆さん元気 一杯に発表されていました.中には全て英語で作成している気合い の入ったポスターもあり,いずれ国際学会等で発表する予定なので しょう.また,生徒さんの話を聞いてみると全般的に地学部の人気 は高いそうで,人数も多く明るい将来が期待できます.きっとこの 中には未来の地質学者がいることでしょう.
午後は,6つの会場で各学術セッションが行われました.第7会場 では,特別講演会「地質地盤情報の利活用と法整備」が開催され, 「地質・地盤情報活用促進に関する法整備推進協議会」の活動紹介 などの講演がありました.地質学会も本協議会に加入しています.
2015長野大会は,長野LOCほか関係者の方々,また参加者の皆様 のご協力により大成功となりました.改めて今回関わった全ての方に 心より御礼申し上げます.また,明日から巡検に行かれる方は,怪我 や事故等ないようにお気を付けていってらっしゃいませ.
来年は,東京・桜上水大会です.皆さん,来年もまた東京でお会い しましょう!
大会最終日の様子を写真でご覧ください.
フォッサマグナシンポ
法地質学国際シンポ
小さなEarth Scientistの集い
表彰式
明日から巡検です.ぜひ良い写真を撮って冬のフォトコンテストに応募してください.
そして来年は東京・桜上水でお会いしましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
【geo-Flash】No.315 長野大会 終了しました!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.315 2015/9/15┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】長野大会 終了しました!
【2】創立125周年記念事業:地質学雑誌特集号の募集
【3】秋季地質調査研修:申込受付始まる!
【4】名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】長野大会 終了しました!
─────────────────────────────────
今年もたくさんの方々にご参加いただき,盛会のうち長野大会は終了いたしま
した.大会の報告記事は,ニュース誌11月号に掲載予定です.
大会様子(写真)はこちらからご覧いただけます.
http://www.geosociety.jp/nagano/content0059.html
来年は,東京・桜上水でお会いしましょう.
★第123年学術大会(東京・桜上水大会)★
2016年9月10日(土)〜12日(月)
会場:日本大学 桜上水キャンパス(東京都世田谷区)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】創立125周年記念事業:地質学雑誌特集号の募集
─────────────────────────────────
2018年に日本地質学会創立125周年を迎えるにあたっての記念事業の一つとして,
地質学雑誌特集号を連続して企画する事が決定しました.本特集号では,創立
100周年時に刊行された「日本の地質学100年」以降の25年間を中心とした各分
野の研究動向をまとめて順次発行します.本特集号への多数の申し込みを期待
しています.
第1次募集締切:2015年11月30日(月)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0160.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】秋季地質調査研修:申込受付始まる!
─────────────────────────────────
実施期間:2015年11月9日(月)〜11月13日(金)(4泊5日)
実施場所:千葉県君津市とその周辺(房総半島中部域)
募集対象者:主に,地質関連会社の若手技術者
募集人員:6名(定員に到達次第,募集終了)
参加費:12万円(往復交通費や宿泊費は含まず)
参加者募集期間:9月14日(月)〜10月13日(火)
実施内容や申込方法などの詳細は,
http://www.geosociety.jp/engineer/content0043.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】 名簿作成アンケートの実施/名簿の訂正・変更・登録のお願い
──────────────────────────────────
日本地質学会では,学会員相互の交流と親睦を図る目的で,2年ごとに会員名
簿を発行することを運営規則にうたっております.2015年はその発行年にあた
り,本年11月末日発行の予定で準備を行っております.
名簿の発行様式は前回と同様で,全会員を収録します.本会としては,個人情
報保護法の制約はあるとしても,会員の皆様が上記の目的に沿って利用できる
ような,従来規模の名簿を作成したいと考えておりますので,調査の実施にご
理解とご協力をお願いいたします.
アンケート提出およびWeb画面更新締切日:2015年10月5日(月)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0132.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■富士山巡検
日程:10月17日(土)〜18日(日),1泊2日 雨天決行
参加費用:一般22,000円,学生・院生13,000円
CPD単位:16単位
募集人数:会員および一般 30名程度(先着順)
申込期間:8月24日(月)〜10月2日(金)(定員に達した時点で締切)
http://www.geosociety.jp/outline/content0157.html
■ミニ・ショートコース:地すべり試験ラボ見学
日程:10月31日(土) 11:00〜16:00
場所:国土防災技術(株) 技術本部試験研究所(福島市南矢野目)
費用:3,000円
CPD単位:4単位
募集人数:10名(先着順,地質学会会員を優先します)
応募締切:10月9日(金)
http://www.geosociety.jp/outline/content0162.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■日本ジオパークネットワークガイドフォーラム
9月15日(火)〜16日(水)
会場:アミティ丹後(京丹後市網野町)
http://jgn2015.com/
■第4回アジア太平洋ジオパークネットワーク山陰海岸シンポジウム
日本地質学会ほか 後援
9月15日(火)〜20日(日)
会場:豊岡市民会館(豊岡市立野町20-34)ほか
http://apgn2015-jpn.com/
■第11回国際化石藻類シンポジウム
日本地質学会 後援
9月14日(月)〜19日(土)
会場:琉球大学
■2015年度日本地球化学会第62回年会
日本地質学会ほか 共催
9月16日(水)〜18日(金)
会場:横浜国立大学常盤台キャンパス
http://www.geochem.jp/conf/2015/
■第10回アジア地域応用地質学シンポジウム
日本地質学会 後援
研究発表会:9月24日(木)〜25日(金)
シンポジウム:9月26日(土)〜27日(日)[その後巡検予定あり]
会場:京都大学宇治黄檗プラザ
http://2015ars.com/
■Arthur Holmes Meeting Tsunami Hazards and Risks: Using the
Geological Record
日本地質学会 共催
9月25日(金)
会場:The Geological Society (Burlington House)(英・ロンドン)
プレ巡検:9月22日(火)〜24日(木)
http://www.geolsoc.org.uk/ahm15
■ 第178回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
9月25日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ902会議室
講師:難波謙二(福島大学環境放射能研究所所長)
テーマ:東京電力福島第一原子力発電所事故と放射性物質汚染
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■国際シンポジウム「沈み込み帯堆積盆地のリソスフェア・ダイナミクス」
日本地質学会 後援
10月5日(月)〜7日(水)(10月8日〜9日:地質巡検)
会場:東京第一ホテルシーフォート(品川区東品川)
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/ILP2015/
■学術フォーラム「高レベル放射性廃棄物の処分に関する政策提言
−国民的合意形成へ向けた暫定保管を巡って」
日本学術会議 主催
10月10日(土)13:00〜18:00
場所 日本学術会議講堂
https://form.cao.go.jp/scj/opinion-0003.html
■筑波大学生命環境科学研究科大学院説明会
10月19日(月)18:00〜20:00
場所:筑波大学東京キャンパス文京校舎119講義室
対象者:平成28年4月博士課程前期(地球科学専攻地球進化科学領域)と
後期(地球進化科学専攻)の入学を希望される方
http://www.ap-graduate.tsukuba.ac.jp/course/les/index.html
■地球惑星科学NYS 2015
10月24日(土)・25日(日)
場所:東京大学 本郷キャンパス
https://sites.google.com/site/nyswakate/2015
■第31回ゼオライト研究発表会
日本地質学会 後援
11月26日(木)〜27日(金)
会場:とりぎん文化会館(鳥取市尚徳町101-5)
要旨原稿締切:10月30日(金)
http://katalab.org/31zeolite/
■第5回学生のヒマラヤ野外実習ツアー(参加者受付中)
日本地質学会 推薦
暫定日程:2016年3月5日〜20日の16日間
参加申込受付期間:2015年5月1日〜11月30日
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0144.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■広島大学大学院理学研究科地球惑星システム学専攻地球惑星システム学講座
(教授)公募(11/30)
■信州大学理学部理学科物質循環学コース教員(助教)公募(11/13)
■海洋研究開発機構:研究職・技術研究職募集(11/5)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.316(臨時)小畠郁生 名誉会員 ご逝去
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.316 2015/09/25 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 小畠 郁生 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
小畠 郁生 名誉会員(国立科学博物館 名誉館員)が,平成27年9月19日(土)
にご逝去されました(享年85歳)。
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げ
ます。なお,ご葬儀はご家族のみですでに執り行われたとのことです。
会長 井龍 康文
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.317 2016年度代議員および役員選挙
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.317 2015/10/6┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2016年度代議員および役員選挙について
【2】2016年度各賞候補者募集について
【3】「割引会費」申請受付開始:2016年度会費払込について
【4】創立125周年記念事業:地質学雑誌特集号の募集
【5】第7回惑星地球フォトコンテスト:間もなく応募開始です
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2016年度代議員および役員選挙について
─────────────────────────────────
10月13日(火)から「代議員」の立候補届の受付が開始されます.選挙告示は
News誌9月号または学会HPをご覧下さい.
代議員立候補受付期間:10月13日(火)〜11月6日(金)*最終日18時必着
詳しくは,
http://sub.geosociety.jp/members/content0088.html(会員のページ)
※「会員のページ」の選挙に関する案内から,立候補届の書式がダウンロード
できるようになっています.「会員のページ」へは会員番号・パスワードによ
るログインが必要です.ログインの方法はこちら.
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2016年度各賞候補者募集について
─────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして,研究の援助・奨励および研究業
績の表彰を行っています.本年も各賞の自薦,他薦による候補者を募集いたし
ます.期日厳守にて,たくさんのご応募をお待ちしております.
応募締切:2015年11月30日(月)必着
推薦書式,対象論文リストなど詳しくは,
http://sub.geosociety.jp/members/content0085.html(会員のページ)
※「会員のページ」へは会員番号・パスワードによるログインが必要です.
ログインの方法はこちら.
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】「院生割引会費」受付開始:2016年度会費払込について
─────────────────────────────────
運営規則により,次年分の会費を前納下さいますようお願いいたします.
学部学生の方,定収のない大学院生(研究生)の方は,早めに割引会費の申請
を行って下さい.割引の適用を希望する場合,申請は毎年必要です.
割引会費申請締切(請求書発行前締切):2015年11月16日(月)
2016年度会費払込について(割引申請の書式もこちらから)
http://www.geosociety.jp/outline/content0164.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】創立125周年記念事業:地質学雑誌特集号の募集
─────────────────────────────────
2018年に日本地質学会創立125周年を迎えるにあたっての記念事業の一つとして,
地質学雑誌特集号を連続して企画する事が決定しました.本特集号では,創立
100周年時に刊行された「日本の地質学100年」以降の25年間を中心とした各分
野の研究動向をまとめて順次発行します.本特集号への多数の申し込みを期待
しています.
第1次募集締切:2015年11月30日(月)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0160.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第7回惑星地球フォトコンテスト:間もなく応募開始です
──────────────────────────────────
ジオフォトの最高峰の写真コンテスト!今年もまもなく応募開始です.
応募締切:2016年2月22日(月)
たくさんのご応募お待ちしています.
詳しくは, http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■ミニ・ショートコース:地すべり試験ラボ見学
日程:10月31日(土) 11:00〜16:00
場所:国土防災技術(株) 技術本部試験研究所(福島市南矢野目)
費用:3,000円
CPD単位:4単位
募集人数:10名(先着順,地質学会会員を優先します)
応募締切:10月9日(金)
http://www.geosociety.jp/outline/content0162.html
■地質研究サミット「ジオハザードと都市地質学」
日程:11月23日(月・祝)10:00〜17:30
場所:日本大学文理学部図書館3階オーバルホール(世田谷区桜上水)
対象:日本地質学会会員および一般(非会員)
参加費:無料,事前申し込み不要 要旨集:有料(1,000円予定)
CPD単位:取得可能(6単位)
詳しくは, http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■国立公文書館 秋の特別展「災害に学ぶ−明治から現代へ−」
9月19日(土)〜10月12日(月・祝)
会場:国立公文書館本館(千代田区北の丸公園)
入場無料
http://www.archives.go.jp/exhibition/index.html
■国際シンポジウム「沈み込み帯堆積盆地のリソスフェア・ダイナミクス」
日本地質学会 後援
10月5日(月)〜7日(水)(10月8日〜9日:地質巡検)
会場:東京第一ホテルシーフォート(品川区東品川)
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/ILP2015/
■平成27年度 東濃地科学センター 地層科学研究 情報・意見交換会
10月29日(木)13:30〜16:50
場所:瑞浪市地域交流センター「ときわ」(岐阜県瑞浪市)
定員:約150名(申込締切:10月16日(金))
http://www.jaea.go.jp/04/tono/topics/topics1509_1/1509_1.html
■瑞浪超深地層研究所 深度300m水平坑道見学会
10月30日(金)9:15〜12:00
場所:瑞浪超深地層研究所
※定員:40名(申込締切:10月16日(金))
http://www.jaea.go.jp/04/tono/topics/topics1509_1/1509_1.html
■第179回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
10月30日(金)18:30〜20:30[事前予約不要]
場所:北とぴあ901会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分)
講師:藤原寿和(廃棄物ネット・ワーク代表)
テーマ:戦後から今日にいたる廃棄物問題の列挙と
今後の日本の国土汚染について
CPD:2単位
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■第31回ゼオライト研究発表会
日本地質学会 後援
11月26日(木)〜27日(金)
会場:とりぎん文化会館(鳥取市尚徳町101-5)
要旨原稿締切:10月30日(金)
http://katalab.org/31zeolite/
■第5回学生のヒマラヤ野外実習ツアー(参加者受付中)
日本地質学会 推薦
暫定日程:2016年3月5日〜20日の16日間
参加申込受付期間:2015年5月1日〜11月30日
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0144.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■山田科学振興財団2016年度研究援助候補推薦(学会締切1/29)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.318(臨時)次期大型研究計画への新規提案についての問合せ
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.318 2015/10/13┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】次期大型研究計画への新規提案についての問合せ
─────────────────────────────────
日本学術会議では、第23 期「学術の大型研究計画に関するマスタープラン」(
マスタープラン2017)の作成に向けて議論が行われています。マスタープラン
2017 公募においては、22期で提案された研究計画とともに新規提案も募集され
る見込みです。
ついては,この公募の前に地球惑星科学分野の大型研究計画の応募推進を図っ
ている日本学術会議地球惑星科学委員会地球・惑星圏分科会から各学協会へ宛
てて新規提案の計画の有無について情報提供の依頼がありました。地質学会を
母体とした新規提案を予定されている方は、10月26日(月)までに地質学会事
務局に概要等を御連絡下さい。
新規提案有の場合、その計画案を前回の大型研究計画調書の様式を用いて回答
することが求められております(締切:12 月11 日(金))。
また,新規提案およびマスタープラン2014採択課題のうち地球惑星科学委員会
地球・惑星圏分科会大型研究計画検討ワーキンググループが追加の情報収集が
必要と認めた計画については、本年12月25日開催予定の地球惑星科学委員会地
球・惑星圏分科会において発表することが求められております。
以上、よろしくお願いします.
(会長 井龍康文)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.319 2016年度代議員および役員選挙立候補受付開始!
【geo-Flash】No.319 2016年度代議員および役員選挙立候補受付開始!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.319 2015/10/20┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2016年度代議員および役員選挙について
【2】2016年度各賞候補者募集について
【3】「割引会費」申請受付開始:2016年度会費払込について
【4】創立125周年記念事業:地質学雑誌特集号の募集
【5】第7回惑星地球フォトコンテスト:作品募集!
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2016年度代議員および役員選挙について
─────────────────────────────────
10月13日(火)から「代議員」の立候補届の受付を開始しています.選挙告示
はNews誌9月号または学会HPをご覧下さい.
代議員立候補受付期間:10月13日(火)〜11月6日(金)*最終日18時必着
詳しくは,
http://sub.geosociety.jp/members/content0088.html(会員のページ)
※「会員のページ」の選挙に関する案内から,立候補届の書式がダウンロード
できるようになっています.「会員のページ」へは会員番号・パスワードによ
るログインが必要です.ログインの方法はこちら.
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2016年度各賞候補者募集について
─────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして,研究の援助・奨励および研究業
績の表彰を行っています.本年も各賞の自薦,他薦による候補者を募集いたし
ます.期日厳守にて,たくさんのご応募をお待ちしております.
応募締切:2015年11月30日(月)必着
推薦書式,対象論文リストなど詳しくは, http://sub.geosociety.jp/
members/content0085.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】「院生割引会費」受付開始:2016年度会費払込について
─────────────────────────────────
運営規則により,次年分の会費を前納下さいますようお願いいたします.
学部学生の方,定収のない大学院生(研究生)の方は,早めに割引会費の申請
を行って下さい.割引の適用を希望する場合,申請は毎年必要です.
割引会費申請締切(請求書発行前締切):2015年11月16日(月)
2016年度会費払込について(割引申請の書式もこちらから)
http://www.geosociety.jp/outline/content0164.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】創立125周年記念事業:地質学雑誌特集号の募集
─────────────────────────────────
2018年に日本地質学会創立125周年を迎えるにあたっての記念事業の一つとして,
地質学雑誌特集号を連続して企画する事が決定しました.本特集号では,創立
100周年時に刊行された「日本の地質学100年」以降の25年間を中心とした各分
野の研究動向をまとめて順次発行します.本特集号への多数の申し込みを期待
しています.
第1次募集締切:2015年11月30日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/125th/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第7回惑星地球フォトコンテスト:作品募集!
──────────────────────────────────
ジオフォトの最高峰の写真コンテスト!今年も作品を募集いたします。
応募締切:2016年2月22日(月)
たくさんのご応募お待ちしています.
詳しくは,http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■地質研究サミット「ジオハザードと都市地質学」
日程:11月23日(月・祝)10:00〜17:30
場所:日本大学文理学部図書館3階オーバルホール(世田谷区桜上水)
対象:日本地質学会会員および一般(非会員)
参加費:無料,事前申込不要 要旨集:有料(1,000円予定)
CPD単位:取得可能(6単位)
詳しくは,http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第179回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
10月30日(金)18:30〜20:30[事前予約不要]
場所:北とぴあ901会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分)
講師:藤原寿和(廃棄物ネット・ワーク代表)
テーマ:戦後から今日にいたる廃棄物問題の列挙と今後の日本の国土汚染につ
いて
CPD:2単位
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■産業技術連携推進会議 地質地盤情報分科会 平成27年度講演会
「3次元地質地盤モデリングの進展とその利活用」
11月6日(金)13:30〜16:50 参加無料・事前申込不要
場所:北とぴあ第一研修室(JR京浜東北線王子駅北口より3分)
CPD:3単位
https://www.gsj.jp/information/domestic/sgr/index.html
■東京地学協会 地学クラブ講演会
「伊能忠敬の世界的偉業」
11月16日(月)15:00〜16:00
場所:東京地学協会 地学会館二階 講堂(千代田区二番町 12-2)
講演:西川 治(東京大学名誉教授)
http://www.geog.or.jp/
■ワークショップ「ジオハザードに対処できる人材の育成:防災国際ネットワー
ク構築に向けた国内連携のあり方」
主催:日本学術会議・産業技術総合研究所,東北大学災害科学国際研究所
日本地質学会 後援
11月20日(金)13:30〜18:00 参加申込不要
場所:東京海洋大学大講義室(越中島キャンパス第4実験棟5階)
問い合わせ:IUGS分科会委員長(国研)海洋研究開発機構,北里 洋(
kitazatoh@jamstec.go.jp)
■第180回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
11月20日(金)18:30〜20:30(事前予約不要)
場所:北とぴあ901会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分)
講師:上砂正一(NPO日本地質汚染審査機構副理事長)
テーマ:自治体の環境行政の諸問題
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■第26回地質汚染調査浄化技術研修会
日本地質学会環境地質部会 共催
11月21日(土)〜23日(月)(時間は各日毎に異なります)
場所:関東ベースンセンター
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
■日本地下水学会セミナー
東京電力福島第一原子力発電所事故による周辺水環境への影響−現状と課題−
日本地質学会 後援
11月24日(火)13:00〜17:40
場所:日本大学文理学部 3号館3203講義室
定員・100名(要予約申込、定員になり次第締切)
http://www.jagh.jp/
■第31回ゼオライト研究発表会
日本地質学会 後援
11月26日(木)〜27日(金)
会場:とりぎん文化会館(鳥取市尚徳町101-5)
要旨原稿締切:10月30日(金)
http://katalab.org/31zeolite/
■東京地学協会 秋季講演会
「地球の大きさと形を測る」―その歴史における伊能忠敬
11月28日(土)14:00〜16:00
場所:弘済会館4F蘭の間(千代田区麹町5-1)
講演:野上道男(東京都立大学名誉教授)
海津 優(元国土地理院地理地殻活動研究センター長)
河荑和重(国土地理院地理地殻活動研究センター研究管理課長)
http://www.geog.or.jp/
■産総研第14回地圏資源環境研究部門成果報告会
「強い技術シーズの創出と展開」
12月10日(木)13:30〜17:25
場所:秋葉原ダイビル・コンベンションホール
申込締切:11月26日(木)
http://green.aist.go.jp/ja/
■第5回学生のヒマラヤ野外実習ツアー(参加者受付中)
日本地質学会 推薦
暫定日程:2016年3月5日〜20日の16日間
参加申込受付期間:2015年5月1日〜11月30日
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0144.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■高知大学理工学部地球環境防災学科(講師)公募(11/20)
■鳥取大学大学院工学研究科教員公募(2016/1/5)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.320 代議員選挙 まもなく立候補締切です!
【geo-Flash】No.320 代議員選挙 まもなく立候補締切です!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.320 2015/11/2┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2016年度代議員および役員選挙 まもなく立候補締切!
【2】2016年度各賞候補者募集について
【3】「割引会費」申請受付中:2016年度会費払込について
【4】創立125周年記念事業:地質学雑誌特集号の募集
【5】第7回惑星地球フォトコンテスト:作品募集!
【6】支部情報
【7】「県の石」選定作業について
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2016年度代議員および役員選挙 まもなく立候補締切!
─────────────────────────────────
代議員および役員選挙 まもなく立候補が締切られます.立候補を予定されている方は,忘れずに届け出を行って下さい.
代議員立候補受付期間:10月13日(火)〜11月6日(金)*最終日18時必着
詳しくは,http://sub.geosociety.jp/members/content0088.html(会員のページ)
★立候補届出状況はHPトップからご確認いただけます★(11/2,12時現在)
http://www.geosociety.jp/
※「会員のページ」の選挙に関する案内から,立候補届の書式がダウンロード
できるようになっています.「会員のページ」へは会員番号・パスワードによ
るログインが必要です.ログインの方法はこちら.
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2016年度各賞候補者募集について
─────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして,研究の援助・奨励および研究業
績の表彰を行っています.本年も各賞の自薦,他薦による候補者を募集いたし
ます.期日厳守にて,たくさんのご応募をお待ちしております.
応募締切:2015年11月30日(月)必着
推薦書式,対象論文リストなど詳しくは, http://sub.geosociety.jp/
members/content0085.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】「院生割引会費」受付中:2016年度会費払込について
─────────────────────────────────
運営規則により,次年分の会費を前納下さいますようお願いいたします.
学部学生の方,定収のない大学院生(研究生)の方は,早めに割引会費の申請
を行って下さい.割引の適用を希望する場合,申請は毎年必要です.
割引会費申請締切(請求書発行前締切):2015年11月16日(月)
2016年度会費払込について(割引申請の書式もこちらから)
http://www.geosociety.jp/outline/content0164.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】創立125周年記念事業:地質学雑誌特集号の募集
─────────────────────────────────
2018年に日本地質学会創立125周年を迎えるにあたっての記念事業の一つとして,
地質学雑誌特集号を連続して企画する事が決定しました.本特集号では,創立
100周年時に刊行された「日本の地質学100年」以降の25年間を中心とした各分
野の研究動向をまとめて順次発行します.本特集号への多数の申し込みを期待
しています.
第1次募集締切:2015年11月30日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/125th/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第7回惑星地球フォトコンテスト:作品募集中
──────────────────────────────────
ジオフォトの最高峰の写真コンテスト!今年も作品を募集いたします。
応募締切:2016年2月22日(月)
たくさんのご応募お待ちしています.
詳しくは,http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■地質研究サミット「ジオハザードと都市地質学」
日程:11月23日(月・祝)10:00〜17:30
場所:日本大学文理学部図書館3階オーバルホール(世田谷区桜上水)
対象:日本地質学会会員および一般(非会員)
参加費:無料,事前申込不要 要旨集:有料(1,000円予定)
CPD単位:取得可能(6単位)
詳しくは,http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】「県の石」選定作業について
──────────────────────────────────
たくさんのご応募をいただき,ありがとうございました。 2014年10月31日に応
募を締め切り,ただいま審査・選定中です。
県の石の発表が予定よりずいぶんと遅れており、申し訳ございません。現在、
選定委員会および各支部において、多くの皆さまにご賛同を得られる選定とな
る よう、検討しております。作業を急いではおりますが、多くの候補が挙げら
れたため,審議に時間がかかっております.結果の発表まで,もうしばらくお
待ちください。
「県の石」選定委員会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■国際地学オリンピック三重大会 運営委員会ニュース(10月)
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/name/olymp/kokusai_chiori_news_2015.10.pdf
■サイエンスアゴラ「フューチャー・アース 〜持続可能な地球社会に向けて〜」
11月14日(土)13:00〜17:00
場所:日本科学未来館 イノベーションホール
http://www.jst.go.jp/csc/scienceagora/program/booth/ab_101/
参加申込締切:11月10日(火)
■生命を育む地球環境の変動予測と適応─我が国におけるIGBP25年間の歩み
11月15日(日)9:00-12:00
政策研究大学院大学 (東京都港区六本木7-22-1)
http://mits10.aori.u-tokyo.ac.jp/kokusai/igbp2015/
■持続可能な社会のための科学と技術に関する国際会議2015
11月15日(日)13:30-18:00
場所:日本学術会議講堂
http://www.pco-prime.com/Science_and_Technology_for_Sustainability2015/index.html
■ワークショップ「ジオハザードに対処できる人材の育成:防災国際ネットワー
ク構築に向けた国内連携のあり方」
主催:日本学術会議・産業技術総合研究所,東北大学災害科学国際研究所
日本地質学会 後援
11月20日(金)13:30〜18:00 参加申込不要
場所:東京海洋大学大講義室(越中島キャンパス第4実験棟5階)
問い合わせ:IUGS分科会委員長(国研)海洋研究開発機構,
北里 洋(kitazatoh@jamstec.go.jp)
■第180回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
11月20日(金)18:30〜20:30(事前予約不要)
場所:北とぴあ901会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分)
講師:上砂正一(NPO日本地質汚染審査機構副理事長)
テーマ:自治体の環境行政の諸問題
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■第26回地質汚染調査浄化技術研修会
日本地質学会環境地質部会 共催
11月21日(土)〜23日(月)(時間は各日毎に異なります)
場所:関東ベースンセンター
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
■日本地下水学会セミナー
東京電力福島第一原子力発電所事故による周辺水環境への影響−現状と課題−
日本地質学会 後援
11月24日(火)13:00〜17:40
場所:日本大学文理学部 3号館3203講義室
定員・100名(要予約申込、定員になり次第締切)
http://www.jagh.jp/
■第31回ゼオライト研究発表会
日本地質学会 後援
11月26日(木)〜27日(金)
会場:とりぎん文化会館(鳥取市尚徳町101-5)
http://katalab.org/31zeolite/
■第181回地質汚染イブニングセミナー
12月18日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ902会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分
講師:楡井 久(国際地質科学連合(IUGS)GEM人工地層と地質汚染研究委員長・
NPO日本地質汚染審査機構理事長)
テーマ:国民生活に関わる人自不整合と人工地層について
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■学術フォーラム「防災学術連携体の設立と東日本大震災の総合対応の継承」
1月9日(土)13:00〜17:30
場所:日本学術会議講堂
http://janet-dr.com
■公開講演会
「強靭で安全・安心な都市を支える地質地盤−あなたの足元は大丈夫?−」
主催:日本学術会議
日本地質学会 後援
1月23日(土)13:30〜17:30
場所:日本学術会議講堂
http://www.scj.go.jp/ja/event/index.html
■第5回学生のヒマラヤ野外実習ツアー(参加者受付中)
日本地質学会 推薦
暫定日程:2016年3月5日〜20日の16日間
参加申込受付期間:2015年5月1日〜11月30日
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0144.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■JAMSTEC地球内部物質循環研究分野ポストドクトラル研究員(11/30)
■平成27年度埼玉県職員採用選考(環境研究職(土壌・地下水・地盤))(12/4)
■高知大学海洋コア総合研究センター(准教授/講師,講師/助教)公募(12/18)
■岡山大学地球物質科学研究センターテニュア・トラック教員(准教授または助教)公募(採用決定次第締切)
■第57回藤原賞授賞候補者の推薦(学会締切2016/1/7)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.321(臨時)代議員選挙:明日(6日)立候補締切です
【geo-Flash】No.321(臨時)代議員選挙:明日(6日)立候補締切です
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.321 2015/11/5┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2016年度代議員選挙:明日(6日)立候補締切です
─────────────────────────────────
代議員選挙の立候補届けは,明日11月6日(金)18時締切です.
代議員及び役員選挙は,2年に一度の選挙で,現在の全ての代議員,全ての理事
が改選となります.
立候補を予定されている方は,くれぐれも期日に遅れないようご提出ください.
★★★ 代議員立候補受付締切:11月6日(金)18時必着 ★★★
本日(5日)14:50 現在の代議員立候補者数は以下のとおりです.( )は定数.
・全国区 52(100)
・地方支部区 38(100)
内訳:北海道:3(5) 東北:2(8) 関東:14(41)
中部:12(17) 近畿:0(11) 四国:2(4)
西日本:5(14)
立候補届出状況はHPトップでもご確認いただけます.http://www.geosociety.jp/
詳しくは,http://sub.geosociety.jp/members/content0088.html(会員のページ)
※「会員のページ」の選挙に関する案内から,立候補届の書式がダウンロード
できます.「会員のページ」へは会員番号・パスワードによるログインが必要
です.ログインの方法はこちら.
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.322(臨時)2016年度代議員選挙について
【geo-Flash】No.322(臨時)2016年度代議員選挙について
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.322 2015/11/10┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2016年度代議員選挙について
【2】2016年度各賞候補者募集について(11/30締切)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2016年度代議員選挙について
─────────────────────────────────
選挙規則ならびに選挙細則に基づき,標記選挙を実施するにあたっての立候補
届は,11月6日に締め切られました.その結果,全国区・地方支部区とも立候補
者数が定数を超えませんでしたので,選挙規則第6条に基づき投票は行わず,全
員を無投票当選といたします.
なお,立候補の抱負など,当選された方の詳細につきましては別途名簿をお送
りいたしますので,ご覧ください.
また,代議員選挙は無投票となりましたが,会長・副会長の意向調査につきま
しては,予定通り実施いたします.意思表明者のマニフェストならびに調査票
は代議員当選者の名簿とともに,11月25日ころまでにお送りいたしますので,
ご返信を宜しくお願いいたします.
詳しくは,http://sub.geosociety.jp/members/content0090.html
2015年11月10日
一般社団法人日本地質学会
選挙管理委員会委員長 金澤 直人
※会員番号・パスワードによるログインが必要です.ログインの方法はこち.
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2016年度各賞候補者募集について(11/30締切)
─────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして,研究の援助・奨励および研究業
績の表彰を行っています.本年も各賞の自薦,他薦による候補者を募集いたし
ます.期日厳守にて,たくさんのご応募をお待ちしております.
応募締切:2015年11月30日(月)必着
推薦書式,対象論文リストなど詳しくは,
http://sub.geosociety.jp/members/content0085.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
地質マンガ 大学でも全裸に見えるポーズがあるんです!?
地質マンガ
大学でも全裸に見えるポーズがあるんです!?
原案:土岐知弘 マンガ:KEY
短パンで白衣を着てしまうと,白衣から生足しか見えないということになってしまいます。
一歩間違えると,かなり際どい外見になりかねませんね。お気をつけ下さい…。
2015年6月16日付原案提供。すでに「旬」を過ぎている可能性もございます…。m(_ _)m
地質マンガ 「GEOって !?」
地質マンガ
GEOって !?
原案:土岐知弘 マンガ:KEY
(注)「GEO」...とある有名なDVDレンタル店の名前です。
【geo-Flash】No.323 各賞候補者募集 11/30締切です!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.323 2015/11/17┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2016年度各賞候補者募集について(11/30締切)
【2】創立125周年記念事業:地質学雑誌特集号の募集
【3】2016年度会費払込のお知らせ
【4】第7回惑星地球フォトコンテスト:作品募集中
【5】支部情報
【6】専門部会より
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】地質マンガ「大学でも全裸に見えるポーズがあるんです !?」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2016年度各賞候補者募集について(11/30締切)
─────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして,研究の援助・奨励および研究業
績の表彰を行っています.本年も各賞の自薦,他薦による候補者を募集いたし
ます.期日厳守にて,たくさんのご応募をお待ちしております.
応募締切:2015年11月30日(月)必着
推薦書式,対象論文リストなど詳しくは,
http://sub.geosociety.jp/members/content0085.html(要会員ログイン)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】創立125周年記念事業:地質学雑誌特集号の募集
─────────────────────────────────
2018年に日本地質学会創立125周年を迎えるにあたっての記念事業の一つとして,
地質学雑誌特集号を連続して企画する事が決定しました.本特集号では,創立
100周年時に刊行された「日本の地質学100年」以降の25年間を中心とした各分
野の研究動向をまとめて順次発行します.本特集号への多数の申し込みを期待
しています.
第1次募集締切:2015年11月30日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/125th/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2016年度会費払込のお知らせ
─────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下さいますよ
うお願いいたします.
■2016年度分会費の引き落とし日:12月24日(木)です.
請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下
さい.
■自動引き落とし以外の方(お振り込み)
12月中旬頃までに請求書兼郵便振替用紙をお送りいたします.折り返しご送金
くださいますようお願いいたします.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0164.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第7回惑星地球フォトコンテスト:作品募集中
──────────────────────────────────
ジオフォトの最高峰の写真コンテスト!今年も作品を募集いたします.
応募締切:2016年2月22日(月)
たくさんのご応募お待ちしています.
詳しくは,http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■地質研究サミット「ジオハザードと都市地質学」
日程:11月23日(月・祝)10:00〜17:30
場所:日本大学文理学部図書館3階オーバルホール(世田谷区桜上水)
対象:日本地質学会会員および一般(非会員)
参加費:無料,事前申込不要 要旨集:有料(1,000円予定)
CPD単位:取得可能(6単位)
詳しくは,http://kanto.geosociety.jp/
■関東支部功労賞募集
関東支部の顕彰制度に基づき2015年度も支部活動や地質学を通して社会貢献さ
れた個人・団体を顕彰いたします.
公募期間:2015年12月10日(木)〜2016年1月10日(日)
詳しくは後日支部HP,ニュース誌に掲載予定です.
問い合せ先・推薦受付:関東支部幹事長 笠間友博
e-mail:kasama@nh.kanagawa-museum.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】専門部会より
──────────────────────────────────
[環境地質部会]
第35回IGCが2016年8月27日〜9月4日まで南アフリカ・ケープタウンで開催され
ます.環境地質のセッションでは人工地層・地質汚染に関わる シンポジウムの
提案が行われておりますので,この機会に環境地質関連の皆さん究成果発表を
してみてはいかがでしょうか?
8.Brian Marker, Ben Mapani, Qingcheng He, Hisashi Nirei and Adriana
Niz Geoscience for environmental management
9.Jonas Satkunas, Hisashi Nirei, Kunio Furuno, Hassina Mouri and
Brian Marker Man Made Strata and Geopollution
詳細は,www.35igc.org/Themes/15/Environmental
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■ワークショップ「ジオハザードに対処できる人材の育成:防災国際ネットワー
ク構築に向けた国内連携のあり方」
日本地質学会 後援
11月20日(金)13:30〜18:00 参加申込不要
場所:東京海洋大学大講義室(越中島キャンパス第4実験棟5階)
http://www.geosociety.jp/outline/content0144.html#now
(ワークショップポスターがダウンロードできます)
■第180回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
11月20日(金)18:30〜20:30(事前予約不要)
場所:北とぴあ901会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分)
講師:上砂正一(NPO日本地質汚染審査機構副理事長)
テーマ:自治体の環境行政の諸問題
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■第26回地質汚染調査浄化技術研修会
日本地質学会環境地質部会 共催
11月21日(土)〜23日(月)(時間は各日毎に異なります)
場所:関東ベースンセンター
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
■日本地下水学会セミナー
東京電力福島第一原子力発電所事故による周辺水環境への影響−現状と課題−
日本地質学会 後援
11月24日(火)13:00〜17:40
場所:日本大学文理学部 3号館3203講義室
定員・100名(要予約申込,定員になり次第締切)
http://www.jagh.jp/
■第31回ゼオライト研究発表会
日本地質学会 後援
11月26日(木)〜27日(金)
会場:とりぎん文化会館(鳥取市尚徳町101-5)
http://katalab.org/31zeolite/
■第25回環境地質学シンポジウム
主催 医療地質-地質汚染-社会地質学会
日本地質学会 共催
11月27日(金)〜28日(土)10:00〜18:00[事前予約不要]
場所:日本大学文理学部オーバルホールhttp://www.jspmug.org/envgeo_sympo/25th_sympo/25th_sympo.html
■地球化学研究協会「公開講座」および「三宅賞」受賞者の受賞記念講演
12月5日(土)14:40〜
場所:霞が関ビル35階東海大学校友会館
参加費:賛助会員および学生は無料,一般1,000円(資料代を含む)
http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~e881147/Geochem/
■東北大学東北アジア研究センター創設20周年記念国際シンポジウム:
セッション「東北アジアの地殻変動―パンサラッサから環太平洋まで」
12月6日(日)9:00〜12:30
場所:仙台国際センター小会議室 参加無料
http://www.cneas.tohoku.ac.jp/news/asia20/
■第181回地質汚染イブニングセミナー
12月18日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ902会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分
講師:楡井 久(国際地質科学連合(IUGS)GEM人工地層と地質汚染研究委員長・
NPO日本地質汚染審査機構理事長)
テーマ:国民生活に関わる人自不整合と人工地層について
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■地学クラブ講演会「天然資源と紛争の政治地理学」
12月18日(金)16:00〜17:00
場所:東京地学協会2F講堂
講演:大木優利氏(ジュネーブ高等国際問題研究所)
参加申込:不要(どなたも無料で参加できます)
http://www.geog.or.jp/lecture/lecturescheduled/255-club294.html
■学術フォーラム「防災学術連携体の設立と東日本大震災の総合対応の継承」
1月9日(土)13:00〜17:30
場所:日本学術会議講堂
http://janet-dr.com
■公開講演会
「強靭で安全・安心な都市を支える地質地盤−あなたの足元は大丈夫?−」
主催:日本学術会議
日本地質学会 後援
1月23日(土)13:30〜17:30
場所:日本学術会議講堂
http://www.scj.go.jp/ja/event/index.html
■第5回学生のヒマラヤ野外実習ツアー(参加者受付中)
日本地質学会 推薦
暫定日程:2016年3月5日〜20日の16日間
参加申込受付期間:2015年5月1日〜11月30日
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0144.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■JAMSTEC地震津波海域観測研究開発センターポストドクトラル研究員(12/9)
■北海道大学低温科学研究所教員公募(1/29)
■東京工業大学理学院地球惑星科学系助教公募(1/4)
■平成28年度東京大学大気海洋研究所共同利用公募(11/30)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】地質マンガ「大学でも全裸に見えるポーズがあるんです !?」
──────────────────────────────────
「大学でも全裸に見えるポーズがあるんです !?」
原案:土岐知弘 マンガ:Key
http://www.geosociety.jp/faq/content0057.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.324(臨時)ジオパークのユネスコ正式事業化決定!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.324 2015/11/19 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】ジオパークのユネスコ正式事業化決定!
─────────────────────────────────
2015年11月17日に開催されました第38回ユネスコ総会において,世界ジオパー
クネットワークの活動が「国際地質科学ジオパーク計画(IGGP)」として正式
にユネスコの事業となりました.
ジオパークは,地質が原点にあります.日本地質学会はそのことを踏まえて,
今後もジオパークの活動に対して学術的支援のほか,教育普及,自然災害の観
点からも支援を続けていきます.
世界ジオパークのユネスコ正式事業化について(JGNのサイトへ)
http://www.geopark.jp/about/datacenter/index.html
本決定に関する日本地質学会のコメント(2015年11月19日)
http://www.geosociety.jp/geopark/content0020.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
No.325(臨時)勝井 義雄 名誉会員 ご逝去
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.325 2015/11/25 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 勝井 義雄 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
勝井 義雄 名誉会員(北海道大学名誉教授)が,平成27年10月20日(火)
に老衰のためご逝去されました(享年90歳).
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げ
ます.なお,ご葬儀はご家族のみですでに終えられており,故人並びにご
家族の意思により,ご厚志は固くご辞退されておられます.
会長 井龍 康文
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.326 第7回惑星地球フォトコンテスト:作品募集中
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.326 2015/12/1┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2016年度会費払込のお知らせ
【2】第7回惑星地球フォトコンテスト:作品募集中
【3】支部情報
【4】その他のお知らせ
【5】公募情報・各賞助成情報等
【6】地質マンガ「GEOって !?」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2016年度会費払込のお知らせ
─────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下さいますよ
うお願いいたします.
■2016年度分会費の引き落とし日:12月24日(木)です.
請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下
さい.
■自動引き落とし以外の方(お振り込み)
12月中旬頃までに請求書兼郵便振替用紙をお送りいたします.折り返しご送金
くださいますようお願いいたします.
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0164.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第7回惑星地球フォトコンテスト:作品募集中
──────────────────────────────────
ジオフォトの最高峰の写真コンテスト!今年も作品を募集いたします.
応募締切:2016年2月22日(月)
たくさんのご応募お待ちしています.
詳しくは, http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■関東支部功労賞募集
関東支部の顕彰制度に基づき2015年度も支部活動や地質学を通して社会貢献さ
れた個人・団体を顕彰いたします.
公募期間:2015年12月10日(木)〜2016年1月10日(日)
詳しくは, http://kanto.geosociety.jp/
[西日本支部]
■西日本支部平成27年度総会・第167回例会
日時:平成28年2月20日(土)9:00〜 例会終了後 懇親会
場所:熊本大学黒髪南キャンパス理学部2号館
講演申込締切:2月4日(木)17時
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■国際地学オリンピック三重大会 運営委員会ニュース(11月)
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/name/olymp/kokusai_chiori_news_2015.10.pdf
■平成27年度国総研講演会
12月3日(木)10:30〜17:00
場所:日本消防会館ニッショーホール(港区虎ノ門)
特別講演「社会・経済イノベーションを導く国土技術政策」
入場無料
http://www.nilim.go.jp
■第181回地質汚染イブニングセミナー
12月18日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ902会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分
講師:楡井 久(国際地質科学連合(IUGS)GEM人工地層と地質汚染研究委員長・
NPO日本地質汚染審査機構理事長)
テーマ:国民生活に関わる人自不整合と人工地層について
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■東北大学多元物質科学研究所産学官連携交流会
ワークショップ"産学官連携への新たなアプローチ"
12月21日(月)13:00〜18:00
会場:東北大学片平さくらホール(仙台市青葉区)
http://www.tagen.tohoku.ac.jp/general/info/event/20151221/
■第15回東北大学多元物質科学研究所研究発表会
12月22日(火)11:00〜
会場:東北大学多元物質科学研究所
http://www.tagen.tohoku.ac.jp/general/info/event/meeting/2015/
■■■■■ 2016年 ■■■■■
■学術フォーラム「防災学術連携体の設立と東日本大震災の総合対応の継承」
1月9日(土)13:00〜17:30
場所:日本学術会議講堂
http://janet-dr.com
■公開講演会
「強靭で安全・安心な都市を支える地質地盤−あなたの足元は大丈夫?−」
主催:日本学術会議
日本地質学会 後援
1月23日(土)13:30〜17:30
場所:日本学術会議講堂
http://www.scj.go.jp/ja/event/index.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0144.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■JAMSTEC次世代海洋資源調査技術研究開発プロジェクトチーム(特任研究職/
特任技術研究職/特任技術職)公募(12/9)
■信州大学学術研究院理学系(地球学領域)助教公募(2/5)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質マンガ「GEOって !?」
──────────────────────────────────
「GEOって !?」
原案:土岐知弘 マンガ:Key
http://www.geosociety.jp/faq/content0057.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.327 「正・副会長候補者の意向調査」実施中(1/9締切)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.327 2015/12/15┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】「正・副会長候補者の意向調査」を実施中です(1/9締切)
【2】学術大会に関わるアンケート(1月末締切)
【3】2016年度会費払込のお知らせ
【4】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されます
【5】Island Arcが新しく変わります
【6】2017年度地震火山こどもサマースクール開催地候補募集
【7】第7回惑星地球フォトコンテスト:作品募集中
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「正・副会長候補者の意向調査」を実施中です(1/9締切)
─────────────────────────────────
詳しくは,
http://sub.geosociety.jp/members/content0026.html(要会員ログイン)
もしくは,お手元の郵便物(11月下旬発送済み)をご確認ください.
回答締切:2016年1月9日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】学術大会に関わるアンケート(1月末締切)
─────────────────────────────────
学術大会をよりよいものにするために,会員からの御意見を頂くアンケートを
地質学会ホームページにて実施しています.学術大会時のハイライト講演リス
ト,シンポジウム,巡検案内書に関するものです.特に「ハイライト」は,ぜ
ひ聞いて頂きたい講演を選び,ニュース誌や講演要旨集に掲載していますが,
その利用状況について御意見を頂きたいと思っています.また,本年の巡検案
内書は,地質学雑誌の原稿の減少のため,急遽,地質学雑誌に掲載されました.
これらについて,忌憚なき御意見を頂ければと思います.アンケートは簡単な
ものですので,ぜひ御回答ください.
(行事委員長 竹内 誠)
回答締切:2016年1月31日
アンケートの回答はこちらから→ http://goo.gl/forms/VMz31pTWNG
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2016年度会費払込のお知らせ
─────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下さいますよ
うお願いいたします.
■2016年度分会費の引き落とし日:12月24日(木)です.
請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下
さい.
■自動引き落とし以外の方(お振り込み)
12月中旬頃までに請求書兼郵便振替用紙をお送りいたします.折り返しご送金
くださいますようお願いいたします.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0164.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されます
─────────────────────────────────
募集期間:2015年12月21日〜2016 年2月12日
・推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
・名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
・そのほか候補となる条件:例えば,,,地質学への顕著な貢献/地質学会の
運営と発展への貢献/教育現場や企業などでの活動を通じた地質学の普及と振
興への貢献など
*上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することはできませ
んが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
(名誉会員推薦委員会 山本高司)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】Island Arcが新しく変わります
──────────────────────────────────
■2016年発行のVol. 25よりIsland Arcは隔月出版となります. これにより速
やかに受理済み論文が掲載されるようになります.
■日本語抄録の掲載:Wiley社のIsland Arcのホームページに,論文の日本語抄
録が掲載されます.
詳しい内容はこちらから(この他にも既に始まっている便利機能等もあります!)
http://www.geosociety.jp/publication/content0087.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】2017年度地震火山こどもサマースクール開催地候補募集
──────────────────────────────────
地震火山こどもサマースクールは,1999年夏から小・中・高校生を対象には
じまった行事で,現在,日本地震学会,日本火山学会,日本地質学会が共同で
実施する地球科学関連では最大規模の体験学習講座です.
このたびは,2017年度(2017年夏)に実施する第18回の開催地を公募致します.
[応募資格]
1.サマースクールの主旨に賛同し,現地事務局を設置できる団体.応募が採
択されたのち,三学会(地震・火山・地質学会)のスタッフと現地事務局で実
行委員会を結成.この実行委員会がサマースクールを実施します.
2.現地学校の夏休み期間中に,1泊2日の日程(土日が望ましい)で,サマー
スクールを実施できること.
3.こどもとスタッフの宿泊に供することができる宿泊施設を確保可能なこと.
募集期間:2016年1月12日〜2月12日
詳しくは,http://www.zisin.jp/modules/pico/index.php?content_id=3273
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】第7回惑星地球フォトコンテスト:作品募集中
──────────────────────────────────
ジオフォトの最高峰の写真コンテスト!今年も作品を募集いたします.
応募締切:2016年2月22日(月)
たくさんのご応募お待ちしています.
詳しくは,http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■関東支部功労賞募集
関東支部の顕彰制度に基づき2015年度も支部活動や地質学を通して社会貢献さ
れた個人・団体を顕彰いたします.
公募期間:2015年12月10日(木)〜2016年1月10日(日)
詳しくは,http://kanto.geosociety.jp/
[西日本支部]
■西日本支部平成27年度総会・第167回例会
日時:平成28(2016)年2月20日(土)9:00〜 例会終了後 懇親会
場所:熊本大学黒髪南キャンパス理学部2号館
講演申込締切:2月4日(木)17時
<お願い>総会に欠席される場合は,委任状をご提出下さい.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第181回地質汚染イブニングセミナー
12月18日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ902会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分
講師:楡井 久(国際地質科学連合(IUGS)GEM人工地層と地質汚染研究委員長・
NPO日本地質汚染審査機構理事長)
テーマ:国民生活に関わる人自不整合と人工地層について
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■■■■■ 2016年 ■■■■■
■新春緊急学術フォーラム「少子化・国際化の中の大学改革」
日本学術会議主催
1月7日(木)13:00〜17:55
場所:日本学術会議講堂
■学術フォーラム「防災学術連携体の設立と東日本大震災の総合対応の継承」
1月9日(土)13:00〜17:30
場所:日本学術会議講堂
http://janet-dr.com
■公開講演会
「強靭で安全・安心な都市を支える地質地盤−あなたの足元は大丈夫?−」
主催:日本学術会議
日本地質学会 後援
1月23日(土)13:30〜17:30
場所:日本学術会議講堂
http://www.scj.go.jp/ja/event/index.html
■第50回水環境学会(徳島)年会
3月16日(水)〜18日(金)
場所:アスティとくしま(徳島市山城町)
参加申込:2月18日(木)締切
https://www.jswe.or.jp/event/lectures/2015.html
■日本地球惑星連合2016年大会
5月22日(日)〜26日(木)
会場:幕張メッセ 国際会議場
投稿開始: 1月7日(木)
早期締切: 2月3日(水) 24:00
最終締切: 2月18日(木)12:00
http://www.jpgu.org/meeting_2016/index.htm
■Goldschmidt2016
日本地質学会 共催
6月26日(日)〜7月1日(金)
会場:パシフィコ横浜
要旨受付:1月1日(金)〜2月26日(金)
http://goldschmidt.info/2016/index
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0144.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■東北大学大学院理学研究科地学専攻教授公募(2/26)
■第47回(平成28年度)三菱財団自然科学研究助成 (1/5-2/2)
■「消防防災科学技術研究推進制度」平成28年度研究開発課題の募集(2/5)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
「日本地方地質誌」完結と「The Geology of Japan」出版
「日本地方地質誌」完結と「The Geology of Japan」出版:日本地質学発展のランドマーク
石渡 明・井龍康文・ウォリス サイモン
地質学の研究者や学生が,日本のある地域の地質を少し詳しく知ろうと思った時,最初に手に取る書物はその地方の地質誌である.また,ある外国の地質を知ろうと思えば,まずその国の地質誌に目を通すことになる.2016年度中に日本地質学会(以下「本学会」)編,朝倉書店発行の「日本地方地質誌」が全巻完結予定,また英国地質学会(The Geological Society of London)から「The Geology of Japan」が刊行予定である.ここでは地方地質誌の歴史と現状を略述して,その意義を明らかにしたい.
日本最初の本格的な地方地質誌は,明治〜大正の1903〜1915年に博文館が刊行した山崎直方・佐藤伝蔵編著の「大日本地誌」全10巻(小林, 1981; 荒井, 1986)である.ちょうど100年前に完結したこのシリーズは,9. 北海道(千島・南樺太を含む,数字は巻番号),2. 奥羽(東北),1. 関東,3. 中部,5. 北陸(福井・石川・富山・新潟),4. 近畿,6. 中国,7. 四国,8. 九州,10. 琉球及び台湾からなり,1910年に併合された韓国(朝鮮)は含まない(日本語による朝鮮の地質誌には立岩(1976)がある).編著者両氏は本学会会長も務めた地質学者であり,各巻には必ず地質の章があって色刷り地質図が付属している.博文館の宣伝文には,「欧州における最新の体式に鑑み全く在来の地誌とその目的方針を異にし」,「彼の乾燥無趣味なる偏狭の地理書と同一視すべからざるを要す」とあり,かなり気合が入っている.数人の文学士や小説家の田山花袋が編集執筆陣に入っていた.例えば,近畿は1256ページと本シリーズ最大で,第一編地文は第一章地形,第二章海洋並に海岸線,第三章地質,第四章気象からなり,次の第二編人文は第一章沿革(歴史),第二章政治宗教,第三章産業,そして第三編地方誌は各府県別の詳細を説く.この巻の序文には「今の大阪平野の一角は,皇祖東征の日,其の御船を寄せ給ひし地なり」という一文があって,この書の雰囲気をよく示している.地質の章は一.汎論,二.始原大統(片麻岩系,晶質剥岩系(今の領家帯と三波川帯)),三.古生大統,四.中生大統,五.新生大統,六.噴出岩(深成岩を含む),七.温泉からなる.他の巻も同様の構成になっているが,奥羽は地形の章の火山の記述が詳しく,「近時における重要な地変」という項目を設けて1894年の庄内(酒田)地震,1896年の陸羽地震,そして同年の三陸海嘯(大津波)について詳しく記述している.地質の章で特に目を引くのは,阿武隈山地の変成岩類の上部(御齋所統と竹貫統)をヒューロニア系(下部原生界),下部をローレンシア系(始生界)としていることである.中部も1891年濃尾地震の記述に5ページを割き,台湾も8ページにわたって同地の地震について記述している.また,北海道にはほぼ実物大のアンモナイトの精密な銅版画が3葉付属している.明治時代後期の各都市の正確な地図や重要施設,景勝地,民俗などの写真が多数添付されていて,非常に資料価値の高い書籍である.このシリーズ各巻の価格は2.5〜3.5円(送料15銭)だった.これは,「地質学の発展を反映して自然地理を中心に詳しい研究成果が盛り込まれ」,「欧米の地誌の編纂順序を参照して自然から人文へと項目がならべられ」,「地誌の定義を地人関係の『関係の説明』と自覚している」(荒井, 1986),当時の世界水準の地誌学書であった.小林(1981)は「大正後期に高校生(旧制)であった私には本書は山歩きや旅行のための大事な参考書であった」と述べている.戦前も戦後も「地誌」と名の付く書物は何種類も刊行されたが,充実した地質の記述があるのはこのシリーズのみである.
余談であるが,さらに古い「皇国地誌」という幻の書物がある.これは明治初期の廃藩置県(1871年)直後の1872年に太政官布告288号によって各県の担当者に調査・執筆させたものであるが,結局1冊も出版されず,その原稿は1923年の関東大震災で焼失してしまったという悲劇的な書物である.しかし,いくつかの府県にその原稿の写しや草稿段階のものが残っており,当時の社会・経済を知る上で貴重な資料になっている(荒井, 1986; 長島, 2008).なお,「大日本地誌大系」というシリーズもあるが,これは江戸時代に幕府が編集した奈良・平安時代からの風土記などの書物を明治以後に活字出版したものである.
さて,現在書店で購入できる日本の地方地質誌には,共立出版と朝倉書店の2つのシリーズがある.共立の「日本の地質」シリーズは1986〜1992年に出版され,北海道から九州(九州は沖縄を含む.中部地方はI東部とII西部に2分,各巻9000円+税)の9巻(+総索引1巻,7000円+税)が完結していて,2005年に全国の新しい情報をまとめた増補版1冊(文献リストのCD-ROM付,13000円+税)も出ている.このシリーズは地質情報を網羅的に記述しており,ある地域の地質概要や地層名,主要文献等を辞書的に調べるのに便利である.増補版は,1995年兵庫県南部地震や2004年新潟県中越地震など近年の地質災害の詳しい記述がある一方,中国地方の中・古生界の新知見の記述がない等,やや不揃いがある.
朝倉の「日本地方地質誌」シリーズは,その地方の地質をある考え方で系統的,理論的に説明しようという志向が強く,過去には1冊の地方地質誌を一人の著者が執筆したものもあった.このシリーズは過去3回出版されている.一回目は戦後間もない1950年からの5年間に東北〜四国の6巻が出版され,1962年にそれらの増補版と九州が出たが,結局北海道が出版されずシリーズは完結しなかった.ただし,一回目のシリーズには小林貞一による総論(副題は「日本の起源と佐川輪廻」,この書は彼の1941年東大紀要英語論文の和訳で,欧州アルプス流のナップの水平移動を含む地向斜論を展開)がある.彼は中国と四国もそれぞれ単著で執筆していて,各巻頭に彼の恩師(小沢儀明と江原眞伍)への献辞がある.近畿の巻頭にも著者松下進の恩師中村新太郎への献辞がある.一方,槇山次郎は中部の序文で「先進国の地質誌が,鉄筋コンクリートのように堅固に構築されているのに比べて,(日本のは)危っかしい気がする」と述べている.二回目は近畿(1971),中部(1975),関東(1980),中国(1984)の改訂版が出たが,やはり完結しなかった.小林(1981)は前年の関東改訂版の出版を,同書旧版(藤本治義著,関東山地のナップ構造,長瀞(三波川・みかぶ)系ジュラ紀説など,今読んでも興味深い)の愛読者として祝い,この時点までの地方地質誌の沿革表をまとめている.三回目は本学会の編集で中部(2006, 写真や地質図等のCD-ROM付),関東(2008),近畿,中国(2009),九州・沖縄,北海道(2010)が既に出版され,2016年度中に四国と東北が出て,三回目にして初めて全8巻のシリーズが完結する見込みである.これら三回のシリーズ各巻の価格表示を見ると時代の変化がわかる.一回目は350〜520円,二回目は3500〜9800円,三回目は22000〜26000円+税である.
現時点で世界に示す日本の地質の総論としては,本学会と学術交流協定を結んでいる英国地質学会から今年4月,我々日本の地質研究者陣が執筆したThe Geology of Japanが出版される運びになっている.このシリーズは英国(北部と中南部の2冊),スペイン,チリ,中欧(ドイツとその隣接国,古生代以前と中生代以後の2冊),タイが既刊であり,これらと読み比べて論評すると面白いだろう.戦後に出版された英語で日本の地質を紹介する書物には,The Geologic Development of Japanese Islands(築地書館1965),Geology and Mineral Resources of Japan(第3版, 地質調査所1977, 第1版1956, 第2版1960),Geology of Japan(テラパブ・Kluwer, 1991, 岩波講座地球科学15「日本の地質」(1980)の英訳),Geology of Japan(東大出版会, 1991, 旧版は1962)の4種類がある.なお,最近の日本列島地質構造発達史に関するコンパクトな総論としてはIsozaki et al. (2010)やWakita (2013)がある.今世紀に出版された日本地方地質誌とThe Geology of Japanはプレート論と付加体地質学に立脚するが,1980〜1990年頃の本は地向斜論からプレート論への過渡期の学界状況を反映している.プレート論確立前の1965年のThe Geologic Development…は地殻の水平運動を認めない地向斜論など独特な考えに基づいており,海外で評判になったが(市川ほか1970序文),「あたらしい事実は,ほとんどとり入れていない」などの声もあった(地学団体研究会1966, p. 31, 94).
実際に現場で,ある地域の地質を観察しようと思えば,地質ガイドブック(地学巡検案内書)の類が必要になる.一般向けの案内書として,コロナ社(旧名森重出版)の「○○県地学のガイド」シリーズと築地書館の「日曜の地学 ○○の自然をたずねて」(旧版は「地質をめぐって」)シリーズが出ている(表1).これらが未刊の北海道は,北大図書刊行会から「○○の自然を歩く」シリーズが出ており,京都,大阪,兵庫,奈良,高知,長崎,大分などでも地元の教育界や大学の有志が案内書を出版している.この他,化石,鉱物,火山,断層・褶曲等に特化した地域別ガイドや全国の見所をまとめたものもある(表1の後半).しかし,宮沢賢治の地元の岩手県,南方熊楠や「稲むらの火」の地元の和歌山県などは,意外にもやや手薄に感じる.どの都道府県でも,20年も経てば交通事情や露頭の状況が変化し,新発見や新学説も出てくるので,定期的な書き換えが必要であろう.地元の関係者のご尽力を期待したい.これらは普及的・実用的な地方地質誌と言うべきもので,その利用価値は重厚な地質誌に勝るとも劣らない.現場に即した詳細な案内は地質研究者にも有用である.
一方,地質図幅とその説明書は,地方地質誌の基礎データであるとともに,それ自身がその図幅範囲の地質誌でもある.地質図は国土基本図の1つであり,その整備は文明国として必須であるが,日本では20万分の1地質図が全国をカバーしていて,ウェブでも閲覧できるものの,5万分の1地質図の整備は遅れていて,全国1248図幅のうち648図幅(52%)程度しかカバーしていない.担当機関の皆様には図幅調査の一層の推進をお願いしたい.調査方法の現代化(客観化・数値化)も急務だと思う.各県の地質図にも詳しい説明書付きのものがあり(青森,群馬,新潟,富山,石川,福井,静岡,滋賀,香川,愛媛,鹿児島など),岐阜県地質図とその解説はウェブサイト「ジオランドぎふ」で閲覧できる.
日本地質学会創立125周年を目前に控え,本学会による「県の石」(岩石,鉱物,化石)の選定が進行中であり,国内のジオパークの飛躍的な発展,東日本大震災で返上した地学オリンピックの日本開催が実現しつつある.ここに本学会編の日本地方地質誌の完結とThe Geology of Japanの出版が加われば,現在の日本地質学の実力を国の内外に示すことになろう.これらの執筆・編集・出版に努力された方々に敬意を表する.これらによって地質学が広く国民に普及され,日本地質学のすばらしさが世界で認識され,日本地質学及び地質関連産業の更なる振興につながることを心から願う.国内全ての自治体や高校・大学の図書館が地方地質誌や巡検案内書を置くようになればよいと思う.拙稿に改善意見を寄せられた池田保夫・棚瀬充史・辻森 樹会員に感謝する.
引用文献
荒井由美, 1986, 日本近代地誌学の発展からみた地誌学の特性に関する一考察(短報).お茶の水地理, http://hdl.handle.net/10083/11688
地学団体研究会, 1966, 科学運動. 築地書館.
市川浩一郎・藤田至則・島津光夫編, 1970, 日本列島地質構造発達史. 築地書館.
Isozaki, Y., Aoki, K., Nakama, T. and Yanai, S., 2010, New insight into a subduction-related orogen: A reappraisal of the geotectonic framework and evolution of the Japanese Islands. Gondwana Research, 18, 82-105.
小林貞一, 1981, 関東の地質誌改訂版と日本地方地質の沿革.地学雑, 90(4), 278-282.
長島雄毅, 2008, 『皇国地誌』を通してみた明治前期の京都と周辺地域の結合関係.立命館地理学, 20, 43-56.
立岩 巌, 1976, 朝鮮―日本列島地帯地質構造論考−朝鮮地質調査研究史.東京大学出版会.654p.
Wakita, K., 2013, Geology and tectonics of Japanese islands: A review: The key to understanding the geology of Asia. Journal of Asian Earth Science, 72, 75-87.
表1.全国各県地学巡検案内書一覧(著者名省略,コロナ・築地の出版社名は適宜省略)
北海道 北海道大学図書刊行会「○○の自然を歩く」シリーズ:札幌(道央)(第3版)2011,道南2002,道北1995,2000,空知1986,1997,十勝2000,道東1999
青森の自然をたずねて2003(旧版 太平洋側・日本海側をめぐって各1975)
岩手県内化石めぐり(岩手県博)1987
秋田県地学のガイド(男鹿半島をめぐって)1986,1994
宮城の自然をたずねて1991,宮城県の地質案内(県地学部会,宝文堂)1975
山形の地質をめぐって1984,山形県地学のガイド2010
福島県地学のガイド1984,福島の大地の生い立ち(歴史春秋社)2004
茨城県地学のガイド1977,1982,茨城の自然をたずねて1994
栃木の自然をたずねて1997(旧版1979)
群馬の自然をたずねて1998(旧版1978,1984),群馬のおいたちをたずねて(上・下,上毛新聞1977)
千葉県地学のガイド1974,1987,2000,続1982,千葉の自然をたずねて1992,房総半島の地学散歩第1巻2008,第2巻2009
埼玉の自然をたずねて1987,2012(旧版1968),埼玉県地学のガイド2000
東京の自然をたずねて1989,1998(旧版1977),東京都地学のガイド1980,1997,東京の自然史(講談社)2011,化石採集の旅 関東(築地1964),
神奈川県地学のガイド1971,新版2003,神奈川の自然をたずねて1992,2003,自然見学ガイド神奈川県の自然(野村出版1973)
山梨の自然をめぐって1984,山梨県地学のガイド1987
新潟県地学のガイド(上1990・下1995),新潟地学ハイキング(地団研高田支部)1978
長野県地学のガイド1979,2001 信州の地質めぐり(地団研松本支部)1995,長野県地学図鑑(信州地学教育研,信濃毎日新聞社)1980
富山 北陸の自然をたずねて2001(旧版1979),大地の記憶 富山の自然史(桂書房)2000, 富山のジオロジー 富山の大地の成り立ちを探る(シー・エー・ピー)1997
石川 北陸の自然をたずねて2001,石川の地形・地質案内(東京法令出版)1985
福井 北陸の自然をたずねて2001,福井県の自然(県教育研)1976,ふくい地質景観百選(福井市自然史博)2009
静岡の自然をたずねて2005(旧版1981),えんそくの地学(県地学会,黒船出版)1983, 東海自然歩道の地学案内(県地学会, 黒船印刷)1976,静岡県地学のガイド1992,2010
愛知県地学のガイド1978,2000,東海の自然をたずねて1997
岐阜の地質をめぐって1980,東海の自然をたずねて1997
三重県地学のガイド1979,東海の自然をたずねて1997
滋賀県地学のガイド1980,改訂版(上・下)2002
京都 新京都五億年の旅(地団研京都支部,法律文化社)1990(旧版1976),京都地学ガイ
ド1978(同社)
大阪 自然史ハイキング(地団研大阪支部)1987,大地のおいたち1999,関西地学の旅(ドライブ関西1995,街道と活断層を行く2001,化石探し2010,街道散歩2013,大阪地域地学研究会,東方出版)
兵庫 ひょうごの地形・地質・自然景観(神戸新聞)1998,大地のおいたち1999
奈良 地学ガイド奈良(地団研京都支部奈良班)1987,大地のおいたち1999
和歌山 大地のおいたち 神戸・大阪・奈良・和歌山の自然と人類(地団研大阪支部, 築地)1999
鳥取の自然をたずねて1997,山陰地学ハイキング(築地)1976
島根の自然をたずねて1998,山陰地学ハイキング(築地)1976
岡山県地学のガイド1980,2013,原色図鑑 岡山の地学(山陽新聞)1982
広島の地質をめぐって1979,増補版1990,広島県地学のガイド1979,2000
山口県地学のガイド1984,山口県の岩石図鑑(山口地学会, 第一学習社)1991
香川県地学のガイド1979
徳島県地学のガイド2001
愛媛の自然をたずねて1988,1997,愛媛県地学のガイド1987
高知 最新・高知の地質 大地が動く物語(南の風社)2012
福岡県地学のガイド2004
佐賀の自然をたずねて1995
長崎県の地学(県地学会)1971
大分県地学の散歩(県地学部会)1983
熊本の自然をたずねて2009,人類以前の熊本 郷土の地質(熊本日日新聞)1964
宮崎県地学のガイド1979,宮崎県の地質フィールドガイド(宮崎地質研究会,コロナ)2013
鹿児島県地学のガイド(上・下)1991
沖縄の島じまをめぐって(沖縄地学会,築地)1982,沖縄の自然 その生いたちを訪ねて(平凡社)1975
全国 日本列島地学散歩,北海道・東北・北関東編1977,南関東・中部編1977,近畿・中国編1978,九州・四国編1977(平凡社カラー新書),日本列島石の旅 東日本編1979, 中部日本編1981(玉川選書,読み物として優れる),日本列島ロマンの旅 景勝・奇岩地学探訪(東洋館1998),日本列島ジオサイト地質百選(オーム社2007),日本列島―地学の旅(和英両語,愛智出版2008),新版日本列島の20億年景観50選(岩波 2009),日本の地形・地質(文一総合出版2012,本学会推薦,同題の応用地質系の本もある:鹿島出版会2001)
火山 フィールドガイド日本の火山(築地,北海道1998,東北1999,関東・甲信越I・II 1998,中部・近畿・中国2000,九州1999),日本の火山図鑑(誠文堂新光社2015)
断層・褶曲等 日本の地質構造100選(本学会構造地質部会編,朝倉2012)
鉱物採集の旅(築地, 1972〜1982頃,北海道1, 2,東北1, 2,関東周辺,信越,近畿1, 2,四国・瀬戸内,九州),日本の岩石と鉱物(和英両語,地質調査所編,東海大出版会1992)
化石 日本の化石(小学館1983),日本全国化石採集の旅(築地1994,続編1996,完結編1998)
地質マンガ 空から見れば
空から見れば
作画 Key 作 chiyodite
【geo-Flash】No.328 平成28年(2016年)第1号!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.328 2016/1/5┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】年頭にあたって(会長 井龍康文)
【2】高レベル放射性廃棄物の最終処分場に関する説明会(1/23)
【3】高等学校理科用『地学』教科書の記述内容に関する意見書
【4】「正・副会長候補者の意向調査」を実施中です(1/9締切)
【5】学術大会に関わるアンケート
【6】名誉会員の推薦が開始されました
【7】第7回惑星地球フォトコンテスト:作品募集中
【8】「日本地方地質誌」完結と「The Geology of Japan」出版
【9】本の紹介 ネパールに学校をつくる:協力隊OBの教育支援35年
【10】支部情報
【11】その他のお知らせ
【12】公募情報・各賞助成情報等
【13】地質マンガ「空から見れば」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】年頭にあたって
─────────────────────────────────
会長 井龍康文
2016(平成28)年の年頭に当たり,日本地質学会理事会を代表して,会員の皆
様にごあいさつを申し上げます.ここでは,1年間の本学会の活動を総括し,
今後の活動方針を示したいと思います.私の任期も半年を切りましたが,最後
まで,一つでも多くの案件がこなせるよう,尽力して参りたいと思っておりま
す.
全文は,こちらから
http://www.geosociety.jp/outline/content0147.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】高レベル放射性廃棄物の最終処分場に関する説明会(1/23)
─────────────────────────────────
国は平成25年より,高レベル放射性廃棄物の最終処分場について,科学的有望
地の要件・基準に関する地層処分技術WGでの検討を重ねてきており,今回標記
の中間報告が公開されました.日本地質学会からは渡部芳夫副会長が学会推薦
委員として参加しており,このたび同WGならびに資源エネルギー庁より、関連
学会に情報提供を行い,専門家間における情報の共有に資すると共に,学術的
知見に基づく意見を求めたいとの要請を受けました.
これを受けて本学会としては,理事会並びに以下の9専門部会に代表出席者の参
加を依頼し,1月23日に学会が説明を受けることといたしました.そこでは,専
門部会という単位での質疑を経て持ち帰り,それぞれの部会で意見を集約して
頂く予定ですので,出席者は限定しております.
一方では,このような課題に対して広く学会員への情報共有と意見集約は行う
べきであるため,下記の9専門部会の部会員以外の方,あるいは部会経由での
やり取りが困難な方にも情報を事前に提供し,お考えを頂く事といたします.
◎ 次の9専門部会に参加を依頼しました
地域地質,岩石,第四紀地質,火山,構造地質,応用地質,環境地質,
海洋地質,堆積地質
◎ 説明会での対象となる報告書「科学的有望地の要件・基準に関する地層処
分技術 WG における中間整理」は以下のサイトです.
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/genshiryoku/
chisou_shobun_wg/pdf/report002_01_00.pdf
◎ 1月23日の説明会で質疑に出して欲しいご質問については,事前に部会幹事
へご連絡下さい.
個別にご意見を出されたい場合には,学会事務局へお送り下さい.執行理事会
が説明会で確認を取れるものについては提示いたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】高等学校理科用『地学』教科書の記述内容に関する意見書
─────────────────────────────────
日本地質学会は、現在の高等学校における地学関連科目の履修率の低さについ
て大いに危機感を持っており、学術団体として地学教育の普及に取り組んでい
るところです。この度、その取り組みの一環として、啓林館および数研出版の
2社から発行されている高等学校理科用『地学』教科書の記述内容のうち、地
質学に関わる部分を学術的に点検し、意見を集約しました。そして、その結果
を各出版社へ送付し,あわせて,文部科学省にも送付しました。
意見書の全文は,こちら(要会員ログイン)
http://www.geosociety.jp/engineer/content0041.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】「正・副会長候補者の意向調査」を実施中です(1/9締切)
─────────────────────────────────
回答締切:2016年1月9日
詳しくは、http://sub.geosociety.jp/members/content0026.html(要会員ログイン)
もしくは,お手元の郵便物(11月下旬発送済み)をご確認ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】学術大会に関わるアンケート
─────────────────────────────────
学術大会をよりよいものにするために,会員からの御意見を頂くアンケートを
地質学会ホームページにて実施しています.学術大会時のハイライト講演リス
ト,シンポジウム,巡検案内書に関するものです.特に「ハイライト」は,ぜ
ひ聞いて頂きたい講演を選び,ニュース誌や講演要旨集に掲載していますが,
その利用状況について御意見を頂きたいと思っています.また,本年の巡検案
内書は,地質学雑誌の原稿の減少のため,急遽,地質学雑誌に掲載されました.
これらについて,忌憚なき御意見を頂ければと思います.アンケートは簡単な
ものですので,ぜひ御回答ください.
(行事委員長 竹内 誠)
回答締切:2016年1月31日
アンケートの回答はこちらから→ http://goo.gl/forms/VMz31pTWNG
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】名誉会員の推薦が開始されました
─────────────────────────────────
募集期間:2015年12月21日〜2016年2月12日
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:
例えば,,,地質学への顕著な貢献/地質学会の運営と発展への貢献/
教育現場や企業などでの活動を通じた地質学の普及と振興への貢献など
*上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することはできませ
んが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
(名誉会員推薦委員会 山本高司)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】第7回惑星地球フォトコンテスト:作品募集中
──────────────────────────────────
ジオフォトの最高峰の写真コンテスト!今年も作品を募集いたします.
応募締切:2016年2月22日(月)
たくさんのご応募お待ちしています.
詳しくは,http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】コラム「日本地方地質誌」完結と「The Geology of Japan」出版
──────────────────────────────────
石渡 明・井龍康文・ウォリス サイモン
地質学の研究者や学生が,日本のある地域の地質を少し詳しく知ろうと思った
時,最初に手に取る書物はその地方の地質誌である.また,ある外国の地質を
知ろうと思えば,まずその国の地質誌に目を通すことになる.2016年度中に日
本地質学会(以下「本学会」)編,朝倉書店発行の「日本地方地質誌」が全巻
完結予定,また英国地質学会(The Geological Society of London)から「
The Geology of Japan」が刊行予定である.ここでは地方地質誌の歴史と現状
を略述して,その意義を明らかにしたい.
全文はこちら、、、http://www.geosociety.jp/faq/content0620.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】本の紹介 ネパールに学校をつくる:協力隊OBの教育支援35年
──────────────────────────────────
酒井治孝 著
東海大学出版部,2015年12月10日発行,A5変判,154頁,定価1600円+税,
ISBN 978-4-486-02086-8
本書は,いわゆる奮戦記,旅行記のたぐいではない.著者が一生をかけてきた,
研究・教育事業の神髄が語られている,強いメッセージである.
著者は,1980年から3年間,大学院生時代に,当時まだ発足して間もない日本
政府の海外支援事業の一環である青年海外協力隊員として,ネパールに派遣さ
れた.専門である地質学を,当時ネパール唯一の国立大学であったトリブバン
大学の大学院生に講義と実験,野外実習を通じて教えるためであった.雨季と
乾季で一年が二分されるヒマラヤの盆地にあるカトマンズの大学での授業のか
たわら,乾季には,ヒマラヤ研究では鍵となるべきレッサーヒマラヤでも,ほ
とんど研究が進んでいなかったかなり離れた地域の野外調査を行った.それら
の研究に基づいて帰国後は九州大学から博士の学位を取得し,その教養部の教
官になり,さらに京都大学に転身して,現在に至っている.その間,さまざま
な苦労をして,現地に5つの学校校舎(様々な種類,小学校,中等高等学校,ま
た大学の分校までも)を建て,さらに奨学金を給付してきた.それだけでも一
般にたやすいことではないが,しかし,本書は,そうしたことを行ってきて,
ついには学成り功遂げた,というサクセスストリーでもない.(もちろん,そ
の間の調査や,その後現在までに継続的に行ってきた研究による,著者のネパー
ルヒマラヤの層序,構造,テクトニクスの研究は,国際的にも高く評価されて
いるが(科学,Vol. 85,No. 10, p. 956-962 (2015年10月号,岩波書店)の論文
参照).また,大学教科書(「地球学入門」東海大学出版部)やTVへの出演な
どを通して,全国の学生,国民などに大きな影響を与えてきたことも知られて
いるが.).
本書は,副題にもある通り,実に35年にわたる教育支援の話が中心となって
いる.学校校舎建設の経緯が詳しく述べられている第1,2部,学生野外実習のあ
りさまと奨学金給付についての第3部,そして2015年4,5月のネパール地震と校
舎再建計画の第4部,さらに交流を通じての「忘れえぬ人々」紹介の第5部から
なっている.また,ネパールの地質的景色や著者のフィールドノートのマッピ
ングの一例や,現地の大学教官や役人の方々,日本からの訪問者の方々(寄付
金の拠出者でもある)の記念写真のほかに,著者の言う「輝いた目を持った現
地の方々」の豊富なカラー写真などが口絵に示されている.
ネパールとの交流では,著者の持って生まれた性格を最大限引き出したさま
ざまな「力」が発揮されたことが分かる.理想の実現に向けた血のにじみ出る
ような努力があったことが分かる.その随所に,本人の透徹した分析力と総合
力,人間と社会を見る的確な洞察力,機に応じて敏な決断力と実行力が発揮さ
れた.しかし,そうした個人の力だけで,ものはうまくいくとは限らない.妨
げるものは現実である.著者は,おそらく若さとパワーで,現実を乗り切った
のだろうと,我々は初めは思う.でも,そこに見られるのは,周囲の人々との
根気のいる議論と,自己の信念の説得,さらに交流から生まれた奇特者からの
援助であった.
現地では,外国人であることの縛り,国柄や政治状況や民族性の違い(民族
としてはモンゴル系とインド系,またカースト制度などの微妙な問題)もあっ
た.困難な問題が山積していたはずである.そこをいかに乗り切ったかは,本
書のいたるところに語られているが,読者を引き付けるのは,そうした転機ご
との筆者の信念の発揮どころである.現地の人々に溶け込み,互いに理解しあ
い,尊敬し,敬愛される.現地語を通訳できるまでに学び,しかも,決してあ
きらめないというこの信念は,強靭な体力と忍耐力によって支えられたと思わ
れる.1980年代は,若者の,何でも見てやろう,という各地への放浪や冒険・
探検がまだ全盛だった頃である.そうした経験を持つ中高年の読者の方も多い
だろう.経験を積んだものには,それが帰国後に,自己の内面の精神的財産と
なって深くしみ込んでいく.著者は,しかし,若い時代の経験を,単に思い出
だけにとどまらせることなく,次の一手を打っていく.
圧巻は,その後著者が,その人間性から来るのであろうが,粘り強い説得と,
交流によってはぐくまれた相互信頼を得,現地での募金と敷地の提供,日本の
篤志家のまさにポケットマニーの拠出を引き出し,それを契機として,教育に
欠かせない災害に強い学校を作る,という夢を次々に実現してゆく,というと
ころにある.その最初の目的は,大学生の地質教育に欠かせない,現地野外実
習の宿泊施設の確保にあった,と述べられている,どこの国でもあるこの事情
を,ヒマラヤで実現したのである.完成した校舎を使って,実に1000人を超え
る学生の野外実習が行なわれて来たとのことである.現地の学生・教師のため
の地質調査案内書までも自らの調査研究に基づいて作ったのである.さらに,
こうして整えられた教育環境のもとで,現地の若者の上級校への入学率は格段
と向上したという.その中からさらに高い教育を受けて,大学を卒業し,立派
な社会人となって巣立っていく若者を見るくだりは,まさに胸を打つ.そこに
は,単に資金援助で箱ものを作った,というありきたりのものをはるかに超え
る,精神的・人間的な援助と交流があったことが分かる.それは,本書の冒頭
に述べられている「教育ほど重要なものはない」,との一語の実現である.そ
こに,著者の,一般の立身出世からは完全に離れた人類愛を見ることができる.
この書の読者諸氏は,著者とは,「地質学」,「研究」,「教育」あるいは「
行政」などの共通した分野を見るであろう.しかし,私は,自分が類似の分野
に属しながらも,彼には全くの別世界での別人格を見る思いがする.感動のあ
まり,天を見上げるだけである.
これらの分野に少しでも関心があると思われる方に,本書を強く推薦する次
第である.なお,蛇足であるが,本書を読んだあと,著者は,19世紀の偉大な
ナチュラリスト,デイビッド・ヘンリー・ソーローと重なる部分が多いことに
気が付いた.自然とともに生きる人間が,「周囲のかかわりのあるべき人間と
社会に,では,自分は何をなすべきか?」との問いを自ら発し,それに人生を
ささげてきた,ということである.
(小川勇二郎)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■関東支部功労賞募集
関東支部の顕彰制度に基づき2015年度も支部活動や地質学を通して社会貢献さ
れた個人・団体を顕彰いたします.
公募締切:2016年1月10日(日)
詳しくは,http://kanto.geosociety.jp/
[西日本支部]
■西日本支部平成27年度総会・第167回例会
日時:平成28年2月20日(土)9:00〜 例会終了後 懇親会
場所:熊本大学黒髪南キャンパス理学部2号館
講演申込締切:2月4日(木)17時
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■国際地学オリンピック三重大会 運営委員会ニュース(12月)
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/name/olymp/kokusai_chiori_news_2015.12.pdf
■北海道立総合研究機構 地質研究所ニュース(2015.12.21発行)
http://www.hro.or.jp/list/environmental/research/gsh/publication/gshnews/gshnews02/vol31_no3.pdf
■学術フォーラム「防災学術連携体の設立と東日本大震災の総合対応の継承」
1月9日(土)13:00〜17:30
場所:日本学術会議講堂
http://janet-dr.com
■公開講演会
「強靭で安全・安心な都市を支える地質地盤−あなたの足元は大丈夫?−」
主催:日本学術会議
日本地質学会 後援
1月23日(土)13:30〜17:30
場所:日本学術会議講堂
http://www.scj.go.jp/ja/event/index.html
■第182回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
1月29日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ902会議室
講師:宮澤 博(環境地水技術研究会理事長)
テーマ:「土壌への雨水浸透」と宅地開発・インフラストラクチュアーへの提言
会費:会員、地質学会会員は500円、非会員は1,000円
■日本堆積学会2016年福岡大会
3月4日(金)〜8日(火)
会場:福岡大学理学部
http://sediment.jp/04nennkai/2016/annai.html
■平成27年度Project A in 奄美大島
3月4日(金)〜8日(火)(7・8日:巡検)
場所:奄美大島・瀬戸内町物産館(鹿児島市金生町2-18)
発表申込締切:2月5日(金)
http://archean.jp/
■日本地球惑星連合2016年大会
5月22日(日)〜26日(木)
会場:幕張メッセ 国際会議場
投稿開始: 1月7日(木)
早期締切: 2月3日(水) 24:00
最終締切: 2月18日(木)12:00
http://www.jpgu.org/meeting_2016/index.htm
■地質学史懇話会
6月19日(日)13:00〜17:00
場所:北とぴあ8階805号室
吉岡有文:日本の科学教育映画の世界:太田仁吉と科学教育映画の曙(仮)
宇井忠英:過去の事例に学ぶ噴火のリスク(仮)
問い合わせ:矢島道子
■Goldschmidt 2016(日本地質学会 共催)
6月26日(日)〜7月1日(金)
会場:パシフィコ横浜
要旨受付:1月1日(金)〜2月26日(金)
http://goldschmidt.info/2016/index
■第35回万国地質学会議
8月27日(土)〜9月4日(日)
会場:南アフリカ共和国ケープタウン
要旨締切:2016年1月31日
http://www.35igc.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0151.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■産総研ポスドク(イノベーションスクール生)公募(1/15)※1/7公募説明会
■産総研第一号契約職員PD(地質情報研究部門)公募(1/28)
■鳥取県職員採用試験(学芸員:地学担当)(受付締切 1/20)
■JAMSTEC地震津波海域観測研究開発センター公募(1/8, 2/9)
■大阪市立大学大学院理学研究科・理学部地球学教室特任講師(2名)の募集(2/1)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】地質マンガ「空から見れば」
──────────────────────────────────
作画 Key 作 chiyodite
http://www.geosociety.jp/faq/content0621.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
地質マンガ「地質マンガの宿題」
地質マンガ「地質マンガの宿題」
作画 Key 作 chiyodite
【geo-Flash】No.329 会長・副会長立候補意思表明者にたいする意向調査結果報告
【geo-Flash】No.329 会長・副会長立候補意思表明者にたいする意向調査結果報告
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.329 2016/1/19┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】会長・副会長立候補意思表明者にたいする意向調査結果報告
【2】第123年学術大会(2016東京・桜上水大会)開催通知
【3】学術大会に関わるアンケート
【4】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(木)
【5】名誉会員の推薦が開始されました
【6】第7回惑星地球フォトコンテスト:作品募集中
【7】 IGCP608「白亜紀アジア−西太平洋生態系」第4回国際研究集会First
Circular 配布開始
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
【11】地質マンガ「地質マンガの宿題」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】会長・副会長立候補意思表明者にたいする意向調査結果報告
─────────────────────────────────
2016年1月13日
一般社団法人日本地質学会
選挙管理委員会委員長 金澤 直人
開票立会人 巌谷 敏光
開票立会人 村上 瑞季
選挙規則ならびに選挙細則に基づき,標記意向調査を実施いたしました.
法人の代表理事は法律により,理事会において選任することが定められていま
す.学会の代表理事となる会長およびその補佐役の副会長を選出するにあたり,
会員の皆様の意向を伺うためにこの調査を行いました
詳しくは,こちら http://sub.geosociety.jp/members/content0092.html
(会員番号・パスワードによるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第123年学術大会(2016東京・桜上水大会)開催通知
─────────────────────────────────
日本地質学会は,関東支部の支援のもと東京都世田谷区の日本大学文理学部キャ
ンパスにて,第123年学術大会(2016年東京・桜上水大会)を「ジオハザードと
都市地質学」というテーマで9月10日(土)から12日(月)に開催いたします.
「第123年学術大会(2016東京・桜上水大会)」
2016年9月10日(土)〜12日(月)
会場:日本大学文理学部(東京都世田谷区桜上水)
★ トピックセッション募集:3月14日(月)締切
★ 東京・桜上水大会に向けてのスケジュール(発表申込締切:6月29日です)
★ 優秀ポスター賞がエントリー制になります
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0069.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】中間報告:学術大会アンケート(今月末締切!)
─────────────────────────────────
学術大会をよりよいものにするためにアンケートを実施しています.
現在までの集計状況を簡単にお知らせします.
○「ハイライト」は役立ってますか?
はい 51%
いいえ 31%
知らなかった 18%
○「ハイライト」は継続すべきですか?
ぜひ継続 27%
あってもいい 46%
なくてもいい 5%
なくすべき 18%
その他 5%
○今年は巡検案内書が地質学雑誌に掲載されました.
このまま継続 66%
見直して継続 11%
やめるべき 23%
この他にも質問や自由記述などございます.忌憚なき御意見をお願いいたします.
回答締切:2016年1月31日
アンケートの回答はこちらから→ http://goo.gl/forms/VMz31pTWNG
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(木)
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は,3月31日(木)です.
次年度も割引会費を希望のかたは,忘れずにご提出ください(締切厳守).
■ 自動引落による納入
昨年12月24日にお届けの金融機関口座より引き落としさせていただきました.通帳記帳等でご確認ください.請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承ください.
■ 郵便振替用紙(またはゆうちょ銀行口座)からのお振り込み
12月中旬に請求書兼郵便振替用紙を発送しました.地質学会の会費は前納制ですので,お早めにご送金ください.
割引会費申請や通常の会費払込について,
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0164.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】名誉会員の推薦が開始されました
─────────────────────────────────
募集期間:2015年12月21日〜2016年2月12日
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:
例えば,,,地質学への顕著な貢献/地質学会の運営と発展への貢献/
教育現場や企業などでの活動を通じた地質学の普及と振興への貢献など
*上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することはできませ
んが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
(名誉会員推薦委員会 山本高司)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】第7回惑星地球フォトコンテスト:作品募集中
──────────────────────────────────
ジオフォトの最高峰の写真コンテスト!今年も作品を募集しています.
応募締切:2016年2月22日(月)
たくさんのご応募お待ちしています.
詳しくは,http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】 IGCP608「白亜紀アジア−西太平洋生態系」第4回国際研究集会First
Circular 配布開始
──────────────────────────────────
IGCP608 Asia-Pacific Cretaceous Ecosystems (白亜紀アジア−西太平洋生
態系)第4回 国際シンポジウム
8月15 日(月)〜17日(水)
場所:ロシア科学アカデミーシベリア支所 Trofimuk石油地質地球物理学研究
所(西シベリア・ノボシビルスク)
巡検:8月18日(木)〜20日(土)「ケメロヴォ地域の白亜系恐竜産出層」
詳しくは,http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*35th IGCで,IGCP608-609-ICDP Songliao Basin合同シンポジウムが開催され
ます.「Cretaceous sea-level changes and Asia-Pacific Cretaceous
Ecosystems (IGCP 609, IGCP 608, ICDP Songliao basin) 」
http://www.35igc.org/Themes/52/Phanerozoic-Earth-History-Stratigraphy-and-the-Geologic-Time-Scale
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■2016年度支部総会・地質技術伝承会
4月16日(土)14:00〜16:45
場所:北とぴあ 7階 第1研修室
伝承会演題(予定)「落石,斜面崩壊の岩盤斜面安定解析(数値)」
講師:萩原育夫氏(サンコ−コンサルタント㈱調査技術部 部長)
*総会に欠席される方は委任状お願いします.
■支部幹事の選出
立候補期間:3月1日(火)〜11日(金)
詳しくは,http://kanto.geosociety.jp/
[西日本支部]
■西日本支部平成27年度総会・第167回例会
2月20日(土)9:00〜 例会終了後 懇親会
場所:熊本大学黒髪南キャンパス理学部2号館
講演申込締切:2月4日(木)17時
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■公開講演会
「強靭で安全・安心な都市を支える地質地盤−あなたの足元は大丈夫?−」
主催:日本学術会議
日本地質学会 後援
1月23日(土)13:30〜17:30
場所:日本学術会議講堂
http://www.scj.go.jp/ja/event/index.html
■第182回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
1月29日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ902会議室
講師:宮澤 博(環境地水技術研究会理事長)
テーマ:「土壌への雨水浸透」と宅地開発・インフラストラクチュアーへの提言
会費:会員,地質学会会員は500円,非会員は1,000円
■第2回 GSJジオ・サロン「化石のおいしい話」
2月1日(月)17:30〜19:30
会場:地質標本館1階ロビー
演者:利光誠一(地質標本館長)
高校生以上対象,資料代:350円(入場は無料)
https://www.gsj.jp/Muse/event/archives/20160201_geosalon.html
■第169回深田研談話会「多発化・激甚化する土砂災害を防ぐために」
2月12日(金)15:00〜17:00
会場:深田地質研究所研修ホール
講師:池谷 浩(砂防・地すべり技術センター研究顧問)
申込締切:2月9日(火)
http://www.fgi.or.jp
■平成27年度 ESR応用計測研究会・第40回フィッション・トラック研究会・ルミ
ネッセンス年代測定研究会 合同研究会
3月4日(金)〜6日(日)
会場:石川県金沢市 しいのき迎賓館
http://ftrgj.org/activities.htm
■シンポジウム:MISASA VI “Frontiers in Earth and Planetary Materials
Research: Origin,Evolution and Dynamics”
3月9日(水)〜11日(金)
場所:倉吉未来中心(鳥取県倉吉市)
アブストラクト,参加登録締切:2月15日
http://www.misasa.okayama-u.ac.jp/jp/news/?eid=01247
■日本地球惑星連合2016年大会
5月22日(日)〜26日(木)
会場:幕張メッセ 国際会議場
早期締切: 2月3日(水) 24:00
最終締切: 2月18日(木)12:00
http://www.jpgu.org/meeting_2016/index.htm
*学生を対象とした旅費補助制度が新設設されました
詳細はこちら,http://www.jpgu.org/meeting_2016/to_student.html
■Goldschmidt 2016(日本地質学会 共催)
6月26日(日)〜7月1日(金)
会場:パシフィコ横浜
要旨受付:1月1日(金)〜2月26日(金)
http://goldschmidt.info/2016/index
■第35回万国地質学会議
8月27日(土)〜9月4日(日)
会場:南アフリカ共和国ケープタウン
要旨締切:2016年1月31日
http://www.35igc.org/
■Techno-Ocean 2016 出展者募集中
10月6日(木)〜8日(土)
会場:神戸国際展示場2号館
http://techno-ocean2016.jp/wp/wp-content/uploads/2015/10/tO2016syuten_mousikomi.pdf
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0151.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・東北大学大学院理学研究科地学専攻准教授公募(2/18)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】地質マンガ「地質マンガの宿題」
──────────────────────────────────
「地質マンガの宿題」 作画 Key 作 chiyodite
http://www.geosociety.jp/faq/content0057.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.330(臨時)地層処分に関する「科学的有望地の要件・基準に関する技術WGにおける中間整理」の意見募集
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.330 2016/1/25┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴ ┴─┴─
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する「科学的有望地の要件・基準
に関する地層処分技術WGにおける中間整理」について、専門家からの意見募集
【2】中間整理についての説明会を開催(2月29日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する「科学的有望地の要件・基準
に関する地層処分技術WGにおける中間整理」について、専門家からの意見募集
─────────────────────────────────
総合資源エネルギー調査会地層処分技術WG(以下、「技術WG」という)では、
高レベル放射性廃棄物の最終処分に関し「科学的により適性の高いと考えら
れる地域(科学的有望地)」の具体的要件・基準について、総合資源エネルギー
調査会にて、専門家の更なる検討を進める。」との国の方針のもと、この科学
的有望地の要件・基準について、地球科学的な観点から、技術的(工学的)対
応可能性を含めた議論を進め、昨年12月にこれまでの議論の成果を中間整理と
して公表しました。
今般、中間整理の学術的知見及び利用する文献・データの妥当性について、
地層処分技術に関連する学会に所属する者や、関連する論文・報告書等の公開
文献の執筆経験を有する者など、本分野についての高い専門性を有する専門家
からの御意見を募集します。
<募集期間>1月20日(水)〜4月19日(火)
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/rw/gijutsu-iken.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】中間整理についての説明会を開催(2月29日)
─────────────────────────────────
資源エネルギー庁にて関連学会の個人会員に向けて説明会を開催する予定です。
日時:2月29日(月)13:30(開始予定)
場所:経済産業省(詳細未定)
※出席ご希望の方は、以下のメール宛てに、?企業・団体名、?所属・役職、
?登録学会、?氏名(漢字)、?氏名(フリガナ)、?メールアドレス、?電
話番号をご記入の上、2月19日(金)までにご登録下さい。
メールアドレス: chisoushobun-setsumeikai@meti.go.jp
詳細等については、ご登録いただいたメールアドレス宛に別途ご連絡をさせて
いただきます。ご不明な点等ございましたら、以下担当にお問い合わせ下さい。
<連絡先>
電力・ガス事業部 放射性廃棄物対策課
経済産業省 資源エネルギー庁
島田、中山、真田
住所 〒100-8901 東京都千代田区霞ヶ関1−3−1
TEL 03−3501−1992、FAX 03−3580−8493
E-mail sanada-hiroyuki@meti.go.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.331 2016東京・桜上水大会:トピックセッション募集中!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.331 2016/2/2┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2016東京・桜上水大会:トピックセッション募集中
【2】高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する「科学的有望地の要件・基準
に関する地層処分技術WGにおける中間整理」について、専門家からの意見募集
【3】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(木)
【4】名誉会員の推薦が開始されました
【5】第7回惑星地球フォトコンテスト:締切間近です
【6】日本地方地質誌7.四国地方 2月下旬刊行(会員特別割引販売)
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2016東京・桜上水大会:トピックセッション募集中
─────────────────────────────────
本大会では,多くのセッション開催を可能にするよう,必要十分数の会場(部
屋)を確保する予定です.ポスター会場については,近年のポスター発表重視
の方向を満たすスペースを確保します.
「第123年学術大会(2016東京・桜上水大会)」
2016年9月10日(土)〜12日(月) 会場:日本大学文理学部
★トピックセッション募集:3月14日(月)締切★
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0068.html
開催通知はこちら,http://www.geosociety.jp/science/content0069.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する「科学的有望地の要件・基準
に関する地層処分技術WGにおける中間整理」について、専門家からの意見募集
─────────────────────────────────
総合資源エネルギー調査会地層処分技術WGでは、高レベル放射性廃棄物の最終
処分に関し「科学的により適性の高いと考えられる地域(科学的有望地)」の
具体的要件・基準について、総合資源エネルギー調査会にて、専門家の更なる
検討を進める。」との国の方針のもと、この科学的有望地の要件・基準につい
て、地球科学的な観点から、技術的(工学的)対応可能性を含めた議論を進め、
昨年12月にこれまでの議論の成果を中間整理として公表しました。
今般、中間整理の学術的知見及び利用する文献・データの妥当性について、
地層処分技術に関連する学会に所属する者や、関連する論文・報告書等の公開
文献の執筆経験を有する者など、本分野についての高い専門性を有する専門家
からの御意見を募集します。
<募集期間>1月20日(水)〜4月19日(火)
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/rw/gijutsu-iken.html
中間整理についての説明会も開催が予定されています(2月29日開催)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/news/n119.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(木)
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は,3月31日(木)です.
次年度も割引会費を希望のかたは,忘れずにご提出ください(締切厳守).
■ 自動引落による納入
昨年12月24日にお届けの金融機関口座より引き落としさせていただきました.
通帳記帳等でご確認ください.請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略
させていただきますのでご了承ください.
■ 郵便振替用紙(またはゆうちょ銀行口座)からのお振り込み
12月中旬に請求書兼郵便振替用紙を発送しました.地質学会の会費は前納制
ですので,お早めにご送金ください.
割引会費申請や通常の会費払込について,
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0164.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】名誉会員の推薦が開始されました
─────────────────────────────────
募集期間:2015年12月21日〜2016年2月12日
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:
例えば,,,地質学への顕著な貢献/地質学会の運営と発展への貢献/
教育現場や企業などでの活動を通じた地質学の普及と振興への貢献など
*上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することはできませ
んが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
(名誉会員推薦委員会 山本高司)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第7回惑星地球フォトコンテスト:締め切り間近です
──────────────────────────────────
ジオフォトの最高峰の写真コンテスト!今年も作品を募集しています.
★★★応募締切:2016年2月22日(月)17時★★★
近年の応募数は,会員からの割合が極端に低くなっています。会員の皆様においては,
地質の美しさ,素晴らしさを表現した渾身の作品を是非ご投稿下さい.お待ちしています.
詳しくは, http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】日本地方地質誌7.四国地方 2月下旬刊行(会員特別割引販売)
─────────────────────────────────
日本地方地質誌7.四国地方(700頁,口絵8頁)が2月下旬に刊行になります.
定価:29,160円,会員特別割引価格:25,600円
*専用申込書はニュース誌1月号または,学会HPからダウンロードして頂けます。
http://sub.geosociety.jp/members/content0092.html
(会員番号・パスワードによるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[北海道支部]
■北海道支部平成27年度(2015年度)総会
2月27日(土)14:30〜16:30
場所:北海道大学理学部6号館2階 6-204室
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[関東支部]
■2016年度支部総会・地質技術伝承会
4月16日(土)14:00〜16:45
場所:北とぴあ 7階 第1研修室
伝承会演題(予定)「落石,斜面崩壊の岩盤斜面安定解析(数値)」
講師:萩原育夫氏(サンコ−コンサルタント(株)調査技術部 部長)
*総会に欠席される方は委任状お願いします.
■支部幹事の選出
立候補期間:3月1日(火)〜11日(金)
■ 矢川地すべり巡検参加者募集
4月23日(土)
巡検場所:群馬県甘楽郡下仁田町大字西野牧字徳若山国有林内
(矢川地すべり地域)
集合:8:00 解散:18:00頃 JR大宮駅西口
募集人数:25人 参加費:6,000〜7,000円程度(人数により変動)
参加申込締切:3月23日(水)
詳しくは,http://kanto.geosociety.jp/
[西日本支部]
■西日本支部平成27年度総会・第167回例会
2月20日(土)9:00〜 例会終了後 懇親会
場所:熊本大学黒髪南キャンパス理学部2号館
講演申込締切:2月4日(木)17時
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■平成26年広島大規模土砂災害調査団報告書「土地の成り立ちを知り土砂災害
から身を守る」が発行されました
(日本応用地質学会 2015年12月発行,A4版 88ページ 定価:3,000円)
http://www.jseg.or.jp/00-main/2014_hiroshima_heavy_rain.html
■国際地学オリンピック三重大会運営委員会ニュース No.4(1月)
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/name/olymp/kokusai_chiori_news_2016.1.pdf
■東日本大震災5周年シンポジウム
「この5年間を,復興の加速と次への備えに活かすために」
主催:土木学会(東日本大震災復興支援特別委員会)
3月1日(火)〜2日(水)10:00〜17:00
場所:発明会館(東京都港区虎ノ門2-9-14)地下2階ホール
http://committees.jsce.or.jp/2011quake/node/178
■第184回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
3月25日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:張 銘(独立産総研地圏環境リスク研究グループ長
テーマ:中華人民共和国の環境関連
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■日本地球惑星連合2016年大会
5月22日(日)〜26日(木)
会場:幕張メッセ 国際会議場
早期締切: 2月3日(水) 24:00
最終締切: 2月18日(木)12:00
http://www.jpgu.org/meeting_2016/index.htm
*学生を対象とした旅費補助制度が新設設されました
詳細はこちら,http://www.jpgu.org/meeting_2016/to_student.html
■(共)Goldschmidt 2016
6月26日(日)〜7月1日(金)
会場:パシフィコ横浜
要旨受付:1月1日(金)〜2月26日(金)
http://goldschmidt.info/2016/index
■(共)第53回アイソトープ・放射線研究発表会
7月6日(水)〜8日(金)
発表論文の申込締切:2月26日(金)
http://www.jrias.or.jp/
■第35回万国地質学会議
8月27日(土)〜9月4日(日)
会場:南アフリカ共和国ケープタウン
要旨締切:2月29日(月)*締切が延長されました*
http://www.35igc.org/Verso/211/Submit-an-Abstract
IGCサイト>http://www.35igc.org/
■(共)第60回粘土科学討論会
9月15日(木)〜17日(土)
会場:九州大学医系キャンパス
講演申込:6月13日(月)〜24日(金)
http://www.cssj2.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0151.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■平成28年度むつ市ジオパーク推進員(非常勤特別職)の募集(2/17)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
地質マンガ ふん化石のいろいろ
「ふん化石のいろいろ」
作画 Key 原作 chiyodite
「月のお下がり」
岐阜県瑞浪地方では、ビカリア(巻き貝)の内側にオパールが沈着してできた、らせん形をした化石(内型・雌型)が産出することで知られています。
http://www.kiseki-jp.com/japanese/museum/collection/vicarya.html(奇石博物館のサイトへ)
【geo-Flash】No.333 長瀞たんけんマップ 新発売!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.333 2016/3/1 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】リーフレット 長瀞たんけんマップ 新発売!
【2】2016東京・桜上水大会:トピックセッション募集中
【3】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(木)
【4】日本地方地質誌7。四国地方 2月下旬刊行(会員特別割引販売)
【5】荒川忠彦会員、第47回東レ理科教育賞 受賞
【6】2016年「地質の日」イベント情報
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】地質マンガ「ふん化石のいろいろ」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】リーフレット 長瀞たんけんマップ 新発売!
──────────────────────────────────
地質リーフレットたんけんシリーズ5
長瀞たんけんマップー荒川が刻んだ地球の窓をのぞいてみようー
長瀞の岩畳は『ジオパーク秩父』でも重要なみどころのひとつです。長瀞の岩
石はどこでできたのか、地形や地質のおはなし、長瀞の楽しみかたなどが、わ
かりやすく解説されています。観察ポイントごとに写真やイラストが付いてい
ますので、野外での観察にも最適です。教材としても是非ご活用下さい。
編集:日本地質学会長瀞たんけんマップ編集委員会
発行:一般社団法人日本地質学会
仕様:A2版 8折 両面フルカラー印刷 定価:400円(会員頒価 300円)
3月中旬頃入荷予定。予約注文お受けします!
http://www.geosociety.jp/publication/content0037.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2016東京・桜上水大会:トピックセッション募集中
─────────────────────────────────
「第123年学術大会(2016東京・桜上水大会)」
2016年9月10日(土)〜12日(月) 会場:日本大学文理学部
★トピックセッション募集:3月14日(月)締切★
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/science/content0068.html
開催通知はこちら、 http://www.geosociety.jp/science/content0069.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(木)
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は、3月31日(木)です。
次年度も割引会費を希望のかたは、忘れずにご提出ください(締切厳守)。
割引会費申請や2016年度の会費払込について、
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/outline/content0164.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】日本地方地質誌7。四国地方 2月下旬刊行(会員特別割引販売)
─────────────────────────────────
日本地方地質誌7。四国地方(700頁、口絵8頁)が2月下旬に刊行になります。
定価:29,160円、会員特別割引価格:25,600円
*専用申込書はニュース誌1月号または、学会HPからダウンロードして頂けます.
http://sub.geosociety.jp/members/content0026.html
(会員番号・パスワードによるログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】荒川忠彦会員、第47回東レ理科教育賞 受賞
─────────────────────────────────
会員の荒川忠彦氏(滋賀県立膳所高等学校 教諭)が、第47回(平成27年)東
レ理科教育賞を受賞されました。
題目「古琵琶湖層群の珪藻化石を教材にした古環境推定の授業展開」
http://www.toray.co.jp/tsf/info/inf_001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】2016年「地質の日」イベント情報
──────────────────────────────────
■■本部行事■■
講演会「日本の地質学:最近の発見と応用2016」
日時:5月21日(土)11:00〜13:00
会場:北とぴあ 第2研修室 (東京都北区王子)
第7回惑星地球フォトコンテストほか入選作品展示会・表彰式
日程:4月19日(火)〜5月22日(日)[表彰式:4月23日(土)午後]
場所:地質標本館(茨城県つくば市東1-1-1)入館無料
■■近畿支部■■
第33回地球科学講演会「カンブリア大爆発のあとさき」
日時:5月8日(日)13:30〜15:30
場所:大阪市立自然史博物館 講堂
講師:江?洋一氏(大阪市立大学大学院理学研究科地球学科教授)
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/name/content0139.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■2016年度支部総会・地質技術伝承会
4月16日(土)14:00〜16:45
場所:北とぴあ 7階 第1研修室
伝承会演題(予定)「落石、斜面崩壊の岩盤斜面安定解析(数値)」
講師:萩原育夫氏(サンコーコンサルタント(株)調査技術部 部長)
*総会に欠席される方は委任状お願いします。
■支部幹事の選出 立候補期間:3月1日(火)〜11日(金)
■ 矢川地すべり巡検参加者募集
4月23日(土)
巡検場所:群馬県甘楽郡下仁田町大字西野牧字徳若山国有林内(矢川地すべり
地域)
集合:8:00 解散:18:00頃 JR大宮駅西口
募集人数:25人 参加費:6,000〜7,000円程度(人数により変動)
参加申込締切:3月23日(水)
詳しくは、 http://kanto.geosociety.jp/
[四国支部]
■愛媛大学ミュージアム企画展【四国の鉱物展】
共催:日本地質学会四国支部
3月2日(水)〜4月27日(水)
場所:愛媛大学ミュージアム
http://www.museum.ehime-u.ac.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する「科学的有望地の要件・基準
に関する地層処分技術WGにおける中間整理」について、専門家からの意見募
<募集期間>1月20日(水)〜4月19日(火)
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/rw/gijutsu-iken.html
■北海道立総合研究機構地質研究所ニュース(Vol.31 No.4)
電磁波を利用して地下の様子を探る〜 MT 探査手法についての研修報告〜ほか
http://www.hro.or.jp/list/environmental/research/gsh/publication/gshnews/gshnews02/index.html
*************(以下、関連団体の行事案内です)****************
■地球研未来設計イニシアティブ国際シンポジウム2016
多様な自然・文化複合をふまえた未来可能な社会への転換
3月5日(土)10:30〜17:30
場所:東京国際フォーラム
聴講無料・要申込
http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2016/0305.html
■地学クラブ講演会:コケ植物による炭酸塩岩の生物風化
3月14日(月)15:00〜
場所:東京地学協会2F講堂
内容:乙幡康之(ひがし大雪自然館)氏・羽田麻美(日本大学)氏講演
http://www.geog.or.jp/lecture/lecturescheduled/259-club295.html
■(共)原子力総合シンポジウム「福島第一原発事故から5年を経て」
3月16日(水)13:00〜17:30
場所:日本学術会議講堂(地下鉄千代田線乃木坂駅徒歩2分)
入場無料
http://www.aesj.net/events/symp20160316
■第184回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
3月25日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:張 銘(産総研地圏環境リスク研究グループ長)
テーマ:中国の土壌・地下水汚染状況と動向
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■第15回重金属類・残土石処分地・廃棄物処分地診断に関わる地質汚染調査
浄化技術研修会
日本地質学会環境地質部会 共催
5月5日(木)〜8日(日)
場所:関東ベースンセンター(千葉県香取市)
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
■日本地球惑星連合2016年大会
5月22日(日)〜26日(木)
会場:幕張メッセ 国際会議場
http://www.jpgu.org/meeting_2016/index.htm
■(共)Goldschmidt 2016
6月26日(日)〜7月1日(金)
会場:パシフィコ横浜
http://goldschmidt.info/2016/index
■(共)第53回アイソトープ・放射線研究発表会
7月6日(水)〜8日(金)
http://www.jrias.or.jp/
■第35回万国地質学会議
8月27日(土)〜9月4日(日)
会場:南アフリカ共和国ケープタウン
http://www.35igc.org/
■(共)第60回粘土科学討論会
9月15日(木)〜17日(土)
会場:九州大学医系キャンパス
講演申込:6月13日(月)〜24日(金)
http://www.cssj2.org/
その他のイベント情報は、学会行事カレンダーもご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/outline/content0151.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■2016年コスモス国際賞候補者推薦(学会推薦3/31)
■平成28年度「日本学術振興会賞」受賞候補者推薦募集(学会締切3/31)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】地質マンガ「ふん化石のいろいろ」
──────────────────────────────────
原案:chiyodite マンガ:KEY
http://www.geosociety.jp/faq/content0057.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
【geo-Flash】No.334 2016年理事および監事選挙(結果報告)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.334 2016/3/15┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2016年理事および監事選挙(結果報告)
【2】第7回惑星地球フォトコンテスト:審査結果
【3】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(木)
【4】2016年「地質の日」イベント情報
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
【8】地質マンガ「どっちもポットホール」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2016年理事および監事選挙(結果報告)
─────────────────────────────────
2016年3月8日
一般社団法人日本地質学会 選挙管理委員会
委員長 金澤 直人
一般社団法人日本地質学会選挙規則ならびに選挙細則に基づき、理事および
監事選挙を実施いたしました。結果をご報告いたします。
詳しくは、
http://sub.geosociety.jp/members/content0087.html(要会員ログイン)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第7回惑星地球フォトコンテスト:審査結果
─────────────────────────────────
第7回惑星地球フォトコンテスト、応募作品全273作品のうち、入選作品13件が
決定いたしました。4月23日(土)に表彰式を開催し、展示会を予定しています。
今回も多数のご応募を頂き、ありがとうございました。作品の詳細は近日WEBで
公開し,ニュース誌にも掲載予定です。
優秀賞「奇岩越しの世界文化遺産」後藤文義(神奈川県)
優秀賞「白亜紀蓋井島花崗岩に記録されたマグマ混交・混合現象」永山伸一(山口県)
優秀賞「赤い惑星」瀬戸口義継(鹿児島県)
ジオパーク賞「巨岩聳える」小林健一(埼玉県) ほか
<表彰式>4月23日(土)13:30 地質標本館(茨城県つくば市)
<白尾審査委員長特別講演会>「地球を見た!撮った!」4月23日(土)14:30
その他の入選作品や展示会情報は、、、http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日(木)
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は、3月31日(木)です。
次年度も割引会費を希望のかたは、忘れずにご提出ください(締切厳守)。
割引会費申請や2016年度の会費払込について、
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0164.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2016年「地質の日」イベント情報
──────────────────────────────────
■■本部行事■■
講演会「日本の地質学:最近の発見と応用2016」
日時:5月21日(土)11:00〜13:00
会場:北とぴあ 第2研修室 (東京都北区王子)
第7回惑星地球フォトコンテストほか入選作品展示会・表彰式
日程:4月19日(火)〜5月22日(日)[表彰式:4月23日(土)午後]
場所:地質標本館(茨城県つくば市東1-1-1)入館無料
■■近畿支部■■
第33回地球科学講演会「カンブリア大爆発のあとさき」
日時:5月8日(日)13:30〜15:30
場所:大阪市立自然史博物館 講堂
講師:江崎洋一氏(大阪市立大学大学院理学研究科地球学科教授)
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/name/content0139.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■2016年度支部総会・地質技術伝承会
4月16日(土)14:00〜16:45
場所:北とぴあ 7階 第1研修室
演題「数値解析手法を用いた岩盤斜面の崩壊挙動評価」
講師:萩原育夫氏(サンコーコンサルタント(株)調査技術部 部長)
*総会に欠席される方は委任状お願いします(締切:4月15日)。
■ 矢川地すべり巡検参加者募集
4月23日(土)
巡検場所:群馬県甘楽郡下仁田町大字西野牧字徳若山国有林内(矢川地すべり
地域)
集合:8:00 解散:18:00頃 JR大宮駅西口
募集人数:25人 参加費:6,000〜7,000円程度(人数により変動)
参加申込締切:3月23日(水)
詳しくは、http://kanto.geosociety.jp/
[四国支部]
■愛媛大学ミュージアム企画展【四国の鉱物展】
共催:日本地質学会四国支部
3月2日(水)〜4月27日(水)
場所:愛媛大学ミュージアム
http://www.museum.ehime-u.ac.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■国際地学オリンピック三重大会運営委員会ニュース No.5(3月)
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/name/olymp/kokusai_chiori_news_2016.3.pdf
■高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する「科学的有望地の要件・基準
に関する地層処分技術WGにおける中間整理」について、専門家からの意見募集
<募集期間>1月20日(水)〜4月19日(火)
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/rw/gijutsu-iken.html
*************(以下、関連団体の行事案内です)****************
■(共)原子力総合シンポジウム「福島第一原発事故から5年を経て」
3月16日(水)13:00〜17:30
場所:日本学術会議講堂(地下鉄千代田線乃木坂駅徒歩2分)
入場無料
http://www.aesj.net/events/symp20160316
■地層処分フォーラム
3月20日(日)14:00〜16:00
場所:東京国際交流館(江東区青梅2-2-1国際研究交流大学村)
http://www.chisou-sympo.jp/forum_taiwa/
■第184回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
3月25日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:張 銘(産総研地圏環境リスク研究グループ長)
テーマ:中国の土壌・地下水汚染状況と動向
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■国際シンポジウム「いま改めて考えよう地層処分〜世界の取り組みから学ぶ〜」
3月28日(月)13:30〜16:30
会場:丸ビルホール(東京駅前丸ビル7階)
参加費:無料
http://www.numo.or.jp/pr-info/pr/event/new_symposium16022909.html
■第171回深田研談話会
関東平野と長周期地震動リスク
4月15日(金)15:00〜17:00
講師:古村孝志(東京大学地震研究所)
80名(先着順)参加費無料
http://www.fgi.or.jp
■「科研費審査システム改革2018」説明会
4月26日(火)13:00〜15:00
場所:安田講堂(東京大学本郷キャンパス内)
対象:研究者等(一般公募、先着順)
参加登録:3月11日(金)〜4月15日(金)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/1367693.htm
■日本地球惑星連合2016年大会
5月22日(日)〜26日(木)
会場:幕張メッセ 国際会議場
早期参加登録:5月10日(火)17:00まで
http://www.jpgu.org/meeting_2016/index.htm
■(共)Goldschmidt 2016
6月26日(日)〜7月1日(金)
会場:パシフィコ横浜
http://goldschmidt.info/2016/index
■(共)第53回アイソトープ・放射線研究発表会
7月6日(水)〜8日(金)
http://www.jrias.or.jp/
■国際シンポジウム 地殻ダイナミクス2016:
異なる時空間スケールにおける地殻ダイナミクス過程の統合的理解
7月19日(火)〜22日(金)(19日:巡検)
場所:高山市民文化会館
参加申込・講演要旨:4月15日締切
http://cd.dpri.kyoto-u.ac.jp/iscd2016/index.htm
■第35回万国地質学会議
8月27日(土)〜9月4日(日)
会場:南アフリカ共和国ケープタウン
http://www.35igc.org/
■(共)第60回粘土科学討論会
9月15日(木)〜17日(土)
会場:九州大学医系キャンパス
講演申込:6月13日(月)〜24日(金)
http://www.cssj2.org/
■Techno-Ocean 2016
10月6日(木)〜8日(土)
場所:神戸コンベンションセンター
http://techno-ocean2016.jp/jp/
■IGCP589「アジアにおけるテチス区の発達」第5回国際シンポジウム
10月27日(木)〜28日(金)
プレ巡検:10月25日(火)〜26日(水)
ポスト巡検:10月29日(土)〜11月2日(水)
場所:Hlaing大学(ミャンマー、ヤンゴン市)
http://igcp589.cags.ac.cn/
その他のイベント情報は、学会行事カレンダーもご参照下さい。
http://www.geosociety.jp/outline/content0151.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■2016年度地球化学研究協会学術賞「三宅賞」および「進歩賞」候補者の募集
(8/31)
詳細およびその他の公募情報は、
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】地質マンガ「どっちもポットホール」
──────────────────────────────────
原作 chiyodite 作画 Key
http://www.geosociety.jp/faq/content0057.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
地質マンガ 「どっちも、ポットホール」
「どっちも、ポットホール」
作画 Key 原作 chiyodite
「ポットホール(甌穴:おうけつ)」
川底など硬い岩の表面にできる大きな円形の深い穴を「ポットホール(甌穴)」 といいます。川の流れ(浸食)によりくぼみができ,このくぼみに小石などが 入り込み,石がくぼみの中を転がり,穴が大きくなっていきます。 (図の出典:地質リーフレットたんけんシリーズ5 長瀞たんけんマップ 写真7 より) この写真ほど大きな「ポットホール」なら自動車も落ちるかもしれませんね!?
【geo-Flash】No.335(臨時)平成28年度大学入試センター試験の地学関連科目に関する申し入れ
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.335 2016/3/22 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】平成28年度大学入試センター試験の地学関連科目に関する申し入れ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】平成28年度大学入試センター試験の地学関連科目に関する申し入れ
──────────────────────────────────
先に実施された平成28年度大学入試センター試験(本試験)において、「地
学」の平均点が38.64と極めて低く、理科2の中で最も平均点が高かった「生物」
の63.62との差が20点以上あるにもかかわらず、受験者数が1万人未満であるこ
とを理由に得点調整が行われませんでした。
日本地質学会は、昨年4月、平成27年度大学入試センター試験の地学関連
科目について、新教育課程の「地学基礎」、「地学」、および、旧教育課程の
「地学I」において、いずれも平均点が他の理科科目に比べて低かったことを憂
慮する旨の意見並びに改善に向けた要望を大学入試センターに申し入れたとこ
ろですが、昨年に引き続き「地学」の平均点が低かったことについて、再び大
学入試センターへ申し入れを行いました。
詳しくは、http://www.geosociety.jp/engineer/content0046.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
第7回フォトコンテスト_入選1
第7回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:ハート型の礫
写真:辻森 樹(宮城県)
撮影場所:台湾,花東海岸
【撮影者より/地質的背景】
台湾東海岸,海岸山脈の鮮新世,石梯坪中凝灰岩の礫岩露頭(台湾花蓮県豊浜郷港口村石梯坪).白色の中性〜酸性凝灰岩に火山角礫岩が互層する石梯坪海岸は花蓮県の景勝地として知られています.この地域はフィリピン海プレート上のルソン弧がユーラシアプレート上の台湾弧に衝突・接合する激しい構造場であり,この写真の礫岩を含む火山砕屑岩の地層はルソン弧北端部の前弧堆積物として,ルソン弧の前弧域の火成活動と発達史を記録しています.数年前,石梯坪海岸を巡検中に写真のハート型の礫を見つけました.淘汰が悪く混沌とした印象の礫岩は,灰色の基質中に淡い単色に近い流紋岩や安山岩の火山岩礫を主としています.しかし,目にとまった 「ハート型の礫」は粗粒の閃緑岩ということもあって異彩な存在でした.ありそうでなかなかない形の礫にほっこり癒され,巡検の思い出に写真に残しました.(辻森 樹:東北大学)
【審査委員長講評】
大したことのないようでも,よく見ると凄いということがありますが,それがこの作品です.ハート型の礫だけが粗粒の火成岩で特に目立ちますが,普通の人には気付きにくいものです.と思ったら,作者はフィールドを得意とする岩石学者でした.遊び心がある楽しい作品です.
目次へ戻る
第7回フォトコンテスト_入選2
第7回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:造形美
写真:大矢 学(東京都)
撮影場所:イギリス・スカイ島
【撮影者より】
スコットランドのインナー・ヘブリディーズ諸島最大島であるスカイ島の北端トロッターニッシュ半島は壮大な地質学的特徴に恵まれた風景が広がります.地滑りの結果形成されたと言われる約50メートルの玄武岩の石柱「オールド・マン・オブ・ストー (Old Man of Storr)」は,まさに自然が作り出す造形美そのもので,朝日に輝く様は荘厳の一言に尽きます.
【審査委員長講評】
スカイ島は,太古代の片麻岩から新生代の火山岩まで多様な岩石が露出します.この作品は,火山岩が広く分布する島北部の名所,Old Man of Storrを早朝の絶妙なタイミングで撮影しています.なだらかな遠景は氷河で削られてできた地形でしょうか.風景写真としても地質写真としても通用する第一級の作品です.
【地質的背景】
スコットランドの西部のインナー・ヘブリディーズ諸島最大の島であるスカイ島では,基盤(トリドニアン砂岩)の上に,古第三紀の約63-52 Ma 頃の玄武岩や分化岩体などが大規模に噴出・貫入しており,マグマの分化,貫入,噴出などの研究上のメッカとして知られています.本写真(スカイ島北部のオールド・マン・オブ・ストー(Old Man of Storr)と呼ばれる)は,玄武岩質のマグマの火道が岩尖状に残された岩体であり,地すべりによって移動してきたものとされています.(小川勇二郎)
目次へ戻る
第7回フォトコンテスト_入選3
第7回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:朝陽輝く幾何学模様の干潟
写真:谷山誠四郎(東京都)
撮影場所:兵庫県たつの市御津町 新舞子海岸
【撮影者より】
新舞子海岸に現出する幾何学模様の干潟は,東西1.5kmにも及ぶ.毎年11月下旬から1月の干潮時の限られた日の僅かな時間である.朝陽に照らされる幾何学模様の干潟が黄金色に輝き,まるで別世界のような感動的な光景です.
【審査委員長講評】
作品の選考は,作品自身の素晴らしさに加えて,類似した作品の有無,学術的な価値,意外性などの視点からも評価されます.新舞子海岸は有名な撮影スポットで,展望台と干潟の位置関係から干潮の明け方に撮影された類似作品が多数あることから,この作品のポイントは下げざるを得ませんでした.ジオの要素がもう少し加わればと思います.
【地質的背景】
砂質海岸で潮が満ちると水面下に沈み,潮が引くと現れる場所を“干潟”と呼んでいます.干潟には上げ潮流・下げ潮流によって砂や泥が運ばれています.流れや波の作用が比較的強いところには砂が多く堆積して“砂干潟”を形成し,流れの働き方によって“砂堆(デューン)”や“砂漣(リップル)”と呼ばれる周期的な微地形ができます.それらと水面との組合せによって様々な幾何学模様が見えるのです.干潟にはまた,様々な生物が棲息し,海水の浄化作用を担ってもいます.(横川美和:大阪工業大学)
目次へ戻る
第7回フォトコンテスト_入選4
第7回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:大地の息吹を感じて
写真:岡本芳隆(神奈川県)
撮影場所:富山県中新川郡立山町
【撮影者より】
立山黒部ジオパークは富山県東部と富山湾をエリアとするジオパークです.約38億年前の日本最古のジルコンに見られる歴史と標高約3000mの北アルプスから水深1000mに達する富山湾の高低差4000mの空間をテーマにしているそうです.この日は秋晴れに恵まれ鮮やかに彩られた紅葉を楽しむことが出来ました.
【審査委員長講評】
室堂から撮影した立山です.紅葉や青空に浮かぶ絹雲も印象的で,作品を見ながら氷期の立山に思いをめぐらすのも楽しいことです.作者は作品の説明で立山黒部ジオパークの1つとしてとらえています.今回は 1枚の作品でしたが,組写真でジオパークの空間・時間的な広がりを示すのも説得力があって面白いかもしれません.
【地質的背景】
立山に活火山のイメージをもつ方もいらっしゃると思いますが,北アルプスの多くやいわゆる立山(雄山・大汝山・富士ノ折立)の山体は隆起した花崗岩類からなります.写真の中央右に写るのは標高2,861 mの真砂岳です.山頂付近には山名の通り花崗岩が風化してできた砂(真砂)が見られ,剱岳などと比べると穏やかな山容をしているのが特徴です.立山黒部アルペンルートの終点である室堂ターミナル(標高2,450 m)から,気軽に登山を楽しむことができます.(増渕佳子:富山市科学博物館)
目次へ戻る
第7回フォトコンテスト_入選5
第7回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:親子で地底湖探検〜龍泉洞第三地底湖
写真:熊谷 誠(岩手県)
撮影場所:岩手県岩泉町龍泉洞 第三地底湖
【撮影者より】
2016年1月に開催された岩手県岩泉町龍泉洞の冬季の親子参加イベント「ナイトケイブ」での一場面です.閉洞後の夜の洞内をプロのケイバーと一緒に親子で探検しながら、普段は見学順路になっていない狭い場所に登ったり、狭い横穴にをもぐったりという体験ができます.洞窟探検の終着点がこの第三地底湖で、この場所から湖面に浮かべたボートに乗り込みます.ボート上の親子の頭上には鍾乳洞の空隙が,眼下にはドラゴンブルーの湖面が広がっています.
【審査委員長講評】
洞窟は狭くて暗いため,一昔前までは最も困難な撮影対象でした.ストロボ1灯だけでは光が全体に回らず,のっぺりした写真になってしまいます.作者は最新のミラーレス一眼を使い,ISO12800の超高感度,普通の照明下で撮影しています.モノトーンの鍾乳洞に,照明の青,ボートの赤,ジャケットの黄が加わり,印象的な作品になりました.
【地質的背景】
北部北上山地の上部三畳系安家層の石灰岩は,ジュラ紀付加体に取り込まれた巨大な海山―生物礁複合体が起源です.石灰岩地帯には,第四紀になってカルスト地形が発達し,多くの鍾乳洞が分布しています.中でも地底湖の美しさを誇る龍泉洞は,国の天然記念物,日本の地質百選,三陸ジオパークのジオサイトとして有名な観光洞です.写真の第三地底湖は水深98mにも及び,世界でも有数な透明度のため,ボートがまるで宙に浮かんでいるかのように見えます.(大石雅之:元岩手県立博物館)
目次へ戻る
第7回フォトコンテスト_入選6
第7回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:海上の城壁
写真:小林健一(埼玉県)
撮影場所:千葉県銚子市屏風ヶ浦
【撮影者より】
銚子半島の南西側の岸壁は「屏風ヶ浦」と呼ばれ,高さ40-50m,延長約10kmにおよぶ海食崖が連続しています.砂岩室の土壌のため浸食に弱く,波消しブロックが設置されています.この日本離れした雄大な景観を今後も後世に引き継いでいきたいものです.
【審査委員長講評】
屏風ヶ浦の崖下に下りられる場所は数カ所しかなく,撮影場所は定番ポイントとなっています.かつてこの崖は毎年0.5mずつ後退していましたが,作者の立っている防波堤で護岸されたことによって後退は止まりましたが,そのために新鮮な崖が見られなくなってしまいました.防波堤がなければこの作品はとれないので,痛し痒しですが・・・・・・・・.
【地質的背景】
写真では,色調・質感の異なる2つの地層群が重なる様子がはっきりと見て取れます.下部は遠方に向かって緩やかに傾斜する,深海堆積層の犬吠層群です.堆積年代は,写真右端で約2百万年前,左端の刑部岬あたりで約78万年前の下部−中部更新統境界付近となります.上部は,犬吠層群をほぼ水平に侵食した面を覆う,茶色の砂岩層からなる浅海堆積層の香取層です.堆積年代は約12万年前の最終間氷期と考えられています.なお地層名は酒井(1990)によります.(岡田 誠:茨城大学)
(文献)酒井豊三郎,1990,千葉県銚子地域の上部新生界―岩相・古磁気・放散虫化石層序―宇都宮大学教育学部紀要 No.23 Sec2 p1-34
目次へ戻る
第7回フォトコンテスト_入選7
第7回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:リーセフィヨルドの説教壇
写真:上砂正一(大阪府)
撮影場所:ノルウェー リーセフィヨルド
【撮影者より/地質学的背景】
フィヨルドは,氷河時代の終わりごろに氷が融けて海面が上がったために,この深い谷の一部が海に沈むことで形成されました.湾口から湾奥まで幅の変化が無く,非常に細長い深い谷を形成しています.海岸線は断崖絶壁となっています.山地,渓谷が沈水してできたリアス式海岸とは大きな違いがあります. リーセフィヨルドは垂直に切り立った,巨大な岩に挟まれた全長42kmのフィヨルドで氷河によって形成された地形と地質を楽しむことができます.このフィヨルドの最大の見所は,プレーケストーレンと呼ばれる一枚岩が海面から垂直に604mの高さで切り立った崖です.真っ平らな崖の頂上の形状は,およそ25m2の正方形で柵も無くここに立つと切り立った崖からスリル満点な眺望を味わえます.あいにく海上からの展望となり,見上げると断崖絶壁の連続でした.この崖の周辺には滝があって,観光船は崖に着けて滝の水を大きなひしゃくで汲んで飲ませてくれました.とてもまろやかで冷たい水でした.岩石は,花崗岩〜花崗片麻岩と思われ,所々に亀裂が入っているのが写真でもわかります.(上砂正一)
【審査委員長講評】
ノルウェー西海岸には多数のフィヨルドがありますが,代表的な観光地がプレーケストーレン(説教壇)です.崖上から撮影された写真が多数紹介されていますが,私は下から見上げた写真を見るのはこれが初めてです.高さは600mもあり,崖上の中央やや右に説教壇が写っています.もしオリジナルに崖上の人が写っていればスケールとなり,作品の価値が一段と高まります.
目次に戻る
第7回フォトコンテスト_佳作1-2
第7回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:青空と砂岩泥岩互層(スマホ・携帯)
写真:藤原寛仁(高知県)
撮影場所:高知県室戸市行当岬
【撮影者より】
野外調査法という集中講義で訪れた行当岬での写真です.前の日に台風が上陸しましたが,この日は晴れたため行当岬に行くことができ,その時に何かレポートの為の写真以外で壮大な写真を撮りたいと思っていたところ,この砂岩泥岩互層に目を奪われ,思わず撮ってしまった1枚です.
目次へ戻る
佳作:神の島(★3枚組写真)
写真:林 昌尚(福井県)
撮影場所:福井県坂井市雄島
【撮影者より】
この島は柱状節理と板状節理が同時に観察できる希少な島です.約1300万年前に噴出した溶岩により出来上がりました.南側は高さ数十メートルに及ぶ柱状節理の岸壁がそそり立ちます.六角形の断面も見えています. 島の西側一帯は板状節理の岩床が続いています.板状の岩が薄い層になって剥がれて行く様子が見て取れます.こちら側は絶えず日本海からの荒波が打ち寄せ,少しずつですが浸食が続いています. この島は昔から「神の島」として崇められてきました.島の南側は西側と同じように板状節理の岩で覆われていますが,こちらはかなり浸食や風化が進み岩が丸みを帯びてきています.また岩の間には植物も入り込んでいます.最南端部分には落雷により電気を帯びた『磁石岩』という岩も存在します.
目次へ戻る
第7回フォトコンテスト_佳作3-4
第7回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:プトラナ台地の洪水玄武岩・トラップ・フィヨルド
写真:奥村晃史(広島県)
撮影場所:69.11N-91.54E シベリア中部プトラナ台地上空
【撮影者より】
たまさかに晴れ上ったシベリア上空では眠っている暇がない.4月上旬レナ川上流を越えて西に進む.不思議な縞模様がが樹林帯から氷雪のプトラナ台地まで徐々に高度を上げる.台地西半ではトラップを刻むフィヨルド状の氷食谷と支流のカール地形が発達し,谷壁にペルム紀洪水玄武岩が露出する.谷底には湖水準変化も刻まれている.エニセイ川まで3時間地球史の饗宴を満喫した.putorana2.jpg とペアで見てほしい.
目次へ戻る
佳作:プトラナ台地のシベリアトラップ
写真:奥村晃史(広島県)
撮影場所:69.02N-92.89E シベリア中部プトラナ台地上空ルフトハンザ715便
【撮影者より】
たまさかに晴れ上ったシベリア上空では眠っている暇がない.4月上旬レナ川上流を越えて西に進む.落葉樹林の地面を覆う不思議な縞模様から,プトラナ台地の氷雪の階段状地形まで徐々に高度を上げていくと,等高線にそって厚紙を切り抜いて重ねた地形模型そのものとなる.これがペルム紀洪水玄武岩が浸食されてできたシベリアントラップの地形であることを降機して学んだ.putorana2.jpg とペアで見てほしい.
目次へ戻る
第7回フォトコンテスト_佳作5-6
第7回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:自然のオブジェ
写真:山内佳子(北海道)
撮影場所:北海道積丹町 島武意海岸,
【撮影者より】
様々な角度の柱状節理の造形が芸術的なオブジェの様に見えました.
目次へ戻る
佳作:南米の大地
写真:長谷川宗也(神奈川県)
撮影場所:南米大陸最高峰アコンカグア
【撮影者より】
南米大陸最高峰アコンカグア 標高6962mへのサミットアタック.登頂期間12日.4300mのベースキャンプを出て6000mの最終キャンプにビバーク.そこで天候悪化で暴風でテントから3日間でれず気温もマイナス30℃近くまで下がる.
目次へ戻る
第7回フォトコンテスト_佳作7-8
第7回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:自然が産んだ宝物
写真:松原大翔(岩手県)
撮影場所:岩手県下閉伊群岩泉町
【撮影者より】
田舎だからこそ自然がいっぱい! そんな所を写真に収めてみました!
目次へ戻る
佳作:渓間のローカル線
写真:斉藤宏和(北海道)
撮影場所:北海道美瑛町
【撮影者より】
北海道美瑛町の丘の間を通る富良野線.しかも一両編成で僅かな乗客を乗せて走る様は,初冬の風景に溶け込み長閑でもあり寂しげでもあります.
目次へ戻る
第7回フォトコンテスト:佳作19_20
第7回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:地球は生きている
写真:長山武夫(神奈川県)
撮影場所:エチオピア エルタ・アレ火山
【撮影者より】日中42〜43度のため,夕方からトレッキングを開始し,4時間ほどで到着した山頂から見えた火口は,まさに「地球は生きている」との実感を覚えさせるに十分な活動をしていた.地球の息吹に驚くとと同時に自然とはこうも綺麗なものかと感動した.
目次へ戻る
佳作:極彩色の世界
写真:長山武夫(神奈川県)
撮影場所:エチオピア ダロール火山
【撮影者より】地球上にこんな色合いの地形があるのかと思わずにいられない極彩色の絶景で,エチオピアの大地溝帯の中に存在する火山だが,標高は海より低いマイナス45mほどで世界で一番低い位置での噴火口とのこと.ただただ驚きの情景だ.
目次へ戻る
第7回フォトコンテスト_佳作9-10
第7回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:俵島の玄武岩の柱状節理
写真:永山伸一(山口県)
撮影場所:山口県長門市油谷向津具下俵島,
【撮影者より】
俵島は向津具半島の最西端にある小島で,後期中新世のアルカリ玄武岩からなる.玄武岩には見事な柱状節理が発達している.空中から見ると,溶岩流は西側に傾斜し,何枚かのフローユニットが見られる.昭和2年6月,国の名勝および天然記念物に指定されている.島には無人灯台がある.(今岡照喜)
目次へ戻る
佳作:岩礁の道筋(スマホ・携帯)
写真:神藤貴之(神奈川県)
撮影場所:城ヶ島(神奈川県三浦市)
【撮影者より】
神奈川県三浦市にある城ケ島の岩礁地帯で撮影した一枚です.この岩礁地帯は観光のコースとして,多くの人が歩く道となっています.波風によって削られた岩肌と,層となって見られる岩の色に,これまで形成されてきた岩礁の道筋を感じました.
目次へ戻る
第7回フォトコンテスト_佳作11-12
第7回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:室戸のタービダイト層
写真:雪本信彰(高知県)
撮影場所:高知県室戸市室戸岬町の室戸岬
【撮影者より】
室戸ジオパークは高知県東部に位置する室戸市全域を範囲とし,2011年9月に世界ジオパークに認定されました.テーマは「海と陸が出会い,新しい大地が誕生する最前線」.プレートテクトニクス理論を陸上で初めて証明した土地であり,今も1000年で平均2mの速度で地面が隆起し続ける地殻変動の最前線にあります.まさに生きている地球を目のあたりにすることが出来る地質学の世界的な研究スポットです.
目次へ戻る
佳作:銀河への定期便
写真:山田宏作(鹿児島県)
撮影場所:鹿児島県鹿屋市
【撮影者より】
内之浦発射場から打ち上げたロケットと天の川をモチーフにした作品で,地球の多様な姿を表現してみました.
目次へ戻る
第7回フォトコンテスト_佳作13-14
第7回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:太古の大波(スマホ・携帯)
写真:米岡克啓(神奈川県)
撮影場所:飛水峡(岐阜)
【撮影者より】
岐阜県飛水峡は甌穴群で有名ですが,今回はその周りに着目した作品です.鮮やかなチャートが層状に露出していて,どこまでも波のようにうねっています.積み重ねた悠久の時間が,一気に迫ってくるようで,迫力満点でした.
目次へ戻る
佳作:天高く
写真:大矢 学(東京都)
撮影場所:イタリア・ドロミーティ山群
【撮影者より】
ユネスコ世界遺産にも登録されているイタリア・ドロミーティ山群のトレ・チーメ・ディ・ラヴァレード.山名の由来である苦灰岩は、石灰石よりも海水や雨水の浸食に比較的強く、緻密で割れ方が比較的鋭いという特徴があるそうです.ラヴァレード峠からの標高差500m近い3本の尖峰を真下から仰ぎ見る迫力は言葉を失います.
目次へ戻る
第7回フォトコンテスト_佳作15-16
第7回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:自然のコントラスト
写真:森 祐紀(福岡県)
撮影場所:Vik, Iceland
【撮影者より】
アイスランド南部Vikの海沿いにあり,そびえ立つ白い柱状節理が黒く広大な海岸に映える感動的な景色.コロネードと呼ばれる太く直線的な柱状節理が地面から生えているようだった.火山灰や丸くなった玄武岩で構成されるこの海岸の砂は真っ黒で,その名の通り「Black Sand Beach」と呼ばれている.現地のツアーバスで訪れ,早く見たいと着いた瞬間,柱状節理目指して一目散に走ったところ,他の外国人参加者に笑われた….
目次へ戻る
佳作:躍動は時を越えて
写真:福原春輔(神奈川県)
撮影場所:飛水峡の甌穴群
【撮影者より】
飛水峡は飛騨川の激しい流れが山を削ってできた峡谷です.その中でも激流が礫を動かして岩に穴を開けたのが甌穴です.ここでは硬いチャートの層が複雑な褶曲、そして飛騨川の強い侵食作用によって出来たダイナミックで美しい岩の模様や甌穴が見られます.太古の大地の動き、そして川の激しい流れ、それらによって生まれた地形は、それさえも躍動しているかの印象を与え、感動しました.
目次へ戻る
第7回フォトコンテスト:佳作17_18
第7回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:マチュピチュ遺跡と花崗岩の造形
写真:横山俊治(高知県)
撮影場所:ペルー鉄道マチュピチュ駅の西(マチュピチュ−インティプンク間のインカ道より俯瞰撮影)
【撮影者より】
マチュピチュ遺跡の花崗岩を使った石積みの造形と、垂直・水平・緩傾斜の節理に規制された花崗岩の造形とのコントラストに目を向けました.インカ鉄道はウルバンバ川に沿って、花崗岩の急崖の間を走っています.写っている青色の列車は観光列車ビスタドーム.
目次へ戻る
佳作:The Bean
写真:池上郁彦(オーストラリア)
撮影場所:ニュージーランド・タウポ湖
【撮影者より】
(豆)と密かに呼ばれているこの直径1メートル弱の奇っ怪な構造は、1.8kaにタウポ・カルデラから噴出したタウポ火砕流堆積物中に形成されている.周囲にある形成途中の類似構造を観察すると、これが柔らかい堆積物のK-H不安定性によって生じるコンボリュート構造の一種であることが分かる.つまり巨大噴火直後の大地震で液状化した火砕流堆積物中に、上位のサージやリワークからなる成層堆積物が落ち込んだものなのであろう.
目次へ戻る
【geo-Flash】No.338 平成28年熊本地震に関して
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.338 2016/4/19┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】平成28年熊本地震に関して
【2】2016年「地質の日」イベント情報
【3】「The Geology of Japan」が出版!:会員特別販売のお知らせ
【4】リーフレット 長瀞たんけんマップ 好評発売中!
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】平成28年熊本地震に関して
──────────────────────────────────
2016年4月14日より,熊本県熊本地方を震源とした大規模な地震が発生し,各地
に甚大な被害をもたらしています.被害に遭われた方々へお見舞いを申し上げ
ますとともに,亡くなられた方々への哀悼の意を表します.
会長 井龍康文
--------------------------------------------------------------
【関連情報リンク】
学会HPから熊本地震の関連情報のリンクを掲載しています.
http://www.geosociety.jp/hazard/content0090.html
【安否確認のお願い】
一部の会員からは,既に安否のご報告をいただいてもおります.大変な状況
とは存じますが,落ち着かれましたら安否確認にご協力をお願い申し上げます.
ご連絡は地質学会事務局 main@geosociety.jp >までお願いいたします.ご
自身だけでなく,周囲の方の安否についてもご存知の範囲内でご連絡いただけ
れば幸いです.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2016年「地質の日」イベント情報
──────────────────────────────────
■■本部行事■■
第7回惑星地球フォトコンテストほか入選作品展示会・表彰式
4月19日(火)〜5月22日(日)[表彰式:4月23日(土)午後]
場所:地質標本館(茨城県つくば市東1-1-1)入館無料
講演会「日本の地質学:最近の発見と応用2016」
5月21日(土)11:00〜13:00
会場:北とぴあ 第2研修室 (東京都北区王子)
*講演要旨をHPにアップしました!
■■近畿支部■■
第33回地球科学講演会「カンブリア大爆発のあとさき」
5月8日(日)13:30〜15:30
場所:大阪市立自然史博物館 講堂
講師:江崎洋一氏(大阪市立大学大学院理学研究科地球学科教授)
テーマ別自然観察会「岸和田市南部の地質」
5月29日(日)終日 雨天中止
場所:岸和田市河合町周辺
対象:小学生以上(小学生は保護者の同伴が必要)
申込締切:5月13日(金)
■■北海道支部■■
記念展示 北海道のジオパーク−地球の営みを体感する−
4月26日(火)〜6月5日(日)9:00〜19:00
場所:札幌市資料館 1階展示室【入場無料】
関連イベント
・市民地質巡検「ぶらり 小樽の地質と軟石建造物」6月5日(日)
・市民セミナー「北海道のジオパークを語る」5月7日(土)
■■その他■■(地質学会後援)
観察会 城ヶ島の関東大震災を体感する
主催:ジオ神奈川
5月7日(土)10:00〜15:00
場所:神奈川県三浦市城ヶ島
申込締切:5月4日(水)
観察会「深海から生まれた城ヶ島」
主催:三浦半島活断層調査会
5月22日(土)10:00〜15:00
場所:神奈川県三浦市城ヶ島
申込締切:5月10日(火)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/name/content0139.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】「The Geology of Japan」が出版!:会員特別販売のお知らせ
──────────────────────────────────
2011年に編集計画がスタートした“The Geology of Japan”ですが,ほぼ5年と
いう歳月をかけて,この3月に出版となりました.本書は,日本地質学会と学術
交流協定を締結しているロンドン地質学会の出版物でありますが,その企画段
階から,日本地質学会の会員が主導的な役割を果たして完成しました.
【購入方法】
1.ロンドン地質学会のHPを通じた購入
販売価格:約8,000円(37.50GBP + 送料 13.50GBP)
ロンドン地質学会の会員と同じ特別価格で購入可能です.
2.日本地質学会を通じた購入(6月下旬納品予定)
販売価格:7,000 円(送料込)
(※)注文部数が目標(200冊)に達した場合にはこの金額よりさらに安くなる
予定です.
目標数:200冊 締め切り:5月26日(木)
書籍の詳細や購入申込など詳しくは,
http://www.geosociety.jp/news/n120.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】リーフレット 長瀞たんけんマップ 好評発売中!
──────────────────────────────────
地質リーフレットたんけんシリーズ5
長瀞たんけんマップー荒川が刻んだ地球の窓をのぞいてみようー
長瀞の岩畳は『ジオパーク秩父』でも重要なみどころのひとつです.長瀞の岩
石はどこでできたのか,地形や地質のおはなし,長瀞の楽しみかたなどが,わ
かりやすく解説されています.観察ポイントごとに写真やイラストが付いてい
ますので,野外での観察にも最適です.教材としても是非ご活用下さい.
編集:日本地質学会長瀞たんけんマップ編集委員会
発行:一般社団法人日本地質学会
仕様:A2版 8折 両面フルカラー印刷 定価:400円(会員頒価 300円)
http://www.geosociety.jp/publication/content0037.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報
──────────────────────────────────
[四国支部]
■愛媛大学ミュージアム企画展【四国の鉱物展】
共催:日本地質学会四国支部
3月2日(水)〜4月27日(水)
場所:愛媛大学ミュージアム
http://www.museum.ehime-u.ac.jp/
[西日本支部]
■第二回西日本地質講習会(CPD講習会)
<講習会>6月1日(水)10:00〜
場所:山口大学 大学会館2階
<地質巡検>6月2日(木)9:00〜
須佐の地質・岩石と日本海の形成(講師:今岡照喜)
申込締切:5月19 日(木)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■海上保安庁海底地形名称の提案募集
海上保安庁では,海底調査で明らかになった海底地形に名称を付与し海図や海
底地形図などに記載するとともに,学術分野等での利用の便宜を図っており,
下記のとおり,新たな海底地形名称の提案を受け付けています.
(本年度の検討会は,5月下旬〜6月中旬に開催を予定)
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KOKAI/ZUSHI3/topographic/topographic.htm
*************(以下,関連団体の行事案内です)****************
■シンポ「いま改めて考えよう地層処分〜科学的有望地の提示に向けて〜」
全国9都市で開催
主催:資源エネルギー庁,原子力発電環境整備機構
[東京]5月9日(月)14:30〜17:00 大手町サンケイプラザ
[秋田]5月12日(木)14:30〜17:00 秋田ビューホテル
[松江]5月14日(土)14:30〜17:00 松江テルサ
[高松]5月17日(火)14:30〜17:00 サンポートホール高松 など
http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160412001/20160412001.html
■海洋地球インフォマティクス2016
−情報・データの科学技術が社会の新しい扉を拓く−
5月11日(水)13:30〜
会場:コクヨホール 2階(東京都港区港南1-8-35)
入場無料(要事前申込)
http://www.jamstec.go.jp/ceist/sympo/2016/
■日本地球惑星連合2016年大会
5月22日(日)〜26日(木)
会場:幕張メッセ 国際会議場
早期参加登録:5月10日(火)17:00まで
http://www.jpgu.org/meeting_2016/index.htm
第186回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
5月27日(金)18:0〜20:30
場所:北とぴあ901会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分
講師:外池幸太郎 博士(エネルギー科学)
テーマ:福島第一事故炉の燃料デブリの臨界性について
http://www.npo-geopol.or.jp/index.htm
■(共)Goldschmidt 2016
6月26日(日)〜7月1日(金)
会場:パシフィコ横浜
http://goldschmidt.info/2016/index
■(共)第53回アイソトープ・放射線研究発表会
7月6日(水)〜8日(金)
http://www.jrias.or.jp/
■三朝国際インターンプログラム 2016(参加者募集)
7月4日(月)〜8 月10日(水)5週間
岡山大学 惑星物質研究所 (旧岡山大学地球物質科学研究センター) では,
国際研究・教育の推進を目的に,国内外から学部3/4年並びに修士課程
1年生を対象として 2005 年より継続して開催されています.
募集人数:10名程度
応募締切:5月9日(月)
http://intern.misasa.okayama-u.ac.jp/misip2016/?page_id=388&lang=ja
■IGCP608「白亜紀アジア−西太平洋生態系」第4回国際シンポジウム
8月15日(月)〜17日(水)
場所:ロシア科学アカデミー シベリア支所 トロフィムク石油地質地球物理学
研究所(ロシア・ノボシビルスク)
ポスト巡検:8月18日(木)〜20日(土)ケメロボ地域の白亜系恐竜産出層
参加登録・要旨締切:5月15日(日)
http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/index.php?id=5#aIndex7
■第35回万国地質学会議
8月27日(土)〜9月4日(日)
会場:南アフリカ共和国ケープタウン
http://www.35igc.org/
■(共)第60回粘土科学討論会
9月15日(木)〜17日(土)
会場:九州大学医系キャンパス
講演申込:6月13日(月)〜24日(金)
http://www.cssj2.org/
■Techno-Ocean 2016
10月6日(木)〜8日(土)
場所:神戸コンベンションセンター
*一般論文,学生ポスターアブストラクト受付中(締切6/10)
http://techno-ocean2016.jp/jp/
■IGCP589「アジアにおけるテチス区の発達」第5回国際シンポジウム
10月27日(木)〜28日(金)
プレ巡検:10月25日(火)〜26日(水)
ポスト巡検:10月29日(土)〜11月2日(水)
場所:Hlaing大学(ミャンマー,ヤンゴン市)
http://igcp589.cags.ac.cn/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0151.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■伊豆大島ジオパーク専門員募集(5/10)
■住友財団研究助成(基礎科学研究助成,環境研究助成)公募(6/16)
■東京大地震研究所「高エネルギー素粒子地球物理学公募研究」公募(5/25)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.337(臨時)ゆざわジオパーク学術研究等奨励補助金の募集
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.337 2016/4/12┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】ゆざわジオパーク学術研究等奨励補助金の募集
【2】2016年「地質の日」イベント情報
【3】公募情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】ゆざわジオパーク学術研究等奨励補助金の募集
──────────────────────────────────
ゆざわジオパークでは,ゆざわジオパークをフィールドとした学術研究等を奨
励するために,昨年度より研究費助成を行っています.
応募締切:平成28年4月28日(木)
補助金限度額:30万円
対象となる研究等:
・地形,地学に関する調査,学術研究等
・ジオパークと地域のかかわりに関する社会学,民俗学,観光学等に関する
調査,学術研究等
・そのほか,ゆざわジオパークの質の向上に資すると認められる調査,学術
研究等
詳しくは, http://www.yuzawageopark.com/2016/04/05/698
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2016年「地質の日」イベント情報
──────────────────────────────────
■■本部行事■■
第7回惑星地球フォトコンテストほか入選作品展示会・表彰式
4月19日(火)〜5月22日(日)
場所:地質標本館(茨城県つくば市東1-1-1)入館無料
<表彰式>4/23(土)13:30〜
<白尾委員長特別講演会>「地球を見た!撮った!」4/23(土)14:30〜
街中ジオ散歩in Tokyo 「国会議事堂の石を見に行こう」
5月14日(土)1回目 10:00〜11:30/2回目 14:00〜15:30
見学場所:国会議事堂衆議院内
募集期間:4月4日(月)〜15日(金)
募集人員:各回25名(今回は会員の参加も受け付けます)
講演会「日本の地質学:最近の発見と応用2016」
5月21日(土)11:00〜13:00
会場:北とぴあ 第2研修室 (東京都北区王子)
*講演要旨をHPにアップしました!
■■近畿支部■■
第33回地球科学講演会「カンブリア大爆発のあとさき」
5月8日(日)13:30〜15:30
場所:大阪市立自然史博物館 講堂
講師:江崎洋一氏(大阪市立大学大学院理学研究科地球学科教授)
テーマ別自然観察会「岸和田市南部の地質」
5月29日(日) 雨天中止
場所:岸和田市河合町周辺
申込締切:5月13日(金)
■■北海道支部■■
記念展示 北海道のジオパーク−地球の営みを体感する−
4月26日(火)〜6月5日(日)9:00〜19:00
場所:札幌市資料館 1階展示室【入場無料】
関連イベント
・市民地質巡検「ぶらり 小樽の地質と軟石建造物」6月5日(日)
・市民セミナー「北海道のジオパークを語る」5月7日(土)
■■その他■■(地質学会後援)
観察会 城ヶ島の関東大震災を体感する
主催:ジオ神奈川
5月7日(土)10:00〜15:00
場所:神奈川県三浦市城ヶ島
申込締切:5月4日(水)
観察会「深海から生まれた城ヶ島」
主催:三浦半島活断層調査会
5月22日(日)10:00〜15:00
場所:神奈川県三浦市城ヶ島
申込締切:5月10日(火)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/name/content0139.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】公募情報
──────────────────────────────────
■京都大学総合博物館助教 1名(地質学鉱物学,博物学)(4/15)
■海洋研究開発機構国際ポストドクトラル研究員 5名 (5/25)
■高知大学海洋コア総合研究センター特任教員 1名募集(5/9)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.339 学会創立125周年記念ロゴ募集開始
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.339 2016/5/2┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】学会創立125周年記念ロゴ募集開始
【2】日本地質学会第8回総会開催
【3】平成28年熊本地震に関して
【4】「原子力施設等防災対策等委託費事業」の終了に伴う掘削試料の譲渡
【5】2016年「地質の日」イベント情報
【6】「The Geology of Japan」が出版!:会員特別販売のお知らせ
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】ジオルジュ(2015年後期号)の訂正
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】学会創立125周年記念ロゴ募集開始
──────────────────────────────────
2年後の2018年は当学会が創立して125年目にあたります.
私たちが営む地球の温暖化を防ぎ,かけがえのない人命や貴重な財産を守るた
めの「防災・減災」には,地質学が必要なことは言うまでもありません.同時
に,エネルギーや資源の確保にも地質学の力は不可欠です.
そのため,当学会では,様々な分野の研究や研究成果の社会での応用,研究者
をはじめとする人材の教育・育成,社会の認知をえるための普及と啓発を進め
ています.
2018年の創立125周年を契機に,当学会は益々発展・興隆し,さらに社会に役立
つ学会とならなければなりません.そこで,125周年を盛り上げるため,会員の
皆様から記念ロゴマーク(以後,記念ロゴ)を募集するものです.
募集期間:2016年4月28日(木)10:00 〜 7月15日(金)17:00
(郵送の場合は消印有効)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/125th/content0006.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】日本地質学会第8回総会開催
──────────────────────────────────
日時 2016年5月21日(土)14:15〜15:15
会場 北とぴあ 第2研修室(東京都北区王子1-11-1)
1. 定款20条により,本総会は役員ならびに代議員による総会となります.
代議員には,総会開催通知とともに総会に必要な資料等を別途お送りいたしま
す.ご都合で欠席される方は,定款28条第1項にもとづき,議決権行使書および
議決権の代理行使(委任状)などにより,総会に出席したものとして議決権を
行使することができます.
2.正会員は,総会に陪席することができます.ただし,総会規則12条3項によ
り,許可のない発言はできません.
議事次第などは,http://www.geosociety.jp/outline/content0170.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】平成28年熊本地震に関して
──────────────────────────────────
学会HPから熊本地震の関連情報のリンクを掲載しています.
熊本地震における地震断層露頭の発見 大橋聖和,田村友識(4/26掲載)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/hazard/content0090.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】「原子力施設等防災対策等委託費事業」の終了に伴う掘削試料の譲渡
──────────────────────────────────
「原子力施設等防災対策等委託費(原子力施設における地質構造等に係る調査・
研究(下北地域における深部ボーリング調査等))事業」の終了に伴う掘削試
料の譲渡のお知らせ
平成28年4月25日
標記の掘削試料を希望する研究者に譲渡します.以下に試料の概要と申込み要
領を記しますので,希望者はどうぞお早めにお申し込み下さい.複数の希望者
がある場合はご希望に添えないことがありますので,予めご了承下さい.
掘削地点:青森県むつ市の近川南東約1.5km, 中野沢北方約1.5kmの地点(下北半島中部).
深さ:1,484m コア回収率90%以上(100%に近い)
地質:上から段丘堆積物(7m),鮮新統砂子又層(主に砂岩,厚さ98m),中新
統蒲野沢層(上部は軽石凝灰岩,下部は砂岩,厚さ204m),中新統泊層(上部
は安山岩質,下部は玄武岩質の溶岩と火山角礫岩,厚さ1175m)
費用:試料は無料ですが,下見・梱包・運送・保管等に係わる費用はすべて希
望者側でご負担下さい.
現在の保管場所:株式会社地球科学総合研究所長岡営業所(新潟県長岡市北園町3-21)
下見内覧会:現在の保管場所で5月末頃を予定.
研究報告書:原子力規制庁が委託した研究の報告書はホームページ等での公開
予定はありませんが,国立国会図書館でご覧になることができます(6月以降
送付予定).譲渡された掘削試料について,それを用いた研究成果を公表する
義務はございませんが,多くの研究成果が出ることを期待します.
添付資料:
1.掘削地点位置及び周辺地域地質図(Fig.1)JPEG
2.掘削試料総合柱状図(Fig.2a, Fig.2b)JPEG
申し込み:
本委託研究事業の名称に「掘削試料譲渡願」と追記したものを表題とし,代表
者の氏名,所属,連絡先と研究チーム全員の氏名・所属,本試料を使用予定の
研究題目と研究計画,希望する試料の掘削深度範囲,内覧会参加の有無と人数
等をA4用紙1枚にまとめて記述し,平成28年5月13日(金)必着で下記まで電子
メール・添付ファイルにて送付して下さい.
連絡先:
〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9六本木ファーストビル9F
原子力規制庁 原子力規制部
安全規制管理官(地震・津波安全対策担当)付
佐藤 秀幸
TEL 03-5114-2119(直通) FAX 03-5114-2182
E-mail hideyuki_satou[at]nsr.go.jp
紹介者:
原子力規制委員会委員 日本地質学会会員 石渡 明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2016年「地質の日」イベント情報
──────────────────────────────────
■■本部行事■■
第7回惑星地球フォトコンテストほか入選作品展示会・表彰式
4月19日(火)〜5月22日(日)
場所:地質標本館(茨城県つくば市東1-1-1)入館無料
講演会「日本の地質学:最近の発見と応用2016」
5月21日(土)11:00〜13:00
会場:北とぴあ 第2研修室 (東京都北区王子)
*講演要旨をHPにアップしました!
■■近畿支部■■
第33回地球科学講演会「カンブリア大爆発のあとさき」
5月8日(日)13:30〜15:30
場所:大阪市立自然史博物館 講堂
講師:江崎洋一氏(大阪市立大学大学院理学研究科地球学科教授)
テーマ別自然観察会「岸和田市南部の地質」
5月29日(日)終日 雨天中止
場所:岸和田市河合町周辺
対象:小学生以上(小学生は保護者の同伴が必要)
申込締切:5月13日(金)
■■北海道支部■■
記念展示 北海道のジオパーク−地球の営みを体感する−
4月26日(火)〜6月5日(日)9:00〜19:00
場所:札幌市資料館 1階展示室【入場無料】
関連イベント
・市民地質巡検「ぶらり 小樽の地質と軟石建造物」6月5日(日)
・市民セミナー「北海道のジオパークを語る」5月7日(土)
■■その他■■(地質学会後援)
観察会 城ヶ島の関東大震災を体感する
主催:ジオ神奈川
5月7日(土)10:00〜15:00
場所:神奈川県三浦市城ヶ島
申込締切:5月4日(水)
観察会「深海から生まれた城ヶ島」
主催:三浦半島活断層調査会
5月22日(日)10:00〜15:00
場所:神奈川県三浦市城ヶ島
申込締切:5月10日(火)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/name/content0139.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】「The Geology of Japan」が出版!:会員特別販売のお知らせ
──────────────────────────────────
1.ロンドン地質学会のHPを通じた購入
販売価格:約8,000円(37.50GBP + 送料 13.50GBP)
ロンドン地質学会の会員と同じ特別価格で購入可能です.
2.日本地質学会を通じた購入(6月下旬納品予定)
販売価格:7,000 円(送料込)
(※)注文部数が目標(200冊)に達した場合にはこの金額よりさらに安くなる
予定です.
目標数:200冊 締め切り:5月26日(木)
書籍の詳細や購入申込など詳しくは,
http://www.geosociety.jp/news/n120.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[北海道支部]
■平成28年度例会(個人講演会)
6月11日(土)10:00〜18:00(予定)
場所:北海道大学理学部5号館301室
講演申込:5月20日(金)
■2016年サッポロ巡検「豊平川の洪水痕跡と150年前の旧河道」
6月12日(日)
9:00 市電「山鼻19条駅」セブンイレブン前 集合
16:00 地下鉄東西閃「バスセンター前駅」 解散
参加申込締切:6月3日(金)
■書籍「北海道自然探検 ジオサイト107の旅」出版
監修:日本地質学会北海道支部
編著:石井正之・鬼頭伸治・田近 淳・宮坂省吾
出版社:北海道大学出版会
定価:2,800円+税(会員割引価格:2,240円+税)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[西日本支部]
■第二回西日本地質講習会(CPD講習会)
<講習会>6月1日(水)10:00〜
場所:山口大学 大学会館2階
<地質巡検>6月2日(木)9:00〜
須佐の地質・岩石と日本海の形成(講師:今岡照喜)
申込締切:5月19 日(木)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■電中研TOPICS Vol.21「次世代ヒートポンプの開発と評価」
http://criepi.denken.or.jp/research/topics/index.html?m=160420
■国際地学オリンピックニュースvol.7
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/name/olymp/kokusai_chiori_news_2016.4_2.pdf
■北海道立総合研究機構 地質研究所ニュースVol.32, No.1
http://www.hro.or.jp/list/environmental/research/gsh/publication/gshnews/gshnews02/vol32_no1.pdf
*************(以下,関連団体の行事案内です)****************
■東京地学協会国内見学会 伊能忠敬の風景地巡り
5月14日(土)〜15日(日)(1泊2日)
見学場所:芝円山公園→九十九里浜→銚子市→佐原市(伊能忠敬記念館等)
案内者:西川 治氏、星埜由尚氏外
参加費:15,000円程度
募集人員:35名(最少催行人数20名)
申込締切:5月9日(月)(どなたも申し込みできます)
http://www.geog.or.jp/tour/tourscheduled/263-kokunaih28.html
■日本地球惑星連合2016年大会
5月22日(日)〜26日(木)
会場:幕張メッセ 国際会議場
早期参加登録:5月10日(火)17:00まで
http://www.jpgu.org/meeting_2016/index.htm
■第29回東京国際ミネラルフェア
6月3日(木)〜7日(火)10:00〜18:00
会場:小田急第一生命ビル2階(東京都新宿)
http://www.tima.co.jp/
■(共)Goldschmidt 2016
6月26日(日)〜7月1日(金)
会場:パシフィコ横浜
http://goldschmidt.info/2016/index
■(共)第53回アイソトープ・放射線研究発表会
7月6日(水)〜8日(金)
http://www.jrias.or.jp/
■ジオパーク新潟国際フォーラム
7月27日(水)〜29日金)
会場:朱鷺メッセ:新潟コンベンションセンター
http://www.city.itoigawa.lg.jp/geopark-forum/
■第35回万国地質学会議(最終のお知らせ)
8月27日(土)〜9月4日(日)
会場:南アフリカ共和国ケープタウン
早期登録締切:5月31日(火)
巡検参加締切:5月31日(火)
*4月30日最終サーキュラーが配信されました.講演申込は終了していますが、
学会と巡検への参加は受け付けています.この機会にぜひ,ご検討ください.
http://www.35igc.org/
■(共)第60回粘土科学討論会
9月15日(木)〜17日(土)
会場:九州大学医系キャンパス
講演申込:6月13日(月)〜24日(金)
http://www.cssj2.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0151.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■神戸大学大学院理学研究科惑星学専攻岩石学・鉱物学・火山学(准教授)(6/30)
■広島大学大学院理学研究科地球惑星システム学専攻地球惑星システム学講座(教授又は准教授)(6/30)
■第11回「科学の芽」賞募集(8/20-9/30)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】ジオルジュ(2015年後期号)の訂正
──────────────────────────────────
ジオルジュ2015年後期号において,【特集2断層岩の世界】P09の図2で示され
る構造線,断層の表記のうち,特に九州での中央構造線延長の推定については,
ある一面的な見解であったにもかかわらず,確定的に表現されてしまいました.
本学会を含む内外では,その存在も含めて複数の議論があります.本来ならば,
このことを図2に付記して掲載すべきところ失したことにつきまして,おわび
し,訂正いたします.
ジオルジュ編集長 坂口有人
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください
【geo-Flash】No.340(臨時)「県の石」発表!
【geo-Flash】No.340(臨時)「県の石」発表!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.339 2016/5/2┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】日本地質学会選定「県の石」発表
【2】Goldschmidt 2016をより充実したものにするために
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】日本地質学会選定「県の石」発表
──────────────────────────────────
日本地質学会は、全国47都道府県について、その県に特徴的に産出する、ある
いは発見された岩石・鉱物・化石をそれぞれの「県の石」として選定いたしま
した。2014年8月に学会のHPやプレスリリースを介して一般にも広く推薦を呼び
かけました。それをもとに学会内で各支部から委員を選出して選定委員会(委
員長:川端清司(大阪自然史博物館))を構成し、約2年をかけて検討し、選定
いたしました。
会長コメント、「県の石」一覧、各「県の石」詳細などこちらから
http://www.geosociety.jp/name/content0121.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】Goldschmidt 2016をより充実したものにするために
──────────────────────────────────
日本地質学会が共催するGoldschmidt2016(http://goldschmidt.info/2016/)
は,6月26日〜7月1日にパシフィコ横浜をメイン会場として開催されます.
Goldschmidt会議が日本で開催されるのは実に13年ぶりです.日本の地球惑星科
学の研究者を中心に,大いに盛り上がることが予想されます.研究発表セッショ
ンはすでにスケジューリングされ,発表者はプレゼンテーションやポスターの
準備を進めていることでしょう.5月26日まではStandard Rateでの参加申し込
みができます(それ以降はオンサイト料金).この場をお借りして,
Goldschmidt期間中,およびその前後に企画されているさまざまな巡検やイベン
トを紹介します.これらのイベントにより,皆様のGoldschmidt 2016がより充
実したものになると幸いです.
●充実したラインアップの巡検 Field Trips
http://goldschmidt.info/2016/eventTypeView?type=Field%20Trip
Goldschmidt 2016開催期間の前後に,13の巡検が企画されています(5月2日現
在4件は募集終了).日本の有名な地質を海外の参加者と巡ってみてはいかがで
しょう.申し込みはJTBのサイトで5月26日まで
●多様なテーマのワークショップ Workshops
http://goldschmidt.info/2016/eventTypeView?type=Workshop
Goldschmidt 2016開催期間の前後に,19のワークショップが企画されています.
ワークショップに参加して,より研究の幅を広め,国際コミュニティーとの交
流を深めてください.締め切りは5月26日.
●ソーシャルイベント Social Events
http://goldschmidt.info/2016/eventTypeView?type=Social%20Event
アイスブレーカーをはじめ,さまざまなソーシャルイベントが企画されていま
す.特に,6月28日(火)のClassical Musical Performanceでは,演奏・コーラ
ス参加者を募集しています.詳細は山岡香子会員まで.
●学生・若手研究者向けイベント Early Career Events
http://goldschmidt.info/2016/eventTypeView?type=Early%20Career%20Event
4人の世界的に有名な研究者によるショートコース(1件は募集終了)が企画さ
れています.日本からは水月湖掘削で放射性炭素年代学に革命を起こした立命
館大学の中川毅先生が講演してくださいます.また,英語口頭発表ワークショッ
プおよび英語論文ワークショップも企画されています.詳細は黒田潤一郎会員
まで.申し込みはOptional Purchaseページから.
●プレナリーセッションで会いましょう Meet the Plenary
http://goldschmidt.info/2016/meetThePlenary
Goldschmidt 2016では,世界的に有名な研究者がお昼のプレナリーセッション
(http://goldschmidt.info/2016/plenaryPeriodsView)で講演します.その講演
者と一緒に昼食を摂りながら気軽に話しができる若手研究者向けの企画です.
申し込みはヘルプデスクhelpdesk@goldschmidt.infoまで.
●ランチボックス
ランチボックス(各日1420円)の申し込みは5月26日まで.申し込みはOptional
Purchaseページから.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.341 まもなく,東京・桜上水大会の演題登録受付開始!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.341 2016/5/17┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[予告]まもなく,東京・桜上水大会の演題登録受付を開始します
【2】日本地質学会第8回総会開催
【3】学会創立125周年記念ロゴ募集開始
【4】Island Arc 論文投稿ワークショップ「論文構成法を理解しよう(仮)」
【5】2016年「地質の日」イベント情報
【6】「The Geology of Japan」が出版!:会員特別販売のお知らせ
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[予告]まもなく,東京・桜上水大会の演題登録受付を開始します
──────────────────────────────────
第123年学術大会(東京・桜上水大会:9/10〜9/12)のおもな申込スケジュール
は以下のように予定しています.詳細は,5月号ニュース誌,HPでお知らせします.
【演題登録・要旨投稿】5月30日(月)〜6月29日(水)締切
【ランチョン・夜間集会】5月30日(月)〜6月29日(水)締切
【大会参加登録】6月初旬〜8月18日(木)締切
【巡検申込】6月初旬〜8月8日(金)締切
*大会サイトは,5月30日オープン予定です!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】日本地質学会第8回総会開催
──────────────────────────────────
日時 2016年5月21日(土)14:15〜15:15
会場 北とぴあ 第2研修室(東京都北区王子1-11-1)
1. 定款20条により,本総会は役員ならびに代議員による総会となります.
代議員には,総会開催通知とともに総会に必要な資料等を別途お送り致しました.
ご都合で欠席される方は,定款28条第1項にもとづき,議決権行使書および
議決権の代理行使(委任状)などにより,総会に出席したものとして議決権を
行使することができます.
2.正会員は,総会に陪席することができます.ただし,総会規則12条3項によ
り,許可のない発言はできません.
議事次第などは,http://www.geosociety.jp/outline/content0170.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】学会創立125周年記念ロゴ募集開始
──────────────────────────────────
125周年を盛り上げるため,会員の皆様から記念ロゴマーク(以後,記念ロゴ)を
募集中です.たくさんのご応募をお待ちしています!
募集締切:2016年 7月15日(金)17:00(郵送の場合は消印有効)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/125th/content0006.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】Island Arc 論文投稿ワークショップ「論文構成法を理解しよう(仮)」
──────────────────────────────────
論文の質を高め,スムーズに採択・出版されるようになるためには,正しい論
文構成法の理解が欠かせません.この論文投稿ワークショップでは,日本地質
学会が発行する国際的な学術英文誌Island Arcの編集委員長を務める武藤鉄司
教授から,論文構成上のポイントについてアドバイスをいただきます.併せて
ワイリーのスタッフが,出版された論文を多くの読者に読んでもらうために著
者自身ができることをご紹介します.
日時:2016年5月23日(月)12:30〜13:30
会場:幕張メッセ国際会議場(日本地球惑星科学連合2016年大会内)1階・103
参加方法:専用サイト bit.ly/JpGUworkshop2016 から申し込み下さい
参加費無料.先着50名様限定で簡単な昼食をご用意します.
詳しくは,http://www.wiley.co.jp/blog/pse/?p=34448
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2016年「地質の日」イベント情報
──────────────────────────────────
■■本部行事■■
第7回惑星地球フォトコンテストほか入選作品展示会・表彰式
4月19日(火)〜5月22日(日)
場所:地質標本館(茨城県つくば市東1-1-1)入館無料
講演会「日本の地質学:最近の発見と応用2016」
5月21日(土)11:00〜13:00
会場:北とぴあ 第2研修室 (東京都北区王子)
*講演要旨をHPにアップしました!
■■北海道支部■■
記念展示 北海道のジオパーク−地球の営みを体感する−
4月26日(火)〜6月5日(日)9:00〜19:00
場所:札幌市資料館 1階展示室【入場無料】
関連イベント
・市民地質巡検「ぶらり小樽の地質と軟石建造物」6月5日(日)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/name/content0139.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】「The Geology of Japan」が出版!:会員特別販売のお知らせ
──────────────────────────────────
1.ロンドン地質学会のHPを通じた購入
販売価格:約8,000円(37.50GBP + 送料 13.50GBP)
ロンドン地質学会の会員と同じ特別価格で購入可能です.
2.日本地質学会を通じた購入(6月下旬納品予定)
販売価格:7,000 円(送料込)
(※)注文部数が目標(200冊)に達した場合にはこの金額よりさらに安くなる
予定です.
目標数:200冊 締め切り:5月26日(木)
書籍の詳細や購入申込など詳しくは,
http://www.geosociety.jp/news/n120.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[北海道支部]
■平成28年度例会(個人講演会)
6月11日(土)10:00〜18:00(予定)
場所:北海道大学理学部5号館301室
講演申込:5月20日(金)
■2016年サッポロ巡検「豊平川の洪水痕跡と150年前の旧河道」
6月12日(日)
9:00 市電「山鼻19条駅」セブンイレブン前 集合
16:00 地下鉄東西閃「バスセンター前駅」 解散
参加申込締切:6月3日(金)
■書籍「北海道自然探検 ジオサイト107の旅」出版
監修:日本地質学会北海道支部
編著:石井正之・鬼頭伸治・田近 淳・宮坂省吾
出版社:北海道大学出版会
定価:2,800円+税(会員割引価格:2,240円+税)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[関東支部]
■清澄フィールドキャンプ 参加者募集
8月29日(月)〜9月4日(日)
場所:東京大学千葉演習林(〒299-5505 千葉県鴨川市清澄)
費用:40,000円程度(宿泊・食事・保険・レンタカー代込)
応募締切:7月8日(金)(*応募書類は所定のフォーマットを使用のこと)
詳しくは,支部HPへ(近日更新) http://kanto.geosociety.jp/
[西日本支部]
■第二回西日本地質講習会(CPD講習会)
<講習会>6月1日(水)10:00〜
場所:山口大学 大学会館2階
<地質巡検>6月2日(木)9:00〜
須佐の地質・岩石と日本海の形成(講師:今岡照喜)
申込締切:5月19 日(木)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■日本地球惑星連合2016年大会
5月22日(日)〜26日(木)
会場:幕張メッセ 国際会議場
http://www.jpgu.org/meeting_2016/index.htm
■(共)Goldschmidt 2016
6月26日(日)〜7月1日(金)
会場:パシフィコ横浜
ワークショップ・巡検申込:5月26日(木)締切
巡検,イベント等の紹介 http://www.geosociety.jp/faq/content0660.html
大会サイト http://goldschmidt.info/2016/index
■(共)第53回アイソトープ・放射線研究発表会
7月6日(水)〜8日(金)
http://www.jrias.or.jp/
■(後)ジオパーク新潟国際フォーラム
7月27日(水)〜29日(金)
---27日:東アジアネットワーク ワークショップ
---28日:基調講演会、パネルディスカッションほか
---29日:見学会(佐渡コース、苗場山麓コース、糸魚川コース)
会場:朱鷺メッセ(新潟コンベンションセンター)
申込締切:5月31日(火)
http://www.city.itoigawa.lg.jp/geopark-forum/
■第35回万国地質学会議(35th IGC)(最終のお知らせ)
8月27日(土)〜9月4日(日)
会場:南アフリカ共和国ケープタウン
早期登録締切:5月31日(火)
巡検参加締切:5月31日(火)
*4月30日最終サーキュラーが配信されました(下記より閲覧・ダウンロード可).
講演申込は終了していますが,学会と巡検への参加は受付中です!
この機会にぜひ,ご検討ください.
http://www.35igc.org/
■(共)日本地球化学会第63回年会
9月14日(水)〜16日(金)
会場:大阪市立大学杉本キャンパス
講演申込:7月14日(木)14時締切
http://www.geochem.jp/conf/2016/
■(共)第60回粘土科学討論会
9月15日(木)〜17日(土)
会場:九州大学医系キャンパス
講演申込:6月13日(月)〜24日(金)
http://www.cssj2.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0151.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■東京大学大学院総合文化研究科広域システム科学系地球科学系助教公募(6/10)
■北海道大学地球惑星科学部門地球惑星システム科学分野助教公募(8/1)
■福井県立恐竜博物館 研究職員(古生物学)募集(6/6)
■JAMSTEC高知コア研究所断層物性研究グループ公募(6/8)
■JAMSTEC地震津波海域観測研究開発センター地震津波予測研究グループ公募(6/24)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.343 東京・桜上水大会 演題登録受付中!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.343 2016/6/7┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】東京・桜上水大会情報
【2】学会創立125周年記念ロゴ募集開始
【3】フォトコンテスト入選作品展示会(in 銀座)
【4】本の紹介:北海道自然探検 ジオサイト107の旅
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】東京・桜上水大会情報
──────────────────────────────────
■演題登録受付中!
【演題登録・要旨投稿】5月30日(月)〜6月29日(水)締切
■その他各種申込も受付中です。
【ランチョン・夜間集会】5月30日(月)〜6月29日(水)締切
【小中高校生徒「地学研究」発表会】7月14日(木)締切
■事前参加登録まもなく受付開始です。
【大会参加登録】6月10日(予定)〜8月18日(木)締切
【巡検申込】6月10日(予定)〜8月8日(金)締切
*詳しくは,大会HPまたはニュース誌5月号をご覧下さい.
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】学会創立125周年記念ロゴ募集開始
──────────────────────────────────
125周年を盛り上げるため,会員の皆様から記念ロゴマーク(以後,記念ロゴ)
を募集中です.たくさんのご応募をお待ちしています!
募集締切:2016年 7月15日(金)17:00(郵送の場合は消印有効)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/125th/content0006.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】フォトコンテスト入選作品展示会(in 銀座)
──────────────────────────────────
第7回惑星地球フォトコンテストほか入選作品展示会
6月11日(火)午後 〜6月25日(日)午前
場所:銀座プロムナードギャラリー(中央区銀座)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/name/content0139.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】本の紹介:北海道自然探検 ジオサイト107の旅
──────────────────────────────────
監修:日本地質学会北海道支部
出版社:北海道大学出版会 定価:2,800円+税
北海道は四国・九州を合わせたよりも広い面積を有し,多彩な自然・地質景
観に恵まれている.北海道には既に2つの世界ジオパークを含め5つのジオパー
クが認定されており,さらに認定を目指して幾つかの地域で準備が進められて
いる.さて,このたび,標記の大変魅力的な本が刊行された.総カラーページ
で多数の写真によって北海道の多彩な自然・景観・地質の魅力が解りやすく紹
介されている.北海道全域を11のコースに分け,それぞれ10カ所前後のジオサ
イトが選定されて,統一したスタイルで各所の見所や面白さが紹介されている.
以下に本書の内容の一部を紹介しよう.
第1コースは「札幌とその周辺」で,北大構内に始まり,北海道民にはなじ
みの深い手稲山や藻岩山,札幌市民の憩いの場である藻南公園などがジオサイ
トとして紹介されている.札幌の地形的・地質的背景を形作っている扇状地,
支笏カルデラ噴火による火砕流台地の形成,石狩平野の成り立ち,活断層によ
る丘陵形成などを知る事ができる.
第2コースは観光地として人気の高い「支笏湖から洞爺湖へ」で,ここでは
有珠山や樽前山などの活動的火山はもとより,湧水や溶結凝灰岩の急崖がもた
らした滝なども紹介されている.また,新第三紀の火山岩が形成する室蘭の地
球岬の絶景も取り上げられている.
第3コース「積丹半島から羊蹄山へ」は,岩登りのメッカとして名高い小樽
の赤岩に始まり,積丹半島の海岸沿いの奇岩・急立した海蝕崖を始め,羊蹄山
やニセコ神仙沼などが紹介されている.特筆したいのは,旧豊浜トンネルや大
規模地すべり地形もジオサイトとして紹介されている事で,悲劇をもたらした
岩盤崩壊の要因や巨大地すべり地形の特徴などが迫力溢れる写真とともに解り
やすく解説されている.
全てのコースを紹介したいが,それは購入してからのお楽しみということで,
特徴点について以下に紹介する.第6コース「夕張から空知へ」では,日本の
近代化を支えた古第三紀の石炭層の壮大な露頭が幾つも取り上げられている.
また,崕山(きりぎしやま)等が紹介されている.紹介者は北海道で生まれ育っ
たので,本書で紹介されている多くは馴染みの場所であったが,崕山のような
絶景がある事を初めて知った.鋭いノコギリの歯のような一見岩脈に見える石
灰岩峰が,緑の森林から立ち上がっている様は絶景であり,その成因も謎に満
ちている.第5コース「渡島半島西海岸を北上」では,縞模様の美しい白亜の
海蝕崖やガウディの建築を思わせるような露頭,北海道の天然記念物に指定さ
れている安山岩の見事な柱状節理など,これまた旅への意欲を駆り立てる魅力
的なジオサイトから構成されている.地質学徒には必見の幌加内の青色片岩,
アポイ岳のかんらん岩,白亜紀中期の海洋無酸素事変,白亜紀—古第三紀境界
などももれなく収録されている.
本書では,大規模斜面崩壊や地すべり,活断層地形なども数多く紹介されて
いる.また,有名観光地や温泉などに関連したジオサイトも多い.北海道には
100名山が9座あるが,本書では6座までが取り上げられているのも嬉しい.ま
た,道東のコースでは,美しい湿原の光景のなかに,数千年間にわたる500年毎
の巨大津波堆積物の歴史が刻み込まれている事が紹介されている.3.11の東日
本大震災による津波や,まだ収束の見えない熊本—阿蘇—大分地震などにより,
津波堆積物や斜面崩壊・活断層にたいする社会的関心が高まっている中で,本
書ではジオサイトとしてそれらが多数収録してあるのはまさに時宜にかなって
いる.
コースは行政区分ではなく,車で移動する事を想定した設定となっている.
例えば,第7コースは「神居古潭から知床半島」,第8コースは「雄冬から稚
内・オホーツクへ」といったコースであるが,実際に各ジオサイトを訪れる時
には合理的なコース設定となっている.
本書は,分かりやすい本作りという意味でも工夫が感じられる.各コースの
最初の2ページは必ず見開きの2ページを用いて,そのコースで観察できるジ
オサイトの概要と,各ジオサイトのタイトルとキャッチフレーズが代表的な写
真とともに示されており,一目でコース全体の概要が分かるように工夫されて
いる.各ジオサイトは3ページにまとめられており,以下のように構成も統一
されている.まずタイトルと写真の次に簡潔な概要が示されている.その下に
はカラーの位置図が掲載されており,そのジオサイトの項目の中で用いられて
いる写真の位置や,ジオサイトへのアクセス方法がまず紹介されている.サイ
トの説明は,「概要」と「特徴」の2項目に分かれており,「概要」で大まか
な見所を理解した上で,「特徴」ではより詳細な内容が解説されている.さら
に「メモ」が付けられていて,専門用語の解説やあるいは科学的背景,歴史的
エピソードなどが紹介されており,より理解を深めれる様に配慮されている.
ページ調整も含めて配置されたように思える6つのコラムは多彩な内容で楽
しめる.また,巻末には北海道の地質のあらましが4ページにわたって簡潔に
紹介されており,表紙裏には107のジオサイト位置が,裏表紙裏には11コース毎
の地史年表が示されている.こうした本作りは他の地域で類似の書籍を企画す
る際に多いに参考になるであろう.
本書の編著者は,民間や北海道の研究機関の地質技術者・研究者として活躍
されてきた方々であるが,日本地質学会北海道支部で取り組まれてきた「北海
道地質百選」の活動の中心メンバーであったと聞く.つまり,活発な学会支部
活動の成果が本書に反映していると言える.本書は地質学の楽しさを伝えると
ともに,地質学を社会に広く発信していく上で大きな役割を果たすに違いない.
こうした良書を纏め上げた編著者に敬意を払うとともに,本書を携行して北海
道を旅するなら,旅の楽しさが一層大きくなるであろう.本書を多くの地質学
会会員に強くお勧めしたい.
なお,著者割引価格(2,240円+税)で購入できる会員限定注文用紙は学会
HP「会員ページ」(要ログイン)からダウンロードできます.
(宮下純夫)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報
──────────────────────────────────
[北海道支部]
■平成28年度例会(個人講演会)
6月11日(土)10:30〜17:30
場所:北海道大学理学部5号館301室
*講演プログラム・講演要旨を公開しました!
■書籍「北海道自然探検 ジオサイト107の旅」出版
監修:日本地質学会北海道支部
出版社:北海道大学出版会
定価:2,800円+税(会員割引価格:2,240円+税)
*会員割引専用申込フォームあり
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[関東支部]
■清澄フィールドキャンプ 参加者募集
8月29日(月)〜9月4日(日)
場所:東京大学千葉演習林(千葉県鴨川市清澄)
費用:40,000円程度(宿泊・食事・保険・レンタカー代込)
応募締切:7月8日(金)(*応募書類は所定のフォーマットを使用のこと)
詳しくは,支部HPへ http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■国際地学オリンピックニュースvol.8
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/name/olymp/kokusai_chiori_news_2016.6.pdf
*************(以下,関連団体の行事案内です)****************
■(共)Goldschmidt 2016
6月26日(日)〜7月1日(金)
会場:パシフィコ横浜
ワークショップ・巡検申込:5月26日(木)締切
巡検,イベント等の紹介 http://www.geosociety.jp/faq/content0660.html
大会サイト http://goldschmidt.info/2016/index
■(共)第53回アイソトープ・放射線研究発表会
7月6日(水)〜8日(金)
http://www.jrias.or.jp/
■(後)ジオパーク新潟国際フォーラム
7月27日(水)〜29日(金)
---27日:東アジアネットワーク ワークショップ
---28日:基調講演会、パネルディスカッションほか
---29日:見学会(佐渡コース、苗場山麓コース、糸魚川コース)
会場:朱鷺メッセ(新潟コンベンションセンター)
http://www.city.itoigawa.lg.jp/geopark-forum/
■第70回地学団体研究会総会(小川町)
8月19日(金)〜21日(日)
会場:リリックおがわ(埼玉県小川町民会館)
事前申込締切:7月31日(日)
http://www.geocities.jp/obt_kk/2016/index.html
■第35回万国地質学会議(35th IGC)
8月27日(土)〜9月4日(日)
会場:南アフリカ共和国ケープタウン
http://www.35igc.org/
■第19回日本水環境学会シンポジウム
9月13日(火)〜15日(木)
会場:秋田県立大学秋田キャンパス
事前参加登録締切:8月22日(月)
http://www.jswe.or.jp/event/symposium/index.html
■(共)日本地球化学会第63回年会
9月14日(水)〜16日(金)
会場:大阪市立大学杉本キャンパス
講演申込:7月14日(木)14時締切
http://www.geochem.jp/conf/2016/
■(共)第60回粘土科学討論会
9月15日(木)〜17日(土)
会場:九州大学医系キャンパス
講演申込:6月13日(月)〜24日(金)
http://www.cssj2.org/
■第6回学生のヒマラヤ野外実習ツアー(参加者募集中)
(日本地質学会推薦)
2017年3月4日〜18日(暫定日程)
コース:中西部ネパールヒマラヤの全断面で、ポカラを通る南北のルート
参加申込締切:11月30日(水)
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0151.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■平成28年度千葉県職員採用(地質職)選考考査(6/23)
■東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教員(教授)公募(7/22)
■JAMSTEC海洋掘削科学研究開発センター(研究員等)(7/19)
■平成29年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞および若手科学者賞
受賞候補者の推薦(学会締切:7/15)
■第20回尾瀬賞の募集(8/31)
■海のフロンティアを拓く岡村健二賞(8/1)
■H28年度京都大学防災研究所特別緊急共同研究の公募(6/30)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.342(臨時)東京・桜上水大会 演題登録受付開始!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.342 2016/5/30┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】東京・桜上水大会の演題登録受付を開始しました(6/29締切)
【2】災害に関連した会費の特別措置
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】東京・桜上水大会の演題登録受付を開始しました(6/29締切)
──────────────────────────────────
第123年学術大会(東京・桜上水大会:9/10〜9/12)の演題登録受付を本日30日
より開始しました.お申込をお待ちしています.
【演題登録・要旨投稿】5月30日(月)〜6月29日(水)締切
【ランチョン・夜間集会】5月30日(月)〜6月29日(水)締切
【大会参加登録】6月初旬〜8月18日(木)締切
【巡検申込】6月初旬〜8月8日(金)締切
注)現在参加登録システムからの申込画面を整備中です.まもなく大会参加登
録も受付開始予定です(6月初旬を予定).
東京・桜上水大会HPもオープンしました。
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0001.html
演題登録はこちらから
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0005.html
優秀ポスター賞のエントリー制:
今大会より,優秀ポスター賞は講演申し込み時にエントリーを希望されたポス
ター発表に対して審査をするエントリー制になりました.詳細は,5月号ニュー
ス誌でもお知らせします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】災害に関連した会費の特別措置
──────────────────────────────────
本年4月に発生した熊本地震ならびに関連する災害により被害を受けられた皆様
に,心よりお見舞い申し上げます.
日本地質学会では,災害救助法適用地域で被災された会員の方々のご窮状をふ
まえ,申請により会費を免除いたします.日本地質学会に届出の住居または
勤務地が災害救助法適用地域に該当する会員のうち,希望する方は2016年度(
平成28年度)もしくは2017年度(平成29年度)会費を免除いたします.
適用を希望される会員は,1. 会員氏名,2. 被災地,3. 被災状況(簡潔に)を
添えて学会事務局にお申し出下さい(郵送,FAX,e-mail、電話のいずれでも可).
締切:2016年10月31日(月)
申込先:一般社団法人日本地質学会
TEL 03-5823-1150
FAX 03-5823-1156
E-mail: main@geosociety.jp
※ 学術大会(2016東京・桜上水大会)の参加登録費については,別途免除措置
がありますので,大会ホームページををご確認ください.
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No344(臨時)[東京・桜上水大会]事前参加登録受付開始
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.344 2016/6/15┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】東京・桜上水大会の事前参加登録受付を開始しました
【2】普及・関連行事の受付を開始しました
【3】演題登録・要旨投稿受付中です!
【4】ランチョン・夜間集会の開催申込も忘れずに!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】東京・桜上水大会の事前参加登録受付を開始しました
──────────────────────────────────
第123年学術大会(東京・桜上水大会:9/10〜9/12)の事前参加登録受付を本日
15日より開始しました.お申込をお待ちしています.
【大会参加登録】8月18日(木)締切
【巡検申込】8月8日(金)締切
参加登録はこちらから
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0016.html
なお,参加登録費については,災害に関連した特別免除措置がありますので,
該当される方は大会HPをご確認ください.
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】普及・関連行事の受付を開始しました
──────────────────────────────────
小さなEarth Scientistのつどい,教師巡検など,普及関連行事の申込受付も開
始しました。
■ 小さなEarth Scientistのつどい〜第14回 小,中,高校生徒「地学研究」
発表会〜(締切:7月14日(木))
以下はすべて,8月31日(水)締切
■ 教師向け巡検「千葉市の昔の海岸線を歩く」
■ 家族巡検「等々力渓谷の地層と東京の大地の生い立ち」
■ 防災施設等見学「ゼロメートル地帯を守る:清澄水門管理事務所と扇橋閘門」
■ GISショートコース
このほか,サイエンスカフェ,若手会員のための業界研究サポートについては,
まもなく受付開始です.
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0040.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】演題登録・要旨投稿受付中です!
──────────────────────────────────
演題登録,要旨投稿も受付中です.期日までにお手続き下さい.
【演題登録・要旨投稿】6月29日(水)締切
*優秀ポスター賞へのエントリー制始まります
今大会から,優秀ポスター賞はエントリー制になりました.エントリーを希望
する発表者は演題登録の際に,必ずエントリーの有無を選択して,意思表示し
てください.
演題登録・要旨投稿はこちらから
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0005.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】ランチョン・夜間集会の開催申込も忘れずに!
──────────────────────────────────
専門部会や研究グループの例年会合を予定されている団体など,忘れずにお申
込下さい。
【ランチョン・夜間小集会の申込】6月29日(水)締切
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0028.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.345[東京・桜上水大会]講演申込は来週締切りです!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.345 2016/6/21┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[東京・桜上水大会]講演申込は来週締切りです!
【2】[東京・桜上水大会]講演予定者で,現在未入会の方へ周知のお願い
【3】[東京・桜上水大会]ランチョン・夜間小集会のお申込はお済みですか?
【4】「平成28年(2016年)熊本地震」による地震災害に関する声明
【5】2016年度会費督促請求について
【6】学会創立125周年記念ロゴ募集中
【7】フォトコンテスト入選作品展示会(in 銀座)開催中
【8】第17回地震火山こどもサマースクール参加者募集
【9】紹介:KAGUYA月面図
【10】支部情報
【11】その他のお知らせ
【12】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[東京・桜上水大会]講演申込は来週締切りです!
──────────────────────────────────
演題登録・要旨投稿は,来週6月29日(水)18時締切です.
期日までに余裕を持ってお申し込み下さい.
※講演要旨の準備が完了していない場合でも,まずは
(1)「新規登録」を行い,
(2)【受付番号】と【パスワード】を発行しましょう!
演題登録に関するQ&Aを大会HPに掲載しています.ご参考にしてください.
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0036.html
■事前参加登録受付中です.
【大会参加登録】8月18日(木)締切
【巡検申込】8月8日(金)締切
■その他各種申込も受付中です.
【小中高校生徒「地学研究」発表会】7月14日(木)締切
*詳しくは,大会HPまたはニュース誌5月号をご覧下さい.
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[東京・桜上水大会]講演予定者で,現在未入会の方へ周知のお願い
──────────────────────────────────
会員の皆さまの周囲に,学術大会で講演予定で,入会申込の手続きを済ませて
いない学部生・院生・職場の同僚の方がおられましたら,6/29(水)までに入
会申込書の郵送手続きを完了するよう,ご周知願います.
講演申込締切時点(6/29)で入会申込書の提出がない場合,発表申込が受理で
きません.入会申込書は6/29までに必着でお願いします.
入会申込書は以下よりダウンロードできます.
http://www.geosociety.jp/outline/content0006.html
〔注〕入会申込中でも演題登録(講演申込)は可能です.入力の際,会員番号
欄は空欄のまま,会員種別欄は『入会申込中』を選択して操作を進めてくださ
い.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[東京・桜上水大会]ランチョン・夜間小集会のお申込はお済みですか?
──────────────────────────────────
ランチョン・夜間小集会のお申込はお済みですか?
今大会も,大会初日9月10日(土)にもランチョンの時間を設けます.
会合を予定されているグループは,忘れずにお申込下さい.
◆ランチョン・夜間小集会 申込締切:6月29日(水)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/tokyo/content0028.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】「平成28年(2016年)熊本地震」による地震災害に関する声明
──────────────────────────────────
2016年4月14日,16日に発生しました「平成28年(2016年)熊本地震」により,
熊本・大分地域の地震災害の犠牲者の方々に心から哀悼の意を捧 げ,ご冥福を
お祈りすると同時に,被災者の皆様におかれましては,一日も早く静穏な日常
生活を取り戻されることをお祈りいたします.
全文を読む,,,,
http://www.geosociety.jp/engineer/content0045.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2016年度会費督促請求について
──────────────────────────────────
1.督促請求のための自動引き落とし日は6月23日(木)です.
2016年度会費が未入金のかたで,1月から5月上旬までの間に自動引落の
手続きをされたかたは6月23日に引き落としがかかります.
引き落とし不備にならぬよう,残高の確認をお願いします.
2.郵便振替用紙によるお振り込みの方には,6月14日(火)に督促請求書
(郵便振替用紙)を郵送しました.お手元に届きましたら,早急にご送金くだ
さいますようお願いいたします.
※7月上旬頃までに入金確認が取れない場合には,7月号の雑誌から送本
停止となります.定期的に雑誌をお受け取りになりたい方は,お早めに
ご送金くださいますよう,よろしくお願いいたします.
※災害に関連した…
◎会費の特別免除措置
http://www.geosociety.jp/outline/content0164.html#saigai
◎学術大会参加登録費の特別免除措置
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0019.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】学会創立125周年記念ロゴ募集中
──────────────────────────────────
125周年を盛り上げるため,会員の皆様から記念ロゴマーク(以後,記念ロゴ)
を募集中です.たくさんのご応募をお待ちしています!
募集締切:2016年 7月15日(金)17:00(郵送の場合は消印有効)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/125th/content0006.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】フォトコンテスト入選作品展示会(in 銀座)開催中
──────────────────────────────────
第7回惑星地球フォトコンテストほか入選作品展示会
6月11日(火)午後 〜6月25日(日)午前中
場所:銀座プロムナードギャラリー(中央区銀座)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/name/content0139.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】第17回地震火山こどもサマースクール参加者募集
──────────────────────────────────
「南紀熊野の海と山のひみつ」
主催:第17回地震火山こどもサマースクール実行委員会(公益社団法人日本地
震学会,特定非営利法人日本火山学会,一般社団法人日本地質学会,南紀熊野
ジオパーク推進協議会)
日時:2016年8月20日(土)午前9時〜8月21日(日)午後4時
活動場所:紀伊大島,串本海中公園,古座川の一枚岩,橋杭岩,串本町文化セ
ンターなど
募集対象・人員:小学5年〜高校生 40名
募集締切:7月15日(金)
http://www.kodomoss.jp/ss/nankikumano/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】紹介:KAGUYA月面図
──────────────────────────────────
発行年:2013(表示なし:製作者の私信による)
データ元:JAXA
画像処理:東海大学情報技術センター,地名監修:白尾元理
制作:(株)渡辺教具製作所(書籍ではなく教具なのでISBNはない)
大きさ:1030 x 728 mm,定価:1620円
(石渡 明)
先日の地球惑星科学連合大会の売店ですばらしい月面図をみつけたので紹介する.これは日本の月周回衛星かぐや(SELENE, 2007年の打ち上げ後1年半観測)の地形カメラとレーザー高度計のデータに基づく地形図で,月面の高低が暖色〜寒色の色調で表現され,傾斜地には弱い陰影が施されている.円筒(メルカトル)図法による緯度70度までの大きい方形図(右半部が月の表側,左半部が裏側)と,70度以上の両極地域の小さい2つの円形図が一枚紙に印刷されている.地球からの観測による月面図や写真集(宮本・服部訳, 1965; 中野, 1967; 高橋, 1974; 山田訳, 2004; 白尾, 2009)と異なり色や明るさの違いは表現されておらず,従ってコペルニクスやティコの周囲の光条やライナーγ渦巻き等の表面の模様は判別できない.かぐやの高解像度テレビカメラによる月面写真集は既に出版済みだが(萬年2011),今回の月面図は地形の全球的な俯瞰と各部分の詳細な比較観察に適する.
一方,米国地質調査所の月面図(USGS, 2002)は1994年の米国の月周回衛星クレメンタインのデータに基づく表裏,東西,南北の6つの半球図(等積図法)からなり,技術的な説明文と各半球の地表高度の頻度分布図・表が付属しているが,解像度はあまりよくない.月面全体の高度ヒストグラムは中国の嫦娥1号(Chang’E-1;読みはチャンオーに近い)のデータに基づくものがあり(Huang et al. 2008),高度の頻度分布は二極型の地球と異なり一極型である.クレメンタインのデータは両極地域に若干空白域があるが,かぐやのデータには空白域がなく,嫦娥と比べても再現性・正確度が高い(Fok et al. 2011).
今回の月面図にはアポロの着陸地点,かぐやの落下地点の他に,3つの深い穴(直径50〜100m, 深さ50〜110m)の位置が示されている(嵐の大洋のマリウス丘,静かの海,賢者の海(裏側南半球)).これらの穴は地下の溶岩トンネルにつながっている可能性があり,少ない被曝線量・温度変化等により将来の月面基地の有力な候補地とされる.さらに月の最高点が裏側中央のエンケンハルト付近(+10.7km),最低点が裏側の南極エイトケン盆地内のアントニアジの底(-9.06km)に示されている.地球から見える月面の範囲は月の秤動(首ふり運動)により変化するので,東西南北端部の秤動ゾーンも示してある.なお,月面では地球に向く面の中心を経緯度原点とし,日の出の方向を東とする(昔は逆だったので「東の海」が西半球の中心にある).また,月面上の緯度10度の距離は約300kmである.
私が今回のかぐやの月面図を見て最も驚いたのは,雨の海(兎の模様の腰の部分)の中心部に巨大な溶岩流が見られることである.雨の海に溶岩流の地形があることは地球からの望遠鏡観察やサーベイヤー,アポロ等の画像でも指摘されていたが,それらは比較的小規模なものだった(水谷訳, 2000, p. 111; 白尾, 2009, p. 68-70).かぐやの月面図に表れているのは,雨の海の多重クレーター構造の最も内側の円の南西端(ランベルトの150km北方)から雨の海の中心を越えて北東方向(プラトーの方向)に延びる長さ300km,幅100km程度の溶岩流で,先端部には数個の円形のローブが見られ,溶岩流の中央には延長方向の溝がある.また,その南西端を覆う,短くて幅広い別の溶岩があるようにも見える.
溶岩以外の火山地形として楯状火山(ドーム)があり,嵐の大洋(兎が餅を搗く臼の部分)に多く見られる.北からリュンカー山,シュレーター谷の周辺(アリスタルコスの西麓),マリウス丘と並び,その東のケプラーとコペルニクスの間の地域(カルパチア山脈の南側:「島々の海」とも言う)にも多い.溶岩台地の上に楯状火山が発達する例は地球のエチオピア巨大火成岩区(LIP)にもある.嵐の大洋で月の火山活動が最も新しい時代まで続いていた証拠として,リヒテンベルクの光条の東部が溶岩に覆われていることが挙げられ,10億年前以降の火山活動が示唆されるが(水谷訳, 2000, p. 137; 白尾, 2009, p.112-114),今回の月面図では残念ながら確認できない.また,裏側の南極に近いシュレーディンガー盆地の東部にも底面直径約30kmの火山があり,その中央を北東―南西方向の溝が分断している.
月の海には波打つ「しわ」状の地形が顕著である.これは溶岩の流出後に自重で中央部に向かって沈むために表面に圧縮力が働いた結果と説明されている(水谷訳, 2000, p. 129-131).神酒の海(兎の右耳)は表面のクレーター密度が高いが,それらは神酒の海の北西隅にあるテオフィルスの形成に伴う二次クレーターと解釈されている(白尾, 2009; p. 80).月の海は一般に周囲の陸地に比べて地形的に低いが,アポロ11号が人類初の月面着陸を行った静かの海(兎の顔)は例外で,特にその東部は周囲より高い台地になっている.これは水星の北半球の大規模な溶岩台地(石渡, 2012)を想起させる.表側東端のスミス海は溶岩に埋没した幽霊クレーターが多く,溶岩流が薄いのかもしれない.嵐の大洋の南,湿りの海の北端にあるガッセンディ(地名表示なし)は「月面の地形博物園」と言われ(高橋, 1974),クレーター底に発達する溝が特徴的だが,表側北東部のアトラス,同西部のヘベリウス,裏側のモスクワの海のコマロフにも同様の溝がある.
構造的な地形としては,巨大多重クレーターの同心円状の断層と放射状の割れ目が目立つ.雨の海(アルプス谷等),東の海(ブーバール谷等),神酒の海(レイタ谷,スネリウス谷等),シュレーディンガー盆地(裏側南半球.同盆地とシュレーディンガー谷は中野(1967)の巻頭写真参照)等が顕著である.東の海の周囲の放射状割れ目の一部は上下方向の変位を伴う断層のように見える.また,経緯度原点付近の中央高地には雨の海の多重クレーター形成時に飛散した岩塊による「インブリアのひっかき傷」が多数見られる(白尾, 2009, p. 76).嵐の大洋の南に続く雲の海の東部にある長さ150kmの「直線の壁」は昔から有名な断層地形で西落ち300m程度の落差があり(宮本・服部訳, 1965, p. 77; 高橋, 1974, p.179),この月面図でも明瞭である.その西方の湿りの海の縁にも落差の大きい直線的な断層があり,雲の海から西南西へ病の沼にかけては海や山を越えて直線的な溝が400km以上延びている.
若干苦言を呈すると,表側東端部の地形の理解のために,地図の右端を東経90度で切らずに100度程度まで延長すればよかった.また,アリアデヌスのラテン語がAriadaeus(N5, E15),メトンがNansen(N73, E20),メンデル=リュードベリ盆地がSouth Pole-Rydberg Basin(S50, W95)等の地名の誤記がある.なお,白尾(2009, p. 155)は「縁の海」を「緑の海」と誤記したのは中野(1967)が最古とするが,後者の巻頭・巻末の月面図や本文p.37の項目名,索引の表記は正しい.今回の月面図にはわざわざ(ふち)と注記してある.
古来日本では月を見ることが風流の1つとされ,百人一首には月を詠み込んだ歌が11首もある(天の原〜,今こむと〜,月みれば〜,朝ぼらけ有明の〜,夏の夜は〜,めぐり逢て〜,やすらはで〜,心にも〜,秋風に〜,郭公(ほととぎす)〜,嘆けとて〜).かぐやの月面図を眺め,月世界の地史に思いを致すのは,現代日本の科学者の最高の風流だと思う.
文 献
Fok, H.S., Shum, C.K., Yi, Y.C., Araki, H., Ping, J.S. et al. (2011)Accuracy assessment of lunar topography models. Earth Planets Space, 63, 15-23.
Huang, Q., Ping, J.S., Yan, J.G. (2008) Chang’E-1 laser altimetry data processing. In: Anil Bhardwaj ed. “Advances in Geosciences, Vol.
19: Planetary science”, 137-149. https://www.researchgate.net/publication/232258309_Chang’E-1_Laser_Altimetry_Data_Processing
石渡 明 (2012) 水星の地質について.geo-Flash, No. 165 (1月6日), 記事2. (日本地質学会News, 15(2), 8-9). http://www.geosociety.jp/faq/
content0352.html
萬年一剛 (2011) 紹介「The Kaguya Lunar Atlas: The Moon in High Resolution. Motomaro Shirao and Charles A. Wood著(Springer)」.日本地
質学会News, 14(6), 8-9.
Moore, P. (1963) Survey of the Moon (Christy & Moore Ltd.). 宮本正太郎・服部昭訳 (1965) 月―形態と観察.地人書館.346 p.
中野繁 (1967) 月面とその観測.恒星社厚生閣.202 p.
Rükl, A. (1990) Atlas of the Moon (Aventinum Nakladatelství). 山田卓訳(2004) 月面ウォッチング新装版.地人書館.234 p.
白尾元理 (2009) 月の地形ウォッチングガイド.誠文堂新光社, 159 p.
Spudis, P. D. (1996) The Once and Future Moon. 水谷仁訳 (2000) 月の科学―月探査の歴史とその将来.シュプリンガー・フェアラーク東京.297 p.
高橋実 (1974) 月面ガイドブック.誠文堂新光社.287 p.
U.S. Geological Survey (USGS) (2002) Color-coded topography and shaded relief map of the lunar hemispheres. Geologic Investigation Series I-2
769, 3 sheets. http://astropedia.astrogeology.usgs.gov/download/Docs/Globes/io_i2769.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】支部情報
──────────────────────────────────
[北海道支部]
■書籍「北海道自然探検 ジオサイト107の旅」出版
監修:日本地質学会北海道支部
出版社:北海道大学出版会
定価:2,800円+税(会員割引価格:2,240円+税)
*会員割引専用申込フォームあり
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[関東支部]
■清澄フィールドキャンプ 参加者募集
8月29日(月)〜9月4日(日)
場所:東京大学千葉演習林(千葉県鴨川市清澄)
費用:40,000円程度(宿泊・食事・保険・レンタカー代込)
応募締切:7月8日(金)(*応募書類は所定のフォーマットを使用のこと)
詳しくは,支部HPへ http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■熊本地震国際合同調査速報シンポジウム
主催:国際地質科学連合(IUGS)環境管理研究委員会・NPO日本地質汚染審査機構
6月25日(土)13:30〜16:30
場所:浦安文化会館 大会議室
http://www.npo-geopol.or.jp
■(共)Goldschmidt 2016
6月26日(日)〜7月1日(金)
会場:パシフィコ横浜
巡検,イベント等の紹介 http://www.geosociety.jp/faq/content0660.html
大会サイト http://goldschmidt.info/2016/index
■次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト公募説明会
7月1日(金)14:30-16:30
場所:イイノホール&カンファレンスセンター
参加申込:6月29日(水)17:00
詳しくは,
http://geosociety.jp/uploads/fckeditor/geoFlash_img/no.345-01.pdf
■(共)第53回アイソトープ・放射線研究発表会
7月6日(水)〜8日(金)
http://www.jrias.or.jp/
■NUMO国際講演会
「スイスのサイト選定におけるコミュニケーション活動」
7月8日(金)13:30〜15:45
会場 :大手町サンケイプラザ3階(東京都千代田区大手町)
講演「スイスにおける地層処分の取り組み」
トーマス・エルンスト氏(放射性廃棄物管理共同組合(NAGRA) CEO)
定員100名
http://www.numo.or.jp/topics/201616061714.html
■熊本地震・3ヶ月報告会
7月16日(土)10:00〜17:45
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木)
主催:日本学術会議 防災減災・災害復興に関する学術連携委員会
共催:防災学術連携体
参加無料,定員300名
http://janet-dr.com/
■(後)ジオパーク新潟国際フォーラム
7月27日(水)〜29日(金)
---27日:東アジアネットワーク ワークショップ
---28日:基調講演会,パネルディスカッションほか
---29日:見学会(佐渡コース,苗場山麓コース,糸魚川コース)
会場:朱鷺メッセ(新潟コンベンションセンター)
http://www.city.itoigawa.lg.jp/geopark-forum/
■第297回地学クラブ講演会「日本の風穴」
7月29日(金)15:00-17:00
場所:東京地学協会2F講堂
参加申込不要(どなたも無料で参加できます)
http://www.geog.or.jp/lecture/lecturescheduled/268-club297.html
■第35回万国地質学会議(35th IGC)
8月27日(土)〜9月4日(日)
会場:南アフリカ共和国ケープタウン
http://www.35igc.org/
■(共)日本地球化学会第63回年会
9月14日(水)〜16日(金)
会場:大阪市立大学杉本キャンパス
講演申込:7月14日(木)14時締切
http://www.geochem.jp/conf/2016/
■(共)第60回粘土科学討論会
9月15日(木)〜17日(土)
会場:九州大学医系キャンパス
講演申込:6月13日(月)〜24日(金)
http://www.cssj2.org/
■第6回学生のヒマラヤ野外実習ツアー(参加者募集中)
(日本地質学会推薦)
2017年3月4日〜18日(暫定日程)
コース:中西部ネパールヒマラヤの全断面で,ポカラを通る南北のルート
参加申込締切:11月30日(水)
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0151.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■JAMSTEC生物地球化学研究分野ポストドクトラル研究員1名(7/19)
■岡山大学惑星物質研究所教員/ポスドク研究員の公募(決定次第締切)
■第37回猿橋賞募集(11/30)
■平成28年度(第57回)東レ科学技術賞および東レ科学技術研究助成の
候補者推薦(学会締切:8/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
125記念トリビア1:地学会編集『本邦化石産地目録』
〜2018年日本地質学会創立125周年を記念して〜
トリビア学史 1 地学会編集『本邦化石産地目録』(1884)
正会員 矢島道子(日本大学文理学部)
▶▶本邦化石産地目録(PDF)5.3MB
図1 『本邦化石産地目録』表紙
はじめに
2018年に日本地質学会は創立125周年を迎える.これまでに50周年,60周年,100周年に記念誌を出版してきた.125周年には各分野の100周年から125周年のレビューを地質学雑誌に特集号として掲載予定である.この動きとは別に,これまでの記念誌に掲載されてこなかった学史的な資料がときどき発見されることがある.また,科学史全体の趨勢として,事実解釈が変更されてきているものもある.125周年が終われば,記念誌の編纂は150周年まで試みられないだろう.最近発見されたことがらは風化して消失してしまう可能性も高い.それで,今号から数回にわたって,「トリビア学史」として,小さいけれど,地質学の歴史で重要になるかもしれないことがらをまとめていきたい.第1回は1884年発行の『本邦化石産地目録』についてお送りする.
目録の発見
2015年秋,東京大学理学部地球惑星科学図書室保存書庫にて,『本邦化石産地目録』を発見した.この目録について,管見にして聞いたことがない.『本邦化石産地目録』は,明治17年当時の地質学・古生物学の様子がよくわかるので,その概要を報告する.明治17年の化石産地は現在でも化石を産しているところも多いが,まったく産しない所もある.各地の博物館で所有している化石の古い産地の検索の一助になればよい.
目録の概要・構成
大きさはB6判,34ページ,1ページは25字12行.正誤表もついている.表紙は図1を参照.小さな薄い冊子なので,目次はついてないが,構成は
表紙,表紙裏:白
凡例 ページ1
本邦化石産地目録 ページ3
第1 古生紀煤炭期之部 ページ3
第2 中生紀三聯期之部 ページ7
第3 中生紀侏羅期之部 ページ8
第4 中生紀白亜期之部 ページ11
第5 第三紀之部 ページ12
第6 時期未定之部 ページ29
第7 北海道之部 ページ32
となっている.
目録の目的
凡例では,この小冊子の目的が4項目記されている.概括すると,
1 本会員が旅行をして,化石産地を探す便を図るために,編集した.
2 地質調査所,東京大学および博物館に所蔵されている化石標本のうち,最も確実なるものについて編集したので,本書は完全な目録というわけではない.この他にも化石産地が諸書に散見されるが,誤謬のないことをめざしたので,本書にはとりあげなかった.
3 化石の産地を主として地質時代でわけた.産出時代が明瞭でないものが少なくないので,別に時期未定の部に編入した.北海道はその地質の調査がまだ極めて不充分なので,産出化石もまだ精細の識別を経てないものが十中八九である.それで,別に北海道の部分をつくった.
4 本書の時期未定の部は漸次その時期を解明されるだろうし,また,新たに化石が発見されるだろうから,ときどき増補改訂して,数年の後,完成させたい.
地学会とは
明治10年(1877)に東京大学が創立してそのうちに地質学採鉱学科が設けられた.明治11年3月27日生物・地質の学生によって,東京大学で開かれた博物友の会は自然史諸学会の発芽であった.生物の会は東京植物会や東京動物会として次々と分化した.地質専門のものは,博物友の会を保存して,地学研究に従事していたが,明治16年5月10日に地学会と改名した(小藤,1885).
地学会の欧文名は The Geo1ogical Society of Japanであり,明治18年地学会誌(Bulletin)甲部の発行を始めた.明治22年には同誌を地学雑誌と改名し,4集(vol.4)までを出版した.明治25年地学会と地学協会とが合体して,地学協会が地学雑誌の発行を継承した.地学雑誌5集からが地学協会の出版物となり,9集から The Journal of Geography と呼ばれるようになった.明治26年には東京地質学会が創立され,地質学雑誌が発刊された(小林,1980).
地学会誌第1集第1巻によれば,地学会の例会は地質調査所で行い,明治18年地学会会長は小藤文次郎,会員は,坂市太郎,富士谷孝雄,原田慎次,原田豊吉,菊池安,巨智部忠承,小藤文次郎,西山正吾,鈴木敏,和田維四郎,山田皓,山下伝吉,横山又次郎であり,その他に副会員として,本多(奈佐)忠行,神保小虎,三浦宗次郎,大塚専一,多田綱宏が記されている(小藤,1885).
明治12年から20年の東京大学理学部地質学教室の卒業生は,明治12年小藤文次郎,明治13年巨智部忠承,西松二郎,山下伝吉,明治14年富士谷孝雄,明治15年中島謙造,山田皓,横山又次郎,明治16年菊池安,鈴木敏,明治17年三浦宗次郎,明治18年多田綱宏,奈佐忠行,明治20年大塚専一,神保小虎である(東京大学理学部地質学・鉱物学教室卒業者合同名簿作成世話人会,1988).明治17年時点で,ドツ人教師のゴッチェやブラウンスはドイツへ帰国したが,ナウマンはまだ地質調査所に,ネットーは工部大学校にいた.アメリカ人のマンローやライマンはいないが,イギリス人のミルンはやはり工部大学校にいた.
目録で扱っている時代について
目録では,古生紀煤炭期,中生紀三聯期,中生紀侏羅期,中生紀白亜期,第三紀となっている.それぞれ古生代石炭紀,中生代三畳紀,ジュラ紀,白亜紀のことである.第三紀が古生代や中生代と同じランクに取り扱われていることは注意を要する.参考までに,小藤(1884)の『金石学一名鉱物学』では,始生代・古生代・中生代・新生代は原始元・中古元・近古元と表わされ,石炭紀・三畳紀・ジュラ紀・白亜紀は煤炭劫・新紅砂石劫・卵石劫・白亜劫と表わされている.その後,小藤は1886年の『鉱物学初歩下巻』では,明治14(1881)年,イタリアのボローニアで開催された第2回万国地質学会で議定された(報告書は1882年)学術語を使用するとして,Eraの著わし方はそのままに,Period-Epochを紀‐期‐代−世と呼ぶとし,石炭紀・二畳紀・三畳紀・卵石紀・白亜紀を使用している.
本冊子と小藤の著書を比較してみると,本書の著者が小藤ではないことは明瞭である.本書では,紀‐期の関係(紀は期の上位ランク)は理解されているが,どのレベルに紀を使うのかは周知されていないようである.なお,1881年の万国地質学会で,ようやく時代名等を世界的に統一しようという動きが出てきた(Vai, 2004)と報告されているので,日本の小冊子での混乱は,世界的な混乱に沿ったものであることがわかる.
産地と化石の種類
本冊子では,紀煤炭期の化石は52地点が記載され,産出化石は,石蓮[ウミユリ],フズリナ虫,貝石,珊瑚,多孔虫[有孔虫のことか]などである.
中生紀三聯期は5地点が記載され,貝石のみ報告されている.
中生紀侏羅期は31地点が記載され,産出化石は 芒刺虫[ウニ],珊瑚,貝石,木葉石,アンモニテス,介石(トリゴニヤ)などがあげられている.
中生紀白亜期は10地点が記載され,貝石,菖蒲石[コダイアマモ]の化石の産出が記載されている.
第三紀は210地点の記載があり,介石,木葉石,蟹石,貝石,木化石,多孔虫,珊瑚(灰石柘撥),石牙,芒刺虫,魚骨石,魚骨,魚石,方言百足石[ウミユリ],セルプラ虫[カンザシゴカイ],魚紋石の化石名が並んでいる.
時期未定としては28地点の記載があり,ラヂオラリヤ虫,17地点,イチオラリヤ虫[不明],1地点,多孔虫,2地点,貝石,6地点,海藻,1地点,木葉石,1地点,オストラコーダ虫,1地点,木化石,1地点が記載されている.
北海道からは24地点の報告があり,近代か?として木葉石,第三紀として介化石,介石,インフゾリヤ[微生物]土,木化石,白亜期か?として 大カボチャ石[アンモナイト],カボチャ石[アンモナイト],介化石,貝石,時代不詳として小動物,介化石,木葉石,木化石,介石が記されている.
化石について
化石名として,現在使用されていないものもいくつかある.
石蓮は平凡社刊『大辞典』(昭和10年刊,昭和28年縮刷刊)にしたがって,ウミユリとした.いくつか他の大きな漢和辞典にも出ている.百足石は雲根志に図が出ており,ウミユリと解釈されているが,この目録では産出層準は第三紀であるので,「方言百足石」と記載されている.
多孔虫は有孔虫と解釈した.
芒刺虫は,『動物書』(安本,1885)にしたがい,はウニとした.
菖蒲石は徳橋・両角(1983)にしたがい,コダイアマモとした.徳橋・両角(1983)では,ショウブイシ,アヤメイシ,オモトイシなどと呼ばれてきたこと,東海道名所図会(寛政9年)巻之二 山田石亭[木内石亭のこと]の項に,「讃州産燕子花石」と説明のついたアヤメ石のスケッチがあること,元木蘆州遺稿燈火録(文化9年)巻之一には「板野郡泉谷菖蒲紋石」と題する記述とスケッチが載っていることが記されている.本目録では阿波国板野郡奥田山村,泉谷村泉澤,板東村が,それに相当すると思われる.
石牙,魚紋石,魚牙石は具体的には不明であるが,形を表したものと理解している.
セルプラ虫はSerpula[カンザシゴカイ] とした.
大カボチャ石とカボチャ石はアンモナイトのこととした.
インフゾリヤ土は微化石を含んだ土と解釈したが不明.イチオラリア虫も不明.
オストラコーダ虫はおそらく日本での最初の記載であろう.
岩石名について
本目録には岩石名はあまり出ていない.第六「時期未定之部」のラジヂオラリヤなどの化石には産出母体の記載がついている.
舎爾や柘撥は1871年に中国で発行された『金石識別』が初出と思われる.『金石識別』はDana(1857)の漢訳書である(武上,2014).『金石識別』は明治期の日本の地質学者によく読まれていたようである.
舎爾はshale(頁岩)の発音そのままに中国語に訳されたもののようである(Fryer,1883).使用された例として,たとえば,栗本廉(1886,p.875 )には「又發火は炭層上盤(天井岩)の性質に係るものありて砂石或は蠻石の上盤を頂くものには少くして粘土或は舎爾に多しと云ふ其理たるや前者は其質粗鬆なるを以て瓦斯を埋蓄せず又熱を飛散し易きも粘土及ひ舎爾は之に反對するの作動あれはなり.」という1文がある.
『金石識別』ではTufaを拓發と訳している(Fryer,1883).日本に入ってきてから,中国語の発音を無視して柘撥あるいは拓撥と書かれるようになったらしい.たとえば,Fescaに「東京地方ノ岡丘ヲ構成スル褐色或ハ黒色ノ壌土ニシテ(第三紀ノ上層ニ在ル)嘗テヱ,キンチ氏ノ所謂拓撥壌土(ルビ:トウフローム)ナルモノハ富士山ヨリ噴出セシ火山灰ト第三紀土壌ノ水気ノ作用ニヨリテ飛散標流(註:ママ)シタルモノト混和シタルモノナリ」の文章がある(久馬,2011).
灰石は三省堂『大辞林』の「火砕流の堆積物に由来する,一部が再び溶けたような組織をもつ火山砕屑岩(さいせつがん).暗灰色をし,阿蘇山や鹿児島湾付近にみられる.」を採用した.
磧礫は平凡社刊『大辞典』(昭和10年刊,昭和28年縮刷刊)にしたがって,河原の小石とした.
産地地点について
産出地点はすべて国・郡・村で記載されている.現在でも有名な化石産地も多い.古生代のものでは,美濃の赤坂,登米の米谷,長門の秋吉,備中の成羽,中生代では,土佐の佐川,鳥の巣,領石,武蔵の五日市,新生代では,武蔵の小柴,王子,下総の木下,美濃の月吉,筑後の三池炭山,石狩の美唄炭田などたくさんある.ハマグリ坂,ハマグリ沢,カキ浜,介石山,有名な土佐のクハズ谷など,地名からいかにも化石の出そうなところもある.この目録の紹介が地域の化石研究の一助になるとよい.
化石については,すでに江戸時代から興味を持っている人々が本草会という名目で交換会をしていた.たとえば天保6年(1835年)に名古屋城南一行院で開催された本草会の目録が残っている.『本草会物品目録』(上野解説,1982)には,化石産地として
本州知多郡須佐村産 此目魚化石,魚石,クモヒトデ化石,キキヤウガヒ化石
美濃産 木化石,石蟹,胡桃仁化石,鯨骨化石,
近江佐治村産 蚌(どぶがい)化石 草蛙蠣(ころびがき)化石
本州知多産 杉化石,櫧(かし)化石
美濃岩村産 魚骨化石
美濃峰谷村産 石骨俗称
美濃古瀬村産 龍歯石俗称
などが並んでいる.
なお,ナウマンの主著『日本群島の構造と起源について』の発行は1885年で本目録の1年後であるが,各時代の化石産地が本目録の産地と一致しているものが多い.ナウマンと地学会のどちらのデータが先か知る由もないが,この時代,これらの情報は地質学者がみな共通して持っていたのかもしれない.
謝辞 東北大学総合学術博物館の永広昌之氏には菖蒲石に関して情報をいただいた.青山学院女子短期大学の八耳俊文氏からは石蓮に関して情報をいただいた.京都大学人文研究所の武上真理子氏からは『金石識別』に関して情報をいただいた.厚く感謝する.
文献
地学会編集, 1884, 本邦化石産地目録. 34p.
Dana,, J. D., 1857, Manual of Mineralogy including observations of mines, rocks, reduction of ores and the applications of the science to the arts with 260 illustrations. New Haven.456p.
Fryer, J. (ed.), 1883, Vocabulary of Mineralogical Terms occuring in the Manual, J. D. Dana, A. M. (傳蘭雅『金石中西名目表』)上海,江南製造局.473 p.
小林貞一, 1980, 四種の地学雑誌と地学会と会誌の草昧期. 地学雑誌, 89, 361-371.
小藤文次郎, 1884, 金石学一名鉱物学.163 p.
小藤文次郎, 1885, 緒言 地学会沿革小史.地学会誌甲部, 1, 1-11.
小藤文次郎, 1886, 鉱物学初歩下巻.沢屋蘇吉, 31 p.
栗本廉, 1886, 坑内發火ノ原因及防禦法.日本鑛業會誌, 2, 870-885.
久馬一剛, 2011, Fesca「甲斐国土性図説明書」と「日本地産論―通編―」からのこぼれ話. 肥料科学, 33, 1〜19.
ナウマン, 山下昇訳, 1966, 日本群島の構造と起源について―ベルリンにおける万国地質学会議のために日本地質調査所が作成した地形図ならびに地質図への付言, 山下昇,日本地質の探究―ナウマン論文集―, 東海大学出版会,167-221.
武上真理子,2014, 漢譯地質學書に見る「西學東漸」−江南製造局刊「地學淺釋」を例として.東洋史研究.73(3),95-128.
東京大学理学部地質学・鉱物学教室卒業者合同名簿作成世話人会, 1988, 東京大学理学部地質学および鉱物学教室卒業者名簿, 26p.
徳橋秀一・両角芳郎, 1983, 和泉層群におけるコダイアマモの分布と産状. 地質ニュース, no.347, 15-27.
上野益三解説, 1982,本草会物品目録, in江戸科学古典叢書45 博物学短篇集(下), 恒和出版,433-512.
安本徳寛編 , 1885, 動物書, 丸善書店,229 p.
Vai, G. B., 2004, The second International Geological Congress, Bologna, 1881.Episodes,27, 13-20.
平凡社刊編,1936,大辞典.639 p.
(日本地質学会News, Vol. 19 No. 8:2016年8月号 p.7-9掲載)
【geo-Flash】No.351(臨時)国際地学オリンピック 金メダルおめでとう!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.351 2016/8/27 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】国際地学オリンピック 金メダルおめでとう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】国際地学オリンピック 金メダルおめでとう!
──────────────────────────────────
世界26ヶ国から約100名の高校生が集まり8月20日から27日までの日程で開催
されていた「第10回国際地学オリンピック大会in三重」で、
日本選手が金メダル3個、銀メダル1個を獲得しました。
受賞者は以下のとおりです。
金メダル
笠見 京平さん 広島学院高等学校(広島県) 3年
坂部 圭哉さん 海陽中等教育学校(愛知県) 5年(高校2年)
廣木颯太朗さん 海城高等学校(東京都) 3年
銀メダル
神原 祐樹さん 大阪府立北野高等学校(大阪府) 3年
おめでとうございます!
来年はフランスのニースで国際地学オリンピックが開催されます。
それに向けての国内予選は12月8日に行われます。
9月1日から募集開始です。中学・高校生のみなさん、チャレンジしてみませんか?
詳しくは、地学オリンピック日本委員会のホームページから、
http://jeso.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.353 東京・桜上水大会開幕!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.353 2016/9/09 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】東京・桜上水大会初日の様子
【2】東京・桜上水大会:9月11日(日)の主なイベント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】東京・桜上水大会初日の様子
──────────────────────────────────
東京・桜上水大が開幕しました! 新宿都心部のすぐそばというたいへん便利な日本大学文理学部キャンパスでの開催です.学術講演,市民講演,ポスター会場,地質情報展までの多くの行事がひとつのビルで完結するという画期的な会場です.しかもエスカレーター付きで廊下まで冷房が効いている快適な環境です.
とりわけ地質情報展と学術講演が同じ場所で行われることは特筆すべき事です.これまでは来訪する市民の利便性から学術講演の会場とは別の場所で開催されることが多かった地質情報展ですが,今回は両方を簡単に見ることができます.毎回こんな大規模な展示を開催していたのか,と思って頂ければ幸いです.
それでは大会の様子を写真でご覧ください.
■朝:地質情報展開会式
■ 大会初日と表彰式が開かれました。
受賞者ポスター
公開シンポジウム
ポスター会場
表彰式
渡部会長挨拶
加藤学部長挨拶
50年会員顕彰
50年会員顕彰
50年会員顕彰
50年会員顕彰
50年会員顕彰
50年会員顕彰
石原舜三会員
小川勇二郎会員
小玉喜三郎会員
鈴木博之会員
田崎和江会員
田宮良一会員
地質学会賞
荒井章司会員
国際賞
Roberto Compagnoni博士
柵山雅則賞
野田博之会員
Island Arc賞
山本伸二会員
小藤文次郎賞
羽田裕貴会員
菅沼悠介会員
小藤文次郎賞
高柳栄子会員
研究奨励賞
研究奨励賞
酒向和希会員
金井拓人会員
功労賞
檀原 徹会員
学会表彰
内藤一樹会員
懇親会.約200名が参加しました.全国47都道府県のお酒(県の酒)と樽酒の鏡開きを行われました.
乾杯!
鏡開き用ハンマー
若手も多数参加
Dr. Min Huh大韓地質学会長らと
樽酒は飲み干さないと帰れません.
「県の酒」企画
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】東京・桜上水大会:9月11日(日)の主なイベント
──────────────────────────────────
大会2日目です.学術発表も,シンポジウムも,ランチョンも,夜間小集会も目白押しです.
・一般公開ジオパークセッション(3205室)8:45−10:30
・若手会員のための地質関連企業研究サポート(4階)
・小さなサイエンティストの集い(ポスター会場)9:00−15:30
・市民講演会「ジオハザードと都市の地質学」(3205室)14:00−16:30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.354[東京・桜上水大会]2日目!大会Go!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.353 2016/9/11 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】東京・桜上水大会2日目の様子
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】東京・桜上水大会2日目の様子
──────────────────────────────────
大会2日目は、さらに多くの参加者が集まり盛況な大会となりました。
公開シンポジウムや市民講演会では一般の街の人の姿が多く見られ、市民の
地質への関心の高さを感じました。
大会の様子を写真でご覧ください.
■
公開シンポジウム
ジオパークセッション
ポスター会場
市民講演会
企業研究会
企業研究会
情報展の実験
情報展の実験
小さなESの集い
小さなESの集い
表彰!
ポスター賞
【geo-Flash】No.355[東京・桜上水大会]大会最終日!巡検いってらっしゃい
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.355 2016/9/12 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】東京・桜上水大会最終日の様子
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】東京・桜上水大会最終日
──────────────────────────────────
いよいよ大会最終日になりました.東京大会は,10部屋のセッション会場に1フロアのポスター会場が一つの建物で完結するという集約された会場でした.炎天下も雨もなく,なんとかに乗り切れました.ところん議論して,たっぷり懇親して,次の日また議論する.サイエンスの醍醐味たっぷりの学術大会でした.
明日からの巡検に参加される皆さん,気を付けて楽しんで来てください.良い写真が撮れましたら惑星地球フォトコンテストに応募してください.
さあ来年は愛媛です! 道後温泉とみかんとMTLが今から楽しみです.それでは松山でお会いしましょう.
■最終日の様子
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です。
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
【geo-Flash】No.346(臨時)[東京・桜上水大会]講演申込まもなく締切!(延長なし)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.346 2016/6/27┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★[東京・桜上水大会]臨時号
【1】講演申込まもなく締切です!6月29日(水)18時締切(延長なし)
【2】講演申込画面(PASREG):入力時の注意
【3】講演予定者で,現在未入会の方へ周知のお願い
【4】ランチョン・夜間小集会のお申込はお済みですか?(6/29締切)
【5】講演/参加申込に関わるQ & Aもご利用下さい
【6】各種申込み締切のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】講演申込まもなく締切です!6月29日(水)18時締切(延長なし)
──────────────────────────────────
東京・桜上水大会講演申込・要旨投稿は,6月29日(水)18時締切(WEB)です.
締切の延長はありませんので,くれぐれもご注意下さい.
締切に近づくと申込が集中しますので,できるだけ余裕をもってお手続き下さ
い.今年もたくさんのお申込をお待ちしています.
講演申込は,こちらから
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0005.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】講演申込画面(PASREG):入力時の注意
─────────────────────────────────
(1)新規登録:まずは〔受付番号〕と〔パスワード〕を取得しましょう!
PASREGトップ画面一番下【→新規登録はこちらから】から新規登録を行い,
〔受付番号〕と〔パスワード〕を取得してください.
登録画面には“演題情報”のほかに“連絡者情報(一度登録しておけば書き換
える必要の無い項目)”もあります.要旨原稿が完成していなくてもまずは新
規登録を行い,〔受付番号〕と〔パスワード〕を取得することをお勧めします!
(2)修正する場合:画面右上【マイページ】からログイン
〔受付番号〕と〔パスワード〕で,【マイページ】からログインいただき,締
切まで何度でも入力情報の修正ができます.
画面操作に慣れていないと,タイムアウトする可能性が高く,締切直前の登録
は入力ミス等も多くなります.要旨原稿が完成していなくても,まずは〔受付
番号〕と〔パスワード〕を取得しましょう!締切までは要旨のみ後で投稿する
事も入力した情報を修正する事も可能です.余裕をもってお手続き下さい.
講演申込(PASREG)は,こちらから
https://www.pasreg.jp/reg/top/geosocjp/author
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】講演予定者で,現在未入会の方へ周知のお願い
──────────────────────────────────
会員の皆さまの周囲に,学術大会で講演予定で,入会申込の手続きを済ませて
いない学部生・院生・職場の同僚の方がおられましたら,6/29(水)までに入
会申込書の郵送手続きを完了するよう,ご周知願います.
講演申込締切時点(6/29)で入会申込書の提出がない場合,発表申込が受理で
きません.入会申込書は6/29までに必着でお願いします.
入会申込書は以下よりダウンロードできます.
http://www.geosociety.jp/outline/content0006.html
〔注〕入会申込中でも演題登録(講演申込)は可能です.入力の際,会員番号
欄は空欄のまま,会員種別欄は『入会申込中』を選択して操作を進めて下さい..
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】ランチョン・夜間小集会のお申込はお済みですか?(6/29締切)
──────────────────────────────────
ランチョン・夜間小集会のお申込はお済みですか?
今大会も,大会初日9月10日(土)にもランチョンの時間を設けます.
会合を予定されているグループは,忘れずにお申込下さい.
◆ランチョン・夜間小集会 申込締切:6月29日(水)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/tokyo/content0028.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】講演/参加申込に関わるQ & Aもご利用下さい
─────────────────────────────────
申込手続きの際に会員から比較的多く寄せられるお問い合わせをQ & Aとしてま
とめました.【演題登録編】【参加登録編】とご用意しましたので,申込手続
きでお困りの際は,ぜひご覧下さい.
大会申込Q&Aはこちら
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0036.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】各種申込み締切のお知らせ
─────────────────────────────────
◆ 事前参加登録
申込締切(Web):8月18日(木)締切[*巡検のみ 8月8日(月)締切]
〔注〕演題登録と事前参加登録は,それぞれ別のお申し込みになります.
ご注意ください.
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0016.html
◆ 小さなEarth Scientistのつどい
〜第14回 小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜参加校募集
申込締切:7月14日(木)締切
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0029.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.347 創立125周年記念ロゴデザイン募集中
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.347 2016/7/5┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[東京・桜上水大会]事前参加登録受付中です
【2】[東京・桜上水大会]講演申込を締切ました
【3】[東京・桜上水大会]参加申込に関わるQ & Aもご利用下さい
【4】学会創立125周年記念ロゴ募集中&WEB投票(予告)
【5】「東日本大震災に関する学術調査・研究活動アンケート」への協力願い
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[東京・桜上水大会]事前参加登録受付中です
──────────────────────────────────
■事前参加登録受付中です.
【大会参加登録】8月18日(木)締切
*講演申込と事前参加登録は,それぞれ別のお申し込みになります.講演申込
をした方は別途忘れずに参加登録もお手続き下さい.
【巡検申込】8月8日(金)締切
*各巡検コース一覧はこちら
→ http://www.geosociety.jp/tokyo/content0022.html
■その他各種申込も受付中です.
【小・中・高校生徒「地学研究」発表会】7月14日(木)締切
*詳しくは,大会HPまたはニュース誌5月号をご覧下さい.
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[東京・桜上水大会]講演申込を締切ました
─────────────────────────────────
6/29に講演申込を締切ました.今年も多数のお申込をいただき,ありがとうご
ざいました.現在各セッション世話人により要旨校閲およびプログラム編成の
作業中です.全体日程,講演プログラムは7月下旬に公開予定です.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[東京・桜上水大会]講演/参加申込に関わるQ & Aもご利用下さい
─────────────────────────────────
事前参加登録の際に会員から比較的多く寄せられるお問い合わせをQ & Aとして
まとめました.申込手続きでお困りの際は,ぜひご覧下さい.
大会申込Q&Aはこちら
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0036.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】学会創立125周年記念ロゴ募集中&WEB投票(予告)
──────────────────────────────────
125周年を盛り上げるため,会員の皆様から記念ロゴマーク
のデザイン案を募集中です.たくさんのご応募をお待ちしています!
募集締切:2016年 7月15日(金)17:00(郵送の場合は消印有効)
締切後,WEBサイトを用いた会員からの投票による一次選考を行います.
(7月下旬〜8/19までの期間)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/125th/content0006.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】「東日本大震災に関する学術調査・研究活動アンケート」への協力願い
──────────────────────────────────
日本学術会議の課題別委員会である「東日本大震災に係る学術調査検討委員会」
では,ミッションの趣旨に基づき1年間の検討を重ね,「東日本大震災に関する
学術調査・研究活動に関するアンケート」を実施することといたしました.
このアンケートは,日本学術会議の会員・連携会員であるかどうかを問わず
東日本大震災に関する学術調査・研究活動を実際に行った全国の研究者・研究
グループの皆さまにご協力をお願いするものです.アンケートの回答画面(後
掲)は日本学術会議の会員・連携会員以外の皆さまにもアクセス可能となって
いますので,東日本大震災に関する学術調査・研究活動を行っておられる研究
者・研究グループの皆さまには,ぜひご協力をお願い申し上げます.
回答期限:2016年7月20日(水)17時
アンケート回答画面のURL:
http://www.numa.iis.u-tokyo.ac.jp/taka/tyousa2/top.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[北海道支部]
■書籍「北海道自然探検 ジオサイト107の旅」出版
監修:日本地質学会北海道支部
出版社:北海道大学出版会
定価:2,800円+税(会員割引価格:2,240円+税)
*会員割引専用申込用紙あり
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[関東支部]
■清澄フィールドキャンプ 参加者募集
8月29日(月)〜9月4日(日)
場所:東京大学千葉演習林(千葉県鴨川市清澄)
費用:40,000円程度(宿泊・食事・保険・レンタカー代込)
応募締切:7月8日(金)(*応募書類は所定のフォーマットを使用のこと)
詳しくは,支部HPへ http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■国際地学オリンピックニュースvol.9
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/name/olymp/kokusai_chiori_news_2016.7.pdf
■(共)第53回アイソトープ・放射線研究発表会
7月6日(水)〜8日(金)
http://www.jrias.or.jp/
■熊本地震・3ヶ月報告会
7月16日(土)10:00〜17:45
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木)
主催:日本学術会議 防災減災・災害復興に関する学術連携委員会
共催:防災学術連携体
参加無料,定員300名
http://janet-dr.com/
■(後)大阪市立自然史博物館
第47回特別展「氷河時代 −化石でたどる日本の気候変動−」
7月16日(土)〜10月16日(日)
会場:大阪市立自然史博物館ネイチャーホール
観覧料:大人500円,高校生・大学生 300円
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
■(後)ジオパーク新潟国際フォーラム
7月27日(水)〜29日(金)
---27日:東アジアネットワーク ワークショップ
---28日:基調講演会,パネルディスカッションほか
---29日:見学会(佐渡コース,苗場山麓コース,糸魚川コース)
会場:朱鷺メッセ(新潟コンベンションセンター)
http://www.city.itoigawa.lg.jp/geopark-forum/
■第188回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
7月29日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分)
講師:佐々木裕子(国立環境研究所環境リスク・健康研究センター,日本地質
汚染審査機構理事)
テーマ:化学物質汚染と子どもの健康ーエコチル調査
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■(共)第17回地震火山こどもサマースクール
「南紀熊野の海と山のひみつ」
8月20日(土)〜8月21日(日)
活動場所:紀伊大島,串本海中公園,古座川の一枚岩,橋杭岩,串本町文化セ
ンターなど
参加者募集締切:7月15日(金)
http://www.kodomoss.jp/ss/nankikumano/
■第1回防災推進国民大会
8月27日(土)〜28日(日)
会場:東京大学本郷キャンパス
http://bosai-kokutai.jp/
■第35回万国地質学会議(35th IGC)
8月27日(土)〜9月4日(日)
会場:南アフリカ共和国ケープタウン
http://www.35igc.org/
■(共)日本地球化学会第63回年会
9月14日(水)〜16日(金)
会場:大阪市立大学杉本キャンパス
講演申込:7月14日(木)14時締切
http://www.geochem.jp/conf/2016/
■(共)第60回粘土科学討論会
9月15日(木)〜17日(土)
会場:九州大学医系キャンパス
http://www.cssj2.org/
■(後)藤原ナチュラルヒストリー振興財団神戸シンポジウム
ナチュラルヒストリー:これまでの貢献と今後へ期待
10月22 日(土) 13:30〜17:00
場所:兵庫県民会館けんみんホール
共催 兵庫県立人と自然の博物館
http://fujiwara-nh.or.jp/
■第6回学生のヒマラヤ野外実習ツアー(参加者募集中)(日本地質学会推薦)
2017年3月4日〜18日(暫定日程)
コース:中西部ネパールヒマラヤの全断面で,ポカラを通る南北のルート
参加申込締切:11月30日(水)
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0151.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■JAMSTEC「よこすか」「かいれい」「みらい」利用課題公募(7/22)
■「朝日賞」候補者推薦(学会締切8/10)
■JAMSTEC生物地球化学研究分野研究員もしくは技術研究員公募(9/5)
■農林水産省経験者採用試験:係長級(技術)(募集期間8/5-8/18)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.348[東京・桜上水大会]全体日程表公開しました
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.348 2016/7/19┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[東京・桜上水大会]全体日程表公開しました
【2】[東京・桜上水大会]事前参加登録受付中です
【3】[東京・桜上水大会]参加申込に関わるQ & Aもご利用下さい
【4】学会創立125周年記念ロゴWEB投票(予告)
【5】第1回防災推進国民大会:大規模災害への備え〜過去に学び未来を拓く〜
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[東京・桜上水大会]全体日程表公開しました
──────────────────────────────────
東京・桜上水大会(9/10〜12:於 日本大学文理学部)の全体日程表を公開しま
した.各シンポ,セッションの予定をはじめ,普及行事や関連行事の日程も決
まりました.各講演(口頭・ポスター)の詳細プログラムは,後日講演者にご
連絡するとともに,大会HPに掲載予定です.大会プログラムは,例年同様ニュー
ス誌8月号掲載予定です.
全体日程表(PDF)は,大会HPよりご覧いただけます.
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0037.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[東京・桜上水大会]事前参加登録受付中です
──────────────────────────────────
■事前参加登録受付中です.
【大会参加登録】8月18日(木)締切
*講演申込と事前参加登録は,それぞれ別のお申し込みになります.講演申込
をした方は別途忘れずに参加登録もお手続き下さい.
【巡検申込】8月8日(金)締切
*コース詳細はこちら
→ http://www.geosociety.jp/tokyo/content0022.html
*コース別申込状況はこちら
→ http://www.geosociety.jp/tokyo/content0026.html
*詳しくは,大会HPまたはニュース誌5月号をご覧下さい.
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[東京・桜上水大会]参加申込に関わるQ & Aもご利用下さい
─────────────────────────────────
事前参加登録の際に会員から比較的多く寄せられるお問い合わせをQ & Aとして
まとめました.申込手続きでお困りの際は,ぜひご覧下さい.
大会申込Q&Aはこちら
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0036.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】学会創立125周年記念ロゴWEB投票(予告)
──────────────────────────────────
125周年を盛り上げるため,会員の皆様から記念ロゴマークのデザイン案を募集
いたしました(7/15締切).多数のご応募をいただきありがとうございました。
まもなく,会員によるWEB投票(一次選考)を予定しています.ぜひご協力をお
願い致します.
WEB投票期間: 7月25日(月)10:00 〜 8月22日(月)17:00
詳しくは, http://www.geosociety.jp/125th/content0006.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第1回防災推進国民大会:大規模災害への備え〜過去に学び未来を拓く〜
──────────────────────────────────
日程:平成28年8月27日(土)〜28日(日)
会場:東京大学本郷キャンパス
◆地質学会出展企画:「都市の地下を知って安全な社会を!」
日時:8月27日(土)10:00〜12:30
場所:理学部1号館 西棟2F206教室(定員120席)
日本国民の多くが住んでいる大都市の地下には、比較的若い時代の脆弱な地層
が厚く存在し,長周期地震動によって高層ビルが大きく揺れたり,液状化や地
盤沈下が起きたりしています.防災対策に必要不可欠な,ボーリング情報をは
じめとした地下の地質情報の収集・公開に関するセミナーです.
地質学会出展企画講演会のプログラムは下記から
http://www.geosociety.jp/news/n125.html
第1回防災推進国民大会WEBサイト→ http://bosai-kokutai.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[北海道支部]
■書籍「北海道自然探検 ジオサイト107の旅」出版
監修:日本地質学会北海道支部
出版社:北海道大学出版会
定価:2,800円+税(会員割引価格:2,240円+税)
*会員割引専用申込用紙あり
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[東北支部]
■2016年日本地質学会東北支部総会
8月27日(土)〜28日(日)
場所:弘前大学理工学部1号館2番講義室
27日(土)13:30〜支部総会議事,個人講演,18:00〜懇親会
28日(日)8:00〜津軽西海岸へのミニ巡検
締切:講演申込:8月17日(水) 要旨締切:8月22日(月)
懇親会参加申込:8月18日(木) 巡検参加申込:8月17日(水)
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■(後)大阪市立自然史博物館
第47回特別展「氷河時代 −化石でたどる日本の気候変動−」
7月16日(土)〜10月16日(日)
会場:大阪市立自然史博物館ネイチャーホール
観覧料:大人500円,高校生・大学生 300円
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
■(後)ジオパーク新潟国際フォーラム
7月27日(水)〜29日(金)
---27日:東アジアネットワーク ワークショップ
---28日:基調講演会,パネルディスカッションほか
---29日:見学会(佐渡コース,苗場山麓コース,糸魚川コース)
会場:朱鷺メッセ(新潟コンベンションセンター)
http://www.city.itoigawa.lg.jp/geopark-forum/
■第188回地質汚染イブニングセミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
7月29日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室(JR京浜東北線王子駅北口より3分)
講師:佐々木裕子(国立環境研究所環境リスク・健康研究センター,日本地質
汚染審査機構理事)
テーマ:化学物質汚染と子どもの健康ーエコチル調査
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■公開シンポジウム「大震災の起きない都市を目指して」
8月1日(月)13:00〜17:30
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木)
http://janet-dr.com/01_home_calendaer/201608/sympo20160801.pdf
■ワークショップ:
地球科学のための図の作成スキル -Adobe Illustratorの基本-
池原 実(高知大),株式会社SASAMI-GEO-SCIENCE 共催
8月19日(金)9:30〜16:00
会場:高知大学海洋コア総合研究センター
参加費:500円
参加申込締切:8月18日(木)
詳しくは, http://eventon.jp/4160
■第189回(上砂追悼)Specialイブニング・セミナー
8月19日(金)18:15〜21:00
場所:北とぴあ701会議室
講師:殿上義久・楡井 久ほか 1名または2名
テーマ:地震時の衝撃波・P波・S波による地質環境災害
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■第1回防災推進国民大会
8月27日(土)〜28日(日)
会場:東京大学本郷キャンパス
*地質学会の出展(講演会)「都市の地下を知って安全な社会を」(8/27)
も開催されます.
http://bosai-kokutai.jp/
■第35回万国地質学会議(35th IGC)
8月27日(土)〜9月4日(日)
会場:南アフリカ共和国ケープタウン
http://www.35igc.org/
■第33回歴史地震研究会(大槌大会)
9月11日(日)〜13日(火)
会場:⼤槌町中央公⺠館(岩⼿県上閉伊郡⼤槌町⼩鎚)
「大槌町津波アーカイブに向けたワークショップ」を予定しています.
http://sakuya.ed.shizuoka.ac.jp/rzisin/menu7.html
■(共)日本地球化学会第63回年会
9月14日(水)〜16日(金)
会場:大阪市立大学杉本キャンパス
http://www.geochem.jp/conf/2016/
■(共)第60回粘土科学討論会
9月15日(木)〜17日(土)
会場:九州大学医系キャンパス
http://www.cssj2.org/
■(後)藤原ナチュラルヒストリー振興財団神戸シンポジウム
ナチュラルヒストリー:これまでの貢献と今後へ期待
10月22 日(土) 13:30〜17:00
場所:兵庫県民会館けんみんホール
共催 兵庫県立人と自然の博物館
http://fujiwara-nh.or.jp/
■第9回HOPEミーティング―ノーベル賞受賞者との5日間―
2017年2月26日(日)〜3月2日(木)
主催:日本学術振興会
参加申込締切:9月5日(月)17:30
http://www.jsps.go.jp/hope/index.html
■第6回学生のヒマラヤ野外実習ツアー(参加者募集中)(日本地質学会推薦)
2017年3月4日〜18日(暫定日程)
コース:中西部ネパールヒマラヤの全断面で,ポカラを通る南北のルート
参加申込締切:11月30日(水)
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0151.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■山梨大学院総合研究部教育学域ポスドク研究員公募(断層岩の年代解析法の
開発)(8/12)
■東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教員の公募(8/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.349[東京・桜上水大会]プログラム公開/巡検申込まもなく締切
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.349 2016/8/2┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[東京・桜上水大会]講演プログラム公開しました
【2】[東京・桜上水大会]巡検申込まもなく締切です!
【3】[東京・桜上水大会]緊急展示申込受付中
【4】[東京・桜上水大会]参加申込に関わるQ&Aもご利用下さい
【5】学会創立125周年記念ロゴデザイン案:WEB投票実施中
【6】惑星地球フォトコンテスト:まもなく応募受付開始です
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】お知らせ:事務局夏期休業と次号配信予定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[東京・桜上水大会]講演プログラム公開しました
──────────────────────────────────
東京・桜上水大会の各シンポ・セッション毎の講演プログラム(PDF版)を公開
しました.今年は口頭・ポスターをあわせて計582件の講演が予定されています.
日程毎のプログラムは,後日公開予定です.
今後.会場や時間,演題情報に若干の変更・修正がある場合があります.最終
的には8月号ニュース誌掲載のプログラムをご確認下さい.
講演プログラムはこちら
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0037.html#program
全体日程表こちら
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0037.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[東京・桜上水大会]巡検申込まもなく締切です!
──────────────────────────────────
お急ぎ下さい!巡検申込まもなく締切です!
【巡検申込】8月8日(金)締切
巡検に参加される方は,締切までに忘れずにお申込下さい.
*コース詳細はこちら
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0022.html
*コース別申込状況(8/2, 17時現在)
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0026.html
【大会参加登録】8月18日(木)締切
*「講演申込」と「事前参加登録」は,それぞれ別のお申し込みになります.
講演申込をした方は別途忘れずに参加登録もお手続き下さい.
【その他,各種申込を受付中です】
・GISショートコース(8/31締切)
・防災施設見学(8/31締切)
・家族巡検(等々力渓谷)(8/31締切)
・サイエンスカフェ」
・地質関連企業研究サポート:出展企業募集中(8/10締切)
*詳しくは,大会HPまたはニュース誌5月号をご覧下さい.
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[東京・桜上水大会]緊急展示申込受付中
─────────────────────────────────
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害調査報告
や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コーナー」(ポスター発表
のみ)を設けます.優秀ポスター賞へのエントリーも可能です.
【緊急展示申込締切】8月31日(水)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/tokyo/content0033.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[東京・桜上水大会]参加申込に関わるQ & Aもご利用下さい
─────────────────────────────────
事前参加登録の際に会員から比較的多く寄せられるお問い合わせをQ & Aとして
まとめました.申込手続きでお困りの際は,ぜひご覧下さい.
大会申込Q&Aはこちら
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0036.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】学会創立125周年記念ロゴデザイン案:WEB投票実施中
──────────────────────────────────
125周年を盛り上げるため,会員の皆様から記念ロゴマークのデザイン案を募集
いたしました(7/15締切).多数のご応募をいただきありがとうございました.
現在,会員によるWEB投票(一次選考)を実施中です.
会員の皆さんからの“ワンクリック”をお待ちしています.ぜひ投票して下さい.
WEB投票締切:8月22日(月)17:00
詳しくは, http://www.geosociety.jp/125th/content0006.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】惑星地球フォトコンテスト:まもなく応募受付開始です
──────────────────────────────────
第8回惑星地球フォトコンテストの応募受付をまもなく開始いたします.今回よ
り応野外に出かける機会の多い「夏」に応募期間を設定することになりました.
皆さんの力作をお待ちしています.
応募作品受付(予定):8月10日(頃)〜12月31日(土)
詳しくは, http://photo.geosociety.jp/
★入選作品展示会のお知らせ★
8月2日(火)〜12日(金)9:00〜19:00(但し,土日祝日はお休み)
場所:NPC日本印刷株式会社 i-Shop(豊島区東池袋)
入場無料・どなたでもお気軽にご覧下さい
http://photo.geosociety.jp/#tenji
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[北海道支部]
■書籍「北海道自然探検 ジオサイト107の旅」出版
監修:日本地質学会北海道支部
出版社:北海道大学出版会
定価:2,800円+税(会員割引価格:2,240円+税)
*会員割引専用申込用紙あり
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[東北支部]
■2016年日本地質学会東北支部総会
8月27日(土)〜28日(日)
場所:弘前大学理工学部1号館2番講義室
27日(土)13:30〜支部総会議事,個人講演,18:00〜懇親会
28日(日)8:00〜津軽西海岸へのミニ巡検
締切:講演申込:8月17日(水) 要旨締切:8月22日(月)
懇親会参加申込:8月18日(木) 巡検参加申込:8月17日(水)
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■道総研「地質研究所ニュース」No. 32 発行
http://www.hro.or.jp/list/environmental/research/gsh/publication/gshnews/gshnews02/index.html
*************(以下,関連団体の行事案内です)****************
■(後)大阪市立自然史博物館
第47回特別展「氷河時代 −化石でたどる日本の気候変動−」
7月16日(土)〜10月16日(日)
会場:大阪市立自然史博物館ネイチャーホール
観覧料:大人500円,高校生・大学生 300円
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
■第189回(上砂追悼)Specialイブニング・セミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
8月19日(金)18:15〜21:00
場所:北とぴあ701会議室
講師:殿上義久・楡井 久ほか 1名または2名
テーマ:地震時の衝撃波・P波・S波による地質環境災害
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■地質学講座1「赤磐市域の地質の成り立ち」(JCCA CPD認定プログラム)
8月21日(日)13:00〜16:00
会場:赤磐市中央公民館(岡山県赤磐市下市337)
講演者:板谷徹丸氏(jGnet, 前岡山理大),鈴木茂之氏(jGnet, 岡山大)石
渡 明氏(原子力規制委員会,元東北大),乙藤洋一郎氏(jGnet, 神戸大名誉
教授)
http://jgnet.org/
*jGnet(NPO法人地球年代学ネットワーク)は,岡山県赤磐市との共催により,
一般向け講演会である地質学講座を開催致します.
■第1回防災推進国民大会
8月27日(土)〜28日(日)
会場:東京大学本郷キャンパス
*日本地質学会の出展(講演会)「都市の地下を知って安全な社会を」(8/27)
も開催されます.
http://bosai-kokutai.jp/
■第35回万国地質学会議(35th IGC)
8月27日(土)〜9月4日(日)
会場:南アフリカ共和国ケープタウン
http://www.35igc.org/
■日本学術会議主催学術フォーラム
「若手生命科学研究者のキャリアパスについて考える
〜卓越研究員制度の現状と未来,そしてさらなる可能性〜」
9月12日(月)13:00〜17:00
場所:東京大学本郷キャンパス小柴ホール
主催:日本学術会議(先着150名,参加費無料)
https://form.cao.go.jp/scj/opinion-0003.html
■(共)日本地球化学会第63回年会
9月14日(水)〜16日(金)
会場:大阪市立大学杉本キャンパス
http://www.geochem.jp/conf/2016/
■(共)第60回粘土科学討論会
9月15日(木)〜17日(土)
会場:九州大学医系キャンパス
http://www.cssj2.org/
■(後)藤原ナチュラルヒストリー振興財団神戸シンポジウム
ナチュラルヒストリー:これまでの貢献と今後へ期待
10月22 日(土) 13:30〜17:00
場所:兵庫県民会館けんみんホール
共催 兵庫県立人と自然の博物館
http://fujiwara-nh.or.jp/
■第8回ネパール地質学会
11月27日(日)〜29日(火)
場所:カトマンズ
「ネパールの発展と災害対応に役立つ地球科学」を学会の主テーマとし,
2015年ネパール地震の特別セッションを予定.
発表要旨締切:9月30日
http://www.ngs.org.np
■地質学史懇話会のお知らせ
12月23日(金・祝)13:00-17:00
場所:北とぴあ8階803号室
眞島英壽「日本海の起源をめぐる言説について」(仮)
石原舜三「日本の花崗岩研究史」(仮)
■第6回学生のヒマラヤ野外実習ツアー(参加者募集中)(日本地質学会推薦)
2017年3月4日〜18日(暫定日程)
コース:中西部ネパールヒマラヤの全断面で,ポカラを通る南北のルート
参加申込締切:11月30日(水)
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
■原子力構造工学国際会議(Abstract募集中)
2017年8月20日(日)〜25日(金)
会場:韓国・釜山
★Abstract募集中★2016年9月2日(金)締切
http://www.aesj.or.jp/information/smirt24.pdf(国内向け投稿依頼文)
http://www.smirt24.org/s/s04
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0151.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■岡山理科大学生物地球学部生物地球学科(恐竜・古生物)講師・助教公募(9/7)
■岐阜大学工学部社会基盤工学科(地球環境工学)教授公募(9/30)
■島根大学大学院総合理工学研究科地球資源環境学領域教員(准教授,講師または助教)公募(9/30)
■東京大学地震研究所(火山地質学分野)准教授公募(10/3)
■平成29年度笹川科学研究助成【学術研究部門】(10/1-14)
■東京大学海洋研究所学術研究船新青丸共同利用公募(9/9)
■第38回沖縄研究奨励賞推薦応募(学会締切:9/15)
■2017年度瀬戸内海文化研究・活動支援助成(9/1-9/30)
■2017年度山田科学振興財団研究費助成(学会締切:2017/1/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】お知らせ:事務局夏期休業と次号配信予定
──────────────────────────────────
下記の期間,事務局は夏期休業となります.
8月11日(木・祝)〜16日(火)
次回geo-Flashの配信は,8月17日(水)となります.ご了承下さい.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.350[東京・桜上水大会]参加登録締切延長:19日(金)10時
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.350 2016/8/17┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[東京・桜上水大会]事前参加登録締切延長:19日(金)午前10時
【2】[東京・桜上水大会]その他各種申込も受付中です
【3】[東京・桜上水大会]緊急展示申込受付中
【4】[東京・桜上水大会]参加申込に関わるQ & Aもご利用下さい
------------------------------------------------------------------------------
【5】創立125周年記念ロゴデザイン案:WEB投票実施中
【6】惑星地球フォトコンテスト:応募受付中
【7】支部情報
【8】上砂さんを偲ぶ会(日本地質学会理事)
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[東京・桜上水大会]事前参加登録締切延長:19日(金)午前10時──────────────────────────────────
【大会参加登録】8月19日(金)午前10時(延長します)
システム上の問題で,一時的に事前参加登録の申込画面がcloseしており,申込
手続きが出来ない状態になっていました(停止期間:8/15 24時〜8/17 10時頃).
至急担当者に確認し,8月17日10時現在,事前参加登録システムが復旧いたしま
した.会員の皆様には,ご迷惑をおかけし大変申し訳ありませんでした.
この不具合による影響をカバーするため,若干ですが申込締切を延長いたします.
まだ少しお時間がありますので,是非参加登録のお手続きを行って下さい.
*「講演申込」と「事前参加登録」は,それぞれ別のお申し込みになります.
講演申込をした方も別途忘れずに参加登録もお手続き下さい.
事前参加登録はこちらから
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0016.html
講演プログラムはこちら
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0037.html#program
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[東京・桜上水大会]その他各種申込も受付中です
──────────────────────────────────
その他各種申込も受付中です
・GISショートコース(8/31締切:定員間近です.お早めにお申込下さい)
・防災施設見学(8/31締切)
・家族巡検(等々力渓谷)(8/31締切)
・サイエンスカフェ(8/31締切)
・教師巡検(10/1実施)(9/16締切)
*詳しくは,大会HPまたはニュース誌5月号をご覧下さい.
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0040.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[東京・桜上水大会]緊急展示申込受付中
─────────────────────────────────
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害調査報告
や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コーナー」(ポスター発表
のみ)を設けます.優秀ポスター賞へのエントリーも可能です.
【緊急展示申込締切】8月31日(水)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/tokyo/content0033.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[東京・桜上水大会]参加申込に関わるQ & Aもご利用下さい
─────────────────────────────────
事前参加登録の際に会員から比較的多く寄せられるお問い合わせをQ & Aとして
まとめました.申込手続きでお困りの際は,ぜひご覧下さい.
大会申込Q&Aはこちら
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0036.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】学会創立125周年記念ロゴデザイン案:WEB投票実施中
──────────────────────────────────
125周年を盛り上げるため,会員の皆様から記念ロゴマークのデザイン案を募集
いたしました(7/15締切).多数のご応募をいただきありがとうございました.
現在,会員によるWEB投票(一次選考)を実施中です.
会員の皆さんからの“ワンクリック”をお待ちしています.ぜひご投票下さい.
WEB投票締切:8月22日(月)17時
詳しくは, http://www.geosociety.jp/125th/content0006.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】惑星地球フォトコンテスト:応募受付中
──────────────────────────────────
第8回惑星地球フォトコンテストの応募受付をまもなく開始いたします.今回よ
り野外に出かける機会の多い「夏」に応募期間を設定することになりました.
皆さんの力作をお待ちしています!
応募作品受付:12月31日(土)
詳しくは, http://photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[北海道支部]
■書籍「北海道自然探検 ジオサイト107の旅」出版
監修:日本地質学会北海道支部
出版社:北海道大学出版会
定価:2,800円+税(会員割引価格:2,240円+税)
*会員割引専用申込用紙あり
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[東北支部]
■2016年日本地質学会東北支部総会
8月27日(土)〜28日(日)
場所:弘前大学理工学部1号館2番講義室
27日(土)13:30〜支部総会議事,個人講演,18:00〜懇親会
28日(日)8:00〜津軽西海岸へのミニ巡検
締切:要旨締切:8月22日(月)
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】上砂さんを偲ぶ会(日本地質学会理事)
──────────────────────────────────
日本地質学会理事上砂正一会員が在任中の4月に急逝されました.会員の皆様に
偲ぶ会のご案内をお知らせ致します.謹んでご冥福をお祈り申し上げます.
9月24日(土)16:00〜18:00
主催:NPO法人日本地質汚染審査機構
会場:東海大学交友会館東海三保霞(千代田区霞が関3-2-5)
参加申込締切:9月16日(金)厳守
出欠連絡先担当:大箸 yoshito.oh@tx.thn.ne.jp > FAX 0545-61-3307
*追悼文関連(希望者)
提出先: kbc@npo-geopol.or.jp > 提出期限:9月9日(金)厳守
詳しくは,下記問い合わせ先まで.
問い合わせ先:NPO法人日本地質汚染審査機構
電話:043-213-8507 FAX:043-213-8508 office@npo-geopol.or.jp >
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■国際地学オリンピックニュースvol.10
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/name/olymp/kokusai_chiori_news_2016.8.pdf
*************(以下,関連団体の行事案内です)****************
■第189回(上砂追悼)Specialイブニング・セミナー
日本地質学会環境地質部会 共催
8月19日(金)18:15〜21:00
場所:北とぴあ701会議室
講師:殿上義久・楡井 久ほか 1名または2名
テーマ:地震時の衝撃波・P波・S波による地質環境災害
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■第1回防災推進国民大会
8月27日(土)〜28日(日)
会場:東京大学本郷キャンパス
*日本地質学会の出展(講演会)「都市の地下を知って安全な社会を」(8/27)
も開催されます.
http://bosai-kokutai.jp/
■第35回万国地質学会議(35th IGC)
8月27日(土)〜9月4日(日)
会場:南アフリカ共和国ケープタウン
http://www.35igc.org/
■公開シンポジウム「熊本地震を踏まえた地域防災力強化の在り方 in東京」
コミュニティ防災の現場からみる地区防災計画制度の可能性と課題
主催:地区防災計画学会
9月6日(火)14:00〜17:00
場所:東京大学生産技術研究所S棟ホール(目黒区駒場)
参加申込締切:9月4日(日)
http://www.gakkai.chiku-bousai.jp/ev160906.html
■(共)日本地球化学会第63回年会
9月14日(水)〜16日(金)
会場:大阪市立大学杉本キャンパス
http://www.geochem.jp/conf/2016/
■(共)第60回粘土科学討論会
9月15日(木)〜17日(土)
会場:九州大学医系キャンパス
http://www.cssj2.org/
■第31回技術サロン(技術者及び技術士を目指す女子学生・女性社会人へ)
9月17日(土)13:30〜16:00
場所:日本技術士会葺手第二ビル5階
対象:技術者及び技術士を目指す女子学生・女性社会人
※技術士の方はご遠慮ください.
内容:『技術士』資格に関する説明及び懇話会
参加費無料
http://www.engineer.or.jp/c_cmt/danjyo/topics/004/004612.html
■(後)第7回日本ジオパーク全国大会(伊豆半島大会)
10月10 日(月)〜12日(水)
場所:静岡県沼津市・プラザ ヴェルテほか
http://7th-jgn-izu-peninsula.jimdo.com/
■(後)藤原ナチュラルヒストリー振興財団神戸シンポジウム
ナチュラルヒストリー:これまでの貢献と今後へ期待
10月22 日(土) 13:30〜17:00
場所:兵庫県民会館けんみんホール
共催 兵庫県立人と自然の博物館
http://fujiwara-nh.or.jp/
■第6回学生のヒマラヤ野外実習ツアー(参加者募集中)(日本地質学会推薦)
2017年3月4日〜18日(暫定日程)
コース:中西部ネパールヒマラヤの全断面で,ポカラを通る南北のルート
参加申込締切:11月30日(水)
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0151.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・東京工業大学理学院地球惑星科学系(助教)公募(9/30)
・山梨大学院総合研究部教育学域ポスドク研究員公募(断層岩の年代解析法の開発)
(9/12)締切が延長されました
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.352[東京・桜上水大会]いよいよ学術大会が始まります!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.352 2016/9/6┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[東京・桜上水大会]いよいよ学術大会が始まります
【2】[東京・桜上水大会]予約確認書を発送しました
【3】[東京・桜上水大会]「県の石」制定記念「県の酒」開催します
【4】[東京・桜上水大会]学術大会でCPD単位が取得出来ます
【5】[東京・桜上水大会]講演キャンセル・変更など(9/6現在)
【6】[東京・桜上水大会]参加申込に関わるQ & Aもご利用下さい
------------------------------------------------------------------------------
【7】2016年度秋季地質調査研修参加者募集のご案内
【8】惑星地球フォトコンテスト:応募受付中
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[東京・桜上水大会]いよいよ学術大会が始まります
──────────────────────────────────
いよいよ東京・桜上水大会が始まります(9月10日〜12日).
初日には,会員顕彰式・各賞表彰式・受賞記念講演・懇親会等が予定されてお
りますので,ぜひ多くの皆様のご参加をお待ちしています.学術大会を,盛り
上げて行きましょう!!
↓ ↓大会HP ↓ ↓
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0001.html
↓ ↓全体日程表↓ ↓
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0037.html
↓ ↓講演プログラム↓ ↓
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0037.html#program
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[東京・桜上水大会]予約確認書を発送しました
──────────────────────────────────
東京・桜上水大会の事前参加登録をした方(参加費合計額が有料の方)に宛て
て,確認書や記名済の名札,クーポン類(懇親会やお弁当を注文された方のみ)
を発送いたしました(9/2(金)発送).
年会当日は,確認書の【受付提出用】の書類を忘れずにご持参ください.受付
にて,全員にご提出をいただきます.
なお,参加登録費の合計金額が0円の方には別途メールでご案内をいたします.
【未入金の方へ】確認書発送時点で一部入金もしくは,入金確認が取れていな
い方へは当日払いの参加費に金額訂正した確認書のみをお送りしました.当日
会場にてご清算をお願いいたします.
【お願い】事前参加登録をキャンセルしたい場合には,必ず日本地質学会事務
局までご一報ください(申込項目により取消料が異なります).
変更・取消については下記をご参照ください.
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0018.html#cansel
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[東京・桜上水大会]「県の石」制定記念「県の酒」開催します
──────────────────────────────────
「県の石」制定を記念して,東京・桜上水大会懇親会にて,各県のお酒を集め
て「県の酒」イベントを開催いたします.懇親会は当日参加も受け付けており
ます.奮ってご参加下さい.
(注)当日受付分は数に限りがあります.参加希望の方は,午前中早めにお申
込下さい.
懇親会については,
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0023.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[東京・桜上水大会]学術大会でCPD単位が取得出来ます
──────────────────────────────────
日本地質学会は,地質技術者への継続教育の一環として,大会参加者・発表者・
巡検参加者へCPD単位を発行します.大会参加と口頭/ポスター発表の参加証明
書を当日会場で発行します.
【発行単位】
・ 学術大会参加に対するCPD(時間に応じて):例)7時間出席 = 7単位
・ 口頭発表に対するCPD:0.4 ×15分発表 = 6単位
・ ポスター発表に対するCPD:2単位
・ 巡検参加に対するCPD:日帰り-8単位,1泊2日-16単位
詳しくは, http://www.geosociety.jp/tokyo/content0049.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[東京・桜上水大会]講演キャンセル・変更など(9/6現在)
─────────────────────────────────
◆講演キャンセル
T2-P-2:高清水康博ほか「日本海東縁変動帯に位置する飛島の完新世段丘中に
挟在する古津波堆積物
T3-O-7:澤畑優理恵「棚倉断層沿いに発達するstrike-slip basinを埋積する新
第三系の古地磁気学的研究」
R1-O-3:大和田正明「西南日本,白亜紀火成活動の形成年代と組成変化」
◆プログラム:発表者訂正
R9-O-3 加藤大和「炭酸凝集同位体温度計の実態と陸域炭酸塩岩への適用」
(誤)狩野彰宏
(正)加藤大和
(注)講演キャンセルをする場合は,必ず事前に行事委員会(会期前は学会事
務局,会期中は学会本部)に連絡して下さい.
また,やむを得ない事情により,あらかじめ連記された共同発表者内で発表者
の変更を希望する場合も,必ず事前に行事委員会(会期前は 学会事務局,会期
中は学会本部)に連絡して下さい.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[東京・桜上水大会]参加申込に関わるQ & Aもご利用下さい
─────────────────────────────────
事前参加登録の際に会員から比較的多く寄せられるお問い合わせをQ & Aとして
まとめました.申込手続きでお困りの際は,ぜひご覧下さい.
大会申込Q&Aはこちら
http://www.geosociety.jp/tokyo/content0036.html#sanka
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】2016年度秋季地質調査研修参加者募集のご案内
──────────────────────────────────
実施地域:千葉県君津市とその周辺(房総半島中部の清澄山系とその周辺)
主催:日本地質学会
共催:産総研地質調査総合センター
実施期間:2016年11月14日(月)〜18日(金)(4泊5日)
講師:徳橋秀一氏(産総研地圏資源環境研究部門客員研究員),
細井 淳氏(産総研地質情報研究部門研究員)
主な対象:地質関連会社の若手技術者
参加費:一人12万円(往復交通費や宿泊費等は参加者負担)
定員:6名(申込順.定員に達し次第,申込受付を終了します.4名に達しなかっ
た場合は実施を中止します.)
申込受付期間:2016年9月15日(木)〜10月14日(金)
問合せ先:日本地質学会事務局 Tel.03-5823-1150
E-mail: main@geosociety.jp
詳しくは, http://www.geosociety.jp/engineer/content0043.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】惑星地球フォトコンテスト:応募受付中
──────────────────────────────────
第8回惑星地球フォトコンテストの応募受付中です!今回より野外に出かける
機会の多い「夏」に応募期間を設定することになりました.
皆さんの力作をお待ちしています!
応募作品受付:12月31日(土)
詳しくは, http://photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■(共)日本地球化学会第63回年会
9月14日(水)〜16日(金)
会場:大阪市立大学杉本キャンパス
http://www.geochem.jp/conf/2016/
■(共)第60回粘土科学討論会
9月15日(木)〜17日(土)
会場:九州大学医系キャンパス
http://www.cssj2.org/
■NUMO セーフティケースに関する外部専門家ワークショップ
(1) 大阪会場(定員:100 名)
9月21日(水)9:30〜17:30
会場:大阪科学技術センタービル4階401号室
(2)東京会場(定員:120 名)
9月23日(金)9:30〜17:30
会場:三田NN ビル地下1階三田NN ホール
参加費:無料 参加申込締切:9月16日(金)
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/geoFlash_img/no351_NUMO_geoflash160906.pdf
■第190回地質汚染イブニング・セミナー
場所:北とぴあ901会議室
9月30日(金)18:30〜20:30
講師:伊藤和明(元NHK解説委員)
テーマ:災害取材体験からの東日本大震災と熊本地震
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■(後)第7回日本ジオパーク全国大会(伊豆半島大会)
10月10 日(月)〜12日(水)
場所:静岡県沼津市・プラザ ヴェルテほか
http://7th-jgn-izu-peninsula.jimdo.com/
■(後)藤原ナチュラルヒストリー振興財団神戸シンポジウム
ナチュラルヒストリー:これまでの貢献と今後へ期待
10月22 日(土) 13:30〜17:00
場所:兵庫県民会館けんみんホール
共催 兵庫県立人と自然の博物館
http://fujiwara-nh.or.jp/
■2016年度地球惑星科学学生と若手の会
学部生・大学院生・若手研究者・地球惑星科学に興味を持つ方であればどなた
でもご参加頂けます!
11月12日(土)〜13日(日)
場所:東京大学 本郷キャンパス (東京都文京区)
内容:講演,参加者同士の研究交流,グループディスカッション,懇親会など
申込締切:10月28日 (金)
https://sites.google.com/site/nyswakate/2016
■第6回学生のヒマラヤ野外実習ツアー(参加者募集中)(日本地質学会推薦)
2017年3月4日〜18日(暫定日程)
コース:中西部ネパールヒマラヤの全断面で,ポカラを通る南北のルート
参加申込締切:11月30日(水)
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0151.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・東京工業大学理学院地球惑星科学系(教授)公募(10/7)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.356 東京・桜上水大会終了しました
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.356 2016/9/20┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】東京・桜上水大会 終了しました!
【2】惑星地球フォトコンテスト:応募受付中
【3】イタリアのラクイラ地震裁判その後
【4】「The Geology of Japan」正誤表
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】東京・桜上水大会 終了しました!
─────────────────────────────────
今年は1,000名以上の方々にご参加いただき,盛会のうち東京・桜上水大会は終
了いたしました.大会の報告記事は,ニュース誌11月号に掲載予定です.
大会様子(写真)はこちらからご覧いただけます.
http://www.geosociety.jp/faq/content0669.html
http://www.geosociety.jp/faq/content0670.html
http://www.geosociety.jp/faq/content0671.html
[忘れもが1点届いています.お心当たりの方は事務局まで]
・グレーの図面ケース(筒形)
来年は,愛媛・松山でお会いしましょう!!
◆日本地質学会第124年学術大会(松山大会)
2017年9月16日(土)〜18日(月)
会場:愛媛大学理学部ほか(松山市文京)
(注)松山市内では同期間中に医学系など他学会の開催が予定されています.
宿泊予約が混み合うことが予想されますので,早めの宿泊予約をお勧め致しま
す(近年学会を通じての宿泊手配は行っていません.各自でお手配をお願いし
ます).
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】惑星地球フォトコンテスト:応募受付中
──────────────────────────────────
第8回惑星地球フォトコンテストの応募受付中です!今回より野外に出かける
機会の多い「夏」に応募期間を設定することになりました.
皆さんの力作をお待ちしています!
応募作品受付締切:2017年1月10日(火)
(締切日の訂正)
(誤)2016年12月31日→(正)2017年1月10日
詳しくは,http://photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】イタリアのラクイラ地震裁判その後
──────────────────────────────────
石渡 明・ウォリス サイモン・渡部芳夫
2012年11月2日,当時の日本地質学会会長(石渡),副会長(ウォリス・渡部),
部会長・理事一同の名で,イタリアのラクイラ地震裁判において地球科学者に
有罪判決が出たことについて,同学会としての「憂慮」をホームページに和文
と英文で表明した(URLは下記).この裁判について,その後の経過を調べてみ
たので,簡単に報告する.
【地震の概要】
2009年4月6日にイタリア中部のラクイラ(L'Aquila)の街をM6.3の地震が襲い,
多くの家屋が倒壊して308人が死亡し約1500人が負傷した.それまでの数カ月間,
この地域では群発地震が続いており,地元の研究者がラドンの観測から大地震
が起こる可能性を公表したので,人々は不安に感じ,屋外に避難していた住民
も多かった.本震6日前の3月31日,政府の防災当局の責任者と地震学者らが現
地に集まって検討会を行い,メディアを通じて「大きな地震が起きる心配はな
い.家の中で寝ても安全だ.」という趣旨の発表を行った.これを聞いて,自
宅に戻って生活を再開した住民も多かったが,その6日後に大地震が起きて多く
の犠牲者が出た.
【裁判の開始】
地震前の現地検討会に出席して「安全会見」を行った防災当局の責任者と地震
学者ら計7人を,この地震による犠牲者の遺族らが地元の裁判所に殺人罪で告訴
し,裁判が始まった.2012年10月に地元の裁判所は7人の被告全員に6年の懲役
と巨額の罰金を課す有罪判決を言い渡した.判決によると,被告らは「地震予
知に失敗した」ことにではなく,「地震の危険に対して『表面的で大雑把で根
拠のない』(superficial, approximate (or ineffective)and generic)評価を
行った」ことに対して有罪とされた(英訳語は記事によって異なる).本学会
はこの判決に対して同年11月2日に憂慮を表明した.
日本地質学会声明「ラクイラ地震裁判における科学者への実刑判決を憂慮する」
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//pubcome/20121102L%27Aquila_Concern_jp.pdf
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//pubcome/20121102L%27Aquila_Concern_en.pdf
【上告審】
被告らは判決を不服として上告し,2014年11月10日に上告審の裁判官らは,被
告のうち地震学者3人,火山学者1人,地震技術者2人の計6人に対して無罪を言
い渡し,防災当局の責任者1人に対しては,執行猶予のついた懲役2年の有罪判
決を言い渡した.原告側はこれを不服として最高裁に上告した.
防災当局の現地責任者だったDe Bernardinis氏の有罪の主な理由は,彼が現地
検討会の前に独自の判断で「大地震の心配はなく安全だ」という趣旨のコメン
トをマスコミに流したことらしい(検討会の結論は,群発地震によって大地震
の可能性が高くなったとも低くなったとも言えないという「中立的」なものだっ
たと上告審は判断し,地震学者らを無罪にしたようだ).
2014年11月18日の米国地球物理連合EOSの記事
(地震学者ら6人の無罪判決について)
https://eos.org/articles/six-laquila-seven-acquitted-appeal
2014年10月30日のEOSの「「ラクイラの7人」の上告審」という記事(これは判
決が出る前の執筆だが,この記事には7人の氏名・所属・専門を示す表がある.)
http://sites.agu.org/wp-content/uploads/2014/10/LAquila_7.pdf
【最高裁の判決】
地元での裁判開始から約5年を経て,2015年11月20日,最高裁は上告を棄却し,
前年の下級審の判決(6人無罪,1人有罪)が確定した.有罪になったのは地震
発生当時のイタリア政府の公衆保安局の課長で,現地で検討会や記者会見を取
り仕切ったBernardo De Bernardinis氏であるが,彼の上司で局長だったGuido
Bertolaso氏の責任を問う別の裁判はまだ続いている.
2015年11月20日のScience誌の記事(最高裁判決)
(DOI:10.1126/science.aad7473)
http://www.sciencemag.org/news/2015/11/italy-s-supreme-court-clears-l-aquila-earthquake-scientists-good
以上のように,ラクイラで続いていた地震活動の今後の見通しについて,専門
家として意見を求められた学者に対して,初審で有罪判決が下されたことにつ
いて,我々が表明した「憂慮」は,その後の上級審の妥当な判決によって解消
されたようである.しかし,今回のラクイラ地震裁判によって,自然災害につ
いて研究者と政府機関が地域住民や一般社会に対してどのタイミングでどのよ
うな情報を発信すべきかに関する問題点が浮き彫りになった.地域住民や一般
社会の安全確保に我々の研究成果がどう生かせるか,時と場合に応じて伝える
べき情報は何か,それをいつどのように伝えるか,住民の安全を第一によく考
え,慎重に判断しながら,我々地球科学分野の研究者が防災・減災活動に参画
していかなければならない事を,今回の事件によって再認識させられたように
思う.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】「The Geology of Japan」正誤表
──────────────────────────────────
日本地質学会と学術交流協定を締結しているロンドン地質学会の出版物であります
「The Geology of Japan」について,編著者より訂正のご連絡がありましたので,
お知らせします.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/news/n126.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報
──────────────────────────────────
[北海道支部]
■秋巡検「三笠ジオパークと蝦夷層群の地質を学ぶ」
10月22日(土)〜23日(日)1泊2日(1日だけの参加も可)
参加費:会員5,000円(2日間参加の場合)
定員:18名
申込締切:10月12日(水)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地震本部ニュース平成28年度夏号発行
http://www.jishin.go.jp/herpnews/
■NUMO セーフティケースに関する外部専門家ワークショップ
(1)大阪会場(定員:100 名)
9月21日(水)9:30〜17:30
会場:大阪科学技術センタービル4階401号室
(2)東京会場(定員:120 名)
9月23日(金)9:30〜17:30
会場:三田NN ビル地下1階三田NN ホール
参加費:無料 参加申込締切:9月16日(金)
詳しくは,
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/geoFlash_img/no351_NUMO_geoflash160906.pdf
■第190回地質汚染イブニング・セミナー
場所:北とぴあ901会議室
9月30日(金)18:30〜20:30
講師:伊藤和明(元NHK解説委員)
テーマ:災害取材体験からの東日本大震災と熊本地震
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■(後)第7回日本ジオパーク全国大会(伊豆半島大会)
10月10 日(月)〜12日(水)
場所:静岡県沼津市・プラザ ヴェルテほか
http://7th-jgn-izu-peninsula.jimdo.com/
■(後)藤原ナチュラルヒストリー振興財団神戸シンポジウム
ナチュラルヒストリー:これまでの貢献と今後へ期待
10月22 日(土) 13:30〜17:00
場所:兵庫県民会館けんみんホール
共催 兵庫県立人と自然の博物館
http://fujiwara-nh.or.jp/
■東北大学多元物質科学研究所:イノベーション・エクスチェンジ2016
10月27日(木)13:00〜17:30
場所:東北大学片平さくらホール
入場無料
参加申込締切:10月14日(金)
http://www2.tagen.tohoku.ac.jp/general/event/Innovation_Exchange/2016/
■2016年度地球惑星科学学生と若手の会
学部生・大学院生・若手研究者・地球惑星科学に興味を持つ方であればどなた
でもご参加頂けます!
11月12日(土)〜13日(日)
場所:東京大学 本郷キャンパス (東京都文京区)
内容:講演,参加者同士の研究交流,グループディスカッション,懇親会など
申込締切:10月28日(金)
https://sites.google.com/site/nyswakate/2016
■第6回学生のヒマラヤ野外実習ツアー(参加者募集中)(日本地質学会推薦)
2017年3月4日〜18日(暫定日程)
コース:中西部ネパールヒマラヤの全断面で,ポカラを通る南北のルート
参加申込締切:11月30日(水)
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0151.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■東京大学地震研究所平成29年度客員教員公募(10/31)
■都留文科大学学校教育学科(仮称)の専任教員(地学)募集(10/31)
■京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻教授公募(10/31)
■静岡大学理学部地球科学科教員(助教)公募(11/30)
■名古屋大学大学院環境学研究科地球環境科学専攻(准教授)(10/31)
■2017年度山田科学振興財団研究援助候補推薦依頼(17/2/14)
■平成29年東京大学地震研究所共同利用(10/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.357 2017年度各賞候補者募集開始
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.357 2016/10/4┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2017年度各賞候補者募集開始
【2】「院生割引会費」受付開始:2017年度会費払込について
【3】『フィールドジオロジー全9巻』電子本の販売が開始されました
【4】惑星地球フォトコンテスト:応募受付中
【5】男女共同参画学協会連絡会大規模アンケートへのご協力のお願い
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2017年度各賞候補者募集開始
──────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして,研究の援助・奨励および研究業
績の表彰を行っています.本年も各賞の自薦,他薦による候補者を募集いたし
ます.期日厳守にて,たくさんのご応募をお待ちしております.
応募締切:2016年11月30日(水)必着
推薦書式,対象論文リストなど詳しくは,
http://sub.geosociety.jp/members/content0094.html(会員のページ)
※「会員のページ」へは会員番号・パスワードによるログインが必要です.
ログインの方法はこちら.
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】「院生割引会費」受付開始:2017年度会費払込について
─────────────────────────────────
運営規則により,次年分の会費を前納下さいますようお願いいたします.
学部学生の方,定収のない大学院生(研究生)の方は,早めに割引会費の申請
を行って下さい.割引の適用を希望する場合,申請は毎年必要です.
割引会費申請締切(請求書発行前締切):2016年11月21日(月)
2017年度会費払込について(割引申請の書式もこちらから)
http://www.geosociety.jp/outline/content0164.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】『フィールドジオロジー全9巻』電子本の販売が開始されました.
──────────────────────────────────
(フィールドジオロジー刊行委員会編集幹事 天野一男)
フィールドジオロジーシリーズは,2004年4月に第1巻(フィールドジオロジー
入門)と第3巻(堆積物と堆積岩)の出版を皮切りとして,2015年9月に第8巻(
火成作用)と第9巻(第四紀)が出版されて,全巻完結しました.10年以上の長
期間にわたっての出版でしたが,著者の皆様の努力と読者からの励ましで,全
巻を出版することができました.読者対象を,地質学専攻の学部学生,専門は
異なるが地質学の基礎を学びたい大学院生・実務担当者・地質技術者,アマチュ
アとしたこともあり,順調に販売の実績をあげています.会員の皆様はじめ,
読者のご支援のたまものと感謝しています.
フィールドに直接持参し露頭の前で開いて使うことを考え,本の大きさを調
査鞄に入るB5版としました.しかし,全9巻を重ねると11.5 cmの厚さになり,
とても一度にフィールドに持っていくことはできません.全9巻を露頭の前で活
用してもらうためにも,本書の電子化は長年の課題でした.電子本は,Amazon
で購入してKindleで読むことができます.また,スマートフォンやタブレット
でも読むことができます.最近では,防水のスマートフォンも発売されていま
すので,野外で活用する条件がますます整ってきたと思います.これを機会に,
ぜひご購入ください.
Googleによる様々な検索,シームレス地質図,電子クリノメーターもあわせ
て使うことにより,より深い露頭観察が可能になります.IT技術を活用した新
しい時代の野外調査の展開といえるのではないでしょうか.野外調査の武器は,
古典的にハンマー,ルーペ,クリノメーターと決まっていましたが,近年新た
な武器が加わってきました.新しい武器とともに21世紀型の新しい地質調査法
が生まれることを期待しています.
▶▶Amazon_Kindle版の購入はこちらから,
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4320046811?ie=UTF8&tag=kyoritsu-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4320046811
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】惑星地球フォトコンテスト:応募受付中
──────────────────────────────────
第8回惑星地球フォトコンテストの応募受付中です!
今年も皆さんの力作をお待ちしています!
応募作品受付:2017年1月10日(火)
詳しくは,http://photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】男女共同参画学協会連絡会大規模アンケートへのご協力のお願い
──────────────────────────────────
男女共同参画学協会連絡会(以下、連絡会)は、自然科学系の学術団体53団体
が正式に加盟し、37団体がオブザーバー参加している団体にて、学協会間での
連携協力を行いながら、科学技術の分野において、女性と男性がともに個性と
能力を発揮できる環境づくりとネットワーク作りを行い、社会に貢献すること
を目的としています。
この連絡会にて、自然科学系の研究者・技術者を取り巻く現状を把握するため
に4,5年に一度、対象者を自然科学系の産学の研究者、技術者、学生として、
回答数約20,000のアンケートを実施しております。
https://wss2.5star.jp/survey/index/n3dd5zyv/9390/
【アンケート回答期間】2016年10月8日(土)〜28日(金)
回答に要する時間は、約20分間です。
本アンケートの内容は、内閣府を通して、政府の男女共同参画の施策に反映さ
れてきており、その重要性は広く認識されております。
ぜひ、ご協力をいただきたく、お願い致します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[北海道支部]
■秋巡検「三笠ジオパークと蝦夷層群の地質を学ぶ」
10月22日(土)〜23日(日)1泊2日(1日だけの参加も可)
参加費:会員5,000円(2日間参加の場合)
定員:18名
申込締切:10月12日(水)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■(後)第7回日本ジオパーク全国大会(伊豆半島大会)
10月10 日(月)〜12日(水)
場所:静岡県沼津市・プラザ ヴェルテほか
http://7th-jgn-izu-peninsula.jimdo.com/
■深田研一般公開2016
10月16日(日)10:00〜16:00
入場無料・申込不要
講演:アンモナイトの死殻は浮くか沈むか:前田晴良
mini講演&実演:富士山の謎をみんなで解明してみよう:池田 宏
http://www.fgi.or.jp
■(後)藤原ナチュラルヒストリー振興財団神戸シンポジウム
ナチュラルヒストリー:これまでの貢献と今後へ期待
10月22 日(土) 13:30〜17:00
場所:兵庫県民会館けんみんホール
共催 兵庫県立人と自然の博物館
http://fujiwara-nh.or.jp/
■第191回地質汚染イブニング・セミナー
10月28日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:水谷和子(一級建築士)
テーマ:豊洲地質汚染問題 状況調査虚偽記載についてご報告
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■女子大学院生・ポスドクと産総研女性研究者との懇談会
11月21日(月)13:00〜17:00
会場:産総研つくばセンター中央
産業技術総合研究所 ダイバーシティ推進室 主催
対象:女子大学院生・ポスドク等
参加費無料
女子大学院生・ポスドク等の方々に,研究職としてのキャリアイメージを得る
機会を提供するため,本研究所の職場紹介,分野毎・少人数に分かれての女性
研究者等との懇談会を開催します.関心をお持ちの方は是非ご参加下さい.
http://unit.aist.go.jp/diversity/ja/event/161121_div_event.html
■第32回ゼオライト研究発表会
12月1日(木)〜12月2日(金)
会場:タワーホール船堀
http://www.jaz-online.org/
■第6回学生のヒマラヤ野外実習ツアー(参加者募集中)(日本地質学会推薦)
2017年3月4日〜18日(暫定日程)
コース:中西部ネパールヒマラヤの全断面で,ポカラを通る南北のルート
参加申込締切:11月30日(水)
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
■(共)4th IGS (international Geoscience Symposium)
Precambrian World 2” in Fukuoka
2017年3月3日(金)〜5日(日)
会場:九州大学西新プラザ
早期申込(格安):10月15日(土)
Abstract締切:11月25日(金)
地球史を通した冥王代から現在に渡る地球活動(地質・環境・生物進化)の最
先端をモーラする研究者が参加予定.若手研究者や大学院生・学部生の参加歓
迎します.
http://www.kochi-u.ac.jp/marine-core/precambrian_world/PW2017/top.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0151.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■JAMSTEC地震津波海域観測研究開発センター
---地震津波予測研究グループポスドク公募(10/28)
---海底地質・地球物理観測研究グループポスドク公募(11/21)
■東北大学大学院 理学研究科 地学専攻 助教公募(11/30)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.359 フォトコンテスト:本年度の締切は正月明け!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.359 2016/11/1┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2017年度各賞候補者募集中(11/30締切!!)
【2】「院生割引会費」受付中:忘れずに申請して下さい!
【3】惑星地球フォトコンテスト:締め切り本年度は正月明けです!
【4】「博士人材追跡調査」の実施について
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2017年度各賞候補者募集中(11/30締切!!)
──────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして,研究の援助・奨励および研究業
績の表彰を行っています.本年も各賞の自薦,他薦による候補者を募集いたし
ます.期日厳守にて,たくさんのご応募をお待ちしております.
応募締切:2016年11月30日(水)必着
推薦書式,対象論文リストなど詳しくは,
http://sub.geosociety.jp/members/content0094.html(会員のページ)
※「会員のページ」へは会員番号・パスワードによるログインが必要です.
ログインの方法はこちら.
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】「院生割引会費」受付中:忘れずに申請して下さい!
─────────────────────────────────
運営規則により,次年分の会費を前納下さいますようお願いいたします.
学部学生の方,定収のない大学院生(研究生)の方は,早めに割引会費の申請
を行って下さい.割引の適用を希望する場合,申請は毎年必要です.
割引会費申請締切(請求書発行前締切):2016年11月14日(月)
(正)2016年11月21日(月)
(*11/1配信号で締切期日を間違って表示していました.お詫びして訂正いたします)
2017年度会費払込について(割引申請の書式もこちらから)
http://www.geosociety.jp/outline/content0164.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】惑星地球フォトコンテスト:締め切り本年度は正月明けです!
──────────────────────────────────
本年度のフォトコンは,地質学会長賞をもうけました!これは,地質学会会員
への特別枠です.
昨今,地質学会員でも美しい露頭をカメラに記録させることが少なくなってき
ました.カメラの精度はどんどん上がっており,スマホやミラーレスカメラな
ど,軽くて便利な機器も増えています.SNSなどでは人物なども含め膨大な写真
が公表されています.ぜひ,露頭に向かって,自分が見た地層が物語る歴史と
その美しさを伝えませんか?露頭を観察し,洞察し,分析していきながら歴史
を振り返る,その最初のステップをぜひ大切にしたいものです.
ぜひ,地質を理解した地質学会会員視点からの,美しい写真を期待しています!
【こんな作品を大募集】
地球の大地が持つ美しい自然風景/断層・津波・火山など活きた地球像/岩石・
地層・化石などが持つ天然美/学術的意義・教育効果の高い地球科学作品/ジ
オパークの知られざる大地の姿/ジオ鉄写真:鉄道と地質/地形とのコラボ/チャ
ンスを逃さない新たな視点のスマホ写真
【賞および賞金】
最優秀賞 1点:賞金5万円/優秀賞 2点:賞金2万円
ジオパーク賞 1点:賞金2万円/地質学会会長賞 1点:賞金1万円
ジオ鉄賞 1点:賞金1万円/スマホ賞 1点:賞金5千円 など
【応募締切】2017年1月10日(火)17時(郵送での応募は同日必着)
今年も皆様からのご応募をお待ちしています.http://photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】「博士人材追跡調査」の実施について
──────────────────────────────────
日本学術会議若手アカデミー若手科学者ネットワークを通じて,科学技術・学
術政策研究所(NISTEP)が実施する標記調査の周知協力依頼がありましたので,
会員の皆様にお知らせします.
**********************
我が国では,毎年15,000人ほどが大学院の博士課程を修了していますが,他の
先進諸国に比べ就業する場が限られ,専門性を生かしたキャリア形成が困難な
状況となっています.文部科学省科学技術・学術政策研究所(NISTEP)では,
このような状況の改善を目指し,客観的根拠に基づく政策形成の実現に向けた
エビデンスを構築するために,「博士人材追跡調査」を実施しています.
◆「博士人材追跡調査(平成27年度博士課程修了者_半年後)」
対象者:平成27年度中に,日本の大学院の博士課程を修了した者全員.
実施日:平成28年10月18日(火)〜11月15日(火).
実施方法:大学から対象者に依頼を行う.
◆「博士人材追跡調査(平成24年度博士課程修了者_3年半年後)」
対象者:平成24年度中に,日本の大学院の博士課程を修了した者.
実施日:平成28年11月14日(月)〜11月30日(水).
実施方法:科学技術・学術政策研究所(NISTEP)から対象者へ直接依頼を行う.
詳しくは,http://www.nistep.go.jp/archives/29390
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報
──────────────────────────────────
[北海道支部]
■出版記念シンポジウム
「北海道自然探検 ジオ(大地)の魅力がいっぱい!」
12月3日(土)13:30〜 シンポジウム,17:30〜 祝賀会
場所:北大理学部5号館 201教室
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html#2016book
[関東支部]
■大磯丘陵北西部・火山灰ミニ巡検
11月26日(土)
講師:笠間友博(神奈川県立生命の星・地球博物館)
費用:保険代ほか1000円(当日集金)
申込締切:11月17日(木)
http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■電中研TOPICS Vol.22発行(20.16.10.25)
http://criepi.denken.or.jp/research/topics/index.html?m=161025
■地震本部ニュース平成28年度秋号発行
http://www.jishin.go.jp/herpnews/
■ユネスコ世界ジオパーク学術研究合同成果発表会 in 東京大学
11月5日(土)13:30〜16:00
会場:東京大学 弥生講堂アネックス(セイホクギャラリー)
申込不要
ジオパークと大学の研究教育連携を考えます.隠岐・糸魚川のユネスコ世界ジオ
パークの助成対象研究の発表が合わせて行われます.
http://www.geo-itoigawa.com/sub/topics2016.html#672
■東京大学大気海洋研究所共同利用研究集会
バイオミネラリゼーションと石灰化ー遺伝子から地球環境までー
11月11日(金)〜12日(土)
場所:東京大学大気海洋研究所(千葉県柏市柏の葉5-1-5)
http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/aori_news/meeting/2016/2016111.html
■第25回素材工学研究懇談会ー放射性物質と素材プロセッシング
11月16日(水)〜17日(水)
場所:東北大学片平さくらホール
http://www2.tagen.tohoku.ac.jp/general/event/sozai/2016/
■第27回地質汚染調査浄化技術研修会
日本地質学会環境地質部会 共催
11月18日(金)〜20日(日)
場所:関東ベースンセンター(千葉県香取市)
会費:会員 45,000円(学生35,000円),非会員 55,000円(非会員学生40,000円)※昼食代を含む
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
■藤原ナチュラルヒストリー振興財団公開シンポジウム
「土と生き物の自然史」
11月20日(日)13:00〜16:00
場所:国立科学博物館日本館講堂
http://fujiwara-nh.or.jp/archives/2016/0810_133757.php#more
■産業技術連携推進会議地質地盤情報分科会平成28年度講演会
「都市平野部の地質学」
11月22日(火)13:00〜16:50 参加無料・事前申込不要
場所:北とぴあ第一研修室(JR京浜東北線王子駅北口より3分)
CPD:3単位
https://www.gsj.jp/information/domestic/sgr/index.html
■第26回環境地質学シンポジウム
11月25日(金)〜26日(土)
場所:日本大学文理学部
--25日:オーバルホール
--26日:レクチャーホール
http://www.jspmug.org/envgeo_sympo/26th_sympo/26th_sympo.html
■第192回地質汚染イブニング・セミナー
11月25日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:炭谷 茂(元環境省事務次官)
テーマ:社会福祉と環境
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■(協)第32回ゼオライト研究発表会
12月1日(木)〜2日(金)
会場:タワーホール船堀
http://www.jaz-online.org/
■日本学術会議主催学術フォーラム
持続可能な社会の実現に向けた草の根活動の振興−IYGU(国際地球理解年)の試み
12月3日(土)13:00〜17:00
場所:日本学術会議講堂
https://form.cao.go.jp/scj/opinion-0003.html
■第16回東北大学多元物質科学研究所研究発表会
12月7日(水)〜8日(木)
場所:東北大学片平さくらホール
http://www2.tagen.tohoku.ac.jp/general/event/meeting/2016/index.html
■第15回地圏資源環境研究部門研究成果報告会
CO2地中貯留の実用化に向けて −技術課題と産総研の役割−
12月9日(金)13:30〜17:25
場所:秋葉原ダイビル・コンベンションホール
https://unit.aist.go.jp/georesenv/information/20161007.html
■地質学史懇話会
12月23日(金・祝)13:30〜17:00
場所:北とぴあ8階803号室
眞島英壽:「日本海拡大と地球科学の方法論」
石原舜三:「日本の花崗岩研究史」
■(共)4th IGS (international Geoscience Symposium)
Precambrian World 2” in Fukuoka
2017年3月3日(金)〜5日(日)
会場:九州大学西新プラザ
Abstract締切:11月25日(金)
http://www.kochi-u.ac.jp/marine-core/precambrian_world/PW2017/top.html
■第6回学生のヒマラヤ野外実習ツアー(参加者募集中)(日本地質学会推薦)
2017年3月4日〜18日(暫定日程)
コース:中西部ネパールヒマラヤの全断面で,ポカラを通る南北のルート
参加申込締切:11月30日(水)
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0151.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.358 2017年度各賞候補者募集中/割引会費申請(忘れずに!)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.358 2016/10/18┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2017年度各賞候補者募集中
【2】「院生割引会費」受付中:2017年度会費払込について
【3】惑星地球フォトコンテスト:応募受付中
【4】支部情報
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2017年度各賞候補者募集中
──────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして,研究の援助・奨励および研究業
績の表彰を行っています.本年も各賞の自薦,他薦による候補者を募集いたし
ます.期日厳守にて,たくさんのご応募をお待ちしております.
応募締切:2016年11月30日(水)必着
推薦書式,対象論文リストなど詳しくは,
http://sub.geosociety.jp/members/content0094.html(会員のページ)
※「会員のページ」へは会員番号・パスワードによるログインが必要です.
ログインの方法はこちら.
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】「院生割引会費」受付中:2017年度会費払込について
─────────────────────────────────
運営規則により,次年分の会費を前納下さいますようお願いいたします.
学部学生の方,定収のない大学院生(研究生)の方は,早めに割引会費の申請
を行って下さい.割引の適用を希望する場合,申請は毎年必要です.
割引会費申請締切(請求書発行前締切):2016年11月14日(月)
2017年度会費払込について(割引申請の書式もこちらから)
http://www.geosociety.jp/outline/content0164.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】惑星地球フォトコンテスト:応募受付中
──────────────────────────────────
第8回惑星地球フォトコンテストの応募作品を募集中です!
今年も皆さんの力作をお待ちしています!
応募作品受付:2017年1月10日(火)
詳しくは,http://photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■大磯丘陵北西部・火山灰ミニ巡検
11月26日(土)
講師:笠間友博(神奈川県立生命の星・地球博物館)
費用:保険代ほか1000円(当日集金)
申込締切:11月17日(木)
http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■(後)藤原ナチュラルヒストリー振興財団神戸シンポジウム
ナチュラルヒストリー:これまでの貢献と今後へ期待
10月22 日(土) 13:30〜17:00
場所:兵庫県民会館けんみんホール
共催 兵庫県立人と自然の博物館
http://fujiwara-nh.or.jp/
■道総研・地質研究所海洋科学研究センター
市民公開講座「小樽の温泉について知る」
10月22日(土)13:30〜16:00
場所:海洋科学研究センター(小樽市築港3-1)
入場無料
http://www.hro.or.jp/list/environmental/research/gsh/information/topics/topics20160927.html
■第191回地質汚染イブニング・セミナー
10月28日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:水谷和子(一級建築士)
テーマ:豊洲地質汚染問題 状況調査虚偽記載についてご報告
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■ユネスコ世界ジオパーク学術研究合同成果発表会 in 東京大学
11月5日(土)13:30〜16:00
会場:東京大学 弥生講堂アネックス(セイホクギャラリー)
申込不要
ジオパークと大学の研究教育連携を考えます.隠岐・糸魚川のユネスコ世界ジオ
パークの助成対象研究の発表が合わせて行われます.
http://www.geo-itoigawa.com/sub/topics2016.html#672
■サイエンスアゴラ2016
災害とレジリエンス−平成28年熊本地震災害の教訓−
11月6日(日)10:30〜12:00 (入場無料)
会場:日本科学未来館7階未来館ホール
主催:科学技術振興機構、日本学術会議
http://janet-dr.com/01_home_calendaer/201611/161106miraikan.pdf
■図書館総合展・学術著作権協会フォーラム
英国教育現場における著作物の利用とライセンス
11月10日(木)13:00〜14:30
会場:パシフィコ横浜
https://www.jaacc.jp
■学術著作権協会シンポジウム
デジタル時代における教育と著作権
11月11日(金)10:30〜12:30
場所:国際文化会館岩崎小彌太記念ホール
https://www.jaacc.jp
■日本学術会議 学術フォーラム
科学者は災害軽減と持続的社会の形成に役立っているか?
11月13日(日)13:00〜17:30
場所:日本学術会議講堂
https://form.cao.go.jp/scj/opinion-0067.html
■第27回地質汚染調査浄化技術研修会
日本地質学会環境地質部会 共催
11月18日(金)〜20日(日)
場所:関東ベースンセンター(千葉県香取市)
会費:会員 45,000円(学生35,000円),非会員 55,000円(非会員学生40,000円)※昼食代を含む
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
■シンポジウム「熊本地震を踏まえた地域防災力強化の在り方 in 大阪」
主催:地区防災計画学会,情報通信学会災害情報法研究会,(一財)関西情報センター
11月20日(日)
場所:大阪大学中之島センター講義室304
http://www.gakkai.chiku-bousai.jp/ev161120.html
■女子大学院生・ポスドクと産総研女性研究者との懇談会
11月21日(月)13:00〜17:00
会場:産総研つくばセンター中央
産業技術総合研究所 ダイバーシティ推進室 主催
対象:女子大学院生・ポスドク等
参加費無料
女子大学院生・ポスドク等の方々に,研究職としてのキャリアイメージを得る
機会を提供するため,本研究所の職場紹介,分野毎・少人数に分かれての女性
研究者等との懇談会を開催します.関心をお持ちの方は是非ご参加下さい.
http://unit.aist.go.jp/diversity/ja/event/161121_div_event.html
■(協)第32回ゼオライト研究発表会
12月1日(木)〜2日(金)
会場:タワーホール船堀
http://www.jaz-online.org/
■第2回防災学術連携シンポジウム
「激甚化する台風・豪雨災害とその対策」
主催:日本学術会議防災減災・災害復興に関する学術連携委員会,防災学術連携体
12月1日(木)10:00〜18:00
会場:日本学術会議講堂
http://janet-dr.com/07_event/event13.html
■(共)4th IGS (international Geoscience Symposium)
Precambrian World 2” in Fukuoka
2017年3月3日(金)〜5日(日)
会場:九州大学西新プラザ
Abstract締切:11月25日(金)
http://www.kochi-u.ac.jp/marine-core/precambrian_world/PW2017/top.html
■第6回学生のヒマラヤ野外実習ツアー(参加者募集中)(日本地質学会推薦)
2017年3月4日〜18日(暫定日程)
コース:中西部ネパールヒマラヤの全断面で,ポカラを通る南北のルート
参加申込締切:11月30日(水)
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0151.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■東北大学大学院 理学研究科 地学専攻 教授/助教公募(11/30)
■国立科学博物館地学研究部研究員公募(17/01/9)
■地球惑星科学振興西田賞推薦募集(12/15)
■平成29年度大気海洋研究所(柏地区)共同利用公募(11/30)
■平成29年度国際沿岸海洋研究センター共同利用公募(11/30)
■平成29年度大気海洋研究所学際連携研究公募(11/30)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.360 “各賞候補者募集” まもなく締切です!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.360 2016/11/15┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2017年度各賞候補者募集中(11/30締切!!)
【2】「院生割引会費」受付中:忘れずに申請して下さい!
【3】惑星地球フォトコンテスト:締め切り本年度は正月明けです!
【4】支部情報
【5】専門部会より
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
【8】訃報:倉沢 一 名誉会員 ご逝去
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2017年度各賞候補者募集中(11/30締切!!)
──────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして,研究の援助・奨励および研究業
績の表彰を行っています.本年も各賞の自薦,他薦による候補者を募集いたし
ます.期日厳守にて,たくさんのご応募をお待ちしております.
応募締切:2016年11月30日(水)必着
推薦書式,対象論文リストなど詳しくは,
http://sub.geosociety.jp/members/content0094.html(会員のページ)
※「会員のページ」へは会員番号・パスワードによるログインが必要です.
ログインの方法はこちら.
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】「院生割引会費」受付中:忘れずに申請して下さい!
─────────────────────────────────
運営規則により,次年分の会費を前納下さいますようお願いいたします.
学部学生の方,定収のない大学院生(研究生)の方は,早めに割引会費の申請
を行って下さい.割引の適用を希望する場合,申請は毎年必要です.
割引会費申請締切(請求書発行前締切):2016年11月21日(月)
(*11/1配信号で締切期日を誤って表示していました.お詫びして訂正致します)
2017年度会費払込について(割引申請の書式もこちらから)
http://www.geosociety.jp/outline/content0164.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】惑星地球フォトコンテスト:締め切り本年度は正月明けです!
──────────────────────────────────
【応募締切】2017年1月10日(火)17時(郵送での応募は同日必着)
本年度のフォトコンは,地質学会長賞をもうけました!これは,地質学会会員
への特別枠です.
昨今,地質学会員でも美しい露頭をカメラに記録させることが少なくなってき
ました.カメラの精度はどんどん上がっており,スマホやミラーレスカメラな
ど,軽くて便利な機器も増えています.SNSなどでは人物なども含め膨大な写真
が公表されています.ぜひ,露頭に向かって,自分が見た地層が物語る歴史と
その美しさを伝えませんか?露頭を観察し,洞察し,分析していきながら歴史
を振り返る,その最初のステップをぜひ大切にしたいものです.
ぜひ,地質を理解した地質学会会員視点からの,美しい写真を期待しています!
【こんな作品を大募集】
地球の大地が持つ美しい自然風景/断層・津波・火山など活きた地球像/岩石・
地層・化石などが持つ天然美/学術的意義・教育効果の高い地球科学作品/ジ
オパークの知られざる大地の姿/ジオ鉄写真:鉄道と地質/地形とのコラボ/チャ
ンスを逃さない新たな視点のスマホ写真
【賞および賞金】
最優秀賞 1点:賞金5万円/優秀賞 2点:賞金2万円
ジオパーク賞 1点:賞金2万円/地質学会会長賞 1点:賞金1万円
ジオ鉄賞 1点:賞金1万円/スマホ賞 1点:賞金5千円 など
今年も皆様からのご応募をお待ちしています.http://photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】支部情報
──────────────────────────────────
[北海道支部]
■出版記念シンポジウム
「北海道自然探検 ジオ(大地)の魅力がいっぱい!」
12月3日(土)13:30〜 シンポジウム,17:30〜 祝賀会
場所:北大理学部5号館201教室
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html#2016book
[関東支部]
■大磯丘陵北西部・火山灰ミニ巡検
11月26日(土)
講師:笠間友博(神奈川県立生命の星・地球博物館)
費用:保険代ほか1000円(当日集金)
申込締切:11月17日(木)
http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】専門部会より
──────────────────────────────────
[第四紀地質部会]
■学会125周年記念特集号「第四紀地質学の新展開」(仮)の提案
趣旨:125周年という節目を利用して,第四紀学に関わりの大きい地質分野にお
いて,まとまりのある分野や普遍性のあるテーマを設定し,最新の研究成果と
研究動向をレビューして,今後の研究の進展に寄与するバックグランドを構築
する.併せて,最新の個別的研究成果も掲載する.
関係者各位の積極的な応募・投稿を期待しています!
[応募締切]11月30日(水)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0175.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第27回地質汚染調査浄化技術研修会
日本地質学会環境地質部会 共催
11月18日(金)〜20日(日)
場所:関東ベースンセンター(千葉県香取市)
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
■(共)第26回環境地質学シンポジウム
11月25日(金)〜26日(土)
場所:日本大学文理学部
(25日:オーバルホール/26日:レクチャーホール)
**講演プログラム公開しました**(11/10)
http://www.jspmug.org/envgeo_sympo/26th_sympo/26th_sympo.html
■第192回地質汚染イブニング・セミナー
11月25日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:炭谷 茂(元環境省事務次官)
テーマ:社会福祉と環境
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■東京都立中央図書館企画展示「東京凸凹地形」
11月26日(土)〜2017年2月12日(日)
場所:東京都立中央図書館企画展示室 入場無料
内容:(第1部)東京の地形の成り立ちや,川,暗渠,坂などの特徴的な地形に
ついて(第2部)5つの特徴的なエリア(麻布,渋谷,日比谷,上野,国分寺)
を紹介.
http://www.library.metro.tokyo.jp/
■(協)第32回ゼオライト研究発表会
12月1日(木)〜2日(金)
会場:タワーホール船堀
http://www.jaz-online.org/
■地球化学研究協会「公開講座」/「三宅賞」受賞者の受賞記念講演
12月3日(土)14時40分より
場所:霞が関ビル35階 東海大学校友会館
参加費:賛助会員および学生は無料,一般1000円(資料代を含む)
http://www.geochem-ass-miyake.com/
■第175回深田研談話会
12月16日(金)15:00〜17:00
場所:深田地質研究所研修ホール
講師:森下泰成(海上保安庁海洋情報部)
テーマ:日本の大陸棚の拡大の取り組みー科学の力で海の領土を拡げるー
参加費無料・先着80名
http://www.fgi.or.jp
■第193回地質汚染イブニング・セミナー
12月16日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:宮崎 毅(東京大学名誉教授)
テーマ:土壌層と水循環
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■(共)4th IGS (international Geoscience Symposium)
Precambrian World 2” in Fukuoka
2017年3月3日(金)〜5日(日)
会場:九州大学西新プラザ
Abstract締切:11月25日(金)
http://www.kochi-u.ac.jp/marine-core/precambrian_world/PW2017/top.html
■第6回学生のヒマラヤ野外実習ツアー(参加者募集中)(日本地質学会推薦)
2017年3月4日〜18日(暫定日程)
コース:中西部ネパールヒマラヤの全断面で,ポカラを通る南北のルート
参加申込締切:11月30日(水)
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0151.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■筑波大学生命環境系常勤研究員公募(地質学)(12/25)
■信州大学理学部助教(特定雇用)公募(12/27)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】訃報:倉沢 一 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
日本地質学会名誉会員 倉沢 一氏(元 地質調査所)が,平成28年11月13日に逝去されました(享年85歳).
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます.
なお,ご葬儀等は下記の通り執り行われます.
通夜祭:11月16日(水)18時より
葬場祭:11月17日(木)11-12時
喪主:倉沢宏子様(ご令室)
式場:ライフケア土浦会堂(土浦市田中2-14-11 電話029-821-4444)
会長 渡部芳夫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
125記念トリビア2:日本にライエルの孫が来た
〜2018年日本地質学会創立125周年を記念して〜
トリビア学史 2 日本にライエルの孫が来た?ビーグル号が来た?
正会員 矢島道子(日本大学文理学部)
ニュース誌8月号の「トリビア学史1」は明治の初めの日本人の奮闘を記したものだが,今回は洋物(カタカナの名前)の話である.なお,これはと思われる珍しい記録・情報などあったら,「トリビア学史」にどしどし投稿されることを歓迎します.
ライエル
チャールズ・ライエル(Charles Lyell 1797-1875)は『地質学原理』の著者として,(『地質学原理』を読んだことがなくても)地質学を志した人ならば誰でも知っている.その孫が日本に来たという話がある.谷沢・渡部(2008)は,その著『日本人とは何か‐「和の心」が見つかる名著』の61ページでトマス・ライエル(1950)の著『一英國人の見たる日本及日本人』を紹介している.写真は佐藤正氏の所蔵されていたものである.古本屋で購入するとかなり高価である.谷沢・渡部は「トマス・ライエルは…チャールズ・ライエルの孫です.ケンブリッジ大学を出て,詩人でもある.戦前から日本のいろんな学校で教えたりして,戦前も30年
近く日本にいた.敵性外国人として一時日本を離れざるをえませんでしたが,戦後いちばん最初に民間イギリス人の先生として日本に来た人です」と書いている.また渡部は「ライエルが上智大学で教授になった年に僕は入学しました」と書き,その授業および,その著書を紹介している.
ほんとうだろうか.私は早速,ライエルの研究家であるミネソタ大学のLeonard G. Wilsonに連絡した.返事は以下のようで,どうやら一族であることは間違いなさそうだが,チャールズの孫ではあり得ないむねが書いてあった.
From: Leonard Wilson,
To: Michiko Yajima
Sent: Saturday, March 29
Subject: Re: Thomas Lyell in Japan
Dear Michiko Yajima,
It is a pleasure to hear from you. With regard to your
question, Sir Charles Lyell had no children. His brother
Colonel Henry Lyell had three sons and a daughter. One of
his sons, Francis Horner Lyell, had two sons, one of whom
Thomas Reginal Guise Lyell, born 3 April 1886, may have
been the Thomas Lyell who taught English at a university in
Japan in the 1930's. in 1930 he would have been forty-four. He
is said to have died abroad, but otherwise I know nothing of
his fate. He was a great nephew of Sir Charles Lyell, but not
a grandson.
With best wishes
Sincerely,
Leonard Wilson
渡部は直接トマス・ライエルに接しながら,どうして勘違いしたのか不明である.
ビーグル号
1970年代,地質学教室の学生だった頃,「ダーウィンの乗ったビーグル号は日本に来たらしい」という話を聞きこんだ.その時にもビーグル号はビーグル号だが違うビーグル号だとも聞いた.出典はどこだか調べてもみなかった.明治以来,いくつもの説があったようだ.ダーウィン生誕200年,『種の起原』刊行150年を記念して刊行出版された松永(2009)によくまとめられている.
イギリス海軍にはビーグル号という名の艦船がいくつも登場する.日本に来たビーグル号は日本名を乾行という.1854年に建造された,元イギリス海軍の機帆船523t,177feetのビーグル(HMS Beagle)は,民間に売却され,薩摩藩が1864年に購入,長崎で受領し「乾行丸」と命名された.戊辰戦争で活躍し,1870年には新政府へ献納され,兵部省所管となり,「乾行」と改名された.その後,練習艦として使用されたり,浦賀に係留されたりしていたが,1889年に売却された.1911年に動物学者の渡瀬庄三郎がダーウィンのビーグル号ではないことをすでに明らかにしている.
ダーウィンの乗船したビーグル号のほうは,イギリス海軍の10門の砲を搭載した純然たる帆船で235t,90feetである.1820年に建造され,ジョージ4世の戴冠式を祝う観艦式に参加し,新しいロンドン橋の下をくぐった最初の船となった.その後3度の探検に参加した.2度目の航海1831年から1836年ではチャールズ・ダーウィンが乗船した.3度目の航海を終えて,1870年に売却され,解体された.今では,ビーグル号の情報はかなり流布し,wikipediaや各種科学史の本にほぼ常識として掲載されている.
文 献
谷沢永一・渡部昇一,2008,日本人とは何か‐「和の心」が見つかる名著,PHP選書.201p.
ライエル,トマス,1950,一英國人の見たる日本及日本人,創元社.349p.
松永俊男,2009,チャールズ・ダーウィンの生涯‐進化論を生んだジェントルマンの社会,朝日選書.321p.
【geo-Flash】No.361 惑星地球フォトコンテスト締め切りは正月明けです!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.361 2016/12/6┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2017年度会費払込について
【2】惑星地球フォトコンテスト:締め切り本年度は正月明けです!
【3】支部情報
【4】その他のお知らせ
【5】公募情報・各賞助成情報等
【6】訃報:江 博明(JAHN, Bor-ming)教授 ご逝去
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2017年度会費払込について
─────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下さいますよ
うお願いいたします.
■2017年度分会費の引き落とし日:12月26日(月)です.
請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下
さい.
■自動引き落とし以外の方(お振り込み)
12月中旬頃までに請求書兼郵便振替用紙をお送りいたします.折り返しご送金
くださいますようお願いいたします.
2017年度会費払込について
http://www.geosociety.jp/outline/content0164.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】惑星地球フォトコンテスト:締め切り本年度は正月明けです!
──────────────────────────────────
【応募締切】2017年1月10日(火)17時(郵送での応募は同日必着)
本年度のフォトコンは,地質学会長賞をもうけました!これは,地質学会会員
への特別枠です.
昨今,地質学会員でも美しい露頭をカメラに記録させることが少なくなってき
ました.カメラの精度はどんどん上がっており,スマホやミラーレスカメラな
ど,軽くて便利な機器も増えています.SNSなどでは人物なども含め膨大な写真
が公表されています.ぜひ,露頭に向かって,自分が見た地層が物語る歴史と
その美しさを伝えませんか?露頭を観察し,洞察し,分析していきながら歴史
を振り返る,その最初のステップをぜひ大切にしたいものです.
ぜひ,地質を理解した地質学会会員視点からの,美しい写真を期待しています!
【こんな作品を大募集】
地球の大地が持つ美しい自然風景/断層・津波・火山など活きた地球像/岩石・
地層・化石などが持つ天然美/学術的意義・教育効果の高い地球科学作品/ジ
オパークの知られざる大地の姿/ジオ鉄写真:鉄道と地質/地形とのコラボ/チャ
ンスを逃さない新たな視点のスマホ写真
【賞および賞金】
最優秀賞 1点:賞金5万円/優秀賞 2点:賞金2万円
ジオパーク賞 1点:賞金2万円/地質学会会長賞 1点:賞金1万円
ジオ鉄賞 1点:賞金1万円/スマホ賞 1点:賞金5千円 など
今年も皆様からのご応募をお待ちしています.http://photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■2016年度功労賞募集
対象者:支部活動や地質学を通して広く社会貢献をされた関東支部内に在住の
個人・団体(*社会貢献や活動の評価においては,必ずしも学問的な成果を問
うものではありません)
公募期間:2016年12月10日(土)〜2017年1月10日(火)
詳しくは,http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■平成28年度国総研講演会
12月8日(木)10:15
場所:日本消防会館ニッショーホール(港区虎ノ門2-9-16)
「生産性向上」,「維持管理・競争力強化」,「防災・減災」の3つの
一般セッションを設定し,最前線の研究成果等を講演します.
http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/kouenkai/kouenkai2016/kouenkai2016.htm
■第193回地質汚染イブニング・セミナー
12月16日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:宮崎 毅(東京大学名誉教授)
テーマ:土壌層と水循環
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■地質学史懇話会
12月23日(金・祝)13:30〜17:00
場所:北とぴあ8階803号室
眞島英壽:「日本海拡大と地球科学の方法論」
石原舜三:「日本の花崗岩研究史」
[2017年]
■都立中央図書館:公開講座「東京凸凹地形散歩」
1月22日(日)13:30〜17:00
会場:東京都立中央図書館多目的ホール
講義1「3D精密地形模型とプロジェクションマッピングでみる東京の成り立ち」
講師:芝原暁彦氏
講義2「東京のスリバチ地形を読み解く 有栖川宮記念公園から始まる冒険」
講師:皆川典久氏
http://www.library.metro.tokyo.jp/
■第194回地質汚染イブニング・セミナー
1月27日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:古野邦雄(元千葉県環境研究センター主席研究員)
高嶋 洋(野田市道路管理課主査)
テーマ:関東地下水盆管理と水循環基本法
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■第21回「震災対策技術展」横浜 来場受付開始(2017年2月)
2月2日(木)〜3日(金) 10:00〜17:00
会場:パシフィコ横浜
参加費無料
https://www.shinsaiexpo.com/yokohama/
■ブルーアース2017
3月2日(木)〜3日(金)
発表課題募集締切:12月16日(金) 【午前12時・正午必着】
募集対象者:「なつしま」,「かいよう」,「よこすか」,「かいれい」,
「みらい」,「ちきゅう」及び「しんかい6500」等深海調査システムを利用した
研究・技術開発に参加した研究者,技術者等
http://www.jamstec.go.jp/maritec/j/blueearth/2017/invitation.html
■(共)4th IGS (international Geoscience Symposium)
Precambrian World 2” in Fukuoka
3月3日(金)〜5日(日)
会場:九州大学西新プラザ
Keynote(予定):
J. カーシュビング教授:Caltec スノーボールアースー生物進化
W. ブローカー博士:カナダ地質調査所 太古代ー原生代大陸復元
A. ホフマン教授:ヨハネスブルグ大学 太古代の表層環境 34億年前のチャート
掘削等
http://www.kochi-u.ac.jp/marine-core/precambrian_world/PW2017/top.html
■第6回学生のヒマラヤ野外実習ツアー(参加者募集中)(日本地質学会推薦)
3月4日〜18日(暫定日程)
コース:中西部ネパールヒマラヤの全断面で,ポカラを通る南北のルート
参加申込締切:11月30日(水)
http://www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
■第51回日本水環境学会年会
3月15日(水)〜17日(金)
会場:熊本大学黒髪キャンパス
https://www.jswe.or.jp/guest/entry.php
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0151.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■産総研イノベーション人材育成コース(博士号取得者向け)募集(12/27)
■JAMSTEC海洋掘削科学研究開発センター研究職もしくは技術研究職公募(2/3)
■三菱財団平成29年度自然科学研究助成(2/7)
■戦略的創造研究推進事業総括実施型研究(ERATO)研究総括候補の推薦(随時受付)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】訃報:江 博明(JAHN, Bor-ming)教授 ご逝去
──────────────────────────────────
2014年度日本地質学会国際賞を受賞された江 博明教授 (JAHN, Bor-ming)(国立台湾大学)
が台北市内の病院で12月1日に急逝されました.
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます.
ご葬儀の予定等
http://geo-ntu.blog.ntu.edu.tw/home/
江教授の2014年度国際賞受賞理由
http://www.geosociety.jp/outline/content0141.html#kokusai
会長 渡部芳夫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
125記念トリビア3:富士谷孝雄
〜2018年日本地質学会創立125周年を記念して〜
トリビア学史 3 富士谷孝雄(? – 明治26(1893))はどこへ消えたか
矢島道子(日本大学文理学部)・浜崎健児(Ultra Trex(株))
*補遺を掲載しました(2017.3.8)
写真:右 ナウマン,左 富士谷孝雄.
撮影年不明.(フォッサマグナミュージアム所蔵)
富士谷孝雄
富士谷孝雄は生年がいまだ不明だが,東京大学理学部地質学科を明治14(1881)年に卒業した,3回目の卒業生である.初代教授ナウマンと一緒に移っている写真(写真1)は有名である.ナウマンが日本人と一緒に移っている写真は大変珍しい.おそらく富士谷だけであろう.ところが,富士谷はその後の地質学史からほとんど消えている.どうしたのだろうかと不思議に思っていた.
東京大学時代
調べてみると,富士谷は東京大学在学中から『学芸志林』などに多くの論文を書いている.また,『東京帝国大学五十年史』(1932年)によれば,明治15(1882)年8月1日から18(1885)年5月まで東京大学助教授である.
『学芸志林』は今の東京大学紀要のようなもので,明治10(1877)年8月から明治18(1885)年11月まで刊行された.富士谷の投稿した論文は下記8本である.
・明治12(1879)年3月 「西俗謬信之說――米國學藝新誌中ヨリ」地質学科2年 富士谷孝雄訳
・明治15(1882)年11月「安房地質志」理学士 富士谷孝雄述
・明治16(1883)年6月「本邦石學一斑」東京大学助教授 富士谷孝雄述
・明治16(1883)年9月「中村穴居考」東京大学助教授 富士谷孝雄述
・明治16(1883)年12月「会名ノ縁由」地学会員 理学士 富士谷孝雄識
・明治17(1884)年2月「飛彈國地貿槪報附圖」東京大学助教授 理学士 富士谷孝雄述
・明治17(1884)年3月「河流新說 」東京大学助教授 富士谷孝雄述
・明治18(1885)年4月「天草郡地質稽査報告」東京大学助教授 理学士 富士谷孝雄,准助教授加藤敬介と供述
富士谷の肩書が理学士から助教授に変化していること,地学会員を使用していることに注目されたい.「安房地質志」「飛彈國地貿槪報附圖」「天草郡地質稽査報告」は秀逸である.「中村穴居考」は人類学の論文である.「会名の縁由」は地学会の名前について書かれたもので,トリビア1に書いた『本邦化石産地目録』は富士谷の筆かもしれない.
東京大学時代に書いた他の雑誌論文と著書
他の雑誌の投稿論文としては,少なくとも,東洋学芸雑誌1本,東京地学協会報告1本,理学協会雑誌7本がわかっている.理学協会雑誌は1883−1889(1−68巻)年に,理学協会が発行した雑誌である.発行人は 丸善の島村利助となっている.天草の地質に関する研究に精力的に取り組んでいたようで,
・明治17(1884)年3月に東洋学芸雜誌 3(42)に「天草地質誌」
・明治16(1883)年ころ理学協会雑誌 2(12) と2(14) に「天草地質誌」
が掲載されている.「中村穴居考」は明治17(1884)年5月に理学協会雑誌に再度掲載されている.
明治16(1883)年11月『地学要略』巻之1,巻之2が原田豊吉閲 富士谷孝雄述で発行された.和田維四郎が序文を書いており,「余が学友富士谷君」と書き出している.編述兼出版人は東京府士族 富士谷孝雄,住所は東京麹町区下六番町三十番地 渡邊悠(欣に心かもしれない)方寓居となっている.また, 同じ本と思われる本の広告が最終ページにある.それには『中学適要 地学要略 1名地質学初歩』 全2冊 農商務省地質調査所長和田維四郎先生序,理学博士原田豊吉先生校閲 理学博士富士谷孝雄先生編述 と書いてある.
外務省時代
その後はどうしたのだろうか.まず,横山又次郎著『自然の面影』(大正15(1926)年)の437ページで富士谷の名前を見つけた.「今から殆ど50年の昔,余がまだ東大の地質学科の学生であった頃,同じく学生であった富士谷孝雄君(今は故人)が,房州には畑の中に大きな岩珊瑚が転がっているそうだが,ずいぶん珍しいことだと話していたのを聞いて,行って一見したいと思った.」富士谷は早世であったのだとわかった.横山は富士谷の1学年下である.横山が1860年生まれなので,富士谷の生年もそのころであろう.その後,文献は忘却したが,外務省に勤務していたことを知った.それからは簡単で,国立国会図書館デジタルコレクションで富士谷を検索すれば,正確な情報を入手できる.
外務省の翻訳官になってからは,官報を追うとよい.
・明治18(1885)年5月30日 外務省翻訳局兼交信局勤務 月俸70円(官報572号)
・明治20(1887)年6月6日 依願免(官報1179号)
・明治21(1888)年8月6日外務省翻訳官試補 年俸900円(官報1531号)
・明治22(1889)年12月24日外務省翻訳官(奏任官四等)中級俸(官報1948号)
・明治24(1891)年3月23日外務省翻訳官(奏任官四等)中級俸(官報2315号)
途中の退職・復職は渡欧した結果とみられる.高田善治郎(滋賀県出身)・吉川真澄と明治20(1887)年6月28日より渡欧した.7月4日に香港,7月11日にサイゴン,7月13日にシンガポール,7月19日にコロンボ,7月29日にアデン,8月8日にマルセイユと経て,8月9日にイギリスに到達した(高田,1889).そののち,明治22(1889)年4月に『綿糸紡績者必読 一名・印度綿及綿糸紡績』 内田老鶴圃を出版した.富士谷の住所はこのとき,牛込区新小川町三丁目十七番地であった.
地質学一般書の刊行
外務省勤務時代も富士谷の地質学一般書の刊行は続いている.
・明治20(1887)年『芸氏地文学 中学校 師範学校教科用書』,アーキバルト・ゲーキー著,富士谷孝雄訳補,文部省編輯局
・明治21−23(1888-1890)年『如氏地理教科書 中等教育』,ケイス・ジョンストン著,富士谷孝雄述,内田老鶴圃
・明治24(1891)年『日本地理教科書』上巻,下巻 富士谷孝雄 著,敬業社・成美堂
・明治25(1892)年『中等鉱物学教科書』富士谷孝雄 著,金港堂
・明治26(1893)年4月『普通地文学 (巻1)』理学士富士谷孝雄 述,敬業社・成美堂
・明治26(1893)年8月『地文学講義』 理学士富士谷孝雄 述,成美堂
「地文学講義」には「明治25年明治議会の夏期講修会に於いて講述せし講義速記録に聊か修正を加え,教員諸君学生諸子の参考に供せんがために上梓したるものなり」という例言がついており,明治26(1893)年7月の日付であった.
また,『少年園』という明治21−18(1888−1895)年に存在した雑誌に
・明治23(1890)年1月3(30)氷原及氷山の說
・明治23(1890)年9月4(46)ジオン,ビリングス氏の哲學
を掲載した.
明治24(1891)年には富士谷の住所は東京市牛込区東五軒町三十五番地であった.しかし,この一般書の多産の中,突然,明治26(1893)年12月11日に富士谷は死亡した(東京地質学会,1894).死亡の詳細は不明である.
なぜ外務省に行ったのか
富士谷の外務省への転出が明治18年5月で,ナウマンの帰国,原田豊吉の東大教授の就任と時期をほぼ同じくしているので,東京大学での地位争いの敗北の説を提唱する研究者もいる.しかし著者らは,後に日本の外務官僚の大御所となる小村寿太郎(1855—1911)の強い勧誘に富士谷が従ったと考える.小村寿太郎が翻訳のスタッフとして富士谷を見込んだと著者らは考える.「明治21年10月,鳩山は今の条約局に当る当時新設の取調局の長に転じ,侯[小村]はその後を襲いて翻訳局長となった.(中略) 新任翻訳局長たる侯の部下局員は赤羽(四郎)参事官,久松(定弘)公使館書記官,富士谷(孝雄),関(澄蔵)の両翻訳官,中略,の人々が居った」(信夫,1942,p 40–41).小村はどうやって富士谷を知ったか.
富士谷孝雄の曽祖父 富士谷成章(なりあきら;1738–1779は儒学者で,儒学者 皆川淇園(きえん;1735–1807)の弟であり,1756年に富士谷家の養子になった.富士谷家は九州柳川藩の京都留守居役であった.
皆川淇園と明治・大正時代の重要な教育者杉浦重剛(1855–1924)は意外にも浅からぬ因縁がある.杉浦は 近江・膳所藩出身であるが,藩侯の本多康禎は皆川淇園父子を招聘し,淇園の計画により藩校の尊義堂を創立した.杉浦の父親は藩校の尊義堂の教授であった(大町ほか,1924).
そして,杉浦と小村は貢進生の同期で,文部省留学生として海外に行き,また個人的に親友でもあった.明治17(1884)年井上馨外務卿の人材さがしで 当時東京大学予備門長の杉浦が小村寿太郎を推薦した(大町ほか,1924)と考えられる.
どうどうまわりをしたが,杉浦と富士谷は膳所藩と皆川の縁で互いをよく知っていたと推定される.そして,この前後に富士谷が外務省勤務を始めていることから,杉浦から小村に推挙の働きかけがあったと思われる.
文 献
大町桂月・猪狩史山『杉浦重剛先生』政教社,大正13(1924)年
信夫淳平『小村寿太郎』新潮社,昭和17(1942)年
高田善治郎 『出洋日記』川勝鴻宝堂, 明治24(1889)年
東京地質学会,1893,「訃音」地質学雑誌,第1巻4号p.205
補遺 トリビア学史3 富士谷孝雄補遺 2017.3.8追加掲載
日本地質学会News, No. 11(2016年11月号)に「トリビア学史3富士谷孝雄(?−明治26(1893))はどこへ消えたか」を掲載したが,間違いが見つかったので修正したい.また,新しい資料も見つかったので,ここで付け加えさせていただく.
間違い
膳所藩の藩校遵義堂を誤って尊義堂と記した.滋賀県立膳所高等学校は遵義堂の跡地に建っている.膳所高校出身の地質学者は多い.大変な失礼をした.膳所高校出身の宍戸 章氏より指摘を受けた.心より感謝する.
地質調査所勤務
富士谷孝雄は1881(明治14)年に東京大学理学部地質学科を卒業後すぐに内務省地質課に入ってナウマンの「東北部」調査に協力したが,その翌年には東大地質の助教授に出向している(山田,2008).1886(明治19)年に完成した「大日本帝国予察東北部地質図」にはナウマン,E.・富士谷孝雄・山田 皓・坂 市太郎・西山正吾の名前が記されている.
東京山林学校で教える
富士谷は1882-1884(明治15-17)年に,東京山林学校の嘱託をしていた(根岸ほか,2007).1882(明治15)年創立の東京山林学校は,第1学年に地質学と鉱物学の講義を設置していたからだ.富士谷の後は,和田維四郎(1856-1920)が助教として,1885(明治18)年に授業した.1886(明治19)年に東京農林学校になってからは,西松二郎(1855-1909)が1886-1890(明治19-23)年に,教授として地質学・鉱物学を授業した.1890(明治23)年に帝国大学農科大学に移行してからは,西松次郎教授が1892(明治25年)まで続行し,1893(明治26)年から1917(大正6)年までは脇水鐵五郎(1867-1942)が講師および助教授として授業した(根岸ほか,2007).
富士谷はなぜイギリスに行ったか
下記二つの資料を入手した.
1889(明治22)年3月15日大阪朝日新聞朝刊に大津通信(3月14日発)より
当国の豪商が資金百万円を以て近江製絨所を創立せんと計画中のよしは先にも報ぜしが,何故か発起人中に取越し苦労をなす者ありて今日まで着手の運びに至らざりしが殊に客年実業視察のため欧州に赴きたる富士谷孝雄氏ほか2名にはいずれも一昨日帰国し昨日は発起人を集め種々相談ありしかば発起人は大いに感ずる所ありしものか至急創業に着手することに決したりとまたいよいよ設立するに至らば富士谷氏を社長とする由.
明治22(1889)年8月21日東京朝日新聞朝刊より
近江銀行の計画
滋賀県の融資者は昨年日本製絨会社という社を設立するつもりにて某知事の周旋により外務翻訳官富士谷孝雄氏が辞職の上わざわざ英国に航するなど興社設計のためそれこれ三万数千円の入費を支払いしにもかかわらず,そのことついに成らずしてむなしく解社し,更に一変して金巾(かなきん)製織会社を起こすこととなり.すでに七分通り協議の整いし処へ過日松方大蔵大臣の大津に来たれるを幸い,大臣の意見を聴きしに其れは以ての外の事にて,十分技術に詳しからざれば能わざるのみならず・・・・・との一言にて急に是も断念することとなり.全くその代りにてもあるまじきけれど,右両者を発起せし・・・・の諸氏等が今度ある筋の勧奨により近江銀行と称する資本金百五十万円の私立銀行を起こし銀行一般の営業を為すこととし・・・去る18日には大津で発起人総会を開きし由なるが,同署の4国立銀行,1私立銀行,もしこの挙の成り立たんには,此れがため,直接に莫大の影響を被るべしとて非常に心配なし居るよし.
近江製絨所,日本製絨会社から金巾製織会社に,そして近江銀行と計画がどんどん変わっていき,近江銀行もうまくいくか心配であると結んでいる.この2つの記事から,富士谷の奇妙な行動(外務省を辞職し,英国に赴いた)の理由がわかる.富士谷はかなり運命を翻弄されたのであろう.また,富士谷と滋賀県の結び付きもかなり強かったといえよう.
文 献
ナウマン,E.・富士谷孝雄・山田 皓・坂 市太郎・西山正吾,1886,大日本帝国予察東北部地質図,農商務省地質局
根岸賢一郎ほか,2007,千葉演習林沿革史資料(6):松野先生記念碑と林学教育事始めの人々,演習林,46号,57-121.
山田直利,2008,ナウマンの「予察東北部地質図」−予察地質図シリーズの紹介その1−,地質ニュース,652号,31-40._
【geo-Flash】No.362 125周年記念特集号の状況について
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.362 2016/12/20┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】125周年記念特集号の状況について
【2】2017年度会費払込について
【3】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されます
【4】惑星地球フォトコンテスト:締め切り本年度は正月明けです!
【5】第3回防災学術連携シンポ熊本地震・一周年報告会(仮)発表募集
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】事務局年末年始休業(12/29〜1/4)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】125周年記念特集号の状況について
─────────────────────────────────
125周年記念特集号企画委員会 宮下純夫
2018年に迎える日本地質学会創立125周年記念事業のさきがけとして,2017年よ
り様々な企画が始まります.今回の125周年にあたっては,「日本の地質学100
年」以降の25年間における各分野の進展や成果を地質学雑誌特集号として2017
年から2年間にわたって順次取りまとめることとなっています.125周年記念特
集号は当初の予定では2017年の1月号からの開始を予定していましたが,実際
の投稿・編集作業の遅れのため,開始時期については多少遅れる見込みです.
続きはこちらから、、、http://www.geosociety.jp/125th/content0003.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2017年度会費払込について
─────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下さいますよ
うお願いいたします.
■2017年度分会費の引き落とし日:12月26日(月)です.
請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下
さい.
■自動引き落とし以外の方(お振り込み)
12月15日に請求書兼郵便振替用紙を発送いたしました.届きましたら折り返し
ご送金くださいますようお願いいたします.
2017年度会費払込について
http://www.geosociety.jp/outline/content0164.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されます
──────────────────────────────────
募集期間:2016年12月20日(火)〜2017年2月10日(金)
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75 歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:例えば,,,地質学への顕著な貢献/地質学会の運
営と発展への貢献/教育現場や企業などでの活動を通じた地質学の普及と振興
への貢献など
*上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することはできませ
んが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
(名誉会員推薦委員会 山本高司)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】惑星地球フォトコンテスト:締め切り本年度は正月明けです!
──────────────────────────────────
【応募締切】2017年1月10日(火)17時(郵送での応募は同日必着)
本年度のフォトコンは,地質学会長賞をもうけました!これは,地質学会会員
への特別枠です.
昨今,地質学会員でも美しい露頭をカメラに記録させることが少なくなってき
ました.カメラの精度はどんどん上がっており,スマホやミラーレスカメラな
ど,軽くて便利な機器も増えています.SNSなどでは人物なども含め膨大な写真
が公表されています.ぜひ,露頭に向かって,自分が見た地層が物語る歴史と
その美しさを伝えませんか?露頭を観察し,洞察し,分析していきながら歴史
を振り返る,その最初のステップをぜひ大切にしたいものです.
ぜひ,地質を理解した地質学会会員視点からの,美しい写真を期待しています!
【こんな作品を大募集】
地球の大地が持つ美しい自然風景/断層・津波・火山など活きた地球像/岩石・
地層・化石などが持つ天然美/学術的意義・教育効果の高い地球科学作品/ジ
オパークの知られざる大地の姿/ジオ鉄写真:鉄道と地質/地形とのコラボ/チャ
ンスを逃さない新たな視点のスマホ写真
【賞および賞金】
最優秀賞 1点:賞金5万円/優秀賞 2点:賞金2万円
ジオパーク賞 1点:賞金2万円/地質学会会長賞 1点:賞金1万円
ジオ鉄賞 1点:賞金1万円/スマホ賞 1点:賞金5千円 など
今年も皆様からのご応募をお待ちしています.http://photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第3回防災学術連携シンポ熊本地震・一周年報告会(仮)発表募集
──────────────────────────────────
防災学術連携体(防災減災・災害復興に関する55学会のネットワーク,地質学
会も参加)では,来年4月15日(土)に熊本県と共催で熊本地震・一周年報告会
を企画しています.
主催:内閣府,日本学術会議,防災減災・災害復興に関する学術連携委員会,
防災学術連携体(防災に関わる55学会のネットワーク),熊本県
日時:2017年4月15日(土)13:00〜18:00
場所:熊本県庁内
シンポジウムの詳細(案)はこちらから,,,
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/geoFlash_img/no.362_bosai3rd_170415.pdf
【発表希望の連絡締切】2017年1月10日(火)<main@geosociety.jp>宛
熊本地震に関わる調査結果を地元に報告する学会を優先するということですの
で,地質学会として発表を希望される方は年明け1月10日(火)までに簡単な発
表内容,発表予定者,連絡先を地質学会事務局までご連絡下さい.複数の応募
があった場合には調整させて頂くこともございます.よろしくお願い申し上げ
ます.
(日本地質学会 防災学術連携体連絡委員 松田達生)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■2016年度功労賞募集
対象者:支部活動や地質学を通して広く社会貢献をされた関東支部内に在住の
個人・団体(*社会貢献や活動の評価においては,必ずしも学問的な成果を問
うものではありません)
公募期間:2016年12月10日(土)〜2017年1月10日(火)
詳しくは,http://kanto.geosociety.jp/
[西日本支部]
■西日本支部平成28年度総会・第168回例会
2017年2月18日(土)9:30〜 例会終了後 懇親会
会場:宮崎大学(木花キャンパス)教育学部
講演申込み締切:2月3日(金)17:00
★★総会に欠席の方は委任状をお送り下さい★★
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■(協)第14回岩の力学国内シンポジウム:JSRM2017
1月10日(火)〜12日(木)
会場:神戸大学百年記念館
http://rock.jsms.jp/jsrm2017/
■ふしぎ発見!鳥取砂丘(鳥取砂丘調査研究報告会)
1月21日(土)13:00〜16:30
場所:とりぎん文化会館第2会議室
主催:鳥取砂丘再生会議
http://www.tottorisakyu.jp/
■第194回地質汚染イブニング・セミナー
1月27日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:古野邦雄(元千葉県環境研究センター主席研究員)
高嶋 洋(野田市道路管理課主査)
テーマ:関東地下水盆管理と水循環基本法
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■(共)4th IGS (international Geoscience Symposium)
Precambrian World 2” in Fukuoka
3月3日(金)〜5日(日)
会場:九州大学西新プラザ
Keynote(予定):
J. カーシュビング教授:Caltec スノーボールアースー生物進化
W. ブローカー博士:カナダ地質調査所 太古代ー原生代大陸復元
A. ホフマン教授:ヨハネスブルグ大学 太古代の表層環境 34億年前のチャート
掘削等
http://www.kochi-u.ac.jp/marine-core/precambrian_world/PW2017/top.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0151.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■平成29年度「消防防災科学技術研究推進制度」研究開発課題の公募(2/6)
■寒地土木研究所任期付研究員公募(斜面災害分野)(1/31,17時)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】事務局年末年始休業(12/29〜1/4)
──────────────────────────────────
学会事務局は,12月29日(木)〜1月4日(水)までお休みとなります.
新年5日より通常営業となります.よろしくお願いいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
★★本号が年内最終の配信となります.次回は新年5日配信予定です★★
日本地質図百景
日本地質図百景
正会員 石渡 明
産業技術総合研究所地質調査総合センター(以下「地調」。旧通商産業省工業技術院地質調査所)の地質図は、1/20万図が北方領土を除く全国122区画(110図幅、うち2区画合体図幅が12)を、1/5万図が全国の約6割(1274区画のうち760)をカバーし、凡例を統一した1/20万全国シームレス地質図も提供されている。北海道については、国土交通省北海道局(旧北海道開発庁)及び北海道立総合研究機構地質研究所(旧地下資源調査所)による地質図も含めると、全道のほとんどの1/5万図が出版済みである(未出版は7区画)。そしてこれらのすべての地質図とその説明書が、地調のホームページにて無料で閲覧・ダウンロードできる(https://www.gsj.jp/Map)。これらの地質図は学校や社会における地学教育にも非常に有用であるが、どの地質図がどのようなテーマの教材として役立つかを示したガイドが、これまで無かったように思う。私は仕事柄全国の地質図を見る機会が多いので、その経験に基づいてテーマごとに地質図の「見どころ案内」を試みる。以下のリストでは、テーマを五十音順に並べ、各テーマをよく表現している地質図の名称を挙げ、そのうち特に見事な百景に●を、1/20万図には「20」を、火山地質図には「△」を、特殊地質図には「☆」を付した。優れた地質図は、見る者に地質プロセスのダイナミズムを感得させるが、どの地質図にも調査者の趣向や考え方、作成当時の学界のレベルや流行学説が色濃く反映されており、作成者や出版年によく注意して利用する必要がある。これらの地質図には半世紀以上昔のものも多く、そこに表現された事実や解釈が全て正しいわけではないので、最新の文献を参照するなど、使用者の責任において活用していただきたい。拙稿に貴重な改善意見をいただいた竹内圭史会員に感謝する。
項目名(五十音順) 図幅名(北から南へ)
圧砕岩(あっさいがん)→マイロナイト / 埋立地(うめたてち)→沖積地(ちゅうせきち)、溜(ため)池(いけ) / エクロジャイト ●新居浜(にいはま)、泊
オフィオライト(玄武岩、斑れい岩、蛇紋岩等の複合岩体) 幌加内(ほろかない)、千(ち)呂(ろ)露(ろ)、幌(ぽろ)尻(しり)岳(だけ)、●20夕張岳、20浦河、●早(はや)池(ち)峰(ね)山(さん)、万場、寄居、三河(みかわ)大野(おおの)、鳥羽(御荷(みか)鉾(ぶ))、鋸崎(のこぎりざき)、小浜(おばま)、舞鶴(まいづる)、綾部(あやべ)、●福知山(ふくちやま)(夜久野(やくの))、小滝、大江山、若桜(わかさ)、上石(かみいわ)見(み)、多里(たり)
オルドビス系(日本最古の地層)早池峰山、小滝、●上(かみ)高地(こうち)(福地)、伊野(日立のカンブリア系は地質図未出版) →地層、チバニアン / 温泉→変質帯
崖(がい)錐(すい)堆積物 乙(おつ)忠部(ちゅうべ)、摩(ま)周(しゅう)湖(こ)、●落合、西(にし)達(たっ)布(ぷ)、大雪山(だいせつざん)
海成(海岸)段丘 礼文(れぶん)島、●焼(やぎ)尻(しり)島、●奥尻島、乙(おつ)忠部(ちゅうべ)、音標(おとしべ)、雄武(おうむ)、寿都(すっつ)、久遠(くどう)、松前、大間(おおま)、佐井(さい)、大畑、●鰺(あじ)ヶ沢、深浦、象潟(きさかた)(飛島)、館山(たてやま)、珠洲(すず)岬(みさき)・能登飯田及び宝(ほう)立山(りゅうざん)、高砂(たかさご)
海底地質 ●渡島(おしま)福島(青函トンネル)、20窪川(くぼかわ)、薩摩(さつま)硫黄(いおう)島(じま)(鬼界(きかい)カルデラ)、20宮古島、20魚釣(うおつり)島(しま) →活断層(海域) →別に各地の海洋地質図がある。
河成(河岸)段丘 ●陸別、20北見、上士幌(かみしほろ)、中士幌(なかしほろ)、高島、十勝池田、糠内(ぬかない)、忠類(ちゅうるい)、遊楽部(ゆらっぷ)岳、舘(たて)、知内(しりうち)、米内(よない)沢、刈和(かりわ)野(の)、鷹ノ巣、青梅、八王子、●東京西南部、20東京、横浜、見附、浜松、岐阜、四日市、亀山
鍵層(かぎそう) ●高島(水平)、●清川、柏崎(かしわざき)、小千谷(おぢや)、富津(ふっつ)、五百石(ごひゃっこく)、師崎(もろさき)、半田、津東部、桑名、水口(みなくち)、京都東北部、大阪東北部、岸和田、三田(さんだ)
花崗(かこう)岩体(巨大なもの) ●太平山(たいへいざん)、土淵(つちぶち)(遠野花崗岩)、千厩(せんまや)(千厩岩体)、浪江(なみえ)及び磐(いわ)城(き)富岡(とみおか)、原町(はらまち)及び大甕(おおみか)、川俣(かわまた)、川前(かわまえ)及び井出(いで)(阿武隈花崗岩)、真壁(まかべ)(筑波)、飯田、妻(つま)籠(ご)、足助(あすけ)、水口(みなくち)、宮津(みやづ)、●広島、根(ね)雨(う)、内之浦、屋久島西南部、20屋久島
累帯( るいたい)深成岩体 ●千厩(せんまや)(折壁岩体)、石動(いするぎ)(宝(ほう)達山(だつさん)花崗岩)、御在所山(鈴鹿花崗岩)
ルーフペンダント 三(みつ)峰(みね)、飯田、妻(つま)籠(ご)、三津(みつ)、●厳(いつく)島(しま)(西能美島)
火山(火山地質図)(数字はスケール、万分の1単位、他項では△で示す) 3十勝(とかち)、3樽前(たるまえ)、2.5有珠(うす)(2版)、5北海道駒ヶ岳、2.5岩手、2.5蔵王(ざおう)、3那須、2.5草津白根、5浅間、2.5伊豆大島、2.5三宅島、1青ヶ島(及び海底火山)、2.5九重(くじゅう)、5阿蘇、2.5雲仙、5霧島、2.5桜島(2版)、2.5口(くち)永(のえ)良部(らぶ)島、2諏訪之瀬(すわのせ)島(火山関係の特殊地質図(他項では☆で示す) ●5富士(2版)、2.5鬼首(おにこうべ)、10八(はっ)甲田(こうだ)地熱地域(八甲田、十和田、碇(いかり)ヶ関)、10仙岩(せんがん)地熱地域(岩手山、秋田駒ヶ岳等)、10栗駒地熱地域(栗駒、鳴子、鬼首等)、10豊(ほう)肥(ひ)地熱地域(九重等))→泥火山 / →活断層(火山体を切る)
火山(カルデラ)屈斜路湖、摩周湖、阿寒湖、20斜里、樽前山(たるまえさん)(支笏(しこつ))、徳舜瞥(とくしゅんべつ)、登別(のぼりべつ)温泉(倶多楽(くったら))、虻田(あぶた)(洞爺(とうや))、濁川(にごりかわ)、20野辺地(恐山)、☆八甲田(十和田、碇(いかり)ヶ関)、☆鬼首(おにこうべ)、☆栗駒(鬼首、鳴子、向町)、宮下(沼沢)、田島(塔のへつり等)、△阿蘇、20熊本、●20大分(阿蘇)、20八代(加久(かく)藤(とう))、●20鹿児島(姶良(あいら))、開聞(かいもん)岳(だけ)(池田)、20開聞岳(“阿多(あた)”)、薩摩(さつま)硫黄(いおう)島(じま)(鬼界(きかい)) →コールドロン
火山(成層火山、火山地質図を除く)利尻島、20留萌(るもい)(暑寒別岳)、大雪山、旭岳(トムラウシ)、20旭川、歌志内(イルムケップ)、然(しかり)別(べつ)湖、留寿都(るすっつ)(羊(よう)蹄山(ていざん))、岩内(いわない)、狩(かり)太(ふと)(ニセコ)、恵山(えさん)、渡島(おしま)大島、大畑(燧(ひうち)岳(だけ))、五所川原、弘前(ひろさき)(岩木山)、●鳥海山(ちょうかいさん)及び吹浦、20仙台(月山、肘折等)、二本松(安達(あだ)太良(たら)山)、燧(ひうち)ヶ岳、男体山、須坂(四阿山(あずまやさん))、沼田、20宇都宮(赤城山)、●榛名(はるな)山、苗場山、飯山(毛無山)、●戸隠(とがくし)(飯(いい)綱(づな)山・黒姫山)、20長野、諏訪(霧ヶ峰)、蓼科山(たでしなさん)、八ヶ岳(やつがたけ)、御岳昇仙峡(みたけしょうせんきょう)、20甲府(茅(かや)ヶ岳)、修善寺(しゅぜんじ)(天城、達磨)、御蔵島(みくらじま)、八丈島、立山(弥陀ヶ原(みだがはら))、乗(のり)鞍(くら)岳(だけ)、御嶽山(おんたけさん)、大山(だいせん)、三瓶山(さんべさん)、20中津(両子山(ふたごやま))、20熊本(多良(たら)岳(だけ)、金峰山(きんぼうさん))、開聞(かいもん)岳(だけ)、薩摩(さつま)硫黄(いおう)島(じま)
火山(単成火山群)伊東、20高梁(たかはし)(北西部)、●小値賀(おぢか)島(じま)、富江 (噴石(スコリア)丘等)
火山(マール)利尻島(沼浦)、●戸賀及び船川(目潟火山群)、大島(波浮)、加治木(かじき)(米丸・住吉池)
火山(溶岩ドーム(円頂丘)、火山地質図を除く)新島(にいじま)、●神津島(こうづしま)、金沢(戸室山)
火山深成複合岩体→コールドロン
火山灰(火砕流)台地 ●20斜里、20釧路(くしろ)、20標津(しべつ)、20根室(屈斜路(くっしゃろ)・摩周・阿寒)、美瑛(びえい)、志(し)比内(びない)、下富良野(しもふらの)、佐幌岳、十勝(とかち)岳(だけ)、●20旭川(十勝岳)、樽前(たるまえ)山、千歳(ちとせ)、20札幌(支笏(しこつ))、虻田(あぶた)、留寿都(るすっつ)(洞爺(とうや))、十和田(とわだ)、八甲田(はっこうだ)、青森西部、黒石(十和田・八甲田)、岩ケ崎、古川(鳴子・鬼首(おにこうべ))、榛名山(はるなさん)、宮原(みやのはる)、竹田(たけた)、●20大分、20熊本、20福岡(阿蘇)、都城(みやこのじょう)、野尻、国分(こくぶ)、鹿屋(かのや)、20鹿児島、20宮崎(姶良(あいら))
化石(アンモナイト等) 達(たっ)布(ぷ)、上芦別(かみあしべつ)、●幾(いく)春(しゅん)別(べつ)岳(だけ)、紅葉山(もみじやま)(付図)、陸中野田、気仙沼、万場(まんば)、荒島岳、臼杵(うすき)、日奈久(ひなぐ)、魚(お)貫崎(にきざき)及び牛深(うしぶか)、中甑(なかこしき) / ガス田→油田
活断層(陸域) 歌棄(うたすつ)(黒松内)、青森西部(黒石、入内等)、喜多方(会津盆地西縁)、●青梅(おうめ)(立川)、横須賀(武山・北武)、熱海(あたみ)(丹那(たんな))、松本(松本・牛伏寺(ごふくじ))、飯山(飯山・常盤)、飛騨古川、白木(しろき)峰(みね)、東茂(ひがしも)住(ずみ)、五百石(ごひゃっこく)(跡津川・牛首)、加子母(かしも)、付知(つけち)、妻(つま)籠(ご)(阿寺(あてら))、谷汲(たにぐみ)、根尾(根尾谷)、北小松(花折)、上野(木津川)、広根、京都西南部(有馬(ありま)・高槻(たかつき)構造線)、大阪東北部、大阪東南部(上町(うえまち)、誉田(こんだ)、生駒(いこま))、神戸、●大阪西北部、須磨(すま)(五助橋等)、宮津(郷村(ごうむら)、山田)、鳥取南部(鹿野・吉岡)、龍野(たつの)、佐用(さよ)、山崎(山崎)、新居浜(にいはま)、20松山(中央構造線)、福岡(警固(けご)等)
活断層(海域) 20長岡、20新潟(2版)、20横須賀、20静岡及び御前崎、今庄及び竹波、●20松山、豊後(ぶんご)杵築(きつき)、20中津、20大分(2版)、20八代(やつしろ)
活断層(火山体を切る) 鳥海山(ちょうかいさん)及び吹浦、●△雲仙(うんぜん)、△那須(なす) (環礁を切る)→サンゴ礁
岩床群(主にドレライト) 母衣(ほろ)月(づき)、●蟹田、小泊(こどまり)、油川(あぶらかわ)、金木、太良(だいら)鉱山(田代岳)、阿仁合(あにあい)(2版)、雫石(しずくいし)、●大沢(青沢)、清川、粟島(あわしま)、坂城(さかき) / 岩屑流(がんせつりゅう)→流山(ながれやま)
岩脈群 利尻島(放射状)、知床岬、札内岳、八海山、●越後湯沢、大島、●御蔵島、父島列島、20豊橋及び伊良湖岬(設楽(したら)コールドロン)、京都東北部、呉、倉橋島及び柱島、●浦郷(放射状)、石垣島東北部
かんらん岩体 ●幌泉(ほろいずみ)(幌(ほろ)満(まん))、新居浜(にいはま)(東赤石(ひがしあかいし)) / グラニュライト ●20夕張岳
玄武岩台地 郷(ごう)ノ浦、●呼子(よぶこ)、唐津、平戸、伊万里、佐世保、蛎(かき)ノ浦、20唐津、20長崎
向斜→褶曲(しゅうきょく) / 黒曜石 ●白滝、諏訪(和田峠)、20長野、神津島(こうづしま)(砂(さ)糠山(ぬかやま))、姫島(観音崎の城山溶岩)
鉱床・鉱物 上渚滑(かみしょこつ)(竜昇殿(北鎮)水銀)、下川(銅)、上支(かみし)湧別(ゆうべつ)(イトムカ水銀)、定山渓(じょうざんけい)(豊羽黒鉱帯)、太良(だいら)鉱山(黒鉱帯)、足尾(銅、砂川一郎氏の鉱物記載)、東茂(ひがしも)住(ずみ)(神岡スカルン)、●荒島岳(中竜(なかたつ)スカルン)、吉野山(大和水銀)、大屋市場(明(あけ)延(のべ)銅)、生野(いくの)(銅)、周匝(すさい)(柵原(やなはら)黄鉄鉱)、温泉津(ゆのつ)及び江津(ごうつ)(石見(いわみ)銀山(ぎんざん)=大森鉱山)、(伊予)三島(佐々連(さざれ)銅)、新居浜(にいはま)(別子(べっし)銅)、川内(せんだい)(串木野(くしきの)金) →石灰岩体、炭田、油田
コールドロン(火山深成複合岩体) 湯沢(院内)、上高地(笠ヶ岳)、20豊橋及び伊良湖岬(設楽)、20岐阜(荒島岳)、那智、20田辺、20木本(きのもと)、20伊勢(熊野)、播州(ばんしゅう)赤穂(あこう)、20浜田(掛合(かけや)(北東部)、波(は)佐(ざ)(南西部))、20山口及び見島(益田、田万川(たまがわ)(北東部))、20高知(石(いし)鎚(づち)(北西部))、竹田、三重町、三田井、熊田、諸塚山、延岡(のべおか)、●20大分、●20延岡(大崩山)、尾鈴山、都農(つの)、富高、神門(みかど)、20延岡(尾鈴山)
砂丘・浜堤 抜海(ばっかい)、稚(わっか)咲内(さかない)、●浜頓別(はまとんべつ)、金木、五所川原、角田(かくだ)、新潟及び内野、●茂原(もばら)、御前崎、津東部、津幡(つばた)、鳥取北部、宮崎
サヌカイト(讃岐岩・高Mg安山岩) 観音寺
サンゴ礁 ●多良間(たらま)島(環礁とそれを切る活断層)、宮古島(来間(くりま)島の活断層)
隆起サンゴ礁(琉球石灰岩) 糸満(いとまん)及び久(く)高島(だかじま)、那覇(なは)及び沖縄市南部、石垣島北東部
山体崩壊堆積物 白馬(しろうま)岳(だけ)(1911年稗田(ひえだ)山崩壊)、●御嶽山(おんたけさん)(1984年伝上(でんじょう)崩壊) →流山(ながれやま)
地すべり 立(たつ)牛(うし)、余(よ)別(べつ)及び積丹(しゃこたん)岬(みさき)、原歌(はらうた)及び狩場山、相(あい)沼(ぬま)、戸隠(とがくし)、●飯山、珠洲(すず)岬・能登飯田及び宝(ほう)立山(りゅうざん)、冠山(かんむりやま)、新居浜(にいはま)、日比原、大洲(おおず)
蛇(じゃ)紋(もん)岩体(蛇紋岩メランジュ) ●敏音(ぴんね)知(しり)、20枝幸(えさし)、石狩(いしかり)金山(かなやま)、岩(いわ)知(ち)志(し)、三石(みついし)、20夕張岳、早(はや)池(ち)峰山(ねさん)、大迫(おおはざま)、人首(ひとかべ)、20盛岡、小滝、白馬(しろうま)岳(だけ)、20富山、鳥羽、大江山、上石(かみいわ)見(み)、多里(たり)、20高梁(たかはし)、伊野、三重町、犬飼、鞍岡、砥用(ともち)、日奈久(ひなぐ)
褶曲(しゅうきょく) 宗谷及び宗谷岬、沼川、●紅葉山(もみじやま)、早来(はやきた)、●20高田、大町、根尾、和歌山及び尾崎、粉河、●20徳島、20岡山及び丸亀、仁位(対馬)→単斜構造
背( はい)斜(しゃ)(ドーム)留萌(るもい)、浜益(はまます)、上芦別(かみあしべつ)、●雄(ゆう)別(べつ)、20釧路(くしろ)、20青森、大沢、松之山温泉、高田東部、高田西部、大町、●谷汲(たにぐみ)、20岐阜、栗栖(くりす)川(アンチフォームを含む)
向( こう)斜(しゃ)(ベーズン)上猿払(かみさるふつ)、20枝幸(えさし)、●遠別(えんべつ)、初浦(はつうら)、端野(たんの)、西徳富(にしとっぷ)、舘(たて)、気仙沼(けせんぬま)、●栃木(足尾帯)、槍ヶ岳(薬師岳付近)、信濃池田、城端(じょうはな)(シンフォームを含む)
撓曲( とうきょく) 十和田、津西部、桑名、水口(みなくち)、●大阪東北部
重力異常と地質の対応 ☆栗駒、珠洲(すず)岬(みさき)・能登飯田及び宝(ほう)立山(りゅうざん)、●境港(さかいみなと)
衝上(しょうじょう)断層 ●大夕張(おおゆうばり)、山部(やまべ)、能代(のしろ)、森岳(能代衝上)、羽後(うご)和田、本荘(ほんじょう)(北由利衝上)、酒田(酒田衝上)、寄居(よりい)(跡倉(あとくら)ナップ、金(きん)勝山(しょうざん)クリッペ)、清水(糸静線則沢クリッペ)、東茂(ひがしも)住(ずみ)、白木(しろき)峰(みね)、八尾(やつお)(横山衝上)、根尾(徳山衝上)、御在所山(竜ヶ岳クリッペ)、彦根東部(霊山(りょうぜん)クリッペ)、山上ヶ岳(奥高原(おくたかはら)地窓・四寸(しすん)岩山クリッペ)、若桜(わかさ)(蛇紋岩が三郡変成岩に衝上)、津山東部(美作(みまさか)衝上)、蒲江(かまえ)、延岡(のべおか)、諸塚(もろつか)山、●神門(みかど)、椎葉村(しいばむら)、村所(むらしょう)(延岡(のべおか)衝上)
石灰岩体 20八戸(はちのへ)、20盛岡(安家(あっか))、●栃木、20宇都宮(葛生(くずう))、根尾、谷汲(たにぐみ)、美濃、近江(おうみ)長浜、彦根東部、20岐阜、20名古屋(舟伏山・伊吹山・霊山(りょうぜん))、20高梁(たかはし)(阿哲・帝釈(たいしゃく))、20山口及び見島(蔵(ぞう)目喜(めき)・秋吉)、20福岡(平尾台など)、20大分、臼杵(うすき)、20延岡(のべおか)、20八代(やつしろ)(秩父(ちちぶ)帯) →サンゴ礁
扇状地(せんじょうち) 八王子、青梅(おうめ)、●長野 / 剪断帯(せんだんたい)→マイロナイト / 溜(ため)池(いけ)と埋立地 ●高砂
単斜構造(地層の) 遠軽(えんがる)(高角、諸説あり)、●姉崎(低角)、坂城(さかき)(ほぼ水平) →褶曲
段丘→海成段丘、河成段丘 / 断層→活断層、衝上(しょうじょう)断層、マイロナイト
炭田(炭層と炭鉱) 築別炭礦(ちくべつたんこう)、歌志内(うたしない)、砂川、夕張、大夕張、吉岡(仙台北方)、川前及び井出、●平(たいら)(常磐)、宇部東部、大牟田(おおむた) →別に各地の炭田図がある。
地溝帯 ●万場(まんば)(山中(さんちゅう)地溝)、邑(おう)知(ち)潟(がた)(邑知地溝)、白木(しろき)峰(みね)(利賀(とが)地溝)、△雲仙(雲仙地溝)
地層(各地質時代の代表的な地層、付加体を除く)→オルドビス系、チバニアン、付加体
シルル・デボン・石炭系 ●早(はや)池(ち)峰山(ねさん)、20盛岡、20一関(いちのせき)、上(かみ)高地(こうち)、伊野、砥用(ともち)、日奈久(ひなぐ)
ペルム(二畳)・トリアス(三畳)・ジュラ系 ●登米(とよま)、気仙沼(けせんぬま)、志津川(しづがわ)、20一関(いちのせき)、20石巻(いしのまき)
白亜系 ●20夕張岳、陸中野田、和歌山、粉河(こかわ)、小倉(こくら)、折尾、魚(お)貫崎(にきざき)及び牛深、中甑(なかこしき)
古第三(古成(こじょう))系 20札幌、20夕張岳、●平(たいら)、母島・父島列島、小倉、折尾、福岡
新第三(新成(しんじょう))系 20留萌(るもい)、●戸賀及び船川、小千谷(おぢや)、柏崎(かしわざき)、五百石(ごひゃっこく)、八尾(やつお)
第四系 ●茂原、姉崎、富津、●東京西南部、横浜、●大阪東北部、奈良
チバニアン(第四系更新統千葉階(提案中)、正しくは「チバン」か)日本油田・ガス田図No. 4「富津(ふっつ)・大多喜(おおたき)」(北端部)及び☆1/10万「東京湾とその周辺」の上総(かずさ)層群国本(こくもと)層中に同階の基底がある(模式地は田淵西方の養老川、Ku2鍵層の約20m下)。1/5万「大多喜」は未刊行だが、「茂原」に北東延長部の説明あり。
沖積(ちゅうせき)地・埋立(うめたて)地 鶴岡、●新潟及び内野、名古屋南部、名古屋北部、津島、佐賀 →泥炭 →別に各地の水理地質図がある。
泥炭(湿原) 稚(わっか)咲内(さかない)、●大楽(おたのし)毛(け)、石狩、札幌、恵庭(えにわ)、長万部(おしゃまんべ)、八雲(やくも) / 泥火山 ●静内(しずない)
流山(ながれやま)・岩屑流(がんせつりゅう)堆積物 △有珠山(うすさん)、大沼公園、駒ヶ岳、△北海道駒ヶ岳、五所川原(岩木山)、象潟(きさかた)、矢島(鳥海山)、雫石(しずくいし)(岩手山、小岩井農場付近)、●鶴岡(月山(がっさん))、喜多方(きたかた)(磐梯山(ばんだいさん))、飯山(毛無山)、△浅間山(あさまやま)、小諸(こもろ)(浅間山(あさまやま))、△雲仙(うんぜん)、△霧島(夷(ひな)守(もり)岳(たけ)) →山体崩壊堆積物 / 熱水→変質帯 / 背(はい)斜(しゃ)→褶曲(しゅうきょく)
氷河堆積物 旭岳、●幌(ぽろ)尻(しり)岳(だけ)、●槍ヶ岳、立山、小滝、白馬岳、上高地 / 浜堤→砂丘
付加体 立(たつ)牛(うし)、20浦河(うらかわ)(日高帯)、一戸(いちのへ)、早(はや)池(ち)峰山(ねさん)(根(ね)田茂(だも)帯・北部北上(きたかみ)帯)、三(みつ)峰(みね)、五日市(いつかいち)(秩父(ちちぶ)帯、四万十(しまんと)帯)、館山(たてやま)、那(な)古(ご)、横須賀(中新世付加体)、南部、清水(瀬戸川帯)、下呂(げろ)、八幡(はちまん)、美濃(みの)、谷汲(たにぐみ)、今庄(いまじょう)及び竹波(美濃帯)、西津、熊川、●北小松*、京都東北部、京都西北部、園部、四谷、綾部(あやべ)(丹波帯)、●山上ヶ岳(さんじょうがたけ)、龍神、栗栖川、江(え)住(すみ)、北川、●20宇和島、三重町、蒲江(かまえ)、熊田、延岡(のべおか)、椎葉村(しいばむら)、尾鈴山、村所(むらしょう)、●末吉*、砥用(ともち)、湯(ゆ)湾(わん)(秩父帯、四万十帯)、小倉(こくら)(秋吉帯) (*デュープレックス構造)
不整合・基底礫岩(れきがん) 生田原(いくたわら)、木古内(きこない)、志津川(しづがわ)、妻及び高鍋、宮崎、●日向(ひゅうが)青島(あおしま)、都井(とい)岬(みさき)
変質帯(熱水・温泉) 愛別、国領、雄(お)冬(ふゆ)、大畑、須坂、諏訪、御岳昇仙峡、八ヶ岳、下田、●神子(みこ)元島(もとじま)、母島列島、豊後(ぶんご)杵築(きつき) →鉱床
変成帯(広域―) 落合、御影、札内岳、札内川上流、神威(かむい)岳(たけ)、上(かみ)豊(とよ)似(に)、楽(らっ)古岳(こたけ)、20夕張岳、20浦河(うらかわ)(日高帯)、三石(神居古潭帯)、白木峰(飛騨帯)、高遠(たかとお)、市野瀬、●御油(ごゆ)、足助(あすけ)、奈良、岩国(領家帯)、寄居、●新居浜(にいはま)、日比原(三波川帯)、砥用(ともち)(肥後帯)
変成帯(接触―) 仁宇(にう)布(ぷ)、滝上(たきのうえ)、早(はや)池(ち)峰山(ねさん)、釜石(かまいし)、須原、足尾、市野瀬、●御油(ごゆ)、北小松、横山、根(ね)雨(う)、20厳原(いずはら)(対馬(つしま)南部)、●熊田、椎葉村(しいばむら)、村所(むらしょう)、●鹿屋(かのや)、20徳之島
ボニナイト(無人岩・高Mg安山岩) 父島列島
マイロナイト(ミロナイト、圧砕岩、剪断(せんだん)帯) 上支(かみし)湧別(ゆうべつ)(日高帯)、20夕張岳、20浦河(うらかわ)(日高主衝上)、20甲府、20豊橋及び伊良湖岬、20伊勢、高遠(たかとう)、●吉野山、岸和田(中央構造線)、魚津、東茂(ひがしも)住(ずみ)(飛騨帯) / マール→火山
ミグマタイト ●上(かみ)豊(とよ)似(に)、神威(かむい)岳(だけ)、楽(らっ)古岳(こだけ)、幌泉(ほろいずみ)(日高)、竹貫(たかぬき)(阿武(あぶ)隈(くま))
油田・ガス田 羽後(うご)浜田、秋田、酒田、●新潟及び内野、柏崎、20新潟、20長岡、20千葉、20東京 →別に各地の油田・ガス田図がある。
溶岩台地 →玄武岩台地
流紋岩体(巨大なもの) 加子母(かしも)、付知(つけち)、金山、●下呂(げろ)、萩原、三日町、飛騨古川、20飯田、20高山(濃飛(のうひ)流紋岩)、近江八幡(おうみはちまん)(湖東(ことう)流紋岩) →コールドロン、火山灰台地
累帯深成岩体・ルーフペンダント→花崗岩
(以上)
(2017.9.5,2018.7.27一部加筆)
【geo-Flash】No.363 新年あけましておめでとうございます
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.363 2017/1/5┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】年頭挨拶:日本地質学会創立125周年を迎えるにあたって
【2】惑星地球フォトコンテスト:まもなく締め切り!
【3】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されます
【4】第3回防災学術連携シンポ熊本地震・一周年報告会(仮)発表募集
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】年頭挨拶:日本地質学会創立125周年を迎えるにあたって
─────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会 会長 渡部芳夫
日本地質学会は,1893年に東京地質学会として創設されて以来,2018年5月に
創立125周年を迎えます.
明治維新の後,日本における地質学は,資源探査と国土の開発のために必須の
学問として,その歴史が始まりました.農業,工・鉱業は日本列島の地質の解
明とともに発展し,鉄道や道路の敷設,トンネル掘削地の決定などの大規模建
設事業には地質学の裏付けが不可欠でした.地質学会の最初の100年の歴史にお
いて,地質学は地層や岩石・化石・鉱物などを対象とする学問として発展する
ことによって,大いに日本の近代化に寄与し,社会の発展に貢献してきました.
続きはこちらから、、、
http://www.geosociety.jp/outline/content0137.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】惑星地球フォトコンテスト:まもなく締め切り!
──────────────────────────────────
【応募締切】2017年1月10日(火)17時(郵送での応募は同日必着)
本年度のフォトコンは,地質学会長賞をもうけました!これは,地質学会会員
への特別枠です.
昨今,地質学会員でも美しい露頭をカメラに記録させることが少なくなってき
ました.カメラの精度はどんどん上がっており,スマホやミラーレスカメラな
ど,軽くて便利な機器も増えています.SNSなどでは人物なども含め膨大な写真
が公表されています.ぜひ,露頭に向かって,自分が見た地層が物語る歴史と
その美しさを伝えませんか?露頭を観察し,洞察し,分析していきながら歴史
を振り返る,その最初のステップをぜひ大切にしたいものです.
ぜひ,地質を理解した地質学会会員視点からの,美しい写真を期待しています!
【賞および賞金】
最優秀賞 1点:賞金5万円/優秀賞 2点:賞金2万円
ジオパーク賞 1点:賞金2万円/地質学会会長賞 1点:賞金1万円
ジオ鉄賞 1点:賞金1万円/スマホ賞 1点:賞金5千円 など
皆様からのご応募をお待ちしています.http://photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されます
──────────────────────────────────
募集期間:2016年12月20日(火)〜2017年2月10日(金)
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75 歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:例えば,,,地質学への顕著な貢献/地質学会の運
営と発展への貢献/教育現場や企業などでの活動を通じた地質学の普及と振興
への貢献など
*上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することはできませ
んが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
(名誉会員推薦委員会 山本高司)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第3回防災学術連携シンポ熊本地震・一周年報告会(仮)発表募集
──────────────────────────────────
防災学術連携体(防災減災・災害復興に関する55学会のネットワーク,地質学
会も参加)では,4月15日(土)に熊本県と共催で熊本地震・一周年報告会を
企画しています.
熊本地震に関わる調査結果を地元に報告する学会を優先するということですの
で,地質学会として発表を希望される方は年明け1月10日(火)までに簡単な発
表内容,発表予定者,連絡先を地質学会事務局までご連絡下さい.複数の応募
があった場合には調整させて頂くこともございます.
【発表希望の連絡締切】2017年1月10日(火)<main@geosociety.jp>宛
日時:2017年4月15日(土)13:00〜18:00
場所:熊本県庁内
シンポジウムの詳細(案)はこちらから,,,
http://www.geosociety.jp/faq/content0686.html#bosai
(日本地質学会 防災学術連携体連絡委員 松田達生)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■2016年度功労賞募集
日本地質学会関東支部では,支部の顕彰制度に基づき2016年度も支部活動や
地質学を通して社会貢献された個人・団体を関東支部として顕彰いたします.
つきましては,下記の要領で支部会員からの推薦を募集します.
対象者:支部活動や地質学を通して広く社会貢献をされた関東支部内に在住の
個人・団体
*社会貢献や活動の評価においては,必ずしも学問的な成果を問うものではあ
りません.
公募期間:2016年12月10日〜2017年1月10日
選考期間:2017年1月11日〜2017年1月31日
関東支部功労賞審査委員会(委員長:伊藤谷生 前支部長)を設置
審査結果報告:NEWS誌、関東支部総会
推薦方法:対象者氏名,推薦者氏名,推薦理由(400字程度)を記入の上,関東
支部功労賞推薦としてメールもしくはFAXにて下記へお送りください.
推薦受付:神奈川県立生命の星・地球博物館 笠間友博
〒250-0031 小田原市入生田499
E-mail:kasama@nh.kanagawa-museum.jp ,FAX:0465-23-8846
参考:これまでの関東支部功労賞受賞者(順不同敬称略)
2010年度 清水惠助
2011年度 府川宗雄,かわさき宙と緑の科学館
2012年度 神戸信和,松島義章,加瀬靖之,下仁田自然学校
2013年度 埼玉県立自然の博物館,早稲田大学高等学院理科部地学班
2014年度 千葉達朗,横須賀市立自然・人文博物館
2015年度 千葉県立中央博物館,神奈川県大井町・株式会社古川
[西日本支部]
■西日本支部平成28年度総会・第168回例会
2017年2月18日(土)9:30〜 例会終了後 懇親会
会場:宮崎大学(木花キャンパス)教育学部
講演申込み締切:2月3日(金)17:00
★★総会に欠席の方は委任状をお送り下さい★★
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
電中研ニュースNo482『地熱発電所の環境アセスメントの効率化に向けて』
http://criepi.denken.or.jp/research/news/index.html?m=161226
*************(以下,関連団体の行事案内です)****************
■(協)第14回岩の力学国内シンポジウム:JSRM2017
1月10日(火)〜12日(木)
会場:神戸大学百年記念館
http://rock.jsms.jp/jsrm2017/
■(後)地質標本館新春特別展 ふるさとの新たな主役「県の石」
1月17日(火)〜 2月26日(日)
場所:産総研地質標本館
https://www.gsj.jp/Muse/exhibition/archives/2017/2017_spring.html
■(後)ふしぎ発見!鳥取砂丘(鳥取砂丘調査研究報告会)
1月21日(土)13:00〜16:30
場所:とりぎん文化会館第2会議室
主催:鳥取砂丘再生会議
http://www.tottorisakyu.jp/
■第194回地質汚染イブニング・セミナー
1月27日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:古野邦雄(元千葉県環境研究センター主席研究員)
高嶋 洋(野田市道路管理課主査)
テーマ:関東地下水盆管理と水循環基本法
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■(共)4th IGS (international Geoscience Symposium)
Precambrian World 2” in Fukuoka
3月3日(金)〜5日(日)
会場:九州大学西新プラザ
http://www.kochi-u.ac.jp/marine-core/precambrian_world/PW2017/top.html
■日本学術会議公開シンポジウム
「学術振興の観点から国立大学の教育研究と国による支援のあり方を考える」
3月1日(水)13:30 〜17:00
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木)
参加費無料・事前登録不要
http://www.scj.go.jp/ja/event/
■第24回GSJシンポジウム「ようこそジオ・ワールドへ」
3月18日(土)13:00〜17:00
会場:TKP神田ビジネスセンター5F(JR神田駅東口)
第一部 体験型講座
「地質学基本の“き”」高橋雅紀
第二部 講演会
「宮澤賢治とジオ・ロマン」加藤碵一
「地学オリンピックの10年-その歩みと功績-」瀧上豊・冨永紘平
「地学教育への期待」川辺文久
https://unit.aist.go.jp/igg/ja/event/sympo001.html
■地質学史懇話会
6月17日(土)13:30〜17:00
場所:北とぴあ 804号室(東京都北区王子)
平山 廉:「カメの始まりから2億年の歴史を語る」(仮)
山田俊弘:「17世紀地球論の発生と展開」(仮)
■(後)科学教育研究協議会第64回全国研究大会
8月7日(月)〜9日(水)
場所:広島なぎさ中学高等学校(広島県佐伯区)
http://kakyokyo.main.jp/
■第10回白亜紀国際シンポジウム(10th ISC 2017)
8月21日(月) 〜24日(木)
場所:オーストリア・ウィーン
UZA II (Universitätszentrum Althanstrasse)
巡検:プレ3コース,ポスト4コース(オーストラリア,スロバキア,チェコ他)
https://10cretsymp.univie.ac.at/home/
■(後)第4回Slope tectonics 2017
10月14日(土)〜18日(水)
場所:京都大学宇治キャンパス黄檗プラザ
http://www.slope.dpri.kyoto-u.ac.jp/SlopeTectonics2017/st2017.html
■IGCP608 Asia-Pacific Cretaceous Ecosystems第5回国際研究集会
10月26日(木) 〜27日(金)
場所:韓国済州島 済州国際コンベンションセンター
巡検:10月23日(月) 〜25日(水) 韓半島南西部下部白亜系慶尚超層群と相当層
First Circularはこちらから→http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0151.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■大阪市立自然史博物館学芸員募集(脊椎動物化石担当)(1/22)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
テクタイトの給源クレーター
テクタイトの給源クレーター
正会員 石渡 明
日本地質学会が執筆協力したThe Geology of Japanが2016年4月にロンドン地質学会から出版された(Nowell, 2016).このシリーズにThe Geology of Thailandがあり,その第21章がテクタイト(tektite)の記述にあてられている(Howard, 2011).また同シリーズのThe Geology of Central Europe(McCann, 2008)の下巻にもテクタイト(モルダバイト)とそれを生じたリース・クレーターに関する記述がある.一方,2016年8〜9月に第35回万国地質学会議(IGC)が南アフリカのケープタウンで開催され,そこで配布されたアフリカの地質ガイドブックにもテクタイトとその給源クレーター(Bosumtwi)の記述がある(Reimold and Gibson, 2016).日本にテクタイトは分布しないが,松田(2008)や下ほか(2010)の優れたまとめがあり,本学会でも林・宇田(1997)の報告がある.ここでは,テクタイトの給源クレーターに関する最近の地質学的知見を中心に略述する.
テクタイトは地球上の特定の地域に散在する径数cm程度の黒色〜緑色のガラス質の物体で,液滴型(球・水滴型)や溶融剥離型(縁つきのボタン・帽子型)のものが多く(松田, 2008),かつては月から飛んできたとする説もあったが(柴田, 1965, 1969, 1970, 1971),現在では天体衝突によって地球の表面の岩石が溶融し,その液滴がクレーターの周囲数100〜数1000kmの範囲に飛散し固結・落下したものと考えられている.化学組成は流紋岩質のものが多く,月の表面に広く分布する玄武岩・斑れい岩とは大きく異なり,地球表面の花崗岩や砂岩などの溶融物と考えて矛盾がない(松田, 2008).
テクタイトの分布地域は地球上に4つあり,米国東部・南部(Chesapeake Crater, 35.5Ma),欧州中部(Ries Crater, 14.7Ma),西アフリカ(Bosumtwi Crater, 1.07Ma)については給源クレーターが各々特定されているが,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム,中国南部,フィリピン,インドネシアなどの東南アジアからオーストラリアにかけてのAustralasia(豪亜地域)に分布するものは,形成年代が約0.8Maと特定されているものの,給源クレーターは未発見で,その推定位置には諸説ある(Howard, 2011).ムオンノン(Muong-Nong)型と呼ばれる,大きくて不規則形で溶融温度が低く縞状構造をもつテクタイトがインドシナ地域に産し,給源が近いことを暗示する(松田, 2008; 下ほか, 2010).
地球上の7つの大規模な隕石衝突構造のクレーター内堆積物についてPoag et al. (2004)が詳しく比較検討している.それらはチェサピーク(Chesapeake:米国バージニア州沿岸,始新世,直径85km),マンソン(Manson:米国アイオワ州,白亜紀後期,35km),サドベリー(Sudbury:カナダ・オンタリオ州,原生代中期,〜200km),モンターニェ(Montagnais:カナダ・ノバスコーシャ沖,始新世,45km),リース(Ries:ドイツ南部,中新世,24km),ロックネ(Lockne:スウェーデン北部, オルドビス紀,21km; 16km離れたMalingen Craterとペア),ポピガイ(Popigai:ロシア・シベリア,始新世,85km)である.いずれのクレーター内堆積物も衝撃変成・変形作用の痕跡が見られる角礫岩を主とし,その下部には基盤岩ないし堆積岩の巨大岩塊(megablock)を伴うことが多い.衝突によって発生した多量の超高温(>2000℃)の溶融物(メルト)が固結した深成岩体(ニッケル鉱床の母岩)を伴うのはサドベリーだけであるが,ポピガイは溶融物の多い角礫岩(tagamite)の層を含み,溶融物を含む特徴的な堆積物(suevite,スエバイト)は多くの衝突構造に見られる.他にも,K/T境界との関連で名高いメキシコ・ユカタン半島のチクシュルブ(Chicxulub)やカナダの三畳紀のマニクアガン(Manicouagan)など,よく研究された衝突構造は多数あり,特にアフリカに多い(Reimold and Gibson, 2016).以下,3つの確認されたテクタイトの給源クレーターについて述べる.
チェサピーク衝突構造に関しては,国際大陸掘削計画(ICDP)がクレーター内堆積物を貫き基盤岩に達する1766mの深部掘削調査を行った(Gohn et al. 2006a, b).これはバージニア州チェサピーク湾の入り口付近にある直径85kmの埋没クレーターで,深部掘削はその中心に近いチャールズ岬のアイアビル(Eyreville)で行われた.このクレーターは始新世に形成され,以後の堆積物に厚く覆われて特徴的な凹地形を全く示さず,Hodge (1994) の世界のクレーターの解説本には載っていない.掘削結果は,地表から深さ444mまで衝突後の堆積物(後期始新世〜鮮新世),1096mまで堆積岩の角礫と巨大岩塊,1371mまで花崗岩の巨大岩塊,1393mまで堆積物,1550mまでスエバイト及び衝突角礫岩,そして1766m(孔底)まで結晶片岩と巨晶花崗岩及び若干の衝突角礫岩脈となっている.衝突当時,1000m程度の厚さの堆積物が花崗岩質の基盤を覆っていたが,天体衝突により堆積岩は全て吹き飛ばされ,基盤も深くえぐられたことになる.本クレーターから飛散したテクタイトはテキサス,ジョージア,コネチカットなどで多数見出されている.
リース・クレーターが形成された地域はライン地溝帯から東へ150km,アルプス山脈前縁のモラッセ盆地の北側に広がるジュラ紀石灰岩の山地 (Schwäbische Alb; Swabian Alb,フランスのジュラ山地の続き) であり,このクレーターより東はFränkische Alb (Franconian Alb)と呼ばれる.南流してドナウ川に合する支流のリース川沿いにあり,氷河堆積物の研究で古くから有名なGünzburg, Mindelheim, Riss, Ulmなどの北方に位置していて,西のBaden-Württemberg州と東のBavaria州の境界付近に当たる.リース・クレーターは地形図上でも明瞭な直径30kmほどの円形の平坦な凹地であるが,噴出物は直径50kmの範囲を覆っており,南西に約30km離れて,同時に形成された直径4km弱のシュタインハイム(Steinheim)クレーターがある(シャターコーンshatter coneの最初の発見地として有名).リース・クレーター内部の堆積物は,衝突角礫岩脈を含む結晶質基盤(花崗岩,片麻岩等)の上に,結晶質角礫岩(主に花崗岩・片麻岩礫からなる:400m),堆積岩質角礫岩(100m),スエバイト(30m)の順に重なり(Poag et al. 2004),もともと基盤岩を覆って存在していた石灰岩を主とするジュラ紀の堆積岩の地層は完全に吹き飛ばされている.このクレーターについては佐々木(1993)の興味深い巡検記がある.ここから放出されたテクタイトはモルダバイトと呼ばれ,他のテクタイトと異なる透き通った緑色が特徴で,その分布はクレーターの東側に偏り,チェコやオーストリアなどから多数発見されている(須藤, 2002).これは衝突天体の西からの低角進入を示唆する.
ボスムトゥイ・クレーターはガーナの旧アシャンティ王国の首都クマシの東方30kmにあり,比高約300mの外輪山に取り囲まれた直径10.5kmのクレーターの底に直径8kmの湖がある(アシャンティの聖なる湖).この湖の堆積物は赤道地域の過去100万年間の気候変動の解析に重要であり,2004年にICDPの掘削が行われた.このICDPコアと外輪山付近のコアの両方からスエバイトが見いだされ,コース石,ジルコンの高温分解物(baddeleyite),平行ラメラ(PDFs)をもつ衝撃石英,溶融ガラスなど,天体衝突による高温・高圧産物が報告されている.ここから放出された「象牙海岸(Ivory Coast)テクタイト」は西〜南西方に偏って分布し,その延長上の大西洋底からはマイクロテクタイトが発見されていて,衝突天体の東からの低角進入を示唆する(Reimold and Gibson, 2016).
テクタイトが多量に形成されるためには,相当な厚さの完全に溶融したメルト層が形成され,それが爆発的に飛散することが必要だと思うが,クレーター内にそのようなメルトの大きな集合体が残っている例はサドベリーやポピガイなど少数の大規模衝突構造に限られる.多くの場合はメルト層の周囲の堆積岩や基盤岩も含めて飛散してしまったのだろう.
日本では,高松クレーター(香川県,直径4km,負の重力異常10mgal)について,「今回の分析結果は,コールドロンであることを示唆するものであったが,完全に隕石クレーターであることを否定するものではない」(山田・佐藤, 1998)という検証結果があるが,御池山クレーター(長野県飯田市,直径0.9kmの一部のみ残存,負の重力異常2mgal)については天体衝突構造の可能性を主張する論文(Sakamoto et al. 2010; 坂本・志知, 2010)に対して批判的検証がまだ行われておらず,衝突年代も不明で,「衝撃石英」以外の高圧鉱物やシャターコーン,角礫岩脈などの衝突構造に特徴的な地質現象も報告されていない.一方,家屋や乗用車などの人工物に隕石が落下した際に形成された隕石孔の実例は複数あり,現地で展示されている(例えば島根県松江市(美保関隕石:島・岡田, 1993),石川県能美市(根上隕石:石渡ほか, 1995)など).日本からはまだテクタイトの報告がないが,琉球列島や小笠原諸島は豪亜テクタイト分布域の北東縁に位置し(Howard, 2011, Fig. 21.12),今後これらの地域からテクタイトが発見される可能性はある.豪亜地域のテクタイトは形成年代が約80万年前(第四紀前期更新世(松山逆磁極期)の末期)と最も若く,分布域の面積が最大で発見数も多く,もし日本で発見されれば給源クレーターの場所の特定に結び付く情報が得られるかもしれない.この分野の今後の研究の進展に期待したい.
文 献
Gohn, G. S., Koeberl, C., Miller, K.G., Reimold, W.U. and Scientific Staff of the Chesapeake Bay Impact Structure Drilling Project, 2006a, Chesapeake Bay impact structure deep drilling project completes coring (Progress Report). Scientific Drilling, 3, 34-37.
Gohn, G.S., Koeberl, C., Miller, K.G., Reimold, W.U., Cockell, C.S., Horton, J.W.Jr., Sanford, W.E., Voytek, M.A. 2006b, Chesapeake Bay impact structure drilled. EOS, 87(35), 349, 355.
Hodge, P., 1994, Meteorite craters and impact structures of the Earth. Cambridge University Press. 124 p.
Howard, K.T., 2011, Tektites. In: M.F. Ridd, A.J. Barber, M.J. Crow (eds), The Geology of Thailand, 573-591. The Geological Society of London.
石渡明・笹谷啓一・田崎和江・坂本浩・中西孝・小村和久・辻森樹・大浦泰嗣・宮本ユタカ・赤羽久忠・渡辺誠・布村克志, 1995, 1995年2月18日落下「根上隕石」概報. 地球科学, 49, 71-76, 179-182.
林愛明・宇田進一, 1997, 中国海南島のテクタイトとシュードタキライト. 地質雑, 103(7), XXII.
松田准一, 2008, テクタイト. 松田准一・圦本尚義編, 地球化学講座2「宇宙・惑星科学」,培風館, 190-208.
McCann, T (ed), 2008, The Geology of Central Europe, Volume 2: Mesozoic and Cenozoic. The Geological Society of London. 1449 p. with index and CD-ROM.
Nowell, D., 2016, https://www.geolsoc.org.uk/Geoscientist/Books-Arts/Geoscientist-book-reviews-online/2016-Book-Reviews-Online/The-Geology-of-Japan
Poag, C.W., Koeberl, C., Reimold, W.U., 2004, The Chesapeake Bay crater: Geology and geophysics of a Late Eocene submarine impact structure. Springer-Verlag, Berlin. 522 p. with CD-ROM.
Reimold, W.U., Gibson, R., 2016, Africa’s impact heritage: A 3,500-million-year-old record of extraterrestrial threats. In: Anhaeusser, C.R., Viljoen, M.J. & Viljoen, R.P. (eds) Africa’s Top Geological Sites. Struik Nature, Cape Town. 160-168.
Sakamoto, M., Gucsik, A., Nishido, H., Ninagawa, K., Okumura, T., Toyoda, S., 2010, MicroRaman spectroscopy of anomalous planar microstructures in quartz from Mt. Oikeyama: Discovery of a probable impact crater in Japan. Meteoritics & Planetary Science, 45, 32-42.
坂本正夫・志知龍一, 2010, 御池山隕石クレーターに検出された負の重力異常.日本惑星科学会誌, 19(4),316-323.
佐々木晶, 1993, ドイツの隕石孔を訪れて. 惑星地質ニュース, 5(2), 16-21 (Webで入手可).
柴田勇, 1965, 1969, 1970, テクタイトに関する最近の資料. 地学雑, 74(4), 226-231, 78(6), 440-441, 79(4), 237-239.
柴田勇, 1971, テクタイトの月起源説に関係ある最近の情報. 地学雑, 80(5), 230.
島正子・岡田昭彦, 1993, 人家を直撃した美保関隕石.地質雑, 99(4), vii-viii.
下良拓・西村智佳子・Czuppon, G.・松本拓也・方中・横山正・中嶋悟・松田准一, 2010, 中国海南島産テクタイトの希ガス組成と含水量について. 地球化学, 44, 43-50.
須藤茂, 2002, プラハの国立博物館. 地質ニュース, 571, 60-67.
山田涼子・佐藤博明, 1998, 香川県高松クレーター産ガラスの岩石学的研究.岩鉱, 93, 279-290.
(2017.2.7掲載)
【geo-Flash】No.364 割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.364 2017/1/17┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日
【2】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されています
【3】支部情報
【4】その他のお知らせ
【5】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は,3月31日(金)です.
次年度も割引会費を希望のかたは,忘れずにご提出ください(締切厳守).
■ 自動引落による納入
昨年12月26日にお届けの金融機関口座より引き落としさせていただきました.
通帳記帳等でご確認ください.請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略さ
せていただきますのでご了承ください.
■ 郵便振替用紙(またはゆうちょ銀行口座)からのお振り込み
12月中旬に請求書兼郵便振替用紙を発送しました.地質学会の会費は前納制で
すので,お早めにご送金ください.
割引会費申請や通常の会費払込について,
http://www.geosociety.jp/outline/content0164.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されています
──────────────────────────────────
募集期間:2016年12月20日(火)〜2017年2月10日(金)
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75 歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:例えば,,,地質学への顕著な貢献/地質学会の運
営と発展への貢献/教育現場や企業などでの活動を通じた地質学の普及と振興
への貢献など
*上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することはできませ
んが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
(名誉会員推薦委員会 山本高司)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】支部情報
──────────────────────────────────
[西日本支部]
■西日本支部平成28年度総会・第168回例会
2017年2月18日(土)9:30〜 例会終了後 懇親会
会場:宮崎大学(木花キャンパス)教育学部
講演申込み締切:2月3日(金)17:00
★★総会に欠席の方は委任状をお送り下さい★★
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■(後)地質標本館新春特別展 ふるさとの新たな主役「県の石」
1月17日(火)〜 2月26日(日)
場所:産総研地質標本館
https://www.gsj.jp/Muse/exhibition/archives/2017/2017_spring.html
■(後)ふしぎ発見!鳥取砂丘(鳥取砂丘調査研究報告会)
1月21日(土)13:00〜16:30
場所:とりぎん文化会館第2会議室
主催:鳥取砂丘再生会議
http://www.tottorisakyu.jp/
■第195回地質汚染イブニングセミナー
2月24日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ902会議室
講師:張 銘(産総研 地圏環境リスク研究グループ長)
テーマ:環境微生物による揮発性有機化合物(VOCs)複合汚染の分解
http://www.npo-geopol.or.jp
■(共)4th IGS (international Geoscience Symposium)
Precambrian World 2” in Fukuoka
3月3日(金)〜5日(日)
会場:九州大学西新プラザ
http://www.kochi-u.ac.jp/marine-core/precambrian_world/PW2017/top.html
■第24回GSJシンポジウム「ようこそジオ・ワールドへ」
3月18日(土)13:00〜17:00
会場:TKP神田ビジネスセンター5F(JR神田駅東口)
第一部 体験型講座
「地質学基本の“き”」高橋雅紀
第二部 講演会
「宮澤賢治とジオ・ロマン」加藤碵一
「地学オリンピックの10年-その歩みと功績-」瀧上豊・冨永紘平
「地学教育への期待」川辺文久
https://unit.aist.go.jp/igg/ja/event/sympo001.html
■JpGU-AGU Joint Meeting 2017
5月20日(土)〜25日(木)
会場:千葉県 幕張メッセ
投稿早期締切 2月3日(金)12:00
http://www.jpgu.org/meeting_2017/
■地質学史懇話会のお知らせ
6月17日(土)13:00〜17:00
場所:北とぴあ8階804号室:JR京浜東北線王子駅下車3分
平山 廉「カメの始まりから2億年の歴史を語る」(仮)
山田俊弘「17世紀地球論の発生と展開」(仮)
■(共)第54回アイソトープ・放射線研究発表会発表論文の募集
7月5日(水)〜7日(金)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1)
発表論文申込締切:2月28日(火)17:00
http://www.jrias.or.jp/
■(後)科学教育研究協議会第64回全国研究大会
8月7日(月)〜9日(水)
場所:広島なぎさ中学高等学校(広島県佐伯区)
http://kakyokyo.main.jp/
■(後)第4回Slope tectonics 2017
10月14日(土)〜18日(水)
場所:京都大学宇治キャンパス黄檗プラザ
http://www.slope.dpri.kyoto-u.ac.jp/SlopeTectonics2017/st2017.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0151.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
■富山県奨学金返還助成制度 助成対象者募集(2/28)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.365(臨時)学会創立125周年記念事業と寄付のお願い
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.365 2017/1/31┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】学会創立125周年記念事業の概要とそれを成功させるための寄付のお願い
【2】学会創立125周年記念ロゴについて
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】学会創立125周年記念事業の概要とそれを成功させるための寄付のお願い
──────────────────────────────────
日本地質学会は,1893年に東京地質学会として創設されて以来,来年の2018年5月に創立125周年を迎えます.記念事業としては,以下のような行事を主に計
画しています.
(1)記念式典を開催します.
(2)記念学術大会,記念シンポジウムを開催します.
(3)100周年以降の25年間における地質学および関連科学の発展について,地質学雑誌特集号としてレビューします.
(4)地質学が社会にいかに貢献しているかを国民にアピールする啓発図書を刊行します.
(5)既に公表している各都道府県の岩石,鉱物,化石を「県の石図鑑-全国都道府県の岩石・鉱物・化石-」として出版します.
(6)広報誌「ジオルジュ」の125周年記念英文特別号を発刊します.
(7)会員証を発行します.
(8)プレ年である2017年から記念ロゴと記念ポスターを活用します.
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html
▶▶125周年記念事業のための寄付のお願い
上記ような記念事業を実行するため,学会では一般会計から引当をするなど資金を工面してきました.しかしながら,それだけでは不足するため,学会員や
賛助会員,さらには関連諸団体に寄付をお願いすることにしました.
寄付のお願いに関する詳細は,下記をご覧下さい.
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html#kifu
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】学会創立125周年記念ロゴについて
──────────────────────────────────
当学会では,125周年事業を盛り上げるために,記念ロゴを作成することにしました.このたび,応募作品をもとにデザイナーのリメイクを経て,記念ロゴが完成しましたので,皆様にご紹介します.
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/125th/content0012.html#logo_happyo
125周年を盛り上げるため,プレ年である2017年からいろいろな媒体,機会に活用します.会員の皆様も記念ロゴを大いに使っていただき,創立125周年を学会
内外に広めてください.私たち日本地質学会員は,125周年の記念事業を通じて会員全ての力を結集させ,「地質学は将来に向かって,さらに社会に貢献し続ける」ことを明確に伝えたいと考えます.会員の皆様もそれぞれのお立場で,共にこの2年間,特別な意識をもって活動してくださることを期待いたします.
******125周年記念サイト*****
http://www.geosociety.jp/125th/content0001.html
********************
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.366 第124年学術大会(2017愛媛大会)開催通知
件名:【geo-Flash】No.366 第124年学術大会(2017愛媛大会)開催通知
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.366 2017/2/7┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】第124年学術大会(2017愛媛大会)開催通知/トピックセッション募集
【2】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日
【3】日本地質学会名誉会員候補者の募集はまもなく締切です
【4】2018年度地震火山こどもサマースクール開催地の公募
【5】コラム:テクタイトの給源クレーター
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】第124年学術大会(2017愛媛大会)開催通知/トピックセッション募集
──────────────────────────────────
日本地質学会は,四国支部の支援のもと愛媛県松山市の愛媛大学城北キャンパ
スにて,第124年学術大会(2017年愛媛大会)を「ようおいでたなもし,四国地
質お遍路の旅へ」というテーマで9月16日(土)〜18日(月)に開催します.
全文はこちらから,
http://www.geosociety.jp/science/content0074.html
▶▶トピックセッション募集:3月13日(月)
トピックセッションを募集します.本大会も前回同様,シンポジウムの一般募
集はありません.セッションは例年通り「レギュラーセッション」,「トピッ
クセッション」,「アウトリーチセッション」に区分します.レギュラーセッ
ションは前回大会と同じ25タイトルを予定しています
http://www.geosociety.jp/science/content0075.html
▶▶愛媛大会に向けてのスケジュールはこちら(講演申込締切:7/5)
http://www.geosociety.jp/science/content0074.html#sch
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は,3月31日(金)です.
次年度も割引会費を希望のかたは,忘れずにご提出ください(締切厳守).
■ 自動引落による納入
昨年12月26日にお届けの金融機関口座より引き落としさせていただきました.
通帳記帳等でご確認ください.請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略さ
せていただきますのでご了承ください.
■ 郵便振替用紙(またはゆうちょ銀行口座)からのお振り込み
12月中旬に請求書兼郵便振替用紙を発送しました.地質学会の会費は前納制で
すので,お早めにご送金ください.
割引会費申請や通常の会費払込について,
http://www.geosociety.jp/outline/content0164.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本地質学会名誉会員候補者の募集はまもなく締切です
──────────────────────────────────
募集期間:2016年12月20日(火)〜2017年2月10日(金)
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75 歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:例えば,,,地質学への顕著な貢献/地質学会の運
営と発展への貢献/教育現場や企業などでの活動を通じた地質学の普及と振興
への貢献など
*上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することはできませ
んが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
(名誉会員推薦委員会 山本高司)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2018年度地震火山こどもサマースクール開催地の公募
──────────────────────────────────
地震火山こどもサマースクールは、1999年夏から小・中・高校生を対象にはじ
まった行事で、現在、日本地震学会、日本火山学会、日本地質学会が共同で実
施する、地球科学関連では最大規模の体験学習講座です。2018年度(2018年夏)
に実施する第19回の開催地を公募いたします。
応募資格
1)地震火山こどもサマースクールの主旨に賛同し、現地事務局を設置できる団
体.なお応募が採択されたのち、三学会(地震・火山・地質学会)のスタッフ
と現地事務局で実行委員会を結成し、この実行委員会がサマースクールを実施
します。
2)現地学校の夏休み期間中に1泊2日の日程(土日が望ましい)でサマースクー
ルを実施できること。
3)こどもとスタッフの宿泊に供することができる宿泊施設を確保可能なこと。
募集期間:2017年1月20日(金)〜2月28日(火)
詳しくは,http://www.zisin.jp/modules/pico/index.php?content_id=3461
なお,今年8月の第18回地震火山こどもサマースクールは,「湧水と大地のひみ
つ」をテーマとして熊本県益城町で開催予定です(参加対象:益城町とその周
辺の児童生徒を予定).
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】コラム:テクタイトの給源クレーター
──────────────────────────────────
正会員 石渡 明
日本地質学会が執筆協力したThe Geology of Japanが2016年4月にロンドン地質
学会から出版された(Nowell, 2016).このシリーズにThe Geology of
Thailandがあり,その第21章がテクタイト(tektite)の記述にあてられている
(Howard, 2011).また同シリーズのThe Geology of Central Europe(
McCann, 2008)の下巻にもテクタイト(モルダバイト)とそれを生じたリース・
クレーターに関する記述がある.一方,2016年8〜9月に第35回万国地質学会議
(IGC)が南アフリカのケープタウンで開催され,そこで配布されたアフリカの
地質ガイドブックにもテクタイトとその給源クレーター(Bosumtwi)の記述が
ある(Reimold and Gibson, 2016).日本にテクタイトは分布しないが,松田
(2008)や下ほか(2010)の優れたまとめがあり,本学会でも林・宇田(1997)
の報告がある.ここでは,テクタイトの給源クレーターに関する最近の地質学
的知見を中心に略述する.
全文は,こちらから,,,
http://www.geosociety.jp/faq/content0688.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[西日本支部]
■西日本支部平成28年度総会・第168回例会
2月18日(土)9:30〜 例会終了後 懇親会
会場:宮崎大学(木花キャンパス)教育学部
★★総会に欠席の方は委任状をお送り下さい★★
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■港郷土資料館コーナー展「港区遺跡展-最近の発掘調査から-」
場所:港郷土資料館(港区芝5-28-4)
期間:平成28年12月16日(金)〜平成29年3月15日(水)
平成29年3月17日(金)〜5月17日(水)
観覧料無料
当該地は「武蔵川越藩松平家屋敷跡遺跡」です。
1875(明治8)年6月に気象庁の前身である内務省地理寮が気象観測を開始した
場所は、現在は東京都港区虎ノ門2丁目のホテルオークラ東京本館(建替中)・
大倉集古館(改修休館中)になっています。内務省地理寮は地質調査所の前身
でもあります。
2014年にこの敷地で行われた発掘調査の出土品の一部がJR田町駅近くの東京都
港区立港郷土資料館で3月15日(水)まで展示されています。日祝ほか休館、入
場無料です。
調査では、明治初年の官舎の煉瓦遺構や、「内務省」の銘が描かれた磁器茶碗
などが発見されました。文献資料ではここで内務省が活動していたことは明ら
かなのですが、「実物」で確認できることになります。この「内務省」碗のほ
か、刻印の付いた煉瓦、洋酒の瓶、スープを取るのに使ったと考えられる牛の
切断骨など、当時の建築材料や食生活をうかがわせるものも展示されています。
http://www.lib.city.minato.tokyo.jp/muse/j/muse_news.cgi?id=270
■ふじのくに地球環境史ミュージアム
国際シンポジウム「人類世の到来―自然史と文化史」
会場:グランシップ(JR東静岡駅東口)
2月11日(土)10:00〜18:00
学術シンポジウム
第一部「人類世の山・湖・海岸」山田和芳ほか3名
第二部「人類世の動植物―多様性・栽培・移住」五箇公一ほか4名
第三部「山岳と人類世―牧畜・鉱山・遺産」Kevin Walshほか3名
2月12日(日)10:00〜12:30
公開シンポジウム『人類世の自然と文化』内山純蔵ほか3名
2月13日(月)関連施設見学ツアー
https://www.fujimu100.jp/sympo2017/
■連続公開シンポジウム:熊本地震において通信とメディアが果たした役割
主催 早稲田大学国際メディア財団プロジェクト、公益情報通信学会
共催 地区防災計画学会、情報通信学会災害情報法研究会ほか
2月14日(火)14:30〜17:40
場所:一般社団法人電波産業会(千代田区霞が関1-4-1)
参加費無料・定員80名(要申込)
http://www.gakkai.chiku-bousai.jp/ev170214.html
■明治大学危機管理研究センター第36回定例研究会・シンポジウム
2月19日(日)10:00〜16:30
会場:明治大学駿河台キャンパスアカデミーコモン8階308F教室
参加無料
公開シンポジウム「政治経済学研究科大学院生発表セッション」
共催シンポジウム「大都市の地震火災と広域避難問題をめぐって(仮)」
第36回定例研究会:講演「防災復興法制を知る: 巨大災害発生時に、すぐ実践
できる措置と改善が求められる措置」(国交省:佐々木晶二)など
問い合わせ,参加申込等
http://www.kisc.meiji.ac.jp/~crisishp/ja/notification.html#20170113
■平成28年度海洋研究開発機構研究報告会
JAMSTEC2017
3月1日(水)13:30〜17:30(開場は13:00)
場所:東京国際フォーラムホールB7(千代田区丸の内3-5-1)
http://www.jamstec.go.jp/j/pr/event/jamstec2017/
■(共)4th IGS (international Geoscience Symposium)
Precambrian World 2” in Fukuoka
3月3日(金)〜5日(日)
会場:九州大学西新プラザ
http://www.kochi-u.ac.jp/marine-core/precambrian_world/PW2017/top.html
■東京都水道歴史館講演会
「荒川流域の地形的な特徴と治水・利水―デジタル標高地形図を題材に―」
※事前申込受付中※
3月11日(土)14:00〜16:00
会場:東京都水道歴史館3階レクチャーホール
http://www.suidorekishi.jp/event.html#event_talk03
■第24回GSJシンポジウム「ようこそジオ・ワールドへ」
3月18日(土)13:00〜17:00
会場:TKP神田ビジネスセンター5F(JR神田駅東口)
第一部 体験型講座
「地質学基本の“き”」高橋雅紀
第二部 講演会
「宮澤賢治とジオ・ロマン」加藤碵一
「地学オリンピックの10年-その歩みと功績-」瀧上豊・冨永紘平
「地学教育への期待」川辺文久
https://unit.aist.go.jp/igg/ja/event/sympo001.html
■日本堆積学会2017年松本大会
3月25日(土)〜28日(火)
会場:信州大学理学部講義棟
25日 ワークショップ
26-27日 個人講演,特別講演,総会等,
28日 巡検
http://sediment.jp/04nennkai/2017/annai.html
■第196回地質汚染イブニングセミナー
3月31日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:後藤文昭(三井住友信託銀行経営企画部CSR推進室)
テーマ:環境と金融〜土壌汚染を題材として〜
http://www.npo-geopol.or.jp
■日本学術会議公開シンポジウム/第3回 防災学術連携シンポジウム
熊本地震 追悼・復興祈念行事「熊本地震・1周年報告会」
4月15日(土)11:00〜18:20
場所:熊本県庁本館 地下大会議室(熊本市中央区水前寺6-18-1)
主催:内閣府 日本学術会議 防災減災・災害復興に関する学術連携委員会/熊本
県/防災学術連携体(防災に関わる55学会のネットワーク)
参加無料・定員450名
資料:発表資料は前日の夕方にHPに掲載予定(資料の配布はありません).
参加申込み等詳細は,http://janet-dr.com/
■JpGU-AGU Joint Meeting 2017
5月20日(土)〜25日(木)
会場:千葉県 幕張メッセ
参加申込早期締切:5月25日(木)12:00
http://www.jpgu.org/meeting_2017/
■(共)第54回アイソトープ・放射線研究発表会
7月5日(水)〜7日(金)
会場:東京大学弥生講堂(東京都文京区弥生1-1-1)
発表論文申込締切:2月28日(火)17:00
http://www.jrias.or.jp/
■(後)科学教育研究協議会第64回全国研究大会
8月7日(月)〜9日(水)
場所:広島なぎさ中学高等学校(広島県佐伯区)
http://kakyokyo.main.jp/
■第34回歴史地震研究会(つくば大会)
9月15日(金)〜月17日(日)
場所:つくばイノベーションプラザ 大会議室
15-16日 研究会・総会・懇親会/17日 巡検
講演申込締切:5月31日(水)
http://sakuya.ed.shizuoka.ac.jp/rzisin/menu7.html
■(後)第4回Slope tectonics 2017
10月14日(土)〜18日(水)
場所:京都大学宇治キャンパス黄檗プラザ
http://www.slope.dpri.kyoto-u.ac.jp/SlopeTectonics2017/st2017.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0151.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻特任准教授公募(2/20)
・東北大学大学院理学研究科地学専攻准教授公募(3/10)
・国土地理協会2017年度学術研究助成(4/3〜4/21)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
125記念トリビア4:白野夏雲
〜2018年日本地質学会創立125周年を記念して〜
トリビア学史 4 不思議に満ちた白野夏雲(1827-1899)
矢島道子(日本大学文理学部)
写真:神官,白野夏雲(白野仁,1984)より
明治の初め,地質学を志した日本人の第1 世代は,ほとんどが欧米から学んだ.榎本武揚のように明治以前に欧米に行って学んだ者や,明治になってからお雇い外国人のコワニエ,ライマン,ナウマンなどに習った者などである.地質学そのものが日本で生まれたのではなく,欧米で生まれた学問だから当たり前のことかもしれない.ところが,今回とりあげる白野夏雲(文政10年‐明治32年)は欧米人に習った形跡も,大学で教育を受けた経験もない.にもかかわらず,白野の地質学的業績はかなり秀でている.すでに佐藤(1983),白野仁(1984),中村(1986)も,白野の不思議さを指摘しているが,この稿で確認したい.また,白野の業績がすべて明らかにはなっているわけではないから,もっと素晴らしい業績も発見されるかもしれない.特に北海道や鹿児島から白野の業績は発見される可能性が高い.
白野夏雲(しらの かうん)の経歴の不思議
白野の地質学的業績の再検討の前に,彼の人生自身が,名前,住所,職業等で不思議に満ちているので,少し検討する.白野は幕末に幕府直轄の甲州で生まれ,江戸に出てきたのち,41歳で明治維新を経験する.降伏して,江戸から静岡に回される.明治3 年(44歳)十勝国が静岡藩の領地だったため,静岡から北海道に回され,そののち明治5 年に開拓使に採用される.明治8 年には内務省に採用され東京の地理寮に勤務する.ところが明治12年鹿児島県に出向となる.明治17年11月に農務省に帰ってきて,地質調査所勤務になる.それもつかの間,明治19年7 月北海道庁勤務となる.北海道庁勤務のまま,明治23年,62歳で札幌神社(現在の北海道神宮)の宮司となる.明治25年北海道庁を依願免職し,亡くなるまで札幌神社宮司であった.
名前
本名は今泉耕作.嘉永4年,23歳で江戸に出るにあたって,出生地白野村に基づいて白野耕作と改名.明治3 年,北海道に行くにあたって,白野夏雲ともう1 度改名.この時代,木戸孝允などに見られるように改名はよく行われたようだ.
住所
生まれたのは甲斐国白野村(現在の山梨県大月市笹子町).父は左官で石和代官の手代だったため,幼くして石和に転居.甲府徽典館(官学)で学ぶうちに江戸から派遣された学頭,岩瀬忠震(いわせただなり)の勧めに従い,江戸に出る.江戸では,幕府・歩兵の輜重隊の頭と軍事顧問を命ぜられ小川町に駐屯していた.元治元年39歳の時に天狗党の乱が起き,日光の警備を命じられ任地に赴く.慶應4年に彰義隊が上野に立てこもった時は浅草の蔵を守っていたが,官軍が江戸に入り徳川の残党を追求するに至って,隊を率いて新宿口から甲州へと逃げることができた.その後,前橋まで逃れ,降伏.江戸から静岡に回される.ここまでは幕末に幕府直轄地に生まれた人間の普通の道である.それでも,山梨の大月から,石和,江戸の後,日光,前橋と転々とした.
本格的に明治時代が始まると,開拓使,内務省,鹿児島県,農務省,北海道庁と任命者が変わって明治政府のために働く.短い東京勤務を挟んで,勤務地は北海道と鹿児島の間を行き来する.北海道内もよく歩いているし,東京での地理寮勤務の間にも地方の調査によく赴いている.鹿児島では琉球列島もよく調査している.地質学の研究者としてみれば,たいへんよく歩いているといえる.
岩瀬忠震と永井玄蕃
白野の学んだ甲府徽典館学頭の岩瀬忠震(文政元(1818)−文久元(1861)) は, 江戸末の優秀な幕臣,外交官であった.石和から江戸に戻り,学頭としての功績が認められ,昌平坂学問所の教授となる.講武所・蕃書調所・長崎海軍伝習所の開設や軍艦,品川の砲台の築造に尽力した.その後も外国奉行にまで出世し,列強との折衝に尽力し,安政2 年(1855年)に日露和親条約締結に臨み,安政5 年(1858年)には日米修好通商条約に井上清直と共に署名した.水野忠徳,小栗忠順と共に「幕末三俊」と顕彰された.
ところが,13代将軍の将軍継嗣問題で徳川慶喜を支持する一橋派に属したので,大老となった井伊直弼による安政の大獄で左遷された.安政6 年(1859年)には蟄居を命じられ,文久元年(1861年),44歳で失意のうちに病死した.
岩瀬の学問的業績,あるいは地質学的知について詳しく調べてないが,外国語にも秀でていたことは確かである.松岡(1981)に岩瀬から橋本佐内あての手紙の写真を見ることができるが,宛名はSanai様,差出人はHigoとなっており,横文字を日常使用していたことがわかる.白野は岩瀬に多くを学んだはずだ.明治16年(1883年)白野は岩瀬を偲んで東向島の白鬚神社に「岩瀬鴎所君之墓碑」を建立している.
白野仁(1984)は永井玄蕃(1816−1891)の影響も多大であると述べている.永井もまた甲府徽典館学頭から始まって,岩瀬と共に生き,安政の大獄を生き延びた後,榎本武揚とともに,函館戦争を戦った.その後,明治5 年より開拓使勤務(東京)となり,白野の開拓使勤務(札幌)と同時期であった.
職業等
開拓使勤務は,上記のように,永井玄蕃の影響があると思われる.その後の内務省,鹿児島県,農務省,北海道庁,そして札幌神宮の動きの原因は不明である.
地質学的研究
地理寮と地質調査所に勤務したのは明治8 年から12年と17年から19年の2 度,全部で6 年に満たないが,その他の職業についていても,随所で地質学的研究を行っている.
まず北海道では明治5 年5 月の墺国博覧会ニ付北海道物産取り調べ方を申し付けられる.この時彼は,北海道で,明治6 年のウィーン万国博覧会用の標本を集めた.岩石・鉱物の相当な知識があったと思われる.北海道には1 年半いて物産地質の調査にあたり,この時アイヌ語の研究にも着手したと思われる.
地理寮時代は,山梨県,静岡県,浜松県,愛知県,足柄県,千葉県,高知県,新潟県などで土石調査を行った.山梨,静岡などは白野にとってのゆかりの深い場所である.明治10年1 月には内務省山林課に転じ地理局に勤め,明治11年には内国勧業博覧会の委員と審査官を命ぜられている.やはり,岩石・鉱物に知識があり,「当時の地質調査所の展示室は夏雲の集めた標本がほとんどだった」(佐藤,1983)という記載もある.
明治15年8 月刊行の「学芸志林」誌に発表した『穴居考』は地質学の論文である.タイトルから見ると,まるで古代の人間のすみかについて論じたもののようだが,内容は噴火作用,海水作用,露滴作用など,地球の作用について論じたものである.学芸志林は明治10年に創刊された,東京大学の紀要のようなもので,著者は多くが東京大学関係者だが,白野のように非東京大学人もいる.白野は明治13年,14年に『古代地名考』(明治13年の所属は静岡だが,明治14年には所属が記されていない)も書いている.明治16年にはやはり非東京大学人の坂市太郎が『地層褶起の説』を地学会会員の肩書で投稿している.
明治19年「地質要報」に『硯材誌』を旧局員[元地質調査所職員の意味]として投稿している.グレースレート,アロムスレートなどのカタカナことばが原綴を付して記されている.岩石に関する知識は豊富で正確である.「地質要報」の『硯材誌』の前に掲載されている論文はドクトルナウマンの粘板岩の報文であるが,それを参照せよとも書いてある.
白野が集めた岩石鉱物の類を息子(次男)の己巳郎がまとめて「金石小解」として出版している.明治12年版,明治15年版および明治17年版(夏雲が改訂)がある.白野が収集していた2 〜3 千余の標本のうち,息子の己巳郎が鑑定し,典型的と思われるものを選んで,その説明をダナ氏のマニュアル・オブ・ミネラロジーから和訳してつけたとされている.
中村(1986)は明治15年刊行の『以太也蚶録』を日本の海底地質論の嚆矢として高く評価している.白野の研究業績は,海洋学,水産学等にもわたっていて,膨大である.あくまでも現場を歩いて,物にふれて,研究していたといえよう.白野について,丁寧な調査に基づいた的確な評価がなされることを望む.
文 献
松岡英夫,1981,『岩瀬忠震―日本を開国させた外交家』中公新書.
中村光一,1986,日本における海底地質研究の黎明2 - 1‐白野夏雲『以太也蚶録』における海底地質論考.地質ニュース,no. 383,45−53.
佐藤博之,1983,先人を偲ぶ(1).地質ニュース,no. 346,52−63.
佐藤博之,1985,博覧会と地質調査所-百年史の一こま(2).地質ニュース, no. 372,17-28.
白野 仁,1984,『白野夏雲』北海道出版企画センター.
著者不詳,1896, 雑報− 白野夏雲翁, 地学雑,8 巻,96号,609.
写真 神官, 白野夏雲( 白野 仁,1984)より.
【geo-Flash】No.367 愛媛大会トピックセッション募集中
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.367 2017/2/21┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[2017愛媛大会情報]トピックセッション募集中
【2】[125周年関連情報]記念事業の概要/記念事業に対する寄付のお願い
【3】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日
【4】2018年度地震火山こどもサマースクール開催地の公募
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2017愛媛大会情報]トピックセッション募集中
──────────────────────────────────
第124年学術大会(2017年愛媛大会)
「ようおいでたなもし,四国地質お遍路の旅へ」
会期:2017年9月16日(土)〜18日(月)
会場:愛媛大学城北キャンパス
http://www.geosociety.jp/science/content0074.html
▶▶トピックセッション募集中:3月13日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0075.html
▶▶演題登録・講演要旨受付:5月末開始〜7月5日(水)締切
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[125周年関連情報]記念事業の概要/記念事業に対する寄付のお願い
──────────────────────────────────
創立125周年記念事業として,2018年5月東京での記念式典をはじめ,様々な事
業を計画しています.また,それら記念事業を実行するため,学会員や賛助会
員,さらには関連諸団体に寄付をお願いしております.
▶125周年記念事業の概要
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html
▶記念事業に対する寄付のお願い
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html#kifu
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は,3月31日(金)です.
次年度も割引会費を希望のかたは,忘れずにご提出ください(締切厳守).
割引会費申請や通常の会費払込について,
http://www.geosociety.jp/outline/content0164.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2018年度地震火山こどもサマースクール開催地の公募
──────────────────────────────────
地震火山こどもサマースクールは,1999年夏から小・中・高校生を対象にはじ
まった行事で,現在,日本地震学会,日本火山学会,日本地質学会が共同で実
施する,地球科学関連では最大規模の体験学習講座です.2018年度(2018年夏)
に実施する第19回の開催地を公募いたします.
募集締切:2017年2月28日(火)
詳しくは,http://www.zisin.jp/modules/pico/index.php?content_id=3461
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地震本部ニュース冬(2017年2月15日)
http://www.jishin.go.jp/herpnews/
■県の化石の展示(日本地質学会が選考した県の石から)
1月13日(金)〜4月9日(日)
会場:荒木集成館(名古屋市天白区中平5-616)
主催:東海化石研究会・荒木集成館
入場料:大人300円
http://www.arakishuseikan.ecweb.jp
■(後)地質標本館新春特別展 ふるさとの新たな主役「県の石」
1月17日(火)〜2月26日(日)
場所:産総研地質標本館
https://www.gsj.jp/Muse/exhibition/archives/2017/2017_spring.html
■ブルーアース2017
3月2日(木)〜3日(金)
会場:日本大学理工学部駿河台キャンパス
http://www.jamstec.go.jp/maritec/j/blueearth/2017/program.html
■(共)4th IGS (international Geoscience Symposium)
Precambrian World 2” in Fukuoka
3月3日(金)〜5日(日)
会場:九州大学西新プラザ
http://www.kochi-u.ac.jp/marine-core/precambrian_world/PW2017/top.html
■日本堆積学会2017年松本大会
3月25日(土)〜28日(火)
場所:信州大学理学部講義棟
25日 ワークショップ
26・27日 個人講演,特別講演,総会等,
28日 巡検
http://sediment.jp/04nennkai/2017/annai.html
■第196回地質汚染イブニングセミナー
3月31日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室(東京都北区王子)
講師:後藤文昭(三井住友信託銀行経営企画部CSR推進室)
テーマ:環境と金融〜土壌汚染を題材として〜
http://www.npo-geopol.or.jp
■日本学術会議公開シンポジウム/第3回 防災学術連携シンポジウム
熊本地震 追悼・復興祈念行事「熊本地震・1周年報告会」
4月15日(土)11:00〜18:20
場所:熊本県庁本館 地下大会議室(熊本市中央区水前寺6-18-1)
参加無料,定員450名
参加申込み等詳細は,http://janet-dr.com/
■第16回重金属類・残土石処分地・廃棄物処分地診断に関わる
地質汚染調査浄化技術研修会
5月1日(月)〜4日(木)
場所:日本地質汚染審査機構関東ベースン実習センター(千葉県香取市)
http://www.npo-geopol.or.jp/index.htm
■JpGU-AGU Joint Meeting 2017
5月20日(土)〜25日(木)
会場:千葉県 幕張メッセ
参加申込早期締切:5月25日(木)12:00
http://www.jpgu.org/meeting_2017/
■西太平洋堆積学会議2017
6月12日(月)〜17日(土)
場所:韓国光州市(Gwangju, Korea: Kimdaejung Convention Center)
12-13日 個人講演
14-17日 巡検(潮間帯+白亜系あるいは潮間帯+火山砕屑岩のいずれか)
ファーストサーキュラー
http://sediment.jp/08related/2017WPSM.html
■IGCP630 Annual Symposium (2017)
Permian-Triassic climatic & environmental extremes and biotic responses
6月14日(水)〜16日(金)
場所:東北大学
https://amarys-jtb.jp/icgp630/
■(共)第54回アイソトープ・放射線研究発表会
7月5日(水)〜7日(金)
場所:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
発表論文申込締切:2月28日(火)17:00
http://www.jrias.or.jp/
■(後)科学教育研究協議会第64回全国研究大会
8月7日(月)〜9日(水)
場所:広島なぎさ中学高等学校(広島市佐伯区)
http://kakyokyo.main.jp/
■第71回地学団体研究会総会(旭川)
8月25日(金)〜27日(日)
場所:北海道旭川市大雪クリスタルホール・神楽市民交流センター
https://sites.google.com/view/soukai2017
■(後)第4回Slope tectonics 2017
10月14日(土)〜18日(水)
場所:京都大学宇治キャンパス黄檗プラザ
http://www.slope.dpri.kyoto-u.ac.jp/SlopeTectonics2017/st2017.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・島原半島ジオパーク協議会専門員及び外国語専門職員募集(3/10)
・JAMSTEC海洋掘削科学研究開発センターポストドクトラル研究員(2/28)
・第14回「日本学術振興会賞」受賞候補者推薦募集(学会締切 3/24)
・高知大学海洋コア総合研究センター全国共同利用研究公募(2/28)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
第8回フォトコン_最優秀
第8回惑星地球フォトコンテスト入選作品
最優秀賞:毘沙門海岸の奇岩
写真:田中健以(神奈川県)
撮影場所:神奈川県三浦市南下浦町,毘沙門海岸
【撮影者より】
自然が創りあげたとは思えない奇妙な外観に美しさを感じ、撮影しました。泡のようにも見える白い部分は濡れると黒くなります。撮影日前後は雨もなく、乾燥した日が続いたため、 海の塩が表面に浮き出ていたのでしょうか?下の方には赤い部分もあり、色の組み合わせがとても魅力的に感じました。
【審査委員長講評】
作者は地元の方で,この海岸をよく歩かれているのでしょう.普通の人が見過ごしがちな奇岩を注意深く撮影しています.この作品ではHDR(High Dynamic Range imaging)という処理を使っています.夕方に西向きに撮影しているので影になっている奇岩を,この処理によって浮き出さしています.ゴミや草などが全くなく(掃除をしたのでしょうか)画面がよく整理され,まさにジオが主役の力強い作品になっています.背景の城島や雲も良いアクセントになっています.
【地質的背景】
三浦半島南部の海岸には完新世の離水波食棚(波の浸食によってできた平らな棚状の地形)が広がり,地層の観察に適しています.写真の地層は泥岩とスコリア凝灰岩の互層からなる中新―鮮新統の三浦層群三崎層です.黒色のスコリア凝灰岩は伊豆・小笠原弧由来と考えられ,写真では吹き付けられた波しぶきから析出した塩が白く見えています.三崎層には断層による地層の繰り返しや注入構造,スランプ構造などが観察され,フィリピン海プレートの沈み込みによってつくられた付加体堆積物として注目されています.(柴田健一郎:横須賀市自然・人文博物館)
目次へ戻る
第8回フォトコン_優秀1
第8回惑星地球フォトコンテスト入選作品
優秀賞:火星
写真:西村礼能留(青森県)
撮影場所:青森県十和田八甲田近く
【撮影者より】
昔ここに定かではないが炭鉱の跡地と?なんか不毛で地球のような気がしない!写真を撮りに行くたびにここは天候により色々な色に変化して不思議な場所です.
【審査委員長講評】
最近ではローバーが火星表面を何年も探査している時代ですから,作者はそんな思いからこのタイトルを付けたのでしょう.手前の草がなければ,火星と勘違いしそうな風景です.手前の草を入れなかった方が,もっと火星的で魅力的な作品になったかもしれません.
【地質的背景】(準備中)
目次へ戻る
第8回フォトコン_優秀2
第8回惑星地球フォトコンテスト入選作品
優秀賞:奇妙な宇宙(SORA)
写真:渡辺昌也(和歌山県)
撮影場所:和歌山県東牟婁郡古座川町池野山
【撮影者より】
国の天然記念物「虫喰岩」を夜撮影しました。岩肌が呼吸をしているような錯覚に陥り,はっとしました。
【審査委員長講評】
夜の虫食岩の撮影はなかなか難しく,フラッシュをたいて撮影するとのっぺらぼうで手前ばかりが明るい写真になってしまいます.このような作品にするためには三脚にカメラを固定,10秒程度の露出をしている最中に,離れた場所から懐中電灯を振り回して虫食岩を照らすようにしなければなりません.色も意図的にコントロールしたのでしょうか.
【地質的背景】
奇岩「鬼の虫喰岩」の表面には,タフォニと呼ばれる奇妙な浸食構造がみられる.タフォニが描く幾何学模様は,夜空の神秘と調和し,無限の空間的広がりを感じさせる.その母岩は,長さ20km,幅数100mに及ぶ火山砕屑岩からなり,太古の巨大カルデラが浸食され,マグマの通路が露出したものと考えられている.すなわち,時空を大きく飛び越え,今ここに存在する宇宙 (SORA) が,この一枚には映し出されている.(電力中央研究所 三浦大助)
目次へ戻る
第8回フォトコン_ジオパーク
第8回惑星地球フォトコンテスト入選作品
ジオパーク賞:波間のプロムナード
写真:古矢さつき(神奈川県)
撮影場所:西伊豆堂ヶ島公園(堂ヶ島・仁科ジオサイト)
【撮影者より】
堂ヶ島の美しい断層を見ながら,海の上を散歩できる遊歩道.景観をこわす過度な手すりも無く,青緑の海を眼下に西伊豆らしさを楽しめる場所です。
【審査委員長講評】
評者は10年以上も堂ヶ島に行っていませんが,現在ではこんなに素晴らしい場所を散策できるとは知りませんでした.過度の手すりなどを設けず,素晴らしい景観を眺められようにしているのは,ジオパーク関係者の見識の高さが窺われます.画面の構成や人物の配置,大きさなど完璧で素晴らしい作品です.
【地質的背景】
西伊豆には海底火山の噴出物を主体とする,白浜層群が広く露出しています.海底火山の地層を広範囲に詳しく観察できるため,風光明媚な観光地である堂ヶ島は地質の研究や教育にとっても貴重な場所です.手前の白い地層は,噴火して海中に巻き上がった軽石が,海底に降り積もったものですが,海水の流れを反映した斜交層理が見えます.中央の黒い巨岩やレキからなる地層は海底火山の斜面に生じた土石流の地層と考えられています.(神奈川県温泉地学研究所 萬年一剛)
目次へ戻る
第8回フォトコン_会長賞
第8回惑星地球フォトコンテスト入選作品
日本地質学会会長賞:安山岩の細胞分裂
写真:牧野帆乃香(福岡県)
撮影場所:沖縄県久米島 奥武島(おうじま)
【撮影者より】
琉球列島の中の久米島という離島から橋で渡れる距離にある小さな島、奥武島。そこで見られる高Mg安山岩の柱状節理です。綺麗に六角柱・五角柱に割れた柱の中央には黒ずんだ核のようなものが見え、岩石がまるで細胞分裂しているようだと思いました。
【審査委員長講評】
畳岩は,天然記念物や地質百選にも選ばれているので,既に多くの作品が撮影されています.その中で高評価を得るためには,見る人をハッと思わせるもうひと工夫がほしかった.ハンマーは真ん中ではなく,右あるいは左寄りの柱状節理の上に置くのがよかったと思います.
【地質的背景】
この写真の場所は「久米島町奥武島(おうじま)の畳石」として平成26年,国の天然記念物に指定されました.平成19年には日本の地質百選にも選ばれています.柱状節理は,柱状の溶岩が束になった構造をしており,一つ一つの柱の断面は六角形など多角形をしています.多角形の縁は急冷するためガラス質が,中心部はゆっくり冷えるため結晶が多くなります.細胞のような模様に秘められた冷却過程の情報は,誰かの解読を待っているかのようです.(神奈川県温泉地学研究所 萬年一剛)
目次へ戻る
第8回フォトコン_ジオ鉄
第8回惑星地球フォトコンテスト入選作品
ジオ鉄賞:あまちゃんの歌が聞こえる
写真:吉村 誠(奈良県)
撮影場所:岩手県下閉伊郡普代村 レストハウスうしお敷地内
【撮影者より】
昨年のゴールデンウィークにみちのく旅行に出かけました。NHKの朝ドラ「あまちゃん」に出てきた美しいリアス式海岸と、三陸鉄道北リアス線を一緒に撮影したいと国道45号線を宮古から八戸にかけて、北上しました。三陸鉄道大沢橋梁を通った時に、テレビで見た光景が目に入り、ここで撮影する事にしました。場所をお借りした“レストハウスうしお“さんからは北リアスの絶景が望め、観光列車が一時停止するそのタイミングでショットしました(お店でいただいた“名物ウニ丼”も絶品でした)。東日本大震災で被災したこのエリアも無事に復旧していました。これからも、この景観を見れるように環境を保存してきたいものです。
【審査委員長講評】
私も去年5月に北三陸を撮影していました.国鉄時代に建設された橋梁とカラフルな車両,遠方に見える見事な海成段丘とまさにジオ鉄に相応しい作品です.撮影者の気の利いたコメントも作品を引き立たせました.
【地質的背景】
三陸鉄道の南北リアス線は「リアス」の名を冠するものの、北リアス線の走る宮古以北はリアス海岸(沈水海岸)ではなく海成段丘(隆起海岸)が広がっています(リアス海岸は宮古以南。南リアス線で展望可能)。写真は太平洋の絶景区間で知られる北リアス線白井海岸〜堀内間。水平線の向こうに真っ平らな三崎半島の海 成段丘が見えます。沿線の海成段丘直下の花崗岩に架橋された大沢橋梁(1974年完成)は、国鉄時代に橋梁技術開発を目的に建設された我が国初の逆ランガーアーチ橋で、谷に対して天を仰ぐアーチは津波に対する安全性も考慮された構造です。三陸鉄道のシンボルカラー赤青白を纏ったオリジナル36形とラッピングの連結車両が、三陸沿岸の立夏の爽やかなジオ鉄風景を引き立てています。(藤田勝代@深田研ジオ鉄普及委員会)
※「ジオ鉄賞」:第6回より深田研ジオ鉄普及委員会より本コンテストに後援を頂き,「ジオ鉄」賞を設けています.鉄道と地球の姿を組み合わせた優れた「ジオ鉄」作品を表彰します.
目次へ戻る
第8回フォトコン_スマホ
第8回惑星地球フォトコンテスト入選作品
スマホ賞:競う曲線美
写真:伊藤正顕(静岡県)
撮影場所:静岡県下田市須崎(恵比須島)
【撮影者より】
田舎に住んで十余年、赤ん坊だった娘も、気が付けば1人の女性になっていた。久し振りに娘と二人きりの休日の午後、年頃の娘が行きたいだろう、デパートも映画館もボーリング場も無いけれど、素敵な自然がここにはある。雨風に削られ美しい斜交層理、女性のからだのような、なだらかな曲線美がそこにありました。
【審査委員長講評】
砂岩層の前に立つ健康的な娘さん.タイトルやコメントを読んでいると真面目に書いているのか,意図的に書いているのがわかりませんが,笑ってしまいます.普通のジオフォトでは人物はもっと小さく扱うべきですが,この作品では大きく扱って正解でした.お父さんがスマホで気軽に撮った雰囲気が伝わってきます.
【地質的背景】
静岡県下田市須崎の恵比須島は伊豆半島ジオパークのジオサイトの一つで,遊歩道が あり,10分程で一周できます.遊歩道沿いの崖には,「角礫からなる礫岩層」と「層 理の良く発達した黄白色凝灰岩層」が露出しています.これらは新第三紀白浜層群 で,海成層です.写真の地層は,層理の良く発達した凝灰岩層です.恵比須島の白浜 層群には生痕化石以外の化石は見られませんが,各種の斜交層理や平行層理の観察に は最適です.(静岡大学理学部地球科学科 北村晃寿)
目次へ戻る
第8回フォトコン_入選1
第8回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:大ヤスリ岩の見下ろす山並み
写真:三浦雅哉(神奈川県)
撮影場所:山梨県北杜市瑞牆山
【撮影者より】
奥秩父山脈の最西端に位置する瑞牆山。大ヤスリ岩の見下ろす先には低い山並みが南アルプスまで延々と続きます。この大ヤスリ岩を含む奇岩・巨岩群は、山体の風化から取り残されて露出したものです。全山が黒雲母花崗岩で形成される瑞牆山は、風化の影響を受けやすく山体の南西部を中心に崩壊が進みました。結果、大ヤスリ岩など奇岩・巨岩群の林立するこのような山体が出来上がりました。
眼下にそびえ立つ岩々と遙かに広がる南アの山並み、構図におさめる際どちらも切り捨て難く、思わず何枚も撮ってしまいました。それらの中で選び抜いた一枚です。
【審査委員長講評】
瑞牆山(みずがきやま,標高2230m)は日本百名山の1つで,山頂部の花崗岩の巨石群(トア)で特徴づけられます.作者は山頂からトアを見下ろしていますが,秋晴れで空気が澄んでいたため,中景の紅葉や遠景の山々がくっきりと見えています.
【地質的背景】
花崗岩はマグマが地下深部でゆっくり冷え固まってできた深成岩の一種であり、大陸地殻を特徴づける岩石です。写真の瑞牆山の花崗岩は、伊豆衝突帯の北端、伊豆-小笠原弧と本州弧との衝突が開始した中期中新世のマグマ活動で形成したものであり、島弧の衝突帯における大陸地殻形成過程を理解する上で重要な位置にあるため、国内外の研究者から注目を集めています。(愛媛大学 齊藤 哲)
目次へ戻る
第8回フォトコン_入選2
第8回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:渓谷の歴史
写真:寺田百合(東京都)
撮影場所:アイスランド (Iceland Fjadrargljufur Canyon)
【撮影者より】
Fjadrargljufur Canyonは,深さ100 m,全長2 km を誇る巨大な渓谷です.蛇行した切り立つ壁は,氷河時代に形成されたパラゴナイトで構成されており,約200万年前のものであると考えられています.氷河から川となって流れ出た水は,その渓谷を侵食し,同時に多くの堆積物を運んだとされています.やがて湖が一杯になり,その堆積層すら削られ始めました.両側に見られる河成段丘から,その歴史をうかがい知ることができます.
【審査委員長講評】
この谷はアイスランドの海岸沿いを走る国道1号線のすぐ近くにあるので,観光地としても人気のある場所です.この作品もHDRで処理しているため,影の中の谷間や雲の細部がしっかりと描写され,まるで絵画を見ているようです.渓谷というより峡谷と呼ぶのが相応しい谷です.
【地質的背景】
溶岩が水底で噴出すると,表面が急冷してガラス化します.この時ガラスにヒビが入り,沸騰する周囲の水に粉砕されるため,水冷破砕溶岩(ハイアロクラスタイト)となります.パラゴナイト(palagonite)は水冷破砕溶岩の火山ガラスが,高温の水の影響で変質したものです.陸上なのに水底の溶岩が広く分布するのは噴火が氷河の下で発生したためです.パラゴナイト化した噴出物は氷河と火山の国アイスランド特有の景観を数多く形作っています.(神奈川県温泉地学研究所 萬年一剛)
目次へ戻る
第8回フォトコン_入選3
第8回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:太平洋のヘソ
写真:滝 玲名(愛知県)
撮影場所:イースター島、チリ
【撮影者より】
イースター島は、不思議な歴史を持つ「モアイ像」で有名な、太平洋に浮かぶ孤島です。 火山島であるこの島は、火山の噴火によって75万年前に形成されたとされ、玄武石で鉄分の多い地質です。島内には多数の休火山、噴火口や火口湖があり、その中でもここ「ラノ・カウ」の火口湖はイースター島内で最大のもの。直径は約1600m、火口壁の高さは約200m、そして湖の水深は深いところで約11mとかなり大規模です。イースター島の最南端に位置しており、火口湖の淵には歴史的にも重要な先住民の儀式村があったことから、かつてこの火口湖が文化的にも非常に神聖かつ重要な場所であったことも伺えます。 また、ここの淡水は、海に囲まれたイースター島に住む約6000人の島民にとって貴重な水源の一つでもあります。
自分が本当に感動した場所が選ばれて、嬉しいです。実際に目の前にすると、この火口湖の大きさには圧倒されます。普通のカメラレンズでは全体像が収まらなかったので、iPhoneのパノラマモードで撮影しました。
【審査委員長講評】
イースター島南西端にある火口湖を撮影した作品です.火口湖の縁に立って火口湖全体を撮影するのは難しく,以前は魚眼レンズや超広角レンズを使うしかありませんでした.この作品はスマホのパノラマ機能が使って撮影したものです.カメラを一端に向けてシャッターを切り,半周回ってからシャッターを再度切るととこのような作品が撮れます.
【地質的背景】
イースター島は南米チリの海岸から約3500 km,最も近い有人島であるピトケアン島からも約2000 km離れた絶海の孤島です.太平洋プレートとナスカプレートの発散境界付近から東に続く海山列(Sala y Gómez Ridge)上にあり,ホットスポット型の火山島です.ラノ・カウ火山はイースター島南西部を占める玄武岩の楯状火山ですが,活動末期には流紋岩の軽石が噴出しています.この大きな噴火口は陥没カルデラと考えられているようです.(神奈川県温泉地学研究所 萬年一剛)
目次へ戻る
第8回フォトコン_入選4
第8回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:太古からの流れ
写真:木下 滋(和歌山県)
撮影場所:和歌山県西牟婁郡すさみ町小附,城川(日置川支流)
【撮影者より】
和歌山県すさみ町に「まだら岩」と呼ばれている地層があります。砂岩と泥岩が交互に重なった地層が、地価の熱水によって熱変性を受け硬化したものだそうです。太古からの水の流れが岩を削り取った模様もたいへん興味深く、自然の凄さを実感できます。
【審査委員長講評】
評者は,このような渓谷があるのを初めて知りました.この作品にはスケールになるようなものが写っていないので,どのくらいの大きさかわかりません.しかし,虎皮のようなパターンが強烈なので,大きさをわからせないのも作品を魅力的にする方法かもしれません.
【地質的背景】
まだら岩は,紀伊半島南部を流れる日置川の支流城川にあります.日置川流域には始新世に堆積した四万十付加体の牟婁付加シークエンス(牟婁層群)が広く分布します.牟婁付加シークエンスは砂岩層,砂岩泥岩互層,泥岩層および礫岩層からなる海底扇状地を形成した堆積体です.城川は中期中新世の火成作用によって形成された,南北にのびる琴の滝変質帯を横切るように流れています.まだら岩はこの熱水変質をうけて,白色化・硬化した牟婁付加シークエンスの砂岩泥岩互層(タービダイト)です.硬化したタービダイトが城川の瀬で磨かれて,砂岩の白,泥岩の黒に,酸化鉄の黄褐色が付加されたまだら岩が城川の清流に映えています.(中屋志津男:南紀熊野ジオパーク学術専門委員)
目次へ戻る
第8回フォトコン_入選5
第8回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:モエラキボールダー
写真:蛯子 渉(沖縄県)
撮影場所:ニュージーランド、モエラキ海岸付近
【撮影者より】
ニュージーランド南島南東部の海岸にある奇岩群「モエラキボールダー」です。この形がどのように出来上がったのかという過程については諸説ありますが、炭酸カルシウムが凝縮して形成された亀甲石凝固であるという説が有力なようです。波に洗われる半球体のその姿は、人知を超えた神秘的な神々しい雰囲気を漂わせています。 ここはいつか行きたいと思っていた場所です。今回海外の撮影に出かけ、やっと見ることができました。しかし引き潮のときしか岩が現れず、また天候も悪くてタイミングが難しかったのですがスローシャッターで波の動きを柔らかくし、空のコントラストを上げると曇っている空がかえって印象的な写真となりました。
【審査委員長講評】
モエラキボルダーは地質マニアには有名な場所で,普通は干潮の時間を狙って砂浜にある球状のボルダーが並んでいるのを撮影します.作者は潮が引いていないときに訪れていますが,スローシャッターや撮影後の画像処理によって,今までに見たことのない作品に仕上げています.
【地質的背景】
この丸石が出来た地層は,6000万年前の海底に堆積しました.堆積物は,穴を掘る貝などによってかきまぜられ,均質になります.この堆積物中では大きな貝殻などを核にして周りの石灰分が成長し,球状大きくなります.1500万年前頃,地殻変動によって陸に持ち上げられ,海岸侵食によってごく最近に転がり落ちたのがモエラキのボルダーです.(白尾元理)
目次へ戻る
125記念トリビア6:女性地質研究者
〜2018年日本地質学会創立125周年を記念して〜
トリビア学史 6 女性地質研究者の嚆矢
矢島道子(日本大学文理学部)
写真 地質学会50周年記念式典(1943.7.25,北海道大学).前から3列目左端から井上,藤原,米満(「日本の地質学100年」 より).
はじめに
2015(平成27)年発行の日本地質学会・会員名簿では,3851名の会員中,女性は373名で1割弱である.地質学会で女性を初めて見かけるようになったのは,1943(昭和18)年のことであるが,実は,その前に日本の化石を研究した外国人女性と日本人女性がいる.概略を記したい.
マリー・ストープス
日本の化石を最初に研究した女性はイギリス人のマリー・ストープス(Marie Stopes 1880-1958)である(矢島,2007).ストープスは,1902(明治35)年ロンドン大学(UCL)より,植物化石の研究で,女性として初めて理学博士を取得した.1903(明治36)年,さらに,ミュンヘン大学のゲーベル(KarlEberhardt von Goebel 1855-1932)教授のもとに留学して研究を続けた.ゲーベル教授は当時,裸子植物研究の第一人者であった.ここで,銀杏の研究のために日本から留学してきた藤井健次郎(1866-1952)と出会う.ストープスは1904(明治37)年にマンチェスター大学の講師となった.理科系ではマンチェスター大学初の女性講師であった.藤井はマンチェスターのストープスを訪れていたが,東京帝国大学理学部の植物学教授への就任の打診を受けて帰国した.1907(明治40)年,ロンドン王立協会の奨学金をえて,ストープスは藤井を追う形で日本にやってくる.被子植物の花の化石研究が目的であった.北海道 の炭田を地質調査し,サンプリングしている.1910(明治43)年,ストープスと藤井の共著論文『白亜紀植物の構造と類縁に関する研究』がロンドン王立協会の雑誌に発表された.ここには,日本の菌類,シダ,球果,針葉樹,被子植物果実17種が記載されている. ストープスは,その後バースコントロールの運動家となり,欧米では有名である.
保井コノ
日本人女性で最初に理学博士を取得した保井コノ(1880-1971)は植物学者といわれているが,彼女の学位論文のテーマは「日本産の亜炭,褐炭,瀝青炭の構造について」であり,北海道・石狩炭田地域の柱状図もたくさん書かれているなど,実際には植物化石の研究者であった.保井は香川県の生まれで,1898(明治31)年 香川県師範学校を卒業した後,女子高等師範学校理科に入学した.1902年に同校理科を卒業し,数年の女学校教諭をへて,1905(明治38)年,女子高等師範学校研究科に入学した.最初は動物学を志していたが,1906(明治39)年に 植物学とくに細胞学の研究に移り,1907年女子高等師範学校研究科を修了し,同校助教授となる.1914(大正3)年アメリカに留学し,1915(大正4)年,ハーバード大学のジェフレー(Edward Charles Jeffrey 1866-1952)教授に師事して石炭の研究を開始した.1916(大正5)年に帰国し,前掲の藤井教授のもとで石炭の研究を継続した.1927(昭和2)年,東京帝国大学より理学博士号を取得した.
日本地質学会では
日本地質学会では,1943(昭和18)年7月25日に,北海道大学で行われた地質学会50周年記念式典の写真に,3名の女子学生が写っている.この3名が,最初の女性地質学者とされている.北海道帝国大学の地質学教室を1944(昭和19)年9月に卒業した,井上(都城)タミ(生年不明),藤原隆代(1917-1992),米満 信(生没年不明)の3名である. 井上タミは,1944年に「石綿の性質について」を発表し,東京女子高等師範学校に就職し,東京大学の地質学教室で研究を続けた.都城秋穂との共著論文も数編ある. 藤原隆代は,1936(昭和11)年に東京女子師範学校2部を卒業し,小学校教師を経た後,1940(昭和15)年に東京高等師範学校副手に任用された.その後,北海道大学理学部地質学教室の聴講生をへて,1945(昭和20)年,北海道大学理学部地質鉱物学教室の副手に採用された(大森,1992).1944年には「蛇紋岩に関するニッケル鉱床の一例について」についての発表であったが,その後化石に含まれる有機物の研究に転じ,1968(昭和43)年には「化石有機物の古生化学的研究」で日本地質学会より学会賞を受賞した. 米満 信は,東芝電気株式会社に就職したことが知られている.
まとめ
上記3名の後,少しずつ女性研究者は増加してきた.初期の女性研究者の来歴を調べると,研究を認めてくれる組織がなかなか見つからず,所属先を転々としていることがよくわかる.大変な努力の積み重ねであったと思う.なお,それぞれの研究者の生没年等,入手できていない情報も多いので,どなたかご存知の方は一報いただければ幸いである.
文 献
大森昌衛,1992.藤原隆代さんのご逝去を悼む.地質学雑誌,98(7),p711.
矢島道子,2007.マリー・ストープスの2つの顔:日本の植物化石研究事始め.大学出版部協会[編],ナチュラル・ヒストリーの時間,20-23,大学出版部協会.
日本地質学会編,1993,日本の地質学会100年:日本地質学会100周年記念.日本地質学会,706p
125記念トリビア7:地質学者宮沢賢治研究の嚆矢?
〜2018年日本地質学会創立125周年を記念して〜
トリビア学史 7 地質学者宮沢賢治研究の嚆矢?
矢島道子(日本大学文理学部)
写真 深田淳夫原稿(1945)第1ページ
はじめに
地質学の歴史を調べていくときに,戦争中の地質学者の動きは重要である.日本地質学会は創立60周年記念誌でかなり詳細に記録しているが,まだ知られていない資料は多い.資料が散逸しないうちに記録されるべきであろう.東京大学の地質学教室の戦時中の歴史を調べているうちに,おもしろい資料を発見したので,公開する.
東京帝国大学地質学教室の疎開
1945年小林貞一教授を筆頭とする東京帝国大学地質学教室第2講座は山形県大石田町に図書や標本とともに疎開した.他の講座はどこに疎開したかはまだ調査していない.1945年3月10日の東京大空襲のときには多くの焼死体を見ながら大学に登校したという当時の学生の証言をえているので,疎開は1945年4月以降の事と思われる.小林の指揮のもと在籍していた学生・職員が荷物の梱包,発送,大石田での研究室づくりなどに奔走した.この困難な間も,東京にいた時のように授業も行い,談話会も開いていたらしい.幸い,疎開自体は一年足らずで終わったが,運んで間もない荷物をまた東京に送りかえして,焼けずに残っていた理学部二号館の教室にもとのように再配置するという労働を余儀なくされた.
東京大学総合研究博物館にある多くの古い標本には,箱を破ったようなラベルがある.おそらく,2度の引っ越しの結果と思われる.
『笹の実』
疎開中の大石田では,同人誌『笹の実』も発行していたらしいことを,当時,学生だった深田淳夫氏(1922-2010)より2007年に伺った.そして,その2号の原稿を,当時助手であった市川健雄氏が保存されていたので,ここに紹介する.
宮澤賢治先生と地質學(深田淳夫)
岩手県花巻の人,宮澤賢治先生こそは二十世紀の日本の生んだ最大の詩人であると申しても宜しいでせう.而も先生が生へ抜きの東北人であり,農村人の辛苦を身を以て躬行した力強き実践者であったことは,今こうして疎開學生として大石田の街に清らかな地方生活を送る身にとって,ひとしお,身近なものを感じてゐる次第です.
更に先生の高弟として農村振興の意欲に燃え,朝に夕に,「精神歌」を唱和し,『アメニモマケズ,カゼニモマケヌ』の朴訥な精神生活に,若き心身を献げて,同じく若干三十八才の幕を閉じられた故松田甚太郎氏は,ほど近き,新庄盆地の産であり,今尚鳥越部落には,『最上共同村塾』が残ってゐるといふから,東北の若き青年諸君が如何に賢治先生の尊き感化をうけてゐるかを想像するに難くないのであります.然しいつかも學校の矢作先生とお話ししたのですが,却って地元の当地等では,松田氏のやうな,はでな,行き過ぎたやり方に対して反対の意見をもってゐる者もあるといふ事を聞いて,“さもありなん”と面白く感じたことです.何はともあれ,賢治先生逝いて已に十三年,在京の有数の作家を編輯者として,はなはなしく全集が刊行され,又東京や花巻では,宮澤賢治の會が組織されるし,『風の又三郎』の映画が世に喧傳されたり,『銀河鉄道の夜』や『ポランの廣場』等の童話がつぎつぎと上演された宮澤賢治文學の一種の流行時代も,いつしか風の如く過ぎ去り,余りにもめまぐるしいその日その日の,あわただしい世相を前にしては,先生の名もいつのまにか忘れさらうとする傾向にあることは,その流行時代の華々しかっただけに,ことさら空虚なさびしい気持にさせられるのです.
決してそんな,流行の対象となるやうな,浅薄な内容のものでなく,所謂“卑劫なる成人共”の充満する今の世にあって,ほんとうに先生の素朴な心に私淑する人の,少しでも多からんことを切望しで止まないものがあります.
詩人としての宮澤賢治,法華経の信者としての先生,花巻農学校の一教師としての先生等に就いては,随分と今迄,いろいろの人によって語り盡されたものであり,今更,私の如き無縁外来の徒の喙を入れる余地を感じないのですが,先生の科学者として,とりわけ地質學に深い造詣をもってをられたことを,今ここにお話してみようと考へてみた次第であります.
今手元に全集は勿論のこと,一切の文献を所有してゐない為に,一々の記憶は誤りの多からんことを,ひそかに懸念するのですが,その点はとくと寛恕あらんことを希望いたします.
私が大學に於て地質學を専門としてえらぶやうになったのも,一つは,先生の影響の絶大であったことを自ら感じてをる次第です.
そして先生が鉛筆を首にブラ下げては,小さなノートを手にして,或いは岩手山に,或は早池峰山その他の北上の山々を,幻想の詩境にさまよい乍ら,思ふ存分に跋渉された姿を,はるかに彷彿として心に畫いたことでした.先生は幼にして既に博物學に興味をもち,珍しい鉱物を採集したり,植物の標本や昆蟲の標本を作ることにも趣味をもってをられた様です.わけても山野を跋渉することは得意中の得意らしく 盛岡中學に在學中にも,土曜日から日曜日にかけて,単身,岩手山に登山することもしばしばであったさうです.
其後盛岡の高等農林農藝化学科を卒業してからも,同校の地質学研究科に於て,関豊太郎博士の指導をうけ,稗貫郡の土性調査を一緒に,各地の地質調査に従事されたことも,想像に難くないのであります.
その頃,盛岡から故郷の父君宛に送った書簡によっても,その間の消息を知ることが出来ます.その中に次のやうにあります.
謹啓・・・・
其の後學校にては大体化學實験の手傳ひを致し居り候・・・略.
次に先月末より求め候書籍漸く仙台の丸善より得申し候.右は左の三冊に御座候.
ハッチ及ラスタル著 岩石學(二)水成岩 四一〇円
ライス著 經濟的地質學 八八〇円
ウェンレイ原著・ヨハンセン英訳 岩石學の基本溶接 五六〇円
右の内ライス著を今夕繙き所々散見仕り候處,實に當地に適切なる岩石鉱物を多数発見仕り,誠に愉快に存じ候.尚左の書籍
I ゼームス・ゲーゲー 構造及野外地質學
II メーリル 非金属鉱物及其應用
III イッデングス 造岩鉱物
同 火成岩(上下)
ハーカー 火成岩 中の三冊
を得度と折角考慮致し候處・・・略
とあるのをみても,地質學の方面に於ても常識以上に,可成突っ込んだ研究をせられたことが想像されるのであります.
又先生はニコル付の鉱物顯微鏡の下に於て,岩石の薄片が,どのやうな鮮かな美しい色を示すかを感歎してをられ,或いは上野の圖書館に,或いは東北帝大の地質學教室に,非常な熱意を以て,地質學を勉強せられたことも察せられます.
又花巻農學校に在學中に,イリドスミンやオウミュウムのやうな稀な鉱物粒を採集せられたり,花巻町小舟渡北上河岸の第三紀層泥岩から 偶蹄類の足跡や胡桃の化石を集められたこともある由であります.
然し又,三十八才の短い生涯の晩年に近く「百姓に石灰肥料を安く供給したい」との念願から,大船渡線松川駅前の東北砕石工場の技手として古生代の石灰岩の採掘に従事されたこともあるさうです.
かくの如く賢治さんの地質學の勉強が,すべて,土壌學もしくは広く農學の爲の,基礎としての地質學であったことは,必然的な成行であると申さねばなりません.
次に其の數多くの作品を讀んでみても,いろいろと地質學上の術語の出て来ることは.枚挙にいとまが無い位です.
先生の詩稿『春と修羅』の中の,いちいちについてのべることは除いても,そのあまたの童話の中にも,我々地質を學ぶ者にとって,とりわけ興味深いものが多いのであります.
就中第一に思い出されるのは作品『楢の木大學士』であります.清廉潔白の貧乏大學士,楢の木君は,インチキ商人(それが飯田橋の岩本鉱物標本店を風刺するものかどうかは論外として)にそそのかされて,東北の山奥にオパール(蛋白石)を採集に行く話です.手にはデッカイハンマーをもち,大きなリュックサックを背負って,上野の驛の雑踏にもまれる光景等は,思ひだすだけでもほほえましくなるほどですし,三陸のどこかの海岸の洞穴で野宿して夢を見,その夢物語りの中に,コルツ(石英)さんと,バイオタさん(黒雲母)とプラヂオさん(長石)との三人が喧嘩を始める有様を,花崗岩の風化にたとへた奇想天外な着想等は全く感心させられる處です.
又『気のいい火山彈』の話の中には私達の東京帝國大學地質學教室の名前が,そのまま出て来るのも愉快であるし,『グスコープドリの傳記』の中に,火山の爆発を人工的に起こす話も面白いし,
『山彦』の中では,地質の學生がたたくカーンカーンといふハンマーの音が,或る山間の鉱山の住宅に住む若い夫婦の間の出来事に関係してくる叙述もいかにも,ありさうな私達のよーく經験する事柄のやうに思はれるのです.その他,直接地質學とは関係のないまでも,山の話や草木の話等々,北上の山々をこの足でつぶさに歩きまわった私には,とりわけ手にとるやうな親しみを感ずるのでした.「風の又三郎」「注文の多い料理店」「どくもみのすきな警察署長さん」「ざしき童子の話」等すべてその尤なるものであります.
かくの如く先生の作品を通覧してみるとき,いかにも無理やこじつけのない素朴な自然さが何よりも貴重なものであり,一つ一つの譬へが実にピッタリとしてゐるのに,驚かざるをえません.
山から生まれた詩であり,子供のやうな,明るい,純な心の産物と申して宜しいでせう.
都会の人からみれば,いらだたしい迄に 気の利かない眞正直で実直な,東北人獨特の性格から,自然に生まれ出たものであるという感じが,しみじみするのです.
その詩篇の中には,全く個人の主觀的な叙情である爲に,難解にして不可解な部分も,これなしとしないのですが,その童話の中には何度味ってみても,興味の盡きない作品のあまたあることを紹介して廣く同學諸兄の閲讀をおすすめしたいと思ひます.
大きく口をあいて童謡を唄ふやうな,子供の気持になりきって,味っていただきたいものです.最後に有名な作品を一つ紹介してこの駄文をおわりませう.
雨ニモマケズ (略) 以上 20[昭和20].7.17
『笹の実』の反応
原稿が発見されてコピーを深田氏に送ったところ「案外反響が少なく,特に東北大学の先生方が無関心なのが不思議でした.唯一,弘前大学の宮城一男さんという方が評価してくださった記憶があります.矢部長克先生や早坂一郎先生もあまり関心がありませんでした.案外地質学者の独善性とひとりよがりを反映しているものかもしれません」という2007年12月17日付のはがきをいただいた.
宮城一男氏は『農民の地学者・宮沢賢治』(築地書館,1975年),『宮沢賢治-地学と文学のはざま』(玉川選書,1977年)などを公刊されているが,深田淳夫氏のことについては何も記されていない.
追記
特定の企業や個人に対して,一部誤解を与えるような表現が含まれているが,原文を尊重してそのまま掲載させていただいた.(2017.5.15追記)
【geo-Flash】No.368 第8回惑星地球フォトコンテスト:審査結果発表!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.368 2017/3/7┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】第8回惑星地球フォトコンテスト:審査結果発表!
【2】[2017愛媛大会情報]トピックセッション募集:まもなく締切り!
【3】[125周年関連情報]記念事業の概要/記念事業に対する寄付のお願い
【4】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日
【5】2017年「地質の日」イベント情報
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】第8回惑星地球フォトコンテスト:審査結果発表!
──────────────────────────────────
応募作品全650作品のうち,最優秀賞1点をはじめ,計12作品が入選しました.
また,10作品が佳作に選ばれました.
*作品の詳細(画像など)は学会HP上にてご紹介しています.
http://www.geosociety.jp/faq/content0009.html
【表彰式】
4月8日(土)12:45〜13:45(時間は多少変更になる場合があります)
会場:北とぴあ901会議室(東京都北区王子)
*入選作品の展示も行います.
【入選作品展示会のお知らせ】
*銀座プロムナードギャラリー(東京)
6月10日(土)午後〜 6月24日(土)午前
場所:銀座プロムナードギャラリー(中央区銀座 東銀座地下歩道壁面)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2017愛媛大会情報]トピックセッション募集中
──────────────────────────────────
第124年学術大会(2017年愛媛大会)
「ようおいでたなもし,四国地質お遍路の旅へ」
会期:2017年9月16日(土)〜18日(月)
会場:愛媛大学城北キャンパス
http://www.geosociety.jp/science/content0074.html
▶▶トピックセッション募集中:3月13日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0075.html
▶▶演題登録・講演要旨受付:5月末開始〜7月5日(水)締切
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[125周年関連情報]記念事業の概要/記念事業に対する寄付のお願い
──────────────────────────────────
創立125周年記念事業として,2018年5月東京での記念式典をはじめ,様々な事
業を計画しています.また,それら記念事業を実行するため,学会員や賛助会
員,さらには関連諸団体に寄付をお願いしております.
▶125周年記念事業の概要
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html
▶記念事業に対する寄付のお願い
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html#kifu
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は,3月31日(金)です.
次年度も割引会費を希望のかたは,忘れずにご提出ください(締切厳守).
割引会費申請や通常の会費払込について,
http://www.geosociety.jp/outline/content0164.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2017年「地質の日」イベント情報
──────────────────────────────────
学会関連の地質のイベント情報をお知らせします.この他の行事の予定も,
学会HPに随時追加していきます.
http://www.geosociety.jp/name/content0155.html
■■本部行事■■
○第8回惑星地球フォトコンテストほか入選作品展示会
6月10日(土)午後〜 6月24日(土)午前
場所:銀座プロムナードギャラリー(中央区銀座 東銀座地下歩道壁面)
■■中部支部■■
○大地のかけらを探せ!! ぼくのわたしの石の標本作り:地質の日 in 白山手取川ジオパーク
主催:金沢大学理工学域自然システム学類地球学コース・白山手取川ジオパーク推進協議会
後援:日本地質学会中部支部
5月13日(土)
申込締切:5月9日(火)17:00
■■その他■■
○観察会「城ヶ島と三崎の地盤隆起:1923年大正関東地震の地殻変動」
主催:ジオ神奈川 後援:日本地質学会ほか
5月13日(土)10:00〜15:00
場所:神奈川県三浦市城ヶ島
申込締切:5月5日(金)
○地質情報普及講座「深海から生まれた城ヶ島」
主催:三浦半島活断層調査会 後援:日本地質学会ほか
5月21日(日)10:00〜15:00
申込締切:5月10日(水)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/name/content0155.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[北海道支部]
■北海道支部平成28年度(2016年度)総会
3月11日(土)14:30〜16:30
場所:北海道大学理学部6号館2階 6-204室
「県の石(北海道)」決定記念講演会:16:45〜17:45
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地質地盤情報の活用と法整備を考える会:連絡No.11
1)国土交通省の第1回「地下空間の利活用に関する安全技術の確立に関する小
委員会」の議事要旨と配布資料→活動報告のページ
2)「地下鉄七隈線延伸工事における道路陥没事故と設計・施工の経緯について」
に関する福岡市交通局の資料→社会の動向・技術情報のページ
http://www.geo-houseibi.jp
*************(以下,関連団体の行事案内です)****************
■第196回地質汚染イブニングセミナー
3月31日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室(東京都北区王子)
講師:後藤文昭(三井住友信託銀行経営企画部CSR推進室)
テーマ:環境と金融〜土壌汚染を題材として〜
http://www.npo-geopol.or.jp
■日本学術会議公開シンポジウム/第3回 防災学術連携シンポジウム
熊本地震 追悼・復興祈念行事「熊本地震・1周年報告会」
4月15日(土)11:00〜18:20
場所:熊本県庁本館 地下大会議室(熊本市中央区水前寺6-18-1)
参加無料,定員450名
参加申込み等詳細は,http://janet-dr.com/
■(後)特別展:石は地球のワンダー〜鉱物と化石に魅せられた2人のコレクション〜
4月22日(土)〜6月4日(日)
場所:大阪市立自然史博物館
*「47都道府県の石(岩石・鉱物・化石)」展を同時開催
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
■(後)日本学術会議公開シンポジウム
「地質地盤情報の共有化を目指して−安全安心で豊かな社会の構築に向けて−」
4月27日(木)13:30〜17:40 参加費無料
場所:日本学術会議講堂
http://www.scj.go.jp/ja/event/index.html
■JpGU-AGU Joint Meeting 2017
5月20日(土)〜25日(木)
会場:千葉県 幕張メッセ
参加申込早期締切:5月25日(木)12:00
http://www.jpgu.org/meeting_2017/
■IGCP630 Annual Symposium (2017)
Permian-Triassic climatic & environmental extremes and biotic responses
6月14日(水)〜16日(金)
場所:東北大学
講演申込・要旨提出,巡検申込締切:3月20日(月)
https://amarys-jtb.jp/icgp630/
■(共)第54回アイソトープ・放射線研究発表会
7月5日(水)〜7日(金)
場所:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
発表論文申込締切:2月28日(火)17:00
http://www.jrias.or.jp/
■(後)科学教育研究協議会第64回全国研究大会
8月7日(月)〜9日(水)
場所:広島なぎさ中学高等学校(広島市佐伯区)
http://kakyokyo.main.jp/
■(共)第61回粘土科学討論会
9月25日(月)〜 27日(水)
会場:富山大学 五福キャンパス共通教育棟
http://www.cssj2.org/
■(後)第4回Slope tectonics 2017
10月14日(土)〜18日(水)
場所:京都大学宇治キャンパス黄檗プラザ
http://www.slope.dpri.kyoto-u.ac.jp/SlopeTectonics2017/st2017.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・室戸ユネスコ世界ジオパーク地質専門員/国際交流専門員募集(3/17)
・JAMSTEC海洋掘削科学研究開発センターポストドクトラル研究員(3/31)
・JAMSTEC地球内部物質循環研究分野・研究員もしくは技術研究員(4/28)
・JAMSTEC数理科学・先端技術研究分野・研究員もしくは技術研究員(5/2)
・地球化学研究協会学術賞「三宅賞」および「進歩賞」候補者の募集(8/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.370 125周年:寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.370 2017/4/4┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【2】第8回惑星地球フォトコンテスト:表彰式・展示会
【3】2017年「地質の日」イベント情報
【4】RFG2018:セッション提案募集(5/1締切)
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
──────────────────────────────────
125周年記念事業として,2018年5月東京での記念式典をはじめ,様々な事
業を計画しています.また,それら記念事業を実行するため,学会員や賛助会
員,さらには関連諸団体に寄付をお願いしております.
>>記念事業に対する寄付のお願い
*クレジットカードもご利用いただけます
ご利用可能カード:VISA, Master, Diners
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html#kifu
>>125周年記念事業の概要
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html
*****お詫び*****
WEBクレジット決済画面が一時的に表示されない状態になっていました(4/1,
17時頃復旧)。ご迷惑をおかけし,大変申し訳ありませんでした。
*************
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第8回惑星地球フォトコンテスト:表彰式・展示会
──────────────────────────────────
応募作品全650作品のうち,最優秀賞1点をはじめ,計12作品が入選しました.
*作品の詳細(画像,講評など)は学会HP上にて紹介しています.
http://www.geosociety.jp/faq/content0009.html
【表彰式】
4月8日(土)12:45〜13:45
会場:北とぴあ901会議室(東京都北区王子)
*白尾委員長による講評,入選作品の展示も行います.
【入選作品展示会のお知らせ】
*銀座プロムナードギャラリー(東京)
6月10日(土)14:00頃〜24日(土)12:00頃
場所:銀座プロムナードギャラリー(中央区銀座 東銀座地下歩道壁面)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2017年「地質の日」イベント情報
──────────────────────────────────
学会関連(主催,共催,後援など)の地質のイベント情報をお知らせします.
この他の行事の予定も,学会HPに随時追加していきます.
http://www.geosociety.jp/name/content0155.html
[本部行事]
○第8回惑星地球フォトコンテスト表彰式 *入選作品の展示も行います
4月8日(土)12:45〜13:45
会場:北とぴあ901会議室(東京都北区王子)
○街中ジオ散歩in Tokyo「国分寺崖線と玉川上水」
5月14日(日)9:45〜16:00 小雨決行(予定)
申込締切:4月10日(月)
定員:30名(申込者多数の場合は抽選)
http://www.geosociety.jp/name/content0155.html
○第8回惑星地球フォトコンテストほか入選作品展示会
6月10日(土)14:00頃〜24日(土)12:00頃
場所:銀座プロムナードギャラリー(中央区銀座 東銀座地下歩道壁面)
[近畿支部]
○第34回地球科学講演会「国石になった翡翠について」
主催: 地学団体研究会大阪支部・日本地質学会近畿支部・大阪市立自然史博物館
5月14日(日)14:00〜16:00(13:00より受付)
場所:自然史博物館 講堂
講師:宮島 宏氏(糸魚川市フォッサマグナミュージアム)
参加費無料(博物館入館料必要)
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
[中部支部]
○大地のかけらを探せ!! ぼくのわたしの石の標本作り:
地質の日 in 白山手取川ジオパーク
主催:金沢大学理工学域自然システム学類地球学コース・白山手取川ジオパーク推進協議会
5月13日(土)
申込締切:5月9日(火)17:00
○富山市科学博物館:とやまの自然探検
「神通川の石ころ観察会」4月29日(土)13:30〜15:30
「常願寺川の石ころ観察会」5月13日(土)13:30〜15:30
いずれも参加無料,要申込
○長岡市立科学博物館:特別展/企画展
ミニ企画展:アルバートサウルスの前・後肢化石(レプリカ)
4月4日(火)〜23日(日)
GW特別展示:ハルキゲニア実物化石と生体復元模型2種
4月29日(祝)〜5月7日(日)
ミニ企画展:パラサウロロフスの下顎化石(レプリカ)
5月10日(水)〜6月4日(日)
○川の石を比べてジオを知る
主催:黒部市吉田科学館
5月14日(日)
[その他]
○観察会「城ヶ島と三崎の地盤隆起:1923年大正関東地震の地殻変動」
主催:ジオ神奈川 後援:日本地質学会ほか
5月13日(土)10:00〜15:00
場所:神奈川県三浦市城ヶ島
申込締切:5月5日(金)
○地質情報普及講座「深海から生まれた城ヶ島」
主催:三浦半島活断層調査会 後援:日本地質学会ほか
5月21日(日)10:00〜15:00
申込締切:5月10日(水)
この他のイベント,詳しい情報などは学会HPを参照して下さい.
http://www.geosociety.jp/name/content0155.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】RFG2018:セッション提案募集(5/1締切)
──────────────────────────────────
RFGは,IUGSが支援する国際会議で,4年に一度のIGC会議の間に実施する mini
-IGCと位置づけられ,来年6月にカナダ・バンクーバーで開催が予定されていま
す。是非日本の地質科学コミュニティーからのセッションをご提案下さい。
**セッション提案募集:2017年5月1日(月)締切**
>RFG2018
日程:2018年6月16日(土)〜21日(木)
場所:カナダ・バンクーバー
http://www.rfg2018.org/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
2017年度総会・地質技術伝承講演会
4月15日(土)14:00〜16:45
場所:赤羽会館(東京都北区赤羽南1-13-1)
地質技術伝承講演会「環境地質調査のはなし−現場手法と解析−(仮)」
講師:岡野英樹((株)東建ジオテック 本店技術部課長)
*総会に欠席される方は委任状提出をお願いします(4月14日(金)まで)
http://kanto.geosociety.jp/
[中部支部]
2017年支部年会
6月17日(土)〜18日(日)
会場:新潟県糸魚川市フォッサマグナミュージアム
17日:シンポジウム,個人講演,懇親会ほか
18日:巡検「ジオガイドと訪ねる糸魚川の大地の秘密」
参加申込締切:6月2日(金)*ただし,シンポ講演申込は5月26日(金)まで
http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■道総研・地質研究所ニュース(vol. 32, No. 4)
津波堆積物:剥は ぎ取り標本の紹介 など
http://www.hro.or.jp/list/environmental/research/gsh/publication/gshnews/gshnews02/index.html
■電中研ニュース No. 483
『送電用鉄塔の巨大地震に対する耐震性評価技術の構築と活用』
http://criepi.denken.or.jp/research/news/index.html?m=170328
■地質地盤情報の活用と法整備を考える会
第7回幹事会報告/第3回「福岡市地下鉄七隈線延伸工事現場における道路陥没に
関する検討委員会」の資料が公開 など
http://www.geo-houseibi.jp
■日本学術会議「軍事的安全保障研究に関する声明」
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-s243.pdf
*************(以下,関連団体の行事案内です)****************
■日本学術会議公開シンポジウム/第3回 防災学術連携シンポジウム
熊本地震 追悼・復興祈念行事「熊本地震・1周年報告会」
4月15日(土)11:00〜18:20
場所:熊本県庁本館 地下大会議室(熊本市中央区水前寺6-18-1)
参加無料,定員450名
参加申込み等詳細は, http://janet-dr.com/
■(後)特別展:石は地球のワンダー〜鉱物と化石に魅せられた2人のコレクション
4月22日(土)〜6月4日(日)
場所:大阪市立自然史博物館
*「47都道府県の石(岩石・鉱物・化石)」展を同時開催
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
■(後)日本学術会議公開シンポジウム
「地質地盤情報の共有化を目指して−安全安心で豊かな社会の構築に向けて−」
4月27日(木)13:30〜17:40 参加費無料
場所:日本学術会議講堂
http://www.scj.go.jp/ja/event/index.html
■第197回地質汚染イブニングセミナー
4月28日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:田村嘉之(一般財団法人千葉県環境財団地質環境課課長)
テーマ:火山灰層、例えば関東ローム層と水循環
http://www.npo-geopol.or.jp
■春の自然史ハイキング「270万年前のメタセコイアとゾウの足跡」
大阪市立自然史博物館地質の日協賛事業
5月7日(日)10:00〜15:00頃 雨天・増水時中止
場所:滋賀県湖南市
対象:小学4年生以上(小学生は保護者同伴)
定員:40名
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
■JpGU-AGU Joint Meeting 2017
5月20日(土)〜25日(木)
会場:千葉県 幕張メッセ
参加申込早期締切:5月8日(月)16:59
http://www.jpgu.org/meeting_2017/
■日本古生物学会2017年年会・総会
6月9日(金)〜11日(日)
場所:北九州市立自然史・歴史博物館
講演申込締切:4月6日(木)
http://www.palaeo-soc-japan.jp/events/
■(共)第54回アイソトープ・放射線研究発表会
7月5日(水)〜7日(金)
場所:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
http://www.jrias.or.jp/
■(後)科学教育研究協議会第64回全国研究大会
8月7日(月)〜9日(水)
場所:広島なぎさ中学高等学校(広島市佐伯区)
http://kakyokyo.main.jp/
■(共)第61回粘土科学討論会
9月25日(月)〜 27日(水)
会場:富山大学 五福キャンパス共通教育棟
http://www.cssj2.org/
■IGCP589「アジアにおけるテチス区の発達」第6回国際シンポジウム
「Western Tethys meets Eastern Tethys」
9月29日(金)〜30日(土)
ポスト巡検:10月1日(日)〜10月5日(木)
場所:AGH University of Science and Technology(ポーランド,クラクフ市)
http://igcp589.cags.ac.cn/
■(後)第4回Slope tectonics 2017
10月14日(土)〜18日(水)
場所:京都大学宇治キャンパス黄檗プラザ
http://www.slope.dpri.kyoto-u.ac.jp/SlopeTectonics2017/st2017.html
■(共)第15回国際放散虫研究集会(15th InterRad)
10月23日(月)〜27日(金)(研究集会)
20日(金)〜22日(日)(プレ巡検)
22日(日)(サイエンスカフェ)
28日(土)〜31日(火)(ポスト巡検)
会場:新潟大学など
http://interrad2017.random-walk.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・第8回日本学術振興会育志賞候補者の推薦(学会締切 5/15)
・山田科学振興財団国際学術集会助成(4/1-18/2/23)
・日本学術振興会若手研究者海外挑戦プログラム募集(5/15-19)
・2018年〜2019年開催 藤原セミナーの募集(学会締切6/30)
・アースウォッチ・ジャパン:フィールド研究プログラム募集(7/20)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.371(臨時)愛媛大会の宿泊予約に関するお知らせ
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.371 2017/4/13┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】愛媛大会の宿泊予約に関するお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】愛媛大会の宿泊予約に関するお知らせ
──────────────────────────────────
**各自,早めに交通手段の確保.宿泊予約をされるようお勧め致します**
松山市内では地質学会同期間中に医学系などの他学会,10月のえひめ国体の事
前行事の開催が予定されており,既に宿泊予約が大変混み合っています。
そのため地質学会では,旅行社を通じて宿泊施設の確保を進めており,現在各
日約300名前後の宿泊施設を確保する予定です,ただ,松山市内だけでは難しい
ため,近郊(奥道後,今治,西条など)にもエリアを拡げての確保を行ってい
ます。
愛媛大会に参加予定の皆様におかれましては,各自,早めに交通手段の確保.
宿泊予約をされるようお勧め致します.
旅行社による確保分については,近々に学会専用の宿泊申込サイトを開設する
予定で,準備ができ次第皆様にURLをお知らせ致します.
************************************************
第124年学術大会 〜ようおいでたなもし,四国地質お遍路の旅へ〜
会期:2017年9月16日(土)〜18日(月)
(巡検:19日(火)〜21日(木)8コース予定)
会場:愛媛大学城北キャンパス(愛媛・松山市)
演題登録・講演要旨受付締切:7月5日(水)
巡検参加申込締切:8月上旬
大会参加登録・懇親会参加申込締切:8月中旬
************************************************
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.372「巡検時等における車両運行指針」の策定に関して
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.372 2017/4/17┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】「巡検時等における車両運行指針」の策定に関して
【2】声明発表:地質学の知見をもって減災につなげるために 熊本地震から
一年を迎えるにあたって
【3】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【4】2017年「地質の日」イベント情報
【5】Island Arc:論文ワークショップ「アクセプトされる論文の書き方」
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「巡検時等における車両運行指針」の策定に関して
──────────────────────────────────
日本地質学会において,野外における巡検や見学会等の開催は,学会活動の
大きな柱の一つです.これらの実施にあたっては,安全に行われてはじめてそ
の目的が達成されます.しかし巡検等では,車両による移動が必要な場合が多
く,事故等のリスクが潜在しています.特にレンタカー等の慣れない車両を運
転し,かつ,通常よりも多い参加者を乗せている場合には,事故が発生する危
険性が高まります.そこで執行理事会では,学会が実施する行事におけるレン
タカー等の車両の利用・運転に係る様々なリスクについて議論してきました.
全文はこちらから、、、
http://www.geosociety.jp/outline/content0179.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】声明発表:地質学の知見をもって減災につなげるために 熊本地震から
一年を迎えるにあたって
──────────────────────────────────
平成28年熊本地震から1年が経とうとしています。この地震は甚大な被害と共に、
数多くの地質学的な教訓をもたらしました。本学会は地質学の役割を自ら再認
識し、その知見を減災に役立てていくために声明を発表します。
(2017年4月10日発表)
全文はこちらから
http://www.geosociety.jp/engineer/content0049.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
──────────────────────────────────
125周年記念事業として,2018年5月東京での記念式典をはじめ,様々な事
業を計画しています.また,それら記念事業を実行するため,学会員や賛助会
員,さらには関連諸団体に寄付をお願いしております.
*醵金者一覧(4月11日現在)
http://www.geosociety.jp/125th/content0014.html
*記念事業に対する寄付のお願い
クレジットカード(VISA, Master, Diners)もご利用いただけます
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html#kifu
*125周年記念事業の概要
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2017年「地質の日」イベント情報
──────────────────────────────────
学会関連(主催,共催,後援など)の地質のイベント情報をお知らせします.
この他の行事の予定も,学会HPに随時追加していきます.
http://www.geosociety.jp/name/content0155.html
[本部行事]
○第8回惑星地球フォトコンテストほか入選作品展示会
6月10日(土)14:00頃〜24日(土)12:00頃
場所:銀座プロムナードギャラリー(中央区銀座 東銀座地下歩道壁面)
[近畿支部]
○第34回地球科学講演会「国石になった翡翠について」
主催:地団研大阪支部・日本地質学会近畿支部・大阪市立自然史博
5月14日(日)14:00〜16:00(13:00より受付)
場所:自然史博物館 講堂
講師:宮島 宏氏(糸魚川市フォッサマグナミュージアム)
参加費無料(博物館入館料必要)
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
[北海道支部]
○地質の日記念展示「北海道のジオサイトに見る化石」
4月28日(金)〜 6月 18日(日)
会場:北海道大学総合博物館1 階企画展示室 【入場無料】
市民セミナー:
5月20日(土)「北海道ジオサイト107への旅に出て」
6月4日(日)「ジオサイトとしての札幌の魅力」
市民巡検:
6月10日(土)「ジオサイト『藻岩山』を歩く」
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[中部支部]
○大地のかけらを探せ!! ぼくのわたしの石の標本作り:
地質の日 in 白山手取川ジオパーク
5月13日(土)
申込締切:5月9日(火)17:00
○富山市科学博物館:とやまの自然探検
「神通川の石ころ観察会」4月29日(土)13:30〜15:30
「常願寺川の石ころ観察会」5月13日(土)13:30〜15:30
いずれも参加無料,要申込
○長岡市立科学博物館:特別展/企画展
ミニ企画展:アルバートサウルスの前・後肢化石(レプリカ)
4月4日(火)〜23日(日)
GW特別展示:ハルキゲニア実物化石と生体復元模型2種
4月29日(祝)〜5月7日(日)
ミニ企画展:パラサウロロフスの下顎化石(レプリカ)
5月10日(水)〜6月4日(日)
○川の石を比べてジオを知る
主催:黒部市吉田科学館
5月14日(日)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/name/content0155.html#chubu
[その他]
○観察会「城ヶ島と三崎の地盤隆起:1923年大正関東地震の地殻変動」
主催:ジオ神奈川 後援:日本地質学会ほか
5月13日(土)10:00〜15:00
場所:神奈川県三浦市城ヶ島
申込締切:5月5日(金)
○地質情報普及講座「深海から生まれた城ヶ島」
主催:三浦半島活断層調査会 後援:日本地質学会ほか
5月21日(日)10:00〜15:00
申込締切:5月10日(水)
http://www.geosociety.jp/name/content0155.html#other
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】Island Arc:論文ワークショップ「アクセプトされる論文の書き方」
──────────────────────────────────
論文の質を高め,スムーズに採択・出版されるためには,正しい論文構成法の
理解が欠かせません.このワークショップでは,国際的な英文誌である日本地
質学会機関誌 Island ArcのEditor-in-Chiefを務める武藤先生より,論文構成
上のポイントについてアドバイスをいただきます.
日時:5月22日(月)12:30〜13:30
会場:幕張メッセ国際会議場201B
対象:英文誌への投稿に関心のある若手研究者
講師:武藤鉄司(Island Arc誌 編集委員長)
・講演は日本語で行われます
・希望者にに昼食をご提供(先着50名様・要事前登録)
・当日参加も可能.スムーズにご入場いただくために事前登録をお勧めします.
http://www.jpgu.org/meeting_2017/seminar.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[中部支部]
2017年支部年会
6月17日(土)10:00〜
会場:新潟県糸魚川市フォッサマグナミュージアム
シンポジウム,個人講演,懇親会ほか
シンポジウム「地質学とジオパーク ―現状と今後の課題―」
参加申込締切:6月2日(金)
*ただし,シンポ講演申込は5月26日(金)まで
http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
[西日本支部]
第三回西日本地質講習会(CPD講習会)
5月17日(水)10:00〜16:40(懇親会(オプション)17:00〜)
会場:山口大学吉田キャンパス大学会館
5月18日(木)地質巡検:徳佐から津和野地域
申込締切:5月8日(月)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
資源エネルギー庁:地層処分に関する地域の科学的な特性の提示に係る要件・
基準の検討結果(4/17ニュースリリース)
http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170417001/20170417001.html
*************(以下,関連団体の行事案内です)****************
■(後)特別展:石は地球のワンダー〜鉱物と化石に魅せられた2人のコレクション
4月22日(土)〜6月4日(日)
場所:大阪市立自然史博物館
*「47都道府県の石(岩石・鉱物・化石)」展を同時開催
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
■(後)日本学術会議公開シンポジウム
「地質地盤情報の共有化を目指して−安全安心で豊かな社会の構築に向けて−」
4月27日(木)13:30〜17:40 参加費無料
場所:日本学術会議講堂
http://www.scj.go.jp/ja/event/index.html
■第197回地質汚染イブニングセミナー
4月28日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:田村嘉之(一般財団法人千葉県環境財団地質環境課課長)
テーマ:火山灰層,例えば関東ローム層と水循環
http://www.npo-geopol.or.jp
■春の自然史ハイキング「270万年前のメタセコイアとゾウの足跡」
大阪市立自然史博物館地質の日協賛事業
5月7日(日)10:00〜15:00頃 雨天・増水時中止
場所:滋賀県湖南市
対象:小学4年生以上(小学生は保護者同伴)
定員:40名
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
■JpGU-AGU Joint Meeting 2017
5月20日(土)〜25日(木)
会場:千葉県 幕張メッセ
参加申込早期締切:5月8日(月)16:59
http://www.jpgu.org/meeting_2017/
■(共)第54回アイソトープ・放射線研究発表会
7月5日(水)〜7日(金)
場所:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
http://www.jrias.or.jp/
■(後)科学教育研究協議会第64回全国研究大会
8月7日(月)〜9日(水)
場所:広島なぎさ中学高等学校(広島市佐伯区)
http://kakyokyo.main.jp/
■第71回地学団体研究会総会(旭川)
8月25日(金)〜27日(日)
会場:北海道旭川市大雪クリスタルホール・神楽市民交流センター
事前申込締切:7月14日(金)
https://sites.google.com/view/soukai2017
■(共)第61回粘土科学討論会
9月25日(月)〜 27日(水)
会場:富山大学 五福キャンパス共通教育棟
http://www.cssj2.org/
■(後)第4回Slope tectonics 2017
10月14日(土)〜18日(水)
場所:京都大学宇治キャンパス黄檗プラザ
http://www.slope.dpri.kyoto-u.ac.jp/SlopeTectonics2017/st2017.html
■(共)第15回国際放散虫研究集会(15th InterRad)
10月23日(月)〜27日(金)(研究集会)
20日(金)〜22日(日)(プレ巡検)
22日(日)(サイエンスカフェ)
28日(土)〜31日(火)(ポスト巡検)
会場:新潟大学など
http://interrad2017.random-walk.org/
■16th Gondwana International Conference/ IAGR 2017 Annual Convention/
14th International Conference on Gondwana to Asia
11月12日(日)〜17日(金)
場所:タイ・バンコク,
登録・発表要旨締切:7月31日
http://www.dmr.go.th
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・東邦大学理学部生命圏環境科学科地球環境科学部門講師または准教授(6/30)
・住友財団2017年度研究助成(基礎科学研究助成・環境研究助成)(6/8)
・ゆざわジオパーク研究費助成募集(5/31)
・南紀熊野ジオパーク研究助成募集(5/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.373 日本地質学会第9回総会開催
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.373 2017/5/2┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】日本地質学会第9回総会開催
【2】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【3】2017年「地質の日」イベント情報
【4】支部情報
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】日本地質学会第9回総会開催
──────────────────────────────────
日時:2017年5月20日(土)12:30〜13:30
会場:幕張メッセ 国際会議場 302
(千葉市美浜区中瀬 ※JpGU-AGU Joint Mettin2017会場内)
1. 定款20条により,本総会は役員ならびに代議員による総会となります.
代議員には,総会開催通知とともに総会に必要な資料等を別途お送りいたしま
す.ご都合で欠席される方は,定款28条第1項にもとづき,議決権行使書および
議決権の代理行使(委任状)などにより,総会に出席したものとして議決権を
行使することができます.
2.正会員は,総会に陪席することができます.ただし,総会規則12条3項によ
り,許可のない発言はできません.
議事次第は, http://www.geosociety.jp/outline/content0170.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
──────────────────────────────────
125周年記念事業として,2018年5月東京での記念式典をはじめ,様々な事
業を計画しています.また,それら記念事業を実行するため,学会員や賛助会
員,さらには関連諸団体に寄付をお願いしております.
*醵金者一覧(4月28日現在)
http://www.geosociety.jp/125th/content0014.html
*記念事業に対する寄付のお願い
クレジットカード(VISA, Master, Diners)もご利用いただけます
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html#kifu
*125周年記念事業の概要
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2017年「地質の日」イベント情報
──────────────────────────────────
学会関連(主催,共催,後援など)の地質のイベント情報をお知らせします.
この他の行事の予定も,学会HPに随時追加していきます.
http://www.geosociety.jp/name/content0155.html
[本部行事]
○第8回惑星地球フォトコンテストほか入選作品展示会
6月10日(土)14:00頃〜24日(土)12:00頃
場所:銀座プロムナードギャラリー(中央区銀座 東銀座地下歩道壁面)
[近畿支部]
○第34回地球科学講演会「国石になった翡翠について」
主催:地学団体研究会大阪支部・日本地質学会近畿支部・大阪市立自然史博
5月14日(日)14:00〜16:00(13:00より受付)
場所:自然史博物館 講堂
講師:宮島 宏氏(糸魚川市フォッサマグナミュージアム)
参加費無料(博物館入館料必要)
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
[北海道支部]
○地質の日記念展示「北海道のジオサイトに見る化石」
4月28日(金)〜 6月18日(日)
会場:北海道大学総合博物館1 階企画展示室 【入場無料】
市民セミナー:
5月20日(土)「北海道ジオサイト107への旅に出て」
6月4日(日)「ジオサイトとしての札幌の魅力」
市民巡検:
6月10日(土)「ジオサイト『藻岩山』を歩く」
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[中部支部]
○大地のかけらを探せ!! ぼくのわたしの石の標本作り:
地質の日 in 白山手取川ジオパーク
5月13日(土)
申込締切:5月9日(火)17:00
○富山市科学博物館:とやまの自然探検
「常願寺川の石ころ観察会」5月13日(土)13:30〜15:30
いずれも参加無料,要申込
○長岡市立科学博物館:特別展/企画展
GW特別展示:ハルキゲニア実物化石と生体復元模型2種
4月29日(祝)〜5月7日(日)
ミニ企画展:パラサウロロフスの下顎化石(レプリカ)
5月10日(水)〜6月4日(日)
○川の石を比べてジオを知る
主催:黒部市吉田科学館
5月14日(日)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/name/content0155.html#chubu
[その他]
○観察会「城ヶ島と三崎の地盤隆起:1923年大正関東地震の地殻変動」
主催:ジオ神奈川 後援:日本地質学会ほか
5月13日(土)10:00〜15:00
場所:神奈川県三浦市城ヶ島
申込締切:5月5日(金)
○地質情報普及講座「深海から生まれた城ヶ島」
主催:三浦半島活断層調査会 後援:日本地質学会ほか
5月21日(日)10:00〜15:00
申込締切:5月10日(水)
http://www.geosociety.jp/name/content0155.html#other
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】支部情報
──────────────────────────────────
[中部支部]
2017年支部年会
6月17日(土)
会場:新潟県糸魚川市フォッサマグナミュージアム
シンポジウム,個人講演,懇親会ほか
シンポジウム「地質学とジオパーク −現状と今後の課題―」
参加申込締切:6月2日(金)
*ただし,シンポ講演申込は5月26日(金)まで
http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
[西日本支部]
第三回西日本地質講習会(CPD講習会)
5月17日(水)10:00〜16:40(懇親会(オプション)17:00〜)
会場:山口大学吉田キャンパス大学会館
5月18日(木)地質巡検:徳佐から津和野地域
申込締切:5月8日(月)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■(後)特別展:石は地球のワンダー〜鉱物と化石に魅せられた2人のコレクション
4月22日(土)〜6月4日(日)
場所:大阪市立自然史博物館
*「47都道府県の石(岩石・鉱物・化石)」展を同時開催
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
■JpGU-AGU Joint Meeting 2017
5月20日(土)〜25日(木)
会場:千葉県 幕張メッセ
参加申込早期締切:5月8日(月)16:59
http://www.jpgu.org/meeting_2017/
■第198回地質汚染イブニングセミナー
5月26日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:楡井 久(NPO法人日本地質汚染審査機構理事長)
テーマ:国民が学んだ教訓―東京豊洲新市場の地質汚染問題と液状化-流動化・
地波問題からー
http://www.npo-geopol.or.jp
■第2回若手科学者サミット
6月2日(金)13:30〜18:00
場所:日本学術会議 講堂(港区六本木)
*口頭・ポスター発表者・パネリスト若干名:募集(5/17締切)
http://www.geosociety.jp/outline/content0096.html
■文部科学省「科研費改革説明会」
(1)東日本会場
6月8日(木)13:30〜16:00
会場:東京大学 安田講堂
(2)西日本会場
6月15日(木)13:30〜16:00(予定)
会場:関西学院大学 中央講堂
対象:研究者
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/1362786.htm
■東京地学協会平成29年度春季講演会
「ネパール−自然の魅力と人々の暮らし−」
6月10日(土)13:15〜
場所:東京グリーンパレス(千代田区二番町2番地)
http://www.geog.or.jp/
■2017年度資源地質学会年会
6月21日(木)〜23日(金)
会場:東京大学 本郷キャンパス 小柴ホール
*国際シンポジウム「The Japanese Porphyry Copper Enigma」
21日(水)13:00〜18:00
//www.resource-geology.jp/events/#p221
■(共)第54回アイソトープ・放射線研究発表会
7月5日(水)〜7日(金)
場所:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
http://www.jrias.or.jp/
■(後)「青少年のための科学の祭典」2017全国大会
7月29日(土)〜30日(日)
会場:科学技術館(千代田区北の丸公園2-1)
http://www.kagakunosaiten.jp/
■(後)科学教育研究協議会第64回全国研究大会
8月7日(月)〜9日(水)
場所:広島なぎさ中学高等学校(広島市佐伯区)
http://kakyokyo.main.jp/
■(共)2017年度日本地球化学会第64回年会
9月13日(水)〜15日(金)
会場:東京工業大学・大岡山キャンパス
講演申込:6月13日(火)〜7月13日(木)14時締切.
http://www.geochem.jp/meeting/index.html
■(共)第61回粘土科学討論会
9月25日(月)〜 27日(水)
会場:富山大学 五福キャンパス共通教育棟
http://www.cssj2.org/
■(後)第4回Slope tectonics 2017
10月14日(土)〜18日(水)
場所:京都大学宇治キャンパス黄檗プラザ
http://www.slope.dpri.kyoto-u.ac.jp/SlopeTectonics2017/st2017.html
■(共)第15回国際放散虫研究集会(15th InterRad)
10月23日(月)〜27日(金)(研究集会)
20日(金)〜22日(日)(プレ巡検)
22日(日)(サイエンスカフェ)
28日(土)〜31日(火)(ポスト巡検)
会場:新潟大学など
http://interrad2017.random-walk.org/
■第71回日本人類学会大会
11月3日(金)〜5日(日)
会場:東京大学本郷キャンパス
講演申込締切:8月21日(月)
http://anthrop-meeting.sakura.ne.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻(固体地球科学分野助教)公募(5/31)
・徳島大学大学院社会産業理工学研究部理工学域自然科学系地球科学分野(構造地質学)教授公募(7/14)
・島原半島ユネスコ世界ジオパーク学術研究奨励事業募集(6/30)
・勝山市ジオパーク学術研究等奨励事業(5/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.376 愛媛大会事前参加登録:受付開始
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.376 2017/6/6┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
[愛媛大会情報]
【1】事前参加登録:受付開始しました
【2】まずは演題登録専用のアカウント登録を!
【3】ランチョン・夜間小集会:受付中
【4】企業等団体展示・書籍販売・広告協賛の募集
【5】おもな申込締切
---------------------------------------------------------------
【6】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【7】[125周年関連情報]お願い:会員氏名のローマ字表記について
【8】2017年「地質の日」イベント情報
【9】山形県地質図(10万分の1)割引販売のお知らせ
【10】支部情報
【11】その他のお知らせ
【12】公募情報・各賞助成情報等
【13】訃報 藤井昭二 名誉会員 ご逝去
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[愛媛大会情報]事前参加登録:受付開始しました
──────────────────────────────────
事前参加登録の受付を開始しました.参加登録に関わるお申込(参加,要旨集,
巡検,懇親会,弁当)は,オンラインによる大会専用参加登録システム(会員
・非会員にかかわらずどなたでも申込可)をご利用の上,お申し込み下さい.
*事前参加登録締切:8月21日(木)18時(WEB)*
お申込はこちら
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/sanka
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[愛媛大会情報]まずは演題登録専用のアカウント登録を!
──────────────────────────────────
<重要>まずは,演題登録専用のアカウント登録を!
**********************************************************
第124年学術大会の演題登録受付中です.まず,愛媛大会演題登録専用のアカウント
登録が必要です(1つのアカウントで複数の演題登録が可能です).
締切まで何度でも要旨や登録内容を修正することができますので,まずはアカ
ウント登録を行い,締切までに演題登録を完了させましょう!
*演題登録・要旨投稿締切:7月5日(水)*
演題登録はこちらから
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/collectsubject
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[愛媛大会情報]ランチョン・夜間小集会:受付中
──────────────────────────────────
会合開催をご希望の場合は,期日までに忘れずに行事委員会宛にお申し込み下さい。
今年もランチョンは大会初日(9/16)より開催可能です。
例年開催されている会合等は,忘れずに締切までにお申し込み下さい.
*ランチョン・夜間集会申込締切:6月29日(木)*
お申込はこちらから
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/meeting
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[愛媛大会情報]企業等団体展示・書籍販売・広告協賛の募集
──────────────────────────────────
関連企業の皆様,奮ってお申込をいただきますようお願い申し上げます.
*一次締切:7月7日(金)・最終締切:8月10日(木)*
詳しくは,こちら
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/company
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[愛媛大会情報]主な申込締切
──────────────────────────────────
【演題登録・要旨投稿】7月5日(水)
【大会参加登録・巡検申込】8月21日(月)締切
【ランチョン・夜間集会】6月29日(木)締切
【小さなEarth Scientistのつどい】7月14日(金)
愛媛大会HPはこちらから
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/top?eventCode=geosocjp124
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
──────────────────────────────────
125周年記念事業として,2018年5月東京での記念式典をはじめ,様々な事
業を計画しています.また,それら記念事業を実行するため,学会員や賛助会
員,さらには関連諸団体に寄付をお願いしております.
*醵金者一覧(6月6日現在)
http://www.geosociety.jp/125th/content0014.html
*記念事業に対する寄付のお願い
クレジットカード(VISA, Master, Diners)もご利用いただけます
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html#kifu
*125周年記念事業の概要
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】[125周年関連情報]お願い:会員氏名のローマ字表記について
──────────────────────────────────
学会では来年の学会創立125周年を記念して,会員証(プラスチック製,カード
タイプ)を作成し,全会員に配布致します.これは,会員証としてだけでなく,
学術大会など会合での名札としても活用できるように企画しています.
会員証に印字する会員氏名は,日本語とローマ字を併記します.ローマ字表記
は,基本的には入会申込書に記載されたものを用いますが,あらためてご登録
頂ければ,そちらを採用致します.ローマ字の表記方法には複数あるものもあ
ります.
*********************************************************
あらためてローマ字表記の登録を希望される方は,手続きをお願いします.
*********************************************************
1)メール,FAXもしくは郵送で,下記の内容を学会事務局宛にお知らせ下さい.
会員氏名・所属(もしくは住所)・希望するローマ字表記
2)申込期限:2017年6月30日(金)
3)宛先は以下のとおりです.
メール:main@geosociety.jp,FAX:03-5823-1156
郵送:〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F
(表記方法が複数ある例)
ち(CHI・TI),じ(JI・ZI),けんいち(Kenichi・Ken-ichi),
たろう(Taro・Tarou),おおた(OTA・OHTA・OOTA)など
特にご希望の無い場合(入会申込書に記載されたローマ字表記で良い方)は,
事務局への連絡は不要です.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】2017年「地質の日」イベント情報
──────────────────────────────────
学会関連(主催,共催,後援など)の地質のイベント情報をお知らせします.
この他の行事の予定も,学会HPに随時追加していきます.
http://www.geosociety.jp/name/content0155.html
[本部行事]
■第8回惑星地球フォトコンテストほか入選作品展示会
6月10日(土)14:00頃〜24日(土)12:00頃
場所:銀座プロムナードギャラリー(中央区銀座 東銀座地下歩道壁面)
[北海道支部]
■地質の日記念展示「北海道のジオサイトに見る化石」
4月28日(金)〜 6月18日(日)
会場:北海道大学総合博物館1 階企画展示室 【入場無料】
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】山形県地質図(10万分の1)割引販売のお知らせ
──────────────────────────────────
昨年11月に,山形大学出版会から山形応用地質研究会著「山形県地質図(10万
分の1)」が出版されました.下記の通り割引販売について会員の皆様にお知ら
せいたします.
編著:山形応用地質研究会,山形大学山形県地質図監修委員会 監修
割引価格:全県4枚セット:18,360円(送料込),地域版1部:5,760円(送料込)
(定価:全県4枚セット20,000円+税・送料,地域版1部6,000円+税・送料)
地質図の紹介(山形大学出版会のサイト)
<http://www.yamagata-u.ac.jp/books/publication/029.html>
割引販売注文先:〒990-8560 山形市小白川町1-4-12
山形大学地域教育文化学部 大友研究室
電話 023-628-4424 e-mail:yukiko[at]e.yamagata-u.ac.jp([at]を@マークに)
購入方法については,山形応用地質研究会のサイトからもご確認いただけます.
<http://www.geocities.jp/yamagataoyo/mousikomi.html>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】支部情報
──────────────────────────────────
[北海道支部]
■平成29年度例会(個人講演会)
6月17日(土)10:00〜18:00(時間は予定)
場所:北海道大学理学部5号館大講堂(5-203)
■2017年春巡検「札幌の失われた川を歩く」
6月18日(日)9:00〜17:00
巡検先:札幌市内(北海道大学(南側)〜北海道大学植物園〜札幌市立中央中
学校(北4条東3丁目)付近を歩きます)
案内者:宮坂省吾(川の案内人)・内山幸二(石の案内人)・土屋 篁(「ビ
ルの岩石学」執筆)
*参加申込締切:6月11日(日)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[中部支部]
■2017年支部年会
6月17日(土)
会場:新潟県糸魚川市フォッサマグナミュージアム
シンポジウム,個人講演,懇親会ほか
シンポジウム「地質学とジオパーク −現状と今後の課題—」
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
[関東支部]
■清澄フィールドキャンプ 参加者募集
8月21日(月)〜26日(土)
場所:東京大学千葉演習林(千葉県鴨川市清澄)
費用:30,000円(学生),40,000円(社会人)程度を予定
*参加申込締切:7月7日(金)
詳しくは,http://kanto.geosociety.jp/
■地学教育・アウトリーチ巡検
「火山灰を追跡する-浅間火山の噴出物と噴火史」
地質学会関東支部では,今まで小中高教員向けに実施してきた教師巡検を見
直し,一般の方々まで参加対象を拡げました.より多くの方々に,野外での観
察を通して地球科学に対する理解を深めていただきたいと思っています.今年
度の巡検は「火山」がテーマです.浅間火山の様々な噴出物を観察し,噴火の
歴史を学びます.また,鬼押出し溶岩等,天明噴火の痕跡を訪れ,火山防災に
ついて考えます.
日程:2017年8月7日(月)〜8日(火)1泊2日
対象:教育関係者および地学に興味のある一般の方(非会員も参加可)
講師:大石雅之(立正大学地球環境科学部)
募集:20人(先着順 *申込期間: 6月1日〜7月10日)
集合:JR高崎駅09:50(バス出発10:00,具体的な場所は1週間前に連絡します)
解散:JR高崎駅18:00予定
予定コース(天候などにより変更することがあります):
8月7日:高崎駅→Stop1:室田→昼食:道の駅くらぶち小栗の里→
Stop2:鎌原観音堂および資料館→Stop3:赤川→宿舎(北軽井沢,2食付)
8月8日:宿舎→Stop4:浅間園(鬼押出し)→Stop5:六里ヶ原→昼食→
Stop6:白糸の滝→Stop7:小諸市南城公園→高崎駅
費用:20,000円(交通費,宿泊費,入館料,保険代など.当日集金)
*直前キャンセルの場合,傷害保険料や宿舎代などキャンセル料が発生します.
申込み・問い合わせ:メールにて下記担当者まで
件名は,「地学教育・アウトリーチ巡検申込み」として下さい.
氏名,所属,日中連絡のつく電話番号を記入してください.
申込者全員に,受付結果についてのメールを返信します.
後日,参加者は保険申込のため性別,住所,生年月日をお伺いします.
担当:関東支部幹事 田村糸子(たむらいとこ)首都大学東京都市環境科学域
メールアドレス itoko[at]tmu.ac.jp([at]を@マークに)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地震本部ニュース平成29年度春号
調査研究レポート:南海トラフでの海底・孔内観測網による海底地殻変動
モニタリング…など
http://www.jishin.go.jp/herpnews/
■地質地盤情報の活用と法整備を考える会 より
・国土交通省の第2回「地下空間の利活用に関する安全技術の確立に関する小委
員会」(4/14)平成28年度活動計画・報告および平成29年度活動計画を掲載.
・日本学術会議公開シンポジウム「地質地盤情報の共有化を目指して−安全安
心で豊かな社会の構築に向けて−(4/27)」報告
当日の「考える会」基調講演PDFファイルをDLできます.
http://www.geo-houseibi.jp
*************(以下,関連団体の行事案内です)****************
■第12回企画展「新島 襄が感じた地球」
5月16日(火)〜7月9日(日)入場無料
場所:同志社大学ハリス理化学館同志社ギャラリー
・公開講演会「新島 襄の地球」(聴講無料,事前申込不要)
講師:林田 明氏(同志社大学理工学部教授)
7月1日(土) 13:00〜
会場:明徳館1番教室(同志社大学今出川キャンパス)
http://harris.doshisha.ac.jp/
■(後)原子力総合シンポジウム2017
6月8日(木) 13:00〜17:10
会場:日本学術会議講堂(港区六本木 7-22-34)
入場無料・事前登録制
http://www.aesj.net/g-symposium2017
■2017年度資源地質学会年会(*一部会場変更)
6月21日(木)〜23日(金)
--21日(水)表彰講演,国際シンポ,懇親会
会場:東京大学 伊藤謝恩ホール(文京区本郷7-3-1)
--22日(木)〜23日(金)一般講演
会場:東京大学 小柴ホール(文京区本郷7-3-1)
*国際シンポジウム「The Japanese Porphyry Copper Enigma」
21日(水)13:00〜18:00
//www.resource-geology.jp/events/#p221
■(共)第54回アイソトープ・放射線研究発表会
7月5日(水)〜7日(金)
場所:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
http://www.jrias.or.jp/
■(後)「青少年のための科学の祭典」2017全国大会
7月29日(土)〜30日(日)
会場:科学技術館(千代田区北の丸公園2-1)
http://www.kagakunosaiten.jp/
■(後)科学教育研究協議会第64回全国研究大会
8月7日(月)〜9日(水)
場所:広島なぎさ中学高等学校(広島市佐伯区)
http://kakyokyo.main.jp/
■(共)2017年度日本地球化学会第64回年会
9月13日(水)〜15日(金)
会場:東京工業大学・大岡山キャンパス
講演申込:6月13日(火)〜7月13日(木)14時締切
http://www.geochem.jp/meeting/index.html
■(共)第61回粘土科学討論会
9月25日(月)〜 27日(水)
会場:富山大学 五福キャンパス共通教育棟
http://www.cssj2.org/
■(後)第4回Slope tectonics 2017
10月14日(土)〜18日(水)
場所:京都大学宇治キャンパス黄檗プラザ
http://www.slope.dpri.kyoto-u.ac.jp/SlopeTectonics2017/st2017.html
■(共)第15回国際放散虫研究集会(15th InterRad)
10月23日(月)〜27日(金)研究集会
20日(金)〜22日(日)プレ巡検
22日(日)サイエンスカフェ
28日(土)〜31日(火)ポスト巡検
要旨締切:6月15日(木)
会場:新潟大学など
http://interrad2017.random-walk.org/
■第10回HOPEミーティング ―ノーベル賞受賞者との5日間―」参加募集
主催:日本学術振興会
2018年3月11日(日)〜15日(木)
対象:博士課程(後期)学生/若手研究者(学位取得後5年未満)
参加申請締切:8月7日(月)本会必着
http://www.jsps.go.jp/hope/index.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・大阪市立大学大学院理学研究科生物地球系専攻地球史学分野(准教授or講師)公募(6/23)
・2017年度「第38回猿橋賞」受賞候補者推薦依頼(学会締切:10/30)
・平成30年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞および若手科学者賞受賞候補者の推薦(学会締切:7/14)
・平成29年度(第58回)東レ科学技術賞および東レ科学技術研究助成の候補者推薦(学会締切:8/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】訃報 藤井 昭二 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
藤井 昭二 名誉会員(富山大学名誉教授)が,平成29年6月5日18時51分にご逝去
されました(享年90歳).
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます.
なお,ご葬儀等は下記の通り執り行われます.
通夜:6月8日(木)19時より
葬儀:6月9日(金)10時より
喪主:藤井 洋様(ご子息)
式場:シティホール富山(富山市桜町1-1-4,電話076-445-4444)
会長 渡部 芳夫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.369 愛媛大会トピックセッション決定
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.369 2017/3/21┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[2017愛媛大会情報]トピックセッション決定
【2】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【3】第8回惑星地球フォトコンテスト:入選作品
【4】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日
【5】2017年「地質の日」イベント情報
【6】Island Arc編集事務局の連絡先変更
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2017愛媛大会情報]トピックセッション決定
──────────────────────────────────
3/13締切でトピックセッションを募集し,行事委員会で検討しました結果,す
べての応募(10件)を採択しました.レギュラーセッション等とあわせて,例
年通り5月末頃から講演申込開始予定です.
(演題登録・講演要旨投稿:5月末受付開始〜7月5日(水)締切予定)
[愛媛大会トピックセッション(10件)]
(1)文化地質学
(2)最近の鬼界カルデラ研究成果と今後の課題
(3)東アジアの古生代古地理学
(4)変動帯日本列島内安定陸塊の探査
(5)日本列島の起源・成長・改変
(6)三次元地質モデル研究の新展開
(7)極々表層堆積学:「堆積物」への記録プロセスの理解
(8)スロー地震の地質学
(9)中央構造線と中央構造線活断層系
(10)「泥火山」の新しい研究展開に向けて
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
──────────────────────────────────
創立125周年記念事業として,2018年5月東京での記念式典をはじめ,様々な事
業を計画しています.また,それら記念事業を実行するため,学会員や賛助会
員,さらには関連諸団体に寄付をお願いしております.
>>記念事業に対する寄付のお願い
*クレジットカードもご利用いただけるようになりました.
ご利用可能カード:VISA, Master, Diners
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html#kifu
>>125周年記念事業の概要
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】第8回惑星地球フォトコンテスト:入選作品
──────────────────────────────────
応募作品全650作品のうち,最優秀賞1点をはじめ,計12作品が入選しました.
*作品の詳細(画像,講評など)は学会HP上にて紹介しています.
http://www.geosociety.jp/faq/content0009.html
【表彰式】
4月8日(土)12:45〜13:45
会場:北とぴあ901会議室(東京都北区王子)
*入選作品の展示も行います.
【入選作品展示会のお知らせ】
*銀座プロムナードギャラリー(東京)
6月10日(土)14:00頃〜24日(土)12:00頃
場所:銀座プロムナードギャラリー(中央区銀座 東銀座地下歩道壁面)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月31日
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は,3月31日(金)です.
次年度も割引会費を希望のかたは,忘れずにご提出ください(締切厳守).
割引会費申請や通常の会費払込について,
http://www.geosociety.jp/outline/content0164.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2017年「地質の日」イベント情報
──────────────────────────────────
学会関連(主催,共催,後援など)の地質のイベント情報をお知らせします.
この他の行事の予定も,学会HPに随時追加していきます.
http://www.geosociety.jp/name/content0155.html
[本部行事]
○第8回惑星地球フォトコンテスト表彰式 *入選作品の展示も行います
4月8日(土)12:45〜13:45
会場:北とぴあ901会議室(東京都北区王子)
○第8回惑星地球フォトコンテストほか入選作品展示会
6月10日(土)14:00頃〜24日(土)12:00頃
場所:銀座プロムナードギャラリー(中央区銀座 東銀座地下歩道壁面)
[中部支部]
○大地のかけらを探せ!! ぼくのわたしの石の標本作り:
地質の日 in 白山手取川ジオパーク
主催:金沢大学理工学域自然システム学類地球学コース・白山手取川ジオパー
ク推進協議会
5月13日(土)
申込締切:5月9日(火)17:00
○富山市科学博物館:とやまの自然探検
「神通川の石ころ観察会」4月29日(土)13:30〜15:30
「常願寺川の石ころ観察会」5月13日(土)13:30〜15:30
いずれも参加無料,要申込
○長岡市立科学博物館:特別展/企画展
ミニ企画展:アルバートサウルスの前・後肢化石(レプリカ)
4月4日(火)〜23日(日)
GW特別展示:ハルキゲニア実物化石と生体復元模型2種
4月29日(祝)〜5月7日(日)
ミニ企画展:パラサウロロフスの下顎化石(レプリカ)
5月10日(水)〜6月4日(日)
○川の石を比べてジオを知る
主催:黒部市吉田科学館
5月14日(日)
[その他]
○観察会「城ヶ島と三崎の地盤隆起:1923年大正関東地震の地殻変動」
主催:ジオ神奈川 後援:日本地質学会ほか
5月13日(土)10:00〜15:00
場所:神奈川県三浦市城ヶ島
申込締切:5月5日(金)
○地質情報普及講座「深海から生まれた城ヶ島」
主催:三浦半島活断層調査会 後援:日本地質学会ほか
5月21日(日)10:00〜15:00
申込締切:5月10日(水)
この他のイベント,詳しい情報などは学会HPを参照して下さい.
http://www.geosociety.jp/name/content0155.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】Island Arc編集事務局の連絡先変更
──────────────────────────────────
2010年以降,Island Arc誌の編集事務局を東京都神田の日本地質学会事務局
内に置いてきましたが,効率的かつ迅速な編集作業の推進を目的として,本年
3月より業務の一部をWiley社に委託することとなりました.これに伴い,編集
事務局のメールアドレスが変更されましたことをご報告申し上げます(新アド
レス: Island_Arc_editorialoffice@wiley.com).今回の編集体制の変更によ
り,スピーディーな査読および編集作業が期待されるなど,著者及び読者の方
々により良いサービスを提供できるものと考えております.会員の皆様方にお
かれましては,今後ともIsland Arc誌の編集発行にご協力いただけますようお
願い申し上げます.
編集委員長 武藤鉄司(長崎大)・田村芳彦(JAMSTEC)
編集事務局長 板木拓也(産総研)
原稿投稿や査読に関するお問い合わせは,新アドレスまで!
Island_Arc_editorialoffice@wiley.com >
>>Island Arc最新刊(Vol.26, Issue 2)はこちら(wileyのサイト)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iar.2017.26.issue-2/
issuetoc
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
2017年度総会・地質技術伝承講演会
4月15日(土)14:00〜16:45
場所:赤羽会館(東京都北区赤羽南1-13-1)
地質技術伝承講演会「環境地質調査のはなし−現場手法と解析−(仮)」
講師:岡野英樹((株)東建ジオテック 本店技術部課長)
*総会に欠席される方は委任状提出をお願いします(4月14日(金)まで)
http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■電中研TOPICS Vol.23
「原子力発電所の安全性向上のためのヒューマンファクター技術」発行
http://criepi.denken.or.jp/research/topics/index.html?m=170313
*************(以下,関連団体の行事案内です)****************
■日本学術会議公開シンポジウム/第3回 防災学術連携シンポジウム
熊本地震 追悼・復興祈念行事「熊本地震・1周年報告会」
4月15日(土)11:00〜18:20
場所:熊本県庁本館 地下大会議室(熊本市中央区水前寺6-18-1)
参加無料,定員450名
参加申込み等詳細は, http://janet-dr.com/
■(後)特別展:石は地球のワンダー〜鉱物と化石に魅せられた2人のコレクショ
ン
4月22日(土)〜6月4日(日)
場所:大阪市立自然史博物館
*「47都道府県の石(岩石・鉱物・化石)」展を同時開催
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
■(後)日本学術会議公開シンポジウム
「地質地盤情報の共有化を目指して−安全安心で豊かな社会の構築に向けて−」
4月27日(木)13:30〜17:40 参加費無料
場所:日本学術会議講堂
http://www.scj.go.jp/ja/event/index.html
■第197回地質汚染イブニングセミナー
4月28日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室(東京都北区王子)
講師:田村嘉之(一般財団法人千葉県環境財団地質環境課課長)
テーマ:火山灰層、例えば関東ローム層と水循環
http://www.npo-geopol.or.jp
■第16回重金属・残土石処分地・廃棄物処分地診断に関わる地質汚染調査浄化
技術研修会
共催:地質汚染診断士の会・日本地質学会環境地質部会・IUGS-GEM日本支部・
社会地質学会
5月1日(月)〜4日(木)
場所:関東ベースンセンター(千葉県香取市)
会費:会員 50,000円,非会員60,000円, 学生15,000円 ※昼食代を含む
http://www.npo-geopol.or.jp
■JpGU-AGU Joint Meeting 2017
5月20日(土)〜25日(木)
会場:千葉県 幕張メッセ
参加申込早期締切:5月8日(月)16:59
http://www.jpgu.org/meeting_2017/
■(共)第54回アイソトープ・放射線研究発表会
7月5日(水)〜7日(金)
場所:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
http://www.jrias.or.jp/
■(後)科学教育研究協議会第64回全国研究大会
8月7日(月)〜9日(水)
場所:広島なぎさ中学高等学校(広島市佐伯区)
http://kakyokyo.main.jp/
■(共)第61回粘土科学討論会
9月25日(月)〜 27日(水)
会場:富山大学 五福キャンパス共通教育棟
http://www.cssj2.org/
■(後)第4回Slope tectonics 2017
10月14日(土)〜18日(水)
場所:京都大学宇治キャンパス黄檗プラザ
http://www.slope.dpri.kyoto-u.ac.jp/SlopeTectonics2017/st2017.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・2017年コスモス国際賞受賞候補者推薦募集(学会締切 3/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
125記念トリビア8:傍系の地質学者 篠本二郎(1863-1933)
〜2018年日本地質学会創立125周年を記念して〜
トリビア学史 8 傍系の地質学者 篠本二郎(1863-1933)
矢島道子(日本大学文理学部)・浜崎健児(Ultra Trex(株)))
写真 篠本二郎,木下(1933a)より
はじめに
鉱床学者,木下龜城(1896-1974)が1933年,『我等の礦物』誌に篠本二郎の追悼文を書いている.略歴も著述目録も詳しく載っている.にもかかわらず,巷では生没年不詳となっているものが多い.本人も自伝のようなものを書かず,木下のほかには評伝や弔辞を書かなかったことが,そうなっている原因だと言えそうだ.こう紹介すると篠本の名は歴史から消えかかっているように思えるが,彼の交友関係は思いのほか広い.
夏目漱石の幼友達
昭和3年版『漱石全集』月報第2号に篠本は「腕白時代の夏目君」を書いた.これは岩波文庫『漱石追想』に再録されている.主題は当然ながら漱石の想い出であるが,ここから,篠本の出自,人生を知ることができる.篠本は夏目と「明治6[1873]年ころ,牛込薬王寺前町の小学校3級で同じ腰掛に座を占めていた」と書かれている.岩波文庫には注もついていて,夏目は1876(明治9)年に市谷柳町の市谷学校第3級に転校したという.いずれにしろ,篠本は1863(文久3)年生まれで,1867(慶應3)年生まれの夏目より少し年上ということになる.篠本の家は「二百年も住みなれた牛込区甲良町」にあった.「余の家も信玄の旗本にて,勝頼天目山に生害せられし後,徳川家に降りて家臣となった」と書いている.篠本二郎は,江戸中期・後期の儒者で奥右筆であった篠本竹堂(1743−1809,『北槎異聞』の筆録者)の孫であったことがわかってきた.
二人ともなかなか腕白な幼少期を送った.篠本の文を読む限りでは,篠本の方が腕白だったようだ.篠本の「両親は余に英語学校に入学することを勧めた.然し当時英語学校は希望者多くして」,「外国語学校の仏語学に入学して,その間別に英語を修めて英語学校に入りて後,大学予備門に進んだ」.そして,「夏目君の如きも,後余と共に,図らず同じ熊本五高に教鞭を執り,中年以降顔を合わせる事になった」と書いている.熊本五高教師の前,篠本は何をしていたのだろうか.
傍 系
篠本は「初め東京帝大化学科に入り,化学を専攻したが,実験中負傷され退学し,明治17[1884]年改めて地質学科の聴講生となって,菊池 安について地質学および鉱物学を学んだ」と原田(1954)が書いている.東京大学理学部地質学教室卒業者名簿にはもちろん載っていないが,木下(1933a)にはもう少し詳しい略歴が載っている.1877(明治10)年東京大学予備門に入り,1881(明治14)年予備門を卒業して,東京大学理学部に入学し化学教室に進学する.1883(明治16)年5月に化学実験中負傷し退学した.1884(明治17)年5月に地質学及び鉱物学を自修し傍ら理科大学教授理学博士,菊池 安(1862-1894)に就き同学科を修む」と書いてある.現在あるような聴講生制度は当時なかったと思われるが,実質的に聴講生であったということであろうか.菊池 安は1883(明治16)年に東京大学を卒業したばかりであった.菊池は1894年に急死するが,そのあとに鉱物学教授となったのは神保小虎(1867-1924)であった.
篠本はその後教職に就き,富山,徳島,岩手,徳島,大分,長崎などと全国の学校を転々とする.1894(明治27)年,第五高等学校の講師を嘱託される.英語,地質,鉱物の教師だったので,明治27年に第五高等学校を去った小泉八雲の後任ということも考えられる.第五高等学校教授となるのは1897(明治30)年である.
鉱物研究
木下(1933a)によれば,篠本の論文は,1890年の大分からの玉滴石の報告に始まり,1917年の土佐のクローム鐵鑛論文まで122本ほどあるとのことだ.少なからぬ篠本の論文(1900,1904)は,神保とのあいだに執拗なまでの論争があったことをうかがわせる.神保小虎の祖父も奥右筆だったようで,篠本家と神保家の確執は2代前に遡るものであったのかもしれない.
篠本は論文を書くだけでなく,多くの鉱物を採集した.その鉱物についているラベルの研究から,篠本の標本が海外の標本商のところにわたっているという報告もあり,それゆえに国内での評価は冷たかったという話もある.また,大分県鯛生の素封家,田島勝太郎が熊本中学に在学中,夏季休暇の篠本による宿題として,採集した鉱石を提出したところ,篠本の鑑定によって良質の金鉱石であることが証明されたことがあった.田島が帰省して父,儀市に話し,儀市は当時金山を経営していた鹿児島県の事業家と共同で鯛生金山経営に乗り出したといわれている.
著書は,1899年に中川久和・篠本二郎・藤井健次郎・丘淺次郎の共著で『新体博物示教』を東京敬業社より発行したことが知られている.およそ100ページで,木版図52,石版図25が掲載されていて,40銭だった.篠本二郎が鉱物学,藤井健次郎が植物学,丘淺次郎が動物学を担当したと思われる.
熊本時代
夏目は1896(明治29)年第五高等学校英語教師となった.篠本が教授となったのは1年遅れである.宮永(2013)は,篠本は鉱物・地学・英語の教師で,「朝顔を洗わず,便所に行っても手を洗わなかった」と書いているが,真偽のほどは不明である.篠本は『五高時代の夏目君』を同じく漱石全集月報に書いているが,篠本本人のことは書いてない.夏目は熊本県で高額納税者であったが,篠本ははるかに給料が低かったと思われる.長い間嘱託であったし,学歴が選科生で終わっていた西田幾太郎(1870-1945)などと似たような待遇だったと考えられる.
桜島大正噴火
篠本が鹿児島にある第七高等学校の講師を嘱託されたのは1905(明治38)年であった.七高で,1914(大正3)年1月12日の桜島噴火に遭遇する.木下(1933b)は鹿児島新聞記者十余名協纂『大正三年櫻島大爆震記』をもとに小文を書いている.すなわち,「第七高等学校造士館講師篠本二郎先生は十日来の地震は火山性のものにして震源地は桜島にあり,近く何等かの現象を呈すべしと観測し,十二日払暁之に関する一文を草し,早朝鹿児島新聞に寄稿したり.右原稿未だ新聞に発表せられる暇なくして・・・」14日には「桜島爆発の順序は極めて規律正しく今後は決して憂うべきことなきを保証す」という意見を発表し,15日には,さらに小爆発を起こすかもしれないが,だんだんと落ち着き,津波をおこすこともないと1文を書き,16日の鹿児島新聞に掲載された.
この経過は柳川(1984)をはじめ多くの著書に引用されている.また,東京大学理学部地球惑星科学教室に保存されていた小藤文庫の引き出しに小藤の手帳とともに,桜島の噴火のスケッチがあり,それは篠本のスケッチと推定されている(岩松,2014).
没年
1916(大正5)年,篠本は第七高等学校を辞し,福岡に移り住んだ.鉱物研究は長く続けた.1933(昭和8)年2月に胃がんが発覚し,5月に亡くなった.木下の追悼文には「内に臓する熱烈なる意気と闘争心」ということばが見られる.傍系の地質学者として,篠本は激しい一生を生ききったのであろう.
謝辞
鉱物趣味のWEBサイトを運営されている澤田 操氏には,篠本二郎の自筆鉱物標本ラベルや戦前の伝記記事の紹介でお世話になったことを記して感謝申し上げます.
文献
原田準平,1954,明治以後の鉱物学界.地学雑誌,63(3),166-175.
岩松 暉,2014,資料に見る桜島噴火.地質学史懇話会会報,43,22-27.
木下龜城,1933a,篠本二郎先生を悼む.我等の礦物,2(7),207-214.
木下龜城,1933b,大正3年の桜島噴火と篠本二郎先生.我等の礦物,2(8),246-247.
宮永 孝,2013,五高の名物教授.社会志林,60(1),130-99.
著者なし(篠本二郎),1890,雑報 玉滴石.地学雑誌,2(18),294-295.
篠本二郎,1900,フリッチュ氏のライン鑛と神保氏のライン鑛に就て. 地質学雑誌,7,219-220.
篠本二郎,1904,越中國立山新湯産玉滴石の神保氏の説に就きて.地質学雑誌,11,414-416.
篠本二郎,1917,土佐のクローム鐵鑛.鑛業界,7(5),4.
柳川喜郎,1984,『桜島噴火記―住民ハ理論ニ信頼セズ』日本放送出版協会.
【geo-Flash】No.374 愛媛大会学会専用宿泊予約サイト:申込受付開始
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.374 2017/5/16┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[愛媛大会関連情報]学会専用宿泊予約サイト 申込受付開始
【2】[愛媛大会関連情報]演題登録:まもなく受付開始です
【3】日本地質学会第9回総会開催
【4】[125周年関連情報]お願い:会員氏名のローマ字表記について
【5】Island Arc:論文ワークショップ「アクセプトされる論文の書き方」
【6】2017年「地質の日」イベント情報
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】訃報 相原安津夫 名誉会員 ご逝去
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[愛媛大会関連情報]学会専用宿泊予約サイト 申込受付開始
──────────────────────────────────
松山市内では地質学会同期間中に医学系などの他学会,10月のえひめ国体の事
前行事の開催が予定されており,既に宿泊予約が大変混み合っています。
そのため地質学会では,旅行社を通じて宿泊施設の確保を進め,学会専用の宿
泊予約サイトを準備いたしました.ただ,松山市内だけでは難しいため,近郊
(奥道後,今治,西条など)にもエリアを拡げての確保も行っており,予約サ
イトでは今後も室数の追加補充を順次行って行く予定です.
確保される室数にも限りがあります.愛媛大会に参加予定の皆様におかれまし
ては,下記予約サイトなどもご利用いただき,各自,早めに交通手段の確保.
宿泊予約をされるようお勧め致します.
*学会専用宿泊予約サイト(外部サイト:東武トップツアーズ)
https://conv.toptour.co.jp/shop/evt/124th_JGS/
*ホテルリスト・価格はこちらから
https://conv.toptour.co.jp/2017/124th_JGS/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[愛媛大会関連情報]演題登録:まもなく受付開始です
──────────────────────────────────
第124年学術大会(愛媛大会:9/16〜9/18)のおもな申込スケジュールは以下の
ように予定しています.詳細は,ニュース誌5月号(5月末配布予定),HPでお
知らせします.今年は,9件のトピックセッションと25件のレギュラーセッショ
ン,およびアウトリーチセッションを用意します(シンポジウムは一般公募な
し).多くのお申込をお待ちしています!
【演題登録・要旨投稿】5月末〜7月5日(水)
【ランチョン・夜間集会】5月末〜6月29日(木)締切
【大会参加登録・巡検申込】6月初旬〜8月21日(月)締切
*大会サイトは,5月30日オープン予定です!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本地質学会第9回総会開催
──────────────────────────────────
日時:2017年5月20日(土)12:30〜13:30
会場:幕張メッセ 国際会議場 302
(千葉市美浜区中瀬 ※JpGU-AGU Joint Mettin2017会場内)
1. 定款20条により,本総会は役員ならびに代議員による総会となります.
代議員には,総会開催通知とともに総会に必要な資料等を別途お送りいたしま
す.ご都合で欠席される方は,定款28条第1項にもとづき,議決権行使書および
議決権の代理行使(委任状)などにより,総会に出席したものとして議決権を
行使することができます.
2.正会員は,総会に陪席することができます.ただし,総会規則12条3項によ
り,許可のない発言はできません.
議事次第は, http://www.geosociety.jp/outline/content0170.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[125周年関連情報]お願い:会員氏名のローマ字表記について
──────────────────────────────────
学会では来年の学会創立125周年を記念して,会員証(プラスチック製,カード
タイプ)を作成し,全会員に配布致します.これは,会員証としてだけでなく,
学術大会など会合での名札としても活用できるように企画しています.
会員証に印字する会員氏名は,日本語とローマ字を併記します.ローマ字表記
は,基本的には入会申込書に記載されたものを用いますが,あらためてご登録
頂ければ,そちらを採用致します.ローマ字の表記方法には複数あるものもあ
ります.
*********************************************************
あらためてローマ字表記の登録を希望される方は,手続きをお願いします.
*********************************************************
1)メール,FAXもしくは郵送で,下記の内容を学会事務局宛にお知らせ下さい.
会員氏名・所属(もしくは住所)・希望するローマ字表記
2)申込期限:2017年6月30日(金)
3)宛先は以下のとおりです.
メール: main@geosociety.jp,FAX:03-5823-1156
郵送:〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F
(表記方法が複数ある例)
ち(CHI・TI),じ(JI・ZI),けんいち(Kenichi・Ken-ichi),
たろう(Taro・Tarou),おおた(OTA・OHTA・OOTA)など
特にご希望の無い場合(入会申込書に記載されたローマ字表記で良い方)は,
事務局への連絡は不要です.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】Island Arc:論文ワークショップ「アクセプトされる論文の書き方」
──────────────────────────────────
論文の質を高め,スムーズに採択・出版されるためには,正しい論文構成法の
理解が欠かせません.このワークショップでは,国際的な英文誌である日本地
質学会機関誌 Island ArcのEditor-in-Chiefを務める武藤先生より,論文構成
上のポイントについてアドバイスをいただきます.
日時:5月22日(月)12:30〜13:30
会場:幕張メッセ国際会議場 201B
対象:英文誌への投稿に関心のある若手研究者
講師:武藤鉄司(Island Arc誌 編集委員長)
・講演は日本語で行われます
・希望者にに昼食をご提供(先着50名様・要事前登録)
・当日参加も可能.スムーズにご入場いただくために事前登録をお勧めします.
http://www.jpgu.org/meeting_2017/seminar.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】2017年「地質の日」イベント情報
──────────────────────────────────
学会関連(主催,共催,後援など)の地質のイベント情報をお知らせします.
この他の行事の予定も,学会HPに随時追加していきます.
http://www.geosociety.jp/name/content0155.html
[本部行事]
■第8回惑星地球フォトコンテストほか入選作品展示会
6月10日(土)14:00頃〜24日(土)12:00頃
場所:銀座プロムナードギャラリー(中央区銀座 東銀座地下歩道壁面)
[北海道支部]
■地質の日記念展示「北海道のジオサイトに見る化石」
4月28日(金)〜 6月18日(日)
会場:北海道大学総合博物館1 階企画展示室 【入場無料】
市民セミナー:
5月20日(土)「北海道ジオサイト107への旅に出て」
6月4日(日)「ジオサイトとしての札幌の魅力」
市民巡検:
6月10日(土)「ジオサイト『藻岩山』を歩く」
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[中部支部]
■長岡市立科学博物館:特別展/企画展
ミニ企画展:パラサウロロフスの下顎化石(レプリカ)
5月10日(水)〜6月4日(日)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/name/content0155.html#chubu
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[北海道支部]
■平成29年度例会(個人講演会)
6月17日(土)10:00〜18:00(時間は予定)
場所:北海道大学理学部5号館大講堂(5-203)
*講演申込締切:5月26日(金)
*講演要旨の提出締切:6月7日(水)
■2017年春巡検「札幌の失われた川を歩く」
6月18日(日)9:00〜17:00
巡検先:札幌市内(北海道大学(南側)〜北海道大学植物園〜札幌市立中央中
学校(北4条東3丁目)付近を歩きます)
案内者:宮坂省吾(川の案内人)・内山幸二(石の案内人)・土屋 篁(「ビ
ルの岩石学」執筆)
*参加申込締切:6月11日(日)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[中部支部]
■2017年支部年会
6月17日(土)
会場:新潟県糸魚川市フォッサマグナミュージアム
シンポジウム,個人講演,懇親会ほか
シンポジウム「地質学とジオパーク −現状と今後の課題―」
*参加申込締切:6月2日(金)
ただし,シンポ講演申込は5月26日(金)まで
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
[関東支部]
■清澄フィールドキャンプ 参加者募集
8月21日(月)〜26日(土)
場所:東京大学千葉演習林(千葉県鴨川市清澄)
費用:30,000〜40,000円程度(暫定額:宿泊・食事・保険・現地での交通費込.
参加者属性によって多少変動します)
*参加申込締切:7月7日(金)(*応募書類は所定の書式を使用のこと)
■地学教育・アウトリーチ巡検「火山灰を追跡する-浅間火山の噴出物と噴火史」
8月7日(月)〜8日(火)1泊2日
対象:教育関係者および地学に興味のある一般の方(非会員も参加可)
講師:大石雅之(立正大学地球環境科学部)
募集:20人(先着順 *申込期間 6月1日〜7月10日)
詳しくは, http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■(後)特別展:石は地球のワンダー〜鉱物と化石に魅せられた2人のコレクション
4月22日(土)〜6月4日(日)
場所:大阪市立自然史博物館
*「47都道府県の石(岩石・鉱物・化石)」展を同時開催
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
■JpGU-AGU Joint Meeting 2017
5月20日(土)〜25日(木)
会場:千葉県 幕張メッセ
http://www.jpgu.org/meeting_2017/
■第198回地質汚染イブニングセミナー
5月26日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:楡井 久(NPO日本地質汚染審査機構理事長)
テーマ:国民が学んだ教訓―東京豊洲新市場の地質汚染問題と液状化-流動化・
地波問題からー
http://www.npo-geopol.or.jp
■第2回若手科学者サミット
6月2日(金)13:30〜18:00
場所:日本学術会議 講堂(港区六本木)
*口頭・ポスター発表者・パネリスト若干名:募集(5/17締切)
http://www.geosociety.jp/outline/content0096.html
■第5回堆積実験オープンスクール
6月4日(日)10:00 〜 16:00(予定)
場所:京都大学理学部1号館
対象:学部3-4回生 参加費無料
*参加申込締切:6月1日(木)
http://goo.gl/mKuxoO
■原子力総合シンポジウム2017
6月8日(木) 13:00〜17:10
会場:日本学術会議講堂(港区六本木 7-22-34)
http://www.aesj.net/
■石油技術協会平成29年度春季講演会
6月14日(水)〜15日(木)
場所:国立オリンピック記念青少年総合センター(東京)
http://www.japt.org/
■(共)第54回アイソトープ・放射線研究発表会
7月5日(水)〜7日(金)
場所:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
http://www.jrias.or.jp/
■(後)「青少年のための科学の祭典」2017全国大会
7月29日(土)〜30日(日)
会場:科学技術館(千代田区北の丸公園2-1)
http://www.kagakunosaiten.jp/
■(後)科学教育研究協議会第64回全国研究大会
8月7日(月)〜9日(水)
場所:広島なぎさ中学高等学校(広島市佐伯区)
http://kakyokyo.main.jp/
■(共)2017年度日本地球化学会第64回年会
9月13日(水)〜15日(金)
会場:東京工業大学・大岡山キャンパス
講演申込:6月13日(火)〜7月13日(木)14時締切
http://www.geochem.jp/meeting/index.html
■(共)第61回粘土科学討論会
9月25日(月)〜 27日(水)
会場:富山大学 五福キャンパス共通教育棟
http://www.cssj2.org/
■(後)第4回Slope tectonics 2017
10月14日(土)〜18日(水)
場所:京都大学宇治キャンパス黄檗プラザ
http://www.slope.dpri.kyoto-u.ac.jp/SlopeTectonics2017/st2017.html
■(共)第15回国際放散虫研究集会(15th InterRad)
10月23日(月)〜27日(金)研究集会
20日(金)〜22日(日)プレ巡検
22日(日)サイエンスカフェ
28日(土)〜31日(火)ポスト巡検
要旨締切:6月15日(木)
会場:新潟大学など
http://interrad2017.random-walk.org/
■IGCP608「白亜紀アジア−西太平洋生態系」第5回国際研究集会
大韓地質学会70周年記念シンポジウムと共催
10月26日(木)〜27日(金)(研究集会:韓国・済州島)
23日(月)〜25日(水)(プレ巡検:韓半島南西部白亜系)
会場:済州国際コンベンションセンター
http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/
■第71回日本人類学会大会
11月3日(金)〜5日(日)
会場:東京大学本郷キャンパス
講演申込締切:8月21日(月)
http://anthrop-meeting.sakura.ne.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・JAMSTEC海底資源研究開発センター資源成因研究G技術支援職公募(6/30)
・東北大学理学研究科地学専攻
---生命起源地球科学 准教授公募1名(7/14)
---火山物質科学 准教授公募1名(7/14)
---隕石学,惑星科学 講師公募1名(7/14)
・福井県立恐竜博物館 研究職員(古生物学)募集(6/2)
・弘前大学教育研究院自然科学系安全システム工学領域(岩石・鉱物学)教授公募(8/18)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】訃報 相原安津夫 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
相原安津夫 名誉会員(九州大学名誉教授)が,平成29年4月30日にご逝去され
ました(享年87歳).
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます.
なお,ご葬儀等は既に近親者のみで執り行われたとのことです.
会長 渡部 芳夫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.375(臨時)愛媛大会演題登録受付開始
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.375 2017/5/31┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
[愛媛大会関連情報]
【1】愛媛大会の演題登録受付を開始しました(7/5締切)
【2】ランチョン・夜間小集会:受付中
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】愛媛大会の演題登録受付を開始しました(7/5締切)
──────────────────────────────────
第124年学術大会(愛媛大会:9/16〜9/18)の演題登録受付を5/31(水)
より開始しました.お申込をお待ちしています.
************************************************
重要:まずは,演題登録専用のアカウント登録を!
************************************************
まず,愛媛大会演題登録専用のアカウント登録が必要です(1つのアカウントで
複数の演題登録が可能です).
締切まで何度でも要旨や登録内容を修正することができますので,まずはアカ
ウント登録を行い,締切までに演題登録を完了させましょう!
おもな締切
【演題登録・要旨投稿】7月5日(水)18:00(WEB)締切
【ランチョン夜間集会申込】6 月29日(木)締切
【大会参加・巡検等申込】8月21日(月)締切(まもなく受付開始予定)
演題登録はこちらから
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/collectsubject
愛媛大会HPもオープンしました。
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/top?eventCode=geosocjp124
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】ランチョン・夜間小集会:受付中(6/29締切)
──────────────────────────────────
会合開催をご希望の場合は,期日までに忘れずに行事委員会宛にお申し込み下さい。
今年もランチョンは大会初日(9/16)より開催可能です。
ランチョン,夜間集会のお申込はこちらから
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/meeting
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.377 愛媛大会演題登録:まずはアカウント登録を!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.377 2017/6/20┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
[愛媛大会情報]
【1】事前参加登録:受付中
【2】まずは演題登録専用のアカウント登録を!
【3】ランチョン・夜間小集会:受付中
【4】おもな申込締切
-----------------------------------------------------
【5】2017年度会費督促請求について
【6】[125周年関連情報]寄付のお願い
【7】[125周年関連情報]お願い:会員氏名のローマ字表記について
【8】フォトコンテスト入選作品展示会(in 銀座)開催中
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[愛媛大会情報]事前参加登録:受付中
──────────────────────────────────
事前参加登録の受付中です.参加登録に関わるお申込(参加,要旨集,巡検,
懇親会,弁当)は,オンラインによる大会専用参加登録システム(会員・非会
員にかかわらずどなたでも申込可)をご利用の上,お申し込み下さい.
*事前参加登録締切:8月21日(木)18時(WEB)*
お申込はこちら
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/sanka
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[愛媛大会情報]まずは演題登録専用のアカウント登録を!
──────────────────────────────────
********************************************
<重要>まずは,演題登録専用のアカウント登録を!
********************************************
第124年学術大会の演題登録受付中です.まず,愛媛大会演題登録専用のアカウ
ント登録が必要です(1つのアカウントで複数の演題登録が可能です).
締切まで何度でも要旨や登録内容を修正することができますので,まずはアカ
ウント登録を行い,締切までに演題登録を完了させましょう!
会員・非会員にかかわらずどなたでも画面入力は可能です.
******************************
演題登録・要旨投稿締切:7月5日(水)
******************************
アカウント登録および演題登録はこちらから
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/collectsubject
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[愛媛大会情報]ランチョン・夜間小集会:受付中
──────────────────────────────────
会合開催をご希望の場合は,期日までに忘れずに行事委員会宛にお申し込み下
さい。今年もランチョンは大会初日(9/16)より開催可能です.
例年開催されている会合等は,忘れずにお申し込み下さい.
******************************************
ランチョン・夜間集会申込締切:6月29日(木)
******************************************
お申込はこちらから
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/meeting
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[愛媛大会情報]主な申込締切
──────────────────────────────────
【演題登録・要旨投稿】7月5日(水)
【大会参加登録・巡検申込】8月21日(月)締切
【ランチョン・夜間集会】6月29日(木)締切
【小さなEarth Scientistのつどい参加】7月14日(金)
愛媛大会HPはこちらから
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2017年度会費督促請求について
──────────────────────────────────
1)督促請求のための自動引き落とし日は,6月23日(金)です.
2017年度会費が未入金のかたで,5月上旬までの間に自動引落の手続きをされた
かたは6月23日に引き落としがかかります.引き落とし不備にならぬよう,残高
の確認をお願いします.
2)郵便振替用紙によるお振り込みの方には,6月16日に督促請求書(郵便振替
用紙)を郵送しました.お手元に届きましたら,早急にご送金くださいますよ
うお願いいたします.
※ 7月上旬頃までに入金確認が取れない場合には,7月号の雑誌から送本停止と
なります.定期的に雑誌をお受け取りになりたい方は,お早めにご送金くださ
いますよう,よろしくお願いいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[125周年関連情報]寄付受付中!(クレジットカードも可)
──────────────────────────────────
125周年記念事業として,2018年5月東京での記念式典をはじめ,様々な事
業を計画しています.また,それら記念事業を実行するため,学会員や賛助会
員,さらには関連諸団体に寄付をお願いしております.
*醵金者一覧(6月6日現在)
http://www.geosociety.jp/125th/content0014.html
*記念事業に対する寄付のお願い
クレジットカード(VISA, Master, Diners)もご利用いただけます
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html#kifu
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】[125周年関連情報]お願い:会員氏名のローマ字表記について
──────────────────────────────────
学会では来年の学会創立125周年を記念して,会員証(プラスチック製,カード
タイプ)を作成し,全会員に配布致します.これは,会員証としてだけでなく,
学術大会など会合での名札としても活用できるように企画しています.
会員証に印字する会員氏名は,日本語とローマ字を併記します.ローマ字表記
は,基本的には入会申込書に記載されたものを用いますが,あらためてご登録
頂ければ,そちらを採用致します.
********************************************************
あらためてローマ字表記の登録を希望される方は,手続きをお願いします.
********************************************************
1)メール,FAXもしくは郵送で,下記の内容を学会事務局宛にお知らせ下さい.
会員氏名・所属(もしくは住所)・希望するローマ字表記
2)申込期限:2017年6月30日(金)
3)宛先は以下のとおりです.
メール: main@geosociety.jp,FAX:03-5823-1156
郵送:〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F
特にご希望の無い場合(入会申込書に記載されたローマ字表記で良い方)は,
事務局への連絡は不要です.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】フォトコンテスト入選作品展示会(in 銀座)開催中
──────────────────────────────────
第8回惑星地球フォトコンテストほか入選作品展示会
開催中〜6月24日(土)12:00頃まで
場所:銀座プロムナードギャラリー(中央区銀座 東銀座地下歩道壁面)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0023.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■清澄フィールドキャンプ
8月21日(月)〜26日(土)
場所:東京大学千葉演習林(千葉県鴨川市清澄)
費用:30,000円(学生),40,000円(社会人)程度を予定
*参加申込締切:7月7日(金)
■地学教育・アウトリーチ巡検
「火山灰を追跡する–浅間火山の噴出物と噴火史」
8月7日(月)〜8日(火)1泊2日
対象:教育関係者および地学に興味のある一般の方(非会員も参加可)
費用:20,000円
講師:大石雅之(立正大学地球環境科学部)
募集:20人(先着順)
*申込期間: 6月1日(木)〜7月10日(月)
詳しくは, http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■道総研・地質研究所ニュース
十勝岳内部構造の解明と火山活動度評価 ほか
https://www.hro.or.jp/list/environmental/research/gsh/publication/gshnews/gshnews02/index.html
*************(以下,関連団体の行事案内です)****************
■第199回地質汚染イブニングセミナー
6月30日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:村瀬 誠(東邦大学薬学部客員教授)
テーマ:雨水利用と水循環について(仮)
http://www.npo-geopol.or.jp
■(共)第54回アイソトープ・放射線研究発表会
7月5日(水)〜7日(金)
場所:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
http://www.jrias.or.jp/
■明治大学危機管理研究センター第38回定例研究会
7月12日(水)18:30〜20:00
場所:明治大学駿河台キャンパス アカデミーコモン9階(参加無料)
テーマ:「大規模災害後の復興プロセスにおける課題:報道の視点から」
講師:五十嵐和大(毎日新聞社 科学環境部)・松本浩司(NHK解説主幹)
http://www.jemaweb.org/news.html#20170613
■特別展「恐竜の卵〜恐竜誕生に秘められた謎〜」
7月14日(金)〜10月15日(日)
場所:福井県立恐竜博物館
博物館セミナー「恐竜の卵と巣のなぞ」:7月16日(日)
http://www.dinosaur.pref.fukui.jp/
■特別展「地球を『はぎ取る』〜地層が伝える大地の記憶〜」
7月15日(土)〜11月5日(日)
場所:神奈川県立生命の星・地球博物館
http://nh.kanagawa-museum.jp
■(後)「青少年のための科学の祭典」2017全国大会
7月29日(土)〜30日(日)
会場:科学技術館(千代田区北の丸公園2-1)
http://www.kagakunosaiten.jp/
■(後)科学教育研究協議会第64回全国研究大会
8月7日(月)〜9日(水)
場所:広島なぎさ中学高等学校(広島市佐伯区)
http://kakyokyo.main.jp/
■(共)2017年度日本地球化学会第64回年会
9月13日(水)〜15日(金)
会場:東京工業大学・大岡山キャンパス
講演申込:7月13日(木)14時締切(注)締切延長なし
参加申込:8月21日(月)17時締切
http://www.geochem.jp/conf/2017/
■第34回歴史地震研究会(つくば大会)
9月15日(金)〜17日(日)
場所:つくばイノベーションプラザ(TXつくば駅徒歩3分)
プログラム公開しました
http://sakuya.ed.shizuoka.ac.jp/rzisin/menu7.html
■(共)第61回粘土科学討論会
9月25日(月)〜 27日(水)
会場:富山大学 五福キャンパス共通教育棟
http://www.cssj2.org/
■(後)第4回Slope tectonics 2017
10月14日(土)〜18日(水)
場所:京都大学宇治キャンパス黄檗プラザ
http://www.slope.dpri.kyoto-u.ac.jp/SlopeTectonics2017/st2017.html
■テクノブリッジフェアフェア in つくば 2017
10月19日(木)〜20日(金)
場所:産総研つくばセンター
産総研では企業との連携強化のための活動(テクノブリッジ事業)を推進して
おり,その一環として,毎年,社会人を対象に産総研の研究を紹介するテク
ノブリッジフェアを開催しています(完全招待制).サイトにご登録いただく
と,フェアを元にした研究カタログと,昨年のフェアでご紹介した様々な研究
テーマをご覧いただけます.さらに今年のフェアにご招待します.
http://technobridge.aist.go.jp
■(共)第15回国際放散虫研究集会(15th InterRad)
10月23日(月)〜27日(金)研究集会
20日(金)〜22日(日)プレ巡検
22日(日)サイエンスカフェ
28日(土)〜31日(火)ポスト巡検
会場:新潟大学など
http://interrad2017.random-walk.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・日本学術会議平成29年度日本カナダ女性研究者交流:派遣者募集(7/10)
・弘前大学地域イノベーション学系戦略的融合領域(北日本新エネルギー研究
所エネルギー材料工学)教授公募(9/22)
・九州大学総合研究博物館開示研究系助教(地質学・古生物学)公募(8/7)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.378(臨時)愛媛大会:宿泊希望者募集【学生限定】
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.378 2017/6/26┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
[愛媛大会情報]
【1】宿泊希望者募集【学生限定】
【2】その他の宿泊情報
【3】まずは演題登録専用のアカウント登録を!
【4】おもな申込締切
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】宿泊希望者募集【学生限定】
──────────────────────────────────
これまでお知らせの通り,松山市内では地質学会同期間中に医学系などの他
学会,10月のえひめ国体の事前行事の開催が予定されており,既に宿泊予約が
大変混み合っています.そのため学会では,旅行社を通じて宿泊施設の確保を
進め,学会専用の宿泊予約サイトするなど対処していますが,これに加えて,
学生・院生限定で下記の通り,宿泊希望者を募集します.
対象:愛媛大会に参加する地質学会会員の学生・院生
宿泊先:松山市内のホテル等(複数の宿泊施設を確保しています.いずれも愛
媛大学まで徒歩圏内です)
部屋タイプ例:
・大部屋ドミトリー(24名大部屋,2段ベット,布団付)
・和室10人部屋(布団付)
・和室3人部屋(布団付)
・洋室(シングル)
・洋室(ツイン)
宿泊可能人数(名):各日とも最大52名
料金:素泊まり 2,000〜3,000円/泊 程度(宿泊施設,部屋タイプにより料金
は異なります)
宿泊の確定・支払方法:申込後,宿泊可否の通知をお送りします.宿泊確定者
には宿泊施設の情報と費用や支払方法等についてお知らせします.
注意事項:
(注1)宿泊施設,部屋タイプの選択はできません.申込順によって男女別に自
動的に割り振ります.
(注2)洋室(シングル)以外は,すべての部屋が相部屋となります.
申込方法:大会WEBサイトから専用フォームにお入りいただきお申込下さい
(定員になり次第締切)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/hotel
ご不明な点は,学会事務局までお問い合わせ下さい。
TEL 03-5823-1150 メール: main@geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】その他の宿泊情報
──────────────────────────────────
学会専用の宿泊予約サイトには掲載されていませんが,会場近隣には下記のよ
うな宿泊施設もあります(学生限定ではありません。
これらの施設に対しては,学会では仲介・斡旋は行っておりませんので,直接
ホテルに電話で空き状況を確認して下さい.
・ホテル泰平(松山市平和通3-1-15)
電話:089-943-5000 料金:シングル4,400円より
http://www.hoteltaihei.co.jp/
・ホテル泰平別館(松山市平和通3-1-34)
電話:089-921-3515 料金:シングル3,960円より
http://www.hoteltaihei.co.jp/bekkan/
・ビジネスホテルレインボー(松山市枝松6-10-6)(全28室)
電話:089-947-5400 料金:シングル3,670円より
http://hotelrainbow.info/
・フリーデイズ イン 横河原(東温市横河原189)(全12室)
電話:089-990-1177 料金:シングル5,000円より
http://www.freedays.jp/yokogawara/
**学会専用の宿泊予約サイトもご利用下さい**
https://conv.toptour.co.jp/shop/evt/124th_JGS/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】まずは演題登録専用のアカウント登録を!
──────────────────────────────────
第124年学術大会の演題登録受付中です.まず,愛媛大会演題登録専用のアカウ
ント登録が必要です(1つのアカウントで複数の演題登録が可能です).
締切まで何度でも要旨や登録内容を修正することができますので,まずはアカ
ウント登録を行い,締切までに演題登録を完了させましょう!
会員・非会員にかかわらずどなたでも画面入力は可能です.
入会申込中でも,会員番号がわからなくても,演題登録・要旨投稿の手続きは
可能です.
**演題登録・要旨投稿締切:7月5日(水)**
アカウント登録および演題登録はこちらから
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/collectsubject
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】おもな申込締切
──────────────────────────────────
【演題登録・要旨投稿】7月5日(水)
【大会参加登録・巡検申込】8月21日(月)締切
【ランチョン・夜間集会】6月29日(木)締切
【小さなEarth Scientistのつどい参加】7月14日(金)
愛媛大会HPはこちらから
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.379(臨時)愛媛大会:演題登録締切まで残り5日!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.379 2017/6/30┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
[愛媛大会:臨時号]
【1】演題登録締切まで残り5日! 7月5日(水)18時締切
【2】宿泊希望者募集中【学生限定】
【3】事前参加登録:受付中
【4】おもな申込締切
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】演題登録締切まで残り5日! 7月5日(水)18時締切
──────────────────────────────────
愛媛大会の演題登録・要旨投稿は,7月5日(水)18時締切(WEB)です.
締切の延長はありません.くれぐれもご注意下さい.
締切間近に近づくと申込が集中しますので,できるだけ余裕をもってお手続き
下さい.今年もたくさんのお申込をお待ちしています.
アカウント登録および演題登録はこちらから
(非会員でも入会申込中でも画面入力は可能です)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/collectsubject
*******************************************************
<注意>まずは,演題登録専用のアカウント登録を!
*******************************************************
まずは,愛媛大会演題登録専用のアカウント登録が必要です(1つのアカウント
で複数の演題登録が可能です).締切まで何度でも要旨や登録内容を修正する
ことができます.まずはアカウント登録を行い,締切までに演題登録を完了さ
せましょう!会員・非会員にかかわらずどなたでも画面入力は可能です.
大会Q&A【演題登録編】もご参照ください.
http://www.geosociety.jp/science/content0087.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】宿泊希望者募集中【学生限定】
──────────────────────────────────
対象:愛媛大会に参加する地質学会会員の学生・院生
宿泊先:松山市内のホテル等(複数の宿泊施設を確保しています.いずれも愛
媛大学まで徒歩圏内です)
部屋タイプ例:
・大部屋ドミトリー(24名大部屋,2段ベット,布団付)
・和室10人部屋(布団付)
・和室3人部屋(布団付) など
宿泊可能人数(名):各日とも最大52名
料金:素泊まり 2,000〜3,000円/泊 程度
(宿泊施設,部屋タイプにより料金は異なります)
宿泊の確定・支払方法:申込後,宿泊可否の通知をお送りします(数日以内).
宿泊確定者には後日,宿泊施設の情報と費用や支払方法等についてお知らせし
ます.
申込方法:大会WEBサイトから専用フォームにお入りいただきお申込下さい
(定員になり次第締切)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/hotel
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】事前参加登録:受付中
──────────────────────────────────
参加登録に関わるお申込(参加,要旨集,巡検,懇親会,弁当)は,オンライ
ンによる大会専用参加登録システム(会員・非会員にかかわらずどなたでも画
面入力可)をご利用の上,お申し込み下さい.
*事前参加登録締切:8月21日(月)18時(WEB)*
お申込はこちら
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/sanka
大会Q&A【参加登録編】もご参照ください
http://www.geosociety.jp/science/content0087.html#sanka
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】おもな申込締切
──────────────────────────────────
【演題登録・要旨投稿】7月5日(水)18時
【大会参加登録・巡検申込】8月21日(月)18時
【小さなEarth Scientistのつどい参加校募集】7月14日(金)
【ランチョン・夜間集会 会合受付】締切ました
愛媛大会HPはこちらから
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.381(臨時)平成29年九州北部豪雨に関して
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.381 2017/7/11┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】平成29年 九州北部豪雨に関して
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】平成29年 九州北部豪雨に関して
──────────────────────────────────
7月5日より,九州北部地方を中心に大規模な豪雨と斜面災害が発生し,各地に
甚大な被害をもたらしています.被害に遭われた方々へお見舞いを申し上げま
すとともに,亡くなられた方々への哀悼の意を表します.
【安否確認のお願い】
一部の会員からは,既に安否のご報告をいただいてもおります.大変な状況と
は存じますが,落ち着かれましたら安否確認にご協力をお願い申し上げます.
ご連絡は地質学会事務局 main@geosociety.jp までお願いいたします.特に罹
災会員については、ご自身だけでなく,周囲の会員の方の安否についてもご存
知の範囲内で以下の連絡先にご連絡いただければ幸いです.
学会事務局
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル6F
電話:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156
e-mail:main@geosociety.jp
【緊急調査のお願い】
地質災害の原因究明は将来の減災につながる重要な活動です.既に現地調査を
開始もしくは検討している会員の皆様もおられると思います.調査にかかる会
員の皆様の安全,そして調査の情報共有のためにも,緊急調査を計画されてお
られる方は地質学会事務局にご連絡をお願いいたします.被災地では救命およ
び行方不明者の捜索活動が行われておりますので,被災地への配慮を引き続き
お願いいたします.
地質災害緊急調査について
http://www.geosociety.jp/hazard/content0024.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.380 愛媛大会演題登録:明日(7/5)18時締切です!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.380 2017/7/4┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
[愛媛大会情報]
【1】演題登録:明日(7/5)18時締切です!
【2】宿泊希望者募集中【学生限定】
【3】事前参加登録:受付中
【4】おもな申込締切
---------------------------------------------------------------
【5】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【6】お知らせ:NHKスペシャル シリーズ 列島誕生 ジオ・ジャパン
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[愛媛大会情報]演題登録:明日(7/5)18時締切です!
──────────────────────────────────
愛媛大会演題登録・要旨投稿は,7月5日(水)18時締切(WEB)です.
締切の延長はありません.くれぐれもご注意下さい.
締切時間に近づくと申込が集中しますので,できるだけ余裕をもってお手続き
下さい.今年もたくさんのお申込をお待ちしています.
アカウント登録および演題登録はこちらから
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/collectsubject
**************************************************************
<注意>まずは,演題登録専用のアカウント登録を!
**************************************************************
まずは,愛媛大会演題登録専用のアカウント登録が必要です(1つのアカウント
で複数の演題登録が可能です).締切まで何度でも要旨や登録内容を修正する
ことができます.まずはアカウント登録を行い,締切までに演題登録を完了さ
せましょう!会員・非会員にかかわらずどなたでも画面入力は可能です.
大会Q&A【演題登録編】もご参照ください.
http://www.geosociety.jp/science/content0087.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[愛媛大会情報]宿泊希望者募集中【学生限定】
──────────────────────────────────
対象:愛媛大会に参加する地質学会会員の学生・院生
宿泊先:松山市内のホテル等(複数の宿泊施設を確保しています.いずれも愛
媛大学まで徒歩圏内です)
部屋タイプ例:
・大部屋ドミトリー(24名大部屋,2段ベット,布団付)
・和室10人部屋(布団付)
・和室3人部屋(布団付) など
宿泊可能人数(名):各日とも最大52名
料金:素泊まり 2,000〜3,000円/泊 程度
(宿泊施設,部屋タイプにより料金は異なります)
宿泊の確定・支払方法:申込後,宿泊可否の通知をお送りします(数日以内).
宿泊確定者には宿泊施設の情報と費用や支払方法等についてお知らせします.
申込方法:大会WEBサイトから専用フォームにお入りいただきお申込下さい
(定員になり次第締切)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/hotel
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[愛媛大会情報]事前参加登録:受付中
──────────────────────────────────
事前参加登録の受付を開始しました.参加登録に関わるお申込(参加,要旨集,
巡検,懇親会,弁当)は,オンラインによる大会専用参加登録システム(会員・
非会員にかかわらずどなたでも申込可)をご利用の上,お申し込み下さい.
*事前参加登録締切:8月21日(月)18時(WEB)*
お申込はこちら
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/sanka
大会Q&A【参加登録編】もご参照ください
http://www.geosociety.jp/science/content0087.html#sanka
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[愛媛大会情報]主な申込締切
──────────────────────────────────
【演題登録・要旨投稿】7月5日(水)
【大会参加登録・巡検申込】8月21日(月)締切
【ランチョン・夜間集会 会合受付】締切ました
【小さなEarth Scientistのつどい参加】7月14日(金)
愛媛大会HPはこちらから
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[125周年関連情報]寄付受付中!(クレジットカードも可)
──────────────────────────────────
125周年記念事業として,2018年5月東京での記念式典をはじめ,様々な事
業を計画しています.また,それら記念事業を実行するため,学会員や賛助会
員,さらには関連諸団体に寄付をお願いしております.
*醵金者一覧
http://www.geosociety.jp/125th/content0014.html
*記念事業に対する寄付のお願い
クレジットカード(VISA, Master, Diners)もご利用いただけます
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html#kifu
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】お知らせ:NHKスペシャル シリーズ 列島誕生 ジオ・ジャパン
──────────────────────────────────
NHKの大型特別番組であるNHKスペシャルでは,特に自然環境関係のテーマが幅
広く選別されていて,ごく新しいものの考え方や見方をとても上手く,一人の
科学少年から居間の家族3代までに分かりやすい構成と画面で放送されて来た
と感じています.今週末に「NHKスペシャル シリーズ 列島誕生 ジオ・ジャパ
ン」が放送予定と掲示さましたが,制作担当者の方が何年も地質学会年会に取
材に来られており,ストーリーには内外の地球科学研究者が関わっており,特
に地質学会員の協力も大きいとうかがいました.非常に期待しています.地質
学研究成果のアウトリーチの一つの形として,是非参考にしたいと思います.
(産業技術総合研究所 渡部芳夫)
http://www6.nhk.or.jp/special/detail/index.html?aid=20170709
NHKスペシャル シリーズ 列島誕生 ジオ・ジャパン
第1集 奇跡の島はこうして生まれた
(本放送)7月9日(日)21:00-21:49
(再放送)7月26日(水)00:10-00:59
第2集 奇跡の島は山国となった
(本放送)7月23日(日)21:00-21:49
(再放送)7月27日(木)01:00-01:49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■清澄フィールドキャンプ
8月21日(月)〜26日(土)
場所:東京大学千葉演習林(千葉県鴨川市清澄)
費用:30,000円(学生),40,000円(社会人)程度を予定
*参加申込締切:7月7日(金)
■地学教育・アウトリーチ巡検「火山灰を追跡する–浅間火山の噴出物と噴火史」
8月7日(月)〜8日(火)1泊2日
対象:教育関係者および地学に興味のある一般の方(非会員も参加可)
費用:20,000円
講師:大石雅之(立正大学地球環境科学部)
募集:20人(先着順)
*申込期間: 6月1日(木)〜7月10日(月)
詳しくは,http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地質地盤情報の活用と法整備を考える会
国土交通省の第3回「地下空間の利活用に関する安全技術の確立に関する小委員
会」の資料が公開されました.ほか
http://www.geo-houseibi.jp/
*************(以下,関連団体の行事案内です)****************
■(共)第54回アイソトープ・放射線研究発表会
7月5日(水)〜7日(金)
場所:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
http://www.jrias.or.jp/
■第1回シンポジウム 水循環の恩恵と千葉県
(NPO法人日本地質汚染審査機構イブニングセミナー200回記念協賛事業)
7月22日(土)13:00〜17:00
場所:明海大学 浦安キャンパス
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
■(後)「青少年のための科学の祭典」2017全国大会
7月29日(土)〜30日(日)
会場:科学技術館(千代田区北の丸公園2-1)
http://www.kagakunosaiten.jp/
■(後)科学教育研究協議会第64回全国研究大会
8月7日(月)〜9日(水)
場所:広島なぎさ中学高等学校(広島市佐伯区)
http://kakyokyo.main.jp/
■(共)2017年度日本地球化学会第64回年会
9月13日(水)〜15日(金)
会場:東京工業大学・大岡山キャンパス
講演申込:7月13日(木)14時締切(注)締切延長なし
参加申込:8月21日(月)17時締切
http://www.geochem.jp/conf/2017/
■(共)第61回粘土科学討論会
9月25日(月)〜 27日(水)
会場:富山大学 五福キャンパス共通教育棟
http://www.cssj2.org/
■第20回水環境学会シンポジウム
9月26日(火)〜28日(木)
場所:和歌山大学
特別講演会「紀の川の水環境」
http://www.jswe.or.jp/event/symposium/
■(後)第4回Slope tectonics 2017
10月14日(土)〜18日(水)
場所:京都大学宇治キャンパス黄檗プラザ
http://www.slope.dpri.kyoto-u.ac.jp/SlopeTectonics2017/st2017.html
■(共)第15回国際放散虫研究集会(15th InterRad)
10月23日(月)〜27日(金)研究集会
20日(金)〜22日(日)プレ巡検
22日(日)サイエンスカフェ
28日(土)〜31日(火)ポスト巡検
会場:新潟大学など
http://interrad2017.random-walk.org/
■防災推進国民大会2017
11月26日(日)〜27日(月)
会場:仙台国際センター(仙台市青葉区青葉山)
http://bosai-kokutai.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・岡山理科大学生物地球学部(恐竜・古生物学)講師または助教募集(9/8)
・東京大学大気海洋研究所特任助教公募(7/31)
・農林水産省経験者採用試験(係長級(技術))(8/4-17)
・藤原ナチュラルヒストリー振興財団学術研究助成(9/1)
・第39回(平成29年)沖縄研究奨励賞推薦応募(学会締切 9/11)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
125記念トリビア9 吾妻山爆発にともなう地質学者の殉難
〜2018年日本地質学会創立125周年を記念して〜
トリビア学史 9 1893(明治26)年吾妻山爆発にともなう地質学者の殉難
矢島道子(日本大学文理学部)
写真 三浦宗次郎(佐藤,1985)より.西山惣吉の写真は見つかっていない.
はじめに
火山はときに大爆発をし,人間の社会生活に甚大な被害を与 えることがある.1893年には会津の吾妻山が爆発し,地質学者 が殉難した.地質学が日本に芽生えてから初めて起きた事件だ ったので,東京地学協会報告や鉱山雑誌等によく記録された. 佐藤(1985)によく再録されているが,当時の新聞等を入手し たので,社会的な影響についても報告したい.
殉難の概要
1893年5月,会津の吾妻山が活動を始めた.翌月,地質調査 所所員の三浦宗次郎(技師)は西山惣吉(技手)を随行して現 地に入った.6月7日,二人が火口付近を調査中,大爆発が起き た.「三浦負傷,西山行方不明」の第一報に所員たちは,「三浦 氏すら負傷する場合 西山氏が無難なる謂れはあらじ,恐らく 悲惨なる死を遂げたるならん」(『東京朝日新聞』1893年6月15 日)と心配しているところに,果たして両名死亡の報が届いた. 火山弾の直撃を浴びたのだ.新聞が連日報じた.
三浦宗次郎
三浦宗次郎(1862 ‐ 1893)は群馬県沼田の生まれで,1884 (明治17)年,東京大学理学部地質学科を卒業した.そして静 岡県師範学校や佐賀県などで教員を務めた後,1887年地質調査 所に移った.卒業論文は『土佐東部の地質概要』で,そこに “radiolarian quartzite” という記述がある( 永井・白木, 2011).日本で最初の放散虫硅岩の記載である.地質調査所に 入所してからは20万分の1地質図幅「豊橋」「名古屋」「足助」 「男鹿島」「秋田」「本庄」などを精力的に作成した.死後出版 になったものは「吾妻山破裂調査概況」(三浦,1893a),「鳥海 山登山の記」(三浦,1893b),「荒川銅山」(三浦,1893c)など がある.
西山惣吉
西山惣吉は1855(安政2)年生まれで,履歴書にはただ「東 京府平民」と記されている(佐藤,1985).初めは東京大学で 雇われ,大学の失火事件のときの大活躍が認められ,1880(明治13)年に地質調査所の職階では「定夫」に採用された.1881 年には「定夫世話方」に昇進した.
雇,外国教師出張のときは常に之に随ひ行き同氏[惣吉]に 非ざれば殆んと事を弁せすと云ふ有様なりしかは習ふより慣 れよの譬へ見覚聞覚へ其道に通せしを以て遂に雇に登用されたり(著者不詳,1893)
ナウマンには,1875(明治8)年の最初のフォッサマグナ行 きから,従者として常に同行した.特に1882(明治15)年の白 根山の調査では大活躍をした.ナウマンは火口での試料採取を 試みたが,うまくいかず,西山惣吉の出番となった.
当時噴烟猛烈なりしにも拘はらず噴口及び熱湯の温度を検測 せんため絶壁を攀(よ)ぢ断崖を渡り辛うじて実験を終わり し後更に噴口壁を繞(めぐ)りて対崖に至り前に経過せし所 を望みたるに峭壁裂け岩角聳え今にも破裂墜落せんとする有 様なれば同行の人々はいづれも戦慄したり(著者不詳, 1893).
ナウマンは資料を採集することが出来,帰独後,白根山の論 文を書いた(Naumann ,1893).西山惣吉はナウマンの帰独後, 原田豊吉,そして三浦宗次郎の調査につきあった. 殉職した二人を悼んで肖像画が描かれた.故三浦を洋画家の 浅井忠が描き,故西山を描いたのは原田豊吉の弟,原田直次郎帝室博物館をへて,いま東京国立博物館に収 蔵されているという (佐藤,1985).
社会への影響
科学者の殉職が驚か れた時代で,報せは皇室にも達した.「破裂 の報一たび叡聞(えいぶん)に達するや爾来 (じらい)深く宸襟(しんきん)を惱ませられ」 (『東京朝日新聞』明治 25年6月15日) た天皇は,三浦技師の最後の 報告書を「最(いと) 細(こま)かに叡覧(えいらん)あらせら れ侍従方に向て斯(かヽ)る異変あるごとに朕へ奏聞せるは総て事後の報告のみなるが学術上の研究に依り山岳の破裂若しくは地震等の如き未発の前に於て樹木の枯疲禽獣魚虫の逃避等 何か前兆あるものにはあらずや」(『東京朝日新聞』明治25年6 月15日)と仰せられ,侍従長らは返答に窮し,地質調査所に質 問に行ったという.事件は歌舞伎「善悪両面吾妻山」を生み(『東京朝日新聞』 明治25年6月30日),志賀重昂も「日本の武人,戦場に斃れるる 者,古往今来何ぞ限らん,独り斯学のために倒れたる者」と 『日本風景論』で特記した(志賀,1894).
文 献
佐藤博之,1985,明治26年吾妻山殉難記-百年史の一こま (3), 地質ニュース, no.374, 18-24.
志賀重昂(近藤信行校訂),1995,『日本風景論』,岩波文庫, 395p.[原書初版は1894年政教社より発行]
永井ひろ美・白木敬一,2011,三浦宗次郎(1884)による放散 虫珪岩の記載.名古屋大学博物館報告,no27,1-11.
Naumann, E., 1893a,Neue Beiträge zur Geologie und Geographie Japans, Damphausbrücheder japanischen Vulkane Shirane und Bandai. Petermanns Mitteilungen ans Justus Perthes' Geogra phischer Anstalt, Ergänzungsheft, 108, 1-15. ナウマン(山下 昇訳),1966, 「日本の火山, 白根と磐梯の蒸気噴火(日本の地質と地理へ の新貢献第1論文)」,『日本地質の探究—ナウマン論文集—』 東海大学出版会,313-330.
三浦宗次郎,1893a,吾妻山破裂調査概況.地学雑誌,5巻,6 号,267-272.
三浦宗次郎,1893b,鳥海山登山の記.地学雑誌,5巻,7号, 324-327.
三浦宗次郎,1893c,荒川銅山.地学雑誌,5巻,8号,369-375.
著者不詳, 1893,雑纂-西山技手ノ履歴.鉱山雑誌,3巻,124.
追記:噴火したのは一切経火山だが,当時も現在も吾妻山と伝えられている.吾妻山は会津よりも福島に近く,これは筆者の間違いである.(2017.8.9 追記)
125記念トリビア10 韃靼の地質調査―榎本武揚,オッセンドフスキ
〜2018年日本地質学会創立125周年を記念して〜
トリビア学史10 韃靼の地質調査—榎本武揚,オッセンドフスキ
矢島道子(日本大学文理学部)
図1『榎本武揚 シベリア日記』(2008)より
はじめに
司馬遼太郎の最後の小説『韃靼疾風録』を知っている人も少 なくなった.韃靼といっても,もうほとんど通じないかもしれ ない.モンゴル付近に住んでいる(いた)タタール人のことを 韃靼という.戦前は,韃靼ということばはある程度知られてい た.日本で間宮海峡といわれている地名は,世界的にはタター ル海峡(韃靼海峡)と呼ばれている.
『韃靼』の地質学者を探しているうちに,榎本武揚が浮上し てきた.榎本武揚と地質学とのかかわりにまずふれたい.
榎本武揚
榎本武揚(1836-1908)は,1879(明治12)年,渡辺洪基ら と東京地学協会を立ち上げた.しかしながら,榎本にどれくら いの地質学の素養があったのかは知られていない.彼が執筆し た『シベリア日記』に露頭のスケッチと砂金地の記載が載って いるので,それを紹介して,読者の判断を仰ぎたい.
榎本の一生は波乱万丈でとても書ききれないので,シベリア 日記に関係することだけ記述する.榎本は,ロシア特命全権公 使に決まった澤宣嘉が1873年10月に病死したので,代役として 1874(明治7)年1月18日,駐露特命全権公使に任命された.榎 本の前職は北海道開拓使で,それも,1872(明治5)年1月6日 に出獄し,3月8日から出仕したのだ.1874(明治7)年1月14日 には海軍中将も拝命している.
ロシア滞在中の1875(明治8)年5月7日に,榎本はロシア外 務大臣アレクサンドル・ゴルチャコフと樺太・千島交換条約を 締結し,その後もしばらくロシアに滞在した.
1878(明治11)年7月26日,ようやくのことで,榎本はサン クトペテルブルクを出発し帰国の途に向かう.帰途の詳細な報 告が『シベリア日記』である.榎本はロシアの実情を知ること を目的にシベリアを横断した.モスクワを経てニジニ・ノヴゴ ロドまで,まず鉄道で行く.途中,韃靼人をよく観察している. その後は,船と馬車を乗り継ぎ,9月29日にウラジオストック に到着する.馬車の揺れと虫刺されでは難儀をしたようである. ウラジオストックで黒田清隆が手配していた汽船・函館丸に乗 船し,10月4日小樽に帰着.札幌滞在の後,10月21日に帰京し た.
日記を読んでいくと,8月4日ペルムにて「ゲネラル某よりペ ルムのゼオロジカルマップ(地質図)と写真壱枚を得たり」と いう1文が出てくる.また,砂金地を熱心に観察し,地質用語 としては,ケレイ(粘土),フルハルデケレイ(凝固粘土),ペ ルム・フォルマーシー(ペルム系,)トッパーズ(いはゆるウ ラルセ・ブリヤント(ウラル宝石),クワルツ(石英),ボラッ キス(硼砂),カオリン(白陶土),スラック(鉱滓),ラーピ ス(硝酸銀)なる物質名が並び,トルフ(泥炭)やガラニート (花崗岩)なる名詞も並ぶ.榎本の,露頭のスケッチ(図1) には,「上からaは土,bは砂礫交じりの赤土,1〜4は赤土だ がクワルツ[石英]の片屑を多く含み,砂金をはらめる土で, 下のcはまた金をはらまない赤土」と記載がついている.
オッセンドフスキ
トリビア学史8で篠本二郎を追っていくうちに,傍系の学者 として,『韃靼』の著者衛藤利夫を知った.『韃靼』を読み進め るうちに,オッセンドフスキという地質学者が登場してきた. 『韃靼』中の「辺彊異聞抄」で,衛藤は「オッセンドウスキイ 博士と言えば,有名なポーランドの地質学者で,曾て王朝時代 のロシアの政府から頼まれて,北満州の辺彊を踏査したことのある人だ.その目的は,地質学者として石油鉱や金鉱を探すこ とで,今日の満洲ゴールド・ラッシュの先縱を成すとまあ言え るワケだが,本職以外の副産物として世界の読書界にとんでも ないスリルを送った.即ち北満州の神秘境を描いた『アジアに 於ける人間と神秘』の文学的労作これである」と書いて,いく つか秘話を紹介している.
オッセンドフスキの原著は,フランス人の協力のもとに, 1924年に英語版で出版された.衛藤の「辺彊異聞抄」の初出は 1932(昭和7)年12月である.その後,『アジアに於ける人間と 神秘』は,1941年,43年に日本語の翻訳が出た.
翻訳本(1941年)によれば,オッセンドフスキは,「10カ年 間に亙って私は,多くの時をそこ(シベリア)で過し,石炭, 塩,金,石油脈の研究に従事し,また多くの鉱泉,薬泉の調査 を以て科学的探検を企てたこともあった」と記しているが,そ の地質学者としての業績がまだみつかっていない.戦前の日本 の大陸での地質調査報告をいくらあたってもオッセンドフスキ の名は出てこない.不明なことが多い.調べた限りで見つかる 人物は,ポーランド生まれのオッセンドフスキ(Ossendowski, Ferdinand, 1876-1944)である.彼はロシアの革命に巻き込ま れ,シベリアに投獄もされて,いろいろな経験を経て文筆家に なり,現在では『小説レーニン』が1番有名なようだ.ポーラ ンドの地学史研究家に問い合わせているが,明確な情報はまだ 得られていない.
文 献
衛藤利夫,1992.『韃靼』中公文庫.
榎本武揚(講談社編集),2008.『榎本武揚 シベリア日記』,講談社学術文庫.
Ossendowski, Ferdinand, 1924. Man and mystery in Asia in collaboration with Lewis Stanton Palen, E. Arnold, Ossendowski, Ferdinand, 1931. Beasts, men and gods, Blue Ribbon Books. オッセンドフスキー(神近市子譯),1940.『動物と人と神々: アジア脱出記』生活社.
オッセンドフスキー(大久保忠利譯),1941.『アジアの人と神 秘』生活社.
オッセンドフスキイ(大塚輝生譯),1943.『亞細亞邊境異聞』 新東亞協會.
オッセンドフスキ(木村毅訳),1979『小説レーニン』恒文社.
【geo-Flash】No.382 愛媛大会:巡検申込はお早めに
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.382 2017/7/18┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
[愛媛大会情報]
【1】巡検申込はお早めに
【2】緊急展示を募集します(締切:8/31)
【3】宿泊希望者受付【学生限定】残りわずか
【4】事前参加登録:受付中
【5】講演要旨集は事前予約をお願いします
---------------------------------------------------------------------------
【6】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】巡検申込はお早めに
──────────────────────────────────
参加申込締切(8/21)まではまだ時間がありますが,既に定員に達したコース
や,まもなく定員に達するコースがあります.参加希望の方は,お早めにお申
込下さい.
巡検申込状況はこちら(7/14現在)
http://www.geosociety.jp/science/content0092.html
お申込はこちら(事前参加登録)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/sanka
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】緊急展示を募集します(締切:8/31)
──────────────────────────────────
***申込締切:8月31日(木)***
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害調査報
告や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コーナー」を募集します.
緊急展示は,正式な学会発表と同じく,コアタイムの時間帯が設けられ,優秀
ポスター賞へのエントリーも可能です.また他の要旨と同様に大会後J-STAGE
上で公開されます.発表における1人1題の制約は及びません.コアタイムの日
程については著者希望を優先します(ただし既にセッションでポスター発表を
予定されている場合は,同日でのコアタイムは設定できません).
申込内容:
1)発表要旨PDF(ニュース誌5月号参照) 2)緊急展示の必要性 3)発表代
表者と連絡先 4)希望枚数(1枚:幅90×180cm) 5)優秀ポスター賞へのエ
ントリーの有無 6)コアタイムの日程希望など展示に関わる要望(2〜6 の様
式は自由)
大会実行委員会と行事委員会が協議の上,採択可否の判断を致します.展示
方法やコアタイム等の希望にはできるだけ応えるようにしますが、最終的には
大会実行委員会の指示に従ってください.
申込先: main@geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】宿泊希望者受付【学生限定】残りわずか
──────────────────────────────────
対象:愛媛大会に参加する地質学会会員の学生・院生
宿泊先:松山市内のホテル等(愛媛大学まで徒歩圏内です)
部屋タイプ例:
・大部屋ドミトリー(24名大部屋,2段ベット,布団付)
・和室10人部屋(布団付)
・和室3人部屋(布団付)など
宿泊可能人数(名):各日とも最大52名
料金:素泊まり 2,000〜3,000円/泊 程度
(宿泊施設,部屋タイプにより料金は異なります)
宿泊の確定・支払方法:申込後,宿泊可否の通知をお送りします(数日以内).
宿泊確定者には宿泊施設の情報と費用や支払方法等についてお知らせします.
申込方法:大会WEBサイトから専用フォームにお入りいただきお申込下さい
(定員になり次第締切)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/hotel
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】事前参加登録:受付中
──────────────────────────────────
事前参加登録の受付を開始しました.参加登録に関わるお申込(参加,要旨集,
巡検,懇親会,弁当)は,オンラインによる大会専用参加登録システム(会員・
非会員にかかわらずどなたでも申込可)をご利用の上,お申し込み下さい.
*事前参加登録締切:8月21日(月)18時(WEB)*
お申込はこちら
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/sanka
大会Q&A【参加登録編】もご参照ください
http://www.geosociety.jp/science/content0087.html#sanka
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】講演要旨集は事前予約をお願いします
──────────────────────────────────
参加登録費が0円の方(非会員招待講演者,名誉会員,50 年会員,学部学生割
引会費適用正会員等)には要旨集は付きません.
要旨集の当日販売もありますが,ここ数年,当日販売分が売り切れてしまうこ
とが多く,購入いただけないケースもあります.愛媛大会へ参加を予定されて
いる方や要旨集を購入希望の方は,事前参加登録または要旨集の予約購入申込
をお願いいたします.
(注)参加登録費が発生する方(正会員や院生割引会費適用正会員等)には,
必ず講演要旨集が1冊付きます.
お申込はこちら
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/sanka
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[125周年関連情報]寄付受付中!(クレジットカードも可)
──────────────────────────────────
125周年記念事業として,2018年5月東京での記念式典をはじめ,様々な事
業を計画しています.また,それら記念事業を実行するため,学会員や賛助会
員,さらには関連諸団体に寄付をお願いしております.
*醵金者一覧
http://www.geosociety.jp/125th/content0014.html
*記念事業に対する寄付のお願い
クレジットカード(VISA, Master, Diners)もご利用いただけます
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html#kifu
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地質地盤情報の活用と法整備を考える会
http://www.geo-houseibi.jp
国土交通省の第4回「地下空間の利活用に関する安全技術の確立に関する小委員
会」(7/4)を傍聴しました.
*************(以下,関連団体の行事案内です)****************
■(後)「放散虫とかたち展」
7月12日(水)〜 8月31日(木)
場所:新潟大学駅南キャンパス「ときめいと」
主催:新潟大学旭町学術資料展示館、理学部など
http://www.lib.niigata-u.ac.jp/tenjikan/kikaku/doc/k170712.html
■(後)「青少年のための科学の祭典」2017全国大会
7月29日(土)〜30日(日)
会場:科学技術館(千代田区北の丸公園2-1)
http://www.kagakunosaiten.jp/
■(後)科学教育研究協議会第64回全国研究大会
8月7日(月)〜9日(水)
場所:広島なぎさ中学高等学校(広島市佐伯区)
http://kakyokyo.main.jp/
■日本学術会議主催学術フォーラム
「放射性物質の移動の計測と予測−あのとき・いま・これからの安心・安全」
8月7日(月)12:00〜17:00(申込締切:8月4日(金))
https://form.cao.go.jp/scj/opinion-0067.html
■(共)2017年度日本地球化学会第64回年会
9月13日(水)〜15日(金)
会場:東京工業大学・大岡山キャンパス
参加申込:8月21日(月)17時締切
http://www.geochem.jp/conf/2017/
■女子大学院生・ポスドクと産総研女性研究者との懇談会 in 名古屋
9月25日(月)13:15〜17:00
会場:産業技術総合研究所 中部センターOSL棟 連携会議場
(名古屋市守山区下志段味穴ケ洞2266-98)
対象:女子大学院生・ポスドク等
参加費無料・事前申込制(定員60名) 申込締切:9月15日(金)
https://unit.aist.go.jp/diversity/ja/event/170925_div_event.html
■(共)第61回粘土科学討論会
9月25日(月)〜 27日(水)
会場:富山大学 五福キャンパス共通教育棟
http://www.cssj2.org/
■(後)第4回Slope tectonics 2017
10月14日(土)〜18日(水)
場所:京都大学宇治キャンパス黄檗プラザ
http://www.slope.dpri.kyoto-u.ac.jp/SlopeTectonics2017/st2017.html
■(共)第15回国際放散虫研究集会(15th InterRad)
10月23日(月)〜27日(金)研究集会
20日(金)〜22日(日)プレ巡検
22日(日)サイエンスカフェ
28日(土)〜31日(火)ポスト巡検
会場:新潟大学など
http://interrad2017.random-walk.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・名古屋大学大学院環境学研究科地球環境科学専攻地質・地球生物学講座教員
公募(10/2)
・「朝日賞」候補者推薦(学会締切8/10)
・平成30年度JAMSTEC「よこすか」「かいれい」研究船利用課題公募(7/24)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
125記念トリビア11 新島襄と地質学
〜2018年日本地質学会創立125周年を記念して〜
トリビア学史 11 新島襄と地質学
矢島道子(日本大学文理学部),林田 明(同志社大学理工学部)
新島襄(1843-1890)は同志社を創設したキリスト者であるが,地質学に親しかったことはすでに知られている(島尾,1986,1989;八耳,2001など).同志社大学は2017年5月16日(火)〜7月9日(日)に,ハリス理化学館同志社ギャラリーにて,第12回企画展「新島襄が感じた地球」を開催した.同志社大学の文化系公認団体である地学研究会が2017年に創立50周年を迎えたのを機に,同志社における地学の意義を考える企画展であった.このとき初めて新島旧邸にある化石及び岩石鉱物標本の肉眼鑑定が実施され,その成果の一部も公開された.
新島はどこで地質学と出会ったか
新島は幕末に国禁を犯して渡米し(1865年),アメリカの高校,大学,神学校で学んだ.日本にいる間にアメリカの地理書『聯邦志略(れんぽうしりゃく)』を読んで感動したという記録があり,世界的な視野から地理に大きな関心を寄せていたが,日本では地学的な情報には出会わなかったと思われる.新島がアメリカで受けた教育は,もちろん,キリスト教の関係が多いが,一般教養的な理学もラテン語も教育課程に含まれており,新島は積極的に学んだ.1867年,アーモスト大学(Amherst College)に入学し,1870年理学士として卒業している.札幌農学校に大きな影響を及ぼしたクラーク(WilliamSmith Clark 1826 - 1886)はアーモスト大学で化学などを教えていたが,新島が入学した年の8月にマサチューセッツ農科大学の学長に就任している.新島がクラークから直接教えを受けた可能性は低いと思われるが,クラークが導入した化学の学生実験は体験した.その後,1872(明治5)年にアメリカで岩倉使節団に出会い,田中不二麿(1845 - 1909)に同行して,初めはアメリカを,そののち,ヨーロッパの高等教育機関などを視察した.1874年,10年ぶりに日本に帰国し,翌年,同志社英学校を京都に設立した.
アメリカで受けた教育
新島はキリスト者の学校で教育を受けたから,エドワード・ヒッチコック(Edward Hitchcock 1794-1864)の自然神学的地質学の教科書(1851年初版)に基づく講義を受けた.ヨーロッパの視察から戻った後,1873年に同書(1860年版)を購入しており,それが新島の蔵書として保管されている.この他に,チャールズ・ライエルの『地質学原理』(第11版, 1873, 1874年),ジェームズ・デーナの鉱物学の教科書(1875年)なども蔵書に存在する.今回の展示では,図1のように,かなり大きな地質断面の概念的説明図があった.GRANITE(“G”の文字は“C”に近い字体)と書かれた基盤岩の上に変成岩,シルル紀,デボン紀,石炭紀,ペルム紀,三畳紀,ジュラ紀(ライアスなど),白亜紀,第三紀の地層が載り,火山は地下の玄武岩が吹き出ているように,エトナ火山は地下の花崗岩の地殻に溶岩が貫入して噴火しているように説明されている.どうやら,これはロンドン大学(UCL)で1855年から77年まで地質学教授を務めたJohn Morris(1810-1886)が1858年に発表した断面図のコピーのようだ.新島の断面図には針でつけたらしい穴もいくつか見られ,筆記体の文字は明らかに新島の筆跡なので,新島が手ずから複写したように思われる.
ヨーロッパでの経験
岩倉使節団に同行して,欧米を視察したときの記録が残っている.新島が何に興味をもったか,よくわかる.たとえば,「[1872年]7月3日(水)私たちはグリニッチ天文台を訪れた.大型の望遠鏡を見学する.水力によって回転する輪により,地球の自転に合わせて回るようになっている.望遠鏡と写真により,磁気嵐を発見する過程を見学した.また風量区,風速,方向を観測する機器をも見た(『新島襄自伝』p.151)」と書き,さらにその機器をスケッチしている.新島のスケッチも今回いくつか展示された.彼が天文学に強い関心を寄せていたことがわかる.記録を読むと,新島が地質学の何に興味をもったのかがわかる.マンチェスターの家は「大概軟石(フリーストーン)で出来ており,」グラスゴー大学の建築材は「大部分がフリーストンで,柱にはスコットランド大理石(真の花崗岩),レッドストーン,緑大理石等を用いて」いると記した.スイスのベルンでは地質学博物館に行き,「アルプスから出たいくつかの標本を見」,ライン川に沿って建つ城の大部分はけわしい岩の上に建てられており,「こうした岩は,火山によって形成されたに違いない」と記す.アメリカでの教育で得た地質学の知見をいかんなく発揮している.
日本での化石・鉱物採集
アメリカで学んだ地質学は,当然ながら帰国後も活かされた.『新島襄自伝』の[1878年]4月2日(火)(p.192)には,「中後閑村の上原春朔君の宅に至り,それより三里も山の奥に行く.フォッスル[化石]の有る所に至り,スペスメン[標本]を取れり.」という記載がある.中後閑村は新島襄ゆかりの地である群馬県安中市の後閑川沿いに位置し,付近には中新世の浅海堆積物が分布する.新島旧邸には中新世の貝化石が数点残されており,これらが安中で採集された標本である可能性が高い.今回の企画展には貝化石の他,植物化石も展示された.植物化石の裏には「明治十九(1886)年八月二十五日播州明石郡名谷村,西垂水村ヲ距ル五十町ヨ」などと記されており,これも新島襄の日記(『新島襄全集5 日記・紀行編』,1984)の記述と一致する.新島が何のために化石を採集したかは全く不明である.なお,トリビア1で紹介した『本邦化石産地目録』(1884年出版)の「第三紀之部」には「上野國確永(碓氷)郡後閑村」に「貝石」が,「播磨國多可郡奥畑村」(現在の西脇市の南東部)に「木葉石」が産出することが記されている. 鉱物としては磁鉄鉱,黄銅鉱,方鉛鉱,赤鉄鉱,あるいは石炭も今回の企画展で展示された.採集地,採集年月日,採集者等不明である.石炭には興味を持っていたようであるし,『石炭之賛』と題する漢詩を創ったりしている.また,[1875年]4月3日には宇治を経て石山に行き,「石灰岩,この石はなかなか割れない」と記した.実際にハンマーでたたいた様子が想起される.
新島は地質学を大切と考える
新島は同志社英学校やハリス理化学校の教育課程に地質学を入れようとした.また,地質学関連の書籍など,自分の蔵書を学生が自由に使えるようにした.キリスト教の布教のために地方を巡るときにも,化石や鉱物採集にいそしんだ.1860年代の欧米では,地質学は重要な基礎学問であり,トリビア10の榎本武揚と同じように,新島も榎本も積極的に学んだのではないだろうか.幕末に欧米で学んだ武士たちは,地質学の基礎をもちろん体得していて,明治の時代を切り開いていくときに,資源は当時の国策と強力に結び付くという基本的な考え方にしたのではないだろうか.
文 献
同志社社史資料センター・同志社大学地学研究会編,『新島襄が感じた地球』,2017年.
同志社編,『新島襄自伝』,岩波文庫 2013年.新島襄,『新島襄全集5 日記・紀行編』,同朋社 1984年.島尾永康,1986,新島襄と科学,科学史研究,25(158),p83-88.
島尾永康,1989,自然神学の時代--同志社英学校所蔵の自然神学書にみる(同志社・新島襄),キリスト教社会問題研究,(37),p67-84.
八耳俊文,2001,『格物窮理問答』の成立と本文,青山学院女子短期大学総合文化研究所年報,127-144.
新島 襄の『地質構造図』(年不詳, 26.3×165cm, 同志社社史資料センター蔵)
【geo-Flash】No.392(臨時)[愛媛大会]最終日
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.392 2017/9/19 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】愛媛大会 2日目と最終日の様子
──────────────────────────────────
台風による2日目の行事中止や緊急対応などイレギュラーな事態が頻発した
大会になり、参加者と関係者の皆様にはご心配とご不便をおかけしました。LOC
および現地スタッフの皆様は懸命の対応をありがとうございました。講演会をはじ
めとした行事は、おかげさまで最終日を迎えることができました。
18日は台風一過の快晴となり、地質巡検は全5コースの催行が決まりました。
巡検に参加される皆様は気を付けて楽しんできてください。
来年は札幌大会です。地質学会125周年の記念大会です。いまから楽しみです!
それでは17日および最終日の様子を写真でご覧ください.
中止決定...
嵐の前の
午後から本降り
大荒れの天気
翌日は快晴!
嵐の跡
企業ブース
ポスター会場の熱気
学生特別セッション
学生特別セッション
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.383[愛媛大会]講演プログラムを公開しました
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.383 2017/8/1┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[愛媛大会情報]講演プログラムを公開しました
【2】[愛媛大会情報]巡検申込はお早めに
【3】[愛媛大会情報]緊急展示募集中です(締切:8/31)
【4】[愛媛大会情報]事前参加登録受付中:要旨集は事前予約を!
-------------------------------------------------------------------
【5】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
【6】一家に1枚 ポスターの企画案「県の石でわかる 日本の大地のつくり」
【7】地層処分に関わる「科学的特性マップ」が公表されました
【8】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[愛媛大会情報]講演プログラム公開しました
──────────────────────────────────
シンポジウム,セッション別の講演プログラム(PDF)を大会HPに公開しました.
全体日程表とあわせてご覧ください.(注)一部演題情報は修正・変更される
場合があります.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/Schedule
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[愛媛大会情報]巡検申込はお早めに
──────────────────────────────────
参加申込締切(8/21)まではまだ時間がありますが,既に定員に達したコース
や,まもなく定員に達するコースがあります.参加希望の方は,お早めにお申
込下さい.
巡検申込状況はこちら(7/31現在)
http://www.geosociety.jp/science/content0092.html
お申込はこちら(事前参加登録)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/sanka
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[愛媛大会情報]緊急展示募集中です(締切:8/31)
──────────────────────────────────
***申込締切:8月31日(木)***
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害調査報
告や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コーナー」を募集します.
緊急展示は,正式な学会発表と同じく,コアタイムの時間帯が設けられ,優秀
ポスター賞へのエントリーも可能です.また他の要旨と同様に大会後J-STAGE
上で公開されます.発表における1人1題の制約は及びません.コアタイムの日
程については著者希望を優先します(ただし既にセッションでポスター発表を
予定されている場合は,同日でのコアタイムは設定できません).
申込内容:
1)発表要旨PDF(ニュース誌5月号参照) 2)緊急展示の必要性 3)発表代
表者と連絡先 4)希望枚数(1枚:幅90×180cm) 5)優秀ポスター賞へのエ
ントリーの有無 6)コアタイムの日程希望など展示に関わる要望(2〜6 の様
式は自由)
大会実行委員会と行事委員会が協議の上,採択可否の判断を致します.展示
方法やコアタイム等の希望にはできるだけ応えるようにしますが、最終的には
大会実行委員会の指示に従ってください.
申込先: main@geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[愛媛大会情報]事前参加登録受付中:要旨集は事前予約を!
──────────────────────────────────
参加登録に関わるお申込(参加,要旨集,巡検,懇親会,弁当)は,オンライ
ンによる大会専用参加登録システム(会員・非会員にかかわらずどなたでも申
込可)をご利用の上,お申し込み下さい.
*****************************************************
事前参加登録締切:8月21日(月)18時(WEB)
*****************************************************
参加登録費が0円の方(非会員招待講演者,名誉会員,50年会員,学部学生割
引会費適用正会員等)には要旨集は付きません.ここ数年,当日販売分が売り
切れてしまうことが多く,購入いただけないケースもあります.要旨集を購入
希望の方は,事前参加登録または要旨集の予約購入申込をお願いいたします.
(注)参加登録費が発生する方(正会員や院生割引会費適用正会員等)には,
必ず講演要旨集が1冊付きます.
お申込はこちら
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/sanka
大会Q&A【参加登録編】もご参照ください
http://www.geosociety.jp/science/content0087.html#sanka
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
──────────────────────────────────
本年7月に発生し九州北部豪雨等災害により被害を受けられた皆様に,心より
お見舞い申し上げます.
日本地質学会では,災害救助法適用地域で被災された会員の方々のご窮状を
ふまえ,申請により会費を免除いたします.「日本地質学会に届出の住居また
は勤務地が災害救助法適用地域に該当する会員のうち,希望する方」は2017年
度(平成29年度)もしくは2018年度(平成30年度)会費を免除いたします.
適用を希望される会員は,1. 会員氏名,2. 被災地,3. 被災状況(簡潔に)を
添えて学会事務局にお申し出下さい(郵送,FAX,e-mail、電話のいずれでも可).
****************************************
申請締切:2017年10月31日(火)
****************************************
※通常の会費払い込みについては,下記をご参照ください.
「2017年会費払い込みについて」
http://www.geosociety.jp/outline/content0164.html
【災害に関連した学術大会参加費の特別措置】
申請により大会参加登録費を免除いたします.該当される方は,必ず事前参加
申込手続き前に学会事務局に申請して下さい(1.会員氏名,2.被災地,3.被災
状況(簡潔に)を添えて学会事務局まで).
(注1)免除の対象は大会参加登録費に限ります.巡検,懇親会等その他の費用
は対象となりません.
(注2)事前参加申込の場合に対してのみ適用しますので,当日会場での申請は
受付ることができません.
一般社団法人 日本地質学会
〒101-0032東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル
Tel.03-5823-1150,Fax.03-5823-1150 e-mail main@geosociety.jp >
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】一家に1枚 ポスターの企画案「県の石でわかる 日本の大地のつくり」
──────────────────────────────────
一家に1枚 ポスターの企画案「県の石でわかる 日本の大地のつくり」
地質学会提案の企画案が、一次審査をとおりました。
第59回科学技術週間(平成30年4月16日〜22日)において配布されるポスターの
企画審査が行われています。表記の地質学会提案も含め、一次審査を通った8テー
マについて、全国各地の科学館、博物館等において意見募集(投票)が、実施
されます。
県の石も最終まで残り美麗なポスターとなって、学校や各家庭などでお役に立
てれば、選定した甲斐があるというものです。
意見募集(投票)の実施期間は,7月27日〜8月13日までです。詳しくは文部科
学省のHPをご覧いただき、ぜひ最寄りの科学館・博物館にアクセスしてみてく
ださい。
http://stw.mext.go.jp/common/pdf/outline/H30poster_ikenbosyu.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】地層処分に関わる「科学的特性マップ」が公表されました
──────────────────────────────────
平成26年11月から2年以上にわたり検討され、今年の4月に要件・基準を取りま
とめらえた「科学的特性マップ」が、7月28日に、経済産業省資源エネルギー庁
から公表されました。科学的特性マップとその付随資料は、以下のウェブサイ
トにアップロードされています。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/rw/kagakutekitokuseimap/
「科学的特性マップ」は、高レベル放射性廃棄物の地層処分を行う場所を選ぶ
際にどのような科学的特性を考慮する必要があるのか、それらは日本全国にど
のように分布しているか、といったことを示すものです。(資源エネルギー庁
サイトより)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】[125周年関連情報]寄付受付中!(クレジットカードも可)
──────────────────────────────────
125周年記念事業として,2018年5月東京での記念式典をはじめ,様々な事
業を計画しています.また,それら記念事業を実行するため,学会員や賛助会
員,さらには関連諸団体に寄付をお願いしております.
*醵金者一覧
http://www.geosociety.jp/125th/content0014.html
*記念事業に対する寄付のお願い
クレジットカード(VISA, Master, Diners)もご利用いただけます
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html#kifu
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地震本部ニュース 平成29年度夏号発行
調査研究レポート:熊本県日奈久断層帯での古地震調査 ほか
http://www.jishin.go.jp/herpnews/
*************(以下,関連団体の行事案内です)****************
■(後)「放散虫とかたち展」
7月12日(水)〜 8月31日(木)
場所:新潟大学駅南キャンパス「ときめいと」
主催:新潟大学旭町学術資料展示館、理学部など
http://www.lib.niigata-u.ac.jp/tenjikan/kikaku/doc/k170712.html
■(後)2017年度特別展:地球を「はぎ取る」〜地層が伝える大地の記憶〜
7月15日(土)〜11月5日(日)(9月以降は月曜日ほか休館日あり)
会場:神奈川県立生命の星・地球博物館1階 特別展示室
http://nh.kanagawa-museum.jp/exhibition/special/ex153.html
■(後)科学教育研究協議会第64回全国研究大会
8月7日(月)〜9日(水)
場所:広島なぎさ中学高等学校(広島市佐伯区)
http://kakyokyo.main.jp/
■記念式典及び第201回地質汚染イブニングセミナー
場所 :北とぴあ901会議室
8月25日(金)18:30〜20:30
18:30〜19:30 第200回記念式典・各理事の祝辞
19:30〜20:30 第201回イブニングセミナー
講師:愛甲義昭(桜富士テクニカルアカデミィ日本事務所代表・NPO日本地質汚
染審査機構専門会員)
テーマ:日本地質汚染審査機構と地質汚染調査・浄化に貢献してきた思い出
http://www.npo-geopol.or.jp
■(共)2017年度日本地球化学会第64回年会
9月13日(水)〜15日(金)
会場:東京工業大学・大岡山キャンパス
参加申込:8月21日(月)17時締切
http://www.geochem.jp/conf/2017/
■(共)海底火山研究国際シンポジウム
海底火山噴火研究の国際的権威であるスミソニアン協会国立自然史博物館元館
長のRichard Fiske博士が日本地質学会国際賞を受賞・来日される機会に、日本
における海底火山研究の進捗状況を総括し、その将来を議論する研究シンポジ
ウムを開催します。
9月20日(水)14:00〜18:00
場所:国立科学博物館本館2階講堂
要事前申込(定員100名)申込締切:9月13日(水)
http://www.kahaku.go.jp/news/2017/seamount/
■女子大学院生・ポスドクと産総研女性研究者との懇談会 in 名古屋
女子大学院生・ポスドク等の方々に研究職としてのキャリアイメージを得る機
会を提供するため、本研究所の職場紹介及び少人数に分かれての女性研究者等
との懇談会を開催します。
9月25日(月)13:15〜17:00
会場:産業技術総合研究所 中部センターOSL棟 連携会議場
対象:女子大学院生・ポスドク等
参加費無料・事前申込制(定員60名)申込締切:9月15日(金)
https://unit.aist.go.jp/diversity/ja/event/170925_div_event.html
■(共)第61回粘土科学討論会
9月25日(月)〜 27日(水)
会場:富山大学 五福キャンパス共通教育棟
http://www.cssj2.org/
■(後)第4回Slope tectonics 2017
10月14日(土)〜18日(水)
場所:京都大学宇治キャンパス黄檗プラザ
http://www.slope.dpri.kyoto-u.ac.jp/SlopeTectonics2017/st2017.html
■(共)第15回国際放散虫研究集会(15th InterRad)
10月23日(月)〜27日(金)研究集会
20日(金)〜22日(日)プレ巡検
22日(日)サイエンスカフェ
28日(土)〜31日(火)ポスト巡検
会場:新潟大学など
http://interrad2017.random-walk.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻地球物理学分野准教授公募(9/29)
・徳島大学大学院社会産業理工学研究部構造地質学教授公募(8/31)締切延長
・東京大学地震研究所国際室外国人客員教員の推薦公募(8/18)
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.384[愛媛大会]事前参加登録まもなく締切です!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.384 2017/8/17┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[愛媛大会情報]事前参加登録まもなく締切です!
【2】[愛媛大会情報]講演プログラム公開中
【3】[愛媛大会情報]緊急展示募集中です(締切:8/31)
【4】[愛媛大会情報]宿泊予約に関する情報
-------------------------------------------------------------
【5】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
【6】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【7】惑星地球フォトコンテスト:まもなく応募受付開始です
【8】コラム:日本地質図百景
【9】その他のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[愛媛大会情報]事前参加登録まもなく締切です!
──────────────────────────────────
*****************************************************
事前参加登録締切:8月21日(月)18時(WEB)
*****************************************************
参加登録に関わるお申込(参加,要旨集,巡検,懇親会,弁当)は,オンライ
ンによる大会専用参加登録システム(会員・非会員にかかわらずどなたでも申
込可)をご利用の上,お申し込み下さい.
(注)参加登録費が0円の方(非会員招待講演者,名誉会員,50年会員,学部学
生割引会費適用正会員等)には要旨集は付きません.ここ数年,当日販売分が
売り切れてしまうことが多く,購入いただけないケースもあります.要旨集を
購入希望の方は,事前参加登録または要旨集の予約購入をお願いいたします.
(注)参加登録費が発生する方(正会員や院生割引会費適用正会員等)には,
必ず講演要旨集が1冊付きます.
事前参加登録はこちら
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/sanka
巡検申込状況はこちら
http://www.geosociety.jp/science/content0092.html
大会Q&A【参加登録編】もご参照ください
http://www.geosociety.jp/science/content0087.html#sanka
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[愛媛大会情報]講演プログラム公開中
──────────────────────────────────
シンポジウム,セッション別の講演プログラム(PDF)を大会HPに公開しました.
全体日程表とあわせてご覧ください.
(注)一部演題情報は修正・変更される場合があります.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/Schedule
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[愛媛大会情報]緊急展示募集中です(締切:8/31)
──────────────────────────────────
***申込締切:8月31日(木)***
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害調査報
告や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コーナー」を募集します.
緊急展示は,正式な学会発表と同じく,コアタイムの時間帯が設けられ,優秀
ポスター賞へのエントリーも可能です.また他の要旨と同様に大会後J-STAGE
上で公開されます.発表における1人1題の制約は及びません.コアタイムの日
程については著者希望を優先します(ただし既にセッションでポスター発表を
予定されている場合は,同日でのコアタイムは設定できません).
申込内容:
1)発表要旨PDF(ニュース誌5月号参照) 2)緊急展示の必要性 3)発表代
表者と連絡先 4)希望枚数(1枚:幅90×180cm) 5)優秀ポスター賞へのエ
ントリーの有無 6)コアタイムの日程希望など展示に関わる要望(2〜6 の様
式は自由)
大会実行委員会と行事委員会が協議の上,採択可否の判断を致します.展示
方法やコアタイム等の希望にはできるだけ応えるようにしますが、最終的には
大会実行委員会の指示に従ってください.
申込先: main@geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[愛媛大会情報]宿泊予約に関する情報
──────────────────────────────────
国体及び関連行事のために松山市内の宿がブロックされていて,宿泊予約が困
難な状態が続いていたことと思います.松山市内中心部の宿に関してはようや
く,8月20日頃からリリースされるとの情報が大会実行委員会よりありました.
8月20日以降,直接宿に電話してご確認ください.
大会HPの宿泊関連情報もご参考にして下さい.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/hotel
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
──────────────────────────────────
本年7月に発生し九州北部豪雨等災害により被害を受けられた皆様に,心より
お見舞い申し上げます.
日本地質学会では,災害救助法適用地域で被災された会員の方々のご窮状を
ふまえ,申請により会費を免除いたします.【申請締切:2017年10月31日(火)】
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0164.html
*災害に関連した学術大会参加費の特別措置について
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/sanka#saigai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[125周年関連情報]寄付受付中!(クレジットカードも可)
──────────────────────────────────
125周年記念事業として,2018年5月東京での記念式典をはじめ,様々な事
業を計画しています.また,それら記念事業を実行するため,学会員や賛助会
員,さらには関連諸団体に寄付をお願いしております.
*醵金者一覧
http://www.geosociety.jp/125th/content0014.html
*記念事業に対する寄付のお願い
クレジットカード(VISA, Master, Diners)もご利用いただけます
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html#kifu
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】惑星地球フォトコンテスト:まもなく応募受付開始です
──────────────────────────────────
第9回惑星地球フォトコンテストの応募受付をまもなく開始いたします.前回よ
り野外に出かける機会の多い「夏」に応募期間を設定しています.皆さんの力
作をお待ちしています.
応募作品受付(予定):8月25日頃〜12月31日(土)
詳しくは, http://photo.geosociety.jp/
★入選作品展示会のお知らせ★
9月16日(土)〜18日(月・祝)
場所:愛媛大学ミュージアム(学術大会:地質情報展会場内)
入場無料・どなたでもお気軽にご覧下さい
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/gyoji#johoten
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】コラム:日本地質図百景
──────────────────────────────────
正会員 石渡 明
産業技術総合研究所地質調査総合センター(以下「地調」。旧通商産業省工業
技術院地質調査所)の地質図は、1/20万図が北方領土を除く全国122区画(110
図幅、うち2区画合体図幅が12)を、1/5万図が全国の約6割(1274区画のうち7
60)をカバーし、凡例を統一した1/20万全国シームレス地質図も提供されてい
る。(中略)
これらの地質図は学校や社会における地学教育にも非常に有用であるが、どの
地質図がどのようなテーマの教材として役立つかを示したガイドが、これまで
無かったように思う。私は仕事柄全国の地質図を見る機会が多いので、その経
験に基づいてテーマごとに地質図の「見どころ案内」を試みる。
全文はこちらは, http://www.geosociety.jp/faq/content0726.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■(後)「放散虫とかたち展」
7月12日(水)〜 8月31日(木)
場所:新潟大学駅南キャンパス「ときめいと」
主催:新潟大学旭町学術資料展示館、理学部など
http://www.lib.niigata-u.ac.jp/tenjikan/kikaku/doc/k170712.html
■(後)2017年度特別展:地球を「はぎ取る」〜地層が伝える大地の記憶〜
7月15日(土)〜11月5日(日)(9月以降は月曜日ほか休館日あり)
会場:神奈川県立生命の星・地球博物館1階 特別展示室
http://nh.kanagawa-museum.jp/exhibition/special/ex153.html
■(後)科学教育研究協議会第64回全国研究大会
8月7日(月)〜9日(水)
場所:広島なぎさ中学高等学校(広島市佐伯区)
http://kakyokyo.main.jp/
■福島県「県の石」選定記念特別講演会
8月20日(日)14時開演
場所:石川町立石川小学校 クリスタルホール
http://www.town.ishikawa.fukushima.jp/event/entry/005686.html
■(共)2017年度日本地球化学会第64回年会
9月13日(水)〜15日(金)
会場:東京工業大学・大岡山キャンパス
参加申込:8月21日(月)17時締切
http://www.geochem.jp/conf/2017/
>プログラム公開しました
http://www.geochem.jp/conf/2017/program.html
■(共)海底火山研究国際シンポジウム
海底火山噴火研究の国際的権威であるスミソニアン協会国立自然史博物館元館
長のRichard Fiske博士が日本地質学会国際賞を受賞・来日される機会に、日本
における海底火山研究の進捗状況を総括し、その将来を議論する研究シンポジ
ウムを開催します。
9月20日(水)14:00〜18:00
場所:国立科学博物館本館2階講堂
要事前申込(定員100名)申込締切:9月13日(水)
http://www.kahaku.go.jp/news/2017/seamount/
■(共)第61回粘土科学討論会
9月25日(月)〜 27日(水)
会場:富山大学 五福キャンパス共通教育棟
http://www.cssj2.org/
■(後)第4回Slope tectonics 2017
10月14日(土)〜18日(水)
場所:京都大学宇治キャンパス黄檗プラザ
http://www.slope.dpri.kyoto-u.ac.jp/SlopeTectonics2017/st2017.html
■(共)第15回国際放散虫研究集会(15th InterRad)
10月23日(月)〜27日(金)研究集会
20日(金)〜22日(日)プレ巡検
22日(日)サイエンスカフェ
28日(土)〜31日(火)ポスト巡検
会場:新潟大学など
http://interrad2017.random-walk.org/
■国際集会:RFG2018(次世代の資源に関する国際集会2018)
2018年6月16日(土)〜21日(木)(要旨締切:2018年1月15日)
場所:カナダ,バンクーバー市,国際会議場
「次世代の資源」に関するコミッションがIUGS内部に組織され,IUGSとカナダ
地質学協会などの共同主催で,ミニIGCとも考えられる国際集会が開かれます.
会議ではエネルギー・鉱物・水資源,地球科学の教育・知識の伝達とそれらの
社会での共有を目指しての諸活動の交換などが主たるテーマです.セッション
には,環太平洋域の自然災害とジオハザード(日本主導のIUGSジオハザード・
タスクグループによる)や海域管理システムの構築,環境問題などの重要な課
題が含まれます.また多数のエキシビション,巡検,ショートコースも計画さ
れています. http://rfg2018.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.385 国際地学オリ金メダル獲得!/愛媛大会情報ほか
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.385 2017/9/5┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】国際地学オリンピック:日本代表選手が金メダル2,銀メダル2を受賞
------------------------------------
【2】[愛媛大会情報]予約確認書を発送しました
【3】[愛媛大会情報]講演プログラム公開中です
【4】[愛媛大会情報]発表者の皆様へ
【5】[愛媛大会情報]講演キャンセル,発表者変更希望がある場合
【6】[愛媛大会情報]宿泊地アンケートにご協力ください
------------------------------------
【7】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
【8】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】国際地学オリンピック:日本代表選手が金メダル2,銀メダル2を受賞
──────────────────────────────────
8月22日〜29日にかけてフランスのコートダジュールで開催された第11回国際地
学オリンピック・フランス大会で、日本選手は金2,銀2(メダルから推定の国
別順位は1位の中国(金3,銀1)に続き、台湾と同率の2位)の優秀な成績をお
さめ、31日に無事帰国しました。
同日、文部科学省を表敬訪問し、 水落副大臣から文部科学大臣表彰をうけまし
た。生徒のみなさんの成績の詳細は以下の通りです。
受賞者詳細:
押見祥太(おしみ しょうた)さん
東京都立小石川中等教育学校(東京都)6年(18歳)金メダル
土屋俊介(つちや しゅんすけ)さん
聖光学院高等学校(神奈川県)3年(17歳)金メダル
越田勇気(こしだ ゆうき)さん
海城高等学校(東京都)3年(17歳)銀メダル
中桐悠一郎(なかぎり ゆういちろう)さん
立命館慶祥高等学校(北海道)3年(17歳)銀メダル
(年齢は本大会終了時点のもの)
http://www.jeso.jp/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[愛媛大会情報]予約確認書を発送しました
──────────────────────────────────
愛媛大会の事前参加登録をした方(参加費合計額が有料のかた)に宛て,確認
書や記名済の名札,クーポン類(懇親会やお弁当を注文されたかたのみ)を発
送いたしました.年会当日の受付にて,【受付提出用】の書類を全員に提出し
ていただきますので,忘れずにご持参ください.
なお,参加登録費の合計金額が0円の方には別途メールでご案内をいたします.
【お願い】事前参加登録者が都合により年会への参加をキャンセルしたい場合
には,必ず日本地質学会事務局までご一報ください(申込項目により取消料が
異なります).
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[愛媛大会情報]講演プログラム公開中です
──────────────────────────────────
シンポジウム,セッション別の講演プログラム(PDF)を大会HPで公開中です.
全体日程表とあわせてご覧ください.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/Schedule
【お詫び】講演プログラム(PDF)へのリンク不備があり,プログラムをご覧い
ただけない状態が続いていました。PDFファイルへのリンク設定を修正しました。
ご迷惑をおかけし,申し訳ありませんでした。(9/4)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[愛媛大会情報]発表者の皆様へ
──────────────────────────────────
・口頭発表をする方へ(PC,プロジェクター等機器使用について…ほか)
・ポスター発表をする方へ(最低掲示時間帯やポスターサイズ,撤収…ほか)
発表者の皆様へそれぞれの発表時の注意点等をご案内しています。
詳しくは,大会WEBサイトをご参照ください(ニュース8月号にも同様に掲載)。
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/happyo
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[愛媛大会情報]講演キャンセル,発表者変更希望がある場合
──────────────────────────────────
講演キャンセルをする場合は,必ず事前に行事委員会(会期前は学会事務局,
会期中は学会本部)に連絡して下さい.
また,やむを得ない事情により,あらかじめ連記された共同発表者内で発表者
の変更を希望する場合も,必ず事前に行事委員会(会期前は学会事務局,会期
中は学会本部)に連絡して下さい.この場合も,シンポジウムおよびアウトリー
チセッション以外の場合は「会員に限り1人1題(発表負担金を支払った場合
は2題)」の制限を守るものとします.代理人の代読,会場内での突然の発表者
変更,発表順序の変更は認めません.
会期前の連絡先:日本地質学会事務局
[at]を@マークにして送信して下さい.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[愛媛大会情報]宿泊地アンケートにご協力ください
─────────────────────────────────
愛媛大会参加にともない,松山市や近隣の市内にご宿泊予定のかたは,宿泊に
関する簡単なアンケートに,ぜひご協力ください.
アンケートは本日(9/4)発送の確認書(【受付提出用】)の上段に記入欄が設け
てあります.アンケート記入済みの【受付提出用】の書類を,愛媛大会の会場
受付にてご提出ください.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
──────────────────────────────────
本年7月に発生し九州北部豪雨等災害により被害を受けられた皆様に,心より
お見舞い申し上げます.
日本地質学会では,災害救助法適用地域で被災された会員の方々のご窮状を
ふまえ,申請により会費を免除いたします.【申請締切:2017年10月31日(火)】
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0164.html
*災害に関連した学術大会参加費の特別措置について
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/sanka#saigai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】[125周年関連情報]寄付受付中!(クレジットカードも可)
──────────────────────────────────
125周年記念事業として,2018年5月東京での記念式典をはじめ,様々な事
業を計画しています.また,それら記念事業を実行するため,学会員や賛助会
員,さらには関連諸団体に寄付をお願いしております.
*醵金者一覧
http://www.geosociety.jp/125th/content0014.html
*記念事業に対する寄付のお願い
クレジットカード(VISA, Master, Diners)もご利用いただけます
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html#kifu
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■八丈島地熱巡検「再生可能エネルギーと地質学」のお知らせ
日程:2017年11月24日(金)〜25日(土)
募集人数:12〜20人
費用:25,000円程度
申込期限:10月31日(先着順)
詳しくは, http://kanto.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■道総研地質研究所ニュース(Vol.33, No.2[2017.8])
https://www.hro.or.jp/list/environmental/research/gsh/publication/gshnews/gshnews02/index.html
■地質地盤情報の活用と法整備を考える会
国土交通省の第4回「地下空間の利活用に関する安全技術の確立に関する小委員
会」の資料が公開されました. http://www.geo-houseibi.jp
*************(以下,関連団体の行事案内です)****************
■(後)2017年度特別展:地球を「はぎ取る」〜地層が伝える大地の記憶〜
7月15日(土)〜11月5日(日)(9月以降は月曜日ほか休館日あり)
会場:神奈川県立生命の星・地球博物館1階 特別展示室
http://nh.kanagawa-museum.jp/exhibition/special/ex153.html
■(共)2017年度日本地球化学会第64回年会
9月13日(水)〜15日(金)
会場:東京工業大学・大岡山キャンパス
http://www.geochem.jp/conf/2017/
>プログラム公開しました
http://www.geochem.jp/conf/2017/program.html
■(共)海底火山研究国際シンポジウム
海底火山噴火研究の国際的権威であるスミソニアン協会国立自然史博物館元館
長のRichard Fiske博士が日本地質学会国際賞を受賞・来日される機会に、日本
における海底火山研究の進捗状況を総括し、その将来を議論する研究シンポジ
ウムを開催します。
9月20日(水)14:00〜18:00
場所:国立科学博物館本館2階講堂
要事前申込(定員100名)申込締切:9月13日(水)
http://www.kahaku.go.jp/news/2017/seamount/
■地学クラブ講演会
ノルデンショルド一行の世界史的偉業と東京地学協会創立時の国際的文化行事
9月22日(金)14:00〜15:00
場所:東京地学協会地学会館
講演者:西川 治(東京大学名誉教授)
http://www.geog.or.jp/lecture/lecturescheduled/307-club302.html
■(共)第61回粘土科学討論会
9月25日(月)〜 27日(水)
会場:富山大学 五福キャンパス共通教育棟
http://www.cssj2.org/
■第202回地質汚染イブニングセミナー
9月29日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ902会議室
講師:中澤 努(産総研地質情報研究部門情報地質研究グループ長)
テーマ:台地の下の軟弱泥層:MIS6開析谷の埋積プロセスと地質特性―関東平
野における―
http://www.npo-geopol.or.jpz
■(後)第4回Slope tectonics 2017
10月14日(土)〜18日(水)
場所:京都大学宇治キャンパス黄檗プラザ
http://www.slope.dpri.kyoto-u.ac.jp/SlopeTectonics2017/st2017.html
■第15回男女共同参画学協会連絡会シンポジウム
10月14日(土)10:00〜17:00
場所:東京大学本郷キャンパス
http://www.djrenrakukai.org/symposium1.html
■(共)第15回国際放散虫研究集会(15th InterRad)
10月23日(月)〜27日(金)研究集会
20日(金)〜22日(日)プレ巡検
22日(日)サイエンスカフェ
28日(土)〜31日(火)ポスト巡検
会場:新潟大学など
http://interrad2017.random-walk.org/
■(協)第33ゼオライト研究発表会
11月30日(木)〜12月1日(金)
会場:長良川国際会議場
https://jza-online.org/events
■国際集会:RFG2018(次世代の資源に関する国際集会2018)
2018年6月16日(土)〜21日(木)(要旨締切:2018年1月15日)
場所:カナダ,バンクーバー市,国際会議場
http://rfg2018.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・東京工業大学理学院地球惑星科学系専任助教公募(10/15)
・東京工業大学理学院地球惑星科学系准教授公募(9/29)
・琉球大学理学部地学系(准教授、講師または助教)公募(9/29)
・平成30年度東京大学地震研究所客員教員公募(10/31)
・2018年度笹川科学研究助成募集(9/15-10/16)
・平成30年度東京大学地震研究所共同利用(10/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.386(臨時)[愛媛大会]台風18号接近に伴う対応について
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.386 2017/9/14┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[愛媛大会]台風18号接近に伴う対応について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[愛媛大会]台風18号接近に伴う対応について
──────────────────────────────────
台風通過等に伴う本大会行事の中止判断等の対応は,愛媛大学の緊急対応指針
に従い,各日ごとに以下のようにいたします.なお,大会期間に合わせて会場
で実施される集会等も本対応の対象となります.
【1】午前7時の時点で松山市に特別警報(高潮及び波浪を除く)又は暴風警報
(以下,特別警報等)が発表されている場合は,午前のプログラムを中止.午
前11時までに特別警報等が解除された場合,午後のプログラムから実施.
【2】午前11時の時点で特別警報等が発表されている場合は,午後のプログラム
を中止
この結果,予定されたプログラムが大幅に中止になった場合でも順延実施は行
いません.中止になったセッションの講演要旨の扱いについては,下記をご参
照ください.
http://www.geosociety.jp/science/content0070.html
また,プログラムが中止の場合,参加登録費等の払い戻しは原則行いません
ので,その旨ご了承ください.
行事中止に関する情報は,大会ホームページおよびgeo-flash(メールマガジン)
を通じて,逐次告知いたしますので,会員の皆様には大会期間中であってもご
確認の程,よろしくお願い申し上げます.
******以下,特に講演者の方へ*******
なお,交通機関等の影響で,やむをえず欠席(講演キャンセル)または遅刻す
る場合は必ず事前にご連絡をお願い致します。
連絡先:
◆ 〜9/15まで:学会事務局
電話03-5823-1150 メール<main[at]geosociety.jp>
◆ 9/16〜9/18:大会現地事務局(担当:アカデミックブレインズ)
電話:080-5363-8921 メール<gsj2017ehime[at]academicbrains.jp>
(注)[at]を@マークにして送信して下さい.
キャンセルの場合については,下記情報もご参照ください
http://www.geosociety.jp/science/content0094.html#090404
***************************
2017年9月14日
一般社団法人日本地質学会
行事委員会 委員長 岡田 誠
愛媛大会実行委員会 委員長 榊原正幸
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.387(臨時)[愛媛大会]台風18号接近に伴う対応について(9月16日15時)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.387 2017/9/16┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[愛媛大会]台風18号接近に伴う対応について(9月16日15時)
──────────────────────────────────
(1)中止情報
・小さなEarth Scientist の集いは中止が決定しました。
・愛媛大学生協は9月17日の終日営業中止が決定しました。
(弁当は注文分のみ準備されます)
(2)注意してください
・その他の行事が中止される場合は下記の時刻に決定されます。
17日午前の行事は当日朝7時に決定されます。
17日午後の行事は当日11時に決定されます。
17日夜の行事は夕方4時に決定されます。
中止情報は決まり次第ホームページおよび会場受付の掲示されます。
こまめに確認いただけますようお願いいたします。
学会サイト http://www.geosociety.jp/
大会サイト https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.389(臨時)[愛媛大会]17日午前の行事中止
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.389 2017/9/17 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】台風18号接近に伴う対応について(9月17日7時)
──────────────────────────────────
・松山市に暴風警報が発令されております。
本日午前の行事は中止が決定されました。
・午後の行事はこのあと11時に決定されます。
・夜の行事は夕方4時に決定されます。
中止情報はホームページ、会場受付に掲示されます。
こまめにチェックして頂けますようお願いします。
学会サイト http://www.geosociety.jp/
大会専用サイト https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.390(臨時)[愛媛大会]17日の全行事中止
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.390 2017/9/17 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】台風18号接近に伴う対応について(9月17日12時)
──────────────────────────────────
今後天候が一段と悪化すると予想されますので、
本日の行事は全て中止になりました。
学生院生で発表予定だった方、ランチョン/夜間小集会の世話人の方、
小さなEarth Scientistの集い関係者の方、特別対応がございます。
詳細はこちらをご覧ください。
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/static/typhoon?eventCode=geosocjp124&pageCode=typhoon
geo-Flashの配信はサーバーのスパム対策により到着に時間差が
生じております。最新の情報はホームページをご確認ください。
学会サイト http://www.geosociety.jp/
大会専用サイト https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.391(臨時)[愛媛大会]台風一過
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.391 2017/9/18 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】台風18号接近に伴う対応について
──────────────────────────────────
松山市の暴風警報は17日の23時過ぎに解除されました。
本日18日の行事は予定通り開催されます。
<注意事項>
・学生対象の17日分の口頭発表
プログラムができました。振るってご参加i頂き、熱い議論をお願いいたします。
http://geosociety.jp/uploads/fckeditor/geoFlash_img/2017Ehime/SP_session.pdf
・学生対象の17日分のポスター発表
希望される方は、本日早めにポスター会場にお越しください。
皆様もぜひ質問して、
geo-Flashの配信はサーバーのスパム対策により到着に時間差が
生じております。最新の情報はホームページをご確認ください。
学会サイト http://www.geosociety.jp/
大会専用サイト https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
http://geosociety.jp/uploads/fckeditor/geoFlash_img/2017Ehime/SP_session.pdf
【geo-Flash】No.393 2018年度代議員および役員選挙について
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.393 2017/9/19┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2018年度代議員および役員選挙について
【2】2018年度各賞候補者募集について
【3】日本地方地質誌全8巻完結!「2.東北地方」特別割引販売のお知らせ
【4】愛媛大会の忘れ物をお預かりしています
【5】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2018年度代議員および役員選挙について
──────────────────────────────────
10月13日(金)から「代議員」の立候補届の受付が開始されます.選挙告示は
News誌9月号または学会HPをご覧下さい.
代議員立候補受付期間:10月13日(金)〜11月6日(月)
詳しくは,
http://sub.geosociety.jp/members/content0096.html(会員のページ)
※「会員のページ」の選挙に関する案内から,立候補届の書式がダウンロード
できるようになっています.「会員のページ」へは会員番号・パスワードによ
るログインが必要です.ログインの方法はこちら.
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2018年度各賞候補者募集について
──────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして,研究の援助・奨励および研究業
績の表彰を行っています.本年も各賞の自薦,他薦による候補者を募集いたし
ます.期日厳守にて,たくさんのご応募をお待ちしております.
応募締切:2017年11月30日(木)必着
詳しくは,
http://sub.geosociety.jp/members/content0098.html(会員のページ)
※「会員のページ」へは会員番号・パスワードによるログインが必要です.
ログインの方法はこちら.
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本地方地質誌全8巻完結!「2.東北地方」特別割引販売のお知らせ
──────────────────────────────────
第8回配本 2.東北地方(712頁,口絵6頁.編集委員長:吉田武義)がまもな
く完成します(10月上旬刊行)。つきましては,日本地質学会会員の皆様に特
別割引価格で販売をお知らせします。
定価29,160円(税込)を会員特別割引価格25,500円(税・送料込)
お申し込みは,専用用紙にて直接朝倉書店までお願いいたします.
(新刊・既刊すべて特別価格で購入可能です)
学会HP「会員ページ」よりDLできます.
http://www.geosociety.jp/user.php
※「会員のページ」へは会員番号・パスワードによるログインが必要です.
ログインの方法はこちら.
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】愛媛大会の忘れ物をお預かりしています
──────────────────────────────────
愛媛大会(9/16-18)での忘れ物をいくつかお預かりしています.
お心当たりの方は,学会事務局( main@geosociety.jp)までお問い合わせ下さい.
・折り畳み傘(黒・グレーなど)
・茶色の小銭入れ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[125周年関連情報]寄付受付中!(クレジットカードも可)
──────────────────────────────────
125周年記念事業として,2018年5月東京での記念式典をはじめ,様々な事
業を計画しています.また,それら記念事業を実行するため,学会員や賛助会
員,さらには関連諸団体に寄付をお願いしております.
*醵金者一覧
http://www.geosociety.jp/125th/content0014.html
*記念事業に対する寄付のお願い
クレジットカード(VISA, Master, Diners)もご利用いただけます
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html#kifu
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■八丈島地熱巡検「再生可能エネルギーと地質学」のお知らせ
日程:2017年11月24日(金)〜25日(土)
募集人数:12〜20人
費用:25,000円程度
申込期限:10月31日(先着順)
詳しくは, http://kanto.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地質地盤情報の活用と法整備を考える会
国土交通省の答申が公開されました:平成29年9月8日、社会資本整備審議会・
交通政策審議会技術分科会 技術部会に設置された「地下空間の利活用に関する
安全技術の確立に関する小委員会」の答申が、大西有三委員長から石井啓一国
土交通大臣に手渡されました。(9月12日)
http://www.geo-houseibi.jp/cont10/main.html
*************(以下,関連団体の行事案内です)****************
■(後)2017年度特別展:地球を「はぎ取る」〜地層が伝える大地の記憶〜
7月15日(土)〜11月5日(日)(9月以降は月曜日ほか休館日あり)
会場:神奈川県立生命の星・地球博物館1階 特別展示室
http://nh.kanagawa-museum.jp/exhibition/special/ex153.html
■(共)第61回粘土科学討論会
9月25日(月)〜 27日(水)
会場:富山大学 五福キャンパス共通教育棟
http://www.cssj2.org/
■第202回地質汚染イブニングセミナー
9月29日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ902会議室
講師:中澤 努(産総研地質情報研究部門情報地質研究グループ長)
テーマ:台地の下の軟弱泥層:関東平野におけるMIS6開析谷の埋積プロセスと地質特性
http://www.npo-geopol.or.jpz
■(後)第4回Slope tectonics 2017
10月14日(土)〜18日(水)
場所:京都大学宇治キャンパス黄檗プラザ
http://www.slope.dpri.kyoto-u.ac.jp/SlopeTectonics2017/st2017.html
■(後)地球史研究所開設記念事業
主催:NPO法人地球年代学ネットワーク
▶オープニング・フェスタ
10月14日(土)10:00〜16:00
場所:赤磐市吉井会館(赤磐市周匝136-1)および周辺施設
参加費:無料
▶記念国際会議
10月15日(土)10:00〜20:30
会場:岡山国際交流センター(岡山市北区奉還町2丁目2-1)
http://jgnet.org/event20171014_1/
■第15回男女共同参画学協会連絡会シンポジウム
10月14日(土)10:00〜17:00
場所:東京大学本郷キャンパス
http://www.djrenrakukai.org/symposium1.html
■(共)第15回国際放散虫研究集会(15th InterRad)
10月23日(月)〜27日(金)研究集会
20日(金)〜22日(日)プレ巡検
22日(日)サイエンスカフェ
28日(土)〜31日(火)ポスト巡検
会場:新潟大学など
http://interrad2017.random-walk.org/
■(協)第33ゼオライト研究発表会
11月30日(木)〜12月1日(金)
会場:長良川国際会議場
https://jza-online.org/events
■国際集会:RFG2018(次世代の資源に関する国際集会2018)
2018年6月16日(土)〜21日(木)(要旨締切:2018年1月15日)
場所:カナダ,バンクーバー市,国際会議場
http://rfg2018.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・信州大学理学部助教(特定雇用)公募(物質循環学コース地球システム解析分野)(10/27)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.394 2018年度代議員選挙立候補:まもなく受付開始
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.394 2017/10/3┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2018年度代議員および役員選挙について
【2】2018年度各賞候補者募集について
【3】日本地方地質誌全8巻完結!「2.東北地方」会員特別割引販売のお知らせ
【4】第9回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
【5】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【6】日本地球惑星科学連合:代議員選挙投票のお願い
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2018年度代議員および役員選挙について
──────────────────────────────────
10月13日(金)から「代議員」の立候補届の受付が開始されます.選挙告示は
News誌9月号または学会HPをご覧下さい.
代議員立候補受付期間:10月13日(金)〜11月6日(月)
詳しくは,
http://sub.geosociety.jp/members/content0096.html(会員のページ)
※「会員のページ」の選挙に関する案内から,立候補届の書式がダウンロード
できるようになっています.「会員のページ」へは会員番号・パスワードによ
るログインが必要です.ログインの方法はこちら.
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2018年度各賞候補者募集について
──────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして,研究の援助・奨励および研究業
績の表彰を行っています.本年も各賞の自薦,他薦による候補者を募集いたし
ます.期日厳守にて,たくさんのご応募をお待ちしております.
応募締切:2017年11月30日(木)必着
詳しくは,
http://sub.geosociety.jp/members/content0098.html(会員のページ)
※「会員のページ」へは会員番号・パスワードによるログインが必要です.
ログインの方法はこちら.
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本地方地質誌全8巻完結!「2.東北地方」会員特別割引販売のお知らせ
──────────────────────────────────
第8回配本 2.東北地方(712頁,口絵6頁.編集委員長:吉田武義)がまもな
く完成します(10月上旬刊行).つきましては,日本地質学会会員の皆様に特
別割引価格で販売をお知らせします.
定価 29,160円(税込)を会員特別割引価格 25,500円(税・送料込)
お申し込みは,専用用紙にて直接朝倉書店までお願いいたします.
(新刊・既刊すべて特別価格で購入可能です)
学会HP「会員ページ」よりDLできます.
http://www.geosociety.jp/user.php
※「会員のページ」へは会員番号・パスワードによるログインが必要です.
ログインの方法はこちら.
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第9回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
──────────────────────────────────
***応募締切:2018年1月11日(木)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.
チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募集!!
投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募フォームからでも
メール添付でもご応募いただけます.
会員の皆様からの応募もお待ちしています.
最優秀賞:1点 賞金5万円
優秀賞:2点 賞金2万円
ジオパーク賞:1点 賞金2万円
日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[125周年関連情報]寄付受付中!(クレジットカードも可)
──────────────────────────────────
125周年記念事業として,2018年5月東京での記念式典をはじめ,様々な事
業を計画しています.また,それら記念事業を実行するため,学会員や賛助会
員,さらには関連諸団体に寄付をお願いしております.
*醵金者一覧
http://www.geosociety.jp/125th/content0014.html
*記念事業に対する寄付のお願い
クレジットカード(VISA, Master, Diners)もご利用いただけます
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html#kifu
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】日本地球惑星科学連合:代議員選挙投票のお願い
──────────────────────────────────
日本地球惑星科学連合では下記の期間に代議員の選挙が行われます.本連合は
地球科学関連の活動に大きく関与し,地質学の分野にとっても重要な組織で,
本学会の会員も代議員の候補となっています.地質学の発言力向上のためにも,
皆様の投票が重要ですので,連合正会員の皆様は各セクションで本選挙への積
極的な投票をお願い申し上げます.
[代議員選挙日程]
選挙投票開始 2017年10月 2日(月)9:00
選挙投票締切 2017年11月 1日(水)17:00
選挙開票,結果報告 2017年11月 6日(月)
[投票方法]
投票期間中に会員ページ(https://www.member-jpgu.org/jpgu/ja/)へご自身の
IDとパスワードでログインし,左側の「代議員選挙」ボタンから投票画面へお
進みください.
[代議員候補者名簿]
https://www.member-jpgu.org/jpgu/ja/election/list/
[現在の投票状況]
https://www.member-jpgu.org/jpgu/ja/election/information/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■八丈島地熱巡検「再生可能エネルギーと地質学」のお知らせ
日程:2017年11月24日(金)〜25日(土)
募集人数:12〜20人
費用:25,000円程度
申込期限:10月31日(先着順)
詳しくは,http://kanto.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地質地盤情報の活用と法整備を考える会
・日本学術会議「記録」公開
9月26日,日本学術会議土木工学・建築学委員会インフラ健全化システム分科会
の記録「インフラとしての情報基盤の整備と利活用について」が公開されまし
た.インフラを構成する地質地盤情報について言及されています.
・日本学術会議公開シンポジウム
9月17日,日本学術会議公開シンポジウム「災害軽減と持続的社会の形成に向け
た科学と社会の協働・協創」が開催されました.佃 栄吉氏が地質地盤に関す
る最新の動向について報告しました.
http://www.geo-houseibi.jp
*************(以下,関連団体の行事案内です)****************
■(後)2017年度特別展:地球を「はぎ取る」〜地層が伝える大地の記憶〜
7月15日(土)〜11月5日(日)
会場:神奈川県立生命の星・地球博物館1階 特別展示室
http://nh.kanagawa-museum.jp/exhibition/special/ex153.html
■(後)第4回Slope tectonics 2017
10月14日(土)〜18日(水)
場所:京都大学宇治キャンパス黄檗プラザ
http://www.slope.dpri.kyoto-u.ac.jp/SlopeTectonics2017/st2017.html
■(後)地球史研究所開設記念事業
主催:NPO法人地球年代学ネットワーク
▶オープニング・フェスタ
10月14日(土)10:00〜16:00
場所:赤磐市吉井会館(赤磐市周匝136-1)および周辺施設
参加費:無料
▶記念国際会議
10月15日(日)10:00〜20:30
会場:岡山国際交流センター(岡山市北区奉還町2丁目2-1)
http://jgnet.org/event20171014_1/
■(共)第15回国際放散虫研究集会(15th InterRad)
10月23日(月)〜27日(金)研究集会
20日(金)〜22日(日)プレ巡検
22日(日)サイエンスカフェ
28日(土)〜31日(火)ポスト巡検
会場:新潟大学など
http://interrad2017.random-walk.org/
■第203回地質汚染イブニングセミナー
10月27日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ 902会議室
講師:蔵冶光一郎(東京大学大学院農学生命科学研究科付属演習林企画部教授)
演題:千葉県と東大のかかわりと水循環
http://www.npo-geopol.or.jp
■日本自治体危機管理学会2017年度研究大会
10月28日(土)
場所:明治大学駿河台キャンパス
参加無料
http://www.jemaweb.org/news.html#20170907
■第28回地質汚染調査浄化技術研修会
共催:日本地質学会環境地質部会ほか
11月17日(金)〜19日(日)
場所:関東ベースンセンター(千葉県香取市)
会費:会員 45,000円,非会員55,000円,学生35,000円※昼食代を含む
http://www.npo-geopol.or.jp
■(協)第33ゼオライト研究発表会
11月30日(木)〜12月1日(金)
会場:長良川国際会議場
https://jza-online.org/events
■第27回環境地質学シンポジウム
12月1日(金)〜2日(土)
場所:日本大学文理学部 オーバルホール
http://www.jspmug.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・海洋研究開発機構(JAMSTEC):
地震津波海域観測研究開発センター特任技術研究員募集 (10/31)
海洋掘削科学研究開発センター研究員or技術研究員募集(11/8)
・山形大学理学部(地球科学分野)准教授公募(11/10)
・北海道大学理学研究院テニュアトラック助教(地球化学)公募(11/14)
・山田科学振興財団2018年度研究援助候補推薦(学会締切18/1/29)
・第59回藤原賞受賞候補者推薦依頼(学会締切11/20)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
125記念トリビア12 誤りは早く直しましょう
〜2018年日本地質学会創立125周年を記念して〜
トリビア学史 12 誤りは早く直しましょう
矢島道子(日本大学文理学部)
60周年記念本における北京大学の記述
『日本の地質学100年』(日本地質学会,1993)の,中国関連の記述に誤りがあると中国科学史家・武上真理子氏(元京都大学人文科学研究所)より指摘を受けた.戦前の中国での地質学研究の記述である.上記100周年記念本を所持されていたら,訂正してほしい.
周年記念本
日本地質学会は戦後,周年記念本を3冊出版している.1953年に60周年記念本,1968年に75周年記念本と,1993年に上記の100周年記念本である.海外地質調査については60周年記念本が実際に現地の機関に勤務していた地質技術者によって記述されていてくわしい.75周年記念本では特に関係の章はなく,表形式で多少の情報が記述されている.100周年記念本では岡野武雄氏(元工業技術院地質調査所)が「第4章 第二次大戦前・中の海外地質調査」を執筆している.岡野氏が緒言で述べているように,60周年記念本,75周年記念本,あるいは東京地学協会の取り組んだ『東亜地質鉱産誌』等を基にして編集したものである.
上海自然科学研究所
最初の誤りは436ページの上海自然科学研究所の記述「1926年12月に設置」として書かれているところである.1926年12月に「大綱」は出来上がったが,この時には予備研究が立ち上げられただけで,研究所の設置がされたわけではない.研究所の正式な開所は1931年4月,建物の竣工は同年6月である.60周年記念本では尾崎金右衛門が執筆しており,「1926年12月には上海自然科学研究所設置を議決した」と記述され,「研究所の建設をまたずに直ちに中国における興味ある研究を開始した」とのことである.「この予備研究時代には…研究したが,…1928年に済南事件が勃発したため,中国側委員は総辞職をなした」と記述は続いている.
北京大学
同じページに,北京大学についての項目があり,「1923年9月,北京大学理学院が再開した」と始まる.しかし,この「1923年」は全くの間違いである.60周年記念本では「1938 〜1945年の北京大学地質学教室」を冨田達が記述している.1923年という文字は一切現れない.「1938年9月初めに北京大学理学院が復開した」と記述は始まる.「院長は文元模氏(大正9年東大物理学科卒業)」,「中国地質学者は殆ど全て北京を離れて去っていたので,冨田達が地質学系主任教授に招聘せられたのであるが,学系唯一の教師であり,また理学院唯一の日本籍教授でもあった.そして名誉教授の任務を代行した」という記述が続く.その後,東大の加藤武夫が1年後に名誉教授に就任し,冨田は首席教授となる.5年後には体制が整い,地質学系には10人の教師がそろった.日本人は冨田のほかに,蔵田延男,酒井栄吾がいた.
武上氏によれば,北京大学の「正史」では,1937年以降に北京大学が日本人によって「再開」されたという事実は,完全に抹消されているそうだ.さらに,私は,2014年に北京で開かれた国際地質科学史シンポジウムに参加したが,中国の地質学史の中にアメリカ人,フランス人等は登場するのだが,日本人地質学者は誰一人登場しなかった.歴史研究において正しい事実を突き止めていくことは重要で,小さな誤謬はすみやかに修正されなければならない.
なお,これまでの周年記念本に誤りが見つかった場合には,できるだけ早くお知らせください.誤りは修正していきたいと思っています.
文 献
日本地質学会,1953,『日本地質学會史:日本地質学会60周年記念』
日本地質学会,1968,『日本の地質学:現状と将来への展望』
日本地質学会,1993,『日本の地質学100年』
【geo-Flash】No.395 [愛媛大会]プログラム中止の要旨等の取り扱い
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.395 2017/10/17┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】台風18号によるプログラム中止となった講演要旨等の取り扱い
【2】会員名簿データを整理中です。住所変更はお早めに!
【3】2018年度代議員および役員選挙について
【4】2018年度各賞候補者募集について
【5】日本地方地質誌全8巻完結!「2.東北地方」会員特別割引販売中
【6】第9回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
【7】[125周年関連情報]オリジナルクリアファイル完成
【8】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】台風18号によるプログラム中止となった講演要旨等の取り扱い
──────────────────────────────────
愛媛大会では,2日目(9月17日)の全行事が台風の影響で中止になり,発表
を予定されていた皆様にはたいへん残念なことになりました.ただし,学生,
院生の発表については,翌3日目(9月18日)に会場等の調整をし,発表してい
ただくことができましたので,その点は良かったと思っております.
つきましては,台風によりプログラムそのものが中止となった講演要旨の扱
いについては,【今回に限り】以下の様に取り扱うことにいたしましたので,
なにとぞご了承ください.
1. 講演要旨に対する著者のプライオリティ保護の見地からJ-STAGEに公開し,
引用可能といたします.ただし,今大会においては専門家による議論には供さ
れておりませんので「台風によりプログラム中止」との文言を明記をいたしま
す.
2. 今回未発表になったものと同じ発表を次年度の学術大会で行いたい等の事
情がある場合は,通常の講演キャンセルと同様の扱いとし,J-STAGEには公開し
ません.この場合,講演要旨は引用不可といたします.講演キャンセルとする
場合は,11月10日(金,厳守)までに事務局あてにご連絡下さい.
2017年10月14日
行事委員会委員長 岡田 誠
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】会員名簿データを整理中です。住所変更はお早めに!
──────────────────────────────────
日本地質学会では,学会員相互の交流と親睦を図る目的で,2年ごとに会員
名簿を発行することを運営規則にうたっております.2017年度はその発行
年にあたり,年度内に発行の予定で準備を行っております.
名簿の発行様式は前回と同様で,全会員を収録します.本会としては,個人
情報保護法の制約はあるとしても,会員の皆様が上記の目的に沿って利用で
きるような,従来規模の名簿を作成したいと考えておりますので,ご理解と
ご協力をお願いいたします.
なお,2017年度末で退会を予定されているかたのお名前は収録いたしません.
***会員情報のWEB画面での更新締切:2017年12月6日(水)***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2018年度代議員および役員選挙について
──────────────────────────────────
「代議員」の立候補届の受付中です.
代議員立候補受付期間:10月13日(金)〜11月6日(月)
詳しくは,
http://sub.geosociety.jp/members/content0096.html(会員のページ)
※「会員のページ」の選挙に関する案内から,立候補届の書式がダウンロード
できるようになっています(要ログイン).
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2018年度各賞候補者募集について
──────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして,研究の援助・奨励および研究業
績の表彰を行っています.本年も各賞の自薦,他薦による候補者を募集いたし
ます.期日厳守にて,たくさんのご応募をお待ちしております.
応募締切:2017年11月30日(木)必着
詳しくは下記より(要ログイン),
http://sub.geosociety.jp/members/content0098.html(会員のページ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】日本地方地質誌全8巻完結!「2.東北地方」会員特別割引販売中
──────────────────────────────────
第8回配本 2.東北地方(712頁,口絵6頁.編集委員長:吉田武義)がまもな
く完成します(10月上旬刊行).つきましては,日本地質学会会員の皆様に特
別割引価格で販売をお知らせします.
定価 29,160円(税込)を会員特別割引価格 25,500円(税・送料込)
お申し込みは,専用用紙にて直接朝倉書店までお願いいたします.
(新刊・既刊すべて特別価格で購入可能です)
学会HP「会員ページ」よりDLできます(要ログイン).
http://www.geosociety.jp/user.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】第9回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
──────────────────────────────────
***応募締切:2018年1月11日(木)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募集!!
投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募フォームからでも
メール添付でもご応募いただけます.
会員の皆様からの応募もお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】[125周年関連情報]オリジナルクリアファイル完成
──────────────────────────────────
惑星地球フォトコンテストでは,毎年素晴らしい写真が入選しています.これ
らの写真を活用できないかと125周年記念事業実行委員会で検討した結果,学会
オリジナルのクリアファイルを作成することになりました.クリアファイルの
表裏に惑星地球フォトコンテストの入選写真や富士山などの国内で撮影された
美しい写真を配しました.「日本の地質」を国内外に紹介するツールとしても
活用できます.こんな綺麗なクリアファイルを使っていると,ご家族,知人,
仕事関係者から必ず注目されること請け合いです.
A4対応 両面フルカラー・3種類1セット:定価 500円
(注)3枚1セットでの販売となります.単品のご注文はお受けできません.
http://www.geosociety.jp/125th/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】[125周年関連情報]寄付受付中!(クレジットカードも可)
──────────────────────────────────
125周年記念事業として,2018年5月東京での記念式典をはじめ,様々な事
業を計画しています.また,それら記念事業を実行するため,学会員や賛助会
員,さらには関連諸団体に寄付をお願いしております.
*醵金者一覧
http://www.geosociety.jp/125th/content0014.html
*記念事業に対する寄付のお願い
クレジットカード(VISA, Master, Diners)もご利用いただけます
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html#kifu
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■八丈島地熱巡検「再生可能エネルギーと地質学」参加者募集
日程:11月24日(金)〜25日(土)
募集人数:12〜20人
費用:25,000円程度
申込期限:10月31日(先着順)
詳しくは, http://kanto.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■(後)2017年度特別展:地球を「はぎ取る」〜地層が伝える大地の記憶〜
7月15日(土)〜11月5日(日)
会場:神奈川県立生命の星・地球博物館1階 特別展示室
http://nh.kanagawa-museum.jp/exhibition/special/ex153.html
■(後)第4回Slope tectonics 2017
10月14日(土)〜18日(水)
場所:京都大学宇治キャンパス黄檗プラザ
http://www.slope.dpri.kyoto-u.ac.jp/SlopeTectonics2017/st2017.html
■第8回「海洋科学研究センター」市民公開講座
「小樽港の歴史と海洋環境」
主催:北海道立総合研究機構 地質研究所
10月21日(土)13:30〜16:00
場所:海洋科学研究センター(小樽市築港3-1)
入場無料・要申込(10/20締切)
定員:30名(先着順)
https://www.hro.or.jp/list/environmental/research/gsh/
■(共)第15回国際放散虫研究集会(15th InterRad)
10月23日(月)〜27日(金)研究集会
20日(金)〜22日(日)プレ巡検
22日(日)サイエンスカフェ
28日(土)〜31日(火)ポスト巡検
会場:新潟大学など
http://interrad2017.random-walk.org/
■海洋理工学会秋季大会シンポジウム
「西之島から地球を知る」
10月26日(木)
場所:京都大学楽友会館
http://amstec.jp/convention/H29_autum.html
■魅せるサイエンスワークショップ02
「タイポグラフィックスー本当のフォント使いー」
10月27日(金)13:15〜15:15
場所:高知コアセンターセミナー室
参加無料
高知大学・笹岡美穂( jm-sasaokam@kochi-u.ac.jp )
http://tonton.amaneku.com/sp/list.php?id=20171004040548_56IRgR
■シンポジウム:九州北部豪雨の教訓と地域防災力
11月23日(木・祝)13:00〜16:30
主催:地区防災計画学会ほか
場所:福岡大学文系センター棟4階第4会議室
対象:地域防災力の強化に興味のある方(参加費無料)
http://gakkai.chiku-bousai.jp/ev171123.html
■(協)第33ゼオライト研究発表会
11月30日(木)〜12月1日(金)
会場:長良川国際会議場
https://jza-online.org/events
■第1回文化地質研究会 総会・研究発表会
2018年3月10日(土)〜11日(日)
場所:大谷大学(京都市北区)
講演要旨締切:12月31日
https://sites.google.com/site/bunkageology/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・JAMSTEC深海・地殻内生物圏研究分野ポストドクトラル研究員募集(11/6)
・JAMSTEC特任技術支援職募集(11/6)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No.396(臨時)代議員選挙:11月6日(月)18時 立候補届け締切です!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.396 2017/11/2┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2018年度代議員選挙:11月6日(月)18時 立候補届け締切です!
─────────────────────────────────
代議員選挙の立候補届けは,11月6日(月)18時締切(必着)です.
代議員及び役員選挙は,2年に一度の選挙で,現在の全ての代議員,全ての理事
が改選となります.立候補を予定されている方は,くれぐれも期日に遅れない
ようにご提出ください.
☆立候補届けを提出の際には,記入漏れが無いか,必ず確認してください.
☆立候補届けは,選挙管理委員会<main@geosociety.jp>あてにお届けください
(本メールに返信しないでください).
********************************************
代議員立候補受付締切:11月6日(月)18時必着
********************************************
本日(11月2日)14:30 現在の代議員立候補者数は以下のとおりです.
( )内の数字は定数.
[全国区]49(100)
[地方支部区]44(100)
内訳:北海道:4(5)・東北:1(8)・関東:10(42)・中部:12(17)
近畿:9(10)・四国:2(4)・西日本:6(14)
立候補届出状況はHPトップからもご確認いただけます.
<http://www.geosociety.jp/>
詳しくは,
<http://sub.geosociety.jp/members/content0096.html>(会員のページ)
※「会員のページ」の選挙に関する案内から,立候補届の書式がダウンロード
できます.「会員のページ」へは会員番号・パスワードによるログインが必要
です.ログインの方法はこちら.
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
地質調査にあたって保護法令などの遵守を
地質調査にあたって保護法令などの遵守を
正会員 小滝篤夫・鈴木寿志
写真1.天然記念物の解説看板下の「注意」は破壊行為後に設置
写真2.地層境界部に記入された文字
近年,研究者の国立公園など法的に保護された区域での試料採取が問題になっています.日本地質学会でも2008年に理事会名で『野外調査において心がけたいこと』を公表し,そのなかで「史跡・名勝・天然記念物においては,文化庁や地元自治体などへの必要な手続きなしには露頭をハンマーでたたいて岩石試料を採取するなどの破壊を伴う調査はもちろん,転石の採取もできません.やむを得ず研究上必要な場合は許可申請の手続きを行い,必要最低限の採取に留めることが重要です.許可を得ておくことによって,その成果を公表することも可能になります.」と述べています.
しかし残念ながら,最近このような呼びかけを全く無視するような行為が,筆者らが関係した露頭であったことを報告し,地質学会会員に地質調査にあたって法令の遵守と常識ある行動を訴えたいと思います.
京都府福知山市三和町菟原下の林道沿いに露出する珪質泥岩の露頭では,はじめに桑原ほか(1991)によりペルム紀最末期の放散虫化石が報告され,後にYamakita et al.(1999)により三畳紀最初期のコノドントが発見されたことで,ペルム紀-三畳紀境界をまたぐ極めて重要な露頭であることが証明されました.このことは京都府レッドデータブック(楠,2015)でも指摘され,人為的破壊が進まないよう保存が求められました.これらの指摘を受け,2016年8月24日に市の天然記念物に指定されて保護が図られ,露頭の科学的意義を解説する説明板が今年の2月27日に設置されました(写真1).それにもかかわらず説明板設置後,二回にわたって無断で露頭にペイントで数字等を書き込み,試料採取を行ったと疑われる行為がありました(写真2).非常に残念なことです.露頭の地主さんをはじめ地域住民からも研究者の常識を疑う声が上がっています.私たちはこの無許可の破壊行為に対し断固として抗議し,二度とこのような勝手な行為が行われないよう求めます.
地質学が広く市民に理解され受け入れられていくためにも,私たち地質学に関わる者は,上記の『心がけたいこと』を一層意識して野外調査にあたっていく必要があることを痛感します.
文 献
桑原希世子ほか, 1991, 地質雑,97, 1005-1008.
Yamakita et al., 1999, Jour. Geol. Soc. Japan, 105, 895-898.
楠 利夫,2015,京都府レッドデータブック第3巻,地形地質自然生態系.224.
2017.11.7掲載
125記念トリビア学史 13 地方で生きる:福井県の場合
〜2018年日本地質学会創立125周年を記念して〜
トリビア学史 13 地方で生きる:福井県の場合
矢島道子(日本大学文理学部)・浜崎健児(Ultra Trex㈱)
図 (左)岩佐巌.葉賀(1991)より (右)市川新松.川崎ほか(2013)より
日本の地質学の歴史を調べていると,話はどうしても東京や京都などの都市中心になる.基本的には東京大学で地質学者が育てられ,地質調査所で調査にはげみ,地質学会で議論するという構図で,日本の地質学は始まったので,致し方がないのかもしれない.ただ,目を凝らして見ていけば,いろいろな地方の動きも見えてくる.福井県を一例として報告してみたい.
岩佐巌
ドイツ・フライベルクにある鉱山学校は世界的に有名だが,そこに入学した最初の日本人は原田豊吉(1861−1894)ではない.福井藩出身の岩佐巌(1852−1899)である.フライベルクで調査した堀越叡氏(1932−2009)から,フライベルクでは今井ウワオと表記されていたと伺っていた(堀越,私信).岩佐巌は福井藩の医師,岩佐家の出で,1860年代後半に今井に改姓し,1880年ころ復姓した.福井藩は進取に富み,外国人技術者の受け入れも,留学者数も全国で飛びぬけて多い.
今井巌は,明治元年にできた医学校(のちの大学東校)に入学したと思われる.東京帝国大学五十年史には明治初年の医学校の動きがくわしく記されているが,最初の入学生については記載がない.また,同じ岩佐家の岩佐純(1835−1912)が東京医学校の制度化に大きく関わっていた.1870(明治3)年,今井巌は医学生としてドイツ留学を命じられるが,フライベルク鉱山学校で鉱山学を修めた.ドイツで青木周藏公使の勧めもあったといわれているが,医学から地質学への転向は珍しい.1877(明治10)年に帰国して,開学したばかりの東京大学の冶金学とドイツ語の教授となる.明治14年には東京大学文学部教授兼務となり,その後,住友の別子銅山に勤務した.岩佐の努力は日本全体への寄与となっていった.
和田維四郎
1870(明治3)年,明治政府は貢進生制度を設けた.福井藩からは南部球吾(1855−1928)が選ばれた.東京開成学校卒業後,明治8年文部省の第1回アメリカ留学生となりコロンビア大学で鉱山学を学んだ.帰国後,三菱鉱山会社に入社し,三菱炭鉱の基礎を作った.
福井県小浜藩からは和田維四郎(1856−1920)が推薦された.和田は,東京開成学校卒業後,明治10年の東京大学開学時には地質学・金石学の助教となっている.
貢進生で地質学者になったのは,小藤文次郎(1856−1935,津和野藩),安東 清人(1854−1886,熊本藩),長谷川芳之助(1856−1912 唐津藩),松井直吉(1857−1911 大垣藩)など数名いる.長谷川,松井の二人も明治8年コロンビア大学に留学して鉱山学を学んだが,長谷川は製鉄会社に就職し,松井は最終的に化学者になった.
本邦金石講究会
今井と和田は,ほぼ同郷で,鉱物が大好きで,東京大学で顔を合わせており,一緒に行動していたこともあったようである.今井と和田が“本邦金石講究会規則”(明治12年)を「会主」として呼びかけている貴重な資料が現存する.原本は(財)益富地学会館の石橋隆氏が保有している.本会則の紹介は別途石橋氏により実施される予定でありその発表が待たれる.
市川新松
市川新松(1868−1941旧姓打方)は現在の福井県福井市に生まれ,小学校を卒業後,その代用教員となり,刻苦努力して独学を続け,三重県師範学校助教諭になった.師範学校在職中に京都帝国大学の比企忠教授を訪ね,美しい鉱物に出会った.1904年師範学校鉱物科教員の免許を取り,山梨県や和歌山県の師範学校に勤務した後,郷里に戻って,鉱物の研究を進めた.自宅を整備し,市川鉱物研究室と称して研究を続けた.当時,東京大学鉱物学教室の神保小虎教授と確執が生じ,今度は英語やドイツ語も自修し,外国語で論文を書き,海外では高い評価を得るようになった.水晶の研究が有名である.1933年に天覧の光栄も浴したという.
市川鉱物研究室は,長男の市川渡(1902−1986)らの整理の努力をへて,その標本類は国の登録記念物に指定された.
福井の人が福井に根をおろして研究を始める歴史も,作り始められたことになる.
文 献
葉賀七三男,1991, 鉱業会百話⑪ 岩佐巌. 『鉱業会百話(上)』.
東京帝國大学編,『東京帝国大学五十年史』上冊,1932年.
川崎雅之・宮島宏 2013,市川新松と市川鉱物研究室.岩石鉱物科学,42,34-40.
【geo-Flash】No.397 2018年度学生・院生の割引会費申請受付開始
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.397 2017/11/7┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[愛媛大会]台風によるプログラム中止となった要旨の取り扱い
【2】2018年度会費払込(学生・院生の割引会費申請受付開始)
【3】会員名簿データを整理中です。住所変更はお早めに!
【4】2018年度代議員および役員選挙
【5】2018年度各賞候補者募集中(11/30締切)
【6】第9回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
【7】コラム:地質調査にあたって保護法令などの遵守を
【8】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[愛媛大会]台風によるプログラム中止となった要旨の取り扱い
──────────────────────────────────
愛媛大会でプログラム中止となり,未発表になったものと同じ発表を次年度の
学術大会で行いたい等の事情がある場合は,通常の講演キャンセルと同様の扱
いとし,J-STAGEには公開しません.この場合,講演要旨は引用不可といたしま
す.「講演キャンセルを希望する場合」は,11月10日(金,厳守)までに学会
事務局までご連絡下さい.
メール<main[at]geosociety.jp> FAX:03-5823-1156
プログラム中止となった講演要旨等の取り扱いについての詳細は,
http://www.geosociety.jp/science/content0077.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2018年度会費払込(学生・院生の割引会費申請受付開始)
──────────────────────────────────
2018年度の会費払込について,学部に在籍している学生の方,定収のない大学
院生(研究生)の方で,それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費
を適用します.対象となる方は忘れずに申請して下さい.
(※割引の適用を希望する場合,申請は毎年必要です)
************************************************************
割引会費請求書発行前締切:2017年11月20日(金)
************************************************************
2018年度会費払込の詳細,割引会費申請用紙はこちらから
http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】会員名簿データを整理中です。住所変更はお早めに!
──────────────────────────────────
現在,会員名簿データを整理中です(2017年3月発行予定).
名簿の発行様式は前回と同様で,全会員を収録します.学会員相互の交流と親
睦を図る目的に沿ってご利用いただけるよう,従来規模の名簿作成を予定して
います。ご理解とご協力をお願いいたします.なお,2017年度末で退会を予定
されている方のお名前は収録いたしません.
***会員情報のWEB画面での更新締切:2017年12月6日(水)***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2018年度代議員および役員選挙について
──────────────────────────────────
代議員及び役員選挙は,2年に一度の選挙で,現在の全ての代議員,全ての理事
が改選となります.代議員の立候補届出は11月6日に締切ました.選挙広報・投
票用紙は,11月25日頃までに届くよう郵送予定です.
選挙の詳細はこちらから(会員のページ・要ログイン)
http://sub.geosociety.jp/members/content0096.html
立候補届出状況はこちから
http://www.geosociety.jp/news/n134.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2018年度各賞候補者募集中(11/30締切)
──────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして,研究の援助・奨励および研究業
績の表彰を行っています.本年も各賞の自薦,他薦による候補者を募集いたし
ます.期日厳守にて,たくさんのご応募をお待ちしております.
応募締切:2017年11月30日(木)必着
詳しくは下記より(要ログイン),
http://sub.geosociety.jp/members/content0098.html(会員のページ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】第9回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
──────────────────────────────────
***応募締切:2018年1月11日(木)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.今年は2018年の学会創立125周年を記念した特別賞も設けました.
会員の皆様からの応募もお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・学会創立125周年記念賞:1点 賞金5万円(今回のみ)
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞(会員限定の賞です):1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp/
**蒲郡市生命の海科学館2017年冬のミニ企画展**
「第8回惑星地球フォトコンテスト入賞作品展」
11月23日(木)〜2018年2月25日(日)入場料無料
http://www.city.gamagori.lg.jp/site/kagakukan/geophoto2017.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】コラム:地質調査にあたって保護法令などの遵守を
──────────────────────────────────
正会員 小滝篤夫・鈴木寿志
近年,研究者の国立公園など法的に保護された区域での試料採取が問題になっ
ています.日本地質学会でも2008年に理事会名で『野外調査において心がけた
いこと』を公表し,そのなかで「史跡・名勝・天然記念物においては,文化庁
や地元自治体などへの必要な手続きなしには露頭をハンマーでたたいて岩石試
料を採取するなどの破壊を伴う調査はもちろん,転石の採取もできません.や
むを得ず研究上必要な場合は許可申請の手続きを行い,必要最低限の採取に留
めることが重要です.許可を得ておくことによって,その成果を公表すること
も可能になります.」と述べています.
しかし残念ながら,最近このような呼びかけを全く無視するような行為が,
筆者らが関係した露頭であったことを報告し,地質学会会員に地質調査にあたっ
て法令の遵守と常識ある行動を訴えたいと思います.
全文はこちら、、、http://www.geosociety.jp/faq/content0745.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】[125周年関連情報]寄付受付中!(クレジットカードも可)
──────────────────────────────────
125周年記念事業として,2018年5月東京での記念式典をはじめ,様々な事
業を計画しています.また,それら記念事業を実行するため,学会員や賛助会
員,さらには関連諸団体に寄付をお願いしております.
*醵金者一覧
http://www.geosociety.jp/125th/content0014.html
*記念事業に対する寄付のお願い
クレジットカード(VISA, Master, Diners)もご利用いただけます
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html#kifu
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】支部情報
──────────────────────────────────
[四国支部]
■第17回四国支部総会・講演会・巡検
<四国支部総会・講演会>
12月16日(土) 11:00〜17:00(予定)
場所:愛媛大学メディアセンター
<巡検「道後のHigh-Mg安山岩」>
12月17日(日)8:30〜11:30
講演・巡検申込締切:12月1日(金)厳守
<市民講演会>
12月17日(日)13:30〜15:30
会場:愛媛大学南加記念ホール
「ジオの視点で地域を元気に! –四国西予ジオパークの取り組み–」
高橋 司(西予市城川支所長,元四国西予ジオパーク推進協議会事務局長)
「南海トラフ巨大地震への備え」
高橋治郎(元愛媛大学教育学部教授)
詳しくは,http://www.gsj-shikoku.com/research.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地震本部ニュース秋号
地震調査研究の最先端(p.10)
地球科学と津波防災:遠地津波の遅れと初動反転の原因解明 ほか
http://www.jishin.go.jp/main/index.html
*************(以下,関連団体の行事案内です)****************
■平成29年度国土技術研究会
「のこすこと、つくること どちらも国土技術です」
11月13日(月)〜14日(火)
会場:中央合同庁舎2号館(千代田区霞が関)
参加費無料
http://www.mlit.go.jp/chosahokoku/giken/
■国際講演会 「ベルギーにおける地層処分計画の現状と今後」
主催:原子力発電環境整備機構(NUMO)※日英同時通訳付
11月14(火)13:30〜16:00
会場:三田NNホール&スペース多目的ホール(東京都港区芝)
参加申込締切:11月10日(金)17時
http://www.numo.or.jp/topics/201717102014.html
■情報通信学会・地区防災計画学会共催 国際コミュニケーション・フォーラム
「ICT×AI×防災・減災」
11月18日(土)15:00〜18:00
場所:早稲田大学早稲田キャンパス(参加費無料)
http://www.jsicr.jp/operation/forum/index.html
■第26回素材工学研究懇談会
金属プロセスと素材の最近の研究開発動向
11月21日(火)〜22日(水)
会場:東北大学片平さくらホール2階会議室
http://www2.tagen.tohoku.ac.jp/general/event/sozai/2017/
■火山災害軽減のための方策に関する国際ワークショップ2017
―火山監視と防災―
11月22日(水)9:30〜16:30
会場:都道府県会館(東京都千代田区平河町)
http://www.mfri.pref.yamanashi.jp/
■(共)蒲郡市生命の海科学館2017年冬のミニ企画展
「第8回惑星地球フォトコンテスト入賞作品展」
11月23日(木)〜2018年2月25日(日)
入場料無料
http://www.city.gamagori.lg.jp/site/kagakukan/geophoto2017.html
■火山噴火国際シンポジウム2017:火山噴火と防災対応
11月24日(金)10:00~16:00
会場:ホテル談露館(山梨県甲府市丸の内)
http://www.mfri.pref.yamanashi.jp/
■第204回地質汚染イブニングセミナー
11月24日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ902会議室
「水俣病と水質汚染健康被害(井戸水ヒ素中毒と対比して)」
緒方 剛(土浦保健所長)
http://www.npo-geopol.or.jp
■(協)第33ゼオライト研究発表会
11月30日(木)〜12月1日(金)
会場:長良川国際会議場
https://jza-online.org/events
■(共)第27回環境地質学シンポジウム
12月1日(金)〜2日(土)
会場:日本大学文理学部
http://www.jspmug.org/
■地球化学研究協会「公開講座」および「三宅賞」受賞者の受賞記念講演
12月2日(土)14:40〜
場所:霞が関ビル35階東海大学校友会館
公開講座「三宅泰雄先生と同位体地球化学—その後の発展の一断面」(和田英
太郎・京都大学名誉教授)
参加費:無料
http://www.geochem-ass-miyake.com/
■第17回東北大学多元物質科学研究所研究発表会
12月4日(月)〜5日(火)
会場:東北大学片平さくらホール
参加申込締切:11月27日(月)
(ポスター発表は11月10日(金)締切)
http://www2.tagen.tohoku.ac.jp/general/event/meeting/2017/
■東北大学多元物質科学研究所イノベーション・エクスチェンジ2017
12月5日(火)13:00〜18:30
会場:東北大学 片平さくらホール
参加申込締切:11月27日(月)
http://www2.tagen.tohoku.ac.jp/general/event/Innovation_Exchange/2017/
■地質調査総合センター(GSJ)第28回シンポジウム
「地圏資源環境の研究ストーリー:社会へつなげる研究を目指して」
12月7日(木)13:30-17:30
場所:秋葉原ダイビル・コンベンションホール
https://unit.aist.go.jp/georesenv/information/20171011.html
■日本学術会議公開シンポジウム
2017年九州北部豪雨災害と今後の対策
12月20日(水)10:00〜17:30
場所:日本学術会議講堂
http://janet-dr.com/07_event/171220sympo/20171220sympo_leef.pdf
■ProjectA ミーティング in 五島列島
2018年3月3日(土)〜7日(水)
3日(土)13:30〜17:00 一般講演会(五島市福江)
4日(日)〜5日(月)五研究発表会(島市奈留島)
6日(火)〜7日(水)巡検 奈留島・久賀島 ボートによる断崖海岸巡検
後援 五島市
申込締切:12月15日(金)
参加費:大人 25,000円 学生 10,000円
詳細は,http://archean.jp
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・九州大学大学院理学研究院化学部門or地球惑星科学部門助教(女性)(12/15)
・JAMSTEC数理科学・先端技術研究分野主任研究員or主任技術研究員募集(12/18)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.398(臨時)2018年度代議員選挙/会員カード発行
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.398 2017/11/10┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2018年度代議員選挙について
【2】会員証(会員カード)をお送りします
【3】2018年度各賞候補者募集中(11/30締切)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2018年度代議員選挙について
──────────────────────────────────
選挙規則ならびに選挙細則に基づき,標記選挙を実施するにあたっての立候補
届は,11月6日に締め切られました.その結果,全国区・地方支部区とも立候補
者数が定数を超えませんでしたので,選挙規則第6条に基づき投票は行わず,全
員を無投票当選といたします.
なお,立候補の抱負など,当選された方の詳細につきましては別途名簿をお送
りいたしますので,ご覧ください.
また,代議員選挙は無投票となりましたが,会長・副会長の意向調査につきま
しては,予定通り実施いたします.意思表明者のマニフェストならびに調査票
は代議員当選者の名簿とともに,11月25日ころまでにお送りいたしますので,
ご返信を宜しくお願いいたします.
2017年11月9日
一般社団法人日本地質学会
選挙管理委員会委員長 佐藤 智之
選挙の詳細はこちらから(会員のページ・要ログイン)
http://sub.geosociety.jp/members/content0026.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】会員証(会員カード)をお送りします!(11/25頃)
──────────────────────────────────
現在125周年記念事業をさまざまに実施、計画しておりますが、その一つとして
「会員証」を発行し、全会員に配布いたします。
カードには氏名の印字とバーコードによる会員番号が表示されています。【1】
の会長・副会長の意向調査の郵便物に会員カードを同封しますので,届
きましたら必ず開封してご確認下さい。
詳しくは, http://www.geosociety.jp/125th/content0018.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2018年度各賞候補者募集中(11/30締切)
──────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして,研究の援助・奨励および研究業
績の表彰を行っています.本年も各賞の自薦,他薦による候補者を募集いたし
ます.期日厳守にて,たくさんのご応募をお待ちしております.
**********************************************
応募締切:2017年11月30日(木)必着
**********************************************
詳しくは下記より(会員のページ・要ログイン)
http://sub.geosociety.jp/members/content0098.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.399 各賞候補者募集まもなく締切です
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.399 2017/11/21┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2018年度各賞候補者募集:まもなく締切(11/30締切)
【2】2018年度代議員および役員選挙
【3】会員証(会員カード)をお送りします!(11/25頃)
【4】2018年度会費払込について
【5】会員名簿データを整理中です.住所変更はお早めに!
【6】第9回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
【7】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2018年度各賞候補者募集:まもなく締切(11/30締切)
──────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして,研究の援助・奨励および研究業
績の表彰を行っています.本年も各賞の自薦,他薦による候補者を募集いたし
ます.期日厳守にて,たくさんのご応募をお待ちしております.
応募締切:2017年11月30日(木)必着
詳しくは下記より(要ログイン),
http://sub.geosociety.jp/members/content0098.html(会員のページ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2018年度代議員選挙について
──────────────────────────────────
選挙規則ならびに選挙細則に基づき,標記選挙を実施するにあたっての立候補
届は,11月6日に締め切られました.その結果,全国区・地方支部区とも立候補
者数が定数を超えませんでしたので,選挙規則第6条に基づき投票は行わず,全
員を無投票当選といたします.
また,代議員選挙は無投票となりましたが,会長・副会長の意向調査につきま
しては,予定通り実施いたします.意思表明者のマニフェストならびに調査票
は代議員当選者の名簿とともに,11月25日ころまでにお送りいたしますので,
ご返信を宜しくお願いいたします.
(選挙管理委員会委員長 佐藤智之)
選挙の詳細はこちらから(会員のページ・要ログイン)
http://sub.geosociety.jp/members/content0026.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】会員証(会員カード)をお送りします(11/25頃)
──────────────────────────────────
現在125周年記念事業をさまざまに実施,計画しておりますが,その一つとして
「会員証」を発行し,全会員に配布いたします.
カードには氏名の印字とバーコードによる会員番号が表示されています.【2】
の会長・副会長の意向調査の郵便物に会員カードを同封しますので,届
きましたら必ず開封してご確認下さい.
詳しくは, http://www.geosociety.jp/125th/content0018.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2018年度会費払込について
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下さいますよ
うお願いいたします.
■2018年度分会費の引き落とし日:12月25日(月)です.
請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下
さい.
■自動引き落とし以外の方(お振り込み)
12月中旬頃までに請求書兼郵便振替用紙をお送りいたします.折り返しご送金
くださいますようお願いいたします.
学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)の方で,それぞ
れ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適用します.対象となる方は
忘れずに申請して下さい.(※割引の適用を希望する場合,申請は毎年必要で
す)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】会員名簿データを整理中です.住所変更はお早めに!
──────────────────────────────────
現在,会員名簿データを整理中です(2017年3月発行予定).
名簿の発行様式は前回と同様で,全会員を収録します.学会員相互の交流と親
睦を図る目的に沿ってご利用いただけるよう,従来規模の名簿作成を予定して
います.ご理解とご協力をお願いいたします.なお,2017年度末で退会を予定
されている方のお名前は収録いたしません.
***会員情報のWEB画面での更新締切:2017年12月6日(水)***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】第9回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
──────────────────────────────────
***応募締切:2018年1月11日(木)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.今年は2018年の学会創立125周年を記念した特別賞も設けました.会員の
皆様からの応募もお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・学会創立125周年記念賞:1点 賞金5万円(今回のみ)
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞(会員限定の賞です):1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp/
**蒲郡市生命の海科学館2017年冬のミニ企画展**
「第8回惑星地球フォトコンテスト入賞作品展」
11月23日(木)〜2018年2月25日(日)入場料無料
http://www.city.gamagori.lg.jp/site/kagakukan/geophoto2017.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】[125周年関連情報]寄付受付中!(クレジットカードも可)
──────────────────────────────────
125周年記念事業として,2018年5月東京での記念式典をはじめ,様々な事
業を計画しています.また,それら記念事業を実行するため,学会員や賛助会
員,さらには関連諸団体に寄付をお願いしております.
*醵金者一覧
http://www.geosociety.jp/125th/content0014.html
*記念事業に対する寄付のお願い
クレジットカード(VISA, Master, Diners)もご利用いただけます
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html#kifu
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
──────────────────────────────────
[四国支部]
■第17回四国支部総会・講演会・巡検
<四国支部総会・講演会>
12月16日(土) 11:00〜17:00(予定)
場所:愛媛大学メディアセンター
<巡検「道後のHigh-Mg安山岩」>
12月17日(日)8:30〜11:30
講演・巡検申込締切:12月1日(金)厳守
<市民講演会>
12月17日(日)13:30〜15:30
会場:愛媛大学南加記念ホール
「ジオの視点で地域を元気に! –四国西予ジオパークの取り組み–」
高橋 司(西予市城川支所長,元四国西予ジオパーク推進協議会事務局長)
「南海トラフ巨大地震への備え」
高橋治郎(元愛媛大学教育学部教授)
詳しくは,http://www.gsj-shikoku.com/research.html
[西日本支部]
■西日本支部平成29年度総会・第169回例会
2018年3月3日(土)〜4日(日)
場所:広島大学 東広島キャンパス
講演申込締切:2月15日(木)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
[関東支部]
■関東支部功労賞募集
公募期間:2017年12月10日〜2018年1月10日
日本地質学会関東支部では,支部の顕彰制度に基づき2017年度も支部活動や地
質学を通して社会貢献された個人・団体を関東支部として顕彰いたします.
http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■(共)蒲郡市生命の海科学館2017年冬のミニ企画展
「第8回惑星地球フォトコンテスト入賞作品展」
11月23日(木)〜2018年2月25日(日)
入場料無料
http://www.city.gamagori.lg.jp/site/kagakukan/geophoto2017.html
■(協)第33ゼオライト研究発表会
11月30日(木)〜12月1日(金)
会場:長良川国際会議場
https://jza-online.org/events
■(共)第27回環境地質学シンポジウム
12月1日(金)〜2日(土)
会場:日本大学文理学部
http://www.jspmug.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・神戸大学内海域環境教育研究センター(地質学)教授公募(11/30)
・JAMSTEC地震津波海域観測研究開発センターポスドク研究員(12/8)
・「消防防災科学技術研究推進制度」平成30年度研究開発課題の募集(12/20)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
トリビア学史 14 京都の鉱物学者‐比企忠(1866−1927)
〜2018年日本地質学会創立125周年を記念して〜
トリビア学史 14 京都の鉱物学者‐比企忠(1866−1927)
矢島道子(日本大学文理学部)・浜崎健児(Ultra Trex㈱)
図1(左)比企忠(脇水,1927)図2(右)島津鉱物顕微鏡の広告(比企,1925)
日本で最初にノーベル賞を受賞した湯川秀樹(1907−1981)の父親である地質学者小川琢治(1870−1941)は,京都大学理学部地質学教室の創設者であることもよく知られている.小川琢治は,1896(明治29)年に東京帝国大学理科大学地質学科を卒業後,農商務省地質調査所に勤務し,その後,1908(明治41)年に京都帝国大学文科大学に地理学講座担当として赴任した.この講座が理学部地質鉱物学科となったのは,1921年のことである.実は,京都大学には,小川琢次よりも前に,すなわち,1897(明治30)年から,地質学・鉱物学者比企忠(ひきただす)が工学部のほうに赴任していた.京都大学総合博物館に所蔵されている鉱物標本の多くは比企忠の蒐集物である.
比企忠の略歴
比企忠が1927年に亡くなると,『地質学雑誌』には地質学者の脇水鉄五郎による追悼文が掲載された.そこから比企の略歴を拾ってみる.比企はトリビア13に掲載された岩佐巌,和田維四郎,市川新松と同じように福井県の出身である.生後すぐに東京に転居し,学習院・第一高等学校をへて,1891(明治24)年東京帝国大学理学部地質学科に入学した.高等学校時代にすでに地質学・鉱物学を志していたという.1893(明治26)年6月6日の吾妻山[一切経山のことだが,当時は吾妻山とよんでいた]大爆発の後,西和田久學と登り,噴出物を調査している(西和田,1893a,b).トリビア9で既出のように,翌7日の爆発で2名が殉職した.比企は1894(明治27)年に東京帝国大学理学部地質学教室を卒業して大学院に進み,神保小虎(1867−1924)助教授の助手を務め,学生の鉱物実験の指導も行った.比企は神保よりも1年年長であった.神保が学歴を素早く駆け上ったといえよう.
1897(明治30)年6月に京都帝国大学が創設され,9月には理工科大学が開校した.比企は鉱物学,地質学,鉱床学の講義を担当し,翌年に採鉱冶金学科が創設された.理工科大学は1914(大正3)年7月,理科大学と工科大学に分離され,1918(大正7年)には工学部採鉱冶金学科となった.比企は1918年に初代教授,1921(大正10)年に工学博士となり,1926(大正15)年5月に定年を迎えた.在職中の1913(大正2)年,欧米に留学し,ドイツをめぐってアメリカに行ったが,病を得て1914(大正3)年に帰国した.比企は健康に気をつけていたが定年後,比較的早く亡くなった.
地質学雑誌創設のころ
1893年,日本地質学会は東京地質学会として創設され,『地質学雑誌』第1巻第1号も発行された.原著論文(論説及び報文)も載っているが,雑録,史伝,応問,雑報などを読むと当時の学会をめぐる動きがよくわかる.学会といっても,東京帝国大学理科大学地質学教室や工科大学冶金学教室の動きが中心である.東京大学では毎週土曜日に地学談話会が開かれていた.1893年に東京地質学会が創設されると,毎月第2土曜日が東京地質学会の日となった.まず談話会での報告が雑報として紹介され,それが雑録を経て,数年後に原著論文になっていく.
東京大学の鉱物学教授菊池安(1862−1894)が地質学会創設の翌年に逝去し,一時松島鉦四郎(地質学教室1888(明治21)年卒,後第一高等学校教授)が講師を務めたが,最終的に神保小虎が助教授となった.神保はそれ以前に研究していた北海道の化石について論文発表している頃であった.当時,地質学雑誌は化石の論文よりも鉱物論文のほうが多く,高壮吉(1897(明治30)年冶金学科卒業,のち九州大学教授),篠本二郎,比企忠,小川琢治などがしきりに論文を投稿した.
鉱物論文の中で,玄能石に関わる比企のことが話題に上ることがある.玄能石は長野県に産し,五無斎として有名な保科百助(1868−1911)の研究でよく調べられていた.比企忠が保科の功績を無視したという風説があるが,これは事実ではない.高(1896)は「緑簾石硫酸苦土鉱玄能石の如き我鉱物学社会にその産出を知られたるは全く同君の賜にして」と保科百助の功績であることをはっきり書いており,比企(1896,1897)もまた,保科と玄能石のことについて書いている.
島津製作所との協力
島津製作所は,やはりノーベル賞受賞者である田中耕一(1959−)が勤務していたことで有名だが,その歴史は古い.1875(明治8)年,島津源蔵(1839−1894)によって,教育用理科機器の製造をするところとして京都に創設された.もちろん,地学に関係する顕微鏡や,標本なども取り扱った.
島津鉱物顕微鏡は図2にあるように,比企忠の協力のもとに製作された.比企は,学生時代から顕微鏡についての雑録(比企,1894)もあり,鉱物研究に顕微鏡は必須であり,海外から購入するととても高価なので,国産化およびその実用化をめざしたと書いている.
岩手大学農学部農業教育資料館には,古い時代のさまざまな標本や模型などが所蔵陳列されている.宮澤賢治に関係しているので,よく調べられている.箱根火山の断面模型の裏に島津製作所のマークが付いていたと記憶している.
文 献
比企忠,1894,顕微鏡岩石學の起源及其発達.地質学雑誌,1巻,181−185.
比企忠,1896,信濃小県郡鉱石産地概況.地質学雑誌,3巻,331−336.
比企忠,1897 信濃國ゲンノー石.地質学雑誌,4 巻,139-141.
比企忠,1925,『鉱物顕微鏡使用法』島津製作所標本部,48p.
市川渡,1980,私と地質学会のかかわり.地質学雑誌, 86巻,2号,147-152.
高壮吉,1897,信濃小県郡鉱物談.地質学雑誌,第3巻,34号, 321-323.
西和田久學,1893a,吾妻山破裂及其噴出物要略.地質学雑誌,1巻,11-18.
西和田久學,1893b,吾妻山破裂及其噴出物要略 : (三)或噴出石略誌.地質学雑誌,1巻,102-108.
脇水鉄五郎,1927,工学博士比企忠君を悼む.地質学雑誌,34巻,407号,口絵.
【geo-Flash】No.401「正・副会長候補者の意向調査」実施中(1/8締切)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.401 2017/12/5┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】「正・副会長候補者の意向調査」実施中(1/8締切)
【2】2018年度会費払込について
【3】会員名簿データを整理中です.住所変更はお早めに!
【4】第9回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
【5】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「正・副会長候補者の意向調査」実施中(1/8締切)
──────────────────────────────────
代議員選挙は無投票となりましたが,会長・副会長の意向調査につきましては,
予定通り実施いたします.意思表明者のマニフェストならびに調査票を代議員
当選者の名簿とともに11月下旬に発送いたしました.お手元の郵便物をご確認
のうえ,ご回答ください.
******************************************
回答締切:2018年1月8日(月)(消印有効)
******************************************
選挙の詳細はこちらから(会員のページ・要ログイン)
http://sub.geosociety.jp/members/content0026.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2018年度会費払込について
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下さいますよ
うお願いいたします.
■2018年度分会費の引き落とし日:12月25日(月)です.
請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下
さい.
■自動引き落とし以外の方(お振り込み)
12月中旬に請求書兼郵便振替用紙をお送りいたします.折り返しご送金くださ
いますようお願いいたします.
学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)の方で,それぞ
れ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適用します.対象となる方は
忘れずに申請して下さい(※割引申請は毎年必要です).
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】会員名簿データを整理中です.住所変更はお早めに!
──────────────────────────────────
現在,会員名簿データを整理中です(2017年3月発行予定).
名簿の発行様式は前回と同様で,全会員を収録します.学会員相互の交流と親
睦を図る目的に沿ってご利用いただけるよう,従来規模の名簿作成を予定して
います.ご理解とご協力をお願いいたします.なお,2017年度末で退会を予定
されている方のお名前は収録いたしません.
***会員情報のWEB画面での更新締切:2017年12月6日(水)***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第9回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
──────────────────────────────────
***応募締切:2018年1月11日(木)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.今年は2018年の学会創立125周年を記念した特別賞も設けました.会員の
皆様からの応募もお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・学会創立125周年記念賞:1点 賞金5万円(今回のみ)
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞(会員限定の賞です):1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp/
**蒲郡市生命の海科学館2017年冬のミニ企画展**
「第8回惑星地球フォトコンテスト入賞作品展」開催中
〜2018年2月25日(日)まで.入場無料
http://www.city.gamagori.lg.jp/site/kagakukan/geophoto2017.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[125周年関連情報]寄付受付中!(クレジットカードも可)
──────────────────────────────────
125周年記念事業として,2018年5月東京での記念式典をはじめ,様々な事
業を計画しています.また,それら記念事業を実行するため,学会員や賛助会
員,さらには関連諸団体に寄付をお願いしております.
*醵金者一覧
http://www.geosociety.jp/125th/content0014.html
*記念事業に対する寄付のお願い
クレジットカード(VISA, Master, Diners)もご利用いただけます
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html#kifu
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[四国支部]
■第17回四国支部総会・講演会・巡検
<四国支部総会・講演会>
12月16日(土)11:00〜17:00(予定)
場所:愛媛大学メディアセンター
<巡検「道後のHigh-Mg安山岩」>
12月17日(日)8:30〜11:30
講演・巡検申込締切:12月1日(金)厳守
<市民講演会>
12月17日(日)13:30〜15:30
会場:愛媛大学南加記念ホール
「ジオの視点で地域を元気に! –四国西予ジオパークの取り組み–」
高橋 司(西予市城川支所長,元四国西予ジオパーク推進協議会事務局長)
「南海トラフ巨大地震への備え」
高橋治郎(元愛媛大学教育学部教授)
詳しくは,http://www.gsj-shikoku.com/research.html
[西日本支部]
■西日本支部平成29年度総会・第169回例会
3月3日(土)〜4日(日)
場所:広島大学 東広島キャンパス
講演申込締切:2月15日(木)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
[関東支部]
■関東支部功労賞募集
公募期間:2017年12月10日〜2018年1月10日
日本地質学会関東支部では,支部の顕彰制度に基づき2017年度も支部活動や地
質学を通して社会貢献された個人・団体を関東支部として顕彰いたします.
http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■(共)蒲郡市生命の海科学館2017年冬のミニ企画展
「第8回惑星地球フォトコンテスト入賞作品展」開催中
〜2018年2月25日(日)まで
入場料無料
http://www.city.gamagori.lg.jp/site/kagakukan/geophoto2017.html
■平成29年度国総研講演会
12月6日(水)10:15〜17:30
場所:日本教育会館 一ツ橋ホール
入場無料・要申込
http://www.nilim.go.jp/
■日本第四紀学会シンポジウム「ジオパークと学校教育」
12月16日(土)9:30〜17:00
場所:お茶の水女子大学共通一号館301(文京区大塚2-1-1)
参加費無料.どなたでも参加できます
http://quaternary.jp/event/qr.html#sympo1216
■第205回地質汚染イブニングセミナー
12月22日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:相川信之(NPO日本地質汚染審査機構理事・大阪市立大名誉教授)
演題:焼却灰の処理:都市ごみ焼却灰中の重金属の不溶化処理の一例
http://www.npo-geopol.or.jp
***2018年***
■日本学士院 ダン・マッケンジー客員教授来日記念講演
「創始者が語るプレートテクトニクス50年」
1月11日(木)14:30〜
場所:日本学士院会館(東京・上野)
聴講無料・定員150名(要申込,先着順)英語講演(逐次通訳付)
http://www.japan-acad.go.jp/japanese/news/2017/112201.html
■うみコン2018
海と産業確信コンベンション:ブルーアースとビジネスの融合
1月16日(火)〜17日(水)10:00〜17:00
場所:大さん橋ホール(横浜港大さん橋国際客船ターミナル内)
入場無料
[同時開催]ブルーアースサイエンス・テク2018
1月16日(火)〜17日(水)
http://yokohama-umi.jp/
■(後)人と自然の博物館&県立大学自然・環境科学研究所
25周年記念フォーラム「日本の恐竜時代を探る!」
2月18日(日)13:00〜17:30
場所:人と自然の博物館 ホロンピアホール(兵庫県三田市弥生が丘)
定員300名(先着順)・参加費無料
http://www.hitohaku.jp/
■第52回水環境学会(札幌)年会
3月15日(木)〜17日(土)
場所:北海道大学工学部(札幌市北区北13条西8丁目)
参加申込:2月20日(火)締切
https://www.jswe.or.jp/event/lectures/index.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・北海道苫小牧市美術博物館学芸員(自然科学担当)募集(12/18)
・山梨県富士山科学研究所(火山防災研究部)非常勤研究員募集(1/26)
・産総研ポスドク(イノベーションスクール生)公募(1/3)
・第49回(平成30年度)三菱財団自然科学研究助成(2/7)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.400(臨時)山本高司 副会長 ご逝去
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.400 2017/11/27 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 山本高司 副会長 ご逝去
──────────────────────────────────
本学会副会長、山本高司氏におかれましては、体調不良のところ、
2017年11月21日に逝去されました(享年59歳)。謹んでお知らせ申し上げます。
山本副会長は、川崎地質株式会社に所属され、地質学会入会以来、学術活動の
ほか、関東支部幹事、同支部幹事長、2012年度からは本学会理事として執行理
事を務められ、また2014年度からは副会長として、主に社会貢献活動、地質技
術者教育に関する活動など学会運営の中心となって、本学会の発展にご尽力い
ただきました。
山本副会長の突然の訃報に接し、誠に残念至極、痛惜の念に堪えません。
会員一同とともにこれまでのご貢献に深く感謝し、心よりご冥福をお祈りいた
します。なお,ご葬儀は24日にご家族で執り行われたとのことです。
一般社団法人日本地質学会
会長 渡部 芳夫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください。
【geo-Flash】No.402 フォトコンテスト締め切りはお正月明けです!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.402 2017/12/19┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】「正・副会長候補者の意向調査」実施中(1/8締切)
【2】2018年度会費払込について
【3】第9回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
【4】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【5】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されます
【6】第20回地震火山こどもサマースクール開催地候補募集
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】事務局年末年始休業(12/29〜1/4)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「正・副会長候補者の意向調査」実施中(1/8締切)
──────────────────────────────────
代議員選挙は無投票となりましたが,会長・副会長の意向調査につきましては,
予定通り実施いたします.意思表明者のマニフェストならびに調査票を代議員
当選者の名簿とともに11月下旬に発送いたしました.お手元の郵便物をご確認
のうえ,ご回答ください.
******************************************
回答締切:2018年1月8日(月)(消印有効)
******************************************
選挙の詳細はこちらから(会員のページ・要ログイン)
http://sub.geosociety.jp/members/content0026.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2018年度会費払込について
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下さいますよ
うお願いいたします.
■2018年度分会費の引き落とし日:12月25日(月)です.
請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下
さい.
■自動引き落とし以外の方(お振り込み)
12/19に請求書兼郵便振替用紙を発送いたしました.折り返しご送金くださ
いますようお願いいたします.
学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)の方で,それぞ
れ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適用します.対象となる方は
忘れずに申請して下さい(※割引申請は毎年必要です).
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】第9回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
──────────────────────────────────
***応募締切:2018年1月11日(木)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.今年は2018年の学会創立125周年を記念した特別賞も設けました.会員の
皆様からの応募もお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・学会創立125周年記念賞:1点 賞金5万円(今回のみ)
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞(会員限定の賞です):1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp/
***蒲郡市生命の海科学館2017年冬のミニ企画展***
「第8回惑星地球フォトコンテスト入賞作品展」開催中
〜2018年2月25日(日)まで.入場無料
http://www.city.gamagori.lg.jp/site/kagakukan/geophoto2017.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[125周年関連情報]寄付受付中!(クレジットカードも可)
──────────────────────────────────
125周年記念事業として,2018年5月東京での記念式典をはじめ,様々な事
業を計画しています.また,それら記念事業を実行するため,学会員や賛助会
員,さらには関連諸団体に寄付をお願いしております.
*醵金者一覧
http://www.geosociety.jp/125th/content0014.html
*記念事業に対する寄付のお願い
クレジットカード(VISA, Master, Diners)もご利用いただけます
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html#kifu
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されます
──────────────────────────────────
募集期間:2017年12月20日(水)〜2018年2月9日(金)
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:例えば,,,地質学への顕著な貢献/地質学会の運
営と発展への貢献/教育現場や企業などでの活動を通じた地質学の普及と振興
への貢献など
*上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することはできませ
んが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
(名誉会員推薦委員会 松田博貴)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】第20回地震火山こどもサマースクール開催地候補募集
──────────────────────────────────
地震火山こどもサマースクールは,日本地質学会,日本地震学会,日本火山学
会と地域自治体や団体が共催する,小・中・高校生を対象とする地球科学関連
の体験学習講座です.2017年度は熊本県益城町で開催し,地元の小・中・高校
生が参加してくれました.2018年度は東京都伊豆大島で開催予定です.今回は,
2019年度の開催地の募集を行います.
*****************************************
募集期間:2018年1月9日(火)〜2月16日(金)
*****************************************
募集の詳細詳は,下記をご覧ください..
(URL)http://www.zisin.jp/opp/gold_summerschool2019_koubo.html
過去の開催の様子は,下記をご覧ください.
(URL)http://www.kodomoss.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[西日本支部]
■西日本支部平成29年度総会・第169回例会
3月3日(土)〜4日(日)
場所:広島大学 東広島キャンパス
講演申込締切:2月15日(木)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
[関東支部]
■関東支部功労賞募集
公募期間:2017年12月10日〜2018年1月10日
日本地質学会関東支部では,支部の顕彰制度に基づき2017年度も支部活動や地
質学を通して社会貢献された個人・団体を関東支部として顕彰いたします.
■気候変動シンポジウム 〜激変する地球と災害リスク〜
3月17日(土)13:00〜18:00
(終了後大学内で懇親会を開催予定)
場所:横浜国立大学教育文化ホール大集会室
*事前申込不要・参加費無料(要旨集は1000円程度を予定)
http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■東京地学協会第304回地学クラブ講演会
「東北日本弧のマグマ供給系と地殻・マントル構造」
1月19日(金)14:00〜15:30
場所:東京地学協会「地学会館」2階講堂
講師:吉田武義(東北大学名誉教授)
参加申込不要(どなたも無料で参加できます)
http://www.geog.or.jp/lecture/lecturescheduled/323-club304.html
■(後)人と自然の博物館&県立大学自然・環境科学研究所
25周年記念フォーラム「日本の恐竜時代を探る!」
2月18日(日)13:00〜17:30
場所:人と自然の博物館 ホロンピアホール(兵庫県三田市弥生が丘)
定員300名(先着順)・参加費無料
http://www.hitohaku.jp/
■日本地球惑星連合2018年大会
5月20日(日)〜24日(木)
場所:幕張メッセおよび東京ベイ幕張ホール
投稿開始: 1月10日(木)
最終締切: 2月19日(月)
早期参加登録受付:1月10日〜5月8日
http://www.jpgu.org/meeting_2018/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・海洋研究開発機構 深海・地殻内生物圏研究分野主任研究員or主任技術研究員募集(1/9)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】事務局年末年始休業(12/29〜1/4)
──────────────────────────────────
学会事務局は,12月29日(金)〜1月4日(木)までお休みとなります.
新年5日より通常営業となります.よろしくお願いいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.403 謹賀新年:いよいよ125周年です
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.403 2018/1/9┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】年頭の挨拶(会長 渡部芳夫)
【2】第9回惑星地球フォトコンテスト:まもなく締切!
【3】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【4】名誉会員候補者の募集が開始されています
【5】第20回地震火山こどもサマースクール開催地候補募集
【6】Island Arc からのお知らせ(最新号発行)
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】岡田博有 名誉会員 ご逝去
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】年頭の挨拶(会長 渡部芳夫)
──────────────────────────────────
学会員の皆様に,日本地質学会の創立125周年の年を迎えるにあたり,年頭の
ご挨拶を申し上げます.
既に昨年より関連記念事業を進めて参りましたが,晴れて事業の本年度とな
りました.2年以上を準備に費やして進めてまいりました周年事業の目的は,
最終的には地質学という学問の再認識とさらなる発展を,日本地質学会が一端
を担う以上に先導すべく決意を共有することでもあります.ここでは地質学を
とりまく潮流について,私見を3点ほどお話しし,今年一年が皆様にとって飛
躍の年になる事を祈念させていただきます.
全文を読む、、、、
http://www.geosociety.jp/outline/content0137.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第9回惑星地球フォトコンテスト:まもなく締切!
──────────────────────────────────
***応募締切:2018年1月11日(木)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.今年は2018年の学会創立125周年を記念した特別賞も設けました.会員の
皆様からの応募もお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・学会創立125周年記念賞:1点 賞金5万円(今回のみ)
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞(会員限定の賞です):1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[125周年関連情報]寄付受付中!(クレジットカードも可)
──────────────────────────────────
125周年記念事業として,2018年5月東京での記念式典をはじめ,様々な事
業を計画しています.また,それら記念事業を実行するため,学会員や賛助会
員,さらには関連諸団体に寄付をお願いしております.
*醵金者一覧
http://www.geosociety.jp/125th/content0014.html
*記念事業に対する寄付のお願い
クレジットカード(VISA, Master, Diners)もご利用いただけます.
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html#kifu
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されています
──────────────────────────────────
募集期間:2017年12月20日(水)〜2018年2月9日(金)
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:例えば,,,地質学への顕著な貢献/地質学会の運
営と発展への貢献/教育現場や企業などでの活動を通じた地質学の普及と振興
への貢献など
*上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することはできませ
んが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
(名誉会員推薦委員会 松田博貴)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第20回地震火山こどもサマースクール開催地候補募集
──────────────────────────────────
地震火山こどもサマースクールは,日本地質学会,日本地震学会,日本火山学
会と地域自治体や団体が共催する,小・中・高校生を対象とする地球科学関連
の体験学習講座です.2017年度は熊本県益城町で開催し,地元の小・中・高校
生が参加してくれました.2018年度は東京都伊豆大島で開催予定です.今回は,
2019年度の開催地の募集を行います.
*****************************************
募集期間:2018年1月9日(火)〜2月16日(金)
*****************************************
募集の詳細詳は,下記をご覧ください..
(URL)http://www.zisin.jp/opp/gold_summerschool2019_koubo.html
過去の開催の様子は,下記をご覧ください.
(URL)http://www.kodomoss.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】Island Arc からのお知らせ(最新号発行)
─────────────────────────────────
最新号 Volume 27, Issue 1(2018年1月号)がオンライン出版されました.
学会WEBサイト会員ページにログインすると,全文無料で閲覧できます(和文要
旨も掲載されています).
ログインはこちらから https://sub.geosociety.jp/login.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[西日本支部]
■西日本支部平成29年度総会・第169回例会
3月3日(土)〜4日(日)
場所:広島大学 東広島キャンパス
講演申込締切:2月15日(木)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
[関東支部]
■気候変動シンポジウム 〜激変する地球と災害リスク〜
3月17日(土)13:00〜18:00
(終了後大学内で懇親会を開催予定)
場所:横浜国立大学教育文化ホール大集会室
*事前申込不要・参加費無料(要旨集は1,000円程度を予定)
http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
電中研ニュース No.484発行
「わが国のPM2.5に対する国内外発生源の寄与を評価」
http://criepi.denken.or.jp/research/news/index.html?m=171222
*************(以下,関連団体の行事案内です)****************
■第206回地質汚染イブニングセミナー
1月26日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:谷 芳生(神奈川県秦野市環境保全課長)
演題:神奈川県秦野盆地の水循環調査とその教訓
http://www.npo-geopol.or.jp
■(後)人と自然の博物館&県立大学自然・環境科学研究所
25周年記念フォーラム「日本の恐竜時代を探る!」
2月18日(日)13:00〜17:30
場所:人と自然の博物館 ホロンピアホール(兵庫県三田市弥生が丘)
定員300名(先着順)・参加費無料
http://www.hitohaku.jp/
■日本地球惑星連合2018年大会
5月20日(日)〜24日(木)
場所:幕張メッセおよび東京ベイ幕張ホール
投稿開始: 1月10日(木)
最終締切: 2月19日(月)
早期参加登録受付:1月10日〜5月8日
http://www.jpgu.org/meeting_2018/
■(後)第55回アイソトープ・放射線研究発表会
7月4日(水)〜6日(金)
場所:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
発表申込締切:2月28日(水)17:00
https://www.jrias.or.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・千葉県職員採用選考(地質職1名)(1/10)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】岡田博有 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
岡田博有 名誉会員(日本地質学会元会長,静岡大学名誉教授)が,平成29年
12月22日(金)にご逝去されました(享年85歳).
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます.
なお,ご葬儀は,すでに近親者によりしめやかに執り行なわれとのことです.
会長 渡部 芳夫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
トリビア学史15 客死した鉱山学者ヘルマン・リットル
〜2018年日本地質学会創立125周年を記念して〜
トリビア学史 15 客死した鉱山学者ヘルマン・リットル
矢島道子(日本大学文理学部)
図.明治天皇開成学校臨幸(東京帝国大学,1932より).場所は,現在の学士会館(千代田区神田錦町).
はじめに
明治初期,開成学校に優秀な鉱山学者ヘルマン・リットル(Hermann Ritter 1827–1874)がいた.ところがリットルは天然痘で1874(明治7)年に死亡し,後任の地質学の教授が必要になった.良く知られている通り,1875(明治8)年エドムント・ナウマン(1854–1927)がやってきて,東京大学地質学教室の初代教授に就任した.地質学史上ナウマンが,日本に地質学をもたらしたことになっている.歴史に「もし」はないけれど,リットルが生きていたら,ナウマンは日本に来なかったかもしれない.
東京日日新聞から
リットルの顕彰碑が谷中霊園にあることもあって,リットルの情報はコンピュータで検索すれば多く出て来る.しかしながら,オリジナルの情報はなかなか出てこない.東京日日新聞1875(明治8)年1月28日(第919号)にリットルの記事をみつけたので,再録する.
東京日日新聞は1872(明治5)年に創刊され,毎日新聞の前身である.基本的に4面で,1面には政府関係の記事などが載っていて,現在の官庁の広報の感じがする.その後,雑報,外報,電報,寄書,広告と続く.1877(明治10)年ころの編輯人であった福地源一郎は後に社主になり,そして戯曲作家になる.
東京日日新聞記事は以下のようである.
明治七年十二月中澣東京開成學校教授獨逸人ドクトルヘルマンリットル君不幸ニシテ天然痘ニ感ス氏ノ始メ其患ニ罹ルヤ同校速ニ宮内省御雇醫官獨逸人ドクトルホフマン氏ヲ延請シ之ニ治療ヲ托シ百万其術ヲ施シ且養生看護至ラザル處ナシト雖モ其効ナク同月廿五日遂ニ死去セリ同月廿六日其壽函ヲ横濱ニ送リ之ヲ埋葬ス此日同國人ハ勿論官員生徒及同氏ノ眷遇ヲ受ケシ者愁然トシテ棺車ニ從ヒ陸續横濱ノ墓地ニ到レリ嗚呼今氏逝矣豈啻開成學校生徒ノ不幸ノミナラン抑又我國教育ヲ賛成スルノ一人ヲ失ヘリト云フ可シ實ニ悲痛哀哭ノ至リニ堪ヘス因テ今爰同氏ノ履歴ヲ畧記ス○ヘルマンリットル氏ハ彼一千八百廿七年ヲ以テ獨逸國「ハンノーウエル」ノ「ヒルデスハイム」ニ生レ「ゲツチンケン」ニ於テ學ヲ攻メ其業未タ成ラザルト雖モ既ニ北米合衆國「セエントロイス」ヨリ化學製造場ノ長ニ招聘セラレ此ニ滞在スルヿ五年ニシテ職ヲ辭シ獨逸ニ歸リプロフェツソール「ウエレル」氏ニ從ヒ勵虗努力其學術を研脩シ遂ニ「フヰロソフヰー」ノ學士トナル后チ幾ナラス魯國「モスカー」ノ近傍ニ化學製造場起立ノ企テアリ然リト雖モ未タ其ノ人ヲ得ス因テ氏ヲ遠ク獨逸ニ聘シ託スルニ此事ヲ以テス氏モ亦之ヲ憺當シ夙夜黽勉遂ニ能ク其ノ功ヲ奏シ以テ魯國ノ望ミヲ全フシ又獨逸ニ歸レリ尋テ魯西亜ニ再遊セントスルニ際シ本邦加州ノ藩主ニ招聘セラレ彼一千八百七十年始メテ我國ニ來レリ然ルニ其着港ニ方リ廢藩立縣ノ擧アルニ遇フ於是轉シテ大阪理學校教師ニ聘セラレ理化學教師トナレリ是明治三年十二月ナリ此時該校ニ英佛兩國ノ學アリ然ルニ氏能ク兩國ノ語ニ通スルヲ以テ英佛生徒ノ授業ヲ兼テ日ニ此ノ二國ノ語ヲ以テ理化學ノ大意ヲ講述セリ現ニ今世ニ刊布セル理化日記ハ乃チ氏ノ日講ヲ譯シテ編成セルモノナリ同六年三月東京ニ來リ開成學校鑛山學教師トナリ専ラ理化學ヲ教授セリ抑モリットル氏ノ人トナリ巖格周密且博學多識其生徒ヲ教導スル極テ黽勉ニシテ其懇切ナル恰モ父母ノ其子ニ於ルガ如ク毫モ愛憎アルナシ是以該校官員及外國教師等皆能ク之ヲ敬遇セザルハナシ嘗テ増給ヲ以テ氏ヲ聘セントセシモノアリ氏肯ンセスシテ曰ク開成學校ニシテ余ヲ棄ツルニ非ルヨリハ余生徒ノ成業ヲ見ズシテ去ルニ忍ビズト其忠志以テ見ル可キナリ氏ノ同校ニ職ヲ奉スル未タ久シカラズト雖モ生徒ノ業大ニ進脩セシハ實ニ氏ノ功多キニ居ルト云可シ故ニ其卒スルヤ文部省及同校大ニ之ヲ痛惜シ其在務中ノ勤勞ヲ追賞シテ日本金貨三百五十圓ヲ其家ニ贈レリ蓋シリットル氏ノ如キ學術精竅且性行脩整ナルハ方今本邦在留ノ歐米人中恐クハ多オアラザル可シ然ルニ今斯人ニシテ此ノ凶酷ニ罹ル嗚呼誰カ哀惜悲痛セセサランヤ 開成學校ノ吏員某
リットルの生涯をかいつまんで記す.リットルは来日の前にアメリカやロシアで働いていた.加賀藩の招請で来日したが,1870(明治3)年12月乞われてハラタマ(Koenraad W. Gratama)の後任として大阪府理学校教師となり,理化学と英仏語を教えた.1873(明治6)年月東京開成校鉱山学講師になったが,天然痘にかかり,ドイツの名医ホフマン氏に治療を依頼したけれども没した.
天覧授業
東京帝国大学五十年史(1932)によれば,明治天皇はしばしば,開成学校や東京大学に行幸している.第1回は1872(明治5)年3月29日,第2回は1873(明治6)年10月9日である.第2回には第1大学区東京開成学校[正式名]開業式に臨席し,その後,7つの授業(法学生徒の法律の起源の講述,理学生徒3名の化学実験,諸芸学生徒3名の大気の性質についての論述,リットルの講義・実験,機械製作所でポンプの製作・使用,体操場で気球の飛揚,体操)を参観した.リットルの授業内容は鉱山学生とともに,アマルガムを作ったり,硫黄・硝石・木炭を混合して爆発させたりするものであった.通訳は安東清人(1854–1886)が行った.安東清人は1870(明治3)年熊本藩の貢進生として入学し,1875(明治8)年7月にフライベルク鉱山学校に官費留学したが,病にかかり1877(明治10)年には帰国した.
文 献
東京帝国大学,1932,東京帝国大学五十年史.
日本ナップ説略史
日本ナップ説略史
正会員 石渡 明
1.はじめに
米国地質学会の情報誌GSA Today最新号の表紙と冒頭に,ギリシャ・ペロポネソス半島のゼウス霊場は,古成(こじょう)(古第三)系暁新(ぎょうしん)統にジュラ・白亜系が衝上(しょうじょう)するクリッペの上にあったという文理融合研究の報告が載っている(Davis, 2017).スイス中部シュヴィッツ(Schwyz)州のヘルベチア帯北縁部の白亜系にペンニン帯のジュラ系石灰岩が衝上するミューテン(ミーテンMythen)クリッペもゲーテが感動した「神話の山」であり,米国モンタナ州ロッキー山脈の白亜系に先カンブリア系が衝上する酋長(しゅうちょう Chief)山クリッペ(現地語名はNinaistako)も雷神が住む聖山だという.日本の山岳信仰の主な対象は富士山,白山(はくさん),御嶽山(おんたけさん)等の火山だが,伊吹山や霊仙(りょうぜん)等のクリッペも古来信仰されてきた.
地質学において,ナップ説(クリッペや衝上断層を含む)の歴史は古く,付加体説はおろか地向斜説より前からあり,日本でも20世紀前半に全国から衝上断層やナップ,クリッペ等が多数報告され,それらを構造発達史に組み込んだ議論がなされていた.何事によらずルーツの把握は重要で,古い文献を読むと現代の研究の盲点に気づくこともある.小論では日本のナップ説の歴史を簡単に紹介し,若い研究者の参考に供したい.
2.アルプスのナップ説
ほぼ水平な衝上(しょうじょう)断層(スラストthrust)をすべり面として,その上を数kmから数10km移動した地層や岩塊をナップとよぶ(英語・仏語nappe,独語Decke,衝上片,衝上体,衝上帯,衝上地塊,横(おう)移(い)岩塊,thrust sheet等ともいう).仏語の日常会話でnappeは「テーブル掛け」のことで,広く平らに覆う物体を言う.ナップを構成する地層は一般にその下盤側の地層より古い時代のもので,ナップ内部の地層の上下が逆転していることもあり,その場合は押(お)(推)し被(かぶ)せ褶曲(しゅうきょく)(recumbent fold,横臥(おうが)褶曲ともいう)の下側の翼(よく)が破断して形成されたと考えられる.ナップには元々押し被せ褶曲だったものが多いようで,アルプスのオフィオライト・ナップにも逆転したものや褶曲の頭が見えるものがある(Ishiwatari, 1985).また,ナップが侵食等によってその本体から切り離されたものをクリッペという(断崖,絶壁の意).これは独語のKlippe(複数はKlippen)で,英語では小文字で書くが(複数はklippesも可),outlier(根無し地塊)という語も使う.ただし,根(root, Wurzel, Heimat)と連続していなくても,大きなものやクリッペの集合はナップ(デッケ)という.なお,上述のミーテンは「Klippen-Decke」に属するが,これはプレアルプスの東方延長に並ぶペンニン帯起源のクリッペ群を指す固有名詞である.
衝上現象はスイスのグラールス(Glarus)州(シュヴィッツ州の東隣)のヘルベチア帯で1840年にArnold Escherにより発見されたが,これを地域地質学的にきちんと記述したのは1870年のAlbert Heim(ハイム)が最初である.Heimは南北両側から押し被せ褶曲が押し寄せたと考えたが,1887年にMarcel Bertrand(ベルトラン)は1つのナップが南から北へ衝上したという考えを発表した.1892年にEdward Suess(ジュース)がBertrandの考えを支持し,Heimも1903年にこの考えに同意した.そして1905年以後,ナップ説に基づくアルプス全体の地質の体系化が,地向斜から地背斜への転化の文脈としてEmile Argand(アルガン)によって完成され(地向斜説),これに基づいて英語によるアルプスの地質のわかりやすい教科書が出版され,日本でも広く読まれた(Collet, 1927).この段落は同書2版(1935)のp. 19に基づくが,杉村(1987, p. 31)も参照されたい.
3.日本の戦前のナップ説
さて,日本初のナップが発見されたのは滋賀・岐阜県境の伊吹山(いぶきやま)である.小藤(ことう)(1910,明治43)はその模式断面図を示し,「[伊吹山麓の]川底の硬砂岩が東西に走り直立し…山腹以上は厚き石灰岩が平層を為しつつ被覆し,[両者の境界の]特種の石灰岩は地層が乗り掛かり横滑りしたる時の摩擦破砕物の如き観あり…これを予は伊吹山の押し辷り構造(overthrust)と名づけり.かくの如き例は本邦に於いてその記事をいまだ知らず.」と述べている(カタカナをひらがなに改め,[ ]内と句読点,送りがな等を補い,〜石は〜岩とした).
次に,中国地方の秋吉台石灰岩のフズリナ化石を研究した小澤(1923)は広域的な地層の逆転を発見し,「逆転の事実には毫も疑う余地はありません.しからば如何なる地質構造になっているのか.未だ私はこの問題についてあまり考えておりません.ですから今はただ簡単に頭に浮かんだ事を少し書いてみましょう.私のような初学者の解釈は不十分の事は勿論(もちろん)ですから,皆様が以上述べたデータで如何ようにでもお考え下さらんことを希望します.矢部[長克(ひさかつ)]先生は秋吉台を見てliegende Falten [独語,横臥褶曲]だと言いました.私も勿論この解釈に賛成するのです」と述べて,南から北へほぼ水平に押し被せた横臥褶曲の断面図を示した(引用文はかなを現代風に改めた).彼は台地の周囲の地層も含む横臥褶曲を考えたが,後の研究者は石灰岩体だけをナップと考えた.しかし,衝上面の位置や衝上の向きの解釈は各人異なり(小林, 1950, p. 60; 河合, 1970, I, p. 36-37),最近は 細片化された構造岩塊の集合体とする解釈もある(Sano and Kanmera, 1991).
そして,秋吉に続き飛騨山地 (藤本, 1930),伊吹山(関, 1939),霊仙(瀧本, 1936),大賀 (張, 1939) 等で衝上断層が報告され,小林 (1941, 1951) は自身の観察も含めてそれらを統合し,西南日本内帯では古生代後期〜三畳紀の秋吉造山輪廻(りんね)の後,ジュラ紀〜白亜紀前期の「大賀時階の佐川造山輪廻」によってこれらの衝上が生じ,衝上の向きは基本的に北から南で,そのフロントに沿って夜久野塩基性岩が貫入したとした.また,西南日本外帯ではやや遅れて白亜紀中頃の「佐川時階の佐川造山輪廻」により,特に四国で多数の衝上断層が形成されたとした.しかしその後,夜久野オフィオライトは古生代後期のナップと判明し(石渡, 1989),私の論文を読んだ小林貞一先生から「秋吉造山輪廻に関する火成活動が一段と解明され…興味深く感じました…平成2歳暮 白貞居士」(当時89歳)という葉書をいただいた.
一方,北海道ではこの頃炭田調査が進み,石狩炭田では石炭を含む新生代の地層の上にアンモナイトやイノセラムスを含む中生代の地層が広く載っていることがわかり,これらが日高山脈側から押し出したナップやクリッペであるとされ,さらに神居古潭(かむいこたん)変成岩や蛇紋岩からなるナップやクリッペも報告された(Imai, 1926; Nagao, 1933; 大立目, 1941).
他方,ナップ説への反対も早くからあった.関東山地北東縁部の一連のナップは藤本(1937)が発見し,澤秀雄や渡部景隆と共に詳しく研究した.三波川変成岩やミカブ緑色岩に帰属不明の花崗岩類,変成岩類,礫岩等が衝上したり,三波川やミカブの下の地(じ)窓(まど)(window, Fenster)に秩父帯の堆積岩が現れたりするが,杉山(1943),井尻ほか(1944),杉山ほか(1944)はこれに反対し,断層はなく一連整合であるか,または火成岩の貫入によるものとし,この論争は戦後も続いた(藤本, 1951, p. 63-65).現在,跡倉と金勝山は十分な野外地質的・年代的根拠によりナップ(クリッペ)とされている(日本地質学会編, 2008).
4.日本の戦後のナップ説
1945年の終戦後,日本の太平洋側の堆積盆は「地向斜」ではなく「地単斜」であり,「地単斜帯では地史の上に特別な造山期というものが認められず」,「日本では作用する力は偶力の状で…大陸側から高水準に,太平洋側からは低水準に…反対に押した形である」という考えを述べた日本地質学会会長もおり(槇山, 1947),太平洋底の岩盤が日本列島に押し寄せ日本列島下に衝下(しょうか)(underthrust, subduct)しているとする,プレートテクトニクスを彷彿とさせるような「太平洋運動」の提唱もあったが(江原, 1963),結果的にそれらは大きな影響力を持たなかった(偶力とは,1つの物体に働く,大きさが同じで向きが逆の一対の力で,2つの作用点を結ぶ方向と力の方向が一致しない場合を言い,物体に回転運動や剪断変形を生じる).しかし,日本各地の地質図作成の中で多数のナップやクリッペの発見が続き(河合, 1970),次の飛躍の基礎となった.主な1/5万地質図を北から挙げる:山部,大夕張,石狩金山,紅葉山**(夕張岳衝上等),能代*,森岳*(能代衝上),羽後和田*,本荘*(北由利衝上),酒田*(酒田衝上),寄居**(金勝山クリッペ),清水*(糸静線則沢クリッペ),八尾,白木峰*,東茂住(横山衝上),荒島岳(伊勢衝上),根尾(徳山衝上),彦根東部*(霊仙クリッペ),御在所山*(竜ヶ岳クリッペ),神戸*(丸山衝上等),若桜*(蛇紋岩),津山東部(美作衝上),蒲江*,延岡**,諸塚山*,神門*,椎葉村**,村所**(延岡衝上)(出版年: 無印1953-70, *1971-90, **1991-2010).
プレートテクトニクスが1970年代に確立され,海溝から日本列島の下に延びる深発地震面やその発震機構,それに伴う地殻変動等がその理論によって説明されるようになっても,地質研究者がその理論を受け入れて,それによって日本の地質を説明するようになるまでには,1980年代の「放散虫革命」(佐藤, 1989; 武村, 2011)を経ねばならなかった.この革命によって,日本列島全体が付加体のナップ構造からなり,衝上断層によって古い付加体が上,新しい付加体が下に重なるという考えが十分な野外地質と化石年代の根拠をもって確立され,1990年代以後は地質研究者の間に広く受け入れられるようになった.
なお,付加体・オフィオライトを限る衝上断層の様子や飛騨ナップの問題については石渡ほか(1999)や石渡(2003a)を参照されたい.そして,ナップ説の現状については,朝倉書店の「日本地方地質誌」全8巻やロンドン地質学会のThe Geology of Japanを参照されたい(石渡ほか, 2016).
5.おわりに
最後に強調したいことは,上に述べたナップと押し被せ褶曲の関係のように,断層と褶曲の間には常に密接な関係があり,付加体のナップ構造も必ず大規模な褶曲を伴っているはずで,さらには(衝上断層に限らず)地表付近の活断層も地下深部の基盤岩の褶曲(基盤褶曲)と関連して発生しているはずだということである(藤田, 1983).例えば,別所文吉によると,1891年濃尾地震を起こした根尾谷断層は美濃帯(ジュラ紀付加体)の背斜(アンチフォーム)軸に沿っている(石渡, 2003b).今後はこのような視点からの断層と褶曲の関係の解明を期待したい.
文献
張麗旭 (1939) 岡山県川上郡大賀四近の地質特に大賀衝上について. 地質学雑誌, 46, 294-295(演旨).
Collet, L.W. (1927) The Structure of the Alps. Edward Arnold & Co. (読んだのは1935年の第2版 304 p).
Davis, G.H. (2017) Tectonic klippe served the needs of cult worship, Sanctuary of Zeus, Mount Lykaion, Peloponnese, Greece. GSA Today, 27(12), 4-9 and cover. Doi: 10.1130/GSATG353A.1.
江原真伍 (1963) 高野山押出シと南海道地震. 地学研究, 14, 109-117 (同誌, 15, 225-226に追悼文と大橋良一による思い出, 337-344に別所文吉による評伝がある).
藤本治義 (1930) 手取川流域に発見せる著しい衝上断層. 地質学雑誌, 37, 570-571 (演旨).
藤本治義 (1937) 関東山地に発見した押し被せ構造. 東京博物学雑誌, 35(60), 377-385.
藤本治義 (1951) 日本地方地質誌 関東地方. 朝倉書店. 315 p.
藤田和夫 (1983) 日本の山地形成論:地質学と地形学の間. 蒼樹書房. 466 p.
井尻正二・杉山隆二・小川賢之輔・岩井四郎・和田信・渡辺善雄・木村正 (1944) 関東山地に於ける推し被せ構造の再検討 1. 堂平山クリッペに就いて. 東京科学博物館研究報告, 14, 1-9.
Imai, H. (1926) Geology of the Ishikari Coal-field, Hokkaido with special reference to an overthrust rock-sheet. Proceedings of the 3rd Pan-Pacific Science Congress, Tokyo. II, 1561-1571.
Ishiwatari, A. (1985) Alpine ophiolites: product of low-degree mantle melting in a Mesozoic transcurrent rift zone. Earth Planet. Sci. Lett., 76, 93-108.
石渡明 (1989) 日本のオフィオライト. 地学雑誌,98, 290-303.
石渡明 (2003a) 飛騨ナップは存在するか:中部日本の地質学の大問題. 月刊地球, 25(12), 898-906.
石渡明 (2003b) 地質家別所文吉の生涯:根尾谷からハルマヘラ島を経て大阪山脈へ. 地質学雑誌, 109(5), 299-302.
石渡明・井龍康文・ウォリスサイモン (2016) 「日本地方地質誌」完結と「The Geology of Japan」出版:日本地質学発展のランドマーク. 日本地質学会News, 19(1), 9-10.
石渡明・辻森樹・早坂康隆・杉本孝・石賀裕明 (1999) 西南日本内帯古〜中生代付加型造山帯のナップ境界の衝上断層.地質学雑誌,105(2), III-IV.
河合正虎 (1970) 日本列島の生い立ちをさぐる(I, II). ラテイス刊. 224 p., 176 p.
Kobayashi, T. (1941) The Sakawa orogenic cycle and its bearing on the origin of the Japanese Islands. Jour. Fac. Sci., Imp. Univ. Tokyo, Sec. 2, 5, 219-578.
小林貞一 (1950) 日本地方地質誌 中国地方. 朝倉書店. 249 p.
小林貞一 (1951) 日本地方地質誌 総論. 朝倉書店. 353 p.
小藤文次郎 (1910) 地質学上ノ見地ニ依ル江濃地震. 震災予防調査会報告, 69, 1-15. 図版5.
槇山次郎 (1947) 会長講演. 地質学雑誌, 53, 42-43.
Nagao, T. (1933) “Nappes” and “klippes” in central Hokkaido. Proceedings of the Imperial Academy, IX, 101-104.
日本地質学会編 (2008) 日本地方地質誌 関東地方. 朝倉書店. 570 p.
大立目謙一郎 (1941) 石狩炭田南部の推被衝上構造の新事実に就て. 矢部教授還暦記念論文集, II, 973-988.
小澤儀明 (1923) 秋吉台石灰岩を含む所謂上部秩父古生層の層位学的研究. 地質学雑誌, 30, 227-243.
Sano, H. and Kanmera, K. (1991) Collapse of ancient oceanic reef complex: what happened during collision of Akiyoshi reef complex? Jour. Geol. Soc. Japan, 97, 297-309.
佐藤正 (1989) 日本中・古生界研究の放散虫革命(シリーズ解説:最近の地質学の発展). 応用地質, 30(3), 153-162.
関武夫 (1939) 伊吹山附近秩父系の層序及び構造に就て. 矢部教授還暦記念論文集, I, 521-535.
杉村新 (1987) グローバルテクトニクス:地球変動学. 東京大学出版会, 250 p.
杉山隆二 (1943) 群馬県,下仁田町附近に発達する所謂跡倉礫岩に就いて. 東京科学博物館研究報告, 7, 1-30.
杉山隆二・井尻正二・岩井四郎 (1944) 関東山地に於ける推し被せ構造の再検討 2. 大霧山推し被せの南縁に就いて. 東京科学博物館研究報告, 14, 9-13.
竹村厚司 (2011) 放散虫革命の立役者, 中世古幸次郎先生のご逝去を悼む. 化石, 90, 67-69.
瀧本清 (1936) 滋賀県犬上郡霊仙山附近の地質構造. 地球, 26, 1-11, 図版1.
(2018.1.23掲載.2.13,2.16一部修正)
【geo-Flash】No.404(臨時)堀口萬吉 名誉会員 ご逝去
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.404 2018/1/16┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 堀口萬吉 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
堀口萬吉 名誉会員(埼玉大学名誉教授)が,平成29年12月26日(火)にご逝去
されました(享年89歳).
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます.
なお,ご葬儀は,すでに近親者によりしめやかに執り行なわれとのことです.
会長 渡部 芳夫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.405 大型研究計画ヒアリングに向けて
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.405 2018/1/23┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】大型研究計画ヒアリングに向けて
【2】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月30日
【3】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【4】名誉会員候補者の募集が開始されています
【5】コラム:日本ナップ説略史
【6】第20回地震火山こどもサマースクール開催地候補募集
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】大型研究計画ヒアリングに向けて
──────────────────────────────────
地球惑星科学分野大型研究計画のヒアリングが実施されます.地質学的に重要
で推進すべき大型研究のプラン,アイデアなど計画がございましたら,関係者
で協議のうえで提案してください.
【提出物】代表者氏名,研究概要(400字以内)
【締切】 2018年1月31日(水)
【提出先】地質学会事務局(main@geosociety.jp)
ここでいう大型研究は100億円規模のものであり,学術会議の次期マスタープラ
ンを視野に入れたものになります.地質学会でエントリ取りまとめて提出いた
します.本エントリシートはヒアリングのためのものであり,その次のステッ
プであるヒアリングの趣旨,内容を考慮に入れてください.詳細は下記をご参
照ください.
――――――――――――――――
第24期日本学術会議地球惑星科学委員会及び地球・惑星圏分科会の依頼文書
1.地球惑星科学分野大型研究計画ヒアリング
日時:2018年3月28日(水)
場所:日本学術会議 6階6-C(1)(2)(3)会議室(予定)
(東京メトロ千代田線「乃木坂駅」5番出口 徒歩1分)
主催:第24期日本学術会議 地球惑星科学委員会
趣旨:
(1)前回からの継続課題のフォローアップ及び新規大型研究計画の創出
(2)マスタープラン2017非採択課題もしくは新規提案課題においては,今後の
改定での採択に向けた支援
(3)今後の文部科学省「重点研究」等の採択に向けた支援
発表内容:計画の概要・進捗状況等(お話し頂きたいポイントは以下の通り)
備考:旅費の負担は致しかねます.どうかご容赦願います.
2.ヒアリングについて
発表時間:10分程度
質疑応答:15分程度(提案件数による)
発表いただきたいポイント:
日本学術会議「提言:第23期学術の大型研究計画に関するマスタープラン」(マ
スタープラン2017)
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-t241-1-0.pdf
に記載されている
1)学術的価値
2)実施主体の明確性(責任を果たせる体制になっているか)
科学者コミュニティの合意(他の提案との重複の有無なども含む)
3)計画の妥当性,成熟度,共同利用体制の充実度
4)社会的価値(国民の理解,知的価値,経済的・産業的価値)
5)大型研究計画としての適否
6)国家としての戦略性,緊急性
7)予算化のための計画の準備状況
の7つの観点に加えて,
8)計画の独自性・強み,どのようなブレークスルーが期待できるか
について評価を行いますので,これらのポイントを明確に発表いただけますよ
うお願いします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月30日
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は,3月30日(金)です.
2018年度の割引会費を希望のかたは,忘れずにご提出ください(締切厳守).
■ 自動引落による納入
昨年12月25日にお届けの金融機関口座より引き落としさせていただきました.
通帳記帳等でご確認ください.請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略さ
せていただきますのでご了承ください.
■ 郵便振替用紙(またはゆうちょ銀行口座)からのお振り込み
12月に請求書兼郵便振替用紙を発送しました.地質学会の会費は前納制で
すので,お早めにご送金ください.
2018年度割引会費申請や通常の会費払込について,
http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[125周年関連情報]寄付受付中!(クレジットカードも可)
──────────────────────────────────
125周年記念事業として,2018年5月東京での記念式典をはじめ,様々な事
業を計画しています.また,それら記念事業を実行するため,学会員や賛助会
員,さらには関連諸団体に寄付をお願いしております.
*醵金者一覧
http://www.geosociety.jp/125th/content0014.html
*記念事業に対する寄付のお願い
クレジットカード(VISA, Master, Diners)もご利用いただけます.
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html#kifu
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されています
──────────────────────────────────
募集期間:2017年12月20日(水)〜2018年2月9日(金)
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:例えば,,,地質学への顕著な貢献/地質学会の運
営と発展への貢献/教育現場や企業などでの活動を通じた地質学の普及と振興
への貢献など
*上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することはできませ
んが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
(名誉会員推薦委員会 松田博貴)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】コラム:日本ナップ説略史
──────────────────────────────────
(正会員 石渡 明)
米国地質学会の情報誌GSA Today最新号の表紙と冒頭に,ギリシャ・ペロポネ
ソス半島のゼウス霊場は,古成(古第三)系暁新統にジュラ・白亜系が衝上す
るクリッペの上にあったという文理融合研究の報告が載っている(Davis, 201
7).スイス中部シュヴィッツ(Schwyz)州のヘルベチア帯北縁部の白亜系にペ
ンニン帯のジュラ系石灰岩が衝上するミューテン(ミーテンMythen)クリッペ
もゲーテが感動した「神話の山」であり,米国モンタナ州ロッキー山脈の白亜
系に先カンブリア系が衝上するチーフ(Chief)山クリッペ(現地語名は
Ninaistako)も雷神が住む聖山だという.日本の山岳信仰の主な対象は富士山,
白山,御嶽山等の火山だが,伊吹山や霊仙等のクリッペも古来信仰されてきた.
地質学において,ナップ説(クリッペや衝上断層を含む)の歴史は古く,付
加体説はおろか地向斜説より前からあり,日本でも20世紀前半に全国から衝上
断層やナップ,クリッペ等が多数報告され,それらを構造発達史に組み込んだ
議論がなされていた.何事によらずルーツの把握は重要で,古い文献を読むと
現代の研究の盲点に気づくこともある.小論では日本のナップ説の歴史を簡単
に紹介し,若い研究者の参考に供したい.
続きを読む、、、http://www.geosociety.jp/faq/content0757.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】第20回地震火山こどもサマースクール開催地候補募集
──────────────────────────────────
地震火山こどもサマースクールは,日本地質学会,日本地震学会,日本火山学
会と地域自治体や団体が共催する,小・中・高校生を対象とする地球科学関連
の体験学習講座です.2017年度は熊本県益城町で開催し,地元の小・中・高校
生が参加してくれました.2018年度は東京都伊豆大島で開催予定です.今回は,
2019年度の開催地の募集を行います.
*****************************************
募集締切:2018年2月16日(金)
*****************************************
募集の詳細詳は,下記をご覧ください..
(URL)http://www.zisin.jp/opp/gold_summerschool2019_koubo.html
過去の開催の様子は,下記をご覧ください.
(URL)http://www.kodomoss.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[西日本支部]
■西日本支部平成29年度総会・第169回例会
3月3日(土)〜4日(日)
場所:広島大学 東広島キャンパス
講演申込締切:2月15日(木)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
[関東支部]
■気候変動シンポジウム〜激変する地球と災害リスク〜
3月17日(土)13:00〜18:00(終了後大学内で懇親会を開催予定)
場所:横浜国立大学教育文化ホール大集会室
*事前申込不要・参加費無料(要旨集は1,000円程度を予定)
■2018年度関東支部幹事選出のお知らせ
幹事定数:20名
任期:2018年関東支部総会終了後〜2020年関東支部総会まで
立候補期間:2018年3月1日(木)〜3月11日(日)
詳しくは,関東支部HP http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第59回科学技術映像祭(作品募集)
参加申込期限 :1月25日(木)(必着)
http://ppd.jsf.or.jp/filmfest/59/youkou.html
■第206回地質汚染イブニングセミナー
1月26日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:谷 芳生(神奈川県秦野市環境保全課長)
演題:神奈川県秦野盆地の水循環調査とその教訓
http://www.npo-geopol.or.jp
■火山噴火予測研究の今!及びその将来展望
1月27日(土)10:15〜13:00
会場:池袋サンシャインシティ文化会館2階
定員:180名(要予約)・参加無料
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/12/1399833.htm
■東北大学東北アジア研究センター公開講演会
玉—その期限と東北アジア先史の「石」文化
2月10日(土)14:00〜17:00
場所:東北大学川内キャンパス
入場無料・参加申込不要
http://www.cneas.tohoku.ac.jp/index.html
■(後)人と自然の博物館&県立大学自然・環境科学研究所
25周年記念フォーラム「日本の恐竜時代を探る!」
2月18日(日)13:00〜17:30
場所:人と自然の博物館 ホロンピアホール(兵庫県三田市弥生が丘)
定員300名(先着順)・参加費無料
http://www.hitohaku.jp/
■日本地球惑星連合2018年大会
5月20日(日)〜24日(木)
場所:幕張メッセおよび東京ベイ幕張ホール
最終締切: 2月19日(月)
早期参加登録締切:5月8日(火)
http://www.jpgu.org/meeting_2018/
■Crossing New Frontiers - Tephra Hunt in Transylvania
(2018年野外研究集会)
主催:International Focus Group on Tephrochronology and Volcanology
(INTAV)(テフラ・火山国際研究グループ)
6月24日(日)〜29日(金)
場所:ルーマニア
早期参加登録締切:4月20日(金)
http://www.bayceer.uni-bayreuth.de/intav2018/
問い合せ先:首都大 鈴木毅彦(suzukit@tmu.ac.jp)
■(後)第55回アイソトープ・放射線研究発表会
7月4日(水)〜6日(金)
場所:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
発表申込締切:2月28日(水)17:00
https://www.jrias.or.jp/
★日本地質学会第125年学術大会
9月5日(水)〜7日(金)
場所:北海道大学(札幌市)
講演申込受付:4月末〜6月13日(水)
http//www.geosociety.jp
■第35回歴史地震研究会(大分大会)
9月22日(土)〜25日(火)
場所:ホルトホール大分(大分市金池南1-5-1)
講演申込締切:5月31日(木)
http://sakuya.ed.shizuoka.ac.jp/rzisin/menu7.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・東京大学大気海洋研究所助教公募(海洋底環境分野)(3/19)
・東京大学地震研究所准教授公募(アクティブテクトニクス分野)(3/26)
・富山県理工系・薬学部生対象奨学金返還助成制度(3/30)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
125記念トリビア16
〜2018年日本地質学会創立125周年を記念して〜
トリビア学史 16 東京大学の演説会
矢島道子(日本大学文理学部)
図.東京日日新聞,明治10年6月5日(1650号)より.
はじめに
「演説」という行為は明治時代には,大変重要だった.福澤諭吉の訳と言われている.明治15年には「演説する女」も現れた(関口,2014).特に自由民権運動における演説は有名であるが,本トリビアはそういう意味ではない.
東京大学は明治10年に創立されたが,『東京日日新聞』の記事を読んでいくと,創立当初から一般の人向けに講演会がおこなわれていたようなのだ.この講演会は演説会あるいは演舌会と言われていた.東京帝国大学五十年史(1927)には,これらの記載が一切ない.進化論を一般向けの講演会で演説したモースの『日本その日その日』にも大学の講演会は一言も触れられていないので,現在,わかり始めたことだけ記す.
邦語演説
東京日日新聞の記事はトリビア15(客死した鉱山学者ヘルマン・リットル)でもふれたが,今回引用する記事は多くが4面の広告記事である.まず,明治10年3月17日(1583号)に東京開成学校の広告が載っている.
「以来毎月第2の土曜日午後7時より講義室に於いて邦語演説,第4の土曜日同刻より英語演説を開き,外来聴聞200人余を許す.聴聞の望ある者は同日午後6時30分までに来校門衛より切手を受け取るべし但し右切手は代価を要せず」
聴講券は切手といったらしい.明治10年4月14日土曜日(1606号)には簡単に東京大学の開学が記されている.
「文部省所轄東京開成学校東京医学校を合併し東京大学と改称候状此の旨布達候事明治10年4月12日文部大輔田中不二麿.文部省所轄東京英語学校を東京大学予備門と改称東京大学に付属せしめ候状此の旨布達候事明治10年4月12日文部大輔田中不二麿」
このひと月ほどのあいだに東京開成学校の看板が変わって東京大学になったが,開成学校の頃から計画していた日本語と外国語の演説(舌)会の企画はそのまま引き継がれ,実行に移されたようだ.
第1回の邦語演説は明治10年4月14日土曜に行われた.東京日日新聞,明治10年4月13日(1605号)には
「本月第2土曜日(即14日)午後7時より邦語演説あり仍ち演説者の姓名及其演題を左に掲げ以て之を広告す.演説者は
当校教授補山岡次郎氏,『水の説』
同教授井上良一氏 『所有物の論』
同教授矢田部良吉氏,『動物変遷論』
明治10年4月 開成学校
但し聴講の望ある者は門衛より切手を請取せき段かねて広告し置き候處,今後は切手を交付せざるに因り爾来聴講を要する者は午後6時50分までに来校すべしもっとも外来聴講200余人に満つるときはたとえ右時限前といえども聴講を断るべし.」
と広告がでた.まだ開成学校の名称を使っており,切手制度ではなく先着順にしようとしている.
明治10年5月11日 (1629号)に第2回目の広告が出た.
「本月第2土曜日(即ち12日)午後7時より邦語演説あり.仍ち演説者の姓名及其演題を左に掲げ以て之を広告す
『南蛮交際始末』 当部教授補 山川健次郎氏
『法律沿革の論』 同法学中級生徒高橋健三氏
『英米仏三大革命論』 江木高遠氏
明治10年5月東京大学法理文三学部」
第2回目で学生にも講演させている.江木高遠は後に江木学校を開いて,モースの一般向け講演会を行った人物である.
第3回目は, 明治10年6月5日(1650号) と明治10年6月6日(1651号)に,同一内容の広告が2回掲載された.
「本月第2土曜日(即ち19日)午後7時より邦語演説あり.仍ち演説者の姓名及其演題を左に掲げ以て之を広告す.
『東京近傍地質略説』 本部教場助手 和田維四郎氏,
『夫婦交際像律』 同法学本科中級生本山正久氏,
『学問は淵源を深くするに在る論』 客員西周氏
明治10年6月東京大学法理文三学部」
ようやくのことで,地質学者和田維四郎が第3回講演会を飾った.
第4回目は明治10年10月19日午後7時より客員 中村正直,
(理学部教場助手)多賀章人,(法学部生徒)大原鎌三郎の講演があった(明治10年10月12日,1760号より).変則的だが10月27日午後7時より『英国ケンブリッジ大学校事情』を理学部教授菊池大麓が講演している(明治10年10月26日,1772号より).
第5回目は11月10日午後7時より.理学部教場職員 松本荘一郎『水道の話』,化学生徒 渡邊渡 『日本固有の鉱山術は全く廃すべからざるの論』(明治10年11月8日,1782号より)と続いていった.
英語演説
最初の英語演説は,演説会が始まってから半年ほど経ってからのことだった.
モースが大森貝塚を発見したことが,明治10年10月8日(1756号)に記事として報告され, 明治10年10月15日に英語演説がなされた.
明日の午後8時より東京大学の演舌館に於いて米国理学博士モース氏が前号にも記せし武州大森に於いて日本古生物発見の事を演説せらるるよし聴聞望の者は午後7時50分までに来校すべしとの事なり.( 明治10年10月15日,1762号)
広告が10月15日に掲載され,読者は10月16日に講演会があると思っただろうが,実は誤りで,演説会は15日に開催された(明治10年10月16日,1763号にお詫び広告が掲載された).記事から,東京大学に演舌館があることがわかる.
少し時をおいて明治10年12月19日に化学科の卒業式が行われ,中村正直氏とモルレー氏が講演をし,希望者200名ほどの聴講を許可した.このことは『東京帝国大学50年史』にも触れられている.
しかしこれまでの演説会はあくまでも臨時の企画で,定期的な英語演説は,明治11年4月13日から始まった.
「13日午後7時より英語演説 Natural Knowledge. Its Character, Exterior Limits and Basis Nägile and Fichte,理学部教授 スミス氏 明治11年4月11日東京大學三學部」(明治11年4月12日(1905号))
という記事が載った.スミス理学部教授はイギリスから来た機械工学の教師であった.機械工学の教師がどんなNatural Knowledgeを話したかはわからない.NägileはおそらくNägeliのまちがいと思われる.
第2回は明治11年5月11日午後8時より午後8時より理学部教授モースが『The Last Glacial period』を話した(明治11年5月10日,1928号の記事より).モースの講演はやはり進化論ではなかった.
第3回は明治11年6月8日午後8時よりにモースが『Arts of Ilustration』を講演した(明治11年6月6日,1951号).やはり進化論ではなかった.
まとめ
これらの記事の後にも講演会はあるが,地質学関係は出てこない.また,いつごろ,どんな理由で,この講演会が中止になるのかということもわかっていない.わからないことばかりなのだが,新しい知見のようなので,ここに披露した.諸賢のお知恵を拝借できれば嬉しい.
文献
関口すみ子『良妻賢母主義から外れた人々湘煙・らいてう・漱石』 2014年,みすず書房.
東京帝国大学『東京帝国大学五十年史』1932年.
エドワード・S・モース(著)石川欣一(訳)『日本その日その日』2013年,講談社学術文庫.
【geo-Flash】No.406 2018札幌大会:トピックセッション募集
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.406 2018/2/6┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[125周年関連情報]記念式典のご案内
【2】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【3】[2018札幌大会情報]トピックセッション募集
【4】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月30日
【5】名誉会員候補者の募集について
【6】JpGU2018:地質学会が共催するJpGUセッション
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[125周年関連情報]記念式典のご案内
──────────────────────────────────
日時:2018年5月18日(金)
記念講演:10:30〜11:30(10:00開場)
記念式典(学会のあゆみ,表彰式等):13:00〜16:00
祝賀会:16:30〜18:30(16:15開場)
会場:北とぴあ(東京都北区王子1-11-1)
(注)記念講演・式典は3階つつじホール,祝賀会は16階天覧の間
参加無料,どなたでもご参加いただけます(祝賀会のみ要事前申込,会費制)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/125th/content0007.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[125周年関連情報]寄付受付中!(クレジットカードも可)
──────────────────────────────────
125周年記念事業として,2018年5月東京での記念式典をはじめ,様々な事
業を計画しています.また,それら記念事業を実行するため,学会員や賛助会
員,さらには関連諸団体に寄付をお願いしております.
*醵金者一覧
http://www.geosociety.jp/125th/content0014.html
*記念事業に対する寄付のお願い
クレジットカード(VISA, Master, Diners)もご利用いただけます.
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html#kifu
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2018札幌大会情報]トピックセッション募集
──────────────────────────────────
第125年学術大会(2018年札幌大会)
「イランカラプテ − 地質学が拓く夢・未来」
会場:北海道大学札幌キャンパス(北海道・札幌市)
日程:2018年9月5日(水)〜7日(金)
http://www.geosociety.jp/science/content0096.html
トピックセッション募集中:3月12日(月)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0097.html
演題登録・講演要旨受付:4月末〜6月13日(水)締切
*札幌大会に向けてのスケジュール
http://www.geosociety.jp/science/content0098.html
----------------------------------------------------------------------------
訂正:2/6配信のメルマガで本記事の記述に誤りがありました。訂正いたします。(2/8)
(誤)(2018年愛媛大会) → (正)(2018年札幌大会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月30日
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は,3月30日(金)です.
次年度も割引会費を希望のかたは,忘れずにご提出ください(締切厳守).
■ 自動引落による納入
昨年12月25日にお届けの金融機関口座より引き落としさせていただきました.
通帳記帳等でご確認ください.請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略さ
せていただきますのでご了承ください.
■ 郵便振替用紙(またはゆうちょ銀行口座)からのお振り込み
12月中旬に請求書兼郵便振替用紙を発送しました.地質学会の会費は前納制で
すので,お早めにご送金ください.
2018年度割引会費申請や通常の会費払込について,
http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】日本地質学会名誉会員候補者の募集について
──────────────────────────────────
募集期間:2017年12月20日(水)〜2018年2月9日(金)
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:例えば,,,地質学への顕著な貢献/地質学会の運
営と発展への貢献/教育現場や企業などでの活動を通じた地質学の普及と振興
への貢献など
*上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することはできませ
んが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
(名誉会員推薦委員会 松田博貴)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】JpGU2018:地質学会が共催するJpGUセッション
──────────────────────────────────
JpGU2018において地質学会は,関係学協会等と共催し下記11のセッションを予
定しています。是非セッションへの投稿をご検討下さい。
******************************************
最終投稿締切:2月19日(金)17:00
http://www.jpgu.org/meeting_2018/presentation.php
******************************************
地質学会が共催するJpGUセッション(セッションタイトル,代表世話人)
・堆積・侵食・地形発達プロセスから読み取る地球表層環境変動(清家弘治)
・活断層と古地震(小荒井衛)
・地域地質と構造発達史(山縣毅)
・上総層群における下部−中部更新統境界GSSP(岡田誠)
・Oceanic and Continental Subduction Processes(Hafiz Ur REHMAN)
・Crust-Mantle Connections(田村芳彦)
・変形岩・変成岩とテクトニクス(中村佳博)
・火山・火成活動および長期予測(及川輝樹)
・岩石・鉱物・資源(門馬綱一)
・ジオパーク(尾方隆幸)
・湿潤変動帯の地質災害とその前兆(千木良雅弘)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[西日本支部]
■西日本支部平成29年度総会・第169回例会
3月3日(土)〜4日(日)
場所:広島大学 東広島キャンパス
講演申込締切:2月15日(木)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
[関東支部]
■気候変動シンポジウム〜激変する地球と災害リスク〜
3月17日(土)13:00〜18:00(終了後大学内で懇親会を開催予定)
場所:横浜国立大学教育文化ホール大集会室
*事前申込不要・参加費無料(要旨集は1,000円程度を予定)
(注)ただし,懇親会のみ事前申込必要>締切:3月10日(土)
http://www.geosociety.jp/outline/content0096.html#kanto-01
■2018年度関東支部幹事選出のお知らせ
幹事定数:20名
任期:2018年関東支部総会終了後〜2020年関東支部総会まで
立候補期間:2018年3月1日(木)〜3月11日(日)
http://www.geosociety.jp/outline/content0096.html#kanto-02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地震本部ニュース2017年冬号
「中央構造線断層帯を中心とした四国地域の活断層の長期評価〜地域評価〜を
公表」ほか http://www.jishin.go.jp/herpnews/
■電中研TOPICS Vol.24「送電設備を雪害から守るための技術開発」
http://criepi.denken.or.jp/research/topics/index.html?m=180129
■明治大学危機管理研究センター第40回定例研究会
「最新の建物ごとの地震被害想定法について」(菅井径世,森保宏:名古屋大)
2月18日(日)13:00〜16:30
場所:明治大学駿河台キャンパス
参加無料
http://www.kisc.meiji.ac.jp/~crisishp/ja/notification.html#20180126
■(後)人と自然の博物館&県立大学自然・環境科学研究所
25周年記念フォーラム「日本の恐竜時代を探る!」
2月18日(日)13:00〜17:30
場所:人と自然の博物館 ホロンピアホール(兵庫県三田市弥生が丘)
定員300名(先着順)・参加費無料
http://www.hitohaku.jp/
■第207回地質汚染イブニングセミナー
2月23日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:田村憲司(筑波大学生命環境系 教授)
テーマ:土壌層位と環境汚染(仮題)
http://www.npo-geopol.or.jp
■産技連地質地盤情報分科会講演会「首都圏の地質地盤」
2月23日(金)13:00〜16:45
会場:北とぴあ・第1研修室
入場無料・参加申込不要
CPD3単位の取得ができます.
https://unit.aist.go.jp/rcpd/sgr/event/images/2017/2017chishitusjiban-kouenkai2.pdf
■日本学術会議九州・沖縄地区会議主催学術講演会
「海の利用と保全への新たな挑戦」
3月1日(木)14:00〜16:10
場所:長崎大学文教スカイホール
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/257-s-0301.pdf
■国際シンポジウム「積雪地域における複合災害と研究動向」
3月3日(土)10:00〜15:00
会場:アートホテル新潟駅前
主催:新潟大学災害・復興科学研究所
日本語-英語同時通訳付
参加費無料.事前申込不要
www.nhdr.niigata-u.ac.jp/news/2018_news/20180124.html
■シンポジウム
「浅層地盤・地質の詳細構造解明に資する精密物理探査の現状と課題」
3月20日(火)13:00〜17:10
主催:産業技術総合研究所 地質情報研究部門
場所:産業技術総合研究所 つくば中央 共用講堂
参加費無料,事前参加登録不要
ポスター発表申込締切:3月2日(金)
https://unit.aist.go.jp/igg/geophy-rg/symposium/
■日本地球惑星連合2018年大会
5月20日(日)〜24日(木)
場所:幕張メッセおよび東京ベイ幕張ホール
最終締切: 2月19日(月)
早期参加登録締切:5月8日(火)
http://www.jpgu.org/meeting_2018/
■地質学史懇話会
6月24日(日)13:30〜17:00
場所:北とぴあ 8階803号室(JR京浜東北線王子駅下車3分)
講演予定者:眞島英壽氏・柴田陽一氏
問い合わせ先:矢島道子 pxi02070[at]nifty.com
■(後)第55回アイソトープ・放射線研究発表会
7月4日(水)〜6日(金)
場所:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
発表申込締切:2月28日(水)17:00
https://www.jrias.or.jp/
■ AOM3;The Third Asian Ostracod Meeting
8月6日(月)〜10日(金)
場所:しいのき迎賓館(石川県金沢市)
大会事務局:神谷隆宏(金沢大学)
メール:tkamiya[at]staff.kanazawa-u.ac.jp
http://www.ostracoda.net/aom3/
★日本地質学会第125年学術大会
9月5日(水)〜7日(金)
場所:北海道大学(札幌市)
講演申込受付:4月末〜6月13日(水)
http://www.geosociety.jp/science/content0096.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・鹿児島市(桜島・錦江湾ジオパーク)嘱託職員募集(2/20)
・高知大学海洋コア総合研究センター共同利用・共同研究課題の公募(2/28)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
(お知らせ)東京大学大気海洋研/JAMSTEC:研究船利用公募の一元化について
http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/coop/20180202.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
第8回_佳作1-2
第8回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:活
写真:小野裕介(愛知県)
撮影場所:箱根 大湧谷
【撮影者より】
この写真を撮ったのは数年前、当時活火山と聞いても日本には活火山がたくさんあるんだな程度の考えでした。ですが、近年日本のいたるところで噴火が起こり、活火山の恐ろしさを思い知らされました。
目次へ戻る
佳作:冬晴れ
写真:山内崇司(北海道)
撮影場所:北海道中富良野町
【撮影者より】
北海道中富良野町で撮影しました。真冬に十勝岳連峰が見えることは多くはないので、その姿に感動しました。
目次へ戻る
第8回_佳作3-4
第8回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:beautiful FUJIYAMA(スマホ・携帯)
写真:本多礼子(東京都)
撮影場所:富士山上空(羽田-福岡便の飛行機内)
【撮影者より】
出張で福岡に行く途中で偶然出会った景色です。真っ白な雲と青い空の中で、富士山の美しさが際立って見えました。 スマホで飛行機からの撮影です。
目次へ戻る
佳作:夕暮れの海金剛
写真:松元澄夫(奈良県)
撮影場所:南紀熊野ジオパーク海金剛
目次へ戻る
第8回_佳作5-6
第8回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:咆哮
写真:辰巳 功(東京都)
撮影場所:栃木県鹿沼市
【撮影者より】
現場に向かうときは雨が降っていました。濡れて縞模様がくっきりした虎岩が撮れると期待しました。しかし到着30分前に雨は上がり日が射してきました。高いところは乾いてしまい、黄色くはなりませんでした。水量は多いようで水の流れは力強く,虎が吠えているような迫力がありました。
目次へ戻る
佳作:大理石の芸術
写真:佐藤 瞳(宮城県)
撮影場所:チリ
【撮影者より】
大理石が約6000年の歳月をかけ、湖水に浸食されてできたものです。少ない滞在日数の中、晴天を待ちやっときれいな青を見ることができました。
目次へ戻る
第8回_佳作7-8
第8回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:時が創った渓谷
写真:乗松賢二(愛媛県)
撮影場所:徳島県三好市大歩危
【撮影者より】
2〜1億年ほど前に海底深く創られた地層が地表に現れてできた岩の彫刻美といわれる大歩危をボート,遊覧船を入れて撮影しました.
目次へ戻る
佳作:天国の洞窟
写真:中尾圭志(神奈川県))
撮影場所:ベトナム フォンニャ=ケバン国立公園
【撮影者より】
ベトナムのフォンニャ=ケバン国立公園の「天国の洞窟」です。比較的最近になって入れるようになった洞窟ですが、その規模と美しさは素晴らしいの一言です。4億年前にできたと言われるカルスト地形が作り出す幻想的な世界がそこには広がっています。
目次へ戻る
第8回_佳作9-10
第8回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:火山の恵み
写真:越智優心(神奈川県)
撮影場所:神奈川県足柄群箱根町大涌谷
【撮影者より】
大涌谷は活発な火山活動を間近で見る事ができます。玉子茶屋の温泉池では,生卵を入れてしばらく待つと,硫化鉄が付着して黒いゆで卵になります。美しい富士山を眺めながらおいしい「くろたまご」を食べている時,僕はとても幸せな気持ちになります。
目次へ戻る
佳作:大地の記憶
写真:早川 満(兵庫県)
撮影場所:高知県土佐清水市竜串
【撮影者より】
この竜串海岸は,岩を海蝕風化させ万化の模様を営々といまも創造しています.人間の想像もつかない神秘な石を鋭利なハモノを振って彫り上げた彫刻のようです.砂岩に刻まれた海蝕連痕模様.鮮やかな褶曲地層が浮かんで雄大な景観をみせてくれます.
目次へ戻る
第9回フォトコン_最優秀
第9回惑星地球フォトコンテスト入選作品
最優秀賞:神の彫刻
写真:白山健悦(青森県)
撮影場所:青森県下北郡佐井村仏ヶ浦
【撮影者より】
巨岩・奇岩が連なる景観の仏ヶ浦,上部にそそり立っている巨岩をアクセントに撮影しました.神の彫刻としか思えない圧倒的な景観が広がっていました.
【審査委員長講評】
仏ヶ浦は下北半島西部にある景勝地で,2000万年前の海底火山噴火で噴出した凝灰岩の浸食によってできた断崖・尖塔が連なっている場所です.陸上・船から多数の写真が撮影されています.今までに見たことのないアングルで,この作品を最初に見た時には仏ヶ浦とはわかりませんでした.低い撮影姿勢で手前に凝灰岩を大きく,青空と白雲の向こうの遠景には尖塔を配置しています.手前の凝灰岩や遠景左側の岩は日陰ですが,うまく露出をコントロールして,質感を失わないようにしています.爽快感のある,力強い作品です.
【地質的背景】
下北半島の西海岸にある仏ヶ浦は,檜川(ひのきがわ)層とよばれる海底火山の噴出物でできています.いまから約1,500万年前,日本は大陸から切り離されて列島になりましたが,この時に檜川層が体積しました.似た地層は,東北日本の日本海側に広く分布し,変質して緑がかった岩相をしているため,“グリーンタフ”とよばれます.しかし,仏像を思わせる奇岩が,この約2kmの海岸だけに発達している理由はよくわかっていないようです.(神奈川県温泉地学研究所 萬年一剛)
目次へ戻る
第9回フォトコン_125記念賞
第9回惑星地球フォトコンテスト入選作品
日本地質学会創立125周年記念賞:月に浮かぶ大瀬崎南火道
写真:露木孝範(静岡県)
撮影場所:静岡県沼津市 大瀬崎南火道
【撮影者より】
週末はダイバーで賑わう大瀬崎.外海のダイビングポイントから少し南に歩いた場所に伊豆半島ジオパークを構成する地形があると知り,月夜に撮影に向かいました.現地では,ヤリイカ狙いの釣り船が,岸近くを強烈な明かりを灯して遊弋していて,ダイナミックな溶岩地形の前で強烈な非日常感を味わいながら撮影を行いました.
【審査委員長講評】
伊豆半島の北西端には大瀬崎があり,その南500mに大瀬崎火道があります.縦位置のこの作品では右半分に大きく大瀬崎火道の溶岩を,その向こうには愛鷹山と富士山,そして沼津市の街明かりを配置しています.大瀬崎南火道に月光が当たる月齢や時間をよく計算された上で撮影されたのでしょう.足場の悪い海岸を夜に歩いて行かなければなりませんが,勝手を知った地元の人ならでは作品です.
【地質的背景】
伊豆半島の北西部は100万〜50万年頃に活動した達磨火山が占めていますが,その北西の海側にほぼ同時代に活動した井田火山と大瀬崎火山があります.大瀬崎火山の南火道は,ハワイのキラウエア・イキ火口1959年の噴火から類推されたもので,噴火当時のようすが良く保存されています.火口からの10数回の溶岩やスパッターの噴き出しによって数か月間かけてできたと推定されています.(審査委員長 白尾元理)
目次へ戻る
【geo-Flash】No.407 2018年度役員選挙(結果報告)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.407 2018/2/20┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2018年度役員選挙(結果報告)
【2】[125周年関連情報]記念式典のご案内
【3】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【4】[2018札幌大会情報]トピックセッション募集
【5】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月30日
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2018年度役員選挙(結果報告)
─────────────────────────────────
2018年2月8日
一般社団法人日本地質学会
選挙管理委員会 委員長 佐藤 智之
一般社団法人日本地質学会選挙規則ならびに選挙細則に基づき,理事選挙を
実施いたしました.結果をご報告いたします.
詳しくは,
http://sub.geosociety.jp/members/content0102.html(要会員ログイン)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[125周年関連情報]記念式典のご案内
──────────────────────────────────
日時:2018年5月18日(金)
記念講演:10:30〜11:30(10:00開場)
記念式典(学会のあゆみ,表彰式等):13:00〜16:00
祝賀会:16:30〜18:30(16:00開場)
会場:北とぴあ(東京都北区王子1-11-1)
(注)記念講演・式典は3階つつじホール,祝賀会は16階天覧の間
参加無料,どなたでもご参加いただけます(祝賀会のみ要事前申込,会費制)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/125th/content0007.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[125周年関連情報]寄付受付中!(クレジットカードも可)
──────────────────────────────────
125周年記念事業として,2018年5月東京での記念式典をはじめ,様々な事
業を計画しています.また,それら記念事業を実行するため,学会員や賛助会
員,さらには関連諸団体に寄付をお願いしております.
*醵金者一覧
http://www.geosociety.jp/125th/content0014.html
*記念事業に対する寄付のお願い
クレジットカード(VISA, Master, Diners)もご利用いただけます.
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html#kifu
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2018札幌大会情報]トピックセッション募集
──────────────────────────────────
第125年学術大会(2018札幌大会)
「イランカラプテ − 地質学が拓く夢・未来」
会場:北海道大学札幌キャンパス(北海道・札幌市)
日程:2018年9月5日(水)〜7日(金)
http://www.geosociety.jp/science/content0096.html
トピックセッション募集中:3月12日(月)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0097.html
演題登録・講演要旨受付:4月末〜6月13日(水)締切
*札幌大会に向けてのスケジュール
http://www.geosociety.jp/science/content0098.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月30日
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は,3月30日(金)です.
次年度も割引会費を希望のかたは,忘れずにご提出ください(締切厳守).
■ 自動引落による納入
昨年12月25日にお届けの金融機関口座より引き落としさせていただきました.
通帳記帳等でご確認ください.請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略さ
せていただきますのでご了承ください.
■ 郵便振替用紙(またはゆうちょ銀行口座)からのお振り込み
12月中旬に請求書兼郵便振替用紙を発送しました.地質学会の会費は前納制で
すので,お早めにご送金ください.
2018年度割引会費申請や通常の会費払込について,
http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[西日本支部]
■西日本支部平成29年度総会・第169回例会
3月3日(土)〜4日(日)
場所:広島大学 東広島キャンパス
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
[関東支部]
■気候変動シンポジウム〜激変する地球と災害リスク〜
3月17日(土)13:00〜18:00
場所:横浜国立大学教育文化ホール大集会室
*事前申込不要・参加費無料
(注)ただし懇親会のみ事前申込必要>締切:3月10日(土)
http://www.geosociety.jp/outline/content0096.html
■2018年度関東支部幹事選出のお知らせ
幹事定数:20名
任期:2018年関東支部総会終了後〜2020年関東支部総会まで
立候補期間:2018年3月1日(木)〜3月11日(日)
http://www.geosociety.jp/outline/content0096.html#kanto-02
■2018年度関東支部総会・地質技術伝承講演会
4月21日(土) 14:00〜16:45
場所:北とぴあ 7階 第2研修室
* 関東支部会員の方で総会に欠席される方は委任状をお願いします.
委任状送付締切:4月20日(金)18:00
http://www.geosociety.jp/outline/content0096.html#kanto-02
[東北支部]
■2017年度東北支部総会のお知らせ
3月17日(土)午後〜18日(日)午前
場所:弘前大学理工学部 1号館426号室(弘前市文京町3)
講演申込締切・懇親会(17日夜)参加申込締切:3月7日(水)
申込先:支部幹事 根本直樹(弘前大学)nemoto[at]hirosaki-u.ac.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第7回学生のヒマラヤ野外実習ツアー
3月4日(日)〜18日(日)
場所:ネパール ヒマラヤ,カリガンダキ河〜ルンビニコース
主催:学生のヒマラヤ野外実習プロジェクト
実施主体:ゴンドワナ地質環境研究所及びトリブバン大学
トリチャンドラキャンパス地質学教室の共同実施
www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
■第305回地学クラブ講演会
「東京都産のトウキョウホタテ標本を探る」
3月16日(金)14:00〜15:30
場所:東京地学協会「地学会館」2階講堂
内容:川辺文久(文部科学省)講演
参加申込不要(どなたも無料で参加できます)
http://www.geog.or.jp/lecture/lecturescheduled/327-club305.html
■第208回地質汚染イブニングセミナー
3月30日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:中野 武(大阪大学 環境安全研究管理センター 招聘教授)
テーマ:セルビアの環境モニタリングと国際連携
http://www.npo-geopol.or.jp
■日本地球惑星連合2018年大会
5月20日(日)〜24日(木)
場所:幕張メッセおよび東京ベイ幕張ホール
早期参加登録締切:5月8日(火)
http://www.jpgu.org/meeting_2018/
■地質学史懇話会
6月24日(日)13:30〜17:00
場所:北とぴあ 8階 803号室(JR京浜東北線王子駅下車3分)
眞島英壽「松本達郎とプレートテクトニクス:高千穂変動と
四万十帯付加体論,そしてその先へ」
柴田陽一「日本地政学史素描」
問い合わせ先:矢島道子 pxi02070[at]nifty.com
■(後)第55回アイソトープ・放射線研究発表会
7月4日(水)〜6日(金)
場所:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
参加費:(事前申込)4,000円(当日申込)5,000円,学生:0円
発表申込締切:2月28日(水)17:00
https://www.jrias.or.jp/isotope_conference/index.html
★日本地質学会第125年学術大会(2018札幌大会)
9月5日(水)〜7日(金)
場所:北海道大学(札幌市)
講演申込受付:4月末〜6月13日(水)
http://www.geosociety.jp/science/content0096.html
■国際ゴンドワナ研究連合(IAGR)2018年会・第15回ゴンドワナから
アジア国際シンポジウム
9月24日(月・祝)〜28日(金)
場所:中国西安市
主催:中国北西大学・IAGR
First circularはこちらから(テキストファイル)
連絡先:Prof. Yunpeng Dong(E-mail: dongyp[at]nwu.edu.cn)
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・国土地理協会 2018年度学術研究助成(4/2-4/20)
・第15回「日本学術振興会賞」受賞候補者推薦(学会締切3/24)
・平成29年度(第58回)東レ科学技術賞および東レ科学技術研究助成の候補者
推薦(学会締切8/31)
・2018(平成30)年度「深田野外調査助成」募集(4/30)
・京都大学大院理研究科地球惑星専攻(地質学鉱物学分野)助教公募(岩石学)
(3/30)
・産業技術総合研究所 地質調査総合センター新規研究職員採用(修士)(H30
学内合同説明会出展情報)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.408 札幌大会トピックセッション募集中
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.408 2018/3/6┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[2018札幌大会情報]トピックセッション募集中
【2】[125周年関連情報]祝賀会参加申込のご案内
【3】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【4】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月30日
【5】第9回惑星地球フォトコンテスト:審査結果発表!
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2018札幌大会情報]トピックセッション募集中
──────────────────────────────────
トピックセッション募集締切:3月12日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0097.html
第125年学術大会(2018札幌大会)
会場:北海道大学札幌キャンパス(北海道・札幌市)
日程:2018年9月5日(水)〜7日(金)
http://www.geosociety.jp/science/content0096.html
*札幌大会に向けてのスケジュール
http://www.geosociety.jp/science/content0098.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[125周年関連情報]祝賀会参加申込のご案内
──────────────────────────────────
日時:2018年5月18日(金)16:30〜18:30(16:00開場)
会場:北とぴあ 16階 天覧の間(東京都北区王子)
会費:5,000円
申込締切:4月10日(火)(注)スペースの都合がありますので,できるだけ早
めにお申し込み下さい.
申込方法:
1)メール・FAX・郵送(銀行振込)
2)WEB申込フォーム(クレジット決済)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/125th/content0007.html#125party
※祝賀会のみ要事前申込・会費制です.
同日同会場の記念講演会(10:30〜),記念式典(13:00〜)は,事前申込不要・
参加無料です.http://www.geosociety.jp/125th/content0007.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[125周年関連情報]寄付受付中!(クレジットカードも可)
──────────────────────────────────
125周年記念事業として,2018年5月東京での記念式典をはじめ,様々な事
業を計画しています.また,それら記念事業を実行するため,学会員や賛助会
員,さらには関連諸団体に寄付をお願いしております.
*醵金者一覧
http://www.geosociety.jp/125th/content0014.html
*記念事業に対する寄付のお願い
クレジットカード(VISA, Master, Diners)もご利用いただけます.
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html#kifu
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月30日
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は,3月30日(金)です.
毎年更新ですので,次年度も割引会費を希望の方は,忘れずにご提出ください
(締切厳守).
2018年度割引会費申請や通常の会費払込について,
http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第9回惑星地球フォトコンテスト:審査結果発表!
──────────────────────────────────
2/23に審査会(白尾元理審査委員長)が開催され,応募作品全590作品のうち,
入選13点,佳作12点が決定しました.作品画像は近日学会HP上にて公開の予定
です.
最優秀賞:1点(賞金5万円)
「神の彫刻」白山健悦(青森県)
日本地質学会創立125周年記念賞:1点(賞金5万円)
「月に浮かぶ大瀬崎南火道」露木孝範(静岡県)
優秀賞:2点(賞金各2万円)
「混濁」小山悠太(長野県)
「異様な光景」長谷 洋(和歌山県)
ジオパーク賞:1点(賞金2万円)
「新燃岳」山田宏作(鹿児島県)
日本地質学会会長賞:1点(賞金1万円)
「ワディの河床」佐藤由理(大分県)
その他の結果は,http://www.photo.geosociety.jp/
下記の通り表彰式,展示会を開催予定です.
【表彰式】(作品展示,白尾委員長の講評など)
5月19日(土)11:00〜12:30(時間は多少変更になる場合があります)
会場:北とぴあ 第2研修室(東京都北区王子)
【作品展示予定】今後予定が追加されます.随時HPに掲載予定です
・銀座プロムナードギャラリー(東京)
4月28日(土)午後〜5月12日(土)午前
場所:銀座プロムナードギャラリー(中央区銀座四丁目地内東銀座地下歩道)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■気候変動シンポジウム〜激変する地球と災害リスク〜
3月17日(土)13:00〜18:00
場所:横浜国立大学教育文化ホール大集会室
事前申込不要・参加費無料
(注)懇親会のみ事前申込必要>締切:3月10日(土)
http://www.geosociety.jp/outline/content0096.html
■2018年度関東支部幹事選出のお知らせ
幹事定数:20名
立候補締切:3月11日(日)
http://www.geosociety.jp/outline/content0096.html#kanto-02
■2018年度関東支部総会・地質技術伝承講演会
4月21日(土) 14:00〜16:45
場所:北とぴあ 7階 第2研修室
* 関東支部会員の方で総会に欠席される方は委任状をお願いします.
委任状送付締切:4月20日(金)18:00
http://www.geosociety.jp/outline/content0096.html#kanto-02
[東北支部]
■2017年度東北支部総会
3月17日(土)午後〜18日(日)午前
場所:弘前大学理工学部 1号館426号室(弘前市文京町3)
講演申込締切・懇親会(17日夜)参加申込締切:3月7日(水)
申込先:支部幹事 根本直樹(弘前大学)nemoto[at]hirosaki-u.ac.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地質地盤情報の活用と法整備を考える会 連絡No.24
広報冊子「国民の安全・安心のため 地質地盤情報の活用と法整備を!」を発行
しました。http://www.geo-houseibi.jp
■日本地球惑星連合2018年大会
5月20日(日)〜24日(木)
場所:幕張メッセおよび東京ベイ幕張ホール
早期参加登録締切:5月8日(火)
http://www.jpgu.org/meeting_2018/
■(後)第55回アイソトープ・放射線研究発表会
7月4日(水)〜6日(金)
場所:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
参加費:(事前申込)4,000円(当日申込)5,000円,学生:0円
https://www.jrias.or.jp/isotope_conference/index.html
★日本地質学会第125年学術大会(2018札幌大会)
9月5日(水)〜7日(金)
場所:北海道大学(札幌市)
講演申込受付:4月末〜6月13日(水)
http://www.geosociety.jp/science/content0096.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・2018年コスモス国際賞候補者推薦(学会締切3/30)
・産業技術総合研究所地質調査総合センター新規研究職員採用(修士)(最大
3名)(4/13)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.409 今年も5/10は「地質の日」!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.409 2018/3/20┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[125周年関連情報]祝賀会参加申込のご案内
【2】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【3】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月30日
【4】2017年度版会員名簿発行
【5】2018年「地質の日」記念行事のご案内
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[125周年関連情報]祝賀会参加申込受付中です
──────────────────────────────────
日時:2018年5月18日(金)16:30〜18:30(16:00開場)
会場:北とぴあ 16階 天覧の間(東京都北区王子)
会費:5,000円
申込締切:4月10日(火)
(注)スペースの都合がありますので,できるだけ早めにお申し込み下さい.
申込方法:
1)メール・FAX・郵送(銀行振込)
2)WEB申込フォーム(クレジット決済)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/125th/content0007.html#125party
※祝賀会のみ要事前申込・会費制です.
同日同会場の記念講演会(10:30〜),記念式典(13:00〜)は,事前申込不要・
参加無料です. http://www.geosociety.jp/125th/content0007.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[125周年関連情報]寄付受付中!(クレジットカードも可)
──────────────────────────────────
125周年記念事業として,2018年5月東京での記念式典をはじめ,様々な事
業を計画しています.また,それら記念事業を実行するため,学会員や賛助会
員,さらには関連諸団体に寄付をお願いしております.
*醵金者一覧
http://www.geosociety.jp/125th/content0014.html
*記念事業に対する寄付のお願い
クレジットカード(VISA, Master, Diners)もご利用いただけます.
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html#kifu
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月30日
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は,3月30日(金)です.
毎年更新ですので,次年度も割引会費を希望の方は,忘れずにご提出ください
(締切厳守).
2018年度割引会費申請や通常の会費払込について
http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2017年度版会員名簿発行
──────────────────────────────────
2017年度版会員名簿を作成しました。
3月号の地質学雑誌・ニュース誌とあわせて会員の皆さまにお届けします(3月
末発送予定)。お手元に届きましたら,ご確認下さい.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2018年「地質の日」記念行事のご案内
──────────────────────────────────
2018年の「地質の日」に関連した日本地質学会主催,共催,後援等の催しをご
紹介します.
<学会主催・共催>
◆第9回惑星地球フォトコンテスト展示会
4月28日(土)午後 〜 5月12日(土)12:00
場所:銀座プロムナードギャラリー
◆第9回惑星地球フォトコンテスト表彰式
5月19日(土)11:00〜12:30
会場:北とぴあ 第2研修室会議室(東京都北区王子)
◆街中ジオ散歩 in Kawasaki「多摩丘陵の100万年を歩く」徒歩見学会
5月13日(日)9:45〜16:00 小雨決行(予定)
申込受付期間:3月31(土)〜4月10日(火)
<その他>
◆地質情報普及講座「深海から生まれた城ヶ島」(日本地質学会 後援)
主催:三浦半島活断層研究会
5月20日(日)10:00 〜15:00(小雨決行)
申込締切:5月10日(木)
詳しくは, www.geosociety.jp/name/content0159.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■2018年度関東支部総会・地質技術伝承講演会
4月21日(土) 14:00〜16:45
場所:北とぴあ 7階 第2研修室
* 関東支部会員の方で総会に欠席される方は委任状をお願いします.
委任状送付締切:4月20日(金)18:00
<地質技術伝承講演会>
講師:山根 誠氏(応用地質株式会社 技術本部 技師長)
演題:「ノンテクトニック構造 −地すべり粘土と流入粘土−」
http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地質地盤情報の活用と法整備を考える会 連絡No.25
ホームページを更新(3月20日)
1.平成29年度の活動報告および平成30年度の活動計画/2.宅地建物取引業法
に関する記事 https://www.geo-houseibi.jp
■日本地球惑星連合2018年大会
5月20日(日)〜24日(木)
場所:幕張メッセおよび東京ベイ幕張ホール
早期参加登録締切:5月8日(火)
http://www.jpgu.org/meeting_2018/
■三朝国際インターンプログラム2018参加者募集
岡山大学惑星物質研究所では,国際研究・教育の推進を目的に国際インターン
シッププログラムを開催します.
7月2日(月)〜8 月10日(金)
応募締切:4月22日(日)
応募条件: 地球科学または関連分野専攻の学部 3・4年生または修士1年生 (国
籍不問)で,英語でのコミュニケーション能力があること
https://intern.misasa.okayama-u.ac.jp/misip2018/
■(後)第55回アイソトープ・放射線研究発表会
7月4日(水)〜6日(金)
場所:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
参加費:(事前申込)4,000円(当日申込)5,000円,学生:0円
https://www.jrias.or.jp/isotope_conference/index.html
★日本地質学会第125年学術大会(2018札幌大会)
9月5日(水)〜7日(金)
場所:北海道大学(札幌市)
講演申込受付:4月末〜6月13日(水)
http://www.geosociety.jp/science/content0096.html
■ 15th International Symposium on Mineral Exploration (ISME-XV)
情報科学や環境科学,惑星科学を含む幅広い分野の研究者を集め,資源探査・
開発に関する最新かつ多角的な情報・意見交換を行います.
11月26日(月)〜27日(火)
場所:京都大学国際科学イノベーション棟
講演申込締切:4月30日(月)
http://www.isme-detec.org/ISMExv/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
第9回フォトコン_優秀1
第9回惑星地球フォトコンテスト入選作品
優秀賞:混濁
写真:小山悠太(長野県)
撮影場所:伊那市伊那谷三峰川
【撮影者より】
三波川帯の泥質起源の結晶片岩.微褶曲がきれいだったのでそこに注目しました.
【審査委員長講評】
混濁というタイトルにふさわしく,一目見ただけでは空中写真を見ているような,顕微鏡を覗いているような,不思議な雰囲気をもった作品です.この作品ではスケールが不明ですが,これがかえって魅力となっています.正面から標本写真のように撮影したのも好感が持てます.この作品はスマホで撮影したものです.
【地質的背景】三峰川は赤石山地北部(南アルプス)の大河で伊奈谷北部の伊那市で天龍川と合流しています.「混濁」は三峰川が本流の天龍川を呑み込んでいる広大な氾濫原で“採集”されました.“標本”は細密な褶曲が美しく現れており,それらを切る劈開(岩石や鉱物がもつ特定方向へ割れやすいという性質)が見事です.「混濁」が生まれた場所を推定してみましょう.長谷地区の三波川帯までは確実ですが,露頭でこの作品と同じように見える訳ではありません.長年の水磨により誕生した逸品です.(日本地質学会名誉会員 松島信幸)
目次へ戻る
第9回フォトコン_優秀2
第9回惑星地球フォトコンテスト入選作品
優秀賞:異様な光景
写真:長谷 洋(和歌山県)(和歌山県)
撮影場所:東牟婁郡古座川町小川 滝の拝
【撮影者より】
南紀熊野ジオパーク,ジオパークサイトの滝の拝のポットホールです.砂岩泥岩層が過去のマグマ活動による熱水を受け,白っぽく硬くなっています.また,大雨時の激流に混ざった岩石類によって削られて穴や溝が出来ています.良く訪れる所ですが,この日は紅葉が紅く水面に反射し,長い年月を経て出来た波打つ奇岩と相まって,まるで動物達の墓場のような「異様な光景」となっていました.
【審査委員長講評】
:「滝の拝」とは変わった名前ですが,和歌山県古座川にある小さな滝とその周辺のポットホールが多数ある河床のことです.作者は滑らかに侵食された岩肌と水面に映った紅葉が新鮮に見えたようで,その部分のみを切り取って撮影しています.シンプルな画面構成にセンスの良さが感じられます.
【地質的背景】
紀伊半島南東部には,前期中新世末から中期中新世に堆積した熊野層群が分布し,古座川の支流小川流域にはその下部層が現れます.熊野層群は,四万十付加体上の前弧海盆に堆積したものです.滝の拝付近は層理面が不明瞭な砂岩からなり,熱水変質を受けて岩石が白色化・硬化しています.このため河床は,さまざまな形のポットホールの発達した岩盤となっています.この変質帯は中期中新世の火成作用によるもので,有名な橋杭岩から北北西に伸びる珪長質火成岩脈群があります.(和歌山大学災害科学教育研究センター 後 誠介)
目次へ戻る
第9回フォトコン_ジオパーク
第9回惑星地球フォトコンテスト入選作品
ジオパーク賞:新燃岳
写真:山田宏作(鹿児島県)
撮影場所:鹿児島県霧島市大浪池付近より(霧島ジオパーク)
【撮影者より】
6年ぶりに噴火した新燃岳が,高千穂峰を背景に火口から噴気を上げている様子を撮影してみました.(2018年1月4日撮影)
【審査委員長講評】
霧島山新燃岳は,今年3月初旬には噴火が活発となり,溶岩を噴出しました.この作品はその直前に2011年の溶岩が火口を埋めている様子をドローンで撮影したものです.溶岩の上に堆積した火山灰,硫黄,水たまり,噴気が克明に捉えられています.噴火が激しくなると立ち入り規制が火口から2〜3kmと広がります.一方ドローンは,原則として飛行できるのは目視できる範囲,飛行高度は直下の地表から150m以下と規制があるので,噴火中の撮影は困難が伴います.
【地質的背景】
霧島火山の新燃岳は,2011年1月に軽石を噴出した後,火口内に溶岩を溜めました.2017年10月のマグマ水蒸気噴火の3ヶ月後に撮影されたこの写真では,2017年の火山灰が2011年の溶岩を覆い隠し,噴石が多数のクレーター作ったことがわかります.その後2018年3月に,新たな溶岩が火口内を埋めたため,この作品は2017年噴火直後の火口を撮影した貴重な記録となりました.奥の特徴的な山はやはり霧島火山の高千穂峰です.(神奈川県温泉地学研究所 萬年一剛)
目次へ戻る
第9回フォトコン_会長賞
第9回惑星地球フォトコンテスト入選作品
日本地質学会会長賞:ワディの河床
写真:佐藤由理(大分県)
撮影場所:スーダン カッサラ州カッサラ ガシ川
【撮影者より・地質解説】
スーダン国東部のカッサラ州を流れるワディ,ガシ川は,隣国エリトリアを源流とし同州内で消滅します.雨期には多量の土砂を含む濁流が流れますが,乾期は干上がり,板状にめくれ上がった河床では級化層理や流痕が観察されます.写真奥に見える山は,カッサラのシンボルのタカ山.緑に見えているのは,メスキートという植物で,乾燥地帯の緑化のために導入されましたが,近年地下水を浪費するとして,駆除が必要とも言われています.
【審査委員長講評】
ワディとは,豪雨の時だけ水が流れる枯れ川のことです.グーグルアースで撮影地を調べると上流にも下流にも流路が消えてしまう不思議な川でした.作者は現地で水資源の仕事に従事されている方なので,作品を見て解説文を読むといろいろなことが学べます.画面の3分の2をワディのひび割れた河床,遠景に岩山,その間に緑に木々の構成と色のバランスも秀逸です.
目次へ戻る
第9回フォトコン_ジオ鉄
第9回惑星地球フォトコンテスト入選作品
ジオ鉄賞:悠久の想い
写真:門脇正晃(千葉県)
撮影場所:埼玉県長瀞町 荒川 秩父鉄道上長瀞〜親鼻
【撮影者より】
秩父長瀞は岩畳の景観で知られており,荒川沿いに河原を歩くと結晶片岩が広く露出しています.結晶片岩は,海洋プレートの沈み込みにより地下深部へ引きずり込まれ高圧による変成作用を受け,その後,再び地表に持ち上げられた岩石です.長瀞の河原に立ち,日本列島創成のダイナミックな歴史に想いを馳せているとデキ502号がやってきました.
【講評・地質解説】
紅葉の季節の長瀞へ誘う美しいジオ鉄作品です.「県の石」にも選ばれた片岩.長瀞では三波川結晶片岩の露頭が荒川沿いに露出しており,それらを基盤として大正3年に架橋されたのが秩父鉄道秩父本線の鉄道橋「荒川橋梁」(153m)です.通称親鼻鉄橋とも呼ばれ当時の面影を残す4段の煉瓦橋脚も見どころのひとつ.宝登山の蝋梅をモチーフに塗装された電気機関車デキ502号(ELロウバイ号)と連結された石灰石専用貨車ヲキ100形・ヲキフ100形編成の運行風景に,当地が誇る石灰石鉱業の歴史をも実感できる一枚です.(深田研ジオ鉄普及委員会 藤田勝代)
※「ジオ鉄賞」:第6回より深田研ジオ鉄普及委員会より本コンテストに後援を頂き,「ジオ鉄」賞を設けています.鉄道と地球の姿を組み合わせた優れた「ジオ鉄」作品を表彰します.
目次へ戻る
第9回フォトコン_スマホ
第9回惑星地球フォトコンテスト入選作品
スマホ賞:流
写真:石田英俊(高知県)
撮影場所:高知県吾川郡 仁淀川支流中津川上流 雨竜の滝
【撮影者より】
撮影者のコメント:水流により時流が削り出され風流と為す.私たちの生活する惑星地球は,悠久とも思える時の流れを地質に重ね上げ現(うつつ)の姿を現しています.ある時から始まった水の流れが私たちを過去へと誘(いざな)う扉を開き,未来へ続く時の流れが更なる過去への誘いを深めていきます.剥き出しにされた過去の記憶,地質.書物すら無い時代の歴史の断面に誰もがロマンを感じこれを風流と呼びます.
【審査委員長講評】
雨竜の滝は,高知県の上流の仁淀川にかかる滝です.滝の高さは16mほどですが,堅いチャートを穿ってできたポットホールやチャットの縞模様や色合いが魅力的に撮られています.露出をアンダー気味にしたので,滝から落ちる水や濡れた岩肌の質感がよく表現されました.注意深く撮影すればこのような作品がスマホで撮影できるのですから,最近のスマホのカメラの進歩には驚かされます.
【地質的背景】
撮影場所の中津渓谷は,秩父帯の北部にあたる中生代の付加体です.ここにはトリアス紀のチャートがあります.チャートは放散虫という珪質プランクトンが深海底に降り積もってできた地層で,海洋プレートとともに移動してきて,日本列島に付加されたものです.ガラス質の地層が規則正しく繰り返す,とてもきれいな縞々です.そしてとても硬いがゆえに,中津渓谷は深くて急峻な崖に囲まれており,すばらしい景観をみせてくれます.(山口大学大学院創成科学研究科 坂口有人)
目次へ戻る
第9回フォトコン_入選1
第9回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:尖塔エギュー・ドゥ・ミディ
写真:高木 嶺(東京都)
撮影場所:フランスシャモニー州,エギュー・ドゥ・ミディ(Aiguille du Midi)
【撮影者より】
この写真はフランスシャモニーの観光地,エギュー・ドゥ・ミディです.氷河が削った2つのU字谷の間が鋭く尖っている様子を超広角レンズで撮影しました.このような自然が織り成す造形美は,行くことが困難な場所も多くありますが,ここは観光地化されており,人がたくさんいるのもまた面白いと思い,尖塔だけではなく人も構図に入れて撮影しました.
【審査委員長講評】
エギュー・ドゥ・ミディは,フレンチアルプスの最高所(3,842m)にある展望台で,ロープーウェイで簡単に行くことができます.目の前にあるモンブランやグランドジョラスにカメラを向けて終わってしまいがちですが,ここでは冷静に岩峰を画面中央に配置して観光施設や観光客をしっかりと写しています.岩峰を構成する岩石もよくわかります.
【地質的背景】
Aiguille du Midiはモンブラン山系の1つでフランス・イタリア国境に位置する標高3,842mの険しく切り立った山です.「Aiguille」は針のように尖った山という意味で,「針峰」と訳されます.その地質はバリスカン造山帯の変成基盤岩類で特徴付けられ,アルプス造山運動により著しく変形した片麻岩・ミグマタイトとカルクアルカリ系の花こう岩から構成されます(放射年代は古生代後期).針峰の地形は氷河の侵食作用によって形成されたものです(東北大学アジア研究センター 辻森 樹)
目次へ戻る
第9回フォトコン_入選2
第9回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:昔 何もなかった頃
写真:矢野根滋明(石川県)
撮影場所:石川県加賀市片野海岸
【撮影者より】
軽石凝灰岩が波に侵食された海岸です.侵食により岩は砂浜の海岸線上にあり,真近に観察することができます.海と夕日を交えて,ノスタルジック風に撮影しました.
【審査委員長講評】
加賀市の片野海岸のある軽石凝灰岩の露頭を夕日とともに撮影した作品です.インターネットで調べると,作品左側に写っている露頭は,かなりりっぱな軽石凝灰岩の露頭のようですが,この作品ではそのことが伝わってきません.美しい作品ですが,もうすこしジオの要素をとりいれて欲しかったと思います.
【地質的背景】
加賀市片野の長者屋敷跡海岸から見た,沈みゆく太陽と雲,海,大地が織りなす幻想的な光景です.ここの磯や崖は尼御前岬層の純白の軽石凝灰岩からなり,火山豆石や気泡が引き延ばされた木片状軽石を多く含んでいます.画面中央に東尋坊や越前松島の中期中新世火山岩(12-13Ma)の丘陵が遠望され,本層はそれより少し古いとされています.画面左手の海岸段丘上には黒色の安山岩(9Ma)の岩塊が多数散在し,長者屋敷伝説のもとになっています.(元日本地質学会会長 石渡 明)
目次へ戻る
第9回フォトコン_入選3
第9回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:風吹く夜に
写真:西 眞史(東京都)
撮影場所:ベトナム北部 ニンビン
【撮影者より】
2017年8月に,ベトナム北部ニンビンにて撮影しました.数日間滞在していたロッジ裏にあった岩山を撮影しました.地元の人々にとって,山間部では珍しくない岩山とのことですが,初めて訪れた私にとって息を飲むほどに壮観な景色でした.
【審査委員長講評】
ハノイの南東100kmにあるニンビンのロッジ裏から撮影した作品です.高さ数10mの岩山の向こうに見える月と星々,雲は流れ,緑がぶれているので風が吹いていることも感じさせます.このような星空を撮影した作品で難しいのは,前景の撮影の仕方です.手前からの照明がないと岩山は真っ暗になり,照明が明るすぎると星空が見にくくなってしまいます.作者は街路灯やロッジの光がうまく当たる場所を選んで撮影されたのでしょうか.
【地質的背景】
北部〜中部ベトナムには,カンブリア系〜三畳系の炭酸塩岩類が広く分布しています.チャンアン(Trang An)地域には,中期三畳紀の微化石などを含む厚い石灰岩が分布していて,カルスト地形や鍾乳洞が発達し,様々な奇景やベトナムの牧歌的な景観を生み出しています.写真のような崖は,その形を動物や身近な物に見立てて名前を付けていることが多いようです.チャンアンの景観群(landscape complex)は,2014年にユネスコの世界遺産に登録されています.(熊本大学 小松俊文)
目次へ戻る
第9回フォトコン_入選4
第9回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:日が暮れる
写真:高橋広太郎(福岡県)
撮影場所:福岡県北九州市小倉南区 平尾台
【撮影者より】
夏の終わりが近づくころの夕陽を,平尾台の特徴的な岩と共に撮影しました.
【審査委員長講評】
この作品は,福岡県のカルスト台地,平尾台の石灰岩柱を日没時に撮影したものです.山口県の秋吉台には墓石状の石灰岩柱が多いのですが,平尾台には円頂型のものが多いようです.作者はその中から馬蹄形のものを選んで撮影しました.日没の光で石灰岩の質感をうまく表現しました.
【地質的背景】
平尾台は秋吉台と同時期(石炭紀〜ペルム紀)の海山上に形成したサンゴ礁が付加したもので,九州最大のカルスト地形です.秋吉台と異なるのは,白亜紀頃の花崗岩や塩基性貫入岩による熱変成により結晶質石灰岩に変化しており,化石などはほとんど報告がなく,よく見ると貫入岩が規則正しく並んでみられます.写真は夕日と丸い侵食地形が美しく,接写部分ではザラメ糖のようなカルサイトの結晶がみられ,平尾台の石灰岩の特徴をしっかりと記録しており,ジオフォトとして高く評価されます.平尾台には4-5カ所一般の人が立ち入るこのできる洞窟もあり,その横には,日本で3番目に大きな石灰岩鉱山(三菱マテリアルなど)があります.詳細は,以下を参照してください.
https://www.gsj.jp/data/bull-gsj/19-07_02.pdf(九州大学 清川昌一)
目次へ戻る
第9回フォトコン_入選5
第9回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:切り立った断崖(中学・高校生部門)
写真:越智優心(神奈川県)
撮影場所:栃木県 日光華厳滝
【撮影者より】
日本三名瀑のひとつに数えられる華厳滝は,男体山から流れ出した溶岩などが川をせき止めて中禅寺湖を作り,あふれた水が溶岩壁から流れ落ちてできたと言われています.滝は溶岩壁を侵食し,現在はできた当時より800mも中禅寺湖側に後退したと考えられています.その侵食によって美しい柱状節理が頭上に見られるようになり,この景観が滝の圧倒的な存在感を高めているように思います.
【審査委員長講評】
日光の中禅寺湖に向かう途中の駐車場からエレベーターで降りるとこの撮影場所,華厳の滝下展望台に着きます.滝を写真の中心に入れてしまいがちですが,ここでは華厳の滝右側の柱状節理を大きく入れています.この柱状節理には,柱状節理に直交する板状節理も発達しているのが分かります.青空の下に新緑もまぶしく,すがすがしい作品となっています.
【地質的背景】
男体山から約22,000年前に流れ出した華厳溶岩が,川を堰き止めてできたのが華厳滝です.華厳溶岩は,上から上部溶岩,上部集塊岩,下部溶岩,下部集塊岩の4層からなるとされます.この写真で柱状節理が見える最上部が上部溶岩,その下の暗い色をした部分が上部集塊岩です.上部溶岩と上部集塊岩の間からは水が湧いています.この水は斜面を流れた後,オーバーハングした部分から落ちていますが,このオーバーハング部が下部溶岩です.(神奈川県温泉地学研究所 萬年一剛)
目次へ戻る
【geo-Flash】No.414 札幌大会:講演申込 締切まであと1週間
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.414 2018/6/5┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[2018札幌大会]事前参加登録受付中です!
【2】[2018札幌大会]講演申込 締切まであと1週間
【3】[2018札幌大会]ランチョン・夜間集会明日(6/6)締切です
【4】[2018札幌大会]宿泊予約はお早めに
【5】地震火山こどもサマースクール in 伊豆大島:参加者募集
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2018札幌大会]事前参加登録受付中です!
──────────────────────────────────
会員・非会員問わずWEB申込画面から事前参加登録のお申込が可能です.巡検
のみの参加もお申込いただけます(アウトリーチ巡検も含む).なお,本大会
より巡検のみに参加する場合は,大会参加登録費は徴収しません.
******************************************************
事前参加登録締切:8月10日(金)18時(WEB)
******************************************************
申込はこちらから, http://www.geosociety.jp/science/content0103.html
◆実習プログラム「無人航空機を利用した数値地表モデルの作成」参加者募集(8/10締切)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/gyoji#uav
◆小さなEarth Scientistのつどい〜第16回小,中,高校生徒「地学研究」発表会
参加校募集(7/13締切)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/gyoji#es
このほか普及・関連行事も盛りだくさんです!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2018札幌大会]講演申込 締切まであと1週間
──────────────────────────────────
演題登録には,『札幌大会演題登録専用のアカウント登録』が必要となりま
す.締切まで何度でも修正や要旨差替が可能ですので,あらかじめアカウント
登録をされることをお勧めします.
非会員の方もこれから入会する方も,画面入力が可能です.入会予定の方は
入会手続きと併行して講演申込の作業を進めて下さい.【締切厳守】
******************************************
演題登録・講演要旨受付締切:6月13日(水)
******************************************
詳しくは,大会HPまで
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2018札幌大会]ランチョン・夜間集会明日(6/6)締切です
──────────────────────────────────
会合開催をご希望の場合は,必要な申込項目をe-mailで行事委員会宛に申し込
んで下さい.
***************************
申込締切:6月6日(水)
***************************
詳しくは,大会HPまで
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/meeting
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2018札幌大会]宿泊予約はお早めに!
──────────────────────────────────
札幌大会(会期 9/5-9/7.巡検 9/8-9/9)は,観光シーズンの最盛期からは若
干外れていますが,それでも初秋の北海道は観光客が多く,さらに中国など海
外からの観光客も増加していて, 宿が混みあうことが予測されます. お早めに
宿を予約されることを強くお勧めいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地震火山こどもサマースクール in 伊豆大島:参加者募集
──────────────────────────────────
第19回 地震火山こどもサマースクールin 伊豆大島ジオパーク
「火山島 伊豆大島のヒミツ」
火山国・日本の中でもとりわけ活動的な火山島であり,観光地でもある伊豆大
島を舞台に,島の誕生から現在までの歴史やそこに成立した地域社会との関係
について,野外観察,身近な材料を使った実験,研究者との対話を通して子ど
もたちが楽しく学ぶことによって,火山噴火や地震のしくみを実感し,自然の
恵み・観光と自然災害についての理解を深めるとともに,島の過去と現在,そ
して未来 を考えます.
日程:
2018年8月7日(火)8:45集合.17:00解散
2018年8月8日(水)8:30集合.17:15解散
※宿泊無しの日帰り2 日間.2日間ともご参加ください.
募集対象・人員:小学校5年生から高校3年生まで40名程度
参加費:2,000円
申込締切:7月2日(月)
詳しくは, http://www.kodomoss.jp/ss/izuoshima/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[中部支部]
■2018年支部年会(山梨大会)
6月16日(土)〜17日(日)
会場:山梨大学教育学部N号館
シンポジウム「南部フォッサマグナの過去・現在・未来」
http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
[北海道支部]
■平成30年度総会・例会(個人講演会)
6月16日(土)総会:11:00〜12:00 例会:13:00〜18:00(時間は予定)
場所:北海道大学理学部5号館大講堂(5-203)
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[関東支部]
■地学教育・アウトリーチ巡検「箱根〜北伊豆地域の自然災害の跡を巡る」
2018年8月7日(火)〜8日(水)1泊2日
対象:教育関係者および地学に興味のある一般の方(会員でなくても可)
参加申込締切:7月6日(金)先着順:定員20名
http://kanto.geosociety.jp
■清澄フィールドキャンプ:参加者募集
8月20日(月)〜8月25日(日)5泊6日
場所:東京大学千葉演習林(千葉県鴨川市清澄)
参加申込締切:7月6日(金)
http://kanto.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■科学的特性マップに関する対話型全国説明会
主催:原子力発電環境整備機構(NUMO)/経済産業省資源エネルギー庁
6月2日(土)〜30日(土)
場所:全国5会場(沖縄,富山,徳島,岡山,高知)
開催案内: https://www.numo.or.jp/taiwa/2018/
■海洋理工学会平成30年度春季大会シンポジウム
「地球内部構造と変動から地震を考える」
6月7日(木)13:00〜17:30
場所:東京海洋大学品川キャンパス 白鷹館
http://amstec.jp/convention/H30_spring.html
■第211回地質汚染イブニングセミナー
6月29日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ・901会議室(東京都北区王子)
講師:原 雄(理工学博士)
テーマ: 廃棄物資源化の真意をどこに置くか
http://www.npo-geopol.or.jp
■日本海洋政策学会 創立10周年記念シンポジム
6月29日(金)15:30〜18:15(祝賀会18:30〜)
場所:笹川平和財団ビル 11階 国際会議場
http://oceanpolicy.jp
■(後)第55回アイソトープ・放射線研究発表会
7月4日(水)〜6日(金)
場所:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
参加費:(事前申込)4,000円(当日申込)5,000円,学生:0円
https://www.jrias.or.jp/isotope_conference/index.html
■(後) ?設計業務等標準積算基準書の解説?説明会(地質編)
主催:全地連・経済調査会
7月2日(月)〜8月31日(金)
場所:全国9地区(東京,高松,大阪,仙台,名古屋,札幌,広島,新潟,福岡)
受講料:6,000円
https://seminar.zai-keicho.or.jp/seminar/detail/index/148/6
■2018年度第1回地区防災学会シンポジウム
九州北部豪雨から1年を振り返って:九州北部豪雨の教訓と地域防災力の在り方
7月28日(土)13:00〜16:30(予定)
場所:九州大学 大橋キャンパス多次元デザイン実験棟(福岡市南区)
対象:地域防災力の強化に興味のある方
参加費無料・定員150名
http://www.gakkai.chiku-bousai.jp/
■第72回地学団体研究会総会(市原)
8月17日(金)〜19日(日)
会場:千葉県市原市市民会館
http://ichihara2018.com/
★日本地質学会第125年学術大会(2018札幌大会)
9月5日(水)〜7日(金)
場所:北海道大学(札幌市)
講演申込締切:6月13日(水)
http://www.geosociety.jp/science/content0096.html
■(共)2018年度日本地球化学会第65回年会
9月11日(火)〜13日(木)
場所:琉球大学・千原キャンパス
http://www.geochem.jp/meeting/index.html
■IAGR2018年会・第15回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム
9月23日:参加登録とアイスブレーカー
24日〜26日:IAGR総会,シンポジウム
27日〜28日:野外巡検(Qinling Mountains)
場所:中国西安市Howard Johnson Ginwa Plaza Hotel
発表要旨締切:6月30日(土)
2nd Circular:
www.geocities.jp/gondwanainst/symposium/IAGR2018Onwards/Secondcircular-IAGR
■第18回アジア学術会議
社会のための科学:アジアにおけるSDGsの達成に向けた戦略
12月5日(水)〜7日(金)
会場:日本学術会議(東京都港区六本木7-22-34)
7月17日:論文要旨(Abstract)提出期限
http://www.scj.go.jp/
■第8回学生のヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集
2019年3月4日〜18日(仮日程)
暫定参加費:20万円(学生・院生),25万円(一般),30万円(公費派遣者)
参加申込締切:12月31日
*「ヒマラヤ造山帯大横断2018」今年3月に実施された第7回学生のヒマラヤ野
外実習ツアーの報告書(E-book:189頁)を発行しました.
http//www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・旭川市地域おこし協力隊(ジオパーク専門員)募集(6/13)
・JAMSTEC生物地球化学研究分野研究員or技術研究員(7/20)
・千葉県職員採用選考考査(地質職)の実施(6/21)
・平成30年度下北ジオパーク研究補助金募集(6/8)
・ゆざわジオパーク平成30年度学術研究等奨励補助金募集(6/25)
・2019年度東北海洋生態系調査研究船(学術研究船)新青丸,深海潜水
調査船支援母船よこすか及び深海調査研究船かいれい共同利用公募(7/30)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
第9回_佳作3-4
第9回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:斜光に浮かぶ柱状節理
写真:大谷 景(北海道)
撮影場所:北海道 天人峡
【撮影者より】
大雪山国立公園の山麓、忠別川の上流に位置する天人峡。三万年前に起きた噴火活動の影響により形成された柱状節理が特徴的。忠別川に沿って巨大な柱状節理が立ち並び、圧巻ともいえる景観を見ることができる。 撮影日はちょうど紅葉の時期で、紅葉を纏ったような柱状節理を斜光でとらえた。
目次へ戻る
佳作:塩見岳の美岩
写真:西出 琢(千葉県)
撮影場所:長野県 塩見岳山頂近く
【撮影者より】
山を登っているときれいな岩を目にすることが多々あります。 南アルプス塩見岳の山頂近くできれいな岩を見つけました。 標高3000m近くの美岩に刻まれた歴史を撮影しました。
目次へ戻る
【geo-Flash】No.410 ミニシンポ「日本地質学会のジオパークへの学術的貢献」
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.410 2018/4/3┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[125周年関連情報]祝賀会参加申込のご案内
【2】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【3】ミニシンポジウム「日本地質学会のジオパークへの学術的貢献」
【4】地学教育関連の意見書・パブリックコメントを提出しました
【5】2018年「地質の日」記念行事のご案内
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[125周年関連情報]祝賀会参加申込受付中です
──────────────────────────────────
日時:2018年5月18日(金)16:30〜18:30(16:00開場)
会場:北とぴあ 16階 天覧の間(東京都北区王子)
会費:5,000円
申込締切:4月10日(火)
(注)スペースの都合がありますので,できるだけ早めにお申し込み下さい.
申込方法:
1)メール・FAX・郵送(銀行振込)
2)WEB申込フォーム(クレジット決済)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/125th/content0007.html#125party
※祝賀会のみ要事前申込・会費制です.
同日同会場の記念講演会(10:30〜),記念式典(13:00〜)は,事前申込不要・
参加無料です. http://www.geosociety.jp/125th/content0007.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[125周年関連情報]寄付受付中!(クレジットカードも可)
──────────────────────────────────
125周年記念事業として,2018年5月東京での記念式典をはじめ,様々な事
業を計画しています.また,それら記念事業を実行するため,学会員や賛助会
員,さらには関連諸団体に寄付をお願いしております.
*醵金者一覧
http://www.geosociety.jp/125th/content0014.html
*記念事業に対する寄付のお願い
クレジットカード(VISA, Master, Diners)もご利用いただけます.
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html#kifu
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】ミニシンポジウム「日本地質学会のジオパークへの学術的貢献」
──────────────────────────────────
主催:日本地質学会ジオパーク支援委員会
5月19日(土) 17:30-20:00
場所:北とぴあ第2研修室(東京都北区王子1-11-1)
2015年にジオパークがユネスコの事業になった結果、ジオパークのあり方につ
いて、いくつかの課題がでてきました。その中で重要なものがジオパークにお
ける学術的内容の担保があげられます。現在、日本には43のジオパーク(内8つ
がユネスコジオパーク)がありますが、活動の主体はそれぞれの地域の自治体
になっています。これらのジオパークの学術的内容の担保については、学会が
中心となって支援することが求められてくる可能性が大きいものと考えられま
す。地質学会としてどんな貢献ができるかについて、シンポジウムの開催し、
今後の可能性について検討します。地質学会員初め、ジオパーク関係者、ジオ
パークに関心のある皆様に多数ご参加いただき、意見交換したいと思います。
プログラムはこちら
http://www.geosociety.jp/geopark/content0021.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地学教育関連の意見書・パブリックコメントを提出しました
──────────────────────────────────
3月に下記の意見書・パブリックコメントを提出しました.
・平成30年度大学入試センター試験の地学関連科目に関する意見書
・高等学校学習指導要領案へのパブリックコメント
詳しくはこちら
http://www.geosociety.jp/engineer/content0051.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2018年「地質の日」記念行事のご案内
──────────────────────────────────
2018年の「地質の日」に関連した日本地質学会主催,共催,後援等の催しをご紹介します.
<学会主催・共催>
◆第9回惑星地球フォトコンテスト展示会
4月28日(土)午後 〜 5月12日(土)12:00
場所:銀座プロムナードギャラリー
◆第9回惑星地球フォトコンテスト表彰式
5月19日(土)11:00〜12:30
会場:北とぴあ 第2研修室会議室(東京都北区王子)
◆街中ジオ散歩 in Kawasaki「多摩丘陵の100万年を歩く」徒歩見学会
5月13日(日)9:45〜16:00 小雨決行(予定)
申込受付期間:3月31(土)〜4月10日(火)
◆第35回地球科学講演会
「都市大阪を生んだ土地のなりたち―遺跡の地層から読む―」
5月13日(日)14:00〜16:00
会場:大阪市立自然史博物館 講堂
申込不要
<その他>
◆地質情報普及講座「深海から生まれた城ヶ島」(日本地質学会 後援)
主催:三浦半島活断層研究会
5月20日(日)10:00 〜15:00(小雨決行)
申込締切:5月10日(木)
◆観察会「城ヶ島の高潮・大正関東地震津波・地盤隆起」
主催:ジオ神奈川
日時:2018年5月19日(土)10:00〜15:00
申込締切:5月6日(日)
詳しくは, www.geosociety.jp/name/content0159.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■2018年度関東支部総会・地質技術伝承講演会
4月21日(土) 14:00〜16:45
場所:北とぴあ 7階 第2研修室
* 関東支部会員の方で総会に欠席される方は委任状をお願いします.
委任状送付締切:4月20日(金)18:00
<地質技術伝承講演会>
講師:山根 誠氏(応用地質株式会社 技術本部 技師長)
演題:「ノンテクトニック構造 −地すべり粘土と流入粘土−」
http://kanto.geosociety.jp/
[中部支部]
■2018年支部年会(山梨大会)
6月16日(土)〜17日(日)
会場:山梨大学教育学部N号館
シンポジウム「南部フォッサマグナの過去・現在・未来」
参加申込締切:5月31日(木)
http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■道総研地質研究所ニュース
・休廃止鉱山から流出を続ける坑内水処理のチャレンジ etc
https://www.hro.or.jp/list/environmental/research/gsh/publication/gshnews/gshnews02/index.html
■地震本部ニュース平成30年(2018年)春号
https://www.jishin.go.jp/herpnews/
■産総研 地質標本館
春の特別展「関東平野と筑波山 関東平野の深い地質のお話」
4月17日(火)〜7月1日(日)
入場料無料
https://www.gsj.jp/Muse/exhibition/archives/2018/2018_spring.html
■産総研 地質標本館一般参加型企画「わたしの街から見える筑波山」
いろんな場所から見える筑波山の写真を募集中です
応募締切:月30日(水)締切
https://www.gsj.jp/Muse/exhibition/archives/2018/2018_spring.html#twi
■第209回地質汚染イブニングセミナー
場所:北とぴあ901会議室
4月27日(金)18:30〜20:30
講師:楡井 久(内閣府認証NPO法人日本地質汚染審査機構理事長・
超党派水循環基本法フォローアップ委員会委員)
テーマ: NPO単元調査法とチバニアン調査法との現場社会貢献度の優位性につ
いて−科学技術には厳しい科学性・倫理性が問われることが世の常である−
http://www.npo-geopol.or.jp
■日本地球惑星連合2018年大会
5月20日(日)〜24日(木)
場所:幕張メッセおよび東京ベイ幕張ホール
早期参加登録締切:5月8日(火)
http://www.jpgu.org/meeting_2018/
■OCEANS’18 MTS / IEEE Kobe / Techno-Ocean2018(OTO’18)
5月28日(月)〜31日(木)
会場:神戸コンベンションセンター
https://www.techno-ocean.com/
■地質調査総合センター2018年度春季地質調査研修(参加者募集)
5月28日(月)〜6月1日(金)
研修場所:島根県出雲市長尾鼻周辺(小伊津海岸)
地質:中期中新世の牛切層の堆積岩など
参加費:60,000円
定員 6名(定員になり次第募集終了)
https://www.gsj.jp/geobank/geotraining.html
■第6回堆積実験オープンスクール
6月3日(日)10:00〜17:00
場所:京都大学理学部1号館
参加費無料
申込締切:5月26日(土)
http://ow.ly/La9330jhzoy
■(後)第55回アイソトープ・放射線研究発表会
7月4日(水)〜6日(金)
場所:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
参加費:(事前申込)4,000円(当日申込)5,000円,学生:0円
https://www.jrias.or.jp/isotope_conference/index.html
★日本地質学会第125年学術大会(2018札幌大会)
9月5日(水)〜7日(金)
場所:北海道大学(札幌市)
講演申込受付:4月末〜6月13日(水)
http://www.geosociety.jp/science/content0096.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・海洋研究開発機構国際ポストドクトラル研究員(5/28)
・鹿児島市(桜島・錦江湾ジオパーク)嘱託職員募集(再募集)(4/16)
・下仁田ジオパーク学術奨励金制度
・山田科学振興財団国際学術集会助成(締切2019/2/22)
・2019-2020年開催藤原セミナーの募集(学会締切6/29)
・平成30年度下仁田ジオパーク学術奨励金制度(4/25)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.411 WEB教材「ボクたちの“足もと”から地球のことを知ろう」が完成しました
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.411 2018/4/17┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[125周年関連情報]祝賀会参加申込(まだ間に合います)
【2】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【3】[札幌大会関連情報]まもなく講演申込を開始します
【4】[札幌大会関連情報]シンポ,セッションが確定しました
【5】[札幌大会関連情報]宿泊予約はお早めに
【6】WEB教材「ボクたちの“足もと”から地球のことを知ろう」が完成しました
【7】2018年「地質の日」記念行事のご案内
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[125周年関連情報]祝賀会参加申込(まだ間に合います)
──────────────────────────────────
会員の皆様には125周年の記念式典・祝賀会にぜひともご参加頂き,125周年を
多いに盛り上げて頂きますよう,お願い致します。
祝賀会は会費制となっています。お申込はまだ間に合いますので,ぜひ参加申
込みをお願い致します。
[祝賀会]
日時:2018年5月18日(金)16:30〜18:30(16:00開場)
会場:北とぴあ 16階 天覧の間(東京都北区王子)
会費:5,000円
申込方法:
1)メール・FAX・郵送(銀行振込)
2)WEB申込フォーム(クレジット決済)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/125th/content0007.html#125party
※祝賀会のみ要事前申込・会費制です.
同日同会場の記念講演会(10:30〜),記念式典(13:00〜)は,事前申込不要・
参加無料です.http://www.geosociety.jp/125th/content0007.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[125周年関連情報]寄付受付中!(クレジットカードも可)
──────────────────────────────────
125周年記念事業として,2018年5月東京での記念式典をはじめ,様々な事
業を計画しています.また,それら記念事業を実行するため,学会員や賛助会
員,さらには関連諸団体に寄付をお願いしております.
*醵金者一覧
http://www.geosociety.jp/125th/content0014.html
*記念事業に対する寄付のお願い
クレジットカード(VISA, Master, Diners)もご利用いただけます.
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html#kifu
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[札幌大会関連情報]まもなく講演申込を開始します
──────────────────────────────────
今年の大会予告記事は,ニュース誌4月号にてご案内予定です。会期に合わせ,
大会のスケジュールは,例年より2〜3週間早めの日程になります.まもなく講
演申込開始予定です(4月末)。余裕をもってご準備をお願いします.
ニュース誌4月号:大会予告記事(演題登録・講演要旨受付開始)
6月13日(水):演題登録・講演要旨受付締切/ランチョン・夜間集会申込締切
ニュース誌7月号:大会プログラム記事
8月10日(金) :大会参加登録/巡検/懇親会参加申込締切
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[札幌大会関連情報]シンポ,セッションが確定しました
──────────────────────────────────
札幌大会では,2つのシンポジウムと32のセッション(トピック6件,レギュラー
25件,アウトリーチ1件)が予定されています.
[シンポジウム:2件]*(発表は招待講演のみ)
S1.125周年記念国際シンポジウム「社会と地質学」
S2.特別シンポジウム「前進する北海道地殻構造解明作業:テクトニクス研究
の新たな展開へ」
[トピックセッション:6件]
T1.文化地質学
T2.モホ(地殻—マントル境界)を掘り抜いたオマーン掘削プロジェクト
T3.日本列島の起源・成長・改変
T4.深海科学掘削50年、過去―現在―未来
T5.北海道とその周辺地域における地震・津波研究の最前線
T6.泥火山と地球化学的・地質地形学的・生物学的関連現象
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[札幌大会関連情報]宿泊予約はお早めに
──────────────────────────────────
札幌大会(会期 9/5-9/7.巡検 9/8-9/9)は,観光シーズンの最盛期からは若
干外れていますが,それでも初秋の北海道は観光客が多く,さらに中国など海
外からの観光客も増加していて, 宿が混みあうことが予測されます. お早めに
宿を予約されることを強くお勧めいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】WEB教材「ボクたちの“足もと”から地球のことを知ろう」が完成しました
──────────────────────────────────
普及用無料WEB教材:
ボクたちの“足もと”から地球のことを知ろう
〜地層と地形が教えてくれるボクたちのルーツとミライ〜
http://yume-earth.geosociety.jp
日本地質学会では,平成29年度の(独)国立青少年教育振興機構の子どもゆ
め基金の助成を受けて,標記のWeb教材の開発制作を行い公開いたしました.
この教材は,小学生から中学生の児童・生徒を対象とした内容です.日本各地
の地層や地形,身近に観察できる場所などを対象に,広く地学に興味を持つこ
とができる内容と構成になっています.また,この教材は,学校や家庭で子供
たちを教える教員及び保護者の皆様にとりましても,有効な教材として,子ど
もたちと一緒に楽しく学んでいただける内容です.スマートフォンやタブレッ
トなどで見ることができるように構成されていますので,教室や家庭の中だけ
ではなく,野外観察などの屋外での学習に対応できるツールとしても,大いに
活用していただきたいと思います.
【大切なお願い】普及活動に是非ご協力下さい!
詳しくは,http://www.geosociety.jp/name/content0161.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】2018年「地質の日」記念行事のご案内
──────────────────────────────────
2018年の「地質の日」に関連した日本地質学会主催,共催,後援等の催しをご
紹介します.
<学会主催・共催>
◆第9回惑星地球フォトコンテスト展示会
4月28日(土)午後 〜 5月12日(土)12:00
場所:銀座プロムナードギャラリー
◆第9回惑星地球フォトコンテスト表彰式
5月19日(土)11:00〜12:30
会場:北とぴあ 第2研修室会議室(東京都北区王子)
◆第35回地球科学講演会
「都市大阪を生んだ土地のなりたち―遺跡の地層から読む―」
5月13日(日)14:00〜16:00
会場:大阪市立自然史博物館 講堂
申込不要
<その他>
◆地質情報普及講座「深海から生まれた城ヶ島」(日本地質学会 後援)
主催:三浦半島活断層研究会
5月20日(日)10:00 〜15:00(小雨決行)
申込締切:5月10日(木)
◆観察会「城ヶ島の高潮・大正関東地震津波・地盤隆起」
主催:ジオ神奈川
日時:2018年5月19日(土)10:00〜15:00
申込締切:5月6日(日)
詳しくは,www.geosociety.jp/name/content0159.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■2018年度関東支部総会・地質技術伝承講演会
4月21日(土) 14:00〜16:45
場所:北とぴあ 7階 第2研修室
***支部会員の方で総会に欠席される方は委任状をお願いします***
委任状送付締切:4月20日(金)18:00
<地質技術伝承講演会>
講師:山根 誠氏(応用地質株式会社 技術本部 技師長)
演題:「ノンテクトニック構造 −地すべり粘土と流入粘土−」
詳しくは,http://kanto.geosociety.jp/
[中部支部]
■2018年支部年会(山梨大会)
6月16日(土)〜17日(日)
会場:山梨大学教育学部N号館
シンポジウム「南部フォッサマグナの過去・現在・未来」
参加申込締切:5月31日(木)
http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地質地盤情報の活用と法整備を考える会 連絡No.26
平成30年4月2日、一般財団法人 国土地盤情報センターが設立されました
http://www.ngic.or.jp/
■日本地球惑星連合2018年大会
5月20日(日)〜24日(木)
場所:幕張メッセおよび東京ベイ幕張ホール
早期参加登録締切:5月8日(火)
http://www.jpgu.org/meeting_2018/
■(後)日本原子力学会 特別国際シンポジウム
「断層リスクに向き合う原子力安全のアプローチ」
5月31日(木)13:30〜18:00
場所:東京大学弥生講堂一条ホール
http://www.aesj.net/activity/conference/symp20180531
■(後)第55回アイソトープ・放射線研究発表会
7月4日(水)〜6日(金)
場所:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
参加費:(事前申込)4,000円(当日申込)5,000円,学生:0円
https://www.jrias.or.jp/isotope_conference/index.html
■(後) 「設計業務等標準積算基準書の解説」説明会(地質編)
主催:全地連・経済調査会
7月2日(月)〜8月31日(金)
場所:全国9地区(東京,高松,大阪,仙台,名古屋,札幌,広島,新潟,福岡)
受講料:6,000円
https://seminar.zai-keicho.or.jp/seminar/detail/index/148/6
★日本地質学会第125年学術大会(2018札幌大会)
9月5日(水)〜7日(金)
場所:北海道大学(札幌市)
講演申込受付:4月末〜6月13日(水)
http://www.geosociety.jp/science/content0096.html
■(共)2018年度日本地球化学会第65回年会
9月11日(火)〜13日(木)
場所:琉球大学・千原キャンパス
http://www.geochem.jp/meeting/index.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・東京大学教養学部学際科学科助教公募(地球科学,化学,生物学)(5/11)
・静岡大学理学部地球科学科教授公募(6/1)
・住友財団2018年度研究助成(基礎科学研究助成/環境研究助成) (6/7)
・学術研究奨励事業助成金の募集(糸魚川ユネスコ世界ジオパーク) (4/20)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.413 創立125周年記念式典(5/18)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.413 2018/5/15┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】創立125周年記念式典(5/18)
【2】[2018札幌大会]講演申込受付中!
【2】[2018札幌大会]ランチョン・夜間集会申込受付中!
【4】[2018札幌大会]宿泊予約はお早めに
【5】日本地質学会第10回総会(5/19)
【6】ミニシンポ「日本地質学会のジオパークへの学術的貢献」(5/19)
【7】IAR論文投稿ワークショップ:アクセプトされる論文のヒント
【8】2018年「地質の日」記念行事のご案内
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
【12】訃報:徳永重元 名誉会員 ご逝去
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】創立125周年記念式典開催(5/18)
──────────────────────────────────
いよいよ学会創立125周年の記念式典が開催されます。
会員の皆様のご来場をお待ちしております。
日時:2018年5月18日(金)10:30〜18:30
会場:北とぴあ つつじホール (東京都北区王子1-11-1)
1)記念講演(10:30〜11:30)(10:00開場)
「地質学はどこで生まれ,どこへ行くのか」
矢島道子(125周年記念事業実行委員会 委員長)
2)記念式典(学会のあゆみ,表彰式等)(13:30〜16:00)(13:00開場)
3)祝賀会(16:30〜18:30)(16:00開場)
会場:北とぴあ16階 東武サロン 天覧の間
詳しくは, http://www.geosociety.jp/125th/content0007.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2018札幌大会]講演申込受付中!
──────────────────────────────────
札幌大会の講演申込が開始されました.今年の大会のスケジュールは,例年よ
り2〜3週間早めの日程になります.余裕をもってご準備をお願いします.
演題登録には,“札幌大会演題登録用の専用アカウント登録”が必要となりま
す.締切まで何度でも修正や要旨差替が可能ですので,あらかじめアカウント
登録をされることをお勧めします.
******************************************
演題登録・講演要旨受付締切:6月13日(水)
******************************************
詳しくは,大会HPまで
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/top
(注)大会参加登録(巡検,懇親会など)は,5月下旬より受付開始予定です.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2018札幌大会]ランチョン・夜間集会申込受付中
──────────────────────────────────
会合開催をご希望の場合は,必要な申込項目をe-mailで行事委員会宛に申し込
んで下さい.
***************************
申込締切:6月6日(水)
***************************
詳しくは,大会HPまで
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/meeting
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2018札幌大会]宿泊予約はお早めに
──────────────────────────────────
札幌大会(会期 9/5-9/7.巡検 9/8-9/9)は,観光シーズンの最盛期からは若
干外れていますが,それでも初秋の北海道は観光客が多く,さらに中国など海
外からの観光客も増加していて, 宿が混みあうことが予測されます. お早めに
宿を予約されることを強くお勧めいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】日本地質学会第10回総会開催(5/19)
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会第10回総会開催いたします
日時:5月19日(土)13:30〜15:30
会場:北とぴあ 第2研修室
定款20条により,本総会は役員ならびに代議員による総会となります.正会員
は,総会に陪席することができます.
※同日同会場にて下記の催しが予定されています.
◆第9回惑星地球フォトコンテスト表彰式・展示会
時間:11:00〜12:30
http://www.geosociety.jp/faq/content0009.html
◆ミニシンポ「日本地質学会のジオパークへの学術的貢献」
時間:17:30〜20:00
http://www.geosociety.jp/geopark/content0021.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】ミニシンポ「日本地質学会のジオパークへの学術的貢献」
──────────────────────────────────
主催:日本地質学会ジオパーク支援委員会
5月19日(土) 17:30〜20:00
場所:北とぴあ第2研修室(東京都北区王子1-11-1)
2015年にジオパークがユネスコの事業になった結果、ジオパークのあり方につ
いて、いくつかの課題がでてきました。その中で重要なものがジオパークにお
ける学術的内容の担保があげられます。現在、日本には43のジオパーク(内8つ
がユネスコジオパーク)がありますが、活動の主体はそれぞれの地域の自治体
になっています。これらのジオパークの学術的内容の担保については、学会が
中心となって支援することが求められてくる可能性が大きいものと考えられま
す。地質学会としてどんな貢献ができるかについて、シンポジウムの開催し、
今後の可能性について検討します。地質学会員初め、ジオパーク関係者、ジオ
パークに関心のある皆様に多数ご参加いただき、意見交換したいと思います。
プログラムはこちら
http://www.geosociety.jp/geopark/content0021.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】Island Arc:論文投稿ワークショップ〜アクセプトされる論文のヒント〜
──────────────────────────────────
投稿論文がスムーズにアクセプトされるには,執筆段階における論文構成法の
順守と分かりやすさの追求が欠かせません.このワークショップでは,日本地
質学会の公式欧文誌Island Arcの武藤鉄司編集委員長より,論文執筆を進める
上で鍵となることがらについてアドバイスをいただきます.
日時:5月22日(月)12:30〜13:30
会場:幕張メッセ国際会議場201B(JpGU2018会場内)
対象:若手研究者・院生
講師:武藤鉄司(Island Arc誌 編集委員長)
・講演は日本語で行われます
・希望者にに昼食をご提供(先着50名様・要事前登録)
・当日参加も可能.スムーズにご入場いただくために事前登録をお勧めします.
お申込はこちら
http://www.jpgu.org/meeting_2018/seminar.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】2018年「地質の日」記念行事のご案内
──────────────────────────────────
2018年の「地質の日」に関連した日本地質学会主催,共催,後援等の催しをご
紹介します.
<学会主催・共催>
◆第9回惑星地球フォトコンテスト表彰式
5月19日(土)11:00〜12:30
会場:北とぴあ 第2研修室会議室(東京都北区王子)
◆第10回 身近に知る「くまもとの大地」
6月2日(土)10:00〜16:00
主催:「地質の日」くまもと実行委員会
共催:日本地質学会西日本支部ほか
会場:びぷれす広場(熊本市通町筋)
◆地質の日記念展示「北海道のジオサイトに見る岩石」
4月27日(金)〜 6月17日(日)
主催:地質の日展実行委員会・北海道大学総合博物館
共催:日本地質学会北海道支部
会場:北海道大学総合博物館1 階企画展示室
市民セミナー,市民地質巡検 街中ジオ散歩 in Sapporo ジオサイト「藻岩山」
を歩くも予定されています.
詳しくは, www.geosociety.jp/name/content0159.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】支部情報
──────────────────────────────────
[中部支部]
■2018年支部年会(山梨大会)
6月16日(土)〜17日(日)
会場:山梨大学教育学部N号館
シンポジウム「南部フォッサマグナの過去・現在・未来」
参加申込締切:5月31日(木)
http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
[北海道支部]
■平成30年度総会・例会(個人講演会)
6月16日(土)総会:11:00〜12:00例会:13:00〜18:00(時間は予定)
場所:北海道大学理学部5号館大講堂(5-203)
講演申込:5月25日(金)締切
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[関東支部]
■地学教育・アウトリーチ巡検「箱根〜北伊豆地域の自然災害の跡を巡る」
2018年8月7日(火)〜8日(水):1泊2日
対象:教育関係者および地学に興味のある一般の方(会員でなくても可)
申込期間:5月31日(木)〜7月6日(金)先着順:定員20名
http://kanto.geosociety.jp
■清澄フィールドキャンプ:参加者募集
8月20日(月)〜8月25日(日)5泊6日
場所:東京大学千葉演習林(千葉県鴨川市清澄)
参加申込締切:7月6日(金)
http://kanto.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■科学的特性マップに関する対話型全国説明会
主催:原子力発電環境整備機構(NUMO)/経済産業省資源エネルギー庁
5月10日(木)〜26日(土)
場所:全国6会場(大阪,茨城,島根,鳥取,兵庫,香川)
https://www.numo.or.jp/taiwa/2018/
■日本地球惑星連合2018年大会
5月20日(日)〜24日(木)
場所:幕張メッセおよび東京ベイ幕張ホール
早期参加登録締切:5月8日(火)
http://www.jpgu.org/meeting_2018/
■Charles K. Paull氏ワークショップ&レクチャー・ツアー
タイトル:Direct measurements of the evolution and impact of sediment
gravity flows as they pass through Monterey Submarine Canyon, offshore
California
5月23日(水)〜29日(火)
(1) 5月23日(水)13:00〜17:30 ワークショップ(千葉大学理学部4号館)
(2) 5月25日(金)15:15〜17:15 講演会(産総研)
(3) 5月28日(月)15:00〜16:30 講演会(京都大学理学部)
(4) 5月29日(火)14:00〜17:00 堆積学ワークショップin KCC(高知大学海洋コ
ア総合研究センター)
詳しくは, http://sediment.jp/
■(後)日本原子力学会 特別国際シンポジウム
「断層リスクに向き合う原子力安全のアプローチ」
5月31日(木)13:30〜18:00
場所:東京大学弥生講堂一条ホール
http://www.aesj.net/activity/conference/symp20180531
■石油技術協会平成30年度春季講演会
6月13日(水)〜14日(木)
場所:朱鷺メッセ(新潟市)
http://www.japt.org/
■深田研ジオフォーラム2018
地質痕跡と古文書から過去の地震津波の実像に迫る
6月16日(土)
場所:深田地質研究所 研修ホール
申込期間:5月16日(水)〜30日(木)
定員50名
http://www.fgi.or.jp
■(後)第55回アイソトープ・放射線研究発表会
7月4日(水)〜6日(金)
場所:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
参加費:(事前申込)4,000円(当日申込)5,000円,学生:0円
https://www.jrias.or.jp/isotope_conference/index.html
■(後) ?設計業務等標準積算基準書の解説?説明会(地質編)
主催:全地連・経済調査会
7月2日(月)〜8月31日(金)
場所:全国9地区(東京,高松,大阪,仙台,名古屋,札幌,広島,新潟,福岡)
受講料:6,000円
https://seminar.zai-keicho.or.jp/seminar/detail/index/148/6
■第72回地学団体研究会総会(市原)
8月17日(金)〜19日(日)
会場:千葉県市原市市民会館
http://ichihara2018.com/
★日本地質学会第125年学術大会(2018札幌大会)
9月5日(水)〜7日(金)
場所:北海道大学(札幌市)
講演申込受付:4月末〜6月13日(水)
http://www.geosociety.jp/science/content0096.html
■(共)2018年度日本地球化学会第65回年会
9月11日(火)〜13日(木)
場所:琉球大学・千原キャンパス
http://www.geochem.jp/meeting/index.html
■IGCP608「白亜紀アジア−西太平洋生態系」第6回国際研究集会
11月15日(木)〜16日(金)(研究集会:タイ・コンケーン)
11月12日(月)〜14日(水)(プレ巡検:コラート高原のジュラ系―白亜系Khorat層群と恐竜化石群)
共催:タイ鉱物資源局,Sirindhorn博物館
http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・東京工業大学理学院地球惑星科学系専任助教公募(6/29)
・勝山市ジオパーク学術研究等奨励補助金公募(5/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】訃報:徳永重元 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
徳永重元 名誉会員(元 地質調査所,パリノ・サーヴェイ株式会社)が平成30
年5月8日(火)にご逝去されました(享年98歳).
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます.
なおご葬儀は、ご本人の遺言ならびにご親族の意向により家族葬にて5月12日
(土)に執り行われたとのことです.
会長 渡部芳夫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.412 札幌大会講演申込受付開始です!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.412 2018/5/1┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[2018札幌大会]講演申込を開始しました
【2】[2018札幌大会]ランチョン・夜間集会申込受付中
【3】[2018札幌大会]宿泊予約はお早めに
【4】[125周年関連情報]祝賀会参加申込(まだ間に合います)
【5】[125周年関連情報]寄付のお願い(クレジットカードも利用可)
【6】日本地質学会第10回総会開催(5/19)
【7】IAR論文投稿ワークショップ:アクセプトされる論文のヒント
【8】2018年「地質の日」記念行事のご案内
【9】「伊豆半島」がユネスコ世界ジオパークに認定!
【10】支部情報
【11】その他のお知らせ
【12】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2018札幌大会]講演申込を開始しました
──────────────────────────────────
札幌大会の講演申込が開始されました.今年の大会のスケジュールは,例年よ
り2〜3週間早めの日程になります.余裕をもってご準備をお願いします.
演題登録には,“札幌大会演題登録用の専用アカウント登録”が必要となりま
す.締切まで何度でも修正や要旨差替が可能ですので,あらかじめアカウント
登録をされることをお勧めします.
******************************************
演題登録・講演要旨受付締切:6月13日(水)
******************************************
詳しくは,大会HPまで
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/top
(注)大会参加登録(巡検,懇親会など)は,5月下旬より受付開始予定です.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2018札幌大会]ランチョン・夜間集会申込受付中
──────────────────────────────────
会合開催をご希望の場合は,必要な申込項目をe-mailで行事委員会宛に申し込
んで下さい.
***************************
申込締切:6月6日(水)
***************************
詳しくは,大会HPまで
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/meeting
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2018札幌大会]宿泊予約はお早めに
──────────────────────────────────
札幌大会(会期 9/5-9/7.巡検 9/8-9/9)は,観光シーズンの最盛期からは若
干外れていますが,それでも初秋の北海道は観光客が多く,さらに中国など海
外からの観光客も増加していて, 宿が混みあうことが予測されます. お早めに
宿を予約されることを強くお勧めいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[125周年関連情報]祝賀会参加申込(まだ間に合います)
──────────────────────────────────
会員の皆様には125周年の記念式典・祝賀会にぜひともご参加頂き,125周年を
多いに盛り上げて頂きますよう,お願い致します.
祝賀会は会費制となっています.お申込はまだ間に合いますので,ぜひ参加申
込みをお願い致します.
[祝賀会]
日時:2018年5月18日(金)16:30〜18:30(16:00開場)
会場:北とぴあ 16階 天覧の間(東京都北区王子)
会費:5,000円
申込方法:
1)メール・FAX・郵送(銀行振込)
2)WEB申込フォーム(クレジット決済)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/125th/content0007.html#125party
※祝賀会のみ要事前申込・会費制です.
同日同会場の記念講演会(10:30〜),記念式典(13:00〜)は,事前申込不要・
参加無料です. http://www.geosociety.jp/125th/content0007.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[125周年関連情報]寄付受付中!(クレジットカードも可)
──────────────────────────────────
125周年記念事業として,2018年5月東京での記念式典をはじめ,様々な事
業を計画しています.また,それら記念事業を実行するため,学会員や賛助会
員,さらには関連諸団体に寄付をお願いしております.
*醵金者一覧
http://www.geosociety.jp/125th/content0014.html
*記念事業に対する寄付のお願い
クレジットカード(VISA, Master, Diners)もご利用いただけます.
http://www.geosociety.jp/125th/content0011.html#kifu
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】日本地質学会第10回総会開催(5/19)
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会第10回総会開催いたします
日時:5月19日(土)13:30〜15:30
会場:北とぴあ 第2研修室
定款20条により,本総会は役員ならびに代議員による総会となります.正会員
は,総会に陪席することができます.
※同日同会場にて下記の催しが予定されています.
◆第9回惑星地球フォトコンテスト表彰式・展示会
時間:11:00〜12:30
http://www.geosociety.jp/faq/content0009.html
◆ミニシンポジウム「日本地質学会のジオパークへの学術的貢献」
時間:17:30〜20:00
http://www.geosociety.jp/geopark/content0021.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】Island Arc:論文投稿ワークショップ〜アクセプトされる論文のヒント〜
──────────────────────────────────
投稿論文がスムーズにアクセプトされるには,執筆段階における論文構成法の
順守と分かりやすさの追求が欠かせません.このワークショップでは,日本地
質学会の公式欧文誌Island Arcの武藤鉄司編集委員長より,論文執筆を進める
上で鍵となることがらについてアドバイスをいただきます.
日時:5月22日(月)12:30〜13:30
会場:幕張メッセ国際会議場201B(JpGU2018会場内)
対象:若手研究者・院生
講師:武藤鉄司(Island Arc誌 編集委員長)
・講演は日本語で行われます
・希望者にに昼食をご提供(先着50名様・要事前登録)
・当日参加も可能.スムーズにご入場いただくために事前登録をお勧めします.
お申込はこちら
http://www.jpgu.org/meeting_2018/seminar.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】2018年「地質の日」記念行事のご案内
──────────────────────────────────
2018年の「地質の日」に関連した日本地質学会主催,共催,後援等の催しをご
紹介します.
<学会主催・共催>
◆第9回惑星地球フォトコンテスト展示会【展示中です!!】
4月28日(土)午後 〜 5月12日(土)12:00
場所:銀座プロムナードギャラリー
◆第9回惑星地球フォトコンテスト表彰式
5月19日(土)11:00〜12:30
会場:北とぴあ 第2研修室会議室(東京都北区王子)
◆第35回地球科学講演会
「都市大阪を生んだ土地のなりたち―遺跡の地層から読む―」
5月13日(日)14:00〜16:00
会場:大阪市立自然史博物館 講堂
申込不要
◆第10回 身近に知る「くまもとの大地」
6月2日(土)10:00〜16:00
主催:「地質の日」くまもと実行委員会
共催:日本地質学会西日本支部ほか
会場:びぷれす広場(熊本市通町筋)
<その他>
◆地質情報普及講座「深海から生まれた城ヶ島」(地質学会後援)
主催:三浦半島活断層研究会
5月20日(日)10:00 〜15:00(小雨決行)
申込締切:5月10日(木)
◆観察会「城ヶ島の高潮・大正関東地震津波・地盤隆起」(地質学会後援)
主催:ジオ神奈川
日時:2018年5月19日(土)10:00〜15:00
申込締切:5月6日(日)
詳しくは, www.geosociety.jp/name/content0159.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】「伊豆半島」がユネスコ世界ジオパークに認定!
──────────────────────────────────
フランス・パリにて開催された第204回ユネスコ執行委員会(4/4-17)におい
て,「伊豆半島」がユネスコ世界ジオパークとして認定されました.
今回11か国13地域が新たに認定され,ユネスコ世界ジオパークは,合計38か国
140地域となりました.「伊豆半島」は国内で9番目のユネスコ世界ジオパーク
となります.詳細は日本ジオパーク委員会のウェブサイトをご覧ください.
http://jgc.geopark.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】支部情報
──────────────────────────────────
[中部支部]
■2018年支部年会(山梨大会)
6月16日(土)〜17日(日)
会場:山梨大学教育学部N号館
シンポジウム「南部フォッサマグナの過去・現在・未来」
参加申込締切:5月31日(木)
http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
[北海道支部]
■平成30年度総会・例会(個人講演会)
6月16日(土)総会:11:00〜12:00例会:13:00〜18:00(時間は予定)
場所:北海道大学理学部5号館大講堂(5-203)
講演申込:5月25日(金)締切
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■科学的特性マップに関する対話型全国説明会
主催:原子力発電環境整備機構(NUMO)/経済産業省資源エネルギー庁
5月10日(木)〜26日(土)
場所:全国6会場(大阪,茨城,島根,鳥取,兵庫,香川)
https://www.numo.or.jp/taiwa/2018/
■日本地球惑星連合2018年大会
5月20日(日)〜24日(木)
場所:幕張メッセおよび東京ベイ幕張ホール
早期参加登録締切:5月8日(火)
http://www.jpgu.org/meeting_2018/
■第210回地質汚染イブニングセミナー
5月25日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ902会議室
講師:三田村宗樹(大阪市立大学大学院理学研究科教授)
テーマ:大阪層群最下部相当の帯水層での自然水位観測とその評価
http://www.npo-geopol.or.jp
■(後)日本原子力学会 特別国際シンポジウム
「断層リスクに向き合う原子力安全のアプローチ」
5月31日(木)13:30〜18:00
場所:東京大学弥生講堂一条ホール
http://www.aesj.net/activity/conference/symp20180531
■日本古生物学会2018年年会
6月22日(金)〜24日(日)
場所:東北大学理学研究科・理学部キャンパス
http://www.palaeo-soc-japan.jp/events/
■(後)第55回アイソトープ・放射線研究発表会
7月4日(水)〜6日(金)
場所:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
参加費:(事前申込)4,000円(当日申込)5,000円,学生:0円
https://www.jrias.or.jp/isotope_conference/index.html
■(後) ?設計業務等標準積算基準書の解説?説明会(地質編)
主催:全地連・経済調査会
7月2日(月)〜8月31日(金)
場所:全国9地区(東京,高松,大阪,仙台,名古屋,札幌,広島,新潟,福岡)
受講料:6,000円
https://seminar.zai-keicho.or.jp/seminar/detail/index/148/6
★日本地質学会第125年学術大会(2018札幌大会)
9月5日(水)〜7日(金)
場所:北海道大学(札幌市)
講演申込締切:6月13日(水)
http://www.geosociety.jp/science/content0096.html
■(共)2018年度日本地球化学会第65回年会
9月11日(火)〜13日(木)
場所:琉球大学・千原キャンパス
http://www.geochem.jp/meeting/index.html
■International Conference on Geoscience for Society (GeoSoc)
2019年3月14日〜17日
場所:バングラデッシュのダッカ市
主テーマ:A. Geoscience Education, B. Geo-resources, Energy and
Mineral based Industries, C. Geosciences in Developing Activities and
Disaster Risk Reduction, D. Women in Geosciences.
締切:事前登録2018年6月,発表要旨2018年8月,発表論文提出2018年12月
https://www.data-box.jp/pdir/7085ba17d18d49959128fd842853976a
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・鹿児島市(桜島・錦江湾ジオパーク)嘱託職員募集(5/11まで延長)
・平成30年度土佐清水ジオパーク構想学術研究支援事業助成金(5/31,7/31)
・アースウォッチ 野外調査プログラム募集(7/20)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.415(臨時)締切まであと2日!札幌大会講演申込
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.415 2018/6/11┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[2018札幌大会]講演申込 締切まであと2日!
【2】[2018札幌大会]事前参加登録受付中です!
【3】[2018札幌大会]宿泊予約はお早めに
【4】[札幌大会関連情報]大会へお子様をお連れになる予定の方へ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2018札幌大会]講演申込 締切まであと2日!
──────────────────────────────────
演題登録には,『札幌大会演題登録専用のアカウント登録』が必要となりま
す.締切まで何度でも修正や要旨差替が可能ですので,あらかじめアカウント
登録をされることをお勧めします.
非会員の方も入会申込中の方も,画面入力が可能です.入会予定の方は
入会手続きと併行して講演申込の作業を進めて下さい.
********************************************************
演題登録・講演要旨受付締切:6月13日(水)18時【締切厳守】
********************************************************
詳しくは,大会HPまで
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2018札幌大会]事前参加登録受付中です!
──────────────────────────────────
会員・非会員問わずWEB申込画面から事前参加登録のお申込が可能です.巡検
のみの参加もお申込いただけます(アウトリーチ巡検も含む).なお,本大会
より巡検のみに参加する場合は,大会参加登録費は徴収しません.
******************************************************
事前参加登録締切:8月10日(金)18時(WEB)
******************************************************
申込はこちらから, http://www.geosociety.jp/science/content0103.html
◆各巡検コースのご案内はこちら
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/excursion
◆実習プログラム「無人航空機を利用した数値地表モデルの作成」参加者募集
(8/10締切)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/gyoji#uav
◆小さなEarth Scientistのつどい〜第16回小,中,高校生徒「地学研究」発表
会参加校募集(7/13締切)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/gyoji#es
このほか普及・関連行事も盛りだくさんです!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2018札幌大会]宿泊予約はお早めに!
──────────────────────────────────
札幌大会(会期 9/5-9/7.巡検 9/8-9/9)は,観光シーズンの最盛期からは若
干外れていますが,それでも初秋の北海道は観光客が多く,さらに中国など海
外からの観光客も増加していて, 宿が混みあうことが予測されます. お早めに
宿を予約されることを強くお勧めいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[札幌大会関連情報]大会へお子様をお連れになる予定の方へ
──────────────────────────────────
ご家族で学会に参加される会員で,大会期間中に保育施設のご利用を希望され
る方には,学会から保育料金の一部を補助いたします(対象:乳幼児〜小学校
就学前).会場内には保育室を設けませんので,市内の施設のご利用をお願い
いたします.大会HPで保育施設等の情報ご案内しています.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/child
これらの施設は学会が推奨または利用を約束するものではありません.いずれ
の施設も予約は先着順になります.また小学生以上のお子様の学童保育を希望
される方がおられましたら,別途学会事務局までご相談下さい.
問い合わせ先 e-mail:main[at]geosociety.jp TEL:03-5823-1150
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.416 会長就任挨拶/地質雑あり方アンケート ほか
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.416 2018/6/19┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】会長就任挨拶
【2】地質学雑誌のあり方についてのアンケート
【3】[2018札幌大会]事前参加登録受付中です!
【4】[2018札幌大会]巡検申込状況:申込はお早めに!
【5】[2018札幌大会]宿泊予約もお早めに
【6】[2018札幌大会]大会へお子様をお連れになる予定の方へ
【7】125周年記念「ジオルジュ」英語版特別号:配布協力のお願い
【8】地震火山こどもサマースクール in 伊豆大島:参加者募集
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】会長就任挨拶
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会 会長(代表理事)
松田博貴(熊本大学)
このたび2018年総会におきまして,2020年までの2年間の任期にて,一般社団法
人日本地質学会の会長(代表理事)に選任されました.与えられた任期の間,
どのように学会を運営し,そしてより魅力ある学会へと進化させていくか,会
員の皆様に所信を述べさせていただき,ご挨拶とさせていただきます.
全文はこちら、、、
http://www.geosociety.jp/outline/content0137.html
新年度執行理事紹介
http://www.geosociety.jp/outline/content0105.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】地質学雑誌のあり方についてのアンケート
──────────────────────────────────
地質学雑誌が原稿不足で毎月発行が危ぶまれる状況にあり,また同時に会員減
により学会財政が厳しい状況にあります.これらをふまえ,地質学雑誌につい
てのアンケートを行いますので,ご回答下さいますようお願いいたします.
********************************
アンケート回答期日:9月末
********************************
◆アンケート回答フォームはこちら
https://goo.gl/forms/YvIpRGp5l1fYAhUi2
◆このアンケートを行う背景について
http://www.geosociety.jp/publication/content0090.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2018札幌大会]事前参加登録受付中です!
──────────────────────────────────
会員・非会員問わずWEB申込画面から事前参加登録のお申込が可能です.巡検
のみの参加もお申込いただけます(アウトリーチ巡検も含む).なお,本大会
より巡検のみに参加する場合は,大会参加登録費は徴収しません.
******************************************************
事前参加登録締切:8月10日(金)18時(WEB)
******************************************************
申込はこちらから, http://www.geosociety.jp/science/content0103.html
◆実習プログラム「無人航空機を利用した数値地表モデルの作成」参加者募集
(8/10締切)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/gyoji#uav
◆小さなEarth Scientistのつどい〜第16回小,中,高校生徒「地学研究」
発表会参加校募集(7/13締切)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/gyoji#es
このほか普及・関連行事も盛りだくさんです!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2018札幌大会]巡検申込状況:申込はお早めに!
──────────────────────────────────
参加申込締切(8/10)まではまだ時間がありますが,まもなく定員に達する
コースがあります.巡検参加希望の方は,お早めにお申込下さい.
巡検申込状況はこちらから確認できます.
http://www.geosociety.jp/science/content0104.html
◆各巡検コースのご案内はこちら
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/excursion
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2018札幌大会]宿泊予約もお早めに!
──────────────────────────────────
札幌大会(会期 9/5-9/7.巡検 9/8-9/9)は,観光シーズンの最盛期からは若
干外れていますが,それでも初秋の北海道は観光客が多く,さらに中国など海
外からの観光客も増加していて, 宿が混みあうことが予測されます. お早めに
宿を予約されることを強くお勧めいたします.
大会サイトにも宿泊予約,航空券セットプランのご案内をリンクしています.
ご参考にして下さい
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/hotel
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[2018札幌大会]大会へお子様をお連れになる予定の方へ
──────────────────────────────────
ご家族で学会に参加される会員で,大会期間中に保育施設のご利用を希望され
る方には,学会から保育料金の一部を補助いたします(対象:乳幼児〜小学校
就学前).会場内には保育室を設けませんので,市内の施設のご利用をお願い
いたします.大会HPで保育施設等の情報ご案内しています.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/child
これらの施設は学会が推奨または利用を約束するものではありません.いずれ
の施設も予約は先着順になります.また小学生以上のお子様の学童保育を希望
される方がおられましたら,別途学会事務局までご相談下さい.
問い合わせ先 e-mail:main[at]geosociety.jp TEL:03-5823-1150
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】125周年記念「ジオルジュ」英語版特別号:配布協力のお願い
──────────────────────────────────
125周年を記念して,海外の方々に読んでいただくために,これまでのジオルジュ
の掲載記事の中から,いくつか記事をピックアップ・翻訳し,英語版特別号を
作成しました.
【Contents】
・The Mt. Fuji, Solitary Mountain
・Was the extinct Desmostylus a good swimmer?
・A message to You, Hundreds of Years in the Future
・Art Created by Nature : The World of Fault Rocks
・The "Tagoto Moon"
学術交流協定を締結している学会や,図書交換先など,海外の関連諸団体に
は寄贈予定ですが,個々の研究者の方々にもできるだけ広くお読み頂きたいと
思います.そこで,これから海外の学会,国際会議等に参加される会員の方は,
ぜひこの英文特別号をお持ち頂き,海外の方々への配布にご協力下さい.
必要部数をお知らせ頂ければ,冊子をお送りいたします.ぜひご協力下さい.
お申込は学会事務局まで(電話:03-5823-1150/main[at]geosociety.jp)
http://www.geosociety.jp/125th/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】地震火山こどもサマースクール in 伊豆大島:参加者募集
──────────────────────────────────
第19回 地震火山こどもサマースクールin 伊豆大島ジオパーク
「火山島 伊豆大島のヒミツ」
日程:2018年8月7日(火)〜8日(水)
※宿泊無しの日帰り2 日間.2日間ともご参加ください.
募集対象・人員:小学校5年生から高校3年生まで40名程度
参加費:2,000円
申込締切:7月2日(月)
詳しくは, http://www.kodomoss.jp/ss/izuoshima/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■地学教育・アウトリーチ巡検「箱根〜北伊豆地域の自然災害の跡を巡る」
2018年8月7日(火)〜8日(水)1泊2日
対象:教育関係者および地学に興味のある一般の方(会員でなくても可)
参加申込締切:7月6日(金)先着順:定員20名
http://kanto.geosociety.jp
■清澄フィールドキャンプ:参加者募集
8月20日(月)〜8月25日(日)5泊6日
場所:東京大学千葉演習林(千葉県鴨川市清澄)
参加申込締切:7月6日(金)
http://kanto.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■科学的特性マップに関する対話型全国説明会
主催:原子力発電環境整備機構(NUMO)/経済産業省資源エネルギー庁
6月30日(土)〜8月1日(水
場所:全国15会場(高知,千葉,岐阜,名古屋,札幌,青森,秋田,広島,
松山,金沢,前橋,新潟,京都,福井,大津)
開催案内: https://www.numo.or.jp/taiwa/2018/
■(後)第55回アイソトープ・放射線研究発表会
7月4日(水)〜6日(金)
場所:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
参加費:(事前申込)4,000円(当日申込)5,000円,学生:0円
https://www.jrias.or.jp/isotope_conference/index.html
■(後) ?設計業務等標準積算基準書の解説?説明会(地質編)
主催:全地連・経済調査会
7月2日(月)〜8月31日(金)
場所:全国9地区(東京,高松,大阪,仙台,名古屋,札幌,広島,新潟,福岡)
受講料:6,000円
https://seminar.zai-keicho.or.jp/seminar/detail/index/148/6
■第212回地質汚染イブニングセミナー
7月27日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:山本義久(水循環基本法フォローアップ委員会幹事長
テーマ:水循環基本法の誕生からフォロ−アップ委員会活動の現状
http://www.npo-geopol.or.jp
★日本地質学会第125年学術大会(2018札幌大会)
9月5日(水)〜7日(金)
場所:北海道大学(札幌市)
事前参加申込締切:8月10日(金)
http://www.geosociety.jp/science/content0096.html
■(共)2018年度日本地球化学会第65回年会
9月11日(火)〜13日(木)
場所:琉球大学・千原キャンパス
http://www.geochem.jp/meeting/index.html
■第8回学生のヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集
2019年3月4日〜18日(仮日程)
暫定参加費:20万円(学生・院生),25万円(一般),30万円(公費派遣者)
参加申込締切:12月31日
*「ヒマラヤ造山帯大横断2018」今年3月に実施された第7回学生のヒマラヤ野
外実習ツアーの報告書(E-book:189頁)を発行しました.
http//www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studentfieldex_index.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・2018年度 「第39回猿橋賞」受賞候補者の推薦(11/30)
・平成31年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞および若手科学者賞
受賞候補者の推薦(学会締切7/13)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.417 「チバニアン」に関する声明
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.417 2018/7/3┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】「チバニアン」に関する声明
【2】地質学雑誌のあり方についてのアンケート
【3】[2018札幌大会]事前参加登録受付中です!
【4】[2018札幌大会]巡検申込状況:申込はお早めに!
【5】[2018札幌大会]若手会員のための地質関連企業研究サポート
【6】[2018札幌大会]宿泊予約もお早めに
【7】[2018札幌大会]会場での受付には「会員カード」を忘れずに!
【8】本の紹介:素敵な石ころの見つけ方
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「チバニアン」に関する声明
──────────────────────────────────
2018年7月1日
一般社団法人日本地質学会
会長 松田 博貴
昨年6月,日本の22機関32名からなる研究グループが,「千葉セクション」
(千葉県市原市田淵の地層露出断面)を『国際標準模式層断面及びポイント』
(Global Stratotype Section and Point; GSSPと略記)の「下部−中部更新統
境界GSSP」に認定されるよう,GSSPの決定機関である国際地質科学連合
(IUGS)に提案しました.これを受けて,IUGSのもとにある,国際層序委員会
(ICS)の第四紀層序小委員会(SQS)下部−中部更新統境界作業部会で,提出
された申請書が審査されました.そして2017年11月,作業部会における投票の
結果,「千葉セクション」がIUGS内の上部の委員会に答申されることになりま
した.その後,日本の別の団体から申請書の科学的データへの異議がIUGSに出
され,IUGSでの認定審査プロセスが本年4月から中断していることが報道されて
います.
地球科学分野における我が国最大の学会と言える日本地質学会として,今回,
研究グループの提案内容を本学会の学術研究部会を中心に検討しました.この
声明は,その結果を踏まえ,提案内容の学術的意味の説明と本学会の見解を,
ホームページに掲載し表明するものです.
全文はこちら、、、
http://www.geosociety.jp/engineer/content0051.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】地質学雑誌のあり方についてのアンケート
──────────────────────────────────
地質学雑誌が原稿不足で毎月発行が危ぶまれる状況にあり,また同時に会員減
により学会財政が厳しい状況にあります.これらをふまえ,地質学雑誌につい
てのアンケートを行いますので,ご回答下さいますようお願いいたします.
********************************
アンケート回答期日:9月末
********************************
◆アンケート回答フォームはこちら
https://goo.gl/forms/YvIpRGp5l1fYAhUi2
◆このアンケートを行う背景について
http://www.geosociety.jp/publication/content0090.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2018札幌大会]事前参加登録受付中です!
──────────────────────────────────
会員・非会員問わずWEB申込画面から事前参加登録のお申込が可能です.巡検
のみの参加もお申込いただけます(アウトリーチ巡検も含む).なお,本大会
より巡検のみに参加する場合は,大会参加登録費は徴収しません.
******************************************************
事前参加登録締切:8月10日(金)18時(WEB)
******************************************************
事前参加登録はこちらから,
http://www.geosociety.jp/science/content0103.html
◆実習プログラム「無人航空機を利用した数値地表モデルの作成」参加者募集
(8/10締切)[申込状況]申込件数:11名(7/2現在)お早めに!
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/gyoji#uav
◆小さなEarth Scientistのつどい〜第16回小,中,高校生徒「地学研究」発表
会 参加校募集(7/13締切)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/gyoji#es
このほか普及・関連行事も盛りだくさんです!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2018札幌大会]巡検申込状況:申込はお早めに!
──────────────────────────────────
巡検申込状況はこちらから確認できます.
http://www.geosociety.jp/science/content0104.html
◆各巡検コースのご案内はこちら
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/excursion
参加申込締切(8/10)まではまだ時間がありますが,すでに定員に達した
コース(受付終了)もあります.参加希望の方は,お早めにお申込下さい.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2018札幌大会]若手会員のための地質関連企業研究サポート
──────────────────────────────────
今年も,実際に企業で活躍されている地質技術者と語り合い,大学で学んだ地
質学が企業でどのように生かされているのか,学生・大学院生および教員の方
々が,企業の生の声を聴くことができるような場を提供したいと考えています.
◆企業の皆様へ◆出展募集中です.出展申込書は下記大会HPよりDLして頂け
ます(申込締切:8/1)
◆学生・大学教員の皆様へ◆地質系企業の様子が直接わかる貴重な機会です.
是非ご参加下さい(参加無料・事前申込不要).また大会HPにPDF版ポスターを
掲載していますので,掲示や配布にご協力をお願いいたします.
日程:2018年9月6日(木)14:00〜17:00(*時間は若干変更になる場合あり)
場所:北海道大学(札幌市・高等教育推進機構棟)
内容:
・会場内の参加者休憩室等における参加各社作成PR用スライド上映.
・参加各社の個別説明会
詳しくは.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/gyoji#comp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[2018札幌大会]宿泊予約もお早めに!
──────────────────────────────────
札幌大会(会期 9/5-9/7.巡検 9/8-9/9)は,観光シーズンの最盛期からは若
干外れていますが,それでも初秋の北海道は観光客が多く,さらに中国など海
外からの観光客も増加していて, 宿が混みあうことが予測されます. お早めに
宿を予約されることを強くお勧めいたします.
大会サイトにも宿泊予約,航空券セットプランのご案内をリンクしています.
ご参考にして下さい
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/hotel
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】[2018札幌大会]会場での受付には「会員カード」を忘れずに!
──────────────────────────────────
*********************************************************************
大会会場での受付は「会員カード」で簡単に手続きできます.
*********************************************************************
「会員カード」を忘れずに持参して下さい.
お忘れになった場合は,大会会期前にお送りする確認書(ハガキ)等でも受付
できますが,時間がかかる場合があります.ご了承下さい.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】本の紹介:素敵な石ころの見つけ方
──────────────────────────────────
「素敵な石ころの見つけ方」渡辺一夫著
中公新書ラクレ626。193p.
2018年6月10日発行。900円+税。
ISBN978-4-12-150629-9.
本書は「石ころ探し人」を自称する著者が、
日本や世界の各地を回り、石ころを採集する
楽しみ、その中で出会った美しい風景や面白
い人たち、そして石ころの地質学的な背景な
どについて語った本である。カバーの略歴に
よると、著者は1941年東京生まれ、青山学
院大学卒業、出版社勤務の後、1979年から
フリーランスの編集・ライターをしていたが、残念ながら今年逝去されたとの
ことである。この著者には「川原の石ころ図鑑」(2002)、「海辺の石ころ
図鑑」(2005)(ポプラ社)、「集めて調べる川原の石ころ」(2010)、
「採集して観察する海岸の石ころ」(2011)、「石ころ採集ウォーキングガ
イド」(2012)、「日本の石ころ標本箱」(2013)、「地球の石ころ標本箱」
(2016)(誠文堂新光社)など多数の著書があり、本書はこれらの綜合・要約
版と言える。本書の巻頭には47個の石ころのカラー写真があり、ちょっとした
図鑑になっている。しかし著者は、「この本は岩石図鑑などのように、学術的
な内容を重視してはいません。岩石としての石の知識以上に、その周辺の自然
や人と触れ合う「石ころ探し」の楽しみに重きを置き、そのノウハウを詰め込
んでいます」と述べていて(p. 10)、あくまでも趣味の本であることを強調し
ている。
趣味で石を集める人は昔からいて、日本では特に1960年代に水石趣味が流行し
た。全国樹石会編(1966)「日本の石」(東西2篇、樹石社)を見ると、全国各
地に名石の産地と「愛石会、玩石会、撫石会、探石会」等があって、趣のある
色、艶、模様、形の石を水盤や台座に載せ、盆栽のように居室の一隅に置いて
楽しみ、品評会に出して趣味を競ったらしく、関連書籍の宣伝文句には、「水
石趣味の歴史始まって500年」、「禅と水石、「わび」と「さび」の考察」、「
河原から拾ってきた石も、一読すれば名石となる」などとある。別所文吉(19
63-64)は「石によせて」(地学研究, 14, 159-167; 15, 133-141, 159-167)
で当時の水石趣味を批判し、「石を自分で探すこと―使役の禁、石を傷つけぬ
こと―加工の禁、石を売買せぬこと―商品化の禁」を提案し、名石は「遠山型」
(遠くの山を盤上に写したような形)と言われるが、「遠山型という名は自然
を写し、自然のおもかげをそのまま縮小しているような感がある。しかし名石
は自然の単なる写生縮小という客観的なものであってはならない。名石は大自
然の一隅、又はある面、又はその一尖端を叙して、大自然の地上地下全体に通
ずるものでなければならない。天地の包容のうちにある石であるべきはずだ」
と述べている。
本書の石は遠山型ではなく円い石ころばかりであるが、著者は別所の「三つの
禁」を完全に遵守していて、哲学的な記述はないものの、大自然と人間世界全
体に通ずる志向をもった著者の心が、個々の円い石に凝縮されているように思
う。しかも最新の地質学的知識をしっかり踏まえていて、日本地質学会の「県
の石」を本文やコラムで取り上げ、ウェブで公開されている産総研地質調査総
合センターのシームレス地質図や地質図幅の利用方法も詳しく紹介し、地質学
雑誌の昨年の論文まで利用している。また、逆から見ると、本書は、地質学界
の最近の普及活動が学界外の地学趣味の人にどのように受け取られ、どのよう
に利用され、どのような効果をもたらしているかを示す好例である。
本書の章立ては、はじめに 魅惑の石ころの世界へようこそ、第1章 石ころ
にはどんな種類があるのか、第2章 石ころ探しの舞台、川原と海岸、第3章
旅に出たならこの石ころを探せ(国内編)、第4章 同(海外編)、第5章
石ころともっと仲良くなる、おわりに、となっている。本書で「旅」として記
述されているのは、北から北海道十勝川(黒曜石)、幌満川(かんらん岩)、
青森県七里長浜(錦石)、尻屋崎(石英閃緑岩)、岩手県鵜住居(うのすまい)
川(餅鉄)、栃木県・群馬県渡良瀬川(桜石)、神奈川県城ヶ島・剣崎(クッ
キー礫岩)、静岡県三保半島(蛇紋岩)、新潟県糸魚川市(きつね石)、富山
県片貝川(眼球片麻岩)、高知県足摺岬(ラパキビ花崗岩)、高知県仁淀川(
虎石)、愛媛県関川(ざくろ石角閃石片岩、エクロジャイト)、大分県佐賀関
半島(結晶片岩)、大野川(溶結凝灰岩)であり、国外はスペイン北の道(シ
ルト岩)、ポルトガル・ナザレ海岸(石英)、フランス・ガルドン川(花崗岩)、
米国コロラド州(花崗岩)、ニュージーランド南島(片麻岩)である。
「きつね石」(p. 123〜127)は本書で初めて知ったが、これは糸魚川付近の海
岸に落ちている、ひすいと間違いやすいきれいな石のことで、だまされるので
こう呼ぶそうである。本書ではロディン岩としているが、マグネサイト岩(
listvenite)も含まれるかもしれない。
石には白・黒の他に緑や茶色、銀色があるとのことだが(p. 5)、白鉄鉱等の
鉱石は別として、普通の石で銀色のものを私はまだ見たことがない。本書の巻
頭図版にも、赤や黄色はあるが銀色はなく、銀色に近い石を強いて挙げれば石
墨片岩だろうか。藍閃石や藍晶石を含む青い石、紫水晶や斧石を含む紫色の石
もあるが、本書では取り上げていない。
城ヶ島の初声層が300-400年前というp. 115の記述は300-400万年前の誤りであ
る。
三保の蛇紋岩の話(p. 116-122)では、これらの蛇紋岩礫は安倍川河口から流
れてきたとしている。しかし、2003年に火山学会Q&Aの#3741に、「『富士海岸
の海岸侵食対策』という題で卒論を書いている学生だが、静岡県富士市の海岸
には海岸侵食対策として三重県鳥羽市菅島産のかんらん岩が養浜材料として海
に投入されており、それがどの辺までどのくらいの量、流されているかを調べ
ている。しかし、かんらん岩を見分けるのに苦労しているので、そのコツを教
えてほしい」という趣旨の質問があり、これに対して私は「斜長石や気泡を含
まない、比重が大きい、磁石が吸いつく」など、いくつかの鑑定基準を教えた
ことがある(金沢大学の石渡ホームページ「かんらん岩(蛇紋岩)を見分ける
方法」)。実際、安倍川の河床礫が1996年と97年の2回三保海岸に投入され、そ
の中の長径128mm以上の蛇紋岩礫が毎月12〜280mの速度で北東へ移動したことが
報告されている(佐藤武(1998)地質学会105年松本大会演旨, p. 90)。つま
り、三保海岸の大きな蛇紋岩礫は、波浪によって自然に安倍川河口から運ばれ
たのではなく、養浜のために人工的に搬入されたものらしい。三保海岸と最も
礫種構成が類似する周辺の河川は安倍川であり(柴正博(2005)静岡の自然を
たずねて新訂版, p. 108-109)、富士海岸と違い異地性の礫が混入したわけで
はないが、河川や海岸の礫の調査では人工改変に注意が必要である。
なお、本書p. 59に「自然の力で真円の石ころはできるのか。これは大いなる謎
です」とあるが、真円(球)に近い石ころは、礬土(ばんど)頁岩(けつがん)の
タマネギ状風化(金沢大学の石渡ページ「ずっしり重い白玉石」)やノジュー
ル(結核)の剥脱などによって形成されることがある。
本書の末尾には参考文献が紹介されていて、千葉とき子・斎藤靖二(1996)
「かわらの小石の図鑑」(東海大出版会)、豊(ぶんの)遙(みち)秋(あき)・青
木正博(1996)「検索入門 鉱物・岩石」(保育社)、ヤーハム(2012)「自
然景観の謎」(ガイアブックス)、小泉武栄(2013)「観光地の自然学 ジオ
パークで学ぶ」(古今書院)といった普及書の後に、皆川鉄雄・佐野栄(2017)
の「関川の岩石鉱物」という地質学雑誌の巡検案内書(123巻7号)を挙げ、「
カラー写真を用いてこれほど詳細に関川流域の地質や岩石・鉱物について解説
したものはほかに見たことがありません」と絶賛し、だれでもウェブで入手可
能と紹介している(印刷版は白黒写真のみ)。本書p.137-141では、「宝石のよ
うな輝きをもつざくろ石の結晶を散りばめた石ころをいともたやすく手に入れ
られる場所は、私が知っている限り、関川しかない」と述べている。
以上のように、本書は石ころ集めの趣味の本ではあるが、そこから地質学へ
の渡し舟の役目を十分に果たすことができる内容を持っている。川の中州での
採集は危険であるとか、外国では海岸にも私有地があるとか、野外でのノウハ
ウも満載である。地質の専門家が書いた普及書と違い、「あっちの川原でも、
そっちの川原でも石ころを探してみたい、という欲張り心で目がくらむ」(p.
64)という強い内面的な動機と、石ころを探して地球全体を歩いた豊富な実体
験に裏打ちされた個性的なコメントが随所に輝いており、本書のご一読をお勧
めする。しかし、本書が著者の遺作となってしまったことが悔やまれる。
(石渡 明:正会員)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■地学教育・アウトリーチ巡検「箱根〜北伊豆地域の自然災害の跡を巡る」
2018年8月7日(火)〜8日(水)1泊2日
対象:教育関係者および地学に興味のある一般の方(会員でなくても可)
参加申込締切:7月6日(金)先着順:定員20名
http://kanto.geosociety.jp
■清澄フィールドキャンプ:参加者募集
8月20日(月)〜8月25日(日)5泊6日
場所:東京大学千葉演習林(千葉県鴨川市清澄)
参加申込締切:7月6日(金)
http://kanto.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■(後)第55回アイソトープ・放射線研究発表会
7月4日(水)〜6日(金)
場所:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
参加費:(事前申込)4,000円(当日申込)5,000円,学生:0円
https://www.jrias.or.jp/isotope_conference/index.html
■(後) 「設計業務等標準積算基準書の解説」説明会(地質編)
主催:全地連・経済調査会
7月2日(月)〜8月31日(金)
場所:全国9地区(東京,高松,大阪,仙台,名古屋,札幌,広島,新潟,福岡)
受講料:6,000円
https://seminar.zai-keicho.or.jp/seminar/detail/index/148/6
★日本地質学会第125年学術大会(2018札幌大会)
9月5日(水)〜7日(金)
場所:北海道大学(札幌市)
事前参加申込締切:8月10日(金)
http://www.geosociety.jp/science/content0096.html
■(共)2018年度日本地球化学会第65回年会
9月11日(火)〜13日(木)
場所:琉球大学・千原キャンパス
http://www.geochem.jp/meeting/index.html
■第35回歴史地震研究会(大分大会)
9月22日(土)〜25日(火)
場所:ホルトホール大分(大分市金池南一丁目5番1号)
プログラムが公開されました.
http://www.histeq.jp/menu7.html
■地質学史懇話会
12月23日(日)13:30〜17:00
会場:北とぴあ 806号室(JR京浜東北線王子駅下車3分)
演者:長田敏明氏ほか
問い合わせ:矢島道子
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・国立科学博物館地学研究部研究主幹(古生物学)公募(8/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
第9回_佳作1-2
第9回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:星空に吠える
写真:堀内 勇(和歌山県)
撮影場所:秋田県男鹿市船川港本山門前垂水(潮瀬崎)
【撮影者より】
秋田県沿岸部に広がる「男鹿半島・大潟ジオパーク」は、「半島と干拓が育む人と大地の物語」をメインテーマとして、恐竜時代から現在までの大地の歴史や人の暮らしを連続して見ることができるジオパークとして評価されています。 応募写真は、ジオパークを代表する一つとして知られる「男鹿半島のゴジラ岩」です。潮瀬崎と呼ばれる岩礁地帯にあり、まるで海に向かって吠えているかのような勇姿で、圧倒的な存在感がありました。
目次へ戻る
佳作:恐竜
写真:島村直幸(福岡県)
撮影場所:山口県 山陽小野田市本山岬公園
【撮影者より】
「くぐり岩」と呼ばれる奇岩を、海岸の苔むした岩の向こうに見てみると、岩がまるで草を食べている恐竜のように見えました。
目次へ戻る
第9回_佳作5-6
第9回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:断崖の記憶から来た人
写真:曳地正刀(福島県)
撮影場所:福島県 いわき市
【撮影者より】
いわき市の、かつての炭鉱の町を散策していたら見つけた断層です。ミルフィールのような地層に惚れ込みました。
目次へ戻る
佳作:富士山型泥火山
写真:木田敦男(福島県)
撮影場所:秋田県 八幡平後生掛自然研究路
【撮影者より】
この場所は初めて訪れました。温泉とともにあちこちから湯煙が登り、また小さいながら泥が吹き上がる様はミニチュア火山でした。写真のはすごくきれいな富士山みたいな形でした。
目次へ戻る
第9回_佳作7-8
第9回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:蛇石の流れ
写真:古屋 治(長野県)
撮影場所:長野県 上伊那郡辰野町横川・横川峡
【撮影者より】
「蛇石」は国指定の天然記念物。横川峡の清流には、粘板岩に貫入してできた岩脈が川底に長細く露出している。石英脈の入った岩脈が蛇腹のように見えるため、「蛇石(じゃいし)」と呼ばれている。秋の午後3時頃、西日が白いシマ模様を浮かぶ上がらせた。 地元の横川地区には、母子2匹の蛇が自分の身を犠牲にして集落を鉄砲水から救ったという民話が残されている。
目次へ戻る
佳作:幽岩
写真:三橋俊之(神奈川県)
撮影場所:神奈川県 荒崎海岸
【撮影者より】
通常時は岩が現れているが、大潮、満潮の時にはこのような光景が見られる。 数千万年かけ自然が創造した美しい風景。
目次へ戻る
第9回_佳作9-10
第9回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:大地の迷路
写真:黒田朋花(岐阜県)
撮影場所:カナダ アルバータ州 ホースシュー渓谷
【撮影者より】
「まるで、大地の迷路みたい…。」この景色を見た瞬間に思いました。ここは、カナダ・アルバータ州バッドランドに広がるホースシュー渓谷。氷河が長い歳月をかけて大地を削り、迷路のような地形を作りました。見渡す限りの赤褐色の大地では作物が育たないため、「Bad lands(悪い土地)」という名前が付いたそうです。もしもこの渓谷の中に降りたら、迷子になってしまいそうなほど、広大で複雑な地形が広がっていました。
目次へ戻る
佳作:美しい宮崎の自然美
写真:野村奈保美(福岡県)
撮影場所:宮崎市青島
【撮影者より】
宮崎県の青島神社。神社に向かう道沿いに広がる水成岩 鬼の洗濯岩と呼ばれ、観光スポットにもなっています。 柔らかい曲線の岩がとても美しく、自然の壮大さを感じます。
目次へ戻る
第9回_佳作11-12
第9回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:貌(かお)
写真:若山拓也(岩手県)
撮影場所:岩手県 釜石市水海(みずうみ)近くの海岸
【撮影者より】
チャート/泥岩 互層でしょうか、きれいな縞模様になった地層が波に洗われている一帯があります。人里離れた場所で、付近は7年前の津波でなぎ倒された木々が当時のままになっていますが、海岸の岩は割れたりすることなくそれまでと同じようにそこにあります。その場所で幾度もの大津波を経験しているだろうことを想像しました。
目次へ戻る
佳作:リアス海岸の恵み
写真:久保田 修(兵庫県)
撮影場所:兵庫県 香美町鎧(よろい)漁港の東側
【撮影者より】
板状の節理が日光に光っていました。この港はリアス海岸の恵みによっておだやかな初冬の景色になっています。
目次へ戻る
【geo-Flash】No.418(臨時)台風第7号及び前線等に伴う大雨に関して
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.418 2018/7/11┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[会員各位]台風第7号及び前線等に伴う大雨に関して
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[会員各位]台風第7号及び前線等に伴う大雨に関して
──────────────────────────────────
台風第7号及び前線等に伴う大雨による大規模な災害が発生し,13府県にわたり
甚大な被害をもたらしました.被害に遭われた方々へお見舞いを申し上げます
とともに,亡くなられた方々への哀悼の意を表します.
***********************
安否確認のお願い
***********************
大変な状況とは存じますが,落ち着かれましたら安否確認にご協力をお願い申
し上げます.
ご連絡は地質学会事務局 main@geosociety.jp までお願いいたします.とくに
罹災会員については,ご自身だけでなく,周囲の会員の方の安否についてもご
存知の範囲内で以下の連絡先にご連絡いただければ幸いです.
学会事務局
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル6F
電話:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156
e-mail: main@geosociety.jp
***********************
緊急調査のお願い
***********************
地質災害の原因究明は将来の減災につながる重要な活動です.既に現地調査を
開始もしくは検討している会員の皆様もおられると思います.調査にかかる会
員の皆様の安全,そして調査の情報共有のためにも,緊急調査を計画されてお
られる方は地質学会事務局にご連絡をお願いいたします.被災地では救命およ
び行方不明者の捜索活動が行われておりますので,被災地への配慮を引き続き
お願いいたします.
地質災害緊急調査について
http://www.geosociety.jp/hazard/content0024.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.419 札幌大会プログラムを公開しました
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.419 2018/7/17┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[2018札幌大会]全体日程表・講演プログラムを公開しました
【2】[2018札幌大会]緊急展示のお申込について
【3】[2018札幌大会]事前参加登録受付中です!
【4】[2018札幌大会]巡検申込状況:申込はお早めに!
【5】[2018札幌大会]若手会員のための地質関連企業研究サポート
【6】[2018札幌大会]宿泊予約もお早めに
【7】[2018札幌大会]会場での受付には「会員カード」を忘れずに!
【8】地質学雑誌のあり方についてのアンケート
【9】大学院生の研究・生活実態に関するアンケート調査ご協力のお願い
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2018札幌大会]全体日程表・講演プログラムを公開しました
──────────────────────────────────
札幌大会の全体日程表・講演プログラム(7/17現在)を公開しました。
なお,一部情報は修正・変更される場合があります。
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/program
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2018札幌大会]緊急展示のお申込について
──────────────────────────────────
今大会でも災害調査報告や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コー
ナー」(ポスタ―展示)を設けます.ご希望の方は,行事委員会までお申込下
さい.
申込締切:2018年8月20日(月)
詳しくは,
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/emergency
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2018札幌大会]事前参加登録受付中です!
──────────────────────────────────
会員・非会員問わずWEB申込画面から事前参加登録のお申込が可能です.巡検
のみの参加もお申込いただけます(アウトリーチ巡検も含む).なお,本大会
より巡検のみに参加する場合は,大会参加登録費は徴収しません.
******************************************************
事前参加登録締切:8月10日(金)18時(WEB)
******************************************************
事前参加登録はこちらから
http://www.geosociety.jp/science/content0103.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2018札幌大会]巡検申込状況:申込はお早めに!
──────────────────────────────────
巡検申込状況はこちらから確認できます.
http://www.geosociety.jp/science/content0104.html
◆各巡検コースのご案内はこちら
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/excursion
参加申込締切(8/10)まではまだ時間がありますが,すでに定員に達した
コース(受付終了)もあります.参加希望の方は,お早めにお申込下さい.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2018札幌大会]若手会員のための地質関連企業研究サポート
──────────────────────────────────
今年も,実際に企業で活躍されている地質技術者と語り合い,大学で学んだ地
質学が企業でどのように生かされているのか,学生・大学院生および教員の方
々が,企業の生の声を聴くことができるような場を提供したいと考えています.
◆企業の皆様へ◆
出展募集中です.出展申込書は大会HPよりDLして頂けます(申込締切:8/1)
◆学生・大学教員の皆様へ◆
地質系企業の様子が直接わかる貴重な機会です.是非ご参加下さい(参加無料・
事前申込不要).また大会HPにPDF版ポスターを掲載していますので,掲示や配
布にご協力をお願いいたします.
日程:2018年9月6日(木)14:00〜17:00(*時間は若干変更になる場合あり)
場所:北海道大学(札幌キャンパス 高等教育推進機構棟)
内容:
・会場内の参加者休憩室等における参加各社作成PR用スライド上映.
・参加各社の個別説明会
詳しくは,
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/gyoji#comp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[2018札幌大会]宿泊予約もお早めに!
──────────────────────────────────
札幌大会(会期 9/5-9/7.巡検 9/8-9/9)は,観光シーズンの最盛期からは若
干外れていますが,それでも初秋の北海道は観光客が多く,さらに中国など海
外からの観光客も増加していて, 宿が混みあうことが予測されます. お早めに
宿を予約されることを強くお勧めいたします.
大会サイトにも宿泊予約,航空券セットプランのご案内をリンクしています.
ご参考にして下さい
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/hotel
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】[2018札幌大会]会場での受付には「会員カード」を忘れずに!
──────────────────────────────────
***********************************************
大会会場での受付は「会員カード」で簡単に手続きできます.
***********************************************
「会員カード」を忘れずに持参して下さい.
お忘れになった場合は,大会会期前にお送りする確認書(ハガキ)等でも受付
できますが,時間がかかる場合があります.ご了承下さい.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】地質学雑誌のあり方についてのアンケート
──────────────────────────────────
地質学雑誌が原稿不足で毎月発行が危ぶまれる状況にあり,また同時に会員減
により学会財政が厳しい状況にあります.これらをふまえ,地質学雑誌につい
てのアンケートを行いますので,ご回答下さいますようお願いいたします.
********************************
アンケート回答期日:9月末
********************************
◆アンケート回答フォームはこちら
https://goo.gl/forms/YvIpRGp5l1fYAhUi2
◆このアンケートを行う背景について
http://www.geosociety.jp/publication/content0090.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】大学院生の研究・生活実態に関するアンケート調査ご協力のお願い
──────────────────────────────────
全国大学院生協議会(全院協)より,大学院生へ向けた大学院生の研究・生活
実態に関するアンケート調査の協力依頼がありましたので,お知らせします。
http://zeninkyo.blog.shinobi.jp/
【アンケート回答フォームURL】 https://goo.gl/R4fUHk
【回答期限】2018年9月30日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■海洋政策研究所第154回海洋フォーラム
「日本で初めての国立自然史博物館を沖縄に!」
7月23日(月)13:00〜17:40(受付開始12:30)
会場:笹川平和財団ビル11階国際会議場(港区虎ノ門1-15-16)
*要事前申込
https://www.spf.org/opri-j/
■学術会議公開シンポジウム「東日本大震災後の10年を見据えて」
7月29日(日)13:30〜16:45
会場:東北大学川内南キャンパス文科系総合講義棟2階
参加費無料
参加申込フォーム
http://www.bureau.tohoku.ac.jp/kenkyo/gakujyutsukaigi/form1.html
詳しくは, http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/264-s-0729.pdf
■企画展「世界の水晶展2〜石川町立歴史民俗資料館所蔵コレクション〜」
8月7日(火)〜11月4日(日)
場所:石川町立歴史民俗資料館
http://www.town.ishikawa.fukushima.jp/info/005916.html
■(後)「設計業務等標準積算基準書の解説」説明会(地質編)
主催:全地連・経済調査会
7月2日(月)〜8月31日(金)
場所:全国9地区(東京,高松,大阪,仙台,名古屋,札幌,広島,新潟,福岡)
受講料:6,000円
https://seminar.zai-keicho.or.jp/seminar/detail/index/148/6
■第213回地質汚染イブニングセミナー
8月31日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ802会議室
講師:佐々木裕子(国立環境研究所 客員研究員)
テーマ:土壌汚染対策法の改正−調査・分析法の動向と課題−
http://www.npo-geopol.or.jp
★日本地質学会第125年学術大会(2018札幌大会)
9月5日(水)〜7日(金)
場所:北海道大学(札幌市)
事前参加申込締切:8月10日(金)
http://www.geosociety.jp/science/content0096.html
■(共)2018年度日本地球化学会第65回年会
9月11日(火)〜13日(木)
場所:琉球大学・千原キャンパス
http://www.geochem.jp/meeting/index.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
(公募)
・東京大学地震研究所 物質科学系研究部門助教公募(10/1)
・神奈川県立生命の星・地球博物館地質(火山・火山灰)学芸員募集(8/14)
・平成30年度千葉県立博物館等職員採用選考(7/26)
・九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部門
---固体地球惑星科学講座教授公募(9/28)
---流体圏・宇宙圏科学講座准教授公募(9/10)
(各賞助成)
・2018年度「朝日賞」候補者推薦(学会締切8/6)
・第40回(平成30年)沖縄研究奨励賞推薦応募(学会締切9/10)
・室戸ユネスコ世界ジオパーク学術研究助成事業募集(8/15)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.420 災害に関連した会費の特別措置
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.420 2018/8/7┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
【2】国際年代層序表(日本語版)の更新
--------------------------------------------
[2018札幌大会・関連情報]
【3】事前参加登録 まもなく締切です!
【4】懇親会にも是非ご参加下さい
【5】緊急展示のお申込について
【6】全体日程表の訂正(懇親会の時間)
【7】夜間小集会「地質学の大型研究」の案内
【8】会場での受付には「会員カード」を忘れずに!
--------------------------------------------
【9】地震火山子どもサマースクールの2019年度開催地決定
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
──────────────────────────────────
本年7月に発生した台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害で被害を受け
られた皆様に,心よりお見舞い申し上げます.
日本地質学会では,災害救助法適用地域で被災された会員の方々のご窮状を
ふまえ,申請により会費を免除いたします.「日本地質学会に届出の住居また
は勤務地が災害救助法適用地域に該当する会員のうち,希望する方」は2018年
度もしくは2019年度会費を免除いたします.
適用を希望される会員は,1. 会員氏名,2. 被災地,3. 被災状況(簡潔に)を
添えて学会事務局にお申し出下さい(郵送,FAX,e-mail、電話のいずれでも可).
****************************************
申請締切:2018年10月31日(水)
****************************************
※通常の会費払い込みについては,下記をご参照ください.
「2018年会費払い込みについて」
http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
【災害に関連した学術大会参加費の特別措置】
申請により大会参加登録費を免除いたします.該当される方は,必ず事前参加
申込手続き前に学会事務局に申請して下さい(1.会員氏名,2.被災地,3.被災
状況(簡潔に)を添えて学会事務局まで).
(注1)免除の対象は大会参加登録費に限ります.巡検,懇親会等その他の費用
は対象となりません.
(注2)事前参加申込の場合に対してのみ適用しますので,当日会場での申請は
受付ることができません.
一般社団法人 日本地質学会
〒101-0032東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル
Tel.03-5823-1150,Fax.03-5823-1150 e-mail main[at]geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】国際年代層序表(日本語版)の更新
──────────────────────────────────
2018年7月13日,国際地質科学連合(IUGS)の国際層序委員会(ICS)が,
国際年代層序表の最新版(v 2018/07)を公開しました.
http://www.geosociety.jp/name/content0062.html
最新版では第四紀の「完新世」Holoceneが後期,中期,前期に細分化され,そ
れぞれ,「メーガーラヤン」 Meghalayan,「ノースグリッピアン」
Northgrippian,「グリーンランディアン」Greenlandianと命名されました.そ
れぞれの下限には国際標準模式層断面及び地点(GSSP: Global Boundary
Stratotype Section and Point)が定められました.また,カンブリア紀の統
/世の「シリーズ 3」Series 3が,「ミャオリンギアン」Miaolingianに改名さ
れ,その中の階/期の「ステージ 5」Stage 5が「ウリューアン」Wuliuanに改名
され,GSSPが定められました.
日本地質学会では,最新表の日本語版を更新すると同時に,「Archean」の訳
語を,従来の「始生代(太古代)」から「太古代(始生代)」に変更しました.
「始生代」は既に世界中で使われなくなった「Archeaozoic」の直訳です.一方,
現在世界で広く用いられている「Archean」の訳語は「太古代」です.日本でも
1990年代から先端の学術論文では「太古代」が使われ始めましたが,いまだに
古い用語が用いられている書籍も多く,表現上の混乱を招いています.日本地
質学会では,この機会に「太古代」に統一することにしました.ただし,これ
までの表現との調整という意味で,しばらくは「太古代(始生代)」と表記す
ることにします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2018札幌大会]事前参加登録 まもなく締切です!
──────────────────────────────────
会員・非会員問わずWEB申込画面から事前参加登録のお申込が可能です.巡検
のみの参加もお申込いただけます(アウトリーチ巡検も含む).なお,本大会
より巡検のみに参加する場合は,大会参加登録費は徴収しません.
******************************************************
事前参加登録締切:8月10日(金)18時(WEB)
******************************************************
事前参加登録はこちらから
http://www.geosociety.jp/science/content0103.html
(注)巡検はすでに定員に達したコース(受付終了)もあります.
状況をご確認のうえ,お申込下さい.巡検申込状況はこちらから
http://www.geosociety.jp/science/content0104.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2018札幌大会]懇親会にも是非ご参加下さい
──────────────────────────────────
〜札幌で“キリンビール”はいかがですか!〜
当日受付には限りがあります。是非事前予約をお願いします。
メインのジンギスカン料理をはじめ,各種料理も用意いたします.
また,懇親会中に「よさこいソーラン」の演舞を企画しています.
すすきのに繰り出す前に,懇親会でジンギスカン料理をご堪能下さい!
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/party
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2018札幌大会]緊急展示のお申込について
──────────────────────────────────
今大会でも災害調査報告や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コー
ナー」(ポスタ—展示)を設けます.ご希望の方は,行事委員会までお申込下
さい.
申込締切:2018年8月20日(月)
詳しくは,https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/emergency
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[2018札幌大会]全体日程表の訂正(懇親会の時間)
──────────────────────────────────
ニュース誌7月号(プログラム記事)掲載の全体日程表に誤りがありますので,お詫びし,訂正いたします。
訂正箇所:懇親会の時間
(誤)9/5(水)18:00-20:00 → (正)9/5(水)19:00-21:00
正しい日程表は下記よりご覧いただけます。https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/program
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】[2018札幌大会]夜間小集会「地質学の大型研究」の案内
──────────────────────────────────
日本学術会議の「大型研究に関するマスタープラン」を念頭に地質学分野にお
ける大型研究を議論します。会員はどなたでも参加可能です。積極的に参加し
てください。 (日本地質学会執行理事会)
日時:9月7日(金)18:15〜19:45
会場:札幌大会 第2会場(N302)
内容:
1.趣旨と概要説明
2.ヒアリング報告
・全地球試料のアーカイブ化とキュレーション施設の構築
・中央構造線掘削
3.その他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】[2018札幌大会]会場での受付には「会員カード」を忘れずに!
──────────────────────────────────
*********************************************************************
大会会場での受付は「会員カード」で簡単に手続きできます.
*********************************************************************
「会員カード」を忘れずに持参して下さい.
お忘れになった場合は,大会会期前にお送りする確認書(ハガキ)等でも受付
できますが,時間がかかる場合があります.ご了承下さい.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/card
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】地震火山子どもサマースクールの2019年度開催地決定
──────────────────────────────────
地震火山子どもサマースクールの2019年度開催地についての連絡です。
2月に決定していましたが、諸般の事情で広報が大幅に遅れていました。
2019年度開催地:
京都府宮津市(NPO法人地球デザインスクール提案)
詳しくは,http://www.zisin.jp/opp/notice_summerschool2019_kekka.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第3回ジオ・サロン
8月18日(土)14:00〜16:00
会場:プロント神田店(JR神田駅南口 徒歩1分)
タイトル:「水の座談会〜食べて飲んで水を知る〜」
お茶は軟水で淹れると美味しい?コーヒーは?など試飲も交えながら,舌と頭で
研究者と水について一緒に考えてみませんか?
講演者:井川怜欧(産総研地質総合センター主任研究員)
対象:高校生以上,参加費:3500円(飲食代込),定員:30名
https://www.gsj.jp/geobank/geosalon.html
■(後)「設計業務等標準積算基準書の解説」説明会(地質編)
主催:全地連・経済調査会
8月31日(金)
場所:福岡県中小企業振興センター(福岡市)
受講料:6,000円
https://seminar.zai-keicho.or.jp/seminar/detail/index/148/6
★日本地質学会第125年学術大会(2018札幌大会)
9月5日(水)〜7日(金)
場所:北海道大学(札幌市)
事前参加申込締切:8月10日(金)
http://www.geosociety.jp/science/content0096.html
■(共)2018年度日本地球化学会第65回年会
9月11日(火)〜13日(木)
場所:琉球大学・千原キャンパス
http://www.geochem.jp/meeting/index.html
■(協)地盤技術フォーラム2018
9月26日(水)〜28日(金)10:00〜17:00
場所:東京ビッグサイト 東5ホール(江東区有明)
土壌・地下水浄化技術展/地盤改良技術展/基礎工技術展
http://www.sgrte.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・山口大学地球科学分野教員公募(助教2名)(9/28)
・東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻広域システム科学系(准教授or講師)公募(8/17)
・JAMSETC:
地震津波海域観測研究開発センタープレート構造研究G特任技術研究員募集(8/8)
高知コア研究所地球深部生命研究G研究員もしくは技術研究員募集(9/11)
・東京地学協会平成30年7月豪雨関連緊急調査・研究助成(8/25)
・三井物産環境基金「2018年度募集に関する説明会」(8/27開催)
・原子力環境整備促進・資金管理センター放射性廃棄物の地層処分に係る萌芽的・基礎的研究テーマ及び研究実施者の募集(8/20)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.422 おめでとう地学オリンピック!世界第2位
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.422 2018/8/21┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】おめでとう地学オリンピック!歴代最高の成績で世界第2位
【2】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
【3】[2018札幌大会]札幌大会開催まであと2週間です
【4】[2018札幌大会]全体日程表の訂正
【5】地質学雑誌のあり方についてのアンケート
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】おめでとう地学オリンピック!歴代最高の成績で世界第2位
──────────────────────────────────
第12回国際地学オリンピック・タイ大会(2018年8月8日〜17日、38か国・地域、
139人参加)で、日本代表が金メダル3、銀メダル1を獲得し、国別順位ではアメ
リカに次ぎ2位になったと発表されました.なお、ゲスト生徒の2名も銀メダル
相当の成績とすばらしい成績を収めました.おめでとうございます.
・青沼惠人さん 筑波大学付属駒場高等学校 金メダル
・大野智洋さん 甲陽学院高等学校 金メダル
・田中 匠さん 栄光学園高等学校 金メダル
・河村菜々子さん 高田高等学校 銀メダル
地学オリンピック日本委員会のサイト: http://jeso.jp/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
──────────────────────────────────
本年7月に発生した台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害で被害を受け
られた皆様に,心よりお見舞い申し上げます.
日本地質学会では,災害救助法適用地域で被災された会員の方々のご窮状を
ふまえ,申請により会費を免除いたします.「日本地質学会に届出の住居また
は勤務地が災害救助法適用地域に該当する会員のうち,希望する方」は2018年
度もしくは2019年度会費を免除いたします.
適用を希望される会員は,1. 会員氏名,2. 被災地,3. 被災状況(簡潔に)を
添えて学会事務局にお申し出下さい(郵送,FAX,e-mail、電話のいずれでも可).
****************************************
申請締切:2018年10月31日(水)
****************************************
※通常の会費払い込みについては,下記をご参照ください.
「2018年会費払い込みについて」
http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2018札幌大会]札幌大会開催まであと2週間です
──────────────────────────────────
札幌大会開催まであと2週間です.会員の皆様のご参加をお待ちしています!
日本地質学会第125年学術大会(2018札幌)
9月5日(水)〜7日(金)
会場:北海道大学・高等教育推進機構(札幌市)
大会サイト; https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/top
*事前参加登録(巡検のみの申込を含む)を頂いた方へ:
近日中に予約確認書(ハガキ)をお送りします.当日は,会員カードとともに
確認書もご持参ください.
*巡検にお申込頂いた方へ:
アウトリーチ巡検を含め,全ての巡検コースの催行が決定しました.たくさん
のお申込を頂きありがとうございました.近日中に確認書(ハガキ)を送付し,
各案内者よりメール等で事前のご連絡がありますので,しばらくお待ち下さい.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2018札幌大会]全体日程表の訂正
──────────────────────────────────
ニュース誌7月号(プログラム記事)掲載の全体日程表に誤りがありますので,
お詫びし,訂正いたします。
訂正箇所:
・懇親会の時間
(誤)9/5(水)18:00-20:00 → (正)9/5(水)19:00-21:00
・小さなESのつどい(日程)
(誤)9/6(木)10:00-17:00 → (正)9/7(金)10:00-17:00
正しい日程表は下記よりご覧いただけます。
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/program
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質学雑誌のあり方についてのアンケート
──────────────────────────────────
地質学雑誌が原稿不足で毎月発行が危ぶまれる状況にあり,また同時に会員減
により学会財政が厳しい状況にあります.これらをふまえ,地質学雑誌につい
てのアンケートを行いますので,ご回答下さいますようお願いいたします.
********************************
アンケート回答期日:9月末
********************************
◆アンケート回答フォームはこちら
https://goo.gl/forms/YvIpRGp5l1fYAhUi2
◆このアンケートを行う背景について
http://www.geosociety.jp/publication/content0090.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■「伊豆大島巡検」参加者募集
11月22日(木)〜24日(土),2泊3日(船中1泊)雨天決行
申込期間:9月20日(木)〜11月10日(土)(定員に達した時点で締め切り)
http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地震本部ニュース2018夏号
「全国地震動予測地図2018年版」の概要 ほか
https://www.jishin.go.jp/herpnews/
■(後)「設計業務等標準積算基準書の解説」説明会(地質編)
主催:全地連・経済調査会
8月31日(金)
場所:福岡県中小企業振興センター(福岡市)
受講料:6,000円
https://seminar.zai-keicho.or.jp/seminar/detail/index/148/6
★日本地質学会第125年学術大会(2018札幌大会)
9月5日(水)〜7日(金)
場所:北海道大学(札幌市)
事前参加申込締切:8月10日(金)
http://www.geosociety.jp/science/content0096.html
■日本学術会議公開シンポジウム「西日本豪雨災害の緊急報告会」
9月10日(月)13:00〜17:30
場所:日本学術会議講堂(港区六本木)
定員:先着300名(参加費無料)
http://janet-dr.com/050_saigaiji/2018/050_2018_gouu/20180910_houkoku/180910_00_leef.pdf
要申込:以下の申込みフォームからお願いいたします
https://ws.formzu.net/fgen/S14170529/
■(共)2018年度日本地球化学会第65回年会
9月11日(火)〜13日(木)
場所:琉球大学・千原キャンパス
http://www.geochem.jp/meeting/index.html
■(協)地盤技術フォーラム2018
9月26日(水)〜28日(金)10:00〜17:00
場所:東京ビッグサイト 東5ホール(江東区有明)
土壌・地下水浄化技術展/地盤改良技術展/基礎工技術展
http://www.sgrte.jp/
■国際シンポジウムMISASA VII「サンプルリターンとアストロバイオロジー」
主催:岡山大学惑星物質研究所 共催:宇宙科学研究所・JAXA
12月19日(水)〜21日(金)
場所:米子コンベンションセンター BiG SHiP(鳥取県米子市)
https://sympo.misasa.okayama-u.ac.jp/misasa_vii/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学(固体地球科学)助教(10/19)
・弘前大学地域イノベーション学系戦略的融合領域准教授又は助教公募(10/5)
・長野県職員(環境保全研究所職員)採用選考(9/27)
・京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻資源工学講座地殻開発工学分野(教授)公募(10/15)
・2019年度笹川科学研究助成公募(9/18-10/16)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.423(臨時)小林英夫 名誉会員 ご逝去
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.423 2018/8/27┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 小林英夫 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
小林英夫 名誉会員(島根大学名誉教授)が,平成30年8月14日(火)にご逝去
されました(96歳).
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます.
なお,ご葬儀は,すでにご家族によりしめやかに執り行なわれとのことです.
会長 松田 博貴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.421(臨時)発表公募:西日本豪雨災害の緊急報告会
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.421 2018/8/9┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】西日本豪雨災害の緊急報告会(9/10開催)への発表公募
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】西日本豪雨災害の緊急報告会(9/10開催)への発表公募
──────────────────────────────────
防災学術連携体より下記の緊急報告会開催と発表学会を募る連絡がありました。
日本地質学会からの発表を希望される会員は,「発表者」、「表題」、希望す
る「セッション番号」を添えて、8月20日(月)までに学会事務局(main@
geosociety.jp)までお申し出下さい。学会を通じて発表を申し込みます。
------------------------------------
学会締切:8月20日(月)
------------------------------------
日本学術会議公開シンポジウム・防災学術連携体緊急報告会
「西日本豪雨災害の緊急報告会」
日時:2018年9月10日(月)13:00 〜 17:30
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木7-22-34)
参加費:無料(要申込)
申込フォーム: https://ws.formzu.net/fgen/S14170529
セッション1)「気象の変化、地形・地質等の状況」
セッション2)「洪水・土砂・流木災害のメカニズム」
セッション3)「避難情報の伝達・避難と救援」
セッション4)「復旧・復興対策」
セッション5)「西日本豪雨ならびに近年の豪雨災害から学ぶ教訓と今後の対策」
----------------------------------------------------------
(以下,防災学術連携大会からメール)
西日本の広い範囲にわたり記録的な大雨となった西日本豪雨(平成30年7月豪
雨)は、各地に河川の氾濫、土砂災害などの被害をもたらし200名を超える犠牲
者を出しています。政府は西日本豪雨災害を、豪雨災害では初めて「特定非常
災害」に指定し、激甚災害に指定しました。
この豪雨災害による地域への影響は広域かつ長期に及び,さらに夏後半から
秋にかけて台風や秋雨前線に伴う土砂災害の拡大などが懸念されることから、
予断を許さない状況にあります。
防災学術連携体(56学会)は7月9日にホームページにこの豪雨災害のページ
を開設し、学会の調査情報、国土交通省・気象庁などの最新情報を掲載し、関
係者間の情報共有に努めてきました。7月16日には緊急集会を開催し、7月22日
には「西日本豪雨・市民への緊急メッセージ」を記者発表しました。
日本学術会議と防災学術連携体は、被害の拡大を防ぐために、西日本豪雨に
関する学会間の情報交流を進め、今後の対策を検討するために緊急報告会を、
9月10日(月)、日本学術会議講堂にて開催することにしました。
添付のプログラム案をみてください。
つきまして、発表学会を募りますので、「学会名称」、「発表者」、「表題」、
及び希望される「セッション番号」を添えて、8月22日夕方5時までに応募して
ください。
このメールに返信の形でお送りください。 一つの学会について、一つの発
表と考えています。
もし多数の学会から申し出があった場合、すべて応募に応えられないかもし
れませんが、その場合はお許しください。
本年12月または1月に同じ課題で本格的なシンポジウムを計画しています
ので、今回の発表も含め、各学会の詳細な調査研究に基づくご発表を期待して
います。 どうぞよろしくお願い致します。
--------------(ここまで)------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.424 札幌大会まもなく開催(台風21号の対応)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.424 2018/9/4┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[2018札幌大会]札幌大会まもなく開催(台風21号の対応)
【2】[2018札幌大会]会場変更,講演キャンセルなど
【3】[2018札幌大会]発表者の皆様へ
【4】[2018札幌大会]ポスター会場のご案内
【5】[2018札幌大会]懇親会にご参加下さい
【6】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
【7】一家に1枚ポスター企画案に投票に参加しましょう!
【8】地質学雑誌のあり方についてのアンケート
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2018札幌大会]札幌大会まもなく開催(台風21号の対応)
──────────────────────────────────
明日から札幌大会(9/5-9/7)が開催されます.期間中に台風21号が本州から北
海道にかけて上陸・通過する予報が出ていますが,札幌市内の交通機関が正常
に運行されている限りは、本大会行事(一般向け行事を除く)は原則実施いた
します.行事 中止に関する情報は,大会サイトおよびgeo-flash(メールマガ
ジン)を通じて,逐次告知いたしますので,会員の皆様には大会期間中であっ
て もご確認の程,よろしくお願い申し上げます.詳しくは下記をご参照くださ
い.
【重要】「台風21 号接近に伴う対応について」(9月1日掲載)
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/hot_topics/Sapporo2018_Typhoon.pdf
【大会サイト】 https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2018札幌大会]会場変更,講演キャンセルなど
──────────────────────────────────
【会場変更】
9/6(木)夜間小集会「博物館の展示リニューアル」
(変更前)理学部5号館2階5-201
(変更後)会場:第4会場(E201)
【講演キャンセル】(4日10時現在)
R2-P-9:森井大輔 9/7(金)
R4-O-1:Etienne Skrzypek 9/6(木)第8会場
◆発表キャンセル・変更/大会参加のキャンセルされる場合のご連絡について
(下記参照)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/etal#cansel
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2018札幌大会]発表者の皆様へ
──────────────────────────────────
口頭発表,ポスター発表,それぞれの発表に関する注意点などをニュース
プログラム記事および大会HPに掲載しています.発表前に今一度ご確認下さい.
詳しくは(発表キャンセル・演者交代等の連絡についても)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/presen
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2018札幌大会]ポスター会場のご案内
──────────────────────────────────
札幌大会のポスター会場は,会場P1〜P9に別れています.
部屋割りについては,大会HPに掲載していますのでご参照下さい.
また大会会場内の掲示もご確認下さい.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/acess
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2018札幌大会]懇親会にご参加下さい
──────────────────────────────────
懇親会に是非ご参加下さい!当日受付に多少余裕があります。参加希望の方は,
直接会場でお早めにお申し込み下さい!
会 費(当日申申込)
正会員:6,000円
院生/学部割引会費適用正会員・名誉会員・50年会員,同伴者:4,000円
(※ 非会員の会費は会員に準じます)
詳しくは,https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/party
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地質学会では,災害救助法適用地域で被災された会員の方々のご窮状を
ふまえ,申請により会費を免除いたします.「日本地質学会に届出の住居また
は勤務地が災害救助法適用地域に該当する会員のうち,希望する方」は2018年
度もしくは2019年度会費を免除いたします.
適用を希望される会員は,1. 会員氏名,2. 被災地,3. 被災状況(簡潔に)を
添えて学会事務局にお申し出下さい(郵送,FAX,e-mail、電話のいずれでも可).
****************************************
申請締切:2018年10月31日(水)
****************************************
※通常の会費払い込みについては,下記をご参照ください.
http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】一家に1枚ポスター企画案に投票に参加しましょう!
──────────────────────────────────
第60回科学技術週間に合わせて発行するポスターテーマに日本地質学会からも
2件応募し,ただ今2次審査(一般WEB投票)まで進行中です。皆さんも是非投票
に参加して下さい!
地質学会応募テーマ
・「県の石」でわかる日本の大地のつくり
・近くて遠い未踏の地「地球の内部」
「一家に1枚シリーズ」:文部科学省では、国民が科学技術に触れる機会を増や
し、科学技術に関する知識を適切に捉えて柔軟に活用することを目的として、
「一家に1枚」ポスターを発行しています。
詳しくは,http://www.geosociety.jp/news/n137.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】地質学雑誌のあり方についてのアンケート
──────────────────────────────────
地質学雑誌が原稿不足で毎月発行が危ぶまれる状況にあり,また同時に会員減
により学会財政が厳しい状況にあります.これらをふまえ,地質学雑誌につい
てのアンケートを行いますので,ご回答下さいますようお願いいたします.
********************************
アンケート回答期日:9月末
********************************
◆アンケート回答フォームはこちら
https://goo.gl/forms/YvIpRGp5l1fYAhUi2
◆このアンケートを行う背景について
http://www.geosociety.jp/publication/content0090.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■「伊豆大島巡検」参加者募集
11月22日(木)〜24日(土),2泊3日(船中1泊)雨天決行
申込期間:9月20日(木)〜11月10日(土)(定員に達した時点で締め切り)
http://kanto.geosociety.jp/
■日本地質学会125周年記念:街中ジオ散歩「日比谷入江を歩く」徒歩見学会
日時:2018年10月21日(日)9:45〜15:30 小雨決行(予定)
見学場所:東京都千代田区丸の内周辺
申込受付期間:2018年9月12(水)〜26日(水)
http://www.geosociety.jp/125th/content0020.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■日本学術会議第一部総合ジェンダー分科会
「人文社会科学系研究者の男女共同参画実態調査」実施中
〜回答にご協力下さい〜(調査締切:9月末)
http://philosophy-japan.org/news/news_2018-06-21/
■空からみた関東大震災(空撮写真展とトークイベント)
9月1日(土)〜30日(日)
場所:横浜市民防災センター(横浜駅西口徒歩10分)・入場無料
主催:ジオ神奈川
http://bo-sai.city.yokohama.lg.jp/
★日本地質学会第125年学術大会(2018札幌大会)
9月5日(水)〜7日(金)
場所:北海道大学(札幌市)
事前参加申込締切:8月10日(金)
http://www.geosociety.jp/science/content0096.html
■日本学術会議公開シンポジウム「西日本豪雨災害の緊急報告会」
9月10日(月)13:00〜17:30
場所:日本学術会議講堂(港区六本木)
定員:先着300名(参加費無料)
http://janet-dr.com/050_saigaiji/2018/050_2018_gouu/20180910_houkoku/180910_00_leef.pdf
要申込:以下の申込みフォームからお願いいたします
https://ws.formzu.net/fgen/S14170529/
■(共)2018年度日本地球化学会第65回年会
9月11日(火)〜13日(木)
場所:琉球大学・千原キャンパス
http://www.geochem.jp/meeting/index.html
■(協)地盤技術フォーラム2018
9月26日(水)〜28日(金)10:00〜17:00
場所:東京ビッグサイト 東5ホール(江東区有明)
土壌・地下水浄化技術展/地盤改良技術展/基礎工技術展
http://www.sgrte.jp/
■第214回地質汚染イブニングセミナー
9月28日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ902会議室
講師:石川友之(中日本技術コンサルタント東京支社長)
テーマ:「国内外初、最先端技術診断で液流動化調査・対策に成功した例―茨城県潮来市日出地区―」
http://www.npo-geopol.or.jp
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・JAMSTEC深海・地殻内生物圏研究分野:
--(定年制職員)上席研究員もしくは上席技術研究員公募 (10/24)
--(任期制職員)研究員もしくは技術研究員公募 (10/24)
・東京大学地震研究所平成31年度客員教員及び共同利用公募(10/31)
・山田科学振興財団2019年度留学費「長期間派遣援助」助成募集(10/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.425 札幌大会スタート!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.425 2018/9/05 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】札幌大会:初日の様子
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】札幌大会 初日の様子
──────────────────────────────────
札幌大会が開幕しました!
台風が過ぎ去り、札幌大会は予定通り開幕を迎えました。さあ、125周年記念大会です。議論して、アイデアを温め、北海道の地質と味を堪能して、充実した大会にしましょう。
それでは大会の様子を写真でご覧ください.
■大会スタート
札幌大会開幕!
企業ブースも人気
熱気あるポスター会場
ポスター会場で議論
■表彰式
松田会長
北海道大学理学研究院長・学部長 石森教授
ロンドン地質学会とMOU延長締結
大韓地質学会LEE教授
ロンドン地質学会TORRENS教授
台湾地質学会SHYU教授
記念品贈呈
Geology of Japanの紹介
寺岡名誉会員
徳岡名誉会員
寺岡名誉会員
徳岡名誉会員
井上永年会員
江藤永年会員
嶋本永年会員
村松永年会員
国際賞Coffin教授
小澤儀明賞澤木会員
柵山雅則賞野崎会員
Island Arc賞宮川会員ほか
Island Arc賞山田会員
Island Arc賞斎藤会員
Island Arc賞宮川会員
論文賞辻会員
小藤文次郎賞小宮会員
研究奨励賞綿貫会員
【geo-Flash】No.426 北海道胆振東部地震 会長声明 & 会員の皆様へ
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.426 2018/9/09 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】会長談話
【2】会員の皆様へ
【3】安否確認のお願い
【4】緊急調査のお願い
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】会長談話
──────────────────────────────────
「平成30年北海道胆振東部地震」に関する会長談話が発表されました。
http://www.geosociety.jp/engineer/content0051.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】会員の皆様へ
──────────────────────────────────
日本地質学会第125年学術大会(2018年札幌大会)に関する会長談話
まずはじめに,2018年9月6日未明に発生しました「平成30年北海道胆振東部
地震」により犠牲になられた方々に心から哀悼の意を捧げ,ご冥福をお祈り
すると同時に,被災者の皆様におかれましては,一日も早く日常生活を取り
戻されることをお祈りいたします.
今回の日本地質学会第125年学術大会では,台風21号ならびに平成30年北海道
胆振東部地震により,日本地質学会創立125周年の記念すべき大会の一部中止
などを余儀なくされました.予期せぬ自然現象とはいえ,参加者・関係者の皆
様には多大なご不便・ご苦労をおかけすることになりましたことを,ここに深
くお詫び申し上げます.
平成30年北海道胆振東部地震では,未明の発災後,北海道大学の大会会場を
含め札幌市内全域が停電,さらにすべての公共交通が運休であったにも関わ
らず,朝から会場には多くの参加者の方々が来場されました.そこで2日目に
関しては,電気を使用せずにできるポスターセッションのみ開催いたしました.
しかしながら3日目は,市内一部で給電が再開されたものの,会場の停電は継
続中であり,また節電要請,日常品の不足などがあり,参加者の安全と復路
の確保を鑑み,これ以上の開催は困難と判断し, 3日目以降のすべての年会
プログラムを中止と判断させていただきました.また巡検についても,余震
ならびに天候悪化による二次災害などを考慮し,全コースの中止を決定させ
ていただきました.
参加者の皆様におかれましては,研究成果の発表に向け入念な準備をなされ
ていたものと存じます.その機会がなくなりましたことを大変残念に思いま
す.中でも,真摯に研究に取り組み,この学会発表のために準備してこられ
た学生・院生を中心とする若手研究者の方々にとって,折角の発表の場が失
われたことは,さぞかし残念であったものと思います.執行部としましては,
若手研究者のために今回の研究発表を実施できる場を設定したく,検討を開
始いたしました.なるべく早期にご連絡できるよういたします.
平成30年北海道胆振東部地震の詳細は,今後の調査・研究結果によりますが,
これまで知られてきた断層とは異なる断層の活動によるものと推定されてい
ます.その強い振動は,厚真町を中心に数多くの斜面災害を引き起こし被害
を拡大させました.また札幌市では,大規模な液状化現象が起こりました.
さらに強い振動による発電所の停止が,その後の市民生活に大きな影響を与
えております.
今回の地震災害の背景には,本地域の地質学的な特徴が反映していることは
言うまでもありません.地殻の構造や断層の配置.加えて表層の地質条件が
地震災害に大きく関係します.これらを総合的に理解,解釈することが災害
の予測と減災に必要不可欠です.そのためには,基礎となる地質学的研究を
進めると共に,最新の知見を活かす必要があります.日本地質学会は,学術
研究の発展と最新の知見の普及・教育を推進し,多くの市民の皆様,そして
関係諸機関と共に,最新の地質学的知見を活かした自然災害の予測と防災・
減災方策を社会と連携して追求してまいりたいと思います.
日本地質学会 会長 松田 博貴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[会員各位]安否確認のお願い
──────────────────────────────────
大変な状況とは存じますが,落ち着かれましたら安否確認にご協力をお願い申
し上げます.
ご連絡は地質学会事務局 main@geosociety.jp までお願いいたします.とくに
罹災会員については,ご自身だけでなく,周囲の会員の方の安否についてもご
存知の範囲内で以下の連絡先にご連絡いただければ幸いです.
学会事務局
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル6F
電話:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156
e-mail: main@geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[会員各位]緊急調査のお願い
──────────────────────────────────
地質災害の原因究明は将来の減災につながる重要な活動です.既に現地調査を
開始もしくは検討している会員の皆様もおられると思います.調査にかかる会
員の皆様の安全,そして調査の情報共有のためにも,緊急調査を計画されてお
られる方は地質学会事務局にご連絡をお願いいたします.被災地では救命およ
び行方不明者の捜索活動が行われておりますので,被災地への配慮を引き続き
お願いいたします.
地質災害緊急調査について
http://www.geosociety.jp/hazard/content0024.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.427 札幌大会:今後の対応について
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.427 2018/9/18┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[札幌大会:今後の対応]参加登録費,巡検費用の返金について
【2】[札幌大会:今後の対応]緊急アンケート実施中
【3】[札幌大会:今後の対応]行事催行中止の証明
【4】[札幌大会:今後の対応]領収書の発行について
【5】[札幌大会:今後の対応]CPD単位の発行について
【6】[札幌大会:今後の対応]忘れ物をお預かりしています
【7】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
【8】一家に1枚ポスター企画案に投票に参加しましょう!
【9】地質学雑誌のあり方についてのアンケート
【10】支部情報
【11】その他のお知らせ
【12】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[札幌大会:今後の対応]参加登録費,巡検費用の返金について
──────────────────────────────────
【巡検参加費】催行中止となった巡検コースの巡検参加費については,現在対
応を検討中です.決まり次第参加者にお知らせ致します.
【上記以外】大会参加登録費,発表負担金,お弁当,懇親会の返金は致しませ
ん.現在代替集会を検討中です.何卒ご了承下さい.なお,大会に参加できな
かった事前申込者(参加費が有料の方)には,後日講演要旨集を送付致します.
2018年札幌大会の今後対応については,大会HPでもご案内します.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/typhoon
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[札幌大会:今後の対応]緊急アンケート実施中
──────────────────────────────────
(注)回答は,札幌大会での講演申込者が対象となります
緊急アンケート「札幌大会の代替集会」を実施中です.札幌大会講演申込者の
方は,ご協力をお願いいたします.詳しくは,
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/question
(注)本アンケートについては,各講演申込者の方へ個別にメールでもご案内
しています.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[札幌大会:今後の対応]行事催行中止の証明
──────────────────────────────────
大会HPよりPDFファイルで書面をダウンロードして頂けます.
「日本地質学会第125 年学術大会プログラム一部催行中止のお知らせ」
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/typhoon
上記以外の書式をご希望の場合は,個別に学会事務局までお申し出下さい.
<main@geosociety.jp>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[札幌大会:今後の対応]領収書の発行について
──────────────────────────────────
【大会参加登録】事前参加登録者の方に事前にお送りした確認書ハガキの下部
部分が大会参加登録費の領収書になっています.
【上記以外】大会参加登録費以外の領収書をご希望の方は,別途必要項目を学
会事務局までお知らせ下さい.<main@geosociety.jp>ご希望に応じて発行いた
します.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[札幌大会:今後の対応]CPD単位の発行について
──────────────────────────────────
実施されなかったプログラムについても,CPD参加証明書の発行が可能な場合が
あります.ご確認のうえ希望者はお申し出下さい.<main@geosociety.jp>
詳しくは,https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/cpd
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[札幌大会:今後の対応]忘れ物をお預かりしています
──────────────────────────────────
大会での忘れ物をいくつかお預かりしています.
お心当たりの方は,学会事務局(main@geosociety.jp)までお問い合わせ下さい.
・USBケーブル(黒):5日 午後 N304(第3会場)
・Mac用アダプター(MagSafe 2 Power Adapter):6-7日 学会事務局の部屋
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地質学会では,災害救助法適用地域で被災された会員の方々のご窮状を
ふまえ,申請により会費を免除いたします.「日本地質学会に届出の住居また
は勤務地が災害救助法適用地域に該当する会員のうち,希望する方」は2018年
度もしくは2019年度会費を免除いたします.
適用を希望される会員は,1. 会員氏名,2. 被災地,3. 被災状況(簡潔に)を
添えて学会事務局にお申し出下さい(郵送,FAX,e-mail,電話のいずれでも可).
******************************************************
申請締切:2018年11月30日(金)*次年度会費請求の準備の都合により
******************************************************
※通常の会費払い込みについては,下記をご参照ください.
http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】一家に1枚ポスター企画案に投票に参加しましょう!
──────────────────────────────────
第60回科学技術週間に合わせて発行するポスターテーマに日本地質学会からも
2件応募し,ただ今2次審査(一般WEB投票)まで進行中です.皆さんも是非投票
に参加して下さい!
<地質学会応募テーマ>
・「県の石」でわかる日本の大地のつくり
・近くて遠い未踏の地「地球の内部」
「一家に1枚シリーズ」:文部科学省では,国民が科学技術に触れる機会を増や
し,科学技術に関する知識を適切に捉えて柔軟に活用することを目的として,
「一家に1枚」ポスターを発行しています.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/news/n137.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】地質学雑誌のあり方についてのアンケート
──────────────────────────────────
地質学雑誌が原稿不足で毎月発行が危ぶまれる状況にあり,また同時に会員減
により学会財政が厳しい状況にあります.これらをふまえ,地質学雑誌につい
てのアンケートを行いますので,ご回答下さいますようお願いいたします.
********************************
アンケート回答期日:9月末
********************************
◆アンケート回答フォームはこちら
https://goo.gl/forms/YvIpRGp5l1fYAhUi2
◆このアンケートを行う背景について
http://www.geosociety.jp/publication/content0090.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■「伊豆大島巡検」参加者募集
11月22日(木)〜24日(土),2泊3日(船中1泊)雨天決行
申込期間:9月20日(木)〜11月10日(土)(定員に達した時点で締切)
http://kanto.geosociety.jp/
■日本地質学会125周年記念:街中ジオ散歩「日比谷入江を歩く」徒歩見学会
10月21日(日)9:45〜15:30 小雨決行(予定)
見学場所:東京都千代田区丸の内周辺
参加申込受付期間:9月12(水)〜26日(水)
http://www.geosociety.jp/125th/content0020.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■(協)地盤技術フォーラム2018
9月26日(水)〜28日(金)10:00〜17:00
場所:東京ビッグサイト 東5ホール(江東区有明)
土壌・地下水浄化技術展/地盤改良技術展/基礎工技術展
http://www.sgrte.jp/
■第214回地質汚染イブニングセミナー
9月28日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ902会議室
講師:石川友之(中日本技術コンサルタント東京支社長)
テーマ:「国内外初,最先端技術診断で液流動化調査・対策に成功した例
―茨城県潮来市日出地区―」
http://www.npo-geopol.or.jp
■科学的特性マップに関する対話型全国説明会
主催:原子力発電環境整備機構(NUMO)/経済産業省資源エネルギー庁
9月30日(日)〜10月28日(日)
場所:北九州市,七尾市,米子市,浜田市,八代市,釜石市,岐阜市
プログラム:地層処分の説明,テーブルでのグループ質疑
https://www.numo.or.jp/taiwa/2018/
■「深田研一般公開2018」〜化石の日関連イベント〜
10月7日(日)10:00〜16:00
講演(13:30〜15:00)
「化石の日制定記念:世界を変えた恐竜たち」
真鍋 真氏(国立科学博物館標本資料センター長,日本古生物学会会長)
その他:深田研レクチャー,研究展示,体験学習,化石展示,実験,恐竜ぬり絵,
スタンプラリーなど盛りだくさんの内容です.
http://www.fgi.or.jp/?p=4099
■2018年度秋期(初級者向け)地質調査研修
主催:産総研コンソーシアム41「地質人材育成コンソーシアム」
10月29日(月)〜11月2日(金)
場所:島根県出雲市長尾鼻周辺(小伊豆海岸)
研修内容:露頭の地層・岩石の観察ポイントからまとめまで,地質図を作成す
るための一連の基本的事項を5日間の研修で習得します.※今回は,大学・会社
等で地質図を1回くらいは書いたことのある初心者向けの内容で行う予定です.
参加申込締切:10月19日(金)(定員になり次第締切)
https://www.gsj.jp/geobank/geotraining.html
■東京大学大気海洋研究所共同利用研究集会
「海底堆積物から地震履歴をどこまで読み取れるのか」
11月13日(火)13:00〜14日(水)16:00(予定)
場所:東京大学大気海洋研究所(柏キャンパス)
発表申込締切:10月1日(月)12時
http://www.aori.u-tokyo.ac.jp
■日本地球惑星科学連合2018年大会
2019年5月26日(日)〜30日(木)
会場:千葉県 幕張メッセ国際会議場・国際展示場ホール8
東京ベイ幕張ホール
http://www.jpgu.org/meeting_2019/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・関西学院大学理工学部環境・応用化学科任期制助教募集(10/31)
・海洋研究開発機構
高知コア研究所地球深部生命研究グループ(研究員or技術研究員)(10/15)
地震津波海域観測研究開発センター
--地震津波予測研究グループ(PD研究員)(10/1)
--海域断層情報総合評価グループ(特任技術職A及びB)(10/1)
--プレート構造研究グループ(PD研究員)(10/2)
数理科学・先端技術研究分野
--(特任研究員/特任技術研究員/特任技術職)(10/4)
--(主任研究員/主任技術研究員)(10/29)
地震津波海域観測研究開発センター等,JAMSTEC固体地球科学研究関連部署
(上席研究員or上席技術研究員)(10/29)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.428[札幌大会:今後の対応]つくば特別大会実施
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.428 2018/10/2┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[札幌大会:今後の対応]つくば特別大会実施のお知らせ
【2】[札幌大会:今後の対応]参加登録費,巡検費用の返金について
【3】2018年度各賞候補者募集について
【4】2019年度の会費払込について(割引会費申請受付開始)
【5】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[札幌大会:今後の対応]つくば特別大会実施のお知らせ
──────────────────────────────────
札幌大会では,昨年度に引き続き自然災害によるプログラム中止のため,参
加者の皆様に多大なるご不便・ご迷惑をおかけする事態となりました.また大
会会期中におけるプログラム中止判断が混乱したことについて,この場をお借
りして深くお詫び申し上げます.
大会期日後に行った緊急会員アンケートでは,多くの会員の皆様から代替大
会の実施と参加希望が寄せられました.以上を受け,執行理事会で検討を重ね
た結果,代替大会を「つくば特別大会」として実施することにいたしました.
実施要領は以下の通りです.
2018年10月1日
行事委員長 岡田 誠
[大会名称]日本地質学会第125年学術大会(2018年つくば特別大会)
[日 程]2018年12月1日(土)〜2日(日)
[場 所]産業技術総合研究所 つくば本部(予定)
[対 象]札幌大会において,(1)台風21号による交通支障により発表をやむ
なく
キャンセルした発表予定者,および(2)北海道胆振東部地震によるプログラム
中止により発表できなかった2日目・3日目の発表予定者(停電・交通支障によ
り2日目のポスターセッションで発表できなかった発表予定者を含む).いずれ
も口頭・ポスター双方を含む.
[参加費]有無を含め後日通知予定
なお,大会ならびに申込等の詳細については, Geo-flash(10/16配信予定)に
てご連絡予定です(各講演者へは個別にメールでもご連絡予定です).
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[札幌大会:今後の対応]参加登録費,巡検費用の返金について
──────────────────────────────────
1) 巡検参加費:催行中止となった巡検コースの巡検参加費については,すべ
て返金致します.なお一部の会員については,返金額を次年度以降の学会費へ
の充当として対応頂きますようお願い致します.返金については,別途メール
にて巡検申込者宛にご連絡致します.
2)上記以外:大会参加登録費,発表負担金,お弁当,懇親会の返金は致し
ません.代替集会(つくば特別大会)を開催予定です.何卒ご了承下さい.
なお,大会に参加できなかった事前申込者(参加費が有料の方)には,後日講
演要旨集を送付致します.
*2018年札幌大会の今後対応については,大会HPでもご案内しています.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/typhoon
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2018年度各賞候補者募集について
──────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして,研究の援助・奨励および研究業
績の表彰を行っています.本年も各賞の自薦,他薦による候補者を募集いたし
ます.期日厳守にて,たくさんのご応募をお待ちしております.
応募締切:2018年11月30日(金)必着
詳しくは,
http://sub.geosociety.jp/members/content0098.html(会員のページ)
※「会員のページ」へは会員番号・パスワードによるログインが必要です.
ログインの方法はこちら.
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2019年度の会費払込について(割引会費申請受付開始)
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下さいます
ようお願いいたします.
学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)の方で,それぞ
れ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適用します.なお,2018年度
までの院生割引会費についての申請は終了しておりますので,2019年度会費に
のみ適用となります(現在学部生または院生で2019年度から社会人になる方は
割引会費の申請はできません).
※割引の適用を希望する場合,申請は毎年必要です.
*************************************************
請求書発行前締切:2018年11月20日(火)
*************************************************
※申請書のDL,会費払い込みについては,下記をご参照ください.
http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地質学会では,災害救助法適用地域で被災された会員の方々のご窮状を
ふまえ,申請により会費を免除いたします.「日本地質学会に届出の住居また
は勤務地が災害救助法適用地域に該当する会員のうち,希望する方」は2018年
度もしくは2019年度会費を免除いたします.
適用を希望される会員は,1. 会員氏名,2. 被災地,3. 被災状況(簡潔に)を
添えて学会事務局にお申し出下さい(郵送,FAX,e-mail,電話のいずれでも可).
******************************************************
申請締切:2018年11月30日(金)*次年度会費請求の準備の都合により
******************************************************
※通常の会費払い込みについては,下記をご参照ください.
http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■シンポジウム「せまりくるジオハザード−関東の自然災害−」
11月18日(日)13:00〜17:30
終了後大学周辺で懇親会を開催
場所:早稲田大学教育学部 早稲田キャンパス 6号館
■「伊豆大島巡検」参加者募集
11月22日(木)〜24日(土),2泊3日(船中1泊)雨天決行
申込期間:9月20日(木)〜11月10日(土)(定員に達した時点で締切)
詳しくは, http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■「深田研一般公開2018」〜化石の日関連イベント〜
10月7日(日)10:00〜16:00
講演(13:30〜15:00)
「化石の日制定記念:世界を変えた恐竜たち」真鍋 真氏(国立科学博物館)
*第9回ほか惑星地球フォトコンテストの入選作品の展示も予定
http://www.fgi.or.jp/?p=4099
■ぼうさいこくたい2018
10月13日(土)〜14日(日)
場所:東京ビッグサイト・そなエリア(東京臨海広域防災公園)
※地質学会も出展します
「防災のための第一歩−子どものうちから身につけたい地球の知識−」
http://bosai-kokutai.jp/
■科学的特性マップに関する対話型全国説明会
主催:経済産業省資源エネルギー庁,NUMO
10月20日(土)〜12月18日(火)
場所:八代市,釜石市,岐阜市,熊本市,綾部市,豊岡市,下関市,四万十市,
能代市,京丹後市,豊橋市,浜松市,平塚市
プログラム:地層処分の説明,テーブルでのグループ質疑
https://www.numo.or.jp/taiwa/2018/
■2018年度秋期(初級者向け)地質調査研修
主催:産総研コンソーシアム41「地質人材育成コンソーシアム」
10月29日(月)〜11月2日(金)
場所:島根県出雲市長尾鼻周辺(小伊豆海岸)
参加申込締切:10月19日(金)(定員になり次第締切)
https://www.gsj.jp/geobank/geotraining.html
■(協)石油技術協会平成30年度秋季講演会
「若手技術者-何を考え何を目指す」
11月1日(木)13:00〜17:40
場所:東京大学小柴ホール東京都文京区本郷
http://www.japt.org/index.html
■第29回地質汚染調査浄化技術研修会
11月16日(金)〜18日(日)
主催:NPO法人日本地質汚染審査機構
共催:地質汚染診断士の会・日本地質学会環境地質部会・社会地質学会
会場:日本地質汚染審査機構 関東ベースン実習センター(千葉県香取市)
会費:会員45,000円・非会員55,000円・学生:15,000円
http://www.npo-geopol.or.jp
■地質学史懇話会
12月23日(日)13:30〜17:00
場所:北とぴあ8階806号室
・長田敏明:ブレーキストン著(1883)「日本列島と大陸の古代の接続につい
ての動物学的痕跡」に関連する2・3の事柄
・清地ゆき子:地質学者としての張資平
■日本地球惑星科学連合2018年大会
2019年5月26日(日)〜30日(木)
会場:千葉県 幕張メッセ国際会議場・国際展示場ホール8
東京ベイ幕張ホール
http://www.jpgu.org/meeting_2019/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・洞爺湖有珠山ジオパークの学術専門員募集(11/30)
・兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科 専任教員公募(11/18)
・信州大学学術研究院理学系助教公募(11/19)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.429 つくば特別大会:発表希望等の確認をお願いします
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.429 2018/10/16┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】つくば特別大会のお知らせ
【2】つくば特別大会:発表希望等の確認をお願いします(回答期日:10/31)
【3】つくば特別大会:緊急展示の申込について
【4】札幌大会の参加登録費,巡検費用の返金について
【5】第10回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
【6】2018年度各賞候補者募集について
【7】2019年度の会費払込について(割引会費申請受付開始)
【8】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
【9】次期地震火山観測研究計画 パブリックコメント募集
【10】支部情報
【11】その他のお知らせ
【12】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】つくば特別大会のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地質学会第125年学術大会(2018年つくば特別大会)
[日 程]2018年12月1日(土)〜2日(日)
[場 所]産業技術総合研究所 つくば本部・共用講堂(つくば市東1-1-1)
[参加費]徴収予定.ただし,札幌大会の事前および当日大会参加登録費をお
支払い済みの方は,本特別大会での新たな費用の徴収はありません.
特別大会にはどなたでもご参加いただけますが,発表は,札幌大会で発表でき
なかった方のみが対象です.新規の発表申込は受付けません(緊急展示を除く).
特別大会の情報は,大会HPで随時お知らせしていきます.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】つくば特別大会:発表希望等の確認をお願いします(回答期日:10/31)
──────────────────────────────────
札幌大会で発表できなかった方(*注)は,全員回答をお願いします.
*********************************************************
札幌大会で発表できなかった方は,特別大会での発表希望,J-STAGEでの公開
希望(見なし発表)などについて,下記WEBフォームより必ず回答して下さい.
期日までに回答頂けない場合は,「見なし発表」として,J-STAGE上で講演要旨
を公開させて頂きます.ご了承下さい.(回答期日:10/31(水))
https://goo.gl/forms/jAFB0MXHppoiD0H13
(*注)札幌大会で発表できなかった方(口頭・ポスター発表のいずれも)
(1)台風21号による交通支障により発表をやむなくキャンセルした発表予定者
(2)北海道胆振東部地震によるプログラム中止により発表できなかった2日目・
3日目の発表予定者
(3)停電・交通支障により2日目のポスターセッションで発表できなかった発
表予定者を含む)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】つくば特別大会:緊急展示の申込について
──────────────────────────────────
北海道胆振東部地震など緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供す
るために,災害調査報告や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コー
ナー」を設けます.ポスター展示を希望する方は,10月31日(水)までに次の
内容を下記申込先にご連絡ください.緊急展示は,正式な学会発表と同じく,
コアタイムの時間帯が設けられます.優秀ポスター賞へのエントリーも可能で
す.また他の要旨と同様に大会後J-STAGE 上で公開されます.発表における1人
1題の制約は及びません.コアタイムの日程については著者希望を優先します(
ただし既にセッションでポスター発表を予定されている場合は,同日でのコア
タイムは設定できません).
1)発表要旨PDF(ニュース誌5月号参照)
2)緊急展示の必要性
3)発表代表者と連絡先
4)ポスター希望枚数(1 枚:ポスターサイズ90×210 cm)
5)優秀ポスター賞へのエントリーの有無
6)コアタイムの日程希望など展示に関わる要望(2〜6 の様式は自由)
行事委員会が協議の上,採択可否の判断を致します.展示方法やコアタイム
等の希望にはできるだけ応えるようにしますが,最終的には行事委員会の
指示に従ってください.
申込締切:10月31日(水)
問い合わせ先・申込先:e-mail: main@geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】札幌大会の参加登録費,巡検費用の返金について
──────────────────────────────────
1) 巡検参加費:催行中止となった巡検コースの巡検参加費については,すべ
て返金致します.なお一部の会員については,返金額を当年or次年度以降の学
会費への充当として対応頂きますようお願いしています.返金に関する詳細は,
巡検申込者宛に別途メールにてご連絡していますので,必ずご確認下さい.
2)上記以外:大会参加登録費,発表負担金,お弁当,懇親会の返金は致し
ません.12月につくば特別大会を開催予定です.何卒ご了承下さい.
なお,大会に参加できなかった事前申込者(参加費が有料の方)には,講演要
旨集を送付しました.
*2018年札幌大会の今後対応については,大会HPでもご案内しています.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/typhoon
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第10回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
──────────────────────────────────
***応募締切:2019年1月末***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募集!!
投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募フォームからでも
メール添付でもご応募いただけます.
会員の皆様からの応募もお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】2018年度各賞候補者募集について
──────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして,研究の援助・奨励および研究業
績の表彰を行っています.本年も各賞の自薦,他薦による候補者を募集いたし
ます.期日厳守にて,たくさんのご応募をお待ちしております.
応募締切:2018年11月30日(金)必着
詳しくは,
http://sub.geosociety.jp/members/content0098.html(会員のページ)
※「会員のページ」へは会員番号・パスワードによるログインが必要です.
ログインの方法はこちら.
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】2019年度の会費払込について(割引会費申請受付開始)
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下さいます
ようお願いいたします.
学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)の方で,それぞ
れ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適用します.なお,2018年度
までの院生割引会費についての申請は終了しておりますので,2019年度会費に
のみ適用となります(現在学部生または院生で2019年度から社会人になる方は
割引会費の申請はできません).
※割引の適用を希望する場合,申請は毎年必要です.
*************************************************
請求書発行前締切:2018年11月20日(火)
*************************************************
※申請書のDL,会費払い込みについては,下記をご参照ください.
http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地質学会では,災害救助法適用地域で被災された会員の方々のご窮状を
ふまえ,申請により会費を免除いたします.「日本地質学会に届出の住居また
は勤務地が災害救助法適用地域に該当する会員のうち,希望する方」は2018年
度もしくは2019年度会費を免除いたします.
適用を希望される会員は,1. 会員氏名,2. 被災地,3. 被災状況(簡潔に)を
添えて学会事務局にお申し出下さい(郵送,FAX,e-mail,電話のいずれでも可).
******************************************************
申請締切:2018年11月30日(金)*次年度会費請求の準備の都合により
******************************************************
※通常の会費払い込みについては,下記をご参照ください.
http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】次期地震火山観測研究計画 パブリックコメント募集
──────────────────────────────────
文部科学省の科学技術・学術審議会測地学分科会では,「災害の軽減に貢献す
るための地震火山観測研究計画」の次期計画の策定に向けて検討を進めてまい
りました.この度,別紙のとおり「災害の軽減に貢献するための地震火山観測
研究計画(第2次)の推進について」(案)を取りまとめました.この計画案
について,パブリックコメント(任意の意見募集)を開始しましたのでお知ら
せいたします.
以下の意見募集ホームページにアクセスし,意見提出フォームからご意見を提
出願います.
〔意見募集ホームページ〕
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001007&Mode=0
【意見提出期限】平成30年11月9日(金)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■シンポジウム「せまりくるジオハザード−関東の自然災害−」
11月18日(日)13:00〜17:30
終了後大学周辺で懇親会を開催
場所:早稲田大学教育学部 早稲田キャンパス 6号館
■「伊豆大島巡検」参加者募集
11月22日(木)〜24日(土),2泊3日(船中1泊)雨天決行
申込締切:11月10日(土)(定員に達した時点で締切)
http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■科学的特性マップに関する対話型全国説明会
主催:経済産業省資源エネルギー庁,NUMO
10月20日(土)〜12月18日(火)
場所:八代市,釜石市,岐阜市,熊本市,綾部市,豊岡市,下関市,四万十市,
能代市,京丹後市,豊橋市,浜松市,平塚市
プログラム:地層処分の説明,テーブルでのグループ質疑
https://www.numo.or.jp/taiwa/2018/
■第215回地質汚染イブニングセミナー
10月26日(金)18:20〜21:10
場所:北とぴあ901会議室
講師:NPO法人日本地質汚染審査機構
テーマ:現場調査報告シンポ―(仮題)
平成30年北海道胆振東部地震地質災害の教訓から学ぶ
関東平野の台地・丘陵・山岳の地質と地震災害の点検
http://www.npo-geopol.or.jp
■(協)石油技術協会平成30年度秋季講演会
「若手技術者-何を考え何を目指す」
11月1日(木)13:00〜17:40
場所:東京大学小柴ホール東京都文京区本郷
http://www.japt.org/index.html
■東京大学大気海洋研究所共同利用研究集会
「海底堆積物から地震履歴をどこまで読み取れるのか」
11月13日(火)13:00〜14日(水)16:00
場所:東京大学大気海洋研究所(柏キャンパス)
http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/aori_news/meeting/2018/20181113.html
■科学と芸術の対話「サイエンス-アート茶話会」
11月19日(月)15:00〜16:00
場所:高知大学海洋コア総合研究センター セミナールーム
参加無料/申込不要/お茶菓子をご用意しています
2019年度アーティストを科学研究航海へ乗船させるAOS(アーティスト・オン・
シップ)を実施予定です.その導入として標記茶話会を開催します.6次元第7
感アーティストの康 夏奈さんをお迎えし,科学者とアーティストの対話を試み
ます.「地球」という共通の探求対象を科学的かつ芸術的に捉える試みです.
問合せ先:ササオカミホ(高知大学 短期研究員)
jm-sasaokam@kochi-u.ac.jp
■20th Project A in Okayama
2019年3月4日(月)〜8日(金)
場所:地球史研究所(Institute of GeoHistory)
岡山県赤磐市周匝1548
地球に関わる異種分野合流の研究発表会および地質巡検
学生・大学院生・若手研究者・研究者だれでも参加OK
参加料:大人25,000円,学生10,000円(4泊食事付)
締切:12月20日(木)
http://archean.jp
■日本地球惑星科学連合2018年大会
2019年5月26日(日)〜30日(木)
会場:千葉県 幕張メッセ国際会議場・国際展示場ホール8
東京ベイ幕張ホール
http://www.jpgu.org/meeting_2019/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・和歌山県ジオパーク専門員(地形・地質)募集(11/12)
・東大大気海洋研(柏地区・沿岸センター・学際連携)共同利用公募(11/30)
・海洋研究開発機構
--地球内部物質循環研究分野研究員or技術研究員(12/11)
--深海・地殻内生物圏研究分野ポストドクトラル研究員(10/25)公募延期
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.430(臨時)熊井久雄名誉会員 ご逝去
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.430 2018/10/31 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 熊井久雄 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
日本地質学会名誉会員 熊井久雄氏(大阪市立大学名誉教授)が、病気療養中の
ところ、平成30年10月28日(日)午前3時、肺炎のため逝去されました(78歳)。
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
なお、通夜ならびに告別式は、下記のとおり執り行われますので併せてお知らせ
申し上げます。
通 夜:11月1日(木)午後 6:00〜
告別式:11月2日(金)午前 9:45〜
会 場:さがみ典礼所沢葬祭センター
(埼玉県所沢市北原町1348-1 電話 04-2993-4411)
https://www.navitime.co.jp/poi?spt=00004.11105200133
喪 主:熊井玲児 様(ご子息)
一般社団法人日本地質学会
会長 松田博貴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真、マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは、月2回(第1・3火曜日)配信予定です。原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.431 2019年度各賞候補者募集中(11/30締切)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.431 2018/11/6┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】つくば特別大会のお知らせ
【2】2019年度各賞候補者募集中(11/30締切)
【3】2019年度の会費払込について(割引会費申請受付中)
【4】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
【5】第10回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】訃報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】つくば特別大会のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地質学会第125年学術大会(2018年つくば特別大会)
[日 程]2018年12月1日(土)〜2日(日)
[場 所]産業技術総合研究所 つくば本部・共用講堂(つくば市東1-1-1)
[参加費]
・一般(会員,非会員問わず):6,000円(注)講演要旨付き
・院生(会員,非会員問わず):4,000円(注)講演要旨付き
・学部学生(会員,非会員問わず):無料(注)講演要旨は付きません
・名誉/50年会員:無料(注)講演要旨は付きません
ただし,札幌大会の事前および当日大会参加登録費をお支払い済みの方は,
本特別大会での新たな費用(参加費)の徴収はありません.
*特別大会での講演希望確認,緊急展示の申込は締切ました。現在プログラム
編成中です.決まり次第,HP,メルマガ等でお知らせします.
特別大会の情報は,大会HPで随時お知らせしていきます.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2019年度各賞候補者募集中(11/30締切)
──────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして,研究の援助・奨励および研究業
績の表彰を行っています.本年も各賞の自薦,他薦による候補者を募集いたし
ます.期日厳守にて,たくさんのご応募をお待ちしております.
応募締切:2018年11月30日(金)必着
詳しくは,http://sub.geosociety.jp/members/content0098.html(会員のページ)
※「会員のページ」へは会員番号・パスワードによるログインが必要です.
ログインの方法はこちら.
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2019年度の会費払込について(割引会費申請受付中)
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下さいます
ようお願いいたします.
学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)の方で,それぞ
れ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適用します.なお,2018年度
までの院生割引会費についての申請は終了しておりますので,2019年度会費に
のみ適用となります(現在学部生または院生で2019年度から社会人になる方は
割引会費の申請はできません).
※割引の適用を希望する場合,申請は毎年必要です.
*************************************************
請求書発行前締切:2018年11月20日(火)
*************************************************
※申請書のDL,会費払い込みについては,下記をご参照ください.
http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地質学会では,災害救助法適用地域で被災された会員の方々のご窮状を
ふまえ,申請により会費を免除いたします.「日本地質学会に届出の住居また
は勤務地が災害救助法適用地域に該当する会員のうち,希望する方」は2018年
度もしくは2019年度会費を免除いたします.
適用を希望される会員は,1. 会員氏名,2. 被災地,3. 被災状況(簡潔に)を
添えて学会事務局にお申し出下さい(郵送,FAX,e-mail,電話のいずれでも可).
******************************************************
申請締切:2018年11月30日(金) *次年度会費請求の準備の都合により
******************************************************
※通常の会費払い込みについては,下記をご参照ください.
http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第10回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
──────────────────────────────────
***応募締切:2019年1月末***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募集!!
投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募フォームからでも
メール添付でもご応募いただけます.
会員の皆様からの応募もお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■シンポジウム「せまりくるジオハザード−関東の自然災害−」
11月18日(日)13:00〜17:30
終了後大学周辺で懇親会を開催
場所:早稲田大学教育学部 早稲田キャンパス6号館
http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
地震本部ニュース2018秋号:南海トラフ広域地震防災研究プロジェクトほか
https://www.jishin.go.jp/herpnews/
*************************************************
■科学的特性マップに関する対話型全国説明会
主催:経済産業省資源エネルギー庁,NUMO
10月20日(土)〜12月18日(火)
場所:八代市,釜石市,岐阜市,熊本市,綾部市,豊岡市,下関市,四万十市,
能代市,京丹後市,豊橋市,浜松市,平塚市
プログラム:地層処分の説明,テーブルでのグループ質疑
https://www.numo.or.jp/taiwa/2018/
■地球科学普及講演会「地球をぶらり」
主催:NPO法人地学オリンピック日本委員会
11月24日(土)13:00〜16:30
場所:城西大学東京紀尾井町キャンパス3号棟5F国際会議場
(千代田区平河町2-3-20)
対象:中高生・一般(保護者同伴で小学生の参加可)
http://jeso.jp/index.html
■平成30年度 東濃地科学センター 地層科学研究 情報・意見交換会
11月29日(木) 13:30〜16:45
場所:瑞浪市地域交流センター「ときわ」(岐阜県瑞浪市)
定員:約130名・入場無料
参加申込締切:11月13日(火)先着順
https://www.jaea.go.jp/04/tono/topics/topics1810_1/index.html
■土岐地球年代学研究所見学会
11月30日(金) 9:00〜10:45
場所:土岐地球年代学研究所(岐阜県土岐市)
定員:30名・入場無料
参加申込締切:11月13日(火)先着順
https://www.jaea.go.jp/04/tono/topics/topics1810_1/index.html
■高知大学海洋コア総合研究センター設立15周年記念公開シンポジウム
「地球を掘ってわかること〜古地震、気候変動、地球の姿〜」
(地球掘削科学共同利用・共同研究拠点の成果と今後の展望)
11月30日(金)〜12月1日(土)
会場:オーテピア ホール(高知市追手筋2-1-1)
https://www.kochi-u.ac.jp/marine-core/seminars/naiyo/181130_15th.html
■地区防災計画学会・日本大学危機管理学部共同シンポジウム
「西日本豪雨等の教訓と地域防災力・災害復興活動」
12月1日(土) 13:30〜16:30(予定)
場所 日本大学三軒茶屋キャンパス
http://www.gakkai.chiku-bousai.jp/
■第29回GSJシンポ地圏資源環境研究部門研究成果報告会
「粘土・粘土鉱物:枯渇の機器にある貴重な国内資源」
12月6日(木)13:30〜17:35
場所:秋葉原ダイビル
https://unit.aist.go.jp/georesenv/
■第16回GSJジオ・サロン
「宇宙から地質Ⅱ〜映画の中のウソ?ホント!?〜」
12月16日(日) 14:00〜16:00
場所:Connecting The Dots 代々木 地下大会議室(渋谷区代々木1-29-5)
定員:18名(定員になり次第締切)
https://www.gsj.jp/geobank/geosalon.html
■日本地球惑星科学連合2018年大会
2019年5月26日(日)〜30日(木)
会場:千葉県 幕張メッセ国際会議場・国際展示場ホール8
東京ベイ幕張ホール
http://www.jpgu.org/meeting_2019/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・名古屋大学宇宙地球環境研究所では、研究機関研究員募集(12/20)
・「消防防災科学技術研究推進制度」平成31年度研究開発課題の募集(12/20)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】訃報:小坂丈予 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
日本地質学会名誉会員 小坂丈予氏(東京工業大学名誉教授)が,平成23年
11月23日病気のため逝去されました(享年87歳)。先日ご家族からのご連
絡により判明致しましたので,お知らせします。これまでの故人の功績を
讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます.
一般社団法人 日本地質学会
会長 松田 博貴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.432(臨時)つくば特別大会:講演プログラム 決定
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.432 2018/11/16┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】つくば特別大会:講演プログラム 決定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】つくば特別大会:講演プログラム 決定
──────────────────────────────────
つくば特別大会の講演プログラムが決定しました。
口頭:120件,ポスター:62件(緊急展示3件を含む)の
計182 件の講演が予定されいています。
日程表・講演プログラム
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/program2
また,会場への交通アクセスなど(お車でおいでの方へなど...)
大会に関する情報を掲載いたしましたので,あわせてご覧下さい.
会場・交通のご案内
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/guide
食事・宿泊等その他のご案内
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/etal2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.433 2019年度各賞候補者募集:まもなく締切!!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.433 2018/11/20┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】つくば特別大会のお知らせ(講演プログラムほか)
【2】2019年度各賞候補者募集:まもなく締切(11/30締切)
【3】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
【4】第10回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】つくば特別大会のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地質学会第125年学術大会(2018年つくば特別大会)
[日 程]2018年12月1日(土)〜2日(日)
[場 所]産業技術総合研究所 つくば本部・共用講堂(つくば市東1-1-1)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/guide
(重要)札幌大会の事前および当日大会参加登録費をお支払い済みの方は,
特別大会での新たな参加費の徴収はありません.当日は忘れずに【会員カード】
をお持ち下さい.
◆ 日程表・講演プログラム
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/program2
また,会場への交通アクセスなど(お車でおいでの方へなど)
大会に関する情報は下記よりご覧下さい.
◆ 会場・交通のご案内
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/guide
◆ 食事・宿泊等その他のご案内
(産総研内の食堂・コンビニはお休み.各自昼食のご用意をお願いします)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/etal2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2019年度各賞候補者募集:まもなく締切(11/30締切)
──────────────────────────────────
日本地質学会は毎年その事業のひとつとして,研究の援助・奨励および研究業
績の表彰を行っています.本年も各賞の自薦,他薦による候補者を募集いたし
ます.期日厳守にて,たくさんのご応募をお待ちしております.
**********************************************
応募締切:2018年11月30日(金)必着
**********************************************
詳しくは, http://sub.geosociety.jp/members/content0098.html
(会員のページ)
※「会員のページ」へは会員番号・パスワードによるログインが必要です.
ログインの方法はこちら.
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地質学会では,災害救助法適用地域で被災された会員の方々のご窮状を
ふまえ,申請により会費を免除いたします.「日本地質学会に届出の住居また
は勤務地が災害救助法適用地域に該当する会員のうち,希望する方」は2018年
度もしくは2019年度会費を免除いたします.
適用を希望される会員は,1. 会員氏名,2. 被災地,3. 被災状況(簡潔に)を
添えて学会事務局にお申し出下さい(郵送,FAX,e-mail,電話のいずれでも可).
******************************************************
申請締切:2018年11月30日(金) *次年度会費請求の準備の都合により
******************************************************
※2019年度会費払い込みについては,下記をご参照ください.
http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第10回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
──────────────────────────────────
***応募締切:2019年1月末***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募集!!
投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募フォームからでも
メール添付でもご応募いただけます.
会員の皆様からの応募もお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■会員の活動
NHKラジオ第2 文化講演会 「恐竜絶滅の経緯」
11月25日(日)9:00〜10:00[再放送]12月1日(土)6:00〜7:00
講演者:海保邦夫会員(東北大学)
http://www4.nhk.or.jp/bunkakouenkai/
*************************************************
■科学的特性マップに関する対話型全国説明会(開催中)
主催:経済産業省資源エネルギー庁,NUMO
開催時期:〜12月18日(火)
場所:四万十市,能代市,京丹後市,豊橋市,浜松市,平塚市
プログラム:地層処分の説明,テーブルでのグループ質疑
https://www.numo.or.jp/taiwa/2018/
■第189回深田研談話会
「沿岸域の地下水挙動の理解に向けて」
12月7日(金)18:00〜19:30
会場:深田研地質研究所研修ホール(文京区本駒込)
講師:徳永朋祥(東京大学)
参加費無料
http://www.fgi.or.jp/?p=4188
(共)第28 回環境地質学シンポジウム
12 月7 日(金)〜8 日(土)
会場 :日本大学文理学部図書館3階オーバル・ホール
http://www.jspmug.org/
(後)兵庫県政150周年記念国際シンポジウム
「巨大恐竜、竜脚類の謎に迫る!」
12月8日(土)13:00〜17:30
場所:兵庫県立人と自然の博物館(兵庫県三田市弥生が丘)
定員300名(先着順)・参加費無料
http://www.hitohaku.jp/infomation/event/sauropoda-sympo2018.html
■第18回東北大学多元物質科学研究所研究発表会
12月13日(木)〜14日(金)
場所:東北大学片平さくらホール(仙台市青葉区)
参加申込締切:12月5日(水)
https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2018/10/event20181022-02.html
■日本地球惑星科学連合2018年大会
2019年5月26日(日)〜30日(木)
会場:千葉県 幕張メッセ国際会議場・国際展示場ホール8
東京ベイ幕張ホール
http://www.jpgu.org/meeting_2019/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・新潟大学災害・復興科学研究所教授公募(19/1/4)
・海洋研究開発機構
---地震津波海域観測研究開発センター海底観測技術開発グループポスドク
研究員公募(11/29)
---深海・地殻内生物圏研究分野特任技術職公募(12/14)
---生物地球化学研究分野主任研究員もしくは主任技術研究員公募(19/1/7)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.434(臨時)つくば特別大会最終案内
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.434 2018/11/29┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★目次
【1】つくば特別大会のお知らせ
【2】発表者の方へ(口頭・ポスター)
【3】【会員カード】を忘れずにお持ち下さい
【4】講演プログラム:座長の情報を追加しました
【5】自動車でおいでの方へ
【6】その他のご案内
【7】地質標本館特別展示:開催中
【8】「地質情報展」を実現のためのクラウドファンディングのお願い
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】つくば特別大会のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地質学会第125年学術大会(2018年つくば特別大会)
[日 程]2018年12月1日(土)〜2日(日)
[場 所]産業技術総合研究所 つくば本部・共用講堂(つくば市東1-1-1)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/guide
[参加費]
・一般(会員,非会員問わず):6,000円
・院生(会員,非会員問わず):4,000円
・学部学生(会員,非会員問わず),名誉会員,50年会員:無料
(注)札幌大会の事前および当日大会参加登録費をお支払い済みの方は,つく
ば特別大会での新たな参加費の徴収はありません.
(注)つくば特別大会用にあらたに講演要旨集は作成しません.必要に応じて
各自札幌大会の要旨集をご持参下さい.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】発表者の方へ(口頭・ポスター)
──────────────────────────────────
【口頭発表】
・1題15分(質疑応答と発表者の交代時間3〜5分を含む).ただしシンポジウム
とセッション招待講演は除きます.
・各口頭発表会場には液晶プロジェクターとPowerPoint対応のWindowsを用意し
ますが,ご自身のPCを使用頂くのがスムーズです(D-Sub15pinとHDMIのケーブ
ルを用意.HDMIを推奨).
・会場設置のPCを使用される場合は,USBメモリなどでファイルをインストール
して下さい.
【ポスター発表】
・掲示する際のチェスピンを会場に準備します.
・最低掲示時間帯(10:00〜17:00)は必ず掲示して下さい.掲示可能時間は
9:00〜18:00です.18:00には撤収して下さい.
・コアタイムは,両日とも13:00 〜14:20です.この時間は必ずポスターに立ち
会い,説明して下さい.
・PCやビデオを使用される場合,機器の準備は各自で行ってください.電源は
確保できませんので,予備バッテリーをご準備下さい.
・申込時にエントリーをした発表に対し,優秀ポスター賞が授与されます.最
低掲示時間帯(10:00〜17:00)に掲示していないポスターは,エントリーして
いても審査対象から除外されます.くれぐれもご注意下さい.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】【会員カード】を忘れずにお持ち下さい
──────────────────────────────────
大会会場での受付は「会員カード」で簡単に手続きいたします.
地質学会会員の方は,「会員カード」を忘れずに持参して下さい.
当日は会員カードを名札として,ホルダーに入れて,身につけて頂きます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】講演プログラム:座長の情報を追加しました
──────────────────────────────────
日程表・講演プログラム(口頭発表座長の情報を追加しました)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/program2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】自動車でおいでの方へ(入構方法など)
──────────────────────────────────
・正門より入構して下さい.正門以外の門は土日は閉鎖されています.
・入構時には正門で手続きが必要です.12/1午前中は,正門で学会担当者が「
駐車許可証」をお渡しします.「駐車許可証」を車内の見える所において駐車
して下さい.また許可書の下部を切り取り,必要事項を記入して学会受付(共
用講堂1階)に提出して下さい.
・駐車場は,案内図の指定の場所をご利用下さい.
詳しくは,https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/guide
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】お食事やその他のご案内
──────────────────────────────────
産総研内の食堂・コンビニは休みです.各自昼食のご用意をお願いします.
特に電車で来られる方は.つくば駅近辺のコンビニなどが便利です.詳しくは
大会HPをご確認下さい.
食事・宿泊ほかその他のご案内を下記に掲載しています.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/etal2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】地質標本館特別展示:開催中
──────────────────────────────────
地質標本館では,特別展「明治からつなぐ地質の知恵 北海道の地質−北海道命
名150周年−」を開催しています.中止となった今年の地質情報展のうち,バネ
ル展示部分をご紹介します.詳しくは,地質標本館ホームページをご覧下さい.
https://www.gsj.jp/Muse/exhibition/archives/2018/2018_winter.html
なお,地質情報展は,後援機関等の依頼もあり,3月29日(金)〜31日(日)の
日程で,札幌の「かでる2・7」で行います.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】「地質情報展」実現のためのクラウドファンディングのお願い
──────────────────────────────────
2018年の地質情報展は9月7日〜9日に札幌市で開催予定でしたが,開催前日の9
月6日未明に北海道胆振東部地震が発生し,やむなく中止といたしました.
北海道在住の方々から「楽しみにしていたのに残念」,「別の機会に開催しな
いのか?」というご連絡をたくさんいただき,また,道内の後援機関からも開
催を期待する声をいただきました.
このため,2019年3月29日(土)〜31日(日)の日程で地質情報展を開催するこ
ととし,経費を確保するため以下のクラウドファンディングに挑戦することに
しました.ご支援のほど,どうぞよろしくお願いいたします.
https://academist-cf.com/projects/89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.435 惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.435 2018/12/4┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】つくば特別大会終了
【2】第10回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
【3】一家に一枚ポスター:企画提案が採択されました
【4】2019年度会費払込について
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】つくば特別大会終了
──────────────────────────────────
つくば特別大会(12/1-2)は,約180件の講演と300名余りの参加者にお集りい
ただき,無事終了いたしました.
↓大会の様子はこちらから↓
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/tsukuba
つくば特別大会と札幌大会については,ニュース誌12月号に報告記事を掲載予
定です.
[お知らせ]いずれも学会事務局までご連絡下さい.
1)CPD参加証明書が必要な方は,大会終了後でも発行可能です.
2)忘れ物をお預かりしています:マフラー1本(チェック柄,茶系,カシミア)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第10回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
──────────────────────────────────
***応募締切:2019年1月末***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募フォームからでも
メール添付でもご応募いただけます.
会員の皆様からの応募もお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】一家に一枚ポスター:企画提案が採択されました
──────────────────────────────────
文部科学省では,国民の皆様が科学技術に触れる機会を増やし,科学技術に関
する知識を適切に捉えて柔軟に活用いただくことを目的として、毎年の科学技
術週間(4月)にあわせて「一家に1枚」ポスターを発行・配布しています.来
年
は地質学会からの『日本列島6億年(仮)』の企画提案が採択されました.
これまでのポスター企画はこちら(PDFダウンロード可)
http://stw.mext.go.jp/series.html
科学技術週間HP http://stw.mext.go.jp/
Facebook https://www.facebook.com/stw.mext/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2019年度会費払込について
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下さいますよ
うお願いいたします.
■2019年度分会費の引き落とし日:12月25日(火)です.
請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下
さい.
■自動引き落とし以外の方(お振り込み)
12月中旬に請求書兼郵便振替用紙をお送りいたします.折り返しご送金くださ
いますようお願いいたします.
学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)の方で,それぞ
れ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適用します.対象となる方は
忘れずに申請して下さい(※割引申請は毎年必要です).
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■関東支部功労賞募集
日本地質学会関東支部では,支部の顕彰制度に基づき2018年度も支部活動や
地質学を通して社会貢献された個人・団体を関東支部として顕彰いたします.
つきましては,下記の要領で支部会員からの推薦を募集します.
対象者:支部活動や地質学を通して広く社会貢献をされた関東支部内に在住
の個人・団体
*社会貢献や活動の評価においては,必ずしも学問的な成果を問うものではあ
りません.
公募期間:2018年12月10日〜2019年1月10日
選考期間:2019年 1月11日〜2019年1月31日
関東支部功労賞審査委員会(委員長:有馬 眞 前支部長)を設置
審査結果報告:NEWS誌、関東支部総会
推薦方法:対象者氏名,推薦者氏名,推薦理由(400字程度)を記入の上,関
東支部功労賞推薦としてメールもしくはFAXにて下記へお送りください.
推薦受付:神奈川県立生命の星・地球博物館 笠間友博 〒250-0031
小田原市入生田499
E-mail:kasama@nh.kanagawa-museum.jp ,FAX:0465-23-8846
これまでの関東支部功労賞受賞者(順不同敬称略)
2010年度:清水惠助
2011年度:府川宗雄,かわさき宙と緑の科学館
2012年度:神戸信和,松島義章,加瀬靖之,下仁田自然学校
2013年度:埼玉県立自然の博物館,早稲田大学高等学院理科部地学班
2014年度:千葉達朗,横須賀市立自然・人文博物館
2015年度:千葉県立中央博物館,神奈川県大井町・株式会社古川
2016年度:門田真人,遠藤 毅,栃木県立博物館
2017年度:故山本高司,中山俊雄*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■戦略的火星探査計画に対する意見募集中(12/11)
日本地質学会の皆様
宇宙理工学委員会 国際宇宙探査専門委員会
火星探査計画の科学探査タスクフォース
臼井寛裕(JAXA宇宙科学研究所)
現在、国際宇宙探査の枠組みで、火星有人探査に向けた火星探査計画の検討
が各国で行われています。日本は、火星衛星探査計画(MMX)に続き、火星無人
探査を計画し、国際宇宙探査における有意義な役割を果たすことが望まれてい
ます。このような背景を踏まえ、JAXA国際宇宙探査専門委員会では、火星探査
計画の科学探査タスクフォース(以下、火星探査TF)を設置し、将来の戦略的
火星探査計画の策定に向けた科学検討を早急に取りまとめることを目指してい
ます。
つきましては、火星探査に関心のある皆様より、科学的観点から広くご意見
を募りたいと思います(締切:2018年12月11日)。皆様から頂いたご意見をも
とに、火星探査TFが報告書にまとめ、2月上旬に皆様へと展開いたします。また、
2月下旬には報告書に対し皆様からのご意見をうかがうことを目的としたワーク
ショップを予定しております。
皆様からのご意見お待ちしております。
○提出書類の形式:
火星探査計画に関する以下の項目のいずれか1つあるいは複数に関し、A4一枚程
度の文書にまとめ、提出お願い申し上げます。なお、提案者(複数の場合は代
表者)の所属・氏名・連絡先の明記もよろしくお願いいたします。
(1)科学的観点から国際宇宙探査における日本の火星探査計画の提案
(2)海外で検討している火星サンプルリターンに対する助言
(3)火星探査に関わる先導する工学・確立すべき技術の提言
○参考情報:
内閣府 宇宙政策委員会 宇宙産業・科学技術基盤部会 宇宙科学・探査小委員会
第22回会合資料
http://www8.cao.go.jp/space/comittee/27-kagaku/kagaku-dai22/siryou3-1.pdf
http://www8.cao.go.jp/space/comittee/27-kagaku/kagaku-dai22/siryou3-2.pdf
http://www8.cao.go.jp/space/comittee/27-kagaku/kagaku-dai22/siryou3-3.pdf
○提出先:火星探査計画の科学探査タスクフォース事務局
○問い合わせ先:火星探査 タスクフォース長 臼井寛裕
■科学的特性マップに関する対話型全国説明会(開催中)
主催:経済産業省資源エネルギー庁,NUMO
開催時期:〜2019年2月4日(月)
場所:豊橋市,浜松市,平塚市ほか
プログラム:地層処分の説明,テーブルでのグループ質疑
https://www.numo.or.jp/taiwa/2018/
(共)第28 回環境地質学シンポジウム
12 月7 日(金)〜8 日(土)
会場 :日本大学文理学部図書館3階オーバル・ホール
http://www.jspmug.org/
(後)兵庫県政150周年記念国際シンポジウム
「巨大恐竜、竜脚類の謎に迫る!」
12月8日(土)13:00〜17:30
場所:兵庫県立人と自然の博物館(兵庫県三田市弥生が丘)
定員300名(先着順)・参加費無料
http://www.hitohaku.jp/infomation/event/sauropoda-sympo2018.html
■第217回地質汚染イブニングセミナー
12月21日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:藤巻 宏和(東北大学名誉教授・NPO法人日本地質汚染審査機構理事)
演題:「アスベストが引き起こした環境問題と建材中のアスベスト分析の問題点」
http://www.npo-geopol.or.jp
■地質学史懇話会
12月23日(日)13:30〜17:00
会場:北とぴあ8階806号室(JR京浜東北線王子駅下車3分)
演者:
1)長田敏明:ブレーキストン著(1883)「日本列島と大陸の古代の接続につい
ての動物学的痕跡」に関連する2・3の事柄
2)清地ゆき子:地質学者としての張 資平
■第53回日本水環境学会年会
2019年3月7日(木)〜9日(土)
開催地:山梨大学(山梨県甲府市)
http://www.jswe.or.jp/event/lectures/2018per.html
■日本地球惑星科学連合2018年大会
2019年5月26日(日)〜30日(木)
会場:千葉県 幕張メッセ国際会議場・国際展示場ホール8
東京ベイ幕張ホール
http://www.jpgu.org/meeting_2019/
■第29回国際地図学会議(ICC2019)
2019年7月15日(月・祝)〜20日(土)
会場:日本科学未来館・東京国際交流館
[募集に関わる日程]
2018年12月5日:論文(Full papers)投稿締切
2018年12月19日:要旨(Abstracts)投稿締切
2019年2月20日:査読結果通知
2019年4月3日:最終原稿提出締切
http://icc2019.org
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻准教授公募(1/31)
・2019年度深田研究助成(2/1)
・第50回(2019年度)三菱財団自然科学研究助成(19/1/9-2/6)
・第60回科学技術映像祭参加作品募集(1/25)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.436 2019年度会費払込について
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.436 2018/12/18┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2019年度会費払込について
【2】第10回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
【3】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されます
【4】2020年度地震火山こどもサマースクール開催地候補募集
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
【8】事務局年末年始休業(12/29〜1/6)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2019年度会費払込について
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下さいますよ
うお願いいたします.
■自動引き落しの方:引き落とし日は,12月25日(火)です.
請求書ならびに引き落とし通 知の発行は省略させていただきますのでご了承下
さい.これより以前に不足額がある場合には加算され,余剰金がある場合はそ
の分を減額して引き落としとなり ます.通帳には金額とともに「チシツカイヒ」
あるいは「フリカエ」,「SMBC」などと表示されますので,必ずご確認下さい.
■自動引き落とし以外の方(お振り込み)
請求書兼郵便振替用紙を発送いたしました.折り返しご送金くださいますよう
お願いいたします.
学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)の方で,それぞ
れ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適用します.対象となる方は
忘れずに申請して下さい(※割引申請は毎年必要です).
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第10回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
──────────────────────────────────
***応募締切:2019年1月末***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募フォームからでも
メール添付でもご応募いただけます.
会員の皆様からの応募もお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されます
──────────────────────────────────
募集期間:2018年12月20日(木)〜2019年2月8日(金)
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:例えば,,,地質学への顕著な貢献/地質学会の運
営と発展への貢献/教育現場や企業などでの活動を通じた地質学の普及と振興
への貢献など
*上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することはできませ
んが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
(名誉会員推薦委員会 佐々木和彦)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2020年度地震火山こどもサマースクール開催地候補募集
──────────────────────────────────
地震火山こどもサマースクールは,1999年夏から小・中・高校生を対象にはじ
まった行事で,現在,日本地震学会,日本火山学会,日本地質学会が共同で実
施する,地球科学関連では最大規模の体験学習講座です.今回,下記により20
20年度に実施する第21回の開催地を公募いたします.
応募資格:
地震火山こどもサマースクールの主旨に賛同し,現地事務局を設置できる団体.
なお応募が採択されたのち,三学会(地震・火山・地質学会)のスタッフと現
地事務局で実行委員会を結成し,この実行委員会がサマースクールを実施しま
す.
現地学校の夏休み期間中に1泊2日又は2日日程の通い形式の日程(土日が望ま
しい)でサマースクールを実施できること.
こどもとスタッフの宿泊に供することができる宿泊施設を確保可能なことが望
ましい.
募集期間:2019年1月21日(月)〜2月15日(金)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/news/n138.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■関東支部功労賞募集
公募締切:1月10日(木)
日本地質学会関東支部では,支部の顕彰制度に基づき2017年度も支部活動や
地質学を通して社会貢献された個人・団体を関東支部として顕彰いたします.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/faq/content0814.html#05
■関東支部:サイエンスカフェ
「磁場ニャン??いやいや,チバニアン」
1月27日(日)14:30〜16:00
会場:イタリアンレストランACQUA E SOLE(千葉市)
(ダイワロイネットホテル千葉中央 1階)
入場料:2,000円
https://sites.google.com/view/chibanian/
[西日本支部]
■平成30年度総会・第170回例会
3月2日(土)例会・総会
場所:長崎大学教育学部棟本館4階
講演申込締切:2月15日(金)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■科学的特性マップに関する対話型全国説明会(開催中)
主催:経済産業省資源エネルギー庁,NUMO
開催時期:〜2019年2月4日(月)
場所:神奈川,兵庫,長野ほか
プログラム:地層処分の説明,テーブルでのグループ質疑
https://www.numo.or.jp/taiwa/2018/
■第217回地質汚染イブニングセミナー
12月21日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:藤巻宏和(東北大学名誉教授・NPO法人日本地質汚染審査機構理事)
演題:「アスベストが引き起こした環境問題と建材中のアスベスト分析の問題点」
http://www.npo-geopol.or.jp
■地質学史懇話会
12月23日(日)13:30〜17:00
会場:北とぴあ8階806号室(JR京浜東北線王子駅下車3分)
演者:清地ゆき子:地質学者としての張 資平
(注)都合により長田氏の講演は中止となりました.
***** 2019年 *****
■日本古生物学会第168回例会
1月25日(金)〜27日(日)
会場:神奈川県立生命の星・地球博物館
http://www.palaeo-soc-japan.jp/events/
★地質情報展2019北海道—明治からつなぐ地質の知恵
3月29日(金)〜31日(日)
会場:かでる2・7(北海道札幌市)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/gyoji
▷「地質情報展」を実現のためのクラウドファンディングのお願い
https://academist-cf.com/projects/89
★日本地質学会主催:市民講演会
『動く大地のしくみを知り,地震・津波災害に備える』
3月30日(土)13:00〜
会場:かでる2・7(北海道札幌市)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/gyoji#koen
■日本地球惑星科学連合2018年大会
5月26日(日)〜30日(木)
会場:千葉県 幕張メッセ国際会議場・国際展示場ホール8
東京ベイ幕張ホール
http://www.jpgu.org/meeting_2019/
■第29回国際地図学会議(ICC2019)
7月15日(月・祝)〜20日(土)
会場:日本科学未来館・東京国際交流館
[募集に関わる日程]
1月8日:要旨(Abstracts)投稿締切(延長しました)
2月20日:査読結果通知
4月3日:最終原稿提出締切
http://icc2019.org
★ 日本地質学会第126年学術大会(2019山口)
9月23日(月・祝)〜25日(水)
場所:山口大学 吉田キャンパス(山口市吉田)
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・産総研ポスドク(イノベーションスクール生)公募(1/3)
・神戸大学大学院人間発達環境学研究科人間環境学専攻助教公募(5/10)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】事務局年末年始休業(12/29〜1/6)
──────────────────────────────────
学会事務局は,12月29日(土)〜1月6日(日)までお休みとなります.
新年7日(月)より通常営業となります.よろしくお願いいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.437 新年のご挨拶
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.437 2019/1/7┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】年頭の挨拶(会長 松田博貴)
【2】第10回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
【3】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されます
【4】2020年度地震火山こどもサマースクール開催地候補募集
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
【8】訃報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】年頭の挨拶(会長 松田博貴)
──────────────────────────────────
学会員の皆様に,2019年の年頭のご挨拶を申し上げます.
昨年,日本地質学会は創立125周年を迎えました.3年以上にわたって準備を進
めてまいりました周年事業も,5月18日に日本地質学会125周年記念式典を開催
し,各支部においては記念事業を実施するとともに,フォトコンテストでは記
念特別賞の授与などを行いました.また地質学雑誌における記念特集号の出版
も進めてまいりました.
続きをよむ、、、、http://www.geosociety.jp/outline/content0137.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第10回惑星地球フォトコンテスト:応募作品受付中
──────────────────────────────────
***応募締切:2019年1月31日(木)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募フォームからでも
メール添付でもご応募いただけます.
会員の皆様からの応募もお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されています
──────────────────────────────────
募集期間:2018年12月20日(木)〜2019年2月8日(金)
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:例えば,,,地質学への顕著な貢献/地質学会の運
営と発展への貢献/教育現場や企業などでの活動を通じた地質学の普及と振興
への貢献など
*上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することはできませ
んが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
(名誉会員推薦委員会 佐々木和彦)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2020年度地震火山こどもサマースクール開催地候補募集
──────────────────────────────────
地震火山こどもサマースクールは,1999年夏から小・中・高校生を対象にはじ
まった行事で,現在,日本地震学会,日本火山学会,日本地質学会が共同で実
施する,地球科学関連では最大規模の体験学習講座です.今回,下記により20
20年度に実施する第21回の開催地を公募いたします.
応募資格:
地震火山こどもサマースクールの主旨に賛同し,現地事務局を設置できる団体.
なお応募が採択されたのち,三学会(地震・火山・地質学会)のスタッフと現
地事務局で実行委員会を結成し,この実行委員会がサマースクールを実施しま
す.
現地学校の夏休み期間中に1泊2日又は2日日程の通い形式の日程(土日が望ま
しい)でサマースクールを実施できること.
こどもとスタッフの宿泊に供することができる宿泊施設を確保可能なことが望
ましい.
募集期間:2019年1月21日(月)〜2月15日(金)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/news/n138.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■関東支部功労賞募集
公募締切:1月10日(木)
日本地質学会関東支部では,支部の顕彰制度に基づき2017年度も支部活動や
地質学を通して社会貢献された個人・団体を関東支部として顕彰いたします.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/faq/content0814.html#05
■関東支部:サイエンスカフェ
「磁場ニャン??いやいや,チバニアン」
1月27日(日)14:30〜16:00
会場:イタリアンレストランACQUA E SOLE(千葉市)
(ダイワロイネットホテル千葉中央 1階)
入場料:2,000円
https://sites.google.com/view/chibanian/
[西日本支部]
■平成30年度総会・第170回例会
3月2日(土)例会・総会
場所:長崎大学教育学部棟本館4階
講演申込締切:2月15日(金)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地震本部ニュース2018冬号:平成30年北海道胆振東部地震の評価
〜地殻変動から探る震源断層〜ほか
https://www.jishin.go.jp/herpnews/
*************************************************
■科学的特性マップに関する対話型全国説明会(開催中)
主催:経済産業省資源エネルギー庁,NUMO
開催時期:〜2019年2月4日(月)
場所:神奈川,兵庫,長野ほか
プログラム:地層処分の説明,テーブルでのグループ質疑
https://www.numo.or.jp/taiwa/2018/
■平成30年度海洋情報研究成果発表会
「南海トラフ研究の最前線」
1月17日(木)13:10-18:15
会場:中央合同庁舎第4号館(千代田区霞ヶ関)
入場無料
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/jhd.html
■第30回GSJシンポジウム「千葉の地質と地震災害を知る」
1月18日(金)13:00〜17:20
会場:千葉市生涯学習センター
https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo30/index.html
■第218回地質汚染イブニングセミナー
1月25日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室(東京都北区王子)
講師:中山敏雄(元東京都土木技術研究所 地質研究室 主任研究員)
演題:「首都東京の地盤沈下・地下水位の変遷と現在の観測体制について」
http://www.npo-geopol.or.jp
■火山災害対策研究フォーラム
―東京の火山災害に備える―
2月9日(土)13:00〜16:00(受付開始:12:30)
場所:首都大学東京南大沢キャンパス講堂小ホール
事前申込・参加費不要
www.tmu-beyond.tokyo/volcanic-hazards-and-their-mitigation/wp-content/uploads/2018/12/Forum20190209poster.pdf
■第7回防災学術連携シンポジウム
「平成30年夏に複合的に連続発生した自然災害と学会調査報告」
主催:日本学術会議 防災減災学術連携委員会 防災学術連携体(56学会)
3月12日(火)10:00-17:30
場所:日本学術会議講堂
http://janet-dr.com/index.html
★地質情報展2019北海道—明治からつなぐ地質の知恵
3月29日(金)〜31日(日)
会場:かでる2・7(北海道札幌市)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/gyoji
▷「地質情報展」を実現のためのクラウドファンディングのお願い
https://academist-cf.com/projects/89
★日本地質学会主催:市民講演会
『動く大地のしくみを知り,地震・津波災害に備える』
3月30日(土)13:00〜
会場:かでる2・7(北海道札幌市)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/gyoji#koen
■日本地球惑星科学連合2018年大会
5月26日(日)〜30日(木)
会場:千葉県 幕張メッセ国際会議場・国際展示場ホール8
東京ベイ幕張ホール
http://www.jpgu.org/meeting_2019/
■第56回アイソトープ・放射線研究発表会
7月3日(水)〜5日(金)
会場:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
発表申込締切:2月28日(木)17:00
https://www.jrias.or.jp/
★ 日本地質学会第126年学術大会(2019山口)
9月23日(月・祝)〜25日(水)
場所:山口大学 吉田キャンパス(山口市吉田)
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・電力中央研究所地球工学研究所正職員1名(3/29)
・土佐清水ジオパーク構想専門員募集(1/31)
・東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教員(准教授)公募(2/28)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】訃報:杉崎隆一名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
杉崎隆一 名誉会員(元名古屋大学教授)が,平成31年1月3日にご逝去されまし
た(87歳).
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます.
なお,ご葬儀は既にご家族で執り行われたとのことです.
会長 松田 博貴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
唐詩にみる石と人の関わり:白居易の「青石」考
唐詩にみる石と人の関わり:白居易の「青石」考
正会員 石渡 明
1.王維の危石
唐詩において,石は自然(山水)を代表する点景として用いられることが多い.詩仏と呼ばれる盛唐の王維(おうい)(701?-761)の「香積寺(こうしゃくじ)を過る(よぎる)」には,「泉声(せんせい)は危石(きせき)に咽び(むせび),日色(にっしょく)は青松(せいしょう)に冷ややかなり」という,谷川の急流が切り立った岩に当たる音と,松林に差し込む落ち着いた日光の色を対置した,非凡な対句(ついく)がある.香積寺は唐の首都長安(陝西省西安(せんせいしょうシーアン))南方にあったが,唐朝の高級官僚だった彼は長安東方40kmの藍田(らんでん)に広大な別荘をもち(輞川荘(もうせんそう)),敷地内の各所に鹿柴(ろくさい),竹里館(ちくりかん)などと名づけて詩友裴迪(ばいてき)とともに遊歩し絶句を賦(ふ)した(輞川集).「空山人を見ず 但(た)だ人語の響くを聞く 返景深林に入り 復(ま)た青苔(せいたい)の上を照らす」(鹿柴),「独(ひと)り坐)ざ)す幽篁(ゆうこう)(竹やぶ)の裏(うち) 琴を弾じ復(ま)た長嘯(ちょうしょう) 深林人知らず 明月来たって相照(あいて)らす」(竹里館)などの名詩はここで作られた.近くには藍田山があり,古くから玉(ぎょく)を産した.そこの山寺を訪れた王維の「藍田山の石門精舎(しょうじゃ)」詩には,「澗芳(かんほう)人衣を襲い(おそい) 山月(さんげつ)石壁(せきへき)に映ず」という対句がある(谷間の花の匂いは人の衣にしみとおり,山の月は岩の壁に映る(まことにこの世の浄土である):都留春雄「王維」中国詩人選集6岩波書店1958).
2.杜甫の孤石
詩聖と呼ばれる盛唐の杜甫(とほ)(712-770)も,石の扱いは王維と同様である.「秋花危石の底(もと) 晩景臥鐘の辺」(秦州雑詩二十首の六),「杖(つえ)に倚(よ)りて孤石を看(み) 壺を傾けて浅沙に就く」(「春帰」唐詩選巻四,金沢大学の石渡ページに拙訳あり)のように石は景色の一部でしかなく,石の種類などどうでもよく,石と人の関わりは薄い.ただし,杜甫には「連山西南を抱き 石角皆な北に向かう」(「剣門」)のように,蜀(しょく)(四川省(しせんしょう))の南部の少数民族が反抗的なことを石の角に例えた例がある(黒川洋一「杜甫 上・下」中国詩人選集9・10岩波書店1958).
3.李白の盤石
一方,盛唐の李白(りはく)(701-762)は詩仙と呼ばれ,「白髪三千丈」(秋浦歌),「千里の江陵一日にして還(かえ)る」(早(つと)に白帝城を発す),「百年三万六千日 一日須(すべからく)傾くべし三百杯」(襄陽(じょうよう)歌)のような豪放磊落(らいらく)な詩句で有名だが,実は全く雰囲気の異なる「社会派」の詞も多く作っている.彼の「丁(てい)都護(とご)歌」は,運河建設に駆り出された人々の労苦を,昔その土地で善政を敷いた地方官を慕(した)う民謡の替え歌の形で表現し,石への恨みを借りて暗に皇帝の政策を批判している.(江蘇省(こうそしょう)の揚子江(ようすこう)下流域,現在の丹陽市の)「雲陽から運河を上る 両岸には商店が並んでいるが 呉牛(水牛)が月に喘(あえ)ぐほど 船を引くのは何と苦しいか 水は濁っていて飲めない 壺の水は半分が土になる (気晴らしに)一度(ひとたび)都護の歌を唱(うた)えば 心(こころ)摧(くだ)けて涙は雨の如し 万人が盤石を鑿(うが)つも 江滸(こうきょ)(揚子江岸)に達するに由(よ)し無し 君看(み)るや石の芒碭(ぼうとう)(荒涼・巨大)たるを 涙を掩(おお)っても悲しみは千古たり(千年も続く)(意訳)」(武部利男「李白 下」中国詩人選集8岩波書店1958に基づく).
中国では隋(ずい)の煬帝(ようだい)(569-618)が大規模な運河の開削工事を行ったが(白居易(はっきょい)の「隋堤柳」詩参照),運河や水路の工事は現在まで延々と続いている.唐代の運河の旅の様子は慈覚大師円仁(えんにん)(794-864;838-847は唐に滞在)の「入唐(にっとう)求法(ぐほう)巡礼行記(ぎょうき)」(東洋文庫)にもリアルに描かれている(ライシャワー著,田村完誓訳「円仁 唐代中国への旅」講談社学術文庫1999も参照).円仁の旅行記はマルコ・ポーロの「東方見聞録」(1298成立)より350年も前の中国の様子を客観的かつ詳細に伝える世界史的な記録である.なお,王維には,唐の高官になった阿倍(あべの)仲麻呂(なかまろ)(698-770;中国名晁衡(ちょうこう))が帰国する際の,長い序文つきの「秘書晁監の日本国に還(かえ)るを送る」という詩があり,李白は阿倍が帰路の海難事故で死んだと聞いて「晁卿衡を哭(こく)す」詩で追悼した.これらは日本と中国の2000年の交流史の中で最も美しい記念碑であろう.ただし,実は阿倍は救助され,その後長安に帰って復職し,そこで客死した.
江蘇省の石に戻ると,私たちが1990年頃に蘇魯(スールー)超高圧変成帯の調査をした時も,新しく開削された水路沿いの連続露頭が,平原の地質構造の把握にとても役立った(江蘇省東海県和堂地区,石渡ほか1992松本徰夫教授記念論文集393-409).しかし,人力だけで岩盤を掘削して運河を切り開く作業は,李白が言う通り大変な苦労だっただろう.地質図を見ると,丹陽市周辺の岩盤は,原生代,古生代,中生代の堆積岩と花崗岩からなっているようだ.
4.白居易の青石
王維の別荘に近い藍田(らんでん)山の石については,中唐の白居易(はっきょい)(白楽天,772-846)の「青石」(副題は「忠烈を激(はげ)ます也(なり)」)という長文の楽府(がふ)体の詞がある.この詞は,彼が朝廷の左拾遺(さしゅうい)(皇帝の過失を諫(いさ)める官)だった35歳頃の作と思われる.「青石は藍田山より出(い)ず 車を兼(つら)ねて運載し長安に来たる 工人磨琢(またく)して何に用いんと欲する 石は能(よ)く言わず我(われ)代わりに言わん」で始まり,青石に成り代わって「人家の墓石にはなりたくない 墓の土がまだ乾かぬうちに名はすでに滅ぶ 官家の徳政碑にはなりたくない 実録を彫らずに虚辞を彫る(意訳)」と言う.そして「顔真卿氏や段秀実氏の碑になりたい」と願う.顔氏は盛唐を揺るがした安禄山の反乱(755)に際して独り義軍を起こしてこれを討ち,魯国公に封じられたが,後に李希烈の反乱の懐柔宣諭(かいじゅうせんゆ)に赴(おもむ)き,李の誘惑や脅迫(きょうはく)に屈せず,李に殺された.段氏は朱芡(しゅせい)の反乱に加わるように誘われたが,怒って朱を殴(なぐ)ったため,朱の一味に殺された.「義心は石の若(ごと)く屹(きっ)として転ばず 死節(死を恐れぬ忠節)は石の若(ごと)く確(かく)として移らず」,「長く不忠不烈の臣をして 碑を観(み)て節(心根)を改め(顔氏と段氏の)人と為り(人格)を慕(した)わしめん」と謳(うた)い,最後は「人と為りを慕わしめ 君に事うることを勧めん」と結ぶ(高木正一「白居易 上・下」中国詩人選集12・13岩波書店1958に基づく.以下も同様).
「長恨歌(ちょうこんか)」や「琵琶行」等の感傷詩,「香鑪峰(こうろほう)下…」等の閑適(かんてき)詩で有名な白居易だが,若い頃は「青石」等の風諭(ふうゆ)詩を多数作った気鋭の硬派官僚だった.他方,王維は安禄山の反乱軍が長_安を占領した時,逃げ遅れて捕らえられ,心ならずも反乱軍の役人になった.反乱平定後,死罪になるべきところ,弟らの尽力で助命された.色々ある石から藍田の石を選んだ白居易の「青石」詞は,「不忠不烈の臣」として藍田ゆかりの王維が念頭にあっただろう.
それはさておき,青石は碑文を彫るのに適した平らで堅い石らしい.藍田山には玉(ネフライトまたはひすい)が産するそうなので,たぶん緑色(りょくしょく)片岩(へんがん)なのだろう.日本でも三波川(さんばがわ)帯の緑色片岩を秩父(ちちぶ)青石(あおいし),紀州(きしゅう)青石,伊予(いよ)青石等と言う.藍田は秦嶺(チンリン)・終南山(ジョンナンシャン)(Qinling-Zhongnanshan)世界ジオパークの根拠地の1つで,秦嶺造山帯は大別山(ターピエシャン)・蘇魯(スールー)地域に続く超高圧変成帯を含むが,藍田の主要テーマは藍田原人と花崗岩で,青石は含まない.私は第30回万国地質学会議の際,長安から約900km北西の祁連(チーリェン)山脈のオルドビス紀の藍閃石(らんせんせき)片岩(へんがん),エクロジャイト,オフィオライトを巡検した( 石渡1996; 地質雑, 102(10),XXVII-XXVIII, 918).そこは我々のモンゴルの古生代付加体の海洋底岩石の研究地(Erdenesaihan et al. 2013;JMPS, 108,303-325)とよく似た「天は蒼々(そうそう) 野は茫々(ぼうぼう) 風吹き草低(た)れて 牛羊を見る」(敕勒(ちょくろく)歌)風景だったが,秦嶺は王維の詩句の通り緑濃い山紫水明の地である.
5.白居易その後
白居易は王維の死の約10年後に生まれた人で,どちらも官途に就いて出世した自然派詩人だが,白居易が憧憬(しょうけい)を表明する先輩詩人は,同時代で年長の韋応物(い おうぶつ)(737?-804?)や400年前の陶淵明(とう えんめい)(365-427)であり,王維は無視している.今回青石の詞を考えてみて,その理由がわかったような気がする.30歳台の白居易は「胡旋の女」という詞で西域の歌舞の流行に警戒を促し,「両朱閣」という詞(副題は「仏寺の寖(ようや)く多きを刺(そし)るなり」)で仏教の流布を批判しており,左拾遺という仕事柄もあり国粋主義的だったので,外来の仏教を篤く信仰した王維を嫌っていたと思われる.王維のように朝廷の高級官僚でありながら反乱軍に投降,協力した人を,若くて忠誠心が強い白居易は許せなかったのだと思う.
ところが,白居易は39歳の時に3歳の愛嬢を失い(「念金鑾子(きんらんし)」,「病中哭金鑾子」詩参照),続いて母を失って喪に服し,この頃から次第に変節して仏教に帰依するようになった.そして44歳の時,ある官僚を刺した賊を捕らえるよう上疏したところ,これが越権行為と判断され,江州(江西省九江市)司馬に左遷された.46歳頃の「水に臨んで坐す」詩では,「昔は宮中の客となり 今は僧団の人となる 水に臨んで座禅をするに 昔を思えば前世のようだ(意訳)」と心境の変化を述べた.50代後半からは洛陽に住み,70歳の時には「在家出家」という詩で「中宵(ちゅうしょう)(夜半)入定(にゅうじょう)(瞑想)し跏趺(かふ)して坐し(座禅し) 女(むすめ)喚(よ)び妻呼べども都(すべ)て応(こた)えず」と嘯(うそぶ)き,71歳の「刑部尚書(ぎょうぶしょうしょ)(法務大臣)致仕(停年退官)」では「路に迷い心廻(めぐ)りて因(よ)って仏に向かい」と白状し,自分を「毘耶(びや)長者白尚書」と名づけている(正式な号は香山居士).毘耶長者は維摩詰(ゆいまきつ)の別称であり,なんと王維も自分を王摩詰と呼んでいた.人間は結局,成りたくないと思っていたものに成る実例である.なお,更に皮肉なことに,白居易74歳(死の前年)の845年,唐の第15代皇帝武宗は道教以外の一切の宗教を禁じ,「会昌の廃仏」を断行して,多数の仏寺を廃し僧尼(そうに)を還俗(げんぞく)させた.当時長安に滞在中の円仁はこのため帰国を余儀なくされたが,この前後の混乱と脱出行を詳細に記録したのは流石(さすが)である.翌年には武宗が死に,宣宗が復仏の詔を発したが,昔は仏教の流布を論難し,今は仏道の恩沢に安居する最晩年の白居易は,この騒動をどう思ったのだろうか.
追 記
香港の東京小子氏は2009年に「石頭(いしころ)他朝成翡翠(ひすい)―中国文化中『青石』的寓意」(http://www.weshare.hk/tokyoboy/articles/1867198)を発表し,唐詩における青石の用例を多数挙げ,特に白居易が様々な寓意を込めて青石を用いたと指摘し,青石は「中国文化の精神の中で,単に物質鑑賞的価値をもつだけでなく,特定の精神文明的寓意を含み,細心の観察と研究を要する」と述べている.しかし,小論で述べたような,白居易が青石に忠烈を語らせた理由や背景の考察はない.また,用例の中で,「雨余青石靄(かす)み 歳(とし)晩(く)れて緑苔(りょくたい)幽(くら)し」と詠んだ「王緯」は王維だと思う.そして,韓愈(かんゆ)の「岣嶁(こうろう)山」詩の「岣嶁山尖神禹碑 字青石赤形模奇」(尖を前とする本も)は,「字青く石赤くして形模(かたち)奇なり」と読み,この碑は赤い石で,青石ではないと思う(「青石に字すること赤く」とも読めるが,苦しい).
ところで,この神禹(禹王)碑の碑文は,石碑の碑文としては中国最古とされ,複雑な形の奇妙な字が9行77個並んでいて,「甲骨文研究家の郭沫若(かく まつじゃく)先生(日本に留学)が3年間研究したが3字しか読めなかった」と言われるほど難読である.韓愈は上に掲げた句に続いて,これらの字を「蝌蚪(おたまじゃくし)が身を拳(まる)め薤(らっきょう)の葉が披(ち)ったよう」と形容している.この碑文の内容は,(紀元前2000年頃に)中国最初の王朝「夏」を開いた禹王が黄河の治水に成功したことを讃える文章とされているが,禹王とは無関係の春秋時代(紀元前600年頃)の戦勝記念碑だという説もある.この碑は宋代に行方不明になったが,多数の拓本と複製が各地に残っている.しかし,2007年7月,湖南省衡陽市衡山県の農家から約1000年ぶりにこの碑が発見されたことが報道された.その石は桃の形の花崗岩とのことなので(http://www.china.com.cn/culture/txt/2007-08/06/content_8634638.htm), やはり青石ではなく赤い石なのだろう.
なお,禹王に関連した石碑(文命碑とも呼ぶ)は日本にも多数あり,水害を治めた神様の碑ということで,江戸時代から現代まで,堤防やダムの竣工記念(兼水害防除のおまじない)に設置された(村上三男2011「中国4000年前の治水神 禹王(文命)との“であい”」 www.jsokuryou.jp/Corner/shibu/03kanto/201001/kt1101_10-11.pdf).日本と中国の間には,古くから仏教,文学,政治,医学等の分野のみならず,このような地学・土木分野のつながりもあったのである.禹王の功績を讃える「地平天成」という語に由来する「平成」の世が押しつまった今年も,豪雨による深刻な水害と多くの犠牲者が出ており,「疎通」の方策など,まだ4000年前の禹王の治水に学ぶことが多いように思う(王敏2014「禹王と日本人 「治水神」がつなぐ東アジア」NHK Books 1226).
【geo-Flash】No.440 割引会費(院生・学部生)の申請は忘れずに!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.440 2019/2/5┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
【2】[2019年山口大会]トピックセッション募集
【3】日本地質学会名誉会員候補者の募集について(まもなく締切)
【4】紹介「セザンヌの地質学」
【5】JpGU2019:地質学会が共催するJpGUセッション
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月29日
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は,3月29日(金)です.
2019年度の割引会費を希望のかたは,忘れずにご提出ください(締切厳守).
■ 自動引落による納入
昨年12月25日にお届けの金融機関口座より引き落としさせていただきました.
通帳記帳等でご確認ください.請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略さ
せていただきますのでご了承ください.
■ 郵便振替用紙(またはゆうちょ銀行口座)からのお振り込み
12月中旬に請求書兼郵便振替用紙を発送しました.地質学会の会費は前納制で
すので,お早めにご送金ください.
2019年度割引会費申請や通常の会費払込について(災害に関連した会費の特別
措置についてもあわせてご案内しています)
http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2019年山口大会]トピックセッション募集
──────────────────────────────────
第126年学術大会(山口大会)は,西日本支部のご協力のもと,山口大学山口キャ
ンパスを会場として2019年9月23日(月・祝)〜25日(水)に開催されます.山
口県には,日本最大のカルスト地形である秋吉台や美しい海食海岸地形を示す
須佐ホルンフェルスなど,地質学的に重要かつ風光明媚なスポットが数多くあ
ります.また古生代から新生代までほぼ全ての地層が分布することから,地質
学に対する一般市民の関心も高いと考えられ,実りある学術大会の開催が期待
されます.山口大会では,多くのセッション開催を可能にするよう,必要十分
数の会場(部屋)を確保する予定です.ポスター会場については,近年のポス
ター発表重視の方向を満たすスペースを確保します.
募集締切:2019年3月12日(火)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/science/content0107.html
【大会に向けてのスケジュール(予定)】
3月12日(火):トピックセッション募集締切
5月末(ニュース誌5月号):大会予告記事(演題登録・講演要旨受付開始)
7月3日(水):演題登録・講演要旨受付締切/ランチョン・夜間集会締切
8月下旬(ニュース誌8月号):大会プログラム記事
8月19日(月):大会参加登録/巡検/懇親会参加申込締切
9月23日(月・祝)〜25日(水):第126年学術大会(山口大会)
2019山口プレサイトはこちら
http://www.geosociety.jp/science/content0106.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本地質学会名誉会員候補者の募集について(まもなく締切り)
──────────────────────────────────
募集期間:2018年12月20日(木)〜2019年2月8日(金)
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:例えば,,,地質学への顕著な貢献/地質学会の運
営と発展への貢献/教育現場や企業などでの活動を通じた地質学の普及と振興
への貢献など
*上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することはできませ
んが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
(名誉会員推薦委員会 佐々木和彦)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】紹介「セザンヌの地質学:サント・ヴィクトワール山への道」
──────────────────────────────────
「セザンヌの地質学:サント・ヴィクトワール山への道」
持田季未子著
青土社,定価1900円(税別)2017年11月30日発行,ISBN978-4-7917-7021-2 C0070
フランスの画家セザンヌ(Paul Cézanne;1839-1906)の画業を地質学というキーワードで捉え直した画論である.セザンヌは西欧美術史の中ではゴッホやゴーギャンとともに後期印象派とされ,ピカソ(1881-1973)からは「私の唯一の先生」と仰がれ(「セザンヌ 生涯と作品」永井隆則著,東京美術,2012),「画聖」あるいは「近代絵画の父」と称される.終生南仏プロヴァンスに拠点を置き,パリとの間を往復するだけでほとんど外国に出ることなく,生まれ育った南仏の自然の中で質素に暮らしながら,死の直前まで野外で描き続けた.本書カバー裏側には,ほころびが目立つ,絵具で汚れたジャケットを着て山高帽を被った老年のセザンヌが,野外で絵筆を持ち,山を睨みながらイーゼルに向かう写真が載っている.
セザンヌの絵は人物画,静物画,風景画など多彩だが,風景画にはサント・ヴィクトワール山(最高点は1011m)などの岩山や殺風景な石切り場を描いたものが多い.著者がよく引用する,セザンヌとの対話を書き連ねたガスケの本(「セザンヌ」ガスケ著,與謝野文子訳,岩波文庫青573-1, 2009)には,セザンヌ自身が地質学に言及している部分が数カ所ある.「風景をうまく描くには,私はまず地質学的な土台を見つけ出さなければならない」,「あくる朝になって,地質的な土台がゆっくり見えてきて,いくつもの層が出来上がり,それは私の絵の大きなプランだが,石のその骨格を頭の中で描く.(中略)この地質的な線,(中略)地球の尺度なる幾何学.やさしい感情におそわれる」,「私には地学を知る必要があるよ.サント・ヴィクトワールがどのように根を下ろしているか,土壌の地質学的な色彩,そういうことは心を動かすし,私をよくしてくれるのだ」などの言葉である.
著者はこれに,セザンヌの若い頃からの親友で地質・古生物学者のマリオン(Antoine-Fortuné Marion; 1846-1900)が大きな影響を与えたと見る.彼は若い頃セザンヌと一緒にエクス・アン・プロヴァンス周辺を歩いて絵を描き,その後マルセイユ大学地質学科(本書では動物学講座)教授になり,ついでマル
セイユの海洋生物研究所長(本書では自然史博物館長)になった人物であり,セザンヌはこの親友からよく地質学の話を聞いていた.ただし,セザンヌの風景画に,地質学的スケッチのような地層の重なりや地質構造の直接的表現はない.なお,マリオンは1870年代にぶどうの害虫駆除法を考案して西欧の広大なワイン畑を虫害から救い,フランス農学会から最高賞を受賞し,1880年にはレジオンドヌール勲章(シュバリエ)を受勲,1884年にフランス科学アカデミー会員に選出された(この段はウィキペディアによる).交友は彼の死まで続いたが(本書),化石好きの少年に過ぎなかった親友のこのような出世を,セザンヌはどんな気持ちで見ていたのだろうか.また,1885年にもう一人の親友ゾラとの友情が破綻したが,これはパリで人気小説家になったゾラが,自作の小説に落伍して自殺する画家を登場させたからである.しかしゾラの予想に反し,その後セザンヌの評価は高まって行く(永井隆則(前出)による).
内田園生(「セザンヌの画」みすず書房,1999)はセザンヌが少年時代にエクスの寄宿制の中学で学び,数人の親友らとともに近くの川で泳いだり,サント・ヴィクトワール山周辺を歩き回ったりして,「多感な少年時代に,自然に対して並々ならぬ愛情と畏敬の念をいだくようになった」と述べ,セザンヌを理解するにはこの原体験に注目すべきとしているが,著者はこの原体験よりも彼が後日マリオンから得た地質学的な認識と洞察を重視している.ただし,本書の題名は「地質学」だが,内容は画論であり,特にセザンヌの絵と彼が尊敬していたプッサン(Nicolas Poussin; 1594-1665)の絵との比較に多くのページを割いていて,主要文献に地質学の文献はなく,謝辞に地質研究者の名はない.
本書の帯には,「芸術と自然哲学の結節点」,「セザンヌ理解を大きく揺るがす,峻厳な『サント・ヴィクトワール山』連作.今この瞬間に死滅し,かつ再生する世界を捕獲せんとするセザンヌの果敢な試行を追う.大胆で挑戦的なセザンヌ論」とある.著者は,「サント・ヴィクトワール山はビベミュス石切り場という『都市文化の土台』,そして古代ローマ共和国の記憶が残る『歴史の土台』に直接つながっているだけでなく,遡って地域の自然史的記憶の底に沈む太古の海という『地質学的土台』から垂直に聳え立っていることを表現したかったのではないだろうか」と述べる(p. 96).そして,「山中に一人でこもって岩や山ばかりを相手にしていても,セザンヌは決して孤独な隠遁者などではない.山が立ち上がる太古の時から万物が風化して廃墟と化す終焉の時まで,長大な時間のもと,表面からは隠れているが実は刻一刻と変化し常に流転してやまない自然.そのような自然を見つめ,色と形で表現しようとする.セザンヌは,自然の本質とは何なのかを考えつめようとした(中略)際立って思索的な画家であった」と結論している(p. 186-187).
この本には,プロヴァンスの地質に関する記述は少ない.著者によると,エクス付近では白亜紀の地層が最も深部にあり,それは「泥灰岩(ドロマイト)」(p. 79)とのことだが,泥灰岩は仏語でマルヌmarne(英語はマールmarl)と言い,粘土(主成分はSiO2とAl2O3)と石灰(CaCO3)が混ざった堆積岩であり,ドロマイト(苦灰岩)の主成分は(Ca, Mg)CO3であって,これらは化学成分が異なる別の岩石である.この地域はアルプス山脈外縁のドフィネ帯(ヘルベチア帯の南方延長)に属し,泥灰岩と石灰岩はジュラ〜白亜紀の地層に多く,ドロマイトはトリアス紀の地層に多い.ただし,この地域の泥灰岩の多くは片岩(schist)になっている.また,地質図を見ると,サント・ヴィクトワール山周辺にはジュラ紀から始新世までの地層が分布するが,花崗岩(御影石)は分布しない.同山の写真を見ると,緩く傾斜した石灰岩層の岩山に見え(ウィキペディアも「石灰岩の山」とする),著者が言う「白い花崗岩の山塊」(p. 80)ではなさそうだ.
本書や関連書籍によってセザンヌの生涯を顧みると宮澤賢治(1896-1933)との共通点に気づく.どちらも地方の小都市で金融業を営む裕福な父親の愛を受けて育ちながら父親の希望する道には進まず,父親との間に確執がありながら成人後も経済的には父親に依存し(「銀河鉄道の父」門井慶喜著,講談社,2017),首都との間を往復しながら生まれ育った土地で活動し,少年時代に自然体験を深め自然を地質学的に理解する知識を持ちながら,一方は独自の色彩,画法,画面構成をもつ絵画で,他方は独自の言葉とリズムをもつ童話や詩で,あくまで自分自身の心の動きと主観的な対象把握に基づき,生涯をかけて独創的な芸術を追求し続けた.そして両者は地元の身近な低山を愛し,作品に描き続けた.
本書の中程には8枚のカラー口絵があり,うち7枚はセザンヌの絵で,その4枚にサント・ヴィクトワール山が描かれ(口絵3, 4, 7,8),カバー表側にも同山の絵がある.これらを見ていると,「生(せい)しののめの草いろの火を 高原の風とひかりにさゝげ」という賢治の詩句(原体剣舞連(はらたいけんばいれん))とともにdah-dah-dah-dah-dah-skodah-dahというリズムが聞こえてくるような気がする.本書の一読をお勧めする.
(石渡 明)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】JpGU2019:地質学会が共催するJpGUセッション
──────────────────────────────────
JpGU2019において地質学会は,関係学協会等と共催し下記のセッションを
予定しています。是非セッションへの投稿をご検討下さい。
******************************************
最終投稿締切:2月19日(火)17:00
http://www.jpgu.org/meeting_2019/
******************************************
地質学会が共催するJpGUセッション(セッションタイトル,代表世話人)
・湿潤変動帯の地質災害とその前兆(千木良雅弘)
・堆積・侵食・地形発達プロセスから読み取る地球表層環境変動(清家弘治
・活断層と古地震(小荒井衛)
・地域地質と構造発達史(大坪 誠)
・Oceanic and Continental Subduction Processes(Hafiz Ur REHMAN)
・地殻?マントル・コネクション(田村芳彦)
・変形岩・変成岩とテクトニクス(針金由美子)
・火山・火成活動と長期予測(及川輝樹)
・岩石・鉱物・資源(野崎 達生)
・アジア・モンスーンの進化と変動,新生代全球気候変化におけるモンスーンの位置づけ(山本正伸)
・ジオパーク(尾方隆幸)
・化学合成生態系と熱水・湧水・泥火山(ジェンキンズ ロバート)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[東北支部]
■2018年度支部総会
3月16日(土)〜17日(日)
場所:秋田大学教育文化学部
申込締切:3月4日(月)
要旨締切:3月11日(月)
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
[関東支部]
■2019年度支部総会・地質技術伝承講演会
4月13日(土)14:00〜16:45
場所:赤羽会館
講師:横井 悟(石油資源開発(株)技術本部フェロー)
「石油地質分野におけるunconventionalあるいは非石油的な話」
総会委任状締切:4月12日(金)18時
http://www.geosociety.jp/outline/content0197.html
[西日本支部]
■平成30年度総会・第170回例会
3月2日(土)例会・総会
場所:長崎大学教育学部棟本館4階
講演申込締切:2月15日(金)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
*************************************************
■科学的特性マップに関する対話型全国説明会(開催中)
主催:経済産業省資源エネルギー庁,NUMO
開催時期:〜2019年3月14日(木)
場所:埼玉,香川,和歌山,山形ほか
プログラム:地層処分の説明,少人数テーブルでのグループ質疑
https://www.numo.or.jp/taiwa/2018/
■第219回地質汚染イブニングセミナー
2月22日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:木村和也(医療地質研究所)
テーマ:東京圏の6年間継続測定からみる空間放射線量率の現状
−安全か、安心か、不安か−
http://www.npo-geopol.or.jp
■国際ワークショップ:東北大学「知のフォーラム」
「Continental Amalgamation and Stabilization of Northeast Asia:
Stories before the Stone Age」
2月21日(木)10:30〜17:30
2月22日(金)9:30〜15:30
場所:東北大学知の館(仙台市青葉区片平)
http://www.tfc.tohoku.ac.jp/event/4224.html
(後)東北大学東北アジア研究センター公開講演会
2月23日(土)13:00〜17:00
場所:東京エレクトロンホール宮城(仙台市青葉区国分町)
「地球生命の起源と進化:ヒトの誕生と現在から近未来の課題まで」
講師:丸山茂徳
http://www.cneas.tohoku.ac.jp/
■日本地学オリンピックとっぷ・レクチャー
3月10日(日)14:00〜17:00
場所:筑波銀行本部ビル 10階大会議室
(つくば市竹園1-7)
募集人数:150名(先着)*事前登録
http://jeso.jp/index.html
■第7回防災学術連携シンポジウム
「平成30年夏に複合的に連続発生した自然災害と学会調査報告」
主催:日本学術会議 防災減災学術連携委員会 防災学術連携体(56学会)
3月12日(火)10:00-17:30
場所:日本学術会議講堂
http://janet-dr.com/060_event/20190312/190312_000_leef.pdf
★地質情報展2019北海道—明治からつなぐ地質の知恵
3月29日(金)〜31日(日)
会場:かでる2・7(北海道札幌市)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/gyoji
▷「地質情報展」を実現のためのクラウドファンディングのお願い
https://academist-cf.com/projects/89
★日本地質学会主催:市民講演会
『動く大地のしくみを知り,地震・津波災害に備える』
3月30日(土)13:00〜
会場:かでる2・7(北海道札幌市)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/gyoji#koen
■日本地球惑星科学連合2018年大会
5月26日(日)〜30日(木)
会場:千葉県 幕張メッセ国際会議場・国際展示場ホール8
東京ベイ幕張ホール
予稿投稿最終締切:2月19日(火)17:00
http://www.jpgu.org/meeting_2019/
(後)第56回アイソトープ・放射線研究発表会
7月3日(水)〜5日(金)
会場:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
発表申込締切:2月28日(木)17:00
事前登録:7,000円、当日登録:9,000円、学生:無料 (いずれも税込)
※今回より要旨集はWeb版に移行いたしました
https://www.jrias.or.jp/
★ 日本地質学会第126年学術大会(2019山口)
9月23日(月・祝)〜25日(水)
場所:山口大学 吉田キャンパス(山口市吉田)
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・東京大学地震研究所2019年度共同利用地震火山災害軽減研究の公募(2/28)
・科学技術振興機構(JST)国際部:日本−ロシア共同研究課題募集(3/4)
・平成31年度苗場山麓ジオパーク学術研究奨励事業助成金募集(3/8)
・インドネシア・スンダ海峡津波関連国際緊急共同研究・調査支援プログラム募集
・2019年度「隠岐ユネスコ世界ジオパーク学術研究奨励事業」募集(5/31)
・海洋研究開発機構(JAMSTEC)
地震津波海域観測研究開発センター地震発生帯モニタリング研究G
---特任技術研究員(2/18)
---ポストドクトラル研究員(2/27)
数理科学・先端技術研究分野ポストドクトラル研究員(2/25)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.439 フォトコンテスト締切間近!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.439 2019/1/22┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
【2】第10回惑星地球フォトコンテスト:締切間近!!
【3】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されています
【4】2020年度地震火山こどもサマースクール開催地候補募集
【5】コラム 唐詩にみる石と人の関わり:白居易の「青石」考
【6】支部情報
【7】JPGU2019年大会に関するお知らせ
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月29日
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は,3月29日(金)です.
2019年度の割引会費を希望のかたは,忘れずにご提出ください(締切厳守).
■ 自動引落による納入
昨年12月25日にお届けの金融機関口座より引き落としさせていただきました.
通帳記帳等でご確認ください.請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略さ
せていただきますのでご了承ください.
■ 郵便振替用紙(またはゆうちょ銀行口座)からのお振り込み
12月中旬に請求書兼郵便振替用紙を発送しました.地質学会の会費は前納制で
すので,お早めにご送金ください.
2019年度割引会費申請や通常の会費払込について(災害に関連した会費の
特別措置についてもあわせてご案内しています)
http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第10回惑星地球フォトコンテスト:締切間近!!
──────────────────────────────────
***応募締切:2019年1月31日(木)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募フォームからでも
メール添付でもご応募いただけます.
会員の皆様からの応募もお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されています
──────────────────────────────────
募集期間:2018年12月20日(木)〜2019年2月8日(金)
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:例えば,,,地質学への顕著な貢献/地質学会の運
営と発展への貢献/教育現場や企業などでの活動を通じた地質学の普及と振興
への貢献など
*上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することはできませ
んが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
(名誉会員推薦委員会 佐々木和彦)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2020年度地震火山こどもサマースクール開催地候補募集
──────────────────────────────────
地震火山こどもサマースクールは,1999年夏から小・中・高校生を対象にはじ
まった行事で,現在,日本地震学会,日本火山学会,日本地質学会が共同で実
施する,地球科学関連では最大規模の体験学習講座です.今回,下記により20
20年度に実施する第21回の開催地を公募いたします.
応募資格:
地震火山こどもサマースクールの主旨に賛同し,現地事務局を設置できる団体.
なお応募が採択されたのち,三学会(地震・火山・地質学会)のスタッフと現
地事務局で実行委員会を結成し,この実行委員会がサマースクールを実施しま
す.
現地学校の夏休み期間中に1泊2日又は2日日程の通い形式の日程(土日が望ま
しい)でサマースクールを実施できること.
こどもとスタッフの宿泊に供することができる宿泊施設を確保可能なことが望
ましい.
募集期間:2019年1月21日(月)〜2月15日(金)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/news/n138.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】コラム 唐詩にみる石と人の関わり:白居易の「青石」考
──────────────────────────────────
唐詩にみる石と人の関わり:白居易の「青石」考唐詩において,石は自然(山
水)を代表する点景として用いられることが多い.詩仏と呼ばれる盛唐の王維
(701?-761)の「香積寺を過る」には,「泉声は危石に咽び,日色は青松に冷
ややかなり」という,谷川の急流が切り立った岩に当たる音と,松林に差し込
む落ち着いた日光の色を対置した,非凡な対句がある.香積寺は唐の首都長安
(陝西省西安)南方にあったが,唐朝の高級官僚だった彼は長安東方40kmの藍
田に広大な別荘をもち(輞川荘),敷地内の各所に鹿柴,竹里館などと名づけ
て詩友裴迪とともに遊歩し絶句を賦した(輞川集).「空山人を見ず 但だ人
語の響くを聞く 返景深林に入り 復た青苔の上を照らす」(鹿柴),「独り
坐す幽篁(竹やぶ)の裏琴を弾じ復た長嘯 深林人知らず 明月来たって相照
らす」(竹里館)などの名詩はここで作られた.近くには藍田山があり,古く
から玉を産した.
つづきを読む、、、http://www.geosociety.jp/faq/content0818.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[東北支部]
■2018年度支部総会
3月16日(土)〜17日(日)
場所:秋田大学教育文化学部
申込締切:3月4日(月)
要旨締切:3月11日(月)
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
[西日本支部]
■平成30年度総会・第170回例会
3月2日(土)例会・総会
場所:長崎大学教育学部棟本館4階
講演申込締切:2月15日(金)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】JPGU2019年大会に関するお知らせ
──────────────────────────────────
日本地球惑星科学連合(JPGU2019年大会)関連の情報をお知らせします。
◆予稿投稿・参加登録が開始されています。
早期締切:2月 4日(月)23:59 (早期投稿料3,240円(税込))
最終締切:2月19日(火)17:00 (通常投稿料4,320円(税込))
http://www.jpgu.org/meeting_2019/presentation.php
◆地質学会提案等のセッションが多数企画されています。
会員の皆様からの投稿をお待ちしています。
http://www.jpgu.org/meeting_2019/program.php#program_menu12
◆学生旅費助成
申請資格
・申請時点で学生(高校生から大学院生)であること
・第一著者かつ発表者であること(ポスター可)
申請受付締切 2019年2月21日(木)
http://www.jpgu.org/meeting_2019/for_student.php
◆今後の予定
2月 4日(月)23:59 早期投稿締切
2月19日(火)17:00 投稿最終締切
3月13日(水) 採択通知
3月14日(木) プログラム公開
5月 8日(水)23:59 早期参加登録締切
5月17日(金) 予稿PDF公開
大会ウェブサイト http://www.jpgu.org/meeting_2019
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■道総研 環境・地質研究本部 地質研究所ニュース
平成30年北海道胆振東部地震の災害調査...など
http://www.hro.or.jp/list/environmental/research/gsh/publication/gshnews/gshnews02/vol34_no3.pdf
*************************************************
■科学的特性マップに関する対話型全国説明会(開催中)
主催:経済産業省資源エネルギー庁,NUMO
開催時期:〜2019年2月4日(月)
場所:神奈川,兵庫,長野ほか
プログラム:地層処分の説明,テーブルでのグループ質疑
https://www.numo.or.jp/taiwa/2018/
■第7回防災学術連携シンポジウム
「平成30年夏に複合的に連続発生した自然災害と学会調査報告」
主催:日本学術会議 防災減災学術連携委員会 防災学術連携体(56学会)
3月12日(火)10:00-17:30
場所:日本学術会議講堂
http://janet-dr.com/060_event/20190312/190312_000_leef.pdf
★地質情報展2019北海道—明治からつなぐ地質の知恵
3月29日(金)〜31日(日)
会場:かでる2・7(北海道札幌市)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/gyoji
▷「地質情報展」を実現のためのクラウドファンディングのお願い
https://academist-cf.com/projects/89
★日本地質学会主催:市民講演会
『動く大地のしくみを知り,地震・津波災害に備える』
3月30日(土)13:00〜
会場:かでる2・7(北海道札幌市)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/gyoji#koen
■日本地球惑星科学連合2018年大会
5月26日(日)〜30日(木)
会場:千葉県 幕張メッセ国際会議場・国際展示場ホール8
東京ベイ幕張ホール
http://www.jpgu.org/meeting_2019/
(後)第56回アイソトープ・放射線研究発表会
7月3日(水)〜5日(金)
会場:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
発表申込締切:2月28日(木)17:00
https://www.jrias.or.jp/
★ 日本地質学会第126年学術大会(2019山口)
9月23日(月・祝)〜25日(水)
場所:山口大学 吉田キャンパス(山口市吉田)
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・首都大学東京火山災害研究センター特任研究員公募2名(2/15)
・丹波市任期付職員(丹波竜化石工房「ちーたんの館」教育普及専門員)(2/15)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.441 山口大会:トピックセッション募集中
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.441 2019/2/19┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[2019年山口大会]トピックセッション募集
【2】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
【3】支部情報
【4】その他のお知らせ
【5】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2019年山口大会]トピックセッション募集
──────────────────────────────────
第126年学術大会(山口大会)は,西日本支部のご協力のもと,山口大学山口キャ
ンパスを会場として2019年9月23日(月・祝)〜25日(水)に開催されます.山
口県には,日本最大のカルスト地形である秋吉台や美しい海食海岸地形を示す
須佐ホルンフェルスなど,地質学的に重要かつ風光明媚なスポットが数多くあ
ります.また古生代から新生代までほぼ全ての地層が分布することから,地質
学に対する一般市民の関心も高いと考えられ,実りある学術大会の開催が期待
されます.山口大会では,多くのセッション開催を可能にするよう,必要十分
数の会場(部屋)を確保する予定です.ポスター会場については,近年のポス
ター発表重視の方向を満たすスペースを確保します.
---------------------------------------
募集締切:2019年3月12日(火)
---------------------------------------
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/science/content0107.html
【大会に向けてのスケジュール(予定)】
3月12日(火):トピックセッション募集締切
5月末(ニュース誌5月号):大会予告記事(演題登録・講演要旨受付開始)
7月3日(水):演題登録・講演要旨受付締切/ランチョン・夜間集会締切
8月下旬(ニュース誌8月号):大会プログラム記事
8月19日(月):大会参加登録/巡検/懇親会参加申込締切
9月23日(月・祝)〜25日(水):第126年学術大会(山口大会)
2019山口プレサイトはこちら
http://www.geosociety.jp/science/content0106.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月29日
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は,3月29日(金)です.
2019年度の割引会費を希望のかたは,忘れずにご提出ください(締切厳守).
■ 自動引落による納入
昨年12月25日にお届けの金融機関口座より引き落としさせていただきました.
通帳記帳等でご確認ください.請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略さ
せていただきますのでご了承ください.
■ 郵便振替用紙(またはゆうちょ銀行口座)からのお振り込み
昨年12月中旬に請求書兼郵便振替用紙を発送しました.地質学会の会費は
前納制ですので,お早めにご送金ください.
2019年度割引会費申請や通常の会費払込について(災害に関連した会費の特別
措置についてもあわせてご案内しています)
http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】支部情報
──────────────────────────────────
[東北支部]
■2018年度支部総会
3月16日(土)〜17日(日)
場所:秋田大学教育文化学部
申込締切:3月4日(月)
要旨締切:3月11日(月)
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
[関東支部]
■2019年度支部総会・地質技術伝承講演会
4月13日(土)14:00〜16:45
場所:赤羽会館
講師:横井 悟(石油資源開発(株)技術本部フェロー)
「石油地質分野におけるunconventionalあるいは非石油的な話」
総会委任状締切:4月12日(金)18時
http://www.geosociety.jp/outline/content0197.html
[西日本支部]
■平成30年度総会・第170回例会
3月2日(土)例会・総会
場所:長崎大学教育学部棟本館4階
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■箱根ジオパーク展
3月2日(土)〜5月12日(日)
場所:神奈川県立生命の星・地球博物館)
http://www.hakone-geopark.jp/information/kikakutenH31.html
*************************************************
■科学的特性マップに関する対話型全国説明会(開催中)
主催:経済産業省資源エネルギー庁,NUMO
開催時期:〜2019年3月14日(木)
場所:埼玉,香川,和歌山,山形ほか
プログラム:地層処分の説明,少人数テーブルでのグループ質疑
https://www.numo.or.jp/taiwa/2018/
■第219回地質汚染イブニングセミナー
2月22日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室
講師:木村和也(医療地質研究所)
テーマ:東京圏の6年間継続測定からみる空間放射線量率の現状
−安全か、安心か、不安か−
http://www.npo-geopol.or.jp
■国際ワークショップ:東北大学「知のフォーラム」
「Continental Amalgamation and Stabilization of Northeast Asia:
Stories before the Stone Age」
2月21日(木)10:30〜17:30
2月22日(金)9:30〜15:30
場所:東北大学知の館(仙台市青葉区片平)
http://www.tfc.tohoku.ac.jp/event/4224.html
(後)東北大学東北アジア研究センター公開講演会
2月23日(土)13:00〜17:00
場所:東京エレクトロンホール宮城(仙台市青葉区国分町)
「地球生命の起源と進化:ヒトの誕生と現在から近未来の課題まで」
講師:丸山茂徳
http://www.cneas.tohoku.ac.jp/
■日本地学オリンピックとっぷ・レクチャー
3月10日(日)14:00〜17:00
場所:筑波銀行本部ビル 10階大会議室(つくば市竹園1-7)
募集人数:150名(先着)*事前登録
http://jeso.jp/index.html
■第7回防災学術連携シンポジウム
「平成30年夏に複合的に連続発生した自然災害と学会調査報告」
3月12日(火)10:00〜17:30
場所:日本学術会議講堂
http://janet-dr.com/060_event/20190312/190312_000_leef.pdf
■学術会議公開シンポジウム:「地理総合」で何が変わるか
3月21日(木・祝)9:00〜15:00
会場:専修大学生田キャンパス10号館1階
参加無料・事前申込不要
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/274-s-0321.pdf
★地質情報展2019北海道—明治からつなぐ地質の知恵
3月29日(金)〜31日(日)
会場:かでる2・7(北海道札幌市)
「地質情報展」を実現のためのクラウドファンディングは,
目標金額に達成しました!ご支援ありがとうございました!
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/gyoji
★日本地質学会主催:市民講演会
『動く大地のしくみを知り,地震・津波災害に備える』
3月30日(土)13:00〜
会場:かでる2・7(北海道札幌市)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/gyoji#koen
■日本地球惑星科学連合2018年大会
5月26日(日)〜30日(木)
会場:千葉県 幕張メッセ国際会議場・国際展示場ホール8
東京ベイ幕張ホール
http://www.jpgu.org/meeting_2019/
(後)第56回アイソトープ・放射線研究発表会
7月3日(水)〜5日(金)
会場:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
発表申込締切:2月28日(木)17:00
事前登録:7,000円、当日登録:9,000円、学生:無料 (いずれも税込)
※今回より要旨集はWeb版に移行いたしました
https://www.jrias.or.jp/
★ 日本地質学会第126年学術大会(2019山口)
9月23日(月・祝)〜25日(水)
場所:山口大学 吉田キャンパス(山口市吉田)
http://www.geosociety.jp/science/content0106.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・三笠ジオパーク専門員募集(3/31)
・ゆざわジオパーク専門員募集(3/8)
・アポイ岳ジオパーク研究者支援(随時受付中)
・2019年度「深田野外調査助成」募集(4/22)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.442 第10回惑星地球フォトコンテスト:審査結果発表!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.442 2019/3/5┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[2019年山口大会]トピックセッション募集
【2】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
【3】地質学雑誌からのお知らせ
【4】Island Arc 編集委員会より
【5】第10回惑星地球フォトコンテスト:審査結果発表!
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2019年山口大会]トピックセッション募集
──────────────────────────────────
第126年学術大会(山口大会)は,西日本支部のご協力のもと,山口大学山口キャ
ンパスを会場として2019年9月23日(月・祝)〜25日(水)に開催されます.山
口県には,日本最大のカルスト地形である秋吉台や美しい海食海岸地形を示す
須佐ホルンフェルスなど,地質学的に重要かつ風光明媚なスポットが数多くあ
ります.また古生代から新生代までほぼ全ての地層が分布することから,地質
学に対する一般市民の関心も高いと考えられ,実りある学術大会の開催が期待
されます.山口大会では,多くのセッション開催を可能にするよう,必要十分
数の会場(部屋)を確保する予定です.ポスター会場については,近年のポス
ター発表重視の方向を満たすスペースを確保します.
---------------------------------------
募集締切:2019年3月12日(火)
---------------------------------------
詳しくは、http://www.geosociety.jp/science/content0107.html
【大会に向けてのスケジュール(予定)】
3月12日(火):トピックセッション募集締切
5月末(ニュース誌5月号):大会予告記事(演題登録・講演要旨受付開始)
7月3日(水):演題登録・講演要旨受付締切/ランチョン・夜間集会締切
8月下旬(ニュース誌8月号):大会プログラム記事
8月19日(月):大会参加登録/巡検/懇親会参加申込締切
9月23日(月・祝)〜25日(水):第126年学術大会(山口大会)
2019山口プレサイトはこちら
http://www.geosociety.jp/science/content0106.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月29日
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は,3月29日(金)です.
2019年度の割引会費を希望のかたは,忘れずにご提出ください(締切厳守).
2019年度割引会費申請や通常の会費払込について(災害に関連した会費の特別
措置についてもあわせてご案内しています)
http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】地質学雑誌からのお知らせ
──────────────────────────────────
(1)125巻2月号が刊行されました
「水路実験による陸上津波堆積物研究の現状と今後の可能性」(総説)山口直
文 ほか計6編
最新号目次はこちら,http://www.geosociety.jp/publication/content0092.html
(2)次の論文がAccepted Manuscriptとして公開になりました
「イングランド北東部フランボロヘッドの上部白亜系チョーク層の断崖」(口
絵)藤内智士ほか (2/26公開)https://sub.geosociety.jp/user.php
(注意:会員ページへのログインが必要です)
(3)124巻12月号がまもなくJ-STAGEで公開されます(3/15公開予定)
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/-char/ja
◆125 周年記念特集 付加体地質中に残る深海堆積相の研究:進展と展望
「付加体深海堆積相における中・古生代微化石研究の最近の進展:放散虫およ
びコノドント研究の現状と将来の展望」(総説)上松佐知子・鎌田祥仁
ほか計7編
目次はこちら,http://www.geosociety.jp/publication/content0092.html#124-12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】Island Arc 編集委員会より
──────────────────────────────────
Wileyの提携しているResearch Square社のサービスに,科学のバックグラウン
ドを持つ作家・声優・アニメーターら専門チームによって制作されるビデオア
ブストラクト(video abstract)があります.ビデオアブストラクトは,論文
の内容を広く分かりやすく紹介する数分間の動画で,YouTubeや研究室ホームペー
ジなどで公開することにより,研究成果を多くの人に知ってもらうのに役立ち
ます.Island Arcの掲載論文サイトでは論文本体の右側にビデオアブストラク
トを添えることが可能であり,これを提供することで,論文閲覧者はビデオに
よる解説も視聴することができます.
Island Arcでこのサービスを初めて利用したのが西之島論文(Tamura et al.,
2018, https://doi.org/10.1111/iar.12285)です.何が問題で,どのような結
論が導かれたのかをアニメーションと現地映像などで平易に解説しており,誌
面だけではなかなか会得しがたい大陸形成のダイナミズムを分かりやすく伝え
ています.
ビデオアブストラクトは,今後,Island Arcから出版される様々な研究成果の
宣伝に資するだけでなく,地質科学の魅力をより多くの人々に伝えることがで
きるかもしれません,大いに活用してください.
https://www.researchsquare.com/videos/wiley/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第10回惑星地球フォトコンテスト:審査結果発表!
──────────────────────────────────
2/25に審査会(白尾元理審査委員長)が開催され,応募作品全348作品のうち,
入選12点,佳作4点が決定しました.作品画像は近日学会HP上にて公開の予定
です.
最優秀賞:1点(賞金5万円)
「月下の大火口」横江憲一(北海道)
優秀賞:2点(賞金各2万円)
「枕と星屑と」森田康平(東京都)
「月明かりのメテオラの谷」川口雅也(東京都)
ジオパーク賞:1点(賞金2万円)
「新緑の六方の滝」齋藤敏雄(神奈川県)
日本地質学会会長賞:1点(賞金1万円)
「ルービックキューブ」島村哲也(茨城県)
ジオ鉄賞:1点(賞金1万円)
「川底を抜けて」桑田憲吾(東京都)
その他の結果は,http://www.photo.geosociety.jp/
下記の通り表彰式,展示会を開催予定です.
【表彰式】(作品展示,白尾委員長の講評など)
5月25日(土)11:00〜12:30(時間は多少変更になる場合があります)
会場:北とぴあ 第2研修室(東京都北区王子)
【作品展示予定】今後予定が追加されます.随時HPに掲載予定です
・東京パークスギャラリー(上野)
5月14日(火)〜5月19日(日)
場所:上野恩賜公園 上野グリーンサロン内(台東区上野公園7-47)
https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/facilities038.html#tkp-secton-02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[東北支部]
■2018年度支部総会
3月16日(土)〜17日(日)
場所:秋田大学教育文化学部
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
[関東支部]
■2019年度支部総会・地質技術伝承講演会
4月13日(土)14:00〜16:45
場所:赤羽会館(東京都北区)
講師:横井 悟(石油資源開発(株)技術本部フェロー)
「石油地質分野におけるunconventionalあるいは非石油的な話」
総会委任状締切:4月12日(金)18時
http://www.geosociety.jp/outline/content0197.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■科学的特性マップに関する対話型全国説明会(開催中)
主催:経済産業省資源エネルギー庁,NUMO
開催時期:〜2019年3月14日(木)
場所:埼玉,香川,和歌山,山形ほか
プログラム:地層処分の説明,少人数テーブルでのグループ質疑
https://www.numo.or.jp/taiwa/2018/
■日本地学オリンピックとっぷ・レクチャー
3月10日(日)14:00〜17:00
場所:筑波銀行本部ビル 10階大会議室(つくば市竹園1-7)
募集人数:150名(先着)*要事前登録
http://jeso.jp/index.html
■第7回防災学術連携シンポジウム
「平成30年夏に複合的に連続発生した自然災害と学会調査報告」
3月12日(火)10:00〜17:30
場所:日本学術会議講堂
*インターネットの同時中継も行います.
https://janet-dr.com/index.html
■第3回ふじのくに地球環境史ミュージアム・静岡県富士山世界遺産センター
合同国際シンポジウム「島嶼環境文明にみる地球の未来」
3月16日(土)〜18日(月)
場所 静岡県コンベンションアーツセンター
「グランシップ」11階会議ホール「風」(JR東静岡駅南口徒歩3分)
参加費無料
https://www.fujimu100.jp/sympo2019/
■第220回地質汚染イブニングセミナー
3月29日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ901会議室(東京都北区)
講師:川辺孝幸(山形大学教授)
演題:退官記念講義/日本列島の地質構造と地質災害そして減災(仮)
http://www.npo-geopol.or.jp
★地質情報展2019北海道—明治からつなぐ地質の知恵
3月29日(金)〜31日(日)
会場:かでる2・7(北海道札幌市)
「地質情報展」を実現のためのクラウドファンディングのお願い
目標金額達成しました!ご支援ありがとうございました!
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/gyoji
★日本地質学会主催:市民講演会
『動く大地のしくみを知り,地震・津波災害に備える』
3月30日(土)13:00〜
会場:かでる2・7(北海道札幌市)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/gyoji#koen
■日本地球惑星科学連合2018年大会
5月26日(日)〜30日(木)
会場:千葉県 幕張メッセ国際会議場・国際展示場ホール8
東京ベイ幕張ホール
http://www.jpgu.org/meeting_2019/
■第222回地質汚染イブニングセミナー
5月29日(水)18:30〜20:30
場所:北とぴあ9階901会議室 (東京都北区)
講師:門間聖子(応用地質株式会社 技術本部技師長室 技師長)
演題:自然由来の重金属等に関する環境リスクマネジメントと改正土壌汚染対策法
http://www.npo-geopol.or.jp
(後)第56回アイソトープ・放射線研究発表会
7月3日(水)〜5日(金)
会場:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
https://www.jrias.or.jp/
★ 日本地質学会第126年学術大会(2019山口)
9月23日(月・祝)〜25日(水)
場所:山口大学 吉田キャンパス(山口市吉田)
http://www.geosociety.jp/science/content0106.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0168.html#now
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・静岡大学理学部地球科学科:准教授,講師または助教(女性1名)(5/10)
・JAMSTEC数理科学・先端技術研究分野特任研究員/特任技術研究員/特任技術職(いずれか1名)(3/29)
・JAMSTEC数理科学・先端技術研究分野ポストドクトラル研究員(3/11)
・第16回日本学術振興会賞候補者推薦募集(学会締切3/20)
・土佐清水ジオパーク構想活動支援事業(4/26)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
第10回フォトコン_最優秀
第10回惑星地球フォトコンテスト入選作品
最優秀賞:月下の大噴煙
写真:横江 憲一(北海道)
撮影場所:北海道 雌阿寒岳 頂上附近の稜線
【撮影者より】
2018年11月17日は,オンネトー国設野営場から雌阿寒岳を目指して登山しました.登山開始から深夜です.実は前週も同じ時間帯の雌阿寒岳に登っており,2週連続です.雌阿寒岳から阿寒富士にかけての稜線にさしかかった時,いつもと違い噴煙が多い事に気がつきました.11月20日以降にポンマチネシリ想定火口を震源とする火山性地震が増加し,23日は噴火警戒レベルが2に引き上げられたので,その前兆かもしれません.写真左側の噴煙がポンマチネシリ想定火口,右側の噴煙が中マチネシリ想定火口.左側の阿寒富士から雌阿寒岳の頂上までの雄大な地形を入れるため,フルサイズの魚眼レンズを使用しました.撮影は,強風・微風の中,激しく舞い上がる両噴煙でしたが,月が見えた一瞬,シャッターを切りました.手前側の赤色から黒色の火山土質,空の青さ,星,氷結した青沼など質感も表現してみました.
【審査委員長講評】
阿寒岳は日本百名山の1つで,月齢10の月が雌阿寒岳の火口を逆光気味に照らしています.魚眼レンズを使用していますが水平にセッテングしているために歪みがなく,たなびく白煙,その向こうに見える阿寒富士,雲海の上に浮かぶ月と星々,広がりがあって気持ちの良い作品です.4500万画素の高画素カメラとシャープなレンズの組み合わせで撮影されており,大伸ばしでの作品をじっくり見たいものです.
【地質的背景】
雌阿寒岳(標高1,499m)は北海道内で最も活動的な火山のひとつで,最近では1988年,1996年,1998年,2006年そして2008年に噴火しました.目の前の大きな凹地形は,ポンマチネシリ山頂火口(数百年前に形成)と呼ばれ,右奥(北西側)がより深く,二段構造になっています.さらにこの中に新しい小火口群が存在し,活発な噴気が,赤沼火口(右奥)と1996年噴火口(左手前)から立ち昇っているのが分かります.手前中央の青沼火口は,雪が解けると美しいエメラルドグリーンの姿を見せるでしょう.左奥に聳える阿寒富士は,約2,000年前にできたスコリア丘(黒い軽石が降り積もってできた火山)です. (長谷川 健:茨城大学)
目次へ戻る
【geo-Flash】No.443(臨時)吉田 尚 名誉会員 訃報
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.443 2019/3/12┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 吉田 尚 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
日本地質学会の事務局長(1984-89)を務められた吉田 尚 名誉会員
(元地質調査所)が,平成31年3月1日(金)に逝去されました(98歳)。
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上
げます。
なおご葬儀は,すでに近親者によりしめやかに執り行なわれとのこと
です.
会長 松田博貴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
第10回フォトコン_優秀1
第10回惑星地球フォトコンテスト入選作品
優秀賞:月明りのメテオラの谷
写真:川口雅也(神奈川県)
撮影場所:ギリシャ テッサリア地方 トリカラ県カランバラ
【撮影者より】
ギリシャのテッサリア平原が尽き、ピンドス山脈が始まる境にカルスト台地が浸食をうけた「メテオラ」がある。巨大な柱のような岩峰が何本も聳え立ち、その岩峰の上に修道院が建っている。14世紀にセビリアの侵攻による混乱を避けた修道士たちが俗世との関わりを断ち切って共同生活を始めたのがその始まりとのこと。「メテオラ」とは、ギリシャ語で「中空の」を意味する「メテオロス」からきていて、流星の「メテオ」と同じ語源だ。
【審査委員長講評】
メテオラはギリシャ北西部にあり,石灰岩の岩峰群の上には14〜16世紀に修道院が建てられました.1988年には世界遺産に登録されています.従来の応募作品には「ジオ+星景」という組合せはありましたが,この作品ではさらに歴史が加わりました.月齢13の月光に照らされた石灰岩の岩肌,修道院の建物,遠くの街明かりからは現代人の営みなどさまざまな思いを辿ることができます.
【地質的背景】
(メテオラの奇岩群) ギリシャ北西部のセサリア(テッサリア)地方にあるメテオラの奇岩群をつくる地層は、後期漸新世から前期中新世(約2300万年前)にかけて、プレート収束域の陸側前弧海盆の海底扇状地に堆積した砂岩や礫岩からなるメテオラ礫岩層である。地層中に発達した断層や節理に沿って、選択的に侵食が進んでできた地形である。奇岩群の上には、15世紀後半〜16世紀頃に建設された東方正教会の修道院があり、奇岩群とともにユネスコ世界遺産(文化・自然複合遺産)に指定されている。(平田大二:神奈川県立生命の星・地球博物館)
参考文献: Ferriere J. et al. (2011) Bull. Soc. Geol. France. 182(5):437-450. Tectonic control of the Meteora conglomeratic formations (Mesohellenic basin, Greece)
目次へ戻る
第10回フォトコン_優秀2
第10回惑星地球フォトコンテスト入選作品
優秀賞:枕と星屑と
写真:森田康平(東京都)
撮影場所:東京都 小笠原村父島 小港海岸
【撮影者より】
小笠原父島.一度も陸続きになっていない海洋島です.水中で吹き出したマグマが急速に冷却されこのような不思議な模様に.枕状溶岩が壁一面見える位置と星を写したくあえて月が出ている時を狙いました.砂浜がレフ板替わりになり月光がこの溶岩の壁を優しく照らしてくれました.雲が流れている感じが時間の経過を表しているように思って撮りました.圧倒されるようなパワーがありとても好きな場所です.
【審査委員長講評】
小笠原諸島の父島周辺には枕状溶岩の露頭がたくさんありますが,海に面した急崖が多く,陸上で見やすい場所は限られます.その数少ない場所が小港海岸で,ここでは多くの写真が撮影されています.この作品も上弦過ぎの月光と超広角レンズを使ってうまく撮影しています.低空に白雲があったのが少し残念でした.
【地質的背景】
枕状溶岩とは溶岩の形態の名前で,水で急速に冷やされて溶岩の表面が固まるためにできます.つまり,この溶岩は海底火山の噴出物です.この露頭の枕状溶岩は,岩石学的には,ボニナイトと呼ばれ,安山岩の仲間ですが,長石を含まず,マグネシウムに富む斜方輝石である古銅輝石を含む,珍しい岩石です.ボニナイトは,世界で初めて小笠原で初めて発見され,名前は小笠原の旧称,無人島(ぶにんじま)の石という意味があります.(萬年一剛:神奈川県温泉地学研究所)
目次へ戻る
第10回フォトコン_ジオパーク
第10回惑星地球フォトコンテスト入選作品
ジオパーク賞:新緑の六方の滝
写真:齋藤敏雄(神奈川県)
撮影場所:湯河原町鍛冶屋 新崎川上流(箱根ジオパーク)
【撮影者より】
湯河原の新崎川の上流,沢沿いに登っていくと紫音の滝が現れます.その滝の横からロープに沿って登ると柱状節理の岩盤からに流れる滝があります.六方の滝は女性的で優しい水流でした.
【審査委員長講評】
六方の滝は,箱根火山のカルデラ形成期噴出物である幕山溶岩にかかる落差20mの滝です.作者は望遠レンズで滝上部をクローズアップしました.滝の飛沫に濡れた柱状節理の岩肌が美しく,後方の新緑と相まって落ち着いた雰囲気の作品となっています.
【地質的背景】
地表に噴出したマグマが冷えて固まる際に,収縮してできる規則的な割れ目が「柱状節理」です.かつて,この滝の近くには登山道がありましたが,廃道となったため滝の存在もほとんど忘れられていました.2008年頃に箱根ジオパークのジオサイトにするための調査が行われましたが,アクセスが悪いためいまでも指定されていません.最近は沢沿いの踏み跡をたどってこの滝を見に来る人が増えているようですが,十分準備してください.(萬年一剛:神奈川県温泉地学研究所)
目次へ戻る
第10回フォトコン_会長賞
第10回惑星地球フォトコンテスト入選作品
日本地質学会会長賞:ルービックキューブ
写真:島村哲也(茨城県)
撮影場所:北海道 雌阿寒岳ポンマチネシリ
【撮影者より】
四角い形状とモザイク状の割れ目が面白くてシャッターを切りました.噴石の大きさは,一辺40cmくらいです.雌阿寒岳はいくつかの火山からなり,その一つのポンマチネシリは現在も噴気が立ち上がる活火山で,最近では2008年に小規模な水蒸気噴火が発生しました.周辺にはマリモで有名な阿寒湖や風光明媚なオンネトーなどの観光地のほか,泥火山“ボッケ”や生きている酸化マンガン鉱床“湯の滝”などの地質学的な見どころもあります.
【審査委員長講評】
この作品は,最優秀賞と同じ雌阿寒岳で撮影されたパン皮状火山弾です.肩の力を抜いてあっさりと撮影したようにみえるのがこの作品の魅力です.火山弾の落下時には割れ目がなく,落下後に内部が膨らむ結果,表面にこのような割れ目ができるのです.火山学の教科書に使いたくなるような作品です.
【地質学的解説】
写真が撮影された雌阿寒岳では,1950年代から現在まで,小規模な水蒸気噴火(御嶽山で2014年に発生したような噴火)が10回以上頻発しています.写真の岩塊は,そのような噴火で放出し,火口付近に堆積したものと思われます.ギザギザしたひびは,岩塊が高温状態から急冷・収縮する際にできたものと思われますが,着弾の衝撃,あるいはその後の経年変化で露出部(地中に埋まっていない部分)のひびがさらに広がったのでしょう.径50cmほどの岩塊がバラバラにならずに保存され,立方体に近い形状と割れ方の偶然も重なって,ルービックキューブ構造を示す奇岩となりました.(長谷川 健:茨城大学)
【geo-Flash】No.444 今年もはじまるよ!2019年地質の日
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.444 2019/3/19┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
【2】2019年地質の日記念行事
【3】地質学雑誌からのお知らせ
【4】支部情報
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】割引会費申請(院生・学部学生)を忘れずに!最終締切 3月29日
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は,3月29日(金)です.
2019年度の割引会費を希望のかたは,忘れずにご提出ください(締切厳守).
2019年度割引会費申請や通常の会費払込について
http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】地質学雑誌からのお知らせ
──────────────────────────────────
(1)次の論文がAccepted Manuscriptとして公開になりました.
・「愛媛県久万高原町の三波川変成岩類中に新たに見つかった“粗粒
な変塩基性岩体」(報告)仲田光輝ほか(3/14公開)
・「飛驒山地加賀沢の花崗岩類のジルコンU−Pb年代」(報告)竹内
誠ほか(3/12公開)
・「山口-出雲地震帯西部に沿って新たに発見された活断層系」(巡
検案内書)相山光太郎・金折裕司(3/12公開)
・「地震探査から見た富山トラフの地殻構造の特徴」(論説:特集
号「富山トラフと周辺部の堆積作用と後背テクトニクス」)野 徹
雄ほか(3/12公開)
https://sub.geosociety.jp/user.php
(注意:会員ページへのログインが必要です)
(2)124巻12号(2018年12月号)が,J-SATAGEで公開されました.
125周年記念特集「付加体地質中に残る深海堆積相の研究:進展と展望」
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/-char/ja
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2019年地質の日記念行事
──────────────────────────────────
2019年の「地質の日」に関連した日本地質学会主催,共催,後援等
の催しをご紹介します.
詳しくは, http://www.geosociety.jp/name/content0165.html
<学会主催・共催>
◆第10回惑星地球フォトコンテスト【表彰式】
5月25日(土)11:00〜12:30(時間は多少変更になる場合があります)
会場:北とぴあ 第2研修室(東京都北区王子)
◆第10回惑星地球フォトコンテスト【展示会】
5月14日(火)〜5月19日(日)
場所:上野恩賜公園 上野グリーンサロン内(台東区上野公園7-47)
◆街中ジオ散歩 in Hamura 「東京の水インフラと地形・地質
〜羽村取水堰とその周辺〜」徒歩見学会
5月12日(日)10:00〜15:00 小雨決行(予定)
申込受付期間:2019年3月30(土)〜4月10日(水)
(注)非会員一般優先
◆第36回地球科学講演会「OSL年代−砂粒に刻まれた時の記憶」
主催:日本地質学会近畿支部ほか
4月20日(土)15:00〜16:30
会場:大阪市立自然史博物館 講堂
<その他>
◆地質の日記念講座「三浦半島活断層群主部,北武断層を歩く!」
後援:日本地質学会・横須賀市
2019年5月4日(土)10:00〜15:00小雨決行
申込締切:4月26日(金)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■2019年度支部総会・地質技術伝承講演会
4月13日(土)14:00〜16:45
場所:赤羽会館(東京都北区)
講師:横井 悟(石油資源開発(株)技術本部フェロー)
「石油地質分野におけるunconventionalあるいは非石油的な話」
総会委任状締切:4月12日(金)18時
http://www.geosociety.jp/outline/content0197.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
★地質情報展2019北海道—明治からつなぐ地質の知恵
3月29日(金)〜31日(日)
会場:かでる2・7(北海道札幌市)
「地質情報展」を実現のためのクラウドファンディングのお願い
目標金額達成しました!ご支援ありがとうございました!
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/gyoji
★日本地質学会主催:市民講演会
『動く大地のしくみを知り,地震・津波災害に備える』
3月30日(土)13:00〜
会場:かでる2・7(北海道札幌市)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp125/static/gyoji#koen
■日本地球惑星科学連合2018年大会
5月26日(日)〜30日(木)
会場:千葉県 幕張メッセ国際会議場・国際展示場ホール8
東京ベイ幕張ホール
http://www.jpgu.org/meeting_2019/
(後)第56回アイソトープ・放射線研究発表会
7月3日(水)〜5日(金)
会場:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
https://www.jrias.or.jp/
(後)第63回粘土科学討論会
9月10日(火)〜12日(木)
(講演会:9月10〜11日,現地見学会:9月12日)
会場:埼玉大学(さいたま市桜区下大久保225)
http://www.cssj2.org/publication/annual_meeting/
★ 日本地質学会第126年学術大会(2019山口)
9月23日(月・祝)〜25日(水)
場所:山口大学 吉田キャンパス(山口市吉田)
http://www.geosociety.jp/science/content0106.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0191.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・2019年コスモス国際賞推薦募集(4/12)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
第10回フォトコン_ジオ鉄
第10回惑星地球フォトコンテスト入選作品
ジオ鉄賞:川底を抜けて
写真:桑田憲吾(東京都)
撮影場所:滋賀県 湖南市JR草津線甲西ー三雲間 大砂川隧道付近
【撮影者より】
沖積平野の上に細長く伸びる地形とその下を潜る短いトンネル,そしてそこには「大砂川」の文字.天井川は堤防の建設という人間の力と,土砂の供給と堆積という自然の力が合わさって出来上がった特異な河川であり,滋賀県を走る草津線には全国的にも珍しい天井川の下を潜るトンネルが存在します.このトンネルは草津線開業の1889年に建設されたもので,天井川は100年以上も前から形成されていたことが分かります.
【講評・地質解説】
写真はJR草津線三雲-甲西間で柘植方面へ列車を見送っている風景です.平らに見える土手は典型的な天井川の大沙(おおすな)川で,列車が河底をくぐる瞬間を捉えています.河川勾配も読み取れる優れたアングルです.大砂川トンネル(14.5m)は1889(明治22)年建設当時のまま今に至る煉瓦造りの貴重な河底隧道で,トンネル完成後に電化したため(草津線の全線電化は1980(昭和55)年),トンネル部分の路盤を低く盤下げして架線を通した様子も作品に写し込まれています.鉄道の旅を通して大地の成り立ちと変化に思いを馳せる「ジオ鉄賞」に相応しい作品でした.(深田研ジオ鉄普及委員会 藤田勝代)
(注)河川名は「大沙川」,トンネル名は「大砂川トンネル」.いずれも読みは「おおすながわ」
※「ジオ鉄賞」:第6回より深田研ジオ鉄普及委員会より本コンテストに後援を頂き,「ジオ鉄」賞を設けています.鉄道と地球の姿を組み合わせた優れた「ジオ鉄」作品を表彰します.
目次へ戻る
第10回フォトコン_スマホ
第10回惑星地球フォトコンテスト入選作品
スマホ賞:大地のグラデーション
写真:加古原恵(東京都)
撮影場所:ベトナム ムイネー,スイティエン(妖精の渓流)
【撮影者より】
砂漠を抜けた先に広がるのは,鮮やかな絶景.自然の造形美に目を奪われます.
【審査委員長講評】
ムイネーはベトナム南部のホーチミン市からバスで6時間の海岸にあるリゾートで,近くにあるのがこの渓流です.長さ600m,崖の高さは20m程度ですが,この作品では崖上部の赤い地層に目が惹かれます.対岸の緑との対比でより鮮やかに赤が際立ちます.しかし雲が青味をおびていることからもわかるように彩度が強調されており,赤い地層も同様です.過度な彩度強調は実物とかけ離れてしまうのでご注意下さい.
【地質的背景】
ベトナム南東部のBinh Thuan省の沿岸には,長さ100 km,最大幅20 km,最大標高150 m以上の砂質堆積物からな丘陵地が発達します.ムイネー地域はその中の美しい砂丘の一つで,この地域では白亜紀の流紋岩などの火成岩類が基盤となって,その上に主に風の作用によって堆積した砂が見られます(風成堆積物).砂の堆積は少なくとも20万年前より前に始まったと考えられています.現在でも植生がない裸地では,東北東からの冬季モンスーンにより横列砂丘や縦列が発達しています.左手の露頭は更新世の風成堆積物で,上部と下部の砂の色の違いは,雨季と乾季を繰り返す半乾燥地の続成作用を反映しています.
目次へ戻る
第10回フォトコン_入選1
第10回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:キラウエア火山の溶岩湖
写真:田中信彦(東京都)
撮影場所:アメリカ キラウエア火山山頂 ジャガーミュージアム前
【撮影者より】
キラウエア火山山頂の火口では,2018年4月末〜5月初に溶岩水位が上昇し,ジャガーミュージアム前の展望台から溶岩湖表面が観察できました.空気で冷却された黒い表面は何枚かに割れ,その割れ目は溶岩の赤い線に囲まれていました.火口壁では時々溶岩のしぶきが上がっていました.その辺りの表面はうねり,引きちぎられて飛ばされていました.
【審査委員長講評】
最初はエチオピアのエルターレ火山の溶岩湖を撮影した作品と勘違いしましたが,キラウエア火山ハレマウマウ火口の直径150m程の溶岩湖の溶岩水位が運良く上昇した時を捉えて撮影した作品でした.このように撮影できたのは最近数十年間ではわずか数か月だけ.その後,南東山麓からの割れ目噴火によってキラウエア山頂部は陥没し,この溶岩湖も消滅しました.
【地質的背景】
撮影地であるジャガーミュージアムは,アメリカの地質学者,トーマス・A・ジャガーに由来します.ジャガーは自費でキラウエア火山の研究をはじめ,様々な人々の支援を受けて,キラウエア火山の山頂火口を見渡せるこの場所に火山観測所を建設しました.ジャガーが意図したように,噴火の様子を見事に写真に収められましたが,現在は火山活動の活発化に伴い閉鎖されたようです.(萬年一剛:神奈川県温泉地学研究所)
目次へ戻る
第10回フォトコン_入選2
第10回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:雷光のヴィーナス
写真:白山 健悦(青森県)
撮影場所:青森県 佐井村仏ヶ浦
【撮影者より】
北海道胆振東部地震発生の7時間前の2018.9.5,午後8時撮影です.この夜は雷が頻繁に発生してその光が岩肌を照らすと共に,月明かりのない空を明るくしました.とても不思議な夜でした.
【審査委員長講評】
昨年は昼の仏ヶ浦で最優秀賞を獲得された作者が,今年は夜の仏ヶ浦を応募されました.夜の仏ヶ浦に行くには長い階段を降りなければならず,潮の満ち引きにも注意しなければなりません.やはり土地勘のある地元の作者ならではの作品です.奇岩の間に見える月光がないのに明るい空と雲間からのぞく無数の星,地平線付近の雷光(街明かり?),夢心地のような作品です.
【地質的背景】
下北半島の西海岸にある仏ヶ浦は,いまから約1500万年前,日本が大陸から切り離されて列島になる時に生じた火山活動でできました.同様の地層は,東北日本の日本海側に広く分布し,変質して緑がかっているため,グリーンタフとよばれます.しかし,仏ヶ浦のような奇岩が発達するのはほかになく,その理由はわかっていないようです.(萬年一剛:神奈川県温泉地学研究所)
目次へ戻る
第10回フォトコン_入選3
第10回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:風雅
写真:佐藤 悠大(福岡県)
撮影場所:長崎県平戸市 生月(いきつきじま)町 潮俵断崖
【撮影者より】
海岸には玄武岩の柱状節理が広がっていた.海水を浴びその色はますます黒い.奥には荘厳な節理の崖がそびえていた.海と空の動・節理の静のコントラストを高濃度NDフィルターを使うことにより強調した.
【審査委員長講評】
北九州には新第三紀の柱状節理が広く見られますが,生月島の潮俵断崖もそのひとつです.この作品は濃いNDフィルターをかけて日没直前に219秒の長時間露光をしたものです.そのため波が手前の柱状節理上面をベールのように覆い,バックの海面の波は消されています.遠方には夕日に照らされた柱状節理の崖,雲の動きも表現されて幻想的な作品になっています.
【地質的背景】
生月島は長崎県の北部の平戸島から1991年に開通した1kmの橋によってつながっており,九州本土から車で行くことが可能となっている.撮影地塩俵断崖は生月島の北部に位置し,なかなかたどり着けない場所である.九州北西部は後期中新世以降(9−2Maごろ)のアルカリ火山岩が日本海拡大時期の中期中新世ごろの堆積岩や基盤岩上に広く覆っており,平戸島から呼子を経て福岡まで火山の痕跡が見られる.生月島では南部には中期中新世ごろの砂岩層が見られ,緩い傾斜の不整合でこのアルカリ火山溶岩が重なる.海岸に連続する垂直な柱状節理は溶岩が平坦なところにたまり,冷却時に収縮して固まったことを示している.(清川昌一:九州大学)
目次へ戻る
第10回フォトコン_入選4
第10回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:巨岩砲
写真:長谷 洋(和歌山県)
撮影場所:和歌山県西牟婁郡白浜町 富田の磯 メズロノ鼻付近
【撮影者より】
"南紀熊野ジオパーク,エリア内の奇岩です.干潮時に現れるひび割れた岩肌から奇岩を撮影しました.遠近法で人物を小さく見せることで,もたれかかった岩をよりダイナミックに表現しました. 後ろに垂直に立つ奇岩も引き立て役となって巨大な大砲のように見えました.".
【審査委員長講評】
不思議な雰囲気の作品です.モデルが立っている地層はほぼ水平ですが,その上に2つの巨岩が置かれています.夏の正午,トップライトの光線でできた影が巨岩の存在感を強く感じさせます.この巨岩はどこから来たのでしょうか.モデルの立ち位置やポーズも決まっています.
【地質的背景】
紀伊半島南西部には,前期中新世末から中期中新世に堆積した田辺層群が分布し,白浜町の海岸沿いにはその上部層が現れます.田辺層群は,四万十付加体上の前弧海盆に堆積したものです.この上部層は砂岩・砂岩泥岩互層・礫岩などの粗粒砕屑岩が優勢で,厚い砂岩層は平行葉理,斜交葉理などのベッドフォームが発達するとともに生痕化石を多産します.砂岩の巨大転石は,その表面に侵食により形成された変化に富む起伏があり,際立った景観を形づくります.(後 誠介:和歌山大学災害科学教育研究センター客員教授)
目次へ戻る
第10回フォトコン_入選5
第10回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:地球を削る(中学・高校生部門)
写真:荒岡 柊二郎(東京都)
撮影場所:東京都西多摩郡奥多摩町 ねじれの滝
【撮影者より】
東京都西多摩郡奥多摩町にある海沢三滝の一つ「ねじれの滝」を撮影しました.夏は一面緑の苔に覆われますが, 冬は褶曲した層状チャートのごつごつとした岩肌が現れます.
【審査委員長講評】
冬の苔の少なくなる時期を選び,岩肌をはっきりととらえたのは良いアイデアでした.ジオフォトらしく,ねじれの滝をつくる層状チャートの岩相が明瞭に映し出されています.しかし難しいのは露出で,岩肌に露出を合わせるとこのように空が露出オーバーになってしまいます.HDRによって空の部分も描写できれば,より魅力的な作品になったことでしょう.
【地質的背景】
「ねじれの滝」は,多摩川支流の海沢谷にありチャート岩盤を流れ落ちる滝である.関東山地南部秩父帯には石灰岩の巨岩を含む御前山層やチャートと砂岩層の繰り返しからなる海沢層などが分布する.三畳紀中期からジュラ紀後期の海沢層はチャート−砕屑岩シーケンスが最低7回繰り返しており,構造的下位から2番目の本シーケンスのチャートに「ねじれの滝」が発達している.海沢層は多摩川本流では観光地鳩ノ巣渓谷を形作している.(久田健一郎:筑波大学)
参考文献:久田健一郎・小池敏夫・棚瀬充史・中山俊雄(2003)東京都奥多摩地域地質図.東京都土木技術研究所
目次へ戻る
第10回_佳作1-2
第10回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:大陸分裂の始まりか−ビクトリアの滝−
写真:横山俊治(東京都)
撮影場所:ジンバブエ共和国 ザンビア共和国 ザンベジ川上空
【撮影者より】
川幅1700mのザンベジ川の水は、川を横断する高さ100mを越える大地の裂け目に流れ込む。これがビクトリアの滝である。雨期には水煙が数100m以上も上がる。滝の水は、並行して走る複数の裂け目の隔壁を穿って、隣の裂け目に流れ込んでいく。ビクトリアの滝のすぐ下流側の隔壁が最も低く、その後は下流側の隔壁の方が高くなっている。この裂け目群に、将来リフトバレーに、さらに大陸分裂に発展していく可能性を見た。
目次へ戻る
佳作:デビルズタワーに昇る夏の大三角
写真:川口雅也(神奈川県)
撮影場所:アメリカ合衆国ワイオミング州クルック郡 デビルズタワー
【撮影者より】
映画「未知との遭遇」で宇宙人とコンタクトする場面で有名な「デビルズタワー」は、堆積岩に貫入した溶岩が固まった響岩質斑岩で、後に周りの堆積岩が侵食されて平原に屹立する岩塔となった。溶岩はゆっくり冷却される時に垂直方向に六角形の柱状節理を発達させた。岩塔の西側には崩れた岩柱が折り重なる岩原が広がっている。撮影時には、月明かりに照らされた「デビルズタワー」にちょうど「夏の大三角」が昇ってきた。
目次へ戻る
第10回_佳作3-4
第10回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:屏風岩の夕景
写真:武藤達郎(千葉県)
撮影場所:千葉県南房総市 根本海岸
【撮影者より】
千葉県南房総市の根本海岸には屏風岩と呼ばれる奇岩群があり、県の天然記念物に指定されています。泥板岩と砂岩の互層が隆起し、それが波の浸食によって削られてできました。とくに冬場になると岩海苔が繁殖して緑色に変色し、独特な景観を生み出します。
目次へ戻る
佳作:歴史(とき)の彫刻
写真:佐藤悠大(福岡県)
撮影場所:福岡県 平尾台
【撮影者より】
平尾台で見つけたカレンフェルトを撮影。表面は溶食からか非常に美しい曲面を持っていた。秋のうろこ雲の合間から太陽が顔を出した瞬間を狙って撮影した。
目次へ戻る
宋詩にみる石と人の関わり
宋詩にみる石と人の関わり:梅堯臣の黒水晶,蘇軾の青石,陸游の山頭石,元好問の碔砆
正会員 石渡 明
1.はじめに
前回は中国唐代(618-907)の詩について白居易の青石を中心に石と人の関わりを考えたので(http://www.geosociety.jp/faq/content0818.html),今回は宋代(960-1279)のいくつかの詩について考えることにする.宋代は日本の平安時代中期から鎌倉時代に当たる.吉川幸次郎(1962)は「宋詩概説」(中国詩人選集第二集第一巻,岩波書店)で宋詩の特徴として,叙述性,生活への密着,連帯感,哲学(論理)性,悲哀からの離脱を挙げ,平静さが最大の特徴だとして,唐詩は酒,宋詩は茶だと述べている.また吉川は,欧陽脩おうようしゅう(六一りくいつ居士,1007-72)が従来の仏教または道教の優位に対して儒教の優位を確立し,この転換が約900年後の清末まで中国文化を規制したとも述べている.欧陽脩は宋朝の高官であり,科挙(官吏登用試験)の知貢挙(試験委員長)を何度も務め,日本刀の切れ味を褒ほめる「日本刀歌」などの詞でも名高い.彼はある試験でかつての同僚,5歳年上の詩人梅堯ばいぎょう臣しんを,科挙に合格したことがないにもかかわらず試験委員として採用した.
2.梅堯臣の黒水晶
梅堯臣(聖兪(せいゆ),宛陵(えんりょう)先生,1002-60)は,官位は低かったが文名は高く,有名な詩に「猫を祭る」がある.五白という名の飼い猫が死んだのを悲しみ,書物を鼠(ねずみ)の害から守った功績を「鶏豚や馬驢に勝る」と讃え,丁寧に水葬する様子を詠んだ詩である.この人は猫だけでなく,鶻(はやぶさ)から烏(からす),蛙(かえる),鰌(どじょう),蚯蚓(みみず),虱(しらみ),蛆虫(うじむし)まで,鋭い観察力を駆使して何でも詩にした.当然,地学的な対象を詠んだ詩もある.「月食」の詩は,「女中がやって来て驚くべきことを伝えた.天は青い玻璃(はり)(ガラス)のようで,月は黒い水精(水晶)のようだと言う.この時期は満月のはずなのに,端が一寸明るいだけだ.主婦は餅を焼き,子供は鏡を敲(たた)く.これは浅はかな考えだが,月を助けようという気持ちは尊い.深夜になると桂兎(月の模様)も回復し,星々は(月に)従って西に傾いた(意訳)」と謳う.月食時の月を「黒水晶」と形容するのは流石であり,月食の詩として約1000年後の現代でも通用する.むしろ現代日本の月食の短歌(拙著本誌15巻9号3-4頁(2012)参照)より情緒がある.また,庭石として珍重される「太湖石」は「醜石」だとし,これを自慢する友人に対し「醜を以って世は悪と為せども 茲(これ)は醜を以って徳と為す 事に固(もと)より醜好無し 醜好は惑わざるを貴ぶ」と言って,本人が好いと思えば好いだけだ,と突き放している(詠劉仲更澤州園中醜石).これは言外に「俺はちっとも好いとは思わん」という心が透けて見える.(参照:筧文生 1962;「梅堯臣」中国詩人選集第二集第三巻,岩波書店)
3.蘇軾の青石
蘇軾(そしょく)(子瞻(しせん),東坡(とうば)居士,1036-1101)は,欧陽脩が委員長,梅堯臣が委員を務めた官吏登用試験の合格者(進士)の一人で,「春宵(しゅんしょう)一刻値(あたい)千金」(春夜)の句で名高い.1078年の徐州(任地,江蘇省北西部)での「雲竜山に登る」詩では,「酔中走って上る黄茆(茅)岡 満岡の乱石群羊の如し 岡頭に酔倒し石牀と作(な)る 仰いで白雲を看れば天茫々たり 歌声谷に落ちて秋風長し 路人首を挙げて東南を望み 手を拍って大笑す使君(知事,蘇軾自身を言う)狂せりと」と豪語する.宋詩は茶だと言うが,この詩は李白の酒の世界に近い.ただし,蘇軾は実は酒が弱かったらしい(吉川,前出).地質図を見ると,この辺は古生代前期の石灰岩が分布しているようである.秋吉台の石灰岩台地の様子を思い浮かべると,「満岡の乱石群羊の如し」という景色が眼前に浮かぶ.しかし彼はこの翌年(44歳),詩文によって朝政を誹謗したとして投獄され,死罪の危機に直面したが,幸い皇帝の恩命を得て死を免れ,湖北省の黄州に流罪となった.その後も何回か朝政参与と流罪を繰り返したが,「人生は寄するが如し 何ぞ楽しまざる」という自由奔放な詩風は終生変わらなかった(小川環樹 1962; 「蘇軾」上・下,中国詩人選集第二集第五・六巻,岩波書店).
蘇軾には石の趣味があり,1092年の「双石并びに叙」では,「揚州(任地,江蘇省中南部)で石を二つ手に入れた.一つは緑色で山や岡がうねって続くような形で穴が一つ貫通している.もう一つは真っ白で鏡のようである.これらを盆水に浸して机の間に置いた(意訳)」と叙べ,これらの石に触発された空想を詩にしている.これは完全に現代の水石趣味と同じである.また,1097年には恵州(流謫(るたく)先,広東省)で「白鶴山の新居に鑿井(さくせい)すること四十尺(約8m),盤石に遇(あ)い,石尽きて泉を得る」という長い題の詩を作り,業者を4人雇って井戸を掘らせた時の様子を詠んでいる.「10日も掘ったが2〜3m進んだだけだ 下に青石の岩盤がある (錐(きり)は)終日ただ火を迸(ほとばし)らせるのみ いつの時か飛瀾(みずしぶき)を見ん 我が粲(さん)(白米)と醪(ろう)(どぶろく)を豊かにせん 汝が錐と鑽(のみ)とを利(するど)くせよ(意訳)」と手前勝手な要求を述べて業者をせっついている.その後ようやく青石の下に,手でつかめるほど軟弱な「黄土」の層が出てきて,水を得ることができた.「我が生,類(おおむ)ね此(かく)の如し 何(いずこ)に適(ゆ)くとして艱難(かんなん)ならざらん」と,まるで自分で掘ったかのように言って喜ぶ.しかし,これは見方を変えれば,世界最初(?)のボーリング調査記録かもしれない.地質図を見ると恵州付近は主にトリアス〜ジュラ系が分布しており,地下水脈が多い石灰質の地盤なのかもしれない.「青石」は必ずしも青い石とは限らず,「中国では少し大きな石を青石と言うことが多い」そうで(小川,前出),石灰岩であってもおかしくない.
4.王安石と黄庭堅
王安石(半山,1021-86)は1042年,22歳で進士となったが,しばらく地方官を務めた.神宗皇帝が即位すると召されて1072年に宰相となり,国家財政立て直しのために大規模な改革を始めた.蘇軾らの保守派はこの改革に強く反対した.王安石らの新法党は前述のように蘇軾を投獄したり流罪にしたりしたが,蘇軾は終生敬意をもって王安石と文人としての付き合いを続けた.王安石の改革は一定の成果を挙げたが,神宗の崩御(1085)により頓挫した.彼はその最晩年に,自分がかつて宰相として行った施策が次々に破棄されるのを見なければならなかった(清水茂 1962;「王安石」中国詩人選集第二集第四巻,岩波書店).王安石の詩は風諭詩,閑適詩,感傷詩など多彩で,政敵を攻撃するものから家族への深い愛情や仏教的な悟りを表明するものまで様々だが,安石の名に背き,あまり地学的対象を詩にしていない.王安石のような文人宰相は稀で,他には1953年にノーベル文学賞を受けた英国のチャーチルくらいしかいない(清水,前出).
黄庭( こうてい)堅(けん)(1045-1105)は「山谷(さんこく)道人」とも呼ばれ,大自然とその中で生きる動植物を愛した詩人だと言われているが,「実は山水の美の忠実な描写はほとんど見られない」(荒井健, 1963;「黄庭堅」中国詩人選集第二集第七巻,岩波書店).「石竹牧牛に題す 并びに引」で「石,吾は甚(はなは)だ之を愛す」と言っているが,これは蘇軾が描いた絵の中の怪石の話であり,李公麟がこの絵に牧童が牛に乗っている図を描き加えたのが気に入らず,難癖をつけるための言いがかりだったように思う.彼自ら「点鉄成金」,「換骨奪胎」と呼ぶ,古人の詩を改変して自分の詩を作り出す手法は,明(みん)代に偽詩として非難された.黄庭堅は蘇軾の弟子であり,師と同様に新法党に憎まれて何度も流罪になり,流謫先で淋しく死んだ.
5.陸游の山頭石
宋は,北方諸民族(遼,西夏,金,モンゴル)の圧力に押され,首都を汴(べん)京(けい)(開封(かいほう))から臨安(杭州)に移した1127年を境に,北宋と南宋に二分される.前述の欧陽脩,梅堯臣,蘇軾,王安石,黄庭堅は北宋の人だが,陸游(りくゆう)(放(ほう)翁(おう),1125-1210)は南宋の人である.陸游は43歳の作「山西の村に遊ぶ」の対句「山重水復疑無路 柳暗花明又一村」で有名だが,彼には医薬の知識があり,「薬袋を提げロバに乗って行けば 村人は歓喜して道を挟んで迎える 口々に以前生き返らせてもらった礼を言い 生まれた多くの子に陸の字をつけたと言う(意訳)」(81歳,「山村経行因施薬」其四)のように老いても人々のために尽くそうとする赤ひげ先生的側面があった.一方で陸游は憂国の詩人であり,宋帝国の失地回復を終生訴え続け,そのため官途では疎(うと)まれて栄達しなかったが,85歳の辞世の詩でも息子に対して,「将来皇帝の軍勢が北に進んで中原を平定したら,家の祭をしてこの父に知らせることを忘れるな(意訳)」と指示するほど一途だった.陸游69歳の1193年の秋,故郷の浙江省山陰(紹興)で作った「山頭の石」という詩は次のように謳う.「秋風万木霣(か)れ 春雨百草生ず 造物初めより何の心ぞ 時到れば自ずから枯栄す 惟(た)だ山頭の石有りて 歳月浩(こう)として測る莫(な)し 四時の運(めぐ)るを知らずして 常に太古の色を帯ぶ 老翁一生此の山に居り 脚力尽きんと欲して猶(な)お躋攀(せいはん)す 時々石を撫して三嘆息す 安(いずく)んぞ此の身の爾(なんじ)の如く頑(がん)なるを得ん」.地質図を見ると,この石は原生代後期の堆積岩らしい.山頭の石に,日常の時間とはかけ離れた「太古の色」を直感したのは流石である.(参照:一海知義 1962;「陸游」中国詩人選集第二集第八巻,岩波書店)
6.元好問の碔砆(ぶふ)
()
ここまでは,投獄や流罪は経験しても,概ね平和のうちに生涯を終えた宋の詩人たちであるが,陸游の65年後に生まれた元好問(遺山,1190-1257)は戦乱の金に生き,亡国を経験した詩人である.金は女真族が満州・華北に建てた中国風の王朝で,1115年に遼から独立して建国,のちに遼を滅ぼし,1127年に宋を南に追って汴京を首都としたが,1214年頃からしばしばモンゴルの侵攻を受け,1234年にはモンゴルと南宋の連合軍が金を攻め,哀宗皇帝が自殺して金は滅んだ.そして今度はモンゴルが南宋を攻め,1276年に臨安が陥落,1279年までに南宋は完全に滅んだ.元朝の成立はフビライが国号を大元と称した1271年とされる.なお,朝鮮(高麗)を経由してモンゴルが日本に襲来した元寇は1274年と1281年(文永・弘安の役)であり,モンゴルはその後インドシナやジャワにも進出し属国とした.
元好問の詩は宋詩ではないが,時代的には全く南宋と重なる中国の詩なので,敢えてここで取り上げる.彼にとっては,南宋ではなく金朝こそが中原の文化の正統な維持者であり,彼が編纂した「中州集」という金一代の詩集はその考えで貫かれる(小栗栄一 1963;「元好問」中国詩人選集第二集第九巻,岩波書店).彼の詩の多くは戦乱に蹂躙(じゅうりん)された祖国を悲嘆する「喪乱詩」であり,緊張感と悲壮感が漲(みなぎ)っていて,「平静さ」を特徴とする宋詩の対極にある.「野(や)蔓(まん)(つる草)情有りて戦骨に縈(まと)い 残陽何の意か空城(廃墟の街)を照らす」(岐陽其二,1231年42歳),「惨憺(さんたん)として竜(りゅう)蛇(だ)(金とモンゴル)日(ひび)に闘争し 干戈(かんか)直ちに生霊(せいれい)(人民)を尽くさんと欲す」(壬辰(1232)十二月車駕東狩後即事其二),「戦地風来りて草木腥(なまぐさ)し」(同),「誰か謂(おも)わん神州(中国)遂に陸沈せんとは」(癸巳(1233)四月二十九日出京)などの詩句からその雰囲気を痛感できる.
彼が好んだ詩人は陶淵明,杜甫,蘇軾であり,「詩論」其の十では,「少陵(杜甫)自ずから連城の璧(へき)を有す 争奈(いか)んせん微之(びし)(元稹(げんじん))碔砆(ぶふ)を識(し)るを」,つまり「杜甫はかれ自身の至宝を持っていたのに,元稹にはまがい玉(だま)しか目に入らなかった」(小栗,前出)と,元稹が書いた杜甫の墓誌をこき下ろしている.碔砆(珷玞)というのは玉(翡翠(ひすい))に似た(玉に次ぐ)美石で,赤地に白い模様があり,湖南省の長沙や臨湘に産するそうである.碧玉(へきぎょく)jasper,瑪瑙(めのう)agate,玉髄(ぎょくずい)chalcedony等の一種らしく,碔砆混玉という四文字熟語もある(玉石混交と似た意味).元稹は白居易の親友で,彼らを称して元軽白俗と悪口を言う人たちがいるが,元好問もその一人らしい.ただし,元好問も,表舞台に登場するときには常に多少の誹謗が伴い,筆禍で免職されたことが何回もある.また,彼は金朝の忠臣だったが,金朝滅亡後,63歳のとき(1252年)にモンゴルのフビライに会って「儒教大宗師」の尊号を奉るなど(小栗,前出),世故(せこ)に長(た)けた部分もある.亡国の戦乱の中で翻弄されながら,そして家族を養いながら,自分の使命を見失わずに作詩を続け,国家的な詩集を編纂して生涯を全うした元好問のしたたかさには,見習うべきものがある.彼は金史の編纂も企てたが,妨害により果たせなかったのは惜しまれる.「若年より山を好んだ彼は老境に入ってからも道すがら谷に分け入ることが少なくなかった」(小栗,前出).彼の強い意志のエネルギーは,案外祖国の山野の自然から得ていたのかもしれない.
7.おわりに
北宋の160年間は,遼や西夏の圧力はあったものの,人々は平和で豊かな生活を享受することができた.欧陽脩,梅堯臣,蘇軾,王安石,黄庭堅らはこの時代の人である.しかし,女真族の金が遼を滅ぼし,1127年には北宋の首都汴京(開封)を奪い,君主徽宋,欽宋の父子を捕虜として満州に連れ去った.皇子高宗は官吏・人民とともに南方に遁れ,臨安(杭州)を首都として揚子江流域を統治した.これが南宋で,その領土内では150年間にわたり,陸游の詩に見るような平和が維持された.陸游は北伐を主張したが,南宋の朝廷は戦争を避け,経済力で平和を買ったのである.一方,金の支配に服した北方の人々は,元好問の詩に見るように,頻発する戦乱に苦しめられ,あげくの果ては金が滅亡し,今度はモンゴルの苛烈な支配に服することになった.金の元好問の深刻な詩を,北宋・南宋の風雅な詩と比べ味わうと,平和の尊さ,ありがたさが改めて実感される.国という字に入るべきなのは玉であり,それに似て非なる碔砆(武夫とも書く)であってはならない,ということである.
【geo-Flash】No.445 コラム「宋詩にみる石と人の関わり」
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.445 2019/4/2┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2019年地質の日記念行事
【2】地質学雑誌からのお知らせ
【3】コラム「宋詩にみる石と人の関わり」
【4】支部情報
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2019年地質の日記念行事
──────────────────────────────────
2019年の「地質の日」に関連した日本地質学会主催,共催,後援等
の催しをご紹介します.
詳しくは, http://www.geosociety.jp/name/content0165.html
<学会主催・共催>
◆第10回惑星地球フォトコンテスト【表彰式】
5月25日(土)11:00〜12:30(時間は多少変更になる場合があります)
会場:北とぴあ 第2研修室(東京都北区王子)
◆第10回惑星地球フォトコンテスト【展示会】
5月14日(火)〜5月19日(日)
場所:上野恩賜公園 上野グリーンサロン内(台東区上野公園7-47)
◆街中ジオ散歩 in Hamura 「東京の水インフラと地形・地質
〜羽村取水堰とその周辺〜」徒歩見学会
5月12日(日)10:00〜15:00 小雨決行(予定)
申込受付期間:2019年3月30(土)〜4月10日(水)
(注)非会員一般優先
◆第36回地球科学講演会「OSL年代−砂粒に刻まれた時の記憶」
主催:日本地質学会近畿支部ほか
4月20日(土)15:00〜16:30
会場:大阪市立自然史博物館 講堂
<その他>
◆地質の日記念講座「三浦半島活断層群主部,北武断層を歩く!」
後援:日本地質学会・横須賀市
2019年5月4日(土)10:00〜15:00小雨決行
申込締切:4月26日(金)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】地質学雑誌からのお知らせ
──────────────────────────────────
◆第125巻第3号(2019年3月号)が刊行されました(4/1発送).
論説「噴出物中の熱水変質鉱物の特徴:十勝岳火山噴出物の例」井村匠ほか
(p.203–218)ほか計5編
最新号目次はこちら
http://www.geosociety.jp/publication/content0092.html
◆受理論文の印刷前に,Accepted ManuscriptとしてPDFファイルを作
成し,順次このWEBサイトで公開しています.
https://sub.geosociety.jp/user.php
(注意:会員ページへのログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】コラム「宋詩にみる石と人の関わり」
──────────────────────────────────
「宋詩にみる石と人の関わり:
梅堯臣の黒水晶,蘇軾の青石,陸游の山頭石,元好問の碔砆」
前回は中国唐代(618-907)の詩について白居易の青石を中心に石と
人の関わりを考えたので
( http://www.geosociety.jp/faq/content0818.html),今回は宋代
(960-1279)のいくつかの詩について考えることにする.宋代は日
本の平安時代中期から鎌倉時代に当たる.吉川幸次郎(1962)は「
宋詩概説」(中国詩人選集第二集第一巻,岩波書店)で宋詩の特徴
として,叙述性,生活への密着,連帯感,哲学(論理)性,悲哀か
らの離脱を挙げ,平静さが最大の特徴だとして,唐詩は酒,宋詩は
茶だと述べている.また吉川は,欧陽脩(六一居士,1007-72)が従
来の仏教または道教の優位に対して儒教の優位を確立し,この転換
が約900年後の清末まで中国文化を規制したとも述べている.
続きをよむ、、、 http://www.geosociety.jp/faq/content0056.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■2019年度支部総会・地質技術伝承講演会
4月13日(土)14:00〜16:45
場所:赤羽会館(東京都北区)
講師:横井 悟(石油資源開発(株)技術本部フェロー)
「石油地質分野におけるunconventionalあるいは非石油的な話」
総会委任状締切:4月12日(金)18時
http://www.geosociety.jp/outline/content0197.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第221回地質汚染イブニングセミナー
4月19日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ8階807会議室(東京都北区:JR王子駅から徒歩5分)
講師:風岡 修(地質汚染診断士・液流動化診断士・東邦大学非常勤講師・
理学博士)
演題:「地質環境と宅地理学診断」
http://www.npo-geopol.or.jp
■第192回深田研談話会
4月20日(土)14:30〜16:00
場所:深田地質研究所 研修ホール(東京都文京区)
講師:早坂康隆 氏(広島大学大学院理学研究科准教授)
演題:ジルコン年代学に基づく西南日本の地質構造発達史
参加費無料 70名(先着)*要事前申込
http://www.fgi.or.jp/?p=4342
■第18回重金属類・残土石処分地・廃棄物処分地診断に関わる
地質汚染調査浄化技術研修会
4月25日(木)〜28日(日)
主催:NPO法人 日本地質汚染審査機構
共催:日本地質学会環境地質部会ほか
会場:日本地質汚染審査機構関東ベースン実習センター(千葉県香取市)
会費:会員:50,000円・非会員:60,000円・学生:15,000円
http://www.npo-geopol.or.jp
■日本地球惑星科学連合2018年大会
5月26日(日)〜30日(木)
会場:千葉県 幕張メッセ国際会議場・国際展示場ホール8
東京ベイ幕張ホール
http://www.jpgu.org/meeting_2019/
(後)第56回アイソトープ・放射線研究発表会
7月3日(水)〜5日(金)
会場:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
https://www.jrias.or.jp/
■地質学史懇話会
6月23日(日)13:30〜17:00
場所:北とぴあ 8階803号室(JR京浜東北線王子駅下車3分)
講演
・若林 悠:行政組織の「専門性」と「評判」の構築―気象行政における
「エキスパート・ジャッジメント」と「機械的客観性」の制度化―
・木村 学:北海道の地質学研究 150年,雑感
■第223回地質汚染イブニングセミナー
6月28日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ902会議室(東京都北区:JR王子駅から徒歩5分)
講師:宮崎 淳(創価大学教授)
演題:「水循環基本法の理念と地下水の法的性質〜公水私水区分論からの脱却〜」
http://www.npo-geopol.or.jp
(後)第63回粘土科学討論会
9月10日(火)〜12日(木)
(講演会:9月10〜11日,現地見学会:9月12日)
会場:埼玉大学(さいたま市桜区下大久保225)
http://www.cssj2.org/publication/annual_meeting/
★ 日本地質学会第126年学術大会(2019山口)
9月23日(月・祝)〜25日(水)
場所:山口大学 吉田キャンパス(山口市吉田)
http://www.geosociety.jp/science/content0106.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0191.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・筑波山地域ジオパーク学術研究助成金の募集(5/31)
・下仁田ジオパーク学術奨励金制度の募集(4/25)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.446(臨時)「一家に1枚」ポスター発行
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.446 2019/4/9┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】日本地質学会企画「一家に1枚 日本列島7億年」ポスター発行
──────────────────────────────────
日本地質学会企画の「一家に1枚」ポスター発行
ー日本列島7億年の歴史と列島の地質をビジュアル化ー
文部科学省では毎年4月の科学技術週間にあわせて「一家に1枚」ポ
スターを製作・配付しています.平成31年度(第60回)は,日本地
質学会が提案した企画が採択され,期間中(平成31年4月15日〜21日),
「一家に1枚 日本列島7億年」ポスターが,全国の小・中・高等学校
等に配布されます.また全国の科学館などで無料配付されます.
「一家に1枚 日本列島7億年」ポスターは,日本列島の地質の複
雑さと,周辺プレート境界の位置を知るための地図の他,プレート
沈み込み帯でできる岩石の写真,プレート沈み込み帯についてのイ
ラストと解説,日本が誕生した約7億年前から,はるか遠い未来,
太平洋が消滅するまでの未来予想まで描いた地質年代表などが,国
産の美しい鉱物・化石の写真と一緒にビジュアル化されています.
「一家に1枚 日本列島7億年」ポスターは,科学技術週間のweb
サイト(http://stw.mext.go.jp/)からA3判をダウンロード可能です.
○一家に1枚シリーズのサイト(ポスターDLはこちらから)
http://stw.mext.go.jp/series.html
○「一家に1枚 日本列島7億年」解説ページ
http://stw.mext.go.jp/series/geo-japan.html
******************************
関連イベントのお知らせ
******************************
今年の科学技術週間(4月15日(月)〜21日(日))にあわせて研究者を
招いたイベントが日本科学未来館で開催されます.
トークセッション「一家に1枚 日本列島7億年」をよみとく
主 催:文部科学省,日本科学未来館
協 力:日本地質学会,産業技術総合研究所地質調査総合センター
日 時:2019年4月21日(日)14:30〜15:30
会 場:日本科学未来館 5階コ・スタジオ(東京都江東区2-3-6)
登壇者:磯崎行雄(東京大学総合文化研究科)
辻森 樹(東北大学東北アジア研究センター)
ファシリテーター:坪井淳子(日本科学未来館)
同会場のアクティビティスペースにて日本地質学会が開発・制作したWEB
教材体験会(http://www.yume-earth.geosociety.jp/)も開催予定です.
日本科学未来館のウェブサイト
https://www.miraikan.jst.go.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No.447[山口大会関連情報]宿泊予約はお早めに!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.447 2019/4/16┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[山口大会関連情報]宿泊予約はお早めに!
【2】日本地質学会が大型研究計画に提案!!
【3】科学技術週間スタート「一家に1枚 日本列島7億年」配布開始
【4】2019年地質の日記念行事
【5】地質図に関するJIS(日本工業規格)改正に関するお知らせ
【6】意見・提言2019
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[山口大会関連情報]宿泊予約はお早めに!
──────────────────────────────────
会場となる山口大学吉田キャンパスは湯田温泉が最寄りの宿泊地と
なります。湯田温泉は断層沿いの湯量豊富な温泉ですが、ビジネス
ホテルのシングルルームは全部で600室と決して多くありません。
現地実行委員会は、そのうち350室を会員向けに準備いたしました。
申込要領をご確認いただき,専用の申込用紙をご利用のうえ,FAX
もしくはE-mailでお申し込み下さい。
大会期間中は秋の行楽シーズンですので、お早めに宿を予約して頂
きますようお願いいたします。
なお若手会員の皆様は、別途リーズナブルな宿泊先を40名分ほど
準備してありますので、そちらもご検討ください。若手会員向け宿
泊施設につきましては、5月上旬より募集開始を予定しております。
申込締切:2019年7月30日(火)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/science/content0108.html
【山口大会プレサイト】http://www.geosociety.jp/science/content0106.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】日本地質学会が大型研究計画に提案!!
──────────────────────────────────
大型研究計画:
地球惑星研究資料のアーカイブ化とキュレーションシステムの構築
大型研究計画とは,世界の学術研究を先導する画期的な成果を挙
げる大型プロジェクトを,社会や国民の幅広い理解と支持を得つつ,
国家プロジェクトとして推進する施策です.研究分野コミュニティ
の意向を踏まえて,日本学術会議が選定し,文部科学省が推進しま
す.3年ごとに改定され,今回が第24期となり,全面的な改定が予定
されています.大型研究計画の提案カテゴリーには大型施設計画と
大規模研究計画があります.日本地質学会では,多くの会員が切望
し,かつ現在のみならず将来にわたって持続的に地球科学研究を発
展させるために「地球惑星研究資料のアーカイブ化とキュレーショ
ンシステムの構築」を大型施設計画として提案しました.
今後の予定として,5月27日(月)に日本地球惑星科学連合2019年
大会のユニオンセッション「地球惑星科学の進むべき道9:大型研究
計画とマスタープラン2020」にて,大型研究計画の公聴会がありま
す.本提案は,14時08分から発表予定です.当日は各発表について,
随時アンケート投票が受け付けられ,地球惑星科学に携わる研究者
から広く意見を聴取する予定です.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/news/n143.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】科学技術週間スタート「一家に1枚 日本列島7億年」配布開始
──────────────────────────────────
日本列島7億年の歴史と列島の地質をビジュアル化
文部科学省では毎年4月の科学技術週間にあわせて「一家に1枚」ポ
スターを製作・配付しています.平成31年度(第60回)は,日本地
質学会が提案した企画が採択され,期間中(平成31年4月15日〜21日),
「一家に1枚 日本列島7億年」ポスターが,全国の小・中・高等学校
等に配布され,全国の科学館などでも無料配付されています.
科学技術週間のwebサイトからポスター(A3判)がダウンロードできます
また,配布協力館の検索も可能です.http://stw.mext.go.jp/index.html
◆「一家に1枚 日本列島7億年」解説ページもご参照ください
http://stw.mext.go.jp/series/geo-japan.html
◆関連イベント
トークセッション:「一家に1枚 日本列島7億年」をよみとく
4月21日(日)14:30〜15:30
会場:日本科学未来館 5階コ・スタジオ(東京都江東区2-3-6)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/news/n141.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2019年地質の日記念行事
──────────────────────────────────
2019年の「地質の日」に関連した日本地質学会主催,共催,後援等
の催しをご紹介します.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/name/content0165.html
<学会主催・共催>
◆第10回惑星地球フォトコンテスト【表彰式】
5月25日(土)11:00〜12:30(時間は多少変更になる場合があります)
会場:北とぴあ 第2研修室(東京都北区王子)
◆第10回惑星地球フォトコンテスト【展示会】
5月14日(火)〜5月19日(日)
場所:上野恩賜公園 上野グリーンサロン内(台東区上野公園7-47)
◆第36回地球科学講演会「OSL年代−砂粒に刻まれた時の記憶」
主催:日本地質学会近畿支部ほか
4月20日(土)15:00〜16:30
会場:大阪市立自然史博物館 講堂
◆地質の日記念展示「失われた川を尋ねて『水の都』札幌」
4月27日(土)〜6月16日(日)
場所:北海道大学総合博物館1階 企画展示室
共催:日本地質学会北海道支部ほか
〇市民セミナー
5月11日(日)第一回「水の都」札幌−コトニ川を尋ねて
6月9日(日)第二回「水の都」その誕生と消滅 〜身近に残る水の痕跡〜
〇市民地質巡検
5/25(土)街中ジオ散歩 in Sapporo 「コトニ川を歩く」
申込締切:5月17日(金)必着
https://www.museum.hokudai.ac.jp/contents/calendar/event/14451/
<その他>
◆地質の日記念講座「三浦半島活断層群主部,北武断層を歩く!」
後援:日本地質学会・横須賀市
5月4日(土)10:00〜15:00小雨決行
申込締切:4月26日(金)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質図に関するJIS(日本工業規格)改正に関するお知らせ
──────────────────────────────────
JIS原案作成委員会(委員長:宮下純夫元会長,日本地質学会推薦)
が取りまとめた地質図に関するJIS(日本工業規格)原案が,経済産
業省の審議を通過し,規格が改正されました(2019年3月20日).
・JIS A0204「地質図−記号,色,模様,用語及び凡例表示」改正
・JIS A0205「ベクトル数値地質図−品質要求事項及び主題属性コード」改正
[日本工業標準調査会HPの検索システム]
http://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
の「JIS規格番号からJISを検索」にA0204ないしA0205を入力し,検
索してください.検索結果からJISの閲覧が可能です.
日本地質学会の出版物等でも,地質年代表記を含む地質用語・記
号等の使用はJISに準拠することを推奨しています.JIS A 0204,
JIS A 0205は,論文や記事を執筆の際にも,地質用語・記号等の表
記法の拠り所となるものですので,会員の皆様も是非ご参照ください.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】意見・提言2019
──────────────────────────────────
・研究論文不正問題を受けて(4/4)
・平成31年度大学入試センター試験の地学関連科目に関する意見書(3/31)
全文はこちら
http://www.geosociety.jp/engineer/content0053.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■男女共同参画学協会連絡会の声明「大学等高等教育機関の入学試験
に対する声明」[JpGUダイバーシティ推進委員会(地質学会も加盟)
も賛同しました]
https://www.djrenrakukai.org/proposal_request.html#20181217
■地震本部ニュース2019春号
日本海溝沿いの地震活動の長期評価の改訂から見る大地震の可能性...ほか
https://www.jishin.go.jp/herpnews/
*******************************************************
■第221回地質汚染イブニングセミナー
4月19日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ8階807会議室(東京都北区:JR王子駅から徒歩5分)
講師:風岡 修(地質汚染診断士・液流動化診断士・東邦大学非常勤講師・理学博士)
演題:「地質環境と宅地理学診断」
http://www.npo-geopol.or.jp
■第192回深田研談話会
4月20日(土)14:30〜16:00
場所:深田地質研究所 研修ホール(東京都文京区)
講師:早坂康隆 氏(広島大学大学院理学研究科准教授)
演題:ジルコン年代学に基づく西南日本の地質構造発達史
参加費無料 70名(先着)*要事前申込
http://www.fgi.or.jp/?p=4342
■第18回重金属類・残土石処分地・廃棄物処分地診断に関わる
地質汚染調査浄化技術研修会
4月25日(木)〜28日(日)
主催:NPO法人 日本地質汚染審査機構
共催:日本地質学会環境地質部会ほか
会場:日本地質汚染審査機構関東ベースン実習センター(千葉県香取市)
会費:会員50,000円・非会員60,000円・学生:15,000円
http://www.npo-geopol.or.jp
■第193回深田研談話会
5月18日(土)14:30〜16:00
場所:深田地質研究所 研修ホール(東京都文京区)
講師:宮田真也 氏(城西大学大石化石ギャラリー学芸員)
演題:日本の魚類化石を観る
参加費無料、70名(先着)*要事前申込
http://www.fgi.or.jp/
■2019年度春期(初心者向け)地質調査研修
5月20日(火)〜24日(金)
場所:島根県出雲市長尾鼻周辺(小伊豆海岸)
定員:6名(締切:5月13日(月)正午)(定員になり次第締切)
https://www.gsj.jp/geobank/geotraining.html
■日本地球惑星科学連合2018年大会
5月26日(日)〜30日(木)
会場:千葉県 幕張メッセ国際会議場・国際展示場ホール8
東京ベイ幕張ホール
大会参加登録(早期割引):5月8日(水)締切
http://www.jpgu.org/meeting_2019/
(後)第56回アイソトープ・放射線研究発表会
7月3日(水)〜5日(金)
会場:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
https://www.jrias.or.jp/
■第7回堆積実験オープンスクール
6月9日(日)10:00 〜 17:00 (予定)
場所:京都大学理学部1号館
対象:学部3・4回生(修士以上も空きがあれば可)
申込締切:6月3日(月)参加費無料
http://ow.ly/La9330jhzoy
■地質学史懇話会
6月23日(日)13:30〜17:00
場所:北とぴあ 8階803号室(JR京浜東北線王子駅下車3分)
講演
・若林 悠:行政組織の「専門性」と「評判」の構築―気象行政における
「エキスパート・ジャッジメント」と「機械的客観性」の制度化―
・木村 学:北海道の地質学研究 150年,雑感
■第223回地質汚染イブニングセミナー
6月28日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ902会議室(東京都北区:JR王子駅から徒歩5分)
講師:宮崎 淳(創価大学教授)
演題:水循環基本法の理念と地下水の法的性質〜公水私水区分論からの脱却〜
http://www.npo-geopol.or.jp
(後)第63回粘土科学討論会
9月10日(火)〜12日(木)
(講演会:9月10〜11日,現地見学会:9月12日)
会場:埼玉大学(さいたま市桜区下大久保225)
http://www.cssj2.org/publication/annual_meeting/
★ 日本地質学会第126年学術大会(2019山口)
9月23日(月・祝)〜25日(水)
場所:山口大学 吉田キャンパス(山口市吉田)
http://www.geosociety.jp/science/content0106.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0191.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・上富良野町ジオパーク専門員募集(十勝岳ジオパーク推進協議会)(5/15)
・フォッサマグナミュージアム臨時職員(学芸業務)募集(5/10)
・第10回日本学術振興会育志賞受賞候補者の推薦(学会締切5/15)
・住友財団2019年度研究助成(6/10)
・2020年〜2021年開催藤原セミナーの募集(7/31)
・伊豆半島ジオパーク学術研究助成の公募(5/20)
・勝山市ジオパーク学術研究等奨励事業募集(5/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No.449[山口大会]若手会員向けルームシェア型宿泊プラン
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.449 2019/5/7┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[山口大会関連情報]宿泊予約はお早めに!
【2】[山口大会関連情報]若手会員向けルームシェア型宿泊プラン
【3】日本地質学会第11回総会開催(5/25)
【4】日本地質学会が大型研究計画に提案!!
【5】地質学雑誌からのお知らせ
【6】Island Arcからのお知らせ
【7】2019年地質の日記念行事
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[山口大会関連情報]宿泊予約はお早めに!
──────────────────────────────────
会場となる山口大学吉田キャンパスは湯田温泉が最寄りの宿泊地と
なります.湯田温泉は断層沿いの湯量豊富な温泉ですが,ビジネス
ホテルのシングルルームは全部で600室と決して多くありません.
現地実行委員会は,そのうち350室を会員向けに準備いたしました.
申込要領をご確認いただき,専用の申込用紙をご利用のうえ,FAX
もしくはE-mailでお申し込み下さい.
大会期間中は秋の行楽シーズンですので,お早めに宿を予約して頂
きますようお願いいたします.
申込締切:2019年7月30日(火)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0108.html
【山口大会プレサイト】http://www.geosociety.jp/science/content0106.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[山口大会関連情報]若手会員向けルームシェア型宿泊プラン
──────────────────────────────────
山口大会では若手会員向けの宿泊施設をご用意いたしました.「若
手同士の交流」と「低価格化」の観点から,本プランは,相部屋で
のご案内となっております.内容をよくご確認の上,ご検討ください.
対象となる若手会員:学生(学部,修士,博士)およびポスドク研究員
申込締切:2019年7月31日(申込み順に受入.満員になり次第終了.)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0110.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本地質学会第11回総会開催(5/25)
──────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会第10回総会開催いたします.
日時:5月25日(土)14:00〜15:30
会場:北とぴあ 第2研修室(東京都北区王子)
定款20条により,本総会は役員ならびに代議員による総会となります.正会員
は,総会に陪席することができます.
※同日同会場にて下記の催しが予定されています.
◆第10回惑星地球フォトコンテスト表彰式・展示会
時間:11:00〜12:30
http://www.geosociety.jp/faq/content0009.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】日本地質学会が大型研究計画に提案!!
──────────────────────────────────
大型研究計画:地球惑星研究資料のアーカイブ化とキュレーション
システムの構築
大型研究計画とは,世界の学術研究を先導する画期的な成果を挙
げる大型プロジェクトを,社会や国民の幅広い理解と支持を得つつ,
国家プロジェクトとして推進する施策です.日本地質学会では,多
くの会員が切望し,かつ現在のみならず将来にわたって持続的に地
球科学研究を発展させるために「地球惑星研究資料のアーカイブ化
とキュレーションシステムの構築」を大型施設計画として提案しま
した.
◆今後の予定(大型研究計画の公聴会)
日程:5月27日(月)14:08より発表予定
会場:JpGU2019年大会ユニオンセッション「地球惑星科学の進むべ
き道9:大型研究計画とマスタープラン2020」会場
当日は各発表について,随時アンケート投票が受け付けられ,地球
惑星科学に携わる研究者から広く意見を聴取する予定です.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/news/n143.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質学雑誌からのお知らせ
──────────────────────────────────
(1)[お詫び]第125巻 第4号(2019年4月号)発送遅延(5/7発送).
第125巻第4号(2019年4月号)が刊行されましたが,大型連休の影響
で印刷工場や発送業者との早めの調整ができず,本日(5/7)発送と
なりました.皆様のお手元には通常より1週間〜10日ほど遅れての到
着となる見込みです.論文著者はじめ会員の皆様には,ご迷惑をお
かけし大変申し訳ございません.何卒ご了承下さい.
【125巻4月号:最新号目次はこちら】
http://www.geosociety.jp/publication/content0092.html
(2)編集規則が改訂されました(4月6日理事会承認).
・カテゴリーに「レター(Letter)」と「用語解説(Glossary)」が
加わりました
・文献欄の書式が変更になりました(英訳は日本語の後にまとめて
記す...)等
改訂版編集規則は,4月号巻末,学会HPに掲載されています.投稿原
稿作成の際は,規則をご確認頂きますようお願い致します.
投稿編集出版規則はこちらから
http://www.geosociety.jp/publication/content0002.html#touko
(3)受理論文の印刷前に,Accepted ManuscriptとしてPDFファイル
を作成し,順次WEBサイトで公開しています. https://sub.geosociety.jp/user.php
(注意:会員ページへのログインが必要です)
早期公開について・・・
http://www.geosociety.jp/publication/content0061.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】Island Arcからのお知らせ
──────────────────────────────────
論文投稿ワークショップ〜国際誌への投稿論文を初めて書く人へのアドバイス〜
投稿論文はプロ研究者による厳しい査読を経たのちに掲載の可否が
決まります.査読を難なくクリアできる論文を書くには,論文構成
法の順守と分かりやすさの洗練が欠かせません.このワークショッ
プでは,日本地質学会の公式英文誌Island Arc(刊行はWiley)の
Editor-in-Chiefを務める長崎大学・武藤教授が,投稿論文を執筆す
る際の基本的なルールと初心者が陥りやすい過ちについて易しく解
説します.講演は日本語で行われます.
主催:日本地球惑星科学連合 協力:ワイリー
日時:5月28日(火)12:30〜13:30
会場:幕張メッセ国際会議場105号室(JpGU2019会場内)
講師:武藤鉄司(Island Arc 編集委員長・長崎大学)
参加費無料・要事前登録
https://wiley.qualtrics.com/jfe/form/SV_6RvmTSRMFBJMFhj
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】2019年地質の日記念行事
──────────────────────────────────
2019年の「地質の日」に関連した日本地質学会主催,共催,後援等
の催しをご紹介します.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/name/content0165.html
<学会主催・共催>
◆第10回惑星地球フォトコンテスト【表彰式】
5月25日(土)11:00〜12:30
会場:北とぴあ 第2研修室(東京都北区王子)
入選作品は,こちら
http://www.geosociety.jp/faq/content0009.html
◆第10回惑星地球フォトコンテスト【展示会】
5月14日(火)〜5月19日(日)
場所:上野恩賜公園 上野グリーンサロン内(台東区上野公園7-47)
入選作品は,こちら
http://www.geosociety.jp/faq/content0009.html
◆地質の日記念展示「失われた川を尋ねて『水の都』札幌」
開催中〜6月16日(日)
場所:北海道大学総合博物館1階 企画展示室
共催:日本地質学会北海道支部ほか
〇市民セミナー
5月11日(日)第一回「水の都」札幌−コトニ川を尋ねて
6月9日(日)第二回「水の都」その誕生と消滅 〜身近に残る水の痕跡〜
〇市民地質巡検
5/25(土)街中ジオ散歩 in Sapporo 「コトニ川を歩く」
申込締切:5月17日(金)必着
https://www.museum.hokudai.ac.jp/contents/calendar/event/14451/
<その他>
◆観察会 城ヶ島 火山と地震痕跡を見る
後援:日本地質学会ほか
5月18日(土)10:00〜15:00
場所:神奈川県三浦市城ヶ島
申込締切:5月13日(月)定員:20名(先着順受付)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
──────────────────────────────────
[東北支部]
地質見学会「能代・八峰・白神地域のジオサイトを訪ねて」
6月22日(土)〜23日(日)
案内人:林信太郎・藤本幸雄・西川 治
募集人数:15名
費用:15,000〜18,000円を予定(初日の昼食は持参)
参加申込締切:6月4日(火)
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
[関東支部]
■清澄フィールドキャンプ
8月19日(月)〜24日(土)5泊6日
場所:東京大学演習林(〒299-5505千葉県鴨川市清澄)
費用:40,000円程度を予定(宿泊・食事・保険・タクシー代込)
定員:最大4名(学生のみ,最少催行人数は3名)
参加申込締切:7月5日(金)
http://kanto.geosociety.jp/
■サイエンスカフェ「マンネン×シバハラ×立体地図(ブラマンネン2)」
6月9日(日)15〜17時(14時半開場)
場所:Bar de 南極料理人 Mirai
ゲストスピーカー:萬年一剛(神奈川県温泉地学研究所)・芝原暁彦(地球科学
可視化技術研究所)
ファシリテータ:岡山悠子(科博SCA)
入場料:2,000円(1ドリンク込)
イベント終了後に演者と希望者による懇親会を開催(4,000円)
https://sites.google.com/view/buraman2/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■阿蘇山の地下を見てみよう ボーリングコア公開と火山講座
防災科研の阿蘇山火山観測施設設置の際のボーリング掘削工事で得られたボー
リングコア試料(深度200mのオールコア4本)を公開展示します.
5月12日(日)13:00〜16:30
場所:阿蘇火山博物館
定員は150名(先着で定員に達し次第締切)
http://www.asomuse.jp/category/news/
■NUMO包括的技術報告書(レビュー版)の外部専門家向け説明会
(1) 大阪会場(定員:80名,参加申込締切:5/17)
日時:5月22日(水) 9:30〜17:30
会場:大阪科学技術センタービル 8階中ホール
(2)東京会場(定員:150名,参加申込締切:5/21)
日時:5月24日(金)9:30〜17:30
会場:CIVI研修センター日本橋
https://www.numo.or.jp/topics/201919042612.html
■日本学術会議主催学術フォーラム
「産学共創の視点から考える人材育成」
5月22日(水)13:00〜17:00
場所:日本学術会議講堂
定員:先着250名(参加費無料)
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/275-s-0522.pdf
■日本地球惑星科学連合2019年大会
5月26日(日)〜30日(木)
会場:千葉県 幕張メッセ国際会議場・国際展示場ホール8
東京ベイ幕張ホール
大会参加登録(早期割引):5月8日(水)締切
http://www.jpgu.org/meeting_2019/
■深田研ジオフォーラム2019
6月8日(土)10:00〜16:00
場所:深田地質研究所 研修ホール(東京都文京区)
講師:上野将司氏(応用地質株式会社社友)
演題:平野と山地の地盤災害を考える〜災害列島での調査経験から〜
参加費:一般5,000円,学生1,000円(資料代を含む)
定員:50名【申込多数の場合は抽選】*要事前申込
http://www.fgi.or.jp/
(後)観察会:荒崎海岸の地形と地質を学ぶ
6月9日(日)10:00〜15:00(雨天中止)
参加費:500円・先着30名
問い合わせ:三浦半島活断層調査会(赤須)
<akasu@jcom.zaq.ne.jp>
(後)第56回アイソトープ・放射線研究発表会
7月3日(水)〜5日(金)
会場:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
https://www.jrias.or.jp/
(後)第63回粘土科学討論会
9月10日(火)〜12日(木)
(講演会:9月10〜11日,現地見学会:9月12日)
会場:埼玉大学(さいたま市桜区下大久保225)
http://www.cssj2.org/publication/annual_meeting/
★ 日本地質学会第126年学術大会(2019山口)
9月23日(月・祝)〜25日(水)
場所:山口大学 吉田キャンパス(山口市吉田)
http://www.geosociety.jp/science/content0106.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0191.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・フォッサマグナミュージアム学芸員(常勤)募集(6/15)
・福井県立恐竜博物館古生物学職研究職員募集(5/31)
・福岡大学理学部地球圏科学科地球科学分野 教授,准教授または講師公募(7/1)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No.448(臨時)地質雑4月号発送遅延[お詫び]
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.448 2019/4/26┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】地質学雑誌からのお知らせ
──────────────────────────────────
(1)[お詫び]第125巻 第4号(2019年4月号)発送遅延(5/7発送).
第125巻第4号(2019年4月号)は校了となり,まもなく刊行されます.
しかし,今年は大型連休の影響で印刷工場や発送業者との早めの調整ができず,
雑誌の発送は5月7日となる予定です.皆様のお手元には例年より1週間〜10日ほ
ど遅れての到着となる見込みです.論文著者はじめ会員の皆様には,ご迷惑を
おかけし大変申し訳ございません.何卒ご了承下さい.
【125巻4月号】(論説)愛知県本宮山地域における領家変成岩中の十字石の
産状を制御する化学的要因 四坂駿弥ほか計5編
最新号目次はこちら
http://www.geosociety.jp/publication/content0092.html
(2)編集規則が改訂されました(4月6日理事会承認).
・カテゴリーに「レター(Letter)」と「用語解説(Glossary)」が加わりました
・文献欄の書式が変更になりました(英訳は日本語の後にまとめて記す...)等
改訂版編集規則は,4月号巻末,学会HPに掲載されています.投稿原稿作成の際
は,規則をご確認頂きますようお願い致します.
投稿編集出版規則はこちらから
http://www.geosociety.jp/publication/content0002.html#touko
(3)受理論文の印刷前に,Accepted ManuscriptとしてPDFファイルを作成し,
順次WEBサイトで公開しています.https://sub.geosociety.jp/user.php
(注意:会員ページへのログインが必要です)
早期公開について・・・
http://www.geosociety.jp/publication/content0061.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No.450[2019山口大会]まもなく講演申込開始です!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.450 2019/5/21┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[2019山口大会]まもなく講演申込開始です!
【2】[2019山口大会]シンポ・セッションが確定しました
【3】[2019山口大会]宿泊予約の情報
【4】日本地質学会第11回総会開催(5/25)
【5】日本地質学会が大型研究計画に提案!
【6】Island Arc:論文投稿ワークショップのご案内
【7】2019年地質の日記念行事
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2019山口大会]まもなく講演申込開始です!
──────────────────────────────────
山口大会予告記事は,ニュース誌5月号にてご案内予定です.5月末頃より
講演申込開始予定です.
余裕をもってご準備をお願いします.
おもな締切は以下の通りです.
・演題登録・講演要旨提出:7月3日(水)
・ランチョン・夜間集会申込:7月3日(水)
・小さなESのつどい発表申込:7月26日(金)
・事前参加登録/巡検/懇親会参加申込:8月19日(金)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2019山口大会]シンポジウム・セッション
──────────────────────────────────
山口大会では,2つのシンポジウムと33のセッション(トピック7件,レギュラー
25件,アウトリーチ1件)が予定されています.
(シンポジウム)
S1. 島弧ダイナミクス研究のフロンティア
S2. 西日本で多発する土石流災害:平成21年7月中国・九州北部豪雨から10年
(トピックセッション)
T1. 日本海拡大に関連したテクトニクス,堆積作用,マグマ活動,古環境
T2. 大学・博物館における学術標本の未来:人口減少・災害多発社会における
標本散逸問題を考える
T3. 人新世の堆積学
T4. 文化地質学
T5. 集大成!南海トラフ地震発生帯掘削計画
T6. 中国地方の活断層,地震活動とひずみ集中帯
T7. 日本列島形成史の新景観
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2019山口大会]宿泊予約の情報
──────────────────────────────────
【宿泊予約】*担当(株)防長トラベル 山口支店
会場最寄りの湯田温泉に約350室を確保しています.
申込締切:2019年7月30日(火)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0108.html
【若手会員向けルームシェア型宿泊プラン】
山口大会では若手会員向けの宿泊施設をご用意いたしました.「若
手同士の交流」と「低価格化」の観点から,本プランは,相部屋で
のご案内となっております.内容をよくご確認の上,ご検討ください.
対象となる若手会員:学生(学部,修士,博士)およびポスドク研究員
申込締切:2019年7月31日(水)先着順
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0110.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】日本地質学会第11回総会開催(5/25)
──────────────────────────────
日時:5月25日(土)14:00-15:30
会場:北とぴあ 第2研修室(東京都北区王子)
定款20条により,本総会は役員ならびに代議員による総会となります.正会員
は,総会に陪席することができます.
議事次第はこちら、 http://www.geosociety.jp/outline/content0152.html
※同日同会場にて下記の催しが予定されています.
◆第10回惑星地球フォトコンテスト表彰式・展示会
時間:11:00-12:30
http://www.geosociety.jp/faq/content0009.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】日本地質学会が大型研究計画に提案
──────────────────────────────────
大型研究計画とは,世界の学術研究を先導する画期的な成果を挙げ
る大型プロジェクトを,社会や国民の幅広い理解と支持を得つつ,
国家プロジェクトとして推進する施策です.
日本地質学会は,「地球惑星研究資料のアーカイブ化とキュレーショ
ンシステムの構築」を大型施設計画として提案しました.
<大型研究計画の公聴会が行われます>
日程:5月27日(月)14:08より発表予定
会場:JpGU2019年大会ユニオンセッション「地球惑星科学の進むべ
き道9:大型研究計画とマスタープラン2020」会場
当日は各発表について,随時アンケート投票が受け付けられ,地球
惑星科学に携わる研究者から広く意見を聴取する予定です.
詳しくは, http://www.geosociety.jp/news/n143.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】Island Arc:論文投稿ワークショップのご案内
──────────────────────────────────
「国際誌への投稿論文を初めて書く人へのアドバイス」
投稿論文はプロ研究者による厳しい査読を経たのちに掲載の可否が
決まります.査読を難なくクリアできる論文を書くには,論文構成
法の順守と分かりやすさの洗練が欠かせません.このワークショッ
プでは,投稿論文を執筆する際の基本的なルールと初心者が陥りや
すい過ちについて易しく解説します.講演は日本語で行われます.
主催:日本地球惑星科学連合 協力:ワイリー
日時:5月28日(火)12:30-13:30
会場:幕張メッセ国際会議場105号室(JpGU2019会場内)
講師:武藤鉄司(Island Arc 編集委員長・長崎大学)
参加費無料・要事前登録
https://wiley.qualtrics.com/jfe/form/SV_6RvmTSRMFBJMFhj
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】2019年地質の日記念行事
──────────────────────────────────
2019年の「地質の日」に関連した日本地質学会主催,共催,後援等
の催しをご紹介します.
詳しくは, http://www.geosociety.jp/name/content0165.html
◆第10回惑星地球フォトコンテスト【表彰式】
5月25日(土)11:00-12:30
会場:北とぴあ 第2研修室(東京都北区王子)
どなたでもご参加いただけます.作品の展示あり.
入選作品は,こちら
http://www.geosociety.jp/faq/content0009.html
◆地質の日記念展示「失われた川を尋ねて『水の都』札幌」
6月16日(日)まで開催中
場所:北海道大学総合博物館1階 企画展示室
共催:日本地質学会北海道支部ほか
〇市民セミナー
6月9日(日)第二回「水の都」その誕生と消滅:身近に残る水の痕跡
https://www.museum.hokudai.ac.jp/contents/calendar/event/14451/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
──────────────────────────────────
[北海道支部]
■令和元年度総会・例会(個人講演会)
6月15日(土)総会:11:00-12:00 例会:13:00-18:00(時間は予定)
場所:北海道大学理学部5号館大講堂(5-203)
講演申込:5月24日(金)締切
講演要旨の提出:6月7日(金)締切
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[東北支部]
■地質見学会「能代・八峰・白神地域のジオサイトを訪ねて」
6月22日(土)-23日(日)
案内人:林信太郎・藤本幸雄・西川 治
募集人数:15名
費用:15,000-18,000円を予定(初日の昼食は持参)
参加申込締切:6月4日(火)
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
[中部支部]
■2019年支部年会
6月29日(土)10:00から
会場:福井県立大学永平寺キャンパス 多目的ホール
・シンポジウム「恐竜渓谷ふくい勝山ジオパークとそれを取り巻く活動(仮)」
・巡検「恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク見学」
日程:6月30日(日),定員:20名,費用:2,000円を予定(昼食代込)
講演・参加申込締切:5月24日(金)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
[関東支部]
■清澄フィールドキャンプ
8月19日(月)-24日(土)5泊6日
場所:東京大学演習林(〒299-5505千葉県鴨川市清澄)
費用:40,000円程度を予定(宿泊・食事・保険・タクシー代込)
参加申込締切:7月5日(金)
http://kanto.geosociety.jp/
■サイエンスカフェ「マンネン×シバハラ×立体地図(ブラマンネン2)」
6月9日(日)15:00-17:00(14:30開場)
場所:Bar de 南極料理人 Mirai
ゲストスピーカー:萬年一剛(神奈川県温泉地学研究所)・芝原暁彦(地球科
学可視化技術研究所)
入場料:2,000円(1ドリンク込)
https://sites.google.com/view/buraman2/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地質研究所ニュース
北海道の被害地震発生ポテンシャル:千島海溝で進む超巨大地震の準備と内陸
地震ほか
http://www.hro.or.jp/list/environmental/research/gsh/publication/gshnews/gshnews02/vol34_no4.pdf
--------------------------------------------
■日本地球惑星科学連合2019年大会
5月26日(日)-30日(木)
会場:千葉県 幕張メッセ国際会議場・国際展示場ホール8
東京ベイ幕張ホール
http://www.jpgu.org/meeting_2019/
■深田研ジオフォーラム2019
6月8日(土)10:00-16:00
場所:深田地質研究所 研修ホール(東京都文京区)
講師:上野将司(応用地質株式会社社友)
演題:平野と山地の地盤災害を考える:災害列島での調査経験から
参加費:一般5,000円,学生1,000円(資料代を含む)
定員:50名【申込多数の場合は抽選】*要事前申込
http://www.fgi.or.jp/
(後)観察会:荒崎海岸の地形と地質を学ぶ
6月9日(日)10:00-15:00(雨天中止)
参加費:500円・先着30名
問い合わせ:三浦半島活断層調査会(赤須)
akasu@jcom.zaq.ne.jp >
■石油技術協会春季講演会
6月12日(水)-13日(木)
会場:国立オリンピック記念青少年総合センター(代々木)
プログラム
https://www2.japt.org/direct/topics/topics_pdf_download/topics_id=1729&disp=inline
(後)第56回アイソトープ・放射線研究発表会
7月3日(水)-5日(金)
会場:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
https://www.jrias.or.jp/
■第73回地学団体研究会総会(東京)
8月23日(金)-25日(日)
場所:東京都港区 芝学園中学校高等学校
https://www.chidanken.jp
■自然史博物館ネットワークに関する国際シンポジウム
主催:自然史学会連合・京都大学総合博物館
参加費無料
【シンポジウム】9月4日(水)
会場:京都大学医学部創立百周年記念施設 芝蘭会館稲盛ホール
【ポスター発表】9月4日(水)-5日(木)
会場:京都大学総合博物館
地質学系学芸員からの参加・展示発表申込をお待ちしています
(発表申込:6/10から).
http://ujsnh.org/sympo/20190904_kyoto/index.html
(後)第63回粘土科学討論会
9月10日(火)-12日(木)
(講演会:9月10-11日,現地見学会:9月12日)
会場:埼玉大学(さいたま市桜区下大久保225)
http://www.cssj2.org/publication/annual_meeting/
★ 日本地質学会第126年学術大会(2019山口)
9月23日(月・祝)-25日(水)
場所:山口大学 吉田キャンパス(山口市吉田)
http://www.geosociety.jp/science/content0106.html
■第73回日本人類学会大会
10月12日(土)-14日(月)
会場:佐賀大学本庄キャンパス(佐賀市本庄町1)
演題登録締切:7月29日(月)
http://anthrop-meeting.sakura.ne.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0191.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・室戸ユネスコ世界ジオパーク研究助成事業(6/15)
・南紀熊野ジオパーク研究助成金交付事業募集(7/5)
・京都大学大学院人間・環境学研究科相関環境学専攻准教授公募(6/28)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No.451(臨時)[2019山口大会]講演申込開始:まずはアカウント登録を!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.451 2019/5/31┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】[2019山口大会]講演申込開始:まずはアカウント登録を!
【2】[2019山口大会]ランチョン・夜間集会申込受付中
【3】[2019山口大会]大会参加登録もまもなく受付開始です
【4】[2019山口大会]小さなEarth Scientistのつどい:参加校募集
【5】[2019山口大会]宿泊予約の情報
★山口大会HP★
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2019山口大会]講演申込開始:まずはアカウント登録を!
──────────────────────────────────
山口大会講演申込・講演要旨投稿の受付を開始しました!
*********************************************
演題登録・講演要旨提出:7月3日(水)18時
*********************************************
お申込は,山口大会HPから
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/collectsubject
<<まずはアカウント登録を>>
登録には,【山口大会演題登録専用のアカウント登録】が必要
となります.締切(7月3日18時)まで何度でも修正や要旨差替が可
能ですので,まずは,アカウント登録をされることをお勧めします.
なお,大会予告記事は,ニュース誌5月号に掲載しています(本日発
送.まもなくお手元に届きます).
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2019山口大会]ランチョン・夜間集会申込受付中
──────────────────────────────────
会合開催をご希望の場合は,必要な申込項目をe-mailで行事委員会宛に忘れずに
お申し込み下さい.
***************************
申込締切:7月3日(水)
***************************
詳しくは,大会HPまで
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/meeting
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2019山口大会]大会参加登録もまもなく受付開始です
──────────────────────────────────
参加登録に関わるお申込(大会参加・要旨集注文,巡検,懇親会,
弁当)についても,例年通りオンラインによる大会専用参加登録シ
ステムを準備中です(会員・非会員とわず,どなたでも申込可能..
6月中旬頃より受付開始予定です.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2019山口大会]小さなEarth Scientistのつどい:参加校募集
──────────────────────────────────
児童・生徒の参加が難しい学校も多くあると予想されます.その場
合は,発表ポスターのみをお送りいただいても結構です.審査は,
昨年札幌大会でも採用されたデジタルポスター審査を行います.こ
の会を通じて日頃の研究成果を披露していただき,地質学,地球科
学への理解が深まって,未来を担う生徒たちの学習意欲への良い刺
激と励みになることを願っております.
日時:9月23日(月・祝)
場所:山口大会ポスター会場(山口大学吉田キャンパス内)
参加申込締切:7月26日(金)
詳しくは,
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/gyoji#es
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2019山口大会]宿泊予約の情報
──────────────────────────────────
【宿泊予約】*担当(株)防長トラベル 山口支店
会場最寄りの湯田温泉に約350室を確保しています.
申込締切:2019年7月30日(火)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0108.html
【若手会員向けルームシェア型宿泊プラン】
山口大会では若手会員向けの宿泊施設をご用意いたしました.「若
手同士の交流」と「低価格化」の観点から,本プランは,相部屋で
のご案内となっております.内容をよくご確認の上,ご検討ください.
対象となる若手会員:学生(学部,修士,博士)およびポスドク研究員
申込締切:2019年7月31日(水)先着順
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0110.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)
配信予定です.原稿は配信前週金曜日までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)
へお送りください.
【geo-Flash】 No.452 山口大会関連情報 ほか
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.452 2019/6/4┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
[2019山口大会情報]
【1】講演申込受付中:まずはアカウント登録を!
【2】ランチョン・夜間集会申込受付中
【3】大会参加登録もまもなく受付開始です
【4】小さなEarth Scientistのつどい:参加校募集
【5】宿泊予約の情報
------------------------------------------------------------
【6】2019年地質の日記念行事
【7】本の紹介「新しい地球惑星科学」
【8】支部情報(関東支部サイエンスカフェのご案内 ほか)
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
【11】訃報:武田裕幸 名誉会員 逝去
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2019山口大会]講演申込受付中:まずはアカウント登録を!
──────────────────────────────────
演題登録には,【山口大会演題登録専用のアカウント登録】が必要
となります.締切(7月3日18時)まで何度でも修正や要旨差替が可
能ですので,まずは,アカウント登録をされることをお勧めします.
*********************************************
演題登録・講演要旨提出:7月3日(水)18時
*********************************************
お申込は,山口大会HPから
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/collectsubject
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2019山口大会]ランチョン・夜間集会申込受付中
──────────────────────────────────
会合開催をご希望の場合は,必要な申込項目をe-mailで行事委員会宛に忘れず
にお申し込み下さい.
***************************
申込締切:7月3日(水)
***************************
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/meeting
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2019山口大会]大会参加登録もまもなく受付開始です
──────────────────────────────────
参加登録に関わるお申込(大会参加・要旨集注文,巡検,懇親会,
弁当)についても,例年通りオンラインによる大会専用参加登録シ
ステムを準備中です(会員・非会員とわず,どなたでも申込可能..
6月中旬頃より受付開始予定です.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2019山口大会]小さなEarth Scientistのつどい:参加校募集
──────────────────────────────────
児童・生徒の参加が難しい学校も多くあると予想されます.その場
合は,発表ポスターのみをお送りいただいても結構です.審査は,
昨年札幌大会でも採用されたデジタルポスター審査を行います.こ
の会を通じて日頃の研究成果を披露していただき,地質学,地球科
学への理解が深まって,未来を担う生徒たちの学習意欲への良い刺
激と励みになることを願っております.
日時:9月23日(月・祝)
場所:山口大会ポスター会場(山口大学吉田キャンパス内)
参加申込締切:7月26日(金)
詳しくは,https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/gyoji#es
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2019山口大会]宿泊予約の情報
──────────────────────────────────
【宿泊予約】*担当(株)防長トラベル 山口支店
会場最寄りの湯田温泉に約350室を確保しています.
申込締切:2019年7月30日(火)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0108.html
【若手会員向けルームシェア型宿泊プラン】
山口大会では若手会員向けの宿泊施設をご用意いたしました.「若
手同士の交流」と「低価格化」の観点から,本プランは,相部屋で
のご案内となっております.内容をよくご確認の上,ご検討ください.
対象となる若手会員:学生(学部,修士,博士)およびポスドク研究員
申込締切:2019年7月31日(水)先着順
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0110.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】2019年地質の日記念行事
──────────────────────────────────
2019年の「地質の日」に関連した日本地質学会主催,共催,後援等
の催しをご紹介します.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/name/content0165.html
◆地質の日記念展示「失われた川を尋ねて『水の都』札幌」
6月16日(日)まで開催中
場所:北海道大学総合博物館1階 企画展示室
共催:日本地質学会北海道支部ほか
〇市民セミナー
6月9日(日)第二回「水の都」その誕生と消滅:身近に残る水の痕跡
https://www.museum.hokudai.ac.jp/contents/calendar/event/14451/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】本の紹介「新しい地球惑星科学」
──────────────────────────────────
「新しい地球惑星科学」
西山忠男・吉田茂生 共編著
培風館,2019年3月13日発行,B5判 287頁カラー刷り,定価3,080円(税別)
本書は熊本大学・九州大学の教員を中心とした30人の執筆陣による大学教養程度の地学の教科書である.「はじめに」によると,大学における教育の質保証のために日本学術会議が平成26年に制定した「教育課程編成上の参照基準 地球科学分野」に基づき,その制定を主導した西山忠男が中心になって,この基準を体現する教科書を制作したものである.本書は基礎編15章,応用編15章よりなり,大学の通年の授業30コマに対応している.
各章の魅力的な題名を簡略化して内容を示すと,基礎編は1. 太陽系の構成と惑星の運動,2. 宇宙の進化,3. 恒星と太陽,4. 高層大気,5. 大気の運動,6. 海洋の運動,7. 風化侵食運搬堆積,8. 地球内部構造,9. 岩石鉱物,10. プレート論,11. 化石と地質時代,12. 火山,13. 地震,14. 気象災害,15. 地球と人類,となっており,応用編は1. 惑星各論,2. 地球の形と重力,3. 同位体と年代学,4. 地球の進化,5. 大気海洋相互作用,6. 地球温暖化,7. マントル対流,8. コアと地磁気,9. 鉱物・結晶学,10. 生物進化と地球史,11. 陸水循環と地層形成,12. 造山運動と変成作用,13. 日本列島の形成,14. 海洋底,15.鉱物エネルギー資源,となっている.付録として1. 静水圧平衡とアイソスタシー,2. 顕生代地質年代表がある.他にコラム記事として渦位(p. 45),ロスビー波の西進(46),断熱温度勾配(87),玄武岩の岩石学的分類(96),弾性体と弾性定数(106),相転移と脱水脆性化(118),ジオイド異常と重力異常(147),s-プロセスとr-プロセス(148),U-Pb年代法の利点(156),惑星形成時の加熱(157), テイラー・プラウドマン定理(194),地磁気ポテンシャル(196),成長速度と駆動力(208),逆空間と逆格子点(211),日本の国石(233),藍閃石(234),かんらん岩・蛇紋岩メランジュ(236),Al2SiO5鉱物の多形(238)があり,どれも興味深いので目次に掲載した方がよい.一部の章末には演習問題があるが,模範解答はない.巻末の引用・参考文献には和文教科書だけでなく洋書や学術雑誌の論文もある.本学会のフィールドジオロジーシリーズも数冊引用してあるが,書誌データの記述法が不統一である.本学会編の日本地方地質誌(「九州沖縄地方」の主編者は西山),本学会が執筆協力したThe Geology of Japanも引用してほしかった.本書は,数研出版「地学図録」(2018改
訂版)に次いでカラーの図や写真が豊富だが,著者構成の影響か災害・露頭写真は九州の例が多い.基礎編14章の冒頭(p.116)で「天災は忘れた頃来る」に関し「西日本新聞の解説を参照」となっている.地震のマグニチュード,震源断層サイズ,平均すべり量の図(p. 111)の背景は九州で,東北地方太平洋沖地震の表面波も雲仙での観測例を取り上げている(p. 107).
最近の同様な教科書として早稲田大学の教員9人による「地球・環境・資源」(共立,2008年),山口大学の教員ら6人による「基礎地球科学 第2版」(朝倉,2010年)があるが,この2編は高校地学で扱う天文・気象分野の内容をほとんど含まないのに対して,本書は基礎編の1〜6章と14章,応用編の1, 5, 6章等でかなり詳しく取り上げている.また,化石や進化は生物学の対象でもあり,これらの点で「はじめに」冒頭の「地球惑星科学の対象は,われわれを取り巻く環境のうち,生物学や天文学が対象としているものを除くすべてである」という記述は本書の内容と合致しない.我々を取り巻く無機的な自然全てを即物的(あるがまま)に科学するのが地学であり,本書は天文学も含む「大学地学の教科書」だと思う.
本書の内容で気がついたことを述べる.基礎編1章p.1最下行に,明るい惑星を「太陽,月と合わせて日月五星とよぶ」とあるが,この語は広辞苑に出ておらず,あまり聞いたことがない.これらを七曜(古代中国では七政)とよび,週の各曜日の名称とするのは常識である.太陽系の惑星軌道の記述(p. 6)にはボーデ(Bode)の法則(2n×3+4, n=−∞,0, 1, 2…)を示してほしい.
基礎編10章p. 78の過去2億年間のプレート運動と大陸移動を示す6枚のカラー図は非常に印象的で,太平洋プレートがいつ,どこで発生し,どのように拡大したかがよくわかる.しかし,松山基範による地磁気逆転の発見と第四紀逆転史に触れていないのは残念である.
応用編1章では新しい隕石分類を解説しているが(p.134),「分化隕石」なのに「始原的エコンドライト」というのは矛盾した命名ではないか.記号ばかり並べて意味不明な分類は,本書のような大学教養の教科書ではやめてほしい.イトカワやリュウグウに言及しているのはタイムリーで良いが,日本国内で相次ぐ隕石の発見も取り上げてほしかった.応用編9章で特性X線の図を出すなら,モーズレー(Moseley)の法則も紹介してほしい.
応用編11章(p. 228) でnonconformityを「無整合」と訳し,不整合の種類を説明しているが,地学事典の不整合項目ではカタカナ書きであり,公式の地質図で「無整合」を使うことはまずない.下側が火成岩・変成岩でも不整合で済ますのが普通で,無用な語だと思う.
私の専門に近い分野しか判断できないが,先人の業績に関する引用の不適が散見される.応用編13章の海洋プレート層序の説明(p. 243) では,Isozaki et al.(1990;Tectonophysics, 181, 179-)または彼のその後の論文を引用すべきだと思う.日本海拡大の平行移動モデル(南北展張もその一種)(p.245) はTerada(1927; 地震研彙報, 3, 67-)が最初に提唱し,Lallemand & Jolivet(1985;EPSL, 76, 375-)がプルアパート運動と結びつけた.「災害は忘れた頃に」を引くなら(p.116),寺田寅彦が日本海拡大説の最初の提唱者だったことも教えてほしい(石渡・磯粼(2011)「東北アジア 大地のつながり」東北大学出版会参照).
各ページ余白の小字の追加説明(脚注)は親切で興味深いが,できれば本文中の主な専門用語の英語表記を示し,その索引をつけてほしい.英語の教科書や論文を読み始める学生の助けになると思う.基礎編10章と応用編6, 7章は本文中に英語が付記されているが,他の章はその配慮が乏しい.ただし基礎編4章にはバウとボウの違い等,面白い解説がある.また,序文の下に培風館の本書ホームページURLがあり,アクセスすると6件の正誤表が載っていた.ただし,「WEB」のサインは本書内になく,上記URLにも追加情報はなかった.
厳しいことも述べたが,この教科書は高校地学の全範囲を網羅し,大学1年生でも大学教員でも面白く読め,地学の楽しさが随所で実感できる,積極的で創意工夫に満ちた,そして地学全体の最新の内容をカラフルに盛り込んだ,これまでにない高品質の大学地学教科書である.本書が今後の大学教育で広く利用されることを期待する.
(石渡 明)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報(関東支部 サイエンスカフェのご案内 ほか)
──────────────────────────────────
[関東支部]
■サイエンスカフェ「マンネン×シバハラ×立体地図(ブラマンネン2)」
6月9日(日)15:00-17:00
場所:Bar de 南極料理人 Mirai
ゲストスピーカー:萬年一剛・芝原暁彦
入場料:2,000円(1ドリンク込)
*イベント終了後,演者と希望者の方々との懇親会を予定しています
(料金別途 4,000円,2時間程度:懇親会申込締切:6月5日(水)朝10時)
https://sites.google.com/view/buraman2/
■清澄フィールドキャンプ
8月19日(月)-24日(土)5泊6日
場所:東京大学演習林(〒299-5505千葉県鴨川市清澄)
費用:40,000円程度を予定(宿泊・食事・保険・タクシー代込)
*ただし,日本地質学会の学生・院生会員,または日本地質学会
に入会することを確約できる学生・院生は,20,000円とします.
参加申込締切:7月5日(金)
http://kanto.geosociety.jp/
[北海道支部]
■令和元年度総会・例会(個人講演会)
6月15日(土)総会:11:00-12:00 例会:13:00-18:00(時間は予定)
場所:北海道大学理学部5号館大講堂(5-203)
講演要旨の提出:6月7日(金)締切
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
[東北支部]
■地質見学会「能代・八峰・白神地域のジオサイトを訪ねて」
6月22日(土)-23日(日)
案内人:林信太郎・藤本幸雄・西川 治
募集人数:15名
費用:15,000-18,000円を予定(初日昼食は持参)
参加申込締切:6月4日(火)
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
[中部支部]
■2019年支部年会
6月29日(土)10:00から
会場:福井県立大学永平寺キャンパス 多目的ホール
シンポジウム「恐竜渓谷ふくい勝山ジオパークとそれを取り巻く活動(仮)」
http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■第9回学生ヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集
日程(仮):2020年3月4日〜18日(出国から帰国まで15日間)
参加申込締切:2019年12月31日
参加費:学生・大学院生 20万円以内
http://www.gondwanainst.org/geotours/Studentfieldex_index.htm
---------------------------------------------------------------------
(後)観察会:荒崎海岸の地形と地質を学ぶ
6月9日(日)10:00-15:00(雨天中止)
参加費:500円・先着30名
問い合わせ:三浦半島活断層調査会(赤須)
(後)第56回アイソトープ・放射線研究発表会
7月3日(水)-5日(金)
会場:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
https://www.jrias.or.jp/
■自然史博物館ネットワークに関する国際シンポジウム
主催:自然史学会連合・京都大学総合博物館
参加費無料
【シンポジウム】9月4日(水)
会場:京都大学医学部創立百周年記念施設 芝蘭会館稲盛ホール
【ポスター発表】9月4日(水)-5日(木)
会場:京都大学総合博物館
地質学系学芸員からの参加・展示発表申込をお待ちしています
(発表申込:6/10から).
http://ujsnh.org/sympo/20190904_kyoto/index.html
(後)第63回粘土科学討論会
9月10日(火)-12日(木)
(講演会:9月10-11日,現地見学会:9月12日)
会場:埼玉大学(さいたま市桜区下大久保225)
http://www.cssj2.org/publication/annual_meeting/
★ 日本地質学会第126年学術大会(2019山口)
9月23日(月・祝)-25日(水)
場所:山口大学 吉田キャンパス(山口市吉田)
http://www.geosociety.jp/science/content0106.html
■第73回日本人類学会大会
10月12日(土)-14日(月)
会場:佐賀大学本庄キャンパス(佐賀市本庄町1)
演題登録締切:7月29日(月)
http://anthrop-meeting.sakura.ne.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0191.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・早稲田大学教育・総合科学学術院地球科学専修専任講師又は准教授公募(7/10)
・JAMSTEC付加価値情報創生部門数理科学・先端技術研究開発センター計算科学・
工学グループ 特任研究員/特任技術研究員/特任技術職のいずれか1名(6/14)
・兵庫県立人と自然の博物館研究員(古生物学・岩石学)募集(6/26)
・栗駒山麓ジオパーク学術研究等奨励補助金の募集(8/31)
・ゆざわジオパーク学術研究等奨励補助金の募集(6/28)
・八峰白神ジオパーク人員(地域おこし協力隊)の募集(随時募集)
・下北ジオパーク研究補助金の募集(6/13)
・第14回「科学の芽」賞募集(8/19-9/21)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】訃報:武田裕幸 名誉会員 逝去
──────────────────────────────────
武田裕幸 名誉会員(元日本地質学会副会長:1984-87)が,令和元
年5月26日(日)に逝去されました(享年92歳).
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申
し上げます.なお,ご葬儀は,近親者のみで執り行われ,ご遺族の
ご意向により弔問,香典、生花、弔電などすべてご遠慮願いたいと
のことです.
会長 松田 博貴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No.453(臨時)山口大会 事前参加登録受付開始!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.453 2019/6/11┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
[2019山口大会情報]
【1】大会参加登録受付を開始しました!
【2】講演申込受付中:まずはアカウント登録を!
【3】ランチョン・夜間集会申込受付中
【4】小さなEarth Scientistのつどい:参加校募集
【5】宿泊予約の情報
【6】企業展示・書籍販売・広告掲載 募集
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2019山口大会]大会参加登録もまもなく受付開始です
──────────────────────────────────
参加登録に関わるお申込(大会参加・要旨集注文,巡検,懇親会,
弁当)については,例年通りオンラインによる大会専用参加登録シ
ステムを準備致しました(会員・非会員とわず,どなたでも申込可
能です).また,巡検のみに参加する場合には,大会参加登録費は
徴収しません.
申込締切:8月19日(月)18時[WEB]
詳しくは、
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/sanka
(注)FAX・郵送による申込を希望する場合は,学会事務局までお
問い合わせ下さい(締切:8月9日(金)必着).
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2019山口大会]講演申込受付中:まずはアカウント登録を!
──────────────────────────────────
演題登録には,【山口大会演題登録専用のアカウント登録】が必要
となります.締切(7月3日18時)まで何度でも修正や要旨差替が可
能ですので,まずは,アカウント登録をされることをお勧めします.
*********************************************
演題登録・講演要旨提出:7月3日(水)18時
*********************************************
お申込は,山口大会HPから
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/collectsubject
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2019山口大会]ランチョン・夜間集会申込受付中
──────────────────────────────────
会合開催をご希望の場合は,必要な申込項目をe-mailで行事委員会宛に忘れず
にお申し込み下さい.
***************************
申込締切:7月3日(水)
***************************
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/meeting
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2019山口大会]小さなEarth Scientistのつどい:参加校募集
──────────────────────────────────
児童・生徒の参加が難しい学校も多くあると予想されます.その場
合は,発表ポスターのみをお送りいただいても結構です.審査は,
昨年札幌大会でも採用されたデジタルポスター審査を行います.こ
の会を通じて日頃の研究成果を披露していただき,地質学,地球科
学への理解が深まって,未来を担う生徒たちの学習意欲への良い刺
激と励みになることを願っております.
日時:9月23日(月・祝)
場所:山口大会ポスター会場(山口大学吉田キャンパス内)
**********************************
参加申込締切:7月26日(金)
**********************************
詳しくは,https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/gyoji#es
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2019山口大会]宿泊予約の情報
──────────────────────────────────
【宿泊予約】*担当(株)防長トラベル 山口支店
会場最寄りの湯田温泉に約350室を確保しています.
申込締切:2019年7月30日(火)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0108.html
【若手会員向けルームシェア型宿泊プラン】
山口大会では若手会員向けの宿泊施設をご用意いたしました.「若
手同士の交流」と「低価格化」の観点から,本プランは,相部屋で
のご案内となっております.内容をよくご確認の上,ご検討ください.
対象となる若手会員:学生(学部,修士,博士)およびポスドク研究員
申込締切:2019年7月31日(水)先着順
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0110.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[2019山口大会]企業展示・書籍販売・広告掲載 募集
──────────────────────────────────
地質関係機関・関連企業の皆様,奮ってお申込をいただきますよう
お願い申し上げます.
申込締切:一次 7月30日(火)・最終 8月19日(月)
詳しくは,https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/tenji
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No.454 地震火山こどもサマースクール参加者募集
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.454 2019/6/18┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
[2019山口大会情報]
【1】大会参加登録受付中です
【2】講演申込受付中:まずはアカウント登録を!
【3】ランチョン・夜間集会申込受付中
【4】小さなEarth Scientistのつどい:参加校募集
【5】宿泊予約の情報
【6】地質関連企業研究サポート:出展企業募集
【7】企業展示・書籍販売・広告掲載 募集
------------------------------------------------------------
【8】地震火山こどもサマースクール:参加者募集
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
【12】訂正[2019山口大会]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2019山口大会]大会参加登録受付中です
──────────────────────────────────
参加登録に関わるお申込(大会参加・要旨集注文,巡検,懇親会,
弁当)については,例年通りオンラインによる大会専用参加登録シ
ステムを準備致しました(会員・非会員とわず,どなたでも申込可
能です).また,巡検のみに参加する場合には,大会参加登録費は
徴収しません.
申込締切:8月19日(月)18時[WEB]
詳しくは,https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/sanka
(注)FAX・郵送による申込を希望する場合は,学会事務局までお
問い合わせ下さい(締切:8月9日(金)必着).
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2019山口大会]講演申込受付中:まずはアカウント登録を!
──────────────────────────────────
演題登録には,【山口大会演題登録専用のアカウント登録】が必要
となります.締切(7月3日18時)まで何度でも修正や要旨差替が可
能ですので,まずは,アカウント登録をされることをお勧めします.
*********************************************
演題登録・講演要旨提出:7月3日(水)18時
*********************************************
お申込は,山口大会HPから
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/collectsubject
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2019山口大会]ランチョン・夜間集会申込受付中
──────────────────────────────────
会合開催をご希望の場合は,必要な申込項目をe-mailで行事委員会宛に忘れず
にお申し込み下さい.
***************************
申込締切:7月3日(水)
***************************
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/meeting
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2019山口大会]小さなEarth Scientistのつどい:参加校募集
──────────────────────────────────
児童・生徒の参加が難しい学校も多くあると予想されます.その場
合は,発表ポスターのみをお送りいただいても結構です.審査は,
昨年札幌大会でも採用されたデジタルポスター審査を行います.こ
の会を通じて日頃の研究成果を披露していただき,地質学,地球科
学への理解が深まって,未来を担う生徒たちの学習意欲への良い刺
激と励みになることを願っております.
日時:9月23日(月・祝)
場所:山口大会ポスター会場(山口大学吉田キャンパス内)
**********************************
参加申込締切:7月26日(金)
**********************************
詳しくは, https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/gyoji#es
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2019山口大会]宿泊予約の情報
──────────────────────────────────
【宿泊予約】*担当(株)防長トラベル 山口支店
会場最寄りの湯田温泉に約350室を確保しています.
申込締切:2019年7月30日(火)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0108.html
【若手会員向けルームシェア型宿泊プラン】
若手会員向けの宿泊施設をご用意いたしました.「若手同士の交流」
と「低価格化」の観点から,本プランは,相部屋となります.内容
をよくご確認の上,お申込下さい.
対象となる若手会員:学生(学部,修士,博士)およびポスドク研
究員など
申込締切:2019年7月31日(水)先着順
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0110.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[2019山口大会]地質関連企業研究サポート:出展企業募集
──────────────────────────────────
日程:9月25日(水)14:00-16:30
場所:山口大学 吉田キャンパス共通教育棟
内容:
・会場内の参加者休憩室等における参加各社作成PR用スライド上映
・参加各社の個別説明会
参加費(出展費)無料
参加申込締切:8月1日(木)(必着)
詳しくは,
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/gyoji#support
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】[2019山口大会]企業展示・書籍販売・広告掲載 募集
──────────────────────────────────
地質関係機関・関連企業の皆様,奮ってお申込をいただきますよう
お願い申し上げます.
申込締切:一次 7月30日(火)・最終 8月19日(月)
詳しくは, https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/tenji
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】地震火山こどもサマースクール:参加者募集
──────────────────────────────────
第20回地震火山こどもサマースクール「研究者と丹後を巡る2日間」
集合:8月10日(土)9時 みやづ歴史の館(宮津市字鶴賀2164)
解散:8月11日(日)17時 アグリセンター大宮(京丹後市大宮口大野228-1)
宿泊:京都府立丹後海と星の見える丘公園(宮津市字里波見)
対象:小学5年生から高校生(24名)
参加費:5,000円
参加申込締切:7月5日(金)
詳しくは,http://www.kodomoss.jp/ss/tango/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■清澄フィールドキャンプ
8月19日(月)-24日(土)5泊6日
場所:東京大学演習林(〒299-5505千葉県鴨川市清澄)
費用:40,000円程度を予定(宿泊・食事・保険・タクシー代込)
*ただし,日本地質学会の学生・院生会員,または日本地質学会
に入会することを確約できる学生・院生は,20,000円とします.
参加申込締切:7月5日(金)
http://kanto.geosociety.jp/
[中部支部]
■2019年支部年会
6月29日(土)10:00から
会場:福井県立大学永平寺キャンパス 多目的ホール
シンポジウム
「恐竜渓谷ふくい勝山ジオパークとそれを取り巻く活動(仮)」
http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■福井県立恐竜博物館
特別展「恐竜の脳力:恐竜の生態を脳科学で解き明かす」
7月12日(金)-10月14日(月・祝)
特別展講演会「カモノハシ恐竜の脳とトサカの機能について」(8/25)
特別展講演会「恐竜の脳について」(9/7)など
https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/
■第9回学生ヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集(地質学会推薦)
日程(仮):2020年3月4日〜18日(出国から帰国まで15日間)
参加申込締切:2019年12月31日
参加費:学生・大学院生 20万円以内
http://www.gondwanainst.org/geotours/Studentfieldex_index.htm
----------------------------------------------------------------------
■地質学史懇話会
6月23日(日)13:30-17:00
場所:北とぴあ 8階803号室(JR京浜東北線王子駅下車3分)
・若林 悠:天気予報における官僚制と社会
―日本の気象行政の歴史分析に向けて―
・木村 学:北海道の地質学研究 150年,雑感
■日本学術会議 in 富山
「富山から発信する学術研究とSDGs対応」
6月28日(金)13:00-17:15
場所:富山大学 黒田講堂ホール(富山市五福3190番地)
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/277-s-0628.pdf
(後)第56回アイソトープ・放射線研究発表会
7月3日(水)-5日(金)
会場:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
https://www.jrias.or.jp/
■第194回深田研談話会
7月5日(金)18:00-19:30
場所:深田地質研究所 研修ホール(東京都文京区)
講師:芦 寿一郎 氏(東京大学大気海洋研究所海洋底地質学分野准教授)
演題:海底から探る南海トラフの断層活動と地震履歴
参加費無料:70名(先着)*要事前申込
http://www.fgi.or.jp/
■第224回地質汚染・災害イブニングセミナー
7月26日(金)18:30-20:30
場所:北とぴあ808会議室(東京都北区 JR王子駅から徒歩5分)
講師:益子 保(公益財団法人中央温泉研究所)
演題:「温泉水の重金属排水問題:水濁法との関係から」
会費:会員500円 非会員 1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
(共)第20回地震火山こどもサマースクール
「研究者と丹後を巡る2日間」*参加者募集中*
8月10日(土)-11日(日)
対象 小学5年生-高校生 24名
参加費:5,000円
参加申込締切:7月5日(金)
http://www.kodomoss.jp/ss/tango/
■第22回日本水環境学会シンポジウム
9月5日(木)-6日(金)
場所:北海学園大学工学部(山鼻キャンパス)
http://www.jswe.or.jp/event/symposium/index.html
(後)第63回粘土科学討論会
9月10日(火)-12日(木)
(講演会:9月10-11日,現地見学会:9月12日)
会場:埼玉大学(さいたま市桜区下大久保225)
http://www.cssj2.org/publication/annual_meeting/
(共)日本地球化学会第66回年会
9月17日(火)-19日(木)
場所: 東京大学・本郷キャンパス
http://www.geochem.jp/meeting/index.html
★ 日本地質学会第126年学術大会(2019山口)
9月23日(月・祝)-25日(水)
場所:山口大学 吉田キャンパス(山口市吉田)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/top
■第227回地質汚染・災害イブニングセミナー
10月25日(金)18:30-20:30
場所:北とぴあ808会議室 (東京都北区 JR王子駅から徒歩5分)
講師:笹川みちる(雨水市民の会理事、雨水まちづくりサポート理事)
演題:「雨水と賢くくらすには:墨田区の取り組みから」
会費:会員500円 非会員 1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■第30回地質汚染調査浄化技術研修会
11月15日(金)-17日(日)
主催:NPO法人 日本地質汚染審査機構
共催:地質汚染診断士の会・日本地質学会環境地質部会・社会地質学会
会場:日本地質汚染審査機構 関東ベースン実習センター
(Tel:0478-59-1491)〒287-0025 千葉県香取市本矢作1277-1
会費:会員45,000円・非会員 55,000円・学生:15,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
■国際ゴンドワナ研究連合2019年総会及び第16回ゴンドワナから
アジア国際シンポ
11月8日(金)-10日(日)
場所:高知県立県民文化会館(高知市)
野外巡検:11-12日,室戸ジオパーク
2nd Circular(6/9)
https://www.data-box.jp/pdir/39aafa3256dd487480194b110293927c
お問い合せ:Prof. Darren Lingley(高知大学人文社会科学部)
E-mail: lingley@kochi-u.ac.jp
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0191.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・「第40回猿橋賞」受賞候補者募集(学会締切10/31)
・令和2年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞および若手科学者賞
受賞候補者の推薦 (学会締切7/12,9/2)
・第60回東レ科学技術賞及び東レ科学技術研究助成の候補者推薦(学会締切8/31)
・阿蘇ジオパーク助成研究の募集(7/1-31)
・岩手大学理工学部システム創成工学科社会基盤・環境コース准教授公募(10/1)
・栗駒山麓ジオパーク専門員(地域おこし協力隊)募集(7/10)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】訂正[2019山口大会]
──────────────────────────────────
前月ニュース誌5月号(Vol. 22 No. 5),山口大会予告記事において,
校正ミスによる以下の誤りがありました.お詫びし訂正いたします.
p.(2)左段上:1.日程(市民講演会の日程)
(誤)9月24日(火)午後
(正)9月22日(日)
p.(22):巡検コース紹介 Eコース美祢層群と豊浦層群の化石群の
「主な見学対象」
(誤)[1]秋吉石灰岩のフズリナ生層序,堆積相,造礁生物,
[2]秋吉台のカルスト地形と秋芳洞
(正)美祢層群と豊浦層群の化石群
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.455(臨時)締切まであとわずか!山口大会講演申込
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.455 2019/6/28┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
[2019山口大会関連情報]
【1】講演申込 締切まであとわずか!
【2】ランチョン・夜間集会 まもなく締切
【3】事前参加登録受付中です!
【4】地質関連企業研究サポート:出展企業募集
【5】企業展示・書籍販売・広告掲載 募集
【6】宿泊予約の情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2019山口大会]講演申込 締切まであとわずか!
──────────────────────────────────
***まずはアカウント登録を!!***
演題登録には,『山口大会演題登録専用のアカウント登録』が必要となりま
す.締切まで何度でも修正や要旨差替が可能ですので,あらかじめアカウント
登録をされることをお勧めします.
非会員の方も入会申込中の方も,画面入力が可能です.入会予定の方は
入会手続きと併行して講演申込の作業を進めて下さい.
********************************************************
演題登録・講演要旨提出:7月3日(水)18時【締切厳守】
********************************************************
詳しくは,大会HPまで
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/collectsubject
大会申込Q&A(演題登録編)はこちら
http://www.geosociety.jp/science/content0101.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2019山口大会]ランチョン・夜間集会まもなく締切
──────────────────────────────────
ランチョン・夜間集会の受付もまもなく締切です.
会合開催をご希望の場合は,必要な申込項目をe-mailで行事委員会
宛に忘れずにお申し込み下さい.
***************************
申込締切:7月3日(水)
***************************
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/meeting
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2019山口大会]事前参加登録受付中です!
──────────────────────────────────
会員・非会員問わずWEB申込画面から事前参加登録のお申込が可能です.
巡検のみの参加もお申込いただけます(アウトリーチ巡検も含む).
なお,巡検のみに参加する場合は,大会参加登録費は徴収しません.
******************************************************
事前参加登録締切:8月19日(月)18時[WEB]
******************************************************
申込はこちらから,
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/sanka
◆小さなEarth Scientistのつどい〜第17回小,中,高校生徒「地学研究」
発表会参加校募集中(7/26締切)
このほか普及・関連行事も盛りだくさんです!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2019山口大会]地質関連企業研究サポート:出展企業募集中
─────────────────────────────────
日程:9月25日(水)14:00-16:30
場所:山口大学 吉田キャンパス共通教育棟
内容:・会場内の参加者休憩室等における参加各社作成PR用スライド上映
・参加各社の個別説明会
参加費(出展費)無料
参加申込締切:8月1日(木)(必着)
詳しくは,
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/gyoji#support
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2019山口大会]企業展示・書籍販売・広告掲載 募集中
──────────────────────────────────
地質関係機関・関連企業の皆様,奮ってお申込をいただきますよう
お願い申し上げます.
申込締切:一次 7月30日(火)・最終 8月19日(月)
詳しくは, https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/tenji
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[2019山口大会]宿泊予約の情報
──────────────────────────────────
【宿泊予約】*担当(株)防長トラベル 山口支店
会場最寄りの湯田温泉に約350室を確保しています.
申込締切:2019年7月30日(火)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0108.html
【若手会員向けルームシェア型宿泊プラン】
若手会員向けの宿泊施設をご用意いたしました.「若手同士の交流」
と「低価格化」の観点から,本プランは,相部屋となります.内容
をよくご確認の上,お申込下さい.
対象となる若手会員:学生(学部,修士,博士)およびポスドク研
究員など
申込締切:2019年7月31日(水)先着順
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0110.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No.456 講演申込締切:本日18時です!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.456 2019/7/3┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
[2019山口大会情報]
【1】講演申込締切:本日18時です!
【2】ランチョン・夜間小集会申込も本日締切
【3】大会参加登録受付中です
【4】小さなEarth Scientistのつどい:参加校募集
【5】宿泊予約の情報
【6】地質関連企業研究サポート:出展企業募集
【7】企業展示・書籍販売・広告掲載 募集
------------------------------------------------------------
【8】地質学雑誌からのお知らせ
【9】Island Arcからのお知らせ
【10】地震火山こどもサマースクール:参加者募集
【11】支部情報
【12】その他のお知らせ
【13】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2019山口大会]講演申込締切:本日18時です!
──────────────────────────────────
間もなく締切です!お急ぎください!
演題登録には,【山口大会演題登録専用のアカウント登録】が必要
となります.締切(本日18時)まで何度でも修正や要旨差替が可
能です.まずは,アカウント登録をされることをお勧めします.
会員、非会員問わず入力可能です.
(注)講演申込と大会参加登録は別システムです.アカウント情報
(ID・パスワード)も 異なります.
*********************************************
演題登録・講演要旨提出:7月3日(水)18時
*********************************************
お申込は,山口大会HPから
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/collectsubject
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2019山口大会]ランチョン・夜間小集会申込も本日締切
──────────────────────────────────
会合開催をご希望の場合は,必要な申込項目をe-mailで行事委員会宛に忘れず
にお申し込み下さい.
***************************
申込締切:7月3日(水)
***************************
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/meeting
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2019山口大会]大会参加登録受付中です
──────────────────────────────────
参加登録に関わるお申込(大会参加・要旨集注文,巡検,懇親会,
弁当)については,例年通りオンラインによる大会専用参加登録シ
ステムを準備致しました(会員・非会員とわず,どなたでも申込可
能です).また,巡検のみに参加する場合には,大会参加登録費は
徴収しません.
申込締切:8月19日(月)18時[WEB]
詳しくは,https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/sanka
(注)FAX・郵送による申込を希望する場合は,学会事務局までお
問い合わせ下さい(締切:8月9日(金)必着).
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2019山口大会]小さなEarth Scientistのつどい:参加校募集
──────────────────────────────────
児童・生徒の参加が難しい学校も多くあると予想されます.その場
合は,発表ポスターのみをお送りいただいても結構です.審査は,
昨年札幌大会でも採用されたデジタルポスター審査を行います.こ
の会を通じて日頃の研究成果を披露していただき,地質学,地球科
学への理解が深まって,未来を担う生徒たちの学習意欲への良い刺
激と励みになることを願っております.
日時:9月23日(月・祝)
場所:山口大会ポスター会場(山口大学吉田キャンパス内)
**********************************
参加申込締切:7月26日(金)
**********************************
詳しくは, https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/gyoji#es
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2019山口大会]宿泊予約の情報
──────────────────────────────────
【宿泊予約】*担当(株)防長トラベル 山口支店
会場最寄りの湯田温泉に約350室を確保しています.
申込締切:2019年7月30日(火)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0108.html
【若手会員向けルームシェア型宿泊プラン】
若手会員向けの宿泊施設をご用意いたしました.「若手同士の交流」
と「低価格化」の観点から,本プランは,相部屋となります.内容
をよくご確認の上,お申込下さい.
対象となる若手会員:学生(学部,修士,博士)およびポスドク研
究員など
申込締切:2019年7月31日(水)先着順
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0110.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[2019山口大会]地質関連企業研究サポート:出展企業募集
──────────────────────────────────
日程:9月25日(水)14:00-16:30
場所:山口大学 吉田キャンパス共通教育棟
内容:
・会場内の参加者休憩室等における参加各社作成PR用スライド上映
・参加各社の個別説明会
参加費(出展費)無料
参加申込締切:8月1日(木)(必着)
詳しくは,
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/gyoji#support
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】[2019山口大会]企業展示・書籍販売・広告掲載 募集
──────────────────────────────────
地質関係機関・関連企業の皆様,奮ってお申込をいただきますよう
お願い申し上げます.
申込締切:一次 7月30日(火)・最終 8月19日(月)
詳しくは, https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/tenji
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】地質学雑誌からのお知らせ
──────────────────────────────────
◆第125巻第6号(2019年6月号)が刊行されました(7/1発送).
柚原雅樹ほか:北部九州白亜紀花崗岩類,添田花崗閃緑岩のU–Pb
ジルコン年代とSr・Nd 同位体比組成:添田花崗閃緑岩の再区分(p.
405–420)ほか 5編/日本地質学会創立125 周年記念地質学雑誌特
集号の終了にあたって(p.461-463)
最新号目次はこちら
http://www.geosociety.jp/publication/content0092.html
◆受理論文の印刷前に,Accepted ManuscriptとしてPDFファイルを作
成し,順次このWEBサイトで公開しています.
https://sub.geosociety.jp/user.php
(注意:会員ページへのログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】Island Arcからのお知らせ
──────────────────────────────────
◆最新号 Volume 28, Issue 4が刊行されました.
PREFACE_Thematic section: Proceedings of InterRad XV
Katsuo Sashida et al
RESEARCH ARTICLES_Post‐Great Oxidation Event Orosirian–Statherian iron formations on the São Francisco craton: Geotectonic implications
Carlos A. Rosière et al ほか
学会WEBサイト会員ページにログインすると,全文無料で閲覧できます
https://sub.geosociety.jp/login.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】地震火山こどもサマースクール:参加者募集
──────────────────────────────────
第20回地震火山こどもサマースクール「研究者と丹後を巡る2日間」
集合:8月10日(土)9時 みやづ歴史の館(宮津市字鶴賀2164)
解散:8月11日(日)17時 アグリセンター大宮(京丹後市大宮口大野228-1)
宿泊:京都府立丹後海と星の見える丘公園(宮津市字里波見)
対象:小学5年生から高校生(24名)
参加費:5,000円
参加申込締切:7月5日(金)
詳しくは,http://www.kodomoss.jp/ss/tango/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■清澄フィールドキャンプ
8月19日(月)-24日(土)5泊6日
場所:東京大学演習林(〒299-5505千葉県鴨川市清澄)
費用:40,000円程度を予定(宿泊・食事・保険・タクシー代込)
*ただし,日本地質学会の学生・院生会員,または日本地質学会
に入会することを確約できる学生・院生は,20,000円とします.
参加申込締切:7月5日(金)
http://kanto.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■福井県立恐竜博物館
特別展「恐竜の脳力:恐竜の生態を脳科学で解き明かす」
7月12日(金)-10月14日(月・祝)
特別展講演会「カモノハシ恐竜の脳とトサカの機能について」(8/25)
特別展講演会「恐竜の脳について」(9/7)など
https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/
■第9回学生ヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集(地質学会推薦)
日程(仮):2020年3月4日〜18日(出国から帰国まで15日間)
参加申込締切:2019年12月31日
参加費:学生・大学院生 20万円以内http://www.gondwanainst.org/geotours/Studentfieldex_index.htm
----------------------------------------------------------------------
(後)第56回アイソトープ・放射線研究発表会
7月3日(水)-5日(金)
会場:東京大学弥生講堂(文京区弥生1-1-1)
https://www.jrias.or.jp/
■第29回国際地図学会議
7月15日(月)-20日(土)
場所:東京国際交流館 ほか(東京都江東区)
http://www.icc2019.org/
市民公開講座「ICA国際地図展」,「バーバラ・ペチュニク子ども地図展」
7月16日(火)-19日(金)9:00-18:00(最終日は15:00まで)
会場:テレコムセンタービル
参加費:無料
http://jcacj.org/
(後)サテライトミュージアム企画展示「アンモナイト展」
7月20日(土)-8月31日(土)
場所:新潟大学駅南キャンパス ときめいと(新潟市中央区笹口1-1プラーカ)
入館無料
http://www.lib.niigata-u.ac.jp/tenjikan/index.html
■第224回地質汚染・災害イブニングセミナー
7月25日(木)18:30-20:30[日程が変更になりました(26日-->25日)]
場所:北とぴあ808会議室(東京都北区 JR王子駅徒歩5分)
講師:益子 保(公益財団法人中央温泉研究所)
演題:「温泉水の重金属排水問題:水濁法との関係から」
会費:会員500円 非会員 1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■地球科学・リモートセンシング国際シンポジウム2019
7月28日(日)-8月2日(金)
場所:パシフィコ横浜
https://igarss2019.org/
■久留里湧水の現場見学会・久留里湧水と水循環フォーラム
:なぜ、湧水って下から湧き出るの?
主催:NPO法人日本地質汚染審査機構
7月27日(土)
1.湧水井戸見学会(10:00-)集合場所:JR久留里駅前 水のみ場
2.久留里湧水と水循環フォーラム(13:00-16:00)
会場:君津市農村環境改善センター・農事研究室(君津市久留里)
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
(後)科教協福岡大会・科学お楽しみ広場
(第66回全国研究大会福岡大会)
8月9日(金)
会場:西南学院大学 西南コミュニティセンター(福岡市早良区)
参加無料
参加者は各展示ブースを回って,自然科学,理科教育に関する様々な
体験や学びができます.児童生徒も参加可.
https://kakyokyo.org/archives/1319
(共)第20回地震火山こどもサマースクール
「研究者と丹後を巡る2日間」*参加者募集中*
8月10日(土)-11日(日)
対象:小学5年生-高校生 24名
参加費:5,000円
参加申込締切:7月5日(金)
http://www.kodomoss.jp/ss/tango/
(後)第63回粘土科学討論会
9月10日(火)-12日(木)
(講演会:9月10-11日,現地見学会:9月12日)
会場:埼玉大学(さいたま市桜区下大久保225)
http://www.cssj2.org/publication/annual_meeting/
(共)日本地球化学会第66回年会
9月17日(火)-19日(木)
場所: 東京大学・本郷キャンパス
http://www.geochem.jp/meeting/index.html
★ 日本地質学会第126年学術大会(2019山口)
9月23日(月・祝)-25日(水)
場所:山口大学 吉田キャンパス(山口市吉田)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/top
(協)第35回ゼオライト研究発表会
12月5日(木)-12月6日(金)
会場:タワーホール船堀(江戸川区船堀4-1-1)
https://jza-online.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0191.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・京都大学院理研究科附属地球熱学研究施設教授公募(8/20)
・島根大学エスチュアリー研究センターで特任助教公募(10/1)
・藤原ナチュラルヒストリー振興財団学術研究助成(地学・植物分野)(9/1)
・糸魚川ジオパーク学術研究奨励事業募集(7/17)
・隠岐ユネスコ世界ジオパーク専門職員(定年制)募集(7/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No.457 2019山口大会:巡検申込はお早めに
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.457 2019/7/16┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
[2019山口大会情報]
【1】大会参加登録受付中:巡検申込はお早めに!
【2】講演要旨集は事前予約をお願いします
【3】小さなEarth Scientistのつどい:参加校募集
【4】宿泊予約の情報
【5】地質関連企業研究サポート:出展企業募集
【6】企業展示・書籍販売・広告掲載 募集
------------------------------------------------------------
【7】地質学雑誌からのお知らせ
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2019山口]大会参加登録受付中:巡検申込はお早めに!
──────────────────────────────────
参加登録に関わるお申込(大会参加・要旨集注文,巡検,懇親会,
弁当)については,例年通りオンラインによる大会専用参加登録シ
ステムを準備致しました(会員・非会員とわず,どなたでも申込可
能です).また,巡検のみに参加する場合には,大会参加登録費は
徴収しません.
巡検は,すでに定員に達したコースもあります。巡検参加を希望さ
れる方はお早めにお申込下さい.
(注)巡検申込状況はこちらから
http://www.geosociety.jp/science/content0104.html
申込締切:8月19日(月)18時[WEB]
詳しくは,https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/sanka
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2019山口]講演要旨集は事前予約をお願いします
──────────────────────────────────
参加登録費が0円の方(非会員招待講演者,名誉会員,50 年会員,学部学生割
引会費適用正会員等)には要旨集は付きません.
要旨集の当日販売もありますが,ここ数年,当日販売分が売り切れてしまうこ
とが多く,購入いただけないケースもあります.山口大会へ参加を予定されて
いる方や要旨集を購入希望の方は,事前参加登録または要旨集の予約購入申込
をお願いいたします.
(注)参加登録費が発生する方(正会員や院生割引会費適用正会員等)には,
必ず講演要旨集が1冊付きます.
お申込はこちら
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/sanka
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2019山口]小さなEarth Scientistのつどい:参加校募集
──────────────────────────────────
児童・生徒の参加が難しい学校も多くあると予想されます.その場
合は,発表ポスターのみをお送りいただいても結構です.審査は,
昨年札幌大会でも採用されたデジタルポスター審査を行います.こ
の会を通じて日頃の研究成果を披露していただき,地質学,地球科
学への理解が深まって,未来を担う生徒たちの学習意欲への良い刺
激と励みになることを願っております.
日時:9月23日(月・祝)
場所:山口大会ポスター会場(山口大学吉田キャンパス内)
**********************************
参加申込締切:7月26日(金)
**********************************
詳しくは, https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/gyoji#es
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2019山口]宿泊予約の情報
──────────────────────────────────
【宿泊予約】*担当(株)防長トラベル 山口支店
会場最寄りの湯田温泉に約350室を確保しています.
申込締切:2019年7月30日(火)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0108.html
【若手会員向けルームシェア型宿泊プラン】
若手会員向けの宿泊施設をご用意いたしました.「若手同士の交流」
と「低価格化」の観点から,本プランは,相部屋となります.内容
をよくご確認の上,お申込下さい.
対象となる若手会員:学生(学部,修士,博士)およびポスドク研
究員など
申込締切:2019年7月31日(水)先着順
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0110.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2019山口]地質関連企業研究サポート:出展企業募集
──────────────────────────────────
日程:9月25日(水)14:00-16:30
場所:山口大学 吉田キャンパス共通教育棟
内容:
・会場内の参加者休憩室等における参加各社作成PR用スライド上映
・参加各社の個別説明会
参加費(出展費)無料
参加申込締切:8月1日(木)(必着)
詳しくは,
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/gyoji#support
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[2019山口]企業展示・書籍販売・広告掲載 募集
──────────────────────────────────
地質関係機関・関連企業の皆様,奮ってお申込をいただきますよう
お願い申し上げます.
申込締切:一次 7月30日(火)・最終 8月19日(月)
詳しくは, https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/tenji
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】地質学雑誌からのお知らせ
──────────────────────────────────
◆第125巻第7号(2019年7月号)予告(7月末発送予定).
・特集号「富山トラフと周辺部の堆積作用と後背テクトニクス」
・山口大会巡検案内書:2編(Cコース/Dコース)
を予定しています。
最新号目次(予告)はこちら
http://www.geosociety.jp/publication/content0092.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■那須野が原博物館
開館15周年記念特別展「昆虫創世記」
昆虫がたどった4億年の道のりがいま明らかに!
開催中-9月23日(月・祝)
http://www2.city.nasushiobara.lg.jp/hakubutukan/
(後)サテライトミュージアム企画展示「アンモナイト展」
7月20日(土)-8月31日(土)
場所:新潟大学駅南キャンパス ときめいと(新潟市中央区笹口1-1プラーカ)
入館無料
http://www.lib.niigata-u.ac.jp/tenjikan/index.html
■第9回学生ヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集(地質学会推薦)
日程(仮):2020年3月4日-18日(出国から帰国まで15日間)
参加申込締切:2019年12月31日
参加費:学生・大学院生 20万円以内http://www.gondwanainst.org/geotours/Studentfieldex_index.htm
-------------------------------------------------------------
(後)科教協福岡大会・科学お楽しみ広場
(第66回全国研究大会福岡大会)
8月9日(金)
会場:西南学院大学 西南コミュニティセンター(福岡市早良区)
参加無料
参加者は各展示ブースを回って,自然科学,理科教育に関する様々な
体験や学びができます.児童生徒も参加可.
https://kakyokyo.org/archives/1319
■第225回地質汚染・災害イブニングセミナー
8月30日(金)18:30-20:30
場所:北とぴあ806会議室(東京都北区王子)
講師:山崎晴雄(首都東京大学名誉教授 理学博士)
演題:『首都圏における活断層』
会費:会員500円・非会員 1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
(後)第63回粘土科学討論会
9月10日(火)-12日(木)
(講演会:9月10-11日,現地見学会:9月12日)
会場:埼玉大学(さいたま市桜区下大久保225)
http://www.cssj2.org/publication/annual_meeting/
(共)日本地球化学会第66回年会
9月17日(火)-19日(木)
場所: 東京大学・本郷キャンパス
http://www.geochem.jp/meeting/index.html
★ 日本地質学会第126年学術大会(2019山口)
9月23日(月・祝)-25日(水)
場所:山口大学 吉田キャンパス(山口市吉田)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/top
(協)第35回ゼオライト研究発表会
12月5日(木)-6日(金)
会場:タワーホール船堀(江戸川区船堀4-1-1)
https://jza-online.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0191.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・岡山大学大学院自然科学研究科地球生命物質科学専攻教員公募(8/26)
・農林水産省経験者採用試験(係長級(技術))(8/2-20)*7/27合同説明会開催
・海洋研究開発機構超先鋭研究開発部門超先鋭研究プログラム技術職(9/9)
・海洋研究開発機構Young Research Fellow 2020公募(8/28)
・日本科学未来館入居プロジェクト公募(9/9)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No.458 2019山口大会:事前参加登録はお済みですか?
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.458 2019/8/6┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
[2019山口大会情報]
【1】[2019山口]全体日程表・講演プログラム公開しました。
【2】[2019山口]事前参加登録はお済みですか?
【3】[2019山口]緊急展示申込受付
【4】[2019山口]会員カードを忘れずに
------------------------------------------------------------
【5】2019年度大学院生の研究・生活実態に関するアンケート調査
【6】本の紹介「The Atom and the Fault」
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2019山口]全体日程表・講演プログラム公開しました。
──────────────────────────────────
山口大会の全体日程表・講演プログラム(セッション別)を公開しました。
なお,一部情報は修正・変更される場合があります。
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/program
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2019山口]事前参加登録はお済みですか?
──────────────────────────────────
参加登録に関わるお申込(大会参加・要旨集注文,巡検,懇親会,
弁当)については,例年通りオンラインによる大会専用参加登録シ
ステムを準備致しました(会員・非会員とわず,どなたでも申込可
能です).また,巡検のみに参加する場合には,大会参加登録費は
徴収しません.
巡検は,すでに定員に達したコースもあります(C, E, G, Hコース)。
巡検参加を希望される方はお早めにお申込下さい.
(注)巡検申込状況はこちらから(8/5,17時現在)
http://www.geosociety.jp/science/content0104.html
申込締切:8月19日(月)18時[WEB](8月9日(金)必着[郵送/FAX])
詳しくは,https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/sanka
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2019山口]緊急展示申込受付
──────────────────────────────────
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災
害調査報告や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コー
ナー」を設けます.ポスター展示を希望する方は,9月5日(水)ま
でにお申込下さい。
(注)コアタイムの時間帯が設けられます.優秀ポスター賞へのエ
ントリーも可能です.発表における1人1題の制約は及びません.
申込締切:9月5日(水)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/emergency
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2019山口]会員カードを忘れずに
──────────────────────────────────
大会会場での受付は「会員カード」で簡単に手続きいたします.
地質学会会員の方は,「会員カード」を忘れずに持参して下さい.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/card
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2019年度大学院生の研究・生活実態に関するアンケート調査
──────────────────────────────────
本調査は、全国大学院生協議会(全院協)が行う、全国の大学院生
を対象としたアンケート調査です。大学院生の研究及び生活実態を
客観的に把握し、もってその向上に資することを目的としておりま
す。本調査へのご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
回答期限:2019年9月13日(金)
詳しくは,https://forms.gle/CP3zxCcEFYySye8E9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】本の紹介「The Atom and the Fault」
──────────────────────────────────
正会員 石渡 明(原子力規制委員会(NRA)委員)
The Atom and the Fault
(Experts, Earthquakes and Nuclear Power)
Richard L. Meehan 著
The MIT Press, 1984,First paperback edition in 1986.
Paperback: \2,316 (in July 2019),Size: 23x15 cm, 161 p.
ISBN: 978-0-262-63106-8
Keywords: atomic power-plants, California
この「原子力と断層」の本は、活断層が多く地震が頻発する米国
カリフォルニア州(以下「加州」)において、1950〜70年代に計画
された商用原子力発電所や試験炉(以下「原発」)が立地調査、建
設、稼働段階において直面した活断層問題について、地質コンサル
タントとしてそれらの調査に直接関与した著者が、自身の経験に基
づいて、問題の詳しい経緯や電力会社、地質コンサルタント会社、
米国地質調査所(USGS)、米国原子力規制委員会(NRC; 1974年以前
はAEC)、大学教授、技術者、訴訟参加者らの立場と考え方を、人間
模様を絡めて物語風に述べたものである。Hart et al. (2012: EEG,
18(4), 313-) は、「地すべりが断層と誤認される場合:米国西部の
事例研究」(https://doi.org/10.2113/gseegeosci.18.4.313)の中
で、「本書は地質技術者と応用地質研究者の必読書だ」と高く評価
している。
序文によると、著者は1960年代に数人の仲間と地質コンサルタン
ト会社を立ち上げ、原発の敷地内や近傍の断層調査を行い、後に
Stanford大学で理工系の学生に講義した内容を基に本書を執筆した。
著者は、「この本は一人の当事者の見解であり、「客観性」に欠け
ると非難されるかもしれない。(中略)しかし、私は決して皆さん
を原発に賛成あるいは反対の立場に転向させることを目的としてい
ない。私の目的はもっと野心的である。私はもっと本質的な問題を
提起している。即ち、科学的専門家の間で、「正直さ」や「客観性」
が現実にどのように存在し得るか、という問題である」と述べてい
る。
加州は太平洋プレートと北米プレートの境界をなすSan Andreas断
層が海岸沿いの陸上または直近の海底を通過しており、プレート境
界が数10km〜100km以上沖を通る日本よりも活断層や地震についての
自然条件が厳しい(ただし、日本でも伊豆半島北側ではプレート境
界が陸上を通り、津波については日本の方が厳しい)。加州では19
50年代から計8つの原子力サイトが選定されたが、そのうち4つ(北
からPoint Arena, Bodega Head, Davenport, Malibu (Corral
Canyon))は立地調査ないし建設段階で活断層が発見されて建設中止
となり(Davenportの公式の中止理由は経済的)、2つ(Humboldt
Bay, Vallecitos)は運転開始の13〜20年後に活断層がみつかって運
転禁止になり、長期間営業運転できたのは2つだけ(Diablo Canyon
(現在も稼働中)とSan Onofre)という状況である。
AEC-NRCの活断層に関する指針は大略次のように変遷してきた(本
書p. 66)。【1956年】いかなる原子力施設も既知の活動的な起震断
層から地表距離で1/4〜1/2マイル(約400〜800m)より近くに設置し
てはならない。【1959年】原子力施設は断層の上に設置してはなら
ない。【1962年】「1/4〜1/2マイル」を「1/4マイル」に変更。【1
973年】新立地基準「10 CFR 100 Appendix A」採択。将来活動する
可能性のある断層(capable fault)を、3.5万年以内に活動または
50万年以内に繰り返し活動した断層等と定義(距離の基準は不明確)。
本書が扱う加州の原発の活断層問題のうち3つを簡単に紹介する。
加州北部のBodega Headは建設初期段階で原子炉位置に活断層が発見
され計画中止になった。この用地はSan Andreas断層をまたぐ岬の太
平洋側の先端にあり、原子炉を容れるための大きな穴を掘ったとこ
ろ、その底や壁を縦断する断層が露出した。そして、この断層は花
崗岩質の基盤岩を覆う4万年前の段丘堆積物を数インチ変位させてい
た。電力会社は、断層が3フィート(約1m)変位してもその動きを吸
収できる設計にするという「宇宙時代的な」補正申請書をAECに提出
したが、結局AECは立地不適と判断した。Schlocker and Bonilla (
1964)の最終報告書は、「本サイトとSan Andreas断層との距離は、
1906年のSan Francisco大地震において2.5〜4フィートの断層変位が
観察された複数の地点と同断層との距離にほぼ同じである。従って
このサイトにおいて2〜3フィートのずれが生じる可能性は否定でき
ない」としている(http://pubs.er.usgs.gov/publication/tei844)。
加州南部のMalibu (Corral Canyon)サイトは、活断層からの距離
が1/4マイル以内かどうかが争点になった。USGSや大学の研究者はこ
のサイトが断層帯の中にあり、原子炉の直下を破砕帯が通ることに
なり、危険度が高いと主張した。地元住民による反対運動が起き、
彼らは100人以上の石油地質関係の学者らを現地視察に招き、酒食で
もてなして「このサイトは原発の建設には安全でない」という文書
に署名させた。Yerkes and Wentworth (1965)は Malibu 海岸断層が
後期更新世(約13〜1万年前)の地層を変位させている露頭を8箇所
示すが(https://pubs.er.usgs.gov/publication/ofr65179)、電力
会社はサイト内で新たに確認された断層も含めて過去1万年間は活動
していないと主張した。しかし、審査委員会とAECは「断層運動を考
慮した設計」を要求し、この要求はBodega Headの例から予想される
ように「そのような設計の先例がない」という理由で最終的な不許
可につながって行く。結局、1万年に1回以下の断層運動のリスクに
より、電力会社はMalibu原発の建設計画を放棄せざるを得なくなっ
た。
加州中央部のGE Vallecitos試験炉(主に同位体製造用)は、運転開
始20年後の1977年の免許更新時に、NRCがその近くに活断層があると
いう情報を得て、GE社に地質調査を指示した。USGSの新しい地質図
に活断層が示されたのである。GEが断層沿いの2地点で長さ300フィー
ト、深さ13フィートのトレンチを掘削した結果、両トレンチに新し
い時代の水平な地層を15フィート変位させる、断層面に粘土を伴う
傾斜25度の逆断層が出現した。専門家の間ではこれが活断層か地す
べりか議論があったが(上記Hart et al. 2012参照)、NRCは結局、
「原子炉を安全に冷温停止状態にし、その状態を維持すること。そ
の状態を変更しようとする場合は理由を示すこと」と命令した。こ
れは運転禁止に等しい。
以上のように、加州では原発建設初期から活断層が非常に大きな
問題になっていた。同様に活断層や地震が多い日本で活断層問題に
より建設中止になった原発はないが、福島第一原発事故後の見直し
の中で、敷地内や近傍の活断層問題で審査が難航し、停止が続いて
いる原発は複数ある。日本の現在の新規制基準では、12〜13万年前
より新しい地層(後期更新世以後の上載層)を1回でも変位させてい
れば「将来活動する可能性のある断層等」とみなし、それが重要施
設の直下に露頭していてはならないと定めている。この「断層等」
は支持地盤に達する地すべり面を含む旨、審査ガイドに明記されて
いる。敷地近傍に起震断層があれば、その地震動を最も厳しい条件
で評価する。しかし、この新規制基準といえども金科玉条ではなく、
活断層や地震・津波・火山等に関する新知見や国際的な規制動向を
取り入れて随時改善し、バックフィットしていく必要がある。
本書には、Point Arenaの「円形の断層」、輸入した米国製原発への
日本人の不満(overly cautious!?)、Benioff博士の日本留学の成
果(耐震基準0.1G!?)など興味深い話が満載だが、一方で著者の勘
違いも若干見られる。例えばp. 5で1958年頃の話としてサンアンド
レアス断層が「プレート」境界と考えられていたと言うが、プレー
ト論の提唱は1960年代後半である。P. 42の2段落目の「過去1100万
年間」は文脈から1.1万年の誤りだと思われる。
本書が最も強調する点は、地質屋と技術屋、理系と工学系の考え方
がいかに違い、それが原子力産業にどう影響したかということであ
る。本書は原発の活断層問題の必読書であるが、地質学と社会の関
係についても考えさせられる。会員各位のご一読をお勧めする。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■シンポジウム:研究の最前線
〜中期更新世以降の関東平野北東部の地質と地形発達〜
10月19日(土) 13:20〜17:00(13:00開場)
会場:つくば市役所コミュニティー棟第一会議室
主催:筑波山地域ジオパーク推進協議会
共催:日本地質学会関東支部
参加費:無料
■筑波山地域ジオパーク巡検
10月20日(日)TXつくば駅9:50集合-17:00解散(予定)
募集:20人(先着順)
講師:久田健一郎(筑波大学)・杉原 薫(筑波大学)
申込期間(予定):9月9日(月)〜10月4日(金)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■企画展「ベリリウムの華 魅惑の緑柱石・金緑石展」
9月10日(火)-11月4日(月)
場所:石川町立歴史民俗資料館 3階展示場
http://www.geosociety.jp/name/content0154.html
■那須野が原博物館
開館15周年記念特別展「昆虫創世記」
昆虫がたどった4億年の道のりがいま明らかに!
開催中-9月23日(月・祝)
http://www2.city.nasushiobara.lg.jp/hakubutukan/
(後)サテライトミュージアム企画展示「アンモナイト展」
7月20日(土)-8月31日(土)
場所:新潟大学駅南キャンパス ときめいと(新潟市中央区笹口1-1プラーカ)
入館無料
http://www.lib.niigata-u.ac.jp/tenjikan/index.html
■第9回学生ヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集(地質学会推薦)
日程(仮):2020年3月4日-18日(出国から帰国まで15日間)
参加申込締切:2019年12月31日
参加費:学生・大学院生 20万円以内
http://www.gondwanainst.org/geotours/Studentfieldex_index.htm
-------------------------------------------------------------
(後)科教協福岡大会・科学お楽しみ広場
(第66回全国研究大会福岡大会)
8月9日(金)
会場:西南学院大学 西南コミュニティセンター(福岡市早良区)
参加無料
参加者は各展示ブースを回って,自然科学,理科教育に関する様々な
体験や学びができます.児童生徒も参加可.
https://kakyokyo.org/archives/1319
第225回地質汚染・災害イブニングセミナー
8月30日(金)18:30-20:30
場所:北とぴあ806会議室(東京都北区王子)
講師:山崎晴雄(首都大学東京名誉教授 理学博士)
演題:『首都圏における活断層』−地層判定の重要性−
会費:会員500円 非会員 1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
(後)第63回粘土科学討論会
9月10日(火)-12日(木)
(講演会:9月10-11日,現地見学会:9月12日)
会場:埼玉大学(さいたま市桜区下大久保225)
http://www.cssj2.org/publication/annual_meeting/
(共)日本地球化学会第66回年会
9月17日(火)-19日(木)
場所: 東京大学・本郷キャンパス
http://www.geochem.jp/meeting/index.html
★ 日本地質学会第126年学術大会(2019山口)
9月23日(月・祝)-25日(水)
場所:山口大学 吉田キャンパス(山口市吉田)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/top
■第226回 地質汚染・災害イブニングセミナー
9月27日(金)18:30-20:30
場所:北とぴあ806会議室(東京都北区王子)
講師:張 銘(産業技術総合研究所 地圏環境リスク研究G長)
演題:「化学と科学でみる自然由来重金属類」
会費:会員500円 非会員 1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
(協)第35回ゼオライト研究発表会
12月5日(木)-6日(金)
会場:タワーホール船堀(江戸川区船堀4-1-1)
https://jza-online.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0191.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・2020年度笹川科学研究助成の募集(9/17-10/16)
・日本アイソトープ協会奨励賞(10/31)
・第41回沖縄研究奨励賞(学会締切9/6)
・大船渡市立博物館地質学芸員募集(8/28)
・新潟大学 災害・復興科学研究所 准教授公募(8/30)
・土木研究所寒地土木研究所 任期付研究員公募(8/26,17時)
・京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻准教授公募(9/30)
・京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻教授または准教授募集 (8/30)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No.459 2019山口大会:参加登録締切延長!(8/22;15時)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.459 2019/8/20┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
[2019山口大会情報]
【1】[2019山口]事前参加登録締切延長(8/22;15時まで)
【2】[2019山口]緊急展示申込受付中
【3】[2019山口]会員カードを忘れずに
【4】[2019山口]全体日程表・講演プログラム
------------------------------------------------------------
【5】2019年度大学院生の研究・生活実態に関するアンケート調査
【6】第36回万国地質学会議(IGC)のご案内
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2019山口]事前参加登録締切延長(8/22;15時まで)
──────────────────────────────────
参加登録に関わるお申込(大会参加・要旨集注文,巡検,懇親会,
弁当)については,例年通りオンラインによる大会専用参加登録シ
ステムよりお申し込み下さい(会員・非会員とわず,どなたでも申込可
能です).また,巡検のみに参加する場合には,大会参加登録費は
徴収しません.
巡検は,すでに定員に達したコースもあります(申込可能コース:A, B, F)
ので,ご注意下さい.
[巡検の申込状況はこちら]
http://www.geosociety.jp/science/content0104.html
申込締切[延長]:8月22日(木)15時[WEB]
詳しくは,https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/sanka
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2019山口]緊急展示申込受付中
──────────────────────────────────
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災
害調査報告や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コー
ナー」を設けます.ポスター展示を希望する方は,9月5日(水)ま
でにお申込下さい。
(注)コアタイムの時間帯が設けられます.優秀ポスター賞へのエ
ントリーも可能です.発表における1人1題の制約は及びません.
申込締切:9月5日(水)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/emergency
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2019山口]会員カードを忘れずに
──────────────────────────────────
大会会場での受付は「会員カード」で簡単に手続きいたします.
地質学会会員の方は,「会員カード」を忘れずに持参して下さい.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/card
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2019山口]全体日程表・講演プログラム
──────────────────────────────────
山口大会の全体日程表・講演プログラム(セッション別)を公開しています。
なお,一部情報は修正・変更される場合があります。
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/program
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2019年度大学院生の研究・生活実態に関するアンケート調査
──────────────────────────────────
本調査は、全国大学院生協議会(全院協)が行う、全国の大学院生
を対象としたアンケート調査です。大学院生の研究及び生活実態を
客観的に把握し、もってその向上に資することを目的としておりま
す。本調査へのご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
回答期限:2019年9月13日(金)
詳しくは,https://forms.gle/CP3zxCcEFYySye8E9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】第36回万国地質学会議(IGC)のご案内
──────────────────────────────────
第36回万国地質学会議
日程:2020年3月2日(月)-8日(日)
https://www.36igc.org/
参加登録:8月31日(土)までは格安.
要旨申込締切:10月15日(火),ただし,9月15日(日)までは無料.
この中では,日本からの提案のセッションも多く設けられています.
日本主導で行っている以下のタスクグループでも,Theme45において,
IUGS Task Group on Geohazards (TGG)
(http://iugstgg.lab.irides.tohoku.ac.jp/)は、Theme 45におい
て “45.8 Geohazards surveys, data integration and their
comprehensive guidelines”のセッションを設けております.
このセッションは、頻発する地震、津波、火山、地すべりなどの地
質災害に対する調査技術、地理情報技術、リスク管理技術と地質災
害調査のガイドラインに焦点を当てるものです。
このセッションへの参加と研究発表をお願いします。特に地質災害
調査のガイドラインは新興国に有効と思いますので、新興国で活躍
されている研究者の方にも参加していただきたいと思います。IGCは
登録費、旅費、滞在費を支援するGeohost Support program
(https://www.36igc.org/geohost-program)を設けていますので是非
利用して下さい。
IUGS Task Group on Geohazards (TGG)に関する問い合わせ
大久保泰邦(元産総研)IUGS Task Group on Geohazards座長
Okubo-Yasukuni@jspacesystems.or.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■シンポジウム:研究の最前線
〜中期更新世以降の関東平野北東部の地質と地形発達〜
10月19日(土) 13:20-17:00(13:00開場)
会場:つくば市役所コミュニティー棟第一会議室
主催:筑波山地域ジオパーク推進協議会
共催:日本地質学会関東支部
参加費:無料
■筑波山地域ジオパーク巡検
10月20日(日)
TXつくば駅9:50集合-17:00解散(予定)
募集:20人(先着順)
講師:久田健一郎(筑波大学)・杉原 薫(筑波大学)
申込期間(予定):9月9日(月)-10月4日(金)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
地震本部ニュース2019夏号発行
首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト:防災科学技術研究
所 ほか https://www.jishin.go.jp/herpnews/
(後)サテライトミュージアム企画展示「アンモナイト展」
7月20日(土)-8月31日(土)
場所:新潟大学駅南キャンパス ときめいと(新潟市中央区笹口1-1プラーカ)
入館無料
http://www.lib.niigata-u.ac.jp/tenjikan/index.html
第9回学生ヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集(地質学会推薦)
日程(仮):2020年3月4日-18日(出国から帰国まで15日間)
参加申込締切:2019年12月31日
参加費:学生・大学院生 20万円以内
http://www.gondwanainst.org/geotours/Studentfieldex_index.htm
-------------------------------------------------------------
第225回地質汚染・災害イブニングセミナー
8月30日(金)18:30-20:30
場所:北とぴあ806会議室(東京都北区王子)
講師:山崎晴雄(首都大学東京名誉教授 理学博士)
演題:首都圏における活断層−地層判定の重要性−
会費:会員500円 非会員 1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
(後)第63回粘土科学討論会
9月10日(火)-12日(木)
(講演会:9月10-11日,現地見学会:9月12日)
会場:埼玉大学(さいたま市桜区下大久保225)
http://www.cssj2.org/publication/annual_meeting/
(共)日本地球化学会第66回年会
9月17日(火)-19日(木)
場所: 東京大学・本郷キャンパス
http://www.geochem.jp/meeting/index.html
★ 日本地質学会第126年学術大会(2019山口)
9月23日(月・祝)-25日(水)
場所:山口大学 吉田キャンパス(山口市吉田)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/top
第226回 地質汚染・災害イブニングセミナー
9月27日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ806会議室(東京都北区王子)
講師:張 銘(産業技術総合研究所地圏環境リスク研究グループ長)
演題:化学と科学でみる自然由来重金属類
会費:会員500円 非会員 1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
ぼうさいこくたい2019
「あなたが知りたい防災科学の最前線:激化する気象災害に備える」
10月19日(土)16:30-18:00
場所:名古屋市ささしまライブ24エリア・メインホールB
http://www.bosai-kokutai.jp/
(協)第35回ゼオライト研究発表会
12月5日(木)-6日(金)
会場:タワーホール船堀(江戸川区船堀4-1-1)
https://jza-online.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0191.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・JAMSTEC海域地震火山部門火山・地球内部研究C 研究員募集(10/7)
・2019年度三井物産環境基金活動助成/研究助成募集(9/24)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No.460 祝!地オリ2019 日本代表4人全員が金メダル
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.460 2019/9/3┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】地学オリンピック2019 日本代表4人全員が金メダル!!
【2】[2019山口]緊急展示申込受付中
【3】[2019山口]若手向けルームシェアプラン(締切延長)
【4】[2019山口]会場周辺の便利マップができました!
【5】[2019山口]会員カードを忘れずに
【6】地質系統・年代の日本語記述ガイドライン 2019年5月改訂版
【7】地質学雑誌からのお知らせ
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】地学オリンピック2019 日本代表4人全員が金メダル!!
──────────────────────────────────
第13回国際地学オリンピックが8月26日から韓国で行われ、日本代表
の高校生4人全員が金メダルを獲得しました.日本が代表を派遣し始
めた2008年以来,初の快挙です.
日本代表として出場し、金メダルを獲得したのは次の4人です.
・大野浩輝君(筑波大学附属駒場高校2年)
・寺西雅貴君(灘高校3年)
・中尾俊介君(洛星高校3年)
・山野元暉君(灘高校3年)
また,日本からは表彰対象にならない特別派遣として,山田 耀君
(筑波大学附属駒場高校3年)も参加し,金メダル相当の成績を挙
げたとのことです.
おめでとうございます!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2019山口]緊急展示申込受付中(9/5締切)
──────────────────────────────────
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災
害調査報告や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コー
ナー」を設けます.ポスター展示を希望する方は,9月5日(水)ま
でにお申込下さい。
(注)コアタイムの時間帯が設けられます.優秀ポスター賞へのエ
ントリーも可能です.発表における1人1題の制約は及びません.
申込締切:9月5日(水)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/emergency
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2019山口]若手向けルームシェアプラン(締切延長)
──────────────────────────────────
山口大会では若手会員向けの宿泊施設をご用意いたしました.学術
大会での若手会員の宿泊先確保を支援し、若手同士の交流機会をつ
くることで、若手会員の皆様の研究活動をサポートしたいと考えて
おります。是非、本プランをご活用いただき、研究仲間の輪を広げ
ていただきたいと思います。
対象となる若手会員:山口大会へ参加する定収のない学生(学部,
修士,博士)およびポスドク研究員等
申込締切:9月18日(水)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0110.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2019山口]会場周辺の便利マップができました!
──────────────────────────────────
山口大学周辺のバス停やコンビニ、そして地元会員オススメの居酒屋を惜しげ
もなく紹介します!これはすばらしい!大会期間中のスケジュールもばっちり
です!
*便利マップ(グーグルマップ)はこちらから
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=19d2hyeGhDpeinI7r-n8
gxaQMPDaxAuNd&hl=ja
*大会HPから実行委員会特製「湯田温泉巡検案内書」(PDF)がDLできます.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2019山口]会員カードを忘れずに
──────────────────────────────────
大会会場での受付は「会員カード」で簡単に手続きいたします.
地質学会会員の方は,「会員カード」を忘れずに持参して下さい.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/card
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質系統・年代の日本語記述ガイドライン 2019年5月改訂版
──────────────────────────────────
地質系統・年代の日本語記述ガイドライン 2019年5月改訂版を掲載
しました.前回からの変更点は下記の通りです,
【変更点】更新世中期の下限が,78.1万年前から77.3万年前に.
http://www.geosociety.jp/name/content0062.html
◆「GSSPとは何か?」GSSP (Global Boundary Stratotype Section
and Point:国際境界模式層断面とポイント)についての解説も掲載
しました. http://www.geosociety.jp/name/content0166.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】地質学雑誌からのお知らせ
──────────────────────────────────
第125巻第8号(2019年8月号)が刊行されました(9/2発送).
8月号は,2019山口大会の巡検案内書4編が掲載されています!
最新号目次はこちら
http://www.geosociety.jp/publication/content0092.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■シンポジウム
「研究の最前線:中期更新世以降の関東平野北東部の地質と地形発達」
10月19日(土) 13:20-17:00(13:00開場)
会場:つくば市役所コミュニティー棟第一会議室
主催:筑波山地域ジオパーク推進協議会
共催:日本地質学会関東支部
参加費:無料
■筑波山地域ジオパーク巡検
10月20日(日)
TXつくば駅9:50 集合-17:00 解散
募集:20人(先着順)
講師:久田健一郎(筑波大学)・杉原 薫(筑波大学)
申込期間:9月9日(月)-10月4日(金)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
京都大学総合博物館特別展『地の宝? 比企鉱物標本』開催中
7月31日(水)-11月3日(日)
場所:京都大学総合博物館(京都市左京区吉田本町)
http://www.museum.kyoto-u.ac.jp/modules/special/content0073.html
第9回学生ヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集(地質学会推薦)
日程(仮):2020年3月4日-18日(出国から帰国まで15日間)
参加申込締切:2019年12月31日
参加費:学生・大学院生 20万円以内
http://www.gondwanainst.org/geotours/Studentfieldex_index.htm
-------------------------------------------------------------
第225回地質汚染・災害イブニングセミナー
8月30日(金)18:30-20:30
場所:北とぴあ806会議室(東京都北区王子)
講師:山崎晴雄(首都大学東京名誉教授 理学博士)
演題:首都圏における活断層−地層判定の重要性−
会費:会員500円 非会員 1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
(後)第63回粘土科学討論会
9月10日(火)-12日(木)
(講演会:9月10-11日,現地見学会:9月12日)
会場:埼玉大学(さいたま市桜区下大久保225)
http://www.cssj2.org/publication/annual_meeting/
(共)日本地球化学会第66回年会
9月17日(火)-19日(木)
場所: 東京大学・本郷キャンパス
http://www.geochem.jp/meeting/index.html
★ 日本地質学会第126年学術大会(2019山口)
9月23日(月・祝)-25日(水)
場所:山口大学 吉田キャンパス(山口市吉田)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/top
第226回 地質汚染・災害イブニングセミナー
9月27日(金)18:30〜20:30
場所:北とぴあ806会議室(東京都北区王子)
講師:張 銘(産業技術総合研究所地圏環境リスク研究グループ長)
演題:化学と科学でみる自然由来重金属類
会費:会員500円 非会員 1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
ぼうさいこくたい2019
「あなたが知りたい防災科学の最前線:激化する気象災害に備える」
10月19日(土)16:30-18:00
場所:名古屋市ささしまライブ24エリア・メインホールB
http://www.bosai-kokutai.jp/
(協力)深田研一般公開2019
10月6日(日)
場所:深田研地質研究所(文京区本駒込)
*第10回フォトコンテスト作品の展示もあります*
http://www.fgi.or.jp/
第227回地質汚染・災害イブニングセミナー
10月25日(金)18:30-20:30
場所:北とぴあ808会議室 (東京都北区 JR王子駅から徒歩5分)
講師:笹川みちる(雨水市民の会理事、雨水まちづくりサポート理事)
演題:「雨水と賢くくらすには:墨田区の取り組みから」
会費:会員500円 非会員 1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
2019年度秋期(初級者向け)地質調査研修【参加者募集中】
10月28日(月)-11月1日(金)
場所:島根県出雲市長尾鼻周辺(小伊津海岸)
定員:6名(締切:10月11日(金))(定員になり次第締切)
https://www.gsj.jp/geobank/geotraining.html
(後)第20回「こどものためのジオ・カーニバル」
11月2日(土)-3日(日)
場所:大阪市立科学館
http://geoca.org/index.html
第30回地質汚染調査浄化技術研修会
11月15日(金)-17日(日)
共催:地質汚染診断士の会・日本地質学会環境地質部会・社会地質学会
会場:日本地質汚染審査機構 関東ベースン実習センター(千葉県香取市)
会費:会員45,000円・非会員 55,000円・学生:15,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
(協)第35回ゼオライト研究発表会
12月5日(木)-6日(金)
会場:タワーホール船堀(江戸川区船堀4-1-1)
https://jza-online.org/
地質学史懇話会
12月22日(日)13:30-17:00
場所:北とぴあ 8階803号室(JR京浜東北線 王子駅下車3分)
八耳俊文:岡田家武と張定?の生涯:上海自然科学研究所化学科員の政治と
科学山田俊弘:地層累重の法則の意味:ステノ『プロドロムス』(1669)出版
350周年を記念して(仮)
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0191.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・山田科学振興財団2020年度海外研究留学助成募集(10/31)
・広島大学大学院理学研究科地球惑星システム専攻助教(女性)公募(10/15)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No.461 まもなく山口大会ですよ!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.461 2019/9/17┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
[2019山口大会関連情報]
【1】予約確認書(はがき)を発送しました
【2】懇親会わずかですが当日申込可能です!
【3】会員カードを忘れずに
【4】大会用に臨時バスが運行されます
【5】若手向けルームシェアプラン申込受付中(締切延長)
【6】会場周辺の便利マップができました!
---------------------------------------
【7】チャレンジ地球 参加者募集!
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2019山口]予約確認書(はがき)を発送しました
──────────────────────────────────
大会事前参加登録者の皆様へ予約確認書(はがき)を発送しました
(9/11).当日は,会員カードとともに会場へお持ち下さい.
なお,入金確認が取れていない方には,未入金の旨が記載されていま
す.当日会場にて「会員カード」もしくは確認書をご提示いただき,
代金の清算をお願いします.行き違いでご入金済の場合は,入金時
の控え等を会場にお持ちください.
当日の受付について
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/reception
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2019山口]懇親会わずかですが当日申込可能です!
──────────────────────────────────
懇親会の当日受付が可能です。ただし数に限りがありますので,ご
希望の方は早めに会場受付にてお申し込み下さい。
今回は地元飲食店等のご協力(広告収入)により,会場周辺の湯田
温泉巡検案内書!?やLOC特製「地質学会ロゴ入り一合枡」のお土産
を用意しています。懇親会では特製枡で,獺祭をはじめとした山口
の地酒を是非ご堪能下さい!
日時:9月23日(月・祝)17:30-19:30
会場:山口大学 吉田キャンパス 第2学生食堂(きらら)
[会費(当日申込)](※ 非会員の会費は会員に準じます)
正会員:6,000円
院生/学部割引会費適用正会員・名誉会員・50年会員,同伴者:4,000円
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2019山口]会員カードを忘れずに
──────────────────────────────────
大会会場での受付は「会員カード」で簡単に手続きいたします.
地質学会会員の方は,「会員カード」を忘れずに持参して下さい.
新規入会の方には,先週カードを発送いたしました(9/12発送).
お手元の郵便物をご確認下さい.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/card
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2019山口]大会用に臨時バスが運行されます
──────────────────────────────────
大会会期中は「湯田温泉バス停」-「山口大学バス停」間を朝夕に臨時便が出ま
す.是非ご利用下さい.
<臨時便等バス時刻表>
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/etc#bus
このほか,会場へのアクセスは,大会HPをご確認下さい.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/acess
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2019山口]若手向けルームシェアプラン(締切延長)
──────────────────────────────────
山口大会では若手会員向けの宿泊施設をご用意いたしました.学術
大会での若手会員の宿泊先確保を支援し、若手同士の交流機会をつ
くることで、若手会員の皆様の研究活動をサポートしたいと考えて
おります。是非、本プランをご活用いただき、研究仲間の輪を広げ
ていただきたいと思います。
対象:山口大会へ参加する定収のない学生(学部,修士,博士)お
よびポスドク研究員等
申込締切:9月18日(水)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0110.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[2019山口]会場周辺の便利マップができました!
──────────────────────────────────
山口大学周辺のバス停やコンビニ、そして地元会員オススメの居酒屋を惜しげ
もなく紹介します!これはすばらしい!大会期間中のスケジュールもばっちり
です!
*便利マップ(グーグルマップ)はこちらから
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=19d2hyeGhDpeinI7r-n8gxaQMPDaxAuNd&hl=ja
*大会HPから実行委員会特製「湯田温泉巡検案内書」(PDF)がDLできます.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】チャレンジ地球 参加者募集!
──────────────────────────────────
小学生のための地学オリンピック:
チャレンジ地球 クイズ30とジオパーク探検
今年は「関東版」「関西版」を企画いたしました!
**関東版**
「ジオパーク探検」(筑波山地域ジオパークの霞ヶ浦湖岸)11月23日(土)
「クイズ30」12月15日(日)13:00-15:00(クイズの時間は60分)
会場:筑波大学東京キャンパス文京校舎
**関西版**
「ジオパーク探検」(山陰海岸ジオパーク)11月10日(日)/12月1日(日)
「クイズ30」12月15日(日)10:00-12:00
会場:大阪教育大学天王寺キャンパス
詳しくは, http://www.geosociety.jp/name/content0167.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■シンポジウム
「研究の最前線:中期更新世以降の関東平野北東部の地質と地形発達」
10月19日(土) 13:20-17:00(13:00開場)
会場:つくば市役所コミュニティー棟第一会議室
主催:筑波山地域ジオパーク推進協議会
共催:日本地質学会関東支部
参加費:無料
■筑波山地域ジオパーク巡検
10月20日(日)
TXつくば駅9:50 集合-17:00 解散
募集:20人(先着順)
講師:久田健一郎(筑波大学)・杉原 薫(筑波大学)
申込期間:9月9日(月)-10月4日(金)
■地学教育・アウトリーチ巡検(チバニアン周辺)
11月24日(日)
集合:小湊鉄道「月崎駅」10:20
内容:チバニアンの地層見学、素掘りのトンネルの見学等
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
第9回学生ヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集(地質学会推薦)
日程(仮):2020年3月4日-18日(出国から帰国まで15日間)
参加申込締切:2019年12月31日
参加費:学生・大学院生 20万円以内
http://www.gondwanainst.org/geotours/Studentfieldex_index.htm
-------------------------------------------------------------
(共)日本地球化学会第66回年会
9月17日(火)-19日(木)
場所: 東京大学・本郷キャンパス
http://www.geochem.jp/meeting/index.html
★ 日本地質学会第126年学術大会(2019山口)
9月23日(月・祝)-25日(水)
場所:山口大学 吉田キャンパス(山口市吉田)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/top
(協力)深田研一般公開2019
10月6日(日)
場所:深田研地質研究所(文京区本駒込)
*第10回フォトコンテスト作品の展示もあります*
http://www.fgi.or.jp/
(協)石油技術協会秋季講演会
10月17日(木)
会場:東京大学 小柴ホール
プログラムも公開しています
https://www.japt.org/gyouji/kouenkai/
ぼうさいこくたい2019
「あなたが知りたい防災科学の最前線:激化する気象災害に備える」
10月19日(土)16:30-18:00 参加費無料
場所:名古屋市ささしまライブ24エリア・メインホールB
http://www.bosai-kokutai.jp/
学術会議公開シンポジウム
「社会調査のオープンサイエンス化へ向けての課題」
10月19日(土)14:30-17:15
会場:首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス
参加費無料・事前申込不要
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/280-s-1019.pdf
石川町立歴史民俗資料館企画展記念講演会
「阿武隈高地の地質」
10月20(日)14:00から
場所:石川町文教福祉複合施設(モトガッコ)
〒963-7852 福島県石川郡石川町字関根165
講師:蟹澤聰史先生(東北大学理学研究科名誉教授)
http://www.town.ishikawa.fukushima.jp/
第10回日本ジオパーク全国大会2019おおいた大会
10月31日(木)-11月5日(火)
https://www.oita-geo2019.jp/
(後)第20回「こどものためのジオ・カーニバル」
11月2日(土)-3日(日)
場所:大阪市立科学館
http://geoca.org/index.html
(協)第35回ゼオライト研究発表会
12月5日(木)-6日(金)
会場:タワーホール船堀(江戸川区船堀4-1-1)
https://jza-online.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0191.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・北海道大学大学院理学研究院 地球惑星システム科学分野教授公募(12/20)
・大阪市立自然史博物館学芸員募集(植物化石/無脊椎動物化石 各1)(10/18)
・山形大学学術研究院(理学部主担当、地球科学分野)講師又は助教公募(11/6)
・2020年度東京大学地震研究所客員教員公募(10/31)
・新学術領域研究「南極の海と氷床」の公募研究の募集 (11/7)
・2020年度東京大学地震研究所共同利用(10/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No.462 開幕!山口大会 写真で紹介
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.461 2019/9/22 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】山口大会:初日の様子
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】山口大会 初日の様子
──────────────────────────────────
山口大会が開幕しました!
台風が過ぎ去り、山口大会は予定通り開幕を迎えました。
■普及事業:市民講演会と地質情報展
情報展開幕!
産総研矢野センター長挨拶
地質学会松田会長挨拶
山口大学田中副学長挨拶
テープカット
大人気化石づくり
憧れのヘルメット
石割体験
巨大地質図
顕微鏡大好き
わいわいがやがや
台風の中で土砂災害の市民講演会
■会場と表彰式
出動!臨時バス
開幕!
熱気あふれる講演会場
高校生ってスゴイ
ポスター会場!
ポスター!ポスター!
企業ブースもフル回転
表彰式開始
会長挨拶
山口大学田中副学長(実は会員)
小玉名誉会員
佐藤永年会員
庄司永年会員
鳥海永年会員
藤本永年会員
田中永年会員
日本地質学会賞 多田会員
小澤儀明賞 齋藤会員
論文賞 佐野会員
論文賞 長谷川会員
奨励賞 葉田野会員
日本地質学会表彰 (株)新興出版啓林館様
日本地質学会表彰 数研出版株式会社
日本地質学会表彰 加納会員
山口大学副学長,理学部長も壇上に
国際賞 Stern博士からビデオメッセージ
■渾身の懇親会
獺祭の樽酒
よいしょ!の掛け声で鏡割り
フグや瓦そばなど山口料理
日本海と瀬戸内の魚
楽しーい
わいわいがやがや
おみやげです.どうぞ!
来年は名古屋で会いましょう!
■2日目と3日目(追加 2019.9/26)
ポスター室の熱気
シンポジウムも大入り
山口の地質学展示
若手会員のための企業研究すサポート
来年は名古屋で合いましょう。
海岸礫は河川礫より円くて扁平である
海岸礫は河川礫より円くて扁平である
石渡 明*(原子力規制委員会)
田上雅彦*・谷 尚幸・ 大橋守人・内藤浩行(原子力規制庁)
(*本会正会員)
河川と海岸で礫(れき)(小石,石ころ)の形に違いがあるかどうかという問題は,小学校や中学校の夏休みの自由研究のテーマのように聞こえるが,両所の礫形の違いについてはっきり述べた教科書はなく,公表された研究結果も少ない.しかし,きちんと計測すれば海岸礫は河川礫より円くて扁平であることが,文献調査と実測により明らかになったので報告する.
中山(1954)による礫の円磨度ρの定義は,角ごとの曲率半径ri,最大内接円半径R,角の数Nとすると,ρ=Σri/NRである.多角形は曲率半径がゼロだからρ=0,円は1角形とみなしてri=Rだからρ=1となる.中山・三浦(1964)は,原語roundnessには磨滅の意味はなく単に円さを意味するとして,訳語を円磨度から円形度に変更した.中山(1965)は浮島海岸(富士〜沼津),三保海岸(安倍川〜清水),高知海岸(仁淀川〜物部川東方)で礫の大きさや形を計測し,彼の河川礫の研究結果と比べて,円形度は海岸礫の方が高く(円に近く),平均円形度が0.60以上であれば海岸礫とみなせると述べ,扁平度(1-c/b)も海岸礫の方が高くて(扁平で),0.40以上のものが多ければ海岸礫とみなせると述べた.要するに,海岸礫は河川礫より円くて扁平であり,碁石やドラ焼きのような形をしていると言うのである.それに対して河川礫の形を一言で言えば「ゴロンとした形」(ジャガイモやカキフライのような形)と言えるだろう.日本の海岸には「碁石浜」が複数あり,これは白と黒の小石が敷きつめられた砂利浜という意味の他に,碁石のように円くて扁平な礫が多いことも意味し,一般人の観察眼の的確さを示している.
平塚市博物館地層観察会(1986)は酒匂(さかわ)川,金目(かなめ)川,相模(さがみ)川の河川礫と小田原〜平塚間の海岸礫を多数計測し,統計処理を行った.礫の長径,中径,短径をa, b, cとし,扁平率Fg=c/√abとすると(中山の扁平度と逆に,球は1,紙は0に近い),Fgは海岸が0.32〜0.49,河川が0.46〜0.61,c/aは海岸が0.28〜0.39,河川が0.39〜0.51,c/bは海岸が0.38〜0.61,河川が0.54〜0.77で,これらの値はどれも河川礫の方が海岸礫よりも統計的な有意差をもって高いという結果が得られた.これは中山(1965)の結果と同様に海岸礫の方が河川礫より扁平な形をしていることを意味している.ただし,b/aの値に顕著な差はなかった.
我々はこれらの文献の結果を確認するために,相模川戸沢橋下右岸と大磯海岸照ヶ崎北西200mにおいて,それぞれ長径5cm程度の礫100個について写真撮影を行い,フリーの画像計測ソフトImage-Jによる解析を行った.写真撮影には多数の円い突起がついたシリコン樹脂製の白いキッチンマットを使用し,1回20〜30個の礫を,まずa軸とc軸の長さがわかるように立て置きにして真上から撮影し,次にa軸とb軸の長さがわかるように寝かせて撮影した.これらの画像をImage-Jに取り込み,二値化処理してゴミやバリを除去し,穴埋めをして計測させた(図1).計測値で注目したのは真円度circularity(=4π✕面積/(周囲長)2)と楕円近似の短径長径比である.単純図形の真円度の実測値/理論値は,正方形が0.79/0.79,正三角形が0.55/0.60,星形が0.28/0.24だった.角張っていて入り組んだ形ほど真円度は低くなるが,円磨度(円形度)とは異なり,全部の角が尖(とが)っていても0にはならない.また,これらの単純図形は,短径長径比の理論値はどれも1だが,実測値はそれぞれ0.94,0.99,0.92だった.今回の測定における真円度と短径長径比の誤差は各々5%程度と判断される.
我々の計測結果によると,礫を寝かせた写真(ab面が見える)で計測して真円度0.78以上,短径長径比(b/a)0.71以上なら海岸礫,礫を立てた写真(ac面が見える)では短径長径比(c/a)0.48以下なら海岸礫という結果になった(立て置きでは真円度に差は出ない).海岸礫の方が河川礫よりも円くて扁平だということは,我々の計測でも明確に示され,これは二値画像を見比べても一目瞭然である(図1).実際に海岸で撮影中に気づいたのは,堆積岩に限らず,火山岩や深成岩の礫も扁平なことである.これは河川と海岸における侵食・運搬の営力の違い(一方向の水流による転動に対して波浪による前後反復滑動)が礫形の違いに反映していることを示唆する.
図1.相模川(A, B)と大磯海岸(C, D)の礫の二値画像.AとCは立て置き(画像から短径と長径がわかる状態),BとDはよこ置き(寝かせた状態).画面横幅はいずれも約55cm.左右の図は,礫は同じで,礫の姿勢を変えて撮影したもの.
保柳ほか(2004)の教科書のp. 104ではKrumbein(1941)の円磨度印象図を掲げて「円磨度の厳密な測定には多大の労力がかかるので……円磨度印象図と比較して半定量的な測定を行う」と述べているが,実際に「多大な労力をかけて」円磨度(円形度)を測定した中山(1965)は,「最近の研究に用いられた円形度はKrumbeinの表から求めたものが多い.しかし,この方法によった値は一般にかなり高く,地点相互の比較は難かしい」,「円形度0.60より高い値は視察ではなかなか区別しにくい」と,この「半定量的な測定法」を半世紀前に批判している.阿部・白井(2013)はKrumbeinの図を用いながらも細かい円磨度の判定は避け,超角礫〜角礫(円磨度0.1〜0.2,全ての頂点が角ばる),亜角礫〜亜円礫(0.3〜0.4,一部の頂点が丸まる),円礫〜超円礫(0.5〜1.0,全ての頂点が丸まる)の3分類とし,河川砂と海浜砂の間でこれら3分類の割合に有意差を見出して内陸の津波堆積物を同定した.教科書に盲従せず,自分の頭で考えて有用な結果を出した例であるが,同じ試料をだれが判定しても同じ結果になるかどうか,疑問は残る.また,Krumbeinの論文には,この図は16〜32mmの小礫用と明記してあり,砂や大礫に用いるものではない.
以上の文献や我々の実測結果に基づけば,海岸沿いの地域で,過去の段丘礫層が河成か海成か判断する必要が生じた場合などに,礫形の計測は有効な判別手段になり得ると考えられる.ただし,この計測は50個(Krumbein)ないし150個(中山)の礫について統計的に行う必要がある(20〜30個計測すれば結果が予想できる).また,画像処理には撮影機器や撮影条件の違い,実施者の習熟度,注意深さ,好み,癖などの影響が強く出るので,まず典型的な河川礫と海岸礫を現場で実測して,礫形の違いがはっきり数字に表れることを確認し,この準備作業をしたのと同じ人が,実際の段丘礫層の試料の計測と評価を行うようにすべきだと思う.なお,100個程度の礫を計測するだけなら,あまり画像処理を使うメリットはなく,現場でノギスを使って3軸長を計測した方が早く確実な結果が得られるが,証拠を残し結果の再現性を確保して検証可能にする意味では,写真を計測した方がよい.
産総研地質調査総合センター(旧地質調査所)の1/5万地質図説明書には段丘礫層の写真を載せているものがある
(https://www.gsj.jp/Map/JP/geology4.html).「仙崎」と「伊野」の河成段丘礫層は主に角礫〜亜角礫からなり,「大樹」と「喜多方」の河成段丘礫もやや角張っているが,「静岡」,「清水」,「御前崎」の河成段丘礫は円礫で定向配列(imbrication)が発達している.一方,「忠類」,「鰺ヶ沢」,「石見大田」,「洲本」の海成段丘礫はよく円磨され,「須磨」のp. 33の大阪層群最上部明美層の礫は「海浜細礫(beach pebble)」と明記されていて,径5cm程度のよく円磨された扁平な礫からなる.このような日本各地の段丘礫層の写真の観察からも,礫の真円度や短径長径比の計測によって河成・海成を識別することは,ある程度可能であるように思う.
文献についてご教示いただいた平塚市博物館の野崎 篤氏に感謝する.
文 献
阿部朋弥・白井正明 (2013) 愛知県渥美半島の沿岸低地で見出された江戸時代の津波起源と推定されたイベント堆積物.第四紀研究, 52(2), 33-42.
平塚市博物館地層観察会 (1986) 平塚市周辺の河川礫及び海浜礫の諸特性と礫調査における問題点.平塚市博物館研究報告 自然と文化,No. 9, 13-42.
保柳康一・公文富士夫・松田博貴 (2004) 堆積物と堆積岩.フィールドジオロジー3.日本地質学会同書刊行委員会編.共立出版.171p.
Krumbein, W.C. (1941) Measurement and geologic significance of shape and roundness of sedimentary particles. Journal of Sedimentary Petrology, 11, 64-72.
中山正民 (1954) 多摩川における礫の円磨度について.地理学評論, 27(12), 497-506.
中山正民・三浦敏彦 (1964) 日本の河川平野部における礫の円形度について.地理学評論, 37(3), 115-130.
中山正民 (1965) 礫浜における堆積物の諸性質について.地理学評論, 38(2), 103-120.
[2019.11.26 訂正](誤)阿部朋弥・白石正明 (2013) →(正)阿部朋弥・白井正明 (2013)
【geo-Flash】 No.464 2020年度役員選挙立候補受付開始,各賞推薦募集中
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.464 2019/10/15┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2020年度役員選挙(代議員立候補受付中:11/5締切)
【2】2020年度学会各賞候補者募集中(12/2締切)
【3】2020年度の会費について
【4】GSSPシンポジウム:国際層序の意味と意義 開催します!
【5】小学生のための地学オリンピック:チャレンジ地球(参加者募集中)
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2020年度役員選挙(代議員立候補受付中:11/5締切)
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会定款ならびに選挙規則・選挙細則に基づ
いて,代議員および役員(監事,理事)選挙を実施いたします.
<代議員選挙>
立候補受付期間:10月11日(金)-11月5日(火)18 時必着
投票期間:11月27日(水)-1月8日(水)*最終日消印有効
詳しくは,http://sub.geosociety.jp/members/content0106.html
(会員ページへのログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2020年度学会各賞候補者募集中(12/2締切)
──────────────────────────────────
日本地質学会では今年も運営規則第16 条および各賞選考規則にした
がい,賞の候補者を募集いたします
ご応募いただいた場合には,必ず受け取りのお返事をお出しします
のでご確認ください.
*********************************************
応募締切:2019年12月2日(月)必着
*********************************************
詳しくは,http://sub.geosociety.jp/members/content0098.html
(会員ページへのログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2020年度の会費について
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下
さいますようお願いいたします.
また,学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)
の方で,それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適
用します.
・割引会費請求書発行前受付締切:11月20日(水)
・災害に関連した会費の特別措置申請締切:11月29日(金)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】GSSPシンポジウム:国際層序の意味と意義 を開催します!
──────────────────────────────────
現在,我が国初めてのGSSPの認定をめぐり,地質学界のみならず社
会の耳目を集めています.一方で,国際層序や地質単元,GSSPなど
地質学・層位学の基礎についての知識と理解が十分でない現状があ
ります.本シンポジウムでは,我が国の地質学をリードすべき地質
学会として,これまでの国際層序に関する取組みを含めて,改めて
その意味・意義,その詳細を再確認します.
主催:日本地質学会
共催:産総研地質調査総合センター,日本古生物学会(予定)
日時:2019年11月23日(土)13:00-17:00
会場:産総研つくば中央 共用講堂
対象:研究者,技術者,院生・学生(会員・非会員問わずどなたでも
ご参加いただけます)
参加費無料,事前申込不要
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0096.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】小学生のための地学オリンピック:チャレンジ地球(参加者募集中)
──────────────────────────────────
今年は,関東版,関西版を開催します.周囲の小学生(5,6年生対象)や
学校関係の方々に是非お声がけ下さい.クイズだけ,巡検だけの参加も
可能です.
[関西版]
・山陰海岸ジオパーク11/10(日)または12/1(日),
・クイズ30:12/15(日).
[関東版]
・筑波山地域ジオパークの霞ヶ浦湖岸11/23(土),
・クイズ30:12/15(日).
申込締切:10月31日(木)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/name/content0167.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■シンポジウム
「研究の最前線:中期更新世以降の関東平野北東部の地質と地形発達」
10月19日(土) 13:20-17:00(13:00開場)
会場:つくば市役所コミュニティー棟第一会議室
主催:筑波山地域ジオパーク推進協議会
共催:日本地質学会関東支部
参加費:無料
■関東支部:地学教育・アウトリーチ巡検(参加申込受付中)
11月24日(日)
集合:小湊鉄道「月崎駅」10:20
内容:チバニアンの地層見学、素掘りのトンネルの見学等
定員になり次第締切.
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html#ex2019-02
■神津島火山巡検
11月30日(土)-12月1日(日)雨天決行
費用:20,000円(現地での見学地の移動費用,1泊3食費,旅行傷害
保険費,案内資料等の実費を含む.ただし,現地までの交通費は含
みません)
申込締切:11月14日(木)17時(定員に達した時点で締め切り)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
みなみさんりく発掘ミュージアムオープン!
南三陸町歌津に2019年8月小さなミュージアムがオープンしました.
震災後の2012年から開業していた,南三陸直売所「みなさん館」(
NPO法人 夢未来南三陸)の販売スペースの2/3を改装したもので,南
三陸町産の魚竜,アンモノイド,モノティス,嚢頭(のうとう)類(
ティラコセファラ)などの化石や民俗資料を展示しています.
かつて南三陸町歌津には「歌津魚竜館」があり,ウタツギョリュウ
やクダノハマギョリュウ,関連する国外の魚竜,南三陸町産のアン
モノイドやモノティスなどの化石を展示していました.「魚竜館」
は,2011年の津波で被災し,その再建は現在まだ具体化せず,所蔵
標本類の多くは標本収蔵施設にあって,公開されていません.「み
なさん館」では,このような現状を打開し,南三陸の資源と歴史を
広く町内外に公開するため,また,子供たちに地元南三陸の森・里・
海の資源を知ってもらい,それらを保護していく活動の拠点とする
ことを目的に,「みなみさんりく発掘ミュージアム」を「みなさん
館」の中に設営することになりました.従来の直販施設の展示棚や
冷凍販売ケースなどを活用した,手作り感満載のミュージアムです.
展示に関しては東北大学総合学術博物館が全面的に協力しました.
南三陸町のペルム紀,三畳紀,ジュラ紀化石約100点と,若干の歴史
遺物や農水産関係の歴史資料からなっていて,化石と地質に関して
は詳細な解説パネルがあります.化石では,ウタツギョリュウやた
くさんのアンモノイドをはじめ,南三陸から最近発見された,日本
最古の両生類化石マストドンサウルス,日本初の嚢頭類などの化石
やレプリカも展示されています.また,化石観察会などで子供たち
が採集した化石の展示コーナーもあり,この部分は少しずつ展示標
本が増えつつあります.
南三陸方面に調査においでの際はぜひお立ち寄りください.地元の
嚢頭類“キャラ”「ティラコ」の図入りのTシャツ,トートバッグ,
クリアファイル,ワッペンなども販売されています.入館料は100円
です.「みなさん館」は歌津管の浜(平成の森下の国道45号線沿い)
にあります.詳しい場所・営業時間などは,
ホームページhttp://minasankan.comをご参照ください.
(正会員 永広昌之)
第9回学生ヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集(地質学会推薦)
日程(仮):2020年3月4日-18日(出国から帰国まで15日間)
参加申込締切:2019年12月31日
参加費:学生・大学院生 20万円以内
http://www.gondwanainst.org/geotours/Studentfieldex_index.htm
-------------------------------------------------------------
ぼうさいこくたい2019
「あなたが知りたい防災科学の最前線:激化する気象災害に備える」
10月19日(土)16:30-18:00
場所:名古屋市ささしまライブ24エリア・メインホールB
http://www.bosai-kokutai.jp/
(後)第20回「こどものためのジオ・カーニバル」
11月2日(土)-3日(日)
場所:大阪市立科学館
http://geoca.org/index.html
令和元年度「津波防災の日」スペシャルイベント
津波×地域防災×企業
11月5日(火)13:00-18:00
場所: TKP市ヶ谷カンファレンスセンター(東京都新宿区市谷)
http://tsunamibousai.jp/tsunami_special_event2019.pdf
日本学術会議主催学術フォーラム「学術の未来とジェンダー平等
〜大学・学協会の男女共同参画推進を目指して〜」
11月17日(日)13:00-18:00
場所:日本学術会議講堂
定員:先着250名(参加費 無料)
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/279-s-1117.pdf
第228回地質汚染・災害イブニングセミナー
11月28日(木)18:30-20:30
場所:北とぴあ701会議室(東京都北区王子)
講師:山本 晃(八千代エンジニヤリング株式会社 地質・地盤部長)
演題:「地下水流動可視化の研究成果」
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
火山災害軽減のための方策に関する国際ワークショップ
テーマ:火山噴火の危機管理
11月28日(木)9:30-16:40
会場 都道府県会館101大会議室(東京都千代田区平河町)
http://www.mfri.pref.yamanashi.jp/
国際シンポジウム2019
火山噴火とリスクコミュニケーション
11月30日(日)9:30-16:30
会場 山梨県富士山科学研究所 ホール(富士吉田市上吉田)
http://www.mfri.pref.yamanashi.jp/
(協)第35回ゼオライト研究発表会
12月5日(木)-6日(金)
会場:タワーホール船堀(江戸川区船堀4-1-1)
https://jza-online.org/
第230回 地質汚染・災害イブニングセミナー
2020年1月31日(金)18:30-20:30
場所:北とぴあ808会議室(東京都北区)
講師:川辺能成(産総研地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門 地圏環境リスク研究グループ 上級主任研究員)
演題:「3.11東日本大震災時に発生した津波堆積物の重金属の分布とその後」
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0191.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・名古屋大学大学院環境学研究科・助教(テニュアトラック)の公募(12/13)
・戦略的創造研究推進事業総括実施型研究(ERATO)テーマ候補等募集(11/29)
・第61回藤原賞候補者推薦(学会締切:11/25)
・山田科学振興財団2020年度研究援助推薦(学会締切:2020/1/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No.463 GSSPシンポジウムを開催します!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.463 2019/10/1┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】GSSPシンポジウム:国際層序の意味と意義 開催します!
【2】小学生のための地学オリンピック:チャレンジ地球(参加者募集中)
【3】[2019山口]忘れ物をお預かりしています
【4】[2019山口]CPD参加証明書が必要な方
【5】地質学雑誌からのお知らせ
【6】コラム:海岸礫は河川礫より円くて扁平である
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】GSSPシンポジウム:国際層序の意味と意義 を開催します!
──────────────────────────────────
現在,我が国初めてのGSSPの認定をめぐり,地質学界のみならず社
会の耳目を集めています.一方で,国際層序や地質単元,GSSPなど
地質学・層位学の基礎についての知識と理解が十分でない現状があ
ります.本シンポジウムでは,我が国の地質学をリードすべき地質
学会として,これまでの国際層序に関する取組みを含めて,改めて
その意味・意義,その詳細を再確認します.
主催:日本地質学会
共催:産総研地質調査総合センター,日本古生物学会(予定)
日時:2019年11月23日(土)13:00-17:00
会場:産総研つくば中央 共用講堂
対象:研究者,技術者,院生・学生(会員・非会員問わずどなたでも
ご参加いただけます)
参加費無料,事前申込不要
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0096.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】小学生のための地学オリンピック:チャレンジ地球(参加者募集中)
──────────────────────────────────
今年は,関東版,関西版を開催します.
周囲の小学生(5,6年生対象)や学校関係者の方々に是非お声がけ下さい.
クイズだけ,巡検だけの参加も可能です.
[関西版]
・山陰海岸ジオパーク11/10(日)または12/1(日),
・クイズ30:12/15(日).
[関東版]
・筑波山地域ジオパークの霞ヶ浦湖岸11/23(土),
・クイズ30:12/15(日).
申込締切:10月31日(木)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/name/content0167.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2019山口]忘れ物をお預かりしています
──────────────────────────────────
大会期間中の会場(山口大学)での忘れ物,落とし物を学会事務局でお預かり
しています(傘,ノート等)。お心あたりのある方は,ご連絡下さい.
詳しくは,
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/etc#lost
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2019山口]CPD参加証明書が必要な方
──────────────────────────────────
会場でCPD参加証明書をお受け取りにならなかった方も,これからでも証明書
を発行いたします.学会事務局までお申し出下さい.
詳しくは, https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp126/static/cpd
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質学雑誌からのお知らせ
──────────────────────────────────
第125巻第9号(2019年9月号)が刊行されます(10/3発送予定).
最新号目次はこちら
http://www.geosociety.jp/publication/content0092.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】コラム:海岸礫は河川礫より円くて扁平である
──────────────────────────────────
石渡 明(原子力規制委員会)・田上雅彦・谷 尚幸・ 大橋守人・内藤浩行(原子力規制庁)
河川と海岸で礫(れき)(小石,石ころ)の形に違いがあるかどう
かという問題は,小学校や中学校の夏休みの自由研究のテーマのよ
うに聞こえるが,両所の礫形の違いについてはっきり述べた教科書
はなく,公表された研究結果も少ない.しかし,きちんと計測すれ
ば海岸礫は河川礫より円くて扁平であることが,文献調査と実測に
より明らかになったので報告する.
続きを読む、、、 http://www.geosociety.jp/faq/content0056.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■シンポジウム
「研究の最前線:中期更新世以降の関東平野北東部の地質と地形発達」
10月19日(土) 13:20-17:00(13:00開場)
会場:つくば市役所コミュニティー棟第一会議室
主催:筑波山地域ジオパーク推進協議会
共催:日本地質学会関東支部
参加費:無料
■筑波山地域ジオパーク巡検
10月20日(日)
TXつくば駅9:50 集合-17:00 解散
募集:20人(先着順)
講師:久田健一郎(筑波大学)・杉原 薫(筑波大学)
申込期間:9月9日(月)-10月4日(金)
■神津島火山巡検
11月30日(土)-12月1日(日)雨天決行
費用:20,000円(現地での見学地の移動費用,1泊3食費,旅行傷害
保険費,案内資料等の実費を含む.ただし,現地までの交通費は含
みません)
申込締切:11月14日(木)17時(定員に達した時点で締め切り)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
第9回学生ヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集(地質学会推薦)
日程(仮):2020年3月4日-18日(出国から帰国まで15日間)
参加申込締切:2019年12月31日
参加費:学生・大学院生 20万円以内
http://www.gondwanainst.org/geotours/Studentfieldex_index.htm
-------------------------------------------------------------
ぼうさいこくたい2019
「あなたが知りたい防災科学の最前線:激化する気象災害に備える」
10月19日(土)16:30-18:00
場所:名古屋市ささしまライブ24エリア・メインホールB
http://www.bosai-kokutai.jp/
(協力)深田研一般公開2019
10月6日(日)
場所:深田研地質研究所(文京区本駒込)
*第10回フォトコンテスト作品の展示もあります*
http://www.fgi.or.jp/
(後)第20回「こどものためのジオ・カーニバル」
11月2日(土)-3日(日)
場所:大阪市立科学館
http://geoca.org/index.html
令和元年度「津波防災の日」スペシャルイベント
津波×地域防災×企業
11月5日(火)13:00-18:00
場所: TKP市ヶ谷カンファレンスセンター(東京都新宿区市谷)
http://tsunamibousai.jp/tsunami_special_event2019.pdf
(協)第35回ゼオライト研究発表会
12月5日(木)-6日(金)
会場:タワーホール船堀(江戸川区船堀4-1-1)
https://jza-online.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0191.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.465(臨時)木村敏雄 名誉会員 訃報
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.465 2019/10/28┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 木村敏雄 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
木村敏雄 名誉会員(東京大学名誉教授)が、令和元年10月11日(金)に
逝去されました(97歳)。これまでの故人の功績を讃えるとともに、
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
なおご葬儀は、すでに近親者によりしめやかに執り行なわれ、御香典、
御供花、御供物の儀はご辞退されるとのことです。
会長 松田博貴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.466(臨時)代議員選挙:11月5日(火)18時 立候補届け締切です!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.466 2019/11/01┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2020年度代議員選挙:11月5日(火)18時 立候補届け締切です!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2020年度代議員選挙:11月5日(火)18時 立候補届け締切です!
─────────────────────────────────
代議員選挙の立候補届けは,11月5日(火)18時締切(必着)です.
代議員及び役員選挙は,2年に一度の選挙で,現在の全ての代議員,全ての理事
が改選となります.立候補を予定されている方は,くれぐれも期日に遅れない
ようにご提出ください.
*立候補届けを提出の際には,記入漏れが無いか,必ず確認してください.
*立候補届けは,選挙管理委員会 main@geosociety.jp あてにお届けください
(本メールに返信しないでください).
********************************************
代議員立候補受付締切:11月5日(火)18時必着
********************************************
本日(11月1日)13:30 現在の代議員立候補者数は以下のとおりです.
( )内の数字は定数.
[全国区]52(100)
[地方支部区]31(100)
内訳:北海道:4(定員5)/東北:3(7)/関東:7(42)/
中部:7(17)/近畿:7(11)/四国:2(4)/西日本:1(14)
立候補届出状況はHPトップからもご確認いただけます.
http://www.geosociety.jp/
※「会員のページ」の選挙に関する案内から,立候補届の書式がダウンロード
できます.「会員のページ」へは会員番号・パスワードによるログインが必要
です.http://sub.geosociety.jp/members/content0106.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No.467 第11回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.467 2019/11/05┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】第11回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
【2】2020年度学会各賞候補者募集中(12/2締切)
【3】2020年度の会費について
【4】GSSPシンポジウム:国際層序の意味と意義 開催します!
【5】特集号原稿募集!(投稿のご案内)
【6】「令和元年台風19号に関する緊急報告会」(仮)発表募集
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】第11回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
──────────────────────────────────
***応募締切:2020年1月末***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募フォームからでも
メール添付でもご応募いただけます.
会員の皆様からの応募をお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2020年度学会各賞候補者募集中(12/2締切)
──────────────────────────────────
日本地質学会では今年も運営規則第16 条および各賞選考規則にした
がい,賞の候補者を募集いたします
ご応募いただいた場合には,必ず受け取りのお返事をお出しします
のでご確認ください.
*********************************************
応募締切:2019年12月2日(月)必着
*********************************************
詳しくは,http://sub.geosociety.jp/members/content0098.html
(会員ページへのログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2020年度の会費について
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下
さいますようお願いいたします.
また,学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)
の方で,それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適
用します.
・割引会費請求書発行前受付締切:11月20日(水)
・災害に関連した会費の特別措置申請締切:11月29日(金)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】GSSPシンポジウム:国際層序の意味と意義 を開催します!
──────────────────────────────────
現在,我が国初めてのGSSPの認定をめぐり,地質学界のみならず社
会の耳目を集めています.一方で,国際層序や地質単元,GSSPなど
地質学・層位学の基礎についての知識と理解が十分でない現状があ
ります.本シンポジウムでは,我が国の地質学をリードすべき地質
学会として,これまでの国際層序に関する取組みを含めて,改めて
その意味・意義,その詳細を再確認します.
主催:日本地質学会
共催:産総研地質調査総合センター,日本古生物学会
日時:2019年11月23日(土)13:00-17:30(予定)
会場:産総研つくば中央 共用講堂
対象:研究者,技術者,院生・学生(会員・非会員問わずどなたでも
ご参加いただけます)
参加費無料,事前申込不要
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0096.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】特集号原稿募集!(投稿のご案内)
──────────────────────────────────
山口大会で開催したトピックセッションT1「日本海拡大に関連した
テクトニクス,堆積作用,マグマ活動,古環境」に関連した特集号
を出版する予定です。セッション会場で実施したアンケートの結果
を受け,英文誌(Island Arcを予定)及び和文誌(地質学雑誌を予
定)の特集号を出版する方向で作業を進めます。特集号の論文投稿・
編集等(査読を含む)は雑誌規則に従います。
多くの会員の皆様から論文が投稿されることを期待しています。新
生代の日本海,日本列島及び周辺地域の地質,テクトニクス,堆積
作用,物理探査,マグマ活動,地球化学,古環境などに関係した論
文を広く募集します。セッションで発表できなかった方も歓迎しま
す。投稿期限は両誌とも2020年8月末の予定です。
◆英文誌特集号(Island Arcを予定)
Special issue: Cenozoic evolution of the Japan Sea, Japanese islands and vicinity (tentative title)
Guest editors: Hiroyuki Hoshi, Hironao Shinjoe, Makoto Otsubo, and Toshiaki Irizuki
◆和文誌特集号(地質学雑誌を予定)
特集:日本海拡大に関連したテクトニクス,堆積作用,マグマ活動,古環境(仮題)
ゲストエディター:星 博幸・細井 淳・斉藤 哲・林 広樹
投稿予定の方は,お手数ですが次の情報を2019年11月29日(金)まで 世話人代表に
メールでご連絡ください。
1)連絡著者(corresponding author)の氏名・メールアドレス
2)投稿予定先(英文誌 / 和文誌)
3)論文著者の氏名(全員;後で追加等可)
4)論文タイトル(仮題可)
5)論文の概要(100字以内)
6)論文種別(論説・総説等;雑誌規則をご確認ください)
7)印刷ページ数(和文誌のみ;大まかな予想でいいです)
8)著者推薦査読者の氏名・メールアドレス(実際の査読者は編集委
員会が決定します)
※ 連絡せず投稿すると特集号投稿論文として受け付けられませんの
でご注意ください。
(参考)雑誌規則
Island Arc:
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14401738/homepage/ForAuthors.html
地質学雑誌:
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor//publication/kiyaku/journal_kisoku.pdf
ご不明の点がありましたら,遠慮なく世話人代表にお問い合わせください。
世話人代表:星 博幸(愛知教育大学)
hoshi[at]auecc.aichi-edu.ac.jp([at]を@マークにして下さい)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】「令和元年台風19号に関する緊急報告会」(仮)発表募集
──────────────────────────────────
防災学術連携体(防災減災・災害復興に関する57学会のネットワー
ク,地質学会も参加)では,12月24日(火)に標記報告会を企画し
ています.
防災学術連携体を構成する57学会から発表者(1学会から1人)を募
集するとのことですので,地質学会として発表を希望される方は11
月20日(水)までに簡単な発表内容,発表予定者,連絡先を地質学
会までご連絡下さい.複数の応募があった場合には調整させて頂き
ます.
【発表希望の締切】2019年11月20日(水)main[at]geosociety.jp
([at]を@マークにして下さい)宛
日本学術会議公開シンポ
「令和元年台風19号に関する緊急報告会」(仮)
日時:12月24日(火)13:00-17:30
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木)
シンポジウムの詳細(案)はこちらから
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/others-pdf/geoflash_no_464_6.pdf
(地質災害委員会委員長,常務理事 斎藤 眞)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[西日本支部]
■西日本支部令和元年度総会・第171回例会の案内
2020年2月29日(土)例会・総会
場所:北九州市立自然史・歴史博物館 いのちのたび博物館
講演申込・参加申込:2月14日(金)締切
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
[関東支部]
■関東支部:地学教育・アウトリーチ巡検(参加申込受付中)
11月24日(日)
集合:小湊鉄道「月崎駅」10:20
内容:チバニアンの地層見学、素掘りのトンネルの見学等
定員になり次第締切.
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html#ex2019-02
■神津島火山巡検
11月30日(土)-12月1日(日)雨天決行
費用:20,000円(現地での見学地の移動費用,1泊3食費,旅行傷害
保険費,案内資料等の実費を含む.ただし,現地までの交通費は含
みません)
申込締切:11月14日(木)17時(定員に達した時点で締め切り)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
第9回学生ヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集(地質学会推薦)
日程(仮):2020年3月4日-18日(出国から帰国まで15日間)
参加申込締切:2019年12月31日
参加費:学生・大学院生 20万円以内
http://www.gondwanainst.org/geotours/Studentfieldex_index.htm
-------------------------------------------------------------
東京地学協会メダル受賞記念講演会
「テフラ研究,これまでの知見と展望」
11月8日(金)15:30-16:30
場所:学士会館
講演者:町田 洋博士
参加申込不要(どなたも無料で参加できます。)
http://www.geog.or.jp/lecture/lecturescheduled/377-r1medal.html
第195回深田研談話会
11月15日(金)18:00-19:30
場所:深田地質研究所 研修ホール(東京都文京区)
講師:千葉達朗氏(アジア航測株式会社)
演題:赤色立体地図の発想と応用
参加費無料,70名(先着)*要事前申込
http://www.fgi.or.jp/
(協)第35回ゼオライト研究発表会
12月5日(木)-6日(金)
会場:タワーホール船堀(江戸川区船堀4-1-1)
https://jza-online.org/
第31回GSJシンポジウム(地圏資源環境研究部門 研究成果報告会)
「地下水、土壌、地中熱の基盤データ整備と利活用」
12月6日(金) 13:30-17:40
場所:秋葉原ダイビル・コンベンションホール
事前登録制・参加費無料・CPD4単位
https://unit.aist.go.jp/georesenv/index.html
第32回GSJシンポジウム
「神奈川の地質と災害」
12月12日(木)13:00ー17:35
会場:TKPガーデンシティ横浜ホールA
事前登録制・参加費無料・CPD4単位
https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo32/index.html
日本遺産「大谷石文化」石のまち宇都宮シンポジウム
12月14日(土)10:30-16:00
会場:宇都宮市文化会館小ホール
入場無料,事前申込不要(先着500名)
問い合わせ:下野新聞社営業局業務推進部 電話028-625-1104
第229回 地質汚染・災害イブニングセミナー
12月20日(金)18:30-20:30
場所:北とぴあ807会議室 (東京都北区)
講師:佐々木裕子(NPO法人日本地質汚染審査機構理事・薬学博士・元東京都環境科学研究所研究員)
演題:「改正土壌汚染対策法の化学分析と調査」
会費:会員500円 非会員 1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
地区防災計画学会・京都大学矢守研究室共同シンポジウム
(第33回研究会)「台風19号等の教訓と地区防災計画」
12月21日(土)13:45-16:45(予定)
場所:キャンパスプラザ京都第4講義室(京都市下京区西洞院通)
参加費無料・定員70名・事前申込制・定員に達した場合は申込締切
http://www.gakkai.chiku-bousai.jp/
(後)北淡国際活断層シンポジウム2020
「活断層研究の新たな展開−阪神淡路大震災から25年」
2020年1月14日(火)-17日(金)
発表申込締切:2019年12月1日
参加申込締切:2019年12月15日
https://home.hiroshima-u.ac.jp/kojiok/20circularJ.pdf
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0191.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・山梨県職員火山防災職の募集(11/29)
・愛媛大学大学院理工学研究科 地球進化学講座・助教公募(11/29)
・JAMSTEC海域地震火山部門地震発生帯研究Cプレート構造研究G公募(20/1/15)
・令和2年度消防防災科学技術研究推進制度研究開発課題公募(12/23)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No.468(臨時)2020年度代議員選挙について
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.468 2019/11/08┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2020年度代議員選挙について
【2】2020年度各賞候補者募集について(12/2締切)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2020年度代議員選挙について
─────────────────────────────────
選挙規則ならびに選挙細則に基づき,表記選挙を実施するにあたっての立候補
届は,11月5日に締め切られました.その結果,全国区・地方支部区とも立候補
者数が定数を超えませんでしたので,選挙規則第6条に基づき投票は行わず,全
員を無投票当選といたします.
なお,立候補の抱負など,当選された方の詳細につきましては別途名簿をお送
りいたしますので,ご覧ください.
また,代議員選挙は無投票となりましたが,会長・副会長の意向調査につきま
しては,予定通り実施いたします.意思表明者のマニフェストならびに調査票
は代議員当選者の名簿とともに,11月25日頃までにお送りいたしますので,ご
返信を宜しくお願いいたします.
詳しくは, http://sub.geosociety.jp/members/content0108.html
2019年11月8日
一般社団法人日本地質学会
選挙管理委員会委員長 飛田健二
※会員番号・パスワードによるログインが必要です.ログインの方法はこち.
http://www.geosociety.jp/outline/content0042.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2020年度学会各賞候補者募集中(12/2締切)
──────────────────────────────────
日本地質学会では今年も運営規則第16 条および各賞選考規則にした
がい,賞の候補者を募集いたします
ご応募いただいた場合には,必ず受け取りのお返事をお出しします
のでご確認ください.
*********************************************
応募締切:2019年12月2日(月)必着
*********************************************
詳しくは,
http://sub.geosociety.jp/members/content0098.html
(会員ページへのログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真,マンガ原稿募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No.469 第11回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.469 2019/11/19┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】第11回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
【2】2020年度代議員選挙について
【3】2020年度学会各賞候補者募集中(12/2締切)
【4】2020年度の会費について
【5】GSSPシンポジウム:国際層序の意味と意義 開催します!
【6】「令和元年台風19号に関する緊急報告会」(仮)発表募集
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】第11回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
──────────────────────────────────
***応募締切:2020年1月末***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募フォームからでも
メール添付でもご応募いただけます.
会員の皆様からの応募をお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2020年度代議員選挙について
─────────────────────────────────
選挙規則ならびに選挙細則に基づき,表記選挙を実施するにあたっての立候補
届は,11月5日に締め切られました.その結果,全国区・地方支部区とも立候補
者数が定数を超えませんでしたので,選挙規則第6条に基づき投票は行わず,全
員を無投票当選といたします.
なお,立候補の抱負など,当選された方の詳細につきましては別途名簿をお送
りいたしますので,ご覧ください.
また,代議員選挙は無投票となりましたが,会長・副会長の意向調査につきま
しては,予定通り実施いたします.意思表明者のマニフェストならびに調査票
は代議員当選者の名簿とともに,11月25日頃までにお送りいたしますので,ご
返信を宜しくお願いいたします.
詳しくは, http://sub.geosociety.jp/members/content0108.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2020年度学会各賞候補者募集中(12/2締切)
──────────────────────────────────
日本地質学会では今年も運営規則第16 条および各賞選考規則にした
がい,賞の候補者を募集いたします
ご応募いただいた場合には,必ず受け取りのお返事をお出しします
のでご確認ください.
*********************************************
応募締切:2019年12月2日(月)必着
*********************************************
詳しくは, http://sub.geosociety.jp/members/content0098.html
(会員ページへのログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2020年度の会費について
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下
さいますようお願いいたします.
また,学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)
の方で,それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適
用します.
・割引会費請求書最終締切:2020年3月31日(火)
・災害に関連した会費の特別措置申請締切:11月29日(金)
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】GSSPシンポジウム:国際層序の意味と意義 を開催します!
──────────────────────────────────
現在,我が国初めてのGSSPの認定をめぐり,地質学界のみならず社
会の耳目を集めています.一方で,国際層序や地質単元,GSSPなど
地質学・層位学の基礎についての知識と理解が十分でない現状があ
ります.本シンポジウムでは,我が国の地質学をリードすべき地質
学会として,これまでの国際層序に関する取組みを含めて,改めて
その意味・意義,その詳細を再確認します.
主催:日本地質学会
共催:産総研地質調査総合センター,日本古生物学会
日時:2019年11月23日(土)13:00-17:30(予定)
会場:産総研つくば中央 共用講堂
対象:研究者,技術者,院生・学生(会員・非会員問わずどなたでも
ご参加いただけます)
参加費無料,事前申込不要
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0096.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】「令和元年台風19号に関する緊急報告会」(仮)発表募集
──────────────────────────────────
防災学術連携体(防災減災・災害復興に関する57学会のネットワー
ク,地質学会も参加)では,12月24日(火)に標記報告会を企画し
ています.
防災学術連携体を構成する57学会から発表者(1学会から1人)を募
集するとのことですので,地質学会として発表を希望される方は11
月20日(水)までに簡単な発表内容,発表予定者,連絡先を地質学
会までご連絡下さい.複数の応募があった場合には調整させて頂き
ます.
【発表希望の締切】2019年11月20日(水) main@geosociety.jp >宛
日本学術会議公開シンポ
「令和元年台風19号に関する緊急報告会」(仮)
日時:12月24日(火)13:00-17:30
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木)
シンポジウムの詳細(案)はこちらから
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/others-pdf/geoflash_no_464_6.pdf
(地質災害委員会委員長,常務理事 斎藤 眞)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[四国支部]
■第19回地質学会四国支部総会・講演会
12月14日(土)13:00-17:00(予定)
場所:香川大学研究交流棟5階研究者交流スペース(幸町北キャンパス内)
講演申込締切:11月29日(土)
参加申込不要・参加無料.
http://www.gsj-shikoku.com/research.html
[西日本支部]
■西日本支部令和元年度総会・第171回例会の案内
2020年2月29日(土)例会・総会
場所:北九州市立自然史・歴史博物館 いのちのたび博物館
講演申込・参加申込:2月14日(金)締切
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
[関東支部]
■シンポジウム「関東のテフラ−最近の年代観と供給源−」
2020年1月25 日(土)10:00-16:30
場所:「北とぴあ」第一研修室(〒114-0002 北区王子1-11-1)
象:日本地質学会会員および一般(非会員)
参加費:無料,事前申込不要
懇親会:会費4,000円程度,懇親会は要事前申込[締切:1月17日(金)]
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
■地学教育・アウトリーチ巡検[延期のお知らせ]
今月24日(日)に予定しておりました上記巡検について,10月25日
に千葉県を襲った豪雨により,見学を予定していた露頭までの通路
が閉鎖され,小湊鐵道も区間運転となっています.そのため,巡検
実施は延期となりました。来年3月中〜下旬にあらためて実施予定で
す。詳細については来年2月頃広報予定です。
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html#ex2019-02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
第9回学生ヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集(地質学会推薦)
日程(仮):2020年3月4日-18日(出国から帰国まで15日間)
参加申込締切:2019年12月31日
参加費:学生・大学院生 20万円以内
http://www.gondwanainst.org/geotours/Studentfieldex_index.htm
道総研地質研究所ニュース:北海道胆振東部地震から1年ほか
https://www.hro.or.jp/list/environmental/research/gsh/publication/gshnews/gshnews02/
-------------------------------------------------------------
(協)第35回ゼオライト研究発表会
12月5日(木)-6日(金)
会場:タワーホール船堀(江戸川区船堀4-1-1)
https://jza-online.org/
(後)北淡国際活断層シンポジウム2020
「活断層研究の新たな展開−阪神淡路大震災から25年」
2020年1月14日(火)-17日(金)
発表申込締切:2019年12月1日
参加申込締切:2019年12月15日
https://home.hiroshima-u.ac.jp/kojiok/20circularJ.pdf
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0191.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
─────────────────────────────────
・岩手大学教育学部理科教育科(地学)准教授公募(1/15)
・兵庫県丹波市任期付職員エデュケーター(教育普及専門員)募集(1/17)
・2020年度産総研ポスドク(イノベーションスクール生)公募(1/6)
・三菱財団2020年度助成金(自然科学研究助成)公募(1/8-2/5)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.470(臨時)訃報:猪郷久義 名誉会員/島津光夫 名誉会員
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.470 2019/11/27┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 猪郷 久義 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
猪郷 久義 名誉会員(筑波大学名誉教授)が、令和元年11月22日(金)に
逝去されました(87歳)。
これまでの故人の功績を讃えるとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
なお、ご葬儀はすでに執り行われたとのことです。
会長 松田博貴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 島津 光夫 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
島津 光夫 名誉会員(新潟大学名誉教授)が、令和元年11月26日(火)に
逝去されました(93歳)。
これまでの故人の功績を讃えるとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
ご葬儀等は下記のとおり執り行われます。
通夜:11月28日(木)19時から
葬儀告別式:11月29日(金)10時から,11時出棺
喪主:島津陽一様(ご子息)
式場:公益社アーバンホール(新潟市西区松美台6-21 電話025-267-8881)
https://www.e-sogi.com/detail_hall/id1239180749-786027.html
会長 松田博貴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.471 会員名簿発行に関するお願い(名簿作成アンケート)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.471 2019/12/3┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】会員名簿の訂正・変更・登録について/名簿作成アンケート
【2】2020年度代議員選挙について(正副会長意向調査のお願い)
【3】2020年度の会費について
【4】第11回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
【5】低頻度巨大災害シンポジウム 発表募集
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】会員名簿の訂正・変更・登録について/名簿作成アンケート
──────────────────────────────────
日本地質学会では,学会員相互の交流と親睦を図る目的で,会員名
簿を発行することを運営規則にうたっております.2019 年度はその
発行年にあたり,年度内に発行の予定で準備を行っております.
名簿の発行様式は前回と同様で,全会員を収録します.本会として
は,個人情報保護法の制約はあるとしても,会員の皆様が上記の目
的に沿って利用できるような,従来規模の名簿を作成したいと考え
ておりますので,調査の実施にご理解とご協力をお願いいたします.
アンケート提出およびWeb 画面更新締切:2020 年1月7 日(火)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0209.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2020年度代議員選挙について(正副会長意向調査のお願い)
─────────────────────────────────
選挙規則ならびに選挙細則に基づき,表記選挙を実施するにあたっ
ての立候補届は,11月5日に締め切られました.その結果,全国区・
地方支部区とも立候補者数が定数を超えませんでしたので,選挙規
則第6条に基づき投票は行わず,全員を無投票当選といたします.
なお,立候補の抱負など,当選された方の詳細につきましては別途
名簿をお送りいたしますので,ご覧ください.
また,代議員選挙は無投票となりましたが,会長・副会長の意向調
査につきましては,予定通り実施いたします.意思表明者のマニフェ
ストならびに調査票は代議員当選者の名簿とともに,11月下旬に発送
いたしました.ご返信を宜しくお願いいたします.
【意向調査結果返信期日】2020年1月8日(水)*消印有効*
詳しくは,http://sub.geosociety.jp/members/content0108.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2020年度の会費について
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下
さいますようお願いいたします.12月中旬に振込用紙を送付いたします。
また,学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)
の方で,それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適
用します.
・割引会費請求書最終締切:2020年3月31日(火)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第11回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
──────────────────────────────────
***応募締切:2020年1月末***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募フォームからでも
メール添付でもご応募いただけます.
会員の皆様からの応募をお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】低頻度巨大災害シンポジウム 発表募集
──────────────────────────────────
防災学術連携体では標記シンポジウムを予定しており,防災学術連
携体を構成する57学会から発表者(1学会から1人)を募集するとの
ことです.地質学会として発表を希望される方は12月23日(月)10
時までに簡単な発表内容,発表予定者,連絡先を地質学会までご連
絡下さい.複数の応募があった場合には調整させて頂きます.
【発表希望の締切】2019年12月23日(月)10時 main@geosociety.jp 宛
第9回防災学術連携シンポジウム
テーマ「低頻度巨大災害」
日時:2020年3月18日(水)12:30-17:30
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木)
https://janet-dr.com/060_event/20200317/20200317_leef.pdf
(地質災害委員会委員長,常務理事 斎藤 眞)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[四国支部]
■第19回地質学会四国支部総会・講演会
12月14日(土)13:00-17:00(予定)
場所:香川大学研究交流棟5階研究者交流スペース(幸町北キャンパス内)
講演申込締切:11月29日(土)
参加申込不要・参加無料.
http://www.gsj-shikoku.com/research.html
[西日本支部]
■西日本支部令和元年度総会・第171回例会の案内
2020年2月29日(土)例会・総会
場所:北九州市立自然史・歴史博物館 いのちのたび博物館
講演申込・参加申込:2月14日(金)締切
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
[関東支部]
■シンポジウム「関東のテフラ−最近の年代観と供給源−」
2020年1月25 日(土)10:00-16:30
場所:「北とぴあ」第一研修室(〒114-0002 北区王子1-11-1)
象:日本地質学会会員および一般(非会員)
参加費:無料,事前申込不要
懇親会:会費4,000円程度,懇親会は要事前申込[締切:1月17日(金)]
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
■ ミニ巡検「大磯丘陵北東部のテフラ」
関東地方のテフラ研究で重要な役割を占めていた大磯丘陵の模式的な
露頭をめぐるミニ巡検を開催します.
2020年2月26日(土)
対象:会員 募集:20人(先着順)
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
第9回学生ヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集(地質学会推薦)
日程(仮):2020年3月4日-18日(出国から帰国まで15日間)
参加申込締切:2019年12月31日
参加費:学生・大学院生 20万円以内
http://www.gondwanainst.org/geotours/Studentfieldex_index.htm
-------------------------------------------------------------
(協)第35回ゼオライト研究発表会
12月5日(木)-6日(金)
会場:タワーホール船堀(江戸川区船堀4-1-1)
https://jza-online.org/
■「地盤情報の利活用と不動産情報」に関するワークショップ
日時:令和元年12月4日(水)13:00-16:00
会場:地域地盤環境研究所 会議室(大阪市中央区大手前
國民會館・住友生命ビル)
問い合わせ先:geo.houseibi@gmail.com
(後)北淡国際活断層シンポジウム2020
「活断層研究の新たな展開−阪神淡路大震災から25年」
1月14日(火)-17日(金)
発表申込締切:2019年12月15日(延長しました)
参加申込締切:2019年12月15日
https://home.hiroshima-u.ac.jp/kojiok/20circularJ.pdf
■ 水蒸気噴火のメカニズムに関する国際ワークショップ
主催:神奈川県温泉地学研究所
1月15日(水)-16日(木)
場所:
研究集会:湯本富士屋ホテル(足柄下郡箱根町湯本256-1)
一般講演会:神奈川県立生命の星・地球博物館(小田原市入生田499)
研究集会への参加は事前登録が必要です。締切:2019年12月25日(水)
https://www.onken.odawara.kanagawa.jp/information/20191015-01.html
■ 第54回日本水環境学会年会
3月16日(月)-18日(水)
場所:岩手大学(岩手県盛岡市)
URL:http://www.jswe.or.jp/event/lectures/2019per.html
■国際ゴンドワナ研究連合(IAGR)2020年総会及び
第17回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム
8月30日-9月1日 会議とシンポジウム
9月2日-7日 アルタイ山地巡検(L)・2日-5日 アルタイ山地巡検(S)
場所:ノボシビルスク(ロシア)
参加申込:3月1日まで(発表要旨:4月30日まで)
問合せ・参加申込・発表要旨送付先:
iagr2020@igm.nsc.ru & inna@igm.nsc.ru
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0191.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
─────────────────────────────────
・2020年度「深田研究助成」(2/3)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.472 正副会長候補者の意向調査実施中です
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.472 2019/12/17┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】会員名簿の訂正・変更・登録について/名簿作成アンケート
【2】正副会長候補者の意向調査実施中
【3】2020年度の会費について
【4】第11回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
【5】低頻度巨大災害シンポジウム 発表募集
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】事務局年末年始休業
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】会員名簿の訂正・変更・登録について/名簿作成アンケート
──────────────────────────────────
2019 年度は名簿発行年にあたり,年度内に発行の予定で準備を行っ
ております.名簿の発行様式は前回と同様で,全会員を収録します.
本会としては,個人情報保護法の制約はあるとしても,会員の皆様
が上記の目的に沿って利用できるような,従来規模の名簿を作成し
たいと考えておりますので,調査の実施にご理解とご協力をお願い
いたします.
アンケート提出およびWeb 画面更新締切:2020 年1月7日(火)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0209.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】正副会長候補者の意向調査実施中
─────────────────────────────────
代議員選挙は無投票となりましたが,会長・副会長の意向調査につ
きましては,予定通り実施いたします.意思表明者のマニフェスト
ならびに調査票は代議員当選者の名簿とともに,11月下旬に発送い
たしました.ご返信を宜しくお願いいたします
【意向調査結果返信期日】2020年1月8日(水)*消印有効*
詳しくは,http://sub.geosociety.jp/members/content0108.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2020年度の会費について
──────────────────────────────────
次年分(2020年度)の会費請求書を12月16日に発送いたしました.
折り返しご送金をお願いいたします.
自動引落の方は,12月23日に引き落しとなります(請求書ならびに
引き落し通知は省略させていただきます).
また,学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)
の方で,それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適
用します.
【割引会費請求書最終締切】2020年3月31日(火)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第11回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
──────────────────────────────────
***応募締切:2020年1月31日(金)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰の
コンテストです.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大
募!!投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募
フォームからでもメール添付でもご応募いただけます.
会員の皆様からの応募をお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】低頻度巨大災害シンポジウム 発表募集
──────────────────────────────────
防災学術連携体では標記シンポジウムを予定しており,防災学術連
携体を構成する57学会から発表者(1学会から1人)を募集するとの
ことです.地質学会として発表を希望される方は12月23日(月)10
時までに簡単な発表内容,発表予定者,連絡先を地質学会までご連
絡下さい.複数の応募があった場合には調整させて頂きます.
【発表希望の締切】2019年12月23日(月)10時 main@geosociety.jp 宛
第9回防災学術連携シンポジウム
テーマ「低頻度巨大災害」
日時:2020年3月18日(水)12:30-17:30
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木)
https://janet-dr.com/060_event/20200317/20200317_leef.pdf
(地質災害委員会委員長,常務理事 斎藤 眞)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[西日本支部]
■西日本支部令和元年度総会・第171回例会の案内
2020年2月29日(土)例会・総会
場所:北九州市立自然史・歴史博物館 いのちのたび博物館
講演申込・参加申込:2月14日(金)締切
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
[関東支部]
■支部功労賞募集
対象者:支部活動や地質学を通して広く社会貢献をされた関東支部
内に在住の個人・団体(*社会貢献や活動の評価においては,必ず
しも学問的な成果を問うものではありません)
募集締切:2020年1月10日(金)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html#sho
■シンポジウム「関東のテフラ−最近の年代観と供給源−」
2020年1月25 日(土)10:00-16:30
場所:「北とぴあ」第一研修室(〒114-0002 北区王子1-11-1)
対象:日本地質学会会員および一般(非会員)
参加費:無料,事前申込不要
懇親会:会費4,000円程度,懇親会は要事前申込[締切:1月17日(金)]
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
■ ミニ巡検「大磯丘陵北東部のテフラ」
関東地方のテフラ研究で重要な役割を占めていた大磯丘陵の模式的な
露頭をめぐるミニ巡検を開催します.
2020年2月16日(日)*日程に誤りがあり訂正しました
(誤)2/26(土)→(正)2/16(日)
対象:会員(空きがあれば一般参加も可能)
募集:20人(先着順)
申込締切:1月31日(金)
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
『熊楠の鉱物・化石コレクション展』開催中
12月6日(金)-2020年2月9日(金)
場所:南方熊楠記念館(和歌山県西牟婁郡白浜町)
http://www.minakatakumagusu-kinenkan.jp/2019/12/01/7926
第9回学生ヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集(地質学会推薦)
日程(仮):2020年3月4日-18日(出国から帰国まで15日間)
参加申込締切:2019年12月31日
参加費:学生・大学院生 20万円以内
http://www.gondwanainst.org/geotours/Studentfieldex_index.htm
-------------------------------------------------------------
■第313回地学クラブ講演会「最近の助成研究から」
12月19日(木)15:00-17:00
場所:アルカディア市ヶ谷
講演者:
蛭田明宏(明治大)柏崎西方の円錐台地形が泥火山なのか判断する
小室 譲(筑波大)地域労働市場からみた国際山岳リゾートの持続性について
佐々木夏来(東京大)八幡平地域の湿地の形成と発達を地形から考える
参加申込不要(どなたも無料で参加できます)
http://www.geog.or.jp/lecture/lecturescheduled/378-club313.html
■公開シンポジウム「令和元年台風第19号に関する緊急報告会」
12月24日(火)13:00-17:55
会場:
・日本学術会議講堂(東京都港区六本木7-22-34)
・常翔ホール(大阪工業大学梅田キャンパス)にて同時中継
参加費:無料
https://janet-dr.com/050_saigaiji/2019/191224/typoon19_UB_plan.pdf
(後)北淡国際活断層シンポジウム2020
「活断層研究の新たな展開−阪神淡路大震災から25年」
1月14日(火)-17日(金)
会場:北淡震災記念公園セミナーハウス・野島断層保存館(兵庫県淡路市)
https://home.hiroshima-u.ac.jp/kojiok/20circularJ.pdf
■シンポジウム
「オープンサイエンス時代の学会誌出版の在り方を模索する」
1月23日(木)13:30-17:00
場所:御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンター(千代田区神
田駿河台4-6)
http://www.jfes.or.jp/reg/?eid=200123
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0191.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
─────────────────────────────────
・九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部門テニュアトラック助教公募(1/17)
・新大学(現大阪府立大・大阪市立大)理学研究院 理学研究科教員公募(1/31)
---教授(地球学専攻・地球情報学分野)
---教授(地球学専攻・固体地球物理学分野)
---准教授(地球学専攻・固体地球物理学分野)
---教授(地球科学 自然災害科学分野)
・JAMSTEC超先鋭研究開発部門高知コア研究所技術副主幹or技術主任公募(2/7)
・2020年度産総研ポスドク(イノベーションスクール生)公募(1/6)
・栗駒山麓ジオパーク専門員(宮城県栗駒市)募集(1/22)
・山田科学振興財団2020年度研究援助申請(2/28)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】事務局年末年始休業
──────────────────────────────────
学会事務局は,27日(金)午後12月28日(土)から1月5日(日)まで
お休みとなります.(訂正)
新年6日(月)より通常営業となります.よろしくお願いいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.473 お詫び:地質学雑誌発送遅延
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.473 2019/12/26┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】お詫び:地質学雑誌発送遅延(1/7頃発送)
【2】会員名簿の訂正・変更受付中:名簿作成アンケート(1/7締切)
【3】正副会長候補者の意向調査実施中
【4】2020年度の会費について
【5】第11回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
【6】事務局年末年始休業(12/27午後からお休みとなります)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】お詫び:地質学雑誌発送遅延(1/7頃発送)
──────────────────────────────────
地質学雑誌125巻12号(2019年12月号)がまもなく刊行されますが,
雑誌発送が年内業務に間に合わず,年明け7日頃発送を予定しており
ます.事務局編集作業の遅れにより,会員の皆様にご迷惑をおかけし
誠に申し訳ございません.
12月号目次,来年1月号の予告はこちら
http://www.geosociety.jp/publication/content0092.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】会員名簿の訂正・変更受付中:名簿作成アンケート(1/7締切)
──────────────────────────────────
2019 年度は名簿発行年にあたり,年度内に発行の予定で準備を行っ
ております.名簿の発行様式は前回と同様で,全会員を収録します.
本会としては,個人情報保護法の制約はあるとしても,会員の皆様
が上記の目的に沿って利用できるような,従来規模の名簿を作成し
たいと考えておりますので,調査の実施にご理解とご協力をお願い
いたします.
【アンケート提出およびWeb 画面更新締切】2020年1月7日(火)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0209.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】正副会長候補者の意向調査実施中
─────────────────────────────────
代議員選挙は無投票となりましたが,会長・副会長の意向調査につ
きましては,予定通り実施いたします.意思表明者のマニフェスト
ならびに調査票は代議員当選者の名簿とともに,11月下旬に発送い
たしました.ご返信を宜しくお願いいたします.
【意向調査結果返信期日】2020年1月8日(水)*消印有効*
詳しくは,http://sub.geosociety.jp/members/content0108.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2020年度の会費について
──────────────────────────────────
次年分(2020年度)の会費請求書を12月16日に発送いたしました.
折り返しご送金をお願いいたします.
自動引落の方は,12月23日に引き落しとなります(請求書ならびに
引き落し通知は省略させていただきます).
また,学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)
の方で,それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適
用します.
【割引会費請求書最終締切】2020年3月31日(火)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第11回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
──────────────────────────────────
***応募締切:2020年1月31日(金)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰の
コンテストです.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大
募!!投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募
フォームからでもメール添付でもご応募いただけます.
会員の皆様からの応募をお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】事務局年末年始休業(12/27午後からお休みとなります)
──────────────────────────────────
学会事務局は,12月27日(金)午後から1月5日(日)までお休みを
頂きます.変則となりご迷惑をおかけしますが,ご了承下さい.
新年は6日(月)より通常営業となります.
2020年もどうぞよろしくお願い致します
皆さま 良いお年をお迎え下さい
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.474 謹賀新年 年頭の挨拶
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.474 2020/1/7┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2020年 年頭のご挨拶
【2】正副会長候補者の意向調査(明日締切!)
【3】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されました
【4】2020年からIsland Arcが新しく変わります
【5】2020年度の会費について
【6】第11回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中!
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2020年 年頭のご挨拶
─────────────────────────────────
皆様に,令和2年の年頭のご挨拶を申し上げます.
昨年,令和の時代を迎え,日本地質学会も創立126年となりました.
次なる25年に向けて,新たに歩み始めたところです.
全文を読む、、、 http://www.geosociety.jp/outline/content0137.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】正副会長候補者の意向調査(明日締切!)
─────────────────────────────────
代議員選挙は無投票となりましたが,会長・副会長の意向調査につ
きましては,予定通り実施いたします.意思表明者のマニフェスト
ならびに調査票は代議員当選者の名簿とともに,11月下旬に発送い
たしました.ご返信を宜しくお願いいたします
【意向調査結果返信期日】2020年1月8日(水)*消印有効*
詳しくは, http://sub.geosociety.jp/members/content0108.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されました
──────────────────────────────────
募集期間:2019年12月20日(金)〜2020年2月7日(金)2020年2月10日(月)*訂正2/4
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:例えば,,,地質学への顕著な貢献/地質学会の運
営と発展への貢献/教育現場や企業などでの活動を通じた地質学の普及と振興
への貢献など
*上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することはできませ
んが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
(名誉会員推薦委員会 佐々木和彦)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2020年からIsland Arcが新しく変わります
─────────────────────────────────
「Island Arcは出版までに時間がかかる」そんなイメージをお持ち
ではありませんか?それは過去の話です.Island Arcでは査読体制
の強化と編集体制の改善に加え,2020年からは,投稿から出版(オ
ンライン掲載)までの時間が標準で3ヶ月程度となる見込みです.
このほか、論文アクセスの無料化・迅速化/超過ページ料金の廃止
... など
新体制のもとIsland Arcは新しく変わります!
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/publication/content0093.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2020年度の会費について
──────────────────────────────────
次年分(2020年度)の会費請求書を昨年12/16に発送いたしました.
折り返しご送金をお願いいたします.
自動引落の方は,12/23に引き落しとなりました(請求書ならびに
引き落し通知は省略させていただきます).
また,学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)
の方で,それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適
用します.
【割引会費請求書最終締切】2020年3月31日(火)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】第11回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
──────────────────────────────────
***応募締切:2020年1月31日(金)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰の
コンテストです.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大
募!!投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募
フォームからでもメール添付でもご応募いただけます.
会員の皆様からの応募をお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp
第10回入選作品の展示会を下記のように予定しています。
大きくプリントされた迫力のある作品を是非ご覧下さい。
・2月9日(日) -3月15日(日):水戸市立博物館
・3月20日(金・祝)-6月28日(日):蒲郡市生命の海科学館
第10回入選作品はこちらからもご覧いただけます.
http://www.geosociety.jp/faq/content0009.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[東北支部]
■2019年度日本地質学会東北支部総会・講演会
2月29日(土)-3月1日(日)
場所:秋田大学教育文化学部
講演申込締切:2月17日(月)
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
[西日本支部]
■西日本支部令和元年度総会・第171回例会の案内
2月29日(土)例会・総会
場所:北九州市立自然史・歴史博物館 いのちのたび博物館
講演申込・参加申込:2月14日(金)締切
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
[関東支部]
■支部功労賞募集
対象者:支部活動や地質学を通して広く社会貢献をされた関東支部
内に在住の個人・団体(*社会貢献や活動の評価においては,必ず
しも学問的な成果を問うものではありません)
募集締切:2020年1月10日(金)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html#sho
■シンポジウム「関東のテフラ−最近の年代観と供給源−」
1月25 日(土)10:00-16:30
場所:「北とぴあ」第一研修室(〒114-0002 北区王子1-11-1)
対象:日本地質学会会員および一般(非会員)
参加費:無料,事前申込不要
懇親会:会費4,000円程度,懇親会は要事前申込[締切:1月17日(金)]
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
■ ミニ巡検「大磯丘陵北東部のテフラ」
関東地方のテフラ研究で重要な役割を占めていた大磯丘陵の模式的な
露頭をめぐるミニ巡検を開催します.
2月16日(日)
対象:会員(空きがあれば一般参加も可能)
募集:20人(先着順)
申込締切:1月31日(金)
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■2019/12/25 電中研メールマガジンより:
原子力発電所の基準地震動策定における地下構造モデル化の現状と今後の展望
https://criepi.denken.or.jp/jp/kenkikaku/report/detail/O19002.html?m=191225-2
■地震本部ニュース2019秋号
『平成28年熊本地震を踏まえた総合的な活断層調査』ほか
https://www.jishin.go.jp/herpnews/
■JABEEメールマガジン 2020年冬号
新連載『技術者教育プログラム認定の海外状況』ほか
https://sites.google.com/jabee.org/koho-magazine/top/2020-winter
-----------------------------------------------------------------
(後)北淡国際活断層シンポジウム2020
「活断層研究の新たな展開−阪神淡路大震災から25年」
1月14日(火)-17日(金)
会場:北淡震災記念公園セミナーハウス・野島断層保存館(兵庫県淡路市)
https://home.hiroshima-u.ac.jp/kojiok/20circularJ.pdf
■第314回地学クラブ講演会
「地震の予測と社会:日本とイタリアの地震裁判から」
1月27日(月)13:00-15:00
場所:東京地学協会地学会館2階講堂
講演者:纐纈一起(東京大学地震研究所)
参加申込不要(どなたも無料で参加できます)
http://www.geog.or.jp/lecture/lecturescheduled/390-club314.html
■第12回HOPEミーティング―パネルディスカッション―
テーマ:Science and Society
3月12日(木)14:00-15:00
場所:つくば国際会議場大ホール
言語英語(同時通訳なし)事前登録制
パネリスト(予定):
・梶田隆章(15年ノーベル物理学賞)
・J・ゲオルグ・ベドノルツ(87年ノーベル物理賞)
・ヨハン・ダイゼンホーファー(88年ノーベル化学賞)ほか
https://sec.tobutoptours.co.jp/web/evt/12thhope_panel_discussion/
■地質学史懇話会
6月20日(土)13:30-17:00
場所:北とぴあ8階805会議室(JR京浜東北線王子駅下車3分)
矢島道子:『地質学者ナウマン伝』を上梓して
加藤碵一:日本列島成立史あれこれ
問い合わせ先:矢島 pxi02070[at]nifty.com
■国際ゴンドワナ研究連合(IAGR)2020年総会及び
第17回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム
8月30日-9月1日 会議とシンポジウム
9月2-7日 アルタイ山地巡検(L)・2-5日 アルタイ山地巡検(S)
場所:ノボシビルスク(ロシア)
参加申込:3月1日まで(発表要旨:4月30日まで)
問合せ・参加申込・発表要旨送付先:
iagr2020@igm.nsc.ru & inna@igm.nsc.ru
■第19回国際物質組織学会議(ICOTOM19)
9月6日(日)-11日(金)
場所:大阪府立大学
要旨締切:2月1日(土)
http://icotom19.com/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0191.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
─────────────────────────────────
・千葉工業大学惑星探査研究センター:科研費に基づく研究員公募(1/31)
・福井県立大学恐竜学研究所専任教員(教授)公募(1/31)
・JAMSTEC超先鋭研究開発部門高知コア研究所技術副主幹or技術主任公募(2/7)
・栗駒山麓ジオパーク専門員(宮城県栗駒市)募集(1/22)
・山陰海岸ジオパーク推進協議会ジオパーク専門員募集(1/31)
・五島列島ジオパーク構想ジオパーク専門員(長崎県五島市)募集(1/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.475(臨時)チバニアン認定!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.475 2020/1/17┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】チバニアン認定!
─────────────────────────────────
国際地質科学連合の理事会が釜山で開催され,千葉県市原市の「千
葉セクション」が前期更新世と中期更新世の境界を示す代表的な地
層であり,77万4000〜12万9000年前の地質時代を「チバニアン」と
呼ばれることが認められました.
地質時代に日本の地名が付くのは初めてのことです.これは日本の
地質学のレベルの高さを示すものであり,たいへん喜ばしいことです.
報道各社のニュース等でも紹介されています.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.476 地質もくわしい!アニメ「恋する小惑星」がスゴイ
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.476 2020/1/21┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】正副会長候補者の意向調査(結果)
【2】「GSSPシンポジウム:国際層序の意味と意義」報告
【3】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されています
【4】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
【5】第11回惑星地球フォトコンテスト:締切間近!
【6】2021年度地震火山こどもサマースクール開催地募集
【7】(紹介)「恋する小惑星」を応援しよう!
【8】(会員の活動紹介)地質標本館は「恋アス」を応援しています。
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】正副会長候補者の意向調査(結果)
─────────────────────────────────
選挙規則ならびに選挙細則に基づき,標記意向調査を実施いたしま
した.法人の代表理事は法律により,理事会において選任すること
が定められています.学会の代表理事となる会長およびその補佐役
の副会長を選出するにあたり,会員の皆様の意向を伺うためにこの
調査を行いました
結果はこちらから,http://sub.geosociety.jp/members/content0109.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】「GSSPシンポジウム:国際層序の意味と意義」報告
─────────────────────────────────
当日は雨の中,約80人が参加した.今話題のチバニアンは,地球全
体の新生代第四紀の中期更新世/前期更新世境界のGSSPを,千葉県
市原市田淵の養老川沿いの上総層群国本層の露頭に設定し,これま
で名前がなかった中期更新世の時代を「チバニアン」と名づけるも
のであり,国際地質科学連合(IUGS)は2020年1月17日に釜山で開催
された会議でチバニアンのGSSPを正式に決定した.
全文はこちら,,http://www.geosociety.jp/science/content0116.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されています
──────────────────────────────────
募集期間:2019年12月20日(金)〜2020年2月7日(金)2020年2月10日(月)*訂正2/4
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:例えば,,,地質学への顕著な貢献/地質学会の運
営と発展への貢献/教育現場や企業などでの活動を通じた地質学の普及と振興
への貢献など
*上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することはできませ
んが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
(名誉会員推薦委員会 佐々木和彦)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
──────────────────────────────────
次年分(2020年度)の会費請求書を昨年12/16に発送いたしました.
折り返しご送金をお願いいたします.
自動引落の方は,昨年12/23に引き落しとなりました(請求書ならび
に引き落し通知は省略させていただきます).
また,学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)
の方で,それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適
用します.
【割引会費請求書最終締切】2020年3月31日(火)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第11回惑星地球フォトコンテスト 締切間近!
──────────────────────────────────
***応募締切:2020年1月31日(金)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰の
コンテストです.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大
募!!投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募
フォームからでもメール添付でもご応募いただけます.
会員の皆様からの応募をお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp
第10回入選作品の展示会を下記のように予定しています.
大きくプリントされた迫力のある作品を是非ご覧下さい.
・2月9日(日) -3月15日(日):水戸市立博物館
・3月20日(金・祝)-6月28日(日):蒲郡市生命の海科学館
第10回入選作品はこちらからもご覧いただけます.
http://www.geosociety.jp/faq/content0009.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】2021年度地震火山こどもサマースクール開催地募集
──────────────────────────────────
募集期間:2020年1月14日(火)〜2月13日(木)
地震火山こどもサマースクールは,1999年夏から小・中・高校生を
対象にはじまった行事で,現在,日本地震学会,日本火山学会,日
本地質学会が共同で実施する,地球科学関連では最大規模の体験学
習講座です.今回,2021年度に実施する第22回の開催地を公募いた
します.
応募資格など詳しくは,http://www.geosociety.jp/news/n146.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】(紹介)「恋する小惑星」を応援しよう!
─────────────────────────────────
愛知教育大学・星 博幸(社会貢献担当理事)
皆さん,「恋する小惑星」(こいするアステロイド;略して,
恋アス)で地質が題材の一部になっているのを知っていますか?
恋アスは『まんがタイムきららキャラット』(芳文社)に2017年
3月号から連載中の漫画で,本年1月3日からテレビアニメも始まりま
した(AT-X,BS11,TOKYO MX,AbemaTVなど複数の放送局・配信サイ
トで視聴可)。高校の地学部を舞台に,小惑星を見つけたいという
夢を持った主人公と,その周囲の地学系女子(ジオジョ)による青
春物語(URL1)です。アニメは萌え系オタクの間でも話題のようで
すが,ここではそれについては触れません。アニメでは地質図,ハ
ンマー,岩石(チャート,安山岩,泥岩,いわゆる鉢巻石,その他),
ルーペなど地質ネタも登場し,SNS上では一部の地質系研究者やマニ
アが喜びの雄叫びをあげています。ネット情報(URL2)によると,
作者のQuro氏は高校時代に地学部に所属し,天文が好きとのこと。
「恋アスをきっかけに地学に興味を持ってくださる方が増えたら」
と述べています(URL2)。アニメには産総研地質調査総合センター
(GSJ/AIST)や地質標本館,宇宙航空研究開発機構(JAXA),国土
地理院(GSI)などが協力しています。
恋アスの何がすごいか? それは,中高生や大学生,オタクなどを
主な視聴層とする番組でほぼ毎回,地球惑星科学ネタが登場するこ
とです。地質に限らず広く天文や気象などの専門用語が中高生や大
学生,オタクなどの耳に毎週届くのです! 地質・地理界隈では「ブ
ラタモリ」が話題で,その人気は周知の通りです。本会も2017年度,
地質学の社会への普及という業績に対して「ブラタモリ」制作チー
ム(日本放送協会)に日本地質学会表彰を授与しました(URL3)。
「ブラタモリ」と同様に,恋アスは地球惑星科学の初歩的な内容を
伝えてくれます。恋アスは若者に地球惑星科学ファンを増やしてく
れるかもしれません。これはすばらしいことではありませんか!
皆さん,恋アスを応援しましょう! 興味のある方は一度アニメを
ご覧ください。「KiraKira増刊号!」というミニアニメもYouTubeに
アップされているので,気軽に見てみてください(ちなみに,この
記事を執筆している1月13日時点ではタイトル「岩石について」が視
聴可)。漫画やアニメに抵抗を感じる方は無理に読んだり視聴した
りすることはありませんが,周囲の若者が恋アスを話題にしている
時は温かい目で見てあげてください。
<引用>
URL1: https://ja.wikipedia.org/wiki/恋する小惑星
URL2: https://www.mashiro-writer.com/interview-quro
URL3: http://www.geosociety.jp/outline/content0180.html#hyosyo
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】(会員の活動紹介)地質標本館は「恋アス」を応援しています.
─────────────────────────────────
産総研 地質標本館 館長・森田澄人
産総研・地質標本館は「恋する小惑星(アステロイド)」(略称:
恋アス)の制作に協力しています。
取材依頼があった当初、どのような妖艶な世界が飛び込んできたか
と、少し身構える思いでしたが、作者のQuroさんやアニメ制作に関
わるスタッフの皆さんの、とても熱心で且つリアルさにこだわるそ
の姿勢にたいへん感銘を受けました。
作品の中では、地学部の女子高校生たちがキラキラをテーマに、石
や地層、星などの魅力を追求していく様子がユーモア満載で表現さ
れています。かなり専門的な部分を含むところもありますので、専
門家側から見た趣きも多分に感じられます。
本作品は、マンガ読者やアニメ視聴者に向けて、石や化石に触れる、
または興味を持つ機会を増やしてくれていることは確かで、地質標
本館の来館者にも恋アスをきっかけに遠方からお越し下さる方は少
なくありません。地学部員たちの、純粋な気持ちをもって一生懸命
に活動に取り組む姿はとても可愛らしく、それがこのような一般の
方々の心も動かしているのでしょう。マンガとアニメを通して、こ
れからも彼女たちを温かく見守っていきたいと考えています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】支部情報
──────────────────────────────────
[東北支部]
■2019年度日本地質学会東北支部総会・講演会
2月29日(土)-3月1日(日)
場所:秋田大学教育文化学部
講演申込締切:2月17日(月)
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
[西日本支部]
■西日本支部令和元年度総会・第171回例会の案内
2月29日(土)例会・総会
場所:北九州市立自然史・歴史博物館 いのちのたび博物館
講演申込・参加申込:2月14日(金)締切
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
[関東支部]
■シンポジウム「関東のテフラ−最近の年代観と供給源−」
1月25 日(土)10:00-16:30
場所:「北とぴあ」第一研修室(〒114-0002 北区王子1-11-1)
対象:日本地質学会会員および一般(非会員)
参加費:無料,事前申込不要
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
■ ミニ巡検「大磯丘陵北東部のテフラ」
関東地方のテフラ研究で重要な役割を占めていた大磯丘陵の模式的な
露頭をめぐるミニ巡検を開催します.
2月16日(日)
対象:会員(空きがあれば一般参加も可能)
募集:20人(先着順)
申込締切:1月31日(金)
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■ 電中研メールマガジン(2020/1/20配信)より
・低線量率被ばくでは発がんリスクが上がらない仕組みの解明に近
づく−幹細胞からミニ小腸(オルガノイド)を作製する技術を用い
「放射線によって誘発される幹細胞競合」を捉えることに成功−
https://criepi.denken.or.jp/press/pressrelease/2020/01_20.html?m=200120-1
*****************************************************
■ 第61回科学技術映像祭:作品募集中
科学技術を正確にわかりやすく伝える優れた映像を選奨することに
より,科学技術への関心を喚起するとともにその普及と向上をはか
り,社会一般の科学技術教養の向上に資することを目的とする.
募集要件:2019年1月1日から2020年1月24日までに完成した作品で本
映像祭へ初出品であること.ほか
募集締切:2020年1月24日(必着)
http://ppd.jsf.or.jp/filmfest/61/youkou.html
(後)企画展「ゴンドワナ:岩石が語る大陸の衝突と分裂」
場所:神奈川県立生命の星・地球博物館
2月29日(土)-5月10日(日)
http://nh.kanagawa-museum.jp/
■ 第197回深田研談話会
2月7日(金)18:00-19:30
場所:深田地質研究所 研修ホール(東京都文京区)
講師:石川孝織 氏(釧路市立博物館学芸専門員)
演題:炭鉱と鉄道—釧路炭田を中心に—
参加費無料,70名(先着)*要事前申込
https://www.fgi.or.jp/
■ 石川町立歴史民俗資料館企画展記念講演会
「阿武隈高地の地質」
2月23(日)14:00
場所:石川町文教福祉複合施設(モトガッコ)
講師:蟹澤聰史(東北大学理学研究科名誉教授)
阿武隈高地でもっとも古い地質で,シマシマ模様を特徴とする変成
岩の成り立ちを中心に,「阿武隈高地の地質」について講演会を開
催します.
問い合わせ先:石川町立歴史民俗資料館 電話 0247-26-3768
申込不要・入場無料
(後)海洋研究開発機構海域地震火山部門講演会
「もっと知ろう,おもしろ海の火山学」
2月23日(日・祝)13:00-15:40
会場: 国立科学博物館日本館(東京都台東区上野公園)
参加費無料,事前登録制(定員に達し次第締切)
http://www.jamstec.go.jp/rimg/j/sympo/img2019/
■ 第231回 地質汚染・災害イブニングセミナー
2月28日(金)18:30-20:30
場所:北とぴあ803会議室(東京都北区王子)
講師:國生剛治(中央大学名誉教授)
演題:「最近の地震被害から見た液状化現象の実像」
会費:会員500円 非会員 1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■ 第9回防災学術連携シンポジウム
「低頻度巨大災害を考える」
3月18日(水)12:30-17:30
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木)
https://janet-dr.com/
■ 日本堆積学会2020年島根大会
3月28日(土)-30日(月)
会場:島根大学松江キャンパス 教養教育棟2号館
http://sediment.jp/
■ 第19回重金属類・残土石処分地・廃棄物処分地診断に関わる
地質汚染調査浄化技術研修会
4月29日(水・祝)-5月2日(土)(部分受講可)
主催:NPO法人 日本地質汚染審査機構
会場:日本地質汚染審査機構関東ベースン実習センター(千葉県香取市)
会費:会員50,000円,非会員60,000円,学生:15,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
■ 地質学史懇話会
6月20日(土)13:30-17:00
場所:北とぴあ8階805会議室(東京都北区王子)
矢島道子:『地質学者ナウマン伝』を上梓して
加藤碵一:日本列島成立史あれこれ
問い合わせ先:矢島 pxi02070[at]nifty.com
☆日本地質学会第127年学術大会
9月9日(水)-11日(金)
会場:名古屋大学東山キャンパス
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞助成情報等
─────────────────────────────────
・下北ジオパーク むつ市ジオパーク推進員(2名)募集(2/20)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.477 (臨時)学術会議マスタープランに地質学会の提案が選定される!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.477 2020/1/30┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】学術会議マスタープランに地質学会の提案が選定される!
─────────────────────────────────
本日,日本学術会議の第24期学術の大型研究計画に関するマスタープラン
(マスタープラン2020)が公表されました.
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/kohyo-24-t286-1.html
このなかにおいて日本地質学会から提案されておりました学術大型研究計画
「地球惑星研究資料のアーカイブ化とキュレーションシステムの構築(計画
番号94 学術領域番号24-1)」が選定されました.
これは、本学会から提案された地質試料の適切な管理と将来のサイエンスの
ためのキュレーション計画の学術的意義が高く評価されたことを意味します.
日本地質学会は今後とも地質学の発展のために,会員皆様からの意見を集め,
議論を重ね,さらなる大型研究の提案,そして重点大型研究計画への選定を
目指して活動する所存です.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真を募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.478 要旨集の電子化を検討しています:アンケート実施中
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬w
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.478 2020/2/4┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】学術大会の講演要旨集の電子化を検討しています:アンケート実施中
【2】2020名古屋大会開催!トピックセッション募集開始!
【3】日本地質学会名誉会員候補者の募集について
【4】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
【5】地質学雑誌からのお知らせ
【6】2021年度地震火山こどもサマースクール開催地募集
【7】第10回惑星地球フォトコンテスト展示会
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】学術大会の講演要旨集の電子化を検討しています:アンケート実施中
──────────────────────────────────
****************************************
回答期限:2020年2月28日(金)
****************************************
現在理事会では,学術大会の要旨集の電子化を検討しています.目的は,資源
節約の観点から冊子体要旨集を廃止し,プログラム作成効率の大幅な向上を図
ると同時に,電子化によるメリットを会員に享受して頂くことです.さらに喫
緊の課題となっている学会事務局の業務軽減にも資することができます.理事
会としては,本アンケートにより会員の意見分布を得た上で最終的な判断をい
たしますので,アンケートへの回答を是非ともお願い申し上げます.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/news/n147.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2020名古屋大会開催!トピックセッション募集開始!
──────────────────────────────────
日本地質学会は,名古屋市の名古屋大学東山キャンパスにて,第127年学術大会
(2020年名古屋大会)を9月9日(水)〜11日(金),巡検(見学旅行)
を9月8日(火)と9月12日・13日(土・日)に開催します.
名古屋は日本のほぼ中心に位置し,交通の便もよく,皆様の旅程も容易に計画
す。ることができます.またすべての学会会場を東山キャンパスの西側に位置
する教養教育院に設け,場所的に集中した複数の会場でコンパクトに行う予定
です.
***********************************************************
トピックセッション募集 締切:2020年3月10日(火)
***********************************************************
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0119.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本地質学会名誉会員候補者の募集について
──────────────────────────────────
募集期間:2019年12月20日(金)〜2020年2月10日(月)
(注)前号メルマガにて募集期日の表示に誤りがありました.
お詫びして訂正いたします.(誤)2月7日(金)→(正)2月10日(月)
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:例えば,,,地質学への顕著な貢献/地質学会の運
営と発展への貢献/教育現場や企業などでの活動を通じた地質学の普及と振興
への貢献など
*上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することはできませ
んが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
(名誉会員推薦委員会 佐々木和彦)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
──────────────────────────────────
次年分(2020年度)の会費請求書を昨年12/16に発送いたしました.
折り返しご送金をお願いいたします.
自動引落の方は,昨年12/23に引き落しとなりました(請求書ならび
に引き落し通知は省略させていただきます).
また,学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)
の方で,それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適
用します.
【割引会費請求書最終締切】2020年3月31日(火)
*災害に関連した特別措置申請締切:2020年2月28日(金)についても
ご案内しています.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質学雑誌からのお知らせ
──────────────────────────────────
126巻1号(2020年1月号)刊行しました.
特集号:「泥火山」の新しい研究展開に向けて
・「泥火山」定義,概念,成因,および最近の研究動向:浅田美穂
・世界の海底泥火山の分布と山体形態に関する一考察:喜岡 新
・泥火山における生物地球化学過程とその意義:井尻 暁
・泥火山研究の最前線−陸上泥火山研究における最近8 年の進展:田中和広ほか
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】2021年度地震火山こどもサマースクール開催地募集
──────────────────────────────────
募集期間:2020年1月14日(火)-2月13日(木)
地震火山こどもサマースクールは,1999年夏から小・中・高校生を
対象にはじまった行事で,現在,日本地震学会,日本火山学会,日
本地質学会が共同で実施する,地球科学関連では最大規模の体験学
習講座です.今回,2021年度に実施する第22回の開催地を公募いた
します.
応募資格など詳しくは,http://www.geosociety.jp/news/n146.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】第10回惑星地球フォトコンテスト展示会
──────────────────────────────────
第10回惑星地球フォトコンテスト入選作品展示会を下記のように予定しています.
是非ご覧ください.
(本年第11回は応募受付を終了しました.審査結果は3月発表予定です)
日程:2020年2月9日(日) 〜 3月15日(日)
場所:水戸市立博物館(茨城県水戸市大町)
http://shihaku1.hs.plala.or.jp/
日程:2020年3月20日(金・祝)〜6月28日(日)
場所:蒲郡市生命(いのち)の海科学館 (愛知県蒲郡市)
http://www.city.gamagori.lg.jp/site/kagakukan/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
──────────────────────────────────
[東北支部]
■2019年度日本地質学会東北支部総会・講演会
2月29日(土)-3月1日(日)
場所:秋田大学教育文化学部
講演申込締切:2月17日(月)
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
[西日本支部]
■西日本支部令和元年度総会・第171回例会の案内
2月29日(土)例会・総会
場所:北九州市立自然史・歴史博物館 いのちのたび博物館
講演申込・参加申込:2月14日(金)締切
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
[関東支部]
■2020年度関東支部幹事選出のお知らせ
支部幹事の改選に伴い,支部幹事立候補者の受付を行います.
立候補期間:2020年3月1日(日)-3月11日(水)
■地学教育・アウトリーチ巡検(チバニアン周辺)
3月22日(日)10:20小湊鉄道月崎駅集合,15:30頃同駅解散予定
場所:市原市田淵周辺
募集人数:30人(日本地質学会会員でなくても可)定員になり次第締め切ります.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■道総研地質研究所ニュース(2020.1.31発行)
https://www.hro.or.jp/list/environmental/research/gsh/publication/gshnews/gshnews02/
*****************************************************
(後)企画展「ゴンドワナ:岩石が語る大陸の衝突と分裂」
場所:神奈川県立生命の星・地球博物館
2月29日(土)-5月10日(日)
http://nh.kanagawa-museum.jp/
(後)海洋研究開発機構海域地震火山部門講演会
「もっと知ろう,おもしろ海の火山学」
2月23日(日・祝)13:00-15:40
会場: 国立科学博物館日本館(東京都台東区上野公園)
参加費無料,事前登録制(定員に達し次第締切)
http://www.jamstec.go.jp/rimg/j/sympo/img2019/
■核-マントルの相互作用と共進化:統合的地球深部科学の創成
令和元年度成果発表会
3月2日(月)〜5日(木)
場所ホテルメルパルク松山別館3階ラフィーネ
http://core-mantle.jp
■第6回地区防災計画学会
3月7日(土)9:30-17:30
場所 兵庫県立大学神戸防災キャンパス
参加費 無料(ただし,梗概集は有料)
https://gakkai.chiku-bousai.jp/ev200307.html
■ 第9回防災学術連携シンポジウム
「低頻度巨大災害を考える」
3月18日(水)12:30-17:30
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木)
https://janet-dr.com/060_event/20200317.html
■第233回地質汚染・災害イブニングセミナー
4月24日(金)18:30-20:30
場所:北とぴあ808会議室(東京都北区王子)
講師:西口 学(国土交通省水資源部水資源政策課長)
演題:「国の水資源政策と水循環基本法」
会費:会員500円 非会員 1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
☆日本地質学会第127年学術大会
9月9日(水)-11日(金)
会場:名古屋大学東山キャンパス
http://www.geosociety.jp/science/content0119.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
─────────────────────────────────
・ふじのくに地球環境史ミュージアム職員公募(地質・岩石・地震)(3/17)
・北海道大学理学研究院地球惑星システム科学分野(岩石学火山学研究グループ)
学術研究員または博士研究員公募(2/25)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.479 理事選挙のお知らせ/要旨集電子化アンケート
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.479 2020/2/18┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2020年度理事および監事選挙について
【2】学術大会の講演要旨集の電子化を検討しています:アンケート実施中
【3】2020名古屋大会開催!トピックセッション募集中
【4】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
【5】地質学雑誌/Island Arc からのお知らせ
【6】第10回惑星地球フォトコンテスト展示会
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2020年度理事および監事選挙について
──────────────────────────────────
選挙規則,選挙細則に基づき2020年度の理事選挙を実施いたします.理事選挙は
2020年度からの新代議員による投票となります.監事については候補者は定数内
のため,監事の投票は行いません.
理事選挙の開票は3月11日(水)15時から学会事務局で行います.開票の立ち会
いをご希望のかたは,3月9日(月)までに選挙管理委員会にお申し出ください.
選挙管理委員会で確認した理事および監事の立候補者名簿は学会HPからご確認
ください.
http://sub.geosociety.jp/members/content0111.html(要会員ログイン)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】学術大会の講演要旨集の電子化を検討しています:アンケート実施中
──────────────────────────────────
****************************************
回答期限:2020年2月28日(金)
****************************************
現在理事会では,学術大会の要旨集の電子化を検討しています.目的は,資源
節約の観点から冊子体要旨集を廃止し,プログラム作成効率の大幅な向上を図
ると同時に,電子化によるメリットを会員に享受して頂くことです.さらに喫
緊の課題となっている学会事務局の業務軽減にも資することができます.理事
会としては,本アンケートにより会員の意見分布を得た上で最終的な判断をい
たしますので,アンケートへの回答を是非ともお願い申し上げます.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/news/n147.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2020名古屋大会開催!トピックセッション募集中
──────────────────────────────────
日本地質学会は,名古屋市の名古屋大学東山キャンパスにて,第127年学術大会
(2020年名古屋大会)を9月9日(水)〜11日(金),巡検(見学旅行)を
9月8日(火)と9月12日・13日(土・日)に開催します.
名古屋は日本のほぼ中心に位置し,交通の便もよく,皆様の旅程も容易に計画する
ことができます.またすべての学会会場を東山キャンパスの西側に位置する教養
教育院に設け,場所的に集中した複数の会場でコンパクトに行う予定です.
***********************************************************
トピックセッション募集 締切:2020年3月10日(火)
***********************************************************
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0119.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
──────────────────────────────────
次年分(2020年度)の会費請求書を昨年12/16に発送いたしました.
折り返しご送金をお願いいたします.
自動引落の方は,昨年12/23に引き落しとなりました(請求書ならび
に引き落し通知は省略させていただきます).
また,学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)
の方で,それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適
用します.
【割引会費請求書最終締切】2020年3月31日(火)
*災害に関連した特別措置申請締切:2020年2月28日(金)についても
ご案内しています.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質学雑誌/Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■地質学雑誌126巻2号(2020年2月号)通常号 予告
・秋田および山形北部地域の新第三系炭酸塩コンクリーションのSr 同位体比と珪藻
化石年代:西川 治ほか(論説)
・日高帯中に見いだされた後期漸新世を示す珪質泥岩層とそのテクトニックな意義
:七山 太ほか(論説)
・母体–松ヶ平帯山上変成岩類のフェンジャイトK–Ar年代−蓮華変成岩類の東北日
本弧への延長の可能性−:宮下 敦ほか(論説)
・山口県北西部における地すべりの地質と防災対策:河内義文ほか(巡検案内書)
■Island Arcの新しい論文が公開されています。
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
・Evolution of lithospheric mantle in the north of Nain‐Baft oceanic crust
(Neo‐Tethyan ophiolite of Ashin, Central Iran):Nargess Shirdashtzadeh
et al (First Published:2/14)
・Variations in trace elements, isotopes, and organic geochemistry during
the Hangenberg Crisis, Devonian–Carboniferous transition, northeastern
VietnamAtena Shizuya (First Published:2/11)ほか
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】第10回惑星地球フォトコンテスト展示会
──────────────────────────────────
第10回惑星地球フォトコンテスト入選作品展示会を下記のように予定しています.
是非ご覧ください.(第11回は募集を終了しました.審査結果は3月発表予定です)
日程:2020年2月9日(日) 〜 3月15日(日)
場所:水戸市立博物館(茨城県水戸市大町)
http://shihaku1.hs.plala.or.jp/
日程:2020年3月20日(金・祝)〜6月28日(日)
場所:蒲郡市生命(いのち)の海科学館 (愛知県蒲郡市)
http://www.city.gamagori.lg.jp/site/kagakukan/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[東北支部]
■2019年度日本地質学会東北支部総会・講演会
2月29日(土)-3月1日(日)
場所:秋田大学教育文化学部
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
[西日本支部]
■西日本支部令和元年度総会・第171回例会の案内
2月29日(土)例会・総会
場所:北九州市立自然史・歴史博物館 いのちのたび博物館
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
[関東支部]
■2020年度関東支部幹事選出のお知らせ
支部幹事の改選に伴い,支部幹事立候補者の受付を行います.
立候補期間:2020年3月1日(日)-3月11日(水)
■2020年度総会・地質技術伝承講演会
4月11日(土)14:00-6:45
場所:北とぴあ 第2研修室(東京都北区王子1-11-1)
関東支部会員の方で総会に欠席される方は委任状をお願いします(4/10締切)
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)企画展「ゴンドワナ:岩石が語る大陸の衝突と分裂」
場所:神奈川県立生命の星・地球博物館
2月29日(土)-5月10日(日)
http://nh.kanagawa-museum.jp/
(後)海洋研究開発機構海域地震火山部門講演会
「もっと知ろう,おもしろ海の火山学」
2月23日(日・祝)13:00-15:40
会場: 国立科学博物館日本館(東京都台東区上野公園)
参加費無料,事前登録制(定員に達し次第締切)
http://www.jamstec.go.jp/rimg/j/sympo/img2019/
■第200回湘南地球科学の会
2月29日(土)12:30-
会場:神奈川県立生命の星・地球博物館 講義室
・藤岡 換太郎 『湘南地球科学200回の回想とこれからの地球科学』
・小宮 剛『冥王代の地球史解読・最古の生命の痕跡』
・磯粼 行雄『日本列島:その最初と最後についての新イメージ』
・小川 勇二郎『日本がプレートテクトニクスに果たした役割と今後のスコープ』
問い合わせ:山下浩之(神奈川県立生命の星・地球博物館)
yama@nh.kanagawa-museum.jp
■第198回深田研談話会
3月6日(金)18:00-19:30
場所:深田地質研究所 研修ホール(東京都文京区)
講師:高木秀雄 氏(早稲田大学教育・総合科学学術院 地球科学教室 教授)
演題:跡倉ナップから探る日本列島の地体構造
参加費無料、70名(先着)*要事前申込
https://www.fgi.or.jp/
■日本地学オリンピック とっぷ・レクチャー
*聴講者募集*
3月15日(日)13:00-17:00
場所:筑波銀行本部ビル10階大会議室
参加無料・先着150名
http://jeso.jp/event/lecture/2020/index.html
■ 第9回防災学術連携シンポジウム
「低頻度巨大災害を考える」
3月18日(水)12:30-17:30
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木)
https://janet-dr.com/060_event/20200317.html
■第232回地質汚染・災害イブニングセミナー
3月27日(金)18:30-20:30
場所:北とぴあ807会議室(東京都北区王子)
講師:藤川典久(気象庁地球環境・海洋部気候情報課長)
演題:「水トピック 日本の降水量:これまでの変化と今後の見通しを中心に」
会費:会員500円,非会員 1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■JpGU2020年大会
5月24(日)-28日(木)
会場:幕張メッセ(千葉市美浜区)
http://www.jpgu.org/meeting_j2020/
☆日本地質学会第127年学術大会
9月9日(水)-11日(金)
会場:名古屋大学東山キャンパス
http://www.geosociety.jp/science/content0119.html(プレサイト)
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
─────────────────────────────────
・静岡大学理学部地球科学科教員公募(助教1名)(5/8)
・秋田大学国際資源学部資源地球科学専攻公募(助教3名)(3/31)
・北海道大学理学研究院地球惑星システム科学分野(岩石学火山学研究G)
学術研究員または博士研究員公募(2/25)←(注)2/4配信時に期日の
表示に誤りがありました.お詫びして訂正いたします.
(誤)2/28 →(正)2/25
・2020年度「深田野外調査助成」(4/20)
・苗場山麓ジオパーク学術研究活動募集(3/6)
・第17回(2020年度)「日本学術振興会賞」受賞候補者推薦(学会締切3/23)
・国土地理協会2020年度学術研究助成(4/1-15)
・2020年コスモス国際賞(学会締切3/27)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.481 第11回惑星地球フォトコンテスト:審査結果発表!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.481 2020/3/3┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】第11回惑星地球フォトコンテスト:審査結果発表!
【2】2020年度「地質の日」行事のご案内
【3】令和2年度大学入試センター試験の地学関連科目に関する意見書 提出
【4】2020年度理事選挙開票について(3/11)
【5】2020名古屋大会:トピックセッション募集中
【6】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
【7】地質系統・年代の日本語記述ガイドライン 2020年1月改訂版
【8】Island Arc からのお知らせ
【9】第10回惑星地球フォトコンテスト展示会(一部会期変更)
【10】支部情報
【11】その他のお知らせ
【12】公募情報・各賞助成情報等
【13】訃報:大八木規夫 名誉会員
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】第11回惑星地球フォトコンテスト:審査結果発表!
──────────────────────────────────
2/20に審査会が開催され,応募作品全374作品のうち,入選12点,佳作13点が
決定しました.作品画像は近日学会HP上にて公開の予定です.
最優秀賞:1点(賞金5万円)
「鷹島の奇岩」佐藤悠大(福岡県)
優秀賞:2点(賞金各2万円)
「Cosmic Blue」根岸桂子(富山県)
「褶曲」西出 琢(千葉県)
ジオパーク賞:1点(賞金2万円)
「巨人のげんこつ」長谷 洋(和歌山県)
日本地質学会会長賞:1点(賞金1万円)
「迷子石」川又基人(東京都)
ジオ鉄賞:1点(賞金1万円)
「滝上を走る列車」細谷正夫(茨城県)
その他の結果は,http://www.photo.geosociety.jp/
下記の通り表彰式,展示会を開催予定です.
【表彰式】(作品展示も予定しています)
5月23日(土)11:00-12:30(予定)
会場:北とぴあ 第2研修室(東京都北区王子)
【作品展示予定】今後予定が追加されます.随時HPに掲載予定です
・東京パークスギャラリー(上野)
5月19日(火)-5月31日(日)
場所:上野恩賜公園 上野グリーンサロン内(台東区上野公園7-47)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2020年度「地質の日」行事のご案内
──────────────────────────────────
日本地質学会および各支部等で予定されている「地質の日」行事をご案内します.
■第11回惑星地球フォトコンテスト展示会
5月19日(火)-31日(日)
場所:東京パークスギャラリー(上野グリンサロン内)(台東区上野公園)
■第11回惑星地球フォトコンテスト表彰式
5月23日(土)11:00-12:30(予定)
場所:北とぴあ 第2研修室会議室(東京都北区王子)
■街中ジオ散歩in Yokohama「身近な地形・地質から探る横浜の発展」徒歩見学会
5月16日(土)9:00-16:00 小雨決行
■近畿支部:第37回地球科学講演会
「北アルプス生成の謎−マグマと短縮テクトニクスが作り出した北アルプス−」
5月10日(日)15:00-16:30
場所:大阪市立自然史博物館 本館
今後も随時情報を追加予定です.お楽しみに!
http://www.geosociety.jp/name/content0168.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】令和2年度大学入試センター試験の地学関連科目に関する意見書 提出
──────────────────────────────────
日本地質学会は,過去5年間にわたり,大学入試センター試験の地学関連科目
の問題および得点調整に関して,それらが適正に行われているかを検討し,そ
の都度,意見や改善に向けた要望を大学入試センターに申し入れてきました.
本年に実施されました令和2年度大学入試センター試験(本試験)の地学関連
科目に関して,以下のような意見を申し入れ致します.
全文はこちら,,,http://www.geosociety.jp/engineer/content0055.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2020年度理事選挙開票について(3/11)
──────────────────────────────────
選挙規則,選挙細則に基づき2020年度の理事選挙を実施いたします.理事選挙は
2020年度からの新代議員による投票となります.監事については候補者は定数内
のため,監事の投票は行いません.
理事選挙の開票は3月11日(水)15時から学会事務局で行います.開票の立ち会
いをご希望のかたは,3月9日(月)までに選挙管理委員会にお申し出ください.
選挙管理委員会で確認した理事および監事の立候補者名簿は学会HPからご確認
ください.
http://sub.geosociety.jp/members/content0111.html(要会員ログイン)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2020名古屋大会:トピックセッション募集中
──────────────────────────────────
日本地質学会は,名古屋市の名古屋大学東山キャンパスにて,第127年学術大会
(2020年名古屋大会)を9月9日(水)-11日(金),巡検(見学旅行)を9月8日(火)と9月12日・13日(土・日)に開催します.
***********************************************************
トピックセッション募集 締切:2020年3月10日(火)
***********************************************************
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0119.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
──────────────────────────────────
次年分(2020年度)の会費請求書を昨年12/16に発送いたしました.
折り返しご送金をお願いいたします.
自動引落の方は,昨年12/23に引き落しとなりました(請求書ならび
に引き落し通知は省略させていただきます).
また,学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)
の方で,それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適
用します.
【割引会費請求書最終締切】2020年3月31日(火)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】地質系統・年代の日本語記述ガイドライン 2020年1月改訂版
──────────────────────────────────
国際地質科学連合(IUGS)の国際層序委員会(ICS)が,国際年代層序表の
最新版(v 2020/01)を公開しました.
・白亜系/紀の階/期の「オーテリビアン」にGSSPが定められました(2019
年12月15日).
・市原市の地層断面「千葉セクション」が下部ー中部更新統境界GSSPに承認
され,第四系/紀の階/期の中部/中期が「チバニアン」Chibanianと命名
されました(2020年1月15日).
最新版ICSチャートはこちらから,
http://www.geosociety.jp/name/content0062.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■Island Arcの新しい論文が公開されています.
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
・Geochemical constraints on the depositional environment of the 1.84
Ga Embury Lake Formation, Flin Flon Belt, Canada
Kento Motomura, et al (First Published: 2/17) ほか
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】第10回惑星地球フォトコンテスト展示会(一部会期変更)
──────────────────────────────────
第10回惑星地球フォトコンテスト入選作品展示会を下記のように予定しています.
*新型コロナウィルし感染拡大の影響を考慮し,会期が変更となりました.
日程:2020年2月9日(日) -3月1日(日)【終了しました】
場所:水戸市立博物館(茨城県水戸市大町)
http://shihaku1.hs.plala.or.jp/
日程:2020年3月25日(水)-6月28日(日)
場所:蒲郡市生命(いのち)の海科学館 (愛知県蒲郡市)
http://www.city.gamagori.lg.jp/site/kagakukan/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■2020年度関東支部幹事選出のお知らせ
支部幹事の改選に伴い,支部幹事立候補者の受付を行います.
立候補期間:2020年3月1日(日)-3月11日(水)
■2020年度総会・地質技術伝承講演会
4月11日(土)14:00-6:45
場所:北とぴあ 第2研修室(東京都北区王子1-11-1)
関東支部会員の方で総会に欠席される方は委任状をお願いします(4/10締切)
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地震本部ニュース2019冬号
調査研究レポート:防災科学技術研究所『S-netから明らかになったスロー
地震と大地震の関係』ほか
https://www.jishin.go.jp/herpnews/
(後)企画展「ゴンドワナ:岩石が語る大陸の衝突と分裂」
場所:神奈川県立生命の星・地球博物館
2月29日(土)-5月10日(日)*3/4−3/15臨時休館
http://nh.kanagawa-museum.jp/
■【開催中止】第198回深田研談話会
3月6日(金)
https://www.fgi.or.jp/
■【開催中止】日本地学オリンピック とっぷ・レクチャー
3月15日(日)
http://jeso.jp/event/lecture/2020/index.html
■ 第9回防災学術連携シンポジウム
「低頻度巨大災害を考える」
3月18日(水)12:30-17:30
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木)
https://janet-dr.com/060_event/20200317.html
■第232回地質汚染・災害イブニングセミナー
3月27日(金)18:30-20:30
場所:北とぴあ807会議室(東京都北区王子)
講師:藤川典久(気象庁地球環境・海洋部気候情報課長)
演題:水トピック 日本の降水量:これまでの変化と今後の見通しを中心に
会費:会員500円,非会員 1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
■JpGU2020年大会
5月24(日)-28日(木)
会場:幕張メッセ(千葉市美浜区)
http://www.jpgu.org/meeting_j2020/
☆日本地質学会第127年学術大会
9月9日(水)-11日(金)
会場:名古屋大学東山キャンパス
http://www.geosociety.jp/science/content0119.html(プレサイト)
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】公募情報・各賞助成情報等
─────────────────────────────────
・産総研地質調査総合センター修士型研究員(任期なし)募集(3/25)
・岡山理科大学理学部基礎理学科教員公募(5/8)
・山口大学理学部地球圏システム科学科講師または助教公募 (6/30)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】訃報:大八木規夫 名誉会員
─────────────────────────────────
大八木規夫 名誉会員(元防災科学技術研究所研究部長,財団法人深田地質研究
所元理事)が,令和2年2月27日早朝に逝去されました(87歳).
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます.
なお,葬儀については家族葬で執り行われるとのことで,参列および香典・
お花等は辞退したいとのご意向です.
会長 松田博貴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.482(臨時)訃報:石原舜三 名誉会員
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.482 2020/3/4┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 石原舜三 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
石原舜三 名誉会員(産業技術総合研究所 特別顧問)が、令和2年3月2日(月)に
逝去されました(85歳)。
これまでの故人の功績を讃えるとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
ご葬儀等は近親者で執り行なわれ、弔問・香典等は固くご辞退されるとのこと
です。また、関係者の方々により「偲ぶ会」が9月・東京で開催予定とのことです。
会長 松田博貴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.483(臨時)訃報:諏訪兼位 名誉会員
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.483 2020/3/16┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 諏訪兼位 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
諏訪兼位 名誉会員(名古屋大学名誉教授)が、令和2年3月15日(日)に
逝去されました(91歳)。
これまでの故人の功績を讃えるとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げ
ます。
ご葬儀等は下記のとおり執り行われます。
通 夜:3月16日(月)18時から
告別式:3月17日(火)10時-11時
場 所:紫雲殿 名東日進斎場
(名古屋市名東区梅森坂3-2115 電話:052-703-4441)
https://www.miwahonten.co.jp/meitonisshin-saijyou
喪 主:諏訪 佳子 様(奥様)
なお、ご葬儀は無宗教で行われ,供花,供物やご香典はご辞退されるとの
ことです。
会長 松田博貴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.484 理事および監事選挙(結果報告)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.484 2020/3/17┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】理事および監事選挙(結果報告)
【2】2020名古屋大会:トピックセッション 決定!
【3】2020年度「地質の日」行事のご案内
【4】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
【5】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】理事および監事選挙(結果報告)
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会選挙規則ならびに選挙細則に基づき,
理事および監事選挙を実施いたしました.ご報告いたします.
詳しくは、http://sub.geosociety.jp/members/content0112.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2020名古屋大会:トピックセッション 決定!
──────────────────────────────────
第127年学術大会(2020年名古屋大会)のトピックセッションが決定しました!
[セッションタイトル( )は代表世話人]
1.広域観測・微視的実験連携による沈み込み帯地震研究の新展開(木下正高)
2.海底地盤変動学のススメ(川村喜一郎)
3.スロー地震に関する地質学的・実験的・地震学的研究の連携と進展(氏家恒太郎)
4.二次改変された過去の弧-海溝系の復元:日本およびその他の例(磯崎行雄)
5.文化地質学(大友幸子)
6.災害多発社会における学術資料・標本散逸問題―大学・博物館は何をすべきか−(堀 利栄)
7.地球年代学が拓く高精度火山噴火史・発達史(上澤真平)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2020年度「地質の日」行事のご案内
──────────────────────────────────
日本地質学会および各支部等で予定されている「地質の日」行事をご案内します.
■第11回惑星地球フォトコンテスト展示会
5月19日(火)-31日(日)
場所:東京パークスギャラリー(上野グリンサロン内)(台東区上野公園)
■第11回惑星地球フォトコンテスト表彰式
5月23日(土)11:00-12:30(予定)
場所:北とぴあ 第2研修室会議室(東京都北区王子)
■街中ジオ散歩in Yokohama「身近な地形・地質から探る横浜の発展」徒歩見学会
5月16日(土)9:00-16:00 小雨決行
■近畿支部:第37回地球科学講演会
「北アルプス生成の謎−マグマと短縮テクトニクスが作り出した北アルプス−」
5月10日(日)15:00-16:30
場所:大阪市立自然史博物館 本館
今後も随時情報を追加予定です.お楽しみに!
http://www.geosociety.jp/name/content0168.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
──────────────────────────────────
学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)の方で,
それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ2020年度分の割引会費を適用します.
【割引会費請求書最終締切】2020年3月31日(火)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■地質学雑誌 126巻3月号(予告)
(論説)
三重県志摩半島の黒瀬川帯蛇紋岩中ドレライト岩塊の地球化学と
起源:内野隆之
富士山東方で1.1 ka に発生した大規模火山性斜面崩壊:山元孝広ほか
兵庫県淡路島、白亜紀泉南流紋岩類のジルコンU–Pb 及びFT 年代:
佐藤大介ほか
(ノート)
日本の現存氷河と氷河の定義・分類:吉田 勝
(報告)
草津白根火山,白根火砕丘群,弓池マールおよび逢ノ峰火砕丘の岩石学
的特徴:亀谷伸子ほか
■Island Arcの新しい論文が公開されています.
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14401738/0/ja
Vitrinite reflectance and consolidation characteristics of
the post‐middle Miocene forearc basin in central and
eastern Boso Peninsula, central Japan: implications for
basin subsidence. Nana Kamiyaet al, First published:03
March 2020
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■地学教育・アウトリーチ巡検(チバニアン周辺)
新型コロナウィルスの感染拡大防止の観点や市原市の公共施設閉鎖などの
理由により、巡検は中止致します。(2020.3.14)
■2020年度総会・地質技術伝承講演会
4月11日(土)14:00-16:45
場所:北とぴあ 第2研修室(東京都北区王子1-11-1)
※関東支部会員の方で総会に欠席される方は委任状をお願いします(4/10締切)
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)企画展「ゴンドワナ:岩石が語る大陸の衝突と分裂」
場所:神奈川県立生命の星・地球博物館
2月29日(土)-5月10日(日)*3月末まで臨時休館中
http://nh.kanagawa-museum.jp/
■ 第9回防災学術連携シンポジウム
「低頻度巨大災害を考える」
3月18日(水)12:30-17:30
(注)日本学術会議講堂からインターネット中継。来場不可。
https://janet-dr.com/060_event/20200317.html
■JpGU2020年大会
5月24(日)-28日(木)
会場:幕張メッセ(千葉市美浜区)
http://www.jpgu.org/meeting_j2020/
☆日本地質学会第127年学術大会
9月9日(水)-11日(金)
会場:名古屋大学東山キャンパス
http://www.geosociety.jp/science/content0119.html(プレサイト)
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
─────────────────────────────────
・京都大学工学研究科(応用地球物理学分野)准教授公募(5/1)
・新大学(現大阪府立大学・大阪市立大学)地球物質学分野 准教授公募(3/27)
・海洋研究開発機構超先鋭研究開発部門高知コア研究所技術支援G技術副主幹
or技術主任 公募(5/11)
・室戸ジオパーク推進協議会専門職員(専門員)募集(3/31)
・栗駒山麓ジオパーク専門員(宮城県栗原市)募集(4/8)
・栗駒山麓ジオパーク活動学術研究等奨励事業の募集(4/1-5/11)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.480(臨時)訃報:柴田 賢 名誉会員
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.480 2020/3/2┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 柴田 賢 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
柴田 賢 名誉会員(元地質調査所首席研究官/元名古屋大学年代測定資料研究
センター長)が、令和2年2月28日(金)に逝去されました(87歳)。
これまでの故人の功績を讃えるとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
なお,ご葬儀等は下記のとおり執り行われます。
通夜:3月2日(月)18時から
葬儀:3月3日(火)11時から(12時出棺)
場所:米野木愛昇殿(愛知県日進市米野木台3丁目 電話:0561-75-0004)
名鉄豊田線(地下鉄鶴舞線の東延長)米野木駅から徒歩7-8分
https://www.aishoden.jp/kaikan/komenoki.php
喪主:柴田明代 様(奥様)
〒470-0232 愛知県みよし市黒笹いずみ2丁目16-18
会長 松田博貴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.485 学術大会要旨電子化アンケート結果報告
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.485 2020/4/7┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】学術大会要旨電子化アンケート結果報告
【2】2020年度「地質の日」行事のご案内
【3】Island Arc からのお知らせ
【4】支部情報
【5】国際賞:Moore教授 追悼
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
【8】お知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】学術大会要旨電子化アンケート結果報告
──────────────────────────────────
会員の皆様に学術大会の要旨を電子化について2020年
2月末から3月末までアンケート調査を行いました。
短い期間にも関わらず100件を超える返信があり、賛成
・反対を含め貴重なご意見を頂きましたこと、感謝申
し上げます。
集計結果:賛成:93%(116人) 反対:7% (9人)
ご意見の中で、要旨電子化に対する懸念事項として特に多かったのが、
これまで使用していたJ-Stageへのアップロードがなくなる点です。
旧システム時の要旨は今後も引き続きJ-Stage上で閲覧できますが、
新システムではConfit提供のサーバー上での閲覧となります。
ネット上ではどちらも同様に検索可能ですので、当面の間は問題は
ございませんが、サーバー上の情報が今後も提供され続ける保証
もありません。学会としては、今後も継続的に過去の要旨提供が
可能な方策を講じ続けていきます。さらに皆様のご意見を、学会
の持続可能な発展と会員利便性の向上のために役立てて参ります
ので、引き続きよろしくお願い申し上げます。
<お寄せ頂いたご意見>
電子化自体は賛成だが、J-Stage登録の維持は何とかならないものでしょうか。このデメリットはきわめて大きいと思います。
電子化してもJ-STAGEに紐付け出来る様にはならないのですか?
JpGUみたいなアプリ希望
会場で今聞いている講演の要旨を見ることができればありがたいです。学会会場のwifi環境をどうするかが鍵で、大学のインフラとは別にwifi環境を構築できればなんとかなるのでは。会場に来る前にダウンロードしておけという解決策もありですが。
簡単になる分には良いのでは.気軽に投稿できる方が投稿者も増えるのでは.
電子化した場合の情報が少なすぎて、賛成か反対か判断しかねる。例)要旨は永年閲覧可能なのか。会期前とは何日前から閲覧可能なのか。会場(大学)のネット環境は十分なのか(特にwifi)。電子化をしなかった場合、どの程度大会登録費は上がるのか。など
J-Stageへのアップロードの代わりに学会HPでpdfを公開したら良い.
今の時代に合ったやり方であると思います.電子化した場合に探したい要旨にすぐ飛べるなど,扱いやすさもあると好ましいと思います.
J-Stageへの登録が出来れば,なお良いと思います.
PCの故障の場合の閲覧はどうなりますか。自分以外のものが閲覧できますか。
パソコンやタブレットでの閲覧が多いと思うので、学会場で電源コードを多く配置するなど、充電できる環境を整備してほしいです。地球化学会では電子化がはじまっていますが、会場で電源探している方が多くいました。
Google scholarなどでの検索にはヒットできるよう対応してほしい
非会員参加者が閲覧できるようにする工夫が必要。当面は現形式でのプログラムの配布も必要と思われる。
当然ながら、大会前に掲載してもらいたい。
ご検討お疲れ様です.お礼申し上げます.J-Stageから切り離すということですので,要旨のアーカイビングは担保されるのかが心配です.
論文集の方も電子化を希望します。
紙の方がパラパラとめくって要旨を眺めることができ便利
会場でWebにアクセスできない方への配慮をお願いします
電子化に基本賛成ですが、大会会場での、Wi-Fi接続環境の充実、パソコン・タブレット等の充電コンセントの十分な確保、紙を必要とする人のためのプリントアウトサービス、など、きめ細やかな対応が必要かと思います。
WEB上で継続して検索できるようにしてほしい。検索は無料に。
大きく賛成です。なるべく学会事務の仕事量軽減につながる効率化策を希望します。
J-STAGEにアップロードできないのであれば、HP上などで過去の大会の要旨を参照することは可能でしょうか。それができるようでしたら全面的に賛成いたします。他の学会業務(役員選挙など)も順次電子化できるとよいと思います。
webにつながないと講演要旨をみることができないのであれば,事前に全ページダウンロードしていく必要があるかと思います.一括ダウンロード(セッション毎ではなく)ができるといいです.また,事前ダウンロードを忘れた人のために,会場はweb接続可能な場所が必須になると思います.このような,事前・会期中のサポートがあれば,電子化をするのはよいことだと思います.ネット接続が難しい会員はネットカフェなどでもダウンロード可能なのでしょうか?
講演要旨の検索システムの操作性に関する情報の不足。スマホアプリへの対応。学術大会会場内でWiFiの環境の整備。など、利便性に関する懸念事項が払拭されれば、賛成したいと思います。
少数でしょうが、Web環境のない会員への配慮、対応策を検討願います。
一般会員・行事イン・世話人いずれにとっても、メリットがデメリットを上回ると思うため、学術大会要旨集の電子化に賛成致します。
JpGUのように検索できると非常に助かります.冊子形態だと手荷物が多くなり,混雑するセッションだと邪魔になってしまう印象です.
年大会に参加する事は 有料で要旨集を購入して情報を得る意味があります。年大会参加費には紙媒体要旨集も含まれています。もし参加費にWeb媒体要旨に含む場合は、参加者の利益が損なわれないように、一定期間アクセス制限が必要かと思います。
要旨集デジタルファイルを学会ウェブサイトからダウンロードできるようにしてください(セッション別のファイル)。USBやCDで配布するのもよいかと思います。
①デメリットに「Webに繋がないと要旨の確認ができない」とのことですが、今まで以上に多くのPCやWiFiを使うことになると思います。今後学術大会開催の各会場で、要旨閲覧のPC・WEB使用環境に問題が生じることはありませんか?
②当日参加登録者への要旨提供サービスはどのように行うのですか?PC持参を条件にするのですか?
③「Confit演題登録システムは次年度から値上げされますが,全システム利用+冊子体印刷廃止で,支出を同額に維持できます.」とありますが、値上げ前の今年度が支出を同額に維持できるのですか?では、次年度値上げしたら支出が増えるのですか?さらに将来値上げがあった場合支出はさらに増えるのですか?一方、印刷費は会員数減少に伴い今後わずかに減少していくと思われますので、Confit演題登録システム導入による支出差はさらに増えると考えてもよいですか?
④「プログラム編成作業が大幅に効率化される」とありますが、効率化された結果、費用の減少金額はどの程度になりますか?
要旨の電子化には賛成ですが、会場移動等で必要になるので、時間割と会場とセッション内容だけ書いたものを紙で配布していただけると助かります。JpGuでは、そういったものを無料配布していたと思います。
ボランティアベースではいずれ破たんする。学会HPから永続的に見られるのであれば、J-Stageである必要はない。
JpGUのようにスマートフォンのアプリで確認できるようになると便利でありがたい
省資源で効率的ですが、J-STAGEにアップロードできると尚よいと存じます。
この時代、電子化は不可避です。
他の学会でも学会誌の電子化が進んでいるが、アンケートに答える機会がなく決められると不快である。印刷経費が削減できた分を年会費の割引に繋がればよいと思いう。
所属している他学会では、日本地球化学会がシンプルに要旨集電子化をされています。
配布しているのは目次・セッションごとの要旨集・日ごとの要旨集・全体を1ファイルにまとめたもので、個人の欲しい形に応じてダウンロードできるようになっています。
他学会の形を参考に利便性の高い実装をしていただけると幸いです
プログラム編成作業や要旨集編集作業の軽減がなによりも重要と思いますので賛成です.
ファイル形式は継続して検討してください。
聴講したい講演に際し出力、持参するため、遅くとも、大会の1週間前位にはアップして貰いたい。
ほかの学会でもやっているように、web閲覧の他、CDR での配布も希望します。
行事委員は大変であると思うが要旨集は冊子版があってほしい。でないと自分の記憶にも記録にも残らない。J-stageで要旨を検索できるのも続けてほしい。学会参加
所属支部が勝手に決められてしまうのはやめた方がいい
要旨集CDを作って配るなどの付加的方策を考えてはどうか。
番号がきちんと振られて、参照できるようになっていれば冊子版を廃止しても構わない。役員の負担軽減を重視して、要旨集電子化に賛成します。
現在,産総研地質調査総合センターの図書を管理しております.これまで日本の地質学の文献を収集してきた一環として,地質学会の講演要旨集も配架させていただいておりました.今後も.産総研地質調査総合センターで収集・閲覧できる状況にしておきたいと考えています.電子化された場合,ファイルをいただき,Cdに焼くなどして産総研地質調査総合センターの図書に配架させていただきたい
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2020年度「地質の日」行事のご案内
──────────────────────────────────
日本地質学会および各支部等で予定されている「地質の日」行事をご案内します.
なお、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、多くの行事が中止、延期となっ
ています。ご注意ください。
■第11回惑星地球フォトコンテスト展示会
5月19日(火)-31日(日)
場所:東京パークスギャラリー(上野グリンサロン内)(台東区上野公園)
■第11回惑星地球フォトコンテスト表彰式【中止】
5月23日(土)
場所:北とぴあ 第2研修室会議室(東京都北区王子)
■街中ジオ散歩in Yokohama「身近な地形・地質から探る横浜の発展」
徒歩見学会【開催延期】
5月16日(土)
■近畿支部:第37回地球科学講演会【中止】
「北アルプス生成の謎−マグマと短縮テクトニクスが作り出した北アルプス−」
5月10日(日)
場所:大阪市立自然史博物館 本館
今後も随時情報を追加予定です.
http://www.geosociety.jp/name/content0168.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■Island Arcの新しい論文が公開されています.
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14401738/0/ja
100 m.y. record of volcanic arc evolution in Nicaragua
Kennet E. Flores et al;e12346 First Published: 03 April 2020
SHRIMP U–Pb ages of zircons from the Lengshuikeng ore field, North
Wuyi Mountains, South China: implications for dating volcaniclastic
rocks
Jian-Hua et al; e12347 First Published: 03 April 2020
Chert–clastic sequence in the Cretaceous Shimanto Accretionary
Complex on the central Kii Peninsula, SW Japan
Yusuke Shimura et al; e12345 | First Published: 18 March 2020
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■2020年度総会・地質技術伝承講演会→【開催延期】
東京都における新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を受け,2020
年4月11日(土)「北とぴあ」での2020年度支部総会・地質技術伝承講
演会・関東支部功労賞表彰式・懇親会は行わないこととしました.
なお支部総会は延期開催の予定で,会場・日程が決まり次第お知らせ
いたします.
■[お知らせ]2019 年度の支部功労賞について
■[お知らせ]2020-2021 年度の支部幹事選挙結果
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
[西日本支部]
■令和元 年度総会第171 回例会:講演要旨集公開しました(みなし発表)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】国際賞:Moore教授 追悼
──────────────────────────────────
付加体学の謙虚な巨人,J. Casey Moore教授を悼む(小川勇二郎)
ケイシーと呼ばれて親しまれていたカリフォルニア大学サンタクルズ校のJames Casey Moore教授が,2020年3月12日,亡くなられた.75歳だった.巨星墜つというには,あまりにも謙虚な研究者だった.モア教授(以下,ケイシーさんと呼ばさせていただく)は,1945年ロスアンジェルスで生まれ,サンタバーバラ校からプリンストン大学へ進み,学位所得後,サンタクルズ校へ移り,生涯をそこで研究教育に尽くした.世界の付加体を,DSDPのごく初期から一貫して研究し,数多くの若手研究者を育てた.この分野では,いわば巨人であったが,巨人というには似合わず,非常に謙虚で愛着のある人柄から,世界中の若手のあこがれの的であった.日本でも,ケイシーさんに薫陶を受けた研究者は数知れず,その実質的な研究とあいまって,まことに得難い「同胞」であった.謹んで哀悼の意を表したい.
ケイシーさんの研究の特徴は,海陸のフィールド観察と室内での理論,実験(土質力学的考察を含む),測定などを融合させた,総合的構造地質学であった.陸上のフィールドでは,初期のうちは,アラスカのコディアク島を選び,そこで多くの学生たちとともに調査にいそしみ,マッピングから構造解析までの研究手法を開発した.また海洋のフィールドでは,世界の海溝付加体のほとんどに足跡を印し,最近まで先頭を走り続けた一大リーダーであった.1973年に早くもDSDPのLeg 31で南海トラフと日本海に来訪し,その後も付加体学を実地の掘削研究に基づいて発展させた.直後には日本の大学で講演し,絶大な影響を与えた.ケイシーさんの初期のうちの最大の業績は,なんといっても,DSDP Leg 66でのメキシコ沖中米海溝の掘削成果に基づいて,海溝堆積物の連続的な付加として明らかにしたことである.それは海溝タービダイトの三分の一ずつが,オフスクレイピング,アンダープレイティング,およびサブダクションに割り振られるということをデータに基づいて明らかにしたことであり,まさに先駆的な概念の提案であった.その論文の載ったロンドン地質学会特別号10号は,この分野の草分け的なバイブルであり続けている.
その後,ケイシーさんは,学生や共同研究者とともに世界中の付加体を海陸から調査研究し,特にバルバドス付加体での掘削,測定の一連の研究を続け,多くの航海を成功に導いた(Leg 87A, 110, 156, 171Aなど).これらの研究では,コディアク島での陸上研究成果を海底下の現象の対応の試みに適用し,プレート沈み込み境界で行われている引きはがし断層(いわゆるデコルマンゾーン)の構造,組織,それに浸透率の発達史的な考察を行った.また,その延長にあるロギングや音波探査実験による間隙水圧とその変化の測定を行い,デコルマンゾーンでの間欠的な透水,砂岩での選択的な透水などを3次元的に明らかにした.それには,当時発展しつつあった正確なポジショニング(GPS)とあいまった3Dサイズミックプロファイリングおよび掘削時ロギング(LWD)との融合が功を奏したと言える.それらの総合的な研究を,測定の困難な現生の付加体で実施し,付加体における脱水と変形過程の総合的に解明におけるリーダーとして携わったのは,ケイシーさんの最大の業績と言える.
ケイシーさんを知る人々での間の共通した印象は,学問的には絶えず最も根本的な概念とその適用を外さなかった見通しの素晴らしさであろう.またそのための基礎的データの重要性を追求した.陸上でも掘削事業でも,ポイントを押さえた指摘と厳しくも愛情あふれた教育的な配慮をした.ここぞというときに,最大の成果を得るための努力を基礎から自ら行った.現場の一人一人に声をかけ,学生,研究者だけでなく,関わっているすべての人々への配慮を忘れなかった.ケイシーさんの元には,アメリカだけでなく,全世界から意欲的な学生が集まった.それらの若手各自に見合ったテーマを与え,それを完遂させる過程で,世界的な研究を次々と完成させ世に問うていった.彼がいるだけで周囲にはいい意味での緊張感があった.学生はそれを自らのへの自然科学観に反映させて研究にいそしんだ.そうして育った彼らは,世界中へ散らばっていった.日本においてもしかりである.バルバドスでの研究が終わった後,さらに進んだ科学技術の適用を模索し,一兵卒となって南海トラフ地震発生帯計画(NanTroSEIZE)や東北地方太平洋沖地震調査掘削(JFAST)へ参加した.ほかの参加者はケイシーさんを実質的な指導者の一人と仰いだかもしれないが,自分自身は,自然への追及を志す初心者としての気持ちを単に表したに過ぎないと考えていたようだ.一仕事が終わっても,次の発展を目指した点は,ケイシーさんの自然への愛着と,それを解明しようとする姿勢を端的に表すものだろう.我々は,このような偉大な研究者と同時代を過ごせたことに,心から感謝するとともに,彼の偉大な業績を顕彰し,さらに次のステップへ進むことができれば.それが,ケイシーさんへの最大の送ることとなることだろう.
(2020年3月19日)
カリフォルニア大学サンタクルズ校の追悼ページより
https://news.ucsc.edu/2020/03/moore-in-memoriam.html
2011年9月9日,日本地質学会第118年学術大会(水戸大会)表彰式にて.
J. Casey Moore教授は、日本地質学会国際賞を受賞され,表彰式の際に
賞金を東日本大震災のために寄付すると申し出られました.
日本地質学会国際賞受賞理由(地質学会HPより)
http://www.geosociety.jp/outline/content0103.html#kokusai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■地震本部ニュース2020春号
調査研究レポート「南海トラフ広域地震防災研究プロジェクト」ほか
https://www.jishin.go.jp/herpnews/
■第233回地質汚染・災害イブニングセミナー【中止】
4月24日(金)
http://www.npo-geopol.or.jp
■第19回重金属類・残土石処分地・廃棄物処分地診断に関わる
地質汚染調査浄化技術研修会【中止】
4月29日(水・祝)-5月2日(土)
http://www.npo-geopol.or.jp
■JpGU2020年大会【オンラインネット開催方式採用】
5月24(日)-28日(木)
会場:幕張メッセ(千葉市美浜区)
http://www.jpgu.org/meeting_j2020/
☆日本地質学会第127年学術大会
9月9日(水)-11日(金)
会場:名古屋大学東山キャンパス
http://www.geosociety.jp/science/content0119.html(プレサイト)
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
─────────────────────────────────
・千葉大学理学研究院地球科学研究部門教員公募(6/1)
・産総研研究職員公募:数値シミュレーションによる地震発生過程の研究(5/11)
・JAMSTEC付加価値情報創生部門 数理科学・先端技術研究開発センター
ポスドク研究員(4/15)
・電力中央研究所 研究員(正職員)公募(5/31)
・下仁田ジオパーク学術奨励金募集(4/25)
・土佐清水ジオパーク学術研究助成募集(4/28)
・勝山市ジオパーク学術研究等奨励事業申請者募集(6/1)
・令和2年度筑波山地域ジオパーク学術研究助成金の募集(5/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】お知らせ
─────────────────────────────────
新型コロナウィルス感染拡大の影響及び東京都の自粛要請を考慮し、
3/30以降学会事務局職員の出勤を一部控えております。
お電話での応対はできません。学会事務局へのご連絡・お問い合わ
せは、メールでお送りいただきますようお願い致します。ご迷惑
をおかけいたしますが、ご了承ください。
・庶務一般:main[at]geosociety.jp
・広報・編集:journal[at]geosociety.jp
(*[at]を@マークにしてください。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
第11回フォトコン入選(最優秀)
第11回惑星地球フォトコンテスト入選作品
最優秀賞:鷹島の奇岩
写真:佐藤悠大(福岡県)
撮影場所:長崎県 松浦市鷹島北部
【撮影者より】
鷹島は第三紀砂岩層を基礎としその上に玄武岩の溶岩台地が載っている.撮影地の北西部の海岸には玄武岩の丸い岩が並び,奥に行くと,砂岩が露出している.鉄分が酸化されることでできるオレンジ色の模様や海蝕でできたのだろうか,流線型の様な形状がとても魅力的に感じた.夕焼けをバックに海を流すためNDフィルターを使用して撮影した.
【審査委員長講評】
昨年も入選した佐藤さんの作品です。輝く夕陽と雲、色鮮やかな砂岩層、海岸に押し寄せる波しぶき。最近のカメラや画像処理ソフトには広い階調を再現できるHDR機能がついているものが多くありますが、このような構図ではカバーしきれません。NDフィルターを使った0.8秒露出で、白糸のような海の描写も秀逸です。
【地質的背景】
鷹島を作っているのは漸新世の佐世保層群鷹島層である。鷹島層は比較的厚い砂岩層と薄い泥岩層の互層からなり、海成の化石を含まず、炭層を伴う。日本海ができる前、ここには大きな川が流れていて、その川が運んだ砂が地層になったと思われる。鷹島層は上位を鮮新世後期の東松浦玄武岩類に覆われているため、海岸沿いの露頭は白い砂岩、波打ち際の転石は黒い玄武岩というコントラストをなしている。(小松原純子:産業技術総合研究所)
目次へ戻る
第11回フォトコン入選作品(優秀01)
第11回惑星地球フォトコンテスト入選作品
優秀賞:Cosmic Blue
写真:根岸桂子 (富山県)
撮影場所:和歌山県 橋杭岩
【撮影者より】
初めて橋杭岩に来て,太古の昔より侵食されてきた岩柱がそそり立つ光景は迫力がありました.朝日が昇り始め,干潟に光が写り込むのを待ちました.多くの岩を画面一杯に入れたくて,魚眼レンズを選びました.全体的に深みのある青で,宇宙をイメージしました.
【審査委員長講評】
橋杭岩は国の天然記念物にも指定され、多数の写真が撮影されています。この作品の良いところは魚眼レンズを使い、従来にない構図で橋杭岩を捉えた点です。早朝に海岸まで降り、良い撮影ポイントを探しまわり、太陽高度が良くなるまで待つ。良い写真を撮るんだという心意気が伝わってきます。
【地質的背景】
国指定名勝かつ国指定天然記念物である橋杭岩は,幅約15m,長さ約900 mにわたり橋脚のような岩塔(橋杭)が直線状に並んだものです.これは新第三紀の堆積岩である熊野層群に貫入した火成岩の岩脈です.橋杭岩周辺には多くの巨礫が散らばっています.これらの巨礫は過去の津波を記録した津波石として知られています.(南紀熊野ジオパーク推進協議会)
目次へ戻る
第11回フォトコン入選作品(優秀02)
第11回惑星地球フォトコンテスト入選作品
優秀賞:褶曲
写真:西出 琢 (千葉県)
撮影場所:イタリア ドロミテ
【撮影者より】
ドロミテの山々をトレッキング.山全体に褶曲の痕跡があり驚きました.
【審査委員長講評】
ドロミテはアルプスの南部にあり、冬はスキー、夏はトレッキングの名所となっています。私も30年ほど前に訪れましたが、このような見事な褶曲があることは知りませんでした。褶曲に斜めから光があたっているために力強い作品となっています。スケールに登山客などが入っているとさらに良かったかもしれません。
【地質的背景】
写真の地層は,イタリア北部ドロミテ山塊の炭酸塩岩プラットフォームを構成する下部ジュラ系の層状石灰岩です(Calcari Grigiとよばれます).主に暗灰色のミクライト質石灰岩からなり,ラグーンでの堆積環境が考えられています.特徴的な褶曲構造は,アルプス造山運動による低角度の衝上断層にともなって形成されたものです.(尾上哲治:九州大学)
目次へ戻る
第11回フォトコン入選作品(ジオパーク)
第11回惑星地球フォトコンテスト入選作品
ジオパーク賞:巨人のげんこつ
写真:長谷 洋 (和歌山県)
撮影場所:和歌山県 白浜町 番所山の海岸
【撮影者より】
白浜町南紀熊野ジオパークエリア内の海食アーチの片側だけを撮り,天に伸びる岩をイメージしました.まるでモデルが巨人の握り拳の上にに乗っかてるようにみえました.
【審査委員長講評】
アーチ状の地形は全体を撮りたくなりますが、片側だけを切り取って迫力のある構図としました。モデルの女性の配置や大きさも適当で良いスケールとなっています。この女性がどうやってここまで辿り着いたか、無事に戻って来られたのか、少し心配になってしまいますが……。
【地質的背景】
モデルが立っている地層は塔(とう)島(じま)礫岩層であり,新第三紀の堆積岩である田辺層群を不整合で覆っています.含まれる礫は砂岩が多く,泥岩や凝灰岩なども含まれます.白浜町にあるジオサイト「円月島」もこの地層からなります.この礫岩層が見られる海岸には波食棚が広がり,多くの磯の生き物を観察することが出来ます.(南紀熊野ジオパーク推進協議会)
目次へ戻る
第11回フォトコン入選作品(会長賞)
第11回惑星地球フォトコンテスト入選作品
日本地質学会会長賞 :迷子石
写真:川又基人 (東京都)
撮影場所:南極 東南極パッダ島(昭和基地から南西80km)
【撮影者より/地質的背景】
日本の南極観測基地である昭和基地から約80 km離れたパッダ島で撮影した一枚.南極大陸には氷に覆われず,地表が露出する露岩が存在する.露岩には過去の氷床後退時にその場に残される迷子石が存在する.その中で一見現代アートのようにも感じられる迷子石を撮影した.片麻岩からなる迷子石は氷床後退後の風化により赤茶けた色に変色しており,空の青さ,氷の大陸と相まって余計にその存在を際立たせ,南極氷床の壮大な変動の歴史を感じさせてくれた.
【審査委員長講評】
南極は氷河に覆われた大陸ですが、この作品のように岩石が露出している場所もあります。現在では南極も観光で行くこともできますが、行けるのはごく一部。この作品のような場所は、研究者だけが近づくことを許された場所です。赤茶色の大地と迷子石、白く眩い氷床、青空とすっきりした画面構成で魅力的な作品になっています。
目次へ戻る
第11回フォトコン入選作品(ジオ鉄賞)
第11回惑星地球フォトコンテスト入選作品
ジオ鉄賞:滝上を走る列車
写真:細谷正夫 (茨城県)
撮影場所:栃木県那須烏山市滝,龍門の滝,JR烏山線(滝-烏山間)
【撮影者より】
新第三紀の地層を削る龍門の滝の上を走るJR烏山線の列車
【ジオ鉄委員会講評/解説】
栃木県高根沢町と那須烏山市を結ぶJR烏山線(愛称「からせん」).その名も滝駅の近くに「龍門の滝」はあります.那珂川支流の江川にかかる高さ12mの滝で,写真は凝灰岩と凝灰角礫岩の互層からなる急崖露頭の陰影を効果的に写り込ませ,列車との高度差をうまく捉えています.駆け抜ける列車は2両編成の蓄電池駆動電車「ACCUM(アキュム)」です.烏山線は那珂川流域の大地を学ぶ「那須烏山ジオパーク構想」エリアにあり,沿線の見どころが豊富な路線.地図を片手に「からせん」のジオポイント探索に出掛けたくなりました.(深田研ジオ鉄普及委員会 藤田勝代)
【参考】
吉田美佳・池田 宏(1999):栃木県烏山町,龍門の滝の成因について,筑波大学水理実験センター報告,no.24,73-79.
那須烏山ジオパーク構想 http://nasukara-geo.jp/index.html
目次へ戻る
第11回フォトコン入選作品(スマホ賞)
第11回惑星地球フォトコンテスト入選作品
スマホ賞:風と波の合作
写真:加藤聡一郎 (愛知県)
撮影場所:台湾 野柳公園
【撮影者より】
台湾北部の野柳公園の風化によってできた奇岩を小山の上から撮影しました.この場所がいかに奇妙で,面白いかが一目でわかる写真だと思います.また,この奇岩の中の1つはクイーンズヘッドと呼ばれており,まるで女王が冠を被った頭のような形をしています.しかし何年風化が進み後3年もすればその女王の首が折れてしまうとも言われており,今しか見ることのできない光景となっています.
【審査委員長講評】
台湾北部の野柳地質公園を撮影した作品です。本コンテストでも過去に何点もの応募がありますが、いずれもキノコ岩をクローズアップしたものでした。本作品では、それらとは異なりやや遠くから撮影もので、地質構造や公園のようすがよくわかります。手前の樹木や草を整理して撮影すれば、すっきりした作品になったと思います。
【地質的背景】
台湾北部の東海岸にある中新世(約2000万年前:N5-N4) 大寮層という浅海性の厚い砂岩層からなる。大寮層には、有孔虫、貝化石、ウニ化石など豊富に含まれており、多くの炭酸塩ノジュールを含む。これらの砂岩層や頁岩層の侵食地形により様々な形態のモニュメントが有名であるが、この構図から、それらがある地層に沿って一列に並んで分布することがよくわかる。野柳は地質公園となっている。地層を写すため草をかき分けて頑張った雰囲気がよく出ている。 http://www.ylgeopark.org.tw/JPN/info/YlIntroduction_jp.aspx (清川昌一:九州大学)
目次へ戻る
第11回フォトコン入選作品(入選01)
第11回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:混成の美
写真:辻森 樹 (宮城県)
撮影場所:ロシア 露カレリア共和国
【撮影者より/地質的背景】
露カレリア共和国の見事なミグマタイト(混成岩)の露頭写真です.巡検中に撮影しました.太古代の大陸地殻の部分溶融の現場がそのまま固まった白(優白部)と黒(優黒部)がはっきりした大露頭は美しく,教育的です.驚くべき事に,この露頭はも含め,この地域いったいは古原生代の大陸衝突でエクロジャイト相の深さまで沈み込んでおり,優黒部の一部には角閃岩化を免れたエクロジャイトが残っています.
【審査委員長講評】
よく調査されている、あるいは話題となっている地層や岩体を案内人が解説してくれるのが巡検で、地質を深く理解するのに役立ちます。特に海外の巡検では、1人では簡単に行けない場所まで案内してくれることもあるので助かります。巡検では限られた時間で撮影しなければなりませんが、辻森さんはそのチャンスを見事にものにされました。
目次へ戻る
第11回フォトコン入選作品(入選02)
第11回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:活火山のある暮らし
写真:迫 勇 (鹿児島県)
撮影場所:鹿児島県 垂水市海潟の高台
【撮影者より】
2019年11月12日23時07分,南岳山頂火口噴火により赤く染まる桜島です.しばらく活動がおとなしめでしたが,この頃,噴火が活発化しており,チャンスを伺っていました.突如訪れたその瞬間は全身鳥肌もの.自然の脅威と美しさを同時に感じた瞬間でした.とはいえ,これは日常の光景.この瞬間も麓では車が走っていました.大噴火が心配されてはいますが,火山と共生する桜島の暮らしを今後も撮っていきたいと思います.
【審査委員長講評】
桜島は、2010年〜2015年は南岳昭和火口からの噴火が盛んでしたが、現在は南岳山頂からの噴火が続いています。何日も通っても運が良くなければこのような噴火には出会いません。この撮影地点からは望遠レンズで噴火のみを捉えがちですが、作者は噴火とともにそこに住む人々の暮らしを写し込む着眼点が良かった。
【地質学的背景】
噴火で放出された火山弾が,桜島の8合目付近まで赤く染めています.昼は黒く見える火山弾も実は赤熱するくらい高温なのです.桜島では「噴火警戒レベル3」が続いていて,南岳山頂火口と昭和火口から2km以内の区域への立ち入りができません.現在の規模の噴火が続く限り,大きな噴火災害は起こらないと思いますが,桜島大正噴火(1914年)規模になると,桜島島内だけでなく周辺市町村でも注意が必要になります.(井村隆介:鹿児島市大学)
目次へ戻る
第11回フォトコン入選作品(入選03)
第11回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:Chocolate Box
写真:長谷川裕二 (長崎県)
撮影場所:長崎県 佐世保市白浜海岸
【撮影者より】
「九十九島」は長崎県北西部,北松浦半島の西岸に散在する208の島からなる小島群です.島の密度は日本一.また,日本で18番目に指定を受けた「外洋性多島海景観」を特色とする国立公園です.島々は主に砂岩でできており,砂が長い年月の間に高い圧力と高い温度で固まったものです.今回見つけた砂岩はまさに「チョコレートボックス」のように,チョコレート形の部分と仕切りの部分で成り立っています.おそらく波が影響して削り出されたと思われますが,どうしてこのような複雑な形になったのかは全く想像することができません.
【審査委員長講評】
九十九島(くじゅうくしま)は西海国立公園にある多島海で、作者はチョコレートボックスのような地層の形に注目しました。3点の組写真で応募されましたが、似たような構図なので1点のみの応募にすべきでした。レンズを絞り込んで、被写界深度を広くしたほうが良かったかもしれません。
【地質的背景】
長崎県の九十九島は南北2地域にわかれており、北は北九十九島、南は南九十九島と呼ばれている。北九十九島は前期〜中期中新世の野島層群、南九十九島はそれよりも下位の相浦層群からなる島々である。どちらも主に白色砂岩と暗灰色泥岩の互層からなり、海岸沿いに露出する砂岩には塩類風化(岩石表面に塩の結晶が析出する際、結晶が成長する圧力で岩石の表面を破壊する作用)によって形成されるタフォニと呼ばれるへこみが目立つ。枠に入ったチョコまんじゅうのようなこのふしぎな形状も塩類風化が原因の可能性がある。(小松原純子:産業技術総合研究所)
目次へ戻る
第11回フォトコン入選作品(入選04)
第11回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選(中高生) :幸(さち)を育む海と大地と,そして空
写真:奥野由寿 (長崎県)
撮影場所:長崎県五島市岐宿町岐宿 城岳展望所
【撮影者より】
長崎県の五島市岐宿にある城岳展望所から望む溶岩台地は約74万年前に流れ出た玄武岩の熔岩でできており,その後風化作用により土壌が形成され,広大な畑地となりました.周辺の凹凸の熔岩海岸では,魚介類や海藻類がよく取れ,イイダコとりを行う格好の場所です.太古の昔の火山活動が海や里の恵みを育む環境を作ってくれて,現在の私たちの生活を支えてくれています.五島産の米,野菜,肉,魚介類はとっても美味しいです.
【審査委員長講評】
地元の高校生がスマホで撮影した作品です。力強い作品ばかりを見ているとくたびれてしまいますが、その中でこのようなのんびりした作品を見るとほっとします。解説文からも郷土愛が感じられ、ほのぼのとします。遠くに見える島や海に写った雲も良いアクセントになっています。
【地質的背景】
撮影者は高校生ですが、地質についてのコメントも勉強した上で撮影しており、ジオパークを目指す地元の普及活動が感じ取れる作品です。五島列島の福江島は、島中央部は中新世の五島層群からなる地質帯で山地を作っているが、南北地域は第四紀の玄武岩が日本海形成時の正断層沿いに噴出しており、平野が広がっている。撮影場所は五島層群の切り立った展望台から見たもので、左中央に見える2つの小島は砂岩泥岩の地層が垂直に立った五島層群からなり、その古い地形を避けるように溶岩が流れていた様子がよくわかります。(清川昌一:九州大学)
目次へ戻る
第11回フォトコン入選作品(入選05)
第11回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選(中高生):ゴジラの爪
写真:田邊はるか (大阪府)
撮影場所:高知県 室戸岬先端 灌頂ケ浜(室戸ジオパーク)
【撮影者より】
特に見えるのは室戸岬の灯台です.室戸の大地の大部分は氷河期時代の終わりに太平洋の深海で堆積した層でできています.海岸からせり出す崖と広がるシマシマの地層.これらはプレートの動きで大地が隆起して作られました.中央にある横長の大きな岩はカレントリップルで,波の化石とも言われ,タービダイト層の所々に見られます.このような海底の痕跡により,ここがかつて海だったことがわかります.まるでゴジラの爪のようです.
【審査委員長講評】
室戸はユネスコ世界ジオパークにも指定され、展示やジオツアーなども充実しており、日本列島の成り立ちを学ぶのに適した場所です。タイトルを見てびっくりしましたが、解説文を読むとしっかりと地層のでき方を理解された上でつけられたタイトルなので安心しました。
【地質的背景】
室戸岬にみられる縞々の地層は,土砂が深海底に運ばれ堆積したタービダイトと呼ばれる地層です.海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込むときに,海底の表層部にあったタービダイトは剥ぎ取られて大陸の縁に付加し,付加体が形作られます.付加体が作られる過程で、もともと水平だった地層は,折れ曲がったり,垂直に立ったりしてしまいます.地震により隆起する室戸岬では,海の中から付加体が顔を出し,新しい大地が誕生している場所になります.地質学的には室戸岬のタービダイトは四万十帯南帯に属し、およそ漸新世―中新世の年代を持つ最も新しい時代の付加体にあたります。背景にある山は隆起量が大きいところで出来る海成段丘で,その段丘面から白い灯台が室戸の人々を100年以上も見守っています.(高橋 唯:室戸ジオパーク推進協議会)
目次へ戻る
第11回_佳作1-3
第11回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:ウェブロック
写真:原澤 宏(埼玉県)
撮影場所:オーストラリア パースから東方約350km
【撮影者より】
パースからエスペランスにダイビングに行く途中、休憩に立ち寄ったのがこのウェーブロック。高さ15m、長さ100mの波のような造形美は圧巻。特に岩肌の模様は大自然が作り上げたアートそのものである。
目次へ戻る
佳作:芥屋の柱状節理
写真:小松原純子(茨城県)
撮影場所:福岡県糸島市志摩芥屋沖
【撮影者より】
糸島半島には白亜紀の花崗閃緑岩が広く分布しているが、それを貫入もしくは被覆して鮮新世のアルカリ玄武岩が点在する。これらアルカリ玄武岩の岩体は浸食に強いため岬や丘陵の頂部を形成している。この露頭はそのような岬を遊覧船で海側から見たもので、一部は海食洞になっており芥屋の大門(けやのおおと)と呼ばれている。全体に柱状節理が発達する。
目次へ戻る
佳作:白いコウモリ
写真:島村直幸(福岡県)
撮影場所:山口県美祢市秋芳洞
【撮影者より】
鍾乳洞の奇景「傘づくし」です。天上からぶら下がるコウモリの群れのように見えました。
目次へ戻る
第11回_佳作4-6
第11回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:人々の営みを支える、息づく大地
写真:八田章光(高知県)
撮影場所:フランス コルシカ島南端の都市ボニファシオの沖合より
【撮影者より】
会議で訪れたコルシカ島のボニファシオ。エクスカーションのボートトリップで、今にも崩壊が起こりそうな、ボニファシオの先端を目の当たりにし、壮大な景色に驚きであった。実際に崩壊した一部も見られた。
目次へ戻る
佳作:滝雲
写真:三浦 光(大分県)
撮影場所:熊本県 阿蘇市山田大観峰
【撮影者より】
阿蘇の外輪山から流れ落ちる濃霧の様子です。夜のうちは外輪山の上に溜まってた濃霧が、日に出の時間になると一斉に流れ落ち始めました。自然の壮大さと力強さは感動するしかなかったです。
目次へ戻る
佳作:湖底出現
写真:都筑和雄(愛知県)
撮影場所:愛知県 新城市宇連ダム
【撮影者より】
36年ぶりに宇連ダムが枯渇しました。初めて見るダムの底に何とも言えない気持ちになりました。禁止されている湖底に降りて散策する人たちもいましたが、そういう気持ちにはなりませんでした。
目次へ戻る
第11回_佳作7-9
第11回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:巨大エイリアン
写真:長谷 洋(和歌山県)
撮影場所:和歌山県 東牟婁郡古座川町相瀬 一枚岩
【撮影者より】
南紀熊野ジオパークジオサイトの一枚岩です。紅葉、雨上がり後の岩に反射する白い筋、無風時の水面のリフレクション、予期せぬカヌー。全てが合わさった瞬間でした。岩と紅葉のリフレクションは、巨大なエイリアンのようにも見えました。
目次へ戻る
佳作:波の舞
写真:伊藤修二(茨城県)
撮影場所:千葉県 屏風ヶ浦
【撮影者より】
屏風ヶ浦には一箇所だけ消波堤の設置されていない場所があり、波が直接海食崖に達します。そこでは入射波と反射波が複雑に干渉するため、いろいろな面白い波形が発生し、水理実験場のような場所になっています。
目次へ戻る
佳作:竜串海岸
写真:加藤昭七(奈良県)
撮影場所:高知県土佐清水市竜串海岸
【撮影者より】
砂岩と泥岩の地層が生み出した奇岩風景
目次へ戻る
第11回_佳作10-12
第11回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:御輿来海岸の砂紋
写真:松浦 寛(福岡県)
撮影場所:熊本県宇土市 御輿来(おこしき)海岸
【撮影者より】
御輿来海岸は、干満の差が日本一大きい有明海にあり、潮が引いた海岸の砂地には風と波による曲線の砂紋が現れます。雲仙の頂に沈む夕日が砂紋を照らし、美しい光景が広がっていました。
目次へ戻る
佳作:断崖絶壁の絶景
写真:藤田文子(滋賀県)
撮影場所:兵庫県豊岡市赤石 玄武洞
【撮影者より】
目の前に立つとそのスケールの大きさに圧倒されます。自然が創り出した大地の息吹とパワーを感じられる素晴らしい空間です。 いつまでも保ってほしいですね!
目次へ戻る
佳作:断崖絶壁
写真:野波和音(東京都)
撮影場所:アメリカ、グランドキャニオン、リムトレイル付近
【撮影者より】
人生で一度でいいからグランドキャニオンを見たくてアメリカへ弾丸ツアーに行きました。想像していた以上に壮大な風景で見えるところすべて、地平線の先まで全てが赤茶色のグラデーションの砂岩の地層で本当に感動しました。 まるで太古の昔にタイムトリップしたような感覚に襲われずっと眺めていました。 ふと横を見たら断崖絶壁に座る人たちを発見して夢中で撮りました。 少しでもグランドキャニオンの壮大さが伝わればと思います。
目次へ戻る
第11回_佳作13
第11回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:異国情緒
写真:永井 秀和(千葉県)
撮影場所:千葉県 御宿町大波月海岸
【撮影者より】
潮が引いた時でしか通れない岩のトンネル。真っ暗いトンネルの中からとても千葉県とは思えない岩礁風景を切り撮りました。
目次へ戻る
【geo-Flash】No.486(臨時)新型コロナウィルス感染拡大防止に関する学会の対応
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.486 2020/4/13 ┬┴┬┴ <*)++<< ┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 新型コロナウィルス感染拡大防止に関する学会の対応 2020年4月13日
──────────────────────────────────
会員・関係者 各位
新型コロナウイルスが,我が国においても都市部を中心に急速に拡
大しはじめました.政府も感染拡大防止のため,7都府県に「緊急事
態宣言」を発出しました.外出自粛,在宅勤務要請,大学閉鎖や博物
館・図書館の休館など,会員の活動にも様々な影響が出てきています.
日本地質学会では,政府の要請に基づき,事務局では原則テレワー
クを実施し,問い合わせ等についてはメールのみでの対応としてい
ます.また委員会等の会議についても,当面,原則としてWeb会議で
行い,各支部の行事においても状況に応じた対応をお願いしており
ます.皆様にはご不便をおかけしますが,ご理解の程,よろしくお
願いいたします.
なお今後の活動の在り方については,社会状況を注視しつつ慎重に
判断していく予定です.5月23日開催予定の総会については,現在,
WEBを用いた形式での開催を検討しております.また,9月9〜11日に
名古屋大学で開催予定の第127年学術大会は開催の方向で準備してお
ります.詳細は,News誌4月号に掲載いたしますが,最終的な開催判
断は7月末頃の新型コロナウイルスの感染状況を考慮して判断する予
定です.
これら情報は,適宜,ホームページ,geo-Flash等でご連絡してまい
ります.あわせてよろしくお願いいたします.
私たち一人ひとりの慎重な行動が新型コロナウイルス感染拡大を防
ぎ,会員や家族,地域や職場の安全を守り,ひいては地質学会の日常
の活動に戻ることにつながります.くれぐれも感染しないよう,させ
ないようにご注意を払われることを切にお願いします.
(一社)日本地質学会
会長 松田 博貴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.487 おうちでも楽しめる!地質のデジタルコンテンツ
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.487 2020/4/21┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2020年度「地質の日」行事のご案内(特設ウェブサイト開設!)
【2】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【3】支部情報
【4】その他のお知らせ
【5】公募情報・各賞助成情報等
【6】学会事務局からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2020年度「地質の日」行事のご案内(特設ウェブサイト開設!)
──────────────────────────────────
コロナウィルスの影響で多くの行事が中止となっています。そこで、自宅で地質を
楽しんで学べる「地質の日」特設ウェブサイトが開設されました。
あつまれ!地質を楽しむデジタルコンテンツ:
https://www.gsj.jp/geologyday/2020/homestudy.html
********************************************************
日本地質学会および各支部等で予定されている「地質の日」行事をご案内します.
「中止」「延期」となった行事が多くあります.HPで情報をご確認ください.
■第11回惑星地球フォトコンテスト展示会
5月19日(火)-31日(日)
場所:東京パークスギャラリー(上野グリンサロン内)(台東区上野公園)
■第11回惑星地球フォトコンテスト表彰式【中止】
5月23日(土)
場所:北とぴあ 第2研修室会議室(東京都北区王子)
■街中ジオ散歩in Yokohama「身近な地形・地質から探る横浜の発展」
徒歩見学会【開催延期】
5月16日(土)
■近畿支部:第37回地球科学講演会【中止】
「北アルプス生成の謎−マグマと短縮テクトニクスが作り出した北アルプス−」
5月10日(日)
場所:大阪市立自然史博物館 本館
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/name/content0168.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■[お詫び]地質学雑誌の発行遅延
第126巻第4号(2020年4月号)はまもなく校了予定ですが、コロナウィルス
感染拡大防止のための自粛、在宅勤務の影響により編集作業が遅れ、雑誌
の発送は5月8日頃となる予定です.皆様のお手元には例年より1週間〜10
日ほど遅れての到着となる見込みです.論文著者はじめ会員の皆様には,ご
迷惑をおかけし大変申し訳ございません.何卒ご了承下さい.
【126巻4月号】
(論説)A new cane rat (Rodentia, Thryonomyidae) from the Upper
Miocene Nakali Formation, northern Kenya. Yoshiki Tanabe et al 計5編
最新号目次はこちら
http://www.geosociety.jp/publication/content0092.html
【早期公開】
受理論文の印刷前に,Accepted ManuscriptとしてPDFファイルを作成し,
順次WEBサイトで公開しています. https://sub.geosociety.jp/user.php
(注意:会員ページへのログインが必要です)
■Island Arcの新しい論文が公開されています.
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14401738/0/ja
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■2020年度支部総会開催(書面会議)のお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から,書面会議(以下,
書面総会)によって開催します.書面総会に参加される方は,議
決権行使書または委任状の提出をお願いします(5/23締切).
議決権行使書または委任状の提出をもって書面総会に参加したも
のとみなします.
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■JpGU2020年大会【オンラインネット開催方式採用】
7月12日(日)-16日(木)*開催日程が延期になりました*
会場:幕張メッセ(千葉市美浜区)
http://www.jpgu.org/meeting_j2020/
☆日本地質学会第127年学術大会
9月9日(水)-11日(金)
会場:名古屋大学東山キャンパス
http://www.geosociety.jp/science/content0119.html(プレサイト)
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】公募情報・各賞助成情報等
─────────────────────────────────
・産総研テニュアトラック型(任期付)orパーマネント型研究員(任期無)公募(5/11)
・第11回日本学術振興会育志賞受賞候補者の推薦(学会締切5/18)
・2021年〜2022年開催藤原セミナーの募集(学会締切7/3)
・山田科学振興財団国際学術集会開催助成(2023年度開催予定の集会)(21/2/28)
・令和2年度 伊豆半島ジオパーク学術研究助成
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】学会事務局からのお知らせ
─────────────────────────────────
新型コロナウィルス感染拡大の影響及び東京都の自粛要請を考慮し、学会事務局は
原則テレワークを実施しております。お電話での応対はできません。学会事務局へ
のご連絡・お問い合わせは、メールでお送りいただきますようお願い致します。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承ください。
・庶務一般:main[at]geosociety.jp
・広報・編集:journal[at]geosociety.jp
*[at]を@マークにしてください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.488 防災学術連携体「感染症と自然災害の複合災害に備えて下さい」
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.488 2020/5/7┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】日本地質学会2020年度(第12回)総会開催
【2】2020年度「地質の日」行事のご案内(デジタルコンテンツもあるよ!)
【3】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【4】防災学術連携体:緊急メッセージ
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
【8】学会事務局からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】日本地質学会2020年度(第12回)総会開催
──────────────────────────────────
2020年度(第12回)の代議員総会を開催いたします。
今回は、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、WEB会議形式にて開催
いたします。代議員の皆様には別途メールで、開催のお知らせを送信しました。
欠席される代議員は、必ず「委任状」or「議決権行使書」をご提出下さい。
日時:2020年5月23日(土) 14:00-15:30
総会議事次第はこちら、http://www.geosociety.jp/outline/content0152.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2020年度「地質の日」行事のご案内(特設ウェブサイト開設!)
──────────────────────────────────
コロナウィルスの影響で多くの行事が中止となっています。そこで、自宅で
地質を楽しんで学べる「地質の日」特設ウェブサイトが開設されました。
「あつまれ!地質を楽しむデジタルコンテンツ」
https://www.gsj.jp/geologyday/2020/homestudy.html
*****************************************************
日本地質学会および各支部等で予定されている「地質の日」行事は多くが、
「中止」「延期」となっています.HPで情報をご確認ください.
詳しくは、http://www.geosociety.jp/name/content0168.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■[お詫び]地質学雑誌の発行遅延
新型コロナウィルス感染拡大防止のための自粛、在宅勤務の影響により編集
作業が遅れ、4月号の発送は5月8日頃となる予定です.皆様のお手元には通常
より1週間〜10日ほど遅れての到着となる見込みです.論文著者はじめ会員の
皆様には,ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません.何卒ご了承下さい.
【126巻4月号】
(論説)A new cane rat (Rodentia, Thryonomyidae) from the Upper Miocene
Nakali Formation, northern Kenya. Yoshiki Tanabe et al 計5編
最新号目次はこちら
http://www.geosociety.jp/publication/content0092.html
【早期公開】
受理論文の印刷前に,Accepted ManuscriptとしてPDFファイルを作成し,
順次WEBサイトで公開しています. https://sub.geosociety.jp/user.php
(注意:会員ページへのログインが必要です)
■Island Arcの新しい論文が公開されています.
Younging zircon fission‐track ages from 13 to 2 Ma in the eastern extension
of the Kathmandu nappe and underlying Lesser Himalayan sediments dis-
tributed to the south of Mt. Everest
Toru Nakajima et al., First Published: 22 April 2020 ほか
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14401738/0/ja
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】防災学術連携体:緊急メッセージ
──────────────────────────────────
「市民への緊急メッセージ 感染症と自然災害の複合災害に備えて下さい」
(2020年5月1日)
(防災学術連携体 幹事会)
新型コロナウィルスの感染について予断を許さない状況が続いています。
この感染症への対策を進めつつ、自然災害の発生による複合災害にも警戒
が必要です。本格的な雨季を迎える前に、災害時の心構えを市民の皆様に
お伝えいたします。
全文はこちらから、http://www.geosociety.jp/news/n151.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■2020年度支部総会開催(書面会議)のお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から,書面会議(以下,書面総会)
によって開催します.書面総会に参加される方は,議決権行使書または委任
状の提出をお願いします(5/23締切).議決権行使書または委任状の提出を
もって書面総会に参加したものとみなします.
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■JpGU2020年大会【オンラインネット開催方式採用】
7月12日(日)-16日(木)
**開催日程・開催が変更になりました**
http://www.jpgu.org/meeting_j2020/
■日本学術会議主催学術フォーラム
メディアが促す人と科学の調和ーコロナ収束後の公共圏を考えるー
7月16日(木)13:00-17:00
場所:日本学術会議講堂※オンライン開催に変更の場合あり
定員250名(先着)(参加費無料・要事前申込)
http://www.scj.go.jp/ja/event/2020/288-s-0716.html
☆日本地質学会第127年学術大会
9月9日(水)-11日(金)
会場:名古屋大学東山キャンパス
http://www.geosociety.jp/science/content0119.html(プレサイト)
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
─────────────────────────────────
・関西学院大学生命環境学部環境応用化学科(仮称)教員公募 (7/31)
・福井県職員選考採用試験(地球科学学芸員)(5/20)
・糸魚川ジオパーク学術研究奨励事業募集(5/22)
・湯沢市ゆざわジオパーク学術研究等奨励補助金募集(5/25)
・東大地震研・大型計算機共同利用公募研究公募(5/22)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】学会事務局からのお知らせ
─────────────────────────────────
新型コロナウィルス感染拡大防止及び緊急事態宣言による自粛要請を考慮し、
学会事務局は現在も原則テレワークを実施しております。
お電話での応対はできません。学会事務局へのご連絡・お問い合わせは、
メールでお送りいただきますようお願い致します。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承ください。
・庶務一般:main[at]geosociety.jp
・広報・編集:journal[at]geosociety.jp *[at]を@マークにしてください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.490 (臨時)名古屋大会の開催中止(延期)と代替企画
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.490 2020/5/25┬┴┬┴ <*)++<<┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 名古屋大会の開催中止(延期)と代替企画について 2020年5月25日
──────────────────────────────────
会員の皆様もご存知の通り,本年2月以降日本においても新型コロナウ
イルスの蔓延が急速に進み,学会のみならず社会全体の活動縮小を余儀な
くされました.いわゆる3密回避のため,学校や会社ではテレワークが推
進され,主要な学会も学術大会をウエッブ形式で開かざるを得なくなって
います.その中にあって,松田前会長をはじめ前執行理事会は,4月下旬
から5月の上旬にかけ,断続的に執行理事会をウエッブ会議として実施し,
状況の推移を見極めるとともに対応策を検討してきました.一方で,9月
に実施予定の名古屋大学における第127年学術大会(以下,名古屋大会)
については,開催校である名古屋大学を中心とした現地実行委員会(LOC)
の皆様が準備を進めて来られました.
しかし,5月の連休あけに至っても状況が急速に改善・復帰する様子は
認められず,会員の皆様に9月に名古屋大会を開催する場合の詳細な事項
をお伝えするタイミングが近づいてきました.
学術大会の開催に関しては,運営規則第14条に基づいて,年1回開催
することになっており,また年会の日程,開催場所は理事会が決めること
になっております.コロナウイルスのワクチンや治療薬のめどがたってお
らず,さらに第2波・第3波感染の危惧ありという現状を見る限り,9月
に1000人規模の学術大会を開くことは,参加される会員の皆様方の安
全確保が厳しいと5月中頃の執行理事会で判断するに至りました。それを
受けて当該執行理事会は2020年第1回理事会において状況を報告し,
第127年学術大会及びそれに付随して行われる行事と共に1年延期する
旨および学術大会に替わる行事を行うことを提案し,理事会の判断を仰ぎ
ました.
5月23日に開かれた2020年第1回理事会(ウエッブ会議)におい
て,この提案について議論された結果,名古屋大会の本年9月の現地開催
は中止し,来年度の同時期まで延期することが決議されました.LOCのこ
れまでのご努力に感謝するとともに,来年度実施に向けて捲土重来の努力
をお願いすることになりました.つきましては,来年度の学術大会開催を
準備されていた関東支部LOCにも,延期をお願いすることになりました.
ただし,名古屋大会で予定していた行事のうち,本年度の各賞授与式に
ついては, 下記の通り9月9日前後(本来の開催日)にウエッブ上で実施す
ることとします.また,新たな企画を計画・検討中ですが,
詳細は改めてご報告します。取り急ぎ,ここでは概要だけお知らせします.
1)例年行っている表彰については, 大規模集会を避けるため,
オンライン方式で執り行います。当初の大会予定日であった2020年9月9日
前後に配信の予定をしています。5月23日の総会で以下の受賞者が報告され
(総会報告参照:ニュース誌掲載予定)。各受賞講演ならびに受賞
コメントはビデオ録画していただいたものを一括配信する予定です。
地質学会賞・受賞講演(山路 敦氏)
Island Arc賞・受賞講演(J. Wakabayashi氏)
地質学会論文賞・受賞講演(星 博幸氏)
地質学会奨励賞・受賞コメント(菊川照英氏,羽地俊樹氏)
学会表彰・受賞コメント(浜島書店,鹿野和彦氏ほか)
名誉会員・コメント(西村祐二郎氏,小松正幸氏)
新規50年会員顕彰者33名:1行コメント(文字のみ学会HPに掲示)
2)表彰式とは別に以下の企画を検討中です。従来の企画の継続の他に,
新規の試みとして「地質学会ショートコース」をスタートさせたいと考え
ています。これらについての詳細は改めて御報告いたします。
A: ショートコース(新規)(Zoom利用;パスワード設定で有料配信)
基礎的科目について時間限定で配信, 希望者は参加費を払って受講,半日
程度.受講時間に応じてCPDを付与。
B: 各支部における学術発表会の充実
C: JABEE関係の資料の刊行と配信
「大学教育大学統合期における地学教育の継続を模索する」資料の刊行
D: 日本地質学会ジュニアセッション(小さなEarth Scientistの集い)
電子ポスターとして継続
E: 若手会員のための地質関連企業の研究サポート
地質系のキャリア情報誌を刊行
日本地質学会会長 磯粼 行雄
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真を募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.489 おうちでも!「地質の日」デジタルコンテンツ
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.489 2020/5/19┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2020年度「地質の日」行事のご案内(デジタルコンテンツもあるよ!)
【2】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【3】支部情報
【4】その他のお知らせ
【5】公募情報・各賞助成情報等
【6】学会事務局からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2020年度「地質の日」行事のご案内(特設ウェブサイト開設!)
──────────────────────────────────
コロナウィルスの影響で多くの行事が中止となっています。そこで、自宅で
地質を楽しんで学べる「地質の日」特設ウェブサイトが開設されました。
「あつまれ!地質を楽しむデジタルコンテンツ」
https://www.gsj.jp/geologyday/2020/homestudy.html
*****************************************************
日本地質学会および各支部等で予定されている「地質の日」行事は多くが、
「中止」「延期」となっています.HPで情報をご確認ください.
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/name/content0168.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■地質学雑誌 126巻5月号(予告)
(論説)
九州北部福岡県筑豊炭田の始新統直方層群下部のジルコン
U–Pb 年代:宮田和周ほか
田沢湖カルデラとその噴出物:鹿野和彦ほか
北海道北部,幌延地域の新第三系〜第四系に挟在するテフラ
のジルコンU–Pb およびフィッション・トラック年代:丹羽
正和ほか
(報告)
新潟県に分布する7 枚の第四紀テフラのLA-ICP-MS による
ジルコンU–Pb年代:伊藤久敏ほか
■Island Arcの新しい論文が公開されています.
Sedimentary and geochemical characterization of Middle–Late Miocene formations
in the Neogene Tsugaru Basin, Japan by means of DTH27‐1 well sediment analysis
Paolo Martizzi Shun Chiyonobu Hiroyuki Arato
First Published: 16 May 2020 ほか
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14401738/0/ja
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
■2020年度支部総会開催(書面会議)のお知らせ​
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から,書面会議(以下,書面総会)
によって開催します.書面総会に参加される方は,議決権行使書または委任状
の提出をお願いします(5/23締切).議決権行使書または委任状の提出を
もって書面総会に参加したものとみなします.
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
■日本学術会議主催学術フォーラム
「Covid-19とオープンサイエンス」
6月3日(水)10:30-16:00
インターネット公開(要・事前申し込み)
http://www.scj.go.jp/ja/event/2020/287-s-0603.html
■地質学史懇話会→【中止】
6月20日(土)
場所:北とぴあ8階805会議室
矢島道子:『地質学者ナウマン伝』を上梓して
加藤碵一:日本列島成立史あれこれ
問い合わせ先:矢島 pxi02070[at]nifty.com
(後)第57回アイソトープ・放射線研究発表会→【中止】
7月7日(火)-9日(木)
会場:東京大学
https://www.jrias.or.jp/
■JpGU2020年大会【オンラインネット開催方式採用】
7月12日(日)-16日(木)
**開催日程・開催が変更になりました**
http://www.jpgu.org/meeting_j2020/
■国際ゴンドワナ研究連合(IAGR)2020年総会及び
第17回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム→【中止】
8月30日-9月1日 会議とシンポジウム
9月2日-7日 巡検
場所:ノボシビルスク(ロシア)
iagr2020@igm.nsc.ru & inna@igm.nsc.ru
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】公募情報・各賞助成情報等
─────────────────────────────────
・京都大学大学院人間・環境学研究科相関環境学専攻助教公募(7/20)
・第15回「科学の芽」賞募集(8/17−9/19)
・第11回日本学術振興会育志賞受賞候補者の推薦*締切延長(学会締切6/15)
・伊豆半島ユネスコ世界ジオパーク専任研究員(常勤)の公募(7/1)
・令和2年度阿蘇ジオパーク助成研究の公募(6/19)
・糸魚川ジオパーク学術研究奨励事業募集(5/22)*延長の可能性あり
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】学会事務局からのお知らせ
─────────────────────────────────
新型コロナウィルス感染拡大防止及び緊急事態宣言による自粛要請を考慮し、
学会事務局は現在も原則テレワークを実施しております。
学会事務局へのご連絡・お問い合わせは、メールでお送りいただきますよう
お願い致します。ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承ください。
・庶務一般:main[at]geosociety.jp
・広報・編集:journal[at]geosociety.jp *[at]を@マークにしてください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.491
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.491 2020/6/2┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【2】取材協力(情報提供)
【3】その他のお知らせ
【4】公募情報・各賞助成情報等
【5】学会事務局からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■地質学雑誌 126巻5月号(まもなく発送です)
(論説)
九州北部福岡県筑豊炭田の始新統直方層群下部のジルコン
U–Pb 年代:宮田和周ほか
田沢湖カルデラとその噴出物:鹿野和彦ほか
北海道北部,幌延地域の新第三系〜第四系に挟在するテフラ
のジルコンU–Pb およびフィッション・トラック年代:丹羽正和ほか
(報告)
新潟県に分布する7 枚の第四紀テフラのLA-ICP-MS による
ジルコンU–Pb年代:伊藤久敏ほか
■Island Arcの新しい論文等が公開されています.
・2020 Island Arc Awardの紹介 ほか
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】取材協力(情報提供)
──────────────────────────────────
NHKの番組制作会社より取材協力依頼です.
「学者がこっそり見せてくれた!『私だけが持っているスゴ動画祭(仮)』」
の制作会社が様々な学問領域から、スゴイ研究映像を捜しています.
関心のある方は事務局にご連絡下さい.当会社の企画書および連絡先をお送り
します.学会組織ではなく個人としての取材協力になることをご了承下さい.
事務局 *[at]を@マークにしてください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
日本学術会議主催学術フォーラム
「Covid-19とオープンサイエンス」
6月3日(水)10:30-16:00
インターネット公開(要・事前申し込み)
http://www.scj.go.jp/ja/event/2020/287-s-0603.html
JpGU2020年大会【オンラインネット開催方式採用】
7月12日(日)-16日(木)
**開催日程・開催が変更になりました**
http://www.jpgu.org/meeting_j2020/
(後)科学教育研究協議会第68回全国大会
[中止・2021年夏に延期]
8月1日-3日
https://kakyokyo.org/
(協)テクノオーシャン2020
テーマ:~海で会いましょう~ ーMeet at Ocean-
10月1日(木)-3日(土)
会場:神戸国際展示場
https://www.techno-ocean.com/
第10回防災学術連携シンポジウム・日本学術会議公開シンポジウム
10月3日(土)-4日(日)
会場:広島国際会議場・屋外展示スペース
https://janet-dr.com/index.html
(後)藤原ナチュラルヒストリー振興財団
設立40周年記念 公開シンポジウム
「海と地球の自然史−変わりゆく海洋環境から
海洋プラスチックごみまで地球の問題を考える−」
10月10日(土)13:30-16:30
場所:東北福祉大学仙台駅東口キャンパス
http://fujiwara-nh.or.jp/
(協)第36回ゼオライト研究発表会
11月19日(木)-20 日(金)
場所:富山国際会議場
https://jza-online.org/events
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】公募情報・各賞助成情報等
─────────────────────────────────
・新潟大学災害・復興科学研究所教授公募(7/27)
・2020年度「第41回猿橋賞」受賞候補者の推薦(11/30)(注)学会推薦:11/6締切
・[JST]輝く女性研究者賞(ジュン アシダ賞)募集(6/30)
・室戸ジオパーク学術研究助成2020年度募集(6/16)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】学会事務局からのお知らせ
─────────────────────────────────
学会事務局は、6月以降も出勤日数や人数を調整しながらテレワークを実施し
ております。
学会事務局へのご連絡・お問い合わせは、できるだけメールでお送りいただ
きますようお願い致します。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
・庶務一般:main[at]geosociety.jp
・広報・編集:journal[at]geosociety.jp *[at]を@マークにしてください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.493 新会長・新執行理事挨拶
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.493 2020/6/16┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】会長就任挨拶/新執行理事挨拶
【2】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【3】2020年度会費督促請求について
【4】大学院生のみなさま:アンケート協力依頼
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
【7】学会事務局からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】会長就任挨拶/新執行理事挨拶
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会
会長 磯崎行雄
(注)「崎」の正しい表記は、「大」→「立」
2020年5月から2年間代表理事(会長)を務めることになりました.微力ながら,
日本地質学会の発展のために最善をつくす覚悟でおります.取り急ぎ,短くご
挨拶させていただきます.
全文はこちらから、、、
http://www.geosociety.jp/outline/content0137.html
新執行理事挨拶はこちらから、、、
http://www.geosociety.jp/outline/content0105.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■地質学雑誌 126巻6月号(予告)
(論説)
栃木県北部,余笹川岩屑なだれ堆積物の層序・年代と運搬過程:
菊地瑛彦・長谷川 健
ローム台地のS波速度構造と地盤震動特性:栃木県宇都宮地域を例に:
中澤 努ほか
(報告)
浜松市北区滝沢町の秩父累帯滝沢石灰岩体から産出した三畳紀後期
(カーニアン後期〜ノーリアン前期)コノドント:鈴木和博ほか
長崎県野母半島樺島花崗岩産ジルコンのU–Pb 年代:長田充弘ほか
■Island Arcの新しい論文等が公開されています.
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14401738/0/ja
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2020年度会費督促請求について
──────────────────────────────────
1.督促請求のための自動引き落とし日は6月23日(火)です.
2020年度会費が未入金のかたで,1月から5月上旬までの間に自動引落の
手続きをされたかたは6月23日に引き落としがかかります.
引き落とし不備にならぬよう,残高の確認をお願いします.
2.郵便振替用紙によるお振り込みの方には,6月9日(火)に督促請求書
(郵便振替用紙)を郵送しました.お手元に届きましたら,早急にご送金
くださいますようお願いいたします.
※7月上旬頃までに入金確認が取れない場合には,7月号の雑誌から送本
停止となります.定期的に雑誌をお受け取りになりたい方は,お早めに
ご送金くださいますよう,よろしくお願いいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】大学院生のみなさま:アンケート協力依頼
──────────────────────────────────
全国大学院生協議会(全院協)が行なう、全国の大学院生を対象
としたアンケート調査の依頼がありましたので、お知らせします。
今年度の調査については、新型コロナウィルス感染拡大が大学院
生の研究・生活に与える影響が多大かつ中長期にわたることをふま
え、例年の調査項目に加えてコロナ関連の項目を設けました。より
多くの方々に回答いただき、調査の精度を高め、問題を広く社会に
発信していくことが求められております。大学構内への入構禁止や
通常授業のオンラインによる代替という状況に鑑み、WEBアンケー
トでの回答をお願いします。各研究室、専攻内でも多くの方が回答
いただければ調査の精度が高まることになります。本調査へのご協
力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
【アンケート回答フォームURL】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVDp5Nqhz4iIWY_sS5s4W5Zg1zNZX0qR8lae91PXYXKAotbA/viewform
【アンケート回答期限】2020年8月31日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
JpGU2020年大会【オンライン大会】
7月12日(日)-16日(木)
http://www.jpgu.org/meeting_j2020/
第37回歴史地震研究会(伊賀大会)
9月26日(土)-29日(火)
場所:ハイトピア伊賀(三重県伊賀市)
http://www.histeq.jp/kenkyukai.html
(協)テクノオーシャン2020
テーマ:海で会いましょう ーMeet at Ocean-
10月1日(木)-3日(土)
会場:神戸国際展示場
https://www.techno-ocean.com/
第10回防災学術連携シンポジウム・日本学術会議公開シンポジウム
10月3日(土)-4日(日)
会場:広島国際会議場・屋外展示スペース
https://janet-dr.com/index.html
(後)藤原ナチュラルヒストリー振興財団
設立40周年記念 公開シンポジウム
「海と地球の自然史−変わりゆく海洋環境から
海洋プラスチックごみまで地球の問題を考える−」
10月10日(土)13:30-16:30
場所:東北福祉大学仙台駅東口キャンパス
http://fujiwara-nh.or.jp/
(協)第36回ゼオライト研究発表会
11月19日(木)-20 日(金)
場所:富山国際会議場
https://jza-online.org/events
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募情報・各賞助成情報等
─────────────────────────────────
・広島大学技術職員(薄片制作ほか)募集(6/23)
・JAMSTEC Young Research Fellow 2021公募(5名)(7/28)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】学会事務局からのお知らせ
─────────────────────────────────
学会事務局は、6月以降も出勤日数や人数を調整しながらテレワークを実施し
ております。営業時間は通常通り、電話対応も再開しておりますが、事務局へ
のご連絡・お問い合わせは、できるだけメールでお送りいただけると幸いです。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。
・庶務一般:main[at]geosociety.jp
・広報・編集:journal[at]geosociety.jp *[at]を@マークにしてください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.492(臨時) 鈴木堯士 名誉会員 ご逝去
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.492 2020/6/4 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 鈴木堯士 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
鈴木堯士 名誉会員(高知大学名誉教授)が、令和2年6月1日(月)に
逝去されました(86歳)。
これまでの故人の功績を讃えるとともに、謹んでご冥福をお祈り申し
上げます。なお、ご葬儀等は近親者で執り行なわれ、供花・香典等は
ご辞退されるとのことです。
会長 磯崎 行雄
(注)「崎」の正しい表記は、「大」→「立」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
昇仙峡は黒富士が造った?(前編)
昇仙峡は黒富士が造った?:「地質図Navi」と「地理院地図」で楽しむ四次元の旅(前編)
正会員 高山信紀
まえがき
本記事は,山梨県甲府市北部に位置する昇仙峡,野猿谷, 大滝と仙娥滝(図-1,図-2)の成り立ちについてのアイデア とそれに基づいて机上で検討した内容を述べたものである. 検討は,産総研地質調査総合センターウェブサイト「地質 図Navi」,国土地理院ウェブサイト「地理院地図」と書籍 やインターネットで公開されている文献により行った.
昇仙峡は,花崗岩の中を富士川水系荒川が流下し,仙娥滝 など美しい渓谷で国の特別名勝に指定されている.昇仙峡上 流の荒川本流にはV字谷の野猿谷が,荒川支流の板敷渓谷に は高さ約30mの大滝がある.また,昇仙峡の北には,黒富士 火山の溶岩円頂丘の一つである黒富士(標高1,633m)があ る.黒富士火山は,デイサイト質の火山で,約100万年前〜 約50万年前(更新世カラブリアン〜チバニアン)に活動し, 周辺には多量の火砕流堆積物が分布している 1),2),3),4) .周辺の地質概要を図-1に示す.
図-1 周辺地質概要
図-2 現在の荒川と
黒富士火砕流前の「旧荒川」
(注)画像をクリックすると大きな画面でご覧いただけます。
1. 検討のきっかけ
(1)巡検と黒富士登山
2018年6月,筆者(地形,地質に 興味を持つ元土木技術者)は,日本地質学会中部支部の地 質巡検「南部フォッサマグナ北縁地域の変動地質」(案内 者;山梨大学の福地龍郎氏) 5) に参加した.韮崎岩屑流の 台地から釜無川の穴山橋(図-1)に下りる途中の崖に白い 堆積物があった(写真-1).同行の方に伺ったところ,「こ れは黒富士の軽石である.黒富士という名前はある所から 眺めると富士山の傍らに黒い富士のように見えることから 名付けられたようだ.」と教えて頂いた.軽石の白と名前の 黒のコントラストが心に残り,行ってみたいと強く思った.
2019年5月,友人達と1泊2日の行程で黒富士に登った.初 日は,甲府駅からバスで昇仙峡に行き,徒歩で昇仙峡(写 真-2),荒川ダム,大滝(写真-3),野猿谷を遡り,燕岩(黒 富士を中心とする放射状岩脈のうちの一つで国の天然記念 物)を見学し,近くのマウントピア黒平に宿泊した.翌日, 黒富士峠に登り,雪が残る八ヶ岳,北アルプス,南アルプ スの山々,白く輝く富士山とその傍らの黒富士(写真-4) を眺め,黒富士に登頂した.その後,亀沢川に沿って下り, 草鹿沢沿いを上り,峠を経て金桜神社を参拝し,御岳川に 沿って昇仙峡に戻った(図-1).
写真1 韮崎岩屑流(白い層の上)と黒富士の軽石(白い層)
写真2 昇仙峡
写真3 大滝
写真4 黒富士峠からの黒富士と
富士山
(注)画像をクリックすると大きな画面でご覧いただけます。
(2)昇仙峡形成のアイデア
黒富士登山から戻り,「地質 図Navi」を使って5万分の1地質図「御岳昇仙峡」 2) で黒富 士火砕流の分布を確認している時,水ヶ森火山岩の窪平泥 流堆積物(図-1,図-2のMm)が板敷渓谷上流,荒川ダム下 流,御岳川上流,草鹿沢,亀沢川に分布していることに気 づいた.一般に,泥流は河川に沿って流下すると考え,当 時の荒川は御岳川から草鹿沢,亀沢川に流れていたが,黒 富士火砕流で堰き止められて昇仙峡に流れを変えたのでは ないかとのアイデアが浮かんだ.
(3)野猿谷形成の友人のアイデア
このアイデアを一緒に 黒富士に登った友人に伝えた数日後,返信のメールが来た. 「荒川上流で目を引く地形は野猿谷の峡谷です.その斜面は 両岸共に45〜50°と急で,谷の断面は典型的なV字を成してい ます.この峡谷は,ある事件の結果荒川が流路をここに定め て激しく下刻して出来た可能性があります.その事件は黒富 士火砕流です.この火砕流により黒平付近から猫坂の西方に 流れていた旧荒川が猫坂付近で堰き止められ,現在の野猿谷 にあった鞍部から水があふれ出したと考えました.」(図-2).
筆者は漠然と野猿谷は黒富士火砕流以前から存在してい たと思っていたので,このアイデアは目から鱗であった. 黒富士火砕流前の荒川を「旧荒川」,板敷渓谷から旧荒川に 合流していた河川を「旧板敷川」と記す(図-2).
(4)層雲峡にて
2019年7月,上記のメールを受けた翌週, 筆者は,大雪山国立公園の黒岳に登った後,層雲峡ビジタ ーセンターを訪れた.そこで,約3万年前,御鉢平カルデラ の火砕流が石狩川を堰き止め巨大な湖ができ,まもなく湖 水があふれ出して侵食により層雲峡が形成されたことを知 った(北海道上川振興局ウェブサイト「大雪ものしり百科: 自然編 大雪山の歴史」).黒富士火砕流による「旧荒川」堰 き止めのアイデアと同じようなことが層雲峡で起こってい たのだ!北海道の旅から戻り,このアイデアが成り立つか 検討を始めた.主な検討内容を以下に述べる.
2. 検討内容
図-3 「旧荒川」の横断面(想像)
図-4 鞍部の断面
(注)画像をクリックすると大きな画面でご覧いただけます。
(1)昇仙峡の形成
昇仙峡の形成を以下のように考えた. 水ヶ森北部にあった山体が崩壊し泥流となって板敷渓谷か ら駆け下りた.当時は昇仙峡は無く,泥流は,花崗岩山体 に行く手を阻まれて一部は山体を駆け上がり,当時の河川 (「旧板敷川」)に沿って現在の御岳川から草鹿沢,亀沢川へ 流下し,その周辺に堆積した(窪平泥流堆積物).その後, 黒富士火砕流が「旧荒川」を堰き止め,花崗岩山体が流れ を阻み昇仙峡上流に堰止湖が生じた.まもなく(数年程度) 花崗岩山体の鞍部から湖水があふれ出し,花崗岩の侵食が 促進され,縦方向の割れ目に沿って岩が崩落して昇仙峡の 峡谷が形成され,荒川の流路変更が起こった.池田は,尖 峰の形成に,花崗岩の性質のうち,とくに割れ目の間隔が 重要な影響を与える 6) と述べている.(図-2)
三村らは,「黒富士火砕流堆積物は大きく5層に分けられ, 各層相互の間には火山活動の休止期を明瞭に指示する湖沼 堆積物が挟在する」 2) ,「最初の活動を示す火砕流堆積物は 1.0Ma,そして山頂の溶岩円頂丘群は0.5Maである.この間 に大規模な火砕流の流出時期は時間間隙を挟んで5回を数え る.したがって,黒富士火山における規模の大きな火砕流 の流出は,単純に計算すると約10万年毎に繰り返されたこ とになる.」 3) と述べている.以下,黒富士第1期火砕流〜 第5期火砕流を「K1火砕流」〜「K5火砕流」と記す.
地形図と5万分の1地質図「御岳昇仙峡」によれば,御岳 川と草鹿沢の間は標高約900m以上の尾根で,「K3火砕流」 が広く分布し,峠(図-2,標高約910m)より北では「K2火 砕流」が標高約920mまで分布している.堰き止め箇所の横 断図(想像)を図-3①に示す(なお,「旧荒川」のルートと 縦断面は(3)に後述する).「旧板敷川」の堰き止めは「K2 火砕流」による可能性が高く,遅くとも約80万年前の「K3 火砕流」により確実に行われたと推定した.
堰き止められた水があふれだした花崗岩山体の鞍部は, 現在の荒川の流路付近で,その標高は約900m以下と考えた. 現在,標高900m以上の箇所は,峡谷の右岸では羅漢寺山 (標高1,058m)周辺だけであり,その対岸にも標高900m以上の尾根があるので,鞍部はこれらの間にあったと推定し た(図-2,図-4(a)).現在の河床には仙娥滝(河床標高約 670m,「地理院地図」の断面図機能を使用)があり,下刻 量は最大約230mとなる.
(2)野猿谷の形成
(1)で述べた昇仙峡と似たことが野猿 谷周辺でも起こった.猫坂(標高約1,130m)付近は黒富士 から四万十層群山体につながる標高1,100m以上の尾根(最 低標高は約1,110m)で,「K3火砕流」などが分布するほか, 局所的ではあるが最低標高あたりには「K2火砕流」が分布 している(図-2,図-3②).これより,猫坂付近における 「旧荒川」の堰き止めも,昇仙峡と同様,約90万年前の「K2 火砕流」による可能性が高く,約80万年前の「K3火砕流」 では確実であると考えた.
堰き止められた水があふれだした四万十層群山体の鞍部 は,標高約1,100m以下で,現在の野猿谷左右岸の高所を結 ぶ箇所にあったと考えた(図-2,図-4(b)).現在,そこは 標高約830mの河床となっており,下刻量は最大で約270m となる.ところで,野猿谷の中間部に大きい屈曲がある (図-2).何故屈曲しているのだろう?局所的な地質の違い かもしれないが,野猿谷が出来る前に四万十層群山体の鞍 部をはさんで北に下る沢と南に下る沢が平面的に少しずれ て存在していたが,鞍部が侵食・下刻されて両方の沢がつ ながり屈曲部となったと想像した.
野猿谷のV字谷はどのようにして出来たのだろうか?文献7)を基に以下のように考えた.四万十層群山体の侵食に 対する抵抗性が強く,かつ左右岸ほぼ同じで,また,四万 十層群の走向傾斜 2) が左右岸の一方が受盤,他方が流れ盤 という状態ではない.このため,下刻に伴い左右岸対称の V字谷となった. (後編へ続く)
参考文献
1) 三村弘二(1967)黒富士火山の火山層序学的研究, 地球 科学 21巻3号
2) 三村弘二・加藤祐三・片田正人(1978)5万分の1地質 図幅「御岳昇仙峡地域の地質」, 地質調査所
3) 三村弘二・柴田賢・内海茂(1994)黒富士火山と甲府盆 地北方に分布する火山岩類の火山活動とK-Ar年代, 岩 鉱
4) 尾崎正紀他(2002)20万分の1地質図幅「甲府」, 産 業技術総合研究所地質調査センター
5) 福地龍朗,鈴木俊(2018) 2018年中部支部年会・シンポ ジウム・地質巡検報告, 日本地質学会News Vol.21 No.8 支部コーナー
6) 池田 碩(1998)花崗岩地形の世界p126, 古今書院
7) 小口 高(2015)東アジアの山地におけるV字谷の地形 学的特徴と形成要因の研究, 科学研究費助成事業研究 成果報告書
後編では,「旧荒川」,「旧板敷川」のルートと縦断 面,大滝,仙娥滝の成り立ちについて述べる.後編はこちらから
(2020.7.31掲載)
【geo-Flash】No.494 令和2年7月 熊本県南部の豪雨災害に関する情報
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.494 2020/7/7┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】令和2年7月 熊本県南部の豪雨災害に関する情報
【2】2020年度会費の納入について
【3】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【4】2021年度地震火山地質こどもサマースクール開催地公募結果
【5】JpGUダイバーシティ推進委員会緊急アンケートのお願い
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】令和2年7月 熊本県南部の豪雨災害に関する情報
──────────────────────────────────
・2020年7月4日に豪雨災害が発生した球磨川流域の地形・地質(産総研)
・令和2年7月3日からの大雨に関する防災科研クライシスレスポンスサイト(防災科研)
・2020年7月豪雨に伴う熊本県南部における災害調査速報(第1報)(熊本大学)
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/hazard/content0098.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2020年度会費の納入について
──────────────────────────────────
1.督促請求のための6月23日に引き落としを致しました.
2020年度会費が未入金のかたで,1月から5月上旬までの間に自動引落の
手続きをされたかたは6月23日に引き落としを致しました.
2.郵便振替用紙によるお振り込みの方には,6月9日(火)に督促請求書
(郵便振替用紙)を郵送しました.急ぎご送金くださいますようお願いい
たします.
※入金確認が取れない場合には,7月号の雑誌から送本停止となります.
定期的に雑誌をお受け取りになりたい方は,急ぎご送金くださいますよう,
よろしくお願いいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■地質学雑誌 126巻7月号(予告)
(2021年・名古屋大会巡検案内書)
・名古屋城石垣に使われている石材の岩石種:西本昌司
・舟伏山地域の美濃帯海洋性岩石の層序と年代:佐野弘好・山縣 毅
・中新統師崎層群の球状炭酸塩コンクリーションと深海性動物群化石:村宮悠介ほか
・紀伊半島中央部の四万十帯と三波川帯の地質トラバース:志村侑亮ほか
■Island Arcの新しい論文等が公開されています.
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14401738/0/ja
U–Pb ages of granitoids around the Kofu basin: Implications for
the Neogene geotectonic evolution of the South Fossa Magna
region, central Japan
Yusuke Sawaki et al, e12361 First Published: 01 July 2020 ほか
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2021年度地震火山地質こどもサマースクール開催地公募結果
──────────────────────────────────
2021年度地震火山地質こどもサマースクールの開催地を公募しました
が応募がありませんでした。地震火山地質こどもサマースクール連合企
画委員会にて対応を検討してきましたが、2020年度の地震火山地質こ
どもサマースクールは来年度に延期することになったため、2021年度の
開催地の公募は採択無しと決しました。
http://www.geosociety.jp/name/content0169.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】JpGUダイバーシティ推進委員会緊急アンケートのお願い
──────────────────────────────────
「COVID-19感染拡大による地球惑星科学者の研究および働き方
(ワークライフバランス)への影響調査」への協力のお願い
*****************************************************
COVID-19感染拡大の影響により,教育機関や研究所など多くの職場が
閉鎖しました.それに伴いテレワークや遠隔授業が実施されるようになり,
学会や研究集会なども中止あるいは WEB開催になるなど,我々の研究教
育活動が大きく変革しました.収入の減少や予想外の出費など生活面へ
の直接的な影響に加え,働き方やワークライフバランスなどに対する考え
方も大きく変わってきています.
JpGUダイバーシティ推進委員会では,多様な背景を持つ会員の皆様に
COVID-19の感染拡大による影響の実態を調査させていただくことにし
ました.集計の結果は,7月12-16日のJpGU-AGU2020: Virtualでの公
表を予定しています.
【回答期日】2020年7月9日(木)
【日本語サイト】
https://forms.gle/oAxQuMAsGygsdLJL9
【英語サイト】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeSUg6-7VXo-RPMRdxxdBknYNm7LZMySds6CYEMRmUJWYlkA/viewform
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
JpGU2020年大会【オンライン大会】
7月12日(日)-16日(木)
学部生は参加費用無料(院生会員割引料金:7700円)です。
旅費もかかりませんので,この機会にJpGU大会をぜひ体験
してください。Virtualの特徴を活かし、地球惑星科学の広がり
を,少しでも楽しんでいただければと思います.
http://www.jpgu.org/meeting_j2020v/
第232回地質汚染・災害イブニングセミナー
7月31日(金)18:30-20:30
場所:北とぴあ902会議室(東京都北区王子)
講師:藤川典久(気象庁地球環境・海洋部気候情報課長)
演題:「水トピック 日本の降水量:これまでの変化と
今後の見通しを中心に」
定員:24名(事前申込制・先着順)
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
(協)テクノオーシャン2020
テーマ:海で会いましょう ?Meet at Ocean-
10月1日(木)-3日(土)
会場:神戸国際展示場
https://www.techno-ocean.com/
ぼうさいこくたい2020
頻発化する大規模災害に備える
−「みんなで減災」助け合いをひろげんさい−
10月3日(土)-4日(日)
会場:広島国際会議場
http://bosai-kokutai.jp/
(後)藤原ナチュラルヒストリー振興財団
設立40周年記念 公開シンポジウム**中止・2021年に延期**
「海と地球の自然史−変わりゆく海洋環境から
海洋プラスチックごみまで地球の問題を考える−」
10月10日(土)
場所:東北福祉大学仙台駅東口キャンパス
http://fujiwara-nh.or.jp/
日本地震学会2020年度秋季大会[オンライン開催]
10月29日(木)-31日(土)
https://www.zisin.or.jp/
(協)第36回ゼオライト研究発表会
11月19日(木)-20 日(金)
場所:富山国際会議場
https://jza-online.org/events
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
─────────────────────────────────
・桜島・錦江湾ジオパーク学術推進員(会計年度任用職員)の募集(7/22)
・令和2年度下北ジオパーク研究助成(7/22)
・第42回(令和2年度)沖縄研究奨励賞推薦応募(9/30)(注)学会締切9/4
・日本アイソトープ協会奨励賞候補者募集(10/30)
・第61回東レ科学技術賞および東レ科学技術研究助成の候補者推薦(10/9)
(注)学会締切9/25
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.495 災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
件名:【geo-Flash】No.495 災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.495 2020/7/21┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
【2】令和2年7月豪雨災害等地質災害緊急調査について
【3】令和2年7月豪雨災害に関する情報
【4】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【5】大学院生を対象にしたアンケート調査(全院協)
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
──────────────────────────────────
この度の豪雨災害で被害を受けられた皆様に,心よりお見舞い申し上げます.
日本地質学会では,災害救助法適用地域で被災された会員の方々のご窮状を
ふまえ,申請により会費を免除いたします.「日本地質学会に届出の住居
または勤務地が災害救助法適用地域に該当する会員のうち,希望する方」は
2020年度もしくは2021年度会費を免除いたします.
適用を希望される会員は,1. 会員氏名,2. 被災地,3. 被災状況(簡潔に)を
添えて学会事務局にお申し出下さい(郵送,FAX,e-mail、電話いずれでも可).
http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html#saigai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】令和2年7月豪雨災害等地質災害緊急調査について
──────────────────────────────────
地質災害の原因究明は将来の減災につながる重要な活動です.既に現地調査を開始
もしくは検討している会員の皆様もおられると思います.調査にかかる会員の皆様
の安全,そして調査の情報共有のためにも,緊急調査を計画されておられる方は地
質学会事務局にご連絡をお願いいたします.被災地では救命および行方不明者の捜
索活動も行われておりますので,被災地への配慮を引き続きお願いいたします.ま
た、現状COVID-19の感染拡大防止に対してもくれぐれもご配慮いただきますよう
お願い致します.
地質災害緊急調査について
http://www.geosociety.jp/hazard/content0024.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】令和2年7月豪雨災害に関する情報
──────────────────────────────────
・防災学術連携体「令和2年7月豪雨の緊急集会」7/15開催
(各発表の動画が公開されています) ほか
詳しくは、http://www.geosociety.jp/hazard/content0098.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■地質学雑誌 126巻7月号(予告)(2021年・名古屋大会巡検案内書)
・名古屋城石垣に使われている石材の岩石種:西本昌司
・舟伏山地域の美濃帯海洋性岩石の層序と年代:佐野弘好・山縣 毅
・中新統師崎層群の球状炭酸塩コンクリーションと深海性動物群化石:村宮悠介ほか
・紀伊半島中央部の四万十帯と三波川帯の地質トラバース:志村侑亮ほか
■Island Arc
新しい論文等が公開されています.
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14401738/0/ja
・U–Pb ages of granitoids around the Kofu basin: Implications for the
Neogene geotectonic evolution of the South Fossa Magna region, central Japan
Yusuke Sawakiet al e12361 | First Published: 01 July 2020 ほか
Island Arcでは著者制作のVideo Abstractの掲載が可能です.
例:https://bcove.video/2DvAdgw
Glimpses of oceanic lithosphere of the Challenger Deep forearc segment in
the southernmost Marianas: The 143°E transect, 5800-4200 m
Robert J. Stern, et al e12359
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】大学院生を対象にしたアンケート調査:全国大学院生協議会(全院協)
──────────────────────────────────
本調査は、全院協が、全国各大学の加盟院生協議会・自治会の協
力の下に実施する、全国規模のアンケート調査です。本調査は、大
学院生の研究及び生活実態を客観的に把握し、もってその向上に
資する目的で行うものです。
全院協では2004年度以来毎年、アンケート調査を行っており、今
年で16回目を迎えます。調査結果は「報告書」としてまとめており、
こうした調査結果をもとに関連省庁、国会議員及び主要政党等に
対して、学費値下げや奨学金の拡充などの要請を行っております。
・大学院生の奨学金借入「500万円以上」が25%(朝日新聞2014/11/27朝刊)
・全国大学院生協議会まとめ 大学院生、6割が経済不安(毎日新聞2014/
12/1/朝刊)
・大学院生 バイトで研究に支障(NHK生活情報ブログ2012/11/30)
www.nhk.or.jp/seikatsu-blog/800/139365.html
学費・奨学金等の重大な問題が存在するにも関わらず、大学院生
の実態に関する全国的な調査は、全院協以外では行なわれており
ません。より多くの方々に回答いただき、調査の精度を高め、問題を
広く社会に発信していくことの意義は今日一層高まっていると考え
ます。ぜひご協力いただきますよう、お願い申し上げます。
【アンケート回答フォームURL】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVDp5Nqhz4iIWY_sS5s4W5Zg1zNZX0qR8lae91PXYXKAotbA/viewform
【回答期限】2020年8月31日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
第232回地質汚染・災害イブニングセミナー
7月31日(金)18:30-20:30
場所:北とぴあ902会議室(東京都北区王子)
講師:藤川典久(気象庁地球環境・海洋部気候情報課長)
演題:「水トピック 日本の降水量:これまでの変化と
今後の見通しを中心に」
定員:24名(事前申込制・先着順)
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
(後)旭町学術資料展示館企画展示
「ジオパークの微化石展」
8月1日(土)-9月6日(日)
会場: 新潟大学旭町学術資料展示館(新潟市中央区旭町通)
http://www.lib.niigata-u.ac.jp/tenjikan/
2020年度第1回(初心者向け)地質調査研修【参加者募集中】
9月28日(月)-10月2日(金)
室内座学:茨城県つくば市(産総研)
野外研修:茨城県ひたちなか市、福島県いわき市
定員 6名(最小催行人数:4名)(定員になり次第締切)
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2020-1.html
(協)テクノオーシャン2020
テーマ:海で会いましょう ーMeet at Ocean-
[開催延期]
https://www.techno-ocean.com/
ぼうさいこくたい2020
頻発化する大規模災害に備える
−「みんなで減災」助け合いをひろげんさい−
10月3日(土)[オンライン大会]
http://bosai-kokutai.jp/
2020年度第2回(経験者向け)地質調査研修【参加者募集中】
10月26日(月)-30日(金)
場所:島根県出雲市長尾鼻周辺(小伊津海岸)
定員:6名(定員になり次第締切)
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2020-2.html
(後)藤原ナチュラルヒストリー振興財団
設立40周年記念 公開シンポジウム
「海と地球の自然史−変わりゆく海洋環境から
海洋プラスチックごみまで地球の問題を考える−」
[開催中止]
http://fujiwara-nh.or.jp/
日本地震学会2020年度秋季大会
[オンライン大会]
10月29日(木)-31日(土)
https://www.zisin.or.jp/
(協)第36回ゼオライト研究発表会
11月19日(木)-20 日(金)
場所:富山国際会議場
https://jza-online.org/events
地質学史懇話会
12月25日(金)13:30より
会場:北とぴあ 701号室(東京都北区王子)
志岐常正:戦後京大地質学教室史ーその虚像と実像
矢島道子:「地質学者ナウマン伝」を上梓して
問い合わせ先:矢島 pxi02070[at]nifty.com
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
─────────────────────────────────
・茨城大学理工学研究科理学野フィールドサイエンス准教授(9/30)
・神奈川県温泉地学研究所地球化学分野(火山・温泉等)研究職公募(8/28)
・JAMSTEC海域地震火山部門火山・地球内部研究C地球内部物質循環研究G
ポストドクトラル研究員公募(8/7)
・「朝日賞」候補者推薦依頼(8/25)(注)学会締切8/3
・東京大学地震研究所2020年度大型計算機共同利用公募研究(7/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.496 令和2年7月豪雨災害についての会長談話
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.496 2020/8/4┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】令和2年7月豪雨災害についての会長談話
【2】令和2年7月豪雨災害等地質災害関連情報
【3】名古屋大会代替企画
【4】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【5】トピック:昇仙峡は黒富士が造った?(前編)
【6】大学院生を対象にしたアンケート調査:全国大学院生協議会(全院協)
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】訃報 高柳洋吉 名誉会員 ご逝去
【10】訃報 斎藤常正 名誉会員 ご逝去
【11】事務局夏季休業のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】令和2年7月豪雨災害についての会長談話
──────────────────────────────────
令和2(2020)年7月に発生しました「令和2年7月豪雨」災害により犠牲
になられた方々に心から哀悼の意を捧げ,ご冥福をお祈りします.被災者
の皆様におかれましては,一日も早く日常生活を取り戻されることをお祈
りいたします.
全文はこちら,http://www.geosociety.jp/engineer/content0055.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】令和2年7月豪雨災害等地質災害関連情報
──────────────────────────────────
令和2年7月豪雨災害関する情報
http://www.geosociety.jp/hazard/content0098.html
地質災害緊急調査について
http://www.geosociety.jp/hazard/content0024.html
会費の特別措置のお知らせ
http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html#saigai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】名古屋大会代替企画
──────────────────────────────────
・2020年度学会各賞受賞記念講演会(WEB)9/13配信予定
・第1回・2回ショートコース 9/19・10/24開催[申込受付期間:第1回分 8/5-9/7]
・コロナ禍での地質学教育に関するサイバーシンポジウム 9月下旬予定
・JABEEオンラインシンポジウム(準備中)
・日本地質学会ジュニアセッション(旧小さなESの集い)参加校募集中:9/30締切
・若手会員のための地質関連企業の研究サポート(準備中)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0041.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■地質学雑誌
・126巻7月号(2021年名古屋大会巡検案内書)7/31に発送になりました
・126巻8月号(予告)特集号「法地質学の進歩」(世話人:杉田律子)
■Island Arc
新しい論文等が公開されています.
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14401738/0/ja
Island Arcでは著者制作のVideo Abstractの掲載が可能です.
例:https://bcove.video/2DvAdgw
Glimpses of oceanic lithosphere of the Challenger Deep forearc segment in
the southernmost Marianas: The 143°E transect, 5800-4200 m
Robert J. Stern, et al e12359
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】トピック:昇仙峡は黒富士が造った?(前編)
──────────────────────────────────
昇仙峡は黒富士が造った?:
「地質図Navi」と「地理院地図」で楽しむ四次元の旅(前編)
正会員 高山信紀
本記事は,山梨県甲府市北部に位置する昇仙峡,野猿谷, 大滝と仙娥滝の
成り立ちについてのアイデアとそれに基づいて机上で検討した内容を述べた
ものである.つづきはこちらから
http://www.geosociety.jp/faq/content0915.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】大学院生を対象にしたアンケート調査:全国大学院生協議会(全院協)
──────────────────────────────────
本調査は,全院協が,全国各大学の加盟院生協議会・自治会の協
力の下に実施する,全国規模のアンケート調査です.本調査は,大
学院生の研究及び生活実態を客観的に把握し,もってその向上に
資する目的で行うものです.
【アンケート回答期限】2020年8月31日
【アンケート回答フォームURL】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVDp5Nqhz4iIWY_sS5s4W5Zg1zNZX0qR8lae91PXYXKAotbA/viewform
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)旭町学術資料展示館企画展示
「ジオパークの微化石展」
8月1日(土)-9月6日(日)
会場: 新潟大学旭町学術資料展示館(新潟市中央区旭町通)
http://www.lib.niigata-u.ac.jp/tenjikan/
2020年度第1回(初心者向け)地質調査研修【参加者募集中】
9月28日(月)-10月2日(金)
室内座学:茨城県つくば市(産総研)
野外研修:茨城県ひたちなか市,福島県いわき市
定員 6名(最小催行人数:4名)(定員になり次第締切)
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2020-1.html
ぼうさいこくたい2020
頻発化する大規模災害に備える
−「みんなで減災」助け合いをひろげんさい−
10月3日(土)[オンライン大会]
http://bosai-kokutai.jp/
2020年度第2回(経験者向け)地質調査研修【参加者募集中】
10月26日(月)-30日(金)
場所:島根県出雲市長尾鼻周辺(小伊津海岸)
定員:6名(定員になり次第締切)
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2020-2.html
(後)藤原ナチュラルヒストリー振興財団
設立40周年記念 公開シンポジウム
「海と地球の自然史−変わりゆく海洋環境から
海洋プラスチックごみまで地球の問題を考える−」
[開催中止]
http://fujiwara-nh.or.jp/
(協)第36回ゼオライト研究発表会
11月19日(木)-20 日(金)
場所:富山国際会議場
https://jza-online.org/events
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
─────────────────────────────────
・京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻(地質学鉱物学分野・岩石学)助教公募(9/14)
・農林水産省経験者採用試験 係長級(技術:地質・地下水調査・指導業務ほか)(8/3-20)
・2020年度藤原ナチュラルヒストリー振興財団学術研究助成応募(9/1)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】訃報 高柳洋吉 名誉会員 ご逝去
─────────────────────────────────
高柳洋吉 名誉会員(東北大学名誉教授)が,令和2年7月21日(火)
に逝去されました(93歳).
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し
上げます.なお,ご葬儀等はすでに御家族のみで執り行なわれ,供花
・香典等はご辞退されるとのことです.
また後日,東北大学地質学古生物学教室同窓会であらためて偲ぶ会を
企画されるとのことです.
会長 磯崎 行雄
(注)「崎」の正しい表記は,「大」→「立」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】訃報 斎藤常正 名誉会員 ご逝去
─────────────────────────────────
斎藤常正 名誉会員(東北大学名誉教授)が,令和2年8月1日(土)
に逝去されました(84歳).
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し
上げます.なお,ご御葬儀等は御家族のみにて執り行なわれます.
また,ご遺族から,現在のCOVID-19の状況を鑑み, 自宅等へのご訪問
も誠に申し訳ありませんがご辞退いたしますと申し受けております.
また後日,東北大学地質学古生物学教室同窓会であらためて偲ぶ会を
企画されるとのことです.
会長 磯崎 行雄
(注)「崎」の正しい表記は,「大」→「立」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】事務局夏季休業のお知らせ
─────────────────────────────────
学会事務局は下記の期間,夏季休業とさせて頂きます.
2020年8月11日(火)から14日(金)
2020年8月17日(月)より通常通りの営業となります.
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが,何卒ご理解の程お願い
申し上げます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
昇仙峡は黒富士が造った?(後編)
昇仙峡は黒富士が造った?:「地質図Navi」と「地理院地図」で楽しむ四次元の旅(後編)
正会員 高山信紀
「前編」に引き続き,後編では,「旧荒川」,「旧板敷川」のルートと縦断面,大滝,仙娥滝の成り立ちについて検討した内容を述べる.
検討内容(続き)
(3) 「旧荒川」,「旧板敷川」のルートと縦断面
「旧荒川」と「旧板敷川」のルート(想像)を図-5のように設定した.「旧荒川」は黒平付近のA地点から「旧板敷川」との合流点B地点を通り千秋橋(C地点)に至り,「旧板敷川」は野猿谷との合流点D地点から御岳川のE地点を経てB地点で「旧荒川」に合流するとした.これらの地点での旧河床の標高を以下のように考えて繋ぎ「旧荒川」と「旧板敷川」の縦断図(図-6③)を作成した.また,黒富士火砕流堆積前の等高線を,A〜E地点の標高および現在地表に露出している四万十層群,花崗岩,水ヶ森火山岩の標高より図-5のように想像した.
黒平付近では黒富士火砕流が線状に分布している2)(図-5).これは「旧荒川」のルートだと考え(図-3③;前編参照),その標高は「K1火砕流」の底面よりA地点(図-5)で約1,020mとした. 荒川下流では,千秋橋(図-1;前編)の河川敷(標高約260m,「地理院地図」の断面図機能を使用)で行われたボーリング8)で,黒富士火砕流が標高約+118m〜約-121mに堆積しており,「旧荒川」のルートは千秋橋(C地点)までとした.
現在の荒川下流の右岸に,わずかではあるが水ヶ森火山岩(片山溶岩)が分布している2)(図-5).この付近は黒富士火砕流とそれ以前の山体の境界に位置し,現在の荒川によって片山溶岩山体が浸食されたのだろう.現在の亀沢川の中・上流部も黒富士火砕流とそれ以前の山体の境界に対応し,亀沢川沿いで黒富士火砕流以前の四万十層群,花崗岩,水ヶ森火山岩の岩体が露出するのは,「旧荒川」による侵食ではなく黒富士火砕流後の亀沢川による侵食だと想像した(図-5).なお,「旧荒川」の流路は甲府盆地では網状だったかもしれず,千秋橋(C地点)は「旧荒川」の氾濫原だったのかもしれない.
御岳川のE地点では標高800mに「K1火砕流」の底面があり,これを「旧板敷川」の河床標高とし,その下流の「旧荒川」・「旧板敷川」合流点(B地点)の標高は約750mとした.「旧板敷川」の野猿谷合流点(D地点)(図-5)の標高は,板敷渓谷の遷急点に着目し,遷急点は野猿谷の形成が始まったことにより渓谷の下流から下刻が進んで形成されたと考え,遷急点より上流の河床勾配(9.6%)を下流に延長し約930mとした(図-6②).
ところで,本地域は甲府盆地から北に向かうほど隆起速度が大きい9).過去約10万年の隆起速度9)を100万年に外挿し,隆起速度地点(図-5)西方の「旧荒川」の標高(想像)から100万年間の隆起量を減じてプロットすると,概ね一本の直線近傍に並ぶ(図-6③).この直線を隆起量を減じた100万年前の「旧荒川」と想像すると,「旧荒川」は千秋橋上流約4.5kmあたりを支点とした右上がりの隆起・沈降のシーソーのように見える.また,直線を時計(この図は右側が隆起なので反時計回り)の針と見なすと,時計が正確(隆起速度が等速度)なら隆起・沈降は約190万年前頃に始まったことになり,時計が進んでいる(隆起速度が加速10)している)のなら隆起開始はもっと前かもしれない.疑問,興味が膨らんでいく.
図-5 黒富士火砕流前の
「旧荒川」のルート(想像)
図-6 現在の荒川と
黒富士火砕流前の「旧荒川」の縦断面
※画像をクリックすると大きな画像をご覧いただけます。
(4) 大滝の成り立ち
板敷渓谷の大滝はどのようにして,何時できたのだろうか?板敷渓谷と野猿谷は同じ四万十層群なのに板敷渓谷には大滝があり野猿谷に滝が無いのは何故だろうか?
野猿谷は板敷渓谷より流量,砂礫とも多いので下刻が進み11),12),板敷渓谷との合流点で野猿谷の河床が板敷渓谷より低くなって滝が形成され,滝は板敷渓谷を後退し現在の大滝になったと考えた.大滝の形成が始まった年代を「滝の後退速度の式」13),14),15),16), 17)で試算した.
D:滝の後退距離(m),T:滝の後退の継続時間(y),A:流域面積(k㎡),P*:流域の年平均降水量(mm/y),W:滝の幅(m),H:滝の高さ(m),ρ:水の密度(kg/㎥),Sc:基礎岩盤の一軸圧縮強度(N/㎡).ただしAP*は流量の単位(㎥/s)に換算.
大滝は,A:6.9 k㎡(「地理院地図」の面積機能を使用),W:3m(仮定),H:32m(「地理院地図」の断面図機能を使用),ρ:1,000kg/㎥とした.一軸圧縮強度Scは,三村ら2)が本地域の四万十層群は頁岩を主体とし随所に砂岩頁岩互層及び砂岩を挟むと述べており,頁岩の一軸圧縮強度の文献18)を参考に,150M N/㎡と仮定した.流域の年平均降水量P*は,関東整備局ウェブサイト「地形・地質・気候(山梨県)」の富士川上流の年間降水量1,000mm〜1,500mmを参考に間氷期は1,200mm/y,氷期は間氷期の半分19)の600mm/y,氷期・間氷期を通じた年間平均降水量を900mm/yと仮定した.大滝の後退速度を上記の式の右辺より求めると約14mm/yとなった.また,Dを400m(野猿谷・板敷渓谷合流点から約400m上流に位置.距離は「地理院地図」の距離機能で計測,以下同様)とすると,大滝の形成年代は約3万年前(400m/14mm/y)となる.
野猿谷・板敷渓谷合流点での下刻について検討してみた.現在の野猿谷・板敷渓谷合流点の標高を約790m,大滝の高さを約30mとし,約80万年前(「K3火砕流」による堰き止め)の合流点標高を約930mとした(前述(3)).約77万年で標高約930mから標高約820m(現在の河床標高約790m に滝の高さ約30mを加算)まで約110m下刻され,約3万年で標高約820mから約790mまで約30m下刻された考えると,滝の形成後の下刻速度は約1.00mm/yとなり滝の形成前の約0.14mm/yより著しく大きい.これについては以下のように考えた.約3万年前までは野猿谷と板敷渓谷の下刻速度は同程度(約0.14mm/y)であったが,約3万年前に野猿谷上流の堰止湖が消滅して大量の砂礫が野猿谷を流下し始めるとともに昇仙峡の堰止湖も消滅して荒川の流速が増大して,野猿谷の下刻速度(約1.00mm/y)が板敷渓谷に比し著しく大きくなった.
(5) 仙娥滝の成り立ち
仙娥滝の後退速度を,大滝と同様に試算した.仙娥滝は,A:79.5k㎡(現在の位置で試算),P*:900mm,W:10m,H:26m,ρ:1,000kg/㎥とし,一軸圧縮強度Sc:190MN/㎡(文献20)を参考に仮定)とした.その結果,後退速度は約37mm/yとなった.
仙娥滝の形成を以下のように想像した.現在,花崗岩が分布している最下流(仙娥滝下流約5.7km,図-5のQ地点)に,「K4火砕流」(約70万年前)で覆われた花崗岩の段差があり,火砕流が侵食されてその段差が露出して滝が形成され,その滝が後退して仙娥滝となった.このアイデアによれば,仙娥滝の形成年代は約15万年(5.7km/37mm/y)前となる.
でも,本検討では滝の後退距離を現在の荒川(昇仙峡)の流路長と仮定したが,適切だろうか?本当に仙娥滝は後退して,現在“たまたま”想像した鞍部の場所に位置しているのであろうか?それとも,滝が形成されて以来ほとんど現在と同じ位置にあるのだろうか?後退すると考えた場合,もしかして,約20万年前に韮崎岩屑流が荒川下流を含む甲府盆地を埋め,その後,釜無川が下刻をし始め,これと合流する荒川に滝が出来て荒川を遡上し始め,現在仙娥滝に達しているのだろうか?分からないことは無数にあり,四次元の旅の興味は尽きない.
あとがき
上述のように,昇仙峡の成り立ちなどについて地形図と地質図,文献から想像,検討を行ったが,興味や疑問が次々に出て思った以上に時間がかかってしまった.大きな間違いがあるかもしれない.ご指摘を頂ければ幸いである.再度,現地に行って地形・地質を確認したいが,しばらくはままならない.「地質図Navi」や「地理院地図」を用いて机上で四次元の旅を楽しむこととしよう. 最後に,日本地質学会中部支部巡検で教えて頂いた方々,層雲峡ビジターセンターで説明して頂いた学芸員の方に御礼申し上げます.また,貴重なヒントを頂いた友人の星野延夫氏に感謝いたします.
参考文献
(注)文献番号は「前編」から通し番号となっている.
2)三村弘二・加藤祐三・片田正人(1978)5万分の1地質図幅「御岳昇仙峡地域の地質」.地質調査所.
8) 興水達司・内山 高・嵯峨山積・八木公史・竹下欣宏(2007) 甲府盆地500mボーリングコアの地質年代と古環境.日本地質学会第114年学術大会講演要旨.
9) 野村勝弘・谷川晋一・雨宮浩樹・安江健一(2017) 日本列島の過去約10万年間の隆起量に関する情報整理.日本原子力開発機構JAEA-Data/Code.
10) 岡田篤正(1980):中央日本南部の第四紀地殻運動-地殻運動の変化と場の移動-.第四紀研究19(3) .
11) 鈴木睦仁・池田 宏(1994) 愛知県豊川上流の乳岩川における平滑な岩盤河床の成因について.筑波大学水理実験センター報告,No.19.
12) 吉田美佳・池田 宏(1999) 栃木県烏山町,竜門の滝の成因について.筑波大学水理実験センター報告,No.24.
13) 早川裕一・松倉公憲(2003)日光,華厳滝の後退速度.地学雑誌,112(4) .
14) Hayakawa Yuichi(2005)Reexamination of a Predictive Equation of Waterfall Recession Rates in Boso Peninsula, Chiba Prefecture, Japan.Geographical Review of Japan,Vol. 78, No.5.
15) 早川裕一・横山勝三・松倉公憲(2005)阿蘇火山・立野峡谷付近における滝の後退速度.地形,第26巻,第4号.
16) Yuichi S. Hayakawa(2011) Postglacial Recession Rates of Waterfalls in Alpine Glacial Valleys.地形,第32巻,第2号.
17) 吉田英嗣・高波紳太郎・大坂早希・疋津 彰・石井 椋・早川裕弌(2016)大隅半島神ノ川流域における滝の形成・後退の地形プロセス.2016年度日本地理学会春季学術大会.
18) 前田寛之・河野勝宣・小竹純平・安藤 勧(2014)続成帯硬質頁岩を基岩とする受け盤型地すべりにおける風化帯の重要性−北海道本岐地すべりの例−.日本地すべり学会誌,51巻,1号.
19) 松末和之・藤原 治・末吉哲雄(2000)日本列島における最終氷期寒冷期の気候.サイクル機構技報,No.6.
20) 梶川昌三・増田幸治・山田功夫・出原 理(1990)粒形の異なる花崗岩に発生する微小クラックの特徴.地震,第43巻.
柱状節理・板状節理(石渡)
柱状節理は低温の発泡膨張,板状節理は高温の流動剪断でできる
正会員 石渡 明
1.序論
地学事典は,溶岩・岩脈・岩床等に見られる柱状節理(columnar joint)について,「岩体の冷却時の体積収縮によって形成され」,「柱状節理の間隔(spacing)は冷却速度に比例し,ゆっくり冷えれば間隔が大きくなると考えられている(Spry, 1962)」と記し,板状節理(platy joint)も「冷却時に形成される」と記している(平野・横田, 1996).米国の地質学辞典も柱状節理を「冷却中の収縮の結果できる」とするが,板状節理の語はない(Neuendorf et al. 2005).構造地質学の教科書は,柱状節理と板状節理を「岩体の収縮を解消するために形成される冷却節理(cooling joint)」としている(狩野・村田, 1998, p. 171; 金川, 2011, p. 118).火山学では,森本(1958, p. 92)の「柱状節理の六角の柱は,冷却面に直角に発達する.板状節理の板の方向は,溶岩の流理面を代表している」が至言であり,McPhie et al. (1993, p. 71) も図入りで同文を記す.地質学の藤本(1977, p. 121)も「柱状体は冷却面に直角」とし,日本の柱状節理の写真集(山本, 2009)を見ると,確かに柱状節理の方向は重力と無関係で,冷却面に直角に見える(垂直な岩脈では柱が水平方向,ドーム状の岩体では放射状).しかし,板状節理が流理面を代表するなら,それは溶岩の流動方向を表し,必ずしも冷却面と一致しないのではないか.また,同じ冷却節理なのに,どういう条件で一方は柱状節理,他方は板状節理になるのか,どの事典・教科書も説明していない.
ところで,安山岩の火山の火口周辺にはしばしば「パン皮火山弾」(bread-crust bomb)が落ちていて,その表面にはフランスパンの皮(または揚げ煎餅や鬼あられ)のような割れ目が発達し,それは柱状節理に似ているが,この割れ目は「火山弾の表面が急冷されて固結した後も,内部は可塑性を保ち発泡が続いたために生じた構造」とされている(荒牧, 1996).つまり表面の急冷収縮ではなく,内部の発泡膨張によって表面が亀甲状に割れるのである.McPhie et al. (1993, p. 82, #3) は枕状溶岩の表面の割れ目が内部の膨張により海嶺のように拡大した様子を示しているが,これは発泡ではなく新しい溶岩の供給による膨張だろう.では,溶岩・岩脈・岩床等が冷却過程で発泡により膨張することはないのだろうか.
一般論として,衝撃や摩擦,広域応力場など外的な原因がない条件で,物体の表面部分に張力割れ目が生じる場合,①内部の体積は変化せずに表面部分の体積が減少(収縮)するか,②表面部分の体積は変化せずに内部の体積が増加(膨張)するか,③表面部分の収縮と内部の膨張が両方同時に起きるか,いずれかのはずである.小論では,柱状節理の成因説として地学事典や多くの教科書に記述されてきた(そして私も長年授業で学生に説明してきた)①の考えは疑問であり,②または③の考えが妥当と考えられること(つまり柱状節理はパン皮火山弾の割れ目と同じメカニズムでできること),溶岩・岩脈・岩床等が冷却する時は,温度が高くて時間当たりの体積収縮率が大きく,まだマグマに流動性がある冷却の初期には,まず板状節理が形成され,その後冷却がかなり進んでから発泡による岩体内部の膨張によって柱状節理が形成されることを述べる.そして発泡による膨張が生じない場合,規則的な柱状節理は形成されず,板状節理だけが発達することについても述べる.
2.柱状節理と板状節理の出現頻度
例えば,箱根火山の溶岩において,柱状節理と板状節理の出現頻度は同程度である.神奈川県立生命の星・地球博物館(2008)の露頭写真と説明に基づいて数えると,柱状節理が発達するものが6つ((数字はページ数,Gはグループ)文庫山の屏風山溶岩 (27),箱根町湯本の山崎付近の早川右岸の米神溶岩G (78),真鶴町真鶴の本小松溶岩G (78-79),湯河原町吉浜の幕山溶岩ドーム (25),湯河原町の外輪山南東部 (75),熱海市の初島溶岩 (5, 19)),板状節理が発達するものが5つ(小田原市根府川の根府川溶岩G (78),真鶴町真鶴の白磯溶岩G (75),南足柄市苅野明神林道の苅野溶岩G (19),箱根町芦ノ湖畔の白糸川溶岩G (21),御殿場市東田中の長尾峠溶岩G (23))である.両者が1つの溶岩に同程度に発達する場合もあるが,柱状節理がほとんど見られず,板状節理のみが発達する溶岩もある.諏訪の鉄平石など,いわゆる洪水安山岩は板状節理のみのものが多い(図1)(永尾ほか, 1995).
図1.熊本県水俣市長崎なべ滝の肥薩火山岩類の「洪水安山岩」の板状節理.柱状節理はほとんど見られない.永尾ほか(1995)と佐藤・石渡(2015)参照.本図以下全ての写真は石渡撮影.
図2.山口県下関市角島の中期中新世のかんらん石玄武岩の溶岩.流理構造と板状節理は頭が南向き(画面で右向き)の押し被せ褶曲をなし,柱状節理はその褶曲構造と無関係に,褶曲構造を切って鉛直方向に発達する(東山ほか, 2012; 佐藤・石渡, 2015).
(注)画像をクリックすると大きな画像をご覧いただけます。
3.柱状節理と板状節理の前後関係
ある1つの溶岩に柱状節理と板状節理の両方が見られる場合,どちらの節理が先にできたかは,切り合いの関係を見れば決定できる.この2種類の節理の切り合いの関係を最もよく示すのは,山口県下関市角島(つのしま)北部海岸の牧崎溶岩(中新世の大津玄武岩類の一部)の露頭である(東山ら, 2012; 佐藤・石渡, 2015, Fig.8).ここでは数cm間隔の板状節理が発達したかんらん石玄武岩の溶岩が,軸面がほぼ水平な押し被せ(おしかぶせ)褶曲(しゅうきょく)をなしており(流理構造とそれに平行な板状節理が頭を南向きにして褶曲),約1m間隔の柱状節理はその褶曲構造を切って(褶曲とは無関係に)鉛直方向に形成されている(図2).このことは,溶岩が流動中に既に板状節理が形成され,溶岩が何らかの障害物を乗り越える時に押し被せ褶曲が形成され,その後溶岩が褶曲構造を保ったまま冷却固結する過程で(褶曲構造とは無関係に)鉛直方向に柱状節理が形成されたことを示している.このことは,板状節理が柱状節理よりも早い時点で,溶岩がまだ流動できるような高温の状態で形成されることを示している.
図3.宮城県岩沼市上河原の安山岩溶岩の採石場に見られる,高温状態で形成された板状節理の割れ目を埋めたと考えられる10〜15cm間隔の4本の平行な分結脈をもつ転石.風化面で白っぽく見える,画面で上下に延びる幅5mm程度の脈が分結脈(木本・石渡, 2014).新鮮な面では見分けにくい.2013年6月10日撮影.
図4.チューブの中を重力によって下降するマヨネーズに形成される水平方向の平行な割れ目群(板状節理).冷蔵庫の中に出口を下にした逆立ち状態でしばらく立てておいた後で,チューブを横にして撮影.適度な粘性が条件であり,どのマヨネーズでもできるわけではない.
(注)画像をクリックすると大きな画像をご覧いただけます。
4.板状節理の形成
節理の割れ目の充填物も,割れ目ができた時期の判断に役立つ.木本・石渡 (2013, 2014) は宮城県岩沼市上河原の採石場に露出する中期中新世の厚さ110mのほぼ水平な安山岩溶岩を調査した.この溶岩には約1m間隔の鉛直方向の柱状節理が発達するが,一見すると板状節理は見られない.しかし,よく観察すると,溶岩の下部(下底から高さ6〜14m)・中部(45〜64m)・上部(80〜95m)の3層準に,柱状節理と直角の方向(ほぼ水平方向)に,幅1〜15mmの細粒の脈が5〜15cmの間隔で見られる(図3).これらは板状節理の割れ目を埋めた分結脈と考えられる.つまり,板状節理が形成された時点では,まだ結晶粒の間に融液がかなり残っていて,結晶分化作用が進行した融液(残液)が板状節理の割れ目に浸み出し(分結し),その割れ目を埋めたと考えられる.分結脈が雁行状になっていることがあり,溶岩の流動による剪断変形が原因と考えられる.一部の分結脈はピジョン輝石を含み,脈の全岩化学組成は溶岩全体の約70%が結晶化した後の残液であることを示す.柱状節理はこれらの分結脈をその固結後に切断しており,柱状節理は分結物を伴わない.
板状節理が溶岩流動中の剪断力によって流理面に沿って形成されるのなら,垂直な岩脈やパイプ中では板状節理も垂直のはずである.しかし,板状節理は重力方向の張力によっても形成され得る.例えば,適度な粘性をもつマヨネーズ(「サラリア」がよい)を,チューブの半分程度まで使用した後,出口を下にして(逆立ち状態で)冷蔵庫に立てておくと,マヨネーズが重力によって出口に向かって下降する過程で,ほぼ水平な割れ目群(板状節理)が形成される(図4).半固結のマグマ中で,熱収縮あるいは側方へのマグマの流出などの物理的原因によって重力方向の張力が働き,このような水平方向の割れ目が生じることはあり得る.しかし,重力説なら,垂直な岩脈中でも板状節理は水平のはずであるが,実際には重力方向とは無関係に,流理面と平行(または雁行状)に板状節理が発達する例の方が多い(森本, 1958; McPhie et al. 1993).つまり,板状節理は,主にマグマの流動による剪断が原因で形成され,単純な冷却節理ではないと考えられる.そして,柱状節理よりも時間的には早く,マグマがまだ流動性をもつ,より高温状態の時に形成されると考えられる.
5.柱状節理の形成
角島の例から,溶岩がまだ流動中の高温状態で板状節理が形成された後,溶岩が停止してかなり冷却してから柱状節理が形成されたことが明らかである.そもそもそのような低温条件では,時間当たりの冷却収縮率は小さく,冷却割れ目はできにくいはずである.ただしその時点でも溶岩は100%固結していたわけではなく,気体成分に富んだ,分化した残液が結晶粒間にまだ残っていた可能性がある.木本・石渡(2013)は岩沼の安山岩溶岩について,約1m間隔の柱状節理に囲まれた溶岩柱(以下「柱」と呼ぶ)の断面において各部分のドリルサンプリングを行い,柱の中心部と周辺部で石基斜長石の粒径や岩石の帯磁率を調べた(図5).柱の中心部では周辺部よりも石基斜長石の粒径(長辺)が約30%大きく,帯磁率も15%ほど高かった(これは中心部の磁鉄鉱の粒径が大きいことを示唆する).柱状節理が形成されると,その割れ目を通じて空気や水が循環し冷却が促進されるので,柱の周辺部は中心部に比べてより速く冷却される.この違いが石基の斜長石や磁鉄鉱の結晶成長に影響したと考えられる.また,木本・石渡(2014)はこれらのドリル試料の密度を測定し,柱状節理の節理面に接する岩石は柱の内部の岩石よりも密度が低く,鏡下では発泡が見られることがわかった.これは,割れ目の形成に伴ってその直近のメルトが減圧発泡したことを示唆する.ただし,柱状節理の割れ目に末期の残液が分結している例は発見できなかった.
なお,溶岩・岩脈・岩床等の中央部で柱状節理が不規則になる場合があるが(colonnadeからentablatureへ),これは冷却の進行と水の侵入(Jerram and Petford, 2011)による発泡の局所化を意味する可能性がある.また,柱状節理に六角形が多いのは,三角形や四角形より割れ目形成に要する力が小さいためと説明されている(藤本, 1977, p. 121脚注).
図5.宮城県岩沼市上河原の採石場の柱状節理に囲まれた幅約1mの「柱」の断面.多数の黒点はドリルサンプリングの跡(木本・石渡, 2013).実は,最初このドリルサンプルの薄片に分結脈を発見し,露頭を再調査して分結脈の普遍性を確認した.
図6.新潟県佐渡市小木の沢崎鼻のピクライト岩床に発達する水平方向の気泡レーヤリングと鉛直方向の柱状節理(Toramaru et al. 1996).気泡が多い層が波浪によって深く侵食され,崖の面が段々になっている(似ているが板状節理ではない).海岸露頭では顕著だが,内陸露頭での気泡レーヤリングの確認は困難である.
(注)画像をクリックすると大きな画像をご覧いただけます。
6.議論
柱状節理の成因について,古くは対流セル説等の様々な考えがあったが,現在は溶岩・岩脈・岩床等の冷却収縮によってできるという説が広く受け入れられていて,私を含めてこれを疑う人はほとんどいなかった.これは水に溶いたデンプン粉を皿に入れて,上から白熱電球で照らして水を蒸発させ,デンプン粉の層の中に柱状節理によく似た蜂の巣パターンの鉛直方向の割れ目(乾裂)ができることを示すアナログ実験 (Müller, 1998) によって説得力を強めた.この場合,デンプン層の上部が収縮し,下部はあまり収縮しないために,上部に割れ目が生じて時間とともに割れ目が下方に伸長し幅が拡大していく.しかし,もし表面部分の冷却収縮によって柱状節理ができるのなら,どの溶岩にも同様に柱状節理が発達するはずであり,柱状節理がなく板状節理だけが発達する溶岩(図1)が多数存在することを説明できない.さらに,この実験は柱状節理が冷却のかなり遅い時期に形成することも説明できない.冷却早期の方が時間当たりの収縮率が大きく,節理ができやすいはずである.
また,佐渡のピクライト岩床や羽越地域のドレライト岩床では,かなり結晶化が進んで残液中に気体成分が濃集した時,岩体の上面から内部に向かって周期的な発泡が進行し,「気泡レーヤリング」と呼ばれる縞状構造が形成されることが報告されている(図6)(Toramaru et al., 1996; 高橋・石渡, 2012, p. 123).これらの岩体にも柱状節理が発達しており,柱状節理が岩体内部の発泡膨張によって形成されたことを支持する1つの証拠になる.結晶化の進行とともに気体成分が残液に濃集し,周辺部から内部に向かって周期的に発泡・膨張するのであれば,柱状節理の遅い形成時期や分結物が見当たらないことも説明できる.
7.結論
物事は相対的であり,溶岩の表面が収縮するのではなく,内部が膨張しても同じ効果(柱状節理)が生まれるはずである.柱状節理は,溶岩の冷却時の発泡によって,内部が膨張する時に形成されるのではないか.つまり,パン皮火山弾の表面の割れ目と同様のメカニズムで形成されるのではないか.気体成分が少ない,気泡の核が少ない,物理的な震動が少ない等の条件によって冷却中に気泡が成長しない場合は,内部の膨張が起こらないので柱状節理ができず,高温の流動時に形成された板状節理だけが見られるのではないか.このように考えると,上述の板状節理と柱状節理の時間的前後関係と充填物の有無,なぜ1つの火山の似たような化学組成の溶岩群に柱状節理の発達した溶岩と板状節理の発達した溶岩がほぼ同数あるのかが説明可能になる.柱状節理は低温の岩体内部の発泡膨張,板状節理は高温の流動剪断で形成され,どちらも単純な冷却節理ではない.これが小論の結論である.ここで述べた柱状節理の「膨張説」は,まだ例証が少なく,仮説の段階であり,今後の検証が必要である.検討項目として,柱状節理の有無や間隔と発泡度の関係,柱状節理面に分結した末期残液の発見と化学分析等がある.検討の際,溶岩は冷却によって収縮するとは限らず,発泡して膨張することもある(場合によっては爆発して火砕流になる)ことを念頭に置くべきである.
謝辞:調査を許可していただいた岩沼市上河原の有限会社平間砕石様に感謝する.箱根火山の調査にご協力いただいた神奈川県立生命の星・地球博物館の平田大二氏に感謝する.拙稿を読んでご意見をいただいた棚瀬充史,池田保夫,武田和久の各氏に感謝する.
文 献
荒牧重雄 (1996) パン皮火山弾.平凡社 地学事典, p. 1051.
藤本治義 (1977) 改訂増補 新地質学汎論.地人書館.310 p.
東山陽次・永尾隆志・長嶌真理子 (2012) 山口県下関市角島に分布する中新世玄武岩類の地質と岩石.火山学会講演予稿集, p. 59.
平野昌繁・横田修一郎 (1996) 柱状節理,板状節理.平凡社 地学事典, p. 829, 1055.
Jerram, D. and Petford, N. (2011) The Field Description of Igneous Rocks. Wiley-Blackwell. 238 p.
金川久一 (2011) 構造地質学(現代地球科学入門シリーズ10 地球のテクトニクスII).共立出版.253 p.
神奈川県立生命の星・地球博物館 (2008) 箱根火山 いま証される噴火の歴史(2008特別展図録).96 p.
狩野謙一・村田明広 (1998) 構造地質学.朝倉書店.298 p.
木本和希・石渡明 (2013) 宮城県岩沼地域に見られる安山岩溶岩の柱状節理と石基結晶の付随事実.日本地球惑星科学連合大会予稿集, SCG61-P11.
木本和希・石渡明 (2014) 宮城県岩沼市に見られる玄武岩質安山岩複合溶岩流の内部分化過程--分結脈から柱状節理へ.日本地球惑星科学連合大会予稿集, SMP48-08.
森本良平 (1958) 日本の火山.創元社(東京).218 p.
McPhie, J., Doyle, M. and Allen, R. (1993) Volcanic Textures. University of Tasmania.196 p.
Müller, G. (1998) Experimental simulation of basalt columns. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 86, 93-96.
永尾隆志・長谷義隆・井川寿之・長峰智・坂口和之・山本正継・周藤賢治・林田賢一 (1995) 九州の平坦面を形成する安山岩の地質学的・岩石学的特徴:‟洪水安山岩”の提唱.地質学論集, 44, 155-164.
Neuendorf, K.K.E., Mehl, J.P.Jr. and Jackson, J.A. (2005) Glossary of Geology (5th Ed.) American Geological Institute. 779 p.
佐藤景・石渡明 (2015) 宮城県北部,石越安山岩の地質・岩石学的特徴とマグマプロセス.岩石鉱物科学, 44, 155-170.
Spry, A. (1962) The origin of columnar jointing, particularly in basalt flows. Journal of the Geological Society of Australia, 8, 191-216.
高橋正樹・石渡明 (2012) 火成作用(日本地質学会編フィールドジオロジー8).共立出版.
Toramaru, A., Ishiwatari, A., Matsuzawa, M., Nakamura, M. and Arai, S. (1996) Vesicle layering in solidified intrusive magma bodies: a newly recognized type of igneous structure. Bulletin of Volcanology, 58, 393-400 (Correction in 58, 655-656 and comment/reply in 61, 343-346).
山本治之 (2009) 大地の鼓動 柱状節理の四季(写真集).光村推古書院.
日本地質学会初代会長神保小虎小伝
日本地質学会初代会長神保小虎小伝
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
神保小虎の遺影(佐藤, 1924a)
筆者は日本地質学会会長の任期を終えるに当たり、初代会長神保(じんぼ)小虎(ことら)(1867-1924)の小伝を記してその心意気を会員諸兄諸姉に伝え、本学会の今後の発展の一助としたい。文中敬称を略す失礼をお許し願いたい。
話を始めるに当たり、まず日本地質学会の会長職の歴史について述べる。本学会は1893年5月に創立され(1934年までは東京地質学会と称した)、現在も続く月刊の地質学雑誌は1893年10月に創刊された(当初は各巻の第1号は10月発行だったが、1898年の第6巻から1月に第1号を発行)。しかし、草創期の本学会には会長職がなく、学生の幹事2名が会務を担当していた。つまり創立当初の本学会は東大地質教室のゼミのようなもので、会費は月10銭(現在の1500円程度)、毎月第3土曜の午後1時から会員が同教室に集まり、「学術上の叢談及び会務の報告」を行っていた。1900年には幹事の他に編集委員3名が設けられた。1905年に会則が変更されて神保小虎が会長になり、彼はこの年に「本邦に於ける地質学の歴史」(地質雑, 12, 393-405)を発表したが、1907年には「会長制を廃し、評議員20名をおき、うち2名を幹事とする」(60周年記念誌年表)ことになった。会長制が復活するのは1913年で、再び神保小虎が選ばれた。現在の日本地質学会の歴代会長表(2013年会員名簿p.34)の最初は1913年だが、1905年が最初だとしても(60周年記念誌)、やはり神保小虎が本学会の初代会長である。彼は1916年も会長になり、都合3回本学会の会長を務めた。この頃の会長の任期は1年だったが、1951年から2年になり、1978年からは副会長が設けられた。こういう経緯なので、初代会長と言っても創立時の会長ではなく、その20年後の会長である。そして筆者は第60代、50人目の会長ということになる。
筆者の前著(News誌17(3), 4-5 (2014)/ geo-flash No.250)でも触れたように、神保小虎は幕臣の家の出で、慶応3年に江戸で生まれ、1887年に東京大学理学部地質学科を卒業した。卒業後北海道庁の技師として道内の地質調査を行い、この間に貯めた金で1892年にドイツへ留学し、古生物学を専攻したが、東大の鉱物学の助教授(菊池安)が急逝したため、専攻を変更して速成の鉱物学者になった。1894年にまだ全線開通前だったシベリア鉄道を乗り継いで帰国し、途中アムール川流域の地質調査を行った。翌年東京大学の鉱物学の助教授、1896年教授になった。1904年の日露戦争で日本が勝利し、樺太(サハリン)の南部を日本が領有することになった時、志賀重昂(拙著、News誌16(10), 8-9 (2013)/ geo-flash No.227)とともに国境画定委員附に任ぜられ、同島の北緯50度線付近の調査を行った(中里重次, 1932; 燃料協会誌, 11(121), 1452-1461)。その前後に遼東半島やウラジオストク地域の調査も行っている。神保小虎の生い立ち、略歴、著作、人物などについては浜崎健児(2011, 地質学史懇話会報36号)がよくまとめており、北海道調査を中心とする業績と文献については松田義章(2010, 同34, 35号)が詳しい。佐藤博之(1983, 地質ニュース346号)は白野夏雲や坂(ばん)市太郎と神保小虎の関わり、特にライマンの評価に関する神保・坂論争を扱っている。神保は定年前に56歳で病没し、佐藤伝蔵が追悼文を献じた(1924a; 地質雑, 30, 図版15, 1924b; 地学雑, 36(421), 179-182)。そこでは北海道の地質構造論と白亜系生層序、日本産鉱物の記載が神保の最も主要な業績とされている。小伝ではなるべくこれらとの重複を避け、雑誌や著書に表れた神保小虎の学問と人となりを中心に述べる。
神保小虎は多くの地質学・鉱物学の書籍を執筆出版したが、現在でも復刻販売されている彼の著書に「アイヌ語会話字典」(北海道出版企画センター1986年再版)がある。これは金澤庄三郎と共著の1892年初版の本であり、旅行や生活の場面や事柄ごとに日本語の会話文に対応するアイヌ語をローマ字で示したものである(例えば「この旦那を知って居るか=Tan nishpa eraman?」)。彼は英、独、仏、露、西語に堪能で、北海道調査の中でアイヌ語も習得し、アイヌ語の地名がその土地の地形や地質をよく表していることを見出し、アイヌの人々に「神保ニシパはアイヌなり」と言わしめたという(佐藤, 1924b)。この一事を見ても神保小虎の類稀な幅広い才能と縦横無尽の活躍が伺える。
神保は学生の指導や地質学の一般人への教育・普及に熱心だった反面、敵・味方がはっきりしていて、敵には容赦ない論争を挑む性癖があった。有名なのはライマンの評価に関する上述の1890年の神保・坂論争(地学雑, 2, 7-11, 53-54, 147-148)で、「私が書いた事がお解りに成りませんければもう一度お読みなさい別にお返事は致しません」という返答の冒頭の一文は今でも語り草である。1912年にも鉱物学の教科書を批判し、その著者の和田八重造が反論した(地質雑, 19, 163-164, 240-249)。神保は「「文部省の教授要目説明書」とも称すべき本書には地質鉱物及び土壌を真に学習せる人が恐らくほとんど一人も賛成しがたき順序をそのままに採用し在り」、「大害無き代りに小益も無かるべし」などと批判して、「この篤学の著者が文部省に代りてその要目の趣意を明らかにしたるは大いに教育家の参考となるべきものにして、その「利害」を明らかにしたる功は没すべからず」と1ページ強の書評を結んでいる。これに対し和田は10ページの反論をなし、最後に「教育上の考の相違から来て居るのであるから遺憾ながら毫も敬服出来ない」と怒りをぶつけている。地質学雑誌における神保の執筆記事は多数あるが、地すべりの調査報告など応用地質関係の雑録・雑報や内外の教科書の解題(書評)が多く、原著論文は案外少ない。ただし、ロシア語の文献紹介や直接会見したロシア人地質学者から聞き書きしたサハリン、シベリアなどの地質に関する記事は貴重である。また、変わったところでは、当時までに落下・発見された国内の隕石についてのレビューを書いている(地質雑, 12, 229-234, 309-317 (1905))。
ここでは、神保の数多い著書の中から、いかにも初代会長にふさわしいタイトルの「日本地質学」(金港堂, 245ページ+索引)を紹介する。この本は1896年初版だが、筆者が読んだのは1916年の再版である。まず巻頭に折り込みの日本地質図(地域割が県界でなく旧国界、阿武隈・飛騨片麻岩や三波川結晶片岩が「太古統」)を掲げ、総論の最初に地質学の目的として、「ただに地の質を学ぶものにあらざるなり。畑の土を記するにあらざるなり。単に地球の諸性を説くにあらずして、その始めより今日に至るまでの発育をもってその最上の主眼となすものなり」と述べている。そのあと、「地質学の応用ならびに日本における地質調査」を詳述し、関連学会や学術誌を列挙しているが、この総論はどう見ても初学者向きではない。本編は1.地殻の察相、2.岩石、3.地殻の変動、4.岩石の生源、5.岩石の配置(地殻構造)、6.地史の各篇に分かれ、附録として地質巡検規則と修学旅行の設計、上野帝国博物館鉱物地質の部案内がある。日本の実例を重視し、前著「新編地質学」ではベスビオス火山の噴火やリスボン地震の例を用いたが、本書では磐梯山・浅間山の噴火や濃尾地震について詳しく解説している。地質巡検(調査)規則では、「地質巡検なるものは徒(いたずら)に杖(つえ)を曳(ひ)き飄然(ひょうぜん)として千歳(せんざい)の古跡を探り或は名勝を尋(たず)ぬるが如きものにあらずして」、「(岩石、化石、鉱脈などを実検して)土地の構造ならびに地盤の変遷の歴史を尋ぬるを以て地質巡検の業とす」と述べている。「記録に関する注意」として、「己れは記憶善(よ)き者と誤認してその筆記を粗(おろそか)にするは最も避くべき事にして如何なる瑣事(さじ)も見たるとき直に之を筆記し後に磨滅等にて不明とならざる様注意すべし」、「夕飯後想起して記録する時は既に誤りを生じ易し」、「午前と午後、坂路の上下に由りて観察に精粗あるを免れず」、「自己の観察は多少不完全なれば必ず多くの図書を参考し」、「その地方の人に就き事実を聞き取るを要す。然れども一々これを信ずべからず。ただ淡泊に聞き天然に発言せしめてその真を得るを務むべし」など、長年の野外調査の経験に基づく勘所を述べている。修学旅行(巡検)案内は、東京上野から上越線に乗り深谷で下車し、秩父、下仁田を経て妙義山まで関東山地を歩き、信越線松井田駅から汽車で上野に帰る11日間のコースと、山口県の防府市三田尻港から山口、厚狭を経て下関に至る1週間のコースを説明している(なぜか秋吉台には行かない)。これらは実際に学生と巡検したコースだと思われ、例えば関東コースの第1日は「上野停車場を出発す。汽車は第四紀洪積世に属するローム(loam)の丘陵に沿うて進む。王子の断崖にてその第三紀層を被覆するを目撃すべし」で始まる。「(蛇紋岩の)破片は非常に鋭きを以て鉄鎚を加うるの際往々手を切ることあり」とか、「砂岩は通例不規則に割れて走向と傾きを測ること極めて難し。シェールもまた然り。注意すべし」といった学生への細かい注意書きが随所に見られる。本書に記述された事実や理論には既に通用しないものがあるが、野外地質学の優れた先達の言葉として今でも味読すべき部分が多い教科書である。
「先生は六尺豊かの体躯の持主で語学に堪能であられ、反面ユウモラスで又温情の持主であった」(江原真伍, 60周年記念誌)。筆者はこの初代会長をもった本学会を誇りとする。佐藤(1924b)の追悼文に掲載された漢詩を読み下し文で再録し、この小伝を結ぶ。
恭(つつし)んで神保理学博士を悼(いた)む 二首 犀東国府種徳
全球を踏み尽くして地層を析(ときひら)く
君に馮(よ)りて奇勝は盛名を昇らす
何ぞ仙境を尋ね 天を排(おしのけ)て去る
旧識の千山 哭して崩れんと欲す
健(けん)歩(ぽ)人を驚かして通らざる莫(な)く
畢生(ひっせい)険しき夷(えびす)の空を跟底(くつぞこ)とす
白雲郷の裏(うち)に鎚(ハンマー)を揮(ふる)うこと迅(はや)く
敲(たた)いて未知の岩石中に入る
メールマガジン geo-Flash No.254 (2014/4/1配信)掲載
【geo-Flash】No.498 WEB表彰式・記念講演会ほか9/13配信!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.498 2020/9/1┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】名古屋大会代替:WEB表彰式・記念講演会ほか 9/13配信
【2】令和2年7月豪雨災害等地質災害関連情報
【3】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【4】コラム:柱状節理は低温の発泡膨張,板状節理は高温の流動剪断でできる
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】名古屋大会代替:WEB表彰式・記念講演会ほか 9/13配信
──────────────────────────────────
2020年度顕彰・各賞受賞式・受賞記念講演会(WEB)
日時:2020年9月13日(日)14時より(どなたでもご視聴いただけます)
配信URL: https://youtu.be/-d_2WIoKmeQ
プログラムはこちら
http://www.geosociety.jp/science/content0124.html
このほかWEBによる代替企画!様々な企画が進んでいます!
第1回ショートコースも間もなく締切です。
・第1回ショートコース 9/19開催[参加申込受付中:9/7締切]
・コロナ禍での地質学教育に関するサイバーシンポジウム 9/27開催
(プレゼンター決定 参加無料、どなたでも視聴可能!)
・ジュニアセッション(旧小さなESの集い)[参加校募集中:9/30締切]
ほか
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0041.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】令和2年7月豪雨災害等地質災害関連情報
──────────────────────────────────
令和2年7月豪雨災害関する情報
http://www.geosociety.jp/hazard/content0098.html
地質災害緊急調査について
http://www.geosociety.jp/hazard/content0024.html
会費の特別措置のお知らせ
http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html#saigai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・126巻8月号 特集号「法地質学の進歩」(9/2発送)
「法地質学入門」(ノート)杉田律子ほか/「石英粒子の形状および表面形態
を用いた法科学的検査法の開発」(論説)板宮裕実ほか/「日本の法地質学
の歩み」(総説)組坂健人ほか/「法地質学の国際動向」(総説)杉田律子/
「The geoforensic search strategy: A high assurance search method to assist
law enforcement locate graves and contraband associated with
homicide, counter terrorism and serious and organized crime」(総説)
Donnelly and Harrison/「法地質学のツールとしての磁気測定:レビュー」
(総説)川村紀子
■ Island Arc
新しい論文等が公開されています.
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14401738/2020/29/1
LaTeXテンプレートを公開しました。
クラウド型共同執筆ツールのAuthoreaでも利用可能です。
https://authorea.com/templates/island_arc_iar_
Island Arcでは著者制作のVideo Abstractの掲載が可能です.
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14401738/homepage/video_abstracts
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】コラム:柱状節理は低温の発泡膨張,板状節理は高温の流動剪断でできる
──────────────────────────────────
正会員 石渡 明
地学事典は,溶岩・岩脈・岩床等に見られる柱状節理(columnar joint)
について,「岩体の冷却時の体積収縮によって形成され」,「柱状節理
の間隔(spacing)は冷却速度に比例し,ゆっくり冷えれば間隔が大きく
なると考えられている(Spry, 1962)」と記し,板状節理(platy joint)
も「冷却時に形成される」と記している(平野・横田, 1996).
続きはこちらから、、、 http://www.geosociety.jp/faq/content0920.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
日本学術会議提言『「地理総合」で変わる新しい地理教育の充実に向けて
―持続可能な社会づくりに貢献する地理的資質能力の育成―』
が公開されました。
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/division-15.html
-----------------------------------------------------------------------
(後)企画展 ゴンドワナ−岩石が語る大陸の衝突と分裂−
会場:神奈川県立生命の星・地球博物館(7/1より再開)
開催中-11月8日(日)
http://nh.kanagawa-museum.jp/exhibition/special/ex188.html
(後)旭町学術資料展示館企画展示
「ジオパークの微化石展」
8月1日(土)-9月6日(日)
会場: 新潟大学旭町学術資料展示館(新潟市中央区旭町通)
http://www.lib.niigata-u.ac.jp/tenjikan/
ぼうさいこくたい2020
頻発化する大規模災害に備える
−「みんなで減災」助け合いをひろげんさい−
10月3日(土)[オンライン大会]
http://bosai-kokutai.jp/
(協)第36回ゼオライト研究発表会
11月19日(木)-20 日(金)
場所:富山国際会議場
https://jza-online.org/events
(共)日本地球化学会第67回オンライン年会
11月12日(木)-26日(木)WEB上での発表資料に対する議論
11月19日(木)-21日(木)Zoomでのセッション企画
(注)地質学会員は地球化学会員と同じ参加費(一般:2000円
/学生:無料)で参加できます.
講演申込締切:9月23日(水)17時
参加申込締切:11月4日(水)17時
https://www.geochem-conf.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募情報・各賞助成情報等
─────────────────────────────────
・弘前大学大学院理工学研究科自然災害科学分野(助教)公募(10/16)
・新潟大学自然科学系地球惑星科学分野助教公募(女性限定・任期無)(10/20)
・千葉県職員採用選考考査(地質職)(受付期間:8/25-9/18)
・山梨県富士山科学研究所任期付研究員募集(10/16)
・2021年度笹川科学研究助成 (9/15-10/15)
・2021年度山田科学振興財団海外研究援助 (10/31)
・原子力規制人材育成事業の令和2年新規採択事業の公募(公募期間:9/3-1カ月)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.499(臨時)名古屋大会代替:構造地質部会例会 開催決定!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.499 2020/9/4┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】名古屋大会代替:構造地質部会2020年度オンライン例会開催決定!
──────────────────────────────────
若手を中心とした研究発表会、「構造地質部会2020年度オンライン例会」を
開催いたします。つきまして、9月28日まで予稿投稿を受け付けております。
皆様、どうぞふるってご参加ください。
http://struct.geosociety.jp/activity.html
大会趣旨
現在、新型コロナウイルス対策のために学術研究発表もその多くが中止・延期とな
っています。これに伴い、地球科学に携わる学生や若手研究者の研究発表の機会
が制限されることが懸念されています。研究開始から間もなく研究業績が求められ
る学生や若手研究者にとって、学術大会は重要な研究発表の場であるため、学会
の中止・延期により各々の業績に「年度間の不公平」が生まれかねません。この状
況を鑑み、構造地質部会では学生や若手研究者の発表の機会を設けるべくオン
ライン会議ツールを使用した学術大会を開催します。本部会において、オンライン
での学術大会開催は初めての試みとなります。若手研究者、学生の方の活発な発
表と皆様の議論の場となりますよう、ご参加・ご協力をお願いいたします。
日程
予稿投稿締切:2020年9月28日(月)
参加登録締切:2020年10月2日(金)
オンライン例会:2020年10月7日(水)-9日(金)
1日3時間程度を想定。発表者数により変動。
参加料・投稿料
本例会では参加料、投稿料はございません。
対象
構造地質3セクション「岩石・鉱物の変形と反応」・「沈み込み帯・陸上付加体」・
「テクトニクス」に関する研究の発表を学生と若手から広く募集します。
ただし、「若手」の定義につきましても学会や機関によりばらつきがありますので、
「自分は若手である」という方の発表も歓迎します。
詳細は下記をご覧下さい.
http://struct.geosociety.jp/activity.html
このほかの名古屋大会 代替企画の情報はこちら
http://www.geosociety.jp/science/content0041.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.501(臨時) 名古屋大会代替:地域地質部会・層序部会合同オン ライン研究発表会の事前アンケート
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.501 2020/9/24┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】名古屋大会代替:地域地質部会・層序部会
合同オンライン研究発表会の事前アンケート(9/30回答締切)
──────────────────────────────────
地域地質部会と層序部会は,若手に研究発表の場を提供するオンラ
イン発表会の開催を検討しています。学術大会レギュラーセッション
「地域地質・地域層序・年代層序」に相当する,地域地質や層序に関
する研究発表を広く受け付ける予定です。この機会にぜひ,ご自身の
研究を広く紹介し,よい意味で自分を売り込んでください。あらかじめ
発表予定数を把握したいため(発表予定数がかなり少ない場合は開
催しない可能性があります),簡単なアンケートにご回答ください。お
知り合いに若手がいる場合はぜひこのアンケートを知らせてあげてく
ださい。ご協力のほど,よろしくお願いいたします。
<対象・その他>
「若手」は主に院生・ポスドク・助教・常勤講師クラスを想定していま
すが,ご自身が「若手」と思っている方は発表できます。発表共著者に
地質学会員の方が含まれていれば会員でなくても発表できます。開
催日は11月中旬の土曜または日曜を想定しています。参加費及び
発表登録費は無料を想定しています。要旨(アブストラクト)の提出
は不要です。大会概要とプログラムをオンライン公開することを想定
しています(必要な方には発表証明書を発行します)。その他の詳細
についてはアンケートをご覧ください。
**************************
アンケート回答期限:9月30日(水)20時
**************************
https://forms.gle/fgPASwRMEHHBd8L39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】名古屋大会代替:サイバーシンポジウム 9/27配信
──────────────────────────────────
コロナ禍での地質学教育に関する情報交換・共有を目的とした
サイバーシンポジウムを開催しますので,ぜひご参加ください(この週末です)。
大学,高校,博物館,ジオパークからの事例報告とディスカッションがあります。
コロナ禍での地質学教育に関するサイバーシンポジウム(オンライン)
日時:2020年9月27日(日)9時30分〜12時15分(予定)
開催方法:YouTubeライブ配信
※どなたでも視聴可能.事前申込不要.参加費無料.
プログラムはこちら
http://www.geosociety.jp/science/content0123.html
WEBによる代替企画,まだまだあります!
・第2回ショートコース(10/24(土)開講)の受講申込受付開始!!
[10/19(月)申込締切,地質学会会員優先,定員100名]
・構造地質部会2020年度オンライン例会 10/7(水)-9(金)開催
[予稿投稿受付中:9月28日締切]
・ジュニアセッション(旧小さなESの集い)[参加校募集中:9/30締切]
・四国支部講演会 12/5開催(対面開催の場合:会場は愛媛大学)
ほか
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0041.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash No.500】 名古屋大会代替企画:様々な企画がどんどん進んでいます!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.500 2020/9/16┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】名古屋大会代替企画
【2】令和2年7月豪雨災害等地質災害関連情報
【3】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【4】その他のお知らせ
【5】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】名古屋大会代替企画
──────────────────────────────────
様々な企画がどんどん進んでいます!
・9/13のWEB表彰・顕彰・記念講演会はYouTubeで限定公開中!
https://youtu.be/-d_2WIoKmeQ
・コロナ禍での地質学教育に関するサイバーシンポジウム 9/27開催
(プレゼンター決定 参加無料、どなたでも視聴可能!)
・ジュニアセッション(旧小さなESの集い)[参加校募集中:9/30締切]
・構造地質部会2020年度オンライン例会(参加費・投稿料無料)
[予稿投稿締切:9/28(月)/参加登録締切:10/2(金)]
・第2回ショートコース 10/24開催[まもなく参加申込受付開始]
・四国支部講演会 12/5開催(対面開催の場合:会場は愛媛大学)
ほか
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0041.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】地質災害関連情報
──────────────────────────────────
令和2年7月豪雨災害関する情報/令和2年台風10号による災害の情報
http://www.geosociety.jp/hazard/category0020.html
地質災害緊急調査について
http://www.geosociety.jp/hazard/content0024.html
会費の特別措置のお知らせ
http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html#saigai
<防災学術連携体>台風10号特設ページ
https://www.janet-dr.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・126巻9月号(予告)
「鹿児島湾奥,新島に露出する最上部更新統〜完新統の層序と起源」(論説)
鹿野和彦ほか/「地震性地殻変動と大規模ラハールによって規制された開析
谷埋積シークエンス」(論説)七山 太ほか/「草津白根火山,本白根火砕丘群
の地質と形成史」(論説)石崎泰男ほか/「御蔵島東方で採取された深海堆積
物のタービダイト泥層と半遠洋性泥層の同定と半遠洋性泥層の堆積年代」(レ
ター)川村喜一郎ほか/「岐阜県高山市高根地域に分布する安山岩質平行岩
脈群のK–Ar 年代」(報告)丹羽正和ほか
■ Island Arc
・新しい論文等が公開されています.
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14401738/0/ja
・LaTeXテンプレートを公開しました。クラウド型共同執筆ツールのAuthoreaでも利用可能です。https://authorea.com/templates/island_arc_iar_
・Island Arcでは著者制作のVideo Abstractの掲載が可能です.
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14401738/homepage/video_abstracts
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)企画展 ゴンドワナ−岩石が語る大陸の衝突と分裂−
会場:神奈川県立生命の星・地球博物館(7/1より再開)
開催中-11月8日(日)
http://nh.kanagawa-museum.jp/exhibition/special/ex188.html
日本鉱物科学会2020年年会
9月16日(水)-18日(金)[オンライン大会]
(注)総会、授賞式のみ9/15に会場で実施
*講演要旨の閲覧とzoomへの参加は無料
http://jams.la.coocan.jp/2020nenkai/2020_nenkai_HP.html
日本学術会議公開講演会
「AI戦略の地方への展開−大学におけるデータサイエンス教育と地域連携」
9月27日(日)12:50-15:45[オンライン開催]
【プログラム】http://www.scj.go.jp/ja/event/2020/285-s-0927.html
定員300名・要事前申込
http://ds22.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~ken-san/SCJ/
原子力総合シンポジウム2020
9月30日(水)13:00-17:10[オンライン]
参加費無料(事前登録制)
http://aesj.net/hp/2020/07/22/symp20200930/
ぼうさいこくたい2020
頻発化する大規模災害に備える
−「みんなで減災」助け合いをひろげんさい−
10月3日(土)[オンライン大会]
http://bosai-kokutai.jp/
地区防災計画学会シンポジウム(第35回研究会)
「ウィズコロナ時代のコミュニティ防災」
10月10日(土)13:00-15:30(予定)
オンライン開催(YouTubeによるライブ配信等)
主催:地区防災計画学会
対象:地域防災力の強化や地区防災計画づくりに興味のある方
参加費無料
https://gakkai.chiku-bousai.jp/
日本堆積学会2020年オンライン大会
11月7日(土),14日(土):特別講演・個人講演,懇親会
(発表者が少ない場合には11月14日のみとなる場合があります)
参加費:一般会員,学生会員,非会員一般,非会員学生 すべて無料
講演申込締切:9月25日(金)
大会参加申込締切:11月6日(金)正午
http://www.sediment.jp/04nennkai/2020/2020online_annai.html
(協)第36回ゼオライト研究発表会
11月19日(木)-20 日(金)
場所:富山国際会議場
https://jza-online.org/events
(共)日本地球化学会第67回オンライン年会
11月12日(木)-26日(木)WEB上での発表資料に対する議論
11月19日(木)-21日(木)Zoomでのセッション企画
(注)地質学会員は地球化学会員と同じ参加費(一般:2000円
/学生:無料)で参加できます.
講演申込締切:9月23日(水)17時
参加申込締切:11月4日(水)17時
https://www.geochem-conf.jp/
第30回環境地質学シンポジウム
11月27日(金)-28日(土)
[オンライン開催](Zoomミーティング使用予定)
発表申込期日:9月30日(水)
https://www.jspmug.org/envgeo_sympo/30th_sympo/30th_sympo.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】公募情報・各賞助成情報等
─────────────────────────────────
・2021年度東京大学地震研究所客員教員(10/30)
・2021年度東京大学地震研究所共同利用(10/30)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.502 2021年度各賞候補者募集(12/1締切)始まります
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.502 2020/10/6┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2021年度学会各賞候補者募集(12/1締切)
【2】名古屋大会代替企画
【3】令和2年7月豪雨災害等地質災害関連情報
【4】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【5】地質学論集58号再度販売いたします
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2021年度学会各賞候補者募集(12/1締切)
──────────────────────────────────
日本地質学会では今年も運営規則第16条および各賞選考規則にした
がい,賞の候補者を募集いたします
ご応募いただいた場合には,必ず受け取りのお返事をお出しします
のでご確認ください.
*********************************************
応募締切:2020年12月1日(水)必着
*********************************************
詳しくは, http://sub.geosociety.jp/members/content0098.html
(会員ページへのログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】名古屋大会代替企画
──────────────────────────────────
様々な企画がどんどん進んでいます!
・コロナ禍での地質学教育に関するサイバーシンポジウム
(終了しました。YouTubeで公開中です)
・ジュニアセッション 16校18件の申込を頂きました
・第2回ショートコース 10/24開催[参加申込受付中:10/12締切]
(午前の部)層序学の基礎と応用
(午後の部)統計解析言語Rを用いた地球科学データ解析基礎実習
・JABEEオンラインシンポ(来春3/7開催)プログラム案掲載しました
ほか
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0041.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】地質災害関連情報
──────────────────────────────────
令和2年7月豪雨災害関する情報/令和2年台風10号による災害の情報
http://www.geosociety.jp/hazard/category0020.html
地質災害緊急調査について
http://www.geosociety.jp/hazard/content0024.html
会費の特別措置のお知らせ
http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html#saigai
<防災学術連携体>台風10号特設ページ
https://www.janet-dr.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・126巻9月号が発行されました
「鹿児島湾奥,新島に露出する最上部更新統〜完新統の層序と起源」(論説)
鹿野和彦ほか/「地震性地殻変動と大規模ラハールによって規制された開析
谷埋積シークエンス」(論説)七山 太ほか/「草津白根火山,本白根火砕丘群
の地質と形成史」(論説)石崎泰男ほか/「御蔵島東方で採取された深海堆積
物のタービダイト泥層と半遠洋性泥層の同定と半遠洋性泥層の堆積年代」(レ
ター)川村喜一郎ほか/「岐阜県高山市高根地域に分布する安山岩質平行岩
脈群のK–Ar 年代」(報告)丹羽正和ほか
・投稿編集出版規則が一部改正されました
先月9/12理事会において、規則の一部改正が承認されました。
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/publication/content0096.html
■ Island Arc
・新しい論文等公開されています.
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14401738/0/ja
・LaTeXテンプレートを公開しました。クラウド型共同執筆ツールのAuthoreaでも利用可能です。 https://authorea.com/templates/island_arc_iar_
・Island Arcでは著者制作のVideo Abstractの掲載が可能です.https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14401738/homepage/video_abstracts
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質学論集58号再度販売いたします
──────────────────────────────────
地質学論集 第58号
「地震イベント堆積物 −深海底から陸上までのコネクション−
藤原 治ほか編 169頁 2004年12月刊行 会員頒価2,900円(+送料)
論集58号は、これまで売り切れとなっていましが、在庫が確認されました
ので、再度販売いたします。冊子購入希望の方は、学会事務局までお申し
込み下さい。
メール: main@geosociety.jp FAX:03-5823-1156
このほか学会出版物在庫案内はこちら
http://www.geosociety.jp/publication/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
・文部科学省の「科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会
学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会」において決定された
ロードマップ2020が公表されました
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/toushin/1388523_00001.htm
------------------------------------------
(後)企画展 ゴンドワナ−岩石が語る大陸の衝突と分裂−
会場:神奈川県立生命の星・地球博物館(7/1より再開)
開催中-11月8日(日)
http://nh.kanagawa-museum.jp/exhibition/special/ex188.html
(協)第36回ゼオライト研究発表会
11月19日(木)-20 日(金)
場所:富山国際会議場
https://jza-online.org/events
(共)日本地球化学会第67回オンライン年会
11月12日(木)-26日(木)WEB上での発表資料に対する議論
11月19日(木)-21日(木)Zoomでのセッション企画
(注)地質学会員は地球化学会員と同じ参加費(一般:2000円
/学生:無料)で参加できます.
参加申込締切:11月4日(水)17時
https://www.geochem-conf.jp/
第31回 地質汚染調査浄化技術研修会
11月13日(金)-15日(日)
会場:NPO法人日本地質汚染審査機構 関東ベースン実習センター
(千葉県香取市)
参加費用:会員45,000円・非会員 55,000円・学生:15,000円
*要事前申込
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
(後)第30回環境地質学シンポジウム
11月27日(金)-28日(土)
[オンライン開催](Zoomミーティング使用予定)
発表申込:10月10日(土)締切延長しました
https://www.jspmug.org/envgeo_sympo/30th_sympo/30th_sympo.html
海と地球のシンポジウム2020(オンライン)
12月17日(木)-18日(金)
東京大学大気海洋研究所(AORI)とJAMSTECは、JAMSTECが
運用する研究船等を利用し、全国の研究者・技術者・学生等
により行われた研究や技術開発の成果報告会を開催します。
http://www.jamstec.go.jp/j/pr-event/ocean-and-earth2020/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
─────────────────────────────────
・愛媛大学大学院理工学研究科地球進化学講座・助教(女性限定)公募(11/6)
・放射性廃棄物の地層処分に係る萌芽的・基礎的研究テーマ及び研究実施者の募集 (10/19)
・2021年度山田科学振興財団研究援助募集(学会締切21/2/10)
・第62回藤原賞募集(学会締切11/30)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.503 学術会議第25期推薦会員任命拒否に関する緊急声明へ賛同
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.503 2020/10/20┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】日本学術会議第25期推薦会員任命拒否に関する緊急声明へ賛同しました
【2】2021年度会費払い込みについて(次年度割引会費申請受付開始)
【3】2021年度学会各賞候補者募集(12/1締切)
【4】名古屋大会代替企画
【5】JpGU2021セッション提案について
【6】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【7】論集58号再度販売いたします
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】日本学術会議第25期推薦会員任命拒否に関する緊急声明へ賛同しました
──────────────────────────────────
現在、日本学術会議の推薦会員の任命を巡っていろいろな報道がなされ
ています。日本地質学会が所属する日本地球惑星科学連合においても、
対応について議論がなされました。また他の学術連合においても同様な
議論がなされ、それらの結果として、複数の学会連合が共同声明を出す
ことになりました。日本地質学会は,日本地球惑星科学連合および自然
史学会連合の参加学会として声明に賛同いたしました。
2020年10月10日
会長 磯崎行雄
詳しくは、http://www.geosociety.jp/engineer/content0055.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2021年度会費払い込みについて(次年度割引会費申請受付開始)
──────────────────────────────────
自動引落を登録されている方:
引き落とし日は,2020年12月23日(水)です.
割引会費の申請について:
学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)の方で,
それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適用します.
なお,2020年度までの院生割引会費についての申請は終了しております
ので,2021年度会費にのみ適用となります.
※割引の適用を希望する場合,申請は毎年必要です.
**************************
2021年度分割引会費(請求書発行前締切):2020年11月20日(金)
**************************
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2021年度学会各賞候補者募集中(12/1締切)
──────────────────────────────────
日本地質学会では今年も運営規則第16条および各賞選考規則にした
がい,賞の候補者を募集いたします
ご応募いただいた場合には,必ず受け取りのお返事をお出しします
のでご確認ください.
*********************************************
応募締切:2020年12月1日(水)必着
*********************************************
詳しくは,http://sub.geosociety.jp/members/content0098.html
(会員ページへのログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】名古屋大会代替企画
──────────────────────────────────
様々な企画がどんどん進んでいます!
・開催決定!第2回コロナ禍での地質学教育に関するサイバーシンポジウム
(11/29(日)YouTube生配信.プレゼンター決まりました)
・ジュニアセッション 16校18件の申込を頂きました.ただいま審査中.
・第2回ショートコース 10/24開催・申込締切ました
・JABEEオンラインシンポ(来春3/7開催)「自然災害列島における
地質技術者の育成−大学統合期における地質学教育ー」プログラム案掲載
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0041.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】JpGU2021セッション提案について
──────────────────────────────────
JpGU2021でセッション提案を予定している方で,地質学会共催にしたい
場合は,併行して下記地質学会のJpGUプログラム委員にご連絡いただき
ますようお願い致します。すでに提案済みの場合も,これからでも結構
ですので,プログラム委員にご連絡をお願い致します.
納谷友規(層序部会選出行事委員) t-naya[at]aist.go.jp
松崎賢史(海洋地質部会選出行事委員) kmatsuzaki[at]g.ecc.u-tokyo.ac.jp
(注)[at]を@マークにして送信してください.
[セッション提案期間]2020年10月13日(火)から11月4日(水)17:00
セッション提案の詳細は,JpGUのサイトをご参照ください.
http://www.jpgu.org/meeting_j2021/for_conv.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・126巻10月号(予告)まもなく発行です.
(口絵)Outcrop of a fault damage zone of the Ikeda fault, the Median
Tectonic Line, in eastern Shikoku, southwest Japan: Michiharu
Ikeda et al/(論説)東京都産古生代前期造山帯の断片:関東山地東部,
黒瀬川帯高圧型変斑れい岩および花崗岩類のジルコンU–Pb年代:沢田
輝ほか/(論説)東京都北区中央公園ボーリングコアにみられる更新統
東京層の層序:納谷友規ほか/(論説)Geological age of the Ayukawa
Formation (Oshika Group) in the South Kitakami Belt, Northeast Japan
based on the ammonoids: Masayuki Ehiro et al/(レター)北海道
神居古潭変成岩類班渓幌内ユニットからの新たなジルコンU–Pb年代:
長田充弘ほか/(レター)北海道南西部,羊蹄火山東麓に分布する緑色
凝灰岩層のジルコンU-Pb年代:上澤真平
■ Island Arc
・新しい論文等が公開されています.
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14401738/0/ja
・LaTeXテンプレートを公開しました。クラウド型共同執筆ツールのAuthorea
でも利用可能です。https://authorea.com/templates/island_arc_iar_
・Island Arcでは著者制作のVideo Abstractの掲載が可能です.
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14401738/homepage/video_abstracts
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】論集58号再度販売いたします
──────────────────────────────────
地質学論集 第58号
「地震イベント堆積物 −深海底から陸上までのコネクション−
藤原 治ほか編 169頁 2004年12月刊行 会員頒価2,900円(+送料)
論集58号は、これまで売り切れとなっていましが、在庫が確認されました
ので、再度販売いたします。冊子購入希望の方は、学会事務局までお申し
込み下さい。メール:main@geosociety.jp FAX:03-5823-1156
このほか学会出版物在庫案内はこちら
http://www.geosociety.jp/publication/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
・北海道立総合研究機構エネルギー・環境・地質研究所
「サイエンスパーク・ファンのコンテンツ」公開中
今年度は、新型コロナウイルス感染症対策等のため、7/20-8/31にWEB上での
開催となりました。開催期間は終了しましたが、当面の間、コンテンツを公開
しております.ぜひご覧ください。
https://www.hro.or.jp/list/industrial/research/eeg/pr/events/scienceparkfan2020.html
------------------------------------------
(後)企画展 ゴンドワナ−岩石が語る大陸の衝突と分裂−
会場:神奈川県立生命の星・地球博物館(7/1より再開)
開催中-11月8日(日)
http://nh.kanagawa-museum.jp/exhibition/special/ex188.html
「おうちで深田研」
深田研一般公開2020オンライン
10月25日(日)10:30-15:00 WEB配信
「研究所紹介」および「化石の日2020スペシャルトーク」を配信
参加費 無料 *要事前登録(申込締切10/21)
https://fukada-g.jp/?p=5134
ICDP掘削提案促進ワークショップ
「新たな掘削提案の展望-陸上から海洋まで-」
11月5日(木)- 6日(金)両日とも9:00 - 12:00
形態:オンライン開催(Zoomミーティング使用)
主催:日本地球掘削科学コンソーシアム(J-DESC)
http://j-desc.org/icdp_ws_2020/
(共)日本地球化学会第67回オンライン年会
11月12日(木)-26日(木)WEB上での発表資料に対する議論
11月19日(木)-21日(木)Zoomでのセッション企画
(注)地質学会員は地球化学会員と同じ参加費(一般:2000円
/学生:無料)で参加できます.
参加申込締切:11月4日(水)17時
https://www.geochem-conf.jp/
第31回 地質汚染調査浄化技術研修会
11月13日(金)-15日(日)
会場:NPO法人日本地質汚染審査機構 関東ベースン実習センター
(千葉県香取市)
参加費用:会員45,000円・非会員 55,000円・学生:15,000円
*要事前申込
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
日本堆積学会2020年オンライン大会
11月14日(土)
参加費:会員・非会員問わず全て無料
参加申込締切:11月11日(水)
http://www.sediment.jp/04nennkai/2020/2020online_annai.html
(協)第36回ゼオライト研究発表会
11月19日(木)-20 日(金)
場所:富山国際会議場
https://jza-online.org/events
堆積学スクール2020
「石油地質学の基礎と地下地質データの堆積学的解析」
11月21日(土)10:00開始,22日(日)16:00終了予定(1日目のみの参加可)
実施形態:Zoomを使用したオンライン開催
参加費:一般会員・学生会員 無料,非会員一般2,000円,非会員学生 1,000円
http://sediment.jp/04nennkai/2020/school.html
(後)第30回環境地質学シンポジウム
11月27日(金)-28日(土)
[オンライン開催](Zoomミーティング使用予定)
https://www.jspmug.org/envgeo_sympo/30th_sympo/30th_sympo.html
海と地球のシンポジウム2020(オンライン)
東京大学大気海洋研究所(AORI)・JAMSTEC共催
12月17日(木)-18日(金)
http://www.jamstec.go.jp/j/pr-event/ocean-and-earth2020/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
─────────────────────────────────
・山形大学学術研究院 (理学部主担当 地球科学分野)助教(女性限定・テニュアトラック)公募(11/13)
・北海道大学大学院理学研究院地球惑星科学部門地球惑星システム科学分野教授公募(12/1)
・JAMSTEC超先鋭研究開発部門超先鋭研究プログラムor高知コア研究所地球微生物学研究G 研究員公募(12/14)
・日本学術会議:共同主催国際会議募集(対象:2022年度開催)(11/30)
・放射性廃棄物の地層処分に係る萌芽的・基礎的研究テーマ及び研究実施者の募集 (11/9:締切延長)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.504 惑星地球フォトコンテスト:作品募集開始
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.504 2020/11/4┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2021年度会費について(学部生・院生割引会費申請受付中)
【2】2021年度学会各賞候補者募集中(12/1締切)
【3】名古屋大会代替企画
【4】第12回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
【6】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【7】論集58号再度販売いたします
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2021年度会費について(学部生・院生割引会費申請受付中)
──────────────────────────────────
・自動引落を登録されている方:引落日は,2020年12月23日(水)です.
新たに会費の自動引落をご希望の方は,振替依頼書を11月9日(月)までに
事務局までお送りください.※口座変更希望の場合も、口座振替依頼書を改
めてお送りください.依頼書は学会HPからダウンロードできます.
・割引会費の申請について:学部に在籍している学生の方,定収のない大学
院生(研究生)の方で,それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引
会費を適用します.なお,2020年度までの院生割引会費についての申請は
終了しておりますので,2021年度会費にのみ適用となります. ※割引の
適用を希望する場合,申請は毎年必要です.
************************************
2021年度分割引会費(請求書発行前締切):2020年11月20日(金)
************************************
・災害に関連した会費の特別措置:日本地質学会では,災害救助法適用
地域で被災された会員の方々のご窮状をふまえ,申請により会費を免除
いたします.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2021年度学会各賞候補者募集中(12/1締切)
──────────────────────────────────
日本地質学会では今年も運営規則第16条および各賞選考規則にした
がい,賞の候補者を募集いたします
ご応募いただいた場合には,必ず受け取りのお返事をお出しします
のでご確認ください.
*********************************************
応募締切:2020年12月1日(水)必着
*********************************************
詳しくは,http://sub.geosociety.jp/members/content0098.html
(会員ページへのログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】名古屋大会代替企画
──────────────────────────────────
まだまだ企画が進行中です!
・第2回コロナ禍での地質学教育に関するサイバーシンポジウム
(11/29(日)YouTube生配信.プログラム公開)
http://www.geosociety.jp/science/content0123.html
・JABEEオンラインシンポ(来春3/7開催)「自然災害列島における
地質技術者の育成−大学統合期における地質学教育ー」プログラム案掲載
http://www.geosociety.jp/science/content0127.html
そのほか代替企画の一覧は,
http://www.geosociety.jp/science/content0041.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第12回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
──────────────────────────────────
***応募締切:2021年2月1日(月)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募フォームからでも
メール添付でもご応募いただけます.
会員の皆様からの応募をお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・126巻11月号(予告)
(レター)天草下島北部の中新世貫入岩体の方向と応力解析:牛丸
健太郎ほか/(論説)室戸岬の玄武岩質貫入岩群の示唆する中期中新世
の逆断層型応力:羽地俊樹ほか/(ノート)On approximations of
EASY%Ro solutions to estimate maximum temperature from vitrinite
reflectance:Shunya Kaneki et al/(報告)愛知県設楽地域東部の
貫入岩体の全岩化学組成,輝度および変質度:図子田和典ほか
ほか計6編を予定
■ Island Arc
・新しい論文等が公開されています.
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14401738/0/ja
・LaTeXテンプレートを公開しました。クラウド型共同執筆ツールのAuthorea
でも利用可能です。https://authorea.com/templates/island_arc_iar_
・Island Arcでは著者制作のVideo Abstractの掲載が可能です.
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14401738/homepage/video_abstracts
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】論集58号再度販売いたします
──────────────────────────────────
地質学論集 第58号
「地震イベント堆積物 −深海底から陸上までのコネクション−
藤原 治ほか編 169頁 2004年12月刊行 会員頒価2,900円(+送料)
論集58号は、これまで売り切れとなっていましが、在庫が確認されました
ので、再度販売いたします。冊子購入希望の方は、学会事務局までお申し
込み下さい。メール:main@geosociety.jp FAX:03-5823-1156
このほか学会出版物在庫案内はこちら
http://www.geosociety.jp/publication/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
──────────────────────────────────
[四国支部]※名古屋大会代替企画
・第20回支部 総会・講演会のご案内
(講演会)12月5日(土) 13:00-17:05(予定)
場所:WEB開催(Zoomおよび愛媛大学理学部地学コースHP)
(総会)12月5日(土) 17:15-7:45(予定)
場所:WEB開催(Zoom)
参加・発表申込締切:11月20日(金)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0212.html#2020koen
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
電中研メールマガジン(2020年10月23日号より)
送電設備の巡視支援を目的とした土砂災害発生可能性の評価法の提案
https://criepi.denken.or.jp/jp/kenkikaku/report/detail/N20002.html?m=201023-1
----------------------------------------------------------
(後)企画展 ゴンドワナ−岩石が語る大陸の衝突と分裂−
会場:神奈川県立生命の星・地球博物館(7/1より再開)
開催中-11月8日(日)
http://nh.kanagawa-museum.jp/exhibition/special/ex188.html
(共)日本地球化学会第67回オンライン年会
11月12日(木)-26日(木)WEB上での発表資料に対する議論
11月19日(木)-21日(木)Zoomでのセッション企画
(注)地質学会員は地球化学会員と同じ参加費(一般:2000円
/学生:無料)で参加できます.
https://www.geochem-conf.jp/
第31回 地質汚染調査浄化技術研修会
(→中止となりました)
11月13日(金)-15日(日)
会場:NPO法人日本地質汚染審査機構 関東ベースン実習センター
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
(協)第36回ゼオライト研究発表会
11月19日(木)-20 日(金)
(注)オンライン開催(Zoom)に変更になりました
https://jza-online.org/events
第233回地質汚染・災害イブニングセミナー
11月20日(金)18:30-20:30
場所:北とぴあ701会議室(東京都北区王子)
講師:紱永朋祥 (東京大学大学院教授・日本地下水学会会長)
演題:「現在の地下水に関わる諸問題(仮題)」
定員:24名(事前申込制・先着順)
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
(後)第30回環境地質学シンポジウム
11月27日(金)-28日(土)
[オンライン開催](Zoomミーティング使用予定)
https://www.jspmug.org/envgeo_sympo/30th_sympo/30th_sympo.html
日本原子力研究開発機構
深地層の研究施設計画に関する報告会2020
12月1日(火)13:00-16:00
YouTubeライブ配信(事前申込制)※視聴無料
参加申込締切:11月20日(金)
https://www.jaea.go.jp/04/tisou/houkokukai/houkokukai_r02.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
─────────────────────────────────
・令和3年度「消防防災科学技術研究推進制度」新規研究開発課題募集 (12/23)
・日本科学未来館「研究エリア」入居プロジェクト募集 (11/27)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
津波と集落
津波と集落
正会員 高山信紀
まえがき
あと数ヶ月で東日本大震災から10年となる.この間,様々な分野で調査・研究が行われ,復興が進められ,膨大な画像や文献が公開されている.本記事では,筆者が訪れたことがあるいくつかの津波被災地の思い出と,このたびインターネットで調べたこれら被災地の津波被害と復興の一端を述べてみたい.
(1)南三陸町
2009年11月,宮城県南三陸町のJR気仙沼線清水浜駅で下車した.駅は高所にあり,駅の下に集落があった(写真1).駅の下で自転車を組立て,同町中心街の志津川から戸倉を通り,同町の津の宮にあった海の傍の民宿に泊り,翌日,戸倉から登米市柳津を経由し石巻に向かった.1年4ヶ月後に東日本大震災が発生するなど想像もしなかった.
南三陸町は,1896年明治三陸津波で死者1,240名,1933年昭和三陸津波で死者87名,1960年チリ津波で死者41名など大きな被害を受け,チリ津波後,高さ(標高.以下同様)4.6m程度の防潮堤の整備などが進められた1).その後,核家族化に伴う世帯数の増加などもあり,チリ津波浸水域の開発が進んだ1).東日本大震災の津波では,最大浸水高19.6m2),死者・行方不明者793名など大きな被害を受けた1).東日本大震災から半年後の2011年9月,岩手県洋野町から宮城県南三陸町までの三陸沿岸を車で見てまわった.清水浜駅は壊れ,駅の下にあった集落は無くなっており(写真2),志津川の市街は破壊され,津の宮の民宿は更地となっていた.
東日本大震災の後,国の“修正された防災基本計画では,今後の津波対策には二つのレベルの津波を想定し,<1>最大クラスの津波に対しては住民等の避難を軸に,ハード・ソフトの様々な施策を組み合わせる,<2>比較的発生頻度の高い一定程度の津波に対しては,人命保護に加え,財産の保護,地域の経済活動の安定化,効率的な生産拠点の確保の観点から,海岸堤防の整備を進めるとされた.”3) 南三陸町では,避難路・避難場所の整備,高台に新たな宅地造成,防潮堤の整備(志津川は高さ8.7m4)),公共施設の再配置等の復興計画が策定され1)復興が行われている.2016年6月,JR気仙沼線柳津駅からBRT(バス高速輸送システム)に乗車し,南三陸町に向かった.車窓より以前通った戸倉や志津川の復興状況が見えた.同町の歌津駅でBRTを下り,自転車で歌津館崎の魚竜化石産地を見学し泊浜の高台にある民宿に泊まった.高台の住宅は津波の被害は無かったが,海辺は更地となっていた.翌日,歌津,モノティスの化石を産する皿貝,高台に新しく造られた住宅街を通り,志津川のさんさん商店街で後続の友人達と合流し,以前泊まった民宿が移転した高台にある新しい宿に泊り,津波時の避難の話を伺った.
写真1 清水浜(2009年11月)
写真2 清水浜(2011年9月)
※写真をクリックすると大きな画像がご覧いただけます
(2) 野田村
岩手県野田村は,明治三陸津波で死者261名,昭和三陸津波で死者6名など大きな被害を受けた5).村の中心街は,海の近くの平地にあり,海辺から順に第1堤防(高さ10.3m,12.0m),防潮林,第2堤防(三陸鉄道,国道45号線.高さ7.8m)が設けられていたが6),東日本大震災では,津波(津波高15.6m6))が第1堤防と防潮林を破壊し第2堤防を越えて中心街を襲い大きな被害が出た5),6),7)(村内の死者38名7)).その後,第1堤防(高さ14.0m),防潮林,第2堤防(三陸鉄道,国道45号線.高さ7.8m),緩衝地帯,第3堤防(盛土.高さ8〜12m)の整備5),8),集団高台移転などの津波復興計画が策定され9),10)復興が行われている.
(3) 普代
岩手県普代村の普代集落は,普代川河口から約1.3km上流にあり,明治三陸津波で死者95名,昭和三陸津波で死者29名など大きな被害を受けた11).1959〜62年度に集落の傍に高さ15.5mの防潮堤(写真3)が設けられたが12),その後,防潮堤の外側に,1968年に普代小学校が新築され(普代小学校ウェブサイトより),1975年には三陸鉄道普代駅が設置され駅周辺で宅地化が進んだ11).1972年に海岸線から約500 m 上流の普代川に高さ15.5mの水門の築造が開始され1984年に竣工した7),12),13).東日本大震災の津波では,普代の水門は破損(写真4)したものの浸水を最小限に食い止め,普代の集落は被害がほとんどなかった6),7),11),13).なお,“実際には到達した津波は高さ約20メートルで水門を超えており,(略)「素早く高台に避難することこそが重要である」という教訓を後世に伝承できる施設でもある.”13)との警鐘もある.
写真3 普代防潮堤(2011年9月)
写真4 普代水門(同左)
(4) 田老
岩手県宮古市の田老地区(旧田老村,旧田老町)は,明治三陸津波で死者・行方不明者1,859名,陸地の生存者は36名のみという大被害を受けた14).津波後,村当局は永久的な「防浪工事」を計画し義援金で津波危険地帯にある全集落を山麓に移転する工事にかかり,5〜6 戸が計画に沿って高所に移転したが,工事は挫折し,移転した家も1戸を除き元に戻り集落を再興した15).昭和三陸津波でも,死者・行方不明者911名など大きな被害を受け,集団高台移転も検討されたが,適地が見当たらなかったこと,村民のほとんどが漁業従事者であったことなどから,村独自で1934年から高さ10mの防潮堤の建造を開始,翌年より県の事業となったが1940年に戦争で中断され,1954年に再開,1958年に完成した14),15).避難路も整備され,1960年のチリ津波(最大波高3.5m)では人や建物の被害はなく,その後,第2防潮堤(1962〜65年度),第3防潮堤(1973〜78年度)も建造され,自治会ごとの避難訓練も行われていた14),15).
東日本大震災では,津波(津波高推定16.3m6))が第3防潮堤と第1防潮堤(写真5)を越え,第2防潮堤を破壊し6)(写真6),死者・行方不明者181名など大きな被害を受けた7),14).その後,防潮堤の整備(一線堤高さ14.7m,二線堤高さ10.0m) 8),16),浸水が予想される区域の高台移転,災害危険地域の住宅建築制限,一部地域の嵩上げなどの田老地区復興まちづくり計画が策定され16),17)復興が行われている.
写真5 田老第1防潮堤(2011年9月)
写真6 田老第2防潮堤(同左)
(5) 吉浜
岩手県大船渡市の吉浜地区(旧吉浜村)は,明治三陸津波で死者・行方不明者204名など大きな被害を受けた18).その後,低地にあった集落は山麓の高所に移転し,高さ8.2mの防潮堤や防潮林も築造され,昭和三陸津波では防潮堤は流出したが被害は比較的小さかった18).東日本大震災では,津波が防潮堤(高さ7.15m12))を破壊し水田が流出するなどしたが,高台の集落の被害は小さかった7),18).復興に当たり,防潮堤を震災前の高さとするかその倍の高さとするか地元住民の討議と投票が行われ19),震災前の高さ7.15 mとされた4),19).
(6) 仙台平野
2013年9月,東北大学で開催された日本地質学会大会の巡検「2011年東北地方太平洋沖地震津波と869年貞観地震津波の浸水域と堆積物」(案内者:東北大学 菅原大助氏, 箕浦幸治氏)20)に参加した.仙台平野の津波被災地の他,弥生時代の遺跡発掘現場と仙台平野の中に掘削されたピットにも案内して頂き,貞観と弥生時代の津波堆積物などについて説明を伺った.
文献によれば,三陸地方は縄文時代以降何回も超巨大津波があり5),21),津波前後で遺跡数の減少などの変化が生じている21).宮城県仙台市の沓形遺跡では水田跡が約2,000年前の津波堆積物に覆われ22),津波後,水田は放棄され,付近の集落は古墳時代前期に再興された23).300年以上集落が再興されなかったのは,津波へのおそれが伝承されたというより,水田の上に堆積した土砂の撤去が困難だったこと,当時は海岸線が現在より内陸約2kmにあり22)排水や除塩24)が困難であったこと(大地震による土地の沈降もあったかもしれない),水田や集落に適した土地が他にあったことなどによるのではないだろうか.
(7) 千葉県九十九里浜
九十九里浜は,江戸時代,イワシの地引網漁が盛んで,それまでの海から離れた集落から海寄りにも集落が形成された25).1703年元禄津波では九十九里浜で2,000名以上が死亡したと言われており,各所に供養塔がある26).しかし,その後,更に海の近くにも集落が形成された25).東日本大震災では,津波が千葉県外房沿岸にも襲来し,特に九十九里浜北端に位置する千葉県旭市の飯岡地区(津波高推定7.6m)は大きな被害を受けた(市内の死者14名)27).2019年4月,友人達と飯岡にあるヨードを含む黒湯の温泉民宿に泊まった.この民宿は津波で流され,その後新築されたもので,御主人より当時の避難の話を伺った.翌日,嵩上げされた海岸堤防(高さ6.0m)の上の九十九里浜サイクリングロードを南下した.海が輝いていた.
あとがき
2011年9月,車で大船渡市越喜来の浦浜地区を通った.ここも大きな被害を受けていた(死者・行方不明者28名28)).道路脇の広場に手作りの児童公園29)があったが,雨が降りそうな天気で人影はなかった.公園に大きな看板があり,手書きで次のように書いてあった(写真7).「ここがオキライですか? ハイ!! でもでもだーい好きです!」
写真7 手作りの児童公園(2011年9月)
文 献
1)南三陸町(2012), 南三陸町震災復興計画(2012.3.26改訂)
2)宮城県土木部(2012), 東日本大震災1年の記録,第8章津波の痕跡調査結果
3)内閣府(2012), 平成24年版防災白書,第2編第2章(5)地震・津波被害の軽減に向けた各行政分野の取組
4)宮城県・岩手県(2016),三陸南沿岸海岸保全基本計画(改訂版)
5)野田村・野田村観光協会(2015, 2016), 岩手・野田村震災の記憶
6)岩手県(2011), 第1回岩手県津波防災技術専門委員会,資料No.3平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波被害に関する被害状況及び考察
7)岩手県(2013), 岩手県東日本大震災津波の記録,2版
8)岩手県(2016), 三陸北沿岸海岸保全基本計画
9)野田村(2012), 野田村東日本大震災津波復興計画
10)三宅 諭(2015), 移転先住宅地での生活再建に向けた「暮らしのデザイン」ワークショップ, 農村計画学会誌,Vol.33,No.4
11)松浦茂樹(2012), 東日本大津波災害と東北復興についての一考察-宮古市田老地区を中心に, 国際地域学研究,第15号
12)岩手県(2019), 岩手県地域防災計画(平成31年3月28日岩手県防災会議決定),資料編2 2-15-3海岸防潮堤防設置一覧
13)震災伝承ネットワーク協議会ウェブサイト「震災伝承施設」
14)宮古市(2017), 東日本大震災宮古市の記録
15)山下文男(2004), 三陸海岸・田老町における「津波防災の町宣言」と大防潮堤の略史, 歴史地震,第19号
16)宮古市(2012), 宮古市東日本大震災地区復興まちづくり計画
17)後藤・安田記念東京都市研究所(2017), 東日本大震災からの復興と自治-自治体再建・再生のための総合的研究-,第3章第1節 宮古市の復興
18)国土交通省東北地方整備局道路部ウェブサイト「津波被害・津波石碑情報アーカイブ」
19)福与徳文,山本徳司,毛利栄征(2014), 海岸堤防の高さに関わる合意形成の新たなかたち, 農業農村工学会誌,第82巻,第3号
20)菅原大助, 箕浦幸治(2013), 2011年東北地方太平洋沖地震津波と869年貞観地震津波の浸水域と堆積物, 地質学雑誌,第119巻
21)相原淳一(2012), 縄文・弥生時代における超巨大地震津波と社会・文化変動に関する予察-東日本大震災津波の地平から-, 東北歴史博物館研究紀要, 13
22)松本秀明,熊谷真樹,吉田真幸(2013), 仙台平野中部にみられる弥生時代の津波堆積物, 人間情報学研究,第18巻
23)斎野裕彦(2012), 仙台平野中北部における弥生時代・平安時代の津波痕跡と集落動態, 東北芸術工科大学東北文化研究センター編, 東北地方における環境・生業・技術に関する歴史動態的総合研究 研究成果報告書Ⅰ
24)友正達美,坂田 賢,内村 求(2012), 平成23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震による津波被災農地における平成23 年春期除塩作業の実施状況と今後の課題, 農村工学研究所技報,第213号
25)菊地利夫(1959), 九十九里浜イワシ漁業の豊凶交替と新田・納屋集落の成立との関係, 新地理,7巻,2号
26)千葉県(2009), 防災誌元禄地震,第2改訂版
27)千葉県(2013), 東日本大震災の記録, 同追補版
28)岩手日報社・IBC岩手放送ウェブサイト「碑の記憶」
29)遠野まごころネットウェブサイト「月刊アーカイブ」2011年11月
※日本地質学会NEWS Vol. 23, No.11(2020年11月号) 掲載
【geo-Flash】No.505 第2回サイバーシンポ(YouTube生配信です)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.505 2020/11/17┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2021年度会費について(院生割引会費申請受付中)
【2】2021年度学会各賞候補者募集中(12/1締切)
【3】第2回コロナ禍での地質学教育に関するサイバーシンポ
【4】第12回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
【6】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【7】論集58号再度販売いたします
【8】支部情報
【9】会員の活動
【10】その他のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2021年度会費について(院生割引会費申請受付中)
──────────────────────────────────
・割引会費の申請について:学部に在籍している学生の方,定収のない大学
院生(研究生)の方で,それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引
会費を適用します.なお,2020年度までの院生割引会費についての申請は
終了しておりますので,2021年度会費にのみ適用となります. ※割引の
適用を希望する場合,申請は毎年必要です.
************************************
2021年度分割引会費(請求書発行前締切):2020年11月20日(金)
************************************
・自動引落を登録されている方:引落日は,2020年12月23日(水)です.
※口座変更を希望される場合は、口座振替依頼書を改めてお送りください.
依頼書は学会HPからダウンロードできます.
・災害に関連した会費の特別措置:学会では,災害救助法適用地域で被災
された会員の方々のご窮状をふまえ,申請により会費を免除いたします.
詳細は学会HPをご参照ください.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2021年度学会各賞候補者募集中(12/1締切)
──────────────────────────────────
日本地質学会では今年も運営規則第16条および各賞選考規則にした
がい,賞の候補者を募集いたします
ご応募いただいた場合には,必ず受け取りのお返事をお出しします
のでご確認ください.
*********************************************
応募締切:2020年12月1日(水)必着
*********************************************
詳しくは,http://sub.geosociety.jp/members/content0098.html
(会員ページへのログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】第2回コロナ禍での地質学教育に関するサイバーシンポ(名古屋代替企画)
──────────────────────────────────
「第2回コロナ禍での地質学教育に関するサイバーシンポジウム」
日時:2020年11月29日(日)9:30-12:15
YouTube生配信 どなたでもご視聴いただけます.
<大学の取り組み>
・コロナ禍における学部生・大学院生の教育および研究:実験室での取り組みオン
・デマンド実験実習科目の実施例:役に立った技術の紹介 ほか
<高校の取り組み>
・オンライン学習の利点・難点と地学教育普及のための活動実践例
・コロナ禍の本校(愛知県立海翔高等学校)における地質学教育の現状と課題
<研究所・博物館の取り組み>
・既存の地質コンテンツの有効活用:「地質の日」事業と「地質情報展」における地質調査総合センター(産総研)の取り組み
・かはくVRとは!?臨時休館中に公開したコンテンツについて
そのほか代替企画の一覧は,
http://www.geosociety.jp/science/content0041.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第12回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
──────────────────────────────────
***応募締切:2021年2月1日(月)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコン
テストです.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募フォームから
でもメール添付でもご応募いただけます.
会員の皆様からの応募をお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・126巻11月号(予告)
(レター)天草下島北部の中新世貫入岩体の方向と応力解析:牛丸
健太郎ほか/(論説)室戸岬の玄武岩質貫入岩群の示唆する中期中新
世の逆断層型応力:羽地俊樹ほか/(ノート)On approximations of
EASY%Ro solutions to estimate maximum temperature from vitrinite
reflectance:Shunya Kaneki et al/(報告)愛知県設楽地域東部の
貫入岩体の全岩化学組成,輝度および変質度:図子田和典ほか
ほか計6編を予定
■ Island Arc
・新しい論文等が公開されています.
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14401738/0/ja
・LaTeXテンプレートを公開しました。クラウド型共同執筆ツールのAuthorea
でも利用可能です。https://authorea.com/templates/island_arc_iar_
・Island Arcでは著者制作のVideo Abstractの掲載が可能です.
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14401738/homepage/video_abstracts
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】論集58号再度販売しています
──────────────────────────────────
地質学論集 第58号
「地震イベント堆積物 −深海底から陸上までのコネクション−
藤原 治ほか編 169頁 2004年12月刊行 会員頒価2,900円(+送料)
論集58号は、これまで売り切れとなっていましが、在庫が確認されました
ので、再度販売いたします。冊子購入希望の方は、学会事務局までお申し
込み下さい。メール:main@geosociety.jp FAX:03-5823-1156
このほか学会出版物在庫案内はこちら
http://www.geosociety.jp/publication/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
オンライン講演会−おうちで学ぶ恐竜研究の最前線−
12月12 日(土)13:00-15:00
Zoomによるオンタイム、オンライン方式
参加費無料,要申込(先着75名)
申込締切:12月5日(土)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html#201212
[四国支部]※名古屋大会代替企画
・第20回支部総会・講演会のご案内
(講演会)12月5日(土) 13:00-17:05(予定)
場所:WEB開催(Zoomおよび愛媛大学理学部地学コースHP)
(総会)12月5日(土) 17:15-7:45(予定)
場所:WEB開催(Zoom)
参加・発表申込締切:11月20日(金)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0212.html#2020koen
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】会員の活動
──────────────────────────────────
会員の学術・教育・社会貢献活動をご紹介します。
-----------------------------------------
ウォリス サイモン会員出演
NHK国際放送「Groud Detective Simon Wallis」第1回秩父ジオパーク編
11/25(水)15:30〜、22/30〜
11/29(日)20:10〜
日本の地質を海外の人にわかりやすく紹介する目的で、NHK 国際放送が
15分の短い番組を複数の企画しています。
詳しくは、http://www.geosociety.jp/science/content0109.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
電中研メールマガジン(2020年11月6日号)
新刊報告書公開:「ドローン電磁探査による斜面の比抵抗構造調査」ほか
https://criepi.denken.or.jp/jp/kenkikaku/cgi-bin/report_reference.cgi?m=201106-4
------------------------------------------------------------
(共)日本地球化学会第67回オンライン年会
11月12日(木)-26日(木)WEB上での発表資料に対する議論
11月19日(木)-21日(木)Zoomでのセッション企画
(注)地質学会員は地球化学会員と同じ参加費(一般:2000円
/学生:無料)で参加できます.
https://www.geochem-conf.jp/
(協)第36回ゼオライト研究発表会
11月19日(木)-20 日(金)
(注)オンライン開催(Zoom)に変更になりました
https://jza-online.org/events
材料研究の最新成果発表週間:ニムスウィーク2020
11月25日(水) -27日(金)
オンライン開催
参加無料(事前登録制)先着600名限定
https://www.nims.go.jp/nimsweek/
(後)第30回環境地質学シンポジウム
11月27日(金)-28日(土)
[オンライン開催](Zoomミーティング使用予定)
https://www.jspmug.org/envgeo_sympo/30th_sympo/30th_sympo.html
令和2年度自然史学会連合講演会
「九州北部から広がる自然史研究:化石からランまで」
12月6日(日)13:30-15:30
場所:北九州市立いのちのたび博物館(ガイド館)
定員:80名(申し込み制)
http://www.kmnh.jp/2020/11/8226/
地質学史懇話会
12月25日(金)13:30より
会場:北とぴあ 701号室(東京都北区王子)
志岐常正:戦後京大地質学教室史ーその虚像と実像
矢島道子:『地質学者ナウマン伝』を上梓して
問い合わせ先:矢島 pxi02070[at]nifty.com
学術フォーラム・防災連携シンポジウム
「東日本大震災から10年とこれから」
2021年1月14日(木)10:00-18:30
会場:東京医科歯科大学 鈴木章夫記念講堂(オンライン+現地開催)
主催:日本学術会議 防災減災学術連携委員会、防災学術連携体(58学会)他
参加費:無料
定員:(会場)150名(500名の定員を1/3に制限しています)
(オンライン)1000名
https://janet-dr.com/060_event/20210114.html
日本地球惑星科学連合2021年大会
開催方式:ハイブリッド開催(オンライン開催+現地開催)
現地会場:パシフィコ横浜ノース
2021年5月30日(日)-6月1日(火)/現地開催(主としてポスター発表)
6月3日(木)-6日(日)/オンライン開催(口頭,ポスター)
※現地開催は縮小もしくは中止となる可能性があります.
http://www.jpgu.org/meeting_j2021/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.506 100周年記念誌 再販のお知らせ
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.506 2020/12/01┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2021年度会費について(院生割引会費申請受付中)
【2】第12回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
【3】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【4】「日本の地質学100年 : 日本地質学会100周年記念」再販のお知らせ
【5】コラム:津波と集落
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2021年度会費について(院生割引会費申請受付中)
──────────────────────────────────
・割引会費の申請について:学部に在籍している学生の方,定収のない大学
院生(研究生)の方で,それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引
会費を適用します.なお,2020年度までの院生割引会費についての申請は
終了しておりますので,2021年度会費にのみ適用となります.
※割引の適用を希望する場合,申請は毎年必要です.
************************************
2021年度分割引会費(最終締切):2021年3月31日(水)
************************************
自動引落を登録されている方:引落日は,2020年12月23日(水)です.
災害に関連した会費の特別措置:学会では,災害救助法適用地域で被災
された会員の方々のご窮状をふまえ,申請により会費を免除いたします.
詳細は学会HPをご参照ください.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第12回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
──────────────────────────────────
***応募締切:2021年2月1日(月)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコン
テストです.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募フォームから
でもメール添付でもご応募いただけます.
会員の皆様からの応募をお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・126巻11月号が発行されました
(レター)天草下島北部の中新世貫入岩体の方向と応力解析:牛丸
健太郎ほか/(論説)室戸岬の玄武岩質貫入岩群の示唆する中期中新
世の逆断層型応力:羽地俊樹ほか/(ノート)On approximations of
EASY%Ro solutions to estimate maximum temperature from vitrinite
reflectance:Shunya Kaneki et al/(報告)愛知県設楽地域東部の
貫入岩体の全岩化学組成,輝度および変質度:図子田和典ほか
ほか計6編を予定
■ Island Arc
・新しい論文等が公開されています.
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14401738/0/ja
・LaTeXテンプレートを公開しました。クラウド型共同執筆ツールの
Authoreaでも利用可能です。https://authorea.com/templates/island_arc_iar_
・Island Arcでは著者制作のVideo Abstractの掲載が可能です.
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14401738/homepage/video_abstracts
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】「日本の地質学100年 : 日本地質学会100周年記念」再販のお知らせ
──────────────────────────────────
学会創立100周年を記念して1993年に発行された書籍です.
書架整理のため,再販いたします.残部稀少.
最後の購入チャンスです.この機会にぜひお買い求めください!
日本地質学会編,1993年4月発行,
706ページ,27cm,無線綴じ,布張上製本.
再販特別価格:3,000円(税・送料込)(参考)当初価格:8,000円
再販期間:2020年12月から2021年3月31日まで
お求めは,ジオストア(クレジット決済可能)もしくは学会事務局まで.
http://geosociety2.sakura.ne.jp/store3/ec/
論集など学会出版物在庫案内はこちら
(論集58号「地震イベント堆積物」も再販しています)
http://www.geosociety.jp/publication/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】コラム:津波と集落
──────────────────────────────────
正会員 高山信紀
あと数ヶ月で東日本大震災から10年となる.この間,様々な分野で調査・
研究が行われ,復興が進められ,膨大な画像や文献が公開されている.
本記事では,筆者が訪れたことがあるいくつかの津波被災地の思い出と,
このたびインターネットで調べたこれら被災地の津波被害と復興の一端
を述べてみたい.
続きはこちら、http://www.geosociety.jp/faq/content0930.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
オンライン講演会「おうちで学ぶ恐竜研究の最前線」
12月12 日(土)13:00-15:00
Zoomによるオンタイム、オンライン方式
参加費無料,要申込(先着75名)
→定員に達しましたので、参加申込は締切ました
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html#201212
[四国支部]※名古屋大会代替企画
・第20回支部総会・講演会のご案内
(講演会)12月5日(土)13:00-17:05(予定)
場所:WEB開催(Zoomおよび愛媛大学理学部地学コースHP)
(総会)12月5日(土)17:15-17:45(予定)
場所:WEB開催(Zoom)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0212.html#2020koen
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
令和2年度自然史学会連合講演会
「九州北部から広がる自然史研究:化石からランまで」
12月6日(日)13:30-15:30
場所:北九州市立いのちのたび博物館(ガイド館)
定員:80名(申し込み制)*12/2締切
http://www.kmnh.jp/2020/11/8226/
海と地球のシンポジウム2020
12月17日(木)-18日(金)
東京大学大気海洋研究所・JAMSTEC共催
プログラム公開しました
http://www.jamstec.go.jp/j/pr-event/ocean-and-earth2020/
学術会議公開シンポジウム(オンライン)
「続発する大災害から史料を守る−現状と課題−」
(第25回史料保存利用問題シンポジウム)
12月19日(土)13:30より
参加費無料・定員300人・先着受付・要事前申込
http://www.scj.go.jp/ja/event/2020/295-s-1219.html
地質学史懇話会
12月25日(金)13:30より
会場:北とぴあ 701号室(東京都北区王子)
志岐常正:戦後京大地質学教室史ーその虚像と実像
矢島道子:『地質学者ナウマン伝』を上梓して
問い合わせ先:矢島 pxi02070[at]nifty.com
学術フォーラム・防災連携シンポジウム
「東日本大震災から10年とこれから」
2021年1月14日(木)10:00-18:30
会場:東京医科歯科大学 鈴木章夫記念講堂(オンライン+現地開催)
主催:日本学術会議 防災減災学術連携委員会、防災学術連携体(58学会)他
参加費:無料
定員:(会場)150名(500名の定員を1/3に制限しています)
(オンライン)1000名
https://janet-dr.com/060_event/20210114.html
日本地球惑星科学連合2021年大会
開催方式:ハイブリッド開催(オンライン開催+現地開催)
現地会場:パシフィコ横浜ノース
2021年5月30日(日)-6月1日(火)/現地開催(主としてポスター発表)
6月3日(木)-6日(日)/オンライン開催(口頭,ポスター)
※現地開催は縮小もしくは中止となる可能性があります.
http://www.jpgu.org/meeting_j2021/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・JAMSTEC海域地震火山部門火山・地球内部研究センター地球内部物質循環
研究グループポストドクトラル研究員公募(12/14:13時)
・広島大学(大学院先進理工系科学研究科地球惑星システム学プログラム)
公募(12/21:17時)
・産総研ポスドク(イノベーションスクール生)公募(1/5)
・おおいた豊後大野ジオパークにおける学生巡検等の宿泊費補助の拡充
・第52回(2021年度)三菱財団自然科学研究助成(1/6−2/3)
・2021年度「深田研究助成」募集(2/5)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.507 2021年度会費について
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.507 2020/12/15┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2021年度会費について
【2】第12回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
【3】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【4】2022年度地震火山地質こどもサマースクール開催地募集
【5】「日本の地質学100年 : 日本地質学会100周年記念」再販セール中です
【6】屋久島たんけんマップ 改版しました
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】学会事務局年末年始休業
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2021年度会費について
──────────────────────────────────
次年分(2021年度)の会費請求書を間もなく発送いたします.折り返し
ご送金をお願いいたします.
自動引落の方は,12月23日(水)に引き落しとなります(請求書ならび
に引き落し通知は省略させていただきます).
また,学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)の
方で,それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適用します.
********************************************
2021年度分割引会費申請(最終締切):2021年3月31日(水)
※申請は毎年必要です.
********************************************
災害に関連した会費の特別措置:学会では,災害救助法適用地域で被災
された会員の方々のご窮状をふまえ,申請により会費を免除いたします.
詳細は学会HPをご参照ください.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第12回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
──────────────────────────────────
***応募締切:2021年2月1日(月)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコン
テストです.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募フォームから
でもメール添付でもご応募いただけます.
会員の皆様からの応募をお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・126巻12月号(ただいま編集中)
(論説)ジュラ系智頭コンプレックス中にみられるテクトニック・メランジュの
変形構造:於保幸正ほか/(論説)北部九州白亜紀花崗岩類における低Sr 花崗岩類
の成因: 村岡やよいほか/(論説)瑞浪層群中村層における脈状岩石の形成過程:
古川邦之ほか/(ノート)オマーンオフィオライト陸上掘削試料を用いたハード
ロック掘削における空隙率測定法の再検討:長荑薫平ほか 計4編を予定
■ Island Arc
・新しい論文等が公開されています.
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14401738/0/ja
・LaTeXテンプレートを公開しました。クラウド型共同執筆ツールの
Authoreaでも利用可能です。https://authorea.com/templates/island_arc_iar_
・Island Arcでは著者制作のVideo Abstractの掲載が可能です.
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14401738/homepage/video_abstracts
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2022年度地震火山地質こどもサマースクール開催地募集
──────────────────────────────────
募集期間:2021年1月12日(火)から2月10日(水)
地震火山地質こどもサマースクールは,1999年夏から小・中・高校生を
対象にはじまった行事で,現在,日本地震学会,日本火山学会,日
本地質学会が共同で実施する,地球科学関連では最大規模の体験学
習講座です.今回,2022年度に実施する開催地を公募いたします.
応募資格など詳しくは,https://kodomoss.jp/applications/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】「日本の地質学100年 : 日本地質学会100周年記念」再販セール中です
──────────────────────────────────
学会創立100周年を記念して1993年に発行された書籍です.
書架整理のため,再販いたします.残部稀少.
最後の購入チャンスです.この機会にぜひお買い求めください!
日本地質学会編,1993年4月発行,
706ページ,27cm,無線綴じ,布張上製本.
再販特別価格:3,000円(税・送料込)(参考)当初価格:8,000円
再販期間:2020年12月から2021年3月31日まで
お求めは,ジオストアから(クレジット決済可能)
http://geosociety2.sakura.ne.jp/store3/ec/
論集など学会出版物在庫案内はこちら
(論集58号「地震イベント堆積物」も再販しています)
http://www.geosociety.jp/publication/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】屋久島たんけんマップ 改版しました
──────────────────────────────────
2009年に発行し、ご好評いただいております屋久島たんけんマップが
最新の情報をアップデートし、改版されました。
かわいいキッキくんとシカノスケ博士が屋久島の地質をわかりやすく
紹介してくれます。ハンディタイプで、野外での観察にも最適です。
教材としても是非ご活用下さい。
地質リーフレットたんけんシリーズ2
屋久島地質たんけんマップー洋上アルプスは不思議がいっぱいー
編 著:日本地質学会地学教育委員会・屋久島地学同好会
A2版 12折 両面フルカラー印刷
定価400円(会員頒価 300円)(20部以上ご注文の場合は割引あり)
お求めは学会事務局まで.
http://www.geosociety.jp/publication/content0037.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
・2020年度関東支部功労賞募集
対象者:支部活動や地質学を通して広く社会貢献をされた関東支部内に
在住の個人・団体
公募期間:2020年12月17日から2021年1月17日
・ アウトリーチ巡検「川の防災と川が作った地形を巡る:
首都圏外郭放水路見学と春日部周辺,中川低地の地形観察」
実施日:2021年1月31日(日)
募集:20人(先着順) 最少催行人数15人
申込締切:2021年1月15日 *定員に達した時点で終了
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
[四国支部]
・第20回支部総会・講演会(名古屋大会代替企画)の講演要旨を公開中
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0212.html#2020koen
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
学術会議公開シンポジウム(オンライン)
「続発する大災害から史料を守る−現状と課題−」
(第25回史料保存利用問題シンポジウム)
12月19日(土)13:30より
参加費無料・定員300人・先着受付・要事前申込
http://www.scj.go.jp/ja/event/2020/295-s-1219.html
地質学史懇話会 →[中止となりました]
12月25日(金)
志岐常正:戦後京大地質学教室史ーその虚像と実像
矢島道子:『地質学者ナウマン伝』を上梓して
問い合わせ先:矢島 pxi02070[at]nifty.com
学術フォーラム・防災連携シンポジウム
「東日本大震災から10年とこれから」
2021年1月14日(木)10:00-18:30
会場:東京医科歯科大学 鈴木章夫記念講堂(オンライン+現地開催)
主催:日本学術会議防災減災学術連携委員会,防災学術連携体(58学会)他
参加費:無料
定員:(会場)150名(500名の定員を1/3に制限しています)
(オンライン)1000名
https://janet-dr.com/060_event/20210114.html
令和2年度国土技術政策総合研究所講演会
2021年1月18日(月)9:00-(オンデマンド配信)
参加無料,事前登録不要
http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/koen2020.html
第55回日本水環境学会年会(オンライン)
3月10日(水)-12日(金)
500件以上の一般講演、各種のセミナーのほか、特別講演会や,
全国環境研協議会研究集会にご参加いただけます.
http://www.jswe.or.jp/event/lectures/2020per.html
日本地球惑星科学連合2021年大会
開催方式:ハイブリッド開催(オンライン開催+現地開催)
現地会場:パシフィコ横浜ノース
2021年5月30日(日)-6月1日(火)/現地開催(主としてポスター発表)
6月3日(木)-6日(日)/オンライン開催(口頭,ポスター)
※現地開催は縮小もしくは中止となる可能性があります.
http://www.jpgu.org/meeting_j2021/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・令和2年度福島県教育委員会学芸員(古生物学)採用選考予備試験実施(12/23)
・JAMSTEC海域地震火山部門地震発生帯研究Cプレート構造研究G 1名公募(1/5)
・ジオパーク秩父 地域おこし協力隊の募集(1/29)
・栗駒山麓ジオパーク専門員(宮城県栗駒市)募集(12/18)
・公益財団法人自然保護助成基金協力型助成金(1/5)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】学会事務局年末年始休業
──────────────────────────────────
学会事務局は,12月29日(火)から1月5日(火)までお休みとなります.
新年6日(水)より通常営業となります.よろしくお願いいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
永瀬清子:宮沢賢治に憧れた女流詩人の地学的側面
永瀬清子:宮沢賢治に憧れた女流詩人の地学的側面
正会員 石渡 明
1.はじめに:赤磐の山々
筆者は2016年8月21日に岡山県赤磐(あかいわ)市で開催された「じぇーじーねっと地質学講座」に招待され,「東アジアの地質 赤磐市の海底岩石とのつながり」の題で講演した.翌月25日,読売新聞日曜版に掲載された永瀬清子(1906〜1995)の特集(名言巡礼:文・松本由圭,写真・林陽一)を読み,宮沢賢治に憧(あこが)れて「雨ニモマケズ」詩の「発見」の現場にも立ち会ったこの女流詩人が,戦後ずっと赤磐市で農婦として働きながら詩作を続けていたことを初めて知った.翌2017年,上記講演に基づく拙著論文「岡山県赤磐市の海底岩石(夜久野オフィオライト)」が「地質技術」第7号に掲載されたが,その末尾に永瀬清子と宮沢賢治の出身地の共通点について指摘し,「赤磐市のなだらかな山々に囲まれた平野の地形は,岩手県の花巻市付近と共通した特徴があるが,それだけでなく,古生代の海底岩石が分布する地質の共通点もあり,このような地形・地質の共通点がある土地に,これら二人の自然派詩人が育ったことは,単なる偶然とは思えない」という卑見を述べて,「永瀬清子」を拙著論文のキーワードに加えた.そして本2020年,赤磐市教育委員会の白根直子氏(上記新聞特集にも登場)から,キーワード検索で拙著論文をみつけ,上述の部分を,永瀬清子の詩「都会わすれ」に関する氏の論考(現代詩手帖, 2020年10号, 134-141頁)に引用したという手紙をいただき,その後「詩人永瀬清子作品集―熊山橋を渡る−」(熊山町永瀬清子の里づくり推進委員会編,1997年)を恵贈いただいた.偶然が重なり,永瀬清子と不思議な縁ができたので,今回はこの詩人について,その地学的側面に着目して簡単に紹介する.
2.どんな詩か:山や河を身につけて
まず,永瀬清子の詩の雰囲気を伝えるために,その詩句をいくつか示す.「星々は夜には/幾多の宿命を含む地上からの視線で/原始以来みがかれた鉱物だ」(詩『星座の娘』),「西の天末にはまだ猫眼石いろの光が/フットライトのように/かなたの半球のあかるみを投げあげている/…/渡り終ろうとして東の方をふりかえれば/数知れぬ星のあふれ/「オリオン!」/私は心をこめてそう呼ぶ」(『熊山橋を渡る』),「新田(しんでん)山がおだやかに横たわっていたその上すれすれに/ぴったり さそり座のアンターレス」(『アンターレス―さそり座への願い』),「木星ばかりが一つ/かがり火のように波にちりばめられている時」(『吉井川によせて』),「山や河を身につけて/私もそんなふうにして冬を過す」(『冬』),「私は自分が/深い茄子(なす)紺(こん)色の大洋の底から/火と硫黄を噴きあげる熱い蒸気であることに驚く」(『私は地球』).「地球は一個の被害者となった/今や地球はみるみるやつれた可哀想なものとなった」(『滅亡軌道』),「やがて青石のかげにかがまる時/すべての詩を書き終る…」(『捕え得ず』).次女の井上奈緒氏は,「道端に生えている小さな花でも,山の中で鳴く鳥の声,夜空の星の名前など質問すると,即座に返事がかえってくることなど…どのようにして学んだのでしょうか.私にはまねのできないことであります」と述べている(上記作品集).
3.略歴:岡山,金沢,名古屋,大阪,東京,岡山
永瀬清子の作品紹介と評伝には,藤原菜穂子 (2011) 「永瀬清子とともに 『星座の娘』から『あけがたにくる人よ』まで」(思潮社),井坂洋子 (2000) 「永瀬清子」(五柳書院)がある.これらと前出の文献による永瀬清子の略歴は次の通りである.1906年岡山県赤磐郡豊田村(後に合併して熊山町,現在は赤磐市)の旧家永瀬家に生まれた.父の転勤により金沢で育ち,石川県師範学校附属小学校,石川県立第二高女を卒業.四高で万葉集講座を聴講するなどした.名古屋に移り1924年に愛知県立第一高女高等科英語部入学,上田敏の詩集と出会って詩人をめざし,佐藤惣之助に師事.1927年東大出の同郷の長船越夫と結婚,大阪に住む.詩集「グレンデルの母親」(1930,詩『星座の娘』」を含む)により詩壇に登場.1931年夫の転任により上京.北川冬彦の「時間」,「磁場」の中核同人として活動.草野心平から宮沢賢治の詩集「春と修羅」を贈られる.1934年2月に東京新宿で開かれた宮沢賢治(前年9月死去)追悼会に心平の誘いで参加し,賢治の弟清六が持参した賢治のトランクのポケットから『雨ニモマケズ』の手帳が発見される場に居合わせた.その後三好達治や高村光太郎とも交流し,「諸國の天女」(1940,光太郎が序文) でも評価を得た.1945年終戦直後に岡山へ戻り,農業をやりながら詩作を続け,詩誌「黄薔薇(きばら)」を主宰.「美しい国」(1948),「薔薇詩集」(1958),「永瀬清子詩集」(1969,1979,続1982,1990) や「蝶(ちょう)のめいてい」(1977),「流れる髪」(1977),「焔(ほのお)に薪(まき)を」(1980),「彩(いろど)りの雲」(1984) 等の短章集を多数出版.この間,ハンセン病療養所での詩の指導など幅広い社会活動に携(たずさ)わり,1952年豊田村教育委員に立候補して当選(当時は公選制),1955年に熊山町婦人会長の肩書でニューデリーの「アジア諸国民会議」に出席,「インドよ」で始まる自作の詩を英語で朗読し民衆の喝采を受け,予定外だが中国代表郭(かく)沫(まつ)若(じゃく)の招きにより帰路中国を訪問,メーデーの大行進を見る.1963年から14年間,県庁内の世界連邦都市岡山県協議会事務局に勤務.1965年岡山市に移る.10年ほど家庭裁判所の調停員を務める(『火星について』,「焔に薪を」).1986年,詩『あけがたにくる人よ』を美智子皇太子妃殿下(当時)が英訳して日本ペンクラブの機関誌に発表され,外国公館等で朗読された(後述参照).1987年の同名の詩集で優れた詩人に贈られる地球賞を,翌年ミセス現代詩女流賞を受賞.1995年死去.同年遺稿集「春になればうぐいすと同じに」(『アンターレス…』と『吉井川…』を含む)出版.
4.月の輪古墳:民衆による発掘
戦後岡山県の故郷に帰り,農業で生計を立て,村人との共同作業にも参加し,四人の子(男二人,女二人)を育てながら詩作を続けるのは大変なことだったと思う.「しかし農業を自分がやってみると,労働が単純なので,仕事中に比較的頭を働かせて空想する自由があることがわかった」(『新しい生活』,「すぎ去ればすべてなつかしい日々」,1990).そして農業と詩作の合間には,学術的な活動にも参加した.『子供たちのこと,地域の人の熱意のこと』(同書)という随筆には,今は廃線になった柵原(やなはら)線沿いの「月の輪古墳」の発掘に通ったことが書かれている.1953年(筆者の生年)の夏,「岡山大学の近藤義郎先生をはじめとして,のべ1万人の農民や労働者や学生,児童までが参加」してこの発掘が行われた.「地元の村の人々も飯岡(ゆうか)小学校を本拠に総出でこの人々のための食事,宿舎をはじめとする万端の手配を引き受けた」.「この昭和28年の夏の熱気は今から思ってもふしぎな高まりを見せた.もちろんそれはその前の戦争時代にはありえない事だったし,またその後の金と機械に押しまくられる高度経済成長期に入ってはなお決して起こり得ない大きな民衆運動だったのだ.山の上は葺(ふき)石(いし)でしきつめられ,ハニワがめぐらしてあった.発掘された山の上の二つの棺は男女二体のものであるとも判った」.「私は依頼され,『月の輪音頭』を作詞した.作曲は箕作(みつくり)秋吉(しゅうきち)先生でとてもいいものになった.毎年8月15日には盆踊りのように輪になって,人々はこの発掘の成功をよろこび踊った.近くの柵原(やなはら)鉱山からもトラックで人々は参加し,皆で夜のふけるまで踊った」.その一節は,「鋤(すき)をかついでもっこを負うて/学ぶ歴史は手とからだ/ヤンレ先生も一踊り」と歌う.我々はこの時代に考古学だけでなく地学でも同様の熱気があったことを知っている.
5.日輪と山:正しくリアルに自分の眼で
永瀬清子が宮沢賢治の絵について述べた『日輪と山』(「蝶のめいてい」,1977)という短章がある.「宮沢賢治が描いた絵に「日輪と山」と云う水彩画があって,高くそびえた山が真中にあり,その頂上よりやや左よりの肩に日輪が懸(か)かっている.がその日輪は山の手前にかいてある」.「はじめその絵をみた時,私はたしかにある種のよほど幼稚な童画のようだと思い,そこが却って面白いと思い,一方,又へんにも思ったが,山の手前に太陽があるのは,宮沢賢治の主観的な空想か誇張にちがいないと思った」.「しかし,私は実際にどのように見えるものか,宮沢賢治がどの程度に主観をまじえて描いたのかを知ろうと思い,ある朝太陽が熊山をはなれるのを待って東の窓に立っていた」.「所が不思議不思議…その時強い光線はかがやきわたり…山の尾根の線はかき消され,すっかり見えなくなってしまったではないか.それは賢治の絵と全く一致しており,それによってまさに賢治の絵がリアリステックに正しい事を知った」.「この事実を,私は正しくリアルに自分の眼でみたことがなかったのを,この時はじめて知ったのであった――」.これは実に科学的な態度である.
6.元日:やさしさと芯の強さ−賢治との違い
永瀬清子には感謝を込めて母親を詠(よ)んだ『元日』という詩がある(「私は地球」,1983).元日に熱が出て寝ていたら,「私と共に/60才になってはじめて百姓になられた母は/今日は私にかわってきれいなお雑煮をつくって下さった」,「お昼からだんだん暖くなって/ふと私の生まれた時を思う」,「その時の若かった母が/この長く閉ざされていた古い家で/再び別れていた私とも一緒になり/かぼそい身体でありとあらゆる事をして下さる」と言う.石牟礼道子は清子の詩を,「三十年も五十年も…さまよい生きるだけの人生の幼な子への,天のごほうび」と呼び,その「うるわしさに涙ぐんだ」(「流れる髪」,1977の帯). 永瀬清子は『微塵(みじん)の一粒−宮沢賢治さんにむかう私−』(「女詩人の手帖」,1951),『賢治思慕b 微少なものへの味方』(「流れる髪」,1977),『あの方の父上は−一番下っぱの弟子のことば』(「春になればうぐいすと同じに」,1995)などの文章で宮沢賢治への憧憬(しょうけい)を表明している.しかし,賢治は『銀河鉄道の夜』でカムパネルラの父親に川岸で時計を見ながら「もう駄目です.落ちてから45分たちましたから」と冷静に言わせたり,『グスコーブドリの伝記』で飢饉(ききん)の時にブドリとネリを家に置き去りにして父母が森の中へ失踪(しっそう)してしまったり,親に厳しい傾向がある.賢治は盛岡高等農林学校で学んだ技師・教師として農民を指導しようとしたが,この人は自ら農民になり切った.賢治は浄土真宗の家に育ったにもかかわらず家業を継がず日蓮宗系の団体に入って法華経を信仰したが,この人は弾圧された僧侶(法中(ほっちゅう))をかくまうための窓のない隠し部屋を持つ日蓮宗不受不施派の旧家に生まれ(『田植と不受不施』,「蝶のめいてい」,1977),家督相続人としてその家を守った.なお,この家は「永瀬清子の里」に保存されていて,近くに展示室もある(JR山陽本線熊山駅徒歩20分).
7.降りつむ:走り寄る人
美智子皇后(現上皇后)陛下 (2019) の「降りつむ」(皇后陛下美智子さまの英訳とご朗読 宮内庁侍従職監修 毎日新聞出版編 毎日新聞出版(朗読DVD付))には,永瀬清子の『降りつむ』(「美しい国」,1948,楽譜つき),『夜に燈(ひ)ともし』(同書),『あけがたにくる人よ』(前出)の原文,英訳,そこに至る経緯と前2詩の陛下による朗読が収録されている.永瀬清子は『縄文のもみじ―ある人に』(「あけがたにくる人よ」,1987,縄文は後に弥生へ変更)で「あなたは私の詩をきいて/一度でそのフレーズを覚えて下さった/やさしい人 あなたは遠い遠い人なのに/一心に走り寄って下さった」と感激している.
8.終わりに:宇宙や地球との時空的一体感
永瀬清子は言う.「詩人はただ美しいある性質を求める仕事なので,本当は「井戸掘り」とか「鉱夫」などと同じものだ」(『詩人』,同書).彼女は宮沢賢治の弟子を自任し,賢治が目指したものを生涯実践し,生前の社会的貢献においては賢治を超え,美しい作品を多く創り出したと思う.彼女の天体や鉱物に関する知識は,彼女が宮沢賢治を知る以前に印刷された『星座の娘』などにも表れており,おそらく学生時代に身につけたものと思われる.「幾億年古い世より/私は在るらしい/…/我が思いは/なつかしき星空へ/…/かの慣れし琴に倚(よ)らんと/わがいのちいま銀河に近づく」(『天空歌』,「大いなる樹木」,1947),「私は地球だ./そこに生きていてそしてそのものと同じだ.」(『私は地球』,「海は陸へと」,1972)といった詩句に見られる宇宙や地球との長大な時空的一体感は,女性的な「やさしさ」,「うるわしさ」とともに,この詩人の大きな特徴だと思う.宮沢賢治の地学者としての側面については既に複数の論考がなされてきたが,永瀬清子の地学的な側面についての研究はこれからだと思う.この拙文が,自然と人間への深い共感と洞察に満ちた永瀬清子の美しい詩の世界へ読者をいざなうことができれば幸いである.
謝 辞:貴重な書籍と資料をご恵与いただいた赤磐市教育委員会熊山分室学芸員の白根直子氏に感謝する.拙稿を読んで貴重なご意見をいただいた同氏と日本地質学会執行理事の小宮 剛氏に感謝する.赤磐市での講演会に招待いただいたNPO法人地球年代学ネットワークの板谷徹丸理事長に感謝する.
Pitch vs. Rake
Pitch vs. Rake
正会員 高木秀雄
pitch(rake)とは,断層面上の条線や,砂岩の底面のソールマークなどのように,傾斜した面構造上に線構造が存在する 時の面構造の走向と線構造とのなす角度を面上で測定したもので,線の傾きを鉛直面上で求めた沈下角(plunge)と区別される.この場合,面構造の走向・傾斜のほかに線構造の沈下方向 と沈下角を測定しなくても,pitchを測定することによりステレオ投影上で線構造の沈下方向(trend)と沈下角(plunge) を求めることができる(第1図).
第1図.傾斜角(δ)の面構造Sと,その上に存在する線構造Lにおけるpitch(α)とplunge(β)の関係(左)とステレオ投影図 (右).0°≦α≦90°,0°≦β≦δ
最近,平凡社の「地学事典」(地学団体研究会1996)の27年 ぶりの改訂をめざし,構造地質分野の項目選定を今年の10月に 依頼された.現版の「地学事典」ではpitch を小島丈児氏が, rakeを小玉喜三郎氏と公文富士夫氏がそれぞれ断層と堆積構造 の例を挙げて解説しているが,総括的な説明はpitchの方でな されている.pitchとrakeは同義なので,「地学事典」の説明も まとめたほうが良い.そこで,どちらを項目として優先すべき か(送り関係をどうするか)を探るために,書棚にある海外の 構造地質の教科書でどちらを採用(優先)しているかを調べた. その結果をまとめたものを第1表に示す.あわせて,国内の構 造地質の教科書も2点挙げておく.
第1表 1970年代以降の構造地質学の教科書におけるpitchまたは rakeの採用状況.Countryは著者(筆頭著者)の所属機関の国名 (○:優先的に記述,△:補助的に記述,×:使わないほうが良い とされている,空白:記述なし
海外の教科書を見ると,米国の大学の著者はrakeを優先し, 英国の大学の著者はpitchを優先している傾向がみられる.た だし,Ragan(1985米国)やRowland et al.(2007米国)はpitch を項目として挙げ,rakeは同義としている.国内の構造地質学 の教科書の決定版とも言える狩野・村田(1998)の「構造地質 学」もrakeを取り上げ,pitchは同義としている.その理由は, おそらく筆者より上の世代はBillings の教科書(初版1942年,2 版1954年)で学んだことによるものと思われる.私自身も,学 部時代には授業でBillingsの教科書を薦められた.その後,大 学院に進学してから始めたマイロナイトの研究に役立った当時 の教科書がHobbs et al.(1976)であり,その教科書ではpitch が使われていたことから,筆者も構造地質学の講義ではずっと pitchを使ってきている.結局のところ,学んだ先生や教科書 の影響で,どちらを使うかが決まるのであろう.米国の著者の 多くもBillingsの教科書の影響が強いものと思われる. それでは,そもそもなぜ同義語が現在に至るまで生き続けて いるのだろうか.その歴史的経緯は,Hills(1972),Dennis (1972)の教科書に触れられており,Dennis(1972)が紹介し ているClark and McIntyre (1951) に詳細が記されていたので 紹介しよう.
地質構造の解析は鉱山開発が発端となっているが,鉱脈の面 に存在する鉱石の線状配列をもともと鉱山技師はpitchと呼ん でいた.Cook(1868)によると,その鉱石の線状配列の傾き を脈面(または層面)上で測定した値としてpitchが用いられ ていたと説明されている.ただし,Cookは鉛直面上で線状配 列と水平面とのなす角度に対してもpitchを使っていた.この 曖昧さについては40年後の1908年に議論があった.H. Louis教 授(英国)は線状配列の鉛直面上での角度についての用語がな いので,pitchを使うべきという主張を展開した.それに対し, Raymond et al.( 1908米国) は反論し,pitch は傾斜した面上で 測定した値として米国の鉱山技師が40年来用いており,それが 浸透しているので,Louis氏の主張は受け入れられないとした. このような混乱の中,Lindgren (1933) やBateman (1942) は, pitch と,「突入」などの意味を持つplungeの使い分けについて 記述した.Clark and McIntyre (1951英国)も,結論として pitch とplungeの使い分けを明確に示している.このような使 い分けが提案されていたものの,鉱山技師の混同が継続していrakeを用いることを推奨した(Billings, 1954),と「地学事典」 では小島氏により説明されている. 国内では米国流のrakeを使う人が多いようであるが,pitch も地質学の歴史が感じられる点で捨てがたい.2023年刊行を目 指している新しい「地学事典」では,どちらに説明がつけられ るだろうか.
文 献(第1表の教科書は省略)
Bateman, A. M., 1942, Economic Mineral Deposits. John Wiley and Sons, New York.
Clark, R. H. and McKintyre, D. B., 1951, The use of the terms pitch and plunge. Am. J. Sci., 249, 591-599.
Cook, G. H., 1868, The Geology of New Jersey . New Jersey Geological Survey, Newark.
Lindgren, W., 1933, Mineral Deposits. McGraw-Hill Book Co., New York.
Raymond, R. W. et al., 1908, Dip and pitch, discussion. Trans. Am. Inst. Min. Eng., 39, 326-327, 898-916.
【geo-Flash】No.508 謹賀新年
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.508 2021/1/6┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2021年 年頭のご挨拶
【2】名誉会員候補者の募集が開始されました
【3】2021年度会費について
【4】第12回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
【5】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【6】2022年度地震火山地質こどもサマースクール開催地募集
【7】「日本の地質学100年 : 日本地質学会100周年記念」再販セール中
【8】コラム:Pitch vs. Rake
【9】コラム:永瀬清子:宮沢賢治に憧れた女流詩人の地学的側面
【10】支部情報
【11】その他のお知らせ
【12】公募情報・各賞助成情報等
【13】訃報 藤田 崇 名誉会員 ご逝去
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2021年 年頭のご挨拶
──────────────────────────────────
会長 磯崎行雄
会員の皆様、明けましておめでとうございます。後の時代の教科書に重大な
歴史的変換点と確実に記述されるであろう西暦2020年が終わりました。2021年
が全世界にとって、また私たちの日本地質学会にとって、明るいものとなること
を切に願います。
全文はこちら,,, http://www.geosociety.jp/outline/content0137.html
(注)「崎」の正しい表記は、「大」は「立」となります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されました
──────────────────────────────────
募集締切:2021年2月10日(水)
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:例えば,,,地質学への顕著な貢献/地質学会の運
営と発展への貢献/教育現場や企業などでの活動を通じた地質学の普及と振興
への貢献...など
(注)上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することはでき
ませんが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
(名誉会員推薦委員会 佐々木和彦)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2021年度会費について
──────────────────────────────────
次年分(2021年度)の会費請求書を12月に発送いたしました.折り返し
ご送金をお願いいたします.自動引落の方は,12月23日に引き落しと
なりました(請求書ならびに引き落し通知は省略させていただきます).
また,学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)の
方で,それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適用します.
********************************************
2021年度分割引会費申請(最終締切):2021年3月31日(水)
※申請は毎年必要です.
********************************************
詳細は学会HPをご参照ください.
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第12回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
──────────────────────────────────
***応募締切:2021年2月1日(月)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコン
テストです.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!
会員の皆様からの応募をお待ちしています.
最優秀賞:1点 賞金5万円/優秀賞:2点 賞金2万円/ジオパーク賞:1点 賞金2万円
/日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・126巻1月号(予告)
(論説)八幡浜大島に分布する大島変成岩体のジルコンU–Pb年代と地体構造上の
意義:小山内康人ほか/(論説)フィッション・トラック熱年代解析およびU-Pb年代
測定に基づいた南九州せん断帯に分布する破砕帯の活動時期:末岡 茂ほか/(論
説)山口県北西部,後期白亜紀原岡山安山岩の層序学的位置の再検討:馬塲園 明
ほか/(レター)赤石山地中央部の小渋川地域に分布する陸源砕屑岩から得られた前
期白亜紀最末期の砕屑性ジルコン:志村侑亮ほか/(報告)中部地方渋川地域三波川
帯におけるヒスイ輝石の再確認:ダナイト中の細脈構成鉱物としての産出:塩谷
輝ほか
■ Island Arc
・新しい論文等が公開されています.
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14401738/0/ja
・LaTeXテンプレートを公開しました。クラウド型共同執筆ツールの
Authoreaでも利用可能です。 https://authorea.com/templates/island_arc_iar_
・Island Arcでは著者制作のVideo Abstractの掲載が可能です.
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14401738/homepage/video_abstracts
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】2022年度地震火山地質こどもサマースクール開催地募集
──────────────────────────────────
募集期間:2021年1月12日(火)から2月10日(水)
「地震火山地質こどもサマースクール」は,1999年夏から小・中・高校生を
対象にはじまった行事で,現在,日本地震学会,日本火山学会,日本地質学会
が共同で実施する,地球科学関連では最大規模の体験学習講座です.
今回,2022年度に実施する開催地を公募いたします.
応募資格など詳しくは, https://kodomoss.jp/applications/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】「日本の地質学100年 : 日本地質学会100周年記念」再販セール中
──────────────────────────────────
書架整理のため,再販いたします.残部稀少.
最後の購入チャンスです.この機会にぜひお買い求めください!
日本地質学会編,1993年4月発行,
706ページ,27cm,無線綴じ,布張上製本.
再販特別価格:3,000円(税・送料込)(参考)当初価格:8,000円
再販期間:2020年12月から2021年3月31日まで
お求めは,ジオストアから(クレジット決済可能)
http://geosociety2.sakura.ne.jp/store3/ec/
論集など学会出版物在庫案内はこちら
・論集58号「地震イベント堆積物」も再販中です
・「屋久島たんけんマップ」改版しました:最新の情報をアップデート!
http://www.geosociety.jp/publication/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】コラム:Pitch vs. Rake
──────────────────────────────────
正会員 高木秀雄
pitch(rake)とは,断層面上の条線や,砂岩の底面のソールマークなどのように,
傾斜した面構造上に線構造が存在する 時の面構造の走向と線構造とのなす角度を
面上で測定したもので,線の傾きを鉛直面上で求めた沈下角(plunge)と区別される.
続きはこちらから,,, http://www.geosociety.jp/faq/content0935.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】コラム:永瀬清子:宮沢賢治に憧れた女流詩人の地学的側面
──────────────────────────────────
正会員 石渡 明
筆者は2016年8月21日に岡山県赤磐市で開催された「じぇーじーねっと地質学
講座」に招待され,「東アジアの地質 赤磐市の海底岩石とのつながり」の題
で講演した.翌月25日,読売新聞日曜版に掲載された永瀬清子(1906〜1995)
の特集(名言巡礼:文・松本由圭,写真・林陽一)を読み,宮沢賢治に憧れて
「雨ニモマケズ」詩の「発見」の現場にも立ち会ったこの女流詩人が,戦後
ずっと赤磐市で農婦として働きながら詩作を続けていたことを初めて知った.
続きはこちらから、、、 http://www.geosociety.jp/faq/content0934.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
・2020年度関東支部功労賞募集
対象者:支部活動や地質学を通して広く社会貢献をされた関東支部内
に在住の個人・団体
公募期間:2020年12月17日から2021年1月17日
・ アウトリーチ巡検「川の防災と川が作った地形を巡る:
首都圏外郭放水路見学と春日部周辺,中川低地の地形観察」
実施日:2021年1月31日(日)
募集:20人(先着順) 最少催行人数15人
申込締切:2021年1月15日 *定員に達した時点で終了
・オンライン講演会「おうちで学ぶ恐竜研究の最前線」開催報告
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
[四国支部]
・第20回支部総会・講演会(名古屋大会代替企画)の講演要旨を公開中
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0212.html#2020koen
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
学術フォーラム・防災連携シンポジウム
「東日本大震災から10年とこれから」
1月14日(木)10:00-18:30
会場:東京医科歯科大学 鈴木章夫記念講堂(オンライン+現地開催)
主催:日本学術会議防災減災学術連携委員会,防災学術連携体(58学会)他
参加費:無料
定員:(会場)150名(500名の定員を1/3に制限しています)
(オンライン)1000名
https://janet-dr.com/060_event/20210114.html
日本地球惑星科学連合2021年大会
開催方式:ハイブリッド開催(オンライン開催+現地開催)
現地会場:パシフィコ横浜ノース
5月30日(日)-6月1日(火)/現地開催(主としてポスター発表)
6月3日(木)-6日(日)/オンライン開催(口頭,ポスター)
※現地開催は縮小もしくは中止となる可能性があります.
http://www.jpgu.org/meeting_j2021/
(後)第58回アイソトープ・放射線研究発表会
7月7日(水)-9日(金)
開催形態:オンライン開催
演題登録期間:2021年1月12日〜3月8日
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2021/top
(後)科学教育研究協議会 第68回全国研究大会・福島大会
7月31日(土)-8月2日(月)
会場:伊達市立霊山中学校(福島県伊達市霊山町)
大会テーマ 自然科学をすべての国民のものに
※新型コロナウイルスの感染状況により,Web大会に変更する場合があります.
https://kakyokyo.org/
国際ゴンドワナ研究連合(IAGR)2021年大会及び
第18回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム
9月17日(金)-19日(日)(会議)
9月20日(月)-21日(火)(野外巡検)
会場:中国青島
ファーストサーキュラー:
www.gondwanainst.org/symposium/2021/IAGR2021Invitation.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部門(無機地球化学)教授公募(2/5)
・鳥海山・飛島ジオパーク 推進協議会研究員の募集 (1/22)
・四国西予ジオパーク 令和3年度任用予定ジオパーク推進員募集(2/1)
・栗駒山麓ジオパーク専門員(地域おこし協力隊)募集 (1/25)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】訃報 藤田 崇 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
藤田 崇 名誉会員(大阪工業大学名誉教授)が、令和2年11月16日に
逝去されました(85歳)。これまでの故人の功績を讃えるとともに、
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。なおご葬儀は、すでにご親族により
しめやかに執り行われたとのことです。
会長 磯崎行雄
(注)「崎」の正しい表記は、「大」は「立」となります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.509 名誉会員候補者の募集が開始されています
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.509 2021/1/19┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】名誉会員候補者の募集が開始されています
【2】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
【3】第12回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
【4】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【5】2022年度地震火山地質こどもサマースクール開催地募集
【6】「日本の地質学100年 : 日本地質学会100周年記念」再販セール中
【7】研究計画の宣伝(promotion)ビデオの例(参考)
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
【11】訃報:黒田吉益 名誉会員 ご逝去
【12】新型コロナウィルス感染拡大防止に関する学会の対応(1月9日付)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されています
──────────────────────────────────
募集締切:2021年2月10日(水)
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:例えば,,,地質学への顕著な貢献/地質学会の運
営と発展への貢献/教育現場や企業などでの活動を通じた地質学の普及と振興
への貢献...など
(注)上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することはでき
ませんが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
(名誉会員推薦委員会 佐々木和彦)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は,3月31日(水)です.
2021年度の割引会費を希望のかたは,忘れずにご提出ください(締切厳守).
■ 自動引落による納入
昨年12月23日にお届けの金融機関口座より引き落としさせていただきました.
通帳記帳等でご確認ください.請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略さ
せていただきますのでご了承ください.
■ 郵便振替用紙(またはゆうちょ銀行口座)からのお振り込み
12月中旬に請求書兼郵便振替用紙を発送しました.地質学会の会費は前納制で
すので,お早めにご送金ください.
2021年度割引会費申請や通常の会費払込について
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】第12回惑星地球フォトコンテスト 作品募集中
──────────────────────────────────
***応募締切:2021年2月1日(月)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコン
テストです.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!
会員の皆様からの応募をお待ちしています.
最優秀賞:1点 賞金5万円/優秀賞:2点 賞金2万円/ジオパーク賞:1点 賞金2万円
/日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・126巻1月号(予告)
(論説)八幡浜大島に分布する大島変成岩体のジルコンU–Pb年代と地体構造上の
意義:小山内康人ほか/(論説)フィッション・トラック熱年代解析およびU-Pb年代
測定に基づいた南九州せん断帯に分布する破砕帯の活動時期:末岡 茂ほか/(論
説)山口県北西部,後期白亜紀原岡山安山岩の層序学的位置の再検討:馬塲園 明
ほか/(レター)赤石山地中央部の小渋川地域に分布する陸源砕屑岩から得られた前
期白亜紀最末期の砕屑性ジルコン:志村侑亮ほか/(報告)中部地方渋川地域三波川
帯におけるヒスイ輝石の再確認:ダナイト中の細脈構成鉱物としての産出:塩谷
輝ほか
■ Island Arc
・新しい論文等が公開されています.
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14401738/0/ja
・LaTeXテンプレートを公開しました。クラウド型共同執筆ツールの
Authoreaでも利用可能です。https://authorea.com/templates/island_arc_iar_
・Island Arcでは著者制作のVideo Abstractの掲載が可能です.
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14401738/homepage/video_abstracts
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2022年度地震火山地質こどもサマースクール開催地募集
──────────────────────────────────
募集期間:2021年1月12日(火)から2月10日(水)
「地震火山地質こどもサマースクール」は,1999年夏から小・中・高校生を
対象にはじまった行事で,現在,日本地震学会,日本火山学会,日本地質学会
が共同で実施する,地球科学関連では最大規模の体験学習講座です.
今回,2022年度に実施する開催地を公募いたします.
応募資格など詳しくは,https://kodomoss.jp/applications/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】「日本の地質学100年 : 日本地質学会100周年記念」再販セール中
──────────────────────────────────
書架整理のため,再販いたします.残部稀少.
最後の購入チャンスです.この機会にぜひお買い求めください!
日本地質学会編,1993年4月発行,
706ページ,27cm,無線綴じ,布張上製本.
再販特別価格:3,000円(税・送料込)(参考)当初価格:8,000円
再販期間:2020年12月から2021年3月31日まで
お求めは,ジオストアから(クレジット決済可能)
http://geosociety2.sakura.ne.jp/store3/ec/
論集など学会出版物在庫案内はこちら
・論集58号「地震イベント堆積物」も再販中です
・「屋久島たんけんマップ」改版しました:最新の情報をアップデート!
http://www.geosociety.jp/publication/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】研究計画の宣伝(promotion)ビデオの例(参考)
──────────────────────────────────
友人のアメリカ人研究者 Paul Falkowski (Rutgers大学)教授から,彼の大学を中心にNASAからの援助のもと進めている研究計画 ”Enigma” に関する宣伝ビデオを作ったので,是非見て欲しいというメールを受け取りました.早速試聴したところ,これがなかなかよくできていて感心しました.子供達にもよくわかるように工夫されているところが,よくありがちな作成者達による自己満足ビデオとは大きく異なると感じました.若い新規会員の獲得を目指す地質学会でも(現在のHPのような静止画像のみではない)宣伝ビデオを用意する必要があり,その際には大いに参考になると思い,ここにご紹介する次第です.(磯粼行雄)
ビデオURL https://youtu.be/DGTPPy2fNyc
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
(中止)アウトリーチ巡検「川の防災と川が作った地形を巡る:
首都圏外郭放水路見学と春日部周辺,中川低地の地形観察」
→1月末に開催を予定していましたが,中止となりました.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
下北ジオパーク学術研究発表会(オンライン)
1月23日(土)13:00-16:00(使用媒体:Microsoft Teams)
参加無料.要事前申込
http://shimokita-geopark.com/2020/12/17/0123presentation/
国際シンポジウム(オンライン)
「持続可能な未来を拓く 〜コロナ時代における自然と人間との共生〜」
主催:国際花と緑の博覧会記念協会,地球環境戦略研究機関(IGES)
2月3日(水)15:00-16:00(日本時間)
要事前申し込み
https://www.expo-cosmos.or.jp/main/cosmos/symposium/20210203/index.html
産業技術総合研究所 第33回GSJシンポジウム(オンライン)
地圏資源環境研究部門 研究成果報告会
「地圏に関わる社会課題の解決に向けて」
2月5日(金)13:00-16:10
方法:Microsoft Teamsライブイベント
参加費無料
https://unit.aist.go.jp/georesenv/index.html
令和2年度海洋プラスチックごみ学術シンポジウム(オンライン)
3月3日(水) 9:30-17:30(予定)
主催:環境省
参加費:無料,定員:500名
参加登録締締切:3月2日(火)17:00
講演者公募締切:1月29日(金)正午
https://www.env.go.jp/press/108945.html
日本地球惑星科学連合2021年大会
開催方式:ハイブリッド開催(オンライン開催+現地開催)
現地会場:パシフィコ横浜ノース
5月30日(日)-6月1日(火)/現地開催(主としてポスター発表)
6月3日(木)-6日(日)/オンライン開催(口頭,ポスター)
※現地開催は縮小もしくは中止となる可能性があります.
http://www.jpgu.org/meeting_j2021/
(後)第58回アイソトープ・放射線研究発表会
7月7日(水)-9日(金)
開催形態:オンライン開催
演題登録期間:2021年1月12日〜3月8日
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2021/top
(後)科学教育研究協議会 第68回全国研究大会・福島大会
7月31日(土)-8月2日(月)
会場:伊達市立霊山中学校(福島県伊達市霊山町)
大会テーマ 自然科学をすべての国民のものに
※新型コロナウイルスの感染状況により,Web大会に変更する場合があります.
https://kakyokyo.org/
国際ゴンドワナ研究連合(IAGR)2021年大会及び
第18回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム
9月17日(金)-19日(日)(会議)
9月20日(月)-21日(火)(野外巡検)
会場:中国青島
ファーストサーキュラー:
www.gondwanainst.org/symposium/2021/IAGR2021Invitation.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・高知大学海洋コア総合研究センター特任専門職員(技術職員)募集(2/12)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】訃報:黒田吉益 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
黒田吉益 名誉会員(信州大学名誉教授)が,令和3年1月4日(月)に
逝去されました(94歳).
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上
げます.なお,ご葬儀はすでにご親族により執り行われたとのことです.
会長 磯崎行雄
(注)「崎」の正しい表記は,「大」は「立」となります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】新型コロナウィルス感染拡大防止に関する学会の対応(1月9日付)
──────────────────────────────────
首都圏における新型コロナウィルス感染症の急速な感染拡大に伴い,令和3年1月7日
(木)に,首都圏の1都3県に「緊急事態宣言」が発出されました.(中略)
この状況を鑑みて,緊急事態宣言が発出されている地域,または自治体からそれに
準ずる宣言等が出されている地域では,対面形式の学会主催の行事・イベントは屋
内外を問わず中止または延期,あるいはオンライン開催への変更のご検討をお願い
いたします.それ以外の地域においても,当面はなるべく対面形式での開催を避
け、オンラインでの開催をお願いいたします.
なお,学会事務局は原則テレワークを実施し,問い合わせ等についてはメールのみ
での対応としています.
全文はこちら,http://www.geosociety.jp/news/n160.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.510 学術大会トピックセッション募集!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.510 2021/2/2┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】学術大会トピックセッション募集!
【2】(名古屋代替)JABEEオンラインシンポ
【3】名誉会員候補者の推薦について
【4】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
【5】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【6】2022年度地震火山地質こどもサマースクール開催地募集
【7】「日本の地質学100年 : 日本地質学会100周年記念」再販セール中
【8】会員の学術・教育・社会貢献活動
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
【11】事務局からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】学術大会トピックセッション募集!
──────────────────────────────────
トピックセッションを募集します 締切:2021年3月10日(水)
128年学術大会を本年9月に開催予定です.開催形態などまだ未定な部分も
ありますが,トピックセッションを募集します.
なお,昨年開催できなかった7セッションについては,本年あらためて開催
の予定です.
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0129.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】(名古屋代替)JABEEオンラインシンポ
──────────────────────────────────
(2020名古屋大会代替企画)JABEEオンラインシンポジウム
自然災害列島における地質技術者の育成−大学統合期における地質学教育ー
開催日時:2021年3月7日(日)14:00-17:15(予定)
配信方法:ZoomにYou Tubeを連動させるオンライン方式
参加費無料.Zoom参加者は事前登録制
(注)総合討論での口頭による直接質問などをご希望の方は,zoomでの
参加をお申込みください.YouTubeご視聴の方は,申込不要ですが,当日は,
チャットによる質問のみとなります.zoom参加の申込締切:2月25日(木)
プログラムや講演概要など詳しくは,
http://www.geosociety.jp/science/content0127.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本地質学会名誉会員候補者の推薦について
──────────────────────────────────
推薦締切:2021年2月10日(水)
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:例えば,,,地質学への顕著な貢献/地質学会の運
営と発展への貢献/教育現場や企業などでの活動を通じた地質学の普及と振興
への貢献...など
(注)上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することはでき
ませんが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
(名誉会員推薦委員会 佐々木和彦)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は,3月31日(水)です.
2021年度の割引会費を希望のかたは,忘れずにご提出ください(締切厳守).
2021年度割引会費申請や通常の会費払込について
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・126巻1月号(発行になりました)
(論説)八幡浜大島に分布する大島変成岩体のジルコンU–Pb年代と地体構造上の
意義:小山内康人ほか/(論説)フィッション・トラック熱年代解析およびU-Pb年代
測定に基づいた南九州せん断帯に分布する破砕帯の活動時期:末岡 茂ほか/(論
説)山口県北西部,後期白亜紀原岡山安山岩の層序学的位置の再検討:馬塲園 明
ほか/(レター)赤石山地中央部の小渋川地域に分布する陸源砕屑岩から得られた前
期白亜紀最末期の砕屑性ジルコン:志村侑亮ほか/(報告)中部地方渋川地域三波川
帯におけるヒスイ輝石の再確認:ダナイト中の細脈構成鉱物としての産出:塩谷
輝ほか
■ Island Arc
・新しい論文等が公開されています.
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14401738/0/ja
・LaTeXテンプレートを公開しました.クラウド型共同執筆ツールの
Authoreaでも利用可能です. https://authorea.com/templates/island_arc_iar_
・Island Arcでは著者制作のVideo Abstractの掲載が可能です.
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14401738/homepage/video_abstracts
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】2022年度地震火山地質こどもサマースクール開催地募集
──────────────────────────────────
募集期間:2021年1月12日(火)から2月10日(水)
「地震火山地質こどもサマースクール」は,1999年夏から小・中・高校生を
対象にはじまった行事で,現在,日本地震学会,日本火山学会,日本地質学会
が共同で実施する,地球科学関連では最大規模の体験学習講座です.
今回,2022年度に実施する開催地を公募しています.
応募資格など詳しくは, https://kodomoss.jp/applications/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】「日本の地質学100年 : 日本地質学会100周年記念」再販セール中
──────────────────────────────────
書架整理のため,再販いたします.残部稀少.
最後の購入チャンスです.この機会にぜひお買い求めください!
日本地質学会編,1993年4月発行,706p,無線綴,布張上製本.
再販特別価格:3,000円(税・送料込)(参考)当初価格:8,000円
再販期間:2021年3月31日まで
お求めは,ジオストアから(クレジット決済可能)
http://geosociety2.sakura.ne.jp/store3/ec/
論集など学会出版物在庫案内はこちら
・論集58号「地震イベント堆積物」も再販中です
・「屋久島たんけんマップ」改版しました:最新の情報をアップデート!
http://www.geosociety.jp/publication/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】会員の学術・教育・社会貢献活動
──────────────────────────────────
*石橋 隆会員 監修 NHKが以下の番組を放映します.
<番組タイトル> 「所さん!大変ですよ」ブーム到来!?不思議な鉱物の世界
<放送予定>2月3日(水)23:45-0:12< NHK総合1・東京>
<内容>いま色とりどりの石に魅せられた“鉱物女子”が増えていることが判明!
鉱物を使った実験や,鉱物で作る料理?など驚きの楽しみ方を紹介する.
*辻森 樹会員らによる
「Crustal evolution of the Paleoproterozoic Ubendian Belt (SW Tanzania)
western margin: A Central African Shield amalgamation tale」
(Gondwana Research, v. 91, p. 286-306)の掲載内容が東北大学から
プレスリリースされました.
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0109.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
産業技術総合研究所 第33回GSJシンポジウム
地圏資源環境研究部門 研究成果報告会
「地圏に関わる社会課題の解決に向けて」
2月5日(金)13:00-16:10
方法:オンライン,Microsoft Teamsライブイベント
参加無料
https://unit.aist.go.jp/georesenv/index.html
公開シンポジウム「桜川低地の成り立ちと里山ジオツアーの勧め」
2月14日(日)13:20-16:45(13:00 開場)
主催:筑波山地域ジオパーク推進協議会
参加形式:オンラインのみ(Zoomを使用)
参加申込締切:2月7日(日)
https://tsukuba-geopark.jp/page/page000704.html
日本学術会議学術フォーラム
新たな地球観への挑戦―地球惑星科学の国際学術組織の活動と日本の貢献―
2月15日(月)13:00-17:30
オンライン開催 参加無料
http://www.scj.go.jp/ja/event/2021/306-s-0215.html
日本地球惑星科学連合2021年大会
開催方式:ハイブリッド開催(オンライン開催+現地開催)
現地会場:パシフィコ横浜ノース
5月30日(日)-6月1日(火)/現地開催(主としてポスター発表)
6月3日(木)-6月6日(日)/オンライン開催(口頭,ポスター)
※現地開催は縮小もしくは中止となる可能性があります.
http://www.jpgu.org/meeting_j2021/
(後)第58回アイソトープ・放射線研究発表会
7月7日(水)-9日(金)
開催形態:オンライン開催
演題登録期間:2021年1月12日-3月8日
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2021/top
(後)科学教育研究協議会 第68回全国研究大会・福島大会
7月31日(土)-8月2日(月)
会場:伊達市立霊山中学校(福島県伊達市霊山町)
大会テーマ 自然科学をすべての国民のものに
※新型コロナウイルスの感染状況により,Web大会に変更する場合があります.
https://kakyokyo.org/
国際ゴンドワナ研究連合(IAGR)2021年大会及び
第18回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム
9月17日(金)-19日(日)(会議)
9月20日(月)-21日(火)(野外巡検)
会場:中国青島
ファーストサーキュラー:
www.gondwanainst.org/symposium/2021/IAGR2021Invitation.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・令和3年度 苗場山麓ジオパーク学術研究奨励事業助成金募集 (3/5)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】事務局からのお知らせ
──────────────────────────────────
現在,学会事務局は原則テレワークを実施し,問い合わせ等についてはメール
のみでの対応とさせてい頂いております(郵便物の受領は可能です).
会員の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが,何卒ご了承ください.
新型コロナウィルス感染拡大防止に関する学会の対応(1月9日付)
http://www.geosociety.jp/news/n160.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.511 令和3年2月 福島県沖を震源とする地震
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.511 2021/2/16┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】地質災害関連情報:令和3年2月 福島県沖を震源とする地震
【2】チバニアン提案書の公開と,その引用について
【3】学術大会トピックセッション募集!
【4】(名古屋代替)JABEEオンラインシンポ
【5】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
【6】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【7】「日本の地質学100年 : 日本地質学会100周年記念」再販セール中
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
【11】事務局からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】地質災害関連情報:令和3年2月 福島県沖を震源とする地震
──────────────────────────────────
(速報)2月13日夜の福島県沖を震源とするM7.3の地震:
地震発生時・直後の仙台市内の様子(辻森 樹・高嶋礼詩)
2021年2月13日午後11時8分ごろ、福島県沖(北緯37.73度、東経141.8度)
でマグニチュード7.3(推定)の地震が発生した。震源の深さは約55kmで、
東北地方を中心に広範囲で揺れを観測し(仙台市青葉区は震度5強)、気象
庁は翌日14日に会見を開き、10年前に起きた東北地方太平洋沖地震(東日
本大震災)の余震と説明した。
地震発生時、私はちょうど自宅(大学宿舎)で眠りについた直後で、長い
揺れで目が覚めた。
全文はこちら、、、http://www.geosociety.jp/hazard/content0101.html
----------------------------------------------------
このほか、令和3年2月福島県沖を震源とする地震に関連する情報を学会HPに
掲載しています。
http://www.geosociety.jp/hazard/content0100.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】チバニアン提案書の公開と,その引用について
──────────────────────────────────
チバニアンGSSPの提案申請書が,IUGS(国際地質科学連合)の学術誌Episodes
に掲載され,ウェブサイトで公開されました.
https://doi.org/10.18814/epiiugs/2020/020080
日本発の地質年代名称「チバニアン: Chibanian」の国際的認知度を高めるため
にも,論文など出版物中で積極的にチバニアンGSSPに言及し,本提案書を引用
してくださいますようお願いいたします.GSSPは10年間のモラトリアム期間が
過ぎると再審査が可能になります.チバニアンの国際的認知度の向上が,将来的
にチバニアンGSSPを維持することにも繋がりますので,会員の皆様には是非と
もご協力お願いいたします.
(日本地質学会学術研究部会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】学術大会トピックセッション募集!
──────────────────────────────────
トピックセッションを募集します 締切:2021年3月10日(水)
128年学術大会を本年9月に開催予定です.開催形態などまだ未定な部分も
ありますが,トピックセッションを募集します.
なお,昨年開催できなかった7セッションについては,本年あらためて開催
の予定です.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0129.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】(名古屋代替)JABEEオンラインシンポ
──────────────────────────────────
(2020名古屋大会代替企画)JABEEオンラインシンポジウム
自然災害列島における地質技術者の育成−大学統合期における地質学教育ー
日時:2021年3月7日(日)14:00-17:15(予定)
配信方法:ZoomにYou Tubeを連動させるオンライン方式
参加費無料.Zoom参加者は事前登録制(Youtube視聴の場合は申込不要)
(注1)総合討論での口頭による直接質問などをご希望の方は,zoomでの
参加をお申込みください。
(注2)CPD単位の発行をご希望の場合は,zoomでの参加をお申込み
ください。
zoom参加の申込締切:2月25日(木)
プログラムや講演概要など詳しくは,
http://www.geosociety.jp/science/content0127.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は,3月31日(水)です.
2021年度の割引会費を希望のかたは,忘れずにご提出ください(締切厳守).
2021年度割引会費申請や通常の会費払込について
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・126巻2月号(予告)
(論説)緑色普通角閃石の主成分および微量成分元素組成による美浜テフラと
四国沖MD012422 コアから検出されたクリプトテフラとの対比と給源の推定:
古澤 明ほか/(論説)領家花崗岩類に伴う同時性岩脈の形成過程:中島 隆
ほか/(論説)秋田県出羽山地の笹森丘陵に分布する新第三系の地質と珪藻化
石層序:加藤悠爾ほか/(レター)An early Carboniferous (late Visean)
brachiopod fauna from the Arakigawa Formation of Hongo, Hida Gaien
Belt, central Japan, and its tectonic significance:Jun-ichi Tazawa et al
(レター)/韓国・錦山地域・沃川帯の古原生代・花崗片麻岩のジルコンU–Pb
年代:岩水健一郎ほか
■ Island Arc
・新しい論文等が公開されています.
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14401738/0/ja
・LaTeXテンプレートを公開しました.クラウド型共同執筆ツールの
Authoreaでも利用可能です.https://authorea.com/templates/island_arc_iar_
・Island Arcでは著者制作のVideo Abstractの掲載が可能です.
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14401738/homepage/video_abstracts
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】「日本の地質学100年 : 日本地質学会100周年記念」再販セール中
──────────────────────────────────
日本地質学会編,1993年4月発行,706p,無線綴,布張上製本.
再販特別価格:3,000円(税・送料込)(参考)当初価格:8,000円
再販期間:2021年3月31日まで
お求めは,ジオストアから(クレジット決済可能)
http://geosociety2.sakura.ne.jp/store3/ec/
論集など学会出版物在庫案内はこちら
・論集58号「地震イベント堆積物」も再販中です
・「屋久島たんけんマップ」改版しました:最新の情報をアップデート!
http://www.geosociety.jp/publication/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
サイエンスカフェ「VR!!地球科学のアソビカタ」
仮想現実(Virtual Reality)ってナニ?VRって役に立つ?地球科学者で,
VRを駆使して研究成果を世界に発信しているゲストスピーカーと,VR
世界の泳ぎ方,新しい情報発信の方法,VRと地球科学の相乗効果などを
参加者の皆さんに体験していただきます.
日程:3月21日(日)
開催場所:クラスターによるVR空間内 参加費:無料
詳しくは,https://sites.google.com/view/vr-earth/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
経済開発協力機構/原子力機関(OECD/NEA)におけるアンケート
「信頼される規制機関の特性」協力依頼
原子力に関する政策・技術に関する情報・意見交換、問題の検討等を行っている
OECD/NEAから、信頼される規制機関の特性について任意のアンケートの対応
依頼が参りましたので、ご案内させていただきます。
OECD/NEAの原子力規制活動委員会(CNRA)に設置された規制機関のパブリック
コミュニケーションに関するワーキンググループ(WGPC)では、原子力規制機関
とステークスホルダー間における信頼の維持・構築について議論をしており、本
アンケートは、WGPCが2023年の出版を目指している実践的ガイド(グリーン
ブックレット)「信頼される規制機関の特性」を作成するための調査として実施
されるものとなります。
※過去の関連資料に、
NEAグリーンブック「The Characteristics of an Effective Regulator」(2014年)、
「The Safety Culture of an Effective Nuclear Regulatory Body」(2016年)
があります。
本アンケートの対象はNEA加盟国における個人であり、政府として回答をひとつに
まとめることは求められておりません。
つきましては、ご関心のある方におかれましては、3月15日までに下記URLから
調査ページを御参照いただき、ご回答いただけますようお願いいたします。
※アンケートの質問、回答は全て英語になります。
https://www.surveymonkey.com/r/XM7JZDG
問い合わせ先:
原子力規制庁大臣官房人事課:奥
電話:03-5114-2100(内線4611)
----------------------------------------------------
多摩六都科学館 春の特別企画展
47都道府県の石ー「県の石」を見てみよう
3月20日(土)-5月9日(日)
(注)感染症の拡大状況によっては中止の可能性もあります.
https://www.tamarokuto.or.jp/event/index.html?c=event&info=2491&day=2021-03-20
第10回学生のヒマラヤ野外実習ツアー(延期)
2021年3月実施予定の表題のツアーは2022年3月に延期となりました.
www.gondwanainst.org/geotours/Studentfieldex_index.htm
学生のヒマラヤ野外実習プロジェクト:世話人会代表 吉田 勝
----------------------------------------------------
東京大学大気海洋研究所共同利用研究集会
琉球弧ダイナミクスの新展開:島弧ダイナミクスの理解への新たな切り口
3⽉3⽇(水)-4日(木) 9:00-12:30,
場所: Zoom meeting(要事前参加登録)
https://www.aori.u-tokyo.ac.jp/aori_news/meeting/2021/20210303.html
日本地球惑星科学連合2021年大会
開催方式:ハイブリッド開催(オンライン開催+現地開催)
現地会場:パシフィコ横浜ノース
5月30日(日)-6月1日(火)/現地開催(主としてポスター発表)
6月3日(木)-6月6日(日)/オンライン開催(口頭,ポスター)
※現地開催は縮小もしくは中止となる可能性があります.
http://www.jpgu.org/meeting_j2021/
地質学史総会・懇話会
6月26日(土)13:00-17:30(予定)
場所:北とぴあ 8階803号室(JR京浜東北線王子駅下車3分)
志岐常正:「戦後京大地質学教室史―その虚像と実像」
矢島道子:『地質学者ナウマン伝』を上梓して
(注)状況によってはオンラインまたはハイブリッドでの開催を検討します.
(後)第58回アイソトープ・放射線研究発表会
7月7日(水)-9日(金)
開催形態:オンライン開催
演題登録期間:2021年1月12日-3月8日
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2021/top
(後)科学教育研究協議会 第68回全国研究大会・福島大会
7月31日(土)-8月2日(月)
会場:伊達市立霊山中学校(福島県伊達市霊山町)
大会テーマ 自然科学をすべての国民のものに
※新型コロナウイルスの感染状況により,Web大会に変更する場合があります.
https://kakyokyo.org/
国際ゴンドワナ研究連合(IAGR)2021年大会及び
第18回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム
9月17日(金)-19日(日)(会議)
9月20日(月)-21日(火)(野外巡検)
会場:中国青島
ファーストサーキュラー:
www.gondwanainst.org/symposium/2021/IAGR2021Invitation.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究施設教員(助教)公募(3/31)
・岡⼭理科⼤学理学部基礎理学科地学分野(岩石・鉱物関連)教員募集(5/7)
・2021年度深田野外調査助成(4/23
・JST未来社会創造事業(探索加速型)重点公募テーマ策定のテーマアイデア募集
(随時募集)
・2021年度日本学術振興会賞受賞候補者の推薦募集 (学会締切3/25)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】事務局からのお知らせ
──────────────────────────────────
現在,学会事務局は原則テレワークを実施しており,問い合わせ等については
メールのみでの対応とさせてい頂いております(郵便物の受領は可能です).
会員の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが,何卒ご了承ください.
新型コロナウィルス感染拡大防止に関する学会の対応(1月9日付)
http://www.geosociety.jp/news/n160.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.512 東日本大震災から10年にあたって
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.512 2021/3/2┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】東日本大震災から10年にあたって
【2】地質学雑誌の完全電子化実現に向けて
【3】学術大会トピックセッション募集(まもなく締切)
【4】(名古屋代替)JABEEオンラインシンポ
【5】「地質の日」オンライン講演会開催します
【6】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
【7】「日本の地質学100年 : 日本地質学会100周年記念」再販セール中
【8】紹介:プレートテクトニクス・トランプ
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】東日本大震災から10年にあたって
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会
会長 磯粼行雄
2011年3月11日に発生した東日本大震災から間もなく10年となります.
未曾有の大災害に対して各地で復興はすすんでいますが,未だ被災者の
皆様の心の傷は十分に癒やされていないことでしょう.この10年間を
顧みると,地震だけでなく,火山噴火,台風や大雨などによる風水害,
土砂災害,大雪による雪害など,個別に挙げるのもためらうくらい多様
な災害に見舞われました.
全文はこちら、
http://www.geosociety.jp/engineer/content0057.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】地質学雑誌の完全電子化実現に向けて
──────────────────────────────────
(日本地質学会執行理事会)
地質学会の会員数は,1999年の5200名をピークに減少の一途をたどっています.
2021年1月末現在の会員数(正会員)は3368名と,この約20年間で実に約1800
名もの会員減です.それに伴い学会運営の根幹となる会費収入も20年前のおよそ
3分の2に激減しました.特に昨今のコロナ禍で会員減少が加速しました(昨年度
比約170名減).このような状況下で学会としては思い切った財政改革が喫緊の
課題となっています.この財政改革の大きな柱が地質学雑誌の完全電子化(冊子
廃止)です.
地質学雑誌の完全電子化については2016年より「地質学雑誌のあり方を考える
タスクフォース」で検討を行いました.完全電子化により大幅な経費削減が見込
まれますが,2018年に実施した会員アンケートでは冊子配布の継続を望む声も
少なくなかったため,翌年の答申では完全電子化の実現は時期尚早との判断をし
ました.しかしコロナ禍で会員減少が加速化し,学会の置かれている状況は大き
く変わりました.私たちは今,早急に完全電子化の実現に向けて,具体的な検討
をすすめる必要があります.
地質学雑誌の完全電子化は,経費削減のみならず,編集出版作業の迅速化,カラー
チャージの廃止,あるいはバーチャル特集号企画が可能になるなど,投稿・編集
出版においても大きなメリットがあります.学術雑誌の電子化は, 日本のみならず
世界の学術研究において大きな流れとなっています.
一方で会員減少に手をこまねいているわけはありません.並行して学生・院生の
入会促進策や,入会後も長く会員を継続してもらうための魅力ある会員サービス
についても検討をすすめています.地質学雑誌の完全電子化は, このような学会
運営の大きな改革の一環と位置づけられます.
以上のように, 執行理事会では完全電子化の実現に向けた具体的な検討を開始し
ました.電子化に向けたスケジュールを含め,検討結果は今後随時ジオフラッ
シュやニュース誌等でお知らせしていきます.会員の皆様には、このような状況
をご理解いただき、ご協力を心よりお願い申し上げる次第です.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】学術大会トピックセッション募集(まもなく締切)
──────────────────────────────────
トピックセッションを募集します 締切:2021年3月10日(水)
128年学術大会を本年9月に開催予定です.開催形態などまだ未定な部分も
ありますが,トピックセッションを募集します.
なお,昨年開催できなかった7セッションについては,本年あらためて開催
の予定です.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0129.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】(名古屋代替)JABEEオンラインシンポ
──────────────────────────────────
(2020名古屋大会代替企画)JABEEオンラインシンポジウム
自然災害列島における地質技術者の育成−大学統合期における地質学教育ー
日時:2021年3月7日(日)14:00-17:15(予定)
配信方法:ZoomにYou Tubeを連動させるオンライン方式
(zoomの参加は受付を締切ました。当日はYouTubeでご視聴ください)
プログラムや講演概要など詳しくは,
http://www.geosociety.jp/science/content0127.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】「地質の日」オンライン講演会開催します
──────────────────────────────────
日本地質学会は,一般の皆様に最新の地質学研究の成果とその意義について
知っていただき,地質学への興味・関心を高めていただくことを目的に,
5/10地質の日にあわせて一般講演会をオンラインで開催いたします。どなた
でも無料で参加できます。チャット(YouTube上での書き込み)で質問・
コメントもできます。
開催日時:5月9日(日) 9:30開会,12:10閉会予定
開催方法:YouTubeライブ配信 どなたでも視聴可能,申込不要,無料
<講師と講演タイトル>
岡田 誠(茨城大学理工学研究科教授)
「地質年代チバニアンと房総の地質」
氏家恒太郎(筑波大学生命環境系准教授)
「断層の地質学的研究から読み解くプレート沈み込み帯地震発生の科学」
このほか、学会関連の「地質の日」行事については、ホームページに随時
情報を掲載していきます。
http://www.geosociety.jp/name/content0175.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は,3月31日(水)です.
2021年度の割引会費を希望のかたは,忘れずにご提出ください(締切厳守).
2021年度割引会費申請や通常の会費払込について
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】「日本の地質学100年 : 日本地質学会100周年記念」再販セール中
──────────────────────────────────
日本地質学会編,1993年4月発行,706p,無線綴,布張上製本.
再販特別価格:3,000円(税・送料込)(参考)当初価格:8,000円
再販期間:2021年3月31日まで
お求めは,ジオストアから(クレジット決済可能)
http://geosociety2.sakura.ne.jp/store3/ec/
論集など学会出版物在庫案内はこちら
・論集58号「地震イベント堆積物」も再販中
・「屋久島たんけんマップ」改版しました:最新の情報をアップデート!
http://www.geosociety.jp/publication/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】紹介:プレートテクトニクス・トランプ
──────────────────────────────────
公益財団法人日本発明振興協会
企画・編集・執筆:柴田治呂(同協会),イラスト:
玉井奈津子(グラパックジャパン(株)),54枚
(ジョーカー2枚含む,紙箱入り)1000円(税込),
89✕57mm 2017(平成29)年から発売
これは表側にプレート(♠),地震(♥),火山(♦),
地質(地球表層)(♣)に関連した図や写真とその
説明文を,裏側に地球全体の衛星画像(インドシナ
中心)を印刷したトランプである.描かれている内容
は学問的にも概ね正確であり,デザインや印刷も美し
く,紙質もしっかりしていて扱いやすく,繰り返し使用に耐える.左上と右下にA
〜Kの英数字と組記号が印刷され,J, Q, Kの札は右上に人物像も描かれている
ので,普通のトランプとして使うのに支障はない.
同じ数字の4枚の札は内容が関連していて,例えばA(エース)の札は世界地図にプ
レート(♠),地震(♥),火山(♦),造山帯(♣)の分布が示されている(付図
参照).模式図や分布図だけでなく,♥3の1995年兵庫県南部地震野島断層トレンチ
露頭,♣Jの2011年東北地方太平洋沖地震による地殻変動,♦9の1986年伊豆大島
噴火,♦Qの2012年ハワイ・キラウェア噴火等,最近発生した実事象の図や写真も
多く使われている.地質分野は,♣2が日本海拡大の図,♣3は阿蘇カルデラ,♣4は
海底のコバルトリッチクラスト,♣5は海底熱水噴出孔,♣6は長瀞の変成岩露頭,
♣7はスイスのグラールス衝上断層露頭,♣8はサンアンドレアス断層の航空写真,
♣9は南房総の海岸段丘,♣10は月出の中央構造線露頭,♣Qはアフリカ大地溝帯
となっている.♠Q,♥Qのようにプルームに関する内容もあり,最後は♠Kの地球
内部構造図,♥Kの地球の自由振動と2004年スマトラ地震の表面波の時刻歴波形,
♦Kの洪水玄武岩とペルム紀末の大量絶滅,♣Kのユカタン半島の隕石衝突と大量
絶滅で締めている.なお各組9は関東地方特集で,♠相模トラフ地震の震源域,
♥関東地震年代表,♦伊豆大島噴火,♣南房総の海岸段丘となっており,各組10
は南海トラフ地震特集で,♠震源域,♥年代表,♦宝永富士山噴火,♣中央構造線
となっている.ジョーカー2枚はゴンドワナ超大陸とパンゲア超大陸を示した半球図
で,それぞれ太平洋スーパープルーム,大西洋スーパープルームの位置が示してある
(これらはジョーク?).パンゲアは北極から南極まで大陸が一列に並んでいたが,
ゴンドワナは大陸が南半球に集中していた.
ところで,最近は多様性の時代なので,カードゲームを「トランプ」というのは
日本だけであることに注意する必要がある.「トランプtrump」は切り札(強い札)
のことで,明治時代に英米人が「トランプ」と叫びながらカードゲームをやってい
るのを見て,この遊びは「トランプ」と言うのだと日本人が勘違いしたのだと言わ
れている.今となっては皮肉に聞こえるが,切り札となる「トランプ」には「すば
らしい人」,「頼もしい人」,「立派な人」という意味がある.英語ではこの遊び
を単にcards, playing cardなどと言い,中国では撲克牌(pūkepái, ポーカー札)と
言う.日本では英米式の13枚✕4組=52枚のトランプが一般的だが,枚数は国によっ
て異なり,イタリアでは40枚,ロシアでは36枚が普通である.日本の花札は4枚×
12ヶ月=48枚だが,これは江戸時代のポルトガルのトランプに従った枚数とされる.
1980年頃から米国発のUNOが流行したが,これは108〜112枚を用いる.さらに,
麻雀máquè(標準中国語では麻将májiàng)牌は日本では普通136個を用いる.
遊び方として,付属の説明書には,「同じ数字のカードには関連性が深い現象が配
置されていますので,‟うすのろ”,‟ドンキー”,‟オーサーズ”など同じ数字のカード
を4枚集めるゲームは特におすすめです」とあり,同じ数字の4枚を集めるオリジナ
ル・ゲームも紹介されている.3枚揃っている時に4枚目が場に出たらポンと言って
取ることができるとのことだが,これはカンではないだろうか.その他,百人一首
のように「読み手がカードの説明文を読み上げ,該当するカードを取り合うという
遊び方もできます」.この場合,「カードが2組あれば簡単にできますが,ない場
合は説明文をコピーする必要があります」とのことである.地学の授業に応用する
には,このトランプを生徒の机上に並べさせ,話の筋に応じて関連する札を探させ
て説明文を読み上げさせたり,3〜4枚の札を選んでストーリーを作らせ,それを発
表させたりすれば,生徒の興味を喚起して学習効果を高めることができると思う.
一般の人にとっても,パラパラめくって見るだけでも楽しく,邪魔になる大きさで
もないので,ちょっとした贈り物にも適していると思う.
発明振興協会はこの他にDNA,元素周期表,電気,ニュートン力学,方程式と
図形,科学技術偉人のトランプを販売しており,それらのトランプを利用した教育
プログラムを提供している.
https://manabi-mirai.mext.go.jp/search_program/detail/000964.html
https://www.kyobun.co.jp/news/20180402_02/
このトランプの内容は,プレートテクトニクスに関連した地学の広い分野の重要な
事項を選択していて,イラストや図表・写真が美しく,説明文も概ね正確で要を得
ており,この分野の学習に大いに役立つものになっていると思う.そして遊び道具
のトランプとしての基本である扱いやすさと耐久性を備えている.地学の教育と普
及に是非この「発明品」を利用していただくよう,会員各位にお勧めする.
拙文の原稿を読んで貴重なご意見を寄せられた池田保夫氏と棚瀬充史氏に感謝する.
(石渡 明)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
サイエンスカフェ「VR!!地球科学のアソビカタ」
仮想現実(Virtual Reality)ってナニ?VRって役に立つ?地球科学者で,
VRを駆使して研究成果を世界に発信しているゲストスピーカーと,VR
世界の泳ぎ方,新しい情報発信の方法,VRと地球科学の相乗効果などを
参加者の皆さんに体験していただきます.
日程:3月21日(日)17-19時
開催場所:クラスターによるVR空間内
先着50名【申込締切:3/14】 参加無料
詳しくは,https://sites.google.com/view/vr-earth/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
第10回学生のヒマラヤ野外実習ツアー(延期)
2021年3月実施予定の表題のツアーは2022年3月に延期となりました.
www.gondwanainst.org/geotours/Studentfieldex_index.htm
学生のヒマラヤ野外実習プロジェクト:世話人会代表 吉田 勝
JAMSTEC 50周年記念行事
「すべらない砂甲子園」参加募集(応募期限:4/30)
全国津々浦々にある砂の中から「一番すべらない砂」=「最強の砂」
を決定する超新感覚室内実験的格闘競技大会です。
エントリーをお待ちしています。
http://www.jamstec.go.jp/50th/suberanai/
----------------------------------------------------
Tokai University Online Workshop
Challenges of Marine Observations and Development
of International Collaboration
3月6日(土) 8:30-16:00 (JST)
http://www.geosociety.jp/outline/content0221.html#2020-5
日本地球惑星科学連合2021年大会
開催方式:ハイブリッド開催(オンライン開催+現地開催)
現地会場:パシフィコ横浜ノース
5月30日(日)-6月1日(火)/現地開催(主としてポスター発表)
6月3日(木)-6月6日(日)/オンライン開催(口頭,ポスター)
※現地開催は縮小もしくは中止となる可能性があります.
http://www.jpgu.org/meeting_j2021/
地質学史総会・懇話会
6月26日(土)13:00-17:30(予定)
場所:北とぴあ 8階803号室(JR京浜東北線王子駅下車3分)
志岐常正:「戦後京大地質学教室史―その虚像と実像」
矢島道子:『地質学者ナウマン伝』を上梓して
(注)状況によってはオンラインまたはハイブリッドでの開催を検討します.
(後)第58回アイソトープ・放射線研究発表会
7月7日(水)-9日(金)
開催形態:オンライン開催
演題登録期間:2021年1月12日-3月8日
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2021/top
(後)科学教育研究協議会 第68回全国研究大会・福島大会
7月31日(土)-8月2日(月)
会場:伊達市立霊山中学校(福島県伊達市霊山町)
大会テーマ 自然科学をすべての国民のものに
※新型コロナウイルスの感染状況により,Web大会に変更する場合があります.
https://kakyokyo.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・伊豆半島ユネスコ世界ジオパーク専任企画研究員募集(3/31)
・JAMSTEC海域地震火山部門地震発生帯研究センター海底地質・地球物理
研究グループ研究員 公募(4/8)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
“ナホトカ号”の重油流出事故の教訓
“ナホトカ号”の重油流出事故の教訓とモーリシャスでの重油流出事故への責任:24年前の事故現場と今も残る流出被害の痕跡
田崎和江*(*本学会正会員)・松浦明久・片山和哉・加波瑞恵・新宅義昭・新宅睦子・福山厚子(市民科学メンバー)・三井 新(朝日新聞)
(注)図の画像をクリックすると大きな画がご覧いただけます。
24年前のナホトカ号の事故とその後の環境被害の概略
1997年1月2日,2時41分頃,ロシア船籍タンカー“ナホトカ号(13,157トン)”の船首部が脱落して,同後部が島根県隠岐島北北東106kmに沈没した.この事故で乗務員32名(全員ロシア人)のうち31名が救出されたものの,船長は死亡した.そして,折からの秒速30m前後の強い西風にあおられ,1月6日には船首部分が福井県三国町安東沖に座礁した.ナホトカ号には重油19,000kl(ドラム缶95,000本分)が積載されており,ナホトカ号から流出した重油は福井県越前海岸に漂着し,さらに1月7日には加賀市塩屋海岸にまで達した.さらに,悪天候により初動対応に遅れが生じ,船からの重油の回収作業,オイルフェンスの設置および処理剤散布ができず,最終的に重油は石川県内のほとんどの海岸に漂着した(図1).漂着した重油は柄杓と素手の手作業で回収され,2月16日までに,三国町でドラム缶12,598本,加賀市で4,716本,門前町で5,632本,輪島市で15,005本,珠洲市で21,099本分の重油が回収されたものの(田崎ほか, 1997),3月下旬になっても,能登半島の海岸には重油の漂着/再漂着が繰り返された.4月末までには石川県内の市町村の一部が対策本部の縮小または終息宣言を出したが,ナホトカ号の本体からは重油の流出が依然として手付かずのまま続いており,特に,海藻・モバの産地である輪島のアタケ海岸では,終息宣言後も,漁業関係者が海岸に打ち寄せる油交じりのロープやフレコンバックを自ら回収して,1-2 m深く掘った海岸脇の砂場に埋めるなどの作業が続いた(図2-1).
図1.調査位置図.
能登半島重油被害現場での体験と環境評価
24年前,田崎は地元の新聞記者と一緒に能登半島の海岸へと向かった.現場には太陽が昇る前に到着したが,波が打ち寄せる音がしなかったのを覚えている.明るくなってから,よく見ると,海面が厚さ約30cmの重油に覆われており,聞こえてくるのは油の下で波がうごめく音だけだった.磯の香りはなく,空気を吸うと,口の中まで重油の臭さでいっぱいになった.流出した油は水にはほとんど溶けず,海流にのって,海の表面を漂いながら拡散していった.色は真っ黒ではなく,茶色を帯びていた.
一般に,海面を漂いながら広がった油は,海に漂うゴミや海藻,貝などを吸着し,流出した油の10倍近い体積になる.そして,色々なものを吸着すると比重が増し,海の底へと沈んでいく.そうなると,もう回収の術はない.ナホトカ号の事故発生直後の教訓として言えるのは,油の回収作業は一刻を争う時間との勝負だということだ.初期の対応で重要なのは汚染源を絶つことである.そのためにはまず,座礁した船からこれ以上の油の流出を防ぐために,オイルフェンスで船を囲い,なるべく多くの油を沖合で回収した方がいい.そして,空から海流の向きを確認し,油が流れて行く方向に船を出して,海上で油をすくい取り,タンクに集めることだ.
漂着してしまった油は人海戦術で回収するしかない.ナホトカ号の事故の際は,北は秋田県から南は島根県まで,25万人以上の地域住民とボランティアがバケツリレーをして,流れ着いた重油をくみ取る作業をするなどの重油回収作業にあたった.燃料油は揮発性であるため,眼鏡やゴーグルをつけていないと目が充血し,マスクなしでは揮発した油で息苦しくなり,頭痛もした.そして,着ていたカッパは油まみれになった.なお,油まみれになったカッパ類は石油につけた雑巾でふき取るときれいになった.一方,目の前では,重油が羽に付着して,身動きが取れなくなった多くの海鳥がバタバタと落ちて死んでいった.たとえ,油から助け出しても,重油をのみ込んでしまったためか,飛べずに息絶えた鳥もたくさんいた.魚類もたくさん死んだ.三国海岸沿いには,きれいなスイセンが群生していたが,重油を吸収しほぼ全滅してしまった.海岸沿いの松林も枯れ木が目立った.このように重油流出事故は海水のみならず,大気・土壌・植物をも含む環境全体に被害を及ぼした.なお,事故当時の詳しい状況は,田崎(1997)を参考にされたい.また,海水組成の変化は,1997年1月10日から12月7日まで三国町安島(船首東)から珠洲市長橋海岸まで43ケ所で測定した海水の性質データ(Tazaki et al., 1997のTable 1)を参照されたい.
図2-1 A:石川県輪島市アタケ海岸(2020.12. 19. 調査),B, C:石川県輪島市アタケ海岸の砂浜に埋まっていたフレコンバック(矢印),D:二つのフレコンバックが埋まっていた,E:図D-bのフレコンバック,F:フレコンバック図Eの中味(当時の重油の塊が認められた)
G:重油(矢印),H:ビニール袋(上方)と重油の塊(下方),I:H2O2 過酸化水素を噴霧し, 5分後に発泡反応あり,J:福井市三国海岸.2020.12.13.現地調査,K:福井市三国海岸.大きな岩の陸側には重油の付着あり,L:福井市三国海岸;大きな岩の窪みには重油の付着が認められる.
2017年と2020年の調査
事故から20年経った2017年に,私たちは,事故の際にアタケ海岸に埋められた漁網やロープ,フレコンバックを掘り出し,それらの電子顕微鏡観察と化学分析を行なった.それらにはまだ重油独特の粘性や臭いが残っており,海岸の岩場にも固まった重油が見られた.一方で,紫外線や重油を分解菌の働きによって,重油は無臭で粘性もない,無害の無機物に変化していた(Tazaki, et al., 2018).
図2-2.三国海岸の岩石表面に見られる重油
さらに,昨年末に,朝日新聞の要請で,三国海岸での重油試料採集,アタケ海岸の現状調査および海岸に埋められていたフレコンバックの分析および電子顕微鏡観察を海岸近辺に住む市民科学メンバーといっしょに行った(図1,図2-1,図2-2).その際に研究用にアタケ海岸で掘り出したロープやフレコンバックの一部は田崎の自宅に現在も保管してある.
2020年12月13日に三国海岸の現地調査を行い,岩石表面に付着していた重油を採取した(図2-2).大きな岩の岸側で波をあまりかぶらない部分や窪地に重油が黒褐色―黄褐色の塊となって,ところどころに残存しているのが認められた.それらの残存重油はすでに粘着性を失っており,化学分析用試料はハンマーを使って採取することができた.さらに,12月19-20日には,輪島市在住の“市民科学”のメンバー(片山・加波)と一緒にアタケ海岸を調査して,海岸に埋まったままになっていたフレコンバックを採取した(図3-1).また,フレコンバック内部に過酸化水素水(H2O2)を噴霧して,有機物や微生物が存在することを確かめた(図3-2).
2021年1月7日に松浦・田崎・三井は石川県工業試験場の走査型電子顕微鏡(JEOL/JSM-6510LA; 加速電圧15-20KV)を用いて,白金蒸着した重油採取試料の検鏡と化学分析を行った(図4-1:三国海岸試料,図4-2:アタケ海岸試料). SEM-EDS分析で得られた微細構造と元素濃度分布から,C,O,Sに濃集した部分は有機物(重油および生息している微生物),AlやSiに濃集した部分は粘土鉱物,そして,Na,Mg,Cl,K,CaおよびFeに濃集した部分は海水から晶出した塩など脚注1に由来すると考えられる.今回の結果は,開放系である三国海岸の環境とフレコンバックに封入して地中に埋められた閉鎖系に近い環境のどちらにおいても重油流出事故によって汚染された重油本来の性質がいまだ残されていることを示している.
----------------------------------------------------------------
脚注1 SEM-EDSによる海水由来物質の分析値Cl 55.07%; Na+30.62%; SO42- 7.72%; Mg2+ 3.68%; Ca2+ 1.17%; K+ 1.10%.様々な混入物がありうるが,全体としてみたとき,NaClは海水に由来するであろう(赤井ほか, 1997).
図3-1 アタケ海岸で採取したフレコンバックの中身.
図3-2 アタケ海岸.過酸化水素水噴霧実験.A:実験前,
B:過酸化水素水噴霧,C:発砲反応(矢印).
図4-1三国海岸SEM-EDS
図4-2 アタケ海岸SEM-EDS.
図4-2continued
日本の海は回復したのか!?
ナホトカ号の事故から,今年で24年が経過した.日本海沖で座礁したナホトカ号の事故では約6200トンの重油が流出し,田崎研究室の学生・大学院生は事故発生の翌日から漂着した重油の回収や分析を続けてきた.そして今,海はどうなっているのだろうか?2017年,輪島市の海岸で砂に埋もれた漁業ロープにはまだ重油独特の粘性や臭いが残っており,海岸の岩場にも固まった重油が見られた.一方で,自然界には重油の分解菌という微生物がいることも明らかになり,紫外線や分解菌の働きによって,重油は蝋燭の一種に変化して,無臭で粘性もない,害のない無機物に変化していた.しかし,2020年の調査では,アタケ海岸で採取した試料は,地中に埋められ24年間経過した後でも,重油本体の性質をいまだに保持していることがわかった.その結果は20年以上経っても能登半島の海岸には重油の成分が残っていると言えよう.
2020年モーリシャスでの重油流出事故
2020年7月25日,インド洋の島国モーリシャスで日本企業の大型貨物船が座礁し,8月6日には積んでいた燃料油が周囲の海に流出した.流出した油は約1000トンにもなり,サンゴ礁やマングローブ林など豊かな自然が広がる海域に広がった.これを受けて,モーリシャス政府が環境非常事態宣言を出すに到り,生態系への影響はこの先何年も続くとも指摘されている.今回は,日本の船がモーリシャスに被害を与えた形だ.報道によれば,コロナの問題があったとはいえ,1週間もの間,何ら対策を施さなかったとされる.事故発生からすでに半年が経過するが,まずは海上や砂浜の油を一刻も早く回収することだ.お金を支払って済ます問題ではないかと思う.他国で被害を引き起こした日本は,早急に専門家を派遣し,その後も責任を持って,『電子顕微鏡レベルで』現地の環境を見守り続けるべきだ.
参考文献
赤井純二・重油流出による海の汚染新潟大学調査研究グループ(1997)新潟への漂着重油の貢献・電顕による観察(予報);平成8年度特定研究経費実施経過報告書. p. 182-192.
田崎和江(1997)日本海重油流出事故に伴う汚染環境の緊急調査と復元に関する研究―現状報告―;平成8年度特定研究経費実施経過報告書. 研究代表者・田崎和江(金沢大学大学院自然科学研究科)p.1−214.
Tazaki K. and Tazaki’s Seminar (1997) The environmental impacts on heavy oil spilled from the wrecked Russian Tanker NAKHODKA attacked the coast of Hokuriku District, Japan, in 1997. 1-46.
田崎和江・鈴木祐恵・藤澤瑛子(2009) 韓国泰安半島における油流出事故による環境汚染;2008年1月の砂海岸と岩海岸における浄化方法. 地球科学, 63巻 1号 29-40.
Tazaki, K., (2009) Oil spill off the Taean Peninsula, South Korea, on December 7th, 2007-survey one month, ten months, and one year after the accident. The Science Reports of Kanazawa University, Vol. 53, 1-23.
Tazaki, K., Fukuyama, A., Tazaki, F., Shintaku Y., Nakamura, K., Takehara T., Katsura, Y., and Shimada, K.(2018)Twenty years after the Nakhodka oil spill accident in the Sea of Japan, how has contamination changed? Minerals 2018, 8(5), 178; doi:10.3390/min8050178
(2021.3.15掲載)
※本記事は,日本地質学会News Vol. 24, No. 3(2021年3月号)にも掲載しています.
【geo-Flash】No.513 21年度割引会費申請(院生・学部生)最終締切です!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.513 2021/3/16┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】「地質の日」オンライン講演会開催します
【2】(名古屋代替)JABEEオンラインシンポを開催しました
【3】地質学雑誌の完全電子化実現に向けて(再掲)
【4】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!(3/31最終締切)
【5】「日本の地質学100年 : 日本地質学会100周年記念」再販セール中
【6】TOPIC “ナホトカ号”の重油流出事故の教訓とモーリシャスでの重油
流出事故への責任:24年前の事故現場と今も残る流出被害の痕跡
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「地質の日」オンライン講演会開催します
──────────────────────────────────
日本地質学会は,一般の皆様に最新の地質学研究の成果とその意義について
知っていただき,地質学への興味・関心を高めていただくことを目的に,
5/10地質の日にあわせて一般講演会をオンラインで開催いたします。どなた
でも無料で参加できます。チャット(YouTube上での書き込み)で質問・
コメントもできます。
開催日時:5月9日(日) 9:30開会,12:10閉会予定
開催方法:YouTubeライブ配信 どなたでも視聴可能,申込不要,無料
<講師と講演タイトル>
・岡田 誠(茨城大学理工学研究科教授)
「地質年代チバニアンと房総の地質」
・氏家恒太郎(筑波大学生命環境系准教授)
「断層の地質学的研究から読み解くプレート沈み込み帯地震発生の科学」
このほか、学会関連の「地質の日」行事については、ホームページに随時情報
を掲載していきます。
http://www.geosociety.jp/name/content0175.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】(名古屋代替)JABEEオンラインシンポを開催しました
──────────────────────────────────
2021年3月7日(日)に、
(2020名古屋大会代替企画)JABEEオンラインシンポジウム
自然災害列島における地質技術者の育成−大学統合期における地質学教育ー
を開催しました(YouTubeライブ配信)。
シンポジウムの内容は、現在もYouTubeで公開中です。ぜひご視聴ください。
https://youtu.be/7hpNtONfNt0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】地質学雑誌の完全電子化実現に向けて
──────────────────────────────────
(日本地質学会執行理事会)
地質学会の会員数は,1999年の5200名をピークに減少の一途をたどっています.
2021年1月末現在の会員数(正会員)は3368名と,この約20年間で実に約1800
名もの会員減です.それに伴い学会運営の根幹となる会費収入も20年前のおよそ
3分の2に激減しました.特に昨今のコロナ禍で会員減少が加速しました(昨年度
比約170名減).このような状況下で学会としては思い切った財政改革が喫緊の
課題となっています.この財政改革の大きな柱が地質学雑誌の完全電子化(冊子
廃止)です.
地質学雑誌の完全電子化については2016年より「地質学雑誌のあり方を考える
タスクフォース」で検討を行いました.完全電子化により大幅な経費削減が見込
まれますが,2018年に実施した会員アンケートでは冊子配布の継続を望む声も
少なくなかったため,翌年の答申では完全電子化の実現は時期尚早との判断をし
ました.しかしコロナ禍で会員減少が加速化し,学会の置かれている状況は大き
く変わりました.私たちは今,早急に完全電子化の実現に向けて,具体的な検討
をすすめる必要があります.
地質学雑誌の完全電子化は,経費削減のみならず,編集出版作業の迅速化,カラー
チャージの廃止,あるいはバーチャル特集号企画が可能になるなど,投稿・編集
出版においても大きなメリットがあります.学術雑誌の電子化は, 日本のみならず
世界の学術研究において大きな流れとなっています.
一方で会員減少に手をこまねいているわけはありません.並行して学生・院生の
入会促進策や,入会後も長く会員を継続してもらうための魅力ある会員サービス
についても検討をすすめています.地質学雑誌の完全電子化は, このような学会
運営の大きな改革の一環と位置づけられます.
以上のように, 執行理事会では完全電子化の実現に向けた具体的な検討を開始し
ました.電子化に向けたスケジュールを含め,検討結果は今後随時ジオフラッ
シュやニュース誌等でお知らせしていきます.会員の皆様には、このような状況
をご理解いただき、ご協力を心よりお願い申し上げる次第です.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】割引会費申請(院生・学部生)は忘れずに!
──────────────────────────────────
割引会費申請(院生・学部学生)の最終締切は,3月31日(水)です.
2021年度の割引会費を希望のかたは,忘れずにご提出ください(締切厳守).
2021年度割引会費申請や通常の会費払込について
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】「日本の地質学100年 : 日本地質学会100周年記念」再販セール中
──────────────────────────────────
日本地質学会編,1993年4月発行,706p,無線綴,布張上製本.
再販特別価格:3,000円(税・送料込)(参考)当初価格:8,000円
再販期間:2021年3月31日まで
お求めは,ジオストアから(クレジット決済可能)
http://geosociety2.sakura.ne.jp/store3/ec/
論集など学会出版物在庫案内はこちら
・論集58号「地震イベント堆積物」も再販中
・「屋久島たんけんマップ」改版しました:最新の情報をアップデート!
http://www.geosociety.jp/publication/content0001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】TOPIC “ナホトカ号”の重油流出事故の教訓とモーリシャスでの重油
流出事故への責任:24年前の事故現場と今も残る流出被害の痕跡
──────────────────────────────────
田崎和江ほか
1997年1月2日,2時41分頃,ロシア船籍タンカー“ナホトカ号(13,157トン)”の
船首部が脱落して,同後部が島根県隠岐島北北東106kmに沈没した.この事故で
乗務員32名(全員ロシア人)のうち31名が救出されたものの,船長は死亡した.
そして,折からの秒速30m前後の強い西風にあおられ,1月6日には船首部分が
福井県三国町安東沖に座礁した...
続きはこちらから,http://www.geosociety.jp/faq/content0941.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
・2021年度関東支部総会(書面会議)
書面総会に参加される方は,議決権行使書または委任状の提出をお願いします.
4月上旬より投票可能。提出締切日:4月30日
・オンライン2021年支部総会報告・地質技術伝承
日時:5月23日(日)オンライン開催13:00から
地質技術伝承会(参加費無料)
演題「地質調査、最近の動向」講師 北川博也 氏
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
第10回学生のヒマラヤ野外実習ツアー(延期)
2021年3月実施予定の表題のツアーは2022年3月に延期となりました.
www.gondwanainst.org/geotours/Studentfieldex_index.htm
学生のヒマラヤ野外実習プロジェクト:世話人会代表 吉田 勝
----------------------------------------------------
日本地球惑星科学連合2021年大会
開催方式:ハイブリッド開催(オンライン開催+現地開催)
現地会場:パシフィコ横浜ノース
5月30日(日)-6月1日(火)/現地開催(主としてポスター発表)
6月3日(木)-6月6日(日)/オンライン開催(口頭,ポスター)
※現地開催は縮小もしくは中止となる可能性があります.
http://www.jpgu.org/meeting_j2021/
地質学史総会・懇話会
6月26日(土)13:00-17:30(予定)
場所:北とぴあ 8階803号室(JR京浜東北線王子駅下車3分)
志岐常正:「戦後京大地質学教室史―その虚像と実像」
矢島道子:『地質学者ナウマン伝』を上梓して
(注)状況によってはオンラインまたはハイブリッドでの開催を検討します.
(後)第58回アイソトープ・放射線研究発表会
7月7日(水)-9日(金)
開催形態:オンライン開催
演題登録期間:2021年1月12日-3月8日
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2021/top
(後)科学教育研究協議会 第68回全国研究大会・福島大会
7月31日(土)-8月2日(月)
会場:伊達市立霊山中学校(福島県伊達市霊山町)
大会テーマ 自然科学をすべての国民のものに
※新型コロナウイルスの感染状況により,Web大会に変更する場合があります.
https://kakyokyo.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・令和3年度消防防災科学技術賞募集(消防防災科学論文ほか)(4/22締切)
・2021年コスモス国際賞推薦募集(学会締切3/26)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.514 三梨 昂 名誉会員 ご逝去
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.514 2021/3/31┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 三梨 昂 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
三梨 昂 名誉会員(元島根大学・教授)が、令和3年3月25日(木)に逝去
されました(94歳)。
これまでの故人の功績を讃えるとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
なお、ご葬儀はすでにご家族で執り行われたとのことです。
会長 磯崎行雄
(注)「崎」の正しい表記は、「大」→「立」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.515 ショートコース「津波堆積物」申込受付開始
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.515 2021/4/6┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】第3回ショートコース「津波堆積物」申込受付開始
【2】「地質の日」オンライン講演会開催します
【3】地質学雑誌の完全電子化実現に向けて(再々掲)
【4】若手研究者のページができました!
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
【8】緊急事態宣言解除後の学会の対応について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】第3回ショートコース「津波堆積物」申込受付開始
──────────────────────────────────
日程:2021年5月23日(日)
今回は「津波堆積物」をキーワードに,その調査によって津波とそれを引き
起こした地震の実像を探るための知識と研究事例を提供します.
講師はこの分野をリードするお二人の研究者です.
<午前>津波堆積物を理解するのに必要な基礎的堆積学:藤野滋弘(筑波大学)
<午後>津波堆積物を理解するのに必要な応用的堆積学:後藤和久(東京大学)
参加費(各1日券):会員2,000円(賛助会員に所属する⽅は会員と同額),
⾮会員 4,000円
申込締切:2021年5月12日(水)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0130.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】「地質の日」オンライン講演会開催します
──────────────────────────────────
日本地質学会は,一般の皆様に最新の地質学研究の成果とその意義について
知っていただき,地質学への興味・関心を高めていただくことを目的に,
5/10地質の日にあわせて一般講演会をオンラインで開催いたします.どなた
でも無料で参加できます.チャット(YouTube上での書き込み)で質問・
コメントもできます.
開催日時:5月9日(日) 9:30開会,12:10閉会予定
開催方法:YouTubeライブ配信 どなたでも視聴可能,申込不要,無料
<講師と講演タイトル>
・岡田 誠(茨城大学理工学研究科教授)
「地質年代チバニアンと房総の地質」
・氏家恒太郎(筑波大学生命環境系准教授)
「断層の地質学的研究から読み解くプレート沈み込み帯地震発生の科学」
このほか,学会関連の「地質の日」行事については,ホームページに随時情報
を掲載していきます.
http://www.geosociety.jp/name/content0175.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】地質学雑誌の完全電子化実現に向けて(再々掲)
──────────────────────────────────
(日本地質学会執行理事会)
地質学会の会員数は,1999年の5200名をピークに減少の一途をたどっています.
2021年1月末現在の会員数(正会員)は3368名と,この約20年間で実に約1800名
もの会員減です.それに伴い学会運営の根幹となる会費収入も20年前のおよそ3分
の2に激減しました.特に昨今のコロナ禍で会員減少が加速しました(昨年度比約
170名減).このような状況下で学会としては思い切った財政改革が喫緊の課題と
なっています.この財政改革の大きな柱が地質学雑誌の完全電子化(冊子廃止)
です.
全文はこちら,http://www.geosociety.jp/faq/content0942.html#03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】若手研究者のページができました!
──────────────────────────────────
学会HPに学部学生,院生等若手研究者の活動や関連するページができました.
ニュース誌の院生コーナーの記事もこちらからご覧いただけます.
近々,TwitterなどSNSでの情報発信も予定しています.ぜひご覧ください.
http://www.geosociety.jp/science/content0128.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報
──────────────────────────────────
[東北支部]
・2020年度東北支部総会代替企画(動画コンテンツYouTube公開中)
「プレコロナ時代のフィールドワークなどを振り返る」
終息の目途が見えない新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため,
2019年度に引き続き,2020 年度の総会・講演会の開催を中止といた
しました.しかしながら,その代替企画として支部の8名の講師にプレ
コロナ時代の海外のフィールドワークや調査航海の様子をプレゼン
テーション動画を作って頂きました.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
[関東支部]
・学生・初級者向け「地質断面図」の書き方講座 ―布良海岸巡検―
実施日:5月22日(土)・23日(日)
募集人数:最大6名(学生優先,余裕がある場合学生以外も受け付けます)
申込期間:4月11日(日)-4月26日(月)―定員になり次第締切
・2021年度関東支部総会(書面会議)
書面総会に参加される方は,議決権行使書または委任状の提出をお願いします.
4月上旬より投票可能.提出締切日:4月30日
・オンライン2021年支部総会報告・地質技術伝承会
日時:5月23日(日)オンライン開催 13:00から
地質技術伝承会(参加費無料)
演題「地質調査,最近の動向」講師:北川博也 氏
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地球惑星科学連合2021年大会
開催方式:ハイブリッド開催(オンライン開催+現地開催)
現地会場:パシフィコ横浜ノース
5月30日(日)-6月1日(火)/現地開催(主としてポスター発表)
6月3日(木)-6月6日(日)/オンライン開催(口頭,ポスター)
※現地開催は縮小もしくは中止となる可能性があります.
http://www.jpgu.org/meeting_j2021/
地質学史総会・懇話会
6月26日(土)13:00-17:30(予定)
場所:北とぴあ 8階803号室(JR京浜東北線王子駅下車3分)
志岐常正:「戦後京大地質学教室史―その虚像と実像」
矢島道子:『地質学者ナウマン伝』を上梓して
(注)状況によってはオンラインまたはハイブリッドでの開催を検討します.
(後)第58回アイソトープ・放射線研究発表会
7月7日(水)-9日(金)
開催形態:オンライン開催
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2021/top
(後)科学教育研究協議会 第68回全国研究大会・福島大会
7月31日(土)-8月2日(月)
会場:伊達市立霊山中学校(福島県伊達市霊山町)
大会テーマ 自然科学をすべての国民のものに
※新型コロナウイルスの感染状況により,Web大会に変更する場合があります.
https://kakyokyo.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・北海道大学理学研究院地球惑星科学部門テニュアトラック助教
(地質学を融合した,地球生命史研究に関連する有機地球化学)公募(5/13)
・情報科学を活用した地震調査研究プロジェクト(STAR-Eプロジェクト)公募
(4/23:17時必着)
・東京大学地震研究所2021年度(第2回)大型計算機共同利用公募(5/31)
・藤原セミナー募集(2023年以降開催)(7/31)
・2021年度勝山市ジオパーク学術研究等奨励補助金の公募 (5/31)
・下仁田ジオパーク学術奨励金募集(4/25)
・室戸ジオパーク推進協議会地質専門員募集(4/30)
・土佐清水ジオパーク構想活動支援事業(学術研究事業)募集(5/21)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】緊急事態宣言解除後の学会の対応について(2021/3/22付)
──────────────────────────────────
新型コロナウィルス感染症の急速な感染拡大に伴い令和3年1月に発出された
緊急事態宣言は,3月21日をもって全都道府県で解除となりました.
(中略)
学会主催の行事・イベントは,当面はなるべく対面形式での開催を避け,
オンラインでの開催をお願いいたします.
なお、学会事務局は交代でのテレワークとすることで,問い合わせ等の電話
対応を再開いたします.一方で,各委員会等の会議については,引き続き,
原則Web会議で行います。
全文はこちらから,http://www.geosociety.jp/news/n160.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.516(臨時) 唐木田 芳文 名誉会員 ご逝去
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.516 2021/4/9┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 唐木田 芳文 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
唐木田 芳文 名誉会員(西南学院大名誉教授)が、令和3年1月21日(木)に
老衰のため逝去されました(97歳)。
これまでの故人の功績を讃えるとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げ
ます。なお、ご葬儀はすでにご家族で執り行われたとのことです。
会長 磯崎行雄
(注)「崎」の正しい表記は、「大」→「立」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.517 学会行動規範の改訂/地雑22年1月より電子化
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.517 2021/4/20 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2021年名古屋大会開催のお知らせ
【2】学会行動規範の改訂について
【3】(理事会報告)地質学雑誌完全電子化実施,2022年1月を目標
【4】第3回ショートコース「津波堆積物」申込受付中
【5】2021年「地質の日」行事のご案内
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】訃報 石井 健一 名誉会員 ご逝去
【10】まん延防止等重点措置実施に関する学会の対応について(2021/4/19付)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2021年名古屋大会開催のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地質学会第128年学術大会 名古屋大会を下記の日程で開催します。
セッション(口頭+ポスター)はオンラインで、LOC主催シンポ、市民講演会
は、現地での開催予定しています。5/20頃より演題登録の受付開始予定です。
会期:2021年9月4日(金)〜7日(月)
会場:名古屋大学東山キャンパス(愛知県・名古屋市千種区)
+ オンライン開催
[関連行事]地質情報展2021あいち
日程:10/8-10/10 場所:名古屋市科学館
詳しくは大会プレページをご参照ください。
http://www.geosociety.jp/science/content0131.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】学会行動規範の改訂について
──────────────────────────────────
会長 磯崎行雄
(注)「崎」の正しい表記は、「大」→「立」
2011年9月に本学会の行動規範が制定されから間もなく10年が経ちます.この10年
で社会情勢は大きく変化し,学会として,学会員の立場や責任について,これまで
以上に社会に明確に示すことが求められるようになりました.そこで執行理事会は
,法務委員会にこれまでの行動規範の見直しを依頼し,検討いただいておりました
.その改訂案が4月3日開催の理事会にて承認されました.
旧行動規範は,本学会が他機関や組織との連携事業を実施する際の学会員の立場や
責任について定めたものでしたが,今回改訂された行動規範では,広く学会活動に
おいて,学会員の立場や責任について時勢に配慮し定めたものとなっております.
会員の皆様には改訂行動規範をご一読いただき,会員として責任のある行動を心が
けていただきますよう,よろしくお願い申し上げます.
学会行動規範はこちらから
http://www.geosociety.jp/outline/content0198.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】(理事会報告)地質学雑誌完全電子化実施,2022年1月を目標
──────────────────────────────────
4月3日開催の理事会において,地質学雑誌の完全電子化の方針と実施スケ
ジュールについて話し合われました.
理事会では,昨今の会員の減少に追い討ちをかけるように,コロナ禍で会員減
少が加速し(会員数昨年度比162名減;ピークの1999年会員数5200名→
2021年3月末3217名),会費収入の大幅減により,本学会には,もはやコロナ禍
以前と同じような活動を行う財政的な体力はないことが説明されました.この
ような学会のひっ迫した財政状況に鑑み,地質学雑誌の完全電子化について,
来年(2022年)1月より開始することを目標に,実現に向けた検討をすすめるこ
とになりました.一方で,現在,地質学雑誌と一緒に毎月郵送されているニュー
ス誌(日本地質学会News)については,当面は現状と同じ月刊(12回/年)
での冊子配布を維持することが確認されました.
今後は,地質学雑誌の完全電子化実現に向けて,電子化の技術面及び編集作業
の問題点の洗い出しとその解決策の検討をすすめることになります.編集出版
作業の迅速化,オープンデータサーバの活用等,電子化のメリットを最大限に
感じていただけるような体制づくりに努めます.検討状況については,ニュー
ス誌やジオフラッシュを用いて,会員の皆様に随時ご報告させていただきます.
地質学雑誌の完全電子化は,現在すすめている学会運営全体の見直しの一環とし
て位置づけられています.並行して,学生・院生会員の会費や大会参加費の見
直し,シニア会員制度の創設,ショートコースの充実,学会公式SNSの立ち上げ
等,新規入会促進や長く会員を継続してもらうための魅力ある会員サービスに
ついても現在検討を進めているところです.こちらもニュース誌やジオフラッ
シュ等により会員の皆様に随時検討状況をご報告させていただく予定です.
会員の皆様には,本学会のこのような状況をご理解いただき,ご協力を心より
お願い申し上げる次第です.
(2021.4.21一部修正)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第3回ショートコース「津波堆積物」申込受付中
──────────────────────────────────
日程:2021年5月23日(日)
今回は「津波堆積物」をキーワードに,その調査によって津波とそれを引き
起こした地震の実像を探るための知識と研究事例を提供します.
講師はこの分野をリードするお二人の研究者です.
<午前>津波堆積物を理解するのに必要な基礎的堆積学:藤野滋弘(筑波大学)
<午後>津波堆積物を理解するのに必要な応用的堆積学:後藤和久(東京大学)
参加費(各1日券):会員2,000円(賛助会員に所属する⽅は会員と同額),
⾮会員 4,000円
申込締切:2021年5月12日(水)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0130.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2021年「地質の日」行事のご案内
──────────────────────────────────
開催日時:5月9日(日) 9:30開会,12:10閉会予定
開催方法:YouTubeライブ配信 どなたでも視聴可能,申込不要,無料
<講師と講演タイトル>
・岡田 誠(茨城大学)「地質年代チバニアンと房総の地質」
・氏家恒太郎(筑波大学)「断層の地質学的研究から読み解くプレート沈み込み帯地震発生の科学」
このほか,学会関連の「地質の日」行事については,ホームページに随時情報
を掲載しています.
・惑星地球フォトコンテスト第12回ほか入選作品展示会(5/4-5/17)
東京パークスギャラリー(台東区上野公園内.入場無料)
・近畿支部:特別展「大阪アンダーグラウンド-掘ってわかった大地のひみつ-」
YouTubeでの配信あり
・近畿支部:特別展普及講演会・地球科学講演会「海洋マントル掘削計画:なぜ?
どこで? 何をする?」(5/9)大阪市立自然史博物館,4/25申込締切,
YouTubeでの配信あり.YouTubeでの聴講は申込不要
詳しくは,http://www.geosociety.jp/name/content0175.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[東北支部]
・2020年度東北支部総会代替企画(動画コンテンツYouTube公開中)
「プレコロナ時代のフィールドワークなどを振り返る」
終息の目途が見えない新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため,
2019年度に引き続き,2020 年度の総会・講演会の開催を中止といた
しました.しかしながら,その代替企画として支部の8名の講師にプレ
コロナ時代の海外のフィールドワークや調査航海の様子をプレゼン
テーション動画を作って頂きました.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
[関東支部]
・学生・初級者向け「地質断面図」の書き方講座 ―布良海岸巡検―
実施日:5月22日(土)・23日(日)
募集人数:最大6名(学生優先,余裕がある場合学生以外も受け付けます)
申込期間:4月11日(日)-4月26日(月)―定員になり次第締切
・2021年度関東支部総会(書面会議)
書面総会に参加される方は,議決権行使書または委任状の提出をお願いします.
4月上旬より投票可能.提出締切日:4月30日
・オンライン2021年支部総会報告・地質技術伝承会
日時:5月23日(日)オンライン開催 13:00から
地質技術伝承会(参加費無料)
演題「地質調査,最近の動向」講師:北川博也 氏
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地球惑星科学連合2021年大会
開催方式:ハイブリッド開催(オンライン開催)
現地会場:パシフィコ横浜ノース
5月30日(日)-6月6日(日)
(注)21年大会はオンライン形式に完全移行となりました.
http://www.jpgu.org/meeting_j2021/
2021年度第1回(未経験者向け)地質調査研修
5月31日(月)-6月4日(金)
室内座学:茨城県つくば市(産総研)
野外研修:茨城県ひたちなか市、福島県いわき市
主催:産総研コンソーシアム「地質人材育成コンソーシアム」
定員:6名(締切:5月20日(木))定員になり次第締切
参加費:30口(1口2000円)の会費が必要です.
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2021.html
観察会「浮島湿原と白滝ジオパーク黒曜石露頭」
北海道自然観察協議会主催
6月19日(土)
開催場所:浮島湿原、白滝ジオパーク、遠軽埋蔵文化センター
参加費…500円
要申込、定員12名
http://www.noc-hokkaido.org/
地質学史総会・懇話会
6月26日(土)13:00-17:30(予定)
場所:北とぴあ 8階803号室(JR京浜東北線王子駅下車3分)
志岐常正:「戦後京大地質学教室史―その虚像と実像」
矢島道子:『地質学者ナウマン伝』を上梓して
(注)状況によってはオンラインまたはハイブリッドでの開催を検討します.
(後)第58回アイソトープ・放射線研究発表会
7月7日(水)-9日(金)
開催形態:オンライン開催
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2021/top
(後)科学教育研究協議会 第68回全国研究大会・福島大会
7月31日(土)-8月2日(月)
会場:伊達市立霊山中学校(福島県伊達市霊山町)
大会テーマ 自然科学をすべての国民のものに
※新型コロナウイルスの感染状況により,Web大会に変更する場合があります.
https://kakyokyo.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・国立科学博物館 科学史または産業技術史研究員公募(6/28)
・令和3年度北海道職員(学芸員又は研究職員(地学(古生物))採用選考(5/14)
・産総研地質調査総合センター新規研究職員公募(5/11)
・2021年度住友財団研究助成公募(6/9)
・第12回(令和3年度)日本学術振興会育志賞候補者推薦依頼(学会締切5/20)
・令和3年度室戸ユネスコ世界ジオパーク学術研究助成金の募集 (5/17)
・三島村ジオパーク学術研究等奨励補助金の募集(5/28)
・令和3年度伊豆半島ジオパーク学術研究助成の募集 (5/31)
・令和3年度筑波山地域ジオパーク学術研究助成金の募集(5/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】訃報 石井 健一 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
石井 健一 名誉会員(元林原自然科学博物館 館長)が、令和3年2月23日
に肺炎のため逝去されました(94歳)。
これまでの故人の功績を讃えるとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げ
ます。なお、ご葬儀はすでにご親族のみで執り行われたとのことです。
会長 磯崎行雄
(注)「崎」の正しい表記は、「大」→「立」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】まん延防止等重点措置実施に関する学会の対応について(2021/4/19付)
──────────────────────────────────
新型コロナウィルス感染症が再び感染拡大している状況を受けて,4月20日までに
10都道府県でまん延防止等重点措置が実施されるに至りました.
学会主催の行事・イベントは,適用を受けた都道府県のみならず,そのほかの地域
においても,当面はなるべく対面形式での開催を避け,オンラインでの開催をお願
いいたします.各委員会等の会議についても,引き続き,原則Web会議とし,各支
部・専門部会の会議等も同様に,状況に応じた対応をお願いいたします.
学会事務局は問い合わせ等の電話対応はしておりますが,交代でテレワークを実施
しております.皆様にはご不便をおかけしますが,ご理解のほど,よろしくお願い
いたします.
全文はこちらから,http://www.geosociety.jp/news/n160.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
第12回惑星地球フォトコンテスト:最優秀
第12回惑星地球フォトコンテスト入選作品
最優秀賞:地底の世界
写真:新垣隆吾(沖縄県)
撮影場所:ルーマニア サリーナ・トゥルダ
【撮影者より】
岩塩坑として使用されていた場所を,テーマパークにしたサリーナ・トゥルダ.撮影地は地下400メートルほど.圧倒されるその世界と,普段目にすることのない空間を遊び心を持ってテーマパークにしてしまう発想が魅力的な場所でした.跡地として残すだけでなく,リノベーションという発想によって,より理解を深めることができることを学んだ場所でした.
【審査委員長講評】
この作品を一瞬見たときは何が写っているだろうと迷いますが,下端に写っている人から巨大な地下空洞を見上げて撮影した作品であることがわかります.ルーマニアには岩塩の坑跡を利用したいくつかの観光地がありますが,撮影地のサリーナ・トゥルダは坑内に観覧車やボート乗り場まであるアミューズメント・パーク.日本ではほとんど知られていませんが,地質マニアならずとも行きたくなる場所です.
【地質的背景】
この岩塩鉱山は,ルーマニアの中心部に位置するテチス海の一部であるパラテチス海で起こった海水蒸発事件(バデニーナ塩分危機 13.8Ma)で堆積した岩塩層が起源となります(de Leeuw et al., 2010; Baldi et al., 2017).この堆積盆地では,ヨーロッパアルプスからつながるルーマニア北部のカルパティア山脈形成時の地殻変動と浮力により岩塩がダイアピルを形成しています.それら岩塩ダイアピアのいくつかは地表に到達し,人々が古代からそれらを利用してきました.写真は,トゥルダ地域(Turda area)には岩塩鉱山として,非常に大きな人工の空洞を作り出しました.現在,鉱床の役目を終え,トゥルダ鉱山複合施設は観光名所に変わっています.(Alexandru Andrasanu : Haţeg UNESCO Global Geopark)
引用文献
de Leeuw et al., 2010; Geology, 38, 715-718. doi: 10.1130/G30982.1
Baldi et al., 2017, GEOLOGICA CARPATHICA, 68, 3, 193-206. doi: 10.1515/geoca-2017-0015
目次へ戻る
第12回惑星地球フォトコンテスト:優秀01
第12回惑星地球フォトコンテスト入選作品
優秀賞:大地の鼓動
写真:横江憲一(北海道)
撮影場所:北海道 弟子屈町川湯温泉硫黄山
【撮影者より】
アサトヌプリは屈斜路カルデラの中に存在する活火山で,地質は,地質は安山岩およびデイサイト,流紋岩.サワンチサッブ,マクワンチサップなどの溶岩ドーム群からなります.噴気活動が活発で,火山ガスや水蒸気を出す噴気孔が1500以上あると言われており,写真は,山肌からはゴウゴウと音を立てながら噴煙がほとばしり,強風の中,黄色の硫黄の結晶がよく見える瞬間を切り取ったものです.
【審査委員長講評】
横江さんは北海道の火山や星景を熱心に撮影している作者で,一昨年の本コンテストでは雌阿寒岳の夜景で最優秀賞を受賞されています.今回は屈斜路カルデラ,硫黄山の硫黄を超広角レンズでクローズアップ.上弦前の月に照らし出された硫黄の黄色,そこから噴き出す水蒸気の白,バックの星空の青とカラフルで爽快感のある作品に仕上がっています.
【地質的背景】
日本最大のカルデラと言われる屈斜路・摩周カルデラの中央部にあるアトサヌプリ(硫黄山)は溶岩ドームで周辺には噴気地帯が発達しています.噴気の温度は100~120℃で,噴気から昇華した硫黄は1963年まで採掘されていました.電磁探査では,アトサヌプリの直下,十数km付近で比抵抗の非常に小さい部分が認められ,マグマだまりである可能性が指摘されています.(萬年一剛:神奈川県温泉地学研究所)
目次へ戻る
第12回惑星地球フォトコンテスト:優秀02
第12回惑星地球フォトコンテスト入選作品
優秀賞:コジラの背
写真:中吉剛彦(東京都)
撮影場所:千葉県 南房総市・屏風岩
【撮影者より】
千葉県は南房総市にある屏風岩を夕刻,長秒で撮ったものです.沈みゆく夕陽にまるでゴジラが追いかけるように海に潜っていくようにも見えました.
【審査委員長講評】
房総半島の南端,南房総市の屏風岩は撮影スポットして有名です.30秒の露出によって波はベール状となり,岩の質感がくっきりと浮き出されました.地層がなぜ直立しているのか知りたくなります.遠景に伊豆大島(右),利島(中),新島(左)のシルエットも高評価に繫がりました.
【地質的背景】
ゴジラの背を作っている地層は,南房総に広く分布する千倉層群下部の白間津層です.白間津層は,約3 Maの海溝陸側斜面で形成された地層と解釈されており,シルト岩と凝灰質砂岩,凝灰岩,火山礫凝灰岩などとの互層で特徴づけられます.凝灰岩と火山礫凝灰岩の中には,シル,ダイク,ラコリスなどの砕屑性貫入岩(インジェクタイト)の特徴が認められます.また,シロウリガイ化石や炭酸塩コンクリーションの産出も一部で認められます.(伊藤 慎:千葉大学)
目次へ戻る
第12回惑星地球フォトコンテスト:ジオパーク
第12回惑星地球フォトコンテスト入選作品
ジオパーク賞:不思議な空間
写真:長谷 洋(和歌山県)
撮影場所:和歌山県 那智勝浦町 浦神半島 一の門付近
【撮影者より】
南紀熊野ジオパーク荒船海岸の海蝕洞です.今年の年末,日本初の民間ロケットが打ち上げられますが,その近くに位置します.複数の海蝕洞に朝陽の光が差し込んでいます.大潮の満潮時で高潮も重なり,波しぶきに光が当たり幻想的なシーンとなりました.
【審査委員長講評】
タイトルのように独特の雰囲気のある作品で,造形の面白さが目を引きました.長谷洋さんは南紀熊野のジオパークガイド.土地勘があり,天候や潮の満ち干などを選んでこの作品を撮影されています.昨年もジオパーク賞を授賞されています.
【地質的背景】
浦神半島は「那智の滝」や「勝浦温泉」が有名な和歌山県那智勝浦町にある長さ3㎞程の半島です.半島北側では約1500万年前の熊野カルデラ形成時,カルデラ縁に貫入した火成岩脈の延長部分が入り江となっています.また熊野層群の砂岩や泥岩が見られ,その中には熱水活動の影響を示す多数の割れ目や熱水脈が存在します.このような部分は波の浸食を受けて削られやすいため,波の強い太平洋側では大小様々な海食洞が多数みられます.(福村成哉:南紀熊野ジオパークセンター)
目次へ戻る
【geo-Flash】No.518 会員の活動成果を学会HPでPRしませんか
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.518 2021/5/7 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2021年名古屋大会開催のお知らせ
【2】(理事会報告)地質学雑誌完全電子化実施,2022年1月を目標(再掲)
【3】第3回ショートコース「津波堆積物」申込受付中
【4】2021年「地質の日」行事のご案内
【5】支部情報
【6】研究、教育や社会貢献など,会員の活動成果を学会HPでPRしませんか
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】訃報 星野通平 名誉会員 ご逝去
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2021年名古屋大会開催のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地質学会第128年学術大会 名古屋大会を下記の日程で開催します.
セッション(口頭+ポスター)はオンラインで,LOC主催シンポ,市民講演会
は,現地での開催を予定しています.5/20頃より演題登録の受付開始予定です.
会期:2021年9月4日(土)-7日(火)
会場:名古屋大学東山キャンパス(愛知県・名古屋市千種区)
+ オンライン開催
[関連行事]地質情報展2021あいち
日程:10/8-10/10 場所:名古屋市科学館
詳しくは大会プレページをご参照ください.
http://www.geosociety.jp/science/content0131.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】(理事会報告)地質学雑誌完全電子化実施,2022年1月を目標(再掲)
──────────────────────────────────
4月3日開催の理事会において,地質学雑誌の完全電子化の方針と実施スケ
ジュールについて話し合われました.
理事会では,昨今の会員の減少に追い討ちをかけるように,コロナ禍で会員減
少が加速し(会員数昨年度比162名減;ピークの1999年会員数5200名→
2021年3月末3217名),会費収入の大幅減により,本学会には,もはやコロナ禍
以前と同じような活動を行う財政的な体力はないことが説明されました.この
ような学会のひっ迫した財政状況に鑑み,地質学雑誌の完全電子化について,
来年(2022年)1月より開始することを目標に,実現に向けた検討をすすめるこ
とになりました.一方で,現在,地質学雑誌と一緒に毎月郵送されているニュー
ス誌(日本地質学会News)については,当面は現状と同じ月刊(12回/年)
での冊子配布を維持することが確認されました.
今後は,地質学雑誌の完全電子化実現に向けて,電子化の技術面及び編集作業
の問題点の洗い出しとその解決策の検討をすすめることになります.編集出版
作業の迅速化,オープンデータサーバの活用等,電子化のメリットを最大限に
感じていただけるような体制づくりに努めます.検討状況については,ニュー
ス誌やジオフラッシュを用いて,会員の皆様に随時ご報告させていただきます.
地質学雑誌の完全電子化は,現在すすめている学会運営全体の見直しの一環とし
て位置づけられています.並行して,学生・院生会員の会費や大会参加費の見
直し,シニア会員制度の創設,ショートコースの充実,学会公式SNSの立ち上げ
等,新規入会促進や長く会員を継続してもらうための魅力ある会員サービスに
ついても現在検討を進めているところです.こちらもニュース誌やジオフラッ
シュ等により会員の皆様に随時検討状況をご報告させていただく予定です.
会員の皆様には,本学会のこのような状況をご理解いただき,ご協力を心より
お願い申し上げる次第です.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】第3回ショートコース「津波堆積物」申込受付中
──────────────────────────────────
日程:2021年5月23日(日)
今回は「津波堆積物」をキーワードに,その調査によって津波とそれを引き
起こした地震の実像を探るための知識と研究事例を提供します.
講師はこの分野をリードするお二人の研究者です.
<午前>津波堆積物を理解するのに必要な基礎的堆積学:藤野滋弘(筑波大学)
<午後>津波堆積物を理解するのに必要な応用的堆積学:後藤和久(東京大学)
参加費(各1日券):会員2,000円(賛助会員に所属する⽅は会員と同額),
⾮会員 4,000円
申込締切:2021年5月12日(水)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0130.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2021年「地質の日」行事のご案内
──────────────────────────────────
開催日時:5月9日(日) 9:30開会,12:10閉会予定
開催方法:YouTubeライブ配信 どなたでも視聴可能,申込不要,無料
・岡田 誠(茨城大学)「地質年代チバニアンと房総の地質」
・氏家恒太郎(筑波大学)「断層の地質学的研究から読み解くプレート
沈み込み帯地震発生の科学」
https://youtu.be/4SXi-w76gWQ
このほか,学会関連の「地質の日」行事については,ホームページに随時情報
を掲載しています.
・惑星地球フォトコンテスト第12回ほか入選作品展示会 開催中(5/4-5/17)
東京パークスギャラリー(台東区上野公園内.入場無料)
・近畿支部:特別展普及講演会・地球科学講演会「海洋マントル掘削計画:なぜ?
どこで? 何をする?」(5/9)YouTube配信.申込不要
詳しくは,http://www.geosociety.jp/name/content0175.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報
──────────────────────────────────
[東北支部]
・2020年度東北支部総会代替企画(動画コンテンツYouTube公開中)
「プレコロナ時代のフィールドワークなどを振り返る」
支部の8名の講師にプレコロナ時代の海外のフィールドワークや調査航海
の様子をプレゼンテーション動画にまとめて頂きました.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0024.html
[関東支部]
・2021年度関東支部総会(書面会議)
書面総会に参加される方は,議決権行使書または委任状の提出をお願いします.
提出締切日:4月30日
・オンライン2021年支部総会報告・地質技術伝承会
日時:5月23日(日)オンライン開催 13:00から
地質技術伝承会(参加費無料)
演題「地質調査,最近の動向」講師:北川博也 氏
申込締切:5月13日(木)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】研究、教育や社会貢献など,会員の活動成果を学会HPでPRしませんか
──────────────────────────────────
地質学会ホームページ「会員の学術・教育・社会貢献活動」
http://www.geosociety.jp/science/content0109.html
では,その名も通り,地質学会員の「学術,教育,社会貢献活動」
をご紹介しています.皆様からの情報をお待ちしています.
例えば,
・自身の学術論文掲載がメディアや所属機関からプレスリリースされた.
・研究成果に関して、テレビやラジオ番組に出演する.
・ジオパークの新規開設や整備・更新をメディアで紹介された
・興味深い授業内容として、メディア等で取り上げられた.
などなど.
ただし、番組、著書・雑誌、既存施設や教室などの紹介や宣伝が目的ではなく、
会員の研究や活動の成果の紹介が目的です。客観性、公共性、速報性、新規性
および内容を考慮し、広報委員会で掲載を判断します.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
JAMSTEC 50周年記念行事
「すべらない砂甲子園」参加募集(応募期限:5月31日)
全国津々浦々にある砂の中から「一番すべらない砂」=「最強の砂」を
決定する超新感覚室内実験的格闘競技大会です.
エントリーをお待ちしています!
詳しくは:http://www.jamstec.go.jp/50th/suberanai/
エキシビションマッチ配信中:
https://www.youtube.com/watch?v=ZomMahkkEJ4&t=2s
------------------------------------------------
地層処分技術オンライン説明会(改訂した包括的技術報告書)
主催:原子力発電環境整備機構
開催日:
【総論】5月13日(木),6月9日(水)
【地質環境】5月20日(木),6月16日(水)
【処分場設計】5月26日(水),6月24日(木)
【長期安全評価】6月3日(木),6月30日(水)
時間(共通):17:00-18:30
https://www.numo.or.jp/topics/202121042815.html
日本地球惑星科学連合2021年大会
開催方式:ハイブリッド開催(オンライン開催)
現地会場:パシフィコ横浜ノース
5月30日(日)-6月6日(日)
(注)21年大会はオンライン形式に完全移行となりました.
http://www.jpgu.org/meeting_j2021/
地質学史総会・懇話会
6月26日(土)13:00-17:30(予定)
場所:北とぴあ 8階803号室(JR京浜東北線王子駅下車3分)
志岐常正:「戦後京大地質学教室史―その虚像と実像」
矢島道子:『地質学者ナウマン伝』を上梓して
(注)状況によってはオンラインまたはハイブリッドでの開催を検討します.
(後)第58回アイソトープ・放射線研究発表会
7月7日(水)-9日(金)
開催形態:オンライン開催
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2021/top
(後)科学教育研究協議会 第68回全国研究大会・福島大会
7月31日(土)-8月2日(月)
大会テーマ「自然科学をすべての国民のものに」
(注)Web大会に変更になりました
https://kakyokyo.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・南紀熊野ジオパーク研究助成事業の募集 (6/9)
・湯沢市ゆざわジオパーク学術研究等奨励補助金の募集 (5/31)
・下北ジオパーク研究補助金の募集 (6/7)
・糸魚川ジオパーク学術研究奨励事業の募集 (5/28)
・筑波山地域ジオパーク推進協議会専門員募集(5/21)
・JAMSTEC超先鋭研究開発部門高知コア研究所(地球微生物学研究G、
同位体地球化学研究G、岩石物性研究Gのいずれか)研究員公募(6/25)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】訃報 星野 通平 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
星野 通平 名誉会員(東海大学名誉教授)が,令和3年4月29日に誤嚥性肺炎
のため逝去されました(98歳).
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げ
ます.なお,ご葬儀はすでに近親者のみで執り行われたとのことです.
会長 磯崎行雄
(注)「崎」の正しい表記は,「大」→「立」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
第12回惑星地球フォトコンテスト:会員
第12回惑星地球フォトコンテスト入選作品
日本地質学会会長賞:上五島で新たに見出された海底地滑り構造
写真:川原和博(長崎県)
撮影場所:長崎県 五島列島中通島 南松浦郡新上五島町 砕石場
【撮影者より】
五島列島中通島の基盤は中新世中期に堆積した非海成の五島層群です.その五島層群を中新世後期の有川層が不整合に覆っています.有川層は下位から上位へ火砕流堆積物,細粒砂岩,泥岩,火砕流堆積物と遷移しています.写真は上部の火砕流堆積物(白色)の一部が下位の泥岩(黒色)へ乱雑に再堆積した海底地滑り堆積物の構造を示しています.
2020年(令和2年)10月24日午前10時撮影.採石場の加藤産業(株)の職員の方に案内してもらい,この露頭を見た瞬間,同行の武内浩一氏(長崎県地学会)と思わず声を上げてしまいました.高さ130m,幅150m以上の大露頭です.右下に削岩機とパワーショベル,重ダンプトラックが写っています.45年前(1976年)この露頭近くのつづら折りの急な町道でルートマップを作成し,有川層の層序を立て,海棲貝化石を採取しました.当時,採石場はまだ稼業していなく,その付近の海岸線は切り立った海食崖の連続で踏査できませんでした.(21.4.26追加)
【審査委員長講評】
巨大な採石場を撮影した作品で,その大きさは右下のパワーショベルからよくわかります.露頭は砂塵などによって不明瞭になってしまうことが多いのですが,この露頭では地質構造が明瞭です.露頭のスケッチと合わせてこの作品をじっくりと眺めたいものです.高い位置から撮影していますが,ドローンでの撮影でしょうか.地質関係者でなければとれない作品です.
【地質的背景】
本層は,上五島の中央部にみられる不思議な礫岩層の巨大露頭である.五島列島では中新世の砂岩泥岩やグリーンタフ火山岩類を基盤としており,本層はこれらの地層を不整合で覆う堆積物である.この上位には厚い流紋岩質の火山砕屑岩が重なっている.どのような場所でどのようなイベントが起こってこの分厚い堆積物ができたか不明であり,特に陸上堆積環境の五島層群に海洋環境なったかどうかを示すカギとなる地層である.古くから採石によりできた巨大露頭は地質事件を示す重要な証拠写真となり,是非とも保存してほしいところである.(清川昌一:九州大学)
目次へ戻る
第12回惑星地球フォトコンテスト:ジオ鉄
第12回惑星地球フォトコンテスト入選作品
ジオ鉄賞:古の海洋堆積物から見上げて
写真:藤岡比呂志(岐阜県)
撮影場所:岐阜県長良川鉄道 美並苅安駅〜赤池駅(下り赤池駅の20秒ほど手前で撮影)
【撮影者より】
長良川鉄道は下りの場合,湯の洞温泉口駅〜徳永駅の約50分間は長良川沿いを通り,露頭を見ながら,地質に関わりながらの旅となります.付加体堆積物である美濃帯堆積岩類の中を主に走り,写真の場所はメランジュからなり,チャート層と泥岩基質の混在岩が見られます.すみきった快晴の中,はるか昔に堆積した海洋堆積物から列車を見上げているという時間のひとこまを切り取ってみました.
【講評・解説】
岐阜県の美濃太田駅(美濃加茂市)と北濃駅(郡上市)を72.1kmで結ぶ長良川鉄道.美濃帯のダイナミックな付加体構造をほぼ南北に縦断しながら走ります.撮影された第3長良川橋梁の架かる区間は1928年(昭和3)に開通しました.作品では露岩の質感を手前に大きく見せ,それを昭和初期のプラットトラス1連が引き立てています.角度が異なる背後の道路橋もアクセントに.新緑に映えるロイヤルレッドの車体は,クラウドファンディングと地元の支援を経て2018春にデビューした観光列車ながら3号「川風号」.ながら1号「森号」,2号「鮎号」と共に地元素材を満載した水戸岡鋭治氏デザインの車両として人気です.ジオの存在感,そして,鉄道があって初めて生まれるジオ鉄の風景,その両方の魅力を知る撮影者の思いが伝わる写真でした.(藤田勝代:深田研ジオ鉄普及委員会)
目次へ戻る
第12回惑星地球フォトコンテス:スマホ
第12回惑星地球フォトコンテスト入選作品
スマホ賞:断層を塞ぐ人工の防風堤
写真:岩田晃一(長崎県)
撮影場所:長崎県 五島市奈留町野首
【撮影者より】
五島市奈留町の北側に野首(ノコビ)と呼ばれる地区があります.五島列島の島々が分かれるきっかけとなった断層がありますが,その場所に,トンネル工事で出た土砂を積み上げた防風提を築いています.断層の影響を受けたこの地形は,冬は北西の風と荒波がたいへん強く,住民を悩ませていました.人工の防風提はこの地区の住民に安らぎを与えています.この付近では,黒曜石も見つかっています.
【審査委員長講評】
作者は地元の方だと思いますが,この作品の良いところは力まずに淡々と日常の風景を撮影しているところです.解説を読み,グーグルアースでこの場所を調べると防風堤に守られて生活している人々の姿が浮かんできます.
【地質的背景】
五島列島の土台である大きな5つの島は,大規模な正断層で分かれています.本層は奈留島北部の断層が見られる場所です.断層部分は地形がくびれており,強い風の通り道となっていました.トンネル作成時のズリをこの凹みにして海岸線の凹みに壁を作っている場所です.ここでは黒曜石の貫入が五島層群の砂岩中にみられるなど,地質学的にも重要な場所です.日本ジオパークを目指す役場の方が,ジオサイト調査時に透き通る海と露頭そして防風堤をいい角度から撮影した,美しいバランスの作品です.(清川昌一:九州大学)
目次へ戻る
第12回惑星地球フォトコンテスト入選01
第12回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選(中高生部門):奇跡の小岩
写真:石谷樹莉(長崎県)
撮影場所:長崎県 五島市玉之浦町大瀬崎
【撮影者より】
この写真は,長崎県五島列島の福江島にある大瀬崎断崖にある岩を撮影したものです.大瀬崎断崖は,西海国立公園の特別地域に指定されています.砂岩と泥岩の互層からなる新第三紀層「五島層群」が,東シナ海から叩きつける荒波で削られて形成された海食崖であり,標高250mの大瀬山山頂まで急斜面が続いています.崖の亀裂に小岩が絶妙に挟まって奇跡的だと思いました.
【審査委員長講評】
この小岩はどのくらいの大きさなのでしょうか.どこからやってきたのか,いつ落ちてしまうのか,いろいろな思いを巡らすことができます.撮影地の五島列島は日本ジオパーク認定を目指して現在活動中です.このフォトコンへの応募も五島列島を知ってもらう良い機会になりますね.
【地質的背景】
本作品は,五島列島福江島で最も有名な観光スポットである大瀬崎灯台(映画・悪人:クライマックスの場所に使われている)での作品です.普通,大瀬崎に行くと周辺部に広がる砂岩泥岩の大露頭に目が行来ますが,この作品では,東西方向の割れ目に挟まれ“頑張って”残った岩石を取り上げています.夕日をバックの高校生の目に映る自然・ジオが垣間見られた気がします.(清川昌一:九州大学)
目次へ戻る
第12回惑星地球フォトコンテスト入選02
第12回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:カルスト台地
写真:百崎礼治(福岡県)
撮影場所:福岡県 北九州市小倉南区平尾台国定公園
【撮影者より】
かつてサンゴ礁であったこの場所が地殻変動により隆起,石灰岩の大地となります.その後雨水による侵食で現在のカルスト台地を形成.日頃草で覆われ隠れているカルスト台地も,野焼きの後は,白い岩々が存在を主張しています.
【審査委員長講評】
福岡県の平尾台は山口県の秋吉台,四国カルストと並んで日本を代表するカルスト台地です.この作品は,溶食で残った石灰岩柱を野焼き直後に望遠レンズで切り取ったもの.このような地形が墓石地形とも呼ばれる理由がわかります.天地を切って余分なものを入れないのが良かった.
【地質的背景】
平尾台は秋吉台と同時期(石炭紀〜ペルム紀)の海山上に形成したサンゴ礁が付加したもので,九州最大のカルスト地形です.秋吉台と異なるのは,白亜紀頃の花崗岩や塩基性貫入岩による熱変成により結晶質石灰岩に変化しており,化石などはほとんど報告はありません.平尾台には4-5カ所一般の人が立ち入るこのできる洞窟もあり,その横には,日本で3番目に大きな石灰岩鉱山(三菱マテリアルなど)があります.(清川昌一:九州大学 )
(参考)清原正人,1968,地質調査月報,19巻7号,471-480. https://www.gsj.jp/data/bull-gsj/19-07_02.pdf
目次へ戻る
第12回惑星地球フォトコンテスト入選:03
第12回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:catastrophe
写真:峯田翔平(広島県)
撮影場所:島根県 益田市礁の鼻
【撮影者より】
益田市の日本海沿には,荒波により削られ,形成された奇岩や巨石,断崖が数多く存在します.その中で一層際立った存在感を出しているのが,「礁の鼻」です.その特徴的な尖った風貌は,日本であることを忘れさせます.この撮影時は,その存在感を更に引き出すような,燃えるような夕焼けでした.このシーンを更に非現実的にするために,NDフィルターを用い,長秒露光を行いました.
【審査委員長講評】
撮影地点の「礁の鼻」は地元では有名な朝日・夕日スポットのようです.この作品も優秀賞の「ゴジラの背」と同様に波の動きを長時間露光によって単純化し,海岸の岩石を強調しています.風景写真としては非常に美しい作品ですが,ジオの要素がもう少し含まれるほうが良かったと思います.
【地質的背景】
島根県の西端に近い小浜港西側の岬です.夕映えの景勝地として地元で愛されています.周辺は,後期白亜紀セノマニアン期〜サントニアン期の花崗岩からなる沈水海岸です.岩盤が黄金色に見えるのは夕日のせいばかりではありません.当地域周辺は,後期鮮新世〜前期更新世の江津層群が下位の花崗岩を広く覆っています.江津層群分布地の基盤岩は深層風化していることが特徴であり,この花崗岩も黄褐色に弱風化しています.(渡辺勝美:島根県地学会)
目次へ戻る
第12回惑星地球フォトコンテスト入選:04
第12回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:地の造形
写真:佐藤悠大(福岡県)
撮影場所:山口県 山陽小野田市本山岬公園
【撮影者より】
礫岩層が海蝕を受け独特の景観を作り出しています.撮影したくぐり岩もその一部で,人が通れるほどの貫通した穴がいくつか空いた形がユニークで観光地になりつつあります.背後に夕日が沈むくぐり岩を遠景に,筋状に走る礫岩層を前景にして広角レンズで遠近感を強調して撮影しました.
【審査委員長講評】
「くぐり岩」はいくつもの海食洞に削られた存在感のある岩です.この作品では「くぐり岩」を遠景に,その延長部である礫岩を手前に配置してクローズアップしています.超広角レンズを使用して全面でピントはシャープ,夕陽をバックに構図も完璧です.階調も申し分ありません.
【地質的背景】
本山岬では宇部層群(漸新統;宇部夾炭層ともよばれる)の下部を構成する厚東川(ことうがわ)礫岩層が海食崖をなしています.主に礫岩,砂岩からなり,直下には泥質片岩や蛇紋岩などからなる周防変成岩との不整合があります.礫岩層・砂岩層には平行層理,斜交成層がよく発達し,泥岩層を含みません.礫は小礫で円磨したものが多く,宇部層群は全体に緩傾斜で,固結度もそれほど高くないため,侵食されると礫が基質から分離しやすい特徴があります.(宮田雄一郎:山口大学)
目次へ戻る
第12回惑星地球フォトコンテスト入選:05
第12回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:柱状節理
写真:本田 誠(神奈川県)
撮影場所:アイスランド レイニスフィヤラ ビーチ
【撮影者より】
アイスランド南部観光のヴィーク近くの柱状節理の岩壁です.火山から流れる溶岩が海などに到達した際,急速に冷え固まると出来る岩石です.砂浜はブラックサンドビーチとも呼ばれる黒い砂浜でも有名です.冬季に訪問し,貴重な日の出ている時間帯に訪れました.
【審査委員長講評】
柱状節理をテーマにして毎回数多くの作品が応募されています.この作品の魅力は,「私も行って見たい」と感じさせる雰囲気があることで,コロナ禍の現在ではなおさらです.2014年に撮影されたやや古い作品ですが,柱状節理に座って海をながめる人の配置もよかった.アイスランドの1月は極寒かと思っていましたが,このような観光もできるのですね.
【地質的背景】
レイニスフィヤラはアイスランド南端近くにあり,カトラユネスコジオパークのジオサイトのひとつです.最終氷期のひとつ前の氷期に発達した氷河の下で発生した噴火によってこの柱状節理が形成されたようです.近隣には2011年にヨーロッパの空路を混乱させた噴火で有名なエイヤフェルトヨックルもあります.カトラ火山はミーダルス氷河の下にありますが,噴火を起こした際に発生した大洪水でこの露頭付近の黒い砂がもたらされました.(萬年一剛:神奈川県温泉地学研究所)
目次へ戻る
第12回惑星地球フォトコンテスト:佳作1-3
第12回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:せめぎ合い
写真:登坂直紀(北海道)
撮影場所:群馬県 沼田市利根川綾戸峡
【撮影者より】
赤城山と子持山の二つの成層火山に挟まれた利根川の綾戸峡.古くより関東と日本海を結ぶ交通の難所であったが,大正時代に鉄道が建設された.ここを通ると今でも自然と人間のせめぎ合いを感じられる.
目次へ戻る
佳作:斜里岳従えて
写真:糸賀一典(千葉県)
撮影場所:北海道斜里郡斜里町 JR釧網本線南斜里駅付近
【撮影者より】
斜里岳は冬季の夕刻が山の鋭鋒をより際立たせ、険しい斜里岳を望める。冬季間に数日しかない、斜里岳がハッキリ見える夕刻に、一日数便しかない列車とのコラボ写真を撮影した.
目次へ戻る
佳作:貫通甌穴ごしにアイコンタクト(長瀞)
写真:本間岳史(埼玉県)
撮影場所:埼玉県秩父郡皆野町下田野,荒川右岸
【撮影者より】
ジオパーク秩父の見どころのひとつである長瀞の荒川右岸,三波川帯の石英片岩中に形成された貫通甌穴.平水位の水面から10mほど上方にあるため,上から穴を覗くと穴を通して水面が見える.長瀞では岩畳をはじめ大小多数の甌穴が存在するが,このような完全な貫通甌穴は他に例がない.甌穴の内径は60〜80㎝,上下の長さは約2.5m.片理面の走向は南北で東へ20度傾いている.貫通甌穴ごしにサーフィンの人とアイコンタクトができる.
目次へ戻る
第12回惑星地球フォトコンテスト:佳作7-9
第12回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:そそり立つ立岩へ
写真:笠井 忠(奈良県)
撮影場所:京都府 京丹後市丹後町間人 立岩
【撮影者より】
竹野川の河口、後ヶ浜海岸の波打ち際にそびえ立つ見事な垂直の柱状節理「立岩」は、高さ20mもある巨大な一枚岩で、山陰海岸ジオパークのシンボルとして親しまれています。日本海にそそり立つ立岩は、竹野川が運んだ花崗岩質の砂州でつながっており、安山岩の直線的な荒々しい岩肌を、間近で見ることができます。立岩と朝の光を受けた砂州、そして白い波のコントラスト、残された人の足跡もこの美しい景観の一部に思えました。
目次へ戻る
佳作:太古の記憶
写真:横江憲一(北海道)
撮影場所:北海道 礼文島 桃岩〜元地散策路
【撮影者より】
桃岩は,マグマがつくった幅200-300m,高さ190mの巨大なドームです.新第三紀中新世に,浅い海底のやわらかな堆積物にデイサイトマグマが貫入してできたものと考えられています。写真は、桃岩遊歩道から撮影したもので、桃岩も表面をよく見ると柱状節理といくつものひだひだが見えています。
目次へ戻る
佳作:和深のタービダイト
写真:木下 滋(和歌山県)
撮影場所:和歌山県串本町和深 JR和深駅から歩いて5分
【撮影者より】
南紀熊野ジオパークエリア内の和深海岸に、砂岩と泥岩が交互に積み重なって海底に堆積した地層・タービダイトがみられます。
目次へ戻る
第12回惑星地球フォトコンテスト:佳作4-6
第12回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:大量の枕
写真:金子敦志(福島県)
撮影場所:北海道根室市花咲岬
【撮影者より】
北海道の根室半島には放射状の節理をもつ車石が有名ですが、根室半島の断崖には、いかにも枕の形をしているとわかる多数の枕状溶岩を見ることができます。いままで観察してきた枕状溶岩はどれも断面であったり、ひとつひとつの立体感を感じられるものではなかったりしたため、この枕状溶岩を見たときに非常に驚きました。根室半島の車石だけでなく、ぜひこの枕状溶岩も有名になってほしいです。
目次へ戻る
佳作:秘境の先の聖地
写真:薄葉友貴(東京都)
撮影場所:沖縄県 うるま市藪地島、ジャネー洞近くの海岸
【撮影者より】
神聖な空気に包まれたジャネー洞の周囲の森を抜けた先にある海岸。夕空が苔むした浜辺を照らしていた。
目次へ戻る
佳作:富士噴火の堆積地層
写真:齋藤敏雄(神奈川県)
撮影場所:静岡県小山町須走り フジアザミライン6km地点の渓谷
【撮影者より】
須走りグランドキャニオン フジアザミライン6km地点大日砂防ダムの上流が、グランドキャニオンといわれる場所です。高さ約30〜40mの切り立った崖が2kmほど続きます。宝永山が噴火いた際の火山灰が蓄積、長い年月で削られ深い谷を形成してできた渓谷という話を聞きました。地層はスコリア(火山噴出物)、塊状で多孔質です。 スコリアの地層を側面から撮影しました。
目次へ戻る
第12回惑星地球フォトコンテスト:佳作10-12
第12回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:柱状節理
写真:本田 誠(神奈川)
撮影場所:アイスランド レイニスフィヤラ ビーチ
【撮影者より】
アイスランド南部観光のヴィーク近くの柱状節理の岩壁です。火山から流れる溶岩が海などに到達した際、急速に冷え固まると出来る岩石です。砂浜はブラックサンドビーチとも呼ばれる黒い砂浜でも有名です。冬季に訪問し、貴重な日の出ている時間帯に訪れました。
目次へ戻る
佳作:大陸の裂け目
写真:林 正彦(兵庫県)
撮影場所:アイスランド シンクヴェトリル国立公園内
【撮影者より】
アイスランドのシンクヴェトリル国立公園内の大陸の裂け目を2019年9月に撮影した写真です。ユーラシアプレートが東に北米プレートが西に広がっている裂け目と思えぬ、紅葉の時期の美しさに感動しました。
目次へ戻る
佳作:タイムトンネル
写真:瀧しま修じ(埼玉県)
撮影場所:神奈川県 三浦半島 荒崎
【撮影者より】
断崖にぽっかり大きな穴が開いている。人工的に開けられたようにも見えるが、そうではなく波の侵食によってえぐられたとのことである。薄暗くなったころにはまるでタイムトンネルとも思わせる神秘的な穴である。
目次へ戻る
第12回惑星地球フォトコンテスト:佳作13-14
第12回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:龍鱗郷の造形美
写真:来栖旬男(山口県)
撮影場所:山口県 萩市上小川東分 田万川上流付近
【撮影者より】
平成3年、農道を建設中にたまたま見つかった柱状節理であるがその規模には目を見張るものがある。長さ14㎞に及ぶ溶岩流をその形状から地元の中学生によって「龍鱗郷」と名付けられた。
目次へ戻る
佳作:ヴァトナヨークトル氷河
写真:加藤 歩(神奈川県)
撮影場所:アイスランドのヴァトナヨークトル氷河
【撮影者より】
ヴァトナヨークトル氷河はヨーロッパ最大の氷河であり、アイスランドの国土の8%を占めています。目の前に広がるパノラマの大自然と、湖に反射する山々はとても美しい光景でした。
目次へ戻る
第13回惑星地球フォトコンテスト:最優秀
第13回惑星地球フォトコンテスト入選作品
最優秀賞:宝永火口岩脈群
写真:露木孝範(静岡県)
撮影場所:静岡県御殿場市 宝永山 山頂付近
【撮影者より】
2021年7月23日01時35分撮影.宝永火口の上部に割れ目を通過するマグマが固まった屏風のような岩脈が連なる一帯があることは,麓からの観察でも確認することができます.その姿を間近で詳細に捉えようと満月期に宝永山を訪れました.西に傾いた明るい月の光が赤い山肌に立ち並ぶ岩脈を浮かび上がらせ,荒涼として壮大な光景を目前に見ることができました.
【審査委員長講評】
富士山の宝永第1火口岩脈群は五合目から撮影されることが多いのですが,作者はぐっと近づいた宝永山山頂からの撮影なので迫力があります.満月の夜,適度な陰影ができる明け方の撮影で,溶岩流とその間に挟まれる火砕物,それらを貫く岩脈の関係がよく判ります.中望遠で画面一杯に捉えた緊張感のある構図が良かった.
【地質的背景】
1707年噴火で形成された宝永火口の壁には,富士火山の内部が見事に露出している.斜面とほぼ平行し横に連続する灰色の固い岩の層は,山頂火口からの爆発的噴火で放出されたスコリアや火山灰が固まったアグルチネートである.一方,縦に連なり火口壁から突出した岩の壁は,山腹割れ目噴火を起こしたマグマの通路が固まって出来た岩脈である.このようにタイプの異なる噴火の産物が同時に観察できる点で,宝永火口は興味深い.(山元孝広:産業技術総合研究所)
目次へ戻る
第13回惑星地球フォトコンテスト:優秀01
第13回惑星地球フォトコンテスト入選作品
優秀賞:3つのStream
写真:加藤順子(東京都)
撮影場所:京都府八幡市
【撮影者より】
桂川,宇治川,木津川の三つの川が出会うこの「三川合流」地点.合流した3つの川は淀川へと名前を変へ大阪平野へと流れ下ります.度々の洪水と水害が発生する地域は,江戸期以来多くの治水事業が繰り返されその結果としてこの他でも例を見ない地形を作り上げ,地域の憩いの場としての美しいランドマークへと変貌しました.なお,この写真は,チャーターしたヘリコプターからの空撮です.(2022.7.13一部加筆)
【審査委員長講評】
評者はこの作品で初めて関西には3つの川が合流する場所があることを知りました.この場所は京都府と大阪府の境界になっています.数百mからの高度から撮影されているようですが,三川合流を地上から眺めるのには「さくらであい館」の展望塔があります.(2022.7.13一部修正)
【地質的背景】
作品に見られる写真上の木津川は領家帯という花こう岩が広く露出する地域を流れており,花こう岩が風化した真砂を運搬してくるために流路にも真砂に由来する土砂が堆積し,また流出する土砂の影響でよく濁ります.宇治川と桂川は主に丹波帯分布域を流れ下って合流していますが,宇治川は琵琶湖南部と天ヶ瀬ダムによる停滞する水域を持つこと,桂川はこのすぐ上流で京都市街を流れる鴨川が合流するなど流域の社会的背景が異なっていて,またそれぞれの流路の水深も違っています.これらの違いが写真で見える3つの川の色の違いにも反映されています.写真上(木津川の南側)に見えるのは八幡市の男山で,丹波帯の付加体やチャートからできていて,頂上部の展望台からはこの写真と反対側からの三川合流部を眺望することができます.(川端清司:大阪市立自然史博物館)
目次へ戻る
第13回惑星地球フォトコンテスト:優秀02
第13回惑星地球フォトコンテスト入選作品
優秀賞:恐怖の石段
写真:高木 嶺(東京都)
撮影場所:パキスタン北部ゴジャール地区フセイニ村
【撮影者より】
フンザ川にかかる世界的に危険で有名なフセイニの吊り橋(長さ約200 m)を渡った先が断崖絶壁になっており,その上の段丘面を利用した羊や山羊の放牧場へと村人が大きな荷物を担いで行き来している姿を狙って撮影しました.断崖の道は薄く剥がれやすいスレートの岩板が敷石となっていますが,地震や土砂災害もある場所で崩れやすいので,恐怖の吊り橋を渡り切っても安心できない道が大変印象的でした.
【審査委員長講評】
撮影地はパキスタン最北部の7000m峰が連なるカラコルム山脈です.垂直な岩壁,積み上げられたスレートの敷板,そこを生活の道として行き来する人,それぞれの配置が絶妙です.私が行ったら足がすくんで動けなくなりそうな場所です.これからも写真を通して世界の秘境を地質学的な見地から紹介してください.
【地質的背景】
北部パキスタンはヒマラヤ山脈の延長でインドプレートの衝突により8000mを超えるカラコルム山脈が連なっております.フンザは白亜紀に日本列島のような島弧であったコヒスタン弧とアジアプレートの衝突境界に位置し,中圧型の変成帯からなります.この付近は南北に圧縮されてできた垂直に立った劈開を持つ岩石が急峻な崖を形成しています.この恐怖の石段は薄くて剥がれやすい性質を持つ粘板岩で作られています.硯やスレート葺きに使用される粘板岩は加工が簡単で積みやすいので家屋や階段の材料としてフンザ谷では頻繁に使用されています.(芳野 極:岡山大学惑星物質研究所)
目次へ戻る
第13回惑星地球フォトコンテスト:ジオパーク
第13回惑星地球フォトコンテスト入選作品
ジオパーク賞:大海に注ぐ湧水
写真:大場建夫(秋田県)
撮影場所:山形県 飽海郡遊佐町 釜磯海岸
【撮影者より】
鳥海山・飛島ジオパークの中にある釜磯海岸の湧水群の夕べ.鳥海山からの伏流水が日本海の浜辺で湧水となって周囲の砂浜を流し日本海に流れ込むシーンは地球の自然がなせる感動を見せてくれます.
【審査委員長講評】
パターンが美しい作品です.最初は何を撮影したのかわかりにくいのですが,奥の方を見ると1mほどの湧水の流れを撮影したものであることが判ってきます.じっくり見るとだんだんわかってくるのがこの作品の魅力です.作者はこの作品のほかにも,視点を変えた2作品を応募されました.組写真での応募でも良かったかもしれません.
【地質的背景】
釜磯は,およそ20年間溶岩流の内部を伏流した地下水が,地表や海底に湧き出す場所です.磁鉄鉱と砂粒を用いて美しい模様を描き続けるこの湧水を涵養するのは,約10万年前に鳥海火山から噴出した吹浦(ふくら)溶岩です.ポットホールや穿孔貝の巣穴が約2mの高さから見つかることから,流下後,地震による隆起を経験したことがうかがえます.(大野希一:鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会)
目次へ戻る
第13回惑星地球フォトコンテスト:会員
第13回惑星地球フォトコンテスト入選作品
日本地質学会会長賞:ミニチュアテラス
写真:金子敦志(福島県)
撮影場所:山形県 飯豊町広河原温泉
【撮影者より】
山形県西置賜郡飯豊町には広河原温泉があり,間欠泉があります.間欠泉付近にはそこから溢れた温泉水の成分が沈殿して形成されたと思われる,まるで棚田のような石灰華段丘があります.鍾乳洞で見たことのある石灰華段丘と比べて,とても小さく,よく見るとたくさんの丸みを帯びた構造物が段丘の中にあり,不思議な景色に心が惹かれました.
【審査委員長講評】
この作品は山形県の広河原温泉の小規模な石灰華テラスを撮影したものです.ローアングルで手前から奥まで見渡せるように撮影しています.一面が褐色のモノトーンで,テラス以外に余分なものが入っていません.探査車「オポチュニティ」は火星表面で発見した「ブルーベリー」を連想させる小球まであり,まるで火星表面にいるような気分になります.
目次へ戻る
第13回惑星地球フォトコンテスト:ジオ鉄
第13回惑星地球フォトコンテスト入選作品
ジオ鉄賞:たまゆらの中の洗濯岩
写真:落合文登(宮崎県)
撮影場所:宮崎県 宮崎市大淀川JR橋
【撮影者より】
JR橋下流の大淀川左岸河床部には,干潮時を中心に宮崎層群砂岩泥岩互層が露頭する.日南海岸沿いの「鬼の洗濯岩」同様に,波食により基盤面が平坦となり地表付近に波食台が形成されている.当該地の“宮崎相”の砂岩強度は,“青島相”より弱く「洗濯板(ギザギザの強度差)」が明瞭ではない.川端康成が絶賛した「たまゆら」の夕景は,すべての時間軸を優しく包み込む絶景スポットであり,私の週末のジョギングコースの1つにもなっている.撮影地点上流にある河岸沿いの橘公園は,かつて宮崎が空前の新婚旅行ブームであった1970年前後の面影として,フェニック並木が続いている.
【講評・解説】
日豊本線(宮崎〜南宮崎間)で有名な鉄道撮影スポットとして知られる大淀川橋梁(436.6m)は,大正4(1915)年の建設から 100 年を超える今も現役で活躍している鉄橋のひとつです.本作品は,大淀川橋梁を渡る特急列車のシルエットと夕景が織りなす写真の美しさもさることながら,河床の宮崎層群が露岩する干潮のベストの時間帯に狙いを絞った撮影で,地元の地質技術者ならではの常日頃の観察眼が感じられます.昭和 40 年代の宮崎新婚旅行ブームに拍車をかけた小説「たまゆら」.原作執筆のため川端康成が滞在した宮崎観光ホテルも右端にわずかに写しこまれています.地元愛あふれたジオ鉄的感性の光る作品です.(藤田勝代:深田研ジオ鉄普及委員会幹事)
目次へ戻る
第13回惑星地球フォトコンテス:スマホ
第13回惑星地球フォトコンテスト入選作品
スマホ賞:島山島のシマシマ
写真:安永 雅(長崎県)
撮影場所:長崎県五島市玉之浦町島山島西海岸
【撮影者より】
島山島は,その名の通りシマシマの山が見られる島.その西海岸では,東シナ海の荒波によって削り出されたシマシマの大断崖が見られる.この大断崖は島の南の大瀬崎から約10kmにわたって続き,高さは最大で100mになる.約2000万年前に大陸から流れていた大河の底に堆積した砂泥互層が迫力の大露頭をなす.
【審査委員長講評】
五島列島は2022年1月,日本ジオパークに認定された地域で,そのためか今回は五島列島から多くの作品が寄せられました.船からしか撮影できないポイントですが,船から眺める10kmの大露頭はさぞかし壮観でしょう.薄曇りだったようで陰があまりなく,地層の詳細がよくわかります.解説も適切でした.
【地質的背景】
五島列島福江島の西海岸は,東シナ海に面する常に大波にさらされる場所で,きれいな縞々の露頭が数キロにわたって連続します.この地層は,河川と氾濫原堆積物からなる約1700年前の陸成層であり,100mの断崖には上方細粒化/薄層化がよく見られます.ここでは,日本海が開く前のユーラシア大陸の縁辺部の堆積環境を記録する地層が,圧倒的なスケールで残されています.安永さんは地元ジオパーク推進協議会の専門委員であり,一般の人がなかなか行けない地の利を生かした素晴らしいジオ写真を提供していただくことができました.(清川昌一:九州大学)
目次へ戻る
【geo-Flash】No.519 2021年名古屋大会:間もなく講演申込開始です
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.519 2021/5/18 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2021年名古屋大会:間もなく講演申込開始です
【2】第4回ショートコースのご案内
【3】2021年「地質の日」行事のご案内
【4】支部情報
【5】研究,教育や社会貢献など,会員の活動成果を学会HPでPRしませんか
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2021年名古屋大会:間もなく講演申込開始です
──────────────────────────────────
日本地質学会第128年学術大会 名古屋大会を下記の日程で開催します.
セッション(口頭+ポスター)はオンラインで,LOC主催シンポ,市民講演会
は,現地での開催を予定しています.5/20頃より演題登録の受付開始予定です.
会期:2021年9月4日(土)-7日(火)
会場:名古屋大学東山キャンパス(愛知県・名古屋市千種区)
+ オンライン開催
詳しくは大会サイトをご参照ください.
https://confit.atlas.jp/geosocjp128
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第4回ショートコースのご案内
──────────────────────────────────
今回は地質学のあり方や論文を書くことの本質について考える機会を提供します.
多くの学生・若手研究者の皆様に受講していただきたいコースです.中堅・ベテラ
ン研究者や学校教員,地質調査業従事者,広く一般の方も,地質学の調査・研究や
教育あるいは科学について見つめ直すよい機会になるに違いありません.講師は,
午前が日本の地質学をリードしてきた研究者の一人である磯崎行雄・本会会長,
午後が『プレートテクトニクスの拒絶と受容:戦後日本の地球科学史』などの
地球科学史研究で知られる泊 次郎氏です.
日程:2021年7月18日(日)
<午前> 10:00-12:00
「吾書くゆえに吾あり:論文執筆についての超個人的視点」磯崎行雄(東京大学)
(注)「崎」の正しい表記は,「大」→「立」
<午後> 13:30-15:30
「地球科学の歴史から何を学ぶか」泊 次郎(科学史研究家)
※5月末頃より申込受付開始予定です.
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0134.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2021年「地質の日」行事のご案内
──────────────────────────────────
5月9日(日)に開催されたオンライン講演会の内容は,
YouTube公開中です.ぜひご覧ください
・岡田 誠(茨城大学)「地質年代チバニアンと房総の地質」
・氏家恒太郎(筑波大学)「断層の地質学的研究から読み解くプレート
沈み込み帯地震発生の科学」
https://youtu.be/4SXi-w76gWQ
このほか,全国の「地質の日」行事については,ホームページに
随時情報が掲載されています.(事業推進員会のHP)
https://www.gsj.jp/geologyday/2021/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】研究,教育や社会貢献など,会員の活動成果を学会HPでPRしませんか
──────────────────────────────────
地質学会ホームページ「会員の学術・教育・社会貢献活動」
http://www.geosociety.jp/science/content0109.html
では,その名も通り,地質学会員の「学術,教育,社会貢献活動」
をご紹介しています.皆様からの情報をお待ちしています.
例えば,
・自身の学術論文掲載がメディアや所属機関からプレスリリースされた.
・研究成果に関して,テレビやラジオ番組に出演する.
・ジオパークの新規開設や整備・更新をメディアで紹介された
・興味深い授業内容として,メディア等で取り上げられた.
などなど.
ただし,番組,著書・雑誌,既存施設や教室などの紹介や宣伝が目的ではなく,
会員の研究や活動の成果の紹介が目的です.客観性,公共性,速報性,新規性
および内容を考慮し,広報委員会で掲載を判断します.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
JAMSTEC 50周年記念行事
「すべらない砂甲子園」参加募集(応募期限:5月31日)
全国津々浦々にある砂の中から「一番すべらない砂」=「最強の砂」を
決定する超新感覚室内実験的格闘競技大会です.
エントリーをお待ちしています!
詳しくは: http://www.jamstec.go.jp/50th/suberanai/
エキシビションマッチ配信中:
https://www.youtube.com/watch?v=ZomMahkkEJ4&t=2s
------------------------------------------------
地層処分技術オンライン説明会(改訂した包括的技術報告書)
主催:原子力発電環境整備機構
開催日:
【総論】5月13日(木),6月9日(水)
【地質環境】5月20日(木),6月16日(水)
【処分場設計】5月26日(水),6月24日(木)
【長期安全評価】6月3日(木),6月30日(水)
時間(共通):17:00-18:30
https://www.numo.or.jp/topics/202121042815.html;
日本地球惑星科学連合2021年大会
開催方式:ハイブリッド開催(オンライン開催)
現地会場:パシフィコ横浜ノース
5月30日(日)-6月6日(日)
(注)21年大会はオンライン形式に完全移行となりました.
http://www.jpgu.org/meeting_j2021/
CPD講習会(山口大学)
オンデマンド方式.6月15日(火)-8月31日(火)までの都合の良い
時間帯に視聴可。
申込締切:5月31日(月)
内容:
1)原発地質学:石渡明(原子力規制委)
2)4成分系で考える岩石・鉱物の組成共生図表:志村俊昭(山口大)
3)おしゃべりなカイミジンコ:岩谷北斗(山口大)
4)カルサイトから岩石やコンクリートの応力/歪を読む新しい手法
:坂口有人(山口大)
5)堆積岩の乾燥湿潤に伴う変形と浸透特性
:長田昌彦(埼玉大/応用地質学会会長)
http://www.sci.yamaguchi-u.ac.jp/ja/sci/info/events/2021/20210615.html
地質学史総会・懇話会
6月26日(土)13:00-17:30(予定)
場所:北とぴあ 8階803号室(JR京浜東北線王子駅下車3分)
志岐常正:「戦後京大地質学教室史―その虚像と実像」
矢島道子:『地質学者ナウマン伝』を上梓して
(注)状況によってはオンラインまたはハイブリッドでの開催を検討します.
学術会議公開シンポジウム(オンライン)
「東日本大震災10年と史料保存−その取組と未来への継承−」
6月26日(土)13:30-17:30
参加費無料,定員:300人
要事前申込(どなたでも参加可)
http://www.scj.go.jp/ja/event/2021/311-s-0626.html
(後)第58回アイソトープ・放射線研究発表会
7月7日(水)-9日(金)
開催形態:オンライン開催
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2021/top
(後)科学教育研究協議会 第68回全国研究大会・福島大会
7月31日(土)-8月2日(月)
大会テーマ「自然科学をすべての国民のものに」
(注)Web大会に変更になりました
https://kakyokyo.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・北海道大学大学院地球環境科学研究院准教授公募(8/16)
・JAMSTEC 超先鋭研究開発部門高知コア研究所研究員公募(6/25)
・東京大学地震研究所2021年度(第2回)大型計算機共同利用公募(5/31)
・一般社団法人カーボンリサイクルファンド 2021年度研究助成(6/14)
・令和3年度おおいた姫島ジオパーク調査研究助成募集(5/30)
・男鹿半島・大潟ジオパーク内での研究活動に関する補助金制度
・南紀熊野ジオパーク研究助成事業の募集 (6/9)
・湯沢市ゆざわジオパーク学術研究等奨励補助金の募集 (5/31)
・下北ジオパーク研究補助金の募集 (6/7)
・糸魚川ジオパーク学術研究奨励事業の募集 (5/28)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
放射性物質を含んでいる福島県太田川河川敷で発見した黒砂中の磁性細菌
放射性物質を含んでいる福島県太田川河川敷で発見した黒砂中の磁性細菌
田崎和江(正会員)・横山明彦 (金沢大学理工研究域)・涌島英揮・石原牧子
2011年3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生し,地震と津波による被害が生じた. さらに, 東京電力福島第一原子力発電所のある福島県では,原子炉の損傷により放射性物質が飛散し,広範囲に被害が及んだ.2020年3月11日に福島県南相馬市双葉町の避難困難区域は解除となったが,多くの住民は安心して帰宅することはできず,いまだに不安を抱えている.その理由の1つとして,放射性物質が飛散したことによる残留放射線の影響が挙げられる.居住地域の表面を覆う土壌はすべて表面を削り取り, 新しい土壌に入れ替えたため, 現在汚染されてはいない.しかし,河川・ダム・ため池の除染作業は原則実施しない方針のため,それらの周囲には,汚染物質除去作業を行っていない土壌が存在している.著者らはこの10年間,除染対策を探るために, 特に福島県南相馬市原町区周辺の河川・ダム・流域の土壌,森林の現地調査および実験室における放射能測定・分析電子顕微鏡による微生物や鉱物の観察, さらにクロマツの植生などの研究を行って論文を公表してきた.ここでは,2020年2〜3月に横川ダム周辺や太田川流域の河川敷にて,高放射能を持つ黒砂を発見したので, そのデータを提供する(図1).
図1.横川ダムと太田川上流の各調査地点とGMサーベーメータによる約1m高の放射線計数率
2020年2月22日, 横川ダム周辺と太田川流域の上流河川において, 放射能測定と土壌・砂・植物・苔などの採取をした(図1).各調査地点におけるGMサーベーメータによる約1m高の放射線計数率(cpm)は,その地点の空間線量を反映していると思われるが,ダム周辺では山林に囲まれた地点で値が高くなる傾向が見られた.また,コケ植物の表面で放射能の濃縮がみられた.さらに, 太田川流域では, 河川敷表面に堆積していた黒砂の放射能を測定・分析したところ高い放射能値が認められた. 加えて,金沢医科大学に設置された分析電子顕微鏡でこの黒砂を観察した結果, 黒砂中に多量のマグネタイトと磁性細菌が認められた(図2). なお, 堆積物中の鉱物はX線粉末回折分析装置で同定を行った. 磁性細菌の同定は金沢大学理工研究域の田岡東博士に鑑定していただいた.
図2.太田川河川敷表面で採取した黒砂の電子顕微鏡観察画像. 左上の写真の濃い黒い小球状粒子の塊は磁性細菌の塊, 濃い灰色の板状粒子は雲母類鉱物, 右上の写真のサイコロ状の塊は磁鉄鉱. 下段の薄い灰色微粒子は粘土鉱物, 角張った不透明のサイコロ状粒子は磁鉄鉱.
なお, その黒砂に過酸化水素水をかけると, 対照実験としてされた福島県松川浦南海岸の黒砂に比べて, 激しく発砲したことから, 黒砂には多くの有機物が含まれており,おそらくその起源となる微生物が多く生息していたと考えられる.また, GMサーベーメータによる河原の砂の平均的な計数率は200cpm(密着測定)であるのに対し,黒砂の部分は約2倍の400cpmの計数率が測定された. 県道沿いにある公会堂の前には,放射線量モニターが設置されており地上1mの高さの放射線量がモニターに表示されていた.それらの値は, 道路上で直接測定した値に対して低い値を示していた.2020年3月下旬に採取した太田川河川敷の黒砂を金沢大学に依頼分析した結果はこれらの物質の放射性セシウム同位体放射能比が福島第一原子力発電所2, 3号炉の放射能比と一致していることを示しており, これらの測定データは2011年3月11日の福島第一原子力発電所の事故により拡散した高濃度の放射性核種が太田川や周辺土壌に広がっていることを示唆している(※1).
以上の結果をもとに, 今後について展望したい. 横川ダム周辺の結果より,ダム周辺の山林の土壌中には原子炉の損傷により飛散した放射性物質が堆積している.特に今回の調査では生活圏でも高い線量が観測できたことから, 活動している地球では, それらの放射性物質はいつまでもそこに留まってくれているわけではなく, 他に移動し, 新たなホットスポットを形成してしまうことが懸念される. さらに, コケ植物などでは生態濃縮が見られたことにより,早急に生活圏を取り巻く周辺地域の汚染物質除去作業を行うことが求められる.また, 採取した磁性細菌では放射能が周囲より高く検出された.磁性細菌が大量に生息しているこの黒砂が放射能汚染水に何らかの形で関与し, 放射性物質を集濃する作用があると推測される.津波中の微生物が水田土壌の環境を変えるとともに,放射能汚染環境が微生物に耐性をもたせ, 進化させるという相互作用が報告されている(田崎ほか, 2011, 2014). これらのことから,元来生息していた磁性細菌が放射能汚染環境に耐性を持ち,それらを体内に取り込んでいる可能性も示唆される.米国を中心とした核開発に力を入れている諸外国では,アクチノイドなど, 取り扱いに制限がある元素を吸着材として用いる研究を行っているが,日本にはそのような研究拠点がない.吸着剤として十分に解明されていない元素を用いるのではなく,身近に存在し,これまでも共生している微生物を放射性物質の吸着剤として用いることができれば,より安全・安心・低コストの吸着材の開発ができるのではないかと考える.
また, 今回発見した細菌には磁性があるため,吸収した放射性物質の回収には電磁石を用いることも可能であり,硫酸還元細菌と併用することで,放射性物質を鉱物化して閉じ込めることも可能であると考える.放射性物質の流れ込む河川において,磁性細菌を利用することで,ダム湖周辺の山林に蓄積している放射能汚染物質の生活圏への流入や海への流失を防げるのではないだろうかと考える.本研究を行うに際し, 現地を案内してくださった福島県南相馬市原町区の住民の皆様に感謝申し上げます.
※1:採取された黒砂は, 別に採取された白砂や海岸で採取された黒砂と同様に, それぞれ円筒形のU8容器に試料の高さが5㎝になるように調整し,秤量した. それぞれの試料について金沢大学アイソトープ理工研究施設に設置された高分解ゲルマニウム半導体検出器でγ線スペクトルを取得し, 同じ形状の日本分析化学会提供標準試料の結果と比較して放射能を定量した. 放射能濃度は圧倒的に河川敷で採取した黒砂が大きいが(134Cs: 2.62x102, 1377Cs: 4.13x103 Bq/kg), 白砂(134Cs: 2.67x10, 137Cs: 4.25x102 Bq/kg)を含めてセシウム同位体放射能比は福島第一原子力発電所2, 3号炉から放出されたものに一致し, ともに起源は一致していることを示す. なお, 海岸の黒砂(137Cs: 3.81 Bq/kg)は放射能が小さく134Csが観測されていないので放射能比は与えられず, 起源について特定できない.
参考文献
田崎和江・高橋正則・鈴木祐恵・井本香如,2011,東日本大震災における空間β線測定. 地球科学, 65,175-177.
田崎和江・霜島康浩・根元直樹・鈴木克久・竹原照明・石垣靖人・中川秀昭, 2014, 津波被害を受けた水田に形成したバイオマットの放射能除染能力の可能性(後編);福島での災害の実態と地域に根ざした取り組み. 地学教育と科学運動, 73, 63-69.
(2021.6.15掲載)
※本記事は,日本地質学会News Vol. 24, No. 6(2021年6月号)にも掲載しています.
【geo-Flash】No.520 2021年度(第13回)代議員総会開催
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.520 2021/6/1 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】日本地質学会2021年度(第13回)総会開催
【2】2021年名古屋大会:講演申込受付中
【3】第4回ショートコースのご案内
【4】令和4年度版学習資料「一家に1枚」の企画募集
【5】研究,教育や社会貢献など,会員の活動成果を学会HPでPRしませんか
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】新型コロナウィルス感染拡大防止に関する学会の対応(2021/6/1)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】日本地質学会2021年度(第13回)総会開催
──────────────────────────────────
2021年度(第13回)の代議員総会を開催いたします。
今年も、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、WEB会議形式にて開催
いたします。代議員の皆様には別途メールで、開催のお知らせを送信しました。
欠席される代議員は、必ず「委任状」or「議決権行使書」をご提出下さい。
日時:2021年6月12日(土)14:00-15:30(WEB会議形式)
総会議事次第はこちら、、、
http://www.geosociety.jp/outline/content0152.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2021年名古屋大会:講演申込受付中
──────────────────────────────────
日本地質学会第128年学術大会 名古屋大会を下記の日程で開催します.
セッション(口頭+ポスター)はオンラインで,LOC主催シンポ,市民講演会
は,現地での開催を予定しています.
会期:2021年9月4日(土)-7日(火)
会場:名古屋大学東山キャンパス+ オンライン開催
・演題登録・講演要旨申込締切:6月30日(水)18時
・ジュニアセッション参加申込締切:8月2日(月)
・誌面ブース出展申込締切:6月30日(水) ...など
詳しくは大会サイトをご参照ください.
https://confit.atlas.jp/geosocjp128
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】第4回ショートコースのご案内
──────────────────────────────────
今回は地質学のあり方や論文を書くことの本質について考える機会を提供します.
多くの学生・若手研究者の皆様に受講していただきたいコースです.中堅・ベテラ
ン研究者や学校教員,地質調査業従事者,広く一般の方も,地質学の調査・研究や
教育あるいは科学について見つめ直すよい機会になるに違いありません.講師は,
午前が日本の地質学をリードしてきた研究者の一人である磯崎行雄・本会会長,
午後が『プレートテクトニクスの拒絶と受容:戦後日本の地球科学史』などの
地球科学史研究で知られる泊 次郎氏です.
日程:2021年7月18日(日)
開催方法:WEB会議システムzoomによるオンライン講義
<午前> 10:00-12:00
「吾書くゆえに吾あり:論文執筆についての超個人的視点」磯崎行雄(東京大学)
(注)「崎」の正しい表記は,「大」→「立」
<午後> 13:30-15:30
「地球科学の歴史から何を学ぶか」泊 次郎(科学史研究家)
参加申込締切:7月5日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0134.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】令和4年度版学習資料「一家に1枚」の企画募集
──────────────────────────────────
文部科学省では,国民の皆様が科学技術に触れる機会を増やし,科学技術に
関する知識を適切に捉えて柔軟に活用いただくことを目的として,学習資料
「一家に1枚」を制作しています,令和4年度の第63 回科学技術週間に合
わせて作成する「一家に1枚」の企画及び監修をしていただく方を募集いた
します,監修者には,テーマ決定から学習資料「一家に1枚」の配布までの
期間,広報媒体の作成を含め様々な広報活動へのご協力いただけることが
要件となります.
期限:令和3年6月30日(水)17時必着
詳しくは,
http://geosociety.jp/uploads/fckeditor/others-pdf/2021ikkaniichimai.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】研究,教育や社会貢献など,会員の活動成果を学会HPでPRしませんか
──────────────────────────────────
地質学会ホームページ「会員の学術・教育・社会貢献活動」
http://www.geosociety.jp/science/content0109.html
では,その名も通り,地質学会員の「学術,教育,社会貢献活動」
をご紹介しています.皆様からの情報をお待ちしています.
例えば,
・自身の学術論文掲載がメディアや所属機関からプレスリリースされた.
・研究成果に関して,テレビやラジオ番組に出演する.
・ジオパークの新規開設や整備・更新をメディアで紹介された
・興味深い授業内容として,メディア等で取り上げられた.
などなど.
ただし,番組,著書・雑誌,既存施設や教室などの紹介や宣伝が目的ではなく,
会員の研究や活動の成果の紹介が目的です.客観性,公共性,速報性,新規性
および内容を考慮し,広報委員会で掲載を判断します.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[中部支部]
・中部支部 2021年支部総会・年会・シンポジウム
6月26日(土)Zoomオンライン
講演申込・事前登録締切:6月18日(金)
シンポジウム「美濃帯の最近の研究事例」
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
日本地球惑星科学連合2021年大会
開催方式:ハイブリッド開催(オンライン開催)
現地会場:パシフィコ横浜ノース
5月30日(日)-6月6日(日)
(注)今大会はオンライン形式に完全移行となりました.
http://www.jpgu.org/meeting_j2021/
地質学史懇話会<ハイブリッドに変更のお知らせ>
6月26 日(土)13:00(30分早くなっています)
場所:早稲田奉仕園セミナーハウス(東京都新宿区西早稲田2-3-1)
TEL: 03-3205-5411
オンラインのURLは6月20日以降、希望者に送ります.
矢島(pxi02070@nifty.com)までご連絡ください.
学術会議公開シンポジウム(オンライン)
「東日本大震災10年と史料保存−その取組と未来への継承−」
6月26日(土)13:30-17:30
参加費無料,定員:300人
要事前申込(どなたでも参加可)
http://www.scj.go.jp/ja/event/2021/311-s-0626.html
(後)第58回アイソトープ・放射線研究発表会
7月7日(水)-9日(金)
開催形態:オンライン開催
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2021/top
(後)科学教育研究協議会 第68回全国研究大会・福島大会
7月31日(土)-8月2日(月)
大会テーマ「自然科学をすべての国民のものに」
(注)Web大会に変更になりました
https://kakyokyo.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・令和3年度 下北ジオパーク研究補助金募集(6/7)
・令和3年度 白滝ジオパーク調査研究助成事業募集(6/11)
・令和3年度 南紀熊野ジオパーク学術研究・調査活動助成事業募集(6/18)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】新型コロナウィルス感染拡大防止に関する学会の対応(2021/6/1)
──────────────────────────────────
新型コロナウィルスの感染が拡大する9都道府県(北海道、東京、愛知、大阪、
兵庫、京都、岡山、広島、福岡)に出されている緊急事態宣言が、令和3年6月
20日まで期限を延長されることになりました.
引き続き,緊急事態宣言が発出されている地域、または自治体からそれに準ずる
宣言等が出されている地域では,対面形式の学会主催の行事・イベントは屋内外
を問わず中止または延期,あるいはオンライン開催への変更のご検討をお願い
いたします.
全文は、http://www.geosociety.jp/news/n160.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.521 名古屋大会講演申込関わるzoom説明会
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.521 2021/6/15 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】【2021名古屋】講演申込受付中
【2】【2021名古屋】講演申込関わるzoom説明会:ぜひご参加ください
【3】【2021名古屋】誌面ブース出展のご案内
【4】【2021名古屋】そのほかのお知らせ
【5】2021年度会費督促請求について
【6】第4回ショートコースのご案内
【7】本の紹介: 絶えて存在しなかったかのように
【8】TOPIC:放射性物質を含んでいる福島県太田川河川敷の黒砂中の磁性細菌
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
【12】地質学雑誌127巻5号,一部不達・遅延のお詫び
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】【2021名古屋】講演申込受付中
──────────────────────────────────
日本地質学会第128年学術大会(2021名古屋大会)での講演申込を受付中です.
**********************************
演題登録・講演要旨申込締切:6月30日(水)18時
**********************************
(注意)
今年の講演要旨は,演題登録システム上で,直接テキストを入力し,必要に応じて
図表(任意)をアップロードします.閲覧用のpdfファイルはシステム上で自動作成
されます.従来のようにA4サイズ1枚分の要旨PDFを作成いただく必要はありません.
詳しくは大会サイトをご参照ください.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/collectsubject
e-posterについて
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/eposter
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】【2021名古屋】講演申込関わるzoom説明会:ぜひご参加ください
──────────────────────────────────
地質学会初のオンライン大会となる2021年名古屋大会では,オンライン大会
ならでは特徴を活かした充実した議論の場をご提供できるよう,準備を進めて
いますが,初めての試みが数多くあります.特にポスター発表(e-poster)は
画像データ以外に動画でのプレゼンやzoomでのコアタイムなども予定してい
ます.e-posterの具体例などもお示ししながら,オンラインでの口頭発表・
ポスター発表の内容について,詳しくご説明します.ぜひご参加ください.
名古屋大会zoom説明会
日時:2021年6月21日(月)12:30から(30分から1時間程度を予定)
https://us02web.zoom.us/j/
ミーティングID: 898 5253 3970
パスコード: 652906
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】【2021名古屋】誌面ブース出展のご案内
──────────────────────────────────
展示ブースの代替として誌面ブースを実施いたします.
日本地質学会が「2021名古屋大会プログラム&誌面ブース」という冊子を
発行し,これを全ての大会参加者に郵送いたします.
配布対象者:学術大会参加申込み者(大学および研究機関の地質研究者,
地質技術者,自然博物館等の学芸員,ジオパークの地質専門員,理科教員,
一般など1,000名弱)
掲載料: 1ページ: 35,000円/見開き2ページ: 60,000円
冊子:A4サイズ,フルカラー印刷体,参加者へ郵送
申込締切:6月30日(水)
詳しくは,https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/tenji
このほかに,「Webを活用する業界サポートサービス〜地質系専門企業への
オンライン訪問〜」も企画しています.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/gyokai_support
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】【2021名古屋】そのほかのお知らせ
──────────────────────────────────
・トピックセッションT4「二次改変された過去の弧-海溝系の復元:日本および
その他の例」招待講演者一部変更
当初予定していた今岡照喜さん(山口大:会員)の招待講演は,ご本人の都合に
よりキャンセルとなり,山本啓司さん(鹿児島大:会員)に変更になりました.
招待講演者の紹介
http://www.geosociety.jp/science/content0135.html#t4
セッション概要
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/session
・第18回日本地質学会ジュニアセッション【参加申込締切:8/2(月)】
学術大会セッションと同様にe-posterによる発表です.審査もオンライン上で
行います.オンラインのため遠方からもご参加いただきやすくなっています.
詳しくは,https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/gyoji#es
このほか,名古屋大会の情報は随時大会サイトを更新しています.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2021年度会費督促請求について
──────────────────────────────────
1.督促請求のための自動引き落とし日は,6月23日(水)です.
2021年度会費が未入金のかたで,1月から5月上旬までの間に自動引落の
手続きをされたかたは6月23日に引き落としがかかります.
引き落とし不備にならぬよう,残高の確認をお願いします.
2.郵便振替用紙によるお振り込みの方には,近日中に督促請求書(郵便
振替用紙)を郵送いたします.お手元に届きましたら,早急にご送金
くださいますようお願いいたします.
※7月上旬頃までに入金確認が取れない場合には,7月号の雑誌から送本
停止となります.定期的に雑誌をお受け取りになりたい方は,お早めに
ご送金くださいますよう,よろしくお願いいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】第4回ショートコースのご案内
──────────────────────────────────
今回は地質学のあり方や論文を書くことの本質について考える機会を提供します.
多くの学生・若手研究者の皆様に受講していただきたいコースです.中堅・ベテラ
ン研究者や学校教員,地質調査業従事者,広く一般の方も,地質学の調査・研究や
教育あるいは科学について見つめ直すよい機会になるに違いありません.講師は,
午前が日本の地質学をリードしてきた研究者の一人である磯崎行雄・本会会長,
午後が『プレートテクトニクスの拒絶と受容:戦後日本の地球科学史』などの
地球科学史研究で知られる泊 次郎氏です.
日程:2021年7月18日(日)
開催方法:WEB会議システムzoomによるオンライン講義
<午前> 10:00-12:00
「吾書くゆえに吾あり:論文執筆についての超個人的視点」磯崎行雄(東京大学)
(注)「崎」の正しい表記は,「大」→「立」
<午後> 13:30-15:30
「地球科学の歴史から何を学ぶか」泊 次郎(科学史研究家)
参加申込締切:7月5日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0134.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】本の紹介: 絶えて存在しなかったかのように
──────────────────────────────────
「絶えて存在しなかったかのように」西山忠男著
(文芸社,2021年6月15日発行,ISBN978-4-286-22642-2,文庫版,183p)
本書は「オラビ瀬の洞門」(紹介文:http://earth.s.kanazawa-u.ac.jp/ishiwata/orabise.htm),「孤峰の蝶」に続く著者の3冊目の小説本であり,今回は書名になっている中編小説(99ページ)の他にもう一編,「海,バンカに揺られて」(78ページ)が含まれている.本書の帯のキャッチフレーズ「黄泉(よみ)と現世(うつしよ)のすべての長崎の人々に捧げる鎮魂の書(小説)」は,長崎原爆被害の地獄図のような描写を含む1番目の小説に当てはまり,帯の裏には「どれほど想像することが難しくともあの日が確かに存在したことはわれらの血に刻まれている」と記されている.2番目の小説も,我々戦後世代に深く内在していて,平和な生活の中で思わぬ形で顕在化する過去の戦争の影を扱っており,帯の裏には「フィリピンで共産ゲリラに捕らわれた「私」が山中の部落で遭遇した前世の自分とは・・・戦争に翻弄された魂(たましい)の懊悩(おうのう)を描く」とある.どちらの小説も「オラビ瀬の洞門」と同様に,過去の暗い歴史を背負った心の奥の魂の叫びと「生まれ変わり(転生,自分は過去のだれかの生まれ変わりかもしれないという意識)」が重低音の基調テーマとなっている.ここでは,内容的に地質学研究と直接関連する2番目の小説を紹介する.なお,「著者」はこの小説の著者(西山),「筆者」はこの紹介文の筆者(石渡)を指す.
この小説の前半の設定はかなりの部分が著者の現実の学究生活そのままである.「私」は変成岩を研究する若い大学教授であり,調子のよい老教授に頼まれてフィリピン人の留学生を引き受けてしまい,その修論研究のフィールド調査指導のためにフィリピンに行くのである.この小説では「ざくろ石角閃岩」が重要なキーワード(キー岩石)になっており,「かんらん岩」も出てくるが,それらの岩石学的な詳細や学問的な意義はもちろん一切語られない.調査地へ行く途中に宿泊する田舎の町で,自動小銃を持ってホテルの玄関の前に立っている警備員に,「もし共産ゲリラが襲ってきたら,あなた一人で大丈夫か」と「私」が聞くと,「大丈夫だ.俺が共産ゲリラだから」と答えた,というような,お腹の皮がよじれるユーモアも散りばめられている.しかし,ざくろ石角閃岩が露出しているはずの岩石海岸に両翼船(バンカ)で上陸すると,楽しい雰囲気は一転して暗黒の世界になる.一行は共産ゲリラに捕らえられて山中の村に連行されるのである.そして「私」以外のメンバーは町に返されてしまい,「私」だけが村に残される.意外なことに,この村の長老は日本語を話す.かつてこの村で一人の元日本兵が暮らしていて,村の女性との間に子供もあったが,あるきっかけで自殺してしまったこと,長老はその日本兵から日本語を習ったこと,「私」がその日本兵の生まれ変わりであり,「私」がこの村に来ることをその日本兵から夢で告げられたこと,などを詳しく語った.そして夜の「歓迎会」で椰子(ヤシ)酒を飲みながら,今も村で生活するその「子供」(中年女性)と話していると,「私」の内部に不思議なことが起こる・・・
この小説は,東・東南アジアの大陸と西太平洋の島々やその波間に散った無数の日本兵への挽歌(ばんか)であり,その歴史から自らを切り離し,意識的か無意識かはともかく,その歴史に向き合うことを避けて生きてきた我々への警鐘でもある.
あとがきには,この小説前半の紀行風のルソン島の記述が著者の実体験に基づくことが述べられており(ゲリラによる拉致は創作),村の長老から聞いたその日本兵の中国における戦争体験の生々しい叙述は,著者の父親の手記に基づくとのことである(フィリピンへの転戦は創作).「歴史に向き合う」ということが,現実にはどういう行為であるかを,著者は身を以って示していると言える.また,あとがきには,この小説に仮名で登場する日本とフィリピンの教授への謝辞が実名を挙げて述べられており,特にフィリピンの教授は研究対象の岩石が筆者と同じオフィオライトで,筆者と同じ日本の大学で博士号をとった人であるため,筆者もよく知っているのでとても懐かしく感じた.
中国の戦記部分に挿入されている李白の黄鶴楼(こうかくろう,湖北省武漢市武昌区の名所)の詩は,揚子江(長江)を揚州の街へ下る友人孟浩然(「春眠暁を覚えず」の詩で高名)を送るもので,後半の「孤帆遠影碧空尽 唯見長江天際流」により広大な天地の時空を提示して無常観と寂寥感を深めていて,作品の終盤でざくろ石角閃岩の断崖上から対岸の日本を想ってフィリピン海を望む日本兵と「私」の心に通じていると思うが,李白の詩に日本兵のような絶望感はないように思う.なお,本書の文章はよく練れていて立派であるが,読みが難しい漢字にはもう少しルビを振っていただけると若い読者に親切だと思う.疚(やま)しさ(p. 79),戦(おのの)き(p. 106),購(あがな)った(p. 117),目を瞑(つむ)る(p. 167)など.
著者は2020年3月末に熊本大学を定年退職したが,新型コロナウィルス感染症パンデミックのため最終講義などの退職記念行事はすべてキャンセルとなったので,自分なりにケジメをつけるため,退職記念としてその1年後に上梓したのが本書とのことである.筆者の友人の中には,非公式の最終講義を音声つきのパワーポイント映像ファイルにしてDVDに焼き,我々に配った人もいる(一度は酒を飲みながら講義したいと思っていたとのことで,それを実行した).筆者は現職就任のために定年3〜4年前の2014年9月に東北大学を退職したが,その時に送別会を催していただいた上に,パンデミック拡大直前の2020年2月にも同大学で筆者の研究に関連したシンポジウムを開いていただき(世話人は井龍康文・辻森樹両教授),遠来の著者を含む参加者の皆様に感謝している.しかしその後は,日本をはじめ世界の多くの国々で,1918年以来約百年ぶりの深刻なパンデミックにより約1年間で300万人以上(実はその数倍?)の人が死亡し,全人類の生活や仕事が激変していて,そもそも新型コロナ感染症で死亡する人とは,近親者による最後のお別れもできないという,心の奥の魂まで慟哭するような事態である.この場をお借りして,このパンデミックがワクチン接種の拡大により一刻も早く収束するよう,強く期待するとともに,本会会員の皆様のご健勝を心からお祈りする.(石渡 明)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】TOPIC 放射性物質を含んでいる福島県太田川河川敷で発見した黒砂中の磁性細菌
──────────────────────────────────
田崎和江(正会員)・横山明彦 (金沢大学理工研究域)・涌島英揮・石原牧子
2011年3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生し,地震と津波による被害が生じた.
さらに, 東京電力福島第一原子力発電所のある福島県では,原子炉の損傷により
放射性物質が飛散し,広範囲に被害が及んだ.2020年3月11日に福島県南相馬市
双葉町の避難困難区域は解除となったが,多くの住民は安心して帰宅することは
できず,いまだに不安を抱えている.
つづきはこちらから,,http://www.geosociety.jp/faq/content0968.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】支部情報
──────────────────────────────────
[中部支部]
・中部支部 2021年支部総会・年会・シンポジウム
6月26日(土)Zoomオンライン
講演申込・事前登録締切:6月18日(金)
シンポジウム「美濃帯の最近の研究事例」
総会に欠席される方は,必ず委任状等をご提出ください.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
地質学史懇話会<ハイブリッドに変更のお知らせ>
6月26 日(土)13:00(30分早くなっています)
場所:早稲田奉仕園セミナーハウス(東京都新宿区西早稲田2-3-1)
TEL: 03-3205-5411
オンラインのURLは6月20日以降,希望者に送ります.
矢島(pxi02070@nifty.com)までご連絡ください.
学術会議公開シンポジウム(オンライン)
「東日本大震災10年と史料保存−その取組と未来への継承−」
6月26日(土)13:30-17:30
参加費無料,定員:300人
要事前申込(どなたでも参加可)
http://www.scj.go.jp/ja/event/2021/311-s-0626.html
(後)第58回アイソトープ・放射線研究発表会
7月7日(水)-9日(金)
開催形態:オンライン開催
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2021/top
(後)科学教育研究協議会 第68回全国研究大会・福島大会
7月31日(土)-8月2日(月)
大会テーマ「自然科学をすべての国民のものに」
(注)Web大会に変更になりました
https://kakyokyo.org/
日本土壌肥料学会2021北海道大会
9月14日(火)〜16日(木)(オンライ大会)
※全面オンライン大会に変更
https://www.jssspn.org/2021/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・JAMSTEC海域地震火山部門地震発生帯研究センターポスドク公募(7/2)
・令和4年度科学技術分野の文部科学大臣表彰受賞候補者の推薦(学会締切7/2)
・藤原セミナー募集(2023年以降開催)(7/31)
・五島列島ジオパーク構想活動支援助成金(6/30)
・令和3年度 霧島ジオパーク学術研究支援補助金の募集(6/30)
・令和3年度阿蘇ジオパーク助成研究の公募(6/28)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】地質学雑誌127巻5号,一部不達・遅延のお詫び
─────────────────────────────────
6月上旬に発送となりました5月号の地質学雑誌(127巻5号)ですが,一部
の会員のかたへの送本が不達であったことが判明しました.
該当する会員に対しましては,昨日(6/14)雑誌およびニュース誌,
ジオルジュ2021年前期号を送本いたしました.
ご心配・ご迷惑をおかけしてしまいましたこと,お詫び申し上げます.
誠に申し訳ございません.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.522(臨時)第128年学術大会講演申込 間もなく締切です!(6/30;18時)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.522 2021/6/23 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】講演申込間もなく締切です!(6/30;18時締切)
【2】第128年学術大会(名古屋大会)の「ここがポイント!」
【3】大会参加登録の受付開始します
【4】誌面ブース出展のご案内
【5】トピックセッションT4招待講演者変更
【6】ジュニアセッション参加校募集中
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】講演申込間もなく締切です!(6/30;18時締切)
──────────────────────────────────
日本地質学会第128年学術大会(2021名古屋大会)での講演申込は,もうすぐ
締切です!期日までのお手続きをお願いいたします.
**********************************
演題登録・講演要旨申込締切:6月30日(水)18時
**********************************
今年の講演要旨は,演題登録システム上で,直接テキストを入力し,必要に応じて
図表(任意)をアップロードします.閲覧用のpdfファイルはシステム上で自動作成
されます.従来のようにA4サイズ1枚分の要旨PDFを作成いただく必要はありません.詳しくは大会サイトの講演申込のページをご参照ください.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/collectsubject
(注)これから地質学会へ入会される方へお伝えください!
講演申込と入会申込は並行して行ってください.入会手続(承認)が完了して
いなくても,講演申込操作は可能です.必ず締切までに講演申込を行って下さい.
ただし,講演申込締切時点で入会申込書が到着していない場合は,受付できません.どちらも急ぎお手続きください.
入会申し込み手続きについては,こちらから
http://www.geosociety.jp/outline/content0006.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第128年学術大会(名古屋大会)の「ここがポイント!」
──────────────────────────────────
皆様に「参加してよかった!」と思っていただけるように,日本地球惑星科学
連合(JpGU)2021年大会も参考にして鋭意準備しています.大会予告記事
(ニュース誌4月号)からの変更点も多いので,最新情報を大会ウェブサイト
で時々確認してください.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/top
1)日本地球惑星科学連合(JpGU)2021年大会の良かった点を可能な限り
取り入れます.
2)口頭発表でもe-poster発表でも,動画ファイルをConfitシステムにアップ
ロードして,会期前から参加者に視聴していただけます.例えば,e-posterで
発表を申し込み,発表の概要やシミュレーション結果なども動画に収録・アップ
ロードして,e-posterと動画を併用して動的・複合的プレゼンテーションを行う,
といった活用が可能です(e-posterでもプレレコ動画で口頭説明が可能).また,
口頭発表で申し込み,当日は時間の都合で説明し切れないと思われる内容を動画
に収録・アップロードして参加者に視聴していただく,といった活用も可能です.
使い方は発表者次第です.
3)e-posterでは十分な長さ(2〜3時間)のコアタイムを確保します.また,コア
タイムにはZoomブレイクアウトルームでの口頭ディスカッションもできるように
します.Confitシステムの文字チャット機能を使用した質疑応答は会期前から会期
後まで長期間可能にします(口頭発表も同様です).
4)懇親会・おしゃべり・打ち合わせなどに使用できる仮想空間システムを導入し
ます(JpGUの休憩スペースで使用されたoViceあるいは類似のシステム).会期中
自由に使用できるようにする予定です.口頭発表やe-posterコアタイムでの質疑
応答延長戦を行っていただいても構いません.
<参考>上記内容を含めた6/21開催のzoom説明会の内容は,YouTubeで公開中
です.ぜひ参考にしてください.https://youtu.be/RN-MbvbIHS0
<参考>e-posterについて(大会サイト)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/eposter
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】大会参加登録の受付を開始します
──────────────────────────────────
大会参加登録の受付を開始します.【大会参加登録締切:8月19日(木)】
大会専用参加登録システムへアクセスし,画面表示に従って入力して下さい.
申込締切後,プログラムへアクセスするためのログイン情報(ID/PW)をメール
でお知らせします.
参加費一例:
正会員:6,000円(発表する)・4,000円(発表しない)
院割会員:3,000円(発表する)・1,000円(発表しない)
(注)講演申込をされた方も別途必ず大会参加登録をして下さい.
大会参加登録はこちらから
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/sanka
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】誌面ブース出展のご案内──────────────────────────────────
展示ブースの代替として誌面ブースを実施いたします.
日本地質学会が「2021名古屋大会プログラム&誌面ブース」という冊子を
発行し,これを全ての大会参加者に郵送いたします.
配布対象者:学術大会参加申込み者(大学および研究機関の地質研究者,
地質技術者,自然博物館等の学芸員,ジオパークの地質専門員,理科教員,
一般など1,000名弱)
掲載料: 1ページ: 35,000円/見開き2ページ: 60,000円
冊子:A4サイズ,フルカラー印刷体,参加者へ郵送
申込締切:6月30日(水)
詳しくは,https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/tenji
このほかに,「Webを活用する業界サポートサービス〜地質系専門企業への
オンライン訪問〜」でも参加企業を募集しています.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/gyokai_support
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】トピックセッションT4招待講演者変更
──────────────────────────────────
トピックセッションT4「二次改変された過去の弧-海溝系の復元:日本および
その他の例」招待講演者一部変更
当初予定していた今岡照喜さん(山口大:会員)の招待講演は,ご本人の都合によりキャンセルとなり,山本啓司さん(鹿児島大:会員)に変更になりました.
招待講演者の紹介
http://www.geosociety.jp/science/content0135.html#t4
セッション概要
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/session
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】ジュニアセッション参加校募集中
──────────────────────────────────
第18回日本地質学会ジュニアセッション【参加申込締切:8/2(月)】
学術大会セッションと同様にe-posterによる発表です.審査もオンライン上で
行います.オンラインのため全国どこからでもご参加いただきやすくなって
います.
詳しくは,https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/gyoji#es
********************************************************************
「第128年学術大会(2021名古屋大会)サイト」
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.523 名古屋大会 参加登録を忘れずに!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.526 2021/7/6┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2021名古屋大会情報
【2】2021年度会費督促請求について
【3】支部情報
【4】原子力規制委員会福島第一原子力発電所事故10年動画
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2021名古屋大会情報
──────────────────────────────────
大会参加登録【参加申込締切:8/19(木)18:00】
(注)講演申込をされた方も別途必ず大会参加登録をして下さい.
(注)申込締切後,プログラムへアクセスするためのログイン情報
(ID/PW)をメールでお知らせします.入金確認が取れない場合は,
ログイン情報を発行できません.ご注意願います.
参加費
正会員: 発表する場合(6,000円)聴講のみ(4,000円)
院割会員:発表する場合(3,000円)聴講のみ(1,000円)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/sanka
「Webを活用する業界サポートサービス」参加企業募集中!
【参加申込締切:7/10】
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/gyokai_support
第18回日本地質学会ジュニアセッション 参加校募集中!
【参加申込締切:8/2(月)】
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/gyoji#es
このほか,名古屋大会の情報は随時大会サイトを更新しています.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2021年度会費督促請求について
──────────────────────────────────
1.督促請求のための自動引き落とし日は,6月23日(水)でした.
2021年度会費が未入金のかたで,1月-5月上旬までの間に自動引落の
手続きをされたかたは6月23日に引き落としがかかります.
引き落とし不備にならぬよう,残高の確認をお願いします.
2.郵便振替用紙によるお振り込みの方には,督促請求書(郵便振替用紙)
を郵送いたしました(6月中旬).早急にご送金くださいますようお願い
いたします.
※7月上旬頃までに入金確認が取れない場合には,7月号の雑誌から送本
停止となります.定期的に雑誌をお受け取りになりたい方は,お早めに
ご送金くださいますよう,よろしくお願いいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】支部情報
──────────────────────────────────
[北海道支部]
・北海道支部令和3年度総会・例会(個人講演会)
7月10日(土)
会場:オンライン開催(Zoomを使用)
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】原子力規制委員会福島第一原子力発電所事故10年動画
──────────────────────────────────
石渡 明(原子力規制委員会 委員)
東日本大震災の後、2011年4月5日、日本地質学会会長の宮下純夫氏は、「東日本大震災に関する地質学からの提言」*で、「超巨大地震と大津波による甚大な被害、原子力発電所の被災によって、日本はこれまでに経験したことのない困難な時期を迎えている」と述べ、同年5月21日の同学会「東日本大震災対応作業部会報告」**には、「このような未曽有の大災害を事前に予測し、被害を防ぐ、あるいは軽減することがなぜできなかったのかという反省や悔しさは学会員の共通の思いであり、それを今後の活動につなげていくことが求められている」との意志表明がある。
その後、原子力発電所の重大事故を繰り返さないために、2012年9月19日、「推進側」の経済産業省や文部科学省から独立した原子力規制委員会とその事務局の原子力規制庁が環境省の外局として設置された。その時は私が日本地質学会会長だったが、同委員会の求めに応じ、原子力発電所の敷地内破砕帯調査に当たる有識者を学会から推薦するとともに、有識者の評価書のピアレビュー会合の座長を務めるなどした。そして、2014年9月19日に私が同委員会の委員に就任し、その後約7年間、全国の原子力発電所や研究炉・核燃料施設などの新規制基準適合性審査やそれに関連する様々な業務に当たってきた。
今回、福島第一原子力発電所事故10年に当たり、原子力規制委員会・規制庁が作成した動画11本が公開された(各20〜60分程度)。これらは、事故の経緯、原因調査の現状、委員会設置の経緯、新規制基準、各委員の方針及び職員との対話、新検査制度等が内容である。特に、私と職員の対話の動画「現場に行って調べる」では、現地調査の映像を交えながら、露頭を直接調査することの重要性と必要な心構えや装備などについて述べられている。「未曽有の大災害」への「反省や悔しさ」を「今後の活動につなげていく」意志を貴学会の会員と共有している我々の活動をご覧いただき、今なお続く「日本がこれまでに経験したことのない困難な時期」を、共に克服していくための活力としていただければ幸いである。
動画視聴はこちらから,
https://www.nsr.go.jp/nra/kaiken/kunji20210311.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
情報計測オンラインセミナーシリーズ
数理・情報科学×計測科学の高度融合による新展開
主催:JST CREST・さきがけ研究領域"情報計測
第1回 6月26日(土)10:30-11:50
第2回 7月10日(土)10:30-11:50
以降、セミナー講演を多数回シリーズで引き続き開催予定
参加費無料,要事前参加登録
https://measurement-informatics-seminars.jp/
(後)第58回アイソトープ・放射線研究発表会
7月7日(水)-9日(金)
開催形態:オンライン開催
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2021/top
(後)科学教育研究協議会 第68回全国研究大会・福島大会
7月31日(土)-8月2日(月)
大会テーマ「自然科学をすべての国民のものに」
(注)Web大会に変更になりました
https://kakyokyo.org/
(共)2021年度日本地球化学会第68回年会
9月1日(水)-15日(水)討論実施期間
9月6日(月)-8日(水)Zoomセッション
9月7日(火)夜間集会
9月9日(木)総会・授賞式・受賞講演
9月9日(木)-10日(金)弘前セッション
9月21日(火)閉会式
(注)全面オンライン開催となった場合:9/6-10 Zoomセッション
場所:オンライン会場および弘前大学会場のハイブリッド開催
http://www.geochem.jp/meeting/
(後)第64回粘土科学討論会
9月14日(火)〜18 日(土)
(ポスター発表はリモートおよびオンデマンド方式)
会場:信州大学 長野(工学)キャンパス
http://www.cssj2.org/event/annual_meeting/
(後)藤原ナチュラルヒストリー振興財団
設立40周年記念公開シンポジウム
「海と地球の自然史−変わりゆく海洋環境から
海洋プラスックごみまで地球の問題を考える−」
10月24日(日)13:00〜17:00(予定)
形式:オンラインと会場のハイブリッド開催
場所:仙台国際センター
https://40th.fujiwara-nh.or.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0208.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・JAMSTEC Young Research Fellow 2022 公募(8/16;13時)
・兵庫県立大学環境人間学部 教員(教授または准教授)公募(8/30)
・兵庫県立大学自然・環境科学研究所地球科学研究部門(地質学)公募(8/25)
・東京大学地震研究所
---2021年度(第3回)大型計算機共同利用公募研究(7/30)
---特定機器(観測機器)22年度共同研究への貸出予約公募(7/30)
---22年度特定共同研究登録課題公募(7/30)
---22年度国際室外国人客員教員の推薦公募(地震火山および関連諸分野)(8/1)
・東レ科学技術賞・科学技術研究研究助成候補者募集(10/8締切;学会締切9/3)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.524(臨時)若手研究者必聴!第4回ショートコース(7/18開催)受講者募集中!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.524 2021/7/12┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】若手研究者必聴!第4回ショートコース(7/18開催)受講者募集中!
──────────────────────────────────
第4回ショートコースの受講者を追加募集中です.
地質学のあり方や論文を書くことの本質について考える絶好の機会です.
多くの皆様の受講をお待ちしています.特に学生及び若手研究者の皆様はぜひ
受講してください.また,大学・研究所等で研究室を主宰する,あるいは指導的
立場にある方は,お近くの学生・若手に情報をお伝えいただきますようお願い申
し上げます.(行事委員長・星 博幸)
********************
申込締切は7月15日(木)です。
********************
次のウェブサイトからお申し込みください.
http://www.geosociety.jp/science/content0134.html
********************
【開催概要】
日程:2021年7月18日(日)
<午前> 10:00-12:00
「吾書くゆえに吾あり:論文執筆についての超個人的視点」磯崎行雄(東京大学)
現代の科学者にとって論文公表は, 研究を継続する上で不可避である.しかし,
そもそも論文を書くことの本質が何であるのかを自ら問う機会は意外に少ない...
(中略)特に若い世代の研究者達が論文執筆の意味を再考する一助としたい.
(注)磯崎の「崎」の正しい表記は、「大」→「立」です.
<午後> 13:30-15:30
「地球科学の歴史から何を学ぶか」泊 次郎(科学史研究家)
私は地球科学の歴史を調べてきました.日本の地質学界では1980年代半ばまで
プレートテクトニクスが受け入れられなかったのはなぜなのか,日本では地震の
予知を目指して...(中略)地球科学や地球科学者のあり方について私見を述べる
予定です.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.525 2021名古屋大会情報(全体日程ほか)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.525 2021/7/20┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】【2021名古屋】全体日程を掲載しました
【2】【2021名古屋】大会参加登録を忘れずに!
【3】【2021名古屋】ジュニアセッション 参加校募集中!
【4】座談交流会 :ジェンダー・ダイバーシティ委員会Workshop
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】【2021名古屋】全体日程を掲載しました
──────────────────────────────────
大会全体日程をお知らせします.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/top
大きな注意点は以下の通りです.
・プログラムの調整により,会期が3日間に短縮になります(9/4−9/6)
・セッション開始時刻(口頭発表)は,8:00からとなります
・ポスターコアタイムは,夕方の時間帯になります
(9/4:16:30−19:00,9/6:16:00−18:30)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】【2021名古屋】大会参加登録を忘れずに!
──────────────────────────────────
大会参加申込締切:8/19(木)18:00
(注)講演申込をされた方も別途必ず大会参加登録をして下さい.
(注)申込締切後,プログラムへアクセスするためのログイン情報
(ID/PW)をメールでお知らせします.入金確認が取れない場合は,
ログイン情報を発行できません.ご注意願います.
参加費
正会員: 発表する場合(6,000円)聴講のみ(4,000円)
院割会員:発表する場合(3,000円)聴講のみ(1,000円)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/sanka
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】【2021名古屋】ジュニアセッション 参加校募集中!
──────────────────────────────────
【参加申込締切:8/2(月)】
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/gyoji#es
このほか,名古屋大会の情報は随時大会サイトを更新しています.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】座談交流会 :ジェンダー・ダイバーシティ委員会Workshop
──────────────────────────────────
座談交流会(ジェンダー・ダイバーシティ委員会Workshop)
「地質分野の多様性を増やすには:持続可能で闊達な学会を目指して」
日時:2021年8月1日(日)10:00-11:30
開催形式:遠隔開催(Zoom)
若手研究者や女性会員も含め多様な背景を持つ会員が、学会運営に携わる
理事達と学会に対する忌憚のない意見を交わし、学会の将来を模索します。
要事前申込・申込締切:7/29(木)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/engineer/content0059.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報
──────────────────────────────────
[北海道支部]
7/10開催された北海道支部令和3年度総会・例会(個人講演会)の
講演要旨を公開しています.
http://www.geosociety.jp/outline/content0023.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
石川町立歴史民俗資料館企画展
町民所有 石川町産鉱物展:我が家のお宝
7月31日(土)-10月3日(日)
観覧料無料・事前申込不要
石川町は「鉱物のまち」として全国的に知られており、石川地方からは150種類
以上の鉱物が確認され、石川町からは129種類と多くの鉱物が確認されています。
「我が家のお宝」を町民の皆様から募集し、このうち、石川町産の水晶、長石、
電気石、柘榴石等、約50点を展示します。
https://www.town.ishikawa.fukushima.jp/info/kikakuten_ishikawakoubutsu_3.pdf
------------------------------------------
(後)科学教育研究協議会 第68回全国研究大会・福島大会
7月31日(土)-8月2日(月)
大会テーマ「自然科学をすべての国民のものに」
(注)Web大会に変更になりました
https://kakyokyo.org/
地区防災計画学会シンポジウム(第37回研究会)
コロナ時代の避難の在り方―静岡県熱海市の土石流災害等を踏まえて―
8月21日(土) 13:00-15:30(予定)
※オンライン開催(YouTubeによる同時配信・再放送なし)
参加費無料・地区防災計画学会HPから申込必要
https://gakkai.chiku-bousai.jp/
(共)2021年度日本地球化学会第68回年会
9月1日(水)-15日(水)討論実施期間
9月6日(月)-8日(水)Zoomセッション
9月7日(火)夜間集会
9月9日(木)総会・授賞式・受賞講演
9月9日(木)-10日(金)弘前セッション
9月21日(火)閉会式
(注)全面オンライン開催となった場合:9/6-10 Zoomセッション
場所:オンライン会場および弘前大学会場のハイブリッド開催
http://www.geochem.jp/meeting/
(後)第64回粘土科学討論会
9月14日(火)〜18 日(土)
会場:信州大学 長野(工学)キャンパス
http://www.cssj2.org/event/annual_meeting/
国際ゴンドワナ研究連合(IAGR)2021年大会及び
第18回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム
9月17日(金)-19日(日)(会議)
9月20日(月)-21日(火)(野外巡検)
会場:中国青島
ファーストサーキュラー:
www.gondwanainst.org/symposium/2021/IAGR2021Invitation.htm
(注)中国国外の参加者については会議にはオンライン参加のみ、
20〜21日の野外巡検は中止となりました
(後)藤原ナチュラルヒストリー振興財団
設立40周年記念公開シンポジウム
「海と地球の自然史−変わりゆく海洋環境から
海洋プラスックごみまで地球の問題を考える−」
10月24日(日)13:00-17:00(予定)
[オンラインとハイブリッド]
場所:仙台国際センター
https://40th.fujiwara-nh.or.jp/
​​地質学史懇話会[オンラインとハイブリッド]
12月19日(日)13:30-16:30
場所:早稲田奉仕園(東京メトロ東西線早稲田駅下車徒歩5分)
青木滋之「ダーウィンと科学哲学 ―同時代、現代の視点から―」
加藤碵一「菜食主義とライマン・宮沢賢治余聞」
連絡先:矢島道子 pxi02070[at]nifty.com
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0221.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・農林水産省経験者採用試験:係長級(技術)(8/16)
・高知大学教育研究部自然科学系理工学部門(植物分類学分野)公募(8/16)
・令和3年度宮崎県教育委員会学芸員(地質他)採用選考試験実施(願書締切9/14)
・秋田大学大学院国際資源学研究科資源地球科学専攻教員公募(9/15)
・JAMSTEC海域地震火山部門 地震発生帯研究C 海底地質・地球物理研究G 研究員(9/15)
・令和3年度原子力人材育成等推進事業費補助金(8/16)
・第43回(令和3年度)沖縄研究奨励賞推薦(学会締切9/3)
・2022年日本アイソトープ協会奨励賞募集(10/29)
・第42回猿橋賞候補者推薦(11/30)
・2021年度「朝日賞」候補者推薦依頼(学会締切8/2)
・藤原NH振興財団 学術研究助成(非動物分野:地学・植物)(9/1)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.526(臨時)参加しましょう! 名古屋大会追加イベント
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.526 2021/7/27┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】参加しましょう! 2021名古屋大会追加イベント
【2】参加申込受付中!座談交流会 ジェンダー・ダイバーシティ委員会Workshop
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】【2021名古屋】参加しましょう! 名古屋大会追加イベント
──────────────────────────────────
2年ぶりの学術大会を大いに盛り上げるために,いくつかの追加イベントを開催
します。演題登録をしなかった・できなかった方にも「おもしろそう!参加したい!」
と思っていただけると思います。ぜひ参加登録してイベントに参加しましょう!
(日本地質学会行事委員長 星 博幸)
1)学生と駆け出し地質屋集合!アカデミックな情報交換を楽しむ会(事前申込要)
学生(学部生+院生)と駆け出し地質屋(ポスドク+新米社員+自分で駆け出し
と思っている人なら誰でも)にアカデミックな話題で楽しんでもらい,互いに
エンカレッジするのが目的のイベントです。
2)地質学露頭紹介(発表者は事前申込要)
多くの人に見てほしい,知ってほしい,議論したい「とっておきの露頭」の写真
を持ち寄り,その地質学的意味について解説・議論するイベントです。
3)ベテラン・シニア懇親会
コロナ禍で旧知の会員としばらく会えていないという方がほとんどだと思われ
ます。懇親会をしましょう! ベテラン・シニアに限らず誰でもご参加いた
だけます!
上記追加企画へ参加希望の場合は,別途大会参加登録も忘れずに行ってください.
詳しくは, https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/tsuika
大会HPはこちら: https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】参加申込受付中!座談交流会 ジェンダー・ダイバーシティ委員会Workshop
──────────────────────────────────
座談交流会(ジェンダー・ダイバーシティ委員会Workshop)
「地質分野の多様性を増やすには:持続可能で闊達な学会を目指して」
日時:2021年8月1日(日)10:00-11:30
開催形式:遠隔開催(Zoom)
若手研究者や女性会員も含め多様な背景を持つ会員が、学会運営に携わる
理事達と学会に対する忌憚のない意見を交わし、学会の将来を模索します。
*************************
要事前申込・申込締切:7/29(木)
*************************
詳しくは, http://www.geosociety.jp/engineer/content0059.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.527(臨時)ジュニアセッション締切延長(2021名古屋大会)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.527 2021/8/1┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】(2021名古屋大会)ジュニアセッションの締切を延長します
──────────────────────────────────
ジュニアセッションの締切を延長します.
*******************************
申込締切(延長):8月4日(水)
*******************************
*申込時には申込書式のみお送りください.
*e-poster投稿期間は8/10頃から8月下旬を予定しています.
コアタイムに相当する質疑応答は,システムのコメント機能を利用して行う予定
です.加えて,zoomブレイクウトルーム(ZBO)でのリアルタイムでの応対も
ご利用いただけます(任意).オンラインの特徴を活かして,ぜひ遠方からも
ご参加ください.お待ちしています!
申込書式など詳しくは,
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/gyoji#es
大会HPはこちら: https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.528 名古屋大会参加登録を忘れずに!(8/19締切)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.528 2021/8/3┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】【2021名古屋】全体日程を掲載しています
【2】【2021名古屋】大会参加登録を忘れずに!
【3】【2021名古屋】ジュニアセッション 参加校申込締切延長!
【4】【2021名古屋】参加しましょう! 名古屋大会追加イベント
【5】日本地質学会第5回ショートコース(予告)
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
【8】7月号冊子(ニュース・地質学雑誌)遅延のお詫び
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】【2021名古屋】全体日程を掲載しています
──────────────────────────────────
大会全体日程を大会HPに掲載しています.まもなく講演プログラムも公開予定
です.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/top
またニュース誌7月号が、まもなくお手元に届きます.こちらにも講演プログラム
が掲載されていますので、あわせてご確認下さい.
(注)今大会の大きな注意点は以下の通りです.
・プログラムの調整により,会期が3日間に短縮になります(9/4−9/6)
・セッション開始時刻(口頭発表)は,朝8:00からとなります
・ポスターコアタイムは,夕方の時間帯になります
(9/4:16:30−19:00,9/6:16:00−18:30)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】【2021名古屋】大会参加登録を忘れずに!
──────────────────────────────────
大会参加申込締切:8/19(木)18:00
********************************************
(注)必ず期日までに参加登録をしてください.当日受付はできません.
(注)講演申込をされた方も別途必ず大会参加登録をして下さい.
(注)申込締切後,プログラムへアクセスするためのログイン情報
(ID/PW)をメールでお知らせします.入金確認が取れない場合は,
ログイン情報を発行できません.ご注意願います.
参加費
正会員: 発表する場合(6,000円)聴講のみ(4,000円)
院割会員:発表する場合(3,000円)聴講のみ(1,000円)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/sanka
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】【2021名古屋】ジュニアセッション 参加校申込締切延長!
──────────────────────────────────
【締切延長:8/4(水)】
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/gyoji#es
このほか,名古屋大会の情報は随時大会サイトを更新しています.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】【2021名古屋】参加しましょう! 名古屋大会追加イベント
──────────────────────────────────
2年ぶりの学術大会を大いに盛り上げるために,いくつかの追加イベントを開催
します。演題登録をしなかった・できなかった方にも「おもしろそう!参加したい!」
と思っていただけると思います。ぜひ参加登録してイベントに参加しましょう!
(日本地質学会行事委員長 星 博幸)
1)学生と駆け出し地質屋集合!アカデミックな情報交換を楽しむ会(要申込)
学生(学部生+院生)と駆け出し地質屋(ポスドク+新米社員+自分で駆け出し
と思っている人なら誰でも)にアカデミックな話題で楽しんでもらい,互いに
エンカレッジするのが目的のイベントです。
2)地質学露頭紹介(発表者は要申込)
多くの人に見てほしい,知ってほしい,議論したい「とっておきの露頭」の写真
を持ち寄り,その地質学的意味について解説・議論するイベントです。
3)ベテラン・シニア懇親会(申込不要)
コロナ禍で旧知の会員としばらく会えていないという方がほとんどだと思われ
ます。懇親会をしましょう! ベテラン・シニアに限らず誰でもご参加いた
だけます!
上記追加企画へ参加希望の場合は,別途大会参加登録も忘れずに行ってください.
詳しくは, https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/tsuika
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】日本地質学会第5回ショートコース(予告)
──────────────────────────────────
日程:2021年10月3日(日)
[午前]応用地質学への招待:私の現場から+α:永田秀尚
[午後]GISとWebGISによるデジタル地質情報の利活用:宝田晋治
申込締切:2021年9月21日(火)*8月下旬より申込受付開始予定です.
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/science/content0137.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
地区防災計画学会シンポジウム(第37回研究会)
コロナ時代の避難の在り方―静岡県熱海市の土石流災害等を踏まえて―
8月21日(土) 13:00-15:30(予定)
※オンライン開催(YouTubeによる同時配信・再放送なし)
参加費無料・地区防災計画学会HPから申込必要
https://gakkai.chiku-bousai.jp/
(共)2021年度日本地球化学会第68回年会
9月1日(水)-15日(水)討論実施期間
9月6日(月)-8日(水)Zoomセッション
9月7日(火)夜間集会
9月9日(木)総会・授賞式・受賞講演
9月9日(木)-10日(金)弘前セッション
9月21日(火)閉会式
(注)全面オンライン開催となった場合:9/6-10 Zoomセッション
場所:オンライン会場および弘前大学会場のハイブリッド開催
http://www.geochem.jp/meeting/
日本鉱物科学会2021年年会・総会(ハイブリッド形式)
9月16日(木)-18日(土)
会場: 広島大学 東広島キャンパス
*口頭発表はZoom(現地の口頭発表もZoomへ接続),
ポスター発表はConfitのeポスターを予定.
https://confit.atlas.jp/guide/event/jams2021/top
(後)第64回粘土科学討論会
9月14日(火)-18 日(土)
会場:信州大学 長野(工学)キャンパス
http://www.cssj2.org/event/annual_meeting/
国際ゴンドワナ研究連合(IAGR)2021年大会及び
第18回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム
9月17日(金)-19日(日)(会議)
9月20日(月)-21日(火)(野外巡検)
会場:中国青島
ファーストサーキュラー:
www.gondwanainst.org/symposium/2021/IAGR2021Invitation.htm
(注)中国国外の参加者については会議にはオンライン参加のみ、
20〜21日の野外巡検は中止となりました
(後)藤原ナチュラルヒストリー振興財団
設立40周年記念公開シンポジウム
「海と地球の自然史−変わりゆく海洋環境から
海洋プラスックごみまで地球の問題を考える−」
10月24日(日)13:00-17:00(予定)
[オンラインとハイブリッド]
場所:仙台国際センター
https://40th.fujiwara-nh.or.jp/
​​地質学史懇話会[オンラインとハイブリッド]
12月19日(日)13:30-16:30
場所:早稲田奉仕園(東京メトロ東西線早稲田駅下車徒歩5分)
青木滋之「ダーウィンと科学哲学 ―同時代、現代の視点から―」
加藤碵一「菜食主義とライマン・宮沢賢治余聞」
連絡先:矢島道子 pxi02070[at]nifty.com
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0221.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・東京学芸大学テニュアトラック教員募集(岩石鉱物学、講師)(9/3)
・東京大学地震研究所衛星リモートセンシングに基づく火山学分野助教公募(10/29)
・東北大学大学院理学研究科地学専攻准教授公募(8/25)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】7月号冊子(ニュース・地質学雑誌)遅延のお詫び
──────────────────────────────────
ニュース誌編集作業の遅れのため、冊子発行が1週間程度遅延の見込みです。
ご迷惑をおかけし大変申し訳ありません。
なお、ニュース誌7月号は、9月学術大会のプログラム記事掲載号となっております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.529(臨時)【2021名古屋】追加イベントにご参加ください!(申込期限あり)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.529 2021/8/17┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】【2021名古屋】追加イベントにご参加ください!(申込期限あり)
──────────────────────────────────
2年ぶりの学術大会を大いに盛り上げるために,いくつかの追加イベントを開催
します。演題登録をしなかった・できなかった方にも「おもしろそう!参加した
い!」と思っていただけると思います。ぜひ参加登録してイベントに参加しま
しょう!
(日本地質学会 行事委員長 星 博幸)
********************************************
(1)学生と駆け出し地質屋集合!アカデミックな情報交換を楽しむ会
(要申込:期限 8/19)
********************************************
学生(学部生+院生)と駆け出し地質屋(ポスドク+新米社員+自分で駆け出しと
思っている人なら誰でも)にアカデミックな話題で楽しんでもらい,互いにエンカ
レッジするイベントです。普段あまり接することのない他機関・他分野の人と接す
ることでインスピレーションが得られると期待できます。これを機に新しい研究の
芽が出ることも期待できます。アカデミックな場では年齢や所属は関係ありませ
ん。モデレーターがいるので不安な方も大丈夫! 少しの勇気を出してぜひ参加
しましょう。研究発表を申し込まなかった学生・駆け出し地質屋も,大会参加
登録してこのイベントに参加すれば「地質学会おもしろい! 地質学会に出て
よかった!」と思っていただけるはずです。
********************************************
(2)地質学露頭紹介(発表者は要申込:期限 8/19)
********************************************
多くの人に見てほしい,知ってほしい,議論したい露頭写真を持ち寄り,その地質
学的意味について解説・議論するイベントです。露頭(写真)を見れば皆何か言い
たくなりますよね!
芸術性よりも地質学的な重要性やおもしろさを重視します。大会終了後,紹介した
内容(写真と簡単な解説)をニュース誌に記名記事として掲載する予定です。
地質学会ならではのイベント!露頭(写真)観察を楽しみましょう!
********************************************
(3)ベテラン・シニア懇親会(申込不要)
********************************************
コロナ禍で旧知の会員としばらく会えていないという方がほとんどだと思われま
す。懇親会をしましょう! ベテラン・シニアに限らず誰でもご参加いただけま
す! お手元に美味しい料理と飲み物を準備して,近況や思い出話などで存分に
楽しみましょう。
これらの追加イベントに参加希望の方は,別途大会参加登録も忘れずに行って
ください.(8/19締切)
申し込み等詳細は, 大会サイト「追加イベント」のページをご覧ください.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/tsuika
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.530 名古屋大会参加登録まもなく締切!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.530 2021/8/17┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】【2021名古屋】講演プログラム公開
【2】【2021名古屋】大会参加登録を忘れずに!
【3】【2021名古屋】発表者の皆様へ(重要)
【4】【2021名古屋】学生の皆様へ:WEBを活用する業界研究サポートサービス
【5】【2021名古屋】参加しましょう! 名古屋大会追加イベント
【6】【2021名古屋】oVice 懇親会開催します!
【7】日本地質学会第5回ショートコース(予告)
【8】全国大学院生協議会:アンケート協力依頼(大学院生対象)
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】【2021名古屋】講演プログラム公開
──────────────────────────────────
講演プログラムを大会HPで公開しました.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/top
(注)今大会の大きな注意点は以下の通りです.
・プログラムの調整により,会期が3日間に短縮になります(9/4−9/6)
・セッション開始時刻(口頭発表)は,朝8:00からとなります
・ポスターコアタイムは,夕方の時間帯になります
(9/4:16:30−19:00,9/6:16:00−18:30)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】【2021名古屋】大会参加登録を忘れずに!
──────────────────────────────────
大会参加申込締切:8/19(木)18:00
********************************************
(注)必ず期日までに参加登録をしてください。当日受付はできません。
(注)講演申込をされた方も別途必ず大会参加登録をして下さい.
(注)申込締切後,プログラムへアクセスするためのログイン情報
(ID/PW)をメールでお知らせします.入金確認が取れない場合は,
ログイン情報を発行できません.ご注意願います.
参加費
正会員: 発表する場合(6,000円)聴講のみ(4,000円)
院割会員:発表する場合(3,000円)聴講のみ(1,000円)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/sanka
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】【2021名古屋】発表者の皆様へ(重要)
──────────────────────────────────
<動画ファイルのアップロードが可能です>(口頭・ポスター発表とも)
任意,最大300MB,ファイル形式MP4,MOV,WMV,AVI.
実験やシミュレーションの動画を示したり,時間の都合で詳しく発表できないことを補足的に動画で説明したりするなど,動的・複合的な活用が可能です.
ぜひ有効にご利用ください.(8/27締切)
<e-poster投稿受付中です(ポスター発表)>(8/27締切)
8/27を過ぎるとアップロードできなくなるので(発表キャンセルになります),
この日まで必ずシステムにe-posterファイルをアップロードしてください。
詳しくは,https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/presen
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】【2021名古屋】学生の皆様へ:WEBを活用する業界研究サポートサービス
──────────────────────────────────
WEBを活用する業界研究サポートサービス:
地質系企業・団体へのオンライン訪問
学生会員へのサービスの一環として毎年開催される学術大会の会場において、学生会員が将来就職する可能性のある地質調査業、建設コンサルタント業をはじめとする地質系企業・団体との対面説明会を企画・開催しています.今年は,新型コロナウィルス感染症の影響により集会ができない状態ですので、WEBを活用して会場に赴くことなくしかも簡易に地質系企業・団体の業界研究をしていただける企画としました。なお、今回の企画では学会の学生会員だけではなく、非会員の大学生や高等専門学校生も対象としています。
オンライン訪問日時:9月5日(日)10:00〜15:00(終了は16:00予定)
**************************
申込締切:9月2日(木)
**************************
参加地質系企業・団体の紹介資料(動画等)を掲載しています.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/gyokai_support
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】【2021名古屋】参加しましょう! 名古屋大会追加イベント
──────────────────────────────────
2年ぶりの学術大会を大いに盛り上げるために,いくつかの追加イベントを開催します。演題登録をしなかった・できなかった方にも「おもしろそう!参加したい!」と思っていただけると思います。ぜひ参加登録してイベントに参加しましょう!(日本地質学会行事委員長 星 博幸)
(1)学生と駆け出し地質屋集合!アカデミックな情報交換を楽しむ会(要申込)
(2)地質学露頭紹介(発表者は要申込)
(3)ベテラン・シニア懇親会(申込不要)
上記追加企画へ参加希望の場合は,別途大会参加登録も忘れずに行ってください.
詳しくは, https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/tsuika
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】【2021名古屋】oVice懇親会開催します!
──────────────────────────────────
「oVice(https://ovice.in/ja/)」によるバーチャル空間を利用した,オンライン
懇親会を開催します.
参加費無料,事前申込不要です.(大会参加登録は必要です)
「懇親会」は2時間程度を予定していますが、時間制限はありませんので、
延長戦を存分にお楽しみください.
たくさんの方々,特に院生・学生などの若手会員のご参加をお待ちしています.
oViceご利用の際の注意点なども大会サイトでご案内しています.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/party
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】日本地質学会第5回ショートコース(予告)
──────────────────────────────────
日程:2021年10月3日(日)
[午前]応用地質学への招待:私の現場から+α:永田秀尚
[午後]GISとWebGISによるデジタル地質情報の利活用:宝田晋治
申込締切:2021年9月21日(火)*8月下旬より申込受付開始予定です.
詳しくは、
http://www.geosociety.jp/science/content0137.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】全国大学院生協議会:アンケート協力依頼(大学院生対象)
──────────────────────────────────
全国大学院生協議会からのアンケート協力依頼がありましたので,ご案内します.
***************************
大学院生のみなさま
突然のご連絡、失礼いたします。私たちは全国大学院生協議会(全院協)です。
この度は、大学院生を対象にしたアンケート調査にご協力いただきたく、ご連絡いたしました。
本調査は、全院協が、全国各大学の加盟院生協議会・自治会の協力の下に実施する、全国規模のアンケート調査です。本調査は、大学院生の研究及び生活実態を客観的に把握し、もってその向上に資する目的で行うものです。
全院協では2004年度以来毎年、アンケート調査を行っており、今年で17回目です。調査結果は「報告書」としてまとめており、こうした調査結果をもとに関連省庁、国会議員及び主要政党等に対して、学費値下げや奨学金の拡充などの要請を行っております。また、本調査により明らかになった大学院生の深刻な実態は、これまで、NHKや朝日新聞をはじめとした各種マスメディアでも取り上げられ、社会的に大きな反響を呼びました。
大学院生の奨学金借入、「500万円以上」が25%
朝日新聞 2014年11月27日 朝刊
全国大学院生協議会まとめ 大学院生、6割が経済不安
毎日新聞 2014年12月1日 朝刊
大学院生 バイトで研究に支障
NHK生活情報ブログ 2012年11月30日
http://www.nhk.or.jp/seikatsu-blog/800/139365.html
学費・奨学金等の重大な問題が存在するにも関わらず、大学院生の生活実態を詳細に明らかにする全国的な調査は、全院協以外では行なわれておりません。より多くの方々に回答いただき、調査の精度を高め、問題を広く社会に発信していくことの意義は今日一層高まっていると考えます。とりわけ今年度はコロナ禍が大学院生の研究生活にどのような影響を与えたかを測る上で、例年以上に重要な意義を帯びてくるのではないかと予測されます。ぜひご協力いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
本アンケート調査で得られた情報は、以上に述べた目的以外に使用されることはありません。また、個人が特定される形で調査結果をまとめることはありません。
回答はこちらから行うことができます。
―――――――――――――――――――――
【アンケート回答フォームURL】https://forms.gle/9GhLr3R2L6p6uWMv8
―――――――――――――――――――――
期限は【2021年9月30日】です。
お忙しいところ恐縮ですが、ご協力よろしくお願い致します。
全国大学院生協議会
〒186-0004 東京都国立市中2-1 一橋大学院生自治会室気付
電話・FAX:042-577-5679
E-mail:zeninkyo.jimu@gmail.com
Twitter:@zeninkyo
Facebook:https://www.facebook.com/zeninkyo/
Website:https://zeninkyo.org/(上記アンケートのURLが開けない場合はこちらから)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
地区防災計画学会シンポジウム(第37回研究会)
コロナ時代の避難の在り方―静岡県熱海市の土石流災害等を踏まえて―
8月21日(土) 13:00-15:30(予定)
※オンライン開催(YouTubeによる同時配信・再放送なし)
参加費無料・地区防災計画学会HPから申込必要
https://gakkai.chiku-bousai.jp/
(共)2021年度日本地球化学会第68回年会
9月1日(水)-15日(水)討論実施期間
9月6日(月)-8日(水)Zoomセッション
9月7日(火)夜間集会
9月9日(木)総会・授賞式・受賞講演
9月9日(木)-10日(金)弘前セッション
9月21日(火)閉会式
(注)全面オンライン開催となった場合:9/6-10 Zoomセッション
場所:オンライン会場および弘前大学会場のハイブリッド開催
http://www.geochem.jp/meeting/
日本科学協会主催セミナー:科学と芸術の交響、時空を超えた対話
9月3日(金)18:00-20:30
ハイブリッド配信
1)会場(港区赤坂1-2-2 日本財団ビル2階)
2)オンライン(Zoom Webinar使用)
参加費:無料(事前登録制)
https://www.jss.or.jp/ikusei/rinsetsu/arts/seminar.html
(後)第64回粘土科学討論会
9月14日(火)-18 日(土)
会場:信州大学 長野(工学)キャンパス
http://www.cssj2.org/event/annual_meeting/
(後)藤原ナチュラルヒストリー振興財団
設立40周年記念公開シンポジウム
「海と地球の自然史−変わりゆく海洋環境から
海洋プラスックごみまで地球の問題を考える−」
10月24日(日)13:00-17:00(予定)
[オンラインとハイブリッド]
場所:仙台国際センター
https://40th.fujiwara-nh.or.jp/
地質学史懇話会[オンラインとハイブリッド]
12月19日(日)13:30-16:30
場所:早稲田奉仕園(東京メトロ東西線早稲田駅下車徒歩5分)
青木滋之「ダーウィンと科学哲学 ―同時代、現代の視点から―」
加藤碵一「菜食主義とライマン・宮沢賢治余聞」
連絡先:矢島道子 pxi02070[at]nifty.com
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0221.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・令和3年度神奈川県(温泉地学研究所)職員選考採用(地質職)(8/27)
・2021年「海のフロンティアを拓く岡村健二賞」授賞候補募集(8/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.531 名古屋オンライン大会終了しました
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.531 2021/9/7┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】【2021名古屋】オンライン大会終了しました
【2】【2021名古屋】一部行事をYouTubeで公開しています
【3】【2021名古屋】講演要旨・e-poster閲覧について
【4】日本地質学会第5回ショートコース:申込受付中
【5】第14回日本地学オリンピックの参加申込開始
【6】地質学雑誌からのお知らせ
【7】支部情報
【8】全国大学院生協議会:アンケート協力依頼(大学院生対象)
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】【2021名古屋】オンライン大会終了しました
──────────────────────────────────
大会に参加してくださった会員の皆様に心よりお礼申し上げます。
----------------------------------
新型コロナウイルス感染症による未曾有の事態に2年以上にわたる準備期間を経て,お陰様で日本地質学会128年学術大会がオンライン開催として無事に滞りなく終了いたしました。大会実行委員会企画として開催した9月5日(日)の特別シンポジウムと市民講演会についても,ZoomとYoutTube配信を合わせて100名以上の皆様にご視聴いただくことができました。
今回,現地開催の無い名古屋大会となりましたが,名古屋近辺では日本の地質を見直すきっかけとなった美濃帯の中古生界,愛知県の石にも選定された師崎層群の深海性化石群を始め,多様な地質体を観察することができます。巡検会を開催できませんでしたが,現状が回復した暁には,地質学雑誌に掲載された巡検案内書とともに機会を見つけられて是非現地に足をお運びください。
大会実行委員会一同,128年学術大会に参加してくださった会員の皆様に心よりお礼申し上げます。
2021年9月7日
日本地質学会第128年学術大会実行委員会
委員長 大路樹生(名古屋大学博物館)
----------------------------------
来年は東京・早稲田大会でお待ちしています!
----------------------------------
2022年の地質学会 東京・早稲田大会のLOC大会委員長を仰せつかっています早稲田大学の高木です.
振り返りますと2017年以降,愛媛,札幌,そして山口大会では連続して学会の期間に大きな台風の影響を受けました.加えて札幌では地震にも見舞われ,私も被災者としての経験をもちました.名古屋大会では自然災害はないことを期待していましたが,まさかの新型コロナウイルスにより延期され,今年もオンライン学会となり,今年予定されていた東京・早稲田大会も1年延期されました.このコロナ禍がいつまで続くのか予断は許しませんが,来年度は対面の学会や巡検ができることを想定し,関東支部の幹事の皆様の全面的なご協力を得まして準備を進めているところです.
私が所属する教育学部の生物学教室が主体となる動物学会も地質学会同様1年延期となり,9月中ということで一緒に会場の先行予約をとることができ,地質学会は来年9月4日(日)から3日間で今年と同じ日程となります.会場は14号館にまとめ,地質情報展と市民講演会などは1984年に早稲田大学で地質学会を実施した15号館ロビーと教室を確保しています.なお,会場を予約・使用する条件として,教室の教員が所属する教育・総合科学学術院との共催とさせていただいていますので,よろしくお願いします.
巡検コースは関東支部が中心となって決定され,チバニアンなど新生界4コースやジオパーク巡検3コースを含む9つのコースが予定されています.
東京の大会としては2016年の日大から連続して私立大学での開催となりますが,桜上水大会以来の自然災害の影響のない大会となることを,強く願っています.withコロナとなる可能性は否定できませんが,皆様の積極的なご参加を,お待ちしています.
日本地質学会第129年学術大会実行委員会
委員長 高木秀雄(早稲田大学 教育・総合科学学術院)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】【2021名古屋】一部行事をYouTubeで公開しています
──────────────────────────────────
大会の中で開催された下記行事の模様は、YouTubeで動画を公開しています.
是非ご視聴ください(9/30まで限定公開のものあります.ご注意ください).
*2021年度顕彰式・表彰式・記念講演会(一定期間公開予定)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/ceremony
*市民講演会「動物の進化を探る〜古生物学の世界〜」(9/30まで限定公開)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/gyoji#koen
*特別シンポジウム:球状コンクリーションの科学(9/30まで限定公開)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/session#s1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】【2021名古屋】講演要旨・e-poster閲覧について
──────────────────────────────────
大会講演要旨・e-posterは,9月末まで(予定)大会参加者のみ閲覧可能です
(要参加者ログイン).講演要旨は,10月以降無料公開を予定しています.
e-posterの公開はありません.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】日本地質学会第5回ショートコース:申込受付中
──────────────────────────────────
今回は応用地質・地質調査業・GIS(地理情報システム)・デジタル地質情報
の利活用などについて学ぶ機会をご提供します.
日程:2021年10月3日(日)*zoomにるオンライン講義
[午前]応用地質学への招待:私の現場から+α:永田秀尚
[午後]GISとWebGISによるデジタル地質情報の利活用:宝田晋治
参加費(1日券):地質学会会員 2,000円
申込締切:2021年9月21日(火)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/science/content0137.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第14回日本地学オリンピックの参加申込開始
──────────────────────────────────
募集期間:2021年9月1日(水)-11月15日(月)
(一次予選)
日時:2021年12月19日(日)14:00-15:30(試験時間は1時間)
会場:受験者自宅等
方法:択一式オンライン試験(PC利用を推奨.ただしスマホでも可)
(二次予選)
日時:2022年1月23日 午後
会場:全国指定会場(札幌,仙台,東京,名古屋,大阪,広島,福岡等)
方法:マークシート式筆記試験
(本選)
日程:2022年3月13日(日)-15日(火)
会場:茨城県つくば市(「グランプリ地球にわくわく」として開催)
チラシPDFもダウンロードできます.
http://www.geosociety.jp/name/content0020.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質学雑誌からのお知らせ
──────────────────────────────────
不正二次利用防止のため、これまでJ-STAGE公開用PDFに保護をかけていました
が、データ活用の妨げになり不便とのご意見を多く頂いておりました。今後はセ
キュリティ保護を解除したPDFを公開します。なお過去分のPDFについても,解
除・差替の作業を順次進める予定ですが、費用・作業量等の都合で少々お時間を
頂戴いたします。ご了承ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[近畿支部]
近畿支部が協賛をする講習会が,以下のとおり行われます.
「地盤情報と地盤防災を学ぶー京都南部地域と木津川周辺を例にしてー」講習会
KG-NET・関西圏地盤研究会・一般社団法人関西地質調査業協会 共催
日本地質学会近畿支部ほか 協賛
9月30日(木)10:30-16:30
開催形式:オンライン会議(Zoom)
定員:200名
受講料:6,000円(税込)
詳しくは,https://www.kg-net2005.jp/index/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】全国大学院生協議会:アンケート協力依頼(大学院生対象)
──────────────────────────────────
全国大学院生協議会からのアンケート協力依頼がありましたので,ご案内します.(再掲)
***************************
学費・奨学金等の重大な問題が存在するにも関わらず、大学院生の生活実態を詳細に明らかにする全国的な調査は、全院協以外では行なわれておりません。より多くの方々に回答いただき、調査の精度を高め、問題を広く社会に発信していくことの意義は今日一層高まっていると考えます。とりわけ今年度はコロナ禍が大学院生の研究生活にどのような影響を与えたかを測る上で、例年以上に重要な意義を帯びてくるのではないかと予測されます。ぜひご協力いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
回答期限:9月30日(木)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/faq/content0979.html#insei
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(防災学術連携体)より「令和3年 豪雨・土砂災害について」
https://janet-dr.com/050_saigaiji/2021/050_202107_ooame.html
(JSECより)JSEC2021:第19回高校生・高専生科学技術チャレンジ
研究作品応募締切:10月4日(月)
https://manabu.asahi.com/jsec/
---------------------------------------
(共)2021年度日本地球化学会第68回年会
9月1日(水)-15日(水)討論実施期間
9月6日(月)-8日(水)Zoomセッション
9月7日(火)夜間集会
9月9日(木)総会・授賞式・受賞講演
9月9日(木)-10日(金)弘前セッション
9月21日(火)閉会式
http://www.geochem.jp/meeting/
(後)第64回粘土科学討論会
9月14日(火)-18 日(土)
会場:信州大学 長野(工学)キャンパス
http://www.cssj2.org/event/annual_meeting/
第31回地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン第1回目)
9月24日(金)18:30-20:30
内容:地質汚染調査・土壌汚染状況調査概論
講師:駒井 武(東北大学大学院教授)
受講方法:ZOOMによるオンライン
申込期限:2021年9月20日まで
受講料:無料
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
(後)藤原ナチュラルヒストリー振興財団
設立40周年記念公開シンポジウム
「海と地球の自然史−変わりゆく海洋環境から
海洋プラスックごみまで地球の問題を考える−」
10月24日(日)13:00-17:00(予定)
[オンラインとハイブリッド]
場所:仙台国際センター
https://40th.fujiwara-nh.or.jp/
(後)第31回社会地質学シンポジウム
11月26日(金)-27日(土)
オンライン開催
発表申込締切:9月30日(厳守)
https://www.jspmug.org/envgeo_sympo/31st_sympo/31st_sympo.html
地質学史懇話会[オンラインとハイブリッド]
12月19日(日)13:30-16:30
場所:早稲田奉仕園(東京メトロ東西線早稲田駅下車徒歩5分)
青木滋之「ダーウィンと科学哲学 ―同時代、現代の視点から―」
加藤碵一「菜食主義とライマン・宮沢賢治余聞」
連絡先:矢島道子 pxi02070[at]nifty.com
海と地球のシンポジウム2021
12月20日(月)-21日(火)
主催:AORI・JAMSTEC
開催方法:実会場とオンライン会場を使ったハイブリッド形式
※感染症の状況により変更・中止する場合があります.
発表課題募集締切:9月17日(金)
https://www.jamstec.go.jp/j/pr-event/ocean-and-earth2021/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0221.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・山梨県富士山科学研究所 任期付研究員募集(9/30)
・2022年度笹川科学研究助成募集(10/15)
・山田科学振興財団2022年度海外研究援助(10/31)
・科学技術振興機構令和3年度採択 日本-米国研究交流「災害レジリエンス」公募(9/27)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.532(臨時)地学オリンピック国際大会の結果 & IGCインドに関する注意喚起ほか
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.532 2021/9/15┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】第14回国際地学オリンピック・オンライン大会の結果
【2】IGCインドに関する注意喚起
【3】(もらってください)地質学雑誌バックナンバー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】第14回国際地学オリンピック・オンライン大会の結果
──────────────────────────────────
第14回国際地学オリンピック(オンライン大会・筆記試験)が8月25日より開催
され,日本代表4名の選手が素晴らしい成績をおさめました.
参加国数 / 人数:34か国・地域 / 185名
日本代表
孫 翰岳さん(筑波大学附属駒場高等学校2年)Excellent
岩崎野笑さん(神戸女学院高等学部3年)Very Good
佐藤弘康さん(栄東高等学校2年)Very Good
井上真一さん(灘高等学校2年)Good
※今年度は Excellent,Very Good,Good;のみが決定され,メダル授与ありません.
ただし、それぞれは従来の金メダル、銀メダル、銅メダルに相当します.
--------------------------------------
また,第14回日本地学オリンピックの参加申込も開始されています.
募集締切:11月15日(月)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/name/content0020.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】IGCインドに関する注意喚起
──────────────────────────────────
国際地質科学連合(IUGS)理事である北里 洋会員よりIGCインドに関する注意
喚起の情報をお寄せいただきましたので,地質学会会員の皆様にお知らせします.
*************************************
第36回万国地質学会(IGC)に参加申し込みされた皆さまへ
2020年3月にインド・デリーで開催予定であった第36回IGCは、コロナ感染の煽り
を受けて中止されました。LOCであるインド地質調査所では、後処理を進めてい
たようですが、この度10月31日をもって36回IGC事務局を閉鎖する旨のアナウンス
がされました。それに伴い、参加費の返却業務も終了するとのことです。まだ、
返却に向けた手続きをとっていらっしゃらない方は、以下の情報とともに、インド
地質調査所内36回IGC事務局、および事務局長宛にメール添付で手続きをとってい
ただければ幸いです。
返却請求をできるのはIGC登録料だけで、ホテル、航空運賃などはそれぞれの会社宛
に連絡してください。
1)Beneficiary Account No. (払戻を受けたい銀行口座番号)
2) Account Holders Name (口座名義人名)
3) Address of account holder (口座名義人住所)
4)Bank and Branch Names (銀行名、支店名)
5)Bank Branch Address (銀行支店住所)
6)Bank Swift code (スウィフト番号、8桁あるいは11桁の数字あるいは
アルファベット)
7)Bank IBAN (銀行のIBAN コード)
もしも、地銀、信用金庫に口座を持っている場合、State Bank of India とは直に取引
をしていない場合があります。その場合には、経由銀行を設定する必要があります
ので、取引銀行窓口で聞いてください。
*******************************
・払戻に関する情報:1)〜7)
・受取り証のコピー(36回IGCに参加登録し、登録料を支払ったという受取り証の
pdf を添付して申し込む必要があります)
を、36igc admin 36igc.admin@gsi.gov.in >;
Dr Ranjit Rath dr.ranjitrath@gmail.com > 宛に
【2021年10月31日まで】に送ってください。
この期限を過ぎますと払戻手続きに入れませんので、ご了解ください。
*******************************
わからない点がございましたら、北里 洋( hkitaz0@kaiyodai.ac.jp)宛に問い合わ
せていただければお答えいたします。ただ、銀行情報など個人情報の受け渡しの仲
介は致しませんので、その点はご理解ください。
また、地質学会以外の方で、IGCに参加登録された方をご存知でしたら、この情報
をシェアーしていただければ幸いです。
国際地質科学連合(IUGS) 財務担当執行理事
北里 洋 (東京海洋大学・早稲田大学)
Email: hkitaz0@kaiyodai.ac.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】(もらってください)地質学雑誌バックナンバー
──────────────────────────────────
地質学雑誌1巻からの寄贈の情報が寄せられました.学会ではすでに1巻1号の冊子
より所蔵しているため,お引き受けできかねます.どなたか雑誌を引き取りたい方
がおられましたら,直接担当者にお問い合わせください.
*******************************
日本地質学会会員の皆様
お茶の水女子大学(地理)の長谷川と申します.地質学雑誌と地学雑誌(訳あり)
をもらっていただける方を探しています.
大学附属図書館所蔵の地質学雑誌と地学雑誌がカビてしまい、大学でカビ除去の
ための予算がなく廃棄予定です.1800年代の第1巻からの貴重なものですので,
もし欲しいという方がおられましたら,【9月末までに】以下のe-mail宛に連絡を
いただけませんでしょうか?
なお,カビの状態ですが,知人の図書館司書に写真を見てもらったところ,アル
コールで取れるくらいとのことです.状態を確認したい方は,メールで写真をお
送りします.また,大学に検討してもらってはいますが,送る際に送料の負担が
できない可能性があり,着払いでの送付になる可能性があります.
雑誌の詳細は以下になります
タイトル(所蔵年次 )
1.地學雜誌(1889-2004)
https://www.lib.ocha.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/AN00322536
https://ci.nii.ac.jp/ncid/AN00322536
2.地質學雜誌(1893-2005)
https://www.lib.ocha.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/AN00141768
https://ci.nii.ac.jp/ncid/AN00141768
以上,ご検討をよろしくお願いいたします.
問い合わせ先:長谷川直子(お茶の水女子大学・地理)
e-mail:hasegawa.naoko@ocha.ac.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.533 第5回ショートコース:申込締切延長
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.533 2021/9/21┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】日本地質学会第5回ショートコース:申込締切延長
【2】【2021名古屋】一部行事YouTube公開中/要旨・e-posterの閲覧
【3】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【4】第14回日本地学オリンピックの参加申込受付中
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】日本地質学会第5回ショートコース:申込締切延長
──────────────────────────────────
***申込締切を延長いたします:9/24(金)***
今回は応用地質・地質調査業・GIS(地理情報システム)・デジタル地質情報
の利活用などについて学ぶ機会をご提供します.
日程:2021年10月3日(日)*zoomによるオンライン講義
[午前]応用地質学への招待:私の現場から+α:永田秀尚
[午後]GISとWebGISによるデジタル地質情報の利活用:宝田晋治
参加費(1日券):地質学会会員 2,000円
申込締切:9月24日(金)
(注)クレジット決済推奨.入金確認が取れない場合,zoomアクセス情報を
お知らせできません.銀行振込を選択する方は,即時入金をお願いいたします.
詳しくは、 http://www.geosociety.jp/science/content0137.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2021名古屋】一部行事YouTube公開中/要旨・e-posterの閲覧
──────────────────────────────────
■一部行事をYouTubeで公開中です.
是非ご視聴ください(9/30まで限定公開のものあります.ご注意ください).
*2021年度顕彰式・表彰式・記念講演会(一定期間公開予定)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/ceremony
*市民講演会「動物の進化を探る〜古生物学の世界〜」(9/30まで限定公開)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/gyoji#koen
*特別シンポジウム:球状コンクリーションの科学(9/30まで限定公開)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/static/session#s1
■大会講演要旨・e-posterは,9月末まで(予定)大会参加者のみ閲覧可能です
(要参加者ログイン).講演要旨は,10月以降無料公開を予定しています.
e-posterの公開はありません.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp128/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
127巻9月号(予告)「特集号:日本海拡大に関連したテクトニクス,堆積作用,
マグマ活動,古環境(その2)」
北陸地方における日本海拡大期火成活動の時空変遷:漸新世-中期中新世火山岩類
の層序,年代,岩石学的特徴:山田来樹ほか(総説)/プレート収れん速度の法則
(Otsuki, 1989)の更新:大槻憲四郎(論説)/青森県南部,湯ノ沢カルデラ噴出物
である尾開山凝灰岩の高精度・高確度噴出年代の決定:田口春那ほか(論説)/四国
北西部,中新統久万層群明神層に含まれる火成岩礫の起源:相田和之ほか(論説)
/貝形虫化石群集に基づく新潟県新津丘陵北部域の更新世の古環境変化」山田桂ほか
(論説)
■ Island Arc
・学会HP「会員ページ」からのIsland Arc無料閲覧へのアクセスにエラーが発生
しております.現在システム担当により,復旧作業中です.会員の皆様にはご迷惑
をおかけして,大変申し訳ありません.復旧まで今しばらくお待ちください.
(9/21, 18時現在)
・新しい論文等が公開されています.
A major change in magma sources in late Mesozoic active margin of the circum-Sea
of Japan domain: Nechaev, V. P., et al ほか
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14401738/0/ja
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第14回日本地学オリンピックの参加申込受付中
──────────────────────────────────
募集期間:2021年9月1日(水)-11月15日(月)
(一次予選)
日時:2021年12月19日(日)14:00-15:30(試験時間は1時間)
会場:受験者自宅等
方法:択一式オンライン試験(PC利用を推奨.ただしスマホでも可)
(二次予選)
日時:2022年1月23日 午後
会場:全国指定会場(札幌,仙台,東京,名古屋,大阪,広島,福岡等)
方法:マークシート式筆記試験
(本選)
日程:2022年3月13日(日)-15日(火)
会場:茨城県つくば市(「グランプリ地球にわくわく」として開催)
チラシPDFもダウンロードできます.
http://www.geosociety.jp/name/content0020.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報
──────────────────────────────────
[近畿支部]
近畿支部が協賛をする講習会が,以下のとおり行われます.
「地盤情報と地盤防災を学ぶー京都南部地域と木津川周辺を例にしてー」講習会
KG-NET・関西圏地盤研究会・一般社団法人関西地質調査業協会 共催
日本地質学会近畿支部ほか 協賛
9月30日(木)10:30-16:30
開催形式:オンライン会議(Zoom)
定員:200名
受講料:6,000円(税込)
詳しくは, https://www.kg-net2005.jp/index/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)藤原ナチュラルヒストリー振興財団
設立40周年記念公開シンポジウム
「海と地球の自然史−変わりゆく海洋環境から
海洋プラスックごみまで地球の問題を考える−」
10月24日(日)13:00-17:00(予定)
[オンラインとハイブリッド]
場所:仙台国際センター
https://40th.fujiwara-nh.or.jp/
2021年度 第2回地質調査研修(参加者募集中)
10月25日(月)- 29日(金)
場所:島根県出雲市長尾鼻周辺(小伊津海岸)
研修内容:室内で岩石の見方等を理解した上で、野外での地層・岩石の
観察ポイントからまとめまで、地質図を作成するための基本的事項を
5日間の研修で習得します。
定員:6名(定員になり次第締切),CPD:40単位
主催:産総研コンソーシアム「地質人材育成コンソーシアム」
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2021-2.html
(後)第31回社会地質学シンポジウム
11月26日(金)-27日(土)
オンライン開催
発表申込締切:9月30日(厳守)
https://www.jspmug.org/envgeo_sympo/31st_sympo/31st_sympo.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0221.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・名古屋大学大学院環境学研究科地球環境科学専攻 准教授公募(10/29)
・横浜国立大学大学院環境情報研究院自然環境と情報部門准教授又は講師公募(10/20)
・2022年度東京大学地震研究所共同利用(説明会開催)(10/5)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
中央構造線活断層系 川上断層の露頭
地学露頭紹介
※画像をクリックすると大きな画像をご覧いただけます
中央構造線活断層系 川上断層の露頭
窪田安打(応用地質)
露頭の場所:愛媛県西条市丹原町湯谷口・中山川河床
写真1 川上断層の露頭(2002年撮影).その後の河川浸食により,現在は露頭範囲が減少している.
概要:中央構造線( Median Tectonic Line: MTL)は西南日本の内帯と外帯を境する断層である.この中央構造線に平行に分布する活断層は中央構造線活断層系と呼ばれており,第四紀に右ずれ運動を生じている(岡田, 1972).愛媛県西条市丹原町湯谷口の中山川河床(北緯33度51分 21.66秒, 東経133度0 分45.81秒)には,中央構造線活断層系の川上断層がMTLより北側80 m付近に分布しており,両断層が連続露頭で観察できる貴重な露頭であるため,ここに紹介する.なお,本露頭は愛媛県指定天然記念物「衝上断層」に指定されているため,試料採取等の行為は許可が必要である
(1) 川上断層の露頭(写真1):上部白亜系和泉層群と鮮新統−中期更新統の岡村層相当の礫層(森野ほか, 2002)が断層 (N70 °–80°E 80°S–90°)で接しており,断層境界の南側には順に和泉層群起源の幅10 m程度の断層ガウジと幅70 m程度のカタクレーサイトが分布する.断層沿いの礫層には地層の引きずりや礫の長軸が断層面に平行にほぼ水平に配列する変形構造が認められる.断層境界から幅約3 mの断層ガウジには右ずれの複合面構造が認められるが,幅5 mより南側の範囲には左ずれ(北側上昇成分を伴う)の複合面構造が認められる.更に南側のカタクレーサイトには,和泉層群の引きずり褶曲や左ずれセンスのせん断面が発達する.このせん断面の一部には右ずれの変形が重複して発達する.以上の地質構造に基づくと,川上断層は左ずれ断層により幅広い破砕帯を形成した後,第四紀に右ずれ断層として活動したと考えられる(Kubota et al., 2020).
写真2 中央構造線の露頭(中山川の右岸側).
(2)中央構造線の露頭(写真2):本露頭のMTLは外帯の三波川結晶片岩類と内帯の和泉層群の境界断層(N80°W 35°N)である.境界には幅4-5 m程度の泥質片岩が著しく破砕されたカタクレーサイトが分布しており(Fig. 2のB, C),中期中新世の岩脈が貫入している.このカタクレーサイトには和泉層群の砂岩片も取り込まれており,両者が接触した関係で破砕されたことを示している(Fig. 2のB).このカタクレーサイトには,Top-to-the-Northの正断層を示す複合面構造が顕著に発達するが,更にNW-SE方向の軸を持つ褶曲構造が重複して分布する.研磨片・薄片の観察の結果,Top-to-the-Northの正断層後に,Top-to-the-SWの左ずれ逆断層が生じたことが判った.Kubota et al.(2020)は,断層ガウジの年代測定等により,両断層運動は和泉層群と三波川帯が接合した市之川フェーズ(59 Ma)と先砥部フェーズ(47-46 Ma)の運動であると示した.
文献:Kubota et al., 2020, Tectonics, 39, e2018TC005372.;森野道夫ほか, 2002, 地質学雑誌, 108, Ⅲ-Ⅳ;岡田篤正, 1972, 愛知県立大文学部論集, 23, 68-94.
2021.10.25掲載
<目次へ戻る
次の露頭へ>
変形構造から読み解くテクトニクス
地学露頭紹介
※画像をクリックすると大きな画像をご覧いただけます
変形構造から読み解くテクトニクス
竹下 徹(北海道大)
図1 新居浜市付近の三波川変成岩中に形成されたD2正断層.本正断層はほぼ垂直で現在の姿勢では横ずれ断層と見なされるが,D3褶曲をもとに戻すと正断層となる.
今回の地質学露頭紹介では「変形構造から読み解くテクトニクス」と題して,短縮と伸張テクトニクスを示す地質構造の露頭の例を紹介した.実際には露頭に現れている短縮テクトニクスを示す地質構造を1つ,伸張テクトニクスを示す地質構造を2つ紹介した.伸張テクトニクスを示す1つの地質構造は,その露頭写真が構造地質部会が作成した『日本の地質構造100選』 (朝倉書店)に掲載されている.また,そのWEB写真集(リンクはこちら)に,短縮テクトニクスを示す地質構造は掲載されている.短縮テクトニクスを示す地質構造は,島根県大社町の大社漁港付近の海岸沿いに位置する.ここは,出雲大社や島根ワイナリーの近くでアクセスが良く,巡検に適している.短縮テクトニクスは,日本海拡大時最盛期に堆積した成相寺層(17.75 Maの有孔虫年代が得られている;野村ほか, 2018, 地質雑)の転倒褶曲構造とそれを切断する逆断層で示され,宍道褶曲帯(例えば,鹿野ほか,1998, 大社地域の地質,5万分の1地質図幅)の一部を構成する.この露頭の成相寺層は良く成層した流紋岩質の凝灰岩で構成され,逆断層部で地層は逆転している.したがって,この転倒褶 曲構造・逆断層は日本海拡大後のインバージョンテクトニクスを示す.なお,この大社漁港付近の露頭を含んで,周囲の地質および露頭は島根大学大学院教育学研究科(当時)の成相俊之氏が作成されたホームページ( 出雲の地質:リンクはこちら)に大変詳しく纏められている.
一方,伸張テクトニクスを示す地質構造については,紹介者が長年研究して来た四国中央部新居浜市付近の三波川変成岩上昇時のそれを示す露頭を紹介した.最初の露頭は国領川沿いの露頭で,既に『日本の地質構造100選』に報告したものである.三波川変成岩は上昇時に最初は流動変形を被ったが,脆性―塑 性転移を越えてさらに上昇した時,正断層形成による伸張テクトニクスを被った(e.g., El-Fakharani and Takeshita, 2008). この露頭は伸張デユープレックス(extensional duplex, https://kotobank.jp/word/伸張デュープレックス-1547364,村田明広氏による)と呼べる構造を示すが,上下をルーフおよびフロアー正断層に挟まれ,その間でレイヤーが数多くの小正断層で切られている.薄片スケールのシェアバンドと同一の構造である.ここでは,ルーフ正断層に沿って厚さ15 cmの石灰岩レイヤーが存在する.最後の露頭写真(図1)は流動変形を伴う正断層を示し,脆性―塑性転移の条件(温度約300℃)で形成されたと推察される.変成した砂岩レイヤーが断層によってドラッグされ,著しく薄化していることに注目して欲しい.
2021.10.25掲載
<目次へ戻る
次の露頭へ>
関東山地北部秩父帯のF1褶曲と変成縞
地学露頭紹介
※画像をクリックすると大きな画像をご覧いただけます
関東山地北部秩父帯の褶曲と変成縞
清水以知子(京都大学)
写真1 褶曲軸部の露頭写真(吉田鎮男氏提供).左側の黒色の泥岩 を主とする互層には級化層理がみられる.右側の珪質層には縞状構 造が発達する.
写真2 珪質層にみられる変成縞のクローズアップ.
関東山地の北部秩父帯のジュラ紀付加コンプレックスは,三波川変成帯の弱変成部とみなされる前期白亜紀の変成作用と延性変形を受けている(Shimizu, 1988, 地質雑;Shimizu and Yoshida, 2004, Island Arc).写真1は群馬県神流町(旧・万場町)の神流川沿いに露出する柏木ユニットの褶曲露頭であり,砂岩・泥岩・酸性凝灰岩互層が大きく曲げられている.水平に近い褶曲軸面に平行に発達する劈開は,顕微鏡下ではイライトや緑泥石の定向 配列による片理面(S1)によって形づくられていることが確認できる.したがって,褶曲は変成ピーク時に片理と同時に形成されたもの(F1褶曲)ということができる.三波川帯や北部秩父帯には片理形成後の褶曲(F2褶曲)は数多く見られるが,F1褶曲は稀であり,この大きさのものはこの露頭でしか確認されていない.褶曲軸部では片理面S1と層理面(S0)が大きく斜交し(写真1),酸性凝灰岩ないし凝灰質砂岩よりなる珪質層には,5 mm程度の間隔でリズミックな縞状構造が発達する(写真2).このことから,縞状構造は初生の堆積構造とは関係なく,変成・変形作用によって形成されたことがわかる.鏡下の観察では縞状構造の暗色部に圧力溶解シームが密に発達しており(Shimizu, 1988, Plate I-4),圧力溶解-沈殿作用によるシリカの移動が変成縞形成の素過程であったと推察される.このように変成分離作用のみによって形成されたことがわかる肉眼的にも明瞭な縞状構造は珍しく,学術的にも大変貴重な露頭である.
2021.10.25掲載,10.28一部修正
<目次へ戻る
次の露頭へ>
蛇紋岩メランジュの蛇紋岩露頭
地学露頭紹介
※画像をクリックすると大きな画像をご覧いただけます
蛇紋岩メランジュの蛇紋岩露頭
辻森 樹(東北大学)
中国山地中央部大佐山蛇紋岩メランジュ(OSM)の蛇紋岩マトリクス中の蛇紋岩ブロックの産状の写真を紹介した。近年、スラブ及び含水ウェッジマントル内部の元素の挙動について、天然試料の岩石学・地球化学と実験岩石学双方のアプローチから素過程を理解する試みがなされている。例えば、ホウ素(10B・11B)は11Bが選択的に液相に移動し、脱水反応によってスラブのB同位体比は軽くなることが知られている。Yamada, Tsujimori et al. (2019a) Lithos は、Martin et al. (2016) Geologyの局所B同位体比(δ11B)分析による蛇紋岩の構造場識別の先駆的な試みを完全に支持する結果を北米フランシスカン帯の蛇紋岩の研究で得て、地球化学モデリングによってスラブ脱水による含水マントルウェッジのB同位体比の空間変化傾向を予測した。さらに、自ら提案した蛇紋岩のB同位体比傾向(高圧変成蛇紋岩のδ11B値は+10‰より小さい)を蓮華帯糸魚川地域の蛇紋岩で検証・確認した後(Yamada, Tsujimori et al. 2019b JMPS)、OSMの蛇紋岩メランジュ内のB同位体比マッピング(アイソスケープ)を試みた(Tsujimori, Yamada et al. 2021 地質学会演旨)。OSMは古生代前期の大江山オフィオライト構成岩及びひすい輝石岩と約3.5億年前の蓮華変成岩が構造的に混合した蛇紋岩メランジュである(Tsujimori 1997 Min.Mag.、辻森 1999 地質雑、Tsujimori and Itaya 1999 IAR、Tsujimori and Liou 2005 IGRなど)。メランジュマトリクスには蛇紋岩化を免れた初生的なマントル鉱物を比較的保存した塊状の蛇紋岩も含まれるが、クロムスピネル残晶の化学組成傾向、含Na透閃石の分布、蛇紋石鉱物の組み合わせで明瞭に両者を識別することはできなかった。ところが、それらのB同位体比と微量元素のマッピングによって、高圧変成作用に関係したスラブ流体の影響を被った低(軽い)δ11B蛇紋岩とそうではない高(重い)δ11B蛇紋岩に識別が可能であることが分かった。この露頭写真の塊状の蛇紋岩は後者に相当し、高δ11B蛇紋岩の分布は地質図スケールでマッピングできる。
2021.10.25掲載
<目次へ戻る
次の露頭へ>
カナダWawa地区の縞状鉄鉱層
地学露頭紹介
※画像をクリックすると大きな画像をご覧いただけます
Wawaの縞状鉄鉱層
大久保英彦(スターミネラルズジャパン)
写真1 縞状鉄鉱層の露頭.左から,淡褐色チャート層,磁鉄鉱を 含む淡灰色チャート層,褶曲した淡褐色チャート層.
写真2 露頭上部の厚い磁鉄鉱層と炭酸塩岩や珪酸塩岩の多様な縞 模様を見せる磁鉄鉱.
【露頭の位置】District of Algoma Province, Ontario, Canada.スペリオル湖東岸のMichipicoten Bayの南東側.トランスカナダハイウエイHWY17をWawaの町から11.1 km南下した場所. 北西にはBridget Lake,南東にはAntoine Lakeがある. 47°53’44.5”N 84°50’48.5”W をグーグルマップで検索し, 場所が表示されたらストリートビューにすると,道路の東側の露頭を見ることができる.
【地質学的背景・意義】Superior Province (3100–2500 Ma)の Wawa Subprovince: Wawa Neoarchean (2750 Ma) に属する, Michipicoten Greenstone Belt( 2750–2735 Ma)地域.Greenstone Beltの上の始生代アルゴマ型縞状鉄鉱層が容易に観察できる.北東に世界最大級のAbitibi Greenstone Belt(2800–2600 Ma)があり,Greenstone Beltと火成複合岩体を調べることは大変 面白い.
【露頭の概況】HWY17の東側に幅100 m,高さ4〜1.2 mに渡っ て露頭があり,右から左(SW–NE)に傾斜している.ここに至る道路の左右には輝緑岩の露頭が続き,グリーンストーンベルト帯であることがわかる.輝緑岩の上に縞状鉄鉱層があり,露頭を登ると最上部は磁鉄鉱層が縞模様を見せて広がっている.道路と同方向に滑らかな垂直な断面と,破壊されて凸凹になった部分がある.
【層序】下部,中部A,中部Bは写真1を,上部は写真2を参照. 下部: 変質した苦鉄質火山岩の輝緑岩(diabase) = Michipicoten Greenstone Belt.露頭での層厚は約3 m〜1 m. 中部A:褶曲が顕著で青みを帯びた磁鉄鉱層を含む淡灰色チャ ート層.磁鉄鉱層は5 mmから30 cm.層厚約1 m. 中部B:褶曲が緩やかな淡褐色チャート層.層厚約1 m.菱鉄鉱(siderite: FeCO3)と思われる濃赤色の層(約10 cm)がある.上部:露頭の上は青みを帯びた黒色の磁鉄鉱層が一面に広がる. 層厚約50 cm.7万年前に北東から,2万年前に東南東から二度の氷河が流れ,上部が約1000 m程度削られている.磁鉄鉱層の起伏には細い珪酸塩岩や炭酸塩岩を含む磁鉄鉱の同心楕円状の模様があり,起伏の方向と氷河と共に移動した石の傷跡で氷河が流れた方向がわかる.アルゴマ型縞状鉄鉱層は小規模だが,オンタリオ州には火成複合岩体と関連するGreenstone Beltが数多く存在し,氷河の痕跡と合わせてカナダの地質時代の大きなイベントが残り,大変興味深い.なお,次のウェヴサイト(https://star-minerals.com/cell/?p=15)にWawaの縞状鉄鉱層の露頭や採集した岩石の写真を載せてある.
(文献) Eyles, N., 2002, Ontario Rocks: Three Billion Years of Environmental Change. ISBN 1550416197. Eyles, N. and Miall, A., 2007, Canada Rocks: The Geologic Journey. ISBN 1550418602. Morris, T.F. et al., 1994, Ontario Geological Survey, Open File Report 5908.
2021.10.25掲載
<目次へ戻る
次の露頭へ>
アイスランドの溶岩断面
地学露頭紹介
※画像をクリックすると大きな画像をご覧いただけます
アイスランドの溶岩断面
星 博幸(愛知教育大)
アイスランド西部,ルンダールハルス地域のガリーに露出する溶岩シーケンス.
筆者は日本学術振興会の二国間交流事業共同研究・セミナー及び国際共同研究加速基金国際共同研究強化(B)の支援を受け(いずれも代表者は山本裕二・高知大学教授),2018年から毎年アイスランドで地質調査をしている(ただし2020年と2021年はCOVID-19パンデミックにより渡航できなかった)この研究の目的は,地磁気の逆転頻度と地磁気平均強度との間に関連性があるという仮説(Aubert et al., 2010)を検証することである.この検証には質・量とも十分な古地磁気データが必要であり,筆者らは手始めにアイスランド西部のルンダールハルス(Lundarháls)地域の鮮新世玄武岩溶岩シーケンスを対象として研究に取り組んでいる.この研究で筆者は地質マッピングによる岩相層序記載と地質構造調査,及び岩石サンプリングを担 当している.ルンダールハルス地域の古地磁気研究の概要については星ほか(2019)が紹介している.写真はルンダールハルス地域のガリー(gully)に露出している溶岩シーケンスの断面である.多数のアア溶岩とパホイホイ溶岩が累重している.この写真中の溶岩は厚さ数mのものが多い.溶岩と溶岩の間に厚さ数cm〜数mの赤褐色〜黄褐色堆積物が挟まることが多いが,複数のパホイホイ溶岩(溶岩ローブ)が堆積物を欠いて連続的に重なることもある.調査セクションに認められるすべての溶岩からサンプルを採取するため,溶岩を見逃さないように慎重に調査・記載する.また,この写真には写っていないが岩脈とシルが貫入していることもあり,それらの識別も重要である.アイスランドは一般に植生が貧弱なので岩石の露出が良好である.日本のフィールドで露頭探しに苦労することの多い地質屋にとって,アイスランドはパラダイスである.ただし物価は決して安くないので,調査を計画する際には注意を要する.
(文献) Aubert et al., 2010, Space Sci. Rev., 155, 337–370. 星ほか, 2019, 地質学会第126年大会演旨, 569.
2021.10.25掲載
<目次へ戻る
次の露頭へ>
香川県庄内半島に見られる花崗岩境界
地学露頭紹介
※画像をクリックすると大きな画像をご覧いただけます
香川県荘内半島に見られる花崗岩境界
下岡和也(愛媛大学・院生)
白亜紀の環太平洋地域では,「フレアアップ」と呼ばれる地殻中へのマグマのインプットが異常に増加する時期が存在した.フレアアップ期の火成活動は,地殻中に巨大バソリス,地上に大規模カルデラを形成し(deSilva et al. 2015, Elements),大陸地殻の成長プロセスを解明するため鍵であると考えられている.中央構造線以北から山陰地域にかけて分布する西南日本の白亜紀花崗岩もこのフレアアップイベントによって形成されたと考えられている(例えば,Takatsuka et al. 2018, Lithos).荘内半島は,香川県三豊市に属する半島で,大部分が白亜紀フレアアップ期の花崗岩を主体とする深成岩からなる.この地域は,他の白亜紀花崗岩地域と比較すると,苦鉄質岩脈や苦鉄質火成包有岩(Mafic Magmatic Enclaves: MME)を多く産する.近年の研究から,これらの苦鉄質岩類と花崗岩とは成因的に関連性があると示されている(例えば,中島 2018, 地質学雑誌). このことから,筆者は,荘内半島の深成岩によりフレアアップ期の火成作用の機序を議論できると考え研究を進めている. 今回紹介する花崗岩境界は,荘内半島先端の三崎灯台から海岸線へと降りて,東に1.2 km程度歩いた地点(北緯34度15分51.0 秒,東経133度33分59.1秒)にて観察できる.写真中では,中央部横方向に粗粒花崗岩(下)と細粒花崗岩(上)の境界が確認できる.粗粒花崗岩は塊状均質な産状であるが,細粒花崗岩はMME(黒色ツブツブ)を多量に産し,しばしば変成岩捕獲岩(画面中央シマシマ)を含む.MMEはその形態や鏡下での特徴から花崗岩質マグマとマグマの状態で共存し形成されたと考えられる.露頭産状による前後関係から,粗粒花崗岩に対して細 粒花崗岩が貫入している.このことは,単調な花崗岩形成から,苦鉄質岩を伴うドラマチックな花崗岩形成へとマグマ溜まり内の様相が変化していることを示唆する.地殻中の熱的・化学的特徴の変化が妄想できる花崗岩境界,是非お立ち寄りください!(干満表読み間違えると瀬戸内海の荒波に揉みくちゃにされます.ランチと飲み物もお忘れなく!)
2021.10.25掲載
<目次へ戻る
次の露頭へ>
河川堆積物に見られるHCSのような構造
地学露頭紹介
※画像をクリックすると大きな画像をご覧いただけます
河川堆積物に見られるHCSのような構造
小松原純子(産総研)
野島層群大屋層の河川流路堆積物中に見られる斜交層理
長崎県佐世保市小佐々町楠泊の海岸に露出している前期中新世野島層群大屋層の河川流路堆積物上部には,ハンモック状斜交層理(HCS)のような低角で比較的波長の長い斜交層理が見られる(小松原ほか, 2003).HCSは一般に荒天時に海底で形成されると考えられており,晴天時波浪限界以下で保存されたものが地層として残る(Harms et al., 1975).堆積環境と堆積構造の不一致が気になっており今回写真を紹介したところ,アンチデューンもしくはHCS-mimicsではないかというコメントをいただいた.HCS-mimicsはアンチデューンとして形成された,HCSによく似た構造のことである(増田ほか, 1993).いずれも高流領域で形成され,陸上の洪水堆積物からも報告がある.今回の構造はこれらである可能性が高いと考えられる.
(文献) Harms J. C., et al., 1975, SEPM Short Course no. 2, 161p. 小松原純子ほか, 2003,地質学雑誌, 109, 20-29. 増田富士雄ほか, 1993, 堆積学研究会報, no. 39, 27-34.
2021.10.25掲載
<目次へ戻る
【geo-Flash】No.534 2022年度の新しい表彰体系について
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.534 2021/10/5┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2022年度の新しい表彰体系について
【2】2022年度学会各賞候補者募集開始(12/1締切)
【3】地質系若者のためのキャリアビジョン誌(2021版)協賛(原稿掲載)募集
【4】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2022年度の新しい表彰体系について
──────────────────────────────────
日本地質学会では,これまでに会員・非会員の表彰を永年行ってきました.
しかし,21世紀に入ってはや20年が経過し,現代的な学会動向の観点から
眺めた際に,これまでの伝統的な体系だけでは必ずしも十分に表彰しきれて
いなかった点が見えてきました.そこで,現在の学会執行部のなかで議論し,
またその原案について理事会・総会でご紹介・ご承認をいただいて,2020-
2021年度に賞体系を大幅に変更しました.その中では,従来よりも賞の数を
増やし,多様な年齢層の会員に対して満遍なく表彰の対象となっていただけ
るように配慮し,またそのための学会規則の変更を行いました.
続きはこちらから,,, http://www.geosociety.jp/outline/content0227.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2022年度学会各賞候補者募集開始(12/1締切)
──────────────────────────────────
日本地質学会では今年も運営規則第16 条および各賞選考規則にした
がい,賞の候補者を募集いたします.応募書式は準備でき次第、HPに
掲載いたします.また,ご応募いただいた場合には,必ず受け取りの
お返事をお出ししますのでご確認ください.
*********************************************
応募締切:2021年12月1日(水)必着
*********************************************
詳しくは, http://sub.geosociety.jp/members/content0098.html
(会員ページへのログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】地質系若者のためのキャリアビジョン誌(2021版)協賛(原稿掲載)募集
──────────────────────────────────
日本地質学会は、昨年度から地質学を専攻とする若者に専門職の魅力を伝えるため
の情報誌「地質系若者のためのキャリアビジョン誌」を刊行・配布を開始いたしま
した.各大学では、この冊子をキャリア教育の教材と活用頂き、そして多くの学生・
院生から専門職を知る機会になったとの声を頂いております.本年も「地質系若者の
ためのキャリアビジョン誌」を発行・配布する予定です.本冊子への協賛と原稿提供
をご検討頂けますと幸甚でございます.
編集協賛費: 3万円(日本地質学会賛助会員は 1 掲載地区分無料)
原稿:A4縦,カラー,自由デザイン,PDF 形式,各社 1 ページスペース
申込締切:10 月 31 日(日)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/engineer/content0003.html#1-5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
来年1月からの完全電子化への準備は進みつつあります.9/11の日本地質学会理事会で,
地質学雑誌電子版投稿編集出版規則の内容が審議されました.現行の規則からあまり
大きく変えないように心掛けました.主要な変更点について,お知らせいたします.
続きはこちら,,, http://www.geosociety.jp/publication/content0099.html
■ Island Arc
[復旧しました]9/21頃-9/28まで学会HP「会員ページ」からのIsland Arc無料閲覧
へのアクセスにエラーが発生しておりました.現在は復旧しております.
学会HP「会員ページ」ログイン→メニュー左上「Island Arc無料閲覧」で,以前の
通り,無料アクセスしていただけます.長期間ご迷惑をおかけし,大変申し訳あり
ませんでした.
・新しい論文等が公開されています.
Age and paleoclimatic implication of middle to upper Miocene plant-bearing
strata in the southern Kanazawa area, Ishikawa Prefecture, central Japan,
based on refined Neogene palynostratigraphy in the Hokuriku district:
Shota Teduka, Toshihiro Yamada ほか
https://sub.geosociety.jp/user.php(要会員ログイン)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
[その他のお知らせ]
2008年岩手・宮城内陸地震の震源インバージョン解析と特性化震源パラメータの推定
(電中研メールマガジン 2021年9月24日号より)
https://criepi.denken.or.jp/hokokusho/pb/reportDetail?reportNoUkCode=NR21001
----------------------------------------------
(協)資源地質学会国際シンポジウム “Gold Exploration in the Circum-Pacific”
10月14日(木) 9:00-16:55(日本時間)
形式:オンライン開催(Cisco Webex)
https://www.resource-geology.jp/
(後)第4回水循環シンポジウム(誌上開催)
主催:日本地質汚染審査機構
香澄の郷・水循環シンポジウム〜水郷水循環の街・環境公共潮来〜
(注)10月17日に茨城県潮来市にて開催を予定していましたが, 冊子を配布
しての「誌上開催」に変更いたしました.
http://www.npo-geopol.or.jp/index.htm
(協)石油技術協会令和3年度秋季講演会
テーマ:脱炭素社会への移行に向けた石油開発産業の課題
10月22日(金)13:00-18:05
開催形態:オンライン開催(当日のライブ配信および後日オンデマンド配信(1週間))
https://www.japt.org/
第31回 地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン第2回目)
10月22日(金)19:30-21:30
内容:健全な水循環と地下水
講師:?嶋 洋(NPO法人日本地質汚染審査機構理事長,第一工科大学自然環境工学科教授)
受講方法:ZOOMによるオンライン
申込期限:2021年10月18日まで
受講料:無料
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm#2021.10.22geopol-sympo
(後)藤原ナチュラルヒストリー振興財団
設立40周年記念公開シンポジウム
「海と地球の自然史−変わりゆく海洋環境から
海洋プラスックごみまで地球の問題を考える−」
10月24日(日)13:00-17:00(予定)
[オンラインとハイブリッド]
場所:仙台国際センター
https://40th.fujiwara-nh.or.jp/
2021年度 第2回地質調査研修(参加者募集中)
10月25日(月)- 29日(金)
場所:島根県出雲市長尾鼻周辺(小伊津海岸)
研修内容:室内で岩石の見方等を理解した上で、野外での地層・岩石の
観察ポイントからまとめまで、地質図を作成するための基本的事項を
5日間の研修で習得します。
定員:6名(定員になり次第締切),CPD:40単位
主催:産総研コンソーシアム「地質人材育成コンソーシアム」
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2021-2.html
東北地区会議公開学術講演会「災害と文明−災害に対する社会の対応−」
10月30日(土)13:30-16:30
オンライン開催
参加費無料,要事前申込(締切:10/24)
https://forms.gle/hXimXds5LhpUyjgK6
九州・沖縄地区会議学術講演会「持続可能な地域の強靭化と将来空間像
:防災・減災対策の次なるステージ を目指して」
11月1日(月)14:00-16:10
オンライン開催
参加費無料,要事前申込
https://www.scj.go.jp/ja/event/2021/313-s-1101.html
第234回地質汚染・災害イブニングセミナー(オンライン)
11月5日(金)18:30-20:30
講師:宮崎 淳(創価大学法学部教授)
演題:「水循環基本法の改正と今後の展望」
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
日本不動産学会 シンポジウム
山岳国立公園管理の将来(レクリエーション・登山のための利活用を探る)
11月10日(水)15:00-18:00
開催形態:インターネット(Zoom)配信
参加費無料・定員200名(先着順)
要参加申込:11月4日(木)
http://www.jares.or.jp/events/2021.11.10_sympo.html
第34回 地質調査総合センターシンポジウム:
防災・減災に向けた産総研の地震・津波・火山研究−東日本大震災から10年の成果と今後−
11月12日(金)10:00-15:35(予定)
方法:オンライン開催
参加費無料(事前登録制・定員500名)
https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo34/index.html
(後)第31回社会地質学シンポジウム
11月26日(金)-27日(土)
オンライン開催
発表申込締切:9月30日(厳守)
https://www.jspmug.org/envgeo_sympo/31st_sympo/31st_sympo.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0221.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・国立科学博物館植物研究部研究員(常勤職員 テニュアトラック)募集(10/29)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.535 2022年度代議員選挙立候補受付開始です!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.535 2021/10/19┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2022年度代議員および役員選挙(代議員立候補受付開始)
【2】2022年度学会各賞候補者募集開始(12/1締切)
【3】2022年度会費払込について(割引申請受付開始)
【4】京都大学の地球科学分野での研究不正問題について
【5】地質系若者のためのキャリアビジョン誌(2021版)協賛(原稿掲載)募集
【6】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2022年度代議員および役員選挙(代議員立候補受付開始)
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会定款ならびに選挙規則・選挙細則に基づ
いて,代議員および役員(理事)選挙を実施いたします.
<代議員選挙>
立候補受付期間:10 月21 日(木)から11 月18 日(木)*最終日18 時必着
投票期間:12 月13 日(月)から 2022 年1月10 日(月)*最終日消印有効
詳しくは,http://sub.geosociety.jp/members/content0106.html
(会員ページへのログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2022年度学会各賞候補者募集中です(12/1締切)
──────────────────────────────────
日本地質学会では今年も運営規則第16 条および各賞選考規則にした
がい,賞の候補者を募集いたします.応募書式は準備でき次第、HPに
掲載いたします.また,ご応募いただいた場合には,必ず受け取りの
お返事をお出ししますのでご確認ください.
*********************************************
応募締切:2021年12月1日(水)必着
*********************************************
詳しくは,http://sub.geosociety.jp/members/content0098.html
(会員ページへのログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2022年度会費払込について(割引申請受付開始)
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下
さいますようお願いいたします.
また,学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)
の方で,それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適
用します.
・割引会費請求書発行前受付締切:11月24日(水)
・災害に関連した会費の特別措置申請締切:11月30日(火)
詳しくは、http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】京都大学の地球科学分野での研究不正問題について
──────────────────────────────────
会長 磯崎行雄
(注)「崎」の正しい表記は、「大」→「立」
新聞やTVニュースなどを通して大きく報道されたので,本学会会員の皆様は既にご存知であると思いますが,国際学術誌に発表された地球科学分野論文をめぐる研究不正疑惑が2019年春に発覚しました.その研究不正を行ったとされたのは,当時京都大学教授であり,また日本地質学会の正会員でした.会員の皆様もこのようなことが私たちの分野で起きたことは残念至極と感じられたことと思います.
不正の指摘があった直後から京都大学では詳しい内部調査を始め,その調査中に当該者は大学を辞職し,また本学会には昨年度退会届を提出しました.発覚から約2年が経過し,先日令和3年9月末に京都大学から最終的な調査報告がなされました.その詳細は大学のホームページ(https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news/2021-09-28-0)に公開されていますので,随時参照できます.その内容は,以下の点に要約されます.
当該者が主著者として公表された最近の主要な4編の国際学術誌論文の中に,主な不正行為として故意のデータの捏造と改竄が37箇所に,また不適切なデータの取り扱い箇所が多数認められる.
これらの箇所を含む論文について,当該者に対して撤回の勧告をした.
同大学就業規則に基づき,懲戒解雇処分相当とする.
再発防止のために,スタッフ及び学生・院生に対する教育を徹底させる.
このような研究不正自体はまさに学問を冒涜するものであり,京都大学が出した結論は極めて妥当です.本件は京都大学の中に閉じた事柄ではく,本学会を含む地球科学コミュニティー全体で真摯に受け止めねばなりません.業績構築のために不正を行う背景には昨今の行き過ぎた研究成果至上主義があると考えられます.とはいえ,卑しくも科学研究に身を置くものにとって研究不正は言語道断であり,そのことを改めて本学会員の間で認識共有する必要があります.今回の一件に関する大学内での調査のために,他の善良な研究者から膨大な研究時間を奪ったと想像され,対応された会員の方々を労いたいと思います.
今回のような研究不正に関係する問題は大学などの学校あるいは研究所に所属する会員だけの話と思われがちですが,そうではありません.今回の不正論文では,当該者が地質調査業者に外注したデータについて改竄がなされ,中には現場調査に関わった業者の方々の同意なしに共著者に加えられていたケースもあったようです.したがって,研究にご協力いただく地質調査業の会員の皆様にも,このような不名誉な事件に巻き込まれないよう注意を喚起したいと思います.
日本地質学会が,あくまで公明正大に学問を進める健全な学会であり続けられるよう,改めて会員の皆様の意識徹底をお願い申し上げます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質系若者のためのキャリアビジョン誌(2021版)協賛(原稿掲載)募集
──────────────────────────────────
日本地質学会は、昨年度から地質学を専攻とする若者に専門職の魅力を伝えるための情報誌「地質系若者のためのキャリアビジョン誌」を刊行・配布を開始いたしました.各大学では、この冊子をキャリア教育の教材と活用頂き、そして多くの学生・院生から専門職を知る機会になったとの声を頂いております.本年も「地質系若者のためのキャリアビジョン誌」を発行・配布する予定です.本冊子への協賛と原稿提供をご検討頂けますと幸甚でございます.
編集協賛費: 3万円(日本地質学会賛助会員は 1 掲載地区分無料)
原稿:A4縦,カラー,自由デザイン,PDF 形式,各社 1 ページスペース
申込締切:10 月 31 日(日)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/engineer/content0003.html#1-5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌(再掲)
来年1月からの完全電子化への準備は進みつつあります.9/11の日本地質学会理事会で,地質学雑誌電子版投稿編集出版規則の内容が審議されました.現行の規則からあまり大きく変えないように心掛けました.主要な変更点について,お知らせいたします.
続きはこちら,,,http://www.geosociety.jp/publication/content0099.html
■ Island Arc
無料閲覧はこちらから
https://sub.geosociety.jp/user.php(要会員ログイン)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[四国支部]
・第21回四国支部 総会・講演会のご案内
講演会:2021年12月4日(土)13:00-16:45(予定)
総 会:2020年12月4日(土)16:55-17:25(予定)(講演会終了後)
いずれもWEB開催(Zoom[予定])
参加・発表申込締切:11月19日(金)
http://www.geosociety.jp/outline/content0212.html#2021sokai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(協)石油技術協会令和3年度秋季講演会
テーマ:脱炭素社会への移行に向けた石油開発産業の課題
10月22日(金)13:00-18:05
開催形態:オンライン開催(当日のライブ配信および後日オンデマンド配信(1週間))
https://www.japt.org/
第31回 地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン第2回目)
10月29日(金)19:30-21:30(日程が変更になりました)
内容:健全な水循環と地下水
講師:
・郄嶋 洋(日本地質汚染審査機構理事長・第一工科大学自然環境工学科教授)
・田村嘉之(日本地質汚染審査機構副理事長・地質汚染診断士の会会長)
受講方法:ZOOMによるオンライン
申込期限:10月27日まで(延長しました)
受講料無料
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm#2021.10.22geopol-sympo
(後)藤原ナチュラルヒストリー振興財団
設立40周年記念公開シンポジウム
「海と地球の自然史−変わりゆく海洋環境から
海洋プラスックごみまで地球の問題を考える−」
10月24日(日)13:00-17:00(予定)
形式:オンラインと会場のハイブリッド開催(会場参加人数:100名)
場所:仙台国際センター
https://40th.fujiwara-nh.or.jp/
アースサイエンスウィーク・ジャパン講演会
(1)10月30日(土)13:30-16:10
震災10年、東北から地球をみつめる(オンラインとハイブリッド)
登壇者:小平秀一(JAMSTEC)・平塚 明(元岩手県立大)・平 朝彦
(JAMSTEC/東海大)・今村文彦(東北大)
http://www.earthsciweekjp.org/plan/plan1/index.html
(2)10月31日(日)13:30-15:30
地質探偵が見た!日本文化と地質の関係(オンラインとハイブリッド)
登壇者:ウォリス サイモン(東京大)・眞木隆志(NHKエデュケーショナル)
http://www.earthsciweekjp.org/plan/plan2/index.html
日本学術会議東北地区会議公開学術講演会
「災害と文明−災害に対する社会の対応−」
10月30日(土)13:30-16:30
オンライン開催
参加費無料,要事前申込(締切:10/24)
https://forms.gle/hXimXds5LhpUyjgK6
九州・沖縄地区会議学術講演会「持続可能な地域の強靭化と将来空間像
:防災・減災対策の次なるステージ を目指して」
11月1日(月)14:00-16:10
オンライン開催
参加費無料,要事前申込
https://www.scj.go.jp/ja/event/2021/313-s-1101.html
第234回地質汚染・災害イブニングセミナー(オンライン)
11月5日(金)18:30-20:30
講師:宮崎 淳(創価大学法学部教授)
演題:「水循環基本法の改正と今後の展望」
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
学術会議公開シンポジウム「防災教育と災害伝承」
(ぼうさいこくたいのセッションとして開催するシンポジウム)
11日6日(土)14:30-16:00
オンライン開催
定員:1000名(Zoomウェビナー)
参加費無料・要事前申込
https://www.scj.go.jp/ja/event/2021/316-s-1106-2.html
茨城大学図書館オンライン土曜アカデミー
「チバニアン誕生:方位磁針のN極が南をさす時代へ」
11月6日(土)14:00-15:30(zoomによるオンライン開催)
講師:岡田 誠(茨城大学理学部教授)
参加費無料・要申込(先着450名)
http://www.lib.ibaraki.ac.jp/news/?id=356
第34回 地質調査総合センターシンポジウム:
防災・減災に向けた産総研の地震・津波・火山研究
−東日本大震災から10年の成果と今後−
11月12日(金)10:00-15:35(予定)
方法:オンライン開催
参加費無料(事前登録制・定員500名)
https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo34/index.html
(後)第31回社会地質学シンポジウム
11月26日(金)-27日(土)
オンライン開催
https://www.jspmug.org/envgeo_sympo/31st_sympo/31st_sympo.html
日本学術会議主催学術フォーラム
「地球環境変動と人間活動―地球規模の環境変化にどう対応したらよいか―」
12日5日(日)13:00-17:50
オンライン開催
参加費無料・要事前申込
https://www.scj.go.jp/ja/event/2021/315-s-1205.html
地質学史懇話会[オンラインと対面のハイブリッド]
12月19日(日)13:30-16:30
場所:早稲田奉仕園(東京メトロ東西線早稲田駅下車徒歩5分)
青木滋之「ダーウィンと科学哲学 ―同時代、現代の視点から―」
加藤碵一「菜食主義とライマン・宮沢賢治余聞」
連絡先:矢島道子 pxi02070[at]nifty.com
海と地球のシンポジウム2021
12月20日(月)-21日(火)
主催:AORI・JAMSTEC
開催方法:実会場とオンライン会場を使ったハイブリッド形式
※感染症の状況により変更・中止する場合があります.
https://www.jamstec.go.jp/j/pr-event/ocean-and-earth2021/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0221.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・九州大学基幹教育院准教授もしくは講師公募(12/9)
・弘前大学教育研究自然科学系安全システム工学領域(地球環境化学分野)助教公募(22/1/4)
・伊豆大島ジオパーク専門員(大島町任期付職員)募集(12/24)
・洞爺湖有珠山ジオパーク学術専門員募集(11/30募集期間延長)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
地球神話とジオパーク
“Geomythology(地球神話)“とジオパーク
正会員 野村律夫
(島根大学/島根半島・宍道湖中海ジオパーク専門員)
はじめに
第11回ジオパーク全国大会が10月3日〜5日にかけて島根県松江市と出雲市で開催された.昨年から続くコロナ禍のため1年延期となったが,637名が参加するオンライン開催であった.パソコンのモニター越しに伝わる静かな雰囲気の大会ではあったが,発言のしやすさなど学ぶことも多かったように思う.
さて,どのジオパークにもシンボル的な自然がある.大会に向けて,島根半島・宍道湖中海ジオパークはなんだろうかと問い直してみた.半島と湖が醸し出す広大な景観は美しい.また,そこは古代からの歴史という空気で満たされた不思議な自然である.少し抽象的な表現になったが,このジオパークは新第三紀中新世の変動地質と第四紀の平野形成といった学術価値のみではなく,古事記や出雲国風土記にある神話・伝説が大地に深く根付いているということだ.
神話・伝説となると,人々の生活の中で語られてきたものであるから,それぞれの地域に特有のものがあるにちがいない.そのようにみると,神話伝説を通して地域の地質地形の特徴や人々の自然に対する精神性についてみるのも面白そうだ.そこで「出雲の大地」での大会を機に全国の44ジオパークに「神話・伝説を科学の目で見て語ってみよう」と題してポスター展示を促してみたところ,12ジオパークからポスターが届いたので紹介したい.
ところで,地域の地質遺産の活用を目指しているジオパークでは,地域住民の地質遺産への学術的価値の理解が極めて重要になる.最近のジオパーク活動の方向は,地質学的に貴重な地質遺産の保護保全を核として,より明確に歴史・文化・人のくらし・産業などの遺産との連携,すなわち地球遺産として融合的な活用へと向かっている.そのためにも,地域の地質地形に関わる神話伝説は,ジオパークを理解するための効果的な動機付けになるにちがいない.
国内の地質研究者はこれまで,神話・伝説について学術的な関心を払ってきたであろうか.神話・伝説はおとぎ話のようなもので,なんら学術とは関係の無い,むしろ神話・伝説的なことにふれることで学術性が失われると思うこともあろう.人々のなかには神話と科学は別々のもので,神話は非論理的・非科学的なものと捉えることが多いのも事実である.しかし,海外では1970年代に神話と地質の密接な関係から「Geomythology」という用語も提案され,現在,「Geomythology」は,地球科学の研究対象ばかりでなく,地域地質や地形の保全,防災教育やジオツーリズムへと応用されている.
1.Geomythologyとは何ぞや
全国大会のポスター展示を報告する前に,神話・伝説の地質学的扱いの現状を整理してみてみたい.「Geomythology」はVitaliano(1973)が提唱した用語である.1970年代は,地向斜-造山論の古い地球観からプレートテクトニクスによる新しい地球観へと移行する地球科学の大革命の時代であった.そのため,地質研究者の「Geomythology」への関心は低かったといえる.適切な日本語訳もないまま現在に至っている. Geomythologyはgeology(地質学)とmythology(神話学)の複合語である.Mythologyはmyth(神話)を論理的に扱う表現であるが,神話学,神話論や単に神話と訳されている.これを日本語に訳すとしたら,geochemistry(地球化学)やgeophysics(地球物理)を参考にして,地球神話又は地球神話学となる.神話伝説の多くは,当然のこととして,人々の生活圏の中で生まれてきたものであるから地域的な話題が多い.したがって,地質神話と言っても問題ないが,地質現象は地質ばかりでなく,気象や海洋と密接に関連していることもある.ここでは総論的にgeomythology=地球神話として,個々の視点で注目すべき現象に焦点を当てる場合は,地質神話,気象神話そして海洋神話といった表現があってもよいと考えている.
Vitaliano(1973)が提唱した地球神話は,地質学と民間伝承の関係を探求することに本質があるが,以下のようなことも指摘しているので少し追加説明を入れて紹介する.
地球神話はエウヘメリズムを地質学的に応用しようとするもの.エウヘメリズムは,紀元前300年頃の古代ギリシアの哲学者エウヘメロスの名に由来するもので,神話は歴史上の人物や出来事を語っていると解釈する.したがって,人々が目撃した実際の地質学的な出来事,たとえば,火山,地震,津波,洪水のような自然災害を神話として後世に伝えようとした.
地球神話には,民俗学にある原因探求神話(etiological myth)または説明神話(explanatory myth)ともよぶものが含まれる.すなわち,身の回りの自然環境の形成について説明しようとしたもので,世界中に多くの例がある.
地球神話は地質学,歴史学,考古学,民俗学などの分野を融合した最も広い学際的な地球科学である.
神話と伝説を明確に区別することは難しいため,地球神話はその起源にかかわらず,地質学的に影響を受けたあらゆる神話・伝説(legend)・民間伝承(folklore)を指すことにする.物語り(märehen)や昔話は娯楽の対象である.
神話・伝説の類似性は,異なる場所で独立して語られた多起源説と,1つの地域での語り(単一起源説)が他の地域に伝達された混交(syncretism)があるが,地球神話は多起源であることが多い.ただし,これには異論もある.たとえば,大林(1966)の神話学入門では神話は単一起源で拡散・混交が主要と考えられている.南西太平洋に点在する島嶼(とうしょ)には,島が海底からつり上げられてできたという「釣り上げ(fishing-up)神話」があり,これには人々の移動と密接に関係していると考えられている(Nunnほか,2007).
神話伝説にはフィクションや口述の変容を伴うことが多く,エウヘメロスの時代から,論争の対象であった.解釈には注意が必要である.
地質学には,ピルトダウン人事件(化石人骨ねつ造;〜1910-1949年)やベリンガー事件(化石のねつ造;〜1726年)のような改ざん事件があった.
2.地球神話(Geomythology)のその後
2004年にイタリア・フィレンツェで開催された第32回国際地質学会では,Vilatiano(1973)の著書に鼓舞された地質・民俗学研究者によって「地球神話は,神話的物語を分析して,そこに描かれている地質学的な出来事を知ること.時には,科学的には知られていない,あるいは知ることが難しい昔の地震,津波,洪水などについて,非常に貴重な情報を得ることができる.神話は,科学者に未知の古い地質学的事象についてのヒントを与えてくれる.」という説明のもとセッションが設けられた.その講演内容は2年後にPiccardi and Masse (2007)によって「Myth and Geology」としてまとめられ,イギリスの地質学学会から出版された.25編の世界各地の神話・伝説が地質学と関連させて語られて興味深い内容となっている.日本からの参加はなかったが,日本の地震と神話の詳しい記述やナマズを押さえ込む鹿島神宮の要石(かなめいし)などが紹介されている.一般的に,海外からみた日本にある神話伝説は地震と津波に関するものが多いのが特徴である. 地質学の専門ではないが,Mayor (2004)は民俗学の立場でギリシア神話に現れる化石,火山,地震,津波,地殻変動,洪水,天然ガス,環境変化などの地球神話の例を紹介しながら,「科学者や歴史家は人類の歴史の中で起こった大変動の話は,世代を超えて伝達され,超自然的な内容になり,神話的な語りの中に埋め込まれたため,その合理性の核心を見逃してきた」,といっている.大地の形を説明するために,魔法で岩に姿を変えられた生物や人間の話など国内でもしばしば各地に伝わっている.古代より,生きているのを見たことがない動物の化石を説明するために,ドラゴン,モンスター,巨大な英雄の物語をつくってきた架空の話も多い.国内の化石につては,荻野(2018)が興味深く解説している.妖怪や擬人化した「ダイダラボッチ」は物語的ではあるが,説明神話として古代の人々の洞察力に現在につながる科学が秘められているように思われる.
最近,Burbery (2021)は「地球神話は科学か?」という章のなかで,"geomythology"という言葉は Oxford English DictionaryやMcGraw-Hill Dictionary of Geology and Mineralogyに掲載されていないと指摘し,地球化学や地球水文学のように,地球神話を捉えることはできないだろうと述べている.しかし,何世紀にもわたって研究者の貴重な味方であり,多くの科学的発見に役立ってきたとし,その意義を認めている.
国内の神話の位置づけについては,大林太良(1966,2019)が海外の研究を参考にしながら,神話は,事物の起源,原古の生物,神々の行為と彼らの人間への関係についての,目に見えるように物語られた真実であると考えられている報告であって,それはその民族の世界観の確定された諸要素からなりたっている....」と述べており,地質学(科学的)検証ができるものとして理解できる説明である.
3.ジオパーク全国大会から
今回の呼びかけでは以下のような展示があった.❶銚子市の猿田神社に伝わる椿海(つばきのうみ)という海跡湖の形成を3人の命(みこと)と魔王の戦いで伝説化する.椿海は利根川構造線沿いにある(銚子GP).❷河川の氾濫や洪水が伝統的な解釈になっている八岐大蛇(やまたのおろち)伝説は,北陸から東北地方の日本海沿岸域(いわゆる古志)では火山活動を語った伝説ではないか(恐竜渓谷ふくい勝山GP).❸鳥取県の内陸部に中国山地と並走する山々が大山(だいせん)(西部)と鷲峰山(じゅうぼうさん)(中東部)の背比べ争いでできたとする伝説.後期中新世−鮮新世のプレート運動を反映していた(山陰海岸GP).❹伊豆大島に伝わるカッパと水の物語(伊豆大島GP).❺兵庫県豊岡市に伝わるアメノヒコボ伝説は,洪水が発生しやすい盆地地形を理解し,円山川河口の開削と盆地の開発の伝承であった(山陰海岸GP).❻島根半島の大船山(おおぶねさん)に宿る神の伝説は,山頂付近から湧き出す旱(ひでり)でも涸(か)れない水の不思議.半島の形成期と形成後にできた2系統の断層と関係していた(島根半島・宍道湖中海GP).❼新潟県糸魚川市のヒスイ,黒姫山一帯の神秘的な石灰岩地形,修験の山としての駒ヶ岳の形成を奴奈川姫(ぬなかわひめ)の伝説として紹介(糸魚川GP).❽1783年の浅間山噴火で描かれた「浅間山夜分大焼の図」にある火口からの火柱は,溶岩噴泉あることが火口地形やキラウエア火山との比較で実際に起こったことが示唆できる(浅間山北麓GP).❾活火山の白山山頂付近の火口湖(千蛇ヶ池(せんじゃがいけ))にできた万年雪や水が湧出する甌穴(弘法池)の説明神話,土石流(明神壁)や火山の噴火災害への警鐘を民謡(白峰かんこ踊り)にして謡う災害神話(白山手取川GP).❿妙義山のなかでも奇岩が多い表妙義.巨人が射抜いた穴として伝わる星穴伝説は,溶岩と火砕岩層の物性の違いでできた穴であった(下仁田GP).⓫秋田県湯沢市広澤寺にある乳神大イチョウの幹にできた気根は,乳信仰の対象となっている.その起源は,広澤寺の開祖された場所に近い川原毛地獄への畏怖があった(ゆざわPG).⓬菅尾磨崖仏(すがおまがいぶつ)に近い所にある水霊石(みずたまいし)や大蛇を川の流れに例えた緒環(おだまき)伝説は水害への警告と川の治水・国の統治を示している(豊後大野GP)
今回紹介いただいた神話・伝説は,古代からの人々の自然観が伝わる興味深いものばかりである.神話伝説の多くは説明神話であるが,災害神話に相当するものも含まれている.これらのポスターを通して,野本(1990,2006)が「聖性地形」と表現した古代人の神霊に対する鋭敏さや聖なるものへの鋭い反応を感じとることができる.そして,地質地形の伝説はフィールドワークを通じて体感できるものという花部(2018)の指摘にも理解できる内容であった.
各ポスターは12月末まで島根半島・宍道湖中海ジオパークのホームページで公開されているので,関心のある方は次のURLへアクセスして欲しい(https://kunibiki-geopark.jp/alljapan_geo-postersession/).
4.おわりに
以上述べてきたように,海外では地球神話はきわめて有効な手段で,地域の自然・文化遺産の理解と保全,防災教育,地域への誇りを醸成する役割を果たしていることへの認識は共通している.ジオツーリズムへの積極的な利用もある.また,地質・環境科学の導入セミナーで地球神話を利用している大学もある(Tepper,1999).しかし,国内では神話の利用がやや躊躇されてきたように思える.今後は神話に秘められた科学性を見抜き,地球神話として積極的に地域にあったプログラム作りが望まれる.最近,地球科学の専門家による日本ジオパーク学術支援連合(JGASU)が組織されたので,地域住民は指導を受けながら地域(ジオサイト)の学術を深めることもできる.地質研究者として,専門性を有効活用することで地域に伝わる神話伝説・民間伝承を深掘りし,もっと地域への知の還元をしてみてはどうだろうか.
謝 辞 今回の呼びかけに応じていただいた以下の各氏に感謝します:岩本直哉,小河原孝彦,荻野慎諧,金山恭子,小林猛生,近藤綾子,メイ・スーザン,関谷知彦,高柳春希,中嶋 亮,成田浩一,古川広樹,吉岡敏和(敬称略).また,ジオパーク支援委員長の天野一男・茨城大学名誉教授からは本トッピク原稿について適切なコメントを頂いた.
文 献
Burbery, T. J., 2021, Geomythology: How Common Stories Reflect Earth Events. Routledge, New York & London.
花部英雄,2018,ジオパークと伝説.三弥井書店.
Mayer, A., 2004, Geomythology. In Selley, R., et al., eds., Encyclopedia of Geology, Elsevier.
野本寛一,1990,神々の風景−信仰環境論の試み.白水社.
野本寛一,2006,神と自然の景観論.講談社学術文庫.
Nunn, P. D. and Pastorizo, M. R., 2007,Geological histories and geohazard potential of Pacific Islands illuminated by myths. In Piccardi, L., et al., eds., Myth and Geology. Geol. Soc. Spec. Publ., 273, 143-163.
荻野慎諧,2018,古生物学者,妖怪を掘る.NHK出版新書.
大林太良,1966,神話学入門.中央公論社.
大林太良,2019,神話学入門.ちくま学芸文庫.
Piccardi, L. and Messe, W. B., eds., 2007, Myth and Geology. Geol. Soc. Spec. Publ., 273,
Tepper, J. H., 1999, Connecting Geology, History, and the Classics through a course in Geomythology. J. Geosci. Educ., 47(3), 221-226.
Vitaliano, D. B. 1973, Legends of the Earth: Their Geological Origins. Indiana Univ. Press, Bloomington.
中国の月探査機「嫦娥5号」持ち帰り試料の地質学的研究結果
中国の月探査機「嫦娥5号」持ち帰り試料の地質学的研究結果
正会員 石渡 明
1.はじめに 着陸地点と調査目的
図1. 月の表側の「海陸分布」のスケッチマップ。兎が餅を搗く図柄に簡略化。海・大洋・入江以外の部分が陸地(高地)。米国アポロ(A)、ソ連ルナ(L)、中国嫦娥(C)の着陸地点や主要なクレーターを示す。
中国の月探査機「嫦娥(じょうが)5号(Chang’e-5)」(チャンオー、eはE表記も)は2020年12月1日に嵐の大洋(兎(うさぎ)が餅(もち)を搗(つ)く臼(うす)の部分)の北部、Rümker(リュムカー)山の北東約170km、露の入江に近い北緯43.06度、西経51.92度に着陸し(図1)、地質試料の採集などを行って、2020年12月16日に内モンゴルの沙漠に帰還した。月からの試料回収は1976年のソ連のルナ24号以来44年ぶりである。2021年10月にこれらの試料の分析結果が発表されたので(Che et al., 2021; Li et al., 2021; Tian et al., 2021)、その概要を紹介する。
着陸地点は南中時の満月の左上隅に近い場所であり(月面の地図や写真集については石渡(2016)参照)、1960〜70年代の米国アポロ、ソ連ルナの着陸地点に比べて最も高緯度である(図1)。この地点は東へ2°程度傾斜する嵐の大洋の平坦地で、東方約20kmに月面最長の蛇行する溝(Rima Sharp: 566km長、0.8〜3km幅、20〜50m深)があり、南方約20kmに残丘(kipuka)がある(Qian et al., 2021)。また、着陸地点の北西422m地点を中心とする直径394mのクレーターがある(Qiao et al., 2021)。試料採集は着陸船から腕を伸ばし、地表付近を掬(すく)い取り(A装置)、掘り取って(B装置)、帰還船に収納した他に、着陸船の直下をドリル掘削してコア試料を採取し、帰還船に収納した。持ち帰った土壌(レゴリス)・岩石試料は1731g(うち~250gは約1m長のボーリングコア)である(Head, 2021)。嫦娥5号の主目標は月の海の中で最もクレーター密度が低い(つまり、最も新しい)地域の溶岩の同位体年代を決定すること、月面全体の中でもカリウム、希土類、リンに富む特異な化学組成をもち「嵐の大洋KREEP地域」と呼ばれるこの地域の溶岩の特徴が、この新しい溶岩にも見られるかどうかを調べることである(Che et al., 2021)。
なお、着陸地点付近の地形・地質の解析には米国と中国の月周回機に加え、日本のかぐやのリモートセンシングも役立っている(Qian et al., 2021; Qiao et al., 2021)。また、嫦娥4号が2019年1月3日に南極エイトケン盆地(直径2500kmの太陽系最大の衝突構造:Lissauer and de Pater, 2019)の南緯45.5度、東経177.6度に着陸し、人類初の月の裏側への着陸となったが、その探査車(玉兎)は現在も走行調査を続けている。
2.嵐の大洋の玄武岩溶岩の年代
月の海の溶岩はこれまで米国のアポロ及びソ連のルナによって地球に持ち帰られた岩石試料の年代測定と地形学的なクレーター分布密度の測定によって、多くが30〜38億年前に噴出したことがわかっているが、嵐の大洋やスミス海にはクレーター分布密度が著しく低い領域があり、大きな新しいクレーターの周囲の光条を覆っている溶岩流もあって、最も若い海の溶岩流は10億年前程度の年代ではないかと言われていた(Spudis, 1996)。嵐の大洋にはクレーター密度年代が10〜20億年前の地域が北部、中部、南部の計3ヶ所あり、今回は北部地域に着陸した(Head, 2021; p. 21, 22)。Qiao et al. (2021)は着陸地域のクレーター密度年代を12〜22億年前と見積もった。
今回採集された嵐の大洋の玄武岩溶岩片のPb-Pb年代はChe et al. (2021)によると1963±57Ma(Maは100万年前)、Li et al. (2021)によると2030±4Maとのことで、12〜22億年前との予想範囲の古い方の年代値になったが、通常の海の溶岩(30〜38億年前)に比べると10億年以上若い。今回のデータは、月の歴史の中で通常の海の溶岩とコペルニクス・クレーターの形成(約8億年前)の間の放射年代の空白期間の真ん中に年代値の標石を立てたことになり、太陽系惑星のクレーター密度年代学に確かな目盛りを提供したことになる(Li et al., 2021)。
3.嵐の大洋の玄武岩溶岩の化学組成
また、採集された溶岩の化学組成分析結果は、それらが嵐の大洋南部のアポロ12号地点で発見され、その東方のフラマウロ高地の同14号地点の角礫岩に大量に含まれていたKREEP玄武岩ではなく、月の海の通常の玄武岩の高Ti系列と低Ti系列の中間的な組成を持ち、非常に結晶分化作用が進んだ鉄に富む玄武岩質溶岩であることを示している。SrとNdの同位体組成もKREEP玄武岩とは起源物質が大きく異なることを示している(Tian et al., 2021; Che et al., 2021)。このことは、嵐の大洋地域が放射性発熱元素であるK、Th、Uなどに富むKREEP玄武岩地域であるから、後々の時代までマントルが熱かったために火山活動が継続したのではなく、月の普通の化学組成のマントルが20億年前までマグマを生産することができたことを示しており、従来の月の熱史を考え直す必要がある(Che et al., 2021)。
4.おわりに 地球科学的意義
月の地質時代は先ネクタリア代(>39億年)、ネクタリア(神酒(みき)の海)代(39-38億年前)、インブリア(雨の海)代(38-31億年前)、エラトステネス代(31〜10億年前)、コペルニクス代(<10億年前)に区分されるが(Spudis, 1990)、今回嫦娥5号が採集した溶岩の年代値は、約20億年間にわたる長い時代に確固たる年代標準点がなく、クレーター密度の時間的変化が小さかった(Spudis, 1996; Fig. 4.8)エラトステネス代の真ん中にクサビを打ち込んだことになる(Li et al., 2021; Fig. 4)。地球上に残る天体衝突構造はこの時代以後のものであり、このクサビは地球や他の太陽系惑星の地史の研究にも有意義である。なお、月面で確認された最新の地形形成イベントの一つはティコ・クレーターの形成であり、その年代はアポロ17号が採集した破片の年代測定により1.8億年前(ジュラ紀)とされている(Spudis, 1996)。また、地球上で発見された月隕石には、嫦娥以前の月の海の玄武岩としては最も若い28.7億年前の年代を示すものがあり、これがKREEP成分に富んでいたので(武田, 2009)、月の冷却が進んだ新しい時代の玄武岩はKREEP成分に富む発熱性のマントルのみから形成されたという考えもあったが、今回の嵐の大洋の20億年前の海の溶岩の化学分析値はこの考えを否定し、月の熱史に変更を迫っている。このように、地球帰還から1年以内に、嫦娥5号が持ち帰った試料の科学研究は重要な結果を出しつつある。今後はボーリングコアの解析結果が待たれる。
文献調査でお世話になり、原稿を見ていただいた千葉大学の市山祐司博士に感謝する。
文 献
Che, X. C., Nemchin, A., Liu, D. Y. et al. (2021.10) Age and composition of young basalts on the Moon, measured from samples returned by Chang’e-5. Science. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abl7957
Head, J. W. (2021.4) Chang’e-5 lunar sample return mission update. Extraterrestrial Materials Analysis Group Spring Meeting April 7-8, 2021 Presentation PDF, 75p. https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/content/-/article/chang-e-5
石渡 明(2016)KAGUYA月面図(紹介)。日本地質学会News, 19(7), 23-24. geo-Flash http://www.geosociety.jp/faq/content0666.html 記事【9】
Li, Q. L., Zhou, Q., Liu, Y. et al. (2021.10) Two-billion-year-old volcanism on the Moon from Chang’E-5 basalts. Nature. https://doi.org/10.1038/s41586-021-04100-2
Lissauer, J. J. and de Pater, I. (2019) Fundamental Planetary Science (updated edition). Cambridge University Press, 604p.
Qian, Y., Xiao, L., Wang, Q. et al. (2021.3) China’s Chang’e-5 landing site: Geology, s tratigraphy, and provenance of materials. EPSL. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2021.116855
Qiao, L., Chen, J., Xu, L. et al. (2021.8) Geology of the Chang’e-5 landing site: Constraints on the sources of samples returned from a young nearside mare. Icarus, 364. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2021.114480
Spudis, P. D. (1990) The Moon. In: Beatty, J.K. & Chaikin, A. (eds) The New Solar System, 3rd ed. 41-52. Sky Pub. Co., Cambridge.
Spudis, P.D. (1996) 水谷仁訳(2000)月の科学−月探査の歴史とその将来。シュプリンガー・フェアラーク東京, 297p.
武田 弘(2009)固体惑星物質進化。現代図書 131p.
Tian, H. C., Wang, H. Chen, Y. et al. (2021.10) Non-KREEP origin for Chang’E-5 basalts in the Procellarum KREEP Terrane. Nature, http://doi.org/10.1038/s41586-021-04119-5
【geo-Flash】No.536(臨時)JpGU2022セッション提案募集(11/2締切)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.536 2021/10/27┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】JpGU2022セッション提案募集(11/2締切)
──────────────────────────────────
JpGU2022でセッション提案を予定している方で,地質学会共催を希望される
場合は,併行して下記の地質学会のJpGUプログラム委員にご連絡いただきます
ようお願い致します。すでに提案済みの場合も,これからでも結構ですので,
プログラム委員にご連絡をお願い致します.
日本地質学会JpGUプログラム委員:
松崎賢史(海洋地質部会選出行事委員) kmatsuzaki[at]g.ecc.u-tokyo.ac.jp
上澤真平(火山部会選出行事委員)uesawa[at]criepi.denken.or.jp
(注)[at]を@マークにしてください
[ご連絡いただく内容]
・タイトル:
・スコープ:
・代表コンビーナ(1名):
・共同コンビーナ(3名まで):
[セッション提案締切]2021年11月2日(火)17:00
セッション提案の詳細は,下記JpGUのサイトをご参照ください.
http://www.jpgu.org/meeting_j2022/for_conv.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.537 地質学露頭紹介のページができました
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.537 2021/11/1┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2022年度代議員選挙立候補受付中!
【2】2022年度学会各賞候補者募集開始(12/1締切)
【3】2022年度会費払込について(割引申請受付中)
【4】地質系若者のためのキャリアビジョン誌(2021版)協賛(締切延長)
【5】地質学露頭紹介のページができましたs
【6】第13回惑星地球フォトコンテスト受付開始
【7】コラム:“Geomythology(地球神話)“とジオパーク
【8】コラム:中国の月探査機「嫦娥5号」持ち帰り試料の地質学的研究結果
【9】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【10】支部情報
【11】その他のお知らせ
【12】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2022年度代議員選挙立候補受付中!
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会定款ならびに選挙規則・選挙細則に基づいて,
代議員および役員(理事)選挙を実施いたします.
<代議員選挙>
立候補受付期間:10 月21 日(木)から11 月18 日(木)*最終日18 時必着
投票期間:12 月13 日(月)から 2022 年1月10 日(月)*最終日消印有効
詳しくは, http://sub.geosociety.jp/members/content0106.html
(会員ページへのログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2022年度学会各賞候補者募集中です(12/1締切)
──────────────────────────────────
日本地質学会では今年も運営規則第16 条および各賞選考規則にした
がい,賞の候補者を募集いたします.応募書式は準備でき次第,HPに
掲載いたします.また,ご応募いただいた場合には,必ず受け取りの
お返事をお出ししますのでご確認ください.
*********************************************
応募締切:2021年12月1日(水)必着
*********************************************
詳しくは, http://sub.geosociety.jp/members/content0098.html
(会員ページへのログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2022年度会費払込について(割引申請受付中)
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下
さいますようお願いいたします.
また,学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)
の方で,それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適
用します.
・割引会費請求書発行前受付締切:11月24日(水)
・災害に関連した会費の特別措置申請締切:11月30日(火)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地質系若者のためのキャリアビジョン誌(2021版)協賛(締切延長)
──────────────────────────────────
締切延長:11月15 日(月)
****************************
日本地質学会は,昨年度から地質学を専攻とする若者に専門職の魅力を伝える
ための情報誌「地質系若者のためのキャリアビジョン誌」を刊行・配布を開始
いたしました.各大学では,この冊子をキャリア教育の教材と活用頂き,そして
多くの学生・院生から専門職を知る機会になったとの声を頂いております.
本年も「地質系若者のためのキャリアビジョン誌」を発行・配布する予定です.
本冊子への協賛と原稿提供をご検討頂けますと幸甚でございます.
編集協賛費: 3万円(日本地質学会賛助会員は 1 掲載地区分無料)
原稿:A4縦,カラー,自由デザイン,PDF 形式,各社 1 ページスペース
申込締切:11月15 日(月)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/engineer/content0003.html#1-5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質学露頭紹介のページができました
──────────────────────────────────
2021年名古屋大会(オンライン)にて,多くの人に見てほしい,知ってほし
い,議論したい露頭の写真を持ち寄り,その地質学的意味について解説・議
論するイベントを開催しました.その内容を各発表者にまとめていただき,
HPとニュース誌10月号に掲載しました.
今回の企画が好評だったことから,今後も開催したいと考えています.
次回はより多くの方から露頭紹介していただけることを期待しています.
--------------------------
中央構造線活断層系 川上断層の露頭/変形構造から読み解くテクトニクス/
関東山地北部秩父帯の褶曲と変成縞蛇紋岩メランジュの蛇紋岩露頭/
Wawaの縞状鉄鉱層/アイスランドの溶岩断面/
香川県庄内半島に見られる花崗岩境界/河川堆積物に見られるHCSのような構造
--------------------------
各紹介記事はこちらから,
http://www.geosociety.jp/faq/content0983.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】第13回惑星地球フォトコンテスト受付開始
──────────────────────────────────
***応募締切:2022年1月31日(月)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募フォームからでも
メール添付でもご応募いただけます.会員の皆様の応募をお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】コラム:“Geomythology(地球神話)“とジオパーク
──────────────────────────────────
正会員 野村律夫
第11回ジオパーク全国大会が10月3日〜5日にかけて島根県松江市
と出雲市で開催された.昨年から続くコロナ禍のため1年延期となった
が,637名が参加するオンライン開催であった.パソコンのモニター越し
に伝わる静かな雰囲気の大会ではあったが,発言のしやすさなど学ぶこ
とも多かったように思う.
さて,どのジオパークにもシンボル的な自然がある.大会に向けて,
島根半島・宍道湖中海ジオパークはなんだろうかと問い直してみた.
半島と湖が醸し出す広大な景観は美しい.また,そこは古代からの歴史
という空気で満たされた不思議な自然である.少し抽象的な表現になった
が,このジオパークは新第三紀中新世の変動地質と第四紀の平野形成と
いった学術価値のみではなく,古事記や出雲国風土記にある神話・伝説
が大地に深く根付いているということだ.
続きはこちらから,,, http://www.geosociety.jp/faq/content0994.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】コラム:中国の月探査機「嫦娥5号」持ち帰り試料の地質学的研究結果
──────────────────────────────────
正会員 石渡 明
中国の月探査機「嫦娥5号(Chang’e-5)」(チャンオー,eはE表記も)は
2020年12月1日に嵐の大洋(兎が餅を搗く臼の部分)の北部,Rümker
(リュムカー)山の北東約170km,露の入江に近い北緯43.06度,西経51.92度
に着陸し,地質試料の採集などを行って,2020年12月16日に内モンゴルの
沙漠に帰還した.月からの試料回収は1976年のソ連のルナ24号以来44年ぶり
である.2021年10月にこれらの試料の分析結果が発表されたので,その概要
を紹介する.
続きはこちらから,,, http://www.geosociety.jp/faq/content0995.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌(再々掲)
来年1月からの完全電子化への準備は進みつつあります.9/11の日本地質学会
理事会で,地質学雑誌電子版投稿編集出版規則の内容が審議されました.現行
の規則からあまり大きく変えないように心掛けました.主要な変更点について,
お知らせいたします.
続きはこちら,,, http://www.geosociety.jp/publication/content0099.html
■ Island Arc
新しい論文が公開されています.
Advanced mosasaurs from the Upper Cretaceous Nakaminato Group in Japan:
Taichi Kato et al.
無料閲覧はこちらから https://sub.geosociety.jp/user.php(要会員ログイン)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】支部情報
──────────────────────────────────
[四国支部]
・第21回四国支部 総会・講演会のご案内
講演会:2021年12月4日(土)13:00-16:45(予定)
総 会:2020年12月4日(土)16:55-17:25(予定)(講演会終了後)
いずれもWEB開催(Zoom[予定])
参加・発表申込締切:11月19日(金)
http://www.geosociety.jp/outline/content0212.html#2021sokai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
学術会議公開シンポジウム「防災教育と災害伝承」
(ぼうさいこくたいのセッションとして開催するシンポジウム)
11日6日(土)14:30-16:00
オンライン開催
定員:1000名(Zoomウェビナー)
参加費無料・要事前申込
https://www.scj.go.jp/ja/event/2021/316-s-1106-2.html
学術会議公開シンポジウム
「21世紀の国難災害を乗り越えるレジリエンスとは:防災統合知の構築戦略」
11月6日(土)16:30-18:00
オンライン(You Tube Live配信)
参加費無料・事前申込不要
https://bosai-kokutai.jp/S40/(ぼうさいここくたいHP)
産業技術連携推進会議地質地盤情報分科会
令和3年度講演会
「地質リスクの低減に向けた地質調査・データクオリティ・解析技術」
11月22日(月)13:30-16:00
Teamsによるオンライン開催
参加費無料,要事前申込(締切:11/19正午)
https://www.gsj.jp/information/domestic/sgr/index.html
(後)第31回社会地質学シンポジウム
11月26日(金)-27日(土)
オンライン開催
https://www.jspmug.org/envgeo_sympo/31st_sympo/31st_sympo.html
第31回地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン第3回目)
12月3日(金)19:30-21:30
内容:土壌汚染状況調査の流れと調査や対策の制約・難しさについて
講師:成澤 昇(株式会社環境地質研究所・地質汚染診断士)
受講方法:ZOOMによるオンライン
申込期限:2021年11月29日まで
受講料:無料
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm# "2021.12.3&17geopol-sympo
(協)テクノオーシャン・ネットワーク(TON)
12月9日(木)-11日(土)
会場:神戸国際展示場
完全事前登録制
https://www.techno-ocean2021.jp/
第31回地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン第4回目)
12月17日(金)19:30-21:30
内容:地質汚染調査のための地層の見方と単元調査法について
講師:風岡 修(地質汚染診断士・理学博士)
受講方法:ZOOMによるオンライン
申込期限:2021年12月13日まで
受講料:無料
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm# "2021.12.3&17geopol-sympo
地区防災計画学会シンポジウム(第38回研究会)
「アフター・コロナとコミュニティ防災」
12月18日(土)13:00-15:30(予定)
オンライン開催(YouTubeによる同時配信・再放送なし)
https://gakkai.chiku-bousai.jp/ev211218.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0221.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・山田科学振興財団2022年度研究援助候補者募集(学会推薦)(学会締切22/2/4)
・千葉県銚子市一般任期付職員(ジオパーク活動に携わる職員)募集(12/17)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
河川と海岸のデジタル礫形計測:その後の進展
河川と海岸のデジタル礫形計測:その後の進展
正会員 石渡 明(原子力規制委員会)
表1.現世の河川と海岸における礫形計測データのまとめ。アナログ法のabcは礫の外接直方体の辺長をノギス(Nonius, calipers)で測り、デジタル法のabcは楕円近似の軸長のドットを数える。(クリックすると大きな画像がご覧いただけます)
石渡ほか(2019)は文献調査と実際の礫のデジタル画像の計測によって河川礫と海岸礫では形が明瞭に異なることを数値で示した。原子力発電所の敷地や敷地周辺の調査では、断層の活動性評価において、断層の上載層(多くは段丘堆積物)が河成か海成か判断する必要が生じることがあり、いくつかの原子力事業者が石渡ほか(2019)の方法による礫形計測を実施した。石渡ほか(2019)では、段丘礫を計測する前に、まず敷地周辺の現世の河川と海岸で礫を計測し、違いが数値に表れることの確認を求めている。これにより、日本各地の現世の河川と海岸における同一のデジタル計測法による礫形データが集積してきたので、2021年末時点での各原子力事業者の結果を簡単にまとめて報告する(表1)。
礫の長径、中径、短径をa, b, cとすると、石渡ほか(2019)が注目したのはab面の形の真円度circularity(4π面積/(周囲長)2:円いほど1に近づく)と楕円近似の短径長径比(c/a:扁平や棒状になるほど0に近づく)である。真円度は中山(1965)の円形度(円磨度)よりもかなり高い値になり、全部の角が尖っていてもゼロにはならない。石渡ほか(2019)は相模川と大磯海岸の礫を計測し、真円度は河川礫が<0.78、海岸礫が>0.78で海岸の方が円く、短径長径比は河川礫が>0.48、海岸礫が<0.48で海岸礫の方が扁平であることを報告した。この傾向はどの地域でも同様であり、現世の河川礫と海岸礫の真円度の境界値は下北半島南部六ヶ所村付近で0.80(日本原燃, 2019)、御前崎付近で0.82(中部電力, 2021)、能登半島西岸で0.77(北陸電力, 2021)程度であり、短径長径比の境界値は下北半島で0.42、御前崎付近で0.40程度であるが、能登半島では河川礫と海岸礫で短径長径比には差がなかった。また、積丹半島の泊地域では、現世ではなく段丘の堆積物について、従来から礫形図法などによって河成礫・海成礫と判断していたものの真円度の境界値は0.79程度との報告がある(北海道電力, 2020)。
まとめると、どの地域でも海岸礫は河川礫より真円度が高く、両者の境界値は地域によって若干異なるが、0.77と0.82の間に入る。また、海岸礫は河川礫より扁平(c/aが小)であり、両者の境界値は地域によって異なるが、0.40と0.48の間に入る。そして下北半島南部や御前崎付近のような平野や低い丘陵地では真円度の境界値は高く(0.80-0.82)、短径長径比の境界値は低い(0.40-0.42)傾向があり、能登半島や積丹半島のように山地が海に迫り岩石海岸が続くような地域では真円度の境界値が低く(0.77-0.79:つまり河川でも海岸でも礫があまり円磨されていない)、短径長径比では河川礫と海岸礫の間にあまり差が見られないという傾向があるように見える。
なお、御前崎地域(中部電力, 2021)ではc/a比よりもc/b比の方が河川礫と海岸礫の差が顕著に出るが、湘南地域(平塚市博物館地層観察会, 1986)ではc/a比の方がc/b比よりも差が顕著であり、どちらの比がより判別に有用か、優劣は決め難い。c/a比では扁平な形と棒状の形の区別がつかないのに対し、c/b比では扁平と棒状の違いが出るので、両方の比を見て判断した方がよい。
以上のように、日本各地の河川と海岸における礫形計測デジタルデータの集積によって、石渡ほか(2019)の「海岸礫は河川礫より円くて扁平である」という命題は更に確実度が増したと言える。段丘礫層が河成か海成か判断する上で、礫形のデジタル計測による数値データは、計測が容易で再現性・客観性が高い根拠資料になると考えられる。ただし、河川礫と海岸礫の礫形データの境界値は地域によって若干異なり、この差の一部は測定機器や画像処理の習熟度の違いなどによる可能性もあるが、上述のように各地域の地形の違い(平野か山地か)を反映しているように見える。また、河川と海岸でa/c比の差が認められない地域が1つあるが(能登半島西岸:ただし礫の真円度には河川と海岸で顕著な違いがある)、これも山地が海に迫り岩石海岸が続く等の地形条件によるものと思われる。様々な地形・地質条件の地域で更なるデータの集積が望まれる。事業者が礫形計測を進める中で、それまで断層の「止め」に用いていた露頭の上載層を「礫の円磨が進んでいない」として海成から河成に変更し、この露頭を断層評価の根拠から外した例もあり(北陸電力(2019)と(2021; p. 382, 388)を比較:ただし、この露頭の礫形データは示されていない)、礫形計測は原子力施設の安全審査の科学的確実化に役立ったと言える。その一方で、石渡ほか(2019)は礫形状の違いを生じる原因として礫の移動プロセスの差異(河川では一方向の水流による転動、海岸では反復する波浪による滑動)を示唆し、日本原燃(2019: p. 121)は文献調査と実際の礫移動の観察によりこの考えを支持したが、今後理論・実験両面で更に検証する必要があろう。
拙稿を読んでご意見をいただいた池田保夫会員と原子力規制庁の内藤浩行・大橋守人両氏に感謝する。
文 献
中部電力株式会社(2021)浜岡原子力発電所基準津波の策定のうち歴史記録及び津波堆積物に関する調査について(補足説明資料)。令和3年12月17日原子力規制委員会第1020回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合、資料2-4, p. 113-119. https://www2.nsr.go.jp/data/000376016.pdf
平塚市博物館地層観察会(1986)平塚市周辺の河川礫及び海浜礫の諸特性と礫調査における問題点。平塚市博物館研究報告 自然と文化, No. 9, 13-42.
北海道電力株式会社(2020)泊発電所3号炉地盤(敷地の地質・地質構造)に関するコメント回答(Hm2段丘堆積物の堆積年代に関する検討)。令和2年4月16日原子力規制委員会第856回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合、資料2-1 (1/16), p. 100-101.https://www2.nsr.go.jp/data/000308358.pdf
北陸電力株式会社(2019)志賀原子力発電所2号炉敷地の地質・地質構造について敷地内断層の活動性評価(コメント回答)。2019年10月25日原子力規制委員会第788回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合、資料1 (2/4, 3/4) p. 130-131, 191. https://www2.nsr.go.jp/data/000288087.pdf/https://www2.nsr.go.jp/data/000288091.pdf
北陸電力株式会社(2021)同上。2021年1月15日第935回審査会合、資料1 (5/6), p. 371-374. https://www2.nsr.go.jp/data/000339887.pdf
石渡明・田上雅彦・谷尚幸・大橋守人・内藤浩行(2019)海岸礫は河川礫より円くて扁平である。日本地質学会News, 22(10), 6-7. http://www.geosociety.jp/faq/content0864.html
中山正民(1965)礫浜における堆積物の諸性質について。地理学評論, 38(2), 103-120.
日本原燃株式会社(2019)再処理施設、廃棄物管理施設、MOX燃料加工施設敷地周辺陸域の活断層評価について。令和元年12月20日原子力規制委員会第325回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合、資料1-1(3/7), p. 121-147. https://www2.nsr.go.jp/data/000294958.pdf
【geo-Flash】No.538(臨時)代議員選挙:11月18日(木)18時 立候補締切です!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.538 2021/11/12┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2022年度代議員選挙:11月18日(木)18時 立候補締切です!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2022年度代議員選挙:11月18日(木)18時 立候補締切です!
─────────────────────────────────
代議員選挙の立候補届けは,11月18日(木)18時締切(必着)です.
代議員及び役員選挙は,2年に一度の選挙で,全ての代議員,全ての理事
が改選となります.立候補を予定されている方は,くれぐれも期日に遅れ
ないように立候補届けをご提出ください.
*立候補届けを提出の際には,記入漏れが無いか,必ず確認してください.
*立候補届けは,選挙管理委員会( main@geosociety.jp)宛にお届けください
(本メールに返信しないでください).
********************************************
代議員立候補受付締切:11月18日(木)18時必着
********************************************
11月11日18時現在の代議員立候補者数は以下のとおりです.
( )内の数字は定数.
■全国区 47(100)
■地方支部区 24(100)
[内訳]北海道:4(定員4)/東北:0(7)/関東:8(43)
中部:1(17)/近畿:8(11)/四国:2(4)/西日本:1(14)
※「会員のページ」の選挙に関する案内から,立候補届の書式がダウンロード
できます.詳しくは,
http://sub.geosociety.jp/members/content0106.html
(会員ページへのログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.539 2022年度代議員選挙:立候補受付まもなく締切
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.539 2021/11/16 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2022年度代議員選挙(代議員立候補まもなく締切)
【2】2022年度学会各賞候補者募集中(12/1締切)
【3】2022年度会費払込について(割引申請受付中)
【4】第13回惑星地球フォトコンテスト受付中
【5】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【6】アンケート協力依頼:第5回科学技術系専門職の男女共同参画実態調査
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】訃報:糸魚川淳二 名誉会員 ご逝去
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2022年度代議員選挙(代議員立候補まもなく締切)
──────────────────────────────────
代議員選挙の立候補届けは,11月18日(木)18時締切(必着)です.
代議員及び役員選挙は,2年に一度の選挙で,全ての代議員,全ての理事
が改選となります.立候補を予定されている方は,くれぐれも期日に遅れ
ないように立候補届けをご提出ください.
<代議員選挙>
立候補受付期間:10 月21 日(木)から11 月18 日(木)*最終日18 時必着
投票期間:12 月13 日(月)から 2022 年1月10 日(月)*最終日消印有効
※「会員のページ」の選挙に関する案内から,立候補届の書式がダウンロード
できます.詳しくは,http://sub.geosociety.jp/members/content0106.html
(会員ページへのログインが必要です)
[参考]11月16日(火)17時現在の代議員立候補者数は以下のとおりです.
( )内の数字は定数.
■全国区 74(100)
■地方支部区 57(100)
[内訳]北海道:4(定員4)/東北:3(7)/関東:13(43)
中部:13(17)/近畿:10(11)/四国:3(4)/西日本:11(14)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2022年度学会各賞候補者募集中です(12/1締切)
──────────────────────────────────
日本地質学会では今年も運営規則第16 条および各賞選考規則にした
がい,賞の候補者を募集いたします.応募書式は準備でき次第,HPに
掲載いたします.また,ご応募いただいた場合には,必ず受け取りの
お返事をお出ししますのでご確認ください.
*********************************************
応募締切:2021年12月1日(水)必着
*********************************************
詳しくは,http://sub.geosociety.jp/members/content0098.html
(会員ページへのログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2022年度会費払込について(割引申請受付開始)
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下
さいますようお願いいたします.
また,学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)
の方で,それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適
用します.
・割引会費請求書発行前受付締切:11月24日(水)
・災害に関連した会費の特別措置申請締切:11月30日(火)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第13回惑星地球フォトコンテスト受付中
──────────────────────────────────
***応募締切:2022年1月31日(月)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募フォームからでも
メール添付でもご応募いただけます.会員の皆様の応募をお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・127月11月号(予定・現在校正中):北上山地中西部の中古生代付加体を貫く
白亜紀岩脈群の岩相・年代と貫入応力解析から得られた引張場(内野隆之ほか)
/北海道北部天塩中川地域から産出した白亜紀中期セノマニアン期の珪藻化石群集
(嶋田智恵子ほか)/愛知県東部中新統北設亜層群の分布域南東部における岩相
層序の再検討:梅平砂岩部層の提唱(藪田桜子ほか)/汎用マイコンとWindows
PC による旧式EPMA(JXA-8600SX)の駆動(植田勇人ほか)/オーストラリア
北西大陸棚に分布するジュラ系天然ガス貯留層(山本和幸ほか)
・地質学雑誌電子版投稿編集出版規則の主要な変更点/雑誌完全電子化実施に
ついて...など大切なお知らせは,学会HPにも掲載しています.
ぜひご覧ください.http://www.geosociety.jp/publication/content0002.html
■ Island Arc
Depositional process of the Byk‐E tephra bed in the Chiba Section, central Japan: a marker bed defining the GSSP for the Chibanian Stage:Yasufumi Satoguchi, et al.,ほか無料閲覧はこちらから https://sub.geosociety.jp/user.php(要会員ログイン)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】アンケート協力依頼:第5回科学技術系専門職の男女共同参画実態調査
──────────────────────────────────
一般社団法人男女共同参画学協会連絡会から以下のような大規模アンケートへの
回答協力の依頼がありました。理系分野のダイバーシティ推進のため、男女問わ
ずご回答の程、是非よろしくお願い致します。
(日本地質学会ジェンダーダイバーシティ委員会)
--------------------------
【大規模アンケート実施とご協力のお願い】
第5回科学技術系専門職の男女共同参画実態調査(大規模アンケート)を実施中
です。
大規模アンケート調査は連絡会が自然科学系の研究者・技術者を取り巻く現状を
把握する重要な調査で,結果は貴重な統計的根拠として様々な場面で引用されたり,
国の政策決定の参考となるものです。研究者・技術者の声を社会に発信する場です。
特に今回は新型コロナ禍にあっての調査となります。より多くの研究者・技術
者の皆様にアンケートへの積極的なご参加をお願いしたいです.
ご協力、どうぞ宜しくお願いいたします.
1)アンケート実施方法:オンラインによる実施(web回答方式)
2)回答はこちらから https://wss3.5star.jp/survey/login/ro93keh1
※回答時間は約20-30分です.
3)アンケート回答締切:11月27日(土)締切延長しました
4)実施団体:男女共同参画学協会連絡会 http://www.djrenrakukai.org/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[四国支部]
・第21回四国支部 総会・講演会のご案内
講演会:2021年12月4日(土)13:00-16:45(予定)
総 会:2021年12月4日(土)16:55-17:25(予定)(講演会終了後)
いずれもWEB開催(Zoom[予定])
参加・発表申込締切:11月19日(金)
http://www.geosociety.jp/outline/content0212.html#2021sokai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
産業技術連携推進会議地質地盤情報分科会
令和3年度講演会
「地質リスクの低減に向けた地質調査・データクオリティ・解析技術」
11月22日(月)13:30-16:00
Teamsによるオンライン開催
参加費無料,要事前申込(締切:11/19正午)
https://www.gsj.jp/information/domestic/sgr/index.html
(後)第31回社会地質学シンポジウム
11月26日(金)-27日(土)
オンライン開催
https://www.jspmug.org/envgeo_sympo/31st_sympo/31st_sympo.html
火山国際ワークショップ2021−火山における登山者の安全確保−
12月3日(金)13:00-16:00
オンライン開催(Zoom)
参加申込・要事前申込(11/26締切)
https://www.mfri.pref.yamanashi.jp
国際シンポジウム2021−富士山登山における噴火時の安全確保−
12月5日(日)13:00-16:30
会場:富士五胡文化センター(山梨県富士吉田市)
参加申込・要事前申込(11/26締切)
https://www.mfri.pref.yamanashi.jp
(協)テクノオーシャン・ネットワーク(TON)
12月9日(木)-11日(土)
会場:神戸国際展示場
完全事前登録制
https://www.techno-ocean2021.jp/
令和3年度国総研講演会
DXなど最前線の研究一挙ご紹介
12月20日(月)9:00から
オンライン(YouTube)
視聴無料・登録不要
http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/koen2021.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0221.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・九州大学理学研究院地球惑星科学部門テニュアトラック助教公募(1/14)
・令和4年度 箱根ジオパーク学術研究助成募集(1/7)
・第1回羽ばたく女性研究者賞(マリア・スクウォドフスカ=キュリー賞)募集(12/13)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】訃報:糸魚川淳二 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
糸魚川淳二 名誉会員(名古屋大学名誉教授)が、令和3年11月11日(木)に
逝去されました(92歳)。
これまでの故人の功績を讃えるとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
なお、ご葬儀はご家族,近親者のみで11月13日にに執り行われました。
会長 磯崎行雄
(注)「崎」の正しい表記は、「大」→「立」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.540 2022年度代議員選挙の投票および会長・副会長意向調査
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.540 2021/12/7 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2022年度代議員選挙の投票および会長・副会長意向調査
【2】2022年度会費払込について(割引申請受付中)
【3】ニュース誌リニューアルと原稿募集
【4】国際年代層序表(日本語版)の更新(2021年10月改訂版)
【5】第13回惑星地球フォトコンテスト受付中
【6】TOPIC:福徳岡ノ場の噴火
【7】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2022年度代議員選挙の投票および会長・副会長意向調査
──────────────────────────────────
11月18日に代議員選挙の立候補が締め切られました.
選挙管理委員会で確認した立候補者の名簿をニュース誌11月号に掲載し,会員の
皆様に郵送いたします.なお,地方支部区においては,立候補者が定数を超えた
支部区はありませんので,全員が無投票当選となり投票は行いません(全国区
のみ投票を行います.地方支部区は,全員無投票当選となり投票は行いません).
また,この選挙と同時に,会長・副会長への立候補意思表明者に対する会員の
意向調査を実施いたします.
選挙広報・投票用紙は,12月10日(金)頃までに届くよう郵送いたします.
期日までの投票をどうぞよろしくお願いいたします.
投票期間:12月13日(月)から 2022 年1月10 日(月)*最終日消印有効
※役員選挙の詳細は(会員ページへのログインが必要です)
http://sub.geosociety.jp/members/content0106.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2022年度会費払込について(割引申請受付開始)
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下さい
ますようお願いいたします.
また,学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)の
方で,それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適用します.
【割引会費請求書最終締切】2022年3月31日(木)
自動引落を登録されている方の引き落とし日は,12月23日(木)です.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】ニュース誌リニューアルと原稿募集
──────────────────────────────────
地質学雑誌が2022年1月から完全電子化に移行するのに伴って,ニュース誌も
リニューアルいたします.読者の皆様に魅力ある誌面を目指して新企画を
スタートします.新企画も含めてニュース誌にぜひとも原稿をお寄せいただけ
ますようお願いいたします.(広報委員会)
<新企画準備中です>
プロジェクト紹介/最近のプレスリリース/あのひとの横顔...など
詳しくは,http://www.geosociety.jp/news/n166.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】国際年代層序表(日本語版)の更新(2021年10月改訂版)
──────────────────────────────────
国際地質科学連合(IUGS)の国際層序委員会(ICS)が,国際年代層序表の
最新版(v2021/10)を公開しました.最新版の層序表(日本語版)や改訂の
内容等を学会HPに掲載しています.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/name/content0062.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第13回惑星地球フォトコンテスト受付中
──────────────────────────────────
***応募締切:2022年1月31日(月)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募フォームからでも
メール添付でもご応募いただけます.会員の皆様の応募をお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】TOPIC:福徳岡ノ場の噴火
──────────────────────────────────
田村芳彦(海洋研究開発機構)
2021年8月13日の午前6時20分頃、気象衛星ひまわりが福徳岡ノ場から
の噴煙を観測した。噴火開始時刻はウエイク島のハイドロフォンに記録され
ているデータから午前5時50分と推測されている。噴煙高度は16㎞に達し
ていた。海上保安庁が8月16日に航空機による観測を実施したときは、既に
噴火は終了していたが、直径約1kmの東西にかっこ型をした二つの新島が
確認された。そして、国土地理院によると、新島の東側の陸地は9月5日に
はすでに海没していた。今回の噴火は3日間と極めて短期で、その噴出物は
1986年の噴火による軽石と類似している。この短期間に噴出して漂流した
大量の軽石が南西諸島に漂着して、被害を起こし、注目を集めている。さら
に、この軽石は黒潮にのって伊豆諸島にも到着しつつある。
詳しくは,http://www.geosociety.jp/hazard/content0104.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・127月12月号(現在校正中):愛知県東部中新統設楽層群玖老勢層に産する
礫岩:藪田桜子ほか/泥ダイアピル周辺の砕屑岩脈の方位解析による広域応力と
局所応力の検出:安邊啓明ほか/四国四万十帯カルサイト脈の同位体組成から
みた沈み込み帯地震発生深度の流体の起源:内田菜月ほか ほか計5編
・地質学雑誌電子版投稿編集出版規則の主要な変更点/雑誌完全電子化実施に
ついて...など大切なお知らせは,学会HPに掲載しています.
ぜひご覧ください.http://www.geosociety.jp/publication/content0002.html
■ Island Arc
新しい原稿が公開されています.
・Depositional process of the Byk‐E tephra bed in the Chiba Section,
central Japan:a marker bed defining the GSSP for the Chibanian Stage
:Yasufumi Satoguchi et al
・U-Pb dating of detrital zircon from Permian successions of the South Kitakami Belt,
Northeast Japan: clues to the palaeogeography of the belt
:Yuxiao Li, Makoto Takeuchi
ほか無料閲覧はこちらから https://sub.geosociety.jp/user.php(要会員ログイン)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
・支部功労賞募集中
支部活動や地質学を通して社会貢献された個人・団体を関東支部として
顕彰いたします.
募集締切:2022年1月10日(月)
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html#2021koro
[四国支部]
・第21回四国支部 総会・講演会の講演要旨を公開しました.
http://www.geosociety.jp/outline/content0212.html#2021sokai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(協)テクノオーシャン・ネットワーク(TON)
12月9日(木)-11日(土)
会場:神戸国際展示場
完全事前登録制
https://www.techno-ocean2021.jp/
日本学術会議主催学術フォーラム:「我が国の学術政策と研究力に関する
学術フォーラム―我が国の研究力の現状とその要因を探る―」
12月11日(土)10:00-17:30
オンライン開催
参加費無料・要事前申込
https://www.scj.go.jp/ja/event/2021/315-s-1211.html
地区防災計画学会シンポジウム(第38回研究会)
「アフター・コロナとコミュニティ防災」
12月18日(土) 13:00-15:30(予定)
場所 オンライン開催(YouTubeによる同時配信等)
対象 地域防災力の強化や地区防災計画づくりに興味のある方
参加費無料・地区防災計画学会HPで申し込み
https://gakkai.chiku-bousai.jp/ev211218.html
学術会議公開シンポジウム:「生命科学分野におけるジェンダー・
ダイバーシティ−大学・企業・学協会におけるダイバーシティ推進に向けた
取り組み−」
12月19日(日)14:00-18:00
オンライン開催(Zoom)
参加費無料・要事前申込
https://www.scj.go.jp/ja/event/2021/317-s-1219.html
海と地球のシンポジウム2021
12月20日(月)-21日(火)
主催:AORI・JAMSTEC
開催方法:実会場とオンライン会場を使ったハイブリッド形式
※感染症の状況により変更・中止する場合があります.
参加費無料・要事前登録(12/13締切)
https://www.jamstec.go.jp/j/pr-event/ocean-and-earth2021/
****2022年****
第36回地質調査総合センターシンポジウム
3次元で解き明かす東京都区部の地下地質
2月25日(金)13:00-16:55
開催形態:オンライン形式
参加費無料、事前登録制
https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/index.html
第27回日本災害医学会総会・学術集会
3月3日(木)-5日(土)
会場:広島国際会議場・広島市文化交流会館ほか
テーマ:災害医療のパラダイムシフトー何を攻め・守り・育てるのかー
https://site2.convention.co.jp/27jadm/
(共)岩石―水相互作用国際会議(WRI-17)
7月30日(土)-8月4日(木)
会場:仙台市
https://www.wri17.com/
(後)第9回国際地学教育会議
8月21 日(日)-25 日(木)
場所:くにびきメッセ(島根県コンベンションセンター)
https://ja.geoscied9.org/
日本地質学会第129年学術大会(2022東京・早稲田大会)
9月4日(日)-6日(火)
会場:早稲田大学 早稲田キャンパス(東京都新宿区西早稲田)
※関連行事「地質情報展2022とうきょう」は同会場で9/3-/5開催予定.
国際ゴンドワナ研究連合(IAGR)2022年総会及び
第19回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム
9月23日-25日(シンポジウム)
9月26日-27日(峨眉山巨大火山区野外巡検)
場所:中国四川省成都工科大学
予備登録:2022年1月15日まで
https://www.data-box.jp/pdir/4aa617ecc00845c284f085edba48eec5
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0221.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・島根大学総合理工学部地球科学科 (鉱物学・岩石鉱物学) 公募(1/14)
・福岡大学理学部地球圏科学科地球科学分野教授,准教授または講師公募(2/1)
・産総研イノベーションスクール第16期スクール生(特別研究員)募集(1/4)
・東京大学地震研究所2022年度大型計算機共同利用公募研究(1/4)
・2022年度「深田研究助成」(2/4)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.541 代議員選挙の投票および会長・副会長意向調査中
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.541 2021/12/21 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2022年度代議員選挙の投票および会長・副会長意向調査中
【2】2022年度会費払込について
【3】名誉会員候補者の募集が開始されました
【4】ニュース誌リニューアルと原稿募集
【5】第13回惑星地球フォトコンテスト受付中
【6】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】事務局年末年始休業(12/29-1/5)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2022年度代議員選挙の投票および会長・副会長意向調査中
──────────────────────────────────
今回の代議員選挙は,全国区のみ投票を行います.地方支部区は,全員無投票
当選となり投票は行いません.また,選挙と同時に,会長・副会長への立候補
意思表明者に対する会員の意向調査を実施いたします.
選挙広報・投票用紙は,12月10日に発送いたしましたので,期日までの投票を
どうぞよろしくお願いいたします.
*************************************
投票締切:2022 年1月10 日(月)*最終日消印有効
*************************************
※選挙の詳細は(会員ページへのログインが必要です)
http://sub.geosociety.jp/members/content0106.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2022年度会費払込について(割引申請受付開始)
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下さい
ますようお願いいたします.近日,請求書兼郵便振替用紙を発送します.
自動引落を登録されている方の引き落とし日は,12月23日(木)です.
また,学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)の
方で,それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適用します.
【割引会費請求書最終締切】2022年3月31日(木)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】名誉会員候補者の募集が開始されました
──────────────────────────────────
募集期間:2021年12月20日(木)から2022年2月10日(木)
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:例えば,,,地質学への顕著な貢献/地質学会の運営
と発展への貢献/教育現場や企業などでの活動を通じた地質学の普及と振興への
貢献 など
(注) 上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することはでき
ませんが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
(名誉会員推薦委員会 佐々木和彦)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】ニュース誌リニューアルと原稿募集
──────────────────────────────────
地質学雑誌が2022年1月から完全電子化に移行するのに伴って,ニュース誌
もリニューアルを予定しています.
読者の皆様に魅力ある誌面を目指して新企画をスタートします.新企画も含
めてニュース誌にぜひとも原稿をお寄せいただけますようお願いいたします.
(広報委員会)
<新企画準備中です>
プロジェクト紹介/最近のプレスリリース/あのひとの横顔...など
詳しくは,http://www.geosociety.jp/news/n166.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第13回惑星地球フォトコンテスト受付中
──────────────────────────────────
***応募締切:2022年1月31日(月)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募フォームからでも
メール添付でもご応募いただけます.会員の皆様の応募をお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
地質学雑誌は,127巻12月号をもって冊子体の発行を終了いたします.来年
(128巻)からは完全電子化となり,J-STAGE上でどなたでも閲覧していた
だけます.https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/-char/ja
地質学雑誌電子版投稿編集出版規則の主要な変更点/雑誌完全電子化実施について...
など大切なお知らせは,学会HPに掲載しています.
http://www.geosociety.jp/publication/content0002.html
■ Island Arc
無料閲覧はこちらから https://sub.geosociety.jp/user.php(要会員ログイン)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
・支部功労賞募集中
支部活動や地質学を通して社会貢献された個人・団体を関東支部として
顕彰いたします.
募集締切:2022年1月10日(月)
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html#2021koro
[四国支部]
・第21回四国支部 総会・講演会の講演要旨を公開しました.
http://www.geosociety.jp/outline/content0212.html#2021sokai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)原子力総合シンポジウム2021(オンライン)
1月17日(月)13:30-16:30
要事前登録
https://www.aesj.net/symp20220117
第235回地質汚染・災害イブニングセミナー(オンライン)
1月21日(金)18:30-20:30
講師:新里忠史 (日本原子力研究開発機構)
演題:福島の森林域を中心とした放射性セシウムの分布と移行状況
参加費:会員:無料,非会員:1,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
(後)第36回地質調査総合センターシンポジウム(オンライン)
3次元で解き明かす東京都区部の地下地質
2月25日(金)13:00-16:55
参加費無料、事前登録制
https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/index.html
第56回日本水環境学会年会(オンライン)
3月16日(水)-18日(金)
参加申込締切:2月28日
https://www.jswe.or.jp/event/lectures/2021per.html
(後)第59回アイソトープ・放射線研究発表会
7月6日(水)-8日(金)
会場:東京大学農学部 弥生講堂ほか(東京都文京区弥生1-1-1)
演題登録期間:1月6日(木)-2月28日(月)17時
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2022/top
(共)岩石―水相互作用国際会議(WRI-17)
7月30日(土)-8月4日(木)
会場:仙台市
https://www.wri17.com/
(後)第9回国際地学教育会議
8月21 日(日)-25 日(木)
場所:くにびきメッセ(島根県コンベンションセンター)
https://ja.geoscied9.org/
日本地質学会第129年学術大会(2022東京・早稲田大会)
9月4日(日)-6日(火)
会場:早稲田大学早稲田キャンパス(東京都新宿区西早稲田)
※関連行事「地質情報展2022とうきょう」は同会場で9/3-/5開催予定
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0222.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・千葉県職員採用選考考査(地質職)の実施(受付締切1/6)
・徳島大学理工学域自然科学系(地球科学分野:堆積・地層学)講師公募(1/14)
・鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会研究員募集(1/21)
・令和4年度むつ市下北ジオパーク推進員募集(1/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】事務局年末年始休業(12/29-1/5)
──────────────────────────────────
学会事務局は年末年始は,下記の通り業務をお休みさせて頂きます。
2021年12月29日(水)から 2022年1月5日(水)
2022年1月6日(水)より通常通りの営業となります。
本年も大変お世話になりありがとうございました。
来年もまた引き続きよろしくお願い申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.542 忘れずに投票しましょう!代議員選挙/正副会長意向調査
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.542 2022/1/6 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】年頭のご挨拶
【2】2022年度代議員選挙の投票および会長・副会長意向調査中
【3】会員名簿の発行中止のお知らせ
【4】地質学雑誌オンデマンド印刷版年間購読受付のお知らせ
【5】2022年度会費払込について
【6】名誉会員候補者の募集が開始されました
【7】ニュース誌リニューアルと原稿募集
【8】第13回惑星地球フォトコンテスト受付中
【9】コラム 河川と海岸のデジタル礫形計測:その後の進展
【10】支部情報
【11】その他のお知らせ
【12】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】年頭のご挨拶
──────────────────────────────────
会長 磯崎行雄
謹賀新年
ワクチン接種後への当初の楽観的予想とは異なり、2021年のパンデミックの
現状はずっと深刻で、いまだ予断を許さない状況にあります。コロナ以前の比較
的安定継続していた生活(通勤・通学そして研究・教育活動)のあり方は突然
終了しました。そんな中、我が地質学会も様々な新対応を試みてきました。
全文はこちらから,http://www.geosociety.jp/outline/content0137.html
(注)「崎」の正しい表記は、「大」→「立」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2022年度代議員選挙の投票および会長・副会長意向調査中
──────────────────────────────────
今回の代議員選挙は,全国区のみ投票を行います.地方支部区は,全員無投票
当選となり投票は行いません.また,選挙と同時に,会長・副会長への立候補
意思表明者に対する会員の意向調査を実施中です.
選挙広報・投票用紙は,12月10日に発送いたしました.期日までに忘れずに
投票いただきますようお願いいたします.
*************************************
投票締切:2022 年1月10 日(月)*最終日消印有効
*************************************
※選挙の詳細は(会員ページへのログインが必要です)
http://sub.geosociety.jp/members/content0106.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】会員名簿の発行中止のお知らせ
──────────────────────────────────
これまで2年に一度紙媒体の会員名簿を発行してまいりましたが,昨今の個人
情報保護の観点や関連諸団体の名簿発行状況等も鑑み,今後は紙媒体の会員名簿
の発行は行わないことが昨年12月11日の理事会において決議されました.
今後は,現在導入準備中のクラウド型会員管理システムを利用し,会員個人が
WEB上で必要な会員情報を検索・確認していただけるよう対応を検討中です.
また,これまで会員名簿に掲載されていた,名簿以外の情報(学会規則類,関連
学協会,賛助会員等の情報など)はそのほとんどが学会HP上でご確認いただけ
ます.
これまでの名簿機能(サービス)をそこなわないよう,順次対応を進めてまいり
ます.ご理解のほど何卒よろしくお願い申し上げます.
2022年1月 日本地質学会総務委員会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地質学雑誌オンデマンド印刷版年間購読受付のお知らせ
──────────────────────────────────
地質学雑誌は,2021年(127巻)12月号をもって冊子体の発行を終了し,2022年
(128巻)より完全電子化されました.掲載論文はJ-STAGE上でどなたでも無料で
閲覧していただけます.ただし,WEB上での論文閲覧が難しい方への対応として,
当⾯地質学雑誌オンデマンド印刷版を作成し,年間購読のお申込を受け付けます.
対象:日本地質学会会員(個人)に限る
年間購読料:12,000 円(送料込)※学会年会費とは別のご請求となります.
受付締切:2022年3月15日(火)
詳細は,http://www.geosociety.jp/news/n169.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2022年度会費払込について(割引申請受付中)
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下さい
ますようお願いいたします.昨年12月に請求書兼郵便振替用紙を発送しました
ので,ご送金をお願いいたします.また,自動引落を登録されている方は,
12月23日に引き落としとなっています.
学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)の
方で,それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適用します.
【割引会費請求書最終締切】2022年3月31日(木)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】名誉会員候補者の募集が開始されています
──────────────────────────────────
募集期間:2021年12月20日(木)から2022年2月10日(木)
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:例えば,,,地質学への顕著な貢献/地質学会の運営
と発展への貢献/教育現場や企業などでの活動を通じた地質学の普及と振興への
貢献 など
(注) 上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することはでき
ませんが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
(名誉会員推薦委員会 佐々木和彦)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】ニュース誌リニューアルと原稿募集
──────────────────────────────────
地質学雑誌が2022年1月から完全電子化に移行するのに伴って,ニュース誌
もリニューアルを予定しています.
読者の皆様に魅力ある誌面を目指して新企画をスタートします.新企画も含
めてニュース誌にぜひとも原稿をお寄せいただけますようお願いいたします.
(広報委員会)
<新企画準備中です>
プロジェクト紹介/最近のプレスリリース/あのひとの横顔...など
詳しくは,http://www.geosociety.jp/news/n166.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】第13回惑星地球フォトコンテスト受付中
──────────────────────────────────
***応募締切:2022年1月31日(月)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募フォームからでも
メール添付でもご応募いただけます.会員の皆様の応募をお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】コラム 河川と海岸のデジタル礫形計測:その後の進展
──────────────────────────────────
正会員 石渡 明
石渡ほか(2019)は文献調査と実際の礫のデジタル画像の計測によって河川礫と
海岸礫では形が明瞭に異なることを数値で示した。原子力発電所の敷地や敷地周
辺の調査では、断層の活動性評価において、断層の上載層(多くは段丘堆積物)
が河成か海成か判断する必要が生じることがあり、いくつかの原子力事業者が
石渡ほか(2019)の方法による礫形計測を実施した。
続きはこちらから、、、http://www.geosociety.jp/faq/content0056.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】支部情報
──────────────────────────────────
[西日本支部]
・支部令和3年度総会・第172回例会の案内
3月5日(土)オンライン開催(ZOOM)
参加費無料・要事前申込(1月31日〆切)
発表会終了後にオンライン懇親会を開催します.
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
[関東支部]
・アウトリーチ巡検:川の防災と川が作った地形を巡るー首都圏外郭放水路
見学と春日部周辺,中川低地の地形観察ー
2月20日(日)10:30-16:30(予定)
講師:杉内由佳氏(元・埼玉県立川の博物館)
参加申込期間:1月23日(日)-2月13日(日)
・支部功労賞募集中
支部活動や地質学を通して社会貢献された個人・団体を関東支部として
顕彰いたします.
募集締切:2022年1月10日(月)
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
[四国支部]
・第21回四国支部 総会・講演会の講演要旨を公開しています.
http://www.geosociety.jp/outline/content0212.html#2021sokai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)原子力総合シンポジウム2021(オンライン)
1月17日(月)13:30-16:30
要事前登録
https://www.aesj.net/symp20220117
第31回 地質汚染調査浄化技術研修会(オンライン)
1月28日(金)19:30-21:30
内容:地質汚染調査のための地層の見方と単元調査法について
講師:風岡 修(地質汚染診断士、理学博士)
申込期限:2022年1月25日 受講料:無料
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
(後)第36回地質調査総合センターシンポジウム(オンライン)
3次元で解き明かす東京都区部の地下地質
2月25日(金)13:00-16:55
参加費無料、事前登録制
https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/index.html
地質学史懇話会
6月18日(土)13:30-16:30
会場:早稲田奉仕園(東京メトロ東西線早稲田駅下車徒歩5分)
オンラインとハイブリッド
講演者;中川智視,五味 篤
問い合わせ:矢島道子
(後)第59回アイソトープ・放射線研究発表会
7月6日(水)-8日(金)
会場:東京大学農学部 弥生講堂ほか(東京都文京区弥生1-1-1)
演題登録期間:1月6日(木)-2月28日(月)17時
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2022/top
(共)岩石―水相互作用国際会議(WRI-17)
7月30日(土)-8月4日(木)
会場:仙台市
https://www.wri17.com/
(後)第9回国際地学教育会議
8月21 日(日)-25 日(木)
会場:くにびきメッセ(島根県コンベンションセンター)
https://ja.geoscied9.org/
日本地質学会第129年学術大会(2022東京・早稲田大会)
9月4日(日)-6日(火)
会場:早稲田大学早稲田キャンパス(東京都新宿区西早稲田)
※関連行事「地質情報展2022とうきょう」は同会場で9/3-/5開催予定
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0222.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・丹波市立丹波竜化石工房のエデュケーター(教育普及専門員)募集(2/4)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.543 2022年度代議員選挙(結果報告)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.543 2022/1/18 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】2022年度代議員選挙および会長・副会長意向調査結果報告
【2】会員名簿の発行中止のお知らせ
【3】地質学雑誌オンデマンド印刷版年間購読受付のお知らせ
【4】2022年度会費払込について
【5】名誉会員候補者の募集が開始されています
【6】第13回惑星地球フォトコンテスト受付中
【7】会員の学術・教育・社会貢献活動
【8】フィールドワークにおける性暴力・セクハラに関するアンケート
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
【12】(探しています)事務局からおたずね
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2022年度代議員選挙および会長・副会長意向調査(結果報告)
──────────────────────────────────
選挙規則ならびに選挙細則に基づき,標記選挙を実施いたしましたので結果を
ご報告いたします.あわせて会長・副会長立候補者への意向調査結果もご報告いたします.なお,全ての立候補者の方に,個別に結果を郵送いたしました.
※選挙結果の詳細は(要会員ログイン)
http://sub.geosociety.jp/members/content0108.html
※2022年度代議員および役員選挙について(要会員ログイン)
http://sub.geosociety.jp/members/content0106.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】会員名簿の発行中止のお知らせ
──────────────────────────────────
これまで2年に一度紙媒体の会員名簿を発行してまいりましたが,昨今の個人
情報保護の観点や関連諸団体の名簿発行状況等も鑑み,今後は紙媒体の会員名簿
の発行は行わないことが昨年12月11日の理事会において決議されました.
今後は,現在導入準備中のクラウド型会員管理システムを利用し,会員個人が
WEB上で必要な会員情報を検索・確認していただけるよう対応を検討中です.
また,これまで会員名簿に掲載されていた,名簿以外の情報(学会規則類,関連
学協会,賛助会員等の情報など)はそのほとんどが学会HP上でご確認いただけ
ます.
これまでの名簿機能(サービス)をそこなわないよう,順次対応を進めてまいり
ます.ご理解のほど何卒よろしくお願い申し上げます.
2022年1月 日本地質学会総務委員会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】地質学雑誌オンデマンド印刷版年間購読受付のお知らせ
──────────────────────────────────
地質学雑誌は,2021年(127巻)12月号をもって冊子体の発行を終了し,2022年
(128巻)より完全電子化されました.掲載論文はJ-STAGE上でどなたでも無料で
閲覧していただけます.ただし,WEB上での論文閲覧が難しい方への対応として,
当⾯地質学雑誌オンデマンド印刷版を作成し,年間購読のお申込を受け付けます.
対象:日本地質学会会員(個人)に限る
年間購読料:12,000 円(送料込)※学会年会費とは別のご請求となります.
受付締切:2022年3月15日(火)
詳細は,http://www.geosociety.jp/news/n169.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2022年度会費払込について(割引申請受付中)
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下さい
ますようお願いいたします.昨年12月に請求書兼郵便振替用紙を発送しました
ので,ご送金をお願いいたします.また,自動引落を登録されている方は,
12月23日に引き落としとなっています.
学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)の
方で,それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適用します.
【割引会費請求書最終締切】2022年3月31日(木)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】名誉会員候補者の募集が開始されています
──────────────────────────────────
募集締切:2022年2月10日(木)
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:例えば,,,地質学への顕著な貢献/地質学会の運営
と発展への貢献/教育現場や企業などでの活動を通じた地質学の普及と振興への
貢献 など
(注) 上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することはでき
ませんが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
(名誉会員推薦委員会 佐々木和彦)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】第13回惑星地球フォトコンテスト受付中
──────────────────────────────────
***応募締切:2022年1月31日(月)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募フォームからでも
メール添付でもご応募いただけます.会員の皆様の応募をお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】会員の学術・教育・社会貢献活動
──────────────────────────────────
地質学会員の「学術,教育,社会貢献活動」をご紹介しています.皆様からの
情報をお待ちしています.
http://www.geosociety.jp/science/content0109.html
*新妻信明会員・岡田 誠会員・菅沼悠介会員
読売新聞夕刊に、「チバニアン外伝」(計8回の連載予定)の掲載が始まりました。
チバニアン承認の礎となる房総半島の地層研究に関わった地質学者の物語です。
*大柳良介会員らをによる
「Hadal aragonite records venting of stagnant paleoseawater in the hydrated
forearc mantle」(Communications Earth & Environment)
の掲載内容がJAMSTECからプレスリリースされました.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】「フィールドワークにおける性暴力・セクシュアルハラスメントに関する
実態調査アンケート」協力のお願い
──────────────────────────────────
共同研究グループ「フィールドワークとハラスメント(HiF)」より標記アンケート
への協力依頼がありましたので,会員の皆様にお知らせいたします.
***************************
共同研究グループ「フィールドワークとハラスメント(HiF)」では、フィールド
ワークという研究手法を採る学生や研究者がフィールドで直面する性被害とその
対策に関する実態把握のために、表題のアンケート調査を行います。性被害に関
する情報収集を通して、フィールドで起こる性暴力、セクシュアルハラスメント
についての対策と啓発をより充実させていくことを目的としています。
なお、本アンケートは、学問分野ごとのフィールドワーク実施状況の調査、およ
び被害防止のための事前学習の有無に関する調査を兼ねております。性被害経験
のない方も、ぜひ回答にご協力ください。
<回答期限:2022年2月15日>
アンケートの趣旨詳細,回答はこちらから
https://safefieldwork.live-on.net/survey/purposes-of-this-survey/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】支部情報
──────────────────────────────────
[西日本支部]
・支部令和3年度総会・第172回例会の案内
3月5日(土)オンライン開催(ZOOM)
参加費無料・要事前申込(1月31日締切)
発表会終了後にオンライン懇親会を開催します.
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
[関東支部]
・アウトリーチ巡検:川の防災と川が作った地形を巡るー首都圏外郭放水路
見学と春日部周辺,中川低地の地形観察ー
2月20日(日)10:30-16:30(予定)
講師:杉内由佳氏(元・埼玉県立川の博物館)
参加申込期間:1月23日(日)-2月13日(日)
・オンライン講演会「県の石 神奈川県」
3月5日(土)13:00-16:05
対象:会員(定員に余裕のある場合,非会員も受け付けます)
参加費:無料(要事前申込)
申込期間:2月1日(火)-24日(木)まで
講演要旨を支部HPに掲載中.
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html#2022kennoishi
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
日本博物館協会緊急フォーラム(オンライン)
文化審議会答申「博物館法制度の今後の在り方」を読み解く
−博物館の振興に向けて−
1月28日(金)13:30-17:00
zoomによるオンライン開催
参加定員:500名・参加費無料(要参加申込)
https://www.j-muse.or.jp
第31回 地質汚染調査浄化技術研修会(オンライン)
1月28日(金)19:30-21:30
内容:地質汚染調査のための地層の見方と単元調査法について
講師:風岡 修(地質汚染診断士、理学博士)
申込期限:1月25日 受講料:無料
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
第35回地質調査総合センター シンポジウム(オンライン)
「ゼロエミッション社会実現に向けたCCSにおける産総研の取り組み」
2月10日(木)13:00-17:15(配信開始 12:30を予定)
参加費:無料(事前登録制)CPD:4単位
https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo35/index.html
(後)第36回地質調査総合センター シンポジウム(オンライン)
「3次元で解き明かす東京都区部の地下地質」
2月25日(金)13:00-16:55(配信開始 12:45を予定)
参加費:無料(事前登録制)CPD:3.5単位
https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo36/index.html
防災科学技術研究所令和3年度成果発表会
来るべき国難夕災害に備えて2022
国難にしないために:モノで守り,行動を変える
2月28日(月)13:00-17:00
会場:東京国際フォーラム(会場参加/オンライン配信)
参加無料,会場参加は要事前申込(2/14締切)
https://www.bosai.go.jp/info/event/2021/seika/index.html
第35回ヒマラヤーカラコラム―チベットワークショップ
5月11日(水)-13日(金)
場所:ネパール・ポカラ(会場は近日決定)
野外巡検:カリガンダキ河コース等4コース(5日間-日帰り)予定
問い合わせ先:Dr. Kabi Raj Paudyal
E-mail: paudyalkabi1976[アット]gmail.com([アット]を@マークにして下さい)
https://ngs.org.np/hkt-2022
地質学史懇話会
6月18日(土)13:30-16:30
会場:早稲田奉仕園(東京メトロ東西線早稲田駅下車徒歩5分)
オンラインとハイブリッド
講演者;中川智視,五味 篤
問い合わせ:矢島道子
(後)第59回アイソトープ・放射線研究発表会
7月6日(水)-8日(金)
会場:東京大学農学部 弥生講堂ほか(東京都文京区弥生1-1-1)
演題登録期間:1月6日(木)-2月28日(月)17時
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2022/top
(共)岩石―水相互作用国際会議(WRI-17)
7月30日(土)-8月4日(木)
会場:仙台市
https://www.wri17.com/
(後)科学教育研究協議会第68回全国研究大会(岡山大会)
8月10日(水)-12日(金)
会場 岡山理科大学 岡山キャンパス
https://kakyokyo.org/
(後)第9回国際地学教育会議
8月21 日(日)-25 日(木)
会場:くにびきメッセ(島根県コンベンションセンター)
https://ja.geoscied9.org/
日本地質学会第129年学術大会(2022東京・早稲田大会)
9月4日(日)-6日(火)
会場:早稲田大学早稲田キャンパス(東京都新宿区西早稲田)
※関連行事「地質情報展2022とうきょう」は同会場で9/3-/5開催予定
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0222.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・山田科学振興財団2022年度研究援助候補者募集(学会推薦)(学会締切2/4)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】(探しています)事務局からおたずね
──────────────────────────────────
1月12日付,ゆうちょダイレクト(インターネットバンキング)より,
「送金人:ニホンチシツガッカイ」という入金がありました.学会費と思われます
が,どなたからの振込か不明です.
お心当たりの方は,学会事務局(main[at]geosociety.jp)までご連絡ください.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.544 【重要】学術大会セッションの変更について
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.544 2022/2/1 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2022東京・早稲田]【重要】学術大会セッションの変更について
【2】[2022東京・早稲田]トピックセッション提案募集
【3】第2回JABEEオンラインシンポ「昔と違う イマドキのフィールド教育」
【4】会員名簿の発行中止のお知らせ
【5】地質学雑誌オンデマンド印刷版年間購読受付のお知らせ
【6】2022年度会費払込について(割引申請受付中)
【7】名誉会員候補者の募集について
【8】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【9】地震火山地質こどもサマースクール開催地募集
【10】会員の学術・教育・社会貢献活動
【11】支部情報
【12】その他のお知らせ
【13】公募情報・各賞助成情報等
【14】(探しています)事務局からおたずね
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2022東京・早稲田]【重要】学術大会セッションの変更について
──────────────────────────────────
本年9月開催予定の東京・早稲田大会から,セッションを「トピックセッション」,「ジェネラルセッション」,「アウトリーチセッション」の3カテゴリに変更しま
す.従来のレギュラーセッションは発展的に解消します.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0142.html
このセッション変更に関するZoom説明会を2月10日(木)12:30から開催します。
セッション世話人に限らず,学術大会に参加される方,講演を予定されている方
は是非ご参加ください.
日時: 2022年2月10日(木)12:30から(40分程度を予定)
https://us02web.zoom.us/j/87423858446
ミーティングID: 874 2385 8446
パスコード: 885804
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2022東京・早稲田]トピックセッション提案募集──────────────────────────────────
第129年(2022年)学術大会を本年9月4日(日)-6日(火)に早稲田大学で
開催する予定です.トピックセッション提案を下記の要領で募集します.
*******************************
締切:2022年3月10日(木)
*******************************
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0143.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】第2回JABEEオンラインシンポ「昔と違う イマドキのフィールド教育」
──────────────────────────────────
地質学教育においてフィールド教育は最も基本的な教育項目であり、地質学を
学ぶ上で最も重要なもののひとつです。また、地質技術者として社会で活躍す
るために必要な技術といえます。昔からフィールド教育は大学で活発に展開さ
れてきましたが、時代と共に大学をめぐる状況も変わり、フィールド教育の実施
方法も多様になっています。地質技術者教育委員会では、本シンポジウムにお
いてJABEE認定大学におけるフィールド教育の実際を報告してもらい、それを
題材として現代に即したフィールド教育について考えてみることにしました。
日程:2022年3月6日(日)14時から(zoom)
参加費無料,
参加申込締切:3月3日(木)
※締切後,zoomアクセスURLをメールでお知らせします.
講演概要,参加申込等はこちらから
http://www.geosociety.jp/science/content0141.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】会員名簿の発行中止のお知らせ
──────────────────────────────────
これまで2年に一度紙媒体の会員名簿を発行してまいりましたが,昨今の個人
情報保護の観点や関連諸団体の名簿発行状況等も鑑み,今後は紙媒体の会員
名簿の発行は行わないことが昨年12月11日の理事会において決議されました.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/news/n168.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質学雑誌オンデマンド印刷版年間購読受付のお知らせ
──────────────────────────────────
地質学雑誌は,2021年(127巻)12月号をもって冊子体の発行を終了し,2022年
(128巻)より完全電子化されました.掲載論文はJ-STAGE上でどなたでも無料で
閲覧していただけます.ただし,WEB上での論文閲覧が難しい方への対応として,
当面地質学雑誌オンデマンド印刷版を作成し,年間購読のお申込を受け付けます.
対象:日本地質学会会員(個人)に限る
年間購読料:12,000 円(送料込)※学会年会費とは別のご請求となります.
受付締切:2022年3月15日(火)
詳細は,http://www.geosociety.jp/news/n169.html
(注)地質学雑誌完全電子化に伴い,冊子体の発行はニュース誌のみとなって
います.2022年1月号からは,ニュース誌のみを郵送でお届けしています.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】2022年度会費払込について(割引申請受付中)
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会運営規則により,次年分の会費を前納下さい
ますようお願いいたします.昨年12月に請求書兼郵便振替用紙を発送しました
ので,ご送金をお願いいたします.また,自動引落を登録されている方は,
12月23日に引き落としとなっています.
学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)の
方で,それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適用します.
【割引会費請求書最終締切】2022年3月31日(木)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】名誉会員候補者の募集について
──────────────────────────────────
募集締切:2022年2月10日(木)
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:例えば,,,地質学への顕著な貢献/地質学会の運営
と発展への貢献/教育現場や企業などでの活動を通じた地質学の普及と振興への
貢献 など
(注) 上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することはでき
ませんが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
(名誉会員推薦委員会 佐々木和彦)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・128巻:新しい論文等が公開されています.
(レター)内野隆之ほか:根田茂帯・北部北上帯境界で見出された古生代後期の
含ざくろ石低温高圧型結晶片岩とその帰属
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/-char/ja
■ Island Arc
・新しい論文等が公開されています.
Hirokuni Abe: et al., Changes in elements and magnetic properties of Sendai
Bay sediments caused by the 2011 Tohoku-oki tsunami ほか
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14401738/0/ja
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】2023及び24年度以降年度地震火山地質こどもサマースクール開催地募集
──────────────────────────────────
募集締切:2022年2月21日(月)
地震火山地質こどもサマースクールは、1999年夏から小・中・高校生を対象に
はじまった行事で、現在、日本地震学会、日本火山学会、日本地質学会が共同
で実施する、地球科学関連では最大規模の体験学習講座です。今回、下記に
より関東地震100年にあたる2023年度の開催地および2024年度以降の実施
を希望する開催地を公募いたします。
なお、2022年度の第22回地震火山地質こどもサマースクールは、2022年8月
17-18日に群馬県嬬恋村・長野原町等で開催予定です。2023年度に開催希望
の方は、スタッフとして2名前後,2022年の準備段階から参加していただく
ことを歓迎いたします。
応募資格など詳しくは, https://kodomoss.jp/applications/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】会員の学術・教育・社会貢献活動
──────────────────────────────────
地質学会員の「学術,教育,社会貢献活動」をご紹介しています.皆様からの
情報をお待ちしています.
*田村芳彦会員が研究を進めている西之島の火成活動に関する最新の知見が
コズミックフロントで紹介されます.
放送予定:NHKBSプレミアム,2月2日(水)23:45-
*宇野正起会員らによる「Volatile-consuming reactions fracture rocks and
self-accelerate fluid flow in the lithosphere」(Proceedings of the National Academy
of Sciences) 119, 3, e2110776118. の掲載内容が東北大学からプレスリリース
されました.
http://www.geosociety.jp/science/content0109.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
・アウトリーチ巡検:川の防災と川が作った地形を巡るー首都圏外郭放水路
見学と春日部周辺,中川低地の地形観察ー
2月20日(日)10:30-16:30(予定)
講師:杉内由佳氏(元・埼玉県立川の博物館)
参加申込期間:1月23日(日)-2月13日(日)
・オンライン講演会「県の石 神奈川県」
3月5日(土)13:00-16:05
対象:会員(定員に余裕のある場合,非会員も受け付けます)
参加費:無料(要事前申込)
申込期間:2月1日(火)-24日(木)まで
講演要旨を支部HPに掲載中.
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html#2022kennoishi
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
東青ヶ島海丘カルデラ熱水サイトシンポジウム(オンライン)
2月24日(木)13:00から
会場:オンライン開催(zoom)
主催:JAMSTEC海洋機能利用部門海底資源センター
http://www.geosociety.jp/outline/content0222.html#2
(後)第36回地質調査総合センター シンポジウム(オンライン)
「3次元で解き明かす東京都区部の地下地質」
2月25日(金)13:00-16:55
参加費:無料(事前登録制)CPD:3.5単位
https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo36/index.html
2022年堆積学会オンライン大会
4月23日(土)-24日(日)
Zoomを使用したオンライン開催
http://www.sediment.jp/04nennkai/2022/2022online_annai.html
(後)第59回アイソトープ・放射線研究発表会(オンライン)
7月6日(水)-8日(金)→オンライン開催に変更になりました
演題登録締切:2月28日(月)17時
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2022/top
(共)岩石―水相互作用国際会議(WRI-17)
7月30日(土)→2023年8月に延期となりました
会場:仙台市
https://www.wri17.com/
(後)科学教育研究協議会第68回全国研究大会(岡山大会)
8月10日(水)-12日(金)
会場 岡山理科大学 岡山キャンパス
https://kakyokyo.org/
(後)第9回国際地学教育会議
8月21 日(日)-25 日(木)
会場:くにびきメッセ(島根県コンベンションセンター)
https://ja.geoscied9.org/
日本地質学会第129年学術大会(2022東京・早稲田大会)
9月4日(日)-6日(火)
会場:早稲田大学早稲田キャンパス(東京都新宿区西早稲田)
※関連行事「地質情報展2022とうきょう」は同会場で9/3-/5開催予定
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0222.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・JAMSTEC超先鋭研究開発部門超先鋭研究プログラムポスドク研究員公募(2/18)
・上富良野町ジオパーク専門員(地域おこし協力隊)募集(2/28)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【14】(探しています)事務局からおたずね
──────────────────────────────────
1月12日付,ゆうちょダイレクト(インターネットバンキング)より,
「送金人:ニホンチシツガッカイ」という入金がありました.学会費と思われ
ますが,どなたからの振込か不明です.
お心当たりの方は,学会事務局(main[at]geosociety.jp)までご連絡ください.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
童謡詩人金子みすゞの地学的側面
童謡詩人金子みすゞの地学的側面
正会員 石渡 明
2011年3月11日の東日本大震災からしばらくの間,AC ジャパン(公共広告機構)が金子みすゞの「こだまでしょうか」という詩をラジオやテレビで流し続けたので,仙台で被災者生活を送った私などは,その詩が未だに耳に残って離れない.この詩人の哲学的,宗教的側面については既に論じられているが(後述),小論ではその地学的側面について述べる.
金子みすゞ(本名テル)の略歴は次の通りである(矢崎, 1984, 2005; 松本, 2022).明治36(1903)年に山口県大津郡仙崎村(現在の長門市仙崎)に生まれ,父母と祖母・兄・弟の6人家族だったが,父はみすゞが3歳の時に死去した.大正9(1920)年大津郡立大津高等女学校を卒業し,大正12(1923)年に母の再婚先の下関の書店に移り,その書店を手伝いながら作詩し,雑誌へ童謡の投稿を始めた.大正15(1926)年書店の店員と結婚し,同年娘が誕生したが,昭和5(1930)年に離婚,その年に自死した.26年の短い生涯だった.
作家・翻訳家の松本(2022, p. 118*)は次のように述べる.「みすゞは,人や田園や花鳥風月を遥かに超えて,もっと深遠なものを詠っている.草を生やす大地の力,人や生きものを生かしている自然と宇宙,そのすべてを成り立たせている目に見えない偉大なものを描いているのだ.そこにあるものは,小さな蟻や雀の短い命から,昼間の青空のむこうで億光年の光を放っている星まで永遠はなく,いつかは終わる限りある命を生きている.石ころといった命なきものたちにも永遠はない.そのものたちの宿命と一瞬の輝きを,虫や花や汚れた雪の気持ちにまで寄り添って書いている.甘く愛らしいだけの詩ではない.もっと深く哲学的なものを見通している」.また,浄土真宗僧侶の中川(2003, p. 186)は次のように述べた.「だれもがさびしく,だれもが悲しく,だれもがあたたかさや,優しさをもとめているそのこころの中へ,おなじさびしさや,悲しみをもってそっとよりそってくれるみすゞさんの作品の一つ一つ….それは,金子みすゞさんをすっぽりとつつみこんだ,お念仏があったからだと思うのです.金子みすゞさんは,生涯,仙崎と下関を出ることはありませんでした.そこで生きとし生けるもののいのちを思い,そのいのちはすべて一繋がりであることを見つめ,生かされてある自分をみつめ,地球という大きな織物のタテ糸の一本にしかすぎない人間の,驕り,たかぶりにこころをいため,そして,どうしようもない人間の根源に自分の姿を重ね,そのなかで,哀しくも短い一つのいのちを終えていったのです」.
仙崎の北に約100mの狭い海峡を挟んで青海(おうみ)島がある.この島は白亜紀の火山岩類を主とする関門(かんもん)層群と阿武(あぶ)層群及びそれらを貫く花崗岩類からなっていて,海岸の急崖にそれらがよく露出する地学巡検の好適地であり(松里, 1980),山口地学会(1991)には青海島の絶景露頭の大判写真が5枚掲載されている.島の南西部,仙崎の近くに「波の橋立」という名所がある.尾崎ほか(2006, p. 106)は,「全長約1kmの湾口礫州で,その山側には青海湖と低地が分布する.なお,波の橋立を構成する堆積物は主に円礫層からなる」と記す**.金子みすゞの「波(なみ)の橋立(はしだて)」という詩(全集III, p. 186, 「仙崎八景」の1編)を見てみよう.
波の橋立よいところ,
右はみづうみ,もぐっちょがもぐる,
左ゃ外海,白帆が通る,
なかの松原,小松原,
さらりさらりと風が吹く.
海のかもめは
みづうみの
鴨とあそんで
日をくらし,
あをい月出りゃ
みづうみの,
ぬしは海辺で
貝ひろふ.
波の橋立,よいところ,
右はみづうみ,ちょろろの波よ,
左ゃ外海,どんどの波よ,
なかの石原,小石原,
からりころりと通りゃんせ
この詩には,この湾口礫州の地形,地質,植生や州の両側の生物と波の違いが手際よく的確に詠みこまれ,松風や波の音,円礫を踏む感触までが伝わってくるようである.「もぐっちょ」はカイツブリの愛称で,川や沼に潜ってよく魚を獲る小型の鳥である.
「濱の石」(全集I, p. 168; 名詩集, p. 156)は次のように唄う(濱は浜,/は空行を表す).
濱辺の石は玉のやう,
みんなまるくてすべっこい./
濱辺の石は飛(と)び魚か,
投げればさっと波を切る./
浜辺の石は唄うたひ,
波といちにち唄ってる./
ひとつびとつの濱の石,
みんなかはいい石だけど,/
浜辺の石は偉(えら)い石,
皆(みんな)して海をかかへてる.
かわいい小石が皆で海をかかえているという認識は非凡だが,地学的には正しく,岩石圏と水圏の空間的,物理的関係を的確に捉えている.また,浜辺の石はただ「まるくてすべっこい」だけではなく,「投げればさっと波を切る」,つまり扁平な形であることを示していて,海岸礫の形の特徴(石渡, 2022)をよく捉えている.そして,そのような形になる原因は「波といちにち唄ってる」からである.この他に「けろりかん」とした「石ころ」の詩(全集I, p. 134; 名詩集, p.178)も有名である.
「赤土山」(全集II, p. 223)は次のように吟ずる(賣は売).
赤土山の赤土は,
賣られて町へゆきました./
赤土山の赤松は,
足のしたから崩(くづ)れてて,
かたむきながら,泣きながら,
お馬車のあとを見送った./
ぎらぎら青い空のした,
しづかに白いみちの上./
町へ賣られた赤土の,
お馬車は遠くなりました.
赤い土,緑の松(幹は赤),青い空,白い道とカラフルな詩材の中で,足元の赤土を持ち去られて傾いた赤松の悲しみが際立っている.岩石圏と生物圏の関係,そして人為的な自然改変の無情を痛切に表現している.土と松の赤は地球の血流を象徴しているようだ.この採土場は仙崎南方の風化した白亜紀火山岩類の小山にあったのだろう***.
以上のように金子みすゞの詩は,「童謡」でありながら的確な自然認識と深い洞察に基づいており,地学の普及・教育に役立つものが多い.
文 献
石渡明(2022)河川と海岸のデジタル礫形計測:その後の進展.日本地質学会News, 25(1), 2-3. http://www.geosociety.jp/faq/content1002.html
金子みすゞ(1984)「新装版 金子みすゞ全集 全3巻 I 美しい町 II 空のかあさま III さみしい王女」JULA出版局,243 p., 281 p., 281 p.
松本侑子(2022*)「金子みすゞ詩集 心にこだまする言葉」(NHKテキスト100分de名著,2022年1月Eテレ放送),NHK出版,127 p.
松里英男(1980)青海島の地質.山口地学会編,村上允英・西村祐二郎監修「山口の地質をめぐって」.築地書館, p. 106-115.
中川真昭(2003)「金子みすゞ いのち見つめる旅」.本願寺出版社,190 p.
尾崎正紀・今岡照喜・井川寿之(2006)地域地質研究報告(5万分の1地質図幅)仙崎地域の地質.産総研地質調査総合センター,127 p.
彩図社文芸部編纂(2011)「金子みすゞ名詩集」.彩図社,191 p.
山口地学会編(1991)西村祐二郎・松里英男他「山口県の岩石図鑑」.第一学習社.224 p.
矢崎節夫(1984)「金子みすゞノート」.JULA出版局,93 p. (全集附録)
矢崎節夫監修(2005)「童謡詩人 金子みすゞ いのちとこころの宇宙」.JULA出版局(同名展覧会記念出版物,2004年12月30日〜2005年1月17日,東京・松屋銀座).
追 記
*この文の初出は松本侑子(2020)の小説「みすゞと雅輔」(新潮文庫)のp. 261-262.
**徳山大学総合研究所の「中国地方の地形環境」によると,波の橋立は5〜6cm程度の扁平な礫からなり,波による浸食を防ぐため多数の低い突堤が櫛の歯状に設けられている.http://chaos.tokuyama-u.ac.jp/souken/gehp/ge-kohyou/y087.htm
***現在の仙崎港は,美祢市秋芳町別府にある採掘現場から延長16.5kmのベルトコンベヤー(大部分はトンネル)で1日約2万トン(年800万トン)運ばれてくる石灰石を国内各地のセメント工場に配送する積み出し拠点になっている(朝日新聞山口版2018年5月27日記事「巨大車両運転 石灰石と格闘」).http://www.asahi.com/area/yamaguchi/articles/MTW20180621360990001.html
【geo-Flash】No.545 【重要】会費などの変更についてのご提案について
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.545 2022/2/15 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】【重要】会費などの変更についてのご提案について
【2】[2022東京・早稲田]【重要】学術大会セッションの変更について
【3】[2022東京・早稲田]トピックセッション提案募集
【4】JABEEオンラインシンポ「昔と違う イマドキのフィールド教育」
【5】地質学露頭紹介 at JpGU2022(発表・参加募集中)
【6】地質学雑誌オンデマンド印刷版年間購読受付のお知らせ
【7】2022年度割引申請を忘れずに!
【8】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【9】(再掲)地震火山地質こどもサマースクール開催地募集
【10】会員の学術・教育・社会貢献活動
【11】コラム:童謡詩人金子みすゞの地学的側面
【12】支部情報
【13】Mars Ice Mapper計画(MIM)での科学観測に関する意見募集中
【14】(再掲)フィールドワークにおけるセクハラ実態調査アンケート
【15】その他のお知らせ
【16】公募情報・各賞助成情報等
【17】(探しています)事務局からおたずね
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】【重要】会費などの変更についてのご提案について
──────────────────────────────────
近年少子化や学会数の増加が顕著となり、他学会と同様、本学会でも会員数
減少が生じています。そのような状況のなか、会員数の減少を防ぎ、学会を
さらに活性化するための施策を導入する必要があり、執行理事会、理事会で
検討した結果、以下の施策を導入することを6月の総会に諮ることにしました。
******************************
・「学生会員」「シニア会員」の再定義と「ジュニア会員」の新設
・学生層やシニア層に対する会費の低減
・学術大会に参加しやすくなるための参加費設定
・長年在会し学会に貢献している会員への永年会員顕彰の拡充
******************************
総会までに、会員の皆様に提案内容をご理解いただくために、その概要を
お知らせいたします.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/news/n171.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2022東京・早稲田]【重要】学術大会セッションの変更について
──────────────────────────────────
第129年学術大会(9/4-9/6:於早稲田大学)から,セッションを
「トピックセッション」,「ジェネラルセッション」,「アウトリーチ
セッション」の3カテゴリに変更します.従来のレギュラーセッションは
発展的に解消します.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0142.html
このセッション変更に関するZoom説明会を2/10に開催しました.
説明会の様子をYouTubeで公開しています.ぜひご確認ください.
http://www.geosociety.jp/science/content0145.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2022東京・早稲田]トピックセッション提案募集中
──────────────────────────────────
第129年学術大会(9/4-9/6:於早稲田大学)のトピックセッション提案を
募集しています.
*******************************
締切:2022年3月10日(木)
*******************************
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0143.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】JABEEオンラインシンポ「昔と違う イマドキのフィールド教育」
──────────────────────────────────
昔からフィールド教育は大学で活発に展開されてきましたが、時代と共に
大学をめぐる状況も変わり、実施方法も多様になっています。
地質技術者教育委員会では、本シンポジウムにおいてJABEE認定大学に
おけるフィールド教育の実際を報告してもらい、それを題材として現代
に即したフィールド教育について考えます.
日程:2022年3月6日(日)14時から(zoom)参加費無料
参加申込締切:3月3日(木)
※締切後,zoomアクセスURLをメールでお知らせします.
講演概要,参加申込等はこちらから
http://www.geosociety.jp/science/content0141.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質学露頭紹介 at JpGU2022(発表・参加募集中)
──────────────────────────────────
日本地質学会2021年オンライン学術大会で好評を博した「地質学露頭紹介」
の第2弾! 今回はJpGUと共同開催です。JpGU2022大会期間中にオンライン
で開催します。とっておきの露頭、解釈がむずかしい露頭などなど.地質学
の露頭について、おおいに語りましょう!
日時:2022年5月29日(日)14:00開始
方法:オンライン(Zoom)+YouTubeライブ配信
発表申込期限:5月9日(月)18時
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0146.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質学雑誌オンデマンド印刷版年間購読受付中
──────────────────────────────────
地質学雑誌は,2022年(128巻)より完全電子化されました.掲載論文は
J-STAGE上でどなたでも無料で閲覧可能です.ただし,WEBでの論文閲覧
が難しい方への対応として,当面地質学雑誌オンデマンド印刷版を作成し,
年間購読のお申込を受け付けます.
対象:日本地質学会会員(個人)に限る
年間購読料:12,000 円(送料込)※学会年会費とは別のご請求です.
受付締切:2022年3月15日(火)
詳細は,http://www.geosociety.jp/news/n169.html
(注)地質学雑誌完全電子化に伴い,冊子体の発行はニュース誌のみに
なりました.2022年1月号から,ニュース誌のみ郵送でお届けしています.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】2022年度割引申請を忘れずに!
──────────────────────────────────
学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)の方で,
それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適用します.
【割引会費請求書最終締切】2022年3月31日(木)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・128巻:新しい論文が公開されています.
(論説)加瀬善洋ほか:北海道津軽海峡沿岸域で認められたイベント堆積物
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/-char/ja
・国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)で,日本語対応の新たなプレ
プリントサーバーが立ち上がりました。現行の地質学雑誌投稿編集出版規則
では,プレプリントサーバーに掲載された原稿は受け付けることも引用する
こともできません。今後,受け付け及び引用について,学会内で早急に議論
を進めていきたいと思います。
■ Island Arc
・新しい論文等が公開されています.
Kenta Yoshida, et al: Variety of the drift pumice clasts from the 2021
Fukutoku‐Oka‐no‐Ba eruption, Japan ほか
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】(再掲)地震火山地質こどもサマースクール開催地募集
──────────────────────────────────
募集締切:2022年2月21日(月)
地震火山地質こどもサマースクールは、1999年夏から小・中・高校生を対象に
はじまった行事で、現在、日本地震学会、日本火山学会、日本地質学会が共同
で実施する、地球科学関連では最大規模の体験学習講座です。今回、下記に
より関東地震100年にあたる2023年度の開催地および2024年度以降の実施
を希望する開催地を公募いたします。
応募資格など詳しくは, https://kodomoss.jp/applications/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】会員の学術・教育・社会貢献活動
──────────────────────────────────
地質学会員の「学術,教育,社会貢献活動」をご紹介しています.皆様からの
情報をお待ちしています.
・吉田健太会員らによる2021年8月に噴火した福徳岡ノ場の軽石に関する
論文の掲載内容がプレスリリースされました.
・宇野正起会員らによる「変質した岩石の化学組成を機械学習で復元! 」
論文の掲載内容がプレスリリースされました.
・石澤尭史会員らによる慶長奥州地震津波の物的証拠に関する論文の掲載
内容がプレスリリースされました.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0109.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】コラム:童謡詩人金子みすゞの地学的側面
──────────────────────────────────
2011年3月11日の東日本大震災からしばらくの間、AC ジャパン(公共広告機構)
が金子みすゞの「こだまでしょうか」という詩をラジオやテレビで流し続けたの
で、仙台で被災者生活を送った私などは、その詩が未だに耳に残って離れない。
この詩人の哲学的、宗教的側面については既に論じられているが(後述)、小論
ではその地学的側面について述べる。
続きはこちら,,http://www.geosociety.jp/faq/content0056.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
・2022年度総会・講演会開催のお知らせ
4月17日(日)14:00-16:45
場所:大田区産業プラザPiO
委任状締切:メール4月15日(水),FAX郵送4月14日(木)必着
・2022年度関東支部幹事選出のお知らせ
立候補期間:3月1日(火)-11日(金)
・オンライン講演会「県の石 神奈川県」
3月5日(土)13:00-16:05
対象:会員(定員に余裕のある場合,非会員も受け付けます)
参加費:無料(要事前申込)
申込締切:2月24日(木)まで
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】Mars Ice Mapper計画(MIM)での科学観測に関する意見募集中
──────────────────────────────────
日本地質学会の皆様
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)では、火星衛星探査計画
(MMX)に次ぐ火星圏探査として、アメリカ航空宇宙局(NASA)、カナダ
宇宙庁(CSA)、イタリア宇宙機関(ASI)とともに、MIMミッションの
コンセプト検討が進められています[1] 。MIMは、合成開口レーダ(SAR)
を搭載した火星周回機により、火星表面下の水・氷分布を観測するミッション
であり、将来の火星有人探査に向けた水資源の把握を第一目的としています[2]。
一方、科学の目的として、氷の起源と分布、そして火星環境変化の解明につな
がる証拠の把握等が設定されています。
現在、MIMでは、国際公募により選出された観測定義チーム(MDT:Measurement
Definition Team)により、観測要求の検討を進めています [3].日本からも
9名のメンバーが参加し、MIMでの観測を日本の目指す将来火星探査プログラム
(JSMEP [4])へと発展させることを目指しています.
今回、MIM計画に期待する観測・探査案およびMIMを含む日本の火星探査計画
の将来像に対する期待および要望に関し、広くコミュニティーの皆様からの意見
を募集します.日本地質学会の皆様からのご意見をMDT活動に反映させることで、
MIMを日本にとってよりよい形の探査にしていきたいと思います.皆様からの
ご提案は、下の投稿フォームにより提出お願い致します.
意見投稿フォームはこちらから(締切:3月4日)
MIMおよびMDT活動に関する詳細は、2/17-2/18に開催される第6回重力
天体(月火星)着陸探査シンポジウム[5]において、紹介いたします.また、
国際火星探査プログラム(MEPAG)での発表資料[2, 3]をご参考ください.
〇問い合わせ先
関 華奈子(東京大学) < k.seki@eps.s.u-tokyo.ac.jp>
関根 康人(東京工業大学)< sekine@elsi.jp>
参考資料
[1] MIMへの参加意向表明書
[2] Mars Ice Mapper計画(MIM)
[3]14th Virtual MEPAG Meeting
[4] 宇宙理学・工学委員会 国際宇宙探査専門委員会「火星探査計画の科学探査タスクフォース:中間報告書(2019年2月14日付)抜粋
[5] 第6回重力天体(月火星)着陸シンポジウム
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【14】(再掲)フィールドワークにおけるセクハラ実態調査アンケート
──────────────────────────────────
有志による共同研究グループ「フィールドワークとハラスメント(HiF)」より
フィールドワークにおける性暴力・セクシュアルハラスメントに関する実態
調査アンケートへの協力依頼がありましたので,会員の皆様にお知らせいた
します.
***************************
<回答期限:2022年2月28日>(延長しました)
アンケートの趣旨詳細,回答はこちらから
https://safefieldwork.live-on.net/survey/purposes-of-this-survey/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【15】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
情報科学を活用した地震調査研究プロジェクト
(STAR-Eプロジェクト)第1回研究フォーラム
「地震×AI、STAR-Eプロジェクトで目指す
イノベーション―注目のAI企業が語る地震研究の可能性―」
2月18日(金)9:30-12:00(開場 9:15)
主催:文部科学省
募集締切:2月17日(木) 12:00
開催形式:オンライン配信(Vimeo)参加費無料
申込URL:https://star-e-project.eventcloudmix.com
(共)地質情報展2022あいち ―発見!あいちの大地―
2月19日(土)- 20日(日)
場所:名古屋市科学館イベントホール
主催:GSJ・日本地質学会・名古屋市科学館
後援:中部地質調査業協会,日本ジオパークネットワーク
https://www.gsj.jp/event/johoten/index.html
(後)第36回地質調査総合センター シンポジウム(オンライン)
「3次元で解き明かす東京都区部の地下地質」
2月25日(金)13:00-16:55
参加費:無料(事前登録制)CPD:3.5単位
https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo36/index.html
第31回地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン第5回目)
2月25日(金)19:30-21:30
内容:地質汚染調査におけるボーリング調査
講師:風岡 修(地質汚染診断士、理学博士)他
受講方法:ZOOMによるオンライン
申込期限:2022年2月21日まで 受講料無料
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
(後)第59回アイソトープ・放射線研究発表会(オンライン)
7月6日(水)-8日(金)→オンライン開催に変更になりました
演題登録締切:2月28日(月)17時
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2022/top
(共)岩石―水相互作用国際会議(WRI-17)
7月30日(土)→2023年8月に延期となりました
会場:仙台市
https://www.wri17.com/
(後)科学教育研究協議会第68回全国研究大会(岡山大会)
8月10日(水)-12日(金)
会場 岡山理科大学 岡山キャンパス
https://kakyokyo.org/
(後)第9回国際地学教育会議
8月21 日(日)-25 日(木)
会場:くにびきメッセ(島根県コンベンションセンター)
https://ja.geoscied9.org/
日本地質学会第129年学術大会(2022東京・早稲田大会)
9月4日(日)-6日(火)
会場:早稲田大学早稲田キャンパス(東京都新宿区西早稲田)
※関連行事「地質情報展2022とうきょう」は同会場で9/3-/5開催予定
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0222.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【16】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・第19回(令和4年度)「日本学術振興会賞」受賞候補者推薦(学会締切3/18)
・2022年度国土地理協会学術研究助成募集(4/1-15)
・令和4年度苗場山麓ジオパーク学術研究活動募集(3/4)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【17】(探しています)事務局からおたずね
──────────────────────────────────
2022年1月12日付,ゆうちょダイレクト(インターネットバンキング)より,
「送金人:ニホンチシツガッカイ」という入金がありました.学会費と思われ
ますが,どなたからの振込か不明です.
お心当たりの方は,学会事務局(main[at]geosociety.jp)までご連絡ください.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.546 JABEEシンポ「昔と違う イマドキのフィールド教育」
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.546 2022/3/1 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】【重要】会費などの変更についてのご提案について
【2】2022年度理事選挙について
【3】[2022東京・早稲田]トピックセッション提案募集
【4】JABEEオンラインシンポ「昔と違う イマドキのフィールド教育」
【5】地質学露頭紹介 at JpGU2022(発表・参加募集中)
【6】地質学雑誌オンデマンド印刷版年間購読受付のお知らせ
【7】2022年度割引申請を忘れずに!
【8】地質学雑誌からのお知らせ
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】【重要】会費などの変更についてのご提案について
──────────────────────────────────
会員数の減少を防ぎ、学会をさらに活性化するため以下の施策を導入する
ことを6月の総会に諮ることにしました。
******************************
・「学生会員」「シニア会員」の再定義と「ジュニア会員」の新設
・学生層やシニア層に対する会費の低減
・学術大会に参加しやすくなるための参加費設定
・長年在会し学会に貢献している会員への永年会員顕彰の拡充
******************************
総会までに、会員の皆様に提案内容をご理解いただくために、その概要を
お知らせいたします.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/news/n171.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2022年度理事選挙について
──────────────────────────────────
2022年度の理事選挙を実施いたします(理事選挙は2022年度からの
新代議員による投票となります)。
理事選挙の開票は3月15日(火)15時からオンライン会議で行います。
開票の立ち会いをご希望のかたは、3月11日(金)までに選挙管理委員
会(main@geosociety.jp)にお申し出ください。
立候補者名簿ほか選挙の詳細は,
http://sub.geosociety.jp/members/content0111.html(要会員ログイン)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2022東京・早稲田]トピックセッション提案募集中
──────────────────────────────────
第129年学術大会(9/4-9/6:於早稲田大学)のトピックセッション提案を
募集しています.
<締切:2022年3月10日(木)>
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0143.html
(参考)【重要】学術大会セッションの変更について
http://www.geosociety.jp/science/content0142.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】JABEEオンラインシンポ「昔と違う イマドキのフィールド教育」
──────────────────────────────────
昔からフィールド教育は大学で活発に展開されてきましたが、時代と共に
大学をめぐる状況も変わり、実施方法も多様になっています。
地質技術者教育委員会では、本シンポジウムにおいてJABEE認定大学に
おけるフィールド教育の実際を報告してもらい、それを題材として現代
に即したフィールド教育について考えます.
日程:2022年3月6日(日)13時半から(zoom)参加費無料
(注)これまでご案内していました14時開催が,13時半開催に変更となります.
参加申込締切:3月3日(木)
※締切後,zoomアクセスURLをメールでお知らせします.
講演概要,参加申込等はこちらから
http://www.geosociety.jp/science/content0141.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質学露頭紹介 at JpGU2022(発表・参加募集中)
──────────────────────────────────
日本地質学会2021年オンライン学術大会で好評を博した「地質学露頭紹介」
の第2弾! 今回はJpGUと共同開催です。JpGU2022大会期間中にオンライン
で開催します。とっておきの露頭、解釈がむずかしい露頭などなど.地質学
の露頭について、おおいに語りましょう!
日時:2022年5月29日(日)14:00開始
方法:オンライン(Zoom)+YouTubeライブ配信
発表申込期限:5月9日(月)18時
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0146.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質学雑誌オンデマンド印刷版年間購読受付中
──────────────────────────────────
地質学雑誌は,2022年(128巻)より完全電子化されました.掲載論文は
J-STAGE上でどなたでも無料で閲覧可能です.ただし,WEBでの論文閲覧
が難しい方への対応として,当面地質学雑誌オンデマンド印刷版を作成し,
年間購読のお申込を受け付けます.
対象:日本地質学会会員(個人)に限る
年間購読料:12,000 円(送料込)※学会年会費とは別のご請求です.
受付締切:2022年3月15日(火)
詳細は,http://www.geosociety.jp/news/n169.html
(注)地質学雑誌完全電子化に伴い,冊子体の発行はニュース誌のみに
なりました.2022年1月号から,ニュース誌のみ郵送でお届けしています.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】2022年度割引申請を忘れずに!
──────────────────────────────────
学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)の方で,
それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適用します.
********************************
【割引会費請求書最終締切】2022年3月31日(木)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】地質学雑誌からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・128巻:新しい論文が公開されています.
(フォト)御前 明洋ほか:国内の上部白亜系におけるアンモノイドを含む
コンクリーションの産状
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/-char/ja
・著者の役割分担の明記について:投稿者の方から,「地質学雑誌では,研究
全体の統括者を最終著者とするルールはないのか」という主旨のご質問があり
ましたので,編集委員会の見解をお伝えいたします。
http://www.geosociety.jp/publication/content0102.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
・2022年度関東支部幹事選出のお知らせ
立候補期間:3月1日(火)-11日(金)
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html#2022senkyo
・サイエンスカフェ「おうちで楽しむ陸と海の火山紀行」
3月21日(月・祝)15:00-16:30(Zoomによる双方向オンライン)
ゲストスピーカー:池上郁彦さん(タスマニア大学)
参加費無料,定員30名(先着順)
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html#2022cafe
・2022年度総会・講演会開催のお知らせ
4月17日(日)14:00-16:45
場所:大田区産業プラザPiO
委任状締切:メール4月15日(水),FAX郵送4月14日(木)必着
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html#2022sokai
[西日本支部]
・令和3年度総会/第172回例会(3/5開催)プログラム集(PDF)を公開しました
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
・次世代放射光施設 ビームライン利用ニーズに関するアンケート協力依頼
<アンケート回答締切:3月25日(金)18:00>
量子科学技術研究開発機構より,標記アンケートへの協力依頼がありました
ので,会員の皆様にお知らせします.
***********************
2024年度の稼働開始に向けて「次世代放射光施設」の整備が、官民地域パートナーシップのもと、東北大学新青葉山キャンパスにて進行しており、すでに基本建屋がほぼ完成し、加速器機器の搬入が開始されています。
放射光は、学術・科学技術、産業利用などにおける幅広い分野の研究開発に利用されており、「次世代放射光施設」は、大学・学術研究機関、民間企業などの所属を問わず、多くの方々に使って頂く「共用施設」となります。
量研と文科省では、現在整備中の10本のビームラインに対する利用ニーズアンケート調査を実施しています。
今後の施設の運用に向けた重要な検討材料となることから、多くの方々にご回答頂きたく、皆様のご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
調査アンケートに関する情報ならびにアンケートへの回答については、下記リンクをご参照ください。
<アンケート回答締切:3月25日(金)18:00>
https://www.qst.go.jp/site/3gev/questionnaire.html
国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構
量子ビーム科学部門 次世代放射光施設整備開発センター
センター長 内海 渉
(問い合わせ先:安藤 ando.shinji@qst.go.jp)
---------------------------------------
日本列島の地殻応力ージャパンストレスマップ(JSM)
3月7日(月)14:00-17:20
場所:土木学会講堂(オンライン併用)
主催:土木学会エネルギー委員会
参加費:無料(事前登録制)CPD:1.9単位
https://committees.jsce.or.jp/enedobo/node/90
第236回イブニングセミナー(オンライン)
3月25日(金)19:30-21:30
演題:「赤色立体地図の原理と応用 特に最近の発展について」
講師:千葉達朗(アジア航測株式会社)
主催:NPO法人日本地質汚染審査機構
参加費:主催NPO会員(無料) 非会員(1,000円)
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
(後)第59回アイソトープ・放射線研究発表会(オンライン)
7月6日(水)-8日(金)
演題登録締切(延長しました):3月7日(月)12時
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2022/top
(共)岩石―水相互作用国際会議(WRI-17)
7月30日(土)→2023年8月に延期となりました
会場:仙台市
https://www.wri17.com/
(後)科学教育研究協議会第68回全国研究大会(岡山大会)
8月10日(水)-12日(金)
会場 岡山理科大学 岡山キャンパス
https://kakyokyo.org/
(後)第9回国際地学教育会議
8月21 日(日)-25 日(木)
会場:くにびきメッセ(島根県コンベンションセンター)
※ハイブリッド開催
https://ja.geoscied9.org/
日本地質学会第129年学術大会(2022東京・早稲田大会)
9月4日(日)-6日(火)
会場:早稲田大学早稲田キャンパス(東京都新宿区西早稲田)
※関連行事「地質情報展2022とうきょう」は同会場で9/3-/5開催予定
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0222.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・JAMSTEC超先鋭研究開発部門超先鋭研究プログラムポスドク研究員公募(3/17)
(※締め切り延長しました)
・三好ジオパーク構想推進協議会専門員募集(3/4)
・2022年度「深田野外調査助成」募集(4/22)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.547 第13回惑星地球フォトコンテスト:審査結果
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.547 2022/3/15 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】【重要】会費などの変更についてのご提案について
【2】第13回惑星地球フォトコンテスト:審査結果発表
【3】2022年「地質の日」行事のご案内
【4】地質学露頭紹介 at JpGU2022(発表・参加募集中)
【5】2022年度割引申請を忘れずに!(最終締切間近です)
【6】地質学雑誌からのお知らせ
【7】会員の学術・教育・社会貢献活動
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
【11】訃報 木崎甲子郎 名誉会員 ご逝去
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】【重要】会費などの変更についてのご提案について
──────────────────────────────────
会員数の減少を防ぎ、学会をさらに活性化するため以下の施策を導入することを
6月の総会に諮ることにしました。
******************************
・「学生会員」「シニア会員」の再定義と「ジュニア会員」の新設
・学生層やシニア層に対する会費の低減
・学術大会に参加しやすくなるための参加費設定
・長年在会し学会に貢献している会員への永年会員顕彰の拡充
******************************
総会までに、会員の皆様に提案内容をご理解いただくために、その概要を
お知らせいたします.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/news/n171.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第13回惑星地球フォトコンテスト:審査結果発表
──────────────────────────────────
応募作品全387作品のうち,入選12点,佳作19点が決定しました.
作品画像は近日学会HP上にて公開の予定です.
最優秀賞:
露木孝範(静岡県)宝永火口岩脈群
優秀賞(2点):
加藤順子(東京都)3つのStream
高木 嶺(東京都)恐怖の石段
ジオパーク賞:
大場建夫(秋田県)大海に注ぐ湧水
日本地質学会会長賞:
金子敦志(福島県)ミニチュアテラス
ジオ鉄賞:
落合文登(宮崎県)たまゆらの中の洗濯岩
その他の結果は,http://www.photo.geosociety.jp/
【作品展示予定】
東京パークスギャラリー(上野)
5月3日(火)-5月15日(日)
場所:上野恩賜公園 上野グリーンサロン内(台東区上野公園7-47)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2022年「地質の日」行事のご案内
──────────────────────────────────
オンライン一般講演会
開催日時:5月8日(日) 9:00-12:00
開催方法:YouTubeライブ配信 どなたでも視聴可能,申込不要,無料
<講師と講演タイトル>
斎藤 眞:地質が身近にある社会を創る−新しい分野への活用に向けて−
鹿野和彦:海底火山の世界を探る「爆発的海底噴火とその噴出物」
このほか,学会関連の「地質の日」行事については,学会ホームページに
随時情報を掲載します.
・惑星地球フォトコンテスト第13回ほか入選作品展示会(5/3-15)(台東区
上野公園内.入場無料)
・街中ジオ散歩ミニ in Tokyo「国分寺崖線」(5/15)
・近畿支部:地球科学講演会「「北アルプス生成の謎−マグマと短縮テクトニクス
が作り出した北アルプス−」(5/8)大阪市立自然史博物館,4/25申込締切,YouTubeでの配信あり.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/name/content0176.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地質学露頭紹介 at JpGU2022(発表・参加募集中)
──────────────────────────────────
日本地質学会2021年オンライン学術大会で好評を博した「地質学露頭紹介」
の第2弾! 今回はJpGUと共同開催です。JpGU2022大会期間中にオンライン
で開催します。とっておきの露頭、解釈がむずかしい露頭などなど.地質学
の露頭について、おおいに語りましょう!
日時:2022年5月29日(日)14:00開始
方法:オンライン Zoom+YouTubeライブ配信
発表申込期限:5月9日(月)18時
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0146.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2022年度割引申請を忘れずに!(最終締切間近です)
──────────────────────────────────
学部に在籍している学生の方,定収のない大学院生(研究生)の方で,
それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会費を適用します.
********************************
【割引会費請求書最終締切】2022年3月31日(木)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質学雑誌からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・128巻:新しい論文が公開されています.
(論説)小松原純子ほか:常時微動観測に基づく東京湾岸地域の沖積層の地盤震動特性とS波速度不連続面の深度
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/-char/ja
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】会員の学術・教育・社会貢献活動
──────────────────────────────────
・辻森 樹会員らによる「Neoproterozoic eclogite-to granulite-facies transition
in the Ubendian Belt, Tanzania, and the timescale of continental collision」
(J. Petrol., egac012, in press)の掲載内容が東北大学からプレスリリース
されました.
・竹下光士会員による「THE GALLERYセレクション展 GEOSCAPE
MTL中央構造線」が開催されます.
東京 4月5日(火)-18日(月)/大阪 5月6日(金)-18日(水)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0109.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
・2022年度総会・講演会開催のお知らせ
4月17日(日)14:00-16:45
場所:大田区産業プラザPiO
委任状締切:WEB 4月15日(水),FAX郵送 4月14日(木)必着
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html#2022sokai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
・研究用ラジオアイソトープ(RI)に対する意識調査」に関するアンケート
調査協力依頼<アンケート回答締切:3/22(火)>
https://www.jrias.or.jp/report/cat1/311.html
—-----------------------------------
(後)第59回アイソトープ・放射線研究発表会(オンライン)
7月6日(水)-8日(金)
演題登録締切(延長しました):3月7日(月)12時
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2022/top
(共)岩石―水相互作用国際会議(WRI-17)
7月30日(土)→2023年8月に延期となりました
会場:仙台市
https://www.wri17.com/
(後)科学教育研究協議会第68回全国研究大会(岡山大会)
8月10日(水)-12日(金)
会場 岡山理科大学 岡山キャンパス
https://kakyokyo.org/
(後)第9回国際地学教育会議
8月21 日(日)-25 日(木)
会場:くにびきメッセ(島根県コンベンションセンター)
https://ja.geoscied9.org/
日本地質学会第129年学術大会(2022東京・早稲田大会)
9月4日(日)-6日(火)
会場:早稲田大学早稲田キャンパス(東京都新宿区西早稲田)
※関連行事「地質情報展2022とうきょう」は同会場で9/3-/5開催予定
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0222.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・東京大学地震研究所2022年度大型計算機共同利用公募研究(5/31)
・伊豆大島ジオパーク推進委員会がジオパーク専門員募集(4/28)
・産総研特定業務任期付職員(地質情報のデータ配信管理業務)公募(4/15)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】訃報 木崎甲子郎 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
木崎甲子郎 名誉会員(琉球大学名誉教授)が、令和4年2月26日に老衰のため
逝去されました(97歳)。
これまでの故人の功績を讃えるとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
なお、ご葬儀は家族葬にてすでに執り行われたとのことです。
会長 磯崎行雄
(注)「崎」の正しい表記は、「大」→「立」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.548 理事選挙の結果報告
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.548 2022/4/5 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】理事選挙の結果報告
【2】【重要】会費などの変更についてのご提案について
【3】2022年「地質の日」行事のご案内
【4】令和4年度大学入試共通テストの地学関連科目に関する意見書
【5】地質学露頭紹介 at JpGU2022(発表・参加募集中)
【6】本の紹介「小説 原子力規制官僚の理一火山リスクに対峙して」
【7】Island Arc からのお知らせ
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】理事選挙の結果報告
──────────────────────────────────
日本地質学会選挙規則ならびに選挙細則に基づき,理事選挙を実施いたしました.
結果をご報告いたします.
<理事選挙実施結果>
有権者総数:186名
投票用紙発送数:186通
投票総数:129通
有効投票数・無効投票数:有効129票/無効0票
詳しくは、http://sub.geosociety.jp/members/content0112.html
(要会員ログイン)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】【重要】会費などの変更についてのご提案について
──────────────────────────────────
会員数の減少を防ぎ、学会をさらに活性化するため以下の施策を導入することを
6月の総会に諮る予定です。
******************************
・「学生会員」「シニア会員」の再定義と「ジュニア会員」の新設
・学生層やシニア層に対する会費の低減
・学術大会に参加しやすくなるための参加費設定
・長年在会し学会に貢献している会員への永年会員顕彰の拡充
******************************
総会までに、会員の皆様に提案内容をご理解いただくために、その概要を
お知らせしております.ぜひご確認ください.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/news/n171.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2022年「地質の日」行事のご案内
──────────────────────────────────
オンライン一般講演会
開催日時:5月8日(日) 9:00-12:00
開催方法:YouTubeライブ配信 どなたでも視聴可能,申込不要,無料
<講師と講演タイトル>
斎藤 眞:地質が身近にある社会を創る−新しい分野への活用に向けて−
鹿野和彦:海底火山の世界を探る「爆発的海底噴火とその噴出物」
このほか,学会関連の「地質の日」行事については,学会ホームページに
随時情報を掲載します.
・惑星地球フォトコンテスト第13回ほか入選作品展示会(5/3-15)
・街中ジオ散歩ミニ in Tokyo「国分寺崖線」(5/15)(4/8申込受付開始)
・近畿支部:地球科学講演会「北アルプス生成の謎−マグマと短縮テクトニクス
が作り出した北アルプス−」(5/8)4/25申込締切,YouTube配信あり.
・中部支部:講演会「深海チャートの地層から地球の歴史を解読する」(5/8)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/name/content0176.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】令和4年度大学入試共通テストの地学関連科目に関する意見書
──────────────────────────────────
大学入試センター宛に令和4年度大学入試共通テストの地学関連科目に
関する意見書を提出しました.
全文はこちら,,,http://www.geosociety.jp/engineer/content0064.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質学露頭紹介 at JpGU2022(発表・参加募集中)
──────────────────────────────────
地質学の露頭について、おおいに語りましょう!
日時:2022年5月29日(日)14:00開始
方法:オンライン Zoom+YouTubeライブ配信
発表申込期限:5月9日(月)18時
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0146.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】本の紹介 小説 原子力規制官僚の理一火山リスクに対峙して
──────────────────────────────────
「小説 原子力規制官僚の理(ことわり)一火山リスクに対峙して」
松崎忠男著
(エネルギーフォーラム 2021年4月12日発行 B6判 333p.
ISBN978-4-88555-514-5 C0093)
(石渡 明)
原子力規制委員会・規制庁(職員総数約1000人)のような専門的な業務に当たる政府の役所で、実際にどんな職員がどんな仕事をしているかを知ることは、一般の会員にはなかなか難しい。この本は、火山リスクという特定の課題を中心に据えて、規制庁の職員だけでなく、そこに関与する火山学者、政治家、原子力事業者、原発訴訟関係者も含めた人間模様を活写しながら、実際の原子力規制行政(特に訴訟対応の業務)に当たる職員の仕事の内容を小説形式でわかりやすく描いており、将来このような官庁への就職を希望する若い会員の参考になると思うので、以下に紹介する。
本書末尾の紹介文によると、「著者は1953年生まれ。東京大学工学部卒業、米国ペンシルベニア大学大学院修士課程修了。旧科学技術庁に入庁。文部科学省で科学技術行政に携わる。デビュー作『小説 1ミリシーベルト』で第4回エネルギーフォーラム小説賞を受賞」(原文のまま)となっている。規制庁には、就職時にこの著者が上司だったという人がいて、その人によると著者名はペンネームではなく本名だそうである。そして本書の帯の宣伝文は、「カルデラ噴火を巡る川内原発取り消し訴訟の控訴審がモデル。裁判官、火山学者、国会議員の思惑が絡み合う中、信念を貫き通す原子力規制官僚は、その矜持を保ち続けることができるか――」である。
この本の目次の2ページ後に、「この作品はフィクションであり、実在する人物・地名・団体・施設などとは一切関係ありません」と書いてはあるが、その次のべ一ジに九州の地図があって、実際の火山やカルデラの位置と「薩摩原発」の場所が、そのあるべき位置に正確に示してあり、第1章の最初の3-4行目には「原子力規制庁は…六本木ファーストビルに入居している」と事実が書いてあって、民自党や協産党がどの団体を指すかも自明なので、この本に書いてあることは決して単なるフィクションではない。それどころか、p. 11に出てくる「火山担当の内山幸恵安全審査専門員」という女性は、「国立大学の理学部地学科で博士課程を修了し、原子力規制庁に入って四年目の若手だ。専門は岩石学で、地震・津波の審査グルーブに所属し、研究グループを兼務している」とのことで、多少経歴・所属等に違いはあるが、私にはこの人の顔がすぐに思い浮かぶ。この小説では悪役になっている「T大学の地震・火山研究所の竹岡弘明教授」(p.18)や「海洋研究所の大山哲研究首席」(p.39, 103)が誰であるかも、ちょっと火山に関心のある人ならすぐにわかる。そして極めつけは、「原子力規制委員会の委員が火山の専門家を恫喝した記録が残っている」(p.38)という部分で、「平成26年8月に設けられた火山活動のモニタリング検討チーム」で「地震・火山担当の桜井正治委員」(失礼なことに「既に他界している」ことになっている)が、「そこまで遡って全部引っ繰り返してしまうと、この検討チーム自体が成り立たない」と言って「火山専門家の批判を押さえ込んだ」のがその「恫喝の記録」なのだという(p.93-94)。P.95にはこの発言が平成26年8月25日の「原子力施設における火山活動のモニタリングに関する検討チーム」の第1回会合だったように書かれているが、実際には翌週の第2回会合(平成26年9月2日)における当時の委員長代理の発言(同議事録p.9*)そのままである。筆者は現職に就任する前だったが、これらの会合にはチーム員の一人として参加していた。かなり「荒れた」会合だったことは事実だが、この発言では炎上せず、検討チームの座長の立場からは当然の発言であって、「恫喝した」とは言えないと思う。
この小説は、原発訴訟に対応する規制庁職員(五十嵐隼人)を主人公として、規制委員会の委員、規制庁の職員、関連省庁の職員、火山関係の大学教授・研究者、閣僚・国会議員・県知事などの政治家、裁判官と訴訟関係者、原子力事業者や五十嵐の家族・親族の人間模様を絡ませながら、霧島火山と薩摩硫黄島の噴火が発生する中で(これらは近年実際に発生したが、その状況は本書の記述と異なる)、薩摩原発が「点検を名目とした自主的な運転停止」に追い込まれるが、選挙で民自党が勝利し、当該訴訟で国が勝利し、国会で「カルデラ法案」が通って省庁横断型のCEP(Caldera Eruption Prediction)プロジェクトが動き出し(これは完全にフィクション)、運転停止は解除されるというストーリーになっている。
本書の題名中の「火山リスク」は、巨大噴火のリスクまたはその関係の訴訟リスクのことらしく、新規制基準への適合性審査やバックフィットにおける火山リスク全般の議論を扱っているわけではない。火山に関する本格的な原子力規制は2012年の本委員会発足後に始まったもので、地震、津波、活断層など他の自然災害リスクに関する規制に比べると、まだ日が浅く経験不足の面があり、審査の後で「新事実」が判明し、場合によっては規則・解釈・審査ガイドなどを改正し、事業者に改めて対応を求めるバックフィットを複数行ってきた。火山噴火時の大気中の火山灰濃度に関するもの**と、新しい火山灰露頭の確認による噴出規模の見直し(それによる火山灰層厚の加増)***が主なものである。一般には「一事不再理」というのが行政・司法の処分の原則だが、原子カのように最新の科学技術に基づく非常に社会的影響の大きい事業に対しては、確実な新知見が得られた場合、既に許可したものであっても再度審査して、必要があれば事業者の対応を求める方針でやっている。
以上のように、この小説は、原子力規制委員会・規制庁が扱う火山リスクとそれに関連する訴訟に係わる規制行政の内容を、虚実取り混ぜではあるものの実際に即してわかりやすく述べており、一般の会員がその概要を理解する糸口になる作品だと思う。「経産省と原子力規制庁は、元はといえば、同じ組織なんだよ」という竹岡弘明教授のセリフ(p.295)や本書の出版社名が示すように、この著者の立ち位置は原子力規制を行う筆者らの立場とは異なっており、個人が特定できる情報を記した上での個人批判には同意できない部分もあるが、「この作品はフィクションであり…」との本書冒頭の宣言を前提として、会員諸兄諸姉のご一読をお勧めする。主人公の五十嵐隼人がどんな信念をもち、原子力規制官僚としての理に叶った、国民のためになる仕事をしたかどうか、確かめていただきたい。
引用文献
*原子力規制委員会(2014.09.02)「原子力施設における火山活動のモニタリングに関する検討チーム 第2回会合」議事録https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11105588/www.nsr.go.jp/data/000049168.pdf
**石渡 明・西来邦章(2018)気中火山灰濃度に関する原子力規制の改善。日本地質学会第125年学術大会(札幌・つくば)発表R24-O-5. https://www.nsr.go.jp/data/000257782.pdf
***原子力規制委員会(2019.04.17)資料3「大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴う報告徴収命令に基づく関西電力株式会社からの報告について」https://www.nsr.go.jp/data/000267920.pdf
関西電力株式会社(2021.05.19)「美浜発電所、高浜発電所および大飯発電所の降下火砕物の層厚評価の見直しに係る原子炉設置変更許可について」https://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2021/pdf/20210519_2j.pdf
石渡 明(原子力規制委員会委員)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ Island Arc
新しい論文が公開されています.
James L. Goedert, et al., Miocene Nautilus (Mollusca, Cephalopoda) from
Taiwan, and a review of the Indo-Pacific fossil record of Nautilus
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iar.12442
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
・2022年度総会・講演会開催のお知らせ
4月17日(日)14:00-16:45
場所:大田区産業プラザPiO(大田区南蒲田)
(講演会)「首都圏の浅部地盤の地質層序と地盤震動特性」
講師:中澤 努氏(産総研)
(総会)委任状締切:WEB 4/15(水),FAX郵送4/14(木)必着
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html#2022sokai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
地震本部ニュース2022春号:地震調査研究プロジェクト 情報科学を活用
した地震調査研究プロジェクト(STAR-E プロジェクト)(その3)ほか
https://www.jishin.go.jp/herpnews/
—-------------------------------------------
日本堆積学会2022年オンライン大会
4月23日(土)
プログラムが公開されました
http://sediment.jp/04nennkai/2022/2022online_annai.html
地質学史懇話会のお知らせ(オンラインとハイブリッド)
6月18日(土)13:30-16:30
場所:早稲田奉仕園(東京メトロ東西線早稲田駅下車徒歩5分)
中川智視「19世紀アメリカにおける専門化の進展」(仮)
五味 篤「高橋是清のペルー銀山事件と地質関係者」
(後)第59回アイソトープ・放射線研究発表会(オンライン)
7月6日(水)-8日(金)
演題登録締切(延長しました):3月7日(月)12時
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2022/top
(共)岩石―水相互作用国際会議(WRI-17)
7月30日(土)→2023年8月に延期となりました
会場:仙台市
https://www.wri17.com/
(後)科学教育研究協議会第68回全国研究大会(岡山大会)
8月10日(水)-12日(金)
会場 岡山理科大学 岡山キャンパス
https://kakyokyo.org/
(後)第9回国際地学教育会議
8月21 日(日)-25 日(木)
会場:くにびきメッセ(島根県コンベンションセンター)
https://ja.geoscied9.org/
日本地質学会第129年学術大会(2022東京・早稲田大会)
9月4日(日)-6日(火)
会場:早稲田大学早稲田キャンパス(東京都新宿区西早稲田)
※関連行事「地質情報展2022とうきょう」は同会場で9/3-/5開催予定
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0222.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
産総研パーマネント型研究員(陸域の地質調査及び地質図の作成他)の公募(5/17)
第13回日本学術振興会育志賞推薦(学会締切:5/13)
2022年コスモス国際賞候補者推薦(学会締切:4/10)
原子力規制人材育成事業の令和4年度新規採択事業公募(4/18)
令和4年度秋田県ジオパーク研究助成事業の募集(5/31)
令和4年度三島村ジオパーク学術研究等奨励補助金(5/30)
令和4年度下仁田ジオパーク学術奨励金事業募集(4/25)
栗駒山麓ジオパーク推進協議会職員(ジオパーク専門員)の募集(4/20)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.549 シンポ「チバニアン,学術的意義とその社会的重要性」
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.549 2022/4/19 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】【重要】会費などの変更についてのご提案について
【2】2022年「地質の日」行事のご案内
【3】日本学術会議シンポジウム「チバニアン,学術的意義とその社会的重要性」
【4】地質学露頭紹介 at JpGU2022(発表・参加募集中)
【5】地質学雑誌 からのお知らせ
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】【重要】会費などの変更についてのご提案について
──────────────────────────────────
会員数の減少を防ぎ、学会をさらに活性化するため以下の施策を導入することを
6/11の総会に諮る予定です。
******************************
・「学生会員」「シニア会員」の再定義と「ジュニア会員」の新設
・学生層やシニア層に対する会費の低減
・学術大会に参加しやすくなるための参加費設定
・長年在会し学会に貢献している会員への永年会員顕彰の拡充
******************************
総会までに、会員の皆様に提案内容をご理解いただくために、その概要を
お知らせしております.ぜひご確認ください.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/news/n171.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2022年「地質の日」行事のご案内
──────────────────────────────────
オンライン一般講演会
開催日時:5月8日(日) 9:00-12:00
開催方法:YouTubeライブ配信 どなたでも視聴可能,申込不要,無料
<講師と講演タイトル>
斎藤 眞:地質が身近にある社会を創る−新しい分野への活用に向けて−
鹿野和彦:海底火山の世界を探る「爆発的海底噴火とその噴出物」
このほか,学会関連の「地質の日」行事については,学会ホームページに
随時情報を掲載しています.
・惑星地球フォトコンテスト入選作品展示会(上野公園:5/3-15)
・近畿支部:地球科学講演会「北アルプス生成の謎−マグマと短縮テクトニクス
が作り出した北アルプス−」(5/8)4/25申込締切,YouTube配信あり.
・中部支部:講演会「深海チャートの地層から地球の歴史を解読する」(5/8)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/name/content0176.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本学術会議シンポジウム「チバニアン,学術的意義とその社会的重要性」
──────────────────────────────────
日時:令和4年(2022年)5月24日(火)13:00-17:10 入場無料
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木 7-22-34)
共催:日本地質学会ほか
※本シンポジウムはハイブリッド形式で行います.
千葉県市原市の地層「千葉セクション」が、国際基準の地層境界である
「国際境界模式層断面とポイント(GSSP)」に認定され、約77万4千年前
〜約12万9千年前の地質時代の名称が「チバニアン」と名づけられました。
本シンポジウムでは、チバニアンの決定における過程を振り返り、その科学
的および社会的な意義を紹介します。
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0147.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地質学露頭紹介 at JpGU2022(発表・参加募集中)
──────────────────────────────────
地質学の露頭について、おおいに語りましょう!
日時:2022年5月29日(日)14:00開始
方法:オンライン Zoom+YouTubeライブ配信
発表申込期限:5月9日(月)18時
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0146.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質学雑誌からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・128巻:新しい論文が公開されています.
(フォト)立石 良ほか:福井県三方郡美浜町で新たに確認された敦賀断層
の露頭
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/128/1/_contents/-char/ja
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
第31回 地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン第6回目)
5月13日(金)19:30-21:30
内容:地質汚染調査におけるボーリング調査
講師:風岡 修(地質汚染診断士、理学博士)他
申込期限:5月10日まで,受講料:無料
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
2022年度 第1回地質調査研修(追加)
5月30日(月)-6月3日(金)
場所:
(室内座学)茨城県つくば市(産総研)
(野外実習)茨城県ひたちなか市,福島県双葉郡広野町・いわき市周辺
定員:6名(定員になり次第締切)
CPD:42単位, 参加費:63口(1口1000円)の会費が必要
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2022-1.html
地質学史懇話会のお知らせ(オンラインとハイブリッド)
6月18日(土)13:30-16:30
場所:早稲田奉仕園(東京メトロ東西線早稲田駅下車徒歩5分)
中川智視「19世紀アメリカにおける専門化の進展」(仮)
五味 篤「高橋是清のペルー銀山事件と地質関係者」
問い合わせ:矢島道子 pxi02070[at]nifty.com
(後)第59回アイソトープ・放射線研究発表会(オンライン)
7月6日(水)-8日(金)
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2022/top
(共)岩石―水相互作用国際会議(WRI-17)
7月30日(土)→2023年8月に延期となりました
会場:仙台市
https://www.wri17.com/
(後)科学教育研究協議会第68回全国研究大会(岡山大会)
8月10日(水)-12日(金)
会場 岡山理科大学 岡山キャンパス
https://kakyokyo.org/
(後)第9回国際地学教育会議
8月21 日(日)-25 日(木)
会場:くにびきメッセ(島根県コンベンションセンター)
https://ja.geoscied9.org/
日本地質学会第129年学術大会(2022東京・早稲田大会)
9月4日(日)-6日(火)
会場:早稲田大学早稲田キャンパス(東京都新宿区西早稲田)
※関連行事「地質情報展2022とうきょう」は同会場で9/3-/5開催予定
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0222.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
福岡大学理学部地球圏科学科地球科学分野公募(教授,准教授又は講師)(7/15)
2023年度国際室外国人客員教員の推薦公募(8/2)
住友財団2022年度「基礎科学研究助成」「環境研究助成」募集(6/30)
2022年度「深田賞」募集(6/30)
令和4年度栗駒山麓ジオパーク学術研究等奨励事業(5/9)
令和4年度 筑波山地域ジオパーク学術研究助成金の募集(5/31)
蔵王ジオパーク構想におけるジオパーク専門員の募集(5/31)
隠岐ユネスコ世界ジオパーク学術奨励事業募集(新規申込5/27締切)
徳島県三好市ジオパーク専門員の募集(5/31まで延長)
令和4年度白山手取川ジオパーク学術研究助成金事業の募集(5/6)
三島村・鬼界カルデラジオパークがジオパーク専門職員募集:随時受付(採用者が決まり次第終了)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
第13回惑星地球フォトコンテスト入選01
第13回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:4億年の記憶
写真:中川達郎(愛媛県)
撮影場所:愛媛県西予市三瓶町周木須崎海岸
【撮影者より】
2022 年1 月に再認定になった「四国西予ジオパーク」のジオサイトのひとつ,黒瀬川構造帯須崎海岸です.赤道付近から移動してきたと考えられているそうで,火山灰が海底に降り積もって固まった凝灰岩層で約4億年前の古い地層とのことです.この岩体は,マンモス岩と呼ばれて親しまれています.数年前の夏,西側から縦じまの地層がクリアに見えるように干潮時の夕刻前に太陽を背にして撮影しました.
【審査委員長講評】
四国西予ジオパークは愛媛県にある東西に細長いジオパークで,その海岸部に位置するのが須崎海岸です.4億年前のシルル紀〜デボン紀の地層は日本では分布が限られますが,海岸にこんなにくっきりと地層まで見える場所があるとは知りませんでした.最近はジオパークのHP等があるので,このような場所にアクセスしやすくなりました.
【地質的背景】
須崎海岸の縦縞の地層は,海の底で水平にたまった凝灰岩層が,その後の地殻変動でできたものです.4億年ほど前に生きていたサンゴの化石や放散虫の化石が見つかっており,それらの研究から,当時オーストラリアや南中国の陸塊が含まれていたゴンドワナ大陸の近くに起源をもつ地層だと推定されています.日本最古級の須崎海岸の地層は,「黒瀬川帯」と呼ばれる地帯に分布する,日本列島誕生の鍵となる地層が保存されている代表的な場所のひとつです.(郄橋 司:四国西予ジオパーク推進協議会)
目次へ戻る
第13回惑星地球フォトコンテスト入選02
第13回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:Inside the Volcano
写真:金井雄亮(東京都)
撮影場所:アイスランド レイキャビック南東20km スリーヌカギガル火山
【撮影者より】
通常噴火が終焉する際には残りのマグマは火口付近で固まり火道が閉じられてしまう.スリーヌカギガルはマグマが後退したことによりできたマグマだまり内部を見学できる世界でただ一つの火山. 最後の噴火は4000年以上前で,再び噴火する兆候はない. 火口はわずか4m四方,しかしゴンドラで降りるその下に広がる空間は自由の女神が入るほど. 日の光が届かないその空間は,赤や黄色,青や紫のカラフルな鉱物に彩られていた.
【審査委員長講評】
スリーヌカギガルはアイスランドの首都レイキャビクの南15kmにあるスコリア丘で,山頂からマグマが退いた火山の深部を覗ける人気の観光スポットになっています.インターネットでは,360°画像や動画が紹介されているので,この作品がどのような場所で撮影されたかがわかるでしょう.溶岩の酸化の度合いや硫黄の昇華物などによって色鮮やかな地底探険となりました.
【地質的背景】
スリーヌカギガル (Þríhnúkagígur) は,レイキャネス半島の割れ目火口群に形成されたスコリア丘のひとつです.このスコリア丘を形成した割れ目噴火では,マグマが地下に戻る際にマグマ供給系の最上部が崩壊せずに空洞として残りました.このため観光客は火口から火道をゴンドラでおりて地下120mの大空間に降りることができます.この大空間はマグマのぬけた岩脈の最上部ですが,マグマだまりへのツアーとして観光スポットとなっているようです.(萬年一剛:神奈川県温泉地学研究所)
目次へ戻る
第13回惑星地球フォトコンテスト入選:03
第13回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:大荒れ橋杭岩
写真:福村成哉(和歌山県)
撮影場所:和歌山県東牟婁郡串本町くじ野川橋杭岩
【撮影者より】
橋杭岩に高波が打ち付けているときに露光時間を長くして写真を撮影しました.手前の波食棚に転がる津波石に波が打ち寄せていますが,雲の上に浮いている岩のように表現できたと思います.
【審査委員長講評】
橋杭岩は毎年応募作品があります.この作品では荒天の日に津浪岩に打ち寄せる白波を長時間露光で雲海のように表現し,今までに見たことのない幻想的な作品にしました.光線が柔らかく,橋杭岩や津浪岩の質感もよくわかります.上側3分の1を占める空の部分が単調になってしまったのが少し残念です.
【地質的背景】
1500万年前の紀伊半島中央部から南部では,複数のカルデラを形成した大規模な火山活動が起こりました.その一連の火山活動の中で流紋岩からなる橋杭岩岩脈が形成されました.その後,周辺の泥岩が浸食によって失われ,橋杭(はしぐい)のように残る姿が南紀熊野ジオパークのジオサイトとなっています.橋杭岩の手前,波食面上に散在する岩塊群は,南海トラフで巨大地震が発生するたびに大津波が橋杭岩からもぎ取り運んだ「津波石」です.(和田穣隆:奈良教育大学)
目次へ戻る
第13回惑星地球フォトコンテスト入選:04
第13回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:ぽっかり
写真:笠井 忠(奈良県)
撮影場所:和歌山市新和歌浦 蓬莱岩
【撮影者より】
日本遺産に認定されている「絶景の宝庫 和歌の浦」.泥質片岩からなる蓬莱岩は,結晶片岩類に見られる片理構造や長い年月による岩の風化,波の侵食によってできた海食洞門などがアクセントをつけ,独特の形から奇岩と言われる和歌浦の名所で,縁起の良い名前からパワースポットとも言われています. 近づいて見ると,ぽっかり空いた穴からは,ぽっかり浮いた雲と海が望め,引き込まれるようなパワーを感じました.
【審査委員長講評】
蓬莱岩は海岸に露出した岩場で,観光名所になっています.超広角レンズを使ってダイナミックに蓬莱岩を捉え,そこに空いた穴からタイミング良くぽっかりと浮いた雲を捉えました.フイルム時代には右側の日陰部分は露出アンダーで表現できませんでしたが,最近のデジタルカメラでは階調域が広く,このような作品ができるようになりました.
【地質的背景】
和歌山市付近には,緑色の特徴的な苦鉄質片岩(緑色片岩)のほか,緑色ではないものの片理の発達した泥質片岩などの三波川変成岩類が分布します.海洋プレートの沈み込みに伴って,岩石が地下深部に到達すると,鉱物や組織などが変化した変成岩ができます.変成岩に含まれる鉱物が生成される温度・圧力の条件を調べて,どのくらい地下深部まで到達したのかを知り,大地の成り立ちを解き明かす研究が続けられています.三波川変成岩類は,白亜紀に変成を被ったものです.(後 誠介:和歌山大学客員教授)
目次へ戻る
第13回惑星地球フォトコンテスト入選:05
第13回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選(中高生部門):広がる世界
写真:谷川七海(長崎県)
撮影場所:長崎県五島市富江町土取
【撮影者より】
五島列島福江島富江の海岸で撮影した写真です.富江半島は福江島の南部に位置しており,流動性の高い玄武岩質溶岩でできた平坦な台地が広がります.この海岸では,流れた当時のしわ模様を残す黒々とした溶岩が見られます.透明度の高い海の向こうには,平坦な富江とは対照的で起伏のある福江のシンボル,鬼岳火山群が見えます.度重なる火山活動で,溶岩台地の上にいくつものスコリア丘ができています.福江島の火山を表す一枚が撮れました.
【審査委員長講評】
これも五島列島ジオパークでの作品です.福江島にはいくつかの単成火山群からなり,海を隔て鬼岳のスコリア丘とそこから広がる溶岩原,その右端には別のスコリア丘が見えます.手前は別の単成火山からの溶岩原で,この付近には日本で有数の溶岩トンネルがあります.力の入った作品ばかりを審査していると,のんびりしたこのような雰囲気の作品を見るとホッとします.
【地質的背景】
県立五島南高校の写真部は,本フォトコンの常連校であり,毎年多くの作品を応募いただいています.五島列島は,1月に日本ジオパークに認定され,ジオフォトの魅力を地域ぐるみで推進していることが感じられます.これら入選作品の撮影場所が,観光スポットにもなっているという話も聞くことができました.今回は,五島海岸の南側のなだらかな富江という場所から,五島の象徴である鬼岳火山(18000年前)を眺めるものです.青い海とパホイホイ溶岩が残る富江海岸は,荒々しい断崖海岸とはひと味違う優しい雰囲気が感じられます.(清川昌一:九州大学)
目次へ戻る
第13回惑星地球フォトコンテスト:佳作1-3
第13回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:坊主の入浴
写真:DHAKAL BISHAL(大分県)
撮影場所:大分県別府市鉄輪海地獄
【撮影者より】
大分県別府市の鬼石坊主地獄にて撮影いたしました。ナトリウム、一塩化物泉で構成された約99度にも達する灰色の熱泥が坊主の頭に見えることより、「鬼石坊主地獄」と呼ばれるようになったそうです。733年(天平5)に編まれた「豊後風土記」に登場するほど歴史が古く、それ以降も数々の書物に登場しています。大小の熱泥がポコポコと音を立てて生まれる様子は、時が経つのを忘れるくらい見入ってしまいました。
目次へ戻る
佳作:銅色の湖
写真:福永拓真(茨城県)
撮影場所:福島県耶麻郡北塩原村 銅沼
【撮影者より】
磐梯山の馬蹄形カルデラの中にある銅沼にて撮影。水酸化鉄などによって赤茶けた強酸性の湖と1888年の噴火でできた火口壁のなす雄大な景色を望む。
目次へ戻る
佳作:山に包まれる
写真:安永 雅(長崎県)
撮影場所:長崎県 五島市黄島
【撮影者より】
五島列島最南端の有人島、黄島(おうしま)には長崎県で最も低い山である細ヶ岳(ほそがたけ)がある。その高さ25m。地元の方々からは「わんわん」という愛称で呼ばれる山。一説には、山から「わんわん」という音が鳴るからとか。実は山の海側は、波による侵食のために大きえぐられており、確かに波が当たると音が響きそうである。潮が引いたときには山の内部に入れ、火山噴出物が美しく堆積した地層を観察できる。山に包みこまれる大好きな場所である。
目次へ戻る
第13回惑星地球フォトコンテスト:佳作4-5-6
第13回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:鬼の洗濯
写真:中吉剛彦(宮崎県)
撮影場所:宮崎県青島
【撮影者より】
宮崎県は青島神社に隣接する海岸は「鬼の洗濯板」と呼ばれている場所です。平らになった岩が幾重にも重なり、まさに洗濯板のようです。鬼の洗濯板とはうまい名前を付けたものです。
目次へ戻る
佳作:後退する氷河
写真:片岡雅子(兵庫県)
撮影場所:スイス ベルナー・オーバーラント、ブリュムリスアルプホルン
【撮影者より】
20年前には黒い岩を氷河が覆っていたように思います。余りの氷河の後退に、驚愕。その奥に聳えるブリュムリスアルプホルン。変わらず、白く輝く姿にほっとしました。氷河の破壊力、そして、自然の力に比べて人間の力ははるかに小さいと感じました。
目次へ戻る
佳作:険しき山
写真:小川智教(岩手県)
撮影場所:北穂高岳山頂から槍ヶ岳方面
【撮影者より】
南紀熊野ジオパークエリア内の和深海岸に、北アルプス山域 縦走をしながら自分の歩いてきた尾根を振り返る。 目の前の山は槍ヶ岳 岩肌をよく見ると地層なのか断層なのか筋が入っていることに気がつきました。 もしかして大昔は海の底にあった地なのでしょうか? こうして景色を眺めながらこの地球の大きさを感じ、そして自分のちっぽけな悩みなんて忘れてしまう。
目次へ戻る
第13回惑星地球フォトコンテスト:佳作7-9
第13回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:魅惑の川廻し洞窟
写真:糸賀一典(千葉県)
撮影場所:千葉県 市原市三間川上流域
【撮影者より】
かつてはコレほどの口径で無かったかもしれないが、風化や崩れるなどして地層が露わになったと思える「川廻し洞窟」。先人の農地などの確保の目的で掘られたとされる。比較的脆い地層であるため、掘りやすかったとされるが、それでも山奥に位置する洞窟堀は難工事であっただろう。川廻し洞窟を流れるせせらぎと、さえずりか聞こえない洞窟内で、しばし、先人の洞窟堀や農地開拓をしようとする熱意や技術などを感じる事が出来た。
目次へ戻る
佳作:崖の前の赤灯台
写真:紱本陽士(長崎県)
撮影場所:長崎県 五島市 玉之浦町 島山島
【撮影者より】
この写真は長崎県五島列島の島山島の地層と険しい波の中に立つ赤い灯台を撮影したものです。五島列島の大地は、約2200〜1700万年前に堆積した(ユーラシア)大陸由来の砂と泥が基であり、その当時は大陸の一部でした。写真に写っている大陸由来の砂と泥の地層(白と黒のしましま地層)のことを「五島層群」と呼びます。この写真を撮る際初めて五島層群を見て、圧倒されました。この写真を通して、五島の自然の雄大さを伝えたいです。
目次へ戻る
佳作:サメの口の中
写真:河野 潔(埼玉県)
撮影場所:岐阜県 高山市 飛騨大鍾乳洞
【撮影者より】
つらら状の鍾乳石に圧倒されました。まるでサメの口の中に入っていくような、芸術作品です。
目次へ戻る
第13回惑星地球フォトコンテスト:佳作10-12
第13回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:筏下り
写真:鈴木文代(和歌山県)
撮影場所:和歌山県 北山村オトノリ
【撮影者より】
オトノリ付近に分布する海底火山の噴出物は、はるか遠方の海洋底で形成された岩石であるそうです。その後、海洋プレートに乗って海溝まで運ばれ、約7000万年前に海溝で堆積した陸源性の地層と混在して大陸に付加したと考えられています。 現在は、観光筏下りとして賑わっています。
目次へ戻る
佳作:阿蘇の大地と春の天の川
写真:草田栄久(千葉県)
撮影場所:熊本県 阿蘇市 杵島岳山頂付近
【撮影者より】
杵島岳より阿蘇を臨む。草千里から噴煙立ち昇る阿蘇中岳までカメラに収めたかったがスケールが違った。草千里の2つの池は太古の火口と聞く。目の前に広がる複雑な起伏は如何に創り上げられたのか?太古の火口の仕業に違いない。烏帽子岳から昇る春の天の川。そして雲海の向こうに阿蘇外輪山が見える。ここに立つと阿蘇カルデラの桁違いのスケールを目の当たりにすることができる。
目次へ戻る
佳作:日本三奇石 生石神社
写真:明野敏行(兵庫県)
撮影場所:兵庫県 高砂市阿弥陀町竜山
【撮影者より】
古代より採石され続けられている石材(竜山石)は凝灰岩で、この石を御神体にいて神社「生石神社」です。
目次へ戻る
第13回惑星地球フォトコンテスト:佳作13-15
第13回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:褶曲の丘
写真:小澤 宏(神奈川県)
撮影場所:神奈川県横須賀市長井 荒崎海岸
【撮影者より】
海岸で隆起した海食台や海食崖が見られ美しい海岸美が見られる荒崎海岸。ジオパークに匹敵する褶曲の露頭を数多く見ることができ、その美しく且つダイナミックな光景に感動しました。
目次へ戻る
佳作:ガンガラ岩と五能線列車
写真:原口孝和(千葉県)
撮影場所:青森県西津軽郡深浦町森山 十二湖〜陸奥岩崎間(2022.5.11訂正)
【撮影者より】
五能線の旅をした際に、車窓から見た日本海の素晴らしい景色と奇岩に感動しました。撮り鉄が趣味だったので、いつか沿線の写真を撮ろうと思っていましたが、その後撮り鉄仲間と撮影に行きその思いを実現する事が出来ました。車で撮影ポイントを探している時に、ガンガラ岩と云う名前が気になり行って見ました。そこには五能線の線路もあったのでここで撮ろうと考え撮った写真です。奇岩と列車、自分では良い写真と思っています。
目次へ戻る
佳作:岩模様
写真:木下 滋(和歌山県)
撮影場所:和歌山県白浜町 権現崎の海岸
【撮影者より】
和歌山県白浜町権現崎にある岩模様です。ここは南紀熊野ジオパークエリア内にあり、田辺層群の泥岩岩脈です。幾層にも重なる模様が目を引きます。また近くには、ポットホールもあります。
目次へ戻る
第13回惑星地球フォトコンテスト:佳作16-18
第13回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:阿蘇カルデラ
写真:峯田翔平(山口県)
撮影場所:熊本県 阿蘇山
【撮影者より】
阿蘇カルデラは、30万年前-9万年前に発生した4回の巨大カルデラ噴火により形成されたカルデラ地形である。阿蘇山は火口湖も海もなく、カルデラの中に立って周囲の外輪山を見渡すことができる。カルデラを取り囲む外輪山も阿蘇火山に含まれ、東西約18キロメートル・南北約25キロメートルに及ぶ。カルデラを見下ろす大観峰などは、カルデラ噴火前の火山活動による溶岩とカルデラ噴火による火砕流堆積物(溶結凝灰岩)で構成された山である。
目次へ戻る
佳作:石灰藻球三千三百万年の旅
写真:井上克幸(長崎県)
撮影場所:長崎県 西海市西海町七ツ釜鍾乳洞近辺
【撮影者より】
説明版によると、「20数億年前、地球上に初めて酸素を作る石灰藻球が現れ、海中で層となり、三千三百万年前に化石層となってこの地に大陸の大移動により運ばれた。火山活動により隆起し山頂まで押し上げられ、台地を形成している。」運よく開放期間に訪れることが出来ました。異空間にいるようで、とてもワクワクしました。
目次へ戻る
佳作:逆層スラブ、穂高岳の溶結凝灰岩
写真:川邉竜也(愛知県)
撮影場所:和岐阜県 高山市、西穂高岳
【撮影者より】
約175万年前の槍穂火山の噴火により形成された、何層もの溶結凝灰岩。今尚残るその面影は、プレートが押し出され100万年をかけて約2000メートル隆起し、雲の上に鎮座した。
目次へ戻る
第13回惑星地球フォトコンテスト:佳作19
第13回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:ブロモ山噴火口
写真:白井里奈(愛知県)
撮影場所:インドネシア ジャワ島 ブロモ山噴火口
【撮影者より】
インドネシア ジャワ島 ブロモ山は日本では無名ですが東ジャワ随一の景勝地です。ジープと馬に乗りブロモ山へ。275段の階段を登ると噴火口。 白煙が立ち昇って硫黄の匂いがします。硫黄も見えます。 ブロモ山は火の神の住む聖なる山なのだそうです。 インドネシアはイスラム教に改宗したがここブロモ山に住む人々だけが今もヒンドゥー信仰を守りぬいているとのこと。祭りの時は今も山羊や鶏を生きたまま噴火口に投げ込むのだそう。噴火口は底に穴のあいたゴツゴツしたすり鉢のようであり、また地獄に続く燃える蟻地獄のように見えて、息をのむほど美しくはあるがとても恐ろしく思えました。
目次へ戻る
【geo-Flash】No.550 地質学露頭紹介 at JpGU2022 発表申込延長します
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.550 2022/5/11 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2022年「地質の日」行事のご案内
【2】日本学術会議シンポジウム?チバニアン,学術的意義とその社会的重要性?
【3】地質学露頭紹介 at JpGU2022(発表・参加募集中)
【4】【重要】会費などの変更についてのご提案について
【5】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2022年「地質の日」行事のご案内
──────────────────────────────────
学会関連の「地質の日」行事については,学会ホームページに随時情報を
掲載しています.
・惑星地球フォトコンテスト入選作品展示会開催中です!(上野公園:5/3-15)
・深海から生まれた城ケ島」 観察会(6/12)参加者募集中
詳しくは, http://www.geosociety.jp/name/content0176.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】日本学術会議シンポジウム?チバニアン,学術的意義とその社会的重要性?
──────────────────────────────────
日時:2022年5月24日(火)13:00-17:10 入場無料
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木 7-22-34)
共催:日本地質学会ほか
※本シンポジウムはハイブリッド形式で行います.
千葉県市原市の地層「千葉セクション」が,国際基準の地層境界である
「国際境界模式層断面とポイント(GSSP)」に認定され,約77万4千年前
から約12万9千年前の地質時代の名称が「チバニアン」と名づけられました.
本シンポジウムでは,チバニアンの決定における過程を振り返り,その科学
的および社会的な意義を紹介します.
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0147.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】地質学露頭紹介 at JpGU2022 発表申込期限を延長します
──────────────────────────────────
多くの会員に発表していただきたいため、発表申込を5/16(月)18時まで延長
します。日本地質学会2021年オンライン学術大会で好評を博した「地質学露頭
紹介」の第2弾です! 今回はJpGUと共同開催です。JpGU2022大会期間中に
オンラインで開催します。
とっておきの露頭、解釈がむずかしい露頭などなど。
露頭について、おおいに語りましょう! お忘れなく申し込みください。
日時:2022年5月29日(日)14:00開始
方法:オンライン Zoom+YouTubeライブ配信
発表申込期限:5月16日(月)18時(延長)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0146.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】【重要】会費などの変更についてのご提案について
──────────────────────────────────
会員数の減少を防ぎ,学会をさらに活性化するため以下の施策を導入することを
6/11の総会に諮る予定です.
******************************
・「学生会員」「シニア会員」の再定義と「ジュニア会員」の新設
・学生層やシニア層に対する会費の低減
・学術大会に参加しやすくなるための参加費設定
・長年在会し学会に貢献している会員への永年会員顕彰の拡充
******************************
総会までに,会員の皆様に提案内容をご理解いただくために,その概要を
お知らせしております.ぜひご確認ください.
詳しくは, http://www.geosociety.jp/news/n171.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質学雑誌からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・128巻:新しい論文が公開されています.
(論説)鹿野和彦ほか:鹿児島湾奥,姶良カルデラにおける後カルデラ
火山活動と環境の変遷
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/128/1/_contents/-char/ja
■ Island Arc
新しい論文が公開されています.
(RESEARCH ARTICLES)Relationship among paleosol types,
depositional settings, and paleoclimates in Tetori group (Lower Cretaceous,
central Japan) Kensuke Kuroshima,et al ほか
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
・学生・初級者向け 「地質断面図」の書き方講座 ―布良海岸巡検―
地層・堆積岩の見方を学び,測定した走向・傾斜をもとに地質断面図を
描けるようにする講座です.
6月4日(土) -5日(日)
申込期間:5月8日(日)-20日(金)定員になり次第締切
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
[中部支部]
・中部支部2022年支部年会・巡検のお知らせ
6月25日(土)10:30-17:30
会場:金沢大学角間キャンパス+Zoomオンライン(ハイブリッド)
事前登録(発表申込):6月17日(金)までに
特別講演「海洋掘削科学:日本海」・特別討論会「珠洲の群発地震」
巡検:白山手取川ジオパーク(6/26実施)巡検申込締切:5/31(金)
http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
第4回国際黒曜石会議(2023/7/3-7/6;於 北海道紋別郡遠軽町)
First Circularが公開されました
http://geopark.engaru.jp/ioc2023/
—---------------------------
シンポジウム:地質技術者育成の課題と対策:防災・減災、国土強靭化
を担う地質技術者の不足を鑑みて(オンライン)
5月21日(土)13:00-16:00
https://www.youtube.com/channel/UCSBjQkKQOIU7tGcn8TA1Wqw/featured
参加費無料,事前登録不要
主催:西日本地質人材コンソーシアム
http://www.geoee.jp/
(後)第59回アイソトープ・放射線研究発表会(オンライン)
7月6日(水)-8日(金)
事前参加登録(7,000円)締切: 6月10日(金)17時
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2022/top
(後)科学教育研究協議会第68回全国研究大会(岡山大会)
8月10日(水)-12日(金)
会場 岡山理科大学 岡山キャンパス
https://kakyokyo.org/
第76回地学団体研究会総会(長野)
8月20日(土) -20日(日)
開催方式:現地開催とオンラインのハイブリッド方式
現地会場:信州大学教育学部(長野県長野市)
https://www.chidanken.jp/
(後)第9回国際地学教育会議
8月21 日(日)-25 日(木)
会場:くにびきメッセ(島根県コンベンションセンター)
https://ja.geoscied9.org/
日本地質学会第129年学術大会(2022東京・早稲田大会)
9月4日(日)-6日(火)
会場:早稲田大学早稲田キャンパス(東京都新宿区西早稲田)
※関連行事「地質情報展2022とうきょう」は同会場で9/3-/5開催予定
第39回歴史地震研究会(高槻大会)
9月17日(土)-19日(月)
場所:関西大学高槻ミューズキャンパス
http://www.histeq.jp/kenkyukai.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0222.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
東北大学大学院理学研究科地学専攻助教公募(6/15)
早稲田大学教育・総合科学学術院(地球化学)准教授または教授(6/3)
桜島・ 錦江湾ジオパーク研究助成(7/1)
勝山市ジオパーク2022年度学術研究等奨励補助金公募(5/31)
伊豆大島ジオパーク学術研究奨励事業補助金募集(6/10)
土佐清水ジオパーク活動支援事業助成金募集(5/31)
白滝ジオパーク令和4年度研究助成の募集(6/3)
糸魚川ジオパーク令和4年度学術研究奨励事業の募集(5/27)
佐渡ジオパーク令和4年度域学連携づくり応援事業補助金募集(5/31)
室戸ユネスコ世界ジオパーク令和4年度学術研究助成金募集(5/17)
栗駒山麓ジオパーク推進協議会職員(ジオパーク専門員)の募集(5/25)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(注)大型連休の都合等のため,5月1回目の配信は本日となりました.
次回定期号は,第3火曜5/17に配信予定です.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.582 まだ間に合います!締切延長!若手巡検 in 北海道
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.582 2023/6/6┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】新しい会員管理システムの公開・利用について(再掲)
【2】若手巡検・研究集会 in 北海道洞爺湖有珠山ジオパーク地域
【3】第8回ショートコース(参加申込受付中)
【4】2023京都大会ニュース:講演申込受付開始!ほか
【5】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【6】若手巡検・研究集会 in 北海道 洞爺湖有珠山ジオパーク地域
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】新しい会員管理システムの公開・利用について(再掲)
──────────────────────────────────
これまで2年に一度冊子体の会員名簿を発行してまいりましたが,昨今の個人情報
保護の観点や関連諸団体の名簿発行状況等も鑑み,2019年度版会員名簿の発行を
最後に冊子体の会員名簿の発行は行わないことが理事会(2021年12月11日)にて
決議されました.その後,クラウド型会員管理システムの導入準備を進め,今年度
から利用していただくことができるようになりました.
新しいシステムでは,
・会員がWeb上でご自身の情報を確認・修正していただけます(住所変更)
・検索機能にて他の学会員の情報も閲覧可能です(会員名簿)
(注)これまでの会員名簿の掲載ルールに則した内容を公開しており,掲載承諾
を得られた項目について閲覧することができますが,非掲載を選択された項目は
閲覧できません.
詳しくは,http://geosociety.jp/news/n176.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】若手巡検・研究集会 in 北海道洞爺湖有珠山ジオパーク地域
──────────────────────────────────
<<参加者募集:締切延長>>
定員に若干名余裕がありますので,受付延長中です!まだ間に合います!
—---------------------------------
若手活動運営委員会では,洞爺湖周辺にて学生・若手研究者向けの巡検を
行います.夜間には,講師による基調講演と一部参加者によるポスター形式
の研究発表を行い,参加者の交流を深め研究活動を促進することを目的と
しています.
日時:2023年7月8日(土)13時から7月9日(日)18時
対象者:35歳未満の日本地質学会正会員
参加費:
正会員(学生会員):8,000円
正会員(一般会員):16,000円
申込締切:定員に達した時点で終了
詳しくは,http://geosociety.jp/science/content0160.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】第8回ショートコース(参加申込受付中)
──────────────────────────────────
日程:2023年7月2日(日)
<午前> 9:00-12:00
レーザーアブレーションーICP質量分析法(LA-ICP-MS法)によるU-Th-Pb年代測定法の原理と最前線:平田岳史(東京大学)
<午後> 14:00-17:00
砕屑性ジルコンU-Pb年代を用いた地質学研究:竹内 誠(名古屋大学)
申込締切:2023年6月22日(木)
詳しくは,http://geosociety.jp/science/content0161.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2023京都大会ニュース:講演申込受付開始!ほか──────────────────────────────────
■ 2023京都大会 本サイトオープンしました!
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/top
■ 演題登録受付を開始しました:7月12日(水)18時締切
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/collectsubject
■ ランチョン・夜間集会申込:7月12日(水)締切
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/meeting
■ジュニアセッション参加申込:8月1日(火)締切
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/gyoji#jr
■ 地質系業界説明会(参加企業・団体募集):6月30日(金)締切
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/gyokai_support
■企業団体展示・書籍販売:8月25日(金)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/tenji
※大会参加登録,巡検申込は,7月初旬より受付開始予定です.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・新しい論文が公開されています.
(論説)照来コールドロン,歌長流紋岩下部凝灰岩の年代:フェムト秒レーザー
アブレーション−多重検出器型ICP質量分析法を用いた後期鮮新世ジルコンの
ウラン−鉛年代測定:羽地俊樹ほか
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/list/-char/ja
・特集号「球状コンクリーションの科学」冊子体販売中:残部に余裕があります.
WEB上でも閲覧可能ですが,1冊のまとまった冊子をぜひお手元に.
http://geosociety.jp/news/n174.html
■ Island Arc
・Vol. 32の新しい論文が公開されています.
Apatite U–Pb dating of dinosaur teeth from the Upper Cretaceous Nemegt
Formation in the Gobi Desert, Mongolia: Contribution to depositional age
constraints: Myu Tanabe et al
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[北海道支部]
・2023年度例会(個人講演会)
6月17日(土)13:00-18:00
場所:北海道大学理学部5号館大講堂
参加費:一般会員500円,非会員1000円,学生無料
講演申込:6月7日(水)締切
・神居古潭巡検
8月18 日(金)-19日(土)
見どころ:蛇紋岩メランジュ中のテクトニックブロック/神居古潭変成岩上昇時の重複変成作用
参加費:正会員(一般・シニア)30,000 円/正会員(学生) 18,000 円
参加申込締切:7月20 日(木)※定員に達し次第締切
詳しくは,http://geosociety.jp/outline/content0023.html
[中部支部]
・2023年支部年会
6月24日(土)
会場:信州大学松本キャンパス
シンポジウム「西南日本の白亜紀花崗岩類」
巡検:大峰帯第四系と爺ヶ岳―白沢天狗カルデラ・黒部川花崗岩(6/25)
事前登録:6月15日(木)
詳しくは,http://geosociety.jp/outline/content0019.html
[関東支部]
・講演会「県の石−埼玉の岩石・鉱物・化石−」
7月8日(土)13:00-16:00
定員 現地60名,オンライン40名(先着順)
申込期間:5月23日(火)-6月16日(金)17:00まで
「秩父青石の利用と宮澤賢治・保阪嘉内が歌に詠んだ岩石鉱物」/「県立自然の
博物館の世界一のパレオパラドキシア化石コレクションとその研究」
現地見学会も予定しています.
http://geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
気象庁:関東大震災特設サイト
―関東大震災から100年―知って備えよう:過去の大災害から学ぶ
https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/1923_09_01_kantoujishin/index.html
防災学術連携体:関東大震災100年関連行事等の特設ページ
https://janet-dr.com/090_abroadandhome/091_100_kantohEQ.html
-------------------------------------------------
日本応用地質学会シンポジウム(ハイブリッド)
6月16日(金)13:00-17:00
テーマ:応用地質学のD&I−多様な人材の活躍による応用地質学の発展
現地:東京大学柏キャンパス新領域環境棟FSホール
WEB:Zoom会議方式
参加申込締切: 6月9日(金)
https://www.jseg.or.jp/00-main/symposium.html
(後)日本学術会議公開シンポジウム(ハイブリッド)
「有人潜水調査船の未来を語る」
6月17日(土)13:00-17:00
場所:日本学術会議講堂
一般参加可,参加費不要
https://www.scj.go.jp/ja/event/index.html
東京地学協会2023年度 特別講演会
6月17日(土)15:00-16:30
場所:アルカディア市ヶ谷(私学会館)
講演:石原あえか(東京大学大学院総合文化研究科教授)
「鉱物コレクターとしてのゲーテ―岩石と対話する詩人」
事前申込不要
http://www.geog.or.jp/lecture/lecturescheduled/476-news230617.html
文部科学省「ナノテラス」利用説明会(ハイブリッド)
現在,仙台市に建設中の次世代放射光施設ナノテラスの説明会を開催します.
日程:6月26日から7月31日まで計8回予定
どなたでも参加いただけます.要参加申込(締切:各回24時間前までに)
https://www.mext.go.jp/b_menu/gyouji/detail/mext_00049.html
第241回イブニングセミナー(オンライン)
6月30日(金)19:30-21:30
演題:PFOSからPFASへーフッ素系界面活性剤を巡る国内外の動きー
講師:柴田康行(前東京理科大学環境安全センター副センター長)
参加費:主催NPO会員及び学生の方(無料)非会員の方(1,000円)
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
(後)第60回アイソトープ・放射線研究発表会
7月5日(水)-7日(金)
会場:東京都内会場(予定)
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2023/top
東京地学協会2023年度 定期講演会
7月8日(土)13:30-16:00
会場:東京グリーンパレス(全国市町村職員共済組合連合会福祉施設)
テーマ:水蒸気噴火のメカニズムと噴火予知への課題─最新の知見と火山防災─
参加費無料・申込不要
http://www.geog.or.jp/lecture/lecturescheduled/475-news230708.html
(共)岩石-水相互作用(WRI-17)または
応用同位体地球化学(AIG-14)合同国際会議
8月18日(金)-22日(火)
会場:仙台国際センター
https://www.wri17.com/
ぼうさいこくたい2023(第8回防災推進国民大会)
9月17日(日)-18日(月・祝)
場所:横浜国立大学(横浜市保土ヶ谷区常盤台)
https://bosai-kokutai.jp/2023/
(共)2023年度日本地球化学会 第70回年会
9月21日(木)-23日(土)
開催場所:東京海洋大学品川キャンパス会場(一部ハイブリッド)
口頭発表(ハイブリッド),ポスター発表(対面)
http://www.geochem.jp/meeting/
(協)Techno-Ocean 2023
10月5日(木)-7日(土)
会場:神戸国際展示場2号館 ほか
https://to2023.techno-ocean.com/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・科学技術振興機構先端国際共同研究推進事業公募(事前7/31,最終8/7)
※公募説明会(6/16開催,要事前登録)
・東京外国語大学AA研フィールドネットラウンジ公募
・海洋研究開発機構リスタート支援公募(7/31)
・原子力規制庁行政職員(技術系:実務経験者)採用公募(6/30)
・五島列島(下五島エリア)ジオパーク活動支援助成金(6/30)
・伊豆半島ジオパーク学術研究助成(6/15締切延長)
・桜島・錦江湾ジオパーク学術研究助成募集(6/9)
・三陸ジオパーク学術研究助成金(6/26)
・南紀熊野ジオパーク学術研究・調査活動助成事業(6/30)
・三陸ジオパーク ジオパーク専門員・コーディネーター募集(7/7)
その他,公募,助成等の情報は,http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.551 2022東京・早稲田大会:まもなく講演申込開始です
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.551 2022/5/17 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2022年度(第14回)代議員総会開催について
【2】【重要】学会活性化に関わる会費などの変更について(第2回)
【3】2022年東京・早稲田大会:間もなく講演申込開始です
【4】地質学露頭紹介 at JpGU2022 露頭について、おおいに語りましょう!
【5】日本学術会議シンポジウム:チバニアン,学術的意義とその社会的重要性
【6】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【7】法地質学研究委員会からお知らせ
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2022年度(第14回)代議員総会開催について
──────────────────────────────────
日時:2022年6月11日(土)14:00-15:30
※WEB会議形式で開催いたします.
正会員は,総会に陪席することができます.ただし,総会規則12条3項により,
許可のない発言はできません.
議事次第はこちら
http://www.geosociety.jp/outline/content0152.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】【重要】学会活性化に関わる会費などの変更について(第2回)
──────────────────────────────────
「学会活性化に関わる会費などの変更についてのご提案」を2022年2月15
日に学会HPに掲載し、会員の皆様にご説明しました。
4月9日開催の理事会において、この内容についての最終承認がされ、本件に
係る定款および運営規則の変更を6月11日開催予定の代議員総会に諮ること
となりました。前回お知らせした変更内容の骨子は以下のとおりです。
******************************
*「学生会員」「シニア会員」の再定義と「ジュニア会員」の新設
*学生層やシニア層に対する会費低減の変更
*学術大会に参加しやすくなるための参加費低減の変更
*長年在会し学会に貢献している会員への永年会員顕彰の拡充変更
******************************
今回は、前回の変更内容にもとづく、定款および運営規則の変更内容につい
て、会員の皆様にお知らせするものです。
総会までに,会員の皆様に提案内容をご理解いただくために,その概要を
お知らせしております.ぜひご確認ください.
詳しくは, http://www.geosociety.jp/news/n171.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2022年東京・早稲田大会:間もなく講演申込開始です
──────────────────────────────────
日本地質学会第129年学術大会東京・早稲田大会を下記の日程で開催します.
今年は口頭発表については3年ぶりに対面で行えるよう準備していますが,
ポスター発表はオンラインで口頭発表とは別日に開催する予定です.
5月下旬から演題登録の受付開始予定です.
会期:2022年9月4日(日)-6日(火)
会場:早稲田大学 早稲田キャンパス14号館,15号館
※(注)ポスター発表は9/10 or 9/11にオンラインで実施します
(e-poster形式).現地会場での対面形式ポスター発表はありません.
大会プレサイトはこちら(本サイトもまもなく公開予定です)
http://www.geosociety.jp/science/content0144.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地質学露頭紹介 at JpGU2022 露頭について、おおいに語りましょう!
──────────────────────────────────
日本地質学会2021年オンライン学術大会で好評を博した「地質学露頭
紹介」の第2弾です! 今回はJpGUと共同開催です。JpGU2022大会期間中に
オンラインで開催します。とっておきの露頭、解釈がむずかしい露頭などなど。
露頭について、おおいに語りましょう!
日時:2022年5月29日(日)14:00開始
参加方法:オンライン Zoom(要事前申込)+YouTubeライブ配信(申込不要)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0146.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】日本学術会議シンポジウム:チバニアン,学術的意義とその社会的重要性
──────────────────────────────────
日時:2022年5月24日(火)13:00-17:10 入場無料
場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木 7-22-34)
共催:日本地質学会ほか
※本シンポジウムはハイブリッド形式で行います.
千葉県市原市の地層「千葉セクション」が,国際基準の地層境界である
「国際境界模式層断面とポイント(GSSP)」に認定され,約77万4千年前
から約12万9千年前の地質時代の名称が「チバニアン」と名づけられました.
本シンポジウムでは,チバニアンの決定における過程を振り返り,その科学
的および社会的な意義を紹介します.
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0147.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・128巻:新しい論文が公開されています.
(論説)鹿野和彦ほか:鹿児島湾奥,姶良カルデラにおける後カルデラ
火山活動と環境の変遷
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/128/1/_contents/-char/ja
■ Island Arc
新しい論文が公開されています.
(RESEARCH ARTICLES)Zircon U–Pb ages of the Higo plutonic
complex: Implication for migration of Cretaceous igneous activity
in Kyushu, southwest Japan Yukiyasu Tsutsumi
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】法地質学研究委員会からお知らせ
──────────────────────────────────
4月理事会において法地質学研究委員会の設立が認められ,活動を開始しました.
→法地質学研究委員会設立趣意書はこちらから
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/geoFlash_img/no551_hochishitsu_shui.pdf
本委員会では我が国における法地質学の普及と発展,また,既存の地質学に関する
情報のさらなる利用による社会貢献を目指して尽力していきたいと考えています.
その一環として,本年度のJpGU学術大会で法地質学関係のセッションを5月25日
に開催いたします.本セッションでは招待講演に国際地質科学連合法地質学イニ
シアティブ(IUGS-IFG)の議長であるLaurance Donnelly博士と連邦捜査局(FBI)
のLibby Stern博士を予定しています.貴重なお話を伺うことができる機会です
ので,是非とも会員の皆様のご来場とご視聴をお願いします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
・学生・初級者向け 「地質断面図」の書き方講座 ―布良海岸巡検―
地層・堆積岩の見方を学び,測定した走向・傾斜をもとに地質断面図を
描けるようにする講座です.
6月4日(土) -5日(日)
申込期間:5月8日(日)-20日(金)定員になり次第締切
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html
[中部支部]
・中部支部2022年支部年会・巡検のお知らせ
6月25日(土)10:30-17:30
会場:金沢大学角間キャンパス+Zoomオンライン(ハイブリッド)
事前登録(発表申込):6月17日(金)までに
特別講演「海洋掘削科学:日本海」・特別討論会「珠洲の群発地震」
巡検:白山手取川ジオパーク(6/26実施)巡検申込締切:5/31(金)
http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
第4回国際黒曜石会議(2023/7/3-7/6;於 北海道紋別郡遠軽町)
First Circularが公開されました
http://geopark.engaru.jp/ioc2023/
-----------------------------------------
マーティン・ヘッド学術講演会
テーマ:人新世について
5月19日(木)15:00-16:30
オンラインzoomセミナー(先着500名)
※英語(同時通訳はありません)
主催:茨城大学研究・社会連携部研究推進課
https://events.admb.ibaraki.ac.jp/2022/09000729.html
シンポジウム:地質技術者育成の課題と対策:防災・減災、国土強靭化
を担う地質技術者の不足を鑑みて(オンライン)
5月21日(土)13:00-16:00
参加費無料,事前登録不要
主催:西日本地質人材コンソーシアム
http://www.geoee.jp/
第237回イブニングセミナー(オンライン)
6月17日(金)19:30-21:30
演題:熱海で発生した泥流被害とその他の近年の土石流・泥流被害
講師:安田 進(東京電機大学 名誉教授)
主催:NPO法人日本地質汚染審査機構
参加費:主催NPO会員(無料) 非会員(1,000円)
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
下北ジオパーク学術研究発表会
6月19日(日)14:00-16:00
使用媒体:Zoom
参加料:無料
要事前申込(6月10日締切)
https://shimokita-geopark.com/2022/05/13/research2022/
(後)第59回アイソトープ・放射線研究発表会(オンライン)
7月6日(水)-8日(金)
事前参加登録(7,000円)締切: 6月10日(金)17時
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2022/top
(後)科学教育研究協議会第68回全国研究大会(岡山大会)
8月10日(水)-12日(金)
会場 岡山理科大学 岡山キャンパス
https://kakyokyo.org/
第76回地学団体研究会総会(長野)
8月20日(土) -20日(日)
開催方式:現地開催とオンラインのハイブリッド方式
現地会場:信州大学教育学部(長野県長野市)
https://www.chidanken.jp/
(後)第9回国際地学教育会議
8月21 日(日)-25 日(木)
会場:くにびきメッセ(島根県コンベンションセンター)
https://ja.geoscied9.org/
日本地質学会第129年学術大会(2022東京・早稲田大会)
9月4日(日)-6日(火)
会場:早稲田大学早稲田キャンパス(東京都新宿区西早稲田)
※関連行事「地質情報展2022とうきょう」は同会場で9/3-/5開催予定
(後)第65回粘土科学討論会
9月7日(水)-8日(木)
(討論会のみの実施,現地見学会は開催しません)
会場:島根大学
http://www.cssj2.org/event/annual_meeting/
第39回歴史地震研究会(高槻大会)
9月17日(土)-19日(月)
場所:関西大学高槻ミューズキャンパス
http://www.histeq.jp/kenkyukai.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0222.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・第17回「科学の芽」賞募集(8/12-9/17)
・東京大学地震研究所共同利用(特定機器利用)公募(6/30)
・EIG CONCERT-Japan第9回共同研究課題原子レベルでの材料設計公募(7/18)
・令和4年度下北ジオパーク研究補助金の募集(6/8)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
日本地質学会の60, 75, 100周年記念誌を読む:125周年に向けて
日本地質学会の60, 75, 100周年記念誌を読む:125周年に向けて
石渡 明(日本地質学会会長、東北大学東北アジア研究センター)
1893年の創立から今年で121年になるが(ただし1934年までは「東京地質学会」)、本学会は60、75、100周年に記念誌を刊行してきた。この他、1985年に地質学論集25号「日本の地質学—1970年代から1980年代へ」、1998年に同49号「21世紀を担う地質学」と50号「21世紀の構造地質学にむけて」の総説集を刊行した。ここでは、これらを読んで簡単な感想を述べ、125周年に向けての一歩としたい。敬称を略すことをお許し願いたい。
1918年の25周年は記念大会を行ったが(山崎直方会長)、記念誌は展覧会の目録以外見当たらない。しかし、1905年の地質学雑誌12巻393-405頁に初代会長神保(じんぼ)小虎の「本邦に於ける地質学の歴史」がある。「西国の開化我国に移らんとして以来経年の短きに比して進歩の甚(はなはだ)著し」という書き出しで約30年間の日本地質学をまとめ、「要するに我国の(地質)探検は、初めは幕府及び開拓使のアメリカ人に因(よ)りて基(もとい)を開かれ、後ドイツ流にて中央政府の地質調査所起こり、之に倣(なら)って北海道庁の地質略察始まり、一方にはドイツ風を輸入せる東京大学の地質学科ありて(中略)今日の状態に達した」と結び、初期の白野夏雲の功に言及している。神保はライマンの地質調査を強烈に批判したが、ここでは彼の業績も淡々と記している。詳細は佐藤伝蔵の追悼文(1923, 地質雑 30, 図版15)、佐藤博之(1983, 地質ニュース346号)、松田義章(2010, 地質学史懇話会会報34, 35号)、浜崎健児(2011, 同36号)を参照されたい。神保は徳川旗本の家の出で、本学会は幕府側出身の会長で出発したことになる。1905年の会員数は161人だったが、会誌は創刊以来毎月発行されていた。
1943年の50周年は太平洋戦争の最中で、東大での総会に加え北大で臨時総会と記念学術大会が開催されたが、記念誌の発行はなかった。そこで、戦争が終結して8年後の1953年に60周年記念の「日本地質学会史」(185頁)を発行した。ソフトカバーで紙質も印刷も悪いが、内容は非常に読み応えがある。編集委員長は鹿間時夫、編集委員は生越(おごせ)忠、小林英夫、牛来(ごらい)正夫、坂田嘉雄、須藤俊男、高井冬二、西山芳枝、宮沢俊弥、向山 広、森本良平、渡部景隆である。内容は、日本地質学会60年略史(早坂一郎)、日本地質学史年表(編集委員会)、部会史(古生物、鉱山、鉱物)、歴代会長名及び評議員名、研究奨励金受賞者、明治時代の日本における地質学(矢部長克)、おもいで(主に明治時代7編)、追悼の辞(鹿間)、物故者一覧(写真つき、82名)、追悼文(五十音順、86名)、各大学研究室の歴史(19教室)、新制大学地学関係教室一覧、地質調査所・博物館・研究所等の歴史、関係学会及び関係団体の歴史、外地の調査研究機関の歴史、関係会社の地質調査研究史、地質学者以外の功労者(須藤)、地質学、鉱物学会における開拓者、特(篤)志家、標本家、標本商列伝(櫻井欽一)、日本産新鉱物表(附台湾・朝鮮産)(櫻井)となっている。特に矢部と櫻井の文章は一読の価値があり、鹿間の追悼の辞も切々と胸に迫るものがある。各人の追悼文を読むと、大部分の人は病死または戦病死であるが、阿波丸に乗船していて台湾沖で「米国潜水艦の魚雷攻撃を受け同船沈没と共に戦死」、「30歳を一期に船と共に爆沈」といった記述が数件あり、「(西南太平洋にて)米軍艦船40隻の来襲を受け戦死」、「仏印寧平南方15粁チョガンにて戦死」という人もいる。一方で「地質調査所に入所間もなく任官辞令を入質して酒を呑んだということは地質開闢(かいびゃく)以来始めてだと先輩をして唖然とさせた」といった楽しいエピソードもある(この人は福井県中竜鉱山附近のクロリトイド片岩の発見者)。朝鮮、台湾、満州、中国、南洋の調査機関の歴史は各機関で指導的立場だった人が執筆しているが、樺太だけは委員長の鹿間が「執筆者不在につき代筆」している。事情は不明だが、鹿間は満州国の新京(長春)工業大学教授として1942年に赴任する前、東北大学副手だった1937年に樺太庁嘱託で南樺太を調査しており(地質雑, 45, 423-424)、そのつながりだろう。私は学部時代に彼の所属教室で過ごし、大陸からの引揚げの苦労話はよく聞いたが、この記念誌を編集・執筆した話は全く聞いておらず、「教室史」にも記事がない。1953年の会員数は1662人であり、半世紀前に比べ1桁増えた。偶然にも私はこの年に生まれた。
1968年に発行された75周年記念の「日本の地質学—現状と将来への展望—」は610頁の黄色のハードカバー本で、編集委員長は大森昌衛、委員は青木滋、大町北一郎、杉村新、高野幸雄、松尾禎士、山下昇であり、年表委員として今井功、小林宇一、服部一敏が加わり、執筆者は共著者を含め48人に達する。75周年記念大会も委員長渡辺武男(会長)、実行委員長森本良平らにより組織された。時は佐藤栄作首相下の高度成長の最盛期、ベトナム戦争に米軍が本格介入していて、日本の大学では反戦運動や70年安保に向けての反対闘争が盛り上がりつつあった頃である。「はしがき」では「専門分野の著しい分化と大量の図書・論文の出現により(中略)他の分野あるいは学界全般の現状を知ることに著しい困難を生じている。本書は、このような問題に対処することを目ざした」と言う。この本には戦争の影は既になく、全巻学問的なレビュー集である。第I部は特別寄稿で、渡辺武男の万国地質学会議の話、矢部長克の四国構造論(英文)、坪井誠太郎の岩石学雑想が載っている。第II部は日本の地質学の展望で、各分野の23編のレビューが掲載されている。第III部は日本の地質学界の展望として、学会史年表、会員数と役員の推移、学会賞・研究奨励金受賞者、大学地学教室一覧、アンケートのまとめ、地学関係研究所、学協会、団体、賛助会員、会社、博物館、そして長期研究計画の現状が掲載されている。この年の会員数は2481人だった。
1985年の論集(518 頁)は日本地質学の地向斜論からプレート論へのパラダイム転換の最中に出版され、今読み直すと非常に面白い。刊行委員長は端山好和、委員は兼平(かねひら)慶一郎、鈴木尉元、床次(とこなみ)正安、楡井(にれい)久、野沢保、浜田隆士、吉田尚で、編集実務は橋辺菊恵(現事務局長)が担当した。極端な地向斜派から急進的なプレート派までを網羅し、端山のまえがきはプレート論に懐疑的だが、プレート論の成立過程やそれに関わった日本の研究を見事にまとめた堀越叡の島弧論が光っている。またこの論集には、本学会のこの種の出版物では初の女性執筆者が登場する(永原裕子「日本の隕石学」)。会員数は4928人と倍増した。
1993年発行の100周年記念誌は706頁の紺地に金文字の堂々たるハードカバー本で、編集委員長は鈴木尉元、委員は天野一男、市川浩一郎、今井 功、遠藤邦彦、酒井豊三郎、島崎英彦、鳥海光弘、端山好和、山下 昇の9名であり、執筆者は78人にのぼる(私を含む)。会長の端山は序文で「現在、日本地質学は、学問体系そのものの転換を求められている」と言っているが、この頃はもう「転換済み」だったと思う。この年はバブル崩壊後の経済停滞期で、オウム真理教の活動が不気味さを増し、2年後に阪神大震災と地下鉄サリン事件が起きた。ソ連崩壊の2年後、湾岸戦争の3年後、天安門事件の4年後に当たる。しかし、地質学会としては、会員数が5000人の大台を超え、前年には皇太子殿下を総裁にお迎えして第28回万国地質学会議(IGC)京都大会を成功させ、英文学術誌The Island Arc(表紙は沈み込み帯の断面図。今はTheがない)が創刊されて、100周年誌はいわば地質学会の絶頂期の記念碑である。この本の冒頭には山下の「ナウマンから江原真伍まで」、端山の「小藤文次郎」、清水大吉郎の「小川琢治」、佐藤正の「小林貞一」などの評伝があり、列島形成論の歴史、島弧論、環境、災害、地下資源、国際交流、地学教育などの各論も充実している。今井功の学会史年表は資料価値が高いが、国際誌に発表した日本の重要論文の採録が少ない。岡野武雄の「第二次大戦前・中の海外地質調査」は多くの資料に基づく労作であるが、樺太の項は短く、日本が関与して成功した北樺太の石油開発の記述がないのは残念である。
1998年の地質学論集49号の編集委員は秋山雅彦、小松正幸、坂幸恭、新妻信明、50号は狩野謙一、高木秀雄、金川久一、木村克己、伊藤谷生、山路敦、小坂和夫で、執筆者は計78人(私を含む)、うち女性は3人である(田崎和江、清水以知子、佐々木みぎわ)。49号は平朝彦の「付加体地質学の誕生と発展」や丸山茂徳の「21世紀の日本の地質学」、陸上・海底掘削のレビュー、弘原海(わたつみ)清の「宏観異常による地震危険予知」などがある。1995年の阪神大震災を受けた杉山雄一の「活断層調査の現状と課題」もあるが原発の語は一つもない。50号はフラクタルなど2編が英語で、基礎的な構造地質学や日本列島地質構造論(磯崎行雄など)の他に月と火星のテクトニクス、応用地質のレビューがあり、「地震予知研究における構造地質学の役割」(嶋本利彦)もある。この時期は地震予知を楽観視していたようだ。会員数は翌1999年に5200人を越えたが、これ以後減少し、現在は4000人を少し下回る。
2014年の現在まで15年間以上、この種の大きな総説集は本学会では刊行されていない。この間、日本国内では直下型の被害地震が多発して柏崎刈羽原発が被災し、ついには「想定外」の海溝型超巨大地震が発生して福島第一原発のメルトダウン事故が起きてしまった。これを受けて、原子力規制委員会による原発敷地内の破砕帯調査が開始され、本学会が推薦した委員が国民注視の中で調査を行う事態になっている。また、イタリアのラクイラ地震裁判では、地震学者や地質学者が不適切な情報を住民に伝え被害を拡大させたとして有罪判決を受け、本学会はこれに憂慮を表明した。さらに、地球温暖化の進行とともに土砂災害も増加し、地質研究者と社会の関わりが増している。最近のジオパークの発展や津波堆積物への世界的関心はその肯定的な面であろう。一方で他の惑星や衛星の地質学が発展し、その成果に基づいて地球の地質を見直す必要が出てきている。現在、70〜80年代の学問的なパラダイム転換とは異質の、科学者としての意識や価値観の転換が求められているように感じる。今、地質学の歩みを振り返り、新しい展望を示すことが、是非とも必要である。4年後の125周年に向けて、日本地質学の新たな展望を示す総括的なレビューを行うべきだと思う。
geo-Flash No.250 2014/2/18掲載
日本地質学会News vol.17, 3月号 p.4-5掲載
【geo-Flash】No.553 2022東京・早稲田大会情報!!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.553 2022/6/7 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2022年度(第14回)代議員総会開催について
【2】【重要】学会活性化に関わる会費などの変更について(第2回)
【3】[2022早稲田]講演申込受付中です
【4】[2022早稲田]ダイバーシティ認定ロゴ導入の取り組み
【5】[2022早稲田]巡検コース紹介掲載しました
【6】[2022早稲田]ランチョン・夜間小集会募集
【7】[2022早稲田]ジュニアセッション(e-poster)参加校募集
【8】[2022早稲田]企業展示・書籍販売 対面開催します
【9】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【10】支部情報
【11】(アンケート協力依頼)若手研究者をとりまく評価に関する意識調査
【12】デジタル配列情報(DSI)に関するオープンレターへの署名のお願い
【13】その他のお知らせ
【14】公募情報・各賞助成情報等
【15】訃報:石田志朗 名誉会員 ご逝去
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2022年度(第14回)代議員総会開催について
──────────────────────────────────
日時:2022年6月11日(土)14:00-15:30
※WEB会議形式で開催いたします.
正会員は,総会に陪席することができます.ただし,総会規則12条3項により,
許可のない発言はできません.
議事次第はこちらhttp://www.geosociety.jp/outline/content0152.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】【重要】学会活性化に関わる会費などの変更について(第2回)
──────────────────────────────────
「学会活性化に関わる会費などの変更についてのご提案」を2022年2月15
日に学会HPに掲載し、会員の皆様にご説明しました。
4月9日開催の理事会において、この内容についての最終承認がされ、本件に
係る定款および運営規則の変更を6月11日開催予定の代議員総会に諮ること
となりました。前回お知らせした変更内容の骨子は以下のとおりです。
******************************
*「学生会員」「シニア会員」の再定義と「ジュニア会員」の新設
*学生層やシニア層に対する会費低減の変更
*学術大会に参加しやすくなるための参加費低減の変更
*長年在会し学会に貢献している会員への永年会員顕彰の拡充変更
******************************
今回は、前回の変更内容にもとづく、定款および運営規則の変更内容につい
て、会員の皆様にお知らせするものです。
総会までに,会員の皆様に提案内容をご理解いただくために,その概要を
お知らせしております.ぜひご確認ください.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/news/n171.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2022早稲田]講演申込受付中です
──────────────────────────────────
日本地質学会第129年学術大会東京・早稲田大会を下記の日程で開催します.
今年は口頭発表については3年ぶりに対面で行えるよう準備しています.
ポスター発表はe-poster(オンライン)で口頭発表とは別日に開催予定です.
会期:
(口頭発表)2022年9月4日(日)-6日(火)
(e-poster)2022年9月10日(土)-11日(日)
(注)口頭発表は現地対面開催.ポスター発表はe-poster(オンライン)のみ.
会場:早稲田大学 早稲田キャンパス 14・15号館
講演申込の受付中です!!
************************************
演題登録・要旨投稿 締切:2022年6月29日(水)18:00 厳守
************************************
はじめに、2022年学術大会専用のアカウント登録が必要です.
1アカウントで複数の演題登録が可能です.
会員・非会員問わず(招待講演者,入会申込中の方も含む),アカウント登録・
演題登録・要旨投稿の操作が可能です.締切まで何度でも修正可能です.
************************************
締切前に,あわてないためにもまずはアカウント登録を!!
************************************
大会サイトはこちらhttps://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2022早稲田]ダイバーシティ認定ロゴ導入の取り組み
──────────────────────────────────
昨年度試験的に導入したダイバーシティ認定ロゴ「ECS (Early Career
Scientist)・EDI(Equality, Diversity and Inclusion)」を皆様のご意見を
反映して改定し,理事会の承認を受け129年学術大会から導入することに
なりました.
EDIロゴ(申請者:セッション世話人)
ECS ロゴ(申請者:学会に参加する該当者本人)
いずれも申請が必要です.積極的申請をよろしくお願いいたします.
申請締切:2022年7月10日
詳しくは,http://www.geosociety.jp/engineer/content0063.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2022早稲田]巡検コース紹介掲載しました
──────────────────────────────────
東京・早稲田大会では,計9コースの巡検を計画しています.
各コースの詳細を大会HP,ニュース誌5月号に掲載しました.
なお,巡検実施にあたってのCOVID-19に関わる対応指針を策定しました.
安全に巡検が実施できるよう,ご協力をお願いいたします.
************************************
申込締切: 8月10日(水)18:00(オンラインのみ)
(申込フォームを準備中です.今しばらくお待ちください)
************************************
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/excursion
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[2022早稲田]ランチョン・夜間小集会募集
──────────────────────────────────
口頭発表の会期中(9月4日-6日)に対面形式で開催いたします.会合開催を
ご希望の場合は,必要な申込項目をe-mailで行事委員会宛に申し込んで下さい.
開始終了時刻は日によって異なります.
<<申込締切:6月29日(水)>>
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/meeting
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】[2022早稲田]ジュニアセッション(e-poster)参加校募集
──────────────────────────────────
東京・早稲田大会では,第20回日本地質学会ジュニアセッションを開催します.
小・中・高等学校の地学クラブの活動および授業の中で児童・生徒が行った研究
の発表を募集します.
今年は,昨年同様ジュニアセッションもe-posterによる発表となります.審査も
オンライン上で行います(当日の表彰は行いません).
ぜひ周囲の学校関係者の方々にご周知ください.
************************************
参加申込書の締切:8月1日(月)
************************************
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/gyoji#es
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】[2022早稲田]企業展示・書籍販売 対面開催します
──────────────────────────────────
企業等団体展示会,書籍・その他物品の販売ブースを対面形式で大会会場内
に設置予定です(期間:9/4-9/6).
詳細が確定次第,大会HPでお知らせいたします.今しばらくお待ちください.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/tenji
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・128巻:新しい論文が公開されています.
(報告)Yui Takahashi et al: Kasimovian (Late Pennsylvanian) conodont fauna
from a limestone block in the Ōtani Formation, Kuzuryu area of the Hida Gaien
belt, Fukui Prefecture, central Japan/(レター)公文冨士夫ほか:沖縄島,残波
岬北東沖で採取されたモモイロサンゴ遺骸の14C年代とその地質学的意義 ほか
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/128/1/_contents/-char/ja
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】支部情報
──────────────────────────────────
[中部支部]
・中部支部2022年支部年会・巡検のお知らせ
6月25日(土)10:30-17:30
会場:金沢大学角間キャンパス+Zoomオンライン(ハイブリッド)
事前登録(発表申込):6月17日(金)までに
特別講演「海洋掘削科学:日本海」・特別討論会「珠洲の群発地震」
巡検:白山手取川ジオパーク(6/26実施)巡検申込締切:5/31(金)
http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】(アンケート協力依頼)若手研究者をとりまく評価に関する意識調査
──────────────────────────────────
日本学術会議若手アカデミーでは,「若手研究者をとりまく評価に関する意識調査
(webアンケート)」が実施されます.若手研究者のより良い研究・学術活動を可
能にする環境構築に向けた調査となります.アンケートにご協力いただきますよう
お願い申し上げます.
調査対象:45歳未満の若手研究者の方々(大学院生や若手の専門職を含む)
アンケートサイト:
(1)https://r10.to/yaj2022(回答は任意です)
(2)所要時間:10分程度
(3)回答締切:2022年7月5日(火)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】デジタル配列情報(DSI)に関するオープンレターへの署名のお願い
──────────────────────────────────
自然史学会連合,日本分類学会連合を通じて,下記署名活動の周知・協力依頼がありましたので,会員の皆様にお知らせします.
生物多様性条約会議(CBD)にて、DNA塩基配列を一例とするデジタル配列情報(Digital seqence Information、以下DSI)の利益配分に関して議論がなされており、今年後半に開催予定のCOP15第二部(昆明)において何らかの決定がなされる。現在遺伝資源の入手時の事前許可や契約の義務等のアクセスと利益配分(ABS)が国際的に義務化されているが、同様の措置がDSIにも課されると、DNAの公的データーベースの利用や生命科学研究において、過度の負担が生じることとなり、停滞の一因にもなりえる。
現在、世界中の科学者コミュニティーが、懸念を示し、いくつかの対応を行っている。そのひとつとして、ドイツのカルチャーコレクションであるDSMZが中心となり、ドイツ教育省からの資金の下、DSI Scientific Networkが研究者の立場からの活動を行っている
https://www.dsiscientificnetwork.org/open-letter/#indiv-signatories
この度、DSI Scientific NetworkがCBD締約国に対し、オープンサイエンスの保護、研究者の発言権などに関する要請を含むオープンレターを作成し、署名機関・団体および個人署名者を募っている。つきましては、DNAの塩基配列の自由な利用が阻害されることで研究活動の停滞を防ぐために、研究者の皆様に署名をお願いしたい。
要請事項
我々はCBD締約国に対し、以下を要請する。
研究者が、国策制定過程、DSI の選択肢の検討、CBD の公式・非公式なプロセスにおいて、確実に発言権を持つようにすること。
DSI の生成とグローバルシステムへの貢献を奨励する多数国間利益配分アプローチに対する科学界からの要請に耳を傾けること。
これらの交渉の結果が科学的プロセスの現実を反映し、現在世界中の何百万人もの利用者に何十億もの配列を提供している何千もの相互リンクされたデータベースを考慮することを確実にする。
DSIへのオープンアクセスを支援する。オープンアクセスは研究と革新を促進し、科学的再現性を向上させ、公衆衛生の危機への迅速な対応を可能にし、能力開発と国際協力を促進し、トレーニングと教育を促進する。
名古屋議定書や他の条約の経験から学び、規制の複雑さと研究コストを増加させ、資源が特に乏しい発展途上国に不釣り合いに影響を与えるようなDSIの新制度を回避することです。
国連の持続可能な開発目標を達成し、2020年以降の生物多様性世界フレームワークを実施したいのであれば、開放性を守り、利益配分を確保するバランスの取れたアプローチを見つけなければならない。DSIに対するオープンで公平な解決策がなければ、科学界は研究を行い、現在の環境と健康の危機に対する解決策を開発する能力に支障をきたすことになる。
2022.4.21
国立遺伝学研究所 鈴木睦昭
msuzuki@nig.ac.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)新潟大学旭町学術資料展示館「ジオパークの大放散虫展」(7/20-8/28)
https://www.lib.niigata-u.ac.jp/tenjikan/index.html
(後)神奈川県立生命の星博物館特別展「みどころ沢山!かながわの大地」(7/16-11/6)
https://nh.kanagawa-museum.jp/www/contents/1651126447345/index.html
第11 回学生のヒマラヤ野外実習ツアー参加者募集
実施時期:2023年3月,定員20名,暫定参加費20万円程度
http://www.gondwanainst.org/geotours/2023tour/SHET-11-AdvJP-yoko20220512.pdf
—---------------------------------
(後)第59回アイソトープ・放射線研究発表会(オンライン)
7月6日(水)-8日(金)
事前参加登録(7,000円)締切: 6月10日(金)17時
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2022/top
(後)科学教育研究協議会第68回全国研究大会(岡山大会)
8月10日(水)-12日(金)
会場 岡山理科大学 岡山キャンパス
https://kakyokyo.org/
(後)第9回国際地学教育会議
8月21 日(日)-25 日(木)
会場:くにびきメッセ(島根県コンベンションセンター)
https://ja.geoscied9.org/
日本地質学会第129年学術大会(2022東京・早稲田大会)
9月4日(日)-6日(火),10日(土)-11日(日)
会場:早稲田大学早稲田キャンパス(東京都新宿区西早稲田)
講演申込・要旨投稿締切:6月29日(水)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/top
(共)2022年度日本地球化学会第69回年会
9月5日(月)-12日(月)
場所:高知⼤学朝倉キャンパス会場+オンライン会場(ハイブリッド開催)
http://www.geochem.jp/meeting/
(後)第65回粘土科学討論会
9月7日(水)-8日(木)
(討論会のみの実施,現地見学会は開催しません)
会場:島根大学
http://www.cssj2.org/event/annual_meeting/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0222.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【14】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・令和5年度科学技術分野の文部科学大臣表彰受賞候補者の推薦(学会締切7/1)
・2022年度「第43回猿橋賞」受賞候補者の推薦募集(11/30)
・東京大学理学系研究科地球惑星科学(地球システム変動学)助教公募(7/25)
・湯沢市ゆざわジオパーク学術研究等奨励補助金の募集(6/24)
・南紀熊野ジオパーク学術研究・調査活動助成事業募集(6/30)
・三陸ジオパーク学術研究助成金の募集(6/27)
・五島列島(下五島エリア)ジオパーク活動支援助成金募集(6/17)
・おおいた姫島ジオパーク調査研究助成募集(7/15)
・霧島ジオパーク学術研究支援補助金(6/30)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【15】訃報:石田志朗 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
石田志朗 名誉会員(元山口大学教授)が、令和4年5月19日(木)に
逝去されました(92歳).
これまでの故人の功績を讃えるとともに、謹んでご冥福をお祈り申し
上げます。なお、ご葬儀はすでに身内の方々のみで執り行われたとの
ことです.
会長 磯崎行雄
(注)「崎」の正しい表記は、「大」→「立」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.570 第6回ショートコース 参加申込受付中!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.570 2022/12/6┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】第6回ショートコース:法地質学/付加体地質学 参加申込受付中!
【2】2023年度以降の会費請求と主な変更点
【3】地質系若者のためのキャリアビジョン誌2022 原稿募集中
【4】第14回惑星地球フォトコンテスト受付中
【5】Island Arcからのお知らせ
【6】第3回JABEEシンポジウム「大学ー企業の架け橋教育 ユニークな実例紹介」
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】第6回ショートコース:法地質学/付加体地質学 参加申込受付中!
──────────────────────────────────
2020年・2021年に計5回開催し,好評を博したショートコースを再開します.
第6回の前半は法地質学、後半は付加体地質学・沈み込み帯掘削に関する最新の
知見を学ぶ機会を提供します.
日程:2022年12月18日(日)
開催方法:zoomによるオンライン講義
受講料(各1日券):
地質学会会員:2,000円(地質学会賛助会員に所属する方は地質学会会員と同額),
非会員:5,000円
申込締切:2022年12月8日(木)
http://www.geosociety.jp/science/content0151.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2023年度以降の会費請求と主な変更点
──────────────────────────────────
運営規則(2022年6月一部改正.以下運営規則)により,2023年度からは新しい
会員種別,会費での運用が始まります.運営規則改正による2023年度以降の会費
請求と主な変更点についてご案内いたします.
(1)23年度の会費の自動引き落とし日は,12月23日(金)です.
(2)23年度から,正会員は「65歳以上のシニア会員」と「65歳未満の一般会員」
とに細分され,24年度分会費より在会年数(会費納入年数)に応じて会費が減額
となります.
(3)23年度から除籍対象となる会費滞納年数が『4年』から『3年』に変更となり
ます.
(注)2023年度分会費請求のための「学生会員」申請は11/30で締切ました.
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0239.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】地質系若者のためのキャリアビジョン誌2022 原稿募集中
──────────────────────────────────
全国48の大学と機関の学生・院生に向けて、専門職の魅力を伝える雑誌
「地質系若者のためのキャリアビジョン誌2022」を刊行します.
関係企業の魅力発信ツールに,また各大学ではキャリア教育の教材として
ご活用いただけます.ぜひ本冊子への協賛と原稿提供をご検討ください.
締切:2022年12月9日(金)
配布:2023年1月上旬
詳しくは, http://photo.geosociety.jp/career2.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第14回惑星地球フォトコンテスト受付中
──────────────────────────────────
***応募締切:2023年1月30日(月)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募フォームからでも
メール添付でもご応募いただけます.会員の皆様の応募をお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】Island Arcからのお知らせ
──────────────────────────────────
■ Island Arc
・新しい論文等が公開されています.
Characteristics of crustal structures in the Yamato Basin, Sea of Japan,
deduced from seismic explorations:Takeshi Sato et al
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】第3回JABEEシンポジウム「大学ー企業の架け橋教育 ユニークな実例紹介」
──────────────────────────────────
今回は「大学ー企業の架け橋教育 ユニークな実例紹介」をテーマとして、
技術者教育における大学の役割や取り組み、実社会での技術者教育の在り方
(社会OJT、学協会による教育、大学院大学(専門職)構想や専門技術学校
などでの教育や育成)を紹介し、そしてこれらの連携や課題などについて考
えます。
日時:2023年3月5日(日)13:30-18:00(予定)
開催方法:Zoomによるオンライン方式
参加は会員、非会員問わず無料。
申込制(2023年1月末から開始予定)。定員先着150名。
詳細については、HP、geo-flash、ニュース誌により今後お知らせします。
学会HP「技術者教育(JABEEとCPD)」のページ「最近の活動状況」を更新
しました.
・「技術士(CPD認定)」にかかわる解説
・「2021年度 地質系若手人材動向調査報告」
を掲載しています.詳しくは,
http://geosociety.jp/engineer/content0003.html#1-4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
・関東支部功労賞を募集します.
対象者:支部活動や地質学を通して広く社会貢献をされた関東支部内に在住の
個人・団体 ※社会貢献や活動の評価においては,必ずしも学問的な成果を問う
ものではありません.
公募期間:2022年12月19日-2023年1月21日
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html#2022koro
・関東支部オンライン講演会「県の石 茨城県」開催
日時:2023年1月22日(日)13:00-16:05
参加費無料(要事前申込)
申込期間:2022年12月19日(月)から2023年1月11日(水)まで
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html#2022ishi
[西日本支部]
・西日本支部令和4年度総会・第173回例会
2023年3月4日(土)例会・総会
会場:島根大学総合理工学部多目的ホールほか
(注)状況によってオンラインでの開催を検討
講演・参加申込締切:2月1日(水)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
日本堆積学会20周年記念リレーセミナー(第1回)
12月15日(木)12:15-13:00
Zoomウェビナーオンライン開催(参加無料)
講演者:池田昌之氏(東京大学)
演題:深海チャートの堆積リズムから読み解く天文学的周期の地球環境変動
https://sites.google.com/view/ssj20th/home
男女共同参画推進委員会主催
「技術サロン(女子学生および社会人女性向け懇話会)」
12月17日(土)13:00-16:00【Zoomによるリモート開催】
対象:技術者及び技術士を目指す女子学生・女性社会人
内容:技術士制度の説明、技術士とのフリーディスカッション等
https://www.engineer.or.jp/c_cmt/danjyo/topics/009/attached/attach_9095_1.pd
f
第38回 地質調査総合センターシンポジウム 美ら海から知る美ら島の歴史
―500 万年間の地史を求めて―
12月21日(水)13:00-17:00(予定)
会場:沖縄県立博物館・美術館(おきみゅー)博物館 講堂
定員:200名(事前登録制)参加費無料
CPD: 3.5単位(ジオ・スクーリングネット)
https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo38/index.html
地球掘削科学国際研究拠点・令和4年度共同利用・共同研究集会
「水中災害考古学研究への水底表層コア試料の活用」
12月21日(水)-12月22日(木)
場所:高知コアセンター・B棟セミナー室
発表形式:対面・オンライン(ZOOM)※ハイブリッド形式
参加方法:対面およびオンラインによる参加希望者はHPから申請
参加対象者:国内の研究機関に所属する研究者(学生を含む)上限100名.
参加登録締切:12/19(月)正午(先着順)
https://hibarajuku.labby.jp/news/detail/2474
文部科学省主催 STAR-E プロジェクト
第2回研究フォーラムー先端研究と産業界の接点ー
2023 年1月24日(火)9:30-12:10
オンライン開催
参加費無料,要申込(1/23締切)
対象:情報科学を活用した地震調査研究にご興味をお持ちの方どなたでも
https://star-e-project-2023.eventcloudmix.com/
第4回国際黒曜石会議
International Obsidian Conference(IOC) Engaru 2023
2023年7月3日(月)-6日(木)
開催地:北海道紋別郡遠軽町
https://sites.google.com/view/iocengaru2023/home
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0222.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・山梨県富士山科学研究所:任期付研究員公募(1/13)
・京都大学大学院都市社会工学専攻地球資源システム助教(女性)公募(12/26)
・23年度産総研イノベーションスクール17期スクール生(特別研究員)募集(1/4)
・令和5年度 箱根ジオパーク学術研究助成募集(1/20)
・下北ジオパーク推進員の募集(12/28)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
2022東京・早稲田
日本地質学会第129年学術大会(2022東京・早稲田)巡検案内書
2022東京・早稲田 大会HP(confit)はこちら
※それぞれの巡検案内書タイトルをクリックすると,J-STAGE上の原稿画面に遷移します.
チバニアンGSSPサイトと陸化した前弧海盆上総層群の層序.岡田 誠・羽田裕貴(地質学雑誌,第129巻,273-288)
房総半島東部,上総層群下部に記録された前弧テクトニクスと海底地すべり.宇都宮正志・大坪 誠(地質学雑誌,第128巻,第1号,265-280ページ)
三浦半島北部の上総層群の地質と冷湧水性化学合成化石群集.野崎 篤・宇都宮正志(地質学雑誌,第128巻,第1号,313-333ページ)
関東山地東縁部の御荷鉾緑色岩類と北部秩父帯柏木ユニットの海洋性岩石およびクリッペ説の検証.原 英俊・富永紘平(地質学雑誌,第128巻,第1号,149-168ページ)
御坂・巨摩山地の黒鉱鉱床:衝突した伊豆弧の海底熱水鉱床.浦辺徹郎・伊藤谷生・藤本光一郎(地質学雑誌,第129巻,35-44ページ) ▶︎ 関連論文:地質学雑誌,第129巻,17-33ページ
千葉県東部,銚子周辺地域の鮮新―更新世テフラと銚子ジオパーク.植木岳雪・田村糸子・岩本直哉(地質学雑誌,第128巻,第1号,345-369ページ)
ジオパーク秩父のジオの多様性.高木秀雄・吉田健一(地質学雑誌,第128巻,第1号,131–141ページ) ▶︎ 関連図表:Figs. 1-3, Table 1(日本語版)
多様な地質環境が生み出した下仁田の文化:下仁田ジオパークみどころめぐり.関谷友彦・保科 裕(地質学雑誌,第128巻,第1号,513-528ページ)
伊豆大島火山:玄武岩質火山でみる噴火史とジオパーク.鈴木毅彦・臼井里佳(地質学雑誌,第128巻,第1号,335-344ページ)
編集後記
【geo-Flash】No.552(臨時)2022東京・早稲田大会:講演申込開始
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.552 2022/5/27 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2022年東京・早稲田大会:講演申込開始です
【2】地質学露頭紹介 at JpGU2022 5/29は露頭について語りましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2022年東京・早稲田大会:講演申込開始です
──────────────────────────────────
日本地質学会第129年学術大会東京・早稲田大会を下記の日程で開催します.
今年は口頭発表については3年ぶりに対面で行えるよう準備しています.
ポスター発表はe-poster(オンライン)で口頭発表とは別日に開催予定です.
会期:
(口頭発表)2022年9月4日(日)-6日(火)
(e-poster)2022年9月10日(土)-11日(日)
(注)口頭発表は現地対面開催.ポスター発表はe-poster(オンライン)のみ.
会場:早稲田大学 早稲田キャンパス 14・15号館
講演申込の受付を開始しました!!
************************************
演題登録・要旨投稿 締切:2022年6月29日(水)18:00 厳守
************************************
はじめに、2022年学術大会専用のアカウント登録が必要です.
1アカウントで複数の演題登録が可能です.
会員・非会員問わず(招待講演者,入会申込中の方も含む),アカウント登録・
演題登録・要旨投稿の操作が可能です.
締切まで何度でも修正可能です.
締切前に,あわてないためにもまずはアカウント登録を!!
大会サイトはこちら
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】地質学露頭紹介 at JpGU2022 5/29は露頭について語りましょう!
──────────────────────────────────
日本地質学会2021年オンライン学術大会で好評を博した「地質学露頭紹介」の
第2弾です!JpGU2022大会期間中にオンラインで開催します。
とっておきの露頭、解釈がむずかしい露頭などなど。露頭について、おおいに
語りましょう!
日時:2022年5月29日(日)13:55配信開始(発表は14:00から)
参加方法:オンライン Zoom+YouTubeライブ配信
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0146.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.554[2022早稲田]講演申込:まずはアカウント登録を!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.554 2022/6/21 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2022早稲田]講演申込受付中です
【2】[2022早稲田]ダイバーシティ認定ロゴ導入の取り組み
【3】[2022早稲田]巡検コース紹介掲載しました
【4】[2022早稲田]ランチョン・夜間小集会募集
【5】[2022早稲田]ジュニアセッション(e-poster)参加校募集
【6】[2022早稲田]企業展示・書籍販売 対面開催します
【7】[2022早稲田]家族巡検「生命の進化を楽しく学ぼう」
【8】会費督促請求に関するお知らせ
【9】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【10】(アンケート協力)JST/RISTEX:新規研究開発テーマに関するアンケート
【11】支部情報
【12】その他のお知らせ
【13】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2022早稲田]講演申込受付中です
──────────────────────────────────
会期:
(口頭発表)2022年9月4日(日)-6日(火)
(e-poster)2022年9月10日(土)-11日(日)
(注)口頭発表は現地対面開催.ポスター発表はe-poster(オンライン)のみ.
会場:早稲田大学 早稲田キャンパス 14・15号館
講演申込の受付中です!!
************************************
演題登録・要旨投稿 締切:2022年6月29日(水)18:00 厳守
************************************
はじめに,2022年学術大会専用のアカウント登録が必要です.
1アカウントで複数の演題登録が可能です.
会員・非会員問わず(招待講演者,入会申込中の方も含む),アカウント登録・
演題登録・要旨投稿の操作が可能です.締切まで何度でも修正可能です.
************************************
締切前に,あわてないためにもまずはアカウント登録を!!
************************************
大会サイトはこちらhttps://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2022早稲田]ダイバーシティ認定ロゴ導入の取り組み
──────────────────────────────────
昨年度試験的に導入したダイバーシティ認定ロゴ「ECS (Early Career
Scientist)・EDI(Equality, Diversity and Inclusion)」を皆様のご意見を
反映して改定し,理事会の承認を受け129年学術大会から導入することに
なりました.
EDIロゴ(申請者:セッション世話人)
ECS ロゴ(申請者:学会に参加する該当者本人)
いずれも申請が必要です.積極的申請をよろしくお願いいたします.
申請締切:2022年7月10日
詳しくは,http://www.geosociety.jp/engineer/content0063.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2022早稲田]巡検コース紹介!
──────────────────────────────────
東京・早稲田大会では,計9コースの巡検を計画しています.
各コースの詳細を大会HPおよびニュース誌5月号に掲載しています.
なお,巡検実施にあたってのCOVID-19に関わる対応指針を策定しました.
安全に巡検が実施できるよう,ご協力をお願いいたします.
************************************
申込締切: 8月10日(水)18:00(オンラインのみ)
(申込フォームを準備中です.今しばらくお待ちください)
************************************
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/excursion
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2022早稲田]ランチョン・夜間小集会募集
──────────────────────────────────
口頭発表の会期中(9月4日-6日)に対面形式で開催いたします.会合開催を
ご希望の場合は,必要な申込項目をe-mailで行事委員会宛に申し込んで下さい.
開始終了時刻は日によって異なります.
<<申込締切:6月29日(水)>>
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/meeting
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2022早稲田]ジュニアセッション(e-poster)参加校募集
──────────────────────────────────
東京・早稲田大会では,第20回日本地質学会ジュニアセッションを開催します.
小・中・高等学校の地学クラブの活動および授業の中で児童・生徒が行った研究
の発表を募集します.
今年は,昨年同様ジュニアセッションもe-posterによる発表となります.審査も
オンライン上で行います(当日の表彰は行いません).
ぜひ周囲の学校関係者の方々にご周知ください.
************************************
参加申込書の締切:8月1日(月)
************************************
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/gyoji#es
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[2022早稲田]企業展示・書籍販売 対面開催します
──────────────────────────────────
企業等団体展示会,書籍・その他物品の販売ブースを対面形式で大会会場内
に設置予定です(期間:9/4-9/6).
詳細が確定次第,大会HPでお知らせいたします.今しばらくお待ちください.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/tenji
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】[2022早稲田]家族巡検「生命の進化を楽しく学ぼう」
──────────────────────────────────
2022東京・早稲田大会に参加された会員の家族が楽しんで学ぶイベントを
企画します.
実物の動物や化石を見ながら生命の進化の歴史を学びませんか.
日程:2022年9月3日(土)
予定:9:50 上野動物園集合,15:00 国立科学博物館解散
募集期間:7月23日(土)から8月8日(月)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/gyoji#family
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】会費督促請求に関するお知らせ
──────────────────────────────────
2022年度会費およびそれ以前の未納会費がある方に対して,請求書(郵便振替
用紙)を6/15に発送いたしました.早急にご送金くださいますようお願いいた
します.また自動引き落としについては,6/23に引き落としを行います.
(注)2022年度分会費が未納の場合は,7月号からのニュース誌の送付を一時的
に中止させていただきます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・128巻:新しい論文が公開されています.
(論説)今岡照喜ほか:山口県後期白亜紀長門−豊北カルデラの地質と岩石/
(論説)工藤 崇:十和田火山,噴火エピソードMの噴出物層序と噴火推移
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/128/1/_contents/-char/ja
■ Island Arc
新しい論文が公開されています.
(RESEARCH ARTICLES)ZMicrobial influences on manganese deposit
formation at Yunotaki Fall, Japan Fumito Shiraishi et al/
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
(RESEARCH ARTICLES)ZMicrobialAn obelisk-shaped granitoid tower
at Mt. Jizogadake in the Southern Alps of Japan: A 3-D morphological
study Masahiro Chigira
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14401738/0/ja
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】(アンケート協力)JST/RISTEX:新規研究開発テーマに関するアンケート
──────────────────────────────────
RISTEXは,文部科学省所管の研究開発法人であるJSTの一部門で,
新たな社会的・公共的価値および経済的価値を創り出すことを目指し,
社会の具体的な問題の解決に向けて成果の社会実装を強く意識した
研究開発を,大学や企業の研究者等への研究委託(ファンディング)に
より推進しています.詳しくは,https://www.jst.go.jp/ristex/aboutus/index.html
現在RISTEXにおいては,複数分野の専門知の活用,専門知と現場知の
協働により社会問題解決を図る研究開発テーマを検討しています.
関連性のある研究や事業等の経験をお持ちの皆様のご意見を踏まえて,
研究開発テーマをよりよいものに仕上げていくため,当方のアイデアに
対するご意見を募集しています.ご協力をお願いいたします.
意見募集期間: 6月8日(水)から7月8日(金)
意見募集のWEBページ:https://form.jst.go.jp/enquetes/ristex-newplan-2022
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)新潟大学旭町学術資料展示館「ジオパークの大放散虫展」(7/20-8/28)
https://www.lib.niigata-u.ac.jp/tenjikan/index.html
(後)神奈川県立生命の星博物館特別展「みどころ沢山!かながわの大地」(7/16-11/6)
https://nh.kanagawa-museum.jp/www/contents/1651126447345/index.html
—---------------------------------
(後)第59回アイソトープ・放射線研究発表会(オンライン)
7月6日(水)-8日(金)
事前参加登録(7,000円)締切: 6月10日(金)17時
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2022/top
学術会議主催学術フォーラム
「国難級災害を乗り越えるためのレジリエンス確保のあり方」
7月7日(木)13:30-17:00
場所:日本学術会議講堂(オンライン配信)
参加費無料・どなたでも視聴可能
https://www.scj.go.jp/ja/event/2022/325-s-0707.html
(後)科学教育研究協議会第68回全国研究大会(岡山大会)
8月10日(水)-12日(金)
会場 岡山理科大学 岡山キャンパス
https://kakyokyo.org/
(後)第9回国際地学教育会議
8月21 日(日)-25 日(木)
会場:くにびきメッセ(島根県コンベンションセンター)
https://ja.geoscied9.org/
日本地質学会第129年学術大会(2022東京・早稲田大会)
9月4日(日)-6日(火),10日(土)-11日(日)
会場:早稲田大学早稲田キャンパス(東京都新宿区西早稲田)
講演申込・要旨投稿締切:6月29日(水)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/top
(共)2022年度日本地球化学会第69回年会
9月5日(月)-12日(月)
場所:高知⼤学朝倉キャンパス会場+オンライン会場(ハイブリッド開催)
http://www.geochem.jp/meeting/
(後)第65回粘土科学討論会
9月7日(水)-8日(木)
(討論会のみの実施,現地見学会は開催しません)
会場:島根大学
http://www.cssj2.org/event/annual_meeting/
第35回ヒマラヤ−カラコルム−チベット ワークショップ(HKT-35)
11月2日-4日
場所:ネパール・ポカラ
発表要旨締切:7月31日
www.gondwanainst.org/symposium/2022/HKT2022/Interimnotice-HKT-20220518.docx
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0222.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・ 北海道大学大学院地球環境科学研究院(札幌キャンパス)助教公募(9/30)
・ 深田地質研究所2023年度任期付き研究員募集(8/31)
・JAMSTEC海域地震火山部門火山・地球内部研究センター主任研究員or研究員
公募(10/31)
・JAMSTEC超先鋭研究開発部門超先鋭研究開発プログラム研究員,准研究員or
技術副主任公募(8/5)
・ 東京大学地震研究所2023年度特定共同研究課題登録(7/29)
・ 第4回輝く女性研究者賞(ジュン アシダ賞)(学会締切7/1)
・ 伊豆大島ジオパーク専門員の再募集(7/29)
・ 栗駒山麓ジオパーク推進協議会職員(ジオパーク専門員)再募集(7/15)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
地学に名を轟かした水戸藩の長久保赤水の改正日本輿地路程全図
地学に名を轟かした水戸藩の長久保赤水の改正日本輿地路程全図
正会員 石渡 明
寛政3(1791)年の改正日本輿地路程全図(赤水図)第二版(常州 水戸 長玄珠子王父製,浪華 浅野弥兵衛発行,京師 畑九兵衛鐫字)の復刻版(129×83cm).高萩市教育委員会生涯学習課が希望者に有料で配布している.申込方法は同課HP参照.ただし,この復刻版の序文の標題は「改正…」ではなく「新刻…」になっている. https://www.city.takahagi.ibaraki.jp/page/page004791.html
伊能忠敬(いのう ただたか)(1745-1818)は幕府の命により全国を実地測量して精密な地図を作ったが,伊能図(大日本沿海輿地全図:文政4(1821)年完成)は秘密とされ一般人は使用できなかった.それに対し,長久保赤水(ながくぼ せきすい)(1717-1801)が作ったのは10里が1寸の縮尺(約130万分の1)の1枚刷り全国図で,経緯線が入り,郡や村,道路,山川,古跡名勝等が詳しく示され,国別の色分けも美しく,安永9(1780)年に大坂で初版を出版して以来,明治の初めまで約100年間にわたって版を重ね,国内はもちろん国外でも,正確で実用的な日本地図として重宝された.伊能も測量の際には赤水図を携行したという.令和2(2020)年に赤水の地図や資料が国の重要文化財に指定され,令和4年5月31日と6月7日の東京新聞朝刊に「伊能忠敬より42年も前に日本地図を作った男 長久保赤水を語る」という佐川春久の論説が載るなど,評価が高まっている.赤水の出身地は常陸国多賀郡赤浜村,現在の茨城県高萩市であり,そこでは復刻出版等の顕彰事業が進む.ところで,幕末の文久4(1864)年に江戸で出版された「大日本海陸全図」(笑寿屋庄七梓,竹口滝三郎刻)の作者整軒玄魚の説明文には,「坊間流布の刊本は何れも全備して誤脱なきは未(いま)だ見(み)及ばず.ただ往年地学に名を轟(とどろ)かしたりし水府赤水先生の輿地(よち)全図は紙幅少くて微細にこそ書記されね錯誤は大方(おおかた)あらぬようなり」(カナを現代風に改変)と書いてある.実際この海陸全図はほとんど赤水図のコピーで,それに不正確な蝦夷(えぞ)島(北海道)の地図を描き加えたものである.この説明文で注目すべきは赤水先生が「地学に名を轟かした」と述べていることで,以下に赤水図が地学的に優れている点を指摘し,「江戸時代中期の地学者」長久保赤水の労作の紹介としたい.
まず,赤水図左下の説明文を見ると,各地で観測された北極星の高度によって緯線を引いたこと,緯度1度はほぼ32里に相当することを述べている(32里は約126kmだが,実際の緯度1度は約111km).江戸付近の緯線を現在の地図と比べると約7分南へずれていて,例えば現在の北緯35度線は伊豆半島の伊東や修善寺の少し北を通るが,赤水図では天城山付近を通る違いはあるものの,当時既に緯度を約0.1度の精度で測定できていたことになる.また,同じ説明文には,太陽は一時(ひととき)(2時間)に30度動き,日本は東海から西海まで経度で10度の差があるから,常陸(ひたち)・陸奥(むつ)の午(うま)の初刻(午前11時頃)は長崎辺の巳(み)の下刻(午前10時過ぎ)だと述べている.これは時差を正確に認識していたことを示す.図の左上には「東都榊原隠士考証」の潮汐についての説明文がある.長門(ながと)付近の満潮は紀伊の満潮と同期し,瀬戸内海両端から入った潮は75里(約300km)先の備中(びっちゅう)白石(島,笠岡市)で合すること,明石の潮は大坂より半時(1時間)ほど遅く,備前(びぜん)の潮は播磨(はりま)より二時(ふたとき)遅く,備中の潮は備前より一時(ひととき)遅いこと,北国(北陸)では潮の干満が小さく,時候によっては5〜7日間一方的に引き潮になることがあり,これを片潮と言うと述べている.丸善の理科年表によると,東京との干満時間のずれは神戸で+2h30m,高松(備中の対岸)で+6h20m,広島で+4h50m,下関で+4h20mとなっていて,赤水図の記述と大差なく,北陸の干満差が小さいのは現在も同様である.「片潮」は広辞苑に無い語だが,海事関係者の間では今も使われる.
赤水図には各地の自然がよく記入されている.例えば新潟焼山,浅間山,阿蘇山,温泉(雲仙)岳,霧島山などの活火山には山上に噴煙が描かれており(なぜか桜島には噴煙がない),温泉岳には「ヂゴクアリ」と注記してあるが,この地図出版の翌1792年,島原大変肥後迷惑と呼ばれる地獄のような火山災害が起きた.富士山には1707年の噴火でできた宝永山が付記してあり,八ヶ岳は山を8つ並べ,妙義山はギザギザの稜線になっている等,山の形は実物に即している.各地の「富士」も示されていて,岩木山には津軽富士と注記され,松山西方の海中に伊予富士(興居(ごご)島:最近は石鎚山系の高知県境の山を伊予富士と言い,この島は伊予小富士という)が描いてある.秋田県にかほ市の象潟(きさかた)は入江になっていて,その中に多数の島が描いてあるが,ここは文化元(1804)年の象潟地震で隆起陸化し,多島海の景観が失われてしまった.山形県大沼にも多数の島が描かれ,「ウキシマアリ」と注記してあるほか,宮城県の松島や長崎県佐世保市の九十九島にも多数の島が描いてある.一方,江戸の西には「ムサシの」として多数の樹木を描いてある.また,「越後に七奇ありと.しかしただ火井と山油を以って奇とするに足る」という注記があり,阿賀野川中流域右岸に火井と山油の産出位置が示してある.当時の重要な鉱山として石見(いわみ)(大森)銀山が示されているが,禁に触れるためか,佐渡金山は示していない※4.伊豆七島の御蔵島と八丈島の間に「黒瀬川広さ30町(約3km)ばかり.また黒潮と言う.片セ(片瀬,片潮)急流.冬春の間にあり,夏秋はなし.舟行甚(はなは)だ難(かた)し」として流れの位置が示してある.
また,全国3カ所の海上の火について特記されている.有明(ありあけ)海・八代(やつしろ)海は,「海面時に火有り.累々として相連なり聚散動止す.けだし陰火なり.景行帝この火に感じ,以って其の国を名づく(大化改新前,肥前・肥後は「火の国」と言った)」とある.また,豊前(ぶぜん)沖には,「海上時に火光を現ず.聚散飛動す.初め山より二火出で,空中で合して戦うが如し.而して海に落ちてまた山に帰る.名づけて不知火(しらぬい)と言う」とある.そして磐城(いわき)四ツ倉沖には,「海上に毎夜陰火起こる.大きさ炬(たいまつ)の如し.竈(かまど)川(夏井川)を遡り,赤井岳(阿加井岳,閼伽井嶽)の麓に至る.大杉の梢(こずえ)を飛び懸け,須臾(しゅゆ)にして林中に隠る.続いてまた上る.初昏より暁(あかつき)に至る.累々乎として不断.その数幾つかを知らず.凡そ月夜即ち火光薄く,暗夜即ち明らかなり.この火独り阿加井岳に於いてこれを見る.他よりこれを観るところ一点の光影なく,また奇なり.これを名づけて阿加井竜灯という」とある.海岸から閼伽井岳までは16kmで,その途中にいわき(平)市街がある.現在,不知火は漁火や街の灯が海面や河面付近の冷気で屈折し,空中を飛動するように見える現象と説明されている(夏に多い).
これら赤水図の記述内容を見ると,「地学に名を轟かした」実力がよくわかる.しかし,赤水は旅行好きだったものの,伊能忠敬のように全国を歩いて地図を作ったわけではない.赤水図第二版の「阿波(あわ)国儒者讃岐(さぬき)柴邦彦」撰の序文によると,自室の壁に白地図を貼って,旅の僧侶や商人を呼び込み,茶菓で歓待してその郷里や道中の地理を聞き出し,新知見を白地図にどんどん書き入れて地図を完成させたのだという.つまり踏査ではなく接待で作り上げた地図ということになる.赤水図の出羽湯沢の北の「言語同断」※1 という書き込みは意味不明だが,もしかしたら,湯沢から来た客が言語道断の振る舞いをしたのかもしれない.また,この図が近年注目されるもう一つの理由は竹島が描かれていることで,「一に磯竹島と言う.高麗(こうらい)と雲州(出雲(いずも))を見,隠州(隠岐(おき))を望む」と注記されている.高萩市教委のパンフによると,赤水は朝鮮輿地之図,中国の三国時代の地図,地球万国全図等も描き,天体の運行を説明した初心者向けの天文書(星座早見盤つき)も刊行したとのことである.
長久保赤水(玄珠,源五兵衛)※2 は農民の子として生を享け,11歳までに両親を失う不幸な生い立ちだったが,勉学に精励して武士格の儒学者となり,晩年には水戸徳川家第6代治保(はるもり)(文公)の侍講を務め,「大日本史」地理誌の編纂を行った.パンフの肖像画からは,明朗快活だが一癖ある,といった性格が伺え,会えば開口一番「お国はどちらですか」と聞かれそうな気がする.江戸時代中期の日本の地学のレベルの高さがよくわかる赤水図のご一覧をお勧めする.※3
※1:「言語同断」は地名であることがわかった.読みは「てくら」で,現在の秋田県雄勝郡東成瀬村手倉付近を指した.ここは湯沢・横手の盆地から東へ向かう街道が山に入る所で,江戸時代はここに番所があり,「国払い」にする罪人を久保田(秋田市)からここまで役人が護送してきて,国に戻ることは言語道断である旨を言い渡すなどして,国外に追放したようである.なお,「てくらだ」と読む姓もあるそうである.
※2:赤水は号,玄珠(はるたか,一説に「はるなが」)は名,子玉(しぎょく)は字、源五兵衛は通称。図の説明2行目の「長玄珠子王父製」の「子王」は「子玉」が正しいと思われる.(2022.8.16追記)
※3:長久保赤水顕彰会長の佐川春久様から日本地質学会を通じて下記の書籍をご恵与いただいたので,ここに紹介する.パンフレットも多数いただいたが,ここでは割愛させていただく.(2022.9.26追記)
※4:石見銀山だけでなく,但馬の「イクノ(生野)銀山」,丹波笹山(篠山)南方の摂津の(多田)銀山,出羽尾花沢近くの(延沢)銀山(現在は銀山温泉がある),そして出羽・陸奥北部の多数の銀山,金山,銅山,銕(鉄)山の位置が示されている.更に,久慈には「コハク(琥珀)出」と記されている.また,海田俊一(2017;地図,55(3),10-17)は赤水図の改版過程について論じ,その中で同図に鳴門の渦と那智の滝のイラストがあることを指摘した.なお,日光には「ケコンタキ(華厳滝)」の記入はあるがイラストはない.(2022.10.25追記)
記(出版年順)
長久保赤水顕彰会(2014)續 長久保赤水書簡集 現代語訳 茨城新聞社 B5判149 p.
長久保赤水顕彰会(2016)長久保赤水書簡集 付 芻蕘談 現代語訳 茨城新聞社B5判169 p.
長久保赤水顕彰会(2017)マンガ 長久保赤水の一生(原康隆作) 付 赤水先生為学入門抄・志学警 茨城新聞社B5判189 p.
長久保赤水顕彰会(2017)マンガ 長久保赤水の生涯(黒澤貴子作)付 長久保赤水海防意見 現代語訳 茨城新聞社B5判213 p.
長久保赤水顕彰会(2018)マンガ 長久保赤水物語(黒澤貴子・原康隆作) 茨城新聞社B6判274 p.
長久保赤水顕彰会(2019)續續 長久保赤水書簡集 現代語訳 茨城新聞社 B5判193 p.
ときさき きよし画 長久保赤水顕彰会発行・編集(2020)りゅうのひかり(長久保赤水関係資料 国の重要文化財指定記念誌 赤井竜灯の絵本と解説)茨城新聞社 21x20.6cm 48+29 p.
長久保赤水顕彰会(2021)道知るべ 續 長久保赤水の一生(マンガ 原ヤスタカ作)茨城新聞社B6判271 p.
川口和彦著 長久保赤水顕彰会編集・発行(2021)長久保赤水の天文学(原寸大の赤水式星座早見盤つき)茨城新聞社 B5判205 p.
川口和彦編著 長久保赤水顕彰会編集・発行(2021)長久保赤水と山本北山〜漢詩論をめぐって〜 茨城新聞社 B5判182 p.
※本原稿は,日本地質学会News,Vol.25,No.7(2022年7月号)にも掲載されています.
【geo-Flash】No.555(臨時)[2022早稲田大会情報]講演申込まもなく締切
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.555 2022/6/27 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
[2022早稲田大会情報]
【1】講演申込まもなく締切です(6/29:18時)
【2】これから地質学会へ入会される方へお伝えください!
【3】ダイバーシティ認定ロゴ導入の取り組み
【4】ランチョン・夜間小集会募集
【5】ジュニアセッション(e-poster)参加校募集
【6】企業展示・書籍販売 対面開催します
【7】家族巡検「生命の進化を楽しく学ぼう」
【8】地質系業界説明会:参加企業・団体募集中
【9】お子様をお連れになる方へ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2022早稲田]講演申込6/29締切です!
──────────────────────────────────
締切前に,あわてないためにもまずはアカウント登録を!!
************************************
演題登録・要旨投稿 締切:2022年6月29日(水)18:00 厳守
************************************
はじめに,2022年学術大会専用のアカウント登録が必要です.
1アカウントで複数の演題登録が可能です.
会員・非会員問わず(招待講演者,入会申込中の方も含む),アカウント登録・
演題登録・要旨投稿の操作が可能です.締切まで何度でも修正可能です.
************************************
大会サイトはこちら https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2022早稲田]これから地質学会へ入会される方へお伝えください!
──────────────────────────────────
早稲田大会で講演予定で,まだ地質学会に入会されていない方がお近くに
おられましたら,急ぎお伝えください.
******************************
講演申込と入会申込は並行して行ってください.
入会手続(承認)が完了していなくても,講演申込操作は可能です.
******************************
必ず6/29締切までに講演申込を行って下さい
ただし,6/29時点で入会申込書(郵送)が到着していない場合は,受付はでき
ません.どちらも急ぎお手続きください.
入会申し込み手続きについては,こちらから
http://www.geosociety.jp/outline/content0006.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2022早稲田]ダイバーシティ認定ロゴ導入の取り組み
──────────────────────────────────
昨年度試験的に導入したダイバーシティ認定ロゴ「ECS (Early Career
Scientist)・EDI(Equality, Diversity and Inclusion)」を皆様のご意見を
反映して改定し,理事会の承認を受け129年学術大会から導入することに
なりました.
EDIロゴ(申請者:セッション世話人)
ECS ロゴ(申請者:学会に参加する該当者本人)
いずれも申請が必要です.積極的申請をよろしくお願いいたします.
申請締切:2022年7月10日(金)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/engineer/content0063.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2022早稲田]ランチョン・夜間小集会募集
──────────────────────────────────
口頭発表の会期中(9/4-6)に対面形式で開催いたします.会合開催をご希望の
場合は,必要な申込項目をe-mailで行事委員会宛に申し込んで下さい.
開始終了時刻は日によって異なります.また,食事を取りながらの会合は開催
できません.
<<申込締切:6月29日(水)>>
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/meeting
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2022早稲田]ジュニアセッション(e-poster)参加校募集
──────────────────────────────────
東京・早稲田大会では,第20回日本地質学会ジュニアセッションを開催します.
小・中・高等学校の地学クラブの活動および授業の中で児童・生徒が行った研究
の発表を募集します.
今年は,昨年同様ジュニアセッションもe-posterによる発表となります.審査も
オンライン上で行います(当日の表彰は行いません).
ぜひ周囲の学校関係者の方々にご周知ください.
************************************
参加申込書の締切:8月1日(月)
************************************
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/gyoji#es
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[2022早稲田]企業展示・書籍販売 対面開催します
──────────────────────────────────
企業等団体展示会,書籍・その他物品の販売ブースを対面形式で大会会場内
に設置予定です(期間:9/4-9/6).
詳細が確定次第,大会HPでお知らせいたします.今しばらくお待ちください.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/tenji
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】[2022早稲田]家族巡検「生命の進化を楽しく学ぼう」
──────────────────────────────────
2022東京・早稲田大会に参加された会員の家族が楽しんで学ぶイベントを
企画します.実物の動物や化石を見ながら生命の進化の歴史を学びませんか.
日程:9月3日(土)
予定:9:50 上野動物園集合,15:00 国立科学博物館解散
募集期間:7月23日(土)から8月8日(月)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/gyoji#family
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】[2022早稲田]地質系業界説明会:参加企業・団体募集中
──────────────────────────────────
毎年開催される学術大会の会場において、学生会員が将来就職する可能性のある
地質・資源・建設分野に関わる地質系企業・団体との対面説明会を企画・開催し、
学生会員が業界を研究するサポートサービスを展開してきました。
今年度は、対面での説明会とオンラインによる説明会の2つを行います.
(対面説明会)学術大会期間中のうちの半日間、会場(早稲田大学)に専用に
ブースを設け、学生会員に対面で説明を行う企画
(オンライン企画)9月16日(金)午後Zoom(予定):当学会のHPを介して
全国の学生が参加企業・団体の紹介動画等を閲覧し、その後オンライン訪問する
企画
**********************
参加企業・団体募集中:7月15日(金)締切
**********************
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/gyokai_support
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】[2022早稲田]お子様をお連れになる方へ
──────────────────────────────────
ご家族で学会に参加される会員で,大会期間中に保育施設のご利用を希望
される方には,学会から利用料金の一部を補助いたします.
補助対象利用日:9月4日(日)から6日(火)
対象者:東京・早稲田大会に参加する会員(保護者)のお子様
保育施設:早稲田大学託児室(早稲田キャンパス99号館)
(注)これ以外の施設を利用した場合も補助の対象となります.
詳しくは, https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/kids
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.556 新会長挨拶/早稲田大会参加登録受付開始
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.556 2022/7/5 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【0】新会長挨拶(会長 岡田 誠)
【1】[2022早稲田]大会参加登録,巡検の申込受付を開始しました
【2】[2022早稲田]ダイバーシティ認定ロゴ導入の取り組み
【3】[2022早稲田]ジュニアセッション(e-poster)参加校募集
【4】[2022早稲田]企業展示・書籍販売 対面開催します
【5】[2022早稲田]家族巡検「生命の進化を楽しく学ぼう」
【6】[2022早稲田]地質系業界説明会:参加企業・団体募集中
【7】[2022早稲田]お子様をお連れになる方へ
【8】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
【11】訃報:加藤 誠 名誉会員 ご逝去
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【0】新会長挨拶(会長 岡田 誠)
──────────────────────────────────
2022年6月11日より代表理事(会長)を務めることになりました.日本地質学会の
維持・発展に最善を尽くしてまいりますので,2年間よろしくお願い申し上げます.
本会は,我が国における地球科学系最大規模の学協会であり,自然科学としての
地質学の発展に寄与するという使命を帯びています.同時に,社会に実装されてい
る様々な地質系関連分野と緊密に連携することで,地質学の最新知見を伝えるとと
もに,社会における地質学的課題解決への貢献が求められています.さらに将来の
地質学発展を担う人材の育成への貢献も必須であり,このために大学との繋がりも
不可欠です.
続きはこちらから http://www.geosociety.jp/outline/content0137.html
*2022年度執行理事のご紹介はこちら
http://www.geosociety.jp/outline/content0105.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2022早稲田]大会参加登録,巡検の申込受付を開始しました
──────────────────────────────────
**************************************
申込締切: 8月10日(水)18:00
**************************************
・事前参加登録者には,オンラインプログラム(要旨閲覧,e-poster)へアクセス
するためのログイン情報を事前にメールでお知らせします.
・お支払方法は,銀行振込,クレジット決済をいずれかを選択できます.
・領収書は,後日各自にダウンロードURLをお知らせします.
・対面会場のみ参加の場合,e-posterのみ参加の場合も参加登録費は変わりません.
・発表する会員には別途発表料金(1,500円/題)が発生します.
・講演要旨集(冊子)はありません.
・セッション共催団体会員の参加登録費と発表料金は地質学会会員に準じます.
詳しくは, https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/sanka
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2022早稲田]ダイバーシティ認定ロゴ導入の取り組み
──────────────────────────────────
昨年度試験的に導入したダイバーシティ認定ロゴ「ECS (Early Career
Scientist)・EDI(Equality, Diversity and Inclusion)」を皆様のご意見を
反映して改定し,理事会の承認を受け129年学術大会から導入することに
なりました.
EDIロゴ(申請者:セッション世話人)
ECS ロゴ(申請者:学会に参加する該当者本人)
いずれも申請が必要です.積極的な申請をよろしくお願いいたします.
申請締切:2022年7月10日(金)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/engineer/content0063.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2022早稲田]ジュニアセッション(e-poster)参加校募集
──────────────────────────────────
東京・早稲田大会では,第20回日本地質学会ジュニアセッションを開催します.
小・中・高等学校の地学クラブの活動および授業の中で児童・生徒が行った研究
の発表を募集します.
今年は,昨年同様ジュニアセッションもe-posterによる発表となります.審査も
オンライン上で行います(当日の表彰は行いません).
ぜひ周囲の学校関係者の方々にご周知ください.
************************************
参加申込書の締切:8月1日(月)
************************************
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/gyoji#es
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2022早稲田]企業展示・書籍販売 対面開催します
──────────────────────────────────
企業等団体展示会,書籍・その他物品の販売ブースを対面形式で大会会場内
に設置予定です(期間:9/4-9/6).
詳細が確定次第,大会HPでお知らせいたします.今しばらくお待ちください.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/tenji
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2022早稲田]家族巡検「生命の進化を楽しく学ぼう」
──────────────────────────────────
2022東京・早稲田大会に参加された会員の家族が楽しんで学ぶイベントを
企画します.実物の動物や化石を見ながら生命の進化の歴史を学びませんか.
日程:9月3日(土)
予定:9:50 上野動物園集合,15:00 国立科学博物館解散
募集期間:7月23日(土)から8月8日(月)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/gyoji#family
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[2022早稲田]地質系業界説明会:参加企業・団体募集中
──────────────────────────────────
毎年開催される学術大会の会場において,学生会員が将来就職する可能性のある
地質・資源・建設分野に関わる地質系企業・団体との対面説明会を企画・開催し,
学生会員が業界を研究するサポートサービスを展開してきました.
今年度は,対面での説明会とオンラインによる説明会の2つを行います.
(対面説明会)学術大会期間中のうちの半日間,会場(早稲田大学)に専用に
ブースを設け,学生会員に対面で説明を行う企画
(オンライン企画)9月16日(金)午後Zoom(予定):当学会のHPを介して
全国の学生が参加企業・団体の紹介動画等を閲覧し,その後オンライン訪問する
企画
**********************
参加企業・団体募集中:7月15日(金)締切
**********************
(企業の皆様へ)対面説明会のお申し込みをたくさん頂戴しています.対面
での参加をご希望の企業,団体は,お早めにお申し込みください.スペースの
都合によりお断りする場合もあります.ご了承ください.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/gyokai_support
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】[2022早稲田]お子様をお連れになる方へ
──────────────────────────────────
ご家族で学会に参加される会員で,大会期間中に保育施設のご利用を希望
される方には,学会から利用料金の一部を補助いたします.
補助対象利用日:9月4日(日)から6日(火)
対象者:東京・早稲田大会に参加する会員(保護者)のお子様
保育施設:早稲田大学託児室(早稲田キャンパス99号館)
(注)これ以外の施設を利用した場合も補助の対象となります.
(注)大学内託児室利用を希望される方はお早めに事務局までお申し出ください.
詳しくは, https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/kids
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・128巻:新しい論文が公開されています.
(フォト)Satoru Imai: Very thickly bedded event deposit in the lower
to middle Miocene Shirahama Formation, southwest Japan
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/128/1/_contents/-char/ja
■ Island Arc
新しい論文が公開されています.
(RESEARCH ARTICLES)Tatsuhiko Yamaguchi et al; Middle Holocene
relative sea-level changes and vertical tectonic crustal movements
on Shikoku Island near the Nankai Trough, Japan
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14401738/0/ja
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)新潟大学旭町学術資料展示館「ジオパークの大放散虫展」(7/20-8/28)
https://www.lib.niigata-u.ac.jp/tenjikan/index.html
(後)神奈川県立生命の星博物館特別展「みどころ沢山!かながわの大地」
(7/16-11/6)
https://nh.kanagawa-museum.jp/www/contents/1651126447345/index.html
---------------------------------
(後)第59回アイソトープ・放射線研究発表会(オンライン)
7月6日(水)-8日(金)
事前参加登録(7,000円)
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2022/top
第31回 地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン第7回目)
7月22日(金)19:30-21:30
内容:地下水汚染調査
講師:成澤 昇(株式会社環境地質研究所,地質汚染診断士)
受講方法:ZOOMによるオンライン
申込期限:2022年7月19日まで 受講料:無料
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
(後)青少年のための科学の祭典2022全国大会
7月30日(土)-31日(日)10:00-15:30
場所:科学技術館(千代田区北の丸公園)
入場無料・事前予約制
http://www.kagakunosaiten.jp/
(後)科学教育研究協議会第68回全国研究大会(岡山大会)
8月10日(水)-12日(金)
会場 岡山理科大学 岡山キャンパス
https://kakyokyo.org/
(後)第9回国際地学教育会議
8月21 日(日)-25 日(木)
会場:くにびきメッセ(島根県コンベンションセンター)
https://ja.geoscied9.org/
日本地質学会第129年学術大会(2022東京・早稲田大会)
9月4日(日)-6日(火),10日(土)-11日(日)
会場:早稲田大学早稲田キャンパス(東京都新宿区西早稲田)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/top
(共)2022年度日本地球化学会第69回年会
9月5日(月)-12日(月)
場所:高知大学朝倉キャンパス会場+オンライン会場(ハイブリッド開催)
http://www.geochem.jp/meeting/
(後)第65回粘土科学討論会
9月7日(水)-8日(木)
(討論会のみの実施,現地見学会は開催しません)
会場:島根大学
http://www.cssj2.org/event/annual_meeting/
地質学史懇話会(オンラインとハイブリッド)
12月17日(土)13:30-16:30
場所:早稲田奉仕園(東京メトロ東西線早稲田駅下車徒歩5分)
山田俊弘・須貝俊彦「望月勝海日記通読プロジェクト」(仮題)
今村遼平「中国地図測量史」
問い合わせ:矢島道子 pxi02070*nifty.com
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0222.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・原子力規制委員会行政職員:安全審査官(地震・津波審査担当)公募(9/30)
・神奈川県立生命の星・地球博物館学芸員 地質学(鉱物学)公募(8/10)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】訃報:加藤 誠 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
加藤 誠 名誉会員(北海道大学名誉教授)が,令和4年6月26日(日)に
逝去されました(90歳).
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し
上げます.ご葬儀はすでに身内の方々のみで執り行われました.
また奥様(憲子様)はご高齢のため,ご自宅への弔問等はお控えいただき
たいとのことです.
会長 岡田 誠
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.557 大会参加登録,巡検の申込はお早めに!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.557 2022/7/19 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2022早稲田]大会参加登録,巡検の申込受付中!
【2】[2022早稲田]ジュニアセッション(e-poster)参加校募集
【3】[2022早稲田]企業展示・書籍販売 対面開催します
【4】[2022早稲田]家族巡検「生命の進化を楽しく学ぼう」
【5】[2022早稲田]お子様をお連れになる方へ
【6】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2022早稲田]大会参加登録,巡検の申込受付中です
──────────────────────────────────
**************************************
申込締切: 8月10日(水)18:00
**************************************
・事前参加登録者には,オンラインプログラム(要旨閲覧,e-poster)へアクセス
するためのログイン情報を事前にメールでお知らせします.
・お支払方法は,銀行振込,クレジット決済をいずれかを選択できます.
・領収書は,後日各自にダウンロードURLをお知らせします.
・対面会場のみ参加の場合,e-posterのみ参加の場合も参加登録費は変わりません.
・発表する会員には別途発表料金(1,500円/題)が発生します.
・講演要旨集(冊子)はありません.
・セッション共催団体会員の参加登録費と発表料金は地質学会会員に準じます.
詳しくは, https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/sanka
(参考)巡検申込状況:
定員に達したコースもあります.お申し込みはお早めに!
http://www.geosociety.jp/science/content0104.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2022早稲田]ジュニアセッション(e-poster)参加校募集
──────────────────────────────────
東京・早稲田大会では,第20回日本地質学会ジュニアセッションを開催します.
小・中・高等学校の地学クラブの活動および授業の中で児童・生徒が行った研究
の発表を募集します.今年は,昨年同様ジュニアセッションもe-posterによる発表
となります.審査もオンライン上で行います(当日の表彰は行いません).
ぜひ周囲の学校関係者の方々にご周知ください.
************************************
参加申込書の締切:8月1日(月)
************************************
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/gyoji#es
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2022早稲田]企業展示・書籍販売 対面開催します
──────────────────────────────────
企業等団体展示会,書籍・その他物品の販売ブースを対面形式で大会会場内
に設置します(期間:9/4-9/6).
募集要項等詳細大会HPに掲載しています.ぜひ出展をご検討ください.
************************************
申込締切:8月5日(金)
************************************
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/tenji
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2022早稲田]家族巡検「生命の進化を楽しく学ぼう」
──────────────────────────────────
2022東京・早稲田大会に参加された会員の家族が楽しんで学ぶイベントを
企画します.実物の動物や化石を見ながら生命の進化の歴史を学びませんか.
日程:9月3日(土)
予定:9:50 上野動物園集合,15:00 国立科学博物館解散
午前:上野動物園(講師 犬塚則久氏)
午後:国立科学博物館(講師 對比地孝亘氏)
募集期間:7月23日(土)から8月8日(月)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/gyoji#family
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2022早稲田]お子様をお連れになる方へ
──────────────────────────────────
ご家族で学会に参加される会員で,大会期間中に保育施設のご利用を希望
される方には,学会から利用料金の一部を補助いたします.
補助対象利用日:9月4日(日)から6日(火)
対象者:東京・早稲田大会に参加する会員(保護者)のお子様
保育施設:早稲田大学託児室(早稲田キャンパス99号館)
(注)これ以外の施設を利用した場合も補助の対象となります.
(注)大学託児室を利用希望の方は,8/8(月)までに学会事務局まで
詳しくは, https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/kids
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・128巻:新しい論文が公開されています.
(論説)星 博幸ほか:長野県中部に分布する守屋層火山岩類(中新統)の
ジルコンU-Pb年代とその層序学的意義/(総説)池原 研:現行堆積作用・
堆積物研究の地質学への展開/(論説)山路 敦ほか:大島造山末期(前期白
亜紀中頃)の北上地域は伸張応力場だったのか?
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/128/1/_contents/-char/ja
■ Island Arc
新しい論文が公開されています.
(RESEARCH ARTICLES)Tetsuo Kawakami; Multi-stage zircon growth recording
polyphase metamorphic evolution caused by pulsed granitoid intrusions into
a low-P/T type metamorphic belt: P-T-D-t evolution of migmatites in the Ryoke
belt, SW Japan ほか
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14401738/0/ja
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)新潟大学旭町学術資料展示館「ジオパークの大放散虫展」(7/20-8/28)
https://www.lib.niigata-u.ac.jp/tenjikan/index.html
(後)神奈川県立生命の星博物館特別展「みどころ沢山!かながわの大地」
(7/16-11/6)
https://nh.kanagawa-museum.jp/www/contents/1651126447345/index.html
---------------------------------
(後)青少年のための科学の祭典2022全国大会
7月30日(土)-31日(日)10:00-15:30
場所:科学技術館(千代田区北の丸公園)
入場無料・事前予約制
http://www.kagakunosaiten.jp/
(後)科学教育研究協議会第68回全国研究大会(岡山大会)
8月10日(水)-12日(金)
会場 岡山理科大学 岡山キャンパス
https://kakyokyo.org/
(後)第9回国際地学教育会議
8月21 日(日)-25 日(木)
会場:くにびきメッセ(島根県コンベンションセンター)
https://ja.geoscied9.org/
日本地質学会第129年学術大会(2022東京・早稲田大会)
9月4日(日)-6日(火),10日(土)-11日(日)
会場:早稲田大学早稲田キャンパス(東京都新宿区西早稲田)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/top
(共)2022年度日本地球化学会第69回年会
9月5日(月)-12日(月)
場所:高知大学朝倉キャンパス会場+オンライン会場(ハイブリッド開催)
http://www.geochem.jp/meeting/
(後)第65回粘土科学討論会
9月7日(水)-8日(木)
(討論会のみの実施,現地見学会は開催しません)
会場:島根大学
http://www.cssj2.org/event/annual_meeting/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0222.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・北海道大学大学院理学研究院地球惑星科学部門地球惑星システム科学分野
(古生物)教授公募(8/3)
・千葉県立博物館等職員採用選考(地質学/動物学)(8/3)
・京都大学工学研究科社会基盤工学専攻資源工学講座教授公募(9/15)
・山梨県富士山科学研究所任期付研究員/研究員の公募(8/17)
・農林水産省経験者採用試験(係長級(技術))公募(8/25)
・東京大学理学系研究科地球惑星科学専攻地球システム変動学助教公募(7/25)
・第20回高校生・高専生科学技術チャレンジ(JSEC2022)(9/1-10/4)
・東レ科学技術賞および東レ科学技術研究助成の候補者推薦(学会締切9/12)
・東レ理科教育賞・企画賞募集(9/9)
・「朝日賞」候補者推薦依頼(学会締切8/2)
・​​第44回(令和4年度)沖縄研究奨励賞推薦応募(学会締切9/5)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.558 全体日程表が公開になりました
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.558 2022/8/2┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2022早稲田]早稲田大会の開催について
【2】[2022早稲田]全体日程表が公開になりました
【3】[2022早稲田]大会参加登録,巡検の申込受付中!
【4】[2022早稲田]企業展示・書籍販売 対面開催します
【5】[2022早稲田]学生のための地質系業界説明会
【6】[2022早稲田]家族巡検「生命の進化を楽しく学ぼう」
【7】[2022早稲田]お子様をお連れになる方へ
【8】トピック:地学に名を轟かした水戸藩の長久保赤水の改正日本輿地路程全図
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2022早稲田]早稲田大会の開催について
──────────────────────────────────
第129年学術大会(2022早稲田大会)は,当初予定通り「対面開催」で準備を
進めております.ただし,今後コロナ感染拡大状況がより一層悪化し,東京都
あるいは国による行動制限等が発令,もしくは早稲田大学からの受入中止等の
連絡があった場合は,対面開催が不可能となります.その場合は口頭日程を
中止し,口頭発表をすべてみなし発表とします.巡検の実施可否も口頭発表
に準じます.
現地会場では,換気徹底,可能な限りスペースに余裕を持たせた各種配置など,
できるだけ対策を講じます.対面参加予定の皆さまにも,マスク着用,黙食等
の基本的な感染対策にご協力をいただきますよう,何卒お願いいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2022早稲田]全体日程表が公開になりました
──────────────────────────────────
口頭,ポスター発表等の日程表を大会HPに掲載いたしました.なお,これから
お手元に届く予定のNews誌プログラム記事(7月号)掲載内容より一部会場に
変更がありますので,ご注意ください.
最新版の全体日程表はこちらから.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/program
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2022早稲田]大会参加登録,巡検の申込 まもなく締切です
──────────────────────────────────
**************************************
申込締切: 8月10日(水)18:00
**************************************
・事前参加登録者には,オンラインプログラム(要旨閲覧,e-poster)へアクセス
するためのログイン情報を事前にメールでお知らせします.
・お支払方法は,銀行振込,クレジット決済をいずれかを選択できます.
・領収書は,後日各自にダウンロードURLをお知らせします.
・対面会場のみ参加の場合,e-posterのみ参加の場合も参加登録費は変わりません.
・発表する会員には別途発表料金(1,500円/題)が発生します.
・講演要旨集(冊子)はありません.
・セッション共催団体会員の参加登録費と発表料金は地質学会会員に準じます.
詳しくは,https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/sanka
(参考)巡検申込状況:http://www.geosociety.jp/science/content0104.html
定員に達したコースもあります.お申し込みはお早めに!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2022早稲田]企業展示・書籍販売 対面開催します
──────────────────────────────────
企業等団体展示会,書籍・その他物品の販売ブースを対面形式で大会会場内
に設置します(期間:9/4-9/6).
募集要項等詳細大会HPに掲載しています.ぜひ出展をご検討ください.
************************************
申込締切:8月5日(金)
************************************
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/tenji
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2022早稲田]学生のための地質系業界説明会
─────────────────────────────────
地質系学科主任・就職担当教員の皆様,地質系学科学部生・院生の皆様,
ぜひご参加ください!
学生が将来就職する可能性のある地質・資源・建設分野に関わる地質系企業等
との対面説明会を企画・開催し,学生が業界を研究するサポートサービスです.
今年度は,対面説明会とオンライン説明会の2つを行います.
・対面説明会 9/5(月)11:00-16:00 場所:早稲田キャンパス第14号館5階
・オンライン説明会 9/16(金)午後.Zoomを使ったオンライン説明会を予定
参加費無料,会員・非会員を問わず,同じ学科の友人をお誘いあわせのうえ,
お気軽にご参加ください.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/gyokai_support
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[2022早稲田]家族巡検「生命の進化を楽しく学ぼう」
──────────────────────────────────
2022東京・早稲田大会に参加された会員の家族が楽しんで学ぶイベントを
企画します.実物の動物や化石を見ながら生命の進化の歴史を学びませんか.
日程:9月3日(土)
予定:9:50 上野動物園集合,15:00 国立科学博物館解散
午前:上野動物園(講師 犬塚則久氏)
午後:国立科学博物館(講師 對比地孝亘氏)
募集締切:8月8日(月)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/gyoji#family
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】[2022早稲田]お子様をお連れになる方へ
──────────────────────────────────
ご家族で学会に参加される会員で,大会期間中に保育施設のご利用を希望
される方には,学会から利用料金の一部を補助いたします.
補助対象利用日:9月4日(日)から6日(火)
対象者:東京・早稲田大会に参加する会員(保護者)のお子様
保育施設:早稲田大学託児室(早稲田キャンパス99号館)
(注)これ以外の施設を利用した場合も補助の対象となります.
(注)大学託児室を利用希望の方は,8/8(月)までに学会事務局まで
詳しくは,https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/kids
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】トピック:地学に名を轟かした水戸藩の長久保赤水の改正日本輿地路程全図
──────────────────────────────────
(正会員 石渡 明)
伊能忠敬(1745-1818)は幕府の命により全国を実地測量して精密な地図を作った
が,伊能図(大日本沿海輿地全図:文政 4(1821)年完成)は秘密とされ一般人
は使用できなかった.それに対し,長久保 赤水(1717-1801)が作ったのは10里
が1寸の縮尺約130万分の1)の1枚刷り全国図で,経緯線が入り,郡や村,道路,
山川,古跡名勝等が詳しく示され,国別の色分 けも美しく,安永9(1780)年
に大坂で初版を出版して以来, 明治の初めまで約100年間にわたって版を重ね,
国内はもちろん国外でも,正確で実用的な日本地図として重宝された.
続きはこちらからhttp://www.geosociety.jp/faq/content1040.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)新潟大学旭町学術資料展示館「ジオパークの大放散虫展」(7/20-8/28)
https://www.lib.niigata-u.ac.jp/tenjikan/index.html
(後)神奈川県立生命の星博物館特別展「みどころ沢山!かながわの大地」
(7/16-11/6)
https://nh.kanagawa-museum.jp/www/contents/1651126447345/index.html
---------------------------------
(後)科学教育研究協議会第68回全国研究大会(岡山大会)
8月10日(水)-12日(金)
会場 岡山理科大学 岡山キャンパス
https://kakyokyo.org/
(後)第9回国際地学教育会議
8月21 日(日)-25 日(木)
会場:くにびきメッセ(島根県コンベンションセンター)
https://ja.geoscied9.org/
日本地質学会第129年学術大会(2022東京・早稲田大会)
9月4日(日)-6日(火),10日(土)-11日(日)
会場:早稲田大学早稲田キャンパス(東京都新宿区西早稲田)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/top
(共)2022年度日本地球化学会第69回年会
9月5日(月)-12日(月)
場所:高知大学朝倉キャンパス会場+オンライン会場(ハイブリッド開催)
http://www.geochem.jp/meeting/
(後)第65回粘土科学討論会
9月7日(水)-8日(木)
(討論会のみの実施,現地見学会は開催しません)
会場:島根大学
http://www.cssj2.org/event/annual_meeting/
2022年度 第2回地質調査研修
2022年10月24日(月)-28日(金)
主催:産総研コンソーシアム「地質人材育成コンソーシアム」
場所:島根県出雲市長尾鼻周辺(小伊津海岸)
内容:野外での地層・岩石の観察ポイントからまとめまで,地質図を作成する
ための基本的事項を事前のe-ラーニングと5日間の対面研修で習得します.
定員:6名(定員になり次第締切),CPD:42単位
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2022-2.html
(協)第38回ゼオライト研究発表会
12月1日(木)-2日(金)
場所:あわぎんホール(徳島県郷土文化会館)
講演申込締切:9月9日(金)
https://jza-online.org/
地質学史懇話会(オンラインとハイブリッド)
12月17日(土)13:30-16:30
場所:早稲田奉仕園(東京メトロ東西線早稲田駅下車徒歩5分)
山田俊弘・須貝俊彦「望月勝海日記通読プロジェクト」(仮)
今村遼平「中国地図測量史」
問い合わせ:矢島道子 pxi02070[atマーク]nifty.com
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0222.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・東京大学地震研究所アクティブテクトニクス研究分野助教公募(10/31)
・JAMSTEC Young Research Fellow 2023 公募(9/6)
・熊本大学大学院先端科学研究部基礎科学部門地球環境科学分野教授公募(8/26)
・東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻広域システム科学系准教授公募(地球科学)(9/18)
・山形大学学術研究院地球科学(地震学,火山学,測地学,気象学等)テニュアトラック教員公募(女性限定)(9/15)
・山形大学地域教育文化学部児童教育コース(地球科学 講師or准教授,女性限定)(8/31)
・2023年-2024年開催藤原セミナーの募集(11/30)
・洞爺湖有珠山ジオパーク学術専門員の募集(10/17)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.559(臨時)[2022早稲田]参加登録・巡検まもなく締切!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.559 2022/8/8┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2022早稲田]早稲田大会の開催について(再掲)
【2】[2022早稲田]全体日程表・講演プログラム公開
【3】[2022早稲田]大会参加登録,巡検のまもなく締切!
【4】[2022早稲田]発表者の皆様へ
【5】[2022早稲田]学生のための地質系業界説明会
【6】[2022早稲田]地質学露頭紹介 発表者募集!
【7】[2022早稲田]家族巡検「生命の進化を楽しく学ぼう」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2022早稲田]早稲田大会の開催について(再掲)
──────────────────────────────────
第129年学術大会(2022早稲田大会)は,当初予定通り「対面開催」で準備を
進めております.ただし,今後コロナ感染拡大状況がより一層悪化し,東京都
あるいは国による行動制限等が発令,もしくは早稲田大学からの受入中止等の
連絡があった場合は,対面開催が不可能となります.その場合は口頭日程を
中止し,口頭発表をすべてみなし発表とします.巡検の実施可否も口頭発表
に準じます.
現地会場では,換気徹底,可能な限りスペースに余裕を持たせた各種配置など,
できるだけ対策を講じます.対面参加予定の皆さまにも,マスク着用,黙食等
の基本的な感染対策にご協力をいただきますよう,何卒お願いいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2022早稲田]全体日程表・講演プログラム公開
──────────────────────────────────
口頭,ポスター発表等の日程表を大会HPに掲載いたしました.News誌
プログラム記事(7月号)掲載内容より一部会場に変更がありますので,
ご注意ください.また講演プログラム(タイムテーブル)も公開になり
ました.タイトル,講演者氏名などで検索も可能です.
最新版の全体日程はこちらから.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/program
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2022早稲田]大会参加登録,巡検の申込 まもなく締切!──────────────────────────────────
**************************************
申込締切: 8月10日(水)18:00 まもなく締め切りです
**************************************
・事前参加登録者には,オンラインプログラム(要旨閲覧,e-poster)へアクセス
するためのログイン情報を事前にメールでお知らせします.
・お支払方法は,銀行振込,クレジット決済をいずれかを選択できます.
・領収書は,締切後各自にダウンロードURLをお知らせします.
・対面会場のみ参加の場合,e-posterのみ参加の場合も参加登録費は変わりません.
・発表する会員には別途発表料金(1,500円/題)が発生します.
・講演要旨集(冊子)はありません.
・セッション共催団体会員の参加登録費と発表料金は地質学会会員に準じます.
詳しくは,https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/sanka
(参考)巡検申込状況はこちら
http://www.geosociety.jp/science/content0104.html
定員に達したコースもあります.お申し込みはお早めに!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2022早稲田]発表者の皆様へ
─────────────────────────────────
それぞれ8/1に下記のご案内メールを送信しています.内容のご確認を
お願いいたします.
(ポスター発表者へ)
件名:【日本地質学会第129年学術大会】フラッシュトークのご案内
(口頭発表者へ)
件名:【日本地質学会第129年学術大会】口頭発表者のzoom出演の希望について
発表者、大会参加登録者へ送信したメール送信履歴は,大会HPからもご確認
いただけます.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/emergency
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2022早稲田]学生のための地質系業界説明会
─────────────────────────────────
地質系学科主任・就職担当教員の皆様,地質系学科学部生・院生の皆様,
ぜひご参加ください!
学生が将来就職する可能性のある地質・資源・建設分野に関わる地質系企業等
との対面説明会を企画・開催し,学生が業界を研究するサポートサービスです.
今年度は,対面説明会とオンライン説明会の2つを行います.
・対面説明会 9/5(月)11:00-16:00 場所:早稲田キャンパス第14号館5階
・オンライン説明会 9/16(金)午後.Zoomを使ったオンライン説明会を予定
参加費無料,会員・非会員を問わず,同じ学科の友人をお誘いあわせのうえ,
お気軽にご参加ください.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/gyokai_support
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[2022早稲田]地質学露頭紹介 発表者募集!
──────────────────────────────────
またまたやります!
とっておきの露頭、解釈がむずかしい露頭、専門家から意見をもらいたい露頭
など、さまざまな露頭の写真を持ち寄り、その学術的意味についてZoomで解説
したり意見交換したりするイベントです(研究発表セッションではありません).
開催日時:2022年9月11日(日)13:30-15:30(予定)
方法:オンライン(Zoom)
発表申込締切:8月31日(水)18時
発表資格:会員,非会員問わずどなたでも発表可能
(学術大会への参加登録の必要はありません) .
詳しくは,https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/etc#rotou
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】[2022早稲田]家族巡検「生命の進化を楽しく学ぼう」
──────────────────────────────────
2022東京・早稲田大会に参加された会員の家族が楽しんで学ぶイベントを
企画します.実物の動物や化石を見ながら生命の進化の歴史を学びませんか.
日程:9月3日(土)
予定:9:50 上野動物園集合,15:00 国立科学博物館解散
午前:上野動物園(講師 犬塚則久氏)
午後:国立科学博物館(講師 對比地孝亘氏)
募集締切:8月10日(水)*締締切延長しました.若干名余裕があります*
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/gyoji#family
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.560 講演プログラム公開中
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.560 2022/8/16┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2022早稲田]全体日程表・講演プログラム
【2】[2022早稲田]大会参加登録・巡検申込を締め切りました
【3】[2022早稲田]発表者の皆様へ
【4】[2022早稲田]学生のための地質系業界説明会
【5】[2022早稲田]地質学露頭紹介 発表者募集!
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2022早稲田]全体日程表・講演プログラム
──────────────────────────────────
口頭,ポスター発表等の講演プログラム.日程表を大会HPで公開中です.
News誌プログラム記事(7月号)掲載内容より一部会場に変更がありますので,
ご注意ください.大会HPからタイトル,講演者氏名などで講演検索が可能です.
講演要旨は,8月末頃公開予定です.
最新版の全体日程
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/program
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2022早稲田]大会参加登録・巡検申込を締め切りました──────────────────────────────────
8/10に学術大会の事前参加登録・巡検申込を締め切りました.
▶︎▶︎事前参加登録者(入金済みの場合):
領収書のダウンロードURLとオンラインプログラム(要旨閲覧,e-poster)へ
アクセスするためのログイン情報をまもなくメールでお知らせします.
現時点で未入金の方は,急ぎご送金ください.
なお,受付用のクーポン券など学会からの事前の郵送物はありません.
大会当日(対面会場)は,「会員カード」もしくは申込時の確認メール
(「注文番号」or「請求書ID」が明記されているもの)を印刷・持参して下さい.
▶︎▶︎事前登録をしていない方:
9/4-6の期間,対面会場(早稲田大学)でのみ当日受付を行います.参加登録費の
有料・無料に関わらず備え付けの『参加登録票』に必要事項を記入し当日用受付
窓口で,お手続きください.その際オンラインプログラム(要旨,e-poster閲覧)
へアクセスするためのログイン情報(ID/PW)も発行します.
対面会場での当日の受付については,下記をご参照ください. https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/reception
▶︎▶︎巡検をお申し込みの皆様へ:
申込結果(催行の可否)は下記よりご確認ください.
http://www.geosociety.jp/science/content0104.html
事前に案内者より当日詳細についてメールでご連絡予定です.
巡検当日の受付は,集合場所にて名簿で確認します.案内書,CPD参加証明書
や領収書は巡検当日に各コースの案内者からお渡しします.
大会HP巡検について
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/excursion
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2022早稲田]発表者の皆様へ
─────────────────────────────────
それぞれ8/1以降下記のご案内メールを送信しています.何らかの理由で(迷惑
メールになった.申込時のアドレス入力に誤りがあった...など)メールを受信or
確認していない方は,ご確認ください.
(ポスター発表者へ)
件名:【日本地質学会第129年学術大会】e-poster投稿に関するご連絡ほか
件名:【日本地質学会第129年学術大会】フラッシュトークのご案内
(口頭発表者へ)
件名:【日本地質学会第129年学術大会】口頭発表者のzoom出演の希望
発表者、大会参加登録者へ送信したメール送信履歴は大会HPからご確認頂けます.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/emergency
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2022早稲田]学生のための地質系業界説明会
─────────────────────────────────
地質系学科主任・就職担当教員の皆様,地質系学科学部生・院生の皆様,
ぜひご参加ください!
学生が将来就職する可能性のある地質・資源・建設分野に関わる地質系企業等
との対面説明会を企画・開催し,学生が業界を研究するサポートサービスです.
今年度は,対面説明会とオンライン説明会の2つを行います.
・対面説明会 9/5(月)11:00-16:00 場所:早稲田キャンパス第14号館5階
・オンライン説明会 9/16(金)午後.Zoomを使ったオンライン説明会を予定
参加費無料,会員・非会員を問わず,同じ学科の友人をお誘いあわせのうえ,
お気軽にご参加ください.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/gyokai_support
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2022早稲田]地質学露頭紹介 発表者募集!
──────────────────────────────────
またまたやります!!
とっておきの露頭、解釈がむずかしい露頭、専門家から意見をもらいたい露頭
など、さまざまな露頭の写真を持ち寄り、その学術的意味についてZoomで解説
したり意見交換したりするイベントです(研究発表セッションではありません).
開催日時:2022年9月11日(日)13:30-15:30(予定)
方法:オンライン(Zoom)
発表申込締切:8月31日(水)18時
発表資格:会員,非会員問わずどなたでも発表可能
(学術大会への参加登録の必要はありません) .
詳しくは, https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/etc#rotou
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)新潟大学旭町学術資料展示館「ジオパークの大放散虫展」(7/20-8/28)
https://www.lib.niigata-u.ac.jp/tenjikan/index.html
(後)神奈川県立生命の星博物館特別展「みどころ沢山!かながわの大地」
(7/16-11/6)
https://nh.kanagawa-museum.jp/www/contents/1651126447345/index.html
---------------------------------
(後)第9回国際地学教育会議
8月21 日(日)-25 日(木)
会場:くにびきメッセ(島根県コンベンションセンター)
https://ja.geoscied9.org/
日本堆積学会堆積学スクール2022「現世干潟の堆積過程」
8月28日(日)
場所:神奈川県川崎市多摩川河口干潟
申込締切:8月12日(金)(定員になり次第締切)
http://www.sediment.jp/04nennkai/2022/2022school.html
日本地質学会第129年学術大会(2022東京・早稲田大会)
9月4日(日)-6日(火),10日(土)-11日(日)
会場:早稲田大学早稲田キャンパス(東京都新宿区西早稲田)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/top
(共)2022年度日本地球化学会第69回年会
9月5日(月)-12日(月)
場所:高知大学朝倉キャンパス会場+オンライン会場(ハイブリッド開催)
http://www.geochem.jp/meeting/
(後)第65回粘土科学討論会
9月7日(水)-8日(木)
(討論会のみの実施,現地見学会は開催しません)
会場:島根大学
http://www.cssj2.org/event/annual_meeting/
第238回イブニングセミナー(オンライン)
9月9日(金)19:30-21:30
演題:「水銀汚染地域における土壌中水銀濃度分布とその化学形(仮)」
講師:冨安卓滋(鹿児島大学大学院理工学研究科)
主催:NPO法人日本地質汚染審査機構
参加費:主催NPO会員及び学生の方(無料) 非会員(1,000円)
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
2022年度 第2回地質調査研修
10月24日(月)-28日(金)
主催:産総研コンソーシアム「地質人材育成コンソーシアム」
場所:島根県出雲市長尾鼻周辺(小伊津海岸)
内容:野外での地層・岩石の観察ポイントからまとめまで,地質図を作成する
ための基本的事項を事前のe-ラーニングと5日間の対面研修で習得します.
定員:6名(定員になり次第締切),CPD:42単位
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2022-2.html
(協)第38回ゼオライト研究発表会
12月1日(木)-2日(金)
場所:あわぎんホール(徳島県郷土文化会館)
講演申込締切:9月9日(金)
https://jza-online.org/
地質学史懇話会(オンラインとハイブリッド)
12月17日(土)13:30-16:30
場所:早稲田奉仕園(東京メトロ東西線早稲田駅下車徒歩5分)
山田俊弘・須貝俊彦「望月勝海日記通読プロジェクト」(仮)
今村遼平「中国地図測量史」
問い合わせ:矢島道子 pxi02070[atマーク]nifty.com
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0222.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・東京大学地震研究所陸域・火山電磁気観測研究分野准教授公募(11/11)
・新潟大学教育研究院人文社会科学系教員(理科教育)准教授or講師公募(10/7)
・東工大理学院(数学,物理学,化学,または地球惑星科学分野)教授or准教授
公募(女性限定)(9/30)
・2023年度笹川科学研究助成募集(9/15-10-17)
・JST国際部 「新たな国際頭脳循環モード促進プログラム」公募(10/11)
・日本化学会2022年度吉野彰研究助成公募(9/30)
・伊豆大島ジオパークジオパーク専門員再募集(10/14)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.561(臨時)[2022早稲田]会員カードを持って早稲田へGO!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.561 2022/9/1┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
[2022早稲田大会情報]
【1】9/4-6対面会場へお越しの皆様へ(会員カードを持参して下さい)
【2】オンラインプログラムの参加方法について
【3】巡検をお申し込みの皆様へ
【4】参加者・発表者へのメール送信履歴
【5】学生のための地質系業界説明会(9/2まで学生事前申込締切延長)
【6】コアタイムの前に「フラッシュトーク」を実施します
【7】ランチョン・夜間小集会(9/4−6対面)のご案内
【8】地質学露頭紹介 発表者募集!(9/3締切延長)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】9/4-6対面会場へお越しの皆様へ(会員カードを持参して下さい)
──────────────────────────────────
(変更)対面会場の受付時間は,各日とも朝8:10より受付開始となります.
—------------------------------
事前参加登録者(入金済みの場合):
—-----------------------------
大会当日は,「会員カード」もしくは申込時の確認メール(「注文番号」or
「請求書ID」が明記されているもの)を印刷・持参して下さい.
受付用のクーポン券など学会からの事前の郵送物はありません.
また,領収書のダウンロードURLとオンラインプログラム(要旨閲覧,e-poster)
へアクセスするためのログイン情報をメールでお知らせしました(8/28).
件名:【日本地質学会第129年学術大会】参加者用ログイン情報のご連絡
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/emergency#0828
—------------------------------
事前登録をしていない方:
—------------------------------
9/4-6の期間,対面会場(早稲田大学)でのみ当日受付を行います.参加登録費の
有料・無料に関わらず備え付けの『参加登録票』に必要事項を記入し当日用受付
窓口で,お手続きください.その際オンラインプログラム(要旨,e-poster閲覧)
へアクセスするためのログイン情報(ID・PW)も発行します.
対面会場での当日の受付については,下記をご参照ください.https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/reception
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】オンラインプログラムの参加方法について
──────────────────────────────────
「参加者用ログイン」の上,各講演プログラムへアクセスして下さい.
講演要旨,e-posterの閲覧が可能です(e-posterは9/4以降).
ポスターコアタイムに参加する場合も,ログインの上,プログラムのタイム
テーブルから該当のポスターセッションzoomにアクセスして下さい.
ポスターコアタイム:ブレイクアウトルームへの入り方(発表者,聴講者共通)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/presen#zbo
(注)e-poste閲覧期間は,10/11までです(要ログイン).10/12以降は
講演要旨のみ無料閲覧可能です(ログイン不要).
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】巡検をお申し込みの皆様へ
──────────────────────────────────
事前に案内者より当日詳細についてメールでご連絡予定です.
巡検当日の受付は,集合場所にて名簿で確認します.案内書,CPD参加証明書
や領収書は巡検当日に各コースの案内者からお渡しします.
大会HP巡検について
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/excursion
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】参加者・発表者へのメール送信履歴
─────────────────────────────────
発表者、大会参加登録者へ送信したメール送信履歴を掲載しています.
何らかの理由で(迷惑メールになった.申込時のアドレス入力に誤りがあった
...など)メールを受信or確認していない方は,ご確認ください.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/emergency
(送信例)
2022年08月28日 領収書ダウンロードURLのお知らせ
2022年08月28日 参加者用ログイン情報のご連絡
2022年08月01日(口頭発表者限定)口頭発表者のzoom出演の希望について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】学生のための地質系業界説明会(9/2まで学生事前申込締切延長)
─────────────────────────────────
学術大会への参加登録は不要ですが,コロナ感染防止の観点から人数把握の
ため対面企画事前参加申込(学生用)を受け付け中です.
**9/2まで締切延長**
当日の飛び込み参加もOKですが、事前申込者を優先します。
*****************************************
地質系学科主任・就職担当教員の皆様,地質系学科学部生・院生の皆様,
ぜひご参加ください!
学生が将来就職する可能性のある地質・資源・建設分野に関わる地質系企業等
との対面説明会を企画・開催し,学生が業界を研究するサポートサービスです.
********************************
対面説明会 9/5(月)11:00-16:00
場所:早稲田キャンパス第14号館5階
事前参加申込(学生用)を受付中.<9/2まで締切延長>
********************************
参加費無料,会員・非会員を問わず,同じ学科の友人をお誘いあわせのうえ,
お気軽にご参加ください.
9/16(金)Zoomを使ったオンライン説明会も開催します.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/gyokai_support
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】ランチョン・夜間小集会(9/4−6対面)のご案内
─────────────────────────────────
口頭発表の会期中(9/4-9/6)に対面形式で開催いたします.
専門部会の会合から学生・若手のための交流会まで幅広く企画されています.
ぜひご参加ください.
ランチョン・夜間小集会の予定はこちらから
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/meeting
(大会プログラムサイト:タイムテーブルからもご確認いただけます)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】コアタイムの前に「フラッシュトーク」を実施します
─────────────────────────────────
ポスターコアタイムの前に、ポスター発表の要点を口頭(zoom)で講演者がアピールするフラッシュトークの時間を設けます(任意、希望者のみ)。e-posterの画像やその他の資料を提示したり自由な発表が予定されています。コアタイムでの活発な議論のきっかけづくりにぜひご視聴ください。
トークスケジュールはこちらから
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/etc
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】地質学露頭紹介 発表者募集!(9/3締切延長)
──────────────────────────────────
またまたやります!!
とっておきの露頭、解釈がむずかしい露頭、専門家から意見をもらいたい露頭
など、さまざまな露頭の写真を持ち寄り、その学術的意味についてZoomで解説
したり意見交換したりするイベントです(研究発表セッションではありません).
開催日時:2022年9月11日(日)13:30-15:30(予定)
方法:オンライン(Zoom)
発表申込締切:9月3日(金)締切延長
発表資格:会員,非会員問わずどなたでも発表可能
(学術大会への参加登録の必要はありません) .
詳しくは,https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/etc#rotou
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.562(臨時)[2022早稲田]帰ってきた対面大会
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.562 2022/9/4 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
[2022早稲田大会情報]
【1】早稲田大会 初日の様子
【2】9/4-6対面会場へお越しの皆様へ(会員カードを持参して下さい)
【3】オンラインプログラムの参加方法について
【4】学生のための地質系業界説明会(学生さんの飛び込み参加も歓迎します!
【5】コアタイムの前に「フラッシュトーク」を実施します
【6】ランチョン・夜間小集会(9/4−6対面)のご案内
【7】地質学露頭紹介 やります!(9/11、zoom)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】早稲田大会 初日の様子
──────────────────────────────────
早稲田大会が開幕しました!
実に3年ぶりの対面の大会です。やっぱり対面はいいなあ。楽しい。ホント楽しい。
2日目も8:45からセッション(口頭)が始まります。対面会場では、当日参加登録
も受け付けています。
■会場の様子と表彰式
早稲田大学です!
メイン会場
会場の様子
講演の様子
地質学会岡田会長挨拶
若林学術院長挨拶
板谷名誉会員
八尾名誉会員
永年会員顕彰 池田会員
永年会員顕彰 紺谷会員
永年会員顕彰 大橋会員
永年会員顕彰 吉田会員
表彰式会場の様子
功績賞 高橋会員
ナウマン賞 片山会員
小澤賞 石輪会員
柵山賞 岡崎会員
柵山賞 宇野会員
Island Arc賞 磯崎会員
論文賞 高嶋会員
論文賞 星会員
論文賞 新正会員
奨励賞 中西会員
学会表彰 伊予原 新氏
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】対面会場へお越しの皆様へ(会員カードを持参して下さい)
──────────────────────────────────
(変更)対面会場の受付時間は,各日とも朝8:10より受付開始となります.
—------------------------------
事前参加登録者(入金済みの場合):
—-----------------------------
大会当日は,「会員カード」もしくは申込時の確認メール(「注文番号」or
「請求書ID」が明記されているもの)を印刷・持参して下さい.
受付用のクーポン券など学会からの事前の郵送物はありません.
また,領収書のダウンロードURLとオンラインプログラム(要旨閲覧,e-poster)
へアクセスするためのログイン情報をメールでお知らせしました(8/28).
件名:【日本地質学会第129年学術大会】参加者用ログイン情報のご連絡
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/emergency#0828
—------------------------------
事前登録をしていない方:
—------------------------------
9/4-6の期間,対面会場(早稲田大学)でのみ当日受付を行います.参加登録費の
有料・無料に関わらず備え付けの『参加登録票』に必要事項を記入し当日用受付
窓口で,お手続きください.その際オンラインプログラム(要旨,e-poster閲覧)
へアクセスするためのログイン情報(ID・PW)も発行します.
対面会場での当日の受付については,下記をご参照ください.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/reception
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】オンラインプログラムの参加方法について
──────────────────────────────────
「参加者用ログイン」の上,各講演プログラムへアクセスして下さい.
講演要旨,e-posterの閲覧が可能です(e-posterは9/4以降).
ポスターコアタイムに参加する場合も,ログインの上,プログラムのタイム
テーブルから該当のポスターセッションzoomにアクセスして下さい.
(注)口頭発表は対面形式のみで開催。zoomのご視聴はできません。
ポスターコアタイム:ブレイクアウトルームへの入り方(発表者,聴講者共通)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/presen#zbo
(注)e-poste閲覧期間は,10/11までです(要ログイン).10/12以降は
講演要旨のみ無料閲覧可能です(ログイン不要).
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】学生のための地質系業界説明会(学生さんの飛び込み参加も歓迎します!)
─────────────────────────────────
地質系学科主任・就職担当教員の皆様,地質系学科学部生・院生の皆様,
ぜひご参加ください!
学生が将来就職する可能性のある地質・資源・建設分野に関わる地質系企業等
との対面説明会を企画・開催し,学生が業界を研究するサポートサービスです.
********************************
対面説明会 9/5(月)11:00-16:00
場所:早稲田キャンパス第14号館5階
事前参加申込(学生用)を受付中.<9/2まで締切延長>
********************************
参加費無料,会員・非会員を問わず,同じ学科の友人をお誘いあわせのうえ,
お気軽にご参加ください.
9/16(金)Zoomを使ったオンライン説明会も開催します.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/gyokai_support
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】ランチョン・夜間小集会(9/4−6対面)のご案内
─────────────────────────────────
口頭発表の会期中(9/4-9/6)に対面形式で開催いたします.
専門部会の会合から学生・若手のための交流会まで幅広く企画されています.
ぜひご参加ください.
ランチョン・夜間小集会の予定はこちらから
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/meeting
(大会プログラムサイト:タイムテーブルからもご確認いただけます)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】コアタイムの前に「フラッシュトーク」を実施します
─────────────────────────────────
ポスターコアタイムの前に、ポスター発表の要点を口頭(zoom)で講演者
がアピールするフラッシュトークの時間を設けます(任意、希望者のみ)。
e-posterの画像やその他の資料を提示したり自由な発表が予定されています。
コアタイムでの活発な議論のきっかけづくりにぜひご視聴ください。
トークスケジュールはこちらから
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/etc
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】地質学露頭紹介 やります!(9/11、zoom)
──────────────────────────────────
またまたやります!!
とっておきの露頭、解釈がむずかしい露頭、専門家から意見をもらいたい露頭
など、さまざまな露頭の写真を持ち寄り、その学術的意味についてZoomで解説
したり意見交換したりするイベントです(研究発表セッションではありません).
開催日時:2022年9月11日(日)13:30-15:30(予定)
方法:オンライン(Zoom)
発表申込は締切ました
発表資格:会員,非会員問わずどなたでも発表可能
(学術大会への参加登録の必要はありません) .
詳しくは,https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/etc#rotou
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.563(臨時)[2022早稲田]ラストスパート!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.563 2022/9/6 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
★★目次 ★★
【1】早稲田大会:2日目と3日目の様子
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】早稲田大会 2-3日目の様子
──────────────────────────────────
さあ2日目。そして3日目。台風も心配されましたが、ちゃんと進行中です。
■地質情報展(15号館)
大会と隣接した会場
情報展の様子
巨大マップ
ほほう。ここか
地質図買いたい
地震を起こせ
■学術大会(14号館)
発表会場
発表会場
企業ブース
企業ブース
企業ブース
学生のための地質系業界説明会
【geo-Flash】No.564 早稲田大会が終了しました.来年は...
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.564 2022/9/20┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2022早稲田大会]学術大会が終了しました
【2】[2022早稲田大会]優秀ポスター賞決定
【3】[2022早稲田大会]講演要旨・e-posterの閲覧について
【4】第15回日本地学オリンピックの参加申込受付中
【5】支部情報
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2022早稲田大会]学術大会終了しました
──────────────────────────────────
9/3プレ巡検に始まり,9/4-6口頭セッション(3年ぶり対面開催),
9/10-11e-poster,9/16地質系業界説明会等々,予定された全ての行事が
終了致しました.大会にご参加頂きました皆様に心より御礼申し上げます.
大会の様子(写真など)は,メルマガ臨時号(学会HP)でも紹介しています.
またニュース誌11月号で大会報告記事を掲載予定です.
No.562(臨時)[2022早稲田]帰ってきた対面大会
No.563(臨時)[2022早稲田]ラストスパート!
http://www.geosociety.jp/faq/content0005.html
----------------------------------
来年は京都大会でお会いしましょう!
日本地質学会第130年学術大会(2023京都)
会場:京都大学 吉田キャンパス
日程:2023年9月17日(日)-19日(火)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2022早稲田大会]優秀ポスター賞決定
──────────────────────────────────
計8件が決定しました.おめでとうございます.
講演内容は,大会サイトから「優秀ポスター賞」で講演検索して閲覧して
いただけます(10/11まで要参加ログイン).受賞者には後日賞状と副賞を
郵送します.
受賞した講演はこちら
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/static/etc#sho
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2022早稲田大会]講演要旨・e-posterの閲覧について
──────────────────────────────────
大会講演要旨・e-posterは,10/11まで大会参加者のみ閲覧可能です
(要参加者ログイン).講演要旨は10/12以降無料公開を予定しています.
e-posterの公開はありません.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第15回日本地学オリンピックの参加申込受付中
──────────────────────────────────
募集期間:9月1日(木)-11月15日(火)
(一次予選)
2022年12月18日(日) 14:00-15:00 択一式オンライン試験
参加資格:小中高校生 参加費:無料
※不正防止のためにカメラ付端末(スマホ可ただしPC利用推奨)が必要
(二次予選)
2023年1月22日(日) 午後 マークシート式筆記試験
会場:全国指定14会場
(本選)
2023年3月12日(日) 午後 -14日(火) 午前 (茨城県つくば市)
詳しくは, https://jeso.jp/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部情報
──────────────────────────────────
[中部支部]
「⼩松の⽯⽂化」現地⾒学会
主催:日本応用地質学会中部支部(地質学会中部支部会員も参加可能)
10月1日(土)13:30-17:30【雨天決行】
場所:石川県小松市内
定員:20名
申込期限:9月28日(水)
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)神奈川県立生命の星博物館特別展「みどころ沢山!かながわの大地」
(7/16-11/6)
https://nh.kanagawa-museum.jp/www/contents/1651126447345/index.html
---------------------------------
JAMSTEC 創立50周年記念式典・研究報告会「JAMSTEC2022」
9月7日(水)13:15-17:30
Zoomオンライン開催(参加無料・事前登録制)
※YouTube配信も予定されています.
https://www.jamstec.go.jp/j/pr-event/jamstec2022/
海底地質リスク評価研究会主催講演会
「地域における再エネ導入と地域共生のあり方」
9月28日(水)10:00-11:30(予定)
講師:東邦大学理学部生命圏環境科学科 竹内彩乃先生
テーマ:地域における再エネ導入と地域共生のあり方
場所:基礎地盤コンサルタンツ本社会議室(東京都江東区亀戸)or オンライン
参加費無料
申込先: https://forms.gle/Z3Ye4BND6ZmmR6m46
https://www.kisojiban.com/sssgr/
地層処分技術に関する研究開発報告会
−第3期中長期目標期間の成果取りまとめ(CoolRepR4)について−
9月30日(金)13:30-16:45
形式:オンライン配信(YouTubeライブ)
申込方法:Web(Googleフォーム)またはEメール
https://www.jaea.go.jp/04/tisou/houkokukai/pdf/houkokukai_r04_gaiyou.pdf
第31回 地質汚染調査浄化技術研修会(現地実習)
10月14日(金)-16日(日)
主催:NPO法人 日本地質汚染審査機構
会場:日本地質汚染審査機構関東ベースン実習センター(千葉県香取市)
会費:主催NPO法人会員50,000円・非会員 60,000円
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
2022年度 第2回地質調査研修(※定員に達したため,キャンセル待ち)
10月24日(月)-28日(金)
主催:産総研コンソーシアム「地質人材育成コンソーシアム」
場所:島根県出雲市長尾鼻周辺(小伊津海岸)
定員:6名(定員になり次第締切),CPD:42単位
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2022-2.html
第5回水循環シンポジウム(水郷の暮らしと水循環シンポジウム)
主催:NPO法人日本地質汚染審査機構
10月22日(土)
(午前)上戸不動の井(茨城県潮来市)等の見学会
(午後)シンポジウム:基調講演:宮崎 淳氏(創価大学法学部教授)
「健全な水循環の維持と地下水マネジメントー流れる水は誰のものか?ー」
他発表,パネルディスカッション
会場:潮来ホテル
http://www.npo-geopol.or.jp/water-sympo.htm
第61回温泉保護・管理研修会
10月25日(火)-26日(水)
場所:北とぴあ つつじホール(東京都北区王子)
主催:公益財団法人中央温泉研究所
http://www.onken.or.jp/seminar.html
(後)科学教育研究協議会第68回全国研究大会(岡山大会)
8月10日-12日
→中止となりました.WEB岡山研究会開催(10/30開催)
詳しくは, https://kakyokyo.org/
国際ゴンドワナ研究連合(IAGR)2022年総会及び
第19回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム(→※11月に延期されました)
11月4日-6日(シンポジウム)
11月7日(峨眉山巨大火山区野外巡検)
場所:中国四川省成都工科大学
※COVID-19感染問題等で国内外移動制限等がある時はオンライン会も併設する
参加申込,問い合わせ,フォースサーキュラーはこちら
http://www.geosociety.jp/outline/content0222.html#2020-11
(後)第22回こどものためのジオ・カーニバル
11月5日(土)-6日(日)
場所:大阪市立自然史博物館(ネイチャーホール)
http://www.geoca.org
(協)第38回ゼオライト研究発表会
12月1日(木)-2日(金)
場所:あわぎんホール(徳島県郷土文化会館)
講演申込締切:9月9日(金)
https://jza-online.org/
地質学史懇話会(オンラインとハイブリッド)
12月17日(土)13:30-16:30
場所:早稲田奉仕園(東京メトロ東西線早稲田駅下車徒歩5分)
山田俊弘・須貝俊彦「望月勝海日記通読プロジェクト」(仮)
今村遼平「中国地図測量史」
問い合わせ:矢島道子 pxi02070[atマーク]nifty.com
海と地球のシンポジウム2022
2023年3月16日(木)-17日(金)
開催方法:実会場(東京海洋大学品川キャンパス)を予定(詳細は後日)
発表課題募集:2022年9月5日(月)-10月10日(月)
参加登録料無料
https://www.jamstec.go.jp/j/pr-event/ocean-and-earth2022/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0222.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・2023-2024年開催藤原セミナー募集(11/30)
・中谷医工計測技術振興財団次世代理系人材育成プログラム助成(10/1-11/20)
・山田科学振興財団2023年度海外研究援助(10/31)
・2023年日本アイソトープ協会奨励賞(10/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.565 2023年度一般社団法人日本地質学会各賞候補者募集
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.565 2022/10/4┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2023年度一般社団法人日本地質学会各賞候補者募集について
【2】[2022早稲田大会]講演要旨・e-posterの閲覧について
【3】第15回日本地学オリンピックの参加申込受付中
【4】その他のお知らせ
【5】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2023年度一般社団法人日本地質学会各賞候補者募集について
──────────────────────────────────
日本地質学会では今年も運営規則第16条および各賞選考規則にしたがい,賞の候補者を
募集いたします.各賞説明・応募要項をご参照の上,各賞選考委員会(学会事務局)あてに,
期日厳守にてご応募下さい.個人(正会員または名誉会員)からの推薦も可能です.たくさん
のご応募をお待ちしております.
******************************************
応募締切:2022年12 月1 日(木)必着
******************************************
各賞の推薦あるいは審査をするにあたって,各賞選考規則等の規則に書かれた説明だけ
ではそれぞれの賞がどういった趣旨のものなのか,どのような方を推薦すればよいのか,
あるいはどのような観点で審査すればよいのかが分かりづらい,との意見をいただきました.
各賞について噛み砕いた内容の説明文を作成しました.各賞候補者応募の際にはご参照
ください.(表彰制度検討WG)
各賞の説明,規則類等詳細はこちら(要会員ログイン)
http://sub.geosociety.jp/members/content0098.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2022早稲田大会]講演要旨・e-posterの閲覧について
──────────────────────────────────
大会講演要旨・e-posterは,10/11まで大会参加者のみ閲覧可能です
(要参加者ログイン).講演要旨は10/12以降無料公開を予定しています.
e-posterの公開はありません.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】第15回日本地学オリンピックの参加申込受付中
──────────────────────────────────
募集期間:9月1日(木)-11月15日(火)
(一次予選)2022年12月18日(日) 14:00-15:00 択一式オンライン試験
参加資格:小中高校生 参加費:無料
※不正防止のためにカメラ付端末(スマホ可ただしPC利用推奨)が必要
(二次予選)2023年1月22日(日) 午後 マークシート式筆記試験
会場:全国指定14会場
(本選)2023年3月12日(日) 午後 -14日(火) 午前 (茨城県つくば市)
詳しくは,https://jeso.jp/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)神奈川県立生命の星博物館特別展「みどころ沢山!かながわの大地」
(7/16-11/6)
https://nh.kanagawa-museum.jp/www/contents/1651126447345/index.html
---------------------------------
第31回 地質汚染調査浄化技術研修会(現地実習)
10月14日(金)(※日程が1日だけに変更になりました)
主催:NPO法人日本地質汚染審査機構
会場:日本地質汚染審査機構関東ベースン実習センター(千葉県香取市)
会費:主催NPO法人会員10,000円・非会員20,000円
(※日程変更に伴い参加費も変更されています)
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
第5回水循環シンポジウム(水郷の暮らしと水循環シンポジウム)
主催:NPO法人日本地質汚染審査機構
10月22日(土)
(午前)上戸不動の井(茨城県潮来市)等の見学会
(午後)シンポジウム:基調講演:宮崎 淳氏(創価大学法学部教授)
「健全な水循環の維持と地下水マネジメントー流れる水は誰のものか?ー」
他発表,パネルディスカッション
会場:潮来ホテル
http://www.npo-geopol.or.jp/water-sympo.htm
ノーベル・プライズ・ダイアログ東京2022
10月23日(日)10:00-17:00(予定)
場所:パシフィコ横浜会議センターメインホール(対面方式)
参加費無料
※ただし、一部の講演者はオンライン参加になります.
https://www.nobelprize.org/water-matters-tokyo-2022/ja
(後)科学教育研究協議会第68回全国研究大会(岡山大会)
8月10日-12日
→中止となりました.WEB岡山研究会開催(10/30開催)
詳しくは,https://kakyokyo.org/
国際ゴンドワナ研究連合(IAGR)2022年総会及び
第19回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム(→※11月に延期されました)
11月4日-6日(シンポジウム)
11月7日(峨眉山巨大火山区野外巡検)
場所:中国四川省成都工科大学
※COVID-19感染問題等で国内外移動制限等がある時はオンライン会も併設する
参加申込,問い合わせ,フォースサーキュラーはこちら
http://www.geosociety.jp/outline/content0222.html#2020-11
(協)石油技術協会令和4年度秋季講演会(ハイブリッド)
11月1日(火)13:00-18:05
場所:東京大学小柴ホール(東京都文京区)
テーマ:エネルギー安定供給とカーボンニュートラル推進の両立を目指す社会に向けて
〜石油開発業界の持続的な役割〜
https://service.gakkai.ne.jp/society-member/auth/apply/JAPT
2020年度東京地学協会メダル 受賞記念講演会
対談:荒牧重雄・藤井敏嗣「噴火と火山防災の60余年」
11月12日(土)11:00-12:45
場所:アルカディア市ヶ谷(私学会館)6階「阿蘇」
申込期限:10月31日(月)(参加費無料,非会員の方も歓迎)
http://www.geog.or.jp/lecture/lecturescheduled/452-2020medal.html
(後)第22回こどものためのジオ・カーニバル
11月5日(土)-6日(日)
場所:大阪市立自然史博物館(ネイチャーホール)
http://www.geoca.org
(協)第38回ゼオライト研究発表会
12月1日(木)-2日(金)
場所:あわぎんホール(徳島県郷土文化会館)
講演申込締切:9月9日(金)
https://jza-online.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0222.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・JAMSTEC超先鋭研究開発部門高知コア研究所物質科学研究G:研究員公募(11/7)
・山形県職員選考試験山形県立博物館学芸員(地学)(11/4)
・土佐清水ジオパーク学術専門員募集(11/30)
・伊豆大島ジオパーク専門員募集(随時受付)
・日本科学未来館「研究エリア」入居プロジェクト公募(11/18)
・第2回羽ばたく女性研究者賞募集(12/20)
・「世界のトップ研究者ネットワーク参画のための国際研究協力プログラム」公募(11/30)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
平安時代の「日本三代実録」の地震・津波・噴火記録:地震西進系列の白眉
平安時代の「日本三代実録」の地震・津波・噴火記録:地震西進系列の白眉
正会員 石渡 明
図1.「日本三代実録」から読み取った毎年の地震数の変化.本文で述べた大地震の発生年を矢印で示す.(クリックすると大きな画像をご覧いただけます)
日本地震周期表(石渡,2019)は最近約360年間の日本の被害地震の時空分布をまとめ,大地震(≧M7.5)が東北日本から関東甲信越・西南日本を経て琉球・台湾へと110〜180年かけて西進すること,その地震系列が約120年周期で繰り返すことを示した.そして,南海トラフ地震の年号により,各西進系列を宝永,安政,昭和,最新と名づけた.例えば,1677延宝三陸・房総沖−1703元禄関東−07宝永南海トラフが宝永系列を代表する地震であり,1793寛政仙台沖−1847弘化長野善光寺−54安政南海トラフが安政系列を代表し,1896明治三陸−1923大正関東−44・46昭和南海トラフが昭和系列を代表する.
東北地方太平洋沖地震(2011年3月11日)は最新系列前半の巨大地震であり,この系列の南海トラフ地震は未発生だが,上の3例では東北の巨大地震の30, 61, 48年後に発生した.この系列の関東地震も未発生だが,2015小笠原西方沖M8.1深発地震は注目される.
平安時代前期にも869貞観(じょうがん)三陸−878元慶(がんぎょう)関東−887仁和(にんな)南海トラフの地震系列が存在し,この系列では東北の巨大地震の18年後に南海トラフ地震が発生した.そして,これらを含む30年間(858-887)の歴史は「日本三代実録」(日本書紀以後の六国史の最後)に日記形式の漢文(天皇の詔勅(しょうちょく)は漢字と万葉仮名(まんようがな))で記述されていて,地震系列の白眉(はくび)と言える.小論では日本三代実録を地震・津波・火山活動及び災害対応の観点から紹介する.なお,684,1096・99,1361,1498,1605年の南海トラフ地震前後の地震系列は不明瞭である※1.
日本三代実録(黒板ほか, 1974; 武田・佐藤, 2009)の概略を紹介する.宇多天皇の寛平(かんぴょう)4(892)年に勅撰の詔が下り,源(みなもとの)能有(よしあり)・藤原時平(ときひら)・菅原道真(みちざね)※2・大蔵善行(よしゆき)・三統(みむねの)理平(まさひら)の5人が執筆・編集に当たったが,途中で能有が死去,道真が左遷(901年,時平の讒言による,903年任地大宰府で死去),理平の転任により,延喜元(901)年に醍醐(だいご)天皇に提出された完成版に名を連ねるのは時平・善行の二人である(善行の貢献が最大とされるが,全50巻の各巻冒頭には「藤原時平等撰」とある).三代というのは第56代清和(せいわ)天皇(850-880, 在位858(天安2)-876),第57代陽成(ようぜい)天皇(868-949, 在位877-884),第58代光孝(こうこう)天皇(830-887, 在位885-887)の御代で,年号は貞観(じょうがん)(859-876),元慶(がんぎょう)(877-884),仁和(にんな)(885-888)である.清和天皇は元服前に幼くして即位した史上初の天皇であり,「清和源氏」の始祖としても有名である.陽成天皇は清和天皇の第一皇子で,清和天皇と同じ年齢で即位した.光孝天皇は第54代仁明(にんみょう)天皇の第三皇子であり,皇統がやや離れていて,老齢で即位した.この三代は摂関政治の始まりとされる.
藤原定家の小倉百人一首には陽成天皇(退位後)と光孝天皇(即位前)の歌が収められている.「つくばねの峰より落つるみなの川こひぞつもりて淵となりぬる」(陽成院),「君がため春の野に出(いで)て若菜つむわが衣手(ころもで)に雪はふりつゝ」(光孝天皇),はこの2人の対照的な性格と人生を表している.陽成天皇は父の清和天皇の譲位により9歳で即位したが,乱暴な振る舞いが多く,母の兄で摂政の藤原基経と対立し,7年で自ら病気を理由に譲位した.しかし,その後65年生きて81歳で亡くなった.この歌は恋歌とされているが,それにしては非常に直線的で暗く,もしかしたら「こひ」に「己非」(仮名のこ,コは己の草体,略体)が掛けてあり,そうであれば転落の人生の述懐にも読める.一方,光孝天皇の歌は明るく,善意と余裕が表れている.藤原基経の推挙により55歳で即位した.血縁関係ではなく,才識・人品を評価しての擁立で,基経の公正な態度に世人は感服したが,その3年後,仁和の南海トラフ地震で被災し,更にその20日後に台風の被害を受けて発病し,地震の26日後に58歳で崩じられた.当時は天災も為政者の責任とされ,被災と心労による,今で言う災害関連死だと思う.日本三代実録は清和天皇即位の日に始まり光孝天皇崩御の日で終わる.
日本三代実録に記録された30年間の地震数の変化を図1に示す.これは京都で感じられた地震を数えたもので,伝聞による遠地地震は数えない.最も記録が多かったのは元慶4(881)年の59回だが,その内訳は12月6日の京都地震と年内25日間の余震で53回に達する.次が南海トラフ地震の仁和3(887)年で,32回に達するが,この年は7月30日の同地震の約1カ月後に記録が終了したので,実は同年内の地震数はこの数倍だった可能性がある.つまり,京都の直下型地震の余震の地震数が最も多かったが,南海トラフ地震の余震もそれと同等かそれ以上だったと考えられる.
気象庁のデータによる2004〜2014年の10年間の京都の有感地震回数は244回で,年平均24回だから,日本三代実録30年間の年平均11回よりも現在の方が2倍以上多い.ただし,当時は震度1の地震は感じない,記録しないことも多かったと思うので,当時と今とで京都の地震数は「大差ない」と見るのが正解だろう.また,南海トラフ地震の前に地震が増加する事実もなく,むしろ元慶6(882)年から仁和2(886)年までの5年間は地震が少なかった(図1,年平均4回).以下,この30年間の大地震と災害対応を古い順に見よう.
貞観5年6月17日(863年7月10日)の越中・越後地震(M≧7:宇佐美,1996)は「地大いに震(ふる)いき.陵谷(りょうこく)処(ところ)を易(か)え(地形が大きく変化し),水泉湧(わ)き出(い)で,民の廬舎(ろしゃ)を壊(こぼ)ち,圧死する者衆(おお)かりき.此より後,毎日常に震いき」と記述されている.柳澤(2017)は清和天皇が元服前だったため,この地震に対する朝廷の具体的な対応が史料に見えないとしているが,8月15日に越中国正(じょう)六位上(ろくいのじょう)の鵜坂(うさかの)姉比竎(あねひめの)神,鵜坂妻比竎(つまひめの)神(富山市婦中町),杉田神に従(しょう)五位下(ごいのげ)を授けたという記事があり,この地震に関連した叙位かもしれない.この年は閏6月があり,叙位は地震の3カ月後である.
貞観10年7月8日(868年8月3日)の播磨・山城地震(M≧7.0:理科年表,以下同)については,15日に播磨の国司から,諸郡の官庁や寺院の堂塔が「皆尽(ことごと)く頽(くず)れ倒れき」という報告があった.京都では「家屋や垣が所々頽破した」程度だった.その後摂津でしばらく余震が続いたので,閏12月10日に天皇は使者を摂津の広田・生田神社に遣(つか)わして,「地震の後に小震が続くので占いをしたところ,こちらの神様がお怒りとのことなので,広田神は従一位,生田神は従三位に昇格させるから,どうか怒りを鎮めて天下平安にしていただきたい」という意味の告文を奉った.広田神はもと正三位,生田神は従四位下だった(12月16日条)ので大昇格である.また,同日,山城の櫟(いちい)谷(たにの)神(かみ)も従五位下から正五位下に昇格させ,閏12月21日,播磨国正六位上射(い)目埼(めきの)神にも従五位下を授けた.これらの叙位は地震の半年後である.宇佐美(1996)と理科年表は山崎断層の活動によるものか?とする.
貞観11年5月26日(869年7月13日),陸奥(むつ)国大地震(Mw8.4)が発生した.2011年の地震・津波と同様の大きな被害が生じたが,その記載文は有名なのでここでは省く(柳澤, 2017参照).清和天皇は9月3日に紀(きの)春枝(はるえ)を検陸奥(むつ)国地震使に任命し,判官(じょう)一人,主典(さかん)一人を付けた.30年間に地震災害は何回もあったが,地震使を派遣したのはこの時だけである.同年10月13日の詔で清和天皇は,「聞く如(なら)く,陸奥国境に地震尤(もっと)も甚(はなは)だしく,或いは海水暴(にわか)に溢(あふ)れて患(わずら)いと為り,あるいは城宇頻(しき)りに圧(つぶ)れて殃(わざわい)を致すと.百姓何の辜(つみ)ありてか,この禍毒に罹(あ)う.憮然として媿(は)じ恐れ,責め深く予に在り.今使者を遣(や)りて,就(ゆ)きて恩喣(おんく)を布(し)かしむ.使,国司と與(とも)に民夷を論ぜず勤めて自ら臨撫し,既に死にし者は尽(ことごと)く収殯(しゅうひん)(埋葬)を加え,その存(い)ける者には詳(つまびらか)に賑恤(しんじゅつ)(援助)を崇(かさ)ねよ.其の害を被(こうむ)ること太甚(はなは)だしき者は,租調(税)を輸(いた)さしむるなかれ.鰥寡(かんか)孤独の,窮して自ら立つ能(あた)わざる者は,在所に斟量(しんりょう)して厚く支え済(たす)くべし.務めて矜恤(きんじゅつ)の旨を尽くし,朕(ちん)親(みずか)ら覿(み)るが若(ごと)くならしめよ」とご自身の責任と地震使の使命を明らかにした.
元慶2年9月29日(878年11月1日)夜の関東地震(M7.4:当時の関東は鈴鹿・不破の関以東)は相模・武蔵で最も被害が大きく,「公私の舎屋一として全き者無く,或は地窪(くぼみ)陥(おちいり)て往還通ぜず,百姓の圧死は勝(あげ)て記すべからず」という状態で,5〜6日間震動が続いた.元慶5年10月3日,相模国の使者が朝廷を訪れ,国分寺の金色の薬師丈六(約5m)像1体,脇侍(きょうじ)の菩薩像2体が「元慶3年」9月29日の地震で破壊されその直後の火事で焼失したので,改めて造立して頂きたい,また太政官の貞観15年7月28日の符により漢河寺を国分尼寺とされたが(この記事は日本三代実録に無い),地震により漢河寺が大破したので,国分尼寺を元の寺に戻して頂きたいと要請したので,詔をもってどちらも許した.この記事の「元慶3年」は2年が正しいとする説が大勢だが,3年が正しい可能性もある.宇佐美(1996)や理科年表は伊勢原断層の活動によるものか?とする.なお,相模国分寺跡は海老名駅近くに現存する.柳澤(2017)は,陽成天皇が元服前のため,この地震に対する朝廷の対応が史料に見えないとする.以下の元慶4年の地震についても同様だろう.
元慶4年10月14日(880年11月23日)の出雲地震(M7.0)は京都でも「地大いに震いき」と記録されており,27日に出雲国の使者が朝廷に次のように報告した.「今月十四日,地大震動し,境内の神社仏寺官舎,及び百姓の居廬(きょろ),或いは顚倒(てんとう)し,或いは傾倚(けいい)し,損傷せし者衆(おお)し.其の後二十二日まで,昼は一二度,夜は三四度,微々震動して,猶(なお)未(いま)だ休止せず」.黒板他(1974)では元慶3年10月14日と27日にも全く同じ記事があり,上の関東地震の年数の誤りもあるので,年月日は鵜呑みにせずよく調査する必要がある.
元慶4年12月6日(881年1月13日)の京都地震(M6.4)は子の刻(真夜中)に発生し,朝までに16回余震があって,宮中や市内の建物が多く損壊した.12月4日に太上(清和)天皇が崩じられたので(この日も5〜6回地震があり,これらは前震かもしれない),大赦の詔を発出したが,これは地震の後に予定通り行われ,7日に囚人200人を解放し各人に30文の銭を賜った.この地震について神社への告文はなかったようだが,陰陽寮(おんみょうりょう)は「地震の徴は,兵賊飢疫を慎むべし」と奏言した.
仁和3年7月30日(887年8月26日)の南海トラフ地震(M8.0〜8.5)は午後4時頃発生した.1時間以上経過しても揺れが止まなかった.光孝天皇は仁寿殿を出て紫宸殿の南庭にお出ましになり,大蔵省に命じて七丈(21m)のテント2つを建てて御在所とした.「諸司の倉屋及び東西京の廬舎,往々にして転覆し,圧殺せらるる者衆(おお)く,或は失神して頓死する者有りき」という状態で,午後10時頃にも3回の余震があり,夜中に雷のような音が2回,東と西に聞こえた.「五畿七道諸国も同日に大震ありて官舎多く損じ,海潮陸に漲(みなぎ)りて溺死者勝(あ)げて計るべからず.そのうち摂津国尤(もっと)も甚(はなはだ)しかりき」.以後毎日余震が数回あり,8月4日は5回あった.この日,達智門上に煙か虹のような気があり,人は羽蟻だと言った.過去に例がないことだったので,陰陽寮が占ったところ,「大風洪水失火等の災有るべし」と出た.翌5日も昼に5回,夜にも大地震があり,京都の人々はみな家から出て路上で過ごした.8日にも羽蟻が出た.地震以後は,読経のために宮中に呼ばれた僧侶数人が夜中に宿舎の外の騒音を聞いて出てみたら何もなかった等,宮中や京都の人々の間に「不根の妖語」が多々語られた.20日の明け方から夕方まで大風雨があり,「樹を抜き屋を発(あば)き」,転倒する家に圧殺される者も多かった.鴨川や葛野川(桂川)の水が「洪波汎溢」して人馬が通行できなかった.22日,太政大臣藤原基経(実質的には関白)ら高官14人が連名で表を奉って光孝天皇に皇太子を立てることを願った.光孝天皇は子息を全て臣籍に降下させ朝(あ)臣(そん)の称を賜っていた.理由は「斯(これ)誠(まこと)に国用(国費)を節し民労を息(やす)むる計(はかりごと)なり」だった.24日,まだ余震が続く中,天皇は第7皇子21歳の定省(さだみ)親王(後の宇多天皇)を皇太子とすることを表明し,26日にその旨の策(辞令)が発出された.この日天皇は「聖体乖予」となり,午前10時頃仁寿殿において崩じられた.「時に春秋(おほむとし)五十八なりき」の一文で日本三代実録全50巻が終わっている.なお,この地震については,仁和4(888)年5月28日に宇多天皇の詔が出たが,これは「阿衡(あこう)の紛議」の最中に発出された(柳澤, 2017).また,父の死の原因となった南海トラフ地震の記述を簡素にしたかった宇多天皇の意向に沿い,日本三代実録全体として,大災害は一々地方からの報告を載せず,発生日に事実を略記したと考えられる(柳澤, 2017).
日本三代実録の30年間に富士山も噴火した.貞観6(864)年5月25日に駿河国司が,「富士郡の正三位浅間大神の大山(富士山)に火あり.其の勢い甚だ熾(さかん)にして,山を焼くこと方一二里,光炎の高さ二十丈許(ばかり),雷有り,地震三度,十余日を歴(へ)れども火猶滅(なおき)えず,巌(いわ)を焦がし嶺を崩し,沙石雨ふる如く,煙雲欝蒸して人近づくを得ず.大山の北西に本栖水海(もとすのうみ)あり.焼けし巌(がん)石(せき),流れて海の中に埋もれ遠さ三十里許(ばかり),広さ三四里許,高さ二三丈許にして,火焔遂に甲斐国の堺に属(つ)く」と報告した.同年8月4日の記事では,亀甲で占ったところ,富士山が噴火したのは甲斐国浅間明神の禰宜(ねぎ)たちが斎敬を勤めなかったためだとして,神に御幣を奉って解謝すべき旨を甲斐国司に下知した.貞観7年12月9日の記事では,甲斐国に神社を造り官社として禰宜を置くことを決めたが,「異火の変,今に止まず,使者を遣りて検察せしむるに,剗海(せのうみ)を埋めること千町許(約10km2)」と記す.この時に今の富士五湖ができたとされる.貞観6年は仁和3年の南海トラフ地震の23年前に当たる.江戸時代の宝永の南海トラフ地震では,約2ヶ月後に富士山が爆発的な大噴火をしたが,安政と昭和の南海トラフ地震の際は噴火しなかった.
この30年間は他の火山の噴火記録も多い.まず,貞観9(867)年1月20日豊後の鶴見岳の噴火(2月26日記事),5月11日夜阿蘇山小噴火(8月6日記事),10月3日夜に阿蘇山神霊池の水が湧き上がった異変(12月26日記事)が相次いだ.貞観13(871)年4月8日出羽国の鳥海山が噴火,溶岩流が海に達し,泥流が広がった(5月16日記事).貞観16(874)年3月4日には開聞岳が噴火(7月2日・29日記事),仁和元(885)年7月12日と8月11-12日にも噴火した(10月9日記事).貞観2年3月20日と同8年4月7日に開聞神の叙位記事があるので,この頃も噴火した可能性がある.安房では仁和2(886)年5月24日の夕刻,南海に黒雲が湧いて電光が現れ,雷鳴地震して夜通し止まなかった.26日に火山灰が降り,山野田園を覆った.厚さは最大2〜3寸.農作物は尽(ことごと)く枯れ,灰がついた草を食べた牛馬が多く死んだ(7月4日記事).これは新島(にいじま)の噴火とされている.貞観時代,赤城(あかぎ)神,二荒(ふたら)神,白山比女(しらやまひめ)神にも叙位記事があるので,赤城山,日光白根山,白山(はくさん)も噴火した可能性がある.そして,仁和3(887)年7月30日の南海トラフ地震とほぼ同時に新潟焼山が噴火し,8月5日までの間に火砕サージ,火砕流,溶岩流を噴出した(早津, 1992).これは同火山史上最大の噴火であるが,日本三代実録にこの記事はない.このように,この30年間は東北,関東,九州の火山活動が盛んだった.これに比べると平成〜令和の日本本土の火山活動は低調である(琉球弧や伊豆・小笠原弧ではやや活発).
終わりに,地震系列の観点からは,東北の大地震の発生後,関東地震・南海トラフ地震の発生前に位置する現時点(2022年)は,日本三代実録の期間の中間点付近(貞観16年頃)に対応する.約1200年前の30年間にわたる自然災害とそれへの対応についてのこれほど網羅的かつ詳細な記録は世界にも例がないと思う.我々はこの貴重な歴史遺産を現代に活かし,自然災害から人の命を守る現実的で効果的な対策を立て,着実に実行する必要がある.
追 記
※1:2022年10月22日の日本経済新聞東京夕刊によると,1454年に東北地方太平洋岸を襲った「享徳の津波」が実際に発生した可能性が高くなったとして,理科年表の2023年版から新たに掲載されるとのことである.そうすると,15世紀にも1454年享徳東北地震・津波−1495年明応鎌倉地震・津波−1498年明応南海トラフ地震・津波という地震西進系列が存在し,東北地震から南海トラフ地震まで44年だったことになる.これにより,歴史上知られている9回の南海トラフ地震のうち過半数の5回で地震西進系列が見られることになり,東北地震から南海地震までの平均間隔は40年(18〜61年)となる.また,1605年慶長南海・房総津波については,その後で1611年慶長三陸地震・津波が発生しており,大地震が東進したように見えるが,両地震の間隔は6年と歴史上最短であり,これを両地震が短期間で相次ぎ発生した西進系列の特殊な場合とみなせば,9回のうち6回となる.(2022.10.25追記)
※2 菅原道真は貞観12(870)年に26歳で方略試(官吏登用の最高国家試験)に合格したが,その時の試験問題の1つが「地震について論ぜよ」だった.彼は対策(たいしゃく)(答案)で中国の古典や仏典に表れる地震の例を縷々述べたが,日本の地震や彼自らの地震体験については全く触れず,出題者の都(みやこの)良香(よしか)による講評は,「論理が通っていない」,「因果関係の分析が不十分」などと手厳しく,評価は合格ギリギリの「中の上」だった(大崎順彦1983「地震と建築」岩波新書240,p. 13-20).この年は貞観11年の陸奥国大地震の翌年であるから,この出題はタイムリーであり,出題者としては前年の地震や津波に関する清和天皇の詔(本文参照)を引用するなどして,日本の現実の地震についても論述して欲しかったのだろう(もしかしたら,出題者がこの詔の起草に関与したかもしれない).「受験の神様」は,漢文は得意だったが,時事問題は苦手だったようである.(2023.1.16追記)
文 献
早津賢二(1992)燃える焼山 知られざる火山−その現在・過去・未来.新潟日報, 171p.
石渡明(2019)日本地震周期表:大地震の西進傾向と将来予測.日本地質学会第126年学術大会(山口)ポスター発表T6-P-2.https://www.nra.go.jp/data/000288489.pdf
黒板勝美・国史大系編修会(1974)新訂増補国史大系普及版 日本三代実録 前篇1-326p.・後篇327-642p.吉川弘文館.(漢文)
武田祐吉・佐藤謙三訳(2009)読み下し日本三代実録 上巻716p.・下巻468p.戎光祥出版.
宇佐美龍夫(1996)新編日本被害地震総覧.493p. 東大出版会.
柳澤和明(2017)『日本三代実録』にみえる五大災害記事の特異性.歴史地震, 32, 19-38.
※本原稿の短縮verが,日本地質学会News,Vol.25,No.10(2022年10月号)に掲載されています.
【geo-Flash】No.566 JpGU2023セッション提案募集(11/2締切)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.566 2022/10/18┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2023年度一般社団法人日本地質学会各賞候補者募集中
【2】[2022早稲田大会]講演要旨無料公開
【3】JpGU2023セッション提案募集(11/2締切)
【4】第15回日本地学オリンピックの参加申込受付中
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2023年度一般社団法人日本地質学会各賞候補者募集中
──────────────────────────────────
各賞説明・応募要項をご参照の上,各賞選考委員会(学会事務局)あてに,
期日厳守にてご応募下さい.個人(正会員または名誉会員)からの推薦も
可能です.たくさんのご応募をお待ちしております.
******************************************
応募締切:2022年12 月1 日(木)必着
******************************************
各賞について噛み砕いた内容の説明文を作成しました.
各賞候補者応募の際にはご参照ください.
各賞の説明,規則類等詳細はこちら(要会員ログイン)
http://sub.geosociety.jp/members/content0098.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2022早稲田大会]講演要旨無料公開
──────────────────────────────────
早稲田大会講演要旨は,10/12以降無料公開となっています.ログイン無し
で,どなたでも閲覧できます.(e-posterの公開はありません)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp129/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】JpGU2023セッション提案募集(11/2締切)
─────────────────────────────────────────────────────
JpGU2023でセッション提案を予定している方で,地質学会共催を希望される
場合は,併行して下記の地質学会のJpGUプログラム委員にご連絡いただきます
ようお願い致します。すでに提案済みの場合も,これからでも結構ですので,
プログラム委員に連絡をお願い致します.
日本地質学会JpGUプログラム委員:
上澤真平(火山部会選出行事委員)uesawa[at]criepi.denken.or.jp
松崎賢史(海洋地質部会選出行事委員) kmatsuzaki[at]g.ecc.u-tokyo.ac.jp
(注)[at]を@マークにしてください
[ご連絡いただく内容]
タイトル/スコープ/代表コンビーナ(1名)/共同コンビーナ(3名まで)
[セッション提案締切]2022年11月2日(水)17:00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第15回日本地学オリンピックの参加申込受付中
──────────────────────────────────
募集期間:9月1日(木)-11月15日(火)
(一次予選)2022年12月18日(日) 14:00-15:00 択一式オンライン試験
参加資格:小中高校生 参加費:無料
※不正防止のためにカメラ付端末(スマホ可ただしPC利用推奨)が必要
(二次予選)2023年1月22日(日) 午後 マークシート式筆記試験
会場:全国指定14会場
(本選)2023年3月12日(日) 午後 -14日(火) 午前 (茨城県つくば市)
詳しくは,https://jeso.jp/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
地震本部ニュース2022秋号「石川県能登地方の地震活動について
:地震活動の評価をまとめ,関連する情報を発信しました」ほか
https://www.jishin.go.jp/herpnews/
(後)神奈川県立生命の星博物館特別展「みどころ沢山!かながわの大地」
(7/16-11/6)
https://nh.kanagawa-museum.jp/www/contents/1651126447345/index.html
印刷博物館企画展示「地図と印刷」(9/17-12/11)日本の近世を中心に
スポットをあて、地図・地誌づくりにおける印刷と人々とのかかわりを
探ります.
https://www.printing-museum.org/collection/exhibition/t20220917.php
---------------------------------
第14回防災学術連携シンポジウム
自然災害を取り巻く環境の変化:防災科学の果たす役割
10月22 日(土)16:30-18:00*要参加申込
https://janet-dr.com/060_event/20221020_01.html
(後)科学教育研究協議会第68回全国研究大会(岡山大会)
10月30日(日)WEB研究会
https://kakyokyo.org/uphtml/WebOKAYAMA_FunFunSquare_NightSession.htm
(協)石油技術協会令和4年度秋季講演会(ハイブリッド)
11月1日(火)13:00-18:05
場所:東京大学小柴ホール(東京都文京区)
テーマ「エネルギー安定供給とカーボンニュートラル推進の両立を目指す
社会に向けて:石油開発業界の持続的な役割」
https://service.gakkai.ne.jp/society-member/auth/apply/JAPT
(後)第22回こどものためのジオ・カーニバル
11月5日(土)-6日(日)
場所:大阪市立自然史博物館(ネイチャーホール)
http://www.geoca.org
学術会議公開シンポジウム
「私たちの地球はどんな惑星か−科学を混ぜて地球を探る」
11月5日(土)10:30-12:00
場所:テレコムセンター1F大ステージ
参加無料,事前申込不要.
https://www.scj.go.jp/ja/event/2022/331-s-1105.html
国際シンポジウム2022「富士山地域DX:山岳観光と次世代通信」
主催:山梨県富士山科学研究所
11月20日(日)13:00-16:30(予定)
Zoomによるオンライン開催
事前申込制:11/10(木)まで
https://www.mfri.pref.yamanashi.jp/
(協)第38回ゼオライト研究発表会
12月1日(木)-2日(金)
場所:あわぎんホール(徳島県郷土文化会館)
https://jza-online.org/
学術会議公開シンポジウム(オンライン開催)
「地名標準化の現状と課題:地名データベースの構築と地名標準化機関の設置に向けて」
12月18日(日)13:00-17:00
参加無料,定員300名
https://www.scj.go.jp/ja/event/2022/331-s-1218.html
海と地球のシンポジウム2022
2023年3月16日(木)-17日(金)
開催方法:実会場(東京海洋大学品川キャンパス)を予定
発表課題締切:2022年10月21日(金)*延長しました
参加登録料無料
https://www.jamstec.go.jp/j/pr-event/ocean-and-earth2022/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0222.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻教授公募(11/30)
・ 第64回藤原賞受賞候補者推薦依頼(学会締切11/30)
・戦略的国際共同研究プログラム「Well Beingな高齢化のためのAI技術」
における日本-カナダ国際産学連携共同研究課題募集(23/4/3)
・山田科学振興財団2023年度研究援助候補推薦依頼(学会締切23/2/1)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.567 2022/11/1 学部学生・院生の方へ:「学生会員」申請を!!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.567 2022/11/1┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2023年度一般社団法人日本地質学会各賞候補者募集中
【2】学部学生・院生の方へ:「学生会員」申請をお願いします!
【3】韓国IGC2024へのサポートレター撤回について
【4】地質系若者のためのキャリアビジョン誌2022 原稿募集開始
【5】第14回惑星地球フォトコンテスト受付開始
【6】JpGU2023セッション提案募集(11/2締切)
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2023年度一般社団法人日本地質学会各賞候補者募集中
──────────────────────────────────
各賞説明・応募要項をご参照の上,各賞選考委員会(学会事務局)あてに,
期日厳守にてご応募下さい.個人(正会員または名誉会員)からの推薦も
可能です.たくさんのご応募をお待ちしております.
******************************************
応募締切:2022年12 月1 日(木)必着
******************************************
各賞について噛み砕いた内容の説明文を作成しました.
各賞候補者応募の際にはご参照ください.
各賞の説明,規則類等詳細はこちら(要会員ログイン)
http://sub.geosociety.jp/members/content0098.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】学部学生・院生の方へ:「学生会員」申請をお願いします!
──────────────────────────────────
2023年度からは新しい会員種別・会費での運用が始まります.
学部学生・院生は,本人の申請により「学生会員」としての会費が適用されます.
「学生会員」になるための申請は,所定のフォームからお手続きください.
(注)申請には,学生証の写し(画像)が必要です.
現時点で学部学生・院生の身分の方ならば,どなたでも申請可能です.
来年4月から就職が内定している方も今申請すれば,会費額が大変お得に
なります!忘れずにお申し込み下さい.
*************************
新制度「学生会員」の会費 (参考)正会員会費:12,000円
・単年度:5,000円(23年度分会費)
・2年パック:8,000円(23-24年度分会費)
・3年パック:9,000円(23-25年度分会費)
*************************
申請締切:2022年11月30日(水)
*************************
専用申込フォームはこちら
http://www.photo.geosociety.jp/gakusei.html
学生会員申請の詳細は,こちらから
http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】韓国IGC2024へのサポートレター撤回について
──────────────────────────────────
日本地質学会は,大韓地質学会からの要請に基づき,2024年に韓国釜山で
開催予定の万国地質学会議(IGC)2024をサポートする旨を2016年に大韓
地質学会宛にサポートレターを送付し表明していましたが,このたび諸問
題によりこのサポートレターを撤回するに至りました.サポートレターの
撤回については2022年9月16日付けでIGC2024の現地組織委員会(LOC)
に通知しております.
また本件に関し,会長より会員の皆様に重要なメッセージがあります.
会員ページをご覧いただけますようお願いいたします.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/science/content0150.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地質系若者のためのキャリアビジョン誌2022 原稿募集開始
──────────────────────────────────
全国48の大学と機関の学生・院生に向けて、専門職の魅力を伝える雑誌
「地質系若者のためのキャリアビジョン誌2022」を刊行します.
関係企業の魅力発信ツールに,また各大学ではキャリア教育の教材として
ご活用いただけます.ぜひ本冊子への協賛と原稿提供をご検討ください.
締切:2022年12月9日(金)
配布:2023年1月上旬
詳しくは,http://photo.geosociety.jp/career2.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第14回惑星地球フォトコンテスト受付開始
──────────────────────────────────
***応募締切:2023年1月30日(月)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募フォームからでも
メール添付でもご応募いただけます.会員の皆様の応募をお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】JpGU2023セッション提案募集(11/2締切)
──────────────────────────────────
JpGU2023でセッション提案を予定している方で,地質学会共催を希望される
場合は,併行して下記の地質学会のJpGUプログラム委員にご連絡いただきます
ようお願い致します。すでに提案済みの場合も,これからでも結構ですので,
プログラム委員に連絡をお願い致します.
日本地質学会JpGUプログラム委員:
上澤真平(火山部会選出行事委員)uesawa[at]criepi.denken.or.jp
松崎賢史(海洋地質部会選出行事委員) kmatsuzaki[at]g.ecc.u-tokyo.ac.jp
(注)[at]を@マークにしてください
[ご連絡いただく内容]
タイトル/スコープ/代表コンビーナ(1名)/共同コンビーナ(3名まで)
[セッション提案締切]2022年11月2日(水)17:00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)神奈川県立生命の星博物館特別展「みどころ沢山!かながわの大地」
(7/16-11/6)
https://nh.kanagawa-museum.jp/www/contents/1651126447345/index.html
---------------------------------
(後)第22回こどものためのジオ・カーニバル
11月5日(土)-6日(日)
場所:大阪市立自然史博物館(ネイチャーホール)
http://www.geoca.org
長久保赤水顕彰会創立30周年記念事業
第6回全国赤水ウオーク(2022年):赤水ゆかりの地を訪ねるウオーク
11月6日(日)集合:JR南中郷駅前8:45
申込方法:当日受付,参加無料
http://nagakubosekisui.org/archives/5103
令和4年国土技術研究会
11月10日(木)-11日(金)
会場:国土交通省 中央合同庁舎(千代田区霞ヶ関2丁目,オンラインでも配信)
参加無料・要事前申込(11/7締切)
https://www.mlit.go.jp/chosahokoku/giken/index.html
東京大学中東地域研究センター公開シンポジウム
「深掘り! オマーン・スルタン国」
11月13日(日)14:00-17:00
会場:東京大学駒場キャンパス(Zoomによるオンライン参加可能)
記念講演:宮下純夫(新潟大学名誉教授)「アラビア半島オマーンの自然と地質
そして人々」ほか
https://park.itc.u-tokyo.ac.jp/UTCMES/2022/09/22/public_symposia/
日本堆積学会20周年記念リレーセミナー(第1回)
11月24日(木)12:15-13:00
Zoomウェビナーオンライン開催(参加無料)
講演者:産業技術総合研究所 中嶋 健 氏
演題:海底自然堤防形態の定量的解析
https://sites.google.com/view/ssj20th/home
(後)第32回社会地質学シンポジウム
11月25 日(金)-26 日(土)
場所:日本大学文理学部オーバル・ホール,オンライン(Zoom)併用
特別講演:
「ポストコロナ時代の国際交流 -大学に今、何が求められているのか-」富田敬子(常磐大学・常磐短期大学学長)Youtubeでも同時配信
招待講演:
「環境地質学の対象としての有明海・八代海」秋元和實(元熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター准教授)
「呉羽山で学ぶ-ジオ・エコ・ヒトのつながり-」安江健一(富山大学学術研究部准教授)
https://www.jspmug.org/envgeo_sympo/32nd_sympo/
(協)第38回ゼオライト研究発表会
12月1日(木)-2日(金)
場所:あわぎんホール(徳島県郷土文化会館)
https://jza-online.org/
学術会議公開シンポジウム(オンライン開催)
地名標準化の現状と課題
:地名データベースの構築と地名標準化機関の設置に向けて
12月18日(日)13:00-17:00
参加無料,定員300名
https://www.scj.go.jp/ja/event/2022/331-s-1218.html
STAR-Eプロジェクト 第1回研究者・学生向けイベント
アイデアソン
「地震・測地などのデータに関する研究展開から社会応用までの幅広い活用方策」
12月27日(火)10:00-17:30
会場:TKP新橋カンファレンスセンター
参加費無料,定員50名
申込締切:12月13日(火)
https://star-e-project-221227.eventcloudmix.com/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0222.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
JAMSTEC
・海域地震火山部門地震津波予測研究開発C地震予測研究G研究員公募(12/19)
・超先鋭研究開発部門超先鋭研究開発プログラム主任研究員公募(12/26)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.568(臨時)秋山 雅彦 名誉会員 ご逝去
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.568 2022/11/9┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 秋山 雅彦 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
秋山 雅彦 名誉会員(元日本地質学会長,元信州大学教授,元札幌学院大学教授)
が、令和4年11月2日(水)に急逝されました(88歳)。これまでの故人の
功績を讃えるとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
なお、ご葬儀はすでにご家族によりしめやかに執り行われ,御香典,御供花,
御供物の儀はご辞退されるとのことです。
会長 岡田 誠
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.569 第6回ショートコース開催します
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.569 2022/11/15┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】第6回ショートコース:法地質学/付加体地質学
【2】2023年度以降の会費請求と主な変更点
【3】学部学生・院生の方へ:「学生会員」申請をお願いします!
【4】2023年度一般社団法人日本地質学会各賞候補者募集中
【5】地質系若者のためのキャリアビジョン誌2022 原稿募集中
【6】第14回惑星地球フォトコンテスト受付中
【7】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【8】(コラム)平安時代の「日本三代実録」の地震・津波・噴火記録
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】第6回ショートコース:法地質学/付加体地質学
──────────────────────────────────
2020年・2021年に計5回開催し,好評を博したショートコースを再開します.
第6回の前半は法地質学、後半は付加体地質学・沈み込み帯掘削に関する最新
の知見を学ぶ機会を提供します.
日程:2022年12月18日(日)
開催方法:zoomによるオンライン講義
受講料(各1日券):
地質学会会員:2,000円(地質学会賛助会員に所属する⽅は地質学会会員と同額),
会員:5,000円
申込締切:12月8日(木)
http://www.geosociety.jp/science/content0151.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2023年度以降の会費請求と主な変更点
──────────────────────────────────
運営規則(2022年6月一部改正.以下運営規則)により,2023年度からは新しい
会員種別,会費での運用が始まります.運営規則改正による2023年度以降の会費
請求と主な変更点についてご案内いたします.
(1)23年度の会費の自動引き落とし日は12月23日(金)です.
(2)23年度から,正会員は「65歳以上のシニア会員」と「65歳未満の一般会員」
とに細分され,24年度分会費より在会年数(会費納入年数)に応じて会費が減額と
なります.
(3)23年度から除籍対象となる会費滞納年数が『4年』から『3年』に変更となり
ます.
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0239.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】学部学生・院生の方へ:「学生会員」申請をお願いします!
──────────────────────────────────
現時点で学部学生・院生の身分の方ならば,どなたでも申請可能です.
来年4月から就職が内定している方も今申請すれば,会費額が大変お得に
なります!忘れずにお申し込み下さい.
*************************
新制度「学生会員」の会費 (参考)正会員会費:12,000円
・単年度:5,000円(23年度分会費)
・2年パック:8,000円(23-24年度分会費)
・3年パック:9,000円(23-25年度分会費)
*************************
申請締切:2022年11月30日(水)
*************************
学生会員申請の詳細は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2023年度一般社団法人日本地質学会各賞候補者募集中
──────────────────────────────────
各賞説明・応募要項をご参照の上,各賞選考委員会(学会事務局)あてに,
期日厳守にてご応募下さい.個人(正会員または名誉会員)からの推薦も
可能です.たくさんのご応募をお待ちしております.
******************************************
応募締切:2022年12 月1 日(木)必着
******************************************
各賞について噛み砕いた内容の説明文を作成しました.
各賞候補者応募の際にはご参照ください.
各賞の説明,規則類等詳細はこちら(要会員ログイン)
http://sub.geosociety.jp/members/content0098.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質系若者のためのキャリアビジョン誌2022 原稿募集中
──────────────────────────────────
全国48の大学と機関の学生・院生に向けて、専門職の魅力を伝える雑誌
「地質系若者のためのキャリアビジョン誌2022」を刊行します.
関係企業の魅力発信ツールに,また各大学ではキャリア教育の教材として
ご活用いただけます.ぜひ本冊子への協賛と原稿提供をご検討ください.
締切:2022年12月9日(金)
配布:2023年1月上旬
詳しくは, http://photo.geosociety.jp/career2.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】第14回惑星地球フォトコンテスト受付中
──────────────────────────────────
***応募締切:2023年1月30日(月)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募フォームからでも
メール添付でもご応募いただけます.会員の皆様の応募をお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・128巻:新しい論文等が公開されています.
(論説)紀伊半島東部の四万十付加体竜神コンプレックスに挟在する珪長質凝灰岩
のジルコンU-Pb及びフィッション・トラック年代:星 博幸ほか/(ノート)名古屋
港で採集された完新世炭酸塩コンクリーションの14C年代測定:南 雅代ほか/
(報告)A new specimen of Anthracokeryx naduongensis (Mammalia, Artiodactyla,
Anthracotheriidae) from the Eocene Na Duong Formation, northeastern Vietnam
Takehisa Tsubamotoほか
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/list/-char/ja
■ Island Arc
・新しい論文等が公開されています.
Editorial for the thematic issue, “Orogens, ophiolites, and oceans: A snapshot
of Earth's tectonic evolution”:Yasufumi Iryuほか
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】(コラム)平安時代の「日本三代実録」の地震・津波・噴火記録
──────────────────────────────────
「平安時代の「日本三代実録」の地震・津波・噴火記録:地震西進系列の白眉」
正会員 石渡 明
日本地震周期表(石渡,2019)は最近約360年間の日本の被害地震の時空
分布をまとめ,大地震(≧M7.5)が東北日本から関東甲信越・西南日本を経て
琉球・台湾へと110〜180年かけて西進すること,その地震系列が約120年
周期で繰り返すことを示した.そして,南海トラフ地震の年号により,各西進
系列を宝永,安政,昭和,最新と名づけた.例えば,1677延宝三陸・房総沖
−1703元禄関東−07宝永南海トラフが宝永系列を代表する地震であり,1793
寛政仙台沖−1847弘化長野善光寺−54安政南海トラフが安政系列を代表し,
1896明治三陸−1923大正関東−44・46昭和南海トラフが昭和系列を代表する.
続きはこちらから、、、 http://www.geosociety.jp/faq/content1052.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
・関東支部功労賞を募集します.
対象者:支部活動や地質学を通して広く社会貢献をされた関東支部内に在住の
個人・団体 ※社会貢献や活動の評価においては,必ずしも学問的な成果を問う
ものではありません.
公募期間:2022年12月19日-2023年1月21日
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html#2022koro
・関東支部オンライン講演会「県の石 茨城県」開催
日時:2023年1月22日(日)13:00-16:05
参加費無料(要事前申込)
申込期間:2022年12月19日(月)から2023年1月11日(水)まで
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html#2022ishi
[西日本支部]
・西日本支部令和4年度総会・第173回例会
2023年3月4日(土)例会・総会
会場:島根大学総合理工学部多目的ホールほか
(注)状況によってオンラインでの開催を検討
講演・参加申込締切:2月1日(水)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)第32回社会地質学シンポジウム
11月25 日(金)-26 日(土)
場所:日本大学文理学部オーバル・ホール,オンライン(Zoom)併用
特別講演:
「ポストコロナ時代の国際交流-大学に今、何が求められているのか-」富田敬子
招待講演:
「環境地質学の対象としての有明海・八代海」秋元和實
「呉羽山で学ぶ-ジオ・エコ・ヒトのつながり-」安江健一
https://www.jspmug.org/envgeo_sympo/32nd_sympo/
ミニシンポ「日本の山火事・野火研究:地質時代から現在まで」
11月26日(土) 13:30-16:00(予定)
場所:大阪公立大学杉本キャンパス 学術総合センター1F文化交流室
要参加申込(11/18まで)
※申込多数の場合には先着順
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/others-pdf/20221126sympo.pdf
大気海洋研究所共同利用研究集会
「フィリピン海プレート北端部テクトニクスの再検討」
11月28日(月)-29日(火)
対面とZoomのハイブリッド開催(要参加申込:11/25締切)
※追加発表も受付中(11/18締切)
https://www.aori.u-tokyo.ac.jp/aori_news/meeting/2022/20221128.html
(協)第38回ゼオライト研究発表会
12月1日(木)-2日(金)
場所:あわぎんホール(徳島県郷土文化会館)
https://jza-online.org/
第239回イブニングセミナー(オンライン)
12月1日(木)19:30-21:30
演題:福島原発事故に伴い発生した膨大な除去土壌の再生利用等の現状と課題
講師:油井三和先生(福島工業高等専門学校)
参加費:主催NPO会員及び学生の方(無料),非会員(1,000円)
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
第37回 地質調査総合センターシンポジウム
令和4年度地圏資源環境研究部門研究成果報告会
地圏資源環境研究部門の最新研究ー新たなチャレンジと展望ー
12月7日(水)13:30-17:20(予定)
会場:ステーションコンファレンス万世橋4階(東京都千代田区神田須田町)
参加費無料・事前登録制
CPD:3.5単位
https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo37/index.html
シンポジウム「御嶽山・箱根山・草津白根山ー水蒸気噴火および防災と観光ー」
12月16日(金)水蒸気噴火に関する学術シンポ
12月17日(土)活火山の防災と観光に関するシンポ
場所:長野県・木曽町文化交流センター(長野県木曽郡木曽町福島5129)
主催:御嶽山・箱根山・草津白根山ー水蒸気噴火および防災と観光ーシンポジウム実行委員会
開催方法:現地・オンライン併用
入場無料・要参加申込
https://ontake-vc.jp/satonews/news25/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0222.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・十勝岳ジオパーク研究助成金募集(12/31)
・伊豆大島ジオパーク専門員募集(随時受付)
・令和4年度伊豆半島ジオパーク学術研究助成(11/30)
・JAMSTEC超先鋭研究開発部門高知コア研究所物質科学研究G研究員orPD公募
(12/6)※締切延長となりました
・第54回(2023年度)三菱財団自然科学研究助成公募(23/2/3)
・東大地震研・京大防災研:令和5年度拠点間連携共同研究の公募(1/13)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.571 若手野外地質研究者向けに研究奨励金を支給します!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.571 2022/12/20┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2023年度日本地質学会研究奨励金募集
【2】「学生会員」追加申請を受け付けます(12/20-2/28)
【3】2023年度の会費払込について
【4】オンラインシンポジウム「ジオパーク地域に伝わる伝承と地質学」
【5】第3回JABEEシンポジウム「大学ー企業の架け橋教育 ユニークな実例紹介」
【6】第14回惑星地球フォトコンテスト受付中
【7】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
【11】事務局年末年始休業のお知らせ(12/29-1/5)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2023年度日本地質学会研究奨励金募集
──────────────────────────────────
日本地質学会では若手育成事業の一環として,野外調査をベースに研究を
行う32歳未満の若手会員を対象とした研究奨励金制度を新たに設けました.
その第1回目となる2023年度研究奨励金の募集を開始いたします.
***********************************
募集期間:2023年1月1日(日)から2023年2月28日(火)必着
***********************************
募集詳細,申請書式等は,下記よりご確認ください.
http://geosociety.jp/outline/content0242.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】「学生会員」追加申請を受け付けます
──────────────────────────────────
2023年度からの新しい会費制度導入に伴い手続きが必要になります.
「学生会員」申請は,会費請求の都合で,一旦11月末で締め切りましたが,
新しい制度への移行期につき,追加申請期間を設けます.
来年4月から就職が内定している方も今申請すれば,会費額が大変お得に
なります!忘れずにお申し込み下さい.
***********************************
新制度「学生会員」の会費 (参考)正会員会費:12,000円
・単年度:5,000円(23年度分会費)
・2年パック:8,000円(23-24年度分会費)
・3年パック:9,000円(23-25年度分会費)
***********************************
追加申請締切:2023年2月28日(火)
***********************************
詳細は, http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2023年度の会費払込について
──────────────────────────────────
運営規則(2022年6月一部改正.以下運営規則)により,2023年度からは新しい
会員種別,会費での運用が始まります.2023年度の会費は.事業年度(会費年度)
が始まる前までに納入下さいますようお願いいたします.
(1)口座引き落としの方:会費の自動引き落とし日は,12/23(金)です.
(2)お振り込みの方:12/22頃に請求書兼郵便振替用紙を発送いたします.
お手元に届きましたら,折り返しご送金をお願いいたします.
このほか,運営規則改正による2023年度以降の会費請求と主な変更点について
は,下記よりご確認ください.
詳しくは, http://www.geosociety.jp/outline/content0239.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】オンラインシンポジウム「ジオパーク地域に伝わる伝承と地質学」
──────────────────────────────────
市民対象オンラインシンポジウム
「ジオパーク地域に伝わる伝承と地質学:古代からの自然観を今に活かす」
国内のジオパーク地域に伝わる伝承をとりあげ,そこに古代から伝わる
自然観を現在の地質科学の視点から理解することをめざしています.
共催:日本ジオパークネットワーク,日本ジオパーク学術支援連合
日程:2023年1月28日(土) 10:00-14:25
開催形態:ZoomおよびYouTubeでの配信
会員・非会員問わず参加無料.
Zoom参加者は事前登録制(YouTube視聴の場合は申込不要)
***********************************
zoom参加申込締切:2023年1月20日(金)
***********************************
プログラム,講演要旨など詳しくは,
http://geosociety.jp/geopark/content0022.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第3回JABEEシンポジウム「大学ー企業の架け橋教育 ユニークな実例紹介」
──────────────────────────────────
今回は「大学ー企業の架け橋教育 ユニークな実例紹介」をテーマとして、技術者
教育における大学の役割や取り組み,実社会での技術者教育の在り方(社会OJT,
学協会による教育,大学院大学(専門職)構想や専門技術学校などでの教育や育
成)を紹介し,そしてこれらの連携や課題などについて考えます.
日時:2023年3月5日(日)13:30-18:00(予定)
開催方法:Zoomによるオンライン方式
参加は会員、非会員問わず無料.
申込制(2023年1月末から開始予定),定員:先着150名
詳細については、今後随時 お知らせします.
http://geosociety.jp/science/content0152.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】第14回惑星地球フォトコンテスト受付中
──────────────────────────────────
***応募締切:2023年1月30日(月)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募フォームからでも
メール添付でもご応募いただけます.会員の皆様の応募をお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円
・大学生・大学院生賞(新設)など
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】地質学雑誌からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・128巻:新しい論文等が公開されています
(論説)下北半島仏ヶ浦地域の凝灰岩からの鮮新世ジルコンU-Pb年代:植田勇人
ほか/(巡検案内書)房総半島東部,上総層群下部に記録された前弧テクトニクス
と海底地すべり:宇都宮正志ほか/(ノート)コンクリーション生成メカニズムの
工学的応用事例:丸山一平ほか/(レター)A new fossil specimen of the Suidae
(Mammalia, Artiodactyla) from the upper Miocene Oiso Formation and a
brief review of Neogene suids from Japan:Tsubamoto et al/
(論説)鳥取県の石「中新世魚類化石群」層準の年代の再検討:山陰東部の前期
中新世末の海進史:羽地俊樹ほか/(レター)北海道北部天塩中川地域から産出
した白亜紀中期チューロニアン期の珪藻化石群集:嶋田智恵子ほか
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/list/-char/ja
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
・関東支部功労賞を募集します.
対象者:支部活動や地質学を通して広く社会貢献をされた関東支部内に在住の
個人・団体 ※社会貢献や活動の評価においては,必ずしも学問的な成果を問
うものではありません.
公募締切:2023年1月21日
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html#2022koro
・関東支部オンライン講演会「県の石 茨城県」開催
日時:2023年1月22日(日)13:00-16:05
参加費無料(要事前申込)
申込締切:2023年1月11日(水)まで
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html#2022ishi
・アウトリーチ巡検
日程:2023年2月19日(日)(予備日:2/26)
対象:当該地域の地形・地質に興味のある方(日本地質学会会員でなくても可)
募集:30人(最少催行人数15)
申込期間:2023年1月16日(月)-2月5日(日)先着順.定員に達した時点で終了
http://geosociety.jp/outline/content0201.html#2022out
[西日本支部]
・西日本支部令和4年度総会・第173回例会
2023年3月4日(土)例会・総会
会場:島根大学総合理工学部多目的ホールほか
(注)状況によってオンラインでの開催を検討
講演・参加申込締切:2月1日(水)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
防災学術連携体:関東大震災100年関連行事等の特設ページ
https://janet-dr.com/090_abroadandhome/091_100_kantohEQ.html
2022年度東京地学協会メダル表彰式・受賞記念講演会
1月15日(日)14:00-15:30
場所:学士会館210号室(東京都千代田区神田錦町)
記念講演:四万十帯,南海トラフ,そして地球深部探査船「ちきゅう」
平 朝彦(東京大学名誉教授,JAMSETEC顧問)
要参加申込:1月10日(火)締切,参加費無料
http://www.geog.or.jp/lecture/lecturescheduled/462-2022medal.html
我が国の深海探査機能の近未来のあり方について考えるシンポジウム
1月19日(木)10:30-17:00
場所:東京大学大気海洋研究所講堂(オンライン併用)
現地参加の定員:60名
現地参加締切:1月12日(木)17:00
オンライン参加締切:1月17日 (火)17:00
https://sites.google.com/g.ecc.u-tokyo.ac.jp/deepseasympo/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0?pli=1
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0222.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・京都大学大学院工学研究科地球工学系助教公募(女性限定)(1/23)
・京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究施設研究員公募(1/31)
・2023年度「深田研究助成」募集(2/3)
・令和5年度採用土佐清水ジオパーク学術専門員募集(随時受付)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】事務局年末年始休業のお知らせ(12/29-1/5)
──────────────────────────────────
[年末年始休業期間]12月29日(木)から1月5日(木)
学会事務局の年末年始の休業期間は上記の通りです.新年は1月6日(金)より
通常通りの営業となります.本年も大変お世話になりありがとうございました.
来年もどうぞよろしくお願い申し上げます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.572 謹賀新年*2023
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.572 2023/1/6┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】年頭の挨拶
【2】2023年度日本地質学会研究奨励金募集
【3】「学生会員」追加申請を受付中(2/28締切)
【4】2023年度の会費払込について
【5】オンラインシンポジウム「ジオパーク地域に伝わる伝承と地質学」
【6】第14回惑星地球フォトコンテスト受付中
【7】地質学雑誌からのお知らせ
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
【11】訃報 端山好和 名誉会員 ご逝去
【12】新型コロナウィルス感染症に関する学会の対応について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】年頭の挨拶
──────────────────────────────────
学会員のみなさま,明けましておめでとうございます.
日本地質学会創立130周年を迎えるにあたり,年頭の挨拶を申し上げます.
2020年初頭以降,世界的に猛威を振るってきたコロナウイルス感染症パンデミック
によって,日常生活同様に学協会における活動も大幅な制限をせざるを得ない状況
が続いてきました.そうした中,昨年9月には第129年学術大会を3年ぶりに対面に
より早稲田大学にて実施することができました.早稲田大学では同時に地質情報展
も開催され,NHKでの報道もあったことから多くの一般市民が訪れ大変盛況でした.
LOCの皆様を始め,大会および情報展開催にご尽力頂いた関係各位に深く感謝申
し上げます.
続きはこちらから,,,http://geosociety.jp/outline/content0137.html
2023年1月6日
一般社団法人日本地質学会
会長 岡田 誠
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2023年度日本地質学会研究奨励金募集
──────────────────────────────────
日本地質学会では若手育成事業の一環として,野外調査をベースに研究を
行う32歳未満の若手会員を対象とした研究奨励金制度を新たに設けました.
その第1回目となる2023年度研究奨励金の募集を開始いたします.
***********************************
募集期間:2023年1月1日(日)から2023年2月28日(火)必着
***********************************
募集詳細,申請書式等は,下記よりご確認ください.
http://geosociety.jp/outline/content0242.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】「学生会員」追加申請を受付中(2/28締切)
──────────────────────────────────
2023年度からの新しい会費制度導入に伴い手続きが必要になります.
「学生会員」申請は,会費請求の都合で,一旦11月末で締め切りましたが,
新しい制度への移行期につき,追加申請期間を設けます.
来年4月から就職が内定している方も今申請すれば,会費額が大変お得に
なります!忘れずにお申し込み下さい.
***********************************
新制度「学生会員」の会費 (参考)正会員会費:12,000円
・単年度:5,000円(2023年度分会費)
・2年パック:8,000円(2023-2024年度分会費)
・3年パック:9,000円(2023-2025年度分会費)
***********************************
追加申請締切:2023年2月28日(火)
***********************************
詳細は,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2023年度の会費払込について
──────────────────────────────────
運営規則(2022年6月一部改正.以下運営規則)により,2023年度からは新しい
会員種別,会費での運用が始まります.2023年度の会費は.事業年度(会費年度)
が始まる前までに納入下さいますようお願いいたします.
(1)口座引き落としの方:12/23に登録の口座より引き落としをいたしました.
通帳記帳等でご確認をお願いいたします.
(2)お振り込みの方:12/22に請求書兼郵便振替用紙を発送いたしました.
ご確認の上,ご送金をお願いいたします.
このほか,運営規則改正による2023年度以降の会費請求と主な変更点について
は,下記よりご確認ください.
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0239.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】オンラインシンポジウム「ジオパーク地域に伝わる伝承と地質学」
──────────────────────────────────
市民対象オンラインシンポジウム
「ジオパーク地域に伝わる伝承と地質学:古代からの自然観を今に活かす」
共催:日本ジオパークネットワーク,日本ジオパーク学術支援連合
日程:2023年1月28日(土) 10:00-14:25
開催形態:ZoomおよびYouTubeでの配信
会員・非会員問わず参加無料.
Zoom参加者は事前登録制(YouTube視聴の場合は申込不要)
***********************************
zoom参加申込締切:2023年1月20日(金)
***********************************
プログラム,講演要旨など詳しくは,
http://geosociety.jp/geopark/content0022.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】第14回惑星地球フォトコンテスト受付中
──────────────────────────────────
***応募締切:2023年1月30日(月)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
投稿は超簡単! スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募フォームからでも
メール添付でもご応募いただけます.会員の皆様の応募をお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円
・大学生・大学院生賞(新設)など
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】地質学雑誌からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・128巻:新しい論文が公開されています
(巡検案内書)三浦半島北部の上総層群の地質と冷湧水性化学合成化石群集:野崎
篤ほか/(巡検案内書)伊豆大島火山:玄武岩質火山でみる噴火史とジオパーク:鈴
木毅彦ほか/(巡検案内書)千葉県東部,銚子周辺地域の鮮新-更新世テフラと銚子ジ
オパーク:植木 岳雪ほか/(ノート)炭酸カルシウムコンクリーションの水理・力学
特性:竹内 真司ほか 計13編が公開されています.
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/list/-char/ja
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
・関東支部功労賞を募集します.
対象者:支部活動や地質学を通して広く社会貢献をされた関東支部内に在住の
個人・団体 ※社会貢献や活動の評価においては,必ずしも学問的な成果を問
うものではありません.
公募締切:2023年1月21日
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html#2022koro
・関東支部オンライン講演会「県の石 茨城県」開催
日時:2023年1月22日(日)13:00-16:05
参加費無料(要事前申込)
申込締切:2023年1月11日(水)まで
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html#2022ishi
・アウトリーチ巡検
日程:2023年2月19日(日)(予備日:2/26)
対象:当該地域の地形・地質に興味のある方(日本地質学会会員でなくても可)
募集:30人(最少催行人数15)
申込期間:2023年1月16日(月)-2月5日(日)先着順.定員に達した時点で終了
http://geosociety.jp/outline/content0201.html#2022out
[西日本支部]
・西日本支部令和4年度総会・第173回例会
2023年3月4日(土)例会・総会
会場:島根大学総合理工学部多目的ホールほか
(注)状況によってオンラインでの開催を検討
講演・参加申込締切:2月1日(水)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
防災学術連携体:関東大震災100年関連行事等の特設ページ
https://janet-dr.com/090_abroadandhome/091_100_kantohEQ.html
地震本部ニュース2022冬号
調査研究機関の取組:日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震に係る防災対策について
ほか https://www.jishin.go.jp/herpnews/
(後)第60回アイソトープ・放射線研究発表会
7月5日(水)-7日(金)
会場:東京都内会場(予定)
発表演題申込締切:2月28日(火)
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2023/top
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0222.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・東北大学大学院環境科学研究科先進社会環境学専攻資源戦略学講座
地球物質・エネルギー学分野准教授公募(1/16)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】訃報 端山好和 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
日本地質学会元会長,端山好和 名誉会員(東京農業大学名誉教授)が、
令和4年2月26日に逝去されました(94歳).昨年末ご家族よりご連絡
を頂きましたので,会員の皆様にお知らせいたします.
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し
上げます.
一般社団法法人日本地質学会
会長 岡田 誠
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】新型コロナウィルス感染症に関する学会の対応について
──────────────────────────────────
未だ続くコロナ禍ではありますが,感染対策の緩和が進み,今年9月には3年
ぶりに対面での学術大会を開催いたしました.各支部でも対面行事が徐々に
再開されています.一方で,国内の感染者数は再び増加傾向にあり,現在は
「第8波」とも言われる状況です.
全文はこちら,,,http://geosociety.jp/news/n160.html
(2022.12.22)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.573 惑星地球フォトコンテストまもなく締切です
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.573 2023/1/17┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】名誉会員候補者の募集が開始されています
【2】2023年度日本地質学会研究奨励金募集
【3】「学生会員」追加申請を受付中(2/28締切)
【4】オンラインシンポジウム「ジオパーク地域に伝わる伝承と地質学」
【5】第3回JABEEシンポジウム「大学ー企業の架け橋教育 ユニークな実例紹介」
【6】第14回惑星地球フォトコンテスト受付中
【7】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【8】専門職における旧姓・通称使用に関する実態調査への協力依頼
【9】支部情報
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】名誉会員候補者の募集が開始されています
──────────────────────────────────
募集締切: 2023年2月9日(木)
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:例えば,,,地質学への顕著な貢献/地質学会の運営と
発展への貢献/教育現場や企業などでの活動を通じた地質学の普及と振興への貢献
など
(注)上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することはできませ
んが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
(名誉会員推薦委員会 星 博幸)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2023年度日本地質学会研究奨励金募集
──────────────────────────────────
日本地質学会では若手育成事業の一環として,野外調査をベースに研究を
行う32歳未満の若手会員を対象とした研究奨励金制度を新たに設けました.
その第1回目となる2023年度研究奨励金の募集をいたします.
***********************************
募集期間:2023年1月1日(日)から2023年2月28日(火)必着
***********************************
募集詳細,申請書式等は,下記よりご確認ください.
http://geosociety.jp/outline/content0242.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】「学生会員」追加申請を受付中(2/28締切)
──────────────────────────────────
2023年度からの新しい会費制度導入に伴い手続きが必要になります.
「学生会員」申請は,会費請求の都合で,一旦11月末で締め切りましたが,
新しい制度への移行期につき,追加申請期間を設けます.
来年4月から就職が内定している方も今申請すれば,会費額が大変お得に
なります!忘れずにお申し込み下さい.
***********************************
新制度「学生会員」の会費 (参考)正会員会費:12,000円
・単年度:5,000円(2023年度分会費)
・2年パック:8,000円(2023-2024年度分会費)
・3年パック:9,000円(2023-2025年度分会費)
***********************************
追加申請締切:2023年2月28日(火)
***********************************
詳細は,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】オンラインシンポジウム「ジオパーク地域に伝わる伝承と地質学」
──────────────────────────────────
市民対象オンラインシンポジウム
「ジオパーク地域に伝わる伝承と地質学:古代からの自然観を今に活かす」
共催:日本ジオパークネットワーク,日本ジオパーク学術支援連合
日程:2023年1月28日(土) 10:00-14:25
開催形態:ZoomおよびYouTubeでのライブ配信
会員・非会員問わず参加無料.
Zoom参加者は事前登録制(YouTube視聴の場合は申込不要)
***********************************
zoom参加申込締切:2023年1月20日(金)
***********************************
プログラム,講演要旨など詳しくは,
http://geosociety.jp/geopark/content0022.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第3回JABEEシンポジウム「大学ー企業の架け橋教育 ユニークな実例紹介」
──────────────────────────────────
第3回は大学から企業への技術者の継続教育に焦点をあてたシンポジウムとし,
技術者教育における大学の役割や取り組み,実社会での技術者教育のあり方などに
ついて議論することを目的とし,JABEEプログラムを有する大学からの実態・課題
の報告を,実社会での専門教育の例として先端地質科学大学院大学(専門職)構想
や掘削技術専門学校での技術者教育計画や実態について紹介していただきます.また,
大学や学会に求められる実社会での技術者教育のあり方についても紹介していただきます.
日時:2023年3月5日(日)13:30-18:00(予定)
開催方法:Zoomによるオンライン方式
参加者:会員,非会員問わず無料.
事前申込制(2023年1月末から開始予定).
定員先着150名.
講演内容など詳しくは,http://geosociety.jp/science/content0152.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】第14回惑星地球フォトコンテスト受付中
──────────────────────────────────
***応募締切:2023年1月30日(月)***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募集!
投稿は超簡単!スマホ・携帯写真でもチャレンジ!専用応募フォームからでも
メール添付でもご応募いただけます.会員の皆様の応募をお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円
・大学生・大学院生賞(新設)など
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
129巻オンデマンド印刷版年間購読受付のお知らせ
昨年同様,WEB上での論文閲覧が難しい方への対応として,地質学雑誌オンデ
マンド印刷版を作成し,年間購読のお申込を受け付けます.ご希望の方は学会
事務局までお申し込みください.受付締切:3月20日(月)
詳しくは,http://geosociety.jp/news/n169.html
■ Island Arc
・新しい論文等が公開されています.
Late Triassic A-type granite boulders in Lower Cretaceous conglomerate
of the Hida belt, Japan: their origin and bearing on the Yamato Tectonic
Line in Far East Asia Yukio Isozaki, et al.
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14401738/0/ja
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】専門職における旧姓・通称使用に関する実態調査への協力依頼
──────────────────────────────────
「科学技術系専門職における旧姓・通称使用に関する実態調査」への協力依頼
地質学会が参画している男女共同参画学協会連絡会から,「科学技術系専門職に
おける旧姓・通称使用に関する実態調査」への協力依頼が来ました.
男女問わず 旧姓・通称使用に関する,大学・高等教育研究機関等においての実態
の調査,および研究者として困った事例の収集,を目的としたものです.
2月19日迄にできるだけ多くの方に,ご回答を頂けますよう,ご協力お願いします.
【回答方法】Google フォームへの入力
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOeTMQXpA58F4u_rZNUQqxQEJboP8ua2rClaq5_CwImDRlWA/viewform
【回答にかかる時間】 15分間程度
【回答期限】2023年2月19日(日)
日本地質学会ジェンダーダイバーシティ委員会
委員長 堀 利栄
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
・関東支部功労賞を募集します.
対象者:支部活動や地質学を通して広く社会貢献をされた関東支部内に在住の
個人・団体 ※社会貢献や活動の評価においては,必ずしも学問的な成果を問
うものではありません.
公募締切:2023年1月21日
http://www.geosociety.jp/outline/content0201.html#2022koro
・アウトリーチ巡検
日程:2023年2月19日(日)(予備日:2/26)
対象:当該地域の地形・地質に興味のある方(日本地質学会会員でなくても可)
募集:30人(最少催行人数15)
申込期間:2023年1月16日(月)-2月5日(日)先着順.定員に達した時点で終了
http://geosociety.jp/outline/content0201.html#2022out
[西日本支部]
・西日本支部令和4年度総会・第173回例会
2023年3月4日(土)例会・総会
会場:島根大学総合理工学部多目的ホールほか
(注)状況によってオンラインでの開催を検討
講演・参加申込締切:2月1日(水)
支部総会委任状締切:2月28日(火)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
気象庁:関東大震災特設サイト
ー関東大震災から100年ー知って備えよう:過去の大災害から学ぶ
https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/1923_09_01_kantoujishin/index.html
防災学術連携体:関東大震災100年関連行事等の特設ページ
https://janet-dr.com/090_abroadandhome/091_100_kantohEQ.html
—-------------------------------------------------
防災・減災セミナー2022名古屋【オンライン】
1月5日(木)-20日(金)
会場:オンライン(防災ログWebサイト)
入場無料(事前登録制)
CPD:5.4単位(JSCE22-1670)
主催:防災ログ実行委員会
https://clk.nxlk.jp/m/HbYcTOs9D
(後)原子力総合シンポジウム2022
テーマ「新たな社会状況に貢献する原子力技術の期待と課題」
1月26日(木)10:00-17:35
場所:日本学術会議講堂およびオンライン(Zoomウェビナー)
https://www.aesj.net/symp20230126
オンラインシンポジウム
災害に強い社会を実現するための科学技術:南海トラフ地震・津波防災
1月30日(月)13:00-17:00 参加無料
主催:防災科研,JAMSTEC
https://clk.nxlk.jp/m/nTLY5U6YD
東海大学海洋研究所主催シンポジウム
「水中考古と地球科学―文理融合から導く総合学術知」
3月12日(日)13:00-17:00
会場:東海大学静岡キャンパス8号館4階PLAT
(YouTubeによる生配信もあります)
http://www.scc.u-tokai.ac.jp/iord/
(後)観察会 「宅地開発で隠れた衣笠断層帯を歩く」
主催:三浦半島活断層調査会
3月18日(日)9:30-15:00時
参加申込締切:3月11日(土)
https://geosociety.jp/uploads/fckeditor/others-pdf/kinugasa2023-1.pdf
地質学史懇話会[オンラインとハイブリッド]
6月10日(土)13:30-17:00
場所:早稲田奉仕園(東京メトロ東西線早稲田駅下車徒歩5分)
小澤健史「ドイツ・ハーツ鉱山とドイツ系日本人ペーター・ハーツィング」
今村遼平「中国地図測量史」続
問い合わせ:矢島道子 pxi02070[at]nifty.com
※[at]を@マークにして送信してください
(後)第60回アイソトープ・放射線研究発表会
7月5日(水)-7日(金)
会場:東京都内会場(予定)
発表演題申込締切:2月28日(火)
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2023/top
(協)Techno-Ocean 2023
10月5日(木)-7日(土)
会場:神戸国際展示場2号館 ほか
https://to2023.techno-ocean.com/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0222.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・山田科学振興財団2023年度研究援助候補推薦依頼(学会締切2/1)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.574 地質系業界オンライン交流会開催します
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.574 2023/2/7┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】名誉会員候補者の募集中です(まもなく締切)
【2】2023年度日本地質学会研究奨励金募集
【3】「学生会員」追加申請受付中(2/28締切)
【4】地質系業界オンライン交流会の開催案内
【5】第3回JABEEシンポジウム「大学ー企業の架け橋教育 ユニークな実例紹介」
【6】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】名誉会員候補者の募集中です(まもなく締切)
──────────────────────────────────
募集締切: 2023年2月9日(木)
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:例えば,,,地質学への顕著な貢献/地質学会の運営と
発展への貢献/教育現場や企業などでの活動を通じた地質学の普及と振興への貢献
など
(注)上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することはできませ
んが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
(名誉会員推薦委員会 星 博幸)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2023年度日本地質学会研究奨励金募集
──────────────────────────────────
日本地質学会では若手育成事業の一環として,野外調査をベースに研究を
行う32歳未満の若手会員を対象とした研究奨励金制度を新たに設けました.
その第1回目となる2023年度研究奨励金の募集をいたします.
***********************************
募集期日:2023年2月28日(火)必着
***********************************
募集詳細,申請書式等は,下記よりご確認ください.
http://geosociety.jp/outline/content0242.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】「学生会員」追加申請受付中(2/28締切)
──────────────────────────────────
2023年度からの新しい会費制度導入に伴い手続きが必要になります.
「学生会員」申請は,会費請求の都合で,一旦11月末で締め切りましたが,
新しい制度への移行期につき,追加申請期間を設けます.
来年4月から就職が内定している方も今申請すれば,会費額が大変お得に
なります!忘れずにお申し込み下さい.
***********************************
新制度「学生会員」の会費 (参考)正会員会費:12,000円
・単年度:5,000円(2023年度分会費)
・2年パック:8,000円(2023-2024年度分会費)
・3年パック:9,000円(2023-2025年度分会費)
***********************************
追加申請締切:2023年2月28日(火)
***********************************
詳細は,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地質系業界オンライン交流会の開催案内
──────────────────────────────────
地質学会若手有志会では,地質学に関わる民間企業や官公庁等に就職を考えている
方向けの「地質系企業オンライン交流会」を開催します.この交流会では,学部学
生・大学院生向けに,地質学に関わる企業に就職をした若手社員の方との座談会と
懇親会を企画しています.本交流会は,地質系の民間企業だけではなく,公務員や
学芸員,ジオパーク職員など,広く地質学に関わる仕事を行っている方に,業界に
入ってよかったこと、楽しかった仕事、学生時代の経験で役に立ったこと、大変だ
と感じたこと、業界でのキャリア形成など、通常の企業説明会や就職説明会などと
は異なる若手社員ならではのお話をしていただきます.
日時:2023年2月17日(金)19:00–21:00
場所:Zoomによるオンライン開催
対象:どなたでも参加いただけます.参加費無料
タイムテーブル:
19:00-20:00各業界の方との座談会(ブレイクアウトルームを使用)
20:00-21:00 懇親会
参加業界:株式会社INPEX/日鉄鉱業株式会社/株式会社蒜山地質年代学研究所
農林水産省/糸魚川フォッサマグナミュージアム
*****************************************
会員・非会員を問わず,友人などをお誘いあわせの上,お気軽にご参加ください.
要事前参加登録:2月16日(木)23:59締切
申込フォーム等詳しくは,
http://geosociety.jp/science/content0128.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第3回JABEEシンポジウム「大学ー企業の架け橋教育 ユニークな実例紹介」
──────────────────────────────────
第3回は大学から企業への技術者の継続教育に焦点をあてたシンポジウムとし,
技術者教育における大学の役割や取り組み,実社会での技術者教育のあり方などについて議論することを目的とし,JABEEプログラムを有する大学からの実態・課題
の報告を,実社会での専門教育の例として先端地質科学大学院大学(専門職)構想
や掘削技術専門学校での技術者教育計画や実態について紹介していただきます.また,大学や学会に求められる実社会での技術者教育のあり方についても紹介していただきます.
日時:2023年3月5日(日)13:30-18:00(予定)
開催方法:Zoomによるオンライン方式
参加者:会員,非会員問わず無料.
事前申込制:2月28日(火)締切
定員先着150名.
申込,講演要旨など詳しくは,http://geosociety.jp/science/content0152.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・129巻の新しい論文等が公開されています.
(総説)球状コンクリーションの理解と応用:吉田英一
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/-char/ja
・129巻オンデマンド印刷版年間購読受付のお知らせ
昨年同様,WEB上での論文閲覧が難しい方への対応として,地質学雑誌
オンデマンド印刷版を作成し,年間購読のお申込を受け付けます.ご希望
の方は学会事務局までお申し込みください.受付締切:3月20日(月)
詳しくは,http://geosociety.jp/news/n169.html
■ Island Arc
・新しい論文等が公開されています.
Magnetic susceptibility, mineral chemistry, and geothermobarometry of
granitoids from Lohit Plutonic Complex, Arunachal Trans-Himalaya,
Northeast India:Diezeneino Meyase, et alほか
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14401738/0/ja
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
・2023年度支部総会・講演会
日時:4月9日(日)14:00-16:45
場所:大田区産業プラザPiO 3階 特別会議室(京急蒲田駅前)
講師:宇根 寛氏(元国土地理院,中央開発(株)技術顧問)
演題:「Web地図を活かして災害リスクを理解する」
総会委任状期日:4月6日(木)必着(FAX)/4月7日(金)18時(e-mail)
http://geosociety.jp/outline/content0201.html#2023sokai
[西日本支部]
・西日本支部令和4年度総会・第173回例会
日程:3月4日(土)例会・総会
会場:島根大学総合理工学部多目的ホールほか
(注)状況によってオンラインでの開催を検討
講演・参加申込締切:2月1日(水)
支部総会委任状締切:2月28日(火)
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
気象庁:関東大震災特設サイト
ー関東大震災から100年ー知って備えよう:過去の大災害から学ぶ
https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/1923_09_01_kantoujishin/index.html
防災学術連携体:関東大震災100年関連行事等の特設ページ
https://janet-dr.com/090_abroadandhome/091_100_kantohEQ.html
—-------------------------------------------------
防災科研令和4年度成果発表会(ハイブリッド)
国難級災害を乗り越えるために 2023
「情報でつなぎ、災害対応を変える。」
2月21日(火)11:30-17:30
会場:東京国際フォーラム ホールB7
参加無料 ※会場参加の応募締切: 2月7日(火)
https://clk.nxlk.jp/m/rQsSa4bpD
2022年度「深田賞」授賞式及び記念講演
2月27日(月)14:00-16:30
開催方法:Zoomウェビナーによるオンライン配信(一般参加)
募集人数:先着80名(一般参加)
参加無料,要事前申込:2/20(月)17時締切
https://fukadaken.or.jp/?page_id=7294
令和4年度海洋プラスチックごみ学術シンポジウム特別セッション
3月4日(土)
場所:秋葉原UDX シアター
(対面で実施.後日録画を期間限定でYouTube 配信)
参加無料,定員80名
参加登録締切:3月2日(木)17:00
https://www.env.go.jp/press/press_01067.html
○地質情報展2023いわて
明日につなぐ大地の知恵
3⽉10⽇(金)-12日(日)
場所:岩手県立博物館 岩手山を望める丘のミュージアム
(注)博物館の入館料がかかります
https://www.gsj.jp/event/johoten/2023/iwate/index.html
令和4年度筑波山地域ジオパーク学術研究助成金成果発表と教育シンポジウム
3月11日(土)13:30-16:30(オンライン)
参加締切:3月5日(日)
https://tsukuba-geopark.jp/page/page001026.html
(後)観察会 「宅地開発で隠れた衣笠断層帯を歩く」
主催:三浦半島活断層調査会
3月18日(日)9:30-15:00時
参加申込締切:3月11日(土)
https://geosociety.jp/uploads/fckeditor/others-pdf/kinugasa2023-1.pdf
地質学史懇話会[オンラインとハイブリッド]
6月10日(土)13:30-17:00
場所:早稲田奉仕園(東京メトロ東西線早稲田駅下車徒歩5分)
小澤健史「ドイツ・ハーツ鉱山とドイツ系日本人ペーター・ハーツィング」
今村遼平「中国地図測量史」続
問い合わせ:矢島道子 pxi02070[at]nifty.com
※[at]を@マークにして送信してください
(後)第60回アイソトープ・放射線研究発表会
7月5日(水)-7日(金)
会場:東京都内会場(予定)
発表演題申込締切:2月28日(火)
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2023/top
(協)Techno-Ocean 2023
10月5日(木)-7日(土)
会場:神戸国際展示場2号館 ほか
https://to2023.techno-ocean.com/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・京都大学大学院人間・環境学研究科特定助教公募(専門分野:広い意味での
地質学)(3/31)
・国土地理協会2023年度学術研究助成(4/17)
・令和5年度苗場山麓ジオパーク学術研究奨励事業助成金募集(3/3)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.575 研究奨励金・学生会員申請 まもなく締切!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.575 2023/2/21┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2023年度日本地質学会研究奨励金:まもなく締切(2/28締切)
【2】「学生会員」追加申請:まもなく締切(2/28締切)
【3】第3回JABEEシンポジウム「大学ー企業の架け橋教育 ユニークな実例紹介」
【4】第7回ショートコース 開催します
【5】第130年学術大会(2023京都)京都大学吉田南構内にて開催
【6】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】おたずね(古い巡検案内書を探しています)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2023年度日本地質学会研究奨励金:まもなく締切(2/28締切)
──────────────────────────────────
日本地質学会では若手育成事業の一環として,野外調査をベースに研究を
行う32歳未満の若手会員を対象とした研究奨励金制度を新たに設けました.
その第1回目となる2023年度研究奨励金の募集をいたします.
***********************************
募集期日:2023年2月28日(火)必着
***********************************
募集詳細,申請書式等は,下記よりご確認ください.
http://geosociety.jp/outline/content0242.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】「学生会員」追加申請:まもなく締切(2/28締切)
──────────────────────────────────
2023年度からの新しい会費制度導入に伴い手続きが必要になります.
「学生会員」申請は,会費請求の都合で,一旦11月末で締め切りましたが,
新しい制度への移行期につき,追加申請期間を設けます.
来年4月から就職が内定している方も今申請すれば,会費額が大変お得に
なります!忘れずにお申し込み下さい.
***********************************
新制度「学生会員」の会費 (参考)正会員会費:12,000円
・単年度:5,000円(2023年度分会費)
・2年パック:8,000円(2023-2024年度分会費)
・3年パック:9,000円(2023-2025年度分会費)
***********************************
追加申請締切:2023年2月28日(火)
***********************************
詳細は,http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】第3回JABEEシンポジウム「大学ー企業の架け橋教育 ユニークな実例紹介」
──────────────────────────────────
第3回は大学から企業への技術者の継続教育に焦点をあてたシンポジウムとし,
技術者教育における大学の役割や取り組み,実社会での技術者教育のあり方など
について議論することを目的とし,JABEEプログラムを有する大学からの実態・
課題の報告を,実社会での専門教育の例として先端地質科学大学院大学(専門職)
構想や掘削技術専門学校での技術者教育計画や実態について紹介していただ
きます.また,大学や学会に求められる実社会での技術者教育のあり方についても
紹介していただきます.
日時:2023年3月5日(日)13:30-18:00(予定)
開催方法:Zoomによるオンライン方式
参加者:会員,非会員問わず無料.
事前申込制:2月28日(火)締切 定員先着150名.
申込,講演要旨など詳しくは,
http://geosociety.jp/science/content0152.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第7回ショートコース 開催します
──────────────────────────────────
今回は応力逆解析法について実習を通じて学ぶ機会を提供します.
応力逆解析法は,現在または地質学的過去の,テクトニクスの原動力を解明する
方法の1つです.「逆」解析と呼ばれるのは,変形の結果として生じた地質構造
から,変形の原因である応力を推定するからです.ぜひふるってご参加ください.
日程:2023年4月2日(日)
(午前)小断層や岩脈などによる応力逆解析法の基礎:佐藤活志(京都大学)
(午後)応力逆解析のための露頭観察法と解析実習:大坪 誠(産総研)
受講料:地質学会正会員(一般・シニア)2,000円,地質学会正会員(学生会員)1,000円 ほか
参加申込締切:2023年3月23日(木)
詳しくは,http://geosociety.jp/science/content0153.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第130年学術大会(2023京都)京都大学吉田南構内にて開催
──────────────────────────────────
日本地質学会は,京都市左京区の京都大学吉田キャンパスにおいて,
第130年学術大会(2023年京都大会)を9月17日(日)から19日(火)に
開催します.また,巡検(見学旅行)を16日(土)と20日(水)に催行します.
続きは,こちらからhttp://geosociety.jp/science/content0157.html
*************************************************
トピックセッション提案募集 締切:3月27日(月)
*************************************************
昨年の大会からセッションは
・「トピックセッション(会員提案型)」
・「ジェネラルセッション」
・「アウトリーチセッション」の3カテゴリになりました.
ここではトピックセッション提案を募集します.
詳しくは,http://geosociety.jp/science/content0155.html
・京都大会プレサイト
http://geosociety.jp/science/content0156.html
・【重要】学術大会セッションの変更について
http://geosociety.jp/science/content0154.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・129巻の新しい論文等が公開されています.
(論説)御坂・巨摩山地の伊豆衝突帯に胚胎する黒鉱鉱床の産状とその
地質学的意義:浦辺徹郎ほか 計8編
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/-char/ja
・129巻オンデマンド印刷版年間購読受付のお知らせ
昨年同様,WEB上での論文閲覧が難しい方への対応として,地質学雑誌
オンデマンド印刷版を作成し,年間購読のお申込を受け付けます.ご希望
の方は学会事務局までお申し込みください.受付締切:3月20日(月)
詳しくは,http://geosociety.jp/news/n169.html
■ Island Arc
・Accepted Articles廃止のお知らせ
2023年3月以降,受理原稿(Accepted Articles: AA)の早期オンライン掲載が
廃止されます.ワイリー社全体の方針で,背景に出版物の責任問題(出版規範
委員会の定義では,AA版と正式版[Version of Record: VOR版]のどちらも
出版物扱い),取り下げ・撤回増加の懸念,ペーパーミル問題の悪化(論文
作成・販売する違法組織織を利用した不正論文の増加),があります.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
・2023年度支部総会・講演会
日時:4月9日(日)14:00-16:45
場所:大田区産業プラザPiO 3階 特別会議室(京急蒲田駅前)
講師:宇根 寛氏(元国土地理院,中央開発(株)技術顧問)
演題:「Web地図を活かして災害リスクを理解する」
総会委任状期日:4月6日(木)必着(FAX)/4月7日(金)18時(e-mail)
http://geosociety.jp/outline/content0201.html#2023sokai
[西日本支部]
・西日本支部令和4年度総会・第173回例会
日程:3月4日(土)例会・総会
会場:島根大学教養講義室棟2号館(会場が変更になりました)
支部総会委任状締切:2月28日(火)
講演プログラム公開しました.
http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
気象庁:関東大震災特設サイト
ー関東大震災から100年ー知って備えよう:過去の大災害から学ぶ
https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/1923_09_01_kantoujishin/index.html
防災学術連携体:関東大震災100年関連行事等の特設ページ
https://janet-dr.com/090_abroadandhome/091_100_kantohEQ.html
-------------------------------------------------
地質情報展2023いわて
明日につなぐ大地の知恵
3月10日(金)-12日(日)
場所:岩手県立博物館 岩手山を望める丘のミュージアム
(注)博物館の入館料がかかります
https://www.gsj.jp/event/johoten/2023/iwate/index.html
第82回地学史研究会
3月11日(土)14:00-17:00
会場:早稲田奉仕園101号室
オンラインとハイブリッド
中陣隆夫「速水頌一郎・星野通平の海洋学的業績と思想について」
問い合わせ:矢島道子 pxi02070@nifty.com
(後)観察会 「宅地開発で隠れた衣笠断層帯を歩く」
主催:三浦半島活断層調査会
3月18日(日)9:30-15:00時
参加申込締切:3月11日(土)
https://geosociety.jp/uploads/fckeditor/others-pdf/kinugasa2023-1.pdf
第240回イブニングセミナー(オンライン)
3月31日(金)19:30-21:30
演題:「零細及び金採掘の管理手法:今後の展開」
講師:村尾 智 先生(第一工科大学 環境エネルギー工学科教授)
主催:NPO法人日本地質汚染審査機構
参加費:主催NPO会員及び学生の方(無料),非会員の方(1,000円)
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
日本学術会議公開シンポジウム・第15回防災学術連携シンポジウム
「気候変動がもたらす災害対策・防災研究の新展開」
3月11日(火)13:00-17:00
zoomウェビナー,定員:1000名
https://janet-dr.com/060_event/20230411.html
日本堆積学会 2023 年新潟大会
4月22日(土)-24日(月)
会場:新潟大学
講演申込締切:3月22日(水)
https://sites.google.com/view/ssjconference2023niigata
(後)第60回アイソトープ・放射線研究発表会
7月5日(水)-7日(金)
会場:東京都内会場(予定)
発表演題申込締切:2月28日(火)
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2023/top
ぼうさいこくたい2023(第8回防災推進国民大会)
9月17日(日)-18日(月・祝)
場所:横浜国立大学(横浜市保土ヶ谷区常盤台)
https://bosai-kokutai.jp/2023/
(協)Techno-Ocean 2023
10月5日(木)-7日(土)
会場:神戸国際展示場2号館 ほか
https://to2023.techno-ocean.com/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・鹿児島大学学術研究院理工学域理学系(火山地質学)教授公募(4/17)
・2024年度地震研究所共同利用特定機器利用公募(4/7)
・2023年度深田野外調査助成募集(4/14)
・令和5年度下北ジオパーク研究補助金募集(3/17)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】おたずね(古い巡検案内書を探しています)
──────────────────────────────────
日本地質学会第84年学術大会(1977年高知大会)の巡検案内書をお持ち
の方がおられましたら,学会事務局までご一報ください.
(TEL03-5823-1150)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.576 ショートコース参加申込受付中!お早めに!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.576 2023/3/7┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】第7回ショートコース 参加申込受付中!お早めに!
【2】第130年学術大会トピックセッション募集中
【3】第3回JABEEシンポジウム 開催しました
【4】TOPIC 日本地質学会の国際的プロファイルの向上
【5】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】第7回ショートコース 参加申込受付中!お早めに!
──────────────────────────────────
今回は応力逆解析法について実習を通じて学ぶ機会を提供します.
応力逆解析法は,現在または地質学的過去の,テクトニクスの原動力を解明する
方法の1つです.「逆」解析と呼ばれるのは,変形の結果として生じた地質構造
から,変形の原因である応力を推定するからです.ぜひふるってご参加ください.
日程:2023年4月2日(日)
(午前)小断層や岩脈などによる応力逆解析法の基礎:佐藤活志(京都大学)
(午後)応力逆解析のための露頭観察法と解析実習:大坪 誠(産総研)
受講料:地質学会正会員(一般・シニア)2,000円,地質学会正会員(学生会員)1,000円 ほか
参加申込締切:2023年3月23日(木)
詳しくは,http://geosociety.jp/science/content0153.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第130年学術大会(2023京都)トピックセッション募集中
──────────────────────────────────
第130年学術大会(2023年京都大会)
会期:2023年9月17日(日)-19日(火)
会場:京都大学吉田南構内
*************************************************
トピックセッション提案募集 締切:3月27日(月)
*************************************************
昨年の大会からセッションは
・「トピックセッション(会員提案型)」
・「ジェネラルセッション」
・「アウトリーチセッション」の3カテゴリになりました.
ここではトピックセッション提案を募集します.
詳しくは,http://geosociety.jp/science/content0155.html
・京都大会プレサイト
http://geosociety.jp/science/content0156.html
・【重要】学術大会セッションの変更について
http://geosociety.jp/science/content0154.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】第3回JABEEシンポジウム 開催しました
──────────────────────────────────
「大学ー企業の架け橋教育 ユニークな実例紹介」
3/5標記のシンポジウムを開催しました.100名以上の方々にご参加をいただき,
ありがとうございました.シンポジウムの内容(動画)は近日中にYouTubeで
公開予定です.ご参加いただけなかった皆様もぜひご覧ください.
なお,当日参加者のうち,CPD参加証明を希望される方は,事務局までお申し出
ください.講演要旨など詳しくは,学会HPをご参照ください.
http://geosociety.jp/science/content0152.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】TOPIC 日本地質学会の国際的プロファイルの向上
──────────────────────────────────
「日本地質学会の国際的プロファイルの向上: 2007年から現在そして未来へ」
ウォリス サイモンa,井龍康文b,石渡 明c
a: 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻
b: 東北大学大学院理学研究科
c: 原子力規制委員会
国際的な情報交換やネットワーク作りが科学全般を発展させるために重要であり,その重要性は年々増加しつつある.日本地質学会の活動においても,国際的協力は欠かせない要素である.日本の地質学分野と海外の関係は19世紀まで遡るが注1(文献1),平成以後では,1992年に第29回万国地質学会を京都で開催したことや,翌年の日本地質学会100周年記念式典へ海外から来賓が招かれたことは多くの会員が記憶するところであり, 現在の地質学会の国際交流体制につながる起点となったといえよう. 近年,正式な合意に基づく交流が重要視されるようになり,その礎とされているのが組織・団体間の学術交流協定(Memorandum of Understanding; MOU)である. 日本地質学会は過去15年に渡り,海外の複数の学術団体とMOUを締結し,積極的に国際協力を行なってきた.このような国際協力の嚆矢は,2007年に韓国地質学会と締結したMOUであり,これは当時の木村 学会長の主導による(これ以後の日本地質学会の国際交流協定・報告等についてはhttp://geosociety.jp/science/content0049.htmlを参照).その後の6年間で国際協力は大きく発展し,モンゴル,タイ,ロンドン,台湾の地質学会とのMOUの締結に至った.われわれ3人は,会長,副会長,国際関係担当執行理事として,これらの協定締結のために尽力した.そこで,本稿では,我々が地質学会の国際協力推進に直接的に関わってきたこの15年間を中心に,何が達成されたのかを総括するとともに,MOU締結先と議論してきた内容について述べる.本稿が,今後のポストコロナ世界で活躍が期待される国際交流担当者に参考になれば幸甚である.
国際交流の主な目的の1つは,共同して科学的成果を出版・公表することにある.このような出版物は,異なる地域の異なるネットワークを結びつけ,情報の効率的な拡散を後押しする.国際交流協定から生まれた主たる科学的成果として,ロンドン地質学会との共同研究を挙げることができる.その第一弾は,2011年に発生した東北地方太平洋沖地震と津波に関するものであった.この頃,英国では過去の津波堆積物の地質学的証拠が見出され,プレート境界から遠く離れた国でも,この問題に関心を持つ必要が認識され始めるようになった.このような背景から,両学会は2つのシンポジウムを開催することにした.まず,2014年9月の日本地質学会第121年学術大会(鹿児島大会)では,藤野滋弘,後藤和久,David R. Tappin,藤原 治が世話人となって「津波ハザードとリスク:地質記録の活用」が開かれ,翌年(2015年)の9月にはロンドンで.Ellie M. Scourse, Neil A. Chapman, David R. Tappin, Simon R. Wallisの主催により「Tsunamis: Geology, Hazards and Risks」が開催された.ロンドンでのシンポジウムは,権威あるロンドン地質学会のArthur Homes Meetingsの1つとして実施された.鹿児島大会では,静岡県および千葉県の東海地震と関東地震の痕跡を伝える地形・津波堆積物・建造物を見学する国際シンポジウム関連巡検が実施された.また,ロンドンでのシンポジウムは,英国北部のシェトランド諸島に分布する津波堆積物を見学する巡検も含む内容であった(文献2).両シンポジウムとも,津波堆積物の地質に関する理解を深め,それをリスク評価の改善と向上に役立てる方法を探ることを目的としていた.これらのイベントの資金は,英国笹川財団の David Cope 教授の尽力により調達され,科学的成果は Island Arcの特別号(文献3)として,またロンドン地質学会のSpecial Publication(文献4)として出版された.
また,日本地質学会とロンドン地質学会の密接な協力関係は,「The Geology of Japan」(文献5)という重要な書籍の刊行という成果に繋がった.同書の執筆には,日本地質学会の多くの会員が参加し,井龍と石渡が序文を寄せた.また,ロンドン地質学会との関係から,日本地質学会会員は同書を割引価格で購入可能という特典があった.同書は国際的に高く評価され,さらにロンドン地質学会が有する幅広い販売網により,日本地質学会とその会員の活動を世界中の人々に紹介し,日本の地質に関する最新の情報を提供することに役立った.
朝鮮半島,特に同半島の先カンブリア紀の基盤は,日本の顕生代の地層の地質学的ルーツであり,日本地質学会と大韓地質学会は,古代から深い交流のある隣国のパートナーとして重要な存在である.学術交流協定の調印以来,両学会は交互に学術大会(総会)に代表団を派遣し,学会の執行部レベルの情報交換を行ってきた.日本地質学会構造地質部会が主催する合同巡検も何度か開催されていた.このような日本地質学会と大韓地質学会の交流は数回に渡ってニュース誌に掲載されてきた注2. 2024年の第37回万国地質学会議の韓国開催という提案への支持表明は,こうした活動の自然な延長線上にあるものであったが,両学会の意見が一致せず, 2024年に韓国で開催予定の万国地質学会議は日本地質学会の公式支援なしで開催されることになった(https://geosociety.jp/science/content0150.html).こうした困難はあるものの,貴重なパートナーであることに変わりはなく,今までの交流実績をさらに発展させることが重要である.
タイやモンゴルの地質学会との関係は,これまで学術大会に相互に代表団を派遣するという活動を主とするものに留まっている.しかし,両国地質学会との学術交流協定は,国際シンポジウムや国際共同研究を実施するための重要な基礎となっており,将来的にさらなる発展が期待される.台湾と日本は地質学の歴史において多くの側面を共有している.台湾地質学会との国際交流協定により,若手研究者を主たる対象とする合同巡検が,磯崎行雄会長の主導のもとで実現に向けて検討されたが,新型コロナウィルス感染症の感染拡大のため実施には至らず,バーチャルなセレモニーで学術交流協定を更新することに留まった.
以上のように,日本地質学会の国際交流は最近の十数年間で大きく発展し,The Geology of Japanの出版のような目に見える成果を挙げてきた.
国際シンポジウムの開催は,日本地質学会の国際的な知名度を向上させるよい方法であり,シンポジウムでの発表内容が国際誌の特集号として出版された例がある.例えば,日本地質学会第122年(2015年長野大会)および第124年(2017年愛媛大会)学術大会では,国際シンポジウム「東アジアの初期テクトニクスと古地理」および「東アジアの古生代古地理」が開催された.両シンポジウムには日本,韓国,英国,タイ,台湾に拠点を置く研究者の講演が集まった. 両シンポジウムは,レスター大学のMark Williams,ウォリス サイモン,大路樹生らの共同研究推進者が得たLeverhulme Trustからの研究助成金が用いられ,その成果はIsland Arcの特集号として結実した(Virtual Issue: The Paleozoic evolution of the Korean Peninsula and Japan; 文献6).この特集号の論文の多くは被引用数が多く,近年のIsland Arcのインパクトファクターの向上に大きく貢献した.また,第122年学術大会では,法地質学に関する国際シンポジウムが開催された.同シンポジウムは,杉田律子がInternational Union of Geological Sciences, Initiative on Forensic Geology(IUGS-IFG)の協力を得て開催したもので,海外からの参加者に対しては財政的なサポートがなされた.シンポジウムの成果は地質学雑誌の特集号「法地質学の進歩」として出版され(文献7),急速に発展する地質学の一分野が,多くの地質学関係者に紹介された.
日本地質学会の将来を展望し,国際的なネットワークのさらなる発展のために,同学会の創立125周年記念として開催された第125回学術大会(2019年札幌大会)では,ウォリス サイモン,矢島道子,竹下 徹が主宰する国際シンポジウム「社会と地質」に国際交流協定締結学会の会員が招待された.残念ながら,胆振東部地震の影響でシンポジウムにおける発表は中止となったが,国際交流協定締結学会の代表者と2時間ほどの会議を行うことができた.同会議では,以下が合意された.
各学会のより質の高い情報や連絡の詳細を開示すれば,相互のコミュニケーションが円滑になり,協力がしやすくなる.
巡検への参加は,その地域の地質を新たに学べるだけでなく,率直な意見交換が可能であり,良好な関係を構築するための優れた方法である.
これまでの成功に終わった国際シンポジウムが示すように,財団や企業の財政的なサポートは国際交流プログラムを維持・発展させるための鍵である.
各学会が実施する年会で,英語を公用語とする国際シンポジウムを定期的に開催すれば,交流はさらに深まると期待される.
ソーシャルメディアは,特に若い世代にとって,コミュニケーションや情報交換を効果的かつ円滑に行うためのツールとなっており,今後,その重要性はさらに高まる.
ウクライナでの戦争は,人類を結びつける共通の価値観の重要性とその存在のもろさを思い起こさせた.国際的な理解と調和に少しでも貢献することは価値があることである.過去15年間,われわれはこの原則に沿って日本地質学会と世界の地球科学関連学会との交流の発展に貢献しようと尽力してきた.コロナ以後の新しい世界では国際協力への新しい挑戦が始まり,これには地理的な境界を越えるオンライン・コミュニケーションの新しいツールが役立っている.われわれは,日本地質学会が国際的な学術活動をさらに活発化させ,地球科学の世界的なハブとしての役割を発展させ続ける次の15年に大きく期待している.
引用文献
Wu, S. X., 2015, Empires of Coal: Fueling China's Entry into the Modern World Order, 1860-1920. Stanford Univ. Press. 280p.
S. Fujino, K. Goto, D. Tappin & O. Fujiwara, eds., 2016, Geological records of storms, tsunamis and other extreme events. Island Arc 25, issue 5.
E. M. Scourse, N. A. Chapman, D. R. Tappin & S. R. Wallis, eds., 2018, Tsunamis: Geology, Hazards and Risks. Spec. Publ. Geol. Soc. London, 252p.
石澤尭史・渡部真史・後藤和久・池原 研・S. R. Wallis・井龍康文, 2016, 地質学雑誌122, I-II.
T. Moreno, S. R. Wallis, T. Kojima & W. Gibbons, eds, 2016, The Geology of Japan. Geological Society of London 522p.
S. R. Wallis, T. Oji, M. Williams & M. Cho, 2019, Virtual Issue: The Paleozoic evolution of the Korean Peninsula and Japan. Island Arc.
杉田律子・川村紀子編,2020,特集号:法地質学の進歩.日本地質学雑誌第126巻, 第8号.
注釈1:
英語の「Geology」を初めて「地質学」と訳したのは, イギリス人のW. Muirhead師(1822–1900)が1853年に著した「地理全誌」(中国語)であり(文献1),その新しい学問が国内に広まったことにドイツ人のH. E. Naumann博士(1854–1927)が大きく寄与したことがよく知られている. すなわち,日本の地質学分野のルーツは国際的な協力に深く関わっていると言える.
注釈2:
日韓地質学会学術交流協定調印. 井龍康文,日本地質学会News, 15(11), 27-28 (2012)
韓国2013秋季地質科学連合学術大会(大韓地質学会第68次定期総会)公式訪問の報告.石渡 明,日本地質学会News, 16(11), 47-48 (2013) https://www.geosociety.jp/faq/content0481.html
鹿児島学術大会での国際交流.ウォリス サイモン,日本地質学会News, 17(11), 49-50 (2014)
日本地質学会第122年学術大会(長野大会)における国際交流活動報告.ウォリス サイモン,日本地質学会News, 19(3), 12 (2016)
2015 Fall Joint Conference of Geological Science of Korea 参加報告.井龍康文,日本地質学会News, 19(3), 13 (2016)
日本地質学会第123年学術大会(桜上水大会)における国際交流活動.井龍康文,日本地質学会News, 19(11), 38 (2016)
大韓地質学会創立 70 周年記念国際シンポジウム参加報告.井龍康文・辻森 樹,日本地質学会News, 21(1), 9 (2018) http://geosociety.jp/uploads/fckeditor/science/20171025korea.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・【129巻オンデマンド印刷版年間購読受付のお知らせ】
昨年同様,WEB上での論文閲覧が難しい方への対応として,地質学雑誌
オンデマンド印刷版を作成し,年間購読のお申込を受け付けます.ご希望
の方は学会事務局までお申し込みください.受付締切:3月20日(月)
詳しくは,http://geosociety.jp/news/n169.html
■ Island Arc
・Accepted Articles廃止のお知らせ
2023年3月以降,受理原稿(Accepted Articles: AA)の早期オンライン掲載が
廃止されます.ワイリー社全体の方針で,背景に出版物の責任問題(出版規範
委員会の定義では,AA版と正式版[Version of Record: VOR版]のどちらも
出版物扱い),取り下げ・撤回増加の懸念,ペーパーミル問題の悪化(論文
作成・販売する違法組織織を利用した不正論文の増加),があります.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
・2023年度支部総会・講演会
日時:4月9日(日)14:00-16:45
場所:大田区産業プラザPiO 3階 特別会議室(京急蒲田駅前)
講師:宇根 寛氏(元国土地理院,中央開発(株)技術顧問)
演題:「Web地図を活かして災害リスクを理解する」
総会委任状期日:4月6日(木)必着(FAX)/4月7日(金)18時(e-mail)
http://geosociety.jp/outline/content0201.html#2023sokai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
気象庁:関東大震災特設サイト
ー関東大震災から100年ー知って備えよう:過去の大災害から学ぶ
https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/1923_09_01_kantoujishin/index.html
防災学術連携体:関東大震災100年関連行事等の特設ページ
https://janet-dr.com/090_abroadandhome/091_100_kantohEQ.html
-------------------------------------------------
地質情報展2023いわて
明日につなぐ大地の知恵
3月10日(金)-12日(日)
場所:岩手県立博物館 岩手山を望める丘のミュージアム
(注)博物館の入館料がかかります
https://www.gsj.jp/event/johoten/2023/iwate/index.html
(後)観察会 「宅地開発で隠れた衣笠断層帯を歩く」
主催:三浦半島活断層調査会
3月18日(日)9:30-15:00時
参加申込締切:3月11日(土)
https://geosociety.jp/uploads/fckeditor/others-pdf/kinugasa2023-1.pdf
技術士を目指そう 修習ガイダンス2023
主催:技術士会修習技術者支援委員会
4月8日(土)13:00-17:00
場所:
1)オンライン(Zoomを使用)定員 700名
2)機械振興会館(東京都港区芝公園3-5-8)定員50名
参加費:3,000円 (会員,非会員共通)
https://www.engineer.or.jp/c_topics/009/009253.html
(後)第60回アイソトープ・放射線研究発表会
7月5日(水)-7日(金)
会場:東京都内会場(予定)
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2023/top
(共)岩石-水相互作用(WRI-17)または
応用同位体地球化学(AIG-14)合同国際会議
8月18日(金)-22日(火)
会場:仙台国際センター
口頭発表登録締切:3月31日
参加料金早期割引締切:4月30日
https://www.wri17.com/
ぼうさいこくたい2023(第8回防災推進国民大会)
9月17日(日)-18日(月・祝)
場所:横浜国立大学(横浜市保土ヶ谷区常盤台)
https://bosai-kokutai.jp/2023/
(協)Techno-Ocean 2023
10月5日(木)-7日(土)
会場:神戸国際展示場2号館 ほか
https://to2023.techno-ocean.com/
国際ゴンドワナ研究連合(IAGR)2023年総会
及び第20回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム
10月8日-9日(シンポジウム)
10月10日-11日(糸魚川ユネスコ世界ジオパーク野外巡検)
会場:新潟大学中央図書館ライブラリーホール
問い合わせ:M. Satish-Kumar iagr2023[at]geo.sc.niigata-u.ac.jp
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・第20回(2023年度)日本学術振興会賞受賞候補者推薦依頼(学会締切3/20)
・原子力規制庁令和5年度原子力規制人材育成事業の公募(3/23)
・2023年コスモス国際賞候補者推薦依頼(学会締切3/31)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.577 今年もはじまるよ!2023年「地質の日」
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.577 2023/3/22┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2023年「地質の日」行事のご案内
【2】第14回惑星地球フォトコンテスト:審査結果発表
【3】第130年学術大会(2023京都)トピックセッションまもなく締切
【4】第3回JABEEシンポジウム:YouTube公開中
【5】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】学会が主催する対面行事・イベントにおけるマスク着用について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2023年「地質の日」行事のご案内
──────────────────────────────────
2008年より,5月10日が『地質の日』に制定され,これを記念した多くの
イベントが,全国各地の博物館・大学で開催されています.
—----------------------------
オンライン普及講演会:「日本列島の地質探訪―古生代から新生代まで」
各地のジオパーク拠点博物館に協力いただき,オンラインで各施設の展示や
地域の露頭等を紹介することで,聴講者が自宅にいながらにして各地の地質
の魅力に“触れ”,日本列島の地質の多様性に“触れる”機会とします.
日時:5月13日(土)9:30-12:05
開催方法:YouTubeライブ配信 どなたでも視聴可能,申込不要,無料
・講演1「四国西予ジオパークと黒瀬川帯
・講演2「銚子半島をつくった孤独でふしぎな中生代の地層」
・講演3「糸魚川からフォッサマグナと日本列島誕生の謎に迫る」
***************************************
このほか,学会関連の「地質の日」行事については,学会ホームページに
随時情報を掲載しています.
・惑星地球フォトコンテスト入選作品展示会(5/16−28)(台東区上野公園)
・街中ジオ散歩in Yokohama「身近な地形・地質から探る横浜の歴史」(5/14)
・近畿支部:第40回地球科学講演会「日本海拡大時の日本列島の変動―地質と
古地磁気の研究からどこまでわかっているかー」(5/14)大阪自然史博物館
申込締切:5/1(月)/YouTube同時配信も行います.
詳しくは,http://geosociety.jp/name/content0178.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第14回惑星地球フォトコンテスト:審査結果発表
──────────────────────────────────
応募作品全359作品のうち,入選12点,佳作11点が決定しました.
作品画像は近日学会HP上にて公開の予定です.
最優秀賞:
朝永武志(長崎県)古代の双六
優秀賞(2点):
近藤 洋(兵庫県)大西洋と砂漠
佐藤竜治(静岡県)リンシェ村
ジオパーク賞:
高場智博(長崎県)個性豊かな、まぁ〜るい畑
日本地質学会会長賞:
大坪 誠(茨城県)屋根瓦のような重なり
ジオ鉄賞:
礒部忠義(福岡県)日南海岸の洗濯岩
その他の結果は,http://www.photo.geosociety.jp/
【作品展示予定】
東京パークスギャラリー(上野)
5月16日(火)-5月28日(日)
場所:上野恩賜公園 上野グリーンサロン内(台東区上野公園7-47)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】第130年学術大会(2023京都)トピックセッションまもなく締切
──────────────────────────────────
第130年学術大会(2023年京都大会)
会期:2023年9月17日(日)-19日(火)
会場:京都大学吉田南構内
*************************************************
トピックセッション提案募集締切:3月27日(月)
*************************************************
昨年の大会からセッションは
・「トピックセッション(会員提案型)」
・「ジェネラルセッション」
・「アウトリーチセッション」の3カテゴリになりました.
詳しくは,http://geosociety.jp/science/content0155.html
(注意)学術大会は9月の連休です.また,京都ではコロナ前の
オーバーツーリズムが夏には戻ってくることが予想されます.
早めの宿の確保をお勧めします!!
【京都大会プレサイト】http://geosociety.jp/science/content0156.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第3回JABEEシンポジウム:YouTube公開中
──────────────────────────────────
第3回JABEEシンポジウム「大学ー企業の架け橋教育 ユニークな実例紹介」
3月5日に標記のシンポジウムを開催しました.
シンポジウムの内容(動画)は,YouTubeで公開中です.
ご参加いただけなかった皆様もぜひご覧ください.
詳しくは,http://geosociety.jp/science/content0152.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・129巻の新しい論文等が公開されています.
(論説)鹿児島県喜界島で発見された下部更新統知念層とその意義:松田博貴ほか/
(論説)中新世の日本海拡大に伴う東北日本前弧域火山活動:茨城県,塩子無斑晶
状安山岩の地球化学的特徴 山元孝広ほか/(総説)暁新世−始新世温暖化極大の海
洋酸性化:山口龍彦ほか
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/-char/ja
■ Island Arc
・Volume 32の新しい論文が公開されています.
Zircon geochronology of the deformed matrix in the NE Jiangxi ophiolitic mélange
belt: Time constraints on the Neoproterozoic evolution of the Paleo–South China
Ocean and assembly of the Yangtze and Cathaysia blocks Zhu Qingbo,et al
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
・2023年度支部総会・講演会
日時:4月9日(日)14:00-16:45
場所:大田区産業プラザPiO 3階 特別会議室(京急蒲田駅前)
講師:宇根 寛氏(元国土地理院,中央開発(株)技術顧問)
演題:「Web地図を活かして災害リスクを理解する」
総会・講演会参加申込締切:4月5日(水)17時
(申込フォーム)https://forms.gle/wwiuejM2pGrfXZ7K6
総会委任状期日:【FAX】4月6日(木)必着/【e-mail】4月7日(金)18時
詳しくは,http://geosociety.jp/outline/content0201.html#2023sokai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
気象庁:関東大震災特設サイト
ー関東大震災から100年ー知って備えよう:過去の大災害から学ぶ
https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/1923_09_01_kantoujishin/index.html
防災学術連携体:関東大震災100年関連行事等の特設ページ
https://janet-dr.com/090_abroadandhome/091_100_kantohEQ.html
-------------------------------------------------
(後)第60回アイソトープ・放射線研究発表会
7月5日(水)-7日(金)
会場:東京都内会場(予定)
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2023/top
(共)岩石-水相互作用(WRI-17)または
応用同位体地球化学(AIG-14)合同国際会議
8月18日(金)-22日(火)
会場:仙台国際センター
口頭発表登録締切:3月31日
参加料金早期割引締切:4月30日
https://www.wri17.com/
WCFS2023 Japan
Floating Solutions for the Next SDGs
8月28日-29日:論文発表等
8月30日:オプション テクニカルツアー
場所:日本大学理工学部(東京都千代田区神田駿河台)(予定)
https://wcfs2023.nextsdgs.org/
ぼうさいこくたい2023(第8回防災推進国民大会)
9月17日(日)-18日(月・祝)
場所:横浜国立大学(横浜市保土ヶ谷区常盤台)
https://bosai-kokutai.jp/2023/
(協)Techno-Ocean 2023
10月5日(木)-7日(土)
会場:神戸国際展示場2号館 ほか
https://to2023.techno-ocean.com/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・産業技術総合研究所地質調査総合センター修士型研究員公募(3/23)
・弘前大学大学院理工学研究科(変動地形学・測地学など)准教授公募(6/8)
・令和5年度ふじのくに地球環境史ミュージアム職員募集(5/9)
・JST「カフラマンマラシュ(トルコ南東部)地震関連国際緊急共同研究・調査
支援プログラム(J-RAPID)」課題募集(5/31)
・2023年度東京大学地震研究所第2回大型計算機共同利用公募(5/31)
・2023年度室戸ユネスコ世界ジオパーク学術研究助成(5/9)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】学会が主催する対面行事・イベントにおけるマスク着用について
──────────────────────────────────
新型コロナウイルス感染症に対する政府のマスク着用の考え方が変更され,
3月13日からはマスクの着用が「個人の判断」に委ねられることになりました.
日本地質学会では,これまで対面行事・イベントでは適切な感染防止対策の
一環としてマスク着用を推奨していましたが,政府の方針変更を受けて,対応
方針を変更いたします.
詳しくは,http://geosociety.jp/news/n160.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.578 特集号「球状コンクリーションの科学」全論文公開!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.578 2023/4/4┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2023年「地質の日」行事のご案内
【2】2023京都大会:トピックセッション採択
【3】第3回JABEEシンポジウム:YouTube公開中
【4】地質学雑誌からのお知らせ
【5】地質学雑誌特集号(冊子)販売のお知らせ
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】学会が主催する対面行事・イベントにおけるマスク着用について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2023年「地質の日」行事のご案内
──────────────────────────────────
2008年より,5月10日が『地質の日』に制定され,これを記念した多くの
イベントが,全国各地の博物館・大学で開催されています.
—----------------------------
オンライン普及講演会:「日本列島の地質探訪―古生代から新生代まで」
各地のジオパーク拠点博物館に協力いただき,オンラインで各施設の展示や
地域の露頭等を紹介することで,聴講者が自宅にいながらにして各地の地質
の魅力に“触れ”,日本列島の地質の多様性に“触れる”機会とします.
日時:5月13日(土)9:30-12:05
開催方法:YouTubeライブ配信 どなたでも視聴可能,申込不要,無料
・講演1「四国西予ジオパークと黒瀬川帯
・講演2「銚子半島をつくった孤独でふしぎな中生代の地層」
・講演3「糸魚川からフォッサマグナと日本列島誕生の謎に迫る」
***************************************
このほか,学会関連の「地質の日」行事については,学会ホームページに
随時情報を掲載しています.
詳しくは,http://geosociety.jp/name/content0178.html
・惑星地球フォトコンテスト入選作品展示会(5/16−28)(台東区上野公園)
・街中ジオ散歩in Yokohama「身近な地形・地質から探る横浜の歴史」(5/14)
・近畿支部:第40回地球科学講演会「日本海拡大時の日本列島の変動―地質と
古地磁気の研究からどこまでわかっているかー」(5/14)大阪自然史博物館
申込締切:5/1(月)/YouTube同時配信.
・西日本支部:第15回「地質の日」企画 身近に知る「くまもとの大地」(5/21)
ほか
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2023京都大会:トピックセッション採択しました
──────────────────────────────────
第130年学術大会(2023京都)のトピックセッションを採択いたしました.
5月末頃演題登録・講演要旨受付開始,7/12:締切の予定です.
T1.岩石・鉱物の変形と反応
T2.変成岩とテクトニクス
T3.大地と人間活動を楽しみながら学ぶジオパーク
T4.中生代日本と極東アジアの古地理・テクトニクス的リンク
T5.テクトニクス
T6.堆積地質学の最新研究
T7.鉱物資源研究の最前線
T8.フィールドデータにおける応力逆解析総決算
T9 .マグマソースからマグマ供給システムまで
T10.文化地質学
T11.南極研究の最前線
T12.地球史
T13.沈み込み帯・陸上付加体
T14.原子力と地質科学
T15.地域地質・層序学:現在と展望
T16.都市地質学:自然と社会の融合領域
2023京都大会プレサイトはこちら
http://geosociety.jp/science/content0156.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】第3回JABEEシンポジウム:YouTube公開中
──────────────────────────────────
第3回JABEEシンポジウム「大学ー企業の架け橋教育 ユニークな実例紹介」
3月5日に標記のシンポジウムを開催しました.
シンポジウムの内容(動画)は,YouTubeで公開中です.
ご参加いただけなかった皆様もぜひご覧ください.
詳しくは,http://geosociety.jp/science/content0152.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地質学雑誌からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・129巻の新しい論文等が公開されています.
(総説)地球と火星に見られる球状鉄コンクリーションの産状と成因:長谷川 精
ほか/(論説)兵庫県北西部,但馬御火浦の下部中新統八鹿層の盆地構造・堆積年
代・古応力:羽地俊樹ほか/(論説)長崎半島東岸長崎市北浦町の上部白亜系層序
の再定義とその地質年代学的意義:宮田和周ほか/(論説)球状鉄コンクリーション
の鉄殻成長過程の実験的解明:岡村裕之ほか(レター)東京低地の埋没谷形状と
地盤震動特性:上野-小岩測線での検討結果:中澤 努ほか
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/-char/ja
・特集 球状コンクリーションの科学―理解と応用― 全論文公開!
http://geosociety.jp/publication/content0103.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質学雑誌特集号(冊子)販売のお知らせ
──────────────────────────────────
球状コンクリーションの科学―理解と応用―
世話人 吉田英一・西本昌司・長谷川 精・勝田長貴
本特集号は,2021年学術大会で開催された特別シンポジウム「球状コンクリー
ションの科学−理解と応用−」で発表された研究およびその趣旨に関連した研究
を集約・紹介し,この分野の今後の発展に資するために企画されたものです.
【内容】本⽂フルカラーA4版,約150ページ
【価格】2,600円/冊+送料370円(会員価格)
【申込受付期間】2023年5月31日(水)
※残部があれば,ジオストアでも販売いたします(定価:3,000円+送料)
それぞれの論文は,地質学雑誌掲載論文としてJ-STAGE上で閲覧可能ですが,
1冊のまとまった冊子をぜひお手元の蔵書に加えて下さい.
詳しくは,http://geosociety.jp/news/n174.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
・2023年度支部総会・講演会
日時:4月9日(日)14:00-16:45
場所:大田区産業プラザPiO 3階 特別会議室(京急蒲田駅前)
講師:宇根 寛氏(元国土地理院,中央開発(株)技術顧問)
演題:Web地図を活かして災害リスクを理解する」
総会・講演会参加申込締切:4月5日(水)17時
(申込フォーム)https://forms.gle/wwiuejM2pGrfXZ7K6
総会委任状期日:【FAX】4月6日(木)必着/【e-mail】4月7日(金)18時
詳しくは,http://geosociety.jp/outline/content0201.html#2023sokai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
気象庁:関東大震災特設サイト
ー関東大震災から100年ー知って備えよう:過去の大災害から学ぶ
https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/1923_09_01_kantoujishin/index.html
防災学術連携体:関東大震災100年関連行事等の特設ページ
https://janet-dr.com/090_abroadandhome/091_100_kantohEQ.html
-------------------------------------------------
(後)第60回アイソトープ・放射線研究発表会
7月5日(水)-7日(金)
会場:東京都内会場(予定)
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2023/top
(共)岩石-水相互作用(WRI-17)または
応用同位体地球化学(AIG-14)合同国際会議
8月18日(金)-22日(火)
会場:仙台国際センター
口頭発表登録締切:3月31日
参加料金早期割引締切:4月30日
https://www.wri17.com/
ぼうさいこくたい2023(第8回防災推進国民大会)
9月17日(日)-18日(月・祝)
場所:横浜国立大学(横浜市保土ヶ谷区常盤台)
https://bosai-kokutai.jp/2023/
(協)Techno-Ocean 2023
10月5日(木)-7日(土)
会場:神戸国際展示場2号館 ほか
https://to2023.techno-ocean.com/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究施設 准教授 公募(6/9)
・福岡大学理学部地球圏科学科地球科学分野公募(地球物質科学:助教)(6/30)
・福岡大学理学部地球圏科学科地球科学分野公募(古生物学・地球史:助教)(5/31)
・2024-2025年開催藤原セミナー募集(7/31)
・伊藤科学振興会2023年度研究助成公募(宇宙地球科学分野)(4/20-7/5)
・2023年度深田賞募集(6/30)
・下仁田ジオパーク学術奨励金(4/25)
・令和5年度隠岐ユネスコ世界ジオパーク学術奨励事業募集(新規5/29,継続4/28)
詳細およびその他の公募情報は,
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】学会が主催する対面行事・イベントにおけるマスク着用について
──────────────────────────────────
新型コロナウイルス感染症に対する政府のマスク着用の考え方が変更され,
3月13日からはマスクの着用が「個人の判断」に委ねられることになりました.
日本地質学会では,これまで対面行事・イベントでは適切な感染防止対策の
一環としてマスク着用を推奨していましたが,政府の方針変更を受けて,
対応方針を変更いたします.
詳しくは,http://geosociety.jp/news/n160.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.579 2023年「地質の日」イベント続々準備中!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.579 2023/4/18┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2023年「地質の日」行事のご案内
【2】今年も地質系業界説明会を開催します!
【3】科学技術系分野における任期付き研究者の雇用問題解決に向けての要望
【4】地質学雑誌からのお知らせ
【5】地質学雑誌特集号(冊子)販売のお知らせ
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2023年「地質の日」行事のご案内
──────────────────────────────────
2008年より,5月10日が『地質の日』に制定され,これを記念した多くの
イベントが,全国各地の博物館・大学で開催されています.
—----------------------------
オンライン普及講演会:「日本列島の地質探訪―古生代から新生代まで」
各地のジオパーク拠点博物館に協力いただき,オンラインで各施設の展示や
地域の露頭等を紹介することで,聴講者が自宅にいながらにして各地の地質
の魅力に“触れ”,日本列島の地質の多様性に“触れる”機会とします.
日時:5月13日(土)9:30-12:05
開催方法:YouTubeライブ配信 どなたでも視聴可能,申込不要,無料
・講演1「四国西予ジオパークと黒瀬川帯
・講演2「銚子半島をつくった孤独でふしぎな中生代の地層」
・講演3「糸魚川からフォッサマグナと日本列島誕生の謎に迫る」
***************************************
このほか,学会関連の「地質の日」行事については,学会ホームページに
随時情報を掲載しています.
詳しくは,http://geosociety.jp/name/content0178.html
・惑星地球フォトコンテスト入選作品展示会(5/16−28)(台東区上野公園)
・街中ジオ散歩in Yokohama「身近な地形・地質から探る横浜の歴史」(5/14)
・近畿支部:第40回地球科学講演会「日本海拡大時の日本列島の変動―地質と
古地磁気の研究からどこまでわかっているかー」(5/14)大阪自然史博物館
申込締切:5/1(月)/YouTube同時配信.
・四国支部:化石発掘体験-化石レプリカを見つけてみよう!(5/13)愛媛大学
ミュージアム
・西日本支部:第15回「地質の日」企画 身近に知る「くまもとの大地」(5/21)
ほか
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】今年も地質系業界説明会を開催します!
──────────────────────────────────
学生会員が将来就職する可能性のある地質・資源・建設分野に関わる地質系企業・
団体との対面説明会を企画・開催し,学生会員が地質系業界を研究するサポート
サービスを展開しています.
対面説明会:9月18日(月・祝) 会場:京都大学(第130年学術大会)
オンライン説明会:9月22日(金)午後
詳しくは,http://geosociety.jp/science/content0159.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】科学技術系分野における任期付き研究者の雇用問題解決に向けての要望
──────────────────────────────────
日本地質学会がオブザーバーとして参加し,JpGU(地質学会は正式加盟学協会)
としては正式加盟している「男女共同参画学協会連絡会」から男女共同参画
学協会連絡会要望書「科学技術系分野における任期付き研究者の雇用問題解決
に向けての要望 :若手・氷河期世代研究者の待遇改善が研究力強化につながる」
とその説明資料についてご案内頂きました.以前皆様にご協力頂いたアンケート
が元となって今回の提言に繋がっております.詳細は以下をご覧下さい.
(日本地質学会ジェンダー・ダイバーシティ委員会)
要望のページ
https://djrenrakukai.org/proposal_request.html
要望書本体PDF
https://djrenrakukai.org/request/230327.pdf
説明資料PDF
https://djrenrakukai.org/request/230327_shiryou.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・129巻の新しい論文等が公開されています.
(案内書)チバニアンGSSPサイトと陸化した前弧海盆上総層群の層序:岡田 誠
ほか/(論説)北海道中央東部糠平湖周辺の後期新生代の古植生と古環境:成田
敦史ほか/(論説)福島県南部,二岐山火山の噴火史とマグマ供給系:渡部将太
ほか/(論説)中新統,師崎層群と瑞浪層群に含まれる軽石質凝灰岩の対比:
古川邦之ほか
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/-char/ja
■ Island Arc
・Vol. 32の新しい論文が公開されています.
Early Paleozoic oceanic slab subduction in South China: Evidence from
adakite-like granodiorite and high-Mg diorite from Puyang pluton in the Wuyi
orogenic belt:Xiaodong Zhou et al
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質学雑誌特集号(冊子)販売のお知らせ
──────────────────────────────────
球状コンクリーションの科学―理解と応用―
世話人 吉田英一・西本昌司・長谷川 精・勝田長貴
本特集号は,2021年学術大会で開催された特別シンポジウム「球状コンクリー
ションの科学−理解と応用−」で発表された研究およびその趣旨に関連した研究
を集約・紹介し,この分野の今後の発展に資するために企画されたものです.
【内容】本⽂フルカラーA4版,約150ページ
【価格】2,600円/冊+送料370円(会員価格)
【申込受付期間】2023年5月31日(水)
※残部があれば,ジオストアでも販売いたします(定価:3,000円+送料)
それぞれの論文は,地質学雑誌掲載論文としてJ-STAGE上で閲覧可能ですが,
1冊のまとまった冊子をぜひお手元の蔵書に加えて下さい.
詳しくは,http://geosociety.jp/news/n174.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[中部支部]
・2023年支部年会開催のお知らせ
6月24日(土)
会場:信州大学松本キャンパス
シンポジウム『西南日本の白亜紀花崗岩類』
巡検:大峰帯第四系と爺ヶ岳ー白沢天狗カルデラ・黒部川花崗岩(6/25)
事前登録:6月15日(木)
巡検参加申込締切:6月1日(木)
詳しくは,http://geosociety.jp/outline/content0019.html
[関東支部]
・学生・初級者向け「地質断面図」の書き方講座のお知らせ―布良海岸巡検―
5月27日(土)千葉県館山市布良海岸付近で野外調査
5月28日(日)JR総武線船橋駅〜千葉駅付近で地質断面図作成(室内作業)
申込期間:2023年5月7日(日)-5月19日(金)定員になり次第締め切り
http://geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
気象庁:関東大震災特設サイト
ー関東大震災から100年ー知って備えよう:過去の大災害から学ぶ
https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/1923_09_01_kantoujishin/index.html
防災学術連携体:関東大震災100年関連行事等の特設ページ
https://janet-dr.com/090_abroadandhome/091_100_kantohEQ.html
-------------------------------------------------
ワークショップ:掘削とモニタリングによる海山沈み込みと
スロー地震の関係の解明
5月27日(土)9:00-
場所:東京大学地震研究所1号館2Fセミナー室(対面+ハイブリッド)
※要参加申込
http://www.cc.kochi-u.ac.jp/~hassy/WS_SS/
(後)日本学術会議公開シンポジウム
「有人潜水調査船の未来を語る」
6⽉17日(⼟)13:00-17:00
場所:日本学術会議講堂 (オンライン配信ハイブリッド)
後援:日本地質学会ほか
⼀般参加可,参加費不要
https://www.scj.go.jp/ja/event/index.html
(後)第60回アイソトープ・放射線研究発表会
7月5日(水)-7日(金)
会場:東京都内会場(予定)
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2023/top
(共)岩石-水相互作用(WRI-17)または
応用同位体地球化学(AIG-14)合同国際会議
8月18日(金)-22日(火)
会場:仙台国際センター
口頭発表登録締切:3月31日
参加料金早期割引締切:4月30日
https://www.wri17.com/
ぼうさいこくたい2023(第8回防災推進国民大会)
9月17日(日)-18日(月・祝)
場所:横浜国立大学(横浜市保土ヶ谷区常盤台)
https://bosai-kokutai.jp/2023/
2023年度日本地球化学会 第70回年会
9月21日(⽊)-23日(土)
開催場所 東京海洋大学品川キャンパス会場(⼀部ハイブリッド)
口頭発表(ハイブリッド),ポスター発表(対面)
http://www.geochem.jp/meeting/
(協)Techno-Ocean 2023
10月5日(木)-7日(土)
会場:神戸国際展示場2号館 ほか
https://to2023.techno-ocean.com/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・JST「カフラマンマラシュ(トルコ南東部)地震関連国際緊急共同研究・調査
支援プログラム(J-RAPID)」課題募集(5/31)
・第14回(令和5年度)日本学術振興会育志賞候補者推薦依頼(学会推薦5/12)
・住友財団2023年度環境研究助成(6/30)
・住友財団2023年度基礎科学研究助成(6/30)
・東京工業大学科学技術創成研究院多元レジリエンス研究センター火山・
地震研究部門助教公募(5/31)
・産総研地質調査総合センター研究職員(パーマネント型研究員)(陸域の地質
調査及び地質図の作成ほか)(5/9)
・ジオパーク関連情報(研究助成,専門員募集など)
その他,公募,助成等の情報は,http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
第14回フォトコンテスト(優秀賞2)
第14回惑星地球フォトコンテスト入選作品
優秀賞:Lingshed Village
写真:佐藤竜治(静岡県)
撮影場所:インド ザンスカール地方,リンシェ村
【撮影者より】
インドのヒマラヤにあるラダック連峰の山奥,ザンスカール地方のリンシェ村です.献身なチベットの仏教の村で標高は約4000m.冬はマイナス30度以下になります.私は標高5000m超えの峠を二つ越え,4日間歩き続けこの村に辿り着きました.雨のほとんど降らないこの山の土地は砂漠のように乾いています.村のあるところにはヒマラヤの雪解け水の川が流れており,厳しい環境ながら大麦を育てられることで,人が住めます.太古の昔この山は海の底にありました.今では人類が住まう最高峰の村の一つであることも感動します.そしてこの地で出会い支えてくれた友人たちに心から感謝します.
【審査委員長講評】
撮影地はインド最北部でパキスタン・中国との国境間近,ヒマラヤ山系のインダス川源流に近い秘境です.滑らかな山腹と谷壁にのぞく地層,どのようにして出来たのか好奇心が湧いてきます.それとともにこのような場所で暮らす人々の生活や信仰にも興味が湧いてきます
目次へ戻る
第14回フォトコンテスト(最優秀賞)
第14回惑星地球フォトコンテスト入選作品
最優秀賞:古代の双六
写真:朝永武志(長崎県)
撮影場所:長崎県平戸市生月島 塩俵断崖
【撮影者より】
地元で見る事が出来る柱状節理。眺めていたら『スゴロクのマス』の様で面白いと感じ撮影しました。
【審査委員長講評】
この作品はドローンを使って柱状節理を撮影したものです.地上からの撮影では柱状節理の上面の六角形だけ,あるいは柱状だけとなりがちですが,ドローンを適切に配置して上面も側面も捉えています.しかも海中にも柱状節理の六角形がたくさん写っています.海面の青緑,白波,玄武岩の褐色,草の緑と色のコントラストも見事です.
【地質的背景】
九州の北西部にはアルカリ玄武岩が広く分布しており、各所で平坦な玄武岩台地が形成されています。この写真の撮影地は陸上で見られる分布域の西端近くにあたる、長崎県平戸市の生月島(いきつきしま)で、いまからおよそ700万年前に噴出した北松浦玄武岩類とよばれる溶岩の見事な柱状節理が捉えられています。北松浦玄武岩は、沈み込み帯でできる一般的な火山とはことなり、下部マントルなどかなり深いところから上昇してきたマントルダイアピルの影響で形成されたマグマが噴出したものと考えられています。(萬年一剛:神奈川県温泉地学研究所)
目次へ戻る
第14回フォトコンテスト(優秀賞1)
第14回惑星地球フォトコンテスト入選作品
優秀賞:大西洋と砂漠
写真:近藤 洋(兵庫県)
撮影場所:ナミビア
【撮影者より】
4人乗りのセスナ機からの撮影です.何しろ狭いのと,窓ガラスの反射が気になって,とても苦労しました.押し寄せる白波の大西洋!荒波にもこの砂漠の面積は一向に減少しないようです.この様子は南北に亘って何キロも續きます.壮観!
【審査委員長講評】
ナミブ砂漠はナミビア西海岸に広がる大砂漠で,大きな砂丘は高さ300mもあります.この砂漠の広がりを写すにはドローンでは無理で,作者は観光用のセスナから撮影しています.この作品を2013年撮影のやや古いものですが,現在ではこのような辺境さえもツアーで容易に行けるようになりました.やや彩度を強調しすぎた感がありますが,インパクトの強い作品となっています.
【地質的背景】
写真は大西洋に面して存在するナミブ砂漠を撮ったものです.ナミブ砂漠は大西洋を北上するベンゲラ海流の影響で形成された西岸砂漠で,ドラケンスバーグ山脈から流れるオレンジ川によって海に供給された砂が強い西風によって陸側に押し返されて形成されます.赤色を呈するのはその際に鉄分が付着し,付着した鉄分が酸化されて,酸化鉄になるためです.(小宮 剛:東京大学)
目次へ戻る
【geo-Flash】No.580 2023年度(第15回)代議員総会開催について
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.580 2023/5/2┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2023年度(第15回)代議員総会開催について
【2】2023年「地質の日」行事のご案内
【3】2023京都大会ニュース
【4】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【5】若手巡検・研究集会 in 北海道 洞爺湖有珠山ジオパーク地域
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2023年度(第15回)代議員総会開催について
──────────────────────────────────
日時:2023年6月3日(土)14:00-15:30
※WEB会議形式で開催いたします.
正会員は,総会に陪席することができます.ただし,総会規則12条3項により,
許可のない発言はできません.
議事次第はこちら
http://www.geosociety.jp/outline/content0152.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2023年「地質の日」行事のご案内
──────────────────────────────────
2008年より,5月10日が『地質の日』に制定され,これを記念した多くの
イベントが,全国各地の博物館・大学で開催されています.
----------------------------
オンライン普及講演会:「日本列島の地質探訪―古生代から新生代まで」
日時:5月13日(土)9:30-12:05
開催方法:YouTubeライブ配信(どなたでも視聴可能,申込不要,無料)
・講演1「四国西予ジオパークと黒瀬川帯
・講演2「銚子半島をつくった孤独でふしぎな中生代の地層」
・講演3「糸魚川からフォッサマグナと日本列島誕生の謎に迫る」
***************************************
このほか,学会関連の「地質の日」行事については,学会ホームページに
随時情報を掲載しています.
詳しくは,http://geosociety.jp/name/content0178.html
・惑星地球フォトコンテスト入選作品展示会(5/16−28)(台東区上野公園)
・街中ジオ散歩in Yokohama「身近な地形・地質から探る横浜の歴史」(5/14)
・近畿支部:第40回地球科学講演会「日本海拡大時の日本列島の変動―地質と
古地磁気の研究からどこまでわかっているかー」(5/14)大阪自然史博物館
YouTube同時配信.
・四国支部:化石発掘体験-化石レプリカを見つけてみよう!(5/13)愛媛大学
ミュージアム
・西日本支部:第15回「地質の日」企画 身近に知る「くまもとの大地」(5/21)
ほか
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2023京都大会ニュース
──────────────────────────────────
■ 京都大会までのスケジュール(予定)
5月末(ニュース誌5月号)大会予告記事(演題登録・講演要旨受付開始)
7月12日(水):演題登録・講演要旨受付締切/ランチョン・夜間小集会申込締切
■ 今年も地質系業界説明会を開催します!
学生会員が将来就職する可能性のある地質・資源・建設分野に関わる地質系企業・
団体との対面説明会を企画・開催し,学生会員が地質系業界を研究するサポート
サービスを展開しています.
対面説明会:9月18日(月・祝) 会場:京都大学(第130年学術大会)
オンライン説明会:9月22日(金)午後
詳しくは,http://geosociety.jp/science/content0159.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
特集号「球状コンクリーションの科学―理解と応用―」(冊子体)販売中!
【内容】本文フルカラーA4版,約150ページ
【価格】2,600円/冊+送料370円(会員価格)
【申込受付期間】2023年5月31日(水)
それぞれの論文は,地質学雑誌掲載論文としてJ-STAGE上で閲覧可能ですが,
1冊のまとまった冊子をぜひお手元の蔵書に加えて下さい.
詳しくは,http://geosociety.jp/news/n174.html
■ Island Arc
・Vol. 32の新しい論文が公開されています.
Granite rock towers shaped by mesh‐like joint sets, which formed in the shallower portion of a granite body during cooling at depth:Masahiro Chigira, Hironori Kato ほか
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】若手巡検・研究集会 in 北海道 洞爺湖有珠山ジオパーク地域
──────────────────────────────────
若手活動運営委員会では,洞爺湖周辺にて学生・若手研究者向けの巡検を
行います。夜間には,講師による基調講演と一部参加者によるポスター形式
の研究発表を行い、参加者の交流を深め研究活動を促進することを目的と
しています.
日時:2023年7月8日(土)13時から7月9日(日)18時
対象者:35歳未満の日本地質学会正会員
参加費:
正会員(学生会員):8,000円
正会員(一般会員):16,000円
申込締切:2023年5月31日(水) 17時
詳しくは、http://geosociety.jp/science/content0160.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[中部支部]
・2023年支部年会開催のお知らせ
6月24日(土)
会場:信州大学松本キャンパス
シンポジウム『西南日本の白亜紀花崗岩類』
巡検:大峰帯第四系と爺ヶ岳―白沢天狗カルデラ・黒部川花崗岩(6/25)
事前登録:6月15日(木),巡検参加申込締切:6月1日(木)
詳しくは,http://geosociety.jp/outline/content0019.html
[関東支部]
・学生・初級者向け「地質断面図」の書き方講座のお知らせ―布良海岸巡検―
5月27日(土)千葉県館山市布良海岸付近で野外調査
5月28日(日)JR総武線船橋駅-千葉駅付近で地質断面図作成(室内作業)
申込期間:2023年5月7日(日)-19日(金)定員になり次第締め切り
http://geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
気象庁:関東大震災特設サイト
―関東大震災から100年―知って備えよう:過去の大災害から学ぶ
https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/1923_09_01_kantoujishin/index.html
防災学術連携体:関東大震災100年関連行事等の特設ページ
https://janet-dr.com/090_abroadandhome/091_100_kantohEQ.html
-------------------------------------------------
(後)日本学術会議公開シンポジウム
「有人潜水調査船の未来を語る」
6月17日(土)13:00-17:00
場所:日本学術会議講堂(オンライン配信ハイブリッド)
一般参加可,参加費不要
https://www.scj.go.jp/ja/event/index.html
(後)第60回アイソトープ・放射線研究発表会
7月5日(水)-7日(金)
会場:東京都内会場(予定)
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2023/top
(共)岩石-水相互作用(WRI-17)または
応用同位体地球化学(AIG-14)合同国際会議
8月18日(金)-22日(火)
会場:仙台国際センター
https://www.wri17.com/
ぼうさいこくたい2023(第8回防災推進国民大会)
9月17日(日)-18日(月・祝)
場所:横浜国立大学(横浜市保土ヶ谷区常盤台)
https://bosai-kokutai.jp/2023/
(共)2023年度日本地球化学会 第70回年会
9月21日(木)-23日(土)
開催場所:東京海洋大学品川キャンパス会場(一部ハイブリッド)
口頭発表(ハイブリッド),ポスター発表(対面)
http://www.geochem.jp/meeting/
(協)Techno-Ocean 2023
10月5日(木)-7日(土)
会場:神戸国際展示場2号館 ほか
https://to2023.techno-ocean.com/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・令和5年度福島県教育委員会学芸員(地質学(古生物学))採用選考(6/28)
・鹿児島大学学術研究院理工学域理学系(火山地質学)教授公募(6/19延長)
・秋田県立大学生物資源科学部生物環境科学科環境管理修復グループ自然生態
管理学分野(助教)(8/31)
・JAMSTEC海洋機能利用部門海底資源C地質地球化学G_PD研究員公募(5/23)
・JAMSTEC海域地震火山部門火山・地球内部研究C研究員公募(6/25)
・JST戦略的国際共同研究プログラム(SICORP)日米(NSF)共同研究
「人間中心のデータを活用したレジリエンス研究」公募(8/19)
・南アルプス学会研究助成(5/8)
・「STI for SDGs」アワード 2023年度募集(7/11)
・令和5年度おおいた姫島ジオパーク調査研究活動助成募集(5/31)
・令和5年度佐渡ジオパーク調査研究に関する補助金(5/19)
・湯沢市ゆざわジオパーク学術研究等奨励補助金の募集(6/9)
・令和5年度秋田県ジオパーク研究助成事業募集(5/31)
その他,公募,助成等の情報は,http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.581 新しい会員管理システムの公開・利用について
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.581 2023/5/16┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】新しい会員管理システムの公開・利用について
【2】第8回ショートコース(予告)
【3】2023年度(第15回)代議員総会開催について
【4】2023年「地質の日」行事のご案内
【5】2023京都大会ニュース
【6】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【7】若手巡検・研究集会 in 北海道 洞爺湖有珠山ジオパーク地域
【8】支部情報
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】新しい会員管理システムの公開・利用について
──────────────────────────────────
これまで2年に一度冊子体の会員名簿を発行してまいりましたが,昨今の個人情報
保護の観点や関連諸団体の名簿発行状況等も鑑み,2019年度版会員名簿の発行を
最後に冊子体の会員名簿の発行は行わないことが理事会(2021年12月11日)にて
決議されました.その後,クラウド型会員管理システムの導入準備を進め,今年度
から利用していただくことができるようになりました.
新しいシステムでは,
・会員がWeb上でご自身の情報を確認・修正していただけます(住所変更)
・検索機能にて他の学会員の情報も閲覧可能です(会員名簿)
(注)これまでの会員名簿の掲載ルールに則した内容を公開しており,掲載承諾
を得られた項目について閲覧することができますが,非掲載を選択された項目は
閲覧できません.
詳しくは,http://geosociety.jp/news/n176.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第8回ショートコース(予告)
──────────────────────────────────
日程:2023年7月2日(日)
<午前> 9:00-12:00
レーザーアブレーションーICP質量分析法(LA-ICP-MS法)によるU-Th-Pb年代測定法の原理と最前線:平田岳史(東京大学)
<午後> 14:00-17:00
砕屑性ジルコンU-Pb年代を用いた地質学研究:竹内 誠(名古屋大学)
詳しくは,http://geosociety.jp/science/content0161.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2023年度(第15回)代議員総会開催について
──────────────────────────────────
日時:2023年6月3日(土)14:00-15:30
※WEB会議形式で開催いたします.
正会員は,総会に陪席することができます.ただし,総会規則12条3項により,
許可のない発言はできません.
議事次第はこちら
http://www.geosociety.jp/outline/content0152.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2023年「地質の日」行事のご案内
──────────────────────────────────
2008年より,5月10日が『地質の日』に制定され,これを記念した多くの
イベントが,全国各地の博物館・大学で開催されています.
----------------------------
惑星地球フォトコンテスト入選作品展示会:始まりました!
期間:5月16日(火)から28日(日)14時
会場:東京パークスギャラリー(台東区上野公園 JR上野駅公園改札出てすぐ)
***************************************
このほか,学会関連の「地質の日」行事については,学会ホームページに
随時情報を掲載しています.
・西日本支部:第15回「地質の日」企画 身近に知る「くまもとの大地」(5/21)
ほか
詳しくは,http://geosociety.jp/name/content0178.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2023京都大会ニュース
──────────────────────────────────
■ 京都大会までのスケジュール(予定)
まもなく講演申込開始です!
5月末(ニュース誌5月号)大会予告記事(演題登録・講演要旨受付開始)
7月12日(水):演題登録・講演要旨受付締切/ランチョン・夜間小集会申込締切
※発表を希望する非会員は,講演申込と合わせて入会申込書をご提出ください.
■ 今年も地質系業界説明会を開催します!
学生会員が将来就職する可能性のある地質・資源・建設分野に関わる地質系企業・
団体との対面説明会を企画・開催し,学生会員が地質系業界を研究するサポート
サービスを展開しています.
対面説明会:9月18日(月・祝) 会場:京都大学(第130年学術大会)
オンライン説明会:9月22日(金)午後
詳しくは,http://geosociety.jp/science/content0159.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
特集号「球状コンクリーションの科学―理解と応用―」(冊子体)販売中!
【内容】本文フルカラーA4版,約150ページ
【価格】2,600円/冊+送料370円(会員価格)
【申込受付期間】2023年5月31日(水)
詳しくは,http://geosociety.jp/news/n174.html
■ Island Arc
・Vol. 32の新しい論文が公開されています.
Elevated sedimentation of clastic matter in pelagic Panthalassa during the early Olenekian: Shun Mutoほか
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】若手巡検・研究集会 in 北海道洞爺湖有珠山ジオパーク地域
──────────────────────────────────
<<参加者募集中!!>>
若手活動運営委員会では,洞爺湖周辺にて学生・若手研究者向けの巡検を
行います。夜間には,講師による基調講演と一部参加者によるポスター形式
の研究発表を行い、参加者の交流を深め研究活動を促進することを目的と
しています.
日時:2023年7月8日(土)13時から7月9日(日)18時
対象者:35歳未満の日本地質学会正会員
参加費:
正会員(学生会員):8,000円
正会員(一般会員):16,000円
申込締切:2023年5月31日(水) 17時
詳しくは、http://geosociety.jp/science/content0160.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部情報
──────────────────────────────────
[中部支部]
・2023年支部年会開催のお知らせ
6月24日(土)
会場:信州大学松本キャンパス
シンポジウム『西南日本の白亜紀花崗岩類』
巡検:大峰帯第四系と爺ヶ岳―白沢天狗カルデラ・黒部川花崗岩(6/25)
事前登録:6月15日(木),巡検参加申込締切:6月1日(木)
詳しくは,http://geosociety.jp/outline/content0019.html
[関東支部]
・学生・初級者向け「地質断面図」の書き方講座のお知らせ―布良海岸巡検―
5月27日(土)千葉県館山市布良海岸付近で野外調査
5月28日(日)JR総武線船橋駅-千葉駅付近で地質断面図作成(室内作業)
申込期間:2023年5月7日(日)-19日(金)定員になり次第締め切り
・講演会「県の石−埼玉の岩石・鉱物・化石−」
7月8日(土)13:00-16:00
定員 現地60名,オンライン40名(先着順)
申込期間:5月23日(火)-6月16日(金)17:00まで
「秩父青石の利用と宮澤賢治・保阪嘉内が歌に詠んだ岩石鉱物」
「県立自然の博物館の世界一のパレオパラドキシア化石コレクションとその研究」
現地見学会も予定しています.
http://geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
気象庁:関東大震災特設サイト
―関東大震災から100年―知って備えよう:過去の大災害から学ぶ
https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/1923_09_01_kantoujishin/index.html
防災学術連携体:関東大震災100年関連行事等の特設ページ
https://janet-dr.com/090_abroadandhome/091_100_kantohEQ.html
-------------------------------------------------
(後)日本学術会議公開シンポジウム
「有人潜水調査船の未来を語る」
6月17日(土)13:00-17:00
場所:日本学術会議講堂(オンライン配信ハイブリッド)
一般参加可,参加費不要
https://www.scj.go.jp/ja/event/index.html
(後)第60回アイソトープ・放射線研究発表会
7月5日(水)-7日(金)
会場:東京都内会場(予定)
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2023/top
(共)岩石-水相互作用(WRI-17)または
応用同位体地球化学(AIG-14)合同国際会議
8月18日(金)-22日(火)
会場:仙台国際センター
https://www.wri17.com/
ぼうさいこくたい2023(第8回防災推進国民大会)
9月17日(日)-18日(月・祝)
場所:横浜国立大学(横浜市保土ヶ谷区常盤台)
https://bosai-kokutai.jp/2023/
(共)2023年度日本地球化学会 第70回年会
9月21日(木)-23日(土)
開催場所:東京海洋大学品川キャンパス会場(一部ハイブリッド)
口頭発表(ハイブリッド),ポスター発表(対面)
http://www.geochem.jp/meeting/
(協)Techno-Ocean 2023
10月5日(木)-7日(土)
会場:神戸国際展示場2号館 ほか
https://to2023.techno-ocean.com/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・東京大学地震研究所2024年度国際室外国人客員教員の推薦公募(8/1)
・2023年海のフロンティアを拓く岡村健二賞(7/3)
・2023年度カーボンリサイクルファンド研究助成(6/15)
・第18回「科学の芽」賞作品募集(8/21-9/16)
・令和5年度 伊豆半島ジオパーク学術研究助成(5/31)
・令和5年度 霧島ジオパーク学術研究支援補助金(6/26)
その他,公募,助成等の情報は,http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
第14回フォトコンテスト(ジオパーク賞)
第14回惑星地球フォトコンテスト入選作品
ジオパーク賞:個性豊かな、まぁ〜るい畑
写真:高場智博(長崎県)
撮影場所:長崎県 五島列島福江島の三井楽半島
【撮影者より】
五島列島福江島とその周辺には,玄武岩質溶岩からなる福江火山群が分布しています.粘り気が少ない玄武岩質溶岩では,平らな溶岩台地となります.畑を作る際に角度を稼ぐ必要があまりないために,大きな畑となりました.この畑,その昔は真ん中に杭を打ち,牛によって耕していたそうです.畑の周りにはツバキの木を植えて防風林にも.福江島の人の暮らしと大地の関わりを示す場所です.
【審査委員長講評】
五島列島ジオパークは昨年1月に認定されたばかりのジオパークで,このジオパークを撮影した多くの作品が集まりました.写真を見ただけではピーンときませんが,解説を読むと丸い畑も納得できます.地上からでは撮影できないドローンならではの作品となっています.
目次へ戻る
第14回フォトコンテスト(会長賞)
第14回惑星地球フォトコンテスト入選作品
日本地質学会会長賞:屋根瓦のような重なり
写真:大坪 誠(茨城県)
撮影場所:兵庫県 南あわじ市阿那賀海岸
【撮影者より】
淡路島南西の海岸では,白亜紀の砂岩泥岩互層(和泉層群)に発達するデュープレックス構造を見ることができます.砂層と泥層の縞々が,小規模な断層によって切られ,瓦を積み重ねたように繰り返して露出しています.厚さ10センチも満たないところに当時のダイナミクスが凝縮されている様子が大変印象的でした.(撮影者本人:地質学会正会員)
【審査委員長講評】
この作品は10cm足らずの地層間の変形構造を撮影したものです.このような小さなスケールの構造は一般の人では見過ごしてしまいますが,さすがは地質のプロの眼です.1200万画素のスマホのカメラで撮影していますが,現在では地質を記録する点では十分です.スケールに置かれたカメラキャップがやや目立ちすぎるので,画面の端に置いたり,カメラキャップ無しの写真も取っておくことをお薦めします.
目次へ戻る
第14回フォトコンテスト(ジオ鉄賞)
第14回惑星地球フォトコンテスト入選作品
ジオ鉄賞:日南海岸の洗濯岩
写真:礒部忠義(福岡県)
撮影場所:宮崎市,JR日南線(内海‐小内海間)
【撮影者より】
宮崎県の日南海岸には,青島を取り巻く「鬼の洗濯板」と言われ砂岩層が板のように積み重なっている波状岩が日南海岸に広く分布している.この海岸に沿って道路が整備され観光やドライブコースになっている.
【講評・地質解説】
宮崎県南部を走るJR日南線(内海−小内海間)の車窓には「青島の隆起海床と奇形波蝕痕」(1934(昭和9)年天然記念物指定)が広がっています.砂岩の系統的節理群を手前に,16mm高角で鬼の洗濯岩の迫力と広がりが上手く表現されており,構図の美しさが評価されました.黄色の単行列車がアクセントとなり作品を引き立てています.列車の進行方向と地層の走向が一致しているのも面白いです.砂岩泥岩互層は全国にありますが,なぜここの地質が洗濯岩になったのか,洗濯岩のでき方を考えさせられます.(藤田勝代:深田研ジオ鉄普及委員会)
※「ジオ鉄賞」:深田研ジオ鉄普及委員会より本コンテストに後援を頂き,「ジオ鉄」賞を設けています.鉄道と地球の姿を組み合わせた優れた「ジオ鉄」作品を表彰します.
目次へ戻る
第14回フォトコンテスト(スマホ賞)
第14回惑星地球フォトコンテスト入選作品
スマホ賞:スナヘビの大群
写真:高場智博(長崎県)
撮影場所:長崎県 五島列島福江島の高浜海岸
【撮影者より】
スナヘビの大群が押し寄せてくるようなそんな一枚です.五島列島福江島の高浜海岸は遠浅の海となっており,潮が引くとリップルマークをみることができます.意外と硬い,砂の塊です.高浜海岸から近いところでは天然記念物「さざなみの化石」があり,2000万年前のリップルマークもみることができます.
【審査委員長講評】
写真とタイトルを見て一瞬,何だろうと思わせるのがこの作品の魅力です.解説を読むとなるほどと納得です.この作品では余分なものを一切いれず,スケールとなるものが入っていないが魅力となっています.現在のスマホでは標準的な1200万画素のカメラで撮影していますが,この程度のスマホのカメラならA4サイズのプリントには十分です.
【地質解説】
高浜ビーチは,五島列島,福江島の北西部に位置する遠浅ビーチです.透明な海水と真っ白い砂浜で夏は海水浴で賑わいます.周囲は中新世の五島層群に取り囲まれ,すこし北に行くと三井楽地域の数万年前の玄武岩台地からなり,黒い岩石の地質帯のなかに突然現れる真っ白い砂は,細かな貝殻の破片からなっています.冬の季節風と強い波によって海底からの細かい貝殻破片が狭い高浜ビーチに寄せ集まります.潮が引くと,ウエーブリップルが教科書のように残り,美しい景観を残しています.接写でリップルの状態を取ったのは,ジオパーク教育が浸透してきたことをうかがえます.一般の人は砂蛇にみえるのかと驚きました.NHK朝ドラの「舞いあがれ」でも何度も登場しました.(清川昌一:九州大学)
目次へ戻る
第14回フォトコンテスト(大学生賞)
第14回惑星地球フォトコンテスト入選作品
大学生・大学院生賞:離島の断崖
写真:福永拓真(神奈川県)
撮影場所:長崎県 壱岐市辰の島
【撮影者より】
長崎県壱岐市の辰ノ島にて撮影した断崖.こちらは新第三紀の勝本層が波によって侵食されて形成された海食崖です.広角レンズで撮影することによってよりダイナミックなスケールが伝わるようにしました.
【審査委員長講評】
壱岐島は博多から高速船で1時間余り,そこから辰ノ島へは遊覧船で気軽に行ける場所のようです.この作品は島の高台から南東方向に海食崖,さらに遠方の地形を撮影したものです.青い空,白い雲,遠方の砂浜には人影も見えて行きたくなるような場所ですが,ジオフォトとしては手前の海食崖にもう一歩インパクトが欲しかった.
【地質解説】
玄界灘に浮かぶ長崎県北部の離島,壱岐島は島の大部分が400万年前頃から60万年頃までに断続的に噴出した溶岩流に覆われています.しかし,北端の辰ノ島や周辺では壱岐島でもっとも古い,中期始新世の勝本層が露出しています.勝本層は厚さが全体で450 m以上あるとされる砂泥互層で,波浪や潮流の影響を受けるような比較的浅い環境で堆積しています.古第三系のユーラシア大陸東部の海岸線の浅い海の状態を垣間見ることができます.(萬年一剛:神奈川県温泉地学研究所)
目次へ戻る
第14回フォトコンテスト(入選1)
第14回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:太古の覗き穴
写真:佐藤 孝(新潟県)
撮影場所:新潟県 佐渡市宿根木
【撮影者より】
新潟県佐渡島は岩礁が多く変化に富んだ景観が各所に見受けられます.南西部には景勝地の佐渡小木海岸があり,宿根木地区には隆起波食台という荒々しい岩場の地形となっています.ここでは長い間に波の渦の力で岩を削り作られた波食甌穴(はしょくおうけつ)という大きな穴があり,自然の造形美を感じることができます.
【審査委員長講評】
評者は甌穴(ポットホール)が川の流水によってできるものだと思っていましたが,この作品を見てはじめて波浪による甌穴があることを知りました.超広角レンズで甌穴を手前に入れ,遠景では海岸の様子を示しています.逆光でおどろおどろしい雰囲気となり,インパクトの強い作品となりました.
【地質解説】
宿根木は海底火山の噴出物である水中火砕岩が広く分布し,海岸には数多くの波食甌穴が認められます.「かめ穴」とも称される甌穴は硬質の礫が波打ち際のくぼみに入り込み,波の作用によって礫が回転,母岩(水中火砕岩)を削り込むことで形成されます.削られやすい岩質をもつ母岩は約1300万年前の日本海拡大期に海底から噴出したものであり,その後の東西圧縮に伴い陸化しました.沿岸には隆起波食台が発達,打ち寄せる暴浪がこの自然の造形を作り出しました.(佐渡ジオパーク推進協議会 相田満久)
目次へ戻る
第14回フォトコンテスト(入選2)
第14回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:刻々と
写真:新垣隆吾(沖縄県)
撮影場所:沖縄県 南城市の海岸
【撮影者より】
沖縄の岩礁で見られるノッチ.朝の静けさと刻々と変化する光が美しかったです.動かない岩礁ですが,刻々と形を変化させていると考えると,地球という惑星に感動しました.
【審査委員長講評】
新垣さんは2年前の当コンテストで『地底の世界』(ルーマニア)で最優秀賞を授賞された方です.今回は地元沖縄の海岸で撮影された作品を応募されました.朝日に照らされた形の良い石灰岩のノッチ,海面に映るノッチや雲の影など,画面構成や露出のコントロールが絶妙で気持ちの良い作品になっています.
【地質解説】
岩石海岸では,波の侵食作用により海面付近にノッチと呼ばれる窪みが形成されます.沖縄本島南部ではノッチが現在の海水面よりも高い位置でみられ,その後退点(ノッチの最も窪んでいる部分)高度は海抜4 mに達します.これは,沖縄本島南部が隆起傾向にあることを意味します.侵食されているのは,第四紀更新世にサンゴ礁とその沖合で形成された堆積物(那覇層)で,撮影地付近の堆積物は70万年以上前の沖合堆積物です.(井龍康文:東北大学)
目次へ戻る
第14回フォトコンテスト(入選3)
第14回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:一期一会の姿
写真:藤倉聖也(群馬県)
撮影場所:東京都 伊豆諸島新島
【撮影者より】
東京は伊豆諸島・新島で出会った大きな断層「白ママ断崖」.古代噴火で形成されたそうで,歴史の重みと地球の営みの威厳を,真横から眺めることで感じ取ることができた.ここはコーガ石という軽石で形成されているので,台風・地震・風化でどんどん崩れているそう.島で出会ったおばあさんの「10年後には全然違う姿になるだろうね」という言葉が印象的で,まさに”生きている”地球の証で,この一期一会の姿に感謝だ.
【審査委員長講評】
新島の東海岸にある白ママ断崖を望遠レンズで南に向けて撮影した作品です.遠景は南2km沖にある早島です.このような露頭は日差しが強く当たると影ができてしまいますが,この作品では全体に光が回って地層ごとの粒度の違いが読み取れます.断崖が新鮮で草などに覆われていないのが気持ち良いです.遠景に人などを入れて露頭の巨大さがわかるとさらによかった.
【地質解説】
東京都の新島は,島の南北および周辺の属島である式根島などを形成する複数の溶岩ドームからなる火山です.この写真が撮られたのは新島の東海岸,羽伏浦の南方にある白ママ断崖と呼ばれるところです.断崖を構成する地層は主として,マグマ水蒸気噴火の際に発生した火砕流の一種であるベースサージの堆積物で,西暦886〜887年に噴火したと考えられる島南部の向山溶岩ドームが噴出する際に形成されました.新島の中央部,空港や集落のある平坦地はこのベースサージ堆積物の上面にあたります.奥に見える島は属島の早島(はんしま)です.(萬年一剛:神奈川県温泉地学研究所)
目次へ戻る
第14回フォトコンテスト(入選4・中高生)
第14回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:真夏の断崖(中高生部門)
写真:新宅草太(熊本県)
撮影場所:鹿児島県薩摩川内市甑島 鹿島断崖
【撮影者より】
鹿児島県の甑島にある鹿島断崖です.高さは150mもあり,白亜紀の地層が連続してみることができました.真夏の猛暑日に観察しましたが,青空の下で目が覚めるような景観に大変驚きました.
【審査委員長講評】
ジオパーク下甑島の鹿島断崖は付近から竜脚類の歯が発見されて有名になっています.作者は,そこを訪れた感動を素直にスナップしています.このような知名度の高い露頭はインターネットなどで多数の画像がみられるので,それらを参考にしてジオフォトとしてレベルアップして欲しいと思います.
【地質解説】
甑島(こしきじま)旧鹿島村の西海岸では上部白亜系の姫浦層群が累々と堆積して,まるでグランドキャニオンを彷彿させる水平の砂泥互層からなる巨大露頭が広がっています.恐竜化石の産出でも有名になったこの地域では,島ごとに巨大な正断層により境されているホルストアンドグラーベン構造をしております.どこまでも続きそうな水平な地層も,正断層活動で境された5キロ続くホルスト部になります.草の緑と地層のコントラストが非常に美しく,非常に光が良いときに撮影されたと思われます.(清川昌一:九州大学)
目次へ戻る
【geo-Flash】No.583 第8回ショートコース まもなく受付終了です!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.583 2023/6/20┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】第8回ショートコース まもなく受付終了です!
【2】[2023京都大会]講演申込受付中です
【3】[2023京都大会]ダイバーシティ認定ロゴご活用下さい
【4】[2023京都大会]ジュニアセッション 参加受付中
【5】[2023京都大会]学生優秀発表賞(新設)について
【6】会費督促請求に関するお知らせ
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】第8回ショートコース まもなく受付終了です!
──────────────────────────────────
日程:2023年7月2日(日)
<午前> 9:00-12:00
レーザーアブレーションーICP質量分析法(LA-ICP-MS法)によるU-Th-Pb年代測定法の原理と最前線:平田岳史(東京大学)
<午後> 14:00-17:00
砕屑性ジルコンU-Pb年代を用いた地質学研究:竹内 誠(名古屋大学)
申込締切:2023年6月22日(木)
詳しくは,http://geosociety.jp/science/content0161.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2023京都大会]講演申込受付中です
──────────────────────────────────
■■■ 2023京都大会 本サイト■■■
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/top
■ 演題登録受付中:7月12日(水)18時締切
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/collectsubject
■ ランチョン・夜間集会申込:7月12日(水)締切
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/meeting
■ジュニアセッション参加申込:8月1日(火)締切
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/gyoji#jr
■ 地質系業界説明会(参加企業・団体募集):6月30日(金)締切
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/gyokai_support
■企業団体展示・書籍販売:8月25日(金)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/tenji
※大会参加登録,巡検申込は,7月初旬より受付開始予定です.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2023京都大会]ダイバーシティ認定ロゴご活用下さい
──────────────────────────────────
特に,セッション世話人,キャリア初期の学生・院生のかたへ
******************************
日本地質学会ジェンダー・ダイバーシティ委員会では,行事委員会と連携し,
「ダイバーシティ認定ロゴ」の活用を通じて,ダイバーシティ推進に努めて
おります.会員の皆様に是非ダイバーシティ認定ロゴをご活用いただきたく,
下記の通りご案内いたします.
【ダイバーシティ認定ロゴとは】
ダイバーシティ認定ロゴの取り組みは,学会内におけるダイバーシティ推進を
「見える化」し,学会活動におけるダイバーシティの推進と当該分野における
キャリア初期の方への応援を目指して作成したロゴマークです.
詳細はこちら http://geosociety.jp/engineer/content0063.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2023京都大会]ジュニアセッション 参加受付中
──────────────────────────────────
今年は4年ぶりに対面開催を再開し,会場は研究者も発表するポスター会場内に,
特設コーナーを用意いたします.
コアタイム日時:2023年9月17日(日)13:30〜15:00頃を予定
※対面開催のみ実施.e-poster/オンラインの対応はありません
※大会会場にて対面形式で1日間掲示できます
場所:京都大会ポスター会場(京都大学吉田南構内)
参加申込締切:8月1日(火)
詳しくは,https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/gyoji#jr
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2023京都大会]学生優秀発表賞(新設)について
──────────────────────────────────
運営規則第16条2項(12)により,優れた学生会員の発表に対して
「日本地質学会学生優秀発表賞」を授与します.
口頭発表,ポスター発表ともに対象となります.
また,優秀発表賞はエントリー制です.エントリーを希望する発表者は,
講演申込時にエントリー希望を選択してください
選考手順等詳しくは,
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/etc#sho
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】会費督促請求に関するお知らせ
──────────────────────────────────
2023年度会費およびそれ以前の未納会費がある方に対して,請求書(郵便振替
用紙)を6/15に発送いたしました.早急にご送金くださいますようお願いいた
します.また自動引き落としについては,6/23に引き落としを行います.
(注)2023年度分会費が未納の場合は,7月号からのニュース誌の送付を
一時的に停止させていただきます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[北海道支部]
・2023年度例会(個人講演会)※要旨PDF公開しました
6月17日(土)13:00-18:00
場所:北海道大学理学部5号館大講堂
参加費:一般会員500円,非会員1000円,学生無料
・神居古潭巡検
8月18 日(金)-19日(土)
見どころ:蛇紋岩メランジュ中のテクトニックブロック/神居古潭変成岩上昇時の
重複変成作用
参加費:正会員(一般・シニア)30,000 円/正会員(学生) 18,000 円
参加申込締切:7月20 日(木)※定員に達し次第締切
詳しくは,http://geosociety.jp/outline/content0023.html
[関東支部]
・講演会「県の石−埼玉の岩石・鉱物・化石−」
7月8日(土)13:00-16:00
定員 現地60名,オンライン40名(先着順)
申込期間:現地参加は6月22日(木)17:00まで受付を延長(定員に到達次第終了)
「秩父青石の利用と宮澤賢治・保阪嘉内が歌に詠んだ岩石鉱物」/「県立自然の
博物館の世界一のパレオパラドキシア化石コレクションとその研究」
現地見学会も予定しています.
http://geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
気象庁:関東大震災特設サイト
―関東大震災から100年―知って備えよう:過去の大災害から学ぶ
https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/1923_09_01_kantoujishin/index.html
防災学術連携体:関東大震災100年関連行事等の特設ページ
https://janet-dr.com/090_abroadandhome/091_100_kantohEQ.html
-------------------------------------------------
深田地質研究所2023年度研究成果報告会
6月30日(金)13:00-16:10
開催形式:会場とオンラインのハイブリッド
場所:深田地質研究所 研修ホール(東京都文京区)/Zoomウェビナー
参加費:無料(Webページより要事前申込)
https://fukadaken.or.jp/?p=7498
(後)第60回アイソトープ・放射線研究発表会
7月5日(水)-7日(金)
会場:日本科学未来館(東京・お台場)
https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2023/top
深田地質研究所 第1回深田研講座「災害地質学」
7月7日(金)10:00-16:30
開催形式:オンライン配信(Zoomウェビナー)
対象:地球科学研究に従事する若手研究者および,地質・地盤調査や環境調査,
測量調査などの実務に従事する技術者
参加費:無料(定員300名)要事前申込
https://fukadaken.or.jp/?p=7540
第32回 地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン第3回目)
7月21日(金)19:30-21:30
内容:土壌汚染状況調査の流れと調査や対策の制約・難しさについて
講師:成澤 昇(株式会社環境地質研究所,地質汚染診断士)
参加費:無料(事前登録制)CPD:2単位
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
第32回地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン第4回目)
8月4日(金)19:30-21:30
内容:地質汚染調査入門その1 地質環境問題の歴史と地質汚染他
講師:風岡 修(地質汚染診断士,理学博士)
参加費:無料(事前登録制)CPD:2単位
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
(共)岩石-水相互作用(WRI-17)または
応用同位体地球化学(AIG-14)合同国際会議
8月18日(金)-22日(火)
会場:仙台国際センター
https://www.wri17.com/
第32回地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン第5回目)
8月18日(金)19:30-21:30
内容:地質汚染調査入門その2 透水層の対比方法,地質汚染調査手順の概要他
講師:風岡 修(地質汚染診断士,理学博士)
参加費:無料(事前登録制)CPD:2単位
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
第77回地学団体研究会総会(ちちぶ)
8月19日(土)-20日(日)
開催方式:現地開催とオンラインのハイブリッド方式
現地会場:秩父市歴史文化伝承館(埼玉県秩父市)
https://www.chidanken.jp/
(後)第66回粘土科学討論会
9月12日(火)-13日(水)
会場:戦災復興記念館(宮城県仙台市青葉区)
http://www.cssj2.org/
ぼうさいこくたい2023(第8回防災推進国民大会)
9月17日(日)-18日(月・祝)
場所:横浜国立大学(横浜市保土ヶ谷区常盤台)
https://bosai-kokutai.jp/2023/
(共)2023年度日本地球化学会 第70回年会
9月21日(木)-23日(土)
開催場所:東京海洋大学品川キャンパス会場
口頭(ハイブリッド),ポスター(対面)
http://www.geochem.jp/meeting/
(協)Techno-Ocean 2023
10月5日(木)-7日(土)
会場:神戸国際展示場2号館 ほか
https://to2023.techno-ocean.com/
地質学史懇話会
12月17日(日)13:30-17:00
場所:王子,北とぴあ 805号室
• 小澤健志:ライプニッツ(1646-1716)から見たP.ハルツィングの風車・水車計画
• 矢島道子:日本最初の理学博士保井コノ
問い合わせ:矢島道子 pxi02070[at]nifty.com
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・令和5年度「東レ理科教育賞(9/30)」,「東レ理科教育賞・企画賞(9/10)」
・原子力環境整備促進・資金管理センター:放射性廃棄物の地層処分に係る
萌芽的・先進的かつ重要な研究開発テーマ及び研究実施者の募集(7/10)
・東京大学地震研究所2024年度共同利用「特定共同研究」研究課題の公募(7/30)
・令和6年度科学技術分野の文部科学大臣表彰(科学技術省賞・若手科学者賞・
研究支援賞)候補者推薦(学会締切7/3)
・大雪山カムイミンタラジオパーク構想ジオパーク専門員(旭川市地域おこし
協力隊)募集(6/30)
・つくば市ジオパーク専門員(任期付職員)の募集(6/30)
その他,公募,助成等の情報は,http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.584 講演申込締切まであと1週間です!
(お詫び)サーバ障害により,7/4配信予定のgeo-Flashが配信されておりませんでした.
改めて配信いたします.
(お願い)今回のNo.584より新会員システムを利用した配信になりました.受信アドレスを
ご確認いただき,必要に応じてご自身の会員情報を適宜更新して下さい.
http://geosociety.jp/news/n176.html (2023.7.6)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.584 2023/7/4┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2023京都大会]講演申込受付中です
【2】[2023京都大会]まもなく事前参加登録受付開始しま
【3】[2023京都大会]ダイバーシティ認定ロゴご活用下さい
【4】[2023京都大会]若手会員向けルームシェア型宿泊プラン
【5】[2023京都大会]ジュニアセッション 参加受付中
【6】[2023京都大会]学生優秀発表賞(新設)について
【7】支部情報
【8】会員の学術・教育・社会貢献活動
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2023京都大会]講演申込受付中です
──────────────────────────────────
■■■ 2023京都大会 本サイト■■■
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/top
■ 演題登録受付中:7月12日(水)18時締切
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/collectsubject
■ ランチョン・夜間集会申込:7月12日(水)締切
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/meeting
■ 若手会員向けルームシェア型宿泊プラン:8/18(金)締切
http://geosociety.jp/science/content0164.html
■ジュニアセッション参加申込:8月1日(火)締切
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/gyoji#jr
■企業団体展示・書籍販売:8月25日(金)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/tenji
■ お子様をお連れになる方へ
ご家族で学会に参加される会員で,大会期間中に保育施設の利用を希望される
方には,学会から利用料金の一部を補助いたします.会場内には保育室を設け
ませんので,近隣施設をご紹介いたします.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/kids
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2023京都大会]まもなく事前参加登録受付開始します
──────────────────────────────────
大会参加登録については,7/7(金)より受付開始で準備中です.
今しばらくお待ちください.
事前参加登録締切:8月31日(木)18:00
巡検参加申込締切:8月8日(火)18:00
[参加費]事前申込
正会員(一般会員):6,000円
正会員(シニア会員):3,000円※2023年4月1日時点で65歳以上の正会員
正会員(学生会員):1,500円
名誉会員/非会員招待者:無料
・昨年大会より,大会参加登録費と発表料金(1,500円/件)を分離しました.
・発表する方は大会参加登録費と発表料金の両方の支払いが必要です.
・講演要旨集の冊子体は作成・販売いたしません.
大会参加登録に関する詳細は,
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/sanka
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2023京都大会]ダイバーシティ認定ロゴご活用下さい
──────────────────────────────────
特に,セッション世話人,キャリア初期の学生・院生のかたへ
******************************
日本地質学会ジェンダー・ダイバーシティ委員会では,行事委員会と連携し,
「ダイバーシティ認定ロゴ」の活用を通じて,ダイバーシティ推進に努めて
おります.会員の皆様に是非ダイバーシティ認定ロゴをご活用いただきたく,
下記の通りご案内いたします.
【ダイバーシティ認定ロゴとは】
ダイバーシティ認定ロゴの取り組みは,学会内におけるダイバーシティ推進を
「見える化」し,学会活動におけるダイバーシティの推進と当該分野における
キャリア初期の方への応援を目指して作成したロゴマークです.
詳細はこちら http://geosociety.jp/engineer/content0063.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2023京都大会]若手会員向けルームシェア型宿泊プラン
──────────────────────────────────
「学会先での宿泊費を抑えたいけれど,ホテルの部屋をシェアする相手が
見つからない...」「地質学会で仲間をつくりたい!」といった若手会員
のために,“ルームシェア型宿泊プラン”を企画しました.
(注)「若手同士の交流」と「低価格化」の観点から,本プランは,
相部屋でのご案内となります.
申込期間:2023年7月1日(土)-8月18日(金)
http://geosociety.jp/science/content0164.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2023京都大会]ジュニアセッション 参加受付中
──────────────────────────────────
今年は4年ぶりに対面開催を再開し,会場は研究者も発表するポスター会場内に,
特設コーナーを用意いたします.
コアタイム日時:2023年9月17日(日)13:30-15:00頃を予定
※対面開催のみ実施.e-poster,オンラインの対応はありません
※大会会場にて対面形式で1日間掲示できます
場所:京都大会ポスター会場(京都大学吉田南構内)
参加申込締切:8月1日(火)
詳しくは,https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/gyoji#jr
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[2023京都大会]学生優秀発表賞(新設)について
──────────────────────────────────
運営規則第16条2項(12)により,優れた学生会員の発表に対して
「日本地質学会学生優秀発表賞」を授与します.
口頭発表,ポスター発表ともに対象となります.
また,優秀発表賞はエントリー制です.エントリーを希望する発表者は,
講演申込時にエントリー希望を選択してください
選考手順等詳しくは,
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/etc#sho
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[北海道支部]
・神居古潭巡検
8月18 日(金)-19日(土)
見どころ:蛇紋岩メランジュ中のテクトニックブロック/
神居古潭変成岩上昇時の重複変成作用
参加費:正会員(一般・シニア)30,000 円/正会員(学生)18,000 円
参加申込締切:7月20日(木)※定員に達し次第締切
詳しくは,http://geosociety.jp/outline/content0023.html
[関東支部]
・関東地震100年関連行事オンライン講演会【予告】
9月30日(土)13:30-16:00.
「関東大震災と土砂災害」井上公夫氏
「地震西進系列と次の関東・南海トラフ地震」石渡 明氏
申込期間:9/1-9/22(金)17:00締切
詳細は来月以降お知らせします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】会員の学術・教育・社会貢献活動
──────────────────────────────────
辻森 樹会員らによる 「Progressive lawsonite eclogitization of the oceanic
crust: Implications for deep mass transfer in subduction zones」(Geology, v. 51,
no. 7, p. 678–682)の掲載内容が東北大学からプレスリリースされました.
詳しくは, http://www.geosociety.jp/science/content0109.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
気象庁:関東大震災特設サイト
―関東大震災から100年―知って備えよう:過去の大災害から学ぶ
https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/1923_09_01_kantoujishin/index.html
防災学術連携体:関東大震災100年関連行事等の特設ページ
https://janet-dr.com/090_abroadandhome/091_100_kantohEQ.html
(後)企画展⽰「みんなの石」展
主催:新潟⼤学学術資料運営機構旭町学術資料展⽰館
7⽉19⽇(水)-8⽉31⽇(木)
場所:駅南キャンパス ときめいと(新潟市中央区笹口)
https://www.lib.niigata-u.ac.jp/tenjikan/index.html
-------------------------------------------------
(後)第60回アイソトープ・放射線研究発表会
7月5日(水)-7日(金)
会場:日本科学未来館(東京・お台場)https://confit.atlas.jp/guide/event/jrias2023/top
第198回深田研談話会
跡倉ナップから探る日本列島の地体構造
7月24日(月)15:00-16:30
場所:深田地質研究所研修ホール+オンライン
講師:高木秀雄(早稲田大学)
参加申込締切:7月18日(火)
https://fukadaken.or.jp/?p=7573
(後)青少年のための科学の祭典2023全国大会
7月29日(土)-30日(日)9:30-16:00
会場:科学技術館1階イベントホール・屋外(千代田区北の丸公園内)
入場無料
http://www.kagakunosaiten.jp/index.php
桧原湖湖底遺跡水中ドローン操縦体験と一般説明会
7月29日(土)10:00-17:00
JAMSTEC高知コア研究所・東海大学共催
場所:大山祗神社・金山集会場(福島県耶麻郡北塩原村桧原湖北部)
桧原湖湖底に眠る水中遺跡(桧原宿跡)の学術調査と関連して,
(1)これまでの研究成果を紹介する説明会
(2)水中ドローンを使用した水中遺跡の観察会
を実際の調査現場で実施します.
参加無料
https://hibarajuku.labby.jp/news/detail/3219
(共)岩石-水相互作用(WRI-17)または
応用同位体地球化学(AIG-14)合同国際会議
8月18日(金)-22日(火)
会場:仙台国際センター
https://www.wri17.com/
(後)学術会議公開シンポジウム
「オープンサイエンス時代における
学術データ・学術試料の保存・保管、共有問題の現状と将来」
8⽉20⽇(⽇)13:00-17:20
場 所:オンライン開催(⼀般参加・可)
https://www.scj.go.jp/ja/event/
(後)第66回粘土科学討論会
9月12日(火)-13日(水)
会場:戦災復興記念館(宮城県仙台市青葉区)
http://www.cssj2.org/
ぼうさいこくたい2023(第8回防災推進国民大会)
9月17日(日)-18日(月・祝)
場所:横浜国立大学(横浜市保土ヶ谷区常盤台)
https://bosai-kokutai.jp/2023/
(共)2023年度日本地球化学会 第70回年会
9月21日(木)-23日(土)
開催場所:東京海洋大学品川キャンパス会場
口頭(ハイブリッド),ポスター(対面)
http://www.geochem.jp/meeting/
(協)Techno-Ocean 2023
10月5日(木)-7日(土)
会場:神戸国際展示場2号館 ほか
https://to2023.techno-ocean.com/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・第64回(令和5年度)東レ科学技術賞および東レ科学技術研究助成の候補者推薦依頼(学会推薦9/20)
・2023年度関西エネルギー・リサイクル科学研究振興財団(KRF)研究助成(8/31)
・若手研究助成プログラム「academist Prize 第3期」募集(7/21)
・神奈川県立生命の星・地球博物館学芸員公募:地質学(鉱物学)(8/10)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.586 各種参加申込受付中です:巡検!懇親会も!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.586 2023/7/18┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2023京都大会]各種参加申込受付中です
【2】[2023京都大会]ジュニアセッション 参加受付中
【3】[2023京都大会]若手会員向けルームシェア型宿泊プラン
【4】[2023京都大会]その他
【5】令和5年7月 九州地方豪雨災害の情報
【6】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2023京都大会]各種参加申込受付中です
──────────────────────────────────
事前参加登録締切:8月31日(木)18:00
懇親会参加申込締切:8月18日(金)18:00
巡検参加申込締切:8月8日(火)18:00
[大会参加費]事前申込
正会員(一般会員):6,000円
正会員(シニア会員):3,000円 ※2023年4月1日時点で65歳以上の正会員
正会員(学生会員の院生):1,500円
名誉会員/非会員招待者/学部学生:無料
・昨年大会より,大会参加登録費と発表料金(1,500円/件)を分離しました.
・発表する方は大会参加登録費と発表料金の両方の支払いが必要です.
・講演要旨集の冊子体は作成・販売いたしません.
大会参加登録に関する詳細は,
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/sanka
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2023京都大会]ジュニアセッション 参加受付中
──────────────────────────────────
今年は4年ぶりに対面開催を再開し,会場は研究者も発表するポスター会場内に,
特設コーナーを用意いたします.
コアタイム日時:2023年9月17日(日)13:30-15:00頃を予定
※対面開催のみ実施.e-poster,オンラインの対応はありません
※大会会場にて対面形式で1日間掲示できます
場所:京都大会ポスター会場(京都大学吉田南構内)
参加申込締切:8月1日(火)
詳しくは,https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/gyoji#jr
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2023京都大会]若手会員向けルームシェア型宿泊プラン
──────────────────────────────────
「学会先での宿泊費を抑えたいけれど,ホテルの部屋をシェアする相手が
見つからない...」「地質学会で仲間をつくりたい!」といった若手会員
のために,“ルームシェア型宿泊プラン”を企画しました.
(注)「若手同士の交流」と「低価格化」の観点から,本プランは,
相部屋でのご案内となります.
申込期間:2023年7月1日(土)-8月18日(金)
http://geosociety.jp/science/content0164.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2023京都大会]その他
──────────────────────────────────
■企業団体展示・書籍販売:8月25日(金)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/tenji
■ お子様をお連れになる方へ
ご家族で学会に参加される会員で,大会期間中に保育施設の利用を希望される
方には,学会から利用料金の一部を補助いたします.会場内には保育室を設け
ませんので,近隣施設をご紹介いたします.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/kids
■■■■■ 2023京都大会 本サイト■■■■■
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】令和5年7月 九州地方豪雨災害の情報
──────────────────────────────────
令和5年7月 九州地方豪雨災害の情報(航測各社の撮影情報)を提供いただき
ましたので,学会HPに掲載しました.
・令和5年7月九州各地における豪雨災害(福岡・熊本)航空写真:国際航業
株式会社(株式会社パスコとの共同撮影)
・23年7月前線による大雨災害:株式会社パスコ(国際航業との共同撮影および
自社撮影)
・九州での記録的大雨被害状況(2023年7月):アジア航測株式会社
・令和5年7月7日からの大雨による被害状況等の航空写真(九州北部):朝日航洋
株式会社
・令和5年(23年)7月の大雨災害(九州北部・熊本県)斜め写真撮影
http://geosociety.jp/hazard/content0107.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・新しい論文が公開されています.
(巡検案内書)瀬戸内区中新統:鮎河層群と綴喜層群:入月俊明ほか/(ノート)微動
アレイ探査の概説:長 郁夫/(報告)福井市西部に分布する中新世貫入岩類の岩石学
的特徴およびK-Ar年代:三好雅也ほか/(フォト)チベット高原南部ムスタン地方に
おける中新統〜鮮新統の古土壌:葉田野 希ほか
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/list/-char/ja
■ Island Arc
・Vol. 32の新しい論文が公開されています.
U–Pb and fission-track dating of Miocene hydrocarbon source rocks in the Akita Basin,
Northeast Japan, and implications for the timing of paleoceanographic changes in the sea
of Japan: Takeshi Nakajima et al ほか
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[北海道支部]
・神居古潭巡検
8月18 日(金)-19日(土)
見どころ:蛇紋岩メランジュ中のテクトニックブロック/
神居古潭変成岩上昇時の重複変成作用
参加費:正会員(一般・シニア)30,000 円/正会員(学生)18,000 円
参加申込締切:7月20日(木)※定員に達し次第締切
詳しくは,http://geosociety.jp/outline/content0023.html
[関東支部]
・関東地震100年関連行事オンライン講演会【予告】
9月30日(土)13:30-16:00.
「関東大震災と土砂災害」井上公夫氏
「将来の関東地震・南海トラフ地震と地震西進系列」石渡 明氏
申込期間:9/1-9/22(金)17:00締切
詳細は来月以降お知らせします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
気象庁:関東大震災特設サイト
―関東大震災から100年―知って備えよう:過去の大災害から学ぶ
https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/1923_09_01_kantoujishin/index.html
防災学術連携体:関東大震災100年関連行事等の特設ページ
https://janet-dr.com/090_abroadandhome/091_100_kantohEQ.html
「関東大震災100年と防災減災科学」(電子版)完成
※日本地質学会も寄稿しました.
https://janet-dr.com/090_abroadandhome/KantohEQ100th_book_A4.pdf
(後)企画展⽰「みんなの石」展
主催:新潟⼤学学術資料運営機構旭町学術資料展⽰館
7⽉19⽇(水)-8⽉31⽇(木)
場所:駅南キャンパス ときめいと(新潟市中央区笹口)
https://www.lib.niigata-u.ac.jp/tenjikan/index.html
-------------------------------------------------
(後)青少年のための科学の祭典2023全国大会
7月29日(土)-30日(日)9:30-16:00
会場:科学技術館1階イベントホール・屋外(千代田区北の丸公園内)
入場無料
http://www.kagakunosaiten.jp/index.php
(共)岩石-水相互作用(WRI-17)または
応用同位体地球化学(AIG-14)合同国際会議
8月18日(金)-22日(火)
会場:仙台国際センター
https://www.wri17.com/
(後)学術会議公開シンポジウム
「オープンサイエンス時代における
学術データ・学術試料の保存・保管、共有問題の現状と将来」
8⽉20⽇(⽇)13:00-17:20
場 所:オンライン開催(⼀般参加・可)
https://www.scj.go.jp/ja/event/
第40回歴史地震研究会(小田原大会)
9月1日(金)- 3日(日)
場所:小田原三の丸ホール・小ホール
http://www.histeq.jp/kenkyukai.html
(後)第66回粘土科学討論会
9月12日(火)-13日(水)
会場:戦災復興記念館(宮城県仙台市青葉区)
http://www.cssj2.org/
ぼうさいこくたい2023(第8回防災推進国民大会)
9月17日(日)-18日(月・祝)
場所:横浜国立大学(横浜市保土ヶ谷区常盤台)
https://bosai-kokutai.jp/2023/
(共)2023年度日本地球化学会 第70回年会
9月21日(木)-23日(土)
開催場所:東京海洋大学品川キャンパス会場
口頭(ハイブリッド),ポスター(対面)
http://www.geochem.jp/meeting/
(協)Techno-Ocean 2023
10月5日(木)-7日(土)
会場:神戸国際展示場2号館 ほか
https://to2023.techno-ocean.com/
JAAS年次大会2023「会いに行ける科学者フェス」
10月7日(土)-13日(金)
会場:秋葉原UDX( 東京都千代田区外神田)&ハイブリッド
ポスター・展示募集:7/21(金)締切
https://meetings.jaas.science/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・第45回(令和5年度)沖縄研究奨励賞推薦応募 (学会締切9/5)
・2023年度朝日賞推薦依頼 (学会締切8/3)
・JAMSTEC Young Research Fellow 2024 公募(8/28)
・東京大学地震研究所2023年度大型計算機共同利用公募研究(8/31)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.585(臨時)明日(7/12;18時)講演申込締切です!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.585 2023/7/11┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2023京都大会]明日(7/12;18時)講演申込締切です!
【2】[2023京都大会]各種参加申込受付開始しました
【3】[2023京都大会]ダイバーシティ認定ロゴご活用下さい
【4】[2023京都大会]若手会員向けルームシェア型宿泊プラン
【5】[2023京都大会]ジュニアセッション 参加受付中
【6】[2023京都大会]学生優秀発表賞(新設)について
【7】[2023京都大会]その他の情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2023京都大会]明日(7/12;18時)講演申込締切です!
──────────────────────────────────
■ 明日(7/12;18時)講演申込締切です!
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/collectsubject
■ ランチョン・夜間集会申込:7月12日(水)締切
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/meeting
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2023京都大会]各種参加申込受付開始しました
──────────────────────────────────
事前参加登録締切:8月31日(木)18:00
懇親会参加申込締切:8月18日(金)18:00
巡検参加申込締切:8月8日(火)18:00
[大会参加費]事前申込
正会員(一般会員):6,000円
正会員(シニア会員):3,000円 ※2023年4月1日時点で65歳以上の正会員
正会員(学生会員の院生):1,500円
名誉会員/非会員招待者/学部学生:無料
・昨年大会より,大会参加登録費と発表料金(1,500円/件)を分離しました.
・発表する方は大会参加登録費と発表料金の両方の支払いが必要です.
・講演要旨集の冊子体は作成・販売いたしません.
大会参加登録に関する詳細は,
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/sanka
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2023京都大会]ダイバーシティ認定ロゴご活用下さい
──────────────────────────────────
特に,セッション世話人,キャリア初期の学生・院生のかたへ
******************************
日本地質学会ジェンダー・ダイバーシティ委員会では,行事委員会と連携し,
「ダイバーシティ認定ロゴ」の活用を通じて,ダイバーシティ推進に努めて
おります.会員の皆様に是非ダイバーシティ認定ロゴをご活用いただきたく,
下記の通りご案内いたします.
【ダイバーシティ認定ロゴとは】
ダイバーシティ認定ロゴの取り組みは,学会内におけるダイバーシティ推進を
「見える化」し,学会活動におけるダイバーシティの推進と当該分野における
キャリア初期の方への応援を目指して作成したロゴマークです.
詳細はこちら http://geosociety.jp/engineer/content0063.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2023京都大会]若手会員向けルームシェア型宿泊プラン
──────────────────────────────────
「学会先での宿泊費を抑えたいけれど,ホテルの部屋をシェアする相手が
見つからない...」「地質学会で仲間をつくりたい!」といった若手会員
のために,“ルームシェア型宿泊プラン”を企画しました.
(注)「若手同士の交流」と「低価格化」の観点から,本プランは,
相部屋でのご案内となります.
申込期間:2023年7月1日(土)-8月18日(金)
http://geosociety.jp/science/content0164.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2023京都大会]ジュニアセッション 参加受付中
──────────────────────────────────
今年は4年ぶりに対面開催を再開し,会場は研究者も発表するポスター会場内に,
特設コーナーを用意いたします.
コアタイム日時:2023年9月17日(日)13:30-15:00頃を予定
※対面開催のみ実施.e-poster,オンラインの対応はありません
※大会会場にて対面形式で1日間掲示できます
場所:京都大会ポスター会場(京都大学吉田南構内)
参加申込締切:8月1日(火)
詳しくは,https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/gyoji#jr
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[2023京都大会]学生優秀発表賞(新設)について
──────────────────────────────────
運営規則第16条2項(12)により,優れた学生会員の発表に対して
「日本地質学会学生優秀発表賞」を授与します.
口頭発表,ポスター発表ともに対象となります.
また,優秀発表賞はエントリー制です.エントリーを希望する発表者は,
講演申込時にエントリー希望を選択してください
選考手順等詳しくは,
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/etc#sho
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他
──────────────────────────────────
■企業団体展示・書籍販売:8月25日(金)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/tenji
■ お子様をお連れになる方へ
ご家族で学会に参加される会員で,大会期間中に保育施設の利用を希望される
方には,学会から利用料金の一部を補助いたします.会場内には保育室を設け
ませんので,近隣施設をご紹介いたします.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/kids
■■■■■ 2023京都大会 本サイト■■■■■
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.587 [2023京都]巡検のお申し込みはお早めに!!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.587 2023/8/1┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2023京都大会]各種参加申込受付中です
【2】[2023京都大会]巡検申込状況:お申し込みはお早めに!!
【3】[2023京都大会]若手会員向けルームシェア型宿泊プラン
【4】[2023京都大会]学生のための地質系業界説明会
【5】[2023京都大会]その他
【6】IGC2024に関する会長メッセージを掲載しました
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】鎮西清高 名誉会員 ご逝去
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2023京都大会]各種参加申込受付中
──────────────────────────────────
事前参加登録締切:8月31日(木)18:00
懇親会参加申込締切:8月18日(金)18:00
巡検参加申込締切:8月8日(火)18:00
[大会参加費]事前申込
正会員(一般会員):6,000円
正会員(シニア会員):3,000円 ※4/1時点で65歳以上の正会員
正会員(学生会員の院生):1,500円
名誉会員/非会員招待者/学部学生:無料
・昨年大会より,大会参加登録費と発表料金(1,500円/件)を分離しました.
・発表する方は大会参加登録費と発表料金の両方の支払いが必要です.
・講演要旨集の冊子体は作成・販売いたしません.
大会参加登録に関する詳細は,
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/sanka
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2023京都大会]巡検申込状況:お申し込みはお早めに!!
──────────────────────────────────
巡検参加申込締切:8月8日(火)18:00
まもなく定員に達するコースもあります.お申し込みはお早めに!!
巡検申込状況はこちらから(8/1,17時現在)
http://geosociety.jp/science/content0104.html
※巡検だけに参加される場合は,大会参加登録は不要です.
巡検の詳細は,
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/excursion
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2023京都大会]若手会員向けルームシェア型宿泊プラン
──────────────────────────────────
「学会先での宿泊費を抑えたいけれど,ホテルの部屋をシェアする相手が
見つからない...」「地質学会で仲間をつくりたい!」といった若手会員
のために,“ルームシェア型宿泊プラン”を企画しました.
(注)「若手同士の交流」と「低価格化」の観点から,本プランは,
相部屋でのご案内となります.
申込締切:8月18日(金)
http://geosociety.jp/science/content0164.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2023京都大会]学生のための地質系業界説明会
─────────────────────────────────
地質系学科主任・就職担当教員の皆様,
地質系学科学部生・院生の皆様,ぜひご参加ください!
学生の皆様に,将来の就職先の一つである地質系業界の実態や各社の業務内容
などを知っていただくために開催する当学会の恒例行事です.今年度の説明会
では,対面とオンラインによるものを別の日程で行います.
今年度は,地質系学科に後援をいただき,大学,企業,学会が連携して高等教育
を終えた専門技術者が社会で活躍・貢献できるようにしたいと考えています.
・対面説明会:9/18(月祝)午後半日,学術大会会場内(京都大学吉田南構内)
・オンライン説明会:9/22(金)午後.Zoomを使ったオンライン説明会
参加費無料,会員・非会員を問わず,同じ学科の友人をお誘いあわせのうえ,
お気軽にご参加ください.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/gyokai_support
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2023京都大会]その他
──────────────────────────────────
■企業団体展示・書籍販売:8月25日(金)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/tenji
■ お子様をお連れになる方へ
ご家族で学会に参加される会員で,大会期間中に保育施設の利用を希望される
方には,学会から利用料金の一部を補助いたします.会場内には保育室を設け
ませんので,近隣施設をご紹介いたします.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/kids
■■■■■ 2023京都大会 本サイト■■■■■
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】IGC2024に関する会長メッセージを掲載しました
──────────────────────────────────
IGC2024の2nd circular (PDFファイルはこちら)が6月末に公開されました.
http://igc2024korea.org/regi/cms/upload/[IGC%202024]%202nd%20Circular_0630.pdf
これに伴い,会長からメッセージがありますので,会員の方は会員ページでご確認ください.(※会員番号によるログインが必要です)
http://sub.geosociety.jp/members/content0117.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
・関東地震100年関連行事:講演会「関東地震から100年」
9月30日(土)13:30-16:10(オンライン)
「関東大震災と土砂災害」井上公夫氏
「地震西進系列と次の関東・南海トラフ地震」石渡 明氏
申込期間:9/1-9/22(金)17:00締切
http://geosociety.jp/outline/content0201.html#kanto-jishin
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
気象庁:関東大震災特設サイト
―関東大震災から100年―知って備えよう:過去の大災害から学ぶ
https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/1923_09_01_kantoujishin/index.html
防災学術連携体:関東大震災100年関連行事等の特設ページ
https://janet-dr.com/090_abroadandhome/091_100_kantohEQ.html
「関東大震災100年と防災減災科学」(電子版)完成
※日本地質学会も寄稿しました.
https://janet-dr.com/090_abroadandhome/KantohEQ100th_book_A4.pdf
(後)企画展⽰「みんなの石」展
主催:新潟⼤学学術資料運営機構旭町学術資料展⽰館
7⽉19⽇(水)-8⽉31⽇(木)
場所:駅南キャンパス ときめいと(新潟市中央区笹口)
https://www.lib.niigata-u.ac.jp/tenjikan/index.html
-------------------------------------------------
(共)岩石-水相互作用(WRI-17)または
応用同位体地球化学(AIG-14)合同国際会議
8月18日(金)-22日(火)
会場:仙台国際センター
https://www.wri17.com/
(後)学術会議公開シンポジウム
「オープンサイエンス時代における
学術データ・学術試料の保存・保管,共有問題の現状と将来」
8⽉20⽇(⽇)13:00-17:20
場 所:オンライン開催(⼀般参加・可)
https://www.scj.go.jp/ja/event/
令和5年度第1回キャリアデザインセミナー
主催:(一財)日本応用地質学会 ダイバーシティ推進委員会
8月23日(水)13:00-15:00
開催形式:Web 開催(Zoom Meeting を使用)
キャリアデザイン紹介:杉原千鶴(国際航業株式会社)/ 武田和久(ハイテック株式会社)
参加費無料・どなたでも参加いただけます
https://www.jseg.or.jp/pdf/20230727_Career_Design_Seminar_20231st.pdf
(後)第66回粘土科学討論会
9月12日(火)-13日(水)
会場:戦災復興記念館(宮城県仙台市青葉区)
http://www.cssj2.org/
ぼうさいこくたい2023(第8回防災推進国民大会)
9月17日(日)-18日(月・祝)
場所:横浜国立大学(横浜市保土ヶ谷区常盤台)
https://bosai-kokutai.jp/2023/
(共)2023年度日本地球化学会 第70回年会
9月21日(木)-23日(土)
開催場所:東京海洋大学品川キャンパス会場
口頭(ハイブリッド),ポスター(対面)
http://www.geochem.jp/meeting/
第32回 地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン第6回目)
9月22日(金)19:30-21:30
内容:地質汚染調査におけるボーリング調査その1
参加費:無料(事前登録制)CPD:2単位
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
(協)Techno-Ocean 2023
10月5日(木)-7日(土)
会場:神戸国際展示場2号館 ほか
https://to2023.techno-ocean.com/
2023年度第2回地質調査研修
10月23日(月)- 27日(金)
場所:島根県出雲市長尾鼻周辺(小伊津海岸)
研修内容:野外での地層・岩石の観察ポイントからまとめまで,
地質図を作成するための基本的事項を事前のe-ラーニングと5日間
の対面研修で習得します.※今回は,大学・会社等で一度は地質図を
書いたことのある初級者向けの内容で行う予定です.
定員:6名(定員になり次第締切)
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2023-2.html
第4回 鉱物肉眼鑑定研修
10月25日(水)-27日(金)
主催:産総研コンソーシアム「地質人材育成コンソーシアム」
研修場所:産総研つくば第七事業所
研修内容:鉱山会社に勤務する技術者が,金属鉱山等で産出する鉱物を
肉眼で鑑定できるよう,実際の鉱物を用いてその特徴を理解し,判別
可能な能力を身につけることを目的とします.
定員:5名(鉱業系の会社(商社含む)・組織の方に限る)
申込締切:10月2日(ただし定員に達し次第受付終了)
https://www.gsj.jp/geoschool/koubutsu/4th.html
第32回 地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン第7回目)
10月27日(金)19:30-21:30
内容:地質汚染調査におけるボーリング調査その2
参加費:無料(事前登録制)CPD:2単位
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
第32回 地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン第8回目)
12月8日(金)19:30-21:30
内容:観測井戸の設置地点・深度,電気検層 他
参加費:無料(事前登録制)CPD:2単位
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・大阪公立大学理学研究科地球学専攻 准教授(女性限定)公募(9/15)
・東京大学地震研究所教授公募(10/13)
・専任研究員(生態学)の募集(伊豆半島ユネスコ世界ジオパーク)(8/31)
・2023年度「第44回猿橋賞」受賞候補者募集(11/30)
・日本アイソトープ協会奨励賞募集(10/31)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】鎮西清高 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
鎮西清高 名誉会員(京都大学名誉教授)が,令和5年7月27日(木)に
逝去されました(89歳).
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます.
なお,ご葬儀はすでにご家族によりしめやかに執り行われ,御香典,御供花,
御供物の儀はご辞退されるとのことです.
会長 岡田 誠
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
2023京都
日本地質学会第130年学術大会(2023京都)巡検案内書
2023京都大会HP(confit)はこちら
※それぞれの巡検案内書タイトルをクリックすると,J-STAGE上の原稿画面に遷移します.
京都盆地-奈良盆地断層帯とその周辺の第四系
山陰海岸ジオパーク地域兵庫県新温泉町〜香美町周辺に分布する新第三紀北但層群とそのジオサイト
瀬戸内区中新統:鮎河層群と綴喜層群 入月俊明,栗原行人(地質学雑誌,第129巻,355-369)
琵琶湖西岸に分布する後期白亜紀花崗岩体と岩脈類(地質学雑誌,第129巻,519-531)
但馬地域の舞鶴帯南帯
超丹波帯と丹波帯(地質学雑誌,第129巻,533-550)
淀川の氾濫と河川改修(アウトリーチ巡検) 三田村宗樹(地質学雑誌,第129巻,405-413)
ワークショップ:堆積学の水理実験・理論講習会 成瀬 元(地質学雑誌,第129巻,441-452)
ワークショップ:オープンソースGISをつかってみよう 根本達也,植田允教,ラガワン ベンカテッシュ(地質学雑誌,第129巻,435-440)
琉球列島:縄文人が挑んだ遠い島と黒潮
琉球列島:縄文人が挑んだ遠い島と黒潮
正会員 高山信紀
図1.琉球列島
まえがき
喜界島で福徳岡ノ場2021年8月噴火のものと見られる漂着軽石1)を見た話を友人にしたとき,「喜界島から屋久島は見えるか?」と聞かれた.本稿は,これをきっかけに,九州から台湾の間の島々(琉球列島,図1)について隣の島が見えるか計算式により確認するとともに,縄文時代の航海への黒潮の影響と当時の航海の限界を考えてみたものである.
当時の航海は,島などを目印にして丸木舟を漕いでいたと考えられる.喜界島や種子島,屋久島,奄美大島,沖縄本島の遺跡から,縄文時代に九州で使われていた形式の土器が出土2),3)しており,九州とこれらの島々の間で航海が行われていたことを示している.一方,木下4)は,相互に目視できない南琉球(宮古・八重山諸島)と中琉球(奄美・沖縄諸島)の文化が出会うのは中琉球に大型船が登場する12世紀で,相互に目視できる八重山諸島と台湾の間でも接触を示す直接的証拠は不明瞭で,「往来するための前提は相互に目視できることであるが,実際に日常的な行為として相手の島と往来するかどうかは島それぞれの文化的事情によって最終的に判断される」と述べている.
1. 隣の島が見えるかの計算方法
インターネットに掲載されている2つの計算方法を紹介する.2つの方法とも,見渡すエリアに障害物がなく遠くまで見通せる場合,観測点から見える水平線(あるいは地平線)までの距離は,地球(球と仮定)の丸さにより限界があり,光の屈折によってその限界距離よりも遠くまで見えるとしている.
(1)計算方法15)
高さhの観測点から水平線までの距離d1は,地球を球と仮定し半径をRとすると,ピタゴラスの定理より(図2の三角形PBO)
d1={h(2R+h)}1/2 ①
光の屈折により①式のd1の1.06倍遠くまで見えるとし,高さhの観測点から見える水平線までの距離d2は
d2=1.06{h(2R+h)}1/2 ②
とされている.
このサイトには1.06倍遠くまで見えるとした根拠は示されていないが,別のサイト6)に,光の屈折は気圧や気温などにより変化し,地平線までの距離は光線が直進すると仮定した場合に比べ7.3%または約6%大きくなると述べられている.なお,地球の半径R(理科年表でR=6378km)に比べhは極めて小さいので,図2のA〜B間の距離はP〜B間の距離dとほぼ同じとなる.
(2)計算方法27)
水平線までの距離の計算に光の屈折の影響を反映するため,地球の半径(この文献ではR=6370kmとしている.)をR=7364kmに 拡大し,図2の高さhの観測点P点から見える水平線(B点)までの距離をd3,その水平線ぎりぎりに見える山の高さをH,B点からその山までの距離をDとすると,d3とDはピタゴラスの定理より求まり,観測点からその山が見えるところまでの距離Lは
L=d3+D={h(2R+h)}1/2+{H(2R+H)}1/2 ③
とされている.高いところから見ると遠くまで見え,山が高いと遠くから見えることになる.
この文献には7364kmの根拠は示されていないが,以下に示すように,R=7364kmとして求めたd3は②式で求めたd2とほぼ同じ値となる.すなわち,d3={h(2R+h)}1/2においてhはRに比し非常に小さいのでd3≒{h2R}1/2,同様に①式のd1≒{h2R}1/2となる.したがって,d3/d1≒(R/R)1/2=(7363/6370)1/2=1.075となり,②式のd2/d1=1.06とほぼ同じで,③式で求めたd3と②式で求めたd2はほぼ同じ値となる.
図2 高さhの観測点Pより見た水平線(イメージ)
2. 琉球列島の見える島と見えない島
喜界島から屋久島が見えるか,また,琉球列島の島々を丸木舟で九州から台湾へ「南下」(沖縄本島以西は西進)する場合と台湾から九州へ「北上」する場合に隣の島が見えるか,③式により検討した.時代は鬼界カルデラ噴火後,縄文海進がほぼ終了した約5000年前以降の縄文時代とし,海面変動,隆起・沈降,火山島の噴火による変化は考慮せず,島の高さ,島と島の間の距離は現在と同じとした.
観測点から隣の島が見えるかの検討は,隣の島の最高地点を対象に行ったが,隣の島が見えるかどうかは,単に隣の島の最高地点の高さとそこまでの距離で決まるのではなく,様々な地点の高さとその地点までの距離で決まることに留意する必要がある.例えば,渡喜敷島から沖縄本島を目指す場合(表1の「北上」),沖縄本島の最高地点の与那覇岳(標高503m)は渡喜敷島の海岸から101kmと遠くて見えないが,34kmの与座岳(標高168m)は見えることになる.
観測点は,隣の島の最高地点(渡喜敷島から沖縄本島への航海は与座岳)との距離が最短となる海岸(出発時の舟の上,集落からそこまで舟で島に沿って進み隣の島に向かうと仮定)とし,そこから隣の島が見えない場合は観測点を島の最高地点とした場合も検討した.観測点の高さhは,観測点の標高+1.5m(目の高さ)とした.
表1 琉球列島の検討結果
・「海上距離」と「距離」は国土地理院ウエブサイト「地理院地図」で計測.
・観測点は海岸(出発時の舟の上,観測点高さh=1.5m)とした. 斜体は,観測点を最高地点(観測点高さh=観測点標高+1.5m)とした場合.
・「地質」は,最高地点の地質.産総研ウエブサイト「地質図 Navi」20万分の1日本シームレス地質図V2で調べ,次のように区分した.V:第四紀火成岩,C:第四紀堆積岩(石灰岩等),G: 新第三紀火成岩(花崗岩類),v:新第三紀火成岩(G以外), T:新第三紀・古第三紀の付加体等,M:中生代以前の付加体等.
*:大隅半島南部の最高地点.〇:海上距離が5km以下.>:Lより大.
検討結果を表1に示す.「高さH」は最高地点の標高,「海上距離」は島と島の間の最短の海上距離,「距離」は出発する島の観測点から目指す島の最高地点までの距離で,下段の斜体は観測点を最高地点とした場合である.「L」は③式で算出したL=d3+Dで,観測点の高さhが1.5 mの場合(海岸や舟上)d3は5kmとなる.なお,島の高さは地質と密接に関係している.
喜界島(最高地点)から屋久島(最高地点)までの「距離」は,③式で求めた「L」(観測点から水平線ぎりぎりに島が見えるところまでの距離)を超え(表1の「北上」),喜界島から屋久島は見えない.屋久島から喜界島(同「南下」)も見えない.なお,表1に示していないが,喜界島と奄美大島の間(海上距離24km)は,どちらの島の海岸からも相手の島が見える.大隅半島から中琉球(奄美・沖縄諸島)の久米島までは,「南下」,「北上」とも全ての島で海岸(出発時の舟の上)から隣の島が見える.
久米島と宮古島の間(海上距離217km)は,島の最高地点からでも相手の島は見えない.伊良部島・下地島と多良間島の間(同45km),石垣島から多良間島(同34km),西表島から与那国島(同65km)は,海岸(出発時の舟の上)から相手の島は見えないが最高地点からは見え,また漁などで沖合に出れば自分の島が見える範囲で相手の島が見える.与那国島の海岸から台湾(同110km)は見える.台湾の海岸から与那国島は見えないが,台湾の最高峰からは与那国島が見える.
3.縄文時代の航海への黒潮の影響と航海の限界
(1)航海への黒潮の影響
黒潮は,与那国島と台湾の間を北上し東シナ海に入り,九州と奄美大島の間のトカラ海峡から太平洋に抜けており,強い流れは幅100kmにも及ぶ8),9)(図1).この流れは6.3 kaもほぼ同じだったと考えられている10).
黒潮は流速が速く,黒潮が流れている区間を丸木舟で航海するときは大きな影響を受ける.黒潮が流れている島と島の間の距離をY,出発地と目的地を結ぶ線に対する黒潮の角度をθ (0°≦θ≦90°とする),その線上の黒潮の平均速度をk(0 < k),「漕いで進む速度」(漕いで進む平均速度で,風や波・うねりの影響,潮汐に伴う潮流の影響,休憩などを含み,黒潮の影響を 除く)をrとすると,隣の島までの航海時間tはピタゴラスの定理より次のようになる(図3).
黒潮に乗って漕ぐ(順潮)場合は
(rt)2 =(Y-kt・cosθ)2 +(kt・sinθ)2 ④
∴t=Y[-k・cosθ+{r2 +k2 (cos2 θ-1)}1/2]/(r2 -k2 ) ⑤
ただしr=kのときは, t=Y/(2k・cosθ) ⑥
なお,目指す島の方向と逆方向に漕いで黒潮に乗って目指す島に行く航海は対象としない.
⑤式のr2 +k2 (cos2 θ-1)=r2 -k2 sin2 θは0以上でなければならず,
k・sinθ≦r ただしθ=90°のときはk<r ⑦
⑦式は,目的地の方向に進むための「漕いで進む速度」 rの条件でrがこれより遅いと黒潮に流されてしまう.
黒潮に逆らって漕ぐ(逆潮)場合は,
(rt)2 =(Y+kt・cosθ)2 +(kt・sinθ)2 ⑧
∴t=Y[k・cosθ+{r2 +k2 (cos2 θ-1)}1/2]/(r2 -k2 ) ⑨
ただし,黒潮に流されないために r>k ⑩
図3 黒潮が流れていく距離と「漕いで進む距離」(イメージ)
(2)トカラ海峡
トカラ海峡の黒潮は,気象庁ウエブサイトの黒潮50m深の日別海流図9)(2021年以降が掲載されている)を見ると,流向は南東と東の間を変動し,流軸(流れの最も強い部分)は口之島の南の時もあるが屋久島と口之島の間にあることが多く,速度は日々変化している.黒潮の速度が大きい屋久島と口之島の間(56km)を対象に,目的地に対する黒潮の角度θ,黒潮の速度k,「漕いで進む速度」rと航海時間tの関係を検討した.Y=56km,黒潮の海面における流向と速度は50m深と同じと仮定し,黒潮の速度が大きい2022年7月7日海流図9)を例に,θ =30°(流向は東),k=3.3km/hr(約1.8kt:ノット,1ktは1.852 km/hr)のときのrとtの関係を⑤式と⑨式により試算した.また,θ=70°(流向が南東)になったときと,黒潮の速度kが1.5 km/hr(約0.8kt)と遅くなったときについても試算した.
図4 トカラ海峡周辺
その結果を図5に示す.屋久島から口之島に進む航海は逆潮なので,「漕いで進む速度」rが黒潮の速度kを超えなければ黒潮に流されてしまう.θ=30°(流向が東)のときは口之島に進む方向と逆向きの流れが強く,黒潮の速度kが3.3km/hrのとき「漕いで進む速度」r=3.9km/hr(後述(3)の実験航海の推測値)で漕ぐと,航海時間tは約83hrとなる.黒潮の流向が変わりθ=70°(南東)になると逆向きの流れが弱くなり,同じ黒潮の速度kと「漕いで進む速度」rでも,航海時間tは約45hrと短くなる.θ=30°で黒潮の速度kが1.5km/hrと遅くなると,同じ「漕いで進む速度」rでも,航海時間tは約22 hrと短くなる.当時の人たちは,伝承や経験から黒潮の流向が変わったり速度が遅くなったりすることを知っており,黒潮の状況が良いときを待って航海したと思われる.なお,口之島に渡るには,屋久島より口永良部島(最高点標高657m,「海上距離」は屋久島12km,口之島54km,各島の海岸から相手の島が見える)からの方が黒潮の影響(逆潮)は小さい.屋久島から口之島へは,黒潮の状況によって口永良部島経由としたのかもしれない.
口之島から屋久島への航海は順潮で,図5右に示すように屋久島から口之島への航海より容易である.
図5 屋久島・口之島間のθ,k,r,tの関係
(3)台湾から与那国島への実験航海
台湾から与那国島へ丸木舟で横断する実験航海が2019年に行われた11).舟は長さ755 cm,最大幅70cm,漕ぎ手はシーカヤックのエキスパートら5名(うち1名は舵とり)で,「ふつうに漕いでいるときのスピードは秒速1.08 m(約3.9 km/hr)ほどと思われる」と述べられている.実験航海は,北向きに流れる 黒潮を考慮して与那国島との距離が最短となる地点よりかなり 南方から7月7日14:38に出航し(出航後20分間の平均時速は約 3.9 km),16:00頃に黒潮の強流区間(黒潮の時速約4.9 km)に 入り,夜間も休憩を取りながら漕ぎ,8日午前6:30過ぎ(約15.9 hr後)に黒潮の強流区間を超えた.8日午後からは休憩の頻度 が目立ち,20:00過ぎから交替で見張をして約8時間睡眠をとり (漕がない舟の速度は約3km/hr),9日5:00前から動き出し11:48 に与那国島に上陸,直線距離206 kmに45 hr10 min(平均時速約4.6 km)を要している(図6).
実験航海(順潮)の「漕いで進む速度」rを,黒潮の強流区 間(添え字1)とそれ以降の区間(添え字2)に分けて⑤式より試算した.文献11)をもとに,黒潮の強流区間の距離Y1=96 km, θ1=40°,k1=4.9km/hrとすると,t1=15.9hrとなる「漕いで進む速度」r1は約3.9km/hrとなる.なお,図6より黒潮の速度k1が多少異なっても「漕いで進む速度」r1はあまり変わらないことが分かる.黒潮も含めた平均速度は96 km/15.9 hr=約6.0 km/hrである.強流区間以降は,Y2=112 km,θ2=40°,k2=3.0 km/hrとすると,漕いだ時間t2が29.3 hr-8.0 hr(睡眠時間) =21.3hrとなる「漕いで進む速度」r2(睡眠時間を除く)は約 3.5 km/hrとなる.「漕いで進む速度」が強流区間より遅いのは,疲労も影響しているのかもしれない.
図6 台湾から与那国島への実験航海
(4)台湾・与那国島間の最短ルートの航海
台湾・与那国島間の最短ルート(約110 km,図6)を航海す る場合について検討した.実験航海時の黒潮を参考に,最短ル ートにおける強流区間の距離Y=50 km,θ=80°,黒潮の速度 k=4.9 km/hrとすると,台湾から与那国島へ進む場合(順潮) の「漕いで進む速度」rは⑦式よりk・sinθ=4.83 km/hr以上で,かつ長時間(r=4.83 km/hrの場合は強流区間だけで約47 hr)漕がなければならず,航海は極めて難しかったと思われる.逆方向(与那国島から台湾)に進む場合は,逆潮なので更に難し くなる.
2021年以降の日別海流図9)を見ると,最短ルートの区間では黒潮はほぼ北向きに流れ2日続けて1.9 km/hr(約1.0 kt)以下となることは滅多にないが,黒潮の速度がk=1.9 km/hrとなったときについて検討した.Y= 110 km,θ= 80°,「漕いで進む速度」r= 3.9 km/hrとすると,台湾から与那国島へ進む場合の 航海時間tは⑤式より約29 hrとなる.しかし,舟の上から与那国島がぎりぎり見える距離「L」は63 km(表1)なので,出航後110 km-63 km=47 km(全区間の39%)の間は舟から与那国島は見えない.海図も羅針盤もない当時,進む方向が違うと 流されてしまう黒潮の中で,目指す与那国島が約11時間(約29 hr×39%)も見えない航海は極めて難しかったと思われる.上記の状況で逆方向(与那国島から台湾)に進む場合,天気がよければ台湾は見え,航海時間は⑨式より約36 hrとなる.しかし,前述のように黒潮が2日続けて1.9 km/hr以下のことは滅多になく,また台湾から与那国島への航海が極めて難しかったの で,台湾と与那国島の間の交流はほとんどなかったと思われる.
(5)航海の限界
土器などの遺物や実験航海の状況と試算結果より,縄文時代の丸木舟による航海ができる条件(航海の限界)は,舟から島が見えることだと考えられる.航海時間は,島と島の間の距離と「漕いで進む速度」,黒潮が流れている区間ではその流向(目的地に対する角度)と速度によっても左右され,当時の無寄港での航海時間の限度は疲労や海況・天候の悪化リスクを回避するため丸2日くらい,当時の「漕いで進む速度」(数時間以上漕ぐ場合)は最大3.9 km/hrくらいと思われる.
あとがき
気象予報,海図や羅針盤が無い時代に危険な外海に漕ぎ出した人たち,航海を左右した黒潮と琉球列島の島々の配置,島々の地質や成り立ちなど興味はつきない.本稿のきっかけの質問と貴重なコメントを頂いた星野延夫氏に感謝いたします.
参考文献
1)海洋研究開発機構ウエブサイト「福徳岡ノ場の噴火-福徳岡ノ場の噴火と軽石の成分-」
2)早田春樹「喜界町発掘調査近況」,地域の特色ある埋蔵文化財活用事業シンポジウム「発見された3,000年前の大集落」資料集,喜界町埋蔵文化財センター , 2016年
3)鹿児島県上野原縄文の森ウエブサイト「縄文の風 かごしま考古ガイダンス第18回朝鮮半島と西北九州と活発に交流, 埋蔵文化財の宝庫・屋久島」
4)木下尚子「先史琉球人の海上移動の動機と文化-台湾と八重山諸島の文化交流の解明に向けて-」,文学部論叢 第109号,熊 本大学, 2018年
5)CASIOウエブサイト「Ke!san地上から見渡せる距離-高精度計算サイト」
6)noteウエブサイト「Dr.Stone 171話と大気屈折を考慮した地平線までの距離|朱理|」
7)田代博「富士山の見え方に拘る-見える限界の場所とダイヤモンド富士-」, 地質ニュース590号, 2003年
8)気象庁ウエブサイト「海水温・海流の知識, 黒潮」
9)気象庁ウエブサイト「海洋の健康診断表,海流に関する診断表,予報,データ,日別海流,東シナ海海域」
10)研究代表郭新宇「万年スケールでみた黒潮の流路変遷と黒潮分岐流の形成メカニズム」,科研費研究報告書,2021 年
11)海部陽介「サピエンス日本上陸3万年前の大航海」,講談社.2020年
※本内容は,日本地質学会News,Vol.26, No.5, およびNo.6(2023年5月号,2023年6月号)に前編後編に分割して掲載されています.
【geo-Flash】No.588 [2023京都]リアル懇親会【残席僅少】まもなく締切です
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.588 2023/8/16┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2023京都大会]全体日程表を公開しています
【2】[2023京都大会]各種参加申込受付中
【3】[2023京都大会]若手会員向けルームシェア型宿泊プラン
【4】[2023京都大会]学生のための地質系業界説明会
【5】[2023京都大会]その他
【6】コラム 琉球列島:縄文人が挑んだ遠い島と黒潮
【7】支部情報
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2023京都大会]全体日程表を公開しています
──────────────────────────────────
大会の全体日程表を更新しました(8/16現在)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/program
講演プログラムも,近日公開予定です(講演要旨は9月公開予定).
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2023京都大会]各種参加申込受付中
──────────────────────────────────
事前参加登録締切:8月31日(木)18:00
懇親会参加申込締切:8月18日(金)18:00
※懇親会は定員になり次第締め切ます.お早めにお申し込みください.
※懇親会の当日受付は行わない可能性があります.忘れずにお申し込み下さい.
[大会参加費]事前申込
正会員(一般会員):6,000円
正会員(シニア会員):3,000円 ※4/1時点で65歳以上の正会員
正会員(学生会員の院生):1,500円
名誉会員/非会員招待者/学部学生:無料
・昨年大会より,大会参加登録費と発表料金(1,500円/件)を分離しました.
・発表する方は大会参加登録費と発表料金の両方の支払いが必要です.
・講演要旨集の冊子体は作成・販売いたしません.
大会参加登録に関する詳細は,
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/sanka
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2023京都大会]若手会員向けルームシェア型宿泊プラン
──────────────────────────────────
「学会先での宿泊費を抑えたいけれど,ホテルの部屋をシェアする相手が
見つからない...」「地質学会で仲間をつくりたい!」といった若手会員
のために,“ルームシェア型宿泊プラン”を企画しました.
(注)「若手同士の交流」と「低価格化」の観点から,本プランは,
相部屋でのご案内となります.
申込締切:8月18日(金)
http://geosociety.jp/science/content0164.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2023京都大会]学生のための地質系業界説明会
─────────────────────────────────
地質系学科主任・就職担当教員の皆様,
地質系学科学部生・院生の皆様,ぜひご参加ください!
学生の皆様に,将来の就職先の一つである地質系業界の実態や各社の業務内容
などを知っていただくために開催する当学会の恒例行事です.今年度の説明会
では,対面とオンラインによるものを別の日程で行います.
今年度は,地質系学科に後援をいただき,大学,企業,学会が連携して高等教育
を終えた専門技術者が社会で活躍・貢献できるようにしたいと考えています.
・対面説明会:9/18(月祝)午後半日,学術大会会場内(京都大学吉田南構内)
・オンライン説明会:9/22(金)午後.Zoomを使ったオンライン説明会
参加費無料,会員・非会員を問わず,同じ学科の友人をお誘いあわせのうえ,
お気軽にご参加ください.
事前参加申込受付中:9/14締切
(来場者数把握のため訪問の希望予定をあらかじめお申し込みください)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/gyokai_support
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2023京都大会]その他
──────────────────────────────────
■企業団体展示・書籍販売:8月25日(金)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/tenji
■ランチョン(企業向け・有料):本年より,学術大会会期中(9/17-19)
に,企業・団体の皆様に,セミナーやPR活動にご利用いただけるよう,
会合利用のサービス(有料)を始めます.
詳しくは,
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/meeting_co
■ お子様をお連れになる方へ
ご家族で学会に参加される会員で,大会期間中に保育施設の利用を希望される
方には,学会から利用料金の一部を補助いたします.会場内には保育室を設け
ませんので,近隣施設をご紹介いたします.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/kids
■■■■■ 2023京都大会 本サイト■■■■■
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】コラム 琉球列島:縄文人が挑んだ遠い島と黒潮
──────────────────────────────────
正会員 高山信紀
喜界島で福徳岡ノ場2021年8月噴火のものと見られる漂着軽石を見た話を
友人にしたとき,「喜界島から屋久島は見えるか?」と聞かれた.本稿は,
これをきっかけに,九州から台湾の間の島々について隣の島が見えるか
計算式により確認するとともに,縄文時代の航海への黒潮の影響と当時の
航海の限界を考えてみたものである.
全文はこちら,,,http://geosociety.jp/faq/content0056.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
・関東地震100年関連行事:講演会「関東地震から100年」
9月30日(土)13:30-16:10(オンライン)
「関東大震災と土砂災害」井上公夫氏
「地震西進系列と次の関東・南海トラフ地震」石渡 明氏
申込期間:9/1-9/22(金)17:00締切
http://geosociety.jp/outline/content0201.html#kanto-jishin
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
地質地盤情報の活用と法整備を考える会
8月1日ホームページを更新しました.
https://www.geo-houseibi.jp
気象庁:関東大震災特設サイト
―関東大震災から100年―知って備えよう:過去の大災害から学ぶ
https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/1923_09_01_kantoujishin/index.html
防災学術連携体:関東大震災100年関連行事等の特設ページ
https://janet-dr.com/090_abroadandhome/091_100_kantohEQ.html
「関東大震災100年と防災減災科学」(電子版)完成
※日本地質学会も寄稿しました.
https://janet-dr.com/090_abroadandhome/KantohEQ100th_book_A4.pdf
-------------------------------------------------
(共)岩石-水相互作用(WRI-17)または
応用同位体地球化学(AIG-14)合同国際会議
8月18日(金)-22日(火)
会場:仙台国際センター
https://www.wri17.com/
(後)学術会議公開シンポジウム
「オープンサイエンス時代における
学術データ・学術試料の保存・保管,共有問題の現状と将来」
8⽉20⽇(⽇)13:00-17:20
場 所:オンライン開催(⼀般参加・可)
https://www.scj.go.jp/ja/event/
WCFS2023 Japan
Floating Solutions for the Next SDGs
8月28日-29日:論文発表等
8月30日:オプション テクニカルツアー
場所:日本大学理工学部(東京都千代田区神田駿河台)
https://wcfs2023.nextsdgs.org/
(後)第66回粘土科学討論会
9月12日(火)-13日(水)
会場:戦災復興記念館(宮城県仙台市青葉区)
http://www.cssj2.org/
ぼうさいこくたい2023(第8回防災推進国民大会)
9月17日(日)-18日(月・祝)
場所:横浜国立大学(横浜市保土ヶ谷区常盤台)
https://bosai-kokutai.jp/2023/
(共)2023年度日本地球化学会 第70回年会
9月21日(木)-23日(土)
開催場所:東京海洋大学品川キャンパス会場
口頭(ハイブリッド),ポスター(対面)
http://www.geochem.jp/meeting/
学術会議公開シンポジウム
文化施設としての自然史系博物館を考える
9月23日(土)13:00-18:00
オンライン開催(配信,定員500名)
参加費無料・要事前登録
9月21日締切(定員になり次第締切)
https://www.scj.go.jp/ja/event/2023/348-s-0923-2.html
第242回イブニングセミナー(オンライン)
9月29日(金)19:30-21:30
演題:「地下水汚染の自然浄化作用と地圏環境リスク評価」
講師:川辺能成 先生(早稲田大学創造理工学部)
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
日本堆積学会20周年記念行事
9月30日(土)
会場 法政大学市ケ谷キャンパススカイホール
早期参加登録(9月15日締切)
https://sites.google.com/view/ssj20th/home
(協)Techno-Ocean 2023
10月5日(木)-7日(土)
会場:神戸国際展示場2号館 ほか
https://to2023.techno-ocean.com/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
山梨県富士山科学研究所任期付研究員募集(9/8)
茨城大学理工学研究科地球環境科学領域助教(テニュア・トラック)公募(10/16)
九州大学理学研究院 地球惑星科学部門 教授公募(9/30)
信州大学理学部理学科地球学コース助教(テニュア・トラック)公募(9/8)
隠岐ユネスコ世界ジオパークの地質研究員募集(随時受付)
箱根ジオパーク(箱根町職員:学芸員)採用試験(8/24)
2024年度笹川科学研究助成募集(9/15-10/16)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.589[2023京都大会]まもなく講演要旨公開です
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.589 2023/9/5┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2023京都大会]講演プログラムが公開しています
【2】[2023京都大会]まもなく講演要旨が公開となります
【3】[2023京都大会]学生のための地質系業界説明会:参加学生申込受付中!
【4】[2023京都大会]その他(ECSロゴのDL/お子様をお連れになる方へ)
【5】本の紹介「高レベル放射性廃棄物処分場の立地選定」
【6】支部情報
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2023京都大会]講演プログラムが公開しています
──────────────────────────────────
講演プログラムを公開しました.プログラムはどなたでもご覧いただけます.
大会サイト画面左下「プログラム」から検索等してください.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2023京都大会]まもなく講演要旨が公開となります
──────────────────────────────────
講演要旨(要ログイン)はまもなく公開予定です。
要旨公開までに、事前参加登録者の皆様に参加者用ログイン情報を
メールでお知らせするため,現在作業中です(9/10頃予定)。
入金確認が取れない場合は,参加者用ログイン情報が発行できません.
まだお支払いがお済みでない方は,急ぎご対応をお願いいたします.
また,領収書のダウンロードURLもメールでお知らせします.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2023京都大会]学生のための地質系業界説明会:参加学生申込受付中!
─────────────────────────────────
地質系学科主任・就職担当教員の皆様,
地質系学科学部生・院生の皆様,ぜひご参加ください!
—---------------------------------
参加学生申込受付中:9/14締切
—---------------------------------
学生の皆様に,将来の就職先の一つである地質系業界の実態や各社の業務内容
などを知っていただくために開催する当学会の恒例行事です.今年度の説明会
では,対面とオンラインによるものを別の日程で行います.
今年度は,地質系学科に後援をいただき,大学,企業,学会が連携して高等教育
を終えた専門技術者が社会で活躍・貢献できるようにしたいと考えています.
過去最大47社(対面32社)の企業団体が集結!地質系業界の情報を最もよく知る
ことのできる機会です.ぜひご参加ください.
・対面説明会:9/18(月祝)13:00-17:00,吉田南総合館北棟1階,東棟1階
・オンライン説明会:9/22(金)午後.Zoomを使ったオンライン説明会
参加費無料,会員・非会員を問わず,同じ学科の友人をお誘いあわせのうえ,
お気軽にご参加ください.
お申し込みは,下記から
(来場者数把握のため訪問の希望予定をあらかじめお申し込みください)
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/gyokai_support
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2023京都大会]その他(ECSロゴのDL/お子様をお連れになる方へ)
──────────────────────────────────
■ECS (Early Career Scientist)ロゴのダウンロード
ECSに該当する方で、7/12までにECSロゴ使用申請を忘れた方、または、
発表は予定していないが学術大会に参加する方で、ECSロゴの使用を希望
される方は以下からロゴをダウンロード頂けます。
大会期間中、自由にお使い頂き、ご自身のキャリアアップ等にお役立て下さい。
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/etc#diversity
■ お子様をお連れになる方へ(保育料補助)
ご家族で学会に参加される会員で,大会期間中に保育施設の利用を希望される
方には,学会から利用料金の一部を補助いたします.会場内には保育室を設け
ませんので,近隣施設をご紹介いたします.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/kids
■■■■■ 2023京都大会 本サイト■■■■■
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】本の紹介「高レベル放射性廃棄物処分場の立地選定」
──────────────────────────────────
正会員 原子力規制委員会委員 石渡 明
「高レベル放射性廃棄物処分場の立地選定−地質的不確実性の事前回避−」
千木良雅弘 著
近未来社 2023年6月8日発行,ISBN 978-4-906431-55-7 c1044,A5判,
168ページ,文献リスト付き 索引なし
著者はこれまで近未来社から「風化と崩壊」(1995),「災害地質学入門」(1998; 2018に「災害地質学ノート」へ改題新版),「群発する崩壊」(2002),「崩壊の場所」(2007),「深層崩壊」(2013),「写真に見る地質と災害」(2016)を出版し,東京大学出版会の島崎英彦・新藤静男・吉田鎮男編「放射性廃棄物と地質科学−地層処分の現状と課題−」(1995)では第8章「岩盤割れ目のセルフシーリング」を執筆した.本書の構成は,「はじめに」(p. 7-),第1章「日本の高レベル放射性廃棄物(HLW)地層処分に向けた研究開発の流れ」(p. 15-),第2章「日本のHLW地層処分の考え方と処分場立地選定の方法」(p. 23-),第3章「日本のHLW地層処分研究の問題点」(p. 39-),第4章「隠れた地質的問題」(p. 45-),第5章「様々な地質の構造と性質」(p. 73-),第6章「不確実性の事前回避と最近の立地選定の状況」(p. 145-),「あとがき」(pp. 155-162)となっている.「はじめに」の冒頭には「本書は私個人の責任で書いた著作であり,私が理事長を務めている公益財団法人深田地質研究所の総意を著したものではない」という断り書きがある.また,10頁では「HLW地層処分関係の研究開発に地質学の立場から第三者的に長くかかわってきた人は意外に少なく,私はその一人だと思う」としてその関わりを述べている.
本書の帯には「変動帯ゆえに見過ごされてきた地質的検討」という見出しで「はじめに」の抜粋があり,それを更に要約すると,「処分場に対する火山活動や断層運動の直接的影響は回避できたとしても,地質構造や地下水にまつわる不確実性は,処分場立地選定の段階的調査において,最後まで持ち越される可能性が高い・・・わが国は変動帯にあるがゆえに,あまりにも地殻変動に目が向き,それ以外の重要な課題を置き忘れたようである」とのことである.この「不確実性」を実例に沿って解説したのが本書のほぼ半分を占める第5章で,原子力発電環境整備機構(NUMO)によるセーフティーケース(包括的技術報告書,概要説明:https://www2.nra.go.jp/data/000359348.pdf)の検討対象母岩の3つのモデルの設定にとらわれず,著者の地質調査経験から,地層本来の均質(不均質)性に注目して,新第三紀火山岩類(寿都・神恵内,NUMOの3モデル外),新第三紀堆積岩類(幌延,NUMOも同語),付加体(「先新第三紀堆積岩類」),花崗岩類(瑞浪,「深成岩類」)の4種の地質を解説している.以下にこれらの要点を紹介する.
新第三紀火山岩類についてNUMOは「処分場の設計および安全評価の観点から深成岩類と類似」とするが,本書ではこれを「間違いである」と断言している(p. 74).深成岩類は割れ目を除けば均質なのに対して,新第三紀火山岩類は本来的な性質として不均質であり,非常に透水性が高い部分があって,同じ地質の泊発電所の例を挙げ,多数のボーリング調査をしないと地下の構造を把握するのが難しく,そのような調査を行うこと自体が,処分場の建設には好ましくないと述べている.
新第三紀堆積岩類は「軟岩」であるがゆえに破断することなく変形し,割れ目ができても続成作用の過程で閉じてしまい,このような性質はHLW地層処分にとって有利な性質と考えられてきた(p. 97).しかし,珪藻泥岩など化学的条件で硬くなった地層は割れやすく,高圧の地下水によって泥火山が生じることもあり,「日本海側の褶曲地域は,油田胚胎地域や断層沿いではないにしても,処分場立地選定にはあまり好ましいとは言えない」(p. 111).なお,石狩,常磐,北九州などの古第三紀堆積岩地域は,その多くが石炭層を含んでおり,将来採掘される可能性があるため,これも処分場立地には不適である.
付加体は資源エネルギー庁の「科学的特性マップ」(2017)の「好ましい特性が確認できる可能性が相対的に高い地域」に多く含まれ,上述のNUMOの3モデルのうち「先新第三紀堆積岩類」に当たる.著者の評価では,付加体は大規模な破砕帯を伴う衝上断層を多く含み,「文献調査の結果断層破砕帯はあまりないように見えても,調査をしてみた結果,多数の破砕帯があった,という結果になりうる.付加体は地質的不確実性が高いことから,HLW地層処分場の立地選定には適していない」(p. 123).
花崗岩類は,我が国など多くの国で処分場の母岩として検討されてきた.実際,フィンランドやスウェーデンでは花崗岩にHLW地層処分場が決定された.ただし,これらは安定大陸にあり,割れ目も少ない.一方,我が国で見る花崗岩は大部分が多くの割れ目を有している.しかし,日本でも花崗岩体の芯の部分は割れ目が少なく,そこはHLW地層処分場の有力候補である(p. 124).岐阜県瑞浪の超深地層研究施設(既に閉鎖,埋め戻し済み)では深さ500mまで立て坑と水平坑道が展開されたが,これらは高角度の断層と交差する形で掘削され,断層近傍の岩盤の性質に関しては詳しいデータが得られたものの,断層から離れた,割れ目の少ない花崗岩の情報は限られている(p. 143).
本書には若干記述不足や誤りと思われる部分がある.本書56頁に,原子力発電所の新規制基準では「将来活動する可能性のある断層等」の活動性評価において,「12〜13万年前より古い地層が断層を被覆し,断層によって切断されていなければ将来的な断層の活動を考慮する必要はないとされている」と書いてある.これは「上載地層法」による評価であり,それ自体は正しいが,実際は原子力規制委員会が新規制基準への適合性を認めた発電所等の約半数において,「鉱物脈法」が用いられてきた(地質審査ガイド,p. 13(5), 20(2)⑥:https://www.nra.go.jp/data/000069164.pdf).日本の原子力発電所は海岸沿いにあるので,その敷地に12〜13万年前の段丘堆積物の地層がある場合が多く,その地層と断層との切り合い関係で活動性が判断できるが,その地層がない場合や,あっても判断が難しい場合は鉱物脈法を用いている.また,57頁1〜2行目の「原子力発電所の場合,将来よりも厳しい基準になる」は意味不明だが,「,将来」の3字を削除すれば意味が通じると思う.
本書では著者の豊富な野外調査経験に基づくエピソードが多く語られる.1/5万地質図「南部」(山梨・静岡県境)で数kmにわたって断層がない山地でも,実は20〜100m間隔で平行な断層が分布し,それに沿って「山向き小崖」や「線状凹地」が発達する(p. 54-55).一方,千葉県北東部の屏風ヶ浦では7kmの範囲で断層がほとんどない(p. 58-59, 口絵①).そして,四万十付加体の中に地下発電所を建設しようとして(場所は不詳),その周囲の半径1km程度を踏査したら,塊状硬質な砂岩が連続して露出していた.この段階で「もう調査はいらないですね」となったが,念のため予定地をボーリング掘削して「大丈夫」なことを確かめた.「このように,「安心して」調査・工事を進められることは,HLW地層処分にあたってきわめて重要である.そのためにも,不確実性の回避は不可欠なことである」(p. 146)という話は,「付加体は処分場の立地に不適」とする上述の著者の主張と一見矛盾するが,HLW地層処分場選定の段階的調査においては,まず地質踏査を優先して行うべきとの著者の指摘(p. 40-44)は説得力がある.
なお,原子力規制委員会は,「第二種廃棄物埋設の廃棄物埋設地に関する審査ガイド」(2022.04.20,改正前は「中深度処分の…」) (https://www.nra.go.jp/data/000387588.pdf),「特定放射性廃棄物の最終処分における概要調査地区等の選定時に安全確保上少なくとも考慮されるべき事項」(2022.08.24,資料の表題は「地層処分において安全確保上…」)(https://www.nra.go.jp/data/000402042.pdf)などを公表してきた.
拙稿に貴重な御意見を賜った原子力規制委員会委員長代理の田中 知先生に感謝する.
(正会員 原子力規制委員会委員 石渡 明)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部情報
──────────────────────────────────
[関東支部]
・関東地震100年関連行事:講演会「関東地震から100年」
9月30日(土)13:30-16:10(オンライン)
「関東大震災と土砂災害」井上公夫氏
「地震西進系列と次の関東・南海トラフ地震」石渡 明氏
申込期間:9/1-9/22(金)17:00締切
http://geosociety.jp/outline/content0201.html#kanto-jishin
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
気象庁:関東大震災特設サイト
―関東大震災から100年―知って備えよう:過去の大災害から学ぶ
https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/1923_09_01_kantoujishin/index.html
防災学術連携体:関東大震災100年関連行事等の特設ページ
https://janet-dr.com/090_abroadandhome/091_100_kantohEQ.html
「関東大震災100年と防災減災科学」(電子版)完成
※日本地質学会も寄稿しました.
https://janet-dr.com/090_abroadandhome/KantohEQ100th_book_A4.pdf
-------------------------------------------------
(後)第66回粘土科学討論会
9月12日(火)-13日(水)
会場:戦災復興記念館(宮城県仙台市青葉区)
http://www.cssj2.org/
ぼうさいこくたい2023(第8回防災推進国民大会)
9月17日(日)-18日(月・祝)
場所:横浜国立大学(横浜市保土ヶ谷区常盤台)
https://bosai-kokutai.jp/2023/
(共)2023年度日本地球化学会 第70回年会
9月21日(木)-23日(土)
開催場所:東京海洋大学品川キャンパス会場
口頭(ハイブリッド),ポスター(対面)
http://www.geochem.jp/meeting/
学術会議公開シンポジウム
文化施設としての自然史系博物館を考える
9月23日(土)13:00-18:00
オンライン開催(配信,定員500名)
参加費無料・要事前登録
9月21日締切(定員になり次第締切)
https://www.scj.go.jp/ja/event/2023/348-s-0923-2.html
(協)Techno-Ocean 2023
10月5日(木)-7日(土)
会場:神戸国際展示場2号館 ほか
https://to2023.techno-ocean.com/
海底地質リスク評価研究会講演会
「我が国は本当に海洋⽴国なのか?」
10月12日 (水)15:00から
会場:基礎地盤コンサルタンツ本社(ハイブリッド)
講師:阪口 秀氏(笹川平和財団海洋政策研究所 所⻑)
https://www.kiso.co.jp/sssgr/topics/events/entry-1007.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・東京大学理学系研究科地球惑星科学専攻地球生命システム動態学分野教授公募(9/11)
・山田科学振興財団2024年度海外研究援助公募(10/31)
・環境省所管競争的研究費「環境研究総合推進費」令和6年度新規課題公募(9/13-10/17)
※公募説明9/22開催
・中谷医工計測技術振興財団科学教育振興助成募集(10/1-11/30)
・五島列島ジオパーク推進協議会ジオパーク専門員募集(10/13)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.590(臨時)[2023京都大会]まもなく学術大会がはじまります!!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.590 2023/9/15┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2023京都大会]講演プログラム・講演要旨公開中
【2】[2023京都大会]学生のための地質系業界説明会:オンラインもあります
【3】[2023京都大会]その他(若手会員向けの取り組み/お子様をお連れになる方へ)
【4】[2023京都大会]会場でのマスク着用,換気のお願い
【5】[2023京都大会]大会期間中はSNSをぜひご確認ください!
■■■■■ 2023京都大会 本サイト■■■■■
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/top
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2023京都大会]講演プログラム・講演要旨公開中
──────────────────────────────────
講演プログラム・講演要旨を公開しています.
プログラムはどなたでもご覧いただけます.
また,大会サイト画面左下「プログラム」から講演の検索ができます.
「招待講演」「ハイライト」「エントリー」「ECS」などの
キーワードでも検索可能です.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/top
講演要旨は,会期後1ヶ月まで,参加者用ログインが必要です.
ログイン情報は,参加者に事前にお知らせいたしました.
詳しくは,https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/emergency
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2023京都大会]学生のための地質系業界説明会:オンラインもあります
─────────────────────────────────
学生の皆様に,将来の就職先の一つである地質系業界の実態や各社の業務内容
などを知っていただくために開催する当学会の恒例行事です.今年度の説明会
では,対面とオンラインによるものを別の日程で行います.
今年度は,地質系学科に後援をいただき,大学,企業,学会が連携して高等教育
を終えた専門技術者が社会で活躍・貢献できるようにしたいと考えています.
過去最大47社(対面32社)の企業団体が集結!地質系業界の情報を最もよく知る
ことのできる機会です.ぜひご参加ください.
・対面説明会:9/18(月・祝)13:00-17:00,吉田南総合館北棟/東棟1階
***当日の飛び入り参加も大歓迎です***
・オンライン説明会:9/22(金)午後.Zoomを使ったオンライン説明会
***オンラインの事前参加受付中:9/19まで締切延長中***
参加費無料,会員・非会員を問わず,
同じ学科の友人をお誘いあわせのうえ,お気軽にご参加ください.
詳しくは,
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/gyokai_support
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2023京都大会]その他(若手会員向けの取り組み/お子様をお連れになる方へ)
──────────────────────────────────
■若手会員向けの様々な取り組みや企画が予定されています.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/etc#diversity
■ お子様をお連れになる方へ(保育料補助)
ご家族で学会に参加される会員で,大会期間中に保育施設の利用を希望される
方には,学会から利用料金の一部を補助いたします.会場内には保育室を設け
ませんので,近隣施設をご紹介いたします.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/kids
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2023京都大会]会場でのマスク着用,換気のお願い
──────────────────────────────────
7-8月と感染拡大傾向が続き,学術大会会場内ではマスク着用をお願いする
こととなりました.
★会場での注意点★
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/reception#caution
特に4年ぶりの対面ポスターは,活発な議論に伴い,室内の密な場面が予想されます.
できるだけマスク着用をお願いいたします.
口頭会場でも,休憩時間などに室温や空調を考慮しつつ適宜換気を行いたいと思います.
参加者の皆様は,ご協力のほどよろしくお願いいたします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2023京都大会]大会期間中はSNSをぜひご確認ください!
──────────────────────────────────
大会期間中のアップデートは,大会サイトのほかSNSを更新します.
ぜひご覧ください.
(X; 旧Twitter)https://twitter.com/gsofjapan
(Instaglam)https://www.instagram.com/gsofjapan/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.591(臨時)[2023京都大会]会場フォト
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬
┬┴┬┴┬┴┬ No.591 2023/9/18┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【0】地質情報展開幕 9月16日
──────────────────────────────────
■地質情報展
開会式!
床張り地質図
水路堆積実験
ロックバランシング
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2023京都大会の様子 9月17日
──────────────────────────────────
■会場の様子と表彰式
京都大会!
立ち見続出
ポスター会場
企業ブース
ジュニアセッション
ジュニアセッション
ジュニアセッション
ポスター会場
ポスター会場
市民講演会
岡田会長挨拶
来賓挨拶
宮下名誉会員
嶋本名誉会員
小林永年会員
柴 永年会員
増田永年会員
矢島永年会員
学会賞 道林会員
功績賞 小山内会員
功績賞 佐藤会員
小澤賞 沢田会員
論文賞 入月会員
論文賞 内野会員
論文賞 野田会員
論文賞 吉田会員
奨励賞 原田会員
奨励賞 佐久間会員
奨励賞 鈴木会員
奨励賞 山岡会員
フィールド賞 江島会員
フィールド賞 羽地会員
式典会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2023京都大会の様子 9月18日
──────────────────────────────────
■講演会2日目
今日も立ち見続出!
ポスター会場
ポスター会場
ポスター会場
業界説明会
業界説明会
地質情報展
地質情報展
地質情報展
地質情報展
地質情報展
地質情報展
【geo-Flash】No.592(臨時)坂巻幸雄 名誉会員 ご逝去
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.592 2023/9/25┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 坂巻 幸雄 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
坂巻 幸雄 名誉会員(元 地質調査所)が、令和5年8月23日に
逝去されました(91歳)。
これまでの故人の功績を讃えるとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げ
ます。なお、ご葬儀はすでに執り行われたとのことです。
会長 岡田 誠
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.593 ショートコース「応力逆解析法」再び!!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.593 2023/10/3┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2024年度各賞候補者募集(12/1締切)
【2】2024年度代議員および役員選挙について
【3】第9回ショートコース:応力逆解析法(参加申込受付中)
【4】ニュース誌の送本希望の選択について
【5】2023京都大会「学生優秀発表賞」決定
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2024年度各賞候補者募集(12/1締切)
──────────────────────────────────
今年も運営規則第16 条および各賞選考規則(本号別途掲載)に基づき,賞の
候補者を募集いたします.ご推薦いただいた方の中から,各賞選考委員会
(委員は理事会の互選と職責により選出)が候補者を選考し,理事会での決定,
総会での承認を経て表彰を行います.期日厳守にてご推薦ください.
個人(正会員または名誉会員)からの推薦も可能です.
なおご推薦にあたっては,被推薦者が常日頃から学会倫理綱領・行動規範や
その他の法令および社会通念上守るべきルールを遵守しているかについて
推薦者には十分にご留意いただき,授賞に相応しい方をご推薦いただきます
ようお願い申し上げます.
応募締切:2023 年12 月1 日(金)必着
詳しくは,こちらから(新会員システムへのログインが必要です)
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
(注)初めてログインする方・パスワードをお忘れの方は こちらから
https://www.geosoc-member.jp/Member/fgform.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2024年度代議員および役員選挙について(10/23より立候補受付開始)
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会定款ならびに選挙規則・選挙細則に基づき,代議員および
役員(監事,理事)選挙を実施いたします.
代議員選挙(選挙人,被選挙人とも正会員)立候補受付期間:
2023年10月23日(月)10時より11月20日(月)17時締切
詳しくは,こちらから(新会員システムへのログインが必要です)
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
(注)初めてログインする方・パスワードをお忘れの方は こちらから
https://www.geosoc-member.jp/Member/fgform.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】第9回ショートコース:応力逆解析法(参加申込受付中)
──────────────────────────────────
今回は,4月に応募者多数につき締切日前に申し込みを締め切らせていただいた
応力逆解析法のショートコース(第7回)を再度行います.
応力逆解析法は,現在または地質学的過去の,テクトニクスの原動力を解明する
方法の1つです.「逆」解析と呼ばれるのは,変形の結果として生じた地質構造
から,変形の原因である応力を推定するからです.今回も多くの学生・若手研究者
の皆様に受講していただきたいコースです
日程:2023年10月22日(日)9:00-/14:00-
*************************************
申込締切:2023年10月16日(月)
*************************************
詳しくは,http://geosociety.jp/science/content0165.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】ニュース誌の送本希望の選択について
──────────────────────────────────
ニュース誌の送本を希望制とし,新しく稼働している会員システムに「送付不要」の
選択ボタンを設けて,皆様に選択していただくようにいたしました.
毎月15日頃までにお手続きいただければ,当月号(月末)の送本から反映されます.
詳しくは,http://geosociety.jp/news/n180.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】2023京都大会「学生優秀発表賞」決定
──────────────────────────────────
39件の発表が「学生優秀発表賞」に決定しました(エントリー総数123件).
なお,該当講演については,「学生優秀発表賞」で講演検索もしていただけます.
受賞一覧は大会HPよりご確認ください.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/etc#sho_kekka
また,ジュニアセッション「優秀賞」「奨励賞」も決定しました.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/static/gyoji#jr
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
地質地盤情報の活用と法整備を考える会
10月1日、ホームページを更新しました.
https://www.geo-houseibi.jp
—-------------------------------
(協)Techno-Ocean 2023
10月5日(木)-7日(土)
会場:神戸国際展示場2号館 ほか
https://to2023.techno-ocean.com/
藤原ナチュラルヒストリー振興財団九州シンポジウム
「天変地異の時代:火山列島に生きる」
会場:アクロス福岡 7階大会議室(福岡市中央区天神1丁目)
ハイブリッド開催
10月15日(日) 13:00-16:45
参加費無料(要参加申込:10/5締切)
https://fujiwara-nh.or.jp/archives/2023/0801_160223.php#!
中谷医工計測技術振興財団オンラインセミナー
「学習指導要領改訂とその後」探究的な学びは生徒と教員をどう変容させるのか?
10月17日(火) 15:00-16:30
参加無料(要事前申込:10/13締切)
https://x.gd/PN9B3
第62回温泉保護・管理研修会
10月30日(月)-31日(火)
場所:北とぴあ つつじホール(東京都北区王子)
主催:公益財団法人中央温泉研究所
http://www.onken.or.jp/seminar.html
(後)第23回こどものためのジオ・カーニバル
11月4日(土)-5日(日)
会場:大阪市立自然史博物館(ネイチャーホール)
参加費無料
http://geoca.org/
堆積学スクール 2023「日南・宮崎層群の深海相と生痕相」
11 月 11 日(土)-13 日(月)
講師:石原与四郎 氏(福岡大)・菊地一輝 氏(中央大)
定員:30 名程度
参加申込締切:10/20(金)
http://sediment.jp/
(後)第33回社会地質学シンポジウム
11月24日(金)-25日(土)
場所:日本大学文理学部(ハイブリッド)
参加登録締切:11/22
https://www.jspmug.org/envgeo_sympo/33rd_sympo/
New Horizons in Forensic Geoscience:
The Bedrock of International Security
in Minerals, Mining, Metals, Murders and the Missing
12月4日(月)-5日(火)
会場:Burlington House, London, UK
https://www.geolsoc.org.uk/012-FGG-New-Horizons
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻助教(宇宙地球科学:女性限定)(10/27)
・令和6年度ふじのくに地球環境史ミュージアム職員(研究職/環境・環境史)募集(10/13)
・産総研質調査総合センター研究職員(パーマネント型研究員)公募(10/11)
・2024年度東京大学地震研究所客員教員(10/31)
・原子力規制庁実務経験者採用公募行政職員(技術系・事務系)(10/23)
・原子力規制庁実務経験者採用公募行政職員(研究職)(10/23)
・三陸ジオパーク専門員(地域おこし協力隊)募集(10/31)
・2024年度東京大学地震研究所共同利用(10/31)
・第65回藤原賞受賞候補者推薦依頼(学会締切11/30)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.603 年頭の挨拶/令和6年能登半島地震の関連情報/会長談話
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.603 2024/1/9 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】年頭の挨拶(会長 岡田 誠)
【2】令和6年能登半島地震の関連情報/会長談話
【3】正副会長意向調査のお願い<1/10(水)17時まで>
【4】若手野外地質研究者向けに研究奨励金を支給します
【5】第10回ショートコース:海底鉱物資源 開催します
【6】名誉会員候補者の募集が開始されています
【7】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【8】学会HP 会員ページ:引っ越しました(旧会員ページの公開終了)
【9】SPring-8 利用ニーズに関するアンケート調査ご協力のお願い
【10】支部のお知らせ
【11】その他のお知らせ
【12】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2024年 年頭の挨拶(会長 岡田 誠)
──────────────────────────────────
学会員のみなさま,明けましておめでとうございます.日本地質学会創立131年目
に当たる令和6年(2024年)を迎えるにあたり,年頭の挨拶を申し上げます.
みなさまご存じの通り,本年元日の夕方に令和6年能登半島地震が発生しました.
犠牲になられた方々に心から哀悼の意を捧げ,ご冥福をお祈りします.同時に,
安否不明の方々の早期発見と,被災者の皆様の日常生活が一日も早く取り戻され
ることをお祈りいたします.
続きはこちらから,https://geosociety.jp/outline/content0137.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】令和6年能登半島地震の関連情報/会長談話
──────────────────────────────────
※令和6年能登半島地震の関連情報(学会サイト)
https://geosociety.jp/hazard/content0108.html
「令和6年能登半島地震」に関する会長談話:
2024年1月1日午後4時ごろに発生しました「令和6年能登半島地震」により
犠牲になられた方々に心から哀悼の意を捧げ,ご冥福をお祈りします.同時に,
未だ安否不明の方々の一刻も早い救出と,被災者の皆様におかれましては,
一日も早く日常生活を取り戻されることをお祈りいたします.
地震・津波に伴う災害の予測や減災に向けた取り組みを進める上で,当該地域
の地質の成り立ちを理解することは必要不可欠です.日本地質学会は,会員
による地質学的研究をサポートし,最新の学術的知見を活用した自然災害の
予測と防災・減災方策を社会と連携して追求する所存です.
今後,令和6年能登半島地震に関する調査報告や研究成果については,会員
から報告があり次第,学会公式ウェブサイト*などから随時発信してまいります.
一般社団法人日本地質学会
会長 岡田 誠
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】正副会長意向調査のお願い<1/10(水)17時まで>
──────────────────────────────────
先にお知らせの通り,会長・副会長立候補意思表明者への意向調査を
選挙システムにて実施中です.
意思表明者のマニフェストならびに調査票は代議員当選者名簿とともに,
学会HP(会員ページ)で公開しています.
意向調査へのご協力(投票)をお願いいたします.
***********************
意向調査(投票)締切:2024年1月10日(水)17時まで
(注)投票はWEBシステムから行ってください.
***********************
詳しくは,会員ページ(要ログイン)→「会員へのお知らせ」「2024年度選挙」
をご参照ください.
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】若手野外地質研究者向けに研究奨励金を支給します
──────────────────────────────────
日本地質学会では若手育成事業の一環として,野外調査をベースに研究を行う
32歳未満の若手会員を対象とした研究奨励金制度を設けています..
また,規則改正により,助成期間の延長も可能となりました.
**************************************
募集期間:2024年1月1日(月)から2月29日(月)必着
**************************************
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0242.html
(申請に関するFAQも掲載しています)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第10回ショートコース:海底鉱物資源 開催します
──────────────────────────────────
日程:2024年2月25日(日)
<午前> 9:00-12:00
海底鉱物資源概論:その研究と開発の過去、現在、未来
講師:中村謙太郎(東京大学)
<午後> 14:00-17:00
海底鉱物資源の探査と成因研究の最前線
講師:町田嗣樹(千葉工業大学)
参加申込締切:2024年2月16日(金)
申込方法:学会ジオストアよりお申し込みください
詳しくは,https://geosociety.jp/science/content0171.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】名誉会員候補者の募集が開始されています
──────────────────────────────────
募集期締切:2024年2月9日(金)
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:地質学への顕著な貢献または教育現場や企業等での
活動を通じた地質学の普及・振興への顕著な貢献が認められ,かつ本学会への
貢献も認められる会員
(注) 上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することは
できませんが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
新しい論文が公開されています.
■ 地質学雑誌
(論説)北海道南西部,濁川火山カルデラ噴火の軽石礫に認められる高Ba異常と
その成因:岩石組織および化学組成からの検討:金田泰明ほか ほか
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/list/-char/ja
■ Island Arc
Magmatic processes forming replacement textures with fluorite alignments in
feldspars in an evolved trachyte from Oki-Dogo Island, Sea of Japan:
Satoshi Nakano and Kuniaki Makino ほか
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
※学会HP会員ページ(要ログイン)からアクセスすることで,全文無料で
閲覧できます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】学会HP 会員ページ:引っ越しました(旧会員ページの公開終了)
──────────────────────────────────
今年5月より,旧システムと併行して新しい会員ページの運用がスタートし
ておりましたがこのたび会員ページの機能,掲載内容を新しいページに全て
移行し,旧会員ページの公開は終了しました.
ログイン情報の管理も本システムに一本化されます.また旧ページに掲載
されていた記事等は,新しい会員ページ及び学会HPに掲載されています.
▶︎新しい学会HP(会員ページ)でできること
・自身の会員情報の変更,更新
・他の学会員の情報の検索・閲覧(会員名簿の機能)
・Island Arc無料閲覧
・会員限定のお知らせの閲覧(各賞募集,選挙など)
(注)これまで旧システムで行うことができた一部の機能(専門部会の掲示板,
ブログなど)は,ご利用できなくなります.ご了承ください.
新しい会員ページのTOP
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】SPring-8 利用ニーズに関するアンケート調査ご協力のお願い
──────────────────────────────────
公益財団法人 高輝度光科学研究センター/国立研究開発法人 理化学研究所
放射光科学研究センターからのアンケート調査のご依頼をお知らせします.
**********************
大型放射光施設SPring-8は、我が国を代表する共用施設として、1997年の利用開始
以来、延べ30万人を超える多くの皆様にご利用頂いてきました。しかしながら、最近
では施設の老朽化が進行し、さらに海外競合施設のアップグレードが進む中で、国
際競争力の低下が懸念されています。
この状況を変革し、長期にわたって我が国の科学技術と社会を支え続けるために、
SPring-8施設の大規模なアップグレードを行う「SPring-8-Ⅱ」計画の検討がはじ
まっています。
今後、詳細な検討を行うにあたり、利用ニーズの定量的な把握が重要となってお
り、このために今回、無記名の「利用ニーズ調査」を実施いたします。詳しくは、
下記の専用サイトをご参照下さい。
専用サイト: https://user.spring8.or.jp/?p=48085
回答期限:2024年1月31日(水)<回答の所要時間は約10分程度>
既にご利用経験がある方にとどまらず、将来の放射光利用にご興味をお持ちの方も含めて、学術・産業界のできるだけ多くの方々からのニーズを承りたく存じます。
皆様のご協力を是非よろしくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[関東支部]
・2024年度関東支部総会・講演会
日時:2024年4月20日(土)14:00-16:45
場所:北とぴあ第2研修室.
講師:向山 栄氏(国際航業株式会社 公共コンサルタント事業部)
講演内容:数値地形画像を用いたダイナミックな地表面変位の可視化.
・2024年度関東支部幹事選出のお知らせ
立候補期間:2024年3月1日(金)-3月11日(月)17時締切
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0201.html
[西日本支部]
・西日本支部令和5年度総会・第174回例会
2024年3月2日(土)
会場:薩摩川内市川内駅コンベンションセンター SSプラザせんだい
参加・講演申込締切:2月1日(木)
講演要旨提出締切:2月22日(木)
支部総会委任状締切:2月29日(木)
https://geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)日本応用地質学会令和5年度技術者倫理講習会
1月16日(火)16:30-18:50
Zoomによりオンライン講習会
参加費:学会員/山口大学理学部地球圏システム科学科支援企業社員1,000円,
非学会員 3,000円
CPD:2.0CPDH
https://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/others-pdf/20240116oyorinrikoshu.pdf
産技連地質地盤情報分科会令和5年度講演会
「ハザードマップ作成における地質地盤情報の利活用」
1月18日(木)13:30-16:00
会場:北とぴあ 第⼆研修室(東京都北区王子),対面のみ
参加無料(事前登録制,定員100名,申込締切:1/12(金)正午)
https://www.gsj.jp/information/domestic/sgr/
(後)原子力総合シンポジウム2023
主催:日本学術会議総合工学委員会,総合工学委員会原子力安全に関する分科会
1月22日(月)13:00-17:10
会場:日本学術会議講堂(港区六本木7-22-34)・オンライン
参加無料
https://www.scj.go.jp/ja/event/2024/353-s-0122.html
第200回深田研談話会(ハイブリッド)
テーマ:謎の海底隆起?!地すべりがつくるノンテクトニック地質構造
講師:田近 淳 氏(株式会社ドーコン 環境事業本部)
1月 26日(金)15:00-16:30
場所:深田地質研究所 研修ホール(東京都文京区)
定員:会場参加(30名)・オンライン参加(上限450名)先着順
参加費無料(要事前申込)
https://fukadaken.or.jp/?p=8001
海と地球のシンポジウム2023
3月1日(金)-2日(土)
開催方法:口頭発表、ポスター発表ともに実会場にて実施.
会場:東京大学弥生キャンパス 弥生講堂
発表課題募集締切:1月9日(火)
https://www.jamstec.go.jp/j/pr-event/ocean-and-earth2023
令和5年度海洋プラスチックごみ学術シンポジウム
主催:環境省
【研究セッション】(オンライン)
3月9日(土)9:00-16:30予定
対象:研究者や専門家を対象
参加費無料,定員:1000名(要参加登録:3/6締切)
講演申込:1/26締切
【特別セッション】(対面)
3月19日(日)9:00-12:00予定
対象:一般の方を対象
場所:秋葉原UDXシアター (東京都千代田区外神田4丁目)
参加費無料,定員:150名
https://www.env.go.jp/press/press_02577.html
日本堆積学会 2024 年熊本大会
4月20日(土)-22 日(月)
会場:熊本大学(黒髪南地区)
http://sediment.jp/
(後)第61回アイソトープ・放射線研究発表会
7月3日(水)-5日(金)
会場 日本科学未来館 7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
https://www.jrias.or.jp/
★日本地質学会第131年学術大会(2024山形)
9月8日(日)-10日(火)
会場:山形大学小白川キャンパス
(協)地盤技術フォーラム2024
9月18日(水)-20日(金)10:00−17:00
場所:東京ビックサイト・東ホール(江東区有明3丁目)
http://www.sgrte.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・令和6年度採択e-ASIA JRP 「代替エネルギー」分野共同研究課題募集(3/29)
およびワークショップ(1/16-17)開催
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
***第15回惑星地球フォトコンテスト:作品募集中!1/31締切!***
https://photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.594 10/23より代議員立候補受付が始まります
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.594 2023/10/17┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2024年度各賞候補者募集(12/1締切)
【2】2024年度代議員および役員選挙について
【3】ニュース誌の送本希望の選択について
【4】[2023京都大会]10/20より講演要旨無料公開
【5】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【6】支部のお知らせ
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2024年度各賞候補者募集(12/1締切)
──────────────────────────────────
今年も運営規則第16 条および各賞選考規則に基づき,賞の候補者を募集
いたします.ご推薦いただいた方の中から,各賞選考委員会(委員は理事会
の互選と職責により選出)が候補者を選考し,理事会での決定,総会での
承認を経て表彰を行います.期日厳守にてご推薦ください.
個人(正会員または名誉会員)からの推薦も可能です.
なおご推薦にあたっては,被推薦者が常日頃から学会倫理綱領・行動規範や
その他の法令および社会通念上守るべきルールを遵守しているかについて
推薦者には十分にご留意いただき,授賞に相応しい方をご推薦いただきます
ようお願い申し上げます.
****************************
応募締切:2023 年12 月1 日(金)必着
****************************
詳しくは,こちらから(新会員システムへのログインが必要です)
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
(注)初めてログインする方・パスワードをお忘れの方は こちらから
https://www.geosoc-member.jp/Member/fgform.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2024年度代議員および役員選挙について(10/23より立候補受付開始)
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会定款ならびに選挙規則・選挙細則に基づき,代議員
および役員(監事,理事)選挙を実施いたします.
***************************************
代議員選挙立候補受付期間:10月23日(月)10時より11月20日(月)17時締切
***************************************
詳しくは,こちらから(新会員システムへのログインが必要です)
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
(注)初めてログインする方・パスワードをお忘れの方は こちらから
https://www.geosoc-member.jp/Member/fgform.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】ニュース誌の送本希望の選択について
──────────────────────────────────
ニュース誌の送本を希望制とし,新しく稼働している会員システムに「送付不要」の
選択ボタンを設けて,皆様に選択していただくようにいたしました.
毎月15日頃までにお手続きいただければ,当月号(月末)の送本から反映されます.
詳しくは,http://geosociety.jp/news/n180.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2023京都大会]10/20より講演要旨無料公開
──────────────────────────────────
京都大会講演要旨は,10/20より無料公開を予定しています.
大会参加者ログイン無しで,どなたでも閲覧,ダウンロード可能です.
https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp130/top
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・新しい論文が公開されています.
(レター)Discovery of Early Paleocene (Danian) tuff from the Yezo Group in the Yubari area, Hokkaido, Northeast Japan:Koh Kubomiほか
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/list/-char/ja
■ Island Arc
・Vol. 32の新しい論文が公開されています.
(RESEARCH ARTICLE)Topography, sedimentology, and biochronology of carbonate
deposits on seamounts in the JA area, northwestern Pacific Ocean:Yasufumi Iryu et al/
(RESEARCH ARTICLE)Late Cretaceous–Paleogene terrestrial sequence in the
northern Kitakami Mountains, Northeast Japan: Depositional ages, clay mineral
contents, and vitrinite reflectance:Atsushi Noda et al ほか
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[関東支部]
関東地震100年関連行事 震生湖巡検のお知らせ
12月2日(土)10:00–15:00頃
観察場所:震生湖周辺および市木沢の中(神奈川県秦野市今泉)
申込期間:11月3日(金)-17日(金)17:00(先着順)
会費:2,000円(現地集金)
http://geosociety.jp/outline/content0201.html#shinseiko
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
深田研一般公開2023
10月22日(日)10:00-16:00
会場:深田地質研究所(東京都文京区本駒込)
入場無料
https://fukadaken.or.jp/?page_id=7719
山梨県富士山科学研究所
火山防災軽減のための方策に関する国際ワークショップ2023
‐大規模噴火による都市部への影響‐
11月2日(木)13:00-16:20
会場:東京・TKP東京駅大手町カンファレンスセンター
(ライブ配信あり)
https://www.mfri.pref.yamanashi.jp/kazan/2023wssp/
山梨県富士山科学研究所
国際シンポジウム2023
大規模噴火による火山近傍への影響と対応
11月4日(土)13:15-16:50
会場:山梨県富士山科学研究所ホール(富士吉田市上吉田)
(ライブ配信あり)
https://www.mfri.pref.yamanashi.jp/kazan/2023wssp/2023SPleaflet.pdf
(後)第23回こどものためのジオ・カーニバル
11月4日(土)-5日(日)
会場:大阪市立自然史博物館(ネイチャーホール)
参加費無料
http://geoca.org/
(協)石油技術協会令和5年秋季講演会
CCS事業化に向けた取組と課題
11月8日(水)9:30-17:30
場所:東京大学小柴ホール(ハイブリッド開催予定)
https://www.japt.org/
第199回深田研談話会
11月10日(金)15:00-16:30
場所:深田地質研究所研修ホール(東京都文京区)(ハイブリッド開催)
テーマ:プチスポット海底火山
講師:平野直人氏
参加費無料
定員:会場(30名),オンライン(上限450名)
https://fukadaken.or.jp/?p=7791
(後)第33回社会地質学シンポジウム
11月24日(金)-25日(土)
場所:日本大学文理学部(ハイブリッド)
参加登録締切:11月22日
https://www.jspmug.org/envgeo_sympo/33rd_sympo/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・JAMSTEC超先鋭研究開発部門高知コア研究所PD研究員公募(11/30)
・東京大学地震研究所(火山地質・岩石学分野)助教公募(12/27)
・産総研地質調査総合センター2023年度修士型研究職採用(秋募集)(10/23)
・北海道教育大学札幌校・地質学教員(准教授または講師)公募(12/11)
・山田科学振興財団2024年度研究援助候補者推薦依頼(学会締切2/1)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.595(臨時)代議員選挙立候補受付開始
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.595 2023/10/24┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2024年度代議員選挙立候補受付開始(11/20, 17時締切)
【2】2024年度学生会費の申請受付(11/30締切)
【3】JpGU2024セッション提案募集(11/1締切)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2024年度代議員選挙立候補受付開始(11/20, 17時締切)
──────────────────────────────────
2024年度代議員選挙立候補の受付を開始いたしました.立候補される方は,
必ず期日までにお手続きをお願いいたします.
***************************************
代議員選挙立候補受付締切:11月20日(月)17時締切
***************************************
詳しくは,こちらから(新会員システムへのログインが必要です)
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
(注)初めてログインする方・パスワードをお忘れの方は こちらから
https://www.geosoc-member.jp/Member/fgform.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2024年度学生会費の申請受付(11/30締切)
──────────────────────────────────
運営規則により,学部学生・院生は,本人の申請により「学生会員」としての
会費が適用されます.必要に応じてお手続きください.
学生会員の会費額は次の通りです.
単年度:5,000円/2年パック:8,000円/3年パック:9,000円
※2024年度会費請求分の申請です.過去年度に遡っての申請はお受けできません.
※これから入会される方は,入会時に別途お手続きください(新入会に期日は
ありません.入会時にパック料金等を受付ます).
対象となる方,申請フォーム等,詳しくは,
https://geosociety.jp/outline/content0185.html
2024年度会費の払込について
https://geosociety.jp/outline/content0239.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】JpGU2024セッション提案募集(11/1締切)
──────────────────────────────────
JpGU2024でセッション提案を予定している方で,地質学会共催を希望される
場合は,併行して下記の地質学会のJpGUプログラム委員にご連絡いただきます
ようお願い致します。すでに提案済みの場合も,これからでも結構ですので,
プログラム委員に連絡をお願い致します.
日本地質学会JpGUプログラム委員:
松崎賢史(海洋地質部会選出行事委員) kmatsuzaki[at]g.ecc.u-tokyo.ac.jp
宇野正起(岩石部会選出行事委員)masa.uno[at]tohoku.ac.jp
(注)[at]を@マークにしてください
[ご連絡いただく内容]
・タイトル:
・スコープ:
・代表コンビーナ(1名):
・共同コンビーナ(3名まで):
[セッション提案締切]2023年11月1日(水)17:00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.613 山形大会トピックセッション募集中
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.613 2024/3/5┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2024年度理事および監事選挙について
【2】2024山形大会:トピックセッション募集中
【3】Island Arc からのお知らせ
【4】支部のお知らせ
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
【7】会員情報に変更があった場合は...
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2024年度理事および監事選挙について
──────────────────────────────────
2024年度の理事選挙を実施いたします(選挙は2024年度からの当選代議員
による投票となります).
理事選挙の開票は,3月14日(木)15時からオンライン会議で行います.
開票の立ち会いをご希望のかたは、3月11日(月)までに選挙管理委員会
(main[at]geosociety.jp)にお申し出ください.
立候補者名簿ほか選挙の詳細は,
学会ホームページ「会員へのお知らせ」をご覧ください(要ログイン).
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2024山形大会:トピックセッション提案募集中
──────────────────────────────────
日本地質学会第131年学術大会(2024山形大会)
会期:2024年9月8日(日)-9月10日(火)
会場:山形大学小白川キャンパス(山形市小白川町)にて
******************
トピックセッション提案募集 締切:2024年3月27日(月)
******************
※大会までのスケジュール(予定)
3月27日(月):トピックセッション提案募集締切
6月19日(水):演題登録・講演要旨受付締切/ランチョン・夜間小集会申込締切
7月中旬:大会プログラム公開(予定)
8月下旬:大会参加登録/巡検参加申込締切
https://geosociety.jp/science/content0168.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
新しい論文が公開されています.
■ Island Arc
Investigating the impact of sample desiccation on Itrax XRF core scanner signal reproducibility. Naveed Hassan, et al
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
※学会HP「会員ページ」(要ログイン)からアクセスすることで,全文無料
で閲覧できます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[関東支部]
・2024年度関東支部総会・講演会
2024年4月20日(土)14:00-16:45
場所:北とぴあ第2研修室.
講師:向山 栄氏(国際航業株式会社 公共コンサルタント事業部)
講演内容:数値地形画像を用いたダイナミックな地表面変位の可視化.
・2024年度関東支部幹事選出のお知らせ
立候補期間:2024年3月1日(金)-3月11日(月)17時締切
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0201.html
[西日本支部]
3月2日に令和5年度総会・第174回例会を開催しました.
例会の講演要旨は,学会HPで公開しています.
https://geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
大阪地学資料室の開設のお知らせ
岡田篤正氏(京都大学名誉教授)の蔵書等をもとに「大阪地学資料室」(関西電力株式会社内:大阪府茨城市)が開設されました.主な収蔵資料,資料の閲覧方法など詳しくは,
http://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/others-pdf/20240305geoflash.pdf
—------------------------------
水・土壌汚染研究部会セミナー(第122回)
3月6日(水)14:00-15:30
場所 おおさかATCグリーンエコプラザ(大阪市住之江区南港北)
講演 本間 勝 氏
題目 宅地造成に関わる地価形成と法規制
参加無料
https://www.ecoplaza.gr.jp/seminar_post/s20240306/
国立沖縄自然史博物館誘致 東京シンポジウム
3月22日(金)16:00‐18:00
場所:笹川平和財団ビル11F国際会議場(東京都港区虎ノ門)
参加費無料 ※要事前申込 3/19締切
https://www.okinawanhm.com/
防災学術連携体「令和6年能登半島地震・3ヶ月報告会」
3月25日(月)9:00-14:40
ZOOM webinar(定員500名・要申込)
Youtube(一般公開・申込不要)配信も予定
※日本地質学会「令和6年能登半島地震震源域の変動地形と海陸境界断層」
石山達也(東京大)発表予定
https://janet-dr.com/050_saigaiji/2024/050_240101_notohantou0325.html
日本学術会議公開シンポジウム
第18 回防災学術連携シンポジウム
「人口減少社会と防災減災」
3月25日(月)15:30-18:50
ZOOM webinar(定員500名・要申込)
Youtube(一般公開・申込不要)配信も予定
https://janet-dr.com/060_event/20240325.htm
第244回イブニングセミナー(オンライン)
3月29日(金)19:30-21:30
演題:「地下水汚染の機構解明の手順 層状水での例」
講師:風岡修先生(地質汚染診断士、理学博士)
参加費:主催NPO会員及び学生の方(無料) 非会員の方(1,000円)
https://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
地質学史懇話会
6月15日(土)13:30-17:00
場所:北とぴあ 807号室(東京都北区王子)
中島由美:平賀源内の秋田行き
小川勇二郎:北米コルディレラの地質とテクトニクスの新説
問い合わせ:矢島道子 pxi02070[at]nifty.com
(後)第61回アイソトープ・放射線研究発表会
7月3日(水)-5日(金)
会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
発表申込締切:2月29日(木)12時
https://www.jrias.or.jp/
★日本地質学会第131年学術大会(2024山形)
9月8日(日)-10日(火)
会場:山形大学小白川キャンパス
(協)地盤技術フォーラム2024
9月18日(水)-20日(金)10:00−17:00
場所:東京ビックサイト・東ホール(江東区有明3丁目)
http://www.sgrte.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・ふじのくに地球環境史ミュージアム職員(環境・環境史)公募(5/10)
・北海道立総合研究機構研究職員公募(地球化学、第四紀地質)(3/31)
・産業技術総合研究所地質調査総合センター2025年度修士卒研究職採用 (3/17)
・原子力規制人材育成事業の令和6年度新規採択事業公募(3/28)
・令和6年度南アルプス学会研究助成(3/29)
・2024年コスモス国際賞受賞候補者推薦依頼(4/12)(学会推薦3/25)
・第21回(2024年度)日本学術振興会賞受賞候補者推薦依頼(学会推薦3/18)
・下北ジオパーク令和6年度研究補助金募集(3/27)
・島原半島ジオパーク協議会専門員募集(3/22)
・室戸ユネスコ世界ジオパークの地理専門員募集(3/15)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】会員情報に変更があった場合は...
─────────────────────────────────
年度末に向け,所属先や自宅等の登録内容にご変更があった場合は,速やかに
情報の更新をお願い致します.情報の変更は,学会ホームページ「会員ページ」
にログインしていただければ,ご自身で登録内容が更新できます.
ご協力をよろしくお願い致します.
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
※初めてログインする方・パスワードをお忘れの方はこちらから
https://www.geosoc-member.jp/Member/fgform.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.596 2024年度代議員選挙立候補受付中(11/20;17時締切)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.596 2023/11/7┬┴┬┴<*)++<<┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2024年度代議員選挙立候補受付中(11/20, 17時締切)
【2】2024年度各賞候補者募集中(12/1締切)
【3】2024年度の会費払込について
【4】2024年度学生会費の申請受付(11/30締切)
【5】地質系若者のためのキャリアビジョン誌2023 原稿募集中
【6】第15回惑星地球フォトコンテスト受付開始
【7】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【8】支部のお知らせ
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2024年度代議員選挙立候補受付中(11/20, 17時締切)
──────────────────────────────────
2024年度代議員選挙立候補の受付を開始いたしました.立候補される方は,
必ず期日までにお手続きをお願いいたします.
***************************************
代議員選挙立候補受付締切:11月20日(月)17時締切
***************************************
詳しくは,こちらから(新会員システムへのログインが必要です)
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
(注)初めてログインする方・パスワードをお忘れの方は こちらから
https://www.geosoc-member.jp/Member/fgform.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2024年度各賞候補者募集中(12/1締切)
──────────────────────────────────
今年も運営規則第16 条および各賞選考規則に基づき,賞の候補者を募集
いたします.ご推薦いただいた方の中から,各賞選考委員会(委員は理事会
の互選と職責により選出)が候補者を選考し,理事会での決定,総会での
承認を経て表彰を行います.期日厳守にてご推薦ください.
個人(正会員または名誉会員)からの推薦も可能です.
なおご推薦にあたっては,被推薦者が常日頃から学会倫理綱領・行動規範や
その他の法令および社会通念上守るべきルールを遵守しているかについて
推薦者には十分にご留意いただき,授賞に相応しい方をご推薦いただきます
ようお願い申し上げます.
****************************
応募締切:2023 年12 月1 日(金)必着
****************************
詳しくは,こちらから(新会員システムへのログインが必要です)
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
(注)初めてログインする方・パスワードをお忘れの方は こちらから
https://www.geosoc-member.jp/Member/fgform.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2024年度の会費払込について
──────────────────────────────────
運営規則により,2024年度の事業年度(会費年度:2024年4月-2025年3月)が
始まる前までに納入下さいますようお願いいたします.
(1)自動引落を登録されている方の引落日は,12月25日(月)です.
(2)自動引落をご利用ください:申込は随時受付しています.今回お申込み
いただいた方は,2024年6月の督促請求時に引落させていただきます.
(3)お振り込みの方:12月中旬までに請求書兼郵便振替用紙を発送いたします.
お手元に届きましたら,折り返しご送金下さいますようお願いいたします.
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0239.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2024年度学生会費の申請受付(11/30締切)
──────────────────────────────────
運営規則により,学部学生・院生は,本人の申請により「学生会員」としての
会費が適用されます.必要に応じてお手続きください.
学生会員の会費額は次の通りです.
単年度:5,000円/2年パック:8,000円/3年パック:9,000円
※2024年度会費請求分の申請です.過去年度に遡っての申請はお受けできません.
※これから入会される方は,入会時に別途お手続きください(新入会に期日は
ありません.入会時にパック料金等を受付ます).
対象となる方,申請フォーム等,詳しくは,
https://geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質系若者のためのキャリアビジョン誌2023 原稿募集中
──────────────────────────────────
日本地質学会は、地質学を専攻とする国内44の大学の2,200名以上の学生と院生に
専門職の魅力を伝える情報誌「地質系若者のためのキャリアビジョン誌2023」を
刊行します.
各大学では、この冊子をキャリア教育の教材として活用頂いており、そして多く
の学生・院生から専門職を知る機会になったとの声が届いております.本冊子へ
の協賛と原稿提供をご検討ください.
締切:2023年12月15日(金)
配布:2024年1月下旬
詳しくは,https://photo.geosociety.jp/career2.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】第15回惑星地球フォトコンテスト受付開始
──────────────────────────────────
***応募締切:2024年1月31日***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
会員の皆様からの応募もお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・新しい論文が公開されています.
(ノート)土佐硯(源谷坑)源岩「三原石」の地質学的特徴:浦本 豪一郎ほか/
(ほか11編)https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/list/-char/ja
■ Island Arc
・Vol. 32の新しい論文が公開されています.
(RESEARCH ARTICLE)X‐ray computed tomography of deep‐sea clay as
tools to detect rare earth elements and yttrium enrichment:Yoichi Usui et al
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[関東支部]
関東地震100年関連行事 震生湖巡検
12月2日(土)10:00-15:00
観察場所:震生湖周辺および市木沢の中(神奈川県秦野市今泉)
申込締切:11月17日(金)17:00(先着順)
会費:2,000円(現地集金)
http://geosociety.jp/outline/content0201.html#shinseiko
県の石―千葉の岩石・鉱物・化石― 講演会(第1報)
2024年1月14日(日)13:00-16:00
場所:千葉県立中央博物館講堂(Zoomを使用したハイブリッド形式)
申込期間:12月8日(金)-26日(火)17:00締切
https://geosociety.jp/outline/content0201.html#2023ken-no-ishi
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(協)石油技術協会令和5年秋季講演会
CCS事業化に向けた取組と課題
11月8日(水)9:30-17:30
場所:東京大学小柴ホール(ハイブリッド開催予定)
https://www.japt.org/
(後)第33回社会地質学シンポジウム
11月24日(金)-25日(土)
場所:日本大学文理学部4号館442教室(ハイブリッド)
参加登録締切:11月22日
<特別講演>(一般公開/Youtube同時配信)
ポタンザニアでのJICAの活動 国際協力の現場から:荒 仁
<招待講演>(参加登録者のみ)
・北海道寿都町,神恵内村の文献調査について:兵藤英明
・日本原子力研究開発機構が実施してきた超深地層研究所計画の歩み:笹尾英嗣
プログラム公開になりました
https://www.jspmug.org/envgeo_sympo/33rd_sympo/
第40回地質調査総合センターシンポジウム
令和5年度地圏資源環境研究部門研究成果報告会
海と陸をつなぐ地下水の動き
―地層処分研究における地圏資源環境研究部門の取り組み―
12月8日(金)13:30-17:15(予定)
会場:秋葉原コンベンションホール & Hybrid スタジオ
定員:150名(事前登録制),参加費無料
CPD: 3.5単位
https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo40/index.html
STAR-Eプロジェクト第3回研究フォーラム
情報科学×地震学で拓く未来と産学共創
12月22日(金)13:00-15:35
対象:情報科学や地震学分野等の大学生・大学院生、研究者等(民間企業も含む)
会場:オンライン(Zoom)
参加費無料
申込締切:12月21日(木)12:00
https://star-e-project-20231222.eventcloudmix.com/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・JAMSTEC
–海域地震火山部門 地震津波予測研究開発センター研究員公募(12/11)
–超先鋭研究開発部門高知コア研究所物質科学研究G研究員公募(12/25)
・産総研イノベーションスクール18期スクール生(特別研究員PD)募集(1/5)
・大阪市立自然史博物館学芸員(脊椎動物化石担当)募集(12/22)
・京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻教授公募(12/27)
・新潟大学教育研究院自然科学系教員(教授)公募(12/13)
・十勝岳ジオパーク学術研究助成事業(12/31)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.599(臨時)代議員選挙11/20(月)17時 立候補締切!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.599 2023/11/17 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2024年度代議員選挙11/20(月)17時 立候補締切!
──────────────────────────────────
代議員選挙の立候補届けは,11月20日(月)17時締切です.
立候補を予定されている方は,くれぐれも期日に遅れないようにお手続きを
お願いいたします.
(注)今年度より実施される代議員および役員選挙は,原則として新しく
導入された選挙システム(WEB)を利用して行います.立候補もWEBより
お届けください.
********************************************
代議員立候補受付締切:11月20日(月)17時必着
********************************************
代議員選挙立候補状況(11月17日17時現在) ※( )は各定員
■全国区代議員:72(101)
■地方支部区:41(99)
[内訳]北海道:2(5),東北:0(7),関東:17(42)
中部:11(16),近畿:7(11),四国:4(4),西日本:0(14)
立候補届,選挙の詳細は下記よりご確認ください.
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
(注)新会員システムへのログインが必要です
(注)初めてログインする方・パスワードをお忘れの方はこちらから
https://www.geosoc-member.jp/Member/fgform.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.597(臨時)訃報:松田時彦 名誉会員
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.597 2023/11/13 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 松田時彦 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
松田時彦 名誉会員(東京大学名誉教授)が、令和5年10月17日に逝去
されました(享年93歳)。これまでの故人の功績を讃えるとともに、
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
なおご葬儀は、すでにご家族によりしめやかに執り行なわれとのことです。
会長 岡田 誠
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.600 2024年度学生会費申請(11/30締切)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.600 2023/11/21 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2024年度各賞候補者募集中(12/1締切)
【2】2024年度の会費払込について(引落は12/25です)
【3】2024年度学生会費の申請受付(11/30締切)
【4】地質系若者のためのキャリアビジョン誌2023 原稿募集中
【5】第15回惑星地球フォトコンテスト受付中
【6】ニュース誌の送本希望の選択
【7】Island Arc からのお知らせ
【8】支部のお知らせ
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
【11】訃報:水野篤行 名誉会員 ご逝去
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2024年度各賞候補者募集中(12/1締切)
──────────────────────────────────
個人(正会員または名誉会員)からの推薦可能です.
なおご推薦にあたっては,被推薦者が常日頃から学会倫理綱領・行動規範や
その他の法令および社会通念上守るべきルールを遵守しているかについて
推薦者には十分にご留意いただき,授賞に相応しい方をご推薦いただきます
ようお願い申し上げます.
****************************
応募締切:2023 年12 月1 日(金)必着
****************************
詳しくは,こちらから(新会員システムへのログインが必要です)
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
(注)初めてログインする方・パスワードをお忘れの方は こちらから
https://www.geosoc-member.jp/Member/fgform.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2024年度の会費払込について(引落は12/25です)
──────────────────────────────────
運営規則により,2024年度の事業年度(会費年度:2024年4月-2025年3月)が
始まる前までに納入下さいますようお願いいたします.
(1)自動引落を登録されている方の引落日は,12月25日(月)です.
(2)自動引落をご利用ください:申込は随時受付しています.今回お申込み
いただいた方は,2024年6月の督促請求時に引落させていただきます.
(3)お振り込みの方:12月中旬までに請求書兼郵便振替用紙を発送いたします.
お手元に届きましたら,折り返しご送金下さいますようお願いいたします.
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0239.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2024年度学生会費の申請受付(11/30締切)
──────────────────────────────────
運営規則により,学部学生・院生は,本人の申請により「学生会員」としての
会費が適用されます.必要に応じてお手続きください.
学生会員の会費額は次の通りです.
単年度:5,000円/2年パック:8,000円/3年パック:9,000円
※2024年度会費請求分の申請です.過去年度に遡っての申請はお受けできません.
※これから入会される方は,入会時に別途お手続きください(新入会に期日は
ありません.入会時にパック料金等を受付ます).
対象となる方,申請フォーム等,詳しくは,
https://geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地質系若者のためのキャリアビジョン誌2023 原稿募集中
──────────────────────────────────
日本地質学会は、地質学を専攻とする国内44の大学の2,200名以上の学生と院生に
専門職の魅力を伝える情報誌「地質系若者のためのキャリアビジョン誌2023」を
刊行します.各大学では、この冊子をキャリア教育の教材として活用頂いており、
そして多くの学生・院生から専門職を知る機会になったとの声が届いております.
本冊子への協賛と原稿提供をご検討ください.
締切:2023年12月15日(金)
配布:2024年1月下旬
詳しくは,https://photo.geosociety.jp/career2.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第15回惑星地球フォトコンテスト受付中
──────────────────────────────────
***応募締切:2024年1月31日***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
会員の皆様からの応募もお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】ニュース誌の送本希望の選択
──────────────────────────────────
ニュース誌の送本を希望制とし,新しく稼働している会員システムに
「送付不要」の選択ボタンを設けて,皆様に選択していただくように
いたしました.
毎月15日頃までにお手続きいただければ,当月号(月末)の送本から
反映されます.詳しくは,https://geosociety.jp/news/n180.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ Island Arc
・Vol. 32の新しい論文が公開されています.
(RESEARCH ARTICLE)Sulfur-rich mafic magma injection into the felsic magma
chamber beneath Asama volcano, central Japan: Records in olivine-hosted melt
inclusions from the Itabana and Tenmei eruptions. Yoshiaki Yamaguchi,
Andreas Auer, Isoji Miyagi
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[関東支部]
県の石―千葉の岩石・鉱物・化石― 講演会(第1報)
2024年1月14日(日)13:00-16:00
場所:千葉県立中央博物館講堂(Zoomを使用したハイブリッド形式)
申込期間:12月8日(金)-26日(火)17:00締切
https://geosociety.jp/outline/content0201.html#2023ken-no-ishi
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)第33回社会地質学シンポジウム
11月24日(金)-25日(土)
場所:日本大学文理学部(ハイブリッド)
参加登録締切:11月22日
<特別講演>(一般公開・YouTube同時配信)
タンザニアでのJICAの活動 国際協力の現場から:荒 仁
<招待講演>(参加登録者のみ)
・北海道寿都町、神恵内村の文献調査について:兵藤英明
・日本原子力研究開発機構が実施してきた超深地層研究所計画の歩み:笹尾英嗣
https://www.jspmug.org/envgeo_sympo/33rd_sympo/
2023年度「深田賞」授賞式及び記念講演会
11月29日(水)14:30-16:15
開催方法:オンライン配信(一般参加)
【記念講演】山岳トンネルを対象とした私の地質工学を振り返る
(国際航業株式会社 最高技術顧問 大島洋志 氏)
参加費無料
申込締切: 11月22日(水)17時
※募集人数(500名)に達し次第締切
https://fukadaken.or.jp/?page_id=7831
(協)第39回ゼオライト研究発表会
11月30日(木)-12月1日(金)
会場:タワーホール船堀(東京都江戸川区)
https://jza-online.org/events/
2023年度分野横断型研究集会
「地球表層における粒子重力流のダイナミクス」
12月6日(水)10:00-18:00
開催場所:防災科学技術研究所東京会議室(東京) & オンライン(zoom)
参加登録は12月1日(金)17時まで
https://sites.google.com/view/gravity-current2023/
第60回技術サロン
12月16日(土)13:00-16:00【Zoom】
対象:技術者及び技術士を目指す女子学生・女性社会人
内容:技術士制度の説明、技術士とのフリーディスカッション等
※受験指導や技術士の斡旋等は行っておりません.技術士の方はご遠慮ください.
参加費無料,定員15名程度
申込締切:12月11日(月)もしくは定員に達した場合
https://www.engineer.or.jp/c_cmt/danjyo/topics/009/attached/attach_9872_1.pdf
第243回イブニングセミナー(オンライン)
12月22日(金)19:30-21:30
演題:「自然から学ぶ放射性廃棄物処分の知恵」
講師:湯佐泰久先生(元JAEA 前富士常葉大学環境防災学部 教授)
参加費:主催NPO会員及び学生の方(無料) 非会員の方(1,000円)
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm
シンポジウム
「火山噴火の中長期的予測に向けた研究の現状と今後の課題」
12月23日(土)9:30-17:30
方式 : オンライン(Zoom Webiner)
主催:地震・火山噴火予知研究協議会,火山計画推進部会
参加無料
https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/YOTIKYO/H31-R5/R5/symposiumKazan20231223.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・三菱財団第55回(2024年度)自然科学研究助成公募(1/5-2/2)
・山梨県富士山科学研究所任期付研究員(追加分)募集(11/24)
・山梨県職員(火山防災職[職務経験者枠])公募(11/27)
・令和6年度苗場山麓ジオパーク学術研究奨励事業助成金募集(1/31)
・島原半島ジオパーク協議会国際交流専門員募集(11/30)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】水野篤行 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
水野篤行 名誉会員(元地質調査所,元日本地質学会事務局長)が,令和5年
11月20日(月)に逝去されました(94歳).
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます.
なお,ご葬儀等は近親者で執り行なわれ、供花・香典等はご辞退されるとの
ことです.
会長 岡田 誠
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.598(臨時)訃報:志岐常正 名誉会員
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.598 2023/11/14 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 志岐常正 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
志岐常正 名誉会員(京都大学名誉教授)が、令和5年11月13日に逝去され
ました(享年94歳)。これまでの故人の功績を讃えるとともに、
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
ご葬儀は下記のとおり執り行われます(お通夜は執り行われません)。
葬儀:2023年11月16日(木)午後2時より
式場:セレマ六地蔵ホール(京都府宇治市六地蔵奈良町72-21)
https://cerema.co.jp/funeral/hall_detail.php?hall_cd=0063&c_cd=0000
喪主:志岐正也様(ご子息)
なお、御香典の儀はご遺族様の希望によりご辞退されるとのことです。
会長 岡田 誠
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp )へお送りください.
【geo-Flash】No.601 代議員選挙結果& 正副会長意向調査のお願い
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.601 2023/12/5 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2024年度代議員選挙について(正副会長意向調査のお願い)
【2】2024年度の会費払込について(引落は12/25です)
【3】地質系若者のためのキャリアビジョン誌2023 原稿募集中
【4】第15回惑星地球フォトコンテスト受付中
【5】ニュース誌の送本希望の選択
【6】学会HP 会員ページ:引っ越しました
【7】地質学雑誌からのお知らせ
【8】支部のお知らせ
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2024年度代議員選挙について(正副会長意向調査のお願い)
──────────────────────────────────
選挙規則ならびに選挙細則に基づき,表記選挙を実施するにあたっての
立候補届は,11月20日に締め切られました.その結果,全国区・地方支
部区とも立候補者数が定員を超えませんでしたので,選挙規則第6条に基
づき投票は行わず,全員を無投票当選といたします.
なお,立候補の抱負など,当選された方の詳細につきましては別途名簿
を会員ページにて公開いたしますので,ご覧ください(12/8頃公開予定).
また,代議員選挙は無投票となりましたが,会長・副会長の意向調査に
つきましては,予定通り実施いたします.
意思表明者のマニフェストならびに調査票は代議員当選者の名簿とともに,
12月8日頃までに公開いたします. 意向調査は選挙システムにて実施いた
しますので,ご理解とご協力のほど宜しくお願いいたします.
***********************
意向調査(投票)期間:
12月13日(水)10時から2024年1月10日(水)17時まで.
***********************
詳しくは,会員ページ(要ログイン)→「会員へのお知らせ」
をご参照ください.
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2024年度の会費払込について(引落は12/25です)
──────────────────────────────────
運営規則により,2024年度の事業年度(会費年度:2024年4月-2025年3月)が
始まる前までに納入下さいますようお願いいたします.
(1)自動引落を登録されている方の引落日は,12月25日(月)です.
(2)自動引落をご利用ください:申込は随時受付しています.今回お申込み
いただいた方は,2024年6月の督促請求時に引落させていただきます.
(3)お振り込みの方:12月中旬までに請求書兼郵便振替用紙を発送いたします.
お手元に届きましたら,折り返しご送金下さいますようお願いいたします.
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0239.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】地質系若者のためのキャリアビジョン誌2023 原稿募集中
──────────────────────────────────
日本地質学会は、地質学を専攻とする国内44の大学の2,200名以上の学生と院生に
専門職の魅力を伝える情報誌「地質系若者のためのキャリアビジョン誌2023」を
刊行します.各大学では、この冊子をキャリア教育の教材として活用頂いており、
そして多くの学生・院生から専門職を知る機会になったとの声が届いております.
本冊子への協賛と原稿提供をご検討ください.
締切:2023年12月15日(金)
配布:2024年1月下旬
詳しくは,https://photo.geosociety.jp/career2.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第15回惑星地球フォトコンテスト受付中
──────────────────────────────────
***応募締切:2024年1月31日***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
会員の皆様からの応募もお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】ニュース誌の送本希望の選択
──────────────────────────────────
ニュース誌の送本を希望制とし,新しく稼働している会員システムに
「送付不要」の選択ボタンを設けて,皆様に選択していただくように
いたしました.
毎月15日頃までにお手続きいただければ,当月号(月末)の送本から
反映されます.詳しくは,https://geosociety.jp/news/n180.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】学会HP 会員ページ:引っ越しました(旧会員ページの公開は終了します)
──────────────────────────────────
今年5月より,旧システムと併行して新しい会員ページの運用がスタートし
ておりましたがこのたび会員ページの機能,掲載内容を新しいページに全て
移行し,旧会員ページの公開は終了します.
ログイン情報の管理も今後は本システムに一本化されます.また旧ページに
掲載されていた記事等は,新しい会員ページ及び学会HPに掲載されています.
▶︎新しい学会HP(会員ページ)でできること
・自身の会員情報の変更,更新
・他の学会員の情報の検索・閲覧(会員名簿の機能)
・Island Arc無料閲覧
・会員限定のお知らせの閲覧(各賞募集,選挙など)
(注)これまで旧システムで行うことができた一部の機能(専門部会の掲示板,
ブログなど)は,ご利用できなくなります.ご了承ください.
新しい会員ページのTOP
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 地質学雑誌
・新しい論文が公開されます(12/6公開予定).
(総説)津波地球化学:現在の知見と今後の展望:篠崎鉄哉/(論説)下北半島
中部で掘削されたSN-010深部ボーリングコア中の中新統泊火山岩類の岩石記載
と層序対比:相澤正隆ほか
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/list/-char/ja
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[関東支部]
県の石―千葉の岩石・鉱物・化石― 講演会
2024年1月14日(日)13:00-16:00
場所:千葉県立中央博物館講堂(Zoomを使用したハイブリッド形式)
申込期間:12月8日(金)-26日(火)17:00締切
https://geosociety.jp/outline/content0201.html#2023ken-no-ishi
[西日本支部]
西日本支部令和5年度総会・第174回例会
2024年3月2日(土)
会場:薩摩川内市川内駅コンベンションセンター SSプラザせんだい
参加・講演申込締切:2月1日(木)
講演要旨提出締切:2月22日(木)
https://geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
地質地盤情報の活用と法整備を考える会
12月1日、ホームページを更新しました
https://www.geo-houseibi.jp
***************************
下北ジオパーク学術研究発表会(zoom)
12月10日(日)14:00-16:00
参加無料・要事前申込
https://x.gd/svZcp
令和5年度国総研講演会
地震災害への国総研のチャレンジー関東大震災から100年ー
12月14日(木)10:00-17:25
会場:東京証券会館(東京都日本橋茅場町)
※ライブ配信あり
参加無料・要申込(締切:12/11)
https://www.nilim.go.jp/lab/bbg/koen2023.html
****2024****
(後)日本応用地質学会令和5年度技術者倫理講習会
1月16日(火)16:30-18:50
Zoomによりオンライン講習会
参加費:学会員・山口大学理学部地球圏システム科学科支援企業社員1,000円,非学会員 3,000円
CPD:2.0CPDH
https://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/others-pdf/20240116oyorinrikoshu.pdf
★日本地質学会第131年学術大会(2024山形)
9月8日(日)-10日(火)
会場:山形大学小白川キャンパス
国際ゴンドワナ研究連合(IAGR)2024年総会及び
第21回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム
11月18日(月)-22日(金))
場所・会場:マレーシア,クチンのWater Front Hotel
参加登録及び発表要旨締切:2024年3月31日
参加登録及び発表要旨提出先:iagr2024[at]curtin.edu.my
問合せ:Prof. Nagarajan Ramasamy, Curtin University, Malaysia
E-mail: nagarajan[at]curtin.edu.my
※[at]を@マークにして送信してください
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・2024年度「深田研究助成」の公募(2/2)
・広島大学先進理工系科学研究科地球惑星システム学プログラムの准教授or助教(テニュアトラック)公募(2/29)
・第3回羽ばたく女性研究者賞(マリア・スクウォドフスカ=キュリー賞)
(12/11)
・山田科学振興財団2024年度研究援助候補者推薦依頼(学会締切2/1)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.602 若手野外地質研究者向け研究奨励金を支給します!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.602 2023/12/19 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】正副会長意向調査のお願い<1/10(水)17時まで>
【2】若手野外地質研究者向けに研究奨励金を支給します
【3】2024年度の会費払込について(引落は12/25です)
【4】名誉会員候補者の募集が開始されています
【5】第15回惑星地球フォトコンテスト受付中
【6】学会HP 会員ページ:引っ越しました(旧会員ページの公開終了)
【7】2026年度以降地震火山地質こどもサマースクール開催地募集
【8】支部のお知らせ
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
【11】事務局年末年始休業(12/29-1/4)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】正副会長意向調査のお願い<1/10(水)17時まで>
──────────────────────────────────
先にお知らせの通り,会長・副会長立候補意思表明者への意向調査を
選挙システムにて実施中です.
意思表明者のマニフェストならびに調査票は代議員当選者名簿とともに,
学会HP(会員ページ)で公開しています.
意向調査へのご協力(投票)をお願いいたします.
***********************
意向調査(投票)締切:2024年1月10日(水)17時まで
(注)投票はWEBシステムから行ってください.
***********************
詳しくは,会員ページ(要ログイン)→「会員へのお知らせ」「2024年度選挙」
をご参照ください.
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】若手野外地質研究者向けに研究奨励金を支給します
──────────────────────────────────
日本地質学会では若手育成事業の一環として,野外調査をベースに研究を行う
32歳未満の若手会員を対象とした研究奨励金制度を設けています.
また,規則改正により,助成期間の延長も可能となりました.
**************************************
募集期間:2024年1月1日(月)から2月29日(月)必着
**************************************
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0242.html
(申請に関するFAQも掲載しています)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2024年度の会費払込について(引落は12/25です)
──────────────────────────────────
運営規則により,2024年度の事業年度(会費年度:2024年4月-2025年3月)
が始まる前までに納入下さいますようお願いいたします.
(1)自動引落を登録されている方の引落日は,12月25日(月)です.
(2)自動引落をご利用ください:申込は随時受付しています.今回お申込み
いただいた方は,2024年6月の督促請求時に引落させていただきます.
(3)お振り込みの方:まもなく請求書兼郵便振替用紙を発送いたします.
お手元に届きましたら,折り返しご送金下さいますようお願いいたします.
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0239.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】名誉会員候補者の募集が開始されています
──────────────────────────────────
募集期締切:2024年2月9日(金)
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:地質学への顕著な貢献または教育現場や企業等での
活動を通じた地質学の普及・振興への顕著な貢献が認められ,かつ本学会への
貢献も認められる会員
(注) 上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することは
できませんが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第15回惑星地球フォトコンテスト受付中
──────────────────────────────────
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
会員の皆様からの応募もお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
*********************************
応募締切:2024年1月31日
*********************************
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】学会HP 会員ページ:引っ越しました(旧会員ページの公開終了)
──────────────────────────────────
今年5月より,旧システムと併行して新しい会員ページの運用がスタートし
ておりましたがこのたび会員ページの機能,掲載内容を新しいページに全て
移行し,旧会員ページの公開は終了しました.
ログイン情報の管理も本システムに一本化されます.また旧ページに掲載
されていた記事等は,新しい会員ページ及び学会HPに掲載されています.
▶︎新しい学会HP(会員ページ)でできること
・自身の会員情報の変更,更新
・他の学会員の情報の検索・閲覧(会員名簿の機能)
・Island Arc無料閲覧
・会員限定のお知らせの閲覧(各賞募集,選挙など)
(注)これまで旧システムで行うことができた一部の機能(専門部会の掲示板,
ブログなど)は,ご利用できなくなります.ご了承ください.
新しい会員ページのTOP
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】2026年度以降地震火山地質こどもサマースクール開催地募集
──────────────────────────────────
地震火山地質こどもサマースクールは,1999年夏から小・中・高校生を対象に
はじまった行事で,現在,日本地震学会,日本火山学会,日本地質学会が共同
で実施する,地球科学関連では最大規模の体験学習講座です.今回2026年度
の実施を希望する開催地を公募いたします.
※2024年度(第23回)は徳島県三好市・板野町等で,2025年度(第23回)は
長野県木曽町周辺(御嶽山)で開催予定です.
****************************
募集締切:2024年2月13日
****************************
応募資格など詳しくは, https://kodomoss.jp/applications/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[関東支部]
県の石―千葉の岩石・鉱物・化石― 講演会
2024年1月14日(日)13:00-16:00
場所:千葉県立中央博物館講堂(Zoomを使用したハイブリッド形式)
定員:会場100名+Zoom(オンライン)100名
参加申込締切:12月26日(火)17:00締切
https://geosociety.jp/outline/content0201.html#2023ken-no-ishi
[西日本支部]
西日本支部令和5年度総会・第174回例会
2024年3月2日(土)
会場:薩摩川内市川内駅コンベンションセンター SSプラザせんだい
参加・講演申込締切:2月1日(木)
講演要旨提出締切:2月22日(木)
支部総会委任状締切:2月29日(木)
https://geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
STAR-Eプロジェクト第3回研究フォーラム
〜情報科学×地震学で拓く未来と産学共創〜
12月22日(金)13:00〜15:35
対象:情報科学や地震学分野等の大学生・大学院生,当核分野における研究者等(民間企業も含む)
会場:オンライン(Zoom)
参加費無料
申込締切:12月21日(木)12:00
https://star-e-project-20231222.eventcloudmix.com/
(後)原子力総合シンポジウム2023
主催:日本学術会議総合工学委員会,総合工学委員会原子力安全に関する分科会
1月22日(月)13:00-17:10
会場:日本学術会議講堂(港区六本木7-22-34)・オンライン
参加無料
https://www.scj.go.jp/ja/event/2024/353-s-0122.html
(後)日本応用地質学会令和5年度技術者倫理講習会
1月16日(火)16:30-18:50
Zoomによりオンライン講習会
参加費:学会員/山口大学理学部地球圏システム科学科支援企業社員1,000円,
非学会員 3,000円
CPD:2.0CPDH
https://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/others-pdf/20240116oyorinrikoshu.pdf
地質学史懇話会
6月15日(土)13:30-17:00
場所:北とぴあ 807号室(東京都北区王子)
中島由美,小川勇二郎 講演
問い合わせ:矢島道子 pxi02070[at]nifty.com
(後)第61回アイソトープ・放射線研究発表会
7月3日(水)-5日(金)
会場 日本科学未来館 7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
https://www.jrias.or.jp/
★日本地質学会第131年学術大会(2024山形)
9月8日(日)-10日(火)
会場:山形大学小白川キャンパス
(協)地盤技術フォーラム2024
9月18日(水)-20日(金)10:00−17:00
場所:東京ビックサイト・東ホール(江東区有明3丁目)
http://www.sgrte.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・JAMSTEC海域地震火山部門PD研究員公募(12/25)
・令和6年度喜界島ジオパーク認定推進員募集(1/31)
・栗駒山麓ジオパーク専門員募集(12/22)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】事務局年末年始休業(12/29-1/4)
──────────────────────────────────
学会事務局は年末年始は,下記の通り業務をお休みさせて頂きます.
<2023年12月29日(金)から 2024年1月4日(木)>
新年5日より通常通りの営業となります.
本年も大変お世話になりありがとうございました.
来年もまた引き続きよろしくお願い申し上げます.
※次回メルマガは,1月9日(火)配信予定です※
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局(geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.604 第10回ショートコース:海底鉱物資源 受講者募集
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.604 2024/1/16 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】令和6年能登半島地震の関連情報
【2】日本地質学会研究奨励金募集(若手野外地質研究者向け)
【3】第15回惑星地球フォトコンテスト受付中
【4】第10回ショートコース:海底鉱物資源 受講者募集中
【5】JABEEシンポ:大学縮小危機のなかで、社会の要求にどのように応えるか
【6】名誉会員候補者の募集が開始されています
【7】本の紹介「北長門海岸国定公園「青海島」のジオツーリズム」
【8】Island Arc からのお知らせ
【9】支部のお知らせ
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】令和6年能登半島地震の関連情報
──────────────────────────────────
令和6年能登半島地震の関連情報を学会HPにまとめています.
*1/16掲載情報
・地震調査研究推進本部地震調査委員会:令和6年能登半島地震の評価
(令和6年1月15日)
・産総研地質調査総合センター:第五報 能登半島北部沿岸域の構造図と
令和6年(2024年)能登半島地震の余震分布
この他,各企業,団体,会員による調査情報なども掲載しています.
https://geosociety.jp/hazard/content0108.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】日本地質学会研究奨励金募集(若手野外地質研究者向け)
──────────────────────────────────
日本地質学会では若手育成事業の一環として,野外調査をベースに研究を行う
32歳未満の若手会員を対象とした研究奨励金制度を設けています..
また,規則改正により,助成期間の延長も可能となりました.
**************************************
応募締切:2024年2月29日(木)必着
**************************************
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0242.html
(申請に関するFAQも掲載しています)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】第15回惑星地球フォトコンテスト受付中
──────────────────────────────────
***応募締切:2024年1月31日***
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
会員の皆様からの応募もお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
詳しくは,http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第10回ショートコース:海底鉱物資源 受講者募集中
──────────────────────────────────
日程:2024年2月25日(日)
<午前> 9:00-12:00
海底鉱物資源概論:その研究と開発の過去、現在、未来
講師:中村謙太郎(東京大学)
<午後> 14:00-17:00
海底鉱物資源の探査と成因研究の最前線
講師:町田嗣樹(千葉工業大学)
参加申込締切:2024年2月16日(金)
申込はこちらから
https://geosociety.jp/science/content0171.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】JABEEシンポ:大学縮小危機のなかで、社会の要求にどのように応えるか
──────────────────────────────────
第4回JABEEオンラインシンポジウム
大学縮小危機のなかで、社会の要求にどのように応えるか
ーJABEEを活用した技術者の育成と輩出ー
日時:2024年3月3日(日)13:30-17:20(予定)
開催方式:Zoomを用いたオンライン方式
参加者:200名(先着順) 会員,非会員を問いません.参加無料
参加申込期間:2024年1月29日(月)-2月26日(月)
詳しくは,https://geosociety.jp/science/content0167.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】名誉会員候補者の募集が開始されています
──────────────────────────────────
募集期締切:2024年2月9日(金)
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:地質学への顕著な貢献または教育現場や企業等での
活動を通じた地質学の普及・振興への顕著な貢献が認められ,かつ本学会への
貢献も認められる会員
(注) 上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することは
できませんが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】本の紹介「北長門海岸国定公園「青海島」のジオツーリズム」
──────────────────────────────────
北長門海岸国定公園「青海島」のジオツーリズム:ジオサイト12の提案
作者:今岡照喜,取材協力:伊藤信行,撮影協力:永山伸一
2023年10月17日,発行者:今岡照喜(自費出版),A4判175頁,
定価:2300円+税
本書は山口県長門市仙崎の北にある景勝地「青海島(おおみじま)」(東西9km×南北4km)の地形・地質・生物を多数のカラー写真入りで紹介した美しいガイドブックであり,作者がそのライフワークの成果をもとに令和元年から5年にかけて地元紙「長門時事」に連載した記事を再編集し,関連するトピックスをコラムとして加筆し,付録として青海島周辺海域の珍しい海洋生物の話題(「自然の水族館 湧昇流と対馬海流が育んだ海洋生物の宝庫」写真・情報提供:ダイビングインストラクター笹川勉・三好芳郁 p. 162-172)を加えたものである.なお,作者は青海島の大部分を含む産総研の1/5万地質図「仙崎」(地質図2005年,説明書2006年発行)の第二著者である.
仙崎は大正〜昭和初期の童謡詩人金子みすゞの出身地であり,筆者は2022年に「童謡詩人金子みすゞの地学的側面」(https://geosociety.jp/faq/content1006.html 日本地質学会News, 25巻2号)を公表したが,作者はこれを読んでこの詩人についても詳しく調査し,本書第4話に彼女の顔写真入りの紹介文を掲載,随所で彼女の詩を引用している.
本書の構成は,冒頭に長門市長と長門市教育委員会教育長の祝辞があり,はじめに(p. 1-),第1話 青海島の魅力と先駆者たち(p. 9-),第2話 青海島の玄関 仙崎砂州(p. 16-),第3話 「青海湖」・「波の橋立」は動く海浜地形(p. 25-),第4話 「王子山」から見下ろせば…(p. 32-),第5話 「竹の子岩」:赤く錆びた花崗岩が語る(p. 41-),第6話 「平家台」はカルデラ火山の地下博物館(p.49-),第7話 「幕岩」の描くマグマ混合絵巻とマグマの流動,そして地下陥没(p. 65-),第8話 「白旗岩」:シルも重なればバソリスになる(p. 78-),第9話 「観音堂」付近の地層はカルデラ湖に堆積(p. 82-),第10話 「大門」:節理の絶妙さを堪能できるジオサイト(p. 86-),第11話 「長浜群洞」:日本海の荒波彫刻(p. 91-),第12話「十六羅漢」:日本海の荒波と岩石の多様性が産んだ地形(p. 93-),第13話 溶結凝灰岩が語る白亜紀の火山活動(p. 101-),第14話 「仏岩」:3回の地震に耐えた貫入性凝灰岩(p. 106-),第15話「屏風岩」カルデラを縁取る境界岩脈(p. 111-),第16話 酷似する青海島と韓国慶尚盆地の地質(p. 115-),第17話 “沈水島”:荒々しい外海vs.穏やかな内湾(p. 123-),第18話 “カルデラ”の形成,そして形態と地下構造(p. 132-),第19話「青海島しまじゅう博物館」(p. 140-),第20話 “青海島ジオサイト12”(p. 146-),おわりに(p. 151-),参考文献(p. 154-),付録(p. 162- 前出)となっている.全体として,青海島をその南端(仙崎の対岸)から時計回りに観光船で一周するコースに沿って解説している.
コラムとしては,「名勝及天然記念物「青海島」の記念碑」(p. 15),「白潟思月句碑」(p. 23-24),「青海温泉と長門五名湯」(p. 29-31),「オスプレー(ミサゴ)」(p. 40),「花崗岩とは」(p. 47-48),「貴重な草花と樹木」(p. 62-64),「蓋井(ふたおい)島とウッツリ〜モドロ岬の苦鉄質火成包有岩」(p. 75-77),「5つのタイプの陥没カルデラ」(p. 80-81),「「長州どり」と「やきとり祭りin長門」」(p. 84-85),「全国で初めて人口ふ化に成功したシロアマダイの稚魚の放流:山口県水産研究センター外海研究部」(p. 85),「長門地域の高級ブランドの一つ「仙崎かまぼこ」」(p. 89-90),「横山白虹句碑「鳥瞰路」」(p. 100),「「青の洞窟」はなぜ青い」(p. 105),「白滝山カルデラの貫入性角礫岩」(p. 108-110),「山口県の流紋岩質岩脈の代表」(p. 113-114),「通(かよい)地区の古式捕鯨,そして青海島鯨墓と通鯨唄」(p. 117-122),「スサノオノミコトが滞在した「大泊」とお静伝説のある「静ヶ浦」」(p. 131),「褐藻綱ホンダワラ属「アカモク」」(p. 138-139),「香月泰男の「花石」」(p. 144-145),「鯨肉郷土料理は「100年フード」認定」(p. 145)がある.
本書の主題は作者が長年研究してきた花崗岩・酸性火山岩とそれらが造るカルデラ構造である.特に青海島北西端の平家台では,ホルンフェルス化した湖底堆積物に石英斑岩,花崗岩が順次貫入する様子が見られ,「カルデラ火山の地下博物館」になっている(第6話).そして,青海島全体が本土側へ34km以上,南そして西へ伸びる「長門−豊北カルデラ」に含まれ,青海島東端の屏風岩にカルデラ縁の岩脈が露出する(第15・18話).ただし,「カルデラ」と言っても円形の構造ではなく,細長い地溝帯状の陥没構造である.
本書には美しいカラー写真が多数掲載されている.表紙は平家台の東上空からの空撮(本書第6話),裏表紙は十六羅漢の遠景である(第12話).写真3-3(p. 28)は波の橋立両側の波の違い(外海と湖)を対照的に写し出した「感動的な一枚」で,「ながとフォトコン2017」のグランプリ作品である.写真4-2(p. 34)は仙崎の町の北上空からの空撮だが,「竜宮みたいに浮かんでいる」家並みとその両側の対照的な海岸の様子(外海と内湾),そして背景の山々が美しい.幕岩(及び下関市吉見沖の蓋井(ふたおい)島)の花崗岩中の苦鉄質包有物(p. 65写真7-1a,b, p. 75コラム),白旗岩の湖成層を貫くアプライト岩床(p. 78写真8),観音堂付近の成層した湖成層(p. 82-83写真9-1, 9-2)も見事である.
本書には気になる点がいくつかある.第3話冒頭の2カ所及び第20話のp. 148で「なかの小原,小石原」という金子みすゞの詩の一節が引用されているが,原文は小原ではなく石原である.第12話の表題が「羅観」となっているが,「羅漢」が正しい.また,第1話冒頭の9頁には島全体の地質概略図があり,主要な地名が示してあるが,本書に出てくる王子山,幕岩,白旗岩など興味深い場所の位置が示されていない.これらは改善していただきたい.なお,青海島の英語表記は,産総研の地質図「仙崎」ではOmi Shimaであるが,本書ではOmijimaである.かな表記は,文化庁の天然記念物リストでは「おうみじま」だが,山口県の文化財データベースや国土地理院地図,本学会編の日本地方地質誌中国地方では「おうみしま」,長門市の観光案内では「おおみじま」であり,本書では現在地元長門市で公式的に使われる「おおみじま」を用いている.
本書の購入を希望する場合は,
青海島観光汽船株式会社(〒759-4106山口県長門市仙崎字漁港南4297-2
TEL:0837-26-0834,FAX:0837-26-0835,
mail: info@omijimakankoukisen.jp; omijimakankoukisen@gmail.com)へ連絡されたい.
(石渡 明)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
新しい論文が公開されています.
■ Island Arc
Eocene extensional tectonics in the Amakusa region, northern Ryukyu arc.
Kentaro Ushimaru, Atsushi Yamaji
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
※学会HP「会員ページ」(要ログイン)からアクセスすることで,全文無料
で閲覧できます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[関東支部]
・2024年度関東支部総会・講演会
2024年4月20日(土)14:00-16:45
場所:北とぴあ第2研修室.
講師:向山 栄氏(国際航業株式会社 公共コンサルタント事業部)
講演内容:数値地形画像を用いたダイナミックな地表面変位の可視化.
・関東支部アウトリーチ巡検 「安房鴨川海岸の地質・地形観察」
2月18日(日)(予備日:3月3日(日))
募集:20人(先着順)
申込期間:1月17日(水)-2月2日(金)17:00終了※定員に達した時点で終了
・2024年度関東支部幹事選出のお知らせ
立候補期間:2024年3月1日(金)-3月11日(月)17時締切
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0201.html
[西日本支部]
・西日本支部令和5年度総会・第174回例会
2024年3月2日(土)
会場:薩摩川内市川内駅コンベンションセンター SSプラザせんだい
参加・講演申込締切:2月1日(木)
講演要旨提出締切:2月22日(木)
支部総会委任状締切:2月29日(木)
https://geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)日本応用地質学会令和5年度技術者倫理講習会
1月16日(火)16:30-18:50
Zoomによりオンライン講習会
参加費:学会員/山口大学理学部地球圏システム科学科支援企業社員1,000円,
非学会員 3,000円
CPD:2.0CPDH
https://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/others-pdf/20240116oyorinrikoshu.pdf
防災学術連携体
緊急報告会「令和6年能登半島地震の概要とメカニズム」
1月19日(金)17:30-19:00
オンライン,参加費無料
YouTube(一般公開・申込不要)でご視聴いただけます
https://youtu.be/wO34MFfcS6A
(後)原子力総合シンポジウム2023
主催:日本学術会議総合工学委員会,総合工学委員会原子力安全に関する分科会
1月22日(月)13:00-17:10
会場:日本学術会議講堂(港区六本木7-22-34)・オンライン
参加無料
https://www.scj.go.jp/ja/event/2024/353-s-0122.html
(後)第61回アイソトープ・放射線研究発表会
7月3日(水)-5日(金)
会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
発表申込期間:1月15日(月)-2月29日(木)12時
https://www.jrias.or.jp/
★日本地質学会第131年学術大会(2024山形)
9月8日(日)-10日(火)
会場:山形大学小白川キャンパス
(協)地盤技術フォーラム2024
9月18日(水)-20日(金)10:00−17:00
場所:東京ビックサイト・東ホール(江東区有明3丁目)
http://www.sgrte.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・山田科学振興財団2024年度研究援助候補者推薦依頼(学会締切2/1)
・JST先端国際共同研究推進事業2024年度日英共同研究提案募集(4/16)
※募集説明会:1/24 zoom開催
・栗駒山麓ジオパーク専門員(地質学、地理学等)募集(1/26)
・伊那市地域おこし協力隊「南アルプス山と人のコミュニケーター」募集(2/2)
・四国西予ジオパーク専門員(個人事業主型地域おこし協力隊)募集(12/31)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.605(臨時)【期間延長】正副会長立候補意思表明者への意向調査
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.605 2024/1/19 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】会長・副会長立候補意思表明者への意向調査結果および期間延長について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】会長・副会長立候補意思表明者への意向調査結果および期間延長について
──────────────────────────────────
日頃の日本地質学会の活動へのご協力ありがとうございます.
今回の代議員選挙は選挙システムを利用した初めての選挙でした.
従来の投票用紙やマニュフェストが学会から送付される選挙と異なり,会員自らが
学会HP,メルマガ及びニュース誌等の学会から発信される情報にアクセスすること
が求められました.
2022年代議員選挙時の意向調査への投票総数は844票でした.先日1月10日に締め切
られた今回の意向調査への投票総数は87票です.初めての選挙システム利用という
ことを考慮しても,前回の1/10という投票数は今後の選挙に課題を残すところです.
本意向調査は,理事会が正副会長を選出する際に参考にする大変重要な調査である
ため,今回の意向調査期間を理事及び監事選挙の立候補期間終了日の2月7日(水)
17時まで延長することといたします.
次回以降の選挙での投票率を高めるために,学会HPやメルマガでの情報発信,会員
への周知徹底に努めます.
会員の皆様のご協力をお願いいたします.
************************************************
会長・副会長立候補意思表明者への意向調査【期間延長】
締切:2024年2月7日(水)17時
************************************************
学会HP「会員ページ」(https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php)へ
ログイン→「2024年選挙」をクリック
立候補意思表明者のマニフェストも「会員ページ」からご覧いただけます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
***第15回惑星地球フォトコンテスト:作品募集中!1/31締切!***
https://photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.606(臨時)【期間延長中】正副会長立候補意思表明者への意向調査
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.606 2024/1/26 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】会長・副会長立候補意思表明者への意向調査結果および期間延長について
──────────────────────────────────
************************************************
会長・副会長立候補意思表明者への意向調査【期間延長】
締切:2024年2月7日(水)17時
************************************************
日頃の日本地質学会の活動へのご協力ありがとうございます.
今回の代議員選挙は選挙システムを利用した初めての選挙でした.
従来の投票用紙やマニュフェストが学会から送付される選挙と異なり,会員自らが
学会HP,メルマガ及びニュース誌等の学会から発信される情報にアクセスすること
が求められました.
2022年代議員選挙時の意向調査への投票総数は844票でした.先日1月10日に締め切
られた今回の意向調査への投票総数は87票です.初めての選挙システム利用という
ことを考慮しても,前回の1/10という投票数は今後の選挙に課題を残すところです.
本意向調査は,理事会が正副会長を選出する際に参考にする大変重要な調査である
ため,今回の意向調査期間を理事及び監事選挙の立候補期間終了日の2月7日(水)
17時まで延長することといたします.
次回以降の選挙での投票率を高めるために,学会HPやメルマガでの情報発信,会員
への周知徹底に努めます.
会員の皆様のご協力をお願いいたします.
************************************************
会長・副会長立候補意思表明者への意向調査【期間延長】
締切:2024年2月7日(水)17時
************************************************
学会HP「会員ページ」(https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php)へ
ログイン→「2024年選挙」をクリック
立候補意思表明者のマニフェストも「会員ページ」からご覧いただけます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
***第15回惑星地球フォトコンテスト:作品募集中!1/31締切!***
https://photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.607 (臨時)J-STAGE長期戦略に関しての意見募集のお願い(2/1締切)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.607 2024/1/26 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】J-STAGE長期戦略に関しての意見募集のお願い(2/1締切)
──────────────────────────────────
地質学雑誌の内容の充実にご尽力いただき誠にありがとうございます。
地質学雑誌の電子発行母体であるJ-Stageより、長期戦略に関しての意見募集がありました。
J-Stageの発展は、地質学雑誌の発展にもつながります.会員の皆さまよりご意見をいただけましたら幸いです。
ご意見は以下のGoogle_formのサイトにご記入ください。
そこで、J-stageの長期戦略や取り組むべき課題なども、ご確認いただけます。
この連絡をJ-Stageから頂いたのは、1月25日で、締切は2月5日となっています。
非常にshort noticeで申し訳ありませんが、
地質学会としての整理,取りまとめも必要となるので、
Google formへの記入は2月1日までとさせていただきます。
****************
意見募集フォーム
https://forms.gle/DKiWnPFLwoiSGRQw8
締切:2月1日(木)
****************
ご協力のほど,よろしくお願いいたします
地質学雑誌 編集委員会
委員長 小宮 剛
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
***第15回惑星地球フォトコンテスト:作品募集中!1/31締切!***
https://photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(main@geosoc-member.jp)は送信用アドレスです.
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.609(臨時)【期間延長】正副会長立候補意思表明者への意向調査
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.609 2024/2/2 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】会長・副会長立候補意思表明者への意向調査結果および期間延長について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】会長・副会長立候補意思表明者への意向調査結果および期間延長について
──────────────────────────────────
日頃の日本地質学会の活動へのご協力ありがとうございます.
今回の代議員選挙は選挙システムを利用した初めての選挙でした.
従来の投票用紙やマニュフェストが学会から送付される選挙と異なり,会員自らが
学会HP,メルマガ及びニュース誌等の学会から発信される情報にアクセスすること
が求められました.
2022年代議員選挙時の意向調査への投票総数は844票でした.先日1月10日に締め切
られた今回の意向調査への投票総数は87票です.初めての選挙システム利用という
ことを考慮しても,前回の1/10という投票数は今後の選挙に課題を残すところです.
本意向調査は,理事会が正副会長を選出する際に参考にする大変重要な調査である
ため,今回の意向調査期間を理事及び監事選挙の立候補期間終了日の2月7日(水)
17時まで延長することといたします.
次回以降の選挙での投票率を高めるために,学会HPやメルマガでの情報発信,会員
への周知徹底に努めます.
会員の皆様のご協力をお願いいたします.
************************************************
会長・副会長立候補意思表明者への意向調査【期間延長】
締切:2024年2月7日(水)17時
************************************************
学会HP「会員ページ」(https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php)へ
ログイン→「2024年選挙」をクリック
立候補意思表明者のマニフェストも「会員ページ」からご覧いただけます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(注)main@geosoc-member.jpは送信用アドレスです。直接のご返信はご遠慮ください。
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.608(臨時)まもなく早期締切:2/1(JpGU2024 地質学会共催セッション)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.608 2024/1/30 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】まもなく早期締切:2/1(JpGU2024 地質学会共催セッション)
──────────────────────────────────
JpGU2024において地質学会は,関係学協会等と共催し下記のセッションを予定しています。
是非セッションへの投稿をご検討下さい。
******************************************
早期締切:2月1日(木) 23:59
最終締切:2月15日(木)17:00
https://www.jpgu.org/meeting_j2024/
******************************************
地質学会が共催するJpGUセッション(セッション ID,タイトル,代表世話人)
H-DS09:人間環境と災害リスク(佐藤 浩)
H-CG23:堆積・侵食・地形発達プロセスから読み取る地球表層環境変動(菊地一輝)
S-SS11:活断層と古地震(小荒井 衛)
S-EM13:地磁気・古地磁気・岩石磁気(臼井洋一)
S-GL18:日本列島および東アジアの地質と構造発達史(羽地俊樹)
S-GL19:年代層序単元境界の研究最前線(星 博幸)
S-MP21:Oceanic and Continental Subduction Processes: petrologic and geochemical perspective(礼満 ハフィーズ)
S-MP24:変形岩・変成岩とテクトニクス(中村 佳博)
S-CG41:地殻表層の変動・発達と地球年代学/熱年代学の応用(末岡 茂)
S-CG45:岩石・鉱物・資源(福士圭介)
B-CG06:地球史解読:冥王代から現代まで(小宮 剛)
M-IS03:Evolution and variability of the Asian Monsoon and Indo-Pacific climate during the Cenozoic Era(佐川拓也)
M-IS08:ジオパーク(尾方隆幸)
M-IS23:地質学のいま(辻森 樹)
各セッション詳細(概要,開催日時など)はこちらから
https://www.jpgu.org/meeting_j2024/sessionlist_jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
***第15回惑星地球フォトコンテスト:作品募集中!1/31締切!***
https://photo.geosociety.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(注)main@geosoc-member.jpは送信用アドレスです。直接のご返信はご遠慮ください。
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.610 明日まで!会長・副会長意向調査【期間延長中】
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.610 2024/2/6 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】会長・副会長立候補意思表明者への意向調査結果および期間延長について
【2】2024山形大会開催!トピックセッション提案募集
【3】日本地質学会研究奨励金募集(若手野外地質研究者向け)
【4】地質系業界オンライン交流会:開催します
【5】第10回ショートコース:海底鉱物資源 受講者募集中
【6】JABEEシンポ:大学縮小危機のなかで、社会の要求にどのように応えるか
【7】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【8】支部のお知らせ
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】会長・副会長立候補意思表明者への意向調査結果および期間延長について
──────────────────────────────────
日頃の日本地質学会の活動へのご協力ありがとうございます.
今回の代議員選挙は選挙システムを利用した初めての選挙でした.
従来の投票用紙やマニュフェストが学会から送付される選挙と異なり,会員自らが
学会HP,メルマガ及びニュース誌等の学会から発信される情報にアクセスすること
が求められました.
2022年代議員選挙時の意向調査への投票総数は844票でした.先日1月10日に締め切
られた今回の意向調査への投票総数は87票です.初めての選挙システム利用という
ことを考慮しても,前回の1/10という投票数は今後の選挙に課題を残すところです.
本意向調査は,理事会が正副会長を選出する際に参考にする大変重要な調査である
ため,今回の意向調査期間を理事及び監事選挙の立候補期間終了日の2月7日(水)
17時まで延長することといたします.
次回以降の選挙での投票率を高めるために,学会HPやメルマガでの情報発信,会員
への周知徹底に努めます.
会員の皆様のご協力をお願いいたします.
************************************************
会長・副会長立候補意思表明者への意向調査【期間延長】
締切:2024年2月7日(水)17時
************************************************
学会HP「会員ページ」https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
へログイン→「2024年選挙」をクリック
立候補意思表明者のマニフェストも「会員ページ」からご覧いただけます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2024山形大会開催!トピックセッション提案募集
──────────────────────────────────
日本地質学会第131年学術大会(2024山形大会)
会期:2024年9月8日(日)-9月10日(火)
会場:山形大学小白川キャンパス(山形市小白川町)にて
******************
トピックセッション提案募集 締切:2024年3月27日(月)
******************
※大会までのスケジュール(予定)
3月27日(月):トピックセッション提案募集締切
6月19日(水):演題登録・講演要旨受付締切/ランチョン・夜間小集会申込締切
7月中旬:大会プログラム公開(予定)
8月下旬:大会参加登録/巡検参加申込締切
https://geosociety.jp/science/content0168.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】日本地質学会研究奨励金募集(若手野外地質研究者向け)
──────────────────────────────────
日本地質学会では若手育成事業の一環として,野外調査をベースに研究を行う
32歳未満の若手会員を対象とした研究奨励金制度を設けています..
また,規則改正により,助成期間の延長も可能となりました.
**************************************
応募締切:2024年2月29日(木)必着
**************************************
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0242.html
(申請に関するFAQも掲載しています)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地質系業界オンライン交流会:開催します
──────────────────────────────────
本交流会は,地質学に関わる民間企業や官公庁等に就職を考えている学生・若手
研究者向けのイベントであり、地質学に関わる企業に就職をした若手社員の方
との座談会と懇親会を企画しています。どのようなお仕事をされているのか、
特にやりがいを感じた仕事、学生時代の経験で役に立ったこと、業界でのキャリ
ア形成など、企業説明会や就職説明会などとは異なる若手社員ならではのお話を
していただき、参加者からの質問に答えていただく予定です。地質系の民間企業
だけではなく、公務員や学芸員、ジオパーク職員など、広く地質学に関わる仕事
を行っている方とお話しできる貴重な機会になりますので、奮ってご参加ください。
日時:2024年2月16日(金)19:00-21:00
場所:Zoomによるオンライン開催
対象:35歳以下の学生・若手研究者(会員・非会員を問わない)
参加申込締切:2月15日(木)23:59
https://geosociety.jp/science/content0172.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】第10回ショートコース:海底鉱物資源 受講者募集中
──────────────────────────────────
日程:2024年2月25日(日)
<午前> 9:00-12:00
海底鉱物資源概論:その研究と開発の過去、現在、未来
講師:中村謙太郎(東京大学)
<午後> 14:00-17:00
海底鉱物資源の探査と成因研究の最前線
講師:町田嗣樹(千葉工業大学)
参加申込締切:2024年2月16日(金)
https://geosociety.jp/science/content0171.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】JABEEシンポ:大学縮小危機のなかで、社会の要求にどのように応えるか
──────────────────────────────────
第4回JABEEオンラインシンポジウム
大学縮小危機のなかで、社会の要求にどのように応えるか
ーJABEEを活用した技術者の育成と輩出ー
日時:2024年3月3日(日)13:30-17:20(予定)
開催方式:Zoomを用いたオンライン方式
参加者:200名(先着順) 会員,非会員を問いません.参加無料
参加申込締切:2月26日(月)
詳しくは,https://geosociety.jp/science/content0167.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
新しい論文が公開されています.
■ 地質学雑誌
(論説)北海道女満別およびその周辺地域の新第三系凝灰岩・凝灰質砂岩に含まれ
るジルコンFT・U–Pb年代とその層序学的意義:加瀬善洋ほか/(論説)谷底低地の
S波速度構造と地盤震動特性:武蔵野台地を刻む神田川および古川沿いの低地を例
に:中澤 努ほか
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/-char/ja
■ Island Arc
Magnetostratigraphic dating of Early Miocene deep-sea fossils from the Morozaki
Group in central Japan: Hiroyuki Hoshi et al
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
※学会HP「会員ページ」(要ログイン)からアクセスすることで,全文無料
で閲覧できます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[関東支部]
・2024年度関東支部総会・講演会
2024年4月20日(土)14:00-16:45
場所:北とぴあ第2研修室.
講師:向山 栄氏(国際航業株式会社 公共コンサルタント事業部)
講演内容:数値地形画像を用いたダイナミックな地表面変位の可視化.
・2024年度関東支部幹事選出のお知らせ
立候補期間:2024年3月1日(金)-3月11日(月)17時締切
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0201.html
[西日本支部]
・西日本支部令和5年度総会・第174回例会
2024年3月2日(土)
会場:薩摩川内市川内駅コンベンションセンター SSプラザせんだい
講演要旨提出締切:2月22日(木)
支部総会委任状締切:2月29日(木)
https://geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
地質地盤情報の活用と法整備を考える会
2024年2月1日、ホームページを更新しました.
https://www.geo-houseibi.jp
********************************************
東京地学協会2023年度第2回定期講演会
望月勝海教授,かく記録せり―日記に読む地体構造論・地誌記述・地学教育の歴史
2月24日(土)14:00-16:00
会場:地学会館2階講堂(東京都千代田区二番町12-2)
講演者:山田俊弘(東京地学協会日本地学史編纂委員)
参加費無料・申込不要
http://www.geog.or.jp/lecture/lecturescheduled/495-news240110.html
日本堆積学会 2024 年熊本大会
4月20日(土)-22 日(月)
会場:熊本大学(黒髪南地区)
講演申込・巡検参加締切:3/22(金)
大会参加申込締切(早期):4/11(木)
https://sites.google.com/view/ssjconference2024kumamoto
(後)第61回アイソトープ・放射線研究発表会
7月3日(水)-5日(金)
会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
発表申込締切:2月29日(木)12時
https://www.jrias.or.jp/
地学団体研究会第78回つくば総会
8月17日(土)-18日(日)
会場:つくばカピオ(茨城県つくば市)
https://www.chidanken.jp
★日本地質学会第131年学術大会(2024山形)
9月8日(日)-10日(火)
会場:山形大学小白川キャンパス
(協)地盤技術フォーラム2024
9月18日(水)-20日(金)10:00−17:00
場所:東京ビックサイト・東ホール(江東区有明3丁目)
http://www.sgrte.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・伊豆大島ジオパーク専門員(学芸員)募集(2/19)
・五島列島(下五島エリア)ジオパーク 専門員募集(2/9)
・大雪山カムイミンタラジオパーク 専門員(地域おこし協力隊)募集(2/8)
・東大地震研2024年度共同利用 地震火山災害軽減研究の公募(2/29)
・国土地理協会2024年度学術研究助成(4/1-15)
・東京地学協会令和6年能登半島地震関連緊急研究・調査助成金(2/24)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.611(臨時)【締切延長】第10回ショートコース:海底鉱物資源
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.611 2024/2/16 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】【締切延長】第10回ショートコース:海底鉱物資源 受講者募集
【2】会長・副会長立候補意思表明者への意向調査(延長)結果報告
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】【締切延長】第10回ショートコース:海底鉱物資源 受講者募集
──────────────────────────────────
定員に少し空きがありますので,参加申し込み締切を2/19まで延長いたします.
この機会にぜひお申し込みください!
日程:2024年2月25日(日)
開催方法:WEB会議システムzoomによるオンライン講義
<午前> 9:00-12:00
海底鉱物資源概論:その研究と開発の過去、現在、未来 講師:中村謙太郎
(東京大学)
<午後> 14:00-17:00
海底鉱物資源の探査と成因研究の最前線 講師:町田嗣樹(千葉工業大学)
受講料:
地質学会正会員(一般・シニア)2,000円
(注)日本地質学会賛助会員に所属する⽅は地質学会会員と同額です.
地質学会正会員(学生会員) 1,000円
***********************
参加申込締切:2月19日(月)
***********************
※締切後,受講者へzoomアクセスURLや事前資料をメールでお送りします.
詳しくはこちらから
https://geosociety.jp/science/content0171.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】会長・副会長立候補意思表明者への意向調査(延長)結果報告
──────────────────────────────────
選挙規則ならびに選挙細則に基づき,標記意向調査を実施いたしました.
当初定めた意向調査期間では,投票総数が87票でした.本意向調査は,理事会が
正副会長を選出する際に参考にする大変重要な調査であるため,理事および監事
選挙の立候補期間終了日の2月7日(水)17時まで延長いたしました.
意向調査の結果を.改めてご報告いたします.
詳しくは,学会HP「会員ページ」へログイン→「会員へのお知らせ」をクリック
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No.612 研究奨励金募集中(若手野外地質研究者向け)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.612 2024/2/20┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2024年度理事および監事選挙について
【2】日本地質学会研究奨励金募集中(若手野外地質研究者向け)
【3】2024山形大会:トピックセッション提案募集
【4】JABEEシンポ:大学縮小危機のなかで、社会の要求にどのように応えるか
【5】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【6】支部のお知らせ
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】会員情報に変更があった場合は...
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2024年度理事および監事選挙について
──────────────────────────────────
2024年度の理事選挙を実施いたします(選挙は2024年度からの当選代議員
による投票となります).
理事選挙の開票は,3月14日(木)15時からオンライン会議で行います.
開票の立ち会いをご希望のかたは、3月11日(月)までに選挙管理委員会
(main[at]geosociety.jp)にお申し出ください.
立候補者名簿ほか選挙の詳細は,
学会ホームページ「会員へのお知らせ」をご覧ください(要ログイン).
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】日本地質学会研究奨励金募集(若手野外地質研究者向け)
──────────────────────────────────
日本地質学会では若手育成事業の一環として,野外調査をベースに研究を行う
32歳未満の若手会員を対象とした研究奨励金制度を設けています..
また,規則改正により,助成期間の延長も可能となりました.
**************************************
応募締切:2024年2月29日(木)必着
**************************************
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0242.html
(申請に関するFAQも掲載しています)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2024山形大会:トピックセッション提案募集
──────────────────────────────────
日本地質学会第131年学術大会(2024山形大会)
会期:2024年9月8日(日)-9月10日(火)
会場:山形大学小白川キャンパス(山形市小白川町)にて
******************
トピックセッション提案募集 締切:2024年3月27日(月)
******************
※大会までのスケジュール(予定)
3月27日(月):トピックセッション提案募集締切
6月19日(水):演題登録・講演要旨受付締切/ランチョン・夜間小集会申込締切
7月中旬:大会プログラム公開(予定)
8月下旬:大会参加登録/巡検参加申込締切
https://geosociety.jp/science/content0168.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】JABEEシンポ:大学縮小危機のなかで、社会の要求にどのように応えるか
──────────────────────────────────
第4回JABEEオンラインシンポジウム
大学縮小危機のなかで、社会の要求にどのように応えるか
ーJABEEを活用した技術者の育成と輩出ー
日時:2024年3月3日(日)13:30-17:20(予定)
開催方式:Zoomを用いたオンライン方式
参加者:200名(先着順) 会員,非会員を問いません.参加無料
参加申込締切:2月26日(月)
詳しくは,https://geosociety.jp/science/content0167.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
新しい論文が公開されています.
■ Island Arc
Field‐based description of near‐surface crustal deformation in a high‐strain
shear zone: A case study in southern Kyushu, Japan. Masakazu Niwa et al
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
※学会HP「会員ページ」(要ログイン)からアクセスすることで,全文無料
で閲覧できます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[関東支部]
・2024年度関東支部総会・講演会
2024年4月20日(土)14:00-16:45
場所:北とぴあ第2研修室.
講師:向山 栄氏(国際航業株式会社 公共コンサルタント事業部)
講演内容:数値地形画像を用いたダイナミックな地表面変位の可視化.
・2024年度関東支部幹事選出のお知らせ
立候補期間:2024年3月1日(金)-3月11日(月)17時締切
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0201.html
[西日本支部]
・西日本支部令和5年度総会・第174回例会
2024年3月2日(土)
会場:薩摩川内市川内駅コンベンションセンター SSプラザせんだい
講演要旨提出締切:2月22日(木)
支部総会委任状締切:2月29日(木)
https://geosociety.jp/outline/content0025.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
地震本部ニュース2023冬号
「内陸で発生する地震の調査観測に関する検討ワーキンググループ」を設置 ほか
https://www.jishin.go.jp/herpnews/
—------------------------------
CPS/WTK & ABC ワークショップ
「生命の起源と進化を規定した惑星表層環境を考える」
主催 惑星科学研究センター CPS
3月7日(木)10:00-18:00
会場:神戸大学CPS + zoom
https://www.gfd-dennou.org/seminars/wtk/2024-03-07/
防災学術連携体「令和6年能登半島地震・3ヶ月報告会」
3月25日(月)9:00-14:40
YouTubeライブ配信(予定)
https://www.youtube.com/watch?v=3aZzeqPZoTg
地質学史懇話会
6月15日(土)13:30-17:00
場所:北とぴあ 807号室(東京都北区王子)
・中島由美:平賀源内の秋田行き
・小川勇二郎:付加体学事始め(仮題)
問い合わせ:矢島道子 pxi02070[at]nifty.com
(後)第61回アイソトープ・放射線研究発表会
7月3日(水)-5日(金)
会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
発表申込締切:2月29日(木)12時
https://www.jrias.or.jp/
★日本地質学会第131年学術大会(2024山形)
9月8日(日)-10日(火)
会場:山形大学小白川キャンパス
(協)地盤技術フォーラム2024
9月18日(水)-20日(金)10:00−17:00
場所:東京ビックサイト・東ホール(江東区有明3丁目)
http://www.sgrte.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・神戸大学大学院理学研究科惑星学専攻(地質学講師・流体地球物理学教授)公募(6/12)
・NPO法人日本ジオパークネットワーク事務局臨時職員募集(2/26)
・2025年度日本学術振興会特別研究員-RPD募集(5/13)
・2024年度深田野外調査助成募集(4/12)
・国土地理協会2024年度学術研究助成(4/15)
・東京大学地震研究所共同利用特定機器利用申請(4/5)
・栗駒山麓ジオパーク専門員(地質学、地理学等)募集【募集期限延長】(2/22)
・四国西予ジオパーク専門員(個人事業主型地域おこし協力隊)募集(24/12/31)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】会員情報に変更があった場合は...
─────────────────────────────────
年度末に向け,所属先や自宅等の登録内容にご変更があった場合は,速やかに
情報の更新をお願い致します.情報の変更は,学会ホームページ「会員ページ」
にログインしていただければ,ご自身で登録内容が更新できます.
ご協力をよろしくお願い致します.
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
※初めてログインする方・パスワードをお忘れの方はこちらから
https://www.geosoc-member.jp/Member/fgform.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
2021名古屋
日本地質学会第128年学術大会(2021名古屋大会)巡検案内書
※新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から,本大会では巡検は実施いたしませんでしたが,2020年の大会準備段階より執筆いただいておりました案内書原稿を公開しています.
※それぞれの巡検案内書タイトルをクリックすると,J-STAGE上の原稿画面に遷移します.
名古屋城石垣に使われている石材の岩石種:西本昌司・木村有作
舟伏山地域の美濃帯海洋性岩石の層序と年代:佐野弘好・山縣 毅
愛知県新城市の中央構造線と周辺部の地質:道林克禎・平内健一・西村拓真(※案内書原稿なし)
古琵琶湖層群の鮮新世動物群:松岡敬二・井上恵介・川瀬基弘
中新統師崎層群の球状炭酸塩コンクリーションと深海性動物群化石:村宮悠介, 氏原 温,大路樹生,吉田英一
岐阜県西部・揖斐川町春日地域の火成岩と接触変成岩:榎並正樹・纐纈佑衣・加藤丈典・壷井基裕・丹羽健文
紀伊半島中央部の四万十帯と三波川帯の地質トラバース:志村侑亮・常盤哲也・竹内 誠
中新統〜更新統瀬戸層群の陸成層と陶土:葉田野 希・吉田孝紀・笹尾英嗣
2019山口
日本地質学会第126年学術大会(2019山口)巡検案内書
※それぞれの巡検案内書タイトルをクリックすると,J-STAGE上の原稿画面に遷移します.
秋吉台石灰石鉱山(住友セメント秋芳鉱山)と宇部沖の山Coal Centerの見学:千々和一豊・播磨雄太・岡藤 考
山口県中央部の後期白亜紀カルデラ群の地質:吉部,山口,生雲,佐々並カルデラ:今岡照喜, 井川寿之, 岸 司, 木村 元, 大中翔平, 西川裕輔, 小室裕明
山口-出雲地震帯西部に沿って新たに発見された活断層系:金折裕司・相山光太郎
山口県西部に分布する三畳系美祢層群とジュラ系豊浦層群の層序と化石群 前田晴良・大山 望
山口県北西部における地すべりの地質と防災対策:河内義文,久永喜代志, 金折裕司, 森山亮一
津和野地域の古原生代花崗岩類と高塩濃度深部流体 木村光佑,早坂康隆,田中和広,村上裕晃
石炭−ペルム系秋吉石灰岩の堆積作用とカルスト化作用: 藤川将之・中澤 努・上野勝美
2018札幌
日本地質学会第125年学術大会(2018札幌)巡検案内書
※それぞれの巡検案内書タイトルをクリックすると,J-STAGE上の原稿画面に遷移します.
小樽の地質と石材:仁科健二・松田義章・松枝大治・竹内勝治・大鐘卓哉・菅原慶郎・高見雅三・北嶋 徹
南西北海道,石狩低地帯におけるテフラ層序学:支笏-洞爺火山地域の噴火履歴:中川光弘・宮坂瑞穂・三浦大助・上澤真平
北海道日高海岸地域の中部〜上部中新統前縁盆地埋積物の堆積システムと石油地質:加瀬善洋・川上源太郎・高野 修
蝦夷層群下部〜中部に記録された白亜紀中頃の温暖化と古環境変動:高嶋礼詩・佐野晋一・林 圭一
神居古潭帯のテクトニクス:白亜紀の沈み込みチャネルから前弧海盆堆積物まで:竹下 徹, 平島崇男, 植田勇人, 岡本あゆみ, 木下周祐, 辛 ウォンジ, 幸田龍星, 安藤瑞帆, 中山貴仁
日高変成帯南部の日高深成変成岩類:高橋 浩・志村俊昭・加藤聡美
千島海溝沿岸域において認められる超巨大地震津波痕跡群と広域地殻変動:七山 太・渡辺和明・重野聖之・石井正之・石渡一人・猪熊樹人
小型無人航空機とGNSSを利用した数値地表モデルの作成実習:渡邊達也・山崎新太郎・亀田 純
日本周辺の地震西進系列と次の関東・南海地震
日本周辺の地震西進系列と次の関東・南海地震
石渡 明(正会員 原子力規制委員会)
図1.日本周辺の過去約350年間(1677-2024)のM≧7.3地震西進系列図.縦軸の概算距離は√((N-20)2+(E-120)2).各系列の一次近似直線も示す.説明は本文参照.各地震のデータはWeb版付録1を参照.
※クリックすると大きな画像をご覧いただけます.
石渡(2019)は最近360年間の日本周辺の大地震について,「南海トラフ巨大地震を中心に,M≧7.5地震が北海道から台湾へ西進する傾向が見られ(中略)これを「地震系列」と名付ける」と述べ,南海トラフ地震発生時の年号により各系列を宝永,安政,昭和と命名した.小論では現在東北地方から西進しつつある最新地震系列の特徴を過去3系列と比べて論じ,今後の推移を考察する.なお,小論の内容の一部は2023年9月30日の日本地質学会関東支部「関東地震から100年」オンライン講演会で述べた.
図1は石渡(2019)の「日本地震周期表」を数値化し,縦軸に台湾南方の北緯(N)20度,東経(E)120度を起点とする震央までの概算距離(√((N-20) 2+(E-120)2):単位は約100km:対応する地域名を示す),横軸に地震発生年(西暦)をとり,兵庫県南部地震や熊本地震以上の規模(M≧7.3)の地震をプロットして各西進系列を表した「日本地震系列図」である.根拠資料は理科年表2024年版の「日本付近のおもな被害地震年代表」と「世界のおもな大地震・被害地震年代表」(丸善),「日本被害地震総覧599-2012」(東大出版会)及び日本の気象庁と台湾の中央気象局のHPである.プロットした各地震のデータはWeb版に付録1として添付する.この図を見てまず気づくのは,各系列を代表する東北の大地震が111年周期(標準偏差7年)で規則的に繰り返すことで,次の大地震は2122±7年と予想できる.また,各系列に伴う火山活動についてはWeb版の付録2を参照されたい.
宝永系列は延宝三陸沖(1677, M7.9),房総沖(1677, M8.0),元禄関東(1703, M7.9〜8.2),宝永東海・南海(1707, M8.6)の地震・津波に代表され,陸中・出羽(1678, M7.5),芸予(1686, M7.4),仙台(1717, M7.5),越後・信濃(1751, M7.4)などの地震を伴った.九州・四国沖(1769, M7.8),明和八重山津波(1771, M7.4),そして台湾の嘉義(1811, M7.5; 1815,M7.7)は本系列尾部の地震と考えられる.
安政系列は陸前・陸中・磐城(1793, M8.0〜8.4)と安政東海・南海(1854, 各M8.4:東海地震は旧暦11月4日,南海地震は翌5日(世界津波の日)に発生)の地震・津波に代表され,この前後に宝暦八戸(1763, M7.4, 7.3),津軽(1763, M7.3),伊勢・美濃・近江(1819, M7.3),羽前・羽後・越後・佐渡(1833, M7.5),根室・釧路(1843, M8.0),長野善光寺(1847, M7.4),伊賀(1854, M7.3),伊予(1854, M7.5),仙台(1855, M7.3),遠州灘(1855, M7.5: 東海地震の余震),八戸(1856, M7.5),三戸・八戸(1858, M7.5),濃尾(1891, M8.0)などの地震が続発した.奄美大島(1901, M7.5),三重県沖(1906, M7.6),宮崎西部(1909, M7.6),喜界島(1911, M8.0),石垣島(1915, M7.4),そして沖縄島北西沖(1926, M7.5)はこの系列尾部の地震と考えられる.台湾の1882 (M7.5), 1908 (M7.3), 1909 (M7.3), 1910 (M8.3), 1920 (M8.3), 1922 (M7.6)年の地震もこの系列に含まれる.
昭和系列は明治三陸(1898, M8.2),大正関東(1923, M7.9),昭和東南海(1944, M7.9, Mw8.1),南海(1946, M8.0)の地震・津波に代表され,この前後に色丹島沖(1893, M7.8),根室沖(1894, M7.9),宮城県沖(1897, M7.4, 7.7),青森東方沖(1901, M7.4),房総南東沖(1909, M7.5),三陸(1915, M7.5),ウルップ島沖(1918, M8.0),安房勝浦沖(1923, M7.3),丹沢(1924, M7.3),丹後(1927, M7.3),北伊豆(1930, M7.3),八戸南東沖(1931, M7.6),昭和三陸津波(1933, M8.1),宮城県沖(1936, M7.4),福島県沖(1938, M7.5連発),積丹半島沖(1940, M7.5)等の地震が頻発した.そして,この系列の尾部には与那国島近海(1947, M7.4),房総沖(1953, M7.4),八重山・台湾沖(1966, M7.8),日向灘(1968, M7.5),台湾の1951 (M7.3, 群発), 1951 (M7.3), 1957 (M7.3), 1959 (M7.7), 1963 (M7.3), 1972 (M7.3)等の地震があり,最後が集集(921)地震(1999, M7.3, Mw7.6)と考えられる.
最新系列は現在進行中の地震系列であり,東北地方太平洋沖地震(東日本大震災,2011, M9.0)は発生したが,関東地震や南海トラフ地震は未発生である.1950年のサハリン南東沖地震(M7.9)や1952年の十勝沖地震(M8.2)に始まり,択捉島沖(1958, M8.3; 1963, M8.5),新潟(1964, M7.5),十勝沖(1968, M7.9),根室半島沖(1973, M7.4),宮城県沖(1978, M7.4),日本海中部(秋田沖1983, M7.7),釧路沖(1993, M7.5),北海道南西沖(1993, M7.8),北海道東方沖(1994, M8.2),三陸はるか沖(1994, M7.6),兵庫県南部(阪神大震災1995, M7.3),サハリン(1995, M7.5),択捉島沖(1995, M7.9),硫黄島近海(2000, M7.9やや深発),鳥取県西部(2000, M7.3),十勝沖(2003, M8.0),三重県沖(2004, M7.4連発),千島沖(2007, M8.2),小笠原東方沖(2010, M7.8),宮城県沖(2011, M7.3東日本大震災2日前の前震),福島県沖(2012, M7.4連発),オホーツク海南部(2012, M7.3),小笠原西方沖(2015, M8.1深発),熊本(2016, M7.3連発),福島県沖(2016, M7.4; 2021, M7.3; 2022, M7.4),能登半島(2024, M7.6)の地震が発生した.最新系列はまだ途中だが,既発生のM≧7.3地震の数32は昭和系列の31,安政系列の29,宝永系列の12を超え,非常に活発な地震活動が進行中だと言える.なお,図1で関東付近に示される最近の地震は,後述のM8級深発地震を含む伊豆・小笠原弧の地震と今年元旦の能登地震である.
もっと昔の地震西進系列は平安時代の貞観三陸地震津波(869),元慶関東地震(878),仁和南海トラフ地震津波(887)にも見られ(石渡2022),室町〜戦国時代の享徳三陸津波(1454),明応鎌倉地震津波(1495),明応南海トラフ地震津波(1498)にも見られる(同Web版追記1).また,戦国〜江戸時代初期の慶長系列は,1586(天正13)年の飛騨美濃近江(白川)地震(M7.8)に始まり,南海トラフ・房総沖の津波(1605, 慶長9, 各M7.9),三陸地震津波(1611, 慶長16, M8.1)と続くので,大地震が東進したように見えるが,1662(寛文2)年の日向灘の地震津波(M7.8: 外所(とんところ)地震,宮崎市の伝承碑が有名)を慶長系列の尾部と見れば(台湾の地震は不詳),全体的には西進系列に見える.つまり,過去1300年間の南海トラフ地震9回のうち6回で西進系列が認められ,現時点で西進系列が不明なのは白鳳(天武)(701),永長東海(1096)・康和南海(1099),正平(1361)の3回である.
次の関東・南海トラフ地震の発生時期が地震系列図(図1)から予想できる.現在進行中の最新地震系列は系列開始後既に74年経過している.系列開始から南海トラフ地震までの年数は,宝永系列が30年,安政系列が91年,昭和系列が51年,平均57年だから,既に発生可能な時期である.また,東北の大地震から南海トラフ地震までは,宝永系列が30年,安政系列が61年,昭和系列が48年であり,平均46(±16)年だから,2057 (2041〜2073)年に次の南海トラフ地震が発生する可能性が高い.ただし,平安時代の仁和系列では18年,室町時代の明応系列では44年,江戸時代初期の慶長系列では−6年(逆順)と短く,これらを含めた平均33(±24)年を採ると2044(2020〜2068)年に早まる.そして関東地震はその7(±8)年前の発生が予想される(21年前に発生した大正関東地震は例外).
次の関東・南海トラフ地震の規模も,地震系列図から予想できる.宝永系列は東北から台湾まで大地震が西進するのに138年を要し,安政系列も163年かかったが,昭和系列は106年で終了した.この差は,宝永M8.6,安政M8.6(東海・南海合算),昭和M8.2(東南海・南海合算)という南海トラフ地震の規模と相関があるように見える.関東地震も宝永系列(元禄地震)と昭和系列(大正地震)を比べると,前者の方が大きい.なお,安政系列ではM8級の関東地震は発生せず,M7級の善光寺地震や江戸地震があった.最新系列は開始後既に74年になるのに関東・南海トラフ地震が未発生であり,系列完了まで長くなるらしいことは,次の関東・南海トラフ地震の規模が過去のものより大きくなる可能性を示唆する.台湾も含めた1つの系列内のM8級地震(M≧7.8)の数は,宝永系列が5, 安政系列が8, 昭和系列が9であるのに対し,最新系列は関東・南海トラフ地震が未発生なのに既に14に達している.各系列で放出された全地震エネルギーを計算すると,1016J(ジュール)を単位として,宝永系列が85,安政系列が149,昭和系列が82であるのに対し,最新系列はまだその途中なのに既に311に達している(Log E=4.8+1.5M式に基づく).最新系列では2011年にM9.0の東北地方太平洋沖地震が発生したが,この地震は単独でいきなり発生したのではなく,東北日本全体の活発な地震活動の一環として発生したことが図1から明らかである.これらのことは,最新系列の延長線上で発生する次の関東・南海トラフ地震が,過去のものより大規模になる可能性を示す.日本周辺の太平洋プレート沈み込み帯の深部で大地震の発生が相次ぐことも,この地域のプレート全体に大きなストレスが加わっていることを示唆する.それらは,千島弧と伊豆小笠原弧の深発スラブ内地震であり,2000.03.28硫黄島近海M7.9(Mw7.3)深さ128km,2012.08.14オホーツク海南部M7.3(Mw7.7)深さ654km,2015.05.30小笠原西方M8.1(Mw7.8)深さ664km,そして図1の範囲外だが2013.05.24オホーツク海北部M8.3(Mw8.3)深さ581km等である.
地球全体の地震活動の活発化が最新系列の活発な地震活動と同期している.地球のM9以上の地震は日本の最新系列開始と同時にカムチャッカ(1952, M9.0)で始まり,チリ(1960, M9.5),アラスカ(1964, M9.2),スマトラ(2004, M9.1:インド洋大津波)と続き,ついに東北地方太平洋沖地震(2011, M9.0)の発生に至った.これら以前の歴史時代のM9地震は1700年のカスカディア地震(北米西岸)だけであるが,この地震の3年後に元禄関東地震,7年後に宝永南海トラフ地震が発生し,1755年には欧州最大のリスボン地震(Mw8.5,死62000, スペイン・モロッコでも被害大)が発生したことも注目すべきである.
大地震のない時期や地域も図1から読み取れる.台湾では地震が多いが,宮古島〜九州南部(縦軸8〜16)では過去数100年間大地震の発生が非常に少ない.西南日本(糸魚川-静岡構造線以西)と関東では東南海(1944)・南海(1946)地震以後,福井地震(1948, M7.1, 死3769)を最後として,しばらく大きな被害地震がなく,日本はこの空白期に高度経済成長を遂げた.しかし,1995年兵庫県南部地震以後,2000年鳥取県西部地震,2005年福岡県西方沖地震などM≦7.3の被害地震が続発するようになり,西南日本は地震活動期に入ったとされるが(尾池, 2007),M≧7.5の地震は1968年の日向灘地震(プレート境界型)以後なかった(2016年熊本地震もM7.3).2024年元旦の能登地震(M7.6)は西南日本で56年ぶりのM≧7.5地震であり,内陸地殻内地震としては1891年濃尾地震(M8.0)以来133年ぶりの大地震である.一方,東北や北海道では昭和系列から空白期なしに活発な地震活動が続く.今後は関東・南海トラフ地震だけでなく,全国で複数のM7級地震の発生が予想され(尾池, 2007, p. 73),都市直近なら大被害になるので,各地域で十分な備えが必要である.
まとめると,現在日本で進行中の最新系列の地震活動には,系列開始後74年経つのに関東・南海トラフ地震が未発生で,系列完了に長期間を要するらしいこと,系列完了に要する時間と南海トラフ地震の規模には正の相関があるらしいこと,東北地方で2011年に日本の歴史上初めて発生したM9地震は,単独で突発したのではなく,深発を含む多数のM8級地震を伴うこと,最新系列の地震エネルギーの和が,過去3回の地震系列のどれよりも多いこと,最新系列の活動は地球全体のM9地震の続発と同期していること等の特徴がある.現在進行中の最新系列の地震活動は過去に例がない活発さで,今後数10年以内に予想される次の関東・南海トラフ地震は先例を超える規模になる可能性があり,その前後には今年元旦の能登地震のようなM7級地震が複数発生することにも警戒が必要である.大地震西進の原因は論じないが,地球上最大で運動が速い太平洋プレートに直面する東日本から奥まった西日本へ,ストレスとその解消のための大地震が伝播するのは当然に思える.
拙稿を読んでご意見をいただいた棚瀬充史,池田保夫両氏に感謝する.
【文 献】
石渡 明(2019)日本地震周期表:大地震の西進傾向と将来予測.日本地質学会第128年学術大会講演要旨T6-P-2.(ポスター)https://www.nra.go.jp/data/000288489.pdf
石渡 明(2022)平安時代の「日本三代実録」の地震・津波・噴火記録:地震西進系列の白眉.日本地質学会News, 25(10), 8-9. https://geosociety.jp/faq/content1052.html
尾池和夫(2007)新版 活動期に入った地震列島.岩波科学ライブラリー, 138. 岩波書店.
【Web版付録】
【Web版付録1】日本周辺地震西進系列表(1677年〜2024年のM≧7.3地震)
【Web版付録2】各地震西進系列に伴う火山活動
【geo-Flash】No.614 2024年度理事および監事選挙(結果報告)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.614 2024/3/19┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2024年度理事および監事選挙(結果報告)
【2】2024山形大会:トピックセッション提案募集中(まもなく締切)
【3】2024年「地質の日」行事のご案内
【4】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【5】コラム 日本周辺の地震西進系列と次の関東・南海地震
【6】支部のお知らせ
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】会員情報に変更があった場合は...
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2024年度理事および監事選挙(結果報告)
──────────────────────────────────
一般社団法人日本地質学会選挙規則ならびに選挙細則に基づき,理事選挙を
実施いたしましたので,ご報告いたします.
開票結果および当選者の名簿は,
学会ホームページ「会員へのお知らせ」をご覧ください(要ログイン).
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
★代議員および理事選挙を終えて(選挙管理委員会より)★
任期満了に伴い,代議員および理事選挙を実施いたしました.(一部略)
今回も「小中高」の所属階層からの理事立候補はありませんでした.
選挙管理委員会は,開票も含め全ての作業,会合をオンラインで実施いたし
ました.また今回の代議員選挙は立候補から投票まで選挙システムを利用した
初めての選挙でした.従来の投票用紙やマニュフェストが学会から送付される
選挙と異なり,2022年代議員選挙時の意向調査への投票総数844票に対して,
1月10日時の投票総数は87票であったため,2月7日まで期間を延長した結果
329票となりました。初めての選挙システム利用ということを考慮しても,
例年を大きく下回る投票数は今後の選挙に課題を残すところです.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2024山形大会:トピックセッション提案募集中(まもなく締切)
──────────────────────────────────
日本地質学会第131年学術大会(2024山形大会)
会期:2024年9月8日(日)-9月10日(火)
会場:山形大学小白川キャンパス(山形市小白川町)にて
******************
トピックセッション提案募集 締切:2024年3月27日(月)
******************
※大会までのスケジュール(予定)
3月27日(月):トピックセッション提案募集締切
6月19日(水):演題登録・講演要旨受付締切/ランチョン・夜間小集会申込締切
7月中旬:大会プログラム公開(予定)
8月下旬:大会参加登録/巡検参加申込締切
https://geosociety.jp/science/content0168.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2024年「地質の日」行事のご案内
──────────────────────────────────
2024年の「地質の日」に関連した日本地質学会主催,共催,後援等の催しを
ご紹介します。
惑星地球フォトコンテスト第15回ほか入選作品展示会/街中ジオ散歩in Tokyo
「身近な地形・地質から探る麻布の歴史と湧水」/講演会「デジタル詳細地形
データを用いた地表面変位計測で見る地震災害」/第41回地球科学講演会「日本
列島の起源と大和構造線」/石の魅力大発見!〜見て・触って・知ってみよう〜
/「地質の日」企画 身近に知る「くまもとの大地」
詳しくは,https://geosociety.jp/name/content0179.html
このほか,地質学会以外の全国の地質の日イベント情報はこちら
https://www.gsj.jp/geologyday/2024/index.html(地質の日事業推進委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
新しい論文が公開されています.
■地質学雑誌
(論説)紀伊半島南部海岸地域の田子含角礫泥岩層「サラシ首層」
の時代と成因について:別所孝範/(レター)京都市安楽寿院の
平安時代後期凝灰岩製石仏の石材産地の検討:川村教一/(総説)
内陸下の低周波地震の特徴と発生メカニズム:小菅正裕/
(フォト)山形県鮭川村観音寺の活断層露頭:中田 英二
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/list/-char/ja
■ Island Arc
Intermittent hydrothermal alteration and silicification of black mudstones
found in the Middle to Upper Miocene Yagen Formation, Shimokita
Peninsula, Northeast Japan:Hirokazu Ueda, Yoshikazu Sampei
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
※学会HP「会員ページ」(要ログイン)からアクセスすることで,IARは全文無料
で閲覧できます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】コラム 日本周辺の地震西進系列と次の関東・南海地震
──────────────────────────────────
石渡 明(正会員 原子力規制委員会)
石渡(2019)は最近360年間の日本周辺の大地震について,「南海トラフ
巨大地震を中心に,M≧7.5地震が北海道から台湾へ西進する傾向が見られ
(中略)これを「地震系列」と名付ける」と述べ,南海トラフ地震発生時の
年号により各系列を宝永,安政,昭和と命名した.小論では現在東北地方
から西進しつつある最新地震系列の特徴を過去3系列と比べて論じ,今後の
推移を考察する.
つづきはこちらから,,,http://geosociety.jp/faq/content1121.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[関東支部]
・2024年度関東支部総会・講演会
2024年4月20日(土)14:00-16:45
場所:北とぴあ第2研修室.
講師:向山 栄氏(国際航業株式会社 公共コンサルタント事業部)
講演内容:数値地形画像を用いたダイナミックな地表面変位の可視化.
https://geosociety.jp/outline/content0201.html#2024sokai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
国際放射線防護委員会(ICRP)出版物ICRP Publication 142の邦訳版が完成し、
ICRPホームページから公開されました
邦題: 産業プロセスにおける自然起源放射性物質(NORM)に対する放射線防護
翻訳版URL: https://www.icrp.org/page.asp?id=506
原子力規制庁URL: https://www.nra.go.jp/activity/kokusai/honyaku_04.html
—---------------------------------------
防災学術連携体「令和6年能登半島地震・3ヶ月報告会」
3月25日(月)9:00-14:40
ZOOM webinar(定員500名・要申込)
Youtube(一般公開・申込不要)配信も予定
※日本地質学会「令和6年能登半島地震震源域の変動地形と海陸境界断層」
石山達也(東京大)発表予定
https://janet-dr.com/050_saigaiji/2024/050_240101_notohantou0325.html
2024年度第1回地質調査研修
主催:産総研コンソーシアム「地質人材育成コンソーシアム」
5月13日(月)- 5月17日(金)
場所:
(室内座学)茨城県つくば市(産総研)
(野外研修)茨城県ひたちなか市、福島県双葉郡広野町・いわき市周辺
※今回は特に企業の地質初心者が対象となります
定員:6名(定員になり次第締切)
参加費:84口(1口1000円)の会費が必要です.
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2024-1.html
(後)第61回アイソトープ・放射線研究発表会
7月3日(水)-5日(金)
会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
発表申込締切:2月29日(木)12時
https://www.jrias.or.jp/
令和6年能登半島地震・7ヶ月報告会
7月30日(火)13:00-17:00(予定)
オンライン開催
主催:防災学術連携体
https://janet-dr.com/index.html
★日本地質学会第131年学術大会(2024山形)
9月8日(日)-10日(火)
会場:山形大学小白川キャンパス
https://geosociety.jp/science/content0168.html(プレサイト)
(協)地盤技術フォーラム2024
9月18日(水)-20日(金)10:00−17:00
場所:東京ビックサイト・東ホール(江東区有明3丁目)
http://www.sgrte.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・深田地質研究所2024年度任期付き研究員募集(3/31)
・東京大学地震研究所共同利用2024年度大型計算機共同利用公募研究(5/31)
・JST先端国際共同研究推進事業2024年度 ASPIRE単独公募募集 (5/9)
※公募説明会(ウェビナー)3/22(金)要事前申込
・JST先端国際共同研究推進事業(ASPIRE) 2024年度日米NSF Global Centers
共同研究提案募集(6/11)
・東京地学協会令和6年度助成事業(調査・研究及び国際研究集会助成/普及・
啓発活動(出版)助成/普及・啓発活動(地学・地理クラブ活動)助成/
普及・啓発活動(地学・地理教育活動)助成(3/31or4/30)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】会員情報に変更があった場合は...
─────────────────────────────────
年度末に向け,所属先や自宅等の登録内容にご変更があった場合は,速やかに
情報の更新をお願い致します.情報の変更は,学会ホームページ「会員ページ」
にログインしていただければ,ご自身で登録内容が更新できます.
ご協力をよろしくお願い致します.
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
※初めてログインする方・パスワードをお忘れの方はこちらから
https://www.geosoc-member.jp/Member/fgform.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
2017愛媛
日本地質学会第124年学術大会(2017愛媛)巡検案内書
※それぞれの巡検案内書タイトルをクリックすると,J-STAGE上の原稿画面に遷移します.
A:松山市周辺の瀬戸内火山岩類 −高Mg安山岩から珪長質岩まで− 新正裕尚・齊藤 哲
B:四国西部の中央構造線断層帯の地形と地質 池田倫治・後藤秀昭・堤 浩之
C:白井孝明:室戸ユネスコ世界ジオパーク ※案内書原稿なし
D:黒瀬川構造帯の模式地と四国西部の秩父帯を巡る:四国西予ジオパーク 村田明広・郄橋 司
E:久万層群と三崎層群:日本海拡大期の西南日本弧前弧中新統が記録するもの 奈良正和・楠橋 直・岡本 隆・今井 悟
F:三波川帯トラバース:最浅部変成岩から最深部超苦鉄質岩まで 青矢睦月・水上知行・遠藤俊祐
G:岩国-柳井地域の領家帯: 島弧地殻における花崗岩質マグマの生成と流体の挙動 寺林 優・山本啓司・亀井淳志
H:関川の岩石鉱物 皆川鉄雄・佐野 栄
2016東京・桜上水
日本地質学会第123年学術大会(2016東京・桜上水)巡検案内書
※それぞれの巡検案内書タイトルをクリックすると,J-STAGE上の原稿画面に遷移します.
安全のしおり
丹沢山地の地質:伊豆衝突帯のジオダイナミクス 石川正弘, 谷 健一郎, 桑谷 立, 金丸龍夫, 小林健太
付加型沈み込み帯浅部の地質構造:房総半島南部付加体-被覆層システム 山本由弦, 千代延 俊, 神谷奈々, 濱田洋平, 斎藤実篤
関東山地北縁部の低角度構造境界 高木秀雄, 新井宏嘉, 宮下 敦
関東山地秩父帯北帯の地質 久田健一郎, 冨永紘平, 関根一昭, 松岡喜久次, 加藤 潔
関東平野南部における上総層群のテフロクロノロジー 鈴木毅彦, 白井正明, 福嶋 徹
房総半島南部沿岸の海岸段丘と津波堆積物に記録された関東地震の履歴 宍倉正展, 鎌滝孝信, 藤原 治
葉山-嶺岡帯トラバース 高橋直樹, 柴田健一郎, 平田大二, 新井田秀一
群馬県吾妻地域における中期中新世以降の火山岩類と変質 中村庄八, 藤本光一郎, 中山俊雄, 方違重治
伊豆半島南部の新第三系白浜層群に見られる浅海底火山活動と堆積・造構過程との相互作用 狩野謙一, 伊藤谷生
富士山山麓を巡る:火山地質から防災を考える 山元孝広, 高田 亮, 吉本充宏, 千葉達朗, 荒井健一, 細根清治
千葉市の昔の海岸線を歩く 米澤正弘
2015長野
日本地質学会第122年学術大会(2015長野)巡検案内書
※それぞれの巡検案内書タイトルをクリックすると,J-STAGE上の原稿画面に遷移します.
蓮華変成岩類と中生代陸成層 竹内 誠, 竹之内 耕, 常盤 哲也
長野盆地西縁の変動地形と活断層 杉戸 信彦, 廣内 大助, 塩野 敏昭
四阿火山:成層火山体の開析地形とその利用 竹下 欣宏, 西来 邦章, 富樫 均
和田峠黒曜岩と石器 牧野 州明, 高橋 康, 中村 由克, 向井 理史, 法橋 陽美, 津金 達郎
戸隠地域の新第三系−第四系と戸隠地質化石博物館 田辺 智隆
北部フォッサマグナ新第三系の斜面前進過程と堆積シーケンス 関 めぐみ, 保柳 康一
北アルプス鹿島槍ヶ岳-爺ヶ岳に露出する,直立した第四紀陥没カルデラ−黒部川花崗岩コンプレックス: 短縮テクトニクスによる傾動山脈隆起の典型例 原山 智
上高地盆地の地形形成史と第四紀槍・穂高カルデラ-滝谷花崗閃緑岩コンプレックス 原山 智
2014鹿児島
日本地質学会第121年学術大会(2014鹿児島)巡検案内書
※それぞれの巡検案内書タイトルをクリックすると,J-STAGE上の原稿画面に遷移します.
九州西部に分布するジュラ紀付加体と海溝斜面堆積物 尾上 哲治, 西園 幸久
甑島列島に分布する上部白亜系姫浦層群の層序と化石および堆積環境 小松 俊文, 三宅 優佳, 真鍋 真, 平山 廉, 籔本 美孝, 對比地 孝亘
日南海岸沿いの深海堆積相と重力流堆積物 石原 与四郎, 郄清水 康博, 松本 弾, 宮田 雄一郎
桜島火山 小林 哲夫, 佐々木 寿
九州中西部地域の変成岩類:黒瀬川構造帯・肥後変成帯・木山変成岩 小山内 康人, 中野 伸彦, 吉本 紋, 亀井 淳志
世界遺産の島・屋久島の地質と成り立ち 安間 了, 山本 由弦, 下司 信夫, 七山 太, 中川 正二郎
南九州,鹿児島リフトの第四系 内村 公大, 鹿野 和彦, 大木 公彦
霧島ジオパークと2011 年霧島山新燃岳噴火 井村 隆介, 石川 徹
Traces of paleo-earthquakes and tsunamis along the eastern Nankai Trough and Sagami Trough, Pacific coast of central Japan Osamu Fujiwara
2013仙台
日本地質学会第120年学術大会(2013仙台)巡検案内書
※それぞれの巡検案内書タイトルをクリックすると,J-STAGE上の原稿画面に遷移します.
2011年東北地方太平洋沖地震津波と869年貞観地震津波の浸水域と堆積物 菅原 大助, 箕浦 幸治
カルデラ縁辺などのリストリック正断層が再動した岩手・宮城内陸地震(M6.9)の地表地震逆断層 遅沢 壮一, 布原 啓史
仙台の大地の成り立ちを知る 宮本 毅, 蟹澤 聰史, 石渡 明, 根本 潤
南部北上帯長坂地域の先シルル紀基盤岩類・中部〜上部古生界と歌津-志津川地域のペルム系〜ジュラ系(付:ペルム系燐酸塩岩の産状) 永広 昌之, 森清 寿郎
中部ジュラ系〜下部白亜系相馬中村層群の層序と化石 竹谷 陽二郎, 遅沢 壮一
岩手県に分布する白亜系宮古層群および久慈層群の浅海〜非海成堆積物と後期白亜紀陸生脊椎動物群 梅津 慶太, 平山 廉, 薗田 哲平, 高嶋 礼詩
仙台南西部に分布する東北日本太平洋側標準層序としての中・上部中新統および鮮新統 藤原 治, 鈴木 紀毅, 林 広樹, 入月 俊明
蔵王火山 伴 雅雄
阿武隈山地東縁の石炭紀および白亜紀アダカイト質花崗岩類 土谷 信高, 大友 幸子, 武田 朋代, 佐々木 惇, 阿部 真里恵
北鹿地域における黒鉱鉱床と背弧海盆火山活動 山田 亮一, 吉田 武義
2012大阪
日本地質学会第119年学術大会(2012大阪)巡検案内書
※それぞれの巡検案内書タイトルをクリックすると,J-STAGE上の原稿画面に遷移します.
巡検案内図 A〜J班
山陰海岸におけるジオパーク活動 −大地と暮らしのかかわり− 先山 徹, 松原 典孝, 三田村 宗樹
兵庫県南東部,川西−猪名川地域の超丹波帯と丹波帯 菅森 義晃, 小泉 奈緒子, 竹村 静夫
和泉山脈西端部:和泉層群と中央構造線 宮田 隆夫, 安 鉉善, 猪川 千晶
中新世の室生火砕流堆積物 佐藤 隆春, 中条 武司, 和田 穣隆, 鈴木 桂子
古琵琶湖層群における新・旧鮮新−更新統の境界 里口 保文, 山川 千代美, 高橋 啓一
領家帯青山高原地域の変成岩類および花崗岩類 河上 哲生, 西岡 芳晴
紀伊半島西部の秩父帯・黒瀬川帯
紀州白亜系四万十帯美山層のメランジュ変形構造と温度圧力履歴 橋本 善孝
GISをつかってみよう 升本 眞二, 根本 達也
大阪の津波碑と地盤沈下対策 三田村 宗樹
2011水戸
日本地質学会第118年学術大会(2011水戸)巡検案内書
※それぞれの巡検案内書タイトルをクリックすると,J-STAGE上の原稿画面に遷移します.
日本最古の地層 —日立のカンブリア系変成古生層 田切美智雄, 廣井美邦, 足立達朗
筑波山周辺の深成岩と変成岩 高橋裕平, 宮崎一博, 西岡芳晴
磐梯・吾妻・安達太良:活火山ランクBの三火山 長谷川 健, 藤縄明彦, 伊藤太久
常磐地域の白亜系から新第三系と前弧盆堆積作用 安藤寿男, 柳沢幸夫, 小松原純子
棚倉断層の新第三紀テクトニクスと火山活動・堆積作用 天野一男, 松原典孝, 及川敦美, 滝本春南, 細井 淳
栃木の新第三系:荒川層群中部の層序と化石および大谷地域の応用地質学 松居誠一郎, 山本高司, 柏村勇二, 布川嘉英, 青島睦治
常陸台地の第四系下総層群の層序と堆積システムの時空変化 大井信三, 横山芳春
鬼怒川低地帯の第四紀テフラ層序 —火山噴火史と平野の形成史— 鈴木毅彦
伊豆地塊北端部,伊豆衝突帯の地質構造 小田原 啓, 林 広樹, 井崎雄介, 染野 誠, 伊藤谷生
地層を見る・はぎ取る・作る 伊藤 孝, 植木岳雪, 中野英之, 小尾 靖, 牧野泰彦
2010富山
日本地質学会第117年学術大会(2010富山)巡検案内書
※それぞれの巡検案内書タイトルをクリックすると,J-STAGE上の原稿画面に遷移します.
富山積成盆地,北陸層群の広域テフラと第四紀テクトニクス 田村糸子, 山崎 雄, 中村洋介
跡津川断層系の変動地形と断層露頭 竹内 章, 道家 涼介, ハス バートル
立山火山 中野 俊, 奥野 充, 菊川 茂
焼岳火山群の大規模ラハール堆積物と火砕流堆積物 及川 輝樹, 石崎 泰男, 片岡 香子
黒部川沿いの高温泉と第四紀黒部川花崗岩 原山 智, 高橋 正明, 宿輪 隆太, 板谷 徹丸, 八木 公史
年代学から見た飛騨変成作用から日本海誕生を経て今日に至るまでの包括的構造発達史 椚座 圭太郎, 清水 正明, 大藤 茂
富山県に分布する上部ジュラ〜下部白亜系手取層群の海成層と恐竜足跡化石 平澤 聡, 柏木 健司, 藤田 将人
糸魚川ジオパークの地質巡り 竹内 誠, 竹之内 耕, 中澤 努
糸魚川ジオパーク ヒスイ探訪ジオツアー 謎多きヒスイを多角的に楽しもう 宮島 宏
2009岡山
日本地質学会第116年学術大会(2009岡山)巡検案内書
※それぞれの巡検案内書タイトルをクリックすると,J-STAGE上の原稿画面に遷移します.
小豆島の瀬戸内火山岩類:水中火山活動とサヌキトイド 巽 好幸, 谷 健一郎, 川畑 博
四万十帯牟岐メランジュにみる沈み込み帯地震発生帯の変形と流体移動 山口飛鳥, 柴田伊廣, 氏家恒太郎, 木村 学
四国中央部三波川変成帯のテクトニクス 岡本和明, 青木一勝, 丸山茂徳
大山・大根島:山陰地方中部の対照的な第四紀火山 沢田順弘, 門脇和也, 藤代祥子, 今井雅浩, 兵頭政幸
秋吉石灰岩から読み取る石炭・ペルム紀の古環境変動 −美祢市(旧秋芳町)秋吉台科学博物館創立50周年記念巡検− 佐野弘好, 〓山哲男, 長井孝一, 上野勝美, 中澤 努, 藤川将之
香川県小豆島の花崗岩のラミネーションシーティングと小豆島石を訪ねて 藤田勝代, 横山俊治
成羽層群の炭層地すべり群−岩相と地史を反映したその構造特性 横田修一郎, 田中 元, 山田琢哉
岡山県東部周辺の舞鶴帯と超丹波帯 竹村静夫, 菅森義晃, 鈴木茂之
岡山市周辺の吉備高原に分布する古第三系「山砂利層」と海成中新統 鈴木茂之, 松原尚志, 松浦浩久, 檀原 徹, 岩野英樹
2008秋田
日本地質学会第115年学術大会(2008秋田)巡検案内書
※それぞれの巡検案内書タイトルをクリックすると,J-STAGE上の原稿画面に遷移します.
男鹿半島の火山岩相: 始新世〜前期中新世火山岩と戸賀火山 大口 健志, 鹿野 和彦, 小林 紀彦, 佐藤 雄大, 小笠原 憲四郎
男鹿半島−能代地域の地形と第四系 白石 建雄, 白井 正明, 西川 治, 鈴木 隼人, 古橋 恭子, 星 多恵子
地学教育の素材としての男鹿半島 藤本 幸雄, 林 信太郎, 渡部 晟, 栗山 知士, 西村 隆, 渡部 均, 阿部 雅彦, 小田嶋 博
出羽丘陵新第三系に発達する変形構造 西川 治, 奥平 敬元, 吉田 昌幸, 白石 建雄
鳥海火山 林 信太郎, 山元 正継
秋田県南部小安・秋の宮地域の地熱地質 高島 勲, 越谷 信
秋田県の珪藻土,パーライト,ゼオライト鉱床 村上 英樹, 村木 克行, 野口 泰彦, 鈴木 清貴
安家−久慈地域の北部北上帯ジュラ紀付加体 永広 昌之, 山北 聡, 高橋 聡, 鈴木 紀毅
北上山地前期石炭紀付加体「根田茂帯」の構成岩相と根田茂帯・南部北上帯境界 内野 隆之, 川村 信人, 川村 寿郎
北上山地に分布する古第三紀アダカイト質流紋岩〜高Mg安山岩と前期白亜紀アダカイト質累帯深成岩体 土谷 信高, 西岡 芳晴, 小岩 修平, 大槻 奈緒子
【資料:見学地点説明】小坂元山黒鉱鉱床の海底熱水鉱化作用と背弧海盆〜島弧の火山活動の特徴 水田 敏夫, 石山 大三
2007札幌
日本地質学会第114年学術大会(2007札幌)巡検案内書
※それぞれの巡検案内書タイトルをクリックすると,J-STAGE上の原稿画面に遷移します.
鮮新世溶岩台地縁辺の地すべり地形:手稲山山体崩壊と天狗岳地すべり 宮坂 省吾, 山崎 茜, 岡村 聡, 英 弘, 石井 正之, 小板橋 重一
日高衝突帯下部地殻の岩石構成と変形運動 小山内 康人, 大和田 正明, 豊島 剛志
北海道中央部の活断層と大規模地すべり地形 田近 淳, 小板橋 重一, 大津 直, 廣瀬 亘, 川井 武志
十勝平野の下部更新統の堆積相と水理地質 高清水 康博, 岡 孝雄
北海道駒ヶ岳火山の噴火履歴 吉本 充宏, 宝田 晋治, 高橋 良
忍路・積丹半島の水底火山活動と岩盤崩壊 岡村 聡, 永田 秀尚
深部付加体としての神居古潭変成岩類の原岩層序・付加プロセス・変形変成作用および流体−岩石相互作用 榊原 正幸, 安元 和己, 池田 倫治, 太田 努
北海道北部,幌延地域における後期鮮新世以降の古地理と地質構造発達史 新里 忠史, 舟木 泰智, 安江 健一
海山沈み込みに伴う前弧域の発達過程と固体物質循環 植田 勇人
北の町の地質系博物館めぐり〈北海道横断編〉 櫻井 和彦, 臼杵(小野) 昌子, 古沢 仁, 加納 学, 東 豊土, 澤村 寛
幌満かんらん岩体の層状構造とその起源 新井田 清信, 高澤 栄一
蝦夷前弧堆積盆の海陸断面堆積相変化と海洋無酸素事変層準:夕張〜三笠 安藤 寿男, 栗原 憲一, 高橋 賢一
地質学のふるさと夕張:石炭形成とその前後の時代の地層 保柳 康一, 川上 源太郎, 宮坂 省吾
第15回_優秀01
第15回惑星地球フォトコンテスト入選作品
優秀賞:道東太平洋岸の特異な地質と固有のナガコンブ
写真:平野直人(宮城県・日本地質学会会員)
撮影場所:北海道 浜中町 恵茶人(えさしと)
【撮影者より・地質学的解説】
玄武岩が海底堆積物(後期白亜紀の砂泥互層)を覆っています.この固い岩石は道東の釧路町から根室半島〜歯舞群島にかけて海岸沿いに露出し,岬や湾をつくりだしています.周囲の海底には岩礁ができ,そこにナガコンブが生育します.道東太平洋沿岸特有の種であるナガコンブは海底の岩場を足場として生長し,15mを超える長さのものもあります.前弧にもかかわらず海岸沿いになぜか分布する固い玄武岩の地質ならではの景色です.
【審査委員長講評】
Webで投稿された写真は2L判にプリントされて審査され,残された作品はパソコンのモニター上で優劣が競われ,賞が決定します.この作品は2L判の審査時にはやや印象が薄かったのですが,大型モニターでは手前のナガコンブの質感,遠景の成層する玄武岩と砂泥互層の対比が素晴らしく,現場に立ったような気分になりました.やや古い作品でしたが,来年は新作に期待します.
目次へ戻る
【geo-Flash】No.615 2024年「地質の日」行事のご案内
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.615 2024/4/2┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2024年「地質の日」行事のご案内
【2】第4回JABEEシンポジウム:YouTube公開中
【3】令和6年度大学入試共通テストの地学関連科目に関する意見書
【4】支部のお知らせ
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
【7】会員情報に変更があった場合は...
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2024年「地質の日」行事のご案内
──────────────────────────────────
2024年の「地質の日」に関連した日本地質学会主催,共催,後援等の催しを
ご紹介します。
惑星地球フォトコンテスト第15回ほか入選作品展示会/「地質の日」オンライン
一般講演会令和6年能登半島地震による地殻変動と地盤災害/街中ジオ散歩
in Tokyo「身近な地形・地質から探る麻布の歴史と湧水」/講演会「デジタル
詳細地形データを用いた地表面変位計測で見る地震災害」/第41回地球科学
講演会「日本列島の起源と大和構造線」/石の魅力大発見!〜見て・触って・
知ってみよう〜/「地質の日」企画 身近に知る「くまもとの大地」ほか
詳しくは,https://geosociety.jp/name/content0179.html
このほか,地質学会以外の全国の地質の日イベント情報はこちら
https://www.gsj.jp/geologyday/2024/index.html(地質の日事業推進委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第4回JABEEシンポジウム:YouTube公開中
──────────────────────────────────
第4回JABEEシンポジウム 大学縮小危機のなかで、社会の要求にどのように応える
かーJABEEを活用した技術者の育成と輩出ー
3月3日に標記のシンポジウムを開催しました.シンポジウムの内容(動画)は,
YouTubeで公開中です.ご参加いただけなかった皆様もぜひご覧ください.
https://youtu.be/dxBQmdgLf3c?feature=shared
プログラム,要旨PDFは学会HPでご覧いただけます.
https://geosociety.jp/science/content0167.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】令和6年度大学入試共通テストの地学関連科目に関する意見書
──────────────────────────────────
独立行政法人大学入試センターへ,令和6年度大学入試共通テストの
地学関連科目に関する意見書を提出しました.
全文はこちら,https://geosociety.jp/engineer/content0074.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[関東支部]
・2024年度関東支部総会・講演会
2024年4月20日(土)14:00-16:45
場所:北とぴあ第2研修室.
講師:向山 栄氏(国際航業株式会社 公共コンサルタント事業部)
講演内容:数値地形画像を用いたダイナミックな地表面変位の可視化.
https://geosociety.jp/outline/content0201.html#2024sokai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)ジオパーク巡回展「地球時間の旅」
現在の開催地:フォッサマグナミュージアム
開催期間:2024年3月2日(土)-4月21日(日)
https://earthtime-journey.geopark.jp/
※全国各地で開催予定!
2024年度第1回地質調査研修
主催:産総研コンソーシアム「地質人材育成コンソーシアム」
5月13日(月)- 5月17日(金)
場所:
(室内座学)茨城県つくば市(産総研)
(野外研修)茨城県ひたちなか市、福島県双葉郡広野町・いわき市周辺
※今回は特に企業の地質初心者が対象となります
定員:6名(定員になり次第締切)
参加費:84口(1口1000円)の会費が必要です.
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2024-1.html
第33回地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン 第1-4/全8回)
5月17日(金)10:00-17:30
内容:健全な水循環と地下水/土壌汚染状況調査の流れと調査や対策の制約・難しさについて/地質汚染調査入門
参加費:無料(事前登録制)CPD:6単位
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
第33回地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン 第5-8/全8回)
5月24日(金)10:00-17:30
内容:地質汚染調査・土壌汚染状況調査概論/地質汚染調査におけるボーリング調査/地下水汚染調査
参加費:無料(事前登録制)CPD:6単位
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
第33回地質汚染調査浄化技術研修会(現地研修(1)ボーリングコア研修)
6月1日(土)10:00-17:00
会場:千葉市文化センター 5階セミナー室
内容:ボーリングコア・地質の記載/柱状図の作成
参加費:当NPO会員・賛助会員:9,000円 /非会員:12,000円
CPD:5単位 定員:30名
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm
(後)第61回アイソトープ・放射線研究発表会
7月3日(水)-5日(金)
会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
発表申込締切:2月29日(木)12時
https://www.jrias.or.jp/
令和6年能登半島地震・7ヶ月報告会
7月30日(火)13:00-17:00(予定)
オンライン開催
主催:防災学術連携体
https://janet-dr.com/index.html
★日本地質学会第131年学術大会(2024山形)
9月8日(日)-10日(火)
会場:山形大学小白川キャンパス
https://geosociety.jp/science/content0168.html(プレサイト)
(協)地盤技術フォーラム2024
9月18日(水)-20日(金)10:00−17:00
場所:東京ビックサイト・東ホール(江東区有明3丁目)
http://www.sgrte.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・(公社)東京地学協会事務局長(嘱託職員)公募(4/12)
・JAMSTEC変動海洋エコシステム高等研究所(WPI-AIMEC) AIMECポスト
ドクトラル研究員公募(5/17)
・東京地学協会令和6年度助成事業 普及・啓発活動(地学・地理クラブ活動)
助成/普及・啓発活動(地学・地理教育活動)助成(4/30)
・令和6年度下仁田ジオパーク学術奨励金募集(4/25)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】会員情報に変更があった場合は...
─────────────────────────────────
年度末に向け,所属先や自宅等の登録内容にご変更があった場合は,速やかに
情報の更新をお願い致します.情報の変更は,学会ホームページ「会員ページ」
にログインしていただければ,ご自身で登録内容が更新できます.
ご協力をよろしくお願い致します.
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
※初めてログインする方・パスワードをお忘れの方はこちらから
https://www.geosoc-member.jp/Member/fgform.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash[at]geosociety.jp)へお送りください.
第15回_ジオ鉄
第15回惑星地球フォトコンテスト入選作品
ジオ鉄賞:夜明けの大山
写真:藤森俊多(島根県)
撮影場所:鳥取県米子市今在家 JR伯備線(岸本〜伯耆大山間)
【撮影者より】
澄み切った秋の朝,空に大山のシルエットが美しく浮かび上がりました.一晩かけて伯備線を越えてきたEF64牽引の貨物列車が伯耆大山駅へと滑り込みます.
【講評・解説】
岡山県倉敷市の倉敷駅と鳥取県米子市の伯耆大山駅を結ぶ伯備線.はるばる関西,山陽方面からきた貨物列車は中央分水界の谷田峠(たんだだわ)を越えて大山の山麓を日本海へ向かって走ります.見る角度で変わる特徴的な大山の山容は,約2万年前まで続いていた火山活動による溶岩ドームや火砕流堆積物,その後の山体崩壊によるもの.作品は伯耆富士の由縁である円錐のなめらかな西側斜面と,荒々しい凹凸のある稜線が際立つ北側の尾根が逆光で重なり映し出されています.幻想的な秋暁の一瞬を捉えた秀作です.(藤田勝代:深田研ジオ鉄普及委員会)
目次へ戻る
第15回_スマホ賞
第15回惑星地球フォトコンテスト入選作品
スマホ賞:離島の夏
写真:澤 健二(島根県)
撮影場所:島根県隠岐郡海士町豊田
【撮影者より】
島根県の隠岐諸島,中ノ島の海士町にある明屋海岸.隠岐諸島はユネスコ世界ジオパークの認定地のひとつ.この海岸にはキャンプ場があり,島民や観光客にも親しみ深い場所となっている.神がお産をしたとされる神話の伝承地でもある.
【審査委員長講評】
隠岐諸島のジオサイトは赤壁が有名で,多くの写真が撮影されています.しかし自分で魅力的な場所を探し出してアングルを工夫して撮ることが撮影の醍醐味です.赤い火山噴出物,植生の緑,青空と白い雲.バランスがよく,気持ち良い作品となっています.
【地質解説】
赤褐色の約60mの海食崖は,後期鮮新世(約280万年前)にアルカリ玄武岩質マグマが噴出してできた火山砕屑物の地層でできています.この海岸一円は火山の噴出源であったとみられ,マグマが急激に膨張し破砕されてできたスコリアが直径約1kmのスコリア丘(明屋スコリア丘とよばれる)をなしていました.火山弾や溶岩の破片が溶結したアグルチネート(岩滓集塊岩)も見られます.赤色は噴出物に含まれる鉄が酸化したためであり,空と海の青さと相まって一層引き立った景観をなしています.(野村律夫:島根半島・宍道湖中海ジオパーク)
目次へ戻る
【geo-Flash】 No. 616 2024年「地質の日」行事 各地で目白押し!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.616 2024/4/16┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2024年「地質の日」行事のご案内
【2】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【3】支部のお知らせ
【4】その他のお知らせ
【5】公募情報・各賞助成情報等
【6】災害に関連した会費の特別措置
【7】会員情報に変更があった場合は...
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2024年「地質の日」行事のご案内
──────────────────────────────────
2024年の「地質の日」に関連した日本地質学会主催,共催,後援等の催しを
ご紹介しています。
惑星地球フォトコンテスト第15回ほか入選作品展示会/「地質の日」オンライン
一般講演会令和6年能登半島地震による地殻変動と地盤災害/街中ジオ散歩
in Tokyo「身近な地形・地質から探る麻布の歴史と湧水」/講演会「デジタル
詳細地形データを用いた地表面変位計測で見る地震災害」/第41回地球科学
講演会「日本列島の起源と大和構造線」/石の魅力大発見!〜見て・触って・
知ってみよう〜/「地質の日」企画 身近に知る「くまもとの大地」ほか
詳しくは,https://geosociety.jp/name/content0179.html
<オンライン講演会のパブリック・ビューイングを開催しませんか?>
オンライン講演会はYouTubeライブで一般に公開します。博物館やジオパーク
などでぜひパブリック・ビューイングを開催してください。申請は不要です。
開催後、開催した旨を事務局にご報告ください。たくさんの方にご覧いただ
けるよう,ご協力をお願いいたします。
このほか,地質学会以外の全国の地質の日イベント情報はこちら
https://www.gsj.jp/geologyday/2024/index.html(地質の日事業推進委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
新しい論文が公開されています.
■地質学雑誌
(論説)活断層と非活断層が持つ断層ガウジと滑り面での微細構造比較:山口県
北東部,渡川地域での事例研究:相山光太郎ほか/(レター)福島県いわき市に
分布する上部白亜系双葉層群足沢層産イノセラムス科二枚貝とその地質学的意義
:特にチューロニアン/コニアシアン階境界付近について:猪瀬弘瑛ほか/(論説)
複合面構造と応力逆解析による断層の運動履歴および応力史の推定:塩ノ平断層
と車断層への適用例:酒井 亨ほか
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/-char/ja(※4/17公開予定)
■ Island Arc
Characterization of serpentinization in olivine‐orthopyroxene‐H2O system
revealed by thermogravimetric and multivariate statistical analyses:
Atsushi Okamoto et al
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
※学会HP「会員ページ」(要ログイン)からアクセスすることで,IARは全文無料
で閲覧できます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[関東支部]
・2024年度関東支部総会・講演会
2024年4月20日(土)14:00-16:45
場所:北とぴあ第2研修室.
講師:向山 栄氏(国際航業株式会社 公共コンサルタント事業部)
講演内容:数値地形画像を用いたダイナミックな地表面変位の可視化.
https://geosociety.jp/outline/content0201.html#2024sokai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)ジオパーク巡回展「地球時間の旅」
現在の開催地:フォッサマグナミュージアム
開催期間:2024年3月2日(土)-4月21日(日)
https://earthtime-journey.geopark.jp/
※全国各地で開催予定!
学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた国の方針に関する説明会
主催:内閣府科学技術・イノベーション推進事務局
第1回 4月25日(木) 17:30-18:00
第2回 4月26日(金) 17:30-18:00
対象:一般公開(特に、学術団体、大学、研究機関等に所属する研究者・
URA・図書館関係者、事務職員、その他学術論文等の即時オープンアクセス
にご関心がある方)
https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20240415.html
(後)第61回アイソトープ・放射線研究発表会
7月3日(水)-5日(金)
会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
https://www.jrias.or.jp/
令和6年能登半島地震・7ヶ月報告会
7月30日(火)13:00-17:00(予定)
オンライン開催
主催:防災学術連携体
https://janet-dr.com/index.html
(後)科学教育研究協議会 第70回全国研究大会・いわて花巻大会
8月7日(水)-9日(金)
会場:花巻市立花巻中学校/花巻市立若葉小学校/花巻市文化会館
(岩手県花巻市若葉町)
https://kakyokyo.org/
★日本地質学会第131年学術大会(2024山形)
9月8日(日)-10日(火)
会場:山形大学小白川キャンパス
https://geosociety.jp/science/content0168.html(プレサイト)
(協)地盤技術フォーラム2024
9月18日(水)-20日(金)10:00−17:00
場所:東京ビックサイト・東ホール(江東区有明3丁目)
http://www.sgrte.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
産業技術総合研究所地質調査総合センター2024年度第1回研究職公募(5/8)
千葉大学大学院理学研究院地球科学研究部門准教授又はテニュアトラック助教
公募(5/31)
2025-2026年開催藤原セミナーの募集(7/31)
第15回(令和6年度)日本学術振興会育志賞受賞候補者の推薦(学会締切5/15)
住友財団2024年度研究助成公募(6/30)
2024年度「深田賞」募集(6/30)
人間文化研究機構第6回(2024年)日本研究国際賞の推薦(学会締切6/10)
令和6年度栗駒山麓ジオパーク学術研究等奨励事業募集(5/10)
令和6年度秋田県ジオパーク研究助成事業(5/31)
旭川市地域おこし協力隊(ジオパーク専門員)募集(随時)
令和6年度 隠岐ユネスコ世界ジオパーク学術奨励事業の募集(新規募集4/29)
令和6年度 糸魚川ジオパーク学術研究奨励事業募集(5/31)
令和6年度豊後大野ジオパーク学術研究・調査活動助成募集(5/31)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】災害に関連した会費の特別措置
─────────────────────────────────
日本地質学会では,災害救助法適用地域で被災された会員の方々のご窮状
をふまえ,「日本地質学会に届出の住居または勤務地が災害救助法適用地域
に該当する会員のうち,希望する方」は当年度の会費を免除いたします.
希望される方は,学会事務局までお申し出ください.
https://geosociety.jp/outline/content0239.html#saigai
(参考)内閣府HP:災害救助法の適用状況
https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】会員情報に変更があった場合は...
─────────────────────────────────
年度末に向け,所属先や自宅等の登録内容にご変更があった場合は,速やかに
情報の更新をお願い致します.情報の変更は,学会ホームページ「会員ページ」
にログインしていただければ,ご自身で登録内容が更新できます.
ご協力をよろしくお願い致します.
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
※初めてログインする方・パスワードをお忘れの方はこちらから
https://www.geosoc-member.jp/Member/fgform.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
第15回_優秀02
第15回惑星地球フォトコンテスト入選作品
優秀賞:龍うねる
写真:門脇正晃(島根県)
撮影場所:島根県松江市鹿島町手結(たゆ)
【撮影者より】
島根半島・宍道湖中海ジオパークに属する島根半島の鹿島町手結にあるスランプ褶曲です.まるで龍がうねるような異様な形状をした地層に太古の地球内部の力のうねりを感じます.
【審査委員長講評】
多く応募作品が地質や地形を遠くから撮影しているのに対して,この作品は地層そのものの面白さを正面からクローズアップで取り組んでいるのが評価されました.このスランプ層だけが彩色されているのは教育として,あるいは芸術として誰がどうやって彩色したのでしょうか.
【地質解説】
このスランプ褶曲は,新第三紀中新世(約1600万年前)の成相寺層に見られるもので,海底堆積物が深海の海底斜面を流れ下ったときにできたものです.火山砕屑岩に挟まれるようにできた水平距離6m,高さ1.7mの紡錘形をした空間に長さ22mの泥岩層が幾重にも屈曲して詰まっている景観は,確かに異様な形状です.この成因は高密度の土石流の中で可塑性の粘土層が急停止したことによるものです.探訪者の多くが驚きの声を上げるジオサイトです.(野村律夫:島根半島・宍道湖中海ジオパーク)
目次へ戻る
第15回_ジオパーク
第15回惑星地球フォトコンテスト入選作品
ジオパーク賞:切通し
写真:島村哲也(茨城県・日本地質学会会員)
撮影場所:東京都 大島町元町字赤禿
【撮影者より】
8月20日(日)晴れ.夜行船で伊豆大島に来島.午前中は日の出浜で海水浴.お昼は岡田港で名物料理,農産物直売所でソフトクリームを頂きました.午後は赤禿や郷土資料館の見学.写真は赤禿でのスナップショットです.翌日には三原山登山にお鉢回り,弘法浜で流れるプール.最終日は動物園,筆島,ボムサッグ,地層切断面を見学しながら島内一周.半分巡検のようになってしまいましたが,伊豆大島を満喫することができました.
【審査委員長講評】
赤禿は大島西海岸にあるスコリアが積み重なった地層で,遊歩道が続いています.青空,露頭の切りとり方,少女の配置などに気配りが感じられる清々しい作品です.娘さんはこの写真を撮るために何回もこの前を歩かされてたのでは・・・.作者は1泊2日で大島に行かれたとのことですが,旅行の雰囲気もよく伝わってきます.
【地質解説】
伊豆大島には中央火口丘の三原山のほかにも北北西‐南南東方向に多数の側火山が分布しており,赤禿(あかっぱげ)もその一つで約3400年前に噴出したスコリア丘からなります.切通しの断面からは溶岩のしぶきが高温酸化して降り積もっていった様子を間近で観察することができます.赤禿では採掘や海食で元のスコリア丘の形は残されていませんが,展望台からは対岸にスコリア丘の形が残っている大室山を見ることができます.(撮影者本人)
目次へ戻る
第15回_会長賞
第15回惑星地球フォトコンテスト入選作品
日本地質学会会長賞:空撮で捉えた付加体の覆瓦構造
写真:木村克己(茨城県・日本地質学会会員)
撮影場所:奈良県 紀伊山地,大台ヶ原上空からの空撮 2023年2月下旬撮影
【撮影者より・地質学的解説】
空撮は大峰山脈北部の大普賢岳(写真中央)から山上ヶ岳(写真右)にいたる険しい大峯奥駈道を捉えています.この経路は四万十帯の付加堆積岩の上位に仏像構造線を介して低角度の構造で衝上する秩父帯の付加堆積岩を縦断しています.写真中央の鋸状の稜線(標高1780mの大普賢岳)の急崖斜面には,北に緩く傾斜した濃淡の縞状構造がくっきりと認められます.黒色の帯は急崖をなし針葉樹林で覆われたチャート層,灰白色の帯は平滑な斜面で落葉広葉樹下の雪を被った砂岩層にそれぞれあたります.この縞状構造は秩父帯のチャート・砕屑岩が付加される際に形成された覆瓦状構造を表現しています.(木村克己:(公財)深田地質研究所)
【審査委員長講評】
日本アルプスなど3000m級の山々では遠方から地質構造がわかりますが,標高2000m以下の山々でもこのような地質構造が見えることは知りませんでした.作者の地質の専門的な知識と撮影時期や方向の選び方など撮影技術の賜物と感心させられます.
【補足説明・参考文献】
※クリックすると大きな画像をご覧いただけます
大和大峯研究グループ(2005)地球科学59 巻 5 号 287-300
木村・八木(2023)深田研年報,24号,63-86
目次へ戻る
第15回_大学生賞
第15回惑星地球フォトコンテスト入選作品
大学生・大学院生賞:草千里
写真:古田大樹(東京都)
撮影場所:熊本県阿蘇郡阿蘇市草千里ヶ浜
【撮影者より
阿蘇・草千里ヶ浜に訪れた際に撮影しました.カルデラの中とは思えないほどの雄大な地形で,人がとても小さく見えます.どれだけの規模の火山活動があったのでしょうか.そこで,地面に目を向けると,特徴的な地形や地層があることに気づきます.火山活動は,プレートやマントル,さらに地球全体の気候にも関わります.そのような全球規模の現象の手がかりを,手に取れる石や地層から得られるのは,地学の大きな魅力の一つです.
【審査委員長講評】
草千里は直径1kmの軽石丘で,草原の中に雨水を湛えた池の構図が一般的ですが,本作品は山焼きが終わったばかりの黒々とした草千里が意表を突きます.そのため観光客の姿がはっきりわかり,草千里の広がりがわかります.意外性のある作品です.
【地質解説】
写真は阿蘇観光の中心地のひとつ,草千里ヶ浜火口の中心部を大胆に切り取っており,火口の全景は収まっていません.奥の山は烏帽子岳で,山頂部は草千里ヶ浜火口が噴出した軽石でできています.この軽石は高温のうちに厚く積み重なったため,強く溶結していますが,その様子は草千里ヶ浜に転石があり観察できます.人がいる平らな丘は,草千里ヶ浜火口ができた後で噴出した溶岩からなり,駒立山と呼ばれます.駒立山の左側が切り立っているのは,駒立山の形成後に左手で噴火が発生して火口が形成されたためです.つまり,草千里ヶ浜は少なくとも2回の噴火をしており,駒立山は後の噴火の火口壁となっているのです.(萬年一剛:神奈川県温泉地学研究所)
目次へ戻る
第15回_入選01
第15回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:大地の目覚め
写真:村上 真(岩手県)
撮影場所:岩手県 八幡平市 焼走り溶岩流
【撮影者より】
この写真は岩手県八幡平市にある「焼走り(やけはしり)溶岩流」で撮影しました.このエリアは1732年に岩手山が噴火した時の形成されたもので黒く固まった熔岩があたり一面に広がっている光景が特徴的です.中でも本格的な冬が訪れる直前の11月,放射冷却現象が特に強く見られる日にはこうして溶岩の表面にびっしりと霜が降りて普段と違った姿を見せてくれます.
【審査委員長講評】
焼走り溶岩は約300年前の噴火で噴出したアア溶岩ですが,表面には植生も少なく,噴火当時の様子が残された場所です.日の出の写真なので普段ならば逆光で面白みのない写真になってしまいがちですが,アアクリンカーに霜がついて立体的な奥行きのある作品となっています.正面の松にかかる太陽,左奧の山など構図的には申し分ありません.
【地質解説】
焼走り溶岩は,1732年の噴火で岩手山の中腹に形成された火口列から流出しました.SiO2が約53%の玄武岩質安山岩で,流下距離は約3 km,末端付近での溶岩流の幅は約1 km程度と,必ずしも大きい溶岩流とはいえませんが,噴火から300年を経ても植生がほとんどなく,噴火直後の様子を今にとどめています.写真に見えるように,この溶岩流の表面はゴツゴツとした岩塊,クリンカで覆われます.表面がクリンカで覆われる形態の溶岩をアア溶岩と呼びます.(萬年一剛:神奈川県温泉地学研究所)
目次へ戻る
第15回_入選02
第15回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:未来に残したい惑星地球の情景
写真:水口和史(福岡県)
撮影場所:宮崎県 宮崎市 内海海岸 イルカ岬
【撮影者より】
鬼の洗濯岩で有名な宮崎市の青島周辺から日南海岸にかけては浸食で変わった表情をした海岸が見られますがここも同じく海岸岩が長い年月をかけて波に浸食されて惑星の表面ような岩の表情となったのではと思います.ほぼ暗い夜に撮影した場所は偶然にも宇宙人の顔みたいな岩があったり面白いうねりをした岩の表情があったりと宇宙の惑星に来たような感じでした.
【審査委員長講評】
最初見た時には,何処で何を撮ったのか頭が混乱しました.解説を読むと鬼の洗濯板のある青島のすぐ近くということですが,どのような堆積物がどのよう に侵食されるのかこんな地表が現れるのか興味津々です.右側からのライティングが効果的でした.
【地質解説】
宮崎県の日南海岸沿いには,新第三系宮崎層群青島層の砂岩泥岩互層が分布します.この互層は前孤海盆の半深海域にもたらされた混濁流による砂岩とバックグラウンドとして堆積した泥岩からなります.青島層にはしばしば厚い砂岩層が挟まれていますが,いるか岬のものは特に厚く,ケスタ地形をなします.これらの厚い砂岩は無構造であることが多いですが,様々なサイズや形態からなるタフォニや節理に沿った風化が認められます.(石原与四郎:福岡大学理学部地球圏科学科)
目次へ戻る
第15回_入選03
第15回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:南中国の褶曲
写真:余 金霏(東京都)
撮影場所:中国 雲南省 昆明市 東川区 昆明の最高峰「雪嶺」と「白石岩」の間の断崖絶壁,夏の北側から撮影.(最高海抜は4344.1m)
【撮影者より・地質解説】
雄大な断層と褶曲があり,それは雲南省の省都昆明市の東川区に位置し,北側から昆明の最高峰である"雪岭"(4300メートル)の東側の断崖から撮影されています. この壮大な断崖は,中元古代の堆積岩(写真の褶曲部分,主に白雲岩)が新古代の構造運動(晋宁運動, 10-8 億年)によって形成されました.これらの運動は楊子プレート(South China Craton)の形成をもたらしまし た,私たちは夏の盛りの日にここに来ましたが,標高4100メートルのため,環境は過酷で,非常に寒冷でした.しかし,雲や霧の中の景色は目を見張るものがあり,地質運動の壮大さを感じさせてくれました.
【審査委員長講評】
中国は広い国なので砂漠から高山まで様々な地質・地形が見られます.原生代の地層の重なりがこのようにくっきり見られるとは羨ましいことです.中央の山 腹を横切る筋は山道でしょうか.スケール感を感じさせる作品です.山頂に雲がかかっているのは惜しかった.
目次へ戻る
第15回_入選(中高生)
第15回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:褶曲
写真:福本朝陽(神奈川県)
撮影場所:三重県志摩町御座
【撮影者より】
地元の方にもあまり知られていないという,御座の褶曲.随分行きにくい場所にあるが,一見の価値がある.
【審査委員長講評】
日本では植生に覆われていない海岸が良い露頭の撮影場所となります.この写真では遠方の露頭まで植生がほとんどなく,地面もゴミ1つない小石の覆われた浜で非常に気持ちのよい作品となっています.ただ太陽光が弱く,やや露頭の力強さに欠けているのが残念です.
【地質解説】
三重県南部の先志摩半島の南岸には,上部白亜系の四万十帯に属する的矢層群の砂岩泥岩互層が露出しています.写真中の暗色部が泥岩,明色部が砂岩からなります.写真中央の泥岩卓越部では地層が激しく褶曲していますが,上部の砂岩卓越部ではそれほどでもないように見えます.このことから,この褶曲は地殻変動によって形成された“褶曲”ではなく,堆積物が未固結時に変形することで形成された“スランプ褶曲”であると思われます.(栗原行人:三重大学)
目次へ戻る
第14回_佳作1-3
第14回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:断崖と白亜の灯台
写真:朝永武志(長崎県)
撮影場所:長崎県佐世保市
【撮影者より】
高さ100mに届くかと言う断崖に建つ白亜の灯台カッコイイですね!
目次へ戻る
佳作:地球の吐息
写真:横江憲一(北海道)
撮影場所:北海道 雌阿寒岳 札幌市白石区
【撮影者より】
雌阿寒岳の中マチネシリ河口を中心に背景に雄阿寒岳、阿寒湖が見えています。中マチネシリはデイサイトや安山岩を主体としており、約2万年前から数回の噴火を繰り返しています。普段は、火口からここまでの水蒸気は見えませんが、気温がマイナス10℃、ほぼ無風状況により、噴煙口がはっきり見えました。
目次へ戻る
佳作:湖底の朝
写真:宮田敏幸(兵庫県)
撮影場所:岡山県苫田郡鏡野町上齋原 恩原湖
【撮影者より】
晩秋になると湖の水は放水され渇水状態となる。今まで水で見えなかった湖底が現れ、その時から草が生え始める。水の流入があるので、それが小川のように見える。朝は時として霧が発生して、朝陽に赤く染まる。 幻想的な赤い世界が広がる。
目次へ戻る
第14回_佳作4-6
第14回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:吸い込まれそう
写真:市谷和也(埼玉県)
撮影場所:埼玉県比企郡嵐山町,荒川水系槻川,嵐山渓谷付近
【撮影者より】
埼玉県比企郡嵐山町の嵐山渓谷付近にある「遠山甌穴」です.岩畳の景観を形成する三波川帯の結晶片岩が見事に穿たれ,吸い込まれそうな造形をしています.埼玉県の岩畳といえば長瀞が有名ですが,ここ嵐山渓谷にも見事な岩畳が広がっています.
目次へ戻る
佳作:迫り上る大地
写真:遠藤悠一(茨城県)
撮影場所:宮城県 南三陸町寺浜 神割崎の海岸付近
【撮影者より】
宮城県南三陸町の神割崎付近(三陸ジオパーク)の離れ小島をドローンで撮影しました.この周辺では前期三畳紀に海で形成された地層が広くみられます.撮影した露頭は,世界最古級の魚竜(ウタツサウルス)が発見されたことでも有名な,大沢層です.海成層である大沢層が,2億5千万年の時を経て,海からせりあがって大地となる瞬間を捉えたかの様な気持ちになりました.
目次へ戻る
佳作:湘南好日
写真:後藤文義(神奈川県)
撮影場所:神奈川県鎌倉市腰越:江ノ電(腰越〜鎌倉高校前駅)
【撮影者より】
22年11月はじめ、江ノ島ヨットハーバーから小動岬の隆起波食台をメインに、走行する江ノ電とヨットを待ち、シャッターを切りました。
目次へ戻る
第14回_佳作7-9
第14回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:遼遠の時を経て
写真:石原孝陽(神奈川県)
撮影場所:神奈川県三浦市三崎町城ヶ島
【撮影者より】
三浦半島には海底地滑りの証拠や褶曲、断層などの惑星地球のダイナミックな活動の証拠が数多く存在します。その中でも城ヶ島は数多のジオサイトがあります。そんな城ヶ島で日が沈み、星々と富士山、そして遼遠の月日を経てその姿を見せている地層の模様の美しさを、一つの写真に取り入れ、地球の大地が有する美しい自然を表しました。
目次へ戻る
佳作:波にも負けず
写真:福村成哉(和歌山県)
撮影場所:和歌山県那智勝浦町浦神半島先端部(耳の鼻)
【撮影者より】
和歌山県那智勝浦町浦神半島の先端「耳の鼻」にある洞窟です。堆積岩が固く変質しており、北東-南西方向に貫通しています。湾になった内海と太平洋の外海をつなぐように貫通しているため、素潜りを行う漁師さんは今でもこの洞窟を通り抜けて外海と内海を行き来しています。
目次へ戻る
佳作:朱、一点
写真:坂内愛莉(長崎県)
撮影場所:長崎県五島市岐宿町大川原のニタン
【撮影者より】
岐宿町の山奥。清流・清滝を魚が登り、深緑美しく苔生す。そこに“朱”の紅葉が落ちる。神秘的に、水と時が流れる場所“ニタン”。ニタンという地名は、かつて川の奥に二反の水田があり、その水田に水を引くために渓流を塞ぎ、池のようにして水を貯めたことに由来するとのこと。岐宿町は、米の産地としても有名。古くからの地形を生かし、現在まで続く稲作文化。私も岐宿のお米をいただいています。今日も大事に「いただきます。」
目次へ戻る
第15回_佳作4-6
第15回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:迫り出す地層
写真:朝永武志(長崎県)
撮影場所:長崎県佐世保市小佐々町楠泊
【撮影者より】
斜めに地層が迫り出してきている場所.海岸を奥へと進むだけで年代をドンドン遡れます。まるでマイムマシンの様。奥へ行くと貝などの化石や当時生息していた動物の足跡迄残っていて興味深い海岸です。
目次へ戻る
佳作:神様のお遊び
写真:指田丈二(茨城県)
撮影場所:兵庫県豊岡市竹野町 はさかり岩展望台
【撮影者より】
とても大きな球体の岩が尖った2つの岩に間に挟まっています。自然に出来たとは思えない…きっと神様のお遊びなのだと思うのです。
目次へ戻る
佳作:分水嶺
写真:三浦大輝(新潟県)
撮影場所:群馬県・新潟県谷川連峰・一ノ倉岳付近
【撮影者より】
この写真の左側は新潟県,右側は群馬県です.上越新幹線を利用すると越後山脈を通るトンネルを境に天候がガラッと変わることを経験することがしばしばあります.日本海からの湿った空気がこの山脈で遮られた結果なのか,左右非対称な山容を眺めることができます.
目次へ戻る
第15回_佳作7-8
第15回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:噴火の再現ドラマのような鬼岳の野焼き
写真:法橋尚宏(兵庫県)
撮影場所:長崎県五島市上大津町
【撮影者より】
五島市福江島のシンボルとして愛されている活火山の鬼岳は,害虫の駆除,林野火災の予防,景観の保全などを目的として,3年ごとに野焼きが行われます.普段は芝生に覆われた島民の憩いの場所ですが,このときだけは,まさに鬼のように豹変し,北風にあおられて煙を上げながら炎に包まれ,噴火の再現となります.野焼きは,火が確認しやすいように夜間に行われます.炎の迫力,離れていても感じる熱風に驚きました.
目次へ戻る
佳作:宍道湖畔を駆ける最後の国鉄型特急
写真:永岡正行(島根県)
撮影場所:島根県松江市玉湯町布志名の宍道湖畔
【撮影者より】
島根県には島根半島・宍道湖中海ジオパークがあります.特に宍道湖と中海は全国でも珍しい連結汽水湖であり,汽水域特有の高い生物生産性から豊かな生態系を形成しており,ラムサール条約登録湿地のひとつでもある有名なジオサイトです.そんな汽水湖畔には山陰本線が走り,最後の国鉄型特急「やくも」も走ります.国鉄型車両は2024年度に引退ですが,宍道湖の豊かな自然はいつまでも残ってほしいものです.
目次へ戻る
第14回_佳作10-11
第14回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:厳冬の岩脈
写真:加藤慶彦(秋田県)
撮影場所:秋田県男鹿市戸賀(男鹿水族館GAOの側)
【撮影者より】
この小豆色をした岩は約3000年前に流れ出た溶岩で奥にそびえているのは岩脈というものである。この迫力ある岩脈を引き立たせるために晴れではなくあえて曇天の天気を選んで撮影しています。撮影中に柔らかい光が入ってくれたのは嬉しい誤算でした。水族館のすぐ側にあるということもあり訪れた際には是非こちらも見て頂きたい風景です。
目次へ戻る
佳作:連なる漢字の所以
写真:荒木英里(神奈川県)
撮影場所:徳島県 大歩危
【撮影者より】
写真では実物の20パーセントほどしか、その雄大さと怖さは伝わらない。何か感じるものがある、センスがある人はぜひ行って欲しい。ただの風景では無い。よく雄大な自然を前にすると自分がちっぽけに感じる…というけれど、ここはまるで自分の生命エネルギーのスケールの小ささを自覚することになる
目次へ戻る
【geo-Flash】No. 636(臨時)ホフマン博士京都賞受賞記念講演会(東京・駒場)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.636 2024/10/10┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】ポール・ホフマン博士京都賞受賞記念講演会(東京・駒場)
【2】ドローン労働安全セミナーのご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】ポール・ホフマン博士京都賞受賞記念講演会(東京・駒場)
──────────────────────────────────
2024年度の京都賞は地質学者のポール・ホフマン博士(ビクトリア大学客員教授/
ハーバード大学スタージス・フーパー地質学名誉教授)に授与されることが決まり
ました.ホフマン博士はプレートテクトニクスが先カンブリア時代まで遡ることや
全球凍結イベントの実証など,地質学を基盤とした研究で輝かしい研究業績を挙げ
られています.
ホフマン博士の2024年度京都賞受賞の記念講演を,東京大学駒場キャンパスで行い
ます.
主催:東京大学駒場宇宙地球部会
後援:日本地質学会
日時:2024年11月14日(木)17:00-19:00
会場:東京大学駒場キャンパス 21KOMCEE EAST K011(地下)
講演者:ポール・ホフマン博士,ジョセフ・カーシュビンク博士
要事前申込(10月19日締切),入場無料(先着230名)
詳しくは,https://geosociety.jp/news/n185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】ドローン労働安全セミナーのご案内
──────────────────────────────────
近年ドローンの産業利用は拡大の一途をたどっており,地質分野においても調査の
省力化や調査範囲の拡大などに貢献しています.その一方でドローン特有の安全上
の懸念もあり,ドローンに特化した労働安全の向上は重要な課題となっています.
このたび長岡技術科学大学システム安全系では,NEDOからの委託事業「次世代空
モビリティの社会実装に向けた実現プロジェクト」の一環として、業務でドローン
を使用される方を対象に,ドローンの労働安全に関するセミナーを開催することと
なりました.
日時:2024年11月7日(木)9:30-17:00
場所・方式:対面(グランパークカンファレンス田町401ホール,東京都港区)
及びリモート(Zoom Webinar)
参加費:無料
定員:対面 72名、リモート 1,000名
申込締切:対面 10月15日,リモート 10月31日
申し込みはこちらのサイトからお願いします:
https://forms.gle/Zg1kpMMB7mErT9D67
問い合わせ先:
長岡技術科学大学システム安全系研究員
加藤知一 tomokazu_kato[at]vos.nagaokaut.ac.jp
※[at]を@マークにして送信してください.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
システマチックなフィールド教育の導入: 山口大学理学部地球圏システム科学科の例
システマチックなフィールド教育の導入:山口大学理学部地球圏システム科学科の例
大橋聖和*(山口大学理学部地球圏システム科学科准教授)
*現所属: 産業技術総合研究所 地質調査総合センター
はじめに
山口大学理学部地球圏システム科学科では,一般社団法人日本技術者教育認定機構(JABEE)に認定されたプログラムに基づいて,地質技術者育成のためのフィールド教育を行っている.JABEE認定プログラムは,最長6年の有効期間満了時に継続審査が行われ,第三者によるピア・レビューが行われる.これに加え本学科では,学科構成員からなるワーキンググループ(WG),および外部有識者からのピア・レビュー(外部アドバイザリー会議)を活用し,プログラムの教育改善サイクルを循環させている.2022年3月に,一般社団法人日本地質学会主催 第2回JABEEオンラインシンポジウム「昔と違う イマドキのフィールド教育」注が行われ,本学科の教育プログラムの特徴を,特に教育改善の観点から紹介する機会をいただいた.折しも2016年度頃から取り組んできたフィールド教育のシステム化(体系化)がほぼ完成した段階にあり,その概要と,学科としてどのように教育改善を行ってきたのかについて紹介させていただいた.本報告では,その後数年をかけて微調整してきた部分や新たな課題を追加した上で,本学科における専門教育の現状を紹介したい.
本学科の概要と特色
本学理学部では学科別入試を実施しており,地球圏システム科学科の入学定員は30名である.初年次教育は,自然への興味・関心を育むことや,地球科学を理解する上での基礎的な知識・技能の修得に重点を置き,2年次以降,知識や技能を段階的に高めてゆくカリキュラムになっている.豊富な野外体験と調査技術の体得に力点を置いた「地域環境科学コース」(JABEE認定)と,幅広い知識とともに科学的な思考と応用力を育成する「環境物質科学コース」を設置しており,3年進級時にコース分けを実施している.JABEE認定コースのミッションは,幅広い年代と岩種からなる様々な地質に対応でき,課題や目的を自ら設定しそれを解決する能力を有する,自立した地質技術者の育成である.JABEE認定コースの学生への浸透度は高く,おおむね7〜8割の学生が「地域環境科学コース」に進学する.これは,新入生ガイダンスを皮切りに,複数回のコース分け説明会を行っており,JABEE認定コースの特徴・メリット・対象とする人物像等を,自身のキャリア形成を意識しながら考えさせているからである.なお,JABEE認定コースは3年次の専門科目「野外実習」(図1,5人程度の班ごとに,与えられた地域の地質図を作成するいわゆる進級論文)が必修になるほか,進級・卒業に必要な単位要件や達成度評価法などに違いがある.
図1 2022年3月,長門市油谷での「野外実習」(進級論文)の様子
カリキュラムの分析と問題点の抽出
新旧の教員が入れ替わり始めていた2015〜2016年度頃,主に「野外実習」を担当した教員から,野外地質調査に関する低年次教育がうまく機能していないのではないかといった問題提起がなされるようになった.具体的には,「調査に必要な持ち物を適切に所持できていない」,「安全な調査の仕方が身についていない」,「現在位置確認やクリノメーターの使用法,マッピングの仕方が身についていない」など知識・技能に関することである.また,姿勢・態度に関する部分についても,「能動的な調査ができない」,「未知のことに取り組む姿勢に乏しい」といった問題点が指摘された.これは,本来学生が「野外実習」の実施前に修得しておくべき知識・技能の復習に現地での貴重な調査時間を割かざるを得ず,結果的にフィールドデータの不足,地質図作成に関する深い議論や考察の欠如,安易な既存研究の追随に至るという構図であった.本学に限ったことではないと思われるが,高校で地学を学んでいない学生が多く存在するため,低年次の実習系科目は自然への興味・関心を育むことが一つの大きな目的である.一方で,従来のカリキュラムでは1年次と2年次で技能に関する修得レベルの違いがそれほど明確ではなく,3年次の「野外実習」において実践的に専門性を高めるカリキュラムであった.また,実習系科目の多くがオムニバス形式や年度ごとのローテーション制であり,引き継ぎや授業間の連携(授業内容の漏れや重複,教員ごとの設定目標の高低)に課題があったことは否めない.その結果,学修内容の年次積み上げによるレベルアップが弱く,3年次の「野外実習」に過度に負担が集中するといった状況が生まれていたと分析した.
カリキュラムの再設計と各授業の開発
表1 野外調査において修得すべき項目表(通称,星取表)
以上の分析結果を踏まえ,(1) 野外地質調査に必要不可欠な項目を,遺漏なく修得させること,(2) 明確な目標設定に基づいて積み上げ教育を機能させること,(3) 学修者にとっても指導者にとっても分かりやすく全体を見通せること,の3つに重点を置いてカリキュラムをデザインし直すこととした.ここでまず取り組んだのは,「何を,いつまでに,どの授業で修得させるか」を突き詰め,明文化した「野外調査において修得すべき項目表」(通称,星取表)の作成である(表1).項目は12の大区分と62の項目からなり,初歩的な技能から実践的な能力まで,具体的に示している.また,卒業までの4年間の年次ごとに,△(まだ不安),〇(おおむね修得),◎(完全に習得)の三段階で達成度の目標を示している.星取表の完成後,これに自己採点欄を付した「自己点検表」も作成し,この2つを学科の全学生に配布することにした.これらはいわゆるルーブリックに相当するものであるが,学生は卒業までに受けるフィールド教育の全体像と現在位置を把握することができ,教員は担当する授業で最低限何を教えるべきかを明確に意識できるようになった.
次に取り組んだのは,星取表で掲げた積み上げ教育を確実に達成するための,具体的なカリキュラム設計と授業開発である.地質学は,(空間三次元)+(時間一次元)=四次元,を取り扱う学問であり,次元が増えるごとに高度な知識とスキルが必要となってくる.そこで,1年次は単一露頭の「点的」な観察・記載,2年次は連続露頭やルート間対比,断面図作成などの「線〜面的」な観察・記載・解析,3年次以降は岩相区分図(平面図)や複数の断面図の作成,地史の構築といった「立体〜四次元」への拡張,とフィールド教育をフェーズ分けした上で実施することとした.また,取り扱う対象も,地質学の基本である堆積岩から始め,鉱物・火成岩,地質構造・変形構造,付加体・変成帯・地体構造,地史へと段階的にステップアップするようにした.これらの基本方針に基づき,WG内でより具体的な問題点を抽出し,改善案を議論した(表2).従来のカリキュラムの問題点をいくつか挙げると,「1年次の実習系科目で座学と実習が反復的に行えていない」,「前期と後期の科目の連携が手薄」,「1年次と2年次の実習内容が差別化できていない」,「担当教員がローテーションで変わるごとに内容が変わる」などである.野外実習の実施場所は,県内の主な巡検場所(20数カ所)をリストアップした上で,「教育内容に最適な場所はどこか」という観点に立って再検討することになった.実習を担当する教員も,まずは適材適所の配置を行い,後に授業担当者が変わっても内容を引き継げるよう独自のテキストを整備した.一部のローテーション制の実習系科目については,学科教員でのピア・レビューや担当者間での引き継ぎを徹底するようにした.
表2 年次ごとの野外調査教育フェーズと現状の問題点および改善案
実施
見直したカリキュラムに基づいて改良・開発した授業は,2017〜2018年度にかけて段階的に開始した.1年次前期の実習系科目では,興味関心の育成から始まって徐々に専門的な内容を教えており,安全対策を含んだ地質調査の初歩的技能の修得と堆積岩の観察・記載を行うこととした.1年次後期では,対象を鉱物・岩石の観察・記載に特化させ,野外実習と室内作業の反復を意識した授業計画にした.2年次前期では,単一ルートにおけるルートマップ作成や,変形構造の解析など,発展的な内容とした.大学バスの使用ルール上,これまで困難であった県外の泊まりがけ巡検(中国・四国巡検,1泊2日,図2)を,学科支援企業からの奨学寄付金を財源に新たに実施することができたのは我々にとっても大きな改革であった.地体構造を体感させるのに,四国での巡検は不可欠だったからである.2年次後期では,これまでの総復習に加え,地質調査における誤差の取り扱いなど,実践的な内容を取り扱うこととした.前半では,ミクロ〜マクロスケールでの柱状図や地質断面図を描くことにより,地質モデルのスケール感を身につけさせる.後半では,丸二日かけて2本のルート調査を行い,同一層準の追跡,ルート柱状図・断面図・総合柱状図の作成を行う.2年次後期の実習系科目は,3年次の「野外実習」に進むための“関所”と位置づけているため,全員が合格水準に達するまで繰り返し指導を行うこととした.「野外実習」では,グループワーク下にあっても一人一人の達成状況を評価するため,現地での技能チェックや個人での地質図の作成などを課すことにした.
図2 2019年6月,中国・四国巡検(砥部衝上断層)
点検・評価と改善
今回のカリキュラム改革の成果を評価するには,学生が星取表どおりに修得すべき項目を身につけているかどうかが1つの指標になる.自己点検表では,△=1点,〇=2点,◎=3点として総スコア(186点満点)を自己採点し,学期末や年度末および卒業時に提出してもらうことにしている.紙媒体を用いると集計に膨大な時間を要することから,2021年度からは本学のLMS(修学支援システム)を用いたWeb集計フォームと,回答結果をエクセル上で解析できるひな形を開発している.これにより学生はスマホなどから簡便に回答できるようになり,教員は事後のデータ解析が容易になった.また,「野外実習」の履修者を対象として,修得状況の良くない項目についてヒアリングとアドバイスを行うこともあった.学生ごとの修得状況の解析結果では,単純な成長だけでなく,その過程や個性なども見え始めている(詳細はシンポジウムの動画を参照).例えば「野外実習」前後の総スコア変化が小さく,一見すると成長の乏しい学生群を修得すべき項目ごとに分析すると,発展的・実践的な項目が前年度比でマイナスになっており,プラス点を打ち消し合っていることが分かった.ヒアリングからは,「自ら調査を行う中で未熟さを自覚した」,「風化や苔むした露頭で岩石鑑定する難しさを実感した」,「2年次に習ったはずの分類法や記載法を忘れた」,といったスコアだけでは見えない悩みや不安を見ることができた.謙虚な(自分に厳しい)学生が低いスコアを付ける場合もあり,ルーブリックのように自己評価の基準を明確化するか,ヒアリングを通して客観的な評価をする(教員と学生の認識の乖離を埋める)ことが必要であろう.一方で,項目ごとの修得状況の解析結果では,全学生の平均スコアが低い項目や前年比でマイナスになる項目が存在し,講義の弱点や反復学習の重要性が見えてきた.平均スコアが低い項目の例を挙げると,「地形判読から地質との関連性を推測できる」,「変成岩の記載が身についている」,「断層や褶曲についての記載が身についている」など発展的・応用的な項目であり,これらの教授法に課題があることも分かった.また,調査道具の適切な所持の仕方や走向傾斜の測定に関しては,低年次に一度教えてもなかなか簡単に身につかないことがあり,重要なことについては,振り返り学習や,反復しながらレベルを上げてゆくスパイラル教育の重要性を感じることとなった.
これらの点検・評価を踏まえて,2022年度頃から様々な改善を追加で実施している.調査道具の適切な所持の仕方に関しては,目を防護するシールド付きのヘルメットを一括購入させたり,安全教育用のパンフレットを作成し,安全のための道具や技能の重要性をわかりやすく伝えている.全学生の平均スコアが低かった変成岩や変形構造に関する観察・記載能力については,関連する講義系科目や室内実験系科目の中に新たな課題を導入するなど,カリキュラム全体での連携を深めている.
おわりに
今回のカリキュラムの再設計を振り返ると,授業の新設や統廃合は行うことなく,教育のフェーズと扱う対象の順番を意識してカリキュラムを体系的に整理し,各授業を発展させた,ということになる.その礎になったのは星取表の整備であり,各授業の教授内容の明確化と達成度評価の厳格化に大きく寄与している.星取表に基づいた新しいカリキュラムは2023年度で6年目を迎え,最初に入学した学生が大学院を修了するタイミングとなった.学部における積み上げ教育は効果的に機能しており,3年次の「野外実習」だけでなく,卒業研究や修士研究のレベルの向上も実感できるようになっている.星取表は,単に「職人的な地質屋」を育成しているだけのように見えるかもしれないが,我々はあくまでも手段であると考えており,大目的は充実したデータに基づく深い洞察や,自分で考える力の醸成にあった(もちろん,フィールド教育を維持し続けられるよう,安全に最大限配慮するという意味も大きい).堅固な専門基礎教育が高度な研究に結びつくことは,論を俟たないであろう.
一方で,教育フェーズの設定や積み上げ教育,スパイラル教育などは,恐らくかつてはどこの地球科学系大学でも普通に行われていたことで,今回の改革は結局の所,野外地質の学科として「あるべき姿を突き詰めただけ」とも言えるかもしれない.昨今の大学における教員の定員削減や,業務の多忙化,理学部1学科化などが,従来の系統的な専門教育を知らず知らずと(あるいは止むに止まれず)変質させてきたのかもしれない.授業のオムニバス形式や,年度ごとの担当教員のローテーション制は,教員への負担軽減を1つの理由として導入される場合もあるが,一方でデメリットについてもきちんと認識する必要性を感じた.現行カリキュラムの分析にあたっては,専任教員らが学科のあるべき(ありたい)姿を議論・共有することに加え,他大学を経験した教員や実務家教員,JABEE審査員,外部アドバイザーなど,第三者の視点を取り入れることが重要であろう.
(注)
詳細は下記もご参照ください.
シンポジウムのYouTube動画(https://www.youtube.com/watch?v=hl-2sYxYiOM)
報告記事(http://geosociety.jp/uploads/fckeditor/engineer/2nd_JABEE_symp_report.pdf)
2024.05.15
【geo-Flash】 No. 617 2024年度代議員総会開催
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.617 2024/5/7┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2024年度代議員総会開催について
【2】[2024山形大会]講演申込受付をまもなく開始いたします
【3】2024年「地質の日」行事のご案内
【4】Island Arc からのお知らせ
【5】支部のお知らせ
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
【8】災害に関連した会費の特別措置
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2024年度代議員総会開催について
──────────────────────────────────
日時:2024年6月8日(土)14:00-15:30
※WEB会議形式で開催いたします.
正会員は,総会に陪席することができます.ただし,総会規則12条3項により,
許可のない発言はできません.
本総会は役員ならびに代議員による総会となります. 代議員には,総会開催
通知とともに総会に必要な資料等を別途お送りいたします.
議事次第はこちら
http://www.geosociety.jp/outline/content0152.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2024山形大会]講演申込受付をまもなく開始いたします
──────────────────────────────────
2024山形大会(9/8-9/10)の講演申込受付をまもなく開始いたします.
6月19日(水):演題登録・講演要旨受付締切
ランチョン・夜間小集会申込締切
7月中旬:大会プログラム公開(予定)
8月下旬:大会参加登録締切
大会HP(プレサイト)
https://geosociety.jp/science/content0168.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2024年「地質の日」行事のご案内
──────────────────────────────────
2024年の「地質の日」に関連した日本地質学会主催,共催,後援等の催しを
ご紹介しています。
5/12(日)「地質の日」オンライン一般講演会
「令和6年能登半島地震による地殻変動と地盤災害」YouTubeライブ配信
惑星地球フォトコンテスト第15回ほか入選作品展示会/街中ジオ散歩
in Tokyo「身近な地形・地質から探る麻布の歴史と湧水」/講演会「デジタル
詳細地形データを用いた地表面変位計測で見る地震災害」/第41回地球科学
講演会「日本列島の起源と大和構造線」/石の魅力大発見!〜見て・触って・
知ってみよう〜/「地質の日」企画 身近に知る「くまもとの大地」ほか
詳しくは,https://geosociety.jp/name/content0179.html
<オンライン講演会のパブリック・ビューイングを開催しませんか?>
オンライン講演会はYouTubeライブで一般に公開します。博物館やジオパーク
などでぜひパブリック・ビューイングを開催してください。申請は不要です。
開催後、開催した旨を事務局にご報告ください。たくさんの方にご覧いただ
けるよう,ご協力をお願いいたします。
このほか,地質学会以外の全国の地質の日イベント情報はこちら
https://www.gsj.jp/geologyday/2024/index.html(地質の日事業推進委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
新しい論文が公開されています.
■ Island Arc
A zone of columnar joints beneath the roof of a granitic pluton: The Okueyama granite, southwestern Japan. Masahiro Chigira, Hironori Kato/
Arc volcanism initiated on the eastern margin of Eurasia during the Early Cretaceous: Geochemistry of the Takanokura volcanic rocks in the Abukuma Mountains, Northeast Japan. Takahiro Yamamoto
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
※学会HP「会員ページ」(要ログイン)からアクセスすることで,IARは全文無料
で閲覧できます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[中部支部]
■ 中部支部2024年支部年会
2024年6月22日(土)-23日(日)
シンポジウム『令和6年能登半島地震とその被害』
参加・発表申込締切:6月13日(木)
巡検:能登半島地震に伴う地変の視察(共催:日本応用地質学会中部支部)
巡検参加申込締切:5月31日(金)
https://geosociety.jp/outline/content0019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
「地質地盤情報の活用と法整備を考える会」は一般社団法人に移行しました.
2024年4月1日および15日にホームページを更新しました.
https://www.geo-houseibi.jp
************************
第2回深田研講座
5月23日(木)13:00-16:15
形式:zoomウェビナーによるオンライン配信
講師:八木浩司氏(深田地質研究所 客員研究員)
テーマ:ヒマラヤにおける斜面災害の背景とその凄まじさを理解する
参加費無料、300名(先着)*要事前申込
https://fukadaken.or.jp/?p=8170
(後)第61回アイソトープ・放射線研究発表会
7月3日(水)-5日(金)
会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
https://www.jrias.or.jp/
令和6年能登半島地震・7ヶ月報告会
7月30日(火)13:00-17:00(予定)
オンライン開催
主催:防災学術連携体
https://janet-dr.com/index.html
(後)科学教育研究協議会 第70回全国研究大会・いわて花巻大会
8月7日(水)-9日(金)
会場:花巻市立花巻中学校/花巻市立若葉小学校/花巻市文化会館
(岩手県花巻市若葉町)
https://kakyokyo.org/
★日本地質学会第131年学術大会(2024山形)
9月8日(日)-10日(火)
会場:山形大学小白川キャンパス
https://geosociety.jp/science/content0168.html(プレサイト)
(協)地盤技術フォーラム2024
9月18日(水)-20日(金)10:00−17:00
場所:東京ビックサイト・東ホール(江東区有明3丁目)
http://www.sgrte.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
島根大学学術研究院環境システム科学系(地球環境科学)教員公募(7/31)
変動海洋エコシステム高等研究所(WPI-AIMEC) AIMEC研究員公募(6/7)
早稲田大学教育・総合科学学術院(教育学部理学科地球科学専修)准教授・講師・准教授(テニュアトラック)・講師(テニュアトラック)のいずれか公募(6/14)
信州大学理学部地球学コース教員(助教)公募(6/14)
島原半島ジオパーク協議会専門員募集(5/15)NEW
佐渡ジオパークに関する調査研究(5/24)
隠岐ユネスコ世界ジオパーク学術奨励事業(新規5/27)
室戸ユネスコ世界ジオパーク学術研究助成募集(5/10)
白山手取川ジオパーク学術研究助成金事業募集(5/10)
栗駒山麓ジオパーク推進協議会職員(ジオパーク専門員)募集(5/8)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】災害に関連した会費の特別措置
─────────────────────────────────
日本地質学会では,災害救助法適用地域で被災された会員の方々のご窮状
をふまえ,「日本地質学会に届出の住居または勤務地が災害救助法適用地域
に該当する会員のうち,希望する方」は当年度の会費を免除いたします.
希望される方は,学会事務局までお申し出ください.
https://geosociety.jp/outline/content0239.html#saigai
(参考)内閣府HP:災害救助法の適用状況
https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No.618(臨時)山形大会講演申込受付開始
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.618 2024/5/9┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2024山形大会]講演申込受付開始しました
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2024山形大会]講演申込受付開始しました
──────────────────────────────────
2024山形大会(9/8-9/10)の講演申込受付開始しました.
6月19日(水):演題登録・講演要旨受付締切
ランチョン・夜間小集会申込締切
7月中旬:大会プログラム公開(予定)
8月1日(木):巡検申込締切
8月20日(火):大会参加登録締切
詳しくは,大会HPをご確認ください(本サイトもオープンしました)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No.619(臨時)山形大会講演申締切:6/26【日程訂正】
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.619 2024/5/17┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2024山形大会]講演申込受付締切の日程を訂正します
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2024山形大会]講演申込受付締切の日程を訂正します
──────────────────────────────────
2024山形大会(9/8-9/10)一部締切の日程を訂正いたします.
演題登録・要旨投稿締切:
(旧)6月19日(水)18時 → (正)6月26日(水)18時
ランチョン・夜間小集会申込締切
(旧)6月19日(水) → (正)6月26日(水)
詳しくは,大会HPをご確認ください(本サイトもオープンしました)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 620[2024山形大会]講演申込受付中です!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.620 2024/5/21┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2024年度代議員総会開催
【2】[2024山形大会]講演申込受付中です!
【3】2024年度(第2回)日本地質学会研究奨励金採択結果
【4】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【5】支部のお知らせ
【6】JpGU2024 地質学会共催セッションにぜひご出席ください
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】災害に関連した会費の特別措置
【10】会員ページ一時利用停止のお知らせ(6/12−14)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2024年度代議員総会開催
──────────────────────────────────
日時:2024年6月8日(土)14:00-15:30 ※WEB会議形式
正会員は,総会に陪席することができます.ただし,総会規則12条3項により,
許可のない発言はできません.陪席を希望される方は学会事務局までお申し出
ください.
本総会は役員ならびに代議員による総会となります. 代議員には,総会開催
通知とともに総会に必要な資料等を別途お送りいたします.
議事次第はこちら
http://www.geosociety.jp/outline/content0152.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2024山形大会]講演申込受付中です!──────────────────────────────────
2024山形大会(9/8-9/10)一部締切の日程を訂正しました.
演題登録・要旨投稿締切:
(旧)6月19日(水)18時 → (正)6月26日(水)18時
ランチョン・夜間小集会申込締切
(旧)6月19日(水) → (正)6月26日(水)
詳しくは,大会HPをご確認ください
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2024年度(第2回)日本地質学会研究奨励金採択結果
──────────────────────────────────
4/13理事会にて6名の方が採択されました.
詳しくはこちら,https://geosociety.jp/outline/content0251.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
新しい論文が公開されています.
■ 地質学雑誌(130巻1号)
(巡検案内書)但馬地域の舞鶴帯南帯:木村光佑ほか/(総説)琉球弧のネオ
テクトニクス−第四紀での隆起・沈降プロセスに関する研究の課題と展望−:
大坪 誠ほか/(フォト)富山県上市町の下部中新統稲村水中地すべり堆積物:
荒戸裕之ほか
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/list/-char/ja
■ Island Arc
Geochronology and geochemistry of granitoids from northern Alxa, northwest China: Petrogenesis and tectonic implications. Chunjiao Wu,et al.
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
※学会HP「会員ページ」(要ログイン)からアクセスすることで,IARは全文無料
で閲覧できます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[中部支部]
■ 中部支部2024年支部年会
共催:日本応用地質学会中部支部,後援:立山黒部ジオパーク協会
2024年6月22日(土)-23日(日)
シンポジウム『令和6年能登半島地震とその被害』
参加・発表申込締切:6月13日(木)
巡検:能登半島地震に伴う地変の視察(参加申込締切:5月31日(金))
https://geosociety.jp/outline/content0019.html
[関東支部]
■ 清澄フィールドキャンプ
8月19日(月)-24日(土) 5泊6日
場所:東京大学千葉演習林(千葉県鴨川市清澄)
費用:一般会員:55,000円,学生会員:28,250円
応募締切日:7月5日(金)
■ 学生・若手会員向け「地質調査の基礎講座」- 城ヶ島巡検
6月8日(土)10:00-15:30 神奈川県三浦市城ヶ島で野外観察・調査
6月9日(日)13:00-16:45 横須賀市産業交流プラザで露頭柱状図作成など
参加費:一般会員:4,000円,学生会員:1,500円
申込締切:6月5日(水)(定員になり次第締め切り)
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】JpGU2024:地質学会共催セッションにぜひご出席ください
──────────────────────────────────
JpGU2024が始まります(5/26-31;於 幕張メッセ).
地質学会は,関係学協会等と共催し下記のセッションを予定しています。
ぜひご出席ください.
******************************************
https://www.jpgu.org/meeting_j2024/
******************************************
(セッション ID,タイトル,代表世話人)
H-DS09:人間環境と災害リスク(佐藤 浩)
H-CG23:堆積・侵食・地形発達プロセスから読み取る地球表層環境変動(菊地一輝)
S-SS11:活断層と古地震(小荒井 衛)
S-EM13:地磁気・古地磁気・岩石磁気(臼井洋一)
S-GL18:日本列島および東アジアの地質と構造発達史(羽地俊樹)
S-GL19:年代層序単元境界の研究最前線(星 博幸)
S-MP21:Oceanic and Continental Subduction Processes: petrologic and geochemical perspective(礼満 ハフィーズ)
S-MP24:変形岩・変成岩とテクトニクス(中村 佳博)
S-CG41:地殻表層の変動・発達と地球年代学/熱年代学の応用(末岡 茂)
S-CG45:岩石・鉱物・資源(福士圭介)
B-CG06:地球史解読:冥王代から現代まで(小宮 剛)
M-IS03:Evolution and variability of the Asian Monsoon and Indo-Pacific climate during the Cenozoic Era(佐川拓也)
M-IS08:ジオパーク(尾方隆幸)
M-IS23:地質学のいま(辻森 樹)
各セッション詳細(概要,開催日時など)はこちらから
https://www.jpgu.org/meeting_j2024/sessionlist_jp/
プログラム・要旨閲覧には,大会参加ログインが必要です.
https://confit.atlas.jp/guide/event/jpgu2024/participant_login
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
東京地学協会2024年度 特別講演会
「隆起痕跡からわかる能登半島地震の履歴」
6月15日(土)15:00-16:30(令和6年度総会終了後)
場所:東京グリーンパレス(麹町)地階「ふじ」
講師:宍倉正展(産業技術総合研究所)
参加無料・申込不要.直接会場にお越し下さい.
http://www.geog.or.jp/
(後)第61回アイソトープ・放射線研究発表会
7月3日(水)-5日(金)
会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
https://www.jrias.or.jp/
令和6年能登半島地震・7ヶ月報告会
7月30日(火)13:00-17:00(予定)
オンライン開催
主催:防災学術連携体
https://janet-dr.com/index.html
(後)科学教育研究協議会 第70回全国研究大会・いわて花巻大会
8月7日(水)-9日(金)
会場:花巻市立花巻中学校/花巻市立若葉小学校/花巻市文化会館
(岩手県花巻市若葉町)
https://kakyokyo.org/
★日本地質学会第131年学術大会(2024山形)
9月8日(日)-10日(火)
講演申込締切:6/26(水)18時
会場:山形大学小白川キャンパス
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131
第41回歴史地震研究会(木曽御嶽大会)
9月13日(金)- 15日(日)
場所:木曽町文化交流センター,王滝村公民館
講演申込締切:5/31(金)
http://www.histeq.jp/kenkyukai.html
(協)地盤技術フォーラム2024
9月18日(水)-20日(金)10:00−17:00
場所:東京ビックサイト・東ホール(江東区有明3丁目)
http://www.sgrte.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・原子力規制委員会行政職員(技術系・事務系)公募(6/28)
・兵庫県立人と自然の博物館研究員(地質学)公募(6/14)
・JAMSTEC海域地震火山部門地震津波予測研究開発C地震予測研究G, PD研究員公募(6/17)
・山梨県火山防災職募集(6/22) ※5/23 募集説明会開催
・令和6年度神奈川県職員採用選考(地質職)(5/24)
・2024年度関西エネルギー・リサイクル科学研究振興財団助成事業募集(7/31or8/31)
・令和6年第19回筑波大学朝永振一郎記念「科学の芽」賞作品募集(8/19-9/17)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】災害に関連した会費の特別措置
─────────────────────────────────
日本地質学会では,災害救助法適用地域で被災された会員の方々のご窮状
をふまえ,「日本地質学会に届出の住居または勤務地が災害救助法適用地域
に該当する会員のうち,希望する方」は当年度の会費を免除いたします.
希望される方は,学会事務局までお申し出ください.
https://geosociety.jp/outline/content0239.html#saigai
(参考)内閣府HP:災害救助法の適用状況
https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】会員ページ一時利用停止のお知らせ(6/12−14)
──────────────────────────────────
学会ホームページの会員ページ(https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
;会員システム)は,サーバー作業のため,下記期間はご利用いただけません.
閲覧,住所変更,支部専門部会メールの配信などはできません.(学会HP本体,
山形大会サイトはご利用いただけます).
ご迷惑をおかけしますが,どうぞよろしくお願いいたします.
***************************
停止期間:2024年6月12日(水)-14日(金)
***************************
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 621 第11回ショートコース「微化石」開催します!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.621 2024/6/4┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】第11回ショートコース「微化石」開催します!
【2】2024年度代議員総会開催
【3】[2024山形大会]講演申込受付中です!
【4】地質学雑誌からのお知らせ
【5】支部のお知らせ
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
【8】会員ページ一時利用停止のお知らせ(6/12−14)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】第11回ショートコース「微化石」開催します!
──────────────────────────────────
日時:2024年7月21日(日)9:00-12:00,14:00-17:00
(午前)「微化石一般と放散虫」 講師:松岡 篤(新潟大)
(午後)「微化石データ活用の最前線」 講師:林 広樹(島根大)
受講料(各1日券):
地質学会正会員(一般・シニア) 2,000円
(※賛助会員企業に所属する⽅は地質学会会員と同額)
地質学会正会員(学生会員) 1,000円
申込締切:2024年7月12日(金)
詳しくはこちら
http://geosociety.jp/science/content0175.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2024年度代議員総会開催
──────────────────────────────────
日時:2024年6月8日(土)14:00-15:30 ※WEB会議形式
正会員は,総会に陪席することができます.ただし,総会規則12条3項により,
許可のない発言はできません.陪席を希望される方は学会事務局までお申し出
ください.
本総会は役員ならびに代議員による総会となります. 代議員には,総会開催
通知とともに総会に必要な資料等を別途お送りいたします.
議事次第はこちら
http://www.geosociety.jp/outline/content0152.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2024山形大会]各種申込を受付中です!
──────────────────────────────────
2024山形大会(9/8-9/10)の各種申込を受付中です!
・演題登録・要旨投稿締切:6月26日(水)18時
・ジュニアセッション:7月16日(火)
・学生のための地質系業界説明会(参加企業募集):7月12日(金)
※賛助会員(先行受付)を本日6/4より開始ました
・企業展示・書籍販売:8月19日(月)
...などなど
大会参加登録,巡検受付はただ今準備中です.今しばらくお待ちください.
詳しくは,大会HPをご確認ください
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地質学雑誌 からのお知らせ
──────────────────────────────────
新しい論文が公開されています.
■ 地質学雑誌(130巻1号)
(論説)青森県,下北半島西部に分布する新第三系年代層序の再検討と
仏ヶ浦カルデラの提唱:盛合 秀ほか
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/list/-char/ja
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[中部支部]
■ 中部支部2024年支部年会
2024年6月22日(土)-23日(日)
共催:日本応用地質学会中部支部
後援:立山黒部ジオパーク協会・富山応用地質研究会
シンポジウム『令和6年能登半島地震とその被害』
参加・発表申込締切:6月13日(木)
巡検(能登半島地震に伴う地変の視察)は定員に達しましたが,キャンセル待ち
をご希望の方は,専用フォーム方からご登録ください.
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0019.html
[関東支部]
■ 清澄フィールドキャンプ
8月19日(月)-24日(土) 5泊6日
場所:東京大学千葉演習林(千葉県鴨川市清澄)
費用:一般会員:55,000円,学生会員:28,250円
応募締切日:7月5日(金)
■ 学生・若手会員向け「地質調査の基礎講座」- 城ヶ島巡検
6月8日(土)10:00-15:30 神奈川県三浦市城ヶ島で野外観察・調査
6月9日(日)13:00-16:45 横須賀市産業交流プラザで露頭柱状図作成など
参加費:一般会員:4,000円,学生会員:1,500円
申込締切:6月5日(水)(定員になり次第締め切り)
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
2024年度深田地質研究所研究成果報告会
6月14日(金)13:00-16:40
形式:会場参加(定員30名先着順)/
zoom ウェビナーによるオンライン配信(定員450名先着順)
参加費無料*要事前申込
https://fukadaken.or.jp/?p=8205
(後)第61回アイソトープ・放射線研究発表会
7月3日(水)-5日(金)
会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
https://www.jrias.or.jp/
令和6年能登半島地震・7ヶ月報告会
7月30日(火)13:00-17:00(予定)
オンライン開催
主催:防災学術連携体
https://janet-dr.com/index.html
(後)科学教育研究協議会 第70回全国研究大会・いわて花巻大会
8月7日(水)-9日(金)
会場:花巻市立花巻中学校/花巻市立若葉小学校/花巻市文化会館
(岩手県花巻市若葉町)
https://kakyokyo.org/
★日本地質学会第131年学術大会(2024山形)
9月8日(日)-10日(火)
講演申込締切:6/26(水)18時
会場:山形大学小白川キャンパス
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131
(協)地盤技術フォーラム2024
9月18日(水)-20日(金)10:00−17:00
場所:東京ビックサイト・東ホール(江東区有明3丁目)
http://www.sgrte.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0246.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・早稲田大学 理工学術院総合研究所次席研究員or研究助手
・京都大学大学院理学研究科 地球惑星科学専攻地球物理学分野/
地球惑星科学専攻地質学鉱物学分野 /附属地球熱学研究施設/
附属地磁気世界資料解析センター 助教(女性限定)公募(7/31)
・東京大学大気海洋研究所海洋底科学部門教授公募(8/30)(7/31)
・大阪市立自然史博物館学芸員(脊椎動物化石担当)募集(7/12)
・海洋研究開発機構海域地震火山部門火山・地球内部研究センター公募(7/16)
・海洋研究開発機構リスタート支援公募(7/15)
・東京大学理学系研究科地球惑星科学専攻助教公募(7/31)
・令和7年度科学技術分野の文部科学大臣表彰(科学技術賞,若手科学者賞,
研究支援賞)候補者推薦(学会締切7/8)
・東京地学協会令和6年度普及・啓発活動(地学・地理クラブ活動および地学・
地理教育)助成金交付申請受付延長(6/30)NEW
・STAR-Eプロジェクト第3回研究者・学生・生徒向けイベント「地震・測地
データ活用アイデアコンテスト2024」(7/5)
・令和6年度三陸ジオパーク学術研究助成金の募集(6/19)
・湯沢市ゆざわジオパーク学術研究等奨励補助金募集(7/5)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】会員ページ一時利用停止のお知らせ(6/12−14)
──────────────────────────────────
学会ホームページの会員ページ(https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
;会員システム)は,サーバー作業のため,下記期間はご利用いただけません.
閲覧,住所変更,支部専門部会メールの配信などはできません.(学会HP本体,
山形大会サイトはご利用いただけます).
ご迷惑をおかけしますが,どうぞよろしくお願いいたします.
***************************
停止期間:2024年6月12日(水)-14日(金)
***************************
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 622 [2024山形大会]講演申込6/26(水)締切です
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.622 2024/6/18┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2024山形大会]各種申込を受付中です!
【2】[2024山形大会]まもなく事前参加登録受付開始します
【3】第11回ショートコース「微化石」開催します!
【4】2024年度会費督促請求に関するお知らせ
【5】支部のお知らせ
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2024山形大会]各種申込を受付中です!
──────────────────────────────────
2024山形大会(9/8-9/10)の各種申込を受付中です!
■ 演題登録・要旨投稿:6月26日(水)18時 締切
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/collectsubject
■ ジュニアセッション:7月16日(火) 締切
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/gyoji#jr
■ ランチョン・夜間集会申込:6月26日(水)締切
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/meeting
■ 企業展示・書籍販売:8月19日(月)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/tenji
■ お子様をお連れになる方へ
大会期間中に保育施設の利用を希望される方には,学会から利用料金の一部
を補助いたします.会場内には保育室を設けませんので,近隣施設をご紹介
の予定です.近日大会HPでご案内いたします.
詳しくは,大会HPをご確認ください
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2024山形大会]まもなく事前参加登録受付開始します
──────────────────────────────────
大会参加登録については,まもなく受付開始で準備中です.
今しばらくお待ちください.
事前参加登録締切:8月20日(火)18:00
巡検参加申込締切:8月1日(木)18:00
[参加費]事前申込
正会員(一般会員):6,000円
正会員(シニア会員):3,000円※2024年4月1日時点で65歳以上の正会員
正会員(学生会員):1,500円
名誉会員/非会員招待者:無料
・大会参加登録費と発表料金(1,500円/件)は分離しています.
・発表する方は大会参加登録費と発表料金の両方の支払いが必要です.
・講演要旨集の冊子体は作成・販売いたしません.
大会参加登録に関する詳細は,
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/sanka
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】第11回ショートコース「微化石」開催します!
──────────────────────────────────
日時:2024年7月21日(日)9:00-12:00,14:00-17:00
(午前)「微化石一般と放散虫」 講師:松岡 篤(新潟大)
(午後)「微化石データ活用の最前線」 講師:林 広樹(島根大)
受講料(各1日券):
地質学会正会員(一般・シニア) 2,000円
(※賛助会員企業に所属する⽅は地質学会会員と同額)
地質学会正会員(学生会員) 1,000円
申込締切:2024年7月12日(金)
詳しくはこちら,http://geosociety.jp/science/content0175.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2024年度会費督促請求に関するお知らせ
──────────────────────────────────
2024年度会費およびそれ以前の未納会費がある方に対して,請求書(郵便振替
用紙)を6月13日に発送しました.早急にご送金くださいますようお願いいた
します.
また自動引落については,6月24日に引落しを行います.
※2024年度分会費が未納の場合は,7月号からのニュース誌送付を一時的に中止
させていただきます.
※2024年度分の学生会員申請は受付を終了しました(遡っての申請はできません)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[関東支部]
■ 清澄フィールドキャンプ
8月19日(月)-24日(土)5泊6日
場所:東京大学千葉演習林(千葉県鴨川市清澄)
費用:一般会員 55,000円,学生会員 28,250円
応募締切:7月5日(金)
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)第61回アイソトープ・放射線研究発表会
7月3日(水)-5日(金)
会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
https://www.jrias.or.jp/
第245回イブニングセミナー(オンライン)
7月5日(金)19:30-21:30
演題:ダイナミック地形学試論−下総台地の水文地形−
講師:近藤昭彦先生(千葉大学名誉教授)
参加費:主催NPO会員及び学生(無料),非会員(1,000円)
https://www.npo-geopol.or.jp/seminer.htm
第201回深田研談話会
テーマ:海と陸から鬼界海底カルデラの実像に迫る
−最新の探査技術から見えてきた縄文の巨大噴火−
7月12日(金)15:00-16:30
場所:深田地質研究所 研修ホール(東京都文京区)
講師:鈴木桂子 氏(神戸大学)
定員:会場参加(30名)、オンライン(450名)*先着順
参加費無料(要事前申し込み)
https://fukadaken.or.jp/?p=8305
令和6年能登半島地震・7ヶ月報告会
7月30日(火)13:00-17:00(予定)
オンライン開催
主催:防災学術連携体
https://janet-dr.com/index.html
(後)科学教育研究協議会 第70回全国研究大会・いわて花巻大会
8月7日(水)-9日(金)
会場:花巻市立花巻中学校/花巻市立若葉小学校/花巻市文化会館
(岩手県花巻市若葉町)
https://kakyokyo.org/
★日本地質学会第131年学術大会(2024山形)
9月8日(日)-10日(火)
講演申込締切:6/26(水)18時
会場:山形大学小白川キャンパス
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131
(共)2024年度 日本地球化学会 第71回年会
9月18日(水)〜20日(金)
会場:金沢大学・角間キャンパス(自然科学本館)
http://www.geochem.jp/meeting/
(協)地盤技術フォーラム2024
9月18日(水)-20日(金)10:00−17:00
場所:東京ビックサイト・東ホール(江東区有明3丁目)
http://www.sgrte.jp/
地質学史懇話会
12月21日(土)13:30-17:00
場所:北とぴあ 806号室(東京都北区王子)
八耳俊文:マンハッタン計画と水俣病―戦後20年日本地球化学史 ほか
問い合わせ:矢島道子 pxi02070[at]nifty.com
※[at]を@マークにして送信してください
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0246.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・北海道大学大学院理学研究院地球惑星科学部門助教公募(9/30)
・富山大学学術研究部都市デザイン学系助教公募(7/25)
・早稲田大学次席研究員(研究院講師)あるいは研究助手公募(6/30)
・令和6年度筑波山地域ジオパーク学術研究助成(6/30)
・霧島ジオパーク学術研究支援補助金対象事業募集(6/24)
・五島列島ジオパーク推進協議会活動支援助成金の募集(6/28)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 623(臨時)[2024山形大会]まもなく講演申込締切です!(6/26(水)18時締切)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.623 2024/6/24┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2024山形大会]6/26(水)18時 講演申込締切です!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2024山形大会]6/26(水)18時 講演申込締切です!
──────────────────────────────────
■ 6月26日(水)18時講演申込締切です!
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/collectsubject
(注)招待講演も期日までに演題登録・要旨投稿が必要です.ご注意ください.
■ ランチョン・夜間集会申込:6月26日(水)締切
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/meeting
2024山形大会(9/8-9/10)の各種申込を受付中です!
■ ジュニアセッション:7月16日(火) 締切
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/gyoji#jr
■ 企業展示・書籍販売:8月19日(月)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/tenji
詳しくは,大会HPをご確認ください
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 624 日本地質学会会長就任にあたって
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.624 2024/7/2┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】日本地質学会会長就任にあたって(会長 山路 敦)
【2】[2024山形大会]各種申込を受付中です!
【3】[2024山形大会]まもなく事前参加登録受付開始します
【4】第11回ショートコース「微化石」開催します!
【5】Island Arc からのお知らせ
【6】地質学雑誌からのお知らせ
【7】支部のお知らせ
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】日本地質学会会長就任にあたって(会長 山路 敦)
──────────────────────────────────
会長 山路 敦
今期(2024年〜2026年)本会の代表理事(会長)を務めさせていただきます.
私の専門は構造地質学,特に,日本列島の新生代テクトニクスです.これが
古典的なテーマであるからこそ,新しい観点を持ち込むことを心掛けてきま
した.本会には大学院進学を機に入会し,あっという間に40年以上が過ぎま
した.その間,年会などで様々な方々と知り合い,本会に育てていただいた
と思っています.微力ではありますが,会長職を務めてまいりますので,
どうかよろしくお願い申し上げます.
つづきはこちらから,,,https://geosociety.jp/outline/content0137.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2024山形大会]各種申込を受付中です!
──────────────────────────────────
2024山形大会(9/8-9/10)の各種申込を受付中です!
■ ジュニアセッション参加校募集:7月16日(火)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/gyoji#jr
■ 企業展示・書籍販売:8月19日(月)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/tenji
■ お子様をお連れになる方へ
大会期間中に保育施設の利用を希望される方には,学会から利用料金の一部
を補助いたします.会場内には保育室を設けませんので,近隣施設をご紹介
しています.
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/kids
■学生のための地質系業界説明会(オンラインのみ)参加企業募集:7月12日(金)
※会場スペースの都合により,対面説明会の募集は終了しました.
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/gyokai_support_kigyoboshu
詳しくは,大会HPをご確認ください
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2024山形大会]まもなく事前参加登録受付開始します
──────────────────────────────────
大会参加登録については,まもなく受付開始で準備中です.
今しばらくお待ちください.
事前参加登録締切:8月20日(火)18:00
巡検参加申込締切:8月1日(木)18:00
[参加費]事前申込
正会員(一般会員):6,000円
正会員(シニア会員):3,000円※2024年4月1日時点で65歳以上の正会員
正会員(学生会員):1,500円
名誉会員/非会員招待者:無料
・大会参加登録費と発表料金(1,500円/件)は分離しています.
・発表する方は大会参加登録費と発表料金の両方の支払いが必要です.
・講演要旨集の冊子体は作成・販売いたしません.
大会参加登録に関する詳細は,
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/sanka
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第11回ショートコース「微化石」開催します!
──────────────────────────────────
日時:2024年7月21日(日)9:00-12:00,14:00-17:00
(午前)「微化石一般と放散虫」 講師:松岡 篤(新潟大)
(午後)「微化石データ活用の最前線」 講師:林 広樹(島根大)
受講料(各1日券):
地質学会正会員(一般・シニア) 2,000円
(※賛助会員企業に所属する⽅は地質学会会員と同額)
地質学会正会員(学生会員) 1,000円
申込締切:2024年7月12日(金)
詳しくはこちら,http://geosociety.jp/science/content0175.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■Island Arcのオンライン投稿・査読のプラットフォームがScholorOneから
Research Exchange (REX)に変更されました。また、オンライン出版の
論文デザインもリニューアルします。
REXについては、こちらのサイトの動画を参照ください。
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/submission-peer-review/research-exchange.html
■新しい論文が公開されています
Significance of serpentinite‐hosted exhumation channels in a palaeo‐subduction
complex, Nishisonogi unit, Nagasaki Metamorphic Complex: P–T trajectories
of mélange blocks and coherent schists; Tadao Nishiyamaet al
Serravallian–Tortonian (Miocene) folding in the Amakusa region, northern
Ryukyu arc: Possible subduction resumption of the Philippine Sea Plate;
Kentaro Ushimaru et al
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
※学会HP「会員ページ」(要ログイン)からアクセスすることで,IARは
全文無料で閲覧できます.
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質学雑誌からのお知らせ
──────────────────────────────────
■新しい論文が公開されています
(報告)A cicadid hind wing fossil (Hemiptera, Cicadidae) from the Lower
Miocene Masaragawa Formation, Seki, Sado Island, Niigata Prefecture;
Yui Takahashi et al/(論説)兵庫–鳥取県境海岸部の下部中新統火山岩類の
分布と岩脈の方向;羽地俊樹ほか
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/list/-char/ja
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[関東支部]
■ 清澄フィールドキャンプ
8月19日(月)-24日(土)5泊6日
場所:東京大学千葉演習林(千葉県鴨川市清澄)
費用:一般会員 55,000円,学生会員 28,250円
応募締切:7月5日(金)
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)第61回アイソトープ・放射線研究発表会
7月3日(水)-5日(金)
会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
https://www.jrias.or.jp/
令和6年能登半島地震・7ヶ月報告会
7月30日(火)13:00-17:00(予定)
オンライン開催
主催:防災学術連携体
https://janet-dr.com/index.html
(後)科学教育研究協議会 第70回全国研究大会・いわて花巻大会
8月7日(水)-9日(金)
会場:花巻市立花巻中学校/花巻市立若葉小学校/花巻市文化会館
(岩手県花巻市若葉町)
https://kakyokyo.org/
(後)第67回粘土科学討論会
9月4日(水)-9月6日(金)
会場:九州工業大学戸畑キャンパス(北九州市戸畑区仙水町1-1)
すべて対面で開催予定(講演会9月4-5日、現地見学会9月6日)
https://www.cssj2.org/event/annual_meeting/
★日本地質学会第131年学術大会(2024山形)
9月8日(日)-10日(火)
講演申込締切:6/26(水)18時
会場:山形大学小白川キャンパス
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131
(共)2024年度 日本地球化学会 第71回年会
9月18日(水)〜20日(金)
会場:金沢大学・角間キャンパス(自然科学本館)
http://www.geochem.jp/meeting/
(協)地盤技術フォーラム2024
9月18日(水)-20日(金)10:00−17:00
場所:東京ビックサイト・東ホール(江東区有明3丁目)
http://www.sgrte.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0246.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・東京大学地震研究所2025年度国際室外国人客員教員の推薦公募(8/1)
・新潟大学教育研究院自然科学系准教授公募(8/19)
・岡山大学惑星物質研究所惑星表層環境部門教授および准教授の公募(9/30)
・東京大学地震研究所第3回大型計算機共同利用公募研究の公募(8/31)
・室戸ユネスコ世界ジオパークの地質専門員募集(8/9)
・伊豆大島ジオパーク,東京都大島町学芸員の募集(随時受付)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 625(臨時号)[2024山形大会]事前参加登録受付開始!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.625 2024/7/11┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2024山形大会]事前参加登録受付開始しました
【2】第11回ショートコース「微化石」まもなく申込締切です
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2024山形大会]事前参加登録受付開始しました
──────────────────────────────────
■ 大会参加登録(8/20, 18時締切)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/sanka
■ 懇親会(8/20, 18時締切)(注)予定数(定員150)に達し次第締切
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/etal
■ 巡検参加申込(8/1, 18時締切)山形を中心に8コースを設定
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/excursion
—-----------------------------------
このほか各種受付中です.
■ ジュニアセッション参加校募集:7月16日(火)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/gyoji#jr
■ 企業展示・書籍販売:8月19日(月)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/tenji
■ お子様をお連れになる方へ
大会期間中に保育施設の利用を希望される方には,学会から利用料金の一部
を補助いたします.会場内には保育室を設けませんので,近隣施設をご紹介
しています.
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/kids
■学生のための地質系業界説明会(オンラインのみ)参加企業募集:7月12日(金)
※会場スペースの都合により,対面説明会の募集は終了しました.
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/gyokai_support_kigyoboshu
詳しくは,大会HPをご確認ください
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第11回ショートコース「微化石」まもなく申込締切です
──────────────────────────────────
日時:2024年7月21日(日)9:00-12:00,14:00-17:00
(午前)「微化石一般と放散虫」 講師:松岡 篤(新潟大)
(午後)「微化石データ活用の最前線」 講師:林 広樹(島根大)
受講料(各1日券):
地質学会正会員(一般・シニア) 2,000円
(※賛助会員企業に所属する⽅は地質学会会員と同額)
地質学会正会員(学生会員) 1,000円
申込締切:2024年7月12日(金)
詳しくはこちら,http://geosociety.jp/science/content0175.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 626 [2024山形大会]各種申込受付中
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.626 2024/7/16┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2024山形大会]事前参加登録受付中
【2】[2024山形大会]懇親会予約はお早めに!
【3】[2024山形大会]巡検:山形を中心に8コースを設定
【4】[2024山形大会]各種申込受付中
【5】Island Arc からのお知らせ
【6】地質学雑誌からのお知らせ
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2024山形大会]事前参加登録受付中──────────────────────────────────
事前参加登録 8/20(火)18時締切
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/sanka
[大会参加費]事前申込
正会員(一般会員) : 6,000円
正会員(シニア会員) : 3,000円 ※2024年4月1日時点で65歳以上の正会員
正会員(学生会員の院生) : 1,500円
名誉会員/非会員招待者/学部学生 : 無料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2024山形大会]懇親会予約はお早めに!
──────────────────────────────────
懇親会 8/20(火)18時締切
予定数(定員150)に達し次第締切ります.ご予約はお早めに!
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/etal
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2024山形大会]巡検 : 山形を中心に8コースを設定
──────────────────────────────────
巡検参加申込 8/1(木) 18時締切
山形を中心に豊富な内容で8コースを設定しました.ぜひご参加ください!
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/excursion
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2024山形大会]各種申込受付中
──────────────────────────────────
■ ジュニアセッション参加校募集 : 7月16日(火)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/gyoji#jr
■ 企業展示・書籍販売 : 8月19日(月)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/tenji
■ お子様をお連れになる方へ
大会期間中に保育施設の利用を希望される方には,学会から利用料金の一部
を補助いたします.会場内には保育室を設けませんので,近隣施設をご紹介
しています.
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/kids
詳しくは,大会HPをご確認ください
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■新しい論文が公開されています
Subduction of the Paleo Pacific Plate at the southeast edge of the South China
Block during the Early to Middle Jurassic: Sedimentary records from Fujian Province;
Long Leng et al
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
※学会HP「会員ページ」(要ログイン)からアクセスすることで,IARは
全文無料で閲覧できます.
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
■Island Arcのオンライン投稿・査読のプラットフォームがScholorOneから
Research Exchange (REX)に変更されました.また,オンライン出版の
論文デザインもリニューアルします.
REXについては,こちらのサイトの動画を参照ください.
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/submission-peer-review/research-exchange.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質学雑誌からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 新しい論文が公開されています
(巡検案内書)山形県南西部の中新統と令和4年8月豪雨災害:星博幸ほか/
(巡検案内書)松島湾地域の地質と地形−日本海拡大から現在までの東北日本
前弧域の地質・地形の発達−;郄嶋 礼詩/(巡検案内書)蔵王火山西部蔵王沢
上流部,蔵王鉱山跡地周辺の火山・鉱床地質:かつて存在した火山熱水系の
痕跡;井村 匠...ほか
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/list/-char/ja
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
令和6年能登半島地震・7ヶ月報告会
7月30日(火)13:00-17:20
オンライン開催
主催:防災学術連携体
https://janet-dr.com/index.html
(後)科学教育研究協議会 第70回全国研究大会・いわて花巻大会
8月7日(水)-9日(金)
会場:花巻市立花巻中学校/花巻市立若葉小学校/花巻市文化会館
(岩手県花巻市若葉町)
https://kakyokyo.org/
産業技術総合研究所地質調査総合センター 研究室見学会
8月27日(火)13:00-17:15
対象 学部生、大学院生、既卒者
募集人数:先着30名
開催地:産業技術総合研究所つくば中央事業所7群(茨城県つくば市)
https://www.gsj.jp/information/recruit/gsj-tour2024.pdf
(後)第67回粘土科学討論会
9月4日(水)-9月6日(金)
会場:九州工業大学戸畑キャンパス(北九州市戸畑区仙水町1-1)
すべて対面で開催予定(講演会9月4-5日、現地見学会9月6日)
https://www.cssj2.org/event/annual_meeting/
★日本地質学会第131年学術大会(2024山形)
9月8日(日)-10日(火)
講演申込締切:6/26(水)18時
会場:山形大学小白川キャンパス
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131
(共)2024年度 日本地球化学会 第71回年会
9月18日(水)〜20日(金)
会場:金沢大学・角間キャンパス(自然科学本館)
http://www.geochem.jp/meeting/
(協)地盤技術フォーラム2024
9月18日(水)-20日(金)10:00−17:00
場所:東京ビックサイト・東ホール(江東区有明3丁目)
http://www.sgrte.jp/
第6回 鉱物肉眼鑑定研修
10月2日(水)-4日(金)
場所:産総研つくば中央事業所7群
定員:4-5名(定員になり次第締切)
CPD:24単位
参加費:48口(1口1000円)の会費が必要です
https://www.gsj.jp/geoschool/koubutsu/6th.html
2024年度第2回 地質調査研修(初級/経験者向け)
10月21日(月)-25日(金)
場所:島根県出雲市長尾鼻周辺(小伊津海岸)
定員:6名(定員になり次第締切)
CPD:42単位
参加費:84口(1口1000円)の会費が必要です
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2024-2.html
2024年度第3回 地質調査研修(中級/経験者向け)
11月11日(月)-17日(日)
場所:福岡県福岡市能古島
定員:6名(定員になり次第締切)
CPD:45単位
参加費:90口(1口1000円)の会費が必要です
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2024-3.html
地質学史懇話会
12月21日(土)13:30-17:00
場所:北とぴあ 806号室(東京都北区王子)
・八耳俊文:マンハッタン計画と水俣病―戦後20年日本地球化学史
・黒田和男:感銘を受けた授業―東中秀雄先生
問い合わせ:矢島道子 pxi02070[at]nifty.com
※[at]を@マークにして送信してください
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0246.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・京都大学大学院理学研究科附属サイエンス連携探索センター教授or准教授公募
(8/23)
・農林水産省社会人採用(地球科学分野を含む技術系職員募集)(8/25)
・美祢市立秋吉台科学博物館学芸員(地学分野)採用試験(8/16)
・福井大学教育学部「地学および小学校理科担当」講師または准教授公募(9/12)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 627(臨時)[2024山形大会]巡検申込お早めに!!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.627 2024/7/25┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2024山形大会]巡検申込はお早めに!(締切8/1)
【2】[2024山形大会]全体日程が公開されています
【3】[2024山形大会]事前参加登録受付中
【4】[2024山形大会]懇親会予約もお早めに!
【5】[2024山形大会]学生・若手のための交流会(9/7開催)
【6】[2024山形大会]学生事前予約受付中:学生のための地質系業界説明会
【7】[2024山形大会]その他
【8】文部科学省アンケート調査依頼(7/31まで)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2024山形大会]巡検申込はお早めに!(締切8/1)
──────────────────────────────────
巡検参加申込:8/1(木) 18時締切
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/excursion
山形を中心に豊富な内容で8コースを設定しました.
締切が大会参加登録より早い設定になっています.既に定員に達して締め
切られたコースもあります.参加希望の方はお早めにお申し込みください.
申込状況を大会サイトで確認いただけます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2024山形大会]全体日程が公開されています
──────────────────────────────────
学術大会の全体日程が公開されています.
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/program
講演プログラムもまもなく公開予定です.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2024山形大会]事前参加登録受付中──────────────────────────────────
事前参加登録 8/20(火)18時締切
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/sanka
[大会参加費]事前申込
正会員(一般会員) : 6,000円
正会員(シニア会員) : 3,000円 ※2024年4月1日時点で65歳以上の正会員
正会員(学生会員の院生) : 1,500円
名誉会員/非会員招待者/学部学生 : 無料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2024山形大会]懇親会予約もお早めに!
──────────────────────────────────
懇親会 8/20(火)18時締切
予定数(定員150)に達し次第締切ります.ご予約はお早めに!
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/etal
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2024山形大会]学生・若手のための交流会(9/7開催)
──────────────────────────────────
「学生・若手のための交流会」
日時:9月7日 (土) 16:30-19:00
場所:山形テルサ(山形市双葉町1-2-3)
地質学に携わる学生および若手の研究活動や交流の促進を目的とする集会です
.学術大会の前に全国の学生・若手と交流しましょう!
その他:交流会の詳細については,地質学会HP等で随時更新していきます.
このほか,2024山形大会では,巡検参加費補助やダイバーシティ認定ロゴ,
求職中シール等,今年も若手会員向けの様々な取り組みが行われます.
ぜひご確認ください.
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/youth
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[2024山形大会]学生事前予約受付中:学生のための地質系業界説明会
──────────────────────────────────
2024年度学生のための地質系業界説明会
〜その業界の仕事を知るためのサポートサービス〜
対面説明会(9/9開催)・オンライン(9/13開催)
対面・オンラインで計50社以上の企業にご参加いただきます.
当日来場の参加も受け付けますが,事前予約の学生さんを優先します.
・対面説明会申込締切:8月29日(木)
・オンライン説明会申込締切:9月5日(木)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/gyokai_support
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[2024山形大会]その他
──────────────────────────────────
■ 企業展示・書籍販売 : 8月19日(月)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/tenji
■ お子様をお連れになる方へ
大会期間中に保育施設の利用を希望される方には,学会から利用料金の一部
を補助いたします.会場内には保育室を設けませんので,近隣施設をご紹介
しています.
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/kids
詳しくは,大会HPをご確認ください
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】文部科学省アンケート調査依頼(7/31まで)
──────────────────────────────────
文部科学省科学技術・学術政策研究所よりアンケート調査の依頼が来ております.
2055年までの重要トピック約840件の発展見通しに関する専門家のご見解を収集するというものです.
関連トピックとして宇宙・海洋・地球・科学基盤分野などが含まれております.
科学技術イノベーション政策立案に資することを目的としておりますので,この
分野の将来に関わる可能性があります.専門家としての見解を下記に示して頂け
ますようお願いいたします.
アンケート:http://www.nistep.go.jp/yosoku12-intro
期間:2024年6月20日から7月31日(実施中)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 628(臨時)[2024山形大会]巡検締切延長!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.628 2024/8/3┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2024山形大会]巡検締切延長!(8/8締切延長)
【2】[2024山形大会]全体日程
【3】[2024山形大会]事前参加登録受付中
【4】[2024山形大会]懇親会予約もお早めに!
【5】[2024山形大会]学生・若手のための交流会(9/7開催)
【6】[2024山形大会]学生事前予約受付中:学生のための地質系業界説明会
【7】[2024山形大会]その他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2024山形大会]巡検締切延長!(8/8締切延長)
──────────────────────────────────
巡検参加申込:8/8(木) 18時締切(延長します)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/excursion
山形を中心に豊富な内容で8コースを設定しました.
申し込み状況を鑑み,申し込み締切を8/8まで延長いたします.
申込状況は大会サイトで確認いただけます.
下記のコースはお申し込みが可能です.
ぜひこの機会に,山形の巡検にご参加ください!
C)山形の地形・地質災害と活断層(1泊2日)9/10-11
F)松島周辺の新第三系(プレ)9/7
G)山寺と山寺層−地質・歴史・文化地質学 9/11
H)鳥海山・飛島ジオパーク ジオツアー(鳥海山編)(プレ)9/7
上記のほか,
「山形城と石材見学会」(13:00〜15:30※小雨決行)(参加無料・要申込)も開催
されます.山形城の歴史を学びながら,霞城公園を巡り石垣等に使われている石材を見学します.
詳しくは,https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/gyoji#sekizai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2024山形大会]全体日程
──────────────────────────────────
学術大会の全体日程が公開されています.
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/program
講演プログラムもまもなく公開予定です.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2024山形大会]事前参加登録受付中──────────────────────────────────
事前参加登録 8/20(火)18時締切
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/sanka
[大会参加費]事前申込
正会員(一般会員) : 6,000円
正会員(シニア会員) : 3,000円 ※2024年4月1日時点で65歳以上の正会員
正会員(学生会員の院生) : 1,500円
名誉会員/非会員招待者/学部学生 : 無料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2024山形大会]懇親会予約もお早めに!
──────────────────────────────────
懇親会 8/20(火)18時締切
予定数(定員150)に達し次第締切ります.ご予約はお早めに!
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/etal
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2024山形大会]学生・若手のための交流会(9/7開催)
──────────────────────────────────
「学生・若手のための交流会」
日時:9月7日 (土) 16:30-19:00
場所:山形テルサ(山形市双葉町1-2-3)
地質学に携わる学生および若手の研究活動や交流の促進を目的とする集会です
.学術大会の前に全国の学生・若手と交流しましょう!
その他:交流会の詳細については,地質学会HP等で随時更新していきます.
このほか,2024山形大会では,巡検参加費補助やダイバーシティ認定ロゴ,
求職中シール等,今年も若手会員向けの様々な取り組みが行われます.
ぜひご確認ください.
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/youth
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[2024山形大会]学生事前予約受付中:学生のための地質系業界説明会
──────────────────────────────────
2024年度学生のための地質系業界説明会
〜その業界の仕事を知るためのサポートサービス〜
対面説明会(9/9開催)・オンライン(9/13開催)
対面・オンラインで計50社以上の企業にご参加いただきます.
当日来場の参加も受け付けますが,事前予約の学生さんを優先します.
・対面説明会申込締切:8月29日(木)
・オンライン説明会申込締切:9月5日(木)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/gyokai_support
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[2024山形大会]その他
──────────────────────────────────
■ 企業展示・書籍販売 : 8月19日(月)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/tenji
■ お子様をお連れになる方へ
大会期間中に保育施設の利用を希望される方には,学会から利用料金の一部
を補助いたします.会場内には保育室を設けませんので,近隣施設をご紹介
しています.
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/kids
詳しくは,大会HPをご確認ください
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 629[2024山形大会]プログラム公開&巡検締切延長中
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.629 2024/8/6┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2024山形大会]巡検締切延長中(8/8締切延長)
【2】[2024山形大会]講演プログラム公開
【3】[2024山形大会]緊急展示
【4】[2024山形大会]学生・若手のための交流会(9/7開催)
【5】[2024山形大会]学生事前予約受付中:地質系業界説明会
【6】Island Arc からのお知らせ
【7】地質学雑誌からのお知らせ
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2024山形大会]巡検締切延長中(8/8締切延長)
──────────────────────────────────
巡検参加申込:8/8(木) 18時締切(延長中です)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/excursion
申し込み状況を鑑み,申し込み締切を8/8まで延長いたします.
申込状況は大会サイトで確認いただけます.
下記のコースはまだお申し込みが可能です.
ぜひこの機会に,山形の巡検にご参加ください!
C)山形の地形・地質災害と活断層(1泊2日)9/10-11
F)松島周辺の新第三系(プレ)9/7
G)山寺と山寺層−地質?歴史?文化地質学 9/11
H)鳥海山・飛島ジオパーク ジオツアー(鳥海山編)(プレ)9/7
※地質学会正会員(学生会員)には,若手育成事業の一環として,
巡検参加費の半額補助が可能です.
詳しくは,https://geosociety.jp/science/content0173.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2024山形大会]講演プログラム公開
──────────────────────────────────
山形大会講演プログラムを公開しました!
講演検索はこちらから
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/search
タイムテーブルはこちらから
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/table/2024-09-08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2024山形大会]緊急展示
──────────────────────────────────
申込締切:8月29日(木)
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害調査報告
や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示」を設けます.
ポスター展示を希望する方は,8月29日(木)までにご連絡ください.
緊急展示は,正式な学会発表と同じく,コアタイムの時間帯が設けられます.
学生優秀発表賞へのエントリーも可能です.
詳しくは,https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/urgent
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2024山形大会]学生・若手のための交流会(9/7開催)
──────────────────────────────────
「学生・若手のための交流会」
日時:9月7日 (土) 16:30-19:00
場所:山形テルサ(山形市双葉町1-2-3)
地質学に携わる学生および若手の研究活動や交流の促進を目的とする集会です
.学術大会の前に全国の学生・若手と交流しましょう!
その他:交流会の詳細については,地質学会HP等で随時更新していきます.
このほか,2024山形大会では,巡検参加費補助やダイバーシティ認定ロゴ,
求職中シール等,今年も若手会員向けの様々な取り組みが行われます.
ぜひご確認ください.
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/youth
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2024山形大会]学生事前予約受付中:地質系業界説明会
──────────────────────────────────
2024年度学生のための地質系業界説明会
〜その業界の仕事を知るためのサポートサービス〜
対面説明会(9/9開催)・オンライン(9/13開催)
対面・オンラインで計50社以上の企業にご参加いただきます.
当日来場の参加も受け付けますが,事前予約の学生さんを優先します.
・対面説明会申込締切:8月29日(木)
・オンライン説明会申込締切:9月5日(木)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/gyokai_support
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■新しい論文が公開されています
(RESEARCH ARTICLE)Estimating the amount of uplift from the current
elevation of strata at the Middle Miocene Climatic Optimum: A case study
of Kibi Plateau in Southwest Japan; Yo-ichiro Otofuji ほか
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
※学会HP「会員ページ」(要ログイン)からアクセスすることで,IARは
全文無料で閲覧できます.
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】地質学雑誌からのお知らせ
──────────────────────────────────
■ 新しい論文が公開されています
(論説)西南日本の山陰バソリスに分布する高田花崗閃緑岩の地質学的
位置づけ:中山瀬那ほか
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/list/-char/ja
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)科学教育研究協議会 第70回全国研究大会・いわて花巻大会
8月7日(水)-9日(金)
会場:花巻市立花巻中学校/花巻市立若葉小学校/花巻市文化会館
(岩手県花巻市若葉町)
https://kakyokyo.org/
TGSG Business Meeting
8月27日(火)18:00-20:00
会場:IGC2024釜山(ハイブリッド)
問い合わせ先:IUGS海底ジオハザード・タスクグループ(議長:川村喜?郎)
詳しくは,
https://www.geosociety.jp/uploads/fckeditor/geoFlash_img/no629_BusinessMeeting240723.pdf
(後)第67回粘土科学討論会
9月4日(水)-9月6日(金)
会場:九州工業大学戸畑キャンパス(北九州市戸畑区仙水町1-1)
すべて対面で開催予定(講演会9月4-5日、現地見学会9月6日)
https://www.cssj2.org/event/annual_meeting/
★日本地質学会第131年学術大会(2024山形)
9月8日(日)-10日(火)
事前参加登録締切:8/20(火)18時
会場:山形大学小白川キャンパス
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131
(共)2024年度 日本地球化学会 第71回年会
9月18日(水)-20日(金)
会場:金沢大学・角間キャンパス(自然科学本館)
http://www.geochem.jp/meeting/
(協)地盤技術フォーラム2024
9月18日(水)-20日(金)10:00−17:00
場所:東京ビックサイト・東ホール(江東区有明3丁目)
http://www.sgrte.jp/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0246.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・高知大学海洋コア国際研究所教員(准教授、講師または助教)公募(9/3)
・令和6年度神奈川県職員採用選考(地質職(第2回);温泉地学研究所)(8/30)
・JAMSTEC Young Research Fellow 2025 公募(8/26)
・東京大学地震研究所共同利用「特定共同研究」研究課題の公募(8/26)
・東京大学地震研究所共同利用「特定機器利用」(9/30)
・2025年度先端国際共同研究推進事業(ASPIRE)日蘭共同研究提案募集【予告】
(25年春公募開始予定)
・日本アイソトープ協会奨励賞募集(10/31)
・第46回沖縄研究奨励賞推薦依頼(学会締切9/5)
・黒部市吉田科学館学芸員募集 (立山黒部ジオパーク)(9/30)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 630[2024山形大会]緊急展示:申込受付中(8/29締切)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.630 2024/8/20┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2024山形大会]緊急展示:申込受付中
【2】[2024山形大会]プログラム公開中
【3】[2024山形大会]まもなく講演要旨が公開となります
【4】[2024山形大会]学生事前予約受付中:地質系業界説明会
【5】[2024山形大会]学生・若手のための交流会(9/7開催)
【6】若手巡検 in 愛知県-岐阜県(10/26開催)
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2024山形大会]緊急展示:申込受付中
──────────────────────────────────
申込締切:8月29日(木)
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害調査報告
や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示」を設けます.
ポスター展示を希望する方は,8月29日(木)までにご連絡ください.
緊急展示は,正式な学会発表と同じく,コアタイムの時間帯が設けられます.
学生優秀発表賞へのエントリーも可能です.
詳しくは,https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/urgent
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2024山形大会]プログラム公開中
──────────────────────────────────
山形大会講演プログラムを公開中
講演検索はこちらから
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/search
タイムテーブルはこちらからhttps://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/table/2024-09-08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2024山形大会]まもなく講演要旨が公開となります
──────────────────────────────────
講演要旨(要ログイン)はまもなく公開予定です。
要旨公開までに、事前参加登録者の皆様に参加者用ログイン情報を
メールでお知らせするため,現在作業中です(8月末頃予定)。
入金確認が取れない場合は,参加者用ログイン情報が発行できません.
まだお支払いがお済みでない方は,急ぎご対応をお願いいたします.
また,領収書のダウンロードURLもメールでお知らせします.
山形大会:事前参加登録について
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/sanka
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2024山形大会]学生事前予約受付中:地質系業界説明会
──────────────────────────────────
2024年度学生のための地質系業界説明会
〜その業界の仕事を知るためのサポートサービス〜
対面説明会(9/9開催)・オンライン(9/13開催)
対面・オンラインで計50社以上の企業にご参加いただきます.
当日来場の参加も受け付けますが,事前予約の学生さんを優先します.
・対面説明会申込締切:8月29日(木)
・オンライン説明会申込締切:9月5日(木)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/gyokai_support
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2024山形大会]学生・若手のための交流会(9/7開催)
──────────────────────────────────
「学生・若手のための交流会」
日時:9月7日 (土)16:30-19:00(16:15より受付開始)
場所:山形テルサ 3F 大会議室(山形市双葉町1-2-3)
地質学に携わる学生および若手の研究活動や交流の促進を目的とする集会です。学術大会の前に全国から集まる学生・若手とお話しませんか?
参加者による自己紹介(希望者はスライド1枚まで使用可)の後、グループ
トーク、フリートークの場を設けます!
学生・若手の皆様、お誘いあわせのうえ,ぜひご参加ください!
※飲み物は各自お持ちください。
参加人数の把握のため、下記のURLから事前申し込みにご協力ください。
当日参加・途中参加も大歓迎です!!
URL:https://forms.gle/botdogmtApFSeWn78
このほか,2024山形大会では,巡検参加費補助やダイバーシティ認定ロゴ,
求職中シール等,今年も若手会員向けの様々な取り組みが行われます.
ぜひご確認ください.
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/youth
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】若手巡検 in 愛知県-岐阜県(10/26開催)
──────────────────────────────────
若手活動運営委員会では,愛知県犬山地域周辺にて学生・若手研究者向け
の巡検を行います.今年は日帰りで,三畳紀からジュラ紀の地層を観察し,
参加者の野外調査スキルや交流を深め研究活動を促進することを目的と
しています.
日時:2024年10月26日(土) 9時名古屋駅集合,18時半解散
対象者:35歳以下の日本地質学会正会員
参加費:
正会員(学生会員):3,250円
正会員(一般会員):6,500円
※正会員(学生会員)の参加費は,日本地質学会若手育成事業より半額が
補助されています.
申込締切:2024年9月27日(金)17時
詳しくは、 https://geosociety.jp/science/content0176.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)第67回粘土科学討論会
9月4日(水)-9月6日(金)
会場:九州工業大学戸畑キャンパス(北九州市戸畑区仙水町1-1)
すべて対面で開催予定(講演会9月4-5日、現地見学会9月6日)
https://www.cssj2.org/event/annual_meeting/
★日本地質学会第131年学術大会(2024山形)
9月8日(日)-10日(火)
事前参加登録締切:8/20(火)18時
会場:山形大学小白川キャンパス
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131
報告会「JAMSTEC2024」
9月11日(水)14:00-17:45
会場:東京国際フォーラム・ホールB7(千代田区丸の内3丁目)
オンライン配信:YouTube(日本語)及びzoom(英語同時通訳)
参加無料
https://www.jamstec.go.jp/j/pr-event/jamstec2024/
(共)2024年度 日本地球化学会 第71回年会
9月18日(水)-20日(金)
会場:金沢大学・角間キャンパス(自然科学本館)
http://www.geochem.jp/meeting/
(協)地盤技術フォーラム2024
9月18日(水)-20日(金)10:00−17:00
場所:東京ビックサイト・東ホール(江東区有明3丁目)
http://www.sgrte.jp/
堆積学スクール 2024
「安倍川源流域の大崩壊が流域の堆積作用と地形発達に与えた影響」
11月2日(土)午後-3日(月)夕方
場所:静岡県静岡市安倍川周辺地域
定員:13名(申し込みが多い場合は学生優先・会員優先)
参加申込締切:9月30日(月)
https://forms.gle/fEM1EK8cD6HWfohn6
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0246.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教員公募(9/24)
・島根大学学術研究院環境システム科学系(自然災害科学)教員公募(10/31)
・2025年度笹川科学研究助成募集(9/17-10/15)
・「環境研究総合推進費」令和7年度新規課題公募(10/18)公募説明会:8/23,9/20
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 631[2024山形大会]まもなく開幕!山形大会!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.631 2024/9/3┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2024山形大会]「参加者個別認証コード」をお知らせしました
【2】[2024山形大会]大会には「会員カード」持参して下さい
【3】[2024山形大会]領収書をダウンロードしてください(9/30まで)
【4】[2024山形大会]巡検案内書続々公開中!
【5】[2024山形大会]学生事前予約受付中:地質系業界説明会
【6】[2024山形大会]学生・若手のための交流会(9/7開催)
【7】若手巡検 in 愛知県-岐阜県(10/26開催)
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2024山形大会]「参加者個別認証コード」をお知らせしました
──────────────────────────────────
講演要旨が公開されています.講演要旨を閲覧するためには,confit大会サイトに
ログインしてください.confitアカウントID, パスワードは任意です.ただし,
初回ログイン時のみ「参加者個別認証コード」が必要です.
事前参加登録者に対して,「参加者個別認証コード」を参加申し込みをいただいた
アドレス宛に送信しましたので,ご確認ください.(8/31送信).
ログインURL:
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/login
山形大会(重要なお知らせ)参加者ログインの方法について
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2024山形大会]大会には「会員カード」持参して下さい
──────────────────────────────────
会員カードでの受付は,裏面バーコードを読み込むだけで簡単スピーディです.
ぜひ「会員カード」を持参してください.
当日「会員カード」をお持ちでない方(新入会の方,非会員の方,忘れた方等)
は,お名前で確認いたします.
(注)クーポン券等学会からの事前の郵送物はありません.
事前登録をしていない方は,会場(山形大学)で当日受付を行います.
参加登録費の有料・無料に関わらず備え付けの『参加登録票』に必要事項を記入し当日用受付で,手続きしてください.
当日の受付について
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/reception
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2024山形大会]領収書をダウンロードしてください(9/30まで)
──────────────────────────────────
参加費等の領収書は,大会サイトにログインして「領収書ダウンロード」
ページよりご確認いただけます.
***************
ダウンロード可能期間:2024/9/30まで
***************
*別途領収書(紙媒体等)が必要な方は,現地大会受付もしくは学会事務局まで
お申し出ください.
*巡検参加費の領収書は,当日案内者よりお渡しいたします.
*【インボイス制度への対応について】本会は登録番号を申請しておりません(課税事業者以外(免税事業者等)です).
領収書ダウンロードページ(要大会サイトログイン)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/receipt
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2024山形大会]巡検案内書続々公開中!
──────────────────────────────────
山形大会巡検各コースの巡検案内書は,J -STAGE(バーチャルIssue)で
順次公開しています.
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/virtualissue/100052/_contents/-char/ja
山形大会巡検について
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/excursion
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2024山形大会]学生事前予約締切延長:地質系業界説明会
──────────────────────────────────
2024年度学生のための地質系業界説明会
〜その業界の仕事を知るためのサポートサービス〜
対面説明会(9/9開催)・オンライン(9/13開催)
対面・オンラインで計50社以上の企業にご参加いただきます.
当日来場の参加も受け付けますが,事前予約の学生さんを優先します.
・対面説明会申込締切:9月5日(木)延長しました
・オンライン説明会申込締切:9月11日(水)延長しました
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/gyokai_support
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[2024山形大会]学生・若手のための交流会(9/7開催)
──────────────────────────────────
「学生・若手のための交流会」
日時:9月7日 (土)16:30-19:00(16:15より受付開始)
場所:山形テルサ 3F 大会議室(山形市双葉町1-2-3)
地質学に携わる学生および若手の研究活動や交流の促進を目的とする集会です。学術大会の前に全国から集まる学生・若手とお話しませんか?
参加者による自己紹介(希望者はスライド1枚まで使用可)の後、グループ
トーク、フリートークの場を設けます!
学生・若手の皆様、お誘いあわせのうえ,ぜひご参加ください!
※飲み物は各自お持ちください。
参加人数の把握のため、下記のURLから事前申し込みにご協力ください。
当日参加・途中参加も大歓迎です!!
URL:https://forms.gle/botdogmtApFSeWn78
このほか,2024山形大会では,巡検参加費補助やダイバーシティ認定ロゴ,
求職中シール等,今年も若手会員向けの様々な取り組みが行われます.
ぜひご確認ください.
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/youth
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】若手巡検 in 愛知県-岐阜県(10/26開催)
──────────────────────────────────
若手活動運営委員会では,愛知県犬山地域周辺にて学生・若手研究者向け
の巡検を行います.今年は日帰りで,三畳紀からジュラ紀の地層を観察し,
参加者の野外調査スキルや交流を深め研究活動を促進することを目的と
しています.
日時:2024年10月26日(土) 9時名古屋駅集合,18時半解散
対象者:35歳以下の日本地質学会正会員
参加費:
正会員(学生会員):3,250円
正会員(一般会員):6,500円
※正会員(学生会員)の参加費は,日本地質学会若手育成事業より半額が
補助されています.
申込締切:2024年9月27日(金)17時
詳しくは、 https://geosociety.jp/science/content0176.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)第67回粘土科学討論会
9月4日(水)-9月6日(金)
会場:九州工業大学戸畑キャンパス(北九州市戸畑区仙水町1-1)
すべて対面で開催予定(講演会9月4-5日、現地見学会9月6日)
https://www.cssj2.org/event/annual_meeting/
★日本地質学会第131年学術大会(2024山形)
9月8日(日)-10日(火)
事前参加登録締切:8/20(火)18時
会場:山形大学小白川キャンパス
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131
(共)2024年度 日本地球化学会 第71回年会
9月18日(水)-20日(金)
会場:金沢大学・角間キャンパス(自然科学本館)
http://www.geochem.jp/meeting/
(協)地盤技術フォーラム2024
9月18日(水)-20日(金)10:00−17:00
場所:東京ビックサイト・東ホール(江東区有明3丁目)
http://www.sgrte.jp/
第246回イブニングセミナー(オンライン)
9月27日(金)19:30-21:30
演題:「住む街で考える土と水の科学ー貝塚をヒントとしてー」
講師:宮崎 毅先生(東京大学名誉教授、もりや市民大学学長、当NPO理事)
参加費:主催NPO会員及び学生の方(無料) 非会員の方(1,000円)
https://www.npo-geopol.or.jp/seminer.htm
jGnet地質学講座2024 地質学の最新研究を学ぶ(ライブ配信あり)
10月5日(土)13:00-16:30
形式:対面方式及びライブ配信(JCCAのCPD認定プログラム202408210016)
会場:岡山理科大学A0133教室(A1号館3階)
講演1「過去のプレート沈み込み帯で形成した変成岩とその地質記録」:辻森樹氏
(東北大学教授)/講演2「最新・日本列島と東アジアのテクトニクス:大・南中国
と大和構造線」:磯崎行雄氏(東京大学名誉教授)
申込締切:9月30日(月),
参加費3,000円(※学生・一般の聴講は無料)
詳細はこちらhttps://jgnet.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0246.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・深田地質研究所 2024年度研究員募集(10/31)
・山梨県職員(火山防災職[大学院卒程度])選考採用試験(10/9受験手続締切)
・原子力規制庁実務経験者採用公募(研究職)(10/31)
・原子力規制庁実務経験者採用公募(技術系・事務系)(10/31)
・島根大学学術研究院環境システム科学系(地球環境科学)教員公募
(9/30)【期間延長】
・山田科学振興財団募集2025年度海外研究援助公募(10/31)
・中谷医工計測技術振興財団【科学教育振興助成】募集(10/1-11/30)
・中谷医工計測技術振興財団【次世代理系人材育成プログラム助成】募集
(10/1-11/30)
・2024年度「第45回猿橋賞」受賞候補者の推薦依頼(11/30)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 632[2024山形大会]写真アップしました!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬
┬┴┬┴┬┴┬ No.632 2024/9/9┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 山形大会の様子
──────────────────────────────────
地質情報展
市民講演会
山形駅でも!
大学入り口
シンポジウム
ジュニアセッション
表彰式会場
会長挨拶
学長挨拶
名誉会員
永年会員
都城秋穂賞
H.E.ナウマン賞
小澤義明賞
柵山雅則賞
Island Arc Award
論文賞
小藤文次郎賞
地質学雑誌特別賞
研究奨励賞
日本地質学会表彰
特別講演
懇親会
ポスター会場
地質系業界説明会
地質遺産説明会
企業ブース
口頭発表会場
ポスター会場
【geo-Flash】 No. 633 若手巡検 in 愛知県-岐阜県(参加申込受付中)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.633 2024/9/17┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2024山形大会]学術大会終了しました
【2】若手巡検 in 愛知県-岐阜県(参加申込受付中!)
【3】第17回日本地学オリンピック:参加申込受付中
【4】支部のお知らせ
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2024山形大会]学術大会終了しました
──────────────────────────────────
9/7プレ巡検に始まり,9/8-10,口頭,ポスターセッション,ポスト巡検,
9/13地質系業界説明会(オンライン)等々,予定された全ての行事が実施され,
無事終了致しました.大会にご参加頂きました皆様に心より御礼申し上げます.
大会の様子(写真など)は,メルマガ臨時号(学会HP)でもご紹介しています.
・No.632(臨時)No. 632[2024山形大会]写真アップしました!
https://geosociety.jp/faq/content1172.html
またニュース誌11月号に大会報告記事を掲載予定です.
講演要旨は,現在大会参加者限定公開(要ログイン)となっています.
来月10日以降無料公開を予定しています.
(大会サイト)https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131
----------------------------------
来年は熊本でお会いしましょう!
日本地質学会第132年学術大会(2025熊本)
会場:熊本大学黒髪地区
日程:2025年9月14日(日)-16日(火)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】若手巡検 in 愛知県-岐阜県(参加申込受付中!)
──────────────────────────────────
若手活動運営委員会では,愛知県犬山地域周辺にて学生・若手研究者向け
の巡検を行います.今年は日帰りで,三畳紀からジュラ紀の地層を観察し,
参加者の野外調査スキルや交流を深め研究活動を促進することを目的と
しています.
日時:2024年10月26日(土) 9時名古屋駅集合,18時半解散
対象者:35歳以下の日本地質学会正会員
参加費:
正会員(学生会員):3,250円
正会員(一般会員):6,500円
※正会員(学生会員)の参加費は,日本地質学会若手育成事業より半額が
補助されています.
申込締切:2024年9月27日(金)17時
詳しくは、 https://geosociety.jp/science/content0176.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】第17回日本地学オリンピック:参加申込受付中
──────────────────────────────────
募集期間:9月1日-11月15日
参加費無料
参加資格:小学生・中学生・高校生
(ただし,本戦に進めるのは中学3年生から高校2年生の生徒のみ)
(一次予選)2024年12月15日(日) オンライン試験
(二次予選)2025年1月26日(日) 全国指定会場にて実施予定
(本選)2025年3月9日(日)-11日(火) (茨城県つくば市)
詳しくは,https://jeso.jp/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[関東支部]
・講演会「県の石−東京都の岩石・鉱物・化石−」
2024年11月10日(日)13:00-16:00
対象 会員及び非会員 小学生3年生以上(内容は大人向けです)
定員 現地100名、オンライン100名
申込期間:2024年10月11日(金)-31日(木)17:00締切
・家族巡検「葛生化石館と周辺の石灰岩の見学」
2024年10月27日(日)10:36-16:09(時刻は電車の時間)
昼食持参,小雨決行,荒天中止
場所:葛生化石館(石灰岩磨き体験を含む)および嘉多山公園.
講師:奥村よほ子 学芸員
申込期間:2024年9月27日(金)-10月17日(木)17:00締切
詳しくは,
https://geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
地質地盤情報の活用と法整備を考える会
・広報冊子を「考える会」からのメッセージに掲載しました.
・6機関に協力会員にご登録をいただきました
(日本地質学会/日本地球惑星科学連合/北海道立総合研究機構エネルギー・環境・
地質研究所/地中熱利用促進協会/日本地震工学会/ 地盤工学会)
https://www.geo-houseibi.jp/
—-----------------------------------
(共)2024年度 日本地球化学会 第71回年会
9月18日(水)-20日(金)
会場:金沢大学・角間キャンパス(自然科学本館)
http://www.geochem.jp/meeting/
(協)地盤技術フォーラム2024
9月18日(水)-20日(金)10:00−17:00
場所:東京ビックサイト・東ホール(江東区有明3丁目)
http://www.sgrte.jp/
東京地学協会2024年度定期講演会
「硝酸性窒素による地下水汚染問題の過去・現在・未来」
10月5日(土)14:00-16:15(申込不要)
場所:地学会館2階講堂(千代田区二番町)
講師1:林健太郎(総合地球環境学研究所)「窒素問題に対する世界の取り組み
とその地下水硝酸性窒素汚染への影響」/講師2:羽賀清典(畜産環境整備機構)
「家畜排せつ物処理と地下水の硝酸性窒素汚染」
http://www.geog.or.jp/
【JST】2025年度ASPIRE日蘭共同研究提案募集に向けたネットワーキングイベント
11月25日(月)-27日(水)
ASPIREは、優秀な若手研究者等の科学技術先進国への渡航や海外からの若手研究者
の招へい、トップレベルの国際共同研究を支援します。
参加対象者:日蘭共同公募「革新的な情報処理技術のための日蘭共同研究」に
関心のある研究者
https://www.jst.go.jp/aspire/event/event_aspire2025_nl.html
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0246.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・Dodson Prize/Laslett Prize/Charles&Nancy Naeser Prize候補者募集(12/1)
※これらの賞は,第19回国際熱年代学会議(Thermo2025,日本地質学会共催)
で授与されます.
・2024年度「第45回猿橋賞」受賞候補者募集(11/30)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 634(臨時)いわゆる「雇い止め問題」についてのアンケート協力依頼
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.634 2024/9/19┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】いわゆる「雇い止め問題」についてのアンケート協力依頼
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】いわゆる「雇い止め問題」についてのアンケート協力依頼
──────────────────────────────────
会員各位
現在、日本全国で研究者が雇用の10年特例ルールのもと「雇い止め問題」に
直面しています。
そこで、以下のように、下記の学会・団体で「雇い止め問題」に関する
緊急的なアンケートが展開されています。
皆様にはご回答いただくとともに、特に若手研究者や関係する方々へ
転送していただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
*************
アンケート回答フォーム:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ5g_2l7zKrTD4wCYd6vRT-x9MM2eYvSVDMWd2eQGrXjrU4Q/viewform
*************
アンケート回答期日:9月23日(月)
*************
日本地質学会ジェンダー・ダイバーシティ委員会
委員長 天野敦子
---------------Original Message---------------
加盟学協会の皆様
この度、神経科学会の呼びかけで、標記のアンケートを実施することになりました
ので、各学協会の会員の皆様に周知をお願いします。
アンケートについての説明はリンク先に記載されておりますので、お読みになって、
差し支えなければアンケートにお答えしていたたけますと幸いです。
結果は9月25日に盛山文部科学大臣に提出する予定です。
*9月23日までに*ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ5g_2l7zKrTD4wCYd6vRT-x9MM2eYvSVDMWd2eQGrXjrU4Q/viewform
東原和成
生物科学学会連合代表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 635 2025年度学会各賞候補者募集受付開始
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.635 2024/10/1┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2025年度学会各賞候補者募集受付開始
【2】[2024山形大会]学生優秀発表賞ほか決定!
【3】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【4】支部のお知らせ
【5】その他のお知らせ
【6】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2025年度学会各賞候補者募集受付開始
──────────────────────────────────
運営規則第16 条および各賞選考規則に基づき,賞の候補者を募集いたします.
ご推薦いただいた方の中から,各賞選考委員会(委員は理事会の互選と職責に
より選出)が候補者を選考し,理事会での決定,総会での承認を経て表彰を行
います.期日厳守にてご推薦ください.個人(正会員または名誉会員)からの
推薦も可能です.
************************
応募締切:2024年12月2日(月)必着
************************
※昨年度の各賞選考委員会および各賞選考検討委員会の引き継ぎ・要望事項を
踏まえて,表彰制度検討WGおよび執行理事会で検討した結果,表彰制度に関連
して修正を加えることとなりました.
詳しくは,https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2024山形大会]学生優秀発表賞ほか決定!
──────────────────────────────────
34件の発表が「学生優秀発表賞」に決定しました(エントリー総数134件).
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/youth#yushusho
日本地質学会ジュニアセッション優秀賞,奨励賞も決定しました.
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131/content/gyoji#jr
大会サイトより,賞の名称で講演検索も可能です.
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
──────────────────────────────────
[地質学雑誌]
■ 新しい論文が公開されています
(報告)天草の姫浦層群は暁新統をふくむのか?:牛丸健太郎, 山路 敦
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/list/-char/ja
[Island Arc]
■Wileyとオープンアクセス転換契約を締結している研究機関(下記リンク)に
所属する著者は、機関の費用負担でオープンアクセスとして論文を公表できる
可能性があります。詳細については、所属機関のAPC支援事業担当者にお問い
合わせください。
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/affiliation-policies-payments/institutional-funder-payments.html#Japan
■ 新しい論文が公開されています
(REVIEW ARTICLE)Bringing the Submarine Mariana Arc and Backarc Basin
to Life for Undergraduates and the Public;Robert J. Stern
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[関東支部]
・講演会「県の石−東京都の岩石・鉱物・化石−」
2024年11月10日(日)13:00-16:00
対象 会員及び非会員 小学生3年生以上(内容は大人向けです)
定員 現地100名、オンライン100名
申込期間:2024年10月11日(金)-31日(木)17:00締切
・家族巡検「葛生化石館と周辺の石灰岩の見学」
2024年10月27日(日)10:36-16:09(時刻は電車の時間)
昼食持参,小雨決行,荒天中止
場所:葛生化石館(石灰岩磨き体験を含む)および嘉多山公園.
講師:奥村よほ子 学芸員
申込期間:2024年9月27日(金)-10月17日(木)17:00締切
詳しくは,
https://geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
日本学術会議主催学術フォーラム
「未来の学術振興構想−実現に向けて−」
10月4日(金)
場所:日本学術会議講堂(オンライン配信)
参加費無料
https://www.scj.go.jp/ja/event/2024/364-s-1004.html
防災科研令和6年度成果発表会
「国土の安全と防災連携」
10月11日(金)13:00-17:00
場所:東京国際フォーラム・ホールB5(オンライン配信)
参加無料
https://www.bosai.go.jp/info/event/2024/seika/index.html
第41回地質調査総合センターシンポジウム
デジタル技術で繋ぐ地質情報と防災対策〜活断層-火山-斜面災害-海洋地質〜
10月25日(金)10:00〜17:00
会場:イイノホール& カンファレンスセンター(東京都千代田区内幸町)
定員:現地200名+オンライン500名(ともに事前登録制、定員になり次第締切)
参加費無料
https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo41/index.html
深田研一般公開2024
10月27日(日)10:00-16:00
会場:深田地質研究所(東京都文京区本駒込2-13-12)
ラボツアーやミニレクチャー、アンモナイトアクセサリー製作などの
体験学習も豊富に用意しています.
入場無料
https://fukadaken.or.jp/?p=8452
国立国会図書館主催フォーラム
オープンサイエンスを社会につなぐために―国立国会図書館の取組を踏まえて
(図書館総合展2024)
11月6日(水)13:00-14:30
場所:パシフィコ横浜 アネックスホール(横浜市西区みなとみらい1-1-1)
参加費無料,定員200名・要事前申込
https://www.libraryfair.jp/forum/2024/1075
(協)石油技術協会 令和6年度秋季講演会
「低炭素エネルギーシステムの社会実装に向けて〜水素・アンモニア〜」
11月12日(火) 10:30-17:30
場 所: 東京大学 小柴ホール(ハイブリッド開催)
参加費:3,000円:石油技術協会会員、賛助会員、協賛団体(所属者)
※地質学会の会員は上記金額で参加可能です.
https://www.japt.org/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0246.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・東京大学地震研究所特任研究員(ポスドク)公募: 科研費(基盤研究S)研究課題「海山の沈み込みは巨大地震域の固着を弱めるか:南海トラフの2海山での検証」
(9/30)
・2025年度東京大学地震研究所客員教員公募(10/31)
・産業技術総合研究所地質調査総合センター2024年度第2回研究職公募(10/10)
・京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻 資源工学講座 地殻開発工学分野
准教授公募(10/31)
・産総研イノベーションスクール人材育成コース(博士研究員20名程度)の募集
(25/1/6)
・2025年度東京大学地震研究所共同利用(10/31)
・Martin Dodson Prize/Geoff Laslett Priz/Charles & Nancy Naeser Prize候補者
募集(12/1)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No. 637 2025年度会費払込/学生会費の申請受付
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.637 2024/10/15┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2025年度学会各賞候補者募集受付中
【2】2025年度の会費払込について
【3】2025年度学生会費の申請受付(12/2(月)締切厳守)
【4】[2024山形大会]10/11より講演要旨無料公開
【5】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【6】支部のお知らせ
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2025年度学会各賞候補者募集受付中
──────────────────────────────────
運営規則第16 条および各賞選考規則に基づき,賞の候補者を募集いたします.
ご推薦いただいた方の中から,各賞選考委員会(委員は理事会の互選と職責に
より選出)が候補者を選考し,理事会での決定,総会での承認を経て表彰を行
います.期日厳守にてご推薦ください.個人(正会員または名誉会員)からの
推薦も可能です.
************************
応募締切:2024年12月2日(月)必着
************************
※昨年度の各賞選考委員会および各賞選考検討委員会の引き継ぎ・要望事項を
踏まえて,表彰制度検討WGおよび執行理事会で検討した結果,表彰制度に関連
して修正を加えることとなりました.
詳しくは,https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
(※会員システムへのログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2025年度の会費払込について
──────────────────────────────────
運営規則により,2025年度の事業年度(会費年度:2025年4月-2026年3月)が
始まる前までに納入下さいますようお願いいたします.
(1)自動引落を登録されている方の引落日は,12月23日(月)です.
(2)一般会員・シニア会員の方は,自動引落をご利用ください(申込は随時受付).
今回お申込みいただいた方は,2025年6月の督促請求時に引落させていただきます.
(3)お振り込みの方:12月中旬までに請求書兼郵便振替用紙を発送いたします.
お手元に届きましたら,折り返しご送金下さいますようお願いいたします.
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0239.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2025年度学生会費の申請受付(12/2(月)締切厳守)
──────────────────────────────────
運営規則により,学部学生・院生は,本人の申請により「学生会員」としての
会費が適用されます.必要に応じてお手続きください.
申請期間の延長・再受付はありません.希望者は忘れずに申請してください.
学生会員の会費額は次の通りです.
単年度:5,000円/2年パック:8,000円/3年パック:9,000円
※2025年度会費請求分の申請です.過去年度に遡っての申請はお受けできません.
※これから入会される方は,入会時に別途お手続きください(新入会に期日は
ありません.入会時にパック料金等を受付ます).
対象となる方,申請フォーム等,詳しくは,
https://geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2024山形大会]10/11より講演要旨無料公開
──────────────────────────────────
京都大会講演要旨は,10/11より無料公開となりました.
大会参加者ログイン無しで,どなたでも閲覧,ダウンロード可能です.
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp131
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
──────────────────────────────────
[地質学雑誌]
■ 新しい論文が公開されています
(巡検案内書)大野希一:火山噴火と自然、文化との関わり–鳥海山・飛島
ジオパーク
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/list/-char/ja
[Island Arc]
■Wileyとオープンアクセス転換契約を締結している研究機関(下記リンク)に
所属する著者は、機関の費用負担でオープンアクセスとして論文を公表できる
可能性があります。詳細については、所属機関のAPC支援事業担当者にお問い
合わせください。
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/affiliation-policies-payments/institutional-funder-payments.html#Japan
■ 新しい論文が公開されています
(RESEARCH ARTICLE)Geochemical Signatures of Igneous Zircon and Apatite:
Generation of Archean TTGs in the Barberton Granitoid-Greenstone Terrain, South
Africa;Shiho Miyakeet al
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[関東支部]
・講演会「県の石−東京都の岩石・鉱物・化石−」
2024年11月10日(日)13:00-16:00
対象:会員及び非会員 小学生3年生以上(内容は大人向け)
定員:現地100名、オンライン100名
申込期間:2024年10月11日(金)-31日(木)17:00締切
・家族巡検「葛生化石館と周辺の石灰岩の見学」
2024年10月27日(日)10:36-16:09(時刻は電車の時間)
昼食持参,小雨決行,荒天中止
場所:葛生化石館(石灰岩磨き体験を含む)および嘉多山公園
講師:奥村よほ子 学芸員
申込期間:2024年9月27日(金)-10月17日(木)17:00締切
詳しくは,
https://geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
日本珪藻学会第43回研究集会
公開シンポジウム「珪藻が出ない!」
10月20日(日) 10:30-13:00
会場:琵琶湖博物館セミナー室(滋賀県草津市下物町1091)+Zoom
参加申込10/17(木)まで:https://forms.gle/hwbxo2W1UN8uCDj99
https://diatomology.org/
(協)石油技術協会令和6年度秋季講演会
「低炭素エネルギーシステムの社会実装に向けて〜水素・アンモニア〜」
11月12日(火) 10:30-17:30
会場: 東京大学 小柴ホール(ハイブリッド開催)
参加費:3,000円:石油技術協会会員、賛助会員、協賛団体(所属者),学生無料
※地質学会の会員は上記金額で参加可能です.
https://www.japt.org/
(後)ポール・ホフマン博士京都賞受賞記念講演(東京・駒場)
11月14日(木)17:00-19:00 (開場:16:00)
会場:東京大学駒場キャンパス 21KOMCEE EAST K011(地下)
要事前申込(10/19締切),入場無料
https://geosociety.jp/news/n185.html
学術会議公開シンポジウム「海底地質災害と洋上風力開発」
11月14日(木)10:00-18:00
会場:日本学術会議講堂およびオンライン配信
要参加申込
https://www.kiso.co.jp/sssgr/topics/events/entry-1155.html
第63回温泉保護・管理研修会
11月18日(月)-19日(火)
場所:北とぴあ つつじホール(東京都北区王子)
主催:公益財団法人中央温泉研究所
後援:環境省
http://www.onken.or.jp/seminar.html
原子力発電環境整備機構(NUMO)講演会
地層処分事業の推進と安全コミュニケーションにおける世代を超えた挑戦
11月22日(金)13:00-16:30
Zoom Video Webinarによるオンライン開催
参加無料,定員100名(先着)(申込締切:11月13日(水)13:00)
詳しくは,
https://www.numo.or.jp/topics/202424101113.html
(後)日本応用地質学会令和6年度技術者倫理講習会
11月27日(水)13:30-17:00
Zoomによるオンライン講習会(質疑応答可能なライブ配信)
定員500名
要事前申込(11月19日締切,先着順)
参加費:応用地質学会会員等:2,000円,非会員6,000円
https://forms.gle/7SxymxsYuB37hSiR7
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0246.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・深田地質研究所2024年度職員募集
※ニュース誌9月号掲載の情報に誤りがありました.
(誤)任期付研究員募集→(正)任期なし,常勤の研究員
・東北大学大学院理学研究科地学専攻・助教の公募
・早稲田大学教育・総合科学学術院(地球系)<技術職>常勤嘱託職員募集
・山田科学振興財団2025年度研究援助候補者推薦依頼(学会締切2/3)
※このほか「女性活躍支援枠」「チャレンジ支援枠」もあります.
・第4回羽ばたく女性研究者賞(マリア・スクウォドフスカ=キュリー賞)公募
・第66回藤原賞候補者募集(学会締切11/29)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No. 638(臨時)JpGU2025セッション提案募集(10/29締切)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.638 2024/10/17┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】JpGU2025セッション提案募集(10/29締切)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】JpGU2025セッション提案募集(10/29締切)
──────────────────────────────────
JpGU2025でセッション提案を予定している方で,地質学会共催を希望される
場合は,併行して下記の地質学会JpGUプログラム委員にご連絡いただきます
ようお願い致します。すでにJpGUへ提案済みの場合も,これからでも結構です
ので,プログラム委員に連絡をお願い致します.
(各部会行事委員を通して既にご連絡済みの場合はそちらで承ります)
日本地質学会JpGUプログラム委員:
宇野正起(岩石部会選出行事委員)masa.uno[at]tohoku.ac.jp
野々垣進(情報地質部会選出行事委員)s-nonogaki[at]aist.go.jp
(注)[at]を@マークにしてください
[ご連絡いただく内容]
・タイトル:
・スコープ:
・代表コンビーナ(1名):
・共同コンビーナ(3名まで):
[セッション提案締切]2024年10月29日(火)17:00
JpGU(日本語版)https://www.jpgu.org/meeting_j2025/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 639 惑星地球フォトコンテスト応募受付中
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.639 2024/11/5┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2025年度学会各賞候補者募集受付中
【2】2025年度の会費払込について
【3】2025年度学生会費の申請受付(12/2(月)締切厳守)
【4】第16回惑星地球フォトコンテスト応募受付中
【5】地質系若者のためのキャリアビジョン誌2024 原稿募集中
【6】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【7】支部のお知らせ
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】訃報 佐藤 正名誉会員ご逝去
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2025年度学会各賞候補者募集受付中
──────────────────────────────────
運営規則第16 条および各賞選考規則に基づき,賞の候補者を募集いたします.
ご推薦いただいた方の中から,各賞選考委員会(委員は理事会の互選と職責に
より選出)が候補者を選考し,理事会での決定,総会での承認を経て表彰を行
います.期日厳守にてご推薦ください.個人(正会員または名誉会員)からの
推薦も可能です.
************************
応募締切:2024年12月2日(月)必着
************************
※昨年度の各賞選考委員会および各賞選考検討委員会の引き継ぎ・要望事項を
踏まえて,表彰制度検討WGおよび執行理事会で検討した結果,表彰制度に関連
して修正を加えることとなりました.
詳しくは,https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
(※会員システムへのログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2025年度の会費払込について
──────────────────────────────────
運営規則により,2025年度の事業年度(会費年度:2025年4月-2026年3月)が
始まる前までに納入下さいますようお願いいたします.
(1)自動引落を登録されている方の引落日は,12月23日(月)です.
(2)一般会員・シニア会員の方は,自動引落をご利用ください(申込は随時受付).
今回お申込みいただいた方は,2025年6月の督促請求時に引落させていただきます.
(3)お振り込みの方:12月中旬までに請求書兼郵便振替用紙を発送いたします.
お手元に届きましたら,折り返しご送金下さいますようお願いいたします.
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0239.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2025年度学生会費の申請受付(12/2(月)締切厳守)
──────────────────────────────────
運営規則により,学部学生・院生は,本人の申請により「学生会員」としての
会費が適用されます.必要に応じてお手続きください.
申請期間の延長・再受付はありません.希望者は忘れずに申請してください.
学生会員の会費額は次の通りです.
単年度:5,000円/2年パック:8,000円/3年パック:9,000円
※2025年度会費請求分の申請です.過去年度に遡っての申請はお受けできません.
※これから入会される方は,入会時に別途お手続きください(新入会に期日は
ありません.入会時にパック料金等を受付ます).
***************************
申請締切:2024年12月2日(月)
***************************
対象となる方,申請フォーム等,詳しくは,
https://geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第16回惑星地球フォトコンテスト応募受付中
──────────────────────────────────
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
会員の皆様からの応募もお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
*********************************
応募締切:2025年2月2日
*********************************
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質系若者のためのキャリアビジョン誌2024 原稿募集中
──────────────────────────────────
日本地質学会は,地質学を専攻とする国内44の大学の2,200名以上の学生と院生に
専門職の魅力を伝える情報誌「地質系若者のためのキャリアビジョン誌2024」を
刊行します.各大学では,この冊子をキャリア教育の教材として活用頂いており,
そして多くの学生・院生から専門職を知る機会になったとの声が届いております.
本冊子への協賛と原稿提供をご検討ください.
締切:2024年12月20日(金)
配布:2025年1月下旬
詳しくは,https://photo.geosociety.jp/career2.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
──────────────────────────────────
[地質学雑誌]
■ 新しい論文が公開されています
(特別寄稿)磯崎行雄:先カンブリア時代を踏破する:2024年「京都賞」受賞者
Paul F. Hoffman博士の地質学的挑戦
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/list/-char/ja
[Island Arc]
■ 新しい論文が公開されています
(REVIEW ARTICLE)Recent Efforts to Improve the Accuracy and Precision of
Carbonate Clumped‐Isotope Analysis; Kazuma Oikawa et al/
(RESEARCH ARTICLE) Zircon Trace‐Element Compositions in Cenozoic
Granitoids in Japan: Revised Discrimination Diagrams for Zircons in I‐Type,
S‐Type, and A‐Type Granites; Yusuke Sawaki et al
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[関東支部]
・2024年度関東支部功労賞募集
対象者:支部活動や地質学を通して広く社会貢献をされた関東支部内に在住の
個人・団体 *社会貢献や活動の評価においては,必ずしも学問的な成果を問う
ものではありません.
公募期間:2024年12月16日(月)から2025年1月17日(金)
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0201.html#2024koro
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(協)石油技術協会令和6年度秋季講演会
「低炭素エネルギーシステムの社会実装に向けて〜水素・アンモニア〜」
11月12日(火) 10:30-17:30
会場: 東京大学 小柴ホール(ハイブリッド開催)
参加費3,000円:石油技術協会会員,賛助会員,協賛団体(所属者)/学生無料
※地質学会の会員は上記金額で参加可能です.
https://www.japt.org/
「堆積構造の世界」連続講義:第1回 堆積構造の基礎
11月19日(火)18時から
Zoomウェビナーオンライン開催(参加無料・要事前申込)
コーディネーター:石原与四郎 先生
講師:横川美和 先生,山口直文 先生,成瀬 元 先生
https://sites.google.com/view/taisekigakukougi?usp=sharing
国際シンポジウム
未来社会のための堅牢なサイバーライフライン
11月21日(木)-22日(金)13:00-17:00
会場 富士山科学研究所(山梨県富士吉田市字吉田)
※ハイブリッド開催 参加無料
https://www.mfri.pref.yamanashi.jp/kazan/sp/
深田研談話会
誘発地震の実態と応用:フィールドデータ解析から大型試験片による再現実験まで
11月22日(金)15:00-16:30(14:30開場)
講師:伊藤 高敏 氏(東北大学)
定員:会場参加(30名)・オンライン参加(上限450名),先着順
参加費:無料(要事前申込)
申込締切: 11月15日(金)17時締切 ※募集人数に達し次第締め切ります
https://fukadaken.or.jp/?p=8536
(後)日本応用地質学会令和6年度技術者倫理講習会
11月27日(水)13:30-17:00
Zoomによるオンライン講習会(質疑応答可能なライブ配信)
定員500名
要事前申込(11月19日締切,先着順)
参加費:応用地質学会会員等:2,000円,非会員6,000円
https://www.jseg.or.jp/02-committee/jseg-edu.html
「環境研究総合推進費」若手研究者による研究成果発表会
主催:環境再生保全機構
11月29日(金)13:30-16:40(オンライン)
参加費無料,要事前申込
https://www.erca.go.jp/suishinhi/kenkyuseika/kenkyuseika_2_r6.html
【JST】ASPIRE Japan-UK Quantum Technology ネットワーキングイベント
12月6日(金)18:30-21:00
開催形式:オンライン(Zoom)
使用言語:英語
参加費無料(要事前申込:11月8日(金)17時締切)
https://www.jst.go.jp/aspire/event/event_aspire2024_uk.html
(後)一般公開講座:大地を分ける「武山断層」
12月21日(土)小雨決行 9:30-15:30
主催:三浦半島活断層調査会
見学参加者募集中(12/17締切)
参加費:500円
https://geosociety.jp/uploads/fckeditor/others-pdf/241221takeyama.pdf
********
2025年
********
海と地球のシンポジウム2024
3月12日(水)-13日(木)
*懇親会:3/12 夕方に予定
開催方法:口頭発表,ポスター発表ともに実会場にて実施
実会場:東京大学弥生キャンパス 弥生講堂
発表課題募集締切:2024年12月13日(金)
https://www.jamstec.go.jp/j/pr-event/ocean-and-earth2024/
(後)第62回アイソトープ・放射線研究発表会
7月2日(水)-4日(金)
会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
発表申込締切:2月28日(金)12時
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/jrias2025
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0246.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・海上保安庁海洋情報部任期付職員(研究官)の募集(11/29)
・海洋研究開発機構超先鋭研究開発部門高知コア研究所 PD公募(10/31)
・山形大学理学部(地球科学分野)准教授or講師(テニュアトラック教員)公募
(11/15)
・北海道大学大学院理学研究院地球惑星科学部門助教公募(12/13)
・金沢大学岩石学および関連する鉱物学,火山学,鉱物資源学など分野 女性限定
テニュアトラック助教公募(25/1/10)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】訃報 佐藤 正名誉会員ご逝去
──────────────────────────────────
佐藤 正 名誉会員(筑波大学名誉教授,元深田地質研究所理事長,
元日本地質学会副会長)が,令和6年9月15日に逝去されました(96歳).
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます.
.
会長 山路 敦
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 640 2025年度学生会費の申請受付中(12/2締切厳守)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.640 2024/11/19┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2025年度学会各賞候補者募集受付中(12/2締切)
【2】2025年度の会費払込について
【3】2025年度学生会費の申請受付中(12/2締切厳守)
【4】第16回惑星地球フォトコンテスト応募受付中
【5】地質系若者のためのキャリアビジョン誌2024 原稿募集中
【6】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【7】支部のお知らせ
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2025年度学会各賞候補者募集受付中(12/2締切)
──────────────────────────────────
運営規則第16 条および各賞選考規則に基づき,賞の候補者を募集いたします.
ご推薦いただいた方の中から,各賞選考委員会(委員は理事会の互選と職責に
より選出)が候補者を選考し,理事会での決定,総会での承認を経て表彰を行
います.期日厳守にてご推薦ください.個人(正会員または名誉会員)からの
推薦も可能です.
************************
応募締切:2024年12月2日(月)必着
************************
※昨年度の各賞選考委員会および各賞選考検討委員会の引き継ぎ・要望事項を
踏まえて,表彰制度検討WGおよび執行理事会で検討した結果,表彰制度に関連
して修正を加えることとなりました.
詳しくは,https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
(※会員システムへのログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2025年度の会費払込について
──────────────────────────────────
運営規則により,2025年度の事業年度(会費年度:2025年4月-2026年3月)が
始まる前までに納入下さいますようお願いいたします.
(1)自動引落を登録されている方の引落日は,12月23日(月)です.
(2)一般会員・シニア会員の方は,自動引落をご利用ください(申込は随時受付).
今回お申込みいただいた方は,2025年6月の督促請求時に引落させていただきます.
(3)お振り込みの方:12月中旬までに請求書兼郵便振替用紙を発送いたします.
お手元に届きましたら,折り返しご送金下さいますようお願いいたします.
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0239.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2025年度学生会費の申請受付中(12/2締切厳守)
──────────────────────────────────
運営規則により,学部学生・院生は,本人の申請により「学生会員」としての
会費が適用されます.必要に応じてお手続きください.
申請期間の延長・再受付はありません.希望者は忘れずに申請してください.
学生会員の会費額は次の通りです.
単年度:5,000円/2年パック:8,000円/3年パック:9,000円
※2025年度会費請求分の申請です.過去年度に遡っての申請はお受けできません.
※これから入会される方は,入会時に別途お手続きください(新入会に期日は
ありません.入会時にパック料金等を受付ます).
***************************
申請締切:2024年12月2日(月)
***************************
対象となる方,申請フォーム等,詳しくは,
https://geosociety.jp/outline/content0185.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第16回惑星地球フォトコンテスト応募受付中
──────────────────────────────────
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
会員の皆様からの応募もお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
*********************************
応募締切:2025年2月2日
*********************************
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質系若者のためのキャリアビジョン誌2024 原稿募集中
──────────────────────────────────
日本地質学会は,地質学を専攻とする国内44の大学の2,200名以上の学生と院生に
専門職の魅力を伝える情報誌「地質系若者のためのキャリアビジョン誌2024」を
刊行します.各大学では,この冊子をキャリア教育の教材として活用頂いており,
そして多くの学生・院生から専門職を知る機会になったとの声が届いております.
本冊子への協賛と原稿提供をご検討ください.
締切:2024年12月20日(金)
配布:2025年1月下旬
詳しくは,https://photo.geosociety.jp/career2.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】Island Arcからのお知らせ
──────────────────────────────────
[Island Arc]
■ 新しい論文が公開されています
(REVIEW ARTICLE)Spatial and Temporal Exhumation of the Northeastern
China: Insights From Low Temperature Thermochronology; Yannan Wang et al
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[関東支部]
・2024年度関東支部功労賞募集
対象者:支部活動や地質学を通して広く社会貢献をされた関東支部内に在住の
個人・団体 *社会貢献や活動の評価においては,必ずしも学問的な成果を問う
ものではありません.
公募期間:2024年12月16日(月)から2025年1月17日(金)
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0201.html#2024koro
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
国土デジタル情報研究所 地質地盤情報の活用と法整備を考える会
ホームページを更新しました。
・日本土地環境学会定期大会2024年11月23日(土)のお知らせを掲載
・プロフィールのページ、協力会員(団体)が7機関に更新
—-----------------------------------
「堆積構造の世界」連続講義:第1回堆積構造の基礎
11月19日(火)18時から
Zoomウェビナーオンライン開催(参加無料・要事前申込)
コーディネーター:石原与四郎 先生
講師:横川美和 先生,山口直文 先生,成瀬 元 先生
https://sites.google.com/view/taisekigakukougi?usp=sharing
(後)日本応用地質学会令和6年度技術者倫理講習会
11月27日(水)13:30-17:00
Zoomによるオンライン講習会(質疑応答可能なライブ配信)
定員500名
要事前申込(11月19日締切,先着順)
参加費:応用地質学会会員等:2,000円,非会員6,000円
https://www.jseg.or.jp/02-committee/jseg-edu.html
(後)第34回社会地質学シンポジウム
12月6日(金)-7日(土)
会場:日本大学文理学部図書館3F オーバルホール+オンライン
参加費:日本地質学会会員は4,000円
https://www.jspmug.org/envgeo_sympo/34th_sympo/
第315回 地学クラブ講演会「最近の助成研究から」
12月6日(金)15:30-17:30
会場:地学会館 2階講堂
講演:栗林 梓(皇學館大・文),田嶋 智(東大・新領域・博士後期課程),山田和芳(早大・人間科学)
参加無料,事前申込不要,直接会場へ
https://www.geog.or.jp/lecture/info/2024-11-07/
第42回 地質調査総合センターシンポジウム
令和6年度 地圏資源環境研究部門 研究成果報告会
「脱炭素と社会・経済が調和したトランジションに向けて エネルギー・環境・資源制約へと対応する燃料資源地質研究」
12月6日(金)13:30-17:30
会場:秋葉原ダイビル・コンベンションホール(東京都千代田区)
※現地開催のみ
参加費無料(要事前要録:締切12/2)
https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo42/index.html
「堆積構造の世界」連続講義:第2回砕屑性堆積物の堆積構造(1)
12月14日(土)13:30から
コーディネーター:酒井哲弥先生
講師:酒井哲弥先生
https://sites.google.com/view/taisekigakukougi?usp=sharing
第43回地質調査総合センターシンポジウム
「地質を用いた斜面災害リスク評価−高精度化に必須の地質情報整備−」
12月20日(金)13:00-17:20
会場:アクロス福岡7階大会議室(福岡県福岡市)
※ストリーミング配信有(講演のみ)
参加費無料(要事前登録:締切12/10)
https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo43/index.html
(後)一般公開講座:大地を分ける「武山断層」
12月21日(土)小雨決行 9:30-15:30
主催:三浦半島活断層調査会
見学参加者募集中(12/17締切)
参加費:500円
https://geosociety.jp/uploads/fckeditor/others-pdf/241221takeyama.pdf
地質学史懇話会
12月21日(土)13:30-17:00
場所:北とぴあ 806号室(東京都北区王子)
・八耳俊文:マンハッタン計画と水俣病―戦後20年日本地球化学史
(注)黒田和夫氏の講演は延期となりました
問い合わせ:矢島道子 pxi02070[at]nifty.com
※[at]を@マークにして送信してください
STAR-Eプロジェクト第4回研究フォーラム
〜情報科学×地震学 学官連携の未来像〜
主催:文部科学省
12月23日(月)15:00-17:35
会場:オンライン(Zoom)
対象:情報科学や地震学分野等の大学生・大学院生、当該分野における研究者等(民間企業も含む)
参加費無料(要事前登録:締切12/23,12:00)
https://evt-cipwos20241016.eventcloudmix.com/
—--------
2025年
—--------
「堆積構造の世界」連続講義:第3回砕屑性堆積物の堆積構造(2)
1月11日(土)13:30から
コーディネーター:酒井哲弥先生
講師:酒井哲弥先生,成瀬 元先生
https://sites.google.com/view/taisekigakukougi?usp=sharing
(後)原子力総合シンポジウム2024
1月20日(月)
会場:日本学術会議講堂+オンライン
参加費無料
https://www.aesj.net/natlsymp2024
北淡国際活断層シンポジウム2025
1月23日(木)-25日(土)
オンライン開催(Zoom webiner)参加費無料
発表申込み期限:2024年12月25日(水)
参加登録期限:2025年1月15日(水)
https://home.hiroshima-u.ac.jp/kojiok/hokudan2025.html
(後)第62回アイソトープ・放射線研究発表会
7月2日(水)-4日(金)
会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
発表申込締切:2月28日(金)12時
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/jrias2025
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0246.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・【期間延長】島根大学学術研究院環境システム科学系教員公募(12/2)
・千葉県職員採用選考考査(地質)受験案内(12/13)
・三菱財団第56回(2025年度)自然科学研究助成募集(1/6-2/3)
・東北大学「火山研究人材育成等支援事業(即戦力となる火山人材育成
プログラム)」即戦力火山人材社会人大学院生等・共同研究公募(12/8)
・十勝岳ジオパーク2024年度研究活動助成事業の募集(12/31)
・令和7年度苗場山麓ジオパーク学術研究奨励事業助成金募集(1/31)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 641 学会各賞候補者募集【締切延長!12/20】
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.641 2024/12/3┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2025年度学会各賞候補者募集【締切延長12/20】
【2】若手野外地質研究者向けに研究奨励金を支給します
【3】2025年度の会費払込について
【4】第16回惑星地球フォトコンテスト応募受付中
【5】地質系若者のためのキャリアビジョン誌2024原稿募集中
【6】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【7】支部のお知らせ
【8】会員の学術・教育・社会貢献活動
【9】その他のお知らせ
【10】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2025年度学会各賞候補者募集【締切延長!12/20】
──────────────────────────────────
標記について,12/2(月)締切で募集いたしましたが、本年度は推薦数が例年
になく少ない状況でした.そのため、応募期間を12/20(金)まで延期します.
個人(正会員または名誉会員)からの推薦も可能です.奮ってご応募ください.
ご推薦いただいた方の中から,各賞選考委員会(委員は理事会の互選と職責に
より選出)が候補者を選考し,理事会での決定,総会での承認を経て表彰を行
います.
************************
応募締切:2024年12月20日(金)延長しました
************************
詳しくは,https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
(※会員システムへのログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】若手野外地質研究者向けに研究奨励金を支給します
──────────────────────────────────
<2025年度日本地質学会研究奨励金>
日本地質学会では若手育成事業の一環として,野外調査をベースに研究を行う
32歳未満の若手会員を対象とした研究奨励金制度を設けています.
また,昨年度規則改正により助成期間の延長も可能となっています.
**************************************
募集期間:2025年1月1日から2月28日必着
**************************************
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0242.html
(申請に関するFAQも掲載しています)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2025年度の会費払込について
──────────────────────────────────
運営規則により,2025年度の事業年度(会費年度:2025年4月-2026年3月)が
始まる前までに納入下さいますようお願いいたします.
(1)自動引落を登録されている方の引落日は,12月23日(月)です.
(2)一般会員・シニア会員の方は,自動引落をご利用ください(申込は随時受付).
今回お申込みいただいた方は,2025年6月の督促請求時に引落させていただきます.
(3)お振り込みの方:12月20日頃に請求書兼郵便振替用紙を発送いたします.
お手元に届きましたら,折り返しご送金下さいますようお願いいたします.
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0239.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第16回惑星地球フォトコンテスト応募受付中
──────────────────────────────────
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
会員の皆様からの応募もお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
*********************************
応募締切:2025年2月2日
*********************************
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質系若者のためのキャリアビジョン誌2024 原稿募集中
──────────────────────────────────
日本地質学会は,地質学を専攻とする国内44の大学の2,200名以上の学生と院生に
専門職の魅力を伝える情報誌「地質系若者のためのキャリアビジョン誌2024」を
刊行します.各大学では,この冊子をキャリア教育の教材として活用頂いており,
そして多くの学生・院生から専門職を知る機会になったとの声が届いております.
本冊子への協賛と原稿提供をご検討ください.
締切:2024年12月20日(金)
配布:2025年1月下旬
詳しくは,https://photo.geosociety.jp/career2.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
──────────────────────────────────
[地質学雑誌]
■ 新しい論文が公開されています
(レター)鳥取県東部,金峯山の中新統の年代制約:降下火山灰堆積物のジルコン
のウラン–鉛年代:羽地俊樹ほか
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/-char/ja
[Island Arc]
■ 新しい論文が公開されています
(RESEARCH ARTICLE)Geological and Geomorphological Causes of Two
Historical Deep‐Seated Catastrophic Landslides Induced by the 1892 Heavy Rainfall
Event in the Shimanto Accretionary Complex, Tokushima, Japan:Noriyuki Arai/
(RESEARCH ARTICLE)Distribution of Stable and Radioactive Iodine Dissolved in
Interstitial Waters Within the Subduction Input Sediment Offshore Sumatra
Subduction Zone:Satoko Owari et al
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[関東支部]
2024年度関東支部功労賞募集
対象者:支部活動や地質学を通して広く社会貢献をされた関東支部内に在住
の個人・団体
*社会貢献や活動の評価においては,必ずしも学問的な成果を問うものでは
ありません.
公募期間:2024年12月16日(月)から2025年1月17日(金)
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0201.html#2024koro
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】会員の学術・教育・社会貢献活動
──────────────────────────────────
酒井治孝会員が,令和6年度秩父宮記念山岳賞を受賞することが決定しました.
業績題名「ヒマラヤ山脈形成史の研究」
https://geosociety.jp/science/content0109.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
地震本部ニュース2024年秋号:「地震本部地域講演会 in 新潟市 新潟地震から
60年〜過去に学び、将来に備える〜」を開催しました ほか
https://www.jishin.go.jp/main/herpnews/2024/aut/herpnews2024aut.pdf
—---------------------------------
(後)第34回社会地質学シンポジウム
12月6日(金)-7日(土)
会場:日本大学文理学部図書館3F オーバルホール+オンライン
参加費:日本地質学会会員は4,000円
https://www.jspmug.org/envgeo_sympo/34th_sympo/
第315回 地学クラブ講演会「最近の助成研究から」
12月6日(金)15:30-17:30
会場:地学会館 2階講堂
講演:栗林 梓(皇學館大),田嶋 智(東大),山田和芳(早大)
参加無料,事前申込不要,直接会場へ
https://www.geog.or.jp/lecture/info/2024-11-07/
(後)一般公開講座:大地を分ける「武山断層」
12月21日(土)小雨決行 9:30-15:30
主催:三浦半島活断層調査会
見学参加者募集中(12/17締切)
参加費:500円
https://geosociety.jp/uploads/fckeditor/others-pdf/241221takeyama.pdf
STAR-Eプロジェクト第4回研究フォーラム
〜情報科学×地震学 学官連携の未来像〜
主催:文部科学省
12月23日(月)15:00-17:35
会場:オンライン(Zoom)
対象:情報科学や地震学分野等の大学生・大学院生、当該分野における研究者等(民間企業も含む)
参加費無料(要事前登録:締切12/23 12:00)
https://evt-cipwos20241016.eventcloudmix.com/
—--------
2025年
—--------
(後)原子力総合シンポジウム2024
1月20日(月)10:00-17:00
会場:日本学術会議講堂(港区六本木)+オンライン
参加費無料
https://www.aesj.net/natlsymp2024
海と地球のシンポジウム2024
3月12日(水)-13日(木)
開催方法:口頭発表、ポスター発表ともに実会場にて実施
実会場:東京大学弥生キャンパス 弥生講堂
【発表課題 募集中!】登録締切:12月13日(金)
フォトコンテストも開催!航海に関連する最高の瞬間をご応募ください!
https://www.jamstec.go.jp/j/pr-event/ocean-and-earth2024/
(後)第62回アイソトープ・放射線研究発表会
7月2日(水)-4日(金)
会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
発表申込締切:2月28日(金)12時
ポスター賞が新設されました.応募をご検討ください.
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/jrias2025
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0246.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・金沢大学・能登里山未来創造センター(自然災害のメカニズムの研究や防災対策
や復興計画に関わる地球科学・社会基盤工学分野)特任教授または特任准教授公募
(1/14)
・原子力規制委員会行政職員(技術系)公募(1/31)
・2025年度深田研究助成(1/31)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 642 学会各賞候補者募集【締切延長!12/20】
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.642 2024/12/17┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2025年度学会各賞候補者募集【締切延長12/20】
【2】若手野外地質研究者向けに研究奨励金を支給します
【3】2025年度の会費払込について
【4】第16回惑星地球フォトコンテスト応募受付中
【5】地質系若者のためのキャリアビジョン誌2024原稿募集中
【6】2027年度の地震火山地質こどもサマースクール開催地候補募集
【7】支部のお知らせ
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】訃報:小西健二 名誉会員ご逝去
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2025年度学会各賞候補者募集【締切延長!12/20】
──────────────────────────────────
標記について,12/2(月)締切で募集いたしましたが、本年度は推薦数が例年
になく少ない状況でした.そのため、応募期間を12/20(金)まで延期します.
個人(正会員または名誉会員)からの推薦も可能です.奮ってご応募ください.
ご推薦いただいた方の中から,各賞選考委員会(委員は理事会の互選と職責に
より選出)が候補者を選考し,理事会での決定,総会での承認を経て表彰を行
います.
************************
応募締切:2024年12月20日(金)延長しました
************************
詳しくは,https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
(※会員システムへのログインが必要です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】若手野外地質研究者向けに研究奨励金を支給します
──────────────────────────────────
<2025年度日本地質学会研究奨励金>
日本地質学会では若手育成事業の一環として,野外調査をベースに研究を行う
32歳未満の若手会員を対象とした研究奨励金制度を設けています.
また,昨年度規則改正により助成期間の延長も可能となっています.
**************************************
募集期間:2025年1月1日から2月28日必着
**************************************
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0242.html
(申請に関するFAQも掲載しています)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2025年度の会費払込について
──────────────────────────────────
運営規則により,2025年度の事業年度(会費年度:2025年4月-2026年3月)が
始まる前までに納入下さいますようお願いいたします.
(1)自動引落を登録されている方の引落日は,12月23日(月)です.
(2)一般会員・シニア会員の方は,自動引落をご利用ください(申込は随時受付).
今回お申込みいただいた方は,2025年6月の督促請求時に引落させていただきます.
(3)お振り込みの方:12月20日頃に請求書兼郵便振替用紙を発送いたします.
お手元に届きましたら,折り返しご送金下さいますようお願いいたします.
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0239.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第16回惑星地球フォトコンテスト応募受付中
──────────────────────────────────
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
会員の皆様からの応募もお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
*********************************
応募締切:2025年2月2日
*********************************
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質系若者のためのキャリアビジョン誌2024 原稿募集中
──────────────────────────────────
日本地質学会は,地質学を専攻とする国内44の大学の2,200名以上の学生と院生に
専門職の魅力を伝える情報誌「地質系若者のためのキャリアビジョン誌2024」を
刊行します.各大学では,この冊子をキャリア教育の教材として活用頂いており,
そして多くの学生・院生から専門職を知る機会になったとの声が届いております.
本冊子への協賛と原稿提供をご検討ください.
締切:2024年12月20日(金)
配布:2025年1月下旬
詳しくは,https://photo.geosociety.jp/career2.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】2027年度の地震火山地質こどもサマースクール開催地候補募集
──────────────────────────────────
地震火山地質こどもサマースクールは、1999年夏から小・中・高校生を対象に
はじまった行事で、現在、日本地震学会、日本火山学会、日本地質学会が共同
で実施する、地球科学関連では最大規模の体験学習講座です。
今回、下記により2027年度の実施を希望する開催地を公募いたします。
【募集期間】2025年2月13日(木)まで
詳しくは,https://kodomoss.jp/applications/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[西日本支部]
西日本支部令和6年度総会・第175回例会
2025年3月1日(土)
会場:北九州市立自然史・歴史博物館
参加・講演申込締切:1月31日(金)
講演要旨提出締切:2月17日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
[関東支部]
2024年度関東支部功労賞募集
対象者:支部活動や地質学を通して広く社会貢献をされた関東支部内に
在住の個人・団体
公募期間:2024年12月16日(月)から2025年1月17日(金)
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0201.html#2024koro
アウトリーチ巡検 「逗子市と鎌倉市の地質・地形観察」
2025年2月8日(土)(予備日:2月16日(日))
参加費用:2,000円(保険代,資料代等.当日集金)
申込期間:1月7日(火)〜24日(金)17:00終了
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0201.html#2024kamakura
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(一社)国土デジタル情報研究所地質地盤情報の活用と法整備を考える会の
HPが更新されました.
・「考える会」からのメッセージ No.1-11に連載されたエッセイ「性能設計
時代の地質・地盤モデル」がひとつの文書にまとめられました.
・協力会員(団体)が8機関に(2024年11月27日現在)
https://www.geo-houseibi.jp/
—----------------------------------
第247回イブニングセミナー(オンライン)
12月19日(木)19:30-21:30
「ナラティブ・アプローチとしての新たなナチュラルアナログ研究の利用法」
講師:佐藤 努先生(北海道大学大学院工学研究院資源循環材料学研究室教授,
日本粘土学会会長)
参加費:主催NPO会員及び学生の方(無料) 非会員の方(1,000円)
https://www.npo-geopol.or.jp/seminer.htm
(後)一般公開講座:大地を分ける「武山断層」
12月21日(土)小雨決行 9:30-15:30
主催:三浦半島活断層調査会
見学参加者募集中(12/17締切)
参加費:500円
https://geosociety.jp/uploads/fckeditor/others-pdf/241221takeyama.pdf
—--------
2025年
—--------
防災学術連携体シンポジウム
阪神・淡路大震災30年、社会と科学の新たな関係
1月7日(火)10:00-18:00
場所:Zoom Webinar,YouTube を用いたオンライン配信
参加費無料(要事前申込)
https://janet-dr.com/index.html
第203回深田研談話会
テーマ:日本の古生物学の歩みをふりかえる
1月17日(金)15:00-16:30
場所:深田地質研究所研修ホール+オンライン
講師:矢島道子(東京都立大非常勤講師)
要事前申込,参加費無料
https://fukadaken.or.jp/?p=8647
(後)原子力総合シンポジウム2024
1月20日(月)10:00-17:00
会場:日本学術会議講堂(港区六本木)+オンライン
参加費無料
https://www.aesj.net/natlsymp2024
(後)第62回アイソトープ・放射線研究発表会
7月2日(水)-4日(金)
会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
発表申込締切:2月28日(金)12時
ポスター賞が新設されました.応募をご検討ください.
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/jrias2025
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0246.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・大阪公立大学 (所属理学研究科,地球学専攻) 特任助教を募集(1/24)
・2025年度箱根ジオパーク学術研究助成募集(1/24)
・山陰海岸ジオパーク推進協議会ジオパーク専門員募集(1/22)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】訃報:小西健二 名誉会員ご逝去
──────────────────────────────────
小西健二 名誉会員(金沢大学名誉教授)が,令和6年10月25日に老衰のため
逝去されました(95歳).御葬儀は家族葬にて執り行われたとのことです.
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます.
会長 山路 敦
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
ベニオフ以前に深発地震帯逆断層説を唱えた日本人地質学者
ベニオフ以前に深発地震帯逆断層説を唱えた日本人地質学者
正会員 石渡 明
現在では,環太平洋式の造山帯は深発地震を伴う海洋プレートの沈み込みによって形成されるということは常識になっている.これは,深発地震の存在を初めて確認した和達清夫(Wadati, 1928; Frohlich, 1987; Suzuki, 2001; 鈴木, 2004a)と,深発地震帯は大陸/大洋境界の逆断層であり海溝はこの断層の運動によってできると喝破したベニオフ(Benioff, 1949; 1954)の貢献とされ,深発地震帯は和達−ベニオフ帯(Wadati-Benioff zone)と呼ばれる(菊地, 1996; 上田・杉村, 1970, p. 36).Benioff (1949)はトンガ・ケルマデック弧とアンデス弧のデータに基づくが,日本を含む他の深発地震帯にも言及している.なお,深発地震の発震機構はHonda (1934)や本多・正務(1940)が解明した.(江原, 1942; 上田・杉村, 1970; Suzuki, 2001; 鈴木, 2004b).
一方,深発地震帯を大陸/海洋境界の大規模な逆断層とし,海溝はこの断層運動によって形成されるとする考えは,Benioff(1949)より前に,地震学的・野外地質学的データに基づいて複数の日本人地質学者が既に提唱していた.江原(1942)は太平洋の深海底岩盤の日本列島下への沈み込みを「太平洋運動」と呼び,その冒頭で,『本邦における太平洋運動は小藤(ことう)先生が始唱者であって,これと共に藤原咲平博士があった.小藤(文次郎)先生はその著「The Rocky Mountain Arcs in Eastern Asia, 1931」において,太平洋深海底の玄武岩(sima)がアジア大陸のsialに対してunderthrustをなし,褶曲山脈と断層山脈を起こすと述べられた.藤原博士はその著「地渦地裂及地震, 1932」において南日本の起震力は北西と南東から押し合っているものと見做され,これを太平洋運動の一部とされた』と述べた.そして,江原(1942)は「太平洋運動と深発性地震帯及Nippon Trench Thrusting Province」なる表題の節において,本多・正務(1940)の論説と深発地震分布図を引用して,(深発地震の)「発震機構は西または北西に30°の傾斜角を有する面を考えるときは,その面の下においては,東または東南より衝(つ)き込み(underthrust),反対にその面の上においては西または北西より衝き上げ(overthrust),この両運動のshearing movementによりて地震となる」と深発地震の発震機構に基づく運動像を明確に述べている(衡は誤字と判断し衝に改めた.カッコ内を補い,かなを現代風に改めた.昔は花崗岩質の大陸地殻をsial(Si-Al),玄武岩質海洋地殻とかんらん岩質マントルをsima(Si-Mg)と言った.シアルはシマの上に浮きアイソスタシーが成り立つ.望月(1940)はこれらを珪礬帯,珪苦帯と呼んだ).そして,太平洋運動の考えは早くも江原(1940)及びYehara (1940)で提唱された(今井, 2006).なお,江原(1942)は野外調査に長年協力した助手の沢田俊治に懇切な謝辞を述べている(石渡, 2004参照).
次は槇山次郎である.石渡(2018)は,『1945年の終戦後,日本の太平洋側の堆積盆は「地向斜」ではなく「地単斜」であり,「地単斜帯では地史の上に特別な造山期というものが認められず」,「日本では作用する力は偶力の状で…大陸側から高水準に,太平洋側からは低水準に…反対に押した形である」という考えを述べた日本地質学会会長(槇山, 1947)』に言及した.槇山次郎は1986年に90歳で没し,糸魚川(1987)の追悼文はほとんど槇山の古生物学への貢献のみについて述べているが,神谷・高橋(2017)の列伝はMakiyama (Sagarites) など軟体動物化石の研究,ナウマンゾウの命名などの他に構造地質・資源地質関係の業績も述べている.その中に「岩石変形学」がある.戦時中の1944年初版とのことだが,私が読んだのは戦後の改訂版(槇山, 1949)である.この本では,槇山(1947)の講演内容がGriggs (1939)による粘性体の流動実験(図1)を示して詳しく説明され,(この実験では)「下層を水ガラスとし,表殻は砂を油で練り上げたものにした.(中略)(左側の図では)表殻内に低角上方摺動(衝上断層)ができ,(中略)あたかもコーバー(Kober)のオロゲン(造山帯)の絵にそっくりであるのは驚くべきことである.右側の図では片側の円筒の回転を止め,他の側だけを動かした場合の結果を示す.下向き褶曲は幅が広く,非対称形で,その急な斜面は対流に面している.左の図は両方の円筒を均等に回転し,対称的な構造を得た.右側で示す実験では流速を増すと表殻は動く側では薄くなり,動かぬ側へ押し寄せられてしまう.これは実に環太平洋式過褶曲を暗示するものでなければならず,左図はアルプス式を意味する」.そして,槇山(1949)は次のように結ばれる.「最近,江原眞伍博士は太平洋運動説を数回に及び述べている.また博士は日本海運動も合わせ考えている(江原, 1940, 1942, 1943).望月勝海氏は対流による説明を若干試みている(望月(1940)はシマ(珪苦帯:太平洋底・フィリピン海底の岩盤)の沈み込みに加え,水平方向の回転流動により伊豆弧の成因を論じた.望月の業績と人物は杉村(1992, 2023)と山田ほか(2023)参照).これ等の所説はまだ地殻下の固体流動の理念を基本としていないのであるが,自今は改めて此所に基準して(固体流動の理論に基づいて)発展を期すべきであると信ずる」(かなを現代風に改めカッコ内を補った).
図1. 槇山(1947)や青山(1948)が引用したグリッグス(Griggs, 1939)による粘性体の流動実験.
もう一人,青山信雄(1948)は全3巻の著書「構造地質学」の第1巻最終節「深発地震」のp. 134で,「1922年Turnerが数100kmの深さの所に震源が存することを発表した時にも,一般にはこれを信じなかった.然るに,この深所震源の存在は1928年和達博士により確証されるに至ったのである」と書き,末尾のp. 137では,「東北地方の東方沖合から日本の下を通ってアジア大陸側へ向かって30〜40°傾斜する一つの面を考えると,この斜面に沿って地震が最も多く起こっていることとなる.あるいは実際かくの如き大規模の断層が生じていて,大陸側の地塊は海洋側の地塊の上に押し上がらんとし,海洋側の地塊は大陸側の地塊の下に潜り込まんとする様な剪断応力が働いているとも想像される」(かなを現代風に改めた)と書いて,次ページに日本付近の浅発地震と深発地震の分布図を掲げた.本書はBenioff (1949)の前年に出版された.翌年の第2巻(p. 236)ではグリッグスの実験(図1)を引用し,左側の図は「Koberの両面性のオロゲン型(Alpsなど)に似ている」,右側の図については「環太平洋山脈の構成はある点までかくの如き見解が適用さるべきものとGriggsは唱えている」と述べた(石渡の卑見では,この実験で(一方を止めずに)両方の軸を同じ向き(左図は反対向き)に回転すれば,島弧と縁海の形成を説明できる).青山はその後,鉱物趣味の会から全4巻の「岩石学」を出版したが,その第3巻(変成岩)の序文(木下亀城筆)は,『(青山が)「輓近鉱物学」,「一般地質学」,「構造地質学」,「地球発達史」を著し,地質学の各部門に広く精通している稀にみる博学多才な地質学者である』と述べている(「構造地質学」の著者肩書は佐賀高等学校教授・九州大学講師).
まとめると,Benioff (1949)より早く,後のプレートテクトニクスにつながる深発地震帯逆断層説を,複数の日本人が公表し,しかも地震学者ではなく地質学者が,深発地震の分布や震源メカニズムの解析,今で言う付加体の褶曲や断層の野外調査データ等に基づいて議論していたことは注目に値する.特に江原の論文は長期の野外調査及び広汎な文献調査と熟慮に基づき独自性が高く,Benioff (1949)以前に深発地震帯逆断層説を明確に論じた.和達−ベニオフ帯は,和達−江原帯と称すべきなのだと思う.
青山(1948/49)の書籍をご恵与いただいた故山崎正男先生と,拙稿を読んで改善意見をいただいた池田保夫・平田大二両会員に感謝する.
文 献
青山信雄(1948/49)「構造地質学」(1)地殻構造と地殻運動, (2)火山, プルトーン, 褶曲, 断裂, 転位, 山地及びオロゲンの構造. 天松堂出版部. 255 p.+索引・文献.
Benioff, H. (1949) Seismic evidence for the fault origin of oceanic deeps. Geological Society of America Bulletin, 60, 1837–1856.
Benioff, H. (1954) Orogenesis and deep crustal structure: additional evidence from seismology. Geological Society of America Bulletin, 65, 385-400.
Frohlich, C. (1987) Kiyoo Wadati and Early Research on Deep Focus Earthquakes: Introduction to Special Section on Deep and Intermediate Focus Earthquake. Journal of Geophysical Research, 92(B13), 13,777-13,788.
Griggs, D. (1939) A theory of mountain building. American Journal of Science, 237 (9) 611-650.
Honda, H. (1934) On the mechanism of deep earthquakes and the stress in the deep layer of the Earth's crust. Geophysical Magazine, 8, 179–185.
本多弘吉(ひろきち)・正務(まさつか)明(1940)本邦付近の地殻内部に於ける起震歪力に就て. 験震時報, 11, 183-216, 546–548.
今井功(2006)地学者列伝 江原真伍の生涯と業績. 地球科学, 60, 73-75.
石渡明(2004)地質家別所文吉の生涯:根尾谷からハルマヘラ島を経て大阪山脈へ. 地質学雑誌, 109, 299-302.
石渡明 (2018) 日本ナップ説略史. 日本地質学会News, 21(2), 11-12.
糸魚川淳二(1987)槇山次郎先生を悼む. 化石, 42, 46-47.
神谷英利・高橋啓一 (2017)地学者列伝 槇山次郎―貝類学・ナウマンゾウ・京都大学地質学鉱物学教室. 地球科学, 71, 185-198.
菊地正幸(1996)和達ベニオフ帯.「新版地学事典」平凡社(2024年最新版も同文).
槇山次郎(1947)会長講演. 地質学雑誌, 53, 42-43.
槇山次郎(1949)「岩石変形学 改訂版」星野書店. 216 p.
望月勝海(1940)七島マリアナ弧の成因. 地理学評論, 16(4), 219-229.
杉村新(1992)私と2人の先生:望月勝海と大塚弥之助.地質ニュース, 455, 4-21.
杉村新(2023)90年間の学歴(1)−駆けだしまで−(地学ニュース 回顧録No.16).地学雑誌, 132(1), N1-N14.
Suzuki, Y. (2001) Kiyoo Wadati and the path to the discovery of the intermediate-deep earthquake zone (Classic paper in the history of geology). Episodes, 24, 118-123.
鈴木尉元(2004a)地学者列伝 和達清夫の地震学と地盤沈下研究への貢献. 地球科学, 58, 61-64.
鈴木尉元(2004b)地学者列伝 本多弘吉の発震機構の研究. 地球科学, 58, 127-130.
上田誠也・杉村新(1970)「弧状列島」岩波書店.
Wadati, K. (1928) Shallow and deep earthquakes: Geophysical Magazine, 1, 162-202.
山田俊弘・矢島道子・須貝俊彦・島津俊之(2023)20世紀日本地学史を日記の読解から再考する―地学者望月勝海の生涯と仕事1914-1963年. 地学雑誌, 132(3), 217-230. https://www.geog.or.jp/library/document_history/mochizuki/
Yehara, S. (1940) On the lateral thrust from the Pacific. Japan Journal of Geology and Geography, 17, 3/4, 233-250.
江原眞伍(1940)太平洋運動と海溝の成因について.地質学雑誌, 47, 352-360.
江原眞伍(1942)太平洋運動とFossa Magnaの成因に就て. 地質学雑誌, 49, 81-91.
江原眞伍(1943)四国の太平洋・日本海両運動とその太平洋水準面及び大東亜海に及ぼす影響に就て. 地学雑誌, 55 (647), 1−12, (649), 85-97. (戦後は表記をEharaに改めた)
【追 記】
「日本の地質学100年」(日本地質学会, 1993年)に,ベニオフと江原について,杉村と山下による次のコメントがあるので追記する.(石渡 明; 2025.02.28)
(1)杉村 新(11. 島弧論 (5), p. 122)
なお,深発地震帯を和達ベニオフ帯*と呼ぶことが多いが,Frohlich (1987)も指摘しているように,ベニオフ(H. Benioff)の名を用いるのは不適当である.筆者は未だかつてこう呼んだことはない.日本の深発地震帯を明らかにしたのは,何人もの日本の研究者であり,これを世界の深発地震帯に拡げたのはGutenberg and Richter (1938; 1949) である.
文 献(他の文献は本文の文献リスト参照)
Gutenberg, B. and Richter, C.F. (1938) Depth and geographical distribution of deep-focus earthquakes. Geol. Soc. Am. Bull., 49, 249-288, 1938.
Gutenberg, B. and Richter, C.F. (1949) Seismicity of the Earth and Associated Phenomena. Princeton University Press, Princeton. 273 p.
*(石渡注)この語を世界に広めたのはSeiya Uyeda (1978; “The New View of the Earth: Moving Continents and Moving Oceans”, Freeman. 217 p. (translated by Masako Onuki) p. 135-137) である.この本は上田誠也(1971; 「新しい地球観」岩波新書779)の英訳であり,多言語に重訳されたが,和文の原本(p. 135)にこの語はない.
(2)山下 昇(「Ⅰ 古典的日本列島像の形成 1. ナウマンの『構造と起源』から江原の「太平洋運動」まで (5), p. 15-16」)
ところで,江原真伍はこの時代の最初から最後まで,そしてさらに次の時代まで活躍し続けた,稀に見る長距離ランナーであった.最初は日本各地の白亜系の研究から入り,やがて四国の地質構造研究へ進み,この時代の末期には「太平洋運動」(1940)を提唱してフォッサマグナの成因を論じた(1942).江原の研究方法には,ジュースやリヒトホーフェン時代の古めかしい方法と,現代的な斬新な構造地質学の手法とが混在している.だから彼の主張には,ある面では夢物語のような掴みがたい所があるが,同時にまた無視することができない面白い着想が含まれている.活断層(1934)という語を用いたのもおそらく江原が最初であろうし,その他,日本海側から日本列島へ向かう運動(日本海運動)とともに太平洋側から日本列島へ向かってunderthrustする太平洋運動がある,と主張するとき,その根拠の一つは野外で観察される小構造であった.その根底には「小構造は大構造の鍵」というまさに現代的な方法論がある.ただ,おしいことに,そのデータはまだきわめて少なく,それを大構造へつなぐ論理の間隙が大きい.けれどもモデル実験をも参考にしたフォッサマグナ成因論は,太平洋のunderthrust説とともに現代の成因論を思わせるものがある.
文献(他の文献は本文の文献リスト参照)
江原眞伍(1934)大阪湾周囲の活断層二例.日本学術協会報告, 9(1), 52-54.
(石渡注)この活断層の1つが若樫(わかかし)断層(大阪府和泉市)であるが,これについては逸話がある.「それは昭和6(1931)年,地質学会が京都であった時である.江原は演壇に立って,和泉山脈にあるNE-SWの並行断層を弁じた.中村(新太郎)は立って,そういう断層は存在しないと言った.和泉山脈の断層がN-Sであることを歩いて確かめていたからである.その時「江原君,君のクリノメーターは45度狂っている」という有名な言葉が出たのである」(別所文吉1964「江原真伍先生小伝」地学研究, 15, 337-344).しかし,江原(1937「丸山断層と若樫断層」地震, 9, 1-5)でもこの断層はNE-SW走向で図示されており,露頭記載は「この断層は附近に発達する旧洪積期の砂利層の上に花崗岩の衝き上げたものであって,断層面の走向北30度東で傾斜は北西に50度内外である」となっている.若樫断層は地調の1/5万岸和田図幅と説明書(市原実・市川浩一郎・山田直利,1986)にも示されているが,それは何とE-W走向であり,江原とは逆に,南側上がりの衝上断層としている.「新編日本の活断層」(東大出版会, 1991)はこの図幅を引用して若樫断層を確実度Ⅰ(確実),活動度C,長さ2kmの活断層としている.いずれにしても,1934年に江原が「若樫より父鬼(ちちおに)に向ふ通路の北側を切割りたる際露出せる」活断層を報告したことは動かせない事実であり,いま考えると,江原らが見た北西側から衝き上げる断層は,若樫断層のバックスラストだった可能性がある.
【補遺】(2025.03.24 石渡)
江原(1934)が論じた「活断層二例」は芦屋断層と槇尾(まきお/まきのお)断層であった(【追記】の若樫断層は後者の一部).断層を横切る測線の水準測量による過去40年以上の期間の水準変動(今村, 1931; Imamura, 1933)に基づき,両断層の活動を論じた.神戸―大津測線では芦屋断層の西側が沈降していたが,1927年の丹後地震後は隆起に転じ,紀ノ川測線の槇尾断層延長部付近では最大約80㎜隆起したという.つまり,江原(1934)の「活断層」は「測量等により現在の動きが確認できる断層」を意味している.なお,芦屋断層は現在も六甲・淡路活断層系の一部として北の五助橋断層,南の甲陽断層の間に確認されているが,槇尾断層は存在が未確認である.また,芦屋断層の北東延長,宝塚西高校北側の露頭については,地質学雑誌1999年105巻12号誌上で松山紀香ほかと林愛明ほかの間で断層の存否に係る討論があった.
文献
今村明恒(1931)京阪地方に於ける地塊運動の特異性に就て.地震, 3(4), 201-219.
Imamura, A. (1933) On crustal deformation in west-central Kii Peninsula. Proc. Imp. Acad., 9(2), 39-42. (この論文は,紀ノ川沿いの和歌山―五條測線上で著しい上下動を示す地点が,江原の主張する槇尾断層に一致すると述べ,地図上に江原の “Makinoo Fault” を示している)
【geo-Flash】 No. 644(臨時号)祝:伊与原 新さん直木賞受賞!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.644 2025/1/17┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】祝:伊与原 新さん直木賞受賞!
──────────────────────────────────
伊与原 新さん(2022年度日本地質学会表彰受賞)の「藍を継ぐ海」が,第172回
直木賞を受賞されました.おめでとうございます!!
伊与原さんは,固体地球物理学の研究で博士(理学)(東京大学)の学位取得後,
大学教員として地球惑星科学の研究・教育に携わり,小説家として活動するという
経歴をお持ちです.代表作には,「お台場アイランドベイビー」や日本地球惑星科
学連合の高校生ポスターセッションでの発表などを題材にした「宙わたる教室」があります.
(参考)2022年度日本地質学会表彰受賞
表彰業績:地球惑星科学研究をいかした小説発表とそれによる科学知識の普及
https://geosociety.jp/outline/content0233.html#hyosho
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 643 謹賀新年 年頭の挨拶
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.643 2025/1/7┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】年頭の挨拶(会長 山路 敦)
【2】若手野外地質研究者向けに研究奨励金を支給します
【3】第16回惑星地球フォトコンテスト応募受付中
【4】名誉会員候補者の募集が開始されています
【5】TOPIC:ベニオフ以前に深発地震帯逆断層説を唱えた日本人地質学者
【6】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
【7】支部のお知らせ
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】年頭の挨拶
──────────────────────────────────
2025年1月1日
一般社団法人日本地質学会 会長 山路 敦
あけましておめでとうございます.初夢,というか,独創性について夢のような
はなしを最初に...
続きはこちらから,,,http://geosociety.jp/outline/content0137.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】若手野外地質研究者向けに研究奨励金を支給します
──────────────────────────────────
<2025年度日本地質学会研究奨励金>
日本地質学会では若手育成事業の一環として,野外調査をベースに研究を行う
32歳未満の若手会員を対象とした研究奨励金制度を設けています.
また,昨年度規則改正により助成期間の延長も可能となっています.
**************************************
募集期間:2025年1月1日から2月28日必着
**************************************
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0242.html
(申請に関するFAQも掲載しています)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】第16回惑星地球フォトコンテスト応募受付中
──────────────────────────────────
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
会員の皆様からの応募もお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
*********************************
応募締切:2025年2月2日
*********************************
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】名誉会員候補者の募集が開始されています
──────────────────────────────────
募集締切:2025年2月7日(金)
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:地質学への顕著な貢献または教育現場や企業等での
活動を通じた地質学の普及・振興への顕著な貢献が認められ,かつ本学会への
貢献も認められる会員
(注) 上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することは
できませんが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】TOPIC:ベニオフ以前に深発地震帯逆断層説を唱えた日本人地質学者
──────────────────────────────────
石渡 明(正会員)
現在では,環太平洋式の造山帯は深発地震を伴う海洋プレートの沈み込みに
よって形成されるということは常識になっている.これは,深発地震の存在を
初めて確認した和達清夫と,深発地震帯は大陸/大洋境界の逆断層であり海溝
はこの断層の運動によってできると喝破したベニオフ(Benioff, 1949; 1954)
の貢献とされ,深発地震帯は和達−ベニオフ帯(Wadati-Benioff zone)と呼ば
れる.
続きはこちらから
https://geosociety.jp/faq/content1183.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質学雑誌・Island Arcからのお知らせ
──────────────────────────────────
[地質学雑誌]
■ 新しい論文が公開されています
(論説)断層幾何学,複合面構造,応力逆解析から推定した断層の運動像:酒井 亨/
(論説)秋田県北部,竜ヶ森花崗岩類のジルコンU–Pb年代:福山繭子ほか/
(論説)高知県室戸半島に露出する古第三系室戸層に見られる乱堆積層:松元
日向子ほか/(論説)愛媛県東温市滑川渓谷の中部中新統石鎚層群高野層と初期の
石鎚火成活動:成田佳南ほか/(レター)関東平野中央部における更新統下総層群の
岩相層序区分とテフラの斜交:米岡佳弥ほか
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/list/-char/ja
[Island Arc]
■ Wileyの査読システム(REX)において査読者が添付ファイルをアップロード
できるようになりました。REXの改良にともなう機能について、あるいはこれ
からの更新予定案件はこちら:
https://editors.wiley.com/page/research-exchange-what's-new
■ 新しい論文が公開されています
(RESEARCH ARTICLE)Holocene Temperature Trend Inferred From Oxygen
and Carbonate Clumped Isotope Profiles of a Stalagmite Collected From
a Maritime Area of Central Honshu, Japan;Akira Murataet al ほか
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[西日本支部]
西日本支部令和6年度総会・第175回例会
3月1日(土)
会場:北九州市立自然史・歴史博物館
参加・講演申込締切:1月31日(金)
講演要旨提出締切:2月17日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
[関東支部]
2024年度関東支部功労賞募集
対象者:支部活動や地質学を通して広く社会貢献をされた関東支部内に
在住の個人・団体
公募締切:1月17日(金)
アウトリーチ巡検 「逗子市と鎌倉市の地質・地形観察」
2月8日(土)(予備日:2月16日(日))
参加費用:2,000円(保険代,資料代等.当日集金)
申込期間:1月7日(火)-24日(金)17:00終了
2025年度関東支部総会・講演会
4月1215日(土)14:00-16:45
場所:北とぴあ第2研修室(北区王子)
講演会「潜水船・水中ドローンによる島弧-海溝系の海底露頭観察」
講師:山口飛鳥氏(東京大学大気海洋研究所)
総会委任状(4/1114最終締切)
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(一社)国土デジタル情報研究所地質地盤情報の活用と法整備を考える会
日本土地環境学会の公開シンポジウム(2024年11月23日,東洋大学)の出席報告
を掲載しました.https://www.geo-houseibi.jp
****************************************
(後)原子力総合シンポジウム2024
1月20日(月)10:00-17:00
会場:日本学術会議講堂(港区六本木)+オンライン
参加費無料
https://www.aesj.net/natlsymp2024
「堆積構造の世界」連続講義
第4回 生物(化学)源堆積物の堆積構造
2月21日(金)17:00から
コーディネーター:松田博貴氏
講師:松田博貴氏,狩野彰宏氏
https://sites.google.com/view/taisekigakukougi?usp=sharing
(後)第62回アイソトープ・放射線研究発表会
7月2日(水)-4日(金)
会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
発表申込締切:2月28日(金)12時
ポスター賞が新設されました.応募をご検討ください.
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/jrias2025
日本地質学会第132年学術大会(2025熊本大会)
9月14日(日)-16日(月)
会場:熊本大学黒髪地区
2025 NEA IDKM Symposium
主催:OECD/NEA(ホスト機関:NUMO)
10月7日(火)-9日(木)
会場:パシフィコ横浜
サイトツアー(10/10):東京電力廃炉資料館、福島第一原子力発電所(予定)
https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_97583/2025-symposium-on-information-data-and-knowledge-management-idkm-for-radioactive-waste-and-geological-disposal
(協)Techno-Ocean 2025
11月27日(木)-29日(土)
会場:神戸国際展示場2号館ほか(神戸市中央区)
https://to2025.techno-ocean.com/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
http://www.geosociety.jp/outline/content0246.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・JAMSTEC変動海洋エコシステム高等研究所(WPI-AIMEC)研究員orポスト
ドクトラル研究員募集(1/26)
・令和7年度むつ市ジオパーク国際交流推進員の募集(1/31)
・旭川市地域おこし協力隊(ジオパーク専門員)募集(2/5)
・越知町地域おこし協力隊募集(横倉山自然の森博物館の活用促進に取り組む
協力隊)(1/27)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 645 地質系業界オンライン交流会 開催します!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.645 2025/1/21┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】若手野外地質研究者向け研究奨励金募集中
【2】名誉会員候補者の募集が開始されています
【3】第16回惑星地球フォトコンテスト応募受付中
【4】地質系業界オンライン交流会 開催します!
【5】Island Arcからのお知らせ
【6】支部のお知らせ
【7】JpGU教育検討委員会よりお知らせ
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】若手野外地質研究者向け研究奨励金募集中
──────────────────────────────────
<2025年度日本地質学会研究奨励金>
日本地質学会では若手育成事業の一環として,野外調査をベースに研究を行う
32歳未満の若手会員を対象とした研究奨励金制度を設けています.
また,昨年度規則改正により助成期間の延長も可能となっています.
**************************************
募集期間:2025年1月1日から2月28日必着
**************************************
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0242.html
(申請に関するFAQも掲載しています)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】名誉会員候補者の募集が開始されています
──────────────────────────────────
募集締切:2025年2月7日(金)
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:地質学への顕著な貢献または教育現場や企業等での
活動を通じた地質学の普及・振興への顕著な貢献が認められ,かつ本学会への
貢献も認められる会員
(注) 上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することは
できませんが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】第16回惑星地球フォトコンテスト応募受付中
──────────────────────────────────
惑星地球フォトコンテストは,ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテスト
です.チャンスを逃さない新たな視点のスマホ写真も大募!!
会員の皆様からの応募もお待ちしています.
・最優秀賞:1点 賞金5万円
・優秀賞:2点 賞金2万円
・ジオパーク賞:1点 賞金2万円
・日本地質学会会長賞:1点 賞金1万円 など
*********************************
応募締切:2025年2月2日
*********************************
http://www.photo.geosociety.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地質系業界オンライン交流会 開催します!
──────────────────────────────────
ー地質を仕事にするってどんなだろう?ー
地質学に関わる民間企業や官公庁等に興味がある若手向けの「地質系業界オンライ
ン交流会」を開催します!本交流会では,学生・若手研究者向けに,地質学に関わ
る仕事に従事する若手職員の方との座談会と懇談会を行います.
地質系の民間企業,研究所職員,ジオパーク職員など, 広く地質学に関わる仕事に
携わる方に, 就職してよかったこと,楽しかった仕事,学生時代の経験で役に立っ
たこと,大変だと感じたこと,業界でのキャリア形成などを伺う予定です.通常の
企業説明会や就職説明会とは異なる,若手職員ならではのお話を聴けるチャンス!皆様,奮ってご参加ください!!
日時:2025年2月14日(金)17:30–19:30
場所:Zoomによるオンライン開催
対象:35歳以下の学生・若手研究者(会員・非会員を問いません)
参加申込締切:2025年2月13日(木)23:59
詳しくは,https://geosociety.jp/science/content0172.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
新編集委員長ご挨拶:
Greetings From the New Editors‐In‐Chief
Takashi Hasegawa, Yuji Ichiyama
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/iar.70004
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[西日本支部]
西日本支部令和6年度総会・第175回例会
3月1日(土)
会場:北九州市立自然史・歴史博物館
参加・講演申込締切:1月31日(金)
講演要旨提出締切:2月17日(月)
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
[関東支部]
2025年度関東支部総会・講演会
4月12日(土)14:00-16:45
場所:北とぴあ第2研修室(北区王子)
講演会「潜水船・水中ドローンによる島弧-海溝系の海底露頭観察」
講師:山口飛鳥氏(東京大学大気海洋研究所)
総会委任状(4/11最終締切)
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】JpGU教育検討委員会よりお知らせ
──────────────────────────────────
小中高教員の皆様へ
JpGU教育検討委員会委員長 宮嶋 敏(埼玉県立熊谷高校)
2025年連合大会の開催セッションが決定しました.
セッション一覧
https://www.jpgu.org/meeting_j2025/sessionlist_jp/
コマ割り(時間割)
https://www.jpgu.org/meeting_j2025/files/session_schedule_j.pdf
2024年度大会から小中高教員は,事前にJpGU会員登録(2000円/年)をすると,
連合大会の全セッションに無料で参加できる措置が試験的になされています.
それまでは,無料で参加できるのはパブリックセッションのみに限定されておりま
した.小中高教員の参加を通じて,地球惑星科学の裾野を広がることが期待されております.
また,会員登録をしますと,メールニュースも配信され,JpGUや各学協会のイベン
トなどの情報も入手することができます.JpGU会員登録について、ご検討いただけ
れば幸いです。よろしくお願いします。 入会案内https://www.jpgu.org/members/
この件に関する問い合わせ先
JpGU事務局 https://business.form-mailer.jp/fms/66b7a829270415
※JpGUはハイブリッド開催です.現地に行けなくてもZoomで参加可能です.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
建設系CPD 協議会シンポジウム(ハイブリッド形式)
-継続学習としてのCPDプログラムの活用と実施例-
2月17日(月)14:00-17:00
場所:日本コンクリート工学会(東京都千代田区麹町)
ZOOM を使用したライブ配信も行います
参加費:1,000 円(税込)
申込締切:2025年2月12日(水)12:00
https://b-p.co.jp/cpd/1218.pdf
地質学史懇話会
2月23日(日)14:00-17:00
場所:北とぴあ 805号室(北区王子)※ハイブリッド
Maddalene Napolitani(フィレンツェ,ガリレオ博物館)
『Earth science's visual culture in the 19th century』
問い合わせ先:矢島道子 pxi02070[at]nifty.com
地質学史懇話会
4月13日(日)14:00-17:00
場所:早稲田奉仕園セミナーハウス101号室(新宿区西早稲田)※ハイブリッド
Marianne Klemun(ウィーン大学歴史学元教授):
『Carl Diener and his trip to Japan in 1913』
問い合わせ先:矢島道子pxi02070[at]nifty.com
(後)第62回アイソトープ・放射線研究発表会
7月2日(水)-4日(金)
会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
発表申込締切:2月28日(金)12時
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/jrias2025
日本地質学会第132年学術大会(2025熊本大会)
9月14日(日)-16日(月)
会場:熊本大学黒髪地区
(協)Techno-Ocean 2025
11月27日(木)-29日(土)
会場:神戸国際展示場2号館ほか(神戸市中央区)
https://to2025.techno-ocean.com/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
https://geosociety.jp/outline/content0255.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻地質学鉱物学分野地球テクトニクス
講座教授公募(3/7)
・栗駒山麓ジオパーク ジオパーク専門員(地質学,地理学等)募集(1/31)
・山田科学振興財団2025年度研究援助候補者推薦依頼(学会締切2/3)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 646(2025熊本)トピックセッション募集開始
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.646 2025/2/4┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】第132年学術大会(2025年熊本)トピックセッション募集開始
【2】若手野外地質研究者向け研究奨励金募集中
【3】名誉会員候補者の募集が開始されています
【4】第5回JABEEオンラインシンポ
【5】地質系業界オンライン交流会
【6】Island Arcからのお知らせ
【7】支部のお知らせ
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】第132年学術大会(2025年熊本)トピックセッション募集開始
──────────────────────────────────
2025年9月14日(日)〜16日(火)
会場:熊本大学黒髪キャンパス ※対面開催
熊本市中央区の熊本大学黒髪キャンパスにおいて,第132年学術大会(2025年熊本
大会)を9月14日(日)から16日(火)に開催します.また,巡検(見学旅行)を
12日(金)-13日(土)と17日(水)-18日(木)に催行します.
—-----------------------------
トピックセッション募集(3/21締切)
—-----------------------------
詳しくは、https://geosociety.jp/science/content0041.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】若手野外地質研究者向け研究奨励金募集中
──────────────────────────────────
<2025年度日本地質学会研究奨励金>
日本地質学会では若手育成事業の一環として,野外調査をベースに研究を行う
32歳未満の若手会員を対象とした研究奨励金制度を設けています.
また,昨年度規則改正により助成期間の延長も可能となっています.
**************************************
募集締切:2025年2月28日(必着)
**************************************
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0242.html
(申請に関するFAQも掲載しています)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】名誉会員候補者の募集が開始されています
──────────────────────────────────
募集締切:2025年2月7日(金)
推薦できる人:日本地質学会会長・副会長,理事,専門部会長
名誉会員候補となる人:75歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件:地質学への顕著な貢献または教育現場や企業等での
活動を通じた地質学の普及・振興への顕著な貢献が認められ,かつ本学会への
貢献も認められる会員
(注) 上記「推薦できる人」以外の会員は,候補者を直接推薦することは
できませんが,「推薦できる人」への情報提供をすることができます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第5回JABEEオンラインシンポ
──────────────────────────────────
高等学校での地学教育と大学での専門教育との連携
〜地球科学の中等教育から高等教育にどのように繋げるか〜
今回は、地学教育委員会との共催で「高等学校での地学教育と大学での専門教育と
の連携」をテーマに開催します。 高等学校・大学の教員をはじめ、実社会の専門
技術者など、多くの方にいわゆる「高大連携」「高大接続」についてご視聴いただ
きます。
日時:2025年3月2日(日)13:30-17:20(予定)
開催方式:Zoomを用いたオンライン方式
参加申込締切:2025年2月25日(火)
詳しくは、https://geosociety.jp/science/content0178.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質系業界オンライン交流会開催
──────────────────────────────────
ー地質を仕事にするってどんなだろう?ー
地質学に関わる民間企業や官公庁等に興味がある若手向けの「地質系業界オンライ
ン交流会」を開催します!本交流会では,学生・若手研究者向けに,地質学に関わ
る仕事に従事する若手職員の方との座談会と懇談会を行います.
地質系の民間企業,研究所職員,ジオパーク職員など, 広く地質学に関わる仕事に
携わる方に, 就職してよかったこと,楽しかった仕事,学生時代の経験で役に立っ
たこと,大変だと感じたこと,業界でのキャリア形成などを伺う予定です.通常の
企業説明会や就職説明会とは異なる,若手職員ならではのお話を聴けるチャンス!
皆様,奮ってご参加ください!!
日時:2025年2月14日(金)17:30–19:30
場所:Zoomによるオンライン開催
対象:35歳以下の学生・若手研究者(会員・非会員を問いません)
参加申込締切:2025年2月13日(木)23:59
詳しくは,https://geosociety.jp/science/content0172.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■Island Arc:新しい論文が公開されています.
(RESEARCH ARTICLE)Zircon U–Pb Dating of the Urahoro Group and Atsunai
Formation in the Shiranuka Hills of Eastern Hokkaido, Northeast Japan: Implications
for Tectonic Development:Toru Takeshita et al
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
学会の会員ページからログインすると全文が無料閲覧できます .
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[西日本支部]
西日本支部令和6年度総会・第175回例会
3月1日(土)
会場:北九州市立自然史・歴史博物館
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
[関東支部]
2025年度関東支部総会・講演会
4月12日(土)14:00-16:45
場所:北とぴあ第2研修室(北区王子)
講演会「潜水船・水中ドローンによる島弧-海溝系の海底露頭観察」
講師:山口飛鳥氏(東京大学大気海洋研究所)
総会委任状(4/11最終締切)
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
「地震本部ニュース」2024冬号
ぼうさいこくたい2024in熊本/地震調査研究プロジェクト/地震調査研究
の最前線ほか
https://www.jishin.go.jp/main/herpnews/2024/win/herpnews2024win.pdf
(協)MicroArt2025(顕微鏡写真の写真コンペ企画)
エントリー期間:2025年1月30日(木)-3月28日(金)
どなたでも応募可能です
http://micro-art.tokyo/
北海道立総合研究機構エネ環地研:第63回試錐研究会
2月19日(水)13:00-17:30
会場:札幌サンプラザ2階 「金枝の間」
配信:オンライン配信(Zoomウェビナー)
参加費無料
申込期限:2月12日(水)
https://www.hro.or.jp/industrial/research/eeg/pr/topics/22319-pZPf0RSSuE.html
日本堆積学会 2025 年東京大会(現地・オンライン)
4月19日(土)-20日(日)
会場:東京大学本郷地区キャンパス小柴ホール
・個人講演(口頭,ポスター)
・特別講演「地球環境の変遷と海洋微生物生態系活動の共進化」(仮)田近英一 氏
4月21日(月)
・日帰り巡検「東京低地のボーリングコア観察会と街歩き巡検」小松原純子氏
講演申込・巡検参加締切:3月21日(金)
大会参加申込締切(早期):4月6日(日)
https://sites.google.com/view/ssjconference2025tokyo
JpGU 2025(ハイブリッド方式)
5月25日(日)-30日(金)
現地会場:幕張メッセ
早期投稿締切:2025年2月 6日(木)23:59
最終投稿締切:2025年2月18日(火)17:00
https://www.jpgu.org/meeting_j2025/
(後)第62回アイソトープ・放射線研究発表会
7月2日(水)-4日(金)
会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
発表申込締切:2月28日(金)12時
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/jrias2025
日本地質学会第132年学術大会(2025熊本大会)
9月14日(日)-16日(月)
会場:熊本大学黒髪地区
https://geosociety.jp/science/content0041.html
(協)Techno-Ocean 2025
11月27日(木)-29日(土)
会場:神戸国際展示場2号館ほか(神戸市中央区)
https://to2025.techno-ocean.com/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
https://geosociety.jp/outline/content0255.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・下仁田ジオパーク専門員募集(2/28)
・北海道上富良野町 地域おこし協力隊(R7郷土学習推進員)募集(2/14)
・越知町地域おこし協力隊募集(横倉山自然の森博物館の活用促進に取り組む
協力隊)(2/28まで延長)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 647 (2025年熊本)トピックセッション募集中
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.647 2025/2/18┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】第132年学術大会(2025年熊本)トピックセッション募集中
【2】若手野外地質研究者向け研究奨励金募集中
【3】第5回JABEEオンラインシンポ
【4】Island Arcからのお知らせ
【5】本の紹介「噴火した! 火山の現場で考えたこと」
【6】支部のお知らせ
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】第132年学術大会(2025年熊本)トピックセッション募集中
──────────────────────────────────
2025年9月14日(日)〜16日(火)
会場:熊本大学黒髪キャンパス ※対面開催
熊本市中央区の熊本大学黒髪キャンパスにおいて,第132年学術大会(2025年熊本大会)を9月14日(日)から16日(火)に開催します.また,巡検(見学旅行)を
12日(金)-13日(土)と17日(水)-18日(木)に催行します.
—-----------------------------
トピックセッション募集(3/21締切)
—-----------------------------
詳しくは,https://geosociety.jp/science/content0041.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】若手野外地質研究者向け研究奨励金募集中
──────────────────────────────────
<2025年度日本地質学会研究奨励金>
日本地質学会では若手育成事業の一環として,野外調査をベースに研究を行う32歳未満の若手会員を対象とした研究奨励金制度を設けています.
また,昨年度規則改正により助成期間の延長も可能となっています.
**************************************
募集締切:2025年2月28日(必着)
**************************************
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0242.html
(申請に関するFAQも掲載しています)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】第5回JABEEオンラインシンポ
──────────────────────────────────
高等学校での地学教育と大学での専門教育との連携
ー地球科学の中等教育から高等教育にどのように繋げるかー
今回は,地学教育委員会との共催で「高等学校での地学教育と大学での専門教育との連携」をテーマに開催します. 高等学校・大学の教員をはじめ,実社会の専門
技術者など,多くの方にいわゆる「高大連携」「高大接続」についてご視聴いただきます.
日時:2025年3月2日(日)13:30-17:20(予定)
開催方式:Zoomを用いたオンライン方式
参加申込締切:2025年2月25日(火)
詳しくは,https://geosociety.jp/science/content0178.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■Island Arc:新しい論文が公開されています.
(RESEARCH ARTICLE)Non‐Uniform Stress Field of the Forearc Region in Middle Miocene Southwestern Japan Inferred From the Orientations of Clastic Dikes and Mineral Veins in the Tanabe Group;Noriaki Abe, Katsushi Sato
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
学会の会員ページからログインすると全文が無料閲覧できます .
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】本の紹介「噴火した! 火山の現場で考えたこと」
──────────────────────────────────
「噴火した! 火山の現場で考えたこと」
荒牧重雄 著
東京大学出版会,2021年10月15日初版,B6大判,縦書き273 p. ISBN978-4-13-063717-6,定価2700円+税
筆者(石渡)がパリ第6(キュリー夫妻)大学助手だった頃,1983年7月29日〜8月5日の間,当時Southampton大学で研究していた故柵山雅則氏およびManchester大学で研究していた巽好幸氏とともに,荒牧重雄先生に誘われてスコットランド西部の火成岩地帯を巡検したことがある.天気は悪かったが,Glasgow大学のBell氏の案内でSkye島やArdnamurchanの溶岩,岩脈,岩床などを詳しく見ることができた.また,先生が会議でパリに来られた時に食事をご一緒したこともあった.こんなご縁で,先生の近著を紹介させていただく.
巻末の略歴によると,著者(荒牧)は1930年生まれ,本書執筆時91歳だった.1975年東京大学地震研究所教授になられ,1991年北海道大学理学部教授,1994年日本大学理学部教授,そして2004年から山梨県富士山科学研究所所長を勤められた.本書は1950年代から日本の火山学の第一人者として活躍してきた著者が,ほぼ年代順に内外の火山調査や火山関連のイベントにつき,豊富なエピソードを交えて記述された縦書きの自伝的エッセー集である. 『「火砕流」という言葉の生みの親であり,日本の火山学と火山防災を牽引してきた著者が自らの体験をとおして臨場感たっぷりに語る.』(本書の帯).
本書の章立ては次の通りである(カッコ内は筆者が補った).
第1章 ひとつの都市が消えた――火砕流序説,プレー火山の噴火(1902)(1961国際火山学会で火砕流pyroclastic flow提案)
第2章 火山研究のきっかけ――伊豆大島1950〜51噴火
第3章 史料と足で読み解いた博士論文――浅間火山天明三(1783)年噴火(1953調査開始)
第4章 実験岩石学や巨大カルデラとの出会い――フルブライト留学生としてアメリカへ(1957)
第5章 フランス気質,イギリス気質――火山をめぐるヨーロッパの国民性(1959)
第6章 ハワイの楯状火山はなぜ上に凸か――キラウェア火山1963年噴火
第7章 月面は玄武岩か,岩塩?か――アポロ11号の月面着陸(1969)
第8章 溶岩と氷河の国アイスランド――極地での野外調査(1969)
第9章 フランス人の大論争に巻き込まれる――スフリエール火山1976年噴火
第10章 「火砕流」と言えない?――有珠火山1977年噴火
第11章 山体崩壊と爆風の威力――セントヘレンズ火山1980年噴火
第12章 迅速な避難と溶岩冷却作戦――三宅島1983年噴火
第13章 全島避難の島で――伊豆大島1986年噴火
第14章 火砕流の恐怖,目撃者の証言――雲仙普賢岳1991年噴火
第15章 大都市のそばの火山――イタリアの火山と防災(1990, 1994)
第16章 ハザードマップと対策本部――有珠火山2000年噴火
第17章 火山噴火災害対策について考える
以下に4つの特筆すべき章を選んで紹介する.アポロ11号が1969年7月20日20:17(世界時,日本時は21日5:17),月に着陸した時に著者(荒牧)が民放の番組に出演し(NHKは久野久先生),アームストロング船長が着陸直後の報告で「岩石は玄武岩のように見える」と言った話が面白い.当時は月の表面の岩石について玄武岩説と花崗岩(+火砕流)説があり,アポロの月着陸は両方を考えた計画になっていたが,着陸直後に窓から外を見ただけで,この問題に決着がついたことになる.宇宙飛行士は事前に火山の溶岩原や火砕流地帯等で地質学的な訓練を受け,船長は成績優秀だったそうである.また,玄武岩basaltは米語ではba-Saltと発音するので,不慣れな同時通訳者が岩塩と訳し,著者は密かに大笑いしたそうだ.
小アンチル諸島のスフリエール火山の1976年噴火では数万人の住民が避難したが,避難の必要性を巡りフランスの2人の学者(タジエフTazieff氏:必要×アレーグルAllègre氏:不必要)が鋭く対立した.タジエフ氏は防災大臣,アレーグル氏は教育大臣を勤めた人で権威があり,自説を主張して引かなかった.この問題を決着させるため,外国人学者だけの検討会が設けられ,著者がそれに参加した.「今後3カ月以内の噴火確率は3%以下」との結論をまとめて海外県大臣に持って行ったところ,3%は高すぎると言われ,数字での表現は断念したが,結局避難指示は解除され,タジエフ氏は火山研究所の職を解かれ,アレーグル氏の勝ちになったそうである.
伊豆大島1986年噴火では,著者(荒牧)は現地の火山観測所を拠点として調査していたが,噴火予知連絡会には参加していなかった.噴火は11月15日に三原山山頂火口のストロンボリ式噴火で始まり,21日に外輪山山腹での大規模な割れ目噴火に発展し,22日に全島避難が完了した.そして11月27日,鈴木都知事から呼ばれ,夜間に1人だけヘリに乗せられて東京まで行き,都知事と会談して個人的に噴火の見通しを説明した.会談後はすぐにヘリで大島に帰され,翌朝は「何食わぬ顔で」観測所に戻ったそうである.当時予知連は中村一明氏の影響で噴火がさらに大規模になるという考えに傾いていたが,著者は野外観察で既に峠を越えたと判断していた.この会談は行政側の予知連報告書の取り扱いやその後の政策に影響を与えたと思われる.著者は1986年伊豆大島噴火の体験が,「人に命令されたことはやらない.自分がやりたいことだけをやる」という理学部的な原則から脱して「私自身が火山防災関連の事案にのめり込んでゆく引き金になったのだと思う」と述べている.なお,著者が借りたレンタカーを立入禁止区域内の駐車場に止めて調査していたら,噴石で車が傷だらけになり,業者の抗議に東大地震研の藤井敏嗣氏が対応してくれたとの余話もある.
本書の体験談で最も凄いのが1991年6月3日の雲仙普賢岳の火砕流災害で,火砕流周辺部の火砕サージの領域からの生還者6人に著者(荒牧)自らが聞き取った,小さい活字で12ページもある証言集が白眉である.九死に一生を得た体験が迫真の筆致で描かれており,警察官やタクシー運転手の殉職の様子も痛々しい.また,この火砕サージで3人の外国人火山学者が亡くなったが,著者はこの3人と知り合いだったため,遭難直後に警察からの依頼で遺体を確認し,その様子の記述も恐ろしい.そのうちの1人は著者の研究室に1年間客員研究員として滞在したので描写が詳しい.
以上のように本書は著者の火山学者人生の総まとめと言うべきもので,現役の地質研究者及び学生・院生が心に留めるべき,この著者でなければ語れない興味深い体験談が満載されている.会員各位のご一読をお勧めする.
【追記】本書には既に七山 太氏(2022; GSJ地質ニュース, 11, 59-61)や矢島道子氏(2022; 科学史研究, 61(301), 89-90)らの書評があるが,本会会員にも広く紹介する必要があると考え筆を執った.また,荒牧重雄先生は2020年度東京地学協会メダルを受賞し(地学雑誌, 130(1), N4-N6),2022年11月12日に藤井敏嗣氏との記念講演対談「噴火と火山防災の60余年」があって,その内容には富士・浅間のハザードマップの話が加わった(https://www.geog.or.jp/lecture/reports_lecture/r02medal/).これらの情報をいただいた池田保夫・平田大二両氏に感謝する.
(正会員 石渡 明)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[中部支部]
2025年支部年会
6月21日(土)-22日(日)
会場:静岡大学静岡キャンパス
巡検『瀬戸川帯南部の超塩基性-塩基性岩類の産状』6/22
参加登録方法:25年4月頃事前参加登録のウェブサイト(google forms)
を準備いたします.
https://geosociety.jp/outline/content0019.html#2025nenkai
[西日本支部]
西日本支部令和6年度総会・第175回例会
3月1日(土)
会場:北九州市立自然史・歴史博物館
詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html
[関東支部]
2025年度関東支部総会・講演会
4月12日(土)14:00-16:45
場所:北とぴあ第2研修室(東京都北区王子)
講演会「潜水船・水中ドローンによる島弧-海溝系の海底露頭観察」
講師:山口飛鳥氏(東京大学大気海洋研究所)
総会委任状(4/11最終締切)
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(協)MicroArt2025(顕微鏡写真の写真コンペ企画)
エントリー締切:3月28日(金)
どなたでも応募可能です
http://micro-art.tokyo/
学術会議公開シンポジウム
「人流ビッグデータがもたらす新しい未来像」
主催:日本学術会議地域研究委員会地域情報分科会
3月1日(土)13:00-17:00
開催地:オンライン開催
参加費無料・要事前申込
https://www.scj.go.jp/ja/event/2025/378-s-0301.html
学術会議公開シンポジウム
「初等教育における世界的な視野の獲得について」
主催・共催:日本学術会議地域研究委員会・地球惑星科学委員会合同地理教育・ESD 分科会、日本地理学会地理教育専門委員会
3月20日(木・祝)9:00-12:00
場所:駒澤大学(東京都世田谷区駒沢1-23-1)(日本地理学会春季学術大会開催地)
事前登録なし・参加費無料
https://www.scj.go.jp/ja/event/2025/379-s-0320.html
東京地学協会2024年度の国内見学会
「つくばの研究機関と筑波山」
3月22日(土),23日(日)
宿泊は自由.一方の日のみの参加も可.
案内者:目代邦康,青木正博,芝原暁彦
募集人数:20名,参加費無料
参加申込締切:3月7日(先着順)
https://www.geog.or.jp/tour/info/2025-02-12/
第248回イブニングセミナー(オンライン)
3月28日(金)19:30-21:30
演題:令和6年能登半島地震に伴う沿岸〜海域の変動 ―現地調査の成果―
講師:立石 良 先生(富山大学学術研究部 都市デザイン学系)
参加費:主催NPO会員及び学生の方(無料),非会員の方(1,000円)
https://www.npo-geopol.or.jp/
JpGU 2025(ハイブリッド方式)
5月25日(日)-30日(金)
現地会場:幕張メッセ
https://www.jpgu.org/meeting_j2025/
(後)第62回アイソトープ・放射線研究発表会
7月2日(水)-4日(金)
会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
発表申込締切:2月28日(金)12時
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/jrias2025
日本地質学会第132年学術大会(2025熊本大会)
9月14日(日)-16日(月)
会場:熊本大学黒髪地区
https://geosociety.jp/science/content0041.html
国際ゴンドワナ研究連合(IAGR)2025年総会及び第22回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム
11月2日(日)-6日(木)
会場:延世大学新村キャンパス(韓国・ソウル)
参加登録・発表要旨締切:4月30日(水)
1st circular
http://www.gondwanainst.org/symposium/Symposiums-index.htm
(協)Techno-Ocean 2025
11月27日(木)-29日(土)
会場:神戸国際展示場2号館ほか(神戸市中央区)
https://to2025.techno-ocean.com/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
https://geosociety.jp/outline/content0255.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・日本学術振興会令和8年度採用分特別研究員の募集
-- 特別研究員-PD・DC募集 25年4月上旬-6/3(火)17:00
-- 特別研究員-RPD募集 25年3月中旬-5/12(月)17:00
・2024年度地質調査総合センター(GSJ)オンライン説明会(2/21)対象:GSJで研究職として働くことに興味がある方(特に2026年卒修士卒採用に興味がある方) 学部生、既卒の方も対象
--GSJ修士卒研究職募集(3/9 23:59エントリーシート締切)
--GSJ博士卒研究職公募情報
・京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻地質学鉱物学分野地球テクトニクス講座教授公募(3/7)
・深田地質研究所2025年度「野外調査助成」(4/11)
・JST先端国際共同研究推進事業(ASPIRE)2025年度日英量子共同研究提案募集 (5/9)
・東京地学協会 2025 (令和7) 年度助成[調査・研究等3/31,普及啓発活動(出版)3/31,普及啓発活動(地学・地理教育活動)6/30,普及啓発活動(地学・地理クラブ活動)6/30]
・国土地理協会2025年度学術研究助成(4/1-15)
・栗駒山麓ジオパーク地域おこし協力隊ジオパーク専門員(地質学、地理学等) 募集(3/7)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
旧石器人の琉球列島への航海(前編)
旧石器人の琉球列島への航海(前編)
高山信紀(正会員)
※本文中の青字肩カッコ数字は,文末の文献を示しています.
※図表類をクリックすると大きな画像がご覧いただけます.
まえがき
表-1 琉球列島の旧石器人骨出土遺跡1)
琉球列島の沖縄本島,伊江島,久米島,宮古島,石垣島から旧石器人骨が発見されている(表-1)1).これらのうち,ミトコンドリアDNA分析が行われた港川フィッシャー遺跡の約2万年前の人骨は,縄文時代,弥生時代,現代の集団の直接の祖先ではないことが示唆されたが,現代の日本列島人集団の祖先のグループに含まれるか非常に近いものであり2),白保竿根田原洞穴遺跡の約2万年前の人骨は中国南部や東南アジアに起源をもつ可能性があると考えられている3).本稿では,時代を4万年前と2万年前に設定し,いくつかの文献をもとに旧石器人の琉 球列島への移動経路を考えてみた.
1.4万年前と2万年前の琉球列島
(1)海水準
全球的な海水準は,約12.5万年前の最終間氷期以降一時的な上昇を何度もはさみながら低下し,4万年前は現在より約80m低下,LGM(Last Glacial Maximum,最終氷期最盛期)にあたる2万年前は130m以上低下したが4),いずれのときもトカラ列島以南の琉球列島は九州や台湾,大陸とつながることはなく1),5),琉球列島の旧石器人は海を渡ってきたと考えられている6).
(2)隆起・沈降
図-1 現在,2万年前,4万年前の琉球列島とその周辺
図-2 徳之島と与那国島の隆起量
最終間氷期以降,琉球列島は隆起している.隆起量7)は同じ島でも地点によりばらつきがあるが,隆起量と年代はおおむね比例関係にある(図-2).そこで,琉球列島各島の4万年前から現在までの隆起量UMは,隆起速度が一定と仮定して各島の12.5万年前(海水準+5m7))から現在までの隆起量(データが複数ある場合は平均値)に4.0/12.5を乗じて算出 した.魚釣島の4万年前以降の隆起量UMは,隆起速度0.4〜1m/ 千年7)より28m(0.7m/千年)とし,大正島も同じとした.12.5万年前の隆起量のデータが無い島の隆起量は,隣の島の隆起量 より推測した.2万年前以降の隆起量ULは,4万年前以降の隆起 量UMの1/2とした.(表-2,図-1表) 台湾の蘇澳周辺(与那国島の対岸付近)の隆起量は,近傍の中央山脈北端付近の隆起速度4.1m/ka8) よりUM=164m, UL=82mとした.なお,台湾の海岸山脈東岸の隆起速度は,完 新世海成段丘の年代と高度より5〜15m/kaと考えられており9), 外挿すると4万年前以降の隆起量UMは200〜600mとなる.大陸, 台湾西側,フィリピンの隆起量は考慮していない.
(3)堆積・浸食
表-2 琉球列島の島々の高さ,隆起量など
「高さH」は現在の最高点標高,ただし宮古曽根はその中で最浅の 重宝曽根の水深15),台湾は与那国島対岸付近の大白山の標高.
・「隆起量UM」は4万年前以降の隆起量,( )は近傍の島より推測.
・「高さHM」は4万年前の海面からの高さ.
・「海上距離」は島と島の間の距離.
・「L」は当該の島の最高点が海上の舟から見える最大距離.(本文2.(3))
・「可視」の左側の○,△,▲,★は九州から台湾方面へ向かう航 海のとき,右側はその逆の航海のときに目指す島が見えるか否か を示す.○は出航時の舟から見える.△は出航時の舟からは見え ないが,島の最高点から見える.▲は島の最高点からは見えない が,出航した島が見える範囲内の海上の舟から見える.★は上述 の全ての所から見えない.(本文2.(3))
琉球列島(火山島も含む)と台湾東側は,海底地形が比較的急峻で堆積・浸食が海岸線の水平位置に及ぼす影響は小さく,堆積・浸食は考慮していない.東シナ海は,長江などから供給された膨大な土砂の堆積場で,地震探査などの結果10)に最終間氷期以降の地層の分布概要が示されているが, 4万年前や2万年前の海岸線の位置の推定は難しい.
(4)当時の海面からの高さ
4万年前と2万年前の海面からの高さHMとHLは,当時の海水準をそれぞれ-80m,-130mとし,大陸(現在の東シナ海)を除き堆積・浸食を考慮せず,①式と②式で求めた.4万年前の海面からの島の高さHMを表-2と図-1に示す.
HM=H+80-UM ①
HL=H+130-UL ②
ここで,H(m)は現在の標高.UM(m)は4万年前から, UL(m)は2万年前から現在までの隆起・沈降(沈降はマイナス).
(5)4万年前の海岸線
4万年前の琉球列島の海岸線は,海図11),12),13)を用い,現在の水深80mから隆起量UMの分だけ浅い位置とした.4万年前の琉球列島が現在と大きく異なるのは,7,300年前に大噴火した鬼界カルデラが巨大な火山として海上にそびえ14)(仮称「古鬼界火山」),奄美大島,加計呂麻島,与路島が一つの島(同「古奄美大島」),沖縄本島,伊江島,古宇利島,渡喜敷島,座間味島が一つの島(同「古沖縄島」),渡名 喜島と久米島が一つの島(同「古久米島」),宮古島と伊良部島・下地島が一つの島(同「古宮古島」),石垣島,竹富島,小浜島,西表島が一つの島(同「古八重山島」)で,宮古島東方の宮古曽根15)が島(同「古宮古曽根島」)として海上に現れていたことである(図-1).
4万年前の台湾は,海水準の低下により西側は大陸とつながっていたが,東側は海で与那国島と隔てられていた.4万年前の大陸の海岸線は-80m等深線より西側であるが,その詳細な位置や大陸周辺にどのような島があったかはよく分からない.
(6)2万年前の海岸線
2万年前の琉球列島の海岸線は,水深130mから隆起量ULの分だけ浅い位置とした.2万年前の琉球列島が4万年前と大きく異なるのは,種子島と屋久島が九州と陸続きになり(仮称「古南九州半島」),4万年前の「古沖縄島」と「古久米島」が一つの島(同「古沖縄・久米島」)になり,久米島南西の西大九曽根15)が島(同「古西大九曽根島」)として海上に現れたことである(図-1).
2万年前の台湾は,海水準が130m低下しても東側は海で与那国島と隔てられていた.2万年前の大陸の海岸線は-130m等深線より西側であるが,その詳細な位置や大陸周辺にどのような島があったかはよく分からない.
(7)黒潮
4万年前と2万年前の東シナ海の黒潮は,現在の黒潮16)と同様,台湾東岸沖を北上し台湾と与那国島の間から東シナ海に入りトカラ海峡から九州・四国沖に出て17),18)(図-1),琉球列島周辺の黒潮の速度や流向は季節とともに日々変化し,黒潮速度はおよそ2〜4km/hrと考えた.
参考文献
1)沖縄県立博物館・美術館 「サキタリ洞遺跡の発掘」
2)東邦大学ウエブサイト 「港川1号人骨のミトコンドリアDNA解析で過去から現在までの日本列島人の遺伝的関係性を解明」, 2021年
3)篠田謙一 『DNAで語る日本人起源論』 p150〜p152, 岩波現代全書073, 岩波書店, 2015年
4)横山祐典 「ターミネーションの気候変動」, 第四紀研究49(6), 日本第四紀学会, 2010年
5)横山祐典ら 「見直される琉球列島の陸橋化」, 科学Vol.88, No.6, 岩波書店, 2018年
6)海部陽介 「黒潮と対峙した3万年前の人類―航海プロジェクトから」, 科学Vol.88,No.6, 岩波書店, 2018年
7)小池一之・町田洋編 『日本の海成段丘アトラス』及びCD-ROM「日本Ⅲ中国・四国・九州・南西諸島-海成段丘による垂直変動量のデータ一覧表」, 東京大学出版会, 2001年
8)CHEN Yen-Chieh et al. 「Stream-power incision model in non-steady-state mountain ranges: An empirical approach」Fig.2, Chinese Science Bulletin, Vol.51, No.22, 2006年
9)山口勝・太田陽子 「台湾海岸山脈東岸の完新世海成段丘と地殻変動」, 地学雑誌111(3), 東京地学協会, 2002年
10)Chen Dai et al. 「A Paleo-Changjiang Delta Complex on the East China Sea Shelf Formed Some 30 ka Ago (at the MIS 3 Stage)」, J. Mar. Sci. Eng, 2023年
11)マリーンネットワークス(株)ウエブサイト 「みんなの海図」
12)海上保安庁 「1:1,500,000漁業用海図 FW210長崎至厦門」, 2007年
13)海上保安庁 「1:2,500,000航海用海図 W1676フィリピン諸島及近海」, 2005年
14)JAMSTECウエブサイト「JAMSTEC BASE-巨大海底火山鬼界カルデラの過去と現在」, 2022年
15)海上保安庁「1:1,000,000海底地形図6720南西諸島」, 2017年
16)気象庁ウエブサイト「海流に関する診断表、予報、データ:日別海流(沖縄周辺)」
17)久保田好美 「最終氷期の黒潮の復元」, 科学Vol.88,No.6, 岩波書店, 2018年
18)研究代表 郭新宇 「万年スケールでみた黒潮の流路変遷と黒潮分岐流の形成メカニズム」, 科学研究費助成事業研究成果報告書, 日本学術振興会, 2021年
(後編へ続く)
【geo-Flash】 No. 648 (臨時)訃報:杉村 新 名誉会員
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.648 2025/3/3 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 杉村 新 名誉会員 ご逝去
──────────────────────────────────
杉村 新 名誉会員(元 神戸大学教授)が、令和7年3月1日に逝去
されました(101歳)。これまでの故人の功績を讃えるとともに、
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
ご葬儀は下記のとおり執り行われます。
日時:2025年3月11日(火)10時より
場所:桐ヶ谷斎場(東京都品川区西五反田5-32-20)
(生花手配:東京花壇祭典 TEL 03-3409-4952)
喪主:杉村丈一様(長男)
会長 山路 敦
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
第16回_最優秀
第16回惑星地球フォトコンテスト入選作品
最優秀賞:時を閉じ込めた青の世界
写真:ジェシー(東京都)
撮影場所:アイスランド南東部、ヴァトナヨークトル国立公園
【撮影者より】
悠久の時を経て創り出された氷河の洞窟.その透明度の高い氷には,数千年もの時が閉じ込められています.氷の壁を見上げる探検者の姿は,人間の小ささと自然の偉大さを対比し,冬の限られた瞬間にしか立ち入ることのできないこの奇跡の空間を象徴しています.氷河は常に変化し続けており,今見ているこの景色もやがて消えてしまう運命にあります.だからこそ,この一瞬を切り取ることに意味があるのです.
【審査委員長講評】
ヴァトナ氷河はアイスランド最大の氷河で,谷埋めの氷河ではなく,氷床と呼ばれる規模の大きな氷河です.氷河の底にできたトンネルを探険するツアーに参加したときの作品だと思いますが,超広角レンズでとらえたトンネル上部の雪氷の質感,ガイドの位置や視線が優れており,自分が案内されているような気分になります.
【地質解説】
ヴァトナヨークトル(Vatnajökull)は,アイスランド最大の氷河(jökull)で,氷河の下には,西部で南北に中央海嶺の一部である東部火山帯が走るほか,東部でもいくつかの火山体が認識されています.この氷河の下の火山はときどき噴火を起こし,1994年には氷河を溶かして,最大流量5×104 m3/sの大洪水(jökulhlaup)が発生しました.最新の噴火は,2011年です.写真のような氷河底へは,複数のガイドツアーが氷河の南にある町を起点に催行されているようです.(萬年一剛:神奈川県温泉地学研究所)
目次へ戻る
第16回_優秀01
第16回惑星地球フォトコンテスト入選作品
優秀賞:朝日を浴びて
写真:芝粼静雄(愛媛県)
撮影場所:高知県 竜串海岸
【撮影者より】
地震による海底地すべりでできたと考えられる欄間石や蜂の巣状の穴がみられます,自然が生み出した奇岩がたくさん見られます.朝陽を待って撮影しました.
【審査委員長講評】
足摺岬の近くにある竜串海岸は砂泥互層がつくる奇勝で,多数の写真が撮影されています.陸側から海側に向かっての構図が多いのですが,この写真は海側から陸側を撮影したもの.この配置によって地層を立体的にみせることができます.山の端から昇ってきたばかり太陽を配置すると露出の調整が大変ですが,うまく処理されています.
【地質解説】
中新統三崎層群は,高知県南西端の土佐清水市に分布する,日本海の拡大時期に前弧海盆を埋めた地層です.竜串海岸では,本層群最上部を構成する竜串層の下部が露出しており,波浪やストームの作用が卓越した沖浜漸移帯〜外浜の堆積物を観察できます.写真中央より向かってやや左側の欄間石(砂岩)は,コンボリュート構造が日本の建築様式にみられる「欄間」を思わせるところが名前の由来です.他にも三崎層群には未固結時の変形構造が発達しており,その多くは地震動に関連してできたと言われています.また,写真中央のストーム成砂岩層の手前側などに点々と見られる赤茶けた丸い塊は,酸化鉄の薄い被膜に覆われた炭酸カルシウムの球状コンクリーション(ノジュール)です.もう一つ,現地に行くと砂岩表面の所々に蜂の巣状の穴が発達しています.これは塩類風化による微地形“タフォニ”です.(藤内智士:高知大学)
目次へ戻る
第16回_優秀02
第16回惑星地球フォトコンテスト入選作品
優秀賞:異空間
写真:徳富 豊(熊本県)
撮影場所:熊本県阿蘇市 阿蘇山杵島岳山頂から中岳を撮影
【撮影者より】
世界最大級のカルデラとも言われる阿蘇山の火映と天の川を捉えた一枚です. 昨年は火映現象が活発な時で暗くなると肉眼でも赤く燃え上がるような光景を目にすることができ, 大地の壮大さを感じさせられました. また背景に天の川があることで地球上とは思えない風景を感じさせることから「異空間」とタイトルを付けさせていただきました.
【審査委員長講評】
画面の中央に火映の灯るどっしりとした阿蘇中岳を配置し,その上に横たわるのは昇ってきたばかりの夏の天の川,すばらしい構図です.地形,天文,火山の知識や高度な撮影技術がなければこのような作品は得られません.こんな光景を眺めたくなりますが,実際には長時間露光による写真の中だけで生み出される世界です.
【地質解説】
火映現象が見られる中岳は,わが国で最も活発な火山の一つで,約2万年前から活動を開始したと考えられ,現在も阿蘇カルデラ内で唯一活動する火口丘です.最近では2021年10月に爆発的な噴火が発生しました.その一方で,写真が撮影された杵島岳は4000年前頃に形成されたスコリア丘で,米塚などとともに阿蘇では最も新しい火山の一つですが,現在はまったく活動しておらず,小規模ながら噴火を続ける中岳とは対照的です.(宮縁育夫:熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター)
※「火映現象」:火山の火口付近にある高温の溶岩や火山ガス等で,火口上空の噴煙や雲が、明るく照らされる現象のこと.
(参考)火山活動全般に関する用語 (気象庁HPより)https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kazan/kazanyougo/katsudo.html
目次へ戻る
第16回_ジオパーク
第16回惑星地球フォトコンテスト入選作品
ジオパーク賞:エメラルドブルーの波蝕甌穴群
写真:伊藤裕也(福井県)
撮影場所:佐渡ヶ島 平根崎
【撮影者より】
夕暮れの海岸.岩場に空いた丸い穴々の不思議さと,エメラルドブルーの色が印象的でした.
【審査委員長講評】
甌穴(ポットホール)は川の流れや波の力によって小石がぐるぐると回ることによって侵食されてできる穴です.佐渡島平根崎は70以上も波蝕甌穴がある日本最大の分布地で,天然記念物となっています.作者はその1つに注目し,中景に白波,遠方の夕陽を配置して印象的な作品となりました.
【地質解説】
波食甌穴とは,波打ち際の地層にできたくぼみに硬い石が入り込み,波の営力によって石が回転,鉛直方向に削られた円筒状の穴のことを言います.平根崎の地層は,1700万年前の日本海誕生時の砂岩,礫岩で構成されており,地層上で回転する礫が多量に供給できたことと,削られやすい砂岩層が広く分布していたことから,約200個もの甌穴が形成されました.日本国内でもその数は圧倒的であり,国の天然記念物に指定されています.(相田満久:佐渡ジオパーク 推進指導員)
目次へ戻る
第16回_会長賞
第16回惑星地球フォトコンテスト入選作品
日本地質学会会長賞:白亜紀末の断崖
写真:佐藤峰南(福岡県・日本地質学会会員)
撮影場所:デンマーク Stevns Klint(シェラン島)
【撮影者より・地質解説】
海岸線に15 kmに渡り続く高さ約40 mの断崖は,下部が軟らかい白亜紀末(マーストリヒチアン)のチョーク,上部が硬い古第三紀初期(ダニアン)の石灰岩から成り,波の侵食によって張り出した形状が作られました.白色の崖と対照的な黒色の浜辺は,波打ち際で円磨された珪質ノジュールによって埋め尽くされており,崖をよく見ると炭酸塩の層理面と調和的なノジュール層が観察されます.(佐藤峰南:九州大学)
【審査委員長講評】
K/Pg(白亜紀−古第三紀)境界はイタリアのグッピオ,スペインのズマヤなど世界各地にありますが,アクセスがよく,連続的に見られる点ではこの露頭が一番でしょう.日本では1987年,NHKの『地球大紀行』で紹介されてから有名になりました.境界層は影の中にほぼ水平に延びています.
目次へ戻る
第16回_ジオ鉄
第16回惑星地球フォトコンテスト入選作品
ジオ鉄賞:稜線の美しさがまぶしい開聞岳と時々枕崎線
写真:水口和史(福岡県)
撮影場所:鹿児島県指宿市山川大山 JR西大山駅付近
【撮影者より】
成層火山である開聞岳の昔の噴火ではコラと呼ばれる火山噴出物が薩摩半島南部に堆積しました.吸水性が悪く固いため農業の障害となっていたが昭和の時代に除去が始まり今では開聞岳周辺にも畑地帯が広がっています.電車が来るたびに多くの撮影者が集まり状況が悪いのか電車の警笛が多く聞こえるのがまるでコラッどいてという風にも聞こえます.相手に注意するときに最初に出る『こらっ』という言葉も鹿児島弁に由来しているようです.
【講評・地質解説】
薩摩半島を走るJR指宿枕崎線(鹿児島中央~枕崎間).薩摩富士とも呼ばれる開聞岳(924m)の東山麓に位置する西大山駅は日本最南端の駅として知られる人気の撮影スポットです.夕陽に照らされた開聞岳のシルエットが美しく,典型的な成層火山の地形とそれを覆う安山岩の溶岩ドーム(885年噴火)の稜線が写しこまれています.逆光の撮影ながら,西大山駅を出発した列車(キハ47形)が光線に包まれる瞬間が絶妙なバランスで捉えられており,眩しくも美しい夕景が印象的なジオ鉄作品になっています.(藤田勝代:深田研ジオ鉄普及委員会)
目次へ戻る
第16回_スマホ
第16回惑星地球フォトコンテスト入選作品
スマホ賞:静寂が語る大地の悪戯
写真:丸山 舞(神奈川県)
撮影場所:北海道大雪山系 忠別川アイシポップ川
【撮影者より】
アイシポップ川を降っていくと水流が突然消え,静寂の美しいゴルジュが現れます.かつては轟々と流れていたのかもしれませんが,今は異様な静けさと神秘的な雰囲気が漂うのみです.ゴルジュの終わりが近づくと伏流した水が一段と冷たい湧水となって復活,そのまま空が開けて羽衣の滝へと流れ込みます.羽衣の滝は,忠別川の下刻侵食により生まれた懸崖瀑で,右岸から二見川が滝中で合流します.静と動が交錯する,隠された自然の神秘がありました.
【審査委員長講評】
弱く溶結した火砕堆積物が侵食されるとこのようなゴルジュができます.太陽光がほとんど当たらないので苔むしたグリーンの世界.シンプルな画面構成の中で登山者の位置や見上げた視線が良かった.こういう時にはスマホの広角レンズが役立ちます.
【地質解説】
大雪山は,少なくとも数十万年以上にわたって,噴出中心を変えつつ活動を続けている火山群です.約3万8千年前,大雪山の中央付近,御鉢平カルデラで巨大な噴火が少なくとも2回発生し,大雪山の周辺は噴出した膨大な火山灰や軽石(御鉢平火砕流堆積物)で埋め尽くされました.このゴルシュは,御鉢平火砕流堆積物が堆積後の冷却過程で溶結し,河川により浸食されて形成されたものです.将来はさらに侵食が進んで天人峡や層雲峡のような深く険しい谷へと姿を変えていくことでしょう.大地が姿を変えていく過程で生まれたこの美しい緑の回廊を,大切に守りながら楽しんでいきましょう.(廣瀬 亘:北海道立総合研究機構)
目次へ戻る
第16回_大学生賞
第16回惑星地球フォトコンテスト入選作品
大学生・大学院生賞:5億5000万年前のデルタ
写真:福山康太(福岡県)
撮影場所:マレーシア ランカウイ島 Sandy Skulls Beach
【撮影者より】
「東南アジア初のジオパーク」そのフレーズに惹かれ,バックパックでマレーシアのランカウイ島に行ってきました.海岸を少し歩くと色鮮やかな露頭が現れ,平行葉理や斜交葉理といった堆積構造が卓越した砂岩を観察できました.5.5億年前という古さに驚きです.ここランカウイ島では島全体がジオパークとして観光地化されています.貴重な地質を観光資源としている成功例として,参考にすべき魅力ある場所だと思います.
【審査委員長講評】
どこの地層だろうと解説を読んだらマレーシア,ランカウイ島の5.5億年前の地層でした.ホームページを見ると堅苦しさはなく,地層とジャングルが広がるジオフォレストパークで,行きたくなるようなリゾートでした.1枚の写真から思いが広がります.
【地質解説】
アジア大陸は中生代から新生代にかけて,微小大陸塊(マイクロ大陸)が集合衝突してできたといわれています.この写真が撮影されたLangkawi(ランカウィ島)は,東南アジアを形成する微小大陸塊のひとつSHAN-THAIに属し,Cimmeria(キンメリア大陸)の一部でした.SHAN-THAIはカンブリア紀にはゴンドワナ大陸の周辺に位置し,南緯30°前後にあったと推定されています.本露頭の砂岩泥岩互層は,デルタ堆積物とみなされています.(参考文献;Charusiri et al. 2002, J. Geol. Soc. Thailand, 1, 1-20)(久田健一郎:NPO法人地学オリンピック日本委員会)
目次へ戻る
第16回_入選01
第16回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:四倉海岸の砂絵
写真:志賀敏広(福島県)
撮影場所:福島県いわき市四倉 四倉海岸
【撮影者より】
いわき市四倉町にある四倉海岸で見た砂模様です.風の作用で出来たのか,波の作用で出来たのか不明です.この模様が出来る砂は黒っぽく湿っています.乾いた白い砂ではありません.オーストラリアの先住民族アボリジニの絵に似ていると思いました.自然が描く大地のアートです.
【審査委員長講評】
最近はインスタグラムの流行によって同じような写真が大量生産される傾向にうんざりしているので,このようなユニークな写真を見るとほっとします.スケールはありませんが,そのことが却ってこの抽象画のようなパターンがどうやってできたのだろうと好奇心を搔き立てられます.
【地質解説】
現世の砂浜海岸の波打ち際で見られる不思議な模様です.黒い部分は砂鉄質(重鉱物の多い)葉理(波が作る1cm以下薄い砂層),白い部分は石英質(無色鉱物の多い)葉理)と推測されます.それらが細かく交互に繰り返した(薄互層)砂浜面にできた,起伏のある波浪侵食微地形面を上から見ているのではないでしょうか.(安藤寿男:茨城大学)
目次へ戻る
第16回_入選02
第16回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:雪化粧したフォッサマグナ
写真:名知典之(愛知県)
撮影場所:長野県上空
【撮影者より】
上空から見たフォッサマグナは,妙高山,黒姫山など個性的な山々や,野尻湖など複雑な地形に富んでいました.
【審査委員長講評】
中央には妙高山,黒姫山,新潟焼山などの火山,その奧には糸魚川の低地が境するフォッサマグナの糸静線,遙か遠方には黒部扇状地が見えます.作者は写真狙いでこの座席を予約していたのでしょうか.翼や窓枠の配置は飛行機に乗っているよう気分にさせられます.冬の日本海側でこのような快晴に恵まれたのはラッキーでした.
【地質解説】
写真の奥から手前に,富山平野の黒部川扇状地(写真左奥),飛騨山脈(北アルプス)からフォッサ・マグナ北部に位置する長野県野尻湖(写真左下)までが写っています.フォッサ・マグナは,日本列島にそって伸びる古い地質構造を断ち切り,二つに大きくわける裂け目で,新しい地層が厚く溜まっている場所です.この裂け目は,かつてユーラシア大陸にくっついていた日本列島が,日本海の形成によって大陸から分かれる時に造られた大きな溝です.フォッサ・マグナの西縁は,糸魚川−静岡構造線とよばれる断層で,この写真の右上の平地に位置する糸魚川から左やや下の方向に伸びる谷沿いにほぼ沿って,その断層が通っています.糸魚川−静構造線の手前側がフォッサ・マグナで,かつての海に堆積した地層が,その後の地殻変動で2400mほどの高さまで隆起して山となっています.その地層がつくる山の上に,新潟焼山や黒姫山,妙高山(野尻湖の奥の山々)などの火山が活動しています.(及川輝樹:産総研地質調査総合センター)
目次へ戻る
第16回_入選03
第16回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選:危峡を貫く
写真:矢粼 煌(埼玉県)
撮影場所:三好市,小歩危峡 JR土讃線(小歩危~阿波川口間)
【撮影者より】
吉野川や四国山地の地層・断層によって成り立ち,様々な特徴が見られる小歩危,自然と人々の間で難工事が続いた土讃線が走ります.「歩危」は古語で川沿いの崖を意味する言葉と謂れています.自然からの大きな力が見られる小歩危は,素晴らしい景観と,地質を観察するには絶好の場所だと感じ撮影しました.
【講評・地質解説】
四国の地質を縦断しながら走るJR土讃線(多度津~窪川).土讃線はジオ鉄として最初に取り組んだ思い入れのある路線です(加藤ほか,2009).徳島県三好市の小歩危展望台からは,四国山地の隆起と吉野川の下刻がつくった河川地形の絶景を展望できます.やってきたのは車両の彩鮮やかな3両編成の観光列車「四国まんなか千年ものがたり」.列車は急峻な地形を克服しながら侵食段丘(岩石段丘)に沿って進みます.
(参考)加藤弘徳・藤田勝代・横山俊治(2009):ジオ鉄を楽しむ-鉄道車窓からのジオツアーの提案(1.JR四国・土讃線), 総特集ジオパーク(2)地球科学がつくる持続的な地域社会,月刊地球,vol.31, no.8,445-454.
(藤田勝代:深田研ジオ鉄普及委員会)
目次へ戻る
第16回_入選04(中高生部門)
第16回惑星地球フォトコンテスト入選作品
入選(中高生):長い時間をかけた鍾乳石
写真:田中孝樹(神奈川県)
撮影場所:沖縄県 おきなわワールド
【撮影者より】
修学旅行で鍾乳洞に入った時の写真です.鍾乳石を見た時とても神秘を感じ,どうやってできるのかなどを調べ,長い年月をかけてできることを知ったのでこのタイトルにしました.
【審査委員長講評】
中高校生部門に応募されました.デジタルではフィルム代がかからないので,たくさん撮ってその中から選ぶことができます.たくさんのジオに接し,よく観察して撮影し,その中から素晴らしい写真を残してください.
【地質解説】
琉球列島には,サンゴ礁性堆積物からなる上〜中部更新統琉球層群が広く分布しています.高温多雨の気候により,これらの石灰岩は溶解し,地下には多くの鍾乳洞が形成されています.内部には,滴下する地下水から,つらら石や石筍,フローストーン,あるいはリムプールなど様々な鍾乳石が生成され,地下宮殿のようになっています.写真でも,石筍やこれらがつらら石とつながった石柱が照明に浮かび上がり,荘厳な雰囲気を醸し出しています.(松田博貴:熊本大学)
目次へ戻る
第16回_佳作01-03
第16回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:楯状火山・テンデュレク山の広がり
写真:長谷川 卓(石川県・日本地質学会会員)
撮影場所:トルコ東部 ドバイからクラクフ(ポーランド)に向かう機上
【撮影者より】
明瞭な2つの火口(奥側は擂鉢状で火口湖)を持つ活火山・テンデュレク山(3584m)はアナトリア・アラビア・ユーラシアの3プレート三重会合点付近に位置しています.溶岩の広がりや組成の違うマグマが複数回流下したことなど楯状火山の全体像がよく解ります.直近の活動は1855年.大アララト山(5137m)と小アララト山(3896m)を背後に望みます.アララト山は旧約聖書の創世記でノアの箱舟の漂着地とされています.iPhone12で撮影しました.
目次へ戻る
佳作:びょうぶ岩の夕暮れ
写真:山口正明(千葉県)
撮影場所:千葉県 南房総市 白浜町根本海岸
【撮影者より】
干潮の時刻を見計らって,びょうぶ岩を訪問.青のりがびっしりと付き,ほほに当たる風は冷たかったものの,しっかりと早春の趣を呈していました.自然の営みを感じました.
目次へ戻る
佳作:海底大地
写真:橋爪稜翔(埼玉県)
撮影場所:高知県室戸市室戸岬
【撮影者より】
高知県室戸岬にタービダイト層と呼ばれる砂や泥が海水と混ざり海底に降り積もり,約2千万年前かけて海底から隆起してきた縞模様の地層.人類の誕生が約20万年前.遙か昔に誕生したこのタービダイト層との対比を表しました.
目次へ戻る
第16回_佳作04-06
第16回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:牙城桜島
写真:楮山 武(鹿児島県)
撮影場所:鹿児島県鹿児島市桜島小池町1025 湯之平展望所
【撮影者より】
人々の生活と共にある活火山桜島.一般の人が立ち入り出来る最高地点.湯之平展望所より撮影しました.いつ噴火するかわからない緊張感の中で,眼前に広がる荒々しい山肌に差し込む光,山肌の麓にある過酷な砂防ダム現場.壮大な自然の力に魅了され,シャッターをきりました.
目次へ戻る
佳作:東シナ海の沿岸流が作り出した甑島の奇岩
写真:水口和史(福岡県)
撮影場所:鹿児島県 薩摩川内市下甑町瀬々野浦
【撮影者より】
甑島は砂岩泥岩からなる姫浦層群が広く分布しており下甑島の長浜地区辺りから南部まで島中心部には花崗閃緑岩の分布もあります.島の沿岸は海食崖による断崖絶壁が多くここ瀬々野浦の周辺も同様で勢いのある沿岸流の浸食を受けて形成されたと思われる奇岩群を間近で見ることができ海成層堆積物からなる明瞭な層理に圧倒されます.そばの磯には奇岩と同じ色のきれいな丸い石が多くあり叩くと表面の強度から砂岩堆積岩と分かります.
目次へ戻る
佳作:湧水砂模様
写真:佐々木亮太郎(秋田県)
撮影場所:山形県 飽海郡遊佐町釜磯海岸
【撮影者より】
撮影地の釜磯海岸は鳥海山から海中まで流れ込んだ溶岩で出来ていてスポンジのような役目をして雨水や雪解け水をためこみ,およそ20年かけて砂浜や岩場の隙間から“ぽこぽこ”と湧き出しています.作品の表現として湧水が樹の枝の様に流れ海に向かっている所です.砂浜に現れた自然のアート作品の様でした.
目次へ戻る
第16回_佳作07-09
第16回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:桜島の爆発的噴火
写真:片平洋一(鹿児島県)
撮影場所:鹿児島市名山町
【撮影者より】
約3万年前に破局噴火によってできた鹿児島湾の北部に位置し,今も活発な活動を続ける活火山の桜島.その4㎞先には人口60万人ほどの鹿児島市街地があり,都市と火山が共生するのは世界的にも珍しいとのこと.
目次へ戻る
佳作:潮騒のレリーフ
写真:小池啓高(東京都)
撮影場所:キリバス共和国 クリスマス島(kiritimati island)
【撮影者より】
この写真はキリバス共和国のクリスマス島(kiritimati)のアウトリーフを空撮したもので,波の浸食とサンゴ礁の成長が生み出した独特の海岸線です.青とエメラルドの海に,隆起と溝が織りなす美しい模様が広がっています.マンタが悠然と泳ぐ姿も捉えられ,豊かな海洋生態系を感じさせます.自然が作り出した壮観な景観と,生命の営みが交差する瞬間を撮影しました.
目次へ戻る
佳作:立山の流れ沢を背に
写真:伊藤裕也(福井県)
撮影場所:富山県 室堂
【撮影者より】
秋の紅葉に染まった立山室堂.雄大な流れ沢を背に歩くハイカーとのスケールの違いを一枚で表現しました.
目次へ戻る
第16回_佳作10
第16回惑星地球フォトコンテスト:佳作
佳作:那智の滝
写真:古田大樹(東京都)
撮影場所:和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山
【撮影者より】
熊野古道を抜けた先,飛瀧神社へ向かう石段を降りると姿を現すのが,古来より熊野の聖地であった那智の滝です.日本最大の落差を誇るこの大瀑布は,火成岩と堆積岩の間の侵食の程度の違いで形成されていると考えられています.滝上部には板状節理が,滝の下部は柱状節理が発達していることが見て取れます.
目次へ戻る
【geo-Flash】 No. 649 今年も「地質の日」始まります!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.649 2025/3/4┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】第132年学術大会(2025年熊本)トピックセッション募集中
【2】2025年「地質の日」行事のご案内
【3】Island Arcからのお知らせ
【4】会員の学術・教育・社会貢献活動
【5】支部のお知らせ
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】第132年学術大会(2025年熊本)トピックセッション募集中
──────────────────────────────────
2025年9月14日(日)〜16日(火)
会場:熊本大学黒髪キャンパス ※対面開催
熊本市中央区の熊本大学黒髪キャンパスにおいて,第132年学術大会(2025年熊本
大会)を9月14日(日)から16日(火)に開催します.また,巡検(見学旅行)を
12日(金)-13日(土)と17日(水)-18日(木)に催行します.
?-----------------------------
トピックセッション募集(3月21日締切)
?-----------------------------
詳しくは,https://geosociety.jp/science/content0041.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2025年「地質の日」行事のご案内
──────────────────────────────────
2025年の「地質の日」に関連した日本地質学会主催,共催,後援等の催しを
ご紹介します。
惑星地球フォトコンテスト第16回ほか入選作品展示会/オンライン一般講演会
「ナウマン来日150年.その功績と足跡を辿る」/三浦半島活断層調査会:海底
に眠る南下浦断層などなど
このほかにも随時情報を更新します.https://geosociety.jp/name/content0181.html
このほか,地質学会以外の全国の地質の日イベント情報はこちら
https://www.gsj.jp/geologyday/2025/index.html(地質の日事業推進委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■Island Arc:新しい論文が公開されています.
(RESEARCH ARTICLE)P?T Evolution of Paleoproterozoic Dangoli Pelitic
Gneisses, Baijnath Klippe, NW Himalaya: Insights From the Geochemistry
and Zircon U?Pb Geochronology. Mallickarjun Joshi et al
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738
学会の会員ページからログインすると全文が無料閲覧できます .
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】会員の学術・教育・社会貢献活動
──────────────────────────────────
岡本 敦会員(東北大学)の研究成果(岩石亀裂内でのシリカ析出による
流体圧振動を発見)が、東北大学からプレスリリースされました.
詳しくは,https://geosociety.jp/science/content0109.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[中部支部]
2025年支部年会
6月21日(土)-22日(日)
会場:静岡大学静岡キャンパス
巡検『瀬戸川帯南部の超塩基性-塩基性岩類の産状』6/22
https://geosociety.jp/outline/content0019.html#2025nenkai
[関東支部]
2025年度関東支部総会・講演会
4月12日(土)14:00-16:45
場所:北とぴあ第2研修室(東京都北区王子)
講演会「潜水船・水中ドローンによる島弧-海溝系の海底露頭観察」
講師:山口飛鳥氏(東京大学大気海洋研究所)
総会委任状(4/11最終締切)
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(協)MicroArt2025(顕微鏡写真の写真コンペ企画)
エントリー締切:3月28日(金)
どなたでも応募可能です
http://micro-art.tokyo/
IUGS - Initiative on Forensic Geology Conference
(IUGS法地質学イニシアチブ会議)
5月21日(水)-23日(金)
会場:Spazio Europe(イタリア・ローマ市)
https://www.iugs-ifg2025.com/
JpGU 2025(ハイブリッド方式)
5月25日(日)-30日(金)
現地会場:幕張メッセ
https://www.jpgu.org/meeting_j2025/
地質学史懇話会例会
6月8日(土)13:30-17:00
場所:北とぴあ 803号(東京北区王子)
加藤茂生:(仮題)最初期の東京地学協会
会田信行:『最新地学事典』の中の地球科学史
(後)第62回アイソトープ・放射線研究発表会
7月2日(水)-4日(金)
会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
発表申込締切:2月28日(金)12時
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/jrias2025
日本地質学会第132年学術大会(2025熊本大会)
9月14日(日)-16日(月)
会場:熊本大学黒髪地区
https://geosociety.jp/science/content0041.html
(協)Techno-Ocean 2025
11月27日(木)-29日(土)
会場:神戸国際展示場2号館ほか(神戸市中央区)
https://to2025.techno-ocean.com/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
https://geosociety.jp/outline/content0255.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・東京学芸大学自然科学系環境科学分野(岩石鉱物学)教員公募 (4/15)
・東京大学地震研究所共同利用「特定機器利用」公募(4/4)
・コスモス国際賞推薦募集(学会締切3/30)
・令和7年度南アルプス学会研究助成(3/24)
・JST先端国際共同研究推進事業(ASPIRE)2025年度日英AI・情報共同
研究提案の募集(5/23)
・令和7年度むつ市ジオパーク推進員募集(3/13)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 650(2025年熊本)トピックセッションまもなく締切
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.650 2025/3/18┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2025年熊本大会 トピックセッション まもなく締切
【2】2025年「地質の日」行事のご案内
【3】Island Arcからのお知らせ
【4】オーサーシップ・二重投稿等に関するアンケート調査への協力依頼
【5】本の紹介「月面フォトアトラス」
【6】支部のお知らせ
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】会員情報に変更があった場合は...
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2025年熊本大会 トピックセッション まもなく締切
──────────────────────────────────
熊本大会トピックセッションはまもなく募集締切です.セッション開催希望
のグループ・団体は,忘れずにお申し込みください.
—-----------------------------
トピックセッション募集(3月21日締切)
—-----------------------------
第132年学術大会(2025年熊本)
2025年9月14日(日)〜16日(火)
会場:熊本大学黒髪キャンパス ※対面開催
詳しくは,https://geosociety.jp/science/content0041.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2025年「地質の日」行事のご案内
──────────────────────────────────
2025年の「地質の日」に関連した日本地質学会主催,共催,後援等の催しを
ご紹介します。
惑星地球フォトコンテスト第16回ほか入選作品展示会/オンライン一般講演会
「ナウマン来日150年.その功績と足跡を辿る」/街中ジオさ散歩
in Chiba/地球科学講演会 などなど
このほかにも随時情報を更新します.
https://geosociety.jp/name/content0181.html
このほか,地質学会以外の全国の地質の日イベント情報はこちら
https://www.gsj.jp/geologyday/2025/index.html(地質の日事業推進委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■Island Arc:新しい論文が公開されています.
(RESEARCH ARTICLE)Diatom and Radiolarian Biostratigraphy in the Vicinity of
the 2011 Tohoku Earthquake Source Fault in IODP Hole 343‐C0019E of JFAST.
Masao Iwai et al
学会の会員ページからログインすると全文が無料閲覧できます .
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】オーサーシップ・二重投稿等に関するアンケート調査への協力依頼
──────────────────────────────────
近年、不適切なオーサーシップや二重投稿など、特定不正行為以外が問題となる
ケースが増えています。研究活動を萎縮させず、研究者が安心して研究活動に
取り組んでいくためには、学協会や学術誌、大学、研究機関等において、研究
活動の実態や研究分野の特性を踏まえたうえで、ルールの策定を含めた適切な
取り組みが進展することが重要です。
そこで今回、オーサーシップと二重投稿に関するアンケートを実施いたします。
ご協力いただけますと幸いです。
【オーサーシップ・二重投稿等の認識に関するアンケート(Web)】
1.調査目的
研究活動にかかわっている研究者のみなさまが、オーサーシップや二重投稿に
ついてどのように考えているかを把握し、研究分野による特性や分野を超えた
認識について明らかにするため。
2.アンケートサイト
(1)URL(以下のリンクよりご回答ください。回答は任意です。)
https://forms.office.com/r/KGbgwSx4Gf
(2)調査対象:研究者(学部生・大学院生、ポスドク等を含む)
(3)所要時間:15分程度
(4)回答締切:2025年3月23日(日)
3.結果の公開
アンケートの結果は、研究者のみなさまや協力いただいた学協会にて
ご活用いただけるよう、プロジェクトウェブサイトにて公開いたします。
また、詳細な分析結果については、学会や学術誌等にて発表する予定です。
<アンケート問い合わせ先>
大阪大学全学教育推進機構・教授 中村征樹
「研究分野の多様性を踏まえた研究公正規範の明確化と共有」
(JST科学技術イノベーション政策のための科学研究開発プロジェクト採択課題)
E-mail : inquiry-ristex21[at]research-integrity.info
https://research-integrity.info/2021ristex/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】本の紹介「月面フォトアトラス」
──────────────────────────────────
月面フォトアトラス 精細画像で読み解く月の地形と地質
白尾元理著
誠文堂新光社 2025年2月15日発行,A4判,239ページ,
ISBN978-4-416-52409-1 定価4400円+税
本書は,著者所有の口径35cm反射望遠鏡で撮影した高解像度の月面写真を用いて,月面の表側(地球に面する側)を14地域に分け,地域ごとに数枚の写真を示して解説を加えた月面写真地図である.著者の前著「月の地形ウォッチングガイド」(誠文堂新光社,2009)では周辺部に漏れた部分があったが,本書では全面を漏れなくカバーしている.前著ではA5判の写真だったのが,本書では全て見開きA3判(面積で4倍)で,各々が1000枚程度の写真を処理して大気の揺らぎの影響を取り除くイメージスタッキング法による高解像度写真なので,迫力と分解能が違う.そして,前著と同様,地域別の写真・解説の前に,月齢順の月の全体写真がある(p.12-59,月齢3〜27).特定の海やクレーターに注目して月齢順に写真を見ていくと,太陽高度の変化による地形の見え方の移り変わりがわかる.著者によると,本書の喉(のど,紙を綴じた部分)は丈夫に作ってあり,ページを大きく開いて見ても大丈夫とのことである.
月齢順の写真の中に満月の写真が2枚あり,そのうち1枚がカラーで,色の違いを強調してある(p.36-37).このような月のカラー写真は初見で驚いた.例えば,アポロ11号が着陸した静かの海(ウサギの顔)は黒く(著者によれば青く),その北の晴れの海(ウサギの胸)は赤くて周辺部が黒い.その西の雨の海(ウサギの胴)は東部が赤くて西部が黒く(p.34,46,172でも明暗の差がわかる),黒い部分は溶岩流の地形が顕著である.嵐の大洋や雲の海・湿りの海など西半球の海は黒い部分が多く,黒い部分はチタンが多い玄武岩とのことである.武田弘(2009)「固体惑星物質進化」(現代図書)のp.87に米国のクレメンタイン探査機による月全球のチタン分布図(蛍光X線分析による)があり,この図の高チタン地域(TiO2=3〜10%程度)は確かにこの写真の黒い部分とよく一致する.実際,アポロ11号は静かの海から高チタン玄武岩を持ち帰り,その中からarmalcoliteFeTi2O5という新しいチタン鉱物が発見された(チタン鉄鉱ilmeniteFeTiO3よりTiが多い.名称は3人の飛行士に因む).その後のアポロは低チタン玄武岩を持ち帰ったが,最後の17号(晴れの海の南東縁)が再び高チタン玄武岩を採集した(ただし,極低チタン玄武岩もあった).
目次に沿って本書の構成を示すと,はじめに,インデックスMAP(各章冒頭にもある),月の地名の読み方,月を見るための機材(双眼鏡・望遠鏡),月齢別月面ガイド(上述),地域別月面ガイド(上述):1.コペルニクス周辺,2.雨の海,3.静かの海,4.晴れの海,5.神酒の海,6.南部高地,7.南東部高地,8.中央部,9.嵐の大洋,10.湿りの海,11.北部高地,12.東縁部,13.雲の海とその東部,14.西縁部,そして「さらに月を知りたい人のために」として,月の公転・自転と見え方の関係,月を撮影するための機材/画像処理方法,LRO(LunarReconnaissanceOrbiter,米国の月周回機)で月を見る,月探査機一覧表,写真データ(著者撮影写真各々の年月日時分,月齢,秤動等),参考文献/ウェブサイト,地名索引を載せる.なお,裏側も含むKAGUYA月面図を併用すれば表側周辺部の歪んだ地形の理解に役立つ(石渡,2016;https://geosociety.jp/faq/content0666.html参照).
本書には,米国のアポロ計画で飛行士が撮影した写真やLROの写真等も,解説の必要に応じ多数示されている.「かぐや」が発見した静かの海の直径100mの縦孔をLROが真上と斜め上から撮影した写真(p.97)は,孔の底に太陽光が当たり,角ばった岩塊が散在する様子や,孔壁に水平な溶岩層が露出する様子が写っている.著者はこの孔底に探査機を着陸させる日本のUZUME計画に期待を寄せている.
本書の地域別の各章には1つずつ充実したコラム記事がある.1.月のクレーター:火山説vs隕石説,2.月の時代区分,3.「かぐや」が発見した月の縦孔(上述),4.タウルス・リトロー谷:アポロ17号の着陸地,5.高地に着陸した唯一のアポロ16号,6.ティコに注目(チクシュルブと兄弟?),7.クレーター年代学とは,8.嵐の大洋はアメリカの無人・有人着陸地点,9.月にもあった大型火山(マリウス丘等),10.月の谷,11.クレーター年代学で若い年代を調べる,12.オニール橋の謎,13.月の表面を形作った衝突と火山活動,14.オリエンタレベイスン(東の海を中心とする多重衝突構造)発見記.そして,各章には詳しい地名解説があり,月齢別写真を含め,各写真の一隅に白文字で説明を記している.
なお,「11.北部高地」の最初の写真(p.168/169)は,虹の入り江に近い雨の海北部の嫦娥3号(中国)着陸地点を示すが,同写真内にある嫦娥5号着陸地点(石渡,2021;https://geosociety.jp/faq/content0995.html参照)は示していない.巻末の月探査機一覧表は昨年(2024)の嫦娥6号まで載せるが,4号と6号は裏側に着陸した.昨年1月に日本のSLIMは危機の海の西方,多重衝突構造内に着陸したが,これは「かぐや」がマントル起源のかんらん石を発見した場所を選んだという(p.107).
本書のカバーは月面写真が全面に印刷されているが,この写真の説明が見当たらない.表紙側にヒギヌス谷とアリアデヌス谷が写っており,上(西)は月面中心を含む上弦の月の欠け際,下(東)は静かの海の西端,右(北)は蒸気の海,左(南)はアルバテクニウスで限られ,デカルト高地のアポロ16号着陸地点を含む地域と思われる.唯一高地に着陸したアポロ16号の予想外の成果については,著者の2009年の前著第33章「中央部の高地:高地に火山活動はあったか?」(p.136-138)に詳しい.この話は本書第5章のコラムにもある.そして,本書第2章p.81はアポロ15号(ハドレー谷),第3章p.89,91,96はアポロ11号(静かの海),第4章のコラムはアポロ17号(晴れの海東部,タウルス・リトロー谷,ショーティ・クレーター),第8章のコラムはアポロ12号(知られた海)と14号(フラ・マウロ丘陵,知られた海東縁)の成果について述べている.
本書は月面全体を大画面で漏れなく示した写真地図として使いやすく,しかも写真の質が非常に高い.双眼鏡や小望遠鏡での月観察にはこの上ない案内書である.科学的な読み物としても優れており,自分で月の写真を撮影したい人には専門的なガイドとなっている.欲を言えば,地名索引だけでなく,事項索引もあればよかった.
満月時は月面の色の違いがわかりやすく,ティコ(1.9億年前,p.125)やコペルニクス(8.5億年前,p.65)から射出する光条(天体衝突の痕跡),月面中央付近の数ヵ所の黒色部(DMD,溶岩噴泉の噴出物,p.139,前著33,110),そして上述の海の溶岩の色の違い(チタン量の差)等,本書を読んで小望遠鏡での月面地質学を楽しもう.
(石渡 明)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[中部支部]
2025年支部年会
6月21日(土)-22日(日)
会場:静岡大学静岡キャンパス
巡検『瀬戸川帯南部の超塩基性-塩基性岩類の産状』6/22
https://geosociety.jp/outline/content0019.html#2025nenkai
[関東支部]
2025年度関東支部総会・講演会
4月12日(土)14:00-16:45
場所:北とぴあ第2研修室(東京都北区王子)
講演会「潜水船・水中ドローンによる島弧-海溝系の海底露頭観察」
講師:山口飛鳥氏(東京大学大気海洋研究所)
総会委任状(4/11最終締切)
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
共同研究グループ「フィールドワークとハラスメント(Harrassment in
Fieldwork, HiF)」の実施した「フィールドワークと性暴力・セクシュアル
ハラスメントに関する実態調査アンケート」(geo-flash No.543,545掲載)
の報告書<第一報>がWEB公開されました.
https://safefieldwork.live-on.net/survey/report1-jp/
—------------------------------------
石川町立歴史民俗資料館第54回企画展
「日本と世界の鉱物〜渡辺敢仁コレクション〜」
会期:3月20日(木)-6月8日(日)
https://www.town.ishikawa.fukushima.jp/admin/ishikawa/info/008645.html
(協)MicroArt2025(顕微鏡写真の写真コンペ企画)
エントリー締切:3月28日(金)
どなたでも応募可能です
http://micro-art.tokyo/
シンポジウム 海洋地質学の50年,そしてこれから
5月24日(土)13:30-17:00(ハイブリッドで配信予定)
場所:東京大学本郷キャンパス伊藤国際謝恩ホール
懇親会(徳山英一先生を偲ぶ会・定員250名):17:00-19:00
※懇親会参加申込・参加費振込締切:4/25 (金) 24:00
※シンポジウム参加無料.懇親会参加費10,000円
https://aori-u-tokyo.jimdosite.com/
JpGU 2025(ハイブリッド方式)
5月25日(日)-30日(金)
現地会場:幕張メッセ
https://www.jpgu.org/meeting_j2025/
産総研 地質調査総合センター第7回 鉱物肉眼鑑定研修
6月4日(水)〜 6月6日(金)
場所:茨城県つくば市(産総研)
定員:4〜5名(定員になり次第締切)
CPD:24単位
参加費:48口(1口1000円)の会費が必要です。
https://www.gsj.jp/geoschool/koubutsu/7th.html
(後)第62回アイソトープ・放射線研究発表会
7月2日(水)-4日(金)
会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/jrias2025
日本地質学会第132年学術大会(2025熊本大会)
9月14日(日)-16日(月)
会場:熊本大学黒髪地区
https://geosociety.jp/science/content0041.html
Magellan Plusワークショップ
「Land-to-Sea Shaking Studies (L2S3-WS) Unlocking the full
potential of subaqueous paleoseismology at active plate boundaries」
(海底・湖底堆積物を用いた地震履歴研究に関するワークショップ)
10月21日(火)-24日(金)
場所:国立台湾大学(台湾・台北市)
主催:L2S3-WS国際実行委員会
国内問い合わせ先:池原研(産総研)/中西諒(京都大学)
https://sites.google.com/view/land2sea-workshop/home
(協)Techno-Ocean 2025
11月27日(木)-29日(土)
会場:神戸国際展示場2号館ほか(神戸市中央区)
https://to2025.techno-ocean.com/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
https://geosociety.jp/outline/content0255.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・JAMSTEC海域地震火山部門 火山・地球内部研究C 地球物理観測研究G
主任研究員、副主任研究員or研究員公募(6/16)
・東大地震研令和7年度第2回 大型計算機共同利用公募研究の公募(5/30)
・令和7年度放射線安全管理功労・環境放射能功労表彰候補者の推薦依頼
(学会締切6/2)
・大阪公立大学理学研究科地球学科地球学専攻/地球進化学講座・地球史学分野助教
または講師(女性限定)(5/9)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】会員情報に変更があった場合は...
─────────────────────────────────
年度末に向け,所属先や自宅等の登録内容にご変更があった場合は,速やかに
情報の更新をお願い致します.情報の変更は,学会ホームページ「会員ページ」
にログインしていただければ,ご自身で登録内容が更新できます.
ご協力をよろしくお願いいたします.
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
旧石器人の琉球列島への航海(後編)
旧石器人の琉球列島への航海(後編)
※「旧石器人の琉球列島への航海(前編)」はこちらから
高山信紀(正会員)
※本文中の青字肩カッコ数字は,文末の文献を示しています.
※図表類をクリックすると大きな画像がご覧いただけます.
2. 旧石器人の航海と黒潮の影響
図-3 黒潮横断航海(概念図)
表-3 4万年前の琉球列島への黒潮横断航海
(1)舟
旧石器人が用いた舟は,草束舟,竹筏舟,丸木舟による実験航海19)の結果より丸木舟と考えられる.なお,フィリピンや台湾から漂流して琉球列島に生存してたどり着く可能性は極めて小さいことが漂流ブイの実験から示されている20).
(2)海上距離
琉球列島の島間の海上距離は海図と国土地理院ウエブサイト「地理院地図」の距離機能を併用し,台湾・与那国島間と大陸・魚釣島間などの海上距離はスケールで計測し,フィリピン・琉球列島間の海上距離は国土地理院ウエブサイト「測量計算(距離と方位角の計算)」を用いた.(表-2,表-3)
(3)航海の条件と限界
旧石器時代に丸木舟による航海を行うには舟の上あるいは島の高所から目指す島が見えることが必要で,見えない島は島があることが分からないので航海は行わなかったと考えた.航海は,舟の上から目指す島を見ながら舟がそこに向かって進むように漕ぎ,舟の上から目指す島が見えないときは出航した島や天体,風向などから目指す島の方向の見当をつけて漕いだと考えられる.
島が見えるかどうかは,文献21)と同様な方法で検討した.その結果を表-2,表-3の「L」と「可視」に示す.海水準が低下すると海面からの島の高さは高くなり遠くから見えるようになるが,4万年前の「古久米島」と「古宮古曽根島」の間は,お互いに島の最高点や出航した島が見える範囲内の海上の舟からでも相手の島は見えない.2万年前の「古沖縄・久米島」と「古西大九曽根島」の間は,お互いに島の最高点から相手の島は見えないが,出航した島が見える範囲内の海上で相手の島が見える所がある.
丸木舟を「漕いで進む速度」は,2019年に行われた台湾から与那国島への実験航海19)の結果から3.7km/hr(3.9km/hrと3.5km/hr21)の平均)とした.実験航海では2日目午後から休憩の頻度が目立ち,出航して45hr10min後(途中約8hrの睡眠休憩)に与那国島に到達している19).また,復元された古代ポリネシア式カヌーを10人の乗組員が櫂で漕いだ走行実験では,屈強なクルーが漕いでも2日間で体力が限界だった22).これらより,平均速度3.7km/hrで漕ぎ続けることができる限界時間は48hrとした.黒潮が流れていない海域での航海距離の限界は 177kmとなる.
(4)航海への黒潮の影響 旧石器人が琉球列島に向けて出航した所は,九州,大陸,台湾(大陸とつながっていた),フィリピンが考えられる.これらの所から琉球列島へ到達するには,全て黒潮を横断しなければならない.黒潮を横断する航海は,黒潮の流れを受ける舟が黒潮に流されることなく目指す島に進むように,出航した島と目指す島の線上に舟が居ることを確認しながら,目指す島より黒潮の上流側に舳先を向けて漕いだと考えられる.
図-3において黒潮区間外のAを出航し黒潮区間CDを横断して黒潮区間外の目的地Bに行くときの航海時間Tは,同図の式で求めることができる.なお,Aから目的地Bにまっすぐ進まず,図-3の点線のようにAからFに進み,Fから黒潮区間を黒潮の流れに沿ってGに進んで目的地Bに行くと,AからBに向かってまっすぐ進むときより航海時間Tが短くなる場合がある.しかし,旧石器人が初めて黒潮を横断して琉球列島の島へ航海したときに,このようなルートをとったとは思えない.
(5)4万年前の琉球列島への航海 4万年前の黒潮横断航海について,出航地と目的地,距離Y1〜Y3,黒潮の流向θを表-3のように推定し,目指す島が見えるかを検討した.また,「漕いで 進む速度」rが3.7km/hr,黒潮速度kが2〜4km/hrのときの航海時間Tを図-3の式で求め,Tが48hr以内となる黒潮速度kを検討した.トカラ海峡の黒潮横断は,海上距離が最も長い屋久島か ら口之島を対象とし,この区間の黒潮は現在と同様に東(θ=145°)と南東(θ=105°)の間を移動していたと考えた.
検討結果を表-3に示す.屋久島から口之島への航海は,逆潮であるが,屋久島から口之島が見え,航海時間Tが48hr以内の ときがあるので,航海が可能なときがあったと考えられる.大正島から「古久米島」や「古宮古島」,魚釣島から「古宮古島」への航海は,目指す島が見えないので航海は行わなかったと考 えられる.魚釣島から「古八重山島」への航海は可能なときがあったと考えられる.大陸やその周辺の島の海岸線は定かではないが,大陸と魚釣島の間は遠く島伝いでも見えずこの間の航 海は行わなかった可能性が高いと推測した.台湾(蘇澳)から与那国島ヘの航海は可能なときがある.なお,蘇澳周辺では,当時は海面からの高さ170m以上の所で与那国島が見えたので,この付近の旧石器人は海の向こうに島があることをよく知っていたと考えられる.フィリピン(イトバヤット島,図-1)から波照間島や与那国島への航海は,目指す島が見えないので航海は行わなかったと考えられ,たとえ航海したとしても航海時間Tが48hrを超えるので成功の可能性は低い.
4万年前の黒潮横断航海以外の航海は,島間の「海上距離」は全て177km以内であるが,「古久米島」と「古宮古曽根島」の間は互いに目指す島は見えない(前述2.(3))ので,航海は行わなかったと考えられる.これ以外の区間は目指す島が見えるので,航海は可能であったと考えられる.
(6)2万年前の琉球列島への航海 2万年前の黒潮横断航海は,4万年前と比べ海水準は更に低下したが目指す島が見えるかは変わらず,航海距離もあまり変わらないので,航海の可否は4 万年前と変わらない.2万年前の大陸や周辺の島の海岸線は4万年前に比べ魚釣島に近く,大陸から魚釣島への航海は行うことが出来た可能性が高いと推測した.
2万年前の黒潮横断航海以外の航海のうち「古沖縄・久米島」と「古西大九曽根島」の間は,出航した島が見える範囲内の海上で相手の島が見える所があり(前述2.(3)),釣漁(サキタリ洞遺跡では2万3千年前の釣針が発見されている1))などで沖合に出て偶然海の向こうに島を見つけてこの間を航海した可能性は否定できない.しかし,出航した島と相手の島の両方が海 上で見える所は限られており,また,約2万年前の港川フィッシャー遺跡(沖縄本島)と白保竿根田原洞穴遺跡(石垣島)の人骨のDNAは異なっており,この間を航海した可能性は低いと推測した.この区間以外の航海は,目指す島が見え,「海上距離」が177km以内なので可能であったと考えられる.
3. 旧石器人の琉球列島への移動経路
図-4 旧石器人の琉球列島への移動経路(概念図)
※2025/4/3訂正・差替
以上の検討結果をまとめると図-4のようになり,旧石器人が琉球列島へ移動した経路は以下のように推測される.
沖縄本島,伊江島,久米島(4万年前の「古沖縄島」と「古久米島」,2万年前の「古沖縄・久米島」)の旧石器人は九州から移動した可能性が高い.
宮古島(4万年前や2万年前の「古宮古島」)の旧石器人は「古八重山島」から移動した可能性が高い.
石垣島(同「古八重山島」)の旧石器人は台湾から与那国島を経由して移動した可能性が高いが,2万年前は大陸から魚釣島を経由して移動した可能性もある.
フィリピンから琉球列島へ移動した可能性は低い.
あとがき
上述のように,宮古島の旧石器人は「古八重山島」(現在の石垣島など)から移動したと推測したが,現在までに発見されている旧石器人骨の年代は宮古島の方が石垣島より古く,食い 違っている.また,本稿では航海を行う条件として目指す島が見えることをあげたが,島が見えなくとも鳥が飛んで来る方向に陸地があると信じて航海に出た23)と考えると移動経路の候補は多くなる.今後の旧石器人骨の発見,人骨の年代やDNA分析結果などに注目したい.黒潮横断航海で目的地にまっすぐ進むより航海時間が短くなるルートがあることや東シナ海の堆積など貴重なコメントを頂いた星野延夫氏に感謝します.
参考文献
(※前編の文献情報も掲載しています)
1)沖縄県立博物館・美術館「サキタリ洞遺跡の発掘」
2)東邦大学ウエブサイト「港川1号人骨のミトコンドリアDNA解析で過去から現在までの日本列島人の遺伝的関係性を解明」,2021年
3)篠田謙一『DNAで語る日本人起源論』p150〜p152,岩波現代全書073,岩波書店,2015年
4)横山祐典「ターミネーションの気候変動」,第四紀研究49(6),日本第四紀学会,2010年
5)横山祐典ら「見直される琉球列島の陸橋化」,科学Vol.88,No.6,岩波書店,2018年
6)海部陽介「黒潮と対峙した3万年前の人類―航海プロジェクトから」,科学Vol.88,No.6,岩波書店,2018年
7)小池一之・町田洋編『日本の海成段丘アトラス』及びCDROM「日本Ⅲ中国・四国・九州・南西諸島-海成段丘による垂直変動量のデータ一覧表」,東京大学出版会,2001年
8)CHENYen-Chiehetal.「Stream-powerincisionmodelinnon-steady-statemountainranges:Anempiricalapproach」Fig.2,ChineseScienceBulletin,Vol.51,No.22,2006年
9)山口勝・太田陽子「台湾海岸山脈東岸の完新世海成段丘と地殻変動」,地学雑誌111(3),東京地学協会,2002年
10)ChenDaietal.「APaleo-ChangjiangDeltaComplexontheEastChinaSeaShelfFormedSome30kaAgo(attheMIS3Stage)」,J.Mar.Sci.Eng,2023年
11)マリーンネットワークス㈱ウエブサイト「みんなの海図」
12)海上保安庁「1:1,500,000漁業用海図FW210長崎至厦門」,2007年
13)海上保安庁「1:2,500,000航海用海図W1676フィリピン諸島及近海」,2005年
14)JAMSTECウエブサイト「JAMSTECBASE-巨大海底火山鬼界カルデラの過去と現在」,2022年
15)海上保安庁「1:1,000,000海底地形図6720南西諸島」,2017年
16)気象庁ウエブサイト「海流に関する診断表,予報,データ:日別海流(沖縄周辺)」
17)久保田好美「最終氷期の黒潮の復元」,科学Vol.88,No.6,岩波書店,2018年
18)研究代表郭新宇「万年スケールでみた黒潮の流路変遷と黒潮分岐流の形成メカニズム」,科学研究費助成事業研究成果報告書,日本学術振興会,2021年
19)海部陽介『サピエンス日本上陸3万年前の大航海』,講談社,2020年
20)海部陽介ら「3万年前の琉球列島への移住は偶然ではなかった−旧石器人の漂流説を否定する新たな証拠−」,東京大学総合研究博物館ウエブサイト,2020年
21)高山信紀「琉球列島:縄文人が挑んだ遠い島と黒潮」,日本地質学会News,Vol.26,No.5,No.6,日本地質学会,2023年
22)後藤明『海を渡ったモンゴロイド』p9,講談社,2003年
23)篠遠喜彦・荒俣宏『楽園考古学―ポリネシアを掘る』p260〜p263,平凡社,2000年
24)菅浩伸「琉球列島のサンゴ礁形成過程」,『琉球列島先史・原史時代における環境と文化の変遷に関する実証的研究研究論文集第2集』,六一書房,2014年
※「まえがき」,「1.4万年前と2万年前の琉球列島」,は2月号ニュース誌に前編として掲載しています.またカラーの図表を学会HPに掲載しています.
【geo-Flash】 No. 651 2025年「地質の日」行事のご案内
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.650 2025/4/1┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2025年「地質の日」行事のご案内
【2】地質学雑誌 からのお知らせ
【3】支部のお知らせ
【4】その他のお知らせ
【5】公募情報・各賞助成情報等
【6】会員情報に変更があった場合は...
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2025年「地質の日」行事のご案内
──────────────────────────────────
2025年の「地質の日」に関連した日本地質学会主催,共催,後援等の催しを
ご紹介します。
惑星地球フォトコンテスト第16回ほか入選作品展示会/オンライン一般講演会
「ナウマン来日150年.その功績と足跡を辿る」/街中ジオ散歩
in Chiba/地球科学講演会 などなど
このほかにも随時情報を更新します.https://geosociety.jp/name/content0181.html
このほか,地質学会以外の全国の地質の日イベント情報はこちら
https://www.gsj.jp/geologyday/2025/index.html(地質の日事業推進委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】地質学雑誌 からのお知らせ
──────────────────────────────────
■地質学雑誌:新しい論文が公開されています.
(ノート)Pythonを使ってSBPを表示しよう;白鳳丸Bathy2010:高下裕章ほか/(論説)徳島平野南東部沿岸地域における地下更新統年代層序:羽田裕貴ほか/
(報告)岐阜県高根地域に分布する美濃帯沢渡コンプレックスから得られた砕屑性ジルコンU–Pb年代:箱岩寛ほか/(報告)鳥取県北東部,羽尾鼻に分布する下部
鮮新統大羽尾溶岩:羽地俊樹ほか
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/-char/ja
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[中部支部]
2025年支部年会
6月21日(土)-22日(日)
会場:静岡大学静岡キャンパス
巡検『瀬戸川帯南部の超塩基性-塩基性岩類の産状』6/22
https://geosociety.jp/outline/content0019.html#2025nenkai
[関東支部]
2025年度関東支部総会・講演会
4月12日(土)14:00-16:45
場所:北とぴあ第2研修室(東京都北区王子)
講演会「潜水船・水中ドローンによる島弧-海溝系の海底露頭観察」
講師:山口飛鳥氏(東京大学大気海洋研究所)
総会委任状(4/11最終締切)
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)神奈川県立生命の星・地球博物館 企画展
「すなーふしぎをみつけようー」
会期:2月22日(土)-5月11日(日)
https://nh.kanagawa-museum.jp/www/contents/1729149555111/index.html
—------------------------------------
産総研 地質標本館 講演会「IUGSヘリテージストーンと筑波山塊の花崗岩」
4月19日(土)14:00-15:00
講演者:杉原 薫 氏(筑波山地域ジオパーク推進協議会)
開催場所:産業技術総合研究所 地質標本館
定員:40名(事前予約必要)
https://www.gsj.jp/Muse/event/archives/20250419_event.html
「堆積構造の世界」連続講義
第5回 火山砕屑物の堆積構造
5月9日17:00から2時間程度
コーディネーター:片岡香子 氏
講師:片岡香子 氏,前野 深 氏
https://sites.google.com/view/taisekigakukougi?usp=sharing
第34回 地質汚染調査浄化技術研修会(座学zoomオンライン研修会)
5月16日(金)9:30-17:30(終了予定)
5月23日(金)9:55-17:30(終了予定)
参加費無料
参加申込期限:5月14日15時まで
ただし,テキスト(資料集3,000円)をご希望の方は5月9日までにお申し込み・お振込み下さい.
https://www.npo-geopol.or.jp/
JpGU 2025(ハイブリッド方式)
5月25日(日)-30日(金)
現地会場:幕張メッセ
https://www.jpgu.org/meeting_j2025/
(後)第62回アイソトープ・放射線研究発表会
7月2日(水)-4日(金)
会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/jrias2025
日本地質学会第132年学術大会(2025熊本大会)
9月14日(日)-16日(月)
会場:熊本大学黒髪地区
https://geosociety.jp/science/content0041.html
(協)Techno-Ocean 2025
11月27日(木)-29日(土)
会場:神戸国際展示場2号館ほか(神戸市中央区)
https://to2025.techno-ocean.com/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
https://geosociety.jp/outline/content0255.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・兵庫県立大学 理学研究科 (地球科学)助教1名公募(4/30)
・山梨県防災危機管理課 山梨県火山防災職募集(5/31)※4/15説明会開催
・2026-2027開催藤原セミナー募集(7/31)
・下仁田ジオパーク学術奨励金(4/25)
・令和7年度 南紀熊野ジオパーク学術研究・調査活動助成事業(5/16)
・下北ジオパーク研究補助金(4/11)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】会員情報に変更があった場合は...
─────────────────────────────────
年度末に向け,所属先や自宅等の登録内容にご変更があった場合は,速やかに
情報の更新をお願い致します.情報の変更は,学会ホームページ「会員ページ」
にログインしていただければ,ご自身で登録内容が更新できます.
ご協力をよろしくお願いいたします.
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 652 第16回惑星地球フォトコンテスト審査結果
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.652 2025/4/15┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】第16回惑星地球フォトコンテスト 審査結果
【2】2025年「地質の日」行事のご案内
【3】Island Arc からのお知らせ
【4】第5回JABEEシンポジウム:YouTube公開中
【5】支部のお知らせ
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
【8】会員情報に変更があった場合は...
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】第16回惑星地球フォトコンテスト審査結果
──────────────────────────────────
今年の応募総数は432点,昨年の2倍以上の応募数となり,レベルの高い
コンテストとなり,最優秀賞をはじめ計12点の入選,10点の佳作が選出
されました.
入選作品の画像,講評等はこちらから
https://geosociety.jp/faq/content0009.html
*入選作品展示会も開催します!ぜひお越しください.
5月13日(火) 午後〜 25日(日)14時まで
場所:東京パークスギャラリー(台東区上野公園)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2025年「地質の日」行事のご案内
──────────────────────────────────
2025年の「地質の日」に関連した日本地質学会主催,共催,後援等の催しを
ご紹介します。
惑星地球フォトコンテスト第16回ほか入選作品展示会/オンライン一般講演会
「ナウマン来日150年.その功績と足跡を辿る」/街中ジオ散歩
in Chiba/地球科学講演会 などなど
このほかにも随時情報を更新します.
https://geosociety.jp/name/content0181.html
<オンライン講演会のパブリック・ビューイングを開催しませんか?>
オンライン講演会「ナウマン来日150年 その功績と足跡を辿る」は,
YouTubeライブで一般に公開します。博物館やジオパークなどでぜひパブリック・
ビューイングを開催してください。申請は不要です。開催後、開催した旨を事務局
にご報告ください。たくさんの方にご覧いただけるよう,ご協力をお願いいたしま
す。
このほか,地質学会以外の全国の地質の日イベント情報はこちら
https://www.gsj.jp/geologyday/2025/index.html(地質の日事業推進委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
■新しい論文が公開されています.
(RESEARCH ARTICLE)Outcrop‐Scale, Ring Structures Discovered
in Northwestern Kyushu, Japan:Atsushi Yamaji/(RESEARCH ARTICLE)
Weathering Effects on Luminescence Dating?An Example of the Toya
Tephra in Japan?:Yoshihiro Ganzawaet al
学会の会員ページからログインすると全文が無料閲覧できます .
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】第5回JABEEシンポジウム:YouTube公開中
──────────────────────────────────
第5回JABEEシンポジウム
『高等学校での地学教育と大学での専門教育との連携
〜地球科学の中等教育から高等教育にどのように繋げるか〜』
共催:地学教育委員会
3月2日に標記のシンポジウムを開催しました.
シンポジウムの内容(動画)は,YouTubeで公開中です.
ご参加いただけなかった皆様もぜひご覧ください.
https://www.youtube.com/watch?v=nAd_VOreVTg
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[関東支部]
学生・若手会員向け「地質調査の基礎講座」-城ヶ島巡検-
5月31日(土)10:00-16:30 集合場所:白秋碑前バス停
神奈川県三浦市城ヶ島で野外観察・調査
6月1日(日)10:00-15:00
集合場所:横須賀市産業交流プラザ第一会議室
露頭柱状図作成など(室内作業)
https://geosociety.jp/outline/content0201.html#2025jogashima
[中部支部]
2025年支部年会
6月21日(土)-22日(日)
会場:静岡大学静岡キャンパス
巡検『瀬戸川帯南部の超塩基性-塩基性岩類の産状』6/22
https://geosociety.jp/outline/content0019.html#2025nenkai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
動画コンテンツ「10万年以上にわたる地層処分場の安全性」公開(NUMO)
10万年以上にわたる地層処分場の安全性に関して、これまでの研究で得られた
知見などを用いて、どのように評価しているのかを分かりやすく説明する動画
を制作し、公開しました.
プレスリリース:https://www.numo.or.jp/press/202525040214.html
トータル版(YouTube):https://youtu.be/cLKi3HzQ3nE
(一社)国土デジタル情報研究所 地質地盤情報の活用と法整備を考える会
ホームページを更新しました.
広報冊子・活動趣旨のパンフレット/2024年度(令和6年度)活動実績
https://www.geo-houseibi.jp
(後)神奈川県立生命の星・地球博物館 企画展
「すなーふしぎをみつけようー」
会期:2月22日(土)-5月11日(日)
https://nh.kanagawa-museum.jp/www/contents/1729149555111/index.html
------------------------------------
JpGU 2025(ハイブリッド方式)
5月25日(日)-30日(金)
現地会場:幕張メッセ
https://www.jpgu.org/meeting_j2025/
(後)第62回アイソトープ・放射線研究発表会
7月2日(水)-4日(金)
会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/jrias2025
日本地質学会第132年学術大会(2025熊本大会)
9月14日(日)-16日(月)
会場:熊本大学黒髪地区
https://geosociety.jp/science/content0041.html
(協)Techno-Ocean 2025
11月27日(木)-29日(土)
会場:神戸国際展示場2号館ほか(神戸市中央区)
https://to2025.techno-ocean.com/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
https://geosociety.jp/outline/content0255.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・2025年度「深田賞」募集(6/30)
・第58回伊藤科学振興会研究助成公募 (化学分野・地球科学分野)(6/25)
・住友財団 2025年度基礎科学研究助・環境研究助成(6/30)
・山陰海岸ジオパーク 学術研究奨励事業(5/12)
・令和7年度白山手取川ジオパーク学術研究助成金事業(5/9)
・令和7年度栗駒山麓ジオパーク学術研究等奨励事業(5/9)
・令和7年度 隠岐ユネスコ世界ジオパーク学術奨励事業(5/7)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】会員情報に変更があった場合は...
─────────────────────────────────
新年度をむかえ,所属先や自宅等の登録内容にご変更があった場合は,速やかに
情報の更新をお願い致します.情報の変更は,学会ホームページ「会員ページ」
にログインしていただければ,ご自身で登録内容が更新できます.
ご協力をよろしくお願いいたします.
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 653 2025年度代議員総会開催について
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.653 2025/5/7┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2025年度代議員総会開催について
【2】2025年「地質の日」行事のご案内
【3】2025年度(第3回)日本地質学会研究奨励金採択結果
【4】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【5】意見・提言2025
【6】支部のお知らせ
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】会員情報に変更があった場合は...
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2025年度代議員総会開催について
──────────────────────────────────
日時:2025年6月7日(土)14:00-15:30
※WEB会議形式で開催いたします.
※正会員は,総会に陪席することができます.ただし,総会規則12条3項により,
許可のない発言はできません.
※本総会は役員ならびに代議員による総会となります. 代議員には,総会開催
通知とともに総会に必要な資料等を別途お送りいたします.
議事次第はこちら
http://www.geosociety.jp/outline/content0152.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2025年「地質の日」行事のご案内
──────────────────────────────────
2025年の「地質の日」に関連した日本地質学会主催,共催,後援等の催しを
ご紹介します。
■ 惑星地球フォトコンテスト第16回ほか入選作品展示会
5月13日(火) 午後〜 5月25日(日)14時まで
場所:東京パークスギャラリー(上野グリンサロン内)(台東区上野公園 JR上野駅 公園改札出てすぐ)入場無料
■ オンライン一般講演会「ナウマン来日150年.その功績と足跡を辿る」
5月10日(土)13:30~16:00 YouTube Liveによるライブ配信
このほかにも,
街中ジオ散歩 in Chiba/地球科学講演会「関西で考えるべき活断層地震の揺れ」
/化石発掘 体験〜君も今日から化石博士!!〜 などなど盛りだくさん!
このほかにも随時情報を更新します.https://geosociety.jp/name/content0181.html
<オンライン講演会のパブリック・ビューイングを開催しませんか?>
オンライン講演会「ナウマン来日150年 その功績と足跡を辿る」は,
YouTubeライブで一般に公開します。博物館やジオパークなどでぜひパブリック・
ビューイングを開催してください。申請は不要です。開催後、開催した旨を事務局
にご報告ください。たくさんの方にご覧いただけるよう,ご協力をお願いいたしま
す。
このほか,地質学会以外の全国の地質の日イベント情報はこちら
https://www.gsj.jp/geologyday/2025/index.html(地質の日事業推進委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2025年度(第3回)日本地質学会研究奨励金採択結果
──────────────────────────────────
4/19理事会にて4名の方が採択されました.
詳しくはこちら,https://geosociety.jp/outline/content0251.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
【地質学雑誌】
■ 新しい論文が公開されています.
(論説)台地を刻む谷底低地の沖積層の形成プロセスと地盤特性:埼玉県芝川低地の例:小松原純子ほか/(論説)砕屑性ジルコンのU–Pb年代測定による下部−中部中新統田辺層群の堆積年代の制約と応力場への示唆:安邊啓明ほか/(報告)
Tenthredinid sawfly (Hymenoptera, Symphyta) fossils from the Chibanian (Middle Pleistocene) Shiobara Group, Tochigi Prefecture, Japan. Yui Takahashiほか/
(論説)Revision of the age of the “Upper Miocene” Mitoku Formation in Misasa
Town, south-central Tottori Prefecture, western Japan.Atsushi Yabeほか
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/-char/ja
【Island Arc】
■ 新しい論文が公開されています.
(RESEARCH ARTICLE)Metamorphic History of the Yoshimi Metamorphic
Rocks, Kanto Mountains, Japan: Implication From Rutile Exsolution Textures.
Tatsuro Adachi et al/The Late Silurian Langmuri Cu‐Ni Deposit in East
Kunlun Orogenic Belt: An Example of Magmatic Sulfide Deposit in a
Post‐Collisional Extensional Setting. Namkha Norbu et al
学会の会員ページからログインすると全文が無料閲覧できます .
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】意見・提言2025
──────────────────────────────────
独立行政法人大学入試センターへ,令和7年度大学入試共通テストの地学関連
科目に関する意見書を提出しました.
https://geosociety.jp/engineer/content0078.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[関東支部]
学生・若手会員向け「地質調査の基礎講座」 ー城ヶ島巡検ー
5月31日(土)10:00-16:30 集合場所:白秋碑前バス停
神奈川県三浦市城ヶ島で野外観察・調査
6月1日(日)10:00-15:00
集合場所:横須賀市産業交流プラザ第一会議室
露頭柱状図作成など(室内作業)
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0201.html#2025jogashima
[中部支部]
2025年支部年会
6月21日(土)-22日(日)
会場:静岡大学静岡キャンパス
巡検『瀬戸川帯南部の超塩基性-塩基性岩類の産状』6/22
https://geosociety.jp/outline/content0019.html#2025nenkai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)神奈川県立生命の星・地球博物館 企画展
「すなーふしぎをみつけようー」
会期:2月22日(土)-5月11日(日)
https://nh.kanagawa-museum.jp/www/contents/1729149555111/index.html
電中研メールマガジンより,電気新聞ゼミナール寄稿文
「EUは気候変動対策に関する規制緩和をどこまで進めるのか?」
https://criepi.denken.or.jp/press/journal/denkizemi/2025/250423.html
防災学術連携体シンポジウム
「防災庁への期待」災害応急対応力をどう強化するか
4/30に開催されたシンポの内容をYoutubeで公開しています.
https://youtu.be/NTVrOaCwA0w
—------------------------------------
2025 エネ環地研成果発表会(オンライン同時配信)
5月22日(木)-23日(金)【開場 9:30】
会場:北海道立道民活動センター かでる2・7(札幌市中央区北2条西7丁目)
参加無料,要事前申込(5/20締切)
https://www.hro.or.jp/industrial/research/eeg/pr/2025seika.html
学術会議公開シンポジウム
地名標準化の現状と課題―UNGEGNの活動を理解し日本の地名を考える―
後援:地理学連携機構
5月24日(土)13:00-17:00(オンライン開催)
定員300人,どなたでも参加いただけます
参加無料・要事前申込(5月23日締切)
https://www.scj.go.jp/ja/event/2025/382-s-0524.html
JpGU 2025(ハイブリッド方式)
5月25日(日)-30日(金)
現地会場:幕張メッセ
https://www.jpgu.org/meeting_j2025/
地質学史懇話会例会
6月8日(日)13:30-17:00
場所:北とぴあ 803号(東京北区王子)
加藤茂生:東京地学協会による中国の地学調査の淵源と展開
会田信行:『最新地学事典』の中の地球科学史
深海底の保護と持続可能な開発に向けた国際海底機構先進技術ワークショップ
第2回「海底モニタリング」
主催:国際海底機構(ISA)
6月10日(火)-12日(金)
会場:オンライン+オンサイト(神戸大学百年記念館)
https://www.isa.org.jm/events/2nd-expert-scoping-workshop-charting-future-horizons-harnessing-advanced-technologies-for-the-protection-and-sustainable-use-of-the-international-seabed-area/
第34回地質汚染調査浄化技術研修会
(現地実習① ボーリングコア記載実習)
6月14日(土)10:00-17:00(終了予定)
参加費:当NPO会員10,000円 当NPO非会員15,000円
参加申込期限:6月10日※ただし定員になり次第締め切り
募集定員30名
https://www.npo-geopol.or.jp/
(後)第62回アイソトープ・放射線研究発表会
7月2日(水)-4日(金)
会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
参加登録(前期)4/14(月)〜6/13(金)12時 7,000円
参加登録(後期)6/23(月)〜7/4(金) 9,000円
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/jrias2025
日本地質学会第132年学術大会(2025熊本大会)
9月14日(日)-16日(月)
会場:熊本大学黒髪地区
https://geosociety.jp/science/content0041.html
(共)19th International Conference on Thermochronology
(第19回国際熱年代学会議/Thermo 2025)
9月14日(日)-20日(土)
会場:金沢商工会議所(金沢市尾山町9-13)
講演要旨締切:4月30日(水)
https://smartconf.jp/content/thermo2025/
(協)Techno-Ocean 2025
11月27日(木)-29日(土)
会場:神戸国際展示場2号館ほか(神戸市中央区)
https://to2025.techno-ocean.com/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
https://geosociety.jp/outline/content0255.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・Sony Women in Technology Award with Nature候補者募集(5/30)
・【再公募】島根大学学術研究院環境システム科学系(自然災害科学)教員公募 (9/30)
・変動海洋エコシステム高等研究所(WPI-AIMEC)研究員orPD公募(6/15)
・東京大学地震研究所2026年度国際室外国人客員教員推薦公募(6/3)
・長崎大学教育学部理科教育分野教育職員公募 (6/30)
・東京科学大学理学院地球惑星科学系助教(2名)公募 (6/6)
・第20回筑波大学朝永振一郎記念「科学の芽」賞募集(8/18-9/13)
・令和7年度おおいた姫島ジオパーク調査研究活動助成募集(6/1)
・令和7年度おおいた豊後大野ジオパーク学術研究・調査活動助成事業(5/30)
・土佐清水ジオパーク活動支援事業募集(5/31)
・令和7年度むつ市ジオパーク推進員募集(随時募集)
・伊豆大島ジオパーク学術研究奨励事業補助金(5/30)
・令和7年度糸魚川ジオパーク学術研究奨励事業(5/30)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】会員情報に変更があった場合は...
─────────────────────────────────
新年度をむかえ,所属先や自宅等の登録内容にご変更があった場合は,速やかに
情報の更新をお願い致します.情報の変更は,学会ホームページ「会員ページ」
にログインしていただければ,ご自身で登録内容が更新できます.
ご協力をよろしくお願いいたします.
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
中教審の答申「知の総和」とレイトスペシャライゼーションへの対応策
中教審の答申「知の総和」とレイトスペシャライゼーションへの対応策
坂口有人(山口大学)
今回の答申・問題提起
中央教育審議会から「我が国の「知の総和」向上の未来像 〜高等教育システムの再構築〜 (答申)」が2月21日に公表された(以下,今回の答申と呼ぶ).今回の答申の特徴は,学生一人一人の能力を高める質の向上,18歳人口減に伴う大学規模適正化,高等教育へのアクセス確保などがあり,それらを実現する手段として文理融合のレイトスペシャライゼーション(以降LSと呼ぶ)が強調されている.本稿はこのLSを中心に論じる.
これまでの大学教育では,学部の卒業要件の約120単位のうち,約40単位分を教養教育に,約80単位分を専門教育に充てるという専門教育主体の教育であった.これに対してLSは学部教育のほとんどを教養教育に充て,専門教育は大学院で行うというものである.すなわち学部の専門教育の大幅削減を意味する.
2040年には大学入学者が現状よりも3割近く減少すると見込まれている(文部科学省,2025).おそらく各大学の交付金・助成金もこれに合わせて大幅にカットされ,それぞれの大学内において選択と集中が進むと予想される.その際に文系と理系を統合した大規模な学部がつくられ,4年間を幅広い教養教育だけが行われれば,各分野の教員は少数で事足りるため,かなりの人員削減を進める事が可能になる.このプロセスにおいて学内で地質学の必要性が十分に理解されていなければ地質系学科・コースの消滅が危惧される.
ここに至る経緯
1990年代以降の大学改革において,大学には「社会ニーズを踏まえた高等教育」「第三者評価による質の保証」「国際通用性」が求められ続けてきた.そして従来の専門教育に対して批判が繰り返されてきたが,基本的には専門教育の立て直しが主題であった.しかし,ここ10年ほどの間に文理融合のLSという考えが前面に出てくるようになった.
ここ最近の動きとしては,AIの急速な発展が見込まれて,多くの仕事がなくなるという推定や(Frey and Osborne, 2013),子供たちの65%が今はまだ存在しない新しい仕事に就くという議論が提起された(Davidson, 2011).「Society5.0 時代に向けた人材育成大臣懇談会」(文部科学省,2018)では,機械が人の仕事を代替して互いに複雑かつ高度に関係し合う社会において,サイエンスや数学,そして分析的に思考する力と全体をシステムとしてデザインする力が必要とされた.そしてAIにできない力として,現実世界を意味あるものと理解して新たなものを生み出していく力とされ,そのためには従来の専門教育ではなく,文理分断からの脱却が謳われた.しかし,その後,AIが仕事を奪うという議論に対して,AIはあらゆる職種に入り込むが職種を消失させないという反論が出された(Arntz et al., 2016).また,子供たちは未だない仕事に就くと提起したDavidson教授自身が「全ての仕事が変化した」と表現を変えるなど(BBC, 2017)トーンダウンしていった.
これに代わって,第5期科学技術基本計画(内閣府,2016)では,Society 5.0というビジョンが打ち出された.これはAIの発達に伴う社会の大変革が起こりうることを前提としている.そのような社会では,高度な専門知識を持ちつつ普遍的な見方のできる能力が求められ,専攻分野の専門性だけではなく,思考力,判断力,俯瞰力,表現力,教養を身に付け,高い公共性・倫理性,論理的思考力を持つ必要があると議論された(文部科学省,2018).そのためには既存の専門教育ではなく,文理横断型の教育に移行するべきだと論じられるようになった(文部科学省,2018).
2020年に科学技術基本法が改正された.この法律にはかつて「科学技術(人文科学のみに係るものを除く)」との一文があった.しかし,人間や社会の在り方と科学技術・イノベーションとの関係が密接不可分になっていることを鑑み,人文科学を排除するという一文が削除された.この改正の過程では,専門家主義がたこツボを作り,それが社会に災厄をもたらしかねない,たこツボの間を動き回り通訳する人間が10%程度必要,という議論も含みつつ,あらゆる分野の知見を総合的に活用して社会課題に対応していくという方針が示された(制度課題ワーキンググループ,2020).法律改正を受けて内閣府から「「総合知」の基本的考え方及び戦略的に推進する方策 中間とりまとめ」が公表された(内閣府,2022).ここでは,人文・社会科学と自然科学を含むあらゆる「知」の融合による「総合知」により,⼈間や社会の総合的理解と課題解決を目指している.ただし,専門知を疎かにするものではない,とも明記されている.そして2025年の今回の答申に至るが,そこでも,専門知そのものの深掘り・広がりとともに,専門知を持ち寄って知の活力を生み出すとされており,専門知そのものは否定されていない.しかし専門知の深さと併せて,俯瞰的・横断的な視野を持つために文理融合のLS導入が必要と結論づけられており,学部における専門教育の重要性は顧みられていない.
この10年の間に,AIにできない人間の役割のためであったり,将来が見通せないからであったり,もしくは細分化した学問分野を俯瞰するためであったりと,理由はいろいろと変化してきたが,従来の専門教育には問題があり,学部では文理融合教育を導入すべきという結論は同じであった.
専門教育批判の背景
専門知は重要としながらもLSを推進して学部での専門科目の単位を減らすというのは,一見矛盾しているようにも見えるが,これは従来の専門教育に対する批判であり,大学教育そのものに対する不信感が背景にあるのかもしれない.
今から60年も前から既に「学生が勉強しないし大学もさせない」といった議論が国会でなされ(衆議院文教委員会,1966),「大学とは何か」(文部科学省,1998)といった根源的な問いかけや,「日本の学士がいかなる能力を証明するものであるのか」(文部科学省,2008)といった痛烈な批判が繰り替えされてきた.そして大学教員に対しても,社会のニーズを顧みずに「個々の教員が教えたい内容を教えている」(文部科学省,2018)という不信感が表明されてきた.これらに対して大学側は,シラバスや3ポリシーの整備,情報公開などに取り組んできたが,まだまだ不信感の払拭には至っていない.
今回の答申の弱点
その一方で今回の答申は,1990年代以降の大学改革における「社会ニーズを踏まえた高等教育」「第三者評価による質の保証」「国際通用性」という,長年の課題に対して踏み込みが甘いと感じる部分がある.
これまでは,各分野において社会ニーズを汲み取った卒業生像を描き,そして卒業時までに身に付ける知識や技能・資質,そしてその定量的な水準を詳細かつ具体的に示したディプロマ・ポリシーを定め,それを実現するためのカリキュラムを組み立てるように求められてきた(文部科学省,2016).例えば目指すべき卒業生像を地質技術者とすれば,岩石学,鉱物学,堆積学,地史学,構造地質学といった基礎知識,野外での地質調査能力,研究成果をまとめる能力といった技能などを,身に付けるべきものとして挙げることができる.
これに対して今回の答申では,専門知を組み合わせた総合知を社会ニーズと定めているため,主体性,リーダーシップ,創造力,課題設定・解決能力,論理的思考力,表現力,集中力,粘り強さ,コミュニケーション能力,人間力などを身に付けるべきとしている(文部科学省,2025).そして,これを実現するために文理融合教育のLSが重要と説いている(文部科学省,2025).今回の答申におけるこれらの社会ニーズ,到達目標,そして身に付けるべき知識・技能・資質は,いずれも抽象的で漠然としていると言わざるを得ない.そしてまた,達成すべき水準についても,今回の答申では在学中にどれくらい力を伸ばすことができたのか,といった定性評価の導入が議論されている.これも従来の議論から大きく後退している.やはり定量評価できる基準を定め,それに適合しているかどうかによって個々の授業の単位が厳格に認定され,そして規定のカリキュラムを履修することで,目指すべき卒業生像に至ると考えられる.これは特に国家資格と連動している教育プログラムには重要なポイントであるし,また卒業生を受け入れる社会にとっても,その学科・コースの学士がいかなる能力を証明するものであるのかを示す重要な指針になるであろう.
今回の答申では専門教育は大学院が担い,質の高い博士人材により高度専門人材が賄われることになっているので(文部科学省,2025),学部の到達目標や水準は抽象的でも良いというロジックかもしれない.しかし,高度専門人材を博士だけで担うのは容易ではない.日本地質学会の調査では,全国の大学から毎年約200名の卒業生・修了生が地質技術職に就いている(佐々木,2025).それでも業界では人手不足との声が根強いので,地質技術職に対する社会ニーズはこれよりも多いのであろう.それに対して博士の修了者は年間に40名程度にすぎず,その半数以上が研究職に就いている(佐々木,2025).地質技術者の需要だけでも現状の5倍以上の博士が必要になり,とても現実的ではない.やはり学部から専門教育を行い,多くの卒・修了生が専門職に就くようにしなければ社会ニーズに応える事はできない.
大学教育に対する第三者評価も大学改革の長年のテーマである.現状では,第三者評価として大学全体を対象とした機関別認証評価が行われ,学部や学科,コース等の授業内容や単位認定基準などの詳細は自己点検でカバーする内部質保証が行われている.この内部質保証ですら今回の答申は負担が重いと捉えている.そもそもこの内部質保証は,かなり不十分なやり方である.その現状を学術論文の査読制度に例えると,出版社の健全性は確認するが,そこの雑誌に掲載される論文のひとつひとつは査読しない,という状態である.やはり論文のひとつひとつについて査読は行われるべきであり,そのことによって論文の質と信頼性が向上する.同様に,大学教育の質保証として,教育主体である学科やコースを対象とした詳細な第三者ピアレビューを積極的に受け入れるべきである.そういった大学教育の審査機関として,医学分野では日本医学教育評価機構(JACME),看護学分野では日本看護学教育評価機構(JABNE),理工農情報分野では日本技術者教育認定機構(JABEE)などが整備されており,これらへの受審率を向上させていくことが筋であろう.
国際通用性は今回の答申でも重要と強調され,国際的な大学間連携やデジタル学習履歴証明が対応策として挙げられている.しかし,特定の大学間のみでしか通用しない状態や,卒業生が学修履歴でもって自らの能力・資質・水準を説明しなければならない状態というのは,大学の国際通用性として十分とは言えない.大学教育においても国際認証制度が運用されている分野があり,そういった分野では学科・コース単位で国際認証を受けることで国際通用性が確保されている.地質学分野では幸いなことにJABEEがワシントンアコードの協定加盟団体であるため,JABEEの認定を受けている学科・コース等の教育は国際的同質性が保証されている.これは留学生の大学選びや,卒業生が海外での業務に携わる場合にも重要であるが,その学科・コースの学士がいかなる能力を証明するものであるのか,という大学の価値そのものを国際的に証明するものでもあり,大学の国際認証はきわめて重要である.
対応案
文理融合のLSが本格的に導入されると専門教育および地質系の学科・コース等が大幅に削減される可能性があり,何らかの手立てが必要になる.ひとつの案として,大学改革の長年の課題である「社会ニーズを踏まえた高等教育」「第三者評価による質の保証」「国際通用性」に正面から取り組み,今回の答申の更に先を行く教育像を示すのも生き残り戦略としてあり得るのではないだろうか.
大学において基礎研究や真理探究を行うという事と,社会と向き合うというという事は何ら矛盾するものではない.むしろ地質関連の業界から「学部段階から,地史学,堆積学,岩石学,鉱物学,古生物学,構造地質学,地質調査法,野外巡検などをしっかり教えてください」と要望してもらえればありがたい.今回の答申では特に地域社会ニーズが強調されているので,たとえば各都道府県の地質調査業協会などに協力を依頼する方法もあるだろう.また,学内での選択と集中においても,顔が見えるレベルの地元業界から専門教育の継続を要望してもらえれば力強い援護になるだろう.
そして今回の答申が提言している定性的な評価に取って代わる質保証に積極的に取り組む事も重要であろう.論文の査読制度が研究の質保証の重要な一翼であるのと同様に,教育にも学科・コース単位での第三者ピアレビューを受け入れて,授業一つ一つのレベルにまで外部の目が入り得るようにすべきである.地質学分野にはJABEEがあるので,この審査を受けるのが良いだろう.JABEEは大学の質保証に既に25年以上も取り組んでおり,ピアレビューによる大学教育向上のノウハウを十分に有している.また,JABEEから認定されれば,同時に国際認証を得る事になる.国際認証は今回の答申を上回る明確な国際通用性となる.
まとめ
18歳人口の減少に連動して交付金や助成金が大幅にカットされる可能性がある.そうなれば各大学の学内での選択と集中が進むだろう.その際に文理融合のLSは定員削減のツールになる危険性がある.専門教育を守るために,今回の答申よりも先進的な高等教育像を示すという手もあるだろう.例えば,地質業界から専門教育に対する要望を受け,社会ニーズを踏まえた具体的な到達目標を掲げ,それを具現化する教育を行い,第三者ピアレビューでその質を保証し,国際認証を取得して国際通用性を確立し,多くの卒業生たちを専門職種に送り出すというアプローチもあるだろう.
これが唯一解ではないだろうが,いずれにしても全国の多くの地質系の学科・コースが今後も維持発展されていくことを願っている.大学自らが,より積極的に教育の質保証を図り,国民から信頼されるように努力することが,学問の自由を守るために重要なのではないだろうか.
引用文献
Arntz, M., Gregory, T., Zierahn, U., 2016, The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, 189, https://dx.doi.org/10.1787/5jlz9h56dvq7-en
BBC, 2017, 65% of Future Jobs Haven't Been Invented Yet? Cathy Davidson Responds to Cathy Davidson and BBC, More or Less, https://www.bbc.co.uk/programmes/p053ln9f
Heffernan, Virginia, 2011, Education Needs a Digital-Age Upgrade, The Opinion page, The New York Times, https://archive.nytimes.com/opinionator.blogs.nytimes.com/2011/08/07/education-needs-a-digital-age-upgrade/
Frey, C. Benedikt and Osborne, A. Michael, 2013, The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation? Oxford: The Oxford Martin School. https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/the-future-of-employment
文部科学省,2008,中央教育審議会,学士課程教育の構築に向けて(答申),(平成20年12月24日),https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1217067.htm
文部科学省,2016,中央教育審議会,「卒業認定・学位授与の方針」(ディプロマ・ポリシー),「教育課程編成・実施の方針」(カリキュラム・ポリシー)及び「入学者受入れの方針」(アドミッション・ポリシー)の策定及び運用に関するガイドライン(平成28年3月31日),https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/houkoku/1369248.htm
文部科学省,2018,中央教育審議会,2040年に向けた高等教育のグランドデザイン(答申)(平成30年11月26日),https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1411360.htm
文部科学省,2025,中央教育審議会,我が国の「知の総和」向上の未来像〜高等教育システムの再構築〜(答申)(令和7年2月21日),https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1420275_00014.htm
文部省,1998,大学審議会,21世紀の大学像と今後の改革方策について ―競争的環境の中で個性が輝く大学―(答申)(平成10年10月26日)
内閣府,2016,第5期科学技術基本計画(平成28年1月22日)https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index5.html
内閣府,2022,科学技術・イノベーション推進事務局、「総合知」の基本的考え方及び戦略的に推進する方策中間とりまとめ(令和4年3月17日),https://www8.cao.go.jp/cstp/sogochi/honbun1.pdf
佐々木和彦,2025,2023年度卒業生・修了生対象地質系若手人材動向調査報告,地質技術者教育委員会,日本地質学会ニュース誌,28,11-14.
制度課題ワーキンググループ,2020,第1回制度課題ワーキンググループ議事録(令和元年8月23日)https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/seidokadai/1kai/giji1.pdf
衆議院文教委員会,1966,第51回国会衆議院文教委員会,第7号,https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105077X00719660304/5
【geo-Flash】 No. 654[2025熊本大会]講演申込受付をまもなく開始いたします
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.654 2025/5/20┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2025年度代議員総会開催について
【2】[2025熊本大会]講演申込受付をまもなく開始いたします
【3】2025年「地質の日」行事のご案内
【4】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【5】JpGU2025:地質学会共催セッションにぜひご出席ください
【6】支部のお知らせ
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
【9】訃報:植村 武 名誉会員ご逝去
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2025年度代議員総会開催について
──────────────────────────────────
日時:2025年6月7日(土)14:00-15:30
※WEB会議形式で開催いたします.
※正会員は,総会に陪席することができます.ただし,総会規則12条3項により,
許可のない発言はできません.
※本総会は役員ならびに代議員による総会となります. 代議員には,総会開催
通知とともに総会に必要な資料等を別途お送りいたします(5/23頃).
議事次第はこちら
http://www.geosociety.jp/outline/content0152.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2025熊本大会]講演申込受付をまもなく開始いたします
──────────────────────────────────
2025熊本大会(9/14-16)の講演申込受付をまもなく開始いたします
(5月下旬予定).
大会までのスケジュール(予定)
7月 9日(水):演題登録・講演要旨受付締切
ランチョン・夜間小集会申込締切
8月初旬:大会プログラム公開(予定)
8月12日(火):巡検参加申込締切
9月 1日(月):大会参加登録締切
採択されたトピックセッション(15件)
https://geosociety.jp/science/content0181.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2025年「地質の日」行事のご案内
──────────────────────────────────
2025年の「地質の日」に関連した日本地質学会主催,共催,後援等の催し
をご紹介します。
■ 惑星地球フォトコンテスト第16回ほか入選作品展示会(開催中)
5月25日(日)14時まで
場所:東京パークスギャラリー(上野グリンサロン内)(台東区上野公園
JR上野駅 公園改札出てすぐ)入場無料
■ オンライン一般講演会「ナウマン来日150年.その功績と足跡を辿る」
(5/10開催)の内容はYouTubeで公開しています.ぜひご覧ください.
https://www.youtube.com/live/BWjqEgzDNuo?si=mzsfu7LSa3a8bnRl
このほか,地質学会以外の全国の地質の日イベント情報はこちら
https://www.gsj.jp/geologyday/2025/index.html(地質の日事業推進委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
【地質学雑誌】
■ 新しい論文が公開されています.
(論説)礼文−樺戸帯に属するサハリン南部モネロン島の白亜紀島弧火山岩:
相澤正隆ほか/(レター)ジルコンのU–Pb法と(U–Th)/He法から推定された
北海道南西部,長万部地域(黒松内低地帯)の約1 Maのテフラ:伊藤久敏ほか
/(報告)Improved definition of the Cretaceous paleomagnetic pole for
southwest Japan using the 100 Ma Hayama Formation:Koji Uno et al/
(論説)山陰バソリス中央部の高田花崗閃緑岩における多段階マグマ注入の
岩石学的証拠:中山瀬那ほか
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/-char/ja
【Island Arc】
■ 新しい論文が公開されています.
(RESEARCH ARTICLE)Emplacement and Cooling History of a Pluton
With Evident Laminated Structure Constrained by Field Anatomy of the
Kinpusan Pluton, Central Japan:Ken Yamaoka et al/Holocene Terraces
Along the Tsailiao River, Western Foothills, Southwest Taiwan:
Lithofacies, Chronology, Fossil Assemblages, and Neotectonic Implications:
Kodai Iwasaki et al/Geotectonic Identity of Cretaceous‐Paleogene Granitoids
in the Tsukuba Igneous Complex, Japan: A New Multi‐Proxy
Reassessment:Wataru Fujisaki et al
学会の会員ページからログインすると全文が無料閲覧できます .
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】JpGU2025:地質学会共催セッションにぜひご出席ください
──────────────────────────────────
JpGU2025が始まります(5/25-30;於幕張メッセ).
日本地質学会は,関係学協会等と共催し下記のセッションを予定しています.
ぜひご出席ください.
******************************************
https://www.jpgu.org/meeting_j2025/
******************************************
(セッション ID,タイトル)
・H-DS11 人間環境と災害リスク
・H-CG21 堆積・侵食・地形発達プロセスから読み取る地球表層環境変動
・S-SS14 活断層と古地震
・S-EM16 地磁気・古地磁気・岩石磁気・環境磁気
・S-GL23 日本列島および東アジアの地質と構造発達史
・S-MP25 Oceanic and Continental Subduction Processes
・S-MP28 変形岩・変成岩とテクトニクス
・S-VC34 火山・火成活動および長期予測
・S-CG44 地殻表層の変動・発達と地球年代学/熱年代学の応用
・S-CG53 岩石・鉱物・資源
・B-CG06 地球史解読:冥王代から現代まで
・M-IS06 Evolution and variability of the Tropical Monsoon and Indo-Pacific
climate during the Cenozoic Era
・M-IS17 地質学のいま
・M-IS20 海底のメタンを取り巻く地圏-水圏-生命圏の相互作用と進化
※プログラム・要旨閲覧には,大会参加ログインが必要です.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[中部支部]
2025年支部年会
6月21日(土)-22日(日)
会場:静岡大学静岡キャンパス
巡検『瀬戸川帯南部の超塩基性-塩基性岩類の産状』6/22
https://geosociety.jp/outline/content0019.html#2025nenkai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
学術会議公開シンポジウム
地名標準化の現状と課題―UNGEGNの活動を理解し日本の地名を考える―
後援:地理学連携機構
5月24日(土)13:00-17:00(オンライン開催)
定員300人,どなたでも参加いただけます
参加無料・要事前申込(5月23日締切)
https://www.scj.go.jp/ja/event/2025/382-s-0524.html
JpGU 2025(ハイブリッド方式)
5月25日(日)-30日(金)
現地会場:幕張メッセ
https://www.jpgu.org/meeting_j2025/
東京地学協会特別講演会
地学クラブ講演会「最近の助成研究から」
6月7日(土)15:00-16:30
会場:リファレンス麹町(東京都千代田区麹町)
講師:岩森 光(東京大学地震研究所 教授)
「日本列島下のマグマ・流体と火山・温泉・地震」
参加無料,事前申込不要
https://www.geog.or.jp/lecture/info/2025-05-14/
地質学史懇話会例会
6月8日(日)13:30-17:00
場所:北とぴあ 803号(東京北区王子)
加藤茂生:東京地学協会による中国の地学調査の淵源と展開
会田信行:『最新地学事典』の中の地球科学史
2025年度深田地質研究所研究成果報告会
6月13日(金)13:00-16:40
場所:深田地質研究所 研修ホール(東京都文京区)
開催形式:会場参加(定員50名),オンライン参加(定員450名)
参加費無料(要事前申込)
https://fukadaken.or.jp/?p=8853
「堆積構造の世界」連続講義
第6回 生痕化石
6月20日(金)17:00から(1-1.5時間程度)
コーディネーター:奈良正和氏
講師:奈良正和氏
https://sites.google.com/view/taisekigakukougi?usp=sharing
(後)第62回アイソトープ・放射線研究発表会
7月2日(水)-4日(金)
会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
参加登録(前期)4/14(月)-6/13(金)12時 7,000円
参加登録(後期)6/23(月)-7/4(金) 9,000円
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/jrias2025
(後)科学教育研究協議会第71回全国研究大会東京大会
テーマ「自然科学をすべての国民のものに」
8月8日(金)-10日(日)
場所:会場 中央大学附属中学校・高等学校(東京都小金井市貫井北町)
https://kakyokyo.org/
(後)第68回粘土科学討論会
9月10日(水)-12日(金)
会場:産業技術総合研究所臨海副都心センター(東京都江東区青海)
申込期間:6月9日(月)-27日(金)
https://www.cssj2.org/event/annual_meeting/
日本地質学会第132年学術大会(2025熊本大会)
9月14日(日)-16日(月)
会場:熊本大学黒髪地区
https://geosociety.jp/science/content0041.html
(共)19th International Conference on Thermochronology
(第19回国際熱年代学会議/Thermo 2025)
9月14日(日)-20日(土)
会場:金沢商工会議所(金沢市尾山町9-13)
https://smartconf.jp/content/thermo2025/
(共)2025年度日本地球化学会第72回年会
9月17日(水)-19日(金)
口頭発表(ハイブリッド),ポスター発表(対面)
場所:東北大学・川内北キャンパス
https://www.geochem.jp/annual-meetings/latest-annual-meeting
第42回歴史地震研究会(豊岡大会)
9月27日(土)- 29日(月)
場所:芸術文化観光専門職大学 (兵庫県豊岡市山王町7-52)
https://www.histeq.jp/kenkyukai.html
国際ゴンドワナ研究連合(IAGR)2025年総会及び
第22回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム
11月2日(日)-6日(木)
会場:延世大学新村キャンパス(韓国・ソウル)
2日:参加登録とアイスブレーカー
3-4日:シンポジウム,総会,晩餐会
5-6日:野外討論会
http://www.gondwanainst.org/symposium/2025/IAGR/IAGR
(協)Techno-Ocean 2025
11月27日(木)-29日(土)
会場:神戸国際展示場2号館ほか(神戸市中央区)
https://to2025.techno-ocean.com/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
https://geosociety.jp/outline/content0255.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・北海道大学大学院理学研究院地球惑星科学部門助教(同位体や微化石に基づく
層序学,または環境 DNA など遺伝子情報を活用した古生物学)公募(9/1)
・東京理科⼤学教養教育研究院教養部教員[地学(鉱物・地形)、地学教育]
公募(8/31)
・原子力規制委員会行政職員(技術系・事務系)の公募(6/30)
・原子力機構夏期休暇実習説明会 in 2025(5/27, 6/5, 6/20, 7/3のAM9:00まで)
・関西エネルギー・リサイクル科学研究振興財団2025年度助成事業(7/31or8/31)
・京都大学大学院理学研究科附属サイエンス連携探索センター准教授公募(6/27)
・JST-ASPIRE2025年度日蘭公募(分野:半導体・量子分野)(9/9)説明会6/3
・湯沢市ゆざわジオパーク学術研究等奨励補助金(7/4)
・五島列島(下五島エリア)ジオパーク活動支援助成金(6/13)
・令和7年度 筑波山地域ジオパーク学術研究助成金(6/6)
・令和7年度島根半島・宍道湖中海ジオパーク学術研究奨励事業補助金募集(6/30)
・佐渡ジオパーク令和7年度大学と地域が連携した地域づくり応援事業(5/30)
・令和7年度三陸ジオパーク学術研究助成金(6/20)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】訃報:植村 武 名誉会員ご逝去
──────────────────────────────────
植村 武 名誉会員(日本地質学会元会長,新潟大学名誉教授)が,令和7年
5月14日にご逝去されました(95歳).御葬儀は近親者により執り行われた
とのことです.これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福を
お祈り申し上げます.
会長 山路 敦
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 655[2025熊本大会]講演申込受付開始
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.655 2025/6/3┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2025年度代議員総会開催について
【2】[2025熊本大会]講演申込受付開始しました
【3】[2025熊本大会]学生のための地質系業界説明会 出展企業団体募集
【4】[2025熊本大会]広告等協賛企業募集
【5】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【6】支部のお知らせ
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2025年度代議員総会開催について
──────────────────────────────────
日時:2025年6月7日(土)14:00-15:30
※WEB会議形式で開催いたします.
※正会員は,総会に陪席することができます.ただし,総会規則12条3項により,
許可のない発言はできません.
※本総会は役員ならびに代議員による総会となります.
議事次第はこちら
http://www.geosociety.jp/outline/content0152.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2025熊本大会]講演申込受付開始しました
──────────────────────────────────
演題登録および原稿締切:7月9日(水)18:00
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/collectsubject
(注)事前参加登録,巡検参加申込等は,6月中旬より申込受付開始予定です.
2025熊本大会HP
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2025熊本大会]学生のための地質系業界説明会 出展企業団体募集
──────────────────────────────────
「2025年度 学生のための地質系業界説明会」
〜その業界の仕事を知るためのサポートサービス〜
対面説明会:2025年9月15日(月・祝)10:00-17:00
申込期限:6月30日(月)※設置可能なブース数に達した場合は先着順
詳しくは,https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/gyokai_support
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2025熊本大会]広告等協賛企業募集
──────────────────────────────────
広告等協賛企業を募集しています.
(1)ニュースプログラム記事号への広告掲載
(2)学術?会HP バナー広告
(3)?会会場内サイン?看板へのロゴ掲載
(4)会場内でのPR スライドの上映
詳しくは,https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/sponsor
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
【Island Arc】
■ 新しい論文が公開されています.
(RESEARCH ARTICLE)Origin of the Sandstone Dikes Intruding Into the Miocene
Shidara Group, Southwest Japan Based on Sandstone Composition and Detrital
Zircon U?Pb Ages:Sakurako Yabuta et al/Holocene Terraces Along the Tsailiao
River, Western Foothills, Southwest Taiwan: Lithofacies, Chronology, Fossil
Assemblages, and Neotectonic Implications;Kodai Iwasaki et al
学会の会員ページからログインすると全文が無料閲覧できます .
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[関東支部]
清澄フィールドキャンプ 参加者募集
2025年8月25日(月)〜8月30日(土)5泊6日
場所:東京大学千葉演習林(千葉県鴨川市清澄)
応募締切日:7月4日(金)
https://geosociety.jp/outline/content0201.html#2025FC
[中部支部]
2025年支部年会
6月21日(土)-22日(日)
会場:静岡大学静岡キャンパス
https://geosociety.jp/outline/content0019.html#2025nenkai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
第249回イブニングセミナー(オンライン)
6月26日(木)19:30-21:30
演題:地下水の知られざる減災機能−新たな水資源マネジメントに向けて
講師:遠藤崇浩(大阪公立大学現代システム科学域)
参加費: 主催NPO会員及び学生の方(無料)非会員の方(1,000円)
https://www.npo-geopol.or.jp/
(後)第62回アイソトープ・放射線研究発表会
7月2日(水)-4日(金)
会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
参加登録(前期)4/14(月)-6/13(金)12時 7,000円
参加登録(後期)6/23(月)-7/4(金) 9,000円
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/jrias2025
東京地学協会【地図講座2025】
8月7日:講座A「Web地図で教材化、授業づくりにひと工夫」
8月7日:講座B「3次元地質地盤図で読み解く首都圏の地盤と災害リスク」
10月19日:巡検C「地形図を持って、河岸段丘の崖線、湧水、断層地形を観察しながら歩く」
11月16日:巡検D「河川争奪など地形地質の成因と人間の関わりを考えながら歩く」
参加費無料,非会員も歓迎.
https://www.geog.or.jp/lecture/info/2025-05-27/
(後)科学教育研究協議会第71回全国研究大会東京大会
テーマ「自然科学をすべての国民のものに」
8月8日(金)-10日(日)
場所:会場 中央大学附属中学校・高等学校(東京都小金井市貫井北町)
https://kakyokyo.org/
(後)第68回粘土科学討論会
9月10日(水)-12日(金)
会場:産業技術総合研究所臨海副都心センター(東京都江東区青海)
申込期間:6月9日(月)-27日(金)
https://www.cssj2.org/event/annual_meeting/
日本地質学会第132年学術大会(2025熊本大会)
9月14日(日)-16日(月)
会場:熊本大学黒髪地区
https://geosociety.jp/science/content0041.html
(共)19th International Conference on Thermochronology
(第19回国際熱年代学会議/Thermo 2025)
9月14日(日)-20日(土)
会場:金沢商工会議所(金沢市尾山町9-13)
https://smartconf.jp/content/thermo2025/?
(共)2025年度日本地球化学会第72回年会
9月17日(水)-19日(金)
口頭発表(ハイブリッド),ポスター発表(対面)
場所:東北大学・川内北キャンパス
https://www.geochem.jp/annual-meetings/latest-annual-meeting
日本土地環境学会公開シンポジウム
「多角的視点から考える土地の環境価値・評価に関する新たな指標」
10月4日(土)14:30-17:00
会場:追手門大学総持寺キャンパス(大阪府茨木市)
https://www.j-lei.jp/
国際ゴンドワナ研究連合(IAGR)2025年総会及び
第22回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム
11月2日(日)-6日(木)
会場:延世大学新村キャンパス(韓国・ソウル)
http://www.gondwanainst.org/symposium/2025/IAGR/IAGR 2025 Circulars.docx
(協)Techno-Ocean 2025
11月27日(木)-29日(土)
会場:神戸国際展示場2号館ほか(神戸市中央区)
https://to2025.techno-ocean.com/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
https://geosociety.jp/outline/content0255.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・農林水産省社会人採用(地球科学分野を含む技術系職員募集)(7/10)
・令和8年度科学技術分野文部科学大臣表彰候補者募集(科学技術賞、若手
科学者賞、研究支援賞)(7/22)
・STAR-Eプロジェクト第4回研究者・学生・生徒向けイベント「地震・測地
データ活用アイデアコンテスト2025」(7/4)
・2025年「海のフロンティアを拓く岡村健二賞」受賞候補者募集(8/22)
・2025年度後期「NHKアーカイブス学術利用」公募(7/31)
・旭川市地域おこし協力隊(ジオパーク専門員)募集(随時)
・霧島ジオパーク学術研究支援補助金(6/27)
・桜島・ 錦江湾ジオパーク研究助成(6/30)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 656[2025熊本大会]各種申込を受付中です!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.656 2025/6/17┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2025熊本大会]各種申込を受付中です!
【2】[2025熊本大会]学生のための地質系業界説明会 出展企業団体募集
【3】2025年度会費督促請求に関するお知らせ
【4】Island Arc からのお知らせ
【5】コラム:中教審の答申「知の総和」とレイトスペシャライゼーションへの対応策
【6】支部のお知らせ
【7】その他のお知らせ
【8】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2025熊本大会]各種申込を受付中です!
──────────────────────────────────
■ 演題登録および原稿締切:7月9日(水)18:00締切
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/collectsubject
■ ジュニアセッション??:7月25日(金) 締切
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/gyoji#jr
■ ランチョン・夜間集会申込:7月9日(水)締切
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/meeting
■ 企業展示・書籍販売:一次締切7月11日(金),最終8月22日(金)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/exhibition_book
■ 広告等協賛企業募集:7月31日(金)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/sponsor
(注)事前参加登録,巡検参加申込等は,6月中旬より申込受付開始予定です.
詳しくは,大会HPをご確認ください.
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2025熊本大会]学生のための地質系業界説明会 出展企業団体募集
──────────────────────────────────
「2025年度 学生のための地質系業界説明会」
〜その業界の仕事を知るためのサポートサービス〜
対面説明会:2025年9月15日(月・祝)10:00-17:00
申込期限:6月30日(月)※設置可能なブース数に達した場合は先着順
締め切りまであと2週間となり、説明ブース枠の残りが少なくなってきました.
まだお申込みされていない賛助会員におかれましては、早めに申し込み手続きを
されることをお勧めいたします.
詳しくは,
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/gyokai_support
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】2025年度会費督促請求に関するお知らせ
──────────────────────────────────
2025年度会費およびそれ以前の未納会費がある方に対して,請求書(郵便振替用紙)
を6月12日に発送しました.早急にご送金くださいますようお願いいたします.
また自動引落については,6月23日に引落しを行います.
※2025年度分会費が未納の場合は,7月号からのニュース誌送付を一時的に中止
させていただきます.
※2025年度分の学生会員申請は受付を終了しました(遡っての申請はできません)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
【Island Arc】
■ 新しい論文が公開されています.
(RESEARCH ARTICLE)Changes in the Redox State of the Nishinoshima
Magmatic System During and After the 2020 Explosive Eruption;
Kenta K. Yoshida,et al
学会の会員ページからログインすると全文が無料閲覧できます .
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】コラム:中教審の答申「知の総和」とレイトスペシャライゼーションへの対応策
──────────────────────────────────
正会員 坂口有人
中央教育審議会から「我が国の「知の総和」向上の未来像 〜高等教育システム
の再構築〜 (答申)」が2月21日に公表された(以下,今回の答申と呼ぶ).
今回の答申の特徴は,学生一人一人の能力を高める質の向上,18歳人口減に伴う
大学規模適正化,高等教育へのアクセス確保などがあり,それらを実現する手段
として文理融合のレイトスペシャライゼーション(以降LSと呼ぶ)が強調されて
いる.本稿はこのLSを中心に論じる.
続きはこちらから,,,https://geosociety.jp/faq/content1216.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[関東支部]
清澄フィールドキャンプ 参加者募集
2025年8月25日(月)〜8月30日(土)5泊6日
場所:東京大学千葉演習林(千葉県鴨川市清澄)
応募締切日:7月4日(金)
https://geosociety.jp/outline/content0201.html#2025FC
[中部支部]
2025年支部年会
6月21日(土)-22日(日)
会場:静岡大学静岡キャンパス
https://geosociety.jp/outline/content0019.html#2025nenkai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
「考える会」連絡 No.53
地盤工学会第60回地盤工学研究発表会の開催案内を掲載しました.
https://www.geo-houseibi.jp
*****************************
(後)第62回アイソトープ・放射線研究発表会
7月2日(水)-4日(金)
会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
参加登録(前期)4/14(月)-6/13(金)12時 7,000円
参加登録(後期)6/23(月)-7/4(金) 9,000円
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/jrias2025
三?浦半島活断層調査会 創立30周年記念講演会
三浦半島の大地を知り減災を考える
7月6日(日)13:00-16:00
会場:横須賀市自然・人文博物館1階 講座室
当日先着80名(申込不要)
https://miurahantou-katudansou-chousakai.hatenablog.com/
「堆積構造の世界」連続講義
7/19(土)第7回 堆積層解析1「堆積層解析の基礎」,「河川堆積相」
講師:伊藤 慎氏,柴田健一郎氏
7/28(月)第8回 堆積層解析2「沿岸堆積相」,「陸棚堆積相」
講師:田村 亨氏,西田尚央氏
8/4(月)第9回 堆積層解析3「深海堆積相」
講師:伊藤 慎氏
https://sites.google.com/view/taisekigakukougi?usp=sharing
第204回深田研談話会
大地震はどのように発生するのか:
地質学と地震学の学祭的立場からの考察
7月11日(金)15:00-16:30
会場:深田地質研究所研修ホール+オンライン
講師:遠田晋次(東北大学災害科学国際研究所)
要事前申込・参加費無料
https://fukadaken.or.jp/
(後)科学教育研究協議会第71回全国研究大会東京大会
テーマ「自然科学をすべての国民のものに」
8月8日(金)-10日(日)
場所:会場 中央大学附属中学校・高等学校(東京都小金井市貫井北町)
https://kakyokyo.org/
第79回地学団体研究会総会(高田)
8月29日(金)-31日(日)
会場:ミュゼ雪小町(新潟県上越市高田駅前)
https://sites.google.com/view/takada2025/
(後)第68回粘土科学討論会
9月10日(水)-12日(金)
会場:産業技術総合研究所臨海副都心センター(東京都江東区青海)
申込期間:6月9日(月)-27日(金)
https://www.cssj2.org/event/annual_meeting/
日本地質学会第132年学術大会(2025熊本大会)
9月14日(日)-16日(月)
会場:熊本大学黒髪地区
https://geosociety.jp/science/content0041.html
(共)19th International Conference on Thermochronology
(第19回国際熱年代学会議/Thermo 2025)
9月14日(日)-20日(土)
会場:金沢商工会議所(金沢市尾山町9-13)
https://smartconf.jp/content/thermo2025/?
(共)2025年度日本地球化学会第72回年会
9月17日(水)-19日(金)
口頭発表(ハイブリッド),ポスター発表(対面)
場所:東北大学・川内北キャンパス
https://www.geochem.jp/annual-meetings/latest-annual-meeting
(後)第6回アジア恐竜国際シンポジウム
9月26日(金)〜30日(火)
会場:福井県立大学永平寺キャンパス(福井県吉田郡永平寺)
https://dinoasia.asia/
2025 NEA IDKM Symposium
10月7日(火)-9日(木)
開催場所:パシフィコ横浜(定員200名)
10月10日(金):東京電力廃炉資料館、福島第一原子力発電所サイトツアー
(定員80名)
プログラムの最新版は下記ウェブサイトより.
国内の学生および若手専門家には参加費と移動費の助成あり(申込締切:6/30)
https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_97583/2025-symposium-on-information-data-and-knowledge-management-idkm-for-radioactive-waste-and-geological-disposal
(協)第41回ゼオライト研究発表会
11?27?(?)〜28?(?)
会場:富?国際会議場
https://jza-online.org/events
(協)Techno-Ocean 2025
11月27日(木)-29日(土)
会場:神戸国際展示場2号館ほか(神戸市中央区)
https://to2025.techno-ocean.com/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
https://geosociety.jp/outline/content0255.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・大阪公立大学地球学専攻/地球環境学講座・地球情報学分野講師or准教授公募
(9/14)
・東京大学大気海洋研究所海洋底科学部門助教1名公募(8/29)
・海上保安庁海洋情報部任期付職員(主任研究官)公募(6/27)
・海上保安庁海洋情報部任期付職員(研究官)公募(7/4)
・海洋研究開発機構リスタート支援公募(研究職,准研究職,技術職)(6/27)
・海洋研究開発機構Young Research Fellow (JYRF)(8/3)
・2025年度伊藤科学振興会研究助成公募(化学分野・地球科学分野)(6/25)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 657[2025熊本大会]大会参加登録受付開始です
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.657 2025/7/1┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2025熊本大会]大会参加登録受付開始です
【2】[2025熊本大会]巡検9コース実施します
【3】[2025熊本大会]各種申込を受付中
【4】2025年度会費督促請求に関するお知らせ
【5】新刊紹介『大地と人の物語−地質学でよみとく日本の伝承』
【6】Island Arc からのお知らせ
【7】支部のお知らせ
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】訃報:Richard S. Fiske氏 逝去
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2025熊本大会]大会参加登録受付開始です.
──────────────────────────────────
申込締切: 9月1日(月)18時
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/sanka
9月14日(日)懇親会も是非ご参加ください!
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/etal
(注)【領収書について】入金を完了された方に対して,領収書PDFのダウン
ロードURLをメールでお知らせします(9/5頃送信予定).巡検の領収書は,
巡検当日にお渡しします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2025熊本大会]巡検9コース実施します
──────────────────────────────────
巡検申込締切:8月12日(火)18時
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/excursion
下記の9コースを準備しています.是非ご参加ください!
A:阿蘇火山: カルデラ形成噴火と後カルデラ活動:9/17
B:北部九州深成岩巡検:9/13
C:長崎変成岩巡検:9/17
D:九州中部の黒瀬川構造帯に見られるシルル紀から石炭紀の化石群:9/17(水)
E:天草諸島や宇土半島に分布する上部白亜系姫浦層群の堆積環境:9/17-18(1泊)
F:九州東部のジュラ紀付加体巡検:9/12-13(プレ・1泊)
G:阿蘇火山と神話から紐解くカルデラの生活−阿蘇ジオパークのサイト巡り−
(アウトリーチ巡検):9/13
H:2016年熊本地震の痕跡と布田川断層:9/17
I:御船層群と御船町恐竜博物館:9/17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2025熊本大会]各種申込を受付中──────────────────────────────────
■ 演題登録および原稿締切:7月9日(水)18:00締切
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/collectsubject
■ ジュニアセッション:7月25日(金) 締切
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/gyoji#jr
■ ランチョン・夜間集会申込:7月9日(水)締切
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/meeting
■ 企業展示・書籍販売:一次締切7月11日(金),最終8月22日(金)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/exhibition_book
■ 広告等協賛企業募集:7月31日(金)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/sponsor
詳しくは,大会HPをご確認ください.
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2025年度会費督促請求に関するお知らせ
──────────────────────────────────
2025年度会費およびそれ以前の未納会費がある方に対して,請求書(郵便振替用紙)
を6月12日に発送しました.早急にご送金をお願いいたします.
また自動引落については,6月23日に引落しを行いました..
※2025年度分会費が未納の場合は,7月号からのニュース誌送付を一時的に中止
させていただきます.
※2025年度分の学生会員申請は受付を終了しました(遡っての申請はできません)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】新刊紹介『大地と人の物語−地質学でよみとく日本の伝承』
──────────────────────────────────
日本地質学会編,創元社2025年6月10日発行,判型:A5判,168頁,
ISBN:978-4-422-44047-7,定価:2,860円(税込)
2023年1月に日本地質学会ジオパーク支援委員会が開催したオンラインシンポ
ジウム『ジオパーク地域に伝わる伝承と地質学―古代からの自然観を今に活かす』
の内容をもとにした,新しい書籍ができました.
https://geosociety.jp/news/n186.html
会員特別販売キャンペーンも実施されます!(創元社商品全品10%割引)
(期間:2025年7月10日〜8月25日まで)
詳しくは,会員ページにログイン
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
【Island Arc】
■ 新しい論文が公開されています.
(RESEARCH ARTICLE)Zircon Crystallization Timings of Granitoids in the
Aoyama Area, Ryoke Belt, Southwest Japan;Fumiko Higashino et al/
(RESEARCH ARTICLE)Changes in the Redox State of the Nishinoshima
Magmatic System During and After the 2020 Explosive Eruption;Kenta K.
Yoshida et al ほか
学会の会員ページからログインすると全文が無料閲覧できます .
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[関東支部]
清澄フィールドキャンプ 参加者募集
2025年8月25日(月)〜8月30日(土)5泊6日
場所:東京大学千葉演習林(千葉県鴨川市清澄)
応募締切日:7月4日(金)
https://geosociety.jp/outline/content0201.html#2025FC
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
国際地理学連合イスタンブール地域会議(IRC2026)のセッション募集開始です
(7/31締切)https://www.irc2026.org/SessionForm/
IRC2026サイトはこちらhttps://www.irc2026.org/en/
那須野が原博物館 特別展「海の王者 海竜」
7月5日(土)-から9月23日(火・祝)
・佐藤たまき氏記念講演会「海竜ー恐竜時代の海の爬虫類ー」
・化石のレプリカづくりのワークショップ など
https://nasunogahara-museum.jp/
*****************************
(後)第62回アイソトープ・放射線研究発表会
7月2日(水)-4日(金)
会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)
参加登録(前期)4/14(月)-6/13(金)12時 7,000円
参加登録(後期)6/23(月)-7/4(金) 9,000円
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/jrias2025
「堆積構造の世界」連続講義(※各回1-2時間程度)
7月19日(土)第7回 堆積層解析1「堆積層解析の基礎」「河川堆積相」
講師:伊藤 慎氏,柴田健一郎氏
7月28日(月)第8回 堆積層解析2「沿岸堆積相」「陸棚堆積相」
講師:田村 亨氏,西田尚央氏
8月4日(月)第9回 堆積層解析3「深海堆積相」
講師:伊藤 慎氏
https://sites.google.com/view/taisekigakukougi?usp=sharing
南海トラフ海底地震津波観測網完成記念シンポジウム
7月29日(火)13:15-16:30
会場:イイノホール(東京都千代田区内幸町)
主催:防災科学技術研究所
https://www.bosai.go.jp/info/event/2025/20250620.html
(後)科学教育研究協議会第71回全国研究大会東京大会
テーマ「自然科学をすべての国民のものに」
8月8日(金)-10日(日)
場所:会場 中央大学附属中学校・高等学校(東京都小金井市貫井北町)
https://kakyokyo.org/
(後)第68回粘土科学討論会
9月10日(水)-12日(金)
会場:産業技術総合研究所臨海副都心センター(東京都江東区青海)
申込期間:6月9日(月)-27日(金)
https://www.cssj2.org/event/annual_meeting/
日本地質学会第132年学術大会(2025熊本大会)
9月14日(日)-16日(月)
会場:熊本大学黒髪地区
https://geosociety.jp/science/content0041.html
(共)19th International Conference on Thermochronology
(第19回国際熱年代学会議/Thermo 2025)
9月14日(日)-20日(土)
会場:金沢商工会議所(金沢市尾山町9-13)
https://smartconf.jp/content/thermo2025/
(共)2025年度日本地球化学会第72回年会
9月17日(水)-19日(金)
口頭発表(ハイブリッド),ポスター発表(対面)
場所:東北大学・川内北キャンパス
https://www.geochem.jp/annual-meetings/latest-annual-meeting
(後)第6回アジア恐竜国際シンポジウム
9月26日(金)〜30日(火)
会場:福井県立大学永平寺キャンパス(福井県吉田郡永平寺)
https://dinoasia.asia/
(協)第41回ゼオライト研究発表会
11⽉27⽇(⽊)〜28⽇(⾦)
会場:富⼭国際会議場
https://jza-online.org/events
(協)Techno-Ocean 2025
11月27日(木)-29日(土)
会場:神戸国際展示場2号館ほか(神戸市中央区)
https://to2025.techno-ocean.com/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
https://geosociety.jp/outline/content0255.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・神戸大学大学院理学研究科惑星学専攻テニュアトラック助教公募(9/30)
・地震研究所共同利用:令和8年度「特定共同研究」研究課題公募(7/31)
・第66回東レ科学技術賞および東レ科学技術研究助成の候補者推薦)(10/10)
(学会締切9/12)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】訃報:Richard S. Fiske氏 逝去
──────────────────────────────────
2017年日本地質学会国際賞(現 都城秋穂賞)受賞者のRichard S. Fiske氏
(元スミソニアン博物館 館長)が逝去されました(92歳).
これまでの故人の功績を讃えるとともに,謹んでご冥福をお祈り申し上げます.
会長 山路 敦
・Peter Fiske氏(ご子息)による追悼文
https://everloved.com/life-of/richard-fiske/
・2017年日本地質学会国際賞受賞理由
https://geosociety.jp/outline/content0180.html#kokusai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 658(臨時)[2025熊本大会]講演申込は明日7/9締切です!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.658 2025/7/8┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2025熊本大会]講演申込は明日7/9締切です!
【2】[2025熊本大会]大会参加登録受付中です
【3】[2025熊本大会]巡検9コース実施します
【4】[2025熊本大会]2025年度学生のための地質系業界説明会
【5】[2025熊本大会]その他各種申込受付中です
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2025熊本大会]講演申込は明日7/9締切です!
──────────────────────────────────
演題登録および原稿締切:7月9日(水)18:00締切
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/collectsubject
(注)招待講演も期日までに演題登録・要旨投稿が必要です.ご注意ください.
(注)お近くに発表を予定していて,これから入会手続きを行う方がいる場合は,
下記大会HPに掲載のお手続きをお伝えください.まだ間に合います!
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2025熊本大会]大会参加登録受付中です.
──────────────────────────────────
申込締切: 9月1日(月)18時
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/sanka
(注)【領収書について】入金を完了された方に対して,領収書PDFのダウン
ロードURLをメールでお知らせします(9/5頃送信予定).巡検の領収書は,
巡検当日にお渡しします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2025熊本大会]巡検9コース実施します
──────────────────────────────────
巡検申込締切:8月12日(火)18時 ※申込状況も掲載しています.
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/excursion
下記の9コースを準備しています.是非ご参加ください!
A:阿蘇火山: カルデラ形成噴火と後カルデラ活動:9/17
B:北部九州深成岩巡検:9/13
C:長崎変成岩巡検:9/17
D:九州中部の黒瀬川構造帯に見られるシルル紀から石炭紀の化石群:9/17(水)
E:天草諸島や宇土半島に分布する上部白亜系姫浦層群の堆積環境:9/17-18(1泊)
F:九州東部のジュラ紀付加体巡検:9/12-13(プレ・1泊)
G:阿蘇火山と神話から紐解くカルデラの生活−阿蘇ジオパークのサイト巡り−
(アウトリーチ巡検):9/13
H:2016年熊本地震の痕跡と布田川断層:9/17
I:御船層群と御船町恐竜博物館:9/17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2025熊本大会]2025年度学生のための地質系業界説明会
──────────────────────────────────
「2025年度学生のための地質系業界説明会」 〜その業界の仕事を知るための
サポートサービス(9/15開催)参加企業が決定しました.
今年の対面ブースは過去最大40の企業・団体にご参加いただきます.専門就職を
お考えの学生の皆様をはじめ、ご関心をお持ちの教員の皆様のご来場をお待ち
しています。
学生参加用申込フォームは大会HPから(申込締切9/9)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/gyokai_support
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2025熊本大会]その他各種申込受付中です.
──────────────────────────────────
■ ジュニアセッション:7月25日(金) 締切
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/gyoji#jr
■ ランチョン・夜間集会申込:7月9日(水)締切
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/meeting
■ 企業展示・書籍販売:一次締切7月11日(金),最終8月22日(金)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/exhibition_book
■ 広告等協賛企業募集:7月31日(金)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/sponsor
詳しくは,大会HPをご確認ください.
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 659[2025熊本大会]巡検申込はお早めに!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.659 2025/7/15┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2025熊本大会]大会参加登録受付中
【2】[2025熊本大会]巡検も申込受付中
【3】[2025熊本大会]各種申込を受付中
【4】[2025熊本大会]その他の情報
【5】紹介:漫画・アニメ「瑠璃の宝石」を応援しよう!
【6】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【7】支部のお知らせ
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2025熊本大会]大会参加登録受付中
──────────────────────────────────
申込締切: 9月1日(月)18時
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/sanka
9月14日(日)懇親会も是非ご参加ください!
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/etal
(注)【領収書について】入金を完了された方に対して,領収書PDFの
ダウンロードURLをメールでお知らせします(9/8頃送信予定).
巡検の領収書は,巡検当日にお渡しします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2025熊本大会]巡検も申込受付中
──────────────────────────────────
巡検申込締切:8月12日(火)18時https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/excursion
D:九州中部の黒瀬川構造帯に見られるシルル紀から石炭紀の化石群:9/17
E:天草諸島や宇土半島に分布する上部白亜系姫浦層群の堆積環境:9/17-18(1泊)
F:九州東部のジュラ紀付加体巡検:9/12-13(プレ・1泊)
G:阿蘇火山と神話から紐解くカルデラの生活−阿蘇ジオパークのサイト巡り−
(アウトリーチ巡検):9/13
H:2016年熊本地震の痕跡と布田川断層:9/17
I:御船層群と御船町恐竜博物館:9/17
大会サイトでは申込状況も更新しています.
なお,A阿蘇火山, B北部九州深成岩, C長崎変成岩の各コースは,すでに定員に
達しました.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2025熊本大会]各種申込を受付中
──────────────────────────────────
■ ジュニアセッション:7月25日(金) 締切
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/gyoji#jr
※生徒,引率者は参加費無料です(大会参加登録不要).ただし,引率者が
地質学会会員の場合,引率者は別途大会参加登録(有料)を行ってください.
■ 企業展示・書籍販売:最終締切8月22日(金)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/exhibition_book
■ 広告等協賛企業募集:7月31日(金)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/sponsor
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2025熊本大会]その他の情報
──────────────────────────────────
■ 学生のための地質系業界説明会:学生参加申込締切9月9日(火)
※対面説明会には,最多40の企業・団体にご出展いただきます!
専門就職をお考えの学生さんはじめ、関心をお持ちの教員方々のご来場
をお待ちしています.スタンプラリーも開催します.
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/gyokai_support
■ 学生・若手のための交流会を開催します(会期前日です)
日時:9月13日(土) 16:30〜19:00
場所:桜の馬場 城彩苑 多目的交流施設(熊本市中央区二の丸)
参加費無料,当日参加可
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/youth#koryukai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】紹介:漫画・アニメ「瑠璃の宝石」を応援しよう!
──────────────────────────────────
郄清水康博・金子 稔(一般会員)
漫画家で鉱物学を修めた渋谷圭一郎さんが,鉱物をテーマとした「瑠璃の宝石」を連載しています.2025年7月6日からはアニメ放送も開始いたしました.主人公で
高校生の谷川瑠璃(たにがわ るり)と大学院生の荒砥 凪(あらと なぎ)が鉱物採集に魅せられ自然へ飛び出していく物語です.日本地質学会会員になじみの岩石ハンマー,タガネや鉱物ルーペなどジオロジストの必需品が登場し,フィールドサイエンスの醍醐味を感じさせてくれる興味深い作品となっています。キラキラと光る鉱物の魅力が質の高い作画で丁寧に表現されており,美しいの一言につきます.当然ですが結晶の形状や質感の描写も科学的に正確です.ストーリーは様々な鉱物採集を中心に進みますが,岩石の種類とでき方,火山の仕組み,流れる水のはたらき,プレートテクトニクス,および自然保護と鉱物採集マナーまで,幅広く地球科学領域のテーマが扱われています.そのため会員の皆様のみならず,お近くの一般の方々,そして未来のジオロジストや自然科学を志す子ども達にも是非,ご紹介いただけますと幸いです.
「瑠璃の宝石」の放送,配信情報はTVアニメ公式サイト(URL1)をご確認下さい.地上波,BSおよびインターネット配信で見られます.また放送開始に先行して「TVアニメ「瑠璃の宝石」がもっと楽しめる特別番組」がアニプレックスチャンネルから公開されています(URL2).第1回目は『日本のあちこちイッテ鉱!』で,出演されている声優さんらと専門の鉱物学研究者による楽しい鉱物学の授業でした.
アニメの原作は2019年より『ハルタ』(KADOKAWA)にて連載中の『瑠璃の宝石』で現在第5巻まで刊行されています.こちらも是非,お読みいただけますとより面白いと思います。また,渋谷さんは「大科学少女」という高校の科学部を題材にした漫画作品も発表されています。科学系の部活動を題材にした漫画であり、大変珍しい分野を扱っています.今後の作品も大いに期待されます.
改めて会員の皆様におかれましては是非,「瑠璃の宝石」の魅力を周辺にお声がけ頂けますと幸いです.若い方々,一般の方々が地質学に対する興味・関心を持っていただける入り口になる可能性があります.皆さん,是非,漫画・アニメ「瑠璃の宝石」を応援しましょう!どうぞよろしくお願いいたします.
<引用>
URL1: https://rurinohouseki.com/
URL2: https://www.youtube.com/watch?v=VuFUsuCzqhw
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
【地質学雑誌】
■ 新しい論文が公開されています.
(巡検案内書)九州中部の黒瀬川帯にみられるシルル紀から石炭紀の
化石群:田中源吾
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/-char/ja
【Island Arc】
■ 新しい論文が公開されています.
(RESEARCH ARTICLE)Low‐Pressure and High‐Temperature Type
Metamorphism on the Suo Belt From Ozushima Island, Seto Inland Sea Area,
Yamaguchi Prefecture, Southwest Japan: Evidence From Detrital Zircon U–Pb
Dating and Mineral Paragenesis;Zejin Lu, Masaaki Owada ほか
学会の会員ページからログインすると全文が無料閲覧できます .
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[中部支部]
6月21-21日開催した,中部支部2025年支部年会(静岡)の報告を掲載しました.
シンポジウム『マントル物質研究の最前線』/一般講演/巡検「瀬戸川帯南部
の超塩基性-塩基性岩類の産状」講演要旨PDFも掲載しています.
https://geosociety.jp/outline/content0019.html#2025nenkai_rep
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)科学教育研究協議会第71回全国研究大会東京大会
テーマ「自然科学をすべての国民のものに」
8月8日(金)-10日(日)
場所:会場 中央大学附属中学校・高等学校(東京都小金井市貫井北町)
https://kakyokyo.org/
(後)第68回粘土科学討論会
9月10日(水)-12日(金)
会場:産業技術総合研究所臨海副都心センター(東京都江東区青海)
申込期間:6月9日(月)-27日(金)
https://www.cssj2.org/event/annual_meeting/
日本地質学会第132年学術大会(2025熊本大会)
9月14日(日)-16日(月)
会場:熊本大学黒髪地区
https://geosociety.jp/science/content0041.html
(共)19th International Conference on Thermochronology
(第19回国際熱年代学会議/Thermo 2025)
9月14日(日)-20日(土)
会場:金沢商工会議所(金沢市尾山町9-13)
https://smartconf.jp/content/thermo2025/
(共)2025年度日本地球化学会第72回年会
9月17日(水)-19日(金)
口頭発表(ハイブリッド),ポスター発表(対面)
場所:東北大学・川内北キャンパス
https://www.geochem.jp/annual-meetings/latest-annual-meeting
第34回 地質汚染調査浄化技術研修会
(現地実習2 地下水モニタリングの基礎)
9月27日(土)10:00〜16:00(終了予定)
参加費:当NPO会員 12,000円,非会員18,000円
参加申込期限:9月20日 ※定員になり次第締切(定員20名)
https://www.npo-geopol.or.jp/workshop.htm#osensurveytraining-groundwater
(後)第6回アジア恐竜国際シンポジウム
9月26日(金)〜30日(火)
会場:福井県立大学永平寺キャンパス(福井県吉田郡永平寺)
https://dinoasia.asia/
産総研地質調査総合センター第8回 鉱物肉眼鑑定研修
10月1日(水)〜3日(金)
場所:茨城県つくば市(産総研)
定員:4〜5名(定員になり次第締切)
CPD:24単位
参加費:48口(1口1000円)の会費が必要です。
https://www.gsj.jp/geoschool/koubutsu/8th.html
産総研地質調査総合センター2025年度第1回追加 地質調査研修
(未経験者向け)
10月6日(月)〜10日(金)
場所:室内座学 茨城県つくば市(産総研)
野外研修 茨城県ひたちなか市、福島県双葉郡広野町・いわき市周辺
定員:6名(定員になり次第締切)
CPD:42単位 ・参加費:84口(1口1000円)の会費が必要https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2025-1-2.html
産総研地質調査総合センター2025年度第2回 地質調査研修
(初級/経験者向け)
10月27日(月)〜31日(金)
場所:島根県出雲市長尾鼻周辺(小伊津海岸)
定員:6名(定員になり次第締切)
CPD:42単位 ・参加費:84口(1口1000円)の会費が必要https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2025-2.html
産総研地質調査総合センター2025年度第3回 地質調査研修
(中級/経験者向け)
11月16日(日)〜22日(土)
場所:福岡県福岡市能古島
定員:6名(定員になり次第締切)
CPD:45単位
参加費:90口(1口1000円)の会費が必要です
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/2025-3.html
(協)第41回ゼオライト研究発表会
11⽉27⽇(⽊)〜28⽇(⾦)
会場:富⼭国際会議場
https://jza-online.org/events
(協)Techno-Ocean 2025
11月27日(木)-29日(土)
会場:神戸国際展示場2号館ほか(神戸市中央区)
https://to2025.techno-ocean.com/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
https://geosociety.jp/outline/content0255.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・山梨県火山防災職募集(8/15)(募集説明会7/25開催)
・JAMSTEC
—超先鋭研究開発部門 超先鋭研究開発プログラム副主任or研究員公募(9/1)
—海域地震火山部門地震津波予測研究開発C観測システム開発研究G, PD(7/23)
・東京学芸大学自然科学系環境科学分野(固体地球科学)教員公募(9/30)
・令和8年度研究船共同利用公募[東北海洋生態系調査研究船(学術研究船)新青丸
及び深海潜水調査船支援母船よこすか/学術研究船白鳳丸(新規航海提案型)/学術研
究船白鳳丸(計画航海参加型)](いずれも8/15)
・第66回東レ科学技術賞および科学技術研究助成の候補者推薦(学会締切9/12)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 660[2025熊本大会]巡検も申込受付:まもなく締切
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.660 2025/8/5┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2025熊本大会]全体日程表が公開になっています
【2】[2025熊本大会]巡検も申込受付:まもなく締切です
【3】[2025熊本大会]緊急展示 受付中
【4】[2025熊本大会]その他の情報
【5】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【6】新刊『大地と人の物語』会員特別販売キャンペーン実施中
【7】支部のお知らせ
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2025熊本大会]全体日程表が公開になっています
──────────────────────────────────
全体日程表はこちら(講演プログラムもまもなく公開予定です)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/program
事前参加登録締切: 9月1日(月)18時
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/sanka
9月14日(日)懇親会も是非ご参加ください(締切: 9月1日(月)18時)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/etal
(注)【領収書について】入金を完了された方に対して,領収書PDFの
ダウンロードURLをメールでお知らせします(9/8頃送信予定).
巡検参加費の領収書は,巡検当日にお渡しします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2025熊本大会]巡検も申込受付:まもなく締切です
──────────────────────────────────
巡検申込締切:8月12日(火)18時https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/excursion
G:阿蘇火山と神話から紐解くカルデラの生活−阿蘇ジオパークのサイト巡り−
(アウトリーチ巡検):9/13
H:2016年熊本地震の痕跡と布田川断層:9/17
I:御船層群と御船町恐竜博物館:9/17
※AからFの各コースは,すでに定員に達しました.
大会サイトでは申込状況も更新しています.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2025熊本大会]緊急展示 受付中
──────────────────────────────────
緊急展示(ポスター発表のみ)を募集します
***申込締切:8月28日(木)***
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害調査報告や
速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示」を設けます.
詳しくは,
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/urgent
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2025熊本大会]その他の情報
──────────────────────────────────
■ 学生のための地質系業界説明会:学生参加申込締切 9月9日(火)
※対面説明会には,最多40の企業・団体にご出展いただきます!
専門就職をお考えの学生さんはじめ、関心をお持ちの教員方々のご来場
をお待ちしています.スタンプラリーも開催します(景品もあります).
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/gyokai_support
■ 学生・若手のための交流会を開催します(会期前日)
日時:9月13日(土) 16:30〜19:00
場所:桜の馬場 城彩苑 多目的交流施設(熊本市中央区二の丸)
参加費無料,当日参加可
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/youth#koryukai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
【地質学雑誌】
■ 新しい論文が公開されています.
(巡検案内書)長崎変成岩西彼杵ユニット中の蛇紋岩メランジュ:超高圧変成岩
を含む雪浦メランジュとヒスイ輝石岩を産する三重メランジュ 西山 忠男/
(レター)福井県に分布する“白亜紀”打波深成岩体から得られた前期ジュラ紀ジルコンの意義:長田充弘ほか
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/-char/ja
【Island Arc】
■ 新しい論文が公開されています.
(RESEARCH ARTICLE)Microstructural Characteristics of Sheared
Gabbroic Rocks From the Mado Megamullion, Shikoku Basin, Philippine Sea
:Kohei Nimuraほか
学会の会員ページからログインすると全文が無料閲覧できます .
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】新刊『大地と人の物語』会員特別販売キャンペーン実施中
──────────────────────────────────
日本地質学会編,創元社2025年6月10日発行,判型:A5判,168頁,
ISBN:978-4-422-44047-7,定価:2,860円(税込)
2023年1月に日本地質学会ジオパーク支援委員会が開催したオンラインシンポ
ジウム『ジオパーク地域に伝わる伝承と地質学―古代からの自然観を今に活かす』
の内容をもとにした,新しい書籍が発行されました.
https://geosociety.jp/news/n186.html
会員特別販売キャンペーン実施中!(創元社商品全品10%割引)
(期間:2025年7月10日〜8月25日まで)
詳しくは,会員ページにログイン
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[関東支部]
講演会「県の石−栃木県の岩石・鉱物・化石−」と見学会
日程:2025年9月27日(土)
(大谷石の建物見学会)10:00-11:30
(講演会)13:00-16:00
申込期間:2025年9月1日(月)-24日(水)17:00締切
https://geosociety.jp/outline/content0201.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
地質地盤情報の活用と法整備を考える会
活動趣旨や課題をまとめた「広報冊子・パンフレット」を掲載しました.
https://www.geo-houseibi.jp
********************
(後)科学教育研究協議会第71回全国研究大会東京大会
テーマ「自然科学をすべての国民のものに」
8月8日(金)-10日(日)
場所:会場 中央大学附属中学校・高等学校(東京都小金井市貫井北町)
https://kakyokyo.org/
(後)第68回粘土科学討論会
9月10日(水)-12日(金)
会場:産業技術総合研究所臨海副都心センター(東京都江東区青海)
申込期間:6月9日(月)-27日(金)
https://www.cssj2.org/event/annual_meeting/
日本地質学会第132年学術大会(2025熊本大会)
9月14日(日)-16日(月)
会場:熊本大学黒髪地区
https://geosociety.jp/science/content0041.html
(共)19th International Conference on Thermochronology
(第19回国際熱年代学会議/Thermo 2025)
9月14日(日)-20日(土)
会場:金沢商工会議所(金沢市尾山町9-13)
https://smartconf.jp/content/thermo2025/
(共)2025年度日本地球化学会第72回年会
9月17日(水)-19日(金)
口頭発表(ハイブリッド),ポスター発表(対面)
場所:東北大学・川内北キャンパス
https://www.geochem.jp/annual-meetings/latest-annual-meeting
(後)第6回アジア恐竜国際シンポジウム
9月26日(金)-30日(火)
会場:福井県立大学永平寺キャンパス(福井県吉田郡永平寺)
https://dinoasia.asia/
(協)第41回ゼオライト研究発表会
11⽉27⽇(⽊)-28⽇(⾦)
会場:富⼭国際会議場
https://jza-online.org/events
(協)Techno-Ocean 2025
11月27日(木)-29日(土)
会場:神戸国際展示場2号館ほか(神戸市中央区)
https://to2025.techno-ocean.com/
地質学史懇話会総会
12月20日(土)13:30-17:00
場所:北とぴあ 803号室(東京都北区王子)
石渡 明:江原眞伍の太平洋運動(1942)の光と影
黒田和男:坪井忠二ほか<1954>「日本全国の重力測定」を読む
問い合わせ先:矢島道子 pxi02070[at]nifty.com
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
https://geosociety.jp/outline/content0255.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・明星大学教育学部教育学科生物学分野教授、准教授または助教(8/31)
・高知大学海洋コア国際研究所技術職員再公募(9/17)
・令和7年度神奈川県職員採用選考(地質職)(8/29)
・名古屋大学環境学研究科 地球環境科学専攻 地球惑星科学系 地質・地球生物学
講座准教授または講師公募(9/22)
・東京海洋大学学術研究院海洋資源エネルギー学部門(海洋底地球科学分野)
准教授または助教(テニュアトラック)公募(9/30)
・高知大学教育学部 地学 准教授、講師又は助教の公募(9/26)
・第47(令和7年度)沖縄研究奨励賞推薦応募(学会締切9/4)
・ 中谷財団次世代理系人材育成プログラム助成募集(10/1-11/20)
・中谷財団科学教育振興助成(10/1−11/30)
・2025年「海のフロンティアを拓く岡村健二賞」受賞候補者募集 (8/22)
・「環境研究総合推進費」令和8年度新規課題公募(9/8-10/10)
・北海道上富良野町 地域おこし協力隊(R7郷土学習推進員)募集(8/20)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 661[2025熊本大会]緊急展示 受付中
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.660 2025/8/19┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2025熊本大会]事前参加登録はお済みですか?
【2】[2025熊本大会]巡検の催行可否について
【3】[2025熊本大会]緊急展示 受付中
【4】[2025熊本大会]その他の情報
【5】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
【6】新刊『大地と人の物語』会員特別販売キャンペーン(8/25まで)
【7】支部のお知らせ
【8】その他のお知らせ
【9】公募情報・各賞助成情報等
【10】災害に関連した会費の特別措置
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2025熊本大会]事前参加登録はお済みですか?
──────────────────────────────────
大会当日のスムーズな受付のために,事前参加登録にご協力をお願いいたします.
事前参加登録締切: 9月1日(月)18時
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/sanka
9月14日(日)懇親会も是非ご参加ください(締切: 9月1日(月)18時)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/etal
(注)【領収書について】入金を完了された方に対して,領収書PDFの
ダウンロードURLをメールでお知らせします(9/8頃送信予定).
巡検参加費の領収書は,巡検当日にお渡しします.
全体日程表はこちら
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/program
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2025熊本大会]巡検の催行可否について
──────────────────────────────────
8/12に巡検のお申し込みを締め切りました.各コースの催行可否については,
大会サイトをご確認ください.
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/excursion
※中止となったコースへお申し込みいただいた方へは,返金等のお手続き
について,学会事務局より個別にご連絡を差し上げます.
※先の記録的豪雨の影響により,一部巡検コースに変更が発生する見込みです.
現在各案内者に確認を行っています.該当コースの参加予定者には個別にご連絡
を差し上げます.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2025熊本大会]緊急展示 受付中
──────────────────────────────────
緊急展示(ポスター発表のみ)を募集します
***申込締切:8月28日(木)***
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害調査報告や
速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示」を設けます.
詳しくは,
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/urgent
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2025熊本大会]その他の情報
──────────────────────────────────
■ 学生のための地質系業界説明会:学生参加申込締切 9月9日(火)
※対面説明会には,最多40の企業・団体が出展!
専門就職をお考えの学生さんはじめ、関心をお持ちの教員方々のご来場
をお待ちしています.スタンプラリーも開催します(景品もあります).
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/gyokai_support
■ 学生・若手のための交流会を開催します(会期前日)
日時:9月13日(土) 16:30〜19:00
場所:桜の馬場 城彩苑 多目的交流施設(熊本市中央区二の丸)
参加費無料,当日参加可
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/youth#koryukai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】地質学雑誌・Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
【地質学雑誌】
■ 新しい論文が公開されています.
(巡検案内書)九州東部に分布する秩父帯のジュラ紀付加体:ペルム紀〜三畳紀
のパンサラッサ海古海洋環境変動:尾上 哲治ほか
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/geosoc/-char/ja
【Island Arc】
■ 新しい論文が公開されています.
(RESEARCH ARTICLE)Origin of Amphibole Cumulates at the Base of an
Exposed Arc Crustal Section: Perspectives From Fiordland, New Zealand;
Patrick Manselle et alほか
学会の会員ページからログインすると全文が無料閲覧できます .
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】新刊『大地と人の物語』会員特別販売キャンペーン(8/25まで)
──────────────────────────────────
日本地質学会編,創元社2025年6月10日発行,判型:A5判,168頁,
ISBN:978-4-422-44047-7,定価:2,860円(税込)
2023年1月に日本地質学会ジオパーク支援委員会が開催したオンラインシンポ
ジウム『ジオパーク地域に伝わる伝承と地質学―古代からの自然観を今に活かす』
の内容をもとにした,新しい書籍が発行されました.
https://geosociety.jp/news/n186.html
会員特別販売キャンペーン実施中!(創元社商品全品10%割引)
(期間:2025年7月10日〜8月25日まで)
詳しくは,会員ページにログイン
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[関東支部]
講演会「日本地質学会選定 県の石−栃木県の岩石・鉱物・化石−」と見学会
9月27日(土)
(大谷石の建物見学会)10:00-11:30[定員20名(抽選)]
(講演会)13:00-16:00 会場:栃木県立博物館講堂[定員現地100+WEB100]
申込期間:2025年9月1日(月)-17日(水)17:00締切
https://geosociety.jp/outline/content0201.html
伊与原新さん講演会
10月26日(日)14:30-16:00
場所:日本大学文理学部 百周年記念館 国際会議場
対象:中高生および保護者(引率教員含む)
入場無料・要事前申込
https://geo-kanto-iyoharashin.peatix.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
AOGS2026福岡(セッション提案期間:10月11日まで)
アジア大洋州地球科学学会Asia Oceanina Geosciences Society (AOGS)
セッション提案期間: 2025年10月11日(土) 24:55 JSTまで
日程:2026年8月2日(日)-7日(金)
会場:福岡国際会議場+マリンメッセ福岡B館
https://www.asiaoceania.org/aogs2026/public.asp?page=home.asp
********************
防災推進国民大会2025セッション
日本学術会議学術シンポジウム/第20回防災学術連携シンポジウム
「複合災害に立ち向かう防災の知恵―新潟と能登の経験から」
9月7日(日)10:30-12:00
会場:Zoom ウェビナーによるオンライン開催
無料,定員:1000名,要参加申込
https://ws.formzu.net/fgen/S2178437/
(後)第68回粘土科学討論会
9月10日(水)-12日(金)
会場:産業技術総合研究所臨海副都心センター(東京都江東区青海)
https://www.cssj2.org/event/annual_meeting/
日本地質学会第132年学術大会(2025熊本大会)
9月14日(日)-16日(月)
会場:熊本大学黒髪地区
https://geosociety.jp/science/content0041.html
(共)19th International Conference on Thermochronology
(第19回国際熱年代学会議/Thermo 2025)
9月14日(日)-20日(土)
会場:金沢商工会議所(金沢市尾山町9-13)
https://smartconf.jp/content/thermo2025/
(共)2025年度日本地球化学会第72回年会
9月17日(水)-19日(金)
口頭発表(ハイブリッド),ポスター発表(対面)
場所:東北大学・川内北キャンパス
https://www.geochem.jp/annual-meetings/latest-annual-meeting
公開シンポジウム「地球的課題解決のための資質・能力を育成する地理教育
―小学校・中学校・高等学校までの一貫カリキュラムに向けて―」
9月21日(日)9:00-12:00
場所:弘前大学(青森県弘前市文京町一番地)地理学会秋季大会第1会場
どなたでも参加いただけます.定員100人程度
参加費無料・事前申込不要
https://www.scj.go.jp/ja/event/2025/387-s-0921.html
(後)第6回アジア恐竜国際シンポジウム
9月26日(金)-30日(火)
会場:福井県立大学永平寺キャンパス(福井県吉田郡永平寺)
https://dinoasia.asia/
(協)第41回ゼオライト研究発表会
11⽉27⽇(⽊)-28⽇(⾦)
会場:富⼭国際会議場
https://jza-online.org/events
(協)Techno-Ocean 2025
11月27日(木)-29日(土)
会場:神戸国際展示場2号館ほか(神戸市中央区)
https://to2025.techno-ocean.com/
変形・透水試験機設計セミナー2026
2026年3月9(月)-11日(水)
場所:京都大学吉田キャンパス
申込期間:2025年9月14(日)-2026年1月16日(金)
https://sites.google.com/view/designseminar2025/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
https://geosociety.jp/outline/content0255.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・2026年度産総研イノベーションスクール人材育成コース公募(11/25)
・学校法人上智学院栄光学園中学高等学校専任教諭募集(地学教員)(9/30)
・東京大学地震研究所令和7年度第3回大型計算機共同利用公募研究公募(8/29)
・三好ジオパーク学術研究助成事業(8/29)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】災害に関連した会費の特別措置
──────────────────────────────────
日本地質学会では,災害救助法適用地域で被災された会員のご窮状をふまえ,
「日本地質学会に届出の住居または勤務地が災害救助法適用地域に該当する
会員のうち,希望する方」は当年度(もしくは次年度)の会費を免除いたします.
希望される方は,学会事務局までお申し出ください.
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0239.html#saigai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】 No. 662(臨時)[2025熊本大会]講演プログラム公開
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.662 2025/8/21┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】[2025熊本大会]講演プログラムが公開になりました
【2】[2025熊本大会]事前参加登録はお済みですか?
【3】[2025熊本大会]巡検の催行可否について
【4】[2025熊本大会]緊急展示 受付中
【5】[2025熊本大会]地質系業界説明会:学生参加申込受付中
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】[2025熊本大会]講演プログラムが公開になりました
──────────────────────────────────
第132年学術大会(2025熊本)の講演プログラムが公開になりました.
大会サイト・メニュー「プログラム」「タイムテーブル」からご覧いただけます.
2025熊本大会サイト
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132
講演要旨は,9月初旬に公開予定です(事前参加登録者限定).
事前参加登録をされた方(入金済みの方)へは,要旨閲覧のためのログイン情報
をメールでお知らせいたします(9/5頃を予定).
(注)入金確認が取れない場合は,ログイン情報を発行できません.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2025熊本大会]事前参加登録はお済みですか?
──────────────────────────────────
大会当日のスムーズな受付のために,事前参加登録にご協力をお願いいたします.
事前参加登録締切: 9月1日(月)18時
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/sanka
9月14日(日)懇親会も是非ご参加ください(締切: 9月1日(月)18時)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/etal
(注)【領収書について】入金を完了された方に対して,領収書PDFの
ダウンロードURLをメールでお知らせします(9/8頃送信予定).
巡検参加費の領収書は,巡検当日にお渡しします.
全体日程表はこちら
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/program
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2025熊本大会]巡検の催行可否について
──────────────────────────────────
8/12に巡検のお申し込みを締め切りました.各コースの催行可否については,
大会サイトをご確認ください.
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/excursion
※中止となったコースへお申し込みいただいた方へは,返金等のお手続き
について,学会事務局より個別にご連絡を差し上げます.
※先の記録的豪雨の影響により,一部巡検コースに変更が発生する見込みです.
現在各案内者に確認を行っています.該当コースの参加予定者には別途ご連絡
を差し上げます.
※巡検当日の詳細につきましては、各コースの案内者よりメールにてご連絡する
予定です
※巡検の領収書は,巡検当日にお渡しします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2025熊本大会]緊急展示 受付中
──────────────────────────────────
緊急展示(ポスター発表のみ)を募集中です
***申込締切:8月28日(木)***
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害調査報告や
速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示」を設けます.
詳しくは,
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/urgent
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2025熊本大会]地質系業界説明会:学生参加申込受付中
──────────────────────────────────
■ 学生のための地質系業界説明会:学生参加申込締切 9月9日(火)
※対面説明会には,最多40の企業・団体が出展!
専門就職をお考えの学生さんはじめ、関心をお持ちの教員方々のご来場
をお待ちしています.スタンプラリーも開催します(景品もあります).
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/gyokai_support
この他,
・学生・若手のための交流会:9月13日(土)16:30〜19:00
・ダイバーシティ認定ロゴ
・求職中ロゴ
など,若手会員向けの取り組みを行っています.
詳しくは,https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/youth
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No. 663 今年は選挙の年です!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.663 2025/9/2┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】今年は選挙の年です!
【2】[2025熊本大会]まもなく講演要旨が公開となります
【3】[2025熊本大会]領収書について
【4】[2025熊本大会]「会員カード」持参して下さい
【5】[2025熊本大会]学生事前予約受付中:地質系業界説明会
【6】[2025熊本大会]学生・若手のための交流会
【7】若手巡検 in 長瀞・皆野地域
【8】Island Arc からのお知らせ
【9】支部のお知らせ
【10】その他のお知らせ
【11】公募情報・各賞助成情報等
【12】災害に関連した会費の特別措置
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】今年は選挙の年です!
──────────────────────────────────
日本地質学会では2年に一度代議員選挙と理事選挙を,4年に一度監事選挙を
行っていますが,今年は代議員選挙と理事選挙を行う年です.併せて,会長・
副会長立候補意思表明者への意向調査も行います.このうち,正会員の皆さん
には,12月頃に代議員選挙と会長・副会長意向調査の投票を行っていただきます.
前回から,投票は原則として会員システムを用いた電子投票で行っています.
今一度,会員システムにログインできるかご確認ください.
詳しくは,https://geosociety.jp/news/n187.html
電子投票ができない環境の会員には,事務局から投票用紙をお配りしています.
事務局まで事前にお問い合わせください.(main[at]geosociety.jp)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】[2025熊本大会]まもなく講演要旨が公開となります
──────────────────────────────────
講演要旨(要ログイン)はまもなく公開予定です。
要旨公開までに、事前参加登録者の皆様に参加者用ログイン情報を
メールでお知らせするため,現在作業中です(9/8頃予定)。
入金確認が取れない場合は,参加者用ログイン情報が発行できません.
まだお支払いがお済みでない方は,急ぎご対応をお願いいたします.
また,領収書のダウンロードURLもメールでお知らせします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2025熊本大会]領収書について
──────────────────────────────────
入金を完了された方に対して,領収書PDFのダウンロードURLをメールで
お知らせします(9/8頃送信予定).
巡検参加費の領収書は,巡検当日にお渡しします.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】[2025熊本大会]「会員カード」持参して下さい
──────────────────────────────────
会員カードでの受付は,裏面バーコードを読み込むだけで簡単スピーディです.
ぜひ「会員カード」を持参してください.
事前参加登録者で,当日「会員カード」をお持ちでない方(新入会の方,
非会員の方,忘れた方等)は,お名前で確認いたします.
(注)クーポン券等学会からの事前の郵送物はありません.
事前登録をしていない方は,会場(熊本大学)で当日受付を行います.
参加登録費の有料・無料に関わらず備え付けの『参加登録票』に必要事項を
記入して,当日用受付で手続きしてください.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】[2025熊本大会]学生事前予約受付中:地質系業界説明会
──────────────────────────────────
「2025年度 学生のための地質系業界説明会」
〜その業界の仕事を知るためのサポートサービス〜
最多40の企業・団体が出展!専門就職をお考えの学生さんはじめ、関心を
お持ちの教員方々のご来場をお待ちしています.
9月15日(月・祝)10:00〜17:00
会場:全学教育棟2階(B201・B202・D201・D202・D203・E204)
学生事前参加申込期限:9月9日(火)※当日飛び込み参加も可能ですが,
希望の企業ブースへの事前予約をおすすめします.
スタンプラリーも開催します(景品もあります).
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/gyokai_support
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】[2025熊本大会]学生・若手のための交流会
──────────────────────────────────
■ 学生・若手のための交流会を開催します(会期前日)
日時:9月13日(土) 16:30〜19:00
場所:桜の馬場 城彩苑 多目的交流施設(熊本市中央区二の丸)
参加費無料・当日参加可能
※人数把握のため、参加希望の方は事前申込にご協力をお願いします.
(9/12正午まで)
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/youth#koryukai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】若手巡検 in 長瀞・皆野地域
──────────────────────────────────
日時:2025年10月18日(土)
集合:8時15分(大宮駅) 解散:18時30分(熊谷駅)
対象者:35歳以下の日本地質学会正会員
※非会員の申込みは事前に地質学会への入会届の提出(今回入会された方も含む)
参加費: 正会員(学生会員):4,300円,正会員(一般会員):8,600円
最少催行人数20名・定員26名
主な見学地:埼玉県 長瀞・皆野地域(景勝地を眺めながら,それらを
かたちづくる変成・変形岩をじっくり観察します)
詳しくは,
https://geosociety.jp/science/content0183.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】Island Arc からのお知らせ
──────────────────────────────────
【Island Arc】
■ 新しい論文が公開されています.
(RESEARCH ARTICLE)Early Miocene Fore‐Arc Magmas Derived From
Subcontinental Lithospheric Mantle During the Japan Sea Opening:
Geochemistry of the Ishimoriyama and Iritono Volcanic Rocks
in the Iwaki District, NE Japan:Takahiro Yamamoto
学会の会員ページからログインすると全文が無料閲覧できます .
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[関東支部]
講演会「日本地質学会選定 県の石−栃木県の岩石・鉱物・化石−」と見学会
9月27日(土)
(大谷石の建物見学会)10:00-11:30[定員20名(抽選)]
(講演会)13:00-16:00 会場:栃木県立博物館講堂[定員現地100+WEB100]
申込期間:2025年9月1日(月)-17日(水)17:00締切(※講演会申込は24日まで)
https://geosociety.jp/outline/content0201.html
伊与原新さん講演会
10月26日(日)14:30-16:00
場所:日本大学文理学部 百周年記念館 国際会議場
対象:中高生および保護者(引率教員含む)
入場無料・要事前申込
https://geo-kanto-iyoharashin.peatix.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
(後)第68回粘土科学討論会
9月10日(水)-12日(金)
会場:産業技術総合研究所臨海副都心センター(東京都江東区青海)
https://www.cssj2.org/event/annual_meeting/
日本地質学会第132年学術大会(2025熊本大会)
9月14日(日)-16日(月)
会場:熊本大学黒髪地区
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132
(共)19th International Conference on Thermochronology
(第19回国際熱年代学会議/Thermo 2025)
9月14日(日)-20日(土)
会場:金沢商工会議所(金沢市尾山町9-13)
https://smartconf.jp/content/thermo2025/
(共)2025年度日本地球化学会第72回年会
9月17日(水)-19日(金)
口頭発表(ハイブリッド),ポスター発表(対面)
場所:東北大学・川内北キャンパス
https://www.geochem.jp/annual-meetings/latest-annual-meeting
NUMO 地層処分技術を考えるシンポジウム2025
9月23日(火・祝)13:00-16:00
場所:サッポロファクトリーホール(札幌市中央区北2条東3丁目)
現地開催
参加費無料・要事前申込(9/18締切)
https://www.numo.or.jp/technology/techpublicity/lecture/250923.html
(後)第6回アジア恐竜国際シンポジウム
9月26日(金)-30日(火)
会場:福井県立大学永平寺キャンパス(福井県吉田郡永平寺)
https://dinoasia.asia/
第250回地質汚染・災害イブニングセミナー (オンライン)
9月26日(金)19:30-21:30,zoomオンライン開催
NPO法人アジア砒素ネットワーク3名の講師が講演予定.
参加費:主催NPO会員及び学生(無料),非会員(1,000円)
https://www.npo-geopol.or.jp/
第64回温泉保護・管理研修会
10月28日(火)-29日(水)
場所:北とぴあ つつじホール(東京都北区王子)
主催:公益財団法人中央温泉研究所
http://www.onken.or.jp/seminar.html
第17回日韓中地理学会議
11月11日(火)-14日(金)
会場:京都テルサ(京都市南区東九条下殿田町70)
参加登録締切・発表要旨締切:9月20日
https://www.dh-jac.net/wp/17jkc/
(協)第41回ゼオライト研究発表会
11⽉27⽇(⽊)-28⽇(⾦)
会場:富⼭国際会議場
https://jza-online.org/events
(協)Techno-Ocean 2025
11月27日(木)-29日(土)
会場:神戸国際展示場2号館ほか(神戸市中央区)
https://to2025.techno-ocean.com/
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
https://geosociety.jp/outline/content0255.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・2026年度笹川科学研究助成募集(10/15)
・2026年度山田科学振興財団海外研究援助(10/31)
・JAMSTEC域地震火山部門地震発生帯研究センタープレート構造研究グループ
特任研究員orPD研究員公募(9/30)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】災害に関連した会費の特別措置
──────────────────────────────────
日本地質学会では,災害救助法適用地域で被災された会員のご窮状をふまえ,
「日本地質学会に届出の住居または勤務地が災害救助法適用地域に該当する
会員のうち,希望する方」は当年度(もしくは次年度)の会費を免除いたします.
希望される方は,学会事務局までお申し出ください.
詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0239.html#saigai
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
【geo-Flash】No. 664 熊本大会!
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬
┬┴┬┴┬┴┬ No.664 2025/9/14〜 ┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 熊本大会の様子
──────────────────────────────────
熊本大会が始まったんだもん!
地質情報展
大会会場
ジュニアセッション
表彰式 会長挨拶
来賓挨拶
50年顕彰
都城秋穂賞
小澤儀明賞
論文賞
論文賞
小藤文次郎賞
研究奨励賞
懇親会
大会委員長挨拶
来賓挨拶
乾杯
5校記念館
市民講演会
地質系業界説明会
企業ブース
【geo-Flash】No. 665 2026年度代議員および役員選挙について(告示)
┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬
┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴
┬┴┬┴┬┴┬ No.665 2025/10/7┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴
┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
【1】2026年度代議員および役員選挙について(告示)
【2】2026年度学会各賞候補者募集
【3】[2025熊本大会]領収書について
【4】JpGU2026セッション提案募集(地質学会共催)
【5】支部のお知らせ
【6】その他のお知らせ
【7】公募情報・各賞助成情報等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2026年度代議員および役員選挙について(告示)
──────────────────────────────────
日本地質学会定款ならびに選挙規則・選挙細則に基づき,代議員および
役員(理事)選挙を実施いたします.選挙実施の要点についてHP,ニュース誌
に記しています.また,選挙規則等も掲載しましたのでご確認ください.
あわせて,会長・副会長立候補意思表明者への意向調査も行います.
※代議員選挙立候補受付期間:10/22(水)10時〜11/19(水)17時
→立候補届は選挙システムの立候補届出フォームより,10/22から受付開始.
詳しくは,会員ページへ(要ログイン):
https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
投票は原則として会員システムを用いた電子投票で行います.
今一度,会員システムにログインできるかご確認ください.
(参考)会員システムの公開・利用について:
https://geosociety.jp/news/n176.html
電子投票ができない環境の会員には,事務局から投票用紙をお配りします.
事務局まで事前にお問い合わせください.(main[at]geosociety.jp)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2026年度学会各賞候補者募集
──────────────────────────────────
運営規則第16 条および各賞選考規則に基づき,賞の候補者を募集いたします.
ご推薦いただいた方の中から,各賞選考委員会(委員は理事会の互選と職責に
より選出)が候補者を選考し,理事会での決定,総会での承認を経て表彰を行
います.期日厳守にてご推薦ください.
個人(正会員または名誉会員)からの推薦も可能です.
************************
応募締切:2025年12月1日(月)必着
************************
詳しくは,https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php
(要会員ログイン)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】[2025熊本大会]領収書について
──────────────────────────────────
熊本大会参加登録を方は,参加費,発表料,懇親会の領収書が大会HPから
ダウンロード可能です.(要大会参加者ログイン)
ダウンロード可能期間:2025/10/15まで
巡検参加費の領収書は,巡検当日に案内者よりお渡しいただいています.
ご確認ください.
https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/geosocjp132/content/receipt
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】JpGU2026セッション提案募集(地質学会共催)
──────────────────────────────────
JpGU2026でセッション提案を予定している方で,地質学会共催を希望される
場合は,併行して下記の地質学会JpGUプログラム委員にご連絡いただきます
ようお願い致します。すでにJpGUへ提案済みの場合も,これからでも結構です
ので,プログラム委員に連絡をお願い致します.
(各部会行事委員を通して既にご連絡済みの場合はそちらで承ります)
JpGU-AGU 2026は,セッション言語に関わらず全てのセッションがJpGU-AGUジョイントセッションとして位置づけられます.
AGUとのジョイント申請は不要ですが,原則として主要言語は英語となります.
パブリックセッションなど一部のセッションにおいてはJ(日本語の使用可)セッションとしてご提案いただけますが,Jセッションとしてご提案される場合には,
その理由を添えて下さい..
日本地質学会JpGUプログラム委員:
野々垣進(情報地質部会選出行事委員)s-nonogaki[at]aist.go.jp
黒田潤一郎(環境変動史部会選出行事委員)kuroda[at]aori.u-tokyo.ac.jp
(注)[at]を@マークにしてください
[ご連絡いただく内容]
・タイトル:
・スコープ:
・代表コンビーナ(1名):
・共同コンビーナ(3名まで):
JpGUセッション提案締切:2025年10月15日(水)17:00
※上記はJpGUの締切です.地質学会へはお早めにご連絡ください.
JpGU(日本語版)https://www.jpgu.org/meeting_j2026/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】支部のお知らせ
──────────────────────────────────
[北海道支部]
2025年度北海道支部例会(個人講演会)
11月15日(土)13:00-18:00
場所:オンライン開催
講演申込:10月21日(火)
https://geosociety.jp/outline/content0023.html
[関東支部]
伊与原新さん講演会
10月26日(日)14:30-16:00
場所:日本大学文理学部 百周年記念館 国際会議場
対象:中高生および保護者(引率教員含む)
入場無料・要事前申込
https://geo-kanto-iyoharashin.peatix.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】その他のお知らせ
──────────────────────────────────
深田研一般公開2025
10月19日(日)10:00-16:00
会場:公益財団法人深田地質研究所(東京都文京区本駒込)
ラボツアーやミニレクチャー,アンモナイトアクセサリー製作
木の葉化石を探そうなどの体験学習も豊富に用意しています
入場無料
https://fukadaken.or.jp/?page_id=9241
第12回 応用地質技術入門講座〜地表地質踏査技術の基礎〜
主催:応用地質学会
WEB学習:10月24日(金)-11月7日(金)の期間にオンデマンド教材を用いた自己学習
オンライン学習:11月13日(木)1-2時間程度のZoomによる学習
現地研修:11月19日(水)-21日(金)2泊3日(開催地:千葉県いすみ市「いすみ
文化会館」付近の露頭)
参加申込締切:10月17日(金)
定員:35名(定員に達し次第締切)
https://www.jseg.or.jp/committee/jseg_edu/
シンポジウム「信頼される科学、活躍できる研究者へ」
10月25日(土)10:30-15:00
会場:日本科学未来館7F 未来館ホール(参加無料)
主催:日本科学振興協会(JAAS)
https://peatix.com/event/4534624/
ブループラネット賞 受賞記念講演会
10月30日(木)(会場:東京大学伊藤国際学術研究センター)
11月1日(土)(会場:京都市国際交流会館)
・ロバート・B・ジャクソン 教授:大気を再生する ー希望・健康・そして人類のためにー
・ジェレミー・レゲット博士:ポスト真実の時代に気候と自然のリスクを伝えるー活動家としての歩みから学んだこと
参加費無料・要事前申込
https://www.af-info.or.jp
(後)〜発注者・若手技術者が知っておきたい〜
『地質調査実施要領』解説講習会
【大阪会場】新梅田研修センター(大阪市福島区福島)
11月12日(水)10:00-17:00
【東京会場】AP市ヶ谷(東京都千代田区五番町)
11月18日(火)10:00-17:00
主催:経済調査会・全国地質調査業協会連合会
受講料:12,100円(税込)/1名+テキスト代
定員120名程度(定員になり次第締切り)
https://seminar.zai-keicho.or.jp/
堆積学スクール 2025「鳥取砂丘を味わい尽くす」
11月22日(土)-24日(月,祝)
小雨決行
場所:鳥取砂丘,鳥取大学
講師:小玉芳敬 氏(鳥取大学)・田村 亨 氏(産総研)
定員:20 名(申し込み多数の場合は学生優先・会員優先)
参加申込締切:10 月 17日(金)(申込が定員に達し次第締切)
http://sediment.jp/04nennkai/2025/2025school.html
(協)第41回ゼオライト研究発表会
11?27?(?)-28?(?)
会場:富?国際会議場
https://jza-online.org/events
(協)Techno-Ocean 2025
11月27日(木)-29日(土)
会場:神戸国際展示場2号館ほか(神戸市中央区)
https://to2025.techno-ocean.com/
(後)三浦半島活断層調査会創立30周年記念 一般公開講座
宅地開発で隠れた衣笠断層帯を歩く
12月6日(土)(小雨決行)
参加申込締切:11月30日
https://geosociety.jp/outline/content0255.html#12
その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.
https://geosociety.jp/outline/content0255.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】公募情報・各賞助成情報等
──────────────────────────────────
・原子力規制委員会行政職員(技術系・事務系)(研究職)公募(10/31)
・東北大学大学院理学研究科地学専攻助教公募(12/19)
・JAMSTEC海域地震火山部門地震津波予測研究開発センター観測システム開発
研究グループPD研究員公募(11/18)
・京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻地質学鉱物学分野教授公募(12/1)
・2026年度東京大学地震研究所共同利用(10/31)
・第46回(2025年度)猿橋賞
・第67回藤原賞受賞候補者推薦(12/15)(学会締切12/1)
その他,公募,助成等の情報は,
http://geosociety.jp/outline/content0016.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.
geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日
までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.
コンテンツ
このサイトに関して
日本地質学会 公式サイトについて
当サイトの運営について
当サイトは、すべて日本地質学会事務局が運営しています。
当サイトの配慮事項
サイト構造を可能な限り簡易的なものとし、閲覧者の操作しやすく読みやすいサイトを目指しています。
ほとんどのページにおいて「パンくずリスト」を表示しており、どのページにいるのか把握できるようにしています。
極力少ないクリック数で目的のページへ到達できるようにしています。
膨大な項目及びページ数における対策としてメニュー欄にAJAX機能を盛り込んでいます。
文字サイズは読みやすい程度に大きくしており、背景色と充分なコントラストをつけ、読みやすくしています。
文字サイズを変更できるように変更ボタンを設置しています。
点滅したり移動したりする文字や画像は使用しておりません。
SSLを導入してセキュアなサイトとして構築しており、皆さまからお寄せいただく情報を暗号化し保護します。
その他、極力テーブルレスなサイトとして構成されており、表示速度の向上を促しています。
推奨ブラウザ
Internet Explorer5.5以降
Mozilla Firefox 2.0以降
safari 2.0以降
OPERA 9.0以降
NETSCAPE 7.0以降
上記に該当しないブラウザをご使用の閲覧者さまにおかれましては、最新ブラウザなどへアップデートをお勧めいたします。
Internet Explorer
Mozilla Firefox
safari
OPERA
NETSCAPE
個人情報の扱い
個人情報の取扱い
個人情報とは
特定個人を識別することが可能な情報のことさし、その情報があれば誰のことか分かってしまう一切の情報を意味します。
日本地質学会では、サイトから会員の会員情報及び「お問い合せ」や「原稿投稿」などから氏名及びメールアドレスなどの個人情報を得ておりますが、下記のプライバシーポリシーにおいて厳重に管理しておりますので、ご安心ください。
またお電話などから得られた情報も同様に、外部へ漏洩することなきよう努めており、万全の体制を整えております。
当サイトの個人情報の取扱いに関して
日本地質学会では、当サイトから得られた個人情報を総務省及び内閣府の定めた個人情報保護法に則り、厳重に管理いたします。
当サイトから得られた個人情報は、法的な事由がない限り第三者への引渡しは一切いたしません。プライバシーは厳守されます。
情報を取り扱う端末に関して
情報を取り扱うコンピューターには、アンチウィルスソフト及びファイヤーウォールを実装しております。回線におけるモデムやルーターにおいてもファイヤーウォールを標準装備されており、端末からの情報漏洩をガードしています。
Winnyのようなファイル共有タイプのソフトは一切使用しておりません。
端末を操作するにあたり日本地質学会事務局のスタッフ以外は操作をいたしません。
必要な時以外はネットを切り離しており、常時接続はいたしておりません。
リンク
リンク
学協会-国内
学協会(海外)
大学(国内・海外)
その他
官公庁・法人
博物館
賛助会員
Q&A
Q&A
ログインができない
対策:Windows版InternetExplorer6以上の場合
1.InternetExplorerメニューバーから「ツール」→「インターネットオプション」→「プライバシー」を開く
2.「詳細設定」をクリック→「Cookie処理を上書きする」をチェック。
3.「ファーストパーティのcookie」「サードパーティのcookie」を「受け入れる」設定をする。
または
1.メニューバーの「ツール」→「インターネットオプション」→「プライバシー」を開く
2.「webサイト」の編集→サイト毎のプライバシー操作画面を表示の上、webサイトのアドレスに
http://www.geosociety.jp/を許可(常に許可)にする。
InternetExplorerは設定後、再起動の必要がある場合があります。
サイトのアドレスは、ドメイン名の一部が表示される場合もあります。
対策:Windows版InternetExplorer6以上の場合 その2
いったん開いているWindows版InternetExplorerをすべて閉じます。
その後再度Windows版InternetExplorerを起動し、当サイトにてログインを試みてください。
対策:アンチウィルスソフトが原因
ときおりお使いのアンチウィルスソフトのセキュリティ関係によりログインできないことがあります。まずは無効にしてログインしてみてください。
無効にしてログインできた場合は、お使いのアンチウィルスソフトのセキュリティレベルを下げてください。
対策:Windows版InternetExplorer以外のブラウザを使用
Windows版InternetExplorer以外のブラウザにてログインすることで問題が解決する場合があります。
推奨ブラウザ:firefox2.0〜
Not Found
Not Found
The requested URL was not found on this server. We are sorry, old URLs were changed due to renewal at September 2007.
English page is here.
お探しのページはありませんでした。日本地質学会ホームページは2007年9月にリニューアルされました。もし旧アドレスでアクセスされたのでしたら、お手数ですがブックマークの変更をお願いいたします。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
もしかして下記のページをお探しではありませんでしたか?
北海道支部
東北支部
関東支部
中部支部
近畿支部
四国支部
西日本支部
岩石部会
第四紀地質部会
構造地質部会
堆積地質部会
ジオパーク
サイトマップ
トップページ
岡山大会
岡山大会TOP
日本地質学会第116年学術大会(岡山)
ー桃太郎と学ぶ地質学ー
大会ポスター
クリックすとpdfファイルをダウンロード出来ます。
岡山大会は盛会のうちに無事終了致しました。
来年は、富山大会でお会いしましょう。
日本地質学会第117年学術大会(富山大会)
会場:富山大学ほか
日程:2010年9月18日(土)〜20日(月・祝)
日程:2009年9月4日(金)〜6日(日)
会場:岡山理科大学25号館ほか
共催 日本地球化学会・岡山理科大学オープンリサーチセンター
後援 岡山理科大学・岡山県教育委員会・岡山市教育委員会
What's New 新着情報!
2009.08.31 新型インフルエンザ等の対応について
2009.08.31 追加募集します:岡山大会見学旅行
2009.08.25 学術大会関連情報のプレスリリースを行いました。
2009.07.27 新企画!会期中に見学旅行コース紹介を開催します。
2009.07.27 9月4日(初日)は、大会専用直通バス運行します。
2009.07.21 全体スケジュールが確定いたしました
2009.07.21 難問に挑戦!大会ポスター岩石名・地層名当てクイズ
2009.07.02 講演要旨集広告協賛の募集:締切延長いたしました。
2009.06.25 小さなEarthscientistのつどい発表募集締切延長いたします
2009.06.22 講演申込締切(web画面)を24時間延長いたします!
2009.06.19 岡山大会に関連したプレス発表を希望される方へ
2009.06.01 理科教員向け見学旅行の情報をUPしました
2009.06.01 一部シンポジウムは英語での発表・議論を推奨いたします
2009.04.28 岡山大会事前参加登録・講演申込受付開始
2009.04.15 2009年岡山大会開催のお知らせ
講演要旨追加・見学旅行案内書予約頒布
■参加登録フォームはこちらから■
講演要旨集のみの予約頒布について
<申込締切 WEB :8月17日(月)18:00,FAX(郵送):8月10日(月)必着(株)日本旅行扱い>
大会参加費には講演要旨集の代金が含まれていますので,大会に参加される場合は別途購入の必要はありません(ただし,準会員・名誉会員・50年会員・非会員学部学生の参加費には,講演要旨集は含まれません.ご希望の方は,別途ご購入下さい).大会に参加されない方ならびに参加する方が複数の講演要旨集を購入される場合の予約頒布です.申込は,「各種申込とお支払いについて」を参照し,申し込んで下さい.要旨集の受け取り方法には,(1)大会後に送付,(2)会場で受取り,があります.(1)の場合は,別途送料が必要です.(2)の場合は,大会受付にて確認書の提示が必要となりますので,必ずご持参下さい.残部があれば大会当日あるいは大会後にも頒布します.売り切れの場合はご容赦下さい.
事前予約(/冊)
当日販売(/冊)
会員
3,000円
4,000円
非会員
4,000円
5,500円
*送付の場合は以下の送料を付加して下さい.
送料:1冊 500円,2冊 600円,3冊 800円,4冊 1,000円,5冊 1,200円
見学旅行案内書の予約頒布
<申込締切 WEB :8月17日(月)18:00,FAX(郵送):8月10日(月)必着(株)日本旅行扱い>
申込は,「各種申込とお支払いについて」を参照し,申し込んで下さい.なお,見学旅行案内書は,地質学雑誌の補遺版(CD)として,12月号刊行時に会員配布されます.案内書の受け取り方法には,(1)大会後に送付,(2)会場で受取り,があります.(1)の場合は,別途送料が必要です.(2)の場合は,大会受付にて確認書の提示が必要となりますので,必ずご持参下さい.見学旅行参加者はできるだけ会期中に会場の受付にて受取って下さい.
残部があれば,大会当日あるいは大会後にも頒布します.売り切れの場合はご容赦下さい.
事前予約(/冊)
会員
2,800円
非会員
2,800円
*送付の場合は以下の送料を付加して下さい.
送料:1冊 500円,2冊 600円,3冊 800円,4冊 1,000円,5冊 1,200円
ランチョン・夜間小集会
ランチョン申込
<申込締切 6月23日(火)必着,行事委員会扱い>
9月5日(土),6日(日)にランチョンの開催を希望する方は,
(1)集会の名称,
(2)世話人氏名,
(3)集会内容等,を明記して(e-mailも可)行事委員会(東京)宛に申し込んで下さい.申込締切は6月23日(火)です.
なお,世話人の方は,終了後集会の内容をニュース誌の大会記事用原稿としてご投稿下さい(800字以内,原稿締切:9月末).
夜間小集会の申込
<申込締切 6月23日(火)必着,行事委員会扱い>
9月5日(土)は18:00〜20:00,6日(日)は17:30〜19:00(予定)です.夜間小集会の開催を希望する方は,
(1)集会の名称,
(2)世話人氏名,
(3)集会内容(50字以内),
(4)参加予定人数,
(5)液晶プロジェクターの要・不要,
(6)その他特記すべきこと,を明記して(e-mailも可),行事委員会(東京)宛に申し込んで下さい.申込締切は6月23日(火)です.
なお,世話人の方は,終了後集会の内容をニュース誌の大会記事用原稿としてご投稿下さい(800字以内,原稿締切:9月末).
懇親会・同窓会・お弁当
懇親会
<申込締切 オンライン :8月17日(月)18:00,FAX(郵送):8月10日(月)必着(株)日本旅行扱い>
日時:9月4日(金)表彰式・記念講演会終了後,18:00頃〜19:30
会場:岡山理科大学食堂
会費は正会員5,000円,名誉会員・院生割引会費適用正会員・準会員および会員の家族は2,000円です.非会員の会費は正会員に準じます.準備の都合上,前金制の予約参加とします.たくさんの方々,特に院生・学生などの若手会員のご参加をお待ちしております.余裕があれば当日参加も可能ですが,予定数に達し次第〆切ります.当日会費は1,000円高くなります.
予約申込は,「12.各種申込とお支払いについて」を参照し,大会参加申込と合わせて8月17日(月)までにお申し込み下さい.当日は参加証を受付にご持参下さい.参加取り消しの場合でも会費の返却はいたしませんのでご了承下さい.
■事前参加登録はこちら(日本旅行のWEB画面)
お弁当予約販売
<申込締切 オンライン:8月17日(月)18:00,FAX(郵送):8月10日(月)必着(株)日本旅行扱い>
9月4日(金)〜9月6日(日)には昼食用の弁当販売をいたします(1個 800円,お茶付き).「12.各種申込とお支払いについて」を参照し,大会参加申込と合わせて,8月17日(月)までにお申し込み下さい.お弁当利用日より9日前〜前日までは50%,当日は100%の取消料がかかります.なお,9月4日(金),5日(土)は,大学食堂も営業しております.学内コンビニエンスストア(22号館1階:会場から徒歩3分)は毎日利用できます.大学周辺には飲食店等はありませんので,上記,お弁当か学内施設をご利用下さい.
■事前参加登録はこちら(日本旅行のWEB画面)
同窓会
<申込締切 7月24日(金)18:00 現地事務局扱い>
懇親会(9/4夜)終了後に各大学同窓会などを希望する方(各大学代表者)は,現地事務局<gsj2009@academicbrains.jp>までお問合せ下さい.希望者があれば会場を準備します.
新着情報
新着情報 2009岡山大会
2009.08.31更新 新型インフルエンザ等に対する対応について
日本地質学会は、新型インフルエンザ予防対策として、会場に手洗い用の消毒薬を用意します.マスクは各自でご用意願います.
なお、38度以上の発熱や呼吸器症状のある方、新型インフルエンザの感染者(疑似症患者を含む) 及び濃厚接触者は、会場への入場を自粛されるようお願いいたします.
会期中またはその後に、38度以上の発熱や呼吸器症状の出た方は、必ず事前に医療機関に電話連絡し、受診方法等について指示を受け、マスクを着用したうえで受診して
ください。新型インフルエンザを含む感染症法の対象となる疾病と診断された場合は、学会本部にもその旨、必ずご連絡をお願いいたします。
<会期中の連絡先> 日本地質学会第116年年会(岡山大会)現地事務局
TEL:0797-24-1333(会場内担当者に転送されます)
FAX:086-256-8480(理科大自然科学研究所気付)
e-mail:gsj2009@academicbrains.jp
<会期後の連絡先>日本地質学会事務局
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目8-15 井桁ビル6F
TEL 03-5823-1150,FAX 03-5823-1156
e-mail:main@geosociety.jp
2009.08.31更新 追加募集します!岡山大会見学旅行
日本地質学会第116年学術大会(岡山大会)の追加募集を行います。申込希望の方は、学会事務局<main@geosociety.jp>または電話:03-5823-1150 まで.
◯B班「四万十帯牟岐メランジェにみる沈み込み帯地震発生帯の変形と流体移動」(残7名分:定員になり次第締切ます)
日程:9月7日(月)〜8日(火)(1泊2日)
主な見学対象:メランジュ/整然層境界断層(シュードタキライトを産出)、メランジュ内部の変形、スラストシート境界断層(ウルトラカタクレーサイト・鉱物脈濃集帯・玄武岩の剪断帯など)
定員:20名 費用:25,000円(2日目の昼食込)
コース詳細は、こちらをご参照下さい
◯G班「成羽層群の炭層地すべり群」(残2名分:定員になり次第締切ます)
日程:9月7日(月)日帰り
主な見学対象:岡山県西部のトリアス系成羽層群分布域に発達する地すべり群,形状と構造,成羽層群の炭層を挟んだ岩相と特徴的な微小構造.成羽層群の基盤をなす石灰岩等との構造関係.古第三系"山砂利層"の層相.
定員:15名 費用:6000円(昼食込み)
コース詳細は、こちらをご参照下さい
2009.08.25更新 学術大会関連情報をプレスリリースいたしました。
日本地質学会から岡山大会のプレス発表(資料投げ込み)を 文部科学省記者会、岡山県大学記者クラブに対して行いました。多くの報道機関で取り上げていただくことを期待しています。
プレス発表の詳細はこちらから。
2009.07.27更新 緊急展示の申し込みについて
学会活動の一端を広く社会に紹介するとともに,ホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害報告や社会的に影響のある新技術紹介などの「緊急展示コーナー」を設けます.緊急展示(ポスタ—展示)を希望する方は,8月21日(金)までに以下の内容で下記の実行委員会にご連絡ください.
1)発表要旨PDF(詳しくはこちら) 2)緊急展示の必要性 3)発表代表者と連絡先 4)希望枚数(1枚:幅90×180cm) 5)展示に関わる要望(2〜5の様式は自由)
実行委員会は行事委員会と協議し,可否の判断を致します.希望にはできるだけ応えるようにしますが,展示方法等については実行委員会の指示に従ってください.
申込先 main@geosociety.jp
担当 鈴木茂之(岡山大会実行委員会)・上野将之(行事委員会)
2009.07.27更新 新企画!見学旅行コース紹介
日時:9月6日(日)14:00〜16:30
会場:講演会場44(25号館4F)
9/7からの岡山大会見学旅行各コースのダイジェストを案内者にご紹介頂きます.見学旅行に参加される方は事前の予習として,また参加されない方も,このダイジェストで全コースの巡検気分を味わってみてはいかがでしょうか.是非ご参集ください.なお,会期中,年会会場内に各コース紹介のポスターも掲示する予定です.こちらもあわせてご注目下さい.
2009.07.21更新 難問に挑戦!大会ポスター岩石名・地層名当てクイズ
大会ポスター(裏表紙参照)桃太郎の衣服などは地層や岩石写真をパッチ状に貼り付けたものです.以下のクイズに挑戦した方の正解者には大会ポスターを贈呈します.
問題 以下に記した衣服部分などの地層名・岩石名を当てて下さい.
・足:
・すね:
・袴:
・刀の柄:
・吉備団子の入れ物(袋):
方法
1 学会会場入り口の受付デスクに準備した解答用紙に記入する.
2 記入した解答用紙を受付デスクのクイズ担当者に提出する(5日と6日のランチタイム)
3 1つ以上正解した方にポスターを贈呈
大会ポスターは、ニュース誌7月号または岡山大会HPトップをご覧下さい。
2009.07.02更新 講演要旨集広告協賛の募集:締切延長いたします。
地質関係機関・関連企業のご活躍を広く地質学会員に広報いただくべく,大会開催にあわせ発行されます講演要旨集・見学旅行案内書において,広告協賛を募集致しております。要旨集印刷日程にあわせて,締切を延長いたしましたので是非ご検討ください。
最終締切:7月31日(金)
広告について、詳しくはこちらから。
2009.06.19更新 岡山大会に関連したプレス発表を希望される方へ
岡山大会での講演や行事について,8月下旬にプレス発表を行う予定です.
昨年の秋田大会でも多数のメディアに取り上げられ,会員の皆様の研究成果が多いに注目されました.岡山大会で発表される予定の案件で,学会からのプレス発表をご希望の方は,8月10日(月)までに学会事務局にご連絡下さい.全ての案件をプレス発表することはできませんが,社会への情報発信として特筆すべき成果は積極的に公表して行きたいと考えております.会員の皆様におかれましては,プレスリリース解禁日をお守りいただき,公平かつ効果的な情報発信にご協力下さい.不明な点は学会事務局までお問い合わせ下さい.
登録締切:8月10日(月) プレス発表(投げ込み):8月21日(金)
現地説明会(解禁日):8月28日(金)(予定)
連絡先:<journal@geosociety.jp>
(情報特任理事 倉本真一)
2009.06.01更新 理科教員見学旅行の情報をUPしました。
実施日:2009年9月5日(土)8:30集合
テーマ:岡山県南部の花崗岩類(万成石)と文化地質学
申込締切:申込者数が定員に達し次第,申込を終了させていただきます.
詳しくは、こちら。
2009.06.01更新 一部シンポジウムは英語での発表・議論を推奨します
・日本列島構造発達史(世話人:磯崎行雄・丸山茂徳)
・坂野昇平追悼シンポジウム(世話人:平島崇男・榎並正樹)
上記2件のシンボジウムについて、世話人からの希望により、外国人招待講演者が,自己以外の発表・議論に参加できるようにするため英語での発表・議論を推奨することとなりました。しかし講演申込開始後の変更となるため、日本語での発表を希望されておられた方に対しては個別に世話人がご相談させていただきますので、よろしくお願いいたします。
各シンポジウムの詳細は、コチラをご参照下さい。
2009.04.28更新 岡山大会事前参加登録・講演申込 受付開始
岡山大会のシンポジウム・一般発表の申込受付が開始されました。今年もJ-STAGE演題登録システムを利用いたします。
講演申込締切は、6月23日(火)です(郵送の場合は6/19)。早めのお申し込みをお願いいたします。
●講演申込ははこちらから。
●事前参加登録はこちらから。
2009.04.15更新 2009年岡山大会開催!!
2009年9月4日(金)〜6日(日)会場:岡山理科大学25号館ほか
2009年日本地質学会年会は,「桃太郎と学ぶ地質学」をキャッチフレーズに,岡山理科大学を中心に西日本支部の会員にご協力をいただき開催いたします.
講演申込TOP
岡山大会講演申込
演題・要旨締切:オンライン 6/23(火) 17時,郵送6/19(金) 必着
演題・要旨締切延長:オンライン 6/24(水) 17時
↓WEBからの講演申込はこちら↓
(修正・変更もこちらから)
▶講演申込要領・発表要領
▶シンポジウム一覧
▶定番セッション・トピックセッション
▶講演要旨原稿について
▶▶講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理,引用方法,校閲について
▶▶講演要旨の作成の注意点とPDFファイル作成の作り方
▶▶講演要旨オンライン投稿手順チェックシート
▶▶保証・同意書(2009岡山)
▶講演申込書 書式pdf(郵送で申し込む場合)
日程・プログラム
全体日程・プログラム
■全体日程表(クリックするとpdfがダウンロードできます)
■各講演プログラム(それぞれの日程をクリックするとpdf形式でご覧になれます)
9/4(金)
口頭
9/5(土)
口頭
9/6(日)
口頭
ポスター
ポスター
ポスター
注意:講演タイトルが一部講演要旨と異なる場合があります。その場合は講演要旨が優先されます。ご了承ください。
申込締切一覧
各種申込締切一覧
オンライン
FAX・郵送
講演申込
6/23(火)17:00
6/19(金)必着
詳細
講演要旨原稿提出
6/23(火)17:00
6/19(金)必着
詳細
オンライン
FAX・郵送
見学旅行
8/17(月)18:00
8/10(月)必着
詳細
宿泊・交通(日本旅行のサイトへ)
8/17(月)18:00
8/10(月)必着
詳細
大会参加(参加登録費)
8/17(月)18:00
8/10(月)必着
詳細
追加要旨・見学旅行案内書頒布
8/17(月)18:00
8/10(月)必着
詳細
懇親会・弁当
8/17(月)18:00
8/10(月)必着
詳細
保育室
8/14(金)
-------
詳細
生徒地学発表会
7/7(火)
-------
詳細
同窓会
7/24(金)
-------
詳細
ランチョン・夜間小集会
6/23(火)
-------
詳細
一次締切
最終締切
広告協賛
6/30(火)18:00
-------
詳細
企業展示の出展募集
6/30(火)18:00
7/24(金)18:00
詳細
書籍・販売
6/30(火)18:00
7/24(金)18:00
詳細
就職支援プログラム
8/1(土)
-------
詳細
会場・交通
会場・交通
一般発表,シンポジウム,表彰式・記念講演会,関連普及行事・生徒「地学研究」発表会
岡山理科大学25号館
(岡山市北区理大町1-1)
市民講演会(9/5)
さん太ホール
(岡山市北区柳町2-1-1)
地質情報展(9/3-9/6)
岡山市デジタルミュージアム(岡山駅西口に隣接)
なお,岡山理科大学の施設位置図及び大学までの公共交通機関は,こちらを参照して下さい.
岡山理科大学まで〜
<徒歩の場合>
JR津山線法界院駅から徒歩約25分.
※4日(金)のみ,法界院駅8:10着(岡山駅8:06発)の方には無料バスを運行します(一度に乗れない場合には複数回往復します).
<岡電バス利用の場合>
岡山駅西口バス乗場から岡山大学経由岡山理科大学正門行(約20分,190円).
※学会専用直行バスについて(9/4朝のみ)
4日(金)7:55〜8:45 は5分間隔でバスが出発しますが,附属高校の通学時間(7:55〜8:20)と重なり混雑が予想されます.そこで,4日(金)のみ,8:00発の学会専用直行バス (講演者優先,200円、会場までの直行便です)3台を運行します.
乗り場:JR岡山駅西口出て、ANAホテル前バス乗り場
なお岡電バス定期路線ではJR西日本のICOCA, PiTaPa, Harecaが使用できます(SUICA,TOICAには対応していません).
<乗用車利用の場合>
岡山ICから約10分
大学付近の教職員用駐車場を無料解放しますのでご利用下さい.利用時間は8時から20時です.20時以降はレバーが降りて出ることができません.翌日の利用時間帯に出すことができます.
表彰式・記念講演会
学会各賞表彰式・記念講演
日程:2009年9月4日(金)14:30-17:45
会場:岡山理科大学25号館 8階大ホール
プログラム
14:30-15:30 新名誉会員,50年会員顕彰式,各賞授与式
15:30-15:50 日本地質学会小澤儀明賞 受賞スピーチ
小宮 剛氏「いろいろやってみる—地球生命環境史の総合解読ー」
須藤 斎氏「忘れられていた珪藻化石ーキートケロス属休眠胞子化石ー」
15:50-16:00 日本地質学会柵山雅則賞 受賞スピーチ
水上知行氏「小さな石」
16:00-16:35 日本地質学会国際賞受賞記念講演
太田昌秀氏「私の北極・南極」
16:35-17:45 日本地質学会賞受賞記念講演
鳥海光弘氏「レオロジーと岩石学,そして地球内部ダイナミックス」
石渡 明氏「オフィオライトと東北アジアの地質学的研究」
保証・同意書(2009岡山)
<郵送での投稿の場合は、原稿に必ず添付して下さい>
■PDFファイルダウンロードはコチラから■
保証及び著作権譲渡等同意書
著作者(下記)は,日本地質学会によって発行される第116年学術大会「講演要旨」・「見学旅行案内書」に掲載する下記表題の原稿(以下「本原稿」という.)について,以下のとおり保証し,かつ著作権を譲渡等いたします.
第1 保証
著作者は,本原稿について,以下の各号記載の事項を保証し,確約します.
1) 本原稿が著作者自身の著作物であり,既にいずれかで出版公表されているものと同一ではないこと.
2) 本原稿が既存の出版公表物などに対する知的財産権のいかなる侵害も含まないこと.
3) 本原稿中に他から転載されているすべての図表について,転載許可を得ていること.
4) 本原稿中,他の論文等の引用がある場合には,当該引用が公正な慣行に合致し,目的上正当な範囲内であること.
5) 著作物には,日本地質学会の名誉を傷つけ,地質学雑誌の信用を毀損する盗用データ,捏造データ,著作物に関する利害を持つ者の合意に反するもの,その他学会の倫理綱領に反するものを含まないこと.
6) 本原稿が共同著作物である場合には,代表して本書に署名捺印する者が,すべての共著者から,本書に著名捺印することについて同意ないし必要な権利を得ていること.
7) 本原稿についての問い合わせ,苦情,紛争などが発生した場合,署名者はすべての責任を負うこと.
8) 本著作物を作成するに当たって行われた調査・研究行為が,適切な方法でなされたものであること.
第2 著作権譲渡等
著作者は,本原稿について,以下の各号記載に同意します.
1) 本原稿のすべての著作財産権(著作権法27条,同29条に定める権利を含む)及び2次著作物の創作・利用に係る権利を日本地質学会へ譲渡すること.
2) 本原稿について,日本地質学会ならびに日本地質学会から正当に権利を取得した第3者及び当該第3者から権利を承継した者に対し,著作人格権(公表権,氏名表示権,同一性保持権)を行使しないこと
3) 本原稿の下記の各利用形態に関する権利を日本地質学会が排他的に行使すること.
a) 複製,翻訳,翻案(出版,電子出版,翻訳出版,データベース化,ビデオグラム化,その他すべての記録メディアへの記録・掲載などを含む)
b) 展示・上映
c) 放送,有線放送,自動公衆送信(地上波,CATV放送衛星,通信衛星,インターネット,パソコン通信,その他あらゆる送信媒体及び将来開発されるすべての送信媒体による公衆送信を含む)
d) 頒布,譲渡,貸与
e) その他,本著作物に関する一切の利用(技術の進歩により将来生じうる利用形態を含む)
以上
日付 2009年 月 日
本原稿表題
著作者(代表者) 印
署名者が代表する共著者すべての氏名
【講演番号 O / P /S - 】
■PDFファイルダウンロードはコチラから■
地学教育・普及・関連行事
地学教育・普及・関連行事
■地質情報展2009おかやま−ワクワク・発見・瀬戸の大地−
■市民講演会「大地から考える地球環境 —地質と生物・農業の深い関係—」
■小さなEarth Scientistのつどい〜第7回小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜
■教員向け見学旅行:岡山県南部の花崗岩類(万成石)と文化地質学(9/5)
■特別講演会 地質学と医学の融合ー癌発生のメカニズムー(9/4)
■ジオパークワークショップ ジオパークによる地域活性化を目指して(9/5)
■一般向け岡山生まれた地球深部探査船「ちきゅう」の活躍(9/6)
地質情報展2009おかやま−ワクワク・発見・瀬戸の大地−
地質情報展2008あきた−発見・体験!地球からのおくりもの−会場風景
日程:9月5日(土)〜6日(日)10:00〜17:00(6日のみ16:00まで)(入場無料)
会場:岡山市デジタルミュージアム 4階
主催:産業技術総合研究所地質調査総合センター,日本地質学会
展示内容:地質調査総合センターが有する日本全国の各種地質情報の中から,特に岡山県に関する様々な研究成果を中心に,展示パネルや映像を使って紹介するとともに,小さなお子さんにも楽しく地学を学んでもらうために体験学習コーナーを用意しています.
詳しくは、http://www.gsj.jp/johoten_2009/index.html
問い合わせ先:産業技術総合研究所地質調査総合センター
吉田朋弘・兼子紗知 TEL:029-861-3754 e-mail:gm-kikaku@m.aist.go.jp
市民講演会「大地から考える地球環境 —地質と生物・農業の深い関係—」
クリックするとA4版チラシがダウンロード出来ます。
日時:9月5日(土)13:30〜16:30(入場無料)
会場:さん太ホール(岡山市柳町2-1-1,JR岡山駅から徒歩15分または,路線バス5分「山陽新聞社前」下車)
「地質と生き物と人々の生活—ヨーロッパそして岡山の風景—」波田善夫(岡山理科大学学長)
身近な岡山の植生や生き物の生態と,地質との関係を,ヨーロッパの例と比較しながら紹介する.地域の農産物やその土地名産の酒類をはぐくむ環境にも言及する.
「おいしいワインのできる畑の地球環境」武田 弘(東京大学名誉教授)
世界の有名なワイン産地のぶどうとその畑の地質・土質・土壌・地形・気候との関係を広い観点で見た結果から発して,地球環境や食の安全問題のとらえ方などに言及する.
座談会では,司会者も含め,地球環境問題や,農産物の安全問題などの最近の課題も含め,地質環境とその上ではぐくまれる植生・農産物,そしてそれに依存して生きる動物や人間との関連,文化,あるべき制度の問題などを大きな視点で論じる.
問い合わせ:岡山大会実行委員会普及・企画(市民講演会)担当:石垣
TEL: 086-224-4311, isgk@hayashibaramuseum.jp
ページトップに戻る
小さなEarth Scientistのつどい〜第7回 小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜
2008年秋田大会の発表会の様子
日本地質学会地学教育委員会では,地学普及行事の一環として,地学教育の普及と振興を図ることを目的として,学校における地学研究を紹介する「地学研究」発表会をおこなっています.岡山大会でも,小・中・高等学校の地学クラブの活動,および授業の中で児童・生徒が行った研究の発表を募集いたします.岡山県内,また中国・四国地方の学校,さらには全国の学校の参加をお待ちしています.会場は研究者も発表するポスター会場内に,特設コーナーを用意いたします.同時並行で研究者の発表も行われますので,児童・生徒同士のみならず,研究者との交流もできます.この会を通じて生徒,研究者,市民の交流が進み,地質学,地球科学への理解が深まって,未来を担う生徒たちの学習意欲への良い刺激と励みになることを願っております.
なお,参加証とともに,優秀な発表に対しては審査のうえ,「優秀賞」を授与いたします.
日時 2009年9月6日(日) 9:00〜15:30
場所 日本地質学会年会ポスター会場(岡山理科大学)
参加対象
・小,中,高校地学クラブならびに理科クラブ等の活動成果の発表
・小,中,高校の授業における研究成果の発表
・活動,研究内容は地学的なもの(地質や気象などの地球科学・環境科学,天文など)
申込締切 2009年7月7日(火), 7月17日(金)まで延長しました。下記,日本地質学会 地学教育委員会あてお申し込み下さい.
発表形式 ポスター発表(展示パネルは幅90cm×高さ180cm程度)
パネルのほかに標本等を展示される場合には,パネルの前に机を用意します.参加申込書にその旨を記載して下さい.その場合は展示パネルの下側が隠れる事をご了承下さい.発表者は決められた時間(および随時)パネルの前に待機し説明をしていただきます.なお,遠隔地および学校行事等のために児童・生徒が参加できない場合は,発表ポスターのみをお送りいただいても結構です.発表の具体的な準備については,申込後に各校あてご連絡いたします.
参加費無料(参加者・引率者とも),開催中の研究者の発表,講演も聴くことができます.
派遣依頼 参加者・引率者については学校長宛,日本地質学会より派遣依頼状を出します.
問い合わせ・申込先:参加申込は,別紙書式をFAXして下さい.e-mailでも結構です.
日本地質学会地学教育委員会(担当 三次)
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F
TEL:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156 e-mail:main@geosociety.jp
参加校は次の通りとなります(8月5日更新)
-----------------------------------------------------------------------
・福岡県立八幡高等学校 /1
堆積物中の二硫化鉄生成の物理化学的検討
・岡山県立林野高等学校 /1
磁気治療器を用いた花崗岩の分類—人形峠周辺の場合
・兵庫県立加古川東高等学校地学部・・・2件 /角閃石班6,竜山石班8
角閃石班・・・山陽帯加古川酸性マグマの累進的酸化〜角閃石の波状累帯構造を
指標として〜
竜山石班・・・マグマ分化末期の流体相の環境条件を推定する〜凝灰岩の加熱実
験から、その赤色化を指標にして〜
・早稲田大学高等学院理科部地学班・・・2件 /6
1.ハワイ島の火山のハザードマップについて
2.関東地方を中心とした段丘面の成因について その3
・岡山県立岡山朝日高等学校化学部 /2
岡山県産の砂鉄を利用したたたら製鉄の研究
・三重県伊勢市立五十鈴中学校 /1
三重県内の中央構造線未確定区域に関する研究
・岡山県岡山市立妹尾中学校 /1
鴨方で恐竜化石を発見できるのか
・岡山県立鴨方高等学校 /2
100円ショップでさがした化石(仮題)
・岡山県立倉敷天城高等学校 /2
岡山県高梁地域におけるスカルン鉱物に関する研究
・岡山県玉野市立日比中学校平成16年度1年生一同 /0
昭和南海地震の被害調査について
・香川県立三本松高等学校 /3
明神浜でのフィールドジオロジー入門
・静岡県立静岡中央高等学校/0
静岡市有度丘陵の有孔虫化石
・岡山理科大学附属高等学校/3
岡山県蒜山原のケイソウ土中のケイソウ化石と現生のケイソウとの比較観察ページトップに戻る
FAX申込書式はこちらかダウンロードして下さい。
■WORD形式
■PDF形式
第8回理科教員対象見学旅行
2008年教員向け見学旅行「地学教育の素材としての男鹿半島」より
恒例となりました理科教員対象見学旅行を,今年も大会中日に,下記の日程・内容で開催いたします.今年はアウトリーチ巡検として,理科教員以外の参加(児童・生徒や一般の方)を想定した半日コースにいたしました.多くの方のご参加をお待ちしております.なおこの行事へは,大会への参加申し込みをしなくても参加できますので,お気軽にお申し込みください.
日時:2009年9月5日(土)8:30集合
テーマ:岡山県南部の花崗岩類(万成石)と文化地質学
岡山県南部の花崗岩類は古(いにしえ)から石材(万成石)や磐座(いわくら)信仰の対象となってきました.この見学会では,地域の文化を考える上での地質学的情報の生かし方を考えるとともに,教材としての利用方法などについて議論したいと考えています.
コース:8:30岡山駅西口集合—県立児童会館ジオトレイル−万成石採石場−12:00岡山駅西口解散
案内者:能美洋介、鈴木寿志、竹下浩征、郷津知太郎、溝口昭子(万成石研究グループ)
定員:40名(児童・生徒を含む,大型バス使用)
費用:1,500円(別途,保険代がかかります)
【注意】児童・生徒の参加数が予測できないので,現在のところ参加者一律の金額としていますが,児童・生徒の参加がある場合は変更する可能性があります.詳細については申込者へ後日連絡いたします.
参加資格:地学に興味のある方ならどなたでも参加できます.なお児童・生徒のみの参加は認めません.
参加申込先:下記の専用アドレスまで電子メールでお申し込みください.
<excursion@geo15.gds.big.ous.ac.jp>
記載事項:申込者の氏名,年齢,所属,非常時連絡先(携帯電話など).児童・生徒が参加する場合は,参加人数と参加児童等の氏名・年齢もお知らせください.
申込締切:申込者数が定員に達し次第,申込を終了させていただきます.
その他:学術大会と同時開催される「地質情報展2009岡山」(9月5日・6日に一般公開,無料,於:岡山デジタルミュージアム)でも,この地域の花崗岩類について,地質学的説明に加えて,石材資源・観光資源の観点から展示が行われます.こちらも併せて,ご覧ください.
特別講演会「地質学と医学の融合 —癌発生のメカニズム−」
演者:中村栄三(岡山大学地球物質科学研究センター)
日時:9月4日(金)13:30〜14:30
会場:岡山理科大学25号館 8Fホール(入場無料)
*学術大会に参加されない方でも、どなたでもご参加いただけます。
日本地質学会学術大会116年の歴史の中で岡山地区開催は初めてです.タイムリーにも表層地質学を出発点に地球惑星科学研究を始めた岡山地区研究者が、癌発生メカニズムに関する新しいモデルを構築し論文を発表しました.本論文は体内での微量元素の濃縮過程とそれに伴う放射性元素による内部放射線被曝を明確に示す画期的なものです.世界が注目する研究内容であり,今後様々な方面で話題沸騰することが大いに期待される内容です.
最新の研究成果の紹介とともに,若い表層地質学研究者へのエンカレッジとなる講演を予定しています.
【発表論文題目】 Accumulation of radium in ferruginous protein bodies formed in lung tissue: association of resulting radiation hotspots with malignant mesothelioma and other malignancies. Proc. Jpn. Acad., Ser. B 85 (2009),229-239.
by Eizo NAKAMURA, Akio MAKISHIMA, Kyoko HAGINO and Kazunori OKABE
ジオパークワークショップ:ジオパークによる地域活性化をめざして—地域と地質学者の連携のあり方をさぐる-
日本地質学会ジオパーク支援委員会は,ジオパークによる地域活性化,Geoheritageの保全および地学の普及のために,地域の方々と地質学者がどのように連携して活動していけばよいかをさぐるために,ワークショップを開催します.本ワークショップでは,実際にジオパークの運営に携わる人と地質学会員が,各地の実践例の発表を元に,地域と地質学者の連携のあり方を議論します.発表者はジオパーク支援委員会が現在依頼中です.ジオパークに関心のある,行政担当者,地域の方,研究者などの皆様の参加を期待します.
日時:9月5日(土)13:00-17:30
場所:岡山市デジタルミュージアム4階主催:日本地質学会ジオパーク支援委員会
共催:日本ジオパークネットワーク
後援:産総研地質調査総合センター
プログラム等詳しくはこちらから、
http://www.geosociety.jp/geopark/content0019.html
お問い合わせ先:
日本地質学会ジオパーク支援委員会
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル
TEL:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156
e-mail: main@geosociety.jp
*なお、ご希望の地域には、9/5(月)10:00-12:00の日程で日本地質学会ジオパーク支援委員会によるジオパーク個別相談(要事前予約)を行いますので、上記までご連絡ください。
一般向け講演会 岡山で生まれた地球探査船「ちきゅう」の活躍
主催 海洋研究開発機構
共催 日本地質学会
日時:9月6日(日)14:00
会場:岡山理科大25号館5F講義室
岡山で誕生した地球深部探査船「ちきゅう」の南海トラフ地震発生帯の掘削の成果と,今後「ちきゅう」を用いた掘削が予定されている「プロジェクトIBM(伊豆ー小笠原ーマリアナ)」や「モホール」は何を目指しているのか.岡山市民の方々にご紹介したいと考えています.
内容:「ちきゅう」の概要,南海トラフ掘削成果速報,今後の計画のねらい,などを一般向け講演として行う.同会場の展示ブース(25号館1F)における展示内容(「ちきゅう」模型も展示予定)と連携した内容の講演を行う.
日本旅行への申込・支払方法について
日本旅行への各種申込とお支払方法について
■参加登録フォームはこちらから■
<申込締切 オンライン :8月17日(月)18:00,FAX/郵送:8月10日(月)必着(株)日本旅行扱い>
(1)申込方法
オンラインによる参加登録申込等を受付けます.申込は株式会社日本旅行岡山支店が窓口となります.大会参加登録ホームページ(HP)又はp**に掲載の大会申込用紙にてお申し込み下さい.参加登録・見学旅行・懇親会・講演要旨集追加注文・お弁当及び割引航空券・宿泊を同時に申込可能です.
(a) 大会登録専用HP(オンライン)による申込:申込フォームに必要事項を記入して送信.
(b) FAX(郵送)による申込:申込用紙に必要事項を記入の上,日本旅行 (086-223-2259)宛FAXにて送信.
郵送先:〒700-0023 岡山市駅前町2丁目1番7号 株式会社日本旅行 岡山支店 日本地質学会岡山大会 受付担当デスク
(a) 大会登録専用HP(オンライン)による申込の場合
1) 学会HPから「2009年日本地質学会年会参加・宿泊申込みHP」,へアクセスして下さい.
2) 画面左のメニュー「参加登録」をクリックして下さい.初めてのご利用の際には個人情報の登録が必要となります.
3) 個人情報の登録後,そのまま参加登録を行うことができます.また参加登録後,他の予約を行う場合は,「続けて同伴者等の登録を行う」をお選び頂けば続けて他の予約をすることができます.
4) 申込み完了後,「予約確認メール」が登録のメールアドレスへ配信されますので内容を必ずご確認下さい.
5) 「お支払い」画面⇒「請求書の表示」をクリックし,請求書をご発行いただいたのち,入金期日を確認の上、各金融機関よりお振込み下さい.また,各種クレジットカードもご利用頂けます.自動メール等で請求の連絡が配信されるわけではありませんので,ご注意下さい.
!注意! 請求書は申込画面より各自で発行・確認し,入金を行って下さい.
6) 振込期日後,お支払いの確認が取れている方へ参加証・予約確認証(兼引換券)等を順次発送致します.大会開催1週間前には参加者の皆様のお手元に届くようお送り致します.お支払いの確認が取れていない方へはご送付できませんので,皆様の振込期日厳守を何卒よろしくお願い致します.
(b) FAX(郵送)による申込の場合
1) FAX/郵送専用の「参加申込書」(ニュース誌4月号にも掲載)に必要事項を記入の上,株式会社日本旅行岡山支店までFAXまたは郵送にてお申込み下さい.恐縮ではございますが確実に行うため,書面またはインターネットにての受付とさせていただきますので,お電話によるお申し込み,変更などの受け付けはご遠慮下さい.また,郵送によるお申込みの際は,必ず「参加申込書」のコピーをお取りいただき保管下さい.
2) 申込受付後,日本旅行より「受付確認書」をe-mail又はFAXにてご連絡申し上げます.その際,「登録番号」が必ず記載されております.こちらの「登録番号」はその後の問合せ,変更,取消等に必要となりますので,恐れ入りますが失念されぬようお願い致します.
3) お支払いは,銀行振込・クレジットカード決済をお選び頂けます.申込後順次,参加者の皆様へ「予約内容確認・ご請求書」を送付致します.銀行振込ご希望の方は,請求書に記載されている振込口座へ指定期日までにお振込み下さい.クレジットカード決済希望の方は,登録申込の際必ずクレジット番号などの必要事項をご記入下さい.振込期日に合わせてご指定のクレジットカードに課金致します.カード会社よりお客様に送付される明細には学会名ではなく「株式会社日本旅行」と表示されます.
4) 入金期日後,お支払いの確認が取れている方へ参加証・予約確認証(兼引換券)等を順次発送致します.大会開催1週間前には参加者の皆様のお手元に届くようお送り致します.お支払いの確認が取れていない方へはご送付できませんので,皆様の振込期日厳守を何卒よろしくお願い致します.
(2)申込締切
大会登録専用HP(オンライン)による申込の場合:8月17日(月) 18:00
FAX/郵送による申込の場合:8月10日(月)必着
(3)取消に関わる返金
所定の取消料の他に返金振込料を差し引いた額を大会終了後お返し致します.クレジットカードにてお支払の場合は,ご利用頂いたカードへご返金となります.
(4)申込後の変更・取消
(a)大会登録専用HP(オンライン)でお申込みの場合:2009年日本地質学会年会参加・宿泊申込みホームページ画面左のメニュー「予約確認・変更」から予約の変更・取消が出来ます.変更・取消完了後,「確認メール」が登録のメールアドレスへ配信されますので内容を必ずご確認下さい.
(b) FAX・郵送で申込む場合:申込後に変更・取消が生じた場合は,日本旅行岡山支店受付担当デスク宛FAX又はe-mailにてご連絡下さい.その際申込受付時に案内される「登録番号」及び「大会名」「氏名」を必ず明記下さい.
参加登録費
参加登録
■参加登録フォームはこちらから■
<申込締切 オンライン 8/17(月)18:00,FAX/郵送 8/10(月)必着(株)日本旅行扱い>
当日会場受付での混雑緩和のため,事前に参加登録申込をお願いします.大会参加登録およびそれに伴う参加費は,全ての参加者(見学旅行のみの場合も)に必要な基本的なお申込です.ただし,会員が同伴する非会員の配偶者ならびに子供については必要ありません.申込は,「日本旅行への各種申込とお支払方法について」を参照し,申し込んで下さい.
参加登録費
講演要旨集付です.講演要旨集が不要の場合でも割引はありません.なお,準会員・名誉会員・50年会員・非会員学部学生の参加費には,講演要旨集は含まれません.ご希望の方は,別途ご購入下さい.
事前申込
当日払い
正会員・共催/協賛団体会員
7,500円
9,500円
要旨集付き
院生割引会費適用正会員
4,500円
6,500円
要旨集付き
準会員・名誉会員・50年会員・非会員学部学生
500円
500円
非会員(一般・院生)
12,000円
15,000円
要旨集付き
*なお,大会に参加できなかった場合は,大会後に講演要旨集をお送りします.参加登録費用の返却はいたしませんのでご了承下さい.
*共催・協賛団体に会員として所属する方の参加登録費は正会員と同額になります.
見学旅行
見学旅行
事前参加登録はこちら(日本旅行Web画面)
新企画!会期中に見学旅行コース紹介を開催します。
コース詳細(各コース名をクッリクすると詳細がご覧いただけます)
A:瀬戸内火山岩(9/7日帰り)
F:風化花崗岩の構造(9/7-8)
B:牟岐メランジュ(9/7-8)
G:成羽層群地すべり(9/7日帰り)
C:三波川変成帯のテクトニクス(9/7-8)
H:舞鶴・超丹波帯(9/7日帰り)
D:大山・大根島(9/7-8)
I:山砂利層と中新統(9/7日帰り)
E:秋吉石灰岩(9/7-8)
「第8回理科教員対象見学旅行」についてはこちらから
ページTOPに戻る
A:小豆島の瀬戸内火山岩類:水中火山活動とサヌキトイド
見学コース:
9/7 07:45岡山駅西口出発→岡山港→土庄→寒霞渓→坂手→三都半島→皇踏山→土庄→岡山港→18:00岡山駅解散.
主な見学対象:
瀬戸内火山岩類の水中火砕岩(流紋岩〜安山岩). 特異なテクトニックセッティングで形成された高Mg安山岩を含むサヌキトイドの産状.
日程:9月7日(月)日帰り
定員:20名
案内者:巽好幸*・谷健一郎・川畑博(JAMSTEC)
費用:7000円
地形図:小江・寒霞渓・土庄・草壁・五剣山(1/2.5万)
備考:バス使用.行程は状況で変更することがあります.昼食はご持参ください.シンポジウム「高Mg安山岩とアダカイト:その起源,テクトニクス,大陸地殻形成における役割」関連企画
ページTOPに戻る
B:四万十帯牟岐メランジュにみる沈み込み帯地震発生帯の変形と流体移動
見学コース:
9/7 08:00岡山駅西口集合→牟岐メランジュ上部セクション→日和佐町(泊)
9/8 09:00宿出発→牟岐メランジュ下部セクション→17:30徳島駅・18:00徳島空港
主な見学対象:
メランジュ/整然層境界断層(シュードタキライトを産出)、メランジュ内部の変形(boudin, web structure, duplexなど)、スラストシート境界断層(ウルトラカタクレーサイト・鉱物脈濃集帯・玄武岩の剪断帯など)
日程:9月7日(月)〜8日(火)(1泊2日)
定員:20名
案内者: 山口飛鳥*(高知大学海洋コア総合研究センター)・柴田伊廣(神奈川県立生命の星・地球博物館)・氏家恒太郎(IFREE/ JAMSTEC)・木村学(東京大学)
費用:25000円(2日目の昼食込)
地形図:牟岐・山河内・日和佐(1/2.5万)
備考:中型バス利用.小雨決行.初日の昼食は各自ご持参ください.膝下程度の渡渉あり(長靴でも可).シンポジウム「「ちきゅう」による南海トラフ地震発生帯掘削計画ステージ1と2の成果(総括)」関連企画
ページTOPに戻る
C:三波川変成帯のテクトニクス
見学コース:
9/7 08:30岡山駅西口出発→吉野川流域川口→大歩危地域→四国中央市別子山泊
9/8 別子山林道および登山→岡山駅解散
主な見学対象:
大歩危地域の三波川変成岩/四万十帯境界露頭の観察.境界の上位の岩石の変成変形構造.別子山地域の林道および権現越のエクロジャイト岩体中の源岩特定および変成変形構造.
日程:9月7日(月)〜8日(火)(1泊2日)
定員:20名
案内者:丸山茂徳、青木一勝(東京工業大学)・岡本和明(埼玉大学)
費用:25000円
地形図:阿波川口・大歩危・新居浜・東予土居・別子銅山・弟地(1/2.5万)
備考:バス使用.行程状況で変更することがあります.「都城秋穂追悼シンポジウム」およびシンポジウム「日本列島構造発達史」関連企画
ページTOPに戻る
D:大山・大根島:山陰中央部の対照的な第四紀火山
見学コース:
9/7 08:00JR岡山駅発(バス)→米子自動車道溝口IC下車→鍵掛峠→大山金門,元谷,中宝珠→大根島(泊)
9/8 08:30宿出発→江島→大根島→14:00米子空港(ANA)→14:30JR米子駅経由→16:30岡山空港→17:30JR岡山駅
主な見学対象:
大山のデイサイト溶岩,岩脈,崩壊岩塊と堆積物,火砕流堆積物,土石流堆積物.大根島・江島の溶岩トンネル,玄武岩溶岩,スコリア丘,テュムラス,溶岩庭園,淡水レンズ湧き出し口
日程:9月7日(月)〜8日(火)(1泊2日)
定員:20名
案内者: 沢田順弘*(島根大学)・門脇和也(島根県自然観察指導員)
費用:14000円
地形図:伯耆大山・境港・揖屋(1/2.5万)
備考:21人乗りバス使用.初日の昼食は各自ご持参ください.初日夜に若手中心の研究発表と討論会を予定.その後,バーベキューパーティー.
ページTOPに戻る
E:秋吉石灰岩から読み取る石炭・ペルム紀の古環境変動
−美祢市(旧秋芳町)秋吉台科学博物館創立50周年記念巡検−
見学コース:
9/7 10:00JR新山口駅出発→美祢市鳶の巣→長者が森>秋吉台上,冠山→地獄台頂上付近→長者が森→美祢市美東町(泊)
9/8 8:30美祢市美東町→秋吉台上,帰り水ドリーネ→美祢市秋吉台科学博物館→15:00JR新山口駅解散
主な見学対象:
秋吉石灰岩層群のサンゴ石灰岩,ウーライト,礁性堆積物,洞窟堆積物,マイクロコディウム,離水相,干潟相,堆積サイクルおよびコア観察
日程:9月7日(月)〜8日(火)(1泊2日)
定員:15名
案内者:佐野弘好(九州大学)*・耵山哲男(福岡大学)・長井孝一(琉球大学)・上野勝美(福岡大学)・中澤 努(産総研)・藤川将之(秋吉台科学博物館)
費用:20000円
地形図:秋吉台北部・秋吉台(2.5万分の1)
備考:JR新山口駅集合・解散.現地での移動はレンタカーを利用します. 1日目の昼食は各自でご用意ください.
ページTOPに戻る
F:香川県小豆島の花崗岩のラミネーションシーティングと小豆島石を訪ねて
見学コース:
9/7 08:30岡山駅→新岡山港→土庄港→小豆島町池田→橘(泊)
9/8 08:30橘→小豆島町岩ケ谷(大坂城石垣石切丁場跡)→小海(大坂城残石公園と現在の小豆島石の丁場)→16:00土庄港解散
主な見学対象:
土渕海峡(ギネス認定:世界一狭い海峡),花崗岩のラミネーションシーティング(割れ目の特徴,発達する岩としない岩,地形との関係,風化帯との関係,未風化核岩との関係,岩盤クリープ),キャップロック地形,昭和49年小豆島災害,未風化核岩を利用した江戸時代の採石と機械力による現在の小豆島石の採石
日程:9月7日(月)〜8日(火)(1泊2日)
定員:15名
案内者: 藤田勝代*(財団法人深田地質研究所)・横山俊治(高知大学)
費用:17000円
地形図:小江・寒霞渓・土庄・草壁(1/2.5万)
備考:初日の昼食は各自ご持参下さい. 2日目の昼食は各自購入の予定. 島内はジャンボタクシーとマイクロバス利用.解散場所の土庄港からは岡山・高松方面へのフェリー有. あるいは昼頃に途中下車で,福田港→姫路港への帰路希望も対応可.
ページTOPに戻る
G:成羽層群の炭層地すべり群−岩相と地史を反映したその構造特性
見学コース:
9/7 08:30岡山駅西口出発→岡山県高梁市川上町(名原→大賀→松原→仁賀→安成→地頭)→18:00岡山駅西口
主な見学対象:
岡山県西部のトリアス系成羽層群分布域に発達する地すべり群,形状と構造(代表的な名原地すべり,安成地すべりを中心に見学),成羽層群の炭層を挟んだ岩相と特徴的な微小構造.成羽層群の基盤をなす石灰岩等との構造関係.古第三系"山砂利層"の層相.
日程:9月7日(月)日帰り
定員:15名
案内者: 横田修一郎*(島根大学)・田中 元・山田琢哉(復建調査設計)
費用:6000円(昼食込み)
地形図:地頭(1/2.5万)
備考:・交通手段は小型バスまたはレンタカー(朝,JR岡山駅西口前出発,帰りはJR高梁駅,岡山空港経由,夕方JR岡山駅西口着)昼食(弁当)は案内者の方で手配する.
ページTOPに戻る
H:岡山県東部周辺の舞鶴帯と超丹波帯
見学コース:
9/7 08:30岡山駅西口出発→美咲町飯岡→美咲町王子〜美作市青野→美作市大原→美作市白水→佐用町西大畠→佐用町小日山→佐用町上月→16:30JR上郡駅解散→18:00岡山駅西口
主な見学対象:
舞鶴帯構成層(舞鶴層群上部層,福本層群),夜久野岩類(変斑れい岩,変花崗岩,”殿敷型角礫岩”),超丹波帯構成層(上月層,山崎層)
日程:9月7日(月)日帰り
定員:18名
案内者:竹村静夫*(兵庫教育大学)・菅森義晃(大阪市立大学)・鈴木茂之(岡山大学)
費用:6500円
地形図:柵原・林野・上月(1/2.5万)
備考:小型バス使用.昼食は各自でご用意下さい.
ページTOPに戻る
I:岡山市周辺の吉備高原に分布する古第三系”山砂利層”と中新統
見学コース:
9/7 08:30岡山駅西口出発→岡山市北部→吉備中央町賀陽→岡山市北部→18:00岡山駅解散
主な見学対象:
古第三系”山砂利層”(34〜35Maと27〜29Maの地層)の堆積相,凝灰岩,基底の不整合と中新統の堆積相,化石,”山砂利層”との不整合
日程:9月7日(月)日帰り
定員:22名
案内者:鈴木茂之*(岡山大学)・松原尚志(兵庫県立人と自然の博物館)・松浦浩久(産総研)・檀原 徹・岩野英樹(京都フィッション・トラック)
費用:6000円(昼食込み)
地形図:豪渓・金川・東山内(1/2.5万),岡山北部・高梁(1/5万)
備考:マイクロバス使用.17:00頃岡山空港経由で岡山駅解散
ページTOPに戻る
就職支援プログラム
就職支援プログラム
「日本地質学会岡山大会就職支援プログラム」参加企業募集
▶参加申込用紙(word) ▶参加申込用紙(PDF)
▶ 2008年秋田大会:就職支援プログラムの様子はこちらから。
来る9月4日から岡山理科大学において日本地質学会第116年学術大会を開催いたします。昨年に引き続き、表記「就職支援プログラム」を開催することになりました。本プログラムは、学会に参加される学生・院生および大学教官の会員、ならびに岡山理科大学・岡山大学の学生・院生・関係者らを対象に、本会賛助会員をはじめとする関連会社との相互の情報交換を行う場を提供しようというものです。
つきましては、ぜひご参加いただきますようご案内をいたします。
<開催・募集 要領>
日 程 2009年9月5日(土) 14:00-17:00
場 所 岡山理科大学 25号館1F
主 催 日本地質学会
内 容 主催者等 挨拶・紹介、参加各社による数分のプレゼンテーション、参加各社の個別説明会(パネル、配布資料等をご用意ください)
対 象 岡山大会に参加する学生・院生および大学教官等の会員・岡山理科大学・岡山大学の学生・院生および教官等
参加費 無料
参加申し込み 別紙「参加申込書」を日本地質学会宛に8月1日(必着)までにFAXでお送りください。スペースに限りがありますので、参加ご希望の場合はお早めにお申し込みください。詳細についてはお申し込み締め切り後にご連絡いたします。
問い合わせ・申込先
日本地質学会担当者
日本地質学会理事 向山 栄
事務局 橋辺菊恵
TEL 03-5823-1150 FAX 03-5823-1156
e-mail:main@geosociety.jp
▶参加申込用紙(word) ▶参加申込用紙(PDF)
問い合わせ
岡山大会問い合わせ先
■大会会期中の問い合わせ先
日本地質学会第116年年会(岡山大会)現地事務局
TEL:0797-24-1333(会場内担当者に転送されます)
FAX:086-256-8480(理科大自然科学研究所気付)
e-mail:gsj2009@academicbrains.jp
■日本地質学会行事委員会 / 地学教育委員会
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目8-15 井桁ビル6F
TEL 03-5823-1150,FAX 03-5823-1156
e-mail:main@geosociety.jp
■行事委員会■(2009.4.15現在)
委員長
斎藤 眞(担当理事)
委 員
吉川敏之(地域地質部会)
大坪 誠(構造地質部会)
岡田 誠(層序部会)
片山郁夫(岩石部会)
北村晃寿(古生物部会)
内山 高(第四紀地質部会)
小松原純子(堆積地質部会)
片山 肇(海洋地質部会)
上野将司(応用地質部会)
石塚吉浩(火山部会)
斎藤文紀(現行地質過程部会)
大久保 進(石油,石炭関係)
坂本正徳(情報地質部会)
中井 均(地学教育関係)
田村嘉之(環境地質部会)
岡田 誠(層序部会)
■日本地質学会第116年年会(岡山大会)現地事務局
(株式会社アカデミック・ブレインズ内)担当:田中
〒665-0022 兵庫県宝塚市野上3-14-5
TEL:0797-24-1333 FAX:0797-24-1334
e-mail: gsj2009@academicbrains.jp
■実行委員会組織■
委員長:板谷徹丸(TEL:086-256-9722, itaya@rins.ous.ac.jp)
事務局長:鈴木茂之(TEL:086-251-7882, zysuzuk@cc.okayama-u.ac.jp)
同補佐:加藤敬史(TEL:086-440-1152,tkato@sci.kusa.ac.jp)
総務:西戸裕嗣(TEL:086-256-9722, nishido@rins.ous.ac.jp)
会計:兵藤博信(TEL:086-256-9724,hhyodo@rins.ous.ac.jp)
見学旅行:鈴木茂之(TEL:086-251-7882, zysuzuk@cc.okayama-u.ac.jp),
辻森 樹(TEL:0858-43-3772,tatsukix@misasa.okayama-u.ac.jp)
渉外:能美洋介(TEL:086-256-9605, y_noumi@big.ous.ac.jp)
普及・企画(市民講演会):石垣 忍(TEL: 086-224-4311, isgk@hayashibaramuseum.jp),野瀬重人(TEL: 086-256-9662,nose@dap.ous.ac.jp),能美洋介(TEL:086-256-9605, y_noumi@big.ous.ac.jp)
会場・展示会場・機器・懇親会:兵藤博信(TEL:086-256-9724,hhyodo@rins.ous.ac.jp),現地事務局((株)アカデミック・ブレインズ(内)) 担当:田中(TEL:0797-24-1333, FAX:0797-24-1334, e-mail:gsj2009@academicbrains.jp)
保育室:兵藤博信(TEL:086-256-9724,info09@rins.ous.ac.jp),現地事務局((株)アカデミック・ブレインズ(内)) 担当:田中(TEL:0797-24-1333, FAX:0797-24-1334, e-mail:gsj2009@academicbrains.jp)
宿泊・交通:日本旅行(株)岡山支店 日本地質学会岡山大会 受付デスク(菅谷)
(TEL:086-225-9283,FAX:086-223-2031,e-mail:okayama_office@nta.co.jp)
実行委員会問合せ用メールアドレス info09@rins.ous.ac.jp
■株式会社日本旅行 岡山支店
日本地質学会岡山大会 受付担当デスク 担当 菅谷(すがや)
TEL 086-225-9283
FAX 086-223-2259
e-mail : okayama_office@nta.co.jp
営業時間:(月〜金) 9:30〜17:30
(営業時間終了以降のお申込・変更・取消は翌日扱いとなります)
変更・取消のご連絡はFAX又はe-mailにてご連絡下さい.
お電話でのご連絡はお受け致しかねますので,ご協力よろしくお願い致します.
広告掲載・企業展示・書籍販売等について
■企業展示出展募集
■書籍・販売ブース募集
■広告掲載募集(7/31締切延長)
企業・研究機関等関係団体による展示会の出展募集
<申込締切 7月24日(金),現地事務局扱い>
地質関係機関・関連企業のご活躍を広く地質学会員に紹介していただくため,会期中,企業展示会を開催致します.企業紹介・業務紹介・研究成果・新技術・特許などご自由に展示内容を構成いただけます.奮ってご出展のお申込をいただきますようお願い申し上げます.
【展示募集概要】
1, 開催期間:搬入設営日9月3日(木),開催日9月4日(金)〜6日(日),搬出撤収日9月6日(日)※予定
2,開催場所:岡山理科大25号館1F(ロビー)
3,募集小間数:小小間16,パネル小間20 ※複数小間のお申込も可能です.
4,小間仕様見本:
※仕様詳細・オプション料金等につきましては,「展示募集要項申込書」をダウンロードの上,ご確認下さい.
5,出展料金:小小間 50,000円(消費税別),パネル小間 20,000円(消費税別)
6,第1次募集締め切り日:6月30日(火) 最終募集締め切り日:7月24日(金)
【出展申込方法】
大会ホームページの「展示募集要項申込書」をダウンロードいただき,必要事項をご記入の上,下記申込先までe-mailへのPDFファイル添付,あるいはFAXにてお申込下さい.募集要項・申込書が別途必要な場合は,現地事務局までご連絡下さい.送付致します.
【お申込・お問合せ先】
〒665-0022 兵庫県宝塚市野上3-14-5 日本地質学会 第116年学術大会 現地事務局 (株式会社アカデミック・ブレインズ内)
TEL:0797-24-1333,FAX:0797-24-1334, e-mail: gsj2009@academicbrains.jp 担当:田中
※日本地質学会賛助会員は出展料金が無料となります.別途,現地事務局までご連絡下さい.
書籍・販売ブースご利用の募集
<申込締切 7月24日(金),現地事務局扱い>
地質学関連の書籍・その他物品の販売にご利用いただくべく会期中ブースを設置致します.奮ってご出展のお申込をいただきますようお願い申し上げます.※見本展示のみでのご利用も可能です.
【書籍・販売ブース出展概要】
1,設置期間:9月4日(金)〜9月6日(日)
2,設置場所:岡山理科大学25号館7F(受付横)
3,募集ブース数:12ブース ※複数ブースのお申込も可能です.
4,ブース仕様見本
※仕様詳細・オプション料金等につきましては,「展示募集要項申込書」をダウンロードの上,ご確認下さい.
5,出展料金:10,000円(消費税別)
6,第1次募集締め切り日:6月30日(火) 最終締め切り日:7月24日(金)
【出展申込方法】
「展示募集要項申込書」をダウンロードいただき,必要事項をご記入の上,下記申込先までe-mailへのPDFファイル添付,あるいはFAXにてお申込下さい.募集要項・申込書が別途必要な場合は,現地事務局までご連絡下さい.送付致します.
【お申込・お問合せ先】
〒665-0022 兵庫県宝塚市野上3-14-5 日本地質学会 第116年学術大会 現地事務局
(株式会社アカデミック・ブレインズ内)
TEL:0797-24-1333,FAX:0797-24-1334, e-mail:gsj2009@academicbrains.jp 担当:田中
講演要旨集・見学旅行案内書,広告協賛の募集
<申込締切 6月30日(火),現地事務局扱い>
<申込締切延長 7月31日(金),現地事務局扱い>
地質関係機関・関連企業のご活躍を広く地質学会員に広報いただくべく,大会開催にあわせ発行されます講演要旨集・見学旅行案内書において,広告協賛を募集致します.企業紹介・業務紹介・研究成果・新技術・特許などの広報活動のご一環として,奮ってお申込をいただきますようお願い申し上げます.
【広告協賛料金】※詳細は「広告協賛募集要項申込書」をダウンロードの上,ご確認下さい.
講演要旨集:1頁 40,000円 1/2頁 20,000円 1/4頁 10,000円(すべて消費税別)
見学旅行案内書:1頁 20,000円 1/2頁 10,000円 1/4頁 5,000円(すべて消費税別)
※共に完全版下,データまたフィルムでの入稿をお願い致します.
【出稿申込方法】
大会ホームページの「広告協賛募集要項申込書」をダウンロードいただき必要事項をご記入の上,下記申込先までe-mailへのPDF添付,あるいはFAXにてお申込下さい.
【お申込・お問合せ先】
〒665-0022 兵庫県宝塚市野上3-14-5 日本地質学会 第116年学術大会 現地事務局
(株式会社アカデミック・ブレインズ内)
TEL:0797-24-1333,FAX:0797-24-1334, e-mail: gsj2009@academicbrains.jp 担当:田中
保育室
一時保育のご案内
<利用申込締切 8月14日(金)現地事務局扱い>
9月4日から6日の学会開催期間中,6ヶ月以上12歳までのお子様同伴の参加者を対象に利用可能な保育ルームを設定しております.
施設名 ドレミの街・ポストメイト保育園 (社)全国ベビシッター協会正会員
岡山市駅前町1-8-5 Tel 086-234-4115 Fax 086-234-4116
URL http://www.postmate.co.jp/sisetuannai.html
利用可能時間 8:15-18:00
利用料・利用方法等 詳細は http://www.rins.ous.ac.jp/gsj09/nursery.htm (申込の前に事前に必ず確認して下さい!)
アクセス】JR岡山駅東口より150m (徒歩3分) ドレミの街ビル 7階
利用問合せ・申込 一時保育のご利用申込は現地事務局までお願いいたします.なお受入準備の都合等もございますので,8月14日(金)までにお申込下さい.利用方法・利用規程等をご覧の上,Fax又は郵送にて利用同意書/申込書にて提出して下さい.
〒665-0022 兵庫県宝塚市野上3-14-5 日本地質学会 第116年学術大会 現地事務局
(株式会社アカデミック・ブレインズ内)
TEL:0797-24-1333,FAX:0797-24-1334, e-mail: gsj2009@academicbrains.jp 担当:田中
申込要領・発表要領
定番/トピックセッション・講演の申込要領・発表要領
注:シンポジウムに関しては、シンポジウムのページを参照して下さい。
演題・要旨締切:オンライン 6/23(火) 17時,郵送6/19(金) 必着
演題・要旨締切延長:オンライン 6/24(水) 17時
↓WEBからの講演申込はこちら↓
■定番セッション一覧はこちら
■トピックセッション一覧はこちら
募集要領
9月4日〜6日の3日間での一般発表を募集します.下記の要領にて口頭,ポスター発表を募集します.できる限りオンラインでの申込にご協力下さい.やむを得ず郵送で申し込む場合は所定の申込書(ニュース誌4月号掲載)に必要事項を記入の上,返信用(自分宛)の官製ハガキ,保証書・同意書,講演要旨とともに6月19日(金)必着で行事委員会宛にお送り下さい.プログラムの編成が終わり次第,発表セッションや発表日時などをe-mailで通知します(郵送の場合は返信ハガキ).なお,発表セッションや会場・時間などのプログラム編成につきましては,各セッションの世話人の協力を得て,行事委員会が決定します.
(1)セッションについて
本年会は,9月4日(金)〜6日(日)の3日間で一般発表を行います.専門部会の提案などにより22件の定番的セッションと,4件のトピックセッションを設けました
(2)講演に関する条件
日本地質学会の会員は,口頭発表かポスター発表かのいずれかの方法で,1人1題に限り講演を行うことができます.共同発表の場合は上記の条件を講演者(=筆頭発表者)に適用します.非会員は筆頭発表者になれませんので,必ず6月19日(金)までに入会手続きを行って下さい.入会申込書が届いていない場合は,講演申込は受理されません.入会手続きはこちら。
(3)招待講演について
昨年同様,トピックセッションにおいても,世話人は会員・非会員を問わずに招待講演を依頼することができます.招待講演は1セッションにつき,半日あたり1講演に限ります.招待講演についても申込期日までに一般発表と同様にお申し込み下さい(世話人が取りまとめでオンライン入力をすることは可能です).定番セッションでは招待講演の設定はありません.なお,非会員の招待講演者に限り参加登録費は免除となります.
(4)講演申込上の注意
1)オンライン申込はJ-STAGE演題登録システムにアクセスし,オンライン入力のフォームに従って入力して下さい.
2)講演方法については,「口頭」「ポスターセッション」,「どちらでもよい」のいずれかを選択して下さい.ただし,申込締切後の変更はできません.
3)発表題目,発表者氏名について,必ず登録フォームと講演要旨の両方を一致させて下さい.
4)共同発表の場合は全員の姓名を完記して下さい.
5)発表を希望するセッションを第2希望まで選んで下さい.
6)コメント欄について:発表の対象とする地域の記入を要するセッションについてはこの欄に国名・県名等を入力して下さい.また,関係する一連の発表があるときは,その順番希望などもこの欄に入力して下さい.
7)口頭発表会場には液晶プロジェクターとWindowsパソコン(OS:Windows Vista, Office Standard 2007)を用意します.パワーポイントを使用する方は,試写室において正常に作動することを事前に確認して下さい.特に,会場に設置するものと異なるバージョンで作成されたファイルは,レイアウトが崩れる事例が報告されていますのでご注意願います.本年は会場の液晶プロジェクターにパソコンの切り替え器(ケーブル形状はD-SUB15ピンを予定)を用意します.Macパソコンをお使いになる方,ソフトの互換性からレイアウトが崩れる可能性のある方はご自分でパソコンをご用意ください.パワーポイントを使用しない方は世話人とご相談下さい.なお,昨年同様35mmスライドプロジェクターの使用はできません.
(5)講演要旨原稿の投稿について
例年と同様に講演要旨をAdobe社が策定したPortable Document Format(PDF)のファイルで電子投稿していただきます.一般講演およびシンポジウムの原稿はA4判1枚(フォーマット参照)で,印刷仕上がり0.5ページ分です.1ページに2件分ずつ印刷します.原稿はそのまま版下となり,70%程度に縮小して印刷されます.文字サイズ,字詰めおよび鮮明度には十分配慮し,PDFファイルを作成して下さい.やむを得ず郵送する場合は,オリジナルか,鮮明にコピーした現物を1枚だけ郵送(差し支えなければ折りたたみ)可)して下さい.FAXやe-mailでの原稿送付は受け付けません.
発表要領
(1)口頭発表
1)講演時間は1題あたり15分(持ち込みパソコンへの切り替え時間及び討論時間3分を含む)です.講演者は,討論など持ち時間を十分考慮し余裕を持って講演を行って下さい.なお,パソコンを持ち込む方は直前の講演のうちにセットしてください
2)各会場には,液晶プロジェクター,Windowsパソコンを各1台とスクリーン1幕を設置します.
(2)ポスター発表
1)1題について1日間掲示できます.各日とも発表者はコアタイム(開催日によって異なる)にその場に立会い,説明をするものとします.設置,撤去時間等については,プログラム(7月末公開予定)をご覧下さい.ボード面積は1題あたり,縦180cm,横90cmです.
2)発表番号・発表名・発表者名をポスターのタイトルとして明記して下さい.
3)掲示に必要な画鋲等は,発表者がご持参下さい.
4)ポスター会場では,コンピューターによる発表や演示等も許可しますが,使用する機器については発表者がご準備下さい.また,電源は確保できませんので,予備のバッテリーをご用意下さい.講演申込の際に機器使用の有無や小机の必要性をコメント欄に記入し,事前に世話人にご相談下さい.
5)運営細則第11条(6)項により,優れたポスター発表に対して「日本地質学会優秀ポスター賞」を授与いたします.具体的な事柄については,7月末ニュース誌に掲載しますのでご注目下さい.
(3)発表者の変更
あらかじめ連記されている共同発表者内での変更は認めますが,必ず事前に行事委員会へ連絡して下さい.この場合も筆頭講演者については上記【一般発表の募集】の(2)の条件が適用されます.
(4)口頭発表の座長の依頼について
セッションによっては各会場の座長を参会者にお願いすることになります.あらかじめ座長依頼を差し上げることになりますが,その際にはぜひともお引き受けいただきたく,ご協力をお願いします.
シンポジウム
シンポジウム
演題・要旨締切:オンライン 6/23(火) 17時,郵送6/19(金) 必着
演題・要旨締切延長:オンライン 6/24(水) 17時
↓WEBからの講演申込はこちら↓
講演申込はこちらから
(修正・変更もこちらから)
8件のシンポジウムを開催します.9月5日〜6日の2日間(いずれも午前),各日4件ずつ行いますが,講演を一般公募しないものがありますので,ご注意下さい(今回は2件で一般公募がありません).
シンポジウムの講演者には,一般講演の1人1件の制約は及びませんので,別途一般講演を申し込むことができます.また昨年同様,世話人は,会員・非会員を問わず招待講演を依頼することができます.なお,非会員の招待講演者に限り参加登録費は免除となります.
一般公募の採択・不採択は,世話人によって決定されます.講演要旨原稿は,一般発表と同じ要領ですので,コチラを参照して原稿の作成をお願いします.
やむを得ず郵送で講演要旨を送る場合は,一般発表の申込フォーム(ニュース誌4月号掲載)をご利用下さい.「シンポジウム」と書き添えた上,必要事項を記入し,保証書・同意書とともに6月19日(金)必着で行事委員会宛にお送り下さい.
(各タイトルをクリックすると、詳細をご覧いただけます)
1)「ちきゅう」による南海トラフ地震発生帯掘削計画ステージ1と2の成果(総括)(日本地球掘削科学コンソーシアム IODP部会 共催)
2)中国地方における新生界の諸問題:新たな地平をめざして
3)高Mg安山岩とアダカイト
4)日本列島構造発達史(岡山理科大学オープンリサーチセンター 共催)*英語での発表・議論を推奨
5)坂野昇平追悼シンポジウム(岡山理科大学オープンリサーチセンター 共催)*英語での発表・議論を推奨
6)都城秋穂追悼シンポジウム(岡山理科大学オープンリサーチセンター 共催)
7)3次元地質モデルの構築手法と利活用(日本情報地質学会 共催)
8)科学を文化にー学校教育・地学分野のこれからー(日本地学教育学会 共催)
1)「ちきゅう」による南海トラフ地震発生帯掘削計画ステージ1と2の成果(総括)(日本地球掘削科学コンソーシアム IODP部会 共催)
Preliminary result of Nankai trough seismogenic zone experiment stage 1 and 2(Summary)
木下正高(JAMSTEC)・芦 寿一郎(東京大)・木村 学(東京大)・斉藤実篤(JAMSTEC)・山口飛鳥(JAMSTEC)・氏家恒太郎(JAMSTEC)・坂口有人*(JAMSTEC;arito@jamstec.go.jp)
統合国際深海掘削(IODP)のもと,地球深部探査船「ちきゅう」による南海トラフ地震発生帯掘削計画が熊野灘沖において2007-2008年にステージ1が実施され,ステージ2も2009年春から夏にかけて計画されている.1944年東南海地震想定破壊域に発達する分岐断層,付加体先端部のプレート境界断層,沈み込みインプット,熊野海盆における掘削同時検層およびコア採取を通じて付加体-地震発生帯システムの理解を目指す.シンポジウムでは航海の報告と最新の研究成果の紹介と議論を行っていく.特にステージ2終了直後という絶好のタイミングで開催されるので,船上の熱気と勢いをそのまま持ち込みたい.なお本シンポジウムに関連して,地震発生深度で形成された断層岩(ウルトラカタクレーサイト,シュードタキライト)が露出する四万十付加体牟岐メランジュでの見学旅行案内も実施する.(一般公募なし・関連の巡検コースあり)
2)中国地方における新生界の諸問題:新たな地平をめざして
The Cenozoic in the Chugoku District, SW Japan : Geology, geochronology,paleontology and tectonics
沢田順弘*(島根大;sawada@riko.shimane-u.ac.jp)・酒井哲弥(島根大)・入月俊明(島根大)・尾崎正紀(産総研)・松原尚志(兵庫県立人と自然の博)
中国地方の堆積岩や火山岩類を中心とした第三系は瀬戸内海沿岸域,中国山地脊梁地域,および山陰海岸沿いに分布する.これらを対象とした研究の中で,この20数年間に既存の考えを覆す新知見が幾つか報告された.その中でも重要なものは年代学的な問題である.例えば,瀬戸内海沿岸域における神戸層群に代表されるもので,1990年代以前には中新統とされていた地層の多くが始新〜漸新統に変更されたことや,山陰地方における下部中新統の標準層序とされてきた「波多層」とその相当層が中部中新統とされたことである.1983年,Otofuji and Matsudaによる島根県下における第三系を対象としたFT年代と古地磁気学からの西南日本の回転運動と日本海の拡大の提案は画期的なものであった.それから25年以上経過し,時代は地質学を基礎とした新たなテクトニクスの提案を要求している.本シンポジウムでは中国地方における第三系の年代学,古生物学,堆積学,火山学,古地磁気学からの成果を総合化し,テクトニクス的背景を議論する.(一般公募あり)
3)高Mg安山岩とアダカイト
Origin of high Mg andesites and adakites
巽 好幸*(JAMSTEC;tsumi@jamstec.go.jp)・田村芳彦(JAMSTEC)
Mg安山岩,アダカイトマグマの発生には,通常の沈み込み帯に比べて高温のプレート・マントルウェッジの存在が必要である可能性が高く,このテクトニックな条件は,初期地球のそれと類似する.従って,これらのマグマの成因とその発生のテクトニックな背景を理解することは,大陸地殻の起源を探る上で重要な束縛条件を与えると考えられる.(一般公募あり・関連の巡検コースあり)
4)日本列島構造発達史 (岡山理科大学オープンリサーチセンター 共催)
Geotectonic subdivision and evolution of the Japanese Islands: A reappraisal
磯崎行雄*(東京大;isozaki@ea.c.u-tokyo.ac.jp)・丸山茂徳(東工大)
古太平洋の誕生に伴う大西洋型大陸縁の時代それに続く太平洋型大陸縁の時代についてそれぞれのテクトニクスに関する新知見と新たな解釈を中心にシンポジウムを企画いたします.(一般公募あり・関連の巡検コースあり・英語での発表・議論を推奨)
5)坂野昇平追悼シンポジウム (岡山理科大学オープンリサーチセンター 共催)
A special symposium to honor Shouhei Banno
平島崇男*(京都大;hirajima@kueps.kyoto-u.ac.jp)・榎並正樹(名古屋大)
坂野昇平氏は,変成岩岩石学,地質学,地球化学などの広い分野で,数々の革新的な研究成果を発表されました.彼が1960年代に開始された熱力学を岩石学に導入する試みは,多成分多相系の熱力学と固溶体の統計力学を融合させることにより,世界に先駆けての地質温度圧力計の提案として結実し,21世紀にも通用する近代岩石学の基礎となりました.また,共同研究者たちと1970年代前半に開始したX線プローブマイクロアナライザーを駆使した相律論岩石学の展開は,日本の三波川帯,神居古潭帯,領家帯,黒瀬川帯,青海蓮華帯やフランシスカン帯,中国蘇魯超高圧変成帯など世界各地の変成帯の温度圧力史の定量的記述を可能にし,これによりプレート収束域の地下深部物理化学過程を詳細に理解できるようになりました.これらの成果は,20世紀後半の地球科学の革命であったプレートテクトニクスの展開に重要な役割を果たしました.彼を追悼するシンポジウムを企画いたします.(一般公募あり,英語での発表・議論を推奨)
6)都城秋穂追悼シンポジウム (岡山理科大学オープンリサーチセンター 共催)
A special symposium to honor Akiho Miyashiro
丸山茂徳*(東工大;smaruyama@geo.titech.ac.jp)・磯崎行雄(東京大)
都城秋穂氏は日本の地域地質学に根ざし,そこから世界に輸出できる新しい概念を次々と生み出してきた巨人でした.アメリカに移られてからも,海洋底玄武岩の成因,熱水変成作用の特徴,中央海嶺の岩石学的構造など地球規模の問題へと研究対象を広げられ,どの分野にも新しい世界を切り開いて見せ,我々の理解を深めてくれました.彼を追悼するシンポジウムを企画いたします.(一般公募あり.関連の巡検コースあり)
7)3次元地質モデルの構築手法と利活用 (日本情報地質学会 共催)
Construction technique and usage of three dimensional geologic model
升本眞二(大阪市大)・木村克己*(産総研;k.kimura@aist.go.jp)・根本達也(大阪市大)・古宇田亮一(産総研)
地質情報を従来の地質図レベルから3次元的な数値モデルとして表現することは,地質情報の高精度化だけでなく,地震動特性や地下水流動,地すべりのリスク評価,各種地球科学・応用科学情報との重ね合わせにおいて不可欠な研究課題である.しかし,西欧諸国の3次元モデル化に対する精力的な取り組みに比べると,我が国でのそれは限定的といわざるを得ない.本シンポジウムでは,3次元地質モデル化の研究推進とその利活用の普及に寄与することを目指して,3次元モデルの構築手法と具体的な利活用の事例を中心に,最新の研究内容の発表と意見交換を行いたい.(一般公募なし.ただし関連テーマでの一般発表希望の場合は,「情報地質」セッションにてお願いする)
8)科学を文化にー学校教育・地学分野のこれからー (日本地学教育学会 共催)
Science for Public: Future of Earth Science Education
藤林紀枝*(新潟大;fujib@ed.niigata-u.ac.jp)・芝川明義(府立花園高)・三次徳二(大分大)・矢島道子(地質情報・活用機構)・七山 太(産総研)
小中学校の来年度入学者から実施される新学習指導要領下での理科の学習指導(高等学校は24年度入学者から実施)では,自然体験・科学的体験,科学技術教育,環境保全教育,言語活動が重視されるようになります.また,理科の授業時間数が大幅に増加して学習内容が充実されます.地学分野としての文系,理系両生徒に対する学問の動機付け,自然体験型の実習あるいはアナログ実験の方法,博物館等との連携,また履修指導はどうなるかなどについて議論したいと思います.また大学では,いわゆる「ゆとり教育」の世代の学生さんたちが教師になってから困らないよう手当てする必要があります.これらの課題について,履修指導,授業実践などの立場から話題提供していただき,討論する予定です.(一般公募あり)
定番セッション・トピックセッション
定番セッション・トピックセッション
演題・要旨締切:オンライン 6/23(火) 17時,郵送6/19(金) 必着
演題・要旨締切延長:オンライン 6/24(水) 17時
↓WEBからの講演申込はこちら↓
講演申込はこちらから
(修正・変更もこちらから)
・セッションテーマ,(提案部会名)(地域名等特記事項),世話人(*印責任者),趣旨の順に掲載.
・特に断りのないセッションは口頭とポスターの両方を募集します.
・提案部会に関わりなく,会員はいずれのセッションにも応募できます.ただし,応募は口頭かポスターのいずれか1件に限ります.
・「地域名必要」の記載があるセッションは,申込書に研究対象の地域名を記入してください.
・口頭発表会場には液晶プロジェクターとWindowsパソコンを用意します.昨年同様スライドプロジェクターの使用はできません.本年は会場の液晶プロジェクターにパソコンの切り替え器(ケーブル形状はD-SUB15ピンを予定)を用意します.Macパソコンをお使いになる方,ソフトの互換性からレイアウトが崩れる可能性のある方はご自分でパソコンをご用意ください.パワーポイントを使用しない方は世話人とご相談下さい.
トピックセッション:4件
1.希ガス年代測定—地質科学への貢献—(日本地球化学会 共催)
兵藤博信*(岡山理科大;hhyodo@rins.ous.ac.jp)・郷津知太郎(蒜山地質年代研)
放射壊変反応を利用した年代測定法を初めて提唱したのは100年前のラザフォードであった.ウランの壊変に伴うα粒子(He)がウラン鉱物に蓄積すると考えた.その手法は当時及びその後長く有効ではなかったが,最近,(U-Th)/He法として若い地質体に適用されつつある.希ガス用質量分析計の開発を待ってK-Ar(Ar-Ar)法,U-Kr(Kr-Kr)法,U-Xe(Xe-Xe)法,3H-3He法,39Ar法,81Kr法など希ガス同位体を用いた年代測定法が開発され地球惑星科学に適用されてきた.これらの手法がもっと有効に地質科学分野に貢献できるためにはどうすれば良いかを検討する機会を用いたいと考え,トピックセッションを企画する.
2.ジュラ系+(読み方:ジュラケイプラス)
松岡 篤*(新潟大;matsuoka@geo.sc.niigata-u.ac.jp)・堀 利栄(愛媛大)・小松俊文(熊本大)・近藤康生(高知大)・尾上哲治(鹿児島大)・石田直人(熊本大)
2002年の新潟大会プレシンポジウム以降,毎年開催しているトピックセッション「ジュラ系+」の成果を踏まえ,ジュラ系および隣接する地質系統の研究に関する到達点を共有するとともに,わが国がジュラ系研究の拠点となることを目指す.ジュラ系の各階のGSSPも次々に決定され,世界各地ではジュラ系の研究が活発におこなわれている.国際ジュラ系小委員会の執行部メンバーも一新され,2010年には中国で第8回国際ジュラ系会議が開催される.このような国際的な動きに対して,アジアから何が発信できるのかを議論したい.夜間小集会も開催予定.
3.「ちきゅう」による南海トラフ地震発生帯掘削計画ステージ1と2の成果
坂口有人*(JAMSTEC; arito@jamstec.go.jp)・斉藤実篤・氏家恒太郎・山口飛鳥
統合国際深海掘削(IODP)のもと,地球深部探査船「ちきゅう」による南海トラフ地震発生帯掘削計画が熊野灘沖において2007-2008年にステージ1が実施され,ステージ2も2009年春から夏にかけて計画されている.1944年東南海地震想定破壊域に発達する分岐断層,付加体先端部のプレート境界断層,沈み込みインプット,熊野海盆における掘削同時検層およびコア採取を通じて付加体−地震発生帯システムの理解を目指す.トピックセッションでは乗船研究者の最新の成果の紹介と議論を行っていく.特にステージ2終了直後という絶好のタイミングで開催されるので,船上の熱気と勢いをそのまま持ち込みたい.
4.IBM(活動的海洋性島弧〜背弧海盆)の発生と進化を探る
新井田清信*(北海道大;kiyo@mail.sci.hokudai.ac.jp)・田村芳彦(JAMSTEC)・石塚 治(産総研)
近年,活動的海洋性島弧の代表例になっている伊豆−小笠原−マリアナ弧(IBM)の前弧〜火山弧〜背弧海盆海域での調査が進展し,新しい地球科学データが急増している.これまで島弧の進化史や大陸地殻形成についての議論が活発に行われているが,ここでは,島弧マグマ活動とともに島弧〜背弧海盆の基盤リソスフェアの実像にも焦点をあてて,島弧の発生〜進化を探ってみる.
定番セッション:22件
5.地域地質・地域層序(地域地質部会・層序部会)(地域名必要)
吉川敏之(産総研;t-yoshikawa@aist.go.jp)・岡田 誠(茨城大)・斎藤 眞(産総研)
国内,海外問わず各地域に関係した地質や層序の発表を広く募集.地域的な年代,化学分析,リモセン,活構造,応用地質等の発表も歓迎.地質災害地の地質,惑星地質もここに含まれる.地域を軸にした討論を期待する.地質図や断面図のポスター発表を特に歓迎.
6.地域間層序対比と年代層序スケール(層序部会)(地域名不要)
里口保文(琵琶湖博物館;satoguti@lbm.go.jp)・岡田 誠(茨城大)
テフラ等の鍵層を用いて異なる地域間の層序対比に主体をおく研究や,鍵層そのものを主体とした研究,または複合的層序学等によるグローバルな年代層序スケールの構築に寄与するような研究についての講演を歓迎します.
7.海洋地質(海洋地質部会)(地域名必要)
片山 肇*(産総研;katayama-h@aist.go.jp)・徳山英一(東大海洋研)・芦 寿一郎(東大海洋研)・小原泰彦(海上保安庁)
海洋地質に関連する分野(海域の地質・テクトニクス・変動地形学・海域資源・堆積学・海洋学・古環境学・陸域地質での海洋環境変遷研究など)の研究発表を募集する.調査速報・アイデアの公表・海底地形地質・画像データなどのポスター発表も歓迎する.
8.砕屑物組成・組織と続成作用(堆積地質部会)
太田 亨*(早稲田大;tohta@toki.waseda.jp)・野田 篤*(産総研)
砕屑物を構成する個々の粒子の特性(形態や化学組成)から砕屑物(岩)の組織・組成を対象とし,砕屑物(岩)の形成・続成過程の復元,後背地や古環境,地質体の発達史を議論する.データ解析手法,現世砕屑物の組成,初期続成過程についての発表も歓迎する.
9.炭酸塩岩の起源と地球環境(堆積地質部会)(地域名必要)
山田 努*(東北大;yamada@dges.tohoku.ac.jp)・松田博貴(熊本大)
炭酸塩岩・炭酸塩堆積物の堆積作用,組織,構造,層序,岩相,生物相,地球化学,続成作用,ドロマイト化作用など,炭酸塩に関わる広範な研究発表を募集する.また,現世炭酸塩の堆積作用・発達様式,地球化学,生物・生態学的な視点からの研究発表も歓迎する.
10.堆積相と堆積システム・シーケンス(堆積地質部会)(地域名必要)
中条武司*(大阪市立自然史博物館;nakajo@mus-nh.city.osaka.jp)・片岡香子(新潟大)
各堆積環境における堆積相の形成過程と認定,各堆積相の分類・記載,その時空分布をもとにした堆積システムの認定や解釈などを扱う.また,堆積相解析を基礎にした堆積システム変遷の解析およびシーケンス層序学など,地層の形成過程のダイナミックな復元に関連する研究発表と議論を行う.
11.堆積作用・堆積過程(現行地質過程部会・堆積地質部会)(地域名必要)
小松原純子*(産総研;j.komatsubara@aist.go.jp)・北沢俊幸(原子力機構)
堆積作用や堆積過程に関して,実験・シミュレーション・現地観測および地層観察などに基づいた研究を募る.特定の地域や年代を超えて適応可能な新しい解析手法や多方面からのアプローチによる堆積関連の研究も募集する.
12.石油・石炭地質学と有機地球化学(石油・石炭関係・堆積地質部会)(地域名必要)
大久保 進(石油資源開発;susumu.okubo@japex.co.jp)・金子信行(産総研)
国内外の石油・石炭地質および有機地球化学に関する講演を集め,石油・天然ガス・石炭鉱床の成因・産状・探査手法など,特にトラップ構造,堆積盆,堆積環境,貯留岩,根源岩,石油システム,資源量,炭化度などについて討論する.
13.岩石・鉱物の破壊と変形(構造地質部会)(地域名不要)
西川 治*(秋田大;nisikawa@lfp03.mine.akita-u.ac.jp)・平内健一(広島大)
断層岩を含む岩石・鉱物の破壊および変形機構,変形微細構造,岩石・鉱物のレオロジーや物性に関する研究を募る.観察・観測・分析・実験・理論など多方面からのアプローチによる成果を歓迎するとともに,会場での活発な議論を期待する.
14.付加体(構造地質部会)(地域名必要)
坂口有人*(JAMSTEC;arito@jamstec.go.jp)・鎌田祥仁(山口大)
現世,過去を問わず,付加体に関するすべての講演を歓迎する.付加体の形成機構,形成史,微細構造,流体移動,シュードタキライト,温度圧力構造など,様々なアプローチによる成果をもとに議論する.
15.テクトニクス(構造地質部会)(地域名必要)
大坪 誠*(産総研;otsubo-m@aist.go.jp)・佐藤活志(京都大)
地球科学の多方面から,大小様々な時間・空間スケールで起こる地質構造の成因や形成機構・発達史に関する講演を広く募集する.野外調査,観測,実験,理論などに基づいた研究発表を歓迎する.
16.ノンテクトニック構造(応用地質部会・構造地質部会)
柏木健司*(富山大;kasiwagi@sci.u-toyama.ac.jp),永田秀尚(風水土),村井政徳(中国開発調査(株))
テクトニックではない構造(例:堆積物の未固結時変形やランドスライド・地震などによる一過性の構造,重力性の構造その他)の記載・解析・テクトニック構造との区別や比較・応用を議論する.時代・時間やスケールを問わないので,さまざまな分野からの参加を期待する.
17.古生物(古生物部会)(地域名不要)
平山 廉(早稲田大)・北村晃寿*(静岡大;seakita@ipc.shizuoka.ac.jp)・太田泰弘(北九州博)・三枝春生(兵庫県立人と自然の博)・須藤 斎(名古屋大)
古生物を扱った,または関連する研究の発表・討論を行う.
18.噴火と火山発達史(火山部会)
世話人:永尾隆志(山口大;tnagao@yamaguchi-u.ac.jp)・石井英一(日本原子力研究開発機構)・石塚吉浩(産総研)
マグマや熱水性流体の上昇過程,噴火様式,噴火推移,噴出物の移動・運搬・堆積,特定火山あるいは火山地域の発達史,火山活動とテクトニクス,およびその他火山地質やモデル化に関する幅広い視点からの議論を期待する.
19.深成岩・火山岩とマグマプロセス(火山部会・岩石部会共催)
世話人:古川邦之(愛知大;kfuru@aichi-u.ac.jp)・齋藤 哲(JAMSTEC)
深成岩および火山岩を対象に,マグマプロセスにアプローチした研究発表を広く募集する.発生から定置・固結に至るまでのマグマの物理・化学的挙動や,テクトニクスとの相互作用について,野外地質学・岩石学・地球化学・年代学など様々な視点からの活発な議論を期待する.
20.変成岩とテクトニクス(岩石部会)(地域名不要)
片山郁夫*(広島大;katayama@hiroshima-u.ac.jp)・桑谷 立(東京大)
国内および世界各地の変成岩を主な対象に,記載的事項から実験的・理論的考察を含め,またマイクロスケールから大規模テクトニクスに関する様々な地球科学的手法・規模の視点に立った斬新な話題提供と活発な議論を期待する.
21.岩石・鉱物・鉱床学一般(岩石部会)(地域名不要)
壷井基裕*(関西学院大;tsuboimot@kwansei.ac.jp)・水上知行(金沢大)
岩石学,鉱物学,鉱床学,地球化学などの分野をはじめとして,地球・惑星物質科学全般にわたる岩石及び鉱物に関する研究発表を広く募集する.地球構成物質についての多様な研究成果の発表の場となることを期待する.
22.情報地質(情報地質部会)(地域名不要)ポスターセッションのみ,口頭講演なし
能美洋介(岡山理科大;y_noumi@big.ous.ac.jp)・坂本正徳(国学院大)
地質情報の数理解析,統計解析,データ処理,画像処理などの理論,応用,システム開発,利用技術など,最近の情報地質分野の研究結果を対象とする.また,これらの成果の地質学の広い分野への応用・普及なども歓迎する.
23.環境地質(環境地質部会)
難波謙二(福島大)・風岡 修(千葉環境研)・三田村宗樹(大阪市大)・田村嘉之*(千葉環境財団;tamura-yoshiyuki@pop07.odn.ne.jp)
医療地質,地盤沈下,湧水,水資源,湖沼・河川,都市環境問題,法地質学,環境教育,地震動,液状化・流動化,地震災害,岩盤崩落など,環境地質に関係する全ての研究の発表・討論を行う.
24.応用地質学一般(応用地質部会)(地域名不要)
上野将司*(応用地質(株);ueno-shouji@oyonet.oyo.co.jp)・横田修一郎(島根大)
種々の地質ハザードの実態,調査,解析,災害予測,ハザードマップの事例・構築方法,土木構造物の設計・施工・維持管理に関する調査,解析など,応用地質学的視点に立った幅広い地質学研究について発表・討論を行う.
25.地学教育・地学史(地学教育部会・地学教育委員会共催)(地域名必要)
矢島道子*(地質情報・活用機構;pxi02020@nifty.com)
新学習指導要領の施行は目前.現場からの問題提起,多くの実践報告を持ちより議論しよう.また地学史からの問題提起,貴重な史的財産の開示を歓迎する.
26.第四紀地質(第四紀地質部会)(地域名必要)
吉川周作*(大阪市大;yoshi@sci.osaka-cu.ac.jp)・内山 高(山梨環境研)
第四紀地質に関する全ての分野(環境変動・気候変動・湖沼堆積物・地域層序など)からの発表を含む.また,新しい調査や研究,方法の開発や調査速報なども歓迎する.
就職支援(2008秋田大会の様子)
第115年秋大会:就職支援プログラム(2008.9.21開催)
地質学会大会の新しい試みとして,札幌大会から始まった就職支援プログラムは,学生・院生および大学教官ほかの会員と,民間企業・団体,研究機関等とが直接対面し,情報交換をしていただくことによって,就職希望者を支援することを目的としています.
秋田大会では,9月21日午後2時から5時まで,ポスターセッション会場の2階に設けられた会場で,まず企業説明会形式で参加企業6社からの紹介プレゼンテーションをご覧いただいた後,各社の出展ブースで詳しい説明や質疑応答に参加していただきました.
今回は,開催期間の中日であったこともあってか,参加者数は札幌大会を大きく上回り,プレゼンテーションのために用意した椅子席も足りない状態でした.その後,各ブースでも終了時間いっぱいまで熱心に説明に聞き入る参加者の姿が見られ,昨年以上に若手会員のニーズの手ごたえを感じました.
学会では,来年以降もこのプログラムを継続する予定です.できるだけ多くの企業等にご参加をいただき,また充実した情報交換ができるよう,開催方法についても検討を進めて行きたいと思います.来年の開催に当たってのご要望がありましたら,担当までお知らせください.最後になりましたが,本行事に参加いただいた企業6社の皆様,企画にご協力をいただいた賛助会員,関連企業の皆様,および本大会の準備委員会に,改めて謝意を表します.
各社によるプレゼンテーション
各社ブースの様子
参加企業(敬称略・申込順):株式会社日さく・応用地質株式会社・明治コンサルタント株式会社・太平洋セメント株式会社・ジーエスアイ株式会社・国際航業株式会社
(理事:運営財政部会 向山 栄)
←2009年岡山大会申込画面に戻る
講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理,引用方法,校閲について
講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理,引用方法,校閲について
(1)講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理
日本地質学会の出版物への投稿原稿に対して,著作者にその倫理性について保証して頂くために「保証書」に,また著作権を日本地質学会に 譲渡することを同意する「著作権譲渡同意書」に,それぞれ署名捺印をして提出していただいています.本大会は電子投稿のため,画面上で「保証 書」と「著作権譲渡等同意書」に同意していただいた場合に限り,電子投稿の画面に進むことができるようになっています.郵送の場合は,保証書及び同意書に署名捺印をして,講演要旨と共にお送り下さい.「保証及び著作権譲渡等同意書(こちらをクリック)」が同封されていない講演申込は受け付けられません.
(2)講演要旨における文献等引用方法
要旨においては引用文献の記載方法は簡略化することが慣習として認められていますが,著者名,発表年,掲載誌名などを明記し,引用文献が特定できるようにして下さい.
(3)講演要旨の校閲
行事委員会は,申し込まれた講演について,会則第4条に示されている日本地質学会の目的ならびに日本地質学会倫理綱領に反していないかということについて のみ校閲を行います.校閲の結果,いずれかの条項に反していると判断された場合には,行事委員会は講演内容の修正を求めるか,あるいは講演申込を受理しな いことがあります.行事委員会の措置に同意できない場合には,当該講演申込者は法務委員会(東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル 日本地質学会事務 局気付)に異議を申し立てることができます.法務委員会は直ちに審理し,結論を行事委員会ならびに異議申立者に伝えることになります.
この受理方法は,招待講演者にも適用されます.
講演申し込み異議申し立てについて
日本地質学会行事委員会は,学術大会において学会の目的及び倫理規定に反する講演申し込みのあった要旨に対して,修正あるいは,受理を拒否することができます.法務委員会では,日本地質学会行事委員会規約に基づき,異議申立の手続及びその処理についての規則を定めています.
日本地質学会法務委員会
■日本地質学会学術大会講演申込異議申立に関する処理機構規則(PDF)■
講演要旨の作成の注意点とPDFファイル作成の作り方
講演要旨の作成の注意点とPDFファイル作成の作り方
講演要旨を作成する際,著者には「保証及び著作権譲渡同意書」第1項の「保証」内容を守って頂きます.行事委員会は,要旨の内容については関知しませんが,当該「保証」内容を逸脱するものがないか校閲します.その結果,不適当とみなされる場合は,修正されるまで講演要旨の受理はされません(不服の場合は法務委員会に訴えることが可能です).
例年最も多い問題点は,引用文献の表示がない場合です.論文のように細かに引用文献を記載することはスペースの都合上不可能なので必要としませんが,雑誌名,号,ページ等,その文献にたどり着ける最低限の情報は要旨原稿内に記載して下さい.
また,要旨の体裁を無視している場合,印刷できませんので体裁を整えて頂くことになります.さらに図等の改変については,著作権法,地質学会著作物利用規定に従って下さい.このほか,PDFファイルにフォントを埋め込んでいないもの(印刷時に文字化けすることがあります),要旨作成時に講演番号記入用のスペースがなかったり,余白に無理があるといった場合,体裁を整えるため修正をお願いしています.これらの問題点があった場合,各コンビーナから投稿締切日から1週間をめどに修正依頼が届きます.ただ,その労力はセッションによっては膨大になりますので,あらかじめ著者で完全なものを投稿するようご協力下さい.あわせて講演要旨投稿手順のチェックシートもご参照下さい.
日本地質学会 行事委員会
2009年4月
■要旨テンプレート(Microsoft Word)■ ■講演要旨投稿手順のチェックシート■
【講演要旨PDFファイル作成時の注意点】
1)
講演要旨原稿はAdobe Acrobat Reader 4.0 以上で表示・印刷可能なPDFファイルで投稿することが必要です.
2)
ファイルサイズは3.0Mバイト以内で作成して下さい.
3)
発表(講演)番号は事務局にて左上に付記するので原稿内には記載しないで下さい.
4)
PDFファイルのセキュリティ設定は「なし」にして下さい.
5)
フォントは必ず「埋め込み」にして下さい.MacOSX以上は標準でフォント埋め込みが用意 されます.MacOS9.2.2以下,Windowsでは下記のソフトが必要です.その際,『すべてのフォント埋め込み』ないし『ハイクォリティー』等, それぞれのソフトの使用説明書に従った指定を必ずして下さい.文字数にもよりますが,できたPDFファイルのサイズが100KB未満の場合,フォントが埋 め込まれなかった可能性がありますので確認して下さい.
6)
作成したPDFファイルを自分で印刷し,図表に充分な解像度があるか,文字化けはないか確認して下さい.
7)
PDFファイルを自分のパソコンに,必ず「.pdf」の拡張子をつけて保存して下さい(Mac, Windowsとも).
■原稿フォーマット見本■
テンプレート
(Microsoft Word)
ダウンロードはこちら
【webでの講演要旨投稿の手順】
1)
参加申し込みの後,web上の講演申し込みページで,講演申し込みの手続きをします(講演申込と同時に要旨投稿をすることもできますし、講演要旨のみ後で投稿する事もできます).
2)
演題・発表者情報登録画面の最下段にある「アップロードファイル」欄から要旨原稿(PDFファイル)を投稿します.欄右側の「参照」ボタンをクリックし,ご自分のPCに保存してあるPDFファイルを選択します.
3)
画面下の「次へ」をクリックし,登録内容確認画面に進みます.登録内容を確認後,画面下の「登録」ボタンをクリックします.これによりサーバーにPDFファイルが格納されます.
4)
『登録が完了いたしました.受付番号は*****です.』という完了画面が表示されます.(注意!!この画面が表示されないと登録は完了していません)
5)
登録したメールアドレスに「講演申込のお知らせ」のメールとともに受付番号(=ID)が配信されます.
★★後から要旨を投稿する場合・申込内容を変更する場合★★
1)ご自分の申込画面に,IDとメールアドレスを用いてアクセスします.
2)「登録内容変更」ボタンをクリックし,画面の最下段にある「アップロードファイル」欄の「修正」ボタンをクリックします.ご自分のPCに保存してあるファイルを選択し,アップロードをします.サーバー側では,ファイル名を元のファイル名から変更し,ID.pdfの名称で格納します.
3)『登録が変更されました.受付番号は*****です.』という操作完了画面が表示されます.(注意!!この画面が表示されないと操作は完了していません)
4)「講演申込内容変更のお知らせ」メールが配信されます.
5)IDとメールアドレスを用いて,投稿締切まで何度でも要旨や登録内容を修正することができます.新しいファイルを投稿すると,古いファイルに上書きされます.そのつど,「講演申込内容変更のお知らせ」メールが配信されます
【参考情報:PDF(Portable Document Format)ファイルの作り方】
PDFファイルの作成方法は「PDF原稿作成ガイド」http://www.gakkai-web.net/pdf/を参考にすると良いでしょう.
ソフトの紹介要望が多いので,下記にいくつか参考例を挙げます.また,"PDF作成サービス"を行う有料,無料のサイトがあります.ソフト,サイトとも検索してみて下さい.なお下記について動作確認等しておりません.また推奨するものでもありません.ご了承ください.
◯ Mac OSXの場合
フォント埋め込み型のPDF作成機能が標準で用意されています.新たなソフトは必要ありません.
◯ Mac OS 8.6-9.2の場合
Adobe Acrobat(それぞれのOS対応品,現在販売されているか不明)
EGWORD Ver.12 for Mac OS X/9/8.6(現在販売されているか不明)
◯ Windows対応品
PrimoPDF FreeのPDF変換ソフト http://www.primopdf.com/
クセロPDF FreeのPDF変換ソフト http://xelo.jp/xelopdf/(有料ソフトあり)
いきなりPDF 2000円弱 http://www.sourcenext.com/products/pdf/
Adobe Acrobat Elements 5000円弱 http://www.adobe.co.jp/
◯ MacOS9.2.2,MacOSX, Windows対応
Adobe Illustrator http://www.adobe.co.jp/
講演要旨オンライン投稿手順チェックシート
講演要旨オンライン投稿手順チェックシート
講演要旨の投稿手順および基本的注意事項です.投稿していただく前に各自でご確認下さい.
1.Word等のソフトで講演要旨原稿を作成します.
「保証及び著作権譲渡同意書」第1項の「保証」内容は守られていますか?
要旨原稿内に引用文献は表示されていますか?
要旨の体裁は守られていますか?(詳細は要旨原稿フォーマットをご確認下さい)
2.原稿をPDFファイルにします.
PDFファイルの作成方法については,本号の「PDFファイルの作り方」を参照して下さい.
フォントは「埋め込み」になっていますか?(できたファイルサイズが100KB未満の場合,フォントが埋め込まれなかった可能性がありますので確認して下さい)
ファイルサイズは3.0MB以内になっていますか?
作成したPDFファイルを印刷し,図表に充分な解像度があるか,文字化けはないか確認して下さい.また,PDFファイルを自分のパソコンに,必ず.pdfの拡張子をつけて保存して下さい.
3.原稿をオンライン投稿します.
web画面から参加申し込みを行いましたか?
講演申し込みページで,講演申し込みの手続きをしましたか?
講演要旨を投稿しましたか?
申込完了画面が表示されましたか(ログイン用のIDが表示されましたか)?
「講演申込のお知らせ」のメールが配信されましたか?
4.一度投稿した原稿を修正したい場合
ご自分の申込画面に,IDと申込時に設定したパスワードを用いてアクセスします.
画面中のPDFファイルのアイコンをクリックし,要旨原稿投稿画面を開きます.書き直した要旨のファイル選択し,投稿動作をします.
修正原稿が受け付けられると,「申込内容変更のお知らせ」メールが配信されます.(締切まで何度でも修正できます).
←講演要旨作成手順のページに戻る
発表者へ
発 表 者 へ
一般講演の発表者は招待講演,一部のシンポジウムを除いて本学会の会員に限ります(共同発表の場合は筆頭者に適用).また,やむを得ない事情により,あらかじめ連記された共同発表者内で筆頭者の変更を希望する場合は,必ず事前に行事委員会(会期前は学会本部へ,会期中は年会本部事務局へ)に連絡して下さい.この場合も,シンポジウム以外の場合は「会員に限り1人1題」の発表制限は守るものとします.代理人による代読,発表会場内での突然の発表者変更,発表順序の変更は一切認めませんのでご注意下さい.とくに口頭発表者の方には発表時間の厳守をお願いいたします.発表に際しては座長の指示に従い,会場の運営がスムーズに行われるようご協力下さい.
<講演をキャンセルされる場合>
学会事務局および世話人宛に 講演番号・講演タイトル・筆頭講演者氏名を明記して、キャンセルの旨をメールでお知らせください。学会事務局<main@geosociety.jp>
口頭発表
・1題15分(討論時間を含む)ただし,シンポジウムは除く
・口頭発表会場には液晶プロジェクターとWindowsパソコン(OS: Windows XP およびVista対応, Microsoft Office PowerPoint 2003-2007 対応)を用意します.なお,35mmスライドプロジェクターの使用はできません.
【講演ファイルをUSBメディアでご持参の方】
口頭発表で使用するファイルのインストールは,PCセンター(試写室)【25号館5階】にて事前に作業を行ってください.インストールは各セッション・各シンポジウム開始30分前までに25号館5階PCセンター(試写室)で受け付けます.なお,大会初日9月4日午前に発表される方についても,〜8:30までPCセンターにて受けます.混雑が予想されますので講演直前にならないよう,十分な時間的余裕を持って確実に行ってください(午前中のセッションであれば前日に,午後のセッションであれば午前中にインストールを完了してください).ファイルは,PCセンターにおいて正常に作動することを事前に確認してください.特に,会場に設置するものと異なるバージョンで作成されたパワーポイントファイルは,レイアウトが崩れる事例が報告されていますのでご注意願います.なお,ファイル名には,発表番号と筆頭演者ご氏名をご使用ください.(例:S-1岡山太郎, O-12吉備次郎)
【ご自分のパソコンを使用して講演をされる方】
本年は会場の液晶プロジェクターにパソコンの切り替え器(ケーブル形状はD-SUB15ピン)を用意します.Macパソコンをお使いになる方,ソフトの互換性からレイアウトが崩れる可能性のある方,パワーポイント以外のプレゼンテーションソフトをご利用の方はご自分でパソコンをご用意ください.各会場のプロジェクターの解像度設定はXGA(1024×768)です.ご講演前にご自身での出力調整をお済ませの上接続してください.Macパソコンをお使いになる方は,必ずD-SUB15ピンへのアダプターをご持参ください.パソコンの接続については,発表者自身が責任を持って実施下さい.切り替えは会場スタッフにて行います.
ポスターセッション
・ 掲示する際のチェスピンは準備いたします.テープのご利用はできませんので,ご了承ください.
・ 展示時間は, 9:00−17:00です.展示準備は早めにお願いします.撤収は, 18:00までにお願いします.
・ コアタイムは,4日(金)が12:30 −13:30,5日(土)と6日(日)が13:00 −14:00です.この時間は必ずポスターに立ち会い,その他の時間は各自の都合によって随時行って下さい.
・ ボード面積は90cm×210cm(ヨコ×タテ)です.
・ 発表番号・発表題名・発表者名をポスタータイトルとして,必ず明記して下さい.
・ コンピューターやビデオを使用される場合,機器の準備は各自で行ってください.電源は確保できませんので,予備バッテリーをご準備下さい.
・ ポスター発表に対し,別記の要領にて優秀講演賞が授与されます.奮ってご準備下さい.
富山大会
富山大会TOP
日本地質学会第117年学術大会(富山大会)
画像をクリックするとA3ポスター PDFファイルがダウンロードして頂けます。
日本地質学会第117年学術大会(富山大会)
−高度差4000mの地質学−
2010年 9月18日(土)〜20日(月・祝)
盛会のうち、無事終了致しました。ありがとうございました。
来年は、水戸大会でお会いしましょう。
2011年9月9日〜11日
事前参加登録は締切ました
【重要】事前参加申込者の皆様へ:予約確認証・引換クーポンの送付について(9/9)
<お願い>今年は学会を通じての、宿泊・交通の申込受付は行いません。
お手配は各自でお願いします。参考までに→日本旅行の宿泊予約サイト
(日本旅行のサイトでは、富山大会参加者数分の宿泊先が確保されています)
★ 新着情報 ★
09/21 講演要旨・見学旅行案内書 残部あります。NEW
********************************************************************************************
09/15 発表者の皆様へ(口頭・ポスター)(News誌8月号掲載内容)
09/13 見学旅行一部追加募集中です!
09/13 富山大会関連情報のプレスリリースを行いました。
09/09 事務局主催 シニア昼食会のお誘い
09/03 見学旅行参加申込状況
08/25 大会期間中のお食事について
08/24 各講演プログラムを掲載しました
08/06 事務局主催 シニア昼食会のお誘い<
08/06 全体日程表を掲載しました
08/03 見学旅行各コースの魅力・みどころをご紹介
07/31 見学旅行もまだまだ申込可能です
07/12 「緊急展示」の申し込みについて
07/05 講演申込(WEB)7/8(木)昼12時まで 締切延長
06/30 富山大会に関連したプレス発表を希望される方へ
06/25 就職支援プログラム出展企業募集 のお知らせをアップしました
06/09 第9回理科教員対象見学旅行:糸魚川ジオパーク ヒスイ探訪ジオツアー の案内をアップしました
06/01 事前参加登録・講演申込ほか各種申込受付開始しました。
新着情報
新着情報 2010富山大会
2010.09.21更新 講演要旨・見学旅行案内書 残部あります。
富山大会講演要旨および見学旅行案内書にわずかですが、残部があります。ご購入希望の方は学会事務局まで<main@geosociety.jp>ご注文ください。
会員価格(いずれも送料別)
・講演要旨 4000円
・見学旅行案内書 2800円
なお、事前注文された方には、近日中に冊子を発送致しますので、しばらくお待ちください。
2010.09.13 更新 見学旅行 一部追加募集中です!
申込・問い合わせは各案内者へお願い致します。
B班 跡津川断層(1-2名) 竹内 章 <takeuchi@sci.u-toyama.ac.jp >
I班 糸魚川ジオパーク ヒスイ楽(若干名) 宮島 宏 <hiroshi.miyajima@city.itoigawa.niigata.jp >
各コースの見どころはこちら
http://www.geosociety.jp/toyama/content0032.html
2010.09.09 更新 事務局主催 シニア昼食会のお誘い
富山大会にご参加いただくシニア会員の方々と事務局職員の昼食会を計画しました.今年は地元の藤井昭二名誉会員にもいろいろお世話をいただきました.
年会の合間のひと時,軽い昼食と近況談義(昔語りでもよいですよ!)などできれば,楽しいかと思います.ここでのシニアの定義は特にありません.我こそはシニア,私もシニア, シニアではない方も,どなたでもお気軽にお集まりいただきたいと思います.
日 時 2010年9月19日(日)12〜14時
食事処 富山第一ホテル 地下1階 日本料理 松川
会 費 2000円前後
申し込み 9月18日(土)(会期の初日)まで受け付けます(担当 橋辺).
地質学会事務局(電話 03-5823-1150)
※ 会期中は会場内の事務局の部屋 A棟2階(A23) 当日は、12時頃1階受付付近集合の予定です。
2010.09.03 更新 見学旅行申込状況
コース名
(申込数/定員)
コース名
(申込数/定員)
A班
第四紀
(13/12)
F班
飛驒から日本海
(20/20)
B班
跡津川断層
(21/20)
G班
手取層群
(12/10)
C班
立山火山
(9/20)
H班
ジオパークの地質
(19/20)
D班
焼岳火山
(4/13)
I班
ジオパーク ヒスイ楽
(11/25)
E班
黒部川
(23/14)
09.03 13時現在
定員に達している場合でも、取消等の可能性がありますので「キャンセル待ち」のお申し込みが可能です。
2010.08.25 更新 大会期間中のお食事について
富山大学周辺に,飲食店等はさほど多くありません.お弁当予約販売,学内施設,学外コンビニエンスストア等をご利用下さい.
◯お弁当予約販売:1個800円,お茶付き
申込締切 オンライン:9月3日(金)18:00,
FAX(郵送):8月31日(火)必着
◯生協食堂および正門横カフェAZAMI:会期中の9月18日
(土)〜20日(月・祝)は営業しています.
◯コンビニエンスストア:会場から徒歩3分程の距離に,コンビニエンスストアが2軒あります.
2010.07.31 更新 見学旅行もまだまだ申込可能です
「高低差4000mの地質学」にふさわしく,日本海から北アルプスまで,豊富な9コースが企画されています.いずれのコースもまだ充分申込可能です.たくさんのご参加をお待ちしています.
2010.07.12 更新 「緊急展示」の申し込みについて
学会活動の一端を広く社会に紹介するとともに,ホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害報告や社会的に影響のある新技術紹介などの「緊急展示コーナー」を設けます.ポスター展示を希望する方は,9月3日(金)までに以下の内容で下記の実行委員会にご連絡ください.
1)発表要旨PDF(ニュース誌4月号参照)
2)緊急展示の必要性
3)発表代表者と連絡先
4)希望枚数(1枚:幅90×180cm)
5)展示に関わる要望 (2〜5の様式は自由)
実行委員会は行事委員会と協議し,可否の判断を致します.希望にはできるだけ応えるようにしますが,展示方法等については実行委員会の指示に従ってください.
申込先:main@geosociety.jp
担 当:大籐 茂(富山大会実行委員会)・上野将之(行事委員会)
2010.07.05 更新 講演申込(WEB)7/8(木)昼12時まで締切延長
多くの方々にご講演いただくため、講演申込(WEB)の締切を延長いたしました。お申し込みをお待ちしています!
講演申込締切:7月8日(木)昼12時(郵送分は締切ました)
2010.6.30 更新 富山大会に関連したプレス発表を希望される方へ
富山大会での講演や行事について,8月下旬にプレス発表を行う予定です. 昨年の岡山大会でも多数のメディアに取り上げられ,会員の研究成果が多いに注目されました.富山大会で発表される予定の案件で,学会からのプレス発表をご希望の方は,8月10日(火)までに学会事務局にご連絡願いま
詳しくは、こちらをご参照下さい。
2010.6.25 更新 就職支援プログラム参加企業募集
本プログラムは、学会に参加される学生・院生および大学教官の会員、ならびに富山大学の学 生・院生・関係者らを対象に、本会賛助会員をはじめとする関連会社との相互の情報交換を行う場を提供しようというものです。
つきましては、ぜひご参加ください。
詳しくは、こちらをご参照下さい。
2010.6.1 更新 第9回理科教員対象見学旅行:糸魚川ジオパーク ヒスイ探訪ジオツアー
第9回理科教員対 象見学旅行:糸魚川ジオパーク ヒスイ探訪ジオツアー の案内をアップしました.
詳しくは、大会HPの地学教育・普及教育のページをご参照下さい。
2010.6.1更新 富山大会事前参加登録・講演申込受付開始
富山大会各種申込受付が開火始されました。今年も講演申込はJ-STAGE演題登録システムを利用いたします。
講演申込締切は、7月7日(水)です(郵送の場合は7/2)。早めのお申し込みをお願いいたします。
■ 講演申込ははこちらから。
■ 事前参加登録はこちらから。
講演申込TOP
富山大会講演申込
演 題・講演要旨締切:
オンライン 7月7日(水)17時(郵送7月2 日(金) 必着)
7月8日(木)昼12時まで 締切延長
(郵送分は締め切りました)
↓WEBからの講演申込はこちら↓
(修正・変更もこちらから)
▶講演申込要領・発表要領
▶シンポジウム一覧
▶定番セッション・トピックセッション
▶講演要旨原稿について
▶▶講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理,引用方法,校閲について
▶▶講演要旨の作成の注意点とPDFファイル作成の作り方
▶▶講演要旨オンライン投稿手順チェックシート
▶▶保証・同意書(2009岡山)
▶講演申込書 書式pdf(郵送で申し込む場合)
申込要領・発表要領
定番およびトピックセッション・講演の申込要領・発表要領
注:シンポジウムに関しては、シンポジウムのページを参照して下さい。
演 題・講演要旨締切:
オンライン 7月7日(水)17時(郵送7月2 日(金) 必着)
7月8日(木)昼12時まで 締切延長
WEBからの講演申込はこちら
(修正・変更もこちらから)
■定番セッション一覧はこちら
■トピックセッション一覧はこちら
募集要領
9月18日〜9月20日の3日間での一般発表を募集します.下記の要領にて口頭,ポスター発表を募集します.できる限りオンラインでの申込にご協力下さい.やむを得ず郵送で申し込む場合は所定の申込書(ニュース誌5月号掲載)に 必要事項を記入の上,返信用(自分宛)の官製ハガキ,保証書・同意書,講演要旨原稿とともに7月2日(金)必着で行事委員会宛にお送り下さい.プログラム の編成が終わり次第,発表セッションや発表日時などをe-mailで通知します(郵送の場合は返信ハガキで).なお,発表セッションや会場・時間などのプ ログラム編成につきましては,各セッションの世話人の協力を得て,行事委員会が決定します.
(1)セッションについて
専門部会の提案な どにより20件の定番セッションと,6件のトピックセッションを設けました.
(2)講演に関する条件
日本地質学会の会員は,口頭発表かポスター発表かのいずれかの方法で,1人1題に限り講演を行うことができます.共同発表の場合は上記の条件を講演者(= 筆頭発表者)に適用します.原則,非会員は筆頭発表者になれませんので,必ず7月2日(金)までに入会手続きを行って下さい.入会申込書が届いていない場 合は,講演申込は受理されません.
(3)招待講演について
昨年同様,トピックセッションにおいては,世話人は会員・非会員を問わずに招待講演を依頼することができます.非会員の招待講演は1セッションにつき,半日あたり1講演に限ります.会員の招待講演数には制限はありません.招待講演についても申込期日までに一般発表と同様にお申し込み下さい(非会員の場合は世話人が取りまとめてオンライン入力をすることは可能です).定番セッションでは招待講演の設定はありません.また,非会員の招待講演者に限り参加登録費は免除となります.
(4)講演申込上の注意
1) オンライン申込はオンライン入力のフォームに従って入力して下さ い.
2) 講演方法については,「口頭」「ポスターセッション」,「どちらでもよい」のいずれかを選択して下さい.ただし,申込締切後の変更はできません.
3) 発表題目,発表者氏名について,必ず登録フォームと講演要旨の両方を一致させて下さい.
4) 共同発表の場合は全員の姓名を完記して下さい.
5) 発表を希望するセッションを第2希望まで選んで下さい.
6) コメント欄について:発表の対象とする地域の記入を要するセッションについてはこの欄に国名・県名等を入力して下さい.また,関係する一連の発表があると きは,その順番希望などもこの欄に入力して下さい.
7) 口頭発表会場には液晶プロジェクターとWindowsパソコン(OS:Windows Vista, Office Standard 2007)を用意します.パワーポイントを使用する方は,試写室において正常に作動することを事前に確認して下さい.特に,会場に設置するものと異なる バージョンで作成されたファイルは,レイアウトが崩れる事例が報告されていますのでご注意願います. パワーポイントを使用しない方やMacパソコンを使用される方は世話人とご相談下さい.なお,35mmスライドプロジェクターの使用はできません.
(5) 講演要旨原稿の投稿について
例年と 同様に講演要旨をAdobe社が策定したPortable Document Format(PDF)のファイルで電子投稿していただきます.一般発表およびシンポジウムの原稿はA4判1枚(フォーマット参照)で,印刷 仕上がり0.5ページ分です.1ページに2件分ずつ印刷します.原稿はそのまま版下となり,70%程度に縮小して印刷されます.文字サイズ,字詰めおよび 鮮明度には十分配慮し,PDFファイルを作成して下さい.やむを得ず郵送する場合は,オリジナルか,鮮明にコピーした現物を1枚だけ郵送(差し支えなければ折りたたみ可)して下さい.FAXやe-mailでの原稿送付は受け付けません.
発表要領(シンポジウムについてはこちら)
(1)口頭発表
1)講演時間は1題あたり15分(討論時間3分を含む)です.講演者は,討論など持ち時間を十分考慮し余裕を持って 講演を行って下さい.
2)各会場には,液晶プロジェクター,Windowsパソコンを各1台とスクリーン1幕を設置します.
(2)ポスター発表
1)1題について1日間掲示できます.各日とも発表者はコアタイム(開催日によって異なる)にその場に立会い,説明をするものとします.設置,撤去時間等については,ホームページまたはニュース誌8月号に掲載されるプログラムをご覧下さい.ボード面積は1題あたり, 縦180cm,横90cmです.
2)発表番号・発表名・発表者名をポスターのタイトルとして明記して下さい.
3)掲示に必要な画鋲等は, 発表者がご持参下さい.
4)ポスター会場では,コンピューターによる発表や演示等も許可しますが,使用する機器については発表者がご準備下さい. また,電源は確保できませんので,予備のバッテリーをご用意下さい.講演申込の際に機器使用の有無や小机の必要性をコメント欄に記入し,事前に世話人ご相 談下さい.
5)運営規則第16条(8)項により,優れたポスター発表に対して「日本地質学会優秀ポスター賞」を授与いたします.具体的な事柄 については,プログラムに掲載しますのでご注目下さい.
(3)発表者の変更
あらかじめ連記されている共同発表者内での変更は認めます が,必ず事前に行事委員会へ連絡して下さい.この場合も筆頭講演者については上記1人1題の条件が適用されます.
(4)口頭発表の座長の依頼につ いて
セッションによっては各会場の座長を参会者にお願いすることになります.あらかじめ座長依頼を差し上げることになりますが,その際にはぜひともお引き受けいただきたく,ご協力をお願いします.
申込方法とお支払について
各種申込とお支払方法について
■参加登録フォームはこちらから■
申し込める内容:参加登録・懇親会・追加講演要旨・見学旅行・見学旅行案内書・お弁当
<申込締切 オンライン :9月3日(金)18:00,FAX/郵送:8月31日(火)必着>
(1)申込方法
オンラインによる参加登録申込等を受付けます.申込は新たに構築した学会独自の参加登録システムをご利用いただきます.大会専用参加登録システム(会員・非会員にかかわらずどなたでも申し込めます.)又は専用申込書(FAX・郵送用)をご利用の上,お申し込み下さい.参加登録・懇親会・追加講演要旨・見学旅行・見学旅行案内書・お弁当を同時に申込むことが出来ます.なお,今年は学会を通じての宿泊・交通手配の斡旋は行いません.宿泊や交通については,各自でお手配をお願いいたします.
(a) 大会専用参加登録システム(オンライン)による申込:申込フォームに必要事項を記入して送信.
(b) FAX・郵送による申込:申込書に必要事項を記入の上,「日本地質学会富山大会参加申込係」宛にお送りください.
FAX番号:03-5823-1156
郵送先:〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル6階「日本地質学会富山大会参加申込係」
(a)大会専用参加登録システム(オンライン)による申込
1) 学会HPから「2010年日本地質学会年会参加申込」,へアクセスして下さい.
2) 画面のメニュー「参加登録」をクリックして下さい.
3) 申込画面の入力欄に氏名と会員番号を入力するだけで,学会に登録されている会員情報(所属・住所等)が表示され,続けて参加登録を行うことができます.
4) 申込み完了後、「申込確認メール」および「ご請求メール」が登録のメールアドレスへ配信されます.内容を必ずご確認下さい.本メールを請求書とさせて頂きます。別途請求書が必要な場合は学会事務局までご連絡ください。
5) 支払い方法について,「銀行振込」を選択された方は,「ご請求」メールを確認の上,指定の金融機関より申込から7日以内にお振込み下さい.また,クレジットカードもご利用頂けます.「クレジット決済」を選択の場合は,ご利用のカード会社の期日に合わせて,口座より引き落としとなります.クレジットカード会社からの明細には「日本地質学会(ニホンチシツガッカイ)」と表示されます.
6) 参加証・各種クーポンは申込締切後に発送します.大会開催1週間前には参加者の皆様のお手元に届くようお送り致します.発送時点で入金確認が取れない場合は,未入金の旨記載されたクーポンが送付されますので,当日会場にて入金のご確認をさせて頂きますので、入金とクーポン発送が入れ違いの場合は,振込み時の控え等を会場にお持ち下さい.確認がスムーズに行えますのでご協力をお願い致します.
(b) FAX・郵送による申込
1) 「FAX・郵送専用申込書」(ニュース誌掲載)に必要事項を記入の上,日本地質学会事務局までFAXまたは郵送にてお申込み下さい.電話による申込,変更などは受け付けられませんので,ご了解ください.また,郵送による申込みの際は,必ず申込書のコピーを各自で保管して下さい.
2) FAX・郵送による申込の場合は,折返し学会より「受付確認証」をe-mail又はFAXにてお送りします.必ずご確認下さい.確認証が届かない場合は,必ず事務局までご連絡ください.確認証には,「受付番号」が記載されています.この「受付番号」はその後の問い合せ,変更,取消等に必要となります.
3) お支払いは,銀行振込またはクレジットカード決済のいずれかを選択できます.申込後順次,「予約内容確認」・「請求書」をお送りします.銀行振込を選択された方は,請求書に記載されている振込口座へ指定期日までにお振込み下さい.クレジット決済を選択された方は,参加申込の際必ずクレジット番号などの必要事項を記入して下さい.ご利用のカード会社の期日に合わせて,口座よりお引き落としとなります.カード会社からの明細には「日本地質学会(ニホンチシツガッカイ)」と表示されます.
4) 参加証・各種クーポンは申込締切後に発送します. 大会開催1週間前には参加者の皆様のお手元に届くようお送り致します.発送 時点で入金確認が取れない場合は,未入金の旨記載されたクーポンが送付されますので,当日会場にて入金のご確認をさせて頂きますので、入金 とクーポン発送が入れ違いの場合は,振込み時の控え等を会場にお持ち下さい.確認がスムーズに行えますのでご協力をお願い致します.
(2)申込締切
大会登録専用HP(オンライン)による申込:9月3日(金) 18:00
FAX・郵送による申込:8月30日(月)必着
(3)申込後の変更・取消
(a) 大会登録専用HP(オンライン)でお申込みの場合:
締切までの間は,2010年日本地質学会年会参加申込みホームページから予約の変更・取消が出来ます.変更・取消完了後,「変更・修正 確認メール」が登録のメールアドレスへ配信されます.内容を必ずご確認下さい.締切後は直接学会事務局(東京)にFAX又はe-mailにてご連絡下さい.クレジット決済の場合は,申込の都度決済が完了しますので,決済スケジュールの都合によっては,口座から重複して引き落とされる場合があります.重複の入金については,振込手数料を差し引いた額をクレジットカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2〜3ヶ月要する場合もありますので,ご了承ください.
(b) FAX・郵送でお申込み場合:
申込後に変更・取消が生じた場合は,日本地質学会宛FAX又はe-mailにてご連絡下さい.その際申込受付時に案内される「受付番号」・「氏名」を必ず明記下さい.
(4)取消に関わる取消料と返金について
(a)締切までの取消:取消料は発生しません.返金がある場合は,振込手数料を差し引いた額をクレジットカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2〜3ヶ月要する場合もありますので,ご了承ください.
(b)締切後〜9/15(大会3日前)までの取消:入金・未入金の如何に関わらず,参加費用の50%を取消料としていただきます.返金がある場合は,振込手数料を差し引いた額をクレジットカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2〜3ヶ月要する場合もありますので,ご了承ください.参加費に講演要旨集が付いている方へは,大会後にお送りします.
(c)9/16(大会2日前)以降の取消:入金・未入金の如何に関わらず,参加費用の100%を取消料としていただきます.参加費に講演要旨集が付いている方へは,大会後にお送りします.
日程・プログラム
全体日程・プログラム
■全体日程表(画像をクリックするとpdf版がダウンロードできます) 8.10更新
■各講演プログラム(それぞれの日程をクリックするとpdf形式でご覧になれます)8.24更新
9/18(土)
口頭
9/19(日)
口頭
9/20(月)
口頭
ポスター
ポスター
ポスター
注意:ニュース誌8月号掲載の略記版講演タイトルを掲載しています。正しいタイトルは講演要旨集をご覧下さい。
表彰式・記念講演会
学会各賞表彰式・記念講演
日程: 9月18日(土) 15:20〜17:35
会場: 富山大学五福キャンパス黒田講堂ホール
15:20-15:40
来賓ご挨拶
Prof. Ochir Gerel(モンゴル地質学会国際関係・高等教育担当理事,IUGS副会長)
西頭紱三氏(富山大学学長)
15:40-16:50
新名誉会員,50年会員顕彰式,各賞授与式
16:50-17:05
日本地質学会小澤儀明賞受賞スピーチ 後藤 和久氏
「巨礫を測り続けて5000個 〜見えてきた琉球列島の津波履歴〜」
17:05-17:35
日本地質学会国際賞受賞スピーチ 劉 忠光氏(Dr. Juhn G. Liou)「Subduction-Zone Metamorphism: From Zeolite- through Blueschist- and Eclogite-Facies to Ultrahigh-Pressure Recrystallization」
地学教育・普及・関連行事
地学教育・普及・関連行事
■地質情報展2010とやま —海・山ありて富める大地—
■小さなEarth Scientistのつどい〜第8回小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜
■教員向け見学旅行:糸魚川ジオパーク ヒスイ探訪ジオツアー
■実行委員会主催 堀越 叡追悼特別講演会
地質情報展2010とやま —海・山ありて富める大地—
地質情報展2009あおかやま−会場風景
日程:9月18日(土)〜19日(日)9:30-16:30 (19日は16:00まで) 入場無料
会場:富山市民プラザ(2階:展示と体験コーナー,3階:市民講演会)
主催:一般社団法人日本地質学会・独立行政法人産業技術総合研究所地質調査総合センター
後援:富山市,富山県教育委員会,富山市教育委員会,NHK富山放送局,北日本新聞社,財団法人立山カルデラ砂防博物館,国立大学法人富山大学,日本ジオパークネットワーク,富山県地質調査業協会,社団法人斜面防災対策技術協会富山県支部
内容:日本地質学会富山大会に合わせ,地質調査総合センター,富山市科学博物館ならびに立山カルデラ砂防博物館が有する各種地質情報から,富山県及び周辺の地質現象について展示パネルや映像それに標本を使って紹介します.また,小さなお子さんにも楽しく地学を学んでもらうために化石レプリカ作成などの体験学習コーナーを用意します.さらに次のような市民講演会も予定しています.
詳しくは,http://www.gsj.jp/Info/event/2010/johoten_2010/index.html
■地質学会関連の展示
・地学オリンピック:目指せ金メダル!
毎年開催される国際地学オリンピック.国内の一次選抜(筆記試験)や二次選抜(実技試験)の問題をポスターで展示します.また国際大会の様子を写真で紹介します.
・惑星地球フォトコンテンスト入賞作品展示
2009年に開催された第1回惑星地球フォトコンテストの入賞作品を展示します.国内外のすばらしい写真の数々をご堪能下さい.
9月18日(土) 市民講演会 14:00〜15:40
『北陸の大地をゆるがす地震と恐竜』
講演
東 洋一「アジアの恐竜と日本の恐竜」
寒川 旭「大地に刻まれた地震痕跡」
問合せ先:産業技術総合研究所地質調査総合センター
高橋裕平・中島 礼 TEL:029-861-3549 e-mail:johoten2010.jimu@m.aist.go.jp
* 画像をクリックするとチラシPDFをダウンロードして頂けます。
ページトップに戻る
小さなEarth Scientistのつどい〜第8回 小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜
2009年岡山大会での発表会風景
日本地質学会地学教育委員会では,地学普及行事の一環として,地学教育の普及と振興を図ることを目的として,学校における地学研究を紹介する「地学研究」発表会をおこなっています.富山大会でも,小・中・高等学校の地学クラブの活動,および授業の中で児童・生徒が行った研究の発表を募集いたします.富山県内,また北陸・中部地方の学校,さらには全国の学校の参加をお待ちしています.会場は研究者も発表するポスター会場内に,特設コーナーを用意いたします.同時並行で研究者の発表も行われますので,児童・生徒同士のみならず,研究者との交流もできます.この会を通じて生徒,研究者,市民の交流が進み,地質学,地球科学への理解が深まって,未来を担う生徒たちの学習意欲への良い刺激と励みになることを願っております.
なお,参加証とともに,優秀な発表に対しては審査のうえ,「優秀賞」を授与いたします.
下記の要領にて参加校を募集します.
1) 日時 2010年9月19日(日) 9:00〜15:30
2) 場所 日本地質学会年会ポスター会場(富山大学五福キャンパス)
3) 後援 富山県教育委員会・富山市教育委員会(予定)
4) 参加対象
・小,中,高校地学クラブならびに理科クラブ等の活動成果の発表
・小,中,高校の授業における研究成果の発表
・活動,研究内容は地学的なもの(地質や気象などの地球科学・環境科学,天文など)
5) 申込締切 2010年7月20日(火)締切ました,下記,日本地質学会 地学教育委員会あてお申し込み下さい.
6) 発表形式 ポスター発表(展示パネルは幅 90cm × 高さ180cm程度)
パネルのほかに標本等を展示される場合には,パネルの前に机を用意します.参加申込書にその旨を記載して下さい.その場合は展示パネルの下側が隠れる事をご了承下さい.発表者は決められた時間(および随時)パネルの前に待機し説明をしていただきます.なお,遠隔地および学校行事等のために児童・生徒が参加できない場合は,発表ポスターのみをお送りいただいても結構です.
発表の具体的な準備については,申込後に各校あてご連絡いたします.
7) 参加費 無料(参加者・引率者とも),開催中の研究者の発表,講演も聴くことができます.
8) 派遣依頼 参加者・引率者については希望に応じて学校長宛,日本地質学会より派遣依頼状を出します.
9) 問い合わせ・申込先:参加申込は,別紙書式をFAXして下さい.e-mailでも結構です.
日本地質学会地学教育委員会(担当 三次)
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F
TEL:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156 e-mail:main@geosociety.jp
参加予定校(7月20日現在)
・静岡県立磐田南高等学校
・熊本県立第二高等学校
・明治学園高等学校
・兵庫県立加古川東高等学校
・大阪府立花園
・岡山県立林野高等学校
・香川県立三本松高等学校
・早稲田大学高等学院
・岡山県立倉敷天城高等学校
申込書式はこちらかダウンロードして下さい。
■WORD形式
■PDF形式
ページトップに戻る
第9回理科教員対象見学旅行:糸魚川ジオパーク ヒスイ探訪ジオツアー
恒例となりました理科教員対象見学旅行を,富山大会の最終日に下記の日程・内容で開催いたします.今年は男女共同参画委員会と共同での企画で,昨年の岡山大会と同じく,理科教員以外の参加(一般の方や子供)を想定した1日コースにいたしました.見学旅行のテーマに興味のある方ならどなたでも,日本地質学会非会員の方も参加できますので多くの方々のご参加をお待ちしております.ただし児童・生徒のみの参加は認めておりません,保護者・先生と一緒に参加してください.また富山大会への参加申し込みをしなくてもこの行事に参加できますので,お気軽にお申し込みください.
1)実施日:9月20日(月・祝日)8:45糸魚川駅前集合,観光バス使用
2)テーマ:「糸魚川ジオパーク:ヒスイ探訪ジオツアー」
日本を代表するヒスイの産地,新潟県糸魚川市を訪ねます.地学的な見どころだけでなく,ヒスイと日本人との関係をさまざまな視点(考古学や宝石としてのヒスイなど)から考える,そのような見学旅行です.
3)コース:糸魚川駅→フォッサマグナミュージアム→長者ヶ原考古館・長者ヶ原遺跡→小滝ヒスイ峡→高浪の池(昼食)→寺地遺跡→青海自然史博物館→青海川ヒスイ峡→糸魚川駅16:00解散予定
4)案内者:宮島 宏(フォッサマグナミュージアム)
5)定員:25名
6)費用:5,000円(バス代・保険代・昼食代・見学資料代)
【注意】子供の参加数が予測できませんので,現在のところ参加者一律の金額としていますが,子供の参加がある場合は変更する可能性があります.詳細については申込者へ後日連絡いたします.子供を含め,参加者全員に保険をかけます.
7)申込期限:7月31日(土)<定員に達した場合は,申込を終了させていただきます>
8)申込先:下記の事項をご記入の上,FAXまたはe-mailで日本地質学会地学教育委員会(見学旅行担当)へお申し込みください. FAX:03-5823-1156 / e-mail:main@geosociety.jp
記載事項:申込者の氏名,年齢,所属,連絡先(携帯電話など)
なお児童・生徒など同伴者がいる場合は,保険手続きに必要ですので同伴者全員の氏名・年齢もお知らせください.
9)その他:解散後,東京へは糸魚川駅から在来線特急・上越新幹線乗り継ぎで19:30頃,大阪へは在来線特急で21:30頃に到着することができます.
申込書式はこちらかダウンロードして下さい。
■WORD形式
■PDF形式
昨年の教師巡検(2009岡山)「万成石と文化地質学」の様子はコチラ。
実行委員会主催 堀越 叡追悼特別講演会
富山大会実行委員会 主催 資源地質学会 共催
日時:9 月19日(日)14:00〜17:00
会場:富山大学理学部2階多目的ホール
昨秋亡くなられた堀越 叡会員は,黒鉱鉱床や別子型鉱床の成因を地質学的に解明された世界的に著名な資源地質学者です。また,地殻進化の立場から,地球史を考え,我が国でもっとも早くプレートテクトニクスの前段階となる考えを受け入れた地質学者でもあります。同氏を追悼し,資源地質学や地殻進化学の未来を語る特別講演会を企画いたしました。
【プログラム】
14:00 開会の辞 鎮西清高・石原舜三
14:05 E-1 堀越 叡教授の「地殻進化学」大藤 茂・鎮西清高・島崎英彦
14:15 E-2 福井県九頭竜川上流の飛騨外縁帯 松本孝之
14:30 E-3 環日本海地域の花崗岩とメタロジェニー:環太平洋の東西のコントラストに関連して 佐藤興平
14:45 E-4 黒鉱鉱床の古海洋学的位置 小室光世・伊藤孝
15:00 E-5 黒鉱層準の再検討:微量成分による酸性岩類解析法 水田敏夫・緒方武幸・ティ・トゥラ・ジョウ・石山大三
15:15 E-6 沈殿カイネテイックスと黒鉱鉱床における鉱物ゾーニング 鹿園直建
15:30 E-7 数理的手法による黒鉱鉱床の資源解析 古宇田亮一
15:45 E-8 黒鉱類似鉱床あるいは黒鉱の末端現象に関る諸問題 山田亮一・長瀬敏郎・長谷川樹
16:00 E-9 日立藤見鉱床の高温接触変成作用と鉱石の化学組成 黒 清貴・加瀬克雄
16:15 E-10 Re-Os放射壊変系による別子型鉱床の生成年代決定と顕生代のグローバル海洋環境変遷 野崎達生・加藤泰浩・鈴木勝彦
16:30 E-11 現世海底熱水鉱床の現場から振り返って見た黒鉱鉱床成因論争 浦辺徹郎
16:45 総合討論 石原舜三・鎮西清高
※本特別講演会の講演要旨は,富山大会講演要旨集に同時収録されます.
問い合わせ先:富山大会実行委員会 大藤 茂
e-mail: shige@sci.u-toyama.ac.jp 電話 076-445-6655
ページトップに戻る
シンポジウム
シンポジウム
演題・講演要旨締切:
オンライン 7月7日(水)17時(郵送7月2日(金) 必着)
7月8日(木)昼12時まで 締切延長
講演申込はこちらから
(修正・変更もこちらから)
今年は8件のシンポジウムを開催します.9月18日〜20日の3日間,各日2-3件ずつ行います.
シンポジウムの講演者には,一般発表の1人1件の制約は及びませんので,シンポジウムの講演者(会員)は別途セッションでも講演を申し込むことができます.また昨年同様,世話人は,会員・非会員を問わず招待講演を依頼することができます.なお,非会員の招待講演者に限り参加登録費は免除となります(講演要旨集は付きません.必要な場合は,別途購入して下さい).一般公募の採択・不採択は,世話人によって決定されます.シンポジウムの一般募集に対して発表を申し込む場合,発表希望者はコンビーナに事前に連絡をとって承認を受けてから講演申込システムに入力して下さい.コンビーナへの事前連絡なしに講演申込をした場合,発表できない場合があります.また,講演を一般募集しないものがありますので,ご注意下さい(今回は5件で一般募集がありません).
講演要旨原稿は,一般発表と同じ分量ですので,原稿フォーマットを参照して原稿の作成をお願いします.
(各タイトルをクリックすると、詳細をご覧いただけます)
1)富山深海長谷とその周辺部の堆積作用と後背テクトニクス・気候(一般公募なし)
2)海底地盤変動学シンポジウム「魁!海底地盤変動塾」(一般公募あり:1-2件)
3)ガスハイドレートの起源と環境・資源へのインパクトはどこまで明らか になったか?(一般公募あり)
4)南海トラフ沈み込み帯研究の最新成果(一般公募なし)
5)故藤田和夫追悼シンポジウム,アジアの山地形成論(一般公募なし)
6)故勘米良亀齢追悼シンポジウム,造山帯を読み解く(一般公募なし)
7)島孤地殻で発生するメルトー流体の挙動 (一般公募なし)
8)21世紀モホール(一般公募あり:基本的にポスター発表で10件程度)
↑このページのTOPに戻る
1)富山深海長谷とその周辺部の堆積作用と後背テクトニクス・気候
Sedimentological features and tectono-climatic background of the Toyama deep-sea channel and vicinities
中嶋 健(産総研)・高野 修*(JAPEX技研;osamu.takano@japex.co.jp)・金子光好(ジャパンエナジー石油開発)
富山深海長谷は世界的にも有数のチャネル長を保持し,チャネルレビーシステムやセディメントウェーブ,ターミナルファンなど,教科書的な様々なタービダイトの堆積形態を示すとともに,東北日本弧と西南日本弧の境界付近に位置することや,有数の隆起帯である北アルプスと直結することから,後背テクトニクスや気候変動の記録体としても注目される.近年,探査技術の向上により,より詳細な堆積スタイルが明らかになり,後背テクトニクスや気候変動の研究も進展しつつあることから,本シンポジウムでは,これらの研究を紹介し,堆積作用や後背テクトニクス・気候の議論を行うこととしたい.(一般公募なし)
2)海底地盤変動学シンポジウム「魁!海底地盤変動塾」
Symposium of current researches on submarine landslides and related topics
川村喜一郎*(深田研;kichiro@fgi.or.jp)・金松敏也(JAMSTEC)・坂口有人(JAMSTEC)・山本由弦(JAMSTEC)
大規模な海底地すべりは,きわめて大きな津波を引き起こすことが指摘されているが,その実体は良くわかっていない.たとえ大規模な地すべりでなくとも,沿岸構造物や海底ケーブルなどの海底敷設物へ被害や石油などの海底資源開発への影響が懸念されている.世界的にも統合国際掘削計画の次期サイエンスプランを検討する「INVEST」会議(2009年9月ブレーメン)において,海底地すべりは海洋ジオハザードを考える上での重要な議題となり,またIGCP-511として国際海底地すべりシンポジウムが開催され続けている.なおこのプログラムは「the 5th International Symposium on Submarine Mass Movements and Their Consequences」として2011年にアジアで初めて京都大学にて開催される.世界的にも盛り上がりを見せている海底地すべり研究ではあるが,しかし巨大地震が頻発するプレート収束帯の研究はほとんど手つかずの状態である.変動帯の海底地すべり科学の先鞭をつけ,世界をリードしていくために本シンポジウムを企画した.幅広い分野の関係者,そして多くの若者にも参集してもらいたい.(一般公募あり:1-2件)
3)ガスハイドレートの起源と環境・資源へのインパクトはどこまで明らかになったか? 研究動向と新展開
Who knows the origin and consequences of marine gas hydrates? Present and future of gas hydrate science.
松本 良*(東京大;ryo@eps.s.u-tokyo.ac.jp)・角和善隆(東京大)・町山栄章(JAMSTEC)・棚橋 学(産総研)
第100年学術大会(東大駒場)で初めてガスハイドレートシンポジウムを開催してからすでに16年,国際深海掘削計画によるガスハイドレート掘削(1995)から15年,経産省/資源エネルギー庁が本格的資源化プロジェクトを始めて10年.国内外でガスハイドレート研究と探査が進み,海洋のガスハイドレートの分布,産状に関する知見は飛躍的に拡大した.その資源ポテンシャルは「将来の夢」としてではなく「明日のエネルギー」として現実的なものとなりつつある.一方,環境インパクトは当初想定していた温暖化=大量分解というほど単純なものではないことも分かってきた.国のプロジェクトとしては南海トラフにおける探査が進められているが,私たちは2004年より日本海東縁・上越沖と北海道奥尻島沖に,メタンフラックスが極めて高い海域を発見し,複合領域的調査を展開し,従来とは異なり集積度の極めて高いハイドレート鉱床を発見しその起源と進化を説明するモデルを提唱し,分解効果を地質学的時間軸の中で評価している.高集積ガスハイドレートは東縁変動帯の比較的浅部に広く分布することが予想され,当該海域のガスハイドレートとメタン活動は,資源ポテンシャルと現海洋環境へのインパクトという両面から重要である.本シンポジウムでは富山湾・上越沖だけでなく当該海域と同様の産状を示す内外の例も含め,変動帯におけるメタン活動とガスハイドレート・システムの進化について知見を統合し”新しい炭素シンク”であるガスハイドレートの人間社会への意義について多角的に議論する.(一般公募あり)
↑このページのTOPに戻る
4)南海トラフ沈み込み帯研究の最新成果
Update of Nankai Trough subduction zone researches
橋本善孝*(高知大;hassy@cc.kochi-u.ac.jp)・氏家恒太郎(JAMSTEC)
南海トラフ沈み込み帯では,2010年秋から地球深部探査船「ちきゅう」による1944年東南海地震震源域を目指した超深度掘削(ステージ3)にいよいよ着手する予定です.一方で,2007-2008年と2009年にそれぞれ実施されたステージ1とステージ2の航海後研究では,掘削コア,孔内検層・計測等による最新のデータが積み上がっています.また地震観測網の充実に伴い,最近になって沈み込みプレート境界やアウトオブシークエンススラスト付近などで様々なスロー地震が発生していることが明らかになってきました.このように南海トラフ沈み込み帯を対象に観察,実験,観測,理論といった多種多様なデータによる研究成果があがりつつあります.そこで,南海トラフ沈み込み帯に関する最新の研究成果の紹介・議論を中心としたシンポジウムを企画致します.(一般公募なし)
5)故藤田和夫追悼シンポジウム,アジアの山地形成論:日本列島からヒマラヤまで
Memorial Symposium of Late Professor Kazuo Huzita— Morphogenesis of mountain ranges in Asia: from Japanese island arcs to Himalayas
酒井治孝*(京都大;hsakai@kueps.kyoto-u.ac.jp)・竹村恵二(京都大)・竹内 章(富山大)
本シンポジウムの目的は,近畿のネオテクトニクスとアジアの変動帯の山地形成を論じ,日本の地質学の発展に大きな功績を残された故藤田和夫,大阪市立大学教授を追悼すると同時に,第四紀に日本列島とアジア各地の変動帯で何が起こったのかを,最近の研究の進歩に基づき総合的に検討し,今後の研究の進むべき道を探ることにある.藤田和夫氏の研究の成果は,1983年に出版された2冊の著書に集約されている.その結論は,「アジアの変動帯の大部分は新第三紀末にいったん準平原化され,第四紀に入って急激に隆起あるいは沈降して現在の大地形の枠をつくった」ということであった.その出版後,四半世紀が経過したが,その間に発生した兵庫県南部地震,集集地震,中越地震,四川地震などを契機に活断層と地震活動の研究は飛躍的に進歩した.また西南日本各地の第四紀の山地と盆地形成過程についても,多くの新しいデータが蓄積され,モデルが提唱され,数値シミュレーションによる検討も行われている.さらに地質学的な基礎データの乏しかったヒマラヤ山脈やチベット高原,インドシナ地域についても,地質学的な研究のみならず,測地学的,地震学的研究も飛躍的に進み,各変動帯の運動像の概要が得られ,山地形成のメカニズムが論じられるようになった.本シンポジウムでは,以下の3つのセクションを設け,最後に総合討論を行う.1.日本列島:(1) 近畿・中国地域,(2) 新潟・北アルプス地域,2.アジアの変動帯:(1) 台湾・東南アジア,(2) チベット高原とその周辺,(3) ヒマラヤ山脈とその周辺,3.測地・地震・モデル,4.総合討論 これらの発表と質疑を通じ,アジア大陸と日本列島の第四紀地殻変動像を描くことを目指す.(一般公募なし)
↑このページのTOPに戻る
6)故勘米良亀齢追悼シンポジウム,造山帯を読み解く
Memorial Symposium of Late Professor Kametoshi Kanmera—Anatomy of Orogenic Belt
西 弘嗣*(東北大学総合学術博物館;hnishi@m.tains.tohoku.ac.jp)・磯崎行雄(東京大)・酒井治孝(京都大)
本シンポジウムの目的は,1974年に世界に先駆け海溝における付加作用のモデルを提唱し,日本列島という造山帯の形成史を全く新しい視点で構築した故勘米良亀齢,九州大学教授を追悼すると同時に,造山帯の研究で,何が,どこまで解ったのか,そして何が未解決の重要な問題なのかを検討することにある.勘米良亀齢氏は1980年に日本で初めて,付加,小大陸の衝突,縁海の拡大という概念を用いて日本列島の形成過程を論じた.その後30年が経過し,世界各地で付加体の深海掘削が実施されると同時に,陸上の造山帯の研究についても飛躍的に研究が進み,海溝付加型および大陸衝突型造山帯の双方について新しいデータが蓄積され,多くのモデルが提唱されている.本シンポジウムの前半のセッション「造山帯を構成する地質体を読み解く」では,チャート,炭酸塩岩,メランジュなどの地質体に関する最近の研究の進歩を総括する.後半のセッション「造山帯の基本構造を読み解く」では,ナップ構造とデタッチメントの形成プロセスとメカニズム,延性剪断帯と変成岩の上昇に関する諸問題などについて議論する.これらの発表と質疑を通じ,造山帯研究の今後の進むべき方向を総合的に検討する.(一般公募なし)
7)島孤地殻で発生するメルト-流体の挙動 -地震学,高圧実験,岩石からの制約‐
Melt-Fluid behavior in arc crust -constraints from seismology, high pressure experiment and petrology-
岡本和明*(埼玉大;kokamoto@mail.saitama-u.ac.jp)・渡辺 了(富山大)・寺林 優(香川大)
沈み込み帯,島孤深部で発生する流体・メルトはさまざまな地質現象を引き起こす.沈み込み帯深部では,「スラブからの脱水流体がマントルウエッジを上昇する」,と考えられてきた.スラブでの脱水流体やマグマだまりから分離する流体は,詳細なトモグラフィーで検出できるまで地震学的に解明されている.しかし脱水流体は温度,圧力等の変化に応じてH2O主体のさらさらの流体からどろどろのメルトまで変化する.またマントルウエッジの部分融解で生じる島孤マグマは上昇の過程でメルト‐流体の分離が起こる.流体‐メルトの挙動を精密に理解するには,高圧実験,岩石学,野外地質学を組み合わせた包括的研究が重要である.平成21年度より東工大高橋栄一教授をリーダーとする地殻流体の総合研究が始まっており,世話人たちもメンバーに含まれている.今シンポジウムでは,1)スラブでの流体‐メルト,2)中部地殻でのマグマからの流体の分離に焦点を絞って話題提供を行いたい.(一般公募なし)
↑このページのTOPに戻る
8)21世紀モホール:マントル掘削計画現状と今後
21st Century Mohole: the present status and the future plan for the Mantle drilling
阿部なつ江*(JAMSTEC;abenatsu@jamstec.go.jp)・海野 進・(金沢大)・倉本真一(JAMSTEC)
年平均にして地球上のマグマ活動のおよそ80%を占める中央海嶺において形成され,沈み込み帯でマントルへと戻ってゆく海洋プレートは,マントル対流の上部熱境界層として地球発達史の中で重要な役割を担っている.また海洋プレートは,海水との反応により,地球内部と地表との熱物質交換のフロントでもある.この様に海洋プレートは,太陽系惑星の中でも水惑星「地球」に固有のプレートテクトニクスの主役を担っている.海洋モホ面を貫き,海底面から最上部マントルまで掘削する計画「21世紀モホール計画」は,IODPにおける重要課題の一つとして,初期科学計画(ISP) から取り上げられ,第2期科学計画においても最優先課題の一つとなることが,2009年9月に行われたINVESTなどのワークショップで確認された.海洋プレートの構造・進化過程の解明,海水との反応フロント(即ち地下生命圏フロント)の探求など,モホール計画では,モホの実体解明やマントル物質採取以外にも,様々な科学成果が期待できる.マントルまでの掘削技術は,今後数年間の内に開発される予定である.一方で,掘削地点を決定するには,現在入手できるデータだけでは不十分であり,さらなる海域調査およびオフィオライトなどの岩石試料を用いた研究が不可欠である.2010年6月には,掘削候補地点の絞り込みと,今後の調査計画,さらに掘削・計測技術開発のロードマップ作成のための国際ワークショップが金沢で開催される予定である.そこで本シンポジウムでは,この数年のモホール計画進捗状況を確認し,今後の計画について議論したい.なお,掘削,計測技術開発に関わる技術者や,岩石学,地球化学,生物学,地球物理学など,モホール計画には,地質学会内外の幅広い分野が関係する.そのため,幅広く会員,特に次世代を担う学生にも参加して貰い議論を深め,計画への参加を促進したい.(一般公募あり:ポスターのみ10件程度)
↑このページのTOPに戻る
参加登録費
参加登録
■参加登録フォームはこちらから■
*「各種の申込方法とお支払いについて」はこちら
申込締切 オンライン 9/3(金)18:00, FAX/郵送 8/31(火)必着
当日会場受付での混雑緩和のため,事前に参加登録申込をお願いします.大会参加登録およびそれに伴う参加費は,全ての参加者(見学旅行のみの場合も)に必要な基本的なお申込です.ただし,会員が同伴する非会員の配偶者ならびに子供については必要ありません.
参加登録費
講演要旨集付です.講演要旨集が不要の場合でも割引はありません.なお,学部割引会員・名誉会員・50年会員・非会員(招待講演・学部学生)の参加費には,講演要旨集は含まれません.ご希望の方は,別途ご購入下さい.
事前申込
当日払い
正会員・共催/協賛団体会員
7,500円
9,500円
要旨集付き
院生割引会費適用正会員
4,500円
6,500円
要旨集付き
学部割引会費適用正会員・名誉会員・50年会員
0円
0円
非会員(一般・院生)
12,000円
15,000円
要旨集付き
非会員(学部学生)
0円
0円
非会員(招待講演)
0円
0円
*なお,大会に参加できなかった場合は,講演要旨集付きの方へは、大会後に講演要旨集をお送りします.参加登録費用の返却はいたしませんのでご了承下さい.
*共催・協賛団体に会員として所属する方の参加登録費は正会員と同額になります.
見学旅行
見学旅行
■申込(参加登録フォーム)はこちらか ら■
★各コースの「魅力・みどころ」ご紹介★
*「各種の申込方法と お支払いについて」はこちら
総計9コースの見学旅行(A〜I班)を計画しました.見学旅行の参加申込は,「各種の申 込方法と お支払いについて」を参照し,申し込んで下さい.参加希望の方は,Web申込手続き手順に従って参加申込を行って下さい.FAX・郵送でのお申込は,ニュース誌掲載の専用申込書を用い,学会事務局(東京)宛に大会参加申込と一緒に申し込んで下さい.見学旅行だけに参加する場合も大会参加登録ならびに参加登録費は必要です.見学旅行と大会参加登録の申込を合わせて行って下さい.
申込に際し,希望の班が満員の場合に備え,①キャンセル待ち,②第2希望の班の指定,③他班希望なくキャンセル待ちせず,のいずれかを必ず指定して下さい.
(1) 参加申込人数が各見学コースの実施最小人数に達しなかった場合,見学旅行を中止することがありますので,早めに申し込んで下さい.
(2) 非会員の方は,申込締切時点で定員に余裕があれば参加可能となりますので,あらかじめ申し込んでおいて下さい.
(3) 日本地質学会ならびに同富山大会実行委員会は見学旅行参加者に対し,見学旅行中に発生する病気,事故,傷害,死亡等に対する責任・補償を一切負いません.これらについては,見学旅行費用に含まれる保険(国内旅行傷害保険団体型)の範囲でのみまかなわれます.
(4) 子供同伴など特別な事情がある場合は,申込前に現地事務局へあらかじめ問い合わせて下さい.
(5) 締切までの間は,ホームページから変更・取消が出来ます.変更・取消完了後,「変更・修正 確認メール」が登録のメールアドレスへ配信されます.内容を必ずご確認下さい.締切後は必ず直接学会事務局(東京)にFAX又はe-mailにてご連絡下さい.締切後は入金・未入金の如何に関わらず,取消料が発生します(詳しくは,「各種の申 込方法とお支払いについて」の取消料の項目参照).
(6) 集合・解散の場所,時刻などを変更することもありますので,大会期間中は掲示などの案内に注意して下さい.
(7) 見学旅行の解説は案内書を使って行います.参加申込時にあらかじめ予約購入して下さい.
*取消料は,申込締め切り後〜出発3日前までは50%,2日前以降は全額となります.
*参加費用には旅行傷害保険(500円)が含まれています.
*集合地点まで,および解散地点からの交通費は各自の負担となります.
*参加費用はあくまで概算の金額です.大きな過不足が生じた場合,見学旅行終了時に調整します.
*案内書は費用には含まれていません.参加申込時に予約購入の手続きを合わせて行ってください.
*集合・解散の場所・時刻等に変更が生じた場合,学会期間中は掲示板に案内されます.
*参加者人数が少ない場合,見学旅行が中止になることもあります.
*レンタカーを使用する場合,参加者の皆様に運転をお願いすることがあります.
コース詳細(各コース名をクッリクすると詳細がご覧いただけます)別途各コースの「みどころ」はこちら
A班 第四紀
F班 飛驒から日本海
B班 跡津川断層
G班 手取層群
C班 立山火山
H班 ジオパークの地質
D班 焼岳火山
I班 ジオパーク ヒスイ楽
E班 黒部川
※一般の見学旅行とは別に「第9回理科教員対象見学旅行」を,I班と同じ内容で9/20(月・祝)に実施予定です.くわしくはコチラ。
A:富山積成盆地,北陸層群の広域テフラと第四紀テクトニクス
<第四紀>
見学コース:
9:00富山駅→小矢部→呉羽山→上市→魚津→17:00富山駅解散
主な見学対象:
大桑層・音川層相当層中の鍵テフラ,呉羽山礫層中の火砕流堆積物,呉羽山断層・魚津断層の活動による地形面の変形
日程:9月21日(火)日帰り
定員:12名
案内者:田村糸子*・山崎晴雄(首都大)・中村洋介(立正大)
概算費用:7,000円(昼食込)
地形図:倶利伽羅・富山・上市・五百石・越中大浦(1/2.5万)
備考:JR富山駅前集合・解散.ワゴン車(レンタカー)使用
ページTOPに戻る
B:跡津川断層系の変動地形と断層露頭
<跡津川断層>
見学コース:
9月21日 8:00 富山大学発→神岡町土→跡津川→東漆山→(山之村—東谷ゲート)→大多和峠→瀬戸谷→祐延貯水池→水須→亀谷温泉
9月22日 8:00亀谷発→有峰湖東岸→折立→真川湖成層→断層露頭→16:50富山駅→17:20富山空港
主な見学対象:
跡津川断層東半部対象.断層破砕帯や活断層の露頭,段丘の横ずれ変位,河道閉塞,流系のオフセット,飛越地震の傷跡を観察する.
日程:9月21日(火)〜9月22日(水)(1泊2日)
定員:20名
案内者:竹内 章*(富山大)・道家涼介(地層科学研究所)・ハスバートル(土木研究所)
概算費用:21,000円(2日目の昼食込)
地形図:五百石・有峰湖・槍ヶ岳・立山(1/5万)鹿間・有峰湖・小見・薬師岳・立山・千垣・東茂住(1/2.5万)
備考:富山大学黒田講堂前集合.中型バス使用.1日目の昼食は各自でご用意下さい.JR富山駅前解散,富山空港・富山大学まで乗車可.
C:立山火山
<立山火山>
見学コース:
9月21日 8:00 富山駅→千寿ヶ原→美女平→大観台→獅子ヶ鼻岩→カルデラ展望台→天狗山→玉殿岩屋→室堂平
9月22日 8:00 室堂平→室堂山→室堂平→雷鳥荘→赤壁→黒壁→地獄谷→室堂平→富山空港→JR富山駅
主な見学対象:
弥陀ヶ原-室堂平の火砕流・溶岩流・テフラ層の観察を行なう.カルデラ縁の展望台からカルデラ及び五色ヶ原の噴出物を遠望する.
日程:9月21日(火)〜9月22日(水)(1泊2日)
定員:20名
案内者:中野 俊*(産総研)・奥野 充(福岡大)・菊川 茂(立山カルデラ砂防博)
概算費用:17,000円(2日目の昼食込)
地形図:立山・小見(1/2.5万)
備考:JR富山駅北口集合.中型バス使用.1日目の昼食は各自でご用意下さい.富山空港経由、JR富山駅北口解散(17:00頃)
ページTOPに戻る
D:焼岳火山の大規模ラハールと火砕流堆積物
<焼岳火山>
見学コース:
9月21日 8:30富山駅出発→中尾→穂高砂防観測所→白水谷→白谷山麓→中尾温泉(泊)
9月22日 8:30中尾温泉→本郷→上宝観測所→神岡→猪谷→17:20富山空港・18:00富山駅(解散)
主な見学対象:
焼岳火山起源の大規模ラハールおよび火砕流堆積物.焼岳火山のマグマ・システムおよび火山活動史.砂防および地震観測所の見学.
日程:9月21日(火)〜9月22日(水)(1泊2日)
定員:13名
案内者:及川輝樹*(産総研)・石崎泰男(富山大)・片岡香子(新潟大)
概算費用:21,000円(2日目の昼食込)
地形図:焼岳・笠ヶ岳・長倉・船津・東茂住・猪谷(1/2.5万)
備考:JR富山駅前集合・解散(帰りは富山空港による).レンタカー使用.1日目の昼食は各自御用意下さい.雨天時は観測所,資料館を中心に見学.
E:黒部川沿いの高温泉と第四紀黒部川花崗岩
<黒部川>
見学コース:
9月21日 9:15黒部峡谷鉄道宇奈月駅集合(地鉄富山駅7:19発).宇奈月駅9:42発→10:06黒薙駅. 黒薙温泉見学 黒薙駅11:30発→12:04鐘釣駅 鐘釣温泉見学 鐘釣駅13:50発→14:12 欅平駅→祖母谷温泉(泊)
9月22日 祖母谷温泉→祖父谷→欅平11:46発→13:04宇奈月解散(地鉄富山駅14:54着の連絡有り)
主な見学対象:
黒部川沿いの高温泉(黒薙温泉・鐘釣温泉・祖母谷温泉),白亜紀北又谷トーナル岩,新第三紀黒部別山花崗岩・欅平閃緑岩,黒部川マイロナイト帯,第四紀黒部川花崗岩
日程:9月21日(火)〜9月22日(水)(1泊2日)
定員:14名
案内者:原山 智*(信州大)
概算費用:16,000円
地形図:黒部(1/5万)宇奈月・黒薙温泉・欅平(1/2.5万)
備考:黒部峡谷鉄道宇奈月駅集合・解散.昼食は、1日目が鐘釣温泉で、2日目は欅平駅で各自とります(持参も可).
ページTOPに戻る
F:年代学から見た飛驒変成作用から日本海誕生後までの構造発達史
<飛驒から日本海>
見学コース:
9月21日 8:00富山大学出発→八尾町→岩稲・楡原→神岡町吉ヶ原・船津→横山衝上断層→庵谷→富山空港→17:15富山駅解散
主な見学対象:
飛驒変成作用による花崗岩ミロナイトと単斜輝石ミグマタイト、白亜紀飛驒帯上昇に関係する神岡鉱床杢地鉱と横山衝上断層、手取層群中の中朝・揚子衝突帯起源の花崗岩礫、日本海形成前の新第三紀層(飛驒帯起源砕屑粒子あり)と形成後の新第三紀層(同左なし)
日程:9月21日(火)日帰り
定員:20名
案内者:椚座圭太郎*・清水正明(富山大)
概算費用:3,500円
案内者:八尾・猪谷・東茂住・鹿間・船津(1/2.5万)
備考:富山大学黒田講堂前集合.中型バス使用.昼食は各自でご用意下さい.希望があれば富山空港経由、JR富山駅前解散,富山大学まで乗車可.
G:富山県に分布する上部ジュラ〜下部白亜系手取層群の海成層と恐竜足印化石
<手取層群>
見学コース:
9月21日 8:00JR富山駅発→有峰北東部東坂森谷→大山地域の恐竜足印化石発掘現場→八尾町(泊)
9月22日 8:30八尾町発→八尾町南部牛負→16:00JR富山駅解散
主な見学対象:
有峰層・桐谷層の岩相と生痕化石,和佐府層の恐竜足印化石の産状.
日程:9月21日(火)〜9月22日(水)(1泊2日)
定員:10名
案内者:平澤 聡*(京都大)・柏木健司(富山大)・藤田将人(富山市科博)
概算費用:23,000円(2日目の昼食込)
地形図:猪谷・小見・千垣(1/2.5万)
備考:JR富山駅前集合・解散.レンタカー使用.1日目の昼食は各自でご用意下さい.
ページTOPに戻る
H:糸魚川ジオパークの地質巡り
<ジオパークの地質>
見学コース:
9月21日 9:00糸魚川駅発→フォッサマグナミュージアム→フォッサマグナパーク→琴沢石切場→虫川→不動滝→不動滝北方採石場→糸魚川市根知(泊)
9月22日 8:30根知発→青海川金山谷出会→橋立ヒスイ峡→デンカ東山切羽→16:00糸魚川駅解散
主な見学対象:
フォッサマグナミュージアム,糸魚川-静岡構造線,中新世枕状溶岩,舞鶴帯構成岩類(火成岩,堆積岩),秋吉帯構成岩類(砂岩,珪質岩,青海石灰岩),舞鶴帯・秋吉帯境界断層,蓮華変成岩,ひすい岩
日程:9月21日(火)〜9月22日(水)(1泊2日)
定員:20名
案内者:竹内 誠*(名古屋大)・竹之内耕(フォッサマグナミュージアム)・中澤 努(産総研)
概算費用:21,000円(2日目の昼食込)
地形図:小滝・糸魚川(1/2.5万)
備考:JR糸魚川駅前集合・解散.マイクロバス使用.1日目の昼食は各自でご用意下さい.
I:糸魚川ジオパーク ヒスイ探訪ジオツアー 謎多きヒスイを多角的に楽しもう
(色・かたさ・生成・加工と利用・再発見・ストロンチウム鉱物…)
<ジオパーク ヒスイ楽>
見学コース:
9月17日 8:45糸魚川駅前集合,8:50糸魚川駅発→フォッサマグナミュージアム(FMM)→長者ケ原考古館・長者ケ原遺跡→小滝ヒスイ峡→高浪の池→寺地遺跡→青海自然史博物館→青海川ヒスイ峡→16:00糸魚川駅前解散
主な見学対象:
ヒスイの自然科学的な謎(FMM,小滝ヒスイ峡,青海川ヒスイ峡など),ヒスイの人文科学的な謎(FMM,長者ケ原考古館など),さまざまな色のヒスイ,宝石質ヒスイ,日本最大の巨大ヒスイ,ヒスイの中に含まれるストロンチウム新鉱物(糸魚川石など)
日程:9月17日(金)日帰り
定員:25名
案内者:宮島 宏*(フォッサマグナミュージアム)
概算費用:5,000円(昼食込)
備考:糸魚川ジオパークマップ(ミウラ折)を配布,小滝・糸魚川(1/2.5万) JR糸魚川駅集合・解散.観光バス使用.昼食は小滝ヒスイ峡近傍の高浪の池のレストランでとります.
ページTOPに戻る
就職支援プログラム
就職支援プログラム
富山大会就職支援プログラム
2009年岡山大会時の様子
来る9月18日から富山大学において日本地質学会第117年学術大会を開催いたします。本年 も、表記「就職支援プログラム」を開催することになりました。本プログラムは、学会に参加される学生・院生および大学教官の会員、ならびに富山大学の学 生・院生・関係者らを対象に、本会賛助会員をはじめとする関連会社との相互の情報交換を行う場を提供しようというものです。
つきましては、ぜひご参加いただきますようご案内をいたします。なお、昨年の就職支援プログラムの様子はホームページでもご紹介しています.
<開催・募集要領>
日 程 2010年9月19日(日)14:00-17:00(*時間帯は若干変更に なる場合があります)
場 所 富山大学 五福キャンパス 共通教育等E棟
主 催 一般社団法人日本地質学会
内 容 主催者等 挨拶・紹介、参加各社による数分のプレゼンテーション.
参加各社の個別説明会(パネル、配布資料等をご用意ください).
対 象 富山大会に参加する学生・院生および大学教官等の会員・富山大学の学生・院生および教官等
参加費 無料
参加予定企業・団体(敬称略・8/10現在):株式会社クレアリア,石油資源開発株式会社,ジーエスアイ株式会社,株式会社ダイヤコンサルタント,明治コンサルタント株式会社,(独)産業技術総合研究所,川崎地質株式会社
問い合わせ先
▶ 2009年岡山大会:就職支援プログラムの様子はこちらから。
就職支援(2009岡山大会の様子)
第116年岡山大会:就職支援プログラム(2009.9.5開催)
2007年札幌大会から始まった就職支援プログラムは,岡山大会で第3回目となりました.このプログラムの目的は,就職を希望される学生・院生会員と,民間企業・団体,研究機関等とが直接相対し,情報交換をしていただく場を提供することです.
本大会では,民間企業に加えて,研究機関として初めて産業技術総合研究所に参加していただきました.9月5日14〜17時まで,企業展示会場脇のスペースで,まず企業説明会形式で参加企業8社と産総研からのプレゼンテーションを行い,その後各社・機関の出展ブースで詳しい説明や質疑応答に参加していただきました.今年も,各ブースでは終了時間いっぱいまで熱心に説明に聞き入る学生の姿が見られ,若手会員のニーズの手ごたえを感じました.
就職支援プログラムは,来年以降も継続の予定です.できるだけ多くの企業・研究機関等にご参加いただき,また,特に学生を指導されている教官の方々にもぜひ会場に足を運んでいただきたいと思います.充実した情報交換ができるよう,開催方法についても工夫していきますので,ご要望がありましたら,理事会担当までお知らせくださいますようお願いいたします.最後に,本行事に参加いただいた企業8社と産総研の皆様,企画にご協力をいただいた賛助会員,関連企業の皆様,および大会準備委員会に,改めて御礼申し上げます.
各社によるプレゼンテーション
各社ブースの様子
参加企業・団体(敬称略):(株)アイ・エヌ・エー,応用地質株式会社,石油資源開発株式会社,ジーエスアイ株式会社,中央開発株式会社,太平洋セメント 株式会社,株式会社ダイヤコンサルタント,明治コンサルタント株式会社,(独)産業技術総合研究所
(担当理事:運営財政部会 向山 栄)
2010年富山大会ページへ戻る
会場・交通
会場・交通
一般発表,シンポジウム,表彰式・記念講演会,
関連普及行事・生徒「地学研究」発表会
富山大学五福キャンパス共通教育棟
(富山市五福3190)
地質情報展・市民講演会
富山市民プラザ
(富山市大手町6-14)
懇親会
富山県民会館内レストラン「キャッスル」
■大学構内(会場)地図(クリックするとPDFがダウンロード出来ます)
◯富山大学までは〜
<JR高山本線利用の場合>
・ 西富山駅より徒歩20分
<富山地方鉄道路線バス利用の場合>
・ JR富山駅南(正面)口交通広場 富山地方鉄道路線バス3番乗場【富山大学方面】発の全てのバス(路線番号10,11,12,14,15,16,19)にて「富山大学前」下車(約20分,230円).
<富山地方鉄道市内電車利用の場合>
・ JR富山駅南(正面)口交通広場 「富山駅前」より2系統【大学前】行き市内電車にて,終点「大学前」下車(約20分,200円).進行方向へ徒歩5分
※富山大学五福キャンパスは駐車スペースが少ないため,乗用車でのご来訪は極力ご遠慮ください.
申込締切一覧
各種申込締切一覧
WEB
FAX・郵送
問い合せ先
講演申込
7/7(水)17時
7/2(金)必着
詳細
行事委員会
講演要旨原稿提出
7/7(水)17時
7/2(金)必着
詳細
行事委員会
WEB
FAX・郵送
大会参加(参加登録費)
9/3(金)18時
8/31(火)必着
詳細
学会事務局
見学旅行
9/3(金)18時
8/31(火)必着
詳細
学会事務局
懇親会
9/3(金)18時
8/31(火)必着
詳細
学会事務局
追加講演要旨・見学旅行案内書
9/3(金)18時
8/31(火)必着
詳細
学会事務局
お弁当
9/3(金)18時
8/31(火)必着
詳細
学会事務局
保育室
9/10(金)
-------
詳細
男女共同参画委
学童ファミリープラン
-------
詳細
男女共同参画委
生徒地学研究発表会
7/20(火)
-------
詳細
地学教育委
教員用巡検
準備中
-------
詳細
地学教育委
ランチョン・夜間小集会
7/2(金)
詳細
行事委員会
一次締切
最終締切
広告協賛
7/30(金)
-------
詳細
現地事務局
企業展示の出展
7/9(金)
8/6(金)
詳細
現地事務局
書籍・販売ブース
7/9(金)
8/6(金)
詳細
現地事務局
就職支援プログラム
準備中
-------
詳細
学会事務局
問い合わせ
富山大会問い合わせ先
■大会会期中の問い合わせ先
日本地質学会第117年学術大会 現地事務局
e-mail:gsj2010@academicbrains.jp
■日本地質学会行事委員会 / 地学教育委員会 / 学会事務局(東京)
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目8-15 井桁ビル6F
TEL 03-5823-1150,FAX 03-5823-1156
e-mail:main@geosociety.jp
■行事委員会■(2010年6月現在)
委員長
星 博幸(担当理事)
委 員
吉川敏之(地域地質部会)
大坪 誠(構造地質部会)
岡田 誠(層序部会)
椚座圭太郎(岩石部会)
北村晃寿(古生物部会)
内山 高(第四紀地質部会)
小松原純子(堆積地質部会)
荒井晃作(海洋地質部会)
上野将司(応用地質部会)
石塚吉浩(火山部会)
斎藤文紀(現行地質過程部会)
大久保 進(石油,石炭関係)
坂本正徳(情報地質部会)
矢島道子(地学教育関係)
田村嘉之(環境地質部会)
■日本地質学会第117年学術大会 現地事務局
(株式会社アカデミック・ブレインズ内)担当:田中
〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1天満橋千代田ビル2号館9階
TEL:06-6949-8137,FAX:06-6949-8138
e-mail:gsj2010@academicbrains.jp
■実行委員会組織■
委員長:竹内 章(TEL:076-445-6654,takeuchi@sci.u-toyama.ac.jp)
事務局長:大藤 茂(TEL:076-445-6655,shige@sci.u-toyama.ac.jp)
総務:石闢泰男(TEL:076-445-6656,ishizaki@sci.u-toyama.ac.jp)
会計:柏木健司(TEL:076-445-6652,kasiwagi@sci.u-toyama.ac.jp)
見学旅行:原山 智(TEL:0263-37-2481,shara@shinshu-u.ac.jp),
竹内 誠(TEL:052-789-2525,takeuchi@eps.nagoya-u.ac.jp)
渉外:椚座圭太郎(TEL:076-445-6300,kunugiza@edu.u-toyama.ac.jp)
普及・企画(市民講演会):藤田将人(TEL:076-491-2125(代),fujita@tsm.toyama.toyama.jp)
会場・展示会場・機器・懇親会:大藤 茂(TEL:076-445-6655,shige@sci.u-toyama.ac.jp),
現地事務局((株)アカデミック・ブレインズ(内))担当:田中(TEL:06-6949-8137,FAX:06-6949-8138,e-mail:gsj2010@academicbrains.jp)
託児室:チャイルドスクウェア総曲店(TEL:076-442-0881,childsquare200010@yahoo.co.jp)
男女共同参画企画:増渕佳子(TEL 076-491-2125,buchi@tsm.toyama.toyama.jp),
現地事務局((株)アカデミック・ブレインズ(内))
担当:田中(TEL:06-6949-8137,FAX:06-6949-8138,e-mail:gsj2010@academicbrains.jp)
地質情報展担当:高橋裕平・中島 礼(TEL:029-861-3549,johoten2010.jimu@m.aist.go.jp)
実行委員会問合せ用メールアドレス info2010@sci.u-toyama.ac.jp
講演要旨追加・見学旅行案内書予約頒布
■申込(参加登録フォーム)はこちらか ら■
*「各種の申込方法と お支払いについて」はこちら
講演要旨集のみの予約頒布
<申込締切 オンライン:9月3日(金)18:00,FAX・郵送:8月31日(火)必着>
大会参加費には講演要旨集の代金が含まれていますので,大会に参加される場合は別途購入の必要はありません(ただし,学部割引会員・名誉会員・50年会員・非会員学部学生・非会員招待者には,講演要旨集は付きません.ご希望の方は,別途ご購入下さい).大会に参加されない方ならびに参加する方が複数の講演要旨集を購入される場合の予約頒布です.要旨集の受け取り方法には,(1)大会後に送付,(2)会場で受取り,があります.(1)の場合は,別途送料が必要です.(2)の場合は,大会受付にて確認書の提示が必要となりますので,必ずご持参下さい.残部があれば大会当日あるいは大会後にも頒布します.売り切れの場合はご容赦下さい.
事前予約(/冊)
当日販売(/冊)
会員
3,000円
4,000円
非会員
4,000円
5,500円
*送付の場合は以下の送料を付加して下さい.
送料:1冊 500円,2冊 600円,3冊 800円,4冊 1,000円,5冊 1,200円
見学旅行案内書の予約頒布
<申込締切 オンライン:9月3日(金)18:00,FAX・郵送:8月31日(火)必着>
大会に参加されない方でもご購入いただけます.なお、見学旅行案内書は,地質学雑誌の補遺版(CD)として, 12月号刊行時に会員配布されます.
案内書の受け取り方法には,(1)大会後に送付,(2)会場で受取り,があります.(1)の場合は,別途送料が必要です.(2)の場合は,大会受付にて引換クーポンの提示が必要となりますので,必ずご持参下さい.見学旅行参加者はできるだけ会期中に会場の受付にてお受取り下さい.
残部があれば,大会当日あるいは大会後にも頒布します.売り切れの場合はご容赦下さい.
事前予約(/冊)
会員
2,800円
非会員
2,800円
*送付の場合は以下の送料を付加して下さい.
送料:1冊 500円,2冊 600円,3冊 800円,4冊 1,000円,5冊 1,200円
ランチョン・夜間小集会
ランチョン
都合により急遽会場が変更になる場合もございますので,会期中の掲示にご注意下さい.
9月19日(日)12:00-13:00
会場④(C21) 岩石部会(世話人 片山郁夫)
会場⑤(C22) 堆積地質部会(世話人 小松原純子)堆積地質部会の定例会合
会場③(C13) 構造地質部会定例会(世話人 橋本善孝)過去の活動報告,会計報告,今後の活動計画など
会場⑥(D21) 火山部会(世話人 石塚吉浩)火山部会の報告,企画
会場①(C11) 地質学雑誌編集委員会(世話人 山路 敦)
会場②(C12) 応用地質部会の運営に関する意見交換(世話人上野将司・小嶋 智)世話人・行事委員の交代,メーリングリストについて
9月20日(月)12:00-13:00
会場⑤(C22) 海洋地質部会(世話人 徳山英一・荒井晃作・芦 寿一郎・小原泰彦)海洋地質部会の活動に関する議論と情報交換
会場⑥(D21) 古生物部会(世話人 北村晃寿)古生物部会の定例会合
会場①(C11) 地域地質部会・層序部会合同(世話人 吉川敏之)部会活動や世話人体制についての議論と情報交換
会場②(C12) Island Arc編集委員会(世話人 原 英俊)Island Arc誌の編集に関する打ち合わせ
夜間小集会
都合により急遽会場が変更になる場合もございますので,会期中の掲示にご注意下さい.
9月19日(日)18:00-20:00
会場④(C21) 南極地質研究委員会(世話人 本吉洋一・外田智千)第51次(2009/10)セールロンダーネ山地地質調査報告/第5 1 次( 2 0 0 9 / 1 0 ) 夏期オペレーションの概要/ 第5 2 次
(2010/11)地質調査計画について/第53次(2012-)以降の調査計画について/南極観測における公開利用研究の募集について/その他
会場⑤(C22) 炭酸塩堆積学に関する懇談会(世話人 中澤努・松田博貴)炭酸塩堆積学に関する最近の話題・トピックスについて討論するとともに,最新研究動向・情報について意見
交換を行う.
会場③(C13) 地学教育(世話人 中井 均)新しい学習指導要領の実施にともなう,各高校のカリキュラム改訂について状況を紹介し,今後の方向を議論する.
会場⑥(D21) 地質学会若手の集い(世話人 大坪 誠・山口直文・大橋聖和・山口飛鳥・池田昌之)若手研究者から学部生が集まり,今後の地質学研究のあり方について議論する.
会場①(C11) 【ジュラ系+】の集い(世話人 松岡 篤(代表)・小松俊文・近藤康生・堀 利栄・石田直人・柿崎喜宏)今夏の国際ジュラ系会議での動向を中心に,最近のジュラ系研
究の進展について話題提供と意見交換を行う.
会場②(C12) 環境地質部会(世話人 田村嘉之・風岡 修)富山県における環境地質に関する講演など.
会場⑦(D22) 考古学への地質学の貢献(10)(世話人 渡辺正巳・井上智博・松田順一郎・趙 哲済・小倉徹也・別所秀高)縄文時代前期の土坑墓から副葬品を伴った人骨が発見されたことで最近新聞を賑わせた小竹貝塚について,(財)富山県埋蔵文化振興財団の町田賢一さんと現在の現場担当の方にお話しいただきます.
大会本部(A21) 超深度海溝掘削(KANAME)(世話人 木村学・金川久一・斎藤実篤)新学術領域研究『超深度海溝掘削(KANAME)』の研究計画と本年度の南海掘削に関する情報交換を行う.
9月20日(月)17:30-19:00
会場④(C21) 地質学史懇話会(世話人 会田信行・金 光男)1.相馬恒雄:飛騨帯の見方の変遷/2.東 洋一:福井県立恐竜博物館の発掘調査とジオパークの取り組み
会場③(C13) 構造地質部会若手の研究発表会(世話人 橋本善孝)構造地質部会若手の研究発表会を夜間小集会において行います.1人20で3名を予定しています.
会場⑥(D21) 学生のヒマラヤ野外実習を考える会(世話人 吉田勝・在田一則・酒井哲也)トリブバン大学地質学教室と共同で,日本の学生実習をネパールヒマラヤで毎年実施する計画を話し合う.とりわけ日本の大学における野外地質学教育の一層の振興を目指し,大学のカリキュラムとして採用する方向を模索したい.
会場①(C11) ジオパークへの地質学会支援のあり方(世話人 天野一男・高木秀雄・渡辺真人)日本各地で進んでいるジオパーク事業への地質学会の支援について,一般会員にも参加いただき討論する.
懇親会・お弁当
懇親会
<申込締切 オンライン :9月3日(金)18:00,FAX・郵送:8月31日(火)必着>
日時:9月18日(土)表彰式・記念講演会終了後(18:30〜20:00)
場所:富山県民会館内レストラン「キャッスル」
会費は正会員5,000円,名誉会員・50年会員・院生割引会費適用正会員・学部割引適用正会員および会員の家族は2,000円です.非会員の会費は正会員に準じます.準備の都合上,前金制の予約参加とします.たくさんの方々,特に院生・学生などの若手会員のご参加をお待ちしております.余裕があれば当日参加も可能ですが,予定数に達し次第〆切ります.当日会費は1,000円高くなります.
大会参加申込と合わせて9月3日(金)までにお申し込み下さい.当日はクーポンを受付にご持参下さい.懇親会に限り,締切後の参加取消の場合は会費の返却は一切いたしませんのでご了承下さい.
■申込(参加登録フォーム)はこちらか ら■
*「各種の 申込方法と お支払いについて」はこちら
お弁当予約販売
<申込締切 オンライン:9月3日(金)18:00,FAX(郵送):8月30日(月)必着>
9月18日(土)〜9月21日(月)には昼食用の弁当販売をいたします(1個 800円,お茶付き).大会参加申込と合わせて,9月3日(金)までにお申し込み下さい.お弁当利用日よ り9日前〜前日までは50%,当日は100%の取消料がかかります.なお,9月18日(金)〜20日(月)は,大学生協食堂およびカフェも営業いたしてお ります.購買部の営業はいたしませんので、大学正門前のコンビニエンスストア等をご利用ください。
■申込(参加登録フォーム)はこちらか ら■
*「各種の 申込方法と お支払いについて」はこちら
託児室・学童ルーム
男女共同参画委員会企画
【託児室のご案内】
<利用申込締切 9月10日(金)施設直接申込>
(1) 開設日時:9月18日(土)〜20日(月)・8:00〜18:30(22:00まで延長可)
(2) 対象:一般社団法人日本地質学会第117年学術講演会参加者を保護者とする生後3ヶ月から小学生迄のお子様.
(3) 場所:チャイルドスクェア(有)総曲輪店 (社)全国ベビーシッター協会正会員
富山市総曲輪2-4-5 Tel 076-442-0881 E-mail childsquare200010@yahoo.co.jp
URL http://www.child-square.co.jp/
(4) アクセス:JR富山駅正面口前 「富山駅前」より1・2系統【南富山駅前】行きまたは3系統環状線市内電車にて「荒町」下車(約10分,200円).徒歩5分
(5) 託児料金:保護者負担分 300円/時間(それ以上の託児費用は,男女共同参画活動事業費より補助いたします)
※食事350円/食・おやつ50円/回・おむつ100円/枚については実費を直接施設へお支払ください。
(6) 利用問合せ・申込み:ご利用希望の方は,上記施設HPの案内をご覧の上,9月10日(金)までに,施設に直接お電話にてお申し込みください。電話 076-442-0881
(7)以下の利用に際してのお願いをご確認の上、ご利用ください。
・健康保険証のコピーをご持参ください。
・お子様用のお荷物(おむつ・お尻拭き・ミルク・哺乳瓶・着替え・タオル・おやつ・ビニール袋等)はひとつのバックにまとめてお預けください。
・万が一の場合に備え、施設加入の損害保険で対応させていただきます。なお、託児施設のご利用に際しては当学術講演会実行委員会・日本地質学会は責任を負いかねますのでご了承ください。
【学童ルームのご案内】
(1) 場所:富山大学五福キャンパス共通教育棟
(2) 対象:原則として小学校低学年以上のお子様.
(3) 利用:学会期間中いつでもご利用できます.ただし,学童の安全確保については保護者の方が責任をもって下さい.一般の休憩室に併設しておりますので,その点はご了承ください.
【学童ファミリープランのご案内】
以下のファミリープランを計画しています.詳細は,ニュース誌6月号にてご紹介いたします.
(1) 親子で行こう糸魚川ジオパーク(9月20日の地学教育見学旅行と同時開催予定)
(2) 親子で行こう地質情報展と富山市科学博物館
ファミリープランについてのお問い合わせは男女共同参画委員会<danjyo@geosociety.jp>まで
広告掲載・企業展示・書籍販売等について
企業等団体展示/書籍販売(富山大学五福キャンパス共通教育棟E棟2階ホール等)
メイジテクノ株式会社,ライカマイクロシステムズ株式会社,新学術領域研究「超深度掘削が拓く海溝型巨大地震の新しい描像」,東北大学グローバルCOEプログラム「変動地球惑星学の統合教育研究拠点」,NPO法人ジオプロジェクト新潟,株式会社クレアリア,独立行政法人海洋研究開発機構,独立行政法人海洋研究開発機構高知コア研究所(8月2日現在)
書籍・物品の展示販売コーナー(共通教育棟E棟3階E32番教室)
株式会社愛智出版,株式会社テラハウス,株式会社古今書院,財団法人東京大学出版会,地学団体研究会,日本地球化学会,株式会社ニュートリノ(7月8日現在)
※申込期限延長,追加募集等がある場合もありますので,随時大会ホームページをご覧ください.
■企業展示出展募集
■書籍・販売ブース募集
■広告掲載募集
企業・研究機関等関係団体による展示会の出展募集
<申込締切 第1次募集締切:7月9日(金) 最終募集締切:8月6日(金)>
地質関係機関・関連企業のご活躍を広く地質学会員に紹介していただくため,会期中,企業展示会を開催致します.企業紹介・業務紹介・研究成果・新技術・特許などご自由に展示内容を構成いただけます.奮ってご出展のお申込をいただきますようお願い申し上げます.
【展示募集概要】
1, 開催期間:搬入設営日9月17日(金),開催日9月18日(土)〜20日(月),搬出撤収日9月20日(月)※予定
2,開催場所:富山大学 五福キャンパス 共通教育棟2F ※予定
3,募集小間数:小小間12,パネル小間16 ※予定 複数小間のお申込も可能です.
4,小間仕様見本:
※仕様詳細・オプション料金等につきましては,「展示募集要項申込書」をダウンロードの上,ご確認下さい.
5,出展料金:小小間 50,000円(消費税別),パネル小間 20,000円(消費税別)
6,第1次募集締め切り日:7月9日(金) 最終募集締め切り日:8月6日(金)
【出展申込方法】
「展示募集要項申込書」をダウンロードいただき,必要事項をご記入の上,下記申込先までe-mailへのPDFファイル添付,あるいはFAXにてお申込下さい.募集要項・申込書が別途必要な場合は,現地事務局までご連絡下さい.送付致します.
【お申込・お問合せ先】
〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1天満橋千代田ビル2号館9階
日本地質学会第117年学術大会 現地事務局 (株式会社アカデミック・ブレインズ内)
TEL:06-6949-8137,FAX:06-6949-8138, e-mail: gsj2010@academicbrains.jp 担当:田中
※日本地質学会賛助会員は出展料金が無料となります.別途,現地事務局までご連絡下さい.
書籍・販売ブースご利用の募集
<申込締切 第1次募集締切:7月9日(金) 最終募集締切:8月6日(金)>
地質学関連の書籍・その他物品の販売にご利用いただくべく会期中ブースを設置致します.奮ってご出展のお申込をいただきますようお願い申し上げます.※見本展示のみでのご利用も可能です.
【書籍・販売ブース出展概要】
1,設置期間:9月18日(土)〜9月20日(月)
2,設置場所:富山大学 五福キャンパス 共通教育棟2F ロビー
3,募集ブース数:6ブース ※予定 複数ブースのお申込も可能です.
4,ブース仕様見本
※仕様詳細・オプション料金等につきましては,「展示募集要項申込書」を ダウンロードの上,ご確認下さい.
5,出展料金:10,000円(消費税別)
6,第1次募集締め切り日:7月9日(金) 最終締め切り日:8月6日(金)
【出展申込方法】
「展示募集要項申込書」をダウンロードいただき,必要事項をご記入の上,下記申込先までe-mailへのPDFファイル添付,あるいはFAXにてお申込下さい.募集要項・申込書が別途必要な場合は,現地事務局までご連絡下さい.送付致します.
【お申込・お問合せ先】
〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1天満橋千代田ビル2号館9階 日本地質学会
第117年学術大会 現地事務局 (株式会社アカデミック・ブレインズ内)
TEL:06-6949-8137,FAX:06-6949-8138, e-mail: gsj2010@academicbrains.jp 担当:田中
講演要旨集・見学旅行案内書,広告協賛の募集
<申込締切 7月30日(金)>
地質関係機関・関連企業のご活躍を広く地質学会員に広報いただくべく,大会開催にあわせ発行されます講演要旨集・見学旅行案内書において,広告協賛を募集致します.企業紹介・業務紹介・研究成果・新技術・特許などの広報活動のご一環として,奮ってお申込をいただきますようお願い申し上げます.
【広告協賛料金】※詳細は「広告協賛募集要項申込書」をダウンロードの上,ご確認下さい.
講演要旨集:1頁 40,000円 1/2頁 20,000円 1/4頁 10,000円(すべて消費税別)
見学旅行案内書:1頁 20,000円 1/2頁 10,000円 1/4頁 5,000円(すべて消費税別)
※共に完全版下,データまたフィルムでの入稿をお願い致します.
【出稿申込方法】
「広告協賛募集要項申込書」をダウンロードいただき必要事項をご記入の上,下記申込先までe-mailへのPDF添付,あるいはFAXにてお申込下さい.
【お申込・お問合せ先】
〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1天満橋千代田ビル2号館9階 日本地質学会
第117年学術大会 現地事務局 (株式会社アカデミック・ブレインズ内)
TEL:06-6949-8137,FAX:06-6949-8138, e-mail: gsj2010@academicbrains.jp 担当:田中
定番セッション・トピックセッション
定番セッション・トピックセッション
講演申込はこちらから
(修正・変更もこちらから)
・セッションテーマ,(提案部会名)(地域名等特記事項),世話人(*印責任者),趣旨の順に掲載.
・特に断りのないセッションは口頭とポスターの両方を募集します.
・提案部会に関わりなく,会員はいずれのセッションにも応募できます.ただし,応募は口頭かポスターのいずれか1件に限ります.
・「地域名必要」の記載があるセッションは,申込書に研究対象の地域名を記入してください.
・トピックセッションにおいては,世話人は会員・非会員を問わずに招待講演を依頼することができます.非会員の招待講演は1セッションにつき,半日あたり1講演に限ります.会員の招待講演数には制限はありません.定番セッションでは招待講演の設定はありません.
・口頭発表会場には液晶プロジェクターとWindowsパソコン(OS: Windows Vista, Office Standard 2007)を用意します.パワーポイントを使用する場合は,試写室において正常に作動する事を確認して下さい.昨年同様スライドプロジェクターの使用はできません.Macパソコンをお使いになる方、パワーポイントを使用しない方は世話人とご相談下さい.
トピックセッション:6件
1.地球史とイベント大事件5:宇宙・生命進化・環境変動の謎に迫る
清川昌一*(九州大;kiyokawa@geo.kyushu-u.ac.jp)・山口耕生(東邦大)・小宮 剛(東工大)・尾上哲治 (鹿児島大)
地球史46億年における,様々な時空スケールの(時に劇的な)イベントの性質とそれに対するレスポンスの解明を目指し,地層や岩石・鉱物に記録された宇宙物質・エネルギー付加の影響・地球内部変動・表層環境変動・微生物活動に関する最新の研究動向を探る.
2.平野地質:堆積と構造
卜部厚志*(新潟大;urabe@gs.niigata-u.ac.jp)・宮地良典(産総研)
これまで沖積層の新展開として,沖積層の層序や堆積環境,堆積システムの解明に関するセッションを企画してきた.これらの課題については,一定の進展が見られたことから,対象範囲を沖積層に限定せず平野や平野周辺の丘陵部などを構成する更新統以降の地層に広げ,堆積と構造をいう点をキーワードとして,堆積環境や堆積システムの復元,海水準変動との関係や地層から読み取れる構造運動(活断層の履歴),第四紀後期の堆積盆地としての発達過程など,海水準変動だけではなく地層の形成要因である構造運動や堆積作用についても視野をひろげ総合的な視点での発達過程を議論する場としたい.
3.地学巡検・地学名所とガイドブック
吉田 勝*(ゴンドワナ地質環境研;gondwana@gaia.eonet.ne.jp)・中井 均(都留文科大)・天野一男(茨城大)
地学関係のシンポジウム等では地学野外巡検が付属して行なわれるのが普通であり,多くの場合,そのためのガイドブックが作成されている.また日本では市民対象の地学日帰り巡検等が学会の支部や博物館等によって行なわれており,あるいはまた旅行社等による市民対象のグループ地学ツアーも毎年いくつか実施されている.一方ユネスコでは数年前からジオパークプログラムを開始し,あるいは日本では地質百選の選定・情宣も行なわれ,国内あるいは世界各地での一層の地学普及に役立っている.しかし,社会一般における地学の理解や普及度,地学教育の重要性への理解と,学界での取り組みは日本ではまだまだ不十分であるといわざるを得ない.米国では,国立公園やハイウエイ沿いにはかなりしっかりした地学パンフレットやガイドブックがあり,社会一般での地学理解の普及と増進に大きく役立っていると思われるし,万国地質学会ではすでに2004年ストラスブルグ大会からジオパークセッションが開かれており,世界各国の地学普を後押ししているが,日本では未だしの感を免れない.本セッションは,地学巡検,地学名所指定やガイドブック等による地学普及活動の情報を交換,共有し,日本及び日本の地質学界におけるより効果的な活動を目指すことを目的とする.そこで,国内外における地学巡検,地学名所の指定,これらの案内書やパンフレットの編集・販売や,これらに関係する諸テーマの口頭及びポスター発表を募集する.
4.河口〜内湾域における歴史時代の汎世界的な環境変動と人為的環境変化
野村律夫(島根大)・秋元和實(熊本大)・瀬戸浩二*(島根大;seto@soc.shimane-u.ac.jp)
河口〜内湾域は,人類の生活場である平野部付近に接しているため,人類の歴史とともに変化している.そのような水域は大規模公共事業による地形の改変,流入河川の改修・付け替え,生活排水による汚濁など,人為改変が特に著しい水域でもある.最近では,人為改変により著しく劣化した水域環境に対し保全・修復を目的とした住民・行政活動が行われようになってきた.しかし,著しく劣化した環境を修復するには明確なビジョンが必要であり,過去のある時期の環境に戻すことをそのビジョンに考える傾向にある.しかし,それは環境再生・修復を議論している人々の過去の記憶や体験によるところが多く,科学的な根拠に乏しいのが現状である.そのような状況の中,過去の安定した科学的環境データを得るには,堆積物に記録された過去の環境を読みとることが最適であり,従来行われてきた地質学的手法を進化させた上で,気候モデリングや年輪による古気候研究など他の分野とも連携する必要がある.本トピックスセッションでは,河口〜内湾域において歴史時代の高解像度(数年〜数百年オーダー)の古環境解析を行った最新の研究成果(人為改変による堆積相の変化や10年規模変動の研究など)を発表し,現状と課題について検討するための材料にしたい.また,そのような古環境解析を念頭に置いた現世の人為改変のモニタリングの成果や水系の堆積システムの解明のための基礎研究の発表についても歓迎する.
5.ジュラ系+ (読み方:ジュラケイプラス)
松岡 篤(新潟大;matsuoka@geo.sc.niigata-u.ac.jp)・堀 利栄(愛媛大)・小松俊文(熊本大)・近藤康生(高知大)・石田直人(新潟大)・柿崎喜宏(金沢大)
2002年の新潟大会プレシンポジウム以降,毎年開催しているトピックセッション「ジュラ系+」の成果を踏まえ,ジュラ系および隣接する地質系統の研究に関する到達点を共有するとともに,わが国がジュラ系研究の拠点となることを目指す.本セッションの講演タイトルは,国際ジュラ系小委員会のNewsletterに掲載され,日本からの研究成果を世界の研究者に伝えるのに役立っている.夜間小集会も申し込む予定である.そこでは,2010年8月に中国で開催される第8回国際ジュラ系会議の模様が報告される.
6.アジア大陸の地質
大藤 茂(富山大;shige@sci.u-toyama.ac.jp)
アジア大陸を対象とした地質研究の最新データを集め,アジア大陸の形成過程を議論するセッションである.他地域の地質研究であっても,アジア大陸と関連づけた内容を持つものであれば歓迎する.日本地質学会員のみならず,協定学会会員の発表を広く受け入れる.参加予想数 50 名.(講演要旨および発表において,英語の使用を推奨する)
定番セッション:20件
7.地域地質・地域層序(地域地質部会・層序部会)(地域名必要)
吉川敏之(産総研・t-yoshikawa@aist.go.jp)・岡田 誠(茨城大)・斎藤 眞(産総研)
国内,海外問わず各地域に関係した地質や層序の発表を広く募集.地域的な年代,化学分析,リモセン,活構造,地質調査法等の発表も歓迎.地質災害地の地質,惑星地質もここに含まれる.地域を軸にした討論を期待する.地質図や断面図のポスター発表を特に歓迎.
8.地域間層序対比と年代層序スケール(層序部会)(地域名不要)
里口保文(琵琶湖博物館; satoguti@lbm.go.jp)・岡田 誠(茨城大)
テフラ等の鍵層を用いて異なる地域間の層序対比に主体をおく研究や,鍵層そのものを主体とした研究,または複合的層序学等によるグローバルな年代層序スケールの構築に寄与するような研究についての講演を歓迎します.
9.海洋地質(海洋地質部会)(地域名必要)
荒井晃作*(産総研・ko-arai@aist.go.jp)・徳山英一(東大大気海洋研)・ 芦 寿一郎(東大大気海洋研)・小原泰彦(海上保安庁)
海洋地質に関連する分野(海域の地質・テクトニクス・変動地形学・海域資源・堆積学・海洋学・古環境学・陸域地質での海洋環境変遷研究など)の研究発表を募集する.調査速報・アイデアの公表・海底地形地質・画像データなどのポスター発表も歓迎する.
10.砕屑物組成・組織と続成作用(堆積地質部会)
太田 亨*(早稲田大:tohta@toki.waseda.jp)・野田 篤*(産総研)
砕屑物を構成する個々の粒子の特性(形態や化学組成)から砕屑物(岩)の組織・組成を対象とし,砕屑物(岩)の形成・続成過程の復元,後背地や古環境,地質体の発達史を議論する.データ解析手法,現世砕屑物の組成,初期続成過程についての発表も歓迎する.
11.炭酸塩岩の起源と地球環境(堆積地質部会)(地域名必要)
山田 努*(東北・t-yamada@m.tains.tohoku.ac.jp)・佐々木圭一(金沢学院)
炭酸塩岩・炭酸塩堆積物の堆積作用,組織,構造,層序,岩相,生物相,地球化学,続成作用,ドロマイト化作用など,炭酸塩に関わる広範な研究発表を募集する.また,現世炭酸塩の堆積作用・発達様式,地球化学,生物・生態学的な視点からの研究発表も歓迎する.
12.堆積相・堆積過程(現行地質過程部会・堆積地質部会)(地域名必要)
小松原純子(産総研;j.komatsubara@aist.go.jp)・片岡香子(新潟大)・成瀬 元(千葉大)
さまざまな環境で生じる堆積過程と堆積相の分類・記載・解釈に関する発表や、堆積相解析に基づく堆積システム・シーケンス層序学についての議論を広く募集する.さらに、堆積作用や地層形成のダイナミクスに関連する理論・アナログ実験・数値シミュレーション・現地観測等の研究発表を歓迎する.
13.石油・石炭地質学と有機地球化学(石油・石炭関係・堆積地質部会)(地域名必要)
大久保 進(石油資源開発・susumu.okubo@japex.co.jp)・金子信行(産総研)
国内外の石油・石炭地質および有機地球化学に関する講演を集め,石油・天然ガス・石炭鉱床の成因・産状・探査手法など,特にトラップ構造,堆積盆,堆積環境,貯留岩,根源岩,石油システム,資源量,炭化度などについて討論する.
14.岩石・鉱物の破壊と変形(構造地質部会)(地域名不要)
西川 治*(秋田大・nisikawa@lfp03.mine.akita-u.ac.jp)・大坪 誠(産総研)
断層岩を含む岩石・鉱物の破壊および変形機構,変形微細構造,岩石・鉱物のレオロジーや物性に関する研究を募る.観察・観測・分析・実験・理論など多方面からのアプローチによる成果を歓迎するとともに,会場での活発な議論を期待する.
15.付加体(構造地質部会)(地域名必要)
坂口有人*(JAMSTEC・arito@jamstec.go.jp)・内野隆之 (産総研)
現世,過去を問わず,付加体に関するすべての講演を歓迎する.付加体の形成機構,形成史,微細構造,流体移動,シュードタキライト,温度圧力構造など,様々なアプローチによる成果をもとに議論する.
16.テクトニクス(構造地質部会)(地域名必要)
佐藤活志*(京都大・k_sato@kueps.kyoto-u.ac.jp)・藤内智士(産総研)
地球科学の多方面から,大小様々な時間・空間スケールで起こる地質構造の成因や形成機構・発達史に関する講演を広く募集する.野外調査,観測,実験,理論などに基づいた研究発表を歓迎する.
17.古生物(古生物部会)(地域名不要)
平山 廉(早稲田大)・北村晃寿*(静岡大・seakita@ipc.shizuoka.ac.jp)・太田泰弘 (北九州博)・三枝春生 (兵庫県立人と自然の博)・須藤 斎 (名古屋大)
古生物を扱った,または関連する研究の発表・討論を行う.
18.噴火と火山発達史(火山部会)
竹下欣宏(信州大,takey@shinshu-u.ac.jp),長谷川健(茨城大)
マグマや熱水性流体の上昇過程,噴火様式,噴火推移,噴出物の移動・運搬・堆積,特定火山あるいは火山地域の発達史,火山活動とテクトニクス,およびその他火山地質やモデル化に関する幅広い視点からの議論を期待する.
19.深成岩・火山岩とマグマプロセス(火山部会・岩石部会共催)
荻津 達*(産総研、itaru-ogitsu@aist.go.jp)、亀井敦志(島根大)
深成岩および火山岩を対象に,マグマプロセスにアプローチした研究発表を広く募集する.発生から定置・固結に至るまでのマグマの物理・化学的挙動や,テクトニクスとの相互作用について,野外地質学・岩石学・地球化学・年代学など様々な視点からの活発な議論を期待する.
20.変成岩とテクトニクス(岩石部会)(地域名不要)
奥平敬元*(大阪市大・ oku@sci.osaka-cu.ac.jp),外田智千(極地研)
国内および世界各地の変成岩を主な対象に,記載的事項から実験的・理論的考察を含め,またマイクロスケールから大規模テクトニクスに関する様々な地球科学的手法・規模の視点に立った斬新な話題提供と活発な議論を期待する.
21.岩石・鉱物・鉱床学一般(岩石部会)(地域名不要)
壷井基裕*(関西学院大・tsuboimot@kwansei.ac.jp),中野伸彦(九州大)
岩石学,鉱物学,鉱床学,地球化学などの分野をはじめとして,地球・惑星物質科学全般にわたる岩石及び鉱物に関する研究発表を広く募集する.地球構成物質についての多様な研究成果の発表の場となることを期待する.
22.情報地質(情報地質部会)(地域名不要)ポスターセッションのみ,口頭講演なし
能美洋介*(岡山理科大・y_noumi@big.ous.ac.jp)・坂本正徳(国学院大)
地質情報の数理解析,統計解析,データ処理,画像処理などの理論,応用,システム開発,利用技術など,最近の情報地質分野の研究結果を対象とする.また,これらの成果の地質学の広い分野への応用・普及なども歓迎する.
23.環境地質(環境地質部会)
難波謙二(福島大)・風岡 修(千葉環境研)・三田村宗樹(大阪市大)・田村嘉之*(千葉環境財団・tamura-yoshiyuki@pop07.odn.ne.jp)
医療地質,地盤沈下,湧水,水資源,湖沼・河川,都市環境問題,法地質学,環境教育,地震動,液状化・流動化,地震災害,岩盤崩落など,環境地質に関係する全ての研究の発表・討論を行う.
24.応用地質学一般およびノンテクトニック構造(応用地質部会)(地域名不要)
上野将司*(応用地質(株)・ueno-shouji@oyonet.oyo.co.jp)・小嶋智(岐阜大)
応用地質学一般では,種々の地質ハザードの実態,調査,解析,災害予測,ハザードマップの事例・構築方法,土木構造物の設計・施工・維持管理に関する調査,解析など,応用地質学的視点に立った幅広い研究を対象とする.また,ノンテクトニック構造では,ランドスライドや地震による一過性の構造,重力性の構造等の記載,テクトニック構造との区別や比較・応用等の研究を対象にして発表・議論する.
25.地学教育・地学史(地学教育部会・地学教育委員会共催)(地域名必要)
矢島道子*(東京医科歯科大・pxi02020@nifty.com)
新学習指導要領の施行は目前.現場からの問題提起,多くの実践報告を持ちより議論しよう.また地学史からの問題提起,貴重な史的財産の開示を歓迎する.
26.第四紀地質(第四紀地質部会)(地域名必要)
吉川周作*(大阪市大, yoshi@sci.osaka-cu.ac.jp)・内山 高(山梨環境研)
第四紀地質に関する全ての分野(環境変動・気候変動・湖沼堆積物・地域層序など)からの発表を含む.また,新しい調査や研究,方法の開発や調査速報なども歓迎する.
講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理,引用方法,校閲について
講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理,引用方法,校閲について
(1)講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理
日本地質学会の出版物への投稿原稿に対して,著作者にその倫理性について保証して頂くために「保証書」に,また著作権を日本地質学会に 譲渡することを同意する「著作権譲渡同意書」に,それぞれ署名捺印をして提出していただいています.本大会は電子投稿のため,画面上で「保証 書」と「著作権譲渡等同意書」に同意していただいた場合に限り,電子投稿の画面に進むことができるようになっています.郵送の場合は,保証書及び同意書に署名捺印をして,講演要旨と共にお送り下さい.「保証及び著作権譲渡等同意書(こちらをクリック)」が同封されていない講演申込は受け付けられません.
(2)講演要旨における文献等引用方法
要旨においては引用文献の記載方法は簡略化することが慣習として認められていますが,著者名,発表年,掲載誌名などを明記し,引用文献が特定できるようにして下さい.
(3)講演要旨の校閲
行事委員会は,申し込まれた講演について,定款第3条に示されている日本地質学会の目的ならびに日本地質学会倫理綱領に反していないかということについて のみ校閲を行います.校閲の結果,いずれかの条項に反していると判断された場合には,行事委員会は講演内容の修正を求めるか,あるいは講演申込を受理しな いことがあります.行事委員会の措置に同意できない場合には,当該講演申込者は法務委員会(東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル 日本地質学会事務局気付)に異議を申し立てることができます.法務委員会は直ちに審理し,結論を行事委員会ならびに異議申立者に伝えることになります.
この受理方法は,招待講演者にも適用されます.
講演申し込み異議申し立てについて
日本地質学会行事委員会は,学術大会において学会の目的及び倫理規定に反する講演申し込みのあった要旨に対して,修正あるいは,受理を拒否することができます.法務委員会では,日本地質学会行事委員会規約に基づき,異議申立の手続及びその処理についての規則を定めています.
日本地質学会法務委員会
■日本地質学会学術大会講演申込異議申立に関する処理機構規則(PDF)■
講演要旨の作成の注意点とPDFファイル作成の作り方
講演要旨の作成の注意点とPDFファイル作成の作り方
講演要旨を作成する際,著者には「保証及び著作権譲渡同意書」第1項の「保証」内容を守って頂きます.行事委員会は,要旨の内容については関知しませんが,当該「保証」内容を逸脱するものがないか校閲します.その結果,不適当とみなされる場合は,修正されるまで講演要旨の受理はされません(不服の場合は法務委員会に訴えることが可能です).
例年最も多い問題点は,引用文献の表示がない場合です.論文のように細かに引用文献を記載することはスペースの都合上不可能なので必要としませんが,雑誌名,号,ページ等,その文献にたどり着ける最低限の情報は要旨原稿内に記載して下さい.
また,要旨の体裁を無視している場合,印刷できませんので体裁を整えて頂くことになります.さらに図等の改変については,著作権法,地質学会著作物利用規定に従って下さい.
このほか,PDFファイルにフォントを埋め込んでいないもの(印刷時に文字化けすることがあります),要旨作成時に講演番号記入用のスペースがなかったり,余白に無理があるといった場合,体裁を整えるため修正をお願いしています.これらの問題点があった場合,各コンビーナから投稿締切日から1週間をめどに修正依頼が届きます.ただ,その労力はセッションによっては膨大になりますので,あらかじめ著者で完全なものを投稿するようご協力下さい.あわせて講演要旨投稿手順のチェックシートもご参照下さい.
日本地質学会 行事委員会
2010年4月
■要旨テンプレート(Microsoft Word)■ ■講演要旨投稿手順のチェックシート■
【講演要旨PDFファイル作成時の注意点】
1)
講演要旨原稿はAdobe Acrobat Reader 4.0 以上で表示・印刷可能なPDFファイルで投稿することが必要です.
2)
ファイルサイズは3.0Mバイト以内で作成して下さい.
3)
発表(講演)番号は事務局にて左上に付記するので原稿内には記載しないで下さい.
4)
PDFファイルのセキュリティ設定は「なし」にして下さい.
5)
フォントは必ず「埋め込み」にして下さい.MacOSX以上は標準でフォント埋め込みが用意 されます.MacOS9.2.2以下,Windowsでは下記のソフトが必要です.その際,『すべてのフォント埋め込み』ないし『ハイクォリティー』等, それぞれのソフトの使用説明書に従った指定を必ずして下さい.文字数にもよりますが,できたPDFファイルのサイズが100KB未満の場合,フォントが埋 め込まれなかった可能性がありますので確認して下さい.
6)
作成したPDFファイルを自分で印刷し,図表に充分な解像度があるか,文字化けはないか確認して下さい.
7)
PDFファイルを自分のパソコンに,必ず「.pdf」の拡張子をつけて保存して下さい(Mac, Windowsとも).
■原稿フォーマット見本■
テンプレート
(Microsoft Word)
ダウンロードはこちら
【webでの講演要旨投稿の手順】
1)
参加申し込みの後,web上の講演申し込みページで,講演申し込みの手続きをします(講演申込と同時に要旨投稿をすることもできますし、講演要旨のみ後で投稿する事もできます).
2)
演題・発表者情報登録画面の最下段にある「アップロードファイル」欄から要旨原稿(PDFファイル)を投稿します.欄右側の「参照」ボタンをクリックし,ご自分のPCに保存してあるPDFファイルを選択します.
3)
画面下の「次へ」をクリックし,登録内容確認画面に進みます.登録内容を確認後,画面下の「登録」ボタンをクリックします.これによりサーバーにPDFファイルが格納されます.
4)
『登録が完了いたしました.受付番号は*****です.』という完了画面が表示されます.(注意!!この画面が表示されないと登録は完了していません)
5)
登録したメールアドレスに「講演申込のお知らせ」のメールとともに受付番号(=ID)が配信されます.
★★後から要旨を投稿する場合・申込内容を変更する場合★★
1)
IDとメールアドレスでログイン:ご自分の申込画面に,IDとメールアドレスを用いてアクセスします.
2)
新しい講演要旨PDFファイルをアップロード:「登録内容変更」ボタンをクリックし,画面の最下段にある「アップロードファイル」欄の「修正」ボタンをクリックします.ご自分のPCに保存してあるファ イルを選択し,アップロードをします.サーバー側では,ファイル名を元のファイル名から変更し,ID.pdfの名称で格納します.
3)
完了画面の確認:『登録が変更されました.受付番号は*****です.』という操作完了画面が表示されます.(注意!!この画面が表示されないと操作は完了していません)
4)
変更確認めーるが配信されます:「講演申込内容変更のお知らせ」メールが配信されます.
5)
IDとメールアドレスを用いて,投稿締切まで何度でも要旨や登録内容 を修正することができます.新しいファイルを投稿すると,古いファイルに上書きされます.そのつど,「講演申込内容変更のお知ら せ」メールが配信されます
【参考情報:PDF(Portable Document Format)ファイルの作り方】
PDFファイルの作成方法は「PDF原稿作成ガイド」http://www.gakkai-web.net/pdf/を参考にすると良いでしょう.
ソフトの紹介要望が多いので,下記にいくつか参考例を挙げます.また,"PDF作成サービス"を行う有料,無料のサイトがあります.ソフト,サイトとも検索してみて下さい.なお下記について動作確認等しておりません.また推奨するものでもありません.ご了承ください.
◯ Mac OSXの場合
フォント埋め込み型のPDF作成機能が標準で用意されています.新たなソフトは必要ありません.
◯ Mac OS 8.6-9.2の場合
Adobe Acrobat(それぞれのOS対応品,現在販売されているか不明)
EGWORD Ver.12 for Mac OS X/9/8.6(現在販売されているか不明)
◯ Windows対応品
PrimoPDF FreeのPDF変換ソフト http://www.primopdf.com/
クセロPDF PDF変換ソフト http://xelo.jp/xelopdf/
いきなりPDF 2000円弱 http://www.sourcenext.com/products/pdf/
Adobe Acrobat Elements 5000円弱 http://www.adobe.co.jp/
◯ MacOS9.2.2,MacOSX, Windows対応
Adobe Illustrator http://www.adobe.co.jp/
講演要旨オンライン投稿手順チェックシート
講演要旨オンライン投稿手順チェックシート
講演要旨の投稿手順および基本的注意事項です.投稿していただく前に各自でご確認下さい.
1.Word等のソフトで講演要旨原稿を作成します.
「保証及び著作権譲渡同意書」第1項の「保証」内容は守られていますか?
要旨原稿内に引用文献は表示されていますか?
要旨の体裁は守られていますか?(詳細は要旨原稿フォーマットをご確認下さい)
2.原稿をPDFファイルにします.
PDFファイルの作成方法については,「PDFファイルの作り方」を参照して下さい.
フォントは「埋め込み」になっていますか?(できたファイルサイズが100KB未満の場合,フォントが埋め込まれなかった可能性がありますので確認して下さい)
ファイルサイズは3.0MB以内になっていますか?
作成したPDFファイルを印刷し,図表に充分な解像度があるか,文字化けはないか確認して下さい.また,PDFファイルを自分のパソコンに,必ず.pdfの拡張子をつけて保存して下さい.
3.原稿をオンライン投稿します.
web画面から参加申し込みを行いましたか?
講演申し込みページで,講演申し込みの手続きをしましたか?
講演要旨を投稿しましたか?
申込完了画面が表示されましたか(ログイン用のIDが表示されましたか)?
「講演申込のお知らせ」のメールが配信されましたか?
4.一度投稿した原稿を修正したい場合
ご自分の申込画面に,IDと申込時に設定したパスワードを用いてアクセスします.
画面中のPDFファイルのアイコンをクリックし,要旨原稿投稿画面を開きます.書き直した要旨のファイル選択し,投稿動作をします.
修正原稿が受け付けられると,「申込内容変更のお知らせ」メールが配信されます.(締切まで何度でも修正できます).
←講演要旨作成手順のページに戻る
保証・同意書(2009岡山)
<郵送での投稿の場合は、原稿に必ず添付して下さい>
■PDFファイルダウンロードはコチラから■
保証及び著作権譲渡等同意書
著作者(下記)は,日本地質学会によって発行される第117年学術大会「講演要旨」・「見学旅行案内書」に掲載する下記表題の原稿(以下「本原稿」という.)について,以下のとおり保証し,かつ著作権を譲渡等いたします.
第1 保証
著作者は,本原稿について,以下の各号記載の事項を保証し,確約します.
1) 本原稿が著作者自身の著作物であり,既にいずれかで出版公表されているものと同一ではないこと.
2) 本原稿が既存の出版公表物などに対する知的財産権のいかなる侵害も含まないこと.
3) 本原稿中に他から転載されているすべての図表について,転載許可を得ていること.
4) 本原稿中,他の論文等の引用がある場合には,当該引用が公正な慣行に合致し,目的上正当な範囲内であること.
5) 著作物には,日本地質学会の名誉を傷つけ,地質学雑誌の信用を毀損する盗用データ,捏造データ,著作物に関する利害を持つ者の合意に反するもの,その他学会の倫理綱領に反するものを含まないこと.
6) 本原稿が共同著作物である場合には,代表して本書に署名捺印する者が,すべての共著者から,本書に著名捺印することについて同意ないし必要な権利を得ていること.
7) 本原稿についての問い合わせ,苦情,紛争などが発生した場合,署名者はすべての責任を負うこと.
8) 本著作物を作成するに当たって行われた調査・研究行為が,適切な方法でなされたものであること.
第2 著作権譲渡等
著作者は,本原稿について,以下の各号記載に同意します.
1) 本原稿のすべての著作財産権(著作権法27条,同29条に定める権利を含む)及び2次著作物の創作・利用に係る権利を日本地質学会へ譲渡すること.
2) 本原稿について,日本地質学会ならびに日本地質学会から正当に権利を取得した第3者及び当該第3者から権利を承継した者に対し,著作人格権(公表権,氏名表示権,同一性保持権)を行使しないこと
3) 本原稿の下記の各利用形態に関する権利を日本地質学会が排他的に行使すること.
a) 複製,翻訳,翻案(出版,電子出版,翻訳出版,データベース化,ビデオグラム化,その他すべての記録メディアへの記録・掲載などを含む)
b) 展示・上映
c) 放送,有線放送,自動公衆送信(地上波,CATV放送衛星,通信衛星,インターネット,パソコン通信,その他あらゆる送信媒体及び将来開発されるすべての送信媒体による公衆送信を含む)
d) 頒布,譲渡,貸与
e) その他,本著作物に関する一切の利用(技術の進歩により将来生じうる利用形態を含む)
以上
日付 2010年 月 日
本原稿表題
著作者(代表者) 印
署名者が代表する共著者すべての氏名
■PDF ファイルダウンロードはコチラから■
参加登録TOP
富山大会事前参加登録ほか申込
■参加登録フォームはこちらから■
<申込締切 オンライン:9月3日(金)18:00,FAX/郵送:8月31日(火)必着>
*申込方法・支払い方法の詳細はこちら
参加フォームから申し込める項目:クリックすると各詳細のご案内をご覧いただけます。
・参加登録(参加費)
・追加講演要旨(冊子のみの購入 可)
・見学旅行
・見学旅行案内書(冊子のみの購入 可)
・お弁当
・懇親会
その他
その他
・ランチョン・夜間小集会
・託児室・学童ルーム(託児室:9/10 締切)
・広告掲載 7/30(金)締切
・企業展示・書籍ほか販売申込 一次締切:7/9(金) 最終締切: 8/6(金)
・講演要旨・見学旅行案内書購入(冊子のみの購入:参加登録フォームからお申し込み下さい) 9/3(金)締切
新着情報 プレス発表について06.29
富山大会に関連したプレス発表を希望される方へ
富山大会での講演や行事について,8月下旬にプレス発表を行う予定です.
昨年の岡山大会でも多数のメディアに取り上げられ,会員の研究成果が多いに注目されました.富山大会で発表される予定の案件で,学会からのプレス発表をご希望の方は,8月10日(火)までに学会事務局にご連絡 願います.全ての案件をプレス発表することはできませんが,社会への情報発信として特筆すべき成果は積極的に公表して行きたいと考 えております.会員の皆様におかれましては,プレスリリース解禁日をお守りいただき,公平かつ効果的な情報発信にご協力願います.不明な点は学会事務局ま でお問い合わせ願います.
登録締切:8月10日(火)
プレス発表(投げ込み):8月下旬
現地説明会(解禁日):8月下旬
連絡先:日本地質学会事務局<journal@geosociety.jp>
日本地質学会広報委員会
富山大会でプレス発表しませんか?
地質学の記事が新聞やTVといったメディアに載ることは,地質学へ関心が高まり,私たちの 研究学術活動への理解が促進されます.地質学全体のパイを広げるためにも皆様のお力をお貸し下さい.日本地質学会はこれまで毎年の学術大会でプレス発表会 を開催してまいりました.その結果,全国紙,地方紙,TV,ウェブなど様々なメディアで取り上げられてきました.富山大会でもプレス発表会を実施いたしま す.会員皆様の一層のご協力をお願いいたします.下記に簡単なQ&Aを準備いたしました.
■ネイチャーやサイエンスに載らないと相手にされないのでは?
そんなことはありません.記者の方は発表媒体は全く問題にしません.それよりも,そのネタは読者の関心を引くのか? もしくは国民に広く周知すべき 事なのか,の二点を重視します.そこがしっかりしていれば多くのメディアに掲載されるでしょうし,逆にそうでなければ,いくら有名雑誌に載っても相手にさ れません.
■どんなメリットがあるの?
発表者ご自身の研究学術活動の内容が紹介されるのはもちろんのこと,所属機関にとっても宣伝になるでしょう.しかしなんといっても地質学の記事が掲 載されることは,私たちの学問全体のメリットになります.全体の利益のためにもぜひ発表をご検討下さい.
■知り合いの記者に話しても同じでは?
親交ある記者の方ならば正しくて深みのある記事を書いて下さるかもしれません.しかし特定の会社にのみ情報を流すと他社から反発を買って,かえって 逆効果になる場合もあります.記者クラブを通じて発表し,その上で個別取材に応じるのが最も効果的です.
■プレス発表って難しそう
基本的には,わかりやすく,かつ記事に使用されやすい資料を記者クラブに送付するだけです.必要とあれば記者会見もセッティングいたします.会見と いってもプロジェクターやボードを使った講演会と質疑応答であり,ワイドショーの記者会見とは全く違います.
資料の作成や売り込み方法など,これまでのノウハウを活かしてサポートいたしますので,どうぞご相談下さい.
■こっちの意図と違う記事になったら嫌だな
せっかく掲載された記事が,誤解に基づくものであったり,ピントのはずれたものであっては互いにマイナスです.そうならないためにも,わかりやすい 資料を準備する必要があります.発表者とメディアの双方にプラスになるようサポートさせて頂きます.
■効果はあるの?
例えば札幌大会の時のダイアモンドの国内初報告の時は,全国の新聞とTVで大きく報道されYahooのトップページにも掲載されました.地質学会の ホームページにアクセスが集中しサーバーはパンク寸前まで追い込まれました.これは特別としてもそれ以降の発表会でも新聞,TV等で毎年報道されていま す.
■どんなネタがいいの?
タイミングや流行があるので一概には言えませんが,ジェネラルなトピックスで幅広い読者の興味を喚起するものがふさわしいです.もしも自分自身が記 者だったらと考えてみて,一般の読者に伝えたい,と思えるかどうかは一つの判断材料になるかもし
れません.
ふさわしいと思える成果がありましたら,どうぞご相談下さい.
連絡先:
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル 6F
TEL. 03-5823-1150 / FAX.03-5823-1156
e-mail:journal@geosociety.jp
広報委員会・行事委員会
記者クラブと日本地質学会
既報のとおり第四紀下限の定義変更に関するシンポジウム「人類の時代・第四紀は残った」が1/22に日本学術会議講堂にて開催されました.これに 先立ちまして,プレス向け勉強会を開催いたしました.これはシンポジウムの趣旨を深く理解して頂くとともに,地質年代の問題が広く報道され国民の皆様に周 知されることを目指したものです.
勉強会は日本地質学会が主導して日本学術会議IUGS分科会INQUA分科会および日本第四紀学会とともに,文部科学省記者クラブにて開催いたしました (開催案内は経済産業省記者クラブにも通知).地質学会からは井龍執行理事(名大)が担当いたしました.当日は10数社のメディアから記者が集まって頂 き,予定時間を大幅にオーバーする盛況な勉強会となりました.その結果,全国紙5社以上のメディアに掲載されました.この時の発表資料,質疑をもとにした Q&A,そして国際地質年代表(日本語版)等は学会ホームページに置いてあります.
今後とも地質学の普及と社会的認知を高めていくためにも,このようなプレス向け勉強会を継続していく予定です.取り上げて欲しいテーマなどご提案がござい ましたら遠慮無くご意見をお寄せください.会員皆様のご支援をお願い致します.
広報委員会
見学旅行のみどころ
日本地質学会第117年学術大会(富山大会)
見学旅行:各コースの魅力と見どころ
富山大会では中部支部を中心に多くの会員・非会員の協力を得て,魅力的な見学コース(9コース)を用意いたしました(一覧地図参照).その多くがシンポジウムや一般発表終了後の9月21-22日の期間に行われ,続く23日は秋分の日(祝日)ですので,参加しやすい日程かと思います.見学旅行の詳細は大会ホームページを参照して頂くこととして,ここでは各コースの魅力と見どころを紹介したいと思います.この機会でないと見学できない対象が多数ありますので,多くの皆様の参加をお待ちしております.
(参加申し込み〆切:FAX・郵送8/31,WEB9/3).
(見学旅行担当:原山 智・竹内 誠)
A班:富山積成盆地,北陸層群の広域テフラと第四紀テクトニクス
A班:大桑層中の恵比須峠-福田テフラ
(9/21日帰り)
案内者: 田村糸子・山崎晴雄(首都大)・中村洋介(立正大)
魅力
富山積成盆地を形成したテクトニクス(富山湾側が沈降し,山地が上昇する)を富山平野周縁の丘陵地で確認できること,積成盆地内の鮮新-更新統中のテフラ対比がテクトニクスの時間軸の精密化に大きく貢献していることを実感できると思います.
見どころ
①①①大田-PMテフラ(3.9 Ma)や谷口テフラ(2.3 Ma),恵比須峠-福田テフラ(1.75 Ma)など,鮮新-更新世の鍵テフラ7層.
②呉羽山断層の最近の動きを示す沖積面の変形や,魚津断層の幅数100mに及ぶ段丘面の長波長の撓曲.
B班:跡津川断層系の活断層露頭と飛越地震
B班:跡津川断層,真川露頭
(9/21-22)
案内者: 竹内 章(富山大)・道家涼介(地層科研)・ハスバートル(土木研)
魅力
跡津川断層は,1858(安政五)年に発生した安政飛越地震の震源断層で,顕著な微小地震活動が観測されています.跡津川断層系は1970年代から内陸活断層のテストフィールドとなっており,GPS測地をはじめ観測データが総合的に集積した結果,日本海側のひずみ集中帯における地殻地震の発生メカニズムの解明が進んでいます.(断層東部の現場は,近年アクセスに様々な規制が強化されていることから,このような機会でないと見学は困難です.)
見どころ
①跡津川断層の中央部〜東端部に至る区間で,断層破砕帯や活断層の露頭,段丘の横ずれ変位,河道閉塞,流系のオフセット,飛越地震の傷跡を見学.
②飛越地震における地表地震断層では,上下変位のほか横ずれ変位も確認できます.
③断層岩に興味がある参加者は,健岩と破砕帯,地震断層のガウジなど,各種サンプリングが可能です.
C班:立山火山
C班:称名の滝.第2期・第3期火山噴出物からなる.
(9/21-22)
案内者: 中野 俊(産総研)・奥野 充(福岡大)・菊川 茂(立山カルデラ砂防博物館)
魅力
活火山である立山火山は中部山岳国立公園内にあり,立入や試料採取の規制が厳しかったり,アプローチが困難だったりして,こうした機会でないと観察や見学は困難な状態にあります.今回は立山黒部アルペンルート沿いの千寿ヶ原から室堂までのコースを見学します.
見どころ
①主な見学対象は,第2期の火砕流堆積物,第3期の溶岩,最新期のテフラ,地獄谷の噴気地帯などで,立入許可を得たうえで歩道を外れて露頭観察をします.
②立山カルデラと五色ヶ原をカルデラ縁から遠望します.
D班:焼岳火山の大規模ラハールと火砕流堆積物
(9/21-22)
案内者: 及川輝樹(産総研)・石崎泰男(富山大)・片岡香子(新潟大・災害復興科学センター)
魅力
100km以上も流下し富山平野に達した大規模ラハール堆積物が,神通川とその上流の高原川流域に分布します.山岳地域で発生したラハールは火山から遠く離れた平野まで達することが多いため,それは火山発達史のみならず河川システムや防災学上重要なテーマとなります.火山地質学のみならず,堆積学,防災関係者の参加も歓迎します.
見どころ
①焼岳起源の大規模ラハールのつくる地形と堆積物
②ラハールの母材,焼岳火山噴出物
③焼岳の観測を行なっている京都大学付属の上宝観測所や穂高砂防観測所の見学.
E班:黒部川沿いの高温泉と第四紀黒部川花崗岩
E班:黒部川花崗岩中の苦鉄質包有岩濃集相)撮影:谷 健一郎(JAMSTEC)
(9/21-22)
案内者: 原山 智(信州大学)
魅力
黒部川峡谷鉄道に乗って,最新の地質成果にふれる見学コースです.この機会を逃すと,個人での見学は困難でしょう.第四紀黒部川花崗岩,大規模マイロナイト帯,高温泉はいずれも飛騨山脈の隆起テクトニクスとの関連でとらえることができます.祖母谷温泉(宿泊地)では,黒部川花崗岩中でのマグマ混合・混交も見学します.なお登山道には入りません.解散時間が早いので,23日に島根大で始まる日本鉱物科学会にも間に合います.
見どころ
①黒部川沿いの高温泉(黒薙・鐘釣・祖母谷温泉)
②第四紀黒部川花崗岩(苦鉄質包有岩・マグマ混合・混交)
③飛騨山脈の隆起テクトニクスに関与したマイロナイト
④花崗岩中の捕獲岩と地帯区分
F班:年代学から見た飛騨変成作用から日本海誕生後までの構造発達史
F班:飛騨片麻岩の露頭
(9/21日帰り)
案内者: 椚座圭太郎・清水正明(富山大)
魅力
飛騨変成作用の時代から白亜紀のテクトニクスを経て,日本海形成前後まで,富山県と周辺地域の構造発達史の早巡り日帰りツアーです.
見どころ
①飛騨変成作用による花崗岩ミロナイトと単斜輝石ミグマタイト
②神岡鉱山杢地鉱と横山衝上断層(白亜紀前期テクトニクス)
③手取層群中の中朝・揚子衝突帯起源の花崗岩礫
④日本海形成前・後の新第三紀層
G班:富山県に分布する上部ジュラ系〜下部白亜系手取層群の海成層と恐竜足印化石
G班:恐竜足跡露頭
(9/21-22)
案内者: 平澤 聡(京都大)・柏木健司(富山大)・藤田将人(富山市科学博物館)
魅力
国内初のよろい竜の足跡化石を産出した恐竜足跡化石露頭面のほか,手取層群海成層の岩相や,放散虫化石等の様々な微化石を含む生痕化石を見学します.
見どころ
①手取層群,有峰層・桐谷層の岩相と微化石・生痕化石
②手取層群,和佐府層の恐竜足印化石
H班:糸魚川ジオパークの地質巡り
H班:糸魚川地域全景
(9/21-22)
案内者: 竹内誠(名古屋大)・竹之内耕(フォッサマグナミュージアム)・中澤 努(産総研)
魅力
新潟県糸魚川市周辺は日本有数のヒスイ産地であり,また代表的な構造線である糸魚川−静岡構造線が分布します.糸魚川市はこれらの多種多様な地質をもとに一般市民への普及活動とジオパークの整備を続け,2009年8月には,糸魚川地域は日本で初めての世界ジオパークに認定されました.一方,2010年春には産総研地質調査総合センターより5万分の1地質図幅「小滝」が発行され,ジオパーク内の地質に多くの新知見が得られています.
見どころ
①フォッサマグナミュージアム展示見学
②糸魚川−静岡構造線露頭
③日本海拡大に伴う中新世枕状溶岩
④青海橋立のヒスイ産地
⑤300 Ma蓮華変成岩の岩相と地質構造
⑥秋吉帯青海石灰岩,舞鶴帯虫川コンプレックス,舞鶴帯と秋吉帯の境界断層
I班:糸魚川ジオパーク ヒスイ探訪ジオツアー 謎多きヒスイを多角的に楽しもう
(9/17日帰り)
案内者: 宮島 宏(フォッサマグナミュージアム)
魅力
ヒスイにまつわる自然科学的な謎,人文科学的謎を多角的にとりあげます.さまざまな色のヒスイ,宝石質ヒスイ,日本最大のヒスイ,生成の科学,ヒスイ中のSr新鉱物,加工と利用,歴史的再発見などなど,ヒスイの魅力をたっぷり堪能していただく探訪の旅です.なお9/20(月)にも,「第9回理科教員対象見学旅行」を同内容で実施予定です.
見どころ
①フォッサマグナミュージアム・青海自然史博物館のヒスイ関連展示見学
②長者原・寺地遺跡のヒスイ
③小滝ヒスイ峡
④青海川ヒスイ峡
クーポン送付について
事前参加登録 引換クーポン等の送付について
2010.9.9
事前参加申込を頂いた方に対して、申込内容に応じて各種引換クーポンをお送り致しました(9/8発送)。いずれの送付物も当日忘れずにご持参下さい。
<入金者の方へ>
予約確認証・各種青いクーポン・参加証(名札)をお送りしました。当日必ずご持参下さい。
*ご返金がある場合: 当日受付窓口でご返金致しますので、予約確認書を提示してその旨お申し出下さい。
<一部入金・未入金の方へ>
予約確認証・各種ピンクのクーポンをお送りしました。当日必ずご持参下さい。
締切(9/3)時点で一部入金もしくは、入金確認が取れていない方に対してのクーポンです。入金と入れ違いの場合はご容赦ください。
当日会場受付にて入金のご確認をさせて頂きますので、振込み時の控え等をご持参下さい.確認がスムーズに行えます.
お支払いがまだの方は、9月13日(月)までに下記いずれかへお振り込みをお願い致します。この場合も振込み時の控え等をご持参下さい。
13日までにお振込いただけなかった場合は、当日会場受付にてご清算をお願い致します。
振込先 (注意:振込時には、振込者氏名の前に必ず申込Noを入力して下さい)
(1)三井住友銀行 神田駅前支店(普通)1711424 (社)日本地質学会 / シャ)ニホンチシツガッカイ
(2)郵便振替 00140-8-28067
ランチョン・夜間小集会申込
ランチョン申込
<申込締切 7月2日(金)必着,行事委員会扱い>
9月19日(日),20日(月)にランチョンの開催を希望する方は,
(1)集会の名称,
(2)世話人氏名,
(3)集会内容等,を明記してe-mailで(ハガキも可)行事委員会:<main@geosociety.jp>宛に申し込んで下さい.申込締切は7月2日(水)です.
なお,世話人の方は,終了後集会の内容をニュース誌の大会記事用原稿としてご投稿下さい(800字以内,原稿締切:10月末).
夜間小集会の申込
<申込締切 7月2日(金)必着,行事委員会扱い>
9月19日(日)は18:00〜20:00,20日(月)は17:30〜19:00(予定)です.夜間小集会の開催を希望する方は,
(1)集会の名称,
(2)世話人氏名,
(3)集会内容(50字以内),
(4)参加予定人数,
(5)液晶プロジェクターの要・不要,
(6)その他特記すべきこと,を明記してe-mailで(ハガキも可),行事委員会:<main@geosociety.jp>宛に申し込んで下さい.申込締切は7月2日(水)です.
なお,世話人の方は,終了後集会の内容をニュース誌の大会記事用原稿としてご投稿下さい(800字以内,原稿締切:10月末).
発表者の皆様へ
発表者の皆様へ
一般講演の発表者は,一部トピックセッションおよびシンポジウムでの招待講演を除いて本学会の会員に限ります(共同発表の場合は筆頭者に適用).また,やむを得ない事情により,あらかじめ連記された共同発表者内で筆頭者の変更を希望する場合は,必ず事前に行事委員会(会期前は学会本部へ,会期中は年会本部事務局へ)に連絡して下さい.この場合も,シンポジウム以外の場合は「会員に限り1人1題」の発表制限は守るものとします.代理人による代読,発表会場内での突然の発表者変更,発表順序の変更は一切認めませんのでご注意下さい.とくに口頭発表者の方には発表時間の厳守をお願いいたします.発表に際しては座長の指示に従い,会場の運営がスムーズに行われるようご協力下さい.
■ 口頭発表
・1題15分(討論時間を含む).ただし,シンポジウムは除く
・口頭発表会場には液晶プロジェクターとWindowsパソコン(OS: Windows XP ,Vistaおよび7対応, Microsoft Office PowerPoint 2003-2007 対応)を用意します.なお,35 mmスライドプロジェクターの使用はできません.
【講演ファイルをUSBメディアでご持参の方】
口頭発表で使用するファイルのインストールは,PCセンター(試写室)【共通教育棟2階A21番教室】にて事前に作業を行ってください.インストールは各セッション・各シンポジウム開始30分前までに共通教育棟2階A21番教室PCセンター(試写室)で受け付けます.なお,大会初日9月18日午前に発表される方についても,AM 8:30までPCセンターにて受けます.混雑が予想されますので講演直前にならないよう,十分な時間的余裕を持って確実に行ってください(午前中のセッションであれば前日に,午後のセッションであれば午前中にインストールを完了してください).ファイルは,PCセンターにおいて正常に作動することを事前に確認してください.特に,会場に設置するものと異なるバージョンで作成されたパワーポイントファイルは,レイアウトが崩れる事例が報告されていますのでご注意願います.なお,ファイル名には,発表番号と筆頭演者ご氏名をご使用ください.(例:S-1富山太郎, O-12神通次郎)
【ご自分のパソコンを使用して講演をされる方】
本年は会場の液晶プロジェクターにパソコンの切り替え器(ケーブル形状はD-SUB15ピン)を用意します.Macパソコンをお使いになる方,ソフトの互換性からレイアウトが崩れる可能性のある方,パワーポイント以外のプレゼンテーションソフトをご利用の方はご自分でパソコンをご用意ください.各会場のプロジェクターの解像度設定はXGA(1024×768)です.ご講演前にご自身での出力調整をお済ませの上接続してください.Macパソコンをお使いになる方は,必ずD-SUB15ピンへのアダプターをご持参ください.パソコンの接続については,発表者自身が責任を持って実施下さい.切り替えは会場スタッフにて行います.
■ ポスターセッション
・ 掲示する際のチェスピンは準備いたします.テープのご利用はできませんので,ご了承ください.
・ 展示時間は, 9:00−17:00です.展示準備は早めにお願いします.撤収は 18:00までにお願いします.
・ コアタイムは,18日(土)が12:00 −13:00,19日(日)と20日(月・祝)が13:00 −14:00です.この時間は必ずポスターに立ち会い,その他の時間は各自の都合によって随時行って下さい.
・ ボード面積は90 cm×210 cm(ヨコ×タテ)です.
・ 発表番号・発表題名・発表者名を必ず明記して下さい.
・ コンピューターやビデオを使用される場合,機器の準備は各自で行ってください.電源は確保できませんので,予備バッテリーをご準備下さい.
・ ポスター発表に対し,毎日優秀ポスター賞が授与されます.奮ってご準備下さい.
水戸大会
水戸大会TOP
日本地質学会第118年学術大会(水戸大会)
画像をクリックすると2.8MBのjpegデータをダウンロードできます.。
日本地質学会第118年学術大会・日本鉱物科学会2011年年会
合同学術大会(水戸大会)
「いま,地球科学に何ができるか?」
一般社団法人日本地質学会・日本鉱物科学会・茨城大学 共催
>>【 水戸大会・大会趣旨 】<<
2011年 9月9日(金)〜11日(日)
盛会のうち、無事終了致しました。ありがとうございました。
次回、大阪でお会いしましょう!
9月15(土)〜17日(月・祝)[予定]
★水戸大会アンケートにご協力ください!▶▶アンケートはこちら
▶▶アンケート結果はこちら
★geo-Flash大会臨時号を配信!▶▶バックナンバーはこちら.
★ 新着情報 ★
9/5
地質学会セミナーの案内を掲載しました.
8/26
確認書等を発送しました!
7/27
全体日程表掲載しました!
7/5
東日本大震災関連ポスター展示について(募集)
6/7
講演発表申込:締切延長しました!
6/6
学術大会に係るプレス発表会へのご協力のお願い
5/27
参加登録申込の受付開始!
5/10
講演発表申込の受付開始!
5/6
ランチョン・企業展示・出展等,その他申込の要領を掲載
2/24
見学旅行:各コースの魅力とみどころ(全コースの情報を更新しました)
1/28
見学旅行:各コースの魅力とみどころ(D〜F班)
2011/1/21
見学旅行:各コースの魅力とみどころ(A〜C班)
12/27
トピックセッション募集(締切:2/14)
2010/12/27
水戸大会 関東支部茨城大学にて開催
新着情報
新着情報 2011水戸大会
2011.9.5更新 地質学会セミナーの案内を掲載しました.
■■■
9月11日開催の地質学会セミナーの案内を掲載しました.
詳細はこちらから
2011.8.26更新 確認書等を発送しました!
■■■
当日ご持参いただく確認書、名札、クーポンを発送しました.忘れずにご持参ください.
詳細はこちらから
2011.7.27更新 全体日程表掲載しました!
■■■
全体日程表を掲載いたしました.各日の日程については近日中にアップいたします.
閲覧はこちらから
2011.7.5更新 東日本大震災関連ポスター展示について
■■■
地質情報展会場にて,市民向け東日本大震災関連ポスター展示を行います.締切は8/22(月)17時です.
申込に関する注意事項や申込方法等,詳しくは,こちらから
2011.6.7更新 講演発表申込:締切延長しました!
■■■
多くの方々にご講演いただくため、講演申込の締切を延長いたしました。 お申し込みをお待ちしています。
(日本地質学会行事委員会)
オンライン講演申込締切:6月8日(水)17時厳守(郵送分は締切ました)
2011.5.27更新 参加登録申込の受付開始!
■■■
参加登録申込の受付を開始いたしました.締切はオンライン 8月5日(金)18時,郵送 8月1日(月)必着です.所属区分によって申込ページが異なりますので,よく読んで申し込んでください.
詳しくは,こちらから
2011.5.10更新 講演発表申込の受付開始!
■■■
講演発表申込の受付を開始いたしました.締切はオンライン 6月7日(火)17時,郵送 6月1日(水)必着です.昨年までと異なる部分がありますので,申込要領,発表要領をよく読んで申し込んでください.
詳しくは,こちらから
2011.5.6更新 ランチョン・企業展示・出展等,その他申込要領を掲載
■■■
ランチョン・夜間小集会の申込,企業・研究機関等関係団体による展示会の出展募集,書籍・販売ブースご利用の募集,託児室・学童ルームの案内について,それぞれ要領を掲載いたしました。
詳しくは,こちらから
2011.2.24更新 見学旅行:各コースの魅力とみどころ(1)・(2)・(3)
■■■
水戸大会では,見学旅行は茨城を中心とした関東周辺地域の地質理解のための重要な行事と位置付け,参加者に満足していただける特徴的なコース作りを目指しております.正式なコース一覧や参加申込の詳細はニュース誌4月号で紹介する予定ですが,それまでに会員の皆様に各コースの魅力や見どころを詳しく紹介していきたいと思います.
各コースの紹介はこちらから(全コースの情報を更新しました)
2010.12.27更新 トピックセッション募集(2011/2/14締切)
■■■
トピックセッション募集締切:2011年2月14日(月)*今年はシンポジウムの公募は行いません。ご注意ください。
詳しくは、こちらから
2010.12.27更新 日本地質学会第118年学術大会・日本鉱物科学会2011年年会 合同学術大会(水戸大会)開催
■■■
日本地質学会は,関東支部の支援のもと,茨城大学(水戸キャンパス)において第118年学術大会(2011年水戸大会)を日本鉱物科学会および茨城大学との共催により2011年9月9日(金)〜11日(日)の日程で開催致します.
詳しくは、こちらから
水戸大会ニュースNo.1
水戸大会ニュースNo. 1
日本地質学会第118年学術大会・日本鉱物科学会2011年年会
合同学術大会(水戸大会)
2011年9月9日(金)〜11日(日)関東支部茨城大学にて開催
日本地質学会は,関東支部の支援のもと,茨城大学(水戸キャンパス)において第118年学術大会(2011年水戸大会)を日本鉱物科学会および茨城大学との共催により2011年9月9日(金)〜11日(日)の日程で開催致します.特に,積年の課題であった鉱物科学会との共催が実現することは歴史的な進歩です.
自然災害,地球環境問題,資源問題などは人類の未来を左右するものですが,その多くが地質学に関わっています.今こそ地質学がこれらの問題にいかに貢献するかが問われています.
水戸大会では,シンポジウム「人類の危機を救う科学—地学は何ができるのか?—(仮題)」を企画し,さまざまな視点から本質に迫る議論を展開し,地質学の緊急の課題を探ります.一方,ジオパークや地学オリンピックなどの普及活動も重要な課題です.ジオパークについては,市民講演会「地域を元気にするジオパーク(仮題)」やポスター展示などにより,ジオパークの一般への普及活動を行いたいと考えています.また,地学オリンピックについての発表や小中高校生による理科研究発表により,地学教育の重要性を社会にアピールしたいと思います.
地質学会の学術大会は,日本各地の多様な地質について理解を深める絶好の機会でもあります.茨城は,およそ5億年前から現在に至るまでの長い地球の歴史が刻まれています.日本百名山の筑波山や,日本3大瀑布に数えられる袋田の滝,日本第二の面積を持つ湖である霞ヶ浦,日本列島形成に重要な役割をはたした棚倉断層など,観光地として有名な所だけではなく,貴重な地質も数多く存在します.茨城県でも茨城大学及び周辺自治体の協力によって,「茨城県北ジオパーク推進協議会」が立ち上がり,「茨城県北ジオパーク構想」の活動が本格的に始まりました.水戸大会では,これらに関連したシンポジウムやこの地域の特徴的な地質を巡る見学旅行が用意されます.
2007年札幌大会以来,新たな行事として就職説明会,懇親会後の同窓会が行われるようになりました.また,講演要旨投稿や参加登録の新たなシステムが導入され,クレジットカード払いが可能になりました.このほか,プレスリリースが本格的に行われるなど,多くの試みがなされて来ました.水戸大会でもこれらのシステムや行事をさらに定着させ,継続的に行うことができる体制を整えるとともに,企業展示や助成金を充実させて,学術大会をより魅力あるものにしていきたいと考えています.また岡山,富山大会に続き,大会開催に係わる業務をイベント会社の協力のもとに行い,開催地の負担軽減のあり方を探ります.
多くの地質学会員の皆様が水戸大会に参加され,研究発表と議論,会員相互の交流と親睦が活発に展開されることを期待しています.水戸大会の成功による学会活動の活性化と新たな進展に向けて,準備委員会一同,懸命に努力する所存です.皆様の御協力をよろしくお願い致します.
なお,同窓会の開催を希望される各大学地質系教室等の代表者の方は,3月31日までに岡田 誠(okada@mx.ibaraki.ac.jp)に御連絡下さい.
大会予告は,ニュース誌4月号を予定しております.
2010年12月
2011年水戸大会準備委員会
委員長 天野一男
事務局長 岡田 誠
定番セッション・トピックセッション
定番セッション・トピックセッション
講演申込・講演要旨締切
オンライン 6月7日(火)17時(郵送6月1日(水)必着)
↓WEBからの講演申込はこちら↓
(修正・変更もこちらから)
<シンポジウム/日本地質学会担当セッション>
・セッションテーマ,(提案名),(共催等特記事項),世話人(*印連絡責任者),趣旨の順に掲載.
・特に断りのないセッションは口頭とポスターの両方を募集します.
・提案部会に関わりなく,会員はいずれのセッションにも応募できます.ただし,応募は口頭あるいはポスター発表のいずれかの方法で,1人1題に限り発表と行うことができます.ただし,今大会では発表負担金(1,500円)を支払うことにより,地質学会担当セッションでもう1題の発表が可能です(最大2題:同一セッションで2題,異なる2セッションで各1題,どちらでも可).
・日本地質学会担当セクションで共同発表(複数の著者の発表)を行う場合は,上記の「1人1題,ただし発表負担金支払いによりもう1題可」という制約を発表者(=発表申込者)に対して適用します.その際,発表者は筆頭著者でなくても構いません(筆頭者に会員・非会員等の条件はありません).講演要旨には,発表者に○(マル)印を付けてください.
・トピックセッションにおいては,世話人は会員・非会員を問わずに招待講演を依頼することができます(締め切りました).定番セッションでは招待講演の設定はありません.日本地質学会・日本鉱物科学会に所属していない非会員招待講演者に限り参加登録費を免除します(講演要旨集は付きませんので,必要な場合は別途購入してください).
・招待講演についても,申込期日は同じです.
・口頭発表会場には液晶プロジェクターとWindowsパソコン(OS: Windows Vista, Office Standard 2007)を用意します.パワーポイントを使用する場合は,試写室において正常に作動する事を確認して下さい.昨年同様スライドプロジェクターの使用はできません.Macパソコンをお使いになる方、パワーポイントを使用しない方は世話人とご相談下さい.
【注意】★印のセッションについては、鉱物科学会の講演申込画面より,お申し込みをお願いいたします。
【鉱物科学会の講演申込画面はこちらから】
それ以外のセッションについては,会員種別に関係なく、上記の地質学会の申込画面から申し込んで下さい。
*下記をクリックすると、各セッションの詳細がご覧頂けます。
トピックセッション(20件)
★印:T1~T8は,地質学会の画面からは講演申込できません。
T1. 岩石−水相互作用★
T2. 月の地質探査と地球物理探査:アポロからセレーネ2まで★
T3. 東日本における活火山の長期活動評価と防災対策★
T4. レオロジー 地殻からコアまで★
T5. 地殻流体のダイナミズム:変形および変成作用に及ぼす流体の影響★
T6. 火成作用と流体★
T7. モンゴル・北東アジアの岩鉱資源★
T8. モホ点描− 超深部掘削計画で何がみえてくるのか?★
T9. 地質情報の利活用
T10. 日本列島の地体構造区分と構造発達史
T11. 平野地質:堆積と構造
T12. 地球史イベント大事件6:地球環境変動の鍵を地層から読み取る!
T13. ジルコンとマルチクロノロジー
T14. グリーンタフ・ルネサンス
T15. 地球表層環境解読と生命進化
T16. 地層処分と地球科学
T17. 新展開沈み込み帯地震発生帯科学:付加,造構性浸食,そして陸上アナログ
T18. ジュラ系+
T19. 関東平野の更新統とテクトニクス
T20. 自然のめぐみとジオパーク
定番セッション(25件)
★印:R1~R5は,地質学会の画面からは講演申込できません。
R1. 鉱物記載・分析評価★
R2. 結晶構造・結晶化学・物性・結晶成長・応用鉱物★
R3. 高圧科学・地球深部★
R4. 地球表層・環境・生命★
R5. 地球外物質★
R6. 深成岩・火山岩及びサブダクションファクトリー
R7. 岩石・鉱物・鉱床学一般
R8. 噴火・火山発達史と噴出物
R9. 変成岩とテクトニクス
R10. 地域地質・地域層序
R11. 地域間層序対比と年代層序スケール
R12. 海洋地質
R13. 堆積物(岩)の起源・組織・組成
R14. 炭酸塩岩の起源と地球環境
R15. 堆積相・堆積過程
R16. 石油・石炭地質学と有機地球化学
R17. 岩石・鉱物の破壊と変形
R18. 付加体
R19. テクトニクス
R20. 古生物
R21. 情報地質(ポスターのみ)
R22. 環境地質
R23. 応用地質学一般およびノンテクトニック構造
R24. 地学教育・地学史
R25. 第四紀地質
トピックセッション:20件
【日本鉱物科学会扱い】
T1.岩石−水相互作用/Water-rock interaction
(資源地質学会 共催)
土屋範芳*(東北大:tsuchiya@mail.kankyo.tohoku.ac.jp)・奥山康子(産総研)・藤本光一郎(東京学芸大)
Noriyoshi Tsuchiya*(Tohoku Univ.), Yasuko Okuyama(AIST), Koichiro Fujimoto(Tokyo Gakugei Univ.)
本トピックセッションでは,「岩石−水相互作用」に関わる分野横断的な研究発表,情報交換を推進すべく,「みず」をキーマテリアルにして,変成岩,火成岩,熱水変質,鉱床,熱水実験などの多くの分野,さらに流体の発生や移動プロセスなど基礎理論と実験に関する講演を広く募集して,地球プロセスにおける「みず」の役割を学際的に検討する.あわせて,放射性廃棄物地層処分,二酸化炭素の地層隔離などの地下利用に関する講演も募集する.
招待講演予定者:渡邊則昭(東北大)・Brian Rusk (James Cook Univ.)
ページtopに戻る
T2.月の地質探査と地球物理探査:アポロからセレーネ2まで/Geologic and geophysical exploration of the Moon: From Apollo to SELENE-2
(日本惑星科学会 共催)
荒井朋子*(千葉工業大:tomoko.arai@it-chiba.ac.jp)・佐伯和人(大阪大)・大竹真紀子(JAXA)・杉原孝充(JAMSTEC)
Tomoko Arai*(Chiba Inst. Tech.)・Kazuto Saiki(Osaka Univ.)・Makiko Ohtake(JAXA)・Takamitsu Sugihara(JAMSTEC)
月探査に基づく月科学研究の成果と将来月探査計画の展望を議論する.月は,サンプルリターン,リモートセンシング,着陸探査の全てが行われている唯一の地球外天体であり,月科学は,探査の成果とともに発展を続けている.アポロ・ルナ探査で得られたデータに基づき,月の成り立ちが大まかには理解され,その後のリモートセンシングや月隕石研究により,従来の理解が修正された.さらに最新のかぐやデータに基づく研究により,新たな月の描像が明らかにされつつある.一方,多様な表層組成・地形を持つ月の成り立ちを理解するためには,内部組成・構造の探査や,地史を理解する鍵となる地点の地質探査が必須であるという認識のもとに,現在着陸機による地質・地球物理探査計画の検討が進んでいる.
本セッションでは,かぐやなどの月探査データや月試料分析の最新研究成果およびセレーネ2月探査計画概要を紹介し,月科学の課題と展望について議論する.
招待講演予定者:なし
T3.東日本における活火山の長期活動評価と防災対策/Evaluation of long-term activity and disaster measures of active volcanoes in East Japan
(地質学会火山部会 共催)
長谷川健*(茨城大:hasegawt@mx.ibaraki.ac.jp)・大場 司(秋田大)・藤縄明彦(茨城大)
Takeshi Hasegawa*(Ibaraki Univ.)・Tsukasa Ohba(Akita Univ.)・Akihiko Fujinawa(Ibaraki Univ.)
今年1月,霧島火山(新燃岳)が噴火を開始し,活動が長期化する恐れがある.霧島火山はランクBに位置づけられる西日本の活火山であるが,東日本にも潜在的噴火リスクを軽視できないランクBの活火山が多数存在する.那須火山は,室町時代に約2年間にわたる噴火活動を起こし,100名以上の犠牲者を出した.福島県中北部にある磐梯・吾妻・安達太良の3火山も,犠牲者を伴う噴火を,明治時代に立て続けて起こしている.北海道の摩周火山は,千年前にVEI5の噴火を起こし,近年は火山性地震も多発している.本セッションでは,東日本の活火山(ランクBに限らず)を広く対象として,主に地質学的および岩石学的研究成果を募り,中・長期的視点から各火山の防災対策に関する提言を行うことを目的とする.理論,実験などによる研究も歓迎する.
招待講演予定者:なし
ページtopに戻る
T4.レオロジー 地殻からコアまで/Rheology, from crust to core
(地質学会岩石部会・地質学会構造地質部会 共催)
片山郁夫*(広島大:katayama@hiroshima-u.ac.jp)・大内智博(愛媛大GRC)・西原 遊(愛媛大GRC)
Ikuo Katayama*(Hiroshima Univ.)・Tomohiro Ohuchi(GRC, Ehime Univ.)・Yu Nishihara(GRC, Ehime Univ.)
地球内部のダイナミクスを支配するレオロジーに関する研究は,近年めまぐるしく進展している.本セッションでは,岩石鉱物のレオロジーに関して,フィールド調査等に基づく地殻の物質移動や変形特性から,実験的手法に基づく地球深部のレオロジー構造まで,幅広いトピックスを募集する.レオロジーという観点から,地球型惑星内部の変動を再検討し,日本発信型の新たな研究テーマを模索することをめざす.
招待講演予定者:武藤 潤(東北大)
ページtopに戻る
T5.地殻流体のダイナミズム:変形および変成作用に及ぼす流体の影響/Dynamism of crustal fluids: Influences of fluids on deformation and metamorphic processes in rocks
(地質学会岩石部会・地質学会構造地質部会 共催)
岡本和明*(埼玉大:kokamoto@mail.saitama-u.ac.jp)・竹下 徹(北海道大)
Kazuaki Okamoto*(Saitama Univ.)・Toru Takeshita (Hokkaido Univ.)
地殻ダイナミクスにおいて流体の存在および移動は不可欠であり,人間における血流に相当する.例えば,地殻の中で変形および変成作用が容易に起こるためには,流体の存在・移動が不可欠である.流体は多くの元素を溶かしこみ元素移動に重要な役割を果たすほか,それ自身の移動が高速の熱の移動を引き起こし(熱移流),周囲の岩石中で変形や変成作用を引き起こす結果となる.特に最近,地殻流体と内陸地震の関連が指摘されており,内陸地震の繰り返し発生機構や歪集中帯の形成機構が盛んに議論されるようになった.本トピックセッションでは流体の変成作用(特にメタソマティズム)に及ぼす役割を研究している岩石学者,変形作用に及ぼす役割を研究している構造地質学者,さらには現在の地殻内部の地震活動や流体の量・分布を観測している地球物理学者が一同に会し,地殻流体のダイナミズムにせまる.
招待講演予定者:Marie Python (Hokkaido Univ.)
ページtopに戻る
T6.火成作用と流体/Fluids in igneous processes
吉村俊平*(東北大:shumpyos@m.tains.tohoku.ac.jp)・奥村 聡(東北大)・栗谷 豪(大阪市大)
Shumpei Yoshimura*(Tohoku Univ.)・Satoshi Okumura(Tohoku Univ.)・Takeshi Kuritani(Osaka City Univ.)
本セッションでは,マントルおよび地殻に存在する流体の物理化学的性質,移動特性,周囲岩石との相互作用およびマグマの形成や分化との関わり,さらにはマグマ中でのガスの発生,火山噴火などのダイナミックな現象について,物質科学に基づいた議論を展開する.天然物質の分析,室内実験,理論の各方面より,意欲的な研究発表を幅広く募集する.
招待講演予定者:なし
T7.モンゴルおよび北東アジアの岩石鉱物資源/Rocks and mineral resources of Mongolia and Northeast Asia
(地質学会岩石部会・地質学会構造地質部会・資源地質学会・モンゴル資源地質学会 共催)
小山内康人*(九州大:osanai@scs.kyushu-u.ac.jp)・渡辺 寧(産総研)・Satish-Kumar, M.(静岡大)
Yasuhito Osanai*(Kyushu Univ.)・Yasushi Watanabe(AIST)・Satish-Kumar, M.(Shizuoka Univ.)
近年,北東アジアの地質とテクトニクスが明らかになるにつれ,この地域がアジア大陸形成の鍵となることが理解され,多方面から地球科学的アプローチがなされてきた.このような背景のもと,様々なテクトニックセッティングと対応して,変成岩岩石学的・火成岩岩石学的新知見が得られつつある.また,それらの地質体に胚胎する各種鉱物資源は,現在のハイテク産業に欠かせないものとして国際的にも注目されている.本セッションでは,モンゴルを含む北東アジア地域のテクトニクスと岩石・鉱物・資源についての新たな研究展開に向けて,意欲的な研究発表を幅広く募集し広範囲の議論を展開したい.
招待講演予定者:Jargalan Sereenen・Bat Erdene
T8.モホ点描− 超深部掘削計画で何がみえてくるのか?/A Moho Sketch: What we expect to obtain through ultra-deep drilling in ocean?
道林克禎*(静岡大:sekmich@ipc.shizuoka.ac.jp)・阿部なつ江(JAMSTEC)・橘 省吾(東京大)・河上哲生(京都大)・平賀岳彦(東大地震研)
Katsuyoshi Michibayashi*(Shizuoka Univ.)・Natsue Abe(JAMSTEC)・Shogo Tachibana(Univ. Tokyo)・Tetsuo Kawakami(Kyoto Univ.)・Takehiko Hiraga(ERI, Univ. Tokyo)
超深部掘削船ちきゅうによって海洋地殻を掘削貫通させてマントルに到達するモホール計画は,掘削候補地点が太平洋の3カ所にまで絞り込まれ,いよいよ事前探査が始まる段階である.この掘削では,海洋地殻形成・進化からモホ面の実体,そして最上部マントルの物性・化学組成など海洋リソスフェアを探求しながら,熱水循環プロセスとそれに伴う地下生命圏限界,さらにグローバルな水・炭素循環過程の解明への寄与が期待されている.これに加えて,モホール計画ではマントルまでの連続した孔内の物性や,地温勾配,電気伝導度などのその場観察その場観測,さらに地球最深部の実験環境として利用可能である.本シンポジウムでは,モホール計画の潜在的な可能性を幅広い分野の研究者によって提示してもらいながら,我々が地球表層や実験によってこれまで推定してきた地球の進化過程や未来の姿をどのように変えていくのか議論してみたい.
招待講演予定者:小平秀一(JAMSTEC)・藤村彰夫(JAXA)
ページtopに戻る
【日本地質学会扱い】
T9.地質情報の利活用/Application of geological information
(地域地質部会・情報地質部会 共同提案)
斎藤 眞*(産総研:saitomkt@ni.aist.go.jp)・野々垣 進(産総研)
Makoto Saito*(AIST)・Susumu Nonogaki(AIST)
これまで地質学会では,人類の地質への理解を進展させるためのさまざまな研究成果が発表されてきた.しかし,野外で地質情報を取得し,それらを意味のある地質情報へと変換し,社会での地質情報の利活用を推進する,という流れを持った研究成果の発表例は少ない.情報処理技術が発展した昨今,野外で取得した地質情報をデジタルデータとして整理・処理・管理する環境はほぼ整った.インターネットを通じて地質情報のデジタルデータを共有・利活用する環境も整いつつある.また,近年,ジオパーク活動が盛んになるにともない,これまで地質学とはつながりが薄かった一般社会でも,地質情報を利活用しようという機運が高まっている.昨年の富山大会でのトピックセッション「地学巡検・地学名所とガイドブック」もこの流れのうちと言える.地域地質部会・情報地質部会では,このような地質学会の現状および,世相の変化を受けて,地質情報の取得から利活用までの流れの中にある研究の成果を発表する場として,表記トピックセッションを計画する.現在,地域地質部会は,毎年の大会において定番セッションとして地域地質・地域層序を層序部会と共同で運営し,地域地質の研究成果を発表する場となっている.また,情報地質部会は,地質情報を処理するための理論・技術の開発および,それらの地質学分野への応 用などの成果を発表する場となっている.そこで,本トピックセッションでは,社会での地質情報の利活用に焦点をあて,
・特定地域から得られた地質情報の利活用および,その問題点や比較検討
・地質情報の利活用に向けた情報取得方法
・ジオパークや博物館等における地質情報の利活用
を具体的発表テーマとする.
招待講演予定者:なし
ページtopに戻る
T10.日本列島の地体構造区分と構造発達史/Geotectonic subdivision and evolution of the Japanese Islands
磯崎行雄*(東京大:isozaki@ea.c.u-tokyo.ac.jp)・山本伸次(東京大)・青木一勝(東京大)
Yukio Isozaki*(Univ. Tokyo)・Shinji Yamamoto(Univ. Tokyo)・Kazumasa Aoki (Univ. Tokyo)
急速に変わりつつある日本列島の地体構造論と形成史について議論する.とくに重要な新手法としての砕屑性ジルコン年代の大量測定がもたらすメリットについて,具体的な研究例を用いて理解を深める.また,その結果明らかになりつつある,構造浸食プロセスの造山論上の意味について議論し,従来の単純な付加体成長論や弧地殻増大史の大改訂を試みる.
招待講演予定者:平田岳史(京都大)
T11.平野地質:堆積と構造/Quaternary basin research: sedimentation and tectonic movement
卜部厚志*(新潟大学:urabe@niigata-u.ac.jp)・宮地良典(産総研)
Atsushi Urabe*(Niigata Univ.)・Yoshinori Miyachi(AIST)
これまで沖積層の新展開として,沖積層の層序や堆積環境,堆積システムの解明に関するセッションを企画してきた.これらの課題については,一定の進展が見られたことから,対象範囲を沖積層に限定せず平野や平野周辺の丘陵部などを構成する更新統以降の地層に広げ,堆積と構造をいう点をキーワードとして,堆積環境や堆積システムの復元,海水準変動との関係や地層から読み取れる構造運動(活断層の履歴),第四紀後期の堆積盆地としての発達過程など,海水準変動だけではなく地層の形成要因である構造運動や堆積作用についても視野をひろげ総合的な視点での発達過程を議論する場としたい.
招待講演予定者:なし
ページtopに戻る
T12.地球史イベント大事件6:地球環境変動の鍵を地層から読み取る!/Events in the Earth's history VI: Decoding key signals from geological archives
清川昌一*(九州大:kiyokawa@geo.kyushu-u.ac.jp)・山口耕生(東邦大)・小宮 剛(東大)・尾上哲治(鹿児島大)・黒田潤一郎(JAMSTEC)
Shoichi Kiyokawa*(Kyushu Univ.)・Kosei Yamaguchi(Toho Univ.)・Tsuyoshi Komiya(Univ. Tokyo)・Tetsuji
Onoue(Kagoshima Univ.)・Junichiro Kuroda(JAMSTEC)
地球史46億年を通して,地球表層環境は絶えずその様相を変化させてきた.その中には,ペルム紀末や白亜紀末などの生物大絶滅をもたらしたカタストロフィックな変動や,地球公転軌道の変化によるリズミカルな変動など,多様なスケールの変動がある.海洋や陸成堆積物は,そういった過去の地球環境の変動を記録してきたテープレコーダーに例えられる.しかし,必ずしも優秀な記録媒体ではなく,多くの研究者が試行錯誤してレコーディングに取り組んできた.本セッションは,特定の時代や地域にとらわれず,さまざまな視点(たとえば宇宙からの寄与・火山活動・大陸成長・海洋循環・生物進化)で地層や岩石,鉱物に記録される地球環境変動を解読する研究発表を募集する.最新の研究動向を探るための,そして将来の研究の指針を得るための,アクティブな情報交換の場となれば幸いである.
招待講演予定者:関根康人(東京大)
ページtopに戻る
T13.ジルコンとマルチクロノロジー/Zircon and multi-chronology
岩野英樹*(京都フィッショントラック:kyoto-ft@ac.auone-net.jp)・折橋裕二(東大地震研)・小笠原正継(産総研)
Hideki Iwano*(Kyoto Fisson-Track)・Yuji Orihashi (ERI, Univ. Tokyo)・Masatsugu Ogasawara(AIST)
ジルコンはU,Thを含むことから,ひとつの鉱物に対しU-Pb法,フィッション・トラック(FT)法,(U-Th)/He法など複数の年代測定手法(マルチクロノロジー)が適用できる対象のひとつである.特にジルコンは普遍的に存在し,それ自体の物理的・化学的安定性も高いという利点から,地球形成初期から第四紀試料まで幅広く利用できる.さらに各手法の閉鎖温度が異なることから,地質年代だけでなく,熱年代情報が得られる点にも強みがある.地質年代学分野において,ジルコン年代学の進歩は目覚しい.最近FT法では,原子炉照射に依存していたウラン濃度評価をレーザーアブレーションICPMSで行う新しい手法に変わりつつある.一方,当初地球形成初期のような非常に古い試料に多用されたジルコンU-Pb年代測定法では,近年の質量分析計の技術革新とともに,第四紀試料の年代測定も射程圏内に入っている.一粒のジルコンからマルチ年代情報を同時に取り出すのがジルコン年代学の最先端であり,達成しうる近未来像である.ジルコンを用いた年代測定法が進歩・融合しつつある現状を踏まえ,本セッションでは,各手法のスペシャリストがジルコン年代測定法最前線を紹介し,特徴や信頼性,課題(例えば共有の標準物質や統一的な誤差論)などが議論できる場としたい.また最新のジルコン年代学に関する応用研究も募集する.これらの発表と質疑を通じ,ジルコンマルチクロノロジーのもつ地質学研究へのポテンシャルをさらに導き出すことを目指す.もう1つの柱として,今回ジルコン年代標準物質候補試料を事前に配布し,本セッションの中で測定データを相互比較する企画も設ける.U-Pb法,FT法,(U-Th)/He法という異なる手法間で共有できる比較的若い年代のジルコンスタンダードは海外でも準備されておらず,それを日本で作成し発行する第一歩にしたい.
招待講演予定者:平田岳史(京都大)
ページtopに戻る
T14.グリーンタフ・ルネサンス/Green tuff Renaissance
細井 淳*(茨城大:10nm315x@mcs.ibaraki.ac.jp)・松原典孝(兵庫県立大)・天野一男(茨城大)
Jun Hosoi*(Ibaraki Univ.)・Noritaka Matsubara(Univ. Hyogo)・Kazuo Amano(Ibaraki Univ.)
グリーンタフは,新生代日本列島のテクトニクス,海底火山活動,グリーンタフ中に胚胎する熱水鉱床などを考える上で重要な地層である.古くから層序を編むことを中心に進められてきたグリーンタフ研究は,1970年代にプレートテクトニクスの概念がもたらされると日本列島の発達史と共に論じられ,1990年代前半に東北日本弧において総括的な研究がなされた.その後グリーンタフ研究は一気に下火となった.しかし国際的には,堆積学的手法にもとづいた水中火山岩類の研究は飛躍的に発展し,高解像度な研究が行われている.さらに国内では,海底熱水鉱床の探査・開発を,2020年を見据えた海洋国家成長戦略の一つとして取り組んでおり,海底火山活動に関連する海底熱水鉱床は注目をされている.本セッションはグリーンタフ研究における,新たな展開をめざすものである.そこで,グリーンタフに関する様々な研究の口頭およびポスター発表を募集する.
招待講演予定者:なし
ページtopに戻る
T15.地球表層環境解読と生命進化/地球表層環境解読と生命進化/Decoding of the surface environmental change through the time and coevolution of life
小宮 剛*(東京大:komiya@ea.c.u-tokyo.ac.jp)・加藤泰浩(東京大)・遠藤一佳(東京大)
Tsuyoshi Komiya*(Univ. Tokyo)・Yasuhiro Kato (Univ. Tokyo)・Kazuyoshi Endo (Univ. Tokyo)
昨今,極限環境下で生息する生命の研究や生命活動に影響を及ぼす元素の研究が急速に進んだ.特に,生体微量元素の研究は地球史を通じての生命生息環境進化と生命進化の共進化を論理的に繋げる重要な役割を担う.最近の局所微量元素分析技術の向上と重元素非常用安定同位体分析技術の発達により,過去の海水温や海水中のCl,P,N,O2,Ni,Fe,Mn,Mo,Na,Kなど生命進化に強く影響を及ぼすパラメータを定量的に解読し得るところまで来た.本セッションでは特に生命進化に焦点を当て,①生命進化,②地球表層環境が生命進化に及ぼす影響と③過去の表層環境解読から探求される生命地球史解読を議論する.
招待講演予定者:招待講演予定者:遠藤一佳(東京大)・鈴木勝彦(JAMSTEC)・中村謙太郎(JAMSTEC)・高井 研(JAMSTEC)
ページtopに戻る
T16.地層処分と地球科学/Geological disposal in Earth Science
(鉱物科学会・日本原子力学会バックエンド部会 共催)
地質環境長期安定性研究委員会(吉田英一*:dora@num.nagoya-u.ac.jp・梅田浩司・高橋正樹・渡部芳夫・宇都宮聡・丹羽正和)
Committee for Geosphere Stability Research(Hidekazu Yoshida*, Koji Umeda, Masaki Takahashi, Yoshio Watanabe, Satoshi Utsunomiya, Masakazu Niwa)
放射性廃棄物の地層処分は,日本の地質環境の理解無しには進めることのできない地球科学的課題である.本セッションでは,事業の安全な推進や安全確保の見込みなど,より具体的な課題への現状認識と問題点や将来見通しなどを俯瞰して,意見交換を目的にトピックセッションとして開催したい.
招待講演予定者:なし
ページtopに戻る
T17.新展開沈み込み帯地震発生帯科学:付加,造構性浸食,そして陸上アナログ/New insights into seismogenic subduction zones: accretion, tectonic erosion, and on-land analogue
氏家恒太郎*(筑波大:kujiie@geol.tsukuba.ac.jp)・橋本善孝(高知大)・金川久一(千葉大)・斎藤実篤(JAMSTEC)・芦寿一郎(東大大気海洋研)・木村 学(東京大)
Kohtaro Ujiie* (Univ. Tsukuba)・Yoshitaka Hashimoto (Kochi Univ.)・Kyuichi Kanagawa (Chiba Univ.)・Saneatsu Saito(JAMSTEC)・Juichiro Ashi(AORI, Univ. Tokyo)・Gaku Kimura(Univ. Tokyo)
沈み込み帯地震発生帯掘削科学は新たな局面をむかえた.付加体が発達する南海沈み込み帯では,巨大地震発生帯直上と巨大分岐断層先端部での長期孔内観測装置の設置に成功し,更には巨大地震発生帯へのインプット物質のほぼ完全なサクセッションが採取された.コスタリカ沖中米海溝では,造構性浸食域と固着域直上において掘削コアの採取と掘削同時検層が実施され,応力場や流体が造構性浸食や地震発生に果たす役割が検討され始める.沈み込み帯で発生する浅部および深部スロー地震群に関しても新たな観測データが出され,多様なすべりを再現した実験やモデル計算が進みつつある.これらの掘削・観測・実験・モデリング研究結果をふまえ,日本列島各地に分布する沈み込み帯陸上アナログを新たな視点で見直す時期にさしかかっており,地質学の果たす役割は今後益々大きくなると予想される.そこで,多種多様な研究成果を持ち寄り,現状の把握と今後の研究発展に向けた学際議論をすることを目的としたトピックセッションを開催したい.
招待講演予定者:J. Casey Moore(UC Santa Cruz)
ページtopに戻る
T18.ジュラ系+/The Jurassic +
松岡 篤*(新潟大:matsuoka@geo.sc.niigata-u.ac.jp)・堀 利栄(愛媛大)・小松俊文(熊本大)・近藤康生(高知大)・石田直人(新潟大)・柿崎喜宏(金沢大)・中田健太郎
Atsushi Matsuoka*(Niigata Univ.)・Rie Hori(Ehime Univ.)・Toshifumi Komatsu(Kumamoto Univ.)・Yasuo Kondo(Kochi Univ.)・Naoto Ishida(Niigata Univ.)・Yoshihiro Kakizaki(Kanazawa Univ.)・Kentaro Nakada(Nat. Mus. Nature and Sci., Tokyo)
2002年の新潟大会プレシンポジウム以降,毎年開催しているトピックセッション「ジュラ系+」の成果を踏まえ,ジュラ系および隣接する地質系統の研究に関する到達点を共有するとともに,わが国がジュラ系研究の拠点となることを目指す.本セッションの講演タイトルは,国際ジュラ系小委員会のNewsletterに掲載され,日本からの研究成果を世界の研究者に伝えるのに役立っている.新分野を開拓するという観点から,アジア大陸との関連を重視したテーマについての講演を呼びかけたい.そのために,中国から研究者を招へいし招待講演者としてプログラムを組むことにしている.また,夜間小集会も申し込む予定である.
招待講演予定者:Li Gang(南京地質古生物研究所)
ページtopに戻る
T19.関東平野の更新統層序とテクトニクス/Pleistocene basin-fill stratigraphy and inferred tectonics beneath the Kanto Plain
(地質学会関東支部提案・日本第四紀学会 共催)
中澤 努*(産総研:t-nakazawa@aist.go.jp)・鈴木毅彦(首都大)・中里裕臣(農業・食品産業技術総合研究機構)・水野清秀(産総研)
Tsutomu Nakazawa*(AIST)・Takehiko Suzuki(Tokyo Metro. Univ.)・Hiroomi Nakazato(NARO)・Kiyohide Mizuno(AIST)
関東盆地を埋積する更新統の層序研究は,この10年で飛躍的に進展した.これにより従来に比べ,より詳細にテクトニクスを議論することが可能となってきた.本トピックセッションでは,関東平野の更新統を対象として,テフロクロノロジー,堆積サイクル,化石層序など,さまざまな視点からの層序研究の発表を募集し,それらを基に層序対比・区分および関東平野の第四紀テクトニクスを議論する場としたい.
招待講演予定者:林 武司(秋田大)
ページtopに戻る
T20.自然のめぐみとジオパーク/Natural blessing and geopark
(茨城大学提案)
天野一男*(茨城大:kazuo@mx.ibaraki.ac.jp)・渡辺真人(産総研)・高木秀雄(早稲田大)・原田憲一(京都造形芸術大)
Kazuo Amano*(Ibaraki Univ.)・Mahito Watanabe(AIST)・Hideo Takagi(Waseda Univ.)・Kenichi Harada(Kyoto Univ. Art and Design)
世界ジオパークネットワークに認定された日本のジオパークは,すでに4ヶ所に及んでいる.世界ジオパークネットワーク,日本ジオパークネットワークからの認定を目指している地域も多く,ジオパークへの関心は大変高いものとなっている.変動帯に属す日本列島のジオパークは,ジオの多様性という観点からも,世界のジオパークの中で特徴的なものになる.変動帯におけるジオパークのあり方について,自然のめぐみとの関連で討論する.また,自然災害の教訓をどのようにジオパークの中に取り込み,一般市民への普及を行うかも極めて重要な課題である.自然災害とジオパークのあり方についても討論したい.
招待講演予定者:なし
ページtopに戻る
定番セッション:25件
【日本鉱物科学会扱い】
R1.鉱物記載・分析評価/Characterization and description of minerals(鉱物科学会)
宮脇律郎*(国立科学博物館:miyawaki@kahaku.go.jp)・赤坂正秀(島根大)・黒澤正紀(筑波大)
Ritsuro Miyawaki*(Nat. Mus. Nature and Sci., Tokyo)・Masahide Akasaka(Shimane Univ.)・Masanori Kurosawa(Univ. Tsukuba)
本セッションでは,鉱物の記載およびそれを可能にする分析手法に関する研究を広く募集する。鉱物の様々な特徴(産状・形態・内部組織・結晶構造・組成・流体包有物・固相包有物・結晶欠陥など)と新鉱物の記載,鉱物の特性を解明する分析手法・解析手法の開発についての発表を歓迎する。
R2.結晶構造・結晶化学・物性・結晶成長・応用鉱物/Crystal structure, crystal chemistry, physical properties of minerals, crystal growth and applied mineralogy(鉱物科学会)
杉山正和*(東北大:kazumasa@imr.tohoku.ac.jp)・吉朝 朗(熊本大)・長瀬敏郎(東北大)
Kazumasa Sugiyama*(Tohoku Univ.)・Akira Yoshiasa(Kumamoto Univ.)・Toshiro Nagase(Tohoku Univ.)
本セッションでは,天然および人工鉱物の原子配列および微細構造,鉱物合成,結晶成長や溶解,相転移や物性および鉱物の応用に焦点を当てた研究を広く募集する.物性では,磁気的性質,光学性質,熱力学的性質,吸着特性などの基本的性質に焦点をあて,その応用についても広く募集する.また,鉱物の応用に関する研究も積極的に応募いただきたい.
R3.高圧科学・地球深部/High-pressure science and deep Earth's material(鉱物科学会)
井上 徹*(愛媛大:inoue@sci.ehime-u.ac.jp)・鍵 裕之(東京大)・永井隆哉(北海道大)
Toru Inoue*(Ehime Univ.)・Hiroyuki Kagi(Univ. Tokyo)・Takaya Nagai(Hokkaido Univ.)
プレートテクトニクスやプリュームテクトニクスの概念は,地球深部のダイナミクスが地球の進化や地球表層の環境に大きな影響を与えていることを示唆し,地球深部の鉱物科学を理解することの重要性がより増してきている.本セッションでは,超高圧高温実験,計算機実験,地球深部起源鉱物の記載などを通じ,地球深部の鉱物科学を広く議論する.対象は鉱物だけではなく,アナログ物質,非晶質,メルトの研究も歓迎する.
R4.地球表層・環境・生命/Earth's surface materials, environments, and life(鉱物科学会)
福士圭介*(金沢大:fukushi@kenroku.kanazawa-u.ac.jp)・村上 隆(東京大)・佐藤 努(北海道大)
Keisuke Fukushi*(Kanazawa Univ.)・Takashi Murakami(Univ. Tokyo)・Tsutomu Sato(Hokkaido Univ.)
地球表層を構成する鉱物の結晶構造・化学組成・表面特性・溶解及び析出反応,バイオミネラリゼーション,鉱物-水-大気-微生物相互作用,無機-有機相互作用など,地球表層鉱物全般および生物作用と環境への影響に関する発表を募集する.
ページtopに戻る
R5.地球外物質/Extraterrestrial materials(鉱物科学会)
圦本尚義*(北海道大:yuri@ep.sci.hokudai.ac.jp)・海田博司(極地研)・橘 省吾(東京大)
Hisayoshi Yurimoto*(Hokkaido Univ.)・Hiroshi Kaiden(NIPR)・Shogo Tachibana(Univ. Tokyo)
プレソーラー粒子,宇宙塵,隕石,月試料など地球以外を起源とする固体惑星物質の鉱物科学的な研究発表を募集する.
ページtopに戻る
【日本地質学会扱い】
R6.深成岩・火山岩及びサブダクションファクトリー/Plutonic rocks, volcanic rocks and subduction factory(鉱物科学会,地質学会火山部会,地質学会岩石部会 共同提案)
伴 雅雄*(山形大:ban@sci.kj.yamagata-u.ac.jp)・田村芳彦(JAMSTEC)・土谷信高(岩手大)
Masao Ban*(Yamagata Univ.)・Yoshihiko Tamura(JAMSTEC)・Nobutaka Tsuchiya(Iwate Univ.)
深成岩および火山岩を対象に,マグマプロセスにアプローチした研究発表を広く募集する.発生から定置・固結に至るまでのマグマの物理・化学的挙動や,テクトニクスとの相互作用について,野外地質学・岩石学・鉱物学・火山学・地球化学・年代学など様々な視点からの活発な議論を期待する.また,大陸地殻の生成場としても重要なサブダクションファクトリーに関連した研究発表も歓迎する.
R7.岩石・鉱物・鉱床学一般/General studies from petrology, mineralogy and economic geology(鉱物科学会,地質学会岩石部会,資源地質学会 共同提案)
安東淳一*(広島大:jando@hiroshima-u.ac.jp)・藤永公一郎(東京大)
Jun-ichi Ando*(Hiroshima Univ.)・Koichiro Fujinaga(Univ. Tokyo)
岩石学,鉱物学,鉱床学,地球化学などの分野をはじめとして,地球・惑星物質科学全般にわたる岩石及び鉱物に関する研究発表を広く募集する.地球構成物質についての多様な研究成果の発表の場となることを期待する.
R8.噴火・火山発達史と噴出物/Eruption, volcanic evolution and volcanic products(地質学会火山部会,鉱物科学会 共同提案)
土志田 潔*(電力中央研究所 : toshida@criepi.denken.or.jp)・工藤 崇(産総研)
Kiyoshi Toshida*(CRIEPI)・Takashi Kudo(AIST)
火山地質ならびに火山現象のモデル化に関し,マグマや熱水性流体の上昇過程,噴火様式,噴火経緯,噴出物の移動・運搬・堆積,各火山あるいは火山地域の発達史,火山活動とテクトニクス・化学組成をはじめとする,幅広い視点からの議論を期待する.
R9.変成岩とテクトニクス/Metamorphic rocks and related tectonics(地質学会岩石部会,鉱物科学会 共同提案)
中村大輔*(岡山大:nakadai@cc.okayama-u.ac.jp)・遠藤俊祐(名古屋大)
Daisuke Nakamura*(Okayama Univ.)・Shunsuke Endo(Nagoya Univ.)
国内および世界各地の変成岩を主な対象に,記載的事項から実験的・理論的考察を含め,またマイクロスケールから大規模テクトニクスまで,様々な地球科学的手法・規模の視点に立った斬新な話題提供と活発な議論を期待する.
ページtopに戻る
R10.地域地質・地域層序/Areal geology/Stratigraphy(地域地質部会・層序部会)
松原典孝* (兵庫県立大:matsubara-n@stork.u-hyogo.ac.jp)・吉川敏之(産総研)・岡田 誠 (茨城大)
Noritaka Matsubara*(Univ. Hyogo)・Toshiyuki Yoshikawa(AIST)・Makoto Okada(Ibaraki Univ.)
国内,海外問わず各地域に関係した地質や層序の発表を広く募集.地域的な年代,化学分析,リモセン,活構造,地質調査法等の発表も歓迎.ジオパークにおける学術研究の成果発表や地質災害地の地質,惑星地質もここに含まれる.地域を軸にした討論を期待する.地質図や断面図のポスター発表を特に歓迎.
ページtopに戻る
R11.地域間層序対比と年代層序スケール/Stratigraphy correlation/Chronostratigraphy(層序部会)
里口保文(琵琶湖博物館:satoguti@lbm.go.jp)・岡田 誠(茨城大)
Yasufumi Satoguchi*(Lake Biwa Mus.)・Makoto Okada (Ibaraki Univ.)
テフラ等の鍵層を用いて異なる地域間の層序対比に主体をおく研究や,鍵層そのものを主体とした研究,または複合的層序学等によるグローバルな年代層序スケールの構築に寄与するような研究についての講演を歓迎します.
R12.海洋地質/Marine geology(海洋地質部会)
荒井晃作*(産総研:ko-arai@aist.go.jp)・徳山英一(東大大気海洋研)・ 芦 寿一郎(東大大気海洋研)・小原泰彦(海上保安庁)
Kohsaku Arai*(AIST)・Hidekazu Tokuyama(AORI, Univ. Tokyo)・Juichiro Ashi(AORI, Univ. Tokyo)・Yasuhiko Ohara(JCG)
海洋地質に関連する分野(海域の地質・テクトニクス・変動地形学・海域資源・堆積学・海洋学・古環境学・陸域地質での海洋環境変遷研究など)の研究発表を募集する.調査速報・アイデアの公表・海底地形地質・画像データなどのポスター発表も歓迎する.
ページtopに戻る
R13.堆積物(岩)の起源・組織・組成/Origin, texture and composition of sediments(堆積地質部会)
太田 亨*(早稲田大:tohta@toki.waseda.jp)・野田 篤(産総研)
Tohru Ohta*(Waseda Univ.)・Atsushi Noda(AIST)
砕屑物の生成(風化・侵食・運搬)から堆積岩の形成(堆積・沈降・埋積・続成)まで,組織(粒子径・形態)・組成(粒子・重鉱物・化学・同位体・年代)・物性などの堆積物(岩)の物理的・化学的・力学的性質を対象とし,その起源・形成過程・後背地・古環境や地質体の発達史を議論する.太古代の堆積岩から現世堆積物まで,珪質岩・火山砕屑岩・風成塵・リン酸塩岩・蒸発岩・有機物・硫化物などについての研究も歓迎する.
R14.炭酸塩岩の起源と地球環境/Origin of carbonate rocks and related global environments(堆積地質部会)
山田 努*(東北大:t-yamada@m.tains.tohoku.ac.jp)・比嘉啓一郎(福岡大)
Tsutomu Yamada*(Tohoku Univ.)・Keiichiro Higa(Fukuoka Univ.)
炭酸塩岩・炭酸塩堆積物の堆積作用,組織,構造,層序,岩相,生物相,地球化学,続成作用,ドロマイト化作用など,炭酸塩に関わる広範な研究発表を募集する.また,現世炭酸塩の堆積作用・発達様式,地球化学,生物・生態学的な視点からの研究発表も歓迎する.
R15.堆積相・堆積過程/Sedimentary facies and processes(現行地質過程部会・堆積地質部会)
片岡香子*(新潟大:kataoka@gs.niigata-u.ac.jp)・成瀬 元(千葉大)・市原季彦(復建調査設計(株))
Kyoko S. Kataoka*(Niigata Univ.)・Hajime Naruse(Chiba Univ.)・Toshihiko Ichihara(Fukken Co. Ltd.)
さまざまな環境で生じる堆積過程と堆積相の分類・記載・解釈に関する発表や,堆積相解析に基づく堆積システム・シーケンス層序学についての議論を広く募集する.さらに,堆積作用や地層形成のダイナミクスに関連する理論・アナログ実験・数値シミュレーション・現地観測等の研究発表を歓迎する..
ページtopに戻る
R16.石油・石炭地質学と有機地球化学/Coal and petroleum geology/Geochemistry(石油・石炭関係・堆積地質部会)
金子信行*(産総研:nobu-kaneko@aist.go.jp)・河村知徳(石油資源開発)
Nobuyuki Kaneko*(AIST)・Tomonori Kawamura(JAPEX)
国内外の石油・石炭地質および有機地球化学に関する講演を集め,石油・天然ガス・石炭鉱床の成因・産状・探査手法など,特にトラップ構造,堆積盆,堆積環境,貯留岩,根源岩,石油システム,資源量,炭化度などについて討論する.
R17.岩石・鉱物の破壊と変形/Rock failure and deformation(構造地質部会)
西川 治*(秋田大:nisikawa@lfp03.mine.akita-u.ac.jp)・大坪 誠(産総研)
Osamu Nishikawa*(Akita Univ.)・Makoto Otsubo(AIST)
断層岩を含む岩石・鉱物の破壊および変形機構,変形微細構造,岩石・鉱物のレオロジーや物性に関する研究を募る.観察・観測・分析・実験・理論など多方面からのアプローチによる成果を歓迎するとともに,会場での活発な議論を期待する.
R18.付加体/Accretionary prism(構造地質部会)
坂口有人*(JAMSTEC:arito@jamstec.go.jp)・内野隆之 (産総研)
Arito Sakaguchi*(JAMSTEC)・Takayuki Uchino(AIST)
現世,過去を問わず,付加体に関するすべての講演を歓迎する.付加体の形成機構,形成史,微細構造,流体移動,シュードタキライト,温度圧力構造など,様々なアプローチによる成果をもとに議論する.
ページtopに戻る
R19.テクトニクス/Tectonics(構造地質部会)
藤内智士*(産総研:s-tonai@aist.go.jp)・佐藤活志(京都大)
Satoshi Tonai*(AIST)・Katsushi Sato(Kyoto Univ.)
地球科学の多方面から,大小様々な時間・空間スケールで起こる地質構造の成因や形成機構・発達史に関する講演を広く募集する.野外調査,観測,実験,理論などに基づいた研究発表を歓迎する.
R20.古生物/Paleontology(古生物部会)
平山 廉(早稲田大)・北村晃寿(静岡大)・太田泰弘(北九州博)・三枝春生(兵庫県立人と自然の博)・須藤 斎*(名古屋大:suto.itsuki@a.mbox.nagoya-u.ac.jp)
Ren Hirayama(Waseda Univ.)・Akihisa Kitamura(Shizuoka Univ.)・Yasuhiro Ota(Kitakyushu Mus.)・Haruo Saegusa(Mus. Nature and Human Activities, Hyogo)・Itsuki Suto*(Nagoya Univ.)
古生物を扱った,または関連する研究の発表・討論を行う.
ページtopに戻る
R21.情報地質/Geoinformatics(情報地質部会)ポスターセッションのみ,口頭講演なし
野々垣 進*(産総研:s-nonogaki@aist.go.jp)・能美 洋介(岡山理大)
Susumu Nonogaki*(AIST)・Yosuke Noumi(Okayama Univ. Sci.)
地質情報の数理解析,統計解析,データ処理,画像処理などの理論,応用,システム開発,利用技術など,最近の情報地質分野の研究結果を対象とする.また,これらの成果の地質学の広い分野への応用・普及なども歓迎する.
R22.環境地質/Environmental geology(環境地質部会)
難波謙二(福島大)・風岡 修(千葉環境研)・三田村宗樹(大阪市大)・田村嘉之*(千葉環境財団:tamura-yoshiyuki@pop07.odn.ne.jp)
Kenji Nanba(Fukushima Univ.)・Osamu Kazaoka(Res. Inst. Environ. Geol., Chiba)・Muneki Mitamura(Osaka City Univ.)・Yoshiyuki Tamura*(Chiba Pref. Environ. Foundation)
地質汚染,医療地質,地盤沈下,湧水,水資源,湖沼・河川,都市環境問題,法地質学,環境教育,地震動,液状化・流動化,地震災害,岩盤崩落など,環境地質に関係する全ての研究の発表・討論を行う.
R23.応用地質学一般およびノンテクトニック構造/Engineering geology and non-tectonic geology(応用地質部会)
小嶋 智(岐阜大)・須藤 宏*(応用地質(株):sudou-hiroshi@oyonet.oyo.co.jp)
Satoru Kojima(Gifu Univ.)・Hiroshi Sudo*(OYO Corp.)
応用地質学一般では,種々の地質ハザードの実態,調査,解析,災害予測,ハザードマップの事例・構築方法,土木構造物の設計・施工・維持管理に関する調査,解析など,応用地質学的視点に立った幅広い研究を対象とする.また,ノンテクトニック構造では,ランドスライドや地震による一過性の構造,重力性の構造等の記載,テクトニック構造との区別や比較・応用等の研究を対象にして発表・議論する.
ページtopに戻る
R24.地学教育・地学史/Geoscience education/History(地学教育部会・地学教育委員会共催)
矢島道子*(東京医科歯科大:pxi02020@nifty.com)
Mchiko Yajima*(Tokyo Med. and Dental Univ.)
新学習指導要領の施行は目前.現場からの問題提起,多くの実践報告を持ちより議論しよう.また地学史からの問題提起,貴重な史的財産の開示を歓迎する.
R25.第四紀地質/Quaternary geology(第四紀地質部会)
吉川周作*(syoshi@kcn.jp)・内山 高(山梨環境研)
Shusaku Yoshikawa*・Takashi Uchiyama(YIES)
第四紀地質に関する全ての分野(環境変動・気候変動・湖沼堆積物・地域層序など)からの発表を含む.また,新しい調査や研究,方法の開発や調査速報なども歓迎する.
ページtopに戻る
日程・プログラム
全体日程・プログラム
9/9(金)
シンポジウム「関東盆地の地質・地殻構造とその形成史」,セッション発表(口頭,ポスター),表彰式・記念講演会,懇親会
9/10(土)
シンポジウム「太陽系固体惑星地質探査:イトカワから火星・金星まで」,セッション発表(口頭,ポスター), ランチョン,夜間小集会,関連普及行事・理科教員向け見学旅行(J班),就職支援プログラム,実行委員会主催特別講演会
9/10(土)〜11(日)
地質情報展
9/11(日)
シンポジウム「大規模災害のリスクマネージメント―東北地方太平洋沖地震に学ぶ―」,セッション発表(口頭,ポスター),市民講演会(午後),ランチョン,夜間小集会,関連普及行事・生徒「地学研究」発表会,地質学会セミナー
9/12(月)〜13(火)
見学旅行
*J班は10日(土)
※電力供給不足,計画停電の影響等により,9月の大会開催時期に状況が変化している可能性もないとは言えません.今後の展開によっては,シンポジウムやセッション等の日程変更や中止等を余儀なくされることもあり得ます.大幅な予定変更が生じた場合は,ホームページやgeo-Flash(メールマガジン)等を通じて速やかに会員の皆様にお知らせします.
■全体日程表(画像をクリックするとpdf版がダウンロードできます.)
※9/1 修正版に更新
■各講演プログラム(それぞれの日程をクリックするとpdf形式でご覧になれます.)
9/9(金)
口頭
9/10(土)
口頭
9/11(日)
口頭
ポスター
ポスター
ポスター
表彰式・記念講演会
学会各賞表彰式・記念講演
日 程: 9月9日(金)13:40〜18:00
会 場: 茨城大学水戸キャンパス講堂
13:40-14:30
日本地質学会新名誉会員・50年会員顕彰式,各賞授与式
14:40-14:50
池田幸雄茨城大学学長ご挨拶
14:50-15:20
日本地質学会小澤儀明賞受賞スピーチ 黒田潤一郎会員
「白い時代の黒い石 〜白亜紀黒色頁岩の魅力と,白黒つかない問題〜」
日本地質学会柵山雅則賞受賞スピーチ 河野義生会員
「弾性波速度を観察して」
15:20-15:50
日本鉱物科学会研究奨励賞受賞スピーチ(2名)
15:55-16:55
日本地質学会国際賞受賞記念講演 Dr. J. Casey Moore
「The Shimanto Complex and Ocean Drilling : Linking Across the Pacific」
日本地質学会賞受賞記念講演 岩森 光会員
「地球内部の地質学」
17:00-18:00
日本鉱物科学会学会賞スピーチ(2名)
※記念講演会は日本鉱物科学会と合同で開催
地学教育・普及・関連行事
地学教育・普及・関連行事
■ 地質情報展2011みと
■ 市民講演会 「東日本大震災と地震・津波・原発」
■ 実行委員会主催 特別講演会
■ 理科教員向け見学旅行 「地学教育:地層を見る・地層を作る」
■ 小さなEarth Scientistのつどい: 第9回小中高校生徒「地学研究」発表会
※各行事の画像をクリックすると,大きな画像,またはPDFをダウンロードできます.
地質情報展2011みと
日時 2011年9月10日(土)〜11日(日)10:00-16:00 (予定)【入場無料】
会場 堀原運動公園 武道館(水戸市新原2-11-1)
*アクセスマップ→http://www.ibaraki-sports.or.jp/horihara/09access/index.htm
主催:独立行政法人産業技術総合研究所地質調査総合センター・国立大学法人茨城大学・一般社団法人日本地質学会
水戸大会に合わせ,地質調査総合センターならびに茨城大学が有する各種地質情報から,茨城県及び周辺の地質現象について展示パネルや映像それに標本を使って紹介します.
「地質情報展2011みと ―未来に活かそう 大地の鳴動―」の詳細は地質調査総合センターのHPを御覧ください。
ページトップに戻る
実行委員会主催特別講演会
日時 2011年9月10日(土)
会場 茨城大学水戸キャンパス 講堂(水戸市文京2-1-1)
*アクセスマップ→http://www.ibaraki.ac.jp/generalinfo/campus/mito/index.html
尾池和夫(日本ジオパーク委員会委員長,前京都大学総長,京都大学名誉教授):日本のジオパーク―列島の大地に学ぶ
問い合わせ先:天野一男(茨城大学理学部)
e-mail: kazuo@mx.ibaraki.ac.jp,
電話 029-228-8390
ページトップに戻る
市民講演会「東日本大震災と地震・津波・原発」
日時 2011年9月11日(日)午後
会場 茨城大学水戸キャンパス 講堂(水戸市文京2-1-1)
*アクセスマップ→http://www.ibaraki.ac.jp/generalinfo/campus/mito/index.html
後援(全て予定)水戸市,各市町村観光協会,茨城産業会議,茨城県地質調査業協会,全国地質調査業協会,NPO地質情報整備・活用機構,日本地理学会,日本第四紀学会
2011年3月11日に起こった東北地方太平洋沖地震は,莫大な被害をもたらした.津波による膨大な被害に加え,それに伴った原子力発電所の災害は世界に類を見ないものとなった.プレートの沈み込み帯という不安定な地域である日本列島において地震による被害は想定されていたとは言え,今回はその想定を大きく上回った.われわれが日本列島に住み続ける限り,地震のような自然災害とはずっとつきあっていかなければならない.そのためには,まず自然災害のメカニズムを科学的に理解することが重要である.本講演会は,東北地方太平洋沖地震とそれに伴った津波について講演を行い,一般市民に地震と津波について自然科学的な理解を深めてもらうことを目的とする.
・都司嘉宣(東京大学地震研究所):巨大津波の教訓
・澤井祐紀(産業技術総合研究所 活断層・地震研究センター):地層が語る過去の巨大地震と津波
・石橋克彦(神戸大学名誉教授):2011年東北地方太平洋沖巨大地震と福島原発震災
問い合わせ先:天野一男(茨城大学理学部)
e-mail: kazuo@mx.ibaraki.ac.jp,
電話 029-228-8390
ページトップに戻る
小さなEarth Scientistのつどい〜第9回 小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜
日時 2011年9月11日(日)9:00-15:30 (予定)
会場 茨城大学水戸キャンパス ポスター会場(水戸市文京2-1-1)
*アクセスマップ→http://www.ibaraki-sports.or.jp/horihara/09access/index.htm
後援 茨城県教育委員会(予定)
日本地質学会地学教育委員会では,地学普及行事の一環として,地学教育の普及と振興を図ることを目的として,学校における地学研究を紹介する「地学研究」発表会をおこなっています.水戸大会でも,小・中・高等学校の地学クラブの活動,および授業の中で児童・生徒が行った研究の発表を募集いたします.茨城県内,また関東地方の学校,さらには全国の学校の参加をお待ちしています.会場は研究者も発表するポスター会場内に,特設コーナーを用意いたします.同時並行で研究者の発表も行われますので,児童・生徒同士のみならず,研究者との交流もできます.この会を通じて生徒,研究者,市民の交流が進み,地質学,地球科学への理解が深まって,未来を担う生徒たちの学習意欲への良い刺激と励みになることを願っております.
なお,参加証とともに,優秀な発表に対しては審査のうえ,「優秀賞」などの賞を授与いたします.
下記の要領にて参加校を募集します.
4)参加対象
・小,中,高校地学クラブならびに理科クラブ等の活動成果の発表
・小,中,高校の授業における研究成果の発表
・活動,研究内容は地学的なもの(地質や気象などの地球科学・環境科学,天文など)
5)申込締切 7月11日(月),下記,日本地質学会地学教育委員会宛にお申し込み下さい.
6)発表形式 ポスター発表(展示パネルは幅90cm×高さ180cm程度)
パネルのほかに標本等を展示される場合には,パネルの前に机を用意します.参加申込書にその旨を記載して下さい.その場合は展示パネルの下側が隠れる事をご了承下さい.発表者は決められた時間(および随時)パネルの前に待機し説明をしていただきます.なお,遠隔地および学校行事等のために児童・生徒が参加できない場合は,発表ポスターのみをお送りいただいても結構です.
7)参加費 無料(参加者・引率者とも),開催中の研究者の発表,講演も聴くことができます.
8)派遣依頼 参加者・引率者については学校長宛,日本地質学会より派遣依頼状を出します.
9)問い合わせ・申込先:参加申込は,別紙書式をFAXして下さい.e-mailでも結構です.
日本地質学会地学教育委員会(担当 三次)
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F
TEL:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156 e-mail:main@geosociety.jp
申込書式はこちらからダウンロードしてください
V V V V V
■WORD形式 ■PDF形式
ページトップに戻る
理科教員向け見学旅(J班)「地学教育:地層を見る・地層をはぎ取る」
日 時:2011年9月10日(土)*日帰り
コース:8:00 茨城大学→9:00 大洗海岸→10:30 水戸市下入野(露頭)→14:00 水戸市東前(露頭)→16:00 茨城大学(実習)→17:30 解散
案内者:伊藤 孝(茨城大教育)・牧野泰彦(茨城大教育)・植木岳雪(産総研)・中野英之(京都教育大)・小尾 靖(神奈川県立相模原青陵高校)
参加費:1,000円 (参加申込費別)
備考:茨城大学集合解散,中型バス使用.昼食は各自でご用意下さい.(地形図)磯浜(1/2.5万)
※地学教育委員会補助事業
魅力
現世の砂浜と第四紀の地層からどういう情報を読めるか,児童・生徒に伝えるか,というのがテーマの一つです.実際に現世の砂浜海岸・第四系を前に皆で議論したいと思います.一方では,諸事情により児童・生徒を野外へと連れ出すことが困難な状況です.そのため,写真や動画では伝えられない地層の質感を教室で表現できる手段として,地層のはぎ取りの作成法とその活用法を提案します.また,簡便な手法で教室において地層を再現する実験法も併せて提示します.
見どころ
1.大洗海岸の地形・堆積物の読み方
2.第四紀海浜堆積物の読み方
3.地層のはぎ取りの実践
4.地層のはぎ取りを活用した授業実践の提示
5.教室で地層を再現する簡易水路実験の実践
**申込は、大会参加登録システムより、他の見学旅行と同様にお申し込みください**
「大会参加登録」>> こちらから
ページトップに戻る
シンポジウム
シンポジウム
講演申込・講演要旨締切:
オンライン 6月7日(火)17時(郵送 6月1日(水) 必着)<
↓WEBからの講演申込はこちら↓
(修正・変更もこちらから)
<シンポジウム/日本地質学会担当セッション>
今大会では3件のシンポジウムを開催します.
シンポジウムの発表者には,セッション発表における1人1件の制約は及びませんので,シンポジウムで発表する日本地質学会あるいは日本鉱物科学会の会員は別途セッションにも発表を申し込むことができます.また昨年同様,世話人は,会員・非会員を問わず招待講演を依頼することができます(締め切りました).なお,日本地質学会・日本鉱物科学会に所属していない非会員の招待講演者に限り参加登録費は免除します(講演要旨集は付きません.必要な場合は,別途購入して下さい).
今大会では1件のシンポジウム「太陽系固体惑星地質探査:イトカワから火星・金星まで」で発表の一般募集があります.採択・不採択は,世話人が決定します.一般募集に発表を申し込む場合は,事前に代表世話人に連絡し,承認を受けてから発表申込システムに入力して下さい.代表世話人へ連絡せずに発表申込をした場合,発表できないことがあります.
講演要旨は,セッション発表と同じ分量ですので,原稿フォーマットを参照して原稿の作成をお願いします.
*各タイトルをクリックすると、詳細をご覧いただけます
シンポジウム
1.太陽系固体惑星地質探査:イトカワから火星・金星まで(一般公募あり)
2.大規模災害のリスクマネージメント―東北地方太平洋沖地震に学ぶ―(一般公募なし)
3.関東盆地の地質・地殻構造とその形成史(一般公募なし)
*印は連絡責任者です.
1. 太陽系固体惑星地質探査:イトカワから火星・金星まで(両学会共同企画)
Geological researches of solid planets in the Solar System: From Itokawa to Mars and Venus
圦本尚義(北海道大)・石渡 明*(東北大)geoishw@cneas.tohoku.ac.jp
Hisayoshi Yurimoto(Hokkaido Univ.)・Akira Ishiwatari*(Tohoku Univ.)
昨年の「はやぶさ」による小惑星「イトカワ」の微粒子回収成功は日本の惑星探査を大きく進展させた.そして,従来の米国・ロシア・日本などの月・火星・金星探査及び隕石研究の進展は,地質学と鉱物科学の対象を大きく地球外に拡大させつつある.日本地質学会と日本鉱物科学会はこの記念すべき年に,太陽系固体惑星科学の現状を総括し,将来の展望を語り合うため,このシンポジウムを共催する.
招待講演予定者:中村智樹(東北大)・顫山 明(大阪大)・大竹真紀子(JAXA)・佐伯和人(大阪大)・野口高明(茨城大学)・後藤和久(千葉工業大)・山路 敦(京都大)(一般公募あり)
2.大規模災害のリスクマネージメント―東北地方太平洋沖地震に学ぶ―(両学会共同企画)
Risk management of large-scale disasters —Major lessons from the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake—
天野一男*(茨城大:kazuo@mx.ibaraki.ac.jp)・木村 眞(茨城大)・藤本光一郎(東京学芸大)・土屋範芳(東北大)・原田憲一(京都造形芸術大)
Kazuo Amano*(Ibaraki Univ.)・Makoto Kimura(Ibaraki Univ.)・Koichiro Fujimoto(Tokyo Gakugei Univ.)・Noriyoshi Tsuchiya(Tohoku Univ.)・Kenichi Harada(Kyoto Univ. Art and Design)
2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は,東日本に莫大な被害をもたらした.変動帯である日本列島に住んでいる限り,我々は地震災害・火山災害をはじめさまざまな自然災害に常におそわれる危険と隣り合わせである.にもかかわらず,私たちは安定大陸で発展した,原子力発電や高速鉄道,超高層ビルなど科学技術に支えられた文明をかなり無批判に導入してきた.
今まで地球科学は自然災害の予測にも力を注いで来たが,戦後における社会環境の変化を十分に考慮しなかったために,その学術的な成果は今回の震災において必ずしも活かされなかった.これは地球科学に携わるものにとって忸怩たるものがある.これを機会に,東北地方太平洋沖地震のような大規模な自然災害のリスクマネージメントの(従来の)あり方を虚心坦懐に見直し,今後の安全・安心な国土利用を国民と共に真剣に考えることが必要である.
今回は,地震と津波による被害ならびに原発被害に焦点を絞り,地球科学の社会への貢献のあり方を様々な分野から検討する.地質学を基礎とした応用科学,災害科学,資源科学などといった自然科学分野のみならず,政策科学や情報科学などといった社会科学的な側面からも討論したい.
招待講演予定者:未定(一般公募なし)
↑このページのTOPに戻る
3.関東盆地の地質・地殻構造とその形成史(共催:日本第四紀学会)
Subsurface Structures and Evolution of the Kanto Basin
佐藤比呂志*(東大地震研:satow@eri.u-tokyo.ac.jp)・小田原 啓(神奈川県温泉地学研)・水野清秀(産総研)・鈴木毅彦(首都大)
Hiroshi Sato*(ERI, Univ. Tokyo)・Kei Odawara(Hot Springs Res. Inst. Kanagawa Pref.)・Kiyohide Mizuno(AIST)・Takehiko Suzuki(Tokyo Metro. Univ.)
本シンポジウムは,2010年11月に日本大学文理学部で開催された,日本地質学会関東支部−日本第四紀学会ジョイントシンポジウムをさらに発展させるべく企画提案するものである.近年,関東地域で実施されてきた地下構造探査(大大特,首都プロ,国府津ー松田プロなど)をはじめとする諸成果をベースに,関東盆地の地質・地殻 構造とその形成史について,様々な角度から議論できる場を提供する.また同シンポジウムでは,昨秋のジョイントシンポジウムで好評であった大スケールプロファイル提示方式をさらに発展させるために,広いプロファイル展示場を用意する予定である.
招待講演予定者:未定(一般公募なし)
↑このページのTOPに戻る
就職支援(2010富山大会の様子)
第117年富山大会:就職支援プログラム(2010.9.19開催)
就職支援プログラムは,富山大会で第4回目となりました.本大会では昨年同様に,民間企業に加えて,研究機関から産業技術総合研究所が参加されました.9月18日午後2時から5時まで,まず企業説明会形式で参加企業6社と産総研からのプレゼンテーションを行い,その後各社・機関の出展ブースで詳しい説明や質疑応答に参加していただきました.今年のプレゼンテーターには,就職支援プログラムを縁として採用が決まり,今や中核社員として活躍されているジーエスアイ株式会社のイセンコさんにもおいでいただきました.各ブースでは,今年も終了時間いっぱいまで,熱心に説明を受ける学生会員の姿が見られました.
就職支援プログラムは,来年以降も継続の予定です.就職情勢がますます厳しくなる中,就職を希望される学生・院生会員の方々には,民間企業・団体,研究機関等との直接情報交換の場として,このプログラムをご利用いただきたいと思います.また,学生を指導されている教官の方々にも,ぜひ会場においでください.また,さらに充実した情報交換ができますよう,会員の皆様からのご要望がありましたら,理事会担当までお知らせください.最後に,本行事に参加いただいた企業6社と産総研の皆様,企画にご協力をいただいた賛助会員,関連企業の皆様,および大会準備委員会・行事委員に,改めて御礼申し上げます.
各社によるプレゼンテーション
各社ブースの様子
参加企業・団体(敬称略):株式会社ダイヤコンサルタント・石油資源開発株式会社・ジーエスアイ株式会社・産業技術総合研究所・川崎地質株式会社・株式会社クレアリア・明治コンサルタント株式会社
(担当理事:運営財政部会 向山 栄)
会場・交通
会場・交通
茨城大学水戸キャンパス
http://www.ibaraki.ac.jp/generalinfo/campus/mito/index.html
JR水戸駅からのアクセス案内
茨城大学専用のバス案内ページ
キャンパスマップ(大学HPより)
キャンパス内:会場案内図はこちら(PDF版をダウンロードできます.)
申込先・締切一覧
各種申込先・締切一覧
WEB
FAX・郵送
申込・問い合せ先
講演申込
6/7(火)17時
6/1(水)必着
詳細
行事委員会
講演要旨原稿提出
6/7(火)17時
6/1(水)必着
詳細
行事委員会
WEB
FAX・郵送
事前参加登録
8/5(金)18時
8/1(月)必着
詳細
学会事務局
見学旅行
(教員用巡検J班含む)
8/5(金)18時
8/1(月)必着
詳細
学会事務局
懇親会
8/5(金)18時
8/1(月)必着
詳細
学会事務局
追加講演要旨・見学旅行案内書
8/5(金)18時
8/1(月)必着
詳細
学会事務局
お弁当
8/5(金)18時
8/1(月)必着
詳細
学会事務局
託児室
8/12(金)
-------
詳細
現地事務局
生徒地学研究発表会
(小さなEarth Scientistのつどい)
7/11(月)
-------
詳細
地学教育委員会
ランチョン・夜間小集会
6/10(金)
-------
詳細
行事委員会
就職支援プログラムへの出展
-------
詳細
学会事務局
一次締切
最終締切
広告協賛
6/28(火)18時
7/22(火)18時
詳細
現地事務局
企業展示への出展
6/28(火)18時
7/22(火)18時
詳細
現地事務局
書籍・販売ブース
-------
7/22(火)18時
詳細
現地事務局
申込要領・発表要領
定番およびトピックセッション・講演の申込要領・発表要領
注:シンポジウムに関しては、シンポジウムのページを参照して下さい。
講演申込・講演要旨締切:
オンライン 6月7日(火)17時(郵送 6月1日(水) 必着)
↓WEBからの講演申込はこちら↓
(修正・変更もこちらから)
<シンポジウム/日本地質学会担当セッション>
■シンポジウム一覧はこちら■
■セッション一覧はこちら■
募集要領
9月9日〜9月11日の3日間での一般発表を募集します.下記の要領にて口頭,ポスター発表を募集します.できる限りオンラインでの申込にご協力下さい.やむを得ず郵送で申し込む場合は所定の申込書(News誌4月号掲載)に 必要事項を記入の上,返信用(自分宛)の官製ハガキ,保証書・同意書,講演要旨原稿とともに6月1日(水)必着で行事委員会宛にお送り下さい.プログラム の編成が終わり次第,発表セッションや発表日時などをe-mailで通知します(郵送の場合は返信ハガキで).なお,発表セッションや会場・時間などのプログラム編成につきましては,各セッションの世話人の協力を得て,行事委員会が決定します.
(1)セッションについて
専門部会の提案などにより20件のトピックセッションと25件の定番セッションを設けました.このうち日本地質学会にて受付をするのは12件,定番セッション20件です.
(2)講演に関する条件
会員は,口頭発表かポスター発表かのいずれかの方法で,1人1題に限り講演を行うことができます.ただし,今大会では発表負担金(1,500円)を支払うことにより,地質学会担当セッションでもう1題の発表が可能です(最大2題:同一セッションで2題,異なる2セッションで各1題,どちらでも可).
日本地質学会担当セクションで共同発表(複数の著者の発表)を行う場合は,上記の「1人1題,ただし発表負担金支払いによりもう1題可」という制約を発表者(=発表申込者)に対して適用します.その際,発表者は筆頭著者でなくても構いません(筆頭者に会員・非会員等の条件はありません).講演要旨には,発表者に○(マル)印を付けてください.原則,非会員は発表者になれませんので,非会員で発表を申し込む方は必ず6月1日(水)までに入会手続きを行って下さい.入会申込書が届いていない場 合は,発表申込は受理されません.
(3)招待講演について
昨年同様,トピックセッションにおいては,世話人は会員・非会員を問わずに招待講演を依頼することができます(締め切りました).招待講演についても申込期日までに一般発表と同様にお申し込み下さい(非会員の場合は世話人が取りまとめてオンライン入力をすることは可能です).定番セッションでは招待講演の設定はありません.また,日本地質学会・日本鉱物科学会に所属していない非会員の招待講演者に限り参加登録費は免除となります(ただし講演要旨集は付きませんので,必要な場合は別途購入してください).
(4)講演申込上の注意
1) オンライン申込はオンライン入力のフォームに従って入力して下さ い.
2) 講演方法については,「口頭」「ポスターセッション」,「どちらでもよい」のいずれかを選択して下さい.ただし,申込締切後の変更はできません.
※なお,電力事情によっては,口頭発表を申し込んでいただいた場合でもポスター発表への変更をお願いすることになるかもしれません(代表世話人が連絡します).その場合はご協力をお願いいたします.
3) 発表題目,発表者氏名について,必ず登録フォームと講演要旨の両方を一致させて下さい.
4) 共同発表の場合は全員の姓名を完記して下さい.また,講演要旨には発表者に○(マル)印を付けてください。
5) 発表を希望するセッションを第2希望まで選んで下さい.
6) コメント欄について:発表の対象とする地域の記入を要するセッションについてはこの欄に国名・県名等を入力して下さい.また,関係する一連の発表があると きは,その順番希望などもこの欄に入力して下さい.
7) 口頭発表会場には液晶プロジェクターとWindowsパソコン(OS:Windows Vista, Office Standard 2007)を用意します.パワーポイントを使用する方は,試写室において正常に作動することを事前に確認して下さい.特に,会場に設置するものと異なる バージョンで作成されたファイルは,レイアウトが崩れる事例が報告されていますのでご注意願います. パワーポイントを使用しない方やMacパソコンを使用される方は世話人とご相談下さい.なお,35mmスライドプロジェクターの使用はできません.
(5) 講演要旨原稿の投稿について
例年と 同様に講演要旨をAdobe社が策定したPortable Document Format(PDF)のファイルで電子投稿していただきます.一般発表およびシンポジウムの原稿はA4判1枚(フォーマット参照)で,印刷 仕上がり0.5ページ分です.1ページに2件分ずつ印刷します.原稿はそのまま版下となり,70%程度に縮小して印刷されます.文字サイズ,字詰めおよび 鮮明度には十分配慮し,PDFファイルを作成して下さい.やむを得ず郵送する場合は,オリジナルか,鮮明にコピーした現物を1枚だけ郵送(差し支えなければ折りたたみ可)して下さい.FAXやe-mailでの原稿送付は受け付けません.
発表要領(シンポジウムについてはこちら)
(1)口頭発表
1)講演時間は1題あたり15分(討論時間3分を含む)です.講演者は,討論など持ち時間を十分考慮し余裕を持って 講演を行って下さい.
2)各会場には,液晶プロジェクター,Windowsパソコンを各1台とスクリーン1幕を設置します.
(2)ポスター発表
1)1題について1日間掲示できます.各日とも発表者はコアタイム(開催日によって異なる)にその場に立会い,説明をするものとします.設置,撤去時間等については,ホームページまたはNews誌7月号に掲載予定のプログラムをご覧下さい.ボード面積は1題あたり, 縦180cm,横90cmです.
2)発表番号・発表名・発表者名をポスターのタイトルとして明記して下さい.
3)掲示に必要な画鋲等は, 発表者がご持参下さい.
4)ポスター会場では,コンピューターによる発表や演示等も許可しますが,使用する機器については発表者がご準備下さい. また,電源は確保できませんので,予備のバッテリーをご用意下さい.講演申込の際に機器使用の有無や小机の必要性をコメント欄に記入し,事前に世話人ご相 談下さい.
5)運営規則第16条(8)項により,優れたポスター発表に対して「日本地質学会優秀ポスター賞」を授与いたします.具体的な事柄 については,プログラムに掲載しますのでご注目下さい.
(3)発表者の変更
あらかじめ連記されている共同発表者内での変更は認めますが,必ず事前に行事委員会へ連絡して下さい.この場合も「1人1題,ただし発表負担金支払いによりもう1題可」が適用されます.
(4)口頭発表の座長の依頼につ いて
セッションによっては各会場の座長を参会者にお願いすることになります.あらかじめ座長依頼を差し上げることになりますが,その際にはぜひともお引き受けいただきたく,ご協力をお願いします.
問い合わせ先
水戸大会問い合わせ先
■大会会期中(9/9-11)の問い合わせ先
日本地質学会第118年学術大会・日本鉱物科学会2011年年会合同学術大会現地事務局
e-mail:mito2011@academicbrains.jp
■日本地質学会行事委員会 / 地学教育委員会 / 学会事務局
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目8-15 井桁ビル6F
(地質学会事務局気付)
TEL:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156
e-mail:main@geosociety.jp
■行事委員会■(2011年3月現在)
委員長
星 博幸(担当理事)
副委員長
吉川敏之(地域地質部会)
委 員
岡田 誠(層序部会)
青矢睦月(岩石部会)
須藤 斉(古生物部会)
内山 高(第四紀地質部会)
片岡香子(堆積地質部会)
荒井晃作(海洋地質部会)
須藤 宏(応用地質部会)
石塚吉浩(火山部会)
斎藤文紀(現行地質過程部会)
河村知徳(石油,石炭関係)
坂本正徳(情報地質部会)
矢島道子(地学教育関係)
田村嘉之(環境地質部会)
大坪 誠(構造地質部会)
■日本地質学会第118年学術大会・日本鉱物科学会2011年年会合同学術大会現地事務局
(株式会社アカデミック・ブレインズ内)担当:田中
〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1天満橋千代田ビル2号館9階
TEL:06-6949-8137 FAX:06-6949-8138
e-mail:mito2011@academicbrains.jp
■実行委員会組織(地質学会)■
委員長 :天野一男(TEL:029-228-8390, kazuo@mx.ibaraki.ac.jp)
副委員長:木村 眞(TEL:029-228-8388, makotoki@mx.ibaraki.ac.jp)
事務局長:岡田 誠(TEL:029-228-8392, okada@mx.ibaraki.ac.jp)
総 務:本田尚正(TEL:029-228-8396, nhonda@mx.ibaraki.ac.jp)
野口高明(TEL:029-228-8387, tngc@mx.ibaraki..jp)
伊藤 孝(TEL:029-228-8268, tito@mx.ibaraki.ac.jp)
会 計:藤縄明彦(TEL:029-228-8398, fujinawa@mx.ibaraki.ac.jp)
長谷川健(TEL:029-228-8397, hasegawt@mx.ibaraki.ac.jp)
見学旅行:安藤寿男(TEL:029-228-8391, ando@mx.ibaraki.ac.jp)
亀尾浩司(案内書担当,kameo@faculty.chiba-u.jp)
普及・企画(市民講演会)
:天野一男(TEL:029-228-8390, kazuo@mx.ibaraki.ac.jp)
久田健一郎(TEL:029-853-4300,hisadak@geol.tsukuba.ac.jp)
会場・展示会場・機器・懇親会
:岡田 誠(TEL:029-228-8392, okada@mx.ibaraki.ac.jp)
現地事務局((株)アカデミック・ブレインズ(内))
担当:田中(TEL:06-6949-8137, FAX:06-6949-8138, e-mail:mito2011@academicbrains.jp)
地質情報展担当
:高橋裕平(TEL:029-861-3549,johoten2011.jimu@m.aist.go.jp)
講演申込TOP
水戸大会講演申込
講演申込・講演要旨締切:
オンライン 6月7日(火)17時(郵送 6月1日(水) 必着)
↓WEBからの講演申込はこちら↓
(修正・変更もこちらから)
<シンポジウム/日本地質学会担当セッション>
▶講演申込要領・発表要領
▶シンポジウム一覧
▶定番セッション・トピックセッション
▶講演要旨原稿について
▶▶講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理,引用方法,校閲について
▶▶講演要旨の作成の注意点とPDFファイル作成の作り方
▶▶講演要旨オンライン投稿手順チェックシート
▶▶保証・同意書(2011水戸)
▶講演申込書 書式pdf(郵送で申し込む場合)
講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理,引用方法,校閲について
講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理,引用方法,校閲について
(1)講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理
日本地質学会の出版物への投稿原稿に対して,著作者にその倫理性について保証して頂くために「保証書」に,また著作権を日本地質学会に 譲渡することを同意する「著作権譲渡同意書」に,それぞれ署名捺印をして提出していただいています.本大会は電子投稿のため,画面上で「保証書」と「著作権譲渡等同意書」に同意していただいた場合に限り,電子投稿の画面に進むことができるようになっています.郵送の場合は,保証書及び同意書に署名捺印をして,講演要旨と共にお送り下さい.「保証及び著作権譲渡等同意書(こちらをクリック)」が同封されていない講演申込は受け付けられません.
(2)講演要旨における文献等引用方法
要旨においては引用文献の記載方法は簡略化することが慣習として認められていますが,著者名,発表年,掲載誌名などを明記し,引用文献が特定できるようにして下さい.
(3)講演要旨の校閲
行事委員会は,申し込まれた講演について,定款第3条に示されている日本地質学会の目的ならびに日本地質学会倫理綱領に反していないかということについて のみ校閲を行います.校閲の結果,いずれかの条項に反していると判断された場合には,行事委員会は講演内容の修正を求めるか,あるいは講演申込を受理しな いことがあります.行事委員会の措置に同意できない場合には,当該講演申込者は法務委員会(東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル 日本地質学会事務局気付)に異議を申し立てることができます.法務委員会は直ちに審理し,結論を行事委員会ならびに異議申立者に伝えることになります.
この受理方法は,招待講演者にも適用されます.
講演申し込み異議申し立てについて
日本地質学会行事委員会は,学術大会において学会の目的及び倫理規定に反する講演申し込みのあった要旨に対して,修正あるいは,受理を拒否することができます.法務委員会では,日本地質学会行事委員会規約に基づき,異議申立の手続及びその処理についての規則を定めています.
日本地質学会法務委員会
■日本地質学会学術大会講演申込異議申立に関する処理機構規則(PDF)■
講演要旨の作成の注意点とPDFファイル作成の作り方
講演要旨の作成の注意点とPDFファイル作成の作り方
講演要旨を作成する際,著者には「保証及び著作権譲渡同意書」第1項の「保証」内容を守って頂きます.行事委員会は,要旨の内容については関知しませんが,当該「保証」内容を逸脱するものがないか校閲します.その結果,不適当とみなされる場合は,修正されるまで講演要旨を受理しません(不服の場合は法務委員会に訴えることが可能です).
例年最も多い問題点は,引用文献の表示がない場合です.論文のように細かに引用文献を記載することはスペースの都合上不可能なので必要としませんが,雑誌名,号,ページ等,その文献にたどり着ける最低限の情報は原稿内に記載して下さい.
また,要旨の体裁を無視している場合,印刷できませんので体裁を整えて頂くことになります.さらに図等の改変については,著作権法,地質学会著作物利用規定に従って下さい.
このほか,PDFファイルにフォントを埋め込んでいないもの(印刷時に文字化けすることがあります),要旨作成時に講演番号記入用のスペースがなかったり,余白に無理があるといった場合,体裁を整えるため修正をお願いしています.これらの問題点があった場合,世話人より投稿締切日から1週間をめどに修正依頼が届きます.ただ,その労力はセッションによっては膨大になりますので,あらかじめ著者で完全なものを投稿するようご協力下さい.あわせて講演要旨投稿手順のチェックシートもご参照下さい.
日本地質学会 行事委員会
2011年4月
■要旨テンプレート(Microsoft Word)■ ■講演要旨投稿手順のチェックシート■
【講演要旨PDFファイル作成時の注意点】
1)
講演要旨原稿はAdobe Acrobat Reader 4.0 以上で表示・印刷可能なPDFファイルで投稿することが必要です.
2)
ファイルサイズは3.0Mバイト以内で作成して下さい.
3)
発表(講演)番号は事務局にて左上に付記するので原稿内には記載しないで下さい.
4)
PDFファイルのセキュリティ設定は「なし」にして下さい.
5)
フォントは必ず「埋め込み」にして下さい.MacOSX以上は標準でフォント埋め込みが用意 されます.MacOS9.2.2以下,Windowsでは下記のソフトが必要です.その際,『すべてのフォント埋め込み』ないし『ハイクォリティー』等, それぞれのソフトの使用説明書に従った指定を必ずして下さい.文字数にもよりますが,できたPDFファイルのサイズが100KB未満の場合,フォントが埋 め込まれなかった可能性がありますので確認して下さい.
6)
作成したPDFファイルを自分で印刷し,図表に充分な解像度があるか,文字化けはないか確認して下さい.
7)
PDFファイルを自分のパソコンに,必ず「.pdf」の拡張子をつけて保存して下さい(Mac, Windowsとも).
■原稿フォーマット見本■
※このフォーマットは,シンポジウム及び日本地質学会担当のセッションに適用されます.
共同発表の場合,講演要旨には発表者氏名の前に○(マル)印を付けてください.
大会予告号(News誌4月号)には後ろとありますが,前に付けてください.
テンプレート
(Microsoft Word)
ダウンロードはこちら
【webでの講演要旨投稿の手順】
1)
参加申し込みの後,web上の講演申し込みページで,講演申し込みの手続きをします(講演申込と同時に要旨投稿をすることもできますし、講演要旨のみ後で投稿する事もできます).
2)
演題・発表者情報登録画面の最下段にある「アップロードファイル」欄から要旨原稿(PDFファイル)を投稿します.欄右側の「参照」ボタンをクリックし,ご自分のPCに保存してあるPDFファイルを選択します.
3)
画面下の「次へ」をクリックし,登録内容確認画面に進みます.登録内容を確認後,画面下の「登録」ボタンをクリックします.これによりサーバーにPDFファイルが格納されます.
4)
『登録が完了いたしました.受付番号は*****です.』という完了画面が表示されます.(注意!!この画面が表示されないと登録は完了していません)
5)
登録したメールアドレスに「講演申込のお知らせ」のメールとともに受付番号(=ID)が配信されます.
★★後から要旨を投稿する場合・申込内容を変更する場合★★
1)
IDとメールアドレスでログイン:ご自分の申込画面に,IDとメールアドレスを用いてアクセスします.
2)
新しい講演要旨PDFファイルをアップロード:「登録内容変更」ボタンをクリックし,画面の最下段にある「アップロードファイル」欄の「修正」ボタンをクリックします.ご自分のPCに保存してあるファ イルを選択し,アップロードをします.サーバー側では,ファイル名を元のファイル名から変更し,ID.pdfの名称で格納します.
3)
完了画面の確認:『登録が変更されました.受付番号は*****です.』という操作完了画面が表示されます.(注意!!この画面が表示されないと操作は完了していません)
4)
変更確認めーるが配信されます:「講演申込内容変更のお知らせ」メールが配信されます.
5)
IDとメールアドレスを用いて,投稿締切まで何度でも要旨や登録内容 を修正することができます.新しいファイルを投稿すると,古いファイルに上書きされます.そのつど,「講演申込内容変更のお知ら せ」メールが配信されます
【参考情報:PDF(Portable Document Format)ファイルの作り方】
PDFファイルの作成方法は「PDF原稿作成ガイド」http://www.gakkai-web.net/pdf/を参考にすると良いでしょう.
ソフトの紹介要望が多いので,下記にいくつか参考例を挙げます.また,"PDF作成サービス"を行う有料,無料のサイトがあります.ソフト,サイトとも検索してみて下さい.なお下記について動作確認等しておりません.また推奨するものでもありません.ご了承ください.
◯ Mac OSXの場合
フォント埋め込み型のPDF作成機能が標準で用意されています.新たなソフトは必要ありません.
◯ Mac OS 8.6-9.2の場合
Adobe Acrobat(それぞれのOS対応品,現在販売されているか不明)
EGWORD Ver.12 for Mac OS X/9/8.6(現在販売されているか不明)
◯ Windows対応品
PrimoPDF FreeのPDF変換ソフト http://www.primopdf.com/
クセロPDF PDF変換ソフト http://xelo.jp/xelopdf/
いきなりPDF 2000円弱 http://www.sourcenext.com/products/pdf/
Adobe Acrobat Elements 5000円弱 http://www.adobe.co.jp/
◯ MacOS9.2.2,MacOSX, Windows対応
Adobe Illustrator http://www.adobe.co.jp/
講演要旨オンライン投稿手順チェックシート
講演要旨オンライン投稿手順チェックシート
講演要旨の投稿手順および基本的注意事項です.投稿していただく前に各自でご確認下さい.
1.Word等のソフトで講演要旨原稿を作成します.
「保証及び著作権譲渡同意書」第1項の「保証」内容は守られていますか?
要旨原稿内に引用文献は表示されていますか?
要旨の体裁は守られていますか?(詳細は要旨原稿フォーマットをご確認下さい)
2.原稿をPDFファイルにします.
PDFファイルの作成方法については,「PDFファイルの作り方」を参照して下さい.
フォントは「埋め込み」になっていますか?(できたファイルサイズが100KB未満の場合,フォントが埋め込まれなかった可能性がありますので確認して下さい)
ファイルサイズは3.0MB以内になっていますか?
作成したPDFファイルを印刷し,図表に充分な解像度があるか,文字化けはないか確認して下さい.また,PDFファイルを自分のパソコンに,必ず.pdfの拡張子をつけて保存して下さい.
3.原稿をオンライン投稿します.
web画面から参加申し込みを行いましたか?
講演申し込みページで,講演申し込みの手続きをしましたか?
講演要旨を投稿しましたか?
申込完了画面が表示されましたか(ログイン用のIDが表示されましたか)?
「講演申込のお知らせ」のメールが配信されましたか?
4.一度投稿した原稿を修正したい場合
ご自分の申込画面に,IDと申込時に設定したパスワードを用いてアクセスします.
画面中のPDFファイルのアイコンをクリックし,要旨原稿投稿画面を開きます.書き直した要旨のファイル選択し,投稿動作をします.
修正原稿が受け付けられると,「申込内容変更のお知らせ」メールが配信されます.(締切まで何度でも修正できます).
←講演要旨投稿手順に戻る
保証・同意書(2011水戸)
<郵送での投稿の場合は、原稿に必ず添付して下さい>
■PDFファイルダウンロードはコチラから■
保証及び著作権譲渡等同意書
著作者(下記)は,日本地質学会第118年学術大会・日本鉱物科学会2011年年会合同学術大会で,一般社団法人日本地質学会(以下「日本地質学会」という)及び日本鉱物科学会によって合同で発行される「講演要旨集」のセクションA又はセクションBに掲載する下記表題の原稿(以下「本原稿」という.)について,以下のとおり保証し,著作権を日本地質学会に譲渡等いたします.
第1 保証
著作者は,本原稿について,以下の各号記載の事項を保証し,確約します.
1) 本原稿が著作者自身の著作物であり,既にいずれかで出版公表されているものと同一ではないこと.
2) 本原稿が既存の出版公表物などに対する知的財産権のいかなる侵害も含まないこと.
3) 本原稿中に他から転載されているすべての図表について,転載許可を得ていること.
4) 本原稿中,他の論文等の引用がある場合には,当該引用が公正な慣行に合致し,目的上正当な範囲内であること.
5) 著作物には,日本地質学会の名誉を傷つけ,当該講演要旨の信用を毀損する盗用データ,捏造データ,著作物に関する利害を持つ者の合意に反するもの,その他日本地質学会の倫理綱領に反するものを含まないこと.
6) 本原稿が共同著作物である場合には,代表して本書に署名捺印する者が,すべての共著者から,本書に著名捺印することについて同意ないし必要な権利を得ていること.
7) 本原稿についての問い合わせ,苦情,紛争などが発生した場合,署名者はすべての責任を負うこと.
8) 本著作物を作成するに当たって行われた調査・研究行為が,適切な方法でなされたものであること.
第2 著作権譲渡等
著作者は,本原稿について,以下の各号記載に同意します.
1) 本原稿のすべての著作財産権(著作権法27条,同29条に定める権利を含む)及び2次著作物の創作・利用に係る権利を日本地質学会へ譲渡すること.
2) 本原稿について,日本地質学会ならびに日本地質学会から正当に権利を取得した第3者及び当該第3者から権利を承継した者に対し,著作人格権(公表権,氏名表示権,同一性保持権)を行使しないこと.
3) 本原稿の下記の各利用形態に関する権利を日本地質学会が排他的に行使すること.
a) 複製,翻訳,翻案(出版,電子出版,翻訳出版,データベース化,ビデオグラム化,その他すべての記録メディアへの記録・掲載などを含む)
b) 展示・上映
c) 放送,有線放送,自動公衆送信(地上波,CATV放送衛星,通信衛星,インターネット,パソコン通信,その他あらゆる送信媒体及び将来開発されるすべての送信媒体による公衆送信を含む)
d) 頒布,譲渡,貸与
e) その他,本著作物に関する一切の利用(技術の進歩により将来生じうる利用形態を含む)
以上
日付 2011年 月 日
本原稿表題
著作者(代表者) 印
署名者が代表する共著者すべての氏名
■PDFファイルダウンロードはコチラから■
参加登録TOP
2011水戸大会事前参加登録ほか申込
※※今年の参加申込は,所属区分によって画面が異なります.該当する画面からお申込ください.※※
参考>>会員情報を自動取得するには?(PDF)
■日本地質学会・日本鉱物科学会両学会に所属の方
■日本地質学会に所属の方
■非会員(招待講演者,一般,院生,学部学生)の方
■共催団体会員[日本鉱物科学会を除く*1]の方
■日本鉱物科学会所属(見学旅行のみ)の方*1
■見学旅行J班(教員巡検)のみに参加する非会員の地学教育関係者の方*2
■年会には参加せず,冊子のみ購入希望の方
(参加登録は,同伴される会員のご家族分1名分まで,あわせてお申し込み頂けます)
*1:日本鉱物科学会所属の方は,日本鉱物科学会の申込ページより参加登録をお申込ください.鉱物科学会のみ所属の方は,地質学会では見学旅行のみ受付しております.参加登録のお申込は受付できません.
*2:地質学会会員で地学教育関係者の方は,『日本地質学会に所属』の画面からお申込ください.
<申込締切 オンライン:8月5日(金)18:00,FAX/郵送:8月1日(月)必着>
*申込方法・支払い方法の詳細は下記ページをご覧下さい.
参加フォームから申し込める項目:クリックすると各詳細のご案内をご覧いただけます。
■ 参加登録費
■ 発表負担金(定番・トピックセッションで2件目の発表を予定の方)
■ 追加講演要旨(大会不参加で冊子のみの購入も可)
■ 見学旅行
■ 見学旅行案内書(大会不参加で冊子のみの購入も可)
■ お弁当
■ 懇親会
申込方法とお支払について
各種申込とお支払方法について
参加登録ページはこちらから
申し込める内容:参加登録・懇親会・追加講演要旨・見学旅行・見学旅行案内書・お弁当
<申込締切 オンライン :8月5日(金)18:00,FAX/郵送:8月1日(月)必着>
(1)申込方法
オンラインによる参加登録申込等を受付けます.申込は学会独自の参加登録システムをご利用いただきます.大会専用参加登録システム(会員・非会員にかかわらずどなたでも申し込めます.)又はNews誌4月号掲載の専用申込書(FAX・郵送用)をご利用の上,お申し込み下さい.参加登録・懇親会・追加講演要旨・見学旅行・見学旅行案内書・お弁当を同時に申込むことが出来ます.なお,学会を通じての宿泊・交通手配の斡旋は行いません.宿泊や交通については,各自でお手配をお願いいたします.
(a) 大会専用参加登録システム(オンライン)による申込:申込フォームに必要事項を記入して送信.
(b) FAX・郵送による申込:申込書に必要事項を記入の上,「日本地質学会水戸大会参加申込係」宛にお送りください.
FAX番号:03-5823-1156
郵送先:〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル6階「日本地質学会水戸大会参加申込係」
(a)大会専用参加登録システム(オンライン)による申込
1) 学会HPから「2011年水戸大会ホームページ」,へアクセスして下さい.
2) トップページの「参加登録はこちら」のボタン,または,画面のメニュー「参加登録」をクリックして下さい.
3) 申込画面の入力欄に氏名と会員番号を入力するだけで,学会に登録されている会員情報(所属・住所等)が表示され,続けて参加登録を行うことができます.
※入力に際してはスペース・半角・全角等注意してください.誤っている場合には,登録情報は反映されません.
会員番号は雑誌送付時の封筒等に記載された7桁の番号です.7桁の後にある( )内の番号は送付時の事務処理番号ですので,入力不要です.
4) 申込み完了後、「申込確認メール」および「ご請求メール」が登録のメールアドレスへ配信されます.内容を必ずご確認下さい.本メールを請求書とさせて頂きます。別途請求書が必要な場合は学会事務局までご連絡ください.
※メールが届かない場合には,入力したメールアドレスが誤っている可能性があります.数時間経っても届かない場合には,日本地質学会事務局へご連絡ください.
5) 支払い方法について,「銀行振込」を選択された方は,「ご請求」メールを確認の上,指定の金融機関より申込から7日以内にお振込み下さい.また,クレジットカードもご利用頂けます.「クレジット決済」を選択の場合は,ご利用のカード会社の期日に合わせて,口座より引き落としとなります.クレジットカード会社からの明細には「日本地質学会(ニホンチシツガッカイ)」と表示されます.
6) 参加証・各種クーポンは申込締切後に発送します(8月下旬までに発送予定).大会開催10日前には参加者の皆様のお手元に届くようお送り致します.発送時点で入金確認が取れない場合は,未入金の旨記載されたクーポンが送付されますので,当日会場にて入金のご確認をさせて頂きますので、入金とクーポン発送が入れ違いの場合は,振込み時の控え等を会場にお持ち下さい.確認がスムーズに行えますのでご協力をお願い致します.
(b) FAX・郵送による申込
1) 「FAX・郵送専用申込書」(News誌4月号掲載)に必要事項を記入の上,日本地質学会事務局までFAXまたは郵送にてお申込み下さい.電話による申込,変更などは受け付けられませんので,ご了解ください.また,郵送による申込みの際は,必ず申込書のコピーを各自で保管して下さい.
2) FAX・郵送による申込の場合は,折返し学会より「受付確認証」をe-mail又はFAXにてお送りします.必ずご確認下さい.確認証が届かない場合は,必ず事務局までご連絡ください.確認証には,「受付番号」が記載されています.この「受付番号」はその後の問い合せ,変更,取消等に必要となります.
3) お支払いは,銀行振込またはクレジットカード決済のいずれかを選択できます.申込後順次,「予約内容確認」・「請求書」をお送りします.銀行振込を選択された方は,請求書に記載されている振込口座へ指定期日までにお振込み下さい.クレジット決済を選択された方は,参加申込の際必ずクレジット番号などの必要事項を記入して下さい.ご利用のカード会社の期日に合わせて,口座よりお引き落としとなります.カード会社からの明細には「日本地質学会(ニホンチシツガッカイ)」と表示されます.
4) 参加証・各種クーポンは申込締切後に発送します(8月下旬までに発送予定). 大会開催10日前には参加者の皆様のお手元に届くようお送り致します.発送時点で入金確認が取れない場合は,未入金の旨記載されたクーポンが送付されますので,当日会場にて入金のご確認をさせて頂きますので、入金 とクーポン発送が入れ違いの場合は,振込み時の控え等を会場にお持ち下さい.確認がスムーズに行えますのでご協力をお願い致します.
(2)申込締切
大会登録専用HP(オンライン)による申込:8月5日(金) 18:00
FAX・郵送による申込:8月1日(月)必着
(3)申込後の変更・取消
(a) 大会登録専用HP(オンライン)でお申込みの場合:
締切までの間は,2011年水戸大会ホームページから予約の変更・取消が出来ます.変更・取消完了後,「変更・修正 確認メール」が登録のメールアドレスへ配信されます.内容を必ずご確認下さい.締切後は直接学会事務局(東京)にFAX又はe-mailにてご連絡下さい.クレジット決済の場合は,申込の都度決済が完了しますので,決済スケジュールの都合によっては,口座から重複して引き落とされる場合があります.重複の入金については,振込手数料を差し引いた額をクレジットカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2〜3ヶ月要する場合もありますので,ご了承ください.
(b) FAX・郵送でお申込み場合:
申込後に変更・取消が生じた場合は,日本地質学会宛FAX又はe-mailにてご連絡下さい.その際申込受付時に案内される「受付番号」・「氏名」を必ず明記下さい.
(4)取消に関わる取消料と返金について
(a)締切までの取消:取消料は発生しません.返金がある場合は,振込手数料を差し引いた額をクレジットカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2〜3ヶ月要する場合もありますので,ご了承ください.
(b)締切後〜9/6(大会3日前)までの取消:入金・未入金の如何に関わらず,参加費用の60%を取消料としていただきます.返金がある場合は,振込手数料を差し引いた額をクレジットカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2〜3ヶ月要する場合もありますので,ご了承ください.参加費に講演要旨集が付いている方へは,大会後にお送りします.
(c)9/7(大会2日前)以降の取消:入金・未入金の如何に関わらず,参加費用の100%を取消料としていただきます.参加費に講演要旨集が付いている方へは,大会後にお送りします.
参加登録費
参加登録
参加登録申込はこちら
*「各種の申込方法とお支払いについて」は>>こちら<<
申込締切 オンライン 8/5(金)18:00, FAX/郵送 8/1(月)必着
当日会場受付での混雑緩和のため,事前に参加登録申込をお願いします.大会参加登録およびそれに伴う参加費は,全ての参加者(見学旅行のみの場合も)に必要な基本的なお申込です.ただし,会員が同伴する非会員の配偶者ならびに子供については必要ありません(同伴者:非会員の家族の懇親会・見学旅行・お弁当の申込は受け付けます).
今年は所属団体や講演発表に応じて登録費用が異なりますので,確認してからお申込ください.
参加登録費
基本的には講演要旨集付です.講演要旨集が不要の場合でも割引はありません.
登録費が無料の方〜学部学生(会員・非会員問わず)・名誉会員・50年会員・非会員招待者・見学旅行J班のみ参加の非会員地学教育関係者〜の方には,講演要旨集は付きません.ご希望の方は,別途ご購入下さい.
参加種別
事前申込
当日払い
備 考
日本地質学会所属
正会員
7,500円
(※9,000円)
9,500円
(※11,000円)
講演要旨集(A・B)付.
※日本鉱物科学会のセッションで講演を予定している場合は講演要旨集(C)代+1,500円.
院生割引会費適用正会員
4,500円
(※6,000円)
6,500円
(※8,000円)
講演要旨集(A・B)付.
※日本鉱物科学会のセッションで講演を予定している場合は講演要旨集(C)代+1,500円.
名誉会員
50年会員
学部学生
無料
講演要旨集は付きません.
(注)追加講演要旨集が必要な場合には,価格を確認してお申し込みください.
日本地質学会・日本鉱物科学会 両学会所属
正会員
9,000円
11,000円
講演要旨集(A・B・C)付.
院生割引会費適用正会員
6,000円
8,000円
講演要旨集(A・B・C)付.
名誉会員
50年会員
学部学生
無料
講演要旨集は付きません.
(注)追加講演要旨集が必要な場合には,価格を確認してお申し込みください.
その他
日本鉱物科学会所属
(見学旅行のみ受付)
※通常の参加登録は鉱物科学会にてお申し込みください.
講演要旨集は付きません.
事前参加申し込みに限ります.
(注)日本地質学会では見学旅行のみの受け付けになります.通常の参加登録は日本鉱物科学会にてお申し込みください.
非会員:一般
12,500円
15,000円
講演要旨集(A・B)付.
非会員:院生
7,000円
95,000円
講演要旨集(A・B)付.
非会員:招待講演者
無料
講演要旨集は付きません.
(注)追加講演要旨集が必要な場合には,価格を確認してお申し込みください.
非会員:学部学生
無料
講演要旨集は付きません.
(注)追加講演要旨集が必要な場合には,価格を確認してお申し込みください.
非会員:見学旅行J班(教員巡検)のみに参加する地学教育関係者
4,500円
−−−
講演要旨集は付きません.
事前参加申し込みに限ります.
(注)日本地質学会会員は『正会員』の参加種別でお申し込みください(要旨集付き参加登録費7,500円をお支払いください).
*この一覧の参加登録費はあくまでも日本地質学会の会員資格に則って参加種別を分け,金額を決めています.
*日本地質学会の会員資格は『正会員』のみであり,割引会費の申請をした方についてのみ,割引会費が適用されています.
*大会に参加できなかった場合は,大会後に講演要旨集をお送りします.参加登録費用の返却はいたしませんのでご了承下さい.
*シンポジウム・セッションの共催・協賛団体に会員として所属する方(日本鉱物科学会会員は除く)の参加登録費は正会員と同額になります.
*講演要旨集は3分冊になります(A・B・C).
(A)プログラム,シンポジウム(3件),索引,広告等を収録
(B)日本地質学会が扱うセッションを収録
(C)日本鉱物科学会が扱うセッションを収録
*追加で講演要旨集をお申し込みされる場合には,価格を確認してお申し込みください.
見学旅行
2011水戸大会:見学旅行
見学旅行 各コースの集合・解散時間と場所
コース名前
集合時間
集合場所
解散予定時間
解散場所
A班:日立古生層
9/12(月)8:00
水戸駅南口
9/13(火)18:00
水戸駅
B班:筑波山
9/12(月)8:00
水戸駅南口
9/12(月)18:00
TXつくば駅前
経由水戸駅前
C班:磐梯・吾妻・安達太良
9/12(月)8:00
茨城大学正門
(生協前)
9/13(火)18:00
郡山駅
D班:常陸堆積盆
9/12(月)8:00
水戸駅南口
9/13(火)18:00
水戸駅
E班:棚倉断層
9/12(月)8:00
水戸駅南口
9/13(火)18:00
水戸駅
F班:栃木新第三系
9/12(月)8:00
水戸駅南口
9/12(月)18:00
宇都宮駅
G班:下総層群
9/12(月)8:00
水戸駅南口
9/12(月)
時間は右記
18:45 JRひたち野うしく駅
→19:00 TXつくば駅
H班:第四紀テフラ
9/12(月)8:00
水戸駅南口
9/13(火)17:00
JR新白河駅
I班:関東のテクトニクス
9/12(月)9:00
小田急線新松田駅前
9/13(火)17:30
JR小田原駅
J班:地学教育
9/10(土)8:30
茨城大正門
(生協前)
9/10(土)17:30
茨城大学
※集合時間は厳守でお願いいたします.
**************************************************
※News誌4月号内において,下記班の見学旅行代金に誤りがございましたので訂正いたします.
A班:(誤)17,000円 -->(正)20,000円
C班:(誤)23,000円 -->(正)20,000円
★各コースの詳細・みどころはこちら★
*「各種の申込方法と お支払いについて」はこちら
総計10コースの見学旅行(A〜J班)を計画しました.見学旅行の参加申込は,「各種申込とお支払について」を参照し,申し込んで下さい.参加希望の方は,Web申込手続き手順に従って参加申込を行って下さい.FAX・郵送でのお申込は,News誌4月号の専用申込書を用い,学会事務局(東京)宛に大会参加申込と一緒に申し込んで下さい.見学旅行だけに参加する場合も大会参加登録ならびに参加登録費は必要です.見学旅行と大会参加登録の申込を合わせて行って下さい.
申込に際し,希望の班が満員の場合に備え,①キャンセル待ち,②第2希望の班の指定,③他班希望なくキャンセル待ちせず,のいずれかを必ず指定して下さい.
(1) 参加申込人数が各見学コースの実施最小人数に達しなかった場合,見学旅行を中止することがあります.
(2) 非会員の方は,申込締切時点で定員に余裕があれば参加可能となります.ご承知下さい.
(3) 日本地質学会ならびに水戸大会実行委員会は見学旅行参加者に対し,見学旅行中に発生する病気,事故,傷害,死亡等に対する責任・補償を一切負いません.これらについては,見学旅行費用に含まれる保険(国内旅行傷害保険団体型)の範囲でのみまかなわれます.
(4) 子供同伴など特別な事情がある場合は,申込前に現地事務局へあらかじめ問い合わせて下さい.
(5) 締切までの間は,ホームページから変更・取消ができます.変更・取消完了後,「変更・修正 確認メール」が登録のメールアドレスへ送信されます.内容を必ずご確認下さい.締切後の変更・取消は,直接学会事務局(東京)にFAXまたはe-mailにてご連絡下さい.締切後は入金・未入金の如何に関わらず,取消料が発生します(下記,注意事項等を参照).
(6) 集合・解散の場所,時刻などを変更することがありますので,大会期間中は掲示などの案内に注意して下さい.
(7) 見学旅行の解説は案内書を使って行います.参加申込時に「見学旅行案内書の予約頒布について」を参照し,あらかじめ予約購入して下さい.
(8) 原発事故や余震の影響により,コース内容の一部変更,コースの取りやめ等の措置をとることがあります.その場合はできるだけ早くお知らせしますが,あらかじめご承知おき下さい.
【注意事項等】
*取消料は,申込締め切り後〜出発3日前までは50%,2日前以降は全額となります.
*参加費用には旅行傷害保険(500円)が含まれています.
*集合地点まで,および解散地点からの交通費は各自の負担となります.
*参加費用はあくまで概算の金額です.大きな過不足が生じた場合,見学旅行終了時に調整します.
*案内書は費用には含まれていません.参加申込時に予約購入の手続きを合わせて行ってください.
*集合・解散の場所・時刻等に変更が生じた場合,学会期間中は掲示板に案内されます.
*参加者人数が少ない場合や,余震等の影響で安全確保に問題があると考えられる場合は,コース内容の一部変更やコースの取りやめ(中止)等の措置をとることがあります.
★各コースの詳細・みどころはこちら★
ページTOPに戻る
見学旅行のみどころ
2011水戸大会:見学旅行
見学旅行:各コースの魅力と見どころ
本年9月に行われる水戸大会では,関東支部を中心に多くの会員の協力を得て,10コースの見学旅行を企画し現在その準備を進めております.水戸大会では,見学旅行は茨城を中心とした関東周辺地域の地質理解のための重要な行事と位置付け,参加者に満足していただける特徴的なコース作りを目指しております.正式なコース一覧や参加申込の詳細はニュース誌4月号(4月末頃)で紹介する予定ですが,それまでに会員の皆様に各コースの魅力や見どころを詳しく紹介していきたいと思います.
(問い合わせ先:見学旅行準備委員会 安藤まで ando@mx.ibaraki.ac.jp)
(見学旅行準備委員会 委員長 安藤寿男,副委員長 山本高司)
A班:日立古生層
B班:筑波山
C班:磐梯・吾妻・安達太良
D班:常陸堆積盆
E班:棚倉断層
F班:栃木新第三系
G班:下総層群
H班:第四紀テフラ
I班:関東のテクトニクス
J班:地学教育
A班:日本最古の地層-日立のカンブリア系変成古生層 (9/12-13)
案内者:田切美智雄(元茨城大理),廣井美邦(千葉大理),足立達朗(九州大)
魅力
日本最古の地層である阿武隈山地南部日立地域のカンブリア系とカンブリア紀花崗岩類を見学します.また,カンブリア紀花崗岩を不整合で覆う石炭系礫岩やカンブリア系を原岩とする西堂平変成岩類を見学します.
見どころ
1.カンブリア紀花崗岩類
2.カンブリア系を原岩とする変成岩類
3.カンブリア紀花崗岩を不整合で覆う石炭系礫岩
4.カンブリア系を原岩とする西堂平変成岩類の堆積構造
5.石炭系を原岩とする変成岩と化石
6.カンブリア系の化石様組織
東連津川の不整合露頭:カンブリア紀花崗岩を不整合で覆う石炭系礫岩
西堂平層の層状堆積構造
ページtopに戻る
B班:筑波山周辺の深成岩・変成岩(9/12日帰り)
案内者:高橋裕平(産総研)・宮崎一博(産総研)・西岡芳晴(産総研)
魅力
筑波山は900mに満たない山ですが,その風格から深田久弥の日本百名山の一つとなっています.筑波山及びその周辺地域の山塊には古第三紀初頭の深成岩類と変成岩類が分布しています.その岩石学性質から西南日本内帯領家帯及び山陽帯の深成岩類・変成岩類の延長と考えられています.変成岩類は典型的な高温低圧型の変成作用を示しています.花崗岩類は石材として国会議事堂をはじめ日本の多くの建物で利用されています.
見どころ
1.稲田花崗岩の採石場見学
2.吾国山変成岩類
3.稲田花崗岩と筑波花崗岩との貫入関係
4.筑波山頂の斑れい岩(ハンマーの使用,岩石採取はできません)
5.筑波変成岩類
6.筑波花崗岩
稲田花崗岩採石場
筑波山山頂付近:女体山側から望む男体山
ページtopに戻る
C班:磐梯・吾妻・安達太良−活火山ランクBの三火山(9/12-13)
案内者:藤縄明彦(茨城大)・長谷川 健(茨城大)・伊藤太久(中央開発)
魅力
福島県の中北部に近接して存在する磐梯・吾妻・安達太良の三火山は,いずれも活火山ランクBに属していますが,潜在的噴火災害リスクは決して小さくありません.三火山は,それぞれ1888年,1893年,1900年に,犠牲者を伴う噴火を起こしています.現在の美しい湖沼や岩峰の景観を作った磐梯火山の1888年噴火は,わが国で最新最大級の岩なだれ災害を引き起こし,500名近くの命を奪いました.防災面でも注目すべきこれら三火山の,特徴的な地形および噴出物を,歴史時代から数十万年前にまで遡ったロングレンジな視点で観察します.
見どころ
1.磐梯火山1888年噴火に伴う地形変化と堆積物
2.磐梯山噴火記念館(展望塔から三火山も一望)
3.吾妻小富士と浄土平(1893年噴火の爪痕など)
4.安達太良火山20万年前の大規模溶岩流
5.安達太良火山12万年前の爆発的噴火堆積物
6.安達太良火山最新期(歴史時代を含む)の水蒸気爆発堆積物
磐梯銅沼付近から望む1888年の火口壁
安達太良沼ノ平火口
ページtopに戻る
D班:常磐地域の白亜系〜新第三系と前弧盆堆積作用(9/12-13)
案内者:安藤寿男(茨城大理)・柳沢幸夫(産総研)・小松原純子(産総研)
魅力
東北日本太平洋岸の常磐地域は白亜紀後期〜新第三紀の前弧堆積盆西縁の河川〜浅海〜陸棚〜大陸斜面相が比較的単純な構造で累重する日本でも稀な地域です.古第三紀の石炭は常磐炭田として1970年代まで採鉱されていました.精細な微化石層序に基づいて,前弧における様々な堆積作用や古生物相・古環境変遷が復元されており,北西太平洋の新第三系層序の模式的な地域の一つです.
見どころ
1.白亜系双葉層群の堆積相と巨大アンモナイト密集層
2.古第三系白水層群石城層の石炭層と扇状地成未固結礫層
3.新第三系の各層群の層序関係と多賀層群の大規模海底チャネル群
4.日本最大規模の五浦海岸の炭酸塩コンクリーションと化学合成群集
5.茨城大学五浦美術文化研究所六角堂と茨城県北ジオパーク構想
古第三系白水層群石城層の扇状地成未固結礫層の巨大露頭
北茨城市五浦海岸の炭酸塩コンクリーション岩礁と六角堂(右端)
ページtopに戻る
E班:棚倉断層のテクトニクスと火山活動・堆積作用(9/12-13)
案内者:天野一男(茨城大理),松原典孝(兵庫県大),及川敦美(オリエンタルコンサルタンツ),滝本春南(茨城大理),細井 淳(茨城大理)
魅力
棚倉断層は現在の日本列島形成に大きく関わった大横ずれ断層です.断層沿いに多くのストライクスリップ堆積盆が発達していますが,断層の活動と海水準変動によりその堆積環境は,湖沼→河川→浅海→深海へと変化しています.また,日本海の拡大と関連して活動した水中火山も存在しています.日本列島の新生代テクトニクスを考える上での要の地域の一つです.
見どころ
1.棚倉断層と断層地形
2.断層活動と関連した土石流堆積物
3.横ずれ堆積盆を埋積したファンデルタ堆積物
4.男体山水中火山とそれを覆うタービダイト
5.堆積盆発生初期の湖沼堆積物と陸成火砕流堆積物
棚倉西縁断層に沿って発達する断層地形
中新世ハイアロクラスタイトからなる袋田の滝
ページtopに戻る
F班:栃木の新第三系−荒川層群中部の層序と化石および大谷地域の応用地質(9/12日帰り)
案内者:松居誠一郎(宇都宮大教育),山本高司(川崎地質),柏村勇二,布川嘉英,青島睦治(栃木県博)
魅力
中部中新統の荒川層群は微化石だけでなく,貝類を主とする大型化石をほぼすべての層準から産します.中位にある大金層では所謂「耶麻動物群」と「塩原動物群」の中間的な性格の貝類化石が密集層を形成します.ここではこの化石の産状と,密接した層準にある水中火砕流堆積物を観察します.大谷石は帝国ホテルなどに石材として利用され,近年は加工技術の工夫で様々な使われ方をしています.一方で旧採掘場の陥没などの地盤災害が問題になっています。今回は一般公開していない陥没モニタリングシステムを見学し,ボーリングコアから大谷石の連続層序を確認することができます.さらに,最新の空洞探査機器(レーダー・空洞カメラ・ミュー粒子)をお見せします.
見どころ
1.那須烏山地域の大金層中部の層序と化石の産状
2.大金層中部の火山灰層による対比と水中火砕流堆積物
3.大谷石採石場跡地と陥没モニタリングシステム見学
4.大谷石構造ボーリングコア観察と地下空洞探査機器のデモンストレーション
大金層中部層準の荒川沿い露頭
大谷石採掘跡を利用した大谷資料館
ページtopに戻る
G班:常陸台地の第四系下総層群の層序と堆積システムの時空変化(9/12日帰り)
案内者:大井信三(国土地理院),横山芳春(アースアプレイザル)
魅力
茨城県中部・南部の常陸台地には第四系更新統下総層群が広く分布しています.今まで研究者間で意見の相違が多かった常陸台地の下総層群の層序について,テフラに基づく新たな層序対比を紹介します.そして堆積相解析・シーケンス層序解析・テフラ層序を総合した常陸台地の堆積システムの時空変化を復元します.
見どころ
1.常陸台地更新統下総層群の指標テフラによる層序対比
2.藪層から常総層の堆積シーケンスの累重関係と堆積システムの時空間変化
3.常陸台地の南北で異なる見和層の堆積相と堆積シーケンス
4.大規模露頭の未固結砂層に発達する浅海〜内湾〜河川堆積相と堆積構造
5.「見和層中部層」の河成礫層に挟まれる海成層と真岡テフラの層位
6.房総の清川層と常陸台地の笠神層との対比-真岡テフラとKy4テフラによるMIS7.3層準の位置付け
7.見和層基底の北関東・箱根系テフラの層位関係
左:涸沼川中流の上泉層開析谷充填層中の大古山軽石(OgP:上)と阿多鳥浜テフラ(Ata-Th:下)
右:鹿島台地において見られる藪層から木下層までの各層準
ページtopに戻る
H班:鬼怒川低地帯の第四紀テフラ層序−火山噴火史と平野の形成史(9/12-13)
案内者:鈴木毅彦(首都大学東京)
魅力
関東北部から上信越にかけては,日本列島の中でもとくに多くの第四紀火山が密に分布する地域です.これら多くの第四紀火山は爆発的噴火を繰り返してきたため,鬼怒川低地帯には多数のテフラが堆積しており,噴火史の構築に適した地域となっています.一方,同低地帯には火山活動,地殻変動,さらに気候変化・海面変化等の古環境変化の影響を受けて形成された段丘,丘陵,第四紀層が顕著に発達します.そしてそれらの編年にテフラは大きな役割をはたします.
見どころ
1.赤城火山,日光火山群,那須火山起源の降下テフラと火山噴火史
2.鬼怒川低地帯の河成段丘と日光火山群の影響
3.中期更新世の扇状地に起源をもつ喜連川丘陵とカルデラ噴火によりもたらされた塩原大田原火砕流堆積物
4.扇状地からなる那須野原の地形
5.前期更新世に噴出した白河火砕流堆積物群と白河丘陵
左:北関東を広く覆う約44kaに噴出した赤城鹿沼テフラ(宇都宮市内)
右:前期更新世に噴出した西郷火砕流堆積物(白河火砕流堆積物群)
ページtopに戻る
I班: 伊豆衝突帯の最前線−関東のテクトニクス(9/12-13)
案内者:小田原啓(神奈川温地研),林広樹(島根大),井崎雄介(島根大・院),伊藤谷生(千葉大),染野誠((株)パスコ)
魅力
神奈川県西部から静岡県東部にかけての一帯は,伊豆弧衝突の最前線として,特に1970年代から80年代にかけて,島弧衝突帯のテクトニクスに関する様々な研究成果が報告されてきました.同時に,トラフ充填堆積物とされる足柄層群や,地層対比と堆積環境解析の強力な武器である第四紀テフラに関する研究も精力的に進められてきた地域です.本地域は近年,地下構造探査プロジェクト(首都直下プロジェクト,国府津−松田断層帯プロジェクト等)により再び注目を集めています.これらの最新の成果を踏まえて,ベテランから若手まで,参加者のみなさまが伊豆弧衝突帯のテクトニクスについて議論できる場を提供したいと考えております.
見どころ
1.神縄・国府津−松田断層系:松田山からの俯瞰,平山断層,駿河小山の神縄断層系(KS断層)
2.畑火道角礫岩(採石場)と火砕流堆積物(生土):爆裂火口跡とその火砕流堆積物
3.足柄層群(トラフ充填堆積物):塩沢層の礫岩,畑層のカキ礁
4.生命の星地球博物館,温泉地学研究所の施設見学(主に雨天時用として)/新しい箱根火山形成モデルに対応した投影型地質模型(温地研)/常時地震観測ネットワークの紹介(温地研)
左:塩沢の神縄断層.第四系足柄層群塩沢層の礫岩に中部中新統丹沢層群大山亜層群の火山砕屑岩が衝上する逆断層.
右:平山断層.下盤は足柄層群根石層と不整合で重なる旧河川礫層.逆断層の上盤は足柄層群瀬戸層.
ページtopに戻る
J班:地層を見る・はぎ取る・作る(9/10)
案内者:伊藤 孝(茨城大教育)・牧野泰彦(茨城大教育)・植木岳雪(産総研)・中野英之(京都教育大)・小尾 靖(神奈川県立相模原青陵高校)
魅力
現世の砂浜と第四紀の地層からどういう情報を読めるか,児童・生徒に伝えるか,というのがテーマの一つです.実際に現世の砂浜海岸・第四系を前に皆で議論したいと思います.一方では,諸事情により児童・生徒を野外へと連れ出すことが困難な状況です.そのため,写真や動画では伝えられない地層の質感を教室で表現できる手段として,地層のはぎ取りの作成法とその活用法を提案します.また,簡便な手法で教室において地層を再現する実験法も併せて提示します.
見どころ
1.大洗海岸の地形・堆積物の読み方
2.第四紀海浜堆積物の読み方
3.地層のはぎ取りの実践
4.地層のはぎ取りを活用した授業実践の提示
5.教室で地層を再現する簡易水路実験の実践
左:地層のはぎ取り作業の様子(水戸市下入野の第四系更新統)
右:簡易水路実験で作成した砂と泥の互層
ページtopに戻る
講演要旨追加・見学旅行案内書予約頒布
申込(参加登録フォーム)ページはこちら
*「各種の申込方法と お支払いについて」はこちら
講演要旨集のみの予約頒布
*大会不参加で冊子のみの購入も可能です
<申込締切 オンライン:8月5日(金)18:00,FAX・郵送:8月1日(月)必着>
大会参加費には講演要旨集の代金が含まれていますので,大会に参加される場合は別途購入の必要はありません.ただし,学部割引会員・名誉会員・50年会員・非会員学部学生・非会員招待者には,講演要旨集は付きません.ご希望の方は,別途ご購入下さい(所属区分や講演するセッションにより,講演要旨集の付き方が違いますので,詳しくは参加登録費の一覧を参照して下さい).大会に参加されない方ならびに参加する方が複数の講演要旨集を購入される場合の予約頒布の申込は,「各種申込とお支払いについて」を参照し,申し込んで下さい.要旨集の受け取り方法には,(1)大会後に送付,(2)会場で受取り,があります.(1)の場合は,別途送料が必要です.(2)の場合は,大会受付にて確認書の提示が必要となりますので,必ずご持参下さい.残部があれば大会当日あるいは大会後にも頒布します.売り切れの場合はご容赦下さい.
事前予約(/冊)
当日販売(/冊)
(A)
(B)
(C)
(A)
(B)
(C)
会員
1,000円
3,000円
1,500円
(※2,000円)
1,000円
4,000円
1,500円
(※2,000円)
非会員
1,000円
4,000円
1,500円
(※2,000円)
1,000円
5,500円
1,500円
(※2,000円)
■講演要旨集(A・B・C)について
(A)プログラム,シンポジウム(3件),索引,広告等を収録
(B)日本地質学会が扱うセッションを収録
(C)日本鉱物科学会が扱うセッションを収録
※講演要旨集(C)は事前予約,当日販売ともに1,500円/冊ですが,「大会後に送付」希望の場合は2,000円/冊になり
ます.(例:Cを当日2冊購入=1.500×2=¥3,000,Cを事前予約で送付希望=2,000×2+600=¥4,600)
*送付の場合は以下の送料を付加して下さい.
送料:1冊 500円,2冊 600円,3冊 800円,4冊 1,000円,5冊 1,200円
見学旅行案内書の予約頒布
*大会不参加で冊子のみの購入も可能です
<申込締切 オンライン:8月5日(金)18:00,FAX・郵送:8月1日(月)必着>
大会に参加されない方でもご購入いただけます.なお、見学旅行案内書は,地質学雑誌の補遺版(CD)として, 12月号刊行時に会員配布されます.
案内書の受け取り方法には,(1)大会後に送付,(2)会場で受取り,があります.(1)の場合は,別途送料が必要です.(2)の場合は,大会受付にて引換クーポンの提示が必要となりますので,必ずご持参下さい.見学旅行参加者はできるだけ会期中に会場の受付にてお受取り下さい(見学旅行代金には見学旅行案内書の代金は含まれておりません.必要な方は別途購入して下さい).
残部があれば,大会当日あるいは大会後にも頒布します.売り切れの場合はご容赦下さい.
価格:2,800円/冊
*送付の場合は以下の送料を付加して下さい.
送料:1冊 500円,2冊 600円,3冊 800円,4冊 1,000円,5冊 1,200円
懇親会・お弁当
懇親会
<申込締切 オンライン :8月5日(金)18:00,FAX・郵送:8月1日(月)必着>
日時:9月9日(金)表彰式・記念講演会終了後(19:00〜20:00)
場所:交渉中 ※
懇親会は,9月9日(金)表彰式・記念講演会終了後,19:00頃〜20:30の間に開催を予定しております.会費は正会員5,000円,名誉会員・50年会員・院生割引会費適用正会員・学部割引適用正会員および会員の家族は2,000円です.非会員の会費は正会員に準じます.準備の都合上,前金制の予約参加とします.たくさんの方々,特に院生・学生などの若手会員のご参加をお待ちしております.余裕があれば当日参加も可能ですが,予定数に達し次第締切ります.当日会費は1,000円高くなります.
予約申込は,「各種申込とお支払について」を参照し,大会参加申込と合わせて8月5日(金)までにお申し込み下さい.
当日はクーポンを受付にご持参下さい.懇親会に限り,締切後の参加取消の場合は会費の返却はいたしませんのでご了承下さい.
※会場につきましては,今回の震災により,当初予定していた会場が利用できなくなりましたため,現在,交渉中です.会場は決定次第学会News誌および大会ホームページ等を通じてお知らせいたします.
申込(参加登録フォーム)は>>こちらから
*「各種の申込方法とお支払いについて」はこちら
お弁当予約販売
<申込締切 オンライン :8月5日(金)18:00,FAX・郵送:8月1日(月)必着>
9月9日(金)〜9月11日(日)には昼食用の弁当販売をいたします(1個700円,お茶付き).大会参加申込と合わせて,8月5日(金)までにお申し込み下さい.締切後〜8月29日(月)までの取消は60%,大会10日前(8月30日(火))〜当日までの取消は100%の取消料がかかります.なお,9月9日(金)〜11日(日)は大学生協食堂は営業いたしております.
申込(参加登録フォーム)は>>こちらから
*「各種の申込方法とお支払いについて」はこちら
その他の申込TOP
その他の申込一覧
■
東日本大震災関連ポスター展示:ポスター募集 8/22(月)17時 締切
■
市民向けポスター展示申込 7/22(金) 締切8/22(月)まで延長
■
ランチョン・夜間小集会申込 締切ました.
■
託児室の利用申込 8/12(金) 締切
■
広告掲載 6月28日(火)締切7/22(金)まで延長
■
企業展示・書籍ほか販売申込 一次締切:6/28(火) 最終締切: 7/22(金)7月末日まで延長
■
追加講演要旨・見学旅行案内書購入(大会不参加で冊子のみの購入も可)
*参加登録フォームからお申し込み下さい Web: 8/5(金)締切
(郵送: 8/1(月)必着)
※News誌4月号の大会予告にて、締切日の記載が異なっている部分がございました。ご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。(News誌4月号(10)ページに記載の日付が正しい締切日です。)
ランチョン・夜間小集会申込
ランチョン申込
<申込締切 6月10日(金)必着,行事委員会扱い>
9月10日(土),11日(日)にランチョンの開催を希望する方は,
(1)集会の名称,
(2)世話人氏名,
(3)集会内容等,を明記してe-mailで行事委員会:<main@geosociety.jp>宛に申し込んで下さい.申込締切は6月10日(金)です.
なお,世話人の方は,終了後集会の内容をニュース誌の大会記事用原稿としてご投稿いただきます(800字以内,原稿締切:9月末).
夜間小集会の申込
<申込締切 6月10日(金)必着,行事委員会扱い>
9月10日(土)は18:00〜20:00,11日(日)は17:30〜19:00(予定)です.夜間小集会の開催を希望する方は,
(1)集会の名称,
(2)世話人氏名,
(3)集会内容(50字以内),
(4)参加予定人数,
(5)液晶プロジェクターの要・不要,
(6)その他特記すべきこと,を明記してe-mailで,行事委員会:<main@geosociety.jp>宛に申し込んで下さい.申込締切は6月10日(金)です.
なお,世話人の方は,終了後集会の内容をニュース誌の大会記事用原稿としてご投稿いただきます(800字以内,原稿締切:9月末).
託児室・学童ルーム
男女共同参画委員会企画
【託児室のご案内】
<利用申込締切 8月12日(金)現地事務局>
(1) 開設日時:9月9日(金)〜11日(日)
(2) 対象:水戸大会参加者(日本地質学会・日本鉱物科学会会員)を保護者とする生後3ヶ月から就学前迄のお子様.
(3) お申し込み・お問い合わせ先:
現地事務局
〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1 天満橋千代田ビル2号館9階
日本地質学会・日本鉱物科学会合同学術大会
現地事務局(株式会社アカデミック・ブレインズ内)
TEL:06-6949-8137,FAX:06-6949-8138,e-mail:mito2011@academicbrains.jp 担当:田中
※託児料金や利用に際しての注意事項等,詳細につきましては,お申し込みの後に保護者の方へご案内いたします.
※万が一の場合に備え,施設加入の損害保険で対応させていただきます.なお,託児施設のご利用に関しては当学術講演実行委員・日本地質学会・日本鉱物科学会は責任を負いかねますのでご了承ください.
広告掲載・企業展示・書籍販売等について
企業等団体展示/書籍販売(茨城大学 水戸キャンパス 学生会館 ※予定)
(お申込頂いた企業様からお名前を掲載させていただく予定です.)
書籍・物品の展示販売コーナー(茨城大学 水戸キャンパス 学生会館 ※予定)
(お申込頂いた企業様からお名前を掲載させていただく予定です.)
※申込期限延長,追加募集等がある場合もありますので,随時大会ホームページをご覧ください.
■企業展示出展募集
■書籍・販売ブース募集
■広告掲載募集
企業・研究機関等関係団体による展示会の出展募集
<申込締切 第1次募集締切:6月28日(火) 最終募集締切:7月22日(金)7月末まで延長>
地質関係機関・関連企業のご活躍を広く地質学会員に紹介していただくため,会期中,企業展示会を開催致します.企業紹介・業務紹介・研究成果・新技術・特許などご自由に展示内容を構成いただけます.奮ってご出展のお申込をいただきますようお願い申し上げます.
【展示募集概要】
1,開催期間:搬入設営日9月8日(木),開催日9月9日(金)〜11日(日),搬出撤収日9月11日(日)※予定
2,開催場所:茨城大学 水戸キャンパス 学生会館 ※予定
3,募集小間数:小小間12,パネル小間16 ※予定 複数小間のお申込も可能です.
4,小間仕様見本:
※仕様詳細・オプション料金等につきましては,
「展示募集要項申込書(pdfファイル)」
「展示募集要項申込書(docファイル)」
をダウンロードの上,ご確認下さい.
5,出展料金:小小間 50,000円(消費税別),パネル小間 20,000円(消費税別)
6,第1次募集締め切り日:6月28日(火) 最終募集締め切り日:7月22日(金)7月末まで延長
【出展申込方法】
上記「展示募集要項申込書」をダウンロードいただき,必要事項をご記入の上,下記申込先までe-mailへのPDFファイル添付,あるいはFAXにてお申込下さい.募集要項・申込書が別途必要な場合は,現地事務局までご連絡下さい.送付致します.
【お申込・お問合せ先】
〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1天満橋千代田ビル2号館9階
日本地質学会・日本鉱物科学会 合同学術大会 現地事務局 (株式会社アカデミック・ブレインズ内)
TEL:06-6949-8137,FAX:06-6949-8138, e-mail: mito2011@academicbrains.jp 担当:田中
※日本地質学会または日本鉱物科学会の賛助会員は出展料金が無料となります.別途,現地事務局までご連絡下さい.
書籍・販売ブースご利用の募集
<申込締切 第1次募集締切:6月28日(火) 最終募集締切:7月22日(金)7月末まで延長>
地質学関連の書籍・その他物品の販売にご利用いただくべく会期中ブースを設置致します.奮ってご出展のお申込をいただきますようお願い申し上げます.※見本展示のみでのご利用も可能です.
【書籍・販売ブース出展概要】
1,設置期間:9月9日(金)〜11日(日)
2,設置場所:茨城大学 水戸キャンパス 学生会館 ※予定
3,募集ブース数:6ブース ※予定 複数ブースのお申込も可能です.
4,ブース仕様見本
※仕様詳細・オプション料金等につきましては,
「展示募集要項申込書(pdfファイル)」
「展示募集要項申込書(docファイル)」
をダウンロードの上,ご確認下さい.
5,出展料金:10,000円(消費税別)
6,第1次募集締め切り日:6月28日(火) 最終締め切り日:7月22日(金)7月末まで延長
【出展申込方法】
上記「展示募集要項申込書」をダウンロードいただき,必要事項をご記入の上,下記申込先までe-mailへのPDFファイル添付,あるいはFAXにてお申込下さい.募集要項・申込書が別途必要な場合は,現地事務局までご連絡下さい.送付致します.
【お申込・お問合せ先】
〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1天満橋千代田ビル2号館9階
日本地質学会・日本鉱物科学会 合同学術大会 現地事務局 (株式会社アカデミック・ブレインズ内)
TEL:06-6949-8137,FAX:06-6949-8138, e-mail: mito2011@academicbrains.jp 担当:田中
講演要旨集・見学旅行案内書,広告協賛の募集
<申込締切 6月28日(火)7月22日(金)>
地質関係機関・関連企業のご活躍を広く地質学会員に広報いただくべく,大会開催にあわせ発行されます講演要旨集・見学旅行案内書において,広告協賛を募集致します.企業紹介・業務紹介・研究成果・新技術・特許などの広報活動のご一環として,奮ってお申込をいただきますようお願い申し上げます.
【広告協賛料金】※詳細は
「広告協賛募集要項申込書(pdfファイル)」
「広告協賛募集要項申込書(docファイル)」
をダウンロードの上,ご確認下さい.
講演要旨集:1頁 40,000円 1/2頁 20,000円 1/4頁 10,000円(すべて消費税別)
見学旅行案内書:1頁 20,000円 1/2頁 10,000円 1/4頁 5,000円(すべて消費税別)
※共に完全版下,データまたフィルムでの入稿をお願い致します.
【出稿申込方法】
上記「広告協賛募集要項申込書」をダウンロードいただき必要事項をご記入の上,下記申込先までe-mailへのPDF添付,あるいはFAXにてお申込下さい.
【お申込・お問合せ先】
〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1天満橋千代田ビル2号館9階
日本地質学会・日本鉱物科学会 合同学術大会 現地事務局 (株式会社アカデミック・ブレインズ内)
TEL:06-6949-8137,FAX:06-6949-8138, e-mail: mito2011@academicbrains.jp 担当:田中
発表負担金
発表負担金について
日本地質学会担当セッションでは,口頭発表あるいはポスター発表のいずれかの方法で,1人1題に限り発表を行うことができます.ただし,今年は例年と異なり,発表負担金(1,500円)を支払うことにより,日本地質学会担当セッションでもう1題の発表が可能です(最大2題).この場合,同一セッションで2題発表することも,異なる2つのセッションで1題ずつ発表することも可能です.
発表申込を予定している方は,発表負担金の項目も忘れずに入力してください.
※日本鉱物科学会担当セッションについては,発表要領,負担金等は日本鉱物科学会の要項に沿った内容となります.
>>>日本鉱物科学会の大会ページ
大会申込Q&A
大会申込Q&A
【演題登録編】 >>【参加登録編】へ
Q:1人何題まで登録できますか?
A:
水戸大会の地質学会担当セクションでは、1人2題まで登録できます。ただし2題目を登録する場合には発表負担金が別途必要になります。(1題のみの場合には無料です。)日本鉱物科学会担当セクションについては、鉱物科学会の申込要領に沿ってお申込ください。
Q:非会員も演題登録はできますか?
A:
システム上,登録はできますが,招待講演者を除き,非会員の発表はできません。現在会員でない場合には,演題登録に合わせて,入会申込もお願いします。(締切時点で入会申込が確認できない場合,登録が取り消されます。)水戸大会では日本地質学会・日本鉱物科学会のどちらかに所属していない場合は『非会員』となります。共催団体の会員は共催のセッションのみ発表できますが、その他セッションで発表を希望する場合には、必ず入会手続きを行ってください。
Q:入会手続しましたが,まだ会員番号(ID)を貰っていません.登録できますか?
A:
登録できます.会員区分の中に『手続き中』という区分がありますので,そちらを選択して登録してください.また登録前は入会申込が多いため,事務局から確認連絡が遅くなる場合があります.入会申込書の送付,初年度会費の送金を済ませた方は連絡を待たずに登録を行ってください.
Q:筆頭著者でなければ発表できないのですか?
A:
水戸大会では、筆頭著者でなくても発表が可能です。ただし、非会員の発表はできません。演題登録時のpdfには、発表者の前に○(まる)印を必ずつけてください。非会員が発表者になっている場合には、登録が取り消される場合があります。
Q:サーバーに接続出来ず、原稿の登録ができませんでした。締切は延長されますか?
A:
締切直前は、申込が殺到し、接続しにくくなります。余裕を持って登録してください。(万が一、操作中にサーバーがダウンして締切時間を過ぎた場合でも、事務局/行事委員会は責任を負いかねます。)
【参加登録編】
Q:講演要旨は付きますか?
A:
以下の会員は参加登録費に講演要旨が含まれます。
正会員・院生割引会費適用会員・非会員
以下の会員は講演要旨が付きません。
名誉会員・50年会員・学部割引会費適用会員・非会員学部学生・非会員招待者
※講演要旨をご希望の場合は、別途ご購入ください。
Q:「後日発送」はいつ送付されてきますか?
A:
大会会期終了後の発送です。会期前の送付はできません。別途送料がかかります。
Q:キャンセル料(取消料)はかかりますか?
A:
受付期間中の変更,キャンセルの場合はかかりません。締切後につきましては,申し込んだものにより、それぞれ異なりますのでご注意ください。
参加登録料:申込締切後〜9/6(大会3日前)60%,9/7(大会2日前)以降100%
※ただし後日講演要旨をお送りいたします。
懇親会:申込締切後100%
見学旅行:申込締切後〜出発3日前まで50%,2日前以降100%
お弁当:申込締切後〜8/29まで60%、大会10日前(8/30)〜当日100%
Q:参加登録をWebでしましたが、確認メールが届きません。
A:
入力したメールアドレスが間違っている可能性があります。学会事務局へ連絡してください。
Q:参加費が無料の会員は,事前登録をしなくてもよいですか?
A:
当日の参加登録でも構いません。ただし、講演要旨の購入を希望される場合は,数に限りがあり,予約と当日購入では料金が異なりますので,ご予約をお勧めします。
Q:代理での申込はできますか?
A:
可能です。ただし、申込の重複、連絡先/発送先の登録には注意してください。(特に非会員招待者、外国人招待者等を登録する場合,誤って登録した場合の確認が取れなくなります。また、確認メールは日本語のみです。)
Q:見学旅行だけに参加したいのですが。
A:
見学旅行だけに参加する場合でも,通常の参加登録が必要です。ご自分の所属区分に合わせて参加登録画面からお申込ください。
Q:参加はしませんが冊子だけの購入はできますか?
A:
冊子だけの購入も可能です。ただし、発送は大会終了後になりますので,ご了承ください。
Q:Web登録がうまくできません。
A:
連絡先など、登録情報の自動取得が行えない場合はこちらを参考にしてください。ただし自動取得は日本地質学会会員のみ利用できます。
正しく操作を行っているにも関わらず、エラーが出る場合等は学会事務局へご連絡ください。
Q:昨年,参加クーポンが届きませんでした。/大会終了後に受け取りました。
A:
参加クーポンは郵送でお送りします。申込の際,発送時期に確実に届く住所を記入・入力してください。(所属先へ送付を希望される方は,特にご注意ください。)発送は大会10日前にはお手元に届くように発送する予定です。締切後に送付先変更を希望される場合は,学会事務局へご連絡ください。また、下記のような場合にも早めにご連絡ください。
例1)締切後から大会直前まで出張、所属先へは顔を出さないまま大会に参加予定。
例2)大学職員・学生の方:夏季休暇中は事務が閉まっていて、郵送物が届きにくい/届かない。
Q:宿泊予約はできますか?
A:
参加申込システムからは予約を承っていません。申し訳ありませんが,各自で手配をお願いいたします。
参考:日本旅行の宿泊予約サイト(日本旅行のサイトでは、水戸大会参加者数分の宿泊先が確保されています)
Q:自分の疑問が解決する答えが載っていませんでした。
A:
ここには比較的多く寄せられた質問を載せています。その他の質問については、お手数ですが学会事務局へご連絡ください。
学術大会に係るプレス発表会へのご協力のお願い
学術大会に係るプレス発表会へのご協力のお願い
平素より日本地質学会の活動にご協力頂きましてありがとうございます.日本地質学会では,学術大会の際に,学術大会や地質情報展の開催案内,そして「特筆すべき研究成果」等を開催地および文科省の記者クラブに情報提供してまいりました.特に開催地での記者会見には,例年多くの報道機関の方が来場され,TV,新聞等で取り上げて頂いております.
本年も水戸大会においてプレス発表会を開催する予定です.会員皆様の学術活動が広く報道されることは,地質学全体にとってプラスになることですから,この機会に会員皆様の成果を「特筆すべき研究成果」として発表くださいますようお願いいたします.皆様からの推薦をもとに,会見にマッチした資料を準備いたしますので,支部,部会,会員皆様からの自薦・他薦等,幅広い情報をお待ちしております.
「特筆すべき研究成果」の応募方法
締め切り:
7月22日 17時
応募方法:
推薦者と発表者の氏名と連絡先(メールおよび電話番号),タイトル,セッション名と簡単な推薦理由を地質学会事務局(journal@geosociety.jp)にお送り下さい.資料作成のために行事委員会および広報委員会より連絡することがあります.
記者会見:
8月下旬
解禁日(掲載日):
9月6日
過去のプレスリリース資料は学会ホームページより閲覧できますので,どうぞご参照ください.できるだけ公式のプレス発表会を活用して頂き,個別会見の場合も解禁日を合わせて,全体として効果的な報道になるようご協力をお願いいたします.
日本地質学会広報委員長
坂口有人
過去のプレスリリースはこちら
下記に簡単なQ&Aを準備いたしました。
■ネイチャーやサイエンスに載らないと相手にされないのでは?
そんなことはありません。記者の方は発表媒体は全く問題にしません。それよりも、そのネタは読者の関心を引くのか? もしくは国民に広く周知すべき事なのか、の二点を重視します。そこがしっかりしていれば多くのメディアに掲載されるでしょうし、逆にそうでなければ、いくら有名ジャーナルに掲載されても記事になりません。
■どんなメリットがあるの?
発表者ご自身の研究学術活動の内容が紹介されるのはもちろんのこと、所属機関にとっても宣伝になるでしょう。しかしなんといっても地質学の記事が掲載されることは、私たちの学問分野全体のメリットになります。全体の利益のためにもぜひ発表をご検討下さい。
■知り合いの記者に話しても同じでは?
親交ある記者の方ならば正しくて深みのある記事を書いて下さるかもしれません。しかし特定の会社にのみ情報を流すと他社から反発を買って、かえって逆効果になる場合もあります。記者クラブを通じて発表し、その上で個別取材に応じるのが最も効果的です。
■プレス発表って難しそう
基本的には、わかりやすく、かつ記事に使用されやすい資料を記者クラブに送付するだけです。必要とあれば記者会見もセッティングいたします。会見といってもプロジェクターやボードを使った講演会と質疑応答であり、ワイドショーの記者会見とは全く違います。
資料の作成や売り込み方法など、これまでのノウハウを活かしてサポートいたしますので、どうぞご相談下さい。
■こっちの意図と違う記事になったら嫌だな
せっかく掲載された記事が、誤解に基づくものであったり、ピントのはずれたものであっては互いにマイナスです。そうならないためにも、わかりやすい説明を行う必要があります。発表者とメディアの双方にプラスになるようサポートさせて頂きます。
■効果はあるの?
例えば札幌大会の時のダイアモンドの国内初報告の時は、全国の新聞とTVで大きく報道されYahooのトップページにも掲載されました。地質学会のホームページにアクセスが集中しサーバーはパンク寸前まで追い込まれました。これは特別としてもそれ以降の発表会でも新聞,TV等で毎年報道されています。
■どんなネタがいいの?
タイミングや流行があるので一概には言えませんが、ジェネラルなトピックスで幅広い読者の興味を喚起するものがふさわしいです。もしも自分自身が記者だったらと考えてみて、一般の読者に伝えたい、と思えるかどうかは一つの判断材料になるかもしれません。
ふさわしいと思える成果がありましたら、どうぞご相談下さい。
東日本大震災関連ポスター展示
東日本大震災関連ポスター展示におけるポスター募集について
<申込締切 8月22日(月)17時,行事委員会扱い>
申込先:main@geosociety.jp
東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)により,東北から関東に至る広い地域が被災しました.今大会開催地である茨城県においても,護岸部・平野部の液状化,山間地の斜面災害,さらには原発に伴う海域汚染など多くの被害が報告されています.そこで,震災において発生した様々な被災状況に関して,地質学的視点から広く社会に紹介する場を計画しました.
茨城県内の市民に向けて,県内の被災状況,さらには近隣を含めた広範囲な震災情報を「東日本大震災関連ポスター展示」として発信したいと考えています.ぜひ,震災調査に関わっている多くの会員の応募をお願いいたします. 東日本大震災関連ポスター展示は,これまでの緊急展示と異なり,「地質情報展」会場(茨城大より徒歩数分)で開催し,一般市民向けといたします.市民の皆様に理解していただくために,以下の点についてご考慮ください.
・写真や図表を多用し,文章は少なくする.
・平易な表現で,『です・ます』調の文体とする.
展示を希望する方は,8月22日(月)17時までに以下の内容を実行委員会(main@geosociety.jp )にメールで提出してください.展示は無料です.筆頭著者は会員・非会員を問いませんが,発表申込者は会員とします.
1)発表要旨(WORD版:題目,発表者,要約文400字以内)
2)発表申込者(代表発表者)と連絡先
3)希望枚数(1枚:幅90×高さ180cm)
4)展示整理のために発表内容を次のキーワードから選択
(地震,津波,断層,液状化,地すべり・斜面崩壊,環境)
【その他の注意点】
・展示期間は9月10日(土)10:00〜11日(日)16:00.
・展示会場は堀原運動公園武道館(地質情報展会場)です.
・説明のコアタイムは9月11日(日)13:00〜14:30とします.この間は,時間が許す発表者は,できるだけポスター前にて市民の方へのご説明をお願いします.その他の時間帯につきましては,実行委員会の担当が全体を通して説明をする予定です.
・実行委員会は行事委員会と協議し,可否の判断を致します.展示場所等については実行委員会の指示に従ってください.
申込先:main@geosociety.jp
担当:
岡田 誠
(水戸大会実行委員会)
須藤 宏
(行事委員会)
山本 高司
(関東支部)
市民向けポスター展示・説明会
市民向けポスター展示・説明会に参加しませんか?
<申込締切 7月22日(金)17時,行事委員会扱い>
秋の学術大会では、いつも開催地のホットなエリアで市民向けの地質情報展が催されています(独立行政法人産業技術総合研究所地質調査総合センター・国立大学法人茨城大学・一般社団法人日本地質学会)。この地質情報展は、それぞれの地方新聞やローカルニュースでも積極的に取り上げられ、多くの皆様がご来場くださり、そして地球科学に関心の高い市民の皆様と専門家との交流の場として成長しています。そこでアウトリーチに関心のある会員の皆様に、情報展のスペースを活用して頂き、地球科学の一段の普及に役立てて欲しいと考えております。そこで下記のポスター展示を募集します。「自分の研究成果を市民に少しでも伝えたい・知ってほしい」という方、ぜひご応募下さい。
展示スペース: 1 件につき幅1m× 高さ1.8m× 奥行0.5m (右図参照)
応募方法: 発表者, タイトル, 概要(400 字程度), キーワード(最大5つ) をメールで送付. 電気やテーブル等必要な場合は, その旨記すこと.
宛先: 行事委員会(main@geosociety.jp)
締め切り:7月22日(金)17時
採択数: 5〜10 件
注意事項:
出展は無料です.
行事委員会が応募内容を検討し,採択/非採択を決定します.
市民に向けたポスター展示ですので,「わかりやすさ」に最大限の配慮をしていただきます.採択後,ポスター作成の注意点をお知らせします.
情報展開催中は,できるだけポスター前にて市民への説明をお願いします.
広報委員会による大会プレス発表で紹介させていただくことがあります.
ご不明な点は行事委員会にお尋ね下さい.
大会趣旨
水戸大会趣旨
2011年水戸大会は,日本地質学会・日本鉱物科学会・茨城大学の共催により
「いま,地球科学に何ができるか?」
をキャッチフレーズに開催いたします.
3月11日の東日本大震災では多くの尊い命が失われ,その後も避難生活を余儀なくされている方が大勢いらっしゃいます.被災地でもある水戸の実行委員会では,このような災害を繰り返さないために,今こそ地球科学の力を結集すべきであると考えました.そこで,日本地質学会・日本鉱物科学会共同企画シンポジウム「大規模災害のリスクマネージメント―東北地方太平洋沖地震に学ぶ―」を開催し,地学的視点から見て我々がいかに自然災害に対処すべきかについて議論を深めたいと考えています.また,震災関連のポスターセッションを企画し,茨城大学調査団を含む各調査団の調査結果を公開します.
そのほか,合同学術大会を特徴づけるシンポジウム「太陽系固体惑星地質探査:イトカワから火星・金星まで」では,人類史上初の快挙である小惑星試料採取の成果について興味深い発表があります.シンポジウム「関東盆地の地質・地殻構造とその形成史」では,関東盆地の形成に関する最新の研究成果が発表されます.また,例年のとおり各専門部会等から提案された定番セッション(25件)と多数の応募の中から選定されたトピックセッション(20件),見学旅行等も準備しています.普及行事としては地質情報展,市民講演会「東日本大震災と地震・津波・原発」などの催しも開催します.また,今年も小・中・高校生徒「地学研究」発表会をポスター会場で行います.
今大会での各種の申込は,昨年の富山大会と同様,学会が独自に構築した参加登録システムを利用します.お支払いは銀行振込またはクレジットカードによる支払いが可能です.発表についても昨年同様,J-STAGE演題登録システムを利用してweb(オンライン)上での申込を受付けます.なお,大会準備がスムーズに運ぶよう,締切日の厳守をお願いいたします.
※電力供給不足,計画停電の影響等により,9月の大会開催時期に状況が変化している可能性もないとは言えません.今後の展開によっては,シンポジウムやセッション等の日程変更や中止等を余儀なくされることもあり得ます.大幅な予定変更が生じた場合は,ホームページやgeo-Flash(メールマガジン)等を通じて速やかに会員の皆様にお知らせします.
地質学会セミナー
地質学会セミナーのご案内
日 時:9/11(日)14:30-16:00(質疑等含む)
会 場:茨城大学水戸キャンパス 共通32
タイトル:地質図に関するJISの解説と2012年改正案の要点
講 師:鹿野和彦(産総研,地質図JIS原案作成委員会事務局)
主 催:日本地質学会地質用語国際標準対応委員会
※画像をクリックすると大きな画像をダウンロードできます.
確認書・クーポン等の送付について
事前参加登録:確認書・クーポン等の送付について
2011.8.26
事前参加申込を頂いた方に対して、申込内容に応じて確認書2枚(本人控・受付提出用)等をお送り致しました(8/26発送)。
受付提出用の確認書、名札、クーポンを当日忘れずにご持参下さい。
<入金者の方へ>
確認証・参加証(名札)・クーポン(懇親会・お弁当を予約された方のみ)をお送りしました。当日必ずご持参下さい。
ネームカードホルダーと、それぞれ申し込み内容に応じて冊子等をお渡しいたします。
受付提出用の確認証がない場合には、受付に時間がかかる場合がありますので必ずご持参ください。
クーポンは懇親会会場入り口、お弁当引換時にそれぞれ提示してください。
<一部入金・未入金の方へ>
締切(8/23)時点で一部入金もしくは、入金確認が取れていない方へは確認書のみをお送りしております。当日必ずご持参ください。入金と入れ違いの場合はご容赦ください。
当日会場受付にて入金のご確認をさせて頂きますので、振込み時の控え等をご持参下さい.確認がスムーズに行えます.
お支払いがまだの方は、9月5日(月)までに下記いずれかへお振り込みをお願い致します。この場合も振込み時の控え等をご持参下さい。
5日までにお振込いただけなかった場合は、当日会場受付にてご清算をお願い致します。
振込先 (注意:振込時には、振込者氏名の前に必ず申込Noを入力して下さい)
(1)三井住友銀行 神田駅前支店(普通)1711424 (社)日本地質学会 / シャ)ニホンチシツガッカイ
(2)郵便振替 00140-8-28067
アンケート結果
アンケート結果
2011年10月2日
アンケートにご協力下さりありがとうございました.お寄せ頂きましたご意見は,今後の大会運営の参考にさせて頂きます.
これまで頂いたご意見
会場内でインターネットに接続できる場所が少なすぎる。
今回の震災は実学としての「地学」がいかに重要であるかを知る良い機会と考えているがどうであろうか。「勉強が出来なくても死ぬことはない」と言う言葉があるが、「地学」を知らないが故に命を落とした人がかなりいるはずである。液状化もまた然りで、平衡感覚が微妙ではあるがくるい気分が悪くなってくるので、住民達はかなりきついであろう事を実感した。地質学会の役割は命に関わる重要性が既にあると思っている。
鉱物学会との共催は,普段の年会では会えない研究者に会えたり,あまり聞くことのできない分野の話が聞けて,とても良かった.
一方で受賞講演までが共催だと長くなり,途中で席を立つ人が例年より多かった.講演者にかえって失礼になっていたように思う.
学会参加費に9500円は高すぎる。収入の無いリタイヤ―組みへの配慮が必要ではないか。退職後ちょっと参加して若手にエールを送る環境を作って頂きたい。経済的な問題があるだろうが、特にポスター会場は狭すぎて、賑やか過ぎて、せっかくの説明もなかなか理解しにくい場面があった。
特に2日目のセッションの組み方がきついと感じた。1日目午前,2日目午前には部屋に空きがあったにもかかわらず,午後のセッションは14:30から18:30まで休憩もなく詰め過ぎなセッションもあると感じた。このため聞きたい講演がいくつか重なり聞けなくて残念であった。
講演は受理されていたが,都合があり事前申し込みできなかった.2日目朝一で参加登録したが,予稿集は完売とのことで購入できなかった.演者が予稿集を入手できないようなシステムはいかがなものか.3日目の受付には予稿集が山積みされていた.現在,事務局には予稿集の残部があるのではないか?非常に不愉快な大会であった.
参加して戸惑った点。工夫が必要ではないかと感じた点。
1.学内場外(校門、校庭、建物入口等)に会場の案内を表示(標識ビラ等)があると、目的会場を探し当てるのに苦労がなかったのではないでしょうか。暑い日差しの下で何回も聞き回り大汗しました。
2.食堂事情を予め案内していただきたかった(学生食堂の利用も含めて)。
3.JR戦等からのアクセス事情、バス停の位置等の案内をもう少し親切にされると参加者は助かったのではないでしょうか。
4.プログラムをもう少し使い易くする必要があるのではないでしょうか(他の学協会等における事例も参考に)。以上
駅から離れていたけど、バスの本数が多かったので、駅からの距離はあまり気になりませんでした。
地質情報展のポスター・看板をもっと出せば良かったのにと思います。近くまで行っても本当にやっているのか、どこでやっているのか、わからなくて不安になりました。
シンポジウムの内容が充実していたと思います。震災、ジオパーク、イトカワなど、一般の人が興味を持てるテーマで、内容はレベルは高く分かり易い説明が聞けたので、とても面白かったです。
会場が分散していたので、移動に時間がかかりセッション間を移動して細かく聞いて回る事ができなかったのが残念でした。
被災大学でありながら、事務局として準備をしていただいた茨城大学のみなさん、本当にありがとうございました。お疲れ様でした。
高校生による展示企画は大変良かったと思います。部屋の奥ではなく、前方の目立つ場所で実施させてあげられれば、より注目度が高かった思います。
地質情報展示は大変良い企画で、会場も広く開放感があり良かったですね。ただ、場所が良く分からないために気がつかない人もいました。学外でもあり、困難は承知の上ですが、行政や警察の許可を取った上で「看板」「のぼり」も必要かなと、感じました。一般の方も、のぼりが沢山あると気に留めますよね。
地震はありましたが、トラブルもなく参加できました。暑さがもどった週末でしたが、スタッフや関係のみなさまの努力とご対応に心より感謝申し上げる次第です。
毎回感じますが、ポスターの幅を大きく、もしくは隣のポスターとの距離をもっと長くとるべきです。今大会のような幅では、パネル1つ空けて貼っても良いと思うぐらいです。地質学会に限ったことではありませんが、これだけは是非にも改善を希望します。
共催であるのに鉱物科学会主催のセッションの予稿集が渡されないのは腑に落ちない.予稿集A,B,Cは一冊にするべきではないだろうか.
鉱物学会分の要旨も欲しかったのですが,どこで手に入るのかよく分かりませんでした.(事前登録の段階で,申し込めたのでしょうか?学会の会場で購入できたのでしょうか?確認不足でしたらすみません)見に行けない発表もあったので,要旨がないのは少し残念です...
地質学会のポスター賞についてですが,これはイラストレーションの美しさのみを競っているものなのでしょうか.とてもサイエンスベースで選考が行われているとは思えません.単なる「模式図」の美しさを競うことに意味があるのでしょうか.他の学会ではもっとサイエンスベースでの選考が行われていると感じておりますが,この点,いかがお考えなのでしょうか.教育的にも非常に問題があると感じております.
深成岩・火山岩、地体構造、地殻流体、レオロジー、沈み込み帯と、聞きたいセッションがことごとく同じ時間に行っていたのが残念でした。似た内容のセッションは異なる時間に配置してほしかったです。
関東平野地下構造の解析結果について,せっかく武道館のスペースが大きかったのだから,全日あそこで展示すれば良かったと思った。シンポジウムの後,1時間足らずというだけでは,時間的に全く足りない。
講演会場・ポスター会場が分散している状況は,移動に時間がかかり,効率的ではない。せめて隣同士の建物なら良かった。
意見ではないが、茨大経由水戸駅行きのバスが、東京駅で積み残しがなかったかどうか気になります。
ポスターの掲載時間(3日目)について、一つご意見申し上げます。
ポスター発表について、プログラム等には18時まで掲載し、18時30分までにはがすように書かれてありました。そのため18時5分頃に会場に行きましたが、すでに会場は撤収作業が進められポスターも勝手に移動されていました。
そのため、受付や本部を奔走してポスターを捜索しましたが、大変困惑しました。また、発表者の許可なく研究成果であるポスターを持ち出すことは問題があり、大変遺憾に思います。確かに、学会運営にあたり撤収作業の都合や時間的な制約などもあるかと思います。しかし、それならばポスターの掲載時間を17:30までなどとすれば宜しいかと思います。少なくともルールを守ってる人に対して、不利益を被るようなことをしてはならないです。以上
お世話になり有り難うございました。ポスター発表について、隣り合うポスターの間に一定の間隔があると、ゆっくりと見ることができたと思います。
二学会共催のため記念講演などの時間が長かった。そのためか色々な進行がタイトに感じられました。特に、初日の口頭講演とポスター発表コアタイムの間に時間が無く、昼食をゆっくり食べていると結果的にコアタイムが短くなってしまうという問題があげられます。また、ポスター会場が分散していてわかりにくかった。なるべく一つないし、同じ階に会場を集め他方が良いでしょう。会場の数が多くなりますが、企業ブースは単独で設けた方が良かったと思います。たくさんの人に観てもらえることから企業側にとっては良かったかもしれませんが、会場が狭くなる上にコアタイムでは混雑が酷く、暑さもあってじっくりとポスターを観ることができませんでした。
合同大会であり、よりスムースな大会運営が必要であることを思います。
被災地での開催に当たり、事務局の皆様の御苦労に感謝いたします。 いくつか気づいた点としては、地質情報展の場所のPRが不足していたように思います。事前に予習(?)していたので、迷うことはありませんでしたが。 また、鉱物学会の要旨集Cがない(別売だった)ことに気づき、販売している場所が分からず、右往左往してしまいました。何とか無事購入できましたが、購入するにもいちいち住所、氏名やら所属学会の記入まで必要で、手続きが煩雑でした。見学旅行の案内書だけを購入する際にも同様の手続きが必要でしたが、なぜ、会員として学会に参加しているのに(ネームカードを見れば一目瞭然)購入者の個人情報を購入のたびに記載させて確認するのかよく分かりません。紙も無駄ですし、個人情報の書かれた購入申込書の処理も大変だと思うのですが・・・。
共催はとても良かったが,授賞式は2日間にするもしくは別会場を確保するなどしないと,冗長になる.受賞講演の前に大量の聴衆が帰ったり(特に後半),講演者には気の毒だったように思います. また,ポスター会場や一部の会場がとても暑かった.今後も大学の施設を使わせていただく以上,節電が求められると思います.開催時期を再検討して欲しい.9月上旬ではつらい.
2学会共催ということで総会などの行事の枠も詰んだ日程となり、参加者に負担が多かったように思う。 ・3日目の変成岩セッションなどは朝から夕方18時までと、最終日の遅くまで日程が組まれており遠方から来ている人間は最後まで聞くことが出来なかった。 ・3日目の日程では変成岩セッションと結晶構造セッションでRAMAN分光に関する講演の時間が被っており、分析手法としてRAMANに興味を持っている人間にとっては非常に残念だった。
講堂(大会場)の正面の立て看で、行事と開催時間とそれを区切るラインの配置が不適切で、行事の開催時間を誤認させるものであった。
はじめて託児を利用しました。大変アットホームな保育園で、子どもも楽しかったようで、安心しました。会場内託児と異なり、遊具が豊富で、手作りおやつも出て、環境を知り尽くした保育士がいるのでよかったと思います。一方で、会場から遠かったため、様子を見に行けず、送迎で参加時間が大幅減など不便でした。利用者減で厳しい運営とは聞きますが是非託児の存続を、また少しでも会場に近い場での提供をお願いしたいと思います。
地質情報展と同じ会場で行った方が行きやすくてよかったと思います。また、ニュースや話題になっている内容の講演・セッションなどをもう少し増やした方が、市民の方も興味を持つし、大会自体も盛り上がると思います。そして、地質学に興味がある人のためだけの内輪の大会ではなく、外部に向けてもっと色々なことを発信できる大会にしていくことで地球科学がもっと盛んな学問になる思います。 鉱物学会だけでなく、そのほかの関連する分野の学会の大会とも、共催出来たらさまざまな話も聞けるしより有意義なものになると思います。
大阪大会
大阪大会TOP
日本地質学会第119年学術大会(大阪大会)
日本地質学会第119年学術大会(大阪大会)
「都市から発信する地質学」
公立大学法人大阪府立大学 共催
会場:大阪府立大学 中百舌鳥(なかもず)キャンパス
2012年9月15日(土)〜17日(月・祝)
【 大阪大会・大会趣旨 】
大阪大会は盛会のうち、無事終了致しました。ありがとうございました。
来年は、仙台大会でお会いしましょう。
2013年9月14日〜16日 (予定)
忘れ物をお預かりしています NEW 9/19更新
事前参加登録は締切ました
→申込内容の取消・取消料について
当日の受付方法について
(事前参加登録をされた方/登録していない方)
★ 新着情報 ★
9/19
忘れ物をお預かりしています。 NEW
9/11
会場へのアクセス・会場内の移動など時間がかかります。ご注意下さい。
9/7
第119年学術大会(大阪大会)関連のプレス発表を行いました
9/6
講演キャンセル・講演者の変更について
9/4
8/30に確認書・クーポンを発送しました
8/30
大会期間中のお食事について(食堂営業時間変更になっています)
8/23
講演プログラムを掲載しました CHECK
8/9
【訂正】市民講演会問い合わせ電話番号
8/6
本大会での新しい試みをご紹介
8/6
学術大会の改革:オープンディスカッション開催します
7/23
全体日程表掲載しました
7/18
プレス発表を希望される方へ(登録締切7/31)
7/17
緊急展示の申込について(8/31締切)
7/11
できるだけ,堺市内に宿泊して下さい
7/6
地質情報展 2012おおさか:過去から学ぼう大地のしくみ HP開設しました
7/2
講演申込:締切延長 7/4(水)17時!
6/13
講演を予定しているが、まだ入会手続きをされていない方へ
6/13
国際ワークショップ「The Geology of Japan」を開催します。
復旧復興にかかわる調査・研究事業の成果発表会を開催します。
宿泊・観光関連のリンクを追加しました。
5/30
参加登録の受付を開始しました。
5/28
講演要旨の受付を開始しました。
4/19
シンポジウム、セッション決定!
大阪大会巡検の見どころを掲載しました。
2/27
トピックセッション募集(締切:3/12)
2012/2/22
大阪大会 近畿支部大阪府立大学にて開催
緊急展示の申込について
緊急展示の申込について
緊急展示の申込について
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害調査報告や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コーナー」を設けます.ポスター展示を希望する方は,8月31日(金)までに次の内容を下記申込先にご連絡ください.
1)発表要旨PDF(大会WEB「講演申込」ページ参照)
2)緊急展示の必要性
3)発表代表者と連絡先
4)希望枚数(1枚:幅90×180cm)
5)展示に関わる要望(2〜5の様式は自由)
実行委員会は行事委員会と協議し,可否の判断を致します.希望にはできるだけ応えるようにしますが,展示方法等については実行委員会の指示に従ってください.
申込先:<main@geosociety.jp>
担当:石井和彦(大阪大会実行委員会)・須藤 宏(行事委員会)
新着情報
新着情報 2012大阪大会
2012.9.19更新 忘れ物が届いています。
■■■
大阪大会の忘れ物を学会事務局でお預かりしています。
お心あたりの方は、学会事務局までご連絡下さい。<main@geosociety.jp> TEL 03-5823-1150
・講演要旨1冊:9/16 B3棟 第1会場(南極地質夜間小集会の後お届けがありました)
2012.9.11更新 会場へのアクセス・会場内の移動など時間がかかります。ご注意下さい。
■■■
会場である大阪府立大学中百舌鳥キャンパスは広く、構内の移動にもかなり時間を要する模様です。
参加者の皆様には,講演時間などをご確認の上、時間に余裕をもって会場にお越し頂きますようお願いいたします。
【最寄り駅〜大学】
南海高野線「中百舌鳥駅」〜大学(中百舌鳥門)まで:約1000m.(徒歩約13分)
地下鉄「なかもず駅」〜大学(中百舌鳥門)まで:約1000m.(徒歩約13分)
南海高野線「白鷺駅」〜大学(白鷺門)まで:約500m.(徒歩約6分)
【大学構内】
白鷺門〜〜講演会場B3棟まで(約400m)
中百舌鳥門〜講演会場B3棟まで(約600m)
会場アクセスなど詳細は、
http://www.geosociety.jp/osaka/content0015.html
2012.9.6更新 講演キャンセル・講演者の変更について
■■■
やむを得ない事情により,講演をキャンせるまたは,あらかじめ連記された共同発表者内で発表者の変更を希望する場合は,必ず事前に行事委員会(会期前は学会事務局<main@geosociety.jp>,会期中は学会本部)に連絡して下さい.
※キャンセルのご連絡があった講演は以下の通りです。(9/13現在)
R7-P-4
R8-O-4
T10-O-6
2012.9.4更新 確認書・クーポンを発送しました。
■■■
8月30日に事前参加登録された方へ確認書およびクーポン(お弁当・懇親会申込者のみ)を発送しました。
【入金確認済みの方】
記名名札と懇親会、お弁当申込の方には、参加・引換用のクーポンを同封しています。確認書(本人控と受付提出用)および名札・クーポンは当日忘れずにご持参下さい。確認書には,巡検を含め,お申込み頂いた内容全てが記載されています。内容にお間違いが無いか,今一度ご確認下さい。
【未入金の方】
確認書送付時点で事前参加登録費が未入金の方には黄色い用紙の確認書(本人控と受付提出用)のみお送りしています。
9月10日(月)までにご送金をお願い致します。本状と行き違いで入金済みの場合は当日受付にて照会いたします。念のため、振込み時の控え等をご持参下さい。9/10日(月)までにお振込いただけなかった場合は、当日会場受付にてご清算をお願いいたします。
<振込先>
振込時には、振込者氏名の前に必ず申込No.を入力して下さい。
(1)三井住友銀行 神田駅前支店(普通)1711424
(社)日本地質学会 / シヤ)ニホンチシツガツカイ
(2)郵便振替 00140-8-28067 (社)日本地質学会
※郵便局に備え付けの郵便振替用紙をご利用ください。
2012.8.9更新 訂正:市民講演会問い合わせ電話番号
■■■
【訂正】
すでに配布済みの市民講演会のポスター・チラシの問い合わせ先(電話番号)が間違っておりました。正しくは下記の通りですので、よろしくお願い申し上げます。関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
問合せ先:大阪府立大学 石井和彦
Tel 072-254-9729
Eメール ishii[at]p.s.osakafu-u.ac.jp [at]の部分を@と差し替えてください
市民講演会についての詳細はこちらから
2012.8.17更新 巡検申込者数(8/17 11時現在)
■■■
巡検申込者(8/16 11時現在)
左から,申込件数/(定員)>班名
07/(20)>A班:山陰海岸
12/(20)>B班:超丹波帯と丹波帯
21/(15)>C班:和泉層群
15/(20)>D班:室生
13/(16)>E班:古琵琶湖層群
16/(15)>F班:領家帯
16/(20)>G班:秩父帯
10/(10)>H班:四万十帯
17/(20)>I班:GIS
30/(20)>J班:地学教育
巡検の申込は、こちらから(締切8/17)
各コースの、みどころ紹介はこちら
2012.8.6更新 学術大会の改革:オープンディスカッション 開催します
■■■
日時:9月17日(月)18:00〜19:30
会場:B3教育棟2階,第5会場(予定)
より多くの会員に「日本地質学会の会員として,学術大会に参加したい! 発表したい!」と思われる大会にしたいと行事委員会は考えています.セッション構成,参加費,院生・ポスドク等の若手やシニアの活躍・交流の場の創設など,さまざまな観点から検討する必要があります.
行事委員会は,今年度中に学術大会の改革案(ブループリント)を作成する予定です.それにむけて,会員の皆様からアイディアや他学協会等の情報を頂き,自由闊達な意見交換をしたいと考え,どなたでも参加できるオープンディスカッションの機会を設けます.大会最終日の夜間ですが,本学会を愛する皆様の積極的なご参加をお待ちしております.
詳しくは、http://www.geosociety.jp/osaka/content0048.html
2012.7.23更新 全体日程表掲載しました!
■■■
全体日程表を掲載いたしました.各日の日程については近日中にアップいたします.
閲覧はこちらから
2012.7.18更新 プレス発表を希望される方へ
■■■
大阪大会での講演や行事について,9月上旬にプレス発表を行う予定です. 例年多数のメディアに取り上げられ,会員の研究成果が大いに注目されています.大阪大会で発表される予定の案件で,学会からのプレス発表をご希望の方は,7月31日(火)までに学会事務局にご連絡願います.全ての案件をプレス発表することはできませんが,社会への情報発信として特筆すべき成果は積極的に公表して行きたいと考えております.大阪大会の成功と地球科学の成果のアピールのため,ご協力よろしくお願い申しあげます.
プレス発表(投げ込み):9月上旬
連絡先:日本地質学会事務局 journal@geosociety.jp
(日本地質学会広報委員会)
2012.7.17更新 緊急展示の申込について
■■■
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害調査報告や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コーナー」を設けます.ポスター展示を希望する方は,8月31日(金)までに次の内容をご連絡ください.
詳しくは、こちらから
2012.7.11更新 できるだけ堺市内に宿泊して下さい。
■■
堺市内宿泊施設の延べ宿泊数によって堺市からの助成金が決まりますので、宿泊予定の方は、できるだけ堺市内に宿泊していただきますようお願いします。 宿泊予約・関連情報はこちらから
2012.7.2更新 講演申込:締切延長 7/4(水)17時!
■■■
日本地質学会第119年学術大会(大阪大会)「都市から発信する地質学」
多くの方々にご講演いただくため、講演申込の締切を延長いたしました。
お申し込みをお待ちしています。(行事委員会)
オンライン講演申込締切:7月4日(水)17時厳守(郵送分は締切ました)
2012.6.28更新 講演申込を予定しているが、まだ入会手続きをされていない方へ
■■■
至急、入会申込書を学会事務局宛に郵送して下さい(7/3必着)。
WEB画面から講演申込操作は現時点でも可能です。入力の際、会員番号欄は空欄のまま操作を進めて下さい。また会員種別欄では『入会申込中』を選択して下さい。
申込締切時点(7/3)で入会申込書が到着していないと、申込が受理されてませんので、必ず入会申込書を郵送して下さい。
2012.6.13更新 大阪大会関連情報-0613
■■■
国際ワークショップ「The Geology of Japan」を開催します。
復旧復興にかかわる調査・研究事業の成果発表会を開催します。
詳細は、こちらから
2012.6.13更新 宿泊・観光関連関連のリンクを追加しました
■■■
学会では宿泊予約の受付はいたしませんが、関連のWEBサイトをご紹介いたします。
詳細は、こちらから
2012.5.28更新 参加登録の受付を開始しました。
■■■
参加登録の受付を開始しました。
8月17日(金)18:00 締切(郵送:8/10締切)です。
※会員区分等によってページが異なりますので、該当するページよりお申込ください。
登録は、こちらから
2012.5.28更新 講演要旨の受付を開始しました。
■■■
講演要旨の受付を開始しました。
7月3日(火)17:00 締切(郵送:6/27締切)です。
登録は、こちらから
2012.4.19更新 シンポジウム、セッション決定!
■■■
シンポジウム,トピック/レギュラーセッションが決まりました。
詳しくは、こちらから
2012.4.19更新 大阪大会巡検の見どころを掲載しました。
■■■
各コースの見どころはこちらから
2012.2.27更新 トピックセッション募集(2012/3/12締切)
■■■
トピックセッション募集締切:2012年3月12日(月)*今年もシンポジウムの公募は行いません。ご注意ください。
詳しくは、こちらから(またはNews誌15-1月号4ページ参照)
2012.2.22更新 日本地質学会第119年学術大会(大阪大会)開催
■■■
日本地質学会は,近畿支部の支援のもと,大阪府立大学中百舌鳥キャンパス(堺市)をメイン会場として2012年9月15日(土)〜17日(月)に開催いたします.
申込要領・発表要領
セッション・講演の申込要領・発表要領
注:シンポジウムに関しては、シンポジウムのページを参照して下さい。
講演申込・講演要旨:
5月28日(月)10時〜7月3日(火)17時(郵送 6月27日(水) 必着)
締切延長 7月4日(水)17時 締切りました。
↓
■シンポジウム一覧はこちら■
■セッション一覧はこちら■
募集要領
セッションの口頭・ポスター発表を下記要領で募集します.できる限りオンラインでの申し込みにご協力下さい.やむを得ず郵送で申し込む場合は、郵送用の発表申込書(PDF)に必要事項を記入の上,返信用ハガキ(自分宛),保証書・同意書,講演要旨原稿とともに6月27日(水)必着で行事委員会宛にお送り下さい.なお,発表セッションや会場・時間等は,各セッションの世話人の協力を得て行事委員会が決定します.プログラム編成作業が終わり次第,発表セッションや日時等をe-mailで(郵送の場合は返信ハガキで)通知します
(1)セッションについて
今大会では11件のトピックセッションと20件のレギュラーセッション,およびアウトリーチセッション(新設)を用意しました.各セッションの詳細については「セッション一覧」をご覧下さい.
(2)発表に関する条件・制約
1)会員は全32セッションのうち1つまたは複数(下記参照)に発表を申し込むことができます(発表申込者=発表者とします).
非会員は発表を申し込めませんので,発表を希望する場合は必ず6月27日(水)までに入会手続きを行って下さい(入会申込書が届いていない場合は発表申込を受理しません).共催団体の会員は共催セッションに限り発表申込が可能です.
2)トピック・レギュラーセッションでは,口頭発表あるいはポスター発表のいずれかの方法で,1人1題に限り発表することができます.ただし,発表負担金(1,500円)を支払うことでもう1題の発表が可能です(最大2題).この場合,同一セッションで2題発表することも,異なる2つのセッションで1題ずつ発表することも可能です.ただし,この制約はアウトリーチセッションには適用しません.
3)共同発表(複数著者による発表)を行う場合は,上記「1人1題,ただし発表負担金支払いによりもう1題可」の制約を発表者(=発表申込者)に対して適用します.その際,発表者は筆頭でなくても構いません(筆頭者に会員・非会員等の条件はありません).講演要旨では,発表者氏名を下線(アンダーライン)表示にして下さい.講演要旨作成についての詳細はこちら。
(3)アウトリーチセッション(新設)
会員による研究成果の社会への発信(アウトリーチ活動)を学会として力強くサポートするために,今大会からトピック・レギュラーと並ぶ第三のカテゴリー「アウトリーチセッション」を設けます.アウトリーチに関心のある会員からの積極的なお申し込みをお待ちしております.
1)本セッションでは,トピック・レギュラーと同様の手続きで演題登録・要旨投稿を行っていただきます.要旨の校閲もトピック・レギュラーと同様に行います.要旨は講演要旨集に収録し,正式な学会発表として扱います.
2)本セッションの発表には,シンポジウム同様上記の発表数に関するルール(発表者1人1題,ただし発表負担金を支払えばもう1題発表可)を適用しません.例えば,レギュラーセッションで1題発表する会員がアウトリーチセッションでもう1題発表する場合,発表負担金は不要です.
3)発表はポスター形式(後述)のみとし,市民講演会会場で実施します(大阪府立大学中百舌鳥キャンパスUホール白鷺のエントランスロビー:口頭発表会場より徒歩1分).市民講演会の前後各1時間をポスターコアタイムとします.
4)市民には講演要旨のコピーを配布します.発表者が希望すれば,学会が配布する要旨コピーとは別にわかりやすい資料を配布していただいても構いません(ただし発表者負担).
5)公開シンポジウムに参加する市民や会員も見られるように,ポスターは会期中(3日間)掲示できます.
6)会場スペース等の都合から,募集件数は10件程度とします.募集件数を上回る応募があった場合は行事委員会にて採否を検討します.
7)優秀ポスター賞の選考対象になります.
(4)招待講演(トピックセッションのみ)
トピックセッションの世話人は,会員・非会員を問わず招待講演を依頼することができます(締め切りました).招待講演者を「セッション一覧」に示しました.招待講演についても申込期日までに一般発表と同様にお申し込みいただく必要があります.非会員の場合は,代表世話人が取りまとめてオンライン入力が可能です(詳細については学会事務局にお問い合わせ下さい).非会員招待講演者に限り参加登録費を免除します(講演要旨集は付きませんので,必要な場合は別途購入していただきます).
(5)発表申込方法
1)オンライン申込は大阪大会HPにアクセスし,オンライン入力フォームに従って入力して下さい.
2)発表方法については,「口頭」「ポスター」「どちらでもよい」のいずれかを選択して下さい(一部セッションはポスターのみ).申込締切後の変更はできません.※会場の都合のため,発表方法(口頭/ポスター)の変更をお願いすることがあります.その場合は代表世話人が連絡します.
3)発表題目と発表者氏名は,必ず登録フォームと講演要旨の両方を一致させて下さい.
4)共同発表の場合は全員の氏名を明記して下さい.共同発表の場合,講演要旨中の発表者氏名を下線(アンダーライン)表示にして下さい.
5)トピック・レギュラーセッションの場合,発表希望セッションを第2希望まで選んで下さい.
6)関係する一連の発表があるときは,必要に応じて発表順希望等をコメント欄に入力して下さい(ご希望に添えない場合があります)
(6) 講演要旨原稿の投稿について
講演要旨原稿はA4判1枚(フォーマット参照)とし,PDFファイルの電子投稿により受け付けます.印刷仕上がり0.5ページ分です(1ページに2件分を印刷).原稿はそのまま版下となり,70%程度に縮小印刷されます.文字サイズ,字詰め,に注意して下さい.やむを得ず郵送する場合は,オリジナルか鮮明なコピーを1枚郵送して下さい(差し支えなければ折りたたみ可).FAXやe-mailでの投稿は受け付けません.
発表要領(シンポジウムについてはこちら)
(1)口頭発表
1)シンポジウムの発表時間は,世話人と発表者による相談の上,世話人の裁量で決定します.
2)セッションの発表時間はトピック,レギュラーとも1題あたり15分です(討論時間3分を含む).発表者は,討論など持ち時間を十分考慮し,余裕を持って発表を行って下さい.
3)各会場にはWindowsパソコン(OS:Windows 7, Power Point 2000〜2010対応)を用意します.パワーポイントを使用する方は,PCセンターにて正常に動くことを事前に確認して下さい.パワーポイントを使用しない方やMacを使用される方はPCセンターにご相談下さい.なお,35mmスライドプロジェクターは使用できません.
(2)ポスター発表
1)1題について1日間掲示できます(アウトリーチセッションは3日間掲示可,上記).ポスターコアタイムでは,発表者は必ずポスターの説明を行って下さい.ポスター設置・撤去等については本誌8月号に掲載予定のプログラム記事をご覧下さい.ボード面積は1題あたり縦210 cm,横120 cmです.※今大会では従来よりも広い面積を利用可能です.
2)発表番号,発表タイトル,発表者名をポスターに明記して下さい.
3)ポスター会場では,コンピューターによる発表や演示等も許可しますが,機材等は発表者がすべて準備して下さい.また,電源は確保できませんので,必要であれば予備のバッテリーを用意して下さい.発表申込の際に機器使用の有無や小机の必要性等をコメント欄に記入し,事前に世話人にご相談下さい.
4)運営規則第16条2項(8)により,優れたポスター発表に対して「日本地質学会優秀ポスター賞」を授与します.詳細についてはプログラムに掲載します.
(3)発表者の変更
あらかじめ連記されている共同発表者内での変更は認めますが,必ず事前に行事委員会へ連絡して下さい.この場合も発表者については発表に関する条件・制約を適用します.
(4)口頭発表の座長依頼
各会場の座長を発表者にお願いすることがあります.あらかじめ世話人から座長依頼を差し上げますが,その際にはぜひお引き受けいただきたく,ご協力をお願いします.
日程・プログラム
全体日程・プログラム
9/14(金)
巡検
9/15(土)
セッション発表(口頭,ポスター),表彰式,記念講演会,懇親会
9/15(土)〜17(月)
地質情報展
9/16(日)
シンポジウム(午前),セッション発表(口頭,ポスター),ランチョン,国際ワークショップ(午後),市民講演会(午後),夜間小集会,関連普及行事・生徒「地学研究」発表会,就職支援プログラム
9/17(月・祝)
シンポジウム(午前),セッション発表(口頭,ポスター),ランチョン,,関連普及行事・教員向け巡検(午後),夜間小集会
9/18(火)〜19(水)
巡検
■全体日程表
画像をクリックするとpdf版がダウンロードできます.
■各講演プログラム 8/23掲載
それぞれの日程をクリックするとpdf形式でご覧になれます.
9/15(土)
口頭発表 ポスター発表
9/16(日)
口頭発表 ポスター発表
9/17(月)
口頭発表 ポスター発表
▶シンポジウム一覧 ▶セッション一覧
▶ランチョン・夜間小集会一覧
要旨のみの予約販売
講演要旨集のみの予約頒布
申込締切
オンライン: 8 月17日(金)18:00,
FAX・郵送: 8 月10日(金)必着
■ WEB参加登録画面はこちら ■
大会参加費には講演要旨集の代金が含まれていますので,大会に参加される場合は別途購入の必要はありません.ただし,名誉会員・50年会員,非会員招待者,学部学生(会員・非会員問わず)には講演要旨集が付きませんのでご希望の方は,別途ご購入下さい.大会に参加されない方ならびに参加する方が複数の講演要旨集を購入される場合の予約頒布です.要旨集の受け取り方法には,(1)大会後に送付,(2)会場で受取り,があります.(1)の場合は,別途送料が必要です.(2)の場合は,大会受付にて確認書の提示が必要となりますので,必ずご持参下さい.残部があれば大会当日あるいは大会後にも頒布します.売り切れの場合はご容赦下さい.
事前予約(/冊)
当日販売(/冊)
会員
3000円
4000円
非会員
4000円
5500円
*「大会後に送付」の場合の送料は以下の通りです.
送料:1冊 500円,2冊 600円,3冊 800円,4冊 1,000円,5冊 1,200円
表彰式・記念講演会
学会各賞表彰式・記念講演
日程:9月15日(土)15:30〜17:30
会場:大阪府立大学中百舌鳥キャンパスUホール白鷺
15:30-15:40 兪 剛民大韓地質学会会長ご挨拶
15:40-15:50 奥野武俊大阪府立大学学長ご挨拶
15:50-16:30 新名誉会員・50年会員顕彰式,各賞授与式
16:40-16:55 日本地質学会小澤儀明賞受賞スピーチ:
山本伸次会員「とことんやってみる−変態科学と私−」
17:00-17:30 日本地質学会賞受賞講演:木村 学会員「地質学の自然観」
(初日の優秀ポスター賞の表彰式も同会場で行います)
参加登録費
参加登録費
申込締切
オンライン: 8 月17日(金)18:00,
FAX・郵送: 8 月10日(金)必着
■ WEB参加登録画面はこちら ■
当日会場受付での混雑緩和のため,事前に参加登録申込をお願いします.大会参加登録およびそれに伴う参加費は,全ての参加者(巡検のみの場合も)に必要な基本的なお申し込みです.ただし,会員が同伴する非会員の配偶者ならびに子供(以下,同伴者)については参加登録申込の必要はありません(同伴者の懇親会・巡検・お弁当の申込も受け付けます).申込は,Web上,FAX・郵送いずれの場合も,会員と同伴者の2名まで一括申込が可能です.
講演要旨集が不要の場合でも割引はありません.参加登録費無料の方(名誉会員・50年会員,非会員招待者,学部学生)には講演要旨集は付きません.ご希望の方は別途購入してください.
事前申込
当日払い
備考
正会員
7500円
9500円
講演要旨付き
院生割引適用正会員
4500円
6500円
講演要旨付き
学部制割引適用正会員・名誉会員・50年会員・非会員学部学生・非会員招待者
無料
無料
講演要旨は付きません
非会員(一般)
12500円
15000円
講演要旨付き
非会員(院生)
7000円
9500円
講演要旨付き
*会員資格は『正会員』のみであり,割引会費の申請をした方についてのみ,割引会費が適用されています.
*大会に参加できなかった場合は,大会後に講演要旨集をお送りします.参加登録費用の返却はいたしませんのでご了承下さい.
*トピックセッションの共催・協賛団体に会員として所属する方の参加登録費は正会員と同額になります.
*追加で講演要旨集をお申し込みされる場合には,参加登録と合わせてお申し込み
ください.
地学教育・普及・関連行事
地学教育・普及・関連行事
■ 地質情報展2012おおさか(9/15-17)
■ 市民講演会 (9/16)
■ 理科教員向け見学旅行 (9/17)
■ 小さなEarth Scientistのつどい(9/16)
■ 理科・地学教科書展示解説(9/15-17)
■ 東日本大震災復旧復興にかかわる調査・研究事業報告 ポスター展示(9/15-17)
■ 国際ワークショップ:The Geology of Japan(9/16)
■ 就職支援プログラム(9/16)
■ 学術大会の改革:オープンディスカッション(9/17)
※各行事の画像をクリックすると,大きな画像,またはPDFをダウンロードできます.
地質情報展2012おおさか:過去から学ぼう 大地のしくみ
日時 2012年9月15日(土)〜17日(月・祝)【入場無料】
9月15日(土) 13:00〜17:00
9月16日(日) 9:30〜17:00
9月17日(月) 9:30〜16:00
会場:大阪市立自然史博物館・花と緑と自然の情報センター
→会場アクセスはこちら
主催:一般社団法人日本地質学会・産業技術総合研究所地質調査総合センター・大阪市立自然史博物館
内容:大阪大会に合わせ,地質調査総合センターが有する各種地質情報から,大阪府及び周辺の地質現象と地震・津波・地盤災害について展示パネルや映像それに標本を使って紹介します.また,小さなお子さんにも楽しく地学を学んでもらうために石割や化石レプリカ作成などの体験学習コーナーを用意します.
問合せ先:産業技術総合研究所地質調査総合センター
渡辺真人・今西和俊 TEL:029-861-3836 e-mail:johoten2012jimu-ml@aist.go.jp
詳しくは専用サイトへ http://www.gsj.jp/event/2012fy-event/osaka2012/index.html
ページトップに戻る
市民講演会 「地震・津波・地盤災害:知ること,伝えること」
日時 2012年9月16日(日)14:30〜17:00
会場 大阪府立大学中百舌鳥キャンパスUホール白鷺
・金田義行「将来の地震津波災害にどう備えるか 〜過去の巨大地震大津波からの教訓〜」
・飯尾能久「内陸地震はどうして起こるのか?」
・三田村宗樹「近畿の地盤特性と地震時の挙動」
【訂 正】すでに配布済みの市民講演会のポスター・チラシの問い合わせ先(電話番号)が間違っておりました。正しくは下記の通りですので、よろしくお願い申し上げます。関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
問合せ先:大阪府立大学 石井和彦
Tel 072-254-9729
Eメール ishii[at]p.s.osakafu-u.ac.jp [at]の部分を@と差し替えてください
詳細は、こちらもご参照ください(大阪府立大サイト)
※ページトップに戻る
小さなEarth Scientistのつどい〜第10回 小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜
後援:大阪市教育委員会,堺市教育委員会,大阪府,大阪市,堺市,NHK大阪放送局,毎日新聞社,朝日新聞社,読売新聞大阪本社,一般社団法人全国地質調査業協会連合会,関西地質調査業協会
日本地質学会地学教育委員会では,地学普及行事の一環として,地学教育の普及と振興を図ることを目的として,学校における地学研究を紹介する「地学研究」発表会をおこなっています.大阪大会でも,小・中・高等学校の地学クラブの活動,および授業の中で児童・生徒が行った研究の発表を募集いたします.大阪府内,また関西地方の学校,さらには全国の学校の参加をお待ちしています.会場は研究者も発表するポスター会場内に,特設コーナーを用意いたします.同時並行で研究者の発表も行われますので,児童・生徒同士のみならず,研究者との交流もできます.この会を通じて生徒,研究者,市民の交流が進み,地質学,地球科学への理解が深まって,未来を担う生徒たちの学習意欲への良い刺激と励みになることを願っております.
日時 2012年9月16日(日) 9:00〜15:30
場所 大阪大会ポスター会場(大阪府立大学学術交流会館)
参加予定校(7月18日現在,12校,15件)
高校(10校)
・兵庫県立加古川東高等学校地学部(3件)
・(香川県)高松第一高等学校
・滋賀県立彦根東高等学校
・大阪府立岸和田高等学校天体部(2件)
・大阪府立清水谷高等学校自然科学部
・大阪府立港高等学校パソコン同好会理科班
・大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎
・大阪府立堺東高校地学部
・城星学園高等学校理科部
・私立水戸葵陵高等学校
・早稲田大学高等学院理科部地学班
中学(2校)
・大阪市立新北島中学校 科学部
・栃木県那須烏山市立下江川中学校特設科学部
問い合わせ・申込先:
日本地質学会地学教育委員会(担当 三次)
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F
TEL:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156 e-mail:main@geosociety.jp
申込書式はこちらからダウンロードしてください
■WORD形式 ■PDF形式
*過去の発表会の様子や「優秀賞」受賞発表はこちらから
ページトップに戻る
理科教員向け巡検「大阪の津波碑と地盤沈下対策」
日時 2012年9月17日(月)午後
参加対象:主に小中高理科教員
参加費・申込等くわしくは巡検一覧J班をご参照ください
**申込は、大会参加登録システムより、他の見学旅行と同様にお申し込みください**
>>参加申込画面はこちらから
*過去の巡検の様子はこちらから
ページトップに戻る
理科・地学教科書展示解説
みなさん,地学の教科書が変わったことをご存知ですか?:新旧の地学教科書・理科教科書を展示します
学習指導要領の改訂(小学校・中学校は2008年,高等学校は2009年)をうけて,小学校の理科教科書は2011年,中学校・高等学校の理科教科書は本年度(2012年)から新しくなりました.このような動きに合わせ,今年の大阪大会ではトピックセッション「新学習指導要領の実施で地学教育はどのように変わるか?」が行われます.このトピックセッション企画に連動して,小・中学校の新旧の理科教科書,高等学校の新旧の地学教科書や実習帳を展示します.日頃,このような教科書・実習帳を見る機会は少ないと思いますので,ぜひご覧いただければと存じます.
展示期間:2012年9月15日〜17日
場所:大阪大会ポスター会場(大阪府立大学学術交流会館)
展示資料
・ 小学校の新旧理科教科書(数社)
・中学校の新旧理科教科書(数社),
・ 高等学校の新課程「地学基礎」の教科書(全社)
・ 高等学校の旧課程「地学Ⅰ」・「地学Ⅱ」の教科書(数社)
・ 高等学校の地学実習帳(埼玉・大阪など)
(日本地質学会地学教育委員会)
ページトップに戻る
就職支援プログラム募集
就職支援プログラム
大阪大会就職支援プログラム
本年も、表記「就職支援プログラム」を開催することになりました。本プログラムは,学会に参加される学生・院生および大学教員の会員,ならびに大阪府立大学等の学生・院生・関係者らを対象に,本会賛助会員をはじめとする関連業界との情報交換を行う場を提供しようというものです.
つきましては、ぜひご参加いただきますようご案内をいたします。
日 程 2012年9月16日(日)14:30-18:00(*時間帯は若干変更になる場合があります)
場 所 大阪府立大学B3棟3F 301〜303
主 催 一般社団法人日本地質学会
内 容 主催者等 挨拶・紹介、参加各社による数分のプレゼンテーション.
参加各社の個別説明会(パネル、配布資料等をご用意ください).
対 象 大阪大会に参加する学生・院生および大学教員等の会員
大阪府立大学等の学生・院生および教員等
出展予定企業(9月4日現在):
・石油資源開発株式会社
・川崎地質株式会社
・太平洋セメント株式会社
・株式会社ダイヤコンサルタント
・ジーエスアイ株式会社
・株式会社地圏総合コンサルタント
・地熱エンジニアリング(株)
▶出展申込用紙(word) ▶出展申込用紙(PDF)
▶ 2011年水戸大会:就職支援プログラムの様子はこちらから。
学術大会の改革:オープンディスカッション
学術大会の改革:オープンディスカッション
学術大会の改革:オープンディスカッション
日時:9月17日(月)18:00〜19:30
会場:B3教育棟2階,第5会場
大阪大会の発表申込件数は岡山大会(2009年),富山大会(2010年)とほぼ同程度でしたが(2011年水戸大会は日本鉱物科学会との共催),発表者実数は減少しています(昨年大会から発表負担金を支払うことによりセッションで2件発表可能になっているため).学会員数の漸減傾向が続いていることが発表者数の減少の理由として大きいと推察していますが,それ以外の影響もあるかもしれません.例えば,レギュラー・トピック合わせて例年30以上のセッションを用意していますが,それらは現代の地質学を十分にカバーしているでしょうか? 魅力的でしょうか?
より多くの会員に「日本地質学会の会員として,学術大会に参加したい,発表したい」と思われる学術大会にしたいと行事委員会は考えています.それが会員の研究活動の活性化につながり,ひいては本学会の活性化と地質学のますますの発展につながるはずと考えます.セッション構成,参加費,院生・ポスドク等の若手やシニアの活躍・交流の場の創設など,さまざまな観点から検討する必要があると考えています.
行事委員会は,今年度中に学術大会の改革案(ブループリント)を作成する予定です.それにむけて,会員の皆様からアイディアや他学協会等の情報を頂き,自由闊達な意見交換をしたいと考え,どなたでも参加できるオープンディスカッションの機会を設けます.
行事委員長が考える「目指したい方向性」は3つあります.
1) 「地質学会の学術大会で面白い(または重要な)セッションをやっている,参加したい,あそこで発表したい,参加者と交流したい」と思われるようなセッションを複数立てたい.
2) 入会した院生やポスドクが企業等に就職した後も「参加したい」と思うような学術大会にしたい.
3) 職場をリタイアしたが「後続のために,市民のために,学会のために,地質学の発展のために何かしたい」と思っているベテランが活躍できる場をつくりたい.シニアも参加しやすい大会にしたい.
大会最終日の夜間ですが,本学会を愛する皆様の積極的なご参加をお待ちしております.
<問い合わせ先>
日本地質学会行事委員長 星 博幸
TEL: 0566-26-2656, hoshi@auecc.aichi-edu.ac.jp
大会趣旨
大阪大会趣旨
2012年大阪大会は,一般社団法人日本地質学会・公立大学法人大阪府立大学の共催により
「都市から発信する地質学」
をキャッチフレーズに開催いたします.
関西大都市圏で開催される大阪大会では,2011年東日本大震災とその後の一般社会も含むさまざまな動きを背景に,内陸地震・海溝型地震・地盤災害などの自然災害と防災,さらに一般社会への普及などをテーマに含むシンポジウムや市民向け講演会・地質情報展などの普及行事を企画しています.学術発表は,各専門部会等から提案された20件のレギュラーセッションと11件のトピックセッション,2件の市民公開シンポジウムを準備しています.今大会から新たに「アウトリーチセッション」というカテゴリーを設け,市民に向けての研究成果紹介(会員によるアウトリーチ活動)を学会として力強くサポートします(正式な学会発表扱いになります).また今年も小・中・高校生徒「地学研究」発表会をポスター会場で行います.
各種申込は,従来と同様の参加登録システムを利用します.お支払いは銀行振込またはクレジットカードによる支払いが可能です.発表についても昨年同様,演題登録システムを利用してweb(オンライン)上での申込を受付けます.なお,大会準備がスムーズに運ぶよう,締切日の厳守をお願いいたします.
本大会の新しい試み
1) 午前の部の終了時間を11:45にします.これにより,昼食およびランチョン(2日目,3日目)の時間確保をはかります.
2) ポスター発表の使用可能面積を大幅に拡大します(高さ210 cm,幅120 cm).これにより,思い切ったポスターレイアウトが可能になります.また,スペースに余裕ができるため,隣のポスターとの干渉も少なくなります.
3) 新設のアウトリーチセッションでは,会員が市民に対して研究成果等を解説し,地質学のアウトリーチを推進します.今回,11題の発表申込がありました.
4) ミーティングルームを用意します(口頭発表会場:B3棟3階).少人数での打ち合わせ等に自由にご利用ください(貸し切りではありません).ミーティングルームでは,無線LANを各自のパソコンでご利用いただけます..
5) 広い無線ネット利用可能エリアを確保します.口頭発表会場(B3棟)の休憩室とミーティングルーム,ポスター発表会場,Uホール白鷺エントランスホールでは,無線LANを各自のパソコンでご利用いただけます.無線LANのご利用方法については、休憩室等に掲示する予定です.
就職支援(2011水戸大会の様子)
第118年水戸大会:就職支援プログラム開催報告(2011.9.10開催)
最近の就職活動では、インターネット等で情報収集するのが普通になり、職場の状況をよく知る方々と直にお話ができる機会は多くありません。地質学会の就職支援プログラムは、就職希望の学生・院生と採用を希望される民間企業・団体、研究機関とが、直接か情報交換できる場です。
本プログラムは水戸大会で第5回目になります。今回も、民間企業に加えて、研究機関から産業技術総合研究所が参加されました。9月10日午後2時から5時まで、まず企業説明会形式で参加企業5社と産総研からのプレゼンテーションがあり、その後、各社・機関の出展ブースで詳しい説明や質疑応答に参加していただきました。今年の会場は発表会場から離れ、必ずしも立ち寄りやすくない場所であったにもかかわらず、各ブースでは終了時間の間際まで、熱心に説明を受ける学生会員の姿が見られました。
このプログラムは来年以降も継続の予定ですので、就職希望の学生・院生の皆様には、ぜひご利用いただきたいと思います。特に、学生を指導されている教官の方々にも、会場に足を運んでいただき、企業の採用状況について情報収集していただくとともに、学生・院生の皆様に積極的な参加を呼びかけていただくようお願いいたします。
最後に、本行事に参加いただいた企業5社と産総研の皆様、企画にご協力をいただいた賛助会員、関連企業の皆様、および大会準備委員会・行事委員に、改めて御礼申し上げます。
各社によるプレゼンテーション
各社ブースの様子
参加企業・団体(敬称略):株式会社クレアリア・(独)産業技術総合研究所・石油資源開発株式会社・関東天然瓦欺開発株式会社・ジーエスアイ株式会社・株式会社日さく
(担当理事:運営財政部会 向山 栄)
会場・交通
会場・交通
★★大阪府立大学キャンパスマップ(会場案内図)はこちら★★
セッション発表,シンポ,国際ワークショップ,
表彰式・記念講演会,関連普及行事
生徒「地学研究」発表会,市民講演会
大阪府立大学中百舌鳥キャンパス
(堺市中区学園町1-1)
地質情報展
大阪市立自然史博物館・花と緑と自然の情報センター
(大阪市東住吉区長居公園1-23)
■大阪府立大学中百舌鳥キャンパスの施設位置図及び大学までの公共交通機関は,
大阪府立大学のホームページhttp://www.osakafu-u.ac.jp/access/index.htmlを参照して下さい.
大阪府立大学中百舌鳥キャンパスの最寄り駅
・南海高野線「中百舌鳥駅」もしくは,地下鉄御堂筋線「なかもず駅」5号出口から南東へ約1000m.
・南海本線「堺駅」から南海バス(南口のりば、北野田駅前行31,32,32-1系統)で約24分,「府立大学前」下車
・JR阪和線・南海高野線「三国ヶ丘駅」から南海バス(310号線沿いバス停、北野田駅前行31,32,32-1系統)で約14分,「府立大学前」下車
・南海高野線「白鷺駅」から南西へ約500m.
JR新幹線新大阪駅,伊丹空港,関西空港からのアクセスは以下の通りです.
・新大阪駅--<地下鉄御堂筋線>--なかもず駅
・伊丹空港--<大阪モノレール>--千里中央--<北大阪急行・地下鉄御堂筋線>--なかもず駅
・伊丹空港--<バス>--梅田駅(大阪駅)--<地下鉄御堂筋線>--なかもず駅
・伊丹空港--<バス>--なんば駅--<南海高野線>--中百舌鳥駅
・伊丹空港--<バス>--天王寺駅(あべの橋)--<地下鉄御堂筋線>--なかもず駅
・関西空港--<JR関西空港線・阪和線>--三国ヶ丘駅--<南海高野線>--中百舌鳥駅
・関西空港--<バス>--中百舌鳥駅
※大阪府立大学中百舌鳥キャンパスは駐車スペースが少ないため,乗用車でのご来訪は極力ご遠慮ください.
※宿泊施設は南海本線堺駅周辺,および大阪市内にあります.(南海本線と南海高野線の違いにご注意ください)
■大阪市立自然史博物館・花と緑と自然の情報センターの施設位置図及び公共交通機関は,
http://www.ocsga.or.jp/n-jyoho/access/index.html(ご利用案内> 交通アクセス)を参照して下さい.
大阪市立自然史博物館・花と緑と自然の情報センターの最寄り駅
地下鉄御堂筋線「長居駅」3号出口より東へ800m
JR阪和線「長居駅」東出口より東へ1,000m
■大阪府立大学キャンパスマップ(キャンパス内:会場案内図はこちら.PDF版をダウンロードできます.)
※会場内で無線LANをご利用頂けます:休憩室とミーティングルーム,および,ポスター会場,Uホール白鷺エントランスホールでは,無線LANを各自のパソコンでご利用できます.無線LANのご利用方法については、休憩室等に掲示する予定です.
※休憩室の他にB3棟3階にミーティングルームを用意しましたので,少人数での打ち合わせ等に自由にご利用ください.ただし,貸し切りではありません.
申込先・締切一覧
各種申込先・締切一覧
WEB
FAX・郵送
申込・問い合せ先
講演申込
7/3(火)17時
7/4(水)17時延長
6/27(水)必着
詳細
行事委員会
講演要旨原稿提出
7/3(火)17時
7/4(水)17時延長
6/27(水)必着
詳細
行事委員会
WEB
FAX・郵送
事前参加登録
8/17(金)18時
8/10(金)必着
詳細
学会事務局
巡検(教員用巡検J班含む)
8/17(金)18時
8/10(金)必着
詳細
学会事務局
懇親会
8/17(金)18時
8/10(金)必着
詳細
学会事務局
追加講演要旨
8/17(金)18時
8/10(金)必着
詳細
学会事務局
お弁当
8/17(金)18時
8/10(金)必着
詳細
学会事務局
託児室
8/24(金)
-------
詳細
現地事務局
生徒地学研究発表会
(小さなEarth Scientistのつどい)
7/17(火)
-------
詳細
地学教育委員会
ランチョン・夜間小集会
6/27(水)
-------
詳細
行事委員会
就職支援プログラムへの出展
8/10(金)
-------
詳細
学会事務局
一次締切
最終締切
広告協賛
-------
7/27(金)18時
詳細
現地事務局
企業展示への出展
6/29(金)18時
7/27(金)18時
詳細
現地事務局
書籍・販売ブース
6/29(金)18時
7/27(金)18時
詳細
現地事務局
問い合わせ先
大阪大会問い合わせ先
■日本地質学会行事委員会 / 地学教育委員会 / 学会事務局
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目8-15 井桁ビル6F
(地質学会事務局気付)
TEL:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156
e-mail:main@geosociety.jp
■行事委員会■(2012年4月現在)
委員長
星 博幸(担当理事)
委 員
内野隆之(地域地質部会)
岡田 誠(層序部会)
水上知行(岩石部会)
須藤 斉(古生物部会)
内山 高(第四紀地質部会)
片岡香子(堆積地質部会)
荒井晃作(海洋地質部会)
須藤 宏(応用地質部会)
長谷川 健(火山部会)
川村喜一郎(現行地質過程部会)
河村知徳(石油,石炭関係)
坂本正徳(情報地質部会)
矢島道子(地学教育関係)
田村嘉之(環境地質部会)
氏家恒太郎(構造地質部会)
■日本地質学会第119年学術大会現地事務局
(株式会社アカデミック・ブレインズ内)担当:田中
〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1天満橋千代田ビル2号館9階
TEL:06-6949-8137 FAX:06-6949-8138
e-mail:gsj2012@academicbrains.jp
■実行委員会組織
委 員 長:前川寛和(TEL:072-254-9734, maekawa@p.s.osakafu-u.ac.jp)
副委員長:宮田隆夫(miyata@kobe-u.ac.jp)
事務局長:石井和彦(TEL:072-254-9729, ishii@p.s.osakafu-u.ac.jp)
事務局補佐:三田村宗樹(TEL:06-6605-2592, mitamura@sci.osaka-cu.ac.jp)
普 及:川端清司(TEL:06-6697-6221, kawabata@mus-nh.city.osaka.jp)
巡 検:奥平敬元(TEL:06-6605-3181, oku@sci.osaka-cu.ac.jp)
巡検案内書:竹村厚司(TEL:0795-44-2206, takemura@hyogo-u.ac.jp)
会場・展示会場・機器・懇親会:石井和彦(TEL:072-254-9729, ishii@p.s.osakafu-u.ac.jp),現地事務局((株)アカデミック・ブレインズ(内)) 担当:田中(TEL:06-6949-8137,FAX:06-6949-8138, e-mail:gsj2012osaka@academicbrains.jp)
男女共同参画企(託児室):きらら保育園プティット堺ルーム(予定) 問合せ先 現地事務局 ((株)アカデミック・ブレインズ(内)) 担当:田中(TEL:06-6949-8137,FAX:06-6949-8138.e-mail:gsj2012osaka@academicbrains.jp)
申込方法と支払について
各種申込とお支払について
(1)申込方法
オンラインによる参加登録申込等を受付けます.申込は昨年同様,学会の参加登録システムをご利用いただきます.大会専用参加登録システム(会員・非会員にかかわらずどなたでも申し込み可)または専用申込書(FAX・郵送用)をご利用の上,お申し込み下さい.参加登録・懇親会・追加講演要旨・巡検・お弁当を同時に申込むことができます.なお,学会を通じての宿泊・交通手配の斡旋は行いません.宿泊や交通については各自で手配願います.
(a)大会専用参加登録システム(オンライン)による申込
1)大会HP画面左のメニュー「参加登録」をクリックして下さい.
2)申込画面の入力欄に氏名と会員番号を入力するだけで,学会に登録されている会員情報(所属・住所等)が表示され,続けて参加登録を行うことができます.
3)申込み完了後,「申込確認メール」および「ご請求メール」が登録のメールアドレスへ配信されます.内容を必ずご確認下さい.
4)支払い方法について,「銀行振込」を選択された方は,「ご請求」メールを確認の上,指定の金融機関よりお振込み下さい.また,クレジットカードもご利用頂けます.「クレジット決済」を選択の場合は,ご利用のカード会社の期日に合わせて,口座より引き落としとなります.クレジットカード会社からの明細には「日本地質学会(ニホンチシツガッカイ)」と表示されます.
5)締切後,参加証・各種クーポンを発送します(9月上旬発送予定).大会開催10日前までには参加者の皆様のお手元に届くようお送り致します.締切時点で入金確認が取れない場合は,未入金の旨記載されたクーポンが送付されますので,当日会場にて入金のご確認をさせて頂きます.入金とクーポン発送が入れ違いの場合は,振込み時の控え等を会場にお持ちいただければ,確認がスムーズに行えます.ご協力をお願い致します.
(b)FAX・郵送による申込
「FAX・郵送専用申込書」(PDF)はこちらから
1)「FAX・郵送専用申込書」に必要事項を記入の上,日本地質学会事務局までFAXまたは郵送にてお申込み下さい.電話による申込,変更などは受け付けられませんので,ご了解下さい.また,郵送による申込みの際は,必ず申込書のコピーを各自で保管して下さい.申込書に必要事項を記入の上,「日本地質学会大阪大会参加申込係」宛にお送り下さい.
FAX番号:03-5823-1156
郵送先:〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-815井桁ビル6階「日本地質学会大阪大会参加申込係」
2)FAX・郵送による申込の場合は,折返し学会より「受付確認証」をe-mailまたはFAXにてお送りします.必ずご確認下さい.確認証が届かない場合は,必ず事務局までご連絡下さい.確認証には,「受付番号」が記載されています.この「受付番号」はその後の問い合せ,変更,取消等に必要となります.
3)お支払いは,銀行振込またはクレジットカード決済のいずれかを選択できます.申込後順次,「予約内容確認」・「請求書」をお送りします.銀行振込を選択された方は,請求書に記載されている振込口座へ指定期日までにお振込み下さい.クレジット決済を選択された方は,参加申込の際必ずクレジット番号などの必要事項を記入して下さい.ご利用のカード会社の期日に合わせて,口座よりお引き落としとなります.カード会社からの明細には「日本地質学会(ニホンチシツガッカイ)」と表示されます.
4)締切後,参加証・各種クーポンを発送致します(9月上旬発送予定).大会開催10日前までには参加者の皆様のお手元に届
くようお送り致します.締切時点で入金確認が取れない場合は,未入金の旨記載されたクーポンが送付されますので,当日会場にて入金のご確認をさせて頂きます.入金とクーポン発送が入れ違いの場合は,振込み時の控え等を会場にお持ちいただければ,確認がスムーズに行えます.ご協力をお願い致します.
(2)申込締切
大会登録専用HP(オンライン)による申込: 8 月17日(金)18:00
FAX・郵送による申込: 8 月10日(金)必着
(3)申込後の変更・取消
(a)大会登録専用HP(オンライン)でお申込みの場合:締切までの間は,2012年大阪大会ホームページから予約の変更・取消が出来ます.変更・取消完了後,「変更・修正 確認メール」が登録のメールアドレスへ配信されます.内容を必ずご確認下さい.締切後は直接学会事務局(東京)にFAX又はe-mailにてご連絡下さい.クレジット決済の場合は,申込の都度決済が完了しますので,決済スケジュールの都合によっては,口座から重複して引き落とされる場合があります.その場合は,振込手数料を差し引いた額をクレジットカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2〜3ヶ月要する場合もありますので,ご了承下さい.
(b)FAX・郵送でお申込み場合:申込後に変更・取消が生じた場合は,日本地質学会宛FAXまたはe-mailにてご連絡下さい.その際申込受付時に案内される「受付番号」・「氏名」を必ず明記下さい.
(4)取消に関わる取消料と返金について
注意:お弁当と巡検は取消料が異なります.詳細は各項目を参照して下さい.
(a)締切までの取消:取消料は発生しません.返金がある場合は,振込手数料を差し引いた額をクレジットカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2〜3ヶ月要する場合もありますので,ご了承下さい.
(b)締切後〜9/12(大会3日前)までの取消:入金・未入金の如何に関わらず,参加費用の60%を取消料としていただきます.返金がある場合は,振込手数料を差し引いた額をクレジットカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2〜3ヶ月要する場合もありますので,ご了承下さい.参加費に講演要旨集が付いている方へは,大会後にお送りします.
(c)9/13(大会2日前)以降の取消:入金・未入金の如何に関わらず,参加費用の100%を取消料としていただきます.参加費に講演要旨集が付いている方へは,大会後にお送りします.
シンポジウム一覧
シンポジウム
講演申込・講演要旨:
5月28日(月)10時〜7月3日(火)17時(郵送 6月27日(水) 必着)
締切延長 7月4日(水)17時 締切りました。
今大会では2件のシンポジウムを開催します.各シンポジウムの詳細については下記をご覧下さい.
シンポジウムの発表者にはセッション発表における1人1件の制約は及びませんので,シンポジウムで発表する会員は別途セッションにも発表申込が可能です.また,世話人は会員・非会員を問わず招待講演を依頼することができます(締め切りました).なお,非会員招待講演者に限り参加登録費を免除します(講演要旨集は付きませんので,必要な場合は別途購入していただきます).発表の一般公募はありません.
シンポジウムの講演要旨は,セッション発表と同じ様式・分量です.フォーマットを参照して原稿を作成して下さい.やむを得ず原稿を郵送する場合は郵送用の発表申込書をご利用下さい.「シンポジウム」と書き添え,必要事項を記入し,返信用ハガキ(自分宛),保証書・同意書,講演要旨原稿とともに6月27日(水)必着で行事委員会宛にお送り下さい.
*各タイトルをクリックすると、詳細をご覧いただけます
シンポジウム
S1.上町断層の地下構造と運動像:都市域伏在活断層の地質学
S2.西日本の海溝型地震と津波を考える
*印は連絡責任者です.
S1.上町断層の地下構造と運動像―都市域伏在活断層の地質学―(近畿支部企画)
Subsurface structure and tectonics of Uemachi Fault Zone in central Japan : geology of active faults concealed in urban areas
竹村恵二*(京都大:takemura@bep.vgs.kyoto-u.ac.jp)・三田村宗樹(大阪市大)・末廣匡基(阪神コンサルタンツ)
Keiji Takemura*(Kyoto Univ.)・Muneki Mitamura(Osaka City Univ.)・Masaki Suehiro(Hanshin Consultant Co. Ltd)
上町断層は,大阪堆積盆地の中央を南北に走る,大阪大都市圏を通過する活断層であり,断層が活動した際は,大都市圏での大きな地震災害規模になることが想定される.したがって,上町断層の地下形状や活動性評価の高度化は,地震災害の軽減にかかわっても,重要な課題である.大阪堆積盆地は中央構造線,有馬-高槻構造線,六甲-淡路断層帯,生駒断層に挟まれ,上町断層はその中央を南北に走り,この地域の構造発達史を考察する上でも重要な断層帯である.シンポジウムでは,上町断層帯の変動地形学的研究の現状と課題を浮き彫りにして,地質学的課題である地下構造や構造発達史の材料をひもときながら,シミュレーション等を含めて,現時点で集積されている上町断層の地質学的実態を明らかにすることを目的とする.最後に,その運動によって起因される強震動の予測に関する情報を紹介する.
招待講演予定者:井上直人(地域地盤環境研)・楠本成寿(富山大)・岩田知孝(京都大防災研)
S2.西日本の海溝型地震と津波を考える(執行理事会社会貢献部会・近畿支部合同企画)
Subduction zone earthquakes and tsunamis in western Japan
藤林紀枝*(新潟大:fujib@ed.niigata-u.ac.jp)・奥平敬元(大阪市立大)・星 博幸(愛知教育大)・藤本光一郎(東京学芸大)・中井 均(都留文科大)
Norie Fujibayashi (Niigata Univ.)・Takamoto Okudaira(Osaka City Univ.)・Hiroyuki Hoshi (Aichi Univ.Education)・Koichiro Fujimoto(Tokyo Gakugei Univ.)・Hitoshi Nakai(Tsuru Univ.)
2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(M9.0)と巨大津波は,1万5千名超の人命を奪い,建物,道路,地盤を広範囲にわたって破壊し,さらには福島第一原子力発電所事故という未曾有の大事故をも引き起こした.皮肉ではあるが,この巨大地震・津波により,これまであまり注視されてこなかった津波堆積物の研究,古文書による歴史地震研究の必要性が明らかになった.西日本でも,そう遠くない将来に大規模な海溝型地震と津波が発生する可能性が指摘されており,最近では3連動とも5連動とも言われる南海トラフ連動型巨大地震の発生とその対策が各方面で検討されている.実際に,仁和地震(887年),宝永地震(1707年)や,大阪を大津波が襲った正平地震(1361年)などの発生例がある.本シンポジウムでは,こうした西日本の海溝型地震・津波に焦点をあて,堆積物や断層物質の地質学的解析を含む多様な方面から地震・津波と関連する分野の研究最前線を紹介し,また教育・アウトリーチ活動の重要性についても議論する.
招待講演予定者:都司嘉宣(元東大地震研)・和澄利男(新潟市立亀田西中)
↑このページのTOPに戻る
シンポ・セッション一覧
シンポジウム,トピック/レギュラーセッションが決まりました
今年の第119年学術大会(大阪大会:9月15日〜17日開催)では下記のシンポジウム・セッションを予定しております.このほかにも市民講演会や地質情報展,国際ワークショップなど,多数の関連事業を企画・準備中です.募集・予告記事は次号ニュース誌5月号に掲載します.また,講演申込や参加登録は5月末頃受付開始予定です.
日本地質学会行事委員会
シンポジウム
タイトル
世話人/担当
備考
S1. 上町断層の地下構造と運動像 ―都市域伏在活断層の地質学―
竹村恵二・三田村宗樹・末廣匡基
近畿支部企画,9/16午前
S2. 西日本の海溝型地震と津波を考える(仮題)
未定
執行理事会社会貢献部会・近畿支部合同企画,9/17午前
トピックセッション
タイトル
世話人/担当
備考
T1. 地質情報の利活用
斎藤 眞・野々垣 進
T2. プレート収束境界の堆積盆形成:構造・堆積作用・テクトニクス
伊藤 康人・高野 修
T3. 地層処分と地球科学
吉田英一・高橋正樹・梅田浩司・渡部芳夫
T4. 地球史イベント大事件7:地層に残される地球史変動(宇宙、環境、テクトニクス、生物活動)
清川昌一・山口耕生・小宮 剛・尾上哲治・黒田潤一郎
T5. 沈み込み帯地震発生帯研究の新たな進展
橋本善孝・氏家 恒太郎・金川久一・斎藤実篤・芦 寿一郎・木村 学
T6. 顕生代の生物多様性変化:急激な増加/減少のパタンと要因
磯崎行雄・小宮 剛・川幡穂高
T7. ジルコン学
山本伸次・青木一勝・牧 賢志・昆 慶明
T8. 新学習指導要領の実施で地学教育はどのように変わるか?
中井 均・浅野俊雄・芝川明義
T9. 地殻流体のダイナミズム その2
竹下 徹・岡本和明
T10. ジュラ系+
松岡 篤・小松俊文・近藤康生・石田直人・中田健太郎
T11. 西南日本地体構造論の現代的問題点(市川浩一郎追悼セッション)
磯崎行雄・前島 渉・堀 利栄
レギュラーセッション
タイトル
世話人/担当
備考
R1. 深成岩・火山岩とマグマプロセス
火山部会・岩石部会
R2. 岩石・鉱物・鉱床学一般
岩石部会
R3. 噴火・火山発達史と噴出物
火山部会
R4. 変成岩とテクトニクス
岩石部会
R5. 地域地質・地域層序
地域地質部会・層序部会
R6. 地域間層序対比と年代層序スケール
層序部会
R7. 海洋地質
海洋地質部会
R8. 堆積物(岩)の起源・組織・組成
堆積地質部会
R9. 炭酸塩岩の起源と地球環境
堆積地質部会
R10. 堆積相・堆積過程
現行地質過程部会・堆積地質部会
R11. 石油・石炭地質学と有機地球化学
石油・石炭関係・堆積地質部会
R12. 岩石・鉱物の破壊と変形
構造地質部会
R13. 付加体
構造地質部会
R14. テクトニクス
構造地質部会
R15. 古生物
古生物部会
R16. 情報地質
情報地質部会
R17. 環境地質
環境地質部会
R18. 応用地質学一般およびノンテクトニック構造
応用地質部会
R19. 地学教育・地学史
地学教育委員会
R20. 第四紀地質
第四紀地質部会
保証書・同意書
<郵送での投稿の場合は、原稿に必ず添付して下さい>
保証及び著作権譲渡等同意書 PDFダウンロードはこちらから PDF
保証及び著作権譲渡等同意書
著作者(下記)は,日本地質学会によって発行される第119年学術大会「講演要旨」・「巡検案内書」に掲載する下記表題の原稿(以下「本原稿」という.)について,以下のとおり保証し,かつ著作権を譲渡等いたします.
第1 保証
著作者は,本原稿について,以下の各号記載の事項を保証し,確約します.
1) 本原稿が著作者自身の著作物であり,既にいずれかで出版公表されているものと同一ではないこと.
2) 本原稿が既存の出版公表物などに対する知的財産権のいかなる侵害も含まないこと.
3) 本原稿中に他から転載されているすべての図表について,転載許可を得ていること.
4) 本原稿中,他の論文等の引用がある場合には,当該引用が公正な慣行に合致し,目的上正当な範囲内であること.
5) 著作物には,日本地質学会の名誉を傷つけ,当該出版物の信用を毀損する盗用データ,捏造データ,著作物に関する利害を持つ者の合意に反するもの,その他学会の倫理綱領に反するものを含まないこと.
6) 本原稿が共同著作物である場合には,代表して本書に署名捺印する者が,すべての共著者から,本書に著名捺印することについて同意ないし必要な権利を得ていること.
7) 本原稿についての問い合わせ,苦情,紛争などが発生した場合,署名者はすべての責任を負うこと.
8) 本著作物を作成するに当たって行われた調査・研究行為が,適切な方法でなされたものであること.
第2 著作権譲渡等
著作者は,本原稿について,以下の各号記載に同意します.
1) 本原稿のすべての著作財産権(著作権法27条,同29条に定める権利を含む)及び2次著作物の創作・利用に係る権利を日本地質学会へ譲渡すること.
2) 本原稿について,日本地質学会ならびに日本地質学会から正当に権利を取得した第3者及び当該第3者から権利を承継した者に対し,著作人格権(公表権,氏名表示権,同一性保持権)を行使しないこと
3) 本原稿の下記の各利用形態に関する権利を日本地質学会が排他的に行使すること.
a) 複製,翻訳,翻案(出版,電子出版,翻訳出版,データベース化,ビデオグラム化,その他すべての記録メディアへの記録・掲載などを含む)
b) 展示・上映
c) 放送,有線放送,自動公衆送信(地上波,CATV放送衛星,通信衛星,インターネット,パソコン通信,その他あらゆる送信媒体及び将来開発されるすべての送信媒体による公衆送信を含む)
d) 頒布,譲渡,貸与
e) その他,本著作物に関する一切の利用(技術の進歩により将来生じうる利用形態を含む)
以上
日付 2012年 月 日
本原稿表題
著作者(代表者) 印
署名者が代表する共著者すべての氏名
学会記入【講演番号: 】
学会記入【受付番号: 】
巡検のみどころ
日本地質学会第119年学術大会(大阪大会)
各コースの詳細と魅力・見どころの紹介
■ 参加申込はこちらから ■
★注意点★
*取り消し料は,申込締め切り後〜出発3日前までは50%,2日前以降は全額となります.
*参加費用には旅行傷害保険(500円)が含まれています.
*集合地点まで,および解散地点からの交通費は各自の負担となります.
*参加費用はあくまで概算の金額です.大きな過不足が生じた場合,巡検終了時に調整します.
*各班の巡検案内書は,印刷したものを巡検当日に配布します.
*集合・解散の場所・時刻等に変更が生じた場合,大会期間中は掲示板に案内されます.
*参加者人数が少ない場合や,安全確保に問題があると考えられる場合は,コース内容の一部変更やコースの取りやめ(中止)等の措置をとることがあります.
A班:山陰海岸におけるジオパーク活動−大地と暮らしのかかわり−
B班:兵庫県南東部,川西−猪名川地域の超丹波帯と丹波帯
C班:和泉山脈西端部:和泉層群と中央構造線
D班:中新世の室生火砕流堆積物
E班:古琵琶湖層群における新・旧鮮新−更新統の境界
F班:領家帯青山高原地域の変成岩および花崗岩類
G班:紀伊半島西部の秩父帯・黒瀬川帯
H班:紀州白亜系四万十帯美山層のメランジュ変形構造と温度圧力履歴
I班:GISをつかってみよう
J班:大阪の津波碑と地盤沈下対策
A班 山陰海岸におけるジオパーク活動−大地と暮らしのかかわり−
(9月18日(火)・19日(水),1泊2日コース)
定員:20名 概算費用:25,000円(1・2日目の昼食込み)
地形図
神鍋・豊岡・城崎・香住・余部・浜坂・鳥取北部
案内者
先山 徹(兵庫県立人と自然の博物館,兵庫県立大学)・松原典孝(兵庫県立コウノトリの郷公園,山陰海岸ジオパーク推進協議会,兵庫県立大学)・三田村宗樹(大阪市立大学)
魅力
山陰海岸ジオパークは,日本海形成と人々の暮らしをテーマにしたジオパークです.ここでは,大地の性質によって生じた豊かな自然・風土と多様な暮らしが成り立っています.地層や岩石だけでなく,地域特有の生き物や人々の暮らしなど,大地に関わる全てのものを地域資源ととらえ,それを活用して地域づくり活動を推進しています.本巡検ではそれら大地と人々の暮らしとの関わりを,実際に現地で活動をしているガイドや住民を通して紹介したいと考えています.
見どころ
・神鍋高原における地質特性を利活用した人々の暮らし
・豊岡盆地の形成とコウノトリの野生復帰活動
・世界的な価値「玄武洞」におけるガイドの取り組み
・香美町における民間発ガイド養成およびジオツーリズム
・昭和24年に創業した遊覧船によるジオサイトツアー
・地域資源を活用した山陰海岸ジオパークにおけるビジネスモデル事業
・日本三大砂丘の一つ,鳥取砂丘と砂丘地での農業開発
巡検コース
9月18日 8:00 大阪府立大学→豊岡市神鍋→豊岡市十戸→豊岡市祥雲寺→豊岡市赤石→香美町(泊)
9月19日 香美町今子→香美町香住→新温泉町三尾→新温泉町浜坂→鳥取市鳥取砂丘→17:00 鳥取空港(解散)→20:00 JR大阪駅(解散)
(左)玄武洞で行われた玄武洞まつり(兵庫県豊岡市)
(右)今子浦の千畳敷とかえる島(兵庫県香美町)
備考 大阪府立大学白鷺門周辺集合.中型バス使用.
ページtopに戻る
B班 兵庫県南東部,川西−猪名川地域の超丹波帯と丹波帯
(9月14日(金),1日コース)
定員:20名 概算費用:6,000円
地形図
広根・妙見山
案内者
菅森義晃(大阪市立自然史博物館,大阪市立大学)・小泉奈緒子(大阪市立大学)・竹村静夫(兵庫教育大学)
魅力
北摂地域の超丹波帯は,かつてジュラ紀の前弧海盆堆積物と考えられていましたが,最近の研究によってペルム紀の付加複合体であると解釈されています.このことから三畳紀―ジュラ紀付加複合体(丹波帯など)の構造的上位に,ペルム紀付加複合体(超丹波帯)が衝上しているという地質学的特徴がいっそう明瞭になってきました.この巡検では,北摂地域西部にあたる兵庫県南東部の川西―猪名川地域に分布する超丹波帯および丹波帯の岩相を見学します.
見どころ
・超丹波帯猪名川コンプレックスの岩相(砂岩泥岩互層,破断砂岩泥岩層)
・超丹波帯国崎コンプレックスの岩相(砂岩泥岩互層,玄武岩)
・猪名川コンプレックスと国崎コンプレックスとの境界
・保存良好のペルム紀放散虫化石を含む砕屑岩
・丹波帯箕面コンプレックスの岩相(混在岩)
巡検コース
9:30 JR新大阪駅→箕面市止々呂美→川西市知明湖(一庫ダム)→猪名川町伏見台・内馬場→川西市東畦野→川西市多田→17:00 JR新大阪駅(解散)
(左)猪名川コンプレックス中の含放散虫珪質泥岩.本露頭からは年代決定に有効な放散虫化石は得られていない.同様の岩相は超丹波帯の味間層や高槻層にも認められ,これらからはペルム紀新世の放散虫化石が産出している.
(右)猪名川コンプレックスの砂岩泥岩互層.本コンプレックスの特徴的な岩相の1つである.この露頭では砂岩層の単層の厚さ25 cm前後のものが卓越する.
備考 JR新大阪駅1F正面口集合.小型バス使用.昼食は各自でご用意下さい(途中コンビニに立ち寄り可能).
ページtopに戻る
C班 和泉山脈西端部:和泉層群と中央構造線
(9月18日(火),1日コース)
定員:15名 概算費用:6,000円
地形図
淡輪・加太
案内者
宮田隆夫(神戸大学)・安 鉉善(神戸大学)・猪川千晶(神戸大学)
魅力
中央構造線に沿って白亜系和泉層群が分布しています.この地層は白亜紀に中央構造線のプルアパート堆積盆に形成されたと考えています.和泉山脈西端部(和歌山市北部〜大阪府岬町地域)において,和泉層群のタービダイト相と酸性凝灰岩,背斜構造,層内褶曲(スランプ褶曲),小断層,砂岩単層のデュープレクス構造,コダイアマモなどを観察します.また中央構造線の幅広い破砕帯や中央構造線から分岐する横ずれ断層を観察します.
見どころ
・中央構造線の破砕帯と変位地形
・和泉層群の背斜構造
・横ずれ断層,砂岩単層のデュープレクス構造,酸性凝灰岩,堆積構造
・和泉層群のスランプ褶曲,小断層,コダイアマモ
・和泉層群と大阪層群の不整合
巡検コース
8:00 大阪府立大→和歌山市有功→和歌山大学入口北方→加太城ケ崎→大阪府岬町豊国崎→南海みさき公園駅→18:00 大阪府立大(解散)
(左)和歌山市加太城ヶ崎に露出する中央構造線の横ずれ断層.写真の左が東.北東−南西方向の断層は左横ずれ変位を示しています.
(右)大阪府岬町豊国崎西方海岸,和泉層群のスランプ褶曲.スケール:百円硬貨.
備考 大阪府立大学白鷺門周辺集合.マイクロバス使用.昼食は各自でご用意下さい.
ページtopに戻る
D班 中新世の室生火砕流堆積物
(9月18日(火),1日コース)
定員:20名 概算費用:6,000円(昼食込み)
地形図
大和大野・柳生・奈良
案内者
佐藤隆春(大阪市立自然史博物館)・中条武司(大阪市立自然史博物館)・和田穣隆(奈良教育大学)・鈴木桂子(神戸大学)
魅力
中新世中期(14.4 Ma)の短期間に噴出した大規模火砕流堆積物を見学します.三重・奈良県さらに大阪府まで,東西60 km以上に分布する室生火砕流堆積物,石仏凝灰岩層などです.これらは紀伊半島中〜南部に形成された陥没カルデラ群から数10 km以上流走し,層厚400 m以上の溶結凝灰岩を形成しました.縁辺相である石仏凝灰岩層では一部溶結した火砕流堆積物とその再堆積層が見られます.強溶結した凝灰岩を構成する異質岩片や火山豆石の有無,本質レンズの岩質の変化などから巨大噴火の姿に迫ることができます.
見どころ
・屏風岩で巨大噴火開始期の火砕流堆積物
・火山豆石の産状
・流紋岩質基質と輝石デイサイト質本質レンズ
・火砕流の堆積域での再堆積作用
巡検コース
8:30 近鉄大阪線榛原駅→曽爾村屏風岩→宇陀市室生区島ヶ谷→奈良市中ノ川→17:00 近鉄奈良線・JR大和路線奈良駅(解散)
(左)曽爾村屏風岩:室生火砕流堆積物がつくる柱状節理
(右)奈良市中ノ川:再堆積性火砕堆積岩の層相
備考 近鉄榛原駅前集合.マイクロバス使用.
ページtopに戻る
E班 古琵琶湖層群における新・旧鮮新−更新統の境界
(9月18日(火),1日コース)
定員:16名 概算費用:5,000円
地形図
水口・三雲・野州・草津
案内者
里口保文(滋賀県立琵琶湖博物館)・山川千代美(滋賀県立琵琶湖博物館)・高橋啓一(滋賀県立琵琶湖博物館)
魅力
2009年に国際的に定義が認められた第四紀のはじまり,つまり鮮新−更新世境界はそれ以前のものよりも古くなりました.鮮新世から更新世への移り変わりは各地域でどのような変化として表れているのでしょうか.この巡検では,鮮新−更新統の新・旧定義における境界層準付近が野外で確認できる陸水成層の古琵琶湖層群を例にとり,陸域における地層にとっての鮮新−更新統境界の観察を行います.
見どころ
・淡水の厚い湖堆積物が露頭で観察できる.
・新・旧定義における鮮新−更新統境界層準の両方を露頭でみる.
・鮮新−更新統境界層準付近の植物化石が採集できる(予定)
・鮮新−更新統境界層分付近の動物足跡化石が見られるかもしれない(当日の露頭状況による)
・現琵琶湖湖畔の地下約800 m地下をボーリングコアで観察ができる.
巡検コース
8:00 JR東海道本線草津駅→甲賀市甲賀町小佐治→湖南市吉永→湖南市石部緑台→琵琶湖博物館→18:00 JR東海道本線草津駅(解散)
(左)鮮新−更新統境界のやや下位にある小佐治火山灰層の露頭(Stop 1).均質な厚い淡水成泥層の上部に挟在する.
(右)五軒茶屋火山灰層(Eb-Fukudaテフラ)の降灰ユニットA1中に見られる火山豆石(Stop 3).この火山灰層は,旧定義による鮮新−更新統境界付近にある.
備考 JR草津駅前集合.レンタカー使用.昼食は各自でご用意下さい.
ページtopに戻る
F班 領家帯青山高原地域の変成岩および花崗岩類
(9月14日(金),1日コース)
定員:15名 概算費用:6,500円
地形図
伊勢路・佐田・平松・初瀬
案内者
河上哲生(京都大学)・西岡芳晴(産業技術総合研究所)
魅力
本地域は,ミグマタイト帯における電気石分解と,それに伴う全岩ホウ素の枯渇プロセスの研究の中心になった地域の1つです.近年,新期領家花崗岩による接触変成作用が本地域一帯で起きたこと,変成岩のジルコン中にメルト包有物が保存されていること等がわかってきました.本地域に分布する部分溶融を経た変成岩類のほか,接触変成の熱源となった新期領家花崗岩と広域変成の熱源となった可能性の高い古期領家花崗岩の貫入関係がわかる露頭を観察します.また,初瀬深成複合岩体の同時性岩脈を観察します.
見どころ
・紅柱石を含む砂泥質片岩
・メタテキサイト
・ダイアテキサイト
・阿保花崗岩・城立トーナル岩の貫入関係がわかる露頭
・含電気石ペグマタイト脈の遠景
・初瀬深成複合岩体の同時性岩脈
巡検コース
8:20 南海高野線・JR阪和線三国ケ丘駅北口→三重県伊賀市広瀬→三重県伊賀市川北→三重県伊賀市・馬野川→三重県伊賀市・奥院川→三重県伊賀市柏尾→奈良県桜井市初瀬→19:00 南海高野線・JR阪和線三国ケ丘駅北口(解散)
(左)青山高原地域のミグマタイトの露頭写真
(右)初瀬深成複合岩体中の同時性岩脈の露頭写真
備考 南海高野線・J R阪和線三国ケ丘駅北口集合.レンタカー使用.昼食は各自でご用意下さい.
ページtopに戻る
G班 紀伊半島西部の秩父帯・黒瀬川帯
(9月18日(火)・19日(水),1泊2日コース)
定員:20名 概算費用:13,000円(2日目の昼食込)
地形図
湯浅・紀伊由良
案内者
八尾 昭(大阪市立大学)
魅力
紀伊半島西部の主に海岸沿いの好露頭を訪れ,秩父帯(含御荷鉾帯)のジュラ紀−白亜紀古世付加体の実態,および黒瀬川帯を構成する先ジュラ紀の諸岩類や地層を見学します.この巡検を通して,“放散虫革命”で何がわかったのか,日本列島の基盤地質構造発達史がどのように書き換わったのかなど,その過程を辿ります.
見どころ
・御荷鉾帯(秩父北帯)のジュラ紀中世—新世珪質岩類
・秩父北帯のジュラ紀古世−中世メランジュと含まれる礫岩
・黒瀬川帯の先ジュラ紀の諸岩類・地層とそれを不整合で覆う下部白亜系
・秩父南帯のジュラ紀中世−白亜紀古世メランジュと後期古生代石灰岩岩体
巡検コース
9月18日 10:00 JR紀勢線箕島駅→有田郡有田町糸野・下六川間→有田市高田海岸→有田郡湯浅町浮石→有田郡湯浅町栖原あやめの浜(泊)
9月19日 有田郡広川町名南風鼻・ばべ鼻→日高郡由良町白崎・立厳→日高郡由良町神谷→16:00 JR紀勢線紀伊由良駅(解散)
(左)黒瀬川帯名南風鼻レンズ状部の三滝花崗岩類(440 Ma前後)と捕獲されたシルル紀石灰岩岩体
(右)秩父南帯のジュラ紀中世—新世メランジュ(右)中に含まれる後期古生代の白崎石灰岩岩体(左)と立厳石灰岩岩体(中央)
備考 J R紀勢線箕島駅前集合.小型バス使用.1日目の昼食は各自でご用意下さい.
ページtopに戻る
H班 紀州白亜系四万十帯美山層のメランジュ変形構造と温度圧力履歴
(9月18日(火),1日コース)
定員:10名 概算費用:5,500円
地形図
川原河
案内者
橋本善孝(高知大学)
魅力
紀州白亜系四万十帯美山層は緑色岩やチャートといった海洋物質を多く含む構造性メランジュからなっており,沈み込みから底付け付加にいたる沈み込みプレート境界に沿った変形および物性変化を追うことができます.また,鉱物脈の発達様式も変形・物性変化に伴って変化しており,さらにそれらの温度圧力も推定されています.沈み込みに伴う変形・物性変化および脱水・流体移動経路の変化を露頭の産状と温度圧力条件とともに議論して行きたいと思います.
見どころ
・構造性メランジュの変形組織
・海洋物質と陸源物質の接触関係
・海洋物質の収斂および連続性
・鉱物脈の産状と変形との関係 ・変形組織のスケール変化と物性変化との関係
巡検コース
8:00 南海高野線白鷺駅前→和歌山県日高郡中津村三十井川沿い→16:30 JR和歌山駅(解散)
(左)緑色岩の露頭の連続性を道路沿いに追うことができる.
(右)初生的な構造性メランジュ組織をシャープに切断する小断層.
備考 南海高野線白鷺駅前集合.レンタカー使用.昼食は各自でご用意下さい.
ページtopに戻る
I班 GISをつかってみよう
(9月18日(火),1日コース)
定員:20名 概算費用:800円
地形図
なし
案内者
升本眞二(大阪市立大学)・根本達也(大阪市立大学)
魅力
GIS(地理情報システム)は時空間情報を取扱う地球科学の分野において非常に有効なシステムです.基盤データの無償公開,ハードウェアの高度化,およびフリーオープンソースソフトウェア(FOSS)の普及などにより身近なものとなってきました.GISを利用するための基礎的な概念や機能について解説し,Windows上で動作するFOSSのGISを用いて基本的な操作方法,および簡単な地形解析等の実習を行います.
内容
・GISの機能と特徴,データの形式と入手方法,基本的な処理,インストール方法
・GISの基本的な使い方(実習1)
・GISによる地形解析(断面図,等高線図,傾斜量図等)(実習2)
・GISによる3次元可視化(実習3)
スケジュール
10:00→16:00 大阪市立大学基礎教育実験棟(007室)
(左)DEMから作成した地形の陰影図(shaded relief map)
(右)地形の3次元可視化(大阪平野)
備考 大阪市立大学基礎教育実験棟前集合.費用はテキスト代です.昼食は各自でご用意下さい.実習用のパソコンはこちらで用意します.
ページtopに戻る
J班 大阪の津波碑と地盤沈下対策
(9月17日(月),半日コース)
定員:20名 概算費用:150円
地形図
大阪西南部
案内者
三田村宗樹(大阪市立大学)
魅力
大阪平野は厚い第四紀層の広がる低平地であることから,これまで地下水過剰揚水に伴う地盤沈下,地震災害,津波災害を被ってきました.また,デルタに発達したアジア特有の都市の特徴でもある「渡し」が現存してもいます.大阪西部の町歩きから見える地盤沈下の痕跡や津波災害や街の状況をたどります.低平地の 都市域での防災教育に向けた街の再認識を行う意味での街の教材活用について現地で議論できればと考えております.
見どころ
・防潮堤と街の構造
・大地震両川口津浪記(安政南海地震の津波の碑)
・防潮水門と「渡し」(落合上渡,甚平衛渡)
・昭和山(地下鉄残土による盛土の山,大阪市内で2番目に標高の高い「山」)
・地盤沈下対策の地盤かさ上げ
巡検コース
13:00 JR難波駅(ポンテ広場)→道頓堀川に沿う防潮堤→大地震両川口津波碑→南海汐見橋駅(南海電鉄高野線乗車)→木津川駅→木津川防潮水門→落合上渡し→千島公園昭和山→甚兵衛渡し→16:00 JR弁天町駅(解散)
(左)大地震両川口津浪記(大阪市浪速区大正橋東詰)
(右)落合上渡と木津川防潮水門
備考 J R難波駅本ポンテ広場前集合.費用は保険代です(当日徴収させて頂きます).公共交通機関で移動しますので、運賃は各自でご用意下さい.
ページtopに戻る
巡検参加申込要領
巡検および巡検案内書
巡検参加事前申込みは,8月17日に締め切りました.参加者への連絡などを大会ホームページに随時掲載いたします.
巡検案内書は,CD-ROM版を118巻8号(2012年8月号)に添付して会員に配布いたします.また,地質学雑誌の一部となっていますので,発行から3ヶ月目にはJ-STAGE<http://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja>にて公開をいたします.
なお,予告記事でもお知らせの通り,今大会の巡検では冊子体の案内書は作成いたしません.巡検参加者には,各班の巡検案内の複写を巡検当日に配布する予定です.
★注意点★
*取消料は,申込締め切り後〜出発3日前までは50%,2日前以降は全額となります.
*参加費用には旅行傷害保険(500円)が含まれています.
*集合地点まで,および解散地点からの交通費は各自の負担となります.
*参加費用はあくまで概算の金額です.大きな過不足が生じた場合,巡検終了時に調整します.
*各班の巡検案内書は,印刷したものを巡検当日に配布します.
*集合・解散の場所・時刻等に変更が生じた場合,大会期間中は掲示板に案内されます.
*参加者人数が少ない場合や,安全確保に問題があると考えられる場合は,コース内容の一部変更やコースの取りやめ(中止)等の措置をとることがあります.
巡検参加申込要領
申込締切
オンライン: 8 月17日(金)18:00,
FAX・郵送: 8 月10日(金)必着
巡検一覧と各コース見どころはこちら
10コースの巡検(A〜J班)を計画しました(巡検一覧を参照).参加希望の方は,Web申込手続き手順に従って参加申込を行って下さい.FAX・郵送でのお申込は,専用申込書を用い,学会事務局(東京)宛に大会参加申込と一緒に申し込んで下さい.巡検だけに参加する場合も大会参加登録ならびに参加登録費が必要です.巡検と大会参加登録の申込を合わせて行って下さい.申込に際し,希望の班が満員の場合に備え,①キャンセル待ち,②第2希望の班の指定,③他班希望なくキャンセル待ちせず,のいずれかを必ず指定して下さい.
(1)参加申込人数が各巡検コースの実施最小人数に達しなかった場合,巡検を中止することがあります.
(2)非会員の方は,申込締切時点で定員に余裕があれば参加可能となります.ご承知下さい.
(3)日本地質学会ならびに同大阪大会実行委員会は巡検参加者に対し,巡検中に発生する病気,事故,傷害,死亡等に対する責任・補償を一切負いません.これらについては,巡検費用に含まれる保険(国内旅行傷害保険団体型)の範囲でのみまかなわれます.
(4)子供同伴など特別な事情がある場合は,申込前に現地事務局へあらかじめ問い合わせて下さい.
(5)締切までの間は,ホームページから変更・取消が出来ます.変更・取消完了後,「変更・修正 確認メール」が登録のメールアドレスへ送信されます.内容を必ずご確認下さい.締切後の変更・取消は,直接学会事務局(東京)にFAX又はemailにてご連絡下さい.締切後は入金・未入金の如何に関わらず,取消料が発生します(詳しくは,下記注意点を参照).
(6)集合・解散の場所,時刻などを変更することもありますので,大会期間中は掲示などの案内に注意して下さい.
(7)Web申込時に巡検参加費(保険代)を徴収せず,巡検当日に現地で徴収するコースもあります(詳しくは,巡検一覧を参照).
(8)今大会では冊子体の巡検案内書を作成・販売いたしませんが,なるべく早く案内書CD-ROMを地質学雑誌に添付できるよう調整中です.また,巡検参加者には,各班の巡検案内の複写を巡検当日に配布する予定です.
講演情報TOP
講演関連
▶講演プログラムはこちらから ▶緊急展示について(申込締切8/31)
▶シンポジウム一覧 ▶セッション一覧
発表者へ
発表者は,本学会または共催学協会の会員に限ります(招待講演者を除く).共同発表の場合は,この制限を代表発表者(講演要旨に下線を引いた著者)に適用 します.やむを得ない事情により,あらかじめ連記された共同発表者内で発表者の変更を希望する場合は,必ず事前に行事委員会(会期前は学会事務局,会期中 は学会本部)に連絡して下さい.この場合も,シンポジウムおよびアウトリーチセッション以外の場合は「会員に限り1 人1 題(発表負担金を支払った場合は2題)」の制限を守るものとします.代理人の代読,会場内での突然の発表者変更,発表順序の変更は認めません.口頭発表者は発表時間を厳守して下さい.発表に際しては座長の指示に従い,会場運営がスムーズに行われるようご協力下さい.
■口頭発表について ■ポスター発表について ■会場での注意点
<講演キャンセル・講演者の変更について>
やむを得ない事情により,講演をキャンせるまたは,あらかじめ連記された共同発表者内で発表者の変更を希望する場合は,必ず事前に行事委員会(会期前は学会事務局<main@geosociety.jp>,会期中は学会本部)に連絡して下さい.
口頭発表
・ 1 題15分(質疑応答3 〜5 分を含む).ただしシンポジウムは除きます.
・ 口頭発表会場には液晶プロジェクターとWindowsパソコン(OS:Windows XP,Vistaおよび7 対応,MicrosoftOffice PowerPoint 2003-2010対応)を用意します.なお,35 mmスライドプロジェクターの使用はできません.
【講演ファイルをUSBメディアでご持参の方】
口頭発表で使用するファイルのインストールは,PCセンター(試写室)【B 3 棟2 階212番教室】にて事前に作業を行ってください.イ ンストールは各セッション・各シンポジウム開始30分前までにB 3 棟2 階(212)PCセンター(試写室)で受け付けます.なお,大会初日9 月15日午前に発表される方についても,朝8 :30までPCセンターにて受けます.混雑が予想されますので講演直前にならないよう,十分な時間的余裕を持って確実に行ってください(午前中のセッショ ンであれば前日に,午後のセッションであれば午前中にインストールを完了してください).ファイルは,PCセンターにおいて正常に作動することを事前に確 認してください.特に,会場に設置するものと異なるバージョンで作成されたパワーポイントファイルは,レイアウトが崩れる事例が報告されていますのでご注 意願います.なお,ファイル名には,発表番号と筆頭演者ご氏名をご使用ください.(例:S1 - O - 1大阪太郎,R1 - O - 1泉州次郎)また,Uホール白鷺で開催されるプログラムにて口頭発表される方は,ホール内ステージ左手のPCオペレーター席までファイルをお持ち込みください.
【ご自分のパソコンを使用して講演をされる方】
本年は会場の液晶プロジェクターにパソコンの切り替え器(ケーブル形状はD-SUB15ピン)を用意します.Macパソコンをお使いになる方,ソフトの互 換性からレイアウトが崩れる可能性のある方,パワーポイント以外のプレゼンテーションソフトをご利用の方はご自分でパソコンをご用意ください.各会場のプ ロジェクターの解像度設定はXGA(1024×768)です.講演前に自身での出力調整の上接続してください.Macパソコン,その他タブレット機器をお 使いになる方は,必ずD-SUB15ピンへのアダプターと電源アダプターをご持参ください.パソコンの接続については,発表者自身が責任を持って実施下さ い.切り替えは会場スタッフにて行います.
画面TOPに戻る
ポスター発表
・ 掲示する際のチェスピンは準備いたします.テープのご利用はできませんので,ご了承ください.
・ 展示時間は, 9 :00〜18:00です.展示準備は早めにお願いします.撤収は,19:00までにお願いします.
・ コアタイムは,
-----15日(土)が12:30〜13:50,
-----16日(日)が13:00〜14:20
-----17日(月)が13:00〜14:20です
(アウトリーチセッションのみ16日(日)13:30〜14:30および17:00〜18:00).
この時間は必ずポスターに立ち会い,説明して下さい.その他の時間は各自の都合により随時説明を行って下さい.
・ボード面積は,高さ210 cm,幅120 cmです.
・発表番号・発表題名・発表者名を必ず明記して下さい.
・ コンピューターやビデオを使用される場合,機器の準備は各自で行ってください.電源は確保できませんので,予備バッテリーをご準備下さい.
・ ポスター発表に対し,優秀ポスター賞が授与されます.奮ってご準備下さい.優秀ポスター賞については、こちらから
画面TOPに戻る
会場での注意点
■拍手徹底
1 題の口頭発表はわずか15分で終了します(セッションの場合).しかし,その発表の裏には,発表者の弛まぬ努力と,研究や発表準備に費やした多くの時間があるはずです.講演が終了したら,惜しみない拍手をお願いします.
■写真撮影・ビデオ撮影の制限
口頭発表・ポスター発表を,発表者に無断で写真撮影・ビデオ撮影してはいけません.撮影には発表者の許可が必要です.
■軽装の勧め
7 月末現在,関西地区の電力供給は逼迫した状況ではないようですが,不測の事態で急な節電要求がある可能性も考えられます.残暑厳しい時期,大会参加の皆様には軽装をお勧めします.ご理解,ご協力をお願いします.
画面TOPに戻る
大阪大会講演申込
講演申込・講演要旨:
5月28日(月)10時〜7月3日(火)17時(郵送 6月27日(水) 必着)
7月4日(水)17時締切りました。
★注意★講演申込を予定しているが,まだ入会手続きをされていない方へ
▶講演申込要領・発表要領
▶シンポジウム一覧
▶セッション一覧
▶講演要旨原稿について
▶▶講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理,引用方法,校閲について
▶▶講演要旨の作成の注意点とPDFファイル作成の作り方
▶▶講演要旨オンライン投稿手順チェックシート
▶▶保証・同意書(2012大阪)
▶講演申込書 書式pdf(郵送で申し込む場合)
企業展示・書籍販売・広告募集
■ 出展募集 ■ 書籍・販売ブースご利用の募集 ■ 広告協賛の募集
企業等団体展示/書籍販売
企業・団体・研究機関などによる展示を行います.会場は,大阪府立大学中百舌鳥キャンパスB3棟1F(106・107)を予定しています.7月27日現在,
・株式会社蒜山地質年代学研究所,
・ライカマイクロシステムズ株式会社,
・石油資源開発株式会社,
・メイジテクノ株式会社,
・高知コアセンター,
・NPO法人ジオプロジェクト新潟,
・独立行政法人海洋研究開発機構,
・東北大学グローバルCOEプログラム「変動地球惑星学の統合教育研究拠点」,
・株式会社地球科学研究所,
・ジーエスアイ株式会社,
・カールツァイスマイクロスコピー株式会社
・山陰海岸ジオパーク推進協議会
から申し込みがありました.
また,学術交流会館サロンでは書籍・物品の展示販売コーナーを設けます.7月27日現在,
・株式会社朝倉書店,
・一般社団法人京都大学学術出版会,
・株式会社テラハウス,
・株式会社古今書院,
・地学団体研究会,
・関西地図センター,
・株式会社ニチカ
からお申込みがありました.
企業・研究機関等関係団体による展示会の出展募集
<申込締切 一次6 月29日(金),最終7 月27日(金) 現地事務局扱い>
地質関係機関・関連企業のご活躍を広く地質学会員に紹介していただくため,会期中,企業展示会を開催致します.企業紹介・業務紹介・研究成果・新技術・特許などご自由に展示内容を構成いただけます.奮ってご出展のお申込をいただきますようお願い申し上げます.
【展示募集概要】
1.開催期間:搬入設営日9月14日(金),開催日9月15日(土)〜17日(月),搬出撤収日9月17日(月)※予定
2.開催場所:大阪府立大学 中百舌鳥キャンパス B3教育棟 ※予定
3.募集小間数:小小間12,パネル小間16 ※予定 複数小間のお申込も可能です.
4.小間仕様見本:
5.出展料金:小小間 50,000円(消費税別),パネル小間 20,000円(消費税別)
6.第1次募集締め切り日: 6 月29日(金) 最終募集締め切り日: 7 月27日(金)
【出展申込方法】
「展示募集要項申込書」をダウンロードいただき,必要事項をご記入の上,下記申込先までe-mailへのPDFファイル添付,あるいはFAXにてお申込下さい.募集要項・申込書が別途必要な場合は,現地事務局までご連絡下さい.送付致します.
「展示募集要項申込書(pdfファイル)」
「展示募集要項申込書(docファイル)」
【お申込・お問合せ先】
〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1天満橋千代田ビル2号館9階
日本地質学会 第119年学術大会 現地事務局(株式会社アカデミック・ブレインズ内)
TEL:06-6949-8137,FAX:06-6949-8138,e-mail:gsj2012osaka@academicbrains.jp 担当:田中
※日本地質学会賛助会員は出展料金が無料となります.別途,現地事務局までご連絡下さい.
書籍・販売ブースご利用の募集
<申込締切 一次6 月29日(金),最終7 月27日(金) 現地事務局扱い>
地質学関連の書籍・その他物品の販売にご利用いただくべく会期中ブースを設置致します.奮ってご出展のお申込をいただきますようお願い申し上げます.※見本展示のみでのご利用も可能です.
【書籍・販売ブース出展概要】
1.設置期間:9月15日(土)〜9月17日(月)
2.設置場所:大阪府立大学 中百舌鳥キャンパス C1学術交流会館サロン
3.募集ブース数:6ブース ※予定 複数ブースのお申込も可能です.
4.ブース仕様見本
5.出展料金:10,000円(消費税別)
6.第1次募集締め切り日: 6 月29日(金) 最終締め切り日: 7 月27日(金)
【出展申込方法】
「展示募集要項申込書」をダウンロードいただき,必要事項をご記入の上,下記申込先までe-mailへのPDFファイル添付,あるいはFAXにてお申込下さい.募集要項・申込書が別途必要な場合は,現地事務局までご連絡下さい.送付致します.
「展示募集要項申込書(pdfファイル)」
「展示募集要項申込書(docファイル)」
【お申込・お問合せ先】
〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1天満橋千代田ビル2号館9階
日本地質学会 第119年学術大会 現地事務局(株式会社アカデミック・ブレインズ内)
TEL:06-6949-8137,FAX:06-6949-8138,e-mail:gsj2012osaka@academicbrains.jp 担当:田中
講演要旨集,広告協賛の募集
<申込締切 7 月27日(金) 現地事務局扱い>
地質関係機関・関連企業のご活躍を広く地質学会員に広報いただくべく,大会開催にあわせ発行されます講演要旨集において,広告協賛を募集致します.企業紹介・業務紹介・研究成果・新技術・特許などの広報活動のご一環として,奮ってお申込をいただきますようお願い申し上げます.
【広告協賛料金】※詳細は大会ホームページの「広告協賛募集要項申込書」をダウンロードの上,ご確認下さい.
講演要旨集:1頁 40,000円 1/2頁 20,000円 1/4頁 10,000円(すべて消費税別)
※完全版下,データまたフィルムでの入稿をお願い致します.
【出稿申込方法】
「広告協賛募集要項申込書」をダウンロードいただき必要事項をご記入の上,下記申込先までe-mailへのPDF添付,あるいはFAXにてお申込下さい.
「広告協賛募集要項申込書(pdfファイル)」
「広告協賛募集要項申込書(docファイル)」
【お申込・お問合せ先】
〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1天満橋千代田ビル2号館9階
日本地質学会 第119年学術大会 現地事務局(株式会社アカデミック・ブレインズ内)
TEL:06-6949-8137,FAX:06-6949-8138,e-mail:gsj2012osaka@academicbrains.jp 担当:田中
ランチョン・夜間集会
ランチョン
都合により急遽会場が変更になる場合もありますので,会期中の掲示にご注意下さい.
9月16日(日)12:00-13:00
第1会場 地域地質部会・層序部会合同(世話人:内野隆之・岡田 誠)部会活動やセッションについての議論と情報交換.
第2会場 海洋地質部会(世話人:荒井晃作・芦 寿一郎・小原泰彦)海洋地質部会の活動に関する議論と情報交換.
第5会場 地質学雑誌編集委員会(世話人:山路 敦)地質学雑誌face-to-face編集委員会.
第6会場 応用地質部会(世話人:小嶋 智・須藤 宏)応用地質部会の進め方,地質技術者教育についてのディスカッション.
第7会場 堆積地質部会(世話人:片岡香子)堆積地質部会の活動報告および国内外の堆積学に関する情報交換を行う.
9月17日(月)12:00-13:00
第1会場 古生物(世話人:平山 廉)古生物部会の定例会合.
第2会場 構造地質部会若手の研究発表会(世話人:大坪 誠・山田泰広・氏家恒太郎)構造地質部会若手の研究発表会をランチョンにおいて行います.1人20分程度で2名ほどを予定.
第3会場 岩石部会(世話人:水上知行)活動報告および協議.
夜間小集会
都合により急遽会場が変更になる場合もありますので,会期中の掲示にご注意下さい.
9月16日(日)18:00-19:30
第1会場 南極地質研究委員会(世話人:本吉洋一・外田智千)53次隊の報告,南極地質将来計画について,その他.
第2会場 おおさかのジオアーケオロジー(世話人:渡邉正巳・松田順一郎・趙 哲済・井上智博・小倉徹也・別所秀高)大阪でのジオアーケオロジーの成果についての講演と,今後の課題について討論.<http://www.cons-ar.co.jp/geoarc12.htm>
第4会場 超深度海溝掘削(KANAME)(世話人:木村 学・金川久一・斎藤実篤)新学術領域研究「超深度海溝掘削(KANAME)」の進捗状況と今後の南海掘削に関する情報交換を行う.
第5会場 地質学史懇話会(世話人:会田信行・金 光男)地質学史に関する講演2題:1)八尾 昭:“放散虫革命”と日本列島の地史(仮題),2)芝川明義:戦後からの大阪の地学教育の変遷と現状(仮題).
第6会場 環境地質部会(世話人:田村嘉之・風岡 修)環境地質に関する講演,事務連絡など.
9月17日(月)18:00-19:30
第1会場 地質技術者教育委員会(世話人:山本高司)中期・短期の具体的な活動を議論する.大学でのフィールド教育の現状,企業の地質出身者の採用状況を報告する.
第2会場 構造地質部会定例会(世話人:大坪 誠・山田泰広・氏家恒太郎)過去の活動報告会計報告,今後の活動計画など.
第5会場 学術大会の改革:オープンディスカッション(世話人:星 博幸)
第6会場 炭酸塩堆積学に関する懇談会(世話人:松田博貴)炭酸塩堆積学に関する最近の話題・トピックスについて討論するとともに,最新研究動向・情報について意見交換を行う.
ランチョン申込
<申込締切6 月27日(水)必着,行事委員会扱い>
9月16日(日),17日(月)にランチョン開催を希望する方は,(1)集会名称,(2)世話人氏名,(3)集会内容等,をe-mail<main@geosociety.jp>またはハガキに明記して行事委員会(東京)宛に申し込んで下さい.申込締切は6月27日(水)です.なお,世話人の方には,大会終了後にランチョンの内容をニュース誌(大会記事)にご投稿いただきます(800字以内,原稿締切:10月中旬).
夜間小集会の申込
<申込締切6 月27日(水)必着,行事委員会扱い>
9月16日(日)は18:00〜20:00,17日(月)は18:00〜19:30(予定)です.夜間小集会の開催を希望する方は,(1)集会の名称,(2)世話人氏名,(3)集会内容(50字以内),(4)参加予定人数,(5)液晶プロジェクターの要・不要,(6)その他特記すべきこと,をe-mail<main@geosociety.jp>またはハガキに明記して行事委員会(東京)宛に申し込んで下さい.申込締切は6月27日(水)です.なお,世話人の方には,大会終了後に集会の内容をニュース誌(大会記事)にご投稿いただきます(800字以内,原稿締切:10月中旬).
セッション一覧
セッション一覧
講演申込・講演要旨:
5月28日(月)10時〜7月3日(火)17時(郵送 6月27日(水) 必着)
7月4日(水)17時 締切りました。
*下記をクリックすると、各セッションの詳細がご覧頂けます。
トピックセッション(11件)
T1.地質情報の利活用
T2. プレート収束境界の堆積盆形成:構造・堆積作用・テクトニクス
T3. 地層処分と地球科学
T4. 地球史イベント大事件7:地層に残される地球史変動(宇宙、環境、テクトニクス、生物活動)
T5. 沈み込み帯地震発生帯研究の新たな進展
T6. 顕生代の生物多様性変化:急激な増加/減少のパタンと要因
T7. ジルコン学
T8. 新学習指導要領の実施で地学教育はどのように変わるか?
T9. 地殻流体のダイナミズム その2
T10. ジュラ系+
T11. 西南日本地体構造論の現代的問題点(市川浩一郎追悼セッション)
レギュラーセッション(20件)
R1. 深成岩・火山岩とマグマプロセス
R2. 岩石・鉱物・鉱床学一般
R3. 噴火・火山発達史と噴出物
R4. 変成岩とテクトニクス
R5. 地域地質・地域層序
R6. 地域間層序対比と年代層序スケール
R7. 海洋地質
R8. 堆積物(岩)の起源・組織・組成
R9. 炭酸塩岩の起源と地球環境
R10. 堆積相・堆積過程
R11. 石油・石炭地質学と有機地球化学
R12. 岩石・鉱物の破壊と変形
R13. 付加体
R14. テクトニクス
R15. 古生物
R16. 情報地質
R17. 環境地質
R18. 応用地質学一般およびノンテクトニック構造
R19. 地学教育・地学史
R20. 第四紀地質
アウトリーチセッション
日本地質学会アウトリーチセッション
トピックセッション:11件
T1.地質情報の利活用/Application of geological information
斎藤 眞*(産総研:saitomkt@ni.aist.go.jp)・野々垣 進(産総研)
Makoto Saito*(AIST)・Susumu Nonogaki(AIST)
これまで地質学会では,人類の地質への理解を進展させるためのさまざまな研究成果が発表されてきた.しかし,野外で地質情報を取得し,それらを意味のある地質情報へと変換し,社会での地質情報の利活用を推進する,という流れを持った研究成果の発表例は少ない.情報処理技術が発展した昨今,野外で取得した地質情報をデジタルデータとして整理・処理・管理する環境はほぼ整った.インターネットを通じて地質情報のデジタルデータを共有・利活用する環境も整いつつある.また,近
年,ジオパーク活動が盛んになるにともない,これまで地質学とはつながりが薄かった一般社会でも,地質情報を利活用しようという機運が高まっている.地域地質部会・情報地質部会では,このような地質学会の現状,および,世相の変化を受けて,
地質情報の取得から利活用までの流れの中にある研究の成果を発表する場として,表記トピックセッションを開催する.
現在,地域地質部会は,毎年の大会においてレギュラーセッションとして地域地質・地域層序を層序部会と共同で運営し,地域地質の研究成果を発表する場となっている.また,情報地質部会は,地質情報を処理するための理論・技術の開発,および,それらの地質学分野への応用などの成果を発表する場となっている.そこで,本トピックセッションでは,社会での地質情報の利活用に焦点をあて,
・特定地域から得られた地質情報の利活用,および,その問題点や比較検討
・地質情報の利活用に向けた情報取得方法
・ジオパークや博物館等における地質情報の利活用
を具体的発表テーマとする.
本トピックセッションは,昨年の水戸大会から活動を開始したものである.将来的には両部会が共同で行うレギュラーセッションを目指す.
招待講演予定者:なし
ページtopに戻る
T2.プレート収束境界の堆積盆形成:構造・堆積作用・テクトニクス/Tectono-sedimentary processes of basin formation on active plate margins
伊藤康人*(大阪府立大:itoh@p.s.osakafu-u.ac.jp)・高野 修(石油資源開発)
Yasuto Itoh*(Osaka Pref. Univ.)・Osamu Takano(JAPEX)
プレート収束境界における堆積盆形成のテクトニクスは,地球の物質循環と環境変遷のプロセスを理解するうえで極めて重要である.近年,反射法地震探査に代表される物理探査技術の長足の進歩によって,堆積盆深部の三次元的な構造可視化が現実のものとなってきた.また,地質年代学の精密化によって,詳細な地層対比と層相の時空分布解明が可能になってきた.それらは,従来地質的に研究されてきた成熟した堆積盆と第四紀のアクティブな堆積域の形態・規模・発達過程を比較検討する基盤が整ったことを意味しており,数値モデリングなどの定量的解析が盛んになりつつある.その状況に鑑み,前弧・背弧を問わず,変動帯の堆積盆テクトニクスを層序学的・堆積学的・構造地質学的・地球物理学的およびそれらの学際的な見地から考察した野心的・魅力的な研究成果を,広く募集する.
招待講演予定者:楠本成寿(富山大)
T3.地層処分と地球科学/Geological disposal of radioactive waste in Earth Science
[共催:日本原子力学会バックエンド部会]
吉田英一*(名古屋大:dora@num.nagoya-u.ac.jp)・高橋正樹(日大)・梅田浩司(日本原子力研究開発機構)・渡部芳夫(産総研)
Hidekazu Yoshida*(Nagoya Univ.)・Masaki Takahashi(Nihon Univ.)・Koji Umeda(JAEA)・Yoshio Watanabe(AIST)
地層処分は,地質学,地球化学,鉱物学,地下水学,土木工学,放射線化学,材料学などの多岐に渡った学際分野である.とくに地層処分場を取り巻く地質環境に関しては,変動帯地質としての日本独自の長期的営みを考えることが不可欠だと言える.本セッションでは,これら地層処分に関する地質学的あるいは地球科学的な課題について,現状認識と問題点,また事業の安全な推進や安全確保の見込みなど,多岐分野間の専門家との意見交換を目的にトピックセッションとして開催する.
招待講演予定者:なし
ページtopに戻る
T4.地球史イベント大事件7:地層に残される地球史変動(宇宙,環境,テクトニクス,生物活動)/Geologic events in the Earth history VII: evolutional environmental record
清川昌一*(九州大:kiyokawa@geo.kyushu-u.ac.jp)・山口耕生(東邦大)・小宮 剛(東京大)・尾上哲治(鹿児島大)・黒田潤一郎(JAMSTEC)
Shoichi Kiyokawa*(Kyushu Univ.)・Kosei Yamaguchi(Toho Univ.)・Tsuyoshi Komiya(Univ. Tokyo)・Tetsuji Onoue(Kagoshima Univ.)・Jun’ichiro Kuroda(JAMSTEC)
地球史46億年を通して様々な時空スケールのイベントが記録されている.地球規模変動は複雑に絡み合っているものの,その中には原因が違っても共通する現象や環境変化を引き起こしていることもある.時代を通り超えた視点で地層や岩石・鉱物に記録された,宇宙からの影響・地球内部変動・表層環境変動・生物活動などの影響による地球の歴史の解明に関する最新の研究動向を探る.
招待講演予定者:Carlos Alberto Rosie`re(UFGM)
ページtopに戻る
T5.沈み込み帯地震発生帯研究の新たな進展/Recent progress in studies on seismogenic zones along subduction zones
橋本善孝*(高知大:hassy@kochi-u.ac.jp)・氏家恒太郎(筑波大)・金川久一(千葉大)・斎藤実篤(JAMSTEC)・芦寿一郎(東大大気海洋研)・木村 学(東京大)
Yoshitaka Hashimoto*(Kochi Univ.)・Kotaro Ujiie(Univ. Tsukuba)・Kyuichi Kanagawa(Chiba Univ.)・Saneatsu Saito (JAMSTEC)・Juichiro Ashi(AORI, Univ. Tokyo)・Gaku Kimura(Univ. Tokyo)
東北地方太平洋沖地震は沈み込み帯地震のこれまでの知見を覆す,いくつかの事実を提示した.非地震領域と考えられていた海溝軸付近での大きなすべりが起こったこと,それが巨大津波の原因として本質的であること,また通常の地震とは異なる長周期のサイクルの存在などが明らかとなった.日本の沈み込みプレート境界地震研究は,これまでも観測・実験・理論・天然を成功裏に融合し世界をリードしてきた.我々はこれを機会に,これまでの成果を見直して新しい知見に基づいた次世代へ
の進展を議論するべきであり,地震後の目覚ましい研究成果はそれが可能であることを支持している.本年は,統合国際深海掘削計画(IODP)による東北地方太平洋沖地震断層掘削,南海トラフ地震発生帯掘削,およびコスタリカ沖掘削が実施される,沈み込み帯掘削の年である.また,関連する観測・実験・理論および陸上試料を対象とした研究も益々活性化している.このような様々な最新の研究成果をもちより,沈み込み帯地震発生帯の今後の進展を学際的な議論から明確にすることを目的としたトピックセッションを開催する.
招待講演予定者:亀田 純(東京大)
ページtopに戻る
T6.顕生代の生物多様性変化:急激な増加/減少のパタンと要因/Phanerozoic biodiversity change: pattern and causes of rapid increase/decline
磯崎行雄*(東京大:isozaki@ea.c.u-tokyo.ac.jp)・小宮 剛(東京大)・川幡穂高(東大大気海洋研)
Yukio Isozaki*(Univ. Tokyo)・Tsuyoshi Komiya(Univ. Tokyo)・Hotaka Kawahata(AORI, Univ. Tokyo)
化石記録が比較的豊富な顕生代の化石生物の産出パタンを通覧すると,生物の多様性は時間と共に定常的に起きたのではなく,むしろ短期間におきた現象であることがわかる.その背景に非定常的/非可逆的な環境要因があったと考えられるが,未だ詳細は不明である.本邦には,下部古生界の分布が極めて少ないが,近年,生物多様性の詳細な変化について新しい情報が急速かつ大量に増えつつある.さらに日本人研究者による海外での野外調査が試みられ興味深い新知見が得られつつある.本セッションは,生命進化史を考える上で極めて重要と考えられる生物多様性の変化,とくに顕生代で複数回おきた急激な増加や減少事件に焦点を当て,関連する最新のデータ発表,既存のデータのレビューを行い,そしてその要因について議論する.
招待講演予定者:姚 建新(Jianxin Yao,中国地質科学院)・張 興亮(Zhang Xinglian,西北大学)
T7.ジルコン学/Zirconology
山本伸次*(東京大:syamamot@ea.c.u-tokyo.ac.jp)・青木一勝(東京大)・牧 賢志(京都大)・昆 慶明(産総研)
Shinji Yamamoto*(Univ. Tokyo)・Kazumasa Aoki(Univ. Tokyo)・Kenshi Maki(Kyoto Univ.)・Yoshiaki Kon(AIST)
ジルコンは,火成岩・変成岩・堆積岩あるいは隕石にいたるまで,あらゆる岩石中に普遍的に存在し,年代情報のみならず岩石成因論や構造発達史にいたるまで,様々な地質情報を引き出すことが可能である.近年では,質量分析技術の向上や新規分析手法の開発が格段に進み,様々な岩石に応用された結果,我々に新しい地質観をもたらしつつある.そこで,本セッションでは,時代・地域・岩石種・分析手法を問わず,ジルコンを用いた様々な分野の具体的な研究例を集い,“ジルコン学”とも呼ぶべき対象を深く相互理解することを目指す.幅広い分野からの投稿(手法開発から応用例まで)を歓迎し,特に若手研究者の積極的な参加を期待する.
招待講演予定者:牛久保孝行(ウィスコンシン大マディソン校)
T8.新学習指導要領の実施で地学教育はどのように変わるか?/How with the enforcement of the new curriculum guidelines, does the earth science education change?
中井 均*(都留文大:hnakai@tsuru.ac.jp)・浅野俊雄・芝川明義(大阪府花園高)
Hitoshi Nakai*(Tsuru Univ.)・Toshio Asano・Akiyoshi Shibakawa(Hanazono Sinior High School)
学習指導要領の改訂に伴う移行処置は,小学校が2010年度,中学校が2011年度に終了し,ともに新課程に完全移行する.また高等学校では2012年度から新課程「地学基礎」・「地学」が始まる.学校教育(特に高等学校)の中での地学教育の地盤沈下が言われて久しいが,新学習指導要領の実施に伴い変化が起こることが期待される.新課程が始まる年にあたり,小学校から高等学校まで,学校現場でどのような変化が起きているか,
1.新学習指導要領による地学分野(小学校〜高等学校まで)の学習内容の変化とそれへの対応
2.高等学校「地学Ⅰ」・「地学Ⅱ」と「地学基礎」・「地学」の開設状況
3.「地学基礎」・「地学」に対応する副教材(実習帳など)の開発状況
など,様々な角度から検証する.
招待講演予定者:なし
ページtopに戻る
T9.地殻流体のダイナミズム その2/Dynamism of crustal fluids Part Ⅱ
竹下 徹*(北大:torutake@mail.sci.hokudai.ac.jp)・岡本和明(埼玉大)
Toru Takeshita*(Hokkaido Univ.)・Kazuaki Okamoto(Saitama Univ.)
本トピックセッションは,昨年開催の同名のトピックセッションに引き続くものである.地殻ダイナミクスにおいて流体の存在および移動は不可欠である.つまり,地殻の中で変形・変成作用が容易に起こるためには,流体の存在・移動が必須である.流体は拡散や元素移動に重要な役割を果たすほか,それ自身の移動が高速の熱の移動を引き起こし(熱移流),周囲の岩石中で変形や変成作用を引き起こす結果となる.前回(水戸大会)のトピックセッションでは,特に交代作用(メタソマティズム)に重点を置いたが,今回は特に圧力溶解など,流体の存在に強く影響を受ける岩石の変形機構に重点を置く.その理由は,東日本大震災が発生し,地震の準備過程をもう一度根本から研究する必要があると言われている今,流体の岩石変形に及ぼす効果が大変重要と考えられるからである.ただし,前回同様,構造地質学,岩石学,地球物理学等,幅広い分野からの発表を期待する.
招待講演予定者:飯尾能久(京都大防災研)
ページtopに戻る
T10.ジュラ系+(ジュラケイプラス)/The Jurassic +
松岡 篤*(新潟大:matsuoka@geo.sc.niigata-u.ac.jp)・小松俊文(熊本大)・近藤康生(高知大)・石田直人(新潟大)・中田健太郎(新潟大)
Atsushi Matsuoka*(Niigata Univ.)・Toshifumi Komatsu(Kumamoto Univ.)・Yasuo Kondo (Kochi Univ.)・Naoto Ishida(Niigata Univ.)・Kentaro Nakada(Niigata Univ.)
2003年静岡大会にて「ジュラ系」として誕生した本セッションは,隣接する地質系統の研究者の要望を取り込んで「ジュラ系+」として発展し,今年で10年目を迎える.この間,国際的なジュラ系研究は,ジュラ系基底のGSSP確定をはじめとする変革期にあったが,本セッションではその動向をいち早く伝え続けてきた.また本セッションは,講演タイトルが国際ジュラ系小委員会のNewsletterに収録されるなど,ジュラ系研究拠点としての日本を国際的にアピールする場ともなり,重要性は今後も増すものと考えられる.参加者は50人程度を見込んでおり,夜間小集会も申し込む予定である.区切りの10年を迎えた今年は,セッションの活動を総括した特集号も計画している.
招待講演予定者:岸本直子(摂南大)
T11.西南日本地体構造論の現代的問題点(市川浩一郎追悼セッション)/Current topics on geotectonics of SW Japan (Memorial Session for late Prof. Koichiro Ichikawa)
磯崎行雄*(東京大:isozaki@ea.c.u-tokyo.ac.jp)・前島 渉(大阪市大)・堀 利栄(愛媛大)
Yukio Isozaki*(Univ. Tokyo)・Wataru Maejima(Osaka City Univ.)・Rie Hori (Ehime Univ.)
1980年代前半におきた付加体と放散虫の研究ブームがすぎて,1990年代初頭にその成果がまとめられた後,約20年間大きなパラダイム変換が起きなかった.しかし2010年以降の最近の2年間に砕屑性ジルコン年代学の導入によって,新しいデータが得られるようになり,改めて地体構造の再定義が必要となっている.本セッションでは,新たな年代データ,それに基づく西南日本の地体構造区分,境界に関する問題点を整理し,解決の方向を探る.新たな地体構造単元の識別基準として現れた砕屑性ジルコン年代学による最新の成果を,かつての放散虫革命がおきた中心であった大阪での大会で総括し,さらにそれ以前の太平洋戦争後に当該分野で活躍された故市川浩一郎(大阪市立大)先生の追悼としたい.
招待講演予定者:青木一勝(東京大)
ページtopに戻る
レギュラーセッション:20件
R1.深成岩・火山岩とマグマプロセス/Plutonic rocks, volcanic rocks and magmatic processes(火山部会・岩石部会)
壷井基裕*(関西学院大:tsuboimot@kwansei.ac.jp)・道林克禎(静岡大)・長谷川健(茨城大)
Motohiro Tsuboi*(Kwansei Gakuin Univ.)・Katsuyoshi Michibayashi(Shizuoka Univ.)・Takeshi Hasegawa(IbarakiUniv.)
深成岩および火山岩を対象に,マグマプロセスにアプローチした研究発表を広く募集する.発生から定置・固結に至るまでのマグマの物理・化学的挙動や,テクトニクスとの相互作用について,野外地質学・岩石学・鉱物学・火山学・地球化学・年代学など様々な視点からの活発な議論を期待する.
R2.岩石・鉱物・鉱床学一般/General studies from petrology, mineralogy and economic geology(岩石部会)
野坂俊夫*(岡山大:nozaka@cc.okayama-u.ac.jp)・中野伸彦(九州大)
Toshio Nozaka*(Okayama Univ.)・Nobuhiko Nakano(Kyushu Univ.)
岩石学,鉱物学,鉱床学,地球化学などの分野をはじめとして,地球・惑星物質科学全般にわたる岩石及び鉱物に関する研究発表を広く募集する.地球構成物質についての多様な研究成果の発表の場となることを期待する.
R3.噴火・火山発達史と噴出物/Eruption, volcanic evolution and volcanic products(火山部会)
和田穣隆*(奈良教育大:ywada@nara-edu.ac.jp)・三好雅也(福井大)・長井雅史(防災科研)
Yutaka Wada*(Nara Univ. Education)・Masaya Miyoshi(Univ. Fukui)・Masashi Nagai(NIED)
火山地質ならびに火山現象のモデル化に関し,マグマや熱水性流体の上昇過程,噴火様式,噴火経緯,噴出物の移動・運搬・堆積,各火山あるいは火山地域の発達史,火山活動とテクトニクス・化学組成をはじめとする,幅広い視点からの議論を期待する.
R4.変成岩とテクトニクス/Metamorphic rocks and related tectonics(岩石部会)
外田智千*(極地研:hokada@nipr.ac.jp)・馬場壮太郎(琉球大)
Tomokazu Hokada*(NIPR)・Sotaro Baba(Univ. Ryukyu)
国内および世界各地の変成岩を主な対象に,記載的事項から実験的・理論的考察を含め,またマイクロスケールから大規模テクトニクスまで,様々な地球科学的手法・規模の視点に立った斬新な話題提供と活発な議論を期待する.
ページtopに戻る
R5.地域地質・地域層序/Areal geology/Stratigraphy(地域地質部会・層序部会)
松原典孝*(兵庫県立大:matsubara-n@stork.u-hyogo.ac.jp)・内野隆之(産総研)・岡田 誠(茨城大)
Noritaka Matsubara*(Univ. Hyogo)・Takayuki Uchino(AIST)・Makoto Okada(Ibaraki Univ.)
国内,海外問わず各地域に関係した地質や層序の発表を広く募集.地域的な年代,化学分析,リモセン,活構造,地質調査法等の発表も歓迎.ジオパークにおける学術研究の成果発表や地質災害地の地質,惑星地質もここに含まれる.地域を軸にした討論を期待する.地質図や断面図のポスター発表を特に歓迎する.
R6.地域間層序対比と年代層序スケール/Stratigraphy correlation/Chronostratigraphy(層序部会)
里口保文*(琵琶湖博物館:satoguti@lbm.go.jp)・岡田 誠(茨城大)
Yasufumi Satoguchi* (Lake Biwa Mus.)・Makoto Okada (Ibaraki Univ.)テフラ等の鍵層を用いて異なる地域間の層序対比に主体をおく研究や,鍵層そのものを主体とした研究,または複合的層序学等によるグローバルな年代層序スケールの構築に寄与するような研究についての講演を歓迎する.
R7.海洋地質/Marine geology(海洋地質部会)
荒井晃作*(産総研:ko-arai@aist.go.jp)・芦寿一郎(東大大気海洋研)・小原泰彦(海上保安庁)
Kohsaku Arai*(AIST)・Juichiro Ashi(AORI, Univ. Tokyo)・Yasuhiko Ohara(JCG)
海洋地質に関連する分野(海域の地質・テクトニクス・変動地形学・海域資源・堆積学・海洋学・古環境学・陸域地質での海洋環境変遷研究など)の研究発表を募集する.調査速報・アイデアの公表・海底地形地質・画像データなどのポスター発表も歓迎する.
R8.堆積物(岩)の起源・組織・組成/Origin, texture and composition of sediments(堆積地質部会)
太田 亨*(早稲田大:tohta@toki.waseda.jp)・野田 篤(産総研)
Tohru Ohta*(Waseda Univ.)・Atsushi Noda(AIST)
砕屑物の生成(風化・侵食・運搬)から堆積岩の形成(堆積・沈降・埋積・続成)まで,組織(粒子径・形態)・組成(粒子・重鉱物・化学・同位体・年代)・物性などの堆積物(岩)の物理的・化学的・力学的性質を対象とし,その起源・形成過程・後背地・古環境や地質体の発達史を議論する.太古代の堆積岩から現世堆積物まで,珪質岩・火山砕屑岩・風成塵・リン酸塩岩・蒸発岩・有機物・硫化物などについての研究も歓迎する.
R9.炭酸塩岩の起源と地球環境/Origin of carbonate rocks and related global environments(堆積地質部会)
山田 努*(東北大:t-yamada@m.tohoku.ac.jp)・比嘉啓一郎(福岡大)
Tsutomu Yamada*(Tohoku Univ.)・Keiichiro Higa(Fukuoka Univ.)
炭酸塩岩・炭酸塩堆積物の堆積作用,組織,構造,層序,岩相,生物相,地球化学,続成作用,ドロマイト化作用など,炭酸 塩に関わる広範な研究発表を募集する.また,現世炭酸塩の堆積作用・発達様式,地球化学,生物・生態学的な視点からの研究発表も歓迎する.
ページtopに戻る
R10.堆積相・堆積過程/Sedimentary facies and processes(現行地質過程部会・堆積地質部会)
成瀬 元*(京都大:naruse@kueps.kyoto-u.ac.jp)・市原季彦(復建調査設計)・横川美和(大阪工業大)
Hajime Naruse*(Kyoto Univ.)・Toshihiko Ichihara(Fukken Co. Ltd.)・Miwa Yokokawa(Osaka Inst. Tech.)
さまざまな環境で生じる堆積過程と堆積相の分類・記載・解釈に関する発表や,堆積相解析に基づく堆積システム・シーケンス層序学についての議論を広く募集する.さらに,堆積作用や地層形成のダイナミクスに関連する理論・アナログ実験・数値シミュレーション・現地観測等の研究発表を歓迎する.
ページtopに戻る
R11.石油・石炭地質学と有機地球化学/Coal and petroleum geology/Geochemistry(石油・石炭関係・堆積地質部会)
金子信行*(産総研:nobu-kaneko@aist.go.jp)・河村知徳(石油資源開発)・三瓶良和(島根大)
Nobuyuki Kaneko*(AIST)・Tomonori Kawamura(JAPEX)・Yoshikazu Sampei(Shimane Univ.)
国内外の石油・石炭地質および有機地球化学に関する講演を集め,石油・天然ガス・石炭鉱床の成因・産状・探査手法など,特にトラップ構造,堆積盆,堆積環境,貯留岩,根源岩,石油システム,資源量,炭化度などについて討論する.
R12.岩石・鉱物の破壊と変形/Rock failure and deformation(構造地質部会)
廣瀬丈洋*(JAMSTEC:hiroset@jamstec.go.jp)・丹羽正和(JAEA)・高橋美紀(産総研)
Takehiro Hirose*(JAMSTEC)・Masakazu Niwa(JAEA)・Miki Takahashi(AIST)
断層岩を含む岩石・鉱物の破壊および変形機構,変形微細構造,岩石・鉱物のレオロジーや物性に関する研究を募る.観察・観測・分析・実験・理論など多方面からのアプローチによる成果を歓迎するとともに,会場での活発な議論を期待する.
ページtopに戻る
R13.付加体/Accretionary prism(構造地質部会)
坂口有人*(JAMSTEC:arito@jamstec.go.jp)・内野隆之(産総研)
Arito Sakaguchi*(JAMSTEC)・Takayuki Uchino(AIST)
現世,過去を問わず,付加体に関するすべての講演を歓迎する.付加体の形成機構,形成史,微細構造,流体移動,シュードタキライト,温度圧力構造など,様々なアプローチによる成果をもとに議論する.
R14.テクトニクス/Tectonics(構造地質部会)
加藤直子*(東大地震研:naoko@eri.u-tokyo.ac.jp)・大坪 誠(産総研)・藤内智士(産総研)
Naoko Kato*(ERI, Univ. Tokyo)・Makoto Otsubo(AIST)・Satoshi Tonai(AIST)
地球科学の多方面から,大小様々な時間・空間スケールで起こる地質構造の成因や形成機構・発達史に関する講演を広く募集する.野外調査,観測,実験,理論などに基づいた研究発表を歓迎する.また,2011年3月に発生した東北地方太平洋沖地震やその地震に関連する地殻変動の研究成果も歓迎する.
R15.古生物/Paleontology(古生物部会)
平山 廉(早稲田大)・北村晃寿(静岡大)・太田泰弘(北九州博)・三枝春生(兵庫県立人と自然の博)・須藤 斎*(名古屋大:suto.itsuki@a.mbox.nagoya-u.ac.jp)
Ren Hirayama(Waseda Univ.)・Akihisa Kitamura(Shizuoka Univ.)・Yasuhiro Ota(Kitakyushu Mus.)・Haruo Saegusa(Mus. Nature and Human Activities, Hyogo)・Itsuki Suto*(Nagoya Univ.)
主として古生物を扱った,または,プロキシとして古生物を利用したものや古生物を用いた新手法などの研究の発表・討論を行う.
ページtopに戻る
R16.情報地質/Geoinformatics(情報地質部会)(ポスター発表のみ)
能美洋介*(岡山理大:y_noumi@big.ous.ac.jp)・野々垣進(産総研)
Yosuke Noumi*(Okayama Univ. Sci.)・Susumu Nonogaki(AIST)
地質情報の数理解析,統計解析,データ処理,画像処理などの理論,応用,システム開発,利用技術など,最近の情報地質分野の研究結果を対象とする.また,これらの成果の地質学の広い分野への応用・普及なども歓迎する.
R17.環境地質/Environmental geology(環境地質部会)
難波謙二( 福島大) ・風岡 修( 千葉環境研) ・三田村宗樹( 大阪市大) ・田村嘉之*( 千葉環境財団:y_tamtam3012@nifty.com)
Kenji Nanba(Fukushima Univ.)・Osamu Kazaoka(Res. Inst. Environ. Geol., Chiba)・Muneki Mitamura(Osaka City Univ.)・Yoshiyuki Tamura(Chiba Pref. Environ. Foundation)
地質汚染,医療地質,地盤沈下,湧水,水資源,湖沼・河川,都市環境問題,法地質学,環境教育,地震動,液状化・流動化,地震災害,岩盤崩落など,環境地質に関係する全ての研究の発表・討論を行う.
R18.応用地質学一般およびノンテクトニック構造/Engineering geology and non-tectonic geolory(応用地質部会)
小嶋 智(岐阜大)・須藤 宏*(応用地質:sudou-hiroshi@oyonet.oyo.co.jp)
Satoru Kojima(Gifu Univ.)・Hiroshi Sudo*(OYO Corp.)
応用地質学一般では,種々の地質ハザードの実態,調査,解析,災害予測,ハザードマップの事例・構築方法,土木構造物
の設計・施工・維持管理に関する調査,解析など,応用地質学的視点に立った幅広い研究を対象とする.また,ノンテクトニック構造では,ランドスライドや地震による一過性の構造,重力性の構造等の記載,テクトニック構造との区別や比較・応用等の研究を対象にして発表・議論する.
ページtopに戻る
R19.地学教育・地学史/Geoscience education/History(地学教育委員会)
矢島道子*(東京医科歯科大:pxi02070@nifty.ne.jp)
Mchiko Yajima*(Tokyo Med. and Dental Univ.)
新学習指導要領の施行は目前.現場からの問題提起,多くの実践報告を持ちより議論したい.また地学史からの問題提起,貴重な史的財産の開示を歓迎する.
R20.第四紀地質/Quaternary geology(第四紀地質部会)
公文富士夫*(信州大:shkumon@gipac.shinshu-u.ac.jp)・内山 高(山梨環境研)
Fujio Kumon*(Shinshu Univ)・Takashi Uchiyama(YIES)
第四紀地質に関する全ての分野(環境変動・気候変動・湖沼堆積物・地域層序など)からの発表を含む.また,新しい調査や研究,方法の開発や調査速報なども歓迎する.
ページtopに戻る
アウトリーチセッション:1件
OR.日本地質学会アウトリーチセッション/Outreach session(ポスター発表のみ)
星 博幸*(愛知教育大:hoshi@auecc.aichi-edu.ac.jp)・須藤 斎(名古屋大)
Hiroyuki Hoshi(Aichi Univ. Education)・Itsuki Suto(Nagoya Univ.)
会員が研究成果を社会へ発信する場として今大会から新たに設けられたセッション.地質学と関連分野を対象とし,開催地(近畿,大阪)とその周辺の地質や地学に関する研究紹介,社会的に注目されている地質および関連トピックの研究紹介,特定分野の研究到達点や課題の解説など.申込多数の場合は行事委員会にて採否を検討する.アウトリーチセッションの詳細はこちらもご参照ください.
宿泊・観光関連情報
□■□■□■□■□■□ 宿泊関連情報 □■□■□■□■□■□
学会では宿泊予約の申込は受け付けておりません。
各自でご予約をお願いいたします。
■日本旅行:宿泊申込サイト■
(日本地質学会大阪大会専用)
■堺市ホテル協会 加盟ホテルリスト■
*************** お願い ***************
堺市内の宿泊施設への宿泊数に応じて,堺観光コンベンション協会より助成金が支給されることになっています.
堺市内の宿泊施設へ宿泊される方は,会期当日,受付にて宿泊施設への提出書類をお渡しいたしますので,ご協力お願い申し上げます.
***********************************
□■□■□■□■□■□ 観光関連情報 □■□■□■□■□■□
■堺市の観光情報:堺観光ガイド■
■大阪の観光情報:OSKA-INFO■
参加登録TOP
★当日の受付について(事前登録をされた方/登録をしていない方)★
2012大阪大会事前参加登録ほか申込
事前参加登録は締切ました。
申込後の変更・取消
(a)大会登録専用HP(オンライン)でお申込みの場合:締切までの間は,2012年大阪大会ホームページから予約の変更・取消が出来ます.変更・取消完了後,「変更・修正 確認メール」が登録のメールアドレスへ配信されます.内容を必ずご確認下さい.締切後は直接学会事務局にFAX又はe-mailにてご連絡下さい.クレジット決済の場合は,申込の都度決済が完了しますので,決済スケジュールの都合によっては,口座から重複して引き落とされる場合があります.その場合は,振込手数料を差し引いた額をクレジットカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2-3ヶ月要する場合もありますので,ご了承下さい.
(b)FAX・郵送でお申込み場合:申込後に変更・取消が生じた場合は,日本地質学会宛FAXまたはe-mailにてご連絡下さい.その際申込受付時に案内される「受付番号」・「氏名」を必ず明記下さい.
取消に関わる取消料と返金について (お弁当と巡検は取消料が異なります:下記参照)
(a)締切までの取消:取消料は発生しません.返金がある場合は,振込手数料を差し引いた額をクレジットカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2-3ヶ月要する場合もありますので,ご了承下さい.
(b)締切後〜9/12(大会3日前)までの取消:入金・未入金の如何に関わらず,参加費用の60%を取消料としていただきます.返金がある場合は,振込手数料を差し引いた額をクレジットカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2-3ヶ月要する場合もありますので,ご了承下さい.参加費に講演要旨集が付いている方へは,大会後にお送りします.
(c)9/13(大会2日前)以降の取消:入金・未入金の如何に関わらず,参加費用の100%を取消料としていただきます.参加費に講演要旨集が付いている方へは,大会後にお送りします.
*巡検の取消料:申込締切後〜出発3日前までは50%,2日前以降は全額となります.
*お弁当の取消料:お弁当利用日より9日前〜前日までは50%,当日は100%の取消料がかかります.
連絡先:日本地質学会事務局(東京)e-mail: main@geosociety.jp FAX 03-5823-1156
参考>>会員情報を自動取得するには?(PDF)
事前参加登録は締切ました。
■日本地質学会会員の方
■非会員(招待講演者,一般,院生,学部学生)の方
■共催団体会員の方
■巡検J班(教員巡検)のみに参加する非会員の地学教育関係者の方*1
■年会には参加せず,冊子のみ購入希望の方
(参加登録は,同伴される会員のご家族分1名分まで,あわせてお申し込み頂けます)
*1:地質学会会員で地学教育関係者の方は,一番上の『日本地質学会会員の方』の画面からお申込下さい
<申込締切 オンライン:8月17日(金)18:00,FAX/郵送:8月10日(金)必着>
*FAX・郵送専用申込書(PDF)はこちら
*申込方法・支払い方法の詳細は下記ページをご覧下さい.
参加フォームから申し込める項目:クリックすると各詳細のご案内をご覧いただけます。
■ 参加登録費
■ 追加講演要旨(大会不参加で冊子のみの購入も可)
■ 巡検 *注意*今年は冊子体での巡検案内書の作成・販売はありません
■ お弁当
■ 懇親会
講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理,引用方法,校閲について
講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理,引用方法,校閲について
(1)講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理
日本地質学会は,当会出版物への投稿原稿に対して,その倫理性について著作者が保証する「保証書」,および著作権を日本地質学会へ譲渡することに同意する「著作権譲渡同意書」に,署名捺印をして提出していただいております.今大会でも,電子投稿のため,画面上で「保証書」と「著作権譲渡等同意書」の内容に同意していただいた場合に限り,電子投稿画面に進むことができるようになっています.郵送の場合は「保証及び著作権譲渡等同意書」に署名捺印し,講演要旨原稿と共にお送り下さい.「保証及び著作権譲渡等同意書」が同封されていない発表申込は受け付けません.
■「保証及び著作権譲渡等同意書」(PDF)ダウンロードはこちらから■
(2)講演要旨における文献引用
講演要旨原稿の中に引用文献を必ず記載して下さい.講演要旨では,引用文献の記載を簡略化することが認められています.著者名,発表年,掲載誌名など,文献を特定できる必要最低限の情報を明記して下さい.
(3)講演要旨の校閲
行事委員会は,講演要旨について,学会の目的ならびに倫理綱領(定款第4条)に反していないかという点について校閲を行います.校閲によりいずれかの条項に反していると判断された場合,行事委員会は発表内容の修正を求めるか,あるいは発表申込を受理しないことがあります.行事委員会の措置に同意できない場合,発表申込者は法務委員会(学会事務局気付)に異議を申し立てることができます.法務委員会は直ちに審理し,結論を行事委員会ならびに異議申立者に伝えることになります.異議申立てに関する詳細は下記を参照してください.なお,校閲は招待講演に対しても行います.
講演申し込み異議申し立てについて
日本地質学会行事委員会は,学術大会において学会の目的及び倫理規定に反する講演申し込みのあった要旨に対して,修正あるいは,受理を拒否することができます.法務委員会では,日本地質学会行事委員会規約に基づき,異議申立の手続及びその処理についての規則を定めています.
日本地質学会法務委員会
■日本地質学会学術大会講演申込異議申立に関する処理機構規則(PDF)■
託児室
託児室
<利用申込締切 8月24日(金)現地事務局申込>
(1)開設日時:9月15日(土)〜17日(月)8:30〜18:30
(※時間延長につきましては現地事務局までお問い合せください)
(2)対象:参加者を保護者とする生後3ヶ月から小学生迄のお子様.
(3)場所:きらら保育園プティット堺ルーム 堺市認証保育所(予定)
所在地:大阪府堺市北区百舌鳥陵南町3-35
Tel 072-279-7355 http://www.kirara-sakai.com/
(4)アクセス:地下鉄御堂筋線中百舌鳥駅下車 徒歩18分 JR阪和線上野芝駅下車 徒歩16分
(5)ご利用をご希望の方は現地事務局までお問合わせください.
*万が一の場合に備え,施設加入の損害保険で対応させていただきます.なお,託児施設のご利用に際しては実行委員会・日本地質学会は責任を負いかねますのでご了承ください.
講演要旨の作成の注意点とPDFファイル作成の作り方
講演要旨の作成の注意点とPDFファイル作成の作り方
講演要旨を作成する際,著者には「保証及び著作権譲渡同意書」第1項の「保証」内容を守って頂きます.行事委員会は,要旨の内容については関知しませんが,当該「保証」内容を逸脱するものがないか校閲します.その結果,不適当とみなされる場合は,修正されるまで講演要旨を受理しません(不服の場合は法務委員会に訴えることが可能です).例年最も多い問題点は,引用文献の表示がない場合です.論文のように細かに引用文献を記載することはスペースの都合上不可能なので必要としませんが,雑誌名,号,ページ等,その文献にたどり着ける最低限の情報は記載して下さい.
また,要旨の体裁を無視している場合,印刷できませんので体裁を整えて頂くことになります.さらに図等の改変については,著作権法,地質学会著作物利用規定に従って下さい.
このほか,PDFファイルにフォントを埋め込んでいないもの(印刷時に文字化けすることがあります),要旨作成時に講演番号記入用のスペースがなかったり,余白に無理があるといった場合,体裁を整えるため修正をお願いしています.これらの問題点があった場合,世話人より投稿締切日から1週間をめどに修正依頼が届きます.ただ,その労力はセッションによっては膨大になりますので,あらかじめ完全なものを投稿するようご協力下さい.あわせて講演要旨投稿手順のチェックシートもご参照下さい.
日本地質学会 行事委員会
2011年4月
■要旨テンプレート(Microsoft Word)■ ■講演要旨投稿手順のチェックシート■
【講演要旨PDFファイル作成時の注意点】
1)
講演要旨原稿はAdobe Acrobat Reader 4.0 以上で表示・印刷可能なPDFファイルで投稿することが必要です.
2)
ファイルサイズは3.0Mバイト以内で作成して下さい.
3)
発表(講演)番号は事務局にて左上に付記するので原稿内には記載しないで下さい.
4)
PDFファイルのセキュリティ設定は「なし」にして下さい.
5)
フォントは必ず「埋め込み」にして下さい.MacOSX以上は標準でフォント埋め込みが用意 されます.MacOS9.2.2以下,Windowsでは下記のソフトが必要です.その際,『すべてのフォント埋め込み』ないし『ハイクォリティー』等, それぞれのソフトの使用説明書に従った指定を必ずして下さい.文字数にもよりますが,できたPDFファイルのサイズが100KB未満の場合,フォントが埋 め込まれなかった可能性がありますので確認して下さい.
6)
作成したPDFファイルを自分で印刷し,図表に充分な解像度があるか,文字化けはないか確認して下さい.
7)
PDFファイルを自分のパソコンに,必ず「.pdf」の拡張子をつけて保存して下さい(Mac, Windowsとも).
■原稿フォーマット見本■
お願い!!共同発表の場合,講演要旨には発表者氏名に下線を引いて下さい.
テンプレート
(Microsoft Word)
ダウンロードはこちら
【webでの講演要旨投稿の手順】
1)
参加申し込みの後,web上の講演申し込みページで,講演申し込みの手続きをします(講演申込と同時に要旨投稿をすることもできますし、講演要旨のみ後で投稿する事もできます).
2)
演題・発表者情報登録画面の最下段にある「アップロードファイル」欄から要旨原稿(PDFファイル)を投稿します.欄右側の「参照」ボタンをクリックし,ご自分のPCに保存してあるPDFファイルを選択します.
3)
画面下の「次へ」をクリックし,登録内容確認画面に進みます.登録内容を確認後,画面下の「登録」ボタンをクリックします.これによりサーバーにPDFファイルが格納されます.
4)
『登録が完了いたしました.受付番号は*****です.』という完了画面が表示されます.(注意!!この画面が表示されないと登録は完了していません)
5)
登録したメールアドレスに「講演申込のお知らせ」のメールとともに受付番号(=ID)が配信されます.
★★後から要旨を投稿する場合・申込内容を変更する場合★★
1)
IDとメールアドレスでログイン:ご自分の申込画面に,IDとメールアドレスを用いてアクセスします.
2)
新しい講演要旨PDFファイルをアップロード:「登録内容変更」ボタンをクリックし,画面の最下段にある「アップロードファイル」欄の「修正」ボタンをクリックします.ご自分のPCに保存してあるファ イルを選択し,アップロードをします.サーバー側では,ファイル名を元のファイル名から変更し,ID.pdfの名称で格納します.
3)
完了画面の確認:『登録が変更されました.受付番号は*****です.』という操作完了画面が表示されます.(注意!!この画面が表示されないと操作は完了していません)
4)
変更確認めーるが配信されます:「講演申込内容変更のお知らせ」メールが配信されます.
5)
IDとメールアドレスを用いて,投稿締切まで何度でも要旨や登録内容 を修正することができます.新しいファイルを投稿すると,古いファイルに上書きされます.そのつど,「講演申込内容変更のお知ら せ」メールが配信されます
【参考情報:PDF(Portable Document Format)ファイルの作り方】
PDFファイルの作成方法は「PDF原稿作成ガイド」http://www.gakkai-web.net/pdf/を参考にすると良いでしょう.
ソフトの紹介要望が多いので,下記にいくつか参考例を挙げます.また,"PDF作成サービス"を行う有料,無料のサイトがあります.ソフト,サイトとも検索してみて下さい.なお下記について動作確認等しておりません.また推奨するものでもありません.ご了承ください.
◯ Mac OSXの場合
フォント埋め込み型のPDF作成機能が標準で用意されています.新たなソフトは必要ありません.
◯ Mac OS 8.6-9.2の場合
Adobe Acrobat(それぞれのOS対応品,現在販売されているか不明)
EGWORD Ver.12 for Mac OS X/9/8.6(現在販売されているか不明)
◯ Windows対応品
PrimoPDF FreeのPDF変換ソフト http://www.primopdf.com/
クセロPDF PDF変換ソフト http://xelo.jp/xelopdf/
いきなりPDF 2000円弱 http://www.sourcenext.com/products/pdf/
Adobe Acrobat Elements 5000円弱 http://www.adobe.co.jp/
◯ MacOS9.2.2,MacOSX, Windows対応
Adobe Illustrator http://www.adobe.co.jp/
懇親会・弁当
懇親会
申込締切
オンライン: 8 月17日(金)18:00,
FAX・郵送: 8 月10日(金)必着
■ WEB参加登録画面はこちら ■
懇親会は,9月15日(土)表彰式・記念講演会終了後,大学生協食堂において行います(18:00頃〜19:30).
事前予約会費
正会員
5000円
名誉会員・50年会員・院生割引・学部割引・会員の家族
2500円
非会員の会費は正会員に準じます.準備の都合上,前金制の予約参加とします.たくさんの方々,特にポスドク,院生などの若手会員のご参加をお待ちしております.余裕があれば当日参加も可能ですが,予定数に達し次第〆切ります.当日会費は1,000円高くなります.大会参加申込と合わせてお申し込み下さい.当日はクーポンを受付にご持参下さい.参加取消の場合でも懇親会費の返却はいたしませんのでご了承下さい.
お弁当予約販売
申込締切
オンライン: 8 月17日(金)18:00,
FAX・郵送: 8 月10日(金)必着
■ WEB参加登録画面はこちら ■
9月15日(土)〜9月17日(月)には昼食用の弁当販売をいたします(1個700円,お茶付き).大会参加申込と合わせてお申し込み下さい.お弁当利用日より9日前〜前日までは50%,当日は100%の取消料がかかります.なお,9月15日(土)〜17日(月)は,昼食時のみ大学生協食堂が営業いたします.購買部の営業はいたしませんので,大学の中百舌鳥門前のコンビニエンスストア等をご利用ください.
要旨投稿チェックシート
講演要旨オンライン投稿手順チェックシート
講演要旨の投稿手順および基本的注意事項です.投稿していただく前に各自でご確認下さい.
1.Word等のソフトで講演要旨原稿を作成します.
「保証及び著作権譲渡同意書」第1項の「保証」内容は守られていますか?
要旨原稿内に引用文献は表示されていますか?
要旨の体裁は守られていますか?(詳細は要旨原稿フォーマットをご確認下さい)
2.原稿をPDFファイルにします.
PDFファイルの作成方法については,「PDFファイルの作り方」を参照して下さい.
フォントは「埋め込み」になっていますか?(できたファイルサイズが100KB未満の場合,フォントが埋め込まれなかった可能性がありますので確認して下さい)
ファイルサイズは3.0MB以内になっていますか?
作成したPDFファイルを印刷し,図表に充分な解像度があるか,文字化けはないか確認して下さい.また,PDFファイルを自分のパソコンに,必ず.pdfの拡張子をつけて保存して下さい.
3.原稿をオンライン投稿します.
web画面から参加申し込みを行いましたか?
講演申し込みページで,講演申し込みの手続きをしましたか?
講演要旨を投稿しましたか?
申込完了画面が表示されましたか(ログイン用のIDが表示されましたか)?
「講演申込のお知らせ」のメールが配信されましたか?
4.一度投稿した原稿を修正したい場合
ご自分の申込画面に,IDと申込時に設定したパスワードを用いてアクセスします.
画面中のPDFファイルのアイコンをクリックし,要旨原稿投稿画面を開きます.書き直した要旨のファイル選択し,投稿動作をします.
修正原稿が受け付けられると,「申込内容変更のお知らせ」メールが配信されます.(締切まで何度でも修正できます).
←講演要旨投稿手順に戻る
当日の受付について
当日の受付について
事前参加登録につきましては,8月17日に締め切りました.
入金済みの事前登録者には締切後,確認書2枚(本人控・受付提出用)と名札,懇親会とお弁当のクーポンを発送します.大会開催10日前には参加者の皆様のお手元に届くようお送り致します.締切時点で入金確認が取れない場合は,未入金の旨記載された確認書のみ送付いたしますので当日会場にて確認書をご提示いただき,入金
の確認をして下さい.入金とクーポン発送が入れ違いの場合は,振込み時の控え等を会場にお持ちください.
当日確認書やクーポンを忘れた方は,専用の確認用紙に申込内容をご記入いただき,受け付けを済ませてください.確認がスムーズに行えますよう,ご協力をお願い致します.なお,別途領収書が必要な方は会場受付でその旨お申し出ください.当日のお支払いは,現金のみの取扱いとなります.クレジットカードはご利用いただけません.
事前参加登録者
入金済の方へ→事前登録者には締切後,確認書2枚(本人控・受付提出用)と名札,懇親会とお弁当のクーポンを発送します.
未入金の方へ→締切時点で入金確認が取れない場合は,未入金の旨記載された確認書のみ送付いたします.
事前登録者用受付にて,確認書に記載されている項目ごとに受付して下さい.
受付にてネームカードホルダーをお渡ししますので『参加証(名札)』を入れ,大会期間中は身に付けてくだ
さい.
1 .確認書の提出(全員)→ネームカードホルダーの配布.要旨付きの場合は,要旨の配布
2 .講演要旨追加購入(予約購入者のみ)→要旨の配布
3 .懇親会→参加者は直接懇親会会場でクーポンを提示してください.
4 .お弁当(予約者のみ)→お弁当の引き換え時にクーポンを提示してください.
5 .巡検(参加者のみ)→名簿確認と参加最終確認
注:未入金者の方は,総合受付で入金確認した後,懇親会やお弁当のクーポンをお渡しします.
→申込の取消・取消料についてはこちらから
事前登録をしていない方
1 . 当日は必ず参加登録をしてください.参加登録費の有料・無料に関わらず備え付けの『参加登録票』に必要事項を記入し当日用受付へ
2 . 当日参加登録費(講演要旨集付きです.要旨集が不要の場合でも割引はありません)
---正会員:9,500円
---院生割引会費適用正会員:6,500円
---学部学生割引適用正会員・名誉会員・50年会員・非会員招待講演者・学部学生(会員・非会員問わず):無料(講演要旨は付きません)
---非会員(一般):15,000円・
---非会員(院生):9,500円
3 .講演要旨当日販売
---会 員:4000円
---非会員:5500円
4 .懇親会の当日参加費(ただし,人数に余裕がある場合に限る)
---正会員・非会員(一般):6,000円
---名誉会員・50年会員・院生および学生割引適用正会員(家族および非会員院生・学生含):3,500円
その他の申込TOP
その他
■ランチョン・夜間小集会
■事務局主催 シニア昼食会 (9/17)どなたでもお気軽にお集り下さい
■託児室の利用
事務局主催シニア昼食会のお誘い
事務局主催シニア昼食会のお誘い
事務局主催シニア昼食会のお誘い
大阪大会にご参加いただくシニア会員の方々と事務局職員の昼食会を今年も予定しています.
年会の合間のひと時,軽い昼食と近況談義などできれば,楽しいかと思います.ここでのシニアの定義は特にありません.我こそはシニア,私もシニア,シニアではない方も,どなたでもお気軽にお集まり下さい.
日 時 2012年9月17日(月)(大会最終日)12〜14時
食事処 未定
会 費 未定(低額)
申 込 9月16日(日)(会期の中日)まで受付ます(担当 橋辺)
地質学会事務局(電話 03-5823-1150)
※会期中は会場内の学会本部の部屋(B3棟3F)
大阪大会関連情報
大阪大会関連情報
(行事委員会)
■国際ワークショップ「The Geology of Japan」を開催します
■復旧復興にかかわる調査・研究事業の成果発表会を開催します
国際ワークショップ「The Geology of Japan」を開催します
【趣旨】
日本列島の地質をテーマとした書籍はこれまで多数出版されていますが,それらの多くは日本語で書かれています.海外への情報発信のためには最新研究成果を含む英語版書籍の出版が必要不可欠ですが,この20年間出版されていない状況です.この空白域を埋めるために,このたびイギリス地質学会が出版する「The Geology of Japan」と題する書籍に日本地質学会が執筆やワークショップ開催等を通じて協力する運びとなりました.これは,日本列島を地域あるいは地質帯で区分し,それぞれの地質概説と形成モデルを簡潔にまとめるとともに,主要露頭や日本の地質を紹介する巡検コース案内から構成される予定です.出版計画の主旨を会員に理解していただくとともに,会員からのコメントを参考にして書籍に収録する内容を充実させるために,大阪大会において学会主催の国際ワークショップを開催します.発表は主要執筆予定者に依頼し,口頭及びポスター形式とします.なお,海外研究者の出席も予定しているため,本ワークショップの使用言語は英語とします.
【世話人】
ウォリス サイモン(名大),石渡 明(東北大),平 朝彦(JAMSTEC),小島 知子(熊本大)
【開催日時】9月16日14:30-18:25(予定)
【会場】B3教育棟1階,第3会場
発表の詳細は,プログラムをご参照ください.
International Workshop on ‘The Geology of Japan’
Workshop summary:
In recent years several works have been published in the Japanese language on the theme of the geology of the Japanese islands. In order to make this information available to an international audience, there is a great need for similar works in English. However, none has been published for more than 20 years. To help fill this gap, a new project has been started working with the Geological Society of London to produce a book entitled 'The Geology of Japan'. The book will be divided into sections treating different geological or geographic regions of the Japanese Islands, each presenting an overview of the relevant geology and a summary of available formation models. In addition, the book will present information on important outcrops and include a section with a geological field guide. To promote the project amongst the members of the Geological Society of Japan and to provide an opportunity for feedback from the members to help improve the final contents of the book, the Geological Society of Japan will hold an international workshop at the upcoming annual meeting in Osaka. The presentations will be solicited from the main book contributors and both oral and poster presentations will be considered. Because we are expecting guests from abroad to attend, this workshop will be held in English.
Conveners:
Simon WALLIS (Nagoya Univ.), Akira ISHIWATARI (Tohoku Univ.), Asahiko TAIRA (JAMSTEC), Tomoko KOJIMA (Kumamoto Univ.)
Schedule:
September 16th (2nd day), pm
復旧復興にかかわる調査・研究事業の成果発表会を開催します
日時:2012年9月15日(土) 〜17日(月)
場所:大阪大会ポスター会場(大阪府立大学学術交流会館)
一般社団法人日本地質学会は社会貢献事業の一環として,2011年3月11日に発生した東日本大震災に関する学術的な復旧・復興事業を会員から公募し,2011年度に下記の6件が採択され,調査・研究が実施されました. すでにニュース誌で標本レスキュー関係の報告記事が掲載されていますが,大阪大会では,ポスター会場でその成果を毎日2件ずつ発表しますので,ぜひ訪れてください.なお,この復旧復興事業プランの公募は,2012年度も規模を縮小して継続しており,7月末段階で,2件の応募が届いています.
2011年度に採択された下の6件の調査・研究成果を,2件ずつ3日に分けて展示します.
9月15日(土)(除染関係)
・ 放射性セシウムに汚染された水田土壌のカヤツリグサ科マツバイによるファイトレメディエーション.榊原正幸・佐野 栄
・ 福島第一原子力発電所周辺の放射線量の測定方法と地質学的除染方法の検討.上砂正一
9月16日(日)(標本レスキュー関係)
・ 歌津魚竜館大型標本レスキュー事業.永広昌之(News誌2012年3月号掲載)
・ 陸前高田市立博物館地質標本救済事業.大石雅之(News誌2012年5月号掲載)
9月17日(月)(応用地質学・環境地質学的視点からの液状化,除染関係)
・ 関東平野内陸部の住宅地での盛土材質の相違による液状化要因の解明.ト部厚志
・ 微生物による放射性物質の除洗の実証実験.高橋正則
日本地質学会理事会
東日本大震災復旧復興事業プランWG
優秀ポスター賞
優秀ポスター賞
今大会でも学術発表の優秀ポスターに対して「日本地質学会優秀ポスター賞」を授与します.毎日3〜5件の予定です.受賞者には学会長から直接賞状を授与します(表彰と写真撮影).受賞ポスターは,その栄誉をたたえ,大会期間中,別途設けるボードに掲示します.大会終了後,News誌(年会報告記事)に氏名,発表題目,受賞理由を掲載します.
【審査】
審査は各賞選考委員会が行い,学会長がこれを承認します.選考委員会は日替わりで,行事委員会委員5名,大会実行委員会代表1名および各賞選考委員会委員2名の合計8名により構成されます.選考委員氏名は大会終了後に公表します(News誌11月号を予定).
【審査のポイント】
・ (研究内容)オリジナリティ
・ (プレゼンテーション)レイアウト・中心点の明示・わかりやすさ・美しさ・斬新さ
【審査結果の発表時間と方法】
発表は16:00以降に行います.表彰は決定後直ちにポスター会場で行います(ただし初日(15日)のみ表彰式会場にて行う予定).審査結果は掲示板,廊下等,要所に貼り出します.受賞ポスターには受賞花をつけます.
大会期間中の食事
大会期間中のお食事について
大会期間中のお食事について
◯お弁当予約販売(予約申込は締切りました).
予約弁当は,B3棟入口(Uホール側)で配布します.引き換えのクーポンを忘れずにお持ち下さい.
◯生協食堂
会期中の9 月15日(土)〜17日(月・祝) 11:30〜14:00(17日のみ13:30まで)に営業します.
(ニュース8月号掲載の内容から営業時間が変更となっています。ご注意下さい)
注意:生協購買部は営業しませんので,中百舌鳥門前のコンビニエンスストア等をご利用ください.そのほか,中百舌鳥キャンパス周辺に飲食店があります.
懇親会
懇親会
懇 親 会
日時:9月15日(土)18:00〜20:00
会場:大阪府立大学生協食堂
原則として予約制です(予約は8月17日に締め切りました).人数に余裕があれば当日参加の申込みも可能です.会場受付で確認し,当日参加の申込みをしてください.その場合の会費は,正会員・非会員(一般)6,000円,名誉会員・50年会員・院生割引会費適用正会員・学部割引適用正会員および会員の家族は3,500円です.非会員の会費は正会員に準じます.
仙台大会
2013仙台大会TOP
日本地質学会第120年学術大会(仙台大会)
...
日本地質学会第120年学術大会
(仙台大会)
2013年9月14日(土)〜16日(月・祝)
会場:東北大学 川内北キャンパスほか
【 大会趣旨 】
共催:
東北大学理学研究科,東北大学災害科学国際研究所,東北大学東北アジア研究センター,東北大学学術資源研究公開センター
後援:
全国地質調査業協会,東北地質調査業協会,宮城県教育委員会(普及事業),仙台市教育委員会(普及事業の一部),河北新報社(普及事業の一部),TBC東北放送(普及事業の一部)
協賛:
(公財)仙台市観光コンベンション協会
悪天候に見舞われましたが、無事盛会のうち終了いたしました。
来年は鹿児島でお会いしましょう。
2014年9月13日(土)〜15日(月・祝)[予定]
会場: 鹿児島大学 ほか
>>>>> 市民講演会開催について <<<<<
予定通り、開催いたします。(10時時点)
ただし、ご来場の際は、台風の状況も踏まえ、無理をなさらず、気をつけてお越しください。
※※演題登録・事前参加登録の受付は終了しました。※※
>>>>> 大会期間中のお食事について <<<<<
★ 新着情報 ★
8/29
各講演プログラムを掲載しました CHECK
事前申込した方へ:確認書等を発送しました
7/23
全体日程表を掲載しました
7/19
若手会員のための業界研究サポート(旧:就職支援プログラム)出展受付開始
緊急展示について(8/30締切)
6/14
宿泊申込サイトオープン!
6/10
巡検M班中止のお知らせ 【中止】
『プレス発表会へのご協力のお願い』を掲載しました。
6/5
事前参加登録の申込受付を開始しました
5/27
講演申込の投稿受付を開始しました
5/23
講演申込を予定しているが,まだ入会手続きをされていない方へ 【重要】
4/19
仙台大会巡検の見どころを掲載しました。
4/8
シンポジウム,セッション決定!
3/19
レギュラーセッションの再編や招待講演について
2013/01/11
仙台大会 東北支部東北大学にて開催
トピックセッション募集(締切:3/11)
新着情報
新着情報 2013仙台大会
2013.8.29更新 各講演プログラムを掲載しました
■■■
各講演日、講演種別ごとのプログラムを掲載しました。8/30発送のNews誌8月号にも掲載されています。
詳しくはこちらから
2013.8.29更新 事前申込をされた方へ:確認書等を発送しました
■■■
事前申込をされた方へ、当日の受付にてご提出いただく確認書等を発送しました。当日忘れずにご持参ください。
詳しくはこちらから
2013.7.23更新 全体日程表を掲載しました。
■■■
全体日程表を掲載しました。各講演ごとのプログラムは現在作成中ですので、掲載までお待ち下さい。
詳しくはこちらから
2013.7.19更新 若手会員のための業界研究サポート(旧:就職支援プログラム)出展受付開始
■■■
若手会員のための業界研究サポート(旧:就職支援プログラム)へ出展募集を受け付けています。
詳しくはこちらから
2013.7.19更新 緊急展示について(8/30締切)
■■■
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害調査報告や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コーナー」を設けます.(8/30締切)
詳しくはこちらから
2013.6.14更新 宿泊申込サイトオープン
■■■
宿泊申込のサイトがオープンしました。学会では宿泊予約の申込は受け付けておりませんので、各自でご予約をお願いいたします。
申込はこちらから ▶▶ http://ec-knt.jp/jgs120/index.html
2013.6.10更新 巡検M班中止のお知らせ
■■■
仙台大会の巡検コースについて,巡検案内者の都合により,下記コースは中止となりました。申込受付開始後の変更のため,皆様にはご迷惑をおかけ致しますが,何卒ご了承下さい。 すでにお申込を頂いた方は,事務局よりキャンセルのお手続きをさせて頂きます。
M班 2008年岩手・宮城内陸地震による斜面災害(案内者 川辺孝幸・籾倉克幹)
2013.6.10更新 『プレス発表会へのご協力のお願い』を掲載しました。
■■■
「特筆すべき研究成果」のプレス発表会へのご協力のお願いを掲載しました。
詳しくは,こちらから
2013.6.5更新 事前参加登録の受付を開始しました
■■■
事前参加登録の受付を開始しました。締切は,8月20日(火)18時(郵送8月16日(金) 必着)です。
なお,巡検のみ8月9日(金)18時締切です。
詳しくは,こちらから
2013.5.27更新 講演申込の投稿受付を開始しました
■■■
講演申込の投稿受付を開始しました。締切は,7月2日(火)17時(郵送 6月26日(水) 必着)です。
講演申込要領・発表要領の内容を確認の上,お申し込みください。
2013.5.23更新 講演申込を予定しているが、まだ入会手続きをされていない方へ
■■■
至急、入会申込書を学会事務局宛に郵送して下さい(7/2必着)。
WEB画面から講演申込操作は現時点でも可能です。入力の際、会員番号欄は空欄のまま操作を進めて下さい。また会員種別欄では『入会申込中』を選択して下さい。
申込締切時点(7/2)で入会申込書が到着していないと、申込が受理されてませんので、必ず入会申込書を郵送して下さい。
2013.4.19更新 仙台大会巡検の見どころを掲載しました。
■■■
今年は13コースを予定しています。
各コースの見どころはこちらから
2013.4.8更新 シンポジウム、セッション決定!
■■■
シンポジウム,トピック/レギュラーセッションが決まりました。
詳しくは、こちらから
2013.3.19更新 レギュラーセッションの再編や招待講演について
■■■
昨年の学術大会(大阪大会)において「学術大会の改革:オープンディスカッション」という公開会議が開催され,学術大会の活性化と本学会の発展,さらには地質学の発展につながるような方策について意見が交わされました(ニュース誌,15(11),29-30).その議論を受けて,行事委員会は現在,レギュラーセッション(以下,RS)の再編やRSでの招待講演について検討を進めています.
詳しくは、こちらから
2013.1.11更新 トピックセッション募集(2013/3/11締切)
■■■
トピックセッション募集締切:2012年3月11日(月)*今年もシンポジウムの公募は行いません。ご注意ください。
詳しくは、こちらから
2013.1.11更新 日本地質学会第120年学術大会(仙台大会)開催
■■■
日本地質学会は,東北支部の支援のもと,東北大学川内北キャンパス(仙台市)をメイン会場として2013年9月14日(土)〜16日(月)に開催いたします.開催通知はこちらから
緊急展示の申込について
緊急展示
会場:C棟ポスター会場
問い合わせ先:行事委員会(main@geosociety.jp)
担当:鈴木紀毅(仙台大会実行委員会)・須藤 宏(行事委員会)
緊急展示の申込について
緊急展示の申込について
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害調査報告や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コーナー」を設けます.ポスター展示を希望する方は,8月30日(金)までに次の内容を下記申込先にご連絡ください.
1)発表要旨PDF(ニュース誌5月号参照)
2)緊急展示の必要性
3)発表代表者と連絡先
4)希望枚数(1枚:幅90×180cm)
5)展示に関わる要望(2〜5の様式は自由)
実行委員会は行事委員会と協議し,可否の判断を致します.希望にはできるだけ応えるようにしますが,展示方法等については実行委員会の指示に従ってください.
申込先:<main@geosociety.jp>
担当:鈴木紀毅(仙台大会実行委員会)・須藤 宏(行事委員会)
確認書・クーポン等の送付について
事前参加登録:確認書・クーポン等の送付について
2011.8.29
事前参加申込を頂いた方に対して、申込内容に応じて確認書2枚(本人控・受付提出用)等をお送り致しました(8/29発送)。
受付提出用の確認書、名札、クーポンを当日忘れずにご持参下さい。
<< 入金者の方へ >>
確認証・参加証(名札)・クーポン(懇親会・お弁当を予約された方のみ)をお送りしました。当日必ずご持参下さい。
ネームカードホルダーと、それぞれ申し込み内容に応じて冊子等をお渡しいたします。
受付提出用の確認証がない場合には、受付に時間がかかる場合がありますので必ずご持参ください。
クーポンは懇親会会場入り口、お弁当引換時にそれぞれ提示してください。
<< 一部入金・未入金の方へ >>
8/29時点で一部入金もしくは、入金確認が取れていない方へは確認書のみをお送りしております。当日必ずご持参ください。
※入金確認まで、時間がかかる場合がありますので、入金と入れ違いの場合はご容赦ください。
当日会場受付にて入金のご確認をさせて頂きますので、振込み時の控え等をご持参下さい.確認がスムーズに行えます.
お支払いがまだの方は、9月9日(月)までに下記いずれかへお振り込みをお願い致します。この場合も振込み時の控え等をご持参下さい。
9日までにお振込いただけなかった場合は、当日会場受付にてご清算をお願い致します。
振込先 (注意:振込時には、振込者氏名の前に必ず申込Noを入力して下さい)
(1)三井住友銀行 神田駅前支店(普通)1711424
(社)日本地質学会 / シャ)ニホンチシツガッカイ
(2)郵便振替 00140-8-28067
一般社団法人日本地質学会
大会期間中のお食事について
大会期間中のお食事について
◯ お弁当予約販売(予約申込は締切りました).予約弁当はB棟2 階受付前廊下で配布します.(クーポンと引き換え)
◯ 大学生協厚生施設:下記施設が会期中の9月14日(土)〜16日(月・祝)11:00〜14:30に営業します.
1)川内の杜ダイニング(カフェテリア)
2)キッチンテラスクルール(麺類・丼もの)
注意:生協購買部は土曜日のみの営業です.川内北キャンパス北側(郵便局側)のコンビニエンスストア等をご利用ください.川内北キャンパス周辺には飲食店がほとんどありません.飲食店が多い市内中心部(仙台国分町)は徒歩20分ほどです.そちらもご利用ください.
プレス発表会へのご協力のお願い
学術大会に係るプレス発表会へのご協力のお願い
平素より日本地質学会の活動にご協力頂きましてありがとうございます.日本地質学会では,学術大会の際に,学術大会や地質情報展の開催案内,そして「特筆すべき研究成果」等を開催地および文科省の記者クラブに情報提供してまいりました.特に開催地での記者会見には,例年多くの報道機関の方が来場され,TV,新聞等で取り上げられています.
本年も仙台大会においてプレス発表会を開催する予定です.会員皆様の学術活動が広く報道されることは,地質学全体にとってプラスになります.この機会に会員皆様の研究成果を「特筆すべき研究成果」として広報委員会へ是非ご推薦下さい.皆様からの推薦をもとに,会見にマッチした資料を準備いたします.支部,部会,会員皆様からの自薦・他薦等,幅広い情報をお待ちしております.
なお,推薦された研究成果は行事委員会と広報委員会によってレビューされます.研究発表者にインタビューすることもあります.プレス発表に適当かどうかを両委員会が慎重に判断し,最終的にプレス発表会で紹介する研究を決定します.従いまして,推薦された研究成果がすべてプレス発表される訳ではありません.その点をご承知おき下さい.
「特筆すべき研究成果」の応募方法
締め切り: 2013年7月19日(金)17時
応募方法: 推薦者と発表者の氏名と連絡先(メールおよび電話番号),タイトル,セッション名と簡単な推薦理由を地質学会事務局(journal@geosociety.jp)にお送り下さい.資料作成のために行事委員会および広報委員会より連絡することがあります.
記者会見: 9月初旬
連絡先:日本地質学会事務局 journal@geosociety.jp
過去のプレスリリース資料は学会ホームページより閲覧できますので,どうぞご参照ください.できるだけ公式のプレス発表会を活用して頂き,個別会見の場合も解禁日を合わせて,全体として効果的な報道になるようご協力をお願いいたします.
日本地質学会広報委員長
内藤一樹
過去のプレスリリースはこちら
下記に簡単なQ&Aを準備いたしました。
■ネイチャーやサイエンスに載らないと相手にされないのでは? そんなことはありません。記者の方は発表媒体は全く問題にしません。それよりも、そのネタは読者の関心を引くのか? もしくは国民に広く周知すべき事なのか、の二点を重視します。そこがしっかりしていれば多くのメディアに掲載されるでしょうし、逆にそうでなければ、いくら有名ジャーナルに掲載されても記事になりません。 ■どんなメリットがあるの? 発表者ご自身の研究学術活動の内容が紹介されるのはもちろんのこと、所属機関にとっても宣伝になるでしょう。しかしなんといっても地質学の記事が掲載されることは、私たちの学問分野全体のメリットになります。全体の利益のためにもぜひ発表をご検討下さい。 ■知り合いの記者に話しても同じでは? 親交ある記者の方ならば正しくて深みのある記事を書いて下さるかもしれません。しかし特定の会社にのみ情報を流すと他社から反発を買って、かえって逆効果になる場合もあります。記者クラブを通じて発表し、その上で個別取材に応じるのが最も効果的です。 ■プレス発表って難しそう基本的には、わかりやすく、かつ記事に使用されやすい資料を記者クラブに送付するだけです。必要とあれば記者会見もセッティングいたします。会見といってもプロジェクターやボードを使った講演会と質疑応答であり、ワイドショーの記者会見とは全く違います。
資料の作成や売り込み方法など、これまでのノウハウを活かしてサポートいたしますので、どうぞご相談下さい。 ■こっちの意図と違う記事になったら嫌だな せっかく掲載された記事が、誤解に基づくものであったり、ピントのはずれたものであっては互いにマイナスです。そうならないためにも、わかりやすい説明を行う必要があります。発表者とメディアの双方にプラスになるようサポートさせて頂きます。 ■効果はあるの? 例えば札幌大会の時のダイアモンドの国内初報告の時は、全国の新聞とTVで大きく報道されYahooのトップページにも掲載されました。地質学会のホームページにアクセスが集中しサーバーはパンク寸前まで追い込まれました。これは特別としてもそれ以降の発表会でも新聞,TV等で毎年報道されています。 ■どんなネタがいいの? タイミングや流行があるので一概には言えませんが、ジェネラルなトピックスで幅広い読者の興味を喚起するものがふさわしいです。もしも自分自身が記者だったらと考えてみて、一般の読者に伝えたい、と思えるかどうかは一つの判断材料になるかもしれません。
ふさわしいと思える成果がありましたら、どうぞご相談下さい。
日程・プログラム
全体日程・プログラム
9/13(金)
プレ巡検
9/14(土)〜16(月)
地質情報展
9/14(土)
セッション発表(口頭,ポスター),表彰式・記念講演会,懇親会,教育・アウトリーチ巡検,第4回津波堆積物ワークショップ(同時開催行事)
9/15(日)
一般公開シンポジウム(午前),セッション発表(口頭,ポスター),ランチョン,夜間小集会,生徒「地学研究」発表会,若手会員のための業界研究サポート
9/16(月・祝)
国際シンポジウム(午前),セッション発表(口頭,ポスター),ランチョン,市民講演会(午後),夜間小集会,原子力規制委員会の評価会合についての意見交換会,シニア昼食会
9/17(火)〜18(水)
ポスト巡検
9/18(水)
第5回津波堆積物ワークショップ(同時開催行事)
■全体日程表
画像をクリックするとpdf版がダウンロードできます.
7/30現在
▶▶▶ English ver.
■各講演プログラム
各日程,種別毎にpdf版がダウンロードできます.
9/14(土)
口頭発表 ・ ポスター発表
9/15(日)
口頭発表 ・ ポスター発表
9/16(月)
口頭発表 ・ ポスター発表
※アウトリーチセッションのプログラムは、[9/16のポスター発表]内に記載しています。
▶各シンポジウム・セッションのハイライト
(pdfのダウンロード)
▶シンポジウム一覧 ▶セッション一覧
▶ランチョン・夜間小集会一覧
巡検申込状況
巡検申込状況(8月9日9時現在)
※巡検はそのほかの申込と締切日が異なります。予定されている方は、早めにお申込ください。
[申込締切] Web: 8/9(金)18:00、FAX/郵送: 8/7(水)必着
■ WEB参加登録はこちらから ■
【巡検一覧と各コース見どころはこちら】
班名
コース名
最小催行人数/定員
申込件数
A班
津波(9/13コース)
(20/30 45)
53
B班
岩手・宮城内陸地震-断層
(15/20)
18
C班
地学教育・アウトリーチ
(15/40)
24
D班
南部北上の古−中生界
(20/25)
20
E班
南部北上帯の中生界
(15/20)
15
F班
岩手県白亜系
(20/20)
20
G班
仙台新第三系
(15/20)
22
H班
蔵王
(13/15)
15
I班
北上山地古生代初期オフィオライト
(20/22)
26
J班
阿武隈東縁の花崗岩
(15/20)
20
K班
北鹿黒鉱
(15/20)
17
L班
津波(9/17コース)
(15/20 45)
44
◆A・C・F・G・H・I・J・L班は受付を終了しました(システムの都合上,申込画面から申込手続きが完了した場合でも,後日お断りさせて頂く事になります。ご了承下さい。なお, C班は別途一般での申込があるため,定員に達しました).
◆参加申込人数が各巡検コースの最小催行人員に達しなかった場合,巡検を中止することがあります.
◆巡検協賛団体の会員の方は,会員同様にお申込を頂けます.それ以外の非会員の方は,申込締切時点で定員に余裕があれば参加可能となります.ご承知おき下さい.
◆C班<地学教育・アウトリーチ>は,小中高の教員ならびに一般市民を優先対象とします.
そのほか、巡検のお申込については、こちらをご確認ください。
大会趣旨
仙台大会趣旨
「東北,いま,たちあがる地質学」
2013年仙台大会は,「東北,いま,たちあがる地質学」をキャッチフレーズに開催いたします.東北地方は,2011年3月11日の震災直後から全国の皆様の暖かい御援助をいただき,復興に邁進してまいりました.しかし,いまだ震災の影響の消えていない地域もあります.本大会では,自然災害と防災に関してあらためて地質学の果たす役割を考えようと,一般社会への普及をテーマに市民公開シンポジウム「東日本大震災:あの時,今,これから」や,作家・評論家の柳田邦男氏による市民講演会「災害に備える安全な社会とは〜求められる発想の転換と主体性〜」を企画しています.また,例年通り地質情報展などの普及行事も開催いたします.学術発表に関しては,各専門部会等から提案された24件のレギュラーセッションと5件のトピックセッションを用意し,アウトリーチセッションやオフィオライトに焦点をあてた国際シンポジウム(日本鉱物科学会との共催)も開催します.また,今年も小・中・高校生徒「地学研究」発表会をポスター会場で行います.
今大会では津波堆積物の観察を含む多くの巡検コース(プレ巡検,ポスト巡検)を用意しました.仙台周辺を巡る日帰りコースのほか,東北各地に出かける宿泊巡検コースも複数設定しました.今大会は従来にもまして巡検に力を入れております.多くの皆様のご参加をお待ちしております.
各種申込は,従来と同様の参加登録システムを利用します.お支払いは銀行振込またはクレジットカードによる支払いが可能です.発表についても演題登録システム(PASREG)を利用したオンライン登録が可能です.なお,大会準備がスムーズに運ぶよう,締切日の厳守をお願いいたします.
仙台大会に関する最新情報は,仙台大会ホームページ に掲載します.
※仙台大会に合わせて,「第4回津波堆積物ワークショップ」(9月14日午前)と「第5回津波堆積物ワークショップ」(9月18日午前)を開催します(いずれも日本堆積学会との共催).詳しくはこちら.
新しい試み、注意事項等
本大会の新しい試み
1)セッション招待講演の充実をはかります.
具体的には,セッション招待講演に限って30分の講演を可能にします(従来は招待講演も15分でした).また,招待講演の講演者と講演予定内容を事前にホームページとニュース誌で紹介します(ニュース誌5月号に掲載済み).
2)世話人が選定した学術発表「ハイライト」をホームページ,ニュース誌(本誌),講演要旨集に掲載します.
「ハイライト」は,特に注目すべき発表やおもしろいサイエンスに接するための参考になると考えられます.本大会のハイライトはこちら(pdf)
3)英語版の全体日程表と講演プログラムを講演要旨集に掲載します.
外国人参加者の増加傾向に対応するために,英語による情報提供を充実させます.
英語版の全体日程表はこちら
昨年大会で導入した「午前の部の終了時間を11:45にして昼食とランチョンの時間確保をはかる」,「ポスター発表の使用可能面積を大幅に拡大する」,「日本地質学会アウトリーチセッションを開催し,地質学のアウトリーチを推進する」,「少人数の打ち合わせ等に利用できるミーティングルームを設置する」,「広い無線LAN利用可能エリアを確保する」は,今大会も引き続き導入します.
会場での注意点
■拍手徹底
1題の口頭発表はわずか15分で終了します(セッションの場合).しかし,その発表の裏には,発表者の弛まぬ努力と,研究や発表準備に費やした多くの時間があるはずです.講演が終了したら,惜しみない拍手をお願いします.
■写真撮影・ビデオ撮影の制限
口頭発表・ポスター発表を,発表者に無断で写真撮影・ビデオ撮影してはいけません.撮影には発表者の許可が必要です.
■軽装の勧め
8月末現在,東北地区の電力供給は逼迫した状況ではありませんが,不測の事態で急な節電要求がある可能性も考えられます.残暑厳しい時期,大会参加の皆様には軽装をお勧めします.ご理解,ご協力をお願いします.
発表者の方へ
発表者は本学会または共催学協会の会員に限ります(招待講演者を除く).共同発表の場合は,この制限を代表発表者(講演要旨に下線を引いた著者)に適用します.やむを得ない事情により,あらかじめ連記された共同発表者内で発表者の変更を希望する場合は,必ず事前に行事委員会(会期前は学会事務局,会期中は学会本部)に連絡して下さい.この場合も,シンポジウムおよびアウトリーチセッション以外の場合は「会員に限り1 人1 題(発表負担金を支払った場合は2題)」の制限を守るものとします.代理人の代読,会場内での突然の発表者変更,発表順序の変更は認めません.口頭発表者は発表時間を厳守して下さい.持ち時間15分のうち,発表は10〜12分とし,質疑応答5 〜 3 分を確保してください(30分の招待講演の場合,発表20〜25分,質疑応答10〜 5 分).発表に際しては座長の指示に従い,会場運営がスムーズに行われるようご協力下さい.
■■■ 口頭発表 ■■■
・ 1 題15分(質疑応答3 〜 5 分を含む).ただしシンポジウムとセッション招待講演は除きます.
・ 口頭発表会場には液晶プロジェクターとWindowsパソコン(OS:Windows XP,Vistaおよび7 対応,PowerPoint2003−2013 対応)を用意します.
【講演ファイルをUSBメディアでご持参の方】
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ファイルのインストールは,セッション開始前に,講演会場前方パソコン設置台にて行ってください.午前中のセッションであれば前日に,午後のセッションであれば午前中にできるだけインストールを完了して下さい。講演会場は,朝8時より開場します。特に午前のセッション発表の方で当日にお越しの方は,時間に余裕をもってお出かけ下さい(大会受付も8時より受付開始)。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ファイルのインストールは,セッション開始前に,講演会場前方パソコン設置台にて行ってください.各会場のパソコンのデスクトップ上には日付(例0914)のフォルダが配置されており,その中にセッション番号のサブフォルダ(例 T1 )が配置されています。そのサブフォルダ内に講演ファイルを保存してください。ファイル名は「発表番号と演者氏名」にしてください(例:S1-O-1仙台太郎,T1-O-13宮城次郎).インストール後,ファイルが正常に投影されることを必ず確認してください.なお,試写にはファイル確認室(C 棟3 階)のPC も利用できます(*試写のみ).特に,会場のPCと異なるバージョンで作成されたパワーポイントファイルは,レイアウトが崩れる場合がありますのでご注意ください.また,萩ホールで開催されるプログラムにて口頭発表される方は,ホール内ステージ左手のPCオペレーター席までファイルをお持ち込みください.
【ご自分のパソコンを使用して講演する方】
Macをお使いになる方,ソフトの互換性からレイアウトが崩れる可能性のある方,パワーポイント以外のプレゼンテーションソフトをご利用の方は,ご自身でパソコンをご用意ください.会場の液晶プロジェクターにパソコンの切り替え器(ケーブル形状はD-SUB15ピン)を用意します.プロジェクターの解像度設定はXGA(1024×768)です.講演前に出力調整の上,接続してください.Macをお使いになる方は,必ずD-SUB15ピンのアダプターをご持参ください.接続は発表者自身が責任を持って行なってください.セッション開始前に試写し,正常に投影されることを必ず確認してください.
口頭発表の注意:
今大会ではPCセンターを設置しません(ニュース誌5月号を参照).セッションが円滑に進むように,次の注意点をよくご確認ください.
1) 発表はできるだけ会場備え付けのWindowsパソコン(OSはWindows 7;PowerPoint 2003〜2013対応)をご使用下さい(ただしMacご利用の方と動画を使用する方はご自身のパソコンをご用意下さい).プロジェクター解像度は1024×768ドット(XGA)です.パワーポイント・ファイルをUSBフラッシュメモリで持参し,セッション開始前にパソコンにコピーして下さい(セッション終了後,世話人がファイルを削除します).フォントは特殊なものではなく,PowerPointに設定されている標準的なものを使用して下さい.セッション開始前に発表会場またはファイル確認室で正常に投影されることを必ず確認して下さい.
2) ご自身のパソコンで発表する方は,セッション開始前に発表会場において正常に接続・投影されることを確認して下さい.事前に解像度(上記)の設定をご確認下さい.会場の接続端子はD-sub15ピン(ミニ)です.パソコンによってはコネクタが必要になる場合がありますので必ずご持参下さい(会場にはありません).確認作業の混雑とそれによるセッション開始の遅れを防ぐため,早めの確認作業をお願いします.なお,発表者が事前確認を怠ったために発表時にトラブルが生じても時間延長等の措置は取りません.
■■■ ポスターセッション ■■■
・ 掲示する際のチェスピンを準備いたします.テープは利用できません.
・ 掲示時間は9:00〜18:00です.遅くとも10時までに必ず掲示してください.撤収は19時までにお願いします.
・ コアタイムは,14日(土)が12:30〜13:50,15日(日)と16日(月)が13:00〜14:20です(アウトリーチセッションのみ16日(月)13:30〜14:30および16:00〜17:00).この時間は必ずポスターに立ち会い,説明して下さい.その他の時間は各自の都合により随時説明を行って下さい.
・ボード面積は,高さ210 cm,幅120 cmです.
・発表番号・発表題名・発表者名を必ず明記して下さい.
・ コンピューターやビデオを使用される場合,機器の準備は各自で行ってください.電源は確保できませんので,予備バッテリーをご準備下さい.
・ ポスター発表に対し,下記の要領にて優秀ポスター賞が授与されます.奮ってご準備下さい.
>>> 優秀ポスター賞についての詳細はこちら.
宿泊・観光関連情報
□■□■□■□■□■□ 宿泊関連情報 □■□■□■□■□■□
学会では宿泊予約の申込は受け付けておりません。
各自でご予約をお願いいたします。
【 近畿日本ツーリスト東北:宿泊申込サイト 】
(日本地質学会 仙台大会専用)
□■□■□■□■□■□ 観光関連情報:準備中 □■□■□■□■□■□
■仙台の観光情報■
表彰式・記念講演会
会員顕彰式・各賞授与式・受賞記念講演
日程:9月14日(土)15:30 - 17:50
会場:東北大学川内北キャンパス・マルチメディア棟2 階MMホール
15:30 - 15:40
会長挨拶・来賓挨拶(福村裕史 東北大学大学院理学研究科長)
15:40 - 16:10
50年会員顕彰式,各賞授与式
16:20 - 16:35
日本地質学会小澤儀明賞受賞スピーチ
尾上哲治会員「放散虫革命ジュニア世代のジュラ紀付加体地質学」
16:35 - 16:50
日本地質学会柵山雅則賞受賞スピーチ
岡本 敦会員「岩石組織とモデルと」
16:50 - 17:20
日本地質学会賞受賞講演
井龍康文会員「細かい観察・分析は地球環境科学を発展させるか−私の地球科学感−」
17:20 - 17:50
日本地質学会賞受賞講演
乙藤洋一郎会員「古地磁気学と地質学」
(初日の優秀ポスター賞の表彰式も同会場で行います)
地学教育・普及・関連行事
地学教育・普及・関連行事
■ 地質情報展2013みやぎ(9/14-16)
■ 市民講演会 (9/16)
■ 一般公開シンポジウム(9/15)
■ 地学教育・アウトリーチ巡検 (9/14)
■ 小さなEarth Scientistのつどい(9/15)
■若手会員のための業界研究サポート(9/15)
■ 原子力規制委員会の評価会合についての意見交換会(9/16)
--------
※各行事の画像をクリックすると,大きな画像,またはPDFをダウンロードできます.
容量が大きなファイルもありますので、ご注意ください。
地質情報展2013みやぎ
日時:2013年9月14日(土)〜16日(月・祝)【入場無料】※ 科学館の常設展入場は有料
9月14日(土) 13:00〜16:45
9月15日(日) 9:00〜16:45
9月16日(月) 9:00〜12:30
会場:仙台市科学館
→会場アクセスはこちら
主催:一般社団法人日本地質学会・産業技術総合研究所地質調査総合センター
共催:スリーエム仙台市科学館
後援:宮城県,宮城県教育委員会,朝日新聞仙台総局,毎日新聞仙台支局,読売新聞東北総局,河北新報社,NHK仙台放送局,一般社団法人全国地質調査業協会連合会,日本ジオパークネットワーク
内容:仙台大会に合わせ,地質調査総合センターが有する各種地質情報から,宮城県及び周辺の地質現象や地震・津波・地盤災害について展示パネルや映像それに標本を使って紹介します.また,小さなお子さんにも楽しく地学を学んでもらうために化石レプリカ作成などの体験学習コーナーを用意します.
地質学会関連の展示:
・第7回国際地学オリンピック インド大会への道!:地球科学の知識・経験を生かす絶好の機会,それが地学オリンピックです.小・中学生地球にわくわく自由コンテストや日本地学オリンピック(兼国際大会選抜)をはじめ,地球科学に興味関心のある子どもたちを応援しています.
・惑星地球フォトコンテンスト入賞作品:第4 回惑星地球フォトコンテストの入賞作品を展示します.今回からジオパーク賞も新設され,作品の幅が広がりました.地質の作った地球の素晴らしい姿を,この機会に是非ご堪能ください.
問合せ先:産業技術総合研究所地質調査総合センター
渡辺真人・澤井祐紀 TEL:029-861-3836 e-mail:johoten2013jimu-ml@aist.go.jp
ページトップに戻る
市民講演会「災害に備える安全な社会とは〜求められる発想の転換と主体性〜」
日時:2013年9月16日(月・祝)14:30〜16:00(13:30開場)【入場無料】
会場:東北大学百周年記念会館川内萩ホール
講師:柳田邦男(作家・評論家)
後援:宮城県教育委員会,仙台市教育委員会,河北新報社,TBC東北放送
▶▶詳しくはこちら
※ページトップに戻る
一般公開シンポジウム「東日本大震災:あの時,今,これから」
日時:2013年9月15日(日)14:30〜18:00(予定)【入場無料】
会場:東北大学百周年記念会館川内萩ホール
後援:宮城県教育委員会,河北新報社,TBC東北放送
講演予定者:日野亮太(東北大)・今村文彦(東北大)・木島明博(東北大)・秋元和實(熊本大)・松澤 暢(東北大)・今泉俊文(東北大)・島崎邦彦(原子力規制委員会)
▶▶詳しくはこちら
※ページトップに戻る
小さなEarth Scientistのつどい〜第11回 小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜
日時:2013年9月15日(日) 9:00〜15:30
場所:仙台大会ポスター会場(川内北キャンパス講義棟C棟)
後援:宮城県教育委員会,仙台市教育委員会
問い合わせ・申込先:
日本地質学会地学教育委員会(担当 三次)
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F
TEL:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156 e-mail:main@geosociety.jp
▶▶申込方法など、詳細はこちらから
*過去の発表会の様子や「優秀賞」受賞発表はこちらから
ページトップに戻る
地学教育・アウトリーチ巡検「仙台の大地の成り立ちを知る」
日時:2013年9月14日(土)9:00集合出発,17:00解散(予定)
後援:宮城県教育委員会,仙台市教育委員会
参加対象:小中高の教員ならびに一般市民を優先
▶▶参加申込はこちらから(大会参加登録システムより、巡検コースC班を選択してください)
★注意★
仙台近郊にお住まいの一般の方で,アウトリーチ巡検のみに参加する(学術大会での講演・聴講をしない)場合は,東北大学総合学術博物館 高嶋(TEL: 022-795-6620)までお問い合わせ下さい。申込窓口や申込期日が異なります(大会参加登録システムからはお申込いただけません)。
*巡検の見どころ・詳細はこちら.
*過去の巡検の様子はこちらから
ページトップに戻る
原子力規制委員会の評価会合についての意見交換会
日時:2013年9月16日(日)17:00〜19:00
【参加対象:日本地質学会会員に限ります】
会場:会場4 (B棟2 階,B203)
日本地質学会では,仙台大会において,原子力規制委員会の評価会合の委員に推薦させて頂いた皆様を中心に,一般会員も含めた意見交換会を行います.この意見交換会では,評価会合の内容について,学会内の専門家の間での率直な意見交換を目的とし,参加者は会員限りとします.非会員、マスコミ関係者は除外します.
既に委員会にお出になっている方々には,現状の報告をしていただくと共に,これまで原発審査等の委員を務め,評価会合の委員推薦時に推薦対象とならなかった会員の方も含めて専門的な意見交換をしたいと考えております.
会員の皆様の参加を期待します.
世話人 斎藤 眞(常務理事)
◆プログラム◆
1. はじめに 世話人より委員選出までの経緯
2. 話題提供
1)敦賀原子力発電所の評価会合の経緯・・・藤本光一郎
2)大飯原子力発電所の評価会合の経緯・・・重松紀生
3)大飯発電所における破砕帯と海成段丘の問題に関する経緯・結果・・・岡田篤正
4)高速増殖原型炉もんじゅの評価会合の経緯・・・大谷具幸・竹内 章
5)原発安全審査における「考慮すべき活断層」の規定類の変遷と課題・・・粟田泰夫
3. 総合討論
※ページトップに戻る
会場・交通
会場・交通
(拡大は画像をクリック)
セッション発表,シンポ,国際ワークショップ,
表彰式・記念講演会,関連普及行事
生徒「地学研究」発表会,市民講演会
東北大学川内北キャンパス
(仙台市青葉区川内41)
東北大学百周年記念会館川内萩ホール・講義棟B棟・講義棟C棟・マルチメディア教育研究棟
★★会場案内図はこちら★★
地質情報展
仙台市科学館
(仙台市青葉区台原森林公園4−1)
【東北大学川内北キャンパスへのアクセス】
■飛行機をご利用の場合:
仙台空港より仙台空港アクセス鉄道に乗車し,JR仙台駅までお越しいただき、仙台駅から下記の仙台市営バスにてご来校ください.
■JR仙台駅,駅前バスのりばから仙台市営バスを利用:(乗車時間約15分)
▶9番のりば
行き先:宮教大・青葉台行 青葉通経由動物公園循環 下車:東北大川内キャンパス・萩ホール前
行き先:川内南キャンパス経由(急行)東北大川内キャンパス 下車:東北大川内キャンパス・萩ホール前
▶16番のりば
行き先:広瀬通経由交通公園・川内(営)行・広瀬通経由交通公園循環 下車:川内郵便局前
※東北大学川内北キャンパスは駐車スペースが少ないため,乗用車でのご来訪は極力ご遠慮下さい.
※キャンパス内をはじめ,喫煙可の表示がない場所は禁煙となっています.
※宿泊施設はJR仙台駅周辺,および仙台市内にあります.なお,仙台市内の宿泊施設の予約は大変取りづらくなっておりますので,宿泊申し込みサイトからお申し込みください.
【スリーエム仙台市科学館へのアクセス】
位置図及び公共交通機関に関しては,
http://www.kagakukan.sendai-c.ed.jp/access/index.html(ご利用案内,交通アクセス等)を参照して下さい.
■仙台市市営地下鉄南北線をご利用の方:
・仙台市地下鉄南北線「旭ヶ丘駅」下車徒歩約5分(「仙台駅」より乗車時間約10分)
■お車を御利用の方:
・東北自動車道「仙台宮城I.C.」を降り,仙台北環状線経由約30分.または東北自動車道「泉I.C.」を降り,国道4号線・県道仙台泉線経由約30分
★★東北大学川内北キャンパスマップ★★
(図をクリックするとpdfをダウンロードできます.)
※ 無線LANをご利用頂けます:会場すべてで,無線LANを各自のパソコンでご利用できます.
無線LANのご利用方法は受付および休憩室等に掲示する予定です.
申込先・締切一覧
各種申込先・締切一覧
WEB
FAX・郵送
申込・問合先
講演申込(演題登録)
7/2(火)17時
6/26(水)必着
詳細
行事委員会
講演要旨原稿提出
7/2(火)17時
6/26(水)必着
詳細
行事委員会
WEB
FAX・郵送
事前参加登録
8/20(火)18時
8/16(金)必着
詳細
学会事務局
巡検
8/9(金)18時
8/7(水)必着
詳細
学会事務局
懇親会
8/20(火)18時
8/16(金)必着
詳細
学会事務局
追加講演要旨
8/20(火)18時
8/16(金)必着
詳細
学会事務局
お弁当
8/20(火)18時
8/16(金)必着
詳細
学会事務局
同窓会ブース
8/20(火)18時
8/16(金)必着
詳細
現地事務局
託児室
8/23(金)※予定
-------
詳細
現地事務局
生徒地学研究発表会
(小さなEarth Scientistのつどい)
7/17(水)
-------
詳細
地学教育委員会
ランチョン・夜間小集会
6/26(水)
-------
詳細
行事委員会
一次締切
最終締切
広告協賛
-------
8/9(金)18時
詳細
現地事務局
企業展示への出展
7/5(金)18時
8/9(金)18時
詳細
現地事務局
書籍・販売ブース
7/5(金)18時
8/9(金)18時
詳細
現地事務局
※※※ 巡検のみ参加申込締切が大会参加登録等と異なりますので,ご注意下さい ※※※
【巡検M班中止のお知らせ】
仙台大会の巡検コースについて,巡検案内者の都合により,下記コースは中止となりました。
申込受付開始後の変更のため,皆様にはご迷惑をおかけ致しますが,何卒ご了承下さい。
すでにお申込を頂いた方は,事務局よりキャンセルのお手続きをさせて頂きます。
【中止】M班 2008年岩手・宮城内陸地震による斜面災害(案内者 川辺孝幸・籾倉克幹)
小,中,高校生徒「地学研究」発表会
小さなEarth Scientistのつどい
第11回小,中,高校生徒「地学研究」発表会
後援:宮城県教育委員会,仙台市教育委員会
参加予定校(7月30日現在, 9校, 1団体より16件)
・学校法人朴沢学園 明成高等学校(宮城県)(3件)
・青森県立八戸北高等学校SSH地学班
・学校法人遺愛学院 遺愛女子中学・高等学校地学部(北海道)
・群馬県立太田女子高校地学部
・横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校天文部
・早稲田大学高等学院理科部地学班
・山梨県立日川高等学校(2件)
・静岡県立磐田南高等学校地学部地質班 ・兵庫県立加古川東高等学校地学部( 3件)
・未来の科学者を育成する新潟プログラム(中学生2件)
********************************************************
小さなEarth Scientistのつどい
第11回小,中,高校生徒「地学研究」発表会
日本地質学会地学教育委員会では,地学普及行事の一環として,地学教育の普及と振興を図ることを目的として,学校における地学研究を紹介する「地学研究」発表会をおこなっています.仙台大会でも,小・中・高等学校の地学クラブの活動,および授業の中で児童・生徒が行った研究の発表を募集いたします.宮城県内,また東北地方の学校,さらには全国の学校の参加をお待ちしています.会場は研究者も発表するポスター会場内に,特設コーナーを用意いたします.同時並行で研究者の発表も行われますので,児童・生徒同士のみならず,研究者との交流もできます.この会を通じて生徒,研究者,市民の交流が進み,地質学,地球科学への理解が深まって,未来を担う生徒たちの学習意欲への良い刺激と励みになることを願っております.
なお,参加証とともに,優秀な発表に対しては審査のうえ,「優秀賞」などの賞を授与いたします.
下記の要領にて参加校を募集します.
日時
2013年9月15日(日) 9:00〜15:30
場所
仙台大会ポスター会場(川内キャンパス講義棟C棟)
参加対象
・小,中,高校地学クラブならびに理科クラブ等の活動成果の発表
・小,中,高校の授業における研究成果の発表
・活動,研究内容は地学的なもの(地質や気象などの地球科学・環境科学,天文など)
申込締切
7月17日(水),下記,日本地質学会地学教育委員会宛にお申し込み下さい.
発表形式
ポスター発表(展示パネルは,縦210cm×横120cm)
パネルのほかに標本等を展示される場合には,パネルの前に机を用意します.参加申し込みの際に,その旨を記載して下さい.その場合は展示パネルの下側が隠れる事をご了承下さい.発表者は決められた時間(および随時)パネルの前に待機し説明をしていただきます.なお,遠隔地および学校行事等のために児童・生徒が参加できない場合は,発表ポスターのみをお送りいただいても結構です.
参加費
無料(参加者・引率者とも),開催中の研究者の発表,講演も聴くことができます.
派遣依頼
参加者・引率者については学校長宛,日本地質学会より派遣依頼状を出します.
問い合わせ
・申込先
所定の書式をFAXまたはe-mailで下記宛にお送り下さい.
日本地質学会地学教育委員会(担当 三次)
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F
TEL:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156 e-mail:main@geosociety.jp
【参加申込書のダウンロード】
発表申込締切: 7/17(水)
問い合わせ先
仙台大会問い合わせ先
■日本地質学会行事委員会 / 地学教育委員会 / 学会事務局
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目8-15 井桁ビル6F
(日本地質学会事務局 気付)
TEL:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156
e-mail:main@geosociety.jp
■行事委員会■(2013年5月現在)
委員長
星 博幸(担当理事)
委 員
内野 隆之(地域地質部会)
岡田 誠(層序部会)
長谷川 健(火山部会)
芦 寿一郎(海洋地質部会)
水上 知行(岩石部会)
片岡 香子(堆積地質部会)
坂本 正徳(情報地質部会)
川村 喜一郎(現行過程地質部会)
田村 嘉之(環境地質部会)
河村 知徳(石油石炭関係)
須藤 宏(応用地質部会)
氏家 恒太郎(構造地質部会)
浅野 俊雄(地学教育委員会)
須藤 斎(古生物部会)
内山 高(第四紀地質部会)
黒田 潤一郎(環境変動史部会)
吉田 英一(地質環境長期安定性研究委員会)
■日本地質学会第120年学術大会現地事務局
(株式会社アカデミック・ブレインズ 内)担当:田中
〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1天満橋千代田ビル2号館9階
TEL:06-6949-8137 FAX:06-6949-8138
e-mail:gsj2013sendai@academicbrains.jp
■実行委員会組織
委 員 長
箕浦幸治(TEL:022-217-6616,minoura@m.tohoku.ac.jp)
東北支部長
川辺孝幸(TEL:023-628-4425,kawabe@kescriv.kj.yamagata-u.ac.jp)
事務局長
西 弘嗣(TEL:022-795-6612,hnishi@m.tohoku.ac.jp)
広 報
鈴木紀毅(TEL:022-795-6623,norinori@m.tohoku.ac.jp),
佐々木 理(sasaki@museum.tohoku.ac.jp)
会 計
海保邦夫(TEL:022-795-6615,kaiho@m.tohoku.ac.jp),
長濱裕幸(h-nagahama@m.tohoku.ac.jp)
プログラム
井龍康文(TEL:022-795-6622,iryu@m.tohoku.ac.jp),
佐藤慎一(kurosato@m.tohoku.ac.jp)
巡 検
高嶋礼詩(TEL:022-795-6620,rtaka@m.tohoku.ac.jp),
平野直人(nhirano@cneas.tohoku.ac.jp),
宮本 毅(t-miya@cneas.tohoku.ac.jp),
遅沢壮一(osozawa@m.tohoku.ac.jp)
巡検案内書
伴 雅雄(TEL:023-628-4642,ban@sci.kj.yamagata-u.ac.jp)
懇 親 会
中森 亨 (nakamori@m.tohoku.ac.jp)
土屋範芳(tsuchiya@mail.kankyo.tohoku.ac.jp)
会場・機器
中村教博(TEL:022-795-6613,n-naka@m.tohoku.ac.jp),
山田 努(t-yamada@m.tohoku.ac.jp),
川村寿郎(t-kawa@staff.miyakyo-u.ac.jp)
現地事務局
((株)アカデミック・ブレインズ 内) 担当:田中
(TEL:06-6949-8137,FAX:60-6949-8138,e-mail:gsj2013sendai@academicbrains.jp)
男女共同参画企画
(託児室)
マザーズ・エスパル保育園(予定)
問合せ先 現地事務局((株)アカデミック・ブレインズ 内)
担当:田中(TEL:06-6949-8137,FAX:06-6949-8138,e-mail:gsj2013sendai@academicbrains.jp)
巡検のみどころ
【巡検および巡検案内書について】
2013.8.29
巡検参加事前申込みは8月9日に締め切りました.参加者への連絡などを大会ホームページに随時掲載いたします.
巡検案内書は,CD-ROM版を119巻8号(2013年8月号)に添付して会員に配布いたします.また,地質学雑誌の一部となっていますので,発行から3 ヶ月目にはJ-STAGEにて公開をいたします.
※冊子体の案内書は作成いたしません.巡検参加者には各班の巡検案内の複写を巡検当日に配布する予定です.
日本地質学会第120年学術大会(仙台大会)
各コースの詳細と魅力・見どころの紹介
■ 参加登録はこちらから ■
申込締切:8/9(金)(郵送 8/7(水) 必着)
★注意点★
*最小催行人員に満たない場合や,安全確保に問題があると考えられる場合は,コース内容の一部変更や巡検中止等の措置をとることがあります.
*各コースの案内書は,印刷したものを巡検当日に配布します.全コース分を収録した冊子体の出版はありません(CD-ROM版のみ).
*集合・解散の場所,時刻等に変更が生じた場合,大会期間中の掲示板に案内します.案内者から直接ご連絡することもあります.
*お申し込みは http://www.geosociety.jp/sendai/content0027.html 「日本地質学会120年学術大会(仙台大会)」にて,申込先着順に受け付け中です.
A班:津波
B班:岩手・宮城内陸地震-断層
C班:地学教育・アウトリーチ
D班:南部北上の古−中生界
E班:南部北上帯の中生界
F班:岩手県白亜系
G班:仙台新第三系
H班:蔵王
I班:北上山地古生代初期オフィオライト
J班:阿武隈東縁の花崗岩
K班:北鹿黒鉱
L班:津波
M班:斜面災害
【巡検M班中止のお知らせ】
仙台大会の巡検コースについて,巡検案内者の都合により,下記コースは中止となりました。
申込受付開始後の変更のため,皆様にはご迷惑をおかけ致しますが,何卒ご了承下さい。
すでにお申込を頂いた方は,事務局よりキャンセルのお手続きをさせて頂きます。
【中止】M班 2008年岩手・宮城内陸地震による斜面災害(案内者 川辺孝幸・籾倉克幹)
A班 2011年東北沖津波と869年貞観津波の浸水域と堆積物
[9月13日(金):1日コース]
定員:30名
地形図
(1/2.5万)仙台東北部・仙台東南部・仙台空港
案内者
菅原大助(東北大災害研),箕浦幸治・山田 努・平野信一(東北大理)
魅力
2011年の東北地方太平洋沖地震に伴い,仙台湾一帯は高さ10mに達する大津波に襲われ,沿岸部は壊滅的な被害を受けました.砂浜や河口周辺では浸食・堆積作用により大規模な地形変化が起こり,内陸には海岸から運ばれてきた砂による地層「津波堆積物」が形成されました.地質学的研究により,仙台平野は869年の貞観津波でもほぼ同じ浸水被害を受けていたことが知られています.本巡検では,東北沖津波による被害や堆積作用の状況,貞観津波の堆積物を見学します.貞観津波堆積物の見学方法が,9月17日の巡検(L班)と異なる予定です.
見どころ
・閖上地区・荒浜地区—被害とその後の状況
・名取川河口—津波の浸食・堆積作用と地形変化
・貞山運河と仙台東部道路—津波に対する機能
・トレンチによる西暦869年貞観津波の堆積物の観察
・末の松山—歴史記録から知る古津波
巡検コース
9:00 仙台駅(集合)→ 10:00 仙台空港→ 11:00 名取市閖上→ 13:00 仙台市若林区荒浜周辺→ 16:00 多賀城市→ 18:00 仙台駅前(解散)
東北沖津波後の名取川河口付近の状況。
貞観津波の堆積物の産出状況.白く見えるのが915年のTo-aテフラである.その直下に見える均質な砂層が貞観津波の堆積物,その下位は堤間湿地の黒色砂質泥である.
備考:弁当持参(コース途中で購入可)
ページtopに戻る
B班 カルデラ縁辺などのリストリック正断層が再動した岩手・宮城内陸地震(M6.9)の地表地震逆断層
[9月13日(金):1日コース]
定員:20名
地形図
(1/2.5万)本寺
案内者
遅沢壮一(東北大理)・布原啓史(テクノ長谷)
魅力
2008年6月14日の岩手・宮城内陸地震では,大崩壊と地表地震断層が特徴的でした.地震断層はカルデラや花崗岩の縁辺の正断層の位置そのものか,近傍に,これらが再動した結果,生じたものです.地震断層は既に改修されていて観察できませんが,これらの縁辺断層を観察します.併せて,グリーンタフ調査ではキイになる,カルデラを充填する陸成層と下位の海成層との区別の仕方を解説したいと思います.充填堆積物と海成層との層位関係は不整合ではありません.
見どころ
・花崗岩縁辺正断層の近傍に生じた地震性逆断層
・カルデラ縁辺正断層の近傍に生じた地震性逆断層
・カルデラ縁辺の陥没性高角断層
・カルデラ外縁側の低角断層と一部の整合境界
・溶結凝灰岩と海成シルト岩
巡検コース
8:00 仙台駅西口(発)→仙台宮城IC →一関IC →一関市本寺→祭畤大橋→昼食(骨寺村荘園交流館“若神子亭”)→枛木立→一関IC →仙台宮城IC → 18:00 仙台駅西口(着)
震源近くの磐井川上流、崩落した祭畤大橋。瑞山カルデラ基底断層周辺の崩壊が大橋崩落の誘因らしい。大崩壊は他にも見られるが、地表地震断層は生じなかった。2013.3.24.
海成層と低角断層を挟んで上位の陸成軽石凝灰岩。凝灰岩の崩壊は地震動による。修復されているが、水田には地表地震断層が現れた。さらに手前側に高角の厳美カルデラ縁辺正断層(再動して逆断層に転化している;今回は不動)。
備考:
ページtopに戻る
C班 仙台の大地の成り立ちを知る
[9月14日(土):1日コース]
定員:40名
地形図
(1/2.5万)仙台西北部,仙台西南部
案内者
宮本 毅,石渡 明(東北大東北アジア研究C)・蟹澤聰史(東北大名誉教授)・根本 潤(東北大理)
魅力
仙台地域は海と陸の時代を繰り返しつつ現在の姿となりましたが,その大地の形成には火山噴火も大きな役割をはたしてきました.そのような火山活動によってもたらされた噴出物を観察し,過去に起こった火山活動について知るとともに,火山噴火の多様性についても理解します.本巡検は地質学会学術大会の巡検としては初のアウトリーチ巡検です.身近な場所にある代表的な露頭を基に,仙台の大地の成り立ちについて一般の方々にも分かりやすく解説します.
見どころ
・大規模な火山活動によって現在の仙台市街地一帯を埋め尽くした火砕流堆積物(広瀬川凝灰岩部層)
・約350万年前の噴火によって埋まった森林跡(立木の化石)
・約8万年前に形成された仙台に最も近く新しい火山からの降下軽石堆積物(安達−愛島軽石層)
・竜ノ口の海の時代に生息していた生物の化石採取
・仙台市街に残る仙台城,亀岡神社の石段などの歴史的建造物の石材となった溶岩(三滝玄武岩)
巡検コース
9:00 東北大学川内南キャンパス萩ホール前出発(バス)→9:15 旧三滝温泉(八幡)→ 10:30 化石の森(郷六)→ 12:00 昼食(東北大川内北キャンパス)→ 13:15 広瀬川河畔(評定河原)→ 14:00 化石林(霊屋)→ 15:00 八木山治山の森(青葉台)→ 16:15 東北大学理学部→ 17:00 東北大学川内南キャンパス萩ホール前(解散)
約350万年前の火山活動による広瀬川凝灰岩部層の模式地である仙台市評定河原の大露頭
仙台市霊屋下の約350万年前の火砕流堆積物によって埋まった立木の化石
備考:弁当持参(コース途中の大学生協レストランで食事可)
ページtopに戻る
D班 南部北上帯長坂地域の先シルル紀基盤岩類・中〜上部古生界と歌津−志津川地域のペルム系〜ジュラ系
[9月17日(火)・18日(水):1泊2日コース]
定員:25名
地形図
(1/2.5万)前沢・沖田・千厩北部・津谷・伊里前・志津川
案内者
永広昌之(東北大総合博)・森清寿郎(信州大理)
魅力
南部北上帯は古生界基盤およびシルル系から白亜系までの浅海成層がまとまって分布するわが国唯一の地域です.長坂地域では,先シルル紀基盤の母体変成岩類や正法寺閃緑岩,それらを覆う中部〜上部古生界(鳶ヶ森層,唐梅館層,竹沢層)の岩相を見学し,層位関係について検討します.南三陸地域では,ペルム〜ジュラ系の岩相・層序を見学します.この地域はわが国唯一の三畳紀・ジュラ紀魚竜化石産地であり,これらの産出層準や現地保存されている化石を観察できます.あわせてペルム系に挟在する燐酸塩・炭酸塩岩の産状を見学します.
見どころ
・南部北上帯西縁部の先シルル紀基盤岩類
・母体変成岩類と鳶ヶ森層の不整合露頭
・上部デボン〜最下部石炭系鳶ヶ森層と下部石炭系唐梅館層の岩相と化石
・南三陸歌津地域の上部ペルム系と燐酸塩岩・炭酸塩岩
・下部三畳系大沢層のウタツギョリュウ化石産地(館崎)
・中部三畳系伊里前層のクダノハマギョリュウ化石産地(管の浜)
・中部ジュラ系細浦層の岩相と化石
巡検コース
1 日目:8:00 仙台−(東北自動車道)→水沢IC →奥州市正法寺(母体変成岩類,正法寺閃緑岩)→一関市東山町田河津(母体変成岩の縞状角閃岩,鳶ヶ森層の赤色岩)→同南磐井里粘土山(鳶ヶ森層)→南磐井里幽玄洞(石炭系唐梅館層・竹沢層)→気仙沼→岩井崎(岩井崎石灰岩)→南三陸町歌津(泊)
2日目:歌津泊崎→石浜(末の崎層の岩相と含燐酸塩岩ノジュール)→田の浦(含燐酸塩岩)→館崎(平磯層・大沢層の岩相とウタツギョリュウ化石産地)→管の浜(クダノハマギョリュウ)→皿貝坂(上部三畳系皿貝層群)→細浦(下部〜中部ジュラ系細浦層)→志津川→登米東和IC(三陸自動車道)→ 17:00 仙台(解散
一関市東山町夏山エチゴ沢中流部の,母体変成岩類と鳶ヶ森層の不整合露頭.Mu.母体変成岩類中の超苦鉄質岩,Tb.鳶ヶ森層基底部の赤色角礫岩,Tm.鳶ヶ森層の赤色泥質岩.矢印はスケールのハンマー.
南三陸町歌津館崎の下部三畳系大沢層の魚竜化石産地.ウタツギョリュウ化石を露頭保存している.
備考:2日間とも昼食代自己負担(コース途中で購入可)
ページtopに戻る
E班 中部ジュラ系〜下部白亜系相馬中村層群の層序と化石
[9月17日(火):1日コース]
定員:20名
地形図
(1/2.5万)新地・相馬中村・磐城鹿島・丸森・青葉
案内者
竹谷陽二郎(福島県博)・遅沢壮一(東北大理)
魅力
福島県太平洋岸北部の丘陵地帯には,南部北上帯に属する中部ジュラ系〜最下部白亜系の相馬中村層群が分布します.本層群は浅海性堆積物と河川堆積物が交互に繰り返しており,環境変化が大きな沿岸相を連続して観察することができます.本層群からは近年新種の発見が相次いでおり,本邦におけるジュラ紀〜白亜紀の重要な化石産地として再評価されています。巡検では,本層群の代表的な岩相を示す露頭を訪れると共に,特に海生動物化石の産出状態を観察します.最後に南相馬市博物館を訪れ,展示されている相馬中村層群産化石の模式標本を見学します.
見どころ
・中部ジュラ系粟津層の泥質岩と含有化石
・上部ジュラ系中ノ沢層の石灰質砂岩〜石灰岩の岩相変化と含有化石
・上部ジュラ系の河川および氾濫原堆積物である富沢層の層相
・最下部白亜系小山田層の層相変化と含有化石
・南相馬市博物館で展示している相馬中村層群産化石の模式標本
巡検コース
8:00 仙台駅(集合)→相馬市西部→南相馬市鹿島区→南相馬市博物館→ 18:00 仙台駅(解散)
南相馬市鹿島区小池に露出する中ノ沢層小池石灰岩の大露頭
南相馬市博物館で展示されている相馬中村層群産化石の完模式標本 平宗雄氏採集 南相馬市博物館蔵
1.Nilssoniocladus tairae Takimoto, Ohana et Kimura (母岩幅27cm)栃窪層 南相馬市鹿島区小山田
2.Aulacosphinctoides tairai Sato et Taketani (化石径14.2cm) 中ノ沢層 南相馬市鹿島区小池
備考:弁当持参
ページtopに戻る
F班 岩手県に分布する白亜系宮古層群及び久慈層群の浅海〜非海成堆積物と後期白亜紀陸生脊椎動物群
[9月17日(火)・18日(水):1泊2日コース]
定員:20名
地形図
(1/2.5万)田野畑・陸中野田・玉川・大川目
案内者
梅津慶太(JAMSTEC)、高嶋礼詩(東北大総合博)、平山 廉(早稲田大)
魅力
岩手県北部沿岸地域に分布する下部白亜系宮古層群及び上部白亜系久慈層群は続成作用の影響が少なく,非常に保存状態が良好で多様な化石を産することが良く知られています.さらに,両層群は細かな堆積構造を観察することができる国内有数の白亜系です.この巡検では,宮古層群の非海成層と,津波堆積物を含む浅海層及び,久慈層群の非海成〜浅海成層の層序,堆積相,化石及びその産状を観察します.また,近年新たな発見が報告されている後期白亜紀陸生脊椎動物化石群発掘サイトを見学します.
見どころ
・宮古層群の海成層及び化石とその産状
・宮古層群の海成層中に挟まる前期白亜紀の津波堆積物
・極めて連続の良い上部白亜系久慈層群の海成〜非海成堆積物の岩相層序変化と堆積構造
・久慈層群下部に挟在するカキ化石密集層とその産状
・後期白亜紀陸生脊椎動物化石群発掘サイト
巡検コース
1日目:9:00 二戸駅発→田野畑地域(コイコロベ海岸,ハイペ海岸,平井賀海岸,明戸海岸)→久慈市(泊)
2日目:久慈市→野田玉川海岸→久慈琥珀博物館→ 17:30 二戸駅着(解散)
ハイペ海岸北の宮古層群からの砂岩転石ブロックの層理面に見られる化石密集層.ウミユリやトリゴニアなどの二枚貝がレンズ状に散在する.
岩手県九戸郡野田村玉川漁港の南に露出する久慈層群下部の砂岩大露頭.数十センチから数メートルの厚さのカキ化石密集層を何層も挟在する.
備考:弁当持参(コース途中で購入可)
ページtopに戻る
G班 仙台南西部に分布する中・上部中新統および鮮新統
[9月17日(火):1日コース]
定員:20名
地形図
(1/2.5万)仙台南西部・仙台北西部
案内者
藤原 治(産総研)・鈴木紀毅(東北大)
魅力
仙台南西部は,東北日本の太平洋側における新第三系が模式的に露出する場所であり,層序,古生物,テクトニクスなどの研究が戦前から連綿と行われてきました.また,名取川下流の河床の大露頭では最近になって堆積相や年代層序の解明が進み,詳細な相対的海水準変動の検討が可能になりました.今回の巡検では,放射年代や生層序が実際に調べられた露頭で層相や鍵層などを観察するとともに,堆積相解析から復元される相対的海水準変動についても現場で議論したいと思います.この巡検を通じて,東北日本弧の地史や,そこに展開した生物相の変遷についてより深く理解することを目指します.
見どころ
・高館層の溶岩を覆う茂庭層と,茂庭層に含まれる中期中新世の初め頃に暖海の岩礁に生息した貝類などの化石.
・名取川河床に露出する延長1000m以上,幅50m前後の連続大露頭.名取層群旗立層から仙台層群までが連続的に露出.旗立層には顕著な上方細粒化−上方粗粒化サイクルが少なくとも7回認められ,相対的海水準変動を示す.
・名取川下流の河床に見られる不整合の形成時期と東北日本のテクトニクス史との関連.
・竜の口渓谷入口の崖に露出する仙台層群(竜の口層から大年寺層まで)の地層群と,それらが示す環境変化.
巡検コース
8:30仙台駅西口→茂庭→旗立→青葉山(工大グランド)→名取川河床→竜の口?あるいは澱橋あたりの竜の口層→仙台駅(16:00頃)
名取川河床に露出する旗立層中部の石灰質砂岩.上方粗粒化サイクルの最上部にあたり,細礫質でフジツボやイタヤガイ科の貝類の破片が集積している.大型のトラフ型斜交層理が発達する.堆積年代は約11Ma.
名取川河床に露出する綱木層上部を構成する砂岩・礫質砂岩の互層.左側が上位で,50度前後の東傾斜を示す.礫質砂岩の部分が凸になっている.堆積年代は約6.4Maで,年代からみると秋保層群の梨野層と同時異相をなす可能性がある.
備考:弁当持参(コース途中で購入可)
ページtopに戻る
H班 蔵王火山
[9月17日(火):1日コース]
定員:15名
地形図
(1/2.5万)蔵王山
案内者
伴 雅雄(山形大理)
魅力
テフラや火口近傍の噴出物を観察することにより、蔵王山最新期(過去約3万年間)の噴火履歴を理解します。
見どころ
・最新期は大きく約3〜1万年前、8〜4千年前、約2千年前以降に細分され、各々活動・噴出物の特徴が異なります。
・各活動によってもたらされた噴出物を代表的な露頭で観察します。
巡検コース
8:00仙台駅→9:40蔵王山大黒天付近のテフラ→10:40蔵王山頂(刈田岳)→五色岳あるいは熊野岳付近の火砕サージ・1895年噴出 物など(雨天の場合はエコーライン沿いの露頭など)→15:00駒草平のアグルチネート→17:00仙台駅
蔵王山、五色岳火砕岩。夥しい数の火砕サージ堆積物&アグルチネートが累重している。
備考:弁当持参
ページtopに戻る
I班 オルドビス紀−デボン紀島弧系の復元と発達過程:岩手県早池峰宮守オフィオライトと母体高圧変成岩類
[9月17日(火)・18日(水):1泊2日コース]
定員:22名
地形図
(1/2.5万)区界・宮守・小友・野手崎・沖田・前沢・水沢
案内者
小澤一仁(東大理)・前川寛和(大阪府立大理)・石渡 明(東北大・東北アジア研究C)
魅力
南部北上山地は,大陸性の地殻がシルル紀−デボン紀に存在していたと考えられる古い地塊です.この地塊の北縁と西縁には,オルドビス紀の島弧性オフィオライト(早池峰・宮守オフィオライト)とオルドビス紀〜デボン紀の間に形成された高圧変成岩類(母体変成岩類)が分布しています.これらは,オルドビス紀以降のおよそ数千万年で成熟した島弧地殻へと進化していった沈み込み帯の発達過程を記録していると考えられます.本巡検では,早池峰・宮守オフィオライトのマントルセクションと,ほぼ同時〜1億年後の沈み込み帯である母体変成岩の露頭を観察し,古生代初期の島弧発達過程の実体を探索します.
見どころ
・早池峰かんらん岩体の主要構成岩石であり,早池峰・宮守オフィオライトの中でも最も始源的なレルゾライトの露頭を観察
・宮守かんらん岩体で,オルドビス紀の年代が得られた角閃石はんれい岩〜角閃石岩の岩相変化を露頭で観察
・宮守かんらん岩体を構成する始源的レルゾライト,層状かんらん岩,高枯渇ハルツバージャイトの露頭を観察
・宮守かんらん岩体のテクトナイトと沈積岩の境界を観察
・沈積岩メンバー中に分布する,極めて特異な岩相である,斜長石含有輝石角閃石岩〜角閃石輝岩とコートランダイトを含む超苦鉄質岩体の観察
・宮沢賢治記念館で賢治の作品世界にふれ,南部北上山地の地質との関わりに思いを馳せる.
・母体変成岩中の変はんれい岩(採石場),枕状溶岩,角閃岩と蛇紋岩の接触関係,アルカリ角閃石を含む緑色片岩を観察
巡検コース
1日目:8:00 盛岡駅出発,砂子沢,五ッ葉,長野峠,大迫,宮守北部,鱒沢駅西,花巻(宮沢賢治記念館・童話村),花巻(泊)
2日目:花巻発,宮守,鱒沢周辺,五輪峠附,白土川,五輪牧野,水沢,黒石,正法寺,一関で18:00(解散)
宮守岩体のテクトナイト層−沈積岩層境界に見られるハルツバージャイト礫(優黒質部分)を含むウエールライト
母体変成岩中の枕状溶岩
備考:2日間とも昼食代自己負担(コース途中で購入可)
ページtopに戻る
J班 阿武隅山地東縁の石炭紀および白亜紀アダカイト質花崗岩類
[9月17日(火):1日コース]
定員:20名
地形図
(1/5万)角田,岩沼
案内者
土谷信高(岩手大教育)・大友幸子(山形大地域教育文化)
魅力
阿武隅山地東縁を走る双葉断層の東側の割山隆起帯には,従来「割山圧砕花崗閃緑岩」と呼ばれていた花崗岩体が分布しています.「割山圧砕花崗閃緑岩」は,最近のジルコンを用いたU-Pb年代測定結果から,約300Maの年代を示す割山花崗岩体と,117〜118Maの年代を示す高瀬花崗岩体に区分されました.割山花崗岩体の約300Maの年代は,これまで日本列島からほとんど見つかっていない花崗岩形成の空白期間に相当する年代であり,その地質学的位置付けは非常に興味深いものです.この巡検では,いずれもアダカイト質である割山・高瀬花崗岩体の地質学的・岩石学的特徴や,その周囲に露出する割山変成岩の特徴および割山隆起帯上昇時に堆積した中新世の金山層の特徴などを観察していただきます.
見どころ
・金彫沢の葉片状の片理や微褶曲が発達する割山変成岩.
・明通峠南東採石場跡の割山花崗岩体と高瀬花崗岩体.マイロナイト化した割山花崗岩体は,スカルン様岩や閃長岩質岩などを含む所属不明の塩基性変成岩類と断層で接し,マイロナイト化した高瀬花崗岩はこの変成岩類に岩脈として貫入していると思われます.
・高瀬峠北東の採石場の割山花崗岩体と所属不明変成岩類.マイロナイト面構造が発達している割山花崗岩マイロナイトと所属不明の塩基性変成岩類が断層で接し,その東には高瀬花崗岩が分布します.
・高瀬峠南西の割山−高瀬花崗岩体の西部に接する中新統金山層下部層の角礫岩.
巡検コース
8:30 仙台駅出発→角田市金彫沢の割山変成岩→山元町明通峠南東の石炭紀割山花崗岩体と白亜紀高瀬花崗岩体→山元町鷲足川の高瀬花崗岩体→山元町高瀬峠北東の割山花崗岩体→山元町小斎峠の高瀬花崗岩体→角田市高瀬峠南西の金山層下部層の角礫岩→ 16:00 頃仙台駅(解散)
明通峠南東採石場跡の割山花崗岩体と断層で接する所属不明の塩基性変成岩類.
所属不明の塩基性変成岩類に岩脈として貫入していると思われる高瀬花崗岩.
備考:弁当持参
ページtopに戻る
K班 北鹿地域における黒鉱鉱床と背弧海盆火山活動
[9月17日(火)・18日(水):1泊2日コース]
定員:20名
地形図
(1/2.5万)大館,小坂,白沢,陸中濁川
案内者
山田亮一(東北大理)・吉田武義(東北大)
魅力
北鹿地域は,東北本州弧の発達過程において,時間的にも空間的にも,背弧リフトから島弧への転換点に相当します.このため,陸弧安山岩から,背弧バイモーダル火山活動を経て,島弧カルデラ火山活動まで,一連の造山イベントが同時に観察できる数少ない地域です.当地域に代表される黒鉱鉱床は,この地質イベントの産物と考えらており,黒鉱露頭では,海底熱水鉱床としての硫化物帯の様々な産状をはじめ,鉱床形成に関与した流紋岩や鉱床を取り巻く粘土変質帯まで,一連の事象を観察できます.
見どころ
・陸弧における安山岩
・背弧リフトのバイモーダル火山活動
・海底熱水鉱床としての黒鉱鉱床
・熱水活動に伴う変質帯や軽石火山
・島弧期における海底珪長質火山活動
巡検コース
1日目:9:00 仙台駅前→小坂鉱山→花岡鉱山→黒鉱試料室→大館(泊)
2日目:8:00 大館→玄武岩採石場→黒鉱下盤流紋岩→黒鉱上盤流紋岩→軽石凝灰岩→小坂発→ 19:00 仙台駅前(解散)
バイモーダル火山活動:下位より粗粒玄武岩シート,玄武岩質火山砕屑岩,枕状溶岩,泥岩および流紋岩
観音堂鉱床のチムニーとチムニー壁の黄鉄鉱球晶
備考:2日間とも昼食代自己負担(コース途中で購入可)
ページtopに戻る
L班 2011年東北沖津波と869年貞観津波の浸水域と堆積物
[9月17日(火):1日コース]
定員:20名
地形図
(1/2.5万)仙台東北部・仙台東南部・仙台空港
案内者
菅原大助(東北大災害研),箕浦幸治・山田 努・平野信一(東北大理)
魅力
2011年の東北地方太平洋沖地震に伴い,仙台湾一帯は高さ10mに達する大津波に襲われ,沿岸部は壊滅的な被害を受けました.砂浜や河口周辺では浸食・堆積作用により大規模な地形変化が起こり,内陸には海岸から運ばれてきた砂による地層「津波堆積物」が形成されました.地質学的研究により,仙台平野は869年の貞観津波でもほぼ同じ浸水被害を受けていたことが知られています.本巡検では,東北沖津波による被害や堆積作用の状況,貞観津波の堆積物を見学します.貞観津波堆積物の見学方法が,9月13日の巡検(A班)と異なる予定です.
見どころ
・閖上地区・荒浜地区—被害とその後の状況
・名取川河口—津波の浸食・堆積作用と地形変化
・貞山運河と仙台東部道路—津波に対する機能
・ジオスライサーによる西暦869年貞観津波の堆積物の観察
・末の松山—歴史記録から知る古津波
巡検コース
9:00 仙台駅(集合)→ 10:00 仙台空港→ 11:00 名取市閖上→ 13:00 仙台市若林区荒浜周辺→ 16:00 多賀城市→ 18:00 仙台駅前(解散)
東北沖津波後の名取川河口付近の状況。
貞観津波の堆積物の産出状況。白く見えるのが915年のTo-aテフラである。その直下に見える均質な砂層が貞観津波の堆積物、その下位は堤間湿地の黒色砂質泥である。
備考:弁当持参(コース途中で購入可)
ページtopに戻る
M班 2008年岩手・宮城内陸地震による斜面災害
【巡検M班中止のお知らせ】
仙台大会の巡検コースについて,巡検案内者の都合により,このコースは中止となりました。
申込受付開始後の変更のため,皆様にはご迷惑をおかけ致しますが,何卒ご了承下さい。
※すでにお申込を頂いた方は,事務局よりキャンセルのお手続きをさせて頂きます。
[9月17日(火):1日コース]
定員:20名
地形図
(1/2.5万)花山湖,切留,栗駒山,岩ヶ崎,沼倉,本寺
案内者
川辺孝幸(山形大地域教育文化)・籾倉克幹(基礎地盤コンサルタンツ)
魅力
22008年岩手・宮城内陸地震は,内陸部の山地と丘陵部との境界付近で発生したM7.2の地震によって,震源域を中心に,各種の斜面崩壊による災害が発生しました.とくに,荒砥沢ダム上流域で発生した巨大グライドは,その規模と発生メカニズムから大きな注目を浴びましたが,その他にも,トップリングや,谷埋め堆積物の液状化,古い崩壊堆積物または人工堆積物の強振動による崩壊など,強震動によって発生する多彩なメカニズムの崩壊が起こっています.巡検では,それぞれのタイプの典型的な崩壊地を見学する予定です.
見どころ
・崩壊堆積物が運ばれてできた花山湖のデルタの堆積状況
・栗原市浅布地区の斜面崩壊堆積物の崩壊
・栗原市小河原地区の谷埋め堆積物の液状化による崩壊
・栗原市小河原地区のトップルによる崩壊
・栗原市湯浜地区のトップルによる崩壊と天然ダム
・栗原市荒砥沢ダム上流域の巨大ブロックグライド冠頭部
巡検コース
8:00 仙台駅(集合)→宮城県栗原市国道398 号→浅布渓谷→湯浜地区→荒砥沢ダム上流域地すべり→ 17:00 くりこま高原駅(解散)
浅布地域の谷埋め堆積物の液状化による崩壊とトップルによる崩壊(国土交通省提供)
湯浜地区のトップルによる崩壊と一迫川にできた天然ダム
備考:弁当持参
ページtopに戻る
講演情報TOP
講演関連
講演申込・講演要旨投稿:受付終了
★注意★講演申込を予定しているが,まだ入会手続きをされていない方へ
▶講演申込要領・発表要領
▶シンポジウム一覧
▶セッション一覧
▶講演要旨原稿について
▶▶講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理,引用方法,校閲について
▶▶講演要旨の作成の注意点とPDFファイル作成の作り方
▶▶講演要旨オンライン投稿手順チェックシート
▶▶保証・同意書(2013仙台)
▶講演申込書 書式(郵送で申し込む場合)
申込要領・発表要領
セッション・講演の申込要領・発表要領
注:シンポジウムに関しては、シンポジウムのページを参照して下さい。
講演申込・講演要旨投稿:受付終了
■シンポジウム一覧はこちら■
■セッション一覧はこちら■
募集要領
セッション発表を下記要領で募集します.オンラインでの演題登録・要旨投稿にご協力下さい.やむを得ず郵送で申し込む場合は郵送用発表申込書(PDF)に必要事項を記入の上,返信用ハガキ(自分宛),保証書・同意書,要旨とともに6月26日(水)必着で行事委員会宛にお送り下さい.発表セッションや会場・発表日時等は行事委員会が決定します.発表セッションや日時等を7月下旬以降に通知します.
(1)セッションについて
今大会では5件のトピックセッションと24件のレギュラーセッション,およびアウトリーチセッションを用意します(セッション再編についてはこちらを参照).
(2)発表に関する条件・制約
1)会員は全30セッションのうち1つまたは複数(下記)に発表を申し込めます.発表申込者=発表者とします.非会員は発表を申し込めません.発表を希望する非会員は6月26日(水)までに入会手続きをして下さい(入会申込書が届くまで発表申込を受理しません).共催団体の会員は共催セッションへの発表申込が可能です.
2)口頭発表あるいはポスター発表を1人1題申し込めます.ただし,発表負担金(1,500円)を支払うことでもう1題(最大2題)の申し込みが可能です.この場合,同一セッションに2題申し込むことも,異なる2つのセッションに1題ずつ申し込むこともできますが,同一セッションに口頭を2題またはポスターを2題申し込むことはできません(招待講演にも適用).同一セッションに2題申し込む場合は口頭1題とポスター1題になります.
3)共同発表(複数著者による発表)の場合は,上記「1人1題,ただし発表負担金支払いによりもう1題可」の制約を発表者(=発表申込者)に対して適用します.その際,発表者は筆頭でなくても構いません(筆頭者に会員・非会員等の条件はありません).講演要旨では,発表者氏名を下線(アンダーライン)表示にして下さい.
(3)アウトリーチセッション
会員による研究成果の社会への発信(アウトリーチ)を学会として力強くサポートするために,前回大会に引き続き,トピック・レギュラーと並ぶ第三のカテゴリー「アウトリーチセッション」を設けます.アウトリーチ活動に関心のある会員はぜひお申し込み下さい.
1)トピック・レギュラーと同様の演題登録・要旨投稿が必要です.要旨校閲(後述)もトピック・レギュラーと同様に行います.要旨は講演要旨集に収録され,正式な学会発表扱いになります.
2)本セッションの発表には,上記の発表数に関するルール(1人1題,ただし発表負担金を支払えばもう1題可)を適用しません.例えば,レギュラーセッションで1題発表する会員がアウトリーチセッションでも発表する場合,発表負担金はかかりません.ただし,同一発表者(=発表申込者)が本セッションで発表できるのは1題のみとします.
3)ポスター発表とし,16日(月)の市民講演会会場で実施します(川内北キャンパス萩ホールのエントランスロビー;口頭発表会場より徒歩5分).市民講演会の前後各1時間をポスターコアタイムとします.
4)市民には講演要旨のコピーを配布しますが,これとは別に資料を独自に配布していただいても構いません(ただし発表者負担).
5)公開シンポジウムの参加市民も見られるように,ポスターを9/15(日)から掲示できます.
6)スペース等の都合から,募集件数は10件程度とします.募集件数を上回る応募があった場合は行事委員会が採否を検討します.
7)優秀ポスター賞の選考対象になります
(4)招待講演
招待講演者を「セッション一覧」および「セッション招待講演の紹介」に示しました.招待講演も期日までに一般発表と同様に演題登録・要旨投稿が必要です.非会員招待講演者の場合は世話人が取りまとめてオンライン入力することも可能です(詳細は学会事務局にお問い合わせ下さい).非会員招待講演者に限り参加登録費を免除します(講演要旨集は付きません).また,招待講演は発表負担金の枠外として扱います(詳細はこちらを参照).
(5)発表申込方法
1)オンライン申込は仙台大会ホームページにアクセスし,オンライン入力フォームに従って入力して下さい.
2)発表方法は「口頭」「ポスター」「どちらでもよい」のいずれかを選択して下さい(アウトリーチセッションはポスターのみ).締切後の変更はできません.会場の都合のため,発表方法(口頭/ポスター)の変更をお願いすることがあります.
3)発表題目と発表者氏名は,登録フォームと講演要旨の両方を一致させて下さい.
4)共同発表の場合は全員の氏名を明記し,講演要旨では発表者氏名を下線(アンダーライン)表示にして下さい.
5)セッション発表の場合,発表希望セッションを必ず第2希望まで選んで下さい.
6)関係する一連の発表があるときは,必要に応じて発表順希望等をコメント欄に入力して下さい(ご希望に沿えない場合があります).
(6)講演要旨の投稿
講演要旨はA4判1枚とし(フォーマット参照),PDFファイルのオンライン投稿により受け付けます.印刷仕上がりは0.5ページ分です(1ページに2件分を印刷).原稿をそのまま版下とし,70%程度に縮小印刷します.文字サイズ,字詰め,鮮明度等に注意して下さい.やむを得ず郵送する場合は,オリジナルか鮮明なコピーを1枚郵送して下さい.FAXやe-mailでの投稿は受け付けません.
発表要領(シンポジウムについてはこちら)
(1)口頭発表
1)セッションの発表時間は,招待講演を除き,トピック・レギュラーとも1題15分です(討論時間3〜5分を含む).発表者は討論時間を必ず確保して下さい.なお,今大会ではPCセンターを設置しません.セッションが円滑に進むように次の注意点をよくご確認下さい.
2)発表はできるだけ会場備え付けのWindowsパソコン(OSはWindows 7;PowerPoint 2003, 2007, 2010対応)をご使用下さい(ただし,Macご利用の方と動画を使用する方はご自身のパソコンをご用意下さい).プロジェクター解像度は1024×768ドット(XGA)です.パワーポイント・ファイルをUSBフラッシュメモリで持参し,パソコンにコピーして下さい(セッション終了後,世話人がファイルを削除します).フォントは特殊なものではなく,PowerPointに設定されている標準的なものを使用して下さい.発表者は,セッション開始前に発表会場または試写コーナー(大会本部に設置)で正常に投影されることを確認して下さい.
3)ご自身のパソコンで発表する方は,セッション開始前に発表会場において正常に接続・投影されることを確認して下さい.事前に解像度(上記)の設定をご確認下さい.会場の接続端子はD-sub15ピン(ミニ)です.パソコンによってはコネクタが必要になる場合がありますので必ずご持参下さい(会場にはありません).確認作業の混雑とそれによるセッション開始の遅れを防ぐため,早めの確認作業をお願いします.なお,発表者が事前確認を怠ったために発表時にトラブルが生じても時間延長等の措置は取りません.
(2)ポスター発表
1)1日間掲示できます(アウトリーチセッションは2日間掲示可,上記).コアタイムでは必ずポスターの説明を行って下さい.ポスター設置・撤去等について,8月にお知らせします。
2)ボード面積は1題あたり縦210 cm,横120 cmです.
3)発表番号,発表タイトル,発表者名をポスターに明記して下さい.
4)コンピューターによる演示等も許可しますが,機材等はすべて発表者が準備して下さい.また,電源は確保できませんので,必要であれば予備のバッテリーを用意して下さい.発表申込の際に機器使用の有無や小机の必要性等をコメント欄に記入し,事前に世話人にご相談下さい.
5)運営規則第16条2項(8)により,優れたポスター発表に対して「日本地質学会優秀ポスター賞」を授与します.詳細は,8月にお知らせします。
(3)発表者の変更
あらかじめ連記されている共同発表者内での変更は認めますが,必ず事前に行事委員会に連絡して下さい.この場合も発表者については上記ルール募集要領(2)の条件を適用します.
(4)口頭発表の座長依頼
各会場の座長を発表者に依頼することがあります.その際はご協力をお願いします.
シンポジウム一覧
シンポジウム
講演申込・講演要旨投稿:受付終了
今大会では2件のシンポジウムを開催します.(一般の講演募集は行いません)
世話人は会員・非会員を問わず招待講演を依頼できます(締め切りました).非会員招待講演者に限り参加登録費を免除します(講演要旨集は付きません).発表時間は世話人が決定します.シンポジウム発表にはセッション発表における1人1件の制約が及びません(くわしくはこちら)ので,シンポジウムで発表する会員は別途セッションにも発表を申し込めます.
講演要旨はセッション発表と同じ様式・分量です.フォーマットを参照して要旨を作成して下さい.やむを得ず要旨を郵送する場合は郵送用の発表申込書をご利用下さい.「シンポジウム」と書き添え,必要事項を記入し,返信用ハガキ(自分宛),保証書・同意書,要旨とともに6月26日(水)必着で行事委員会宛にお送り下さい.
*各タイトルをクリックすると、詳細をご覧いただけます
シンポジウム
S1.東日本大震災:あの時,今,これから
S2.環太平洋オフィオライト:沈み込み,付加作用,マントル・プロセス
*印は連絡責任者です.
S1.東日本大震災:あの時,今,これから(仙台大会LOC企画,一般公開シンポジウム)
The 2011 Tohoku-Oki earthquake: at that moment, now and in the future
井龍康文*(東北大:iryu@m.tohoku.ac.jp)・西 弘嗣(東北大)
Yasufumi Iryu*(Tohoku Univ.)and Hiroshi Nishi(Tohoku Univ.)
東日本大震災は我々に多くの教訓を残した.地質学的研究により,東北沿岸は,過去に,大規模な津波に繰り返し襲われていたことが明らかにされていたにも関わらず,その事実が行政や住民に理解・周知されず,十分な防災・減災対策がとられなかった.一方,東日本大震災の甚大な被害を契機として,東海・東南海・南海(連動型)地震に対する関心が高まり,被害予測は大幅に引き上げられ,適切な防災・減災対策を速やかに考え,実施することが要請されている.そこで,本シンポジウムでは,東日本大震災が発生した時に何が起きたのか(あの時),その結果,どのような状況にあるのか(今),そして,これから何が起きるのか(これから)について,気鋭の研究者6名に研究成果を公開していただき,議論するとともに,将来を展望する.
【講演予定者】日野亮太(東北大)・今村文彦(東北大)・木島明博(東北大)・秋元和實(熊本大)・松澤 暢(東北大)・今泉俊文(東北大)
S2.環太平洋オフィオライト:沈み込み,付加作用,マントル・プロセス(仙台大会LOC企画,国際シンポジウム)[共催:日本鉱物科学会]
Circum-Pacific ophiolites: subduction, accretion, and mantle processes
石渡 明*(東北大:geoishw@cneas.tohoku.ac.jp)・宮下純夫(新潟大)
Akira Ishiwatari*(Tohoku Univ.)and Sumio Miyashita(Niigata Univ.)
オフィイオライト研究は地球の大規模な火成作用やテクトニクスの解明に貢献してきた.最近は,海嶺や沈み込み帯域に由来する従来型のオフィオライトだけでなく,マントル・スーパープルームが作り出したとされる海洋巨大火成岩区由来の緑色岩体が,そこに伴われるコマチアイトや鉄ピクライトなどの特徴的な超苦鉄質火山岩とともに注目されている.また,これらの超苦鉄質火山岩は火星や水星などの表面に広く分布することが最近の惑星探査で明らかになり,その岩石成因論は惑星地質学的にも重要となってきた.この国際シンポジウムでは,環太平洋地域に重点を置き,米国・ロシア・日本のオフィオライトとマントル岩石の第一線の研究者が,マントル・プロセスと火成作用,付加体形成に関わるテクトニクス,沈み込み変成作用などオフィオライトに関連する問題について地質学的,岩石学的,地球化学的レビューと議論を行い,今後の展望を述べる.
Studies on ophiolites have greatly contributed to understand the earth's large-scale magmatism and tectonics. In addition to the conventional mid ocean ridge(MOR)-type and supra subduction zone(SSZ)-type ophiolites, the greenstone bodies derived from oceanic large igneous provinces originated in mantle superplumes are recently drawing attention with the associated characteristic ultramafic volcanic rocks such as komatiite and ferropicrite. These ultramafic volcanic rocks are known to be widespread on the surface of Mars and Mercury as deciphered by recent planetary explorations, and their petrogenesis becomes important in planetary geology. In this international symposium, leading researchers of ophiolites and mantle rocks in USA, Russia and Japan will provide geological, petrological, and geochemical reviews, discussion, and perspective of future studies on the mantle processes and magmatism, accretion-related tectonics, subduction metamorphism, and other relevant problems around ophiolites.
【講演予定者】Dilek, Y.(Miami Univ., USA),Harris, R.(Brigham Young Univ., USA),Sokolov, D.(Geol. Inst., Rus. Acad.Sci.),Ishiwatari, A.(Tohoku Univ.),Miyashita, S.(Niigata Univ.),Arai, S.(Kanazawa Univ.)and Tsujimori, T.(Okayama Univ.)
↑このページのTOPに戻る
セッション一覧
セッション一覧
講演申込・講演要旨投稿:受付終了
*下記をクリックすると、各セッションの詳細がご覧頂けます。
トピックセッション(5件)
T1.地質情報の利活用
物質科学・比較惑星地質学から解読する太陽系と地球の進化史
T3. 砕屑性ジルコン年代学と日本列島・太平洋型造山帯
T4. 海溝での生物と巨大地震との関連性
T5. 2011年東北地方太平洋沖地震とその付随現象に関する地質学的研究の進展
レギュラーセッション(24件)
R1. 深成岩・火山岩とマグマプロセス
R2. 岩石・鉱物・鉱床学一般
R3. 噴火・火山発達史と噴出物
R4. 変成岩とテクトニクス
R5. 地域地質・地域層序
R6. ジオパーク
R7. 地域間層序対比と年代層序スケール
R8. 海洋地質
R9. 堆積物(岩)の起源・組織・組成
R10.炭酸塩岩の起源と地球環境
R11. 堆積相・堆積過程
R12. 石油・石炭地質学と有機地球化学
R13. 岩石・鉱物の破壊と変形
R14. 沈み込み帯・陸上付加体
R15. テクトニクス
R16. 古生物
R17. ジュラ系+
R18. 情報地質
R19. 環境地質
R20.応用地質学一般およびノンテクトニック構造
R21.地学教育・地学
R22.第四紀地質
R23.地球史
R24.原子力と地質科学
アウトリーチセッション
日本地質学会アウトリーチセッション
トピックセッション:5件
T1.地質情報の利活用/Application of geological information
斎藤 眞*(産総研:saitomkt@ni.aist.go.jp)・野々垣 進(産総研)
Makoto Saito*(AIST)・Susumu Nonogaki(AIST)
これまで地質学会では,人類の地質への理解を進展させるためのさまざまな研究成果が発表されてきた.しかし,野外で地質情報を取得し,それらを意味のある地質情報へと変換し,社会での地質情報の利活用を推進する,という流れを持った研究成果の発表例は少ない.情報処理技術が発展した昨今,野外で取得した地質情報をデジタルデータとして整理・処理・管理する環境はほぼ整った.インターネットを通じて地質情報のデジタルデータを共有・利活用する環境も整いつつある.また,近年,ジオパーク活動が盛んになるにともない,これまで地質学とはつながりが薄かった一般社会でも,地質情報を利活用しようという機運が高まっている.
地域地質部会・情報地質部会では,このような地質学会の現状,および,世相の変化を受けて,地質情報の取得から利活用までの流れの中にある研究の成果を発表する場として,表記トピックセッションを開催する.
現在,地域地質部会は,毎年の大会においてレギュラーセッションとして地域地質・地域層序を層序部会と共同で運営し,地域地質の研究成果を発表する場となっている.また,情報地質部会は,地質情報を処理するための理論・技術の開発,および,それらの地質学分野への応用などの成果を発表する場となっている.そこで,本トピックセッションでは,社会での地質情報の利活用に焦点をあて,
・特定地域から得られた地質情報の利活用,および,その問題点や比較検討
・地質情報の利活用に向けた情報取得方法
・ジオパークや博物館等における地質情報の利活用
を具体的発表テーマとする.本トピックセッションは,昨年の水戸大会から活動を開始したものである.将来的には両部会が共同で行うレギュラーセッションを目指す.
招待講演予定者:なし
ページtopに戻る
T2.物質科学・比較惑星地質学から解読する太陽系と地球の進化史/Evolution of the solar system and Earth: approach from material science and planetary geology
尾上哲治*(熊本大:onoue@sci.kumamoto-u.ac.jp)・後藤和久(東北大)
Tetsuji Onoue*(Kumamoto Univ.)and Kazuhisa Goto(Tohoku Univ.)
地球は,磁気圏,流体圏,固体圏,生物圏から構成されており,各構成要素はエネルギー,物質のやり取りを通して互いに関連しているという地球システムの考え方はすっかり定着した.本トピックセッションでは,この枠組を地球外へと拡張し,岩石中に残された地球外物質やエネルギー付加の記録(例えば隕石衝突,宇宙線など)から,太陽系,地球,生命の進化史について包括的な理解を目指す.また1990年以降の高性能観測機器を搭載した惑星探査機の研究により,地球以外の惑星や惑星間物質に関する知識は近年爆発的に増加している.火星に代表される岩石惑星は地球の重要な比較対象であり,その観測データは地球システムの本質と進化史を理解するうえで重要かつ客観的な材料を提供する.このような背景のもと本セッションでは,地球とその他の太陽系天体の比較惑星地質学に関する研究についても広く募集する.観測や物質科学的研究のみならず,理論やモデルを中心とした研究も歓迎する.
【招待講演予定者】関根康人(東京大)・丸岡照幸(筑波大)→招待者の紹介はこちら
T3.砕屑性ジルコン年代学と日本列島・太平洋型造山帯/Detrital zircon chronology applied to the Japanese Islands and Pacific-type orogenic belt
磯崎行雄*(東京大:isozaki@ea.c.u-toyko.ac.jp)・青木一勝(東京大)
Yukio Isozaki*(Univ. Tokyo)and Kazumasa Aoki(Univ. Tokyo)
砂岩中に含まれる砕屑性ジルコンのU-Pb年代の大量測定が,威力抜群の新規研究手法として近年世界中で採用されている.その応用範囲は広大だが,私たちが住む日本列島およびその周辺地域の構造発達史を解明する上でも極めて重要な知見をもたらしつつある.とくに古期地層について,有効な示準化石を産しない場合でもかなり正確な堆積年代を推定することが可能となり,従来の層序および年代論の改訂が不可避となっている.一方で,相対的に古い砕屑粒子に注目することでその由来から後背地の情報を取り出すことが可能となり,古地理復元についても従来では得られなかった重要な制限条件が明らかにされつつある.とくに同一の弧—海溝系をなす単一の造山帯の内部における,物質の移動経路の特定できるようになり,現実性の高い造山帯の大構造復元が可能となりつつある.その中で,従来見過ごされていた構造侵食の効果が明示され,また火山弧に関連した各種堆積盆地の発達・分化過程が議論出来るようになった.さらに東アジアの近隣諸国の地質との関連を議論する際にも大きな貢献を果たしつつある.本セッションでは,日本列島をはじめとする太平洋型造山帯における砕屑性ジルコン年代学がもたらす最新の成果を報告する.
招待講演予定者:なし
ページtopに戻る
T4.海溝での生物と巨大地震との関連性/Association between a great earthquake and lives in a trench
川村喜一郎*(山口大:kiichiro@yamaguchi-u.ac.jp)・辻 健(九州大)・伊藤喜宏(東北大)
Kiichiro Kawamura*(Yamaguchi Univ.),Takeshi Tsuji(Kyushu Univ.)and Yoshihiro Ito(Tohoku Univ.)
震災後,さまざまな緊急調査が行われ,地球物理学的,堆積学的,地球化学的,生物学的な海底撹乱が日本海溝において,次々と報告されてきた.M9地震のような巨大イベントは,地質学や地球物理学などの一分野だけの研究側面だけで全体を理解することは難しく,多分野における多角的な視点からの観察とその交流こそが,現象の本質を紐解くブレイクスルーをもたらす.現行地質過程部会としては,地質学と,特に生物学,さらには,化学や物理学との統合的な議論を通して,従来の震災像に新たな側面で現行過程を議論することを目的として,本トピックセッションを提案する.
【招待講演予定者】野牧秀隆(海洋研究開発機構)・笠谷貴史(海洋研究開発機構)→招待者の紹介はこちら
ページtopに戻る
T5.2011年東北地方太平洋沖地震とその付随現象に関する地質学的研究の進展/Advance in geological study on the 2011 Tohoku-oki earthquake and its incidental phenomena
菅原大助*(東北大:sugawara@irides.tohoku.ac.jp)・藤野滋弘(筑波大)・卜部厚志(新潟大)・宮地良典(産総研)
Daisuke Sugawara*(Tohoku Univ.),Shigehiro Fujino(Univ. Tsukuba),Atsushi Urabe(Niigata Univ.)and Yoshinori Miyachi(AIST)
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震は東日本一帯に様々な影響を及ぼし,かつてない規模の被害をもたらした.一方,日本の太平洋沿岸には地震・津波を念頭に,稠密な測地・測量・観測網と調査体制が整備されており,地震に前後して得られたデータの豊富さには特筆すべきものがある.この2年間,膨大な観測データを背景に,地震とこれに伴う地質学的現象の調査・研究が進められており,目覚ましい成果が数多く公表されつつある.このことは,地震とその付随現象に対する我々の理解を進歩させ,今後の日本および世界各地における災害への備えに新たな指針を与えるものになると期待される.本トピックセッションでは,東北地方太平洋沖地震に伴って生じた地盤沈降・津波・地滑り・液状化,誘発地震による活断層などの地質学的諸現象について,幅広い分野から最新の研究成果に関する発表を募り,過去の巨大地震の実態解明と将来予測に取り組む上での課題と今後の方向性について議論する場としたい.
【招待講演予定者】池田安隆(東京大)・西村卓也(京都大)→招待者の紹介はこちら
ページtopに戻る
レギュラーセッション:24件
R1.深成岩・火山岩とマグマプロセス/Plutonic rocks, volcanic rocks and magmatic processes(火山部会・岩石部会)
長谷川 健*(茨城大:hasegawt@mx.ibaraki.ac.jp)・加々島慎一(山形大)・足立佳子(新潟大)
Takeshi Hasegawa*(Ibaraki Univ.),Shin-ichi Kagashima(Yamagata Univ.)and Yoshiko Adachi(Niigata Univ.)
深成岩および火山岩を対象に,マグマプロセスにアプローチした研究発表を広く募集する.発生から定置・固結に至るまでのマグマの物理・化学的挙動や,テクトニクスとの相互作用について,野外地質学・岩石学・鉱物学・火山学・地球化学・年代学など様々な視点からの活発な議論を期待する.
【招待講演予定者】石原舜三(産総研)・小澤一仁(東京大)→招待者の紹介はこちら
R2.岩石・鉱物・鉱床学一般/General studies from petrology, mineralogy and economic geology(岩石部会)[共催:日本鉱物科学会]
水上知行*(金沢大:peridot@staff.kanazawa-u.ac.jp)・草野有紀(金沢大)
Tomoyuki Mizukami*(Kanazawa Univ.)and Yuki Kusano(Kanazawa Univ)
岩石学,鉱物学,鉱床学,地球化学などの分野をはじめとして,地球・惑星物質科学全般にわたる岩石及び鉱物に関する研究発表を広く募集する.地球構成物質についての多様な研究成果の発表の場となることを期待する.
R3.噴火・火山発達史と噴出物/Eruption, volcanic evolution and volcanic products(火山部会)
大場 司*(秋田大:t-ohba@gipc.akita-u.ac.jp)・長井雅史(防災科研)・長橋良隆(福島大)
Tsukasa Ohba*(Akita Univ.),Masashi Nagai(NIED)and Yoshitaka Nagahashi(Fukushima Univ.)
火山地質ならびに火山現象のモデル化に関し,マグマや熱水流体の上昇過程,噴火様式,噴火経緯,噴出物の移動・運搬・堆積,各火山あるいは火山地域の発達史,火山活動とテクトニクス・化学組成をはじめとする,幅広い視点からの議論を期待する.
【招待講演予定者】高橋正樹(日大)・中田節也(東京大)→招待者の紹介はこちら
R4.変成岩とテクトニクス/Metamorphic rocks and related tectonics(岩石部会)[共催:日本鉱物科学会]
岡本 敦*(東北大:okamoto@mail.kankyo.tohoku.ac.jp)・桑谷 立(東北大)
Atsushi Okamoto*(Tohoku Univ.)and Tatsu Kuwatani(Tohoku Univ.)
国内および世界各地の変成岩を主な対象に,記載的事項から実験的・理論的考察を含め,またマイクロスケールから大規模テクトニクスまで,様々な地球科学的手法・規模の視点に立った斬新な話題提供と活発な議論を期待する.
【招待講演予定者】伊藤喜宏(東北大)→招待者の紹介はこちら
ページtopに戻る
R5.地域地質・地域層序/Areal geology/Stratigraphy(地域地質部会・層序部会)
松原典孝*(兵庫県立大:matsubara-n@stork.u-hyogo.ac.jp)・内野隆之(産総研)・岡田 誠(茨城大)
Noritaka Matsubara*(Univ. Hyogo),Takayuki Uchino(AIST)and Makoto Okada(Ibaraki Univ.)
国内外を問わず,地域に関連した地質や層序の発表を広く募集する.年代,化学,分析,リモセン,活構造,地質調査法等の様々な内容の発表を歓迎し,地域を軸にした討論を期待する.発表形式としては,地質図や断面図のポスター発表を特に歓迎する.
R6.ジオパーク/Geopark(地域地質部会・ジオパーク支援委員会)
天野一男*(茨城大:kazuo@mx.ibaraki.ac.jp)・高木秀雄(早稲田大)・渡辺真人(産総研)
Kazuo Amano*(Ibaraki Univ.),Hideo Takagi(Waseda Univ.)and Mahito Watanabe(AIST)
日本のジオパーク活動も4年が経過して,日本ジオパークとして認定された地域は25地域となり,その内の5地域は世界ジオパークに認定されている.ヨーロッパでは考えられない位のスピードで増加しており,これから新たに申請を考えている地域も多い.昨年度は5地域が日本ジオパークとして再認定された.このような状況下で,ジオパークの質を向上させるための様々な課題が出てきている.ジオパークは,貴重な地質・地形に生態学的・歴史的・文化的な遺産を加えて,それらを観光資源として活用し,地域の教育や経済的振興をめざす事業である.その活動の中心的なものがジオツアーである.このツアーは,
知的あるいは学術的な基礎のもとに一般の方を対象として観光を展開するという点で,従来の観光ツアーとは大きく異なる.一般市民に学術的に質を落とさないで,いかに楽しんでもらえるかが重要な課題となる.ジオツアーの案内は,地元のインタープリターやガイドが行っており,ガイドの質がジオツアーの質を決定している.各ジオパークでは,さまざまな工夫をしてインタープリター,ガイドの育成を行っている.育成に当たってのガイドの質の保証が極めて重要な課題である.特に,地域の大学,博物館,研究所の研究者の関わり方が問われている.この観点から,地質学会として,問題点を整理し,ジオパークへの貢献の仕方を考えたい.様々な実践例の発表,課題解決方法の提案など広く講演を募集する.
【招待講演予定者】柴田伊廣(室戸ジオパーク)→招待者の紹介はこちら
ページtopに戻る
R7.地域間層序対比と年代層序スケール/Stratigraphy correlation/Chronostratigraphy(層序部会)
里口保文*(琵琶湖博物館:satoguti@lbm.go.jp)・岡田 誠(茨城大)
Yasufumi Satoguchi*(Lake Biwa Mus.)and Makoto Okada(Ibaraki Univ.)
テフラ等の鍵層を用いて異なる地域間の層序対比に主体をおく研究や,鍵層そのものを主体とした研究,または複合的層序学等によるグローバルな年代層序スケールの構築に寄与するような研究についての講演を歓迎する.
R8.海洋地質/Marine geology(海洋地質部会)
荒井晃作*(産総研:ko-arai@aist.go.jp)・芦 寿一郎(東京大)・小原泰彦(海上保安庁)
Kohsaku Arai*(AIST),Juichiro Ashi(Univ. Tokyo)and Yasuhiko Ohara(JCG)
海洋地質に関連する分野(海域の地質・テクトニクス・変動地形学・海域資源・堆積学・海洋学・古環境学・陸域地質での海洋環境変遷研究など)の研究発表を募集する.調査速報・アイデアの公表・海底地形地質・画像データなどのポスター発表も歓迎する.
【招待講演予定者】加藤泰浩(東京大)・鈴木勝彦(海洋研究開発機構)→招待者の紹介はこちら
R9.堆積物(岩)の起源・組織・組成/Origin, texture and composition of sediments(堆積地質部会)[共催:日本堆積学会・石油技術協会探鉱技術委員会・日本有機地球化学会]
太田 亨*(早稲田大:tohta@toki.waseda.jp)・野田 篤(産総研)
Tohru Ohta*(Waseda Univ.)and Atsushi Noda(AIST)
砕屑物の生成(風化・侵食・運搬)から堆積岩の形成(堆積・沈降・埋積・続成)まで,組織(粒子径・形態)・組成(粒子・重鉱物・化学・同位体・年代)・物性などの堆積物(岩)の物理的・化学的・力学的性質を対象とし,その起源・形成過程・後背地・古環境や地質体の発達史を議論する.太古代の堆積岩から現世堆積物まで,珪質岩・火山砕屑岩・風成塵・リン酸塩岩・蒸発岩・有機物・硫化物などについての研究も歓迎する.
R10.炭酸塩岩の起源と地球環境/Origin of carbonate rocks and related global environments(堆積地質部会)[共催:日本堆積学会・石油技術協会探鉱技術委員会・日本有機地球化学会]
山田 努*(東北大:t-yamada@m.tohoku.ac.jp)・足立奈津子(鳴門教育大)
Tsutomu Yamada*(Tohoku Univ.)and Natsuko Adachi(Naruto Univ. Educ.)
炭酸塩岩・炭酸塩堆積物の堆積作用,組織,構造,層序,岩相,生物相,地球化学,続成作用,ドロマイト化作用など,炭酸塩に関わる広範な研究発表を募集する.また,現世炭酸塩の堆積作用・発達様式,地球化学,生物・生態学的な視点からの研究発表も歓迎する.
ページtopに戻る
R11.堆積相・堆積過程/Sedimentary facies and processes(堆積地質部会・現行地質過程部会)[共催:日本堆積学会・石油技術協会探鉱技術委員会・日本有機地球化学会]
市原季彦*(復建調査設計(株):ichihara@fukken.co.jp)・横川美和(大阪工業大)・高清水康博(新潟大)
Toshihiko Ichihara(Fukken Co. Ltd.),Miwa Yokokawa(Osaka Inst. Tech.)and Yasuhiro Takashimizu(Niigata Univ.)
さまざまな環境で生じる堆積過程と堆積相の分類・記載・解釈に関する発表や,堆積相解析に基づく堆積システム・シーケンス層序学についての議論を広く募集する.さらに,堆積作用や地層形成のダイナミクスに関連する理論・アナログ実験・数値シミュレーション・現地観測等の研究発表を歓迎する.
R12.石油・石炭地質学と有機地球化学/Coal and petroleum geology/Organic geochemistry(石油石炭関係・堆積地質部会)[共催:石油技術協会探鉱技術委員会・日本有機地球化学会・日本堆積学会]
金子信行*(産総研:nobu-kaneko@aist.go.jp)・河村知徳(石油資源開発)・三瓶良和(島根大)
Nobuyuki Kaneko*(AIST),Tomonori Kawamura(JAPEX)and Yoshikazu Sampei(Shimane Univ.)
国内外の石油・石炭地質および有機地球化学に関する講演を集め,石油・天然ガス・石炭鉱床の成因・産状・探査手法など,特にトラップ構造,堆積盆,堆積環境,貯留岩,根源岩,石油システム,資源量,炭化度などについて討論する.
【招待講演予定者】稲垣史生(海洋研究開発機構)・横井 悟(石油資源開発)→招待者の紹介はこちら
ページtopに戻る
R13.岩石・鉱物の破壊と変形/ Rock failure and deformation(構造地質部会)
廣瀬丈洋*(海洋研究開発機構:hiroset@jamstec.go.jp)・丹羽正和(日本原子力研究開発機構)・高橋美紀(産総研)
Takehiro Hirose*(JAMSTEC),Masakazu Niwa(JAEA)and Miki Takahashi(AIST)
断層岩を含む岩石・鉱物の破壊および変形機構,変形微細構造,岩石・鉱物のレオロジーや物性に関する研究を募る.観察・観測・分析・実験・理論など多方面からのアプローチによる成果を歓迎するとともに,会場での活発な議論を期待する.
R14.沈み込み帯・陸上付加体/ Subduction zone and on-land accretionary complex(構造地質部会・海洋地質部会)
氏家恒太郎*(筑波大:kujiie@geol.tsukuba.ac.jp)・橋本善孝(高知大)・坂口有人(山口大)・菅森義晃(大阪市大)
Kohtaro Ujiie*(Univ. Tsukuba),Yoshitaka Hashimoto(Kochi Univ.),Arito Sakaguchi(Yamaguchi Univ.)and Yoshiaki Sugamori(Osaka City Univ.)
沈み込み帯・陸上付加体に関するあらゆる分野からの研究を歓迎する.野外調査,微細構造観察,分析,実験,理論,モデリングのみならず海洋における反射法地震探査,地球物理観測,地球化学分析,微生物活動など多様なアプローチに基づいた活発な議論を展開したい.次世代の沈み込み帯・陸上付加体研究者を育てるべく,学生による研究発表も大いに歓迎する.
【招待講演予定者】片山郁夫(広島大)・小平秀一(海洋研究開発機構)→招待者の紹介はこちら
R15.テクトニクス/ Tectonics(構造地質部会)
加藤直子*(東京大:naoko@eri.u-tokyo.ac.jp)・大坪 誠(産総研)・藤内智士(高知大)
Naoko Kato*(Univ. Tokyo), Makoto Otsubo(AIST)and Satoshi Tonai(Kochi Univ.)
地球科学の多方面から,大小様々な時間・空間スケールで起こる地質構造の成因や形成機構・発達史に関する講演を広く募集する.野外調査,観測,実験,理論などに基づいた研究発表を歓迎する.また,2011年3月に発生した東北地方太平洋沖地震やその地震に関連する地殻変動の研究成果も歓迎する.
ページtopに戻る
R16.古生物/Paleontology(古生物部会)
平山 廉(早稲田大)・北村晃寿(静岡大)・太田泰弘(北九州博)・三枝春生(兵庫県立人と自然の博)・須藤 斎*(名古屋大:suto.itsuki@a.mbox.nagoya-u.ac.jp)
Ren Hirayama(Waseda Univ.),Akihisa Kitamura(Shizuoka Univ.),Yasuhiro Ota(Kitakyushu Mus.),Haruo Saegusa(Mus. Nature and Human Activities, Hyogo)and Itsuki Suto*(Nagoya Univ.)
主として古生物を扱った,または,プロキシとして古生物を利用したものや古生物を用いた新手法などの研究の発表・討論を行う.
R17.ジュラ系+/The Jurassic +(古生物部会)
松岡 篤*(新潟大:matsuoka@geo.sc.niigata-u.ac.jp)・近藤康生(高知大)・小松俊文(熊本大)・石田直人(新潟大)・中田健太郎(城西大)
Atsushi Matsuoka*(Niigata Univ.),Yasuo Kondo(Kochi Univ.),Toshifumi Komatsu(Kumamoto Univ.),Naoto Ishida(Niigata Univ.)and Kentaro Nakada(Josai Univ.)
2003年の静岡大会において「ジュラ系」として誕生した本セッションは,隣接する地質系統の研究者の要望を取り込んで「ジュラ系+」として発展し,10年間にわたりトピックセッションとして継続開催されてきた.この間,ジュラ系の研究を中心に,関連する講演がまとまって発表される場として定着し,ジュラ系研究の情報を研究者の間で共有することに貢献してきた.この10年の国際的なジュラ系研究は,ジュラ系基底のGSSP確定をはじめ重要な進展があったが,本セッションではその動向をいち早く伝え続けてきた.また本セッションの講演タイトルが国際ジュラ系層序小委員会のNewsletterに収録されるなど,ジュラ系研究拠点としての日本を国際的にアピールする場ともなっている.このような活動は,GSSPの決定に際し投票権をもつ国際ジュラ系層序小委員会のVoting Memberが日本から選出されたことにも繋がっている.本セッションを開催することによって,ジュラ系と上下の地質系統の研究について,各方面からのデータを提供しあい多角的に検討する場を提供する.このことは,日本からの国際発信力を強化することにも寄与する.
R18.情報地質/Geoinformatics(情報地質部会)(ポスター発表のみ)
能美洋介*(岡山理大:y_noumi@big.ous.ac.jp)・野々垣 進(産総研) Yosuke Noumi*(Okayama Univ. Sci.)and Susumu Nonogaki(AIST)
地質情報の数理解析,統計解析,データ処理,画像処理などの理論,応用,システム開発,利用技術など,最近の情報地質分野の研究結果を対象とする.また,これらの成果の地質学の広い分野への応用・普及なども歓迎する.
R19.環境地質/Environmental geology(環境地質部会)
難波謙二(福島大)・風岡 修(千葉環境研)・三田村宗樹(大阪市大)・田村嘉之*(千葉環境財団:y_tamtam3012@nifty.com)
Kenji Nanba(Fukushima Univ.),Osamu Kazaoka(Res. Inst. Environ. Geol., Chiba),Muneki Mitamura(Osaka CityUniv.)and Yoshiyuki Tamura*(Chiba Pref. Environ. Foundation)
地質汚染,医療地質,地盤沈下,湧水,水資源,湖沼・河川,都市環境問題,法地質学,環境教育,地震動,液状化・流動化,地震災害,岩盤崩落など,環境地質に関係する全ての研究の発表・討論を行う.
ページtopに戻る
R20.応用地質学一般およびノンテクトニック構造/Engineering geology and non-tectonic geology(応用地質部会)
小嶋 智(岐阜大)・須藤 宏*(応用地質:sudou-hiroshi@oyonet.oyo.co.jp)
Satoru Kojima(Gifu Univ.)and Hiroshi Sudo*(OYO Corp.)
応用地質学一般では,種々の地質ハザードの実態,調査,解析,災害予測,ハザードマップの事例・構築方法,土木構造物の設計・施工・維持管理に関する調査,解析,エネルギー問題の調査・研究など,応用地質学的視点に立った幅広い研究を対象とする.また,ノンテクトニック構造では,ランドスライドや地震による一過性の構造,重力性の構造等の記載,テクトニック構造との区別や比較・応用等の研究を対象にして発表・議論する.
【招待講演予定者】釜井俊孝(京都大)・笹田政克(地中熱利用促進協会)→招待者の紹介はこちら
R21.地学教育・地学史/Geoscience education/History(地学教育委員会)
矢島道子*(東京医科歯科大:pxi02070@nifty.com)・三次徳二(大分大)
Mchiko Yajima*(Tokyo Med. and Dental Univ.)and Tokuji Mitsugi(Oita Univ.)
地学教育,地学史に関わる研究発表を広く募集する.新学習指導要領が完全実施された教育現場からの問題提起や,実践報告に加え,大学や博物館,研究所等が行うアウトリーチに関わる実践報告についても歓迎する.また地学史からの問題提起,貴重な史的財産の開示を歓迎する.
R22.第四紀地質/Quaternary geology(第四紀地質部会)
公文富士夫*(信州大:shkumon@gipac.shinshu-u.ac.jp)・内山 高(山梨環境研)
Fujio Kumon*(Shinshu Univ)and Takashi Uchiyama(YIES)
第四紀地質に関する全ての分野(環境変動・気候変動・湖沼堆積物・地域層序など)からの発表を含む.また,新しい調査や研究,方法の開発や調査速報なども歓迎する.
R23.地球史/History of the Earth(環境変動史部会)
清川昌一*(九州大:kiyokawa@geo.kyushu-u.ac.jp)・山口耕生(東邦大)・小宮 剛(東京大)・尾上哲治(熊本大)・須藤 斎(名古屋大)
Shoichi Kiyokawa*(Kyushu Univ.),Kosei Yamaguchi(Toho Univ.),Tsuyoshi Komiya(Univ. Tokyo),Onoe Tetsuji(Kumamoto Univ.)and Itsuki Suto(Nagoya Univ.)
地質学的視点から,さまざまな時間スケールで地球の変動を捉えようとする研究の発表や議論の場としたい.時代は特定せず,初期地球から有史時代まで幅広い時代の研究発表を期待している.地球表層環境変動と生命進化,固体地球,テクトニクスとの相互作用など,「地球史」というキーワードで繋がるあらゆる研究分野をターゲットとしている.
【招待講演予定者】石橋純一郎(九州大)→招待者の紹介はこちら
R24.原子力と地質科学/Nuclear energy and geology(地質環境の長期安定性研究委員会)[共催:日本原子力学会バックエンド部会]
吉田英一*(名古屋大:dora@num.nagoya-u.ac.jp)・梅田浩司(日本原子力研究開発機構)・高橋正樹(日大)・渡部芳夫(産総研)
Hidekazu Yoshida*(Nagoya Univ.),Koji Umeda(JAEA),Masaki Takahashi(Nihon Univ.)and Yoshio Watanabe(AIST)
原子力は,ウラン資源探査,活断層等を考慮した耐震安全性評価,廃棄物の地層処分,放射性物質の環境動態等の多くの地質科学的課題を有している.本セッション「原子力と地質科学(Nuclear Energy and Geology)」は,このような日本の原子力に関わる地質科学的課題について,地球科学的知見の議論及び関連する学会や研究者間の意見交換を行うことを目的としており,幅広い分野からの参加,発表を歓迎する.
【招待講演予定者】杤山 修(原子力安全研究協会)→招待者の紹介はこちら
ページtopに戻る
アウトリーチセッション:1件
OR.日本地質学会アウトリーチセッション/Outreach session(ポスター発表のみ)
星 博幸*(愛知教育大:hoshi@auecc.aichi-edu.ac.jp)・須藤 斎(名古屋大)
Hiroyuki Hoshi(Aichi Univ. Education)・Itsuki Suto(Nagoya Univ.)
会員が研究成果を社会へ発信する場として設けられたセッション.地質学と関連分野を対象とし,開催地(東北,仙台)とその周辺の地質や地学に関する研究紹介,社会的に注目されている地質および関連トピックの研究紹介,特定分野の研究到達点や課題の解説など.客層は会員(専門家)ではなく市民であることに注意.市民講演会の会場で開催する.申込多数の場合は行事委員会にて採否を検討する.アウトリーチセッションの詳細については,こちら
講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理,引用方法,校閲について
講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理,引用方法,校閲について
(1)講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理
本学会は,本学会出版物への投稿原稿に対して,その倫理性について著作者が保証する「保証書」および著作権を本学会へ譲渡することに同意する「著作権譲渡同意書」に署名捺印をして提出していただいています.電子投稿では,画面上で「保証書」と「著作権譲渡等同意書」の内容に同意していただいてから電子投稿画面に進めるようになっています.郵送の場合は「保証及び著作権譲渡等同意書」に署名捺印し,講演要旨原稿と共にお送り下さい.「保証及び著作権譲渡等同意書」が同封されていない発表申込は受け付けません.
「保証及び著作権譲渡等同意書」ダウンロードはこちらから
(2)講演要旨における文献引用
引用した文献の情報を必ず記載して下さい.講演要旨では文献記載の簡略化が認められています.著者名,発表年,掲載誌名など,文献を特定できる必要最低限の情報を明記して下さい.
(3)講演要旨の校閲
行事委員会は,すべての(招待講演を含む)講演要旨について,学会の目的ならびに倫理綱領(定款第4条)に反していないかという点について校閲を行います.校閲によりいずれかの条項に反していると判断された場合,行事委員会は修正を求めるか,あるいは発表申込を受理しないことがあります.行事委員会の措置に同意できない場合,発表申込者は法務委員会(学会事務局気付)に異議を申し立てることができます.
講演申し込み異議申し立てについて
日本地質学会行事委員会は,学術大会において学会の目的及び倫理規定に反する講演申し込みのあった要旨に対して,修正あるいは,受理を拒否することができます.法務委員会では,日本地質学会行事委員会規則に基づき,異議申立の手続及びその処理についての規則を定めています.
日本地質学会法務委員会
■日本地質学会学術大会講演申込異議申立に関する処理機構規則(PDF)■
講演要旨の作成の注意点とPDFファイル作成の作り方
content_id: 22 subject: 講演要旨の作成の注意点とPDFファイル作成の作り方 cat_id: 2 vpath: created: 2013-7-3 17:07 (58.87.204.36) 事務局(6) modified: 2014-5-13 11:36 (218.41.59.146) 事務局(6) filters: htmlheader: body:
講演要旨の作成の注意点とPDFファイルの作り方
講演要旨を作成する際,著者には「保証及び著作権譲渡同意書」第1項の「保証」内容を守って頂きます.行事委員会は,要旨の内容については関知しませんが,当該「保証」内容を逸脱するものがないか校閲します.その結果,不適当とみなされる場合は,修正されるまで講演要旨を受理しません(不服の場合は法務委員会に訴えることができます).
引用文献を適切に記載していない要旨原稿が毎年多く認められます.論文のように細かに引用文献を記載することはスペースの都合上不可能なので必要としませんが,雑誌名,号,ページ等,その文献にたどり着ける最低限の情報は記載して下さい.図等の改変については,著作権法と学会著作物利用規定に従って下さい.このほか,PDFファイルにフォントを埋め込んでいない(印刷時に文字化けすることがあります),講演番号記入用のスペースがない,余白が足りない等の場合は,体裁を整えるため修正していただきます.これらの問題点が認められる場合,世話人より投稿締切日から1週間をめどに修正依頼を送付しますが,編集作業の労力を極力少なくするために(世話人にはボランティアで協力していただいています),あらかじめ完全なものを投稿するようにして下さい.あわせて講演要旨投稿手順のチェック項目(次頁)もご参照ください.
日本地質学会行事委員会
2013年4月
講演申込・講演要旨投稿:受付終了
■要旨テンプレート(Microsoft Word)■ ■講演要旨投稿手順のチェックシート■
【講演要旨PDFファイル作成時の注意点】
1)
講演要旨原稿はAdobe Acrobat Reader 4.0 以上で表示・印刷可能なPDFファイルで投稿して下さい.
2)
ファイルサイズは3.0Mバイト以内で作成して下さい.
3)
事務局にて発表(講演)番号を左上に付記するので原稿左上(題目の左)は空白にし,何も記載しないで下さい.
4)
PDFファイルのセキュリティ設定は「なし」にして下さい.
5)
フォントは必ず「埋め込み」にして下さい.その際,『すべてのフォント埋め込み』ないし『ハイクォリティー』等,それぞれのソフトの使用説明書に従った指定を必ずして下さい.文字数にもよりますが,できたPDFファイルのサイズが100KB未満の場合,フォントが埋め込まれなかった可能性がありますので確認して下さい.
6)
作成したPDFファイルを自分で印刷し,図表に充分な解像度があるか,文字化けはないか確認して下さい.
7)
PDFファイルを自分のパソコンに,必ず「.pdf」の拡張子をつけて保存して下さい(Mac, Windowsとも).
■原稿フォーマット見本■
お願い!!共同発表の場合,講演要旨には発表者氏名に下線を引いて下さい.
テンプレート
(Microsoft Word)
ダウンロードはこちら
オンラインでの講演要旨投稿の手順
1)
オンラインで講演申込をします:HP上の講演申し込みページにアクセスし,画面に従って連絡者情報等を入力し,講演申し込みの手続きをします(講演申込と同時に要旨投稿をすることもできますし,講演要旨のみ後で投稿することもできます).
2)
講演要旨PDFを投稿します:演題・発表者情報登録画面の最下段にある「アップロードファイル」欄から要旨原稿(PDFファイル)を投稿します.欄右側の「参照」ボタンをクリックし,ご自分のPCに保存してあるPDFファイルを選択します.
3)
登録内容を確認:画面下の「次へ」をクリックし,登録内容確認画面に進みます.登録内容を確認後,画面下の「登録」ボタンをクリックします.これによりサーバーにPDFファイルが格納されます.
4)
完了画面を確認して下さい:『登録が完了いたしました.受付番号は*****です.』という完了画面が表示されます(注意!この画面が表示されないと登録は完了していません).
5)
確認メールが届きます:登録したメールアドレスに「講演申込のお知らせ」のメールとともに受付番号(=ID)が配信されます.
後から要旨を投稿する/申込内容を変更する場合
1)
IDとメールアドレスでログイン:ご自分の申込画面に,IDとメールアドレスを用いてアクセスします.
2)
新しい講演要旨PDFファイルをアップロード:「登録内容変更」ボタンをクリックし,画面の最下段にある「アップロードファイル」欄の「修正」ボタンをクリックします.ご自分のPCに保存してあるファ イルを選択し,アップロードをします.サーバー側では,ファイル名を元のファイル名から変更し,ID.pdfの名称で格納します.
3)
完了画面の確認:『登録が変更されました.受付番号は****です.』という操作完了画面が表示されます.(注意!!この画面が表示されないと操作は完了していません)
4)
変更確認メールが届きます:「講演申込内容変更のお知らせ」メールが配信されます.
5)
IDとメールアドレスを用いて,投稿締切まで何度でも要旨や登録内容 を修正することができます.新しいファイルを投稿すると,古いファイルに上書きされます.そのつど,「講演申込内容変更のお知ら せ」メールが配信されます
【参考情報:PDFファイルの作り方】
PDFファイルの作成方法は「PDF原稿作成ガイド」http://www.gakkai-web.net/pdf/を参考にすると良いでしょう.PDFファイルを作成するためのソフトはAdobe Acrobatをはじめ多数あります.各自インターネット等で検索,入手してください.
・ベクター(http://www.vector.co.jp/)
・窓の杜(http://www.forest.impress.co.jp/)
等のサイトが役立ちます.
Windowsでは,Miocrosoft Office 2010(Word, Excel,PowerPoint等)を用いてフォント埋め込み型のPDFファイルを作成できます.Mac OSX以上には,フォント埋め込み型のPDFファイル作成機能が標準で用意されています.
重要!!講演申込をされる方は別途忘れずに,事前参加登録の画面操作も行ってください!!
(※要旨投稿済であっても、事前参加登録をしない場合は,当日参加申込になります.)
要旨投稿チェックシート
講演要旨オンライン投稿手順チェックシート
講演要旨の投稿手順および基本的注意事項です.投稿していただく前に各自でご確認下さい.
1.Word等のソフトで講演要旨原稿を作成します.
「保証及び著作権譲渡同意書」第1項の「保証」内容は守られていますか?
要旨原稿内に引用文献は表示されていますか?
要旨の体裁は守られていますか?(詳細は要旨原稿フォーマットをご確認下さい)
2.原稿をPDFファイルにします.PDFファイルの作成方法については,「PDFファイルの作り方」を参照して下さい.
フォントは「埋め込み」になっていますか?(できたファイルサイズが100KB未満の場合,フォントが埋め込まれなかった可能性がありますので確認して下さい)
ファイルサイズは3.0MB以内になっていますか?
作成したファイルを自分でプリントアウトしてみましたか?(図表や写真に充分な解像度があるか,文字化けはないか確認して下さい)
PDFファイルを自分のパソコンに,必ず.pdfの拡張子をつけて保存して下さい.
3.講演申込&要旨原稿をオンライン投稿する.
講演申し込みの手続きをしましたか?(講演申込システム:PASREG)
申込完了画面が表示されましたか(ログイン用の受付番号(=ID)が表示されましたか)?
「講演申込のお知らせ」のメールが配信されましたか?
←講演要旨投稿手順に戻る
保証書・同意書
<郵送での投稿の場合は、原稿に必ず添付して下さい>
保証及び著作権譲渡等同意書 PDFダウンロードはこちらから
保証及び著作権譲渡等同意書
著作者(下記)は,日本地質学会によって発行される第120年学術大会「講演要旨」・「巡検案内書」に掲載する下記表題の原稿(以下「本原稿」という.)について,以下のとおり保証し,かつ著作権を譲渡等いたします.
第1 保証
著作者は,本原稿について,以下の各号記載の事項を保証し,確約します.
1) 本原稿が著作者自身の著作物であり,既にいずれかで出版公表されているものと同一ではないこと.
2) 本原稿が既存の出版公表物などに対する知的財産権のいかなる侵害も含まないこと.
3) 本原稿中に他から転載されているすべての図表について,転載許可を得ていること.
4) 本原稿中,他の論文等の引用がある場合には,当該引用が公正な慣行に合致し,目的上正当な範囲内であること.
5) 著作物には,日本地質学会の名誉を傷つけ,当該出版物の信用を毀損する盗用データ,捏造データ,著作物に関する利害を持つ者の合意に反するもの,その他学会の倫理綱領に反するものを含まないこと.
6) 本原稿が共同著作物である場合には,代表して本書に署名捺印する者が,すべての共著者から,本書に著名捺印することについて同意ないし必要な権利を得ていること.
7) 本原稿についての問い合わせ,苦情,紛争などが発生した場合,署名者はすべての責任を負うこと.
8) 本著作物を作成するに当たって行われた調査・研究行為が,適切な方法でなされたものであること.
第2 著作権譲渡等
著作者は,本原稿について,以下の各号記載に同意します.
1) 本原稿のすべての著作財産権(著作権法27条,同28条に定める権利を含む)及び2次著作物の創作・利用に係る権利を日本地質学会へ譲渡すること.
2) 本原稿について,日本地質学会ならびに日本地質学会から正当に権利を取得した第3者及び当該第3者から権利を承継した者に対し,著作人格権(公表権,氏名表示権,同一性保持権)を行使しないこと
3) 本原稿の下記の各利用形態に関する権利を日本地質学会が排他的に行使すること.
a) 複製,翻訳,翻案(出版,電子出版,翻訳出版,データベース化,ビデオグラム化,その他すべての記録メディアへの記録・掲載などを含む)
b) 展示・上映
c) 放送,有線放送,自動公衆送信(地上波,CATV放送衛星,通信衛星,インターネット,パソコン通信,その他あらゆる送信媒体及び将来開発されるすべての送信媒体による公衆送信を含む)
d) 頒布,譲渡,貸与
e) その他,本著作物に関する一切の利用(技術の進歩により将来生じうる利用形態を含む)
以上
日付 2013年 月 日
本原稿表題
著作者(代表者) 印
署名者が代表する共著者すべての氏名
学会記入【講演番号: 】
学会記入【受付番号: 】
招待講演者の紹介
セッション招待講演の紹介
世話人や専門部会から提案され,行事委員会が承認したセッション招待講演(予定)の概要を紹介します.学術的にも社会的にも注目されている研究者やテーマが目白押しです.会員の皆様,この機会をお見逃しなく! なお,講演時間は変更になる場合があります.
(行事委員会)
招待講演が予定されているセッション(略称)
T2 太陽系と地球の進化史
T4 海溝での生物と巨大地震との関連性
T5 東北地方太平洋沖地震とその付随現象
R1 深成岩・火山岩
R3 噴火・火山発達史
R4 変成岩とテクトニクス
R6 ジオパーク
R8 海洋地質
R12 石油石炭
R14 沈み込み帯・陸上付加体
R20 応用地質・ノンテク
R23 地球史
R24 原子力と地質科学
T2 物質科学・比較惑星地質学から解読する太陽系と地球の進化史
■関根康人氏(東京大学) 30分
関根氏は,惑星化学と地球大気進化を大きな柱とした研究を行っており,タイタンや火星の進化過程から太古代の地球大気,小惑星衝突が大気に及ぼす影響など,その化学反応過程を室内実験,理論計算や野外調査によって調べている.最近では,インド・ロナクレーターの掘削を通じてアジア気候変動の研究も行っている.
■丸岡照幸氏(筑波大学) 30分
丸岡氏は,炭素・硫黄同位体比などの地球化学的手法を用いて,白亜紀/古第三紀境界の隕石衝突イベントが当時の地球環境や生命に与えた影響について研究を進めている研究者である.また同氏は,隕石衝突と大量絶滅に関するわかりやすい解説本も執筆しており,地球科学の普及にも貢献している.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T4 海溝での生物と巨大地震との関連性
■野牧秀隆氏(海洋研究開発機構) 30分
野牧氏は日本海溝において震災前後を通じて生物学的な研究を多角的に行っている生物学者である.同氏はJAMSTECのYK11-E06をはじめとした東北地方の緊急航海にも参加している.それらの行動は記者発表もされており,社会的にインパクトのある研究成果が現在まとめられつつある.
■笠谷貴史会員(海洋研究開発機構) 30分
笠谷会員はJAMSTECのYK11-E06をはじめとした東北地方の緊急航海に参加し,広域サーベイにも携わり,数多くの生物学者と連携して東北沖の調査を精力的に行っている,現場を知り尽くした研究者である.また,同氏は海溝周辺でのAUVなどの機器を用いた調査にも従事している.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T5 2011年東北地方太平洋沖地震とその付随現象に関する地質学的研究の進展
■池田安隆会員(東京大学) 30分
池田会員は,地質学的歪み速度と測地学的歪み速度の矛盾からプレート境界固着面全体がすべる巨大歪み解放イベントが存在することを,2011年の東北地方太平洋沖地震の発生以前から論じていた.
■西村卓也氏(京都大学) 30分
西村氏は,過去120年間の東北日本の地殻変動の時間変化を測地観測データから示し,2011年の地震以降進行中の余効変動が上記池田会員によって指摘されていた矛盾を解消する鍵になり得ることを指摘している.
画面topに戻る
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R1 深成岩・火山岩とマグマプロセス
■石原舜三会員(産業技術総合研究所) 30分
石原会員は深成岩,とくに花崗岩研究の第一人者であり,現在も国際的に使用される岩石化学的花崗岩区分法(マグネタイト系およびイルメナイト系)の提案者である.最近では,花崗岩の成因とレアアース・レアメタル含有量の関連性について精力的に分析・執筆を重ねている.
■小澤一仁会員(東京大学) 30分
小澤会員は地球深部におけるマグマの発生から進化までのプロセスを,天然物質の観察と室内実験に基づく物質科学的手法を用いて研究している.最近は,天然の岩石から鉱物間反応と変形の情報を抽出し,マントルの運動解析およびマントル物質の起源解明に取り組んでいる.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R3 噴火・火山発達史と噴出物
■高橋正樹会員(日本大学) 30分
高橋会員は桜島火山や浅間火山の火山地質学・岩石学研究を継続的に行い,噴火の長期予測に有益な研究成果を多数残している.火山学に関する学術書・一般書の著書も多い.最近では,長期火山活動評価の視点から地層処分に関する提言を精力的に行っている.
■中田節也会員(東京大学) 30分
中田会員は雲仙火山科学掘削計画を主導・成功させ,活火山の火道の実態を世界ではじめて明らかにした.同時にマグマの脱ガスと噴火様式に関する火山学的新知見も明らかした.最近では,噴火活動中の霧島火山(新燃岳)における短〜中期活動予測(シナリオ作成)で注目される.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R4 変成岩とテクトニクス
■伊藤喜宏会員(東北大学) 30分
深部低周波微動は沈み込み帯の深さ35 km,温度400 ℃程度で起こる特徴的な現象である.その痕跡は高圧変成帯に残されている可能性が非常に高いが,いまだに物質科学的な証拠に基づいたモデルは構築されていない.伊藤会員は深部低周波微動,ゆっくり地震の研究の第一人者である.地震学的にそれらがどのような現象で,地震学者はどういう実体と考えているかについて講演していただく.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R6 ジオパーク
■柴田伊廣会員(室戸ジオパーク) 30分
室戸ジオパークは日本における世界ジオパークの一つであり,インタープリター・ガイドの質は極めて高い.学術的な事柄を市民にわかりやすく説明するのみならず,楽しませる技術をさまざま工夫している.柴田会員はこのガイドの育成に中心的に携わってきた.同会員の実践的な報告は,他のジオパークにおけるインタープリター育成において参考になるだろう.
画面topに戻る
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R8 海洋地質
■加藤泰浩会員(東京大学) 30分
加藤会員は,タヒチ沖やハワイ沖などの太平洋の海底にレアアースに富んだ遠洋性泥が存在することを発見し,組成・分布の調査を精力的に進めている.レアアース資源の賦存量や分布,さらにその成因解明に関する最先端の研究について講演していただく.
■鈴木勝彦氏(海洋研究開発機構) 30分
鈴木氏は,Re−Os年代測定法を用いた鉱床の形成年代の推定や熱水による変質の評価研究などを行ってきた.また,最近ではJAMSTEC・東京大学による資源泥の共同調査を計画・推進し,南鳥島周辺において超高濃度のレアアースが海底堆積物に含まれることを明らかにした.海洋調査の概要と最新の成果について講演していただく.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R12 石油・石炭地質学と有機地球化学
■稲垣史生氏(海洋研究開発機構) 30分
海洋科学掘削の最深記録を更新したIODP下北八戸沖ライザー掘削は,石炭層と深部地下微生物圏の関係解明,地下生命圏の探索などで注目されている.掘削により未熟成な石炭層が確認され,その続成過程で供給された低分子有機化合物が深部での地下微生物圏を形成していることが推察された.同航海の共同主席研究者である稲垣氏に,ガスハイドレートの起源としても注目される微生物起源のメタン生成にまで踏み込んで講演していただく.
■横井 悟会員(石油資源開発) 30分
米国発のシェール革命により,天然ガスの需給構造や価格が大きく変化し,震災後のわが国のエネルギー構造の変化とも関連して国産エネルギー資源に対する期待が高まっている.秋田県に分布する女川層は優秀な石油根源岩であり,古くから石油地質学的な研究が行われてきた.横井会員は,根源岩と考えられてきた女川層に対してシェールオイル(タイトオイル)の可能性をいち早く指摘し,実証試験にまで導いた.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R14 沈み込み帯・陸上付加体
■片山郁夫会員(広島大学) 講演時間未定
21世紀の固体地球科学分野における大きな発見の1つに,沈み込み帯におけるスロー地震群の発見がある.片山会員は,岩石試料観察と浸透率測定に基づいて,スロー地震群の成因に関する興味深い考察を行っている.地質学研究者が今後スロー地震群の地質学的描像を描き出すうえで参考となる優れた研究を紹介していただく.
■小平秀一氏(海洋研究開発機構) 講演時間未定
小平氏を代表とするJAMSTEC構造探査チームは,反射法地震探査や海底地形探査に基づいて,2011年東北地方太平洋沖地震において地震破壊が海溝軸付近にまで及んだことを明らかにした.海洋物理探査で明らかになった海溝型巨大地震の実態を本会会員に広く知ってもらうべく講演していただく.
画面topに戻る
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R20 応用地質学一般およびノンテクトニック構造
■釜井俊孝氏(京都大学防災研究所) 30分
釜井氏は,旧地形の谷を盛土した「谷埋め盛土」の地震時や豪雨時の危険性について野外調査・研究を長年続けており,中越地震や東日本大震災時など多数の事例について研究成果を発表している.講演予定の「宅地盛土地すべりの現状と課題」は,応用地質分野としてもその実態を理解し,社会に役立てる必要のあるテーマである.
■笹田政克会員(地中熱利用促進協会) 30分
笹田会員は,自然再生エネルギーとして活用が注目されている地中熱利用研究の第一人者である.講演予定の「地中熱利用の現状と展望」は,応用地質分野としてもその現状について理解し,社会に普及させることが求められているテーマである.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R23 地球史
■石橋純一郎氏(九州大学) 30分
熱水系は,初期地球を知る上でも,また時代ごとの変遷やイベントを知る上でも重要である.石橋氏は新学術領域「海底下の大河」(平成19〜24年度)のリーダーの一人であり,地球化学と鉱床学の切口から沖縄トラフ掘削や西太平洋背弧群の研究,鹿児島県ミコモトカルデラについての研究を進めている.それらの成果を踏まえて,海底熱水系環境やそこで生み出される堆積物について最新成果を紹介していただく.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R24 原子力と地質科学
■杤山 修氏(原子力安全研究協会) 30分
杤山氏は,地層処分における性能評価に欠かせない核種移行研究とその議論を長年にわたりリードしてきた.また本セッションを共催する日本原子力学会バックエンド部会長(2002〜2003年)として部会を指導し,バックエンド部会の発展にも尽くしてきた.その他,国の放射性廃棄物小委員会等の要職も歴任するなど,現在も第一線で活躍している.今回は「地質環境に関する長期的安全評価手法」に関する情報や考え方について講演していただく予定である.
優秀ポスター賞
優秀ポスター賞
今大会でも学術発表の優秀ポスターに対して「日本地質学会優秀ポスター賞」を授与します.毎日3〜5件の予定です.受賞者には学会長から直接賞状を授与します(表彰と写真撮影).受賞ポスターは,その栄誉をたたえ,大会期間中,別途設けるボードに掲示します.大会終了後,News誌(年会報告記事)に氏名,発表題目,受賞理由を掲載します.
【審査】
審査は各賞選考委員会が行い,学会長がこれを承認します.選考委員会は日替わりで,行事委員会委員5名,大会実行委員会代表1名および各賞選考委員会委員2名の合計8名により構成されます.選考委員氏名は大会終了後に公表します(News誌11月号を予定).
【審査のポイント】
・ (研究内容)オリジナリティ
・ (プレゼンテーション)レイアウト・中心点の明示・わかりやすさ・美しさ・斬新さ
【審査結果の発表時間と方法】
発表は16:00以降に行います.表彰は決定後直ちにポスター会場で行います(ただし初日(14日)のみ表彰式会場にて行う予定).審査結果は掲示板,廊下等,要所に貼り出します.受賞ポスターには受賞花をつけます.
参加登録TOP
2013仙台大会事前参加登録ほか申込
当日会場受付での混雑緩和のため,事前に参加登録申込をお願いします.大会参加登録およびそれに伴う参加費は,参加者(巡検のみ参加の場合も)に必要な基本的なお申し込みです.ただし,会員が同伴する非会員の配偶者ならびに子供(以下,同伴者)については参加登録申込の必要はありません(懇親会・巡検・お弁当については同伴者も申込が必要).会員と同伴者の2名まで一括申込が可能です.申込は,「各種申込とお支払について」を参照し,下記フローチャートを進んで該当する申込画面よりお申込をお願い致します。
<申込締切 オンライン:8月20日(火)18:00,FAX/郵送:8月16日(金)必着>
<事前受付は終了しました>
当日登録の方法等につきましては、近日中に掲載いたします。
(News誌8月号にも掲載)
懇親会は予約制ですが、人数に余裕があれば当日参加の申込も可能です。
受付状況については、会場受付にて確認してください。
下のフローチャートに従って進み,該当する申込画面をクリックして
それぞれ申込手続きをおこなって下さい
※巡検協賛学協会・セッション共催団体リストはこちら
参考>>会員情報を自動取得するには?(PDF)
*FAX・郵送専用申込書(PDF)はこちら
【巡検M班中止のお知らせ】
仙台大会の巡検コースについて,巡検案内者の都合により,下記コースは中止となりました。
申込受付開始後の変更のため,皆様にはご迷惑をおかけ致しますが,何卒ご了承下さい。
すでにお申込を頂いた方は,事務局よりキャンセルのお手続きをさせて頂きます。
【中止】M班 2008年岩手・宮城内陸地震による斜面災害(案内者 川辺孝幸・籾倉克幹)
*申込方法・支払い方法の詳細についてはこちら ▶▶各種申込とお支払について
参加フォームから申し込める項目:クリックすると各詳細のご案内をご覧いただけます。
■ 参加登録費
■ 追加講演要旨(大会不参加で冊子のみの購入も可)
■ 巡検 *注意* 8月9日締切.冊子体での巡検案内書の作成・販売はありません
■ お弁当
■ 懇親会
会員が同伴する非会員の配偶者ならびに子供(以下,同伴者)については
参加登録申込の必要はありません.
(懇親会・巡検・お弁当については同伴者も申込が必要:会員の申込と一括で申込可能)
共催・協賛団体の一覧
2013仙台大会:巡検協賛およびセッション共催団体一覧
巡検協賛団体
セッション協賛団体
・資源地質学会
・石油技術協会
・地学団体研究会
・東北地理学会
・一般社団法人日本応用地質学会
・特定非営利活動法人日本火山学会
・日本活断層学会
・日本鉱物科学会
・日本古生物学会
・日本自然災害学会
・日本堆積学会
・日本第四紀学会
・日本地球化学会
・公益社団法人日本地球惑星科学連合
・日本地学教育学会
・公益社団法人東京地学協会
・石油技術協会探鉱技術委員会
・日本鉱物科学会
・日本堆積学会
・日本有機地球化学会
・原子力学会バックエンド部会
(6月3日現在)
参加登録TOP画面に戻る
当日の受付について
当日の受付について
事前参加登録につきましては,FAX・郵送によるお申し込みを8月16日,オンラインによるお申込みを8月20日に締め切りました.
入金済みの事前登録者には締切後,確認書2枚(本人控・受付提出用)と名札,懇親会とお弁当を予約の方へはそれぞれクーポンを発送します.大会開催10日前には事前登録された皆様のお手元に届くようお送り致します.発送時点で入金確認が取れない場合は,未入金の旨記載された確認書のみ送付いたしますので当日会場にて確認書をご提示いただき,入金の確認をして下さい.入金と確認書がゆき違いの場合は,送金時の控え等を会場にお持ちください.
当日確認書やクーポンを忘れた方は,専用の用紙に申込内容をご記入いただき,受け付けを済ませてください.確認がスムーズに行えますよう,ご協力をお願い致します.なお,別途領収書が必要な方は会場受付でその旨お申し出ください.当日のお支払いは,現金のみの取扱いとなります.クレジットカードはご利用いただけません.
事前参加登録者
入金済の方へ→事前登録者には締切後,確認書2枚(本人控・受付提出用)と名札,懇親会とお弁当のクーポン(クーポンは予約者のみ)を発送します.
未入金の方へ→締切時点で入金確認が取れない場合は,未入金の旨記載された確認書のみ送付します.
事前登録者用受付にて,確認書に記載されている項目ごとに受付して下さい.
受付にてネームカードホルダーをお渡ししますので『参加証(名札)』を入れ,大会期間中は身に付けてくだ
さい.
1 .確認書の提出(全員)→ネームカードホルダーの配布.要旨付きの場合は,要旨の配布
2 .講演要旨追加購入(予約購入者のみ)→要旨の配布
3 .懇親会→参加者は直接懇親会会場でクーポンを提示してください.
4 .お弁当(予約者のみ)→お弁当の引き換え時にクーポンを提示してください.お弁当の受取はクーポンと引換です.
5 .巡検(参加者のみ)→名簿確認と参加最終確認
注:未入金者の方は,総合受付で入金確認した後,懇親会やお弁当のクーポンをお渡しします.
→申込の取消・取消料についてはこちらから
事前登録をしていない方
1 . 当日は必ず参加登録をしてください.参加登録費の有料・無料に関わらず備え付けの『参加登録票』に必要事項を記入し当日用受付へ
2 . 当日参加登録費(講演要旨集付きです.要旨不要でも割引はありません)
---正会員:9,500円
---院生割引会費適用正会員:6,500円
---学部学生割引適用正会員・名誉会員・50年会員・非会員招待講演者・学部学生(会員・非会員問わず):無料(講演要旨は付きません)
---非会員(一般):15,000円・
---非会員(院生):9,500円
3 .講演要旨当日販売
---会 員:4000円
---非会員:5500円
4 .懇親会の当日参加費(ただし,人数に余裕がある場合に限る)
---正会員・非会員(一般):6,000円
---名誉会員・50年会員・院生および学生割引適用正会員(家族および非会員院生・学生含):3,500円
申込方法と支払について
各種申込とお支払について
■ WEB参加登録はこちらから ■
(1)申込方法
オンラインによる参加登録申込等を受付けます.申込は従来同様,学会独自の参加登録システムをご利用いただきます.大会専用参加登録システム(会員・非会員にかかわらずどなたでも申し込み可)または専用申込書(FAX・郵送用)をご利用の上,お申し込み下さい.参加登録・懇親会・追加講演要旨・巡検・お弁当を同時に申込むことができます.なお,学会を通じての宿泊・交通手配の斡旋は行いません.宿泊や交通については各自で手配願います.
(a)大会登録専用HP(オンライン)による申込
1)大会HP画面左のメニュー「参加登録」をクリックして下さい.
2)申込画面の入力欄に氏名と会員番号を入力するだけで,学会に登録されている会員情報(所属・住所等)が表示され,続けて参加登録を行うことができます.
3)申込み完了後,「申込確認メール」および「ご請求メール」が登録のメールアドレスへ配信されます.内容を必ずご確認下さい.(※メールが届かない場合は,登録アドレスが間違っている可能性があります.事務局へご連絡ください.)
4)支払い方法について,「銀行振込」を選択された方は,「ご請求」メールを確認の上,指定の金融機関よりお振込み下さい.また,クレジットカードもご利用頂けます.「クレジット決済」を選択の場合は,ご利用のカード会社の期日に合わせて,口座より引き落としとなります.クレジットカード会社からの明細には「日本地質学会(ニホンチシツガッカイ)」と表示されます.
5)締切後,名札・確認書・クーポン(一部の方)を発送します(8月末頃発送予定).大会開催10日前までには参加者の皆様のお手元に届くようお送り致します.締切時点で入金確認が取れない場合は,未入金旨記載された確認書のみが送付されます(名札・クーポンは送付されません)ので,当日会場にて入金のご確認をさせて頂きます.入金とクーポン発送が入れ違いの場合は,振込み時の控え等を会場にお持ちいただければ,確認がスムーズに行えます.ご協力をお願い致します.
(b)FAX・郵送による申込
「FAX・郵送専用申込書」(PDF)はこちらから
1)「 FAX・郵送専用申込書」に必要事項を記入の上,日本地質学会事務局までFAXまたは郵送にてお申込み下さい.電話による申込,変更などは受け付けられませんので,ご了解下さい.また,郵送による申込みの際は,必ず申込書のコピーを各自で保管して下さい.
FAX番号:03-5823-1156
郵送先:〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-815井桁ビル6階「日本地質学会大阪大会参加申込係」
2)申込後,折返し学会より「受付確認」をe-mailまたはFAXにてお送りします.必ずご確認下さい.受付確認が届かない場合は,必ず事務局までご連絡下さい.受付確認には,「受付番号」が記載されています.この「受付番号」はその後の問い合せ,変更,取消等に必要となります.
3)お支払いは,銀行振込またはクレジットカード決済のいずれかを選択できます.申込後順次,「予約内容確認」・「請求書」をお送りします.銀行振込を選択された方は,請求書に記載されている振込口座へ指定期日までにお振込み下さい.クレジット決済を選択された方は,参加申込の際必ずクレジット番号などの必要事項を記入して下さい.ご利用のカード会社の期日に合わせて,口座よりお引き落としとなります.カード会社からの明細には「日本地質学会(ニホンチシツガッカイ)」と表示されます.
4)締切後,名札・確認書・クーポン(一部の方)を発送します(8月末頃発送予定).大会開催10日前までには参加者の皆様のお手元に届くようお送り致します.締切時点で入金確認が取れない場合は,未入金旨記載された確認書のみが送付されます(名札・クーポンは送付されません)ので,当日会場にて入金のご確認をさせて頂きます.入金とクーポン発送が入れ違いの場合は,振込み時の控え等を会場にお持ちいただければ,確認がスムーズに行えます.ご協力をお願い致します.
(2)申込締切
大会登録専用HP(オンライン)による申込:8月20日(火)18:00
FAX・郵送による申込:8月16日(金)必着
(3)申込後の変更・取消
(a)大会登録専用HP(オンライン)でお申込みの場合:締切までの間は,大会登録専用HPから予約の変更・取消が出来ます.変更・取消完了後,「変更・修正 確認メール」が登録のメールアドレスへ配信されます.内容を必ずご確認下さい.締切後は直接学会事務局(東京)にFAX又はe-mailにてご連絡下さい.クレジット決済の場合は,申込の都度決済が完了しますので,決済スケジュールの都合によっては,口座から重複して引き落とされる場合があります.その場合は,振込手数料を差し引いた額をクレジットカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2〜3ヶ月要する場合もありますので,ご了承下さい.
(b)FAX・郵送でお申込み場合:申込後に変更・取消が生じた場合は,学会事務局(東京)にFAXまたはe-mailにてご連絡下さい.その際申込受付時に案内される「受付番号」・「氏名」を必ず明記下さい.
(4)取消に関わる取消料と返金について
注意:弁当と巡検は取消料が異なります.
(a)締切までの取消:取消料は発生しません.返金がある場合は,振込手数料を差し引いた額をクレジットカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2〜3ヶ月要する場合もありますので,ご了承下さい.
(b)締切後〜9/11(大会3日前)までの取消:入金・未入金の如何に関わらず,参加費用の60%を取消料としていただきます.返金がある場合は,振込手数料を差し引いた額をクレジットカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2〜3ヶ月要する場合もありますので,ご了承下さい.参加費に講演要旨集が付いている方へは,大会後にお送りします.
(c)9/12(大会2日前)以降の取消:入金・未入金の如何に関わらず,参加費用の100%を取消料としていただきます.参加費に講演要旨集が付いている方へは,大会後にお送りします.
(d)お弁当の取消:利用日より9日前〜前日までは50%,当日は100%の取消料がかかります.
(e)巡検の取消:締切後〜出発3日前までは50%,2日前以降は全額となります.
参加登録費
参加登録費
当日会場受付での混雑緩和のため,事前に参加登録申込をお願いします.大会参加登録およびそれに伴う参加費は,参加者(原則として巡検のみ参加の場合も)に必要な基本的なお申し込みです.ただし,会員が同伴する非会員の配偶者ならびに子供(以下,同伴者)については参加登録申込の必要はありません(懇親会・巡検・お弁当については同伴者も申込が必要).
申込は,オンライン,FAX・郵送いずれの場合も,会員と同伴者の2名まで一括申込が可能です.申込は,「各種申込とお支払について」を参照し,申し込んで下さい.
<申込締切 オンライン:8月20日(火)18:00,FAX・郵送:8月16日(金)必着>
■ WEB参加登録はこちらから ■
講演要旨集が不要の場合でも割引はありません.参加登録費無料の方(名誉会員・50年会員,非会員招待者,学部学生)には講演要旨集は付きません.ご希望の方は別途購入してください.
事前申込
当日払い
備考
正会員
7,500円
9,500円
講演要旨付き
院生割引適用正会員
4,500円
6,500円
講演要旨付き
学部制割引適用正会員・名誉会員・50年会員・非会員学部学生・非会員招待者
無料
無料
講演要旨は付きません
非会員(一般)
12,500円
15,000円
講演要旨付き
非会員(院生)
7,000円
9,500円
講演要旨付き
*日本地質学会の会員資格は『正会員』のみであり,割引会費の申請をした方についてのみ,割引会費が適用されています.
*大会に参加できなかった場合は,大会後に講演要旨集をお送りします.参加登録費用の返却はいたしませんのでご了承下さい(取消料の項目参照).
*セッション共催団体および巡検協賛団体会員の参加登録費は正会員と同額になります.
*追加で講演要旨集を購入される場合は,「講演要旨集のみの予約頒布」の価格表を確認してお申し込み下さい.
要旨のみの予約販売
講演要旨集のみの予約頒布
<申込締切 オンライン:8月20日(火)18:00,FAX・郵送:8月16日(金)必着>
■ 購入申込はこちらから ■
大会参加費には講演要旨集の代金が含まれていますので,大会に参加される場合は別途購入の必要はありません.ただし,名誉会員・50年会員,非会員招待者,学部学生(会員・非会員問わず)には講演要旨集は付きません.ご希望の方は,別途ご購入下さい.大会に参加されない方ならびに参加する方が複数の講演要旨集を購入される場合の予約頒布の申込は,「各種申込とお支払いについて」を参照し,申し込んで下さい.要旨集の受け取り方法には,(1)大会後に送付,(2)会場で受取り,があります.(1)の場合は,別途送料が必要です.(2)の場合は,大会受付にて確認書の提示が必要となりますので,必ずご持参下さい.残部があれば大会当日あるいは大会後にも頒布します.売り切れの場合はご容赦下さい.
※大会前の送付は行っておりません.
事前予約(/冊)
当日販売(/冊)
会員
3,000円
4,000円
非会員
4,000円
5,500円
*「大会後に送付」の場合の送料は以下の通りです.
送料:1冊 500円,2冊 600円,3冊 800円,4冊 1,000円,5冊 1,200円
巡検参加申込
巡検参加申込
<申込締切 オンライン:8月9日(金)18:00,FAX・郵送:8月7日(水)必着>
※巡検のみ参加申込締切が大会参加登録等と異なりますので,ご注意下さい.
■ WEB参加登録はこちらから ■
【巡検一覧と各コース見どころはこちら】
【巡検M班中止のお知らせ】
仙台大会の巡検コースについて,巡検案内者の都合により,下記コースは中止となりました。
申込受付開始後の変更のため,皆様にはご迷惑をおかけ致しますが,何卒ご了承下さい。
すでにお申込を頂いた方は,事務局よりキャンセルのお手続きをさせて頂きます。
【中止】M班 2008年岩手・宮城内陸地震による斜面災害(案内者 川辺孝幸・籾倉克幹)
総計13コースの巡検(A〜M班)を計画しました(巡検一覧参照).巡検の参加申込は,「各種申込とお支払いについて」を参照し,申し込んで下さい.参加希望の方は,オンライン申込手続き手順に従って参加申込を行って下さい.FAX・郵送でのお申込は,専用申込書を用い,学会事務局(東京)宛に大会参加申込と一緒に申し込んで下さい.原則として,巡検だけに参加する場合も大会参加登録ならびに参加登録費は必要です.巡検と大会参加登録の申込を合わせて行って下さい.実施日程の異なる場合,複数の巡検コースへの申込を行うことも出来ます(最大3コース).
(1)参加申込人数が各巡検コースの最小催行人員に達しなかった場合,巡検を中止することがあります.
(2)巡検協賛団体の会員の方は,会員同様にお申込を頂けます.それ以外の非会員の方は,申込締切時点で定員に余裕があれば参加可能となります.ご承知おき下さい.
(3)日本地質学会ならびに同仙台大会実行委員会は巡検参加者に対し,巡検中に発生する病気,事故,傷害,死亡等に対する責任・補償を一切負いません.これらについては,巡検費用に含まれる保険(国内旅行傷害保険団体型)の範囲でのみまかなわれます.
(4)子供同伴など特別な事情がある場合は,申込前に現地事務局へあらかじめ問い合わせて下さい.
(5)締切までの間は,ホームページから変更・取消が出来ます.変更・取消完了後,「変更・修正 確認メール」が登録のメールアドレスへ送信されます.内容を必ずご確認下さい.締切後の変更・取消は,直接学会事務局(東京)にFAX又はe-mailにてご連絡下さい.締切後は入金・未入金の如何に関わらず,取消料が発生します(詳しくは,巡検一覧取消料の項目参照).
(6)集合・解散の場所,時刻などを変更することがありますので,大会期間中は掲示などの案内に注意して下さい.
(7)今大会の巡検では冊子体の案内書は作成いたしません.案内書CD-ROMを地質学雑誌8月号に添付する予定です(8月下旬頃).巡検参加者には,各班の巡検案内の複写を巡検当日に配布する予定です.
(8)主催者の都合および自然条件等の理由により巡検が実施されなかった場合は,参加費から保険料を除いた金額を返金いたします。
懇親会・弁当
【懇親会】
9月14日(土)18:15〜20:00
会場:東北大学川内北キャンパス・川内の杜ダイニング
原則として予約制です(予約は8 月20日(火)に締め切りました).人数に余裕があれば当日参加の申込みも可能です.会場受付で確認し,当日参加の申込みをしてください.その場合の会費は,正会員・非会員(一般)6,000 円,名誉会員・50 年会員・院生割引会費適用正会員・学部割引適用正会員および会員の家族は3,500 円です.非会員の会費は正会員に準じます.
【同窓会ブースのご案内】
(申込校のみ・8月21 日現在,山形大学・宮城教育大学・信州大学より申込あり.)
懇親会終了後(20:00 〜 21:00),旧友・卒業生・恩師との親睦を図るため,各大学の同窓会ごとのブースを設けます.
***************************************************************
懇親会
<申込締切 オンライン:8月20日(火)18:00,FAX・郵送:8月16日(金)必着>
■ WEB参加登録はこちらから ■
懇親会は,9月14日(土)表彰式・記念講演会終了後,大学生協食堂において行います(18:30頃 18:15〜20:00).
事前予約会費
正会員
5000円
名誉会員・50年会員・院生割引・学部割引・会員の家族
2500円
非会員の会費は会員に準じます.準備の都合上,前金制の予約参加とします.たくさんの方々,特に院生・学生などの若手会員のご参加をお待ちしております.余裕があれば当日参加も可能ですが,予定数に達し次第〆切ります.当日会費は1,000円高くなります.
予約申込は,大会参加申込と合わせて8月20日(火)までにお申し込み下さい.当日はクーポンを受付にご持参下さい.参加取消の場合でも懇親会費の返却はいたしませんのでご了承下さい.
○懇親会申込・問い合わせ ▶▶▶ WEB参加登録 または FAX・e-mailにて『学会事務局』へ
同窓会ブースのご案内
<申込締切 8月20日(火)現地事務局まで>
懇親会に引き続き(20:00〜21:00),旧友・卒業生・恩師との親睦を図るため,各大学の同窓会ごとのブースを設ける予定です.ブースを希望される各大学同窓会関係者の方は,8月20日(火)までに下記連絡先まで,大学名と担当者名をご連絡下さい.持ち込み可能です.ふるってご参加下さい.
【お申込・お問合せ先】
日本地質学会第120年学術大会 現地事務局(株式会社アカデミック・ブレインズ内)
TEL:06-6949-8137,FAX:06-6949-8138,
e-mail:gsj2013sendai@academicbrains.jp 担当:田中
○同窓会ブース申込・問い合わせ ▶▶▶ e-mail等にて『現地事務局』へ
お弁当予約販売
<申込締切 オンライン:8月20日(火)18:00,FAX・郵送:8月16日(金)必着>
■ WEB参加登録はこちらから ■
9月14日(土)〜9月16日(月)には昼食用の弁当販売をいたします(1個700円,お茶付き).大会参加申込と合わせて,お申し込み下さい.お弁当利用日より9日前〜前日までは50%,当日は100%の取消料がかかります.なお,9月14日(土)〜16日(月)は,主会場前の大学生協食堂が営業いたします.購買部も営業致します.会場近隣のコンビニエンスストアは徒歩5分となります.
大会期間中の食事
大会期間中のお食事について
大会期間中のお食事について
◯お弁当予約販売(予約申込は締切りました).
予約弁当は,B3棟入口(Uホール側)で配布します.引き換えのクーポンを忘れずにお持ち下さい.
◯生協食堂
会期中の9 月15日(土)〜17日(月・祝) 11:30〜14:00(17日のみ13:30まで)に営業します.
(ニュース8月号掲載の内容から営業時間が変更となっています。ご注意下さい)
注意:生協購買部は営業しませんので,中百舌鳥門前のコンビニエンスストア等をご利用ください.そのほか,中百舌鳥キャンパス周辺に飲食店があります.
その他の申込TOP
その他
■ランチョン・夜間小集会(受付終了):日程一覧あり
■同窓会ブース(8/20締切)
■若手会員のための業界研究サポート(旧就職支援プログラム)(出展申込締切:8/9)
■託児室の利用(8/23締切)
■シニア昼食会
ランチョン・夜間集会
ランチョン・夜間集会
※都合により急遽会場が変更になる場合もありますので,会期中の掲示にご注意下さい.
■ランチョン
▶9月15日(日)12:00-13:00
会場1 構造地質部会若手の研究発表会
(世話人:大坪 誠・山田泰広・氏家恒太郎)
構造地質部会若手の研究発表会:一人20分程度で2名ほどを予定.
会場2 岩石部会
(世話人:水上知行)
岩石部会の活動報告、今後の活動方針の相談、および情報交換.
会場3 地質学雑誌編集委員会
(世話人:秋元和實)
地質学雑誌の諸問題について改善を図るための,face-to-face意見交換.
会場4 現行地質過程部会
(世話人:川村喜一郎)
現行地質過程部会の今後の運営および体制の話し合い.
会場5 地域地質、層序部会合同
(世話人:岡田 誠)
部会活動やセッションについての議論と情報交換.
会場6 Integrated Ocean Drilling Program (IODP)の10年の成果と新IODP
(世話人:梅津慶太)
2003年に開始され,この9月で一区切りを迎えるIODPの10年の成果についての月刊地球特集号(今秋出版予定)の紹介と10月から新たにスタートするIODPの枠組みの紹介.
会場7 堆積地質部会
(世話人:片岡香子)
堆積地質部会の活動報告および国内外の堆積学に関する情報交換.
▶9月16日(月)12:00-13:00
会場1 構造地質部会定例会
(世話人:大坪 誠・山田泰広・氏家恒太郎)
過去の活動報告、会計報告、今後の活動計画など.
会場3 応用地質部会
(世話人:小嶋 智・須藤 宏)
①レギュラーセッションでの他学会との共催②レギュラーセッションでの次年度招待講演③地質学における学際的な問題解決方法(トランス・サイエンス問題)④学会次期中期ビジョンについての部会コメント⑤その他.
会場4 古生物部会
(世話人:平山廉・須藤 斎)
会場5 第四紀地質部会
(世話人:長橋良隆)
第四紀地質学に関する情報交換と話題提供(講演会),今後の部会体制について等.
会場6 海洋地質部会
(世話人:荒井晃作・芦 寿一郎・小原泰彦)
海洋地質関連の研究機関における最近の研究動向と今後の調査の紹介を行い,各種情報を共有するとともに,海洋地質部会の活動について議論する.
■夜間小集会
▶9月15日(日)18:00-19:30
会場1 超深度海溝掘削(KANAME)
(世話人:木村 学・斎藤実篤・金川久一)
新学術領域研究「超深度海溝掘削(KANAME)」の進捗状況と今後の南海掘削に関する情報交換.
会場2 南極地質研究委員会
(世話人:本吉洋一・外田智千)
南極地質将来計画について・その他.
会場3 環境地質部会
(世話人:田村嘉之・風岡 修)
環境地質に関する講演、事務連絡など.
会場4 地質学史懇話会
(世話人:会田信行)
東北地方の地質学史に関する講演2題 蟹澤聰史:歌枕と津波,永広昌之:北上山地の地質自慢.
会場5 東日本大震災と博物館;標本レスキューから復興に向けて
(世話人:柴 正博・平田大二・大石雅之・川端清司)
1次作業が終了しつつある,東日本大震災で被災した博物館の標本レスキューについての活動をまとめるとともに、これからの博物館活動の復興に向けての活動を紹介し、今後の方向性を議論.
会場6 考古遺跡における津波(自然災害)痕跡
(世話人:渡辺正巳・井上智博・趙 哲済・松田順一郎・小倉徹也・別所秀高)
仙台市沓形遺跡で発見された津波堆積物についての講演(斎野裕彦 氏:仙台市教委)と、考古遺跡に残された津波(自然災害)の痕跡調査についての意見交換.
会場7 炭酸塩堆積学に関する懇談会
(世話人:加藤大和・松田博貴)
最新の炭酸塩堆積学に関する研究紹介と情報交換を行い,炭酸塩堆積学のこれからの方向性・発展について議論.
ミーティングルーム1 地質技術者教育委員会
(世話人:山本高司)
今後の委員会としての取り組み方針について議論.
▶9月16日(月)18:00-19:30
会場3 業務で困った!学会で解決しよう!
(世話人:小嶋 智・須藤 宏)
地質コンサルタントなどの企業に勤務されている会員の方々は,業務上で困った問題に出くわすことがよくあるのではないでしょうか?そんな問題・悩み,あるいは解決法を持ち寄り,皆で紹介しあうことも,時には有意義ではないでしょうか?そんな思いから夜間小集会を企画しました.なお集会後は懇親会も企画しています.
会場5 放散虫関連:INTERRADなど国際会議の日本招致に関する意見交換
(世話人:松岡 篤・板木拓也・鈴木紀毅)
2018年に,INTERRAD(国際放散虫研究者協会)とIPC(国際古生物学会)を日本に招致するという議論が行われており,これらに対し,国内の放散虫コミュニティーとしてどのように対応するか議論.
ランチョン申込
<申込締切 6月26日(水)必着,行事委員会扱い>
9月15日(日),16日(月)にランチョン開催を希望する方は,(1)集会名称,(2)集会内容(50〜100字程度),(3)世話人氏名・連絡先(メールアドレスと電話番号),(4)その他ご希望等,をe-mailで行事委員会(東京)宛に申し込んで下さい.申込締切は6月26日(水)です.開催日時のご希望に沿えない場合がありますので予めご承知おき下さい.世話人には,大会終了後に集会内容をニュース誌(大会記事)にご投稿いただきます(800字以内,原稿締切は10月下旬を予定).
夜間小集会の申込
<申込締切 6月26日(水)必着,行事委員会扱い>
9月15日(日),16日(月)ともに18:00〜19:30(予定)です.夜間小集会の開催を希望する方は,(1)集会名称,(2)集会内容(50〜100字程度),(3)世話人氏名・連絡先(メールアドレスと電話番号),(4)その他ご希望等,をe-mailで行事委員会(東京)宛に申し込んで下さい.申込締切は6月26日(水)です.開催日時のご希望に沿えない場合がありますので予めご承知おき下さい.世話人には,大会終了後に集会内容をニュース誌(大会記事)にご投稿いただきます(800字以内,原稿締切は10月下旬を予定).
託児室
託児室
男女共同参画委員会では,ご家族で学会参加される会員の皆様に以下のプランをご用意いたしました.ご希望の方は,利用条件をよくご覧になりお申し込み下さい.
>>現地事務局申込<<
<利用申込締切: 8月23日(金)>
(1)開設日時:
9月14日(土)8:00〜21:00
9月15日(日)8:30〜18:00
9月16日(月)8:30〜18:00
(2)対象:
仙台大会参加者を保護者とする生後6ヶ月から未就学のお子様.
(3)場所:
マザーズ・エスパル保育園(予定)
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1丁目1-1
(JR仙台駅上エスパル内6階)
http://www.mother-s.jp/spal/index.html
(4)アクセス:
JR仙台駅上エスパル内6階
*ご利用をご希望の方は現地事務局までお問合わせ下さい.万が一の場合に備え,施設加入の損害保険で対応させていただきます.なお,託児施設のご利用に際しては当仙台大会会実行委員会・日本地質学会は責任を負いかねますのでご了承下さい.
企業展示・書籍販売・広告募集
企業等団体展示/書籍販売
企業・団体・研究機関などによる展示を行います.会場は,東北大学川内北キャンパス講義棟C棟2階C201-C203を予定しています.(8月5日現在)
・株式会社地層科学研究所
・ライカマイクロシステムズ株式会社
・メイジテクノ株式会社
・住友金属鉱山株式会社
・石油資源開発株式会社
・株式会社蒜山地質年代学研究所
・株式会社建設技術研究所
・NPO法人ジオプロジェクト新潟
・独立行政法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)
・高知コアセンター
・カールツァイスマイクロスコピー株式会社
・International Ocean Discovery Program(IODP)
・株式会社環境研究センター
・株式会社ニコンインスティック
・株式会社東栄科学産業
また,講義棟B棟2階談話室(受付横)では書籍・物品の展示販売コーナーを設けます.(8月9日現在)
・株式会社朝倉書店
・地学団体研究会
・株式会社古今書院
・RC GEAR
・株式会社ニュートリノ
・株式会社テラハウス
・株式会社ニチカ
**************************************************************************
■ 出展募集 ■ 書籍・販売ブースご利用の募集 ■ 広告協賛の募集
企業・研究機関等関係団体による展示会の出展募集
<申込締切 一次7月5日(金),最終8月9日(金) 現地事務局扱い>
地質関係機関・関連企業のご活躍を広く地質学会員に紹介していただくため,会期中,企業展示会を開催致します.企業紹介・業務紹介・研究成果・新技術・特許などご自由に展示内容を構成いただけます.奮ってご出展のお申込をいただきますようお願い申し上げます.
【展示募集概要】
1.開催期間:搬入設営日9月13日(金),開催日9月14日(土)〜16日(月),搬出撤収日9月16日(月)※予定
2.開催場所:東北大学 川内北キャンパス 講義棟C棟1階 ※予定
3.募集小間数:小小間16,パネル小間4 ※予定 複数小間のお申込も可能です.
4.小間仕様見本:
5.出展料金:小小間 50,000円(消費税別),パネル小間 20,000円(消費税別)
6.第1次募集締め切り日:7月5日(金) 最終募集締め切り日:8月9日(金)
【出展申込方法】
「展示募集要項申込書」をダウンロードいただき,必要事項をご記入の上,下記申込先までe- mai l へのPDFファイル添付,あるいはFAXにてお申込下さい.募集要項・申込書が別途必要な場合は,現地事務局までご連絡下さい.送付致します.
「展示募集要項申込書(pdfファイル)」
「展示募集要項申込書(docファイル)」
【お申込・お問合せ先】
〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1天満橋千代田ビル2号館9階
日本地質学会 第120年学術大会 現地事務局(株式会社アカデミック・ブレインズ内)
TEL:06-6949-8137,FAX:06-6949-8138,e-mail:gsj2013sendai@academicbrains.jp 担当:田中
※日本地質学会賛助会員は出展料金が無料となります.別途,現地事務局までご連絡下さい.
書籍・販売ブースご利用の募集
<申込締切 一次7月5日(金),最終8月9日(金) 現地事務局扱い>
地質学関連の書籍・その他物品の販売にご利用いただくべく会期中ブースを設置致します.奮ってご出展のお申込をいただきますようお願い申し上げます.※見本展示のみでのご利用も可能です.
【書籍・販売ブース出展概要】
1.設置期間:9月14日(土)〜9月16日(月)
2.設置場所:東北大学 川内北キャンパス 講義棟B棟2階
3.募集ブース数:11ブース ※予定 複数ブースのお申込も可能です.
4.ブース仕様見本
※仕様詳細・オプション料金等につきましては,大会ホームページの「展示募集要項申込書」をダウンロードの上,ご確認下さい.
5.出展料金:10,000円(消費税別)
6.第1次募集締め切り日:7月5日(金) 最終募集締め切り日:8月9日(金)
【出展申込方法】
「展示募集要項申込書」をダウンロードいただき,必要事項をご記入の上,下記申込先までe- mai l へのPDFファイル添付,あるいはFAXにてお申込下さい.募集要項・申込書が別途必要な場合は,現地事務局までご連絡下さい.送付致します.
「展示募集要項申込書(pdfファイル)」
「展示募集要項申込書(docファイル)」
【お申込・お問合せ先】
〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1天満橋千代田ビル2号館9階
日本地質学会 第120年学術大会 現地事務局(株式会社アカデミック・ブレインズ内)
TEL:06-6949-8137,FAX:06-6949-8138,e-mail:gsj2013sendai@academicbrains.jp 担当:田中
講演要旨集,広告協賛の募集
<申込締切 8 月9日(金) 現地事務局扱い>
地質関係機関・関連企業のご活躍を広く地質学会員に広報いただくべく,大会開催にあわせ発行されます講演要旨集において,広告協賛を募集致します.企業紹介・業務紹介・研究成果・新技術・特許などの広報活動のご一環として,奮ってお申込をいただきますようお願い申し上げます.
【広告協賛料金】※詳細は「広告協賛募集要項申込書」をダウンロードの上,ご確認下さい.
講演要旨集:1頁 40,000円 1/2頁 20,000円 1/4頁 10,000円(すべて消費税別)
※完全版下,データまたフィルムでの入稿をお願い致します.
【出稿申込方法】
「広告協賛募集要項申込書」をダウンロードいただき必要事項をご記入の上,下記申込先までe-mailへのPDF添付,あるいはFAXにてお申込下さい.
「広告協賛募集要項申込書(pdfファイル)」
「広告協賛募集要項申込書(docファイル)」
【お申込・お問合せ先】
〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1天満橋千代田ビル2号館9階
日本地質学会 第120年学術大会 現地事務局(株式会社アカデミック・ブレインズ内)
TEL:06-6949-8137,FAX:06-6949-8138,e-mail:gsj2013sendai@academicbrains.jp 担当:田中
就職支援プログラム募集
若手会員のための業界研究サポート
出展予定企業(敬称略)
・ ジーエスアイ株式会社
・ 石油資源開発株式会社
・ 国際石油開発帝石株式会社
・ 建設設計コンサル
・ 日本工営株式会社仙台支店
・ 株式会社建設技術研究所
・ 太平洋セメント株式会社
・ 川崎地質株式会社
・ 株式会社地圏総合コンサルタント
「若手会員のための業界研究サポート」
(旧:就職支援プログラム)
出 展 募 集
来る9月14日から東北大学において日本地質学会第120年学術大会を開催いたします.昨年までの「就職支援プログラム」の内容を発展させ,地質学会の若手会員・大学教員に向けて地質企業の現状や求める人材について語り合う交流会を企画します.
東日本大震災以降,特に防災や環境に関して地質学に対する社会的要請が強くなっています.また,今後の日本のエネルギー政策として地熱・地下資源が改めて注目を集めています.
地質企業に興味のある学生・大学院生および指導にあたっている教員の方々に対して,実際に企業で活躍されている地質技術者と語り合い,大学で学んだ地質学が企業でどのように生かされているか,企業の生の声を聴く.そんな場を提供したいと考えています.
つきましては,ぜひ本「若手会員のための業界研究サポート」にご参加(出展)いただきますようご案内をいたします.
日 程:2013年9月15日(日)14:00-17:00(*時間帯は若干変更になる場合があります)
場 所:東北大学川内北キャンパス
主 催:一般社団法人日本地質学会
内 容:主催者等 挨拶・紹介、参加各社による数分のプレゼンテーション.
参加各社の個別説明会(パネル、配布資料等をご用意ください).
対 象:仙台大会に参加する学生・院生および大学教官等の会員
東北大学等の学生・院生および教官等
参加費(出展費):無料
参加申し込み:別紙「参加申込書」を下記日本地質学会宛に8月9日(金)(必着)までにFAX・E-mailでお送りください.スペースに限りがありますので,参加ご希望の場合はお早めにお申し込みください.詳細についてはお申し込み締め切り後にご連絡いたします.
一般社団法人日本地質学会
担当理事 山本高司
▶出展申込用紙(word) ▶出展申込用紙(PDF)
▶ 2012年大阪大会:就職支援プログラムの様子はこちらから
就職支援(2012大阪大会の様子)
第119年大阪大会:就職支援プログラム開催報告(2012.9.16開催)
地質学会では,就職希望の学生・院生が民間企業・団体,研究機関と直接に情報交換できる場として就職支援プログラムを企画し,今年で第6回目になります.本年度も大会2日目の午後2時半から6時まで行い,民間企業8社が参加しました.
まず,各社から業務内容や求める人材について5分程度のプレゼンテーションがあり,その後に各社の出展ブースで個別に詳しい説明や質疑応答が行われました.今年度は資源・土木・測量・機器製作といった幅広い分野の企業が参加されたこともあり,学生・院生が希望の分野やその業界のことを熱心に聞く姿がみられました.ただし,会場が講演会場のフロアーの異なることや宣伝不足もあり参加者は限定されているように思われました.今後は就職担当の教員へのアプローチも必要でないかと考えています.
このプログラムは来年度からは名前を変えて,内容やプレゼンテーションの仕方など見直していきたいと計画しています.これは,経団連の「採用選考に関する企業の倫理憲章」により企業の広報活動開始時期は12月以降とされたことを考慮したもので,業界の現状や採用状況等の情報提供を主に置き,幅広く地質関連企業を紹介していくことを考えています.この時期は,学生・院生は地質を生かした仕事に何があるのか,自分の将来設計も含めて迷っています.その選択幅を広くするような情報提供が就職後のミスマッチを少なくするものと思われます.
来年度は,就職希望の学生・院生の皆様には,ぜひご利用いただきたいと思います.特に,学生を指導されている教官の方々にも,会場に足を運んでいただき,企業の採用状況について情報収集していただくとともに,学生・院生の皆様に積極的な参加を呼びかけていただくようお願いいたします.
最後に,本行事に参加いただいた企業8社の皆様,企画にご協力をいただいた賛助会員,関連企業の皆様,および大会準備委員会・行事委員に,改めて御礼申し上げます.
各社によるプレゼンテーション
各社ブースの様子
参加企業・団体一覧(敬称略・申込順):石油資源開発株式会社・川崎地質株式会社・太平洋セメント株式会社・株式会社ダイヤコンサルタント・ジーエスアイ株式会社・株式会社地圏総合コンサルタント・地熱エンジニアリング株式会社・アジア航測株式会社
山本高司(運営財政部会担当 執行理事)
事務局主催シニア昼食会のお誘い
事務局主催シニア昼食会のお誘い
仙台大会にご参加いただくシニア会員の方々と事務局職員の昼食会を今年も予定しています.
年会の合間のひと時,軽い昼食と近況談義などできれば,楽しいかと思います.ここでのシニアの定義は特にありません.我こそはシニア,私もシニア,シニアではない方も,どなたでもお気軽にお集まり下さい.
日 時 2013年9月16日(月・祝)12〜14時
食事処 未定
会 費 未定(低額)
申 込 9月15日(日:会期の中日)まで受付ます(担当 橋辺)
地質学会事務局(電話 03-5823-1150)
※会期中は会場内の学会本部の部屋へお越し下さい.(C棟3F)
鹿児島大会
2014 鹿児島大会TOP
画像をクリックするとpdf版[約850KB]をダウンロードできます.
日本地質学会第121年学術大会
(鹿児島大会)
2014年9月13日(土)〜15日(月・祝)
会場:鹿児島大学 郡元キャンパス ほか
【 大会趣旨 】
共催:
鹿児島大学大学院理工学研究科,鹿児島大学総合研究博物館,鹿児島大学地域防災教育研究センター
後援:
鹿児島県地質調査業協会,鹿児島県建設コンサルタンツ協会
盛会のうち、無事終了いたしました。
来年は長野でお会いしましょう。
日程:2015年9月11日(金)〜13日(日)
会場:信州大学 ほか
大会中の様子はメルマガでも配信いたしました。
写真等、大会の様子はこちらから
★ 大会期間中の最新情報やお知らせはこちら ★
(随時更新予定です!!)
○大会期間中のお食事について
○事務局主催シニア昼食会のお誘い
○懇親会について
○巡検へ参加される方へ 重要
○緊急展示について
○鹿児島大会に関連したプレス発表
○鹿児島市内の宿泊施設に宿泊される方へ
★ 更新情報 ★
2014/09/10
鹿児島大会に関わるプレス発表を行いました
2014/09/01
各講演プログラムを掲載しました
2014/08/29
事前申込した方へ:確認書等を発送しました
2014/08/22
地質技術者の皆さん 鹿児島大会でCPD単位が取得出来ます
2014/08/19
事前参加登録は締切りました。
2014/07/17
緊急展示の申込について(8/29締切)
2014/07/16
全体日程が確定しました!
2014/06/16
Web事前参加登録 受付開始しました!
2014/05/27
演題登録(講演要旨提出)受付開始しました!
2014/05/13
講演申込を予定しているが、まだ入会手続きをされていない方へ 重要
2014/04/08
シンポジウム・セッション決定
2014/02/03
鹿児島大会 西日本支部鹿児島大学にて開催
トピックセッション募集(締切:3/17)
鹿児島大会:決定シンポ・セッション一覧
鹿児島大会:シンポジウム・セッション一覧
行事委員会より
本年9月に開催される第121年学術大会(鹿児島大会)のシンポジウムとセッションが決定しましたので,速報としてお知らせします.詳細は5月中旬頃,またニュース誌5月号(大会予告号)に掲載します.
■ シンポジウム(2件)
• 九州が大陸だった頃の生物と環境(一般公開シンポジウム)
• Tsunami hazards and risks: using the geological record(国際シンポジウム)
■ トピックセッション(9件)
• 火山島弧の造山運動:沈み込み,付加,衝突およびリサイクリング
• 文化地質学
• グリーンタフ・ルネサンス
• 砕屑性ジルコン年代学:その未来とさらなる応用
• ポスト冥王代研究
• 三次元地質モデル研究の新展開
• 古生代から中生代への地球環境進化
• 超深度掘削による新次元の地球科学
• 平野地質
■ レギュラーセッション(25件)
行事委員会は学術大会の活性化と本学会の発展,さらには地質学の発展を目指すための試みの一つとして,レギュラーセッションの新設や再編に毎年取り組んでいます.今大会では下の25タイトルを用意します(カッコ内は担当専門部会/委員会).これまで開催されてきたレギュラーセッションに加え,今回新たに「鉱物資源と地球物質循環」を用意しました.また,従来の「岩石・鉱物の破壊と変形」は「岩石・鉱物の変形と反応」に,「情報地質」は「情報地質とその利活用」にそれぞれ名称変更しました.地質学を広くカバーする,今まで以上に充実したレギュラーセッションのラインアップになったと考えています.
• 深成岩・火山岩とマグマプロセス(火山部会・岩石部会)
• 岩石・鉱物・鉱床学一般(岩石部会)
• 噴火・火山発達史と噴出物(火山部会)
• 変成岩とテクトニクス(岩石部会)
• 地域地質・地域層序(地域地質部会・層序部会)
• ジオパーク(地域地質部会・ジオパーク支援委員会)
• 地域間層序対比と年代層序スケール(層序部会)
• 海洋地質(海洋地質部会)
• 堆積物(岩)の起源・組織・組成(堆積地質部会)
• 炭酸塩岩の起源と地球環境(堆積地質部会)
• 堆積相・堆積過程(堆積地質部会・現行地質過程部会)
• 石油・石炭地質学と有機地球化学(石油石炭関係・堆積地質部会)
• 岩石・鉱物の変形と反応(構造地質部会・岩石部会)
• 沈み込み帯・陸上付加体(構造地質部会・海洋地質部会)
• テクトニクス(構造地質部会)
• 古生物(古生物部会)
• ジュラ系+(古生物部会)
• 情報地質とその利活用(情報地質部会・地域地質部会)
• 環境地質(環境地質部会)
• 応用地質学一般およびノンテクトニック構造(応用地質部会)
• 地学教育・地学史(地学教育委員会)
• 第四紀地質(第四紀地質部会)
• 地球史(環境変動史部会)
• 原子力と地質科学(地質環境長期安定性研究委員会)
• 鉱物資源と地球物質循環(鉱物資源部会)
■ 日本地質学会アウトリーチセッション
このセッションは,会員が研究成果を社会に発信する場として,一昨年(2012)の大阪大会から設けられたセッションです.詳細についてはニュース誌15巻11号,29〜30ページを参照してください.
■ 会員の皆様へ
地質学に携わるすべての方が「日本地質学会の学術大会はおもしろい!」と思っていただけるように,行事委員会は学術大会の改善に努めます.会員の皆様も,何かよいアイディアやご意見等があれば,所属する専門部会/委員会の行事委員を通じて,あるいは直接行事委員会(main@geosociety.jp)にご連絡ください.お待ちしております.
行事委員長(行事担当理事) 星 博幸
招待講演者の紹介
セッション招待講演の紹介
世話人や専門部会から提案され,行事委員会が承認したセッション招待講演(予定)の概要を紹介します.学術的にも社会的にも注目されている研究者やテーマが目白押しです.会員の皆様,この機会をお見逃しなく! なお,講演時間は変更になる場合があります.
(行事委員会)
T1.火山島弧の造山運動:沈み込み,付加,衝突およびリサイクリング
T2.文化地質学
T3.グリーンタフ・ルネサンス
T4.砕屑性ジルコン年代学:その未来とさらなる応用
T5.ポスト冥王代研究
T6.三次元地質モデル研究の新展開
T7.古生代から中生代への地球環境進化
T8.超深度掘削による新次元の地球科学
-----
R6.ジオパーク
R8.海洋地質
R10.炭酸塩岩の起源と地球環境
R12.石油・石炭地質学と有機地球化学
R13.岩石・鉱物の変形と反応
R14.沈み込み帯・陸上付加体
R15.テクトニクス
R20.応用地質学一般およびノンテクトニック構造
R23.地球史
R24.原子力と地質科学
R25.鉱物資源と地球物質循環
-----
T1.火山島弧の造山運動:沈み込み,付加,衝突およびリサイクリング
■Bor-ming Jahn氏(National Taiwan Univ.)30分
本トピックセッションでは,島弧,大陸の成長およびリサイクリングに焦点をしぼる.Jahn氏には花崗岩の果たす大陸成長の役割を議論していただく.
■丸山茂徳会員(東京工業大学)30分
本トピックセッションでは,島弧,大陸の成長およびリサイクリングに焦点をしぼる.丸山会員には付加体形成とリサイクリングを,地球内部進化も含めて議論していただく.
T2.文化地質学
■長 秋雄氏(産業技術総合研究所)30分
長氏は産総研にて花崗岩の物性に関する研究を続けてきた.近年は花崗岩と人々の暮らしについて積極的に情報発信を行っている.特に地質情報展,例えば2006年(高知)「生活の中の花崗岩」,2009年(岡山)「瀬戸内の花こう岩」,2011年(水戸)「ふるさとの石 茨城の花こう岩」にて,花崗岩と地域文化との関連を示してきた.花崗岩の文化地質学について講演いただくのに最適な研究者である.
■原田憲一会員(シンクタンク京都自然史研究所) 30分
原田氏は元々地質学者でありながら,原田会員は地質学者でありながら,比較文明学に造詣が深い.比較文明学会の副会長を務めた経験をもつ.伊東俊太郎氏や染谷臣道氏など文明論の論客と親交が深く,地質学を幅広い見地から捉えた執筆を続けている.本セッションの学際的側面について講演いただくのに最適な研究者である.
T3.グリーンタフ・ルネサンス
■鹿野和彦会員(鹿児島大学)30分
鹿野会員はグリーンタフの模式層序である男鹿半島の層序を,精確な年代測定とともに大幅に修正した.これは従来の層序に基づいたグリーンタフ研究において基本となる時代尺度を根本的に見直す必要があることを示す.今後のグリーンタフ研究の方向性を示すためにも鹿野氏の研究は重要である.
T4.砕屑性ジルコン年代学:その未来とさらなる応用
■澤木祐介会員(東京工業大学)15分
澤木会員は連合王国の古生層や中国の原生代地層についての豊富な研究経験をもつ.最新の成果を紹介していただく.
T5.ポスト冥王代研究
■丸山茂徳会員(東京工業大学)30分
丸山会員は,いまだ物質的証拠が皆無に近い冥王代について,原初大陸の存在を予言し,その探索方法を提案している.今後の研究指針を提示していただく.
■土屋卓久氏(愛媛大学)30分
土屋氏は,密度汎関数理論に基づく第一原理計算を利用して,地球及び惑星の内部物質の物性を制約しようと,方法論を開発中である.地球物理学最前線の研究動向を紹介していただく.
T6.三次元地質モデル研究の新展開
■守屋俊治会員(石油資源開発)30分
守屋会員は石油業界で用いられる二次元,三次元の石油生成・移動・集積モデリング,および性状情報を加えた三次元貯留層モデリングの専門家であり,同テーマで留学経験があるとともに,現職においても様々な石油開発プロジェクトにおいて同モデリング手法の適用を行っている.モデリングの最新手法をレビューしていただくのにふさわしい人物である.
■石原与四郎会員(福岡大学)30分
石原会員は浅部地下構造モデルの新手法であるボーリングデータ解析による三次元モデルを開発した.同手法を東京低地,東京湾岸,福岡平野において適用し,浅部地下の地質を可視化し,堆積的な地層形成過程を解き明かしている.同手法は,応用目的も含めて大変有用であり,その普及が期待されている.
T7.古生代から中生代への地球環境進化
■磯崎行雄会員(東京大学)30分
磯崎会員は,地球生命史やテクトニクスを中心とした研究を行っており,特にP/T境界の大量絶滅研究では,海洋無酸素事変を提唱するなど顕著な業績をあげている.最近では,地球磁場変動,マグマ活動,寒冷化,生物絶滅を総合的に説明した統合版「プルームの冬」モデルから,全く新しいP/T境界大量絶滅シナリオを提唱しており,大量絶滅の原因解明に取り組んでいる.
Isozaki, Y., 2009. Integrated "plume winter" scenario for the double-phased extinction during the Paleozoic-Mesozoic transition: The G-LB and P-TB events from a Panthalassan perspective. Journal of Asian Earth Sciences, 36, 459-480.
■堀 利栄会員(愛媛大学)30分
堀会員は,古生物学的,地球化学的手法を用いて,古生代から中生代の大量絶滅とその後の回復過程について研究を行っている.最近では,三畳紀/ジュラ紀境界のイリジウム濃集層や,海洋酸性化とその後の中和過程について,国内外の遠洋性堆積岩を中心に研究成果をあげている.
T8.超深度掘削による新次元の地球科学
■廣瀬丈洋会員(海洋研究開発機構)30分
廣瀬会員は「ちきゅう」による南海トラフ超深度掘削において最大深度3058.5 mに至るライザー掘削を行った最新航海(IODPExp. 348)の主席研究員を務めた研究者であり,ライザー掘削で得られるカッティングスを用いた科学的分析・実験について試行錯誤してきた.実際に得られたカッティングス試料の分析・実験について,またその結果が持つ科学的意味について講演を行っていただく.
Integrated Ocean Drilling ProgramExpedition 348 Scientific Prospectus. など
■Demian Saffer氏(Pennsylvania State University)30分
Saffer氏はプレート沈み込み帯の水理学の第一人者であり,「ちきゅう」による南海トラフ地震発生掘削計画をはじめ,IODPによる乗船経験も豊かである.南海トラフやコスタリカ,ニュージーランドのヒクランギの超深度掘削計画にも立案から深く関与しており,本セッションに招待するにふさわしい.
R6.ジオパーク
■大岩根 尚会員(鹿児島県三島村役場)30分
大岩根会員は,学位取得後人口400人弱の三島村の役場に勤務し,村を構成する島々の地球科学的見どころを活かしたツアーを主催するなどの活動を行い,それをさらに発展させてジオパークの設立につなげようとしている.離島のコミュニティを地球科学者の力で活性化しようとする氏の活動は,各地のジオパークにとって参考になるとともに,地球科学系博士の新たな活躍の場を切り開くものとして若手研究者の関心も高いと考えられ,本セッションの招待講演者としてふさわしい.
R8.海洋地質
■浦辺徹郎会員(国際資源開発研修センター)30分
熱水鉱床学のバックグラウンドを持つ浦辺会員は,全地球的な視野での海洋地殻中の熱水循環の解明を目指した新学術領域研究「海底下の大河」計画をPIとして主導した.また,2012年から国連大陸棚限界委員会委員を務めている.氏には,日本の延伸大陸棚を取り巻く状況や,その資源ポテンシャル等について,魅力的な講演をしていただけると期待できる.
■石塚 治会員(産業技術総合研究所)30分
石塚氏は,Ar-Ar法による火山岩の年代測定を幅広く実施し,その方法を主軸に伊豆・小笠原・マリアナ弧の発達史の解明に精力的に取り組んでいる.日本政府の大陸棚調査においては,Ar-Ar法による九州・パラオ海嶺等のフィリピン海の古島弧の年代を決定し,フィリピン海の発達史の精密化を行うことで,日本の延伸大陸棚の決定に貢献した.石塚氏には,日本の大陸棚調査データに基づく最新のフィリピン海の発達史モデルについて,魅力的な講演をしていただけると期待できる.
R10.炭酸塩岩の起源と地球環境
■吉村和久氏(九州大学)30分
吉村氏は,炭酸塩の溶解と沈澱に関する研究を,専門である化学の側面から長年続けている当該分野の代表的研究者である.また,近年では鍾乳石やトゥファなどの陸成炭酸塩堆積物を用いた古環境復元に関する研究論文も多い.上記研究の基礎となる,炭酸塩生成の素過程と微量成分や同位体から読み解くことのできる情報について,最新の研究成果を交えながら,魅力的な講演をしていただけるものと期待できる.
R12.石油・石炭地質学と有機地球化学
■加藤 進会員(地球科学総合研究所)30分
加藤会員は国内における石油探鉱開発に従事しており,地質学・地球化学的見地から石油・天然ガス鉱床の研究を行ってきた.近年は,日南・宮崎・佐土原ガス田,沖縄本島南部ガス田などについて研究を進め,新第三系の微生物起源ガスとは別に,基盤岩起源の熱分解メタンからなる水溶性天然ガス鉱床が広く存在する可能性を指摘した.鹿児島での地質学会開催に際し,九州南部〜沖縄における石油資源ポテンシャルについて講演していただく.
■山中寿朗氏(岡山大学)30分
山中氏は国内におけるhydrothermal petroleum研究のパイオニアであり,その端緒となった研究地域は鹿児島湾である.その成果とともに,文科省科研費で進めている「海底熱水系における熱水性石油の生成条件の再検証」について講演していただき,有機物の熟成と温度の関係について再考する機会を得たい.
R13.岩石・鉱物の変形と反応
■平賀岳彦会員(東京大学)30分
マントル流動の素過程へ迫るレオロジーは,地球科学を超えて広く関心を集めている研究分野である.その中において平賀会員は,実験的なアプローチからサイエンスを刺激する成果を発信し続けている.最近,マントル鉱物を用いた「マントル岩石」の合成技術,結晶粒成長,多様な出発物質を用いた変形に関する一連の実験から,粒界すべりや拡散に支配される粒径依存型クリープがマントルの大部分に卓越するという,新たなマントル像を提示した.変形の物理量だけではなく組織発達についても解析を行い,プロセスと観察のリンクを可能とする地質学的にも重要なデータを提示している.その知見はマントル岩石にとどまらず,様々な岩石を対象とするフィールド地質学にとっても新たな視点を提供するものである.本セッションで講演していただくことで,実験とフィールドをつなぐ議論の活性化につながると期待できる.
R14.沈み込み帯・陸上付加体
■井出 哲氏(東京大学)30分
井出氏は世界を代表する地震学者である.とりわけ沈み込み帯で発生するスロー地震群に関して画期的な成果を次々とあげている.最近では,深部微動発生数と観測潮位の関係をもとにプレート境界においてすべり速度強化の摩擦則が働いていることを導き出し,周期的な潮汐力とすべり速度強化の摩擦則の組み合わせがプレート運動を支配し,南海トラフの定常地震活動の長期変化や大地震の弱い周期性を説明する可能性を導き出している.氏の最新の研究成果を本会会員に広く知ってもらうべく,講演していただく.
■高田陽一郎氏(京都大学)30分
干渉合成開口レーダー(InSAR)は宇宙測地学の一種である.InSARは近年急速に発達しており,地質学におけるフィールドワークとのコンビネーションが可能なほどの極めて高い空間分解能を有するようになってきた.高田氏はInSARを用いて,2011年東北地方太平洋沖地震に伴い東北日本弧の複数の活火山で沈降が起こったことを明らかにした.その沈降プロセスを考えるうえで地質学の果たす役割は大きい.高田氏にInSARの基本解説とそれを用いた研究例を本会会員に広く知ってもらうべく,講演していただく.
R15.テクトニクス
■木村 学会員(東京大学) 30分
木村会員は長年,陸上・海洋付加体の研究を精力的に進め,プレート沈み込み帯を含む島弧のテクトニクスの復元について研究を行ってきた.近年では,物質科学的側面においてこれらの付加体を研究することで,プレート収束帯に関わる幅広い研究分野の融合を先導している.鹿児島大会では,陸上付加体物質の研究から西南日本におけるテクトニクスの復元およびプレート境界地震の発生に関する話題提供をしていただく予定である.
■松本 聡氏(九州大学)30分
松本氏は地震波を用いた地殻の速度・散乱構造解析および地殻応力解析を専門とし,九州地方での地震や地殻変動観測を続ける第一人者である.近年は,地震波トモグラフィによる九州地方の詳細な地殻構造解析および2005年福岡県西方沖地震の余震観測から地殻の不均質構造と応力場の関係について精力的な研究を進めている.鹿児島大会では,九州地方の地震活動などの現在進行している地殻変形に関する話題提供をしていただく予定である.
R20.応用地質学一般およびノンテクトニック構造
■地頭薗 隆氏(鹿児島大学)30分
地頭薗氏は,土砂災害,深層崩壊,シラス斜面の崩壊,桜島の土石流,森林と水,屋久島の水などをキーワードに,火山地帯等における斜面崩壊と水文現象にかかわる研究を広く行っている.鹿児島で年会を開催するにあたり,氏に九州の応用地質,特に斜面災害に関する講演を行っていただく.予定テーマ「九州における土砂災害と防災研究」.
■大澤英昭氏(日本原子力研究開発機構)30分
大澤氏は,放射性廃棄物の地層処分研究に関わる中で,社会における合意形成の問題の重要性を認識し,社会学的心理学的研究を行っている.この問題は近年の応用地質学にも重要な要因となっており,会員にも興味を持って受け入れられるものと考える.予定テーマ「地層処分の社会的受容の要因は何か?:社会心理学的視点から」.
R23.地球史
■菅沼悠介会員(国立極地研究所)30分
菅沼会員は,海底堆積物の堆積残留磁化獲得メカニズムや地磁気逆転の精密な年代値について,従来の古地磁気学的手法に加えて,宇宙線生成核種分析や放射年代測定を組み合わせることで多角的に研究を進めている.特に,地磁気変動と残留磁化獲得の間には有意な時間差(獲得深度差)が存在すること,そして,この時間差からB-M境界年代値が従来より1万年程度若くなる可能性を示した.また最近,二次イオン質量分析計を用いた火山灰層中のジルコン単結晶のU-Pb年代測定によって,B-M年代値を世界最高精度で求め,上記仮説の検証にも成功している.これらの成果は地層対比や編年だけでなく,地球史上の各イベントの年代値についても影響を与えうるものである.
R24.原子力と地質科学
■鷺谷 威氏(名古屋大学)30分
鷺谷氏は,地震学において,測地データに基づいた東南海地震や南海地震の震源モデルに関する研究や,GPSデータを用いた日本列島の地殻変動の研究を行うなど,当該分野の先端的研究を展開している.また近年では,東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震学の問題点をNature等に発表するなど,地層処分の地下環境,岩盤の長期的応力状態や状態変化に関する観点のみならず,原子 力分野における地質科学の役割などの議論を行える研究者の一人である.本講演では,地震学の知見も踏まえ,地層処分等の原子力分野の課題等について講演していただく.
R25.鉱物資源と地球物質循環
■田近英一氏(東京大学)30分
田近氏は,グローバル物質循環とその変遷に関する研究の第一人者であり,炭素・酸素のグローバル循環と地球表層環境の変動に関する研究をはじめ,地球物理学,地質学,地球化学,惑星環境学にまたがる包括的研究を展開している.近年では,全球凍結イベントによる酸素濃度の上昇とマンガン鉱床の形成との関連を指摘しており,本セッションの目指す「地球表層-内部環境,テクトニックセッティング,ダイナミクスと,資源の形成メカニズムとの関わり」についての最新の話題を提供していただくのに最もふさわしい方である.
新着情報
新着情報 2014鹿児島大会
2014.9.10更新 大会期間中の情報やお知らせも随時更新を予定しています。
■■■
大会期間中の情報やお知らせは,こちらのページに更新を予定しています。
2014.9.10更新 鹿児島大会に関わるプレス発表を行いました
■■■
鹿児島大会に関わるプレス発表を行いました。詳しくはこちらから
2014.9.1更新 各講演プログラムを掲載しました
■■■
各講演日、講演種別ごとのプログラムを掲載しました。News誌8月号にも掲載されています。
詳しくはこちらから
2014.8.29更新 事前申込をされた方へ:確認書等を発送しました
■■■
事前申込をされた方へ、当日の受付にてご提出いただく確認書等を発送しました。当日忘れずにご持参ください。
詳しくはこちらから
2014.8.22更新 地質技術者の皆さん 鹿児島大会でCPD単位が取得出来ます
■■■
日本地質学会は,地質技術者への継続教育の一環として,大会参加者・発表者・巡検参加者へCPD単位を発行します.
詳しくはこちらから
2014.7.16更新 緊急展示の申込について
■■■
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害調査報告や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コーナー」を設けます.(8/29締切)
詳しくはこちらから
2014.7.16更新 全体日程表が確定しました。
■■■
鹿児島大会の全体日程が確定いたしました。口頭・ポスターの詳細プログラムは,整い次第大会HPへ公開し,各講演者へもご連絡の予定です。
全体日程は,コチラから
2014.6.16更新 Web事前参加登録 受付開始しました!
■■■
Web事前参加登録の受付を開始しました。締切は,8月19日(火)18時(郵送の場合は,8月15日(金)必着)です。
ただし巡検のみ,8/8(金)18時締切です。早めにお申込ください。
お申込は,コチラから
2014.5.27更新 演題登録(講演要旨提出)受付を開始しました。
■■■
演題登録(講演要旨提出)の受付を開始しました。締切は,7月1日(火)18時です(郵送の場合は,6月25日(水)必着)。
レギュラーセッション,トピックセッション,シンポジウムとも同様にお申込下さい。
詳しくは,コチラから
2014.5.13更新 講演申込を予定しているが、まだ入会手続きをされていない方へ
■■■
至急、入会申込書を学会事務局宛に郵送して下さい(7/1必着)。
WEB画面から講演申込操作は現時点でも可能です。入力の際、会員番号欄は空欄のまま操作を進めて下さい。また会員種別欄では『入会申込中』を選択して下さい。
申込締切時点(7/1)で入会申込書が到着していないと、申込が受理されませんので、必ず入会申込書を郵送して下さい。
2014.4.8更新 シンポジウム・セッション決定
■■■
シンポジウムとセッションが決定しましたので、速報としてお知らせします。詳細は後日大会HPまたはNews誌5月号(大会予告号)に掲載します。
一覧は、こちらから
2014.2.3更新 トピックセッション募集(2014/3/17締切)
■■■
トピックセッション募集締切:2012年3月11日(月)*今年もシンポジウムの公募は行いません。ご注意ください。
詳しくは、こちらから
2014.2.3更新 日本地質学会第121年学術大会(鹿児島大会)開催
■■■
日本地質学会は,西日本支部の支援のもと,鹿児島大学郡元キャンパスにおいて第121年学術大会(2014年鹿児島大会)を2014年9月13日(土)〜15日(月)に開催いたします.開催通知はこちらから
緊急展示の申込について
緊急展示について
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,会場内に,災害調査報告や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コーナー」を設ける予定です.
会場:第2体育館ポスター会場
問い合わせ先:行事委員会(main@geosociety.jp)
担当:山本啓司(鹿児島大会実行委員会)・須藤 宏(行事委員会)
緊急展示の申込について
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害調査報告や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コーナー」を設けます.ポスター展示を希望する方は,8月29日(金)までに次の内容を下記申込先にご連絡ください.
1)発表要旨PDF(ニュース誌5月号参照)
2)緊急展示の必要性
3)発表代表者と連絡先
4)希望枚数(1枚:幅120×210cm)
5)展示に関わる要望(2〜5の様式は自由)
実行委員会は行事委員会と協議し,可否の判断を致します.希望にはできるだけ応えるようにしますが,展示方法等については実行委員会の指示に従ってください.
申込先:main@geosociety.jp
担当:山本啓司(鹿児島大会実行委員会)・須藤 宏(行事委員会)
確認書・クーポン等の送付について
事前参加登録:確認書・クーポン等の送付について
2014.8.29
事前参加申込を頂いた方に対して、申込内容に応じて確認書2枚(本人控・受付提出用)等をお送り致しました(8/29発送)。
受付提出用の確認書、名札、クーポンを当日忘れずにご持参下さい。
※参加者数を把握するため、参加登録費が無料のかた(名誉会員・50年会員・学部学生)も受付提出用の確認書を大会当日の受付へご提出ください。
<< 入金者の方へ >>
確認書2枚(本人控・受付提出用)・記名名札・クーポン(懇親会・お弁当を予約された方のみ)をお送りしました。当日必ずご持参下さい。
ネームカードホルダーと、それぞれ申し込み内容に応じて冊子等をお渡しいたします。
受付提出用の確認書がない場合には、受付に時間がかかりますので必ずご持参ください。
クーポンは懇親会会場入り口、お弁当引換時にそれぞれ提示してください。
<< 一部入金・未入金の方へ >>
確認書発送時点で一部入金もしくは、入金確認が取れていない方へは当日払いの参加費に金額訂正した確認書のみをお送りしております。当日必ずご持参ください。
※入金確認まで、時間がかかる場合がありますので、入金と入れ違いの場合はご容赦ください。
当日学会デスクにて入金のご確認をさせて頂きますので、振込み時の控え等をご持参下さい.確認がスムーズに行えます.
お支払いがまだの方は、9月8日(月)までに下記いずれかへお振り込みをお願い致します。この場合も振込み時の控え等をご持参下さい。
8日までにお振込いただけなかった場合は、当日学会デスクにてご清算をお願い致します。
振込先 (注意:振込時には、振込者氏名の前に必ず申込Noを入力して下さい)
(1)三井住友銀行 神田駅前支店(普通)1711424
(社)日本地質学会 / シャ)ニホンチシツガッカイ
(2)郵便振替 00140-8-28067
一般社団法人日本地質学会
大会期間中のお食事について
大会期間中のお食事について
◯ お弁当予約販売(予約申込は締切りました).予約弁当は共通教育棟2号館1Fで配布します.(クーポンと引き換え)
◯ 大学生協厚生施設:下記施設が会期中の9月13日(土)8:00〜19:30に営業します.
鹿児島大学生協中央食堂(食料品の売店もあります.営業時間11:00〜19:30)
注意:上記以外の日時には郡元キャンパス周辺(東側)のコンビニエンスストア等をご利用ください.郡元キャンパス周辺には飲食店が多くありますので,そちらもご利用ください.
9月14日(日)15日(月・祝)については昼食時に上記鹿児島大学生協中央食堂が限定メニューで営業致しますので,こちらもご利用ください.
日程・プログラム
全体日程・プログラム
9/13(土)〜15(月)
地質情報展2014かごしま−火山がおりなす自然の恵み−
9/13(土)
セッション発表(口頭,ポスター),市民講演会(午後),表彰式・記念講演会,懇親会,教育・アウトリーチ巡検
9/14(日)
国際シンポジウム,セッション発表(口頭,ポスター),ランチョン,夜間小集会,生徒「地学研究」発表会,若手会員のための業界研究サポート
9/15(月)
一般公開シンポジウム(午前),セッション発表(口頭,ポスター),ランチョン,夜間小集会
9/16(火)〜18(水)
ポスト巡検:日帰り〜2泊3日のコースあり
■全体日程表
クリックするとPDFファイルがダウンロードできます
■各講演プログラム
9/13(土)
口頭発表 ・ ポスター発表
9/14(日)
口頭発表 ・ ポスター発表
9/15(月)
口頭発表 ・ ポスター発表
※アウトリーチセッションのプログラムは、[9/13のポスター発表]内に記載しています。
▶各シンポジウム・セッションのハイライト
(pdfのダウンロード)
▶シンポジウム一覧 ▶セッション一覧
▶ランチョン・夜間集会一覧
[English version]
13 Sept. (Sat)
Oral ・ Poster & Outreach
14 Sept. (Sun)
Oral ・ Poster
15 Sept. (Mon)
Oral ・ Poster
大会趣旨
鹿児島大会趣旨
「わがこっじゃっど,地質学」
2014年鹿児島大会は,「わがこっじゃっど,地質学」をキャッチフレーズに西日本支部の支援のもと,鹿児島大学郡元キャンパ スにおいて第121年学術大会(2014年鹿児島大会)を2014年9月13日(土)〜15日(月)に開催いたします.
2014年は大正3(1914)年に発生した桜島火山の大正噴火から,ちょうど100周年にあたります.鹿児島大会では,2つの大噴 火(100年前の桜島の大正噴火と200年前(1813年)に諏訪之瀬島火山で発生した文化噴火)を紹介し,火山防災を考える市民講 演会「桜島と諏訪之瀬島の大噴火と火山災害」と地学教育・アウトリーチ巡検「2011年新燃岳噴火と霧島ジオパーク」を開催し ます.また,ロンドン地質学会と共催の国際シンポジウム「Tsunami hazards and risks: using the geological record」や,近年, 話題となっている恐竜化石などに焦点を当てた一般公開学術シンポジウム「九州が大陸だった頃の生物と環境」も開催します.
学術発表に関しては,各専門部会等から提案された25件のレギュラーセッションと9件のトピックセッションを用意し,アウ トリーチセッションも開催します.例年通り,小さなEarth Scientistのつどい:小・中・高校生徒「地学研究」発表会や,「地質 情報展2014かごしま」なども開催します.
巡検は,鹿児島や桜島周辺を巡る日帰りコースのほか,鹿児島県のみならず宮崎県や熊本県を含む南九州各地に出かける宿泊 巡検コースも複数設定しました.今大会は従来にもまして巡検に力を入れております.多くの皆様のご参加をお待ちしておりま す.
各種申込は,従来と同様の参加登録システムを利用します.お支払いは銀行振込またはクレジットカードによる支払いが可能 です.発表についても演題登録システム(PASREG)を利用したオンライン登録が可能です.なお,大会準備がスムーズに運ぶ よう,締切日の厳守をお願いいたします. 鹿児島大会に関する最新情報は,「2014年鹿児島大会HP」に掲載します.
「わがこっじゃっど,地質学」:鹿児島には,「ひとんこっちゃ,わがこっ」という格言があります.これは「他人のことも自分 のこと」,すなわち「他人に起きた事でも,いつ自分に起きるか分からないので気を付けなさい」という意味があります.地質学 は,自然災害から自分の身を守り,将来の地球と人間のあり方を考えるために重要な学問分野であり,この地球に住む人々が遍 く学び,身につけて欲しい,そして身につけるべき,全ての人々にとって関わりのある学問分野です.今大会のキャッチコピー は,地質学は,自分に関わる学問=「わがこっ」なのだという思いを表しています.
注意事項等
会場での注意点
■拍手徹底
1題の口頭発表はわずか15分で終了します(セッションの場合).しかし,その発表の裏には,発表者の弛まぬ努力と,研究や発表準備に費やした多くの時間があるはずです.講演が終了したら,惜しみない拍手をお願いします.
■写真撮影・ビデオ撮影の制限
口頭発表・ポスター発表を,発表者に無断で写真撮影・ビデオ撮影してはいけません.撮影には発表者の許可が必要です.また,それらを発表者の許可なく,SNS等で配信もしてはいけません.
■軽装の勧め
7月末現在,九州地区の電力供給は逼迫した状況ではありませんが,不測の事態で急な節電要求がある可能性も考えられます.残暑厳しい時期,大会参加の皆様には軽装をお勧めします.ご理解,ご協力をお願いします.
発表者の方へ
発表者は本学会または共催学協会の会員に限ります(招待講演者を除く).共同発表の場合は,この制限を代表発表者(講演要旨に下線を引いた著者)に適用します.やむを得ない事情により,あらかじめ連記された共同発表者内で発表者の変更を希望する場合は,必ず事前に行事委員会(会期前は学会事務局,会期中は学会本部)に連絡して下さい.この場合も,シンポジウムおよびアウトリーチセッション以外の場合は「会員に限り1 人1 題(発表負担金を支払った場合は2題)」の制限を守るものとします.代理人の代読,会場内での突然の発表者変更,発表順序の変更は認めません.口頭発表者は発表時間を厳守して下さい.持ち時間15分のうち,発表は10〜12分とし,質疑応答5 〜 3 分を確保してください(30分の招待講演の場合,発表20〜25分,質疑応答10〜 5 分).発表に際しては座長の指示に従い,会場運営がスムーズに行われるようご協力下さい.
■■■ 口頭発表 ■■■
・ 1 題15分(質疑応答3 〜 5 分を含む).ただしシンポジウムとセッション招待講演は除きます.
・ 口頭発表会場には液晶プロジェクターとWindowsパソコン(OS: Windows XP,Vistaおよび7対応,PowerPoint2003-2013 対応)を用意します.
【講演ファイルをUSBメディアでご持参の方】
ファイルのインストールは,セッション開始前に,講演会場前方パソコン設置台にて行ってください.各会場のパソコンのデスクトップ上には日付(例0914)のフォルダが配置されており,その中にセッション番号のサブフォルダ(例 T1 )が配置されています。そのサブフォルダ内に講演ファイルを保存してください。ファイル名は「発表番号と演者氏名」にしてください(例::S1-O-1鹿児島太郎,T1-O-13薩摩花子).インストール後,ファイルが正常に投影されることを必ず確認してください.特に,会場のPCと異なるバージョンで作成されたパワーポイントファイルは,レイアウトが崩れる場合がありますのでご注意ください.
【ご自分のパソコンを使用して講演する方】
Macをお使いになる方,ソフトの互換性からレイアウトが崩れる可能性のある方,パワーポイント以外のプレゼンテーションソフトをご利用の方は,ご自身でパソコンをご用意ください.会場の液晶プロジェクターにパソコンの切り替え器(ケーブル形状はD-SUB15ピン)を用意します.プロジェクターの解像度設定はXGA(1024×768)です.講演前に出力調整の上,接続してください.Macパソコンをお使いになる方は,必ずD-SUB15ピンのアダプターをご持参ください接続は発表者自身が責任を持って行なってください.セッション開始前に試写し,正常に投影されることを必ず確認してください.
口頭発表の注意:
昨年に引き続き,今大会もPCセンターを設置しません(ニュース誌5月号を参照).セッションが円滑に進むように,次の注意点をよくご確認ください.
1) 発表はできるだけ会場備え付けのWindowsパソコン(OSはWindows 7;PowerPoint 2003〜2013対応)をご使用下さい(ただしMacご利用の方と動画を使用する方はご自身のパソコンをご用意下さい).プロジェクター解像度は1024×768ドット(XGA)です.パワーポイント・ファイルをUSBフラッシュメモリで持参し,セッション開始前にパソコンにコピーして下さい(セッション終了後,世話人がファイルを削除します).フォントは特殊なものではなく,PowerPointに設定されている標準的なものを使用して下さい.セッション開始前に発表会場またはファイル確認室で正常に投影されることを必ず確認して下さい.
2) ご自身のパソコンで発表する方は,セッション開始前に発表会場において正常に接続・投影されることを確認して下さい.事前に解像度(上記)の設定をご確認下さい.会場の接続端子はD-sub15ピン(ミニ)です.パソコンによってはコネクタが必要になる場合がありますので必ずご持参下さい(会場にはありません).確認作業の混雑とそれによるセッション開始の遅れを防ぐため,早めの確認作業をお願いします.なお,発表者が事前確認を怠ったために発表時にトラブルが生じても時間延長等の措置は取りません.
■■■ ポスターセッション ■■■
・ 掲示する際のチェスピンを準備いたします.テープは利用できません.
・ 掲示時間は9:00〜18:00です.遅くとも10時までに必ず掲示し,17時までははがさないでください.撤収は19時までにお願いします.
・ コアタイムは,13日(土)が13:30〜14:50,14日(日)と15日(月)が13:00〜14:20です(アウトリーチセッションのみ13日(土)13:30〜14:30および16:00〜17:00).この時間は必ずポスターに立ち会い,説明して下さい.その他の時間は各自の都合により随時説明を行って下さい.
・ボード面積は,高さ210 cm,幅120 cmです.
・発表番号・発表題名・発表者名を必ず明記して下さい.
・ コンピューターやビデオを使用される場合,機器の準備は各自で行ってください.電源は確保できませんので,予備バッテリーをご準備下さい.
・ ポスター発表に対し,別記の要領にて優秀ポスター賞が授与されます.奮ってご準備下さい.
>>> 優秀ポスター賞についての詳細はこちら.
宿泊・観光関連情報
□■□■□■□■□■□ 宿泊関連情報 □■□■□■□■□■□
鹿児島大会期間中,鹿児島市内では他学協会のイベント等も予定されています。
宿泊予約が混み合う可能性がありますので,お早めの手配をお勧め致します。
【 宿泊申込サイト 】
(日本地質学会 鹿児島大会専用ページ)
地質学会では,近年学会を通じての宿泊・交通手配の斡旋を行っていません。
宿泊や交通については,各自で手配をお願い致します。
□■□■□■□■□ 観光関連情報:準備中 □■□■□■□■□
■鹿児島の観光情報■
巡検申込状況
巡検申込状況(8月8日12時 現在)
※巡検はそのほかの申込と締切日が異なります。予定されている方は、早めにお申込ください。
[申込締切] Web: 8/8(金)18:00、FAX/郵送: 8/6(水)必着
■ WEB参加登録はこちらから ■
【巡検一覧と各コース見どころはこちら】
※国際シンポジウム関連巡検は申込方法が異なります。詳しくはこちらから
コース
コース名
定員(最小催行)
申込件数
1
付加体
20(15)
22
2
上部白亜系の層序と化石,堆積相
12( 9)
11
3
堆積岩
20(10)
20
4
桜島火山
20(15)
20
5
変成岩
20(10)
24
6
屋久島の付加体・深成岩
20(14)
17
7
第四系
24(15)
27
8
地学教育・アウトリーチ
40(20)
26
国際
国際シンポ関連巡検
22(--)
15
◆コース1・2・3・4・5は受付を終了しました(システムの都合上,申込画面から申込手続きが完了した場合でも,後日お断りさせて頂く事になります.ご了承下さい).
◆参加申込人数が各巡検コースの最小催行人員に達しなかった場合,巡検を中止することがあります.
◆巡検協賛団体の会員の方は,会員同様にお申込を頂けます.それ以外の非会員の方は,申込締切時点で定員に余裕があれば参加可能となります.ご承知おき下さい.
◆コース8<地学教育・アウトリーチ>は,小中高の教員ならびに一般市民を優先対象とします.
そのほか、巡検のお申込については,こちらをご確認ください.
表彰式・記念講演会
会員顕彰式・各賞授与式・受賞記念講演
日程:9月13日(土)15:00 〜 17:50
会場:鹿児島大学郡元キャンパス共通教育棟1号館121教室
15:00 - 15:10
来賓挨拶(蔵脇淳一 鹿児島大学理学部副学部長)
15:10 - 15:40
50年会員顕彰式,各賞授与式
15:50 - 16:05
日本地質学会小澤儀明賞受賞スピーチ
菅沼悠介会員「 堆積物の磁化,いつどこで獲得?−地磁気の目盛りで地球史を読む−」
16:05 - 16:20
日本地質学会小澤儀明賞受賞スピーチ
田村 亨会員「海岸地形と地層の間」
16:20 - 16:50
日本地質学会国際賞受賞講演
江 博明氏
16:50 - 17:20
日本地質学会賞受賞講演
川幡穂高会員「 二酸化炭素がもたらす2つの地球環境問題−GEOLOGYと人類の未来−」
17:20 - 17:50
日本地質学会賞受賞講演
斎藤文紀会員「地層と地形から読み解く:沖積層と現行堆積過程の研究」
地学教育・普及・関連行事
地学教育・普及・関連行事
※一般公開行事実施の際の警報等発令時及び地震発生時の対応指針(PDF)
■ 地質情報展2014かごしま(9/13-15)
■ 市民講演会 (9/13)
■ 地学教育・アウトリーチ巡検 (9/13)
■ 小さなEarth Scientistのつどい(9/14)
■若手会員のための業界研究サポート(9/14)
■一般公開シンポジウム(9/15)
■その他
※各行事の画像をクリックすると,大きな画像,またはPDFをダウンロードできます.
地質情報展2014かごしま
日時:2014年9月13日(土)〜15日(月・祝)【入場無料】
小さいサイズ [約260KB]
大きいサイズ [約17MB]
小さいサイズ [約300KB]
大きいサイズ [約10MB]
9月13日(土) 13:00〜17:00
9月14日(日) 9:30〜17:00
9月15日(月) 9:30〜16:00
会場:鹿児島市中央公民館
→会場アクセスはこちら
主催:一般社団法人日本地質学会・産業技術総合研究所地質調査総合センター
共催:桜島・錦江湾ジオパーク協議会・鹿児島大学博物館
後援: 鹿児島県・鹿児島県教育委員会・鹿児島市・鹿児島市教育委員会・NHK鹿児島放送局・南日本新聞社・エフエム鹿児島・全国地質調査業協会連合会・日本ジオパークネットワーク・霧島ジオパーク推進連絡協議会
内容:地質調査総合センターが有する各種地質情報から,鹿児島県及び周辺の地質現象や地震・火山・地盤災害の起こるしくみについて展示パネルでの解説を行います.また,小さなお子さんにも楽しく地学を学んでもらうために化石レプリカなどの体験学習コーナーを用意します.
展示テーマ:鹿児島の地質・地質災害・活火山・金鉱床,地震と津波,再生可能エネルギー,ジオパークほか.
体験コーナー:液状化実験,化石レプリカ作り,石割り体験,火山噴火実験ほか.
地質学会関連の展示:
・第5回惑星地球フォトコンテスト入選作品展示
・ 地学オリンピックへおじゃったもんせ!:地学オリンピックは地球科学に興味・関心のある子どもたちを応援しています.中学生・高校生の皆さん,第7回日本地学オリンピックへ参加してみませんか?また,2016年に三重県で開催予定の第10回国際地学オリンピックへのご協力もお待ちしております.詳しい情報は展示ブースにて.
詳しくはこちらから
https://www.gsj.jp/event/2014fy-event/kagoshima2014/index.html
問合せ先:産業技術総合研究所地質調査総合センター
渡辺真人・川邉禎久 TEL:029-861-3687 e-mail:johoten2014jimu-ml@aist.go.jp
ページトップに戻る
市民講演会「桜島と諏訪之瀬島の大噴火と火山災害」
日時:2014年9月13日(土)14:30〜16:00【入場無料/事前申込不要】[14:00開場]
注)終了時間が変更になりました(8/22現在).(変更)17:00→16:00
会場:鹿児島大学郡元キャンパス共通教育棟1号館111教室
講師:小林哲夫(鹿児島大学大学院理工学研究科・教授)
概要:鹿児島県では,桜島と諏訪之瀬島の2つの火山が,現在もっとも活発に火山活動を続けています.しかし100〜200年ほど前には,現在よりもはるかに大規模な噴火が発生しました.桜島ではちょうど100年前の大正噴火,諏訪之瀬島ではほぼ200年前の文化噴火です.この両火山については,長年の調査・研究成果をもとに,2013年に火山地質図が公表されました.講師は九州地域の火山の研究を長年続けており,この2つの火山地質図の作成にも関与しています.今回は桜島と諏訪瀬島という2つの火山で,100年前と200年前に発生した大噴火に焦点をあて,噴火の推移と災害の実態について,平易かつ詳しく解説します.あわせて,鹿児島における火山災害軽減への取り組みについても紹介する予定です.
【市民講演会問い合わせ先】
一般社団法人 日本地質学会事務局
e-mail: 電話:03-5823-1150
※ページトップに戻る
一般公開シンポジウム「九州が大陸だった頃の生物と環境」
日時:2014年9月15日(月)9:00〜12:30【入場無料/事前申込不要】[8:30開場]
会場:鹿児島大学郡元キャンパス共通教育棟1号館111教室
近年,九州からは古第三紀の哺乳類や白亜紀の恐竜化石が 多く発見され,九州のみならず全国的にも注目をあびている が,白亜紀から新第三紀前半の九州を中心とする西南日本が ユーラシア大陸の一部であった時代における陸上生物相の変 遷や,当時の九州の古地理的な位置づけについては十分な研 究が行われているとはいいがたい. そこで,本シンポジウムでは,九州を中心にした西南日本 における白亜紀の恐竜化石,白亜紀〜新第三紀前半の爬虫類 化石(カメ),古第三紀哺乳類化石(初期有蹄類),新第三紀 哺乳類化石(ゾウなど),白亜紀の花粉化石,古第三紀大型 植物化石などからみた陸上生物相や古気候の変遷と,この時 代を通じた地質環境の発達史について,日本各地から集まっ た気鋭の研究者8名に最新の研究成果を講演していただき, 議論する.また,ユーラシア大陸の生物相との比較から九州 を中心とした西南日本の古生物地理的な位置づけについて総 括的な議論を行いたい.
【講演内容】
・ 對比地孝亘(東京大学)
・小松俊文(熊本大学)鹿児島県下甑島上部白亜系産出の恐竜化石
・ 池上直樹(御船町恐竜博物館)御船層群上部層の陸生脊椎動物化石
・ 平山 廉(早稲田大学)九州の白亜紀から新第三紀初頭のカメ類化石
・ 宮田和周(福井県立恐竜博物館)九州の古第三紀大型陸生哺乳類化石
・ 三枝春生(兵庫県立大学・兵庫県立人と自然の博物館)九州およびその周辺地域の新第三紀の長鼻類およびその他哺乳類
・ 矢部 淳(国立科学博物館)大型植物化石からみた始新世〜漸新世の陸上植生と気候
・ ルグラン ジュリアン(中央大学)
・矢部 淳(国立科学博物館)
・宮田和周(福井県立恐竜博物館)
・西田治文(中央大学・東京大学)中生代の花粉化石からみた日本の植生と古環境
・ 斎藤 眞(産業技術総合研究所)九州の地質構造発達史,特に白亜紀〜古第三紀の付加体と正常堆積物の時代と分布に注目して
[世話人:仲谷英夫(鹿児島大学)]
※ページトップに戻る
小さなEarth Scientistのつどい〜第12回 小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜
日時:2014年9月14日(日) 9:00〜15:30
場所:鹿児島大会ポスター会場(郡元キャンパス)
問い合わせ・申込先:
日本地質学会地学教育委員会(担当 三次)
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F
TEL:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156 e-mail:main@geosociety.jp
▶▶参加校など、詳細はこちらから
*過去の発表会の様子や「優秀賞」受賞発表はこちらから
ページトップに戻る
地学教育・アウトリーチ巡検「2011年新燃岳噴火と霧島ジオパーク」
日時:2014年9月13日(土)8:30集合出発,17:00解散(予定)
参加対象:小中高の教員ならびに一般市民を優先
★★参加申込は締切締切りました★★
【申込・問い合わせ先】
〒890-0065
鹿児島市郡元1-21-35 鹿児島大学理学部地球環境科学科
井村研究室気付 地質学会霧島巡検係
電話:099-285-8144 FAX:099-259-4720
E-mail : kirishima_geopark@hotmail.co.jp
*巡検の見どころ・詳細はこちらから
*過去の巡検の様子はこちらから
ページトップに戻る
若手会員のための業界研究サポート
日時:2014年9月14日(日)9:00-17:00(*時間帯は若干変更になる場合があります)
場所:鹿児島大学郡元キャンパス共通教育棟1号館(3階)
内容:主催者等 挨拶・紹介、参加各社による数分のプレゼンテーション.参加各社の個別説明会(パネル、配布資料等をご用意ください).
対象:鹿児島大会に参加する学生・院生および大学教官等の会員,鹿児島大学等の学生・院生および教官等
★★★出展企業募集中!!(8/8締切)★★★
▶ 2013年仙台大会の様子はこちらから
ページトップに戻る
その他
日本地質学会第121年学術大会(2014鹿児島)開催に合わせて,鹿児島県立博物館本館の1階企画展示室で,以下の展示会(いずれも無料)が行われますので,あわせてお知らせいたします.
◆鹿児島大学総合研究博物館
第14回特別展「現代によみがえる生き物たち ―種子島にゾウがいた頃―」
期間:9月4日(木)〜9月15日(月)
◆鹿児島県立博物館
平成26年度企画展「かごしまに生きた古生物たち」
期間:7月26日(土)〜99月15日(月)
<鹿児島県立博物館へのアクセス>
市電「天文館通り」電停から徒歩約7分
市バス「天文館」または「金生町」バス停から徒歩約7分
※ページトップに戻る
CPD単位取得について
CPD単位取得について
地質技術者の皆さん 鹿児島大会でCPD単位が取得出来ます
日本地質学会は,地質技術者への継続教育の一環として,大会参加者・発表者・巡検参加者へCPD単位を発行します.大会参加と口頭/ポスター発表の参加証明書は,参加日の15時以降に「CPD受付」(会場内総合受付付近を予定)においてお渡しします.また,巡検参加者については各コースにおいて案内者よりお渡しすることになります.
【CPD単位】
・ 学術大会参加に対するCPD(時間に応じて):例)7時間出席=7単位
・ 口頭発表に対するCPD:0.4×15分発表=6単位
・ ポスター発表に対するCPD:2単位
・ 巡検参加に対するCPD:日帰り-8単位,1泊2日-16単位
日本地質学会は,土質・地質技術者生涯学習協議会ジオ・スクーリングネット(GEO・Net:https://www.geo-schooling.jp/)に加入し,地質技術者の継続教育(CPD)に携わっています.大会への参加だけでなく,講演や巡検の参加についてもそれぞれ単位が取得出来ます.またGEO・Netに掲載されている協議会加盟団体のイベント情報についても同様に検索・参加申込などが出来ます(参加の場合は,もちろんCPD単位が取得出来ます).
積極的にご登録頂き,GEO・Netをご活用下さい.
また,各支部で主催する講演会や巡検等各種イベントについても,随時本サイトに掲載し,GEO・Net登録者にご参加いただけるようにしていきたいと思います.
技術者継続教育,CPD単位については,下記をご参照ください。
http://www.geosociety.jp/engineer/content0003.html
(地質技術者教育委員会 山本高司)
会場・交通
会場・交通
メイン会場
鹿児島大学郡元キャンパス(鹿児島市郡元1丁目)
共通教育棟1号館・2号館・第2体育館・学習交流プラザ
地質情報展
鹿児島市中央公民館
(鹿児島市山下町5番9号)
(拡大は画像をクリック)
★★会場案内図はこちら★★
【鹿児島大学郡元キャンパスへのアクセス】
鹿児島大学郡元キャンパスの施設位置図及び大学までの公共交通機関は,鹿児島大学のホームページを参照して下さい.
■鹿児島空港〜市内:
鹿児島空港より鹿児島市内行バス(2番のりば)に乗車し,JR鹿児島中央駅までお越しいただき,鹿児島中央駅から下記の鹿児島市電にてご来校ください.
■鹿児島中央駅前市電のりばから市電を利用:(乗車時間約10分)
行き先:郡元行き:唐湊(または工学部前)電停で下車
※鹿児島大学郡元キャンパスは駐車スペースがないため,乗用車でのご来訪はご遠慮下さい.
※キャンパス内をはじめ,喫煙可の表示がない場所は禁煙となっています.
【鹿児島市中央公民館へのアクセス】
鹿児島市中央公民館の位置図及び公共交通機関に関しては,こちらを参照して下さい.
JR:
「鹿児島中央」駅からタクシー約10分
「鹿児島」駅から徒歩約20分
市電:
「朝日通り」電停から徒歩約5分
バス:
「天文館」バス停から徒歩約10分
「金生町」バス停から徒歩約5分
空港バス:
鹿児島空港から約50分,「天文館」または「金生町」(吉野経由のみ)で下車
★★鹿児島大学郡元キャンパス会場案内図★★
(図をクリックするとpdfをダウンロードできます.)
※ 無線LANをご利用頂けます:総合受付・休憩室・ミーティングルームで,無線LANを各自のパソコンでご利用頂けます.
無線LANのご利用方法は受付および休憩室等に掲示する予定です.
申込先・締切一覧
各種申込先・締切一覧
WEB
FAX・郵送
申込・問合先
講演申込(演題登録)
7/1(火)18時
6/25(水)必着
詳細
行事委員会
講演要旨原稿提出
7/1(火)18時
6/25(水)必着
詳細
行事委員会
緊急展示の申込
8/29(金)
-------
詳細
行事委員会
WEB
FAX・郵送
事前参加登録
8/19(火)18時
8/15(金)必着
詳細
学会事務局
巡検
8/8(金)18時
8/6(水)必着
詳細
学会事務局
懇親会
8/19(火)18時
8/15(金)必着
詳細
学会事務局
追加講演要旨
8/19(火)18時
8/15(金)必着
詳細
学会事務局
お弁当
8/19(火)18時
8/15(金)必着
詳細
学会事務局
同窓会ブース
8/19(火)18時
8/15(金)必着
詳細
現地事務局
託児室
8/22(金)※予定
-------
詳細
現地事務局
生徒地学研究発表会
(小さなEarth Scientistのつどい)
7/16(水)
-------
詳細
地学教育委員会
業界研究サポート
8/8(金)
詳細
ランチョン・夜間小集会
6/25(水)
-------
詳細
行事委員会
一次締切
最終締切
広告協賛
-------
8/8(金)18時
詳細
現地事務局
企業展示への出展
7/4(金)18時
8/8(金)18時
詳細
現地事務局
書籍・販売ブース
7/4(金)18時
8/8(金)18時
詳細
現地事務局
※※※ 巡検のみ参加申込締切が大会参加登録等と異なりますので,ご注意下さい ※※※
問い合わせ先
鹿児島大会問い合わせ先
■大会期間中の問い合わせ先
大会現地事務局気付
e-mail:gsj2014kagoshima@academicbrains.jp
電話:080-5363−8921
■日本地質学会行事委員会 / 地学教育委員会 / 学会事務局(東京)
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目8-15 井桁ビル6F
(日本地質学会事務局 気付)
TEL:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156
e-mail:main@geosociety.jp
■行事委員会■(2014年7月現在)
委員長
竹内 誠(担当理事)
委 員
内野 隆之(地域地質部会)
芦 寿一郎(海洋地質部会)
長谷川 健(火山部会)
中条 武司(堆積地質部会)
鵜澤(平原) 由香(岩石部会)
辻 健(現行地質過程部会)
坂本 正徳(情報地質部会)
河村 知徳(石油石炭関係)
田村 嘉之(環境地質部会)
氏家 恒太郎(構造地質部会)
須藤 宏(応用地質部会)
須藤 斎(古生物部会)
浅野 俊雄(地学教育委員会)
黒田 潤一郎(環境変動史部会)
廣瀬 孝太郎(第四紀地質部会)
吉田 英一(地質環境長期安定性研究委員会)
岡田 誠(層序部会)
中村 謙太郎(鉱物資源部会)
■日本地質学会第121年学術大会 現地事務局
(株式会社アカデミック・ブレインズ 内)担当:田中
〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1天満橋千代田ビル2号館9階
TEL:06-6949-8137 FAX:06-6949-8138
e-mail:gsj2014kagoshima@academicbrains.jp
■実行委員会組織
委 員 長
小林 哲夫(TEL:099-285-8146,koba@sci.kagoshima-u.ac.jp)
西日本支部長
佐野 弘好(TEL:092-642-2606,sano@geo.kyushu-u.ac.jp)
事務局長
仲谷 英夫(TEL:099-285-8139,nakaya@sci.kagoshima-u.ac.jp)
巡 検
井村 隆介(TEL:099-285-8144,imura@sci.kagoshima-u.ac.jp)
巡検案内書
志村 俊昭(TEL:083-933-5766,smr@yamaguchi-u.ac.jp)
現地事務局
((株)アカデミック・ブレインズ 内) 担当:田中
(TEL:06-6949-8137,FAX:60-6949-8138,e-mail:gsj2014kagoshima@academicbrains.jp)
男女共同参画企画
(託児室)
問合せ先 現地事務局((株)アカデミック・ブレインズ 内)
担当:田中(TEL:06-6949-8137,FAX:06-6949-8138,e-mail:gsj2013sendai@academicbrains.jp)
参加登録TOP
2014鹿児島大会事前参加登録ほか申込
事前参加登録は締切りました(8/19)
当日会場受付での混雑緩和のため,事前に参加登録申込をお願いします.大会参加登録およびそれに伴う参加費は,参加者(巡検のみ参加の場合も)に必要な基本的なお申し込みです.ただし,会員が同伴する非会員の配偶者ならびに子供(以下,同伴者)については参加登録申込の必要はありません(懇親会・巡検・お弁当については同伴者も申込が必要).会員と同伴者の2名まで一括申込が可能です.申込は,「各種申込とお支払について」を参照し,下記フローチャートを進んで該当する申込画面よりお申込をお願い致します。
<申込締切 オンライン:8月19日(火)18:00,FAX/郵送:8月15日(金)必着>
※ 学会を通じての宿泊・交通手配の斡旋は行いません.宿泊や交通については各自で手配願います.※
※鹿児島近郊にお住まいの一般の方で,アウトリーチ巡検のみに
参加する(学術大会での講演・聴講をしない)方は,【 こちらへ 】※
下のフローチャートに従って進み,該当する申込画面をクリックして
それぞれ申込手続きをおこなって下さい.
すべての事前参加申込は締め切りました。
※巡検協賛学協会・セッション共催団体リスト
参考>>会員情報を自動取得するには?(PDF)
*FAX・郵送専用申込書(PDF)はこちら
*申込方法・支払い方法の詳細についてはこちら ▶▶各種申込とお支払について
参加フォームから申し込める項目:クリックすると各詳細のご案内をご覧いただけます。
■ 参加登録費
■ 追加講演要旨(大会不参加で冊子のみの購入も可)
■ 巡検 *注意* 8月8日締切.冊子体での巡検案内書の作成・販売はありません
■ お弁当
■ 懇親会
■ 宿泊関連
会員が同伴する非会員の配偶者ならびに子供(以下,同伴者)については
参加登録申込の必要はありません.
(懇親会・巡検・お弁当については同伴者も申込が必要:会員の申込と一括で申込可能)
当日の受付について
当日の受付について
事前参加登録につきましては,FAX・郵送によるお申し込みを8月15日,オンラインによるお申込みを8月19日に締め切りました.
※確認書やクーポン等を8月29日に発送しました.
■ 事前参加登録者
【入金済みの事前登録者】
締切後,確認書2枚(本人控・受付提出用)と名札,懇親会とお弁当を予約の方へはそれぞれクーポンを発送します.大会開催10日前には参加者の皆様のお手元に届くようお送り致します.当日会場へ持参してください.
【確認書発送時点で入金確認が取れない場合】
未入金の旨記載された確認書のみ送付いたしますので当日会場にて確認書をご提示いただき,入金の確認をして下さい.請求額は当日払いの金額に変更になります.入金と確認書の発送が入れ違いの場合は,振込み時の控え等を会場にお持ちください.当日差額分のご精算をお願いします.
事前登録者用受付にて,確認書に記載されている項目ごとに受付して下さい.
受付にてネームカードホルダーをお渡ししますので『参加証(名札)』を入れ,大会期間中は身に付けてください.
1.確認書の提出(全員)→ネームカードホルダーの配布.要旨付きの場合は,要旨の配布
2.講演要旨追加購入(予約購入者のみ)→要旨の配布
3.懇親会→参加者は直接懇親会会場でクーポンを提示してください.
4.お弁当(予約者のみ)→お弁当の引き換え時にクーポンを提示してください.
5.巡検(参加者のみ)→名簿確認と参加最終確認
注:未入金者の方は,総合受付で入金確認した後,懇親会やお弁当のクーポンをお渡しします.当日確認書やクーポンを忘れた方は,専用の用紙に申込内容をご記入いただき,受け付けを済ませてください.確認がスムーズに行えますよう,ご協力をお願い致します.
→申込の取消・取消料についてはこちらから
■ 事前登録をしていない方
1. 当日は必ず参加登録をしてください.参加登録費の有料・無料に関わらず備え付けの『参加登録票』に必要事項を 記入し当日用受付へ
2.当日参加登録費(講演要旨集付きです.要旨集が不要の場合でも割引はありません)
正会員:9,500円
院生割引会費適用正会員:6,500円
学部学生割引適用正会員・名誉会員・50年会員・非会員招待講演者・学部学生(会員・非会員問わず):無料(講 演要旨は付きません)
非会員(一般):15,000円
非会員(院生):9,500円
3.講演要旨当日販売
会 員:4,000円
非会員:5,500円
4.懇親会の当日参加費(ただし,人数に余裕がある場合に限る) 正会員・非会員(一般):6,000円
名誉会員・50年会員・院生および学生割引適用正会員(家族および非会員院生・学生含):3,500円
別途領収書が必要な方は会場受付でその旨お申し出ください.当日のお支払いは,現金のみの取扱いとなります.クレジットカードはご利用いただけません.
申込方法と支払について
各種申込とお支払について
■ 事前参加登録:受付終了しました ■
(1)申込方法
オンラインによる参加登録申込等を受付けます.申込は従来同様,学会独自の参加登録システムをご利用いただきます.大会専用参加登録システム(会員・非会員にかかわらずどなたでも申し込み可)または専用申込書(FAX・郵送用)をご利用の上,お申し込み下さい.参加登録・懇親会・追加講演要旨・巡検・お弁当を同時に申込むことができます.なお,学会を通じての宿泊・交通手配の斡旋は行いません.宿泊や交通については各自で手配願います.
(a)大会登録専用HP(オンライン)による申込
1)上記リンクまたは画面左のメニュー「参加登録」をクリックして下さい.
2)申込画面の入力欄に氏名と会員番号を入力するだけで,学会に登録されている会員情報(所属・住所等)が表示され,続けて参加登録を行うことができます.
3)申込み完了後,「申込確認メール」および「ご請求メール」が登録のメールアドレスへ配信されます.内容を必ずご確認下さい.(※メールが届かない場合は,登録アドレスが間違っている可能性があります.事務局へご連絡ください.)
4)支払い方法について,「銀行振込」を選択された方は,「ご請求」メールを確認の上,指定の金融機関よりお振込み下さい.また,クレジットカードもご利用頂けます.「クレジット決済」を選択の場合は,ご利用のカード会社の期日に合わせて,口座より引き落としとなります.クレジットカード会社からの明細には「日本地質学会(ニホンチシツガッカイ)」と表示されます.
5)締切後,名札・確認書・クーポン(一部の方)を発送します(8月末頃発送予定).大会開催10日前までには参加者の皆様のお手元に届くようお送り致します.締切時点で入金確認が取れない場合は,未入金旨記載された確認書のみが送付されます(名札・クーポンは送付されません)ので,当日会場にて入金のご確認をさせて頂きます.入金とクーポン発送が入れ違いの場合は,振込み時の控え等を会場にお持ちいただければ,確認がスムーズに行えます.ご協力をお願い致します.
(b)FAX・郵送による申込
「FAX・郵送専用申込書」(PDF)はこちらから
1)「 FAX・郵送専用申込書」に必要事項を記入の上,日本地質学会事務局までFAXまたは郵送にてお申込み下さい.電話による申込,変更などは受け付けられませんので,ご了解下さい.また,郵送による申込みの際は,必ず申込書のコピーを各自で保管して下さい.
FAX番号:03-5823-1156
郵送先:〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-815井桁ビル6階「日本地質学会 鹿児島大会参加申込係」
2)申込後,折返し学会より「受付確認」をe-mailまたはFAXにてお送りします.必ずご確認下さい.受付確認が届かない場合は,必ず事務局までご連絡下さい.受付確認には,「受付番号」が記載されています.この「受付番号」はその後の問い合せ,変更,取消等に必要となります.
3)お支払いは,銀行振込またはクレジットカード決済のいずれかを選択できます.申込後順次,「予約内容確認」・「請求書」をお送りします.銀行振込を選択された方は,請求書に記載されている振込口座へ指定期日までにお振込み下さい.クレジット決済を選択された方は,参加申込の際必ずクレジット番号などの必要事項を記入して下さい.ご利用のカード会社の期日に合わせて,口座よりお引き落としとなります.カード会社からの明細には「日本地質学会(ニホンチシツガッカイ)」と表示されます.
4)締切後,名札・確認書・クーポン(一部の方)を発送します(8月末頃発送予定).大会開催10日前までには参加者の皆様のお手元に届くようお送り致します.締切時点で入金確認が取れない場合は,未入金旨記載された確認書のみが送付されます(名札・クーポンは送付されません)ので,当日会場にて入金のご確認をさせて頂きます.入金とクーポン発送が入れ違いの場合は,振込み時の控え等を会場にお持ちいただければ,確認がスムーズに行えます.ご協力をお願い致します.
※いずれの申込も締切時点で入金確認が取れない場合は,当日払いの参加費にて請求いたします.
(2)申込締切
大会登録専用HP(オンライン)による申込:
8月19日(火)18:00
FAX・郵送による申込:
8月15日(金)必着
(3)申込後の変更・取消
(a)大会登録専用HP(オンライン)でお申込みの場合:締切までの間は,大会登録専用HPから予約の変更・取消が出来ます.変更・取消完了後,「変更・修正 確認メール」が登録のメールアドレスへ配信されます.内容を必ずご確認下さい.締切後は直接学会事務局(東京)にFAX又はe-mailにてご連絡下さい.クレジット決済の場合は,申込の都度決済が完了しますので,決済スケジュールの都合によっては,口座から重複して引き落とされる場合があります.その場合は,振込手数料を差し引いた額をクレジットカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2〜3ヶ月要する場合もありますので,ご了承下さい.
(b)FAX・郵送でお申込み場合:申込後に変更・取消が生じた場合は,学会事務局(東京)にFAXまたはe-mailにてご連絡下さい.その際申込受付時に案内される「受付番号」・「氏名」を必ず明記下さい.
(4)取消に関わる取消料と返金について
注意:弁当と巡検は取消料が異なります.
(a)締切までの取消:取消料は発生しません.返金がある場合は,振込手数料を差し引いた額をクレジットカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2〜3ヶ月要する場合もありますので,ご了承下さい.
(b)締切後〜9/10(大会3日前)までの取消:入金・未入金の如何に関わらず,参加費用の60%を取消料としていただきます.返金がある場合は,振込手数料を差し引いた額をクレジットカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2〜3ヶ月要する場合もありますので,ご了承下さい.参加費に講演要旨集が付いている方へは,大会後にお送りします.
(c)9/11(大会2日前)以降の取消:入金・未入金の如何に関わらず,参加費用の100%を取消料としていただきます.参加費に講演要旨集が付いている方へは,大会後にお送りします.
(d)お弁当の取消:利用日より9日前〜前日までは50%,当日は100%の取消料がかかります.
(e)巡検の取消:締切後〜出発3日前までは50%,2日前以降は全額となります.
参加登録費
参加登録費
当日会場受付での混雑緩和のため,事前に参加登録申込をお願いします.大会参加登録およびそれに伴う参加費は,参加者(巡検のみ参加の場合も)に必要な基本的なお申し込みです.ただし,会員が同伴する非会員の配偶者ならびに子供(以下,同伴者)については参加登録申込の必要はありません(懇親会・巡検・お弁当については同伴者も申込が必要).
申込は,オンライン,FAX・郵送いずれの場合も,会員と同伴者の2名まで一括申込が可能です.申込は,「各種申込とお支払について」を参照し,申し込んで下さい.
<申込締切 オンライン:8月19日(火)18:00,FAX・郵送:8月15日(金)必着>
■ 事前参加登録:受付終了しました ■
○参加登録費(講演要旨集付です)
講演要旨集が不要の場合でも割引はありません.参加登録費の発生する方には,講演要旨集が必ず付きます.なお,名誉会員・50年会員,非会員招待者,学部学生(会員・非会員問わず)には講演要旨集は付きません.ご希望の方は別途購入して下さい.
事前申込
当日払い
備考
正会員
7,500円
9,500円
講演要旨集付き
院生割引適用正会員
4,500円
6,500円
講演要旨集付き
学部制割引適用正会員・名誉会員・50年会員・非会員学部学生・非会員招待者
無料
無料
講演要旨集は付きません
非会員(一般)
12,500円
15,000円
講演要旨集付き
非会員(院生)
7,000円
9,500円
講演要旨集付き
*日本地質学会の会員資格は『正会員』のみであり,割引会費の申請をした方についてのみ,割引会費が適用されています.
*大会に参加できなかった場合は,大会後に講演要旨集をお送りします.参加登録費用の返却はいたしませんのでご了承下さい(取消料の項目参照).
*セッション共催団体および巡検協賛団体会員の参加登録費は会員に準じます。
*追加で講演要旨集を購入される場合は,「講演要旨集のみの予約頒布」の価格表を確認してお申し込み下さい.
要旨のみの予約販売
講演要旨集のみの予約頒布
<申込締切 オンライン:8月19日(火)18:00,FAX・郵送:8月15日(金)必着>
■ 事前予約:受付終了しました ■
大会参加費には講演要旨集の代金が含まれていますので,大会に参加される場合は別途購入の必要はありません.ただし,名誉会員・50年会員,非会員招待者,学部学生(会員・非会員問わず)には講演要旨集は付きません.ご希望の方は,別途ご購入下さい.大会に参加されない方ならびに参加する方が複数の講演要旨集を購入される場合の予約頒布の申込は,「各種申込とお支払いについて」を参照し,申し込んで下さい.要旨集の受け取り方法には,(1)大会後に送付,(2)会場で受取り,があります.(1)の場合は,別途送料が必要です.(2)の場合は,大会受付にて確認書の提示が必要となりますので,必ずご持参下さい.残部があれば大会当日あるいは大会後にも頒布します.売り切れの場合はご容赦下さい.
※大会前の送付は行っておりません.
事前予約(/冊)
当日販売(/冊)
会員
3,000円
4,000円
非会員
4,000円
5,500円
*「大会後に送付」の場合の送料は以下の通りです.
送料:1冊 500円,2冊 600円,3冊 800円,4冊 1,000円,5冊 1,200円
巡検参加申込
巡検参加申込
<申込締切 オンライン:8月8日(金)18:00,FAX・郵送:8月6日(水)必着>
※巡検のみ参加申込締切が大会参加登録等と異なりますので,ご注意下さい.
■ 事前参加登録:受付終了しました ■
【巡検一覧と各コース見どころ】
総計8コースの巡検を計画しました(巡検一覧はこちらから).巡検の参加申込は,「各種申込とお支払いについて」を参照し,申し込んで下さい.参加希望の方は,オンライン申込手続き手順に従って参加申込を行って下さい.FAX・郵送でのお申込は,専用申込書(ダウンロードはこちら)を用い,学会事務局(東京)宛に大会参加申込と一緒に申し込んで下さい.巡検だけに参加する場合も大会参加登録ならびに参加登録費が必要になります.巡検と大会参加登録の申込を合わせて行って下さい.実施日程の異なる場合,複数の巡検コースへの申込を行うこともできます(最大2コース).
(1)参加申込人数が各巡検コースの最小催行人員に達しなかった場合,巡検を中止することがあります.
(2)巡検協賛団体の会員の方は,会員同様にお申込を頂けます.それ以外の非会員の方は,申込締切時点で定員に余裕があれば参加可能となります.ご承知おき下さい.
(3)本学会ならびに鹿児島大会実行委員会は巡検参加者に対し,巡検中に発生する病気,事故,傷害,死亡等に対する責任・補償を一切負いません.これらについては,巡検費用に含まれる保険(国内旅行傷害保険団体型)の範囲でのみまかなわれます.
(4)子供同伴,肢体不自由など特別な事情がある場合は,申込前に現地事務局へあらかじめ問い合わせて下さい.
(5)締切までの間は,ホームページから変更・取消が出来ます.変更・取消完了後,「変更・修正 確認メール」が登録のメールアドレスへ送信されます.内容を必ずご確認下さい.締切後の変更・取消は,直接学会事務局(東京)にFAX又はe-mailにてご連絡下さい.締切後は入金・未入金の如何に関わらず,取消料が発生します(詳しくは,巡検一覧取消料の項目参照).
(6)集合・解散の場所,時刻などを変更することもありますので,大会期間中は掲示などの案内に注意して下さい.
(7)冊子体の案内書は作成しません.案内書CD-ROMを地質学雑誌8月号に添付する予定です(8月下旬または9月上旬にお手元に届きます).また,巡検参加者には,各班の巡検案内の複写を巡検当日に配布する予定です.
巡検コース一覧/みどころ
日本地質学会第121年学術大会(鹿児島大会)
各コースの詳細と魅力・見どころの紹介
■ 申込は締め切りました ■
参加者への連絡などを大会ホームページに随時掲載いたします.
巡検案内書は,CD-ROM版を120巻8号(2014年8月号)に添付して会員に配布いたします.また,地質学雑誌の一部となっていますので,発行から3ヶ月目にはJ-STAGEにて公開をいたします.
なお,予告記事でもお知らせの通り,冊子体の案内書は作成いたしません.巡検参加者には各班の巡検案内の複写を巡検当日に配布する予定です.
★注意点★
1)取り消し料は,申込締め切り後〜出発3日前までは50%,2日前以降は全額となります.
2)参加費には,日程に応じた旅行傷害保険(少額)が含まれます.
3)最小催行人員に満たない場合や,安全確保に問題があると考えられる場合は,コース内容の一部変更や巡検中止等の措置をとることがあります.
4)各コースの案内書は,印刷したものを巡検当日に配布します.全コース分を収録した冊子体の出版はありません(CD-ROM版のみ).
5)集合・解散の場所,時刻等に変更が生じた場合,大会期間中の掲示板に案内します.案内者から直接ご連絡することもあります.
6)コース8<地学教育・アウトリーチ>は,学会補助事業です.小中高の教員ならびに一般市民を優先対象とします.
※各コース案内の定員の後の( )は最小催行人数
コース1:付加体
コース2:上部白亜系の層序と化石,堆積相
コース3:堆積岩
コース4:桜島火山
コース5:変成岩
コース6:屋久島の付加体・深成岩
コース7:第四系
コース8:地学教育・アウトリーチ
【国際シンポジウム「津波ハザードとリスク」関連巡検】
Traces of paleo-earthquakes and tsunamis along the eastern Nankai Trough and Sagami Trough, Pacifi c coast of central Japan
※学術大会の巡検とは申込方法が異なります.
[詳細・参加申込はこちら] [シンポジウムの詳細はこちら]
コース1 九州西部に分布するジュラ紀付加体と海溝斜面堆積物
[9月16日(火)日帰り]
定員:20(15) 名
地形図
(1/2.5万)佐敷
案内者
尾上哲治(熊本大)・西園幸久(西日本技術開発)
魅力
本巡検では,九州西部の球磨川沿いに分布する秩父・三宝山帯を対象として,この地帯を構成するジュラ紀付加体の起源と形成過程を議論します.秩父・三宝山帯の陸源砕屑岩類は,玄武岩・チャート・石灰岩などの雑多な岩相・年代の海洋性岩石を異地性・異時代の岩塊として含むことが知られています.本巡検では特に,これら海洋性岩石の付加以前の初生的な層序や付加過程について焦点をあてた巡検を企画しています.また,ジュラ紀付加体を被覆すると考えられる上部ジュラ系海溝斜面堆積物の岩相・層序についても見学します.
見どころ
○三宝山帯の上部三畳系海洋島玄武岩,メガロドン石灰岩,遠洋性堆積岩(チャート.珪質ミクライト)
○三宝山帯の最上部ジュラ系泥質混在岩相
○秩父帯上部ジュラ系箙瀬層の石灰岩および泥質岩(海溝斜面堆積物)
○秩父帯の石炭系石灰岩,中部ジュラ系混在岩
巡検コース
8:00JR 鹿児島中央駅(集合)→人吉インターチェンジ→球泉洞→球磨村蔀→芦北町白木→球磨村神瀬→人吉インターチェンジ→ 17:00 鹿児島空港→ 18:00 鹿児島中央駅(解散)
球磨川「槍倒しの瀬」に露出する三宝山帯の上部三畳系石灰岩.三畳紀後期の厚歯二枚貝化石であるメガロドンが国内で初めて報告された露頭として有名である.
三宝山帯の枕状溶岩.枕状溶岩の間隙を充填するinterpillow limestoneからは,三畳紀後期のコノドント化石が産出する.
備考:8:00 鹿児島中央駅西口観光バス駐車場 集合、昼食付
ページtopに戻る
コース2 甑島列島に分布する上部白亜系姫浦層群の層序と化石および堆積環境
[9月16日(火)〜18日(木)2泊3日]
注)天候不順により, 予定通りに島に渡れない可能性(この場合は巡検中止),島から帰れない可能性もあります.参加者は日程に余裕を作っておいてください.
定員:12(9)名
地形図
(1/2.5万)中甑
案内者
小松俊文(熊本大)・三宅優佳( 熊本大)・真鍋 真(国立科学博)・平山 廉(早稲田大)・ 藪本美孝(北九州市立自然史・歴史博)・對比地孝亘(東京大)
魅力
甑島列島に分布する上部白亜系の姫浦層群は,露出が良く保存状態の良い化石を多産することで知られています.特に下甑島北部では,カンパニアン階下部〜中部を示すイノセラムスやアンモナイト,放散虫化石が産出しています.さらに周辺の露頭では,近年になって恐竜やワニ,カメなどを含む陸生の脊椎動物化石も見つかっています.また土石流堆積物やスランプ堆積物などの重力流堆積物や波浪堆積物,カキ礁を伴う潮汐堆積物などが海岸沿いに露出しており,美しい堆積構造を観察することができます.
見どころ
○陸棚斜面堆積物と土石流堆積物中の化石の産状.
○カキ礁や貝殻密集層と非海成堆積物.
○鹿島支所内の地質・化石展示室(甑島の姫浦層群から産出した軟体動物化石や脊椎動物化石等を見学).
○波浪堆積物と海生軟体動物化石.
○下部〜中部カンパニアン階の層序.
○陸棚堆積物と海生軟体動物化石.
*天候が良ければ船上からの断崖見学や露頭観察を実施する予定.
巡検コース
[1日目]10:20 串木野港集合(フェリー乗船)→上甑島里港→中甑島平 良→上甑島里港(フェリー乗船)→下甑島長浜港→下甑島鹿島町藺牟田(泊)
[2日目]下甑島鹿島町藺牟田→鹿島町熊ヶ瀬周辺→鹿島支所(地質・化石展示室)→鹿島町夜萩円山周辺→鹿島町円山北側海岸周辺→鹿島町中山周辺→下甑島鹿島町藺牟田(泊)
[3日目]7:50 下甑島鹿島町藺牟田→鹿島港(フェリー乗船)→ 10:30 串木野港解散
下甑島北西部の鹿島断崖(夜萩円山)を形成する姫浦層群の砂岩や泥岩.砂岩には大規模な斜交層理やハンモック状斜交層理が発達.
夜萩円山産のイノセラムス.下甑島の姫浦層群からは,白亜紀後期の二枚貝や巻貝,アンモナイト,ウニなどの海生動物化石が多産.
備考:10:20串木野港のフェリー乗り場待合室 集合.
昼食付.朝・夕食代として現地で5,000円程度を別途徴収します
ページtopに戻る
コース3 日南海岸沿いの深海相と重力流堆積物
[9月16日(火)〜17日(水)1泊2日]
定員:20(10)名
地形図
(1/2.5万)油津,田野,日向青島,郷之原
案内者
石原与四郎(福岡大)・高清水康博(新潟大)・松本 弾(産総研)・宮田雄一郎(山口大)
魅力
宮崎県の日南海岸沿いには,古第三系〜新第三系の深海相がよく露出します.日南市の猪崎で見られる,古第三系日南層群のオリストリスのタービダイトにはソールマークや生痕化石,様々な液状化・流動化構造がよく発達します.日南層群を不整合で覆う宮崎層群のうち"宮崎相"は狭い陸棚をもつ斜面上に形成されたファンデルタシステムで,相対的海水準の変動と対応した堆積相の分布を示します.一方"青島相"は海岸沿いによく露出し,特異な重力流堆積物を多く含む"タービダイト"サクセッションからなります.そして一部にはイベント堆積物である厚層理砂岩層も挟在します.本巡検では,これらの深海相・タービダイトサクセッションをめぐり,様々な重力流堆積物やそれらが構成する地層を見学します.
見どころ
○日南層群(猪崎鼻)(チャネル・レビーシステム,ソールマーク,液状化・流動化構造)
○深海津波堆積物
○宮崎層群宮崎相(海底谷内の粗粒堆積相等)
○宮崎層群青島相(ファンデルタ沖合相のタービダイトサクセッションと特異な重力流堆積物)
巡検コース
[1日目]鹿児島市→日南市猪崎(日南層群タービダイト: チャネル・レビーシステム,ソールマーク,液状化・流動化構造)→日南市瀬平崎(深海津波堆積物)(宮崎市内泊)
[2日目]宮崎市内(宮崎相: 深海チャネル堆積相)→宮崎市内日南海岸(青島相: ファンデルタ沖合相)→宮崎空港(16:30)→鹿児島市(19:00)
日南層群のタービダイトの基底に見られるソールマーク.タービダイトには様々な液状化・流動化構造が発達するとともに,その基底には多様なソールマークや生痕が認められる.
宮崎層群青島層の連続性の良い"タービダイト"サクセッション.青島層の砂岩層は古流向に沿って連続性が良く,海岸に沿ってこれらの側方変化も見ることができる.中央やや上寄りは見学ポイントである巾着島.
備考:8:00 鹿児島中央駅西口 出発、昼食付
ページtopに戻る
コース4 桜島火山
[9月16日(火)日帰り]
定員:20(15)名
地形図
(1/2.5万)桜島北部,桜島南部,鹿児島北部,鹿児島南部
案内者
小林哲夫(鹿児島大)・佐々木寿(アジア航測)
魅力
本コースでは有村展望台で歴史時代の溶岩の表面地形の違いと平成火砕丘のスロープを遠望→長崎鼻の採石場にて天平宝字溶岩(764年)とそれを覆う歴史時代の降下軽石層を観察→地獄河原の火山麓扇状地の観察→黒神の埋没鳥居→園山にて安永諸島を遠望→湯之平展望台で大正溶岩原(西側)の遠望→大正溶岩の露頭観察,を予定しています.
見どころ
○有村展望台で歴史時代の溶岩の表面地形の違いと平成火砕丘のスロープを遠望
○長崎鼻の採石場にて天平宝字溶岩(764年)とそれを覆う歴史時代の降下軽石層
○地獄河原の火山麓扇状地と平成火砕丘
○大正噴火(1914年)で埋没した黒神の鳥居
○安永諸島
○湯之平展望台で大正溶岩原(西側)の遠望
○大正溶岩の露頭観察
巡検コース
鹿児島中央駅西口(8:00)→有村展望台(東側大正溶岩の遠望)→採石場→地獄河原→(昼食)→安永諸島の遠望→湯之平展望台→西側大正溶岩→鹿児島中央駅(17:30 解散)
左:有村展望台から見た南岳.右肩に昭和火口からの噴煙,松の茂った正面奥には昭和溶岩(1946年)の急崖が連なっているのが見える.右:湯之平展望台からの眺め.手前の斜面の全域が大正溶岩の分布域.道路脇の褐色部分は溶岩堤防の斜面で,その裏側に湯之平火口が存在した.
備考:8:00 鹿児島中央駅西口バスターミナル(集合)、昼食付
ページtopに戻る
コース5 九州中西部地域の変成岩類:黒瀬川構造帯・肥後変成帯・木山変成岩
[9月16日(火)〜17日(水):1泊2日]
定員:20(10)名
地形図
(1/2.5万)計石,鏡,柿迫,宮園,甲佐,松橋,大矢野原
案内者
小山内康人・中野伸彦・吉本 紋(九州大学)・亀井淳志(島根大)
魅力
九州中西部に点在する変成岩分布地域の中で,西南日本外帯に位置する黒瀬川構造帯と同内帯に位置する肥後変成帯の各種変成岩類、および木山変成岩を訪ねる.黒瀬川構造帯では,蛇紋岩メランジュ中にブロックとして産する高圧変成岩類(カンブリア紀の海洋地殻起源とみなされる青色片岩,ヒスイ輝石—藍閃石変ハンレイ岩など)と高温変成岩類(オルドビス紀の活動的大陸縁における火山弧火成活動に由来するザクロ石—単斜輝石グラニュライト,ザクロ石角閃岩など)を見学する.緑色片岩相からグラニュライト相にいたる一連の地殻断面を示す肥後変成帯では,部分溶融現象を伴う泥質グラニュライトや過アルミナ質のサフィリングラニュライトなど,ペルム紀末の変成作用を受けた下部地殻(一部は白亜紀の重複変成作用)を見学する.また,木山変成岩では,石炭紀の高圧変成岩(青色片岩)を見学する.これらを通して,日本列島形成に関する古生代テクトニクスについて現地討論する.
見どころ
○黒瀬川構造帯(蛇紋岩中にブロックとして産するザクロ石−単斜輝石グラニュライトやザクロ石角閃岩等の高温型変成岩類およびヒスイ輝石藍閃石岩や青色片岩等の高圧型変成岩類)
○肥後変成帯(ザクロ石菫青石片麻岩やサフィリングラニュライト等の高温型変成岩類)
○木山変成岩(青色片岩等の高圧低温型変成岩類)
巡検コース
[1日目] 鹿児島中央駅西口(8:30)→芦北町坪木の鼻(黒瀬川構造帯・ザクロ石グラニュライト等)→八代市泉(黒瀬川構造帯・ヒスイ輝石藍閃石岩等)→五木村(黒瀬川構造帯・青色片岩等)→山都町目丸(17:00 頃着・泊)
[2日目] 山都町目丸(8:30 発)→宇城市小川町田平(肥後変成帯・ザクロ石菫青石片麻岩等)→松橋町内田(肥後変成帯・サフィリングラニュライト等)→益城町下陳(木山変成岩・青色片岩等)→熊本駅(16:00 頃解散)
黒瀬川構造帯・坪木の鼻海岸の高温変成岩露頭.ハンレイ岩起源のザクロ石角閃岩,ザクロ石単斜輝石グラニュライトのほか,珪長質片麻岩が広範囲に分布する.八代海をはさんで,遠景は天草諸島.
肥後変成帯・松橋町内田のサフィリングラニュライト.主要な構成鉱物はサフィリン,コランダム,スピネル,菫青石であり,フロゴパイト,An成分に富む斜長石を含む.疣状に突出する鉱物は自形性の強いコランダム.
備考:8:30 鹿児島中央駅西口バスターミナル付近 集合
1日目の昼食は,各自ご持参ください.
宿泊代,ガソリン代として,現地で15,000円を別途徴収します.
ページtopに戻る
コース6 世界遺産の島・屋久島の地質と成り立ち
[9月16日(火)〜17日(水):1泊2日]
注)天候不順により, 予定通りに島に渡れない可能性(この場合は巡検中止),島から帰れない可能性もあります. 参加者は日程に余裕を作っておいてください.
定員:20(14)名
地形図
(1/2.5万)宮之浦岳,屋久宮之浦,永田岳,栗生,尾之間,安房,一湊
案内者
安間 了(筑波大)・山本由弦(JAMSTEC)・下司信夫・七山 太(産総研)・中川正二郎(屋久島地学同好会)
魅力
世界遺産にも指定された洋上アルプス、屋久島。その生物多様性を支える屋久島花崗岩がどのように貫入したのか、正長石巨晶の配列、母岩の四万十層群の変形や接触変成作用の観察を通して考えましょう。四万十層群の堆積物や枕状溶岩の産状、圧密や変形構造の発達、地震による液状化構造などを観察し、付加体が発達する過程を理解します。喜界カルデラの噴火に伴う段丘堆積物の液状化構造などを観察し、第三紀と現世に発達した構造を対照します。
見どころ
○正長石の巨晶を含む屋久島花崗岩主岩相と花崗岩類のバリエーション
○四万十層群の構造と枕状溶岩の産状
○堆積性メランジュと造構性メランジュの対比
○幸屋火砕流堆積物と段丘堆積物に見られる液状化構造
巡検コース
[1日目]7:20 鹿児島港集合→7:45 鹿児島港出発(トッピー112 便)→9:45 宮之浦港到着→宮之浦の生痕化石→白谷雲水峡 (昼食: 弁当)→宮之浦川右岸の火砕流露頭→楠川の砂岩脈とデュープレクス→小瀬田のメランジュ→宮之浦泊.
[2日目]永田いなか浜の屋久島花崗岩と含菫青石花崗岩→大川の滝と接触変成作用→千尋之滝と屋久島花崗岩(昼食)→安房の噴礫→田代の枕状溶岩→ 落之川の石英斑岩→空港で解散(16:30)
永田浜付近の花崗岩露頭.
屋久島花崗岩と正長石の巨晶.
落之川河口付近に見られる石英斑岩の大岩脈.
デュープレクス状の構造を示す砂岩脈.
備考:7:20 鹿児島本港南埠頭高速船(トッピー)乗り場 集合,三食付.
屋久島からの帰路は各自の負担となります.
ページtopに戻る
コース7 南九州, 鹿児島リフトの第四系
[9月16日(火):日帰り]
定員:24(15)名
地形図
(1/2.5万)脇元,国分,日当山
案内者
内村公大・鹿野和彦(鹿児島大総研博)・大木公彦(鹿児島大名誉教授)
魅力
鹿児島リフトは,島原の雲仙地溝から沖縄トラフへと断続的に島弧方向に配列する複数の沈降域のひとつです.このリフトとその周辺は,リフティングを続けている地域にも関わらず,鹿児島湾奥にあってマグマが集積し隆起している姶良カルデラ縁でリフトを充てんする火砕流堆積物と湖沼成堆積物,内湾〜浅海堆積物を観察することができます.この巡検では,これらが鹿児島リフトのリフティングと火山活動,そして海水準変動とが連関したプロセスの中で形成されたことを裏付けるサクセッションを観察します.
見どころ
○0.5 Ma以降の温暖期に形成された浅海堆積物(吉田貝層).フジツボ化石と海棲貝化石,それらの破片が密集し,その中に安山岩やデイサイトの岩片,軽石火山礫が散在する.
○1.0〜0.5 Maの内湾〜浅海成堆積物(国分層群)と,その中にあって火山ガラス片が異常に厚く集積した細粒凝灰岩(麓凝灰岩).
○桜島起源の9.5 kaのSz-13(P-11)層準下から発掘された上野原遺跡での昼食.
○複数のフローユニットからなる入戸火砕流堆積物の大露頭.
○阿多火砕流堆積物から岩戸テフラ(岩戸2,7,8,9),大塚テフラ,深港テフラ,毛梨野テフラ,大隅降下軽石,妻屋火砕流堆積物,亀割坂角礫層と入戸火砕流堆積物に至る一連のテフラサクセッション.
巡検コース
鹿児島中央駅西口(集合)8:00 →8:30 鹿児島市西佐多町西中ガイアテック吉田工場9:30 → 10:00 鹿児島市東佐多町麓柏原白土採掘場11:00 → 11:30 霧島市国分上野原縄文の森( 昼食)12:30 → 13:00霧島市国分川原岩崎建材採掘場13:30 → 14:00 霧島市国分重久岩戸15:30 →鹿児島中央駅16:30(解散)
(A)波状〜低角度に斜交成層した吉田貝層,(B)吉田貝層中の貝殻片,安山岩・デイサイト角礫と軽石火山礫の接写(鹿児島市西佐多町西中).
岩戸テフラ(Iwt-7,8,9),岩戸テフラの古土壌面を凹状に侵食して覆う大塚テフラとその上位のテフラ,古土壌のリップアップクラストを含む(霧島市国分重久岩戸).
備考:8:00 鹿児島中央駅西口バスターミナル 集合,弁当配布
ページtopに戻る
コース8 2011年新燃岳噴火と霧島ジオパーク
[9月13日(土):日帰り]※会期中巡検
定員:40(20)名
地形図
(1/2.5万)日向小林,高千穂峰,韓国岳,霧島温泉
案内者
井村隆介(鹿児島大)・石川 徹(霧島市)
魅力
霧島山は,南九州の鹿児島・宮崎の県境に位置する,第四紀の複成火山です.本コースでは,2010年に日本ジオパークネットワークに登録された霧島ジオパークのジオサイトを巡りながら,霧島山の噴火史や2011年1月に始まった新燃岳(しんもえだけ)噴火について紹介します.巡検では,まず,麓から霧島火山全体の地形や生い立ちを学び,その後,高千穂河原(たかちほがわら)や新湯(しんゆ)付近にて,2011年の噴出物や噴火による地形の変化などを観察する予定です.噴出物に覆われた地域の植生回復の様子も見どころのひとつです.
見どころ
2011年新燃岳噴火による堆積物観察、霧島火山の噴火史・地形の学習、霧島ジオパークのジオサイト,拠点施設見学
巡検コース
鹿児島市(8:30 集合)→高千穂牧場(10:00) → 霧島神宮(11:00)→高千穂河原(12:00)→新湯展望台(14:00)→えびの高原(14:30)→鹿児島市(17:00)
2011年1月26日16時22分頃の準プリニー式噴火の様子.新燃岳の南約7.5kmから撮影.噴煙の高さは7,500mに達した.
新湯温泉付近から見た新燃岳(a: 噴火前2009.05.25撮影,b: 噴火後2013.04.22撮影).
備考:8:30 鹿児島中央駅西口バスターミナル 集合、昼食付
小中高の教員ならびに一般市民を優先
学会補助事業
ページtopに戻る
巡検TOP
巡 検 TOP
◆
巡検コース一覧/各コースのみどころ
◆
巡検申込 (受付終了しました)
◆
巡検へ参加される方へ 重要
その他
緊急展示について
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,会場内に,災害調査報告や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コーナー」を設ける予定です.
会場:第2体育館ポスター会場
問い合わせ先:行事委員会(main@geosociety.jp)
担当:山本啓司(鹿児島大会実行委員会)・須藤 宏(行事委員会)
鹿児島大会に関連したプレス発表
鹿児島大会での注目すべき学術発表や行事について,9月上旬にプレス発表を行う予定です.例年多数のメディアに取り上げられ,会員の研究成果が大いに注目されています.プレス内容は,発表後学会ホームページに掲載いたします.
鹿児島市内の宿泊施設に宿泊される方へ
鹿児島市内の宿泊施設への宿泊者数に応じて,鹿児島観光コンベンション協会より助成金が支給されることになっています.鹿児島市内に宿泊される方は,年会の総合受付にて宿泊施設への提出書類をお渡しいたしますので,必要事項を記入の上,宿泊施設へ必ずご提出下さい.ご協力をお願い致します.
懇親会について
日時:2014年9月13日(土)18:30〜20:00
会場:鹿児島大学学習交流プラザ
原則として予約制です(予約は8月19 日(火)に締め切りました).人数に余裕があれば当日参加の申込みも可能です.会場受付で確認し,当日参加の申込みをしてください.その場合の会費は,正会員・非会員(一般)6,000 円,名誉会員・50 年会員・院生割引会費適用正会員・学部割引適用正会員および会員の家族は3,500 円です.非会員の会費は正会員に準じます.
懇親会・弁当
懇親会
<申込締切 オンライン:8月19日(火)18:00,FAX・郵送:8月15日(金)必着>
■ 事前参加登録:受付終了しました ■
懇親会は,9月13日(土)受賞講演会終了後,大学内で行います(18:30頃から2時間程度を予定).
事前予約会費
正会員
5,000円
名誉会員・50年会員・院生割引・学部割引・会員の家族
2,500円
非会員の会費は会員に準じます.準備の都合上,前金制の予約参加とします.たくさんの方々,特に院生・学生などの若手会員のご参加をお待ちしております.余裕があれば当日参加も可能ですが,予定数に達し次第締切ります.当日会費は1,000円高くなります.
予約申込は,大会参加申込と合わせて8月19日(火)までにお申し込み下さい.当日はクーポンを受付にご持参いただきます.参加取消の場合でも懇親会費の返却はいたしませんのでご了承下さい.
○懇親会申込・問い合わせ ▶▶▶ WEB参加登録 または FAX・e-mailにて『学会事務局』へ
お弁当予約販売
<申込締切 オンライン:8月19日(火)18:00,FAX・郵送:8月15日(金)必着>
■ 事前参加登録:受付終了しました ■
9月13日(土)〜9月15日(月)には昼食用の弁当販売をいたします(1個700円,お茶付き).大会参加申込と合わせて,お申し込み下さい.お弁当利用日より9日前〜前日までは50%,当日は100%の取消料がかかります.会場近隣のコンビニエンスストアは徒歩数分のエリアに複数あります.
Tsunami Symposium, Excursion
Tsunami Hazards and Risks, JGS-GSL International Symposium, Excursion:
Traces of paleo-earthquakes and tsunamis along the eastern Nankai Trough and Sagami Trough, Pacific coast of central Japan
Date 16-18 September 2014
[Excursion details]
Sep. 16
8:00 Leave Kagoshima-chuo Station (travel by Shinkansen Mizuho)
11:44 Arrive at Shin-Osaka Station
11:53 Leave Shin-Osaka Station (travel by Shinkansen Kodama)
13:47 Arrive at Hamamatsu Station
14:20 Leave Hamamatsu Station (travel by charter bus)
→ overnight in Hamamatsu
Sep. 17
8:30 Leave Hamamatsu (travel by charter bus)
16:20 Arive at Shizuoka Station
16:48 Leave Shizuoka Station
18:17 Arrive at Tokyo Station, overnight in Tokyo
Sep. 18
8:30 Leave Tokyo Station (travel by charter bus)
10:30 Arrive at Tateyama → Stops 10–14
15:00 Leave Tateyama
17:20 Arrive at Narita Airport (finish of field trip)
1: 25,000-scale topographic maps
Araimachi, Hamamatsu, Iwata, Fukuroi, Kakezuka, Omaezaki, Tateyama, Mera, Shirahama, Chikura.
Corresponding author,
Osamu. Fujiwara,<o.fujiwara[@]aist.go.jp>
Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST),
共催・協賛団体の一覧
2014鹿児島大会:巡検協賛およびセッション共催団体一覧
巡検協賛団体
セッション共催団体/セッション番号
・資源地質学会
・石油技術協会
・地学団体研究会
・特定非営利活動法人日本火山学会
・日本活断層学会
・日本鉱物科学会
・日本古生物学会
・日本自然災害学会
・日本堆積学会
・日本第四紀学会
・日本地球化学会
・公益社団法人日本地球惑星科学連合
・一般社団法人日本応用地質学会
・日本地学教育学会
・公益社団法人東京地学協会
・日本古生物学会/S1
・ロンドン地質学会/S2
・日本情報地質学会/T6
・日本掘削科学コンソーシアム(J-DESC)/T8
・海洋研究開発機構海洋掘削科学研究開発センター/T8
・日本堆積学会/R9,R10,R11,R12
・石油技術協会探鉱技術委員会/R9,R10,R11,R12
・日本有機地球化学会/R9,R10,R11,R12
・地質汚染−医療地質−社会地質学会/R19
・日本原子力学会バックエンド部会/R24
参加登録TOP画面に戻る
講演情報TOP
講演関連
講演申込・講演要旨投稿
受付終了
★注意★講演申込を予定しているが,まだ入会手続きをされていない方へ
▶講演申込要領・発表要領
▶シンポジウム一覧
▶セッション一覧
▶招待講演者一覧
---------------------------------------------------------------------------------
▶講演要旨原稿について
▶▶講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理,引用方法,校閲について
▶▶講演要旨の作成の注意点とPDFファイル作成の作り方
▶▶講演要旨オンライン投稿手順チェックシート
▶▶保証・同意書(2014鹿児島)
▶講演申込書 書式(郵送で申し込む場合)[PDF]
申込要領・発表要領
セッション・講演の申込要領・発表要領
講演申込・講演要旨投稿
受付終了
■シンポジウム一覧はこちら■
■セッション一覧はこちら■
募集要領
注:シンポジウムに関しては、シンポジウムのページを参照して下さい。
セッション発表を下記要領で募集します.オンラインでの演題登録・要旨投稿にご協力下さい.やむを得ず郵送で申し込む場合は郵送用発表申込書(PDF)に必要事項を記入の上,返信用ハガキ(自分宛),保証書・同意書,要旨とともに6月25日(水)必着で行事委員会宛にお送り下さい.発表セッションや会場・発表日時等は行事委員会が決定します.発表セッションや日時等を7月下旬以降に通知します.
(1)セッションについて
今大会では9件のトピックセッションと25件のレギュラーセッション,およびアウトリーチセッションを用意します(セッション再編についてはこちら.各セッションの詳細についてはこちらをご覧下さい.).
(2)発表に関する条件・制約
1)会員は全35セッションのうち1つまたは複数(下記)に発表を申し込めます.発表申込者=発表者とします.非会員は発表を申し込めません.発表を希望する非会員は6月25日(水)までに入会手続きをして下さい(入会申込書が届くまで発表申込を受理しません).共催団体の会員は共催セッションへの発表申込が可能です.
2)口頭発表あるいはポスター発表を1人1題申し込めます.ただし,発表負担金(1,500円)を支払うことでもう1題(最大2題)の申し込みが可能です.この場合,同一セッションに2題申し込むことも,異なる2つのセッションに1題ずつ申し込むこともできますが,同一セッションに口頭を2題またはポスターを2題申し込むことはできません(招待講演にも適用).同一セッションに2題申し込む場合は口頭1題とポスター1題になります.ただし,これらの制約はアウトリーチセッションには適用しません(後述).
セッションA:口頭2件…………………………………………………×(申込不可)
セッションA:ポスター2件……………………………………………×(申込不可)
セッションA:口頭,ポスター各1件ずつ……………………………○(申込可)
セッションA:口頭1件,セッションB:口頭1件…………………○(申込可)
セッションA:ポスター1件,セッションB:ポスター1件………○(申込可)
3)共同発表(複数著者による発表)の場合は,上記「1人1題,ただし発表負担金支払いによりもう1題可」の制約を発表者(=発表申込者)に対して適用します.その際,発表者は筆頭でなくても構いません(筆頭者に会員・非会員等の条件はありません).講演要旨では,発表者氏名を下線(アンダーライン)表示にして下さい.
(3)アウトリーチセッション
このセッションは,会員による研究成果の社会への発信(アウトリーチ)を学会として力強くサポートするために,前回大会に引き続き,トピック・レギュラーと並ぶ第三のカテゴリーとして設けられているものです.市民に対するアウトリーチ活動に関心のある会員はぜひお申し込み下さい.
1)トピック・レギュラーと同様の演題登録・要旨投稿が必要です.要旨校閲(後述)もトピック・レギュラーと同様に行います.要旨は講演要旨集に収録され,正式な学会発表扱いになります.
2)本セッションの発表には,上記の発表数に関するルール(1人1題,ただし発表負担金を支払えばもう1題可)を適用しません.例えば,レギュラーセッションで1題発表する会員がアウトリーチセッションでも発表する場合,発表負担金はかかりません.ただし,同一発表者(=発表申込者)が本セッションで発表できるのは1題のみとします.
3)ポスター発表のみとし,13日(土)の市民講演会会場で実施する予定です.市民講演会の前後各1時間をポスターコアタイムとします.
4)市民には講演要旨のコピーを配布しますが,これとは別に資料を独自に配布していただいても構いません(ただし発表者負担).
5)公開シンポジウムの参加市民も見られるように,ポスターを9/15(日)から掲示できます.
6)スペース等の都合から,募集件数は10件程度とします.募集件数を上回る応募があった場合は行事委員会が採否を検討します.
7)優秀ポスター賞の選考対象になります
(4)招待講演
招待講演者を「セッション一覧」および「セッション招待講演の紹介」に示しました.招待講演も期日までに一般発表と同様に演題登録・要旨投稿が必要です.非会員招待講演者の場合は世話人が取りまとめてオンライン入力することも可能です(詳細は学会事務局にお問い合わせ下さい).非会員招待講演者に限り参加登録費を免除します(講演要旨集は付きません).また,招待講演は発表負担金の枠外として扱います(詳細はこちらを参照).
(5)発表申込方法
1)オンライン申込は大会ホームページにアクセスし,オンライン入力フォームに従って入力して下さい.
2)発表方法は「口頭」「ポスター」「どちらでもよい」のいずれかを選択して下さい(アウトリーチセッションはポスターのみ).締切後の変更はできません.会場の都合のため,発表方法(口頭/ポスター)の変更をお願いすることがあります.
3)発表題目と発表者氏名は,登録フォームと講演要旨の両方を一致させて下さい.
4)共同発表の場合は全員の氏名を明記し,講演要旨では発表者氏名を下線(アンダーライン)表示にして下さい.
5)発表希望セッションを必ず第2希望まで選んで下さい.
6)関係する一連の発表があるときは,必要に応じて発表順希望等をコメント欄に入力して下さい(ご希望に沿えない場合があります).
(6)講演要旨の投稿
講演要旨はA4判1枚とし(フォーマット参照),PDFファイルのオンライン投稿により受け付けます.印刷仕上がりは0.5ページ分です(1ページに2件分を印刷).原稿をそのまま版下とし,70%程度に縮小印刷します.文字サイズ,字詰め,鮮明度等に注意して下さい.やむを得ず郵送する場合は,オリジナルか鮮明なコピーを1枚郵送して下さい.FAXやe-mailでの投稿は受け付けません.
発表要領(シンポジウムについてはこちら)
(1)口頭発表
1)セッションの発表時間は,招待講演を除き,トピック・レギュラーとも1題15分です(討論時間3〜5分を含む).発表者は討論時間を必ず確保して下さい.なお,前回(仙台大会)に引き続き,今大会でもPCセンターを設置しません.セッションが円滑に進むように次の注意点をよくご確認下さい.
2)発表はできるだけ会場備え付けのWindowsパソコン(OSはWindows 7;PowerPoint 2003, 2007, 2010対応)をご使用下さい(ただし,Macご利用の方と動画を使用する方はご自身のパソコンをご用意下さい).プロジェクター解像度は1024×768ドット(XGA)です.パワーポイント・ファイルをUSBフラッシュメモリで持参し,パソコンにコピーして下さい(セッション終了後,世話人がファイルを削除します).フォントは特殊なものではなく,PowerPointに設定されている標準的なものを使用して下さい.発表者は,セッション開始前に発表会場でで正常に投影されることを確認して下さい.
3)ご自身のパソコンで発表する方は,セッション開始前に発表会場において正常に接続・投影されることを確認して下さい.事前に解像度(上記)の設定をご確認下さい.会場の接続端子はD-sub15ピン(ミニ)です.パソコンによってはコネクタが必要になる場合がありますので必ずご持参下さい(会場にはありません).確認作業の混雑とそれによるセッション開始の遅れを防ぐため,早めの確認作業をお願いします.なお,発表者が事前確認を怠ったために発表時にトラブルが生じても時間延長等の措置は取りません.
(2)ポスター発表
1)1日間掲示できます.コアタイムでは必ずポスターの説明を行って下さい.ポスター設置・撤去等について,8月にお知らせします。
2)ボード面積は1題あたり縦210 cm,横120 cmです.
3)発表番号,発表タイトル,発表者名をポスターに明記して下さい.
4)コンピューターによる演示等も許可しますが,機材等はすべて発表者が準備して下さい.また,電源は確保できませんので,必要であれば予備のバッテリーを用意して下さい.発表申込の際に機器使用の有無や小机の必要性等をコメント欄に記入し,事前に世話人にご相談下さい.
5)運営規則第16条2項(8)により,優れたポスター発表に対して「日本地質学会優秀ポスター賞」を授与します.詳細は,8月にお知らせします。
(3)発表者の変更
あらかじめ連記されている共同発表者内での変更は認めますが,必ず事前に行事委員会に連絡して下さい.この場合も発表者については上記の「発表に関する条件・制約」(2)の条件を適用します.
(4)口頭発表の座長依頼
各会場の座長を発表者に依頼することがあります.その際はご協力をお願いします.
シンポジウム一覧
シンポジウム
講演申込・講演要旨投稿
受付終了
今大会では2件のシンポジウムを開催します. 世話人は会員・非会員を問わず招待講演を依頼できます(締め切りました).非会員招待講演者に限り参加登録費を免除します (講演要旨集は付きません).発表時間は世話人が決定します.シンポジウム発表にはセッション発表における1人1件の制約 が及びません(くわしくはこちら)ので,シンポジウムで発表する会員は別途セッションにも発表を申し込めます.
講演要旨はセッション発表と同じ様式・分量です.フォーマットを参照して要旨を作成して下さい.やむを得ず要旨 を郵送する場合は郵送用の発表申込書をご利用下さい.「シンポジウム」と書き添え,必要事項を記入し,返信用ハガキ(自分 宛),保証書・同意書,要旨とともに6月25日(水)必着で行事委員会宛にお送り下さい.
*各タイトルをクリックすると、詳細をご覧いただけます
シンポジウム
S1.九州が大陸だった頃の生物と環境(一般公開シンポジウム)
S2.津波ハザードとリスク:地質記録の活用(国際シンポジウム)
*印は代表世話人(連絡責任者)です.
S1.九州が大陸だった頃の生物と環境(一般公開シンポジウム)[共催:日本古生物学会]
Biology and environments of Kyushu Island when it was linked to the Eurasian continent
仲谷英夫*(鹿児島大:nakaya@sci.kagoshima-u.ac.jp)
Hideo Nakaya* (Kagoshima Univ.)
近年,九州からは古第三紀の哺乳類や白亜紀の恐竜化石が多く発見され,九州のみならず全国的にも注目をあびているが,白亜紀から新第三紀前半の九州を中心とする西南日本がユーラシア大陸の一部であった時代における陸上生物相の変遷や,当時の九州の古地理的な位置づけについては十分な研究が行われているとはいいがたい.
本シンポジウムでは,九州を中心にした西南日本における白亜紀の恐竜化石,白亜紀〜新第三紀前半の爬虫類化石(カメ),古第三紀哺乳類化石(初期有蹄類),新第三紀哺乳類化石(ゾウ),古第三紀大型植物化石など,陸上生物相の変化と地質環境について,最近の研究成果を総括する.また,ユーラシア大陸の生物相との比較から九州を中心とした西南日本の古生物地理的な位置づけについても考察する.
【講演予定者】對比地孝亘(東京大)・平山 廉(早稲田大)・宮田和周(福井県立恐竜博)・三枝春生(兵庫県立人と自然の博・兵庫県立大)・矢部 淳(国立科博)・斎藤 眞(産総研)
S2.津波ハザードとリスク:地質記録の活用(国際シンポジウム)[共催:ロンドン地質学会]
Tsunami hazards and risks: using the geological record
後藤和久*(東北大:goto@irides.tohoku.ac.jp)・藤原 治(産総研)・藤野滋弘(筑波大)
Kazuhisa Goto* (Tohoku Univ.), Osamu Fujiwara (AIST), Shigehiro Fujino (Tsukuba Univ.)
過去の津波現象の実態を解明することは,将来の津波リスク評価を適切に行うために極めて重要である.特に,先史時代にまで遡って津波の履歴や規模を明らかにするためには,津波堆積物などの地質学的記録を活用する必要がある.しかし,津波堆積物の認定基準やリスク評価への活用方法,非地震性津波の特徴など,今後の研究の進展が望まれる課題も多い.本シンポジウムは,ロンドン地質学会との共催で国内外の著名な津波研究者を招き,地質学的な津波研究の現状と課題に加え,津波リスク評価への活用方法を議論する.
Understanding past tsunami events is critically important for future tsunami risk assessment. Studies of the geological record play an indispensible role in developing our understanding of the recurrence interval and magnitude of prehistoric tsunamis. However, there are many issues in this field that remain unresolved. Important examples are: establishing reliable identification criteria of tsunami deposits and developing a clearer understanding of how to make use of such deposits for risk assessment. It is also important to consider how to distinguish tsunamis generated by non-seismic hazards. This is the first of a twin set of symposia organized by Geological Societies of Japan and London. A group of leading experts in the field have been invited with the aim of discussing the current state of the art including an assessment of problems presented by geological studies of tsunami and the role of these studies in future tsunami risk assessment.
【講演予定者】馬場俊孝(海洋研究開発機構)・Catherine Chague-Goff(New South Wales Univ.)・Simon Day(Univ. College London)・藤野滋弘(筑波大)・藤原 治(産総研)・後藤和久(東北大)・Jim Hansom(Univ. Glasgow)・原田賢治(静岡大)・市原季彦(復建設計)・西村裕一(北海道大)・佐竹健治(東京大)・澤井祐紀(産総研)・菅原大助(東北大)・David Tappin(British Geol. Survey)
※ 本シンポジウムはグレイト・ブリテン・ササカワ財団(The Great Britain Sasakawa Foundation)からの助成を受けて開催します.
会期後(9/16〜18)に関連巡検を実施します.▶▶▶ 詳しくはこちら.
↑このページのTOPに戻る
セッション一覧
セッション一覧
講演申込・講演要旨投稿:受付終了
*下記をクリックすると、各セッションの詳細がご覧頂けます。
トピックセッション(9件)
T1.火山島弧の造山運動:沈み込み,付加,衝突およびリサイクリング
T2.文化地質学
T3.グリーンタフ・ルネサンス
T4.砕屑性ジルコン年代学:その未来とさらなる応用
T5.ポスト冥王代研究
T6.三次元地質モデル研究の新展開
T7.古生代から中生代への地球環境進化
T8.超深度掘削による新次元の地球科学
T9.平野地質
レギュラーセッション(25件)
R1.深成岩・火山岩とマグマプロセス
R2.岩石・鉱物・鉱床学一般
R3.噴火・火山発達史と噴出物
R4.変成岩とテクトニクス
R5.地域地質・地域層序
R6.ジオパーク
R7.地域間層序対比と年代層序スケール
R8.海洋地質
R9.堆積物(岩)の起源・組織・組成
R10.炭酸塩岩の起源と地球環境
R11.堆積相・堆積過程
R12.石油・石炭地質学と有機地球化学
R13.岩石・鉱物の変形と反応
R14.沈み込み帯・陸上付加体
R15.テクトニクス
R16.古生物
R17.ジュラ系+
R18.情報地質とその利活用
R19.環境地質
R20.応用地質学一般およびノンテクトニック構造
R21.地学教育・地学史
R22.第四紀地質
R23.地球史
R24.原子力と地質科学
R25.鉱物資源と地球物質循環
アウトリーチセッション
OR.日本地質学会アウトリーチセッション
トピックセッション:9件
T1.火山島弧の造山運動:沈み込み,付加,衝突およびリサイクリング/Orogenic processes in island arcs: subduction, accretion, collision and recycling
Hafiz Ur Rehman*(鹿児島大:hafiz@sci.kagoshima-u.ac.jp)・岡本和明(埼玉大)
Hafiz Ur Rehman* (Kagoshima Univ.) and Kazuaki Okamoto (Saitama Univ.)
当セッションでは島弧の造山運動,沈み込み帯,付加体,大陸衝突およびそれらの物質のリサイクルについて論議・討論する.岩石および鉱物に取り残されている地質学的,物理的および地球化学的な情報をマルチアプローチで取り出し島弧の起源,沈み込み帯のメカニズム,付加体の作成,大陸衝突および海洋性島弧の衝突,そしてそれらの物質のリサイクルプロセスを明らかにする.
The session considers the processes involved with the formation of oceanic and continental island arcs, slabs subduction, accretion, collision of plates, and recycling of the subducting material into mantle. In this session we aim a multi-disciplinary approach to extract the information preserved in rocks and minerals via field, petrologic, textural, chemical and isotopic observations. The session also aims at exchanging ideas among geoscientists applying different approaches on problems related to the theme of this session.
【招待講演予定者】Bor-ming Jahn (National Taiwan Univ.)・丸山茂徳(東工大)→招待者の紹介はこちら
T2.文化地質学/Cultural geology
鈴木寿志*(大谷大:hsuzuki@res.otani.ac.jp)・一田昌宏(京都大博)
Hisashi Suzuki* (Otani Univ.) and Masahiro Ichida (Kyoto Univ. Mus.)
かつて地質学は石炭などの資源探査に必要な学問として発展してきた.しかし日本の炭鉱,鉱山が次々と閉山するにつれ,地質学の資源探査に対する社会の要請は低下していった.国土開発が盛んに行われた高度経済成長期には,土木地質学が発展した.近年では自然災害の被害軽減のために防災地質学への要請が強い.古今東西いずれの学問も純粋科学としての面をもつが,多くの学問分野は社会の要請に伴って発展してきた.そのような中,日本の地質学はどうだろうか.えてして学問のための学問になっていないだろうか.純粋科学を否定はしないが,これまで社会や人との関わりを絶った学問分野は衰退していった.
そこで本分科会では,かつての役割を終えつつある地質学に,新たな分野を提唱したい.「文化地質学」である.文化地質学は人類の文化・文明が,地質とどのように関わってきたかを研究する学問分野である.人類が地球上の生物である以上,そこに花開いた文化・文明は,必ず地球と関わりがある.それもほとんどは表層地質に依拠している.人々は大地の上に住み,土地を耕し,地質の上に歴史と文化を形作った.人々は地質を資源として利用し,さまざまな道具や機械を作製してきた.さらに人々は地質景観に魅せられ,国立・国定公園やジオパークを整備した.このようにみると,地質学は人類存在の根源に他ならない.地質学と文化・文明との関わりについて論じたすべての研究発表を歓迎する.
【招待講演予定者】長 秋雄(産総研)・原田憲一(シンクタンク京都自然史研)→招待者の紹介はこちら
T3.グリーンタフ・ルネサンス/Green Tuff renaissance
天野一男*(茨城大:kazuo@mx.ibaraki.ac.jp)・細井 淳(茨城大)・松原典孝(兵庫県立大)
Kazuo Amano* (Ibaraki Univ.), Jun Hosoi (Ibaraki Univ.) and Noritaka Matsubara (Univ. Hyogo)
グリーンタフは,新生代日本列島のテクトニクス,とりわけ島弧進化史考える上で極めて重要な地層である.従来グリーンタフの研究は層序を編むことを中心に進められ,1990年代前半に総括がなされた.この古典的な層序学的研究の総括を基づいて,プレートテクトニクスの概念により東北日本弧形成テクトニクスのモデルが提示されたが,その後新しい研究手法が導入されなかったことも一つの原因で,グリーンタフ研究は一気に下火となった.一方,国際的にはグリーンタフに類似した水中火山岩類の堆積学的研究は飛躍的に進展し,高解像度な研究が行われ成果を上げていた.また,近年グリーンタフの模式層序である男鹿半島の層序が大幅修正にされた.グリーンタフの総括的研究から20年以上経過した今こそ,新しい視点でグリーンタフを見直すことにより,新たな地平を開くことが可能と考える.本セッションでは,グリーンタフに関する層序学,地質学,構造地質学,岩石学,古地磁気学など様々な研究の口頭およびポスター発表を募集する.グリーンタフを様々な研究視点から再検討し,島弧進化史研究の新たな展開をめざすものである.
【招待講演予定者】鹿野和彦(鹿児島大)→招待者の紹介はこちら
▲ページtopに戻る
T4.砕屑性ジルコン年代学:その未来とさらなる応用/Detrital zircon chronology: its future and further applications
磯崎行雄*(東京大:isozaki@ea.c.u-tokyo.ac.jp)・山本伸次(東京大)
Yukio Isozaki* (Univ. Tokyo) and Shinji Yamamoto (Univ. Tokyo)
砂岩中に含まれる砕屑性ジルコンのU-Pb年代の大量測定が,威力抜群の新規研究手法として近年世界中で採用されている.その応用範囲は広大で,とくに古期地層について,有効な示準化石を産しない場合でもかなり正確な堆積年代を推定することが可能となり,従来の層序および年代論の改訂が不可避となっている.一方で,相対的に古い砕屑粒子に注目することでその由来から後背地の情報を取り出すことが可能となり,古地理復元についても従来では得られなかった重要な制限条件が明らかにされつつある.とくに同一の弧-海溝系をなす単一の造山帯の内部における,物質の移動経路の特定できるようになり,現実性の高い造山帯の大構造復元が可能となりつつある.その中で,従来見過ごされていた構造侵食の効果が明示され,また火山弧に関連した各種堆積盆地の発達・分化過程が議論出来るようになった.日本でもこれまでに,東アジアの近隣大陸塊との関連と日本列島の起源,付加体の成長と構造浸食などに関する多くの新知見がもたらされつつある.本セッションでは,日本列島をはじめとする太平洋型造山帯のみならず,世界各地における砕屑性ジルコン年代学の新しい成果を報告する.
【招待講演予定者】澤木祐介(東工大)→招待者の紹介はこちら
T5.ポスト冥王代研究/Studies on the post-Hadean
磯崎行雄*(東京大:isozaki@ea.c.u-tokyo.ac.jp)・堤 之恭(国立科博)
Yukio Isozaki* (Univ. Tokyo) and Yukiyasu Tsutsumi (National Mus. Nature and Sci.)
地球史最初期の冥王代(46−40億年前)に生命誕生の基本条件が整えられたことは疑いがない.しかし,その当時の地球の実態は未知である.現存する最古岩石は約42億年前のもので,冥王代に関する物質的証拠はごく稀である.世界中で35カ所ある冥王代直後の岩石分布域において,45億年前の原初大陸の破片(岩体,岩石,鉱物)が発見される可能性がある.特にジルコンは,後の高温高圧変成作用に対して抵抗性が強く,初生的情報を残しやすく,現時点で西オーストラリア・イルガルン地塊産の44億年前ジルコン粒が最古例である.月と同様の初期形成過程を経た初期地球にはアノーソサイト質の原初大陸が存在した可能性があり,惑星表層に巨大な大陸を胚胎したという点で,生命誕生を導いた地球史最初の6億年(冥王代)と大型生命が大繁栄した最後の6億年(顕生代)は共通点が多い.ほとんどが未知の冥王代の研究において,顕生代地質学の知識が有用である.一方,生命を胚胎した原初大陸は,後の時代の構造浸食によりマントル深部に沈み込み表層からは完全に消失した.しかし,現在のマントル深部には冥王代原初大陸地殻(Ca-ペロブスカイト)の残骸が溜まっていると予測される.地震波データをもとにその可視化が期待される.新しい視点にたって,従来と異なる研究分野の開拓を試みる.
【招待講演予定者】丸山茂徳(東工大)・土屋卓久(愛媛大)→招待者の紹介はこちら
T6.三次元地質モデル研究の新展開/Recent progress in three-dimensional geological modeling[共催:日本情報地質学会]
木村克己*(産総研:k.kimura@aist.go.jp)・升本眞二(大阪市大)・高野 修(石油資源開発)・根本達也(大阪市大)
Katsumi Kimura* (AIST), Shinji Masumoto (Osaka City Univ.), Osamu Takano (JAPEX) and Tatuya Nemoto (Osaka City Univ.)
三次元地質モデリングは,その応用的な有用性から世界各国で注目され,国内では,都市工学,地震防災,石油・資源分野などで研究・開発が進められている.昨年,地質学雑誌8月号にて「三次元地質モデル研究の新展開に向けて」と題する特集号が発行され,国内外の研究動向,三次元地質モデルの基本理念と地質構造の論理モデル,サーフェスモデルとボクセルモデルの構築方法とその実例,地球統計学的モデリングの概要とその実例,応用分野での活用事例について,研究紹介がなされた.しかし,この数年,航空・地上レーザーなどの三次元計測技術や地上・地下を含めた三次元情報の統合と可視化技術,地球統計学的モデリングなど,三次元地質モデリングの基盤となる研究・技術開発の進歩がめざましい.これらの技術開発を背景に,地震動や地下水広域流動の評価,石油資源探査を目的として,大スケールの地殻構造や海陸シームレスの三次元地質構造モデル,堆積や地質学的不確実性を反映させた地球統計学的モデル,浅部地盤の詳細な三次元モデルなどの具体的な三次元地質モデルの研究成果が発表されてきている.こうした最近の学際的な研究および技術開発の到達点も含めて,三次元地質モデリングに関する最新の研究動向・成果を集約し,今後の地質学的な研究課題を展望する場として本セッションを開催したい.
【招待講演予定者】守屋俊治(石油資源開発)・石原与四郎(福岡大)→招待者の紹介はこちら
▲ページtopに戻る
T7.古生代から中生代への地球環境進化/Environmental evolution across the Paleozoic–Mesozoic transition
尾上哲治*(熊本大:onoue@sci.kumamoto-u.ac.jp)・高橋 聡(東京大)・池田昌之(静岡大)・上松佐知子(筑波大)
Tetsuji Onoue* (Kumamoto Univ.), Satoshi Takahashi (Univ. Tokyo), Masayuki Ikeda (Shizuoka Univ.) and Sachiko Agematsu (Univ. Tsukuba)
史上最大の大量絶滅で特徴付けられる古生代/中生代境界においては,それまでの古生代型動物群に変わって,現代型の動物群が爆発的に進化・繁栄した時代として知られている.大きな絶滅事変が起きたペルム紀/三畳紀(P/T)境界の研究が進む一方で,この生態系の大変革は,ペルム紀中期のグアダルピアンローピンジアン(G/L)境界の絶滅事変からはじまり,三畳紀の気候変動と生物の爆発的進化,そして三畳紀/ジュラ紀(T/J)境界において再び起きた大量絶滅までの長い時間スケールでとらえる見方ができることが分かってきた.これらの絶滅や生物進化と背景になった環境原因については,大規模な火山活動や温暖化・寒冷化等との関連性が指摘されてきているが,不明な点も多い.本セッションでは,G/L境界,P/T境界およびT/J境界の大量絶滅事変や,大量絶滅後の生物群集の爆発的進化や環境回復過程に関する研究を中心に広く募集する.現在多くの研究者が上述の研究課題に取り組んでおり,一同に会して活発な議論を行うことで,古生代から中生代への地球環境進化の実態に迫る国内における情報発信の場としたい.
【招待講演予定者】磯崎行雄(東京大)・堀 利栄(愛媛大)→招待者の紹介はこちら
T8.超深度掘削による新次元の地球科学/New sciences in deep riser-drilling[共催:日本掘削科学コンソーシアム(J-DESC),JAMSTEC:海洋掘削科学研究開発センター]
川端訓代*(鹿児島大:katsuragisan2424@gmail.com)・坂口有人(山口大)・伊藤喜宏(京都大)・斎藤実篤(海洋研究開発機構)
Kuniyo Kawabata* (Kagoshima Univ.), Arito Sakaguchi (Yamaguchi Univ.), Yoshihiro Ito (Kyoto Univ.) and Saneatsu Saito (JAMSTEC)
「ちきゅう」によって進められている超深度掘削は,地球表層における熱や応力的な擾乱から逃れ,地球惑星内部の本質に迫る画期的なプロジェクトである.しかしライザー掘削技術で取得できるデータセットは,従来の掘削とは全く異質のものである.コアリングはスポットに限定され,ほとんどの区間ではカッティングス(削り岩片)が唯一の地質試料である.その一方で掘削流体が循環しているので,地質流体を船上観測することが可能である.ロギングや孔内観測,サイスミックなどと組み合わせて,初めてディープな世界が垣間見えるだろう.生物,構造地質,地球化学,岩石学,地球物理,地震学など幅広い話題を募集する.
【招待講演予定者】廣瀬丈洋(JAMSTEC)・Demian Saffer(Pen. State Univ.)→招待者の紹介はこちら
T9.平野地質/Quaternary basin research
卜部厚志*(新潟大:urabe@gs.niigata-u.ac.jp)・宮地良典(産総研)
Atsushi Urabe* (Niigata Univ.) and Yoshinori Miyachi (AIST)
平野や平野周辺の丘陵部などを構成する地層からは,堆積環境,堆積システム,地層の形成過程,構造運動(活断層の履歴),発達史などさまざまな事象が複合して記録されている.これらを地層から読み解くことは,単に平野の発達過程を復元するだけでなく,地層に記録されたイベント(災害)や表層地盤の課題(軟弱地盤や液状化)などを明らかにすることにつながる.地質学的視点から平野を総合的に理解することは,人間の生活環境の安全性を考える上でも重要である.本セッションでは,平野に係る様々な知見から,人間が生活する平野を理解するための場としたい.
【招待講演予定者】なし
▲ページtopに戻る
レギュラーセッション:24件
R1.深成岩・火山岩とマグマプロセス/Plutonic rocks, volcanic rocks and magmatic processes(火山部会・岩石部会)
柚原雅樹*(福岡大:yuhara@fukuoka-u.ac.jp)・亀井淳志(島根大)・長谷川 健(茨城大)
Masaki Yuhara* (Fukuoka Univ.),Atsushi Kamei (Shimane Univ.) and Takeshi Hasegawa (Ibaraki Univ.)
深成岩および火山岩を対象に,マグマプロセスにアプローチした研究発表を広く募集する.発生から定置・固結に至るまでのマグマの物理・化学的挙動や,テクトニクスとの相互作用について,野外地質学・岩石学・鉱物学・火山学・地球化学・年代学など様々な視点からの活発な議論を期待する.
R2.岩石・鉱物・鉱床学一般/Petrology, mineralogy and economic geology(岩石部会)
斉藤 哲*(愛媛大:saitotetsu@sci.ehime-u.ac.jp)・壷井基裕(関西学院大)
Satoshi Saito* (Ehime Univ.) and Motohiro Tsuboi (Kwansei Gakuin Univ.)
岩石学,鉱物学,鉱床学,地球化学などの分野をはじめとして,地球・惑星物質科学全般にわたる岩石及び鉱物に関する研究発表を広く募集する.地球構成物質についての多様な研究成果の発表の場となることを期待する.
R3.噴火・火山発達史と噴出物/Eruption, evolution and products of volcanic processes(火山部会)
長谷川 健*(茨城大:hasegawt@mx.ibaraki.ac.jp)・長井雅史(防災科研)
Takeshi Hasegawa* (Ibaraki Univ.),Masashi Nagai (NIED)
火山地質ならびに火山現象のモデル化に関し,マグマや熱水流体の上昇過程,噴火様式,噴火経緯,噴出物の移動・運搬・堆積,各火山あるいは火山地域の発達史,火山活動とテクトニクス・化学組成をはじめとする,幅広い視点からの議論を期待する.
▲ページtopに戻る
R4.変成岩とテクトニクス/Metamorphic rocks and tectonics(岩石部会)
宮本知治*(九州大:miyamoto@geo.kyushu-u.ac.jp)・森 康(北九州市立自然史・歴史博物館)mori@kmnh.jp
Tomoharu Miyamoto* (Kyushu Univ.) and Yasushi Mori (Kitakyushu Mus. Natural Hist. Human Hist.)
国内および世界各地の変成岩を主な対象に,記載的事項から実験的・理論的考察を含め,またマイクロスケールから大規模テクトニクスまで,様々な地球科学的手法・規模の視点に立った斬新な話題提供と活発な議論を期待する.
R5.地域地質・地域層序/Regional geology and stratigraphy(地域地質部会・層序部会)
松原典孝*(兵庫県立大:matsubara-n@stork.u-hyogo.ac.jp)・内野隆之(産総研)・岡田 誠 (茨城大)
Noritaka Matsubara* (Univ. Hyogo),Takayuki Uchino (AIST) and Makoto Okada (Ibaraki Univ.)
国内外を問わず、地域に関連した地質や層序の発表を広く募集する.年代,化学,分析,リモセン,活構造,地質調査法等の様々な内容の発表を歓迎し、地域を軸にした討論を期待する.発表形式としては、地質図や断面図のポスター発表を特に歓迎する.
R6.ジオパーク/Geopark(地域地質部会・ジオパーク支援委員会)
天野一男*(茨城大:kazuo@mx.ibaraki.ac.jp)・高木秀雄(早稲田大)・渡辺真人(産総研)
Kazuo Amano* (Ibaraki Univ.),Hideo Takagi (Waseda Univ.) and Mahito Watanabe (AIST)
日本のジオパーク活動も6年が経過して,日本ジオパークとして認定された地域は33地域となり,その内の6地域は世界ジオパークに認定されており,これから新たに申請を考えている地域も多い.このような状況下で,ジオパークの質を向上させるための様々な課題が出てきている.ジオパークは,貴重な地質・地形を中心とした各種自然・文化遺産の価値を地元の人が良く理解し保全しながら、地域の教育や経済的振興をめざす事業である.その活動の中心的なものがジオツアーである.このツアーは,学術的な基礎のもとに一般の方を対象として観光を展開するという点で,従来の観光ツアーとは大きく異なる.学術的に質を落とさないで,いかに一般市民に楽しんでもらえるかが重要な課題となる.ジオツアーのインタープリター,ガイドの育成に当たって、地域の大学,博物館,研究所の研究者の協力は不可欠である.この観点から,地質学会として,問題点を整理し,ジオパークの質的向上への貢献に寄与したい.様々な実践例の発表,課題解決方法の提案など広く講演を募集する.
【招待講演予定者】大岩根 尚(三島村役場)→招待者の紹介はこちら
▲ページtopに戻る
R7.地域間層序対比と年代層序スケール/Stratigraphic correlation and chronostratigraphic scales(層序部会)
里口保文*(琵琶湖博物館:satoguti@lbm.go.jp)・岡田 誠(茨城大)
Yasufumi Satoguchi* (Lake Biwa Mus.) and Makoto Okada (Ibaraki Univ.)
テフラ等の鍵層を用いて異なる地域間の層序対比に主体をおく研究や,鍵層そのものを主体とした研究,または複合的層序学等によるグローバルな年代層序スケールの構築に寄与するような研究についての講演を歓迎する.
R8.海洋地質/Marine geology(海洋地質部会)
荒井晃作*(産総研:ko-arai@aist.go.jp)・芦 寿一郎(東大大気海洋研)・小原泰彦(海上保安庁)
Kohsaku Arai* (AIST),Juichiro Ashi (AORI, Univ. of Tokyo) and Yasuhiko Ohara (JCG)
海洋地質に関連する分野(海域の地質・テクトニクス・変動地形学・海域資源・堆積学・海洋学・古環境学・陸域地質での海洋環境変遷研究など)の研究発表を募集する.調査速報・海底地形地質・画像データなどのポスター発表も歓迎する.
【招待講演予定者】浦辺徹郎(国際資源開発研修センター:JMEC)・石塚 治(産総研)→招待者の紹介はこちら
R9.堆積物(岩)の起源・組織・組成/Origin, texture and composition of sediments(堆積地質部会)[共催:日本堆積学会・石油技術協会探鉱技術委員会・日本有機地球化学会]
太田 亨*(早稲田大:tohta@toki.waseda.jp)野田 篤(産総研)
Tohru Ohta* (Waseda Univ.) and Atsushi Noda (AIST)
砕屑物の生成(風化・侵食・運搬)から堆積岩の形成(堆積・沈降・埋積・続成)まで,組織(粒子径・形態)・組成(粒子・重鉱物・化学・同位体・年代)・物性などの堆積物(岩)の物理的・化学的・力学的性質を対象とし,その起源・形成過程・後背地・古環境や地質体の発達史を議論する.太古代の堆積岩から現世堆積物まで,珪質岩・火山砕屑岩・風成塵・リン酸塩岩・蒸発岩・有機物・硫化物などについての研究も歓迎する.
▲ページtopに戻る
R10.炭酸塩岩の起源と地球環境/Origin of carbonate rocks and related global environments(堆積地質部会 )[共催:日本堆積学会・石油技術協会探鉱技術委員会・日本有機地球化学会]
山田 努*(東北大:t-yamada@m.tohoku.ac.jp)・足立奈津子(鳴門教育大学)
Tsutomu Yamada* (Tohoku Univ.) and Natsuko Adachi (Naruto Univ. Educ.)
炭酸塩岩・炭酸塩堆積物の堆積作用,組織,構造,層序,岩相,生物相,地球化学,続成作用,ドロマイト化作用など,炭酸塩に関わる広範な研究発表を募集する.また,現世炭酸塩の堆積作用・発達様式,地球化学,生物・生態学的な視点からの研究発表も歓迎する.
【招待講演予定者】吉村和久(九州大)→招待者の紹介はこちら
R11.堆積相・堆積過程/Sedimentary facies and processes(堆積地質部会・現行地質過程部会)[共催:日本堆積学会・石油技術協会探鉱技術委員会・日本有機地球化学会]
横川美和*(大阪工業大:miwa@is.oit.ac.jp)・高清水康博(新潟大)・西田尚央(産総研)
Miwa Yokokawa* (Osaka Inst. Tech.) ,Yasuhiro Takashimizu (Niigata Univ.) and Naohisa Nishida (AIST)
さまざまな環境で生じる堆積過程と堆積相の分類・記載・解釈に関する発表や、堆積相解析に基づく堆積システム・シーケンス層序学についての議論を広く募集する.さらに、堆積作用や地層形成のダイナミクスに関連する理論・アナログ実験・数値シミュレーション・現地観測等の研究発表を歓迎する.
R12.石油・石炭地質学と有機地球化学/Geology and geochemistry of petroleum and coal(石油石炭関係・堆積地質部会)[共催:石油技術協会探鉱技術委員会・日本有機地球化学会・日本堆積学会]
金子信行*(産総研:nobu-kaneko@aist.go.jp)・河村知徳(石油資源開発)・三瓶良和(島根大)
Nobuyuki Kaneko* (AIST),Tomonori Kawamura (JAPEX) and Yoshikazu Sampei (Shimane Univ.)
国内外の石油・石炭地質および有機地球化学に関する講演を集め,石油・天然ガス・石炭鉱床の成因・産状・探査手法など,特にトラップ構造,堆積盆,堆積環境,貯留岩,根源岩,石油システム,資源量,炭化度などについて討論する.
【招待講演予定者】加藤 進((株)地球科学総合研究所)・山中寿朗(岡山大) →招待者の紹介はこちら
▲ページtopに戻る
R13.岩石・鉱物の変形と反応/Deformation and reactions of rocks and minerals(構造地質部会・岩石部会)
廣瀬丈洋*(海洋研究開発機構:hiroset@jamstec.go.jp)・高橋美紀(産総研)・大坪 誠(産総研)・水上知行(金沢大)
Takehiro Hirose* (JAMSTEC),Miki Takahashi (AIST),Makoto Otsubo (AIST) and Tomoyuki Mizukami (Kanazawa Univ.)
岩石・鉱物の変形(破壊,摩擦,流動現象)と反応(物質移動,相変化)およびその相互作用を,観察・分析・実験を通じて物理・化学的な側面から包括的に理解し,地球表層から内部における地質現象の解明を目指す.地質学,岩石学,鉱物学,地球化学など様々な視点・アプローチによる成果をもとに議論する.
【招待講演予定者】平賀岳彦(東京大学地震研)→招待者の紹介はこちら
R14.沈み込み帯・陸上付加体/Subduction zones and on-land accretionary complexes(構造地質部会・海洋地質部会)
氏家恒太郎*(筑波大:kujiie@geol.tsukuba.ac.jp)・橋本善孝(高知大)・坂口有人(山口大)・菅森義晃(鳥取大)
Kohtaro Ujiie* (Univ. Tsukuba),Yoshitaka Hashimoto (Kochi Univ.),Arito Sakaguchi (Yamaguchi Univ.) and Yoshiaki Sugamori (Tottori Univ.)
沈み込み帯・陸上付加体に関するあらゆる分野からの研究を歓迎する.野外調査,微細構造観察,分析,実験,理論,モデリングのみならず海洋における反射法地震探査,地球物理観測,地球化学分析,微生物活動など多様なアプローチに基づいた活発な議論を展開したい.次世代の沈み込み帯・陸上付加体研究者を育てるべく,学生による研究発表も大いに歓迎する.
【招待講演予定者】井出 哲(東京大)・高田陽一郎(京都大)→招待者の紹介はこちら
R15.テクトニクス/Tectonics(構造地質部会)
武藤 潤*(東北大:muto@m.tohoku.ac.jp)・安江健一(JAEA)・針金由美子(産総研)
Jun Muto* (Tohoku Univ.),Ken-ichi Yasue (JAEA) and Yumiko Harigane (AIST)
陸上から海洋における野外調査や各種観測の他,実験や理論などに基づき,日本や世界各地に発達するあらゆる地質体の構造,成因,形成過程や発達史に関する講演を募集する.また,現在進行している地殻変形や活構造に関する研究成果も歓迎する.
【招待講演予定者】木村 学(東京大)・松本 聡(九州大)→招待者の紹介はこちら
▲ページtopに戻る
R16.古生物/Paleontology(古生物部会)
平山 廉(早稲田大)・北村晃寿(静岡大)・太田泰弘(北九州博)・三枝春生(兵庫県立人と自然の博)・須藤 斎*(名古屋大:suto.itsuki@a.mbox.nagoya-u.ac.jp)
Ren Hirayama(Waseda Univ.), Akihisa Kitamura(Shizuoka Univ.), Yasuhiro Ota(Kitakyushu Mus.), Haruo Saegusa(Mus. Nature and Human Activities, Hyogo)and Itsuki Suto*(Nagoya Univ.)
主として古生物を扱った,または,プロキシとして古生物を利用したものや古生物を用いた新手法などの研究の発表・討論を行う.
R17.ジュラ系+/The Jurassic +(古生物部会)
松岡 篤*(新潟大:matsuoka@geo.sc.niigata-u.ac.jp)・近藤康生(高知大)・小松俊文(熊本大)・石田直人(明治大)・中田健太郎(城西大)
Atsushi Matsuoka* (Niigata Univ.),Yasuo Kondo (Kochi Univ.),Toshifumi Komatsu (Kumamoto Univ.),Naoto Ishida (Meiji Univ.) and Kentaro Nakada(Josai Univ.)
2003年の静岡大会において「ジュラ系」として誕生した本セッションは,隣接する地質系統の研究者の要望を取り込んで「ジュラ系+」として発展し,10年間にわたりトピックセッションとしてを継続開催されてきた.この間,ジュラ系の研究を中心に,関連する講演がまとまって発表される場として定着し,ジュラ系研究の情報を研究者の間で共有することに貢献してきた.この10年の国際的なジュラ系研究は,ジュラ系基底のGSSP確定をはじめ重要な進展があったが,本セッションではその動向をいち早く伝え続けてきた.また本セッションの講演タイトルが国際ジュラ系層序小委員会のNewsletterに収録されるなど,ジュラ系研究拠点としての日本を国際的にアピールする場ともなっている.このような活動は,GSSPの決定に際し投票権をもつ国際ジュラ系層序小委員会のVoting Memberが日本から選出されたことにも繋がっている.本セッションを開催することによって,ジュラ系と上下の地質系統の研究について,各方面からのデータを提供しあい多角的に検討する場を提供する.このことは,日本からの国際発信力を強化することにも寄与する.
R18.情報地質とその利活用/Geoinformatics and its application(情報地質部会・地域地質部会)
野々垣 進*(産総研:s-nonogaki@aist.go.jp)・斎藤 眞(産総研)
Susumu Nonogaki* (AIST) and Makoto Saito (AIST)
地質情報の取得,デジタル化,データ処理,画像処理,数理解析,統計解析,データベース管理,SNSを含むWebによる発信・共有などに関する理論・技術・システム開発など,情報地質分野の研究成果を広く募集する.さらに,これらの成果から得られた地質情報の利活用事例,利活用における問題点,比較検討などの研究発表を募集する.
▲ページtopに戻る
R19.環境地質/Environmental geology(環境地質部会)[共催:地質汚染−医療地質−社会地質学会]
難波謙二(福島大)・風岡 修(千葉環境研)・三田村宗樹(大阪市大)・田村嘉之*(千葉県環境財団:y_tamtam3012@nifty.com)
Kenji Nanba(Fukushima Univ.), Osamu Kazaoka(Res. Inst. Environ. Geol., Chiba), Muneki Mitamura(Osaka City Univ.)and Yoshiyuki Tamura*(Chiba Pref. Environ. Foundation)
地質汚染、医療地質,地盤沈下,湧水,水資源,湖沼・河川,都市環境問題,法地質学,環境教育,地震動,液状化・流動化,地震災害,岩盤崩落など,環境地質に関係する全ての研究の発表・討論を行う.
R20.応用地質学一般およびノンテクトニック構造/Engineering geology and non-tectonic structures(応用地質部会)
小嶋 智(岐阜大)・須藤 宏*(応用地質:sudou-hiroshi@oyonet.oyo.co.jp)・西山賢一(徳島大)
Satoru Kojima(Gifu Univ.), Hiroshi Sudo*(OYO Corp.)and Ken-ichi Nishiyama(Tokushima Univ.)
応用地質学一般では,種々の地質ハザードの実態,調査,解析,災害予測,ハザードマップの事例・構築方法,土木構造物の設計・施工・維持管理に関する調査,解析など,応用地質学的視点に立った幅広い研究を対象とする.また,ノンテクトニック構造では,ランドスライドや地震による一過性の構造,重力性の構造等の記載,テクトニック構造との区別や比較・応用等の研究を対象にして発表・議論する.
【招待講演予定者】地頭薗 隆(鹿児島大)・大澤英明(日本原子力研究開発機構)→招待者の紹介はこちら
R21.地学教育・地学史/Geoscience Education/History of Geoscience(地学教育委員会)
矢島道子*(東京医科歯科大:pxi02070@nifty.ne.jp)・三次徳二(大分大)
Michiko Yajima* (Tokyo Medical and Dental Univ.) and Tokuji Mitsugi (Oita Univ.)
地学教育,地学史に関わる研究発表を広く募集する.新学習指導要領が完全実施された教育現場からの問題提起や,実践報告に加え,大学や博物館,研究所等が行うアウトリーチに関わる実践報告についても歓迎する.また地学史からの問題提起,貴重な史的財産の開示を歓迎する.
▲ページtopに戻る
R22.第四紀地質/Quaternary geology(第四紀地質部会)
公文富士夫*(信州大:shkumon@gipac.shinshu-u.ac.jp)・廣瀬孝太郎(福島大)
Fujio Kumon* (Shinshu Univ.) and Kotaro Hirose (Fukushima Univ.)
第四紀地質に関する全ての分野(環境変動・気候変動・湖沼堆積物・地域層序など)からの発表を含む.また,新しい調査や研究,方法の開発や調査速報なども歓迎する.
R23.地球史/History of the Earth(環境変動史部会)
清川昌一*(九州大:iyokawa@geo.kyushu-u.ac.jp)・山口耕生(東邦大)・小宮 剛(東京大)・尾上哲治(熊本大)・須藤 斎(名古屋大)
Shoichi Kiyokawa* (Kyushu Univ.),Kosei Yamaguchi (Toho Univ.),Tsuyoshi Komiya (Univ. Tokyo),Onoe Tetsuji (Kumamoto Univ.) and Itsuki Suto (Nagoya Univ.)
地質学的視点から,さまざまな時間スケールで地球の変動を捉えようとする研究の発表や議論の場としたい.時代は特定せず,初期地球から有史時代まで幅広い時代の研究発表を期待している.地球表層環境変動と生命進化,固体地球,テクトニクスとの相互作用など,「地球史」というキーワードで繋がるあらゆる研究分野をターゲットとしている.
【招待講演予定者】菅沼悠介(極地研)→招待者の紹介はこちら
R24.原子力と地質科学/Nuclear energy and geological sciences(地質環境長期安定性研究委員会)[共催:日本原子力学会バックエンド部会]
吉田英一*(名古屋大:dora@num.nagoya-u.ac.jp)・梅田浩司(日本原子力研究開発機構)・高橋正樹(日大)・渡部芳夫(産総研)
Hidekazu Yoshida* (Nagoya Univ.),Koji Umeda (JAEA),Masaki Takahashi (Nihon Univ.) and Yoshio Watanabe (AIST)
原子力は,ウラン資源探査,活断層等を考慮した耐震安全性評価,廃棄物の地層処分,放射性物質の環境動態等の多くの地質科学的課題を有している.本セッション「原子力と地質科学(Nuclear Energy and Geological Sciences)」は,このような日本の原子力に関わる地質科学的課題について,地球科学的知見の議論及び関連する学会や研究者間の意見交換を行うことを目的としており,幅広い分野からの参加,発表を歓迎する.
【招待講演予定者】鷺谷 威(名古屋大学減災連携研究センター)→招待者の紹介はこちら
R25.鉱物資源と地球物質循環/Mineral resources and global material cycles(鉱物資源部会)
加藤泰浩*(東京大:kato@sys.t.u-tokyo.ac.jp)・岩森 光(JAMSTEC)・中村謙太郎(東京大)
Yasuhiro Kato* (Univ. Tokyo),Hikaru Iwamori (JAMSTEC) and Kentaro Nakamura (Univ. Tokyo)
近年,海底鉱物資源をはじめとする新しい資源の開発に向けた動きが活発化し,鉱物資源への注目が高まっている.鉱物資源の形成過程に関わる様々な元素の輸送・濃集過程は,ダイナミックな地球における物質循環と分化の一部に他ならず,鉱物資源の成因を考える上では,地球全体にまたがるグローバルな物質循環とその変遷,そしてその資源形成との関わりについての包括的な理解が不可欠である.本セッションでは,鉱物資源そのものに加え,これまで着目されることが少なかった資源形成をとりまく地球表層-内部環境,テクトニックセッティング,ダイナミクスと,資源の形成メカニズムとの関わりについても,グローバルに議論する場を提供したい.
【招待講演予定者】田近英一(東京大)→招待者の紹介はこちら
▲ページtopに戻る
アウトリーチセッション
OR.日本地質学会アウトリーチセッション/Outreach session (一般公開,ポスター発表のみ)
星 博幸*(愛知教育大:hoshi@auecc.aichi-edu.ac.jp)・須藤 斎(名古屋大)
Hiroyuki Hoshi*(Aichi Univ. Education)and Itsuki Suto(Nagoya Univ.)
研究成果を社会に発信する場として設けられたセッション.地質学と関連分野を対象とし,開催地(九州,鹿児島)とその周辺の地質や地学にかんする研究紹介,社会的に注目されている地質および関連トピックの研究紹介,特定分野の研究到達点や課題の解説など.客層は会員(専門家)ではなく市民であることに注意.市民講演会の会場で開催する.申込多数の場合は行事委員会にて採否を検討する
▲ページtopに戻る
国際シンポジウム関連巡検
国際シンポジウム関連巡検:
Traces of paleo-earthquakes and tsunamis along the eastern Nankai Trough and Sagami Trough, Pacific coast of central Japan
(注意)本巡検は,学術大会の巡検とは申込方法が異なります.
参加申込は,こちらの[専用申込ページ]よりお申込下さい.
申込締切:8月8日(金)18:00
申込締切 延長:8月18日(月)18:00
見学コース
:
浜松〜静岡〜東京〜館山〜成田空港
主な見学対象
:
東海地震と関東地震の痕跡を伝える地形,津波堆積物,建造物,南海トラフ巨大地震への対策として作られた津波避難タワーと命山
日 程
:
9/16〜18(2泊3日) 16日浜松泊,17日東京泊
定 員
:
22名
案 内 者
:
藤原 治(産総研)
魅 力
:
本巡検では,東海地震や関東地震の痕跡を伝える建物や地層・地形を巡るとともに,自治体等による防災対策の状況を視察する.静岡県西部では東海地震・津波で移転した関所跡や,川の土手に露出する津波堆積物を見学する.また,巨大津波を想定して作られた津波避難タワーなども視察する.房総半島では大正・元禄の関東地震で隆起した海岸や,縄文時代の津波堆積物を挟む露頭を見学する.これらを通じて,地形や地層から古地震や津波を復元する研究を実感してもらい,その意義と今後の方向性について議論する機会としたい.
見どころ
:
・ 江戸時代の東海地震で移転を繰り返した新居関所.
・ 磐田市(太田川)の河川敷に露出する明応津波の堆積物.
・ 大正・元禄の関東地震で隆起した房総半島南部の海岸.
・ 縄文時代に房総半島南部の溺れ谷に堆積した津波堆積物.
参 加 費
:
約29,000円
※ 新幹線,貸切バス,2泊分のホテル代を含む.ただし, 昼・夜の食事代は含みません.
地 形 図
:
新居町,浜松,磐田,袋井,掛塚,御前崎,館山,布良,白浜,千倉(すべて1/2.5万)
集合場所
:
16日14:00浜松駅出発
そ の 他
:
※移動は,新幹線と貸切バスを利用
※参加者数によって参加費が多少変動します.締切後に確定し,お支払い方法とあわせて連絡します
※露頭観察の際,ひざ下まで濡れる可能性あり.長靴があったほうがよい(沢のに入らなくても露頭を見ることはできます)
問い合わせ先
:
藤原 治(産業技術総合研究所)
o.fujiwara@aist.go.jp
静岡県袋井市に作られた津波避難タワー.内閣府が公表した南海トラフで発生が考えられる「最大クラスの地震・津波」への対策が進んでいる.
房総半島南部の溺れ谷に,約7500年前に形成された津波堆積物.津波で運びこまれた礫や貝殻などからなる津波堆積物が内湾の泥層を覆っている.
(注意)本巡検は,学術大会の巡検とは申込方法が異なります.
参加申込は,こちらの[専用申込ページ]よりお申込下さい.
申込締切:8月8日(金)18:00
申込締切 延長:8月18日(月)18:00
巡検へ参加される方へ
巡検へ参加される方へ
「野外見学,調査,試料採取における注意喚起」をご一読下さい
重要 巡検へ参加される方は,参加の前に是非「野外見学,調査,試料採取における注意喚起」をご一読下さい。
「野外調査において心がけたいこと」国立・国定公園や史跡・名勝・天然記念物、あるいは一般的な露頭における調査上の注意点
「安全のしおり(巡検案内書より)」巡検や野外調査における安全上の注意点と自然保護に関する注意点
「巡検案内書を頼りに野外調査へ出かける方へ」露頭での調査や試料採取にあたっての注意点(「野外調査において心がけたいこと」から一部抜粋)
優秀ポスター賞
優秀ポスター賞
今大会でも学術発表の優秀ポスターに対して「日本地質学会優秀ポスター賞」を授与します.毎日3〜5件の予定です.受賞者には学会長から直接賞状を授与します(表彰と写真撮影).受賞ポスターは,その栄誉をたたえ,大会期間中,別途設けるボードに掲示します.大会終了後,News誌(年会報告記事)に氏名,発表題目,受賞理由を掲載します.
【審査】
審査は各賞選考委員会が行い,学会長がこれを承認します.選考委員会は日替わりで,行事委員会委員5名,大会実行委員会代表1名および各賞選考委員会委員2名の合計8名により構成されます.選考委員氏名は大会終了後に公表します(News誌11月号を予定).
【審査のポイント】
・ (研究内容)オリジナリティ
・ (プレゼンテーション)レイアウト・中心点の明示・わかりやすさ・美しさ・斬新さ
【審査結果の発表時間と方法】
発表は各日毎16時以降に行います.表彰は17時前後にポスター会場で行います.ただし今回は,初日(13日)の表彰は,2日目(14日)の表彰時にあわせて行う予定です.審査結果は掲示板や廊下等の要所に貼り出します.受賞ポスターには受賞花をつけます.
その他の申込TOP
その他
■ ランチョン・夜間小集会(申込:6/25締切)
■ 若手会員のための業界研究サポート(旧就職支援プログラム)
(出展申込:8/8締切)
■ 小さなEarth Scientistのつどい〜第12回小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜
(申込:7/16締切)
■ 託児室の利用(申込:8/22締切)
■ 緊急展示(申込:8/29締切)
ランチョン・夜間集会
ランチョン・夜間集会
■ランチョン
▶9月14日(日)12:00-13:00
第3会場 岩石部会
(世話人:世話人:鵜澤(平原)由香)
岩石部会に関連した審議の必要な事項について,会員間で審議を行う.また,会員への報告が必要な件についても報告を行う.他にも,提案したり,連絡をすべき件があれば,ランチョンでの議題として取り上げる.
第4会場 地学教育委員会
(世話人:三次徳二・浅野俊雄)
小,中,高等学校における理科教育(地学教育)の現状について情報交換を行う.また,学会が行う活動に対しての意見交換を行う.
第5会場 海洋地質部会
(世話人:荒井晃作・芦 寿一郎・小原泰彦)
海洋地質関連の研究機関における最近の研究動向と今後の調査の紹介を行い,各種情報を共有するとともに,海洋地質部会の活動について議論する.
第6会場 構造地質部会若手の研究発表会
(世話人:大坪 誠・武藤 潤・氏家恒太郎)
構造地質部会若手の研究発表会をランチョンにおいて行います.一人20分程度で2名ほどを予定しています.
第7会場 地質学雑誌編集委員会
(世話人:秋元和實)
地質学雑誌の諸問題について改善を図るために,face-toface で意見交換する.
第8会場 現行地質過程部会
(世話人:川村喜一郎)
現行地質過程部会の今後の運営や計画について話し合う.どなたでも参加大歓迎.お弁当持参でお集りください.
▶9月15日(月・祝)12:00-13:00
第2会場 堆積地質部会
(世話人:中条武司)
堆積地質部会の活動報告および国内外の堆積学に関する情報交換を行う.
第4会場 応用地質部会
(世話人:小嶋 智・須藤 宏)
1)長野大会レギュラーセッションでの招待講演(内容・人選)について,2)地質学雑誌「講座」の応用地質部会から参画(内容・執筆者)について,3)その他
第5会場 地域地質部会・層序部会合同
(世話人:内野隆之・岡田 誠)
部会活動やセッションについての議論と情報交換
第6会場 文化地質学
(世話人:鈴木寿志)
「文化地質学」の開催に伴い,文化地質学の今後の進展と研究活動について,相互の情報交換を行う.
第7会場 古生物部会
(世話人:須藤 斎)
古生物部会の定例会合
第8会場 構造地質部会定例会
(世話人:大坪 誠・武藤 潤・氏家恒太郎)
過去の活動報告,会計報告,今後の活動計画など
■夜間小集会
▶9月14日(日)18:00-19:30
第2会場 大学博物館と地域の博物館
(世話人:川端清司)
大学博物館を含めた,博物館関係者のための集会です.地方の大学博物館の活動について話題提供いただき,あわせて地域の博物館との連携についても議論を進めたいと考えています.
第3会場 南極地質研究委員会
(世話人:外田智千)
・第56次(2014/15)観測計画の概要,・南極地質将来計画について,・その他
第4会場 地殻ダイナミクス:地質学と地球物理学の知見の総合
(世話人:竹下 徹)
地震の発生過程から地質学的時間スケールで生じる地殻変動の実体を解明するための地質学と地球物理学の研究協力はいかにあるべきか,最先端の共同研究について議論する.
第5会場 炭酸塩堆積学に関する懇談会
(世話人:松田博貴)
最新の炭酸塩堆積学に関する研究紹介と情報交換を行い,炭酸塩堆積学のこれからの方向性・発展について議論する.
第6会場 放散虫関連:INTERRADの参加・招致に関する意見交換
(世話人:松岡 篤・鈴木紀毅・板木拓也・栗原敏之)
INTERRAD(国際放散虫研究者協会)の参加・招致に関する意見交換.NOM会津(11/29-30,福島県立博物館)に関する連絡.
第7会場(212) 環境地質部会
(世話人:田村嘉之)
環境地質に関する講演,事務連絡など
第7会場(213) 地質学史懇話会
(世話人:会田信行)
鹿児島の地質学史に関する講演2題.岩松 暉:史料にみる桜島大正噴火,上村直巳:リヒトホーフェンの見た明治初年の鹿児島
第8会場 超深度海溝掘削(KANAME)
(世話人:木村 学・斎藤実篤・金川久一)
新学術領域研究「超深度海溝掘削(KANAME)」の事後評価報告と今後の沈み込み帯掘削に関する情報交換を行う.
▶9月15日(月・祝)18:00-19:30
第6会場 地質技術者教育委員会(会場が第4→第6に変更になりました。9/3現在)
(世話人:山本高司)
定例委員会,1)業界最新動向と新規採用状況,2)中期ビジョンへの対応
ランチョン申込
<申込締切 6月25日(水)必着,行事委員会扱い>
9月14日(日),15日(月)にランチョン開催を希望する方は,(1)集会名称,(2)集会内容(50〜100字程度),(3)世話人氏名・連絡先(メールアドレスと電話番号),(4)その他ご希望等,をe-mailで行事委員会(東京)宛に申し込んで下さい.申込締切は6月25日(水)です.開催日時のご希望に沿えない場合がありますので予めご承知おき下さい.世話人には,大会終了後に集会内容をニュース誌(大会記事)にご投稿いただきます(800字以内,原稿締切は10月下旬を予定).
夜間小集会の申込
<申込締切 6月25日(水)必着,行事委員会扱い>
9月14日(日),15日(月)ともに18:00〜19:30の予定です.夜間小集会の開催を希望する方は,(1)集会名称,(2)集会内容(50〜100字程度),(3)世話人氏名・連絡先(メールアドレスと電話番号),(4)その他ご希望等,をe-mailで行事委員会(東京)宛に申し込んで下さい.申込締切は6月25日(水)です.開催日時のご希望に沿えない場合がありますので予めご承知おき下さい.世話人には,大会終了後に集会内容をニュース誌(大会記事)にご投稿いただきます(800字以内,原稿締切は10月下旬を予定).
小,中,高校生徒「地学研究」発表会
小さなEarth Scientistのつどい
第12回小,中,高校生徒「地学研究」発表会
参加校一覧
・北海道札幌あすかぜ高等学校自然科学部地学班
・群馬県立太田女子高校地学部
・東京学芸大学附属高等学校
・早稲田大学高等学院理科部地学班
・山梨県立日川高等学校(2件)
・兵庫県立加古川東高等学校地学部(2件)
・兵庫県立西脇高等学校地学部(2件)
・鹿児島玉龍高等学校サイエンス部天文班
・鹿児島県立鶴丸高等学校地学部
・鹿児島県立錦江湾高等学校理数科3年地学班
・鹿児島県立国分高等学校理数科課題研究地学班
小さなEarth Scientistのつどい
第12回小,中,高校生徒「地学研究」発表会
日本地質学会地学教育委員会では,地学普及行事の一環として,地学教育の普及と振興を図ることを目的として,学校における地学研究を紹介する「地学研究」発表会をおこなっています.鹿児島大会でも,小・中・高等学校の地学クラブの活動,および授業の中で児童・生徒が行った研究の発表を募集いたします.鹿児島県内,また九州地方の学校,さらには全国の学校の参加をお待ちしています.会場は研究者も発表するポスター会場内に,特設コーナーを用意いたします.同時並行で研究者の発表も行われますので,児童・生徒同士のみならず,研究者との交流もできます.この会を通じて生徒,研究者,市民の交流が進み,地質学,地球科学への理解が深まって,未来を担う生徒たちの学習意欲への良い刺激と励みになることを願っております.
なお,参加証とともに,優秀な発表に対しては審査のうえ,「優秀賞」などの賞を授与いたします.
下記の要領にて参加校を募集します.
日時
2014年9月14日(日) 9:00〜15:30
場所
鹿児島大会ポスター会場(郡元キャンパス)
参加対象
・小,中,高校地学クラブならびに理科クラブ等の活動成果の発表
・小,中,高校の授業における研究成果の発表
・活動,研究内容は地学的なもの(地質や気象などの地球科学・環境科学,天文など)
申込締切
7月16日(水),下記,日本地質学会地学教育委員会宛にお申し込み下さい.
発表形式
ポスター発表(展示パネルは,縦210cm×横120cm)
パネルのほかに標本等を展示される場合には,パネルの前に机を用意します.参加申し込みの際に,その旨を記載して下さい.その場合は展示パネルの下側が隠れる事をご了承下さい.発表者は決められた時間(および随時)パネルの前に待機し説明をしていただきます.なお,遠隔地および学校行事等のために児童・生徒が参加できない場合は,発表ポスターのみをお送りいただいても結構です.
参加費
無料(参加者・引率者とも),開催中の研究者の発表,講演も聴くことができます.
派遣依頼
参加者・引率者については学校長宛,日本地質学会より派遣依頼状を出します.
問い合わせ
・申込先
所定の書式をFAXまたはe-mailで下記宛にお送り下さい.
日本地質学会地学教育委員会(担当 三次)
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F
TEL:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156 e-mail:main@geosociety.jp
【参加申込書のダウンロード】
発表申込締切: 7/16(水)
託児室
託児室
男女共同参画委員会では,ご家族で学会参加される会員の皆様に以下のプランをご用意いたしました.ご希望の方は,利用条件をよくご覧になりお申し込み下さい.
>>現地事務局申込<<
<利用申込締切: 8月22日(金)>
(1)開設日時:
9月13日(土)8:00〜20:00(予定)
9月14日(日)8:30〜20:00(予定)
9月15日(月)8:30〜20:00(予定)
(2)対象:
鹿児島大会参加者を保護者とする生後6ヶ月から未就学のお子様.
(3)場所:
キッズベース鹿児島(予定)
〒890-0052 鹿児島市上之園町14-30有迫ビル1F
http://www.kidsbase-ccc.com/
(4)アクセス:
JR鹿児島中央駅 徒歩10分
*ご利用をご希望の方は現地事務局までお問合わせ下さい.万が一の場合に備え,施設加入の損害保険で対応させていただきます.なお,託児施設のご利用に際しては当鹿児島大会実行委員会・日本地質学会は責任を負いかねますのでご了承下さい.
企業展示・書籍販売・広告募集
企業等団体展示/書籍販売
企業・団体・研究機関などによる展示を行います.会場は,鹿児島大学郡元キャンパス第2体育館を予定しています.8月7日現在,
安井器械株式会社,
メイジテクノ株式会社,
石油資源開発株式会社,
株式会社蒜山地質年代学研究所,
株式会社建設技術研究所,
NPO法人ジオプロジェクト新潟,
独立行政法人海洋研究開発機構,
カールツァイスマイクロスコピー株式会社,
日本地球掘削科学コンソーシアム(J-DESC),
Conwy Valley Systems Ltd.(UK),
ライカマイクロシステムズ株式会社,
株式会社加速器分析研究所,
から申し込みがありました.
また,同じく鹿児島大学郡元キャンパス第2体育館では書籍・物品の展示販売コーナーを設けます.8月7日現在,
株式会社ニュートリノ,
株式会社ニチカ,
有限会社徳田屋書店,
株式会社古今書院,
からお申込みがありました.
※ 申込期限延長,追加募集等がある場合もあります.随時大会ホームページをご覧ください.
■ 展示会出展募集 ■ 書籍・販売ブースご利用の募集 ■ 広告協賛の募集
企業・研究機関等関係団体による展示会の出展募集
<申込締切 一次7月4日(金),最終8月8日(金) 現地事務局扱い>
地質関係機関・関連企業のご活躍を広く地質学会員に紹介していただくため,会期中,企業展示会を開催致します.企業紹介・業務紹介・研究成果・新技術・特許などご自由に展示内容を構成いただけます.奮ってご出展のお申込をいただきますようお願い申し上げます.
【展示募集概要】
1.開催期間:搬入設営日9月12日(金),開催日9月13日(土)〜15日(月),搬出撤収日9月15日(月)※予定
2.開催場所:鹿児島大学 郡元キャンパス 教育学部第2体育館 ※予定
3.募集小間数:小小間20,パネル小間20 ※予定 複数小間のお申込も可能です.
4.小間仕様見本:
※仕様詳細・オプション料金等につきましては,下記「展示募集要項申込書」をダウンロードの上,ご確認下さい.
5.出展料金:小小間 50,000円(消費税別),パネル小間 20,000円(消費税別)
6.第1次募集締め切り日:7月4日(金) 最終募集締め切り日:8月8日(金)
【出展申込方法】
「展示募集要項申込書」をダウンロードいただき,必要事項をご記入の上,下記申込先までe- mai l へのPDFファイル添付,あるいはFAXにてお申込下さい.募集要項・申込書が別途必要な場合は,現地事務局までご連絡下さい.送付致します.
「展示募集要項申込書(pdfファイル)」
「展示募集要項申込書(docファイル)」
【お申込・お問合せ先】
〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1天満橋千代田ビル2号館9階
日本地質学会 第121年学術大会 現地事務局(株式会社アカデミック・ブレインズ内)
TEL:06-6949-8137,FAX:06-6949-8138,e-mail:gsj2014kagoshima@academicbrains.jp 担当:田中
※日本地質学会賛助会員は出展料金が無料となります.別途,現地事務局までご連絡下さい.
書籍・販売ブースご利用の募集
<申込締切 一次7月4日(金),最終8月8日(金) 現地事務局扱い>
地質学関連の書籍・その他物品の販売にご利用いただくべく会期中ブースを設置致します.奮ってご出展のお申込をいただきますようお願い申し上げます.※見本展示のみでのご利用も可能です.
【書籍・販売ブース出展概要】
1.設置期間:9月13日(土)〜9月15日(月)
2.設置場所:鹿児島大学 郡元キャンパス 教育学部第2体育館 ※予定
3.募集ブース数:20ブース ※予定 複数ブースのお申込も可能です.
4.ブース仕様見本
※仕様詳細・オプション料金等につきましては下記「展示募集要項申込書」をダウンロードの上,ご確認下さい.
5.出展料金:10,000円(消費税別)
6.第1次募集締め切り日:7月4日(金) 最終募集締め切り日:8月8日(金)
【出展申込方法】
「展示募集要項申込書」をダウンロードいただき,必要事項をご記入の上,下記申込先までe- mai l へのPDFファイル添付,あるいはFAXにてお申込下さい.募集要項・申込書が別途必要な場合は,現地事務局までご連絡下さい.送付致します.
「展示募集要項申込書(pdfファイル)」
「展示募集要項申込書(docファイル)」
【お申込・お問合せ先】
〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1天満橋千代田ビル2号館9階
日本地質学会 第121年学術大会 現地事務局(株式会社アカデミック・ブレインズ内)
TEL:06-6949-8137,FAX:06-6949-8138,e-mail:gsj2014kagoshima@academicbrains.jp 担当:田中
講演要旨集,広告協賛の募集
<申込締切 8月8日(金) 現地事務局扱い>
地質関係機関・関連企業のご活躍を広く地質学会員に広報いただくべく,大会開催にあわせ発行されます講演要旨集において,広告協賛を募集致します.企業紹介・業務紹介・研究成果・新技術・特許などの広報活動のご一環として,奮ってお申込をいただきますようお願い申し上げます.
【広告協賛料金】※詳細は下記「広告協賛募集要項申込書」をダウンロードの上,ご確認下さい.
講演要旨集:1頁 40,000円 1/2頁 20,000円 1/4頁 10,000円(すべて消費税別)
※完全版下,データまたフィルムでの入稿をお願い致します.
【出稿申込方法】
「広告協賛募集要項申込書」をダウンロードいただき必要事項をご記入の上,下記申込先までe-mailへのPDF添付,あるいはFAXにてお申込下さい.
「広告協賛募集要項申込書(pdfファイル)」
「広告協賛募集要項申込書(docファイル)」
【お申込・お問合せ先】
〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1天満橋千代田ビル2号館9階
日本地質学会 第121年学術大会 現地事務局(株式会社アカデミック・ブレインズ内)
TEL:06-6949-8137,FAX:06-6949-8138,e-mail:gsj2014kagoshima@academicbrains.jp 担当:田中
若手会員のための 業界研究サポート出展募集
若手会員のための業界研究サポート
本年も,「若手会員のための業界研究サポート」を開催いたします.本行事は,地質系企業に興味のある学生・大学院生および指導にあたっている教員の方々を対象とし,地質系企業の現状や求める人材について語り合う交流会を目的としています. 東日本大震災以降,国土強靱化の施策のもとに“防災・減災”と“インフラの維持管理”が重要なキーワードとなっております.この社会的要請に対して地質技術者が不足しており,その人材確保に企業の皆様も苦労されていると思います.また,今後の日本のエネルギー政策として“地熱”・“地下資源”の開発が改めて注目を集めています.実際に企業で活躍されている地質技術者と語り合い,大学で学んだ地質学が企業でどのように生かされているのか,学生・大学院生および教員の方々が,企業の生の声を聴くことができるような場を提供したいと考えています.つきましては,ぜひご参加いただきますようご案内をいたします.
日 程:2014年9月14日(日)9:00-17:00(*時間帯は若干変更になる場合があります)
場 所:鹿児島大学郡元キャンパス共通教育棟1号館132,133
内容:主催者等挨拶・紹介,参加各社による数分のプレゼンテーション.参加各社の個別説明会.
対象:鹿児島大会に参加する学生・院生および大学教員等の会員,鹿児島大学等の学生・院生および教員等
出展予定企業(敬称略.8月8日現在)
(株)地圏総合コンサルタント
日本オイルエンジニアリング(株)
八州開発(株)
川崎地質(株)
中央開発(株)
石油資源開発(株)
応用地貿(株)
住友金属鉱山(株)
(株)建設技術研究所
(株)エイト日本技術開発
問い合わせ先:
日本地質学会 担当理事 緒方信一/事務局 堀内昭子
電話:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156
e-mail: main@geosociety.jp
「若手会員のための業界研究サポート」
(旧:就職支援プログラム)
出 展 募 集
来る9月13日から鹿児島大学において日本地質学会第121年学術大会を開催いたします。本年も、表記「若手会員のための業界研究サポート」を開催することになりました。本行事は、地質企業に興味のある学生・大学院生および指導にあたっている教員の方々を対象とし、地質企業の現状や求める人材について語り合う交流会を目的としています。
東日本大震災以降、国土強靱化の施策のもとに“防災・減災”と“インフラの維持管理”が重要なキーワードとなっております。この社会的要請に対して地質技術者が不足しており、その人材確保に企業の皆様も苦労されていると思います。また、今後の日本のエネルギー政策として“地熱”・“地下資源”の開発が改めて注目を集めています。実際に企業で活躍されている地質技術者と語り合い、大学で学んだ地質学が企業でどのように生かされているのか、学生・大学院生および教員の方々が、企業の生の声を聴くことができるような場を提供したいと考えています。
つきましては、ぜひ本「若手会員のための業界研究サポート」にご参加(出展)いただきますようご案内をいたします。
日 程:2014年9月14日(日)9:00-17:00(*時間帯は若干変更になる場合があります)
場 所:鹿児島大学郡元キャンパス共通教育棟1号館(3階)
主 催:一般社団法人日本地質学会
内 容:主催者等 挨拶・紹介、参加各社による数分のプレゼンテーション.
参加各社の個別説明会(パネル、配布資料等をご用意ください).
対 象:鹿児島大会に参加する学生・院生および大学教官等の会員
鹿児島大学等の学生・院生および教官等
参加費(出展費):無料
参加申込:別紙「参加申込書」を下記日本地質学会宛に8月8日(金)(必着)までにFAX・E-mailでお送りください.スペースに限りがありますので,参加ご希望の場合はお早めにお申し込みください.詳細についてはお申し込み締め切り後にご連絡いたします.
一般社団法人日本地質学会
担当理事 緒方信一
▶出展申込用紙(word) ▶出展申込用紙(PDF)
▶ 2013年仙台大会:就職支援プログラムの様子はこちらから
会員のための 業界研究サポート-2013仙台
第120年仙台大会:若手会員のための業界研究サポート開催報告(2013.9.14開催)
地質学会では,就職希望の学生・院生が民間企業・団体,研究機関と直接に情報交換できる場として就職支援プログラムを企画してきました.今年からは「若手会員のための業界研究サポート」と名称を変えて第7回目の開催になります.名称変更は,経団連の「採用選考に関する企業の倫理憲章」により企業の広報活動開始時期は12月以降とされたことを考慮したものです.本年度も大会2日目の午後2時半から6時まで行い,民間企業8社が参加しました.
会場はポスター会場の前でもあり,例年に比べて学生・院生の参加者が増えました.企業のプレゼンや各ブースで希望の分野やその業界のことを熱心に聞く姿がみられました.今後は就職担当の教員へのアプローチも必要でないかと考えています.
来年度も,就職希望の学生・院生の皆様には,ぜひ会場に足を運んでいただき,企業の採用状況について情報収集していただくようお願いいたします.
最後に,本行事に参加いただいた企業8社の皆様,企画にご協力をいただいた賛助会員,関連企業の皆様,および大会準備委員会・行事委員に,改めて御礼申し上げます.
各社ブースの説明の様子
参加企業・団体一覧(敬称略・申込順):ジーエスアイ株式会社・石油資源開発株式会社・国際石油開発帝石株式会社・日本工営株式会社仙台支店・株式会社建設技術研究所・太平洋セメント株式会社・川崎地質株式会社・株式会社地圏総合コンサルタント
山本高司(運営財政部会担当 執行理事)
事務局主催シニア昼食会のお誘い
事務局主催シニア昼食会のお誘い
鹿児島大会にご参加いただくシニア会員の方々と事務局職員の昼食会を今年も予定しています.
年会の合間のひと時,軽い昼食と近況談義などできれば,楽しいかと思います.ここでのシニアの定義は特にありません.我こそはシニア,私もシニア,シニアではない方も,どなたでもお気軽にお集まり下さい.詳細は,会場内に掲示いたしますのでご覧下さい.
大会中のお知らせ
大会期間中の最新情報・お知らせなど
****鹿児島大会期間中の最新情報やお知らせを掲載予定です****
◆2014.9.12 「県の石」:鹿児島県先行決定!!
日本地質学会では,全国の各都道府県を代表する「岩石」「鉱物」「化石」を指定することを目指しています.そのうち鹿児島県だけは,日本地質学会第121年学術大会が鹿児島市で開催されていることを記念して,鹿児島県の「県の石」を下記の通り先行決定いたしました.
■ 鹿児島県の石:「シラス(主に入戸火砕流堆積物)」
■ 鹿児島県の鉱物:「菱刈金山の金鉱石(自然金)」(2014.9/13.”自然金”を追記)
■ 鹿児島県の化石:「甑島・獅子島の白亜紀動物化石群」
選定理由など詳しくは,こちら(プレス資料PDF)
◆2014.9.12 いよいよ鹿児島大会が始まります
口頭,ポスターあわせて600件以上の発表が予定されています。日本最大の「地質学の祭典」をお楽しみください.
警報等発令時及び地震発生時の対応指針
一般社団法人日本地質学会一般公開行事実施の際の警報等発令時及び地震発生時の対応指針
2014年7月28日
本指針は,日本地質学会のもとに行われる一般公開行事に適用する.
1.行事実施地域に特別警報または暴風警報(以下警報等という)が発令された場合.
(1)一般公開行事開始予定時刻3時間前の時点で,警報等が発令されている場合は,一般公開行事を中止とする.
(2)一般公開行事実施中に警報等が発令された場合は,速やかに行事を中止する.
(3) 一般公開行事の中止の告知は,地質学会ホームページにて行う.またあらかじめ公表した行事に関する問い合わせ先の電話によって対応を行う.
2.地震が発生した場合.
(1) 一般公開行事の最中に地震が発生した場合は,地震の規模や周辺状況を冷静に判断し,第一に参加者の身の安全確保に務める.避難が必要な場合は,揺れがおさまったら,安全な場所に避難誘導する.
(2)会場および周辺に被害が発生し,一般公開行事の続行が困難な場合は中止とする.
(3)一般公開行事開始予定時刻前に地震が発生し,一般公開行事の実施が困難な場合は中止とする.
(4) 一般公開行事の中止の告知は,地質学会ホームページにて行う.またあらかじめ公表した行事に関する問い合わせ先の電話によって対応を行う.
講演申込:その他お知らせ等
トピックセッションの招待講演
トピックセッションの招待招待には前回(仙台大会)と同じルールを適用します.前回,ルールを大きく変更しましたが,その背景については前回の募集記事(本誌16巻1号)をご覧ください.
1)招待講演は1セッションにつき最大2名とし,会員,非会員を問いません.世話人が「自分を招待する」ことは認めません.
2)発表時間(質疑応答を含む)は世話人が15分または30分のいずれかを選択できます.なお,1人の発表者(招待講演者を含む)が1つのセッションで口頭発表できるのは1件です.
3)招待講演者の選定理由とその裏付けとなる情報(セッションテーマに関連した代表的な論文,著書等)が必要です.
4)会員招待講演者が招待講演の他に非招待の発表を1件申し込む場合,発表負担金はかかりません.さらにもう1件(招待講演の他にセッションで2件)発表する場合は負担金がかかります.
長野大会
2015 長野TOP
日本地質学会第122年学術大会(長野大会)
2015年9月11日(金)〜13日(日)
会場:信州大学 長野(工学)キャンパス ほか
共催:信州大学,信州大学理学部,信州大学工学部
後援:長野県地質ボーリング業協会,
(公財)ながの観光コンベンションビューロー
【 開催通知 】
---------------------------------------------------------------------------------------------------
盛会のうち、無事終了いたしました。来年は東京でお会いしましょう。
日本地質学会第123年学術大会(東京・桜上水大会)
2016年 9月10日(土)〜12日(月)
会場:日本大学 桜上水キャンパス(東京都世田谷区)
大会ポスターPDF
(修正版)DLはこちら
2015.9.10
★ 大会期間中の写真や最新情報はこちら ★
[講演に関するご連絡]
・発表者の皆様へ ・ アウトリーチ(OR)及びジオパークセッション(R6)のポスター発表について
・講演キャンセル,プログラム一部変更
[巡検に関するご連絡]
・巡検へ参加される方へ
[その他のご連絡]
・当日の受付について ・会場での注意点 ・締切後の取消と取消料について
・一般公開行事実施の際の警報等発令時及び地震発生時の対応指針
★ 更新情報 ★
2015/09/16
特別講演会「地質地盤情報の利活用と法整備」講演要旨を掲載しましたNEW
2015/09/10
大会ポスター(修正版)を掲載しました
2015/09/03
長野大会に関わるプレス発表を行いました
2015/09/02
特別講演会「地質地盤情報の利活用と法整備」の情報を掲載しました
2015/08/28
地質技術者の皆さん:今年も学術大会でCPD単位が取得できます
2015/08/28
予約確認書・名札等を発送しました
2015/08/27
講演プログラムを掲載しました
2015/08/26
表彰式・受賞記念講演のプログラムを掲載しました
2015/08/26
小さなESのつどい:参加予定校を掲載しました
2015/08/26
若手会員のための業界研究サポート:出展予定企業掲載しました
2015/08/18
事前参加登録の受付は締め切りました.
2015/08/11
巡検の参加申込を締め切りました.全巡検コースを実施予定です
2015/08/10
参加登録画面が一時停止していましたが,復旧しました.
2015/07/22
若手会員のための業界研究サポート:出展企業募集(8/10締切)
2015/07/21
緊急展示(ポスター)を募集します
2015/07/17
全体日程表を公開しました
2015/07/13
巡検各コースの魅力・みどこ情報を更新しました
2015/06/30
講演申込は締切りました
2015/06/24
「地質情報展2015ながの」HPがオープンしました
2015/06/22
大会申込関するQ&Aを掲載しました
2015/06/16
宿泊予約サイト(日本旅行のサイト)がオープンしました
2015/06/16
事前参加登録の受付を開始しました
2015/06/08
キャンセルされた講演要旨の扱いについて
2015/05/29
大会参加等お申込に関わる情報を公開しました.
2015/05/23
講演申込の受付を開始します(5/25 10時オープン)
2015/05/12
講演申込を予定しているが、まだ入会手続きをされていない方へ
2015/05/07
シンポジウム・セッション決定
2015/01/06
長野大会 中部支部信州大学にて開催
トピックセッション募集(締切:3/16)
新着情報
新着情報 2015長野大会
2015.9.10更新 大会ポスター修正版
■■■
長野大会のポスターについて,一部に引用標記の漏れがありましたので,修正いたしました.関係各位にご迷惑をおかけした事を深くお詫び申し上げます.
>大会ポスター(修正版13.7MB)ダウンロードはこちらから
2015.9.10 一般社団法人 日本地質学会
2015.9.8更新 無料シャトルバスを運行します(9.11のみ)
■■■
大会初日(11日)のみ,大学からメルパルク長野(表彰式・懇親会会場)までの直通バス(無料)を運行予定です.ぜひご利用下さい.(信州大学長野(工学)キャンパスから,徒歩の場合は約20分)
運行区間:信州大学長野(工学)キャンパス→メルパルク長野(直通)(注)大学→メルパルクまでの片道運行です.
運行日・時間帯:11日(金)14:00〜16:00(約15分間隔)
乗り場:工学部講義棟近くのロータリー
2015.8.18更新 事前参加登録を締切りました.
■■■
たくさんのお申込をいただき,ありがとうございました.締切後のキャンセルやキャンセル料などについては,こちらをご覧下さい,
2015.8.11更新 巡検申込を締め切りました.
■■■
この度は,長野大会の参加をお申込いただき,ありがとうございます。8/7に巡検の参加申込を締め切りました.今回も多くの皆様にお申込をいただき,現状,全てのコースを実施する予定です(8/11現在)。また,お申込を頂いた方々は皆様ご参加いただけます(定員超過で参加をお断りをするコースはありません)。各コースの詳細については,案内者からのご連絡をお待ち下さい。
2015.8.10更新 参加登録画面が復旧しました.
■■■
参加登録画面が復旧しました。画面の調整作業のため,画面が8/7-8/10の間,一時使用できない状態となっていました。ご迷惑をおかけし大変申し訳ありませんでした.(8/10 10:00現在)
2015.6.22更新 大会申込Q & Aを掲載しました
■■■
講演申込,事前参加登録それぞれに関わるQ&Aを掲載しました。申込の際参考にして下さい。こちら→http://www.geosociety.jp/nagano/content0054.html
2015.6.16更新 事前参加登録受付開始しました。
■■■
日本地質学会第122年学術大会(長野大会)の事前参加登録の受付を開始しました。演題登録受付中です!今年もたくさんの参加・発表申込をお待ちしています。巡検のみ締切が異なりますので,ご注意下さい。 参加申込受付中です。コチラから。
事前参加登録:8/18(火)締切[※巡検のみ 8/7(金)締切]
2015.6.8更新 キャンセルした講演の講演要旨の扱いについて
■■■
学術大会にて発表を申し込まれた講演を講演要旨印刷後にキャンセルした場合,該当講演の要旨は印刷物として存在することになりますが,その発表は全てキャンセルと見なされるので,次年度以降に要旨内容を学術大会で再度講演することができます.このような講演要旨の扱いについてお知らせします.詳しくはこちら
2015.5.29更新 参加登録等,大会予告の情報をアップしました.
■■■
参加登録に関わるお申込(参加,要旨集,巡検,懇親会,弁当)やランチョン,夜間小集会の申込など,大会予告の情報をアップしました.参加申込の受付は,6月初旬より開始の予定です(締切;8/18).今しばらくお待ち下さい.
2015.5.23更新 講演申込の受付を開始します.10時オープン
■■■
25日10時よりをの受付を開始します.シンポジウム,セッションとも演題登録・要旨投稿はオンライン入力フォームに従ってお申込下さい.
締切 6月30日(火)18時です. *郵送の場合は6月24日(水)必着
講演申込・講演要旨投稿はこちらから
2015.5.12更新 講演申込を予定しているが、まだ入会手続きをされていない方へ
■■■
至急、入会申込書を学会事務局宛に郵送して下さい(6月30日必着)。
WEB画面からの講演申込操作は入会申込中でも可能です。入力の際、会員番号欄は空欄のまま操作を進めて下さい。また会員種別欄では『入会申込中』を選択して下さい。
申込締切時点で入会申込書が到着していないと、申込が受理されませんので、必ず入会申込書を郵送して下さい。
2015.5.7更新 シンポジウム・セッション決定
■■■
シンポジウム,セッションが採択されました.まもなく講演申込,事前参 加登録が開始予定です(5月末予定).皆様ぜひ長野大会へご参加下さい.
シンポジウム一覧はこちら セッション一覧はこちら
2015.1.6更新 トピックセッション募集(2015/3/16締切)
■■■
トピックセッション募集締切:2015年3月16日(月)*今年もシンポジウムの公募は行いません。ご注意ください。
詳しくは、こちらから
2015.1.6更新 日本地質学会第122年学術大会(長野大会)開催
■■■
日本地質学会は,中部支部の支援のもと長野市若里の信州大学長野(工学)キャンパスにて,第122年学術大会(2015年長野大会)を9月11日(金)から13日(日)に開催いたします.開催通知はこちらから
シンポジウム一覧
シンポジウム
(2015/5/7掲載,6/30更新)
*各タイトルをクリックすると、詳細をご覧いただけます
シンポジウム
S1.北部フォッサマグナ —東西日本の地質境界:過去,現在,そして未来—
S2.東アジアのテクトニクスと古地理(国際シンポジウム)
S3.法地質学の進歩(国際シンポジウム)*ポスター発表のみ一般公募あり
今大会では3件のシンポジウムを開催します.S3 シンポのポスター発表のみ一般公募を行います.その他のシンポジウム発表は招待講演のみです.いずれの発表も通常のセッション同様,締切までに演題登録・要旨投稿を行って下さい.発表時間は世話人が決定します.シンポジウム発表にはセッション発表における1人1件の制約が及びませんので,シンポジウムで発表する会員は別途セッションにも発表を申し込めます.また,世話人は会員・非会員を問わず招待講演を依頼できます(締め切りました).非会員招待講演者に限り参加登録費を免除します(講演要旨集は付きません).講演要旨はセッション発表と同じ様式・分量です.詳しくは、こちらをご参照ください。
*印は代表世話人(連絡責任者)です.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S1.北部フォッサマグナ —東西日本の地質境界:過去,現在,そして未来—[信州大学山岳科学研究所共催]*発表の一般公募なし
North Fossa Magna : Past, present and future of the geologic boundary between NE and SW Japan Arc.
世話人:原山 智*(信州大:shara@shinshu-u.ac.jp),廣内大助(信州大),常盤哲也(信州大)
Conveners: Satoru Harayama* (Shinshu Univ.), Daisuke Hirouchi (Shinshu Univ.) and Tetsuya Tokiwa (Shinshu Univ.)
およそ130年前にナウマンによって発見・命名されたフォッサマグナは,現在では成因が全く異なる北部フォッサマグナと南部フォッサマグナに区別されている.北部フォッサマグナが東西日本の地質境界とする一般的認識と,先新第三系地帯構造の不連続に基づく棚倉破砕帯境界説との議論は,本邦地質学黎明期からの問題である. 一方,2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震以降,震源から400kmほど離れた北部フォッサマグナ地域でも様々な規模の地震が増加している.この地域では, 2011長野県北部地震(M=6.7),2011長野県中部地震(M5.8),2014長野県北西部地震(M6.7)により,人的・物的被害が生じている.これらの内陸地震は,日本海東縁に沿う東西短縮地殻変形のスナップショットであり,いわゆる日本海東縁プレート境界説との関連を指摘する研究者も少なくない. 本シンポジウムでは,これら地質学的時間スケールで考えるべき学術的課題から,自然災害など人々の生活に直結する現在の問題について,最新の研究成果を総括しつつ異なる手法や多様な視点で検討を行う.
【講演予定者】廣内大助(信州大)・ 佐藤比呂志(東大地震研)・ 原山 智(信州大)・飯尾能久(京大防災研)・高橋雅紀(産総研)ほか
国際シンポジウム:「東アジアの地質」,「法地質学」
International Symposiums on Geology of East Asia and Forensic Geology
オーガナイザー:ウォリス サイモン*(名古屋大: swallis@eps.nagoya-u.ac.jp),保柳康一(信州大: hoya101@shinshu-u.ac.jp)
Organizers: Simon Wallis* (Nagoya Univ.)and Koichi Hoyanagi (Shinshu Univ.)
S2.東アジアのテクトニクスと古地理(国際シンポジウム) [日本古生物学会共催],*発表の一般公募なし
Early Tectonics and Paleogeography of East Asia
世話人:ウォリス サイモン*(名古屋大: swallis@eps.nagoya-u.ac.jp),井龍康文(東北大),Mark Williams (Leicester Univ.),大路樹生(名古屋大),村越直美(信州大)
Conveners: Simon Wallis* (Nagoya Univ.), Yasufumi Iryu (Tohoku Univ.), Mark Williams (Leicester Univ.), Tatsuo Oji (Nagoya Univ.)and Naomi Murakoshi(Shinshu Univ.)
ユーラシア大陸東部から西太平洋縁辺部にかけての東アジアには最高峰をもつヒマラヤ山地と最深部をもつ日本海溝があり,多彩な地形を作っている.このような地形形成は現在の複雑なクトニックス及び長い地質学的な背景がある.このシンポジウムでは, 古地理や関連分野について,日本地質学会と国際交流協定を結んでいる各国の地質学会及び本学会の第一線の研究者を招き講演と討論をおこなうことで、さらなる国際研究交流の活性化につなげると同時に、日本列島を含む東アジアのテクトニックな履歴について意見交換を行う.
From the eastern part of the Himalayan chain to the Japan ocean trench, east Asia contains some of the highest mountains and some of the deepest oceans in the world. The great variation in geomorphology in East Asia reflects the complexity of both the present geological setting and its long geological history. In this symposium we invite experts in paleogeography and related fields from different partner societies and the Geological Society of Japan, with the aim of offering a chance to exchange information on the tectonic history of eastern Asia, including the early geological foundations of the Japanese islands.
【講演予定者】Mark Williams (Leicester Univ.), David Siveter (Leicester Univ.), Thasinee Charoentitirat (Chulalongkorn Univ.), Andrew T-S Lin (National Central Univ., Taiwan),Moonsup Cho (Seoul National Univ.), Yukio Isozaki (Univ. of Tokyo)ほか.
S3.法地質学の進歩(国際シンポジウム) [IUGS-法地質学イニシアチブ,日本法科学技術学会,地質汚染−医療地質−社会地質学会共催]*ポスター発表のみ一般公募あり
Development of Forensic Geology (Cosponsored by JGS, IUGS-IFG, Japanese Association of Forensic Science and Technology (JAFST) andthe Japanese Society of Geo-pollution, Medical Geology and Urban Geology(PMUG))
世話人:杉田律子*(科学警察研究所: sugita@nrips.go.jp)
Ritsuko Sugita* (National Research Institute of Police Science)
本シンポジウムはIUGS法地質学イニシアチブの活動の一環として、欧米の法地質学の専門家により、その歴史から現在の最新の情報まで、幅広く講演をしていただく予定である。主に微細証拠資料としての地質学的試料に着目し、地質学がいかに犯罪捜査を通じて社会に貢献できるかを日本の地質学関係者に知っていただき、研究対象として関心を持っていただくことを目的としている。欧米では大学や民間において法地質学の研究が広く行われており、地学教育にも取り入れられている。日本においても過去数10年にわたり研究が行われてきた分野であるが、地質学界ではやっと知られるようになってきたところである。このシンポジウムをきっかけに、日本の地質学的特徴を活かした、法地質学の研究が広く行われるようになることを期待している。
This symposium forms part of the activities of the IUGS-IFG and aims to provide information on forensic geology from its origins to present day cutting-edge with presentations by forensic geologists from Europe and America. The symposium will focus on discussion of how geological material can be used as forensic evidence and thus contribute to society through helping to solve crimes. Forensic geology is part of the activities both of universities and private companies, and has recently been introduced as part of geological curriculum in some institutes. In Japan this field has been active for several 10s of years, although it has only recently become widely known. We hope this symposium will add to the growing interest in this field and help demonstrate how the geological characteristics of Japan may be used by forensic geologists.
【講演予定者】Raymond Murray (Forensic Geologist, Montana, USA),Alastair Ruffell (Queen's Univ. Belfast, Ireland),Jennifer McKinley (Queen's Univ. Belfast, Ireland),
William M. Schneck (Microvision Northwest - Forensic Consulting, Inc.,Washington),Hiromi Itamiya (NRIPS),Ritsuko Sugita (NRIPS)ほか
↑このページのTOPに戻る
スケジュール(概略)
長野大会に向けてのスケジュール(概略)
122年学術大会(長野大会)に向けてのスケジュールの概略をお知らせします.例年とほぼ同じ日程です.各項目に関して,余裕をもってご準備お願いします.
1月末
(ニュース誌1月号)トピックセッション募集開始
3月16日(月)
トピックセッション募集締切
5月下旬
(ニュース誌5月号) 長野大会予告記事.演題登録・アブスト受付開始
6月下旬
演題登録・講演要旨受付締切.ランチョン・夜間小集会申込締切.
8月上旬
巡検参加申込締切
8月中旬
大会参加登録・懇親会参加申込締切
9月10日(木)
プレ巡検
9月11日(金)〜13日(日)
地質学会第122年学術大会(長野大会)
9月14日(月)〜15日(火)
ポスト巡検
セッション一覧
セッション一覧
※ 本年のレギュラーセッションでは「地域地質・地域層序」と「地域間層序対比と年代層序スケール」が「R5. 地域地質・地域層序・年代層序」に再編し,「堆積相・堆積過程」が「R10. 堆積過程・堆積環境・堆積地質」と名称変更し広く堆積関係の研究を募集することになりました.また,セッションの招待講演者については,こちらをご覧下さい.
下記をクリックすると、各セッションの詳細がご覧頂けます。
トピックセッション(6件)
T1.グリンタフ・ルネサンス
T2.文化地質学
T3.水蒸気噴火と火山体構造
T4.三次元地質モデル研究
T5.泥火山
T6.日本の地球史研究25年
レギュラーセッション(24件)
R1.深成岩・火山岩
R2.岩石・鉱物・鉱床学一般
R3.噴火・火山発達史と噴出物
R4.変成岩とテクトニクス
R5.地域地質・地域層序・年代層序
R6.ジオパーク
R7.海洋地質
R8.堆積物(岩)の起源・組織・組成
R9.炭酸塩岩
R10.堆積過程・堆積環境:堆積地質
R11.石油・石炭地質と有機地球化学
R12.岩石・鉱物の変形と反応
R13.沈み込み帯・陸上付加体
R14.テクトニクス
R15.古生物
R16.ジュラ系+
R17.情報地質とその利活用
R18.環境地質
R19.応用地質・ノンテク構造
R20.地学教育・地学史
R21.第四紀地質
R22.地球史
R23.原子力と地質科学
R24.鉱物資源と地球物質循環
アウトリーチセッション
OR.アウトリーチセッション
*印は代表世話人(連絡責任者)です
トピックセッション:6件
T1.グリーンタフ・ルネサンス/Green Tuff renaissance
天野一男*(茨城大学:ikap[at]cap.ocn.ne.jp),細井 淳(産業技術総合研究所),松原典孝(兵庫県立大学大学院)
Kazuo Amano(Ibaraki Univ.), Jun Hosoi(AIST) and Noritaka Matsubara(Univ. of Hyogo)
日本列島の新生代テクトニクスは,1990年代初頭に古い概念を脱却しプレートテクトニクス理論に基づいて再構築された.しかし,年代論などの新たなデータの蓄積にともない,陳腐化していることは否めない.日本列島新生代テクトニクスの新しいモデルが提唱されてからすでに20年以上が経過しているが,今こそ全面的な見直しを行い,研究のあらたな局面にむかって突破口を開く時期である.
グリーンタフは新生代テクトニクス解明のための鍵となる素材であるが,長年にわたって,その攻略法が不明で研究が停滞していた.近年,火山砕屑岩類の堆積相解析に基づいたグリーンタフ分布地での古火山体の復元などが行われるようになり,新たな研究の展開が期待される.また,日本海の拡大に伴った島弧の回転についても新たなデータが出始めている.
本セッションはグリーンタフを中心として,層序学・構造地質学・岩石学・古地磁気学等,広い視野から検討し,新生代の日本列島テクトニクス研究と島弧進化過程の研究にブレークスルーを図ることを目指している.地域地質学的な話題からグローバルな話題まで,分野を限らずに歓迎する.
【招待講演予定者】星 博幸(愛知教育大),中嶋 健(産総研)
T2.文化地質学/Cultural geology
鈴木寿志*(大谷大:hsuzuki[at]res.otani.ac.jp)・先山 徹(兵庫県立大・院)・石橋弘明(大谷大)
Suzuki, Hisash(Otani Univ.),Tohru Sakiyama(Univ. of Hyogo), Hiroaki Ishibashi(Otani Univ.)
文化地質学は人類の文化・文明が,地質とどのように関わってきたかを研究する学問分野である.いうなれば,人と密接に関わる地質学ということができる.前回の鹿児島大学でのトピックセッションにおいて,初めて文化地質学に関する具体的な研究成果が発表された.講演内容は,おおよそ次のように総括される.(1)地質を素材や資源として活用した事例研究,(2)地質学史や人類史と絡めた研究,(3)京都,鹿児島,但馬地方の地域文化との密接な関わりを論じた研究,(4)博物館などでの普及・教育実践についての研究.
鹿児島での成果を受け,今年の長野大会でも「文化地質学」トピックセッションを開催したい.対象範囲は前年の内容に縛られない.みなさんは地質調査中に現地を歩いていて,興味深い地質の活用事例を見たことはないだろうか.地質学と人々との関わりについて論じたすべての研究発表を歓迎する.
【招待講演予定者】尾池和夫(京都造形芸術大)
T3.水蒸気噴火と火山体構造/Phreatic eruption and related volcanic structures
長谷川 健*(茨城大:hasegawt[at]mx.ibaraki.ac.jp)・及川輝樹(産総研)・竹下欣宏(信州大)
Takeshi Hasegawa(Ibaraki Univ.)・Teruki Oikawa (AIST)・YoshihiroTakeshita(Shinshu Univ.)
水蒸気噴火は.規模が小さいものが多いため堆積物としても残りにくく.個々の火山の噴火史のなかで見落とされる場合が多い.しかし.昨年の御嶽山の事例のように突発的に発生することもあるため.大きな人的被害や社会的影響をもたらすことがある.発生頻度も高く.重要な噴火現象である割には.火山学的にもその理解が進んでいるとはいえない.また.より規模の大きいマグマ噴火の前駆現象として発生する場合もあり.地質学的にその推移を明らかにすることは.防災上も重要である.
本セッションは.火山地質学.層序・編年学.堆積学.岩石・鉱物学.地球化学.構造地質学.あるいは地球物理学などの視点から水蒸気噴火にアプローチした研究発表を募集する.御嶽山噴火に限らず.国内外の火山のケーススタディーを広く募集する.また.水蒸気噴火の発生プロセスを考えるうえでは.地下浅所の熱水系とそれをもたらす火山体構造を把握することが重要課題である.そのため.水蒸気噴火やそれに関連する山体内部構造.特に熱水系の実態なども視野にいれた活発な議論を期待する.
【招待講演予定者】大場司(秋田大),寺田暁彦(東工大)
▲ページtopに戻る
T4.三次元地質モデル研究の新展開/Recent progress on the three-dimensional geological modeling
木村克己*((独)防災科学技術研究所災害リスク研究ユニット(NIED)k.kimura[at]bosai.go.jp)・升本眞二(大阪市大・院)・高野 修(石油資源開発)・根本達也(大阪市大・院)
Katsumi Kimura(Disaster Risk Research Unit, NIED)・Shinji Masumoto(Graduate School of Science, Osaka City Univ.)・Osamu Takano(JAPEX )・Tatsuya Nemoto(Graduate School of Science, Osaka City Univ.)
三次元地質モデリングは,その応用的な有用性から世界各国で注目され,国内では,都市工学,地震防災,石油・資源分野などで研究・開発が進められている.一昨年,地質学雑誌8月号にて「三次元地質モデル研究の新展開に向けて」と題する特集号が発行され,国内外の研究動向,三次元地質モデルの基本理念と地質構造の論理モデル,サーフェスモデルとボクセルモデルの構築方法とその実例,地球統計学的モデリングの概要とその実例,応用分野での活用事例について,研究紹介がなされた.しかし,この数年,航空・地上レーザーなどの三次元計測技術や地上・地下を含めた三次元情報の統合と可視化技術,地球統計学的モデリングなど,三次元地質モデリングの基盤となる研究・技術開発の進歩がめざましい.これらの技術開発を背景に,地震動や地下水広域流動の評価,石油資源探査を目的として,大スケールの地殻構造や海陸シームレスの三次元地質構造モデル,堆積や地質学的不確実性を反映させた地球統計学的モデル,浅部地盤の詳細な三次元モデルなどの具体的な三次元地質モデルの研究成果が発表されてきている.こうした最近の学際的な研究および技術開発の到達点も含めて,三次元地質モデリングに関する最新の研究動向・成果を集約し,今後の地質学的な研究課題を展望する場として本セッションを開催したい.
【招待講演予定者】関口春子(京都大防災研),秋山泰久(国際航業(株))
T5.「泥火山」の新しい研究展開に向けて/Advanced Mud Volcano Studies
浅田美穂*(JAMSTEC:asadam[at]jamstec.go.jp)・土岐知弘(琉球大)・井尻 暁(JAMSTEC)・辻 健(九州大)・森田澄人(産総研)
Miho Asada(JAMSTEC)・Tomohiro Toki(Univ. Ryukyus)・Akira Ijiri(JAMSTEC)・Takeshi Tsuji(Kyushu Univ.)・Sumito Morita(AIST)
世界各地で観察されている泥火山は.地下深部の物質が地表に噴出する地質現象である.それは.深部の流動化した砕屑物を地表まで運搬すると同時に.容易には手にすることのできない貴重な情報を我々にもたらす.泥火山についてはこれまで.堆積・層序学.構造地質学.地球化学.地球物理学.地下微生物学など.多岐にわたる研究分野からのアプローチが試みられ.そのダイナミクスや活動史.起源や成因などが議論されてきた.また近年一部では.間隙流体の起源やその原位置での性状が明らかになってきた.
いま私たちは.泥火山が地下深部物質の「出口」であり.且つ地下の情報を切り開く重要な「入口」となる研究フロンティアであることを共に認識し.泥火山研究を更に発展させて.地下深部情報を利活用するための議論を展開する段階に来た.このために.これまでに蓄積された研究事例を背景に近年の新しい成果をも加え.国内外および海域・陸域を問わず泥火山に関わる研究を集結させて.泥火山研究を次のステップに進めることを目的として本セッションを提案する.
本提案にあたっては.現行過程地質部会および海洋地質部会の両専門部会から後援を受けている.
【招待講演予定者】田中和広(山口大),稲垣史生(JAMSTEC)
T6.地球史から宇宙史へ:日本の地球史研究25年/From geohistory to cosmohistory: A quarter century of Earth history studies in Japan
磯崎行雄*(東京大;isozaki[at]ea.c.u-tokyo.ac.jp)・小宮 剛(東京大)・片山郁夫(広島大)
Yukio Isozaki(The University of Tokyo)・Tsuyoshi Komiya(The University of Tokyo)・Ikuo Katayama(Hiroshima Univ.)
明治以来.約100年間の日本の地質学は.基本的に欧米での研究手法の輸入に明け暮れ.また顕生代日本列島の研究に主眼をおいたため.高圧変成岩や島弧火成岩のような特殊な岩石の産出・記載を除くと.世界の地質学の中での注目度が低かった.また少数行われた国外フィールド研究も世界の趨勢に大きな影響を与えることはなかった.このようないわば「研究植民地」的状況が大きく変わったのは.1990年に積極的に先カンブリア時代地質学の組織的な研究が日本から始まった時だった.それまで日本で蓄積されながらも.外国に十分アピールできていなかった付加体地質学の意義を先カンブリア時代まで拡張して.世界最古の38億年前付加体の発見.太古代初期のプレートテクトニクスの実証.35億年前の最古化石バクテリアの中央海嶺の熱水噴出域起源の認定.地球史を通した地温勾配の変遷.海水のマントル内への逆流など.世界の地球科学界に大きなインパクトを与えた成果を次々にもたらして来た.くしくも2015年は.このような日本における地球史研究の開始から数えて.ちょうど25周年の節目にあたる.日本人研究者によって明らかにされた多様な新知見は.いまや月の地質.火星の地質の理解にも大きく影響し始めており.いよいよ地球史から宇宙史の解読へと発展しようとしている.この機会に.これまでの研究史および成果の整理を行い.現在発展中の研究フロンティアの位置を理解した上で.さらに今後の研究展望を試みる.各分野のレビュー的内容の発表を中心とする.
【招待講演予定者】 B.F. ウインドレー(英・レスター大),戎崎俊一(理研)
▲ページtopに戻る
レギュラーセッション:24件
( )内は責任母体となる専門部会または委員会です.
R1.深成岩・火山岩とマグマプロセス(火山部会・岩石部会)
Plutonic rocks, volcanic rocks and magmatic processes
長谷川 健*(茨城大:hasegawt@mx.ibaraki.ac.jp),高橋俊郎(新潟大)
Takeshi Hasegawa* (Ibaraki Univ.),Toshiro Takahashi (Niigata Univ.)
深成岩および火山岩を対象に,マグマプロセスにアプローチした研究発表を広く募集する.発生から定置・固結に至るまでのマグマの物理・化学的挙動や,テクトニクスとの相互作用について,野外地質学・岩石学・鉱物学・火山学・地球化学・年代学など様々な視点からの活発な議論を期待する.
R2.岩石・鉱物・鉱床学一般(岩石部会)
Petrology, mineralogy and economic geology
壷井基裕*(関西学院大:tsuboimot@kwansei.ac.jp),纐纈佑衣 (名古屋大)
Motohiro Tsuboi* (Kwansei Gakuin Univ.), Yui Kouketsu (Nagoya University)
岩石学,鉱物学,鉱床学,地球化学などの分野をはじめとして,地球・惑星物質科学全般にわたる岩石及び鉱物に関する研究発表を広く募集する.地球構成物質についての多様な研究成果の発表の場となることを期待する.
R3.噴火・火山発達史と噴出物(火山部会)
Eruption, evolution and products of volcanic processes
長井雅史*(防災科研:mnagai@bosai.go.jp),長谷川 健(茨城大),上澤真平(電中研)
Masashi Nagai* (NIED),Takeshi Hasegawa (Ibaraki Univ.),Shinpei Uesawa (CRIEPI)
火山地質ならびに火山現象のモデル化に関し,マグマや熱水流体の上昇過程,噴火様式,噴火経緯,噴出物の移動・運搬・堆積,各火山あるいは火山地域の発達史,火山活動とテクトニクス・化学組成をはじめとする,幅広い視点からの議論を期待する.
▲ページtopに戻る
R4.変成岩とテクトニクス(岩石部会)
Metamorphic rocks and tectonics
小林記之(名古屋学院大:t-koba@ngu.ac.jp)足立達朗(九州大),吉田健太(大阪市大)
Tomoyuki Kobayashi* (Nagoya Gakuin Univ.),Tatsuro Adachi (Kyusyu Univ.),Kenta Yoshida (Osaka City Univ.)
国内および世界各地の変成岩を主な対象に,記載的事項から実験的・理論的考察を含め,またマイクロスケールから大規模テクトニクスまで,様々な地球科学的手法・規模の視点に立った斬新な話題提供と活発な議論を期待する.
【招待講演予定者】板谷徹丸(岡山理科大),廣井美邦(千葉大)
R5.地域地質・地域層序・年代層序(地域地質部会・層序部会)
Regional geology and stratigraphy, chronostratigraphy
松原典孝* (兵庫県立大:matsubara-n@stork.u-hyogo.ac.jp),内野隆之(産総研),岡田 誠 (茨城大)
Noritaka Matsubara* (Univ. Hyogo),Takayuki Uchino (AIST),Makoto Okada (Ibaraki Univ.)
国内外を問わず,地域の地質や層序,および年代層序に関連した発表を広く募集する.年代,化学,分析,リモセン,活構造,地質調査法等の様々な内容の発表を歓迎し,地域を軸にした討論を期待する.発表形式としては,地質図や断面図のポスター発表を特に歓迎する.
R6.ジオパーク(地域地質部会・ジオパーク支援委員会)
Geopark
天野一男*(茨城大:kazuo@mx.ibaraki.ac.jp),高木秀雄(早稲田大),渡辺真人(産総研)
Kazuo Amano* (Ibaraki Univ.),Hideo Takagi (Waseda Univ.),Mahito Watanabe (AIST)
日本のジオパーク活動も7年が経過して,日本ジオパークとして認定された地域は36地域となり,その内の7地域は世界ジオパークに認定されており,これから新たに申請を考えている地域も多い.このような状況下で,ジオパークの質を向上させるための様々な課題が出てきている.ジオパークは,貴重な地質・地形を中心とした各種自然・文化遺産の価値を地元の人が良く理解し保全しながら,地域の教育や経済的振興をめざす事業である.その活動の中心的なものがジオツアーである.このツアーは,学術的な基礎のもとに一般の方を対象として観光を展開するという点で,従来の観光ツアーとは大きく異なる.学術的に質を落とさないで,いかに一般市民に楽しんでもらえるかが重要な課題となる.ジオツアーのインタープリター,ガイドの育成に当たって,地域の大学,博物館,研究所の研究者の協力は不可欠である.この観点から,地質学会として,問題点を整理し,ジオパークの質的向上への貢献に寄与したい.様々な実践例の発表,課題解決方法の提案など広く講演を募集する.
【招待講演予定者】松原典孝(兵庫県立大・院)
▲ページtopに戻る
R7.海洋地質(海洋地質部会)
Marine geology
芦 寿一郎*(東大大気海洋研:ashi@aori.u-tokyo.ac.jp),小原泰彦(海上保安庁),板木拓也(産総研)
Juichiro Ashi* (AORI, Univ. of Tokyo),Yasuhiko Ohara (JCG),Takuya Itaki (AIST)
海洋地質に関連する分野(海域の地質・テクトニクス・変動地形学・海域資源・堆積学・海洋学・古環境学・陸域地質での海洋環境変遷研究など)の研究発表を募集する.調査速報・海底地形地質・画像データなどのポスター発表も歓迎する.
【招待講演予定者】横瀬久芳(熊本大),石橋純一郎(九州大)
R8.堆積物(岩)の起源・組織・組成(堆積地質部会)[共催:日本堆積学会,石油技術協会探鉱技術委員会,日本有機地球化学会]
Origin, texture and composition of sediments
太田 亨*(早稲田大:tohta@toki.waseda.jp),野田 篤(産総研)
Tohru Ohta* (Waseda Univ.),Atsushi Noda (AIST)
砕屑物の生成(風化・侵食・運搬)から堆積岩の形成(堆積・沈降・埋積・続成)まで,組織(粒子径・形態)・組成(粒子・重鉱物・化学・同位体・年代)・物性などの堆積物(岩)の物理的・化学的・力学的性質を対象とし,その起源・形成過程・後背地・古環境や地質体の発達史を議論する.太古代の堆積岩から現世堆積物まで,珪質岩・火山砕屑岩・風成塵・リン酸塩岩・蒸発岩・有機物・硫化物などについての研究も歓迎する.
【招待講演予定者】太田充恒(産総研),大山隆弘(電中研)
R9.炭酸塩岩の起源と地球環境(堆積地質部会)[共催:日本堆積学会,石油技術協会探鉱技術委員会,日本有機地球化学会]
Origin of carbonate rocks and related global environments
山田 努*(東北大:t-yamada@m.tohoku.ac.jp),足立奈津子(鳴門教育大)
Tsutomu Yamada* (Tohoku Univ.),Natsuko Adachi (Naruto Univ. Educ.)
炭酸塩岩・炭酸塩堆積物の堆積作用,組織,構造,層序,岩相,生物相,地球化学,続成作用,ドロマイト化作用など,炭酸塩に関わる広範な研究発表を募集する.また,現世炭酸塩の堆積作用・発達様式,地球化学,生物・生態学的な視点からの研究発表も歓迎する.
▲ページtopに戻る
R10.堆積過程・堆積環境・堆積地質(堆積地質部会・現行地質過程部会)[共催:日本堆積学会,石油技術協会探鉱技術委員会,日本有機地球化学会]
Sedimentary geology, processes and environments
高清水康博*(新潟大:takashimi@ed.niigata-u.ac.jp),西田尚央(産総研),酒井哲弥(島根大)
Yasuhiro Takashimizu* (Niigata Univ.), Naohisa Nishida (AIST), Tetsuya Sakai (Shimane Univ.)
野外観察や室内実験によって堆積粒子の挙動や堆積物形成過程について検討した研究や,堆積物が形成される場としての環境(砂丘を含む風成環境,湖沼,河川,沿岸,陸棚,深海など)の特徴について,堆積学的手法や各種分析・測定によって検討した研究を広く募集する.また,露頭観察や得られた試資料に基づく堆積システムや地層形成のダイナミクスに関する研究を歓迎する.前年までの「堆積相・堆積過程」セッションを引き継ぐ.
【招待講演予定者】伊藤 慎(千葉大)
R11.石油・石炭地質学と有機地球化学(石油石炭関係・堆積地質部会)[共催:石油技術協会探鉱技術委員会,日本有機地球化学会,日本堆積学会]
Geology and geochemistry of petroleum and coal
金子信行*(産総研:nobu-kaneko@aist.go.jp),千代延仁子(石油資源開発),三瓶良和(島根大)
Nobuyuki Kaneko* (AIST),Satoko Chiyonobu (JAPEX),Yoshikazu Sampei (Shimane Univ.)
国内外の石油・石炭地質および有機地球化学に関する講演を集め,石油・天然ガス・石炭鉱床の成因・産状・探査手法など,特にトラップ構造,堆積盆,堆積環境,貯留岩,根源岩,石油システム,資源量,炭化度などについて討論する.
【招待講演予定者】奥井明彦(出光オイルアンドガス(株)),森田澄人(産総研)
R12.岩石・鉱物の変形と反応(構造地質部会・岩石部会)
Deformation and reactions of rocks and minerals
高橋美紀*(産総研:miki.takahashi@aist.go.jp),廣瀬丈洋(JAMSTEC),大坪 誠(産総研),水上知行(金沢大)
Miki Takahashi* (AIST), Takehiro Hirose (JAMSTEC), Makoto Otsubo (AIST), Tomoyuki Mizukami (Kanazawa Univ.)
岩石・鉱物の変形(破壊,摩擦,流動現象)と反応(物質移動,相変化)およびその相互作用を,観察・分析・実験を通じて物理・化学的な側面から包括的に理解し,地球表層から内部における地質現象の解明を目指す.地質学,岩石学,鉱物学,地球化学など様々な視点・アプローチによる成果をもとに議論する.
【招待講演予定者】大内智博(愛媛大),片山郁夫(広島大)
▲ページtopに戻る
R13.沈み込み帯・陸上付加体(構造地質部会・海洋地質部会)
Subduction zones and on-land accretionary complexes
氏家恒太郎*(筑波大:kujiie@geol.tsukuba.ac.jp),橋本善孝(高知大),坂口有人(山口大),中村恭之(JAMSTEC)
Kohtaro Ujiie* (Univ. Tsukuba),Yoshitaka Hashimoto (Kochi Univ.),Arito Sakaguchi (Yamaguchi Univ.),Yasuyuki Nakamura (JAMSTEC)
沈み込み帯・陸上付加体に関するあらゆる分野からの研究を歓迎する.野外調査,微細構造観察,分析,実験,理論,モデリングのみならず海洋における反射法地震探査,地球物理観測,地球化学分析,微生物活動など多様なアプローチに基づいた活発な議論を展開したい.次世代の沈み込み帯・陸上付加体研究者を育てるべく,学生による研究発表も大いに歓迎する.
【招待講演予定者】ウォリス サイモン(名古屋大),山下幹也(JAMSTEC)
R14.テクトニクス(構造地質部会)
Tectonics
武藤 潤*(東北大:muto@m.tohoku.ac.jp),安江健一(JAEA),針金由美子(産総研)
Jun Muto* (Tohoku Univ.),Ken-ichi Yasue (JAEA),Yumiko Harigane (AIST)
陸上から海洋における野外調査や各種観測の他,実験や理論などに基づき,日本や世界各地に発達するあらゆる地質体の構造,成因,形成過程や発達史に関する講演を募集する.また,現在進行している地殻変形や活構造に関する研究成果も歓迎する.
【招待講演予定者】田上高広(京都大)
R15.古生物(古生物部会)
Paleontology
生形貴男(京都大),太田泰弘(北九州博),三枝春生(兵庫県立人と自然の博),上松佐知子*(筑波大:agematsu@geol.tsukuba.ac.jp)
Takao Ubukata (Kyoto Univ.),Yasuhiro Ota (Kitakyushu Museum),Haruo Saegusa (Mus. Nature and Human Activities, Hyogo),Sachiko Agematsu* (Tsukuba Univ.)
主として古生物を扱った,または,プロキシとして古生物を利用したものや古生物を用いた新手法などの研究の発表・討論を行う.
▲ページtopに戻る
R16.ジュラ系+(古生物部会)
The Jurassic +
松岡 篤*(新潟大:amatsuoka@geo.sc.niigata-u.ac.jp)近藤康生(高知大),小松俊文(熊本大),石田直人(明治大),中田健太郎(城西大)
Atsushi Matsuoka* (Niigata Univ.),Yasuo Kondo (Kochi Univ.),Toshifumi Komatsu (Kumamoto Univ.),Naoto Ishida (Meiji Univ.),Kentaro Nakada(Josai Univ.)
2003年の静岡大会において「ジュラ系」として誕生した本セッションは,隣接する地質系統の研究者の要望を取り込んで「ジュラ系+」として発展し,10年間にわたりトピックセッションとしてを継続開催されてきた.この間,ジュラ系の研究を中心に,関連する講演がまとまって発表される場として定着し,ジュラ系研究の情報を研究者の間で共有することに貢献してきた.この10年の活動は,地質学雑誌の特集『トピックセッション「ジュラ系+」の10年』として結実した.2015年2月号には,「(その1)日本のジュラ系」が,同3月号には「(その2)ジュラ系研究の将来展望」が掲載されている.「ジュラ系+」は,2013年からは古生物部会のセッションとして,新たなスタートを切っている.本セッションでは,ジュラ系と上下の地質系統の研究について,各方面からのデータを提供しあい,多角的に検討する場を提供する.このことは,日本からの国際発信力を強化することにも寄与する.なお2018年には,第10回国際ジュラ系会議がメキシコで開催される.
【招待講演予定者】伊庭靖弘(北海道大)
R17.情報地質とその利活用(情報地質部会・地域地質部会)
Geoinformatics and its application
野々垣 進*(産総研:s-nonogaki@aist.go.jp),斎藤 眞(産総研)
Susumu Nonogaki* (AIST),Makoto Saito (AIST)
地質情報の取得,デジタル化,データ処理,画像処理,数理解析,統計解析,データベース管理,SNSを含むWebによる発信・共有などに関する理論・技術・システム開発など,情報地質分野の研究成果を広く募集する.さらに,これらの成果から得られた地質情報の利活用事例,利活用における問題点,比較検討などの研究発表を募集する.
R18.環境地質(環境地質部会)[共催:地質汚染−医療地質−社会地質学会]
Environmental geology
難波謙二(福島大),風岡 修(千葉環境研),三田村宗樹(大阪市大),田村嘉之*(千葉県環境財団)
Kenji Nanba (Fukushima Univ.),Osamu Kazaoka (Res. Inst. Environ. Geol., Chiba),Muneki Mitamura (Osaka City Univ.),Yoshiyuki Tamura* (Chiba Pref. Environ. Foundation)
地質汚染,医療地質,地盤沈下,湧水,水資源,湖沼・河川,都市環境問題,法地質学,環境教育,地震動,液状化・流動化,地震災害,岩盤崩落など,環境地質に関係する全ての研究の発表・討論を行う.
【招待講演予定者】中屋眞司(信州大)
▲ページtopに戻る
R19.応用地質学一般およびノンテクトニック構造(応用地質部会)
Engineering geology and non-tectonic structures
西山賢一(徳島大),亀高正男*((株)ダイヤコンサルタント)須藤 宏(応用地質(株))
Ken-ichi Nishiyama (Tokushima Univ.),Masao Kametaka* (Dia Consultants),Hiroshi Sudo (OYO Corp.)
応用地質学一般では,種々の地質ハザードの実態,調査,解析,災害予測,ハザードマップの事例・構築方法,土木構造物の設計・施工・維持管理に関する調査,解析など,応用地質学的視点に立った幅広い研究を対象とする.また,ノンテクトニック構造では,ランドスライドや地震による一過性の構造,重力性の構造等の記載,テクトニック構造との区別や比較・応用等の研究を対象にして発表・議論する.
【招待講演予定者】佐々木靖人(土木研),近藤久雄(産総研)
R20.地学教育・地学史(地学教育委員会)
Geoscience Education/History of Geoscience
矢島道子*(東京医科歯科大:pxi02070@nifty.ne.jp),三次徳二(大分大)
Michiko Yajima* (Tokyo Medical and Dental Univ.),Tokuji Mitsugi (Oita Univ.)
地学教育,地学史に関わる研究発表を広く募集する.新学習指導要領についての教育現場からの問題提起や,実践報告に加え,大学や博物館,研究所等が行うアウトリーチに関わる実践報告についても歓迎する.また地学史からの問題提起,貴重な史的財産の開示を歓迎する.
R21.第四紀地質(第四紀地質部会)
Quaternary geology
公文富士夫*(信州大:shkumon@gipac.shinshu-u.ac.jp),竹下欣宏(信州大)
Fujio Kumon* (Shinshu Univ.),Yoshihiro Takeshita (Shinshu Univ.)
第四紀地質に関する全ての分野(環境変動・気候変動・湖沼堆積物・地域層序など)からの発表を含む.また,新しい調査や研究,方法の開発や調査速報なども歓迎する.
▲ページtopに戻る
R22.地球史(環境変動史部会)
History of the Earth
清川昌一*(九州大:kiyokawa@geo.kyushu-u.ac.jp),山口耕生(東邦大),小宮 剛(東京大),尾上哲治(熊本大),須藤 斎(名古屋大)
Shoichi Kiyokawa* (Kyushu Univ.),Kosei Yamaguchi (Toho Univ.),Tsuyoshi Komiya (Univ. Tokyo),Onoe Tetsuji (Kumamoto Univ.),Itsuki Suto (Nagoya Univ.)
地球史では,火山活動などの地球内部の突発的な活動や,太陽活動やミランコビッチサイクルや・隕石衝突など地球外要因の影響により,表層大気や生物活動などが大きく変化している.これらの記録は地層や化石などに記憶されており,これらを様々な手法により紐解くことで,地球史上での変動を明らかしている.本セッションでは,それぞれの時代を地球史の視点で考え,また,他の時代との相違点や共通点を認識していくことを目標に,地球史上に残される環境変動や地殻変動について議論していく.
【招待講演予定者】前野 深(東京大地震研)
R23.原子力と地質科学(地質環境の長期安定性研究委員会)[共催:日本原子力学会バックエンド部会]
Nuclear energy and geological sciences
吉田英一*(名古屋大:dora@num.nagoya-u.ac.jp),梅田浩司(日本原子力研究開発機構),高橋正樹(日本大),渡部芳夫(産総研)
Hidekazu Yoshida* (Nagoya Univ.),Koji Umeda (JAEA),Masaki Takahashi (Nihon Univ.),Yoshio Watanabe (AIST)
原子力は,ウラン資源探査,活断層等を考慮した耐震安全性評価,廃棄物の地層処分,放射性物質の環境動態等の多くの地質科学的課題を有している.本セッション「原子力と地質科学(Nuclear Energy and Geological Sciences)」は,このような日本の原子力に関わる地質科学的課題について,地球科学的知見の議論及び関連する学会や研究者間の意見交換を行うことを目的としており,幅広い分野からの参加,発表を歓迎する.
【招待講演予定者】山崎晴雄(首都大)
R24.鉱物資源と地球物質循環(鉱物資源部会)
Mineral resources and global material cycles
加藤泰浩*(東京大:ykato@sys.t.u-tokyo.ac.jp),岩森 光(JAMSTEC),中村謙太郎(東京大)Yasuhiro Kato* (Univ. Tokyo),Hikaru Iwamori (JAMSTEC),Kentaro Nakamura (Univ. Tokyo)
近年,海底鉱物資源をはじめとする新しい資源の開発に向けた動きが活発化し,鉱物資源への注目が高まっている.鉱物資源の形成過程に関わる様々な元素の輸送・濃集過程は,ダイナミックな地球における物質循環と分化の一部に他ならず,鉱物資源の成因を考える上では,地球全体にまたがるグローバルな物質循環とその変遷,そしてその資源形成との関わりについての包括的な理解が不可欠である.本セッションでは,鉱物資源そのものに加え,これまで着目されることが少なかった資源形成をとりまく地球表層-内部環境,テクトニックセッティング,ダイナミクスと,資源の形成メカニズムとの関わりについても,グローバルに議論する場を提供したい.
【招待講演予定者】小宮 剛(東京大)
▲ページtopに戻る
アウトリーチセッション
OR. 日本地質学会アウトリーチセッション(一般公開,ポスター発表のみ)
Outreach session
星 博幸*(愛知教育大:hoshi[at]auecc.aichi-edu.ac.jp)・須藤 斎(名古屋大)
Hiroyuki Hoshi* (Aichi Univ. Education) and Itsuki Suto (Nagoya Univ.)
研究成果を社会に発信する場として設けられたセッション.地質学と関連分野を対象とし,開催地(中部地方,長野)とその周辺の地質や地学にかんする研究紹介,社会的に注目されている地質および関連トピックの研究紹介,特定分野の研究到達点や課題の解説など.客層は会員(専門家)ではなく市民であることに注意.市民講演会の会場で開催する.申込多数の場合は行事委員会にて採否を検討する.
▲ページtopに戻る
申込先・締切一覧
各種申込先・締切一覧
※※※ 「巡検」のみ参加申込締切が大会参加登録等と異なります.ご注意下さい ※※※
WEB
FAX・郵送
申込・問合先
講演申込(演題登録)
6/30(火)18時
6/24(水)必着
詳細
行事委員会
講演要旨原稿提出
6/30(火)18時
6/24(水)必着
詳細
行事委員会
緊急展示の発表申込
8/31(月)
詳細
行事委員会
事前参加登録
8/18(火)18時
8/14(金)必着
詳細
学会事務局
巡 検
8/7(金)18時
8/5(水)必着
詳細
学会事務局
懇親会・お弁当
8/18(火)18時
8/14(金)必着
詳細
学会事務局
追加講演要旨
8/18(火)18時
8/14(金)必着
詳細
学会事務局
託児室
8/21(金)
-------
詳細
現地事務局(日本旅行)
生徒地学研究発表会
(小さなESのつどい)
7/16(木)
-------
詳細
地学教育委員会
業界研究サポート
8/10(月)
詳細
学会事務局
ランチョン・夜間小集会
6/24(水)
-------
詳細
行事委員会
一次締切
最終締切
広告協賛
-------
8/7(金)18時
詳細
現地事務局(日本旅行)
企業展示への出展
7/3(金)18時
8/7(金)18時
詳細
現地事務局(日本旅行)
書籍・販売ブース
7/3(金)18時
8/7(金)18時
詳細
現地事務局(日本旅行)
発表要領(シンポ・セッション共通)
発表要領 シンポ・セッション共通
発表要領
(1)口頭発表
1)セッションの発表時間は, 招待講演を除き,トピック・レギュラーとも1題15分です(討論時間3〜5分を含む).シンポジウムの発表時間は世話人が決めます.発表者は討論時間を必ず確保して下さい.なお,今大会でもPCセンターを設置しません.シンポ・セッションが円滑に進むように次の注意点をよくご確認下さい.
2)発表はできるだけ会場備え付けのWindowsパソコン(OSはWindows 7;PowerPoint 2007,2010, 2013対応)をご使用下さい(ただし,Macご利用の方と動画を使用する方はご自身のパソコンをご用意下さい).プロジェクター解像度は1024×768ドット(XGA)です.パワーポイント・ファイルをUSBフラッシュメモリで持参し,パソコンにコピーして下さい(シンポ・セッション終了後,世話人がファイルを削除します).フォントは特殊なものではなく,PowerPointに設定されている標準的なものを使用して下さい. 発表者は,シンポ・セッション開始前に発表会場で正常に投影されることを確認して下さい.
3)ご自身のパソコンで発表する方も,シンポ・セッション開始前に発表会場において正常に接続・投影されることを確認して下さい.事前に解像度(上記)の設定をご確認下さい.会場の接続端子はD-sub15ピン(ミニ)です.パソコンによってはコネクタが必要になる場合がありますので必ずご持参下さい(会場にはありません).確認作業の混雑とそれによる講演開始の遅れを防ぐため,早めの確認作業をお願いします.なお, 発表者が事前確認を怠ったために発表時にトラブルが生じても時間延長等の措置は取りません.
(2)ポスター発表
1)1日間掲示できます.コアタイムでは必ずポスターの説明を行って下さい.ポスター設置・撤去等については本誌8月号掲載予定のプログラム記事をご覧下さい.
2)ボード面積は1題あたり縦210 cm,横90 cmです.
3)発表番号,発表タイトル,発表者名をポスターに明記して下さい.
4)コンピューターによる演示等も許可しますが,機材等はすべて発表者が準備して下さい.また,電源は確保できませんので,必要であれば予備のバッテリーを用意して下さい.発表申込の際に機器使用の有無や小机の必要性等をコメント欄に記入し,事前に世話人にもご相談下さい.
5)運営規則第16条2項(8)により,優れたポスター発表に対して「日本地質学会優秀ポスター賞」を授与します.詳細はプログラム記事(本誌8月号)に掲載します.
(3)発表者の変更
あらかじめ連記されている共同発表者内での変更は認めますが,必ず事前に行事委員会に連絡して下さい.この場合もセッション発表者については発表に関する条件・制約を適用します.
(4)口頭発表の座長依頼
各セッション会場の座長を発表者に依頼することがあります.その際はご協力をお願いします.
確認書・クーポン等の送付について
事前参加登録:確認書・クーポン等の送付について
事前参加申込を頂いた方に対して、申込内容に応じて確認書2枚(本人控・受付提出用)等をお送り致しました(8/28発送)。
受付提出用の確認書、名札、クーポン(懇親会・弁当用)を当日忘れずにご持参下さい。
※参加者数を把握するため、参加登録費が無料の方(名誉会員・50年会員・学部学生)も受付提出用の確認書を大会当日の受付へご提出ください。
<< 入金者の方へ >>
確認書2枚(本人控・受付提出用)・記名名札・クーポン(懇親会・お弁当を予約された方のみ)をお送りしました。当日必ずご持参下さい。
ネームカードホルダーと、それぞれ申し込み内容に応じて冊子等をお渡しいたします。
受付提出用の確認書がない場合には、受付に時間がかかりますので必ずご持参ください。
クーポンは懇親会会場入り口、お弁当引換時にそれぞれ提示してください。
<< 一部入金・未入金の方へ >>
確認書発送時点で一部入金もしくは、入金確認が取れていない方へは当日払いの参加費に金額訂正した確認書のみをお送りしております。当日必ずご持参ください。
※入金確認まで、時間がかかる場合がありますので、入金と入れ違いの場合はご容赦ください。
当日学会デスクにて入金のご確認をさせて頂きますので、振込み時の控え等をご持参下さい.確認がスムーズに行えます.
お支払いがまだの方は、9月7日(月)までに下記いずれかへお振り込みをお願い致します。この場合も振込み時の控え等をご持参下さい。
7日までにお振込いただけなかった場合は、当日学会デスクにてご清算をお願い致します。
振込先 (注意:振込時には、振込者氏名の前に必ず申込Noを入力して下さい)
(1)三井住友銀行 神田駅前支店(普通)1711424
(社)日本地質学会 / シャ)ニホンチシツガッカイ
(2)郵便振替 00140-8-28067
一般社団法人日本地質学会
表彰式・記念講演会
会員顕彰式・各賞授与式・受賞記念講演
日程:9月11日(金)16:00〜18:00
会場:メルパルク長野
16:00〜16:10
会長挨拶,来賓挨拶(赤羽貞幸 信州大学副学長)
16:10〜16:25
Geological Society Located in Taipei・Geological Society of Japan 学術交流協定調印式
16:25〜17:15
名誉会員証授与,50年会員顕彰,各賞授与式
17:15〜17:30
日本地質学会小澤儀明賞受賞スピーチ:
辻 健会員「地質学に貢献する地震探査」
17:30〜18:00
日本地質学会賞受賞講演:
脇田浩二会員「地質図とともに−付加体地質図とシームレス地質図−」
*工学→メルパルクまでの無料シャトルバスを運行します(9/11のみ運行)
大会初日(11日)のみ,大学からメルパルク長野(表彰式・懇親会会場)までの直通バス(無料)を運行予定です.
ぜひご利用下さい.(信州大学長野(工学)キャンパスから,徒歩の場合は約20分)
運行区間:信州大学長野(工学)キャンパス→メルパルク長野(直通)(注)大学→メルパルクまでの片道運行です.
運行日・時間帯:11日(金)14:00〜16:00(約15分間隔)
乗り場:工学部講義棟近くのロータリー
参加登録TOP
2015長野大会事前参加登録のご案内
事前参加登録は8月18日(火)18時で締切りました
オンライン:8月18日(火)18:00,
FAX/郵送:8月14日(金)必着
[下のフローチャートから申込手続き行って下さい]
[お詫び]
参加登録画面が復旧しました。画面の調整作業のため,画面が一時使用できない状態となっていました。
ご迷惑をおかけし大変申し訳ありませんでした.(8/10 10:00現在)
参加登録に関わるお申込(参加,要旨集,巡検,懇親会,弁当)は,オンラインによる大会専用参加登録システム(会員・非会員にかかわらずどなたでも申込可)をご利用の上,お申し込み下さい.郵送・FAXでのお申込を希望される方は,学会事務局(電話 03-5823-1150)までご連絡ください.
大会参加登録およびそれに伴う参加費は,参加者(巡検のみ参加の場合も)に必要な基本的なお申し込みです.会員が同伴する非会員の家族等(以下,同伴者)についても懇親会・巡検・お弁当については事前に申込が必要です.申込は,会員と同伴者の計2名まで一括申込が可能です.なお,学会を通じての宿泊・交通手配の斡旋は行いません.宿泊や交通については各自で手配願います.
下のフローチャートに従って進み,該当する申込画面をクリックして
それぞれ申込手続きをおこなって下さい.
画面 A へ
事前参加登録は締め切りました
画面 B へ
巡検の申込は締切りました
画面 C へ
講演要旨の予約注文は
締め切りました
※巡検協賛学協会・セッション共催団体リスト
参考>>会員情報を自動取得するには?(PDF)
当日の受付について
当日の受付について
総合受付では,初日朝8:30から受付を開始します。大会初日は受付混雑が予想されます。時間に余裕をもってお出かけ下さい。万一受付混雑のため講演に間に合わない場合は,直接講演会場へご入場下さい。受付手続きは講演後に必ず行って下さい。
■ 事前参加登録をされた方
【入金済みの事前登録者】
事前参加登録につきましてはお申込みを8月17日にすべて締め切りました.
確認書2枚(本人控・受付提出用)と名札,懇親会とお弁当を予約の方にはそれぞれクーポンをお送りします.大会開催10日前頃には,皆様のお手元に届くようお送りします.確認書を当日会場へ持参してください.注1).※確認書やクーポン等を8月末に発送予定です.
【確認書発送時点で入金確認が取れない場合】
請求金額は当日払いの金額に変更になります.また,大会10 日前頃までに未入金の旨記載された確認書のみ送付いたします注2).当日会場にて確認書をご提示いただき,代金の清算をして下さい.期日を過ぎて入金された場合でも,会場にて差額分のご精算をお願いします.その際は,入金時の控え等を会場にお持ちください.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
事前登録者用受付にて,確認書に記載されている項目ごとに受付して下さい.
受付にてネームカードホルダーをお渡ししますので『参加証(名札)』を入れ,大会期間中は身に付けてください.
1.確認書の提出(全員)→ネームカードホルダーの配布.要旨付きの場合は,要旨の配布
2.講演要旨追加購入(予約購入者のみ)→要旨の配布
3.懇親会→参加者は直接懇親会会場でクーポンを提示してご入場ください.
4.お弁当(予約者のみ)→お弁当の引換所にてクーポンを提示して,引き換えてください.
5.巡検(参加者のみ)→名簿確認と参加最終確認
注1)当日確認書やクーポンを忘れた方は,専用の用紙に申込内容をご記入いただき,受け付けを済ませてください.確認がスムーズに行えますよう,ご協力をお願い致します.
注2)未入金の方には,会場受付での入金確認後,懇親会やお弁当のクーポンをお渡しします.
→申込の取消・取消料についてはこちらから
■ 事前登録をしていない方(当日受付)
1.当日は必ず参加登録をしてください.参加登録費の有料・無料に関わらず備え付けの『参加登録票』に必要事項を記入し当日用受付にて受付して下さい.
2.当日参加登録費(講演要旨集付きです.要旨集が不要の場合でも割引はありません)
正会員:9,500 円
院生割引会費適用正会員:6,500 円
学部 学生割引適用正会員・名誉会員・50 年会員・非会員招待講演者・学部学生(会員・非会員問わず):無料(講演要旨は付きません)
非会員(一般):15,000 円
非会員(院生):9,500 円
3.講演要旨当日販売
会員:4,000 円
非会員:5,500 円
4.懇親会の当日参加費(ただし,人数に余裕がある場合に限る)
正会員・非会員(一般):7,000 円
名誉 会員・50年会員・院生および学生割引適用正会員(家族および非会員院生・学生含):4,000 円
別途領収書が必要な方は会場受付でその旨お申し出ください.当日のお支払いは,現金のみの取扱いとなります.クレジットカードはご利用いただけません.
申込方法と支払について
各種申込とお支払について
<申込締切 オンライン:8月18日(火)18:00,FAX/郵送:8月14日(金)必着>
■事前参加申込は締切ました■
(1)申込方法
1)参加登録システム(オンライン)による申込(申込締切 8月18日(火)18:00)
大会専用参加登録システムへアクセスし,画面表示に従って入力をして下さい(6 月初旬より受付開始です). 申込み完了後,「申込確認メール」および「ご請求メール」が登録のメールアドレスへ配信されます.内容を必ずご確認下さい.お支払いは,銀行振込またはクレジットカード決済のいずれかを選択できます.「銀行振込」を選択された方は,「ご請求」メールを確認の上,指定の金融機関よりお振込み下さい.「クレジット決済」を選択の場合は,ご利用のカード会社の期日に合わせて,口座より引き落としとなります.クレジットカード会社からの明細には「日本地質学会(ニホンチシツガッカイ)」と表示されます.
2)FAX・郵送による申込(申込締切:8月14日(金)必着) 「FAX・郵送専用申込書」(p.(XX))に必要事項を記入の上,学会事務局までFAXまたは郵送にてお申込み下さい.電話による申込,変更などは受け付けられません.また,郵送による申込みの際は,必ず申込書のコピーを各自で保管して下さい. 申込後,折返し学会より「受付番号」を記した「受付確認」をe-mailまたはFAXにてお送りします.必ずご確認下さい.「受付確認」が届かない場合は,必ず事務局までご連絡下さい.この「受付番号」はその後の問い合せ,変更,取消等に必要となります. お支払いは,銀行振込またはクレジットカード決済のいずれかを選択できます.申込後順次,「予約内容確認」・「請求書」をお送りします.銀行振込を選択された方は,請求書に記載されている振込口座へ指定期日までにお振込み下さい.クレジット決済を選択された方は,参加申込書に必ずクレジット番号などの必要事項を記入して下さい.ご利用のカード会社の期日に合わせて,口座よりお引き落としとなります.カード会社からの明細には「日本地質学会(ニホンチシツガッカイ)」と表示されます. 申込先 申込書に必要事項を記入の上,下記宛にお送り下さい.
[送付先]〒101-0032東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル6階
「日本地質学会長野大会参加申込係」 FAX:03-5823-1156
オンライン,FAX,郵送いずれの申込も締切後,名札・確認書・クーポン(一部の方)を発送します(8月末頃発送予定).大会開催10日前までには参加者の皆様のお手元に届くようお送り致します.
(注意)締切時点で入金確認が取れない場合:請求金額は,「当日払い」の金額となり,未入金旨記載された確認書のみが送付されます(名札・クーポンは送付されません).入金とクーポン発送が入れ違いの場合は,入金(振込)時の控え等を会場にお持ち下さい.ご協力をお願い致します.
(2)申込後の変更・取消
1)参加登録システム(オンライン)でお申込みの場合:
締切までの間は,大会登録専用HPから予約の変更・取消が出来ます.変更・取消完了後,「変更・修正 確認メール」が登録のメールアドレスへ配信されます.内容を必ずご確認下さい.締切後は直接学会事務局(東京)にFAX又はe-mailにてご連絡下さい(大会会期中はこちらにご連絡下さい).お支払いがクレジット決済の場合は,申込の都度決済が完了します.決済スケジュールの都合によっては,口座から重複して引き落とされる場合があります.その場合は,振込手数料を差し引いた額をクレジットカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2〜3ヶ月要する場合もありますので,ご了承下さい.
2)FAX・郵送でお申込み場合:
申込後に変更・取消が生じた場合は,学会事務局(東京)にFAXまたはe-mailにてご連絡下さい.その際申込受付時に案内される「受付番号」・「氏名」を必ず明記下さい.
(3)取消に関わる取消料と返金について
下記の通り,申込項目により取消料が異なります.
締切日
(8/18)まで
大会3日前
(9/8)まで
大会2日前
(9/9)以降
参加登録費
0%
60%
100%
追加要旨
0%
60%
100%
懇親会
0%
100%
100%
弁 当
0%
50%
100%
巡 検
0%
50%
100%
参加登録費
参加登録費
○参加登録費(講演要旨集付です)
事前申込
当日払い
備考
正会員
7,500円
9,500円
講演要旨集付き
院生割引適用正会員
4,500円
6,500円
講演要旨集付き
学部制割引適用正会員・名誉会員・50年会員
非会員学部学生・非会員招待者・同伴者
無料
無料
講演要旨集は付きません
非会員(一般)
12,500円
15,000円
講演要旨集付き
非会員(院生)
7,000円
9,500円
講演要旨集付き
※参加費有料の方には必ず要旨集1冊が付きます.講演要旨集が不要の場合でも割引はありません.
※講演要旨集の付かない方はご希望に応じて別途購入して下さい.
※日本地質学会の会員資格は『正会員』のみであり,割引会費の申請をした方についてのみ,割引会費が適用されています.
※セッション共催団体および巡検協賛団体会員の参加登録費は地質学会会員に準じます.
要旨集予約頒布
講演要旨集の予約頒布
参加費無料の方は要旨集が付きません.要旨が必要な方は,参加登録時に追加講演要旨集の申込をして下さい.複数の講演要旨集を追加購入頂くこともできます.受け取り方法には,(1)大会後に送付(要別途送料*)(2)会場で受取 があります.大会へ参加しない方も要旨のみ事前予約できます(大会後に送付).
事前予約(/冊)
当日販売(/冊)
会員
3,000円
4,000円
非会員
4,000円
5,500円
*「大会後に送付」の場合の送料は以下の通りです.
送料:1冊 500円,2冊 600円,3冊 800円,4冊 1,000円,5冊 1,200円
巡検参加申込
巡検に関するご連絡
○ 巡検案内書は,例年冊子体は作成せずCD-ROMで発行しておりましたが,今大会では地質学雑誌121巻7号および8号(2015年7月および8月号)に掲載いたします.また,J-STAGE にて公開をいたします.
○ 巡検参加者には各参加コース箇所の巡検案内書を巡検当日に配布します.
○ 重 要 巡検へ参加される方は,参加の前に是非「野外見学,調査,試料採取における注意喚起」をご一読下さい。
「野外調査において心がけたいこと」国立・国定公園や史跡・名勝・天然記念物、あるいは一般的な露頭における調査上の注意点
「安全のしおり(巡検案内書より)」巡検や野外調査における安全上の注意点と自然保護に関する注意点
「巡検案内書を頼りに野外調査へ出かける方へ」露頭での調査や試料採取にあたっての注意点(「野外調査において心がけたいこと」から一部抜粋)
巡検参加申込
※巡検のみ参加申込締切が大会参加登録等と異なりますので,ご注意下さい.
申込締切 WEB: 8月7日(金)18:00 FAX・郵送: 8月5日(水)必着
巡検のお申込は締切ました
総計8コースの巡検を計画しました(詳しくは,コース一覧を参照).
巡検のみ参加する場合も大会参加登録ならびに参加登録費が必要になります.
実施日程の異なる場合,複数の巡検コースへの申込を行うことができます(最大3コース).
申込人数が各巡検コースの最小催行人員に達しなかった場合,巡検を中止することがあります.
会員・非会員問わずお申込頂けますが,定員超過の場合は会員が優先となります.巡検協賛団体の会員の方は,会員同様にお申込が可能です.
本学会ならびに長野大会実行委員会は巡検参加者に対し,巡検中に発生する病気,事故,傷害,死亡等に対する責任・補償を一切負いません.これらについては,巡検費用に含まれる保険(国内旅行傷害保険団体型)の範囲でのみまかなわれます.
中学生以下の場合は,必ず保護者同伴でお申し込み下さい.また,長時間の歩行や川原など足場の悪い場所で露頭観察を行う場合もあります.巡検の性質上,自立歩行が難しい方のご参加はご遠慮願います.
集合・解散の場所,時刻などを変更することもありますので,大会期間中は掲示などの案内に注意して下さい.
冊子体の案内書は作成しません.案内書CD-ROMを地質学雑誌8月号に添付する予定です(8月下旬または9月上旬にお手元に届きます).また,巡検参加者には,各班の巡検案内の複写を巡検当日に配布する予定です.
会期後,大会報告記事(ニュース誌11月号を予定)において,参加者氏名を掲載させて頂きます.あらかじめご了承ください.
巡検コース一覧/みどころ
巡検コース一覧
申込締切 WEB: 8月7日(金)18:00 FAX・郵送: 8月5日(水)必着
巡検のお申込は締切ました
★注意点★
1) 取消料は,申込締切後〜大会3日前(9/8)までは50%,大会2日前(9/9)以降は全額となります(取消料のページ参照).申込締切後の変更・取消は,直接学会事務局(東京)にFAX又はe-mailにてご連絡下さい.
2) 参加費には,日程に応じた旅行傷害保険(少額)が含まれます.
3) 最小催行人員に満たない場合や,安全確保に問題があると考えられる場合は,コース内容の一部変更や巡検中止等の措置をとることがあります.
4) 参加者へは,各コース毎の案内書を巡検当日に配布します.全コース分を収録した冊子体の出版はありません(CD-ROM版のみ).
5) 集合・解散の場所,時刻等に変更が生じた場合,大会期間中会場内の掲示板等に案内します.また,案内者から直接ご連絡することもあります.
6) 2班<地学教育・アウトリーチ>は,学会補助事業です.小中高の教員ならびに一般市民を優先対象とします.
7) 中学生以下の場合は,必ず保護者同伴でお申し込み下さい.また,長時間の歩行や川原など足場の悪い場所で露頭観察を行う場合もあります.巡検の性質上,自立歩行が難しい方,介助が必要な方のご参加はご遠慮願います.
1班:上高地(9/10)
2班:教育・アウトリーチ(9/13)
3班:堆積(9/14)
4班:火山体内部(9/14)
5班:変動地形(9/14)
6班:黒曜石(9/14)
7班:飛騨山脈(9/14-15)
8班:蓮華帯(9/14-15)
1班 上高地の地形地質発達史
*定員の後の( )は最小催行人数です.
魅力:日本を代表する山岳景勝地である上高地は,槍・穂高連峰などの高峰に囲まれた谷底盆地です(写真1).山岳地域の河谷の多くが急勾配で狭いV字谷であるのに対し,上高地盆地の勾配(大正池−徳沢間10 km)は8‰と小さく,盆地の幅は600〜900 mと広い.この緩傾斜平坦で幅広の谷底盆地は,12.4 kaに焼岳火山群白谷山−アカンダナ火山の活動により岐阜県側に流下していた古梓川がせき止められ,,せき止め湖として生じた古上高地湖が埋積されてたことにより形成されました.槍・穂高連峰を構成する第四紀カルデラ火山−深成複合体を観察する上でも,上高地では優れた巡検が可能なコースです.第四紀花崗岩である滝谷花崗閃緑岩(写真2)も,巨大カルデラカルデラを埋積したデイサイト質溶結凝灰岩も遊歩道沿いで観察できます.また形成まもない新しいカルデラ火山では観察不可能な,カルデラ内部の陥没カルデラ縁断層,カルデラ床が観察できる点でも貴重な巡検フィールドです.
みどころ:
・焼岳火山の火山地形と上高地盆地の地形
・田代池一帯の流れ山地形
・ウェストン碑:第四紀滝谷花崗閃緑岩
・槍・穂高カルデラ埋積火山岩
・槍・穂高カルデラ東縁の組織地形
・槍・穂高カルデラのカルデラ床をなす美濃帯中生層
巡検コース:大正池→河童橋→清水川→小梨平→明神→明神池→岳沢登山口→上高地BT
主な見学対象:1.埋積谷地形 2.田代池・河童橋流山地形 3.第四紀滝谷花崗閃緑岩4.清水川湧水 5.槍穂高カルデラ埋積火山岩 6.カルデラ床基盤岩
日程:2015 年9 月10 日(木)(日帰り)
定員:30(10)
案内者:原山 智(信州大)
参加費:2,000 円
必要な地図(1/2.5 万): 焼岳,上高地
集合・解散:集合6:30(大正池ホテル前),解散15:00(上高地BT)(当日長野市まで移動可)
その他往路:上高地直行バスさわやか信州号(東京,大阪・京都9 日夜発)利用を前提(各自手配).12km 歩行.昼食各自持参
写真1:12 kaのせき止めで生じた上高地盆地と穂高連峰の山岳景
写真2:1.4 Maの滝谷花崗閃緑岩の岩盤に埋め込まれたウェストン碑
ページtopに戻る
2班:海だった長野の生い立ちを学ぶ ★地学教育・アウトリーチ巡検★
魅力:新しく誕生した,妙高戸隠連山国立公園の魅力を地質学的に探ります.戸隠地域から発見される海の生物の化石を基にした,ちょっと変わった博物館も体験します.
みどころ:
・善光寺地震の断層崖
・裾花川沿いの新第三系・化石の産出状況(写真1)
・地質と地形・生活との関連
・小学校廃校を利用した自然史博物館(写真2)
巡検コース:茂菅→善光寺温泉→小鍋→川下→博物館
主な見学対象:1. 裾花川沿いの海成層 2. 地質と地形・ヒトとの関係 3. 化石の産状 4. 地質系博物館の見学
日程:2015 年9 月13 日(日)(日帰り)
定員:40(25)
案内者:田辺智隆(戸隠地質化石博物館) 参加費:2,500 円
必要な地図(1/2.5 万): 長野,若槻,戸隠
集合解散:長野駅東口 集合8:30 解散16:00
その他:一般参加者優先・地質学会補助あり.昼食は各自持参(コンビニ店へ立ち寄りも可能)
中学生以下の場合は,必ず保護者同伴でお申し込み下さい.また,長時間の歩行や川原など足場の悪い場所で露頭観察を行う場合もあります.巡検の性質上,自立歩行が難しい方,介助が必要な方のご参加はご遠慮願います.
写真1:裾花川沿いの化石の産出露頭(新第三系)
写真2:小学校廃校を利用した戸隠地質化石博物館
ページtopに戻る
3班:地層形成と海水準変動
魅力:長野盆地と松本盆地の間の山地は,主に新第三系の堆積岩類から構成されています.これらの堆積岩は日本海拡大によって形成された海盆を中新世以降に埋積してつくられたもので,重力流堆積物から浅海堆積物を経て河川成堆積物へと堆積相が変化していく様子を見ることが出来ます.そして,地層中に記録された海水準の上昇と低下をこれらの堆積物の堆積相変化から読み取ることも可能です.
みどころ:
・小川村の小川層砂岩中の堆積相変化,ハイパーピクナル流から堆積したタービダイトからハンモック状斜交層理の見られる浅海性砂岩への変化.
・大町市美麻の小川層中の陸上侵食面(シーケンス境界)とその後の海水準上昇によって堆積した海岸やエスチュアリーの堆積物.
巡検コース:長野駅東口8:00 →小川村小川川→小川村土尻川→大町市美麻金熊川→長野市大岡→長野駅東口(17:30 予定)
主な見学対象:1. 斜面とデルタ前面の堆積作用 2. 斜面埋積による浅海化過程 3. デルタプレーン上の浅海堆積物 4. 陸上侵食面とシーケンス境界
日程:2015 年9 月14(月) (日帰り)
定員: 25(15)
案内者:保柳康一(信州大)・関めぐみ(野尻湖ナウマンゾウ博物館)
参加費:7,000 円
必要な地図:(1/2.5 万) 高府,日名
集合解散:長野駅東口 集合8:00 解散17:30
その他:昼食各自持参(参加者数によっては,こちらで用意すことがあります.その場合は事前に連絡します)
写真1:小川層の砂岩層上面に見られるウェーブリップル
写真2:小川層中の陸上侵食面.HCSが見られる外浜堆積物(右手前),それを削り込んで(写真中央)堆積している河川成堆積物(左奥).
ページtopに戻る
4班 成層火山体の内部
魅力:四阿火山の山頂部には“四阿カルデラ”と呼ばれる直径3kmほどの凹地があり,この火山の地形的な特徴となっています.このカルデラから流れ出る米子川の上流域には,厚さ150 mに達する溶岩層が作る断崖絶壁が約1kmも続き,不動滝や権現滝をはじめとする落差70〜80 mほどの複数の滝が見られます.また,カルデラ内には硫黄鉱床が存在し,1960(昭和35)年まで採掘が続けられていました.このほか周辺には,中世の山岳修験道に由来をもつ米子不動奥之院や但唱上人が木食行を行ったと伝えられる遺跡も存在します.本巡検では,四阿カルデラ,不動滝や権現滝といった成層火山体の開析地形とそれらを構成する火山岩類を観察するとともに,米子硫黄鉱山跡や米子不動奥之院といった人文的景観についても見学する予定です.
みどころ
・長野盆地や飯縄火山などの四阿火山周辺の地形観察
・不動滝や権現滝をはじめとする米子の滝群と米子溶岩の大岩壁
・成層火山体の開析地形と遺跡の立地
・四阿カルデラとカルデラ内の地すべり地形
・硫黄鉱床や熱水変質帯および廃坑から流出する酸性水
巡検コース:米子の滝駐車場→不動滝→権現滝→権現沢上流(登山道沿い)→米子鉱山跡地→鉱山事務所跡地→米子の滝駐車場
主な見学対象:1.米子溶岩(不動滝・権現滝) 2.米子不動寺と地形の関係 3.四阿カルデラ内の侵食崩壊地形 4.米子鉱山跡,硫黄鉱床(熱水変質帯) 5.四阿カルデラと滝群
日程:2015年9 月14 日(月)(日帰り)
定員: 20(15)
案内者:竹下欣宏(信州大)・西来邦章(原子力規制庁・産総研)・富樫 均(長野県環境保全研)
参加費:7,000 円
必要な地図(1/2.5 万):須坂,四阿山
集合解散:長野駅東口 集合:7:30 解散:17:00
その他昼食各自持参.コンビニ店へ立寄り.
写真1:米子溶岩の岩壁にかかる不動滝(右)と権現滝(左)
写真2:鉱山事務所跡から望む米子硫黄鉱山跡地と四阿カルデラ.写真左手の岩壁に見られる白い脈状の部分が硫黄鉱床(泉坑)跡.
ページtopに戻る
5班:長野盆地の変動地形
魅力:長野盆地西縁断層帯は,羽越褶曲断層帯の南端付近に位置する西側隆起の逆断層です.本断層帯は,盆地西縁部に断層変位
地形や先行谷を発達させ,豊野層や南郷層とその分布・構造に深く関与してきました.1847年に発生した弘化善光寺地震は,この断層帯が引き起こしたM7.4の大地震です.明瞭な地表地震断層が出現し,多数の斜面崩壊が発生した点で,同じく羽越褶曲断層帯で発生した2004年新潟県中越地震などと共通点が多いといえるでしょう.本巡検では,変動地形の分布と大地震に伴う地表変位,また関連する地質および地質構造の発達史について,災害という側面を意識しながら,地形・地質学的観点から議論します.
みどころ
・城山丘陵の変動地形と先行谷
・豊野層の露頭(長野市指定天然記念物)
・高丘丘陵の変動地形
・草間の変動地形と地下構造
・南郷層の露頭
・飯山市街地の変動地形と地下構造
・常盤上野〜大倉崎の変動地形と先行谷
巡検コース:長野駅東口集合8:00 →城山丘陵→長野市豊野町豊野横町→高丘丘陵→中野市草間→飯山市街地→飯山市常盤上野→飯山駅千曲川口15:30 →長野駅東口解散16:45
主な見学対象:1. 城山丘陵の変動地形と先行谷 2.豊野層の露頭(長野市指定天然記念物)3.高丘丘陵の変動地形 4.草間の変動地形と地下構造 5.南郷層の露頭6.飯山市街地の変動地形と地下構造 7.常盤上野〜大倉崎の変動地形と先行谷
日程:2015 年9 月14 日(月)(日帰り)
定員:20(15)
案内者:杉戸信彦(法政大),廣内大助(信州大),塩野敏昭(北信ボーリング)
参加費8,500 円
必要な地図(1/2.5 万):長野,若槻,中野西部,飯山,往郷
集合解散 集合:8:00(長野駅東口) 解散:15:30(飯山駅) 16:45(長野駅)
その他:昼食「ビアンテ信州中野店」(昼食代は参加費に含む).帰りは飯山駅に寄ってから長野駅に戻ります.飯山駅からお帰りいただくことも可能です(ただし,飯山駅から長野駅までのバス移動に関わる費用は返還しません).
写真1:長野盆地中部の西縁に発達する長丘丘陵.南西方を望む.盆地内を北流してきた千曲川は長丘丘陵の背後を先行河川として流れる.上陵の手前には夜間瀬川扇状地が広がっている.
写真2:急傾斜する豊野層(湖成堆積物)を不整合で覆う南郷層(河成堆積物).長野市豊野町豊野横町にあるこの露頭は1999年に長野市指定天然記念物となった.
ページtopに戻る
6班:黒曜石と石器
魅力:火道,溶岩流,火砕流など様々な産状の黒曜岩を巡ります.
みどころ:黒曜岩と流紋岩との関係や多種球顆の存在により生じる岩相の違いを見ます.また,火砕流堆積物の大規模な露頭で岩片として見られる新鮮な黒曜岩(石器品質)やパーライトの産状を観察します.鷹山遺跡群のトレンチ調査の結果,石器黒曜石は火道周辺の黒曜石を爆発時に取り込んだ火砕流岩片であることを紹介します.
巡検コース:長野駅発8:00東餅屋→男女倉→三ノ俣→黒曜石体験ミュージアム→上田駅解散16:00
主な見学対象:1.東餅屋火道跡 黒曜岩と流紋岩関係 2.黒曜岩溶岩 男女倉 黒曜石と球顆流紋岩 3.火砕流 三の俣 軽石と黒曜岩岩片およびパーライト 4.石器黒曜石 黒曜石体験ミュージアム 石器剥片の岩石的特異性
日程:2015 年9 月14 日(月)(日帰り)
定員:20(15)
案内者:牧野州明(信州大)・高橋 康(信州大)・中村由克(明治大)
参加費:8,000 円
必要な地図(1/2.5 万) 霧ヶ峰
集合解散: 集合: 8:00(長野駅東口) 解散:16:00(上田駅) 17:00(長野駅)
その他:昼食各自持参(途中コンビニ立寄り).ヘルメット,革手袋の持参をお願いします.
写真1:球顆流紋岩断面(bar=1cm)
写真2:球顆の内容物(2相混合物+vesicle)
ページtopに戻る
7班:飛騨山脈の傾動隆起
魅力:北アルプス北部,鹿島槍ヶ岳から爺ヶ岳(写真1),蓮華岳一帯には,第四紀更新世前期のカルデラ火山-深成コンプレックスの断面が広く露出しています.この一帯ではカルデラ火山の活動と花崗岩マグマの上昇定置の直後にあたる1.6 Ma〜0.6 Maの間に傾動を伴う隆起が生じており,カルデラ火山岩層が80°前後の直立に近い状態まで南北水平軸回転しています(写真2).さらにカルデラ外に流走したアウトフロー堆積物である大峰帯の大峰火砕流堆積物を観察します.北アルプスの隆起に引き続いて松本盆地東縁断層に沿って生じた傾動隆起により,大峰帯も東に40°前後傾斜しており,ともに第四紀以降の北部フォッサマグナと飛騨山脈一帯を支配した短縮テクトニクス場での構造運動により生じました.巡検を通して,中部日本の第四紀のテクトニクスについて活発な議論をお願いしたいと思います.
みどころ:
・0.8 MaのジルコンU-Pb年代の報告された黒部川花崗岩と複合体をなし爺ヶ岳火山岩類.
・爺ヶ岳南峰-中央峰間のカルデラ湖堆積物の垂直層
・黒部川花崗岩のいたるところに濃集する暗色包有岩
・爺ヶ岳カルデラからアウトフローした大峰火砕流堆積物
巡検コース:
[1 日目]長野駅8:00 →扇沢→柏原新道→種池山荘(泊)
[2 日目]爺ヶ岳往復→扇沢→大峰帯火砕流堆積物→長野駅
主な見学対象:1.扇沢 黒部川花崗岩/ 爺ヶ岳火山岩類の接触境界 2.爺ヶ岳火山岩類のカルデラ湖成層(垂直層) 3.黒部川花崗岩と暗色包有岩 4.大峰帯における飛騨山脈爺ヶ岳カルデラ由来の火砕流堆積物
日程:2015 年9 月14日(月)〜 15日(火)(1泊2日)
注)台風など天候により登山中止や下山日が延びる可能性があります.参加者は日程に余裕を作っておいて下さい.
定員:20(12)
案内者:原山 智(信州大)
参加費:23,000 円(山小屋宿泊費1 泊2食込)
必要な地図(1/2.5 万):立山,大町,十字峡, 神城
集合解散: 14日 長野駅東口8:00集合 15日 17:00解散
その他:健脚者のみ(登山経験者) 標高差1300m,3.5時間の登りあり
宿泊:種池山荘 TEL:080-1379-4042 http://www.kasimayari.jp/index.htm
14 日昼食は各自持参 15 日昼はコンビニに立寄り
写真1:北アルプス爺ヶ岳から望む鹿島槍ヶ岳.一帯には更新世前期に活動していたカルデラ火山-黒部川花崗岩コンプレックスの断面が露出しています.
写真2:爺ヶ岳南峰と中央峰の間に露出する直立した凝灰岩層(カルデラ湖堆物).1.6Ma〜0.6 Maの間に水平軸回転を伴う隆起運動が生じたことを示しています.
ページtopに戻る
8班:蓮華変成岩類と中生代陸成層
魅力:本地域に分布する宇奈月変成岩類は,トリアス紀からジュラ紀の南北中国地塊の衝突帯の延長と考えられ,また,蓮華変成岩類は日本の付加体形成における初期の付加体です.このため,この地域は,日本の古生代から中生代の地質構造発達史を解明する上で極めて重要な位置を占めています.さらに両地帯には
ジュラ紀〜白亜紀の地殻変動に伴って形成された浅海成〜陸成層が分布します.これらの堆積物の組成は,地殻変動によって隆起した地質体の情報を示し,また堆積相は堆積環境を示すため,地殻変動の性質を明らかにする上での鍵となります.蓮華変成岩類では,近年発見されたエクロジャイトユニットと非エクロジャイトユニットの変形過程の比較を行います.また,中生界では,LA-ICP-MSによる砕屑性ジルコンのU-Pb年代を基に陸成層の堆積年代の制約や地層の再定義,また後背地の検討がなされました.現地でのこれらの地質見学と共に中生代の地殻変動について考えましょう.
みどころ:
・2015年3月にリニューアルオープンしたフォッサマグナミュージアム(写真1)
・蓮華変成岩類のエクロジャイトユニット,非エクロジャイトユニット黒雲母帯と緑泥石帯の変形様式の比較
・来馬層群最下部の凝灰質岩の岩相とジルコンU-Pb年代(写真2)
・陸成層及び岩脈の産状とジルコンU-Pb年代により再定義された白亜系
巡検コース
[1 日目]糸魚川駅(9:00 集合)→フォッサマグナミュージアム→小滝ひすい峡→ホテルホワイトクリフ(泊)
[2 日目]ホテルホワイトクリフ→青海川→境川→糸魚川駅(15:30 解散)
主な見学対象:1. フォッサマグナミュージアム 2.青海石灰岩と地すべり地形 3.小滝ヒスイ峡 4.蓮華変成岩類 5.来馬層群(大所川層,蒲原沢層) 6.手取層群水上谷層凝灰質岩と岩脈 7.上部白亜系尻高山層
日程:2015年9月14日(月)〜 15日(火)(1泊2日)
定員:20(12)
案内者:竹内 誠(名古屋大)・竹之内 耕(フォッサマグマミュージアム)・常盤哲也(信州大)
参加費:20,000 円(宿泊費1泊2食込)
必要な地図(1/2.5 万):越後平岩,小滝,糸魚川,親不知
集合解散:糸魚川駅 集合:14 日 9:00 解散:15 日15:30
その他:1 日目の昼食は各自持参 2 日目の昼食はコンビニ店へ立ち寄り予定
宿泊:ホテルホワイトクリフ
〒949-0554 新潟県糸魚川市大字山口151-1
TEL:025-558-2316/FAX:025-558-2300 http://park8.wakwak.com/~whitecliff/
写真1:リニューアルされたフォッサマグナミュージアムのシアター
写真2:来馬層群最下部の凝灰質砂岩.斜交葉理や平行葉理が発達し,火山ガラス片を多く含む凝灰質砂岩.飛騨帯の火成活動との関係はどうなのでしょうか.
ページtopに戻る
キャンセルした講演の講演要旨の扱いについて
キャンセルした講演の講演要旨の扱いについて
学術大会にて発表を申し込まれた講演を講演要旨印刷後にキャンセルした場合,該当講演の要旨は印刷物として存在することになります.この講演要旨の扱いについて,以下の通りとします.
1.講演をキャンセルした場合,講演要旨も取り下げたものとします.講演要旨集に要旨は残りますが,キャンセルされた講演の要旨は引用できません.これまではキャンセルされた講演の要旨もJ-Stage に掲載していましたが,今後は掲載しません.
2.学術大会終了後,地質学雑誌にキャンセルされた講演を掲載し,キャンセルされた旨を周知します.
3.次年度以降の学術大会にて,キャンセルした講演の要旨を再掲し,発表を希望する場合は,再掲する要旨に「本講演は第○○年学術大会にて発表をキャンセルしたもので,本講演要旨は第○○年学術大会講演要旨集に掲載されたものを再掲したものである」旨を明記してください.
一般社団法人日本地質学会
行事委員長
竹内 誠
2015年6月6日
大会申込Q&A
大会申込Q&A
【演題登録編】 >>【参加登録編】へ
Q:1人何題まで発表できますか?
A:
トピック・レギュラーセッション(全31セッション)では,1人2題まで発表できます.ただし2題発表する場合には発表負担金(1,500円)をお支払い下さい(1題のみの場合は無料).また,同一セッション内で口頭2件やポスター2件の発表はできません.詳しくは,セッション発表の募集要領『2)発表に関する条件・制約』を参照してください.
Q:発表負担金はどこで支払えばよいですか?
A:
演題登録画面には課金システム機能はありません. 事前参加登録画面にトピックセッション(T1〜T6)・レギュラーセッション(R1〜R24)での発表件数を選択する項目があります.『2件(1,500円)』を選択いただければ,事前参加登録費とともに発表負担金も課金され請求されます.
※トピック・レギュラーセッションにて招待講演者になっている発表者が,もう1題を別セッション(または招待されているセッションと同一セッションの異なる発表形式)で一般発表する場合には,発表負担金(1,500円)は発生しません(招待講演分は発表負担金の発生する”2件目”としてカウントしません).
Q:非会員も演題登録(発表)はできますか?
A:
招待講演者を除き,非会員の発表はできません.現在,非会員のかたで長野大会において発表を予定されているかたは,演題登録に合わせて入会申込の手続きもしてください(締切時点で入会申込が確認できない場合,登録が取り消されます).共催団体の会員は共催セッションのみ発表できますが,それ以外の他セッションで発表を希望する場合には,必ず入会手続きを行ってください.
Q:入会手続しましたが,まだ入会承認されていません.会員番号(ID)もないのです
が,演題登録はできますか?
A:
入会承認がまだのかたでも演題登録はできます.お早めに登録手続きしてください.会員区分の項目欄に『入会申込中』の選択項目がありますので,そちらを選択して登録してください.
Q:筆頭著者でなければ発表はできないのですか?
A:
筆頭著者でなくても発表は可能です(筆頭著者は会員・非会員を問いません).
ただし,発表者は地質学会の会員でなければなりません.
共同発表(複数の著者の発表)の場合には,講演要旨(pdf)に明記する著者名の
うち,発表者が分かるように発表者氏名に下線を引いてください.
※非会員が発表者になっている場合には,登録が取り消される場合があります.
Q:前回大会において急遽発表キャンセルをしてしまったため,今年の大会で同内容で発表したいのですが.演題登録してもいいですか?
A:
前回の学術大会にて発表を申し込まれた講演を講演要旨印刷後にキャンセルした場合,該当講演の要旨は印刷物として存在することになります.キャンセルした講演の要旨を再掲し,発表を希望する場合は,再掲する要旨に「本講演は第○○年学術大会にて発表をキャンセルしたもので,本講演要旨は第○○年学術大会講演要旨集に掲載されたものを再掲したものである」旨を明記してください.
詳しくは行事委員会から発表の『キャンセルした講演の講演要旨の扱いについて』を参照して下さい.
Q:演題登録画面のキーワードの入力ができません.
A:
キーワードを入力したい場合には,デフォルトで”0”件となっている入力欄に,ご自身が登録したいキーワードの数を半角数字で入力し,【件数変更】のボタンをクリックしてください.入力欄が下に表示されます.キーワードは最大10件まで登録できます.
※キーワードの入力は任意です(必須項目ではありません).
※『所属機関情報』や『著者情報』の件数・人数入力欄の増減も同様の操作で対応できます.
Q:演題登録画面の『著者情報』に21人以上の共著者を登録したいのですが.
A:
演題登録画面上では『著者情報』の入力は最大20件までしか登録できません.
21人以上登録したい場合には,演題登録時の受付番号(100〜ではじまる6桁の数字)と21人目〜の著者情報(氏名と所属先名:和英とも)を学会事務局に連絡してください.プログラム作成時に反映します.
Q:講演要旨がまだ出来上がっていないので,演題登録ができません.どうしたらいいですか?
A:
演題登録画面には”演題情報”のほかに,”連絡者情報(一度登録しておけば書き換える必要の無い項目)”の入力もあります.締め切り間際になってから全ての項目を登録しようとするのではなく,発表題目や共著者情報などはとりあえず”仮情報”で構いませんので,まず先に新規登録を行い〔受付番号〕と〔パスワード〕を取得してください.
〔受付番号〕と〔パスワード〕取得後は,【マイページ】へログインいただき,演題情報などを繰り返し修正していくことをおすすめします.
※締切(6/30日,18時)までには,完成原稿をアップロードしてください!!
Q:(演題登録締切後)講演要旨に誤りを見つけてしまったので,差し替えたいのですが.
A:
演題登録締切後,著者(発表者)の都合による要旨の差替え(演題内容の修正)依頼は受け付けません.
演題登録締切後,すぐにプログラムデータの整理・講演要旨の校閲作業を開始し,限られた時間の中で各世話人が要旨の校閲作業をしております.
修正原稿は,その都度校閲をしなければならなくなり,世話人の手間も増えることとなりますから,期日内にきちんと講演要旨を完成させ,登録を済ませていただきますよう,何卒ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします.
※要旨の校閲後に世話人から修正を求められた際,求められた箇所以外の修正をしてしまう著者(発表者)がまれにいますが,世話人に指摘された箇所のみを修正してください.
Q:演題登録の締切は延長されますか?
A:
昨年同様,演題登録の締切延長はありません.6月30日(火)18時締切厳守(郵送は6/24日(水)必着)です.余裕をもってお早めにご登録ください.
【参加登録編】
Q:講演要旨は付きますか?
A:
参加登録費が有料のかたには,必ず講演要旨集が1冊付きます.
→正会員・院生割引会費適用正会員・非会員一般・非会員院生
参加登録費が無料のかた(※)には,講演要旨集は付きません.
→名誉会員・50年会員・学部割引会費適用正会員・非会員学部学生・
非会員招待者・同伴者(非会員で会員の家族に限る)
※講演要旨をご希望の場合は,別途ご購入ください(事前参加登録にて追加
講演要旨の購入申込ができます).
Q:講演要旨集の「後日発送」は,いつ頃送付されてきますか?
A:
大会会期終了後の発送です.会期前の送付はできません.別途送料がかかります.
Q:キャンセル料(取消料)はかかりますか?
A:
事前参加申込期間中の変更・キャンセルの場合は取消料はかかりません.締切後につきましては,申し込んだものにより,キャンセル料がそれぞれ異なりますのでご注意ください.
参加登録費:
申込締切後〜9/8日(大会3日前)60%,9/9日(大会2日前)以降100%
※後日,講演要旨をお送りします.
追加講演要旨:
申込締切後〜9/8日(大会3日前)60%,9/9日(大会2日前)以降100%
懇親会:申込締切後100%
弁当:申込締切後〜9/8日(大会3日前)50%,9/9日(大会2日前)以降100%
巡検:申込締切後〜9/8日(大会3日前)まで50%,9/9日(大会2日前)以降100%
Q:Web上で事前参加登録をしましたが,確認メールが届きません.
A:
入力したメールアドレスが間違っている可能性があります.学会事務局へ連絡してください.
Q:事前参加登録をしましたが,登録内容の修正の仕方が分かりません.
A:
事前参加登録の申込時に,①[初回申込]確認,②[ご請求]連絡の2通のメールが必ず自動返信されています(クレジット決済まで完了した人は③決済完了のお知らせメールも届きます).
[初回申込]確認メールの文中には,
・【変更・修正】および【取消】操作をおこなうための案内
・【変更・修正】および【取消】操作の画面にログインするためのURL
・ログインに必要な[お申込No.]と[パスワード]
が明記されております.説明をよく読んでお手続きください.
※できるだけ,一番最初に取得した[お申込No.]と[パスワード]で登録内容の【変更・修正】をしてください.何度も何度も新規でお申込すると,[お申込No.]と[パスワード]を登録した回数分取得することになり,重複申込者の確認漏れの原因にもなります.
Q:参加費無料の会員種別の人は,事前登録をしなくてもよいですか?
A:
当日の参加登録でも構いません.ただし,講演要旨の購入を希望される場合は,数に限りがあり,事前予約と当日購入では冊子体の価格が異なりますので,事前参加登録にてご予約することをおすすめします.ここ数年,大会会期中に講演要旨集の売り切れが続いておりますので,なるだけ事前にお申込みください.
Q:代理での申込はできますか?
A:
可能です.ただし,申込の重複や連絡先/発送先の登録には注意してください.とくに非会員招待者や外国人招待者などを代理で登録する場合は,代理で登録してくださるかたの連絡先を確認書やクーポンの送付先として登録してください(海外の住所では,確認書やクーポンの発送を,ご本人の手元に届くよう間に合わせることができません).また,登録時の確認メールは日本語のみです.
Q:巡検だけに参加したいのですが.
A:
地質学会会員は巡検だけに参加する場合でも,基本の参加登録費がかかります.事前参加登録【画面A】からお申込ください.
非会員のかたで,『巡検協賛学協会』のいずれかにご所属されているかた,または小・中・高の教員のかたは,【画面B】からお申込みください.
Q:大会には参加しませんが,講演要旨だけの購入はできますか?
A:
講演要旨だけの予約購入も可能です.事前参加登録【画面C】からお申し込みください.ただし,講演要旨の発送は大会終了後になりますので,ご了承ください.
Q:Web登録がうまくできません。
A:
連絡先など,登録情報の自動取得が行えない場合はこちらを参考にしてください.ただし自動取得は日本地質学会会員のみ利用できます.
正しく操作を行っているにも関わらず,エラーが出る場合は学会事務局へご連絡ください.
Q:昨年,確認書やクーポンが届きませんでした./大会終了後に受け取りました.
A:
確認書やクーポンは郵送でお送りします.申込の際,発送時期に確実に届く住所を記入・入力してください(所属先へ送付を希望される方は,とくにご注意ください).発送は大会10日前にはお手元に届くように発送する予定です.締切後に送付先変更を希望される場合は,学会事務局へご連絡ください.また,下記のような場合にも早めにご連絡ください.
例1)会社勤めのかた:大会直前まで出張(現場で野外調査)し,出張先から大会に参加するため,出張先(宿泊先)に確認書やクーポンを送ってほしい./直接大会会場で受け取りたい.
例2)大学職員・学生のかた:夏季休暇中は事務が閉まっていて,郵送物が届きにくい/届かない.
Q:宿泊予約はできますか?
A:
参加申込システムからは宿泊予約はお受けしておりません.各自手配をお願いします.日本旅行の宿泊予約サイト(長野大会参加者数分の宿泊先が確保されています)からお申込みいただけます.
Q:自分の疑問が解決する答えが載っていませんでした.
A:
ご不明な点がありましたら,学会事務局へご連絡ください.
地学教育・普及・関連行事
地学教育・普及・関連行事
※一般公開行事実施の際の警報等発令時及び地震発生時の対応指針
■ 地質情報展2015ながの(9/11-13)
■ 市民講演会(9/12)
■ 地学教育・アウトリーチ巡検(9/13)
■ 小さなEarth Scientistのつどい(9/13)
■ 若手会員のための業界研究サポート(9/12)
■ 特別講演会「地質地盤情報の利活用と法整備」(9/13)
※各行事の画像をクリックすると,大きな画像,またはPDFをダウンロードできます.
地質情報展2015ながの 知っていますか信濃の大地
日時:2015年9月11日(金)〜13日(日)【入場無料】
9月11日(金)9:30〜17:00
9月12日(土)9:30〜17:00
9月13日(日)9:30〜16:00(時間はいずれも予定)
会場:長野市生涯学習センター(TOiGOトイーゴ)4階
主催:一般社団法人日本地質学会・産業技術総合研究所地質調査総合センター
内容:長野大会に合わせ,長野県及び周辺の地質現象や火山・地震・地盤災害についてパネル,映像,標本を使って展示・解説する「地質情報展2015ながの」を開催します.化石レプリカ作成などの体験学習コーナーなども用意し,実験や実演を通じて小学校入学前のお子さんからお年寄りまで,皆さんに楽しみながら「地質」をわかりやすく学んでいただけるイベントです.ぜひ,「地質情報展2015ながの」にご来場ください.
問い合せ先:産業技術総合研究所地質調査総合センター地質情報展企画運営事務局
TEL:029-861-3540
e-mail:johoten2015jimu-ml@aist.go.jp
情報展のHPはこちら
https://www.gsj.jp/event/2015fy-event/nagano2015/index.html
ページトップに戻る
市民講演会「信州の自然とともに生きる−地震と火山の防災地学−」
日時:2015年9月12日(土)14:30〜16:00【事前申込不要】
画像をクリックすると PDF(A4版)がダウンロードできます
会場:ホクト文化ホール(長野県県民文化会館)小ホール(長野県長野市若里1-1-3)
概要:長野県では昨年は多くの災害に見舞われました.7月9日の南木曽土石流,9月27日の御嶽山の水蒸気爆発,そして11月22日の長野県神城断層地震.このような状況で,あらためて私たちの住む長野県の成り立ちと地質学的特徴を理解し,より安全な市民生活を送る一助となることを願って,次のような講演を企画いたしました.
講演予定:
「信州の火山を知ろう」三宅康幸(信州大学理学部教授)
「糸静構造線活断層地震が起きたとき,長野盆地・松本盆地の震災は」塚原弘昭(信州大学名誉教授)
講師は長年信州大学でそれぞれ活火山と地震の研究に携わってこられたお二人です.御嶽山を含む長野県の活火山の分布とそれらの活動の“癖”や,県内の地震発生と活断層との関係や震災について,やさしく詳しく解説します.さらに,これらをふまえた防災・減災の面からの提案をもとに,市民のみなさんにも参加していただいて議論を深めていく予定です.
*講演会の前後には,アウトリーチセッション(研究成果を社会に発信する場として設けられたセッション),ジオパークセッションのポスター発表も行います.
[ORアウトリーチセッション]コアタイム(13:00〜14:00,16:30〜17:30;計2回)
[R6ジオパークセッション]掲示のみ,コアタイムはありません.
*セッション名をクリックするとセッションの紹介をご覧いただけます。セッションの講演プログラムはこちらから
※ページトップに戻る
小さなEarth Scientistのつどい〜第13回 小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜
日時:2015年9月13日(日) 9:00〜15:30
場所:長野大会ポスター会場(信州大学(工学)キャンパス内)
参加対象
・小,中,高校地学クラブならびに理科クラブ等の活動成果の発表
・小,中,高校の授業における研究成果の発表
・活動,研究内容は地学的なもの(地質や気象などの地球科学・環境科学,天文など)
参加予定校(7月30 日現在,13 校・1団体参加,18 件)
・長野県松本深志高等学校地学会
・長野県長野西高等学校
・岐阜県立加茂高等学校(2件)
・山梨県立日川高等学校物理・地学部(2件)
・新潟大学理学部未来の科学者養成講座(2件)
・群馬県立太田女子高校地学部
・千葉県立柏高等学校課題研究Ⅱ受講者
・東京学芸大学附属高等学校
・早稲田大学高等学院理科部地学班
・学校法人奈良学園奈良学園高等学校SS 研究チーム
・滋賀県立彦根東高等学校SS 部地学班
・兵庫県立西脇高等学校地学部(2件)
・兵庫県立加古川東高等学校地学部
・鹿児島玉龍高等学校サイエンス部天文班
*過去の発表会の様子や「優秀賞」受賞発表はこちらから
ページトップに戻る
地学教育・アウトリーチ巡検「海だった長野の生い立ちを学ぶ」
日時:2015年9月13日(日)8:30 長野駅集合,16:00解散(予定)
参加対象:小中高の教員ならびに一般市民を優先
新しく誕生した、妙高戸隠連山国立公園の魅力を地質学的に探ります。戸隠地域から発見される海の生物の化石を基にした、ちょっと変わった博物館も体験します。
みどころ:善光寺地震の断層崖・裾花川沿いの新第三系・化石の産出状況・地質と地形・生活との関連小学校廃校を利用した自然史博物館
参加費やコースの詳しい内容は巡検コース一覧2班の欄をご参照下さい(こちらから)
(注意)中学生以下の場合は,必ず保護者同伴でお申し込み下さい.また,長時間の歩行や川原など足場の悪い場所で露頭観察を行う場合もあります.巡検の性質上,自立歩行が難しい方,介助が必要な方のご参加はご遠慮願います.
申込締切:8月7日(金)<申込は締切ました>
*過去の巡検の様子はこちらから
ページトップに戻る
若手会員のための業界研究サポート
日時:2015年9月12日(土)14:00-17:00(*時間帯は若干変更になる場合があります)
場所:信州大学長野(工学)キャンパス 工学部講義棟2階203
内容:内容 主催者等 挨拶・紹介,参加各社の個別説明会(今回は,例年以上に多くの企業にご参加頂けることになりました.そのため会場の都合上,実施内容を一部変更いたします.各社によるプレゼンテーションはありません).
対象:長野大会に参加する学生・院生および大学教官等の会員,信州大学等の学生・院生および教官等
参加企業等詳しくは,こちらから
▶ 2013年仙台大会の様子はこちらから
特別講演会「地質地盤情報の利活用と法整備」
日時:2015年9月13日(日)14:30-17:00
会場:第7会場(信州大学工学部 学部共通棟 3)
お詫び:ニュース8月号プログラム記事(p.(41))の掲載に誤りがありました.正しい会場は「第7会場」です.
(誤)会場:工学部 講義棟 300(第4会場)
(正)会場:工学部 学部共通棟 3(第7会場)
主催:一般社団法人日本地質学会
【開催趣旨】
日本学術会議は,平成25 年1月31 日,提言「地質地盤情報の共有化に向けて−安全・安心な社会構築のための地質地盤情報に関する法整備−」を公開しました.提言の骨子は,
①地質地盤情報に関する包括的な法律の制定,②地質地盤情報の整備・公開と共有化の仕組みの構築,③社会的な課題解決のための地質地盤情報の活用の促進と国民の理解向上,の3 項目です.
この提言に示されるように,日本の国土を構成している地質・地盤の状況を把握し,その情報を社会の安全に役立てることが必要です.そこで平成25 年4 月,地質・地盤に関する学協会・業界・研究機関等が中心になって,「地質・地盤情報活用促進に関する法整備推進協議会」が設立されました.日本地質学会も本協議会に加入しています.
講演会では,本協議会の活動を紹介し,地質地盤情報の整備・利用の現状,学術研究の進展,法整備の必要性,および日本地質学会の現状について報告します.総合討論では,今後の活動の進め方について議論します.
【プログラム】 すべての講演要旨はこちらからダウンロードできます
司会:松浦一樹((株)ダイヤコンサルタント)・佐脇貴幸(産業技術総合研究所)
1.開催趣旨と法整備推進協議会の活動
栗本史雄(地質・地盤情報活用促進に関する法整備推進協議会,産業技術総合研究所)
2.地質地盤情報を用いた学術研究とその整備に対する提言
増田富士雄(同志社大学理工学部)
3.地質地盤情報の整備と工学的地盤モデル
山本浩司((一財)地域地盤環境研究所)
4.地質地盤情報の利用とビジネスモデル
丸山昌則(基礎地盤コンサルタンツ(株))
5.二次利用を促進するための法整備
平野 勇(地質・地盤情報活用促進に関する法整備推進協議会,応用地質(株))
6.日本地質学会と地質地盤情報の整備・活用
小嶋 智(岐阜大学工学部)
7.総合討論
(プログラム訂正:9/5)
(誤)3.地質地盤情報の整理と工学的地盤モデル
(正)3.地質地盤情報の整備と工学的地盤モデル
問い合わせ先:栗本史雄 kurimoto-chikao[at]aist.go.jp
地質・地盤情報活用促進に関する法整備推進協議会ホームページ
http://www.zenchiren.or.jp/suishin/suishin_index.html
懇親会・お食事
懇親会
日時:9月11 日(金)18:30 〜20:00
会場:メルパルク長野 3 階 白鳳
(表彰式,記念講演会も同会場で行います)
原則として予約制です(予約は8月18日に締め切りました).人数に余裕があれば当日参加の申込みも可能です.会場受付で確認し,当日参加の申込みをしてください.その場合の会費は,正会員・非会員(一般)7,000円です.名誉会員・50年会員・院生割引会費適用正会員・学部割引適用正会員および会員の家族は4,000円です.非会員の会費は正会員に準じます.
事前予約会費
当日会費
正会員
6,000円
7,000円
名誉会員・50年会員・院生割引・学部割引・会員の家族
3,000円
4,000
*非会員の会費は会員に準じます.
*締切後の参加取消の場合は,会費の返却はいたしませんのでご了承下さい.詳しくは,取消料のページを参照.
*工学→メルパルクまでの無料シャトルバスを運行します(9/11のみ運行)
大会初日(11日)のみ,大学からメルパルク長野(表彰式・懇親会会場)までの直通バス(無料)を運行予定です.
ぜひご利用下さい.(信州大学長野(工学)キャンパスから,徒歩の場合は約20分)
運行区間:信州大学長野(工学)キャンパス→メルパルク長野(直通)(注)大学→メルパルクまでの片道運行です.
運行日・時間帯:11日(金)14:00〜16:00(約15分間隔)
乗り場:工学部講義棟近くのロータリー
お弁当予約販売と会期中のお食事
予約のお弁当は、各日ごとに信州大学工学部キャンパス講義棟1Fで配布します.あらかじめ引換えクーポンをお送りします(予約は締切りました)。
会期中の大学生協厚生施設の営業について
信州大学工学部生協食堂:
9月11日(金)11:30〜13:30
9月12日(土)11:30〜13:30
9月13日(日)11:30〜13:30
信州大学生協食堂隣の売店(飲料や菓子類の販売あり):
9月11日(金)11:00〜16:00のみ営業
注意:上記以外の日時にはキャンパス北側(駅方向:徒歩10分)のコンビニエンスストア等をご利用ください.信州大学工学部周辺には飲食店が少ないので,ご注意ください.
共催・協賛団体の一覧
2015長野大会:巡検協賛およびセッション共催団体一覧
巡検協賛団体
セッション共催団体(セッション番号)
・資源地質学会
・石油技術協会
・地学団体研究会
・東京地学協会
・日本応用地質学会
・日本火山学会
・日本活断層学会
・日本鉱物科学会
・日本古生物学会
・日本自然災害学会
・日本堆積学会
・日本第四紀学会
・日本地学教育学会
・日本地球化学会
・日本地球惑星科学連合
・信州大学山岳科学研究所(S1)
・日本古生物学会(S2)
・IUGS−法地質学イニシアチブ(S3)
・日本法科学技術学会(S3)
・地質汚染−医療地質−社会地質学会
(S3,R18)
・日本堆積学会(R8,R9,R10,R11)
・石油技術協会探鉱技術委員会
(R8,R9,R10,R11)
・日本有機地球化学会(R8,R9,R10,R11)
・日本原子力学会バックエンド部会(R23)
参加登録TOP画面に戻る
巡検へ参加される方へ
巡検へ参加される方へ
「野外見学,調査,試料採取における注意喚起」をご一読下さい
重要 巡検へ参加される方は,参加の前に是非「野外見学,調査,試料採取における注意喚起」をご一読下さい。
「野外調査において心がけたいこと」国立・国定公園や史跡・名勝・天然記念物、あるいは一般的な露頭における調査上の注意点
「安全のしおり(巡検案内書より)」巡検や野外調査における安全上の注意点と自然保護に関する注意点
「巡検案内書を頼りに野外調査へ出かける方へ」露頭での調査や試料採取にあたっての注意点(「野外調査において心がけたいこと」から一部抜粋)
講演情報TOP
講演関連
講演申込・講演要旨投稿はこちらから
講演の申込は締め切りました
締切 6月30日(火)18時 Web申込
*郵送の場合は6月24日(水)必着
★注意★講演申込を予定しているが,まだ入会手続きをされていない方へ
シンポジウム,セッションとも演題登録・要旨投稿はオンライン入力フォームに従ってお申込下さい.発表セッションや会場・発表日時等は行事委員会が決定し,7月下旬以降に通知します.やむを得ず郵送で申し込む場合は,学会事務局までお問い合わせ下さい.発表申込書等必要な書式をお送りします.提出書類等,要旨原稿をご準備の上,6月24日(水)必着で学会事務局までお送り下さい.講演申込をされる方は,別途事前に大会参加登録も行って下さい.
▶シンポジウム
▶▶シンポジウム一覧および申込
▶セッション発表の募集
▶▶セッション一覧
▶▶セッション招待講演者の紹介
---------------------------------------------------------------------------------
▶講演要旨について(シンポ・セッション共通)
▶▶講演要旨の作成の注意点とPDFファイル作成の作り方
▶▶講演要旨オンライン投稿手順チェックシート
▶▶保証・同意書(2015長野)
▶発表要領(シンポ・セッション共通)
セッション発表の募集
セッション発表の募集(募集要領)
講演申込・講演要旨投稿はこちらから
講演の申込は締め切りました
締切 6月30日(火)18時 Web申込
■シンポジウム一覧はこちら■
■セッション一覧はこちら■
注:シンポジウムに関しては、シンポジウムのページを参照して下さい。
(1)セッションについて
今大会では6件のトピックセッションと24件のレギュラーセッション,およびアウトリーチセッションを用意します.各セッションの詳細については上記「シンポジウム・セッション一覧」をご覧下さい.
(2)発表に関する条件・制約
1)会員は全31セッションのうち1つまたは複数(下記)に発表を申し込めます.発表申込者=発表者とします.非会員は発表を申し込めません.発表を希望する非会員は6月24日(水)までに入会手続きをして下さい(入会申込書が届くまで発表申込を受理しません).共催団体の会員は共催セッションへの発表申込が可能です.
2)口頭発表あるいはポスター発表を1人1題申し込めます.ただし,発表負担金(1,500円)を支払うことでもう1題(最大2題)の申し込みが可能です.発表可能な組み合わせは下記を参照して下さい.
セッションA:口頭2件
×(申込不可)
セッションA:ポスター2件
×(申込不可)
セッションA:口頭,ポスター各1件ずつ
○(申込可)
セッションA:口頭1件,セッションB:口頭1件
○(申込可)
セッションA:ポスター1件,セッションB:ポスター1件
○(申込可)
※発表可能な形式の組み合わせは,招待講演も同様です
※これらの制約はアウトリーチセッションには適用しません(後述)
3)共同発表(複数著者による発表)の場合は,上記「1人1題,ただし発表負担金支払いによりもう1題可」の制約を発表者(=発表申込者)に対して適用します.その際,発表者は筆頭でなくても構いません(筆頭者に会員・非会員等の条件はありません).講演要旨では,発表者氏名を下線(アンダーライン)表示にして下さい.
(3)アウトリーチセッション
このセッションは,会員による研究成果の社会への発信(アウトリーチ)を学会として力強くサポートするために,トピック・レギュラーと並ぶ第三のカテゴリーとして設けられているものです.市民に対するアウトリーチ活動に関心のある会員はぜひお申し込み下さい.
1)トピック・レギュラーと同様の演題登録・要旨投稿が必要です.要旨校閲(後述)もトピック・レギュラーと同様に行います.要旨は講演要旨集に収録され,正式な学会発表扱いになります.
2)本セッションの発表には,上記の発表数に関するルール(1人1題,ただし発表負担金を支払えばもう1題可)を適用しません.例えば,レギュラーセッションで1題発表する会員がアウトリーチセッションでも発表する場合,発表負担金はかかりません.ただし,同一発表者(=発表申込者)が本セッションで発表できるのは1題のみとします.
3)ポスター発表のみとし,12日(土)の市民講演会会場と(講演会の前1時間,後30分をポスターコアタイム)と13日(日)の大会ポスター会場(信州大学長野キャンパス,コアタイムでの立ち会いは必須としない)で実施する予定です.
4)市民には講演要旨のコピーを配布しますが,これとは別に資料を独自に配布していただいても構いません(ただし発表者負担).
5)スペース等の都合から,募集件数は10件程度とします.募集件数を上回る応募があった場合は行事委員会が採否を検討します.
6)優秀ポスター賞の選考対象になります.
(4)招待講演
「セッション招待講演の紹介」をご覧下さい. 招待講演も期日までに一般発表と同様に演題登録・要旨投稿が必要です.非会員招待講演者の場合は世話人が代理でオンライン入力することも可能です.非会員招待講演者に限り参加登録費を免除します(講演要旨集は付きません).また,招待講演は発表負担金の枠外として扱います.
(5)セッション発表申込の際の注意点
1)発表方法は「口頭」「ポスター」「どちらでもよい」のいずれかを選択して下さい(アウトリーチセッションはポスターのみ).締切後の変更はできません.会場の都合のため,発表方法(口頭⇄ポスター)の変更をお願いすることがあります.
2)発表題目と発表者氏名は,登録フォームと講演要旨の両方を一致させて下さい.
3)発表希望セッションを必ず第2希望まで選んで下さい.
4)関係する一連の発表があるときは,必要に応じて発表順希望等をコメント欄に入力して下さい(ご希望に沿えない場合があります).
講演要旨について(シンポ・セッション共通)
講演要旨 シンポ・セッション共通
(1)講演要旨の投稿
講演要旨はA4判1枚とし,PDFファイルのオンライン投稿により受け付けます.印刷仕上がりは0.5ページ分です(1ページに2件分を印刷).原稿をそのまま版下とし,70%程度に縮小印刷します.文字サイズ,字詰め,鮮明度等に注意して下さい.やむを得ず郵送する場合は,オリジナルか鮮明なコピーを1枚郵送して下さい.FAXやe-mailでの投稿は受け付けません.「PDFファイルの作り方」,フォーマット,wordテンプレートをご参照ください。
(2)講演要旨の倫理責任と著作権管理
本学会は,本学会出版物への投稿原稿に対して,その倫理性について著作者が保証する「保証書」および著作権を本学会へ譲渡することに同意する「著作権譲渡同意書」に署名捺印をして提出していただいております.学術大会の講演要旨投稿では,オンライン画面上で「保証書」と「著作権譲渡等同意書」の内容に同意していただいてから電子投稿画面に進めるようになっています.
「保証及び著作権譲渡等同意書」ダウンロードはこちらから
(3)講演要旨における文献引用
引用した文献の情報を必ず記載して下さい.講演要旨では文献記載の簡略化が認められています.著者名,発表年,掲載誌名など,文献を特定できる必要最低限の情報を明記して下さい.
(4)講演要旨の校閲
行事委員会は,すべての(招待講演を含む)講演要旨について,学会の目的ならびに倫理綱領(定款第4条)に反していないかという点について校閲を行います.校閲によりいずれかの条項に反していると判断された場合,行事委員会は修正を求めるか,あるいは発表申込を受理しないことがあります.行事委員会の措置に同意できない場合,発表申込者は法務委員会(学会事務局気付)に異議を申し立てることができます(下記参照).
講演申し込み異議申し立てについて
日本地質学会行事委員会は,学術大会において学会の目的及び倫理規定に反する講演申し込みのあった要旨に対して,修正あるいは,受理を拒否することができます.法務委員会では,日本地質学会行事委員会規則に基づき,異議申立の手続及びその処理についての規則を定めています.
日本地質学会法務委員会
■日本地質学会学術大会講演申込異議申立に関する処理機構規則(PDF)■
セッション招待講演者の紹介
セッション招待講演の紹介
世話人や専門部会から提案され,行事委員会が承認した招待講演者(予定)の概要を紹介します.学術的にも社会的にも注目されている研究者やテーマが目白押しです.会員の皆様,この機会をお見逃しなく! なお,講演時間は変更になる場合があります.
(行事委員会)
T1.グリーンタフ・ルネサンス
T2.文化地質学
T3.水蒸気噴火と火山体構造
T4.三次元地質モデル研究
T5.泥火山
T6.日本の地球史
R4.変成岩とテクトニクス
R6.ジオパーク
R7.海洋地質
R8.堆積物の起源・組織・組成
R10.堆積過程・堆積環境・堆積地質
R11.石油・石炭地質学
R12.岩石・鉱物の変形と反応
R13.沈み込み帯
R14.テクトニクス
R16.ジュラ系+
R18.環境地質
R19.応用地質・ノンテク
R22.地球史
R23.原子力と地質学
R24.鉱物資源と地球物質循環
T1.グリーンタフ・ルネサンス
■ 星 博幸(愛知教育大学)会員,30分
星氏は,古地磁気研究に基づいた新生代日本列島テクトニクス研究を中心的に展開してきた研究者である.特に,日本海拡大に伴う島弧の回転運動について新たな観点から検討を続けている.日本海の拡大はグリーンタフ形成と密接に関連しているので,本セッションでの招待講演者として適任である.講演は,日本海の拡大と島弧テクトニクスについてレビューをお願いする予定である.
■ 中嶋 健(産業技術総合研究所)会員,30分
中嶋氏は,層序学,堆積学をベースに研究を展開し,島弧中軸地域の奥羽脊梁山脈において,シン〜ポストグリーンタフ時代の地史,テクトニクスを詳細に解明した.グリーンタフ形成の時代から現在の島弧への発達史は,グリーンタフのテクトニクスを解明する上で重要であり,本セッションでの招待講演者として適任である.東北日本弧中軸地域におけるシン〜ポストグリーンタフ変動を中心に講演頂く予定である.
T2.文化地質学
■ 尾池和夫(京都造形芸術大学)非会員,30分
尾池和夫先生は,2008年まで京都大学の総長を務められた地震学者である.その後は,国際高等研究所所長を経て,現在は京都造形芸術大学の学長である.先生は地震学者でありながら,国際高等研究所でジオ多様性のプロジェクトを立ち上げ,地質と文化の関連を発信してきた.また現在は芸術大学長として,地球科学と芸術の関連も述べている.幅広い視野をもつ先生の講演が,地質学と文化の関わりについて,私たちに新たな視点をもたらせてくれることは間違いない.
T3.水蒸気噴火と火山体構造
■大場 司(秋田大学)会員,30分
大場氏は,主に物質科学的な観点から水蒸気噴火およびその発生源となる浅所火山体構造の解明に関する研究を継続的に行っており,国内においてこの分野リードする研究者である.これらの研究成果は,国際誌等にも精力的に公表されており,本セッションの招待講演者として適切であると考える.
■寺田暁彦(東工大火山流体研究センター)会員,30分
寺田氏は,主に地球物理学的観測から復元される熱水卓越型火山の浅所火山体構造の解明に関する研究を継続的に行っており,国内においてこの分野をリードする研究者である.これらの研究成果は,国際誌等にも精力的に公表されており,本セッションの招待講演者として適切であると考える.
T4三次元地質モデル研究の新展開
■関口春子(京都大学防災研究所)非会員,30分
日本の平野域については,すべての都市圏で地震動評価用の深部地下構造モデルが作成されているがその多くは,地層境界面は従属的で,主要には微動アレイ探査などの物理探査による速度構造とその境界面で近似されている.日本では,唯一,関口氏ほかによる大阪堆積盆モデルが,詳しい地下構造探査による地層境界の同定とそれらのポイントデータに基づいて,正確な地層境界面モデルを作成し,その上で,各層内部の物性を地質年代と深度変換式をあてることで,任意の空間の物性(S波速度,密度)を与えるモデルを構築している.三次元地質モデルの構築手法の内容の点で有意義で,物理探査,地震波観測データによるチューニングを経て,高い精度の速度構造モデルにしあげている事例として特筆できる.
■秋山泰久(国際航業(株))非会員,30分
ICTの発達に伴い,国土交通省は土木分野での3次元モデルの作成・活用の取り組みとしてCIM(Construction Information Modeling)を進めつつある.CIMの中での地質・地盤の3次元モデルのあり方は,今後の3次元地質モデルの構築環境を大きく変える可能性がある.これまで全国地質調査業協会連合会の情報化委員として,このことに取り組んでこられた秋山氏を招待講演として選定した.
T5「泥火山」の新しい研究展開に向けて
■田中和広(山口大学)会員,30分
地学雑誌に泥火山研究の特集号が組まれた際の編集者であり,2007年地球惑星科学連合大会において特別セッションを開催するなど,日本の泥火山研究を牽引してきたまさに第一人者である.泥火山について既に理解されている事柄や課題をセッション冒頭でご紹介いただき,聴衆に共通の基礎知識を与えていただく.
■稲垣史生(海洋研究開発機構)非会員,30分
泥火山を海底炭素循環の出口と位置づけ,近年精力的に泥火山研究を進め取りまとめてきたグループのリーダーである.地球化学の理解を軸にした生物学や地質学等幅広い分野を網羅する理解を基にした,これからの泥火山研究に期待される役割と未解決事項を解説いただく.
T6.地球史から宇宙史へ:日本の地球史研究25年
■ B. F. ウインドレー(英・レスター大学) 非会員,15分
1970年代に出版された初版以来,世界の地球史研究の入門書として愛読されてきた”Evolving continent”の著者であり,早くから日本での地球史研究にも深い理解を示して来た.
■ 戎崎俊一(理研)非会員,15分
1980年代に京都大学の林グループが打ち立てた太陽系形成の標準モデルは世界中で受け入れられて来たが,近年の系外惑星の大量発見によって再検討が迫られている.戎崎氏は,既存モデルの問題点を整理し,より普遍性の高い新しい一般的モデルを提唱している.
R4.変成岩とテクトニクス
■板谷徹丸(岡山理科大学)会員,30分
板谷氏は,希ガス用高性能質量分析計及び希ガスの迅速分析技術を K-Ar年代測定に適用し様々な地質事象の解明に貢献した.特に中新世以降の火山活動の分解能を格段に高め,プレート運動の変遷に制御された火山活動論に貢献した.さらに,微細な変成鉱物の系統的なK-Ar年代測定を行い,西南日本の高圧変成岩などの地帯構造を明らかにし,島弧―海溝系の造山運動の新たなモデル構築を行うとともに,西アルプスの研究では,大陸衝突型の沈み込み変成作用の時代論に貢献した.最近では,様々な地質プロセスにおける鉱物や岩石中のArの挙動について精力的に研究を進めており,K-Ar年代測定法の精密な適用と解釈に関する新知見を提示している.板谷氏には,K-Ar年代測定法および微小領域のAr/Ar年代測定法を用いた,新たな地球惑星科学に関する,魅力的な講演を期待する.
■廣井美邦 (千葉大学) 会員 30分
廣井氏は,徹底した岩石組織観察と厳密な岩石学的解析に基づき,国内外の高温・超高温変成岩を用いて,地下深部での部分溶融現象の岩石学的研究を行い,造山帯深部における様々な地質過程や岩石のダイナミックな動きを明らかにしてきた.特に,世界に先駆けて,温度‐圧力‐時間経路の概念を提示した阿武隈変成帯の研究は特筆に価する.最近では,大陸衝突帯に産出する高温・超高温変成岩のザクロ石結晶中から,花崗岩質メルトが過冷却し,極度の非平衡条件下で結晶化したことを示す,珪長岩包有物(felsite inclusion)を見出している.これは,従来の高温・超高温変成岩の地下深部からの上昇・冷却過程に関する常識を覆す発見であるとともに,地殻深部の諸過程の解明に新しい手掛かりとなるものである.廣井氏には,高温・超高温変成岩の部分溶融現象ならびに地殻深部から上昇・冷却を含めた地質過程に関する,魅力的な講演を期待する.
R6.ジオパーク
■ 松原典孝(兵庫県立大学大学院)会員,30分
松原典孝氏は,火山砕屑岩の層序と堆積相解析に基づく島弧の構造発達史の研究を専門としつつ,学生時代から茨城県北ジオパーク構想の推進に関わり,現在は山陰海岸ジオパークを学術面から支えるとともに,日本ジオパーク委員会の審査にも貢献している.これらの経験を元に,同氏は現在のジオパークの到達点と課題を講演することができ,本セッションの招待講演者にふさわしい.
R7.海洋地質
■ 横瀬久芳(熊本大学)非会員,30分
北部沖縄トラフ,特にトカラ列島海域の火山地質学を精力的に推進しており,これをテーマに大学での教育にも力を入れるとともに,TV出演等,アウトリーチ活動もしっかりと展開している.同氏からは,「トカラ列島海域の火山地質学に関する総合レビュー」などの講演を期待できる.
■ 石橋純一郎(九州大学)非会員,30分
沖縄トラフなどの海底熱水系の地球化学的研究を研究キャリアを通じて行ってきた,海底熱水研究の第一人者の一人である.新学術領域研究「海底下の大河」では,計画研究の研究代表者に一人として領域研究の成功に尽力した.その成果は,同氏を筆頭エディターとした論文集「Subsefloor biosphere linked to hydrothermal systems: TAIGA concept」(Springer, 2015)として刊行された.同氏からは,「沖縄トラフの海底熱水系のレビュー」などの講演を期待できる.
R8.堆積物(岩)の起源・組織・組成
■太田充恒(産総研)非会員,30分
太田充恒氏は現世河川堆積物を用いた地球化学図の第一人者であり,化学組成から地球表層の物質移動を解き明かす研究を進めている.今回はある元素に注目して,後背地からどのように物質が移動・濃集するかについての講演を頂く予定である.
■大山隆弘(電中研)会員,30分
大山隆弘氏は風化作用の専門家であり,今回は化学的風化作用の総論についてお話し頂く予定である.いずれの発表も,現世風化プロセスを理解するために重要であり,地質時代の風化度の研究を進めている会員にとって有益であると期待される.
R10堆積過程・堆積環境・堆積地質
伊藤 慎(千葉大学)会員,30分
伊藤会員は,露頭観察に基づいて堆積過程や堆積環境を解明する研究に一貫して取り組んでおり,この分野をリードする一人である.特に,直接観察・観測が困難で露頭観察の役割が大きい深海環境に注目し,セディメントウェーブを含む重力流堆積物の形成プロセスに関する多数の成果を挙げてきた.このため,近年の研究動向のレビューも交えて最新の知見を紹介いただき,堆積学研究における露頭観察の意義について再考する機会としたい.
R11石油・石炭地質学と有機地球化学
■奥井明彦(出光興産(株))非会員,30分
奥井氏は石油システムに関するモデリングのエキスパートであり,国内外の石油探鉱開発業務に従事している.長野大会を機会に,新潟堆積盆地の直江津地域の石油システムに関する講演をして頂き,地質学の研究が石油探鉱にどうのように活用されているかを講演して頂く.
■森田澄人(産業技術総合研究所)会員,30分
森田氏は経産省・資源エネルギー庁による委託研究「日本海表層型メタンハイドレートの資源量把握のための調査」の責任者として調査・研究を統率している.現在,進められている調査の概要と,地質学的な面白そうないくつかの話題について講演して頂く.
R12岩石・鉱物の変形と反応
■大内智博(愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センター)非会員,30分
大内智博氏は,岩石の組織発達・構造形成に関する動的過程の実験研究で最先端に立つ研究者の一人である.近年,高圧力・含水量の幅広い条件においてマルチアンビルを用いた剪断変形実験や構造発達のその場観察に取り組み,上部マントルかんらん岩のレオロジーの多様性を示す結果を発表されている.今回は最近議論が活発となっている上部マントル流動の素過程についてお話をしていただきたい.実験室とフィールドの視点を合わせて地球物質科学的な議論の活性化に期待する.
■片山郁夫(広島大学大学院理学研究科)会員,15分
片山氏は,フィールド調査や変形・透水実験を通して地球内部での物質循環に関する研究を精力的に展開されている.特に,沈み込み帯深部での流体移動や岩石レオロジーへの水の影響に注目して,プレート境界で起きる地震や火山に関する魅力的な研究成果を発信し続けている.本セッションにおいて,ここ数年取り組まれている摩擦ヒーリングに関する最新の成果を講演していただき,地質学,岩石学,鉱物学など様々な視点から地震と断層に関する議論をおこないたい.
R13沈み込み帯・陸上付加体
■ウォリス サイモン(名古屋大学)会員,30分
ウォリス氏は三波川変成岩類を対象に岩石学的・構造地質学的研究を長年精力的に進め,興味深い成果を次々とあげられている.近年,三波川変成岩類は南海トラフ深部におけるスロー地震(Episodic Tremor and Slip: ETS)発生域の陸上アナログとして注目を浴びている.ウォリス氏らのグループは,三波川帯中の蛇紋岩における反応・変形・鉱物組み合わせを検討し,それらを南海トラフにおけるETSの地球物理学的観測結果と比較することで,ETSをコントロールする地質学的要因を論じている.ETSの地質学的描像構築を目指したこれまでの研究成果を詳しく紹介して頂くとともに,今後取り組むべき課題を議論していきたい.
■山下幹也(海洋研究開発機構)非会員,30分
山下氏は反射法地震探査による地下構造の研究を専門とし,例えばパレスベラ海盆の反射断面を用いて海盆の初期発達過程を明らかにするなどの成果をあげられてきた.近年では,南海トラフ軸域を対象とした高分解能反射法探査を担当されており,前縁断層帯等,トラフ軸近傍の構造を詳細に明らかにしつつある.これまでに得られた結果をご紹介いただくことで,南海トラフ沈み込み帯最浅部での付加体や断層帯の発達を議論したい.
R14 テクトニクス
■ 田上高広(京都大学)会員, 30分
候補者は,熱年代学を用いた地質学的時間スケールで山岳の隆起/侵食史を明ら かにする研究を行ってきた.熱年代学とは,放射年代が熱によってリセットされ る現象を利用して温度変化を伴う地質イベントの年代を求める学問領域であり, 候補者は同分野の第一人者である.この手法を地下深部の高温領域から地表 ま で上昇してきた岩石に適用することによって,過去数100万年スケールにおい て,測地学的手法にも迫る数mm/yr程度の分解能で山岳の隆起・削剥速度を見積 ることが可能である.本講演では長野大会では最適である,熱年代学を用いた中 央アルプスなどの隆起史復元について最新の話題提供を期待する.
R16ジュラ系+
■ 伊庭靖弘(北海道大学)会員,30分
伊庭氏は,中生代におけるテチス−パンサラサの海洋環境変遷を,生物地理学的なアプローチから議論している.軟体動物や原生生物など,多様な海洋生物を取り扱い,複眼的な視点から現象をとらえようとするところに研究の特徴がある.招待講演では,今後の研究の展望を含む内容になるよう依頼しているので,活発な議論が交わされることを期待したい.
R18 環境地質
■ 中屋眞司(信州大学)非会員,30分
中屋氏は,地層中の断層・節理・クラックなどの亀裂を考慮した岩盤透水性の研究や地下水資源管理・保全に関わる研究ですぐれた業績を上げている.中屋氏が所属する信州大学工学部で年会を開催するに当たって,その成果を講演頂き,地質学会の多くの方々と議論,情報交換することは大変有意義である.
R19応用地質学一般およびノンテクトニック構造
■ 佐々木靖人(土木研究所)会員,30分
佐々木氏は,応用地質学の立場から,日本全域の直轄国道の道路斜面防災に関する研究を推進している.1996年に発生した北海道・豊浜トンネル事故のように,突発的に発生する岩盤崩壊は,通行車両に甚大な影響を与えるため,危険な道路斜面をあらかじめ抽出し,定期的な監視と維持管理を継続する必要がある.そのためには,斜面の地質学的な理解に基づく危険度評価が必須となる.招待講演では,具体的な道路被災事例と防災対策,ならびにそれらの課題に関する講演を期待する.
■ 近藤久雄(産業技術総合研究所)会員,30分
近藤氏は,現在糸魚川-静岡構造線活断層系(以下,糸静線)を最も精力的に調査している研究者の1人である.変動地形調査やトレンチ調査を継続して実施し,糸静線全体の活動性や連動性を明らかにしようと試みている.昨年11月の長野県北部の地震では地震直後に神城断層の現地調査を行い,地表変状や地盤災害の状況を報告された.本報告では最新の調査結果を中心に,活断層と地震災害についての講演を期待する.
R22地球史
■ George M. Tetteh(ガーナ,鉱業・資源大学)非会員,30分
(当初の予定より招待講演者は変更となりました.2015/6/24)
R23原子力と地質科学
■ 山崎晴雄(首都大学東京)会員,30分
山崎氏は,地形発達史研究を中心に,第四紀地殻変動や地震断層等に関する分野の研究を精力的に進めてきており,近年では,総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原子力小委員会放射性廃棄物WG委員をなどを務める.とくに日本の長期的な地質環境の変化を踏まえた上で,地質科学の原子力における役割について議論の行える研究者の1人だと言える.招待講演では,第四紀変動に関する知見も踏まえて,原子力分野の課題についてどう対処していくべきか等の講演を頂く予定である.
R24.鉱物資源と地球物質循環
■ 小宮 剛 (東京大学)会員,30分
小宮氏は,グローバル物質循環と,その全地球史を通じた変遷に関する研究の第一人者である.近年,カナダにおいて最古の表成岩を発見し,初期地球の表層環境解読に関する重要な成果を挙げられている.また,資源形成と関連の深い地球表層の酸化還元状態の変遷について,レドックスセンシティブな元素(Fe, C, Sなど)と水や親水元素の挙動から明らかにする研究を,精力的に展開されており,本セッションの目指す「地球表層-内部環境,テクトニックセッティング,ダイナミクスと,資源の形成メカニズムとの関わり」についての最新の話題を提供して頂くのに最も相応しい方である
その他の申込TOP
その他のお申込
■ ランチョン・夜間小集会(申込:6/24締切>締切りました)
■ 小さなEarth Scientistのつどい〜第13回小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜(申込:7/16締切)
■ 託児室の利用(申込:8/21締切)
■ 企業展示・書籍販売・要旨集広告掲載募集(7/3一次締切,8/7最終締切)
■ 緊急展示(申込:8/31締切)
■ 若手会員のための業界研究サポート(旧就職支援プログラム)
(出展申込:8/10締切)
ランチョン・夜間集会
9/11ランチョン
9/12ランチョン
9/12夜間集会
9/13ランチョン
9/13夜間集会
ランチョン
昼休みの時間帯を利用した会合です.昼食の用意はありませんので,各自でご用意下さい(口頭会場内は飲食不可の場合があります.ご確認ください).都合により急遽会場が変更になる場合もありますので,会期中の掲示にご注意下さい.
9 月11日(金)12:45〜13:45
第1会場 地域地質部会・層序部会合同(世話人:内野隆之)
部会活動やセッションについての議論と情報交換
9 月12日(土)12:00〜13:00
第1会場 堆積地質部会(世話人:中条武司)
堆積地質部会の活動報告および国内外の堆積学に関する情報交換を行う.
第2会場 三次元地質モデル研究の展望(世話人:木村克己・升本眞二・高野 修・根本達也)
三次元地質モデル研究に関する国内外の最新動向をレビューし,今後の研究展開や技術開発の課題について,意見交換を行う.
第4会場 火山部会(世話人:長谷川 健)
次期部会幹事体制について,本大会トピックセッションの総括と特集号について話し合う.
第5会場 構造地質部会若手の研究発表会(世話人:武藤 潤)
構造地質部会若手の研究発表会を一人20分程度で2名ほどを予定.
第6会場 地質学雑誌編集委員会(世話人:秋元和實)
地質学雑誌の発行などに関する諸課題の解決に向けて,意見および情報交換する.
第8会場 文化地質学(世話人:鈴木寿志)
文化地質学の研究活動について,科研費研究の進展状況,特集号の編集状況を含め,情報交換を行う.これらに関わっていなくても,関心のある方はどなたでもご参加ください.
9 月13日(日)12:00〜13:00
第1会場 海洋地質部会(世話人:芦 寿一郎・小原泰彦・板木拓也)
海洋地質関連の研究機関における最近の研究動向と今後の調査の紹介を行い,各種情報を共有するとともに,海洋地質部会の活動について議論する.
第2会場 構造地質部会定例会(世話人:武藤 潤・丹羽正和・氏家恒太郎)
過去の活動報告,会計報告,今後の活動計画など
第5会場 岩石部会(世話人:鵜澤(平原)由香)
岩石部会に関連した審議の必要な事項について,審議を行う.また,会員への報告が必要な件についても報告を行う.
その他にも,提案したり,連絡をすべき件があれば,ランチョンでの議題として取り上げる.
第7会場 現行地質過程部会(世話人:辻 健)
現行地質過程部会の活動報告,年間予定などを話し合う.部会以外の人たちも大歓迎.
夜間小集会
都合により急遽会場が変更になる場合もありますので,会期中の掲示にご注意下さい.
9 月12日(土)18:00〜19:30
第1会場 炭酸塩堆積学に関する懇談会(世話人:奥村知世・高島千鶴・松田博貴)
炭酸塩堆積学に関連する最近の研究動向や成果について紹介し,意見・情報交換を行う.
第2会場 産官学の堆積学者の集い:明日の堆積学を担う若手研究者の育成プログラム(世話人:武藤鉄司・田村 亨)
堆積学系研究者の若手育成・人材確保を主目的とした産官学連携の緩やかなコンソーシアムを設立する方向で検討が進められている.本集会をもって,コンソーシアム設立に関わる意見集約の場の一つとしたい.
第3会場 地殻ダイナミクス(世話人:竹下 徹)
新学術領域研究「地殻ダイナミクス」に関する研究紹介と情報交換を行う.本領域に直接関連されていない方の参加を歓迎する.
第4会場 南極地質研究委員会(世話人:外田智千)
・南極観測の現況と南極地質将来計画について
・その他(第12回国際南極地学シンポジウム報告)
第5会場 地質学史懇話会(世話人:会田信行)
信州の地質学史に関する講演2題
・田辺 智隆:信州地質学の原点 保科五無斎−明治時代の在野の地質学者−
・富樫 均:信州の地学遺産とその活用
第6会場 環境地質部会(世話人:田村嘉之・風岡 修)
環境地質に関する講演,事務連絡など
第7会場 地質技術者教育委員会(世話人:山本高司)
①中期ビジョンに対しての具体的取り組み,
②ジオスクリーニングのCPD単位基準変更,
③その他(就職・民間から公務員への転職)
第8会場 博物館における地質系学芸員の戦略(世話人:川端清司・平田大二)
規模の大小を問わず全国各地の博物館では,地質系学芸員がそれぞれの現状を踏まえて他館との連携も含めてユニークな活動をしている.今後は,さらに連携が期待されていくものと思われます.今後の活動のヒントになるようなTIPS紹介や,各館における課題(収蔵庫,後継学芸員の採用など)について,今後の戦略を考える機会にしたい.
講義棟101(休憩室) ジオ・アーケオロジー(世話人:渡辺正巳・井上智博・趙 哲済・松田順一郎・小倉徹也・別所秀高)
長野県北部の「立が鼻遺跡」で発掘調査を続けている野尻湖発掘調査団の内山 高さん(山梨県富士山科学研究所)に,「長野県北部野尻湖遺跡の自然環境と人類」として講演して頂く.
講義棟203 15th INTERRADに関する意見交換(世話人:松岡 篤・鈴木紀毅・板木拓也・栗原敏之)
第15回INTERRAD(国際放散虫研究者協会)の2017年10月日本開催に向けて,準備状況を共有し,これからの取組について意見交換を行う.
9 月13日(日)18:00〜19:30
第8会場 ジオパークの活性化をめざして(世話人:天野一男・平田大二・渡辺真人)
近年,日本において多くのジオパークが成立している.また,本年9月にはユネスコの正式プログラムになる可能性が大きい.この状況の中で,日本地質学会のジオパーク支援のあり方について率直な意見交換を行う.
会合のお申込
<申込締切: 6 月24日(水)>
会合開催をご希望の場合は,必要な申込項目をe-mailで行事委員会宛(main[@]geosociety.jp)に申し込んで下さい.開催日時のご希望には沿えない場合があります.また,世話人には,集会内容を大会報告記事(ニュース誌11月号を予定)に投稿していただきます(800字以内,原稿締切は10月下旬を予定).
ランチョン申込
開催予定:大会会期中の昼休み
(今大会では,大会初日9月11日(金)にもランチョンの時間を設けました)
申込項目:
(1)集会名称,
(2)集会内容(50〜100字程度)
(3)世話人氏名・連絡先(メールアドレスと電話番号)
(4)その他ご希望等(日程,参加予定人数など)
夜間小集会の申込
開催予定:9月12日(土),13日(日)18:00〜19:30
申込項目:
(1)集会名称,
(2)集会内容(50〜100字程度)
(3)世話人氏名・連絡先(メールアドレスと電話番号)
(4)その他ご希望等(日程,参加予定人数など)
小,中,高校生徒「地学研究」発表会
小さなEarth Scientistのつどい
第13回小,中,高校生徒「地学研究」発表会
参加校募集
発表申込締切: 7/16(木)
会場風景
日本地質学会地学教育委員会では,地学普及行事の一環として,地学教育の普及と振興を図ることを目的として,学校における地学研究を紹介する「地学研究」発表会をおこなっています.長野大会でも,小・中・高等学校の地学クラブの活動,および授業の中で児童・生徒が行った研究の発表を募集いたします.長野県内,また中部地方の学校,さらには全国の学校の参加をお待ちしています.会場は研究者も発表するポスター会場内に,特設コーナーを用意いたします.同時並行で研究者の発表も行われますので,児童・生徒同士のみならず,研究者との交流もできます.この会を通じて生徒,研究者,市民の交流が進み,地質学,地球科学への理解が深まって,未来を担う生徒たちの学習意欲への良い刺激と励みになることを願っております.なお,参加証とともに,優秀な発表に対しては審査のうえ,「優秀賞」などの賞を授与いたします.下記の要領にて参加校を募集します.
日 時
2015年9月13日(日)9:00〜15:30
場 所
長野大会ポスター会場(信州大学長野(工学)キャンパス内)
参加対象
・小,中,高校地学クラブならびに理科クラブ等の活動成果の発表
・小,中,高校の授業における研究成果の発表
・活動,研究内容は地学的なもの(地質や気象などの地球科学・環境科学,天文など)
申込締切
7月16日(木),下記,日本地質学会地学教育委員会宛にお申し込み下さい.
発表形式
ポスター発表(展示パネルは,縦210cm×横90cm)パネルのほかに標本等を展示される場合には,パネルの前に机を用意します.参加申し込みの際に,その旨を記載して下さい.その場合は展示パネルの下側が隠れる事をご了承下さい.発表者は決められた時間(および随時)パネルの前に待機し説明をしていただきます.
なお,遠隔地および学校行事等のために児童・生徒が参加できない場合は,発表ポスターのみをお送りいただいても結構です.
参 加 費
無料(参加者・引率者とも),開催中の研究者の発表,講演も聴くことができます.
派遣依頼
参加者・引率者については学校長宛,日本地質学会より派遣依頼状を出します.
問い合わせ
・申込先
所定の書式をFAXまたはe-mailで下記宛にお送り下さい.
日本地質学会地学教育委員会(担当 三次)
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F
TEL:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156 e-mail:main@geosociety.jp
【参加申込書のダウンロード】 PDF版 word版
託児室
託児室
<利用申込締切: 8月21日(金)>
男女共同参画委員会では,ご家族で学会参加される会員の皆様に大会期間中にご利用いただける託児所のプランをご用意いたしました対象は,長野大会参加者を保護者とする生後6ヶ月から未就学のお子様となります.
1.開設日時(予定):
9月11日(金)8:00〜20:00,
9月12日(土)8:30〜20:00,
9月13日(日)8:30〜20:00
2.対象:長野大会参加者を保護者とする生後6ヶ月から未就学のお子様.
3.場所:託児所アマービレ(予定)〒380-0921長野市栗田1020番地6ステラビルB・2階
http://www.amabile.vc/updates
4.アクセス:JR長野駅東口すぐ 徒歩2分
申込:ご利用を希望の方はまず下記現地事務局までお問い合わせ下さい.託児所のご案内をお送りします.その後,利用者が直接託児所へ申込手続きを行って下さい.万が一の場合に備え,施設加入の損害保険で対応させていただきます.なお,託児施設のご利用に際しては長野大会実行委員会・日本地質学会は責任を負いかねますのでご了承下さい.
問い合わせ・申込先:
日本地質学会第122年学術大会現地事務局(株式会社 日本旅行 松本支店内)
〒390-0811長野県松本市中央2-6-1住友生命松本ビル1階
TEL:0263-34-5555,FAX:0263-35-3925,
e-mail:gsj2015_nagano@nta.co.jp
担当:土川・伴野・丸山・熊崎
営業時間 月〜金曜10:00〜17:00 土日・祝日休み
会場・交通
会場・交通
メイン会場:信州大学長野(工学)キャンパス(長野市若里4-17-1:講義棟・学部共通棟・体育館・太田国際記念館)
表彰式・記念講演会・懇親会:メルパルク長野(長野市鶴賀高畑752-8)
市民講演会,アウトリーチセッション*:ホクト文化ホール(長野市若里1-1-3)*ポスター発表
地質情報展:長野市生涯学習センター「TOiGO(トイーゴ)4階」(長野市大字鶴賀問御所町)
→地図画像をクリックするとPDFがダウンロードできます.
【信州大学長野(工学)キャンパスまでのアクセス】(メイン会場)
(注意)長野市内には長野(工学)キャンパス(長野市若里4−17−1)の他に,長野(教育)キャンパス(長野市西長野6のロ)があります.メイン会場は,長野(工学)キャンパスです.お間違えのないようにお越しください.
参照URL<http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/maps/map03.html>
工学部キャンパス内マップ
←画像をクリックするとPDFがダウンロードできます.
バス:
(長野電鉄バス)JR長野駅東口から長電バス21番のりば「屋島・保科温泉・日赤行き」バス停より,「日赤経由アークス中央行き」「日赤経由水野美術館行き」「保科温泉行き」のいずれかに乗車(5分),バス停「信大工学部」で下車して,進行方向と反対に直進し「北市」交差点を左折してから,徒歩約2分(約200m).
(アルピコバス)JR長野駅善光寺口を出てアルピコバス2番のりばで,「日赤経由大塚南行き」「松岡行き」「サンマリーン行き」「ビッグハット行き」のいずれかに乗車(8分),バス停「信大工学部前」で下車し,進行方向に向かって徒歩約3分(約300m).
徒歩:JR長野駅東口から,徒歩約20分
※信州大学長野(工学)キャンパスは駐車スペースがないため,乗用車でのご来訪はご遠慮下さい.宿泊施設はJR長野駅周辺にあります.
【メルパルク長野へのアクセス】(表彰式,記念講演会,懇親会)
参照URL<http://www.mielparque.jp/nagano/access/>
徒歩:JR長野駅東口より徒歩約5分
信州大学長野(工学)キャンパスより徒歩約20分
自動車:上信越自動車道長野I.C.から約20分.須坂長野東I.C.から約15分
※メルパルク長野地下駐車場が満車の際は,近隣の有料駐車場をご利用いただきますようお願いいたします.
※大会初日(11日のみ),大学からメルパルク長野までの直通バス(無料)を運行します.
【ホクト文化ホール(長野県県民文化会館)へのアクセス】(市民講演会)
参照URL http://www.n-bunka.jp/traffic/
バス:
(川中島バス)JR長野駅善光寺口,2番乗り場から日赤経由大塚南行き・工業高校経由犀北団地循環に乗車し,中御所下車(約4分),徒歩5分.
(長電バス)JR長野駅東口,1番乗り場から日赤壇田線・保科温泉行きに乗車し,文化会館入り口下車(約3分),徒歩5分.
自動車:上信越自動車道長野I.C.から約20分.須坂長野東I.C.から約15分.
※駐車スペースに限りがあるため,公共交通機関をご利用下さい.
徒歩:JR長野駅東口から徒歩約15分.
信州大学長野(工学)キャンパスより徒歩約10分
【長野市生涯学習センター「TOiGO(トイーゴ)」へのアクセス】(地質情報展)
参照URL http://www.toigo.co.jp/access/
徒歩:
JR長野駅善光寺口より徒歩約10分.
長野電鉄市役所前駅より徒歩約3分.
バス:
(川中島バス)JR長野駅善光寺口1番乗り場から善光寺行きに乗車し,昭和通り下車,徒歩約1分.
(長電バス)JR長野駅善光寺口4番乗り場から長野市循環バス「ぐるりん号」に乗車し,昭和通り下車,徒歩約1分.
自動車:上信越自動車道 須坂長野東I.C.から約20分.上信越自動車道 長野I.C.から約20分
※TOiGOパーキングを利用できます.
大会実行委員会・問い合わせ先一覧
大会実行委員会・問い合わせ先一覧
大会期間中(9/11-9/13)の問い合わせ先
日本地質学会第122年学術大会 現地事務局
(株式会社日本旅行松本支店内 担当:熊崎)
電話:080-3434-8211
e-mail:gsj2015_nagano@nta.co.jp
実行委員会
委員長:公文富士夫(信州大学)
中部支部長:原山 智(信州大学)
事務局長:保柳康一(信州大学)
巡検:原山 智(信州大学)
巡検案内書:小嶋 智(岐阜大学)
男女共同参画企(託児室):現地事務局(担当:熊崎)
問い合わせ先一覧
(1)日本地質学会行事委員会・地学教育委員会・学会事務局
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル6F
TEL:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156
e-mail:main@geosociety.jp
日本地質学会行事委員会(2015年4月現在)
委員長
竹内 誠(担当理事)
委 員
内野 隆之(地域地質部会)
鵜澤(平原)由香(岩石部会)
坂本 正徳(情報地質部会)
田村 嘉之(環境地質部会)
亀高 正男(応用地質部会)
田村 糸子(地学教育委員会)
廣瀬 孝太郎(第四紀地質部会)
岡田 誠(層序部会)
板木 拓也(海洋地質部会)
中条 武司(堆積地質部会)
辻 健(現行地質過程部会)
千代延 仁子(石油石炭関係)
氏家 恒太郎(構造地質部会)
上松 佐知子(古生物部会)
黒田 潤一郎(環境変動史部会)
吉田 英一(地質環境長期安定性研究委員会)
中村 謙太郎(鉱物資源部会)
(2)日本地質学会第122年学術大会 現地事務局(株式会社日本旅行松本支店内)
〒390-0811 長野県松本市中央2-6-1住友生命松本ビル1階
TEL:0263-34-5555,FAX:0263-35-3925
e-mail:gsj2015_nagano@nta.co.jp
担当:土川・伴野・丸山・熊崎
営業時間 月〜金曜10:00〜17:00 土日・祝日休み
企業展示・書籍販売・広告募集
企業等団体展示/書籍販売
企業・団体・研究機関などによる展示を行います.会場は,信州大学工学部キャンパス講義棟2階を予定しています.7月30日現在,以下の各社よりお申込がありました.
企業等団体展示
Exelis VIS株式会社
国立研究開発法人海洋研究開発機構
株式会社加速器分析研究所
株式会社建設技術研究所
株式会社SASAMI-GEO-SCIENCE
株式会社ジオシス
特定非営利活動法人ジオプロジェクト新潟
ジャスコインタナショナル株式会社
日本地球掘削科学コンソーシアム
石油資源開発株式会社
株式会社蒜山地質年代学研究所
メイジテクノ株式会社
安井器械株式会社
ライカマイクロシステムズ株式会社
書籍・物品の展示販売コーナー
エルゼビア・ジャパン株式会社
近未来社
株式会社古今書院
「高遠ぶらり」制作委員会
地学団体研究会
株式会社ニチカ
株式会社ニュートリノ
若手会員のための 業界研究サポート出展募集
若手会員のための業界研究サポート
本年も,表記「若手会員のための業界研究サポート」を開催することになりました.本行事は,地質企業に興味のある学生・大学院生および指導にあたっている教員の方々を対象とし,地質企業の現状や求める人材について語り合う交流会を目的としています.東日本大震災から4年,国土強靱化の施策のもとに“防災・減災に対するハード・ソフト対策”と“戦後から高度成長期にかけて建設されたインフラの維持管理・更新”が重要なキーワードとなっております.この社会的要請に対して地質技術者が不足しており,その人材確保に企業の皆様も苦労されていると思います.また,今後の日本のエネルギー政策として“地熱”・“地下資源”の開発が改めて注目を集めています.実際に企業で活躍されている地質技術者と語り合い,大学で学んだ地質学が企業でどのように生かされているのか,学生・大学院生および教員の方々が,企業の生の声を聴くことができるような場を提供したいと考えています.
日程 2015 年9 月12 日(土)14:00 〜17:00(*時間帯は若干変更になる場合があります)
場所 信州大学長野(工学)キャンパス 工学部講義棟2 階203
主催 一般社団法人日本地質学会
内容 主催者等 挨拶・紹介,参加各社の個別説明会(今回は,例年以上に多くの企業にご参加頂けることになりました.そのため会場の都合上,実施内容を一部変更いたします.各社によるプレゼンテーションはありません).
対象 長野大会に参加する学生・院生および大学教員等の会員.信州大学等の学生・院生および教員等
出展予定企業(敬称略.8月10 日現在)
・川崎地質株式会社
・石油資源開発株式会社
・株式会社建設技術研究所
・中央開発株式会社
・株式会社日さく長野営業所
・日鉄鉱業株式会社
・日本綜合建設株式会社
・三井石油開発株式会社
・応用地質株式会社
・株式会社地圏総合コンサルタント
・株式会社サクセン
・有限会社アルプス調査所
問い合わせ先:
日本地質学会 担当理事 緒方信一/ 事務局 堀内昭子
電話:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156 e-mail:main@geosociety.jp
会場での注意点
その他のお知らせや注意
会場での注意点
■拍手徹底
1題の口頭発表はわずか15分で終了します(セッションの場合).しかし,その発表の裏には,発表者の弛まぬ努力と,研究や発表準備に費やした多くの時間があるはずです.講演が終了したら,惜しみない拍手をお願いします.
■写真撮影・ビデオ撮影の制限
口頭発表・ポスター発表を,発表者に無断で写真撮影・ビデオ撮影してはいけません.撮影には発表者の許可が必要です.また,それらを発表者の許可なく,SNS等で配信もしてはいけません.
■軽装の勧め
7月末現在,信越地区の電力供給は逼迫した状況ではありませんが,不測の事態で急な節電要求がある可能性も考えられます.残暑厳しい時期,大会参加の皆様には軽装をお勧めします.ご理解,ご協力をお願いします.
手荷物について
会場内での手荷物のお預かりは致しません.参加者各自での管理をお願い致します.
無料シャトルバスの運行(9/11のみ運行)
大会初日(11日)のみ,大学からメルパルク長野(表彰式・懇親会会場)までの直通バス(無料)を運行予定です.ぜひご利用下さい.(信州大学長野(工学)キャンパスから,徒歩の場合は約20分)
運行区間:信州大学長野(工学)キャンパス→メルパルク長野(直通)(注)大学→メルパルクまでの片道運行です.
運行日・時間帯:11日(金)14:00〜16:00(約15分間隔で運行)
乗り場:工学部講義棟近くのロータリー
無線LANをご利用頂けます
総合受付周辺および,休憩室で,無線LANを各自のパソコンでご利用頂けます.利用方法は,会場内に掲示します.
CPD単位取得について
CPD単位取得について
地質技術者の皆さん 学術大会でCPD単位が取得出来ます
日本地質学会は,地質技術者への継続教育の一環として,大会参加者・発表者・巡検参加者へCPD単位を発行します.大会参加と口頭/ポスター発表の参加証明書は,参加日の15時以降に「CPD受付」(会場内総合受付付近)においてお渡しします(初日のみ13時から発行可能).また,巡検参加者については各コースにおいて案内者よりお渡しすることになります.
【CPD単位】
・ 学術大会参加に対するCPD(時間に応じて):例)7時間出席 = 7単位
・ 口頭発表に対するCPD:0.4 ×15分発表 = 6単位
・ ポスター発表に対するCPD:2単位
・ 巡検参加に対するCPD:日帰り-8単位,1泊2日-16単位
日本地質学会は,土質・地質技術者生涯学習協議会ジオ・スクーリングネット(GEO・Net:https://www.geo-schooling.jp/)に加入し,地質技術者の継続教育(CPD)に携わっています.大会への参加だけでなく,講演や巡検の参加についてもそれぞれ単位が取得出来ます.またGEO・Netに掲載されている協議会加盟団体のイベント情報についても同様に検索・参加申込などが出来ます(参加の場合は,もちろんCPD単位が取得出来ます).積極的にご登録頂き,GEO・Netをご活用下さい.
また,各支部で主催する講演会や巡検等各種イベントについても,随時本サイトに掲載し,GEO・Net登録者にご参加いただけるようにしていきたいと思います.
技術者継続教育,CPD単位については,下記をご参照ください。
http://www.geosociety.jp/engineer/content0003.html
(地質技術者教育委員会 山本高司)
日程・プログラム
全体日程・プログラム
9/10(木)
プレ巡検(日帰り)
9/11(金)
セッション発表(口頭,ポスター),ランチョン
表彰式・記念講演会,懇親会
9/12(土)
国際シンポジウム,セッション発表(口頭,ポスター),
ランチョン,夜間小集会,
若手会員のための業界研究サポート,市民講演会(午後)
9/13(日)
国際シンポジウム(午前),シンポジウム,
セッション発表(口頭,ポスター),,ランチョン,夜間小集会,
地学教育・アウトリーチ巡検,生徒「地学研究」発表会,
9/14(月)〜15(火)
ポスト巡検(日帰り,1泊2日のコースあり)
以下,クリックするとPDFファイルがダウンロードできます
■全体日程表(8.3 一部修正・更新)
15分コマ割表示(カラー)はこちら
■ 各講演プログラム(8.27公開)
★講演キャンセル,プログラム一部変更のお知らせ(9/10, 10時現在)NEW
9/11(金) 口頭発表 ・ ポスター発表
9/12(土) 口頭発表 ・ ポスター発表
9/13(日) 口頭発表 ・ ポスター発表 ---------------------------------------------
▶セッションのハイライト
▶シンポジウム一覧
▶セッション一覧
▶ランチョン・夜間集会一覧
■ Schedule
■ Program coming soon
11 Sept. (Fri)
Oral ・ Poster
12 Sept. (Sat)
Oral ・ Poster
13 Sept. (Sun)
Oral ・ Poster
-->
発表者への注意
発表者へ
発表者は本学会または共催学協会の会員に限ります(招待講演者を除く).共同発表の場合は,この制限を代表発表者(講演要旨に下線を引いた著者)に適用します.やむを得ない事情により,あらかじめ連記された共同発表者内で発表者の変更を希望する場合は,必ず事前に行事委員会(会期前は学会事務局,会期中は学会本部)に連絡して下さい.この場合も,シンポジウムおよびアウトリーチセッション以外の場合は「会員に限り1人1題(発表負担金を支払った場合は2題)」の制限を守るものとします.代理人の代読,会場内での突然の発表者変更,発表順序の変更は認めません.口頭発表者は発表時間を厳守して下さい.持ち時間15 分のうち,発表は10 〜 12 分とし,質疑応答と講演者の交代時間を確保してください(30 分の招待講演の場合,発表20 〜 25 分).発表に際しては座長の指示に従い,会場運営がスムーズに行われるようご協力下さい.
口頭発表
*口頭発表の会場へは,朝8:15より入場可能です。
口頭発表の会場へは,朝8:15より入場可能です。ご自身による事前のデータ準備(ファイルのインストール)が必要となりますので,特に午前のセッションで発表する方は,時間に余裕をもってお出かけ下さい(大会初日は朝8:30から総合受付にて受付開始)。データ準備のためや受付混雑のために受付前に発表会場に入場される事も可能です。受付手続きは発表後に必ず行って下さい。
・ 1題15分(質疑応答と講演者の交代時間3〜5分を含む).ただしシンポジウムとセッション招待講演は除きます.
・ 口頭発表会場には液晶プロジェクターとWindowsパソコン(OS:Windows 7対応,PowerPoint2007. 2010. 2013 対応)を用意します.
【講演ファイルをUSBメディアでご持参の方】
ファイルのインストールは,セッション開始前に,講演会場前方パソコン設置台にて行ってください.各会場のパソコンのデスクトップ上には日付(例0911)のフォルダが配置さ
れており,その中にセッション番号のサブフォルダ(例T1)が配置されています.そのサブフォルダ内に講演ファイルを保存してください.ファイル名は「発表番号と演者氏名」にしてください(例:S1-O-1長野太郎,T1-O-13松本花子).インストール後,ファイルが正常に投影されることを必ず確認してください.特に,会場のPCと異なるバージョンで作成されたパワーポイントのファイルは,レイアウトが崩れる場合がありますのでご注意ください.
【ご自分のパソコンを使用して講演する方】
Macパソコンをお使いになる方,ソフトの互換性からレイアウトが崩れる可能性のある方,パワーポイント以外のプレゼンテーションソフトをご利用の方は,ご自身でパソコンをご用意ください.会場の液晶プロジェクターにパソコンの切り替え器(ケーブル形状はD-SUB15ピン)を用意します.プロジェクターの解像度設定はXGA(1024×768)です.講演前に出力調整の上,接続してください.Macパソコンをお使いになる方は,必ずD-SUB15ピンのアダプターをご持参ください.接続は発表者自身が責任を持って行なってください.セッション開始前に試写し,正常に投影されることを必ず確認してください.
口頭発表の注意
今大会もPCセンターを設置しません(ニュース誌5月号を参照).セッションが円滑に進むように,次の注意点をよくご確認ください.
発表はできるだけ会場備え付けのWindowsパソコンをご使用下さい(ただしMacご利用の方と動画を使用する方はご自身のパソコンをご用意下さい).プロジェクター解像度は1024×768ドット(XGA)です.パワーポイント・ファイルをUSBフラッシュメモリで持参し,セッション開始前にパソコンにコピーして下さい(セッション終了後,世話人がファイルを削除します).フォントは特殊なものではなく,PowerPointに設定されている標準的なものを使用して下さい.セッション開始前に発表会場で正常に投影されることを必ず確認して下さい.
ご自身のパソコンで発表する方は,セッション開始前に発表会場において正常に接続・投影されることを確認して下さい.事前に解像度(上記)の設定をご確認下さい.会場の接続端子はD-SUB15ピン(ミニ)です.パソコンによってはコネクタが必要になる場合がありますので必ずご持参下さい(会場にはありません).確認作業の混雑とそれによるセッション開始の遅れを防ぐため,早めの確認作業をお願いします.なお,発表者が事前確認を怠ったために発表時にトラブルが生じても時間延長等の措置は取りません.
ポスターセッション
掲示する際のチェスピンを準備いたします.テープは利用できません.
掲示可能時間は9:00〜18:00です.最低掲示時間帯(10:00〜17:00.ただし11日は10:00〜15:05)は必ず掲示して下さい!.撤収は必ず19:00までにお願いします.
コアタイムは,11日(金)が13:45〜15:05,12日(土)と13日(日)が13:00〜14:20です.この時間は必ずポスターに立ち会い,説明して下さい.その他の時間は各自の都合により随時説明を行って下さい.
ボード面積は,高さ210 cm,幅120 cmです.
ポスターには,発表番号・発表題名・発表者名を必ず明記して下さい.
コンピューターやビデオを使用される場合,機器の準備は各自で行ってください.電源は確保できませんので,予備バッテリーをご準備下さい.
ポスター発表に対し,別記の要領にて優秀ポスター賞が授与されます.奮ってご準備下さい.
OR,R6のポスター発表について
ORアウトリーチセッション,R6ジオパークセッションは,一般市民へのアウトリーチ活動を目的として,下記のように発表を行います.
[ORアウトリーチセッション]
12日 (土):場所 ホクト文化ホール(市民講演会会場).掲示可能時間(11:00〜17:30),コアタイム(13:00〜14:00,16:30〜17:30;計2回)
13日 (日):場所 工学部体育館(ポスター会場).掲示のみ,コアタイムはありません.(※ポスター賞審査対象日)
[R6ジオパークセッション]
12日 (土):場所 ホクト文化ホール(市民講演会会場).掲示のみ,コアタイムはありません.
13日 (日):場所 工学部体育館(ポスター会場).コアタイム(13:00〜14:20)(※ポスター賞審査対象日)
優秀ポスター賞について
今大会でも学術発表の優秀ポスターに対して「日本地質学会優秀ポスター賞」を授与します.毎日3〜5件の予定です.受賞者には学会長から直接賞状を授与します(表彰と写真撮影).受賞ポスターは,その栄誉をたたえ,大会期間中,別途設けるボードに掲示します.大会終了後,News誌(年会報告記事)に氏名,発表題目,受賞理由を掲載します.
【審査】
審査は各賞選考委員会が行い,学会長がこれを承認します.選考委員会は日替わりで,行事委員会委員5名,大会実行委員会代表1名および各賞選考委員会委員2名の合計8名により構成されます.選考委員氏名は大会終了後に公表します(News誌11月号を予定).
【審査のポイント】
・(研究内容)オリジナリティ
・(プレゼンテーション)レイアウト・中心点の明示・わかりやすさ・美しさ・斬新さ
【審査結果の発表時間と方法】
発表は各日毎16時頃に行います.表彰は17時前後にポスター会場で行います.ただし,初日(11日)の表彰は,2日目(12日)の表彰時にあわせて行う予定です.審査結果は掲示板や廊下等の要所に貼り出します.受賞ポスターには受賞花をつけ,会期中ポスター会場に掲示します.
巡検申込状況
巡検申込状況(8月6日 12時 現在)
※巡検はそのほかの申込と締切日が異なります。予定されている方は、早めにお申込ください。
[申込締切] Web: 8/7(金)18:00、FAX/郵送: 8/5(水)必着
■ WEB参加登録はこちらから ■
【巡検一覧と各コース見どころはこちら】
班
コース名
定員(最小催行)
申込件数
1
上高地
30(10)
26
2
教育・アウトリーチ
40(25)
21
3
堆積
25(15)
25
4
火山体内部
20(15)
15
5
変動地形
20(15)
12
6
黒曜石
20(15)
17
7
飛騨山脈
20(12)
20
8
蓮華帯
20(12)
18
※定員に近い班は黄色マーカーで示しています.
※定員に達した班はピンク色マーカーで示しています.
◆参加申込人数が各巡検コースの最小催行人員に達しなかった場合,巡検を中止することがあります.
◆巡検協賛団体の会員の方は,会員同様にお申込を頂けます.それ以外の非会員の方は,申込締切時点で定員に余裕があれば参加可能となります.ご承知おき下さい.
◆2班<地学教育・アウトリーチ>は,小中高の教員ならびに一般市民を優先対象とします.
そのほか、巡検のお申込については,こちらをご確認ください.
緊急展示
緊急展示の申込について
申込締切:8月31日(月)
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害調査報告や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コーナー」を設けます.ポスター展示を希望する方は,8月31日(月)までに次の内容を下記申込先にご連絡ください.緊急展示は,正式な学会発表と同じく,コアタイムの時間帯が設けられ,優秀ポスター賞の審査対象となります.また他の要旨と同様に大会後J-STAGE上で公開されます.発表における1人1題の制約は及びません.コアタイムの日程については著者希望を優先します(ただし既にセッションでポスター発表を予定されている場合は,同日でのコアタイムは設定できません).
次の内容を下記申込先にご連絡ください.
1)発表要旨PDF(ニュース誌5月号参照)
2)緊急展示の必要性
3)発表代表者と連絡先
4)希望枚数(1枚:幅90×210cm)
5)コアタイムの日程希望など展示に関わる要望(2〜5の様式は自由)
実行委員会は行事委員会と協議し,可否の判断を致します.希望にはできるだけ応えるようにしますが,展示方法等については実行委員会の指示に従ってください.
申込先:<main@geosociety.jp>
担当:亀高正男(行事委員会)ほか
大会期間中の更新情報
大会期間中のお知らせ
****長野大会期間中の最新情報やお知らせを掲載します****
9月13日(土)
○ 大会最終日 明日から巡検!
明日から巡検です.ぜひ良い写真を撮って冬のフォトコンテストに応募してください.
そして来年は東京・桜上水でお会いしましょう!
最終日の様子はこちらです.
9月12日(金)
○ 長野大会2日目!
国際シンポジウム,若手会員のための企業研究サポート,市民講演会,地質情報展など開催!
2日目の様子はこちらです.
9月11日(金)
○ いよいよ長野大会がはじまりました!
口頭,ポスターあわせて600件以上の発表が予定されています。日本最大の「地質学の祭典」をお楽しみください.地質情報展も開幕,講演会スタート,国際学術交流協定締結,表彰式,懇親会などの写真はこちらです.
プログラム変更
プログラム変更
9/10(木)10時現在
講演キャンセル
9/12(土)
R20-O-3 松田義章(R20.地学教育・地学史)
R24-O-13 加藤泰浩(R24.鉱物資源)
9/13(日)
S3-O-4 SCHINECK William M.(S3.法地質学の進歩)
T5-O-9 MOORE Gregory et al (T5. 「泥火山」の新しい研究展開に向けて)
R7-O-14 中嶋 新ほか (R7. 海洋地質)
時間・内容変更
9/13(日)
S3.法地質学の進歩 内容変更
10:25-10:40 S3-O-4(キャンセル)
下記に変更
10:15-10:25→10:15-10:20 休憩
10:20-10:30 What was found as geological trace evidence? SUGITA Ritsuko
10:30-10:40 Forensic Geology― Methods and Cases. MURRAY Ray
T5. 「泥火山」の新しい研究展開に向けて 時間変更
11:15-11:30 T5-O-9(キャンセル)
Active mud volcanism on Ramree and Cheduba Islands, offshore west Myanmar.Moore Gregory F.・Aung Lin Thu・Kopf Achim
以下,講演時間を繰り上げ
11:30-11:45→11:15-11:30 T5-O-10
LUSI泥火山の特徴と発生過程の再検討(レビュー).谷川 亘・西尾嘉朗
11:45-12:00→11:30-11:45 T5-O-11
フランシスカン・メランジュの最終的配置:泥岩の注入説.小川勇二郎
学術大会でのハイライト
学術大会でのハイライト
2013年仙台大会からの試みとして,「シンポジウム・セッションハイライト」を作成しています.それぞれのシンポジウム・セッションがより盛り上がることを期待して,また,会場で学術大会に不慣れな方(学生など)にわかりやすく情報を提供し,おもしろいサイエンスにひとつでも多く接してもらうことを目的に,「おもしろそう,注目すべき,ぜひ聞いてほしい」発表を世話人に選んでいただき,ニュース誌プログラム記事,学会HPと講演要旨集に掲載しています.2015年長野大会では,30のシンポ,セッションから63件の発表をハイライトとしてご紹介しました.
◆ 第122年学術大会(2015長野大会)のハイライト一覧はこちらから(PDF)
学会創立125周年記念
125周年TOP
創立125周年WEB site
日本地質学会は
2018年に 創立125周年を迎えました
[更新情報]
18/09/19 「ジオルジュ」英語版特別号 全文ダウンロードしていただけます NEW
18/09/11 125周年記念式典 開催報告・講演内容スライドを公開しています
18/09/10 125周年記念 街中ジオ散歩「日比谷入江を歩く」徒歩見学会のお知らせ
18/06/19 「ジオルジュ」英語版特別号 配布協力のお願い
18/03/01 125周年記念式典:祝賀会の参加申込受付開始 記念行事
18/02/06 125周年記念式典 記念行事
18/02/05 コラム:トリビア学史16 東京大学の演説会
17/12/27 コラム:トリビア学史15 客死した鉱山学者ヘルマン・リットル
17/12/15 西日本支部シンポジウム「中央構造線と中央構造線系活断層」(3/3-4) 記念行事
17/12/12 コラム:トリビア学史14 京都の鉱物学者‐比企忠(1866−1927)
17/11/10 会員証(会員カード)をお送りします
17/11/07 コラム:トリビア学史13 地方で生きる:福井県の場合
17/10/17 記念出版「はじめての地質学」
17/10/17 学会オリジナルクリアファイル
17/10/13 コラム:トリビア学史12 誤りは早く直しましょう
17/09/26 コラム:トリビア学史 11 新島襄と地質学
17/08/09 コラム:トリビア学史10 韃靼の地質調査—榎本武揚,オッセンドフスキ
17/08/09 コラム:トリビア学史 9 1893(明治26)年吾妻山爆発にともなう地質学者の殉難
17/06/19 コラム:トリビア学史8 傍系の地質学者 篠本二郎(1863-1933)
17/05/16 会員証_ローマ字表記に関するお願い(6/30締切)
17/05/01 コラム:トリビア学史7 地質学者宮沢賢治研究の嚆矢?
17/04/12 記念事業への醵金者名簿を掲載しました
17/04/07 コラム:トリビア学史6 女性地質研究者の嚆矢
17/03/21 寄付のお願い:クレジットカードもご利用いただけるようになりました
17/03/08 コラム:トリビア学史3 補遺 富士谷孝雄補遺 を掲載しました
17/03/08 コラム:トリビア学史5 中村彌六(1855-1929):地質学に近しい林学者
17/02/07 コラム:トリビア学史4 不思議に満ちた白野夏雲(1827-1899)
17/01/31 記念事業の概要と寄付のお願い 大切なおねがい
17/01/31 記念ロゴ/記念ポスターが完成しました!
16/12/20 記念事業 地質学雑誌特集号の状況について
16/12/15 コラム:トリビア学史3 富士谷孝雄(? – 明治26(1893))はどこへ消えたか
16/11/19 コラム:トリビア学史2 日本にライエルの孫が来た?ビーグル号が来た?
16/09/05 コラム:トリビア学史1 地学会編集『本邦化石産地目録』(1884)
16/07/25 記念事業 125周年記念ロゴ WEB投票(一次選考)>締切ました
16/04/28 記念事業 125周年記念ロゴ募集中(4/28-7/15)>締切ました
16/02/05 記念事業 地質学雑誌特集号の状況について
15/08/26 記念事業 地質学雑誌特集号の募集
15/05/23 日本地質学会125周年を迎えるにあたって
14/02/18 コラム:日本地質学会の60, 75, 100周年記念誌を読む:125周年に向けて
125周年記念事業実行委員会 (2015.5.23発足)
委員長 矢島道子
委 員 渡部芳夫,久田健一郎,平田大二,天野一男,永広昌之,
緒方信一,佐々木和彦,佃 栄吉,宮下純夫(順不同)
記念ロゴ(一次選考WEB投票)
記念ロゴ 一次選考ウェブ投票
125周年記念ロゴデザイン案
一次選考(WEB投票)はこちらから
(会員限定)
WEB投票受付期間 7月25日(月)〜8月22日(月)17時
締切ました.
ご協力ありがとうございました.
会員の皆様から記念ロゴデザイン案を募集いたしました(4月28日〜7月15日).まずは、会員の皆様による一次選考(WEB投票)を行います。ぜひご協力をお願いいたします(投票は1人1回のみ有効です).
1次選考ののち、選考委員会にて2次選考を行います(ロゴデザイン案の募集〜選考に関する詳細はこちらから).
125周年を迎えるにあたって
日本地質学会125周年を迎えるにあたって
日本地質学会125周年を迎えるにあたって
一般社団法人日本地質学会理事会
125周年記念事業検討委員会
日本地質学会は1893(明治26)年に創設され,明治30年の会員数は128名であった.それ以来,日本地質学会は営々と学問の歴史を築き,現在の会員数は約3800名,2018年には125周年を迎える.
明治維新後,日本における地質学は国土の開発のために必須の学問としてその歴史が始まった.農業,工・鉱業は日本列島の地質の解明とともに発展し,鉄道や道路の敷設,トンネル掘削地の決定などは地質学の裏付けが不可欠であった.その後も地質学は大いに日本の近代化に寄与し,発展に貢献してきた.近年になり,経営的観点から炭鉱をはじめとする日本の鉱山の大部分が閉山となったが,2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震とそれに続く原子力発電所事故により,地質学に対しては,社会の持続的発展に向け,国土が適切に利用されるための情報の供与,評価が求められるようになった.
地質学は地層や岩石,化石,鉱物などを探求する学問として発展して来たが,現在では地球の生成から現在に至るまでの地球史の統合的理解が進み,未来予測までもが学問の対象となっている.このような進歩により,巨大津波についての予測の提供ができるようになり,レア・メタルやメタンハイドレート,深海底熱水鉱床の発見など,未来につながる新しい発見も相次いでいる.さらに,頻発する巨大自然災害や火山噴火,地球環境問題の複雑化への対応において,地質学的観点が重視されるようになり,地質学が果たすべき役割は一定の認知を得ている.一方で,ジオパークの推進,地学教育の充実ならびに自然災害や環境問題に対する市民の理解を高めることは,日本の地質学における今後の継続的課題である.
日本地質学会の創立125周年は,地質学の来し方,行く末を見つめ直す機会であり,地質学のさらなる地位向上と地質学会の社会的発信力を強化していく絶好の機会でもある.私たちはこのような状況を踏まえ,創立125周年にむけて,一連の記念事業の実施を計画している.記念事業を成功させるためには,多くの会員諸氏の参画・協力が不可欠であるので,本記念事業への参画・協力を広くお願いしたい.
2015年5月23日
(追記)5月23日より,125周年記念事業実行委員会が発足しました.
メンバー:渡部芳夫,久田健一郎,平田大二,矢島道子,天野一男,永広昌之,緒方信一,佐々木和彦,佃 栄吉,宮下純夫(順不同)
記念事業_地質学雑誌特集号の募集
日本地質学会125周年記念地質学雑誌特集号の状況について
日本地質学会125周年記念地質学雑誌特集号の状況について
125周年記念特集号企画委員会 宮下純夫
2016年12月
2018年に迎える日本地質学会創立125周年記念事業のさきがけとして,2017年より様々な企画が始まります.今回の125周年にあたっては,「日本の地質学100年」以降の25年間における各分野の進展や成果を地質学雑誌特集号として2017年から2年間にわたって順次取りまとめることとなっています.125周年記念特集号は当初の予定では2017年の1月号からの開始を予定していましたが,実際の投稿・編集作業の遅れのため,開始時期については多少遅れる見込みです.
前回に報告して以降,さらに追加の申し込みがあり,現在予定されている記念特集号は14タイトル16号分となっています.また,実際の分量によってはさらに号数が増える可能性もあります.以下に記念特集号の構成を示しますが,タイトルに関しては仮題であり,順序は掲載順序を示すものではありません。また、地学教育に関しての個別総説論文も予定されています。これらの特集号が順調に進行し,地質学会の学術活動がさらに活発化することを願っています.
125周年記念特集号の個別タイトル
○深海掘削計画(IODP)と深部掘削船「ちきゅう」10年の成果(2分冊)
○水蒸気噴火の地質学的研究の進展
○日本の火成岩研究の進展と展望
○日本の変成岩研究の進展と展望
○構造地質学の最近25年の成果と今後の展開(2分冊)
○日本列島の形成
○グリーンタフ・ルネサンス
○日本の応用地質学の進展と展望
○オマーンオフィオライト
○「泥火山」の新しい研究展開に向けて
○付加体地質中に残る深海堆積相の研究:進展と展望
○日本の古津波
○堆積学・堆積地質学の日本における進展と展望
○第四紀地質学の新展開
(○地学教育に関する個別総説論文)
(2016.12.20掲載)
◆ 記念特集号募集案内(2015.11.30締切)
日本地質学会125周年記念地質学雑誌特集号の状況について
日本地質学会125周年記念地質学雑誌特集号の状況について
125周年記念特集号企画委員会
昨年の11月末を〆切としていた地質学会125周年記念地質学雑誌特集号には多くの申し込みを頂きました.特集号としては10件,個別総説論文としては2件の申し込みがありました.これらの内容について企画委員会で検討を重ねてきましたが,現時点での状況について会員の皆様へお知らせします.10件の特集号の申し込みのうち,下記の9件の特集号が企画委員会として採択されています.1件については保留となっており,再提案を受けて再度検討することとなっています.
1.深海掘削計画(IODP)と深部掘削船「ちきゅう」10年の成果 14編 2分冊
2.水蒸気噴火の地質学的研究の進展 5編
3.グリーンタフ・ルネサンス 5編
4.オマーンオフィオライト 8編
5.日本の火成岩研究の進展と展望 9編
6.日本の変成岩研究の進展と展望 10編
7.「泥火山」の新しい研究展開に向けて 12編 2分冊
8.日本の構造地質研究の進展と展望 16編 3分冊
9.日本の応用地質学の進展と展望 6編
(ナンバリングは整理の都合上の番号で,掲載順を意味していません)
これらのうち,5,6,8の中には日本列島の形成に深く関連した論文が数編あります.また,個別総説論文の1編も同様のカテゴリーに入るので,それらをまとめて独自の特集号とするべく現在調整中です.したがって,現在のところ,10タイトルの特集号で号数にすると13号分の特集号企画の準備が進行中です.2017年1月号への掲載を目指して,順次,具体的な作業が進行している最中です.
また,上記のタイトルを概観すると,まだ欠けている分野やテーマもあります.古環境解析や津波堆積物研究の進展をはじめとした堆積学関係などの分野についても,特集号企画の準備をすすめています.
(2016.2.5掲載)
日本地質学会125周年記念事業 地質学雑誌特集号の募集
日本地質学会125周年記念地質学雑誌特集号企画委員会
1.はじめに
2018年に日本地質学会創立125周年を迎えるにあたっての記念事業の一つとして,地質学雑誌特集号を連続して企画する事が決定し,その推進のために日本地質学会125周年記念地質学雑誌特集号企画委員会が設置されました.
本特集号では,創立100周年時に刊行された「日本の地質学100年」以降の25年間を中心とした各分野の研究動向をまとめて順次発行します.掲載は2017年から開始し,およそ2年間にわたって隔月で刊行される予定です.以下に記念特集号の概要を示しますが,自薦・他薦など本特集号への多数の申し込みを期待しています.
2.記念特集号の意義
100周年記念事業の際にはハードカバーの単行本して「日本の地質学100年」が刊行されました.今回の地質学雑誌特集号とすることのメリット・意義は以下のようにまとめられます.
1)
地質学会全会員へ配布されるので,高度化・細分化・学際化しつつある各分野の研究動向に関する情報を全会員が享受することが出来,会員サービスの向上と地質学会の強化につながります.
2)
地質学雑誌の安定的刊行とその魅力の増大にとって,総説論文を増すことや特集号の企画が重要である事が従来から強調されてきましたが,今回の連続した特集号の企画は,その方針とも合致しています.
3)
今回の特集号の企画・実施プロセスにおいて,専門部会や多様な研究グループなどの活動を活発化させる事が期待され,本学会の核心的な事業内容である学術的活動の活性化にもつながります.
4)
単行本に比べて財政的負担も少なく済みます.
3.125周年記念特集号の要項
1)
概ねこの25年間の日本地質学会会員による学術的進展を主題とした総説論文を中心としますが.最新のトピック紹介や短い原著論文などが入っても構いません.
2)
個別特集号のテーマ設定は,例えば,ある分野全体の研究動向を体系的にまとめたもの,ある特定の研究対象・事象を中心とした構成や,境界領域に広くわたる場合など,多様であって良い.
3)
国際的なアッピールの場にしたいという事も想定して,英語原稿で構成される特集号(あるいは個別論文)が混在しても良い.
4)
地学教育やアウトリーチ,ジオパーク,自然災害や環境問題などに関わる課題に関しては,別途,「社会と地質学」といったカテゴリーのもとで社会一般への アッピールを目的とした取りまとめが検討されています.しかし,本記念特集号は観点が異なりますので,これらと課題が重複しても構いません.
5)
原稿の種別や作成要領は地質学雑誌の投稿規定に基づきます.
6)
12冊の個別特集号へと纏め上げていく過程での調整は本企画委員会において行いますが,個別の特集号への投稿や編集作業は地質学雑誌編集委員会のもとで,地質学雑誌投稿編集出版規則の細則2(地質学雑誌特集号刊行までの手順に関する細則)に基づいて進められます.
(*もし地質学雑誌の発行形態が変化する場合はその変化に対応して対処します)
4.募集要項
1)
細則2に準じて記念特集号申し込みを行って下さい.ただし,通常の特集号申し込みとは異なり,この段階では原稿そのものは必要ありません.また,個別論文(総説)の企画も受け付けます.また,ある人にこういうテーマで書いてほしいといった他薦も受け付けます.
2)
第1次募集は2015年11月30日〆切とします.掲載時期が2017-2018年の2年間にわたりますので,状況に応じて第2次募集を行います.他薦に関しては早めに申し込み下さい.
3)
申込先は 地質学会事務局気付で本委員会宛として下さい.本委員会の構成は以下の通りです.
秋元和実,伊藤 慎,永広昌之(副委員長),狩野謙一,小嶋 智,佃 栄吉,中川光弘,久田健一郎,廣井美邦,宮下純夫(委員長),山路 敦
*地質学雑誌投稿編集出版規則(細則を含む)は,こちらから
http://www.geosociety.jp/publication/content0002.html#touko
記念出版:地質学と社会
記念出版:「はじめての地質学」
はじめての地質学:日本の地層と岩石を調べる
125周年を記念して、広く社会や市民に地質学の面白さと重要性を理解してもらうための普及書を刊行しました。タイトルは「はじめての地質学―日本の地層と岩石を調べる」です。日本地質学会編著で、ベレ出版から9月に出版されました。
本書は、もちろん書店等で購入できますが、125周年記念事業に対し、個人会員では2口(1万円)以上の拠金をしていただいた方に1冊謹呈しております。ぜひ記念事業に拠金をしていただき、1冊受け取っていただければありがたく存じます。
なお、本書は読み物としてのスタイルで出版しております。ご家族や知人の方々に地質学の面白さをわかってもらうために、また企業・団体では地質学以外の専門分野の方々に地質学を理解していただくために、ご活用ください。
「はじめての地質学―日本の地層と岩石を調べる」
日本地質学会編著
ベレ出版,2017年9月19日発行,四六版,247ページ,
ISBN: 978-4-86064-522-9,定価1,600円+税
https://www.beret.co.jp/books/detail/662(ベレ出版のサイト)
沿革
日本地質学会 沿革
1893(明治26)
5月:東京地質学会 創立
“地質学雑誌”(The Gelogical Magazine .
現在はJournal of the Geological Society of Japan)創刊
1934(昭和 9)
10月:日本地質学会に改称
1953(昭和28)
日本地質学会賞 創設
1968(昭和43)
“地質学論集”創刊(75周年記念討論会論文集として)
1992(平成 4)
欧文誌“The Island Arc”(Blackwell社)創刊
1998(平成 9)
“日本地質学会News”(地質学雑誌より分離)創刊
2008(平成20)
12月1日:一般社団法人日本地質学会 設立
2010(平成22)
5月23日:任意団体日本地質学会 解散.
2018(平成30)
5月:創立125周年
記念事業
125周年記念事業
2018.2.5現在
記念式典(2018年5月18日)
記念学術大会,記念シンポジウム(2018年9月北海道大学)
地質学雑誌特集号
記念出版:「はじめての地質学」(2017年9月出版)
記念出版:「県の石図鑑-全国都道府県の岩石・鉱物・化石-」(2018年予定).
広報誌「ジオルジュ」記念英文特別号(2018年).
会員証(会員カード)発行(2017年11月)
記念ロゴ・記念ポスター
オリジナルクリアファイル
記念ロゴ募集
記念ロゴマーク募集
皆さんのデザインした記念ロゴで125周年記念事業を盛り上げよう!
日本地質学会創立125周年記念ロゴ募集開始!
2016年3月
日本地質学会125周年記念事業実行委員会
委員長 矢島道子
2年後の2018年は当学会が創立して125年目にあたります.
私たちが営む地球の温暖化を防ぎ,かけがえのない人命や貴重な財産を守るための「防災・減災」には,地質学が必要なことは言うまでもありません.同時に,エネルギーや資源の確保にも地質学の力は不可欠です.
そのため,当学会では,様々な分野の研究や研究成果の社会での応用,研究者をはじめとする人材の教育・育成,社会の認知をえるための普及と啓発を進めています.
2018年の創立125周年を契機に,当学会は益々発展・興隆し,さらに社会に役立つ学会とならなければなりません.そこで,125周年を盛り上げるため,会員の皆様から記念ロゴマーク(以後,記念ロゴ)を募集するものです.
ロゴ募集のスケジュール
(1)ニュース誌2016年4月号に記念ロゴの募集を掲載し,同時にWEBサイトジオフラッシュにも掲載します.
(2)募集期間は2016年4月28日から2016年7月15日です.
(3)日本地質学会WEBサイトを用いた会員からの投票による一次選考と,選考委員会による二次選考の2段階選考を行います.
(4)8月下旬までに,記念ロゴ原案として,最優秀作品1点,優秀作品3点を選びます.
(5)デザイナーによるリメイクを行い,ニュース誌2016年11月号に,選考状況,最優秀および優秀作品と作成者,決定した記念ロゴの紹介をおこないます.
(6)最優秀および優秀作品の作成者には表彰状と記念品(後述)を贈呈し,記念ロゴの原案となった最優秀作品作成者については,2018年5月の125周年記念式典にて顕彰します.
(7)2017年1月1日より,記念ロゴの使用を始めます.
募集要項
(1)応募資格は,日本地質学会会員であり,会員種別は問いません.会員家族のアイデアによる応募も歓迎します(ただし,応募は会員名で).
(2)応募作品は,カラー,白黒なんでも受け付けます.綺麗にレタリングやトレースができていなくても,デッサン程度でもOKです.
(3)作品の応募は,WEB専用申込フォームもしくは,「応募用紙」(ニュース誌4月号にも掲載)に必要事項を記入し,下記までお送り下さい.
▶▶ WEB 専用申込フォームはこちらから(締切ました)
▶▶ 郵送先:〒101-0032 東京都千代田区岩本町2−8−15井桁ビル
日本地質学会 125周年記念ロゴ応募係(担当 佐々木和彦)
「応募用紙」(pdfファイル)のダウンロードはこちらから
(4)募集期間:2016年4月28日(木)10:00 〜 7月15日(金)17:00(郵送の場合は消印有効)
(5)応募作品は返却しません.採用された作品の著作権は学会に帰属し,学会が独自に加筆修正を行います.
(6)最優秀作品(1点)には5万円の,優秀作品(3点程度)には1万円の商品券をそれぞれお贈りします.
(7)東京オリンピックのエンブレム盗作事件を鑑み,応募の際には,応募者の責任において商標権や著作権の侵害がないようにしてください.
多くの作品の応募をお待ちしています
記念式典
記念式典
開催報告
式典開催報告記事はこちら(日本地質学会News Vol. 21, No. 8:2018年8月号掲載)
また,式典当日の講演内容スライドを公開しています(表題をクリックすると各PDFをダウンロードして頂けます).
記念講演「地質学はどこで生まれ,どこへ行くのか」(矢島道子 125周年記念事業実行委員会 委員長)
開会挨拶(代表理事・会長 渡部芳夫)
記念報告「日本地質学会125年の歩み」 (佐々木和彦 125周年記念事業実行委員会 副委員長)
日本地質学会創立125周年記念式典
式典チラシ_Full ver.(PDF)
式典チラシ_記念講演ver(PDF)
日時:2018年5月18日(金)10:30〜18:30(予定)
会場:北とぴあ(東京都北区王子1-11-1)
(注)記念講演・式典は3階 つつじホール
祝賀会は16階 東武サロン天覧の間で行います
▶アクセス地図はこちら
JR京浜東北線 王子駅下車北口より徒歩2分
地下鉄南北線 王子駅下車5番出口直結
都電荒川線 王子駅前駅下車徒歩5分
参加無料・事前申込不要 どなたでもご参加いただけます
(注)祝賀会のみ要事前予約,会費制
1)記念講演(10:30〜11:30)(10:00開場)
「地質学はどこで生まれ,どこへ行くのか」(矢島道子 125周年記念事業実行委員会 委員長)
日本地質学会の創立は1893年で,世界最古の英国の地質学会の創立は1807年です.しかし地質学のルーツはもっと古く,16–17世紀まで遡ります.大地の現象を解明しようとした「地球論」を端緒として,“鉱山学の父”といわれるアグリコラの著『デ・レ・メタリカ』のように鉱山や人間の生活に応用する部分が相交わって地質学は発展してきました.これからも,さらなる理論的な深化と,災害対応など人間生活に密接に関わる部分が合い交わって進んでいくことでしょう.今回は,地質学のルーツを辿りながら,未来に向かって地質学が社会にどのように関わり,そして発展していくのかを考えたいと思います.
2)記念式典(学会のあゆみ,表彰式等)(13:30〜16:00)(13:00開場)
開会挨拶 代表理事・会長 渡部芳夫
来賓祝辞
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 理事長
一般社団法人 全国地質調査業協会連合会 会長
一般社団法人 日本地球惑星科学連合 会長
記念報告「日本地質学会125年の歩み」
125周年記念特別表彰
個人(4名:50音順)
阿部國廣(地学教育の推進に貢献)
小玉喜三郎(地質調査総合センターの発展に貢献)
佐藤 正(国際研究活動の推進に貢献)
橋辺菊恵(日本地質学会の発展に貢献)
団体(6団体:50音順)
株式会社 朝倉書店(地学図書出版活動の推進に貢献)
共立出版 株式会社(地学図書出版活動の推進に貢献)
一般社団法人全国地質調査業協会連合会(地質学の実社会への応用に貢献)
特定非営利活動法人地学オリンピック日本委員会(高校生の地学教育推進と地学の普及に貢献)
特定非営利活動法人日本ジオパークネットワーク(ジオパーク整備と地質学の普及に貢献)
日本放送協会(放送事業を通じ、地学の国民的啓発に貢献)
閉会挨拶
3)祝賀会(16:30〜18:30)(16:00開場)
※祝賀会のみ要事前申込,会費制(事前申込は締切ましたが,多少人数に余裕がございます.参加ご希望の方は当日会場でお申し出下さい)
会場:北とぴあ16階 東武サロン 天覧の間
会費:5,000円
(注)会場スペースの都合がありますので,できるだけ早めにお申し込み下さい.
祝賀会申込方法:
1)メール・FAX・郵送(銀行振込)
参加者氏名,所属先,受領通知の返信先(住所or FAX番号orメールアドレス),を記入のうえ,下記までお申込下さい.あわせて会費を下記振込先へご送金下さい.折り返し,受領通知(兼当日用の受付票)をご返信します.
[申込先] 日本地質学会創立125周年記念祝賀会受付係
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル6F
E-mail:main[at]geosociety.jp FAX:03-5823-1156
[振込先]
三菱東京UFJ銀行 神田駅前支店 普通預金 0108667 シヤ)ニホンチシツガツカイ
みずほ銀行 神田駅前支店(普通)2229416 シヤ)ニホンチシツガツカイ
三井住友銀行 神田駅前支店(普通)1711424 シヤ)ニホンチシツガツカイ
ゆうちょ銀行 〇一九(ゼロイチキュウ)店 当座 0028067 シヤ)ニホンチシツガツカイ
郵便振替:00140-8-28067 一般社団法人日本地質学会
2)WEB申込フォーム(クレジット決済)
学会HPの専用申込フォームへ必要事項をご記入のうえ,お申し込み下さい.お支払い方法は,クレジット決済のみとなります.
▶申込画面はこちらから
記念出版:フォトコン写真集
記念出版:惑星地球フォトコンテスト 写真集
ただ今,準備中です
記念事業の概要と寄付のお願い
日本地質学会創立125周年記念事業の概要とそれを成功させるための寄付のお願い
日本地質学会創立125周年記念事業の概要と
それを成功させるための寄付のお願い
一般社団法人日本地質学会 会長 渡部芳夫
125周年記念事業実行委員会 委員長 矢島道子
125周年記念募金委員会 委員長 佃 栄吉
日本地質学会は,1893年に東京地質学会として創設されて以来,来年の2018年5月に創立125周年を迎えます.
当学会は,創立125周年を契機として,先端的研究の推進と成果の共有をさらに進め,ジオパークや地学オリンピックを発展させるとともに,全国民的地学教育の充実を目指します.
そして,それらの成果が相まって,自然災害や地圏の安全な利活用に対する市民の理解を高める事となり,それにより産業の持続的発展や新たなイノベーションを支えることができると信じているからです.
なお,125周年を迎えるにあたって,当学会がどのように活動してきて,今後取り組む必要があるアクションプランについては,こちらをご覧ください(2017年年頭挨拶のページへ).
創立125周年記念事業としては,以下のような行事を主に計画しています.
2018年5月東京で記念式典を開催します.
2018年9月北海道大学で記念学術大会,記念シンポジウムを開催します.
100周年以降の25年間における地質学および関連科学の発展について,地質学雑誌特集号としてレビューします.これは2017年3月号から隔月を原則として2018年末まで連載する予定です.
地質学が社会にいかに貢献しているかを国民にアピールする啓発図書を刊行します(2017年8月頃刊行予定).
125周年を契機として既に公表している各都道府県の岩石,鉱物,化石を「県の石図鑑-全国都道府県の岩石・鉱物・化石-」として出版します(2018年4月出版予定).
広報誌「ジオルジュ」の125周年記念英文特別号を発刊します(2018年予定).
125周年を記念して,これまで作成していなかった会員証を発行します(2017年末予定).
125周年を盛り上げるため,プレ年である2017年から記念ロゴと記念ポスターを活用します.
記念ロゴの選定については,こちらで紹介されていますので,ご覧ください.
記念ポスターは,2017年1月末に支部,賛助会員や関連諸団体に配布します.あわせて,印刷したポスターに加え,PDFデータをダウンロードしてご活用頂けます(ダウンロードはこちらから).記念ポスターには,支部や専門部会の行事案内を記載できるスペースを確保している図案がありますので,それを元図としてダウンロードし必要事項を記載すれば,行事案内ポスターとしても使えるようになっています.
記念ロゴと記念ポスターを使って,125周年のプレ年である2017年から大いに盛り上げましょう.
このような記念事業を実行するため,学会では一般会計から引当をするなど資金を工面してきました.しかしながら,それだけでは不足するため,学会員や賛助会員,さらには関連諸団体に寄付をお願いすることにしました.
なお,当学会は一般社団法人ですので,当学会への寄付は,所得税法および法人税の寄付金控除の対象とはなりません.
1.個人会員にお願いする寄付
一口5000円で,一口以上をお願いします.
寄付してくださった会員については,氏名と口数をニュース誌,HPに掲載します.
二口以上寄付してくださった会員には,地質学が社会にいかに貢献しているかを国民にアピールする記念図書(2017年8月頃刊行予定)を1冊差し上げます.
寄付は,2017年2月から2018年末まで受け付けますが,できるだけ2017年中のご寄付をお願いします.
寄付の申し込みについては,現金,銀行振込,郵便振替,クレジットカードで受け付けます.
[振込先]
● 三菱東京UFJ銀行 神田駅前支店 普通預金 0108667 シヤ)ニホンチシツガツカイ
● みずほ銀行 神田駅前支店(普通)2229416 シヤ)ニホンチシツガツカイ
● 三井住友銀行 神田駅前支店(普通)1711424 シヤ)ニホンチシツガツカイ
● ゆうちょ銀行 〇一九(ゼロイチキュウ)店 当座 0028067 シヤ)ニホンチシツガツカイ
● 郵便振替:00140-8-28067 一般社団法人日本地質学会
【お詫び】上記振込先情報に一部誤りがありました.大変申し訳ありませんでした(2017.2.28)
[クレジット決済専用]寄付申込画面 はこちら
※ご利用可能カード:VISA, Master, Diners
>>醵金者名簿(個人会員,賛助会員,企業・団体)はこちら
2.賛助会員や関連諸団体にお願いする寄付
一口5万円で,一口以上をお願いします.
寄付してくださった賛助会員や関連諸団体については,団体名と口数をニュース誌,HPに掲載します.あわせて,地質学が社会にいかに貢献しているかを国民にアピールする記念図書(2017年8月頃刊行予定)を1冊差し上げます.
寄付は,2017年2月から2018年末まで受け付けますが,できるだけ2017年中のご寄付をお願いします.
別途寄付依頼の文書を賛助会員や関連諸団体にお送りし,必要に応じて募金委員会メンバーがお伺いし,寄付のお願いをします.
以上ご説明しました125周年の記念事業を通じ,日本地質学会会員全ての力をお借りして,地質学は将来に向かって,さらに社会に貢献し続ける事を明確に伝えたいと考えます.会員の皆様もそれぞれのお立場で,共にこの2年間,特別な意識をもって活動してくださることを期待いたします.
>>醵金者名簿(個人会員,賛助会員,企業・団体)はこちら
記念ロゴ決定
記念ロゴ・記念ポスター
125周年記念ロゴ,ポスターを支部活動など会員の皆様にも大いにご活用いただき,創立125周年を学会内外に広めてください。
記念ロゴ_モノクロver
JPEG
記念ロゴ_カラーver
JPEG
記念ポスター
15.4MB
記念ポスター
15.4MB
※右下スペースに支部活動等の案内を記してご利用頂けます。
それぞれの画像をクリックすると画像データがダウンロードできます。
日本地質学会創立125周年記念ロゴについて
日本地質学会創立125周年記念ロゴについて
一般社団法人日本地質学会会長 渡部芳夫
125周年記念事業実行委員会委員長 矢島道子
125周年記念ロゴ選考委員会委員長 佐々木和彦
日本地質学会は,1893年に東京地質学会として創設されて以来,来年の2018年5月に創立125周年を迎えます.
本号に別途掲載してある「日本地質学会創立125周年を迎えるにあたって」に詳しく記載してあるように,当学会は,創立125周年を契機として,先端的研究の推進と成果の共有をさらに進め,ジオパークや地学オリンピックを発展させるとともに,全国民的地学教育の充実を目指します.
そして,それらの成果が相まって,自然災害や地圏の安全な利活用に対する市民の理解を高める事となり,それにより産業の持続的発展や新たなイノベーションを支えることができると信じています.
当学会では,125周年事業を盛り上げるために,記念ロゴを作成することにしました.このたび,応募作品をもとにデザイナーのリメイクを経て,記念ロゴが完成しましたので,皆様にご紹介します.
1. 会員からデザインの募集
ニュース誌4月号に,記念ロゴのデザイン募集案内の記事が掲載されました.2016年5月から2.5か月の募集期間を経て,7月中旬までに11名の会員から計17案のデザインが応募されました.
2. 会員によるWEB投票
7月末から8月末までの1か月間に,17案のデザインを学会HPに掲載して,会員によるWEB投票を行いました.
59名の会員が投票してくださり,1位5点,2位3点,3位1点というように得点化して評価しました.その結果,1位作品は126点,2位作品は71点,3位作品は67点と,1位作品が他の圧倒する高得点でした.
3. 記念ロゴ選考委員会による選考
9月上旬から中旬にかけて,7名の委員からなる選考委員会が,最優秀賞と優秀賞作品の選考にあたりました.結果は,1位作品は会員投票1位の作品で35点,2位作品は会員投票2位の作品で21点,3位作品は会員投票4位で9点,そして4位作品は会員投票3位で5点となりました.
1位と2位が抜きんでており,会員によるWEB投票結果を裏付けた結果でした.その結果,1位作品を最優秀賞として記念ロゴの元となるデザインに,2位作品を優秀賞とすることにしました.
最優秀賞受賞は千徳明日香会員(The University of Queensland),
最優秀賞 千徳さん喜びの声:この度は「日本地質学会125周年記念ロゴ」最優秀賞を頂き,誠にありがとうござ います.本作は調査用具のルーペを題材に描きました.ルーペのレンズ部分は,『地質学会の歴史』を地層として表現し,ケース部分の倍率が示されるところに は創立125周年記念の『×125』を描いています.また,ルーペを題材にすることにより,地質学の過去,現在,未来をつぶさに見つめ直すという意味合い を含みました.今後も地質学会の一員として,知見を地道に積み上げ,少しでも地質学研究の発展に貢献できるよう努力していきたいと思います.
優秀賞受賞は西田 梢会員(東京大学総合研究博物館※応募当時)です.
お二人にはそれぞれ副賞をお送りしました.受賞おめでとうございます.
また,受賞されたお二人以外に作品を応募してくださった方々,WEB投票していただいた会員の皆さんのご協力に深く感謝いたします.
4. 記念ロゴの完成
最優秀賞の作品をもとにデザイナーがリメイクした図案を,125周年記念実行委員会で約1.5か月かけて何度も修正意見がかわされました.そして,11月19日の執行理事会,12月3日の理事会の確認を経て,記念ロゴが完成しました.
記念ロゴには,カラー版と白黒版の2種類があります.
5. 記念ロゴの活用
125周年を盛り上げるため,プレ年である2017年から記念ロゴを学会誌発送の封筒やHPなどいろいろな媒体,機会に活用します.会員の皆様も記念ロゴを大いに使っていただき,創立125周年を学会内外に広めてください.ロゴマークのダウンロードはこちらから.
私たち日本地質学会員は,125周年の記念事業を通じて会員全ての力を結集させ,「地質学は将来に向かって,さらに社会に貢献し続ける」ことを明確に伝えたいと考えます.
会員の皆様もそれぞれのお立場で,共にこの2年間,特別な意識をもって活動してくださることを期待いたします.
以 上
醵金者名簿
日本地質学会創立125周年記念事業への醵金者(個人会員,賛助会員,企業・団体)
※2018年12月28日現在(敬称略・50音順)
現時点での醵金者は次のとおりです。創立125周年記念事業に対しご寄付を賜り、厚く御礼申し上げます。
今後とも何卒ご協力をよろしくお願いいたします。
■個人会員・・・寄付申込者も含む(1口5千円以上 計199名 586口)
名誉会員
(10口)
石原舜三 岡田博有 斎藤靖二 徳岡隆夫 山田直利
(6口)
大場忠道 唐木田芳文 波田重煕
(5口)
水谷伸治郎
(4口)
沖村雄二 蟹澤聰史 志岐常正 柴田 賢 鈴木堯士 鈴木博之
(2口)
秋山雅彦 猪郷久義 石崎國熙 石田志朗 糸魚川淳二 井上英二 植村 武 黒田吉益 佐藤 正 杉村 新 諏訪兼位 原 郁夫 藤田 崇 町田 洋 水野篤行 村田正文 吉田 尚
(1口)
加藤 誠 中澤圭二 星野通平
正会員
(20口)
石渡 明 白尾元理
(15口)
井龍康文
(10口)
金 光男 佃 栄吉 矢島道子 匿名による醵金者1名
(6口)
天野一男 安藤寿男 小尾 亮 平 朝彦 渡来めぐみ
(5口)
太田英将 佐々木和彦 山本高司
(4口)
大藤 茂 大友幸子 緒方信一 木村 学 小井土由光 嶋本利彦 田上洋人 田宮良一 棟上俊二 仲井 豊 藤本光一郎
(3口)
石橋 隆
(2口)
青野道夫 赤羽貞幸 浅野俊雄 足立勝治 阿部國廣 荒戸裕之 在田一則 有馬 眞 安間 莊 池田保夫 石井良治 石田 高 市川八州夫 伊藤 孝 伊藤谷生 伊藤 慎 井本伸広 岩部良子 岩森 光 上原康裕 植村和彦 後 誠介 内村公大 浦野隼臣 永広昌之 遠藤 毅 大平芳久 大和田正明 岡田 誠 小野 晃 小幡喜一 小原泰彦 笠原芳雄 加藤 潔 加藤芳郎 金澤直人 狩野彰宏 川端清司 KUEPPERS Andreas 木戸芳樹 木村公志 清川昌一 倉本真一 栗原俊己 栗本史雄 小嶋 智 小玉喜三郎 小林哲夫 小林弘幸 小宮 剛 斎藤 眞 齋藤文紀 榊原正幸 坂口有人 坂巻幸雄 嵯峨山 積 櫻井皆生 佐野晋一 澤口 隆 宍戸 章 菖蒲幸男 神保幸則 杉田律子 鈴木徳行 醍醐隆治 高木秀雄 高嶋礼詩 高橋直樹 高柳栄子 滝田良基 竹内圭史 竹内 誠 武田和久 田近 淳 田村芳彦 辻森 樹 堤 浩之 椿 和弘 利光誠一 鳥越祐司 内藤一樹 永岡靖雄 仲川隆夫 中里俊行 中澤 努 中野伸彦 仲谷英夫 奈良正和 新井田清信 西 弘嗣 二ノ宮 淳 楡井 久 橋本修一 長谷川敏喜 林 誠司 久田健一郎 平田大二 平野義明 廣木義久 福冨幹男 藤林紀枝 星 博幸 保柳康一 堀ノ内 央 本合弘樹 松田達生 松田博貴 松田義章 三浦 亮 水野清秀 満岡 孝 宮下純夫 宮田隆夫 向山 栄 森野善広 山口耕生 山崎俊嗣 山路 敦 山野井 徹 山本芳樹 柚原雅樹 吉田晶樹 米田茂夫 和田穣隆 渡部芳夫 匿名による醵金者3名
(1口)
荒木英夫 石井秀明 江藤哲人 北里 洋 君波和雄 阪口和則 芝川明義 田切美智雄 丹羽俊二
■賛助会員,企業・団体・・・寄付申込企業・団体も含む.計36団体
(1口5万円以上:35団体 52口,1口未満:1団体)
賛助会員
(2口)
応用地質株式会社 川崎地質株式会社 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 株式会社建設技術研究所 国際航業株式会社 国際石油開発帝石株式会社 石油資源開発株式会社 総合地質調査株式会社 株式会社ダイヤコンサルタント 中央開発株式会社
(1口)
興亜開発株式会社 JX石油開発株式会社 株式会社日さく 株式会社ニュージェック 株式会社パスコ
企業・団体
(3口)
大成建設株式会社
(2口)
株式会社愛智出版 清水建設株式会社 一般社団法人全国地質調査業協会連合会 株式会社阪神コンサルタンツ 山本司法書士事務所
(1口)
株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 株式会社安藤・間 株式会社九州地質コンサルタント 株式会社京都フィッショントラック 四国電力株式会社 島建コンサルタント株式会社 中電技術コンサルタント株式会社 西日本技術開発株式会社 日本原子力発電株式会社 株式会社蒜山地質年代学研究所 株式会社復建技術コンサルタント 北電総合設計株式会社 八洲開発株式会社 匿名による醵金企業 1社
(1口未満)
NPO法人日本地質汚染審査機構
会員証_ローマ字表記に関するお願い
会員氏名のローマ字表記について
[お願い]会員氏名のローマ字表記について
あらためてローマ字表記の登録を希望される方は,下記の手続きをお願いします.
学会では来年の学会創立125周年を記念して,会員証(プラスチック製,カードタイプ)を作成し,全会員に配布致します.これは,会員証としてだけでなく,学術大会など会合での名札としても活用できるように企画しています.
会員証に印字する会員氏名は,日本語とローマ字を併記します.ローマ字表記は,基本的には入会申込書に記載されたものを用いますが,あらためてご登録頂ければ,そちらを採用致します.ローマ字の表記方法には複数あるものもあります(下記例参照).あらためてローマ字表記の登録を希望される方は,下記の手続きをお願いします.
1)メール,FAXもしくは郵送で,下記の内容を学会事務局宛にお知らせ下さい.
会員氏名・所属(もしくは住所)・希望するローマ字表記
2)申込期限:2017年6月30日(金)
3)宛先は以下のとおりです.
メール:main[at]geosociety.jp([at]を@マークにして下さい)
FAX:03-5823-1156
郵送:〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F
(表記方法が複数ある例)
ち(CHI・TI),じ(JI・ZI),けんいち(Kenichi・Ken-ichi),
たろう(Taro・Tarou),おおた(OTA・OHTA・OOTA)など
特にご希望の無い場合(入会申込書に記載されたローマ字表記で良い方)は,
事務局への連絡は不要です.
(2017.5.16掲載)
記念事業:オリジナルクリアファイル
創立125周年記念事業:オリジナルクリアファイル
創立125周年記念事業:オリジナルクリアファイル
惑星地球フォトコンテストでは、毎年素晴らしい写真が入選しています。これらの写真を活用できないかと125周年記念事業実行委員会で検討した結果、学会オリジナルのクリアファイルを作成することになりました。クリアファイルの表裏に惑星地球フォトコンテストの入選写真や富士山などの国内で撮影された美しい写真を配しました。「日本の地質」を国内外に紹介するツールとしても活用できます。こんな綺麗なクリアファイルを使っていると、ご家族、知人、仕事関係者から必ず注目されること請け合いです。
A4対応 両面フルカラー/3種類1セット:定価 500円
(注)送料:1〜10部まで100円,3枚1セットでの販売となります.単品のご注文はお受けできません.
ご注文は学会事務局まで(main@geosociety.jp, 電話03-5823-1150)
写真の地質解説などは,ホームページ「地質フォト」からご覧いただけます。
http://www.geosociety.jp/faq/content0009.html
会員証(会員カード)発行
会員証(会員カード)発行
日本地質学会会員のみなさまへ
会員証(会員カード)発行
125周年記念事業をさまざまに実施、計画しておりますが、その一つとして「会員証」を発行し、全会員に配布いたします。カードの情報としては氏名の印字とバーコードによる会員番号のみですが、今後はカードの有効利用についても検討したいと考えています。まずは、学会の行事等に参加されるときには、ぜひ会員カードを携行されるようにお願いいたします。
会員カードは日本地質学会会員の証明としてお使い頂きますとともに、日本地質学会の会員として、それぞれの場で一層ご活躍頂きますことを祈念いたします。
2017.11.10掲載
125記念関東支部ジオ散歩
日本地質学会125周年記念 街中ジオ散歩「日比谷入江を歩く」徒歩見学会
日本地質学会125周年記念
街中ジオ散歩「日比谷入江を歩く」徒歩見学会
身近な地質とその地質に由来する地形について,それらを利用してきた先人から現在の私たちまでの営みを,専門研究者の案内で楽しく学ぼうという企画です.今回は,都心部においてかつて存在していた日比谷入江(日比谷公園付近を挟んで南北方向に分布していた細長い入江)をテーマに散策します.また、水準原点や石垣に残る几号(きごう)水準点を観察し,水準の歴史も学びます.
主催:一般社団法人日本地質学会関東支部
日時:2018年10月21日(日)9:45〜15:30 小雨決行(予定)
見学場所:東京都千代田区丸の内周辺
案内者:中山俊雄(東京都土木技術支援・人材育成センター)
会費:高校生以上・一般:1,000円,小・中学生:500円(保険代含む)
(注)参加費は,当日現金をご持参ください.昼食は各自ご用意下さい.
集合場所・時間:桜田門前 9:45集合(最寄駅:東京メトロ有楽町線桜田門駅)
見学コース(予定):①桜田門における几号(きごう)水準点→②台地上からの江戸城→③三宅坂水準原点→④日比谷図書文化館(剥ぎ取り試料ほか)→⑤日比谷公会堂の地盤沈下観察(几号水準点)→(昼食は日比谷公園内を予定しています)→⑥伊豆の安山岩の石垣→⑦稲田花崗岩のビル→⑧丸の内界隈における地盤沈下跡→⑨歴史資料室西側通り沿いの看板説明→⑩三菱1号館歴史資料室→⑪旧丸ビル基礎の松杭→東京駅丸の内口解散(15時半予定)
*雨天の場合はコースを変更する可能性があります.
募集人数:25名程度
対象:小学生以上.ただし,小・中学生の方は保護者の同伴でお申し込み下さい.また,地質学会会員の申込も可能ですが,本行事は一般向け普及行事のため,非会員の一般市民の参加を優先します.定員を超えた場合,会員は若干名とさせていただきます.
申込受付期間:2018年9月12(水)〜9月26日(水)
(申込者多数の場合は抽選を行います.結果は10月10日までに郵送で全員にお知らせします)
申込方法:WEB専用申込フォームまたは,FAXにてお申込み下さい.
【WEB専用申込フォーム】 こちらから
【FAXの場合】記入事項1〜6をすべて記入願います.メール等がない場合は“なし”とご記入下さい. 1.氏名,2.自宅住所(郵便物を受け取れる住所),3.携帯等電話番号,4.メールアドレス,5.生年月日,6.性別
(注1)小・中学生の申込の際は, 1, 5, 6 について保護者の情報も明記して下さい.また,学生の方は学年のご記入をお願いします.
(注2)家族,友人など,グループでの参加希望の場合は,それぞれ申込の際に備考欄に代表者名を記入してください.グループでの応募は,本人を含め最大4名までとします.
申込・問い合わせ先:一般社団法人日本地質学会関東支部(担当 細矢)
電話:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156
メール:kanto[at]geosociety.jp
記念事業「ジオルジュ」記念英文特別号
記念事業「ジオルジュ」記念英文特別号
英文特別号冊子PDFをダウンロードしていただけます。(38.5MB)
125周年を記念して,海外の方々に読んでいただくために,これまでのジオルジュの掲載記事の中から,いくつか記事をピックアップ・翻訳し,英語版特別号を作成しました。
Contents *( )内に概要を付します。
Yufu River Gorge (表紙:大分県由布峡谷の写真)
The illusion of volcanoes (口絵:桜島の写真と説明)
The Mt. Fuji, Solitary Mountain (富士山の概況+歴史)
Was the extinct Desmostylus a good swimmer? (デスモスチルス)
A message to You, Hundreds of Years in the Future(大阪などの地震被害を伝承する試み)
Art Created by Nature : The World of Fault Rocks(断層岩)
The "Tagoto Moon"(信濃国・姨捨山の棚田に映る月)
International Earth Science Olympiad in Mie, Japan (地学オリンピックの紹介)
The Geological Society of Japan (裏表紙・由布渓谷の説明と地質学会の説明)
学術交流協定を締結している学会や,図書交換先など,海外の関連諸団体には寄贈いたしましたが,個々の研究者の方々にもできるだけ広くお読み頂きたいと思います.そこで,これから海外の学会,国際会議等に参加される会員の方は,ぜひこの英文特別号をお持ち頂き,海外の方々への配布にご協力下さい.必要部数をお知らせ頂ければ,冊子をお送りいたします.ぜひご協力をお願い致します.お申込は学会事務局まで(電話:03-5823-1150,メール:main[at]geosociety.jp)
→ 作成部数をほぼ配布いたしました.ご協力頂きありがとうございました。(2018年12月)
2016年東京・桜上水大会
2016東京・桜上水TOP
画像をクリックすると JPEGファイル(6MB)がダウがンロードできます
日本地質学会第123年学術大会
(東京・桜上水大会)
盛会のうち、無事終了いたしました。
来年は愛媛(松山)でお会いしましょう。
「出番ですぜ!江戸前地質学:ジオハザード都市地質学」
(開催挨拶)(2017年松山大会)
2016年 9月10日(土)〜 12日(月)
会場:日本大学文理学部キャンパス(世田谷区桜上水)
共催:日本大学文理学部
次回:第124年学術大会(2017愛媛大会)
日程:2017年9月16日(土)〜18日(月)
会場:愛媛大学理学部ほか(松山市文京)
講演に関するご連絡 NEW
その他のご連絡 NEW
・発表者への注意
・講演取消,変更,訂正
・R6, ORポスター発表について
・申込後の変更・取消について
・会場での注意点
・手荷物・無線LAN
・CPD参加証明書について
★ 更新情報 ★
2016/09/08
学術大会の情報をプレスリリースしました
2016/09/05
確認書を発送しました(9/2(金)) 重要
2016/08/19
講演のキャンセル,発表者の変更は必ず事前にご連絡ください 重要
2016/08/18
参加登録のシステムの不具合と復旧について:2 復旧しました
2016/08/17
事前参加登録の締切延長:8/19(金)午前10時
2016/08/17
参加登録のシステムの不具合と復旧について
2016/08/10
サイエンスカフェの申込受付開始しました
2016/08/09
巡検実施の可否について(一部コースは中止となります) 重要
2016/07/29
講演プログラム(セッション毎・PDF版)の情報を公開しました
2016/07/26
緊急展示の申込を受付けます
2016/07/26
小さなESのつどい参加校が決まりました
2016/07/19
全体日程表を公開しました
2016/07/19
巡検各コースの申込状況(随時更新中)
2016/07/12
若手会員のための地質関連企業研究サポート(9/11):出展企業募集
2016/06/29
演題登録・講演申込の申込は締切ました
2016/06/15
宿泊予約について
2016/06/15
普及・関連行事の専用申込サイトがオープンしました
2016/06/15
事前参加登録の受付を開始しました
2016/05/30
講演申込の受付を開始します(5/30,0時オープン)
2016/05/27
優秀ポスター賞のエントリー方法について
2016/05/25
講演申込を予定しているが、まだ入会手続きをされていない方へ
2016/05/25
シンポジウム・セッション決定
シンポジウム一覧
シンポジウム
講演申込・講演要旨投稿はこちらから
申込は締切ました
演題登録,要旨投稿 6月29日(水)18時締切(Web)
*郵送の場合は6月23日(木)必着
★注意★講演申込を予定しているが,まだ入会手続きをされていない方へ
(2016/5/30掲載)
*各タイトルをクリックすると、詳細をご覧いただけます
シンポジウム
S1.みんなで考えよう,都市ハザードから放射性廃棄物問題まで−科学技術と社会科学の融合−(企業編)10日(土),(研究編)11日(日)(一般公開シンポジウム)
S2.Geological and paleogeographical evolution of the Ryukyu Islands in the late Cenzoic(国際シンポジウム)
今大会では2件のシンポジウムを開催します.シンポジウム発表は招待講演のみです.いずれの発表も通常のセッション同様,締切までに演題登録・要旨投稿を行って下さい.発表時間は世話人が決定します.シンポジウム発表にはセッション発表における1人1件の制約が及びませんので,シンポジウムで発表する会員は別途セッションにも発表を申し込めます.また非会員招待講演者に限り参加登録費を免除します(講演要旨集は付きません).講演要旨はセッション発表と同じ様式・分量です.詳しくは、こちらをご参照ください。
*印は代表世話人(連絡責任者)です.
S1.一般公開シンポジウム:みんなで考えよう,都市ハザードから放射性廃棄物問題まで−科学技術と社会科学の融合−(企業編)10日(土),(研究編)11日(日)*発表の一般公募なし
Thinking Together Issues from Urban Hazards to Radioactive Waste: An Integration of Scientific Technology and Social Sciences
世話人:竹内真司(日本大)
Conveners: Shinji Takeuchi (Nihon Univ.)
近年話題になっている東日本大震災などの自然災害に関する防災や減災への対策,東京電力福島第一原子力発電所事故の影響,放射性廃棄物の地中処分問題などについて,
自然科学と社会科学の知の融合をテーマに科学技術と社会科学それぞれの観点から話題提供をいただき,今後のあるべき姿について議論することを目的とする.シンポジウムは,初日に民間企業による関連技術に関する話題提供を,二日目に大学・研究機関関連の研究成果等に関する話題提供を予定している.
【講演予定者(機関)】
(企業編)応用地質(株),大林組,(株)ダイヤコンサルタント,mcm Japan,ほか
(研究編)平田 直(東大),木村克己(産総研),中森広道(日本大),佐藤 浩(日本大),藤原 治(産総研),竹内真司(日本大),吉田英一(名古屋大),小松崎俊作(東京大)
S2. 国際シンポジウム:Geological and paleogeographical evolution of the Ryukyu Islands in the late Cenzoic *発表の一般公募なし
後期新生代における琉球列島の地質および古地理発達史
世話人:井龍康文*(東北大),太田英利(兵庫県立大学/人博),荒井晃作(産総研)
Conveners: Yasufumi Iryu(Tohoku Univ.),HidetoshiOta(Univ. Hyogo/Mus. Nature and Human Activities),Kohsaku Arai(GSJ, AIST)
The Ryukyu Islands(Ryukyus)are situated to the southwest of mainland Japan and encompasses several tens of islands and islets, extending from Tane-ga-shima in the northeast to Yonaguni-jima in the southwest. Most islands in the Central and Southern Ryukyus are rimed by modern coral reefs and are covered with the Quaternary carbonates deposited in reefs and associated shallow lagoons and island shelves. The current terrestrial fauna and flora in the Ryukyus are characterized by a high frequency of endemic taxa. Based mainly on geological data including those for the Pleistocene fossils, some hypotheses were once presented for the paleogeographic changes, which supposedly caused coral reef‘turn-on’and gave rise to the current characteristic phylogeographical patterns in various terrestrial organismal lineages in the Ryukyus. However, recent molecular phylogenetic and evolutionary studies have yielded data that are obviously incongruent with those previous hypothetical scenarios. This symposium aims to integrate the latest geological and biogeographic data in the Ryukyus and create a new hypothesis for tectonic evolution of the islands.
【講演予定者】Shu-Kun Hsu(National Central University, Taiwan),Don Sunwoo(Korean Institute of Geoscience and Mineral Resources, Korea),Hidetoshi Ota(Univ. Hyogo/Mus. Nature and Human Activities),Mamoru Toda(Univ. Ryukyus),Koh Nakamura(Hokkaido Univ.)
↑このページのTOPに戻る
セッション一覧
講演申込・講演要旨投稿はこちらから
申込は締切ました
演題登録,要旨投稿 6月29日(水)18時締切(Web)
*郵送の場合は6月23日(木)必着
★注意★講演申込を予定しているが,まだ入会手続きをされていない方へ
セッション一覧
※ セッションの招待講演者については,こちらをご覧下さい.
下記をクリックすると、各セッションの詳細がご覧頂けます。
トピックセッション(9件)
T1.活断層破砕帯の掘削
T2.日本海沿岸での津波堆積物
T3.グリーンタフ・ルネサンス
T4.表層型メタンハイドレート
T5.都市地盤の地質学
T6.日本列島構造発達史再考
T7.文化地質学
T8.極々表層堆積学
T9.付加体遠洋性堆積岩の研究
レギュラーセッション(24件)
R1.深成岩・火山岩
R2.岩石・鉱物・鉱床学一般
R3.噴火・火山発達史と噴出物
R4.変成岩とテクトニクス
R5.地域地質・地域層序・年代層序
R6.ジオパーク
R7.海洋地質
R8.堆積物(岩)の起源・組織・組成
R9.炭酸塩岩
R10.堆積過程・堆積環境:堆積地質
R11.石油・石炭地質と有機地球化学
R12.岩石・鉱物の変形と反応
R13.沈み込み帯・陸上付加体
R14.テクトニクス
R15.古生物
R16.ジュラ系+
R17.情報地質とその利活用
R18.環境地質
R19.応用地質・ノンテク構造
R20.地学教育・地学史
R21.第四紀地質
R22.地球史
R23.原子力と地質科学
R24.鉱物資源と地球物質循環
アウトリーチセッション
OR.アウトリーチセッション
*印は代表世話人(連絡責任者)です
トピックセッション:9件
T1.活断層破砕帯の掘削と断層年代測定による断層活動性の評価/Trenching and drilling into active fault damage zone and assessment of fault activity by dating
林 愛明*(京都大;slin@kugi.kyoto-u.ac.jp)・田上高広(京都大) ・堤 昭人(京都大)・宮脇昌弘(原子力規制庁)
Lin Aiming,Tagami Takahiro,Tsutsumi Akihito(Kyoto Univ),Miyawaki Masahiro(Secretariat of Nuclear Regulation Authority)
断層破砕帯は,断層活動により地殻浅部の脆性領域で形成されるもので,主に断層ガウジと角礫やカタクレーサイトなどから構成される.最近,断層破砕帯は,原子力発電所の敷地の安全性評価と構造物のサイト選定や断層活動性の判断などに関連して社会的に緊急な研究課題になっており,国内・国外で注目されている.本セッションは,断層の最新活動性評価に関わる諸問題に対して,変動地形学・構造地質学・年代学・地球物理学・地盤工学を含む固体地球科学諸分野におけるトレンチとボーリング掘削を含む活断層破砕帯の調査・実験・シミュレーション等多様な観点からの知見を統合して理解を深めることを目標とする.異なる分野の専門家が集まり,変動地形と断層破砕帯の物質を用いた年代測定や破砕帯の性状に基づいた断層活動性の評価手法に関する適用条件・断層摩擦特性と断層破砕帯の年代のリセット温度・応力・地下流体との関係などの課題についての議論を深めることを目指す.本セッションでは,最近行われてきた活断層・地震断層破砕帯のトレンチとボーリング掘削,フィールド観察,断層物質の年代測定,断層摩擦すべり実験,活断層周辺域の応力解析,断層破砕帯物性の解析など,様々な分野にわたる研究発表を歓迎する.
【招待講演予定者】なし
T2.日本海沿岸での津波堆積物研究の展開/Recent approach of the tsunami deposit researches in the Japan Sea area
卜部厚志*(新潟大災害・復興科学研究所;urabe@gs.niigata-u.ac.jp)・高清水康博(新潟大)
Atsushi URABE(NHDR, Niigata Univ), Yasuhiro TAKASHIMIZU(Faculty of Education, Niigata Univ.)
2011年の東北地方太平洋沖地震による津波災害以降,日本海側においても津波リスクの見直しが急務とされ,波源となる断層の想定や沿岸各県による津波浸水想定が行われてきた.一方,各地域の津波履歴については,歴史記録が少ないことから江戸時代後半以前の津波被害については明確ではないことから,津波堆積物によるイベントの認定と復元が行われ,各地域における津波の履歴が明らかにされつつある.そこで,本セッションでは,主に2011年以降に行われた各地域の津波(イベント)堆積物に関する層相の特徴,認定方法,履歴,地域間の対比,波源の推定など検討を総括し,特に礫質なイベント堆積物の認定,履歴を復元できる古地形の推定と年代感をはじめとした共通する課題の整理を行うとともに,現時点での履歴のとりまとめや波源を復元していくための課題などについても整理を行い,今後の展開方法を議論し共有したい.
【招待講演予定者】平川一臣(北海道大:非会員),佐藤比呂志(東京大・地震研:会員)
T3.グリーンタフ・ルネサンス/Green Tuff renaissance
天野一男*(日本大;ikap@cap.ocn.ne.jp)・ 細井 淳(産総研)
Kazuo Amano(Nihon Univ.),Jun Hosoi(GSJ/AIST)
日本列島の新生代テクトニクスは,1990年代初頭に古い概念を脱却しプレートテクトニクス理論に基づいて再構築された.しかし,年代論などの新たなデータの蓄積にともない,陳腐化していることは否めない.日本列島新生代テクトニクスの新しいモデルが提唱されてからすでに20年以上が経過しているが,今こそ全面的な見直しを行い,研究のあらたな局面にむかって突破口を開く時期である. グリーンタフは新生代テクトニクス解明のための鍵となる素材であるが,長年にわたって,その攻略法が不明で研究が停滞していた.近年,火山砕屑岩類の堆積相解析に基づいたグリーンタフ分布地での古火山体の復元などが行われるようになり,新たな研究の展開が期待される.また,日本海の拡大に伴った島弧の回転についても新たなデータが出始めている. 本セッションはグリーンタフを中心として,層序学・構造地質学・岩石学・古地磁気学等,広い視野から検討し,新生代の日本列島テクトニクス研究と島弧進化過程の研究にブレークスルーを図ることを目指している.本セッションは2008年より4回にわたって開催し,若者達に野外地質学の重要性と面白さをアピールしてきた.地域地質学的な話題からグローバルな話題まで,分野を限らずに歓迎する.
【招待講演予定者】松原典孝(兵庫県立大,会員),高嶋礼詩(東北大,会員)
▲ページtopに戻る
T4.表層型メタンハイドレートの地質と資源ポテンシャル/Geology and resource potential of shallow gas hydrates
松本 良*(明治大;ryo_mat@meiji.ac.jp)・角和善隆(明治大)・棚橋 学(明治大)・戸丸 仁(千葉大)・森田澄人(産総研)
Ryo Matsumoto,Yoshitaka Kakuwa,Manabu Tanahashi(Gas Hydrate Laboratory Meiji Univ.),Hitoshi Tomaru(Chiba Univ.), Sumito Morita(AIST)
提案者らの継続的学術調査により,西太平洋の縁海域,オホーツク海,日本海,南シナ海には,海底下の比較的浅所にガスチムニーを作って集積する表層型メタンハイドレートが広く分布する事が分かって来た.我が国では20年近くにわたり南海トラフの砂層型メタンハイドレートが資源化の対象として調査されているが,これとは別に,2013年度からの3年間,国のプロジェクトとして,表層型メタンハイドレートの資源把握調査が集中的に行なわれ,明治大学ガスハイドレート研究所がこの調査を中心的に担って来た.高分解能3D地震探査,深部掘削とLWD,保圧コアリング,オスモサンプラーによる深海底での長期連続採水,深海メタンセンサーによる3次元的濃度プロファイルの解明など3年間の集中的かつ革新的調査により,表層型メタンハイドレートの起源と集積過程を理解する上で必須となるデータを多数得ることができた.一方,南シナ海,熊野灘でも表層型と似た産状のハイドレートが報告されている(招待講演).本セッションでは,これら複数のデータセットを基礎として,地学,生物,物質科学,資源科学,環境科学など多様な関心とアプローチを統合し,メタンハイドレート研究の次の10年を展望したい.
【招待講演予定者】Saulwood Lin(台湾国立大,非会員),井尻 暁(JAMSTEC,会員)
T5. 都市地盤の地質学/Geological research on urban ground
中澤 努*(産総研;t-nakazawa@aist.go.jp)・小松原純子(産総研)・北田奈緒子(地域地盤環境研究所)・松浦一樹(株式会社ダイヤコンサルタント)
Tsutomu Nakazawa,Junko Komatsubara(GSJ, AIST),Naoko Kitada(Geo-Research Institute),Kazuki Matsuura(Dia Consultants Co. Ltd.)
都市地盤は従来工学分野で扱われることが多かったが,近年では都市地盤を地層の形成プロセスから考察し,物理特性や地盤災害,地質環境と関連づける研究が多くみられるようになってきた.都市地盤を構成する地層の層序学的・堆積学的研究は都市地盤を理解する上で重要な第一歩である.また近年の3次元モデリング技術の発展に伴い,得られた地質学的情報から地下を3次元で可視化することも試みられるようになってきた.このような都市地盤に関する地質学の成果は,地盤工学,地震工学,水文学など,関連分野に活かし,発展させていくことが重要である.そのためには地質の調査・研究成果をだれしもが利用できる地質地盤情報として適切に整備・蓄積していくことも必要である.首都東京での大会開催を機に,都市地盤の層序学・堆積学,またそれらを活用した応用研究,さらには地質地盤情報整備の取り組みなど,都市地盤について地質学を軸に多方面から捉えるトピックセッション「都市地盤の地質学」を開催する.
【招待講演予定者】先名重樹(防災科研,非会員),栗本史雄(産総研,会員)
T6.日本列島の構造発達史再考/Geotectonic evolution of the Japanese Islands: revisited
磯崎行雄*(東京大;isozaki@ea.c.u-tokyo.ac.jp)・青木一勝(岡山理科大)
Yukio Isozaki(Univ. Tokyo), Kazumasa Aoki(Okayama Univ. Sci.)
最近5年間に日本列島に産する多様な造山帯砂岩について,砕屑性ジルコンのU-Pb年代測定という新たな手法が導入され,構造浸食による既存の地質体の消滅という従来のテクトニクス解釈とは大きく異なる解釈が提案されている.これによると,約5億年前まで遡る日本列島の地殻形成史前半の解明については,極めて限定された地質学的証拠の探索が不可欠となる.しかし改めて新しい観点で本邦産の古期岩類の検討から,興味深い新発見がもたらされている.一方で,比較的若い過去の造山帯産物がよく残存している白亜紀以降の弧-海溝系テクトニクスについても,やはり砕屑性ジルコン年代学の成果が,既存の解釈に様々な変更を要求している.例えば,火山フロントを中心とする若い花崗岩バソリスの成長史を通して,前弧盆地,弧内盆地そして背弧盆地の分化過程などを,より詳細に提示することが可能となった.また新生代におきた背弧域の拡大(日本海の形成)についても,あらたな視点の導入が不可欠となっている.これらの多様なテーマを内包する本セッションでは,日本列島形成史の最新の描像を探る.
【招待講演予定者】堤 之恭(国立科学博,会員),坂田周平(学習院大,会員)
T7. 文化地質学/Cultural geology
鈴木寿志*(大谷大;hsuzuki@res.otani.ac.jp)・一田昌宏(豊橋市自然博)・長 秋雄(産総研)・田口公則(神奈川県博)・加藤碵一(産総研)
Hisashi Suzuki, Masahiro Ichida, Akio Cho, Kiminori Taguchi, Hirokazu Kato
今年は宮沢賢治生誕120周年を迎える.宮沢賢治は地質学に造詣が深く,文学作品には岩石や鉱物に関わる記述がふんだんにみられる.地質が人とどのように関わっているかを考える文化地質学では,文学作品も重要な研究対象になる.この度のトピックセッション文化地質学では,宮沢賢治研究の文学者と18世紀ドイツ文学の研究者を招待し,地質と文学に関わる研究に焦点をあてる.人々が岩石や鉱物をどのように捉えているか,考える端緒となろう.文学作品にみられる地質学的記述について詳しい方は,ぜひこの機会にご講演いただきたい.
一方で,これまで2回にわたるトピックセッション文化地質学では,(1)地質を素材や石材資源として活用した事例研究,(2)京都,日本,メソポタミアの文化・文明を地質学的に説明した研究,(3)神社や寺院,遍路などでの宗教と地質の関わりを論じた研究,(4)博物館・ジオパークなどにおける普及教育実践に関わる研究,が発表されてきた.文学だけでなく,これまでの例のような地質と人々との関わりについて論じたあらゆる研究発表を歓迎したい.
【招待講演予定者】鈴木健司(文教大,非会員),廣川智貴(大谷大,非会員)
T8. 極々表層堆積学:「堆積物」への記録プロセスの理解/Superficial sedimentology: Deciphering record processes into sediments
新井和乃*(JAMSTEC;k_arai@jamstec.go.jp)・成瀬 元(京都大)・小栗一将(JAMSTEC)・清家弘治 (東京大)・川村喜一郎(山口大)
Kazuno Arai(JAMSTEC),Hajime Naruse(Kyoto Univ), Kazumasa Oguri(JAMSTEC), Koji Seike(Unive.of Tokyo),Kiichiro Kawamura(Yamaguchi Univ)
堆積物には様々な記録が保存される.地震,津波,流向,水温,気温など,どれも過去の地球の営みを理解するための重要な情報ばかりである.しかしながら,それらの「堆積物」への記録プロセス,すなわち,海底極表層での物理化学的プロセスはよくわかっていない.比喩表現ではあるが,一連の記録システムがテープレコーダーだとしたら,堆積物という名のテープに録音された音楽を鑑賞するためには,音が録音されるヘッド部での機構を知る必要があるだろう.本セッションでは,海底極表層部で生じている多岐にわたる物理化学的現象を議論したい.堆積学,と称してはいるが,地質学,地球物理学,地球化学,生物学など,学際的なセッションにしたい.
【招待講演予定者】菅沼悠介(国立極地研,会員),野田 篤(産総研, 会員)
T9. 付加体地質中に残る遠洋性堆積岩の研究:進展と展望/Study on pelagic sedimentary rocks in the accretionary complex:Progress and prospects
尾上哲治*(熊本大;onoue@sci.kumamoto-u.ac.jp)・高橋 聡(東京大)
Tetsuji Onoue(Kumamoto Univ),Satoshi Takahashi(The University of Tokyo)
日本の付加体中に含まれる中古生代の遠洋性堆積岩(主に層状チャートからなる)は,陸源砕屑物の到達しないパンサラサ海遠洋域で堆積した長期間の記録を持つ.これらの堆積岩類は,1970年代後半に始まった微化石研究の進展いわゆる“放散虫革命”により詳しい年代決定が可能になり,さらに1990年代からは主要・微量元素や同位体分析による多元素の情報を得ることで,高い時間解像度で古海洋環境の復元が可能になっている.過去の地球システムの全体像を理解するためには,大陸縁辺部で堆積した地層の情報だけではなくパンサラサ海遠洋域に関する情報が必要不可欠であり,日本の遠洋性深海堆積岩から復元された古環境情報が注目を集めている.また,近年では,美濃帯などの付加体は古い海洋プレート上の堆積物が沈み込んでいるという点で日本海溝の陸上アナログになると考えられてきており,付加体の形成過程や内部の流体移動・物質循環を理解する上でも重要な研究対象と認識されてきている.本セッションでは,現在様々な手法を用いて研究が進められている付加体中の遠洋性堆積岩についての発表を広く募集し,同堆積岩研究の国内における情報発信の場としたい.
【招待講演予定者】山口飛鳥(東京大,会員),佐藤友彦(東京工大,会員)
▲ページtopに戻る
レギュラーセッション:24件
( )内は責任母体となる専門部会または委員会です.
R1.深成岩・火山岩とマグマプロセス(火山部会・岩石部会)
Plutonic rocks, volcanic rocks and magmatic processes
草野有紀*(産総研;y.kusano@aist.go.jp),鈴木和恵(東京大),上澤真平(電中研)
Yuki Kusano* (AIST), Kazue Suzuki (Univ. Tokyo), Shimpei Uesawa (CRIEPI)
深成岩および火山岩を対象に,マグマプロセスにアプローチした研究発表を広く募集する.発生から定置・固結に至るまでのマグマの物理・化学的挙動や,テクトニクスとの相互作用について,野外地質学・岩石学・鉱物学・火山学・地球化学・年代学など様々な視点からの活発な議論を期待する.
R2.岩石・鉱物・鉱床学一般(岩石部会)
Petrology, mineralogy and economic geology
湯口貴史*(山形大;takashi_yuguchi@sci.kj.yamagata-u.ac.jp),坂田周平 (学習院大),五十公野裕也(山形大)
Takashi Yuguchi* (Yamagata Univ.), Shuhei Sakata (Gakushuin Univ.) , Yuya Izumino (Yamagata Univ.)
岩石学,鉱物学,鉱床学,地球化学などの分野をはじめとして,地球・惑星物質科学全般にわたる岩石及び鉱物に関する研究発表を広く募集する.地球構成物質についての多様な研究成果の発表の場となることを期待する.
R3.噴火・火山発達史と噴出物(火山部会)
Eruption, evolution and products of volcanic processes
上澤真平*(電中研;uesawa@criepi.denken.or.jp),長井雅史(防災科研)
Shimpei Uesawa* (CRIEPI), Masashi Nagai (NIED)
火山地質ならびに火山現象のモデル化に関し,マグマや熱水流体の上昇過程,噴火様式,噴火経緯,噴出物の移動・運搬・堆積,各火山あるいは火山地域の発達史,火山活動とテクトニクス・化学組成をはじめとする,幅広い視点からの議論を期待する.
▲ページtopに戻る
R4.変成岩とテクトニクス(岩石部会)
Metamorphic rocks and tectonics
吉田健太*(JAMSTEC;yoshida_ken@jamstec.go.jp),小林記之(名古屋学院大),足立達朗(九州大)
Kenta Yoshida* (JAMSTEC) , Tomoyuki Kobayashi (Nagoya Gakuin Univ.), Tatsuro Adachi (Kyusyu Univ.)
国内および世界各地の変成岩を主な対象に,記載的事項から実験的・理論的考察を含め,またマイクロスケールから大規模テクトニクスまで,様々な地球科学的手法・規模の視点に立った斬新な話題提供と活発な議論を期待する.
R5.地域地質・地域層序・年代層序(地域地質部会・層序部会)
Regional geology and stratigraphy, chronostratigraphy
松原典孝* (兵庫県立大;matsubara-n@stork.u-hyogo.ac.jp),内野隆之(産総研),納谷友規(産総研)
Noritaka Matsubara* (Univ. Hyogo),Takayuki Uchino (AIST),Tomonori Naya (AIST)
国内外を問わず,地域の地質や層序,および年代層序に関連した発表を広く募集する.地質図,年代,化学,分析,リモセン,活構造,地質調査法等の様々な内容の発表を歓迎し、地域を軸にした討論を期待する.
R6.ジオパーク(地域地質部会・ジオパーク支援委員会:一般公開)
Geopark
天野一男*(日本大:ikap@cap.ocn.ne.jp),高木秀雄(早稲田大)
Kazuo Amano* (Nihon Univ.),Hideo Takagi (Waseda Univ.)
昨年11月に世界ジオパークは正式にユネスコの活動として認められ,ユネスコ世界ジオパークとなった.日本のジオパーク活動も8年が経過して,日本ジオパークとして認定された地域は39地域となり,その内の8地域は世界ジオパークに認定されており,これから新たに申請を考えている地域も多い.このような状況下で,一層ジオパークの質の向上が求められている.ジオパークは,貴重な地質・地形を中心とした各種自然・文化遺産の価値を地元の人が良く理解し保全しながら、地域の教育や経済的振興をめざす事業である.自然遺産の保全,ジオパークで行われるジオツアーのインタープリター,ガイドの育成に当たって,地域の大学,博物館,研究所の研究者の協力は不可欠である.この観点から,地質学会として,問題点を整理し,ジオパークの質的向上への貢献に寄与したい.様々な実践例の発表,課題解決方法の提案など広く講演を募集する.
【招待講演予定者】渡辺真人(産総研:会員)
▲ページtopに戻る
R7.海洋地質(海洋地質部会)
Marine geology
芦 寿一郎*(東大大気海洋研:ashi@aori.u-tokyo.ac.jp),小原泰彦(海上保安庁),板木拓也(産総研)
Juichiro Ashi* (AORI, Univ. of Tokyo),Yasuhiko Ohara (JCG),Takuya Itaki (AIST)
海洋地質に関連する分野(海域の地質・テクトニクス・変動地形学・海域資源・堆積学・海洋学・古環境学・陸域地質での海洋環境変遷研究など)の研究発表を募集する.調査速報・海底地形地質・画像データなどのポスター発表も歓迎する.
【招待講演予定者】兵藤 守(JAMSTEC:非会員)・池原 研(産総研:会員)
R8.堆積物(岩)の起源・組織・組成(堆積地質部会)[共催:日本堆積学会,石油技術協会探鉱技術委員会,日本有機地球化学会]
Origin, texture and composition of sediments
太田 亨*(早稲田大:tohta@toki.waseda.jp),野田 篤(産総研)
Tohru Ohta* (Waseda Univ.),Atsushi Noda (AIST)
砕屑物の生成(風化・侵食・運搬)から堆積岩の形成(堆積・沈降・埋積・続成)まで,組織(粒子径・形態)・組成(粒子・重鉱物・化学・同位体・年代)・物性などの堆積物(岩)の物理的・化学的・力学的性質を対象とし,その起源・形成過程・後背地・古環境や地質体の発達史を議論する.太古代の堆積岩から現世堆積物まで,珪質岩・火山砕屑岩・風成塵・リン酸塩岩・蒸発岩・有機物・硫化物などについての研究も歓迎する.
【招待講演予定者】笹尾英嗣(JAEA:会員),安江健一(JAEA:会員)
R9.炭酸塩岩の起源と地球環境(堆積地質部会)[共催:日本堆積学会,石油技術協会探鉱技術委員会,日本有機地球化学会]
Origin of carbonate rocks and related global environments
山田 努*(東北大:t-yamada@m.tohoku.ac.jp),足立奈津子(鳴門教育大)
Tsutomu Yamada* (Tohoku Univ.),Natsuko Adachi (Naruto Univ. Educ.)
炭酸塩岩・炭酸塩堆積物の堆積作用,組織,構造,層序,岩相,生物相,地球化学,続成作用,ドロマイト化作用など,炭酸塩に関わる広範な研究発表を募集する.また,現世炭酸塩の堆積作用・発達様式,地球化学,生物・生態学的な視点からの研究発表も歓迎する.
【招待講演予定者】松田博貴(熊本大:会員)
▲ページtopに戻る
R10.堆積過程・堆積環境・堆積地質(堆積地質部会・現行地質過程部会)[共催:日本堆積学会,石油技術協会探鉱技術委員会,日本有機地球化学会]
Sedimentary geology, processes and environments
西田尚央*(東京学芸大;nishidan@u-gakugei.ac.jp),酒井哲弥(島根大),高野 修(石油資源開発)
Naohisa Nishida* (Tokyo Gakugei Univ.),Tetsuya Sakai (Shimane Univ.),Osamu Takano (JAPEX)
野外観察や室内実験によって堆積粒子の挙動や堆積物形成過程について検討した研究や,堆積物が形成される場としての環境(砂丘を含む風成環境,湖沼,河川,沿岸,陸棚,深海など)の特徴について,堆積学的手法や各種分析・測定によって検討した研究を広く募集する.また,露頭観察や得られた試資料に基づく堆積システムあるいは地層形成のダイナミクスに関する研究も歓迎する.
【招待講演予定者】片岡香子(新潟大災害・復興科学研:会員)
R11.石油・石炭地質学と有機地球化学(石油石炭関係・堆積地質部会)[共催:石油技術協会探鉱技術委員会,日本有機地球化学会,日本堆積学会]
Geology and geochemistry of petroleum and coal
金子信行*(産総研:nobu-kaneko@aist.go.jp),千代延仁子(石油資源開発),三瓶良和(島根大)
Nobuyuki Kaneko* (AIST),Satoko Chiyonobu (JAPEX),Yoshikazu Sampei (Shimane Univ.)
国内外の石油・石炭地質および有機地球化学に関する講演を集め,石油・天然ガス・石炭鉱床の成因・産状・探査手法など,特にトラップ構造,堆積盆,堆積環境,貯留岩,根源岩,石油システム,資源量,炭化度などについて討論する.
【招待講演予定者】小鷹 長(合同石油(株):会員),三田 勲(日本天然ガス(株):会員)
R12.岩石・鉱物の変形と反応(構造地質部会・岩石部会)
Deformation and reactions of rocks and minerals
大坪 誠*(産総研:otsubo-m@aist.go.jp),高橋美紀(産総研),廣瀬丈洋(JAMSTEC),水上知行(金沢大)
Makoto Otsubo* (AIST),Miki Takahashi (AIST),Takehiro Hirose (JAMSTEC),Tomoyuki Mizukami (Kanazawa Univ.)
岩石・鉱物の変形(破壊,摩擦,流動現象)と反応(物質移動,相変化)およびその相互作用を,観察・分析・実験を通じて物理・化学的な側面から包括的に理解し,地球表層から内部における地質現象の解明を目指す.地質学,岩石学,鉱物学,地球化学など様々な視点・アプローチによる成果をもとに議論する.
【招待講演予定者】野田博之(京都大防災研:会員),中島淳一(東京工業大:非会員)
▲ページtopに戻る
R13.沈み込み帯・陸上付加体(構造地質部会・海洋地質部会)
Subduction zones and on-land accretionary complexes
氏家恒太郎*(筑波大:kujiie@geol.tsukuba.ac.jp),橋本善孝(高知大),坂口有人(山口大),中村恭之(JAMSTEC)
Kotaro Ujiie(Tsukuba Univ.), Yoshitaka Hashimoto(Kochi Univ.), Arito Sakaguchi(Yamaguchi Univ.), Yasuyuki Nakamura(JAMSTEC)
沈み込み帯・陸上付加体に関するあらゆる分野からの研究を歓迎する.野外調査,微細構造観察,分析,実験,理論,モデリングのみならず海洋における反射法地震探査,地球物理観測,地球化学分析,微生物活動など多様なアプローチに基づいた活発な議論を展開したい.次世代の沈み込み帯・陸上付加体研究者を育てるべく,学生による研究発表も大いに歓迎する.
【招待講演予定者】日野亮太(東北大学:非会員),森 康(北九州自然史博:会員)
R14.テクトニクス(構造地質部会)
Tectonics
武藤 潤*(東北大:muto@m.tohoku.ac.jp),安江健一(JAEA),針金由美子(産総研)
Jun Muto* (Tohoku Univ.),Ken-ichi Yasue (JAEA),Yumiko Harigane (AIST)
陸上から海洋における野外調査や各種観測の他,実験や理論などに基づき,日本や世界各地に発達するあらゆる地質体の構造,成因,形成過程や発達史に関する講演を募集する.また,現在進行している地殻変形や活構造に関する研究成果も歓迎する.
【招待講演予定者】谷 健一郎(国立科博:非会員)
R15.古生物(古生物部会)
Paleontology
生形貴男(京都大),太田泰弘(北九州自然博),上松佐知子*(筑波大;agematsu@geol.tsukuba.ac.jp)
Takao Ubukata (Kyoto Univ.),Yasuhiro Ota (Kitakyushu Museum),Sachiko Agematsu* (Univ. of Tsukuba)
主として古生物を扱った,または,プロキシとして古生物を利用したものや古生物を用いた新手法などの研究の発表・討論を行う.
▲ページtopに戻る
R16.ジュラ系+(古生物部会)
The Jurassic +
松岡 篤*(新潟大:amatsuoka@geo.sc.niigata-u.ac.jp),近藤康生(高知大),小松俊文(熊本大),石田直人(鳥取大),中田健太郎(いわき市アンモナイトセンター)
Atsushi Matsuoka* (Niigata Univ.),Yasuo Kondo (Kochi Univ.),Toshifumi Komatsu (Kumamoto Univ.),Naoto Ishida (Tottori Univ.),Kentaro Nakada(Ammonite Center, Iwaki City)
2003年の静岡大会において「ジュラ系」として誕生した本セッションは,隣接する地質系統の研究者の要望を取り込んで「ジュラ系+」として発展し,10年間にわたりトピックセッションとして継続開催されてきた.この間,ジュラ系の研究を中心に,関連する講演がまとまって発表される場として定着し,ジュラ系研究の情報を研究者の間で共有することに貢献してきた.10年の活動は,2015年に地質学雑誌の特集『トピックセッション「ジュラ系+」の10年』として結実した(2015年2月号「(その1)日本のジュラ系」,3月号「(その2)ジュラ系研究の将来展望」).「ジュラ系+」は,2013年からは古生物部会のセッションとなっている.本セッションでは,ジュラ系およびその上下の地質系統の研究について,各方面からのデータを持ち寄り,多角的に検討する場を提供する.このことは,日本からの国際発信力を強化することにも寄与する.なお,2018年には,第10回国際ジュラ系会議がメキシコで開催される.
【招待講演予定者】長谷川 卓(金沢大:会員)
R17.情報地質とその利活用(情報地質部会・地域地質部会)
Geoinformatics and its application
野々垣 進*(産総研:s-nonogaki@aist.go.jp),斎藤 眞(産総研)
Susumu Nonogaki* (AIST),Makoto Saito (AIST)
地質情報の取得・デジタル化・データベース構築をはじめとして,デジタル管理した地質情報の数理解析・統計解析・画像処理・地理空間情報との統合利用,地質プロセスや地質構造の認識を基礎にした地殻の3次元表現である3次元地質モデルの構築・可視化,ボーリングデータの管理・分析,SNSを含むWebを通した地質情報の発信・共有など,地質情報の情報処理に関する全ての研究成果(理論・技術・システム開発・実践事例・応用事例など)の発表を歓迎する.また,これらの成果から得られた地質情報の利活用事例,利活用における問題点,比較検討・動向調査などの研究発表も歓迎する.
R18.環境地質(環境地質部会)
Environmental geology
難波謙二(福島大),風岡 修(千葉環境研),三田村宗樹(大阪市大),田村嘉之*(千葉県環境財団;tamura@ckz.jp)
Kenji Nanba (Fukushima Univ.),Osamu Kazaoka (Res. Inst. Environ. Geol., Chiba),Muneki Mitamura (Osaka City Univ.),Yoshiyuki Tamura* (Chiba Pref. Environ. Foundation)
地質汚染、医療地質,地盤沈下,湧水,水資源,湖沼・河川,都市環境問題,法地質学,環境教育,地震動,液状化・流動化,地震災害,岩盤崩落など,環境地質に関係する全ての研究の発表・討論を行う.
▲ページtopに戻る
R19.応用地質学一般およびノンテクトニック構造(応用地質部会)
Engineering geology and non-tectonic structures
西山賢一(徳島大),亀高正男*((株)ダイヤコンサルタント),須藤 宏(応用地質(株))
Ken-ichi Nishiyama (Tokushima Univ.),Masao Kametaka* (Dia Consultants),Hiroshi Sudo (OYO Corp.)
応用地質学一般では,種々の地質ハザードの実態,調査,解析,災害予測,ハザードマップの事例・構築方法,土木構造物の設計・施工・維持管理に関する調査,解析など,応用地質学的視点に立った幅広い研究を対象とする.また,ノンテクトニック構造では,ランドスライドや地震による一過性の構造,重力性の構造等の記載,テクトニック構造との区別や比較・応用等の研究を対象にして発表・議論する.
【招待講演予定者】向山 栄(国際航業(株):会員)
R20.地学教育・地学史(地学教育委員会)
Geoscience Education/History of Geoscience
矢島道子*(東京医科歯科大:pxi02070@nifty.ne.jp),三次徳二(大分大)
Michiko Yajima* (Tokyo Medical and Dental Univ.),Tokuji Mitsugi (Oita Univ.)
地学教育,地学史に関わる研究発表を広く募集する.新学習指導要領についての教育現場からの問題提起や,実践報告に加え,大学や博物館,研究所等が行うアウトリーチに関わる実践報告についても歓迎する.また地学史からの問題提起,貴重な史的財産の開示を歓迎する.
R21.第四紀地質(第四紀地質部会)
Quaternary geology
公文富士夫*(信州大:shkumon@shinshu-u.ac.jp),竹下欣宏(信州大)
Fujio Kumon* (Shinshu Univ.),Yoshihiro Takeshita (Shinshu Univ.)
第四紀地質に関する全ての分野(環境変動・気候変動・湖沼堆積物・地域層序など)からの発表を含む.また,新しい調査や研究,方法の開発や調査速報なども歓迎する.
▲ページtopに戻る
R22.地球史(環境変動史部会)
History of the Earth
黒田潤一郎*(JAMSTEC;kurodaj@jamstec.go.jp),小宮 剛(東京大),尾上哲治(熊本大),須藤 斎(名古屋大),清川昌一(九州大),山口耕生(東邦大)
Junichiro Kuroda* (JAMSTEC),Tsuyoshi Komiya (Univ. Tokyo),Onoe Tetsuji (Kumamoto Univ.), Itsuki Suto (Nagoya Univ.),Shoichi Kiyokawa (Kyushu Univ.),Kosei Yamaguchi (Toho Univ.)
地球史を通して,大気や海洋,それに生命圏は様々な時間スケールで大きな変化を遂げてきた.それは,火山活動などの地球内部の活動や,太陽活動や公転軌道要素,隕石衝突など地球外要因によっても駆動されている.地球史における大気・海洋・生命圏の変動は,地層や化石に記録される.これらの変動を,多岐にわたる科学的手法により紐解くことは,地質学の大きな醍醐味の一つといえよう.本セッションは,特定の時代や特定の科学的手法にとらわれず,地球史上に残される環境変動や地殻変動の謎に迫る研究を広く募集し,インタラクティブな議論を展開する場にしたい.
【招待講演予定者】大河内直彦(JAMSTEC:会員)
R23.原子力と地質科学(地質環境の長期安定性研究委員会)[共催:日本原子力学会バックエンド部会]
Nuclear energy and geological sciences
吉田英一*(名古屋大:dora@num.nagoya-u.ac.jp),梅田浩司(弘前大),高橋正樹(日本大),渡部芳夫(産総研)
Hidekazu Yoshida* (Nagoya Univ.),Koji Umeda (Hirosaki Univ.),Masaki Takahashi (Nihon Univ.),Yoshio Watanabe (AIST)
原子力は,ウラン資源探査,活断層等を考慮した耐震安全性評価,廃棄物の地層処分,放射性物質の環境動態等の多くの地質科学的課題を有している.本セッション「原子力と地質科学(Nuclear Energy and Geological Sciences)」は,このような日本の原子力に関わる地質科学的課題について,地球科学的知見の議論及び関連する学会や研究者間の意見交換を行うことを目的としており,幅広い分野からの参加,発表を歓迎する.
【招待講演予定者】丸井敦尚(産総研:非会員),須貝俊彦(東京大:非会員)
R24.鉱物資源と地球物質循環(鉱物資源部会)
Mineral resources and global material cycles
加藤泰浩*(東京大:ykato@sys.t.u-tokyo.ac.jp),岩森 光(JAMSTEC),中村謙太郎(東京大)
Yasuhiro Kato* (Univ. Tokyo),Hikaru Iwamori (JAMSTEC),Kentaro Nakamura (Univ. Tokyo)
近年,海底鉱物資源をはじめとする新しい資源の開発に向けた動きが活発化し,鉱物資源への注目が高まっている.鉱物資源の形成過程に関わる様々な元素の輸送・濃集過程は,ダイナミックな地球における物質循環と分化の一部に他ならず,鉱物資源の成因を考える上では,地球全体にまたがるグローバルな物質循環とその変遷,そしてその資源形成との関わりについての包括的な理解が不可欠である.本セッションでは,鉱物資源そのものに加え,これまで着目されることが少なかった資源形成をとりまく地球表層-内部環境,テクトニックセッティング,ダイナミクスと,資源の形成メカニズムとの関わりについても,グローバルに議論する場を提供したい.
【招待講演予定者】安川和孝(東京大:会員)
▲ページtopに戻る
アウトリーチセッション
OR. 日本地質学会アウトリーチセッション(一般公開,ポスター発表のみ)
Outreach session
星 博幸*(愛知教育大:hoshi@auecc.aichi-edu.ac.jp),須藤 斎(名古屋大)
Hiroyuki Hoshi* (Aichi Univ. Education) , Itsuki Suto (Nagoya Univ.)
研究成果を社会に発信する場として設けられたセッション.地質学と関連分野を対象とし,開催地(関東地方,東京)とその周辺の地質や地学にかんする研究紹介,社会的に注目されている地質および関連トピックの研究紹介,特定分野の研究到達点や課題の解説など.客層は会員(専門家)ではなく市民であることに注意.申込多数の場合は行事委員会にて採否を検討する.
▲ページtopに戻る
講演情報TOP
講演関連
講演申込・講演要旨投稿はこちらから
申込は締切ました
演題登録,要旨投稿 6月29日(水)18時締切(Web)
*郵送の場合は6月23日(木)必着
★注意★講演申込を予定しているが,まだ入会手続きをされていない方へ
シンポジウム,セッションとも演題登録・要旨投稿は申込システムにアクセスし,入力フォームに従ってお申込下さい.発表セッションや会場・発表日時等は行事委員会が決定し,7月下旬以降に通知します.やむを得ず郵送で申し込む場合は,学会事務局までお問い合わせ下さい.発表申込書等必要な書式をお送りします.提出書類,要旨原稿をご準備の上,6月23日(木)必着で学会事務局までお送り下さい.講演申込をされる方は,別途事前に大会参加登録も行って下さい.なお,今大会より,優秀ポスター賞は講演申し込み時にエントリーを希望されたポスター発表に対して審査をするエントリー制になりました.エントリーを希望される発表者は,講演申込時にポスター賞エントリー希望を選択してください.
▶シンポジウム
▶▶シンポジウム一覧および申込
▶セッション発表の募集
▶▶セッション一覧
▶▶セッション招待講演者の紹介
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
▶講演要旨について(シンポ・セッション共通)
▶▶講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理,引用方法,校閲について
▶▶講演要旨の作成の注意点とPDFファイル作成の作り方
▶▶講演要旨オンライン投稿手順チェックシート
▶▶保証・同意書(2016東京・桜上水)
▶▶キャンセルした講演の講演要旨の扱いについて
▶発表要領(シンポ・セッション共通)
セッション発表の募集
セッション発表の募集(募集要領)
申込は締切ました
演題登録,要旨投稿 6月29日(水)18時締切(Web)
*郵送の場合は6月23日(木)必着
■シンポジウム一覧はこちら■
■セッション一覧はこちら■
注:シンポジウムに関しては、シンポジウムのページを参照して下さい。
(1)セッションについて
今大会では9件のトピックセッションと24件のレギュラーセッション,およびアウトリーチセッションを用意します.各セッションの詳細については上記「シンポジウム・セッション一覧」をご覧下さい.
(2)発表に関する条件・制約
1)会員は全34セッションのうち1つまたは複数(下記)に発表を申し込めます.発表申込者=発表者とします.非会員は発表を申し込めません.発表を希望する非会員は6月23日(木)までに入会手続きをして下さい(入会申込書が届くまで発表申込を受理しません).共催団体の会員は共催セッションへの発表申込が可能です.
2)口頭発表あるいはポスター発表を1人1題申し込めます.ただし,発表負担金(1,500円)を支払うことでもう1題(最大2題)の申し込みが可能です.発表可能な組み合わせは下記を参照して下さい.
セッションA:口頭2件
×(申込不可)
セッションA:ポスター2件
×(申込不可)
セッションA:口頭,ポスター各1件ずつ
○(申込可)
セッションA:口頭1件,セッションB:口頭1件
○(申込可)
セッションA:ポスター1件,セッションB:ポスター1件
○(申込可)
※発表可能な形式の組み合わせは,招待講演も同様です
※これらの制約はアウトリーチセッションには適用しません(後述)
3)共同発表(複数著者による発表)の場合は,上記「1人1題,ただし発表負担金支払いによりもう1題可」の制約を発表者(=発表申込者)に対して適用します.その際,発表者は筆頭でなくても構いません(筆頭者に会員・非会員等の条件はありません).講演要旨では,発表者氏名を下線(アンダーライン)表示にして下さい.
(3)アウトリーチセッション
このセッションは,会員による研究成果の社会への発信(アウトリーチ)を学会として力強くサポートするために,トピック・レギュラーと並ぶ第三のカテゴリーとして設けられているものです.市民に対するアウトリーチ活動に関心のある会員はぜひお申し込み下さい.
1)トピック・レギュラーと同様の演題登録・要旨投稿が必要です.要旨校閲(後述)もトピック・レギュラーと同様に行います.要旨は講演要旨集に収録され,正式な学会発表扱いになります.
2)本セッションの発表には,上記の発表数に関するルール(1人1題,ただし発表負担金を支払えばもう1題可)を適用しません.例えば,レギュラーセッションで1題発表する会員がアウトリーチセッションでも発表する場合,発表負担金はかかりません.ただし,同一発表者(=発表申込者)が本セッションで発表できるのは1題のみとします.
3)ポスター発表のみとし,2日間にわたって掲示します.10日(土)の一般公開シンポジウム(企業編)会場(コアタイムでの立ち会いを必須としない)と11日(日)の市民講演会・一般公開シンポジウム(研究編)会場(市民講演会の前1時間,後30分をポスターコアタイム)で実施する予定です.
4)市民には講演要旨のコピーを配布しますが,これとは別に資料を独自に配布していただいても構いません(ただし発表者負担).
5)スペース等の都合から,募集件数は10件程度とします.募集件数を上回る応募があった場合は行事委員会が採否を検討します.
6)講演申し込み時に優秀ポスター賞のエントリーを希望すれば優秀ポスター賞の選考対象になります.
(4)招待講演
「セッション招待講演の紹介」をご覧下さい.招待講演も期日までに一般発表と同様に演題登録・要旨投稿が必要です.非会員招待講演者の場合は世話人が代理でオンライン入力することも可能です.非会員招待講演者に限り参加登録費を免除します(講演要旨集は付きません).また,招待講演は発表負担金の枠外として扱います.
(5)セッション発表申込の際の注意点
1)発表方法は「口頭」「ポスター」「どちらでもよい」のいずれかを選択して下さい(アウトリーチセッションはポスターのみ).締切後の変更はできません.会場の都合のため,発表方法(口頭・ポスター)の変更をお願いすることがあります.
2)発表題目と発表者氏名は,登録フォームと講演要旨の両方を一致させて下さい.
3)発表希望セッションを必ず第2希望まで選んで下さい.
4)関係する一連の発表があるときは,必要に応じて発表順希望等をコメント欄に入力して下さい(ご希望に沿えない場合があります).
5)R6ジオパークおよびアウトリーチセッションは,一般公開のためポスターの掲示場所が通常の発表と異なります.また,アウトリーチセッションのみ掲示が2日間にわたりますのでご注意下さい(9/10,9/11を予定).ただし,コアタイムでの立ち会いは9/11のみ必須となります.
セッション招待講演者の紹介
セッション招待講演の紹介
世話人や専門部会から提案され,行事委員会が承認した招待講演者(予定)の概要を紹介します.学術的にも社会的にも注目されている研究者やテーマが目白押しです.会員の皆様,この機会をお見逃しなく! なお,講演時間は変更になる場合があります.
(行事委員会)
T2.日本海沿岸での津波堆積物
T3.グリーンタフ・ルネサンス
T4. 表層型メタンハイドレート
T5. 都市地盤の地質学
T6. 日本列島構造発達史再考
T7. 文化地質学
T8. 極々表層堆積学
T9. 付加体遠洋性堆積岩
R6.ジオパーク
R7.海洋地質
R8.堆積物(岩)の起源・組織・組成
R9.炭酸塩岩の起源と地球環境
R10.堆積過程・堆積環境・堆積地質
R11.石油・石炭地質学と有機地球化学
R12.岩石・鉱物の変形と反応
R13.沈み込み帯・陸上付加体
R14.テクトニクス
R16.ジュラ系+
R19.応用地質・ノンテク
R22.地球史
R23.原子力と地質科学
R24.鉱物資源・地球物質循環
T2.日本海沿岸での津波堆積物研究の展開
■平川一臣(北海道大:非会員)30分
平川氏は,これまでも北海道や東北地域などの各地において,さまざまな層相の津波を起源と推定されるイベント堆積物を検出してきた先駆的な研究者である.日本海側についても,2011年以降地形学の視点から津波堆積物を挟在する古地形の抽出から先駆的にイベント堆積物の検討を行っており,全体像を総括する上で有益なアイデアを提案できる.
■佐藤比呂志(東京大・地震研:会員)30分
佐藤会員は,文科省の「ひずみ集中帯PJ」や「日本海地震津波調査PJ」などにおいて,日本海側の陸域・海域の構造探査を行ってきた第一人者である.特に,日本海側での津波に関しては,国土交通省での委員会や文科省のプロジェクト検収において,津波の波源となる海底活断層の構造探査を行い,各波源断層に関するモデルの構築を行っている.本セッションは津波堆積物をテーマとしているが,津波堆積物を研究する上で,もともとの津波波源に関する最新のモデルをしることは,研究の前提となる.また,日本海での最新の構造探査の成果や波源モデルは,本学会会員にとっても関心が非常に高いテーマであると考えられ,招待講演として有益なものとなることが高く期待される.
▲ページTOPに戻る
T3.グリーンタフ・ルネサンス
■松原典孝(兵庫県立大:会員)30分
松原会員は,野外における堆積相解析を主な手法として,グリーンタフ地域において古海底火山の詳細な復元を行っている若手の研究者である.中でも南部フォッサマグナの丹沢山地については,島弧−島弧衝突テクトニクスの立場でユニークな研究を展開してきた.南部フォッサマグナのテクトニクスについて,従来の研究のレビューと今後の展望について野外地質学の観点から話題提供できる招待講演者として適任である.
■高嶋礼詩(東北大:会員)30分
高島会員は,近年アパタイト微量元素組成を用いて凝灰岩の高精度の対比にチ ャレンジしている.グリーンタフ中の凝灰岩中の火山ガラスは熱水変質を被っており,従来の手法では対比は困難であった.しかし,この手法によればグリーンタフの正確な対比が可能になり,グリーンタフ研究に新たな局面の展開が可能となる.新手法の紹介と今後の可能性について話題提供できる招待講演者として適任である.
T4. 表層型メタンハイドレートの地質と資源ポテンシャル
■ Saulwood Lin(国立台湾大学:非会員)30分
Lin (台湾国立大学海洋研究所 准教授)氏は,地球化学を専門とするが,10年以上前から,台湾南西沖の南シナ海北端付近に無数に発達する泥火山および関連するメタン湧出に注目,ROV, 掘削調査,地震探査など様々な手法でこの奇妙な地形地質の研究を続け,最近,この海域より塊状のメタンハイドレートの回収に成功した.これらの産状は,日本海の表層型メタンハイドレートと酷似しており,その成因,起源を理解する上で,南シナ海での確認は重要である.
■井尻 暁(JAMSTEC:会員)30分
地球化学,地球微生物学を基礎として,海洋と堆積物の化学過程の研究を推進している研究者で,熱水活動にも冷湧水活動にも多くの経験があり,最近は,南海トラフの泥火山に伴うハイドレート,インド洋のハイドレート調査にも参加しており,提案するセッションの重要な寄与になり,招待講演をお願いしたい.
▲ページTOPに戻る
T5. 都市地盤の地質学
■先名重樹(防災科研:非会員)15分
「首都圏の地下構造モデルと強震動予測」:先名氏は地震本部および防災関連のSIP課題で首都圏の地下構造モデル構築とそれに基づく強震動予測研究を推進する地震工学の専門家である.先名氏には本トピックセッションで,SIPで実施している首都圏地盤に関する総括的な取り組みを紹介していただくとともに,地震工学分野から地質の研究者・技術者への期待についても述べて頂く.
■栗本史雄(産総研:会員)15分
「地質・地盤情報の法整備に向けた取り組み」:栗本会員は,日本学術会議の地質地盤情報共有化に向けた提言をとりまとめたメンバーのひとりであり,「地質地盤情報の活用と法整備を考える会」の代表世話人である.この取り組みは地質学会も賛同し協力しているもので,学会員にも広く知ってもらいたいことから,関連の深い都市地盤セッションにおいて紹介して頂く.
T6. 日本列島の構造発達史再考
■ 堤 之恭(国立科学博:会員)15分
■ 坂田周平(学習院大:会員)15分
両氏は,LA-ICPMSを用いたジルコンの粒子個別年代測定を日本の地質学に定着させ,多くの研究者との共同研究を通して,次々と新しい知見を解明している.それは,1980年代におきた微化石年代決定による付加体研究ブーム以来の,大きなブレークスルーを導いている.本セッションで扱う内容はまさにこれらの成果である.この機会に,最先端の測定技術の向上の様子,ならびにそれがもたらした最新の成果を,両氏に紹介して頂く.
▲ページTOPに戻る
T7. 文化地質学
■鈴木健司(文教大:非会員)30分
鈴木氏は,宮沢賢治文学作品の屹立過程を宗教や化学・地学的観点から理論構築しようとしている文学者である.文系研究者としては珍しく,賢治が見てきた岩石・鉱物を自分でも採集し,宮沢文学を読み解こうとする異色の文学者である.地質と文学の関係を理解する上で,地質学者とは異なった視点での岩石・鉱物の捉え方に気づかされるだろう.
■廣川智貴(大谷大:非会員)30分
廣川氏は,近世ドイツ文学にみられるテキストが,宗教や自然科学的知見の進展に伴い変化することに着目して,地道に研究を続けているドイツ文学者である.近年は18〜19世紀のドイツにおける地質学の発達が,ドイツ文学に与えた影響を考察しており,当時のドイツ人が地質をどのように捉えていたかを知る機会となろう.
T8. 極々表層堆積学:「堆積物」への記録プロセスの理解
■菅沼悠介(国立極地研:会員)30分
菅沼会員は,古地磁気学,年代層序学を専門としており,特に,表層における古地磁気獲得プロセスに関して詳しい.菅沼会員は,海底堆積物における堆積残留磁化の獲得メカニズムの解明の研究から,2014年度に,日本地質学会小澤儀明賞を受賞している.本セッションでは,学際的な意図があり,表層での古地磁気学の議論が不可欠である.上記の理由から,菅沼会員を招待講演者として推薦する.
■野田 篤(産総研:会員)15分
野田会員は,堆積学,堆積地質学,海洋地質学を専門としており,特に,源流域から海溝底までの地球表層に堆積した堆積物(岩)を対象にし,それらに記録されている過去の地球表層でのできごとを明らかにしている.また,砕屑物からみる地球表層プロセスを解明することにも従事しており,地質学会での続成作用に関するセッションの世話人もしている.このように,野田会員は表層プロセス全般に知識があり,表層地質を広く議論する際に重要な人物である.
▲ページTOPに戻る
T9. 付加体地質中に残る遠洋性堆積岩の研究:進展と展望
■山口飛鳥(東京大:会員)15分
山口会員は,構造地質を扱う第一線で活躍する若手研究者である.山口会員の研究は,プレート沈み込み帯とその周辺で起こるテクトニックな現象を,海洋掘削や陸域地質調査で得た試料を化学的・物性的な側面から分析するものである.中でも,本セッションに関連する付加体中の堆積岩の変形構造や変形中に形成された流体の痕跡を扱った研究は,過去のプレート運動の記録を読み取り現在進行型のテクトニクスを理解するアナログとして意義深い成果を挙げている.
■佐藤友彦(東京工大:会員)15分
佐藤会員は,地球環境史を地質学・古生物学・地球化学を応用して高い成果を挙げてきた若手研究者である.多様な時代の研究を展開する佐藤会員の研究において,深海チャートのなかに含まれる鉄の化学状態を,メスバウアー分光法を用いて分析し,赤色や灰色など多様な色調を呈する層状チャートの経験した堆積時,続成時の酸化還元環境を解読する研究は,本セッションに重要な知見を与える.
R6.ジオパーク
■渡辺真人(産総研:会員)30分
渡辺会員は日本のジオパーク推進に初期から関わっており,世界ジオパークネットワークの活動にも深く関わっている.昨年11月のジオパークのユネスコ正式プログラム化とInternational Geoscience and Geopark Programmeの発足を受けて,ジオパークの現状と今後,学会が果たすべき役割などについて基調講演を依頼したい.
R7.海洋地質(海洋地質部会)
■兵藤 守(JAMSTEC:非会員)30分
兵藤氏は南海トラフの地震発生現象を計算機シミュレーションにより再現する研究を行っており,この分野で最近最も成果をあげている研究者と言える.海洋地質セッションではタービダイトを用いた地震履歴研究の発表も多く,地震・津波発生の数値モデル計算がどのように行われているかを知る機会を持ちたく招待したい.
■池原 研(産総研:会員)30分
池原会員は堆積学,古環境学を中心に海洋地質学の広い分野の研究を行っており,特に地震性タービダイトの研究では優れた成果を多数あげている.地震性タービダイトは地震履歴復元において強力なツールとして挙げられるが,一方で適用できる条件について十分な検討が必要である.海洋古地震研究の国内外の最近の動向と問題点,今後の地震性タービダイト研究の課題について講演していただきたく招待したい.
▲ページTOPに戻る
R8.堆積物(岩)の起源・組織・組成
■笹尾英嗣(JAEA:会員)30分
笹尾会員は,ウラン鉱床の形成プロセスを中心に研究を実施されており,その過程で堆積岩中のウラン鉱床形成プロセスを続成作用と関連付けた検討を行っている.当セッションの重要課題の一つである続成作用についてウラン鉱床の形成を例にご講演頂き,堆積物は堆積後にどう変化するのかを考えるきっかけとしたい.
■安江健一(JAEA:会員)15分
安江会員は,地震地質学の専門家であり,活断層の履歴解明,断層運動に伴う山地隆起や段丘形成などの研究を中心に行なってこられた.最近では,数十万年スケールでの山地形成過程や堆積物供給源の変化を把握する目的で,石英粒子のESR信号等を利用した後背地解析技術の研究開発を進めている.今回は,その手法の持つ利点や適用の可能性についてご講演を頂く.
R9.炭酸塩岩の起源と地球環境
■松田博貴(熊本大:会員)30分
松田会員は炭酸塩堆積学および続成過程に関する研究に一貫して取り組んでおり,この分野をリードする一人である.炭酸塩堆積物や生物骨格の地球化学的情報を用いた古環境解析が盛んに試みられているが,そうした研究の中には,堆積・続成過程が充分に考慮されていないものも散見される.炭酸塩の堆積・続成過程に関する幅広い知見を紹介いただき,炭酸塩研究のさらなる発展のために礎を改めて考える機会としたい.
R10.堆積過程・堆積環境・堆積地質
■片岡香子(新潟大災害・復興科学研:会員)30分
片岡会員は,火山砕屑物を対象として堆積学的視点から地層・現行過程双方の研究に取り組んでおり,この分野をリードする第一人者である.特に,日本各地の火山とその周辺において,火山噴火が関わる突発的で大規模な火山泥流(ラハール)の定性・定量的復元や,河川堆積作用への影響および堆積環境変遷の解明を目的とし,フィールド調査を基礎として卓越した成果を挙げてきた.近年では,御嶽火山2014年噴火後に発生した火山泥流と積雪・融雪期における火山土砂輸送も対象として調査研究を推進している.このような研究は,火山大国日本における防災・減災の基礎として社会的な貢献も期待される.このため,近年の研究動向のレビューも交えて最新の知見を紹介いただき,堆積学的視点に基づく火山砕屑物研究の意義や役割について理解を深める機会としたい
▲ページTOPに戻る
R11.石油・石炭地質学と有機地球化学
■小鷹 長(合同石油(株):会員)30分
小鷹会員は現在,石油技術協会会長,合同石油開発(株)社長の要職に就いている.同会員は石油開発会社に就職以来,石油探鉱技術者として国内,海外の一線で活躍をされて来られ,特に地震探鉱が適用できない難地域においてストロンチウム同位体層序や流体包有物分析などの新技術を駆使して,解釈を進めて来られた.パプアニューギニアでの天然ガス発見から28年を経て,2014年5月に液化天然ガスの出荷が開始されたが,初期の探鉱段階からガス田の開発に従事してこられた同会員に,プロジェクトの概要と地質評価,そして石油探鉱・開発の魅力について講演した頂くとともに,石油鉱業界からの地質学への要望も期待したい.
■三田 勲(日本天然ガス(株):会員)30分
三田会員は石灰質ナンノ化石の専門家であり,房総地域の新第三系の層序に関する数多くの論文の共著者である.今回は関東(東京)開催ということで,国内最大の水溶性ガス田である南関東ガス田の資源と地質について講演して頂く.南関東ガス田ではメタンガスの採取とともに,鹹水からヨウ素を生産し,その量は全世界の生産量の約1/3を占める.また,茂原地域では生産開始後にガス水比が急増する世界的にも珍しい産出挙動が知られている.三田会員らは,ガス田地下に分布するタービダイト砂岩の三次元的な分布を,坑井の検層データや微化石分析により明らかにしてきた.本講演では,ヨウ素濃度やガス水比とタービダイト砂岩貯留層との関係などについて講演をお願いする.三田会員は現在,日本天然ガス(株)の社長である.
R12.岩石・鉱物の変形と反応
■野田博之(京都大防災研:会員)30分
野田会員は,断層岩調査や変形実験で得られる成果を地震発生のモデルに組み込み,断層で起きる様々な現象についてより現実的なシナリオの模索を続けておられる.講演では,モデリングを通して地震現象を解明する上で,地質学を専門とする人がどのような点で貢献できるかについて実例をもとにお話しをしていただく.
■中島淳一(東京工業大:非会員)30分
中島氏は,沈み込み帯の地震・火山テクトニクスの理解をめざし,地震波不均質構造と地殻流体や島弧マグマ活動の関わりを軸に広い視野のもとご研究を続けておられる.本レギュラーセッションで議論する様々な成果は中島氏の研究のように沈み込み帯の包括的な理解を目指す研究へと強く連携されるべきところである.活発な議論が期待できる.
▲ページTOPに戻る
R13.沈み込み帯・陸上付加体
■日野亮太(東北大学:非会員)30分
日野氏らのグループは,日本海溝沈み込み帯を対象に地震・測地観測と数値計算を組み合わせた研究を行い,2011年東北地方太平洋沖地震後の地殻・マントルを含む粘弾性緩和や周期的なスロースリップと大地震発生の関連性解明など,特筆すべき顕著な成果をあげられている.本講演を通じて,地質学を専門とする人に沈み込み帯における最新の地球物理研究成果を提供するとともに活発な議論を展開したい.
■森 康(北九州自然史博:会員)30分
森会員は,長崎変成岩を対象に地質学的研究を精力的に進め,スラブ–マントル境界で形成された蛇紋岩メランジュにおける岩石流体相互作用を明らかにしてきた.これは沈み込み帯深部で発生するスロー地震の発生場や地質学的描像を理解するうえで,貴重な情報を提供している可能性がある.講演ではこれまでの研究成果を紹介して頂くとともに,スロー地震の理解目指して今後地質学がどのような役割を果たしていくべきか,話題提供して頂きたいと考えている.
R14.テクトニクス
■谷 健一郎(国立科博:非会員)30分
谷氏は陸上から海洋底までの幅広いフィールドで,岩石学・ジルコンU-Pb年代学・地球化学を用いて,花崗岩質大陸地殻の発達過程を明らかにする研究を行っている.特に伊豆-小笠原弧などの海洋性島弧からの大陸地殻発達過程に注目して研究を精力的に行い,興味深い成果を上げてきた.近年では現在進行形である島弧ー島弧衝突が生じている伊豆衝突帯の丹沢複合深成岩体について,これらの手法を適用した結果,深部地殻の発達過程について新たな知見が見いだされた.これらの内容は,東京大会として最適であり,候補者が解明した伊豆衝突帯の深部地殻構造について話題提供を期待する.
R16.ジュラ系+(古生物部会)
■長谷川 卓(金沢大:会員)30分
長谷川会員は炭素同位体比層序の研究を牽引してきた.これまでに白亜系については多くの研究業績をあげている.近年,長谷川会員はジュラ系についての炭素同位体比層序についても興味を示している.招待講演では,トリアス・ジュラ系境界付近の炭素同位体比層序に関する講演を期待している.
▲ページTOPに戻る
R19.応用地質学一般およびノンテクトニック構造(応用地質部会)
■向山 栄(国際航業(株):会員)30分
向山 会員は,近年急速に発達してきた新しい地形解析・地形表現技術の開発とその適用に関する研究を一貫して推進されてきた.また,現在進められている日本地質学会125周年記念誌の応用地質特集号の執筆を進められている.本講演では,地形解析・地形表現の新技術とその応用地質学的な適用性・発展性に関する研究動向などについてご報告をいただくこととしたい.
R22.地球史(環境変動史部会)
■大河内直彦(JAMSTEC:会員)30分
大河内会員は,有機地球化学・同位体地球化学研究の第一人者である.彼は地球史の様々な時代(完新世,更新世,中新世,白亜紀,ペルム紀,先カンブリア紀など)の海洋生態や海洋環境,気候変動や元素循環の解明に取り組み,多くの業績を残してきた.とりわけ,独自の分析手法開発により新たなプロキシを編み出して古環境解析に応用する研究スタイルは聴講者を大いに刺激するものになるだろう.「チェンジングブルー -気候変動の謎に迫る」や「地球の履歴書」など優れた書籍を多く出版されており,科学者のみならず一般のファンも多い.大河内会員に地球史セッションで最新の話題を提供していただく.
R23.原子力と地質科学
■丸井敦尚(産総研:非会員)30分
丸井氏は,原子力廃棄物に関する国の地層処分技術WGのメンバーであり,資源エネルギー庁の沿岸域地下水研究を2004年から実施してきた.また,沿岸工業団地の設計指針策定や水循環基本法ならびに同計画にも関わってきた,わが国における沿岸域地下水研究の第一人者である.わが国における地層処分の科学的有望地は,今年中にも沿岸地下に選考されようとしている.今後,地質学会に求められる沿岸域の地下地質やその構造などの評価を行う際に,事業主体の要求や地下水・工学など他分野の情報を的確に得ておく必要があるため,最新の話題を提供していただき,有意義な議論を進めるのに最も適した人材である.
■須貝俊彦(東京大:非会員)30分
須貝氏は,自然地理学,とくに第四紀後期の地形発達史の復元が専門であり,地質環境の長期的挙動に関する分やの第一人者として,これまで地殻変動,気候・海水準変動と斜面・河川プロセスによる陸上環境の長期変動についての研究を展開してきた.これらの知見は,地層処分のサイト選定やサイト調査において不可欠であり,当該分野の最新の話題を提供していただき,有意義な議論を進めるのに最も適した人材である.
▲ページTOPに戻る
R24.鉱物資源と地球物質循環(鉱物資源部会)
■安川和孝(東京大:会員)
安川会員は,主成分・微量元素組成の解析を通じて,深海堆積物の起源とその背後にある地球表層環境変動と資源形成との関連を解明しようと精力的に研究を進めている.特に,独立成分分析という新しい統計解析手法を深海堆積物の化学組成解析に導入することでこの分野の研究に新展開をもたらし,注目すべき成果を挙げている若き第一人者である.招待講演では,深海堆積物を研究対象とした「地球表層-内部環境,テクトニックセッティング,ダイナミクスと,資源の形成メカニズムとの関わり」について,新しいアプローチによる最新の話題を提供して頂く予定である.
▲ページTOPに戻る
発表要領(シンポ・セッション共通)
発表要領 シンポ・セッション共通
発表要領
(1)口頭発表
1)セッションの発表時間は,招待講演を除き,トピック・レギュラーとも1題15分です(討論時間3〜5分と演者交代時間を含む).シンポジウムの発表時間は世話人が決めます.発表者は討論時間を必ず確保して下さい.なお,今大会でもPCセンターを設置しません.シンポ・セッションが円滑に進むように次の注意点をよくご確認下さい.
2)発表はできるだけ会場備え付けのWindowsパソコン(OSはWindows 10;PowerPoint 2007,2010,2013,2016対応)をご使用下さい(ただし,Macご利用の方と動画を使用する方はご自身のパソコンをご用意下さい).プロジェクター解像度は1024×768ドット(XGA)です.
パワーポイント・ファイルをUSBフラッシュメモリで持参し,パソコンにコピーして下さい(シンポ・セッション終了後,世話人がファイルを削除します).フォントは特殊なものではなく,PowerPointに設定されている標準的なものを使用して下さい.発表者は,シンポ・セッション開始前に発表会場で正常に投影されることを確認して下さい.
3)ご自身のパソコンで発表する方も,シンポ・セッション開始前に発表会場において正常に接続・投影されることを確認して下さい.事前に解像度(上記)の設定をご確認下さい.会場の接続端子はD-sub15ピン(ミニ)です.パソコンによってはコネクタが必要になる場合がありますので必ずご持参下さい(会場にはありません).確認作業の混雑とそれによる講演開始の遅れを防ぐため,早めの確認作業をお願いします.なお,発表者が事前確認を怠ったために発表時にトラブルが生じても時間延長等の措置は取りません.
(2)ポスター発表
1)1日間掲示できます(アウトリーチセッションを除く).コアタイムでは必ずポスターの説明を行って下さい.ポスター設置・撤去等については本誌8月号掲載予定のプログラム記事をご覧下さい.
2)ボード面積は1題あたり縦210cm,横120cmです.
3)発表番号,発表タイトル,発表者名をポスターに明記して下さい.
4)コンピューターによる演示等も許可しますが,機材等はすべて発表者が準備して下さい.また,電源は確保できませんので,必要であれば予備のバッテリーを用意して下さい.発表申込の際に機器使用の有無や小机の必要性等をコメント欄に記入し,事前に世話人にもご相談下さい.
5)運営規則第16条2項(8)により,優れたポスター発表に対して「日本地質学会優秀ポスター賞」を授与します.今回より,優秀ポスター賞はエントリー制になりました.エントリーを希望される発表者は,講演申し込み時に優秀ポスター賞エントリー希望を選択してください.発表当日,エントリーされた講演番号のボードに「エントリー講演」と書かれた紙が貼付してありますので,ご確認ください.この紙はポスター貼付後も見える位置に貼付しておいてください.
(3)発表者の変更
口頭,ポスター発表に関わらず,あらかじめ連記されている共同発表者内での変更は認めますが,必ず事前に行事委員会に連絡して下さい.この場合もセッション発表者については「発表に関する条件・制約」を適用します.
(4)口頭発表の座長依頼
各セッション会場の座長を発表者に依頼することがあります.その際はご協力をお願いします.
発表者への注意
発表者へ
発表者は本学会または共催学協会の会員に限ります(招待講演者を除く).共同発表の場合は,この制限を代表発表者(講演要旨に下線を引いた著者)に適用します.やむを得ない事情により,あらかじめ連記された共同発表者内で発表者の変更を希望する場合は,必ず事前に行事委員会(会期前は学会事務局,会期中は学会本部)に連絡して下さい.この場合も,シンポジウムおよびアウトリーチセッション以外の場合は「会員に限り1 人1 題(発表負担金を支払った場合は2 題)」の制限を守るものとします.代理人の代読,会場内での突然の発表者変更,発表順序の変更は認めません.口頭発表者は発表時間を厳守して下さい.持ち時間15分のうち,発表は10〜12分とし,質疑応答と講演者の交代時間を確保してください(30分の招待講演の場合,発表20〜25分).発表に際しては座長の指示に従い,会場運営がスムーズに行われるようご協力下さい.
口頭発表
・ 1 題15分(質疑応答と講演者の交代時間3〜5 分を含む).ただしシンポジウムとセッション招待講演は除きます.
・ 学術大会では,PCセンターを設置しません(ニュース誌5月号を参照).セッションが円滑に進むように,注意点を確認ください.
・ 口頭発表会場には液晶プロジェクターとWindowsパソコン(OS:Windows 10対応,PowerPoint2007. 2010. 2013.2016対応)を用意します.発表はできるだけ会場備え付のWindowsパソコンをご使用下さい(ただしMacご利用の方,動画を使用する方などはご自身のパソコンをご用意下さい) . プロジェクター解像度は1024 × 768ドット(XGA)です.セッション開始前に試写し正常に投影されることを必ず確認してください.
・ 確認作業の混雑とそれによるセッション開始の遅れを防ぐため,早めの確認作業をお願いします.なお,発表者が事前確認を怠ったために発表時にトラブルが生じても時間延長等の措置は取りません.
【講演ファイルをUSBメディアでご持参の方】
ファイルのインストールは,セッション開始前に,講演会場前方パソコン設置台にて行ってください.各会場のパソコンのデスクトップ上には日付(例0911)のフォルダが配置されており,その中にセッション番号のサブフォルダ(例:T1)が配置されています.そのサブフォルダ内に講演ファイルを保存してください.ファイル名は「発表番号と演者氏名」にしてください(例:S1-O- 1東京太郎,T1-O-13 江戸花子).インストール後,ファイルが正常に投影されることを必ず確認してください.特に,会場のPC と異なるバージョンで作成されたパワーポイントのファイルは,レイアウトが崩れる場合がありますのでご注意ください.フォントは特殊
なものではなく,PowerPoint に設定されている標準的なものを使用して下さい.セッション終了後,世話人がファイルを削除します.
【ご自分のパソコンを使用して講演する方】
Mac パソコンをお使いになる方,ソフトの互換性からレイアウトが崩れる可能性のある方,パワーポイント以外のプレゼンテーションソフトをご利用の方は,ご自身でパソコンをご用意ください.会場の液晶プロジェクターにパソコンの切り替え器(ケーブル形状はD-SUB15 ピン)を用意します.
プロジェクターの解像度設定はXGA(1024 × 768)です.講演前に出力調整の上,接続してください.Mac パソコンなどパソコンによってはコネクタが必要になる場合があります.必ずD-SUB15 ピンのアダプターをご持参ください(会場にはありません).接続は発表者自身が責任を持って行なってください.セッション開始前に試写し,正常に投影されることを必ず確認してください.
ポスターセッション
・ 掲示する際のチェスピンを準備いたします.テープは利用できません.
・ 掲示可能時間は9 :00 〜18:00 です.最低掲示時間帯(10:00〜17:00)は必ず掲示して下さい.撤収は必ず19:00 までにお願いします.
・ コアタイムは,10 日(土)が13:45 〜 15:05,11 日(日)と12 日(月)が13:00 〜 14:20 です.この時間は必ずポスターに立ち会い,説明して下さい.その他の時間は各自の都合により随時説明を行って下さい.
・ ボード面積は,高さ210cm,幅120cm です.
・ ポスターには,発表番号・発表題名・発表者名を必ず明記して下さい.
・ コンピューターやビデオを使用される場合,機器の準備は各自で行ってください.電源は確保できませんので,予備バッテリーをご準備下さい.
・ 申込時にエントリーをしたポスター発表に対し,別記の要領にて優秀ポスター賞が授与されます.奮ってご準備下さい.
OR,R6のポスター発表について
OR アウトリーチセッション,R 6 ジオパークセッションは,一般市民へのアウトリーチ活動を目的として,下記のように発表を行います.
[ORアウトリーチセッション]
10 日 (土):場所 3 号館2 階(市民講演会会場前).掲示のみ,コアタイムはありません.
11 日 (日):場所 3 号館2 階(市民講演会会場前).コアタイム(13:00-14:00,16:30-17:30;計2 回)(※ポスター賞審査対象日)
[R6ジオパークセッション]
11 日 (日):場所 3 号館2 階(市民講演会会場前).コアタイム(13:00-14:20)(※ポスター賞審査対象日)
優秀ポスター賞について
今大会でも学術発表の優秀ポスターに対して「日本地質学会優秀ポスター賞」を授与します.今大会より,優秀ポスター賞はエントリー制になります.発表当日エントリーされた講演番号のボードに「エントリー講演」と書かれた紙が貼付してありますので,ご確認ください.賞の授与は毎日3 〜 5 件の予定です.受賞者には学会長から直接賞状を授与します(表彰と写真撮影).受賞ポスターは,その栄誉をたたえ,大会期間中, 別途設けるボードに掲示します. 大会終了後,News 誌(年会報告記事)に氏名,発表題目,受賞理由を掲載します.
【審査】
審査は各賞選考委員会が行い,学会長がこれを承認します.選考委員会は日替わりで,行事委員会委員5名,大会実行委員会代表1名および各賞選考委員会委員2名の合計8名により構成されます.選考委員氏名は大会終了後に公表します(News誌11月号を予定).
【審査のポイント】
・(研究内容)オリジナリティ
・(プレゼンテーション)レイアウト・中心点の明示・わかりやすさ・美しさ・斬新さ
【審査結果の発表時間と方法】
発表は各日毎16時頃に行います.表彰は17時前後にポスター会場で行います.ただし,初日(11日)の表彰は,2日目(12日)の表彰時にあわせて行う予定です.審査結果は掲示板や廊下等の要所に貼り出します.受賞ポスターには受賞花をつけ,会期中ポスター会場に掲示します.
学術大会でのハイライト
学術大会でのハイライト
それぞれのシンポジウム・セッションがより盛り上がることを期待して,また,会場で学術大会に不慣れな方(学生など)にわかりやすく情報を提供し,おもしろいサイエンスにひとつでも多く接してもらうことを目的に,「おもしろそう,注目すべき,ぜひ聞いてほしい」発表を世話人に選んでいただき,わかりやすく紹介いただきました.ハイライトは,本プログラム記事のほか,学会 HP と講演要旨集に掲載し,さらに学会プレス発表時に報道機関に配布いたします.何らかの理由で学会のプレス推薦候補にならなかった優れた研究が埋もれているかもしれません.そのようなものをできるだけ発掘し,より多くの学術情報を提供したいと考えます.今大会では2 件のシンポジウムと34 件のセッション(トピック,レギュラー,アウトリーチ)が開催され,580 題を超える多くの発表が行われる予定です.このハイライト情報はきっと皆様のお役に立つと思います.日本最大の「地質学の祭典」をお楽しみください.
◆ 第123年学術大会(2016東京・桜上水大会)のハイライト一覧はこちらから
参加登録TOP
2016東京・桜上水大会事前参加登録のご案内
[下のフローチャートに従って,申込手続き行って下さい]
(お詫び)事前参加登録システムが復旧しました.17日夕刻より再度にシステムに不具合が生じ,申込手続きが出来ない状態になっていました.たびたびご迷惑をおかけし大変申し訳ありませんでした.(8/18,10:47現在)
締切延長:8/19(金)午前10時(web)
事前参加登録は締め切りました.
事前参加登録締切:8月18日(木)18時(web)
FAX/郵送:8月15日(月)必着
参加登録に関わるお申込(参加,要旨集,巡検,懇親会,弁当)は,オンラインによる大会専用参加登録システム(会員・非会員にかかわらずどなたでも申込可)をご利用の上,お申し込み下さい.
郵送で申し込む場合は,学会事務局までお問い合わせ下さい.郵送用申込書等必要な書式をお送りします.提出書類をご準備の上,8月15日(月)必着で学会事務局までお送り下さい.
大会参加登録およびそれに伴う参加費は,参加者(巡検のみ参加の場合も)に必要な基本的なお申し込みです.会員が同伴する非会員の家族等(以下,同伴者)についても懇親会・巡検・お弁当については事前に申込が必要です.申込は,会員と同伴者の計2名まで一括申込が可能です.なお,学会を通じての宿泊・交通手配の斡旋は行いません.宿泊や交通については各自で手配願います.
下のフローチャートに従って進み,該当する申込画面をクリックして
それぞれ申込手続きをおこなって下さい.
画面 A へ
画面 B へ
画面 C へ
※巡検協賛学協会・セッション共催団体リストはこちらから
参考>>会員情報を自動取得するには?(PDF)
当日の受付について
当日の受付について
大会の受付時間
10 日(土)8:00 〜16:30
11 日(日)8:00 〜16:30
12 日(月)8:00 〜15:00
*大会初日は受付混雑が予想されます。時間に余裕をもってお出かけ下さい。万一受付混雑のため講演に間に合わない場合は,直接講演会場へご入場下さい。受付手続きは講演後に必ず行って下さい。
■ 事前参加登録をされた方
【入金済みの場合】
確認書2枚(本人控・受付提出用)と名札,懇親会とお弁当を予約の方にはそれぞれクーポンをお送りします.大会開催10 日前頃には,皆様のお手元に届くようお送りします.当日会場へ持参してください注1).*9/2に確認書を発送しました
【期日までに入金確認が取れていない場合】
請求金額は当日払いの金額に変更になります.また,大会10 日前頃までに未入金の旨記載された確認書のみ送付いたします注2).当日会場にて確認書をご提示いただき,代金の清算をして下さい注1).期日を過ぎて入金された場合でも,会場にて差額分のご精算をお願いします.その際は,入金時の控え等を会場にお持ちください.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
事前登録者用受付にて,確認書に記載されている項目ごとに受付して下さい.
受付にてネームカードホルダーをお渡ししますので『参加証(名札)』を入れ,大会期間中は身に付けてください.
1.確認書の提出(全員)→ネームカードホルダーの配布.要旨付きの場合は,要旨の配布
2.講演要旨追加購入(予約購入者のみ)→要旨の配布
3.懇親会→参加者は直接懇親会会場でクーポンを提示してご入場ください.
4.お弁当(予約者のみ)→お弁当の引換所にてクーポンを提示して,引き換えてください.
5.巡検(参加者のみ)→名簿確認と参加最終確認
注1)当日確認書やクーポンを忘れた方は,専用の用紙に申込内容をご記入いただき,受け付けを済ませてください.確認がスムーズに行えますよう,ご協力をお願い致します.
注2)未入金の方には,会場受付での入金確認後,懇親会やお弁当のクーポンをお渡しします.
→申込の取消・取消料についてはこちらから
■ 事前登録をしていない方(当日受付)
1.当日は必ず参加登録をしてください.参加登録費の有料・無料に関わらず備え付けの『参加登録票』に必要事項を記入し当日用受付へ
2.当日参加登録費(講演要旨集付きです.要旨集が不要の場合でも割引はありません)
正会員:9,500 円
院生割引会費適用正会員:6,500 円
学部 学生割引適用正会員・名誉会員・50 年会員・非会員招待講演者・学部学生(会員・非会員問わず):無料(講演要旨は付きません)
非会員(一般):15,000 円
非会員(院生):9,500 円
3.講演要旨当日販売
会 員:4,000 円
非会員:5,500 円
4.懇親会の当日参加費(ただし,人数に余裕がある場合に限る)
正会員・非会員(一般):6,000 円
名誉 会員・50 年会員・院生および学生割引適用正会員(家族および非会員院生・学生含):4,000 円
別途領収書が必要な方は会場受付でその旨お申し出ください.当日のお支払いは,現金のみの取扱いとなります.クレジットカードはご利用いただけません.
申込方法と支払について
各種申込とお支払について
<申込締切 オンライン:8月18日(火)18:00,FAX/郵送:8月14日(金)必着>
■事前参加申込はこちらから■
(1)申込方法
1)参加登録システム(オンライン)による申込(申込締切 8月18日(木)18:00)
大会専用参加登録システムへアクセスし,画面表示に従って入力をして下さい(6 月初旬より受付開始です). 申込み完了後,「申込確認メール」および「ご請求メール」が登録のメールアドレスへ配信されます.内容を必ずご確認下さい.お支払いは,銀行振込またはクレジットカード決済のいずれかを選択できます.「銀行振込」を選択された方は,「ご請求」メールを確認の上,指定の金融機関よりお振込み下さい.「クレジット決済」を選択の場合は,ご利用のカード会社の期日に合わせて,口座より引き落としとなります.クレジットカード会社からの明細には「日本地質学会(ニホンチシツガッカイ)」と表示されます.
2)FAX・郵送による申込(申込締切:8月15日(金)必着) まずは学会事務局までお問い合わせ下さい.郵送用申込書等必要な書式をお送りします.申込書類をご準備の上,8月15日(月)必着で学会事務局までお送り下さい.お申込みの際は,必ず申込書のコピーを各自で保管して下さい.電話による申込,変更などは受け付けられません.
申込後,折返し学会より「受付番号」を記した「受付確認」をe-mailまたはFAXにてお送りします.必ずご確認下さい.「受付確認」が届かない場合は,必ず事務局までご連絡下さい.この「受付番号」はその後の問い合せ,変更,取消等に必要となります.
お支払いは,銀行振込またはクレジットカード決済のいずれかを選択できます.申込後順次,「予約内容確認」・「請求書」をお送りします.銀行振込を選択された方は,請求書に記載されている振込口座へ指定期日までにお振込み下さい.クレジット決済を選択された方は,参加申込書に必ずクレジット番号などの必要事項を記入して下さい.ご利用のカード会社の期日に合わせて,口座よりお引き落としとなります.カード会社からの明細には「日本地質学会(ニホンチシツガッカイ)」と表示されます. 申込先 申込書に必要事項を記入の上,下記宛にお送り下さい.
[送付先]〒101-0032東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル6階
「日本地質学会東京・桜上水大会参加申込係」 FAX:03-5823-1156
オンライン,FAX,郵送いずれの申込も締切後,名札・確認書・クーポン(一部の方)を発送します(8月末頃発送予定).大会開催10日前までには参加者の皆様のお手元に届くようお送り致します.
(注意)締切時点で入金確認が取れない場合:請求金額は,「当日払い」の金額となり,未入金旨記載された確認書のみが送付されます(名札・クーポンは送付されません).入金とクーポン発送が入れ違いの場合は,入金(振込)時の控え等を会場にお持ち下さい.ご協力をお願い致します.
(2)申込後の変更・取消
1)参加登録システム(オンライン)でお申込みの場合:
締切までの間は,大会登録専用HPから予約の変更・取消が出来ます.変更・取消完了後,「変更・修正 確認メール」が登録のメールアドレスへ配信されます.内容を必ずご確認下さい.締切後(8/19以降)は直接学会事務局(東京)にFAX又はe-mailにてご連絡下さい.お支払いがクレジット決済の場合は,申込の都度決済が完了します.決済スケジュールの都合によっては,口座から重複して引き落とされる場合があります.その場合は,振込手数料を差し引いた額をクレジットカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2〜3ヶ月要する場合もありますので,ご了承下さい.
2)FAX・郵送でお申込み場合:
申込後に変更・取消が生じた場合は,学会事務局(東京)にFAXまたはe-mailにてご連絡下さい.その際申込受付時に案内される「受付番号」・「氏名」を必ず明記下さい.
(3)取消に関わる取消料と返金について
下記の通り,申込項目により取消料が異なります.
締切日
(8/18)まで
大会3日前
(9/7)まで
大会2日前
(9/8)以降
参加登録費
0%
60%
100%
追加要旨
0%
60%
100%
懇親会
0%
100%
100%
弁 当
0%
50%
100%
締切日
(8/8)まで
大会3日前
(9/7)まで
大会2日前
(9/8)以降
巡 検
0%
50%
100%
(注)返金がある場合は,振込手数料を差し引いた金額をクレジットカード会社もしくは学会から返金します.返金までに2−3ヶ月要する場合もありますので,ご了承下さい.
参加登録費
参加登録費
■当日の受付についてはこちらをご参照下さい■
○参加登録費(講演要旨集付です)
事前申込
当日払い
備考
正会員
7,500円
9,500円
講演要旨集付き
院生割引適用正会員
4,500円
6,500円
講演要旨集付き
学部制割引適用正会員・名誉会員・50年会員
非会員学部学生・非会員招待者・同伴者
無料
無料
講演要旨集は付きません
非会員(一般)
12,500円
15,000円
講演要旨集付き
非会員(院生)
7,000円
9,500円
講演要旨集付き
※参加費有料の方には必ず要旨集1冊が付きます.講演要旨集が不要の場合でも割引はありません.
※講演要旨集の付かない方はご希望に応じて別途購入して下さい.
※日本地質学会の会員資格は『正会員』のみであり,割引会費の申請をした方についてのみ,割引会費が適用されています.
※セッション共催団体および巡検協賛団体会員の参加登録費は地質学会会員に準じます.
※災害に関連した参加費の特別措置:熊本地震で被災された会員の方々(災害救助法適用地域に居住している方)のご窮状をふまえ,申請により大会参加登録費を免除いたします.該当される方は,必ず事前参加申込手続き前に学会事務局に申請して下さい(1. 会員氏名,2. 被災地,3. 被災状況(簡潔に)を添えて学会事務局まで.郵送,メールいずれも可).
(注1)免除の対象は大会参加登録費に限ります.巡検,懇親会等その他の費用は対象となりません.
(注2)事前参加申込の場合に対してのみ適用しますので,当日会場での申請は受付ることができません.
要旨集予約頒布
講演要旨集の予約頒布
(お知らせ)
当日販売分の要旨集は売り切れました.
会期後の要旨集のご注文もお受けできません.ご了承下さい.
参加費無料の方は要旨集が付きません.要旨が必要な方は,参加登録時に追加講演要旨集の申込をして下さい.複数の講演要旨集を追加購入頂くこともできます.受け取り方法には,(1)大会後に送付(要別途送料*)(2)会場で受取 があります.大会へ参加しない方も要旨のみ事前予約できます(大会後に送付).
事前予約(/冊)
当日販売(/冊)
会員
3,000円
4,000円
非会員
4,000円
5,500円
*「大会後に送付」の場合の送料は以下の通りです.
送料:1冊 500円,2冊 600円,3冊 800円,4冊 1,000円,5冊 1,200円
巡検参加申込
巡検へ参加される方へ
1)巡検参加事前申込みは8 月8 日に締め切りました.締切時点で申込者数が,最小催行人数に達しなかったため,残念ながら一部の巡検コースは中止となりました.また.一部のコースについては実施内容を変更したうえで実施予定です.参加者への連絡などは案内者よりご連絡いたします.
巡検案内書は,例年冊子体は作成せずCD-ROMで発行しておりましたが,昨年に引き続き,今大会も地質学雑誌122巻7 号および8 号(2016年7 月および8 月号)に掲載いたします.また,J-STAGE<http://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja>にて公開をいたします.なお,予告記事でもお知らせの通り,巡検参加者には各参加コース箇所の巡検案内書を巡検当日に配布します.
2) 重要 「野外見学,調査,試料採取における注意喚起」をご一読下さい
巡検へ参加される方は,参加の前に是非「野外見学,調査,試料採取における注意喚起」をご一読下さい。
「野外調査において心がけたいこと」国立・国定公園や史跡・名勝・天然記念物、あるいは一般的な露頭における調査上の注意点
「安全のしおり(巡検案内書より)」巡検や野外調査における安全上の注意点と自然保護に関する注意点
「巡検案内書を頼りに野外調査へ出かける方へ」露頭での調査や試料採取にあたっての注意点(「野外調査において心がけたいこと」から一部抜粋)
[巡検実施の可否について](2016年8月9日)
8月8日締切時点で申込者数が,最小催行人数に達しなかったため,残念ながら一部の巡検コースは「中止」とさせて頂きます.また一部コースは,当初の予定を一部変更して実施することと致しました.各コースの参加者へは別途直接ご連絡をいたします.
班
コース名
実施の可否
A
丹沢衝突帯(9/13-14)
実施します
B
浅部付加体(9/13-15)
実施します
C
葉山ー嶺岡帯(9/13-14)
実施します
D
関東山地北縁部(9/13-14)
実施します
E
秩父帯北帯(9/13-14)
実施します
F
吾妻渓谷(9/13-14)
実施します
G
伊豆南部(9/13-14)
中止
H
富士山(9/13-15)
中止
I
教師向け巡検(10/1)
申込受付中(9/16締切)
J
上総層群(9/9)
実施します
K
関東地震(9/9)
実施します
巡検コース一覧/みどころ
巡検コース一覧
申込締切 WEB: 8月8日(月)18:00
FAX・郵送: 8月5日(金)必着
■巡検のお申込(事前参加申込)はこちらから■
★注意点★
1)取消料は,申込締切後〜大会3日前(9/7)までは50%,大会2日前(9/8)以降は全額となります.申込締切後の変更・取消は,直接学会事務局(東京)にFAX又はe-mailにてご連絡下さい.
2)参加費には,日程に応じた旅行傷害保険(少額)が含まれます.
3)最小催行人員に満たない場合や,安全確保に問題があると考えられる場合は,コース内容の一部変更や巡検中止等の措置をとることがあります.
4)案内書は昨年同様,地質学雑誌 7, 8月号に掲載予定です.CD-ROMは作成しません.また,雑誌発行と同時にJ-STAGE上で公開します.参加者へは,各コース毎の案内書を巡検当日に配布します.
5)集合・解散の場所,時刻等に変更が生じた場合,大会期間中会場内の掲示板等に案内します.また,案内者から直接ご連絡することもあります.
6) Iコース<教師向け巡検>について:学会補助事業です.小中高の教員ならびに一般市民を優先対象とします.また本巡検のみ会期外の10月1日実施予定です.申込締切や申込フォームも他のコースとは異なります.ご注意下さい.
7)中学生以下がIコースに参加する場合は,必ず保護者同伴でお申し込み下さい.また,長時間の歩行や川原など足場の悪い場所で露頭観察を行う場合もあります.巡検の性質上,自立歩行が難しい方,介助が必要な方のご参加はご遠慮願います.
Aコース:丹沢衝突帯(9/13-14)
Bコース:浅部付加体(9/13-15)
Cコース:葉山—嶺岡帯(9/13-14)
Dコース:関東山地北縁(9/13-14)
Eコース:秩父帯北帯(9/13-14)
Fコース:吾妻渓谷(9/13-14)
Gコース:伊豆南部(9/13-14)
Hコース:富士山(9/13-15)
Iコース:教師向け巡検(10/1)
Jコース:上総層群(9/9)
Kコース:関東地震(9/9)
Aコース丹沢山地の地質:伊豆衝突帯のジオダイナミクス
巡検コース:
[1日目]横浜駅(集合)9:00→山北→皆瀬川→小山→玄倉→中川温泉→丹沢湖キャンプサイト
[2日目]丹沢湖キャンプサイト→中川橋→河内川→大滝沢→世附→細川谷→松田駅・横浜駅(解散)17:00
主な見学対象:1.丹沢複合深成岩体 2.丹沢層群(枕状溶岩) 3.丹沢変成岩 4.足柄層群 5.ざくろ石流紋岩 6.神縄断層 7.塩沢断層
日程:9月13日(火)-14日(水)(1泊2日)
定員(最少催行人数):12(10)
案内者:石川正弘(横浜国立大)・谷健一郎(国立科学博物館)・金丸龍夫(日本大)・桑谷立(JAMSTEC)・小林健太(新潟大)
参加費:12,000円
必要な地図(1/2.5万):「中川」,「山北」,「駿河小山」
集合・解散:集合:13日9:00(横浜駅) 解散:14日17:00(横浜駅)
その他:案内者が食費・雑費を現地にて別途徴収(3,000円程度).
移動にはレンタカー使用.参加人数によってレンタカー利用料金負担が変動する可能性あり.帰路はJR松田駅にも立ち寄る.
ページtopに戻る
Bコース:付加型沈み込み帯浅部の地質構造:房総半島南部付加体-被覆層システム
巡検コース:
[1日目]館山駅西口(集合)10:00→南房総市千倉→西川名→館山市見物→筑波大学館山研修所(泊)
[2日目]筑波大学館山研修所→鴨川市太海→鴨川市磑森→筑波大学館山研修所(泊)
[3日目]筑波大学館山研修所→館山市犬掛→富津市志駒・岩本付近→道の駅富楽里(解散)15:00
主な見学対象:1.埋没深度約1 kmの付加体と被覆層 2.埋没深度約2-4 kmの付加体と被覆層 3.海溝斜面堆積物 4.前弧海盆堆積物
日程:9月13日(火)-15日(木)(2泊3日)
定員(最少催行人数):15(12)
案内者:山本由弦(JAMSTEC)・千代延俊(秋田大)・神谷奈々(日本大)・斎藤実篤(JAMSTEC)
参加費:16,000円
必要な地図(1/2.5万):「館山」,「千倉」,「那古」,「安房古川」,「安房和田」,「鴨川」,「鬼泪山」
集合・解散:集合:13日10:00(館山駅西口) 解散:15日15:00(道の駅富楽里)
その他:
参加費に昼食・夕食代は含まれない.昼食は近くの店舗で購入の予定.
解散場所の道の駅富楽里では東京・横浜方面に高速バスあり(参考:富楽里15:25→東京駅16:46;富楽里15:35→横浜駅17:00;富楽里15:35→君津バスターミナル乗り換え→羽田空港17:03).
移動にはレンタカー使用.参加人数によってレンタカー利用料金負担が変動する可能性あり.
ページtopに戻る
Cコース:葉山—嶺岡帯トラバース
巡検コース:
[1日目]千葉駅(集合)8:00→鴨川市鴨川漁港→鴨川市嶺岡中央林道→南房総市平久里→鋸南町勝山→道の駅保田小学校(泊)
[2日目]道の駅保田小学校→横須賀市野比→横須賀市平作→横須賀市芦名→横須賀市立石→葉山町森戸→逗子市桜山→新逗子駅(解散)16:00
主な見学対象:1.嶺岡帯構成岩石とその配列 2.蛇紋岩と堆積岩との関係 3.房総半島西岸オフィオライト岩体 4.北武断層破砕帯 5.三浦半島葉山層群各層及び田越川不整合
日程:9月13日(火)-14日(水)(1泊2日)
定員(最少催行人数):20(15)
案内者:高橋直樹(千葉県立中央博物館)・柴田健一郎(横須賀市自然・人文博物館)・平田大二(神奈川県立生命の星・地球博物館)
参加費:18,000円
必要な地図(1/2.5万):「鴨川」,「金束」,「保田」,「浦賀」,「横須賀」,「秋谷」,「鎌倉」
集合・解散 集合:13日 8:00(JR千葉駅) 解散:14日 16:00(京急新逗子駅)
その他:参加費に昼食代は含まれない.1日目は昼食各自持参.二日目昼食は近くの店舗で購入の予定.
2日目の房総半島−三浦半島間は東京湾フェリーを利用.道の駅保田小学校(宿泊先)では4人1組の相部屋を予定.
ページtopに戻る
Dコース:関東山地北縁部の低角度構造境界
巡検コース:
[1日目]西武池袋線 石神井公園駅(集合)8:30(*)→比企丘陵→小川町→金勝山→長瀞高砂橋付近→甘楽ふるさと館(泊)
[2日目]甘楽ふるさと館→下仁田→西武池袋線 石神井公園駅(解散)18:00(*)
主な見学対象: 1.領家帯マイロナイトと青岩礫岩 2.寄居変成岩,3.金勝山石英閃緑岩,4. 緑色岩メランジュ, 5. 三波川帯内部の低角度断層境界, 6.跡倉ナップの押し被せ褶曲 7. 跡倉押しかぶせ断層と跡倉礫岩,8.ペルム紀ナップ(金勝山ナップ)基底断層
日程:9月13日(火)-14日(水)(1泊2日)
定員(最少催行人数):20(15)
案内者:高木秀雄(早稲田大)・新井宏嘉(早稲田大本庄高等学院)・宮下敦(成蹊高校)
参加費:24,500円
必要な地図(1/2.5万):「武蔵小川」,「安戸」,「鬼石」,「下仁田」
集合・解散:西武池袋線石神井公園駅 集合:13日8:30 解散:14日18:00
その他:参加費に2日目昼食代を含む.1日目は弁当持参または途中の高坂SAで購入可能.
*(訂正)ニュース誌5月号予告記事での「巡検コース」欄での集合・解散場所の記述に誤りがありました.お詫びして訂正いたいます.(2016.6.7)
(誤)[1日目]日大文理学部(集合)8:00
(正)[1日目]西武池袋線 石神井公園駅(集合)8:30
(誤)[2日目]・・・日大文理学部(解散)18:00
(正)[2日目]・・・西武池袋線 石神井公園駅(解散)18:00
ページtopに戻る
Eコース:関東山地の秩父帯北帯
巡検コース
[1日目]西武秩父駅(集合)10:00→群馬県神流町間物沢沿い→叶山鉱山→神流川沿い→秩父小鹿野温泉旅館 梁山泊(泊)
[2日目]秩父小鹿野温泉旅館 梁山泊→浦山ダム→風早峠→安戸→小川町駅(解散)17:30
主な見学対象: 1.間物沢沿いの蛇木ユニット 2.叶山鉱山 3.神流川沿いの住居附ユニット 4.浦山ダム沿いの変斑れい岩 5.風早峠ユニット 6.安戸の柏木ユニット
日程:9月13日(火)-14日(水)(1泊2日)
定員(最少催行人数):22(18)
案内者:久田健一郎(筑波大)・加藤潔(駒澤大)・松岡喜久次(埼玉県立川越女子高)・関根一昭(埼玉県立秩父高)・冨永紘平(筑波大)
参加費:21,000円
必要な地図(1/2.5万):「神ヶ原」,「両神山」,「秩父」,「皆野」,「鬼石」,「安戸」
集合・解散:集合: 13日 9:00(西武秩父駅) 解散:14日 17:00(小川町駅)
その他:参加費に昼食代は含まれない.昼食は近くの店舗で購入の予定.1日目秩父太平洋セメント(株)叶山鉱山を見学
*(時間変更)ニュース誌5月号予告記事の情報から下記の通り変更になりました.集合・解散時間に変更があります.(2016.8.5)
(変更前)[1日目]西武秩父駅(集合)9:00
(変更後)[1日目]西武秩父駅(集合)10:00
(変更前)[2日目]・・・小川町駅(解散)17:00
(変更後)[2日目]・・・小川町駅(解散)17:30
ページtopに戻る
Fコース:吾妻渓谷地域の地質
巡検コース
[1日目]JR吾妻線川原湯温泉駅(集合)12:30→吾妻渓谷遊歩道→久々戸沢→国立大学草津セミナーハウス(泊)
[2日目]国立大学草津セミナーハウス→殺生河原→応桑地区→林地区→川原畑地区→JR吾妻線川原湯温泉駅(解散)15:30
主な見学対象:1.吾妻渓谷遊歩道ぞいの変質火山岩類および断裂 2.変質帯地盤 3.酸性熱水変質帯 4.前期更新世の火山岩類 5.岩屑なだれ堆積物の特徴
日程:9月13日(火)-14日(水)(1泊2日)
定員(最少催行人数):20(15)
案内者:中村庄八(前橋工科大)・中山俊雄(東京都)・藤本光一郎(東京学芸大)・方違重治(国土防災技術株式会社 関東支社)
参加費:16,500円
必要な地図(1/2.5万):「上野草津」,「長野原」,「大前」
集合解散:JR吾妻線川原湯温泉駅 集合:13日 12:30 解散:14日 15:30
その他: 1日目昼食は集合前までに済ませておくこと.参加費に2日目昼食代を含む.
ページtopに戻る
Gコース:伊豆半島南部,新第三系白浜層群での浅海底火山活動
巡検コース:
[1日目]伊豆急下田駅(集合)10:45→須崎恵比寿島→田牛竜宮窟→あいあい岬→中木→リゾートイン タケマル(泊)
[2日目]リゾートイン タケマル→入間港→入間千畳敷→室岩洞→堂ヶ島→JR三島駅(解散)17:00
主な見学対象: 1.浅海性堆積物の堆積構造,水底土石流堆積物 2.自破砕溶岩、自破砕状貫入岩,柱状節理の発達した貫入岩体, 未固結堆積物への貫入構造、砕屑岩脈 3.ぺぺライト、熱水変質 4.波曲構造 5.ジオパークビジターセンター
日程:9月13日(火)-14日(水)(1泊2日)
定員(最少催行人数):20(15)
案内者:狩野謙一(静岡大)・伊藤谷生(帝京平成大)
参加費:26,000円
必要な地図(1/2.5万):「下田」,「神子元島」,「伊豆松崎」
集合・解散 集合:13日 10:45(伊豆急下田駅) 解散:14日 17:00(JR三島駅)
その他:参加費に2日目昼食代を含む.1日目昼食は弁当持参.国立公園内および観光地のため,ハンマーの使用・岩石の採取は不可.見学地点は海岸部のため,天候 (波浪を含む)によっては大幅なコース変更あり.
ページtopに戻る
Hコース:富士山山麓を巡る〜火山地質から防災を考える〜
巡検コース
[1日目]富士山駅(集合)8:30→新富士駅10:00→宝永火口→太郎坊→御殿場岩屑なだれ→アジア航測保養所「山中荘」(泊)
[2日目]アジア航測保養所「山中荘」→雁穴溶岩→精進湖(枕状溶岩)→蝙蝠穴(溶岩洞窟)→西の家(泊)
[3日目]西の家→田貫湖岩屑なだれ→風祭火砕流→富士川河口(水神溶岩)→新富士駅14:00→富士山駅(解散)15:30
主な見学対象:1.宝永山火口 2.火山灰 3.溶岩洞窟 4.枕状溶岩等 5.岩屑なだれ 6.火砕流 7.遠方まで流れた溶岩
日程:9月13日(火)-15日(木)(2泊3日)
定員(最少催行人数): 25(20)
案内者: 山元孝広(産総研)・吉本充宏(山梨富士山科研)・千葉達朗(アジア航測(株))・荒井健一(アジア航測(株))・細根清治(大和探査技術(株))
参加費:32,500円
必要な地図(1/2.5万) 無し
集合・解散 :集合:13日 8:30(富士急 富士山駅) 10:00(JR新富士駅)
解散:15日 14:00(JR新富士駅) 15:30(富士急富士山駅)"
その他:参加費に昼食代は含まれない.1日目昼食は弁当持参.2日目および3日目昼食は宿泊施設で手配予定.1日目夕は温泉施設「紅富士の湯」を利用予定(実費負担).1日目は集合場所の富士山駅の後は新富士駅に立ち寄る.3日目は新富士駅に立ち寄った後に富士山駅にて解散.
ページtopに戻る
I コース:千葉市の昔の海岸線を歩く(教師向け巡検)
巡検コース:JR稲毛海岸駅(集合)9:30→浅間神社→稲毛陸橋付近→稲毛公園→幕張2丁目付近→JR幕張駅(解散)15:00
主な見学対象:1.浅間神社とクロマツ林 2.砂丘・砂州 3.旧汀線
日程:10月1日(土)日帰り[会期外実施]
定員:教師15,一般15(合計で30)
案内者:米澤正弘(千葉大)・加藤 潔(駒澤大)
参加費 :1,000円(保険代+資料代)を現地で徴収.160円(京成稲毛〜京成幕張)を自己負担.
必要な地図(1/2.5万):「千葉西部」
集合・解散:集合:9:30(JR稲毛海岸駅) 解散:15:00(JR幕張駅)
その他:
※地質学会期間とは別日程(10/1)で実施.申込締切:9月16日(金).申込は大会HP内専用申込サイト(こちらから)から
昼食は持参または近くの店舗で購入の予定.
ページtopに戻る
J コース:関東平野南部における上総層群のテフロクロノロジー[プレ巡検]
巡検コース:立川駅北口多摩信用金庫前広場(集合)8:00→武蔵村山市→所沢市→立川市・日野市→八王子市→稲城市→東横線綱島駅(解散)17:00
主な見学対象: 1.狭山丘陵 2.多摩川河床・多摩丘陵
日程: 9月9日(金)日帰り [プレ巡検]
定員(最少催行人数) :25(20)
案内者:鈴木毅彦(首都大)・白井正明(首都大)・福嶋 徹(むさしの化石塾)
参加費:7,000円
必要な地図(1/2.5万):「所沢」,「立川」,「八王子」,「武蔵府中」,「溝口」,「川崎」
集合・解散: 集合:7:30(立川駅北口) 解散:17:00(東横線綱島駅)
その他:大会前日に開催(プレ巡検).昼食は首都大の生協などを利用予定.
*(時間変更)ニュース誌5月号予告記事の情報から下記の通り変更になりました.集合・解散時間に変更があります.(2016.8.5)
(変更前)[1日目]立川駅北口(集合)7:30
(変更後)[1日目]立川駅北口多摩信用金庫前広場(集合)8:00
ページtopに戻る
Kコース:房総半島における関東地震の隆起・津波痕跡[プレ巡検]
巡検コース: 東京駅(集合)8:30→館山駅→館山市見物海岸→館山市巴川河岸→南房総市千倉町→館山駅→東京駅(解散)18:00
主な見学対象: 1.関東地震隆起痕跡 2.津波堆積物露頭 3.完新世海岸段丘
日程: 9月9日(金)日帰り [プレ巡検]
定員(最少催行人数): 25(20)
案内者:宍倉正展(産総研)・鎌滝孝信(秋田大)
参加費:8,000円
必要な地図(1/2.5万):「館山」,「千倉」
集合・解散 : 東京駅 集合:8:30 解散:18:00
その他 :
大会前日に開催(プレ巡検).参加費に昼食代は含まれない.昼食は持参または近くの店舗で購入の予定.往路は集合場所の東京駅の後は館山駅に立ち寄る.帰路は館山駅に立ち寄った後に東京駅にて解散.
ページtopに戻る
新着情報(2016東京)
新着情報 2016東京・桜上水大会
2016.9.5更新 手荷物・無線LANについて
■■■
・手荷物について:会場内での手荷物のお預かりは致しません.参加者各自での管理をお願い致します.
・無線LANをご利用頂けます:会場内(3号館)では,無線LANを各自のパソコンでご利用頂けます.利用方法は,会場内に掲示します.
2016.9.5更新 確認書を発送しました(9/2(金))
■■■
東京・桜上水大会の事前参加登録をしたかた(参加費合計額が有料のかた)にあてて,確認書や記名済の名札,クーポン類(懇親会やお弁当を注文されたかたのみ)を発送いたしました(発送日:9/2(金)).年会当日の受付にて,【受付提出用】の書類を全員に提出していただきますので,忘れずにご持参ください.
なお,参加登録費の合計金額が0円のかたには別途メールでご案内をいたします.
【お願い】事前参加登録者が都合により年会への参加をキャンセルしたい場合には,必ず日本地質学会事務局までご一報ください(申込項目により取消料が異なります).
2016.8.19更新 講演キャンセル,発表者変更希望について
■■■
講演キャンセルをする場合は,必ず事前に行事委員会(会期前は学会事務局,会期中は学会本部)に連絡して下さい.
また,やむを得ない事情により,あらかじめ連記された共同発表者内で発表者の変更を希望する場合も,必ず事前に行事委員会(会期前は学会事務局,会期中は学会本部)に連絡して下さい.この場合も,シンポジウムおよびアウトリーチセッション以外の場合は「会員に限り1人1題(発表負担金を支払った場合は2題)」の制限を守るものとします.代理人の代読,会場内での突然の発表者変更,発表順序の変更は認めません.
会期前の連絡先:日本地質学会事務局
[at]を@マークにして送信して下さい.
2016.8.18更新 参加登録システムの不具合と復旧について:2
■■■
事前参加登録システムが復旧しました.17日夕刻より再度にシステムに不具合が生じ,申込手続きが出来ない状態になっていました.たびたびご迷惑をおかけし大変申し訳ありませんでした.(8/18,10:47現在)
2016.8.17更新 参加登録システムの不具合と復旧について
■■■
システム上の問題で,一時的に事前参加登録の申込画面がcloseしており,申込手続きが出来ない状態になっていました(停止期間8/15 24時〜8/17 10時頃)。至急担当者に確認し,8月17日10時現在,事前参加登録システムが復旧いたしました。事務局夏期休業(8/11-8/16)のため本日の対応となりました。会員の皆様には,ご迷惑をおかけし大変申し訳ありませんでした。
2016.6.15更新 宿泊予約について
■■■
近年学会を通じての宿泊手配は行っていません.各自でお手配をお願いします.また都内では外国人観光客増加なども起因して,一部では宿泊代金の高騰や空室不足などの現象も起こっているようです.できるだけ早めの宿泊予約をお勧め致します.
2016.6.15更新 事前参加登録および関連行事のWEB受付を開始しました.
■■■
本日15日より事前参加登録のWEB受付を開始します.それぞれ,オンライン入力フォームに従ってお申込下さい.
事前参加申込締切 8月18日(木)18時です. *郵送の場合は8月15日(月)必着
▶▶事前参加登録のお申込はこちらから
関連行事(教師巡検,家族巡検など)の各専用申込サイトもオープンもしました。
▶▶普及・関連行事のお申込はこちらから
2016.5.27更新 講演申込の受付,間もなく開始.5月30日(月)オープン
■■■
5月30日(月)より演題登録(講演申込)の受付を開始します.シンポジウム,セッションとも演題登録・要旨投稿はオンライン入力フォームに従ってお申込下さい.
締切 6月29日(水)18時です. *郵送の場合は6月23日(木)必着
講演申込・講演要旨投稿はこちらから
2016.5.27更新 優秀ポスター賞へのエントリー方法について
■■■
今大会から,優秀ポスター賞はエントリー制になりました(既報).
エントリーを希望する発表者は演題登録のオンライン入力フォーム内に優秀ポスター賞へのエントリーに関する選択欄を設けていますので,必ずエントリーするか・しないかを選択し,意思表示してください.
優秀ポスター賞へのエントリーも演題登録の締切日と同日とします.
■□■□講演申込(演題登録)受付期間■□■□
(優秀ポスター賞へのエントリー受付期間)
5月30日(月)〜6月29日(水)18時
*郵送の場合は6月23日(木)必着
2016.5.25更新 講演申込を予定しているが、まだ入会手続きをされていない方へ
■■■
至急、入会申込書を学会事務局宛に郵送して下さい(6月29日必着)。
WEB画面からの講演申込操作は入会申込中でも可能です。入力の際、会員番号欄は空欄のまま操作を進めて下さい。また会員種別欄では『入会申込中』を選択して下さい。
申込締切時点で入会申込書が到着していないと、申込が受理されませんので、必ず入会申込書を郵送して下さい。
2016.5.25更新 シンポジウム・セッション決定
■■■
シンポジウム,セッションが採択されました.まもなく講演申込,事前参加登録が開始予定です(5月末予定).皆様ぜひ長野大会へご参加下さい.
シンポジウム一覧はこちら セッション一覧はこちら
2016.1.19更新 トピックセッション募集(2016/3/14締切)
■■■
トピックセッション募集締切:2016年3月14日(月)*今大会もシンポジウムの一般公募は行いません。ご注意ください。
詳しくは、こちらから
2016.1.19更新 日本地質学会第123年学術大会(東京・桜上水大会)開催
■■■
日本地質学会は,関東支部の支援のもと東京都世田谷区の日本大学文理学部キャンパスにて,第123年学術大会(2016年東京・桜上水大会)を9月10日(土)から12日(月)に開催いたします.開催通知はこちらから
懇親会・お食事
懇親会
■事前参加申込はこちらから■
日時:9月10 日(土)18:00〜20:00
会場:日本大学文理学部3号館 1階
カフェテリア 秋桜(コスモス)
原則として予約制です(予約は8月18日に締め切りました).人数に余裕があれば当日参加の申込みも可能です会場受付で確認し,当日参加の申込みをしてください.その
場合の会費は,正会員・非会員(一般)6,000円です.名誉会員・50年会員・院生割引会費適用正会員・学部割引適用正会員および会員の家族は4,000円です.非会員の会費は正会員に準じます
準備の都合上,前金制の予約参加とします.たくさんの方々,特に院生・学生などの若手会員のご参加をお待ちしております.余裕があれば当日参加も可能ですが,予定数に達し次第締切ります.当日会費は1,000円高くなります.
事前予約会費
当日会費
正会員
5,000円
6,000円
名誉会員・50年会員・院生割引
学部割引・会員の家族
3,000円
4,000
*非会員の会費は会員に準じます.
*締切後の参加取消の場合は,会費の返却はいたしませんのでご了承下さい.詳しくは,取消料のページを参照.
お弁当予約販売と会期中のお食事
◯お弁当予約販売(予約申込は締切りました)予約弁当は日本大学文理学部3号館3F弁当配布コー
ナーで配布します.
○日大文理学部キャンパス近隣の飲食キャンパス正門を出て,右折,下高井戸駅への「日大通
り」に多数の飲食店・コンビニンエスストアがございます.こちらもご利用いただけます.
○ 会期中,文理学部3 号館1 Fの売店・食堂・軽食コーナー等は営業しておりません.
共催・協賛団体の一覧
2016東京・桜上水大会:巡検協賛およびセッション共催団体一覧
巡検協賛団体
セッション共催団体(セッション番号)
・資源地質学会
・石油技術協会
・地学団体研究会
・東京地学協会
・日本応用地質学会
・日本火山学会
・日本活断層学会
・日本鉱物科学会
・日本古生物学会
・日本自然災害学会
・日本堆積学会
・日本第四紀学会
・日本地学教育学会
・日本地球化学会
・日本地球惑星科学連合
・日本堆積学会(R8,R9,R10,R11)
・石油技術協会探鉱技術委員会
(R8,R9,R10,R11)
・日本有機地球化学会(R8,R9,R10,R11)
・日本原子力学会バックエンド部会(R23)
参加登録TOP画面に戻る
巡検申込状況
巡検申込状況
(8月8日 18時 締め切りました)
[申込締切] Web: 8/8(月)18:00、FAX/郵送: 8/5(金)必着(注)Iコースのみ 9/16(金)締切
【巡検コースの詳細はこちら】
班
コース名
定員(最小催行)
申込件数
A
丹沢衝突帯(9/13-14)
12(10)
12 (7/22 時点)
B
浅部付加体(9/13-15)
15(12)
10
C
葉山ー嶺岡帯(9/13-14)
20(15)
17
D
関東山地北縁部(9/13-14)
20(15)
13
E
秩父帯北帯(9/13-14)
22(18)
8
F
吾妻渓谷(9/13-14)
20(15)
9
G
伊豆南部(9/13-14)
20(12)
7
H
富士山(9/13-15)
25(20)
7
I
教師向け巡検(10/1)受付中
30
4
J
上総層群(9/9)
25(20)
20
K
関東地震(9/9)
25(20)
18
※定員に近い班は黄色マーカーで示しています.
※定員に達した班はピンク色マーカーで示しています.
◆参加申込人数が各巡検コースの最小催行人員に達しなかった場合,巡検を中止することがあります.
◆巡検協賛団体の会員の方は,会員同様にお申込を頂けます.それ以外の非会員の方は,申込締切時点で定員に余裕があれば参加可能となります.ご承知おき下さい.
◆ Iコース<教師向け巡検>は,小中高の教員ならびに一般市民を優先対象とします.
そのほか、巡検のお申込については,こちらをご確認ください.
関連行事申込状況
(8月25日現在.受付中)
【各行事の詳細・専用申込サイトはこちら】
実施日
コース名(申込締切日)
定員(最小催行)
申込件数
9/9
GISショートコース(受付終了)
20
20
9/11
サイエンスカフェ(8/31)
20人程度
7
9/11
家族巡検(8/31)
15(4)
7
9/13
防災施設見学(8/31)
15(5)
3
10/1
教師向け巡検(9/16)
30
6
その他の申込TOP
その他のお申込
■ ランチョン・夜間小集会
■ 小さなEarth Scientistのつどい〜第14回小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜(
■ 託児室の利用
■ 企業展示・書籍販売
■ 緊急展示
■ 若手会員のための地質関連企業研究サポート(旧称 若手会員のための業界研究サポート)
■ GISショートコース
■ 防災施設等見学「ゼロメートル地帯を守る:清澄水門管理事務所と扇橋閘門」
■ 家族巡検「等々力渓谷の地層と東京の大地の生い立ち」
■ サイエンスカフェ「海溝型巨大地震と津波の脅威 -地質・歴史記録に学ぶ自然災害-」
大会申込Q&A
大会申込Q&A
【演題登録編】 >>【参加登録編】へ
Q:1人何題まで発表できますか?
A:
トピック・レギュラーセッション(全33セッション)では,1人2題まで発表できます.ただし2題発表する場合には発表負担金(1,500円)をお支払い下さい(1題のみの場合は無料).また,同一セッション内で口頭2件やポスター2件の発表はできません.詳しくは,セッション発表の募集要領『2)発表に関する条件・制約』を参照してください.
Q:発表負担金はどこで支払えばよいですか?
A:
演題登録画面には課金システム機能はありません. 事前参加登録画面にトピックセッション(T1〜T9)・レギュラーセッション(R1〜R24)での発表件数を選択する項目があります.『2件(1,500円)』を選択いただければ,事前参加登録費とともに発表負担金も課金され請求されます.
※トピック・レギュラーセッションにて招待講演者になっている発表者が,もう1題を別セッション(または招待されているセッションと同一セッションの異なる発表形式)で一般発表する場合には,発表負担金(1,500円)は発生しません(招待講演分は発表負担金の発生する”2件目”としてカウントしません).
Q:非会員も演題登録(発表)はできますか?
A:
招待講演者を除き,非会員の発表はできません.現在,非会員のかたで東京大会において発表を予定されているかたは,演題登録に合わせて入会申込の手続きもしてください(締切時点で入会申込が確認できない場合,登録が取り消されます).セッション共催団体の会員は共催セッションのみ発表できますが,それ以外の他セッションで発表を希望する場合には,必ず入会手続きを行ってください.
Q:入会申込中(承認待ち)のため,会員番号(ID)もないのですが,演題登録はできますか?
A:
入会承認がまだのかたでも演題登録はできます.お早めに登録手続きしてください.会員区分の項目欄に『入会申込中』の選択項目がありますので,そちらを選択して登録してください.
Q:筆頭著者でなければ発表はできないのですか?
A:
筆頭著者でなくても発表は可能です(筆頭著者は会員・非会員を問いません).
ただし,発表者は地質学会の会員でなければなりません.
共同発表(複数の著者の発表)の場合には,講演要旨(pdf)に明記する著者名の
うち,発表者が分かるように発表者氏名に下線を引いてください.
※非会員が発表者になっている場合には,登録が取り消される場合があります.
Q:前回大会において急遽発表キャンセルをしてしまったため,今年の大会で同内容で発表したいのですが.演題登録してもいいですか?
A:
前回の学術大会にて発表を申し込まれた講演を講演要旨印刷後にキャンセルした場合,該当講演の要旨は印刷物として存在することになります.キャンセルした講演の要旨を再掲し,発表を希望する場合は,再掲する要旨に「本講演は第○○年学術大会にて発表をキャンセルしたもので,本講演要旨は第○○年学術大会講演要旨集に掲載されたものを再掲したものである」旨を明記してください.
詳しくは行事委員会から発表の『キャンセルした講演の講演要旨の扱いについて』を参照して下さい.
Q:演題登録画面のキーワードの入力ができません.
A:
キーワードを入力したい場合には,デフォルトで”0”件となっている入力欄に,ご自身が登録したいキーワードの数を半角数字で入力し,【件数変更】のボタンをクリックしてください.入力欄が下に表示されます.キーワードは最大10件まで登録できます.
※キーワードの入力は任意です(必須項目ではありません).
※『所属機関情報』や『著者情報』の件数・人数入力欄の増減も同様の操作で対応できます.
Q:演題登録画面の『著者情報』に21人以上の共著者を登録したいのですが.
A:
演題登録画面上では『著者情報』の入力は最大20件までしか登録できません.
21人以上登録したい場合には,演題登録時の受付番号(100〜ではじまる6桁の数字)と21人目〜の著者情報(氏名と所属先名:和英とも)を学会事務局に連絡してください.プログラム作成時に反映します.
Q:講演要旨がまだ出来上がっていないので,演題登録ができません.どうしたらいいですか?
A:
演題登録画面には”演題情報”のほかに,”連絡者情報(一度登録しておけば書き換える必要の無い項目)”の入力もあります.締め切り間際になってから全ての項目を登録しようとするのではなく,発表題目や共著者情報などはとりあえず”仮情報”で構いませんので,まず先に新規登録を行い〔受付番号〕と〔パスワード〕を取得してください.
〔受付番号〕と〔パスワード〕取得後は,【マイページ】へログインいただき,演題情報などを繰り返し修正していくことをおすすめします.
※締切(6/29日,18時)までには,完成原稿をアップロードしてください!!
Q:(演題登録締切後)講演要旨に誤りを見つけてしまったので,差し替えたいのですが.
A:
演題登録締切後,著者(発表者)の都合による要旨の差替え(演題内容の修正)依頼は受け付けません.
演題登録締切後,すぐにプログラムデータの整理・講演要旨の校閲作業を開始し,限られた時間の中で各世話人が要旨の校閲作業をしております.
修正原稿は,その都度校閲をしなければならなくなり,世話人の手間も増えることとなりますから,期日内にきちんと講演要旨を完成させ,登録を済ませていただきますよう,何卒ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします.
※要旨の校閲後に世話人から修正を求められた際,求められた箇所以外の修正をしてしまう著者(発表者)がまれにいますが,世話人に指摘された箇所のみを修正してください.
Q:演題登録の締切は延長されますか?
A:
昨年同様,演題登録の締切延長はありません.6月29日(水)18時締切厳守(郵送は6/23日(木)必着)です.余裕をもってお早めにご登録ください.
【参加登録編】
Q:講演要旨は付きますか?
A:
参加登録費が有料か無料かで異なります(詳しくはこちらもご覧下さい).
(a)参加登録費が有料のかたには,必ず講演要旨集が1冊付きます.
→正会員・院生割引会費適用正会員・非会員一般・非会員院生
(b)参加登録費が無料のかたには,講演要旨集は付きません.
→名誉会員・50年会員・学部割引会費適用正会員・非会員学部学生・
非会員招待者・同伴者(非会員で会員の家族に限る)
※(b)のかたが講演要旨を希望する場合は,別途ご購入ください.
事前参加登録の『追加講演要旨』の注文欄で【注文する】を選択し,
『冊数選択』欄と『受取方法』欄の項目も選択して,お申し込みください.
Q:地質学会会員が招待講演者になった場合,参加登録費はどうなりますか.
A:
学会員は参加登録費は有料です(免除にはなりません).必ず参加登録してください.
※シンポジウム,各セッションともに,参加登録費が免除になるのは,非会員招待講演者に限ります.
Q:講演要旨集の「後日発送」は,いつ頃送付されてきますか?
A:
大会会期終了後の発送です(別途送料がかかります).会期前の送付はできません.
Q:キャンセル料(取消料)はかかりますか?
A:
事前参加申込期間中の変更・キャンセルの場合は取消料はかかりません.締切後につきましては,申し込んだものにより,キャンセル料がそれぞれ異なりますのでご注意ください.
参加登録費:
申込締切後〜9/7日(大会3日前)60%,9/8日(大会2日前)以降100%
※後日,講演要旨をお送りします.
追加講演要旨:
申込締切後〜9/7日(大会3日前)60%,9/8日(大会2日前)以降100%
懇親会:申込締切後100%
弁当:申込締切後〜9/7日(大会3日前)50%,9/8日(大会2日前)以降100%
巡検:申込締切後〜9/7日(大会3日前)まで50%,9/8日(大会2日前)以降100%
Q:Web上で事前参加登録をしましたが,確認メールが届きません.
A:
入力したメールアドレスが間違っている可能性があります.学会事務局へ連絡してください.
Q:事前参加登録をしましたが,登録内容の修正の仕方が分かりません.
A:
事前参加登録の申込時に,①[初回申込]確認,②[ご請求]連絡の2通のメールが必ず自動返信されています(クレジット決済まで完了した人は③決済完了のお知らせメールも届きます).
[初回申込]確認メールの文中には,
・【変更・修正】および【取消】操作をおこなうための案内
・【変更・修正】および【取消】操作の画面にログインするためのURL
・ログインに必要な[お申込No.]と[パスワード]
が明記されております.説明をよく読んでお手続きください.
※できるだけ,一番最初に取得した[お申込No.]と[パスワード]で登録内容の【変更・修正】をしてください.何度も何度も新規でお申込すると,[お申込No.]と[パスワード]を登録した回数分取得することになり,重複申込者の確認漏れの原因にもなります.
Q:参加費無料の会員種別の人は,事前登録をしなくてもよいですか?
A:
当日の参加登録でも構いません.ただし,講演要旨の購入を希望される場合は,数に限りがあり,事前予約と当日購入では冊子体の価格が異なりますので,事前参加登録にてご予約することをおすすめします.ここ数年,大会会期中に講演要旨集の売り切れが続いておりますので,なるだけ事前にお申込みください.
Q:代理での申込はできますか?
A:
可能です.ただし,申込の重複や連絡先/発送先の登録には注意してください.とくに非会員招待講演者や外国人招待者などを代理で登録する場合は,代理で登録してくださるかたの連絡先を確認書やクーポンの送付先として登録してください(海外の住所では,確認書やクーポンの発送を,ご本人の手元に届くよう間に合わせることができません).また,登録時の確認メールは日本語のみです.
Q:巡検だけに参加したいのですが.
A:
地質学会会員は巡検だけに参加する場合でも,基本の参加登録費がかかります.事前参加登録【画面A】からお申込ください.
非会員のかたで,『巡検協賛学協会』のいずれかにご所属されているかたは,【画面B】からお申込みください.
Q:大会には参加しませんが,講演要旨だけの購入はできますか?
A:
講演要旨だけの予約購入も可能です.事前参加登録【画面C】からお申し込みください.ただし,講演要旨の発送は大会終了後になりますので,ご了承ください.
Q:Web登録がうまくできません。
A:
連絡先など,登録情報の自動取得が行えない場合はこちらを参考にしてください(自動取得は日本地質学会会員のみ利用できます).
正しく操作を行っているにも関わらず,エラーが出る場合は学会事務局へご連絡ください.
Q:クレジット決済ができません。
A:
タブレット(iPadやスマートフォンなど)で事前参加登録をした場合,クレジット決済はご利用できません(対応機種ではありません).クレジット決済をしたいかたは,PCをご利用ください.
Q:同伴者の欄に【大学の友人】や【職場の同僚】を登録してもいいですか?
A:
【大学の友人】や【職場の同僚】は同伴者にはなれません.それぞれ別個に参加登録してください.あくまでも,同伴者は【会員の家族】を想定しての申し込み欄です.なお,会員の家族でも夫婦や親子で地質学会会員の場合は,同伴者にはなれませんので,別個に会員として参加登録してください.
Q:私は地質学会会員(正会員)ですが,所属先の身分は大学院生なので【正[院生割引]会員】の会員種別で参加登録してもよいですか?
A:
大学院生でも正会員のかたは,【正会員】で参加登録してください.
【正[院生割引]会員】として参加登録できるのは,今年度にかかる割引会費申請者に限ります.申請を出さなかった会員(今年度の学会費が12,000円だった人)は【正会員】ですので,正会員の会員種別で参加登録してください.
※今年度の割引会費の申請は,今年の3月末で締め切りました.今から遡って申請することはできません.
Q:私は地質学会会員(正会員)ですが,セッション共催団体(または巡検協賛団体)では院生会員なので,そちらの会員種別で参加登録してもよいですか?
A:
地質学会会員のかたは,地質学会の会員種別で参加登録してください.
「セッション共催団体」や「巡検協賛団体」の会員種別でお申し込みできるのは,地質学会非会員のかたに限ります.
Q:事前参加登録をしたのに,確認書の参加費が当日払いの金額になって届きました.
A:
事前参加登録をしても,確認書を郵送する時点で参加登録費の入金が確認できなかった場合は,当日の参加登録費の金額で確認書を発行し,ご請求します.
所属先(会社や大学,研究所)からの公費払いの都合で,参加登録費の入金が遅くなる場合は,この限りではありませんが,必ず学会事務局に予めの連絡をしてください.
Q:昨年,確認書やクーポンが届きませんでした./大会終了後に受け取りました.
A:
確認書やクーポンは郵送でお送りします.申込の際,発送時期に確実に届く住所を記入・入力してください(所属先へ送付を希望される方は,とくにご注意ください).発送は大会10日前にはお手元に届くように発送する予定です.締切後に送付先変更を希望される場合は,学会事務局へご連絡ください.また,下記のような場合にも早めにご連絡ください.
例1)会社勤めのかた:大会直前まで出張(現場で野外調査)し,出張先から大会に参加するため,出張先(宿泊先)に確認書やクーポンを送ってほしい./直接大会会場で受け取りたい.
例2)大学職員・学生のかた:夏季休暇中は事務が閉まっていて,郵送物が届きにくい/届かない.
※東京・桜上水大会(2016年)からは,参加登録費の合計金額が有料のかたのみ確認書や名札等を郵送します.それ以外のかた(合計金額が0円で支払が発生しないかた)は,大会当日の受付で名札をお受け取り下さい.
Q:宿泊予約はできますか?
A:
参加申込システムからは宿泊予約はお受けしておりません.各自手配をお願いします.
Q:自分の疑問が解決する答えが載っていませんでした.
A:
ご不明な点がありましたら,学会事務局へご連絡ください.
ランチョン・夜間集会
ランチョン・夜間小集会
9/10ランチョン
9/11ランチョン
9/11夜間集会
9/12ランチョン
9/12夜間集会
ランチョン
昼休みの時間帯を利用した会合です.昼食の用意はありませんので,各自でご用意下さい(口頭会場内は飲食不可の場合があります.ご確認ください).都合により急遽会場が変更になる場合もありますので,会期中の掲示にご注意下さい.
9 月10日(土)12:45〜13:45
第4 会場(3303教室) 地質学雑誌face-to-face編集委員会(世話人:大藤 茂)
地質学雑誌の諸問題について改善をはかるためのface-toface意見交換.
9 月11日(日)12:00〜13:00
第1 会場(3305教室) 海洋地質部会(世話人:芦 寿一郎・小原泰彦・板木拓也)
海洋地質関連の研究機関における最近の研究動向と今後の調査の紹介を行い,各種情報を共有するとともに,海洋地質部会の活動について議論する.
第2 会場(3307教室) 構造地質部会若手の研究発表会(世話人:丹羽正和・平内健一・山本由弦)
構造地質部会若手の研究発表会をランチョンにおいて行います. 1 人20分程度で2 名を予定しています.
第3 会場(3308教室) 古生物部会(世話人:上松佐知子)
地質学会における古生物部会の活動について,直近の課題および今後の活動を報告・周知し,意見交換する機会としたい.
第4 会場(3303教室) 堆積地質部会(世話人:中条武司)
堆積地質部会の活動報告および国内外の堆積学に関する情報交換を行う.
第5 会場(3405教室) 文化地質学(世話人:鈴木寿志)
新特集号の原稿募集,現行科研費の進捗状況,新規科研費の応募,研究会立ち上げ等について話し合います.興味のある方,新規参加者どなたでも大歓迎.
第6 会場(3407教室) 岩石部会(世話人:桑谷 立)
岩石部会に関連した事項について,審議・報告を行う.その他にも,提案したり,連絡をすべき件があれば,ランチョンでの議題として取り上げる.
第8 会場(3403教室) 火山部会(世話人:及川輝樹)
火山部会の活動報告並びに今後の方針を決定する.
9 月12日(月)12:00〜13:00
第2 会場(3307教室) 構造地質部会定例会(世話人:丹羽正和・平内健一・山本由弦)
過去の活動報告,会計報告,今後の活動計画など.
第5 会場(3405教室) 現行地質過程部会(世話人:新井和乃)
現行地質過程部会の活動報告,年間予定などを話し合う.
第8 会場 地域地質部会・層序部会合同ランチョン(世話人:内野隆之・岡田 誠)
部会活動やセッションについての議論と情報交換
夜間小集会
都合により急遽会場が変更になる場合もありますので,会期中の掲示にご注意下さい.
9 月11日(土)18:00〜19:30
第1 会場(3305教室) 地殻ダイナミクス(世話人:竹下 徹)
新学術領域研究「地殻ダイナミクス」の研究内容の紹介と情報交換を行う.特に,本領域に直接関連されていない方の参加を歓迎する.
第2 会場(3307教室)沈み込み帯スロー地震・巨大地震(世話人:氏家恒太郎)
沈み込み帯におけるスロー地震・巨大地震を対象とした大型研究プロジェクトが複数立ち上がっている.各プロジェクトにおける最新の知見・動向を持ち寄り,意見交換を行うとともに今後の研究の方向性を議論する.
第3 会場(3308教室) 15th INTERRADに関する意見交換
(世話人:松岡 篤・鈴木紀毅・板木拓也・栗原敏之)
第15回INTERRAD(国際放散虫研究者協会)の日本開催(2017年10月22−27日)に向けて,準備状況を共有し,これからの取組について意見交換をおこないます.
第4 会場(3303教室) 「産官学の堆積学者の集い:明日の堆積学を担う若手研究者の育成プログラム」(世話人:高野 修)
昨今の堆積学研究者・履修者層の減少は,直近の人材不足のみならず,今後の学問分野としての継承にも重大な問題を残す可能性をはらんでいる.このような状況を鑑み,「産官学のより緊密な連携体制の構築」を1つの切り口として,問題解決に近づける方策を話し合う.
第5 会場(3405教室) 地質学史懇話会(世話人:会田信行)
東京の地質学史に関する講演2 題. 1 .古滝修三:房総地学会の歴史(仮題) 2 .会田信行:東京の地学遺産
第6 会場(3407教室) 南極地質研究委員会(世話人:外田智千)
・ 第57次南極地域観測隊(2015/16)中央ドロンイングモードランド調査報告
・ 第58次南極地域観測隊(2016/17)地質調査計画の概要
・ その他
第7 会場(3408教室) 環境地質部会夜間小集会(世話人:田村嘉之・風岡 修)
環境地質部会の事務連絡および報告,環境地質に関する講演等.
第8 会場(3403教室) 博物館の展示リニューアル:地学系展示で何をどのようにつたえていくか(世話人:川端清司・田口公則)
展示は博物館の顔であり,展示リニューアルは計画的に進めていく必要があります.この小集会では,既に展示リニューアルを行ったあるいは,現在リニューアル目前の博物館から話題提供いただき,そこから展示に関わる新しいスタンスを模索していきたいと思います.みなさまのご参加をお待ちしております.
3205教室 ジオ・アーケオロジー(世話人:渡辺正巳・松田順一郎・井上智博・趙 哲済・小倉徹也・別所秀高)
神奈川県を中心とする南関東地方の火山や地震災害の痕跡を調査していらっしゃる,上本進二(神奈川災害考古学研究所)さんに,『関東ローム層の遺跡特有の地震跡』として講演して頂きます.
9 月12日(日)18:00〜19:30
第2 会場(3307教室) 泥火山研究の最前線(世話人:井尻暁・浅田美穂・土岐知弘・森田澄人・辻 健)
泥火山研究の最新情報の交換を行う.それとともに昨年の地質学会,今年の連合大会の泥火山セッションでの講演内容をふまえた特集号を出す可能性についても議論する.
第3会場(3308教室) 静大地学同窓会(世話人:竹内真司・藤岡換太郎)
静岡大学の地学出身者は,旧制静高時代より大塚弥之助,松本達郎,杉村 新らを輩出し,現在でも各界で多くの研究者・教育者・技術者らが活躍している.静大OBの交流を深めるべく,同窓会設立のための会議を開催する.
第4 会場(3303教室) 炭酸塩堆積学に関する懇談会(世話人:柿崎喜宏・松田博貴)
炭酸塩堆積学に関する最近の話題・トピックスについて討論するとともに,最新研究動向・情報について意見交換を行う.
第7会場(3480教室) 第6回地質技術教育委員会(世話人:山本高司)
①地質系企業の採用状況,②フィールドマスター制度の進捗状況,③その他.
小,中,高校生徒「地学研究」発表会
小さなEarth Scientistのつどい
第14回小,中,高校生徒「地学研究」発表会
参加校募集
発表申込締切: 7/14(木)
会場風景
日本地質学会地学教育委員会では,地学普及行事の一環として,地学教育の普及と振興を図ることを目的として,学校における地学研究を紹介する「地学研究」 発表会をおこなっています.東京・桜上水大会でも,小・中・高等学校の地学クラブの活動,および授業の中で児童・生徒が行った研究の発表を募集いたしま す.都内,また関東地方の学校,さらには全国の学校の参加をお待ちしています.会場は研究者も発表するポスター会場内に,特設コーナーを用意いたします. 同時並行で研究者の発表も行われますので,児童・生徒同士のみならず,研究者との交流もできます.この会を通じて生徒,研究者,市民の交流が進み,地質 学,地球科学への理解が深まって,未来を担う生徒たちの学習意欲への良い刺激と励みになることを願っております.なお,参加証とともに,優秀な発表に対し ては審査のうえ,「優秀賞」などの賞を授与いたします.下記の要領にて参加校を募集します.
日 時
2016年9月11日(日)9:00〜15:30
場 所
東京・桜上水大会ポスター会場(日本大学文理学部3号館)キャンパス内)
参加対象
・小,中,高校地学クラブならびに理科クラブ等の活動成果の発表
・小,中,高校の授業における研究成果の発表
・活動,研究内容は地学的なもの(地質や気象などの地球科学・環境科学,天文など)
申込締切
7月14日(木),下記,日本地質学会地学教育委員会宛にお申し込み下さい.
発表形式
ポスター発表(展示パネルは,縦210cm×横120cm)パネルのほかに標本等を展示される場合には,パネルの前に机を用意します.参加申し込みの際 に,その旨を記載して下さい.その場合は展示パネルの下側が隠れる事をご了承下さい.発表者は決められた時間(および随時)パネルの前に待機し説明をして いただきます.なお,遠隔地および学校行事等のために児童・生徒が参加できない場合は,発表ポスターのみをお送りいただいても結構です.
参 加 費
無料(参加者・引率者とも),開催中の研究者の発表,講演も聴くことができます.
派遣依頼
参加者・引率者については学校長宛,日本地質学会より派遣依頼状を出します.
問い合わせ
・申込先
所定の書式をFAXまたはe-mailで下記宛にお送り下さい.
日本地質学会地学教育委員会(担当 三次)
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F
TEL:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156 e-mail:main@geosociety.jp
【参加申込書のダウンロード】 PDF版 word版
託児室
託児室
<利用申込締切: 8月19日(金)>
男女共同参画委員会では,ご家族で学会参加される会員の皆様に大会期間中にご利用いただける託児所のプランをご用意いたしました対象は,東京・桜上水大会参加者を保護者とする生後3ヶ月から6歳のお子様となります。
1.開設日時(予定):
9月10日(土)8:00〜20:00
9月11日(日)8:30〜20:00
9月12日(月)8:30〜20:00
2.対象:東京・桜上水大会参加者を保護者とする生後3ヶ月から6歳のお子様。
3.場所:わんぱくランド(予定)〒160-0021東京都新宿区歌舞伎町1-15-1吉本ビル2F
http://wanpaku-land1.com/
4.アクセス:西武新宿線・新宿駅を出て、靖国通りを東へ約1分
申 込:ご利用を希望の方はまず下記現地事務局までお問い合わせ下さい。託児所のご案内をお送りします。その後,利用者が直接託児所へ申込手続きを行って下さい。万が一の場合に備え,施設加入の損害保険で対応させていただきます。なお,託児施設のご利用に際しては東京・桜上水大会実行委員会・日本地質学会は責任を負いかねますのでご了承下さい。
問い合わせ・申込先:
日本地質学会第123年学術大会現地事務局(株式会社アカデミック・ブレインズ内)
〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1天満橋千代田ビル2号館10階
e-mail: gsj2016tokyo[at]academicbrains.jp(*[at]を@マークに変換して下さい)
TEL : 06-6949-8137(代表) FAX : 06-6949-8138
営業時間 : 月〜金曜日 10:00〜17:45
企業展示・書籍販売・広告募集
企業等団体展示/書籍販売
企業・団体・研究機関などによる展示
会場:3 号館3 F・4 F
・株式会社 地層科学研究所
・メイジテクノ株式会社
・株式会社建設技術研究所
・安井器械株式会社
・ライカマイクロシステムズ株式会社
・特定非営利活動法人 ジオプロジェクト新潟
・株式会社 パスコ
・株式会社 蒜山地質年代学研究所
・株式会社 テラ
・京都大学大学院理学研究科 活断層破砕帯評価プロジェクト
・高知コアセンター
・日本 地球掘削科学コンソーシアム(J-DESC)/海洋研究開発機構(JAMSTEC)
・石油資源開発株式会社
物品の展示販売コーナー
会場:3 号館3 F・4 F
・地学団体研究会
・共立出版株式会社
・株式会社 ニチカ
・株式会社 朝倉書店
・株式会社 古今書院
・株式会社愛智出版
・株式会社 ニュートリノ
・エルゼビア・ジャパン株式会社
・第四紀文献センター
・英文校正エナゴ/論文翻訳ユレイタス
・NSK出版
■ 展示会出展募集 ■ 書籍・販売ブースご利用の募集 ■ 広告協賛の募集
企業・研究機関等関係団体による展示会の出展募集
<申込締切 一次7月1日(金),最終8月5日(金)現地事務局扱い>
地質関係機関・関連企業のご活躍を広く地質学会員に紹介していただくため,会期中,企業展示会を開催致します.企業紹介・業務紹介・研究成果・新技術・特許などご自由に展示内容を構成いただけます.奮ってご出展のお申込をいただきますようお願い申し上げます.
【展示募集概要】
開催期間:搬入設営日9月9日(金),開催日9月10日(土)〜12日(月),搬出撤収日9月12日(月)※予定
開催場所:日本大学 文理学部キャンパス 3号館 ※予定
募集小間数:小小間20,パネル小間20※予定 複数小間のお申込も可能です.
小間仕様見本:
仕様詳細・オプション料金等につきましては,下記「展示募集要項申込書」をダウンロードの上,ご確認下さい.
5.出展料金:小小間 50,000円(消費税別),パネル小間 20,000円(消費税別)
※日本地質学会賛助会員は出展料金が無料となります.別途,現地事務局までご連絡下さい.
6.第1次募集締め切り日:7月1日(金)最終募集締め切り日:8月5日(金)
【出展申込方法】
下記「展示募集要項申込書」をダウンロードのうえ,必要事項をご記入の上,下記申込先(現地事務局)までお申込下さい.
〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1 天満橋千代田ビル2号館10F
日本地質学会第123 年学術大会現地事務局(株式会社 アカデミック・ブレインズ内)
TEL:06-6949-8137,FAX:06-6949-8138,e-mail:gsj2016tokyo@academicbrains.jp
担当:田中
営業時間 月〜金曜10:00〜17:45 土日・祝日休み
「展示募集要項申込書(pdfファイル)」
「展示募集要項申込書(docxファイル)」
△ページTOPに戻る
書籍・販売ブースご利用の募集
<申込締切 一次7月1日(金),最終8月5日(金)現地事務局扱い>
地質学関連の書籍・その他物品の販売にご利用いただくべく会期中ブースを設置致します.奮ってご出展のお申込をいただきますようお願い申し上げます.※見本展示のみでのご利用も可能です.
【書籍・販売ブース出展概要】
1,設置期間:9月10日(土)〜9月12日(月)
2,設置場所:日本大学 文理学部キャンパス 3号館 ※予定
3,募集ブース数:20ブース ※予定 複数ブースのお申込も可能です.
4,ブース仕様見本
※仕様詳細・オプション料金等につきましては,下記「展示募集要項申込書」をダウンロードの上,ご確認下さい.
5,出展料金:10,000円(消費税別)
6,第1次募集締め切り日:7月1日(金)最終締め切り日:8月5日(金)
【出展申込方法】
下記「展示募集要項申込書」をダウンロードのうえ,必要事項をご記入の上,下記申込先(現地事務局)までお申込下さい.
〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1 天満橋千代田ビル2号館10F
日本地質学会第123 年学術大会現地事務局(株式会社 アカデミック・ブレインズ内)
TEL:06-6949-8137,FAX:06-6949-8138,e-mail:gsj2016tokyo@academicbrains.jp
担当:田中
営業時間 月〜金曜10:00〜17:45 土日・祝日休み
「展示募集要項申込書(pdfファイル)」
「展示募集要項申込書(docxファイル)」
△ページTOPに戻る
講演要旨集,広告協賛の募集
<申込締切 8月5日(金)>
地質関係機関・関連企業のご活躍を広く地質学会員に広報いただくべく,大会開催にあわせ発行されます講演要旨集において,広告協賛を募集致します.企業紹介・業務紹介・研究成果・新技術・特許などの広報活動のご一環として,奮ってお申込をいただきますようお願い申し上げます.
【広告協賛料金】
講演要旨集:1頁 40,000円 1/2頁 20,000円 1/4頁 10,000円(すべて消費税別)
詳細は下記「広告協賛募集要項申込書」をダウンロードの上,ご確認下さい.
完全版下,データまたフィルムでの入稿をお願い致します.
【出展申込方法】
下記「広告協賛募集要項申込書」をダウンロードのうえ,必要事項をご記入の上,下記申込先(現地事務局)までお申込下さい.
お申込・お問合せ先
〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1 天満橋千代田ビル2号館10F
日本地質学会第123 年学術大会現地事務局(株式会社 アカデミック・ブレインズ内)
TEL:06-6949-8137,FAX:06-6949-8138,e-mail:gsj2016tokyo@academicbrains.jp
担当:田中
営業時間 月〜金曜10:00〜17:45 土日・祝日休み
「広告協賛募集要項申込書(pdfファイル)」
「広告協賛募集要項申込書(docxファイル)」
若手会員のための 業界研究サポート出展募集
若手会員のための地質関連企業研究サポート
「若手会員のための地質関連企業研究サポート」
(旧称 若手会員のための業界研究サポート)
地球科学系の
学生・大学教員の皆さんへ
企業研究サポートへ
ぜひ参加しませんか!!
チラシPDFをダウンロードできます
昨年までの「若手会員のための業界研究サポート」の名称を新たに「「若手会員のための地質関連企業研究サポート」として開催することになりました.本行事は,地質企業に興味のある学生・大学院生および指導にあたっている教員の方々を対象とし,地質企業の現状や求める人材について語り合う交流会を目的としています. 熊本地震,豪雨災害にも見舞われた今年,東日本大震災以来の国土強靱化の施策のもとに“防災・減災に対するハード・ソフト対策”と“戦後から高度成長期にかけて建設されたインフラの維持管理・更新”が一層重要なキーワードとなっております.この社会的要請に対して地質技術者が不足しており,その人材確保に企業の
皆様も苦労されていると思います.また,今後の日本のエネルギー政策として“地熱”・“地下資源”の開発が改めて注目を集めています.今年も,実際に企業で活躍されている地質技術者と語り合い,大学で学んだ地質学が企業でどのように生かされているのか,学生・大学院生および教員の方々が,企業の生の声を聴くことができるような場を提供したいと考えています.
日程:2016年9 月11日(日)14:00〜17:00(*時間帯は若干変更になる場合があります)
場所:日本大学文理学部3 号館4 階(3401-3402教室)
主催:一般社団法人日本地質学会
内容:各社ブースでの個別説明会(各社によるプレゼンテーションは行いません).会場内で休憩室にて参加企業の紹介用pptを上映します.
対象:東京・桜上水大会に参加する学生・院生および大学教員等の会員.日本大学等の学生・院生および教員等
出展予定企業(敬称略)
・石油資源開発株式会社
・株式会社 パスコ
・株式会社 建設技術研究所
・川崎地質株式会社
・中央開発株式会社
・三井石油開発株式会社
・株式会社 地圏総合コンサルタント
・株式会社地層科学研究所
・日本総合建設株式会社
問い合わせ先:
日本地質学会 担当理事 緒方信一/ 事務局 堀内昭子
電話:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156
緊急展示
緊急展示の申込について
申込締切:8月31日(水)
緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために,災害調査報告や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊急展示コーナー」を設けます.ポスター展示を希望する方は,8月31日(水)までに次の内容を下記申込先にご連絡ください.緊急展示は,正式な学会発表と同じく,コアタイムの時間帯が設けられす.優秀ポスター賞へのエントリーも可能です.また他の要旨と同様に大会後J-STAGE上で公開されます.発表における1人1題の制約は及びません.コアタイムの日程については著者希望を優先します(ただし既にセッションでポスター発表を予定されている場合は,同日でのコアタイムは設定できません).
1)発表要旨PDF(ニュース誌5月号参照)
2)緊急展示の必要性
3)発表代表者と連絡先
4)希望枚数(1枚:幅120×210 cm)
5)優秀ポスター賞へのエントリーの有無
6)コアタイムの日程希望など展示に関わる要望(2〜6の様式は自由)
実行委員会は行事委員会と協議し,可否の判断を致します.希望にはできるだけ応えるようにしますが,展示方法等については実行委員会の指示に従ってください.
申込先:
担当:亀高正男(行事委員会)ほか
日程・プログラム
全体日程・プログラム
9/9(金)
プレ巡検(日帰り),GISショートコース
9/10(土)
セッション発表(口頭,ポスター),一般公開シンポ(企業編)
ランチョン, 表彰式・記念講演会,懇親会
9/11(日)
セッション発表(口頭,ポスター)
一般公開シンポ(研究編)
若手会員のための地質関連企業研究サポート(旧:業界研究サポート)
生徒「地学研究」発表会
市民講演会,サイエンスカフェ,家族巡検
ランチョン/夜間小集会
9/12(月)
セッション発表(口頭,ポスター),国際シンポ
ランチョン/夜間小集会
9/13(火)〜15(木)
ポスト巡検(日帰り〜2泊3日),防災施設見学(13日午前)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
以下,クリックするとPDFファイルがダウンロードできます
■ 全体日程表(9/5更新) NEW
■ 各講演プログラム(9.5公開)NEW
9/10(土) 口頭発表 ・ ポスター発表
9/11(日) 口頭発表 ・ ポスター発表
9/12(月) 口頭発表 ・ ポスター発表
※講演キャンセル,プログラム一部変更のお知らせ---------------------------------------------
▶セッションのハイライト
▶シンポジウム一覧
▶セッション一覧
▶ランチョン・夜間集会一覧
各シンポ・セッション毎の講演プログラムがご覧いただけます
(注)一部演題情報は修正・変更される場合があります.
シンポジウム(2件)
S1.一般公開シンポジウム
S2.国際シンポジウム
トピックセッション(9件)
T1.活断層破砕帯の掘削
T2.日本海沿岸での津波堆積物
T3.グリーンタフ・ルネサンス
T4.表層型メタンハイドレート
T5.都市地盤の地質学
T6.日本列島構造発達史再考
T7.文化地質学
T8.極々表層堆積学
T9.付加体遠洋性堆積岩の研究
レギュラーセッション(24件)
R1.深成岩・火山岩
R2.岩石・鉱物・鉱床学一般
R3.噴火・火山発達史と噴出物
R4.変成岩とテクトニクス
R5.地域地質・地域層序・年代層序
R6.ジオパーク
R7.海洋地質
R8.堆積物(岩)の起源・組織・組成
R9.炭酸塩岩
R10.堆積過程・堆積環境:堆積地質
R11.石油・石炭地質と有機地球化学
R12.岩石・鉱物の変形と反応
R13.沈み込み帯・陸上付加体
R14.テクトニクス
R15.古生物
R16.ジュラ系+
R17.情報地質とその利活用
R18.環境地質
R19.応用地質・ノンテク構造
R20.地学教育・地学史
R21.第四紀地質
R22.地球史
R23.原子力と地質科学
R24.鉱物資源と地球物質循環
アウトリーチセッション
OR.アウトリーチセッション
会場
会場・交通
メイン会場:日本大学文理学部 3号館
(東京都世田谷区桜上水3−25−40)
※市民講演会・アウトリーチセッション・地質情報展・シンポジウム・懇親会も同館で行います.
※京王線下高井戸駅,桜上水駅下車 徒歩8分
(新宿駅からの乗車時間は約10分)
▷文理学部へのアクセスはこちら
3号館(講演会場)案内図は下記をクリックして下さい(PDF)
表彰式・記念講演会
会員顕彰式・各賞授与式・受賞記念講演
日程:9月10日(土)15:30〜17:30(予定)
会場:日本大学文理学部 百周年記念館(3号館より徒歩3分)
16:00〜16:10 会長挨拶,来賓挨拶(加藤直人日本大学文理学部長(予定))
15:40〜16:15 50年会員顕彰式,各賞授与式
16:15〜16:30 日本地質学会柵山雅則賞受賞スピーチ 野田博之会員
「構造地質学における概念的断層モデルの数理モデルとしての具体化に向けて」
16:30〜17:00 日本地質学会国際賞受賞講演 Roberto Compagnoni 氏(トリノ大学)
「Lithostatic pressure vs.tectonic overpressure: a geological conundrum?」
17:00〜17:30 日本地質学会賞受賞講演 荒井章司会員「マントル物質と地質学」
普及・関連行事
普及・関連行事
※日本地質学会学術大会に関する緊急時対応
■ 地質情報展2016とうきょう(9/10-12)
■ 市民講演会(9/11)
■ 教師向け巡検(10/1)★
■ 小さなEarth Scientistのつどい(9/11)
■ サイエンスカフェ(9/11)★
■ 家族巡検「等々力渓谷…」(9/11)★
■ 防災施設見学(9/13)★
■ GISショートコース(9/9)★
■ 若手会員のための地質関連企業研究サポート(9/11)
★印の申込状況はこちらから
※各行事の画像をクリックすると,大きな画像,またはPDFをダウンロードできます.
地質情報展2016とうきょう:首都をささえる大地のしくみ
▶▶情報展WEBサイトはこちら
日程:9月10日(土)〜12日(月)入場無料
9月10日(土)10:00〜17:00
9月11日(日)10:00〜17:00
9月12日(月)10:00〜16:00(時間はいずれも予定)
会場:日本大学文理学部3号館
主催:一般社団法人日本地質学会・産業技術総合研究所地質調査総合センター
内容:東京・桜上水大会に合わせ,東京都及び関東周辺の地質現象や都市地質、地震や火山についてパネル,映像,標本を使って展示・解説する「地質情報展2016とうきょう」を開催します.化石レプリカ作成などの体験学習コーナーなども用意し,実験や実演を通じて小学校入学前のお子さんからお年寄りまで,楽しみながら「地質」を皆さんにわかりやすく学んでいただけるイベントです.ぜひ,「地質情報展2016とうきょう」にご来場ください.
問い合せ先:産業技術総合研究所地質調査総合センター地質情報展企画運営事務局
TEL:029-861-3540
e-mail:johoten2016jimu-ml[at]aist.go.jp ▶▶情報展WEBサイトはこちら
ページトップに戻る
市民講演会「ジオハザードと都市の地質学」
日時:9月11日(日)14:00〜16:30 参加費無料・事前申込不要
画像をクリックすると PDF(A4版)1.2MB がダウがンロードできます
会場:日本大学文理学部3号館(東京都世田谷区桜上水3−25−40)
概要:首都圏の防災,減災のためには,コンクリートに覆われた地下の地質がどのようになっているのかを,元もとの地形を踏まえて知る必要があります.今回は,赤色立体地図を駆使して首都圏の地形・地質と都市の関係について市民に分かりやすく解説する講演と最近活動の活発化が注目されている火山に着目した講演とを行います.
講演予定:
「首都圏と火山」高橋正樹(日本大学文理学部教授)
首都圏においては,直下型地震をはじめ,地震災害に関する関心はある程度高まっているが,火山噴火については残念ながら理解が進んでいるとは言えない状況です.首都圏の場合,富士火山など西方の火山の噴火による降灰の影響が心配され,その影響は降雪をはるかに超えます.正しい理解がないと,首都機能の混乱,大規模な2次災害も予想されます.このようなことに備えるためにも火山噴火の正しい認識を市民の方々に持ってもらうことを目的とします.
「首都圏の地形地質の特徴」千葉達朗(㈱アジア航測)
土砂災害や洪水は,きわめて発生頻度が高い身近な問題です.これらは降水量が引き金になりますが,その場所の地形地質に左右されます.地震動の大きさや液状化も同様に地形地質の影響を大いに受けます.首都圏では,コンクリートの上で生活しているため,原地形と人工改変された地形,構造物との区別ができません.講演では首都圏の地形地質の特徴を演者の発明による赤色立体地図によって理解し,自分がどのような場所に住んでいるかを認識し,防災,減災に役立てていただくことを目的とします.
*講演会の前後には,アウトリーチセッション(研究成果を社会に発信する場として設けられたセッション)のポスター発表も行います.
[ORアウトリーチセッション]コアタイム(13:00〜14:00,16:30〜17:30;計2回)
*セッション名をクリックするとセッションの紹介をご覧いただけます。セッションの講演プログラムはこちらから
※ページトップに戻る
小さなEarth Scientistのつどい〜第14回 小,中,高校生徒「地学研究」発表会〜
*過去の発表会の様子や「優秀賞」受賞発表はこちらから
【参加予定校一覧(7/26現在)】
・群馬県立太田女子高校地学部
・横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校天文部岩石班
・東京都立府中高等学校地学部
・早稲田大学高等学院理科部地学班
・早稲田高校地学部
・東京学芸大学附属高等学校(3件)
・中央大学附属中学校・高等学校地学研究部
・駒場東邦中学高等学校地学部(3件)
・法政大学第二中学校科学部(2件)
・愛知教育大学附属岡崎中学校
・兵庫県立西脇高等学校地学部(3件)
・兵庫県立加古川東高等学校自然科学部地学班
・学校法人奈良学園奈良学園高等学校
・岡山理科大学附属高等学校
・鹿児島玉龍高等学校サイエンス部天文班(3件)
・熊本県立熊本西高等学校地学部
日本地質学会地学教育委員会では,地学普及行事の一環として,地学教育の普及と振興を図ることを目的として,学校における地学研究を紹介する「地学研究」発表会をおこなっています.東京・桜上水大会でも,小・中・高等学校の地学クラブの活動,および授業の中で児童・生徒が行った研究の発表を募集いたします.都内,また関東地方の学校,さらには全国の学校の参加をお待ちしています.会場は研究者も発表するポスター会場内に,特設コーナーを用意いたします.同時並行で研究者の発表も行われますので,児童・生徒同士のみならず,研究者との交流もできます.この会を通じて生徒,研究者,市民の交流が進み,地質学,地球科学への理解が深まって,未来を担う生徒たちの学習意欲への良い刺激と励みになることを願っております.なお,参加証とともに,優秀な発表に対しては審査のうえ,「優秀賞」などの賞を授与いたします.下記の要領にて参加校を募集します.
1)日時:2016年9月11日(日)9:00〜15:30
2)場所:東京・桜上水大会ポスター会場(日本大学文理学部3号館)
キャンパス内)
3)参加対象
・小,中,高校地学クラブならびに理科クラブ等の活動成果の発表
・小,中,高校の授業における研究成果の発表
・活動,研究内容は地学的なもの(地質や気象などの地球科学・環境科学,天文など)
4)参加申込締切:7月14日(木)(締切ました)
5)ポスター発表(展示パネルは,縦210cm×横120cm)パネルのほかに標本等を展示される場合には,パネルの前に机を用意します.参加申し込みの際に,その旨を記載して下さい.その場合は展示パネルの下側が隠れる事をご了承下さい.発表者は決められた時間(および随時)パネルの前に待機し説明をしていただきます.なお,遠隔地および学校行事等のために児童・生徒が参加できない場合は,発表ポスターのみをお送りいただいても結構です.
6)参加費 無料(参加者・引率者とも),開催中の研究者の発表,講演も聴くことができます.
7)派遣依頼 参加者・引率者については学校長宛,日本地質学会より派遣依頼状を出します.
8)問い合わせ・申込先:下記の所定の書式をFAXまたはe-mailでも下記宛にお送り下さい.
日本地質学会地学教育委員会(担当 三次)
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F
TEL:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156
e-mail:main@geosociety.jp
【参加申込書のダウンロード】 PDF版 word版
ページトップに戻る
教師向け巡検「千葉市の昔の海岸線を歩く」
日時:2016年10月1日(土) 9:30 JR稲毛海岸駅集合,15:00 JR幕張駅解散(予定)
参加対象:小中高の教員ならびに一般市民を優先
募集人数:30名(教員枠15名+一般枠15名)
参加費:1,000円(当日現地徴収)
申込等:巡検の申込および巡検コース一覧Iコースの欄をご参照下さい
(注意)会期とは異なる10月1日実施予定です.参加申込窓口および申込締切も他のコースとは異なります.申込締切:9月16日(金).
▶▶▶申込はこちらの専用申込サイトから
*過去の巡検の様子はこちらから
ページトップに戻る
サイエンスカフェ「海溝型巨大地震と津波の脅威 -地質・歴史記録に学ぶ自然災害-」
地質記録や歴史記録を読み解き,東日本周辺を中心に過去の海溝型巨大地震と津波について紹介します.
ゲストスピーカー:後藤和久(東北大学)
共催:下高井戸商店街振興会
日時:2016年9月11日(日)昼休み(予定)
場所:下高井戸コワーキングスペース iNVENTO(京王線下高井戸駅徒歩2分)
参加対象:一般市民優先
募集人数:20名程度
参加費:500円(+1ドリンク)
▶▶▶申込は専用申込サイトから(申込受付中)
申込締切:8月末(予定)
ページトップに戻る
家族巡検「等々力渓谷の地層と東京の大地の生い立ち」
今大会は、是非ご家族でお越しください。都内には見どころがたくさんありますが、等々力渓谷は東京の地下の様子を露頭で見られる貴重な場所です。なお、本巡検は2015年度街中ジオ散歩で訪れたコースをたどります。
巡検コース:等々力駅→等々力渓谷遊歩道→横穴古墳→等々力不動→丸子川→日本庭園→多摩川河川敷→野毛大塚古墳→等々力駅
主な見学対象:1.等々力渓谷(遊歩道:地層観察) 2.横穴古墳(TP火山灰) 3.等々力不動(不動の滝) 4.丸子川(六郷用水)5.日本庭園(昼食) 6.多摩川河川敷(石の観察) 7.野毛大塚古墳(帆立貝式古墳)
日程: 9月11日(日)(日帰り)
定員:15名(最少催行人数4名)
案内者:関東支部幹事 細矢 卓(中央開発)・田村糸子(首都大)
参加費:500円(当日現地徴収)
必要な地図(1/2.5万):東京西南部
集合・解散:10:00集合(東急大井町線等々力駅),15:00解散(東急大井町線等々力駅)
参加対象:会員の家族
▶▶▶申込はこちらの専用申込サイトから
申込締切:8月31日(水):締切りました。
ページトップに戻る
防災施設等見学「ゼロメートル地帯を守る:清澄水門管理事務所と扇橋閘門」
東京のゼロメートル地帯にも、多くの人が暮す街があります。その現状と管理施設を合わせて見学します。なお、本見学会は2014年度街中ジオ散歩で訪れたコースをたどります。
巡検コース:清澄水門管理事務所(排機場)→ゼロメートル地帯を歩き→扇橋閘門
主な見学対象:1.清澄水門管理事務所 2.清澄庭園 3.扇橋閘門
日程: 9月13日(火)(日帰り)
定員:15名(最少催行人数5名)
案内者:関東支部幹事 小田原 啓(神奈川温地研)・田村糸子(首都大)
参加費:1000円(保険料込み)(当日現地徴収)
必要な地図(1/2.5万):東京主部
集合と解散:集合9:30 大江戸線清澄白河駅改札 解散15:00 都営新宿線住吉駅
参加対象:会員
▶▶▶申込はこちらの専用申込サイトから
申込締切:8月31日(水):締切りました。
ページトップに戻る
GISショートコース
フリーオープンソースの地理情報システム(FOSS4G)であるQGISを使って,GISの基本操作と地形・地質モデリングの実習をします.実習終了後には,実習で作成した地図を見ながら神田川周辺のジオツアーを楽しみます.
日程: 9月9日(金)
場所:日本大学文理学部図書館棟メディア・ラボ
費用:3,000円
対象:GIS初学者
人数:20名
講師:木村克己(防災科研)
達成目標:GISの基礎概念と基礎操作法の理解,地形DEMを使った地形面モデルの表示・解析,三次元的な地形の可視化,観察地点・走向傾斜測定データの整理・表示,ポイントデータからグリッド補間,面モデルの処理,地形面・地層境界面の表示と断面図解析など.
内容予定:
9:45集合(日本大学文理学部3号館2階エレベーター前),QGISを用いた作図講習
15:00〜日本大学文理学部周辺の神田川周辺のジオツアー
17:00解散(京王線明大前駅)
参加者が準備するもの:ノートPC(指定するソフトウェアを予めインストールしておくこと)
*会場設備の都合で主催者側でPCを用意いたします。PCの持参は不要となります(2016.7.1訂正)
▶▶▶申込はこちらの専用申込サイトから
申込締切:8月31日(水):締切りました。
ページトップに戻る
若手会員のための地質関連企業研究サポート
地球科学系の
学生・大学教員の皆さんへ
企業研究サポートへ
ぜひ参加しませんか!!
チラシPDFをダウンロードできます
(旧称:若手会員のための業界研究サポート)
日 程 2016年9月11日(日)14:00-17:00(*時間帯は若干変更になる場合があります)
場 所 日本大学文理学部キャンパス(世田谷区桜上水)
主 催 一般社団法人日本地質学会
内 容 会場内の参加者休憩室等における参加各社作成PR用スライド上映.
参加各社の個別説明会(パネル,配布資料等をご用意ください).
なお,事前に頂いた上映スライドの1枚目は説明会での総合配布資料として利用させて頂きます.
対 象 東京・桜上水大会に参加する学生・院生および大学教官等の会員/関東近県の学生・院生および教官等
参加費(出展費) 無料
出展申込締切 8月10日(水)(必着)(出展の受付は締め切りました)
▶ 詳しくはこちら
▶ 2015年長野大会の様子はこちらから
申込先・締切一覧
各種申込先・締切一覧
*それぞれの項目をクリックすると詳細画面へ遷移します
オンライン(WEB)
FAX・郵送
申込先
講演に関わる項目
講演申込
(演題登録)
6月29日(水)18時
6月23日(木)必着
行事委員会/
講演申込システム
講演要旨原稿提出
6月29日(水)18時
6月23日(木)必着
行事委員会/
講演申込システム
参加登録に関わる項目
大会参加登録
8月18日(木)18時
締切延長:8/19(金)10時
8月15日(月)必着
学会事務局/
参加申込システム
懇親会,弁当
8月18日(木)18時
締切延長:8/19(金)10時
8月15日(月)必着
学会事務局/
参加申込システム
追加講演要旨
8月18日(木)18時
締切延長:8/19(金)10時
8月15日(月)必着
学会事務局/
参加申込システム
巡 検
8月 8日(月)18時
8月 5日(金)必着
学会事務局/
参加申込システム
その他の項目
教師向け巡検
9 月16日(金)18時
---
学会事務局/
専用申込フォーム
家族巡検,
防災施設見学,
GISショートコース
8月31日(水)18時
---
学会事務局/
各専用申込フォーム
サイエンスカフェ
8月31日(水)
---
学会事務局/
専用申込フォーム
締切
申込先
託児室
8月19日(金)
---
現地事務局
(アカデミック・ブレインズ)
生徒「地学研究」発表会
(小さなESのつどい)
7月14日(木)
---
地学教育委員会
ランチョン
夜間小集会
6月29日(木)
---
行事委員会
若手会員のための
地質関連企業研究サポート
(企業出展)
8月10日(水)
---
学会事務局担当
一次締切
最終締切
申込先
広告協賛
---
8月5日(金)18時
現地事務局
(アカデミック・ブレインズ)
企業展示への出展
7月1日(金)18時
8月5日(金)18時
現地事務局
(アカデミック・ブレインズ)
書籍・販売ブース
7月1日(金)18時
8月5日(金)18時
現地事務局
(アカデミック・ブレインズ)
LOC・問い合わせ先一覧
大会実行委員会・問い合わせ先一覧
(注) [at]を@マークに変換して下さい
大会期間中(9/10-9/12)の問い合わせ先
日本地質学会第123年学術大会現地事務局(担当:田中・豊澤)
電話:080-5363-8921,9048
e-mail:gsj2016tokyo[at]academicbrains.jp
実行委員会
委員長:高橋正樹(takahashi.masaki[at]nihonu.ac.jp)
関東支部長:有馬 眞(tigerbay2007[at]yahoo.co.jp)
事務局長:笠間友博(TEL:0465-21-1515,kasama[at]nh.kanagawa-museum.jp)
巡検:大坪 誠(TEL:029-849-1098,otsubo-m[at]aist.go.jp)
巡検案内書:亀尾浩司(TEL:043-290-2802,kameo[at]faculty.chiba-u.jp)
男女共同参画企(託児室):現地事務局(担当:田中・寺西)
現地事務局((株)アカデミック・ブレインズ(内))担当:田中・寺西
TEL:06-6949-8137,FAX:06-6949-8138,
e-mail:gsj2016tokyo[at]academicbrains.jp
問い合わせ先一覧
(1)日本地質学会行事委員会・地学教育委員会・学会事務局
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル6F
TEL:03-5823-1150 FAX:03-5823-1156
e-mail:main[at]geosociety.jp
日本地質学会行事委員会(2016年5月末現在)
委員長
岡田 誠(担当理事)
委 員
内野 隆之(地域地質部会)
上澤 真平(火山部会)
桑谷 立(岩石部会)
野々垣 進(情報地質部会)
田村 嘉之(環境地質部会)
亀高 正男(応用地質部会)
田村 糸子(地学教育委員会)
竹下 欣宏(第四紀地質部会)
岡田 誠(層序部会)
板木 拓也(海洋地質部会)
中条 武司(堆積地質部会)
辻 健(現行地質過程部会)
千代延 仁子(石油石炭関係)
山本 由弦(構造地質部会)
上松 佐知子(古生物部会)
黒田 潤一郎(環境変動史部会)
吉田 英一(地質環境長期安定性研究委員会)
中村 謙太郎(鉱物資源部会)
(2)日本地質学会第123年学術大会 現地事務局(株式会社アカデミックブレインズ(内))
〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1天満橋千代田ビル2号館10F
TEL:06-6949-8137,FAX:06-6949-8138
e-mail:gsj2016tokyo@academicbrains.jp
担当:田中・寺西
営業時間 月〜金 10:00〜17:45(土日・祝日休み)
開催挨拶
開催挨拶
4月に発生した熊本地震により被害を受けられた皆様に,心からお見舞い申し上げます.
日本地質学会は,「出番ですぜ!江戸前地質学」をキャッチフレーズに,関東支部を中心に,東京都世田谷区桜上水の日本大学文理学部キャンパスを会場として,第123年学術大会(2016年東京桜上水大会)を9月10日(土)から12日(月)に開催いたします.
大都会である首都東京は地質学とは無縁であるかのような印象を受けるかもしれません.しかし,関東平野の南部に位置し,フィリピン海プレートの沈み込み境界である相模トラフにも近い東京は,実は第1級の変動帯に位置しており,1923年の関東地震を初め,多くの大規模な地震災害に繰り返し見舞われてきました.2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震の際にも,長周期地震や地層の液状化によって林立する高層建築に被害が出ました.こうした地震災害には,地盤の地質が大きな影響を与えます.東京の地下に伏在する活断層の問題も重要です.東京の下町では地盤沈下があり,これは地震時に発生する津波災害にも関係してきます.また,天井川の存在は大規模な都市洪水をもたらす危険があります.東京の山手では,集中豪雨時の小規模河川の洪水や,斜面崩壊なども問題です.これらの自然災害は,何れも東京の地質・地形と密接に関係しています.実は,東京ほど地質学を必要としている場所はないのです.まさに,「出番ですぜ!(江戸弁)江戸前地質学」です.
本大会では「ジオハザードと都市地質学」をメインテーマに,社会に役立つ地質学,社会から必要とされる地質学を中心に,わが国の地質学の様々な分野における最新の学術的到達点を示したいと考えています.みなさん,東京の桜上水に集まり,大いに議論し,親交を深めましょう.多くの方々の御参集をお待ちしております.
巡検コースも多様な地質現象を対象としたコースを用意しています.こちらにも,多くの方のご参加をお待ちしております
各種申込は,従来と同様の参加登録システムを利用します.お支払いは銀行振込またはクレジットカードによる支払いが可能です.発表についても演題登録システム(PASREG)を利用したオンライン登録が可能です.なお,大会準備がスムーズに運ぶよう,締切日の厳守をお願いいたします.
2016年5月
一般社団法人日本地質学会
第123年学術大会実行委員会
若手会員のための業界研究サポート:2015長野報告
若手会員のための業界研究サポート:報告
▶2016(東京・桜上水大会)出展募集に戻る
若手会員のための業界研究サポート(2015長野大会 報告)
今年は阪神淡路大震災から20年,東日本大震災から4年の年になり,“防災”や“環境”に関して重要な理学である地質学に対して社会的要請が一層強くなった年であった.また,今後の日本のエネルギー政策として“地熱”・“地下資源”も注目を集めている.地質学会では,実際に企業で活躍されている地質技術者と語り合い,大学で学んだ地質学が企業でどのように生かされているのか,学生・大学院生および教員の方々が,企業の生の声を聴くことができるような場を提供したいと考え,今年も本企画を開催した.今回は9回目で,経団連の「採用選考に関する指針」を踏まえて行っている.例年と同様に,大会2日目の午後2時半から5時まで行い,昨年より更に多い民間企業12社にご参加頂いた.
今年の会場は,学術大会第1会場と同じ建屋の3階で参加しやすい場所であったが,出展企業紹介会場や関連書籍資料販売会場を経た最奥のやや不利な会場条件であった.会場が狭いこともあり,プレゼンは行わず,休憩室にプロジェクタを設置し参加企業の説明スライドを上映する,当日午後から会員が集まる場所での呼び込みを行うなどのPRを行った.その甲斐あってか,昨年度よりも10人以上多い40人に及ぶの学生・院生の方々が参加し,企業の個別ブースで業界のこと,業界での技術者としての活躍を熱心に聞く姿が見られた.ただ今年も学生・院生を預かる教員の方々の参加がなく残念であった.大学関係者向けには事前のポスター配布によるPRも行ったが,結果論となるがタイトルの「若手会員のための」が教員の方々に誤った理解を与えたかも知れないと感じている.今後は,今回できなかった参加企業毎の直接のプレゼンも含めて,改善して臨みたいと考えている.来年度も,就職希望の学生・院生の皆様,教員の皆様には,ぜひ会場に足を運んでいただき,企業での地質技術者の活躍の様子について大いに情報収集していただくようお願いいたします.
最後に,本行事に参加いただいた企業12社の皆様,企画にご協力いただいた賛助会員,関連企業の皆様,および大会準備委員会,行事委員各位に,改めて御礼申し上げます.
(担当理事 緒方信一)
参加企業・団体一覧(業界別50音順)
[資源エネルギー関係]
石油資源開発株式会社(東京)
日鉄鉱業株式会社(東京)三井石油開発株式会社(東京)
[建設コンサルタント関係]
有限会社アルプス調査所(安曇野市)
株式会社サクセン(松本市)
日本綜合建設株式会社(長野市)
応用地質株式会社(東京)
川崎地質株式会社(東京)
株式会社建設技術研究所(東京)
株式会社地圏総合コンサルタント(東京)
中央開発株式会社(東京)
株式会社日さく(東京)
▶2016(東京・桜上水大会)出展募集に戻る
予告
予告
第124年学術大会(2017年松山大会)
日程:2017年9月16日(土)〜18日(月)
会場:愛媛大学理学部ほか(松山市文京)
(注)松山市内では同期間中に医学系など他学会の開催が予定されています.宿泊予約が混み合うことが予想されますので,早めの宿泊予約をお勧め致します(近年学会を通じての宿泊手配は行っていません.各自でお手配をお願いします).
キャンセル・プログラム変更
キャンセル・プログラム変更
講演キャンセルをする場合は,必ず事前に行事委員会(会期前は学会事務局,会期中は学会本部)に連絡して下さい.
また,やむを得ない事情により,あらかじめ連記された共同発表者内で発表者の変更を希望する場合も,必ず事前に行事委員会(会期前は 学会事務局,会期中は学会本部)に連絡して下さい.この場合も,シンポジウムおよびアウトリーチセッション以外の場合は「会員に限り1人1題(発表負担金 を支払った場合は2題)」の制限を守るものとします.代理人の代読,会場内での突然の発表者変更,発表順序の変更は認めません.
会期前の連絡先:日本地質学会事務局 [at]を@マークにして送信して下さい.
講演キャンセル
◆T2-P-2:高清水康博ほか「日本海東縁変動帯に位置する飛島の完新世段丘中に挟在する古津波堆積物
◆T3-O-7:澤畑優理恵「棚倉断層沿いに発達するstrike-slip basinを埋積する新第三系の古地磁気学的研究」
◆R1-O-3:大和田正明「西南日本,白亜紀火成活動の形成年代と組成変化」
訂正・変更(演者交代など)
◆プログラム:発表者訂正
(誤)狩野彰宏
(正)加藤大和
R9-O-3:加藤大和「炭酸凝集同位体温度計の実態と陸域炭酸塩岩への適用」
会場での注意点
会場での注意点
■発表終了時には拍手をお願いします
1 題の口頭発表はわずか15分で終了します(セッションの場合).しかし,その発表の裏には,発表者の弛まぬ努力と,研究や発表準備に費やした多くの時間があるはずです.講演終了時には,惜しみない拍手をお願いします.
■無断で撮影をしてはいけません!
口頭発表・ポスター発表を,発表者に無断で写真撮影・ビデオ撮影してはいけません.撮影には発表者の許可が必要です.また,それらを発表者の許可なく,SNS等で配信もしてはいけません.
■軽装でお出かけ下さい
8 月中旬現在,関東地区の電力供給は逼迫した状況ではありませんが,不測の事態で急な節電要求がある可能性も考えられます.残暑厳しい時期,大会参加の皆様には軽装でお出かけ下さい.ご理解,ご協力をお願いします.
CPD単位取得
CPD単位取得について
地質技術者の皆さん 学術大会でCPD単位が取得出来ます
日本地質学会は,地質技術者への継続教育の一環として,大会参加者・発表者・巡検参加者へCPD単位を発行します.大会参加と口頭/ポスター発表の参加証明書は,参加日の15時以降に「CPD受付」(3階総合受付付近)においてお渡しします.また,巡検参加者については各コースにおいて案内者よりお渡しすることになります.
【CPD単位】
・ 学術大会参加に対するCPD(時間に応じて):例)7時間出席 = 7単位
・ 口頭発表に対するCPD:0.4 ×15分発表 = 6単位
・ ポスター発表に対するCPD:2単位
・ 巡検参加に対するCPD:日帰り-8単位,1泊2日-16単位
日本地質学会は,土質・地質技術者生涯学習協議会ジオ・スクーリングネット(GEO・Net:https://www.geo-schooling.jp/) に加入し,地質技術者の継続教育(CPD)に携わっています.大会への参加だけでなく,講演や巡検の参加についてもそれぞれ単位が取得出来ます.また GEO・Netに掲載されている協議会加盟団体のイベント情報についても同様に検索・参加申込などが出来ます(参加の場合は,もちろんCPD単位が取得出 来ます).積極的にご登録頂き,GEO・Netをご活用下さい.
また,各支部で主催する講演会や巡検等各種イベントについても,随時本サイトに掲載し,GEO・Net登録者にご参加いただけるようにしていきたいと思います.
技術者継続教育,CPD単位については,下記をご参照ください。
http://www.geosociety.jp/engineer/content0003.html
(地質技術者教育委員会 山本高司)