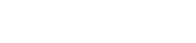地球なんでもQ&A
ログイン
MAIN MENU
日本地質学会初代会長神保小虎小伝
石渡 明(東北大学東北アジア研究センター)
 |
| 神保小虎の遺影(佐藤, 1924a) |
筆者は日本地質学会会長の任期を終えるに当たり、初代会長神保(じんぼ)小虎(ことら)(1867-1924)の小伝を記してその心意気を会員諸兄諸姉に伝え、本学会の今後の発展の一助としたい。文中敬称を略す失礼をお許し願いたい。
話を始めるに当たり、まず日本地質学会の会長職の歴史について述べる。本学会は1893年5月に創立され(1934年までは東京地質学会と称した)、現在も続く月刊の地質学雑誌は1893年10月に創刊された(当初は各巻の第1号は10月発行だったが、1898年の第6巻から1月に第1号を発行)。しかし、草創期の本学会には会長職がなく、学生の幹事2名が会務を担当していた。つまり創立当初の本学会は東大地質教室のゼミのようなもので、会費は月10銭(現在の1500円程度)、毎月第3土曜の午後1時から会員が同教室に集まり、「学術上の叢談及び会務の報告」を行っていた。1900年には幹事の他に編集委員3名が設けられた。1905年に会則が変更されて神保小虎が会長になり、彼はこの年に「本邦に於ける地質学の歴史」(地質雑, 12, 393-405)を発表したが、1907年には「会長制を廃し、評議員20名をおき、うち2名を幹事とする」(60周年記念誌年表)ことになった。会長制が復活するのは1913年で、再び神保小虎が選ばれた。現在の日本地質学会の歴代会長表(2013年会員名簿p.34)の最初は1913年だが、1905年が最初だとしても(60周年記念誌)、やはり神保小虎が本学会の初代会長である。彼は1916年も会長になり、都合3回本学会の会長を務めた。この頃の会長の任期は1年だったが、1951年から2年になり、1978年からは副会長が設けられた。こういう経緯なので、初代会長と言っても創立時の会長ではなく、その20年後の会長である。そして筆者は第60代、50人目の会長ということになる。
筆者の前著(News誌17(3), 4-5 (2014)/ geo-flash No.250)でも触れたように、神保小虎は幕臣の家の出で、慶応3年に江戸で生まれ、1887年に東京大学理学部地質学科を卒業した。卒業後北海道庁の技師として道内の地質調査を行い、この間に貯めた金で1892年にドイツへ留学し、古生物学を専攻したが、東大の鉱物学の助教授(菊池安)が急逝したため、専攻を変更して速成の鉱物学者になった。1894年にまだ全線開通前だったシベリア鉄道を乗り継いで帰国し、途中アムール川流域の地質調査を行った。翌年東京大学の鉱物学の助教授、1896年教授になった。1904年の日露戦争で日本が勝利し、樺太(サハリン)の南部を日本が領有することになった時、志賀重昂(拙著、News誌16(10), 8-9 (2013)/ geo-flash No.227)とともに国境画定委員附に任ぜられ、同島の北緯50度線付近の調査を行った(中里重次, 1932; 燃料協会誌, 11(121), 1452-1461)。その前後に遼東半島やウラジオストク地域の調査も行っている。神保小虎の生い立ち、略歴、著作、人物などについては浜崎健児(2011, 地質学史懇話会報36号)がよくまとめており、北海道調査を中心とする業績と文献については松田義章(2010, 同34, 35号)が詳しい。佐藤博之(1983, 地質ニュース346号)は白野夏雲や坂(ばん)市太郎と神保小虎の関わり、特にライマンの評価に関する神保・坂論争を扱っている。神保は定年前に56歳で病没し、佐藤伝蔵が追悼文を献じた(1924a; 地質雑, 30, 図版15, 1924b; 地学雑, 36(421), 179-182)。そこでは北海道の地質構造論と白亜系生層序、日本産鉱物の記載が神保の最も主要な業績とされている。小伝ではなるべくこれらとの重複を避け、雑誌や著書に表れた神保小虎の学問と人となりを中心に述べる。
神保小虎は多くの地質学・鉱物学の書籍を執筆出版したが、現在でも復刻販売されている彼の著書に「アイヌ語会話字典」(北海道出版企画センター1986年再版)がある。これは金澤庄三郎と共著の1892年初版の本であり、旅行や生活の場面や事柄ごとに日本語の会話文に対応するアイヌ語をローマ字で示したものである(例えば「この旦那を知って居るか=Tan nishpa eraman?」)。彼は英、独、仏、露、西語に堪能で、北海道調査の中でアイヌ語も習得し、アイヌ語の地名がその土地の地形や地質をよく表していることを見出し、アイヌの人々に「神保ニシパはアイヌなり」と言わしめたという(佐藤, 1924b)。この一事を見ても神保小虎の類稀な幅広い才能と縦横無尽の活躍が伺える。
神保は学生の指導や地質学の一般人への教育・普及に熱心だった反面、敵・味方がはっきりしていて、敵には容赦ない論争を挑む性癖があった。有名なのはライマンの評価に関する上述の1890年の神保・坂論争(地学雑, 2, 7-11, 53-54, 147-148)で、「私が書いた事がお解りに成りませんければもう一度お読みなさい別にお返事は致しません」という返答の冒頭の一文は今でも語り草である。1912年にも鉱物学の教科書を批判し、その著者の和田八重造が反論した(地質雑, 19, 163-164, 240-249)。神保は「「文部省の教授要目説明書」とも称すべき本書には地質鉱物及び土壌を真に学習せる人が恐らくほとんど一人も賛成しがたき順序をそのままに採用し在り」、「大害無き代りに小益も無かるべし」などと批判して、「この篤学の著者が文部省に代りてその要目の趣意を明らかにしたるは大いに教育家の参考となるべきものにして、その「利害」を明らかにしたる功は没すべからず」と1ページ強の書評を結んでいる。これに対し和田は10ページの反論をなし、最後に「教育上の考の相違から来て居るのであるから遺憾ながら毫も敬服出来ない」と怒りをぶつけている。地質学雑誌における神保の執筆記事は多数あるが、地すべりの調査報告など応用地質関係の雑録・雑報や内外の教科書の解題(書評)が多く、原著論文は案外少ない。ただし、ロシア語の文献紹介や直接会見したロシア人地質学者から聞き書きしたサハリン、シベリアなどの地質に関する記事は貴重である。また、変わったところでは、当時までに落下・発見された国内の隕石についてのレビューを書いている(地質雑, 12, 229-234, 309-317 (1905))。
ここでは、神保の数多い著書の中から、いかにも初代会長にふさわしいタイトルの「日本地質学」(金港堂, 245ページ+索引)を紹介する。この本は1896年初版だが、筆者が読んだのは1916年の再版である。まず巻頭に折り込みの日本地質図(地域割が県界でなく旧国界、阿武隈・飛騨片麻岩や三波川結晶片岩が「太古統」)を掲げ、総論の最初に地質学の目的として、「ただに地の質を学ぶものにあらざるなり。畑の土を記するにあらざるなり。単に地球の諸性を説くにあらずして、その始めより今日に至るまでの発育をもってその最上の主眼となすものなり」と述べている。そのあと、「地質学の応用ならびに日本における地質調査」を詳述し、関連学会や学術誌を列挙しているが、この総論はどう見ても初学者向きではない。本編は1.地殻の察相、2.岩石、3.地殻の変動、4.岩石の生源、5.岩石の配置(地殻構造)、6.地史の各篇に分かれ、附録として地質巡検規則と修学旅行の設計、上野帝国博物館鉱物地質の部案内がある。日本の実例を重視し、前著「新編地質学」ではベスビオス火山の噴火やリスボン地震の例を用いたが、本書では磐梯山・浅間山の噴火や濃尾地震について詳しく解説している。地質巡検(調査)規則では、「地質巡検なるものは徒(いたずら)に杖(つえ)を曳(ひ)き飄然(ひょうぜん)として千歳(せんざい)の古跡を探り或は名勝を尋(たず)ぬるが如きものにあらずして」、「(岩石、化石、鉱脈などを実検して)土地の構造ならびに地盤の変遷の歴史を尋ぬるを以て地質巡検の業とす」と述べている。「記録に関する注意」として、「己れは記憶善(よ)き者と誤認してその筆記を粗(おろそか)にするは最も避くべき事にして如何なる瑣事(さじ)も見たるとき直に之を筆記し後に磨滅等にて不明とならざる様注意すべし」、「夕飯後想起して記録する時は既に誤りを生じ易し」、「午前と午後、坂路の上下に由りて観察に精粗あるを免れず」、「自己の観察は多少不完全なれば必ず多くの図書を参考し」、「その地方の人に就き事実を聞き取るを要す。然れども一々これを信ずべからず。ただ淡泊に聞き天然に発言せしめてその真を得るを務むべし」など、長年の野外調査の経験に基づく勘所を述べている。修学旅行(巡検)案内は、東京上野から上越線に乗り深谷で下車し、秩父、下仁田を経て妙義山まで関東山地を歩き、信越線松井田駅から汽車で上野に帰る11日間のコースと、山口県の防府市三田尻港から山口、厚狭を経て下関に至る1週間のコースを説明している(なぜか秋吉台には行かない)。これらは実際に学生と巡検したコースだと思われ、例えば関東コースの第1日は「上野停車場を出発す。汽車は第四紀洪積世に属するローム(loam)の丘陵に沿うて進む。王子の断崖にてその第三紀層を被覆するを目撃すべし」で始まる。「(蛇紋岩の)破片は非常に鋭きを以て鉄鎚を加うるの際往々手を切ることあり」とか、「砂岩は通例不規則に割れて走向と傾きを測ること極めて難し。シェールもまた然り。注意すべし」といった学生への細かい注意書きが随所に見られる。本書に記述された事実や理論には既に通用しないものがあるが、野外地質学の優れた先達の言葉として今でも味読すべき部分が多い教科書である。
「先生は六尺豊かの体躯の持主で語学に堪能であられ、反面ユウモラスで又温情の持主であった」(江原真伍, 60周年記念誌)。筆者はこの初代会長をもった本学会を誇りとする。佐藤(1924b)の追悼文に掲載された漢詩を読み下し文で再録し、この小伝を結ぶ。
恭(つつし)んで神保理学博士を悼(いた)む 二首 犀東国府種徳
全球を踏み尽くして地層を析(ときひら)く
君に馮(よ)りて奇勝は盛名を昇らす
何ぞ仙境を尋ね 天を排(おしのけ)て去る
旧識の千山 哭して崩れんと欲す
健(けん)歩(ぽ)人を驚かして通らざる莫(な)く
畢生(ひっせい)険しき夷(えびす)の空を跟底(くつぞこ)とす
白雲郷の裏(うち)に鎚(ハンマー)を揮(ふる)うこと迅(はや)く
敲(たた)いて未知の岩石中に入る