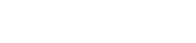地球なんでもQ&A
ログイン
MAIN MENU
宋詩にみる石と人の関わり:梅堯臣の黒水晶,蘇軾の青石,陸游の山頭石,元好問の碔砆
正会員 石渡 明
1.はじめに
前回は中国唐代(618-907)の詩について白居易の青石を中心に石と人の関わりを考えたので(http://www.geosociety.jp/faq/content0818.html),今回は宋代(960-1279)のいくつかの詩について考えることにする.宋代は日本の平安時代中期から鎌倉時代に当たる.吉川幸次郎(1962)は「宋詩概説」(中国詩人選集第二集第一巻,岩波書店)で宋詩の特徴として,叙述性,生活への密着,連帯感,哲学(論理)性,悲哀からの離脱を挙げ,平静さが最大の特徴だとして,唐詩は酒,宋詩は茶だと述べている.また吉川は,欧陽脩(六一居士,1007-72)が従来の仏教または道教の優位に対して儒教の優位を確立し,この転換が約900年後の清末まで中国文化を規制したとも述べている.欧陽脩は宋朝の高官であり,科挙(官吏登用試験)の知貢挙(試験委員長)を何度も務め,日本刀の切れ味を褒める「日本刀歌」などの詞でも名高い.彼はある試験でかつての同僚,5歳年上の詩人梅堯臣を,科挙に合格したことがないにもかかわらず試験委員として採用した.
2.梅堯臣の黒水晶
梅堯臣(聖兪,宛陵先生,1002-60)は,官位は低かったが文名は高く,有名な詩に「猫を祭る」がある.五白という名の飼い猫が死んだのを悲しみ,書物を鼠の害から守った功績を「鶏豚や馬驢に勝る」と讃え,丁寧に水葬する様子を詠んだ詩である.この人は猫だけでなく,鶻から烏,蛙,鰌,蚯蚓,虱,蛆虫まで,鋭い観察力を駆使して何でも詩にした.当然,地学的な対象を詠んだ詩もある.「月食」の詩は,「女中がやって来て驚くべきことを伝えた.天は青い玻璃(ガラス)のようで,月は黒い水精(水晶)のようだと言う.この時期は満月のはずなのに,端が一寸明るいだけだ.主婦は餅を焼き,子供は鏡を敲く.これは浅はかな考えだが,月を助けようという気持ちは尊い.深夜になると桂兎(月の模様)も回復し,星々は(月に)従って西に傾いた(意訳)」と謳う.月食時の月を「黒水晶」と形容するのは流石であり,月食の詩として約1000年後の現代でも通用する.むしろ現代日本の月食の短歌(拙著本誌15巻9号3-4頁(2012)参照)より情緒がある.また,庭石として珍重される「太湖石」は「醜石」だとし,これを自慢する友人に対し「醜を以って世は悪と為せども 茲は醜を以って徳と為す 事に固より醜好無し 醜好は惑わざるを貴ぶ」と言って,本人が好いと思えば好いだけだ,と突き放している(詠劉仲更澤州園中醜石).これは言外に「俺はちっとも好いとは思わん」という心が透けて見える.(参照:筧文生 1962;「梅堯臣」中国詩人選集第二集第三巻,岩波書店)
3.蘇軾の青石
蘇軾(子瞻,東坡居士,1036-1101)は,欧陽脩が委員長,梅堯臣が委員を務めた官吏登用試験の合格者(進士)の一人で,「春宵一刻値千金」(春夜)の句で名高い.1078年の徐州(任地,江蘇省北西部)での「雲竜山に登る」詩では,「酔中走って上る黄茆(茅)岡 満岡の乱石群羊の如し 岡頭に酔倒し石牀と作る 仰いで白雲を看れば天茫々たり 歌声谷に落ちて秋風長し 路人首を挙げて東南を望み 手を拍って大笑す使君(知事,蘇軾自身を言う)狂せりと」と豪語する.宋詩は茶だと言うが,この詩は李白の酒の世界に近い.ただし,蘇軾は実は酒が弱かったらしい(吉川,前出).地質図を見ると,この辺は古生代前期の石灰岩が分布しているようである.秋吉台の石灰岩台地の様子を思い浮かべると,「満岡の乱石群羊の如し」という景色が眼前に浮かぶ.しかし彼はこの翌年(44歳),詩文によって朝政を誹謗したとして投獄され,死罪の危機に直面したが,幸い皇帝の恩命を得て死を免れ,湖北省の黄州に流罪となった.その後も何回か朝政参与と流罪を繰り返したが,「人生は寄するが如し 何ぞ楽しまざる」という自由奔放な詩風は終生変わらなかった(小川環樹 1962; 「蘇軾」上・下,中国詩人選集第二集第五・六巻,岩波書店).
蘇軾には石の趣味があり,1092年の「双石并びに叙」では,「揚州(任地,江蘇省中南部)で石を二つ手に入れた.一つは緑色で山や岡がうねって続くような形で穴が一つ貫通している.もう一つは真っ白で鏡のようである.これらを盆水に浸して机の間に置いた(意訳)」と叙べ,これらの石に触発された空想を詩にしている.これは完全に現代の水石趣味と同じである.また,1097年には恵州(流謫先,広東省)で「白鶴山の新居に鑿井すること四十尺(約8m),盤石に遇い,石尽きて泉を得る」という長い題の詩を作り,業者を4人雇って井戸を掘らせた時の様子を詠んでいる.「10日も掘ったが2〜3m進んだだけだ 下に青石の岩盤がある (錐は)終日ただ火を迸らせるのみ いつの時か飛瀾を見ん 我が粲(白米)と醪(どぶろく)を豊かにせん 汝が錐と鑽とを利くせよ(意訳)」と手前勝手な要求を述べて業者をせっついている.その後ようやく青石の下に,手でつかめるほど軟弱な「黄土」の層が出てきて,水を得ることができた.「我が生,類ね此の如し 何に適くとして艱難ならざらん」と,まるで自分で掘ったかのように言って喜ぶ.しかし,これは見方を変えれば,世界最初(?)のボーリング調査記録かもしれない.地質図を見ると恵州付近は主にトリアス〜ジュラ系が分布しており,地下水脈が多い石灰質の地盤なのかもしれない.「青石」は必ずしも青い石とは限らず,「中国では少し大きな石を青石と言うことが多い」そうで(小川,前出),石灰岩であってもおかしくない.
4.王安石と黄庭堅
王安石(半山,1021-86)は1042年,22歳で進士となったが,しばらく地方官を務めた.神宗皇帝が即位すると召されて1072年に宰相となり,国家財政立て直しのために大規模な改革を始めた.蘇軾らの保守派はこの改革に強く反対した.王安石らの新法党は前述のように蘇軾を投獄したり流罪にしたりしたが,蘇軾は終生敬意をもって王安石と文人としての付き合いを続けた.王安石の改革は一定の成果を挙げたが,神宗の崩御(1085)により頓挫した.彼はその最晩年に,自分がかつて宰相として行った施策が次々に破棄されるのを見なければならなかった(清水茂 1962;「王安石」中国詩人選集第二集第四巻,岩波書店).王安石の詩は風諭詩,閑適詩,感傷詩など多彩で,政敵を攻撃するものから家族への深い愛情や仏教的な悟りを表明するものまで様々だが,安石の名に背き,あまり地学的対象を詩にしていない.王安石のような文人宰相は稀で,他には1953年にノーベル文学賞を受けた英国のチャーチルくらいしかいない(清水,前出).
黄庭堅(1045-1105)は「山谷道人」とも呼ばれ,大自然とその中で生きる動植物を愛した詩人だと言われているが,「実は山水の美の忠実な描写はほとんど見られない」(荒井健, 1963;「黄庭堅」中国詩人選集第二集第七巻,岩波書店).「石竹牧牛に題す 并びに引」で「石,吾は甚だ之を愛す」と言っているが,これは蘇軾が描いた絵の中の怪石の話であり,李公麟がこの絵に牧童が牛に乗っている図を描き加えたのが気に入らず,難癖をつけるための言いがかりだったように思う.彼自ら「点鉄成金」,「換骨奪胎」と呼ぶ,古人の詩を改変して自分の詩を作り出す手法は,明代に偽詩として非難された.黄庭堅は蘇軾の弟子であり,師と同様に新法党に憎まれて何度も流罪になり,流謫先で淋しく死んだ.
5.陸游の山頭石
宋は,北方諸民族(遼,西夏,金,モンゴル)の圧力に押され,首都を汴京(開封)から臨安(杭州)に移した1127年を境に,北宋と南宋に二分される.前述の欧陽脩,梅堯臣,蘇軾,王安石,黄庭堅は北宋の人だが,陸游(放翁,1125-1210)は南宋の人である.陸游は43歳の作「山西の村に遊ぶ」の対句「山重水復疑無路 柳暗花明又一村」で有名だが,彼には医薬の知識があり,「薬袋を提げロバに乗って行けば 村人は歓喜して道を挟んで迎える 口々に以前生き返らせてもらった礼を言い 生まれた多くの子に陸の字をつけたと言う(意訳)」(81歳,「山村経行因施薬」其四)のように老いても人々のために尽くそうとする赤ひげ先生的側面があった.一方で陸游は憂国の詩人であり,宋帝国の失地回復を終生訴え続け,そのため官途では疎まれて栄達しなかったが,85歳の辞世の詩でも息子に対して,「将来皇帝の軍勢が北に進んで中原を平定したら,家の祭をしてこの父に知らせることを忘れるな(意訳)」と指示するほど一途だった.陸游69歳の1193年の秋,故郷の浙江省山陰(紹興)で作った「山頭の石」という詩は次のように謳う.「秋風万木霣れ 春雨百草生ず 造物初めより何の心ぞ 時到れば自ずから枯栄す 惟だ山頭の石有りて 歳月浩として測る莫し 四時の運るを知らずして 常に太古の色を帯ぶ 老翁一生此の山に居り 脚力尽きんと欲して猶お躋攀す 時々石を撫して三嘆息す 安んぞ此の身の爾の如く頑なるを得ん」.地質図を見ると,この石は原生代後期の堆積岩らしい.山頭の石に,日常の時間とはかけ離れた「太古の色」を直感したのは流石である.(参照:一海知義 1962;「陸游」中国詩人選集第二集第八巻,岩波書店)
6.元好問の碔砆
ここまでは,投獄や流罪は経験しても,概ね平和のうちに生涯を終えた宋の詩人たちであるが,陸游の65年後に生まれた元好問(遺山,1190-1257)は戦乱の金に生き,亡国を経験した詩人である.金は女真族が満州・華北に建てた中国風の王朝で,1115年に遼から独立して建国,のちに遼を滅ぼし,1127年に宋を南に追って汴京を首都としたが,1214年頃からしばしばモンゴルの侵攻を受け,1234年にはモンゴルと南宋の連合軍が金を攻め,哀宗皇帝が自殺して金は滅んだ.そして今度はモンゴルが南宋を攻め,1276年に臨安が陥落,1279年までに南宋は完全に滅んだ.元朝の成立はフビライが国号を大元と称した1271年とされる.なお,朝鮮(高麗)を経由してモンゴルが日本に襲来した元寇は1274年と1281年(文永・弘安の役)であり,モンゴルはその後インドシナやジャワにも進出し属国とした.
元好問の詩は宋詩ではないが,時代的には全く南宋と重なる中国の詩なので,敢えてここで取り上げる.彼にとっては,南宋ではなく金朝こそが中原の文化の正統な維持者であり,彼が編纂した「中州集」という金一代の詩集はその考えで貫かれる(小栗栄一 1963;「元好問」中国詩人選集第二集第九巻,岩波書店).彼の詩の多くは戦乱に蹂躙された祖国を悲嘆する「喪乱詩」であり,緊張感と悲壮感が漲っていて,「平静さ」を特徴とする宋詩の対極にある.「野蔓(つる草)情有りて戦骨に縈い 残陽何の意か空城(廃墟の街)を照らす」(岐陽其二,1231年42歳),「惨憺として竜蛇(金とモンゴル)日に闘争し 干戈直ちに生霊(人民)を尽くさんと欲す」(壬辰(1232)十二月車駕東狩後即事其二),「戦地風来りて草木腥し」(同),「誰か謂わん神州(中国)遂に陸沈せんとは」(癸巳(1233)四月二十九日出京)などの詩句からその雰囲気を痛感できる.
彼が好んだ詩人は陶淵明,杜甫,蘇軾であり,「詩論」其の十では,「少陵(杜甫)自ずから連城の璧を有す 争奈んせん微之(元稹)碔砆を識るを」,つまり「杜甫はかれ自身の至宝を持っていたのに,元稹にはまがい玉しか目に入らなかった」(小栗,前出)と,元稹が書いた杜甫の墓誌をこき下ろしている.碔砆(珷玞)というのは玉(翡翠)に似た(玉に次ぐ)美石で,赤地に白い模様があり,湖南省の長沙や臨湘に産するそうである.碧玉jasper,瑪瑙agate,玉髄chalcedony等の一種らしく,碔砆混玉という四文字熟語もある(玉石混交と似た意味).元稹は白居易の親友で,彼らを称して元軽白俗と悪口を言う人たちがいるが,元好問もその一人らしい.ただし,元好問も,表舞台に登場するときには常に多少の誹謗が伴い,筆禍で免職されたことが何回もある.また,彼は金朝の忠臣だったが,金朝滅亡後,63歳のとき(1252年)にモンゴルのフビライに会って「儒教大宗師」の尊号を奉るなど(小栗,前出),世故に長けた部分もある.亡国の戦乱の中で翻弄されながら,そして家族を養いながら,自分の使命を見失わずに作詩を続け,国家的な詩集を編纂して生涯を全うした元好問のしたたかさには,見習うべきものがある.彼は金史の編纂も企てたが,妨害により果たせなかったのは惜しまれる.「若年より山を好んだ彼は老境に入ってからも道すがら谷に分け入ることが少なくなかった」(小栗,前出).彼の強い意志のエネルギーは,案外祖国の山野の自然から得ていたのかもしれない.
7.おわりに
北宋の160年間は,遼や西夏の圧力はあったものの,人々は平和で豊かな生活を享受することができた.欧陽脩,梅堯臣,蘇軾,王安石,黄庭堅らはこの時代の人である.しかし,女真族の金が遼を滅ぼし,1127年には北宋の首都汴京(開封)を奪い,君主徽宋,欽宋の父子を捕虜として満州に連れ去った.皇子高宗は官吏・人民とともに南方に遁れ,臨安(杭州)を首都として揚子江流域を統治した.これが南宋で,その領土内では150年間にわたり,陸游の詩に見るような平和が維持された.陸游は北伐を主張したが,南宋の朝廷は戦争を避け,経済力で平和を買ったのである.一方,金の支配に服した北方の人々は,元好問の詩に見るように,頻発する戦乱に苦しめられ,あげくの果ては金が滅亡し,今度はモンゴルの苛烈な支配に服することになった.金の元好問の深刻な詩を,北宋・南宋の風雅な詩と比べ味わうと,平和の尊さ,ありがたさが改めて実感される.国という字に入るべきなのは玉であり,それに似て非なる碔砆(武夫とも書く)であってはならない,ということである.