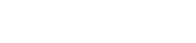地球なんでもQ&A
ログイン
MAIN MENU
システマチックなフィールド教育の導入:山口大学理学部地球圏システム科学科の例
大橋聖和*(山口大学理学部地球圏システム科学科准教授)
*現所属: 産業技術総合研究所 地質調査総合センター
はじめに
山口大学理学部地球圏システム科学科では,一般社団法人日本技術者教育認定機構(JABEE)に認定されたプログラムに基づいて,地質技術者育成のためのフィールド教育を行っている.JABEE認定プログラムは,最長6年の有効期間満了時に継続審査が行われ,第三者によるピア・レビューが行われる.これに加え本学科では,学科構成員からなるワーキンググループ(WG),および外部有識者からのピア・レビュー(外部アドバイザリー会議)を活用し,プログラムの教育改善サイクルを循環させている.2022年3月に,一般社団法人日本地質学会主催 第2回JABEEオンラインシンポジウム「昔と違う イマドキのフィールド教育」注が行われ,本学科の教育プログラムの特徴を,特に教育改善の観点から紹介する機会をいただいた.折しも2016年度頃から取り組んできたフィールド教育のシステム化(体系化)がほぼ完成した段階にあり,その概要と,学科としてどのように教育改善を行ってきたのかについて紹介させていただいた.本報告では,その後数年をかけて微調整してきた部分や新たな課題を追加した上で,本学科における専門教育の現状を紹介したい.
本学科の概要と特色
本学理学部では学科別入試を実施しており,地球圏システム科学科の入学定員は30名である.初年次教育は,自然への興味・関心を育むことや,地球科学を理解する上での基礎的な知識・技能の修得に重点を置き,2年次以降,知識や技能を段階的に高めてゆくカリキュラムになっている.豊富な野外体験と調査技術の体得に力点を置いた「地域環境科学コース」(JABEE認定)と,幅広い知識とともに科学的な思考と応用力を育成する「環境物質科学コース」を設置しており,3年進級時にコース分けを実施している.JABEE認定コースのミッションは,幅広い年代と岩種からなる様々な地質に対応でき,課題や目的を自ら設定しそれを解決する能力を有する,自立した地質技術者の育成である.JABEE認定コースの学生への浸透度は高く,おおむね7〜8割の学生が「地域環境科学コース」に進学する.これは,新入生ガイダンスを皮切りに,複数回のコース分け説明会を行っており,JABEE認定コースの特徴・メリット・対象とする人物像等を,自身のキャリア形成を意識しながら考えさせているからである.なお,JABEE認定コースは3年次の専門科目「野外実習」(図1,5人程度の班ごとに,与えられた地域の地質図を作成するいわゆる進級論文)が必修になるほか,進級・卒業に必要な単位要件や達成度評価法などに違いがある.
 |
| 図1 2022年3月,長門市油谷での「野外実習」(進級論文)の様子 |
カリキュラムの分析と問題点の抽出
新旧の教員が入れ替わり始めていた2015〜2016年度頃,主に「野外実習」を担当した教員から,野外地質調査に関する低年次教育がうまく機能していないのではないかといった問題提起がなされるようになった.具体的には,「調査に必要な持ち物を適切に所持できていない」,「安全な調査の仕方が身についていない」,「現在位置確認やクリノメーターの使用法,マッピングの仕方が身についていない」など知識・技能に関することである.また,姿勢・態度に関する部分についても,「能動的な調査ができない」,「未知のことに取り組む姿勢に乏しい」といった問題点が指摘された.これは,本来学生が「野外実習」の実施前に修得しておくべき知識・技能の復習に現地での貴重な調査時間を割かざるを得ず,結果的にフィールドデータの不足,地質図作成に関する深い議論や考察の欠如,安易な既存研究の追随に至るという構図であった.本学に限ったことではないと思われるが,高校で地学を学んでいない学生が多く存在するため,低年次の実習系科目は自然への興味・関心を育むことが一つの大きな目的である.一方で,従来のカリキュラムでは1年次と2年次で技能に関する修得レベルの違いがそれほど明確ではなく,3年次の「野外実習」において実践的に専門性を高めるカリキュラムであった.また,実習系科目の多くがオムニバス形式や年度ごとのローテーション制であり,引き継ぎや授業間の連携(授業内容の漏れや重複,教員ごとの設定目標の高低)に課題があったことは否めない.その結果,学修内容の年次積み上げによるレベルアップが弱く,3年次の「野外実習」に過度に負担が集中するといった状況が生まれていたと分析した.
カリキュラムの再設計と各授業の開発
| 表1 野外調査において修得すべき項目表(通称,星取表) |
 |
以上の分析結果を踏まえ,(1) 野外地質調査に必要不可欠な項目を,遺漏なく修得させること,(2) 明確な目標設定に基づいて積み上げ教育を機能させること,(3) 学修者にとっても指導者にとっても分かりやすく全体を見通せること,の3つに重点を置いてカリキュラムをデザインし直すこととした.ここでまず取り組んだのは,「何を,いつまでに,どの授業で修得させるか」を突き詰め,明文化した「野外調査において修得すべき項目表」(通称,星取表)の作成である(表1).項目は12の大区分と62の項目からなり,初歩的な技能から実践的な能力まで,具体的に示している.また,卒業までの4年間の年次ごとに,△(まだ不安),〇(おおむね修得),◎(完全に習得)の三段階で達成度の目標を示している.星取表の完成後,これに自己採点欄を付した「自己点検表」も作成し,この2つを学科の全学生に配布することにした.これらはいわゆるルーブリックに相当するものであるが,学生は卒業までに受けるフィールド教育の全体像と現在位置を把握することができ,教員は担当する授業で最低限何を教えるべきかを明確に意識できるようになった.
次に取り組んだのは,星取表で掲げた積み上げ教育を確実に達成するための,具体的なカリキュラム設計と授業開発である.地質学は,(空間三次元)+(時間一次元)=四次元,を取り扱う学問であり,次元が増えるごとに高度な知識とスキルが必要となってくる.そこで,1年次は単一露頭の「点的」な観察・記載,2年次は連続露頭やルート間対比,断面図作成などの「線〜面的」な観察・記載・解析,3年次以降は岩相区分図(平面図)や複数の断面図の作成,地史の構築といった「立体〜四次元」への拡張,とフィールド教育をフェーズ分けした上で実施することとした.また,取り扱う対象も,地質学の基本である堆積岩から始め,鉱物・火成岩,地質構造・変形構造,付加体・変成帯・地体構造,地史へと段階的にステップアップするようにした.これらの基本方針に基づき,WG内でより具体的な問題点を抽出し,改善案を議論した(表2).従来のカリキュラムの問題点をいくつか挙げると,「1年次の実習系科目で座学と実習が反復的に行えていない」,「前期と後期の科目の連携が手薄」,「1年次と2年次の実習内容が差別化できていない」,「担当教員がローテーションで変わるごとに内容が変わる」などである.野外実習の実施場所は,県内の主な巡検場所(20数カ所)をリストアップした上で,「教育内容に最適な場所はどこか」という観点に立って再検討することになった.実習を担当する教員も,まずは適材適所の配置を行い,後に授業担当者が変わっても内容を引き継げるよう独自のテキストを整備した.一部のローテーション制の実習系科目については,学科教員でのピア・レビューや担当者間での引き継ぎを徹底するようにした.
| 表2 年次ごとの野外調査教育フェーズと現状の問題点および改善案 |
 |
実施
見直したカリキュラムに基づいて改良・開発した授業は,2017〜2018年度にかけて段階的に開始した.1年次前期の実習系科目では,興味関心の育成から始まって徐々に専門的な内容を教えており,安全対策を含んだ地質調査の初歩的技能の修得と堆積岩の観察・記載を行うこととした.1年次後期では,対象を鉱物・岩石の観察・記載に特化させ,野外実習と室内作業の反復を意識した授業計画にした.2年次前期では,単一ルートにおけるルートマップ作成や,変形構造の解析など,発展的な内容とした.大学バスの使用ルール上,これまで困難であった県外の泊まりがけ巡検(中国・四国巡検,1泊2日,図2)を,学科支援企業からの奨学寄付金を財源に新たに実施することができたのは我々にとっても大きな改革であった.地体構造を体感させるのに,四国での巡検は不可欠だったからである.2年次後期では,これまでの総復習に加え,地質調査における誤差の取り扱いなど,実践的な内容を取り扱うこととした.前半では,ミクロ〜マクロスケールでの柱状図や地質断面図を描くことにより,地質モデルのスケール感を身につけさせる.後半では,丸二日かけて2本のルート調査を行い,同一層準の追跡,ルート柱状図・断面図・総合柱状図の作成を行う.2年次後期の実習系科目は,3年次の「野外実習」に進むための“関所”と位置づけているため,全員が合格水準に達するまで繰り返し指導を行うこととした.「野外実習」では,グループワーク下にあっても一人一人の達成状況を評価するため,現地での技能チェックや個人での地質図の作成などを課すことにした.
 |
| 図2 2019年6月,中国・四国巡検(砥部衝上断層) |
点検・評価と改善
今回のカリキュラム改革の成果を評価するには,学生が星取表どおりに修得すべき項目を身につけているかどうかが1つの指標になる.自己点検表では,△=1点,〇=2点,◎=3点として総スコア(186点満点)を自己採点し,学期末や年度末および卒業時に提出してもらうことにしている.紙媒体を用いると集計に膨大な時間を要することから,2021年度からは本学のLMS(修学支援システム)を用いたWeb集計フォームと,回答結果をエクセル上で解析できるひな形を開発している.これにより学生はスマホなどから簡便に回答できるようになり,教員は事後のデータ解析が容易になった.また,「野外実習」の履修者を対象として,修得状況の良くない項目についてヒアリングとアドバイスを行うこともあった.学生ごとの修得状況の解析結果では,単純な成長だけでなく,その過程や個性なども見え始めている(詳細はシンポジウムの動画を参照).例えば「野外実習」前後の総スコア変化が小さく,一見すると成長の乏しい学生群を修得すべき項目ごとに分析すると,発展的・実践的な項目が前年度比でマイナスになっており,プラス点を打ち消し合っていることが分かった.ヒアリングからは,「自ら調査を行う中で未熟さを自覚した」,「風化や苔むした露頭で岩石鑑定する難しさを実感した」,「2年次に習ったはずの分類法や記載法を忘れた」,といったスコアだけでは見えない悩みや不安を見ることができた.謙虚な(自分に厳しい)学生が低いスコアを付ける場合もあり,ルーブリックのように自己評価の基準を明確化するか,ヒアリングを通して客観的な評価をする(教員と学生の認識の乖離を埋める)ことが必要であろう.一方で,項目ごとの修得状況の解析結果では,全学生の平均スコアが低い項目や前年比でマイナスになる項目が存在し,講義の弱点や反復学習の重要性が見えてきた.平均スコアが低い項目の例を挙げると,「地形判読から地質との関連性を推測できる」,「変成岩の記載が身についている」,「断層や褶曲についての記載が身についている」など発展的・応用的な項目であり,これらの教授法に課題があることも分かった.また,調査道具の適切な所持の仕方や走向傾斜の測定に関しては,低年次に一度教えてもなかなか簡単に身につかないことがあり,重要なことについては,振り返り学習や,反復しながらレベルを上げてゆくスパイラル教育の重要性を感じることとなった.
これらの点検・評価を踏まえて,2022年度頃から様々な改善を追加で実施している.調査道具の適切な所持の仕方に関しては,目を防護するシールド付きのヘルメットを一括購入させたり,安全教育用のパンフレットを作成し,安全のための道具や技能の重要性をわかりやすく伝えている.全学生の平均スコアが低かった変成岩や変形構造に関する観察・記載能力については,関連する講義系科目や室内実験系科目の中に新たな課題を導入するなど,カリキュラム全体での連携を深めている.
おわりに
今回のカリキュラムの再設計を振り返ると,授業の新設や統廃合は行うことなく,教育のフェーズと扱う対象の順番を意識してカリキュラムを体系的に整理し,各授業を発展させた,ということになる.その礎になったのは星取表の整備であり,各授業の教授内容の明確化と達成度評価の厳格化に大きく寄与している.星取表に基づいた新しいカリキュラムは2023年度で6年目を迎え,最初に入学した学生が大学院を修了するタイミングとなった.学部における積み上げ教育は効果的に機能しており,3年次の「野外実習」だけでなく,卒業研究や修士研究のレベルの向上も実感できるようになっている.星取表は,単に「職人的な地質屋」を育成しているだけのように見えるかもしれないが,我々はあくまでも手段であると考えており,大目的は充実したデータに基づく深い洞察や,自分で考える力の醸成にあった(もちろん,フィールド教育を維持し続けられるよう,安全に最大限配慮するという意味も大きい).堅固な専門基礎教育が高度な研究に結びつくことは,論を俟たないであろう.
一方で,教育フェーズの設定や積み上げ教育,スパイラル教育などは,恐らくかつてはどこの地球科学系大学でも普通に行われていたことで,今回の改革は結局の所,野外地質の学科として「あるべき姿を突き詰めただけ」とも言えるかもしれない.昨今の大学における教員の定員削減や,業務の多忙化,理学部1学科化などが,従来の系統的な専門教育を知らず知らずと(あるいは止むに止まれず)変質させてきたのかもしれない.授業のオムニバス形式や,年度ごとの担当教員のローテーション制は,教員への負担軽減を1つの理由として導入される場合もあるが,一方でデメリットについてもきちんと認識する必要性を感じた.現行カリキュラムの分析にあたっては,専任教員らが学科のあるべき(ありたい)姿を議論・共有することに加え,他大学を経験した教員や実務家教員,JABEE審査員,外部アドバイザーなど,第三者の視点を取り入れることが重要であろう.
(注)
詳細は下記もご参照ください.
- シンポジウムのYouTube動画(https://www.youtube.com/watch?v=hl-2sYxYiOM)
- 報告記事(http://geosociety.jp/uploads/fckeditor/engineer/2nd_JABEE_symp_report.pdf)
2024.05.15